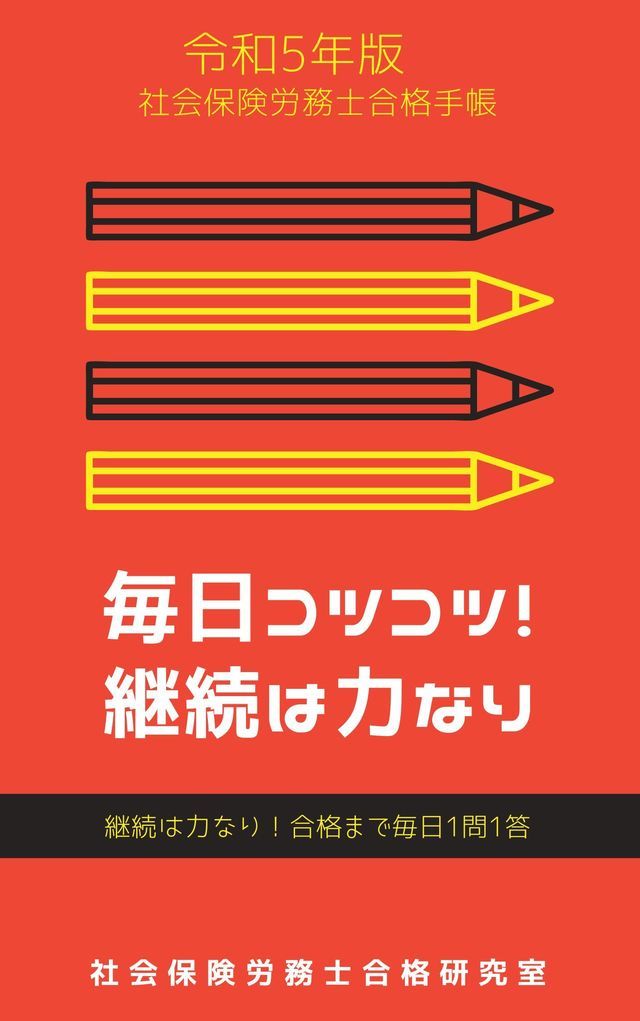
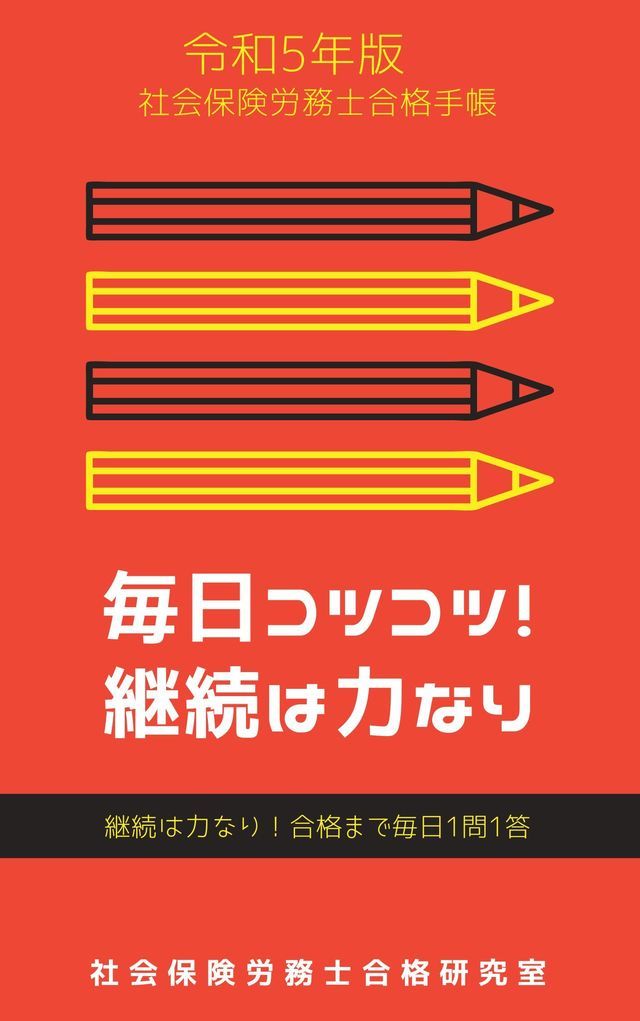
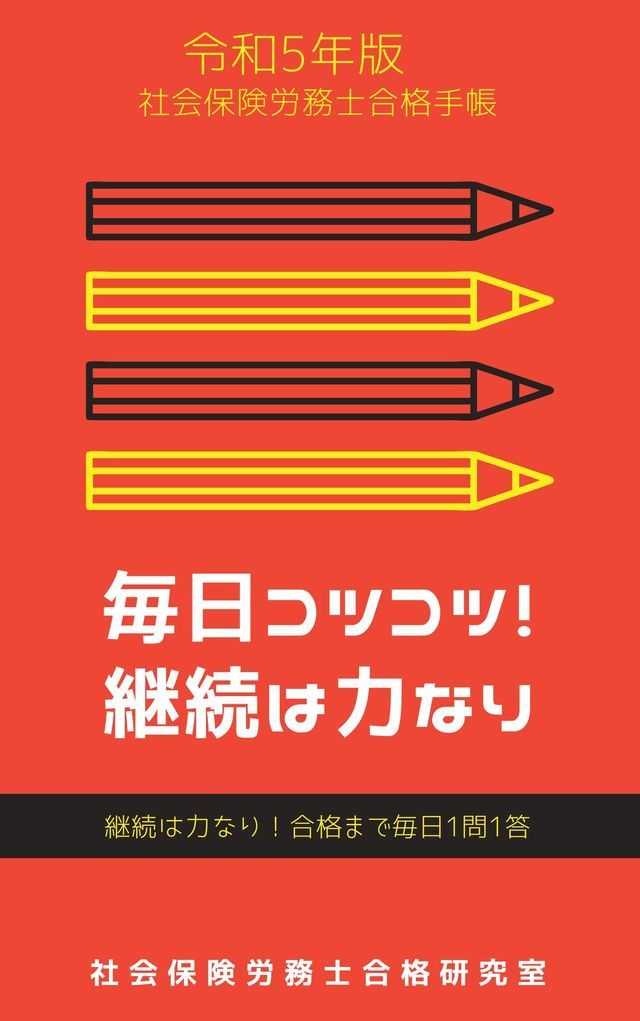
合格手帳の皆様へ
今日のワンポイント!
 8月27日(日) 当日です!
8月27日(日) 当日です!
 毎日コツコツ頑張ってきた皆様の合格を祈ります!
毎日コツコツ頑張ってきた皆様の合格を祈ります!
★ 2023年8月26日(土)8月27日(日)まであと 1日
社会保険労務士法第1条の2社会保険労務士の職責の条文です。
目的条文と併せてチェックしておきましょう。
★ 2023年8月25日(金)8月27日(日)まであと 2日
★基金の給付の基準
・ 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
・ 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
★ 2023年8月24日(木)8月27日(日)まであと 3日
健康保険組合が設立事業所を増加(加入)・減少(分離)させようとする場合の要件です。
なお、設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後も、政令で定める数以上でなければなりません。
★ 2023年8月23日(水)8月27日(日)まであと 4日
事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その者に係る印紙保険料を納付しなければなりません。
印紙保険料の納付は、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければなりません。
★ 2023年8月22日(火)8月27日(日)まであと 5日
高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給対象月の賃金」が「みなし賃金日額×30」の61%未満の場合は、支給対象月の賃金の15%となります。
ただし、上記で計算した支給額+支給対象月の賃金が支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給額となります。
★ 2023年8月21日(月)8月27日(日)まであと 6日
「全部又は一部を行わないことができる」がポイントです。「保険給付を行わない」ではありません。
★ 2023年8月20日(日)8月27日(日)まであと 7日
「すべての労働者」ではなく、「常時使用」する労働者が対象です。
★ 2023年8月19日(土)8月27日(日)まであと 8日
1年単位の変形労働時間の採用ルールは確認しておきましょう。
ちなみに、対象期間の「連続して労働させる日数」の限度は原則として6日です。特定期間については、連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数となります。
★ 2023年8月18日(金)8月27日(日)まであと 9日
介護保険法の保険給付は、次の3つです。
① 被保険者の要介護状態に関する保険給付 (介護給付)
② 被保険者の要支援状態に関する保険給付 (予防給付)
③ 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの (市町村特別給付)
★ 2023年8月17日(木)8月27日(日)まであと 10日
「対象家族」とは
・配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
・父母
・子
・配偶者の父母
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
★ 2023年8月16日(水)8月27日(日)まであと 11日
厚生年金保険法の標準報酬月額の等級は、(1級)88,000円から(32級)
650,000円までです。
★ 2023年8月15日(火)8月27日(日)まであと 12日
国会議員は、昭和55年3月31日までは、国民年金に任意加入もできませんでした。
なお、昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までは、国民年金に任意加入することができました。
★ 2023年8月14日(月)8月27日(日)まであと 13日
被扶養者に関する保険給付には、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金があります。被扶養者ではなく「被保険者」に支給されます。
★ 2023年8月13日(日)8月27日(日)まであと 14日
労働保険事務組合の届出のチェックポイント!
・定款などに記載された事項に変更を生じた場合 → 14日以内
・労働保険事務の処理の委託又は解除があったとき → 遅滞なく
・労働保険事処理の業務を廃止しようとするとき → 60日前までに
★ 2023年8月12日(土)8月27日(日)まであと 15日
「職業能力の開発及び向上」の部分もチェックしてください。
★ 2023年8月11日(金)8月27日(日)まであと 16日
通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則で定められています。
★ 2023年8月10日(木)8月27日(日)まであと 17日
面接指導の対象となる労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者です。
★ 2023年8月9日(水)8月27日(日)まであと 18日
労働基準法第27条の出来高払制の保障給です。
なお、労働者が労働しなかった場合は、第27条の保障給を支払う義務はありません。
★ 2023年8月8日(火)8月27日(日)まであと 19日
紛争解決手続代理業務には、「紛争解決手続について相談に応ずること」、「紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと」、「紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること」が含まれます。
★ 2023年8月7日(月)8月27日(日)まであと 20日
最高裁判決で確立している解雇権濫用法理の規定です。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用に該当するものとして解雇は無効になることを明らかにしています。
★ 2023年8月6日(日)8月27日(日)まであと 21日
特別加算のポイント!
・ 特別加算の額は、受給権者の生年月日によって定められています。生年月日が若いほど高くなるのが特徴です。
・ 昭和18年4月2日以降生まれは、特別加算の額は一律となります。
★ 2023年8月5日(土)8月27日(日)まであと 22日
4分の3免除は88万円、4分の1免除は168万円です。
★ 2023年8月4日(金)8月27日(日)まであと 23日
長期高額疾病の負担軽減の制度です。
①人工透析を実施している慢性腎不全、②血友病、③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群の自己負担の限度額は1万円です。
ただし、①の場合、標準報酬月額が53万円以上の70歳未満の者については、2万円となります。
★ 2023年8月3日(木)8月27日(日)まであと 24日
メリット制が適用されるための「継続性の要件」です。
連続する3保険年度の最後の保険年度に属する3月31日を基準日といいます。
メリット制が適用され労災保険率が改定されるのは、基準日の属する年度の翌々保険年度です。
★ 2023年8月2日(水)8月27日(日)まであと 25日
失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合
((収入の1日分の額-1,310円)+基本手当の日額)が賃金日額の100分の80以下の場合は、基本手は減額されず全額が支給されます。
★ 2023年8月1日(火)8月27日(日)まであと 26日
負担ではなく「補助」です。
★ 2023年7月31日(月)8月27日(日)まであと 27日
業種を問わず適用されるのがポイントです。
★ 2023年7月30日(日)8月27日(日)まであと 28日
試みの試用期間中でも、14日を超えれば、解雇予告が必要です。
★ 2023年7月29日(土)8月27日(日)まであと 29日
事業主等は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行います。
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができます。
★ 2023年7月28日(金)8月27日(日)まであと 30日
「労働協約」の効力の発生も確認しましょう。
労働組合法第14条 (労働協約の効力の発生)
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。
★ 2023年7月27日(木)8月27日(日)まであと 31日
定額部分の額の計算式は、1628円×改定率×被保険者期間の月数です。
定額単価は、昭和21年4月1日以前生まれの場合は、読み替えがあります。
また、被保険者期間の月数は、生年月日に応じて上限があります。
★ 2023年7月26日(水)8月27日(日)まであと 32日
名目手取り賃金変動率です。
名目賃金変動率と間違えないようにしましょう。
★ 2023年7月25日(火)8月27日(日)まであと 33日
167,400円か558,000円のどちらかをおぼえておけばOKです。
・医療費が558,000円の場合は、一部負担金は558,000円×100分の30=167,400円です。
・一部負担金が167,400円の場合は、医療費は、167,400円÷30×100=558,000円です。
★ 2023年7月24日(月)8月27日(日)まであと 34日
メリット制が適用されるための「規模の要件」です。
一括有期事業の場合は、確定保険料の額で判断します。
★ 2023年7月23日(日)8月27日(日)まであと 35日
「特定受給資格者」の範囲のポイントはしっかりおさえましょう。
★ 2023年7月22日(土)8月27日(日)まであと 36日
国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法などで保護されているからです。
★ 2023年7月21日(金)8月27日(日)まであと 37日
努力義務がポイントです。
★ 2023年7月20日(木)8月27日(日)まであと 38日
労働契約全体が無効になるのではなく、無効になるのは、労働基準法で定める基準に達しない部分です。
★ 2023年7月19日(水)8月27日(日)まであと 39日
「社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」を目的とします。
「社会保障」もおさえてください。また「国民保健」です。「保険」ではありませんので注意してください。
★ 2023年7月18日(火)8月27日(日)まであと 40日
最低賃金は、「時間」で定められていることもポイントです。
★ 2023年7月17日(月)8月27日(日)まであと 41日
事後重症の条文です。
「65歳に達する日の前日」→前日を忘れないように注意してください。
★ 2023年7月16日(日)8月27日(日)まであと 42日
振替加算の額は、224,700円×改定率×受給権者の生年月日に応じて政令で定める率で計算します。
生年月日に応じた率は、大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれは「1.000」~昭和36年4月2日~昭和41年4月1日生まれは「0.067」です。
生年月日が若いほど率が小さくなるのが特徴です。
★ 2023年7月15日(土)8月27日(日)まであと 43日
「保険者」が定める、の部分にも注意してください。
★ 2023年7月14日(金)8月27日(日)まであと 44日
印紙保険料の額の認定決定の際の追徴金の割合について
100分の10ではなく、100分の25です。
★ 2023年7月13日(木)8月27日(日)まであと 45日
日雇労働求職者給付金の普通給付の支給日数は、13日~17日です。
★ 2023年7月12日(水)8月27日(日)まであと 46日
給付基礎日額=原則として労働基準法の平均賃金です。
★ 2023年7月11日(火)8月27日(日)まであと 47日
労働衛生指導医は都道府県労働局に置かれます。
★ 2023年7月10日(月)8月27日(日)まであと 48日
A「裁判所」に注意してください。所轄労働基準監督署長ではありません。
★ 2023年7月9日(日)8月27日(日)まであと 49日
懲戒の3つの種類は覚えましょう。
★ 2023年7月8日(土)8月27日(日)まであと 50日
契約期間中の解雇についてルールです。
「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は解雇することができません。
★ 2023年7月7日(金)8月27日(日)まであと 51日
事業主負担分も被保険者負担分も免除されます。
★ 2023年7月6日(木)8月27日(日)まであと 52日
学生が国民年金に強制加入になったのは、平成3年4月からです。
★ 2023年7月5日(水)8月27日(日)まであと 53日
健康保険組合の解散についての条文です。
Cは「事業主」です。被保険者には負担を求められません。
なお、「協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。」と規定されています。
★ 2023年7月4日(火)8月27日(日)まであと 54日
メリット制によって引上げ又は引き下げた率は、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率になります。
★ 2023年7月3日(月)8月27日(日)まであと 55日
雇用保険法の不服申し立ての手順です。
なお、「処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」とされています。
★ 2023年7月2日(日)8月27日(日)まであと 56日
労災保険法の不服申立ての手順です。
なお、「処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」とされています。
★ 2023年7月1日(土)8月27日(日)まであと 57日
健康診断個人票の保存期間も5年間です。
★ 2023年6月30日(金)8月27日(日)まであと 58日
労基法第5条「強制労働の禁止」の条文です。
第5条違反は、労働基準法上最も重い罰則が課せられます。
★ 2023年6月29日(木)8月27日(日)まであと 59日
社会保険審査官・社会保険審査会と間違えないようにしましょう。
★ 2023年6月28日(水)8月27日(日)まであと 60日
パートタイム・有期雇用労働法第8条「不合理な待遇の禁止」の条文です。
★2023年6月27日(火)8月27日(日)まであと 61日
厚生年金保険の被保険者資格は、「70歳に達した日」に喪失します。70歳に達するのは誕生日の前日ですので、6月30日です。
また、年金額の改定は、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月からです。
★2023年6月26日(月)8月27日(日)まであと 62日
「法定免除」についての問題です。
法定免除事由に該当するに至ったときは、当該事実があつた日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければなりません。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、提出は不要です。
★2023年6月25日(日)8月27日(日)まであと 63日
運営委員会とは?
事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置くことになっています。
★2023年6月24日(土)8月27日(日)まであと 64日
確定保険料申告書の提出は、保険関係が消滅した日から50日以内で、当日起算です。
なお、保険関係の消滅日は、廃止又は終了の翌日です。
6月30日に廃止の場合は、7月1日に保険関係が消滅します。
★2023年6月23日(金)8月27日(日)まであと 65日
事業主Bで被保険者として雇用された期間と事業主Aので被保険者として雇用された期間の間が1年超えているため、通算できません。
★2023年6月22日(木)8月27日(日)まであと 66日
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられているものに限られています。
★2023年6月21日(水)8月27日(日)まであと 67日
主語が「事業者」です。事業者の責務についての規定です。
「職場における労働者の安全と健康を確保」の部分にも注意してください。安全と衛生ではなく、安全と健康です。
★2023年6月20日(火)8月27日(日)まであと 68日
日日雇い入れられる者は、労働者名簿の調整は不要です。
★2023年6月19日(月)8月27日(日)まであと 69日
第2号被保険者の介護保険料は、医療保険料といっしょに医療保険の保険者が徴収します。
★2023年6月18日(日)8月27日(日)まであと 70日
男女雇用機会均等法第2条は「基本的理念」の規定です。
今日は1項からの問題でした。
2項も目を通しておきましょう。
↓
「事業主並びに国及び地方公共団体は、基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。」
★2023年6月17日(土)8月27日(日)まであと 71日
繰上げ徴収をする場合は、督促はしません。
★2023年6月16日(金)8月27日(日)まであと 72日
保険料全額免除期間は計算に入らない事にも注意してください。
★2023年6月15日(木)8月27日(日)まであと 73日
健康保険の保険料は被保険者と事業主が2分の1ずつ負担し、納付する義務は事業主が負っています。
任意継続被保険者については、任意継続被保険者が全額負担し、納付する義務も任意継続被保険者が負います。
★2023年6月14日(水)8月27日(日)まであと 74日
概算保険料の認定決定については、追徴金が徴収されないことにも注意してください。
★2023年6月13日(火)8月27日(日)まであと 75日
「失業の日の属する月の前2月間」がポイントです。
「月」単位で納付要件をみていきます。
★2023年6月12日(月)8月27日(日)まであと 76日
「保険給付を行わない」がポイントです。絶対的給付制限です。
★2023年6月11日(日)8月27日(日)まであと 77日
派遣労働者に対する安全衛生教育について
・雇入れ時の安全衛生教育 → 「派遣元」に実施義務
・作業内容変更時の安全衛生教育 → 「派遣元」と「派遣先」の両方に実施義務
・特別の教育 → 「派遣先」に実施義務
・職長等教育 → 「派遣先」に実施義務
★2023年6月10日(土)8月27日(日)まであと 78日
1週間単位の非定型的変形労働時間制です。
1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
★2023年6月9日(金)8月27日(日)まであと 79日
第1号被保険者と第2号被保険者は、保険料の徴収方法が異なります。
市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければなりませんが、対象は第1号被保険者です。
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険が、医療保険料といっしょに徴収します。
★2023年6月8日(木)8月27日(日)まであと 80日
では、「家事使用人」は?
過去問で確認しましょう。(H24年出題)
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。
解答は「〇」です。
★2023年6月7日(水)8月27日(日)まであと 81日
資格喪失日として、死亡したときはその「翌日」、年齢の場合は「その日」はよく出ますので、おぼえましょう。
★2023年6月6日(火)8月27日(日)まであと 82日
年金は、「権利が消滅した月」まで支給されます。
4月に死亡した場合は、年金は4月まで支給されます。
2、4、6、8、10、12月の年6期に前月分までが支給されますので、ただし、年金は後払いです。
2月分と3月分は4月に支給されていますので、未支給は4月分となります。
★2023年6月5日(月)8月27日(日)まであと 83日
今日は、「決算」についての問題でした。
合わせて、「事業計画と予算」の条文もチェックしましょう。
「全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」
★2023年6月4日(日)8月27日(日)まであと 84日
特別加入者は、二次健康診断等給付の対象にならないことに注意しましょう。
★2023年6月3日(土)8月27日(日)まであと 85日
この場合、受給期間は1年+60日となります。
★2023年6月2日(金)8月27日(日)まであと 86日
書類の保存期間は、他の科目と比較しながら横断的におぼえましょう。
★2023年6月1日(木)8月27日(日)まであと 87日
「労働災害」の定義です。
★2023年5月31日(水)8月27日(日)まであと 88日
「請求した場合」に注意してください。
産前休業は「請求」が必要です。
また、軽易な業務への転換も「請求」が要件です。
★2023年5月30日(火)8月27日(日)まであと 89日
労働基準法の「児童」と比較しましょう。
労働基準法は、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」と定義しています。
★2023年5月29日(月)8月27日(日)まであと 90日
労働契約の成立の基本原則は「合意の原則」です。
合意によって成立しますので、契約内容について書面を交付することまでは求められていません。
★2023年5月28日(日)8月27日(日)まであと 91日
厚生年金の「保険給付」には、「老齢厚生年金」、「障害厚生年金及び障害手当金」、「遺族厚生年金」があります。
「保険給付」を受ける権利の時効は5年ですが、この保険給付には障害手当金も入っています。
国民年金の死亡一時金の事項は2年ですので、違いに注意して下さい。
★2023年5月27日(土)8月27日(日)まであと 92日
国民年金法の「給付」には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。
「死亡一時金」以外は、「年金給付」です。
「年金給付」を受ける権利の時効は5年ですが、「死亡一時金」を受ける権利の時効は2年です。
★2023年5月26日(金)8月27日(日)まであと 93日
ちなみに、「保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。」という規定もあります。
・「行わない」と「行わないことができる」の違い
・「全部又は一部」と「一部」の違い
を意識してください。
★2023年5月25日(木)8月27日(日)まであと 94日
1円未満の端数は、第1期分に加算します。
★2023年5月24日(水)8月27日(日)まであと 95日
書類の保存期間は、他の科目と比較しながら横断的におぼえましょう。
★2023年5月23日(火)8月27日(日)まであと 96日
・前者を「求償」、後者を「控除」といいます。
★2023年5月22日(月)8月27日(日)まであと 97日
・事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければならない。
1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2 書面を労働者に交付すること。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
・事業者は、委員会の開催の都度、一定事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
★2023年5月21日(日)8月27日(日)まであと 98日
育児時間を請求できるのは女性のみです。男性は請求できません。
★2023年5月20日(土)8月27日(日)まであと 99日
「医療費適正化基本方針」を定め、6年ごとに、6年1期として、全国医療費適正化計画を定めるのは、厚生労働大臣です。
★2023年5月19日(金)8月27日(日)まであと 100日
民間企業の法定雇用率2.3%もおぼえましょう。
★2023年5月18日(木)8月27日(日)まであと 101日
「負担」という用語もおさえておきましょう。
★2023年5月17日(水)8月27日(日)まであと 102日
「生計を同じく」と「生計を維持」は区別して覚えましょう。
★2023年5月16日(火)8月27日(日)まであと 103日
埋葬料は5万円です。
埋葬費は、5万円の範囲内の実費です。
★2023年5月15日(月)8月27日(日)まであと 104日
<期の分け方>
・4月1日~7月31日
・8月1日~11月30日
・12月1日~3月31日
<最初の期>
保険関係成立日が7月1日で、その期の末日(7月31日)まで2か月以内です。
そのため、最初の期は、次の期と合わせて、11月30日までとなります。
<最初の期分の納期限>
納期限は、保険関係が成立した日から20日以内です。「翌日起算」ですので、7月1日の翌日から起算して20日以内の7月21日となります。
★2023年5月14日(日)8月27日(日)まであと 105日
A 通所手当です。
誤字、申し訳ないです。
受講手当は、公共職業訓練等を受講しない日、待期中の日、傷病手当の支給対象となる日については支給されません。(行政手引52851)
★2023年5月13日(土)8月27日(日)まであと 106日
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」からです。
★2023年5月12日(金)8月27日(日)まであと 107日
「作業を適切に管理」の「作業」という用語にも注意して下さい。
★2023年5月11日(木)8月27日(日)まであと 108日
既往の労働→既に労働した分、という意味です。
まだ労働していない分まで支払う義務はありません。
★2023年5月10日(水)8月27日(日)まであと 109日
事業の健全な「発達」です。発展と間違えないようにしましょう。
★2023年5月9日(火)8月27日(日)まであと 110日
「定年」は定めなくても構いませんが、定める場合は、原則として60歳を下回ることはできません。
★2023年5月8日(月)8月27日(日)まであと 111日
「合意分割」についてです。
「第1号改定者」は、対象期間標準報酬総額が多い方で、分割する方です。
「第2号改定者」は、対象期間標準報酬総額が少ない方で、分割を受ける方です。
★2023年5月7日(日)8月27日(日)まであと 112日
厚生年金保険法と比較してみましょう。
厚生年金保険法第2条の2
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
厚生年金保険法の方は、「賃金」が入ります。
★2023年5月6日(土)8月27日(日)まであと 113日
資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主は、「報酬月額算定基礎届」、「報酬月額変更届」、「賞与支払届」は、電子申請で行うものとされています。
★2023年5月5日(金)8月27日(日)まであと 114日
都道府県・市町村の行う事業は「二元適用事業」です。
国の行う事業は二元適用事業ではありません。国の行う事業は、労災保険が成立しないからです。
★2023年5月4日(木)8月27日(日)まであと 115日
「資格喪失届」は、事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、提出しなければなりません。この場合、被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、原則として、資格喪失届に離職証明書を添えなければなりません。
例外的に、被保険者が離職票の交付を希望しないときは離職証明書を添えないことができます。ただし、離職の日に59歳以上の被保険者については、希望の有無に関係なく、離職証明書を添えなければなりません。
★2023年5月3日(水)8月27日(日)まであと 116日
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合でも、逸脱又は中断の間は通勤になりません。
★2023年5月2日(火)8月27日(日)まであと 117日
ちなみに、元方事業者のうち特定事業(=建設業又は造船業に属する事業)を行う者を特定元方事業者といいます。
★2023年5月1日(月)8月27日(日)まであと 118日
「打切補償」について確認しましょう。
第81条 (打切補償)
療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
★2023年4月30日(日)8月27日(日)まであと 119日
「有限均衡方式」といいます。100年程度の長期の均衡を図ります。
★2023年4月29日(土)8月27日(日)まであと 120日
「実施機関たる共済組合等」は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付します。
★2023年4月28日(金)8月27日(日)まであと 121日
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。通算がポイントです。
★2023年4月27日(木)8月27日(日)まであと 122日
保険関係は、事業の廃止、又は終了の日の翌日に消滅します。
保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。この場合、当日起算となります。
★2023年4月26日(水)8月27日(日)まであと 123日
日雇労働者の定義は、しっかりおさえましょう。
★2023年4月25日(火)8月27日(日)まであと 124日
死亡の推定の対象は、「船舶」と「航空機」の事故だけですので、注意してください。
★2023年4月24日(月)8月27日(日)まであと 125日
3年と間違わないようにしましょう。
★2023年4月23日(日)8月27日(日)まであと 126日
なお、賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない、とされています。
★2023年4月22日(土)8月27日(日)まであと 127日
障害認定日の属する月まで計算に入ります。
★2023年4月21日(金)8月27日(日)まであと 128日
「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。
★2023年4月20日(木)8月27日(日)まであと 129日
資格取得時決定の有効期間の問題です。
1月1日~5月31日に資格取得 → その年の8月まで
6月1日~12月31日に資格取得 → 翌年の8月まで
★2023年4月19日(水)8月27日(日)まであと 130日
中小事業主が労災保険に特別加入するには、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することが条件です。
★2023年4月18日(火)8月27日(日)まであと 131日
マルチジョブホルダー制度についてです。
本人からの「申出」により、申出を行った日からマルチ高年齢被保険者となります。
★2023年4月17日(月)8月27日(日)まであと 132日
労働保険事務組合の事務処理を委託できる事業主の範囲は覚えましょう。
金融・保険・不動産・小売業 → 50人以下
卸売・サービス業 → 100人以下
その他の事業 → 300人以下
★2023年4月16日(日)8月27日(日)まであと 133日
「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」と「職長等の教育」には、記録の保存期間の義務規定はありません。
★2023年4月15日(土)8月27日(日)まであと 134日
公民権行使の場合の給与は、有給でも無給でも当事者の自由に委ねられています。
★2023年4月14日(金)8月27日(日)まであと 135日
「障害認定日」は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」又は、「1年6か月以内に傷病が治った場合はその治った日」です。ちなみに「治った日」には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日が含まれます。
★2023年4月13日(木)8月27日(日)まであと 136日
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、老齢基礎年金の年金額に反映するのは、20歳以上60歳未満の期間です。20歳前と60以後の期間は、合算対象期間となります。
★2023年4月12日(水)8月27日(日)まであと 137日
「運営委員会」と間違えないように注意してください。
運営委員会は、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に置かれます。
★2023年4月11日(火)8月27日(日)まであと 138日
「又は」に注意してください。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、概算保険料の額に関係なく延納ができます。
★2023年4月10日(月)8月27日(日)まであと 139日
管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たっては、失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとされています。
★2023年4月9日(日)8月27日(日)まであと 140日
社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所とは、労災病院等のことです。
★2023年4月8日(土)8月27日(日)まであと 141日
1000人以上、500人以上の「以上」にも注意してください。
1000人ちょうど、500人ちょうども含みます。
★2023年4月7日(金)8月27日(日)まであと 142日
解雇の予告期間が16日ですので、予告手当は14日分以上必要です。
解雇の予告期間には、解雇予告をした日は入りませんので注意しましょう。
★2023年4月6日(木)8月27日(日)まであと 143日
障害手当金は「治っている」ことが条件です。
★2023年4月5日(水)8月27日(日)まであと 144日
なお、年金は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前月分までが支払われます。その際の支払額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てです。
★2023年4月4日(火)8月27日(日)まであと 145日
特定適用事業所とは、事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のこと
★2023年4月3日(月)8月27日(日)まであと 146日
「確定保険料の認定決定」の問題です。
確定保険料の認定決定の通知は「納入告知書」で行われます。
★2023年4月2日(日)8月27日(日)まであと 147日
最低保障が適用されるのは、日給制、時給制、出来高払い制その他の請負制の場合です。
★2023年4月1日(土)8月27日(日)まであと 148日
「一時差し止める」とは、一時的に金銭の給付を止めることです。差止め事由がなくなれば、留保された分が支払われます。
★2023年3月31日(金)8月27日(日)まであと 149日
「遅滞なく」の部分も注意してください。
★2023年3月30日(木)8月27日(日)まであと 150日
有給休暇の付与、深夜業の割増賃金は、第41条該当者にも適用されます。
★2023年3月29日(水)8月27日(日)まであと 151日
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、おぼえておきましょう。
★2023年3月28日(火)8月27日(日)まであと 152日
国民年金に任意加入できるのは、第2号被保険者でもなく、第3号被保険者でもなく、第1号被保険者の要件も満たさない人です。
★2023年3月27日(月)8月27日(日)まであと 153日
保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものは、訪問介護療養費の対象から除かれます。
★2023年3月26日(日)8月27日(日)まであと 154日
翌日起算になることがポイントです。
例えば、3月26日に保険関係が成立した場合は、3月27日から起算して20日以内に納付しなければなりません。
★2023年3月25日(土)8月27日(日)まであと 155日
特例一時金の受給期限は離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までです。
★2023年3月24日(金)8月27日(日)まであと 156日
逸脱・又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合でも、逸脱又は中断の間は通勤となりません。
★2023年3月23日(木)8月27日(日)まであと 157日
衛生管理者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任義務があります。
労働者数によって、選任人数が決まっていることもポイントです。
★2023年3月22日(水)8月27日(日)まであと 158日
年次有給休暇の時季指定義務です。
ポイントは
・対象は年次有給休暇が10日以上付与される労働者です
・年5日は、使用者が時季を指定して取得させなければなりません
・しかし、年次有給休暇を5日以上取得している労働者には、時季指定する必要はありません。
★2023年3月21日(火)8月27日(日)まであと 159日
「在職定時改定」の条文です。
65歳以上の人が対象の制度です。
★2023年3月20日(月)8月27日(日)まであと 160日
年金の給付は、「年6期・偶数月・後払い」と覚えましょう。
例えば、4月15日に支払われるのは、2月分と3月分の年金です。
★2023年3月19日(日)8月27日(日)まであと 161日
以前42日の「以前」に注目してください。
出産の日当日は、産前42日に含まれます。
★2023年3月18日(土)8月27日(日)まであと 162日
第3種特別加入保険料率は、「一律」で決まっているのがポイントです。
★2023年3月17日(金)8月27日(日)まであと 163日
「証明書」で失業の認定をうけることができるパターンは4つ。しっかり覚えましょう。
★2023年3月16日(木)8月27日(日)まであと 164日
療養の開始後「3年」がポイントです。
1年6か月と間違えないようにしましょう。
★2023年3月15日(水)8月27日(日)まであと 165日
「以上」ではなく「超える」がポイントです。
★2023年3月14日(火)8月27日(日)まであと 166日
事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるのは「労働時間を算定し難い」ときです。
★2023年3月13日(月)8月27日(日)まであと 167日
①~③は短期要件、④は長期要件です。
★2023年3月12日(日)8月27日(日)まであと 168日
配偶者は「子と生計を同じくしている」ことが、遺族基礎年金を受ける条件です。
★2023年3月11日(土)8月27日(日)まであと 169日
<C>は10年ではなく25年です。注意してください。
★2023年3月10日(金)8月27日(日)まであと 170日
通算して1年6月の「通算」もポイントです。
★2023年3月9日(木)8月27日(日)まであと 171日
・保険年度の6月1日から40日以内 → 当日起算です。
・保険年度の中途に保険関係が成立したもの
保険関係が成立した日から50日以内 → 翌日起算です。
★2023年3月8日(水)8月27日(日)まであと 172日
・待期は「通算」して7日です。連続していなくても完成します。
★2023年3月7日(火)8月27日(日)まであと 173日
・「葬祭を行う者」とは、通常は遺族となる場合が多いですが、遺族がない場合は、遺族の代わりに葬祭を行うにふさわしい立場の人が該当することもあります。
★2023年3月6日(月)8月27日(日)まであと 174日
・「都道府県労働局長」の許可です。
労働基準監督署長などと間違えないように気をつけてください。
★2023年3月5日(日)8月27日(日)まであと 175日
・絶対的明示事項の「昇給に関する事項」以外は、原則として書面の交付によって明示しなければなりません。
・労働者が希望した場合は、ファクシミリや電子メール等での明示も可能です。
★2023年3月4日(土)8月27日(日)まであと 176日
・「子」ついては、「障害基礎年金」の加算の対象になります。
・3級の障害厚生年金には、加給年金額は加算されません。
★2023年3月3日(金)8月27日(日)まであと 177日
「被保険者期間」は、月単位で計算します。
資格を取得した日の属する月~資格を喪失した日の属する月の前月までを算入します。
★2023年3月2日(木)8月27日(日)まであと 178日
健康保険の保険給付には、「現物給付」と「現金給付」があります。
療養費は現金給付です。
★2023年3月1日(水)8月27日(日)まであと 179日
「下請負事業の分離」の規定です。
・認可が必要です。
・概算保険料が160万円以上又は請負金額が1億8000万円以上でなければなりません。
「かつ」ではなく「又は」がポイントです。
★2023年2月28日(火)8月27日(日)まであと 180日
未支給の失業等給付は、死亡した者の名ではなく、「自己の名」で請求します。
★2023年2月27日(月)8月27日(日)まであと 181日
介護補償給付が支給される要件の「常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、 常時又は随時介護を受けている」の「かつ」がポイントです。
★2023年2月26日(日)8月27日(日)まであと 182日
「安全管理者」、「衛生管理者」のキーワードは、「労働基準監督署長」と「増員又は解任の命令」です。
「総括安全衛生管理者」のキーワードは、「都道府県労働局長」と「勧告」です。
★2023年2月25日(土)8月27日(日)まであと 183日
年次有給休暇は、「6か月間継続勤務」し、全労働日の「8割以上」出勤した場合に、発生します。
出勤率は、「全労働日(労働する義務のある日)」に対する出勤した日の割合です。
★2023年2月24日(金)8月27日(日)まであと 184日
配偶者の成年月日ではなく、老齢厚生年金の受給権者の生年月日です。
★2023年2月23日(木)8月27日(日)まであと 185日
200円×200か月=40,000円です。
納付する付加保険料の額は400円です。200円と400円を間違えないようにしましょう。
★2023年2月22日(水)8月27日(日)まであと 186日
「入院時食事療養費の額」=「食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から、「食事療養標準負担額」を控除した額です。
★2023年2月21日(火)8月27日(日)まであと 187日
労災保険率は、最高が1000分の88、最低が1000分の2.5です。
★2023年2月20日(月)8月27日(日)まであと 188日
基本手当の日額 = 賃金日額×一定の率です。
「一定の率」は「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」で異なりますので注意しましょう。
★2023年2月19日(日)8月27日(日)まであと 189日
労災保険の保険給付は
・業務災害に関する保険給付
・複数業務要因災害に関する保険給付
・通勤災害に関する保険給付
・二次健康診断等給付
です。
★2023年2月18日(土)8月27日(日)まであと 190日
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医の選任義務があります。
全ての業種が対象です。
★2023年2月17日(金)8月27日(日)まであと 191日
労働基準法で「使用者」と定義されるのは、次の3つです。
①事業主
②事業の経営担当者
③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
★2023年2月16日(木)8月27日(日)まであと 192日
例えば、3級の場合は障害基礎年金をうけることはできません。その場合、障害厚生年金の額には最低保障が設けられています。最低保障の額は、障害基礎年金(2級)の額×4分の3です。
★2023年2月15日(水)8月27日(日)まであと 193日
「初診日」とは、「傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。
★2023年2月14日(火)8月27日(日)まであと 194日
保険医・保険薬剤師は「登録」
保険医療機関、保険薬局は「指定」です。
★2023年2月13日(月)8月27日(日)まであと 195日
「請負事業の一括」は、建設の事業だけが対象です。立木の伐採の事業には適用されませんので注意しましょう。
★2023年2月12日(日)8月27日(日)まであと 196日
ちなみに、「技能習得手当」として、受講手当と通所手当があります。
★2023年2月11日(土)8月27日(日)まであと 197日
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場の要件は、すべての基本になりますのでしっかり覚えましょう。
★2023年2月10日(金)8月27日(日)まであと 198日
法定休日の定義です。
休日は原則として、毎週少なくとも1回与えなければなりません。
★2023年2月9日(木)8月28日(日)まであと 199日
「被保険者期間を有する者」とは、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあることという意味です。
65歳以上の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば、支給されます。
★2023年2月8日(水)8月27日(日)まであと 200日
老齢基礎年金の受給権は、要件を満たせば、65歳に達したときに受給権が発生します。
★2023年2月7日(火)8月27日(日)まであと 201日
船員保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者等は、任意継続被保険者になることができません。
★2023年2月6日(月)8月27日(日)まであと 202日
保険関係成立届は、成立した日の「翌日から起算して」10日以内に提出します。
★2023年2月5日(日)8月27日(日)まであと 203日
提出期限はよく出題されます。
★2023年2月4日(土)8月27日(日)まであと 204日
休業補償給付は、1日あたり、給付基礎日額の100分の60です。
★2023年2月3日(金)8月27日(日)まであと 205日
作業場を巡視する義務の有無、巡視の頻度は、しっかり覚えましょう。
★2023年2月2日(木)8月27日(日)まであと 206日
「労働することが条件」となると、労働者を拘束することになってしまいます。そのため禁止されています。
★2023年2月1日(水)8月27日(日)まであと 207日
健康保険の標準報酬月額等級の区分と異なりますので、比較して覚えましょう。
★2023年1月31日(火)8月27日(日)まであと 208日
年齢による資格喪失は「当日」です。
ちなみに第2号被保険者は20歳以上60歳未満という要件がありませんので、60歳に達しても資格は喪失しません。
★2023年1月30日(月)8月27日(日)まであと 209日
報酬支払基礎日数が17日以上の月で計算します。
なお、短時間労働者は11日です。
★2023年1月29日(日)8月27日(日)まであと 210日
特例納付保険料は、2年を超えて遡って雇用保険に加入した場合の保険料です。
★2023年1月28日(土)8月27日(日)まであと 211日
雇用保険は給付の名称が覚えにくいですが、体系だてて整理しましょう。
★2023年1月27日(金)8月27日(日)まであと 212日
傷病補償年金の支給要件です。
労働基準監督署長の職権で支給が決定されることもポイントです。
★2023年1月26日(木)8月27日(日)まであと 213日
命令ではなく「勧告」です。
★2023年1月25日(水)8月27日(日)まであと 214日
頭文字の「ぎょう・さん・し・いく・し」でおぼえましょう。
平均賃金の計算の際、分母(総日数)からも分子(賃金の総額)の両方から控除します。
★2023年1月24日(火)8月27日(日)まであと 215日
年齢を理由に資格を喪失する場合は、翌日ではなく当日喪失です。
★2023年1月23日(月)8月27日(日)まであと 216日
「昭和61年4月1日」も超重要年号です。
昭和61年4月前の年金制度は旧法、昭和61年4月以降の年金制度は新法といいます。
基礎年金制度、2階建ての年金、会社員等に扶養される妻(夫)の年金加入は、新法からの制度です。
★2023年1月22日(日)8月27日(日)まであと 217日
随時改定は、「著しく高低を生じた月の翌月」から改定されます。「固定的賃金の変動があった月の4か月目から」と表現することもあります。
★2023年1月21日(土)8月27日(日)まであと 218日
有期事業の一括は法律上当然に行われます。
規模の要件は、「又は」ではなく「かつ」であることがポイントです。
★2023年1月20日(金)8月27日(日)まであと 219日
失業の認定日に失業認定申告書に添えるのは「受給資格者証」です。雇用保険被保険者証と間違えないように注意してください。
★2023年1月19日(木)8月27日(日)まであと 220日
葬祭補償給付ではありませんので、注意しましょう。
★2023年1月18日(水)8月27日(日)まであと 221日
主語は「産業医」です。
★2023年1月17日(火)8月27日(日)まであと 222日
1週の法定労働時間は原則40時間ですが、特例の事業場の場合は44時間となります。
人数要件の「10人未満」と業種はしっかり覚えましょう。
★2023年1月16日(月)8月27日(日)まであと 223日
「被保険者期間」は月単位です。
例えば、令和5年1月16日に資格取得、同年8月31日退職(9月1日資格喪失)の場合は、被保険者期間は、令和5年1月から令和5年8月までです。
★2023年1月15日(日)8月27日(日)まであと 224日
国民年金が全面施行された「昭和36年4月1日」は最重要年号です。
★2023年1月14日(土)8月27日(日)まであと 225日
「療養の給付」の範囲です。
なお、食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養、選定療養は、療養の給付に入りません。
★2023年1月13日(金)8月27日(日)まであと 226日
「建設の事業」が対象です。
労災保険関係成立票です。労「働」保険関係成立票と間違えないようにしましょう。
★2023年1月12日(木)8月27日(日)まであと 227日
直前の28日とは、前回の失業の認定日から今回の失業の認定日の前日までです。
★2023年1月11日(水)8月27日(日)まであと 228日
「通勤」の定義はよく出題されます。
過去問をしっかりチェックしましょう。
★2023年1月10日(火)8月27日(日)まであと 229日
総括安全衛生管理者の仕事は「統括管理」です。
総括管理ではありませんので、ご注意ください。
★2023年1月9日(月)8月27日(日)まであと 230日
労働基準法第4条は、一般的な男女差別を禁止しているのではありません。禁止しているのは、「賃金」についての差別です。なお、有利に扱う事も差別となります。
★2023年1月8日(日)8月27日(日)まであと 231日
【解答】
厚生年金保険の被保険者は70歳までです。
なお、第10条は任意単独被保険者です。
★2023年1月7日(土)8月27日(日)まであと 232日
国民年金の場合は、「保険給付」という言い方はしませんので注意してください。
20歳前の障害基礎年金など、保険料を納付しなくても支給される年金があるからです。
★2023年1月6日(金)8月27日(日)まであと 233日
「臨時に受けるもの」「3月を超える期間ごとに受けるもの」は報酬に入りません。
なお、「3月を超える期間ごとに受けるもの」は「賞与」となります。
★2023年1月5日(木)8月27日(日)まであと 234日
徴収法の「賃金」の定義です。
徴収法では、保険料の算定に「賃金」をつかいます。
通貨以外のもので支払われるものとは、現物給与のことです。
★2023年1月4日(水)8月27日(日)まであと 235日
「失業」とは単に離職することではありません。
労働の意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず、就職できない状態のことをいいます。
★2023年1月3日(火)8月27日(日)まであと 236日
労災保険のメインの目的は「保険給付」を行うことです。
併せて、社会復帰促進等事業も行うことができます。
★2023年1月2日(月)8月27日(日)まであと 237日
労働安全衛生法はもともと労働基準法の一部でした。
労働基準法と労働安全衛生法は、「一体としての関係」にあることがポイントです。
★2023年1月1日(日)8月27日(日)まであと 238日
「法定労働時間」は、原則1週40時間、1日8時間以内です。
拘束時間から「休憩時間」を除いた時間が労働時間です。
社労士受験のあれこれ 令和5年度