合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和7年度版
毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ
このページは令和7年度版です。
こちらのページは令和7年度試験向けに書いた記事です。
法改正は反映されていませんので、ご注意ください。
令和8年度試験向けの「社労士受験のあれこれ」はこちらからどうぞ。
社労士受験のあれこれ(令和8年度版)
当日の最終チェック
R7-361 8.24
いよいよ当日です!社一の第1条をチェックします
当日です! 100%の力が発揮できるよう、祈っています。 一つずつ、落ち着いて取り組んでくださいね。 応援しています! |
社一の法律の第1条を総ざらいしましょう。
★国民健康保険法 第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
★高齢者の医療の確保に関する法律 第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
★船員保険法 第1条 (目的) この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★介護保険法 第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
★確定給付企業年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★確定拠出年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★児童手当法 第1条 (目的) この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
★社会保険労務士法 第1条 (目的) この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
本試験前の最終チェック
R7-360 8.23
本試験前に第1条を総ざらいしましょう!(穴埋め問題もあります)
最後の1日です。
覚えたことは忘れないように 自信をもって解答できるように 最後の1日は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。 気になるところは、必ず見返してくださいね。 |
各法律の第1条を総ざらいしましょう。
条文を読んでみましょう。
最後に穴埋め問題もあります。
労働基準法第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働安全衛生法第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
労働者災害補償保険法第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
雇用保険法第1条(目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
労働保険徴収法第1条(趣旨) この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
健康保険法第1条(目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
国民年金法第1条(国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
厚生年金保険法第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
空欄を埋めてみましょう
★労働基準法第1条 (労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

【解答】
★労働基準法第1条 (労働条件の原則)
<A> 人たるに値する生活
<B> この基準
★労働安全衛生法第1条 (目的)
この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための< B >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、 < C >を促進することを目的とする。

【解答】
★労働安全衛生法第1条 (目的)
<A> 労働基準法
<B> 危害防止基準
<C> 快適な職場環境の形成
★労働者災害補償保険法第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< B >を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の< C >に寄与することを目的とする。

【解答】
★労働者災害補償保険法第1条
<A> 複数事業労働者
<B> 保険給付
<C> 福祉の増進
★雇用保険法第1条(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。

【解答】
★雇用保険法第1条(目的)
<A> 所定労働時間を短縮することによる就業
<B> 福祉の増進
★労働保険徴収法第1条(趣旨)
この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、< A >等に関し必要な事項を定めるものとする。

【解答】
★労働保険徴収法第1条(趣旨)
<A> 労働保険事務組合
★健康保険法第1条(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

【解答】
★健康保険法第1条(目的)
<A> 福祉の向上
★国民年金法第1条(国民年金制度の目的)
国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の< B >に寄与することを目的とする。

【解答】
★国民年金法第1条(国民年金制度の目的)
<A> 日本国憲法第25条第2項
<B> 維持及び向上
★厚生年金保険法第1条 (この法律の目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。

【解答】
★厚生年金保険法第1条 (この法律の目的)
<A> 福祉の向上
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法<最終チェック>
R7-359 08.22
覚えたことは忘れない「元方事業者」(労働安全衛生法)
本試験まで、あと2日です。
覚えたことは忘れないように 自信をもって解答できるように 最後の2日間は、今までみてきたテキストをもう一度見直しましょう。 |
今回のテーマは「元方事業者」です。
条文を読んでみましょう。
★業種の如何にかかわらず元方事業者に適用される規定です
(元方事業者の講ずべき措置等) 法第29条 ① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 ② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 ③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 |
★特定元方事業者とは、「建設業・造船業」の元方事業者です
(特定元方事業者等の講ずべき措置) 法第30条第1項 ① 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 (1) 協議組織の設置及び運営を行うこと。 (2) 作業間の連絡及び調整を行うこと。 (3) 作業場所を巡視すること。 (4) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 (5) 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。 (6) 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項 |
★製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者の講ずべき措置です
法第30条の2第1項 ① 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。 ※政令で業種が定められていませんので、「製造業(造船業除く)」のみに適用されます |
過去問をチェックしましょう
①【H19年選択式】
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

【解答】
①【H19年選択式】
<A> 一の場所
②【H18年出題】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

【解答】
②【H18年出題】 〇
第29条は、「業種のいかんを問わず」適用されることがポイントです
③【H22年出題】
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

【解答】
③【H22年出題】 ×
元方事業者は、「関係請負人の労働者」に対しても、指導及び指示を行わなければなりません。
(法第29条)
④【H26年出題】
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

【解答】
④【H26年出題】 ×
労働安全衛生法第29条第2項違反に、罰則はありません。
⑤【H27年出題】
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
作業期間中少なくとも1週間に1回ではなく、毎作業日に少なくとも1回巡視しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
則第637条 (作業場所の巡視) ① 特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも1回、これを行なわなければならない。 ② 関係請負人は、特定元方事業者が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 |
⑥【H20年出題】
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第20条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。

【解答】
⑥【H20年出題】 ×
関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。
・ 特定元方事業者が講ずべき措置
→ 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」です。
関係請負人の労働者の安全衛生教育を行うのではなく、「安全衛生教育に対する指導及び援助」を行います。
・ 関係請負人である事業者の義務
→ 関係請負人の労働者に対し、「作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育」を行わなければなりません。
⑦【H22年出題】
造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

⑦【H22年出題】 〇
「造船業に属する事業の元方事業者」=「特定元方事業者」です。
「特定元方事業者」は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければなりません。
⑧【H18年出題】
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

【解答】
⑧【H18年出題】 ×
「協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置」は、特定元方事業者に義務付けられている措置です。
製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければなりませんが、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置は義務付けられていません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険労務士法に出てくる数字
R7-358 08.21
意外と問われる社会保険労務士法の数字
社会保険労務士法で問われる数字をチェックしましょう。
過去問からどうぞ!
①【R4年出題】
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
「3年」をおぼえましょう。
条文を読んでみましょう。
法第5条 (欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 (1) 未成年者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (4) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの (5) 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの (6) 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (7) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者 (8) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの (9) 税理士法の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの |
②【R2年出題】
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。

【解答】
②【R2年出題】 ×
「60万円」ではなく「120万円」です。
条文を読んでみましょう。
「紛争解決手続代理業務」について(法第2条第1項1号の4~1号の6) ① 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 ② 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 ③ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 |
※③について
単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は120万円となります。
③【R5年出題】
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
「1年間」ではなく「2年間」保存しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
法第19条 (帳簿の備付け及び保存) ① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 ② 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。 |
④【H24年選択式】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

④【H24年選択式】
<A> 2年間
<B> 100万円以下の罰金
⑤【H15年出題】
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。

【解答】
⑤【H15年出題】 ×
・労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為(第15条不正行為の指示等の禁止)
→ 罰則が科せられます
・信用又は品位を害するような行為(第16条信用失墜行為の禁止)
→ 罰則は科せられません。
ポイント!
第15条違反については、社会保険労務士法で最も重い罰則が科せられます。
第32条 第15条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 |
⑥【H15年出題】
開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

⑥【H15年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第21条 (秘密を守る義務) 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。 |
第21条に違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
(法第32条の2)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<横断>書類の保存期間
R7-357 08.20
<横断編>書類の保存期間を確認しましょう 「安衛・労災・雇用・徴収・健保・厚年」
各法律の書類の保存期間を確認しましょう。
条文で確認しましょう。
★労働安全衛生法 ※労働安全衛生法については、よく出る箇所だけおぼえましょう 則第23条第4項 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 (1) 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 (2) 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
則第38条 (特別教育の記録の保存) 事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
則第51条 (健康診断結果の記録の作成) 事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
則第52条の6第1項 (面接指導結果の記録の作成) 事業者は、法第66条の8の面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。)の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
★労災保険法 則第51条 (書類の保存義務) 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
★雇用保険法 則第143条 (書類の保管義務) 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、 4年間)保管しなければならない。
★労働保険徴収法 則第72条 (書類の保存義務) 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、 4年間)保存しなければならない。
★健康保険法 則第34条 (事業主による書類の保存) 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
★厚生年金保険法 則第28条 (書類の保存) 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
★労働安全衛生法
①【H30年出題】
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
定期自主検査の記録は、5年間ではなく「3年間」保存しなければならないとされています。
(則第135条の2)
②【H22年出題】
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しなければならない。

【解答】
②【H22年出題】 〇
特別教育の記録は、「3年間」保存しなければなりません。
③【R2年出題】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

【解答】
③【R2年出題】 ×
面接指導の結果の記録の保存すべき年限は3年ではなく「5年」です。
④【H27年出題】
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

【解答】
④【H27年出題】 ×
健康診断個人票の保存期間は、3年間ではなく「5年間」です。
★労災保険法
【R1年出題】
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

【解答】
【R1年出題】 ×
労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。
(則第51条)
★雇用保険法
【R4年出題】
事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

【解答】
【R4年出題】 〇
雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)は、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は、4年間)保管しなければなりません。
★労働保険徴収法
【H28年出題】(雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】
【H28年出題】(雇用) 〇
その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければなりません。
(則第72条)
★健康保険法
【H25年出題】
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

【解答】
【H25年出題】 ×
その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。
(則第34条)
★厚生年金保険法
【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。

【解答】
【H29年出題】 ×
事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければなりません。5年間という例外はありません。
(則第28条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健保・厚年>短時間労働者が被保険者になる条件
R7-356 08.19
短時間労働者が被保険者になる条件のポイント!<健保・厚年>
短時間労働者が被保険者になる要件をチェックしましょう。
★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者は、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 報酬の月額が88,000円以上であること
③ 学生でないこと
■健康保険法の問題をチェックしましょう。
(1)特定適用事業所とは
①【健保H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【健保H29年出題】 〇
「特定労働者の総数が常時50人を超える」がポイントです。
(H24法附則第46条第12項)
(2)所定労働時間について
①【健保R2年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】
①【健保R2年出題】 〇
・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)
②【健保R3年出題】
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

【解答】
②【健保R3年出題】 ×
通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満である者が被保険者として取り扱われるためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。問題文の場合は18時間ですので、被保険者になりません。
(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)
(3)報酬の月額について
①【健保R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
①【健保R4年選択式】
<A> 88,000円以上
②【健保H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
②【健保H30年出題】 ×
最低賃金法において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)
■月額88,000円の算定に含まれないもの
・ 臨時に支払われる賃金(例)結婚手当
・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例)賞与
・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例)割増賃金
・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金
→ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(4)学生でないことについて
①【健保R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
④【健保R3年出題】 ×
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
■学生でないこととして取り扱われるもの
「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。」とされています。
(R4.9.28保保発0928第6号)
■厚生年金保険法の問題もチェックしましょう
①【厚年R5年出題】※改正による修正あり
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。

【解答】
①【厚年R5年出題】 ×
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。
※特定労働者とは、「70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの」をいいます。
(H24法附則第17条第12項)
②【厚年R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
②【R2年出題】 〇
特定適用事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
(H24法附則第17条第1項)
③【R4年出題】※改正による修正あり
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
※Xは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。

【解答】
③【R4年出題】 ×
Xは、厚生年金保険の被保険者となります。
「国・地方公共団体」は、50人超えという人数が問われないことがポイントです。
Xは、「① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「② 報酬の月額が88,000円以上であること」、「③ 学生でないこと」の要件を満たし、「地方公共団体」で働いているので、厚生年金保険の被保険者となります。
(H24法附則第17条第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<横断>「賃金」について 労基・雇用・徴収
R7-355 08.18
<横断編>賃金の定義(労基・雇用・徴収)
労働基準法、雇用保険法、労働保険徴収法の「賃金」の定義を確認しましょう。
また、労働基準法の「平均賃金」、「割増賃金」、雇用保険法の「賃金日額」、徴収法の「労働保険料」の算定に含むもの、含まれないものもみていきます。
「賃金」の定義を横断で確認しましょう。
★労働基準法 第11条 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
★雇用保険法 第3条第4項、第5項 ④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
★労働保険徴収法 第2条第2項、第3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 |
過去問をどうぞ!
★労働基準法
①【労基H23年出題】
労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。

【解答】
①【労基H23年出題】 ×
「使用者又は顧客が」ではなく、「使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。
(法第11条)
②【労基H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
②【労基H27年出題】 〇
退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金となりません。
但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金となります。
(昭22.9.43発基第17号)
③【労基H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

【解答】
③【労基H27年出題】 ×
「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額から除外されますが、「通勤手当及び家族手当」は、計算に含まれます。
★平均賃金を計算する際「日数」と「賃金総額」の両方から控除するもの
・業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間
・試みの使用期間
★平均賃金の計算の基礎となる賃金総額に算入しない賃金
・臨時に支払われた賃金
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
④【労基H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】
④【労基H26年出題】 〇
通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金には算入されません。
★割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
(法第37条第5項、則第21条)
※家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当は名称にかかわらず、実質によって取り扱うとされています。
例えば、家族数に関係なく一律に支給されている家族手当は、平均賃金の算定に含まれます。
★雇用保険法
①【雇用H21年出題】
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。

【解答】
①【雇用H21年出題】 ×
「通貨以外のもので支払われるもの(=現物給付)で、厚生労働省令で定める範囲」のものは賃金に含まれます。
(法第4条第4項、則第2条第1項)
②【雇用H26年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

【解答】
②【雇用H26年出題】 ×
「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるとされています。
食事、被服、住居の利益は、公共職業安定所長が定めるまでもなく、賃金の範囲に算入されます。
問題文の住居の利益は、賃金となります。
(則第2条第1項、行政手引50403、行政手引50501)
③【雇用H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

【解答】
③【雇用H22年出題】 ×
「家族手当、通勤手当及び住宅手当」は、賃金日額の計算に算入されます。
(行政手引50501)
★賃金日額を計算する際に賃金総額から除外されるもの
・臨時に支払われる賃金
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
★労働保険徴収法
①【徴収H19年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むとされている。

【解答】
①【徴収H19年出題】(雇用) 〇
労働保険徴収法の「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含みます。
(法第2条第2項、則第3条第1項)
②【徴収R5年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

【解答】
②【徴収R5年出題】(雇用) ×
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、「厚生労働大臣」が定めることとされています。
(法第2条第3項)
③【徴収H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
③【徴収H26年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、賃金となりません。
(昭25.2.16基発127号)
④【徴収H24年出題】(労災)
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。

【解答】
④【徴収H24年出題】(労災) 〇
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されません。
(平15.10.1基徴発1001001号)
⑤【H29年出題】(労災)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。

【解答】
⑤【H29年出題】(労災) 〇
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入するとされています。
(平15.10.1基徴発1001001号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-354 08.17
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年8月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年8月11日から16日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・障害者雇用促進法を確認しましょう(労働に関する一般常識)
・労働契約法の「判例」のポイントをチェックしましょう(労働に関する一般常識)
・労働契約の原則のキーワードをチェック(労働契約法)
・<横断編>支給制限「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」など(労災・健保・国年・厚年)
・生計維持の条件を横断整理しましょう(労災・健保・国年・厚年)
・「時効」を横断整理(労災・雇用・健保・国年・厚年)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<横断編>時効
R7-353 08.16
「時効」を横断整理(労災・雇用・健保・国年・厚年)
時効を横断整理します。
★労災保険法
時効には、「2年」と「5年」があります。
療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、葬祭料(複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
ポイント!
療養(補償)等給付は、「療養の費用の支給を受ける権利」です。
障害・遺族の「前払一時金」は「2年」です。
障害(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。
遺族(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。
障害(補償)年金差額一時金は「5年」です。
傷病(補償)等年金は、時効の問題は生じません
過去問をどうぞ!
★労災保険法
①【H27年出題】 ※改正による修正あり
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
介護補償給付(複数事業労働者介護給付、介護給付)を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年ではなく「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。
(法第42条第1項)
「特別支給金」の申請期限も確認しましょう。
②【R2年出題】
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

【解答】
②【R2年出題】 ×
休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して「2年」以内に行うこととされています。
(特支則第3条第6項)
③【H24年出題】
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 ×
遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して「5年以内」に行わなければなりません。
(特支則第5条第8項)
<特別支給金の申請期限について>
・休業特別支給金は「2年以内」、それ以外は「5年以内」です。
★雇用保険法
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
過去問をどうぞ!
★雇用保険法
①【H28年出題】※改正による修正あり
失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

①【H28年出題】 〇
失業等給付等を受ける権利、その返還を受ける権利の時効は2年です。
(法第74条第1項)
②【R4年出題】
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付すべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。

②【R4年出題】 〇
政府が返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利の時効は、2年です。
(法第74条第1項)
③【R2年出題】
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び雇用保険法第10条の4に規定する不正受給による失業等給付の返還命令又は納付命令により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、この権利を行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
③【R2年出題】 ×
「この権利を行使することができることを知った時から」ではなく、「これらを行使することができる時から」2年を経過したときは、時効によって消滅します。
★健康保険法
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
過去問をどうぞ!
★健康保険法
①【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「現物給付」である「療養の給付」には、時効はありません。
②【R5年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】
②【R5年出題】 ×
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年ですが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日ではなくその「翌日」です。
時効の起算日にも注意しましょう。
(昭30.9.7保険発199号の2)
③【R1年出題】
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
③【R1年出題】 ×
出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日」ではなく、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅します。
(昭30.9.7保険発199号の2)
④【H30年出題】
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

【解答】
④【H30年出題】 ×
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算されます。
コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、「コルセットを装着した日」ではなく、「代金を支払った日」の翌日から消滅時効が起算されます。
(昭31.3.13保文発199の2)
★国民年金法
・ 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
・ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
ポイント
年金は「5年」、死亡一時金は「2年」です
過去問をどうぞ!
★国民年金法
①【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき
時効によって消滅します。
年金給付と死亡一時金の違いに注意しましょう。
(法第102条)
②【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②【R2年出題】 〇
支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点となります。
(法第102条)
★厚生年金保険法
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
ポイント
「保険給付」には障害手当金が含まれます。障害手当金の時効は5年です
国民年金法の「死亡一時金」の時効は2年ですので、違いに注意しましょう。
過去問をどうぞ!
★厚生年金保険法
①【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【H29年出題】 ×
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
(第92条第1項)
②【R4年出題】
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点です。
(法第92条第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<横断編>法律で異なる生計維持の定義
R7-352 08.15
生計維持の条件を横断整理しましょう(労災・健保・国年・厚年)
「生計維持」が認定される要件を、横断で整理します。
★労災保険法★
「遺族補償年金」について
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
ポイント!
もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。
(昭41.1.31基発第73号)
では、過去問をどうぞ!
★労災保険法
①【H17年出題】
遺族(補償)等年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。

【解答】
①【H17年出題】 ×
「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる」とされています。
(昭和41年1月31日付基発第73号)
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
②【H28年出題】 〇
遺族補償給付には「年金」と「一時金」がありますが、条件の違いに注意しましょう。
・年金の場合
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする」ことが条件ですので、生計を維持していなかった場合は、受給権者にはなりません。
・一時金の場合
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とされています。
(1) 配偶者
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3) 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
一時金の場合は、「生計を維持していなかった」場合でも受給者となり得ます。
★健康保険法★
「被扶養者」の認定について
ポイント!
「被扶養者」の条文を読んでみましょう。
第3条第7項 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
※注意 問題文の認定対象者は、日本国内に住所を有しているものとします。

【解答】
②【R1年出題】 〇
■「認定対象者」が被保険者と同一世帯に属している場合
(1)認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) (1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
とされています。
(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
②【H30年出題】
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。
※注意 問題文の配偶者の母は、日本国内に住所を有しているものとします。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「配偶者の母」が被扶養者となるには、「被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する」ことが要件です。
被保険者と別居している場合は、被扶養者に該当しません。
③【R3年出題】
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。

【解答】
③【R3年出題】 〇
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされています。
(令和2.4.10事務連絡)
★国民年金法・厚生年金保険法
・生計維持の認定要件を確認しましょう。
① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者は除く。)→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
② 障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者
→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
(平23.3.23年発0323第2号)
★障害基礎年金、障害厚生年金は、受給権が発生した後でも、結婚や出生などで加算の要件を満たした場合は、その翌月から加算が行われます。
過去問をどうぞ!
①【国民年金R2年出題】
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。

【解答】
①【国民年金R2年出題】 ×
前年の収入が年額850万円以上でも、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められる場合は、収入に関する認定要件に該当します。
②【厚生年金保険法H27年出題】
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

【解答】
②【厚生年金保険法H27年出題】 ×
①の問題と同じです。問題文の場合は、生計維持関係が認定されます。
③【厚生年金保険法H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
③【厚生年金保険法H29年出題】 〇
配偶者を有するに至った日の属する月の「翌月」から、加給年金額が加算されるのがポイントです。
障害基礎年金と障害厚生年金は、「受給権を取得した日の翌日以後」にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者(障害基礎年金の場合は子)を有するに至ったときでも、加算の対象になります。
条文を読んでみましょう。
国民年金法第33条の2第2項 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
厚生年金保険法第50条の2第3項 障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
横断<労災・健保・国年・厚年>
R7-351 08.14
<横断編>支給制限「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」など
今日は「支給制限」の横断です。
まず、労災保険法と健康保険法を比較しましょう。
条文の空欄を埋めてみましょう
★労災保険法
第12条の2の2
① 労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が< C >若しくは重大な過失により、又は< D >ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
<A> 故意に
<B> 直接の原因
<C> 故意の犯罪行為
<D> 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
★健康保険法
第116条
被保険者又は被保険者であった者が、< A >により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< B >。
第119条
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< C >を行わないことができる。

【解答】
<A> 自己の故意の犯罪行為
<B> 全部又は一部を行わないことができる
<C> 一部
過去問をどうぞ!
★労災保険法
①【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、「政府は保険給付を行わない」となります。
(法第12条の2の2第1項)
②【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
②【R2年出題】 〇
「政府が保険給付の全部又は一部を行わないとすることができる」のは、「重大な過失」の場合です。
「(重大でない)過失」の場合は、適用されません。
(法第12条の2の2第2項)
③【R6年出題】
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

③【R6年出題】 〇
「重大な過失」のときは、「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
④【R2年出題】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
④【R2年出題】 〇
政府が保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」のは、「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより疾病の程度を増進させた場合です。正当な理由があれば、支給制限されません。
(法第12条の2の2第2項)
★健康保険法
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「保険給付は、行わない」となるのは、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に」給付事由を生じさせたときです。「重過失」は入っていません。
(法第116条)
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全額について行わないものとする。

【解答】
②【H23年出題】 ×
闘争、泥酔、著しい不行跡については、「その全部又は一部を行わないことができる」となります。
(法第117条)
③【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」に、行わないことができるのは、保険給付の「一部」です。
よく出る箇所ですので注意してください。
(法第119条)
④【H28年出題】
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
④【H28年出題】 〇
条文の空欄を埋めてみましょう。
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、< A >。

【解答】
<A> 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
(法第121条)
次は、国民年金法と厚生年金保険法を比較しましょう。
条文の空欄を埋めてみましょう
★国民年金法
第69条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、< A >。
第70条
故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
第71条
① 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < C >死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を < C >死亡させた者についても、同様とする。
② 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< C >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
<A> 支給しない
<B> 重大な過失
<C> 故意に
★厚生年金保険法
第73条
被保険者又は被保険者であった者が、< A >、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第73条の2
被保険者又は被保険者であった者が、< B >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第74条
障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は< C >ことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
第76条
① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< D >死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< D >死亡させた者についても、同様とする。
② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< D >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
<A> 故意に
<B> 自己の故意の犯罪行為
<C> 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない
<D> 故意に
過去問をどうぞ!
★国民年金法
①【R5年出題】
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「支給しない」となります。
(法第69条)
②【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

【解答】
②【R1年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅します。
(法第71条第2項)
③【R1年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

【解答】
③【R1年出題】 〇
「故意に」死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給されません。
④【H26年選択式】
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。

【解答】
④【H26年選択式】
<A> 療養に関する指示に従わない
<B> 全部又は一部を行わない
(法第70条)
⑤【R1年出題】
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
条文を読んでみましょう。
法第72条 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
<参考>年金給付の支払を一時差し止めることができるとき 第73条 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 |
⑥【R4年出題】
国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
「受診命令に従わず、又は当該職員の診断を拒んだ」ときは、一時差し止めではなく、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができるとなります。
(第72条第2号)
★厚生年金保険法
①【R1年出題】
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「故意に」のときは「支給されない」。
「重大な過失」のときは「全部又は一部を行わないことができる」。
(法第73条、第73条の2)
②【H29年出題】
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その「障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」の給付制限です。
(法第74条)
③【R2年出題】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

③【R2年出題】 〇
「職員の質問に応じなかった」ときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができるとなります。
条文を読んでみましょう。
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3) 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
<参考>「一時差し止め」の条文も読んでみましょう。 第78条第1項 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働に関する一般常識(労働契約法の基本)
R7-350 08.13
労働契約法「労働契約の原則」のキーワードをチェック
条文の穴埋めからどうぞ!
第1条 (目的)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< A >により成立し、又は変更されるという< A >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< B >に資することを目的とする。

【解答】
<A> 合意
<B> 個別の労働関係の安定
第2条 (定義)
① この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
② この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して< A >をいう。

【解答】
<A> 賃金を支払う者
第3条 (労働契約の原則)
① 労働契約は、労働者及び使用者が< A >における< B >に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
② 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、< C >を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
③ 労働契約は、労働者及び使用者が< D >にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
④ 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、 < E >しなければならない。
⑤ 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを < F >することがあってはならない。

【解答】
<A> 対等の立場
<B> 合意
<C> 均衡
<D> 仕事と生活の調和
<E> 権利を行使し、及び義務を履行
<F> 濫用
第4条 (労働契約の内容の理解の促進)
① 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、< A >を深めるようにするものとする。
② 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り< B >により確認するものとする。

【解答】
<A> 労働者の理解
<B> 書面
第5条 (労働者の安全への配慮)
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその< A >を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

【解答】
<A> 生命、身体等の安全
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

【解答】
①【H24年出題】 〇
家事使用人にも労働契約法は適用されます。
「家事使用人」は、労働契約法の適用は除外されていません。
※労働契約法の適用が除外されるものを確認しましょう。
適用除外の条文を読んでみましょう。
第21条 (適用除外) ① この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 ② この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 |
②【H29年出題】
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

【解答】
②【H29年出題】 ×
労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。
「したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであること。これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念であること。」とされています。
(平24.8.10基発0810第2号)
③【R1年出題】
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
「法第4条第1項は、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであること。これは、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものであること。」とされています。
(平24.8.10基発0810第2号)
⑤【H30年出題】
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
■第5条の趣旨と内容を確認しましょう。
(1) 趣旨 通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかになっていないところである。 このため、法第5条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 (2) 内容 ア 法第5条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。 イ 法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。 ウ 法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。 エ 法第5条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものであること。 (平24.8.10基発0810第2号) |
⑥【H28年出題】
労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を求めているが、その内容は一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。

【解答】
⑥【H28年出題】 〇
⑤の問題と同じ、第5条の内容についての問題です。
⑦【H22年出題】
使用者は、労働契約に伴い、労働者及びその家族がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。

【解答】
⑦【H22年出題】 ×
使用者の安全配慮義務の対象に、「家族」は、含まれません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働に関する一般常識(労働契約法)
R7-349 08.12
労働契約法の「判例」のポイントをチェックしましょう
労働契約法の過去問を解きながら、よく出題される判例の重要ポイントをチェックしましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H26年出題】 〇
■労働者が疾病のためその命じられた義務のうち一部の労務の提供ができなくなったことから直ちに債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできないとされた事例です。
労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務(現場監督)について労務の提供が十全にはできないとしても他の業務(事務作業)について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。
→ 「そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものになるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である」とされています。
(片山組事件平成10年4月9日最高裁判所第一小法廷)
②【H28年出題】
いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
②【H28年出題】 ×
■使用者が労働者に対し個別的同意なしにいわゆる在籍出向を命ずることができるとされた事例です。
「いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下においては、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに出向を命ずることができる。」とされています。
※「在籍出向」は、出向元との労働契約関係が存続していることがポイントです。
(新日本製鐵事件 平成15年4月18日最高裁判所第二小法廷)
③【H30年出題】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
③【H30年出題】 ×
■使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する
■就業規則が法的規範として拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する
使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するとするのが最高裁判所の判例です。
(フジ興産事件 平成15年10月10日最高裁判所第二小法廷)
④【H26年出題】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
④【H26年出題】 〇
③の問題と同じです。
さらに、就業規則に拘束力を生ずるために、「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られている」ことが必要です。
(フジ興産事件 平成15年10月10日最高裁判所第二小法廷)
⑤【H30年出題】
いわゆる採用内定の制度は、多くの企業でその実態が類似しているため、いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、それまでの間、内定企業の作成した誓約書に記載されている採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立しているものとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
「企業が大学の新規卒業者を採用するについて、早期に採用試験を実施して採用を内定する、いわゆる採用内定の制度は、従来わが国において広く行われているところであるが、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきである。したがって、具体的事案につき、採用内定の法的性質を判断するにあたっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要がある」とされています。
ちなみに、大日本印刷事件は、「大学卒業予定者の採用内定により、就労の始期を大学卒業直後とする解約権留保付労働契約が成立したものと認められた事例」です。
(大日本印刷事件 昭和54年7月20日最高裁判所第二小法廷)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働に関する一般常識(障害者雇用促進法)
R7-348 08.11
障害者雇用促進法を確認しましょう
「障害者雇用促進法」を確認しましょう。
今回の内容です
・民間企業の障害者雇用率
・令和6年障害者雇用状況の集計結果のポイント
・目的条文の穴埋め
・障害者の雇用義務について条文
・対象障害者の雇用に関する状況の報告
・人数の数え方
・除外率について
・障害者雇用調整金、障害者雇用納付金
・過去問
法第34条 (障害者に対する差別の禁止)
法第36条の2 (障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
合理的配慮に関する基本的な考え方
法違反とならない措置
YouTubeでお話ししています
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-347 08.10
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年8月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年8月4日から9日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう(厚生年金保険法)
・ 確定給付企業年金法・確定拠出年金法を比較してみましょう(社会保険に関する一般常識)
・国民健康保険法の制度について(社会保険に関する一般常識)
・保険料の比較~高齢者医療確保法・介護保険法(社会保険に関する一般常識)
・給付について~確定給付企業年金と確定拠出年金(社会保険に関する一般常識)
・ 社一横断「都道府県?」それとも「市町村?」(社会保険に関する一般常識)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「横断編」
R7-346 08.09
社一横断「都道府県」それとも「市町村」?
例えば、介護保険法では、介護認定審査会は「市町村」に置かれます。また、介護保険審査会は、「都道府県」に置かれます。
よく似た名称が出てきますし、「市町村」か「都道府県」かを問う問題も繰り返し出題されます。
今回は、よく出題される個所を横断的にみていきます。
条文を読んでみましょう。
★国民健康保険法
法第11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会) ① 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 ② 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
第91条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第92条 (審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 第93条 (組織) ① 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |
★高齢者医療確保法
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 第49条 (特別会計) 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第104条 (保険料) 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
第128条 (審査請求) ① 後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第129条 (審査会の設置) 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 |
★介護保険法
第14条 (介護認定審査会) 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。 第15条 (委員) ① 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。 第16条 (共同設置の支援) ① 都道府県は、認定審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 ② 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第183条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第184条 (介護保険審査会の設置) 介護保険審査会は、各都道府県に置く。 第185条 (組織) ① 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 (1) 被保険者を代表する委員 3人 (2) 市町村を代表する委員 3人 (3) 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数 ② 委員は、都道府県知事が任命する。 ③ 委員は、非常勤とする。 |
過去問をどうぞ!
★国民健康保険法
①【H18年出題】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
①【H18年出題】 ×
審査請求は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」に対して行います。
②【R6年出題】
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」が誤りです。
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織されます。
★高齢者医療確保法
①【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
最初の「都道府県は」が誤りです。
後期高齢者医療広域連合を設けるのは都道府県ではなく、「市町村」です。
②【H23年出題】※改正による修正あり
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
「都道府県及び市町村(特別区を含む。)は」が誤りです。
後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないのは、「市町村(特別区を含む。)」です。
(第104条)
③【H22年出題】
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】
③【H22年出題】 ×
「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない、となります。
(第49条)
④【H25年出題】※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
④【H25年出題】 ×
「社会保険審査会」ではなく「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができる、となります。
⑤【R4年出題】※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
⑤【R4年出題】 〇
「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができます。
★介護保険法
①【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
介護認定審査会は、市町村から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされています。
(第27条第5項)
②【R3年出題】
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。

【解答】
②【R3年出題】 ×
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。」とされています。
③【H27年出題】
市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができます。
④【R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければなりません。
⑤【R5年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」という規定はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識(給付を比較してみましょう)
R7-345 08.08
給付について(確定給付企業年金法・確定拠出年金法)
確定給付企業年金法と確定拠出年金法の「給付」をみていきます。
最初に、それぞれの給付の種類を確認しましょう。
過去問をどうぞ!
(確定給付企業年金法)
【H26年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】
【H26年出題】 〇
・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う
・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)
(第29条)
(確定拠出年金法)
【H20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
【H20年出題】 〇
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。
また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。
では、給付の内容をみていきます。
過去問をどうぞ!
(確定給付企業年金法)
①【H26年出題】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。
ちなみに「事業主等」とは、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金「基金型企業年金」を実施する場合にあっては、企業年金基金)のことです。
(法第30条)
②【H26年出題】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、<A>にわたり、<B>以上定期的に支給するものでなければならない。
<A> 終身又は5年以上
<B> 毎年1回
(第33条)
次は、「老齢給付金」の問題です。
まず、条文を読んでみましょう。
第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② 規約で定める要件は、次に掲げる要件(「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 (1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ 前項(2)の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
第38条 (支給の方法) ① 老齢給付金は、年金として支給する。 ② 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
第40条 (失権) 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 (2) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 (3) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならないとされています。
②【H26年出題】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

【解答】
②【H26年出題】 ×
老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができます。
③【H30年選択式】
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】
③【H30年選択式】
<A> 60歳以上70歳以下
<B> 50歳未満
④【R2年出題】
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】
④【R2年出題】 ×
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が「死亡したとき」、老齢給付金の「支給期間が終了したとき」と、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」に消滅します。
次は脱退一時金の問題です。
【R3年選択式】
確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、< A >を超える加入者期間を定めてはならないとされている。

【解答】
【R3年選択式】
<A> 3年
(確定拠出年金法)
①【R5年出題】
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく< A >に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
<A> 75歳
(第34条)
②【R1年選択式】
確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について < A >までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
②【R1年選択式】
<A> 障害認定日から75歳に達する日の前日
③【H29年出題】
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】
③【H29年出題】 ×
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができます。
この要件においては、通算拠出期間が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であることとされています。
政令で定める期間内は1月以上5年以下、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下とされています。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については<A>であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が<B>であることとされている。
<A> 1月以上5年以下
<B> 25万円以下
(附則第3条、令第60条)
ちなみに、個人型年金に加入していた者の脱退一時金を請求するための要件として、他に、「60歳未満であること」などもあります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識(比較してみましょう)
R7-344 08.07
保険料の比較(高齢者医療確保法と介護保険法)
最初に、「高齢者医療確保法」と「介護保険法」の財源を確認しましょう。
★高齢者医療確保法の「後期高齢者医療」の財源について
公 費(約5割) | |
保険料(約1割) | 後期高齢者支援金(約4割) |
※後期高齢者(原則75歳以上)の保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)
→令和6・7年度は12.67%
★介護保険法の財源について
公費(50%) |
保険料(50%) |
第1号被保険者→23%
第2号被保険者→27%
今回は、「保険料」をみていきます。
★後期高齢者医療の保険料について条文を読んでみましょう。
高齢者医療確保法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収」の定義が逆です。
・市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付します。
「市町村による保険料の徴収」について条文を読んでみましょう。
第107条第1項 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 |
②【R4年出題】
後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】
②【R4年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
③【H30年出題】
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
後期高齢者医療制度の保険料が年金から特別徴収されるのは、年間の年金額が18万円以上の場合です。
ただし、同一の月に徴収されると見込まれる後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料の合計が、老齢年金等給付の額の2分の1を超える場合等は、「特別徴収」の対象にはなりません。「普通徴収」の対象となります。
「口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない」ことはありません。
(令第22条、第23条)
④【H23年出題】※改正による修正あり
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】
④【H23年出題】 ×
「おおむね5年」ではなく、「おおむね2年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。
★介護保険の保険料について条文を読んでみましょう。
介護保険法第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
第131条 (保険料の徴収の方法) 保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。
第132条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む)」です。
保険料が課されるのは、「第1号被保険者」です。
②【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。
第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料と一緒に徴収し、医療保険者から納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付しています。
③【R3年出題】
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
④【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
④【H30年選択式】
<A> 3年
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識(国民健康保険法)
R7-343 08.06
国民健康保険法の制度について
国民健康保険法の目的などをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民健康保険) 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条 (保険者) ① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 ② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 |
過去問をどうぞ!
<目的>
【R6年選択式】
国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】
【R6年選択式】
<A> 社会保障及び国民保健の向上
<保険者>
【R2年選択式】
国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、< A >の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

【解答】
【R2年選択式】
<A> 1又は2以上の市町村
【R4年出題】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】
【R4年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第17条 ① 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ② 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 |
問題文の「10人以上」と「100人以上」が誤りです。
また、「都道府県知事の認可」もポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
【H28年出題】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

【解答】
【H28年出題】 〇
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
<国、都道府県及び市町村の責務>
【R1年選択式】
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、< A >、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

【解答】
【R1年選択式】
<A> 安定的な財政運営
【R6年出題】
市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

【解答】
【R6年出題】 ×
市町村(特別区を含む。)ではなく「都道府県」の責務です。
<被保険者>
被保険者について条文を読んでみましょう。
第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 (1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (2) 船員保険法の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 (6) 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 (7) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。(ただし以下省略) (8) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 (9) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (10) 国民健康保険組合の被保険者 (11) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第7条 (資格取得の時期) 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。
第8条 (資格喪失の時期) ① 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |
【R3年出題】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】
【R3年出題】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にはなりません。(その保護を停止されている世帯を除きます。)
【H20年出題】※改正による修正あり
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
【H20年出題】 〇
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
【H20年出題】※改正による修正あり
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
【H20年出題】 〇
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
【R3年出題】
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

【解答】
【R3年出題】 ×
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得します。「翌日」が誤りです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識は「比較」が有効
R7-342 08.05
確定給付企業年金法・確定拠出年金法を比較してみましょう
確定拠出年金法は「平成13年10月」、確定給付企業年金法は「平成14年4月」から施行された法律です。
過去問で比較しながら覚えていきましょう。
★目的条文の比較
(確定給付企業年金法)
【H19年出題】
確定給付企業年金法とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。

【解答】
【H19年出題】 ×
問題文は、「確定拠出年金法」の目的です。
確定給付企業年金法は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける」仕組みです。
(確定給付企業年金法第1条)
(確定拠出年金法)
【H18年出題】
この法律において、「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。

【解答】
【H18年出題】 ×
問題文は「確定給付企業年金法」の目的です。
「確定拠出年金」とは、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける」ことができるようにする仕組みです。
(確定拠出年金法第1条)
★用語の定義を比較
(確定給付企業年金法)
【H28年出題】
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

【解答】
【H28年出題】 ×
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、第4号厚生年金被保険者が含まれます。
条文を読んでみましょう
第2条 ① 「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。 ③ 「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。 |
(確定拠出年金法)
【R3年出題】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
【R3年出題】 〇
・「確定拠出年金」には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。
「企業型年金」→厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施
「個人型年金」→「国民年金基金連合会」が実施
・「企業型年金加入者」
→ 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
第1号等厚生年金被保険者=第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者
・「個人型年金加入者」
→ 国民年金法第1号被保険者
法定免除(生活保護法の生活扶助を受ける者に限る。)、申請全額免除、一部免除を受ける者を除く。
→ 国民年金法第2号被保険者
企業型掛金拠出者等を除く。
→ 国民年金法第3号被保険者
→ 国民年金法任意加入被保険者
20歳以上60歳未満の老齢給付等を受けることができるものを除く。
★給付の種類を比較
(確定給付企業年金法)
【H26年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】
【H26年出題】 〇
・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う
・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)
(第29条)
【H30年選択式】
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < A >

【解答】
【H30年選択式】
<A> 脱退一時金
【R4年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

【解答】
【R4年出題】 ×
「障害給付金」については、「規約で定めるところにより、給付を行うことができる」となります。
(確定拠出年金法)
【H20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
【H20年出題】 〇
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。
また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。
★掛金の拠出を比較
(確定給付企業年金法)
【H28年出題】
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】
【H28年出題】 ×
「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」とされています。
また、事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとされています。
(第55条第1項、第56条第1項)
【R2年出題】
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。

【解答】
【R2年出題】 ×
「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」とされています。加入者が、掛金の全部を負担することはできません。
(第55条第2項)
(確定拠出年金法)
【R3年出題】
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】
【R3年出題】 〇
企業型年金については、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。
(第19条第1項)
【R6年出題】
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

【解答】
【R6年出題】 〇
企業型年金加入者は、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができるとされています。
(第19条第3項)
【R3年出題】
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
【R3年出題】 〇
・「事業主掛金」の額は、企業型年金規約で定めるものとされています。(ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とされています。
・「企業型年金加入者掛金」の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するとされています。
(第19条第2項、第4項)
【R5年出題】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】
【R5年出題】 ×
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するとされています。
(第68条第1項)
【R6年出題】
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
【R6年出題】 〇
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。
(第68条第2項)
【R2年選択式】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】
【R2年選択式】
<A> 48,000
国民年金第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円です。ただし、国民年金基金の掛金を納付している場合は、その額を控除した額となります。
そのため、68,000円−20,000円=48,000円となります。
(令第36条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害厚生年金」
R7-341 08.04
障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう
障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう。
 テーマその1
テーマその1
初診日に高齢任意加入被保険者だった場合
 テーマその2
テーマその2
3級の障害厚生年金の受給権者に新たに3級の障害が生じた場合
→「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」がポイントです
 テーマその3
テーマその3
障害厚生年金の受給権者に新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合
 テーマその4 障害厚生年金の失権
テーマその4 障害厚生年金の失権
→3級の障害厚生年金を受けていたが、63歳のときに3級に該当しなくなり障害厚生年金の支給が停止されている場合、障害厚生年金が失権するのはいつの時点?
YouTubeでお話ししています
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-340 08.03
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年7月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月28日から8月2日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 遺族厚生年金の事例問題を解いてみましょう(厚生年金保険法)
・ 年金給付の受給権者等には障害手当金は支給されない(厚生年金保険法)
・ 船員保険の保険給付~健保との違いを意識しながら(社一船員保険法)
・ 社会保険労務士法の懲戒処分(社会保険に関する一般常識)
・ 高齢者医療確保法の制度について(社会保険に関する一般常識)
・ 介護保険法の制度について(社会保険に関する一般常識)
YouTubeでお話ししています
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「介護保険法」
R7-339 08.02
介護保険法の制度について
介護保険は、平成12年4月に施行された社会保険です。
被保険者になるのは、40歳以上の者です。
では、目的条文などを読んでみましょう。
第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 ① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 ② 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 ③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 ④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、< A >並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< B >に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【解答】
①【H27年選択式】
<A> 機能訓練
<B> 国民の共同連帯の理念
②【R5年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、介護保険を行うのは、「市町村(特別区を含む。)」です。
(法第3条)
③【H27年出題】
市町村又は特別区(以下「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
「市町村又は特別区」ではなく「国」の責務です。
条文を読んでみましょう。
第5条 (国及び地方公共団体の責務) ① 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 ② 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 ③ 都道府県は、助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。 ④ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 ⑤ 国及び地方公共団体は、④に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。 |
④【R1年出題】
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

【解答】
④【R1年出題】 〇
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする「市町村介護保険事業計画」を定めます。
条文を読んでみましょう。
第116条第1項 (基本指針) 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第117条第1項 (市町村介護保険事業計画) 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 |
⑤【H29年選択式】
介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して< A >とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。

【解答】
⑤【H29年選択式】
<A> 常に健康の保持増進に努める
第4条第1項「国民の努力及び義務」からの出題です。
ちなみに、第4条第2項には、「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」と定められています。
⑥【H24年出題】
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。

【解答】
⑥【H24年出題】 〇
第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
(第9条)
⑦【R4年選択式】
介護保険法における「要介護状態」とは、< A >があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、< B >の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である< A >が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が < B >に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

【解答】
⑦【R4年選択式】
<A> 身体上又は精神上の障害
<B> 6か月
★「要介護状態」とは
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)
★「要介護者」とは
(1) 要介護状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
(第7条、則第2条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」
R7-338 08.01
高齢者医療確保法の制度について
高齢者医療確保法では、75歳以上の後期高齢者について、健康保険法などの医療保険各法から独立した医療制度を設けています。
また、65歳以上75歳未満の前期高齢者については、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みが設けられています。
目的条文などを読んでみましょう。
第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (基本的理念) ① 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 ② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
第3条(国の責務) 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条 (地方公共団体の責務) 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 ② 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。
第5条 (保険者の責務) 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
第7条 (定義) ① この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 (1) 健康保険法 (2) 船員保険法 (3) 国民健康保険法 (4) 国家公務員共済組合法 (5) 地方公務員等共済組合法 (6) 私立学校教職員共済法 ② この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 |
過去問をどうぞ!
① 【R6年選択式】
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< A >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< B >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【解答】
① 【R6年選択式】
<A> 共同連帯
<B> 費用負担
②【H22年出題】
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
都道府県ではなく「国」の責務です。
ヒントは、「必要な各般の措置を講じなければならない」です。
③【H24年出題】
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 ×
国ではなく「地方公共団体」の責務です。
ヒントは、「住民」、「所要の施策を実施しなければならない」です。
④【H24年出題】
保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
「保険者」の責務です。
ヒントは、「推進するよう努める」と、「協力しなければならない」です。
⑤【H29年出題】※改正による修正あり
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
高齢者医療確保法における「保険者」の定義です。
全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団です。
⑥【R5年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

【解答】
⑥【R5年出題】 〇
都道府県が定める「都道府県医療費適正化計画」の問題です。
条文を読んでみましょう。
第8条 (医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画) 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第9条 (都道府県医療費適正化計画) 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第10条 (厚生労働大臣の助言) 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 |
⑦【H30年出題】
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

【解答】
⑦【H30年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第9条第8項 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 |
⑧【H29年出題】※改正による修正あり
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。

【解答】
⑧【H29年出題】 ×
5年ごとに、5年を1期ではなく、「6年ごとに、6年を1期として」です。
条文を読んでみましょう。
第18条 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
第19条 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
第20条 (特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。 |
⑨【R5年選択式】
高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< A >以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

【解答】
⑨【R5年選択式】
<A> 40歳
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」
R7-337 07.31
社会保険労務士法の懲戒について
社会保険労務士法の懲戒処分についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第25条 (懲戒の種類) 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。 (1) 戒告 (2) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 (3) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒) ① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、①に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 (参考) 法第15条 (不正行為の指示等の禁止) 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第25条の3 (一般の懲戒) 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。
第25条の3の2 (懲戒事由の通知等) ① 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 ② 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
問題文の場合は、社会保険労務士会は、「注意勧告」をすることができます。
条文を読んでみましょう。
第25条の33(注意勧告) 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 |
②【H25年出題】
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。

【解答】
②【H25年出題】 〇
故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、厚生労労働大臣は、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができます。
問題文のように、失格処分を受けることがあります。
③【H28年出題】
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。

【解答】
③【H28年出題】 ×
開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、厚生労働大臣は、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる。」とされています。
「失格処分」の対象にはなりません。
④【H20年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

【解答】
④【H20年出題】 ×
懲戒処分をすることができる厚生労働大臣の権限は、全国社会保険労務士会連合会には委任されていません。
⑤【H26年出題】
社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえる。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
社会保険労務士法第25条の30では、「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。」と定められています。
また、第25条の3 (一般の懲戒)で、「この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」は、厚生労働大臣は懲戒処分することができることが定められています。
所属する社会保険労務士会の会則の不遵守=社会保険労務士法に違反した場合は、厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえます。
⑥【H25年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。

【解答】
⑥【H25年出題】 ×
官報をもって公告する必要があります。
条文を読んでみましょう。
第25条の5 (懲戒処分の通知及び公告) 厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「船員保険法」
R7-336 07.30
船員保険の保険給付~健保との違いを意識しながら
健康保険との違いを意識しながら、船員保険の保険給付をみていきましょう。
★療養の給付
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
船員保険も健康保険と同様に療養の給付が行われますが、船員保険の療養の給付には、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が含まれます。
(法第53条)
★傷病手当金
条文を読んでみましょう。
第69条 ① 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ② 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。(以下省略します) ④ 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。 ⑤ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。 ⑥ 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関しその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上であることを要する。 ⑦ 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。 |
過去問をどうぞ!
②【R2年出題】
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】
②【R2年出題】 ×
船員保険の傷病手当金には、待期がありません。
「その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から」が誤りです。
③【H28年出題】※改正による修正あり
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。

【解答】
③【H28年出題】 ×
傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して「1年6か月間」ではなく「3年間」です。
④【R4年出題】
船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
④【R4年出題】 ×
疾病任意継続被保険者にも傷病手当金が支給されますが、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、傷病手当金は支給されません。
問題文は、令和3年10月5日に疾病任意継続被保険者の資格を取得し、令和4年4月11日に傷病を発しています。資格取得から1年以上経過していませんので、傷病手当金の支給を受けることができます。
★出産手当金
⑤【H28年出題】
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
船員法第87条で「船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。」と定められています。
そのため、出産手当金の支給期間は、出産の日以前は、「妊娠中のため職務に服さなかった期間」となります。出産の日後は56日以内において職務に服さなかった期間です。
(法第74条)
★行方不明手当金
条文を読んでみましょう。
法第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
法第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
法第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。
法第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
過去問をどうぞ!
⑥【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

【解答】
⑥【H28年出題】 〇
・被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。
・行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。
・被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません。
⑦【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】
⑦【R3年選択式】
<A> 被扶養者
⑧【R2年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

【解答】
⑧【R2年出題】 〇
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。ただし、行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。
⑨【R5年出題】
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

【解答】
⑨【R5年出題】 ×
「2か月」ではなく「3か月」が限度です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害手当金」
R7-335 07.29
年金給付の受給権者等には障害手当金は支給されない
以下の者には、障害手当金が支給されません。
・厚生年金保険・国民年金の年金給付(老齢・障害・遺族)の受給権者
・同一の傷病で、労災保険の障害(補償)等給付を受ける権利を有するもの
条文を読んでみましょう。
法第55条 (障害手当金の受給権者) 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
第56条 障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 (1) 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) (2) 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) (3) 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者 |
(1)(2)障害年金について
障害手当金は支給されない | 例外 | |||
1級 |
|
|
|
|
2級 |
|
|
| |
3級 |
|
| ||
3級未満 | 3年 | |||
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
障害手当金は支給されません。
障害の程度を定めるべき日において「年金たる保険給付(老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金)の受給権者には障害手当金は支給されません。
※例外
最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)は除かれます。
②【R4年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者に障害手当金は支給されない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
③【R1年出題】
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】
③【R1年出題】 ×
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、障害手当金は支給されません。
④【H28年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金は支給されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されません。
⑤【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
同一の傷病で、障害手当金の受給権と労災保険法の障害補償給付の受給権を取得した場合は、障害手当金は支給されません。
⑥【H25年出題】
障害手当金は、障害の程度を定める日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

【解答】
⑥【H25年出題】 ×
障害手当金は、障害の程度を定める日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されません。また、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者にも支給されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「遺族厚生年金」
R7-334 07.28
遺族厚生年金の事例問題を解いてみましょう
遺族厚生年金の事例問題を解きながら、遺族厚生年金のポイントをつかみましょう。
今回のテーマ
・その1 保険料納付要件(原則と特例)
※「特例」については、「前々月までの1年間」の具体例が出題されています
・その2 短期要件と長期要件について ※短期要件と長期要件は計算ルールが異なります。
短期要件と長期要件の両方に当てはまる人の事例です。
・その3 遺族の要件
※55歳の夫で子がいる場合の遺族厚生年金の注意点 ※子の遺族厚生年金の失権時期の具体例
YouTubeでお話ししています
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-333 07.27
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年7月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月21日から26日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 遺族基礎年金の事例問題を解いてみましょう(国民年金法)
・ 延滞金の徴収(労働保険徴収法)
・ 休業特別支給金の額と支給申請(労災保険法)
・ 保険医療機関・保険薬局の指定(健康保険法)
・ 保険医・保険薬剤師の登録(健康保険法)
・ 資格喪失後に傷病手当金と出産手当金が継続給付される要件(健康保険法)
YouTubeでお話ししています
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「資格喪失後の継続給付」
R7-332 07.26
資格喪失後に傷病手当金と出産手当金が継続給付される要件
健康保険の被保険者資格を喪失した後も、継続して傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
資格喪失後も継続して傷病手当金・出産手当金が支給される要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
下の図でイメージしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者でなければなりませんが、この被保険者期間は、同一の保険者でなくても構いません。
②【R1年出題】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

【解答】
②【R1年出題】 〇
資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。
転職等で異なった保険者における被保険者期間を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たします。ただし、1日の空白もなく継続していることが必要です。
③【R4年出題】
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。
ただし、「1年以上」の計算から、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
問題文の場合は、「共済組合の組合員としての6か月間」は計算に入らないことがポイントです。資格喪失日の前日まで、A健康保険組合の被保険者であった期間が、「7か月」+「3か月」の10か月しかないため、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。
④【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。(3日間の待期を満たす必要があります。)
資格喪失後の傷病手当金を受けるには、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けていることが必要ですが、労務不能となった日から3日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていません。
そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。
1日目 | 2日目 | 3日目 |
休 | 休 | 休 退 職 ※傷病手当金を 受けられる状態にない |
(昭27.6.12保文発3367)
⑤【R5年出題】
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていませんので、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 |
休 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 退職 |
⑥【H26年出題】
5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】
⑥【H26年出題】 ×
出産手当金は、出産の日又は出産の予定日以前42日に至った日に受給権が発生します。
5月25日が出産予定日で同年3月20日に退職している場合は、退職日に出産手当金を受ける状態にありません。(出産手当金の受給権が発生していません)
そのため、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることはできません。
⑦【H23年出題】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

【解答】
⑦【H23年出題】 ×
資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たしていれば、傷病手当金の継続給付を受けることができます。
⑧【H27年出題】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

【解答】
⑧【H27年出題】 〇
資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
(法附則第3条第5項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
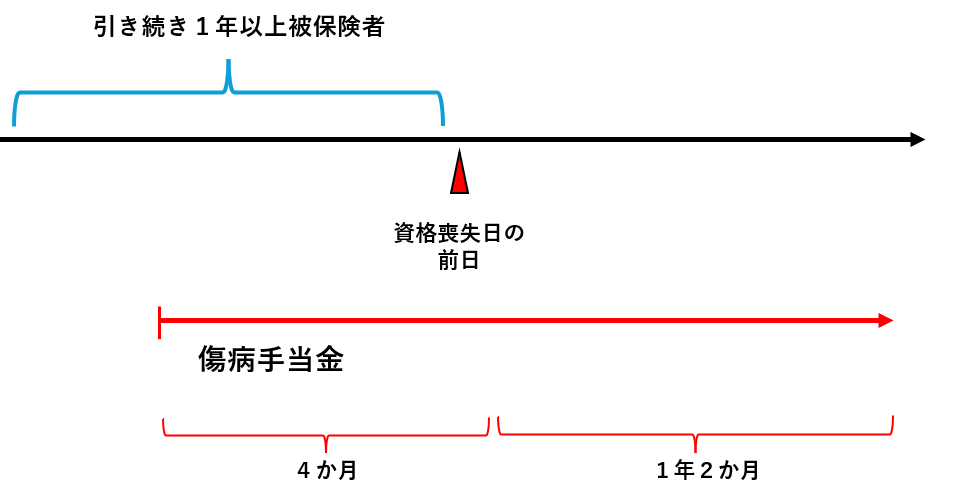
健康保険法「保険医」
R7-331 07.25
保険医・保険薬剤師の登録
保険医療機関・保険薬局は厚生労働大臣の「指定」を受けますが、保険医・保険薬剤師は、厚生労働大臣の「登録」を受けます。
条文を読んでみましょう。
法第64条 (保険医又は保険薬剤師) 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。
法第71条 ① 保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 ② 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる。 (1) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。 ((2)~(4)省略) ③ 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき
・保険医療機関、保険薬局の指定を取り消そうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしないこととするとき
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録をしないこととするとき
②【H29年出題】
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、健康保険法第63条第3項第1号の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

【解答】
②【H29年出題】 〇
個人の診療所、個人の薬局についての保険医療機関又は保険薬局のみなし指定の規定です。
問題文のように保険医の登録をした個人開業医の診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされますので、指定の手続きは必要ありません。
条文を読んでみましょう。
法第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。 |
③【H19年出題】
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から10年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
申請者が、保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき等は、厚生労働大臣は、登録をしないことができる、とされています。10年ではありません。
④【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
保険医療機関又は保険薬局は、「1月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、「1月以上」の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる、とされています。
(法第79条)
⑤【R6年出題】
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
保険医等の登録には、有効期間はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険医療機関」
R7-330 07.24
保険医療機関・保険薬局の指定
厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所又は薬局を「保険医療機関」又は「保険薬局」といいます。
保険医療機関、保険薬局では、すべての人が必要な診療等を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
法第65条 (保険医療機関又は保険薬局の指定) ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 ② その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。 ③ 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができる。 (1) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。 (2) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。 (以下(3)~ (6)省略) ④ 厚生労働大臣は、病院又は病床を有する診療所について申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、指定を行うことができる。 (1) 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法に規定する厚生労働省令で定める員数及び厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。 (以下(2)~(4)省略) |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき
・保険医療機関、保険薬局の指定を取り消そうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしないこととするとき
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録をしないこととするとき
②【R6年出題】
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

【解答】
②【R6年出題】 〇
・ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。
・ 申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるとされています。
・ 厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければなりません。
③【R1年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる、とされています。
(法第65条第3項第3号)
④【R2年選択式】
健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、< A >するものとされている。

【解答】
④【R2年選択式】
<A> 地方社会保険医療協議会に諮問する
⑤【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年です。
(法第69条第1項)
⑥【H28年出題】
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
法第68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 ② 保険医療機関(病院又は病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなす。 |
指定の有効期間は6年ですので、指定の更新が必要です。
ただし、保険医個人が開設する診療所は、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされます。この規定は、「病院又は病床を有する診療所」には、適用されないのがポイントです。
⑦【R6年出題】
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

【解答】
⑦【R6年出題】 ×
「病院及び病床を有する診療所」には適用されません。
⑧【H22年出題】
保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。

【解答】
⑧【H22年出題】 ×
保険医療機関または保険薬局は、「3か月以上」ではなく「1か月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができるとされています。
なお、「登録の抹消」は、「保険医又は保険薬剤師」に対応する用語です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「特別支給金」
R7-329 07.23
休業特別支給金の額と支給申請
「特別支給金」は、「社会復帰促進等事業」の中の、「被災労働者等援護事業」として行われていて、「保険給付」の上乗せとして支給されます。
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」があります。
下の図で特別支給金をイメージしましょう。
今回のテーマは「休業特別支給金」です。
「休業特別支給金」について条文を読んでみましょう。
特別支給金規則第3条 (休業特別支給金) ① 休業特別支給金は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額とする。(以下省略) ② 省略 ③ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ④ 省略 ⑤ 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。 ⑥ 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。 |
★特別支給金の申請期限について
・休業特別支給金 → 2年以内
・それ以外 → 5年以内
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】※改正による修正あり
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
特別支給金の申請は、原則として関連する保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
②【R2年出題】
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

【解答】
②【R2年出題】 ×
休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行うこととされています。
③【H28年出題】
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

【解答】
③【H28年出題】 ×
休業特別支給金の額は、1日につき「算定基礎日額」ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額です。
★「給付基礎日額」と「算定基礎日額」の違いに注意しましょう。
・「給付基礎日額」について
→ 保険給付の計算のもとになります。
給付基礎日額は、原則として「労働基準法の平均賃金」に相当する額です。
「臨時に支払われた賃金」、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入されません。
・「算定基礎日額」について
→ 「ボーナス特別支給金」の計算のもとになります。
「算定基礎年額」は、「負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額です。
ただし、「特別給与の総額」が、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額が算定基礎年額となります。
また、「150万円」を超える場合には、「150万円」となりますので、算定基礎年額の上限は150万円です。
※「臨時に支払われた賃金」は、給付基礎日額にも算定基礎年額の計算にも入りません。
なお、「算定基礎日額」は、算定基礎年額÷365です。
④【H28年出題】
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならないとされています。
また、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければなりません。
(特別支給金規則第12条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「延滞金」
R7-328 07.22
延滞金の徴収
労働保険料を滞納した場合は、「延滞金」が徴収されることがあります。
今回は、延滞金の額や、延滞金が徴収されない場合をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第28条 (延滞金) ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ② 労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。 ③ 延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 |
<延滞金の割合の特例について>
令和7年中の延滞金の割合は、
「年14.6%」→「年8.7%」
「年7.3%」→「年2.4%」
となります。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
延滞金は、「指定した期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日」から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算されます。
納期限 | 納期限の 翌日 |
|
| 督促状の 指定期限 | 完納の 前日 | 完納 |
▲ | ▲ |
|
| ▲ | ▲ | ▲ |
|
|
| ||||
②【H29年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
②【H29年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、督促状に指定された期限までに完納したときは、延滞金は徴収されません。
③【R1年出題】(雇用)
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

【解答】
③【R1年出題】(雇用) 〇
労働保険料の額が1,000円未満である、又は、延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
④【H29年出題】(雇用)
認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。

【解答】
④【H29年出題】(雇用) ×
延滞金の対象になるのは、「労働保険料」のみです。追徴金は労働保険料ではありませんので、追徴金には延滞金は課されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R7-327 07.21
遺族基礎年金の事例問題を解いてみましょう
今回は、遺族基礎年金の事例問題を解いています。
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、一定の遺族に支給されます。
次の(1)から(4)のいずれかに該当することが要件ですが、
(1)と(2)は保険料納付要件が問われます。
(1) 被保険者が、死亡したとき。
(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
(3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
(4) 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
事例問題を解きながら、4つの要件を具体的にイメージしましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-326 07.20
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年7月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月14日から19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・障害基礎年金の事例問題を解いてみましょう(国民年金法)
・賃金日額の算定に含むもの、含まないもの(雇用保険法)
・介護(補償)等給付の支給額(労災保険法)
・傷病手当金の支給期間(健康保険法)
・在職老齢年金の仕組み(厚生年金保険法)
・70歳以上の使用される者の在職老齢年金について(厚生年金保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「70歳以上の在職老齢年金」
R7-325 07.19
70歳以上の使用される者の在職老齢年金について
厚生年金保険の被保険者になるのは「70歳未満」の者です。
70歳に達したときに厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。
ただし、70歳以上でも、適用事業所に使用される場合は、保険料の負担はありませんが、在職老齢年金の対象になります。
70歳以上の者について条文を読んでみましょう。
法第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、又は 70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
「70歳以上の使用される者」とは、「被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの」です。
厚生労働省令定める要件は、「適用事業所に使用される者であって、かつ、法第12条各号(適用除外)に定める者に該当するものでないこと」です。
そのため、適用事業所で使用される70歳以上の者でも、適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象となりません。
(法第27条、則第10条の4)
②【R4年出題】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
②【R4年出題】 ×
70歳以上の者に対しても、在職老齢年金の仕組みは、適用されます。
③【H28年出題】
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
平成27年10月の改正で、昭和12年4月1日以前生まれの者も、在職老齢年金の対象となっています。
④【H23年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金を受給している被保険者であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。

【解答】
④【H23年出題】 〇
「70歳以上の使用される者」は、保険料を納めることはありませんが、在職老齢年金の仕組みが適用され、要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「在職老齢年金」
R7-324 07.18
在職老齢年金の仕組み
働きながら(=厚生年金保険に加入しながら)、老齢厚生年金を受給する場合は、年金がカットされることがあります。この仕組みを、在職老齢年金といいます。
条文を読んでみましょう。
法第46条第1項 (支給停止) 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、「総報酬月額相当額」及び「基本月額」との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、「支給停止基準額」に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
用語の定義を確認しましょう
★総報酬月額相当額
→ 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
★基本月額
→ 老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額
★支給停止基準額
→ 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
★支給停止調整額について → 令和7年度は51万円
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
<選択肢>
① 支給調整開始額 ② 支給調整基準額 ③ 支給停止開始額
④ 支給停止額 ⑤ 支給停止基準額 ⑥ 支給停止調整額
⑦ 総報酬月額 ⑧ 総報酬月額相当額 ⑨ 定額部分
⑩ 標準賞与月額相当額 ⑪ 平均標準報酬月額 ⑫ 報酬比例部分

【解答】
①【H28年選択式】
<A> ⑧ 総報酬月額相当額
<B> ⑥ 支給停止調整額
<C> ⑤ 支給停止基準額
②【R4年出題】
在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。

【解答】
②【R4年出題】 〇
支給停止調整額は、年度ごとに改定される場合があります。
(法第46条第3項)
③【R3年出題】
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

【解答】
③【R3年出題】 ×
基本月額は、老齢厚生年金の額を12で除して得た額ですが、「加給年金額」は除かれます。
④【R6年出題】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
★加給年金額について
・在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合でも、加給年金額は支給されます。
・在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部が停止される場合は、加給年金額も支給停止となります。
⑤【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となりません。
⑥【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
経過的加算額も繰下げ加算額も、基本月額の計算には入りません。
(昭60法附則第62条第1項)
⑦【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
⑦【R4年出題】 ×
老齢基礎年金は在職中でも支給停止の対象になりません。
また、経過的加算額についても在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
⑧【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】
⑧【H24年出題】 ×
60歳台後半の在職老齢年金においては、経過的加算額と老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「傷病手当金」
R7-323 07.17
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第99条第4項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。 |
|
|
| 支 給 |
|
|
| 支 給 |
| 支 給 |
待期 | 欠 勤 | 出 勤 | 欠 勤 | 出 | 欠 勤 | ||||
| ▲支給開始 |
|
|
|
| ||||
| ↓ |
| ↓ |
| ↓ | ||||
通算して1年6か月
過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】 ※改正による修正あり
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。
<選択肢>
①4月1日から ②4月3日から ③4月4日から ④4月5日から
⑤日 ⑥日の2日後 ⑦日の3日後 ⑧日の翌日

【解答】
①【R1年選択式】
<A> ④4月5日から
<B> ⑤日
②【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

【解答】
②【H26年出題】 ×
傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6か月間」です。
問題文の場合は、傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から通算して1年6か月間です。
③【R5年出題】
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。

【解答】
③【R5年出題】 ×
健康保険の被保険者資格は、死亡したときはその翌日に喪失します。
死亡した日は被保険者の資格は有効ですので、傷病手当金は当該被保険者の死亡日の当日分まで支給されます。
④【R4年出題】
傷病手当金の支給を受けている間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。

【解答】
④【R4年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
則第84条の2第7項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第99条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 |
後の傷病に係る待期期間の経過した日を「後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日」として額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額が支給されます。
この場合、後の傷病に係る傷病手当金の「支給を始める日」が確定するため、前の傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病手当金について再度額を算定する必要はありません。
(H27.12.18事務連絡)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「介護補償給付」
R7-322 07.16
介護(補償)等給付の支給額
★介護補償給付の支給要件を確認しましょう。
・ 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有すること
・ 厚生労働省令で定める程度の障害であること
→第1級は「すべて」、第2級は「精神神経・胸腹部臓器の障害」のみ
・ 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること
なお、以下の施設に入所している間は、介護補償給付は支給されません。
・ 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
・ 病院又は診療所に入院している間
など
(法第12条の8第4項、則第18条の3の2)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 |
★「常時介護」の場合の支給額をみていきましょう。(則第18条の3の4)
「介護の費用として支出した額」(実費)が支給されるのが原則です。
ただし、上限と最低保障額が設定されています。
| ①介護の費用を支出した | 実費 (上限177,950円) |
親族等の介護を受けている | ②介護の費用を支出していない | 最低保障額 85,490円 |
③介護の費用を支出したが、 85,490円を下回る |
※「最低保障額」が適用されるのは、親族等(親族、友人、知人)の介護を受けている場合です。
※「随時介護」の場合は、上限88,980円、最低保障額42,700円です。
★介護補償給付は「月単位」で支給されます。
「支給すべき事由が生じた月」から「支給すべき事由が消滅した月」の各月について支給されます。
ただし、「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されません。
・上の表の②の場合
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(その翌月から支給されます)
・上の表の③の場合
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、「実費」が支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、 < A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行われる。

【解答】
①【H19年選択式】
<A> 常時又は随時
<B> 当該労働者
②【H23年出題】
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】
②【H23年出題】 〇
条文を穴埋めでチェックしましょう
第19条の2
介護補償給付は、< A >を単位として支給するものとし、その月額は、 < B >介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して< C >が定める額とする。
・・・・・・・・・・・
<A> 月
<B> 常時又は随時
<C> 厚生労働大臣
③【H25年出題】
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】
③【H25年出題】 〇
「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません。
そのため、親族等による介護を受けたとしても、介護に要する費用として支出された額が労災保険法施行規則に定める額に満たない場合は、当該介護に要する費用として支出された額(実費)が支給されます。
④【R2年出題】
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」は誤りです。
「その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき」は、最低保障額が支給されます。(支給すべき事由が生じた月は支給されません。)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「賃金日額」
R7-321 07.15
賃金日額の算定に含むもの・含まないもの
基本手当の日額は、「賃金日額」×一定の率で算定します。
今回は、基本手当の日額の算定に使う「賃金日額」についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第17条(賃金日額) ① 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 ② ①による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、当該各号に掲げる額とする。(最低保障) (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数で除して得た額と(1)に掲げる額との合算額 |
★賃金日額の原則の算定式
被保険者期間として計算された最後の6か月間に 支払われた賃金の総額 |
180 |
★最低保障額の算定式
・日給制、時給制、出来高払制その他の請負制の場合
被保険者期間として計算された 最後の6か月間に支払われた賃金の総額 | × | 70 |
最後の6か月間に労働した日数 | 100 |
では、過去問をどうぞ!
①【H18年選択式】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲と定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。

【解答】
①【H18年選択式】
<A> 45
<B> 算定対象期間
<C> 被保険者期間
<D> 当該最後の6か月間に労働した日数
<E> 70
②【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。

【解答】
②【H22年出題】 〇
賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金で計算します。
③【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

【解答】
③【H22年出題】 ×
家族手当、通勤手当及び住宅手当は、賃金日額の計算に入ります。そのため、それらの多寡によって基本手当の日額が異なります。
(行政手引50501)
④【R5年出題】
支給額の計算の基礎が月に対応する住宅手当の支払が便宜上年3回以内にまとめて支払われる場合、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれない。

【解答】
④【R5年出題】 ×
単に支払事務の便宜等のために年間の給与回数が3 回以内となるものは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当しません。
そのため、例えば通勤手当、住宅手当等その支給額の計算の基礎が月に対応する手当が支払の便宜上年3回以内にまとめて支払われた場合には、当該手当は賃金日額の算定の基礎に含まれることとなる、とされています。
(行政手引50453)
⑤【H30年出題】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
月給者が月の中途で退職し、その月の分の給与が全額支払われる場合は、退職日の翌日以後の分に相当する金額は、賃金日額には算入されません。
(行政手引50503)
⑥【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
未払賃金のある月については、未払額を含めて賃金額を算定します。
未払賃金とは、支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいいます。
(行政手引50609)
⑦【R5年出題】
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
退職金について
労働者の退職後(退職を事由として、事業主の都合等により退職前に一時金として支払われる場合を含む。)に一時金又は年金として支払われるもの | 賃金日額算定の基礎に算入されない |
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払ういわゆる「前払い退職金」 | 臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる |
(行政手引50503)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R7-320 07.14
障害基礎年金の事例問題を解いてみましょう
障害基礎年金の受給権は、次の3つの要件を満たした場合、障害認定日に発生します。 ・初診日要件
・保険料納付要件
・障害認定日要件
事例の過去問を解きながら、障害基礎年金のルールを身につけましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-319 07.13
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年7月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年7月7日から12日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・併給調整についてお話しします(国民年金法)
・少年院に収容された場合等の給付制限と保険料免除(健康保険法)
・労働保険事務組合が行う手続き(まとめ)(徴収法)
・遺族基礎年金配偶者に支給する額と子に支給する額の違い(国民年金法)
・ 配偶者の遺族基礎年金の減額改定と失権(国民年金法)
・ 業務上の疾病の範囲(労災保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「業務上の疾病」
R7-318 07.12
業務上の疾病の範囲
業務上の疾病は、「労働基準法施行規則別表第一の二」に例示されています。
例えば、「暑熱な場所における業務」に従事していた労働者に「熱中症」が発生した場合は、「業務起因性」を推定できるようにするためです。
第1号から第11号までで構成され業務上の疾病の種類が例示されています。「職業病リスト」ともよばれます。
では、過去問を解きながら内容をみていきましょう
①【H18年選択式】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
<選択肢>
① 業務上の事故による疾病 ② 業務上の負傷に起因する疾病
③ 業務と因果関係のある疾病 ④ 業務に起因することの明らかな疾病
⑤ 労働安全衛生規則 ⑥ 労働基準法施行規則
⑦ 労働基準法施行令 ⑧ 労働者災害補償保険法施行規則
⑨ 労働者災害補償保険法施行令

【解答】
①【H18年選択式】
<A> ⑥ 労働基準法施行規則
<B> ⑧ 労働者災害補償保険法施行規則
<C> ④ 業務に起因することの明らかな疾病
★<C>について
「包括的救済規定」といわれる規定です。具体的に列挙されていない疾病は、第11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」に該当すれば、業務上の疾病となります。
②【H28年出題】
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

【解答】
②【H28年出題】 〇
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されています。
③【H19年出題】
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2の「第1号」で定められています。
④【H19年出題】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

【解答】
④【H19年出題】 〇
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されていますので、業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければなりません。
⑤【R5年出題】
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914 第1 号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。
ア 狭心症
イ 心停止(心臓性突然死を含む。)
ウ 重篤な心不全
エ くも膜下出血
オ 大動脈解離

【解答】
⑤【R5年出題】
5つ
労働基準法施行規則別表第1の2第8号は、「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病」です。
認定基準では、次に掲げる脳・心臓疾患が対象疾病として取り扱われています。
1 脳血管疾患
(1) 脳内出血(脳出血) 、(2) くも膜下出血、(3) 脳梗塞、(4) 高血圧性脳症
2 虚血性心疾患等
(1) 心筋梗塞、(2) 狭心症、(3) 心停止(心臓性突然死を含む。)
(4) 重篤な心不全、(5) 大動脈解離
⑥【H30年出題】
認定要件においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
労働基準法施行規則別表第1の2第9号は、「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」です。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」では、認定要件として、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱うとされています。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
(令和5年9月1日基発 0901 第2号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「配偶者の遺族基礎年金の額」
R7-317 07.11
配偶者の遺族基礎年金の減額改定と失権
配偶者の遺族基礎年金には、必ず子の加算額が加算されます。
子の加算額は、子の数に応じて算定されます。
子の数が減少すると、それに応じて、子の加算額が減額されます。
条文を読んでみましょう。
法第39条第3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (5) 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |
■ 配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が2人の場合)
2人の子のうち1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態ではない)は、子の加算額が「2人分」から「1人分」に減額改定されます。
■配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が1人の場合)
1人しかいない子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態ではない)は、子がいなくなるため配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。「減額改定」ではありませんので、注意して下さい。
「配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、法第40条第1項の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。」
(法第40条第2項)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H25年出題】 〇
生計を同じくしている子が1人の妻が遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
②【R4年出題】
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合で、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、夫の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
③【H19年出題】※改正による修正あり
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき」は失権します。
そのため、加算事由に該当するすべての子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、配偶者の遺族基礎年金は失権します。
ちなみに、子が直系血族又は直系姻族の養子となったときでも、子自身の遺族基礎年金は失権しません。
(法第40条第1項第3号)
④【R5年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
・配偶者の遺族基礎年金について
→ 「すべての子が配偶者以外の者の養子となった場合」は配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。問題文のように「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合」は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
・子の遺族基礎年金について
→ 養子となった場合でも、「直系血族又は直系姻族の養子になった」場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金の額」
R7-316 07.10
<遺族基礎年金>配偶者に支給する額と子に支給する額の違い
遺族基礎年金の額についてみていきます。
「配偶者」に支給する額と「子」に支給する額は、それぞれ計算式が異なりますので注意しましょう。
・遺族基礎年金の額(基本の額)について条文を読んでみましょう。
法第38条 (年金額) 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
・配偶者に支給する額について条文を読んでみましょう。
法第39条第1項 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち 2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |
★配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず「子の加算」が加算されます。
子が1人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率) |
子が2人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (224,700円×改定率) |
子が3人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (224,700円×改定率)+(74,900円×改定率) |
・子に支給する額について条文を読んでみましょう。
法第39条の2第1項 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、780,900円×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 |
★子に支給される遺族基礎年金の額
子が1人の場合 | (780,900円×改定率) ※加算はありません |
子が2人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率) |
子が3人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (74,900円×改定率) |
それぞれの子に支給される額は、「子の人数で除して得た額」です。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

【解答】
①【R2年出題】 〇
配偶者が遺族基礎年金を受ける要件は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、子と生計を同じくすること」です。
配偶者は必ず子と生計を同じくしていますので、配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず、子の加算額が加算されます。
②【R3年出題】
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
(※令和3年度の給付額です)

【解答】
②【R3年出題】 ×
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として「224,700円、74,900円、74,900円」を合計した金額です。
子それぞれが受給する額は、子の数で除した金額となります。
③【H22年出題】
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

【解答】
③【H22年出題】 ×
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に「224,700円に改定率を乗じて得た額」を加算した額を2(子の人数)で除して得た額となります。
④【H28年出題】
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

【解答】
④【H28年出題】 ×
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、「224,700円に改定率を乗じて得た額」と「74,900円に改定率を乗じて得た額」を加算し、その合計額を3で除した額が3人の子それぞれに支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R7-315 07.09
労働保険事務組合が行う手続き(まとめ)
労働保険事務組合が行う手続きをまとめました。
条文を読んでみましょう。
法第33条 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、①に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ③ 認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ④ 厚生労働大臣は、労働保険事務組合が労働保険関係法令規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 則第63条 (認可の申請) ① 法第33条第2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、所定の事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ② 申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 (1) 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。) (2) 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類 (3) 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
則第64条 (委託等の届出) ① 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ② 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
則第65条 (変更の届出) 労働保険事務組合は、認可申請書又は添付書類の(1)、(2)に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
則第66条 (業務の廃止の届出) 業務の廃止の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】(雇用)
労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

【解答】
①【H28年出題】(雇用) 〇
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、「都道府県労働局長に委任する」とされています。
(1)法第8条第2項の規定による認可(下請負事業の分離の認可)に関する権限
(2)法第9条の規定による認可及び指定(継続事業の一括の認可と指定)に関する権限
(3)法第33条第2項の規定による認可(労働保険事務組合の認可)、同条第3項の規定による届出の受理(労働保険事務組合の業務廃止の届出)及び同条第4項の規定による認可の取消し(労働保険事務組合の認可の取消し)に関する権限
(4) 法第26条(特例納付保険料)第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
(則第76条)
②【R3年出題】雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
②【R3年出題】(雇用) ×
労働保険事務の処理の委託があったときは、「委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に」ではなく、「遅滞なく」届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
③【H20年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
③【H20年出題】(雇用) 〇
労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
④【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

【解答】
④【R1年出題】(雇用) ×
「厚生労働大臣」ではなく、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」に提出しなければなりません。
⑤【H20年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
⑤【H20年出題】(雇用) 〇
労働保険事務組合は、「労働保険事務組合認可申請書」又は「労働保険事務組合認可申請書」に添付された「定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)」、「労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類」の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
⑥【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
⑥【R1年出題】(雇用) ×
労災二元適用事業に係るものは、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」を経由して都道府県労働局長に提出します。
⑦【H23年出題】(労災)
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
⑦【H23年出題】(労災) ×
「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、「労働保険事務組合業務廃止届」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険給付の制限など」
R7-314 07.08
少年院に収容された場合等の給付制限と保険料免除
被保険者又は被保険者であった者が、少年院に収容されたときや刑事施設に拘禁されている場合は、公費で療養等が行われるので、健康保険の保険給付は行われません。また、保険給付が行われないため、保険料が免除されます。
条文を読んでみましょう。
第118条 ① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 (1) 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 (2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 ② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 |
ポイント!
・給付制限の対象になるのは、「疾病、負傷、出産」です。
「死亡」については給付制限の対象ではありません。死亡の場合は、埋葬料(埋葬費)が支給されます。
少年院に収容された場合などは、保険給付が制限されますので、保険料も徴収されません。
条文を読んでみましょう。
法第158条 (保険料の徴収の特例) 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。 ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。(→該当するに至ったときと該当しなくなったときが同じ月にある場合は、保険料が徴収されます) |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されていても、被扶養者に係る保険給付は行われます。
②【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
被扶養者に係る保険給付は行われます。
③【H27年出題】
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、保険料が徴収されないのは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間です。
④【H29年出題】
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
刑事施設に拘禁されていても、「任意継続被保険者」には保険料免除の規定は適用されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「併給調整」
R7-313 07.07
国民年金法の併給調整についてお話しします
一人の人に複数の年金の受給権が発生することがあります が、原則は「一人一年金」です。
ただし、併給できる組合せもあります。
よく出題されますので、問題を解けるようにしましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-312 07.06
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年6月第5週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月30日から7月5日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・学生納付特例制度についてお話しします(国民年金法)
・厚生年金保険の被保険者の資格喪失事由と時期(厚生年金保険法)
・就業促進手当の一つ「再就職手当」について(雇用保険法)
・有期事業の延納(労働保険徴収法)
・年次有給休暇の比例付与(労働基準法)
・他の法令による保険給付と健康保険の保険給付の調整(健康保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「他の法令との調整」
R7-311 07.05
他の法令による保険給付と健康保険の保険給付の調整
他の法令による保険給付を受けることができる場合の健康保険の調整規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第55条 (他の法令による保険給付との調整) ① 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 ③ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 ④ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
健康保険では、「労働者災害補償保険法に規定する業務災害」以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行います。
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、健康保険の給付が行われます。
(H25.8.14事務連絡)
②【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「被保険者に係る療養の給付等は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。」となります。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法に基づく給付を受けることができる場合は、健康保険の埋葬料は支給されません。
③【H29年出題】
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われません。
④【H22年出題】
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

【解答】
④【H22年出題】 ×
「同一の疾病、負傷または死亡について」の部分が誤りです。「同一の疾病又は負傷について」となります。
介護保険法には、「死亡」に関する給付がありません。
「死亡」については、介護保険の給付と調整されませんので、健康保険の給付が行われます。
⑤【R5年出題】
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
「被保険者に係る療養の給付等は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。」となります。
⑥【H30年出題】
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
災害救助法の目的は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」です。
同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において健康保険の保険給付は行われません。
⑦【H16年出題】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

【解答】
⑦【H16年出題】 〇
健康保険による保険給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われます。
健康保険による保険給付が及ばない部分が、生活保護法による医療扶助の対象となります。
(生活保護法第4条第2項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「年次有給休暇」
R7-310 07.04
年次有給休暇の比例付与
所定労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇の権利が発生します。
ただし、比例付与の対象となり、年次有給休暇の付与日数が少なくなることがあります。
では、条文を読んでみましょう。
法第39条第3項、則第24条の3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 (1) 1週間の所定労働日数が4日以下の労働者 (2) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者 |
★比例付与の対象になるのは
・週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
※週以外の期間によって労働日数が定められる場合
・年間所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
ポイント!
1週間の所定労働時間が30時間以上の者は比例付与の対象になりません
★比例付与の日数の計算
比例付与の有休の日数は、通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)との比率で計算されます。
例えば、6か月間継続勤務した週所定労働日数が4日の労働者に付与される日数は、
10日×4日/5.2日≒7日(1未満切り捨て)となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R6年出題】
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。

【解答】
①【R6年出題】 ×
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者です。
問題文の場合は、週5日労働ですので、1週間の所定労働時間が20時間でも比例付与の対象になりません。
6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
②【R6年出題】
月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。
〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日 端数を切り捨てて7日

【解答】
②【R6年出題】 ×
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者ですので、1週間の所定労働時間が32時間の労働者は、週4日労働でも比例付与の対象になりません。
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
③【H17年出題】
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。

【解答】
③【H17年出題】 〇
年次有給休暇の権利は、基準日に発生します。
基準日に予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものとされています。
問題文の場合、雇入れの日から起算して6か月継続勤務した時点で、「週4日勤務・ 1日の所定労働時間8時間」ですので、比例付与の対象ではありません。
そのため、10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「延納」
R7-309 07.03
有期事業の延納
概算保険料は延納(分割納付)することができます。
今回は、有期事業の延納をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
則第28条 ① 有期事業であって納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。 ※期の中途に保険関係が成立した事業について → 保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。 ② 延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない。 |
有期事業の延納のポイント!
・「最初の期の取り方と納付期限」に注意しましょう。
・継続事業と一括有期事業は、「年度単位」で保険料を算定しますので、3期に分けるのが原則です。
有期事業は、「全期間」を通して算定しますので、3期に限りません。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】(労災)
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

【解答】
①【R3年出題】(労災) 〇
問題文の有期事業は延納の申請をすることにより、概算保険料を分割納付できます。
★有期事業の延納の要件を確認しましょう。
①・概算保険料の額が75万円以上
又は
・労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
②事業の全期間が6月以内でない
問題文の「事業の全期間が200日」、「概算保険料の額が80万円」の有期事業は、概算保険料を分割納付できます。
②【R5年出題】(雇用)
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

【解答】
②【R5年出題】(雇用) ×
★期の分け方の基本!
全期間を通じて、毎年「4月1日から7月31日」まで、「8月1日から11月30日」まで「12月1日から翌年3月31日」までの各期に分けることができます。
| 4月1日~ 7月31日 | 8月1日~ 11月30日 | 12月1日~ 3月31日 |
納期限 | 3月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
★最初の期について
・保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるとき
→ 保険関係成立の日からその日の属する期の末日まで
・保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月以内のとき
→ 保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日まで
を最初の期とする。
■問題文は保険関係成立の日が5月1日です。
5月1日の属する期の末日(7月31日)までの期間が「2月を超え」ます。
そのため、最初の期は、保険関係成立の日からその日の属する期の末日(7月31日)までとなります。
基本の分け方に当てはめます。
R4.5.1 ~ R4.7.31 | R4.8.1 ~ R4.11.30 | R4.12.1 ~ R5.3.31 | R5.4.1 ~ R5.7.31 | R5.8.1 ~ R5.11.30 | R5.12.1 ~ R6.2.28 |
1期目 | 2期目 | 3期目 | 4期目 | 5期目 | 6期目 |
6期に分けることができますので、第1期に納付する概算保険料は
「120万円」÷6=20万円です。
③【H29年出題】(労災)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。

【解答】
③【H29年出題】(労災) 〇
■最初の期について
保険関係成立の日(6月15日)からその日の属する期の末日(7月31日)までの期間が2月以内ですので、保険関係成立の日(6月15日)からその日の属する期の次の期の末日(11月30日)までが第1期となります。
6月15日 ~ 11月30日 | 12月1日 ~ 3月31日 | 4月1日 ~ 6月5日 |
1期目 | 2期目 | 3期目 |
■最初の期の納期限について
最初の期の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内です。
6月15日の翌日から起算して20日以内ですので、第1期の納期限は平成29年7月5日です。
④【H27年出題】(雇用)
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

【解答】
④【H27年出題】(雇用) 〇
有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、納期限の延長はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「再就職手当」
R7-308 07.02
就業促進手当の一つ「再就職手当」について
令和7年3月31日をもって「就業手当」が廃止されました。
そのため、「就業促進手当」は、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」の3つとなっています。
今回は、「再就職手当」をみていきます。
■再就職手当の概要
再就職手当は、受給資格者が安定した職業に就いた場合において、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の 3 分の1未満である場合を除いて、安定所長が必要と認めたときに、支給残日数の10分の6(就職日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である場合にあっては、10分の7)に相当する日数分に基本手当日額を乗じた額が支給される。(行政手引57041)
条文を読んでみましょう。
「再就職手当」の対象者 法第56条の3第1項第1号 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の 3分の1以上であるもの
則第82条 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。 (1) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。 (2) 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。 (3) 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限の適用を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。 (4) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当は支給されません。
②【H30年出題】
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合は、再就職手当を「受給することができます」。
再就職手当の支給要件の一つを確認しましょう。
1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると安定所長が認めたものに限る。)を開始したこと。(行政手引57052)
③【H26年出題】
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
受給資格に係る離職について離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたことが条件です。
★事業を開始した場合は、事業開始日が待期期間の満了後1か月間の経過後にあることが条件です。そのため、受給資格者が離職理由による給付制限を受け、待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することはできません。
(行政手引57052)
④【R5年出題】
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
再就職手当の支給要件の一つは、「就職日又は事業を開始した日前3年以内の就職又は事業開始について「就業促進手当」の支給を受けたことがないこと。」です。
(法第56条の3第2項、則第82条の4、行政手引57052)
⑤【R1年出題】
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「10分の6」ではなく、「10分の7」です。
<再就職手当の額>
就職日の前日における支給残日数 |
|
3分の2以上 | 「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」 ×「10分の7」 |
3分の1以上 | 「基本手当日額」×「支給残日数に相当する日数」 ×「10分の6」 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「被保険者」
R7-307 07.01
厚生年金保険の被保険者の資格喪失事由と時期
適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然に、厚生年金保険の被保険者となります。
今回は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する事由と、喪失時期をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第14条(資格喪失の時期) 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に資格を取得するに至ったとき、又は(5)に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき。 (2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。 (3) 任意適用事業所の脱退又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。 (4) 適用除外に該当するに至ったとき。 (5) 70歳に達したとき。(※当日喪失)
|
では過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【R1年出題】 ×
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、「その日」に被保険者の資格を喪失します。
年齢で喪失する場合は「当日」です。
なお、「70歳に達した日」とは、70歳の誕生日の前日です。
②【H27年出題】
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。

【解答】
②【H27年出題】 ×
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときは「その翌日」に、70歳に達したときは「その日」に被保険者資格を喪失します。
③【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
「10日以内」ではなく「5日以内」です。
(則第22条)
④【R2年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者資格は、70歳に達した日に喪失しますが、70歳以降も引き続き当該事業所に使用される場合は、「70歳以上被用者」に該当し、厚生年金保険の保険料は徴収されませんが、在職老齢年金の対象となります。
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当する場合で、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、「70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届」を省略できます。
なお、70歳到達日の前日における標準報酬月額と「異なる」場合は、5日以内に提出しなければなりません。
(則第15条の2、則第22条)
⑤【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
⑥【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
ポイントを確認しましょう
・第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したとき
→ 被保険者の資格は翌月の1日に喪失
・遺族厚生年金の受給権
→ 死亡した日に発生
・遺族厚生年金は
→ 死亡した日の属する月の翌月から支給される
(法第36条第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「学生納付特例」
R7-306 06.30
学生納付特例制度についてお話しします
学生が国民年金に強制加入となったのは、平成3年4月からです。
平成3年3月までは、学生は任意加入でした。
学生も第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければなりませんが、学生については、保険料の納付が猶予される制度があります。
「学生納付特例制度」といいます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-305 06.29
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年6月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月23日から28日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・国民年金法の事例問題を解いてみましょう(国民年金法)
・国民年金原簿と訂正の請求(国民年金法)
・保険料納付猶予制度について(国民年金法)
・日雇特例被保険者の保険料納付要件(健康保険法)
・資格取得時、定時決定、随時改定の際の休業手当の扱い(健康保険法)
・30歳未満の妻の遺族厚生年金の失権(厚生年金保険法)
(令和7年6月第4週目)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「遺族厚生年金」
R7-304 06.28
30歳未満の妻の遺族厚生年金の失権
まず、遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」の要件を確認しましょう。
★遺族厚生年金の遺族の要件として、妻には年齢要件はありません。
「夫」については、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件です。
★国民年金法の遺族基礎年金の遺族となる「配偶者」については、「子」と生計を同じくすることが要件ですが、厚生年金保険の遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」は子の有無は問われません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■夫の死亡当時30歳未満の妻については、遺族厚生年金が「5年間」の有期年金となる場合があります。
遺族基礎年金の受給権の有無(子の有無)などで、5年間の起算日が変わるのがポイントです。
では、30歳未満の妻の失権事由について条文を読んでみましょう。
法第63条第1項第5号 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときに該当するに至ったときは、消滅する。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき → 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 |
図でイメージしましょう
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権を取得した当時「30歳未満である妻」が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく「遺族基礎年金の受給権を取得しない場合」は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
5年は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算することがポイントです。
②【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該遺族厚生年金の受給権は、「当該妻が30歳になったとき」ではなく、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅します。
③【R5年出題】
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

【解答】
③【R5年出題】 〇
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅します。
5年の起算日が、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」であることがポイントです。
④【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
④【H29年出題】 ×
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合で、当該消滅した日に妻が30歳に到達する日前であった場合は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」からではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
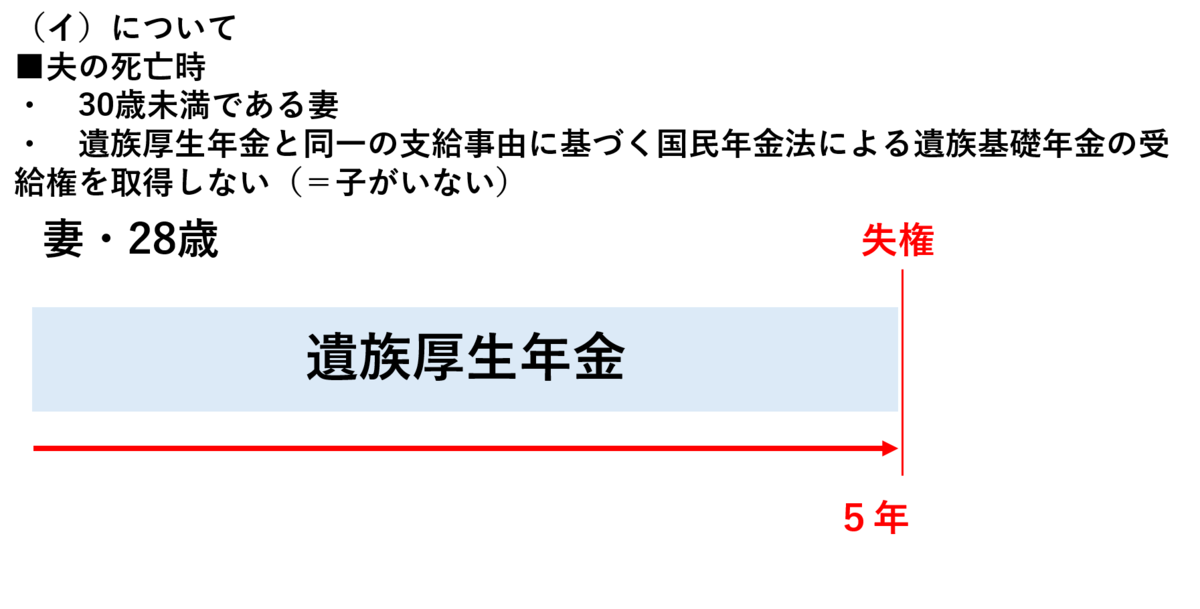
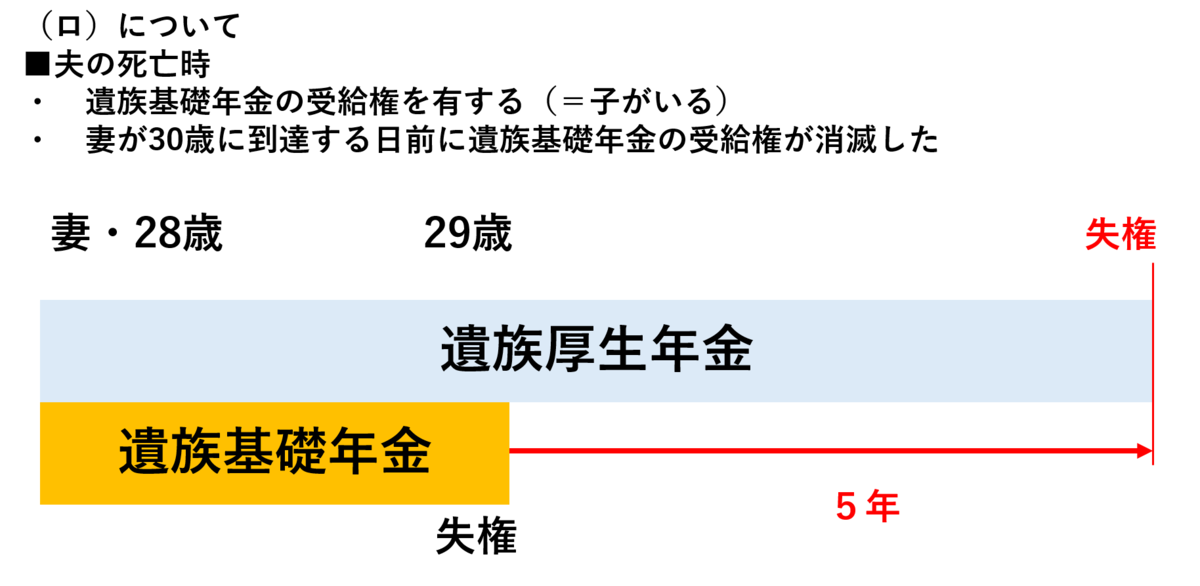
健康保険法「一時帰休」
R7-303 06.27
資格取得時、定時決定、随時改定の際の休業手当の扱い
「一時帰休」の際に支払われる休業手当等の扱いを過去問でみていきましょう。
さっそく過去問です!
①【R4年出題】
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

【解答】
①【R4年出題】 〇
ポイント!
■新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合
→ 雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する
■自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定について
→ 現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定する
→ 休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とする
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
②【R1年出題】
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
②【R1年出題】 〇
ポイント!
■定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休が解消しているかどうかは、「7月1日」で判断する
■7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う
→ 例えば、4月及び5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う
(令5.6.27事務連絡)
③【R6年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

【解答】
③【R6年出題】 〇
ポイント!
■標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合
→ その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。
→ 例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定する
■標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合
→ 定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する
→ 「9月以降において受けるべき報酬」とは?
→ 7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出する。
→ 例えば4・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行う
(令5.6.27事務連絡)
④【R3年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
④【R3年出題】 〇
ポイント!
■一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合
→ これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とする
→ ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限る
■休業手当等をもつて標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したとき → 随時改定の対象とする
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「日雇特例被保険者」
R7-302 06.26
健康保険の日雇特例被保険者の保険料納付要件
日雇特例被保険者が、療養の給付を受ける際の流れをおさえましょう。
・日雇特例被保険者は、厚生労働大臣から「日雇特例被保険者手帳」の交付を受ける
↓
・療養の給付を受けるとき
所定の保険料が納付されていることを日雇特例被保険者手帳によって証明して申請する
↓
・保険者は、これを確認したことを表示した「受給資格者票」を発行し、又は既に発行した「受給資格者票」にこれを確認したことを表示する
↓
・日雇特例被保険者は、「受給資格者票」を保険医療機関等に提出して療養の給付を受ける
日雇特例被保険者の「療養の給付」の受給要件を条文で読んでみましょう。
法第129条 (療養の給付) ① 日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、療養の給付を行う。 ② 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。 (1) 当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。 (2) 前号に該当することにより当該疾病又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日から1年(結核性疾病に関しては、5年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。 ③ 保険者は、日雇特例被保険者が、①第1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。 ④ 日雇特例被保険者が療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。 |
ポイント!
「前2月間」、「前6月間」は暦月で計算します。
(例)6月26日に療養の給付を受けようとする場合
4月 | 5月 | 6月 |
通算して26日分以上納付 |
| |
又は
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
通算して78日分以上納付 |
| |||||
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための保険料納付要件
・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上
又は
・療養の給付を受ける日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されていること
日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、原則として、上記の保険料納付要件を満たさなければなりません。
②【H30年出題】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「日雇特例被保険者が出産」した場合の保険料納付要件に注意しましょう。
・出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることが要件です。
「出産育児一時金」、「出産手当金」に適用されます。
(法第137条、第138条)
③【R5年出題】
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

【解答】
③【R5年出題】 〇
日雇特例被保険者本人が出産した場合の保険料納付要件は、「出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料」が納付されていることです。
また、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときの保険料納付要件は、原則通りです。出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることが要件です。
(法第144条)
④【H26年出題】
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

【解答】
④【H26年出題】 〇
日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後、療養の給付を受けるために、原則2か月ほど必要です。
そのため、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等に対しては、「特別療養費」が支給されます。
特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)です。
例えば、6月26日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は8月31日までです。
7月1日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は8月31日までです。
(法第145条)
⑤【R1年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「全国健康保険協会」ではなく、「厚生労働大臣」が行います。
条文を読んでみましょう。
第123条 ① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とする。 ② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「納付猶予」
R7-301 06.25
保険料納付猶予制度について
・保険料納付猶予制度は、50歳未満(50歳に達する日の属する月の前月まで)の第1号被保険者が対象です。
・所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
★保険料納付猶予のポイント!
・所得は本人のみならず、配偶者の所得も一定以下であることが条件です
・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

【解答】
①【R5年出題】 ×
・学生納付特例制度 → 国民年金法本則(法第90条の3)に規定されています
・納付猶予制度 → 本則ではなく、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されています。
②【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

【解答】
②【R3年出題】 ×
納付猶予制度は、令和12年6月までの時限措置です。ちなみに、3月までではなく6月までですので注意しましょう。
学生納付特例制度は時限措置ではなく、恒久的な制度ですので問題文は誤りです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「国民年金原簿」
R7-300 06.24
国民年金原簿と訂正の請求
国民年金原簿には、保険料の納付状況などが記録されています。
また、年金記録が事実と異なると思う人は、年金記録の訂正を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
法第14条 (国民年金原簿) 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
法第14条の2第1項 (訂正の請求) ① 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
法第14条の3 (訂正に関する方針) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 ② 厚生労働大臣は、方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
法第14条の4 (訂正請求に対する措置) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 ② 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 ③ 厚生労働大臣は、決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
当分の間、第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録・訂正の請求の対象から除かれています。
第2号被保険者については、「第1号厚生年金被保険者」のみが対象となります。
(法附則第7条の5第1項)
②【R4年出題】
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)又は私立学校教職員共済制度の加入者(第4号厚生年金被保険者)であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されません。
(法附則第7条の5第1項)
③【R1年出題】
国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項は、国民年金原簿の記載事項です。
(則第15条)
④【H30年出題】
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

【解答】
④【H30年出題 〇
寡婦年金を受けることができる妻は、死亡した夫に関する国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。
(法第14条の2第2項)
⑤【R2年出題】
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
厚生労働大臣は、「社会保険審査会」ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければなりません。
⑥【H27年選択式】
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は< A >に委任されており、 < A >が決定しようとするときは、あらかじめ< B >に諮問しなければならない。

【解答】
⑥【H27年選択式】
<A> 地方厚生局長又は地方厚生支局長
<B> 地方年金記録訂正審議会
条文を読んでみましょう。
法第109条の9 ① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第109条の5第1項及び第2項並びに第10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ② 地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ③ 第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。 ※厚生労働省組織令第153条の2 ① 地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。 ② 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
事例問題(国民年金法)
R7-299 06.23
国民年金法の事例問題を解いてみましょう
厚生年金保険に7年間、第1号被保険者として保険料を27年間納付した男性が54歳で死亡した場合の「事例問題」を解いていきます。
<問題のテーマ>
①遺族が80歳の母の場合
②遺族が50歳の妻の場合
③遺族が12歳と15歳の子の場合
④遺族が50歳の弟と60歳の兄の場合
⑤事実婚関係の45歳の妻と13歳の妻の連れ子の場合
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-298 06.22
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年6月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月16日から21日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・入院時食事療養費についてお話しします(健康保険法)
・ 健康保険の時効と起算日(健康保険法)
・ 保険料納付済期間の定義(国民年金法)
・ 障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定(国民年金法)
・ その他障害との併合による障害基礎年金の額の改定(国民年金法)
・ 障害基礎年金の失権(国民年金法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R7-297 06.21
障害基礎年金の失権
障害基礎年金の受給権の消滅時期を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (3) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
図でイメージしましょう。
少なくとも、65歳までは失権しないことがポイントです。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第31条 (併給の調整) ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
②【H20年出題】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
②【H20年出題】 ×
★ポイント!
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態 → 3級のことです。
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、その時点では当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金が失権する時期は、「3級に該当しなくなった日から3年を経過」か「65歳」のどちらか遅い方です。
3級に該当しなくなった日から3年を経過しても、65歳未満の場合は、失権しません。
③【H30年出題】
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
「3級に該当する程度の状態」の場合は、障害基礎年金は失権しませんので注意してください。
図でイメージしましょう。
63歳の時に障害状態が3級程度に軽減した場合、障害基礎年金の支給が停止されますが、3級に該当する程度の状態にある間は失権はしません。
そのため、3級に該当する状態のまま、5年経過後に再び障害状態が悪化し2級に該当した場合は、支給停止が解除されます。
④【R3年出題】
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
④【R3年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときは、当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
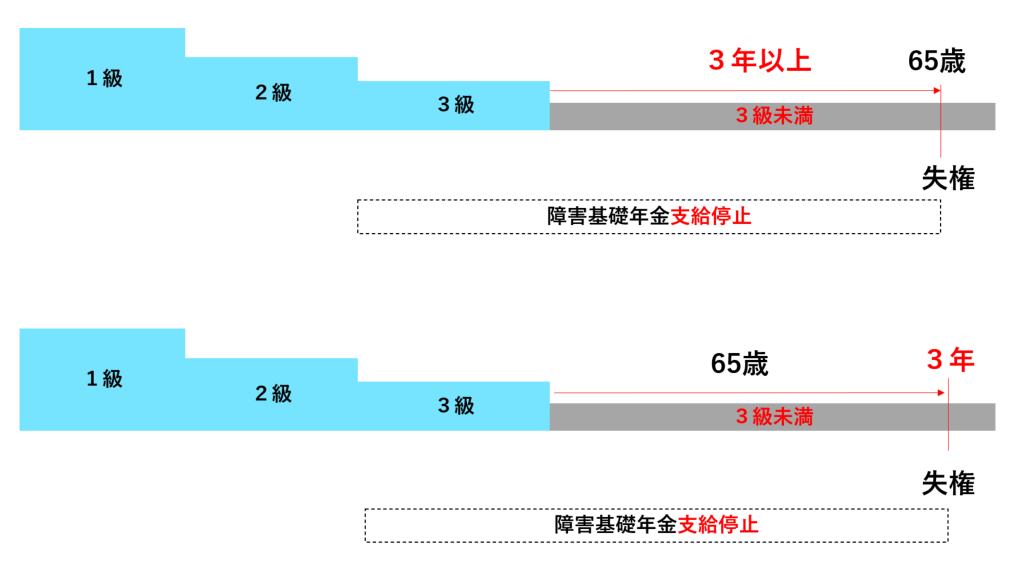
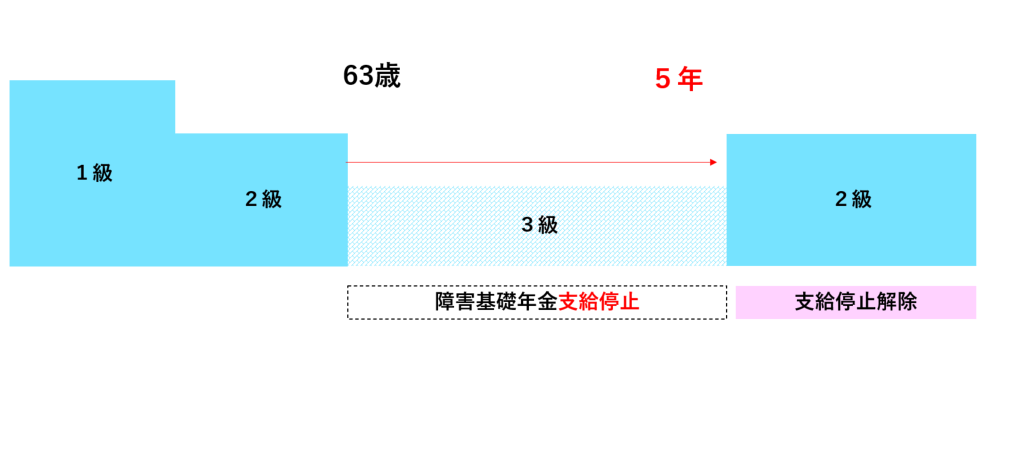
国民年金法「障害基礎年金」
R7-296 06.20
その他障害との併合による障害基礎年金の額の改定
例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害(1級・2級未満の障害)が発生し、前後の障害を併合すると障害の程度が1級に増進した場合は、障害基礎年金の額の改定を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
法第34条第4項 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 |
図でイメージしましょう。
<その他障害のポイント!>
・1級、2級に該当しないこと(3級以下)
・初診日要件、保険料納付要件を満たしていること
<額の改定の要件>
・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したこと
+
・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に額の改定を請求すること
過去問をどうぞ!
【H26年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

【解答】
【H26年出題】 ×
その他障害による額の改定の要件は、「その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、従前の障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」です。
問題文のように、その他障害の初診日の段階で、66歳の場合は、要件を満たしませんので、障害基礎年金の額の改定請求はできません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
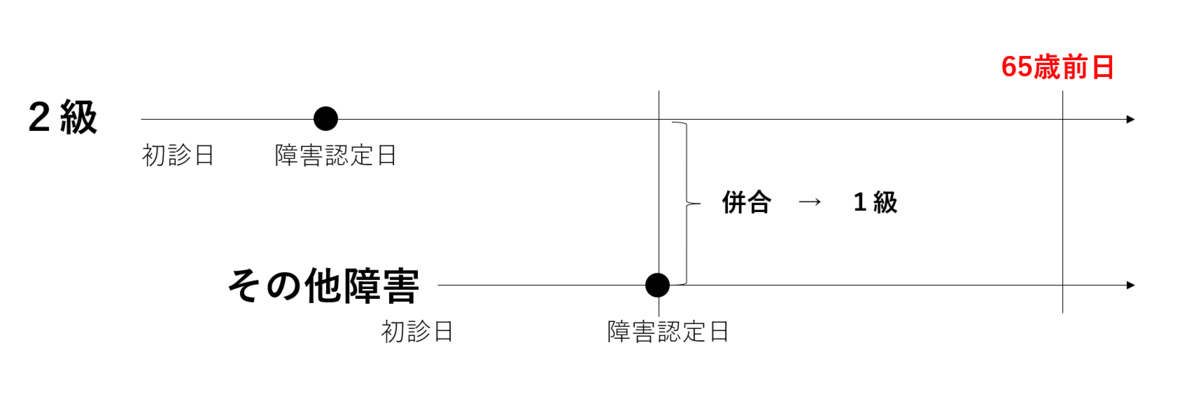
国民年金法「障害基礎年金」
R7-295 06.19
障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定
例えば、障害等級が2級から1級に変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。
今回は、
・厚生労働大臣の職権による改定
・受給権者からの請求による改定
をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第34条第1項~第3項 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ③ 請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
★障害の程度が増進(重くなった)ときは、受給権者は、額の改定を請求できます。
<請求の要件>
・障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後
又は
・厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても請求できます。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
受給権者が65歳以上でも、障害基礎年金の額の改定の対象となります。
②【R5年出題】
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
③【R6年出題】
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】
③【R6年出題】 ×
「1年6か月」ではなく、「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
④【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

④【R2年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合」は、「障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合」に該当しますので、1年経過しなくても、年金額の改定の請求をすることができます。
(則第32条の2の2第1項第9号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「用語の定義」
R7-294 06.18
「保険料納付済期間」の定義
「用語の定義」を正確におさえておくと、条文も読みやすくなります。
今回は「保険料納付済期間」の定義をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第5条第1項 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中の納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
<保険料納付済期間とは>
★第1号被保険者としての被保険者期間
・保険料を納付した期間
※督促・滞納処分により徴収された保険料を含む
※一部免除によりその残余の額が納付又は徴収されたものは除く。
・産前産後期間中の免除を受けた期間
★第2号被保険者としての被保険者期間
★第3号被保険者としての被保険者期間
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

【解答】
①【H24年出題】 〇
督促及び滞納処分により保険料が納付された期間も、保険料納付済期間に含まれます。
②【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
②【H24年出題】 〇
保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
(法第94条)
③【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】
③【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用されている者で、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。
(法第5条第1項、第6項)
④【R2年出題】
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「産前産後期間の保険料免除」により保険料を免除された期間は、「保険料納付済期間」となります。
ちなみに、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間です。
(法第5条第1項、第3項)
⑤【H28年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
第2号被保険者としての被保険者期間は「保険料納付済期間」に含まれます。
ただし、「老齢基礎年金」については、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。
条文を読んでみましょう。
昭60年法附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
⑥【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
⑥【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、合算対象期間となります。
「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」には、そのような扱いはありません。第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、原則とおり、「保険料納付済期間」となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「時効」
R7-293 06.17
健康保険の時効と起算日
健康保険の時効について条文を読んでみましょう。
法第193条 (時効) ① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |
健康保険の時効は「2年」です。
また、「時効」が適用されないもの、「時効の起算日」にも注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「現物給付」については、時効は適用されません。
②【H30年出題】
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

【解答】
②【H30年出題】 ×
療養費の時効の起算日は、「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
問題文の場合は、「コルセットを装着した日の翌日」ではなく、「コルセットの代金を支払った日の翌日」から起算します。
コルセットを装着しただけで費用を支払っていない場合は、「療養費請求の権利を行使し得ない」からです。
(昭和31.3.13保文発第1903号)
③【H28年出題】※改正による修正あり
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

【解答】
③【H28年出題】 ×
高額療養費の時効の起算日が誤りです。
<消滅時効の起算日について>
・療養費 → 療養に要した費用を支払った日の翌日
・高額療養費 → 診療月の翌月1日
※診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日
・高額介護合算療養費 → 計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日
(昭和48.11.7庁保険発第21号、保険発第99号、平成21.4.30保保発第430001号)
④【R5年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】
④【R5年出題】 ×
傷病手当金を受ける権利の時効の起算日は労務不能であった日ごとにその「当日」ではなく「労務不能であった日ごとにその「翌日」」です。
(昭和30.9.7保険発第199-2号)
⑤【R1年出題】
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日」からではなく、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算します。傷病手当金の時効の起算日と同じ考え方です。
なお、「出産育児一時金」の時効については、「出産した日の翌日」から起算します。
(昭和30.9.7保険発第199-2号)
⑥【H26年出題】
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

【解答】
⑥【H26年出題】 〇
埋葬料と埋葬費の起算日の違いに注意しましょう。
埋葬料 → 実際に埋葬を行ったかどうかは関係ないため、時効の起算日は保険事故発生の日(死亡した日)の翌日
埋葬費 → 埋葬を行った事実に対して支払われるので、時効の起算日は保険事故発生日(埋葬した日)の翌日
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「入院時食事療養費」
R7-292 06.16
入院時食事療養費についてお話しします
入院時食事療養費は、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、支給されます。
<入院時食事療養費の額>
「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から「食事療養標準負担額」を控除した額です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-291 06.15
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年6月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月9日から14日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・休日の振替についてお話しします(労働基準法)
・「面接指導」は3種類の違いがポイント(労働安全衛生法)
・ 労働安全衛生法の書類の保存期間(労働安全衛生法)
・ 派遣労働者の労災についての出題(労災保険法)
・証明書による失業の認定(雇用保険法)
・「介護保険料率」の定め方(健康保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「介護保険料率」
R7-290 06.14
「介護保険料率」の定め方
健康保険の被保険者の保険料額は以下の通りです。
① 介護保険第2号被保険者である被保険者
→ 一般保険料額と介護保険料額との合算額
② 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者
→ 一般保険料額
★一般保険料額とは?
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額
★介護保険料額とは?
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額
今回は、「介護保険料率」の定め方をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第160条第16条 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 |
★介護保険料率について
介護納付金の額 ÷ 介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)の総報酬額総額の見込
で計算します。
★介護納付金とは
健康保険の保険者は、介護保険第2号被保険者から介護保険料を徴収し、「介護納付金」として社会保険診療報酬支払基金に納付します。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】※改正による修正あり
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
介護保険料率は、「介護納付金の額」÷「介護保険第2号被保険者の総報酬額総額の見込」で計算します。
②【R4年出題】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

【解答】
②【R4年出題】 ×
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を「当該年度」における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の「総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。」となります。
ちなみに「総報酬額」とは、標準報酬月額と標準賞与額を合算した額です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「失業の認定」
R7-289 06.13
証明書による失業の認定
失業の認定は、受給資格者本人が、失業の認定日に出頭して受けることが原則です。
しかし、やむを得ない理由によって出頭できないときは、証明書による失業の認定を受けることができます。
「証明書による失業の認定」が受けられるのは、4つの理由に限定されています。
条文を読んでみましょう。
法第15条第4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 (1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 (2) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合に、証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。
「継続して20日」の場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
★疾病又は負傷の場合の取扱いを整理しましょう。
15日未満 | 証明書による失業の認定で基本手当を受けることができる |
15日以上 | 傷病手当を受けることができる ※ただし、傷病手当の支給要件は、「求職の申込みをした後で疾病又は負傷のために職業に就くことができなくなったこと」 |
※ ちなみに、疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は、受給期間の延長の措置を受けることができます。
ただし、その疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合には、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象になりません。
(行政手引50271)
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。
15日未満の場合は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
③【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

【解答】
③【H25年出題】 ×
証明書を提出することによって失業の認定を受けることができるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときです。
「民間の職業紹介事業者」の紹介に応じて求人者に面接する場合は、証明書による失業認定は受けられません。
ちなみに、公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合は、失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
(行政手引51351)
④【R1年出題】
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

【解答】
④【R1年出題】 〇
天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、証明書による失業の認定を受けることができます。
具体的な手続きを条文で読んでみましょう。
則第28条第1項 法第15条第4項第4号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。 (1) 受給資格者の氏名及び住所又は居所 (2) 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間 (3) 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかった期間 |
問題文の通り、受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができます。
(行政手引51401)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「派遣労働者」
R7-288 06.12
派遣労働者の労災についての出題
「派遣労働者」は、「派遣元事業主」とは「労働契約関係」にあり、「派遣先事業主」とは「指揮命令関係」にあります。
「派遣労働者」の労災保険は、労働契約関係にある派遣元事業主が労災保険の適用事業となります。
「労働者災害補償保険法に関しては、同法第3条第1項は「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されており、また、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課される以上、労災保険法と労働基準法との関係を考慮すれば、労災保険法の適用についても同様に取り扱い、派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当である。」とされています。
(昭61.6.30基発第383号)
さっそく過去問をどうぞ!
①【H22年選択式】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が< A >との間の労働契約に基づき< A >の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき< B >の支配下にある場合には、一般に< C >があるものとして取り扱われる。
(選択肢)
① 業務起因性 ② 業務遂行性 ③ 条件関係 ④ 相当因果関係
⑤ 派遣先事業主 ⑥ 派遣先責任者 ⑦ 派遣元事業主
⑧ 派遣元事業主及び派遣先事業主
⑨ 派遣元事業主又は派遣先事業主
⑩ 派遣元責任者

【解答】
①【H22年選択式】
<A> ⑦ 派遣元事業主
<B> ⑤ 派遣先事業主
<C> ② 業務遂行性
(昭61.6.30基発第383号)
②【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。

【解答】
②【R1年出題】 〇
①の選択式と同じ問題です。
(昭61.6.30基発第383号)
③【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。

【解答】
③【R1年出題】 〇
派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるとされています。
(昭61.6.30基発第383号)
④【R1年出題】
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。

【解答】
④【R1年出題】 〇
<派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たって>
・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となる
・したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる
とされています。
(昭61.6.30基発第383号)
⑤【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
・保険給付請求書の事業主の証明は派遣元事業主が行います。
・派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写を当該保険給付請求書に添付させることとされています。
(昭61.6.30基発第383号)
⑥【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

【解答】
⑥【R1年出題】 ×
派遣労働者の保険給付の請求に当たり、保険給付請求書の事業主の証明は「派遣先」ではなく「派遣元事業主」が行うこととされています。
(昭61.6.30基発第383号)
⑦【H30年出題】
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

【解答】
⑦【H30年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第46条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主又は船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法「書類の保存」
R7-287 06.11
労働安全衛生法の書類の保存期間
労働安全衛生法の書類の保存期間については、よく出題される「3年」のものと「5年」のものをおさえましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
定期自主検査の結果の記録は、5年間ではなく「3年間」保存しなければなりません。
(則第135条の2)
②【H22年出題】
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。

【解答】
②【H22年出題】 〇
「特別の安全衛生教育」の記録は、「3年間」保存しなければなりません。
(則第38条)
ちなみに、雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育、職長等の教育には、記録の保存期間は定められていません。
<ほかに3年の保存期間が定められているもの>
「安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会」の開催の都度、所定の事項を記録し、これを「3年間」保存しなければなりません。
③【H27年出題】
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
「3年間」ではなく「5年間」です。
労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも5年間保存しなければなりません。
(則第51条)
④【R2年出題】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「3年間」ではなく「5年間」です。
労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、5年間保存しなければなりません。
(則第52条の6)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法「面接指導」
R7-286 06.10
「面接指導」は3種類の違いがポイント
労働安全衛生法の「面接指導」には、「長時間労働者全般に対する面接指導」、「研究開発業務に従事する者に対する面接指導」、「高度プロフェッショナル制度の対象者に対する面接指導」の3つがあります。
それぞれの違いがポイントです。
条文を読んでみましょう。
(1)労働者全般
法第66条の8第1項 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(研究開発業務に従事する者及び高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。
則第52条の2 ① 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。(以下省略) ② 超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 ③ 事業者は、超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、超えた時間が一月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
(面接指導の実施方法等) 則第52条の3 ① 法第66条の8の面接指導は、前条①の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。 ② 申出は、前条第②の期日後、遅滞なく、行うものとする。 ③ 事業者は、労働者から申出があつたときは、遅滞なく、法第66条の8の面接指導を行わなければならない。 ④ 産業医は、前条①の要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。 |
(2)研究開発業務に従事する者
法第66条の8の2第1項 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(研究開発業務に従事する者に限る。労働基準法第41条各号に掲げる者及び高度プロフェッショナル制度の対象者を除く。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない 則第52条の7の2第1項 法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き一週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間とする。 |
(3)高度プロフェッショナル制度の対象者
法第66条の8の4第1項 事業者は、高度プロフェッショナル制度により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 則第52条の7の4 法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で定める時間は、一週間当たりの健康管理時間(労働基準法第41条の2第1項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間とする。 |
ポイントをまとめました
(1)労働者全般 | (2)研究開発業務に従事する者 | (3)高度プロフェッショナル制度の対象者 |
★時間外・休日労働が 月80時間超 ★疲労の蓄積がある ★労働者からの申出が必要 | ★時間外・休日労働が 月100時間超(申出不要) | ★1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間が月100時間超(申出不要) |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
1月当たり60時間ではなく、「1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合」です。
②【H21年出題】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。

【解答】
②【H21年出題】 ×
「本人の申出にかかわらず」ではなく、「労働者から申出があった場合」に面接指導を実施しなければなりません。
③【H18年選択式】
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう < A >することができる旨規定されている。

【解答】
③【H18年選択式】
<A> 勧奨
④【R2年出題】
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。

【解答】
④【R2年出題】 ×
研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間」ではなく「100時間」を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければなりません。
⑤【R6年出題】
労働安全衛生法第66条の8の2において、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者(労働基準法第41条各号に掲げる者及び労働安全衛生法第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に対して事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働時間に関する要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間を超える者とされている。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務に従事する者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、一月当たり100時間を超える者が面接指導の対象です。なお、この場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければなりません。
⑥【R2年出題】
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

【解答】
⑥【R2年出題】 〇
高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、その健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものが面接指導の対象となります。労働者からの申出の有無は問われません。
⑦【R2年出題】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

【解答】
⑦【R2年出題】 ×
労働時間の状況の把握は、労働者の健康確保措置を適切に実施するためのものです。
対象になるのは、次の表に載っている労働者を含めたすべての労働者です。
① 研究開発業務従事者 |
② 事業場外労働のみなし労働時間制の適用者 |
③ 裁量労働制の適用者 |
④ 管理監督者等 |
⑤ 派遣労働者 |
⑥ 短時間労働者 |
⑦ 有期契約労働者 |
なお、高度プロフェッショナル制度対象労働者は除かれます。
問題文の場合、「労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者」は、労働時間の状況を把握する対象となります。なお、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」はその対象から除かれます。
(H31.3.29基発0329 第2号)
⑧【R6年出題】
事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。

【解答】
⑧【R6年出題】 〇
労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も労働時間の状況を把握しなければならない対象に含まれます。
(H31.3.29基発0329 第2号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「休日の振替」
R7-285 06.09
休日の振替についてお話しします。代休との違いに注意しましょう(労働基準法)
「休日の振替」についてお話しします。
ポイント!
・代休との違い
・休日の振替とは、あらかじめ「休日」と「労働日」を入れ替えること
・場合によっては、「時間外労働」の割増賃金が必要になることもあります
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-284 06.08
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年6月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年6月2日から7日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・特別支給の老齢厚生年金の基本をお話しします(厚生年金保険法)
・時効を比較しましょう(国民年金法と厚生年金保険法)
・高齢者医療確保法の保険料について(社会保険一般常識)
・介護保険法の保険料について(社会保険一般常識)
・訪問看護療養費のポイント(健康保険法)
・労基法の退職手当に関する出題(労働基準法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「退職手当」
R7-283 06.07
労基法の「退職手当」に関する出題
労働基準法の「退職手当」に関する出題を集めました。
テーマは以下の通りです。
・退職手当は労働基準法の「賃金」に当たるか否か
・賃金支払い5原則の例外
・退職手当は、就業規則の相対的必要記載事項
・金品の返還
・退職金に関する判例
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労働基準法では、退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこととされています。
ただし、退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金とされます。
(昭22.9.13発基第17号)
②【R3年出題】
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。

【解答】
②【R3年出題】 ×
賃金は、「通貨払い」が原則です。
例外的に、「労働者の同意」を得た場合は、「当該労働者の預金又は貯金への振込み」によることができます。また、退職手当については、「銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付する」ことによることができます。
③【H12年出題】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
③【H12年出題】 ×
退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。
退職手当は、「予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」とされています。
(法第23条、昭26.12.27基収5483号)
④【H28年出題】
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。

【解答】
④【H28年出題】 ×
「退職手当」は、就業規則の相対的必要記載事項です。
退職手当の制度を設ける場合は、就業規則に、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を定めなければなりません。
退職手当についての不支給事由又は減額事由は、退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当します。そのため、就業規則に記載しなければなりません。
(法第89条、H11.3.31基発168号)
⑤【H27年出題】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
「全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。」とされています。
労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力は、肯定されています。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷)
⑥【H30年選択式】
最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が< A >的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」
<選択肢>
① 功労報償 ② 就業規則を遵守する労働者への生活の補助
③ 成果給 ④ 転職の制約に対する代償措置

【解答】
⑥【H30年選択式】
<A> ① 功労報償
「この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の同法3条、16条、24条及び民法90条等の規定にはなんら違反するものではない。」とされています。
(昭和52.8.9最高裁判所第二小法廷)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「訪問看護療養費」
R7-282 06.06
訪問看護療養費のポイント
訪問看護療養費は、居宅で療養している人が対象です。
主治医の指示により、訪問看護ステーションの看護師等から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に支給されます。
条文を読んでみましょう。
法第88条(訪問看護療養費) ① 被保険者が、指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 ② 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 ③ 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 ④ 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、一部負担金に相当する額を控除した額とする。 ⑤ 厚生労働大臣は、④の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】※改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

①【H28年選択式】
【解答】
<A> 保険者
<B> 自己
②【H25年出題】
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるもの」は訪問看護療養費の対象から除かれています。
「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、「療養の給付」の対象となります。
③【H24年出題】
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

【解答】
③【H24年出題】 ×
訪問看護を行うものに、「医師、歯科医師」は入りません。
(則第68条)
④【R5年出題】
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたものである。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。

【解答】
④【R5年出題】 〇
・訪問看護療養費は、保険者が必要と認める場合に限り支給する
・指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたもの
・看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
(則第67条、第68条)
⑤【R1年出題】
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
保険者は、被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用を、被保険者に代わり、指定訪問看護事業者に支払うことができます。
これによって、訪問看護療養費は、現物給付となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険一般常識「介護保険法」
R7-281 06.05
介護保険法の保険料について
介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。
法第9条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
では、「保険料」について条文を読んでみましょう。
法第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
市町村又は特別区から保険料を徴収されるのは、第1号被保険者です。
②【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
②【H30年選択式】
<A> 3年
③【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。
・第2号被保険者については、医療保険者が医療保険料といっしょに介護保険料を徴収します。
医療保険者は、社会保険診療報酬支払基金に納付金を納付します。
条文を読んでみましょう。
法第150条 (納付金の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金は年度ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。 ③ 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
法第125条(介護給付費交付金) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。 第126条 (地域支援事業支援交付金) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険一般常識「高齢者医療確保法」
R7-280 06.04
高齢者医療確保法の保険料について
高齢者医療確保法の保険料についてみていきましょう。
高齢者医療確保法の「後期高齢者医療制度」の被保険者は以下の通りです。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |
では、保険料について条文を読んでみましょう。
法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業による費用の拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
法第107条 (保険料の徴収の方法) 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者から年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】※改正による修正あり
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
保険料を徴収するのは、「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、「市町村(特別区を含む。)」です。
②【H23年出題】※改正による修正あり
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
おおむね「5年」ではなく、「2年」です。
③【R5年出題】
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
特別徴収と普通徴収の説明が逆です。原則は「特別徴収」です。
「市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる「特別徴収」の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する「普通徴収」の方法によらなければならない。」となります。
④【H30年出題】
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
年金の年間の給付額が18万円以上の場合は特別徴収の対象です。
ただし、一定の要件に該当する場合は、特別徴収ではなく普通徴収となります。口座振替の方法により保険料を納付することは一切できないわけではありません。
(法第110条、令第21条、22条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金・厚生年金保険「時効」
R7-279 06.03
<国年・厚年比較>時効について
国民年金法と厚生年金保険法の「時効」を比較してみましょう。
まず、国民年金の条文を読んでみましょう。
国民年金法第102条 (時効) ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
ポイント!
「年金給付」→ 年金のみです。死亡一時金は入りません。
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
第92条 (時効) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ③ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 |
ポイント!
「保険給付」 → 障害手当金も入ります。年金のみではありません。
過去問をどうぞ!
国民年金法
①国年【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①国年【H27年出題】 ×
「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
「死亡一時金」を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
②国年【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②国年【R2年出題】 〇
「年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うもの」を「支分権」といいます。
支分権の時効についての問題です。
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は「支払期月の翌月の初日」から起算して5年を経過したときに時効によって消滅します。
厚生年金保険法
①厚年【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①厚年【H29年出題】 ×
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
国民年金の「死亡一時金」は「2年」ですので違いに注意しましょう。
②厚年【H30年出題】
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

【解答】
②厚年【H30年出題】 ×
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、「進行しない」。
③厚年【R4年出題】
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
③厚年【R4年出題】 〇
支分権の時効の問題です。
時効の起算点の「支払期月の翌月の初日」がポイントです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「特別支給の老齢厚生年金」
R7-278 06.02
特別支給の老齢厚生年金についてお話しします
本来の「老齢厚生年金」は、65歳から、老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
60歳から65歳まで支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳以上の本来の老齢厚生年金とは別の有期年金です。
・特別支給の老齢厚生年金の支給要件
・平成6年改正と平成12年改正
・生年月日や性別による支給開始年齢の違い
などを、図を使ってお話ししています。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-277 06.01
【毎日コツコツ社労士受験】<総集編>振替加算の動画をまとめました+配偶者加給年金額
「振替加算」のお話をまとめました。
振替加算を知るためには欠かせない「配偶者加給年金額」も入れています。
是非、ご活用ください。
内容は以下の通りです。
・振替加算の基本をお話しします
・振替加算が加算される要件
・振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・老齢基礎年金を繰り上げたとき、繰り下げたときの振替加算
・老齢厚生年金・障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「配偶者加給年金額」
R7-276 05.31
配偶者加給年金額(老齢厚生年金・障害厚生年金)
★まず、老齢厚生年金に加算される加給年金額をみていきましょう。
加給年金額の対象になるのは、「配偶者」と「子」です。
今回は、「配偶者」を中心にみていきます。
<加給年金額のポイント!>
・老齢厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)
→ その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であること
・加給年金額の対象になる人
→ 受給権者がその権利を取得した当時、受給権者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子
→老齢厚生年金の権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時、受給権者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子
※子の条件→ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子
★次に、障害厚生年金に加算される加給年金額をみていきましょう。
<加給年金額のポイント!>
・障害厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)
→ 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当すること(3級には加給年金額は加算されません)
・加給年金額の対象になる人
→ 受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者
(受給権が発生した後で生計を維持することになった場合でも加給年金額の対象になる)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。

【解答】
①【R2年出題】 〇
・老齢厚生年金の加給年金額
配偶者 | 224,700円×改定率 |
子 | 2人目まで 224,700円×改定率 3人目以降 74,900円×改定率 |
(法第44条第2項)
②【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
被保険者資格を喪失した際に(退職時改定により)、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されるようになります。
(法第44条第1項)
③【R3年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級又は2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
法第46条第6項で、「加給年金額が加算された老齢厚生年金については、その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」と規定されています。
問題文は、「老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害厚生年金(1級・2級・3級)及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。」となります。
加算対象の配偶者が3級の障害厚生年金を受給している場合でも、配偶者についての加給年金額は支給停止されます。
④【R4年出題】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

【解答】
④【R4年出題】 〇
加給年金額の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合は、夫に加算されていた加給年金額は支給が停止されます。
⑤【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
⑤【H28年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は引き続き支給されます。
イメージ図をみてみましょう。
⑥【H30年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなります。
★配偶者加給年金額には「特別加算」が加算されます。
受給権者の生年月日 | 特別加算の額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円×改定率 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,300円×改定率 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,500円×改定率 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,600円×改定率 |
昭和18年4月2日~ | 165,800円×改定率 |
特別加算のポイント!
・生年月日は「老齢厚生年金の受給権者の生年月日」。加算の対象になっている配偶者の生年月日ではありません。
・特別加算が加算されるのは、「昭和9年4月2日」以降生まれ。
・生年月日が若いほど、特別加算の額が大きくなる
・昭和18年4月2日以降生まれは一律
⑦【R4年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
⑦【R4年出題】 ×
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、特別加算はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
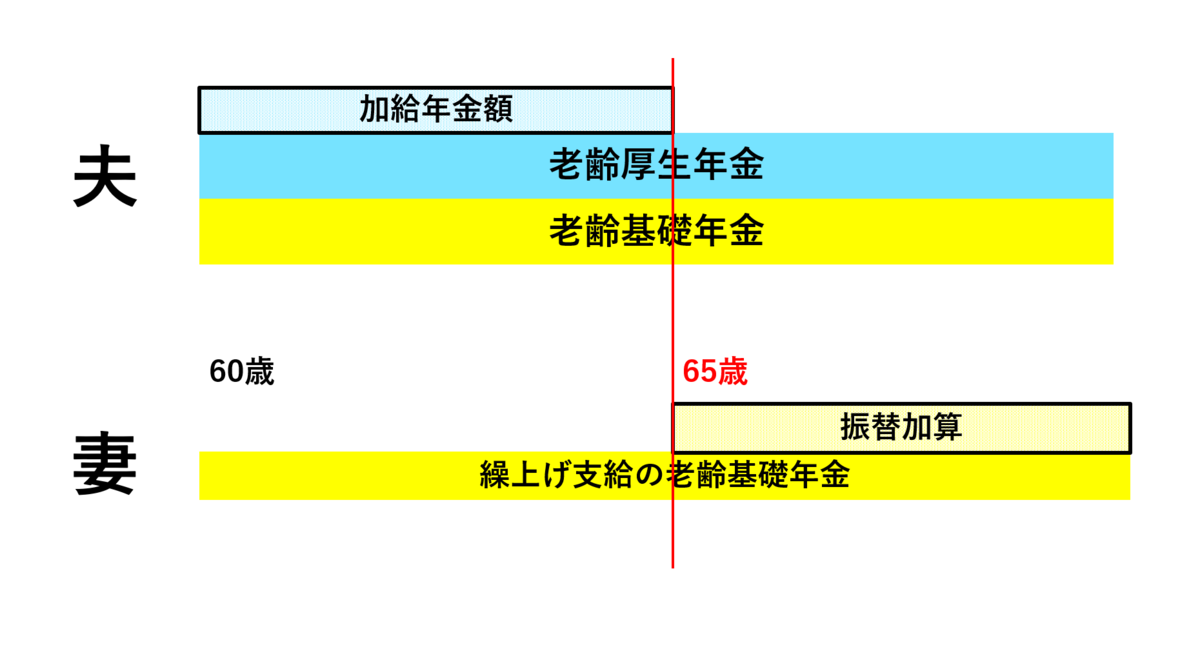
国民年金法「振替加算の練習その4」
R7-275 05.30
<振替加算第4回目>老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
今回は第4回目です。
老齢基礎年金は、請求によって繰上げて受けることができ、また、申出によって繰り下げて受けることもできます。
<老齢基礎年金の繰上げについて>
・繰上げ請求のあった日の属する月の翌月から支給される
・繰り上げた月数によって減額される
<老齢基礎年金の繰下げについて>
・申出のあった日の属する月の翌月から支給される
・繰り下げた月数によって増額される
老齢基礎年金を繰り上げて、又は繰り下げて受ける場合の振替加算の扱いをみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 振替加算は、「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「65歳に達した日の属する月の翌月」から加算されます。振替加算は、繰上げされません。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 問題文のとおり「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます
(昭60法附則第14条)
②【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
②【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算されません。
③【R3年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】
③【R3年出題】 〇
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後に加算されます。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 振替加算も繰下げて支給されます。ただし、振替加算額には、繰下げによる増額はありません。
④【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】
④【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「振替加算の練習その3」
R7-274 05.29
<振替加算第3回目>振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
今回は第3回目です。
<振替加算が行われないとき>
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、要件に該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
※政令で定めるものは、老齢厚生年金又は退職共済年金で、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上のものです。 (昭61年経過措置令第25条) |
<振替加算が支給停止されるとき>
昭60年法附則第16条 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
単なる老齢厚生年金ではなく、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金であることに注意して下さい。
②【H27年出題】
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
②【H27年出題】 〇
合意分割の結果、離婚時みなし被保険者期間を含めて厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となる老齢厚生年金を受けることになった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。
③【R3年出題】
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

【解答】
③【R3年出題】 ×
「中高齢の期間短縮特例」により、昭和26年4月2日生まれの女性は、35歳以後の厚生年保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が19年ある場合は、「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」あるとみなされます。
問題文の妻は、中高齢の期間短縮特例を満たしているため、妻の老齢基礎年金に振替加算は行われません。
④【H30年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】
④【H30年出題】 〇
障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算は支給が停止されます。
⑤【H21年出題】
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

【解答】
⑤【H21年出題】 〇
障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間振替加算が支給停止されます。
⑥【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

【解答】
⑥【H21年出題】 ×
障害基礎年金の受給権を有していても、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。
⑦【R3年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
⑦【R3年出題】 ×
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときでも、振替加算の支給は停止されません。
⑧【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

【解答】
⑧【H21年出題】 〇
配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚しても、離婚したことを理由とする振替加算の支給停止はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「振替加算の練習その2」
R7-273 05.28
<振替加算第2回目>振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
今回は第2回目です。
<振替加算の額>
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であるもの)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)=1級・2級 |
★振替加算の額は
224,700円×改定率×「その者の生年月日に応じて政令で定める率」です。
政令で定める率は、以下の通りです。
受給権者の生年月日 | 政令で定める率 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日まで | 1.000 |
↓ | ↓ |
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日まで | 0.067 |
生年月日が若いほど、政令で定める率が小さくなる(振替加算の額が少なくなる)のがポイントです。
<振替加算のみの老齢基礎年金>
老齢基礎年金の額がゼロでも、要件に該当する場合は、振替加算のみの老齢基礎年金が支給されることがあります。
・保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間を除く。)を有しない場合は、老齢基礎年金の額はゼロです。
↓
・合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例期間に限る。)を合算した期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。ただし、老齢基礎年金の額はゼロです。
↓
・そのような者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。
(昭60法附則第15条第2項)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれたものであるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
振替加算の額は、「受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額です。
②【H18年出題】
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。

【解答】
②【H18年出題】 ×
振替加算の金額は、「224,700円に改定率を乗じて得た額」に、「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者の生年月日」に応じて定められた率を乗じた額です。
③【H27年出題】
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】
③【H27年出題】 〇
・甲(妻)は、合算対象期間のみ40年有していて、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしている。
・甲(妻)は乙(夫)の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていて、65歳時点で夫に生計を維持されている
・甲には、65歳になると「振替加算額に相当する額の老齢基礎年金」が支給されます
④【H21年出題】
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

【解答】
④【H21年出題】 ×
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月でもあれば、その期間で計算された老齢基礎年金が支給されます。
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」ではなく、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)の月数に応じて計算された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「振替加算の練習その1」
R7-272 05.27
<振替加算第1回目>振替加算が支給される要件
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
今回から4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
今回は第1回目です。
振替加算が加算される要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であるもの)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)=1級・2級 |
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。

【解答】
①【H22年出題】 〇
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に振替加算を加算する特例が設けられています。
②【H21年出題】
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
遺族基礎年金には振替加算は加算されません。
③【R2年出題】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

【解答】
③【R2年出題】 〇
「振替加算の対象となる者」に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る「振替加算の加算開始事由に該当した日」における生計維持関係により行われます。
④【H30年出題】
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
④【H30年出題】 〇
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算される要件は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることです。
ただし、中高齢の期間短縮特例が適用される場合もあります。問題文の昭和25年4月2日生まれの男性の場合は、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が19年以上あれば要件を満たします。
問題文の夫の老齢厚生年金には加給年金額が加算されていますので、妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
⑤【H27年出題】
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
65歳より後に要件に該当した場合でも、振替加算は加算されます。
問題文の妻には、老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
⑥【H27年出題】
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
⑥【H27年出題】 〇
妻が65歳になった後で振替加算の要件に該当した場合の問題です。
夫は67歳のときに、退職時改定で、老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間(20年以上)の要件を満たした
・夫に生計を維持されている老齢基礎年金を受給している66歳の妻に、その時点から振替加算が加算されます。
(図でイメージしましょう)
なお、その際、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
(昭60法附則第14条第2項、則第17条の3第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
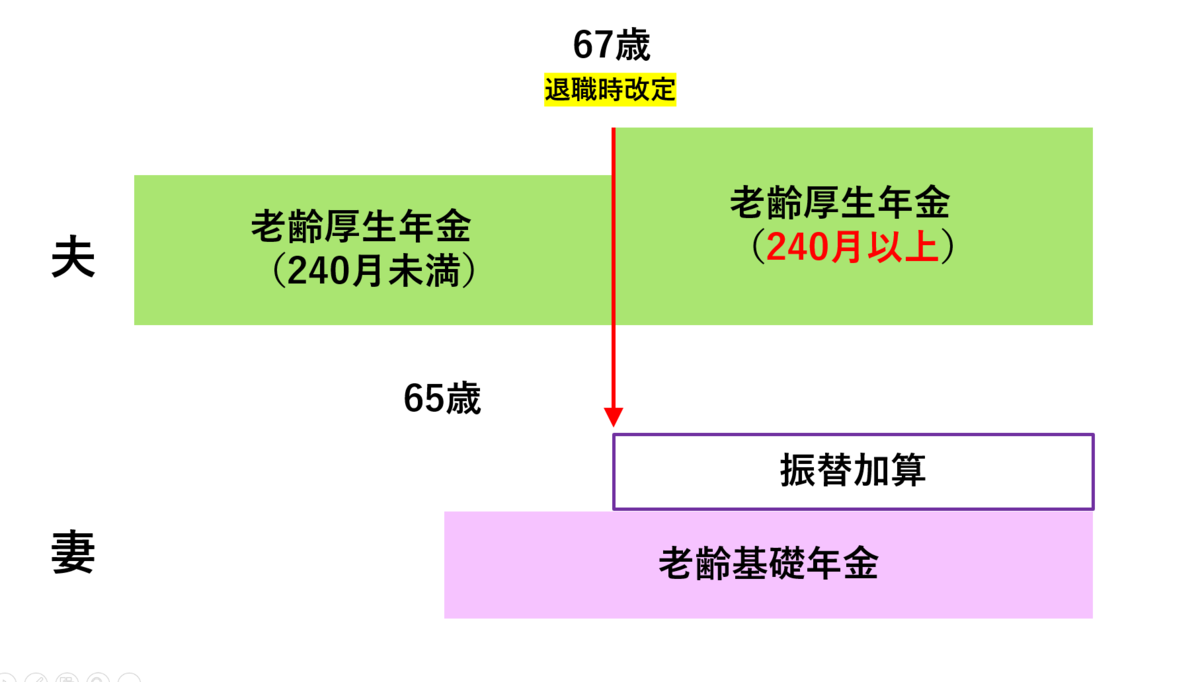
国民年金法「振替加算」
R7-271 05.26
「振替加算」の基本をお話しします
「振替加算」の基本をお話しします。
振替加算は、昭和61年4月1日前の「旧法」の制度や、厚生年金保険法の加給年金額の仕組みを知ると、分かりやすいです。
「なぜ、振替加算の制度ができたのか?」
「なぜ、振替加算の額は生年月日によって変わるのか?」 等お話ししています。
また、5月27日以降、4回に分けて振替加算問題も解いていきます。
【今後のスケジュール】
5月27日<1回目> 振替加算が加算される要件
5月28日<2回目> 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
5月29日<3回目> 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
5月30日<4回目> 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたときの振替加算
また、5月31日は、老齢厚生年金と障害厚生年金に加算される「配偶者加給年金額」もみていきます。
YouTubeはこちらから
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-270 05.25
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年5月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年5月19日から5月24日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・3号分割制度についてお話しします(厚生年金保険法)
・ 厚生年金保険の給付制限事由(厚生年金保険法)
・ 特定元方事業者の統括安全衛生責任者(労働安全衛生法)
・ 「遺族補償年金」の失権事由(労災保険法)
・ 基本手当の受給資格の決定(雇用保険法)
・ 健康保険の強制適用事業所と任意適用事業所(健康保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「適用事業所」
R7-269 05.24
健康保険の強制適用事業所と任意適用事業所
健康保険は、個人ごとではなく事業所ごとに適用されます。健康保険に加入している事業所のことを適用事業所といいます。
法律上強制的に加入する事業所を「強制適用事業所」、任意に認可を受けて加入した事業所のことを「任意適用事業所」といいます。
条文を読んでみましょう。
法第3条第3項 「強制適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 (1) 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人経営) イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 (2) 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(=常時従業員が1人でもいれば強制適用事業) |
<強制適用事業所になるもの>
| 17業種 | サービス業・農業・漁業等 | |
| 5人以上 | 5人未満 |
|
個人経営 | 強制 | (任意) | (任意) |
法 人 | 1人でもいれば強制 | ||
次に、任意適用事業所について条文を読んでみましょう
法第31条 ① 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
法第33条 ① 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 ② 脱退の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
擬制的任意適用事業について条文を読んでみましょう
法第32条 強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所について任意加入の認可があったものとみなす。(=擬制的任意適用事業) |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
法人の事業所は、常時1人でも従業員を使用する場合は強制適用事業所となります。
また、法人の代表者でも、法人から「労務の対償」として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
そのため、代表者が1人の法人の事業所でも、強制適用事業所となります。
②【H23年出題】
常時10人以上の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人以上の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。

【解答】
②【H23年出題】 〇
飲食業は法定17業種以外の業種ですので、個人経営の場合は、人数に関係なく強制適用事業所となりません。
また、法人の場合は、常時1人でも従業員を使用していれば、業種関係なく、強制適用事業所となります。
③【R5年出題】
令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
外国法事務弁護士は対象となります。
なお、対象になるのは、弁護士、公認会計士その他政令で定める者ですが、政令で定めるものは以下の通りです。
・ 公証人
・ 司法書士
・ 土地家屋調査士
・ 行政書士
・ 海事代理士
・ 税理士
・ 社会保険労務士
・ 沖縄弁護士
・ 外国法事務弁護士
(令第1条)
④【R2年出題】
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

【解答】
④【R2年出題】 ×
任意適用事業所で被保険者の4分の3以上の申出があった場合でも、事業主は適用事業所でなくするための認可の申請をする義務はありません。
⑤【R5年出題】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、「任意加入の認可があったものとみなす」とされていますので、事業主は認可の申請をする必要はありません。自動的に健康保険の適用が継続されます。
YouTubeはこちらです
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「受給資格の決定」
R7-268 05.23
基本手当の受給資格の決定
基本手当は受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。
条文を読んでみましょう。
法第15条第1項、第2項 (失業の認定) ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
則第19条 (受給資格の決定) ① 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて又は個人番号カードを提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあっては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を提出しなければならない。この場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するとき、又は受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。 ③ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、基本手当の受給資格の規定に該当すると認めたときは、失業の認定日を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示した者であって、「受給資格通知」の交付を希望するものにあっては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。 ④ 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第13条第1項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が2枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
2枚以上の離職票を保管するときは、すべての離職票を提出しなければなりません。
②【R6年出題】
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合、管轄公共職業安定所に対し離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 〇
離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合は、離職票及び離職の理由を証明することができる書類を提出しなければなりません。
③【R6年出題】
公共職業安定所長は、離職票を提出した者が雇用保険法第13条第1項所定の被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければならない。

【解答】
③【R6年出題】 〇
公共職業安定所長は、離職票を提出した者が被保険者期間の要件を満たさないと認めたときは、離職票にその旨を記載して返付しなければなりません。
④【R2年出題】
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。

【解答】
④【R2年出題】 ×
内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については、労働の意思を有するものとして扱うことはできないとされています。
自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念しているものと取り扱われます。
(行政手引50102)
⑤【R2年出題】
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
求職条件として短時間就労のみを希望する者については、雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有するものとして扱うこととされています。
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者は、労働の意思を有する者とは扱われません。
(行政手引50102)
⑥【R2年出題】
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。

【解答】
⑥【R2年出題】 ×
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから、代理人による失業の認定はできないとされています。
(行政手引51252)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「遺族補償年金」
R7-267 05.22
労災「遺族補償年金」の失権事由
遺族補償年金の失権事由をみていきましょう。
ちなみに、遺族補償年金には、「転給」の制度があります。
例えば、労働者が死亡し、要件を満たす妻と子がいる場合は、妻と子が受給資格者となります。受給資格者内の順位は①妻、②子で、遺族補償年金を受ける受給権者は、最先順位者の妻となります。
その後、妻が失権した場合、次順位者の子が受給権者となります。
では、失権について条文を読んでみましょう。
法第16条の4 ① 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。(=養子縁組の解消) (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 ② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 |
「妻」以外は、労働者の死亡当時、「年齢」要件か「障害」要件を満たしている必要があります。
例えば、年齢要件のみで受給資格者となった子の場合は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。
また、子が労働者の死亡の当時から引き続き障害状態にあり、「障害」要件を満たしている場合は、年齢は関係ありません。
障害状態でなくなった場合は失権しますが、障害状態でなくなっても年齢要件を満たしている場合(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき)は失権しません。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利は、婚姻したときは消滅します。婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、消滅します。
②【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。

【解答】
②【H23年出題】 ×
遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族である者の養子」となったときは、消滅しません。
③【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】
③【H28年出題】 〇
自分の伯父は傍系血族です。遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったときは消滅しますので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
④【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

【解答】
④【H23年出題】 ×
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。
⑤【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
障害の状態にあった祖父母がその障害の状態がなくなったときでも、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合(年齢要件を満たしている場合)は、消滅しません。
⑥【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】
⑥【H23年出題】 ×
障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき(年齢要件を満たしているとき)は、消滅しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法「統括安全衛生責任者」
R7-266 05.21
特定元方事業者の統括安全衛生責任者
統括安全衛生責任者の選任や職務についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条 ① 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業・造船業に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「特定元方事業者」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下 「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。 ② 統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。 ⑤ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、統括安全衛生責任者の業務の執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に勧告することができる。 |
統括安全衛生責任者の選任が必要な規模
原 則 | 常時50人以上の労働者 |
ずい道等の建設の仕事 |
常時30人以上の労働者 |
圧気工法による作業を行う仕事 | |
一定の橋梁の建設の仕事 |
※労働者の人数は、特定元方事業者の労働者+関係請負人の労働者です。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。

【解答】
①【H20年出題】 ×
特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
(令第7条)
②【H22年出題】
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。

【解答】
②【H22年出題】 〇
統括安全衛生責任者の職務は、「元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。」と規定されています。
第30条第1項各号について条文を読んでみましょう。
第30条第1項 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 (1) 協議組織の設置及び運営を行うこと。 (2) 作業間の連絡及び調整を行うこと。 (3) 作業場所を巡視すること。 (4)~(6) 省略 |
③【H20年出題】
労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。

【解答】
③【H20年出題】 ×
統括安全衛生責任者は、「当該作業場所を巡視することに関する措置」を講ずる必要があります。
④【R4年出題】
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。
甲社 鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時5人
乙①社 甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時10人
乙②社 甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時10人
丙①社 乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時14人
丙②社 乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時14人
A 甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
B 甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
C 甲社は、当該建設工事の請負契約を締結している事業場に、当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
D 甲社は、労働災害を防止するために協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には自社が請負契約を交わした乙①社及び乙②社のみならず丙①社及び丙②社も参加する組織としなければならない。
E 甲社は、丙②社の労働者のみが使用するために丙②社が設置している足場であっても、その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

【解答】
<誤> C
<A> 〇
元方事業者の労働者+関係請負人の労働者=53人ですので、甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
<B> 〇
「統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業に属する事業を行うものは、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない」とされています。
甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。
※なお、「造船業」は、元方安全衛生管理者を選任する義務はありません。
<C> ×
「店社安全衛生管理者」は、統括安全衛生責任者の選任が義務付けられている現場では、選任する必要はありません。
(法第15条の3)
<D> 〇
「協議組織」は、「特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する」ものでなければなりません。自社が請負契約を交わした乙①社及び乙②社のみならず丙①社及び丙②社も参加する組織としなければなりません。
(則第635条)
<E> 〇
法第29条で「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」と規定されています。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「保険給付の制限」
R7-265 05.20
厚生年金保険の給付制限事由
厚生年金保険法の保険給付が制限される条件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第73条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第73条の2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第74条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第75条 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について届出若しくは確認の請求又は訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。(=保険給付が行われる。)
第76条 ① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3)前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
※第96条 (受給権者に関する調査) 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。 ※第97条 (診断) 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
第78条 ① 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 ② 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。 |
※「一時差し止めることができる」について
「支給停止」との違いに注意しましょう。
「支給停止」は停止事由がなくなれば、その翌月から支給が再開されますが、停止された期間分の保険給付は支払われません。
「一時差し止める」は、受給権者から届出等が行われれば、差し止められた分の保険給付が遡って支払われます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
・「故意に」 → 支給しない。
・「自己の故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」 → 保険給付の全部又は一部を行なわないことができる
②【H29年出題】
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき
→ 実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
③【R2年出題】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

【解答】
③【R2年出題】 〇
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
④【H27年出題】
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。

【解答】
④【H27年出題】 〇
・ 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われません。
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付が行われます。
⑤【H27年出題】※改正による修正あり
第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を「一時差し止めることができる」です。支給を停止するではありませんので注意しましょう。
⑥【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)が、加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります。
YouTubeはこちらです
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「離婚分割」
R7-264 05.19
3号分割についてお話しします
★3号分割制度のポイントをYouTubeでお話ししています。
・平成20年4月1日施行
・特定被保険者(第2号被保険者)と被扶養配偶者(第3号被保険者)の分割
・分割の割合は2分の1
・第2号被保険者の同意は不要
YouTubeはこちらです
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-263 05.18
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年5月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年5月12日から5月17日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 遺族年金の子の支給停止の違いをお話しします(国民年金法・厚生年金保険法)
・ 障害基礎年金との併合に基づく障害厚生年金の額の改定(厚生年金保険法)
・ 退職時改定(厚生年金保険法)
・ 厚生年金保険の被保険者期間の計算(厚生年金保険法)
・ 離婚分割「合意分割制度」基本編(厚生年金保険法)
・ 離婚時みなし被保険者期間の扱い(厚生年金保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「離婚分割」
R7-262 05.17
離婚時みなし被保険者期間の扱い
「離婚時みなし被保険者期間」についてみていきます。
「離婚時みなし被保険者期間」の定義を条文で読んでみましょう。
第78条の6第3項 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。 =離婚時みなし被保険者期間という。 |
★離婚時みなし被保険者期間を図でイメージしましょう
※3号分割の「被扶養配偶者みなし被保険者期間」も同じ考え方です。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「1年以上の被保険者期間を有すること」です。この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含みません。
(法附則第17条の10)
②【H27年出題】
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

【解答】
②【H27年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「1年以上の被保険者期間を有すること」ですが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含みません。
そのため、厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(法附則第17条の10)
③【H29年出題】
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の額の計算には算入されますが、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算には入りません。
(法附則第17条の10)
④【R3年出題】
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるための「被保険者期間の月数が240以上」の当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
(法第78条の11)
⑤【H28年出題】※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものに限る。)を取得した後に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
遺族厚生年金は、「被保険者又は被保険者であった者」が要件に該当した場合に、遺族に支給されます。
「被保険者であった者」については、「長期要件に該当する場合にあっては、「離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。」とされています。
そのため、厚生年金保険の被保険者であったことがなかった者でも、「離婚時みなし被保険者期間を有する」に至り、長期要件を満たしている場合は、遺族厚生年金が支給されます。
(法第78条の11)
⑥【H19年出題】
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。

【解答】
⑥【H19年出題】 〇
⑤の問題と同じ趣旨です。
⑦【H29年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定された場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が合意分割により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定されます。
ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。
(法第78条の10第2項)
⑧【国年H27年出題】(国民年金法の問題です)
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
⑧【国年H27年出題】(国民年金法の問題です) 〇
妻が、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金の受給権者である場合は、振替加算は行われません。
この被保険者期間の計算には、離婚時みなし被保険者期間が含まれます。
そのため、合意分割によって、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算は行われなくなります。
(昭60法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
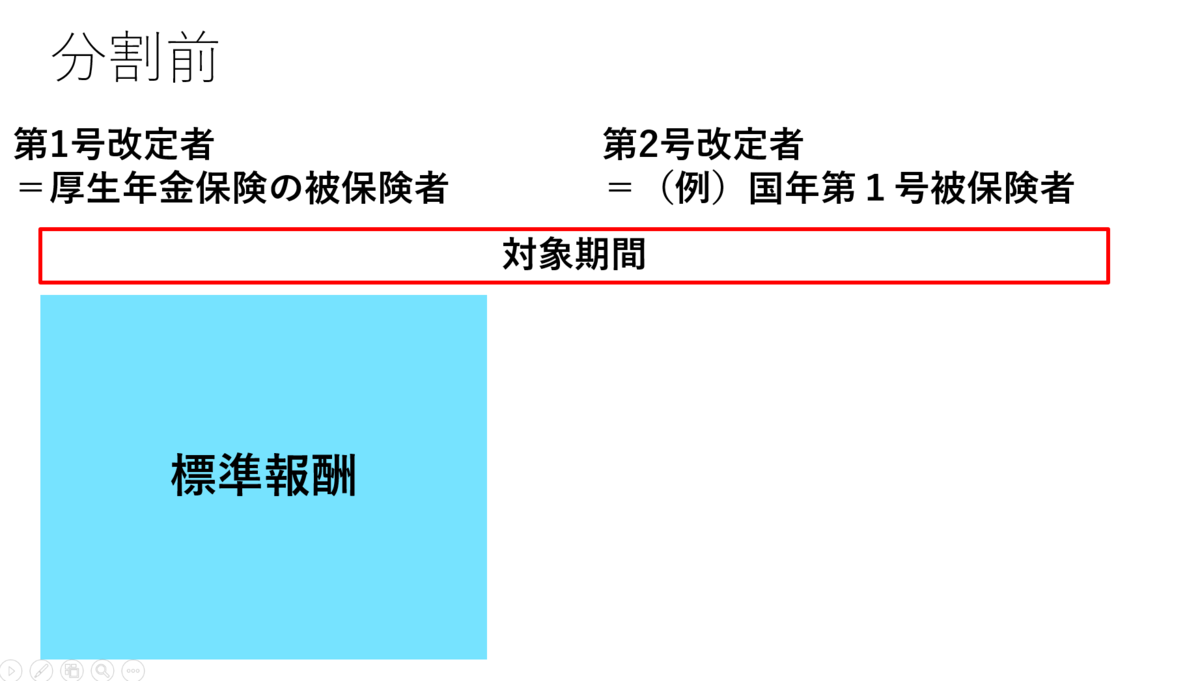
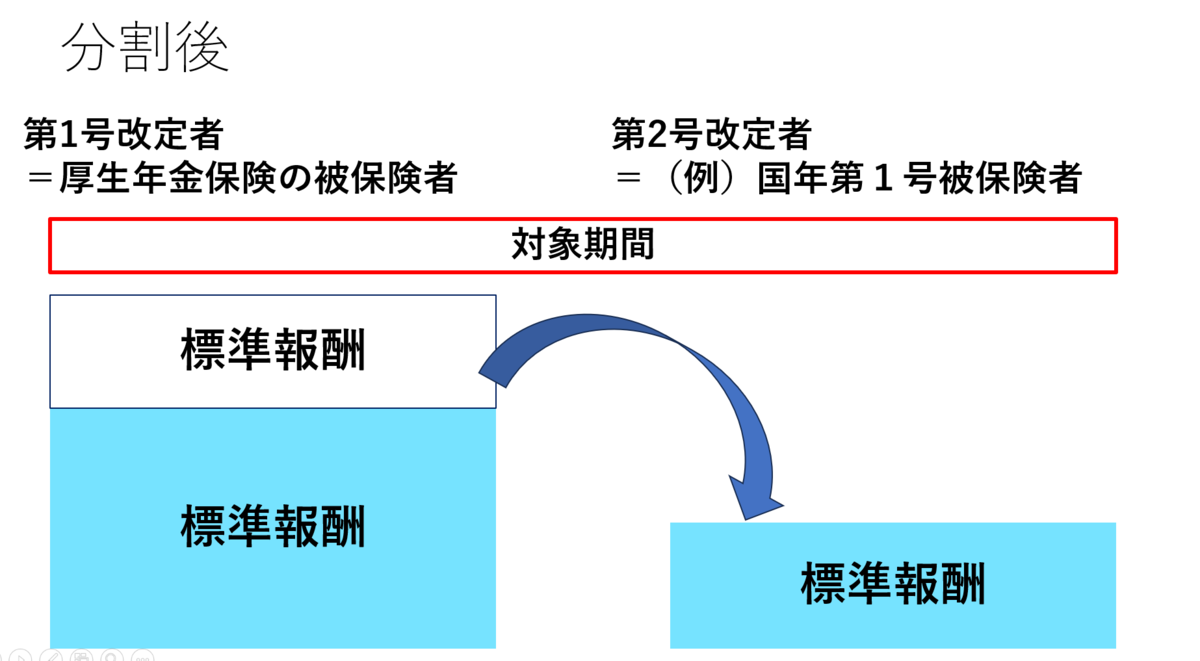
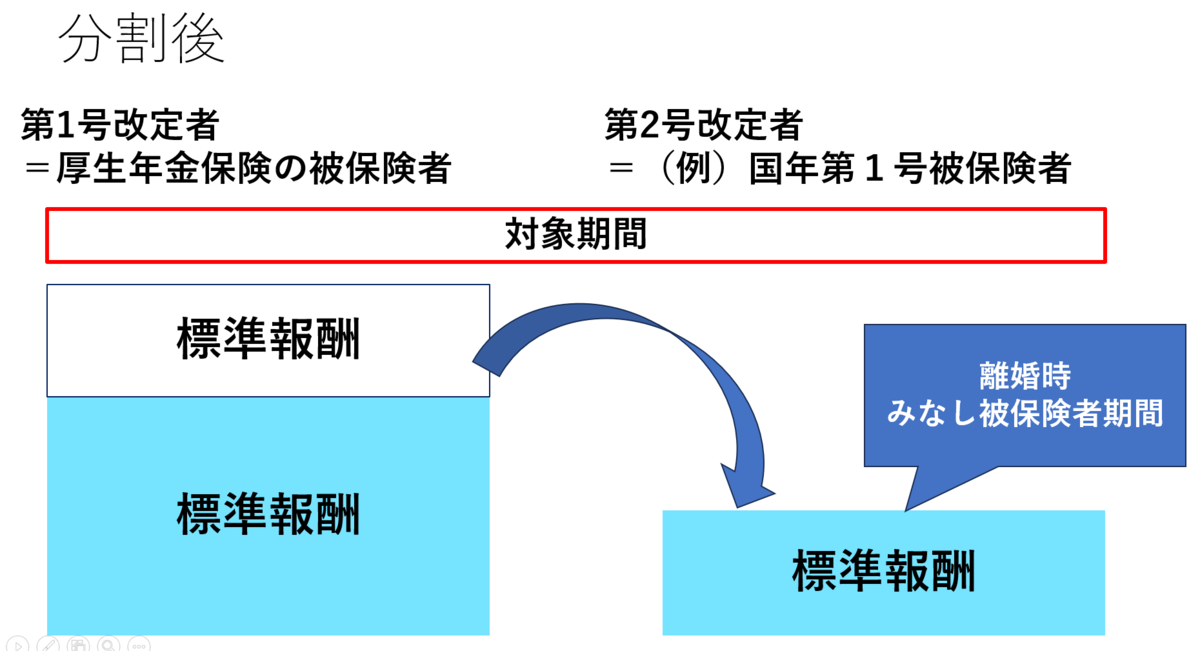
厚生年金保険法「離婚分割」
R7-261 05.16
離婚分割「合意分割制度」基本編
離婚分割には、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
今回は、「合意分割制度」をみていきます。
合意分割制度は、当事者が合意または裁判手続きにより按分割合を定め、婚姻期間中の「標準報酬月額・標準賞与額」を分割する制度です。
条文を読んでみましょう。
第78条の2 ① 第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。=標準報酬が多い方・分割する方)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。=標準報酬が少ない方・分割を受ける方)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (1) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。)について合意しているとき。 (2) 家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ② 標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 ③ 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
第78条の3 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「 按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して、標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。

【解答】
①【H21年出題】 〇
合意分割制度は、平成19年4月1日に施行されました。平成19年4月1日以後に離婚等をしたことが条件ですが、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も分割の対象です。
②【H29年選択式】
厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日< A >を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。
また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、< B >の範囲内でそれぞれ定められなければならない。
(選択肢)
① 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
② 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
④ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
⑤ から起算して6か月 ⑥ から起算して3か月
⑦ の翌日から起算して6か月 ⑧ の翌日から起算して3か月

【解答】
②【H29年選択式】
<A> ⑦ の翌日から起算して6か月
<B> ③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
(法第78条の3第1項)
按分割合とは?
「第1号改定者・第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額」に対する「第2号改定者」の持分です。
按分割合の上限は50%です。
<分割前>
第1号改定者(80%) | 第2号改定者(20%) |
按分割合は、20%を超え50%以下の範囲内で定めなければなりません。
按分割合を「50%」にした場合
↓
<分割後>
第1号改定者(50%) | 第2号改定者(50%) |
③【R2年選択式】
厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき< A >について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから< B >を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
(選択肢)
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 6か月
⑤ 按分割合 ⑥ 改定額 ⑦ 改定請求額 ⑧ 改定割合

【解答】
③【R2年選択式】
<A> ⑤ 按分割合
<B> ② 2年
④【H29年出題】
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求は、離婚等をしたときから「2年」を経過したときは、行うことができません。
(第78条の2、第78条の4)
⑤【H27年出題】
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができるのは、「家庭裁判所」です。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(第78条の2第2項)
⑥【H29年出題】
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

【解答】
⑥【H29年出題】 〇
「1か月以内」がポイントです。
(第78条の2、令3条の12の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「被保険者期間」
R7-260 05.15
厚生年金保険「被保険者期間の計算」
「被保険者期間」の計算ルールをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第19条 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 ④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 ⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。 |
ポイント!
<同月得喪(資格を取得した月にその資格を喪失した)の場合>
★(原則)被保険者期間は「1か月」で計算します。
★その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
例えば、5月1日にA社で資格を取得し同月15日に退職。同月16日にB社で資格を取得した場合
↓
B社の資格のみで、被保険者期間を1か月と計算します。
★その月に更に国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く。)の資格を取得したとき
例えば、5月1日にC社で資格を取得し同月15日に退職。その後国民年金第1号被保険者になった場合
↓
厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。5月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付します。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

①【H21年出題】 ×
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間は「被保険者であった期間」です。
②【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
②【R5年出題】 〇
被保険者期間は、「月」単位で計算します。
③【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
③【H30年出題】 〇
被保険者期間には、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。
平成30年3月30日に資格喪失した場合、資格を喪失した月である平成30年3月は被保険者期間に算入されません。
④【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
ただし、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
問題文の場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。
⑤【R6年出題】
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
令和6年5月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。
令和6年5月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。
⑥【H20年出題】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。

【解答】
⑥【H20年出題】 〇
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった場合(=平成20年6月1日に資格喪失)、被保険者期間に算入されるのは、4月(資格を取得した月)と5月(資格を喪失した月の前月)です。
⑦【R3年出題】
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
⑦【R3年出題】 〇
・同一の月において被保険者の種別に変更があったとき
→その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす
・同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき
→最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「老齢厚生年金」
R7-259 05.14
老齢厚生年金「退職時改定」
働きながら(働く=厚生年金保険の被保険者という意味です。厚生年金保険料を負担していることです)受給する老齢厚生年金は、在職老齢年金といわれます。
厚生年金保険の被保険者でかつ老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の資格を喪失すると、負担した保険料を年金額に反映させるため、年金額の再計算が行われます。
このことを退職時改定といいます。
退職時改定について、条文を読んでみましょう。
第43条第3項 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 なお、第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 第14条第2号~第4号 (2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。(退職したとき) (3) 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があつたとき。 (4) 適用除外に該当するに至ったとき。 |
(例)5月31日に退職した場合(6月1日資格喪失)
「退職した日」から起算して1月を経過した日の属する月=6月から年金額が改定されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】※改正による修正あり
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
<問題文のチェックポイント>
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
②【R5年出題】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

【解答】
②【R5年出題】 ×
老齢厚生年金の額の計算の基礎とされるのは、その被保険者の資格を喪失した月「以前」ではなく「前」における被保険者であった期間です。
被保険者期間は、「資格を喪失した月の前月」までで、資格を喪失した月は保険料が徴収されないからです。
また、年金の額が改定されるのは、「資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から」ですが、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき等は、その日から起算して1か月を経過した日の属する月から」です。
③【H28年出題】
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【解答】
③【H28年出題】 ×
年金の額が改定されるのは、「資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から」ですが、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき等は、その日から起算して1か月を経過した日の属する月から」です。
問題文は、1月31日付けで退職していますので、「1月31日」から起算して1か月を経過した日の属する月(=2月)から改定されます。
④【R2年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

【解答】
④【R2年出題】 ×
昭和25年7月1日生まれの者が70歳に到達するのは、「令和2年6月30日」で、その日に資格を喪失します。
年金額は、令和2年6月30日(資格を喪失した日)から起算して1か月を経過した日の属する月から改定されます。令和2年8月分ではなく「令和2年7月」から年金の額が改定されます。
⑤【H30年出題】
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
老齢厚生年金は65歳に達する前に、繰上げて受給することができます。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者で、繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、老齢厚生年金の額が再計算されます。
具体的には、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算に算入し、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額が改定されます。
(法附則第7条の3第5項)
⑥【H28年出題】
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
障害厚生年金には、退職時改定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害厚生年金」
R7-258 05.13
障害基礎年金との併合に基づく障害厚生年金の額の改定
1級又は2級の障害厚生年金の受給権者に、新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
図でイメージしましょう
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この場合において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。

【解答】
①【R5年出題】 〇
併合によって1級の障害基礎年金の受給権が発生した場合は、それに合わせて、障害厚生年金の額も1級に改定されます。
②【H27年出題】
障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。

【解答】
②【H27年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第52条の2第2項 障害厚生年金の受給権者(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項(その他障害による額の改定)及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
図でイメージしましょう。
・ 障害等級2級の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になった
↓
・第1号被保険者期間中に初診日がある傷病によって障害基礎年金とその他障害との併合が行われた
↓
・併合により障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された
↓
それに合わせて、障害厚生年金も障害等級1級の額に改定される
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
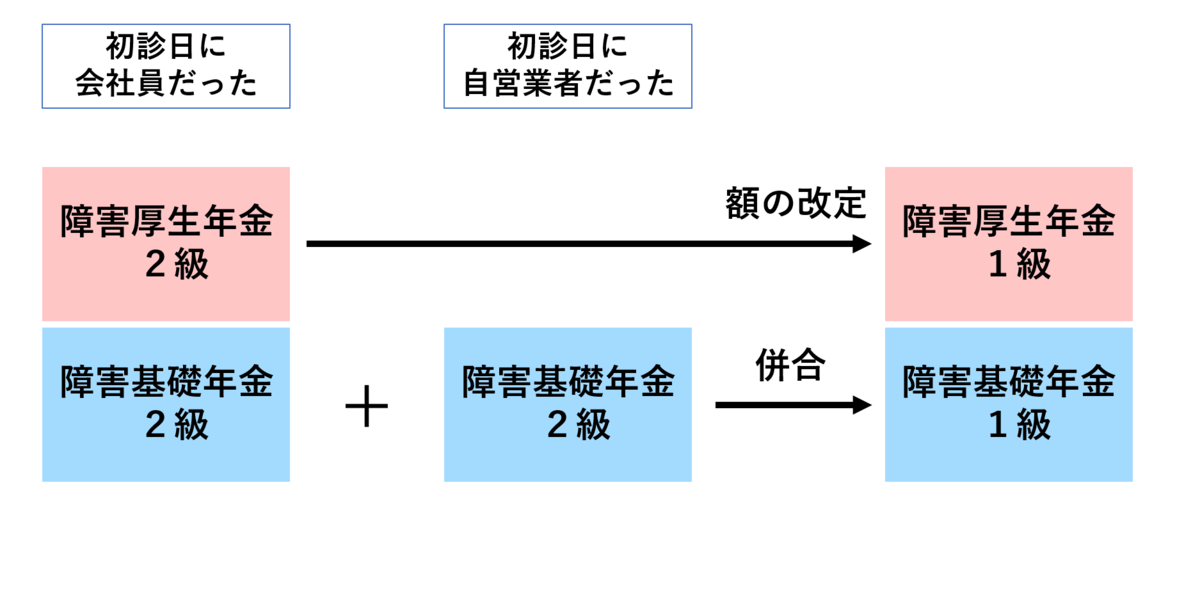
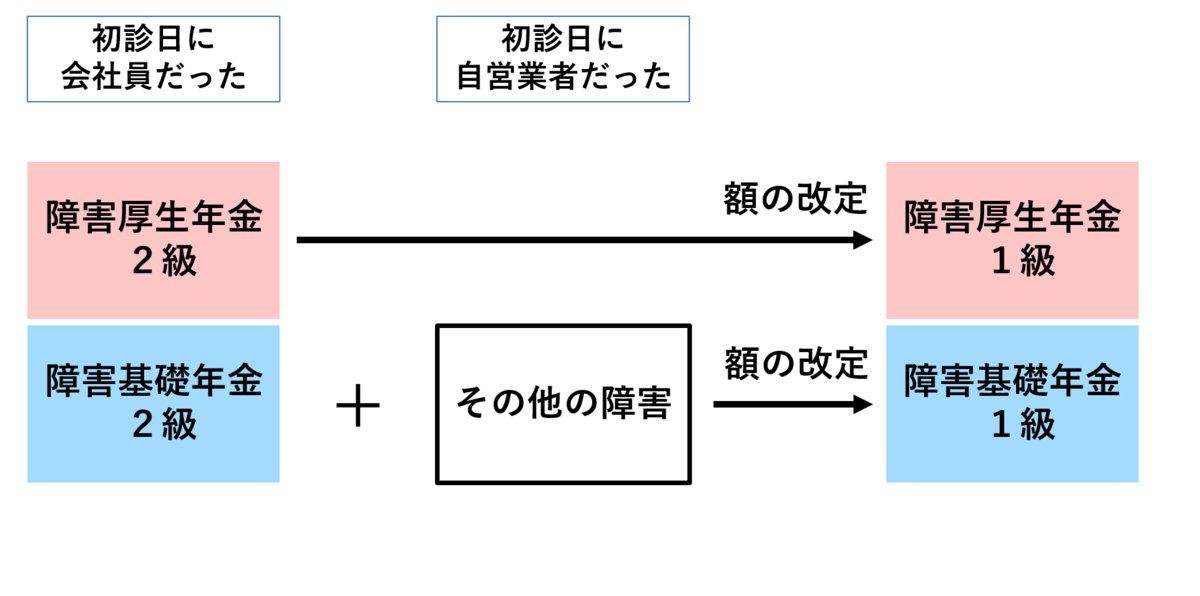
<比較>遺族基礎年金と遺族厚生年金
R7-257 05.12
【国年と厚年を比較】遺族年金の子の支給停止の違いをお話しします
遺族基礎年金と遺族厚生年金の「子」の支給停止の扱いについてお話しします。
<共通事項>
・配偶者が遺族基礎(厚生)年金の受給権を有する場合、子の年金はどうなる?
<例外>
・配偶者の年金が申し出により支給停止になった場合
・生計を同じくするその子の父・母がある場合
<応用>
・配偶者に遺族基礎年金の受給権がない場合
などお話しします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-256 05.11
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年5月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年5月5日から5月10日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・申請免除についてお話しします(国民年金法)
・未支給の失業等給付の請求(雇用保険法)
・労働保険事務組合の責任など(労働保険徴収法)
・第3号被保険者の取得・喪失・種別変更の届出(国民年金法)
・第3号被保険者の届出が遅れた場合の特例(国民年金法)
・第3号被保険者「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」
(令和7年5月第1週目)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第3号被保険者届出その3」
R7-255 05.10
第3号被保険者「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」
第3号被保険者に関する届出のうち「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
則第6条の3 (種別確認届) 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。 |
※配偶者である第2号被保険者が転職等により加入する年金制度が変わったときに必要な届出です。
(届出が必要な例)
・民間企業の会社員が転職で国家公務員になった
(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得した)
・地方公務員が民間企業に転職した
(第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した)
など
※届出が要らない場合
・第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき
・実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあっては私学教職員共済制度の加入者をいう。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したとき
第12条の2 (被扶養配偶者でなくなったことの届出) 第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
則第6条の2の2 (被扶養配偶者でなくなったことの届出) 法第12条の2第1項の規定による届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行わなければならない。 |
※届出が必要なとき
・第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた
・離婚した
※届出が要らない場合
・第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった
・第3号被保険者が「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」
・死亡した
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、種別確認の届出が必要です。
②【R4年出題】
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

【解答】
②【R4年出題】 ×
「種別変更」ではなく「種別確認」の届出を日本年金機構に対して行わなければなりません。
③【R2年出題】
第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、被扶養配偶者でなくなった旨の届書の提出は不要です。
④【H27年出題】
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

【解答】
④【H27年出題】 〇
・第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者から第1号被保険者の種別の変更の届出が必要です。
・さらに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければなりません。
※なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者が、その被扶養配偶者であった者について健康保険の被扶養者でなくなったことの届出を事業主を経由して日本年金機構に提出したときは、「被扶養配偶者非該当届」の提出があったものとみなし、被扶養配偶者非該当届の提出は不要とされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第3号被保険者届出その2」
R7-254 05.09
第3号被保険者の届出が遅れた場合の特例
「第3号被保険者」の制度は、昭和61年4月の新法施行時に創設されました。
当初は、第3号被保険者に該当したときは、本人が市町村に直接届出をしなければならなかったので、届出もれが多くみられました。
平成14年4月からは、第2号被保険者が雇用される会社等を通じて、届出を行うようになっています。
今回は、届け出漏れがあった人を救済するための特例をみていきます。
「平成17年4月1日前」と「平成17年4月1日以後」の違いに注意してください。
条文を読んでみましょう。
★平成17年4月1日前 平成16年法附則第21条 ① 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間について、厚生労働大臣に届出をすることができる。 ② 届出が行われたときは、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 |
・「第3号被保険者」に該当していたが、届出をしていなかった場合、2年前以前の期間は、「未納期間」と同じ扱いになります。
↓
・厚生労働大臣に届出をすると、届出を行った日以後、その期間は「保険料納付済期間」として算入されます。
ポイント!
「届出」が遅滞したことの理由は問われません。
★平成17年4月1日以後 法附則第7条の3 第3号被保険者となったことに関する届出又は第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、保険料納付済期間に算入しない。 ② 第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、①の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。 ③ ②の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 |
・第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた
↓
・届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間は保険料納付済期間に算入される
・それ以外は、保険料納付済期間に算入されない
↓
・保険料納付済期間に算入されない期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由がある
↓
・厚生労働大臣にその旨を届け出る
↓
・届出が行われた日以後、保険料納付済期間に算入される
ポイント!
届出の遅滞につき「やむを得ない」事由があること
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

【解答】
①【R4年出題】〇
ポイントを箇条書きで確認します。
・第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったとき
・第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得する
・ただし、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間
・保険料納付済期間に算入されない期間について、届出の遅滞につきやむを得ない事由がある
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
・その場合、届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入される
②【H29年出題】
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

【解答】
②【H29年出題】 〇
・平成26年4月1日に第3号被保険者に該当した
↓
・資格取得の届出が遅れた(平成29年4月13日)
↓
・保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のみ(平成27年3月以降の各月のみ保険料納付済期間に算入される)
↓
・算入されなかった期間について、届出の遅滞につきやむを得ない事由がある
↓
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
↓
・届出が行われた日以後、当該届出に係る期間(保険料納付済期間に算入されなかった平成26年4月から平成27年2月までの期間)が保険料納付済期間に算入される
③【H19年出題】
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

【解答】
③【H19年出題】 〇
厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、保険料納付済期間に算入されます。
④【H22年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。

【解答】
④【H22年出題】 〇
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)については、保険料納付済期間に算入されるのは、原則として、「届出をした日の属する月の前々月までの2年間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第3号被保険者届出その1」
R7-253 05.08
第3号被保険者の取得・喪失・種別変更の届出
「第3号被保険者」の制度は、昭和61年4月の新法施行時に創設されました。
当初は、第3号被保険者に該当したときは、本人が市町村に直接届出をしなければならなかったので、届出もれが多くみられました。
平成14年4月からは、第2号被保険者が雇用される会社等を通じて、届出を行うようになっています。
条文を読んでみましょう。
第12条 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
★届け出について
第1号被保険者 | 市町村長(特別区の区長を含む。) |
第3号被保険者 | 厚生労働大臣 |
(法第12条第1項、第5項)
②【R2年出題】
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
第3号被保険者は、市町村長ではなく「厚生労働大臣」に提出します。
なお、提出先は、「日本年金機構」です。
条文を読んでみましょう。
則第1条の4第2項 第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによつて行わなければならない。 |
③【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。
(則第1条の4第2項)
④【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

【解答】
④【R1年出題】 〇
第3号被保険者
|
→ |
事業主等 |
→ |
厚生労働大臣 |
事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
⑤【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者に係る届出に係る事務の一部を「事業主が設立する健康保険組合」に委託することができます。
なお、全国健康保険協会には委託できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R7-252 05.07
労働保険事務組合の責任など
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料の申告・納付などの労働保険事務を処理します。
今回は、「労働保険事務組合に対する通知」、「労働保険事務組合の責任」、「帳簿の備付け」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第34条 (労働保険事務組合に対する通知等) 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
第35条 (労働保険事務組合の責任等) ① 委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ② 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ③ 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 ④ 労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定(不正受給者からの費用徴収)及び雇用保険法第10条の4第2項(不正受給者に対する返還命令等)の規定の適用については、事業主とみなす。
第36条 (帳簿の備付け) 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 則第68条 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。 (1)労働保険事務等処理委託事業主名簿 (2)労働保険料等徴収及び納付簿 (3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) 〇
委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、法律上当然に、通知の効果が委託事業主に及ぶことになります。
政 府
|
→ 通知等 |
労働保険 事務組合 |
→ 通知の効果が 当然に及ぶ |
委託事業主 |
②【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。

【解答】
②【H25年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合に対してなされた通知等は、法律上当然に、その通知等の効果が委託事業主に及びます。
労働保険事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容には関係ありません。
③【H25年出題】(雇用)
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。

【解答】
③【H25年出題】(雇用) ×
第35条第2項で、「その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」とされています。
問題文の場合は、労働保険事務組合が、延滞金の納付の責任を負います。
④【H29年出題】(雇用)
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

【解答】
④【H29年出題】(雇用) ×
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、「当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる」ではなく、「その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」ものとなります。
労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合は、「その残余の額を当該事業主から徴収することができる」とされています。
金銭を労働保険事務組合に交付したとしても、事業主は、全責任を免れるわけではありません。
⑤【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

【解答】
⑤【R5年出題】(労災) ×
第35条第2項で、「その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」とされています。
問題文の場合は、労働保険事務組合は政府に対して追徴金の納付責任を負います。
⑥【R3年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。

【解答】
⑥【R3年出題】(雇用) 〇
労働保険事務組合が備えなければならない帳簿をおぼえましょう。
(1)労働保険事務等処理委託事業主名簿
(2)労働保険料等徴収及び納付簿
(3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
⑦【H28年出題】(雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】
⑦【H28年出題】(雇用) 〇
労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類は、その完結の日から3年間保存しなければなりません。ただし、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」は4年間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「未支給の失業等給付」
R7-251 05.06
未支給の失業等給付の請求
「未支給の失業等給付」について条文を読んでみましょう。
第10条の3 (未支給の失業等給付) ① 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。 ② 未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。

【解答】
①【R3年出題】 〇
未支給の失業等給付を受けるべき者の順位は、「配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。死亡した受給資格者に配偶者も子もいないときは、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母が未支給の失業等給付を請求することができます。
②【R3年出題】
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。

【解答】
②【R3年出題】 ×
未支給の失業等給付は、「死亡した者の名」ではなく「自己の名」で請求します。
③【R3年出題】
正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。

【解答】
③【R3年出題】 ×
未支給の失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給されます。
そのため、本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されません。
問題文の、「正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間」については、受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができませんので、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当は支給されません。
(行政手引53103)
④【R3年出題】
死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
未支給失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給されます。
(行政手引53103)
⑤【R3年出題】
受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
当該受給資格者の死亡の翌日から起算して「3か月」ではなく「6か月」以内に請求しなければなりません。
(則第17条の2第1項)
⑥【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

【解答】
⑥【H28年出題】 〇
「未支給失業等給付にかかるもの」及び「公共職業能力開発施設に入校中の場合」は、代理人による失業の認定が認められています。
(則第17条の2第4項、則第27条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法(申請免除)
R7-250 05.05
申請免除についてお話しします
申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)についてみていきます。
・対象になる人 (ポイントは所得要件など)
・対象になる期間
→ 最大で2年2月前までさかのぼります。(通常は2年1月前です)
・前年の所得で判断されますが、1月から6月分は前々年の所得で判断されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-249 05.04
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年4月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月28日から5月3日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 1か月単位の変形労働時間制についてお話しします(労働基準法)
・ 全額払いの原則と端数処理(労働基準法)
・ 就業規則作成の手続(労働基準法)
・ 「労働者の過半数を代表する者」とは(労働基準法)
・ 「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入(労働基準法)
・ 休業補償給付の額(労災保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「休業補償給付」
R7-248 05.03
休業補償給付の支給額
さっそく「休業補償給付」について条文を読んでみましょう。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |
<部分算定日の例をみてみましょう>
午 前 | 午 後 |
通院のため休業 | 勤 務 |
給付基礎日額 → 12,000円
午後の労働に対する賃金 → 5,000円
休業補償給付の額
=(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×100分の60
=(12,000円-5,000円)×100分の60
=4,200円
※複数事業労働者が、一方の事業場で休業し、他方の事業場で年次有給休暇を取得した場合なども部分算定日に該当します。
<部分算定日の休業補償給付のポイント!>
・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)×100分の60
★「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合
→ (最高限度額を適用しない給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)×100分の60
★控除して得た額が最高限度額を超える場合
→ 最高限度額×100分の60
過去問をどうぞ!
①【R5年選択式】
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。
(選択肢)
① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失
⑪ 療養

【解答】
①【R5年選択式】
<A> ⑪ 療養
<B> ⑦ 4
<C> ② 100分の60
②【H30年出題】※改正による修正あり
業務上の傷病により、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

②【H30年出題】 〇
「療養開始後1年6か月」とは
→ 療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後は、「年齢階層別の最高限度額」が適用されます。
療養開始後1年6か月未満の場合は、「年齢階層別の最高限度額」は適用されませんので、「休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60」に相当する額となります。
③【R2年出題】
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

【解答】
③【R2年出題】 ×
例えば、給付基礎日額が10,000円、所定労働時間の労働した時間に対して支払われる賃金が給付基礎日額の20%(2,000円)の場合で考えてみましょう。
休業補償給付=(10,000円−2,000円)×100分の60=4,800円
休業特別支給金=(10,000円−2,000円)×100分の20=1,600円
休業補償給付と休業特別支給金とを合わせても、給付基礎日額の100%にはなりません。
④【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
④【H30年出題】 〇
休業補償給付は、「賃金を受けない日」について支給されます。
「賃金を受けない日」は、以下のような日をいいます。
全部労働不能の場合 | 平均賃金の60%未満の金額しか受けない日 |
一部労働不能の場合 | ・労働不能の時間について全く賃金を受けない日 ・「平均賃金と実労働時間に対する賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日 |
問題文は、「全部労働不能」で休業中に「平均賃金の6割以上」の金額が支払われているので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため、休業補償給付は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「1週間単位の非定型的労働時間制」
R7-247 05.02
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入
「労使協定」の締結によって、1週間単位で労働時間を弾力的に設定することができる制度です。
対象になるのは、規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業に限られます。
条文を読んでみましょう。
第32条の5 ① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、1日について10時間まで労働させることができる。 ② 使用者は、1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
則第12条の5 ① 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。 ② 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。 ③ 法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。 |
※1週間単位の非定型的変形労働時間制には、「1週間44時間」の特例は適用されません。
そのため、1週40時間・1日10時間以内で設定しなければなりません。
(則第25条の2)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
いわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、「小売業、旅館、料理店若しくは飲食店」の事業で、「常時使用する労働者の数が30人未満」の事業場です。
「いずれか1つに該当する事業場」ではなく事業の種類と労働者数の両方に該当しなければなりません。
②【H22年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限は「10時間」と定められています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「過半数代表者」
R7-246 05.01
労働基準法の「労働者の過半数を代表する者」とは
労働者の過半数を代表する者とは、当該事業場のすべての労働者の過半数を超える者によって代表者とされた者です。
「労使協定」などの際に登場します。
例えば、第36条の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」が協定当事者となります。
「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合とは、「そもそも労働組合がない」又は「労働組合があっても当該事業場の労働者の過半数で組織されていない」場合です。
では、過半数代表者の条件について条文を読んでみましょう。
則第6条の2 ① 労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 (2) 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 |
では過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」が誤りです。
「投票、挙手等の方法による手続」としては、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当します。
(平11.3.31基発169号)
②【R5年出題】
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」という要件も満たさなければなりません。
③【H25年出題】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトは含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

【解答】
③【H25年出題】 〇
労働基準法第36条の協定は、当該事業において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものです。
そのため、労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトも含まれます。
なお、派遣労働者は、「派遣元」の人数に含まれます。
(平11.3.31基発168号)
④【H13年出題】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

【解答】
④【H13年出題】 ×
「第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者」も労働基準法の「労働者」です。そのため、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者も含まれます。
なお、「第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者」は、「労働者の過半数を代表する者」にはなれません。
⑤【H23年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
いわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者でない場合は、当該協定は有効とは認められないとするのが最高裁判所の判例です。その場合、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務はありません。
(最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決)
⑥【H19年出題】
使用者は、労働者が労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【解答】
⑥【H19年出題】 〇
過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならないこととしたものです。
「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれます。
(平11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「就業規則」
R7-245 04.30
就業規則作成の手続
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。変更した場合も、同様に、行政官庁に届け出なければなりません。
今回は、就業規則作成・変更の際の手続をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

【解答】
①【H20年出題】 ×
「同意を得なければならない」ではなく「意見を聴かなければならない」です。
同意を得ることまで義務付けられていません。意見を聴けば労働基準法違反になりません。
②【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

【解答】
②【H21年出題】 〇
就業規則の作成だけでなく、その変更についても、意見を聴かなければなりません。
③【H26年出題】
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
就業規則の作成又は変更については、協議をすることまで使用者に要求していません。
(昭25.3.15基収525号)
④【R3年出題】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

【解答】
④【R3年出題】 ×
同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えありません。
ただし、当該一部の労働者に適用される就業規則は、当該事業場の就業規則の一部です。
そのため、その作成または変更については、当該事業場の「全労働者」の過半数で組織する労働組合又は「全労働者」の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数ではありません。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【H30年出題】
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則のみ行えば足りる。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるのではなく、パートタイム労働者についての就業規則は、就業規則の本則の一部となります。
そのため、当該事業場の「全労働者」の過半数で組織する労働組合又は「全労働者」の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「端数処理」
R7-244 04.29
全額払いの原則と端数処理
賃金は労働の対償ですので、使用者は、労働者にその全額を支払わなければなりません。
ただし、賃金の支払額については、便宜上、端数処理が認められています。
★遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理について
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し、違法とされています。
なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しません。
(昭63.3.14基発150号)
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
①【H19年出題】 ×
1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、「法違反」となります。
★なお、「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められますので、違反になりません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H25年出題】
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、法違反になりませんが、「1日」単位では法違反になります。
後半は、正しいです。以下の処理は、法違反になりません。
「1時間当たり」の賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、上記と同様に処理すること
③【H29年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
③【H29年出題】 〇
1か月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことは、法違反として取り扱わないとされています。
(昭63.3.14基発150号)
④【H24年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
④【H24年出題】 〇
1か月の賃金支払額に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、法違反としては取り扱わないこととされています。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【H27年出題】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
「過払いした賃金を精算・調整するため、後に支払われるべき賃金から控除すること」
↓
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、第24条第1項項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。
この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。」
とされています。
「その金額が少額」であればよいということではありません。
(昭和44年12月18日最高裁第一小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「1か月単位の変形労働時間制」
R7-243 04.28
1か月単位の変形労働時間制についてお話しします
1か月の変形労働時間制の採用についてお話しします
★変形期間の労働時間のトータルが次の計算式の時間の範囲内であること
1週間の法定労働時間×(変形期間の暦日数÷7)
※1週間の法定労働時間は、原則40時間、特例44時間
※変形期間は1か月以内の一定の期間 ★「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」
※「又は」がポイント ※労使協定は届出が必要
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-242 04.27
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年4月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月21日から4月26日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 脱退一時金についてお話しします(国民年金法)
・ 任意継続被保険者の保険料の前納(健康保険法)
・ 特別加入者「一人親方等」について(労災保険法)
・ 特別加入者に対する支給制限(費用徴収との違い)(労災保険法)
・ 時間外、休日、深夜労働の割増率(労働基準法)
・ 割増賃金の1時間当たりの賃金額の算出(労働基準法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「割増賃金の単価」
R7-241 04.26
割増賃金の1時間当たりの賃金額の算出
割増賃金は以下のように計算します。
1時間当たりの賃金額 × 時間外労働の時間数 × 割増率
(休日労働の時間数・深夜労働の時間数)
「1時間あたりの賃金額」の算出について条文を読んでみましょう。
則第19条第1項 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 (1) 時間によって定められた賃金については、その金額 (2) 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 (3) 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 (4) 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 (6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |
基本給以外の「手当」も、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
ただし、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる手当は除外することができます。
条文を読んでみましょう。
則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金) 家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 (1) 別居手当 (2) 子女教育手当 (3) 住宅手当 (4) 臨時に支払われた賃金 (5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数:240日
計算の基礎となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間
(A) 300,000円÷(21×7)
(B) 300,000円÷(21×8)
(C) 300,000円÷(30÷7×40)
(D) 300,000円÷(240×7÷12)
(E) 300,000円÷(365÷7×40÷12)

①【H28年出題】
【解答】
(D) 300,000円÷(240×7÷12)
月給制の場合は、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」は、
「月給」÷月の所定労働時間数
で計算します。
ただし、月によって所定労働時間数が異る場合は、「月給」÷「1か月の平均所定労働時間数」となります。
問題文の場合、年間の所定労働日数が240日で、対象月の所定労働日数が21日です。
月によって所定労働時間数が異なるので、「1か月の平均所定労働時間数」で割ることになります。
1か月の平均所定労働時間数は、240日×7時間÷12か月で計算します。
※7時間=拘束時間8時間(午前9時から午後5時)-休憩1時間です。
②【H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法の第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「通勤手当」は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。
③【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
家族手当でも、「家族数に関係なく」一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎に含めなければなりません。
(昭22.11.5基発231号)
④【H19年出題】
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】
④【H19年出題】 ×
住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、除外される住宅手当には該当しません。
問題文のように、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当しません。そのため、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(平11.3.31基発170号)
⑤【H18年出題】
賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項又は第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足りる。

【解答】
⑤【H18年出題】 〇
賃金が出来高払制その他の請負制の場合は、「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額」÷「総労働時間数」で計算します。
所定労働時間ではなく「総労働時間数」で計算するのがポイントです。総労働時間には、時間外労働時間も含まれます。
⑥【H17年出題】
年間賃金を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。

【解答】
⑥【H17年出題】 〇
年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しません。
そのため、割増賃金の支払いは、「月例給与に賞与部分を含めた年俸額」を基礎として支払わなければなりません。
(平12.3.8基収78号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「割増賃金」
R7-240 04.25
時間外、休日、深夜労働の割増率
時間外労働、休日労働、深夜労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
今回は、「割増率」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第37条第1項、第4項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) ① 使用者が、第33条(災害等による臨時の必要がある場合)又は第36条第1項の規定(36協定)により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金率(第37条、時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)
・深夜労働と時間外又は休日労働が重なる場合 則第20条 ① 時間外労働が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合は、 5割以上(その時間の労働のうち、1か月について60時間を超える時間外労働に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ② 休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合は、6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、休日労働のみの割増率(3割5分増)となります。時間外労働の割増率は合算する必要はありません。
(H11.3.31基発168号)
②【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間
<A> 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】
<A> ×
日曜の10時間の労働については、深夜業に該当しなければ、時間外労働の割増率は加算する必要はありません。8時間を超えた2時間も含めて、休日労働に対する割増率のみで構いません。
(H11.3.31基発168号)
<B> 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】
<B> ×
「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。
そのため、問題文の場合、休日割増賃金の対象になるのは、日曜日の午後12時までです。月曜の午前0時以降は、休日割増賃金を支払う義務はありません。
(H6.5.31基発331号)
0時 | |
日曜(法定休日) 休日割増 | 月曜(平日) |
<C> 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】
<C> 〇
時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合は、「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない」とされています。
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、日付が変わっても月曜の超過勤務時間となります。
<D> 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】
<D> ×
「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前0時以降は休日労働の割増賃金で計算しなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
<E> 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

【解答】
<E> ×
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
| 2時間 | 2時間 |
4時間 |
|
8時間 |
8時間 | ||||||
6時間 |
6時間 |
6時間
|
6時間 |
木曜 → 時間外労働2時間(8時間を超えた分)
金曜 → 時間外労働2時間(8時間を超えた分)
土曜 → 時間外労働4時間(週の通算労働時間が44時間(木・金のそれぞれ2時間の時間外は除きます)となるので、40時間を超えた分)
③【H23年出題】
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

【解答】
③【H23年出題】〇
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ない時間外又は休日労働は違法です。
ただし、法定労働時間を超えた場合、又は休日労働させた場合は割増賃金を支払わなければならないため、違法な時間外労働・休日労働をさせた場合でも、使用者は、割増賃金の支払義務は免れません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「支給制限と費用徴収の違い」
R7-239 04.24
特別加入者に対する支給制限
労災保険の特別加入者は次の3種類です。
■中小事業主等
■一人親方その他の自営業者・特定作業従事者
■海外派遣者
特別加入者の「支給制限」について条文を読んでみましょう。
法第34条第1項第4号 中小事業主及びその事業に従事する者の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が中小事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。
法第35条第1項第7号 一人親方その他の自営業者・特定作業従事者の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
法第36条第1項第3号 海外派遣者の事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
ポイント!
「労働者」との違いに注意しましょう。
★労働者の場合
事業主が一般保険料(=労働者の保険料)を納付しない期間中に生じた事故については、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を「事業主から徴収することができる。」とされています。労働者の保険給付の支給を制限するのではなく、事業主から費用徴収します。
★特別加入者の場合
特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、費用徴収ではなく、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」と支給制限が行われます。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(※問題文修正しています)
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。
ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。
②【H26年出題】(※問題文修正しています)
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。
ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。
③【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
③【R3年出題】 ×
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定され、その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「特別加入者」
R7-238 04.23
特別加入者「一人親方等」について
労災保険には「特別加入」の制度があります。
特別加入には大きく3つの種類があります。
・中小事業主等
・一人親方等、特定作業従事者
・海外派遣者
今回は、「一人親方等、特定作業従事者」についてみていきます。
★一人親方等が労災保険に特別加入する場合は、一人親方等の団体が手続きを行います。
一人親方等 |
↓ |
一人親方等の団体 |
↓ |
所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長経由) |
・一人親方等その他の自営業者とは、「厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者」と「その者が行う事業に従事する者」です。
厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりです。(則第46条の17)
(1) 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) (2) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など) (3) 漁船による水産動植物の採捕の事業((7)に掲げる事業を除く。) (4) 林業の事業 (5) 医薬品の配置販売の事業 (6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業(廃品回収業) (7) 船員法第1条に規定する船員が行う事業 (8) 柔道整復師が行う事業 (9) 高年齢者の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、高年齢者が行う事業 (10) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 (11) 歯科技工士が行う事業 (12) 特定受託事業者が「業務委託事業者」から業務委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの(特定フリーランス事業) |
ポイント!
「特定フリーランス事業」の特別加入について
・令和6年11月1日から対象となっています。
・企業等から業務委託を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)が対象で、業種や職種は問われません。
・「特定作業従事者」とは、厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者です。厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりです。(則第46条の18)
・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業 ・ 特定の農業機械を用いる一定範囲の農作業 ・ 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの 職場適応訓練 事業主団体等委託訓練として行われる作業 ・ 家内労働者又は補助者が行う作業のうちプレス機械を使う加工作業等の特定のもの ・ 労働組合等の常勤役員が行う集会の運営、団体交渉等の労働組合等の活動に係る作業 ・ 介護関係業務に係る作業及び家事支援作業 ・ 芸能の提供の作業または演出・企画の作業 ・ アニメーションの制作の作業 ・ 情報処理システムの設計、開発、管理、監査その他の情報処理に係る作業 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
介護作業に加え、「家事支援作業」が新たに特別加入の対象となったのは、平成30年4月です。「家事支援作業」は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務です。
介護作業従事者として特別加入している者は、「介護作業及び家事支援作業」のいずれの作業にも従事するものとして取り扱われます。
そのため、平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることがあります。
(則第46条の5、平30.2.8基発0208第1号)
②【H30年選択式】
労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、< A >の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< B >はその一例に該当する。
(選択肢)
A | ① 介護事業 ② 畜産業 ③ 養蚕業 ④ 林業 |
B | ① 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者 ② 介護作業従事者 ③ 個人タクシー事業者 ④ 船員法第1条に規定する船員 |

【解答】
②【H30年選択式】
<A> ④ 林業
<B> ③ 個人タクシー事業者
★<B>について
一人親方等・特定作業従事者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者については、「通勤災害」に関する保険給付が適用されません。
<通勤災害が適用されない者>
・ 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー・個人貨物運送業者など)
・ 漁船による自営漁業者
・ 危険有害な農作業(特定農作業・指定農業機械作業)に従事する者
・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業に従事する者
・ 家内労働に従事する者
(則第46条の22の2)
③【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
③【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確に区別できないため、通勤災害に関する労災保険は適用されません。
②【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されません。
③【H22年出題】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

【解答】
③【H22年出題】 ×
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、通勤災害は適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「任意継続被保険者」
R7-237 04.22
任意継続被保険者の保険料の前納
任意継続被保険者は、保険料を、その月の10日までに納付しなければなりません。
なお、初めて納付すべき保険料は、保険者が指定する日までに納付しなければなりません。
例えば、4月27日に退職したとすると、4月28日に被保険者資格を喪失します。
任意継続被保険者となった場合は、4月28日に任意継続被保険者の資格を取得します。任意継続被保険者としての保険料は、4月分から徴収されます。
任意継続被保険者の保険料は前納することができます。
条文を読んでみましょう。
第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) ① 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 ④ 保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
<保険料の納付期日>
・一般の被保険者の保険料は、翌月末日
・任意継続被保険者の保険料は、その月の10日(ただし、初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定する日」まで)
「任意継続被保険者の資格取得の申出をした日」は誤りです。
(法第164条第1項)
②【R2年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

【解答】
②【R2年出題】 ×
前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額となります。
③【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

【解答】
③【H26年出題】 〇
★任意継続被保険者の保険料の前納期間の単位について
(原則)
4月から9月までの6か月間 10月から翌年3月までの6か月間 |
4月から翌年3月までの12か月間 |
当該6か月又は12か月の間に、 「任意継続被保険者の資格を取得した者」 | その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間について前納できる |
当該6か月又は12か月の間に、 「その資格を喪失することが明らかである者」 | その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間について前納できる |
(令第48条)
④【H30年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
「4月から翌年3月までの12か月間」の単位もあります。
また、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者についての例外もあります。
③の問題をご覧ください。
⑤【R5年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
なお、国民年金の保険料の前納との違いに注意しましょう。
国民年金は、「前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。」となります。(国民年金法第93条)
⑥【H22年選択式】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納をおこなうことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
<A> 各月の初日
<B> 初月の前月末日
<C> 年4分の利率
<D> 5月
★<D>について
6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。
問題文は、4月に資格を取得していますので、5月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。
(則第139条、令第48条、令第49条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「脱退一時金」
R7-236 04.21
脱退一時金についてお話しします(国年)
脱退一時金は外国人に対して支給される給付で、平成7年4月に創設されました。
日本国籍を有しない人が、公的年金制度の被保険者資格を喪失し、
日本国内に住所を有しなくなった場合に支給されるものです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R7-235 04.20
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年4月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月14日から4月19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 令和7年度の年金額の改定についてお話しします(国民年金法)
・ 労働保険事務組合に委託できる事務の範囲(徴収法)
・ 出産・育児に関する総合問題を解いてみましょう(健康保険法)
・ 療養費(現金給付)が支給されるとき(健康保険法)
・ 治ゆ前の保険給付(療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金)(労災保険法)
・ 資格喪失後の「出産育児一時金」の条件(健康保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「資格喪失後の出産」
R7-234 04.19
資格喪失後の「出産育児一時金」の条件
退職後(被保険者の資格喪失後)に、出産した場合、要件を満たせば、最後の保険者から出産育児一時金を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付) 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 ※1年以上被保険者であった者 → 「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者
※支給額 → 1児につき48万8千円(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は50万円) |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合についての問題です。
「被保険者本人としての出産育児一時金」、「被扶養者としての家族出産育児一時金」の受給資格ができますが、どちらを受給するかは請求者の選択によります。
(昭48.11.7保険発99・庁保険発21)
②【R2年出題】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
要件を満たしたもの者が資格喪失後6か月以内に出産した場合、資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が対象者に対して出産育児一時金の支給を行います。
そのため、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができます。
(平23.6.3保保発0603第2号)
③【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
その者が健康保険法の規定に基づく資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができます。②の問題と同じです。
④【H30年出題】
被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第107条 (船員保険の被保険者となった場合) 前3条の規定(「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」)にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。 |
資格喪失後の出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合は、船員保険法から支給を受けることができますので、健康保険法の出産育児一時金は支給されません。「いずれかを選択して受給することができる」は誤りです。
⑤【H26年出題】
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」及び「資格喪失後の出産育児一時金の給付」は行われません。船員保険から支給を受けることができるからです。
⑥【R6年選択式】
任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金を受けることができるのは、< A >であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
<選択肢>
① 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
② 資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
③ 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を含む。)
④ 資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

【解答】
<A> ① 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
図でイメージしましょう。
退職 | ・資格喪失 = ・任継取得 | ~ | 任継喪失 |
引き続き1年以上被保険者 | 任意継続被保険者 | ||
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「治ゆする前の保険給付」
R7-233 04.18
【労災】治ゆ前の保険給付(療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金)
治ゆ前の保険給付の関係を図でイメージしましょう。
ポイント!
「療養補償給付」と「休業補償給付」は併給されます。
「療養補償給付」と「傷病補償年金」は併給されます。
「休業補償給付」と「傷病補償年金」は併給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付は行われない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
療養補償給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで(治ゆするまで)行われます。
傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとされます。
治ゆすると療養補償給付は行われません。ただし、再発した場合は、再び療養補償給付が行われます。
(昭23.1.13基災発第3号)
②【H30年出題】
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
②【H30年出題】 ×
1年ではなく「1年6か月」です。
「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後「1年6か月」を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級から3級)に該当すること。
(法第12条の8第3項)
③【H24年出題】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

【解答】
③【H24年出題】 〇
療養補償給付も、休業補償給付も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、休業補償給付は「所得補償」のためのものです。
療養補償給付と休業補償給付は併給される場合があります。
(法第13条、第14条)
④【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
④【H24年出題】 〇
療養補償給付も、傷病補償年金も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、傷病補償年金は「所得補償」のためのものです。
療養補償給付と傷病補償年金は併給される場合があります。
(法第12条の8第3項、法第13条)
⑤【H24年出題】
休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
法第18条第2項で、「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。」と規定されています。
休業補償給付は、傷病補償年金と併給されることはありません。
なお、「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」とされています。
傷病補償年金の支給事由が生じた場合は、その支給すべき事由が生じた月の末日までは、休業補償給付が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 |
| 傷病補償年金の 支給事由が発生 |
|
休業補償給付 | 休業補償給付 | 傷病補償年金 |
⑥【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはありません。⑤の問題と同じです。
⑦【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。
8月 | 9月 | 10月 |
| 傷病補償年金の受給権 消滅 |
|
傷病補償年金 | 傷病補償年金 | 休業補償給付 |
⑧【H21年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けられない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

【解答】
⑧【H21年出題】 ×
「政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する」が誤りです。
休業補償給付が支給されるには、労働者の請求が必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
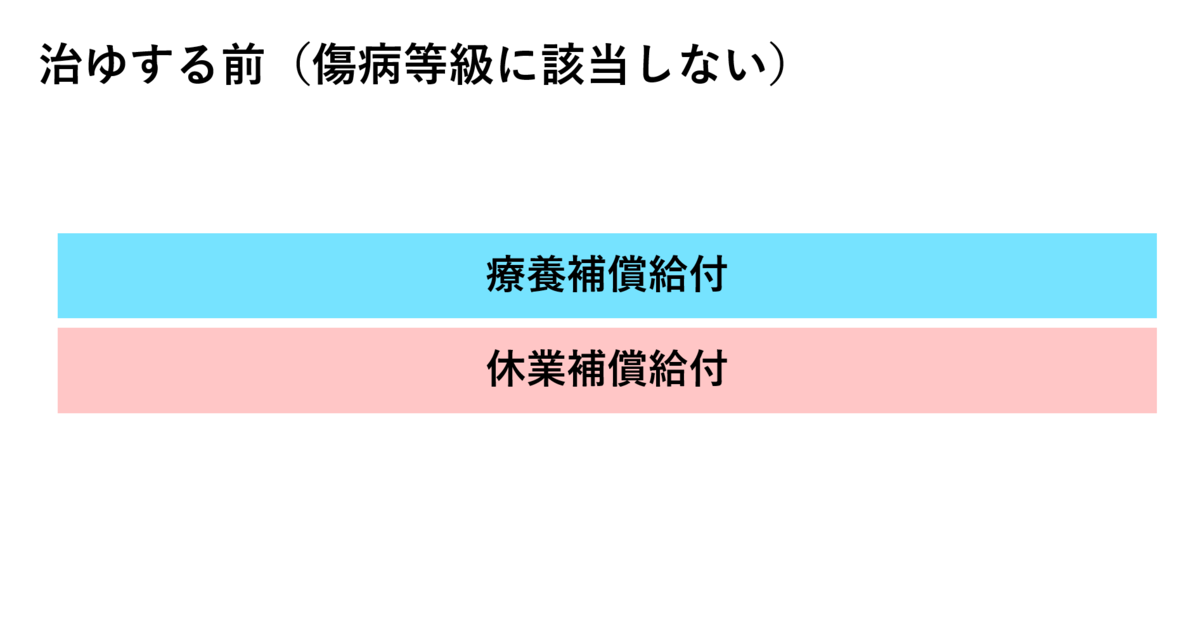
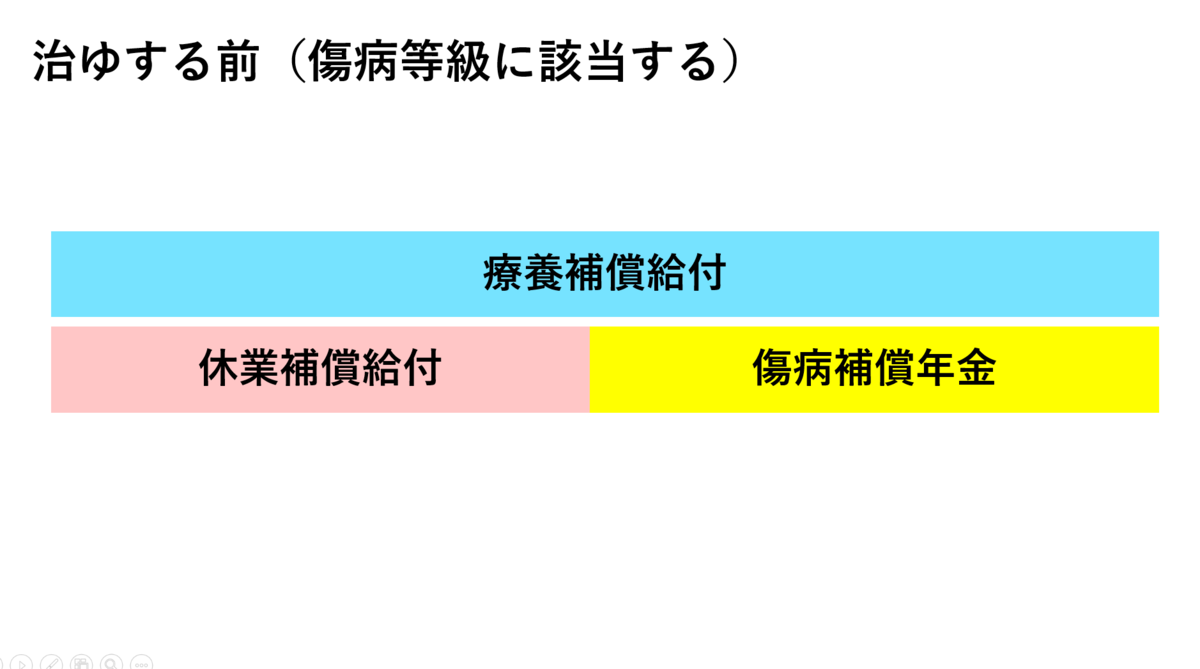
健康保険法「療養費」
R7-232 04.17
【健保】療養費(現金給付)が支給されるとき
健康保険は、『現物給付』が原則です。
しかし、現物給付を行うことが困難であると認めるときなどは、その費用について、現金で「療養費」が支給されます。
「療養費」が支給される要件などをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第87条第1項、第2項 (療養費) ① 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 ② 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 |
「療養費」が支給されるのは以下の2つの場合です。
① 「療養の給付等」を行うことが困難であると保険者が認めるとき
② 被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合で、保険者がやむを得ないものと認めるとき
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【解答】
①【R3年出題】 〇
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を「基準として、保険者が定める。」の部分がポイントです。
②【R1年出題】
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
療養費が支給されるのは、「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき」、又は「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき」です。
「訪問看護療養費の支給を行うことが困難」であるのは、どちらにも該当しませんので、療養費は支給されません。
③【H27年出題】
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。

【解答】
③【H27年出題】 〇
無医村で応急措置として緊急に売薬を服用した場合は、「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当しますので、療養費の支給を受けることができます。
(昭13.8.20社庶1629)
④【R5年出題】
現に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
「その地方に保険医がいない場合又は保険医はいても、その者が傷病等のために、診療に従事することができない場合」等には、療養費の支給が認められます。
・緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた時には、療養費は支給されません。
・現に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められません。
(昭24.6.6保文発1017号)
⑤【R5年出題】
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
★海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について
・療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
・療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
・現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこととされています。
・現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこととされています。
・ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いることとされています。
(昭56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
⑥【H27年出題】
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。

【解答】
⑥【H27年出題】 ×
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされています。
その支給は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて換算されます。その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこととされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「産前産後・育児休業等」
R7-231 04.16
【健保】出産・育児に関する総合問題を解いてみましょう
産前産後、育児休業等について、以下の内容をみていきます。
・産前産後休業期間中の保険料免除
・出産手当金の支給期間
・育児休業期間中の保険料免除
・育児休業等終了時改定の申出
・育児休業等終了時改定の有効期間
さっそく過去問をどうぞ!
【H27年出題】
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 10:00
終業時刻 17:00
休憩時間 1時間
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額12,000円の日給制
給与の締切日 毎月20日
給与の支払日 毎月末日
(ア) 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(イ) 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
(ウ) 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(エ) 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
(オ) 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
A(アとイ) B(アとオ) C(イとウ) D(ウとエ) E(エとオ)

【解答】
A(アとイ)

(ア) ×
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
問題文の場合、産前産後休業の開始が3月7日、終了が8月10日です。
事業主は出産した年の3月から「7月まで」の期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができます。

(イ) ×
条文を読んでみましょう。
第102条第1条(出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
問題文を条文に当てはめると、出産の日が出産の予定日より後で、多胎妊娠ですので、出産手当金が支給されるのは、出産予定日(6月12日)以前98日(=3月7日)から出産の日後56日(=8月10日)までの間において労務に服さなかった期間です。

(ウ) 〇
条文を読んでみましょう。
第159条 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の保険料免除を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
問題文の場合、産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間は、「3月~7月」です。
育児休業期間中の保険料が免除される期間は、
・育児休業等を開始した日の属する月(=産前産後休業期間中の保険料免除期間の終了月の翌月=8月)
から
・育児休業等が終了する日の翌日(1歳に達した日の翌日=6月15日)が属する月の前月(=5月)
までとなります。

(エ) 〇
条文を読んでみましょう。
第43条の2第1項 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 |
<随時改定と比較しましょう>
随時改定 | 育児休業等を終了した際の改定 |
固定的賃金に変動があった | 固定的賃金に変動がなくても対象になる |
2等級以上の差が生じた | 1等級以上の差が生じた |
3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上) | 報酬払基礎日数が17日未満の月は除く (短時間労働者は11日未満) |
問題文のポイントです。
6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
育児休業等終了日の翌日 |
|
|
|
算入しない | (7月+8月)÷2 |
| |
従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができます。

(オ) 〇
条文を読んでみましょう。
第43条の2第2項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ~ | 翌年8月 |
育児休業等終了日の翌日 |
|
|
|
|
|
算入しない | (7月+8月)÷2 | 改定 |
|
| |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R7-230 04.15
労働保険事務組合に委託できる事務の範囲
「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等です。
認可で新しい団体が設立されるのではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものです。
労働保険事務組合について条文を読んでみましょう。
第33条第1項、第2項 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務の処理を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
則第62条第1項(委託事業主の範囲) 法第33条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
委託できる事業主の範囲
|
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。

【解答】
①【H19年出題】(雇用) ×
厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となった団体は、「その事業の一環として」、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理します。専業で行わなければならないものではありません。
②【R1年出題】(雇用)
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【解答】
②【R1年出題】(雇用) 〇
「金融業」を主たる事業とする事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは、「常時使用する労働者が50人以下」の場合です。「50人」を超える場合は、委託できません。
③【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

【解答】
③【R5年出題】(労災) 〇
令和2年4月より、労働保険事務組合に委託する事業主の所在地の制限がなくなっています。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができます。
④【H23年出題】(雇用)
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
<A> 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
<B> 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
<C> 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
<D> 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
<E> 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務

【解答】
④【H23年出題】(雇用)
誤り → <B>
「印紙保険料に関する事項」は、労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲から除かれています。
<B>印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険事務組合に委託して処理させることはできません。
⑤【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

【解答】
⑤【R1年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合は、「労災の保険給付に関する請求の事務」を行うことはできません。
★労働保険事務組合に委託できない事務
・印紙保険料に関する事項
・保険給付に関する請求書等の事務手続
・雇用保険の二事業に係る事務手続
⑥【H19年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【解答】
⑥【H19年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができ、また、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務も「処理することができる」となります。
⑦【R3年出題】(雇用)
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

【解答】
⑦【R3年出題】(雇用) 〇
「保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行」、「雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行」、「印紙保険料に関する事項」は、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「令和7年度の年金額」
R7-229 04.14
令和7年度の年金額の改定についてお話しします
年金額は、780,900円×改定率で計算します。
令和7年度の年金額は、831,700円です。
(昭和31年4月1日以前生まれは、829,300円です。)
・改定率の基準
新規裁定者→名目手取り賃金変動率
既裁定者→物価変動率
・物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っている場合
・マクロ経済スライド についてお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-228 04.13
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年4月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年4月7日から4月12日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・令和7年度国民年金保険料についてお話しします(国民年金法)
・資格の取得・喪失は厚生労働大臣の確認で効力を生ずる(厚生年金保険法)
・労基法第35条「休日の与え方」(労働基準法)
・被扶養者に関する健康保険の給付(健康保険法)
・事業主からの特別の費用徴収「故意・重大な過失」の認定(労災保険法)
・「待期」離職後最初の求職の申込みの日から起算された通算7日(雇用保険法)
(令和7年4月第1週目)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「待期」
R7-227 04.12
「待期」離職後最初の求職の申込みの日から起算された通算7日
基本手当は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されません。なお、7日には疾病又は負傷のため職業に就くことができない日が含まれます。
条文を読んでみましょう。
第21条 (待期) 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】
雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(< A >のため職業に就くことができない日を含む。)が< B >に満たない間は、支給しない。」と規定している。
<選択肢>
① 激甚災害その他の災害 ② 疾病又は負傷 ③ 心身の障害
④ 妊娠、出産又は育児 ⑤ 通算して7日 ⑥ 引き続き7日
⑦ 通算して10日 ⑧ 引き続き10日

【解答】
①【R1年選択式】
<A> ② 疾病又は負傷
<B> ⑤ 通算して7日
②【H23年出題】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

【解答】
②【H23年出題】 〇
待期は、受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日から進行し、その日以後に通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しません。
そのため、失業している日が通算して5日の時点で就職して被保険者となった場合は、待期が満了していませんので、その5日について基本手当が支給されることはありません。
③【H29年出題】
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされます。
公共職業安定所における失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものですので、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならないとされています。
(行政手引51102)
④【H26年出題】
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目から基本手当が支給される。

【解答】
④【H26年出題】 ×
待期期間には、「疾病により職業に就くことができなくなった」日数も含まれます。
そのため、他の要件を満たす限り、当該求職の申込みをした日の11日目ではなく、8日目から基本手当が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「事業主からの費用徴収」
R7-226 04.11
事業主からの特別の費用徴収「故意・重大な過失」の認定
一定の要件に該当する事故については、事業主の注意を促すために、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。
条文を読んでみましょう。
第31条第1項 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 (1) 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間(政府が認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 (2) 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故 (3) 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故として、正しいものはどれか。
<A> 事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故
<B> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
<C> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
<D> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
<E> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

【解答】
①【H26年出題】
<A> ×
保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故でも、「重大でない過失」の場合は、費用徴収されません。
<B> ×
一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について費用徴収が行われるのは、「督促状に指定する期限後の期間」に限られます。政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故については、費用徴収されません。
<C> 〇
事業主が重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故については、費用徴収が行われます。
<D> ×
「第一種特別加入保険料」を納付しない期間中に生じた事故は、費用徴収の対象になりません。特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第34条)
<E> ×
<D>と同じく、特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第35条
②【R1年選択式】
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後< A >以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから< B >を経過してもなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。
<選択肢>
<A> ① 3日 ② 5日 ③ 7日 ④ 10日
<B> ① 3か月 ② 6か月 ③ 9か月 ④ 1年

【解答】
<A> ④10日
<B> ④ 1年
ポイント!
① 事業主の故意の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがある事業主であって、その提出を行っていないものについては、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
② 事業主の重大な過失の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とする。費用徴収率は40%とする。
(令5.7.20基発第0720第1号)
③【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】
③【H27年出題】 〇
保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、原則、費用徴収率は100%となります。
(令5.7.20基発第0720第1号)
④【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】
④【H27年出題】 〇
加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、原則、費用徴収率は100%となります。
(令5.7.20基発第0720第1号)
⑤【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定され、費用徴収率は40%となります。
(令5.7.20基発第0720第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「家族療養費など」
R7-225 04.10
被扶養者に関する健康保険の給付
「被扶養者」に関する給付として以下の給付があります。
・家族療養費 (療養の給付、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費に当たります) ・家族訪問看護療養費 ・家族移送費 ・家族埋葬料 ・家族出産育児一時金 |
「家族療養費」の給付割合について
①6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である被扶養者 | 100分の70 |
②6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被扶養者 | 100分の80 |
③70歳に達する日の属する月の翌月以後である被扶養者 (④を除く) | 100分の80 |
④70歳以上の現役並所得者である被保険者の70歳以上の被扶養者 | 100分の70 |
ポイント!
被扶養者に関する給付は、「被保険者に」支給されることがポイントです。
例えば、法第110条第1項では、
「被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。」と規定されています。
「被扶養者に対し、家族療養費を支給する」という問題は誤りです。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
被保険者に対して「入院時生活療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されます。
(法第110条第1項)
②【H30年出題】
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。

【解答】
②【H30年出題】 ×
被扶養者が6歳の年度末以前の場合、家族療養費の給付割合は、「100分の80」です。
(法第110条第2項)
③【H29年出題】
68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

【解答】
③【H29年出題】 ×
★被扶養者が70歳以上の場合の家族療養費の給付割合
・100分の80
・ただし、被保険者が70歳以上で現役並所得者の場合(=一部負担金の割合が100分の30)は、70歳以上の被扶養者の家族療養費の割合も100分の70になります。
問題文の場合は、被保険者が70歳未満ですので、被保険者の収入の額に関係なく、70歳以上の家族療養費の給付割合は80%です。
(法第110条第2項)
④【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
第114条で、「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。」と規定されています。
「被扶養者」が出産した場合に支給されますので、被扶養者である配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合にも支給されます。
(法第114条)
⑤【H29年出題】
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、「被扶養者」でなく、「被保険者」に対しその指定訪問看護に要した費用について、「訪問看護療養費」ではなく「家族訪問看護療養費」を支給する、となります。
(法第111条)
⑥【H30年出題】
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
「家族療養費」は、「被保険者」に対して支給されます。
そのため、被保険者が死亡し被保険者の資格を喪失すると、家族療養費は支給されません。
(法第110条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「休日」
R7-224 04.09
労基法第35条「休日の与え方」
「休日」とは労働義務のない日のことです。
まず、休日について条文を読んでみましょう。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
■休日の与え方
<原則>毎週少なくとも1回
<例外>4週間を通じ4日以上の休日
★休日のイメージ
<原則 毎週1回>
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
休 | 休 | 休 | 休 |
<例外 4週4休>
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
休休 | 休休 |
|
※就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとされています。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

【解答】
①【H23年出題】 〇
休日は、「毎週1回」与えるのが原則ですが、例外で、「4週間を通じ4日以上」の休日を与えることもできます。
4週4休日の場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしなければなりません。
(法第35条、則第12条の2)
②【H13年出題】
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】
②【H13年出題】 ×
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制については、特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。
どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。
特定の4週間を明確にするため、就業規則等で起算日を明らかにすることとされています。
(昭和23.9.20基発1384号)
③【H29年出題】
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】
③【H29年出題】 ×
「休日」とは、単に連続24時間の休業ではありません。
「休日」とは「暦日」を指し、午前0時から午後12時までの休業のことをいいます。
(昭23.4.5基発535号)
④【H21年出題】
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【解答】
④【H21年出題】 ×
8時間3交替制勤務で、要件に該当する場合は、「継続24時間」の休息を与えれば、暦日でなくても労働基準法第35条の休日を与えたことになります。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【H13年出題】
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。

【解答】
⑤【H13年出題】 ×
④の問題のように、要件に該当する8時間3交替制の場合は、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることが認められています。
⑥【H24年出題】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
⑥【H24年出題】 〇
労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 公休日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第7日の午前0時から継続した24時間は「休日」となります。
非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日を与えたものとは認められません。
(昭23.11.9基収2968号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「資格の得喪の確認」
R7-223 04.08
<厚年>資格の取得・喪失は厚生労働大臣の確認で効力を生ずる
「確認」についてみていきます
★被保険者がいつ入社したのか(いつ資格取得したのか)、いつ退職したのか(いつ資格喪失したのか)を厚生労働大臣が確認します。
例えば、4月8日に社員Aが入社した場合、会社は、「資格取得届」を提出します。
↓
厚生労働大臣が、「4月8日にAが資格を取得した」と確認します。
↓
厚生労働大臣の確認によって、資格取得の効力が発生します。
・Aについて、4月分から厚生年金保険料の納付義務が発生します
・保険事故が起きた場合、年金などを受ける権利が発生します
(厚生年金保険の被保険者としての権利と義務が生まれます。)
条文を読んでみましょう。
第18条 (資格の得喪の確認) ① 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 <確認が要らないもの> ・任意単独被保険者の資格の取得と厚生労働大臣の認可による喪失 ・高齢任意加入被保険者の資格の取得と喪失 ※適用事業所の高齢任意加入被保険者→退職・適用除外で喪失の場合は確認が必要 ※適用事業所以外の高齢任意加入被保険者→任意単独被保険者と同じ ・任意適用事業所が適用事業所でなくなったことによる資格喪失 ② 確認の方法 ・事業主による資格取得、喪失の届出 ・第31条第1項の規定による確認の請求 ・職権 ③ 確認については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。 ④ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、確認の規定は、適用しない。
第31条 (確認の請求) ① 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 ② 厚生労働大臣は、請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
確認の方法は次の3つです。
・事業主による届出
・被保険者若しくは被保険者であった者からの請求
・職権
②【R4年出題】
適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。

【解答】
②【R4年出題】 〇
被保険者(在職中)又は被保険者であった者(退職後)は、いつでも、確認を請求することができます。
③【H29年出題】
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
任意適用事業所の適用取消しには厚生労働大臣の認可が必要で、認可があった場合全員が資格を喪失します。そのため、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認は要りません。
④【H29年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者が、「厚生労働大臣の認可」によって被保険者資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の確認は要りません。
⑤【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申出が受理された日に資格を取得しますので、厚生労働大臣の確認は不要です。
⑥【H16年出題】※改正による修正あり
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣の適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。

【解答】
⑥【H16年出題】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の理由が、「被保険者が事業所に使用されなくなったとき」の場合は、厚生労働大臣の確認が必要です。
(令第6条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「保険料の額」
R7-222 04.07
令和7年度国民年金保険料についてお話しします
令和7年度の国民年金保険料は17510円です。
17510円は、「17,000円×1.030」で計算します。
17000円、1.030の根拠についてお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-221 04.06
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年3月第5週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月31日から4月5日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・寡婦年金のすべてお話しします(国民年金法)
・雇用保険日雇労働被保険者の要件(雇用保険法)
・特別加入保険料の算定(労働保険徴収法)
・<R7年4月改正>離職理由による給付制限(雇用保険法)
・労働保険徴収法の「督促・滞納処分」、「延滞金」のポイント!
・偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた場合(健康保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「不正利得の徴収」
R7-220 04.05
<健保>偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた場合
詐欺など不正行為で保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者から不正行為によって受けた分のすべてを徴収することできます。
条文を読んでみましょう。
第58条 (不正利得の徴収等) ① 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 ② ①の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 ③ 保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用等の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。 |
②について
事業主、保険医、主治の医師が不正行為に絡んでいる場合は、保険者は保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
③について
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者が不正の行為で診療報酬の支払いを受けたときは、その額につき返還させるほか、返還させる額の100分の40を支払わせることができます。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。

【解答】
①【H25年出題】 〇
偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
★「全部又は一部」の意味について
↓
偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることがあるため
↓
偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという意味です。
(昭32.9.2保険発123)
②【R6年出題】
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。

【解答】
②【R6年出題】 ×
全部又は一部という意味は、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることがあるためです。偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨です。
①の問題と同じです。
③【H29年出題】
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。

【解答】
③【H29年出題】 ×
事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、事業主に対しても保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
④【R3年出題】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

【解答】
④【R3年出題】 〇
指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができます。
⑤【H26年出題】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
その支払った額について返還させるほか、その返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「督促及び滞納処分等」
R7-219 04.04
労働保険徴収法の「督促・滞納処分」、「延滞金」のポイント!
労働保険料を滞納した場合などの扱いについて、条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
第28条 (延滞金) ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ② 労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。 ③ 延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
法附則第12条 (延滞金の割合の特例) 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、 年14.6%の割合 → 延滞税特例基準割合+年7.3% 年7.3%の割合 → 延滞税特例基準割合+年1%(当該加算した割合が7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) とされます。 |
下の図でイメージしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。

【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
概算保険料・確定保険料について所定の期限までに申告しなかった場合は、政府が認定決定をし、事業主に通知します。その場合、督促が行われるのは、「通知があってもなお、法定納期限(通知を受けた日から15日以内)までに納付しないときに限られます。
(法第27条)
②【R1年出題】(雇用)
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

【解答】
②【R1年出題】(雇用) 〇
督促・滞納処分の対象になる「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」については、「労働保険料」だけではありません。
労働保険料ではない「追徴金」も督促・滞納処分の対象になっていることに注意してください。
(昭55.6.5発労徴40号)
③【H29年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
③【H29年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、事業主が督促状に指定された期限までに完納したときは、延滞金は徴収されません。
④【R1年出題】(雇用)
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

【解答】
④【R1年出題】(雇用) ×
延滞金の期間の日数は、「督促状で指定した期限の翌日」ではなく「納期限の翌日」からその完納又は財産差押えの日の前日までです。
ちなみに、延滞金の割合は、「年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)です。
⑤【R1年出題】(雇用)
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

【解答】
⑤【R1年出題】(雇用) 〇
労働保険料の額が1,000円未満であるとき・延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
⑥【H26年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
⑥【H26年出題】(雇用) ×
・督促、滞納処分は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない」場合に行われます。
・延滞金は、「労働保険料の納付を督促したとき」に徴収されます。
延滞金の対象になるのは「労働保険料」のみです。
追徴金は労働保険料ではありませんので、延滞金の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
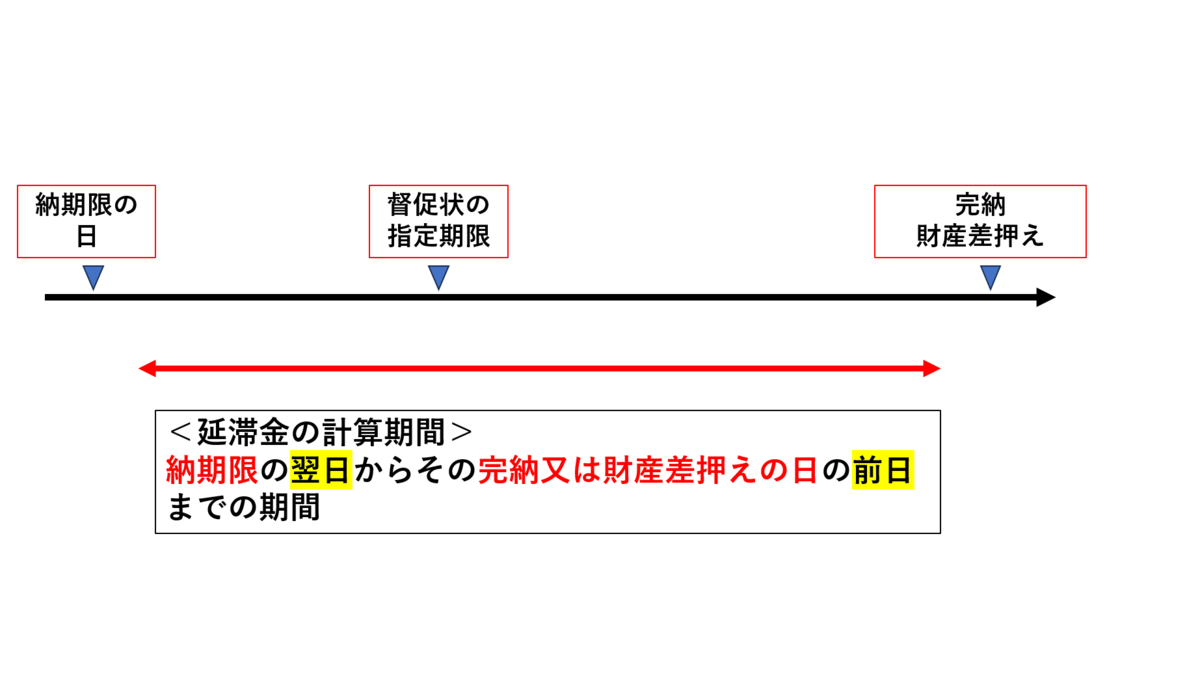
雇用保険法「R7年4月1日改正」
R7-218 04.03
<改正>離職理由による給付制限
まず、離職理由による給付制限を下の図でイメージしましょう。
離職理由によっては、待期期間満了後1~3か月間は基本手当が支給されません。
令和7年4月以降、教育訓練等を受けた場合は、給付制限が解除されることになりました。※正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合に限られます。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、次に掲げる受給資格者については、この限りでない。 (1) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。) (2) 第60条の2第1項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前1年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。次号において同じ。) (3) 前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者
※ (1)に掲げる者にあっては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間に限る (3)に掲げる者にあっては(2)に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わった日後の期間に限る。 |
法第60条の2第1項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練は以下のとおりです。
(イ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練
(ロ) 公共職業訓練等
(ハ) 短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練
(ニ) 被保険者又は被保険者であった者が自発的に受講する訓練であって、その訓練の内容に照らして雇用の安定及び就職の促進に資するものとして職業安定局長が定めるもの
(行政手引52205-2)
★ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合の給付制限期間は、原則3か月です。
★ 正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は、原則1 か月です。
ただし、当該退職した日が令和 7年3月31日以前である場合の給付制限期間は、
2か月です。
また、当該退職した日から遡って5年間のうちに 2回以上、正当な理由なく自己の都合により退職し求職申込みをした者については、当該退職にかかる給付制限期間は 3か月となります。
(行政手引52205-1)
改正のポイント!
・離職日前1年以内に教育訓練等を受けたことがある場合
→ 待期満了後から給付制限が解除され、基本手当が支給されます。(全ての期間について、給付制限が解除されます。)
・離職日以後に教育訓練を受ける場合
→ 受講開始日以降は給付制限が行われませんので、基本手当が支給されます。
★対象になるのは、「正当な理由なく自己の都合により退職した場合」のみです。
「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇」の場合は、対象外です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

【解答】
①【H26年出題】 〇
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等」の受講開始日以後は、給付制限が解除されます。こちらについては、被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合でも適用されます。
(法第33条第1項第1号)
②【H28年出題】
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 ×
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して 1か月以上 3か月以内の間は、基本手当は支給されません。そのため、この間については、「失業の認定を行う必要はない。」とされています。
(行政手引52205-1)
③【H29年出題】
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

【解答】
③【H29年出題】 〇
「従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによる解雇」は、「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」となり、給付制限の対象になります。
(行政手引52202)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
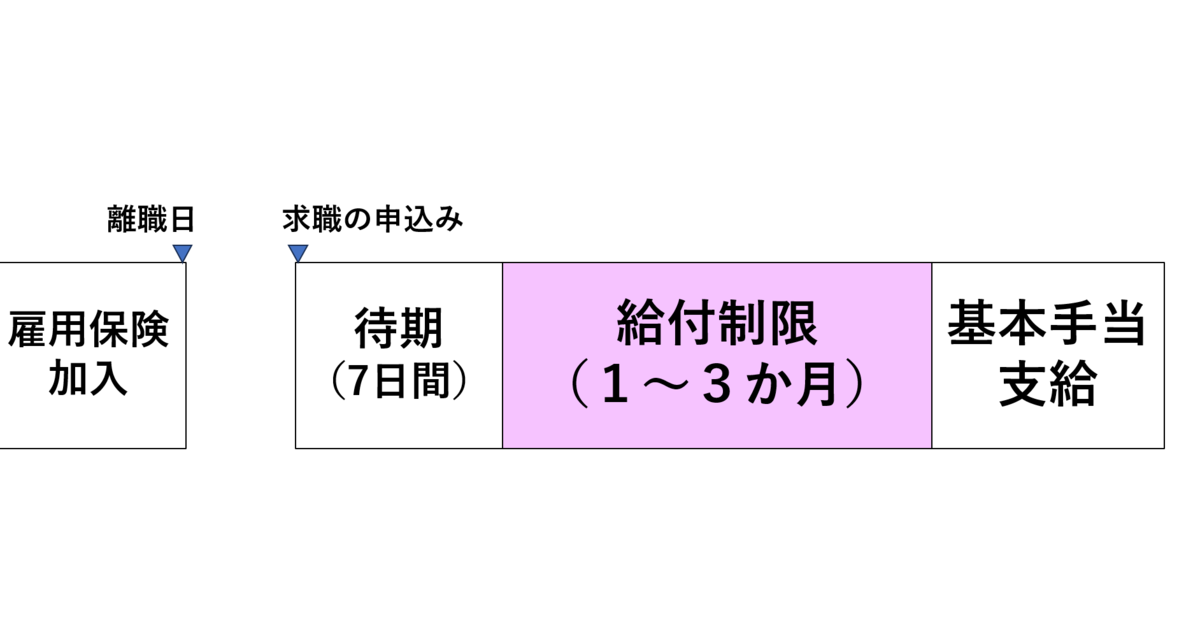
労働保険徴収法「特別加入保険料」
R7-217 04.02
特別加入保険料の算定
特別加入保険料の計算方法を確認しましょう。
・第1種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第1種特別加入保険料率 ・第2種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第2種特別加入保険料率 ・第3種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第3種特別加入保険料率 |
「特別加入保険料算定基礎額」は、原則として、「給付基礎日額×365」で計算します。
一般の労働者でいうと、個々の労働者の1年間の賃金の額です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

【解答】
①【R2年出題】(労災) 〇
特別加入者には、二次健康診断等給付が適用されませんので、第1種特別加入保険料率は、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」を減じた率となります。
ただし、「厚生労働大臣の定める率」は、「零」ですので、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業の労災保険率と同一の率となります。
(法第13条)
②【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
②【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類によって、1000分の3から1000分の52の範囲で、それぞれ定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、則別表5)
③【H26年出題】(労災)※改正による修正あり
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和7年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

【解答】
③【H26年出題】(労災) ×
第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に「1000分の3」です。
(法第14条の2、則第23条の3)
④【R2年出題】(労災)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。

【解答】
④【R2年出題】(労災) ×
当該月数に1月未満の端数があるときは「その月数を切り捨てる」ではなく、「これを1月とする。」となります。
★ 「継続事業」で、保険年度の中途に特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額」について
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)÷12」×「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
「特別加入者とされた期間の月数」に1月未満の端数があるときは、1月とします。
・保険年度の中途に新たに特別加入者となった者
→ 特別加入申請の承認日の属する月を「1月」と算定します
・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者
→ 特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を「1月」と算定します
★例えば、特別加入の承認が6月30日、消滅日が翌年2月18日の場合
6月と翌年2月は「1月」で算定しますので、特別加入者とされた期間の月数は9か月となります。
(則第21条第1項、H7.3.30労徴発28号)
⑤【R5年出題】(労災)
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
「有期事業」の場合
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)÷12」×「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
端数処理は、継続事業と異なるので注意してください。
有期事業についての特別加入期間のすべてで端数処理をします。
例えば、有期事業の全期間が「12か月11日」の場合は、端数の11日を1月で算定し、13か月となります。
(則第21条第2項、H7.3.30労徴発28号)
⑥【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。

【解答】
⑥【R5年出題】(労災) 〇
第1種特別加入保険料は、「12,000円×365」×1,000分の4=17,520円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「日雇労働被保険者」
R7-216 04.01
雇用保険の日雇労働被保険者の要件
まず、「日雇労働者」の定義を条文で読んでみましょう。
第42条 日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して 31日以上雇用された者(日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。 (1) 日々雇用される者 (2) 30日以内の期間を定めて雇用される者 |
★「日雇労働者」とは、
・日々雇用される者
・30日以内の期間を定めて雇用される者
のことをいいます。
★ただし、以下に当てはまる場合は、日雇労働者となりません。
・連続する前2暦月の各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき
・同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用されたとき
→ 日雇労働被保険者資格継続の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われます。
(参考:行政手引90001)
次に「日雇労働被保険者」について条文を読んでみましょう。
法第43条第1項、第2項 ① 被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する。 (1) 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者 (2) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 (3) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者 (4) (1)から(3)に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者 ② 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
雇用保険法第42条は、同法第3章4節において< A >とは、< B >又は < C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。

【解答】
①【H25年選択式】
<A> 日雇労働者
<B> 日々雇用される者
<C> 30日
<D> 18日
<E> 31日
②【H29年選択式】
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。

【解答】
②【H29年選択式】
<A> 2月
<B> 18日
③【H22年出題】
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。

【解答】
③【H22年出題】 〇
1週間の所定労働時間が20時間未満でも、日雇労働被保険者に該当する者については、雇用保険が適用されます。
第6条第1号で、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者については、雇用保険法は適用しない」と規定されています。
(ただし、例外があります)
・第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者
・雇用保険法を適用することとした場合において第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者
は、被保険者となります。
④【H29年出題】
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

【解答】
④【H29年出題】 〇
日雇労働被保険者には、確認の制度が適用されません。
(法第43条第4項)
⑤【H24年出題】
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
ポイントをおさえましょう。
・日雇労働被保険者は、適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を、管轄公共職業安定所の長に提出しなければなりません。
※管轄公共職業安定所とは、「その者の住所又は居所を管轄」する公共職業安定所です。
(則第71条第1項)
⑥【H20年出題】
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

【解答】
⑥【H20年出題】 ×
日雇労働被保険者が交付を受けなければならないのは、「日雇労働被保険者手帳」です。「雇用保険被保険者証」は交付されません。
条文を読んでみましょう。
則第73条第1項 管轄公共職業安定所の長は、日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき又は日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、「日雇労働被保険者手帳」を交付しなければならない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「寡婦年金」
R7-215 03.31
寡婦年金のすべてお話しします
寡婦年金は、夫が死亡した場合、妻に支給される年金です。
死亡した夫の要件と
受給できる妻の要件をおさえましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-214 03.30
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年3月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月24日から29日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・遺族基礎年金の額についてお話しします(国民年金法)
・健康保険の被扶養者の範囲と要件(健康保険法)
・健康保険と労災保険の保険給付の調整(健康保険法)
・療養の給付を受ける場合の一部負担金(健康保険法)
・障害基礎年金と障害厚生年金の額の計算(国年・厚年)
・特定受給資格者の定義と範囲(雇用保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「特定受給資格者」
R7-213 03.29
特定受給資格者の定義と範囲
特定受給資格者は(1)「倒産」等により離職した者、(2)「解雇」等により離職した者の2つに分けられます。
「特定受給資格者」について条文を読んでみましょう。
法第23条第2項 特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者を除く。)をいう。 (1) 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (2) 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 |
過去問を解きながら範囲をみていきましょう。
①【R3年出題】
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「事業所の廃止」に伴い離職した者は特定受給資格者となりますが、「事業の廃止」には、当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含みますが、「事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるもの」は除かれます。
そのため、問題文は誤りです。
(則第35条第3号、行政手引50305)
②【H30年出題】
次の記述のうち、特定受給資格者に該当している者として誤っているものはどれか。
<A> 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
<B> 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
<C> 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
<D> 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
<E> 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。

【解答】
②【H30年出題】 <C>
<A> 〇
「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第5号ホ)
<B> 〇
「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号)
<C> ×
以下に当てはまる場合は特定受給資格者に該当します。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由として離職した者。
問題文の「離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働」については、要件に該当しません。
(則第36条第5号ロ、ハ)
<D> 〇
「事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等に伴い、当該事業主に雇用される被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した場合」は特定受給資格者に該当します。
(則第35条第2号、行政手引50305)
<E> 〇
以下の場合は、特定受給資格者に該当します。
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
(則第36条第7号、7号の2)
③【R3年出題】
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
「事業主が労働者の配置転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」を理由に離職した場合は特定受給資格者に該当します。
家族的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等の事情がある場合)を抱える労働者が、遠隔地(通勤するために、概ね往復4時間以上要する場合)に転勤を命じられた場合等は、これに該当します。
問題文の「常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職」した場合は、特定受給資格者に該当します。(則第36条第6号、行政手引50305)
④【H26年出題】
事業主が健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったことで健康障害の生ずるおそれがあるとして離職した者は、当該離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができる。

【解答】
④【H26年出題】 〇
「事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと」により離職した者は、「特定受給資格者」に該当します。
そのため、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、他の要件を満たす限り、基本手当を受給することができます。
(則第36条第5号ニ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害基礎年金と障害厚生年金
R7-212 03.28
障害基礎年金と障害厚生年金の額の計算
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級、2級、3級があります。
国民年金法の条文を読んでみましょう。
国民年金法第33条 ① 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 |
(障害基礎年金の額)
1級 → 2級の額×100分の125
2級 → 78万900円×改定率
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第50条 ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 ③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
第50条③について
・障害基礎年金が支給されない障害厚生年金には最低保障額が設けられています。
最低保障額は、障害基礎年金の額(2級)×4分の3です。
※最低保障額が適用されるのは
・障害等級3級の場合(障害基礎年金が支給されないので)
・老齢年金の受給権を有する65歳以上の者が、厚生年金保険加入中に障害になった場合
(老齢年金の受給権を有する65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者にならないので、1・2級でも障害基礎年金が支給されないからです。)
では、過去問をどうぞ!
<国民年金法>
①【国年R3年出題】
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円に端数処理を行った、976,100円となる。
(注)令和3年度の給付額です。

【解答】
①【国年R3年出題】 ×
・ 障害等級2級の額は、780,900円×改定率で、端数処理は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げます。
・ 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の障害基礎年金×1.25となりますが、端数処理は、原則の方法となり50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
そのため、1級の額は780,900円×1.25=976,125円となります。(ちなみに令和3年度は1円未満の端数が出ませんでした)
<厚生年金保険法>
①【厚年R4年出題】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

【解答】
①【厚年R4年出題】 ×
2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金と同じように計算します。
・被保険者期間は、障害認定日の属する月の「前月」ではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間を基礎とします。
例えば、令和7年3月1日が障害認定日だとすると、計算に入るのは令和7年3月までの被保険者期間です。
・計算の基礎となる月数が300に満たないときは、300で計算します。
②【厚年R1年出題】
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

【解答】
②【厚年R1年出題】 〇
障害等級1級の場合は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(被保険者期間の月数が300未満のときは、300とする。)の100分の125です。
③【厚年R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】
③【厚年R2年出題】 ×
最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の「4分の3」に相当する額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「一部負担金」
R7-211 03.27
療養の給付を受ける場合の一部負担金
療養の給付を受ける場合は一部負担金を支払わなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第74条第1項 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 (1) 70歳に達する日の属する月以前である場合→ 100分の30 (2) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) → 100分の20 (3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき(現役並み所得者) → 100分の30
令第34条第1項 (一部負担金の割合が100分の30となる場合) 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。 |
(70歳未満の場合)
療養に要する費用の額(100万円) | |||||
一部負担金
|
療養の給付 | ||||
30万円 |
|
|
|
|
|
では、過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の< A >以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
<選択肢>
① 前月の標準報酬月額が28万円
② 前月の標準報酬月額が34万円
③ 標準報酬月額が28万円
④ 標準報酬月額が34万円

【解答】
<A> ③ 標準報酬月額が28万円
②【H27年選択式】
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< A >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< B >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
<選択肢>
① 70歳に達する日 ② 70歳に達する日の属する月
③ 70歳に達する日の属する月の翌月 ④ 70歳に達する日の翌日
⑤ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑥ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑧ 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

【解答】
<A> ③ 70歳に達する日の属する月の翌月
<B> ⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
<B>について条文を読んでみましょう。
令第34条 (一部負担金の割合が100分の30となる場合) ① 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。 ② 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 (1) 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者 (2) 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当するものをいう。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が 520万円に満たない者 |
★なお、令第34条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、申請が必要です。
被保険者が70歳以上の場合
■療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上(現役並み所得者)の場合は、一部負担金の割合は「100分の30」です。
ただし、以下の場合は、申請によって「100分の20」となります。
(1)
・ 被保険者と70歳以上の被扶養者を合算した収入が520万円未満
・ 70歳以上の被扶養者がいない場合は、被保険者のみの収入が383万円未満
(2)
・ 被扶養者が後期高齢者医療の被保険者になったため被扶養者でなくなり、70歳以上の被扶養者がいなくなった場合は、その被扶養者であった者の収入を合算して520万円未満
★問題文について
標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者は、一部負担金の割合は3割です。
ただし、「被保険者のみの収入の額が383万円未満」の場合は、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となります。
なお、収入を合算できるのは70歳以上の被扶養者のみです。問題では、被扶養者が67歳の妻のみですので、被扶養者の収入は合算できません。
③【H24年出題】
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。

【解答】
③【H24年出題】 〇
70歳以上・標準報酬月額28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、一部負担金は申請により2割負担となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「労災との調整」
R7-210 03.26
健康保険と労災保険の保険給付の調整
健康保険と労災保険との調整について条文を読んでみましょう。
法第55条第1項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
例えば、労災保険で通勤災害の保険給付を受けることができる場合は、健康保険の保険給付は行われません。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
通勤災害については労災保険からの給付が優先されます。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法の給付が行われる場合は、健康保険の埋葬料は支給されません。
②【H26年出題】
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。

【解答】
②【H26年出題】 ×
「労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害については、それが、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険で給付する」とされています。
ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われません。
(昭48.12.1保険発105・庁保発24)
③【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】
③【H28年出題】 〇
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が行われます。
(H25.8.14事務連絡)
④【R4年出題】
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。

【解答】
④【R4年出題】 ×
「健康保険は、業務外の疾病や負傷等に対して保険給付を行い、労災保険は、業務上の疾病や負傷等に対し保険給付を行います。その条件に当てはまるかどうかは、それぞれの保険者が自らの判断により行うものであるため、労災保険の認定が確定していないことを理由に、健康保険の保険給付の申請を受理しないことは認められないことになります。」
「労災保険給付の請求が行われている場合であっても、健康保険の被保険者は、健康保険の保険者に保険給付の申請を行うことが可能です。」
とされていますので、問題文の場合は、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合でも、健康保険の保険給付の申請は可能です。
(平成24.6.20事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「被扶養者」
R7-209 03.25
健康保険の被扶養者の範囲と要件
健康保険法の「被扶養者」となる範囲と要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
ポイント!
被扶養者の要件を整理しましょう。
① | ・直系尊属 ・配偶者(事実婚を含む。) ・子 ・孫 ・兄弟姉妹 | 主として被保険者により生計を維持するもの (別居でも可) |
② | ・3親等内の親族(①以外) ・事実婚の配偶者の父母及び子 ・事実婚の配偶者の死亡後の父母及び子 | 被保険者と同一の世帯に属している + 主として被保険者により生計を維持するもの |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】 ※改正による修正あり
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。なお、当該63歳の母は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「被保険者の配偶者の母」が被扶養者となるには、「被保険者と同一世帯」+「生計維持」の要件を満たさなければなりません。
「被保険者と別居」している場合は、被扶養者になりません。
②【R1年出題】 ※改正による修正あり
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。なお、認定対象者は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
②【R1年出題】 〇
「被扶養者としての届出に係る者が被保険者と同一世帯に属している」場合の認定基準を確認しましょう。
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する ② ①の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない (S52.4.6保発第9号・庁保発第9号) |
③【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。なお、当該父は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
③【H26年出題】 ×
「認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合」の認定基準を確認しましょう。
| 認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する |
被保険者の父は、被保険者と同一世帯に属していなくても、要件を満たせば被扶養者に該当しますが、父の年収が被保険者からの援助による収入額より少ないことが条件です。
「その援助の額にかかわらず」は誤りです。
(S52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
④【H27年出題】 ※改正による修正あり
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年間100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合は、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、当該母は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
④【H27年出題】 ×
58歳で障害者ではない母の年収が100万円の遺族厚生年金+パート労働による給与120万円=220万円ですので、母は被扶養者になることはできません。
⑤【R3年出題】
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
被扶養者の収入の確認に当たり、「被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むもの」とされています。
(令2.4.10事務連絡)
⑥【R2年出題】
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

【解答】
⑥【R2年出題】 ×
被保険者の配偶者の父は、「生計維持」にプラスして「被保険者と同一世帯」に属していることが要件です。
問題文の場合、当該父は日本国外に居住し同一世帯にありませんので、被扶養者にはなりません。
⑦【H28年出題】※改正による修正あり
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。なお、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
⑦【H28年出題】 〇
後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R7-208 03.24
遺族基礎年金の額についてお話しします
遺族基礎年金の額のポイントをお話しします。
■「配偶者」に支給する場合
→ 必ず、「子」の数に応じた加算額が加算されます。
子がいない場合は、配偶者に遺族基礎年金は支給されません。
■「子」に支給する場合
→ 「子」が1人のみの場合は、加算額はありません。
「子」が2人以上の場合は、加算額が加算されます。
なお、子が2人以上の場合、それぞれの子に支給される額は、「子の数」で除した額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-207 03.23
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年3月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月17日から22日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・法定免除についてお話しします(国民年金法)
・特定理由離職者の範囲(雇用保険法)
・標準報酬月額の定時決定(健康保険法)
・育児休業等期間中・産前産後休業中の健康保険料が免除される期間(健康保険法)
・随時改定の3つの要件(健康保険法)
・法人の役員である被保険者等に係る保険給付の特例(健康保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「法人の役員である被保険者等の保険給付」
R7-206 03.22
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例
法人の役員である被保険者については、その法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷、死亡に対しては、健康保険から保険給付は行われないのが原則です。
ただし例外もあります。
条文を読んでみましょう。
第53条の2 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
則第52条の2 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 |
ポイント!
法人の役員としての業務でも、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務で、従業員が従事する業務と同一であると認められる業務に起因する疾病、負傷、死亡については、保険給付が行われます。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
法人の理事、監事、取締役、代表社員等であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。
(昭24.7.28保発74号)
②【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
②【H30年出題】 〇
・被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者について
・業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合がある
・対象になる業務は、当該法人の従業員が従事する業務と同一であると認められるもの
③【R4年出題】
被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
「5人以上」ではなく「5人未満」です。
「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。」となります。
「傷病手当金」も支給されることがポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「随時改定」
R7-205 03.21
随時改定の3つの要件
「随時改定」とは、固定的賃金の変動があった場合に標準報酬月額を見直すことです。
随時改定に当てはまる要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 随時改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
★随時改定は次の3つの要件を満たした場合に行われます。
① 昇給や降給などで、固定的賃金に変動があったこと。
② 固定的賃金が変動した月からの3か月間に支払われた報酬の平均月額とこれまでの標準報酬月額に2等級以上の差が生じたこと。
③ 継続した3か月の報酬支払基礎日数が各月とも17日以上(短時間労働者は11日以上)あること。
★著しく高低を生じた月の翌月から改定されます
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 固定的賃金の変動 |
| 著しく 高低を生じた月 | 標準報酬月額 改定 |
|
|
|
|
|
例えば、3月に昇給で固定的賃金が変動し、3月、4月、5月の報酬の平均月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合、「6月」から随時改定により、標準報酬月額が改定されます。
「著しく高低を生じた月の翌月」とは「固定的賃金の変動があった月から4か月目」です。
★定時決定との違いに注意しましょう。
「定時決定」→ 17日未満(短時間労働者は11日未満)の月がある場合は、その月を除いて平均を出します。
「随時改定」→ 継続した3か月間に17日未満(短時間労働者は11日未満)の月がある場合は行われません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
・特定適用事業所において被保険者である短時間労働者について
「定時決定」は、報酬支払基礎日数が11日未満の月があるときは、その月を除いて行う。「随時改定」は、継続した3か月間で、各月とも報酬支払基礎日数が11日以上でなければ行わない。
(法第41条第1項、第43条第1項)
②【H26年出題】
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「昇給及び降給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合」は、随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額で算定されます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|
| 昇給差額 |
|
| 改 定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5月+6月+7月の報酬-昇給差額)÷3 |
| ||
・3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた
↓
・随時改定の対象になるのは「5月、6月、7月の3か月間に受けた報酬の総額」÷3の額
ポイント!
「昇給差額」は除いて計算すること
差額が支払われた5月が起算月となること
↓
標準報酬月額が改定されるのは8月から
(法第43条、R5.6.27事務連絡)
③【R3年出題】
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。

【解答】
③【R3年出題】 〇
時給単価の変動はないが、契約時間が変わった場合は、固定的賃金の変動に該当します。
(R5.6.27事務連絡)
④【R4年出題】
被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

【解答】
④【R4年出題】 ×
減給制裁は固定的賃金の変動には当たりません。そのため、随時改定の対象になりません。
(R5.6.27事務連絡)
⑤【H28年出題】
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
「産休等により通勤手当が不支給となっている場合で、通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはならない。」とされています。
(令3.4.1事務連絡)
⑥【H30年出題】
標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
随時改定の要件は、原則として2等級以上の差が生じることです。
ただし、49級→50級、1級→2級、50級→49級、2級→1級の場合、1等級の差でも随時改定が行われることがあります。
<49級→50級、50級→49級>
片方の月額が1,415,000円以上
もう片方の月額が1,295,000円以上1,355,000円未満(49級)
<1級→2級、2級→1級>
片方の月額が53,000円未満
もう片方の月額が63,000円以上73,000円未満(2級)
問題文は、標準報酬月額等級第49級にあったものが、昇給で1,415,000円になっていますので、1等級でも随時改定の対象になり、50等級に改定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険料の免除」
R7-204 03.20
育児休業等期間中・産前産後休業中の健康保険料が免除される期間
育児休業等の期間中、産前産後休業中は、健康保険料が免除されます。
★育児休業等とは、「育児休業及び育児休業に準じる休業」のことで、3歳に満たない子を養育するための休業です。
育児休業等期間の免除について条文を読んでみましょう。
第159条第1項 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
ポイント!
■標準報酬月額に係る保険料の免除について
(1) 「育児休業等開始日」の属する月と「育児休業等終了日」の翌日が属する月が異なる場合
↓
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月
<例>
育児休業等開始日3月20日、育児休業等終了日が6月20日の場合
3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
3月~5月までの保険料が免除されます。
(2) 育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一の場合
↓
当該月における育児休業等の日数が14日以上(ただし、当該被保険者が出生時育児休業を取得する場合には、事業主が当該被保険者を就業させる日数を除く。)である場合は、当該月の保険料が免除されます。
<例>
3月4日に開始、同月25日に終了した場合
3月 | 4月 |
育児休業等開始日 育児休業等終了日の翌日 |
|
3月の育児休業等の日数が14日以上ですので、3月の保険料が免除されます。
■標準賞与額に係る保険料の免除について
「1か月を超える」育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。
<例1>
・3月5日~4月25日まで育児休業等を取得し、3月に賞与が支払われた場合
↓
1か月を超える育児休業等を取得しているので、賞与の保険料が免除されます。
<例2>
・3月14日~4月2日まで育児休業等を取得し、3月に賞与が支払われた場合
↓
1か月以内ですので、賞与の保険料は免除されません。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【R5年出題】- 〇
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和5年1月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月(令和5年3月)
令和5年1月から令和5年3月までの保険料が免除されます。
②【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月」が同一で、育児休業等の期間が14日未満ですので、保険料は免除されません(保険料が徴収されます)。
③【R6年出題】
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
③【R6年出題】 ×
令和5年10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和5年10月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月(令和5年12月)
令和5年10月から12月までの保険料が免除され、令和6年1月分の保険料は免除されません(徴収されます)。
★産前産後休業期間中の免除の問題です
④【R5年出題】
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
問題文の場合、「産前産後休業を開始した日の属する月=令和4年12月」から、「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月=令和5年2月」までの保険料が免除されます。
⑤【R1年出題】
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象となる。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
産前産後休業は、多胎妊娠でない場合は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間です。
出産予定日が5月16日の場合は、産前休業は出産予定日以前42日の4月5日から開始されます。そのため、保険料免除の対象は4月分からとなります。
しかし、問題文のように出産予定日より前の5月10日に出産した場合、産前休業の開始日は、出産日以前42日の3月30日に変更されます。
被保険者は3月25日から出産のため休業していますので、3月分から免除対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「定時決定」
R7-203 03.19
標準報酬月額の定時決定
「定時決定」とは、標準報酬月額を毎年見直すことです。
定時決定について条文を読んでみましょう。
第41条 (定時決定) ① 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ② 定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする ③ 定時決定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定、又は産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 |
<例1>
4月 報酬 249,800円(報酬支払基礎日数20日)
5月 報酬 275,920円(報酬支払基礎日数22日)
6月 報酬 257,430円(報酬支払基礎日数21日)
(249,800円+275,920円+257,430円)÷3≒261,050円(報酬月額)
報酬月額(261,050円)を標準報酬月額等級に当てはめ、
標準報酬月額は、26万円となります。
<例2>
4月 報酬 249,800円(報酬支払基礎日数20日)
5月 報酬 163,800円(報酬支払基礎日数15日)
6月 報酬 257,430円(報酬支払基礎日数21日)
(249,800円+257,430円)÷2≒253,615円(報酬月額)
標準報酬月額は、26万円となります。
ポイント!
17日未満の月は除いて計算しますので、分母は「3」とは限りません。「2」、「1」の場合もあります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされています。
① 月給者については、各月の暦日数によること。
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。
③ 日給者については、各月の出勤日数によること。
問題文の場合、「その月における暦日の数から」ではなく、「就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。
(平18.5.12庁保険発第0512001号)
②【H19年出題】
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)

【解答】
②【H19年出題】 〇
4~6月に支払った賃金で算定します。
問題文の場合、定時決定は、
4月15日支払(3月1日~31日)
+
5月15日支払(4月1日~30日)
+
6月15日支払(5月1日~31日)
で、算定します。
③【R3年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
③【R3年出題】 ×
短時間労働者は、「11日未満」の月を除いて算定します。
問題文は、報酬支払の基礎となった日数が「11日以上」の月である4月、5月、6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行います。
④【H29年出題】
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
6月1日に被保険者資格を取得した者についても、その年の定時決定は行われません。
⑤【H24年出題】
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として「翌年の6月30日までの1年間」ではなく、「翌年の8月」まで用います。
ちなみに、資格取得時に決定された標準報酬月額は、「被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となります。
(法第42条)
⑥【R3年出題】
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

【解答】
⑥【R3年出題】 ×
7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合も、その年の標準報酬月額の定時決定は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「特定理由離職者」
R7-202 03.18
特定理由離職者の範囲
「特定理由離職者」の範囲をみていきましょう
条文を読んでみましょう。
法第13条第3項 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者に該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
則第19条の2 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 (1) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) (2) 法第33条第1項の正当な理由 |
ポイント!
★(1)について
次のいずれにも該当する場合は、「特定理由離職者」となります。
(A) 当該労働契約の更新がないため離職した者
→契約の更新が有ることは明示されているが更新の確約がない場合が、該当します。
(B) 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
→「労働者が希望していたにもかかわらず」とは、労働者本人が契約期間満了日までに契約更新を申し出た場合が該当します。
★注意しましょう!
以下の場合は、「特定受給資格者」となります。
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなった
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された(更新の確約がある)場合において当該契約が更新されないこととなった
★(2)について
法第33条の正当な理由のある自己都合退職者が該当します。
(行政手引50305-2)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。

【解答】
①【H22年出題】 〇
期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約の場合、更新について確約がないこと、また「3年以上引き続き雇用される」に至っていないため、「特定理由離職者」に当たります。
(行政手引50305、則第36条第7号、第7号の2)
②【H22年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者は、特定理由離職者に当たらない。

【解答】
②【H22年出題】 〇
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した」者は、特定理由離職者ではなく「特定受給資格者」に当たります。
(則第36条第2号)
③【R3年出題】
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。

【解答】
③【R3年出題】 〇
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、「特定理由離職者」に当たります。
(行政手引50305-2)
④【H22年出題】
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。

【解答】
④【H22年出題】 〇
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たります。
(行政手引50305-2)
⑤【H27年出題】
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
「期間の定めのない労働契約」、「正当な理由なく離職」の場合は、特定理由離職者の要件に該当しませんので、特定理由離職者にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「法定免除」
R7-201 03.17
法定免除についてお話しします
国民年金法の「法定免除」についてお話しします 。
<内容です>
・法定免除の要件
・法定免除の対象になる被保険者
・免除される期間(いつからいつまで)
・既に納付された保険料はどうなる?
・前納した保険料は還付される?
・法定免除に該当しても保険料を納付できる?
・届出が必要
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-200 03.16
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年3月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月10日から15日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・老齢厚生年金に加算される加給年金額についてお話しします(厚生年金保険法)
・老齢基礎年金の計算式<フルペンション減額方式>(国民年金法)
・3歳未満の子の養育期間の従前標準報酬月額(厚生年金保険法)
・労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外(労基法第41条)
・都道府県労働局に置かれる労働衛生指導医(労働安全衛生法)
・同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合(労災保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「社会保険との調整」
R7-199 03.15
同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合
同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合のポイントを確認しましょう。
同一の事由により、障害補償年金・傷病補償年金・休業補償給付と 厚生年金保険法の障害厚生年金及び国民年金法の障害基礎年金 が支給される場合
同一の事由により、遺族補償年金と 厚生年金保険法の遺族厚生年金及び国民年金法の遺族基礎年金若しくは寡婦年金 が支給される場合
労災保険の年金給付は「政令で定める率」を乗じて得た額(減額された額)となります。 ※厚生年金保険・国民年金の年金は、全額支給され、減額されません。(労働者が自ら保険料を負担しているからです。)
※通勤災害、複数業務要因災害に関する保険給付も同様に減額されます。 (法別表第1、法第14条第2項) |
過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。

【解答】
①【H18年出題】 ×
労災年金と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合は、労災年金は、減額された額が支給されます。
②【H12年出題】
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。

【解答】
②【H12年出題】 〇
年金だけでなく、休業補償給付も、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されます。
(法第14条第2項)
③【H12年出題】
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。

【解答】
③【H12年出題】 〇
労災保険の各種年金給付の額は、「同一の事由」により、厚生年金保険法又は国民年金法の年金を受けることができる場合は、減額されます。
老齢厚生年金、老齢基礎年金を受けることができても、支給事由が異なりますので、労災保険の各種年金給付は減額されません。
④【R5年出題】
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額とする。

【解答】
④【R5年出題】 〇
同一の事由により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となります。
(令第2条)
⑤【R5年出題】
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
障害基礎年金のみを既に受給している者が「新たに」障害補償年金を受け取る場合は、支給事由が異なりますので、障害補償年金の額は、減額されません。
⑥【R5年出題】
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額とする。

【解答】
⑥【R5年出題】 ×
障害基礎年金と遺族補償年金は、支給事由が異なりますので、遺族補償年金は減額されません。
⑦【R5年出題】
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、「0.80」の調整率を乗じて得た額となります。
(令第2条)
⑧【R5年出題】
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
⑧【R5年出題】 ×
遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は減額されません。
⑨【H14年出題】
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。

【解答】
⑨【H14年出題】 ×
厚生年金保険法で、「当該傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には、障害手当金を支給しない。」と定められています。(厚生年金保険法第56条第3号)
同一事由による障害手当金は不支給となり、障害補償一時金又は障害一時金は全額支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法「労働衛生指導医」
R7-198 03.14
都道府県労働局に置かれる労働衛生指導医
「労働衛生指導医」について条文を読んでみましょう。
第95条 (労働衛生指導医) ① 都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。 ② 労働衛生指導医は、第65条第5項又は第66条第4項の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。 ③ 労働衛生指導医は、労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。 ④ 労働衛生指導医は、非常勤とする |
第65条第5項 (作業環境測定) ⑤ 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
第66条第4項 (健康診断) ④ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
★ポイント!
労働衛生指導医は、都道府県労働局長が指示する「作業環境測定の実施」、「臨時の健康診断の実施」について意見を述べます。
練習問題です!
< A >は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< B >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
(選択肢)
① 労働基準監督署長 ② 労働基準監督官 ③ 都道府県労働局長
④ 産業医 ⑤ 労働衛生指導医 ⑥ 労働衛生コンサルタント

【解答】
<A> ③ 都道府県労働局長
<B> ⑤ 労働衛生指導医
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
選択式対策のため、赤字の部分はおぼえましょう。
<都道府県労働局長>は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、<労働衛生指導医の意見>に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を<指示>することができる。
(法第65条第5項、則第42条の3)
②【H23年出題】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

【解答】
②【H23年出題】 〇
選択式対策のため、赤字の部分はおぼえましょう。
<都道府県労働局長>は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、<労働衛生指導医の意見>に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を<指示>することができる。
(法第66条第4項、則第49条)
③【H23年出題】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の精神的健康を保持するために必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。

【解答】
③【H23年出題】 ×
このような規定はありません。
④【H25年出題】
都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定により臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させることができる。

【解答】
④【H25年出題】 〇
条文で確認しましょう。
第96条第4項 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を労働安全衛生法第65条第5項の規定による作業環境測定の実施等の指示又は同法第66条第4項の規定により臨時の健康診断の実施等の指示に関する事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法第41条
R7-197 03.13
労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外(労基法第41条)
労基法第41条に定められた労働者には、「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。
条文を読んでみましょう。
第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外) 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 (1) 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 →農業の事業・水産の事業に従事する者 (2) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 (3) 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの |
ポイント!
★適用除外になるのは、「労働時間・休憩・休日」に関する規定です。
「深夜業」、「年次有給休暇」については適用されます。
★「林業」については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されます。
★監視又は断続的労働に従事する者については、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
過去問をどうぞ!
①【H23年選択式】
労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、< A >及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
(選択肢)
① 深夜業 ② 事業場外のみなし労働時間制
③ フレックスタイム制 ④ 労働時間の通算

【解答】
<A> ① 深夜業
②【H22年出題】
労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。

【解答】
②【H22年出題】 〇
監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者です。
ただし、管理監督者に該当するか否かは、地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断されます。
(昭63.3.14基発150号)
③【H27年出題】
労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも機密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

【解答】
③【H27年出題】 〇
「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいいます。
(昭22.9.13発基17号)
④【R4年出題】
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、労働基準法第36条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

【解答】
④【R4年出題】 〇
宿直又は日直勤務を断続的勤務として許可を受けた場合は、その宿直又は日直の勤務については、労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されません。
そのため、使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、36協定がなくても、休日に日直をさせることができます。
(昭23.1.13基発33号)
⑤【H26年選択式】
小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)として取り扱われるなど不適切な事案もみられるところであることから、平成20年9月9日付け基発0909001号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、< A >において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する< B >となる。」ことがあげられている。
(選択肢)
① 時間単価に換算した賃金額 ② 総賃金額 ③ 平均賃金額
④ 役職手当額 ⑤ 考慮要素 ⑥ 重要な要素 ⑦ 参考 ⑧ 補強要素

【解答】
<A> ① 時間単価に換算した賃金額
<B> ⑥ 重要な要素
(平成20年9月9日基発第0909001号 )
⑥【H25年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を < C >旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
(選択肢)
① 時間帯 ② 長さ ③ 密度 ④ 割増
⑤ 午後10時から午前5時まで ⑥ 午後10時から午前6時まで
⑦ 午後11時から午前5時まで ⑧ 午後11時から午前6時まで
⑨ 行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する
⑩ 厚生労働省令で定める ⑪ 適用する ⑫ 適用しない

【解答】
<A> ② 長さ
<B> ⑤ 午後10時から午前5時まで
<C> ⑫ 適用しない
「管理監督者に該当する労働者は,深夜割増賃金を請求することができる」という点がポイントです。
(平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「養育期間の標準報酬月額の特例」
R7-196 03.12
3歳未満の子の養育期間の従前標準報酬月額
3歳未満の子を養育している期間中に標準報酬月額が低下したとしても、将来の年金額は、子を養育する前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)に基づいて計算される特例をみていきます。
特例が適用されるには、被保険者からの申出が必要です。
条文を読んでみましょう。
第26条第1項、第4項(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例) ① 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。 (1) 当該子が3歳に達したとき。 (2)第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 (3)当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。 (4)当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。 (5)当該被保険者に係る第81条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。 (6)当該被保険者に係る第81条の2の2第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。 ④ 第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者について、①の規定を適用する場合においては、「申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。 |
★従前標準報酬月額のイメージ
→ 将来の年金額は、「従前標準報酬月額」を用いて計算されます。
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3歳未満の子の養育期間 | ||||
従前標準報酬月額 |
|
|
|
|
ポイント!
「従前標準報酬月額」とは
・養育開始月の前月の標準報酬月額のことです。
・養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合は、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前標準報酬月額となります。
「対象となる期間」は
→ 3歳未満の子の養育を開始した月から養育する子が3歳に達したとき等に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までです。
過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに < A >までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前< B >における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
<選択肢>
① 1年以内 ② 1年6か月以内 ③ 2年以内 ④ 6か月以内
⑤ 至った日の属する月 ⑥ 至った日の属する月の前月
⑦ 至った日の翌日の属する月 ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月

【解答】
①【H30年選択式】
<A> ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
<B> ① 1年以内
②【R3年出題】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

【解答】
②【R3年出題】 ×
「標準報酬月額」の特例が適用されるのは、特例の申出が行われた日の属する月前の月については、特例の申出が行われた日の属する月の前月までの「2年間」のうちにあるものに限られています。
★ 特例がさかのぼって適用されるのは、申出が行われた日の属する月の前月までの「2年間」です。
③【R5年出題】
本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事務所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。
※本特例→「厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」のことです。以下同じです。

【解答】
③【R5年出題】 〇
★本特例についての実施機関に対する申出について
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者
→その使用される事務所の事業主を経由して行います
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者
→事業主を経由せず直接行います
④【R5年出題】
本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。

【解答】
④【R5年出題】 ×
保険料額の計算は、従前標準報酬月額ではなく、実際の標準報酬月額を用います。
⑤【R5年出題】
甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。さらに、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
本特例は適用されません。
「従前標準報酬月額」は子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額です。
問題文の甲は、養育を開始した日の属する月の前月(=令和5年5月)は被保険者ではありません。
養育を開始した日の属する月の前月に被保険者でない場合は、「当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月」の標準報酬月額が従前標準報酬月額となります。
しかし「甲」は、「当該月(=令和5年5月)前1年以内に被保険者であった月がありません。
そのため、甲には本特例は適用されません。
⑥【H30年出題】
被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
被保険者の配偶者が出産した場合でも、特例の申出をすることができます。
⑦【H27年出題】
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

【解答】
⑦【H27年出題】 ×
従前標準報酬月額は、子を養育することとなった日の属する月の前月(=問題文の場合は8月)の標準報酬月額です。
定時決定で改定された標準報酬月額240,000円は9月から適用されます。そのため、従前標準報酬月額は、8月の標準報酬月額の280,000円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金」
R7-195 03.11
老齢基礎年金の計算式(フルペンション減額方式)
満額の老齢基礎年金は、780,900円×改定率で計算します。
満額の老齢基礎年金は、「保険料納付済期間」が480月ある場合に支給されます。
免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金が減額されます。
条文を読んでみましょう。
第27条 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。 (1) 保険料納付済期間の月数 (2) 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数 (3) 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数 (4) 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数 (5) 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数 (6) 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数 (7) 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数 (8) 保険料全額免除期間(学生納付特例期間・50歳未満の納付猶予期間に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数 |
老齢基礎年金の額の計算は、「国庫負担」と関連します。
国庫負担については、こちらをどうぞ
→http://www.syarogo-itonao.jp/17370185749152
★老齢基礎年金の計算式については下の図をどうぞ
★例えば、
・保険料納付済期間400月
・4分の3免除期間の月数40月
・全額免除期間の月数40月
の場合の計算式は以下のようになります。
780,900円 ×改定率 | × | 400月+40月×8分の5(25月)+40月×2分の1(20月) |
480 |
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。
(法第27条第4号)
②【R4年出題】
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
②【R4年出題】 ×
「納付猶予の期間」及び「学生納付特例の期間」は、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されません。
(法第27条第8号、H16法附則第19条第4項、H26法附則第14条第3項)
③【R4年出題】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
③【R4年出題】 ×
老齢基礎年金では、第2号被保険者の20歳未満と60歳以降の期間は「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の額には反映しません。
問題文では、60歳から65歳までの5年間は合算対象期間ですので、老齢基礎年金を計算するための保険料納付済期間は、37年間です。
そのため、老齢基礎年金の額は満額にはなりません。
(S60法附則第8条第4項)
④【R5年出題】
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の負担割合も免除の種類に応じて異なっている。

【解答】
④【R5年出題】 ×
国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたのは、平成15年4月1日以降ではなく、「平成21年4月1日」以降です。
ちなみに、「保険料の全額免除期間」については、その後追納しない場合、
・平成21年4月1日前の分 → 3分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます
・平成21年4月1日以降の分 → 2分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます
(H16法附則第9条、第10条)
⑤【R3年出題】
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、 60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円※令和3年度の給付額)となる。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
問題文は、満額にはなりません。
ポイント!
・保険料納付済期間「1」が反映する期間
→ 30歳から60歳までの30年間+60歳から65歳までの5年間=35年間
・全額免除期間(20歳から30歳までの10年間)のうち、国庫負担が行われる期間
■ 全額免除期間について、国庫負担が行われるのは、「480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数」が限度です。
■ 問題の場合は、480から保険料納付済期間の月数(35年×12=420月)を控除して得た月数である「60月(5年間)」について、3分の1の国庫負担が行われます。※平成21年4月前の期間なので、「3分の1」となります。
■ 全額免除期間のうち残りの5年は国庫負担が行われないので、年金額に反映しません。
■ 老齢基礎年金の額に反映するのは、420月+60月×3分の1となり、満額にはなりません。
(法第27条、H16法附則第10条第15項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
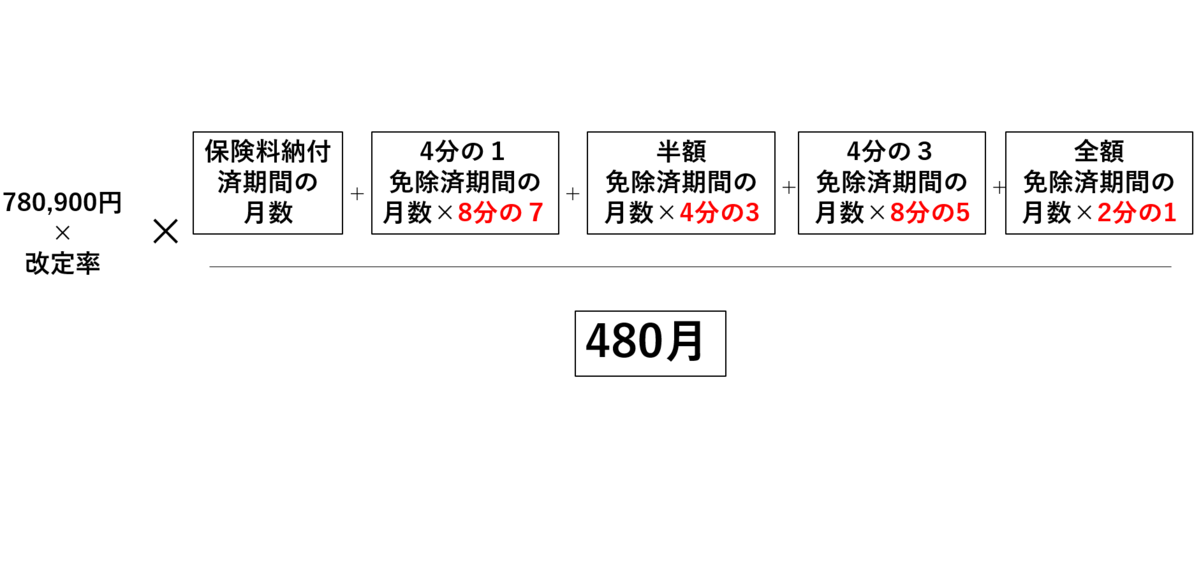
厚生年金保険法「加給年金額」
R7-194 03.10
老齢厚生年金に加算される加給年金額についてお話しします
老齢厚生年金の受給権者に、生計を維持する「配偶者・子」がいる場合は、加給年金額が加算されます。
(今日の内容です)
・加給年金額の加算対象になる「配偶者・子」の要件
・加給年金の額と特別加算
・加給年金額が減額されるとき
・配偶者に係る加給年金額が支給停止されるとき
・子に係る加給年金額が支給停止されるとき
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-193 03.09
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年3月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年3月3日から8日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・遺族基礎年金の失権事由についてお話しします(国民年金法)
・解雇が制限される期間と例外(労基法)
・遺族補償一時金を受けることができる遺族(労災保険法)
・高年齢雇用継続給付「支給対象月」について(雇用保険法)
・労働保険料の精算(確定保険料の申告と納付)(労働保険徴収法)
・任意継続被保険者の資格取得と喪失(健康保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険法>任意継続被保険者
R7-192 03.08
任意継続被保険者の資格取得と喪失
健康保険の資格を喪失した後も、任意で健康保険に加入することができます。
「任意継続被保険者」の資格取得と喪失をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第3条第4項 「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
第37条 ① 任意継続被保険者となる申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 ② 申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 (1) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 (2) 死亡したとき。 (3) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 (4) 被保険者となったとき。 (5) 船員保険の被保険者となったとき。 (6) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 (7) 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
保険者は、「正当な理由があると認めるとき」は、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされています。
②【R4年出題】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
例えば、3月8日退職、翌日の9日に資格を喪失した場合で考えてみましょう。
・任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日(=3月8日)まで継続して2か月以上被保険者であることが条件です。
・任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月(=3月)から算定されます。
(法第157条第1項)
③【R3年出題】
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。

【解答】
③【R3年出題】 ×
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。
ただし、「その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたとき」は、任意継続被保険者となることができます。
④【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

【解答】
④【H27年出題】 ×
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、納付期日の翌日に資格を喪失します。
なお、任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「その月の10日」ですので、保険料の納付期日までに納付しなかったときは、11日に資格を喪失します。
⑤【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。
⑥【R6年出題】
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑥【R6年出題】 ×
「その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」は、その翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
例えば、3月8日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪失日となり、3月分の保険料の納付が必要です。
⑦【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失します。
(令3.12.27事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働保険徴収法>確定保険料
R7-191 03.07
労働保険料の精算(確定保険料の申告と納付)
労働保険料は、「申告制」で納付することになっています。
■継続事業・一括有期事業の場合
労働保険料は、「保険年度」単位で、申告・納付することになっています。
保険年度の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、保険年度の終了後に、「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。
■有期事業の場合
労働保険料は、事業の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、事業終了後に「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。
今回は、「確定保険料」の申告と納付の手続きをみていきます。
条文を読んでみましょう。
★継続事業・一括有期事業の確定保険料(一般保険料について) 第19条第1項 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から 40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。 (一般保険料の額) ・その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定する
★有期事業の確定保険料(一般保険料について) 第19条第2項 有期事業については、その事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。 (一般保険料の額) ・当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定する |
「賃金総額」の違いを確認しましょう。
★概算保険料
「賃金総額の見込額」で計算します。
★確定保険料
実際に支払った「賃金総額」で計算します。
過不足の精算について条文を読んでみましょう。
第19条 ③ 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書に添えて、「継続事業・一括有期事業」にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。
⑥ 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(雇用)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】(雇用) 〇
申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官です。
納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、確定保険料申告書の提出は必要です。
(則第38条)
②【R6年出題】(雇用)
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】(雇用) ×
・前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の確定保険料について
「次の保険年度の6月1日から40日以内」に提出しなければなりません。
「当日」起算ですので、「7月10日」が提出期限です。
・保険年度の中途に保険関係が消滅した場合
「保険関係が消滅した日から50日以内」に提出しなければなりません。
こちらも「当日」起算です。
問題文の場合、「3月31日」に事業が廃止されているので、翌日の「4月1日」に保険関係が消滅します。
4月1日(当日)から起算して50日以内ですので、期限は、5月10日ではなく「5月20日」です。
(法第19条)
③【R6年出題】(雇用)
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
③【R6年出題】(雇用) ×
有期事業の確定保険料申告書は、「保険関係が消滅した日から50日以内」に提出しなければなりません。なお、「当日」起算です。
3月31日に事業が終了した場合、翌日の4月1日に保険関係が消滅します。
4月1日(当日)から起算して50日以内ですので、期限は5月20日となります。
(法第19条)
④【H26年出題】(雇用)
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
④【H26年出題】(雇用) 〇
6月30日に事業が廃止された場合、翌日の7月1日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書は、7月1日(当日)から起算して50日以内ですので、その年の8月19日が期限となります。
(法第19条)
⑤【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

【解答】
⑤【R5年出題】(雇用) ×
事業の廃止が10月31日の場合、保険関係は11月1日に消滅します。
確定保険料申告書は、11月1日(当日)から起算して50日以内ですので、12月20日が期限です。
(法第19条)
⑥【R1年出題】(労災)
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
⑥【R1年出題】(労災) ×
労働保険料還付請求書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく、「官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出しなければなりません。
還付を受ける場合は、請求が必要です。
・ 確定保険料申告書を提出する際に、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)はその超過額を還付します。
・ 還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他徴収金に充当します。
(則第36条、第37条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<雇用保険法>高年齢雇用継続給付
R7-190 03.06
高年齢雇用継続給付「支給対象月」について
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)は、「支給対象月」単位で支給されます。
今回は、「支給対象月」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
(高年齢雇用継続基本給付金) 第61条第2項 「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
ポイント!
「支給対象月」は「暦月」単位です。
図でイメージしましょう。
(高年齢再就職給付金) 第61条の2第2項 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
★再就職後の支給対象月について
高年齢再就職給付金の支給期間を確認しましょう。
・支給残日数が200日以上の場合
就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年を経過する日の属する月までの期間内にある月
・支給残日数が100日以上200日未満の場合
就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して1年を経過する日の属する月までの期間内にある月
※ただし、2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合は、65歳に達する日の属する月までとなります。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

【解答】
①【R1年出題】 〇
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年未満の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
しかし、その後継続雇用され5年に達した場合は資格ができますので、「5年に達する日の属する月」から「65歳に達する日の属する月」まで高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
②【H22年出題】
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。

【解答】
②【H22年出題】 〇
高年齢再就職給付金は、「就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(又は1年)を経過する日の属する月」まで支給されますが、その前に65歳に達した場合は、65歳に達する日の属する月までとなります。
そのため、基本手当の支給残日数にかかわらず、65歳に達する日の属する月よりも後の月については支給されません。
③【H27年出題】
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。

【解答】
③【H27年出題】 〇
「支給対象月」には、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者である」という要件があります。
暦月の途中で、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合は、その月は初日から末日まで引き続いて被保険者である月ではありませんので、高年齢雇用継続給付は支給されません。
④【R1年出題】
再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
例えば、3月6日に再就職した場合、3月は初日から末日まで引き続いて被保険者である月ではありません。そのため3月は支給対象月ではなく、高年齢再就職給付金は支給されません。
⑤【R4年出題】
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。」とされています。
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合は、支給対象月にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労災保険法>遺族補償一時金
R7-189 03.05
<労災>遺族補償一時金を受けることができる遺族
今回は、遺族補償一時金を受けることができる遺族についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第16条の7 ① 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 配偶者 (2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 (3) 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 ② 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。 |
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。
① | 配偶者(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく) |
② | 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた 子、父母、孫、祖父母 |
③ | 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった 子、父母、孫、祖父母 |
④ | 兄弟姉妹(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく) |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
<A> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
<B> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
<C> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
<D> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
<E> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

【解答】
①【R3年出題】
<A> ×
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より「後順位」となります。
配偶者は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、第1順位です。
<B> 〇
生計を維持していた祖父母は、生計を維持していなかった父母より先順位です。
<C> 〇
生計を維持していた孫は、生計を維持していなかった子より先順位です。
<D> 〇
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった子より後順位です。
兄弟姉妹は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、順位は最後です。
<E> 〇
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった父母より後順位です。
②【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
②【H25年出題】 〇
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
③【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることもあります。
<例>
・遺族補償年金を受けていた死亡労働者の妻が再婚し、遺族補償年金が失権。他に遺族補償年金の受給権者がいない場合で
↓
・妻に支給された遺族補償年金の額の合計が1000日未満の場合
↓
・1000日分との差額が遺族補償一時金として妻に支給されます
※身分は、労働者の死亡当時の身分関係で判断されます。再婚したとしても、労働者の死亡当時は労働者の妻だったので、一時金を受ける資格があります。
④【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
④【H18年出題】 ×
遺族補償給付には、「年金」と「一時金」があります。
「年金」は「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」が絶対条件です。
しかし「一時金」は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなくても、対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働基準法>解雇制限
R7-188 03.04
解雇が制限される期間と例外
労働基準法では、解雇が禁止される期間を設けています。
条文を読んでみましょう。
法第19条 ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
★解雇制限期間と例外を確認しましょう。
解雇が禁止される期間 | 例外で解雇できる場合 |
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間+その後30日間 | ・打切補償を支払う場合(行政官庁の認定不要) ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定を受けること) |
②産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間+その後30日間 | ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定を受けること) |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
・就業規則で定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めている。
・従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっている。
↓
定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しません。
(昭26.8.9基収3388号)
②【H29年出題】
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
業務上の傷病により治療中でも、休業しないで就労している場合は、解雇は制限されません。
解雇が制限されるのは「休業する期間+30日間」です。
(昭24.4.12基収1134号)
③【R1年出題】
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
③【R1年出題】 〇
産前の休業を請求しないで就労している場合は、解雇は制限されません。
(昭25.6.16基収1526号)
④【H26年出題】
労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。

【解答】
④【H26年出題】 〇
産前産後の女性の解雇が制限されるのは、「第65条の規定によって休業する期間+その後30日間」です。
第65条で規定される産後の休業は、「産後8週間」です。
そのため、産後8週間を超えて休業している期間は、解雇は制限されません。
産後8週間を超えて休業していても、解雇が制限されるのは、「産後8週間及びその後の30日間」となります。
⑤【H30年出題】
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
「税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合」は、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には当たりません。
(昭63.3.14基発150号)
⑥【R5年出題】
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。

【解答】
⑥【R5年出題】 〇
「従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合」は、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に当たりません。
(昭63.3.14基発150号)
⑦【H28年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第19条第1項の解雇制限が解除されるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法〔労働基準法〕において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法〔労災保険法〕に基づく保険給付が行われている場合とで、同項〔労働基準法第19条第1項〕ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には< A >として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が< A >の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後< B >を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による< A >の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」

【解答】
<A> 打切補償
<B> 3年
(最高二小平27.6.8)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>遺族基礎年金
R7-187 03.03
遺族基礎年金の失権事由についてお話しします<国年>
「遺族基礎年金」を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者又は子」です。
・配偶者と子の共通の失権事由 ・配偶者特有の失権事由
・子特有の失権事由をみていきましょう。
★特によく出題されるのは、「配偶者の遺族基礎年金が失権する事由」です。
(例)遺族が配偶者と子1人の場合で、その子が18歳の年度末を終了したときは、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-186 03.02
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年2月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月14日から3月1日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・老齢厚生年金の計算についてお話しします(厚生年金保険法)
・保険年度の中途で保険料率の引上げを行ったときの「追加徴収」(徴収法)
・出産手当金の支給期間・支給額など(健康保険法)
・付加年金は老齢基礎年金とワンセット(支給要件と年金額)(国民年金法)
・厚生年金保険の被保険者期間44年以上の場合の特例(厚生年金保険法)
・後期高齢者医療制度の内容と対象者(高齢者医療確保法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
高齢者医療確保法「後期高齢者医療制度」
R7-185 03.01
後期高齢者医療制度の内容と対象者
後期高齢者医療は、原則として75歳以上の人が対象です。
75歳になるまでは、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法)の加入者となります。
では、後期高齢者医療制度について条文を読んでみましょう。
第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 (1) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (2) 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合を設けるのは、都道府県ではなく「市町村」です。
②【H22年出題】
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
『「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、「政令」で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。』となります。
③【H29年出題】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとされています。死亡に関する給付も行っています。
なお、出産に関する給付はありません。
④【H22年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

【解答】
④【H22年出題】 ×
年齢が誤りです。
70歳以上ではなく「75歳以上の者」、「65歳以上70歳未満」ではなく「65歳以上75歳未満の者であって・・・」となります。
⑤【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療の適用が除外されます。
⑥【R5年出題】
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
⑥【R5年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
問題文の誤りの部分は、「都道府県」ではなく「後期高齢者医療広域連合」、「高齢者医療確保法の定めるところにより」ではなく、「条例の定めるところにより」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「長期加入者の特例」
R7-184 02.28
厚生年金保険の被保険者期間44年以上の場合の特例
長期加入者の特例は、60歳台前半の老齢厚生年金が、「報酬比例部分」のみになる場合が対象です。
要件を満たした場合、定額部分・加給年金額が加算されます。
例えば、昭和28年4月2日生まれの男子が長期要件に該当した場合
61歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
定額部分(特例) | 老齢基礎年金 |
★長期加入者の特例が適用される要件を確認しましょう。(法附則第9条の3)
・厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けていること
・厚生年金保険の被保険者でないこと(退職していること)
・請求手続きは不要
・加給年金額の対象者がいる場合は、加給年金額も加算される
過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
(1) 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
(2) 被保険者期間が< A >以上であるとき
(3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が< B >以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 < C >であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、< D >である。
(選択肢)
A | ① 42年 ②43年 ③44年 ④45年 |
B | ① 10年 ②15年 ③20年 ④25年 |
C | ① (1)及び(2) ② (1)、(2)及び(3) ③ (2)のみ ④ (2)及び(3) |
D | ① (1)のみ ② (1)及び(2) ③ (1)及び(3) ④ (1)、(2)及び(3) |

【解答】
①【H27年選択式】
<A> ③ 44年
<B> ② 15年
<C> ① (1)及び(2)
<D> ① (1)のみ
ポイント!
・ 報酬比例部分に定額部分が加算される特例には、(1)「障害者の特例」、(2)「長期加入者の特例」、(3)「坑内員・船員の特例」の3つのパターンがあります。
・ 「被保険者でない」という要件があるものは、(1)「障害者の特例」と(2)「長期加入者の特例」です。
・ 受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)なものは、(1)「障害者の特例」のみです。
②【R6年出題】
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
長期加入者の特例が適用される条件は、「厚生年金保険の被保険者でないこと」です。問題文は、「第1号厚生年金被保険者として在職中である」となっていますので、老齢厚生年金の額の計算に係る特例は適用されません。
③【R3年出題】
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外の被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

【解答】
③【R3年出題】 ×
44年の計算については、2以上の種別の被保険者であった期間は、合算されません。
問題文の第1号厚生年金被保険者としての4年と第2号厚生年金被保険者としての40年は合算できませんので、定額部分は加算されません。
(法附則第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「付加年金」
R7-183 02.27
付加年金は老齢基礎年金とワンセット(支給要件と年金額)
付加保険料(月400円)を納付した場合、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
条文を読んでみましょう。
第43条 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
第48条 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。
第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は対象となりません。
②【R4年出題】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

【解答】
②【R4年出題】 ×
付加保険料に係る納付済期間が60月ある場合の付加年金の額は、400円ではなく、「200円」に60月を乗じて得た額です。
付加保険料の月額が400円ですので、60月納付した場合、納付した付加保険料の総額は24,000円、支給される付加年金は1年あたり12,000円です。2年受給すると納付した付加保険料と同額になります。
③【H29年出題】
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

【解答】
③【H29年出題】 ×
付加年金の額は、改定率による改定はありません。200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で計算します。
④【R5年出題】
老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。

【解答】
④【R5年出題】 ×
老齢基礎年金と付加年金はワンセットです。老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合は、付加年金も繰上げて支給され、老齢基礎年金と同じ率で減額されます。
(法附則第9条の2第6項)
⑤【H29年出題】
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金も支給が繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
(法第46条)
⑥【H20年出題】
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。

【解答】
⑥【H20年出題】 ×
付加年金が支給停止されるのは、「老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているとき」です。「全部又は一部」ではありません。
⑦【R4年出題】
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。

【解答】
⑦【R4年出題】 〇
老齢基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も老齢基礎年金とセットで支給されます。
(法第20条)
⑧【R4年出題】
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

【解答】
⑧【R4年出題】 〇
障害基礎年金を受給することを選択したときは、老齢基礎年金の支給は停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると、付加年金もセットで支給が停止されます。
(法第20条、第47条)
⑨【H26年出題】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。

【解答】
⑨【H26年出題】 ×
65歳以上については、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も支給されます。
(法第20条)
⑩【H21年出題】
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

【解答】
⑩【H21年出題】 ×
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を取得し、遺族基礎年金を選択した場合は老齢基礎年金の支給が停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると付加年金の支給も停止されます。
(法第20条、第47条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「出産手当金」
R7-182 02.26
出産手当金の支給期間・支給額など
出産手当金について条文を読んでみましょう。
第102条 ① 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 ② 第99条第2項及び第3項の規定(傷病手当金の額)は、出産手当金の支給について準用する。
第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額(傷病手当金の額)より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 |
出産手当金が支給される期間をイメージしましょう。
|
| 出産日 | 出産の 翌日 |
|
|
|
産前休業 42日(多胎妊娠98日) | 産後休業 56日 | |||||
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)< A >(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日< B >までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。

【解答】
①【H30年選択式】
<A> 以前42日
<B> 後56日
②【H18年出題】
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。

【解答】
②【H18年出題】 〇
出産予定日より遅れて出産した場合は、その分、産前休業の期間が延長されます。
|
| 出産 予定日 |
| 出産日 | 出産の 翌日 |
|
|
|
42日 | 5日 | 56日 | ||||||
産前休業 | 産後休業 | |||||||
問題文の場合は、産前休業は42日+5日=47日、産後休業は、出産の翌日から56日となります。
(昭31.3.14保文発1956号)
③【R2年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

【解答】
③【R2年出題】 ×
出産手当金が支給されるのは、「労務に服さなかった期間」です。
「通常の労務に服している期間」は、出産手当金は支給されません。
④【R4年出題】
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

【解答】
④【R4年出題】 〇
出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中でも出産手当金が支給されます。
なお、出産手当金が支給される場合で、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額が調整されます。
(平11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)
⑤【R4年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】
⑤【R4年出題】 〇
出産手当金の支給要件と傷病手当金の支給要件を、同時に満たした場合は、出産手当金の支給が優先されます。
・出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている
→ 傷病手当金は支給されません。
・出産手当金の額が傷病手当金の額より少ない
→差額の傷病手当金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「概算保険料の追加徴収」
R7-181 02.25
保険年度の中途で保険料率の引上げを行ったときの「追加徴収」
今回は、概算保険料の追加徴収です。
条文を読んでみましょう。
法第17条 (概算保険料の追加徴収) ① 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。 ② 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
則第26条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 (1) 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 (2) 納期限 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
政府が、保険年度の中途に保険料率の引上げを行ったときの追加徴収は、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」行われることがポイントです。
②【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。

【解答】
②【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収される概算保険料の納付は、「納付書」によって行われます。納入告知書ではありません。
(則第38条)
③【R4年出題】(雇用)
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

【解答】
③【R4年出題】(雇用) 〇
追加徴収される概算保険料は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなります。
事業主は、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はありません。
④【H22年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。

【解答】
④【H22年出題】(労災) ×
追加徴収の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
⑤【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、延納することはできない。

【解答】
⑤【H30年出題】(労災) ×
追加徴収される概算保険料は、延納することができます。
ただし、元々の概算保険料の延納を行う事業主に限られています。
(則第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険「老齢厚生年金」
R7-180 02.24
老齢厚生年金の計算についてお話しします
老齢厚生年金は、「老齢基礎年金」に上乗せされる年金です。
65歳以上で、老齢基礎年金の受給要件を満たしていて、かつ、1か月でも厚生年金保険の被保険者期間があれば、支給されます。
<今日のお話の内容です>
・総報酬制導入前、導入後の計算の違い
・在職定時改定について
・退職時改定について
よく出るポイントを中心にお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-179 02.23
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年2月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月17日から22日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・事後重症の障害基礎年金についてお話しします(国民年金法)
・子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう(国民年金法)
・「配偶者・子」に対する遺族厚生年金の調整(厚生年金保険法)
・妊産婦の「変形労働時間制の適用」・「時間外労働・休日労働・深夜労働」(労働基準法)
・遺族補償年金の受給資格者と受給権者(労災保険法)
・公共職業訓練等を受講する場合の「訓練延長給付」(雇用保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<雇用保険法>訓練延長給付
R7-178 02.22
公共職業訓練等を受講する場合の「訓練延長給付」
基本手当の所定給付日数の延長制度として、「訓練延長給付」、「個別延長給付」、「広域延長給付」、「全国延長給付」、「地域延長給付」の5つが設けられています。
今回は、「訓練延長給付」をみていきます。
訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象で、3つの期間があります。
①所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間
②受講している期間
③受講終了後
要件に該当した場合、所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができます。
★対象者は以下の要件を満たす者です。(行政手引52352)
・ 公共職業訓練等の受講を指示した日において受給資格者であること
・公共職業 安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること。
・公共職業訓練等の期間が2年以内のものを受ける者であること。
① 公共職業訓練等を受けるために待期している期間
→ 公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 90 日間の期間内の失業している日が対象です。 (行政手引52353) |
② 公共職業訓練等を受講している期間
→ 公共職業訓練等を受講している場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間の失業している日が対象です。(2年が限度) (行政手引52354) |
③ 公共職業訓練等を受け終わった後
→ 公共職業訓練等を受け終わった者については、(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものが対象です。 (イ) 当該公共職業訓練等を受け終わる日における支給残日数が 30日に満たない者 (ロ) 公共職業安定所長が政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めた者 (行政手引52355) |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「1年以内」ではなく、「2年以内」のものに限られています。
(第24条、令第4条)
②【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日も、訓練延長給付の支給対象となります。
公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 90 日間の期間内の失業している日が対象です。
(法第24条、令第4条)
③【R5年出題】
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

【解答】
③【R5年出題】 〇
終了後については、「30日」がキーワードです。
(第24条、令第5条)
④【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

【解答】
④【R2年出題】 〇
訓練延長給付の日額は本来の基本手当の日額と同額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労災保険法>遺族補償年金
R7-177 02.21
<労災>遺族補償年金の受給資格者と受給権者
労災保険法の「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今回は「遺族補償年金」の対象になる遺族についてみていきます。
遺族補償年金には「受給資格者」と「受給権者」があります。
遺族補償年金を受ける資格のある遺族が「受給資格者」です。受給資格者には、順位があり、その中の最先順位の遺族が実際に年金を受給する「受給権者」となります。
受 給 資 格 者 | ① | 受給権者 |
② |
| |
③ |
| |
④ |
| |
⑤ |
|
なお、遺族補償年金には「転給」の制度があります。
①の遺族が失権した場合は、②の遺族に受給権が移ります。
では、条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項~第3項 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 (3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 (4) 前3号の要件(年齢要件)に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
③ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。 |
ポイント!
・労働者の死亡当時、労働者の収入によって生計を維持していたものが対象です。
・妻以外は、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たしていることが必要です。
★昭40法附則第43条について
・夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものも遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。
・ただし、その者が60歳に達する月までの間は、遺族補償年金は支給停止されます。(若年停止)といいます。
★受給資格者の順位は次のようになります。
① | 「妻」又は「60歳以上又は障害状態の夫」 |
② | 18歳の年度末までの間にある又は障害状態の子 |
③ | 60歳以上又は障害状態の父母 |
④ | 18歳の年度末までの間にある又は障害状態の孫 |
⑤ | 60歳以上又は障害状態の祖父母 |
⑥ | 18歳の年度末までの間にある又は60歳以上又は障害状態の兄弟姉妹 |
⑦ | 55歳以上60歳未満の夫 |
⑧ | 55歳以上60歳未満の父母 |
⑨ | 55歳以上60歳未満の祖父母 |
⑩ | 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
遺族補償年金は、業務上の即死又は業務上の負傷若しくは疾病に起因する死亡の場合に支給されます。
傷病補償年金の受給者がその傷病が原因で死亡した場合は、業務上の死亡となり、遺族補償年金が支給されます。
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

【解答】
②【H28年出題】 ×
「生計を維持していた」とは、「専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態があれば足りる。共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになる」とされています。
問題文の「労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻」は、「生計を維持していた」に当たりますので、遺族補償年金を受けることができます。
(昭41.1.31基発73号)
③【H19年出題】
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】
③【H19年出題】〇
遺族の要件の一つである「厚生労働省令で定める障害の状態」のキーワードは、「第5級以上」、「労働が高度の制限を受ける」の部分です。
なお、この規定は、複数事業労働者遺族年金にも準用されます。
(則第15条)
④【R5年出題】
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。

【解答】
④【R5年出題】 ×
夫については、労働者の死亡当時、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
「障害の状態にない50歳の夫」は、両方とも満たしていませんので、遺族補償年金は受けられません。
⑤【R2年出題】
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
「子」については、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
・19歳の大学生について
→「年齢要件」を満たしていませんので、受給資格者になりません。なお、「障害要件」を満たしていれば受給資格者となります。
・17歳の高校生について
→「年齢要件」を満たしていて、かつ、「定期的に養育費を送金されていた=生計を維持されていた」ので、受給資格者となります。
⑥【R5年出題】
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

【解答】
⑥【R5年出題】 ×
「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす」とされています。生まれたときから、受給資格者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働基準法>妊産婦
R7-176 02.20
妊産婦の「変形労働時間制の適用」・「時間外労働・休日労働・深夜労働」
母性保護のため、妊産婦については、「変形労働時間制の適用」が制限され、「時間外労働・休日労働・深夜労働」が禁止されています。
ただし、「妊産婦が請求した場合」に限られていることがポイントです。個人差に配慮したためです。
では、条文を読んでみましょう。
第66条 ① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の規定にかかわらず、1週間についての法定労働時間、1日についての法定労働時間を超えて労働させてはならない。 ② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、「災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合」及び「公務のため臨時の必要がある場合」並びに「36協定による場合」にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
①について
→「フレックスタイム制」は制限されません。
→「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の適用を禁止する意味ではありません。
制限される時間は、変形労働時間制によって、1日又は1週間の法定労働時間を超える時間です。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

【解答】
①【H25年出題】 〇
妊産婦が請求した場合は、第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項の規定(36協定による場合)にかかわらず、時間外労働・休日労働は禁止されます。
②【R3年出題】
労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

【解答】
②【R3年出題】 ×
監督又は管理の地位にある者には、労働時間に関する規定が適用されません。
妊産婦で監督又は管理の地位にある者についても、労働時間に関する規定は適用されません。
そのため、妊産婦から請求があった場合でも、監督又は管理の地位にある者の場合は、「労働時間に関する規定」は適用されません。
★妊産婦で監督又は管理の地位にある者には、「妊産婦の労働時間に関する規定(「変形労働時間制の適用の制限」、「時間外労働・休日労働の禁止」)は適用されません。
(昭61.3.20基発第151号)
③【H19年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。

【解答】
③【H19年出題】 ×
第66条第2項の規定は、第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦には適用されません。
(昭61.3.20基発第151号)
④【H17年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【解答】
④【H17年出題】 ×
監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働をさせることはできます。
ただし、「深夜」の規定は監督又は管理の地位にある者にも適用されます。そのため、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があった場合は、深夜業をさせることはできません。
(昭61.3.20基発第151号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<厚生年金保険法>遺族厚生年金
R7-175 02.19
「配偶者・子」に対する遺族厚生年金の調整
遺族厚生年金の「配偶者と子」に対する支給停止事由をみていきましょう。
遺族厚生年金の遺族の順位は、「配偶者及び子」→「父母」→「孫」→「祖父母」の順です。
「配偶者と子」は同じ順位で、配偶者と子で調整されます。
原則は「配偶者」が優先しますが、例外もおさえましょう。
条文を読んでみましょう。
第66条 ① 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文(60歳未満の夫に対する支給停止、次項本文(次の②)又は次条(所在不明による支給停止)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 ② 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定(所在不明による支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
第67条 ① 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② 配偶者又は子は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、「配偶者」が優先しますので、子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。
なお、問題文のように、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。子に対する遺族厚生年金は引き続き支給が停止されます。
「国民年金法の遺族基礎年金」との違いに注意してください。
こちらの記事と比較してください。
↓
http://www.syarogo-itonao.jp/17397987862029
「子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう」
②【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【解答】
②【R3年出題】 ×
「妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。」が誤りです。子の遺族厚生年金の支給停止は解除されず、引き続き支給停止されます。
妻が「障害基礎年金と障害厚生年金」を選択し、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」が全額支給停止となった場合でも、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金については、引き続き支給停止となります。
③【R5年出題】
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

【解答】
③【R5年出題】 〇
★ 「遺族厚生年金」については、母と同居することになったとしても、子に対する遺族厚生年金は支給停止となりません。
★ 「子に対する遺族基礎年金」は「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」は、その間、その支給が停止されます。
違いに注意しましょう。
④【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
※本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。

【解答】
④【H26年出題】 〇
配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合で、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、配偶者の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。
下の図でイメージしましょう。
⑤【R4年選択式】
厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、< A >である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
(選択肢)
① V ② W ③ Y ④ Z

【解答】
⑤【R4年選択式】
<A> ② W
それぞれに発生する年金の受給権を確認しましょう。
・Xの妻Y
→ 遺族厚生年金の受給権のみ発生
※Xの子と生計を同じくしていないため、Yには遺族基礎年金の受給権は発生しません。
・Yの先夫との子であるZ(XとZは養子縁組をしていない)
→ 遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。
「子」は死亡した者の実子か養子であることが条件です。Zは死亡したXと養子縁組をしていないので「子」になりません。
・Xの先妻であるV
→ Xの妻ではありませんので、遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。
・XとVとの子W
→ Xの子で、かつXによって生計を維持されていた(養育費の支払い)ので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給権が発生します。
★「Xの妻Y」と「XとVとの子W」に遺族厚生年金の受給権が発生しますが、「Xの妻Y」には遺族基礎年金の受給権がありません。
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が遺族基礎年金の受給権を有する」状態ですので、妻の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。
遺族厚生年金が最初に支給されるのは、「XとVとの子W」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>遺族基礎年金
R7-174 02.18
子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう
遺族基礎年金には「支給停止」規定があります。
今回は、「子」独自の支給停止事由を見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第41条第2項 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項(受給権者の申出による年金の支給停止)又は次条第1項の規定(配偶者の所在が1年以上明らかでないときに、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請による支給停止)によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
第42条第1項、第2項 ① 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② 遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる |
では、過去問をどうぞ!
①【R6年出題】
第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。

【解答】
①【R6年出題】 ×
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、原則として「支給停止」されます。
問題文の場合は、「夫」が遺族基礎年金を受給し、その間は、「子」に対する遺族基礎年金が支給停止されます。
★第2号被保険者である妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫と16歳の子がいる場合
→ 夫には「遺族基礎年金」の受給権が発生しますが、年齢要件を満たさないので遺族厚生年金の受給権は発生しません。16歳の子には「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の受給権が発生します。
この場合、夫が遺族基礎年金を受給し、子は遺族厚生年金のみ受給します。
②【H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるのが原則です。
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、例外で、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
③【H30年出題】
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
(本問における子は 18 歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

③【H30年出題】 ×
・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合
→子の遺族基礎年金は支給停止となります。
・妻が再婚した場合
→妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
→子の遺族基礎年金は、当該妻(子からみると母)と生計を同じくしている場合は、支給停止となります。
④【H30年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。

【解答】
④【H30年出題】 ×
「その申請のあった日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給が停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
「国民年金法」事後重症の障害基礎年金
R7-173 02.17
事後重症の障害基礎年金についてお話しします
今回の内容は以下の通りです。
★「通常の障害基礎年金」と「事後重症の障害基礎年金」との大きな違い
・通常の障害基礎年金→障害認定日に受給権が発生します
・事後重症の障害基礎年金→請求によって受給権が発生します
★「事後重症の障害基礎年金」の大切なキーワード
・65歳に達する日の前日までに
・請求する
★請求をしなくても事後重症の障害基礎年金が支給される例外の仕組みもおさえましょう
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-172 02.16
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年2月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月10日から15日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・追納についてお話しします(国民年金法)
・育児休業給付金は原則1歳に満たない子が対象(雇用保険法)
・延納(継続事業・一括有期事業の場合)(労働保険徴収法)
・傷病手当金の支給要件(健康保険法)
・標準賞与額に係る保険料(健康保険法)
・障害基礎年金に加算される子の加算(国民年金法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>障害基礎年金
R7-171 02.15
(国年)障害基礎年金に加算される子の加算
障害基礎年金には、1級と2級があり、生計を維持する子がいる場合は、加算額がプラスされます。
障害基礎年金の額は、以下の通りです。
第1級 780,900円×改定率×100分の125
第2級 780,900円×改定率
※50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。
「子」の加算について条文を読んでみましょう。
法第33条の2 ① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 ③ 子の加算額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 (3) 婚姻をしたとき。 (4) 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 (5) 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |
★子の加算額について
1人目・2人目 | 224,700円×改定率 |
3人目以降 | 74,900円×改定率 |
では過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
障害基礎年金には、配偶者に係る加算額は加算されません。
★配偶者については、「1級・2級の障害厚生年金」に加給年金額が加算されます。
②【H25年出題】
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に子を有することとなった場合でも、加算額の対象となります。
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至った場合は、子を有するに至った日の属する月の翌月から加算額が加算されます。
③【H22年出題】
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。

【解答】
③【H22年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときでも、加算額は減額されません。
「受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき」は減額されます。受給権者の配偶者の養子になっても、減額されません。
④【H19年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。

【解答】
④【H19年出題】 ×
子の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときに終了しますが、その子が障害等級に該当する障害の状態にあるときは終了しません。
「その子の障害の状態に関わらず、減額される。」が誤りです。
18歳年度末・障害なし
▼
|
18歳年度末・障害状態 20歳
▼ ▼
|
|
18歳年度末 障害状態でなくなった 20歳
(障害状態)
▼ ▼ ▼
|
|
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険法>保険料
R7-170 02.14
(健保)標準賞与額に係る保険料
「標準賞与額」に係る保険料を確認しましょう。
「賞与」の定義を条文で読んでみましょう。
法第3条第6項 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
★年3回以下支給されるボーナス等が該当します。
「標準賞与額の決定」について条文を読んでみましょう。
法第45条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 |
★健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円です。
★「標準賞与額」に係る保険料
標準賞与額×毎月の保険料と同じ保険料率で計算します。
「保険料の源泉控除」について条文を読んでみましょう。
法第167条第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
その年度における標準賞与額の累計額が540万円ではなく、「573万円」です。
②【R1年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

【解答】
②【R1年出題】 〇
賞与の累計は、「保険者単位」で行います。
同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、「同一の保険者である期間」に支払われた賞与について累計します。
(H18.8.18事務連絡)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
全国健康保険協会管掌健康保険 | |||||||||||
|
|
| 150 万円 |
|
|
| 250 万円 |
|
|
| 173万円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
全国健康保険協会管掌健康保険 | 健康保険組合管掌健康保険 | ||||||||||
|
|
| 150 万円 |
|
|
| 250 万円 |
|
|
| 200 万円 |
③【R4年出題】
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

【解答】
③【R4年出題】 〇
育児休業期間中などの保険料免除期間中に支払われた賞与についても、標準賞与額として決定し、年間累計額に含みます。
(H18.8.18事務連絡)
④【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
④【H29年出題】 〇
法第156条第3項で、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と定められています。
そのため、前月から引き続き被保険者で、7月10日賞与支給、同月25日退職、同月26日被保険者資格喪失の場合、7月の賞与に係る保険料を納付する義務はありません。
⑤【R3年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
前月から引き続き被保険者である場合、資格喪失月に支払われた賞与については保険料を納付する義務はありません。
ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額には含まれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険法>傷病手当金
R7-169 02.13
傷病手当金の支給要件
病気やケガで仕事に就くことができない場合は、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第99条第1項・第4項 ① 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ④ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。 |
<傷病手当金の支給要件を確認しましょう>
① 業務外の事由による傷病の療養のために労務に服することができないこと
② 連続して3日間労務不能であること(待期完成)
③ 労務不能の期間について報酬の支払いがないこと
過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】※改正による修正あり
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。
<選択肢>
① 4月1日から ② 4月3日から ③ 4月4日から ④ 4月5日から
⑤ 日 ⑥ 日の2日後 ⑦ 日の3日後 ⑧ 日の翌日

【解答】
<A> ④ 4月5日から
<B> ⑤ 日
ポイント!
傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。
<A> 4月1日に労務不能となり3日間休業→同月4日通常どおり出勤→翌5日から再び労務不能となって休業した場合→傷病手当金は4月5日から支給されます。
4月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
休 | 休 | 休 | 出勤 | 休 |
待期完成 |
| 支給開始 | ||
<B> 報酬があったために、その当初から傷病手当金が支給停止されていた場合
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
有給 | 有給 | 有給 | 有給 | 有給 | 無給 | 無給 |
待期完成 | 停止 | 停止 | 支給開始 |
| ||
②【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
・就業時間中に傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合
→ その日の報酬の全部又は一部を受けると否とを問わず、その日は待期3日に含まれます。
・業務終了後に、傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合
→待期は、翌日から起算します。
問題文は、就業中に労務不能になっていますので、待期期間の起算日は、「入院の日」となります。
(昭5.10.13保発52)
③【R3年出題】
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
一般の被保険者の場合、「療養」は、保険医から療養の給付を受けることに限られません。自費診療による療養も、傷病手当金の対象となります。
(昭2.2.26保発345)
④【R5年出題】
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期の適用がない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
待期期間を完成させなければならないのは、最初に療養のため労務不能となった場合のみです。その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期は不要です。
(昭2.3.11保理1085)
⑤【R2年出題】
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より小さい場合は、差額の傷病手当金が支給されます。そのため、「傷病手当金が支給されることはない」は誤りです。
(昭33.7.8保険発95の2)
⑥【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

【解答】
⑥【H26年出題】 ×
傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。問題文の場合、支給期間は、4月28日からではなく、傷病手当金の支給が始まった日=「6月1日」から通算して1年6か月間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働保険徴収法>延納
R7-168 02.12
延納(継続事業・一括有期事業の場合)
「概算保険料」は延納(分割払)をすることができます。
今回は、継続事業・一括有期事業の延納をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第18条 (概算保険料の延納) 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料(認定決定も含みます)、増加概算保険料、概算保険料の追加徴収により納付すべき労働保険料を延納させることができる。 |
ポイント!
「確定保険料」は延納できません。
<延納の条件>
・概算保険料の額が40万円以上
(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上
又は
・労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
・保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは延納できません。
・事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合
(原則)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | |||||||||
7月10日 (保険年度の6月1日から起算して40日以内) | 10月31日 ・労働保険事務組合に委託 →11月14日 | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 | |||||||||
(年度途中に保険関係が成立した場合)
★4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業
第1期 | 第2期 | 第3期 |
保険関係成立の日 ~ 7月31日 | 8月1日 ~ 11月30日 | 12月1日 ~ 3月31日 |
保険関係成立の日の 翌日から起算して 50日以内 | 10月31日 ・労働保険事務組合に委託 →11月14日 | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 |
★6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業
第1期 | 第2期 |
保険関係成立の日 ~ 11月30日 | 12月1日 ~ 3月31日 |
保険関係成立の日の 翌日から起算して 50日以内 | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 |
★10月1日以降に保険関係が成立した事業は延納できません。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。

【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託」している事業主は、概算保険料の額に関係なく延納できます。問題文の場合は、延納の申請を行うことができます。
②【R2年出題】(雇用)
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。

【解答】
②【R2年出題】(雇用) 〇
7月1日に保険関係が成立した場合は、2回に分けて納付することができます。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 | 第2期 | |||||||
保険関係成立の日の翌日から起算して 50日以内 (8月20日) | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 | |||||||
③【H29年出題】(労災)
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

【解答】
③【H29年出題】(労災) 〇
10月1日以降に保険関係が成立したときはその年度は延納できませんので、一括で納付しなければなりません。
保険年度の中途に保険関係が成立した場合、当該保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)に納付しなければなりませんので、納付期限は、平成29年11月20日となります。
(法第15条、則第27条)
④【H27年出題】(雇用)
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

【解答】
④【H27年出題】(雇用) 〇
第1期の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、延長されません。
(則第27条第2項)
⑤【H29年出題】(労災)
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

【解答】
⑤【H29年出題】(労災) ×
1円未満の端数は、「第1期分」にまとめます。
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合は、第1期の納付額は56,668円、第2期及び第3期の納付額は各56,666円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<雇用保険法>育児休業給付金
R7-167 02.11
育児休業給付金は原則1歳に満たない子が対象
★令和7年4月に改正があります。
「育児休業等給付」は、「育児休業給付」、「出生後休業支援給付」、「育児時短就業給付」の3つになります。
・「育児休業給付」は、①「育児休業給付金」、②「出生時育児休業給付金(→産後パパ育休)」の2つ。
・「出生後休業支援給付」は、「出生後休業支援給付金」
・「育児時短就業給付」は、「育児時短就業給付金」
となります。
今回は、「育児休業給付金」をみていきます。
育児休業給付金は、原則として1歳未満の子が対象です。
ただし、雇用の継続のために特に必要と認められる場合は、「1歳6か月まで」、「2歳」まで延長されます。
1歳 | 1歳6か月 | 2歳 |
育児休業給付金 | 延 長① | 延 長② |
※なお、パパママ育休プラスの場合は、原則として1歳2か月までが対象となります。
条文を読んでみましょう。
第61条の7第1項 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子 (その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、2歳に満たない子))を養育するための休業(以下「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。 |
★休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について→令和7年4月に改正されます。
「育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合(速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る。)アンダーライン部分が追加されます。
厚生労働省令では、他にも理由が定められていますが、今回は省略します。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上みなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

【解答】
①【R4年出題】 〇
育児休業給付金の支給には、「育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあっては、初回の育児休業とする)を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上」必要です。
ただし、「育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)」にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あればよいとされています。
「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」には、「事業所の休業」も入っています。
そのため、「1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合」は、原則の2年間に「1年間」が加算されます。育児休業開始日前「3年間」に通算して12か月以上みなし被保険者期間があれば、育児休業給付金が支給されます。
(則第101条の29)
②【R4年出題】
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。

【解答】
②【R4年出題】 ×
延長後の対象育児休業の期間はその子が「1歳9か月に達する日」ではなく「2歳に達する日」の前日までです。
(法第61条の7第1項)
③【R3年出題】
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
問題文の2回目の育児休業は、育児休業給付金の支給対象となります。
条文を読んでみましょう。
法第61条の7第2項 被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。 |
育児休業給付金は、同一の子について2回目の育児休業まで支給されます。3回目以降は原則として支給されません。
④【R5年出題】
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
(A) 0か月
(B) 3か月
(C) 4か月
(D) 5か月
(E) 6か月

【解答】
④【R5年出題】
(D) 5か月
ポイント!
令和6年11月9日から同年12月8日までの雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業は、育児休業給付金の支給対象になりません。
★支給単位期間について
支給単位期間は、各月における休業開始日又は休業開始日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「応当日」という。)から、それぞれその翌月の応当日の前日までの1か月間を単位とします。
<1回目>
令和6年
「2月4日~3月3日」
「3月4日~4月3日」
「4月4日~5月3日」
<2回目>
「6月10日~7月9日」
「7月10日~8月9日」
支給単位期間は、5か月となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>追納
R7-166 02.10
保険料の追納についてお話しします
国民年金には、「保険料免除」の制度があります。
「免除」を受けた期間がある場合は、その分、老齢基礎年金の年金額が減額されます。
また、学生納付特例・納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しません。
そのため、免除を受けた期間については後から「追納」することができます。
追納すると、その期間は「保険料納付済期間」となります。
・追納の要件(追納できる人)
・追納できる期間
・追納する額(加算が行われる場合があります)
などをお話しします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-165 02.09
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年2月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年2月3日から8日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・遺族基礎年金と遺族厚生年金を比較しましょう(国年・厚年)
・総括安全衛生管理者の選任(労働安全衛生法)
・介護補償給付の支給要件(労災保険法)
・介護補償給付の支給額・原則は実費・上限あり・最低保障額あり(労災保険法)
・賃金日額の算定ルール(雇用保険法)
・基本手当の受給期間(雇用保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法(受給期間)
R7-164 02.08
基本手当の受給期間
「受給期間」とは、「基本手当」を受けることができる有効期間です。
今回は「受給期間」をみていきましょう。
★基本手当の「受給期間」は以下の通りです。
基本手当は、受給期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給されます。
| (1) (2)(3)以外 | 受給資格に係る離職の日(以下「基準日」)の翌日から起算して1年 |
(2) 基準日において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の就職困難者 (所定給付日数が360日) | 基準日の翌日から起算して 1年に60日を加えた期間 |
(3) 基準日において45歳以上60歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者 (所定給付日数が330日) | 基準日の翌日から起算して 1年に30日を加えた期間 |
★受給期間の延長
<1>定年退職者等の受給期間の延長
■離職理由が次のどちらかに当てはまる場合です。
・定年(60歳以上の定年に限る。)に達したことによる離職
・60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したことによる離職
■申し出が必要です
離職の日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長等申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出します。
■最大1年間延長されます
原則の受給期間に「求職の申込みをしないことを希望する一定の期間」(1年が限度です。)が加算されます。
(例)1年間求職の申込みをしないことを希望する場合
| (受給期間)1年間+1年間 | |
| 原則の受給期間(1年) | 1年間 |
▲
離職日
<2>妊娠、出産、疾病等により引き続き30日以上職業に就くことができない場合の延長
■以下の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が対象です。
・妊娠
・出産
・育児
・疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
・上記以外で、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
■申し出が必要です
引き続き30日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から基準日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)に申出をしなければなりません。
■受給期間が最長4年間になります
原則の受給期間に職業に就くことができない日数が加算されます。加算された期間が4年を超えるときは4年となります
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
離職の日に55歳、算定基礎期間が25年である特定受給資格者の所定給付日数は330日です。受給期間は基準日の翌日から起算して1年+30日です。
(法第20条第1項第3号)
②【H28年出題】
60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
定年退職者等の受給期間の延長は、次のいずれかの理由で離職した者が対象です。
・ 60歳以上の定年に達したこと
・ 60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
※勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要です。
問題文のように、定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。
(法第20条第2項、則第31条の2第2項、行政手引50281)
③【H24年出題】
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 〇
60歳以上で定年退職した者による受給期間の延長の申出は、原則として当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければなりません。
(則第31条の3第2項)
④【H28年出題】
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。

【解答】
④【H28年出題】 ×
出産は「本人」の出産に限られますので、「配偶者の出産」の場合は、受給期間の延長は行われません。
(行政手引50271)
⑤【H23年出題】
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
所定給付日数が270日の場合、受給期間は基準日の翌日から起算して1年です。その間に、出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合は、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年+180日となります。
⑥【H28年出題】
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
問題文の場合、受給期間はさらに延長されます。
・定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合
→さらに受給期間の延長が認められます。
・定年退職者等の受給期間とされた期間に、疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数を加えることができます。
→ 加えた期間が4年を超えるときは、受給期間は4年となります。(受給期間は、最長4年間です)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法(賃金日額)
R7-163 02.07
賃金日額の算定ルール
「基本手当の日額」は、賃金日額×厚生労働省令で定める率で計算します。
今回は、「賃金日額」の算定方法をみていきます。
「賃金日額」の算定方法を条文で読んでみましょう。
第17条第1項、第2項 ① 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 ② 賃金日額の最低保障の額 (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と(1)の額との合算額 |
<賃金日額の原則の算定式>
最後の6か月間に支払われた賃金の総額 |
180 |
※「賃金の総額」から、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれます。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
・賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、次の計算式の額のどちらか「高い方」となります。
<原則の計算式>
・ 被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額÷180
<最低保障>
・ 被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額÷当該最後の6か月間に労働した日数×100分の70
②【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額に含まれます。
(行政手引50501)
③【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

【解答】
③【H30年出題】 ×
被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金は、賃金日額の算定に含まれます。
そのため、賃金支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を含めて賃金額を算定します。
(行政手引50451、行政手引50609)
次は、賃金日額の最高限度額と最低限度額の問題です。
④【H26年出題】
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。

【解答】
④【H26年出題】 〇
<賃金日額の最高限度額>
・賃金日額の最高限度額は、「30歳未満」、「30歳以上45歳未満」、「45歳以上60歳未満」、「60歳以上65歳未満」の4つに分けて設定されています。
最も高く設定されているのが「45歳以上60歳未満」です。
<最低限度額>
・最低限度額は年齢に関わりなく一律です。
⑤【R5年出題】
雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高限度額、最低限度額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更されます。(自動変更対象額といいます。)
ただし、自動変更対象額による最低限度額が、「最低賃金日額」を下回る場合は、最低賃金日額が最低限度額となります。
最低賃金日額は「地域別最低賃金の全国加重平均額× 20÷7」で計算した額です。
具体的には、1,004 円(令和6年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7=2,869円です。
(法第18条第3項、則第28条の5)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法(介護補償給付その2)
R7-162 02.06
介護補償給付の支給額(原則実費・上限、最低保障額あり)
前回は、介護補償給付の支給要件についてお話ししました。
今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。
★原則は介護費用として支払った額(実費)が支給されますが、上限と最低保障額があることがポイントです。
では、条文を読んでみましょう。
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
則第18条の3の4 (介護補償給付の額) (1) その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合 → その月において介護に要する費用として支出された費用の額(実費) ※その額が177,950円を超えるときは、177,950円とする。(上限) (2) 親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合(最低保障額が適用される) ・ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある・親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある・介護に要する費用として支出された費用の額が81,290円に満たないとき → 81,290円(最低保障額) ・ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない・親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある(介護費用を支出せず、親族等による介護のみ) → 81,290円(最低保障額) |
★「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません
「支給すべき事由が生じた月」において、介護に要する費用として支出された額が81,290円に満たない → 介護に要する費用として支出された額(実費・最低保障なし)
そのため、「支給事由が生じた月」に親族等による介護を受けた場合でも、介護に要する費用として支出された費用がゼロの場合は、介護補償給付の額もゼロとなります。
★ 「随時介護を要する状態」の場合は、上限が「88,980円」、最低保障額が「40,600円」となります。常時介護の2分の1です。(端数処理があります)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】
①【H23年出題】 〇
介護補償給付は、「月」単位で支給されます。
②【H25年出題】
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】
②【H25年出題】 〇
★最低保障額のポイント!
・ 「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額は適用されません。
・ 最低保障額が適用される要件は、「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある」ことです。
※ 例えば、「支給すべき事由が生じた月」が1月で、介護に要する費用として支出された額が81,290円未満で、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合
→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付の額は「介護に要する費用として支出された額=実費」です。
2月以降は最低保障額の81,290円が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
実 費 | 最低保障額 | 最低保障額 | 最低保障額 |
③【R2年出題】
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
介護費用を支払わなくても、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合は、介護補償給付は支給されます。
※ ただし、「支給すべき事由が生じた月」は最低保障はありません。
例えば「支給すべき事由が生じた月」が1月で、介護に要する費用を支出しないで、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合
→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付は支給されません。
2月以降は最低保障額の81,290円が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
支給なし | 最低保障額 | 最低保障額 | 最低保障額 |
なお、「介護に要した費用の額の証明書」は、「介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合」に、添付しなければなりません。介護費用を支払っていない場合は、添付する必要はありません。
(則第18条の3の5)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法(介護補償給付その1)
R7-161 02.05
介護補償給付の支給要件
介護補償給付が支給される要件と、支給されない場合をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条の8第4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) (2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 (3) 病院又は診療所に入院している間 |
★厚生労働省令で定める程度とは?
→「第1級(すべて)」と「第2級の精神神経の障害、胸腹部臓器の障害」です。
★障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものとは?
(1) 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
など
過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、 < A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行われる。

【解答】
①【H19年選択式】
<A> 常時又は随時
<B> 当該労働者
②【H21年出題】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

【解答】
②【H21年出題】 ×
介護補償給付は、「常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき」に支給されます。
「その障害の程度にかかわらず」ではなく、「障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のもの」であることが要件です。
③【H24年出題】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

【解答】
③【H24年出題】 〇
老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。
(則第18条の3の3)
④【H30年出題】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
病院又は診療所に入院している間は、介護補償給付は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法(総括安全衛生管理者)
R7-160 02.04
総括安全衛生管理者の選任
「総括安全衛生管理者」は、事業場ごとに選任します。(企業単位ではありません。)
工場長などその事業場の労働者のトップが充てられます。
条文を読んでみましょう。
第10条 (総括安全衛生管理者) ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は救護の措置の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 (1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 (2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 (3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 (4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの ② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 ③ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。 |
★総括安全衛生管理者を選任すべき事業場
林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 | 常時100人以上 |
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
常時300人以上 |
その他の業種 | 常時1000人以上 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
労働安全衛生法は、「事業場単位」で、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしています。
事業場の適用単位の考え方は、労働基準法の考え方と同じで、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます。(昭47.9.18発基第91号)
そのため、総括安全衛生管理者は、企業全体における労働者数ではなく、「事業場」の労働者数を基準として、「事業場単位」の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられています。
②【H19年出題】
総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。

【解答】
②【H19年出題】 ×
総括安全衛生管理者は、「当該事業場においてその事業の実施を「統括管理」(※総括管理ではありません)する者をもって充てなければならない」とされています。
厚生労働大臣の定める研修の修了は要件ではありません。
なお、「事業の実施を統括管理する者」とは、工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者をいいます。
(昭47.9.18基発第602号)
③【H24年出題 】
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。

【解答】
③【H24年出題 】 〇
・常時120人の労働者を使用する清掃業の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。
・当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合でも、その者を総括安全衛生管理者に選任することができます。
④【H26年出題】
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。

【解答】
④【H26年出題】 ×
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、「総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる」ではなく、「総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる」です。
⑤【H28年選択式】
労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、< A >をもって充てなければならない。」とされている。
<選択肢>
① 当該事業場において選任が義務づけられている安全管理者及び衛生管理者の資格を有する者
② 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
③ 当該事業において、3年以上安全衛生管理の実務に従事した経験を有する者
④ 当該事業場における安全衛生委員会委員の互選により選任された者

【解答】
<A> ② 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
R7-159 02.03
遺族基礎年金と遺族厚生年金を比較しましょう
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を比較しましょう!
・死亡した人の要件
・遺族の範囲 を
比較してみましょう。
<今日の内容>
・ 遺族基礎年金の支給要件
・ 遺族厚生年金の支給要件
・ 遺族基礎年金の遺族の範囲
・ 遺族厚生年金の遺族の範囲
・ 遺族基礎年金の過去問
・ 遺族厚生年金の過去問
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-158 02.02
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年1月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年1月26日から2月1日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用について(健保・厚年)
・労働者の労働保険料「一般保険料」の額の計算(労働保険徴収法)
・第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の資格喪失の時期(国民年金法)
・障害基礎年金の受給権の消滅(国民年金法)
・障害厚生年金に加算される加給年金額(厚生年金保険法)
・労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約(労働基準法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働契約」
R7-157 02.01
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約
労働基準法では、労働条件の最低基準が定められています。
今回は、労働基準法の基準を下回る労働契約についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
・ 労働基準法で定められている1日の労働時間の上限は8時間です。
↓
・ ある労働契約で1日の労働時間を10時間と定めました。(労働基準法の基準を下回っている)
↓
・ 労働契約全体が無効になるのではなく、「労働基準法で定める基準に達しない」部分のみ無効になります。
↓
・ 法第13条により、「1日8時間」とする労働契約に修正されます。
★労働協約・就業規則との効力の力関係も確認しましょう。
労働基準法 | > | 労働協約 | > | 就業規則 | > | 労働契約 |
強い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弱い
ポイント!
・使用者が一方的に定めた就業規則よりも、労働組合と使用者が対等の立場で約束した「労働協約」の方が強い
・個々の労働者ごとに締結した労働契約より、職場のルールである就業規則の方が強い。
・労働協約、就業規則、労働契約は、労働基準法の基準は守らなければならない。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
無効となるのは、労働基準法で定める基準に「達しない」(=不利な)労働条件を定める部分です。労働基準法で定める基準より労働者に「有利」なものは有効です。
②【R5年出題】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

【解答】
②【R5年出題】 ×
法第14条第1項に規定する期間(「高度の専門的知識等を有する労働者」及び「満60歳以上の労働者」については5年、その他のものについては「3年」)を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、その部分は無効となります。
その場合、労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項に規定する期間(5年又は3年)となります。
(平成15.10.22基発第1022001号)
③【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。

【解答】
③【H25年出題】 〇
労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約については、その部分は無効となり、無効となった部分は、労働基準法所定の基準で補充されます。
④【H27年出題】
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

【解答】
④【H27年出題】 〇
労働組合法と労働基準法の異なる点を確認しましょう。
・労働組合法第16条
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。」
・労働基準法第13条
「労働基準法で定める基準に達しない(=不利な)労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害厚生年金」
R7-156 01.31
障害厚生年金に加算される加給年金額
1級、2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第50条の2 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを 100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
ポイント!
・3級の障害厚生年金には、加給年金額は加算されません。
・「65歳未満の配偶者」が対象です。「子」については、国民年金法の「障害基礎年金」に加算が行われます。
・加給年金額は、22万4700円×改定率で計算します。老齢厚生年金と異なり、「特別加算」はありません。
・「受給権を取得した当時」だけでなく、「権利を取得した日の翌日以後」に
配偶者を有するに至った場合でも加給年金額の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも加給年金額が加算されます。加給年金額は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加算されます。
②【H29年出題】
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

【解答】
②【H29年出題】 ×
子は、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。子は国民年金法の障害基礎年金の加算の対象となります。
③【R4年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算は行われません。
④【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。

【解答】
④【R1年出題】 〇
障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額は、以下に該当した場合は、加算が終了します。
(1) 死亡したとき。
(2) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
(3) 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
(4) 配偶者が、65歳に達したとき。
加給年金額の対象になるのは65歳未満の配偶者ですので、「配偶者が65歳に達したとき」は加算されなくなります。
また、加給年金額が加算されなくなり年金額が改定されるのは、「該当するに至った月の翌月」からとなります。
ちなみに、配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も加給年金額の対象となります。
(法第44条第4項、法第50条の2第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R7-156 01.30
障害基礎年金の受給権の消滅
障害基礎年金の受給権の消滅をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定(障害基礎年金の併合によって従前の障害基礎年金の受給権の消滅)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、65歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (3) 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
ポイント!
「国民年金法」の障害等級は「1級、2級」ですが、「厚生年金保険法」の障害等級は「1級、2級、3級」です。
厚生年金保険法の障害等級は3級まであることに注意してください。
では、図①と図②でイメージしましょう。
ポイント!
少なくとも「65歳」までは失権しません。
それでは過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
①【H20年出題】 ×
※厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害=障害等級3級です。
63歳時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、65歳までは障害基礎年金の受給権は消滅しません。問題文の場合、63歳時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。
②【R3年出題】
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(=3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとしても、65歳に達していないときは障害基礎年金の受給権は消滅しません。
③【H30年出題】
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
63歳の時に障害状態が3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当した場合は、「支給停止が解除されます」。
「3級」に該当している間は、失権することはありません。
図③でイメージしましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
図①
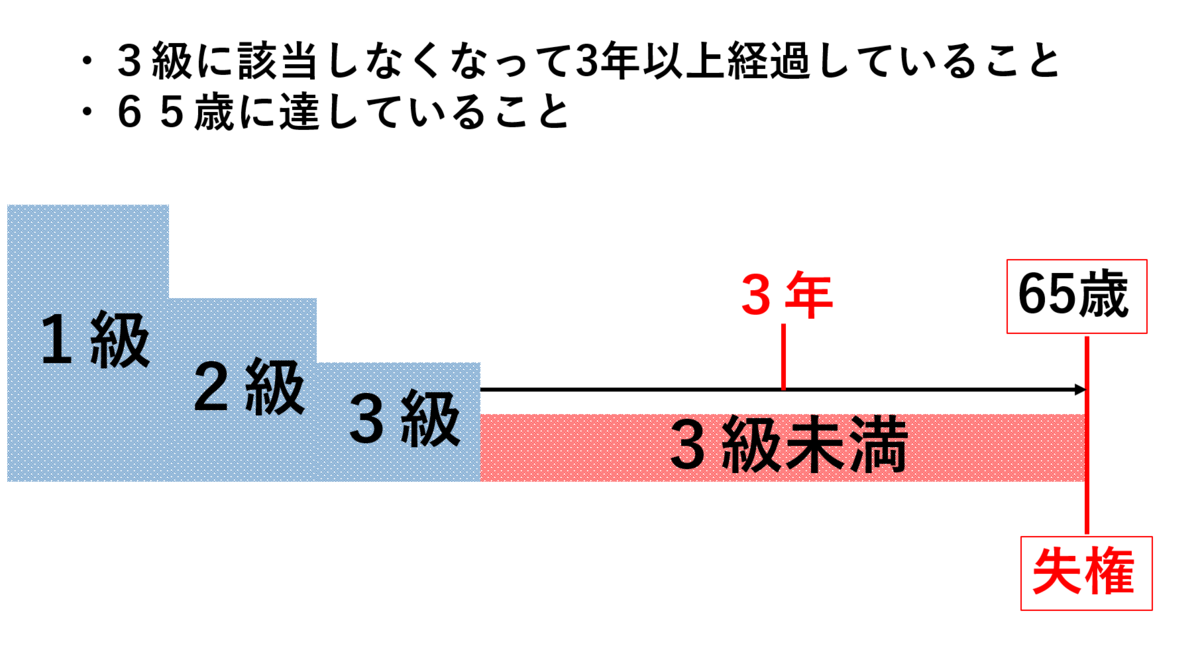
図②
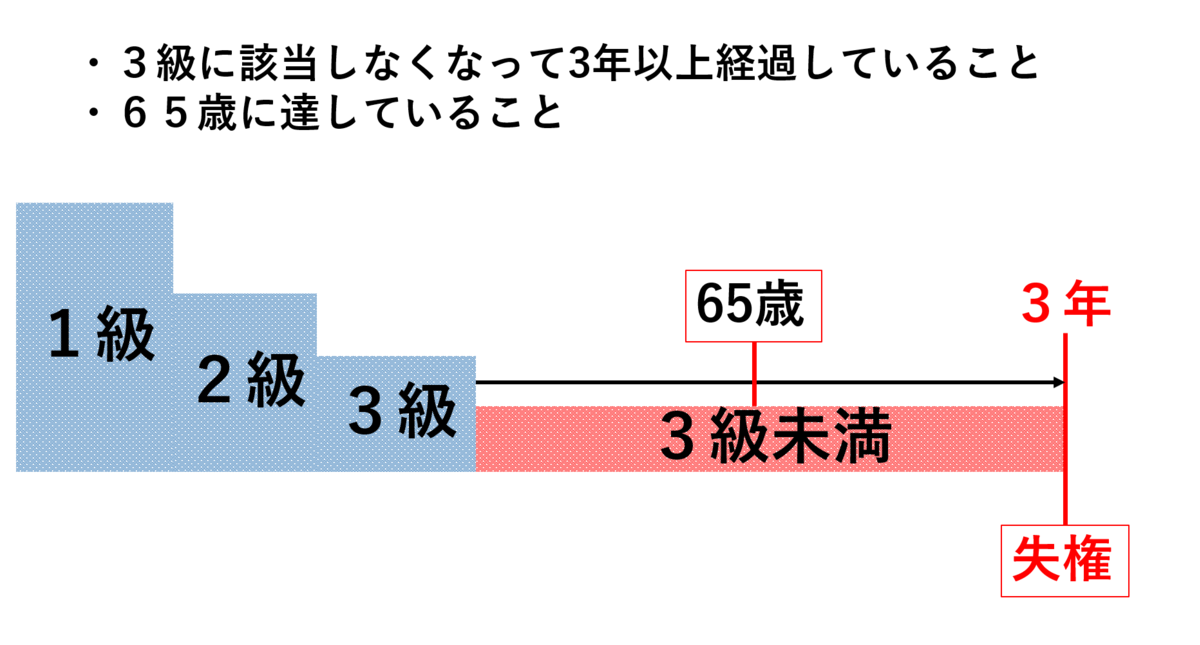
図③
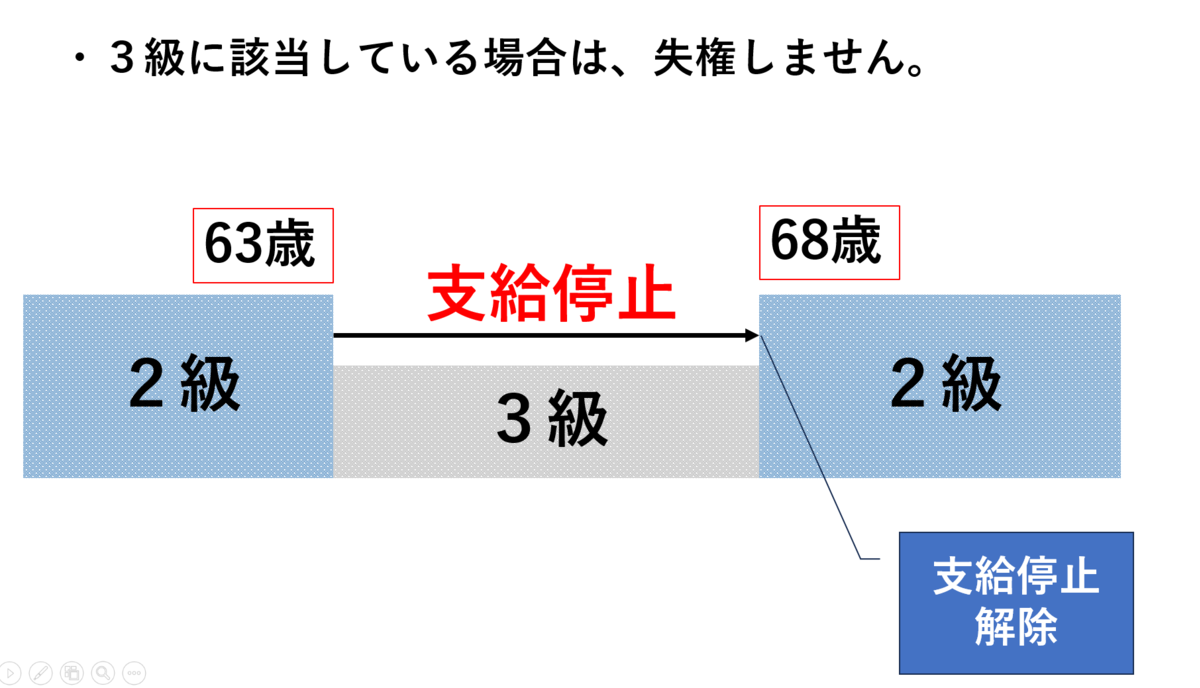
国民年金法「資格喪失」
R7-155 01.29
第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の資格喪失の時期
国民年金の強制被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種別があります。
それぞれの資格喪失の時期をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第9条 (資格喪失の時期) 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日((2)に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は(3)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき((4)については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき→(翌日喪失・共通) (2) 日本国内に住所を有しなくなったとき→(翌日喪失・第1号被保険者) (3) 60歳に達したとき(当日喪失・第1号被保険者、第3号被保険者) (4) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(翌日喪失・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき当日喪失・第1号被保険者) (5) 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(当日喪失・第2号被保険者) (6) 被扶養配偶者でなくなったとき(翌日喪失・第3号被保険者) |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【H30年出題】 〇
「第1号被保険者」、「第3号被保険者」は、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますので、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。「当日」喪失がポイントです。
なお、60歳に達した日とは、60歳の誕生日の前の日です。例えば、令和7年1月29日が60歳の誕生日だとすると、第1号被保険者・第3号被保険者は、令和7年1月28日に資格を喪失します。
②【R4年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
第1号被保険者又は第3号被保険者は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。また、死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失します。
③【H25年出題】 ※改正による修正あり
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【H25年出題】 ×
第2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、60歳に達したことによる資格の喪失はありません。
④【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
④【R4年出題】 〇
「厚生年金保険の被保険者」は原則として、「国民年金の第2号被保険者」です。
ただし、65歳以上で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者は、第2号被保険者となりません。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
⑤【R3年出題】
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点で、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、国民年金の被保険者資格を喪失するのではなく、第3号被保険者から第1号被保険者又は、第3号被保険者から第2号被保険者への「種別変更」となります。
例えば、日本国内に居住する40歳の者が、離婚し被扶養配偶者でなくなった時点で無職の場合は、第1号被保険者に「種別変更」となります。
20歳 40歳
第3号被保険者 | 第1号被保険者 |
→ | 種別変更 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「一般保険料」
R7-154 01.28
労働者の労働保険料「一般保険料」の額の計算
労働保険料には6つの種類があります。
① 一般保険料
② 第1種特別加入保険料(中小事業主等が特別加入したときの保険料)
③ 第2種特別加入保険料(一人親方等が特別加入したときの保険料)
④ 第3種特別加入保険料(海外派遣者が特別加入したときの保険料)
⑤ 印紙保険料(日雇労働被保険者の雇用保険料。印紙で納付する。)
⑥ 特例納付保険料(雇用保険法の特例対象者の保険料)
今回は一般保険料の計算についてお話しします。
一般保険料は、一般の労働者の保険料で、原則として、労災保険料+雇用保険料です。
★一般保険料の額の計算について
「賃金総額」×「一般保険料率(一般保険料に係る保険料率)」で計算します。
■「賃金総額」とは→ 事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。
■一般保険料率
①労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業
→「労災保険率」+「雇用保険率」
②労災保険に係る保険関係のみが成立している事業
→「労災保険率」
③雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
→「雇用保険率」
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(労災)
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

【解答】
①【R1年出題】(労災) ×
労働保険料は、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、「特例納付保険料」の計6種類です。
(法第10条第2項)
②【H30年出題】(雇用)
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

【解答】
②【H30年出題】(雇用) ×
二元適用事業は、「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」を別個の事業とみなして徴収法を適用します。そのため、一般保険料額も、「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」を別々に計算します。
一元適用事業の一般保険料額は、「賃金総額」×「一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)」で算定します。
ただし、雇用保険法の適用を受けない者がいる場合は、「労災保険」と「雇用保険」で賃金総額が異なります。そのため、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することになります。
(整備省令第17条第1項)
★下の図でイメージしましょう。
③【R4年出題】(雇用)
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

【解答】
③【R4年出題】(雇用) 〇
一元適用事業で、二元適用事業に準じ、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する場合でも、二元適用事業ではありませんので、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様です。
(整備省令第17条第1項、第2項)
④【H30年出題】(雇用)
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

【解答】
④【H30年出題】(雇用) ×
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されます。
保険料の計算のもとになる「賃金総額」は事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。そのため、1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金も、賃金総額に含まれます。
(法第11条第2項)
⑤【R4年出題】(雇用)
A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

【解答】
⑤【R4年出題】(雇用) ×
Xは、A及びBの2つの適用事業主に雇用され、Aとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあります。
★雇用保険料について
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする=問題文の場合はA)についてのみ被保険者となります。(行政手引20352)
そのため、雇用保険料の算定は、問題文の通り、「A」の雇用保険料は、Xに支払われる賃金を賃金総額に含めて行います。「B」の雇用保険料には、Xに支払われる賃金は賃金総額には含まれません。
★労災保険料について
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、それぞれで労災保険の適用を受けます。そのため、Aの労災保険料は、AにおいてXに支払われる賃金は賃金総額に含まれ、また、Bの労災保険料もBにおいてXに支払われる賃金が賃金総額に含まれます。
⑥【H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
⑥【H26年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、労働保険徴収法では「賃金として取り扱わない」ことになっています。
そのため、労働保険料の算定基礎となる賃金総額には含みません。
(昭25.2.16基発127号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険
R7-153 01.27
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用についてお話しします
「1週間の所定労働時間」又は「1月間の所定労働日数」が 通常の労働者の4分の3未満でも 健康保険・厚生年金保険に加入することになる短時間労働者の条件についてお話ししています。
★基本の条件をおさえましょう。
①「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に使用されている
または
「国・地方公共団体に属する事業所」に使用されている
②次の要件をすべて満たしている
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円以上
・学生でない
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-152 01.26
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年1月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年1月20日から1月25日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・遺族厚生年金の額の計算についてお話しします(厚生年金保険法)
・「賃金支払い5原則」通貨払いの原則と例外(労働基準法)
・雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育(労働安全衛生法)
・労災「支給制限」労働者に対するペナルティ(労災保険法)
・基本手当の受給資格「算定対象期間」(雇用保険法)
・所定給付日数の基になる「算定基礎期間」(雇用保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「所定給付日数」
R7-151 01.25
所定給付日数の基になる~算定基礎期間~
基本手当の所定給付日数は、離職理由、就職困難者であるかどうか、雇用保険に加入した期間(算定基礎期間)、年齢で決まります。
今回は「算定基礎期間」をみていきます。
算定基礎期間は、雇用保険に加入した期間です。
では、条文を読んでみましょう。
なお、「基準日」とは、「受給資格に係る離職の日」のことです。
法第22条第3項~第5項 ③ 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 ④ 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があつた日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。 ⑤ 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知っていた者を除く。)については、被保険者の負担すべき保険料がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日に被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。 (1) その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。 (2) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき保険料がその者に支払われた賃金から控除されていた(=雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期があること。 |
★下の図でイメージしましょう。
では過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合は、基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、前職で被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれません。
②【R3年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、2年前の日より前の期間は、算定基礎期間の算定には入りません。
ただし、給与明細等の確認書類により、確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期があるときは、その時期のうち最も古い時期までさかのぼることができます。
問題文のように、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前で、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれません。
③【R3年出題】
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。

【解答】
③【R3年出題】 〇
算定基礎期間は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間を除いて算定します。
(第61条の7第9項)
④【H29年出題】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
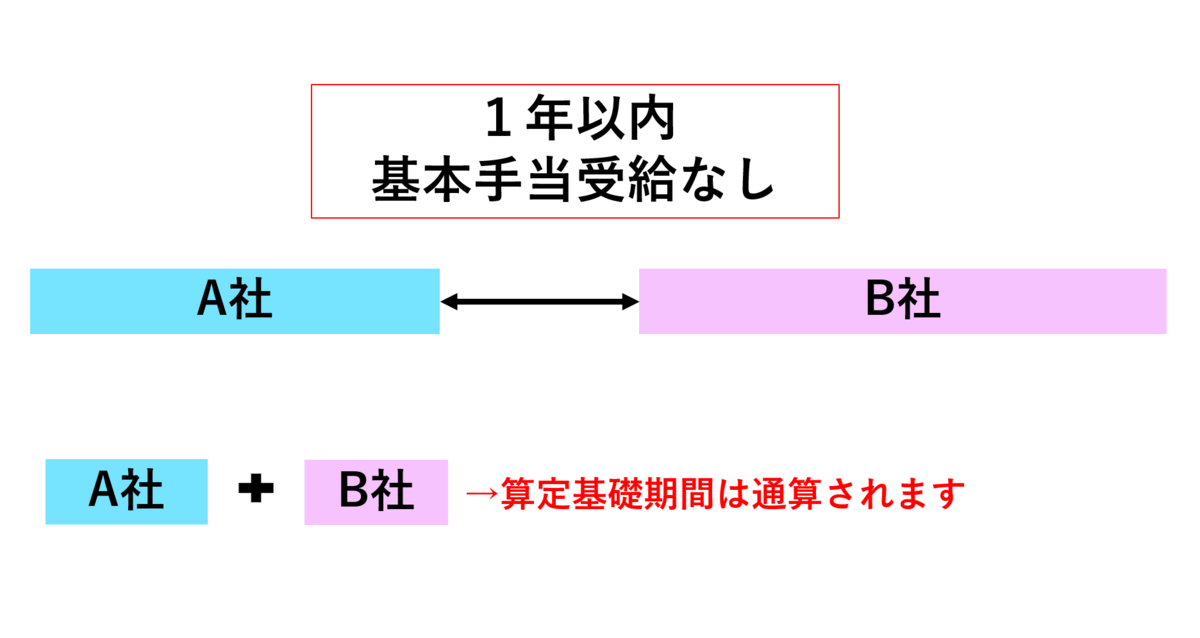
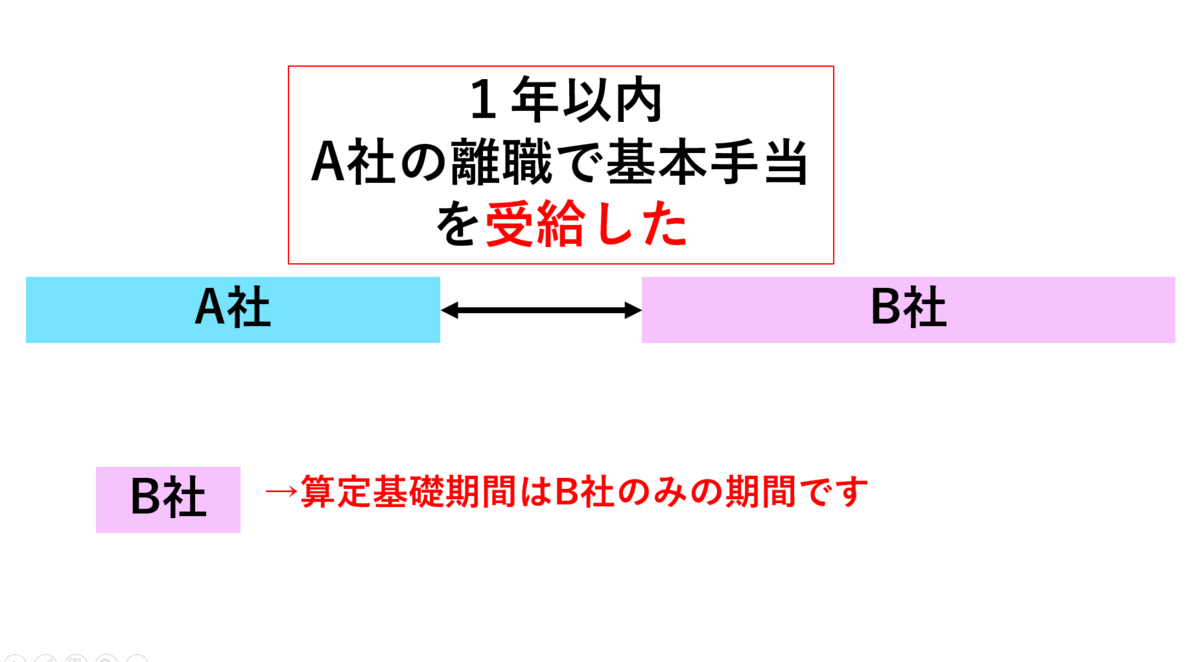
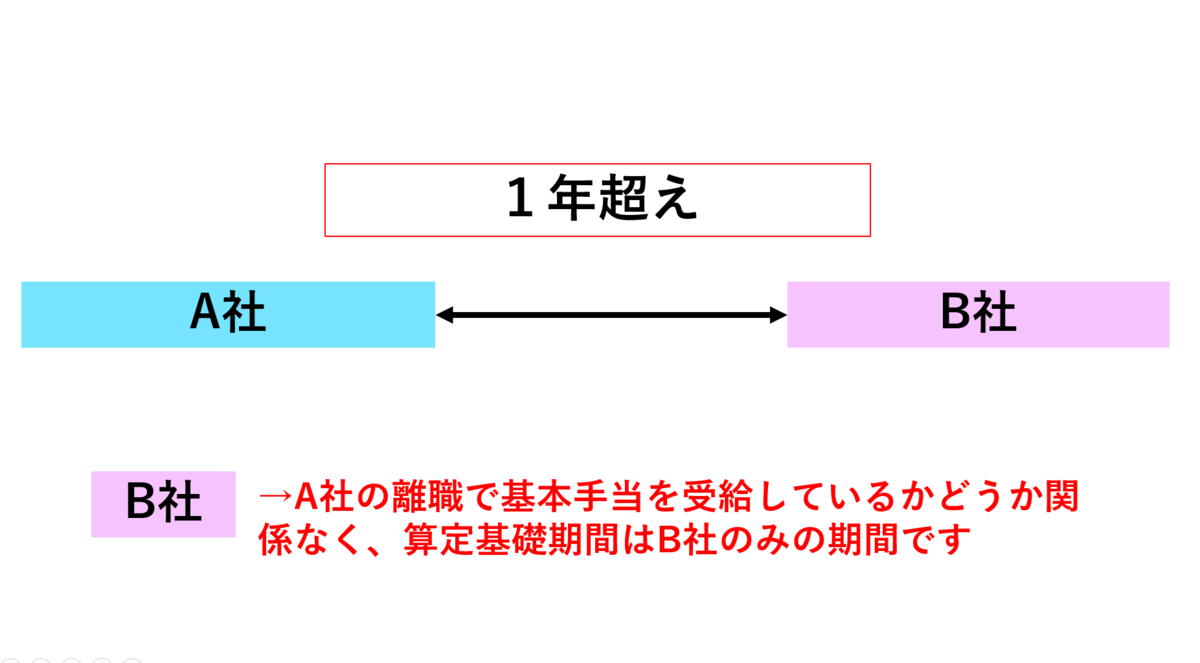
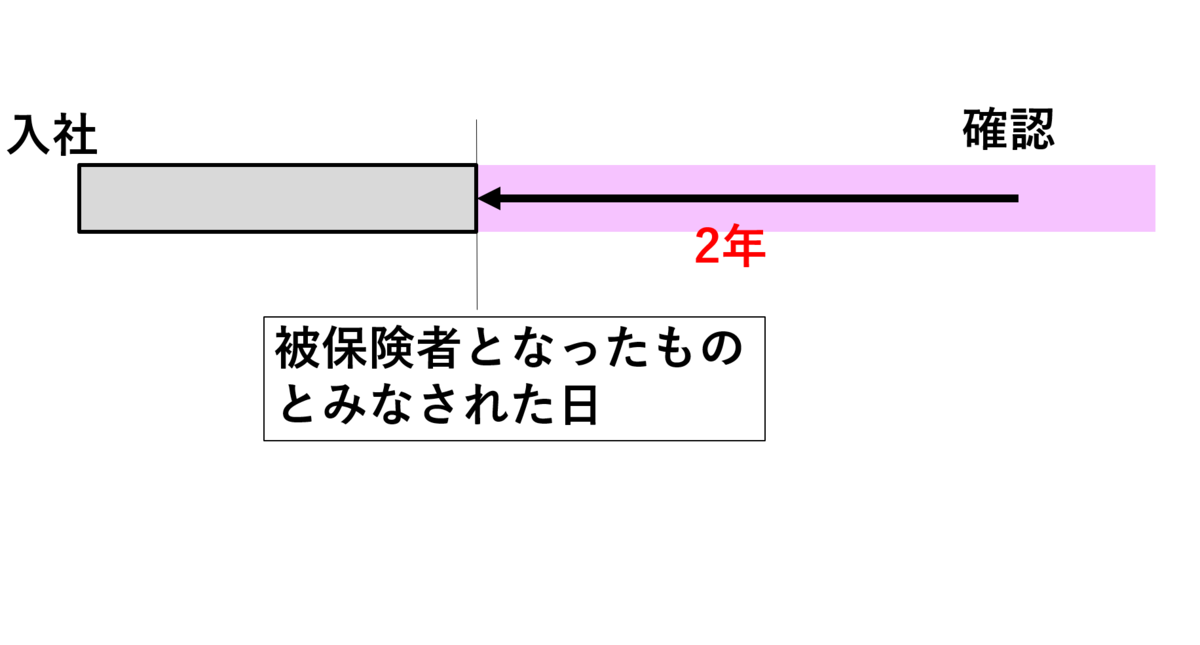
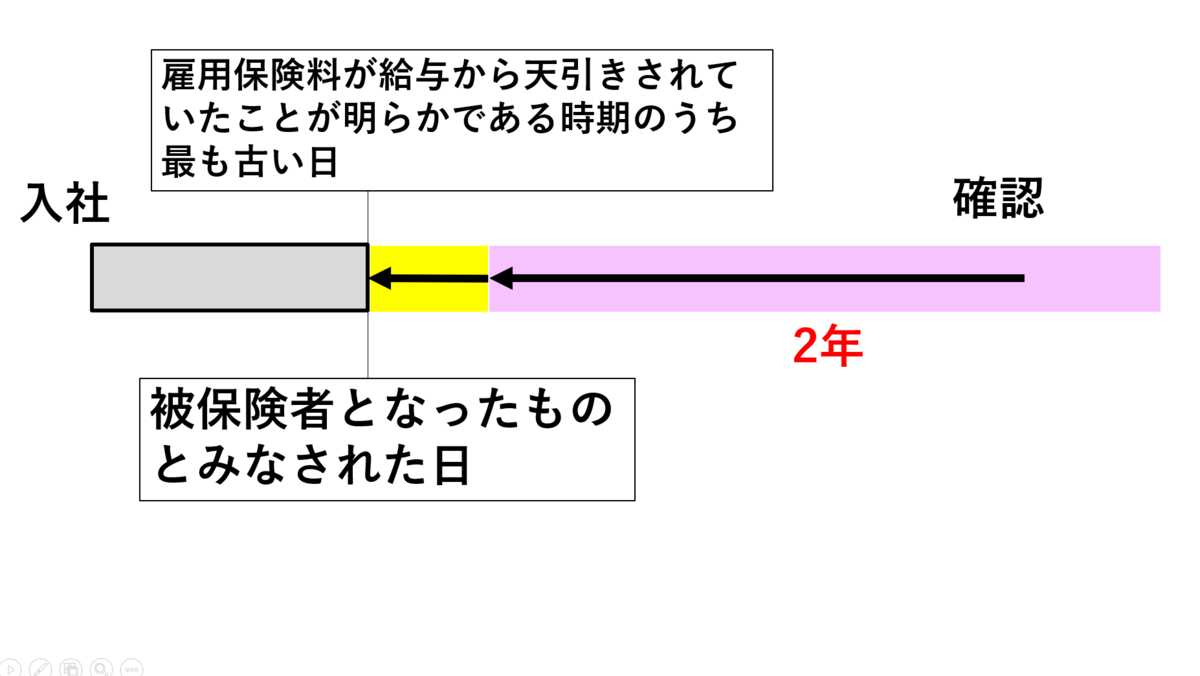
雇用保険法「基本手当」
R7-150 01.24
基本手当の受給資格~算定対象期間~
基本手当の支給を受けることができる資格のことを「受給資格」、受給資格を有する者を受給資格者といいます。
基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12か月以上あることです。
今回は「算定対象期間」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第13条第1項 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。「算定対象期間」という。)に、被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給する。 |
★特定理由離職者及び特定受給資格者について
・離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格を満たします。
■算定対象期間とは
→ (原則)離職の日以前2年間(特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は2年間又は1年間)
→ (受給要件の緩和)
当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則の算定対象期間に加算した期間(最長4年間)
※受給要件の緩和が認められる理由
・疾病、負傷(業務上、業務外の別を問わない。)
・事業所の休業
・出産
・事業主の命による外国における勤務
・国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用
・前各号に掲げる理由に準ずる理由で、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
★算定対象期間について下の図でイメージしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年選択式】
被保険者期間の算定対象期間は、原則として、離職の日以前2年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は < A >)(以下「原則算定対象期間」という。)であるが、当該期間に疾病、負傷その他一定の理由により引き続き< B >日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間について被保険者期間を計算する。

【解答】
①【R3年選択式】
<A> 1年間
<B> 30
②【H26年出題】
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合の算定対象期間は、離職の日以前2年間にその6か月間を加算した期間となります。
③【H26年出題】
事業主の命により離職の日以前外国の子会社に出向していたため日本での賃金の支払いを引き続き5年間受けていなかった者は、基本手当の受給資格を有しない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
外国の子会社への出向は、算定対象期間の延長の理由となります。
しかし、算定対象期間は延長した場合でも4年間が最長です。問題文の場合は、離職の日以前4年間に、賃金の支払いを受けていないため、被保険者期間もありません。そのため、基本手当の受給資格はありません。
④【H29年出題】
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係る者に該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。

【解答】
④【H29年出題】〇
算定対象期間の延長の要件は、賃金を受けなかった日数が、「30日以上継続」することです。そのため、問題文の「80日間」については、算定対象期間に加算されますが、「15日間」は原則は加算されません。
しかし、問題文のように、15日欠勤し、復職後再び「同一の理由」で80日欠勤した場合で、中断の期間が「30日未満(問題文では20日)」の場合は、「15日の欠勤期間」も算定対象期間に加算されます。
問題文の場合は「15日間」と「80日間」の両方の期間が加算され、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となります。
(行政手引50153)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
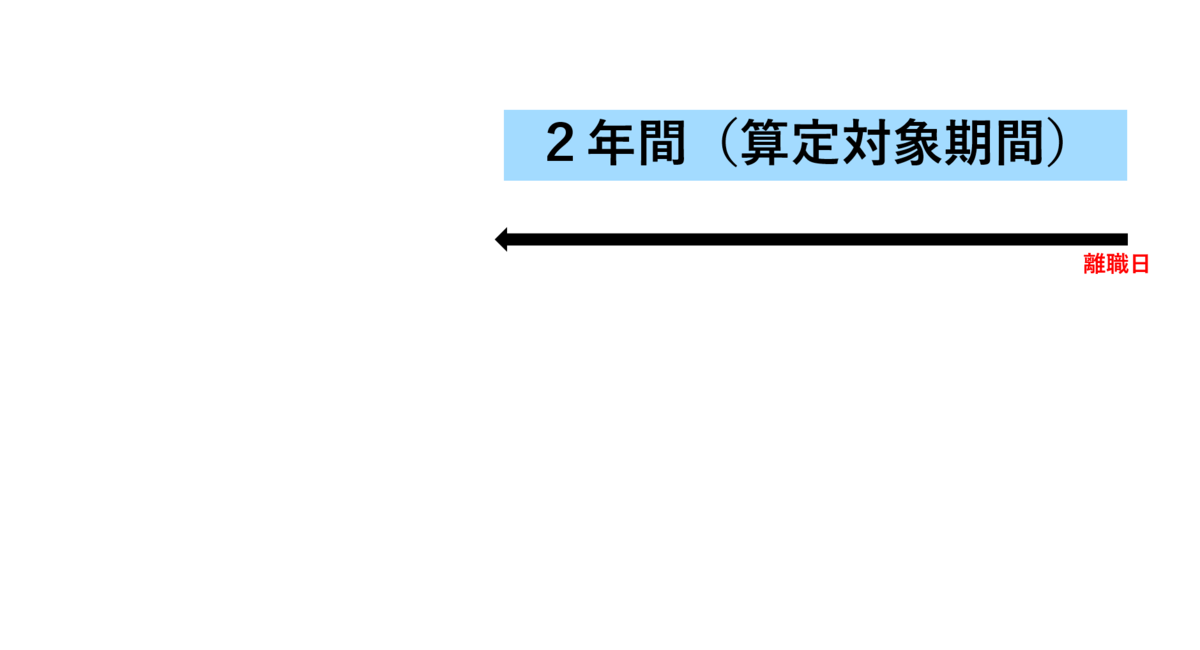
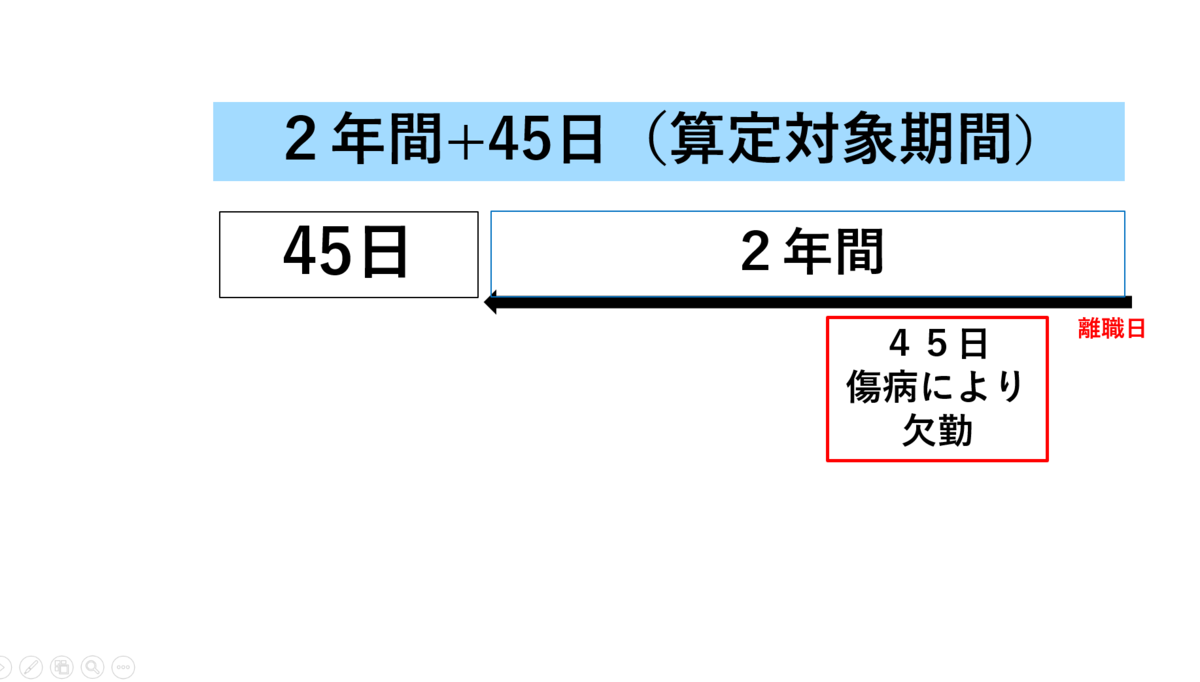
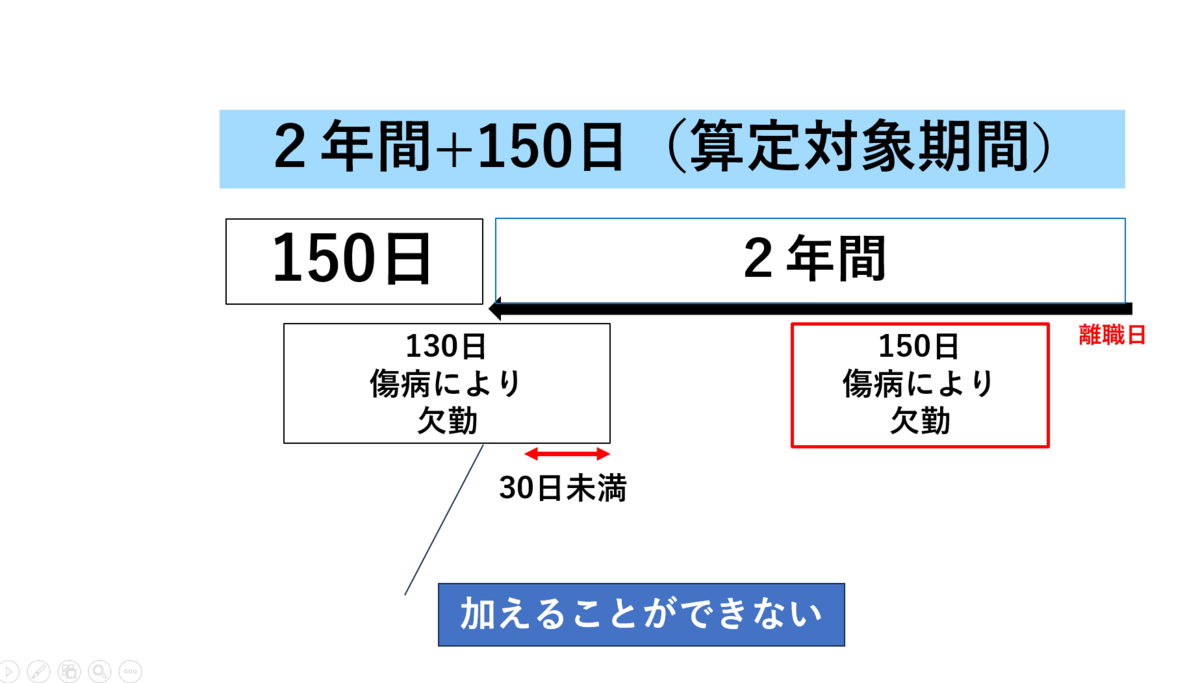
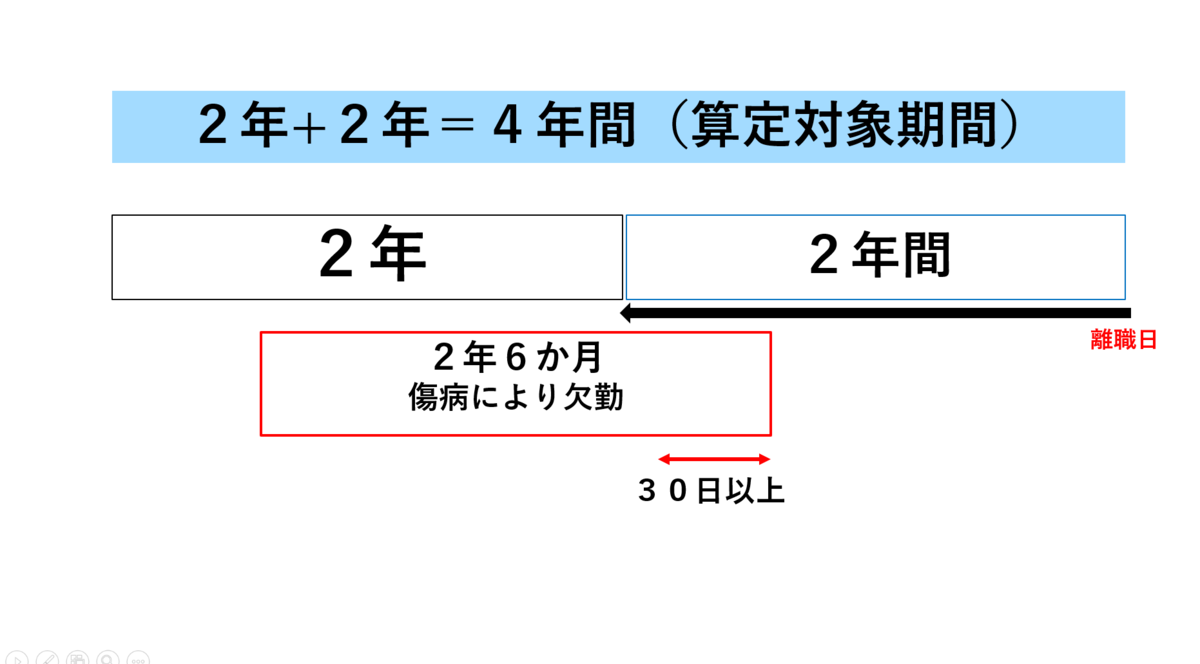
労災保険法「支給制限」
R7-149 01.23
<労災>支給制限(労働者に対するペナルティ)
例えば、労働者が故意にケガの原因となった事故を生じさせた場合は、労災保険の保険給付は行われません。
事故の発生について労働者に非がある場合は、保険給付の支給制限を行うことによってペナルティが課されます。
支給制限の条文を読んでみましょう。
第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「故意に」のときは、政府は、「保険給付を行わない」=絶対的給付制限となります。
②【H26年出題】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「故意に」のときは、絶対的給付制限です。
③【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
「故意に」のときは、絶対的給付制限です。
④【H26年出題】
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
④【H26年出題】 〇
「正当な理由なく療養に関する指示に従わない」場合は、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」となります。
⑤【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」のは、「重大な過失」の場合です。単なる「過失」の場合は、支給制限は行われません。
⑥【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
⑥【R2年出題】 ×
「故意の犯罪行為」の場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」です。
⑦【R6年出題】
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
⑦【R6年出題】 〇
「重大な過失」の場合は、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」となります。
⑧【R2年出題】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
⑧【R2年出題】 〇
「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができるとなります。指示に従わないことに正当な理由があれば、支給制限は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法「安全衛生教育」
R7-148 01.22
雇入時、作業内容変更時の安全衛生教育
労働安全衛生法の「雇入時・作業内容変更時」の安全衛生教育をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第59条第1項、第2項 ① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
則第35条 (雇入れ時等の教育) ① 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 (1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 (2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 (3) 作業手順に関すること。 (4) 作業開始時の点検に関すること。 (5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 (6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 (7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 ② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 |
※特定の業種で一部教育項目の省略が認められていましたが、令和6年4月より省略規定は廃止されています。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
常時使用する労働者だけでなく、臨時に雇用する労働者についても、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことが義務付けられています。
②【R2年出題】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

【解答】
②【R2年出題】 〇
作業内容を変更したときも、新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければなりません。
③【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

【解答】
③【H17年出題】 ×
「雇入れ時の健康診断」と「雇入れ時の安全衛生教育」の対象となる労働者の範囲が違うことに注意してください。
・雇入れ時の健康診断の対象となる労働者 → 常時使用する労働者
・雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者 → 常時使用する労働者だけでなく「すべての労働者」
です。
(雇入れ時の健康診断→則第43条)
④【H22年出題】
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。

【解答】
④【H22年出題】 ×
全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することができます。
⑤【H19年出題】
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

【解答】
⑤【H19年出題】 ×
| 派遣元事業者 | 派遣先事業者 |
雇入れ時の安全衛生教育 | 義務あり |
|
作業内容変更時の安全衛生教育 | 義務あり | 義務あり |
「作業内容変更時の安全衛生教育」の実施義務は、派遣元事業者と派遣先事業者の両方に課せられています。
ちなみに、「雇入れ時の安全衛生教育」の実施義務は派遣元事業者のみに課せられています。(労働契約関係にあるのは派遣元なので)
(派遣法第45条)
⑥【R2年出題】
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならない。

【解答】
⑥【R2年出題】 〇
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間です。安全衛生教育は所定労働時間内に行なうことが原則ですが、法定労働時間外に安全衛生教育を行った場合は、割増賃金を支払う義務があります。
(昭47.9.18基発602号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「賃金支払い5原則」
R7-147 01.21
賃金の通貨払いの原則と例外
賃金は、「労働の対償」として支払われるものです。
労働者が、労働した分の賃金を、間違いなく受け取ることができるよう、労働基準法では、賃金の支払いについて5つの原則を定めています。
賃金支払い5原則は次のとおりです。
① 通貨払い
② 直接払い
③ 全額払い
④ 毎月1回以上払い
⑤ 一定期日払い
条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
今回は、「通貨払いの原則とその例外」をみていきます。
原則 → 賃金は通貨(例えば、1万円札や100円硬貨など)で支払わなければなりません。
例外 → 通貨以外で支払うことができる場合もあります。
・ 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
・ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

【解答】
①【R1年出題】 ×
賃金を「通貨以外のもの」で支払うことができるのは、「法令に別段の定めがある場合又は「労使協定」がある場合」ではなく、「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」です。
「労働協約」と「労使協定」の違いに注意しましょう。
★「労働協約」とは
↓
労働組合(労働者側)と使用者又はその団体(使用者側)との間の労働条件等に関する約束のことです。労働者側が「労働組合」であることがポイントです。労働組合がない事業場では、労働協約は締結できません。
★「労使協定」とは
↓
・事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
・労働者の過半数を代表する者
との書面による協定です。労働組合がなくても労使協定は締結できます。
労使協定は、事業場全体に効力が及びます。
②【H29年出題】
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
労働協約は、締結当事者である「使用者」と「労働組合とその構成員」のみに適用されます。
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。労働協約の適用を受けない労働者については、通貨以外のもので支払うことはできません。
(昭63.3.14基発150号)
③【H28年出題】
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。

【解答】
③【H28年出題】 〇
労働者の「同意」を得た場合は、賃金を口座振込みで支払うことができます。
「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問われません。
労働者が、賃金の振込み対象として労働者本人名義の預貯金口座の指定を行えば、原則として、同意が得られているものと解されます。
(則第7条の2、昭63.1.1基発1号)
④【R3年出題】
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。

【解答】
④【R3年出題】 ×
退職手当の支払についても、労働者の預金又は貯金への振込みで支払う場合は、「労働者の同意」が必要です。
また、通常の賃金とは違い、退職手当は、小切手を労働者に交付することによって支払うことができますが、この場合も「労働者の同意」が必要です。
(則第7条の2第2項)
⑤【R6年出題】 ※問題文を修正しています
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、賃金の支払いに係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が500万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が500万円を超えた場合に当該額を速やかに500万円以下とするための措置を講じていることが、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定められている。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
いわゆる賃金のデジタル払いの要件の一つに「賃金の支払に係る資金移動を行う口座残高上限額を100万円以下に設定又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。」があります。
問題文は500万円になっているので誤りです。
(則第7条の2第1項第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「遺族厚生年金」
R7-146 01.20
【社労士受験】遺族厚生年金の額の計算についてお話しします
遺族厚生年金の額の計算のポイントをお話ししています。
★「短期要件」と「長期要件」それぞれの要件をおさえましょう
★遺族厚生年金の計算の注意点
「短期要件」→被保険者期間に300月の最低保障があります
「長期要件」→生年月日によって給付乗率の引上げがあります
★遺族が「65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者」の場合の計算式をおさえましょう
★65歳以上で、「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の受給権がある場合は、「老齢厚生年金」が優先します
図でイメージしながらポイントをつかみましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-145 01.19
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年1月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年1月13日から1月19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・併給調整の覚え方をお話しします(国民年金法)
・令和7年4月1日高年齢雇用継続給付の支給率が改正されます(雇用保険法)
・「療養の給付」を受けようとする場合(健康保険法)
・国庫負担と国庫補助(健康保険法)
・給付費に対する国庫負担(国民年金法)
・ 年金の内払調整(厚生年金保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「年金の支払調整」
R7-144 01.18
厚生年金保険法の内払調整について
例えば、「遺族厚生年金」の受給権者が「障害厚生年金」の受給権を取得し、「障害厚生年金」の支給を受けることを選択した場合、「遺族厚生年金」の支給は停止されます。
にもかかわらず、届出が遅れたことなどによって、引き続き「遺族厚生年金」が支払われる場合があります。
その場合、遺族厚生年金を返還させ、改めて障害厚生年金を支給するのは、利便性に欠けますので、調整を簡単にするため、遺族厚生年金と障害厚生年金について「内払調整」を行います。
なお「内払」は「同一人」の年金の間の調整です。
「内払」について、図でイメージしましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第39条 (年金の支払の調整) ① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 ② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 ③ 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 |
■内払調整
①について
・乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅したにもかかわらず、翌月以後、乙年金の支払が行われた
・同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合に、翌月以後、乙年金の支払が行われた
②について
・年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われた
・年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、翌月以後も減額しない額の年金が支払われた
③について(国民年金と厚生年金保険の調整)
・同一人に対して国民年金法の年金の支給を停止して、厚生年金保険の年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合に、翌月以後の分として国民年金の年金の支払が行われた
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】 ※問題文の者は、「第1号厚生年金被保険者期間」のみを有するものとします。(改正による修正)
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。

【解答】
①【H25年出題】 〇
従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、「従前の障害厚生年金の返還を求める」のではなく、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の「内払とみなす」となります。
②【H25年出題】※問題文の者は、「第1号厚生年金被保険者期間」のみを有するものとします。(改正による修正)
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。

【解答】
②【H25年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合、遺族厚生年金の支給が停止されますが、にもかかわらず、翌月以後も遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の「内払とみなす」となります。
③【R6年出題】
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

【解答】
③【R6年出題】 〇
同一人に対する「国民年金法による年金たる給付」と「年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)」との間の内払調整の規定です。
④【H25年出題】(※改正による修正あり)
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。

【解答】
④【H25年出題】 〇
③の問題と同じです。
※国民年金法の寡婦年金と60歳台前半の老齢厚生年金は、どちらか選択です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
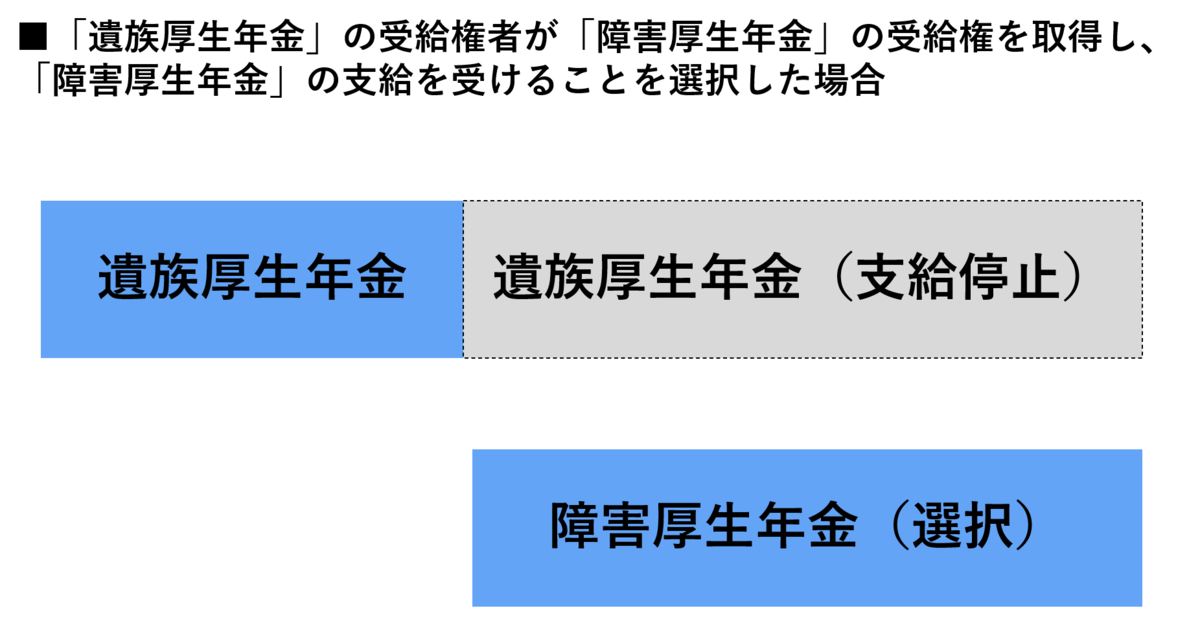
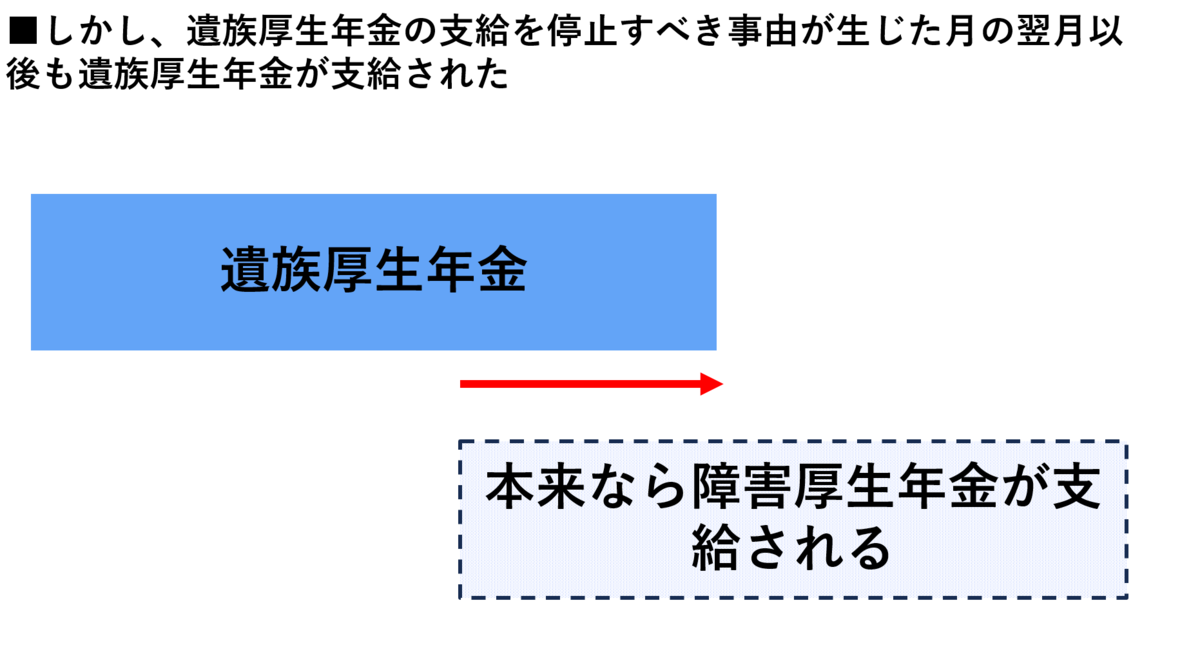
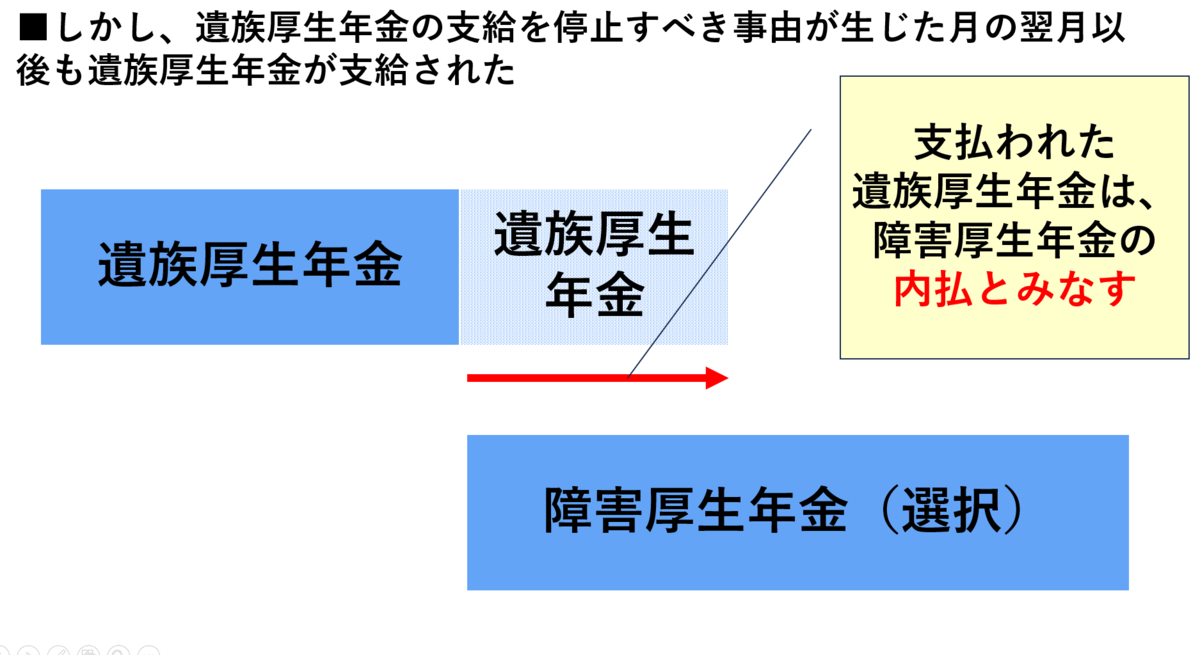
国民年金法の国庫負担
R7-143 01.17
国民年金の給付費に対する国庫負担
通常、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の給付に要する費用の総額の「2分の1」は国庫負担で賄われています。
また、免除期間等については、特別国庫負担があります。
下の図①でイメージしてください。
問題を解いてみましょう。
①【H26年出題】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
<ポイントその1>
・4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担
→ 「480」から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数が限度となります。
★例えば、60歳以降に任意加入した場合、480月を超える場合がありますが、国庫負担が行われるのは、「480月」が限度です。
図②でイメージしましょう。
<ポイントその2>
・保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、その7分の4を国庫が負担します。
「7分の4」とは?図③でイメージしましょう。
(法第85条)
②【R3年出題】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
「学生納付特例」及び「納付猶予」の期間は国庫負担の対象となりません。そのため、老齢基礎年金の額は、ゼロで計算されます。
(法第85条)
③【R3年出題】
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の「4分の1」ではなく、「2分の1」に相当する額を合計した、当該費用の「100分の40」ではなく「100分の60」に相当する額を負担することになっています。
図④でイメージしましょう。
(法第85条)
④【R4年出題】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

【解答】
④【R4年出題】 〇
「付加年金」の給付に要する費用及び「死亡一時金の加算額(8500円)」の給付に要する費用の総額の「4分の1」に相当する額に、国庫負担が行われています。
(昭60法附則第34条第1項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
図①
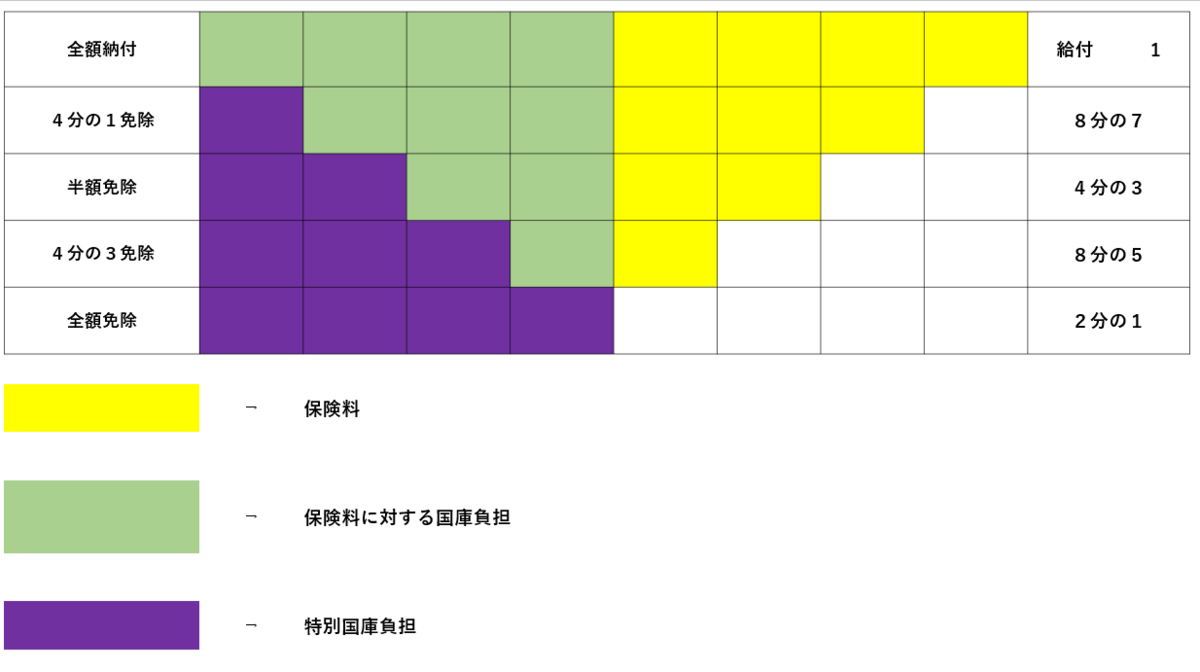
図②
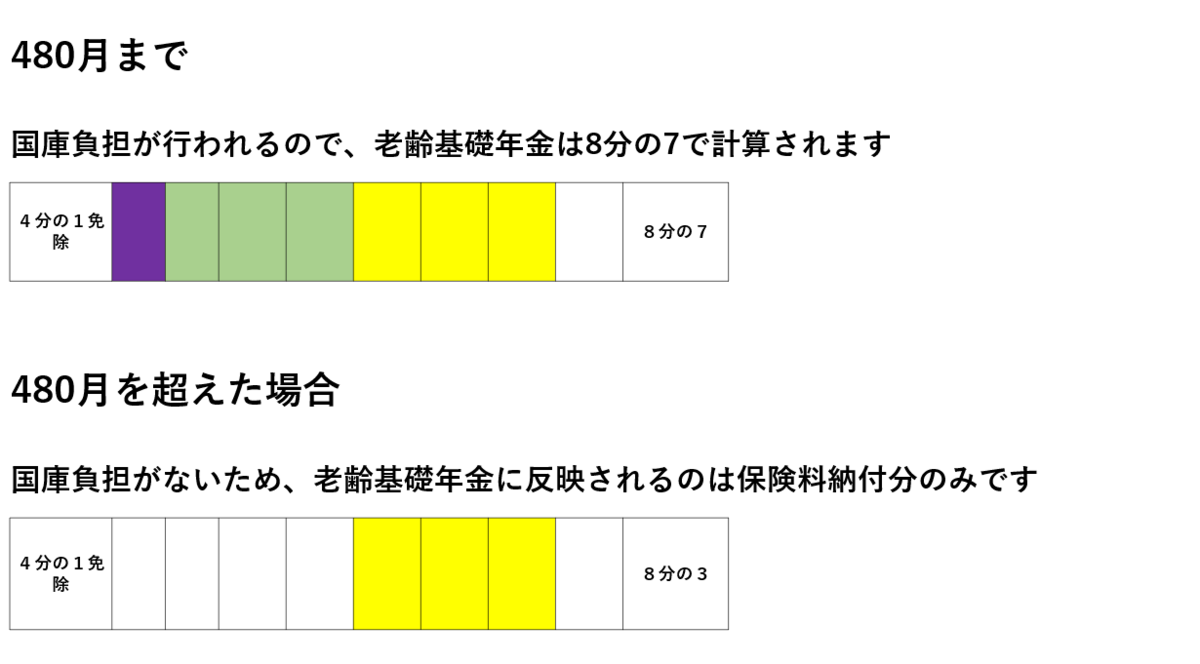
図③
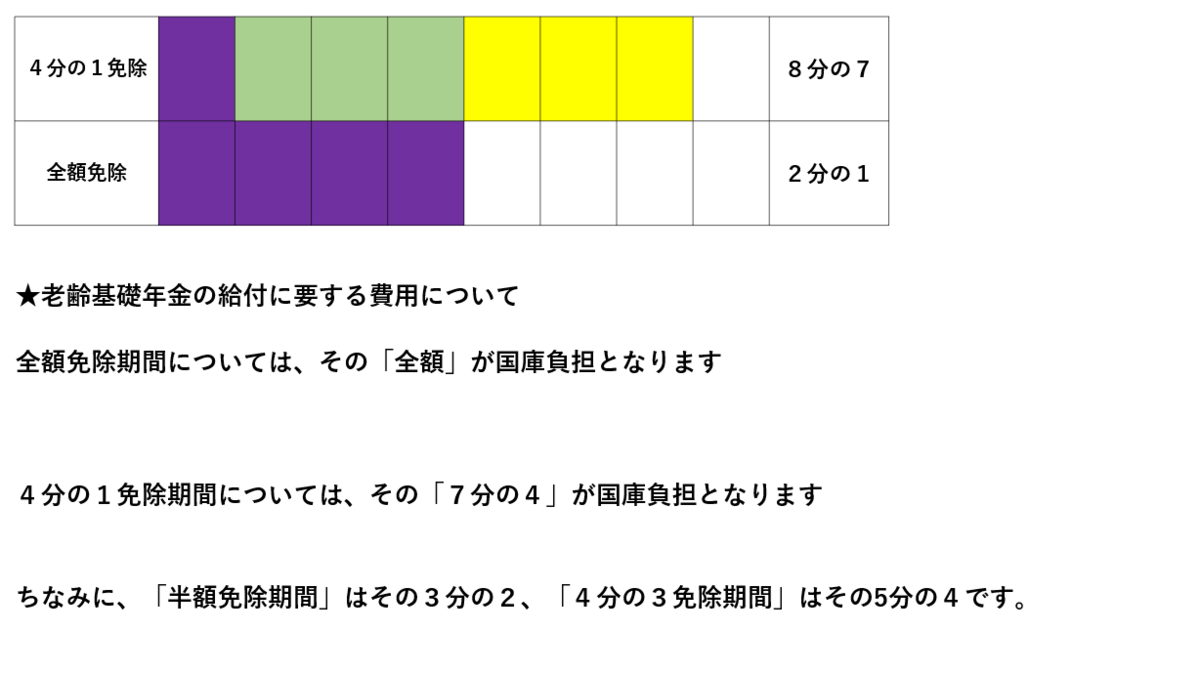
図④
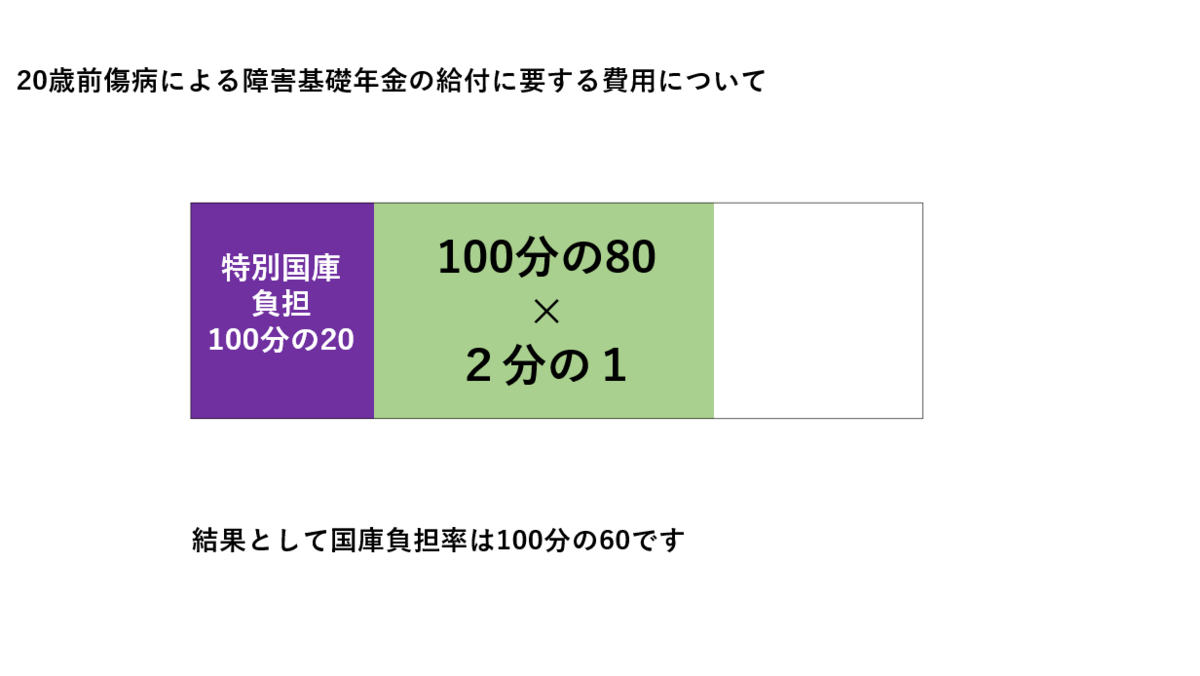
健康保険法「国庫負担等」
R7-142 01.16
健康保険の「国庫負担」と「国庫補助」
健康保険の事業を運営するための費用には、保険給付に要する費用、事務の執行に要する費用などがあります。
今回は、国庫が負担する費用、国庫が補助する部分をみていきます。
「国庫負担」の条文を読んでみましょう。
法第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。 |
事務の執行に要する費用(事務費)については、国庫が全額負担します。
過去問をどうぞ!
①【H23年選択式】※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。

【解答】
<A> 予算
<B> 介護納付金
<C> 被保険者数
<D> 概算払い
★介護納付金のイメージ
| 介護保険第2号被保険者 (40歳以上65歳未満) |
|
|
|
|
↓(介護保険料)
|
|
|
|
| 健康保険組合・全国健康保険協会 |
|
|
|
|
↓(介護納付金)
|
|
|
|
| 社会保険診療報酬支払基金 |
|
|
|
|
↓
|
|
|
|
| 介護保険 |
|
|
|
②【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、全国健康保険協会に対しても、健康保険組合に対しても、国庫が負担しています。
②【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払をすることができる。

【解答】
②【R6年出題】 〇
国庫は、健康保険組合に対しても、事務費を負担しています。健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数が基準となっています。「被扶養者数や標準報酬月額」などは基準に入っていませんので、注意してください。
また、その国庫負担金は、概算払をすることができることになっています。
次は、「国庫補助」についての過去問です。
【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】
【R3年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の療養の給付などの支給に要する費用等の1000分の164について、国庫補助が行われています。
ただし、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
(法第153条)
最後に、特定健康診査等についての過去問です。
【H30年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】
【H30年出題】 ×
費用の全部ではなく、「費用の一部」です。
条文を読んでみましょう。
第154条の2 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「療養の給付」
R7-141 01.15
健康保険の「療養の給付」を受けようとする場合
「療養の給付」は、健康保険の代表的な給付です。
療養の給付は「現物給付」で、病気で医療機関に行くと、診察等を受けて、かかった費用の原則3割の一部負担金を医療機関に支払います。
「療養の給付」が受けられる医療機関をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第63条第3項 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとする。 (1) 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。) (2) 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの (3) 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 |
それぞれをイメージしてみましょう。
(1)保険医療機関・保険薬局(誰でも行くことができる一般の病院など)
(2)事業主医局(健康保険組合管掌健康保険の事業主が開設する病院)など
(3)健康保険組合が開設する病院など
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「保険医療機関」は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うもので、一部の被保険者及び被扶養者に限定することはできません。
「保険医療機関として指定を受けた」場合は、健康保険組合が開設した病院でも、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することはできません。
(昭32.9.2保険発123号)
②【R6年出題】
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局が、当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うには、「保険医療機関の指定」を受けなければなりません。
(昭32.9.2保険発123号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
高年齢雇用継続給付の支給率(雇用保険法)
R7-140 01.14
令和7年4月1日高年齢雇用継続給付の支給率が改正されます
「高年齢雇用継続給付」の支給率が、令和7年4月1日に改正されます。ポイントをみていきましょう。
令和7年4月1日前(改正前)
賃金の低下率 | 支給率 |
61%未満 | 15% |
61%以上75%未満 | 15%から一定の割合で逓減する率 |
75%以上 | 不支給 |
↓
令和7年4月1日以後(改正後)
賃金の低下率 | 支給率 |
64%未満 | 10% |
64%以上75%未満 | 10%から一定の割合で逓減する率 |
75%以上 | 不支給 |
条文を読んでみましょう。
法第61条第5項、第6項(令和7年4月以降) ⑤ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。 (1) 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額未満であるとき → 100分の10 (2) 前号に該当しないとき → みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率 ⑥ 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない。 |
ポイント!
★支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上の場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
★「支給対象月に支払われた賃金の額」+「高年齢雇用継続基本給付金として算定された額」が支給限度額を超える場合
→ 「支給限度額」-「支給対象月の賃金の額」が高年齢雇用継続基本給金の額となります。
※支給限度額は令和6年8月から376,750円です。
★「高年齢雇用継続基本給付金として算定された額」が「賃金日額の最低限度額×100分の80」を超えない場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金は、支給されません。
※令和6年8月から「賃金日額の最低限度額×100分の80」は、2,869円×100分の80=2,295円です。
では、過去問をどうぞ!
①【R6年出題】※令和7年4月改正に合わせて問題文を修正しています
高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の10となる。

【解答】
①【R6年出題】 ×
高年齢再就職給付金の額が、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の10となるのは、再就職後の支給対象月の賃金額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の85に相当する額未満」ではなく、「100分の64に相当する額未満」であるときです。
(法第61条の2第3項)
②【R1年出題】※令和7年4月改正に合わせて問題文を修正しています
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の10を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

【解答】
②【R1年出題】 〇
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合(100分の64未満の場合)、高年齢雇用継続基本給付金の支給率は、「100分の10」となります。
③【R6年出題】
支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)の100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

【解答】
③【R6年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないときは、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法の併給調整
R7-139 01.13
国民年金の「併給調整」の覚え方をお話しします
同一人に複数の年金の受給権が発生することがあります。
★原則は一人一年金です
★例外もあります
<例外の重要ポイント!>
・老齢基礎年金と付加年金はセットで支給されます
・支給事由が同じ「国民年金の年金」と「厚生年金保険の年金」は2階建てで併給されます
・支給事由が異なっていても「65歳以上限定」で併給される組合せがあります
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-138 01.12
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年1月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年1月6日から1月11日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・繰上げ支給の老齢基礎年金についてお話しします(国民年金法)
・日本最初の社会保険「健康保険法」についてお話しします
・国民年金法・厚生年金保険法「最低限おさえたい歴史」
・ 国民年金法・厚生年金保険法「目的の異なる点」
・ 退職等の際の金品の返還義務(労働基準法)
・ 特別加入者のうち「中小事業主等」について(労災保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険の特別加入制度
R7-137 01.11
労災特別加入者のうち「中小事業主等」について
労災保険には「特別加入制度」があります。
・労災保険法は「労働者」を保護するための制度ですが、労働者に準じて保護するにふさわしい者は、特別加入することができます。
・また、労災保険は日本国内に限って適用されますが、日本から海外の事業場に派遣された労働者についても、特別加入することができます。
特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つの種別があります。
今回は、「中小事業主等」についてお話しします。
「中小事業主等」として特別加入できる者の要件を確認しましょう。
① 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
② ①の事業主が行う事業に従事する者(→家族労働者や法人企業の場合の代表権をもたない重役など)
※厚生労働省令で定める数について
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外 | 300人以下 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。

【解答】
①【H26年出題】 〇
特別加入の制度は、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨で設けられています。
(昭40.11.1基発第1454号)
②【H30年選択式】
労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で< A >に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は< B >を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< C >である。
<選択肢>
A | ① 社会保険事務所 ② 商工会議所 ③ 特定社会保険労務士 ④ 労働保険事務組合 |
B | ① 小売業 ② サービス業 ③ 不動産業 ④ 保険業 |
C | ① 20,000円 ② 22,000円 ③ 24,000円 ④ 25,000円 |

【解答】
<A> ④ 労働保険事務組合
<B> ② サービス業
<C> ④ 25,000円
(法第33条第1号、第34条、則第46条の16、則第46条の20)
③【R4年出題】
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
<A> 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<B> 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<C> 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<E> 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

【解答】
③【R4年出題】
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法第23条金品の返還
R7-136 01.10
退職時の金品の返還義務
労働者が死亡又は退職した際に、権利者の請求があった場合、使用者は請求があった日から7日以内に金品を返還しなければなりません。
労働者の足止め策に利用させないようにするためです。
第23条 (金品の返還)
① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② 賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、①の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 |
請求する権利がある「権利者」は、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は遺産相続人です。一般債権者は含まれません。
(昭22.9.13発基17号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
労働者の死亡又は退職の際に
・ 権利者の請求があった場合 → 7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません
ただし、
・賃金又は金品に関して争いがある場合 → 異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければなりません
②【H30年出題】
労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」です。
労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたりません。
(昭23.3.17基発464号)
③【H12年出題】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
③【H12年出題】 ×
退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。
退職手当は、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足ります。
(昭26.12.27基収5483号)
④【R6年出題】
労働基準法第23条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、7日以内に賃金を支払う必要はない。

【解答】
④【R6年出題】 ×
通常の賃金は、「一定期日払い」の原則がありますが、第23条はその特例で、権利者の請求があれば7日以内に支払うことを強行的に義務付けています。
そのため、就業規則で労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定していたとしても、請求があれば7日以内に賃金を支払わなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法・厚生年金保険法の違い
R7-135 01.09
国民年金法・厚生年金保険法の目的の異なる点
国民年金法と厚生年金保険法の違いを条文で確認しましょう。
国民年金法の第1条と第2条です。
第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 |
(参考)
日本国憲法第25条
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づいています。
厚生年金保険法第1条です。
第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
過去問をどうぞ!
①【国年H28年選択式】
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】
<A> 安定
<B> 共同連帯
②【国年R5年選択式】
国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して< A >を行うものとする。」と規定されている。
<選択肢>
① 年金支給
② 年金の給付
③ 必要な給付
④ 保険給付

【解答】
<A> ③ 必要な給付
③【国年H26年出題】
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

【解答】
③【国年H26年出題】 ×
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して「必要な保険給付」ではなく、「必要な給付」を行うものとされています。
「保険原理」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる仕組みのことですが、国民年金法の給付には、保険原理によらないものもあります。例えば、20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料の負担なく給付されるものです。
国民年金法に基づくすべての給付が保険原理により行われるものではないので、国民年金法では「保険給付」ではなく、「必要な給付」という用語を使います。
なお、厚生年金保険法では「保険給付」という用語を使います。
ちなみに法律の名称も「国民年金法」には「保険」が入っていません。「厚生年金保険法」は「保険」が入っています。
④【厚年H30年出題】
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

【解答】
④【厚年H30年出題】 ×
問題文は国民年金制度の目的条文です。国民年金はすべての国民が対象ですので、「国民」という言葉が使われています。
厚生年金保険制度は「労働者」が対象ですので、「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的」としています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法・厚生年金保険法について
R7-134 01.08
国民年金法・厚生年金保険法で最低限おさえたい歴史
国民年金法、厚生年金保険法の歴史で重要な年号をまとめました。
昭和14年 | 船員保険法制定 | ・社会保険方式による日本で最初の公的年金 ・昭和15年施行 |
昭和16年 | 労働者年金保険法制定 | ・昭和17年施行 ・昭和19年に「厚生年金保険法」に改称 |
昭和34年 | 国民年金法制定 | ・昭和34年11月福祉年金(無拠出制)開始 |
昭和36年 4月 | 国民皆年金の実施 | ・国民年金(拠出制)開始 |
昭和61年 4月 | 基礎年金の導入 | ・「基礎年金」と「報酬比例」の2階建て ・基礎年金は全国民が対象 第1号被保険者(自営業等) 第2号被保険者(会社員、公務員等) 第3号被保険者(専業主婦等) |
平成27年 10月 | 被用者年金一元化 | ・被用者の年金制度が厚生年金に統一された |
年金の歴史を図でイメージしましょう。(下の図を参照してください)
ポイント!
・昭和36年4月「国民皆年金」
・昭和61年4月「基礎年金の導入」
★昭和61年4月前の制度を「旧法」、昭和61年4月以降の制度を「新法」といいます。
過去問をどうぞ!
①【H19年出題(社一)】
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。

【解答】
①【H19年出題(社一)】 〇
国民年金法は昭和34年に制定、昭和36年4月から全面施行され、国民皆年金が実現しました。
②【H19年出題(国年)】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
②【H19年出題(国年)】 ×
国民年金法は昭和34年に制定され、同年10月ではなく「同年11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始されました。また、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立しました。
③【H15年選択式(国年)】
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
<選択肢>
① 大正15年4月1日
② 大正15年4月2日
③ 昭和2年4月1日
④ 昭和2年4月2日
⑤ 裁定日
⑥ 初診日
⑦ 障害認定日
⑧ 裁定請求日

【解答】
<A> ② 大正15年4月2日
<B> ⑦ 障害認定日
ポイント!
・ 「大正15年4月2日」以降生まれの人は、老齢基礎年金(新法の年金)の対象となります。ただし、施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった人を除きます。
・ 「障害認定日」が昭和61年4月1日以降の人は、障害基礎年金(新法の年金)の対象となります。
④【R6年出題(社一)】
日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。

【解答】
④【R6年出題(社一)】 〇
日本の公的年金制度は、「賦課方式」を基本とした仕組みで運営されていることがポイントです。
賦課方式とは、現役世代の保険料負担で、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みです。
(令和5年版厚生労働白書P256)
【R1年出題(社一)】※問題文修正あり
被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは、平成27年10月1日である。

【解答】
【R1年出題(社一)】 〇
被用者年金一元化が行われたのは、平成27年10月1日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
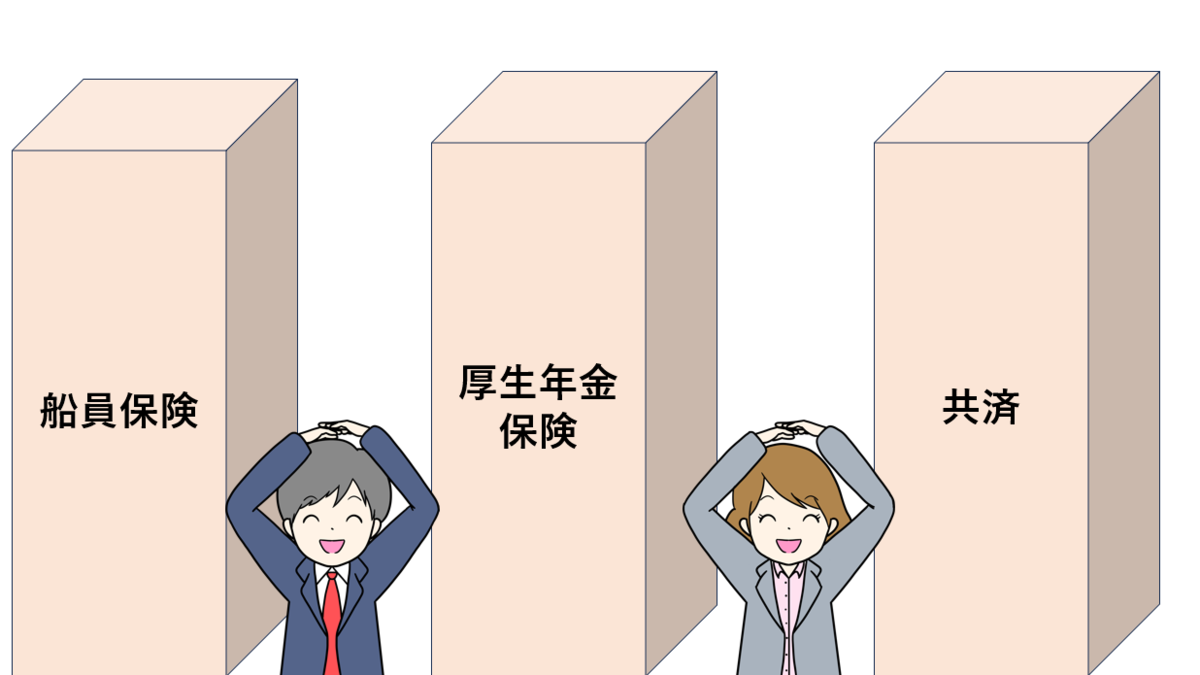
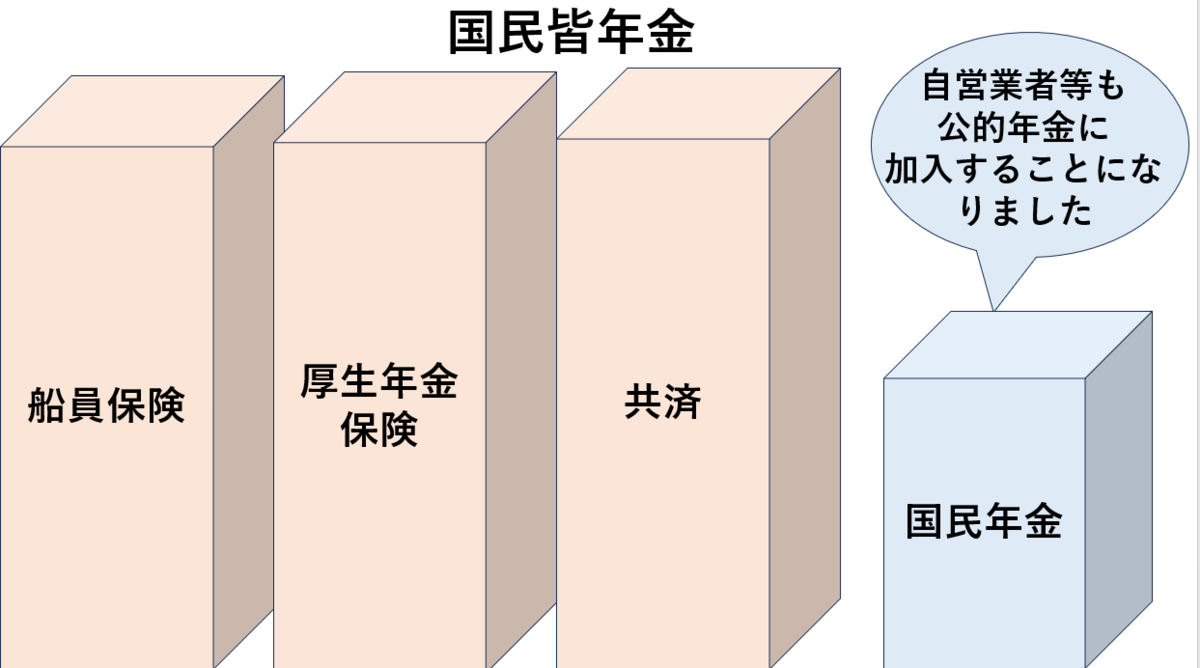
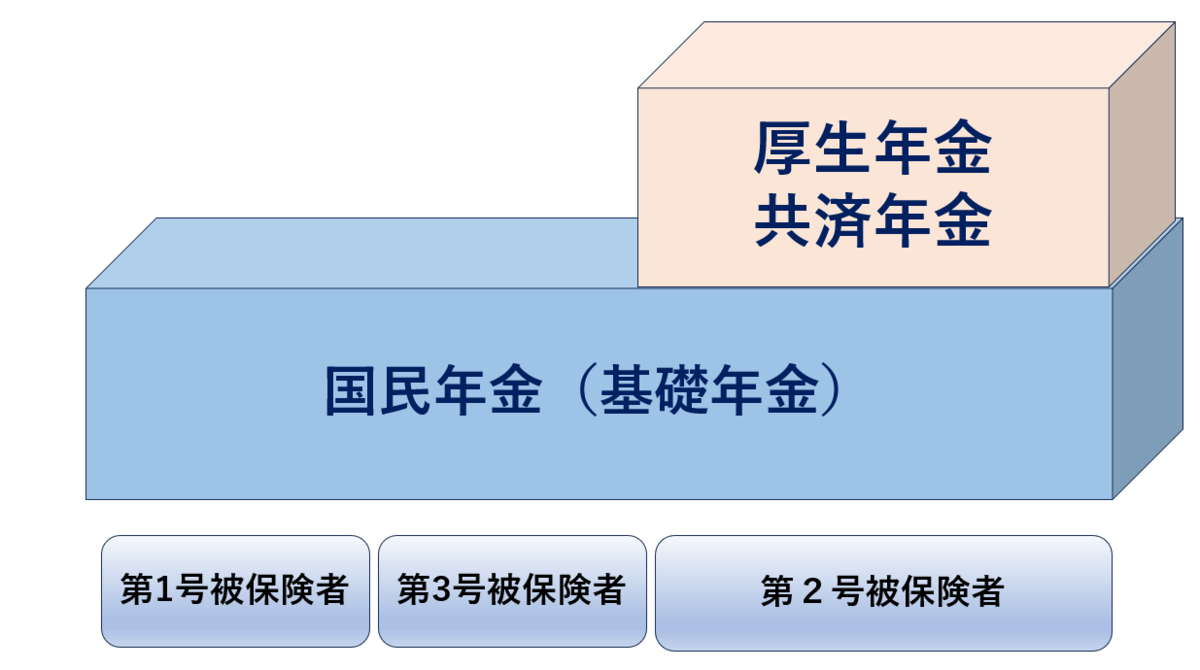
健康保険法について
R7-133 01.07
日本最初の社会保険「健康保険法」についてお話しします
<健康保険の歴史>
健康保険法は労働者を対象にした保険で、大正11年に制定された日本で最初の社会保険です。
しかし、大正12年に関東大震災が発生したため、全体が施行されたのは、昭和2年です。
当初の健康保険は業務上の傷病等も保険給付の対象になっていました。当時は、業務上、業務外を判別することが難しかったからです。ただし、昭和22年に労災保険法がスタートし、業務災害は労災保険の対象になりました。
ちなみに、日本で最初の社会保険方式の公的年金は、昭和14年に制定された船員保険制度の年金です。
国民皆保険が実現したのは、国民皆年金と同じ昭和36年4月です。
国民皆保険のイメージ
健 康 保 険 |
船 員 保 険 |
国家公務員共済組合 |
地方公務員共済組合 |
私立学校教職員共済 |
国民健康保険 |
後期高齢者医療(原則75歳以上) |
健康保険法の第1条を読んでみましょう。
第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式(社一)】
世界初の社会保険は、< A >で誕生した。当時の< A >では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、 < A >に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、< B >に「健康保険法」を制定した。
<選択肢>
① アメリカ
② イギリス
③ ドイツ
④ フランス
⑤ 昭和13年
⑥ 昭和16年
⑦ 大正11年
⑧ 大正15年

【解答】
<A> ③ ドイツ
<B> ⑦ 大正11年
(平成23年版厚生労働白書P35)
②【H21年出題】
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。

【解答】
②【H21年出題】 ×
健康保険法は、大正11年に制定された日本で最初の社会保険に関する法ですが、制定と同時に施行されたのではありません。
施行は大正15年(保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年)です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
繰上げ支給の老齢基礎年金
R7-132 01.06
繰り上げ支給の老齢基礎年金についてお話しします
繰上げ支給の老齢基礎年金のポイントは、
・請求によって受給権が発生すること
・繰り上げた月数に応じて減額されること
です。
その他さまざまな注意点があり、本試験でも頻出される箇所です。
繰り上げ支給の老齢基礎年金の注意点をYouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-131 01.05
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年12月第5週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月30日から令和7年1月4日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・適用除外を整理しましょう(労基、安衛、労災、雇用、健保、厚年、国年)
・各法律から適用除外されるもの(実践編)(労基、安衛、労災、雇用、健保、厚年、国年)
・労働基準法第1条を読んでみましょう(労働基準法)
・制定時の状況などから労働安全衛生法を知りましょう(労働安全衛生法)
・労災保険法の沿革をお話しします~労災保険法の歴史(労災保険法)
・雇用保険法の沿革をお話しします(雇用保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法とは?
R7-130 01.04
雇用保険法の沿革をお話しします
今日は、雇用保険法についてお話しします。
<歴史>
昭和22年に「失業保険法」が施行されました。
当初の目的条文は、「失業保険は、被保険者が失業した場合に、失業保険金を支給して、その生活の安定を図ることを目的とする。」となっていて、保険の対象は「失業」のみでした。
「雇用保険法」が施行されたのは、昭和50年4月からです。「雇用保険法」の保険の対象は「失業」だけではありません。
<目的>
では、現在の目的条文を読んでみましょう。
第1条 (目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
第3条 (雇用保険事業) 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 |
雇用保険事業の内容を体系図でみてみましょう。
(この記事の下に図を入れています。)
では、過去問をどうぞ!
【H28年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< A >を図るとともに、< B >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< C >を図ることを目的とする。」と規定されている。

【解答】
<A> 生活及び雇用の安定
<B> 求職活動
<C> 福祉の増進
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
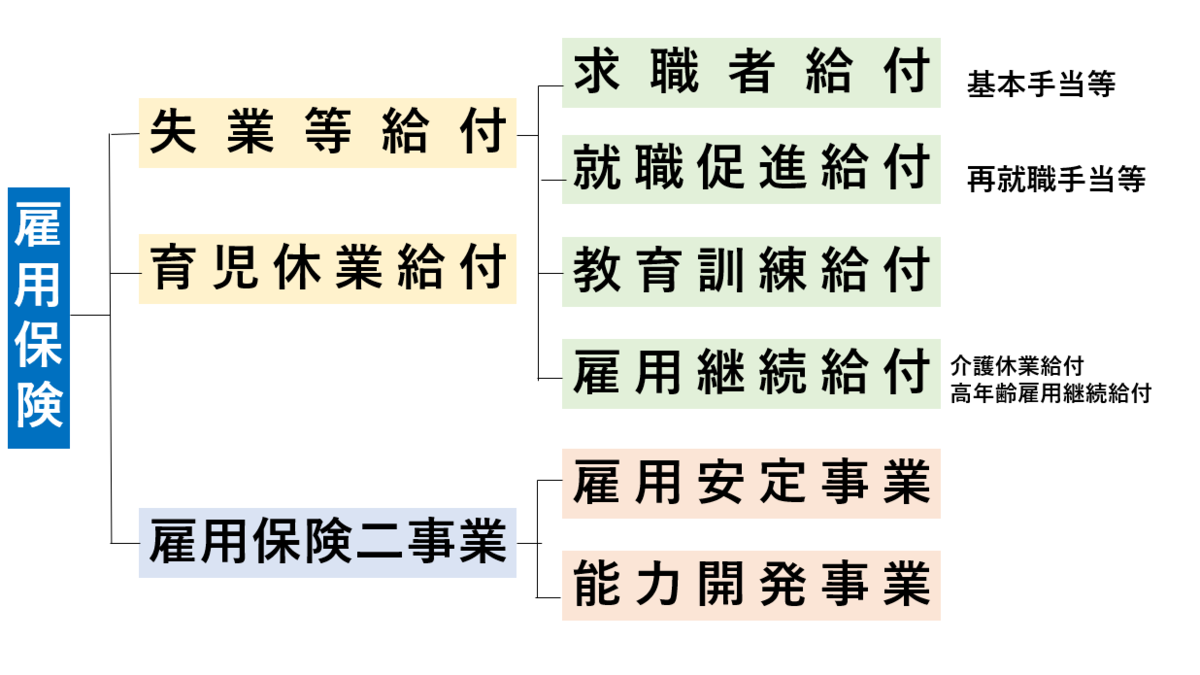
労災保険法の歴史
R7-129 01.03
労災保険法の沿革をお話しします~労災保険の歴史
★ 労働者災害補償保険法は、昭和22年4月7日公布、同年9月1日から施行されました。
★ 労働条件の最低基準を定めた労働基準法は昭和22年9月に施行、同時に、業務上の災害を保護するため、労働者災害補償保険法が施行されました。
<その後の主な改正>
■昭和48年
「通勤災害」について、業務災害に準じた保護が加えられることになりました
■平成13年
「二次健康診断等給付」が施行されました。「二次健康診断」とその結果に基づく「特定保健指導」を労災保険の保険給付として行うことになりました。
■令和2年
「複数業務要因災害」に関する保険給付が加わりました。
条文を読んでみましょう。
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
労災保険の第1の目的は「保険給付」を行うことです。
第2の目的が、「社会復帰促進等事業」です。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 (1) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 (2) 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。) (3) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 (4) 二次健康診断等給付
第29条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 (1) 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 (2) 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 (3) 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 |
過去問をどうぞ!
【令和元年選択式】 ※改正による修正あり
労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、< A >法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び< B >給付の4種類である。通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び< C >年金である。
<選択肢>
<A> ① 労働関係調整 ② 労働基準 ③ 労働組合 ④ 労働契約
<B> ① 求職者 ② 教育訓練 ③ 失業等 ④ 二次健康診断等
<C> ① 厚生 ② 国民 ③ 傷病 ④ 老齢

【解答】
<A> ② 労働基準
<B> ④ 二次健康診断等
<C> ③ 傷病
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法とは?
R7-128 01.02
制定時の状況などから労働安全衛生法を知りましょう
労働安全衛生法は、昭和47年に公布されました。
【労働安全衛生法制定の背景】
『近年のわが国の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この著しい経済興隆のかげに、今なお多くの労働者が労働災害を被っているという状況にある。』中で、労働安全衛生法は制定されました。
『1970年代に入り、従来の経済成長のあり方に反省が加えられ、国の施策の重点は国民福祉の向上へ向けられつつある。このような情勢のもとに、今後における労働災害防止対策は、人命尊重の基本的理念に立ち、この法律を軸として、より強力、より的確に推進されなければならない。』とされています。
(参照:昭和47.9.18発基第91号)
労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立したものです。
【労働基準法との関係】
『労働安全衛生法は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の労働条件の重要な一端を占めるものというべく、第1条(目的)、労働基準法第42条等の規定により、この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。』となっています。
『したがって、労働基準法の労働憲章的部分(具体的には第1条から第3条まで)は、この法律の施行にあたっても当然その基本とされなければならない。』
『賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まって、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないもの』となっています。
(参照:昭和47.9.18発基第91号)
労働安全衛生法第1条(目的)を読んでみましょう。
| この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
労働安全衛生法の目的は、「職場における労働者の安全と健康を確保」すること、「快適な職場環境の形成を促進すること」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】
労働安全衛生法は、その目的を第1条で「労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< A >の形成を促進することを目的とする。」と定めている。

【解答】
<A>快適な職場環境
②【H24年選択式】
労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< C >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< D >を促進することを目的とすると規定している。

【解答】
<C> 危害防止基準
<D> 快適な職場環境の形成
③【H15選択式】
労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の< E >の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と< E >についての一般法である労働基準法とは < F >関係に立つものである、とされている。

【解答】
<E> 労働条件
<F> 一体としての
④【H29年出題】
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

【解答】
④【H29年出題】 〇
労働安全衛生法と労働条件についての一般法である労働基準法とは、「一体としての関係」に立つものです。そのため、労働基準法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行にあたっても、その基本とされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法第1条
R7-127 01.01
労働基準法第1条を読んでみましょう!
労働基準法第1条を読んでみましょう。
法第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
<第1条のポイント!>
・ 第1条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働条件を保障することを宣明したものです。労働基準法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならないものです。
・ 労働者が人たるに値する生活を営むためにはその標準家族の生活をも含めて考えることとされます。
・ 第2項については労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて認定されます。経済諸条件の変動に伴うものは本条に抵触するものとされません。
(昭和22.9.13発基第17号)
過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

【解答】
①【H19年選択式】
<A> が人たるに値する生活を営む
②【H25年出題】
労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、労働者の職場に関する一切の待遇をいいますので、賃金、労働時間、解雇、災害補償等だけでなく、安全衛生、寄宿舎等の条件も含まれます。
③【H28年出題】
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】
③【H28年出題】 〇
労働基準法第1条は、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されます。
(昭和22.9.13発基第17号)
④【H25年出題】
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。

【解答】
④【H25年出題】 〇
労働基準法で定める労働条件の最低基準が標準とならないように、この最低基準を理由として労働条件を低下させることは禁止され、その向上を図るように努めることが労働関係の当事者に義務づけられています。
⑤【R3年出題】
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいいます。社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合は、労働基準法の基準が理由になっていませんので、同条に抵触しません。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
各法律の適用除外の実践編
R7-126 12.31
<実践編>各法律の適用を除外されるもの
前回は、各法律から適用除外されるものを整理しました。
こちらをどうぞ(YouTubeでお話ししています)
↓
 https://youtu.be/dwiAd9i80bI?si=Pg9gvWQba8Od0TVL
https://youtu.be/dwiAd9i80bI?si=Pg9gvWQba8Od0TVL
今回は適用除外の実践編です。
過去問を解きながら、おぼえましょう。
労働基準法
①【R4年出題】
同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。

【解答】
①【R4年出題】 ×
同居の親族のみを使用する事業で、一時的に使用される「親族以外の者」は、労働基準法の労働者に該当します。
②【H29年出題】
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。

【解答】
②【H29年出題】 ×
法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者は、「家事使用人」ですので、労働基準法は適用されません。
(H11.3.31基発168号)
③【H16年出題】
船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。

【解答】
③【H16年出題】 ×
船員にも労働基準法が一部適用されます。
船員法第1条第1項に規定する船員については、労働基準法の第1条から第11条までとそれに関連する罰則規定が適用されます。
第1条「労働条件の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分は適用されます。
(第116条)
労働安全衛生法
【R2年出題】
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

【解答】
【R2年出題】 〇
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所、家事使用人には適用されません。
(法第2条)
労災保険法
①【H29年出題】
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
市の経営する水道事業の非常勤職員には、労災保険が適用されます。
★ 地方公務員のうち、「現業部門の非常勤職員」には、労災保険が適用されます。
なお、現業部門の「常勤職員」は、地方公務員災害補償法の規定で、労災保険の適用が排除されています。
②【H29年出題】
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

【解答】
②【H29年出題】 ×
行政執行法人の職員には、労災保険法は適用されません。行政執行法人の職員は、国家公務員災害補償制度の対象となります。
③【H29年出題】
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

【解答】
③【H29年出題】 ×
非現業の一般職の国家公務員には、労災保険は適用されません。非現業の一般職の国家公務員は、国家公務員災害補償制度の対象となります。
(法第3条)
④【H29年出題】
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

【解答】
④【H29年出題】 〇
国の直営事業は、労災保険の適用が除外されています。
(法第3条)
⑤【H29年出題】
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
常勤の地方公務員には、労災保険は適用されません。
(地方公務員災害補償法の規定による)
雇用保険法
①【H27年出題】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
学生又は生徒は雇用保険の適用が除外されますが、「休学中の者」は、雇用保険法の被保険者となり得ます。
(法第6条第4号、則第3条の2)
②【H25年出題】
船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

【解答】
②【H25年出題】 〇
船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むために雇用される者は、雇用保険の適用が除外されますが、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。
(法第6条第5号)
健康保険法
①【R5年出題】
適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。

【解答】
①【R5年出題】 〇
「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、健康保険の適用が除外されます。
ただし、契約の更新等により実際には最初の雇用契約の期間を超えて継続して使用されることが見込まれる場合は、最初の雇用契約の期間から被保険者資格を取得します。
最初の雇用契約の期間が2月以内であっても、次の(ア)又は(イ)に該当する場合は、「2月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」に該当するものとして、最初の雇用契約に基づき使用され始めた時に被保険者資格を取得することになります。
(ア) 就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
(イ) 同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき使用されている者が、契約更新等により最初の雇用契約の期間を超えて使用された実績があること。
(令和4.9.9事務連絡)
②【R2年出題】
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

【解答】
②【R2年出題】 ×
当初4か月以内の期間において使用される予定で季節的業務に使用される者については、健康保険の被保険者になりません。業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合でも、被保険者になりません。
(法第3条第1項)
③【H20年出題】
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。

【解答】
③【H20年出題】 ×
共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となります。
④【R1年出題】
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
「国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者」であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない、と規定されています。
また、共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要すると規定されています。
(法第200条)
厚生年金保険法
①【R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満で、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
(法第12条第5号)
②【H25年出題】 × ※修正あり
船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
船舶所有者に使用される船員の場合は、継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合でも、最初から厚生年金保険の被保険者となります。
(法第12条第3号)
③【H25年出題】※修正あり
船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇入れられる場合は厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
③【H25年出題】 ×
船舶所有者に臨時に使用される船員の場合は、日々雇入れられる場合でも、厚生年金保険の被保険者となります。
(法第12条第1号)
④【H25年出題】※修正あり
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者については、その者が引き続き6か月以上使用される場合でも厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
④【H25年出題】 〇
巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者は、使用される期間に関係なく、厚生年金保険の被保険者にはなりません。
(法第12条第2号)
⑤【H25年出題】※修正あり
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合は厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
臨時的事業の事業所に使用される者で、継続して6か月を超えない期間使用される場合は、厚生年金保険の被保険者になりません。
(法第12条第4号)
国民年金法
【R3年出題】
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

【解答】
【R3年出題】〇
日本の国籍を有しない者で、次に該当する場合は、国民年金の第1号被保険者、第3号被保険者から除外されます。
・日本に相当期間滞在して、病院もしくは診療所に入院し疾病もしくは傷害について医療を受ける活動または当該入院の前後に当該疾病もしくは傷害について継続して医療を受ける活動を行う場合
・ 日本に1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行う場合
(則第1条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
各法律の適用除外について
R7-125 12.30
各法律の適用除外を整理しましょう<横断編>
各法律の適用を除外されるものを整理しましょう
★労働基準法
船員や公務員についてなど
★労働安全衛生法
労働者から除外されるものなど
★労災保険法
公務員についてなど
★雇用保険法
雇用保険から除外されるもの(学生など)
★健康保険法
短時間労働者などについて
★厚生年金保険法
臨時に使用される者、季節的業務に使用される者、臨時的事業の事業所に使用されるものなど
★国民年金法
国民年金の適用を除外すべき特別の理由がある者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-124 12.29
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年12月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月23日から28日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・死亡一時金についてお話しします(国民年金法)
・労働安全衛生調査からの出題(労働に関する一般常識)
・日雇特例被保険者に関する問題(健康保険法)
・保険医療機関・保険薬局の指定(健康保険法)
・保険医・保険薬剤師の登録(健康保険法)
・資格を取得した際の標準報酬月額の決定(厚生年金保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-123 12.28
<令和6年の問題を振り返って>(厚生年金保険)資格を取得した際の標準報酬月額の決定
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
資格取得時の標準報酬月額の決定について条文を読んでみましょう。
法第22条 (被保険者の資格を取得した際の決定) ① 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (1) 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 (2) 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 (3) (1)、(2)によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 (4) 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額 ② 決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
(資格取得時の標準報酬月額の有効期間)
例えば、令和6年5月15日に資格を取得した場合
定時決定(7月1日現在)
△
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月~翌年8月 |
資格取得時の標月 | 資格取得時の標月 | 資格取得時の標月 | 資格取得時の標月 | 定時決定で定められた 標準報酬月額 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-B】
厚生年金保険法第22条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。

【解答】
【R6年問7-B】 〇
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 → 月給制や週給制等です。
例えば、週給の場合、週給の額÷7日(その期間の総日数)×30が「報酬月額」となります。その報酬月額を標準報酬月額等級に当てはめて、その者の標準報酬月額が決定されます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

【解答】
【H30年出題】 〇
ポイントを確認しましょう。
・日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合 → 日給制や時給制など
資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額=報酬月額となり、標準報酬月額が決まります。
・有効期間
資格取得時の標準報酬月額の有効期間は、資格を取得した月からその年の8月までです。9月以降は、その年の定時決定で定められた標準報酬月額となります。
ただし、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は、翌年の8月までです。
6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定を行わないからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-122 12.27
<令和6年の問題を振り返って>保険医・保険薬剤師の登録
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
保険医、保険薬剤師とは?
厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師を「保険医」、薬剤師を「保険薬剤師」といいます。
保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険医又は保険薬剤師でなければなりません。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-ウ】
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

【解答】
【R6年問9-ウ】 ×
保険医等の登録には、有効期間がありませんので誤りです。
なお、保険医療機関・保険薬局の指定には、6年間の有効期間がありますので違いに注意して下さい。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

①【H29年出題】 〇
「保険医療機関又は保険薬局のみなし指定」の規定です。
条文を読んでみましょう。
第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について保険医又は保険薬剤師の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。 |
「保険医」として登録を受けた個人の開業医が開設した診療所で、かつ、開設者である医師のみが診療に従事している場合は、保険医療機関の指定の申請をしなくても、「保険医療機関」の指定があったものとみなされます。
②【H19年出題】
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。

【解答】
②【H19年出題】 〇
保険医又は保険薬剤師は、健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤も担当します。
(法第72条)
③【H19年出題】
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から10年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
以前に登録を取り消されたことがあり、その取消の日から「5年」を経過しない者であるときは、厚生労働大臣は登録しないことができるとされています。
(法第71条第2項)
④【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
④【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定
・保険医療機関、保険薬局の指定の取り消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取り消し
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしない
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)
・保険医、保険薬剤師の登録をしない
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-121 12.26
<令和6年の問題を振り返って>保険医療機関・保険薬局の指定
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
保険医療機関、保険薬局とは?
→ 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。)又は薬局のこと
※保険医療機関、保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。
※保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師でなければなりません。
→ 「保険医」・「保険薬剤師」といいます。
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問9-ア】
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

【解答】
①【R6年問9-ア】 ×
保険医療機関・保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年です。6年を経過したときは、効力を失います。
ただし、「その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。」扱いがあります。ただし、この規定から、「病院又は病床を有する診療所」は除かれています。
この規定が適用されるのは、個人開業医です。
個人開業医については、「指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間」に、「更新しない」旨の申出をしなければ、保険医療機関の申請があったものとみなされ、指定が更新されます。
(法第68条)
②【R6年問9-イ】
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

【解答】
②【R6年問9-イ】 〇
・ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。
(法第65条第1項)
・ 厚生労働大臣は、申請があった場合、法第65条第3項第1号~第6号のいずれかに該当するときは、指定をしないことができます。
「申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき」は、第1号に該当しますので、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができます。
(法第65条第3項第1号)
・ 厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、「地方社会保険医療協議会」の議を経なければならないとされています。「中央社会保険医療協議会」と間違えないようにしてください。
(法第67条)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
問題文は、法第65条第3項第3号に該当しますので、厚生労働大臣は、指定をしないことができます。
②【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】
②【H29年出題】 ×
予告期間は、14日以上ではなく「1月以上」です。
法第79条 ① 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 ② 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 |
③【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
③【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定
・保険医療機関、保険薬局の指定の取り消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取り消し
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしない
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)
・保険医、保険薬剤師の登録をしない
④【R2年選択式】
健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、< A >ものとされている。
<選択肢>
① 中央社会保険医療協議会に諮問する
② 地方社会保険医療協議会に諮問する
③ 社会保障審議会の意見を聴く
④ 都道府県知事の意見を聴く

【解答】
<A> ②地方社会保険医療協議会に諮問する
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-120 12.25
<令和6年の問題を振り返って>日雇特例被保険者に関する問題
和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
日雇特例被保険者の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
条文を読んでみましょう。
第123条 ① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とする。 ② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
★ 日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収は、「厚生労働大臣」が行います。
では、「日雇拠出金」について条文を読んでみましょう。
第173条 (日雇拠出金の徴収及び納付義務) ① 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。 ② 日雇関係組合は、「日雇拠出金」を納付する義務を負う。 |
日雇関係組合 ・日雇特例被保険者を使用する 事業主の設立する健康保険組合 | →→→→→→→→→ 日雇拠出金 | 厚生労働大臣 |
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、「保険料の徴収」と、「日雇関係組合から拠出金の徴収」を行います。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問2-E】
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。

【解答】
【R6年問2-E】 〇
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収します。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

【解答】
①【H21年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
②【R1年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

【解答】
②【R1年出題】 ×
全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。
③【R4年出題】
日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負います。
ただし、日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合は、初めにその者を使用する事業主が、保険料を納付する義務を負います。
問題文の場合は、午前と午後で2か所の事業所に使用されていますが、午前に働いた適用事業所(初めにその者を使用する事業主)から受ける賃金額で標準賃金日額を決定し、保険料の納付も、午前に働いた適用事業所(初めにその者を使用する事業主)が健康保険印紙を貼り、消印して行います。
(第169条第2項、第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働に関する一般常識)
R7-119 12.24
<令和6年の問題を振り返って>労働安全衛生調査からの出題
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働に関する一般常識の択一式です。
令和6年は、「令和4年労働安全衛生調査(実態調査)(事業所調査)(厚生労働省)」から出題されました。
※なお、令和6年7月25日に、「令和5年」の結果が公表されています。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問1-A】
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は6割を超えている。このうち、対策に取り組んでいる事業所の取組内容(複数回答)をみると、「ストレスチェックの実施」の割合が最も多く、次いで「メンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施」となっている。

【解答】
①【R6年問1-A】 〇
<メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合>
令和5年調査では63.8%(令和4年調査63.4%)ですので、6割を超えています。
<事業所の取組内容(複数回答)>
・最も割合が多いのは、「ストレスチェックの実施」です。
(令和5年調査65.0%、令和4年調査63.1%)
・次は、「メンタルヘルス不調の労働者に対する必要な配慮の実施」です。
(令和5年調査49.6%、令和4年調査53.6%)
②【R6年問1-B】
過去1年間(令和3年11月1日から令和4年10月31日までの期間)に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合は約7割となっている。このうち、所見のあった労働者に講じた措置内容(複数回答)をみると、「健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた」の割合が最も多くなっている。

【解答】
②【R6年問1-B】 〇
<過去1年間に一般健康診断を実施した事業所のうち所見のあった労働者がいる事業所の割合>
・約7割(令和4年調査69.8%)です。
<所見のあった労働者に講じた措置内容(複数回答)>
・最も割合が多いのは、「健康管理等について医師又は歯科医師から意見を聴いた」です。(令和4年調査45.3%)
③【R6年問1-C】
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合は約6割となっている。このうち、取組内容(複数回答)をみると、「通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整)」の割合が最も多く、次いで「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」となっている。

【解答】
③【R6年問1-C】 〇
<治療と仕事を両立できるような取組がある事業所の割合>
・約6割(令和4年調査 58.8%)です。
<取組内容(複数回答)>
・最も割合が多いのは、「通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整)」です。(令和4年調査 86.4%)
・次が「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」です。(令和4年調査 35.9%)
④【R6年問1-D】
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた労働者が治療と仕事を両立できるような取組がある事業所のうち、取組に関し困難や課題と感じていることがある事業所の割合は約8割となっている。このうち、困難や課題と感じている内容(複数回答)をみると、「上司や同僚の負担」の割合が最も多く、次いで「代替要員の確保」となっている。

【解答】
④【R6年問1-D】 ×
<治療と仕事を両立できるような取組がある事業所のうち、取組に関し困難や課題と感じていることがある事業所の割合>
・約8割(令和4年調査 81.8%)です。
<困難や課題と感じている内容(複数回答)>
・最も割合が多いのは、「代替要員の確保」です。(令和4年調査 77.2%)
・次が「上司や同僚の負担」です。(令和4年調査 51.2%)
⑤【R6年問1-E】
転倒災害を防止するための対策に取り組んでいる事業所の割合は8割を超えている。このうち、転倒災害防止対策の取組内容(複数回答)をみると、「通路、階段、作業場所等の整理・整頓・清掃の実施」の割合が最も多く、次いで「手すり、滑り止めの設置、段差の解消、照度の確保等の設備の改善」となっている。

【解答】
⑤【R6年問1-E】 〇
<転倒災害を防止するための対策に取り組んでいる事業所の割合>
・8割を超えています。(令和4年調査 84.6%)
<転倒災害防止対策の取組内容(複数回答)>
最も割合が多いのは、「通路、階段、作業場所等の整理・整頓・清掃の実施」です。
(令和4年調査 85.4%)
次が、「手すり、滑り止めの設置、段差の解消、照度の確保等の設備の改善」です。
(令和4年調査 56.6%)
<参照>
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法<死亡一時金>
R7-118 12.23
国民年金「死亡一時金」についてお話しします
YouTubeで「死亡一時金」についてお話ししました。
今日の内容です。
・死亡一時金の支給要件 → キーワードは36月
・死亡一時金が支給されないのは、どんなとき? → (ヒントは掛け捨てにならない)
・死亡一時金の遺族となるのは? → 生計維持と生計同一の違いもポイントです
・死亡一時金の額(最低と最高は覚えましょう)
・付加保険料を納付していた場合の加算
・死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たしたとき
・死亡一時金と遺族厚生年金は併給できる?
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-117 12.22
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年12月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月16日から21日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
寡婦年金についてお話しします(国民年金法)
労働基準法の適用単位(労働基準法)
複数事業労働者の休業(補償)等給付について(労災保険法)
自己の労働によって収入を得た場合(雇用保険法)
偽りその他不正の行為により支給を受けた場合(雇用保険法)
追徴金の額・納期限など(労働保険徴収法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
R7-116 12.21
<令和6年の問題を振り返って>追徴金の額・納期限など
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
「追徴金」について条文を読んでみましょう。
法第21条第1項、2項 (追徴金) ① 政府は、事業主が認定決定された確定保険料又は不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。 ② 認定決定された確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。
法第25条第1項、2項 ① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、①により認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
★追徴金が徴収される場合
確定保険料の額を認定決定した場合 | 100分の10 |
印紙保険料の額を認定決定した場合 | 100分の25 |
※「概算保険料の額」を認定決定した場合は、追徴金は徴収されません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問10-E(雇用)】
労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

【解答】
【R6年問10-E(雇用)】 ×
追徴金の納期限は、「事業主が通知を受けた日」から起算して30日ではなく「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
また、追徴金は、「納付書」ではなく「納入告知書」で通知することもポイントです。
(法第21条第3項、則第26条)
★認定決定された保険料の納期限について
認定決定された概算保険料(納付書) | その通知を受けた日から15日以内 |
認定決定された確定保険料(納入告知書) |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題(雇用)】
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
①【H26年出題(雇用)】 ×
認定決定された概算保険料については、追徴金は徴収されません。
②【R4年出題(労災)】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。

【解答】
②【R4年出題(労災)】 〇
以下の場合は、追徴金は徴収されません。
■事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合
■認定決定された確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるとき
→「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいいます。「法令の不知、営業の不振、資金難等」は含まれません。
問題文のように「事業主が法令の改正を知らなかった」場合は、追徴金が徴収されます。
③【H28年出題(雇用)】
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】
③【H28年出題(雇用)】 ×
追徴金は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10ではなく「100分の25」です。
④【H25年出題(雇用)】
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
④【H25年出題(雇用)】 〇
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(法第25条、則第38条第5項)
⑤【H28年出題(雇用)】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
⑤【H28年出題(雇用)】 ×
認定決定された印紙保険料と追徴金は、雇用保険印紙ではなく、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に「現金」で納付します。日本銀行に納付することもできます。
(則第38条第3項第2号)
⑥【H26年出題(雇用)】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
⑥【H26年出題(雇用)】 ×
追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促します。ただし、追徴金については、延滞金は徴収されません。
(法第27条、第28条)
条文を読んでみましょう。
法第27条第1項 労働保険料その他この法律の規定による徴収金(→追徴金も含まれます)を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 法第28条 政府は、労働保険料(→追徴金は含まれません)の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
R7-115 12.20
<令和6年の問題を振り返って>偽りその他不正の行為により支給を受けた場合
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、雇用保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
法第34条第1項、2項 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 ② ①に規定する者が①に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-オ】
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者にやむを得ない理由がある場合、基本手当の全部又は一部を支給することができる。

【解答】
【R6年問5-オ】 〇
基本手当は、「求職者給付」の中の一つです。
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者には、基本手当の支給を受けた日以後、基本手当を支給しないのが原則です。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができるとされています。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第60条第1項、第2項 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。 ② ①に規定する者が①に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。 |
②【H25年出題】
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月に限り、基本手当を支給しない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、「以後、基本手当を支給しない」となります。「1か月に限り」は誤りです。
(法第34条)
③【R2年出題】
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。

【解答】
③【R2年出題】 〇
再就職し新たに受給資格を取得したときには、新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給されます。
(法第34条第2項)
④【R2年出題】
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。

【解答】
④【R2年出題】 〇
条文を読んでみましょう
法第61条の3 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。 (1) 高年齢雇用継続基本給付金 → 高年齢雇用継続基本給付金 (2) 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 → 高年齢再就職給付金 |
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金を受けた者は、受けた日以後高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた被保険者が、その後離職した場合、当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限は受けません。
(法第34条)
⑤【H22年出題】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

【解答】
⑤【H22年出題】 〇
不正な行為により「高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付」の支給を受けた者には、以後、高年齢再就職給付金は支給されません。
問題文の場合は、不正な行為により基本手当の支給を受けていますので、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできません。
(法第61条の3第2号)
⑥【R3年出題】
偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第60条の3 ① 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、教育訓練給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、教育訓練給付金の全部又は一部を支給することができる。 ② ①の規定により教育訓練給付金の支給を受けることができない者とされたものが、①に規定する日以後、新たに教育訓練給付金の支給を受けることができる者となった場合には、教育訓練給付金を支給する。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
R7-114 12.19
<令和6年の問題を振り返って>自己の労働によって収入を得た場合
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、雇用保険法の択一式です。
「自己の労働によって収入を得た」場合について、条文を読んでみましょう。
法第19条第1項、第3項 (基本手当の減額) ① 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(以下「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 ① 「収入の1日分に相当する額-控除額」+「基本手当の日額」(=「合計額」) → 「合計額」が賃金日額の100分の80以下の場合 → 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。(減額されません) ② 「合計額」が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき → その超える額(超過額)を基本手当の日額から控除した残りの額×基礎日数を支給する。(減額されます) ③ 超過額が基本手当の日額以上の場合 → 基礎日数分の基本手当を支給しない。(基礎日数分の基本手当は支給されません)
③ 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。 |
※「控除額」は、令和6年8月1日以後、1,331円→ 1,354円に引き上げられています。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-ア】
基本手当の受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合、当該収入が基本手当の減額の対象とならない額であっても、これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる。

【解答】
【R6年問5-ア】 ×
自己の労働によって収入を得たときは、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければなりません。
管轄公共職業安定所の長は、届出をしない受給資格者について、自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下「支給日」という。)まで延期することができることになっています。
「これを届け出なければ不正の行為として取り扱われる」という規定はありません。
(則第29条第2項)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。

【解答】
①【R1年出題】 〇
自己の労働による収入とは短時間就労による収入で、原則として1日の労働時間が 4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)で、就職とはいえない程度のものをいいます。(雇用関係の有無は問われません)。また「自己の労働による収入」ですので、衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息等は含みません。
(行政手引51652(2))
②【H26年出題】
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

【解答】
②【H26年出題】 ×
その収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当は減額されません。
「基本手当の日額に100分の80を乗じ」ではなく、「基本手当の日額」に基礎日数を乗じて得た額が支給されます。
③【H26年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
条文で確認しましょう。
則第29条 ① 受給資格者が自己の労働によって収入を得た場合に行う届出は、その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。 ② 管轄公共職業安定所の長は、届出をしない受給資格者について、自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日まで延期することができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-113 12.18
<令和6年の問題を振り返って>複数事業労働者の休業(補償)等給付について
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労災保険法の択一式です。
■複数事業労働者の給付基礎日額の算定方法を確認しましょう。
法第8条第3項 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。 |
複数事業労働者の給付基礎日額は、複数の就業先ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。
■「部分算定日」定義を確認しましょう。
★療養のために所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
★賃金が支払われる休暇(有給休暇、通勤手当・住宅手当等が支給される休業日)
例えば、給付基礎日額が10,000円、午前中の労働に対する賃金が4,000円の場合、休業(補償)等給付の額は以下の式で計算します。
(10,000円-4,000円)×60%=3,600円
・(給付基礎日額-部分算定日に対して実際に支払われた賃金)×60%です。
「複数事業労働者」についての通達を確認しましょう。
<複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件について>
(1) 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業(補償)等給付」という。)の給付事由
①「療養のため」
②「労働することができない」ために
③「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の
第4日目から支給されます。
(2) 「労働することができない」とは
必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいいます。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはなりません。 |
★複数事業労働者について
複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要があります。
→ 例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となります。
→ ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがあります。
(3) 「賃金を受けない日」について
「賃金を受けない日」には、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日があります。 →賃金の一部を受けない日とは ① 所定労働時間の全部について「労働することができない」場合で、平均賃金の 60%未満の金額しか受けない日 ② 通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合で、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日 |
★複数事業労働者については
複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより賃金を受けない日に該当しない状態でありながら、他の事業場において、傷病等により無給での休業をしているため、賃金を受けない日に該当する状態があり得ます。
したがって、複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行うこととされています。
その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱うこととなっています。
一方、全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わないこととなっています。
(令和3年3月18日/基管発0318第1号/基補発0318第6号/基保発0318第1号/)
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問4-A】
休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。

【解答】
①【R6年問4-A】 〇
A社では労働者として就労している。しかし、B社では業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない。
→「労働することができない」に該当すると認められることがある。
②【R6年問4-B】
休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。

【解答】
②【R6年問4-B】 〇
A社では、年次有給休暇等により平均賃金相当額の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態である。しかし、B社では無給での休業をしている
→ 「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-112 12.17
<令和6年の問題を振り返って>労働基準法の適用単位
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働基準法の択一式です。
労働者の定義を条文で読んでみましょう。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
労働基準法の「労働者」は、「事業」に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
「事業」のイメージです。
〇〇株式会社 | ||||
本社
|
|
工場 |
|
営業所 |
〇〇株式会社全体が事業となるのではなく、「本社」、「工場」、「営業所」それぞれが事業となります。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問2-ア】
労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。

【解答】
【R6年問2-ア】 〇
|
|
|
| 工 場 |
|
|
| 診療所 |
<原則>
・一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定する
→ 同一場所にあるものは原則として1個の事業とする
→ 場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする
<例外>
・ 例えば工場内の診療所、食堂のように同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合は?
→ その部門を一の独立の事業とする
・ 場所的に分散しているものであっても、出張所や支社等で、一の事業という程度の独立性がないものは?
→ 直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

①【H26年出題】 ×
労働基準法第9条にいう「事業」とは、場所的観念によって決定されるべきものです。支店、工場等それぞれが事業となりますので、それぞれで労働基準法が適用されます。
②【H29年出題】
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
労働基準法の労働者は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
事業とは、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう」とされています。
何ら事業を営むことのない大学生が、引っ越しの作業を手伝ってもらった友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しません。
(昭22.9.13発基17号など)
③【R4年出題】
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

【解答】
③【R4年出題】 〇
事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者は、労働基準法の労働者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法<寡婦年金>
R7-111 12.16
寡婦年金についてお話しします<国民年金法>
今日は寡婦年金についてお話ししています。
寡婦年金は「第1号被保険者」独自の給付です。
・死亡した夫の要件
・妻の要件
・寡婦年金の額の計算方法
・寡婦年金の失権 などがポイントです。
特に、「繰上げ支給の老齢基礎年金」との関係、「死亡一時金」との関係もよく出題されますので注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-110 12.15
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年12月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月9日から14日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
合算対象期間の「基本」についてお話しします(国民年金法)
障害・遺族基礎年金と労働基準法の災害補償との調整(国民年金法)
保険料の督促・滞納処分、延滞金(厚生年金保険法)
産前産後休業中の保険料免除(厚生年金保険法)
標準報酬月額の最高等級(厚生年金保険法)
未支給の保険給付(厚生年金保険法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-109 12.14
<令和6年の問題を振り返って>【厚生年金保険】未支給の保険給付
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第37条第1項、3項~5項 (未支給の保険給付) ① 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ③ 死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 ④ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。 ⑤ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
★ 年金は、後払い(例えば、12月に支給される年金は10月分と11月分です)で、受給権が消滅した月まで支給されます。
そのため、年金の受給権者が死亡した場合は、必ず未支給の年金が発生します。
★ 国民年金との違い
厚生年金保険法は「未支給の保険給付」
→ 「死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったもの」ですので、年金だけでなく一時金も対象です。
国民年金法は「未支給年金」
→ 「死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったもの」となりますので、「年金」だけが対象です。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問8-D】
未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として、死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合、祖父が先順位者になる。

【解答】
【R6年問8-D】 〇
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序」とされています。妹と祖父がいる場合は、祖父が先順位者になります。
(令第3条の2)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。

【解答】
①【R4年出題】 〇
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表で請求します。
②【H23年出題】
保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。

【解答】
②【H23年出題】 ×
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給するのではなく、代表の者に全額支給されます。
③【H26年出題】
脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。

【解答】
③【H26年出題】 〇
脱退一時金も未支給の保険給付の請求の対象となります。
(法附則第29条第9項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-108 12.13
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(健康保険との比較も)
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
法第20条第2項 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-A】
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高等級である第31級の上に第32級が追加された。第32級の標準報酬月額は65万円である。

【解答】
【R6年問7-A】 〇
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、「第32級」です。第32級の標準報酬月額は65万円です。
「平成28年3月以降、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が、当時の最高等級(第31級:62万円)を超える状況が続き、令和2年3月末においても、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が62万円を超えていたことから、令和2年9月より、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(第32級(65万円)を加える)こととした。」とされています。
(厚生労働省ホームページより)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】※改正による修正あり
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第32級650,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、その年の4月1日からではなく、その年の9月1日からです。
②【R5年出題】
毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「毎年12月31日」ではなく「毎年3月31日」における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、「その年の9月1日から」、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の「改定を行わなければならない」ではなく、「改定を行うことができる。」です。
<比較>健康保険法の条文も読んでみましょう。
法第40条第2項、第3項 ② 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。 ③ 厚生労働大臣は、政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。 |
健康保険法の標準報酬月額の上限は、「第50等級1,390,000円」で、全被保険者に対する上限該当者の割合は、0.79%です。
(厚生労働省ホームページより)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-107 12.12
<令和6年の問題を振り返って>産前産後休業中の保険料免除
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) ① 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 ② 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、①の規定を適用する場合においては、「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-E】
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。

【解答】
【R6年問7-E】 〇
事業主負担分と被保険者負担分の両方が免除されます。
過去問をどうぞ!
①【R4年選択式】
厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を< A >からその産前産後休業が< B >までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。

【解答】
<A> 開始した日の属する月
<B> 終了する日の翌日が属する月の前月
②【H29年出題】
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

【解答】
②【H29年出題】 〇
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出について
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者
→ 当該被保険者が使用される事業所の事業主が行う
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者
→ 被保険者本人が行う
③【H30年出題】
産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
産前産後休業期間中の報酬の支払いの有無は問われません。
④【R1年出題】
適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
産前産後休業期間中や育児休業期間中の保険料の免除が適用されている者に対して、賞与を支給した場合でも、賞与額の届出は必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-106 12.11
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険の保険料の督促・滞納処分、延滞金
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
督促と延滞金を図でイメージしましょう。
納期限 ▼ |
| 督促状 ▼ |
| 督促状の指定期限 ▼ |
| 完納 ▼ | |
|
| 10日以上経過した日 |
|
| |||
納期限の翌日 |
|
|
|
|
| 完納又は財産差押えの日の前日 | |
条文を読んでみましょう。
法第86条 (保険料等の督促及び滞納処分) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、繰上徴収により保険料を徴収するときは、この限りでない。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 ④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 ⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 (1) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 (2) 納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 ⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
法第87条 (延滞金) ① 督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 (1) 保険料額が1000円未満であるとき。 (2) 納期を繰り上げて徴収するとき。 (3) 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。 ② 保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。 ③ 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 ⑤ 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
※延滞税特例基準割合(1.4%)に基づく令和6年中の延滞金の割合は以下の通りです。
・納期限の翌日から3月を経過する日までの期間 → 年2.4%
・納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後 → 年8.7%
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問2-B】
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
①【R6年問2-B】 〇
公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されません。
②【R6年問2-C】
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。

【解答】
②【R6年問2-C】 ×
厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した額(=延滞金の金額)が1,000円未満ではなく「100円未満」であるときは、延滞金は徴収されません。
③【R6年問2-D】
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

【解答】
③【R6年問2-D】 ×
納付義務者の居住地等の市町村に対して市町村税の例による処分を請求した場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5ではなく「100分の4」に相当する額を当該市町村に交付しなければなりません。
④【R6年問2-E】
滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。

【解答】
④【R6年問2-E】 ×
徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、日本年金機構の理事長が任命する、とされています。
(第100条の6第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-105 12.10
<令和6年の問題を振り返って>障害・遺族基礎年金と労働基準法の災害補償との調整
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第36条第1項 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
第41条第1項 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
第52条 寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-B】
労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。

【解答】
【R6年問3-B】 〇
・ 労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金は、6年間、支給が停止されます。
・ 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、支給が停止されます。
「労働基準法の障害補償(遺族補償)」との調整規定です。「労働者災害補償保険法の障害(補償)年金、遺族(補償)年金」ではありませんので注意しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。

【解答】
①【H20年出題】 ×
同一の支給事由で、労働者災害補償保険法による遺族補償年金と遺族基礎年金が支給されるときは、遺族補償年金が減額され、遺族基礎年金は全額支給されます。
(労災保険法別表第1)
同一事由で労災保険法から年金が支給されても、国民年金・厚生年金は、本人が保険料を負担していますので、減額されません。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですので、同一事由で、労災保険の年金と国民年金・厚生年金が支給される場合は、労災保険の年金が減額されます。
②【H26年出題】
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、労災保険法の遺族補償年金が減額され、遺族基礎年金は支給停止されません。
③【H20年出題】
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

【解答】
③【H20年出題】 〇
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときは、障害補償年金が減額され、障害基礎年金は全額支給されます。
(労災保険法別表第1)
こちらの問題もどうぞ!
①【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「20歳前傷病による障害基礎年金」独自の支給停止事由です。
労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項、第2項 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金(=20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、その支給を停止する。 (1) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 (2)以下省略します ② (1)に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、支給停止されない。 |
②【H25年出題】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

【解答】
②【H25年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときは、その該当する期間、その支給が停止されます。
ただし、労働者災害補償保険法による年金たる給付の全額が支給停止されているときは、原則として、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>合算対象期間
R7-104 12.09
国民年金の合算対象期間の<基本>についてお話しします
合算対象期間の「基本」についてお話しします。
合算対象期間は「カラ期間」ともいわれます。
老齢基礎年金の受給資格期間の10年の計算には入りますが、 老齢基礎年金の「年金額」の計算には入らないからです。
合算対象期間の代表例で、よく出題される期間をみていきます。
・厚生年金保険等の加入期間のうち、合算対象期間になる期間
・日本国籍を有する者が海外に在住している期間のうち合算対象期間になる期間
・会社員、公務員の被扶養配偶者だった期間のうち合算対象期間になる期間
などです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-103 12.08
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年12月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年12月2日から7日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
国民年金の任意加入被保険者についてお話しします(国民年金法)
労基法上の賃金の解釈(労働基準法)
全国健康保険協会の事業(健康保険法)
全国健康保険協会の一般保険料率(健康保険法)
基礎年金拠出金の算定(国民年金法)
国民年金基金の加入員(国民年金法)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-102 12.07
<令和6年の問題を振り返って>国民年金基金の加入員
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金基金には、「地域型国民年金基金」(地域型基金)と「職能型国民年金基金」職能型基金)があります。
国民年金基金の加入について条文を読んでみましょう。
第127条 (加入員) ① 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 ② 申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。 ③ 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日((1)又は(4)に該当するに至ったときは、その日とし、(3)に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。 (1) 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。 (2) 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。 (3) 保険料を納付することを要しないものとされたとき(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む。) (4) 農業者年金の被保険者となったとき。 (5) 当該基金が解散したとき。 ④ 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。 |
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問2-エ】
国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。

【解答】
①【R6問2-エ】 〇
「申出をした日」(当日)に、加入員の資格を取得します。
②【R6問2-オ】
国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【R6問2-オ】 ×
第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を「喪失した日」に、加入員の資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
国民年金基金の加入は任意ですが、加入後に任意に資格を喪失することはできません。
②【H29年出題】
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【H29年出題】 〇
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。
③【H29年出題】
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

【解答】
③【H29年出題】 〇
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。
④【H27年出題】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
④【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員が、保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失します。
⑤【R2年出題】
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
任意加入被保険者のうち、次の者は、国民年金基金の加入員となることができます。
■ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
■ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
(法附則第5条第11項)
⑥【H29年出題】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
地域型国民年金基金の加入員となることができます。
「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者」は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができます。
⑦【H24年出題】
第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。

【解答】
⑦【H24年出題】×
「第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。」となっていますので、地域型か職能型のどちらかを選択できます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-101 12.06
<令和6年の問題を振り返って>基礎年金拠出金の算定
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金保険料を負担しませんが、第2号被保険者と第3号被保険者にも、基礎年金が支給されます。
第2号被保険者と第3号被保険者に支給される基礎年金の費用に充てるため、厚生年金保険の保険者は、基礎年金拠出金を負担します。
「基礎年金拠出金」について条文を読んでみましょう。
第91条の2 (基礎年金拠出金) ① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 ③ 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第94条の3 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 ② 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。 ③ 実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。 |
<基礎年金拠出金の計算式>
|
| 政府及び実施機関に係る被保険者の総数 (第2号被保険者+第3号被保険者) |
保険料・拠出金算定対象額
| × |
国民年金の被保険者の総数 |
★政府及び実施機関に係る被保険者の総数
■厚生年金保険の実施者たる政府 → 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者+その被扶養配偶者である第3号被保険者
■実施機関たる共済組合等
・国家公務員共済組合連合会 → 第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
・地方公務員共済組合連合会 → 第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
・日本私立学校振興・共済事業団 → 第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問1-D】
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

【解答】
【R6問1-D】 〇
基礎年金拠出金の額は、「国民年金(1号、2号、3号)の被保険者数」と「第2号+第3号の被保険者数」の人数比で按分されます。
過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。

【解答】
①【R2年選択式】
<A> 実施機関たる共済組合等
★実施機関たる共済組合等の定義も確認しましょう。
「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(法第5条第9項)
②【R4年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

【解答】
②【R4年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者」とされています。
納付者が対象ですので、「保険料全額免除」を受けている者や滞納している者は算入されません。
(令第11条の3)
③【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

【解答】
③【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について
・第1号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者数 → 20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者数 → すべての者
となります。
第2号被保険者数は、すべての者ではなく、第1号被保険者の年齢の範囲に合わせて、「20歳以上60歳未満の者」です。
(令第11条の3)
④【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
国民年金保険料を納付しなければならないのは、第1号被保険者のみです。
第2号被保険者・第3号被保険者は、国民年金保険料を納付する必要はありません。
条文を読んでみましょう。
法第94条の6 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-100 12.05
<令和6年の問題を振り返って>全国健康保険協会の一般保険料率
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
全国健康保険協会の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で、支部被保険者を単位として協会が決定します。
支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といい、その支部被保険者に適用されます。
条文を読んでみましょう。
法第160条第5項 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問3-オ】
協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

【解答】
【R6問3-オ】 ×
健康保険事業の収支の見通しを作成し、「厚生労働大臣に届け出る」ではなく、「公表するものとする。」です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

【解答】
①【H26年出題】 〇
協会の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130までの範囲内」で、支部被保険者を単位として「協会」が決定します。支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいいます。
(法第160条第1項)
②【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
条文で確認しましょう。
「登場人物」に特に注意してください。
法第160条第6項~9項 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 |
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率を変更することができます。
条文を読んでみましょう。
法第160条第10項、11項 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 |
④【H24年選択式】
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として < B >が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、< C >についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< D >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< E >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】
④【H24年選択式】
<A>1,000分の30から1,000分の130
<B> 全国健康保険協会
<C> 翌事業年度以降5年間
<D> 健康保険事業の収支の均衡
<E> 社会保障審議会
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-099 12.04
<令和6年の問題を振り返って>全国健康保険協会の事業
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第7条の28 第1項、2項 (財務諸表等) ① 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。 ② 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第2項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第7条の29第1項~3項 (会計監査人の監査) ① 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 ② 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 ③ 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
第7条の30(各事業年度に係る業績評価) ① 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。 ② 厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問2-D】
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。

【解答】
①【R6問2-D】 〇
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなりません。
会計監査人は厚生労働大臣が選任し、また、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。
②【R6問1-A】
全国健康保険協会は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。

【解答】
②【R6問1-A】 ×
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について評価を行い、遅滞なく、協会に対し、「評価の結果を通知」するとともに、これを「公表」しなければなりません。
評価の結果を公表するのは厚生労働大臣です。全国健康保険協会ではありません。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
協会の毎事業年度の決算は翌事業年度の5月31日までに完結しなければなりません。
また、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。
②【H30年出題】
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行う
↓
評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表する
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-098 12.03
<令和6年の問題を振り返って>労働基準法上の賃金の解釈
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
【R6問1-E】
労働者に支給される物又は利益にして、所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うものは労働基準法第11条にいう「賃金」とみなさない。

【解答】
【R6問1-E】 ×
問題文の場合は、「賃金」とみなすとされています。
通達を確認しましょう。
① 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと。
(1) 所定貨幣賃金の代りに支給するもの、即ちその支給により貨幣賃金の減額を伴うもの。
(2) 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されているもの。
② 右に掲げるものであっても、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなさないこと。
(1)代金を徴収するもの、但しその代金が甚だしく低額なものはこの限りでない。
(2) 労働者の厚生福利施設とみなされるもの。
③ 退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。
(昭22.9.13発基第17号)
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
退職手当で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、労働基準法上の「賃金」となり、「臨時に支払われる賃金」に当たります。
(昭22.9.13発基第17号)
②【R1年出題】
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は「実費弁償」に当たります。賃金ではありません。
(昭63.3.14基発150号)
③【H26年出題】
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

【解答】
③【H26年出題】 ×
賞与、家族手当、住宅手当は、労働基準法第11条の賃金に当たりますが、「解雇予告手当」は賃金ではありません。
(昭23.8.18基収2520号)
④【R3年出題】
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
労働者が法令により負担すべき所得税等を事業主が労働者に代わって負担することは、労働者が法律上当然生ずる義務を免れることとなりますので、事業主が労働者に代わって負担する部分は、福利厚生ではなく、「賃金」となります。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【R2年出題】
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
食事の供与は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、次の要件を満たす場合は、原則として賃金ではなく「福利厚生」として取り扱われます。
①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと
②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと
③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること
(昭30.10.10基発644号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>任意加入被保険者
R7-097 12.02
国民年金の「任意加入被保険者」についてお話しします
国民年金の強制被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)に該当しない場合は、任意加入することができます。
任意加入する目的は次の2つです。
①老齢基礎年金の額を増やすため
(満額にするor満額に近づける)
②老齢基礎年金等の受給資格期間を満たすため
任意加入被保険者には、「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の2種類あります。
★「任意加入被保険者」は①と②のどちらの目的でも加入できます。
★「特例による任意加入被保険者」は、②の目的のみです。老齢基礎年金等の受給権がある場合は、任意加入できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-096 12.01
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年11月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年11月25日から11月30日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
高齢任意加入被保険者についてお話しします(厚生年金保険法)
厚生年金保険料の納期限(厚生年金保険法)
厚生年金保険法の脱退一時金(厚生年金保険法)
学生納付特例制度について(国民年金法)
遺族基礎年金の支給要件(国民年金法)
付加保険料の納付(国民年金法)
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-095 11.30
<令和6年の問題を振り返って>付加保険料の納付
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
付加保険料の納付について条文を読んでみましょう。
第87条の2 ① 第1号被保険者(保険料の免除を受けている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、400円の付加保険料を納付する者となることができる。 ② 付加保険料の納付は、国民年金の保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 ③ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 ④ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、③の申出をしたものとみなす。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問8-ウ】
付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。

【解答】
【R6年問8-ウ】 ×
産前産後期間で保険料を納付することを要しないものとされた各月についても、付加保険料を納付することができます。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
保険料の免除を受けている者(法定免除、申請全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除)は、付加保険料を納付できません。
②【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
追納を行った月については、付加保険料を納付できません。
③【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
付加保険料の納付は、申出によってやめることができます。「その申し出をした日の属する月以後」ではなく、「その申出をした日の属する月の前月以後」の各月の付加保険料を納付する者でなくなることができます。
④【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料を納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

【解答】
④【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付することができません。国民年金基金の加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
⑤【R4年出題】
厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
付加保険料の納期限は、翌月末日です。
納期限までに納付しなかったときでも、納付期限から2年間は付加保険料を納付できます。
問題文のような扱いはありません。
⑥【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
⑥【R2年出題】 〇
「任意加入被保険者」も、付加保険料を納付できます。
(法附則第5条第9条)
ちなみに「特例による任意加入被保険者」は、付加保険料を納付できません。
(H6法附則第11条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-094 11.29
<令和6年の問題を振り返って>遺族基礎年金の支給要件
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
遺族基礎年金の支給要件について条文を読んでみましょう。
法第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 (1) 被保険者が、死亡したとき。 (2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。 (3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 (4) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
(1)と(2)を「短期要件」、(3)と(4)を長期要件といいます。
ポイント!
★(1)と(2)は保険料納付要件が問われます。
★(3)と(4)の25年の計算には、合算対象期間も含みます。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問6-D】
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

【解答】
①【R6年問6-D】 ×
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上あることが必要です。
老齢基礎年金は、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が10年以上あれば受給権が発生しますが、長期要件の遺族基礎年金の場合は25年以上必要です。
②【R6年問6-E】
国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

【解答】
②【R6年問6-E】 〇
国民年金の被保険者である者が死亡した時(=短期要件)の場合は、保険料納付要件が問われます。「死亡日の前日」に、死亡日の属する月の「前々月」までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の「3分の2以上」ある場合は、保険料納付要件を満たします。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

【解答】
①【H30年出題】 〇
保険料納付要件の特例を満たしています。
「死亡日」が令和8年4月1日前にあり、死亡した者が65歳未満であれば、保険料納付要件の特例が適用されます。特例の要件は、「死亡日の前日」に、「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」ことです。
問題文の場合は、平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡(60歳未満)、死亡日の前日(平成30年4月1日)に、死亡日の属する月の前々月までの1年間(平成29年3月から平成30年2月までの期間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(=未納がない)ので、特例の要件を満たします。
(S60法附則第20条第2項)
②【R4年出題】
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。

【解答】
②【R4年出題】 〇
長期要件の「25年以上」の計算には、合算対象期間も含みます。
(法附則第9条)
③【H30年出題】
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
※本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする。)

【解答】
③【H30年出題】 ×
老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した場合、短期要件には該当しないので、「長期要件」で要件をみます。
長期要件の場合、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上必要です。
問題文の者は、保険料納付済期間を15年有するのみですので、遺族基礎年金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-093 11.28
<令和6年の問題を振り返って>学生納付特例制度
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
「学生納付特例制度」について条文を読んでみましょう。
法第90条の3第1項 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 (1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 (2) 第90条第1項第2号及び第3号に該当するとき。 ・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ・ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。 (3) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 |
(1)の前年の所得について
扶養親族等がないときは、「128万円」となります。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-B】
学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。

【解答】
【R6問5-B】 ×
定時制及び通信制課程の生徒も、学生納付特例制度を利用することができます。
(令第6条の6)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
学生納付特例の所得要件は、学生本人のみの所得で判断します。
「世帯主又は配偶者」の所得は問われないのがポイントです。
②【H28年選択式】
国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
<選択肢>
① 1年2か月
② 1年6か月
③ 2年2か月
④ 2年6か月

【解答】
<A> ③ 2年2か月
(平成26年3月31日年管発0331第9号)
免除の申請は、保険料の納期限から2年を経過していない期間について行うことができます。
例えば、令和4年9月分の納期限は、令和4年10月31日です。免除の申請期限は、令和6年10月31日までとなります。申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。
しかし、休日等の関係で納期限が翌々月になることがあります。その場合は2年2か月前までが対象となります。
厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の2年2か月前の月から申請のあった日の属する年の翌年3月までが対象です。
④【H28年出題】
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

④【H28年出題】 〇
申請全額免除の対象から、学生は除外されています。
(法第90条第1項)
⑤【R5年出題】
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
保険料の法定免除の要件に該当した場合は、学生も法定免除の適用を受けることができます。
(法第89条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-092 11.27
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険の脱退一時金
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
★脱退一時金は、「日本国籍を有しない者」が対象で、日本を出国した場合に請求できます。
なお、国民年金にも同じく脱退一時金の制度があります。
では、脱退一時金について条文を読んでみましょう。
法附則第29条第1項~第6項 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) ① 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者等は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有するとき。 (2) 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。 (3) 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 ② 請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 ③ 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。 ④ 支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 ⑤ 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。 ⑥ 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
★脱退一時金の計算式
「被保険者であった期間の平均標準報酬額」×「支給率」
★支給率とは
「最終月の属する年の前年10月の保険料率」×「2分の1」×「被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数」
★被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 | 支給率 |
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |
例えば、被保険者期間が60月以上の場合の支給率は、
1000分の183×2分の1×60≒5.5となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6問8-A】
脱退一時金の支給額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額である。この支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月(最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月)の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。なお、当該政令で定める数の最大値は60である。

【解答】
【R6問8-A】 〇
脱退一時金の支給額の計算に使う「支給率」について確認しましょう。
支給率=「最終月の属する年の前年10月の保険料率」×「2分の1」×「被保険者であった期間に応じて政令で定める数」で計算します。
ちなみに、最終月は、「最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月」です。
最終月の属する年の前年「10月」の保険料率を使いますが、最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月の保険料率を使います。
また、「被保険者であった期間に応じて政令で定める数」の最大値は60です。
(令第12条の2)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき」は、脱退一時金の支給は受けられません。
②【H30年出題】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
脱退一時金の請求要件は、「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年経過していないこと」です。また、国民年金の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過していないことです。
③【R3年出題】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【解答】
③【R3年出題】 〇
最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過していても、「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」から起算して2年経過していない場合は、脱退一時金の請求が可能です。
問題文は、「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日から1年が経過」となっていますので、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能です。
④【H27年出題】
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。

【解答】
④【H27年出題】 ×
最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の「前年9月」ではなく「前年10月」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-091 11.26
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険料の納期限
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
保険料の納期限について条文を読んでみましょう。
第82条第1項、2項(保険料の負担及び納付義務) ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 ② 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
法第83条第1項 (保険料の納付) 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問7-C】
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。

【解答】
【R6問7-C】 〇
厚生年金保険の保険料は、被保険者と事業主が、それぞれ半額を負担します。また、事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負い、納期限は翌月末日です。
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の場合は、事業主の同意がない場合、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。その場合も、保険料の納期限は翌月末日です。
(法第82条、法附則第4条の3)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日ではなく「翌月末日」までに、納付しなければなりません。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
②【H27年出題】 ×
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の場合は、事業主の同意がない場合、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。
その場合の保険料の納期限は翌月末日です。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、「納期限の日」ではなく「納期限の属する月の前月の末日」に、その資格を喪失します。
(法附則第4条の3)
③【R2年出題】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は「徴収されます」。
条文を読んでみましょう。
法第19条第1項 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 法第81条第2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 |
<令和6年4月10日に資格取得、11月26日に退職(11月27日に資格喪失)の場合>
被保険者期間は、令和6年4月~10月まで、保険料の徴収も令和6年4月分から10月分までとなります。
<令和6年4月10日に資格取得、11月30日に退職(12月1日に資格喪失)の場合>
被保険者期間は、令和6年4月~11月まで、保険料の徴収も令和6年4月分から11月分までとなります。
月末退職の場合は、翌月1日が資格喪失となります。保険料は資格を喪失した月の前月まで徴収されますので、月末退職の場合、退職した日の属する月の保険料は徴収されます。
④【H22年出題】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【解答】
④【H22年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第84条第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 |
事業主は、被保険者負担分の保険料を報酬から控除できますが、控除できるのは、「前月の標準報酬月額に係る保険料」です。
また、退職の場合は、「前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除することができます。
例えば、11月30日に退職した場合は、11月分まで保険料が徴収されます。
11月支払の報酬から、10月分(前月分)と11月分(当月分)の保険料を控除することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<厚生年金保険法>高齢任意加入被保険者
R7-090 11.25
厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」についてお話しします
厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」についてお話しします。
厚生年金保険の被保険者を整理してみましょう。
| 適用事業所 | 適用事業所以外の事業所 | |
| 70歳未満 | 当然被保険者 | 任意単独被保険者 |
| 70歳以上 | 高齢任意加入被保険者 | 高齢任意加入被保険者 |
・「高齢任意加入被保険者」とは、「70歳以上で老齢年金の受給権がない人」です。
・高齢任意加入被保険者には、「厚生年金保険の適用事業所」に使用される者と「適用事業所以外の事業所」に使用される者の2つのパターンがあります。
・加入の手続き、喪失事由、保険料の負担と納付義務などをおさえましょう。
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-089 11.24
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年11月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年11月18日から11月23日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
★任意継続被保険者のすべてをお話しします(健康保険法)
★再就職手当と高年齢再就職給付金(雇用保険法)
★健康保険の資格取得と喪失(健康保険法)
★資格喪失後の傷病手当金の継続給付(健康保険法)
★一人一年金の原則(厚生年金保険法)
★遺族厚生年金の遺族の要件(厚生年金保険法)
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-088 11.23
<令和6年の問題を振り返って>遺族厚生年金の遺族の要件
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
遺族厚生年金の遺族について条文を読んでみましょう。
法第59条第1項、2項 ① 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 ② 父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-ウ】
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が50歳の父と54歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。

【解答】
【R6問5-ウ】 ×
「父母」は、被保険者の死亡当時「55歳以上」であることが要件です。
50歳の父と54歳の母については、どちらにも遺族厚生年金の受給権は発生しません。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
生計維持関係は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時」 で判断するのが原則です。
ただし、失踪の宣告を受けた被保険者であった者については、「行方不明となった当時」の生計維持関係が問われます。
②【R1年出題】
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

【解答】
②【R1年出題】 ×
54歳の夫と21歳の子は、どちらも遺族厚生年金を受けることができる遺族ではありません。
③【R2年出題】
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
55歳以上の夫は受給権者になり得ます。子の有無は問われません。
④【R2年出題】
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。

【解答】
④【R2年出題】 〇
遺族厚生年金には転給がありません。
遺族厚生年金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。
① | 配偶者又は子 |
② | 父母 |
③ | 孫 |
④ | 祖父母 |
例えば、被保険者等の死亡当時、「配偶者又は子」がいる場合は、父母以下は遺族厚年金を受けることはできません。
問題文の場合、被保険者の子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、被保険者の父は遺族となりません。その後、子の受給権が消滅したとしても、父に受給権が転給することもありません。
⑤【R5年出題】
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
夫は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であれば遺族厚生年金の受給権者となりますが、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されます。
ただし、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金の支給停止は解除され、遺族厚生年金を受給することができます。
条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-087 11.22
<令和6年の問題を振り返って>一人一年金の原則
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
年金の併給調整について条文を読んでみましょう。
第38条第1項、法附則第17条 (併給の調整) 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金についても同様とする。 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-イ】
厚生年金保険の被保険者である甲は令和2年1月1日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時40歳)と子である丙(当時10歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和6年8月1日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。

【解答】
【R6問5-イ】 〇
1人に対して、複数の年金の受給権が発生することがあります。
問題文の丙には、「甲の死亡に基づく遺族厚生年金」と「乙の死亡に基づく遺族厚生年金」の受給権が発生していますが、同じ遺族厚生年金でも、甲の死亡に基づくものと乙の死亡に基づくものは別です。
「1人1年金の原則」に基づいて、丙は、そのどちらかを選択して受給することになります。ちなみに、選択しなかった方の年金は、支給停止されます。
(法第38条)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38条第1項及び同法附則第17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金

【解答】
①【R4年出題】
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給できない
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給できない
どちらか一方の年金の支給が停止されるもの組み合わせは、イとオの2つです。
②【H23年出題】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。
障害厚生年金は、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。
②【H26年出題】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「65歳以上」の場合、「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」は、併給することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-086 11.21
<令和6年の問題を振り返って>資格喪失後の傷病手当金の継続給付
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
資格喪失後の継続給付について条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6問4-E】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。

【解答】
【R6問4-E】 〇
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、被保険者の資格を喪失した日の前日において被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額が、傷病手当金の額の算定の基礎に用いられます。
(法第84条の2)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるための要件に、「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」があります。
転職等で異なった保険者における被保険者期間だったとしても、合算して1年になれば、要件を満たします。なお、1日の空白もなく継続していなければなりません。
また、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含みません。
(法第104条)
②【R4年出題】
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
②【R4年出題】 ×
図にしてみましょう。
退職
共済組合 6か月 | A健康保険組合 10か月 | |
|
| 傷病手当金 |
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」が必要です。「1年以上」には、共済組合の組合員であった期間は含みません。
問題文は、A健康保険組合の期間が10か月しかありませんので、傷病手当金の継続給付は受けられません。
(法第104条)
③【H27年出題】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

【解答】
③【H27年出題】 〇
・資格喪失後に任意継続被保険者になった場合
→ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができます。
・資格喪失後に特例退職被保険者となった場合
→ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
(法第104条、法附則第3条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-085 11.20
<令和6年の問題を振り返って>健康保険の資格取得と喪失
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
【R6問1-C】
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではない。

【解答】
【R6問1-C】 ×
派遣労働者の社会保険は、雇用関係にある「派遣元事業主(派遣会社)」で、適用されます
★登録型派遣労働者の適用
→ 派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないとされています。
★被保険者資格の喪失手続等
→ 登録型派遣労働者について、1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこととされています。
問題文では、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか「遅い日をもって」、の部分が誤りです。
ちなみに、「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の区別は廃止されています。すべての労働者派遣事業が「許可制」となっています。
(H27.9.30保保発0930第9号、年管管発0930第11号)
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
被保険者は、「適用事業に使用されるに至った日」から資格を取得します。
試用期間だとしても、適用事業に使用されていますので、試用期間を経過した日の翌日からではなく、入社した日に資格を取得します。
(法第35条)
②【R2年出題】
新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされている。

【解答】
②【R2年出題】 〇
当初から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立している、かつ、休業手当が支払われているときは、休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得します。
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
③【R5年出題】
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。

【解答】
③【R5年出題】 ×
一時帰休中の者の被保険者資格については、休業手当が支払われるときは、被保険者の資格は存続するものとされています。
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
④【H27年出題】
被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。

【解答】
④【H27年出題】 〇
解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除いて、事業主から被保険者資格喪失届の提出があったときは、裁判が提起されたときでも、一応資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等、所定の手続をなすこととされています。
(昭25.10.9保発第68号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
R7-085 11.19
<令和6年の問題を振り返って>再就職手当と高年齢再就職給付金
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
「再就職手当」の要件をみてみましょう。
法第56条の3第1項第1号ロ 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの |
「高年齢再就職給付金」の要件をみてみましょう。
第61条の2第1項 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。 (2) 再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 |
「再就職手当」と「高年齢再就職給付金」の両方の要件にあてはまった場合はどうなるでしょう?
第61条の2第4項 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係るもの(=再就職手当)に限る。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問6-B】
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)を受けたときは、当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。

【解答】
【R6問6-B】 ×
就業促進手当(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものに限る。)とは、再就職手当のことです。
「再就職手当」を受けたときは、高年齢再就職給付金は支給されません。「当該就業促進手当に加えて同一の就職につき高年齢再就職給付金を受けることができる。」は誤りです。
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。」ではなく、「再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。」となります。
②【R1年出題】
厚生労働省で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
「安定した職業」に就いた者で、基本手当の支給残日数が「3分の1以上」あるものが受給できるのは、就業手当ではなく「再就職手当」です。
ちなみに、「就業手当」を受給できるのは、「職業に就いた者(安定した職業に就いた者を除く。)」で、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の「3分の1以上かつ45日以上」であるものです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険>任意継続被保険者
R7-084 11.18
【社労士受験】任意継続被保険者のすべてお話しします
任意継続被保険者のすべてをお話しします。
①任意継続被保険者の要件
「申出」の期限は?
②任意継続被保険者の資格の喪失
「翌日喪失」or「当日喪失」がポイント
任意継続被保険者をやめる申出
③任意継続被保険者の標準報酬月額
④任意継続被保険者の保険料
保険料を納付期日までに納付しなかったとき
前納について
⑤任意継続被保険者の保険給付
傷病手当金、出産手当金の扱い
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-083 11.17
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年11月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年11月11日から11月16日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
★国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者についてお話しします
★基準障害による障害基礎年金について(国民年金法)
★テレワークと事業場外みなし労働時間制(労働基準法)
★高度プロフェッショナル制度の導入(決議の届出)(労働基準法)
★年次有給休暇の発生要件である出勤率(労働基準法)
★労災特別加入(海外派遣者)について(労災保険法)
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-082 11.16
<令和6年の問題を振り返って>労災特別加入(海外派遣者)について
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
特別加入には、次の3つの種類があります。
中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等) |
一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等) 特定作業従事者 |
海外派遣者 |
今日は、「海外派遣者」についてみていきます。
海外派遣者として特別加入できるものの範囲を確認しましょう。(労災保険法第33条)
■独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者
■日本国内の事業主(有期事業を除く)から、海外で行われる事業に労働者として派遣される者
※「労働者として派遣される者」と「海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者」があります。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問6-A】
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

【解答】
①【R6問6-A】 〇
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
(法第36条)
②【R6問6-B】
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。

【解答】
②【R6問6-B】 〇
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係は、転勤、在籍出向、移籍出向など様々な形態で処理されていたとしても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではありません。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
ちなみに、「海外出張」については、特別加入しなくても、国内の所属の事業場の労災保険から保険給付が行われます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
派遣先の海外の事業が中小規模の場合は、その事業の代表者は、労災保険の海外派遣者として特別加入の対象となります。
中小規模の事業(特定事業といいます)は以下の通りです。
業 種 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
なお、特定事業に該当しない場合は、代表者などは特別加入できません。労働者のみが対象となります。
②【H26年出題】
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

【解答】
②【H26年出題】 ×
現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない、とされています。
問題文の海外支店に直接採用された者は、特別加入できません。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
③【R3年出題】
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

【解答】
③【R3年出題】 〇
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限りません。既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である、とされています。
海外派遣されてからでも派遣元の事業主が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-081 11.15
<令和6年の問題を振り返って>年次有給休暇の発生要件である出勤率
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
年次有給休暇の発生要件について条文を読んでみましょう。
第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
年次有給休暇の発生には
・6か月間継続勤務していること
・出勤率が8割以上あること
今回は、「出勤率」をみていきます。
出勤率は「全労働日(労働義務のある日)」に対する「出勤した日」の割合です。
出勤した日 |
全労働日 |
で算定します。
★出勤したとみなされる期間があります。
法第39条第10項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、これを出勤したものとみなす。 |
また、「年次有給休暇」を取得した日も、出勤したものとみなされます。
(H6.3.31基発181号)
★出勤率の基礎となる全労働日について
① 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
② 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、③に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
③ 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(1) 不可抗力による休業日
(2) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(3) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
(H25.7.10基発0710第3号)
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-E】
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、同法第39条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。

【解答】
【R6年問6-E】 ×
生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間」は、労働基準法上出勤したものとみなされませんが、「当事者の合意によって出勤したものとみなすことも差し支えない」とされています。
(H22.5.18基発0518第1号)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

【解答】
①【H28年出題】 〇
年次有給休暇を取得した日は、「出勤した」ものとして出勤率を計算します。
②【H28年出題】
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
「所定の休日に労働させた」場合におけるその日は、全労働日に「含まれません」。
(H25.7.10基発0710第3号)
③【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >というべきである。」
<選択肢>
① 影響を与えない ② 影響を与えるもの
③ 含まれない ④ 含まれるもの

【解答】
A ④ 含まれるもの
(平成25年6月6日 第一小法廷判決)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-081 11.14
<令和6年の問題を振り返って>高度プロフェッショナル制度の導入(決議の届出)
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「高度プロフェッショナル制度」の導入手順を確認しましょう。
①労使委員会を設置する
↓
②労使委員会で決議をする
※委員の5分の4以上の多数による決議がなされていることが条件です。
↓
③労使委員会の決議を所轄労働基準監督署長に届け出る
↓
④対象労働者の同意を書面で得る
↓
⑤対象労働者を対象業務に就かせる
条文を読んでみましょう。
第41条の2第1項 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により定められた事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における一定の業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第3号から第5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。 (以下省略します) |
高度プロフェッショナル制度の対象になる労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-オ】
労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。

【解答】
【R6年問5-オ】 〇
高度プロフェッショナル制度の導入については、労使委員会の決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、効力が生じます。
単に労使委員会の決議が行われただけでは、導入できません。
過去問をどうぞ!
①【H17年出題】
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまでも取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。

【解答】
①【H17年出題】 ×
企画業務型裁量労働制を採用するための労使委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければなりません。届出を行わない場合は、企画業務型裁量労働制の効力は発生しません。
(法第38条の4、H12.1.1基発第1号)
②【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】
②【H24年出題】 〇
36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて、時間外労働等を行わせることが適法となります。単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れません。
(法第36条第1項)
条文で確認しましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
③【R3年出題】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】
③【R3年出題】 〇
36協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、時間外労働等は適法となります。
令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、効力が発生するのはその日以降ですので、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、労働基準法違反となります。
④【R4年出題】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。

【解答】
④【R4年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ただし、届出は労使協定の効力の発生要件ではありません。届出をしていなくても、労使協定が締結されていれば1か月単位の変形労働時間制の効力が発生します。
なお、届出をしなくても効力は発生しますが、届出を怠ったことに対して罰則が適用されます。
(法第32条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-080 11.13
<令和6年の問題を振り返って>テレワークと事業場外みなし労働時間制
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインより
★在宅勤務については、事業主が労働者の私生活にむやみに介入すべきではない自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから、一定の場合には、労働時間を算定し難い働き方として、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働のみなし労働時間制(以下「みなし労働時間制」という。)を適用することができる。 在宅勤務についてみなし労働時間制が適用される場合は、在宅勤務を行う労働者が就業規則等で定められた所定労働時間により勤務したものとみなされることとなる。業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該必要とされる時間労働したものとみなされ、労使の書面による協定があるときには、協定で定める時間が通常必要とされる時間とし、当該労使協定を労働基準監督署長へ届け出ることが必要となる(労働基準法第38条の2)。 (H20.7.28基発第0728001号) |
では、事業場外みなし労働時間制の条文を読んでみましょう。
第38条の2 ① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ② ①のただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。 則第24条の2第3項 労使協定の届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-ウ】
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。

【解答】
【R6問5-ウ】 ×
「テレワーク」に、事業場外みなし労働時間制を適用できる条件を確認しましょう。
★次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。
①当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
(H16.3.5基発第0305001号)
「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」のみでは、適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
上の令和6年の問題の解説のように、要件を満たした場合、情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)にも、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されます。
②【H18年出題】
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。

【解答】
②【H18年出題】 〇
・労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いとき
↓
<原則>所定労働時間労働したものとみなされる
<業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合>
当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。
<労使協定があるとき>
労使協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる
③【R1年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

【解答】
③【R1年出題】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-079 11.12
<令和6年の問題を振り返って>基準障害による障害基礎年金について
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
基準障害による障害基礎年金とは?
・複数の障害があるが、単独では障害等級1・2級に該当しない
↓
・併合して初めて障害等級1・2級に該当すると、障害基礎年金が支給される仕組み
↓
・併合のきっかけになる傷病が「基準傷病」、基準傷病にかかる障害が「基準障害」
↓
・基準障害の障害認定日が基準障害による障害基礎年金の障害認定日になる
↓
・初診日、保険料納付要件は、「基準障害」について問われる
第1の傷病 | ● ● 初診日 障害認定日 | |||||
|
|
|
|
| 併合 初めて2級以上に該当 | |
|
|
|
|
| ||
基準傷病 |
| ● ● 初診日 障害認定日 | ||||
基準障害による障害基礎年金の条文を読んでみましょう。
第30条の3 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ③ 基準障害による障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。 |
★保険料納付要件は、「基準傷病」に係る初診日の前日で判断されます。
(法第30条の3第2項)
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問10-D】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】
【R6問10-D】 ×
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、1・2級に該当した日に受給権が発生します。ただし、支給は請求のあった「月の翌月」からです。請求のあった月からではありません。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
初診日要件は、「基準傷病に係る初診日」で判断されます。基準傷病以外の傷病については、初診日要件は問われません。
②【H29年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
基準障害による障害基礎年金は、「65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当」することが条件ですが、請求は、65歳に達した日以後でも行うことができます。
③【H20年出題】
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】
③【H20年出題】 ×
基準障害の規定による障害基礎年金について
・所定の要件に該当すれば受給権は発生します
・障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができます
・支給は「請求のあった月の翌月から」開始されます。「当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から」ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金の強制被保険者について
R7-078 11.11
【社労士受験】国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者についてお話しします
今日の内容です。
・第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の定義をおさえましょう
・「国内居住要件」の有無、「年齢要件」の有無がポイントです。
・第1号被保険者と第3号被保険者から除外されるものをおぼえましょう。
・第3号被保険者は、国内に住所を有することが原則ですが、海外特例に該当すると、国内に住所を有しなくても第3号被保険者となります。
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-077 11.10
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年11月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年11月4日から11月9日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
遺族厚生年金の短期要件と長期要件についてお話しします。
配偶者以外の者が遺族厚生年金の受給権者の場合(厚生年金保険法)
年金の内払調整(厚生年金保険法)
障害基礎年金の支給要件についての基本問題(国民年金法)
国民年金保険料の前納(国民年金法)
国民年金の適用(技能実習、海外に居住する場合など)(国民年金法)
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-076 11.09
<令和6年の問題を振り返って>国民年金の適用(技能実習、海外に居住する場合など)
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金の強制被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種類があります。
国民年金の強制被保険者の要件について条文を読んでみましょう。
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「第1号被保険者」という。) (2) 厚生年金保険の被保険者(「第2号被保険者」という。) (3) 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(「第3号被保険者」という。)
則第1条の2 (第1号被保険者、第3号被保険者の適用を除外される者) (1) 日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(=在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」の場合) (2) 日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの (=在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」の場合)
則第1条の3 (国内居住要件の特例) 第3号被保険者の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 (1) 外国において留学をする学生 (2) 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (4) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの (5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
令和6年の問題を解いてみましょう
①【R6年問4-A】
技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。

【解答】
①【R6年問4-A】 ×
技能実習の在留資格で日本に在留する外国人も公的年金に加入しなければなりません。実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合
・講習期間中 → 「国民年金」に加入します
・実習期間中 → 「厚生年金保険」に加入します ※厚生年金保険の適用事業所でない場合は、引き続き国民年金に加入します
「講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。」ではなく、「講習期間は国民年金、実習期間は厚生年金保険の対象となる」となります。
(参照:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/content/000721075.pdf)
②【R6年問4-B】
日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。

【解答】
②【R6年問4-B】 〇
第1号被保険者は、「国内居住要件」がありますので、海外に居住する場合は、資格を喪失します。ただし、「20歳以上65歳未満」の「日本国籍を有する者」は、国民年金の任意加入被保険者になることができます。
③【R6年問4-D】
第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【R6年問4-D】 ×
第3号被保険者は、日本国内に住所を有することが原則です。
ただし、「外国において留学をする学生」は、国内居住要件の例外が認められますので第3号被保険者の資格は喪失しません。
(則第1条の3第1号)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
外国人も国民年金の対象となります。
ただし、「本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」は、除外されます。
(則第1条の2第2号)
②【R3年出題】
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
第3号被保険者は「国内居住要件」を満たすことが原則ですが、「外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったとき」は、海外特例で第3号被保険者の資格は喪失しません。
(則第1条の3)
③【R3年出題】
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

【解答】
③【R3年出題】 〇
第3号被保険者は、国内居住要件を満たすことが原則ですが、「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する」場合は、海外特例で、第3号被保険者となることができます。
(則第1条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-075 11.08
<令和6年の問題を振り返って>国民年金保険料の前納
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金の保険料の納付期限は、翌月末日が原則ですが、前払い(前納)することもできます。
保険料の前納について条文を読んでみましょう。
第93条 ① 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問1-C】
国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。

【解答】
【R6年問1-C】 ×
条文で確認しましょう。
令第7条 (保険料の前納期間) 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。 |
★前納は「6か月」又は「年」を単位とするのが原則ですが、それ以外の期間も可能です。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
昭和34年8月2日生まれの者は、60歳に達した日(令和元年8月1日)に資格を喪失し、被保険者期間は令和元年7月までとなります。
平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することができます。
②【R2年出題】
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
一部免除の保険料も、前納することができます。
③【H30年出題】
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「各月が経過した際に」、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
④【H29年出題】
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。

【解答】
④【H29年出題】 〇
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に「被保険者の資格を喪失した場合」、「第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合」は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付されます。
(令第9条)
⑤【H24年出題】
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
国民年金保険料を前納する方法で、最も割引率が高くなるのは、「口座振替による支払」です。
(令第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-074 11.07
<令和6年の問題を振り返って>障害基礎年金の支給要件についての基本問題
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の受給権発生要件は、次の3つです。
①初診日
②保険料納付要件
③障害認定日
条文を読んでみましょう。
第30条 ① 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 (1) 被保険者であること。 (2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 昭60法附則第20条第1項 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件を満たすものとする。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。 |
★3つの要件を満たした場合は、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問2-ア】
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。

【解答】
①【R6年問2-ア】 〇
「初診日」要件についての問題です。
初診日に①か②のどちらかに該当していることです。
① 国民年金の被保険者であること
② 国民年金の被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
②【R6年問2-ウ】
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。

【解答】
②【R6年問2-ウ】 〇
「保険料納付要件」についての問題です。
「保険料納付要件」の原則
・ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である
「保険料納付要件」の特例
・ 初診日が令和8年4月1日前にある
・ 初診日に65歳未満
・ 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない(=保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと)
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

【解答】
①【H29年出題】 〇
初診日に、「被保険者であった者(かつて被保険者だったが、初診日には被保険者ではない)」の場合、初診日に「日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。」が条件です。
問題文の場合は、「日本国内に住所を有しない」となっているので、障害基礎年金は支給されません。
②【H27年出題】
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

【解答】
②【H27年出題】 〇
障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」です。
ただし、初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となります。なお、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われます。
③【H29年出題】
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
(令第4条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-073 11.06
<令和6年の問題を振り返って>年金の内払調整
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
今日のテーマは「内払」です。
「内払」とは、「払いすぎた額を今後支払う年金額から減額すること」です。(参照:日本年金機構のホームページ)
条文を読んでみましょう。
第39条 ① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 ② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 ③ 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 |
(例)①について
消滅
乙年金 | 支払い |
|
|
|
| 甲年金の内払とみなす ↓ |
| ||
| 甲年金 | |||
・乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得した
↓
・そのため乙年金の受給権が消滅したにも関わらず
↓
・翌月以後の分として、乙年金の支払が行われた
↓
・払いすぎた乙年金を返還させて改めて甲年金を支払うのではなく
↓
・支払われた乙年金は、甲年金の「内払とみなす」ことになっています。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-A】
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

【解答】
【R6年問3-A】 〇
同一人に対する「国民年金法による年金たる給付」と「厚生年金保険法の年金たる保険給付」も内払の調整を行うことができます。ただし「厚生年金保険法の年金たる保険給付」は、厚生労働大臣が支給するものに限られます。
(法第39条第3項)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。

【解答】
①【H25年出題】 〇
・遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得
↓
・障害厚生年金の支給を選択
↓
・にもかかわらず、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われた
↓
・支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。
支給停止
遺族厚生年金 | 支払い |
|
|
|
| 障害厚生年金の内払とみなす ↓ |
| ||
選択→ | 障害厚生年金 | |||
(法第39条第1項)
②【H25年出題】(※改正による修正あり)
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。

【解答】
②【H25年出題】 〇
支給停止
寡婦年金 | 支払い |
|
|
|
| 老齢厚生年金の 内払とみなすことができる。 ↓ |
| ||
選択→ | 60歳台前半の老齢厚生年金 | |||
(法第39条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-072 11.05
<令和6年の問題を振り返って>配偶者以外の者が遺族厚生年金の受給権者の場合
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給するときのルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第60条第2項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとに算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 第61条第1項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 |
例えば、遺族厚生年金の受給権者が、父と母の場合、それぞれの遺族厚生年金の額は、年金の額を2で割った額となります。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-エ】
夫(70歳)と妻(70歳)は、厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず、老齢基礎年金を受給している。また、夫妻と同居していた独身の子は厚生年金保険の被保険者であったが、3年前に死亡しており、夫妻は、それに基づく遺族厚生年金も受給している。この状況で夫が死亡し、遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたときは、増減が生じた月の翌月から、妻の遺族厚生年金の年金額が改定される。

【解答】
【R6年問5-エ】 〇
遺族厚生年金の受給権者が2人(死亡した者からみると父と母)ですので、それぞれに、遺族厚生年金の額を2で割った額が支給されます。
その後、夫(父)が死亡した場合、遺族厚生年金の受給権者は2人から1人に減少します。その場合、減少が生じた月の翌月から、母(妻)の遺族厚生年金の年金額が改定されます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金額を改定する。

【解答】
①【R2年出題】 〇
増減を生じた月の「翌月から」、年金額が改定されます。「翌月から」がポイントです。
②【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。

【解答】
②【H26年出題】 〇
例えば、遺族厚生年金の受給権者である子がAとBの2人いる場合で、Aが死亡したときは、Bに支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定されます。
ちなみに、Bの年金額は、Aと2分の1ずつだったものが、Aの死亡によりBが1人で受けることになりますので、Bの年金額は増額します。
③【H21年出題】
被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。

【解答】
③【H21年出題】 〇
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合で、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者の数で除して得た額となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族厚生年金の短期要件と長期要件のこと
R7-071 11.04
【社労士厚生年金】遺族厚生年金の短期要件と長期要件についてお話しします。
遺族厚生年金には短期要件と長期要件があります。
・短期要件とは?
・長期要件とは?
・短期要件と長期要件の両方に当てはまる場合があります
・短期要件と長期要件の計算式の違い
についてお話ししています。
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-070 11.03
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年10月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月28日から11月2日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
【労災保険法】 通勤の定義についてお話しします
【労災保険法】 通勤災害と認められた事例・認められなかった事例
【国民健康保険法】の問題を解いてみましょう
【健康保険法】 労災と出産育児一時金との関係
【健康保険法】 保険料の負担と納付義務
【健康保険法】 育児休業期間中の保険料免除
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-069 11.02
<令和6年の問題を振り返って>育児休業期間中の保険料の免除【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
育児休業期間の保険料免除について条文を読んでみましょう。
第159条第1項 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間の保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
★(1)について(開始日の属する月と終了する日の翌日が属する月が異なる)
開始日 |
|
|
| 終了日の翌日 |
免 除 | 免 除 | 免 除 | 免 除 |
|
★(2)について(開始日の属する月と終了する日の翌日が属する月が同一)
| 開始日 終了日の翌日 |
|
| 14日以上 免 除 |
|
★賞与について
育児休業等の期間が1か月以下の場合は、「標準報酬月額」に係る保険料に限って免除されます。賞与の保険料は、1か月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問10-C】
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
【R6問10-C】 ×
保険料が徴収されないのは、育児休業等を開始した日の属する月(令和5年10月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和6年1月1日)が属する月の前月(令和5年12月)までの月です。
令和6年1月分の保険料は、免除されません(=徴収されます)
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の前月(令和5年3月)までの月の保険料は徴収されません。
②【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合は、育児休業等の日数が14日以上あることが必要です。
問題文の育児休業期間は、令和5年1月4日~16日で13日しかありません。
そのため、令和5年1月分の保険料は免除されません(徴収されます)。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-068 11.01
<令和6年の問題を振り返って>健康保険の保険料の負担と納付義務【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
保険料について条文を読んでみましょう。
第161条第1項~3項(保険料の負担及び納付義務) ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ② 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 ③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第162条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例) 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
第164条第1項 (保険料の納付) 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問7-A】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。

【解答】
【R6問7-A】 ×
一般保険料額又は介護保険料額は、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担するのが原則です。
ただし、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき割合を「増減」ではなく「増加」することができます。
ポイント!
・「増加」できるのは、事業主の負担割合です。被保険者の負担割合は増加できません。
・規約で「増加」できるのは、「健康保険組合」のみです。全国健康保険協会には、適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
重要キーワードは、「健康保険組合」、「事業主の負担割合」、「増加」です。
②【H30年出題】
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
②【H30年出題】×
任意継続被保険者の初めて納付すべき保険料は、「保険者が指定する日」までに納付しなければなりません。
表にまとめました。
| 負担割合 | 納付義務 | 納付期日 |
一般の被保険者 | 2分の1 | 事業主 | 翌月末日 |
任意継続被保険者 | 全 額 | 自 己 | その月の10日 初めて納付すべき保険料は、 「保険者が指定する日」 |
③【R1年出題】
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込みがない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

【解答】
③【R1年出題】 〇
被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、使用関係は存続しているため、保険料を負担しなければなりません。事業主及び被保険者は保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負います。
(昭和26.3.9保文発第619号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-067 10.31
<令和6年の問題を振り返って>労災と出産育児一時金の関係【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
出産育児一時金の条文を読んでみましょう。
第101条 (出産育児一時金) 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 |
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の額は、
★産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合
↓
1児につき50万円
★産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
↓
1児につき48万8千円
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問8-B】
被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

【解答】
【R6問8-B】 〇
業務中に転倒強打したことに対して、労災保険法から補償が行われたとしても、健康保険法に規定される保険事故(出産)として、出産育児一時金が支給されます。
(昭24.3.26保文発523)
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、「出産」に対して、健康保険から出産育児一時金の支給が行われます。
なお、流産でも妊娠4か月以上の場合は、健康保険法の出産となります。
(昭24.3.26保文発523)
②【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】
②【R5年出題】 〇
産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に出産した場合は、出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、1児につき50万円支給されます。双子の場合は100万円となります。
また、家族出産育児一時金は、被扶養者ではなく、「被保険者に対し」支給されることにも注意して下さい。
(法第101条、104条、令第36条、令和5.3.30保保発0330第8号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民健康保険法)
R7-066 10.30
<令和6年の問題を振り返って>(社一)国民健康保険法の問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民健康保険法の択一式です。
国民健康保険法の問題を解いてみましょう。
押さえておきたいのは、①と④の問題です。
①【R6問8-A】重要!
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

【解答】
①【R6問8-A】重要! ×
国民健康保険組合に指導及び助言を行うのは、「市町村(特別区を含む)」ではなく「都道府県」です。
国、都道府県、市町村の責務を条文で確認しましょう。
第4条 ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 |
②【R6問8-B】
国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

【解答】
②【R6問8-B】 〇
国民健康保険組合は、「組合員及び組合員の世帯に属する者」を被保険者としますので、世帯単位で適用されるのが原則です。
また、「国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」と定められています。
(法第19条)
③【R6問8-C】
国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。

【解答】
③【R6問8-C】 ×
監事ではなく理事です。
条文で確認しましょう。
第32条の4 (清算人) 国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 |
④【R6問8-D】重要!
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

【解答】
④【R6問8-D】 ×
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び「公益」を代表する委員各3人をもって組織されます。
国民健康保険審査会について条文を読んでみましょう。
第91条第1条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
第92条(審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。
第93条 (組織) ① 国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |
⑤【R6問8-E】
市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】
⑤【R6問8-E】 ×
厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
条文を読んでみましょう。
第107条(事業状況の報告) 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 (1) 都道府県 → 厚生労働大臣 (2) 市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 → 当該市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-065 10.29
<令和6年の問題を振り返って>通勤災害と認められた事例、認められなかった事例【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
通勤災害と認められた事例と認められなかった事例をみていきます。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問2-A】
マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】
①【R6年問2-A】 ×
通勤災害と認められます。
・ マイカー通勤者が車のライトの消し忘れなどに気づき、駐車場に引き返すことは一般にあること。
・ いったん事業場に入った後でも、まだ時間の経過もほとんどないことから通勤に通常随伴する行為と認められる。
(昭和49.6.19基収第1739号)
②【R6年問2-B】
マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】
②【R6年問2-B】 ×
通勤災害と認められます
・ 妻の勤務先が同一方向にあり、かつ、夫の通勤経路からそれほど離れていない
・ 通勤をマイカーで行い、妻の勤務先を経由することは通常おこなわれるもの
・ 当該経路は合理的な経路として取り扱うのが妥当
(昭和49.3.4基収第289号)
③【R6年問2-C】
頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷したした場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。

【解答】
③【R6年問2-C】 ×
通勤災害と認められます。
・入院中の夫の看護のため、妻が病院に寝泊まりすることは社会慣習上、通常行われること
・手術当日から長期間継続して寝泊まりしていた事実がある
・被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての「住居」と認められる
(昭和52.12.23基収第981号)
④【R6年問2-D】
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】
④【R6年問2-D】 〇
通勤災害とは認められません。
・事業主の支配下にある事業場施設の状況により生じた災害である
(昭和49.4.9基収第314号)
⑤【R6年問2-E】
長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。

【解答】
⑤【R6年問2-E】 ×
通勤災害とは認められません。
・ 発病の原因となるような通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごとなどが認められないため「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められない
・ 通勤を単なるきっかけとして偶然に生じたものに過ぎない
(昭和50.6.9基収第4039号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<社労士労災保険>通勤について
R7-064 10.28
労災「通勤」の定義についてお話しします
「通勤」の定義は、選択式でも択一式でも、よく出題されます。
用語の意義など、一つずつ解説します。
「通勤」とは、 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 住居と就業の場所との間の往復
(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-063 10.27
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年10月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月21日から26日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
【国民年金法】 国民年金の法定免除についてお話しします
【厚生年金保険法】 遺族厚生年金の原則の計算式
【厚生年金保険法】 不服申立ての超基本問題
【厚生年金保険法】 老齢厚生年金の繰下げの条件
【労働基準法】 1か月単位の変形労働時間制の導入要件
【労働基準法】 専門業務型裁量労働制の適用手順
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-062 10.26
<令和6年の問題を振り返って>専門業務型裁量労働制の適用手順【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「専門業務型裁量労働制」の導入には、「労使協定」の締結が必要です。
労使協定で、対象業務やみなし労働時間を定めます。
条文を読んでみましょう。
第38条の3 ① 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を対象業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 (1) 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下「対象業務」という。) (2) 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 (3) 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 (4) 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 (5) 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
★専門業務型裁量労働制の「対象業務」は、厚生労働省令・告示によって20業務が定められています。
★対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間は、「1日当たりの労働時間」を定めます。(みなし労働時間といいます)
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-エ】
使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。

【解答】
【R6年問5-エ】 〇
専門業務型裁量労働制を適用することについて、労使協定で、「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければなりません。
また、「適用労働者の同意の撤回に関する手続き」も協定する必要があります。
(則第24条の2の2第3項)
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

【解答】
【H19年出題】 〇
ポイントを確認しましょう。
★労使協定に定めるべき時間は、「1日当たり」の労働時間です。
★休憩、深夜業及び休日に関する規定は適用されます。そのため、例えば、法定休日に労働させた場合には、割増賃金の支払いが必要です。
(H12.1.1基発第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-061 10.25
<令和6年の問題を振り返って>1か月単位の変形労働時間制の導入要件【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
1か月単位の変形労働時間制について条文を読んでみましょう。
第32条の2 ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(法定労働時間)を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の労使協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
★ 1か月単位の変形労働時間制を導入するには、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」が必要です。
なお、常時10人以上の労働者を使用する使用者は「就業規則」の作成と届出義務があります。
そのため、1か月単位の変形労働時間制を導入する手続きは以下のようになります。
常時使用する労働者数 | 導入要件 |
10人以上 | 労使協定 又は 就業規則 |
10人未満 | 労使協定 又は 就業規則その他これに準ずるもの |
労使協定で導入する場合は、届出が必要です。
★ 1か月以内の一定の期間(変形期間といいます)を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間(原則40時間・特例の事業場は44時間)を超えないようにしなければなりません。
変形期間の労働時間の総枠は次の式で計算します。
1週間の法定労働時間(40時間又は44時間)×変形期間の暦日数÷7
たとえば、法定労働時間が原則の40時間で、変形期間を1か月とした場合、
31日の月の労働時間の総枠は、40時間×31日÷7=177.1時間
30日の月の労働時間の総枠は、40時間×30日÷7=171.4時間
となります。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-ア】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。

【解答】
【R6年問5-ア】 ×
常時10人未満の労働者を使用する使用者が1か月単位の変形労働時間制を適用するには、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらか必要です。
「必ず就業規則を作成」が誤りです。「労使協定」で導入することもできますし、「就業規則に準ずるもの」で導入することもできます。
なお、「1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定め」とありますが、特例の事業場の場合は「44時間」となります。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、労使の話合いによる制度の導入を促進するため、また、1か月単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制の導入要件は労使協定により定めることとされていることも勘案し、就業規則その他これに準ずるものによる定め又は労使協定による定めのいずれによっても導入できるとされています。
就業規則その他これに準ずるものによる定めがある場合は、労使協定は不要です。
また、労使協定で採用する場合は、所轄労働基準監督署長への届出が必要ですが、届出によって効力が発生するわけではありません。そのため、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる」も誤りです。
(H11.1.29基発第45号)
②【R4年出題】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。

【解答】
②【R4年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を労使協定で採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。しかし、1か月単位の変形労働時間制の効力は労使協定の締結で発生しますので、「労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。」は誤りです。
③【H19年出題】
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

【解答】
③【H19年出題】 〇
変形期間の所定労働時間の総枠の計算式のポイントも確認しましょう。
「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」
・週法定労働時間は40時間が原則ですが、特例の事業場は44時間です。
・暦日数は、暦上の日数です。労働日数ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-060 10.24
<令和6年度厚年>老齢厚生年金の繰下げの条件【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
老齢厚生年金の繰下げの要件について条文を読んでみましょう。
第44条の3第1項 (支給の繰下げ) 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して 1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 |
<老齢厚生年金の繰下げの申し出の条件です>
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していないこと
・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でないこと
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていないこと
★他の年金たる給付とは?
・他の年金たる保険給付 → 障害厚生年金、遺族厚生年金
又は
・国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。) → 遺族基礎年金
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問4】
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはいくつあるか。
なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。
ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。
イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。
オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。

【解答】
ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません。
イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません。
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができます。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができます。
オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません。
老齢厚生年金の繰下げの申出ができないのは、ア、イ、オの3つです。
過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
③ 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
④ 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
⑤ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑥ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑦ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

【解答】
<A> ② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
<B> ⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
②【H28年出題】
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

【解答】
②【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金の受給権を有していても、条件を満たせば、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-059 10.23
<令和6年度>厚生年金保険の不服申立ての超基本問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
厚生年金保険法の審査請求・再審査請求について条文を読んでみましょう。
第90条第1項、3項、4項、5項 (審査請求及び再審査請求) ① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定(厚生年金保険原簿の訂正請求に対する措置)については、この限りでない。 ③ 審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ④ 審査請求並びに再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ⑤ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第91条第1項 ① 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第91条の3(審査請求と訴訟との関係) 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
下の図で確認しましょう。
(参考にどうぞ)
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の審査請求先も確認しましょう。
(1) 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合審査会
(2) 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合審査会
(3) 第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問1-A】
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

【解答】
①【R6年問1-A】 ×
厚生労働大臣による「被保険者の資格」に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会ではなく「社会保険審査官」に対して審査請求をすることができます。
②【R6年問1-B】
厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
②【R6年問1-B】 ×
厚生労働大臣による「保険料の賦課」の処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
③【R6年問1-C】
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

【解答】
③【R6年問1-C】 〇
厚生労働大臣による「脱退一時金」に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
条文を読んでみましょう。
法附則第29条第6項 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
④【R6年問1-D】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨の決定をした場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
④【R6年問1-D】 ×
厚生年金保険原簿の訂正請求に対する処分は、厚生年金保険法に基づく審査請求の対象にはなりません。当該処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。
⑤【R6年問1-E】
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

【解答】
⑤【R6年問1-E】 ×
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。となります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に審査請求をし、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる、とされています。
②【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】
②【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求先は「社会保険審査会」です。
ちなみに、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者の審査請求先は「社会保険審査会」で正しいです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-058 10.22
<令和6年度厚年>遺族厚生年金の原則の計算式【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
遺族厚生年金の額の計算式について条文を読んでみましょう。
第60条第1項 (年金額) 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 (1) 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項(老齢厚生年金の額)の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金(短期要件の遺族厚生年金)については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 (2) 第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 「(1)原則の遺族厚生年金の額」又は次の「イ及びロに掲げる額を合算した額」のうちいずれか多い額 イ (1)に定める額(原則の遺族厚生年金の額)に3分の2を乗じて得た額 ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く。)に 2分の1を乗じて得た額 |
今日は(1)の原則の計算式を見ていきます。
遺族厚生年金の原則の計算式は、
「死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分(平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数)×4分の3」です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年5-ア】
死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。

【解答】
①【R6年5-ア】 ×
死亡した者が短期要件に該当する場合は、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われません。
短期要件と長期要件の違い
| 短期要件 | 長期要件 |
給付乗率 | 1,000分の5.481 (定率) | 生年月日に応じて 1,000分の5.562 ~ 1,000分の7.308 |
被保険者期間の月数 | 300月の最低保障あり | 実期間で計算 |
②【R6年問5-オ】
繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫(厚生年金保険の被保険者ではない。)が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻には、夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる加算額を含む。)の4分の3が遺族厚生年金として支給される。なお、妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず、老齢基礎年金のみを受給しているものとする。

【解答】
②【R6年問5-オ】 ×
夫の老齢厚生年金の額の4分の3が遺族厚生年金として支給されますが、繰下げによる加算額は含まれません。
ちなみに、妻は老齢厚生年金の受給権を有していないので、遺族厚生年金は原則の計算式で計算されます。
過去問をどうぞ!
【H27年出題】(改正による修正あり)
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

【解答】
【H27年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡は「長期要件」に該当しますので、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<社労士国民年金>法定免除について
R7-057 10.21
国民年金の法定免除についてお話しします【社労士受験対策】
法定免除についてお話しします。
今日の内容です。
★法定免除の対象から除外される人
→ 産前産後の保険料の免除を受ける人、一部免除を受ける人
★法定免除される期間(いつからいつまで免除される?)
→ 法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間
★法定免除される事由
→ 障害基礎年金等の受給権者、生活保護法の生活扶助を受ける人、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
★法定免除事由に該当しても保険料の納付は可能
→ 被保険者等から、保険料を納付する旨の申出があったとき
★法定免除事由に該当したときの届出
→ 14日以内
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
YouTubeでお話ししています。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-056 10.20
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年10月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月13日から19日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
【国民年金法】老齢基礎年金の繰下げについてお話しします
【健康保険法】 任意継続被保険者の資格喪失
【健康保険法】療養の給付に含まれないもの
【国民年金法】老齢基礎年金の繰下げの申し出ができない者
【国民年金法】老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせ
【国民年金法】障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
YouTubeでお話ししています。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-055 10.19
<令和6年度国年>障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害の状態が変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。
今日は、職権で改定される場合と、受給権者からの請求によって改定される場合をみていきます。
障害の程度が変わった場合の額の改定について条文を読んでみましょう。
法第34条第1項~3項 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は①の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
①は厚生労働大臣の職権による改定です。
②は、障害の程度が増進した場合(重くなった場合)の受給権者からの改定請求です。「障害基礎年金の受給権を取得した日」又は「厚生労働大臣の診査を受けた日」から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を経過しなくても行うことができます。
では令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-B】
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】
【R6年問6-B】 ×
「1年6か月」ではなく「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して 「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を経過しなくても行うことができます。
②【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、「心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」状態に至った場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合」に該当し、1年を経過しなくても額の改定請求を行うことができます。
(法第34条第3項、則第33条の2の2第1項第9号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-054 10.18
<令和6年度国年>老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせ【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
★ 年金は1人1年金が原則です。
例えば、「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」の受給権がある場合は、両方を一緒に受けることはできません。どちらかを選択して受給します。
その際、遺族基礎年金を受給することを選択した場合は、障害基礎年金は支給停止となります。
逆に、障害基礎年金を受給することを選択した場合は、遺族基礎年金は支給停止となります。
★ 同じ理由で支給される基礎年金と厚生年金は併給できます。
老齢厚生年金
|
|
障害厚生年金 |
|
遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
|
|
障害基礎年金 |
|
遺族基礎年金 |
★ 65歳以上の場合は、以下の組み合わせを選択することができます。
遺族厚生年金
|
|
老齢厚生年金 |
|
遺族厚生年金 |
|
老齢基礎年金
|
|
障害基礎年金 |
|
障害基礎年金 |
|
さっそく、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-ア】
65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。

【解答】
【R6年問7-ア】 〇
65歳以上の場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できますが、65歳未満は併給できません。
そのため、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金は65歳まで支給停止されます。65歳以降は、繰り上げて減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。
60歳 65歳
遺族厚生年金 | 支給停止 | 遺族厚生年金 |
| 老齢基礎年金繰り上げ | |
(法第20条、法附則第9条の2の4)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、「他方の年金の受給権は消滅する」ではなく、「他方の年金は支給停止」されます。
例えば、障害基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金は支給停止となります。老齢基礎年金の受給権は消滅するのではなく、「支給停止」ですので、いつでも老齢基礎年金に選択替えをすることができます。
(法第20条)
②【H30年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

【解答】
②【H30年出題】 〇
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されませんが、65歳以降は併給できます。
(法第20条、法附則第9条の2の4)
③【R5年出題】
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
65歳以上の場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
(法第20条、法附則第9条の2の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-053 10.17
<令和6年度国年>老齢基礎年金の繰下げの申し出ができない者【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
老齢基礎年金の繰下げの条件について条文を読んでみましょう。
第28条第1項(支給の繰下げ) ① 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 |
★老齢基礎年金の繰下げの申し出の条件は、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していないことです。
ただし、①「65歳」に達したときに、「他の年金たる給付」の受給権者であった、②65歳に達した日から66歳に達した日までの間に「他の年金たる給付」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。
「他の年金たる給付」とは、「他の年金給付(付加年金を除く。)」又は「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」のことをいいます。
「他の年金給付(付加年金を除く。)」とは、国民年金の障害基礎年金と遺族基礎年金のこと、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」とは、障害厚生年金と遺族厚生年金です。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-B】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

【解答】
【R6年問9-B】 ×
問題文の場合は、支給繰下げの申し出はできません。
「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき」は繰下げの申し出はできません。
実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合でも、遺族厚生年金の受給権者です。そのため、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。
(法第28条第1項)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を有していても、老齢基礎年金の支給繰下げをすることは可能です。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げる必要はありませんので、問題文のように、老齢基礎年金のみ繰り下げることもできます。
(法第28条第1項)
②【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
②【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。
(法第28条第1項)
③【H24年出題】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

【解答】
③【H24年出題】 ×
「寡婦年金」は他の年金たる給付の中には入りませんので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-052 10.16
<令和6年度健保>療養の給付に含まれないもの【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
「療養の給付」について条文を読んでみましょう。
第63条第1項、第2項 ① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 (1) 診察 (2) 薬剤又は治療材料の支給 (3) 処置、手術その他の治療 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ② 次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。 (1) 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) (2) 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) イ 食事の提供である療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 (3) 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) (4) 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) (5) 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問4-A】
入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。

【解答】
【R6年問4-A】 〇
・入院時の食事の提供に係る費用→「入院時食事療養費」
・特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用→「入院時生活療養費」
・評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用→「保険外併用療養費」
の対象となります。
単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはなりません。
(S27.9.29保発第56号)
医師の手当を必要とする異常分娩は療養の給付の対象ですが、正常分娩は療養の給付の対象になりません。
(S17.2.27社発第206号)
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
入院療養と併せて行う食事の提供は、療養の給付には含まれません。「入院時食事療養費」の対象になります。
(法第63条第2項第1号)
②【H28年出題】(改正による修正あり)
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

【解答】
②【H28年出題】 〇
患者申出療養は、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。
(法第63条第2項第4号、法第86条)
③【H28年出題】
定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
健康診断は療養の給付の対象になりませんが、精密検査は療養の給付の対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-051 10.15
<令和6年度健保>任意継続被保険者の資格喪失【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
任意継続被保険者の資格喪失について条文を読んでみましょう。
第38条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(④から⑥までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 ① 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 ② 死亡したとき。 ③ 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 ④ 被保険者となったとき。 ⑤ 船員保険の被保険者となったとき。 ⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 ⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問1-B】
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【R6年問1-B】 ×
「その申し出た日」ではなく、「その申出が受理された日」の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
(法第38条第7号)
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前で、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することになります。
(令和3年12月27日事務連絡)
②【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

【解答】
②【H27年出題】 ×
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、「納付期日の翌日」にその資格を喪失します。納付期日はその月の10日ですので、翌日の11日に資格を喪失します。
(法第38条第3号)
ちなみに、初めて納付すべき保険料を納付しなかったときは、「任意継続被保険者とならなかったものとみなす」とされています。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りではありません。
(法第37条第2項)
③【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

【解答】
③【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日ではありません。
(法第38条第6号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<社労士国民年金>老齢基礎年金の繰下げ
R7-050 10.14
老齢基礎年金の繰下げについてお話しします【社労士受験対策】
老齢基礎年金の繰下げについてYouTubeでお話ししています。
内容は以下の通りです。
・老齢基礎年金の繰下げの申し出ができる人の要件
・66歳後に他の年金給付の受給権を取得した場合
・繰下げ加算率
・特例的な繰下げみなし増額制度
YouTubeでご覧ください。
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です。
R7-049 10.13
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和6年10月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和6年10月7日から12日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
【厚生年金保険法】 在職老齢年金の基本をお話しします
【厚生年金保険法】 特別支給の老齢厚生年金長期加入者の特例
【労働基準法】就業規則等に関する問題
【労働安全衛生法】第88条の計画の届出
【労災保険法】遺族補償年金の受給権の消滅
【労働保険徴収法】保険関係の成立と消滅など
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(徴収法)
R7-048 10.12
<令和6年出題徴収>保険関係の成立と消滅など【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問8-A(雇用)】
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当する日に至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

【解答】
①【R6年問8-A(雇用)】 ×
労災保険・雇用保険の保険関係は、「その事業が開始された日」に、事業主の意思に関係なく強行的に成立します。
また、雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が、雇用保険法の適用事業に該当するに至った場合は、「その該当する日」に保険関係が強行的に成立します。
なお、保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければなりません。
「保険関係成立届」を提出することによって保険関係が成立するのではありません。
(法第3条、4条の2、法附則第3条)
②【R6年問8-B(雇用)】
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続きを一元的に処理する事業として定められている。

【解答】
②【R6年問8-B(雇用)】 ×
「都道府県及び市町村の行う事業」、「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、「二元適用事業」ですので、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係は、別個の事業とみなして徴収法を適用します。
ちなみに、「国の行う事業」は、二元適用事業とされていません。国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立しないからです。
(法第39条、則第70条)
③【R6年問8-C(雇用)】
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
③【R6年問8-C(雇用)】 〇
「名称、所在地等変更届」の問題です。
名称、所在地等に変更があったときは、変更を生じた日の「翌日から起算」して「10日以内」に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
(法第4条の2第2項、則第5条)
④【R6年問8-D(雇用)】
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

【解答】
④【R6年問8-D(雇用)】 ×
雇用保険暫定任意適用事業については、任意に保険関係を消滅させることができます。その場合は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要です。
保険関係の消滅の申請をした場合、「厚生労働大臣の認可があった日の翌日」に、その事業についての当該保険関係が消滅します。「厚生労働大臣の認可があった日」ではありません。
(法附則第4条第2項)
⑤【R6年問8-E(雇用)】
雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

【解答】
⑤【R6年問8-E(雇用)】 ×
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、「その翌日」に消滅します。
(法第5条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-047 10.11
<令和6年出題労災>遺族補償年金の受給権の消滅【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
遺族補償年金の受給権の消滅について条文を読んでみましょう。
第16条の4第1項 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 |
★(6)について
夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、労働者の死亡当時、「年齢」か「障害」のどちらかの要件を満たす必要があります。
「障害要件」に該当しなくなった場合は、受給権は消滅します。
ただし、障害要件に該当しなくなっても、年齢要件を満たしていれば、受給権は消滅しません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5】
遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。
ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。
イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。
ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。

【解答】
ア 〇
遺族補償年金の受給権者が死亡したときには受給権は消滅します。
イ 〇
遺族補償年金の受給権者が婚姻をしたときには受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合でも消滅します。
ウ 〇
遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときには、受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合でも消滅します。
エ ×
遺族補償年金の受給権者である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには、受給権は原則として消滅します。
ただし、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは、18歳の年度末になっても消滅しません。
「労働者の死亡時から引き続き障害の状態にあるときは消滅しない」という要件が抜けているので誤りです。
オ ×
「エ」の問題と同じです。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅します。
②【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】
②【H28年出題】 〇
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が「直系血族又は直系姻族以外の者」の養子になったときには消滅します。自分の伯父は、直系血族でも直系姻族でもありませんので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
③【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

【解答】
③【H23年出題】 ×
兄弟姉妹が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、原則として遺族補償年金の受給権は消滅します。
ただし、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。
④【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

【解答】
④【H23年出題】 ×
労働者の死亡の当時60歳以上であった祖父母は、労働者の死亡時に年齢要件を満たしていますので、障害の状態がなくなっても遺族補償年金の受給権は消滅しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働安全衛生法)
R7-046 10.10
<令和6年出題安衛>労働安全衛生法第88条の計画の届出【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働安全衛生法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第88条第1項~3項 (計画の届出等) ① 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。 ② 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 ③ 事業者は、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。 |
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問10-A】
労働安全衛生法第88条第1項柱書は、「事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。」と定めている。

【解答】
①【R6年問10-A】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
工事の開始の日の14日前ではなく、「30日前」までに労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(法第88条第1項)
②【R6年問10-B】
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に届け出なければならない。

【解答】
②【R6年問10-B】 ×
★特に大規模な建設業の仕事の計画(厚生労働大臣への届出)
仕事の開始の日の30日前までに、都道府県労働局長ではなく「厚生労働大臣」に届け出なければなりません。
(法第88条第2項)
③【R6年問10-C】
事業者は、建設業に属する事業の仕事(重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを除く。)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

【解答】
③【R6年問10-C】 〇
★建設業等の仕事を開始しようとするときの労働基準監督署長への届出
仕事の開始の日の「14日前」までに、「労働基準監督署長」に届け出なければなりません。
(法第88条第3項)
④【R6年問10-D】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる。

【解答】
④【R6年問10-D】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
クレーンは届出が必要ですが、「つり上げ荷重が1トン未満のものは除かれる」という規定はありません。
(クレーン則第5条、第44条)
⑤【R6年問10-E】
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには動力プレス(機械プレスでフランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、圧力能力が5トン未満のものは除かれる。

【解答】
⑤【R6年問10-E】 ×
★機械等で危険又は有害な作業を必要とするもの等に係る届出
動力プレス(機械プレスでフランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)は届出が必要ですが、「圧力能力が5トン未満のものは除かれる。」という規定はありません。
(則別表第7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-045 10.9
<令和6年出題労基>就業規則等に関する問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R6年問7-A】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

【解答】
①【R6年問7-A】 ×
絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則も、他の要件を具備している限り「有効」です。ただし、そのような就業規則を作成し届け出たとしても、使用者の法第89条違反の責任は免れません。
②【R6年問7-B】
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

【解答】
②【R6年問7-B】 〇
「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」、「建設物及び設備の管理に関する事項」は、必要的記載事項ですので、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されません。
(法第95条)
③【R6年問7-C】
同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。

【解答】
③【R6年問7-C】 〇
同一事業場で、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することもできます。別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となります。それぞれが単独に同条の就業規則となるものではありません。
(H11.3.31基発168号)
④【R6年問7-D】
育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。

【解答】
④【R6年問7-D】 〇
育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれます。育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載しなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
⑤【R6年問7-E】
労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

【解答】
⑤【R6年問7-E】 〇
労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」にも法第89条は適用されます。そのため、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければなりません。
(S23.12.25基収4281号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-044 10.8
<令和6年度厚年>特別支給の老齢厚生年金長期加入者の特例【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
今日は長期加入者の特例です。
・長期加入者の特例は、特別支給の老齢厚生年金が「報酬比例部分のみ」になる年代が対象です。
例えば、昭和32年4月2日生まれの男性は、63歳から報酬比例部分が支給されます。
60歳 63歳 65歳
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
|
| 老齢基礎年金 |
「長期加入者の特例」の要件に該当すると、下の図のように定額部分が加算されます。
60歳 63歳 65歳
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
| 定額部分 | 老齢基礎年金 |
また、要件を満たせば加給年金額も加算されます。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-C】
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。

【解答】
【R6年問9-C】 ×
「在職中」は、長期加入者の特例は適用されませんので、定額部分は加算されません。
(法附則第9条の3)
★長期加入者の特例が適用される条件を確認しましょう。
・厚生年金保険の被保険者でないこと(=退職していること)
・厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
★「障害者の特例」との違い
・「障害者の特例」は、「特例の適用を請求」することが条件ですが、「長期加入者の特例」については、特例の適用を請求する必要はありません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

【解答】
①【R3年出題】 ×
長期加入者の特例の要件は「厚生年金保険の被保険者期間が44年以上」あることです。ただし、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、「44年以上」の計算は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用されます。
問題文の場合、第1号厚生年金被保険者としての4年と第2号厚生年金被保険者としての40年は合算できません。そのため長期加入者の特例の要件を満たしませんので、63歳から支給されるのは報酬比例部分のみで、定額部分は支給されません。
(法附則第9条の3、法附則第20条第2項)
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者期間30年と第2号厚生年金被保険者期間14年は合算できませんので、61歳から定額部分は支給されません。
(法附則第9条の3、法附則第20条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
在職老齢年金でよく出るところ(厚生年金保険法)
R7-043 10.7
在職老齢年金の基本をお話しします【社労士受験対策】
在職老齢年金のキーワードをおさえましょう。
・「在職老齢年金」の「在職」とは?
・総報酬月額相当額とは?
・基本月額とは?
・支給停止調整額とは?
・支給停止基準額とは?
「加給年金額」、「繰下げ加算額」、「経過的加算額」が支給停止の対象となるか、ならないかが問われるポイントです。
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
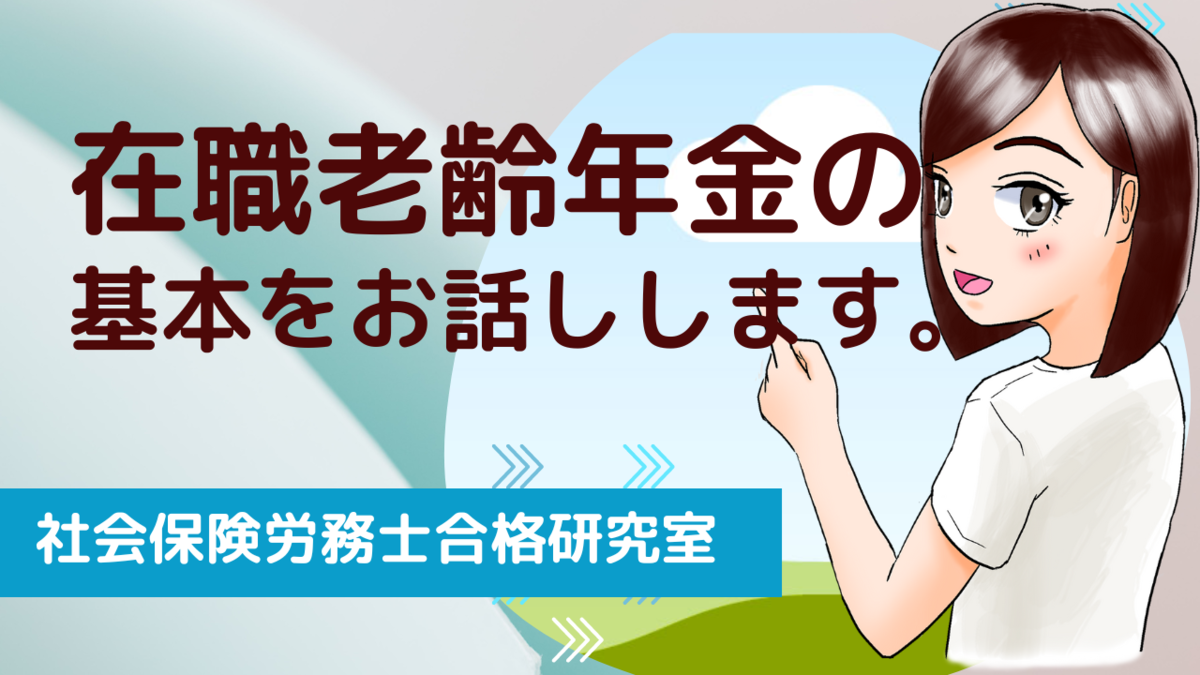
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-042 10.6
<令和6年度国年>障害基礎年金の受給権者がさらに障害基礎年金の受給権を取得した場合【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の併合について条文を読んでみましょう。
第31条 ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
年金は「一人一年金」が原則ですが、障害基礎年金の受給権が複数発生した場合の特別規定です。
障害基礎年金の受給権が複数発生した場合は、一年金を選択するのではなく、前後の障害を併合した程度の障害基礎年金が支給されます。
第32条 ① 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるためにその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-A】
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得するが、後発の障害に基づく障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために支給停止される場合は、当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される。

【解答】
【R6年問6-A】 ×
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得します。
ただし、後発の障害基礎年金が、労働基準法の障害補償を受けることができるために6年間支給停止される場合は、「その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。」となります。
(法第32条第2項)
過去問もどうぞ!
【R4年出題】
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】
【R4年出題】 ×
新たに取得した障害基礎年金が障害補償による支給停止の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し「同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金」ではなく、「従前の障害基礎年金を支給する。」です。
(法第32条第2項)
こちらの過去問もどうぞ!
【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する

【解答】
【R1年出題】 〇
前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、「従前の障害基礎年金の受給権は消滅」するのがポイントです。支給停止ではありません。
(法第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-041 10.5
<令和6年度健保>定時決定の対象月に休業手当が支払われた場合【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-D】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

【解答】
【R6年問6-D】 〇
定時決定の算定対象月(4月・5月・6月)に休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定します。
★ちなみに、休業手当等が支払われた月のみで決定するわけではありません。
例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。
ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。(次の問題で解説します)
(令和5年6月27日事務連絡)
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
【R1年出題】 〇
一時帰休の状態が解消しているかどうかは、7月1日時点で判断します。
7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要がありますので、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出します。
例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行います。
6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行います。
(令和5年6月27日事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(確定拠出年金法)
R7-040 10.4
<令和6年度社一>確定拠出年金法です【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、確定拠出年金法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問7-A】
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

【解答】
①【R6年問7-A】 〇
企業型確定拠出年金の掛金は事業主が拠出しますが、事業主掛金に加えて、加入者も掛金を拠出することができます。マッチング拠出といいます。
条文で確認しましょう。
第19条 ① 事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。 ③ 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 ④ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 |
ちなみに、企業型年金加入者掛金は、事業主掛金を超えず、かつ、事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内であることが必要です。
②【R6年問7-B】
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

【解答】
②【R6年問7-B】 〇
企業型年金加入者掛金は、「事業主を介して」資産管理機関に納付します。
条文で確認しましょう。
第21条第1項 (事業主掛金の納付) 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。
第21条の2第1項 (企業型年金加入者掛金の納付) 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
第21条の3(企業型年金加入者掛金の源泉控除) ① 企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 ② 事業主は、企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 |
③【R6年問7-C】
企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

【解答】
③【R6年問7-C】 〇
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わります。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによります。
(法第31条)
④【R6年問7-D】
個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

【解答】
④【R6年問7-D】 ×
「個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を国民年金基金連合会に届け出なければならない」とされています。
(法第66条)
⑤【R6年問7-E】
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
⑤【R6年問7-E】 〇
個人型年金加入者掛金の額は、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。
条文で確認しましょう。
第68条 (個人型年金加入者掛金) ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(最低賃金法)
R7-039 10.3
<令和6年度労一>最低賃金法の基本です【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、最低賃金法の択一式です。
まず、最低賃金法の条文を読んでみましょう。
第1条 (目的) この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第3条 (最低賃金額) 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によつて定めるものとする。
第4条第1項、第2項 (最低賃金の効力) ① 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 ② 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 |
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問4-イ】
最低賃金法第8条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。

【解答】
【R6年問4-イ】 〇
使用者は、最低賃金の概要を、労働者に周知させるための措置をとらなければなりません。
過去問をどうぞ!
①【H20年選択式】
最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となった部分は、最低賃金< B >定をしたものとみなす。

【解答】
<A> 無効
<B> と同様の
(第4条第1項)
②【H29年出題】
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。

【解答】
②【H29年出題】 ×
最低賃金額は、「時間」によって定めるものとされています。「時間又は日」ではありません。
(第3条)
③【H24年選択式】※問題文修正しています
最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、< A >ことを目的とする。」と規定している。
< B >別最低賃金は、同法によれば< B >における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の< C >を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、< D >に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

【解答】
<A> 国民経済の健全な発展に寄与する
<B> 地域
<C> 賃金支払能力
<D> 生活保護
④【R1年出題】
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

【解答】
④【R1年出題】 〇
派遣中の労働者については、「派遣先の」事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用されます。
(法第13条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
R7-038 10.2
<令和6年度徴収>労働保険料の申告について【社労士受験対策】
本日、令和6年度の合格発表でした。 合格された皆様、おめでとうございます!! また、合格の報告をくださった皆様も本当にありがとうございます。 一つ一つのメッセージを嬉しく読んでいます。
来年、初めて受験される方、再度挑戦される方。 毎日コツコツ頑張って、一歩ずつ来年の「合格」に近づいていきましょう。 |
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問10-A(雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合は同年5月10日までに提出しなければならない。

【解答】
①【R6年問10-A(雇用)】 ×
継続事業の確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内(7月10日までに)提出しなければなりません。
なお、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
継続事業の保険関係は、事業が廃止されたときは、その翌日に消滅します。
3月31日に廃止された場合は、4月1日に保険関係が消滅します。確定保険料申告書の期限は保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)ですので、5月20日までに提出しなければなりません。
(法第19条)
②【R6年問10-B(雇用)】
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
②【R6年問10-B(雇用)】 ×
3月31日に事業が終了した有期事業の保険関係は4月1日に消滅します。
有期事業の確定保険料申告書の期限は、「保険関係が消滅した日から50日以内」(当日起算)ですので、5月20日までに提出しなければなりません。
(法第19条第2項)
③【R6年問10-C(雇用)】
2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
③【R6年問10-C(雇用)】 ×
一括有期事業についての報告書は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に提出しなければなりません。確定保険料申告書を提出する際に提出します。
当該事業が継続している場合は、7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(則第34条)
④【R6年問10-D(雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。

【解答】
④【R6年問10-D(雇用)】 〇
確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが確定した賃金であれば、その保険年度間に現実に支払われていないものも含まれます。
前保険年度の3月31日に賃金締切日があり、当該保険年度の4月20日に支払う賃金も前保険年度の確定保険料を算定する際の賃金総額に含まれます。
(昭24.10.5基災収5178号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
R7-037 10.1
<令和6年度雇用>雇用保険の被保険者となるものならないもの【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問1-A】
報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者と認められる株式会社の代表取締役は被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

【解答】
①【R6年問1-A】 ×
雇用保険法は、適用事業に使用される「労働者」を被保険者とします。
代表取締役は、労働者ではないので、被保険者となりません。
(行政手引20351)
②【R6年問1-B】
適用事業の事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、当該適用事業の事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす限り被保険者となる。

【解答】
②【R6年問1-B】 〇
事業主に雇用されつつ自営業を営む者は、事業主の下での就業条件が被保険者となるべき要件を満たす場合は、被保険者となります。
(行政手引20352)
③【R6年問1-C】
労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

【解答】
③【R6年問1-C】 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。
(行政手引20352)
④【R6年問1-D】
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、組合との間に同法に基づく組合関係があることとは別に、当該組合との間に使用従属関係があり当該使用従属関係に基づく労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われている場合、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

【解答】
④【R6年問1-D】 〇
中小企業等協同組合法に基づく企業組合の組合員は、「組合との間に使用従属関係があること」、「労働の提供に対し、その対償として賃金が支払われていること」の2つの要件を満たしている場合は、被保険者となります。
(行政手引20351)
⑤【R6年問1-E】
学校教育法に規定する大学の夜間学部に在籍する者は、被保険者となるべき他の要件を満たす限り被保険者となる。

【解答】
⑤【R6年問1-E】 〇
学校教育法に規定する学校の学生又は生徒は、雇用保険法の適用は除外されます。
ただし、次に掲げる者は被保険者となります。
(1) 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
(2) 休学中の者
(3) 定時制の課程に在学する者
(4) 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(則第3条の2、行政手引20303)
大学の夜間学部等の定時制の課程の者は、雇用保険の被保険者となります。
過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
株式会社の取締役は原則として被保険者となりませんが、問題文のような場合は被保険者となります。
(行政手引20351)
②【R5年出題】
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
家事使用人は、被保険者となりません。
(行政手引20351)
③【R5年出題】
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。

【解答】
③【R5年出題】 〇
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者になりません。ただし、問題文のような場合は、被保険者となります。
(行政手引20351)
④【R5年出題】
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、被保険者となりません。
(行政手引20352)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族厚生年金は夫と妻で内容が異なります
R7-036 9.30
遺族厚生年金夫と妻の違い【社労士受験対策】
遺族厚生年金の夫と妻の違いについてお話します。
①受給権の発生要件 夫は55歳以上であること
②30歳未満で子のない妻
③中高齢寡婦加算
④夫の遺族基礎年金と遺族厚生年金
YouTubeでお話しています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-035 9.29
<令和6年度労基>第16条賠償予定の禁止からの問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
第16条の条文を読んでみましょう。
第16条 (賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |
ポイント!
「契約をしてはならない」となっていますので、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結しただけで16条違反になります。違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときではありません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-C】
使用者が労働者に対して損賠賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは、労働基準法第16条が禁止するところではないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条に抵触するものではない。

【解答】
【R6年問3-C】 〇
第16条は、「金額を予定すること」を禁止しています。現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。
債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条には抵触しません。
(昭22.9.13発基第17号)
過去問もどうぞ!
【R4年出題】
労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

【解答】
【R4年出題】 ×
違約金などを現実に徴収した時ではなく、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結しただけで、違反が成立します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-034 9.28
<令和6年度労基>第3条「均等待遇」についての判例【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
まず、第3条を読んでみましょう。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
ポイント!
★第3条で禁止されている差別は、「国籍・信条・社会的身分」を理由とする差別に限定されています。「性別による差別」は第3条には含まれません。
★「有利」に取り扱うことも差別的取扱いに当たります。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問1-B】
「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R6年問1-B】 ×
判例のポイント!
・ 企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
・ 労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。
問題文の場合、「特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めること」も、当然に違法とすることはできません。
ちなみに、雇入れた後は、雇入れの場合のような広い範囲の自由はありません。
「労働基準法3条は、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するもの」とされています。
(大法廷判決 昭48.12.12三菱樹脂事件)
過去問もどうぞ!
【H28年出題】
労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H28年出題】 〇
労働基準法第3条は、「雇入れそのものを制限する規定ではない」とされています。
(大法廷判決 昭48.12.12三菱樹脂事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-033 9.27
<令和6年度厚年>在職老齢年金の加給年金額【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
在職老齢年金の加給年金額のポイント!
★老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合
→ 基本月額は加給年金額を除いて計算します。
★在職老齢年金によって、老齢厚生年金が一部支給停止(=一部支給)される場合
→ 加給年金額は全額支給されます。
★在職老齢年金によって、老齢厚生年金が全額支給停止される場合
→ 加給年金額も全額支給停止されます。
(法第46条第1項)
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問8-C】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。

【解答】
【R6年問8-C】 ×
在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合(=老齢厚生年金の一部が支給される場合)は、加給年金額は支給されます。
在職老齢年金の仕組みで、老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も支給停止されます。
(法第46条)
過去問をどうぞ!
【R3年出題】
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

【解答】
【R3年出題】 ×
総報酬月額相当額の定義は、問題文の通りです。
基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを除く。)を12で除して得た額のことです。
(法第46条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-032 9.26
<令和6年度厚年>同月得喪の場合の被保険者期間【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
「被保険者期間」の計算について条文を読んでみましょう。
法第19条第1項、第2項 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 |
ポイント!
★被保険者期間は「月単位」で計算します。
(例1)令和6年2月21日入社・同年9月25日退職(26日喪失)の場合
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
取得 |
|
|
|
|
|
| 喪失 |
・被保険者の資格を取得した月(2月)からその資格を喪失した月(9月)の前月まで
・被保険者期間→ 2月から8月まで
(例2)令和6年2月21日入社・同年9月30日退職の場合
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
取得 |
|
|
|
|
|
|
| 喪失 |
・9月30日退職の場合、10月1日が資格喪失日です。
・被保険者の資格を取得した月(2月)からその資格を喪失した月(10月)の前月まで
・被保険者期間→ 2月から9月まで
(例3)令和6年10月3日入社・同月20日退職、その月にさらに厚生年金保険・国民年金の被保険者の資格を取得していない場合
10月 |
取得 喪失 |
・資格を取得した月に資格を喪失した場合
・被保険者期間 → 1か月
(例4)令和6年10月3日入社・同月20日退職、その月にさらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合
10月 |
取得 喪失 |
・被保険者期間に算入しない
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-D】
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

【解答】
【R6年問3-D】 ×
厚生年金保険の資格を取得した月に資格を喪失した場合は、1か月として、厚生年金保険の被保険者期間に算入されるのが原則です。
ただし、その月にさらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合は、その月は、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
問題文は、「同年5月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入しない。」となります。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の「資格を取得した月」からその「資格を喪失した月の前月」までを算入します。
②【R2年出題】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
「厚生年金保険の保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」とされています。
・ 被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば、厚生年金保険の保険料は徴収されます。例えば、9月30日に資格取得した場合でも、9月分の保険料は徴収されます。
・ 資格を喪失した月については、保険料は徴収されません。月末日で退職したときは、翌月1日が資格喪失日になりますので、「退職した日が属する月」の保険料は徴収されます。
・ 先ほどの(例2)をみてみましょう。
令和6年2月21日入社・同年9月30日退職の場合
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
取得 |
|
|
|
|
|
|
| 喪失 |
・ 9月30日退職の場合、10月1日が資格喪失日です。被保険者期間に算入されるのは、 2月から9月までですので、9月分(退職した日が属する月)の保険料が徴収されます。
(法第81条第2項)
③【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
③【H30年出題】 〇
平成29年10月1日に資格取得・平成30年3月30日に資格喪失の場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間です。
資格を喪失した月(平成30年3月)は、被保険者期間には算入されません。
④【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
平成28年3月について
1日資格取得・20日付け退職・21日に資格喪失、さらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得
→ 平成28年3月は、厚生年金保険の被保険者期間に算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-031 9.25
<令和6年度厚年>2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金額【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
老齢厚生年金に加算される加給年金額については、被保険者期間が20年(240月)以上ある者で、一定の条件を満たす配偶者や子を有する場合に、加算されます。
令和6年問2の問題を解いてみましょう。
【R6年問2-A】
甲は第1号厚生年金被保険者期間を140か月有していたが、後に第2号厚生年金被保険者期間を150か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

【解答】
【R6年問2-A】 ×
加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間が240月以上あることが条件です。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算して240月になれば、要件を満たします。
甲は第1号厚生年金被保険者期間140か月+第2号厚生年金被保険者期間150か月=
290か月ですので、加給年金額が加算される要件を満たします。
なお、加給年金額は、一の年金に加算されることになり、優先順位が決まっています。
① 一の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの
↓
② 最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、最も長い一の期間に基づく老齢厚生年金
↓
③ 最も長い一の期間が2以上ある場合は、次の順序
第1号厚生年金被保険者期間
↓
第2号厚生年金被保険者期間
↓
第3号厚生年金被保険者期間
↓
第4号厚生年金被保険者期間
甲の場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生しています。
そのため、加給年金額は、「最も長い一の期間」に基づく老齢厚生年金に加算されます。「第1号」厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ではなく、長い方の「第2号厚生年金被保険者期間に基づく」老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、令3条の13)
過去問をどうぞ!
①【H28年問5-C】
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【解答】
①【H28年問5-C】 〇
第1号厚生年金被保険者期間170か月+第2号厚生年金被保険者期間130か月=300か月で、加給年金額が加算される要件を満たします。
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を同じ日に取得していますので、期間が長い方の「第1号厚生年金被保険者期間」に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、令3条の13)
②【H30年問4-エ】
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

【解答】
②【H30年問4-エ】 ×
2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なっている場合は、「遅い日」ではなく「最も早い日」に受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができます。
(法第78条の27、令3条の13)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-030 9.24
<令和6年度厚年>2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
例えば、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する場合、老齢厚生年金の額は、それぞれの被保険者期間ごとに区分して計算します。
条文を読んでみましょう。
法第78条の26第2項 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、 第43条の規定(老齢厚生年金の年金額)を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であった全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であった期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。 |
例えば、第2号厚生年金被保険者期間を30年、第1号厚生年金被保険者期間を10年有する場合の老齢厚生年金の支給を図でイメージしましょう。
第2号 30年 | 第1号 10年 |
国家公務員共済組合が支給 | 厚生労働大臣が支給 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-B】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。

【解答】
【R6年問9-B】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、第1号厚生年被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用して、平均標準報酬額を算出し計算します。
(第78条の26第2項)
過去問もどうぞ!
【H29年問9】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

【解答】
【H29年問9】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を「合算」するのではなく、各号の厚生年金被保険者期間ごとに、平均標準報酬額を算出します。
(法第78条の26第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-029 9.23
<令和6年度国年>国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【社労士受験対策】
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について
令和6年に4肢出題されました。
①免除される期間
②保険料免除に関する届出
③付加保険料の納付
④保険料納付済期間
問題を解きながら要点をチェックしましょう!
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
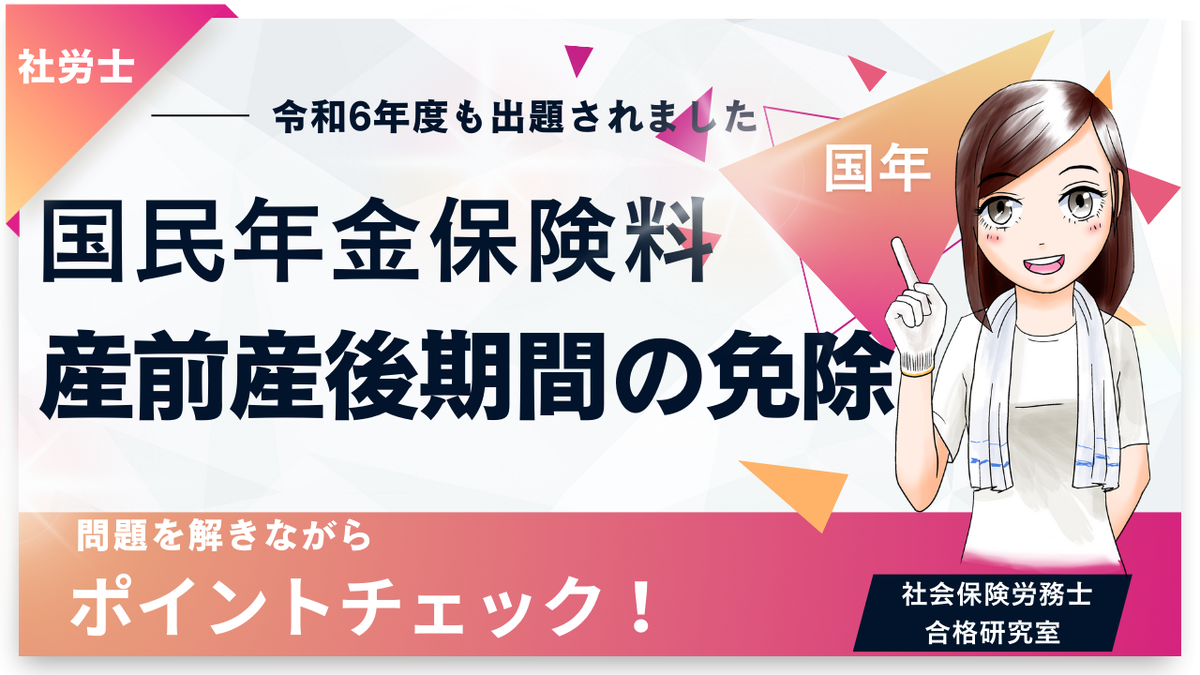
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-028 9.22
<令和6年度国年>事例問題・特例による任意加入被保険者【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
【R6年出題問9】
甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

【解答】
【R6年出題問9】 ×
甲の年金加入歴を図で確認しましょう。
20歳 | 23歳 | 30歳 | 45歳 60歳 | 65歳 |
3年間 | 7年間 | 15年間 | 20年間 | |
未加入 | 厚年被保険者 | 第3号被保険者 | 厚年被保険者(第2号) | |
カラ期間 | 保険料納付済期間 | カラ期間 | ||
★老齢基礎年金の額は以下のよう計算します。
・ 保険料納付済期間=7年+15年+15年(45歳~59歳)=37年
・ 合算対象期間=3年間(任意加入しなかった期間)+5年間(60歳~64歳)
=8年
老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×444月/480月
★甲は「65歳」ですので、任意加入するとすれば、特例による任意加入となります。
特例による任意加入の条件を確認しましょう。
H16法附則第23条第1項 昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するも(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
特例による任意加入は、65歳になっても、老齢基礎年金の受給権がない者が対象です。
甲は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有しますので、特例による任意加入はできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-027 9.21
<令和6年度健保>任意継続被保険者・特例退職被保険者の標準報酬月額【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問1】
健康保険組合において、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる。

【解答】
①【R6年問1】 〇
「任意継続被保険者」の標準報酬月額について、条文を読んでみましょう。
第47条 (任意継続被保険者の標準報酬月額) ① 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 (1) 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
② 保険者が健康保険組合である場合においては、(1)に掲げる額が(2)に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、(1)に掲げる額(当該健康保険組合が(2)に掲げる額を超え(1)に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。 |
問題文は、第47条第2項からの出題です。
(法第47条第2項)
②【R6年問3】
特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から同法第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。

②【R6年問3】 ×
当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における「特例退職被保険者以外の全被保険者」の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額、となります。
(法附則第3条第4項)
こちらの過去問もどうぞ!
【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、原則として、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
<選択肢>
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
③ 9月30日における健康保険の
④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

【解答】
<A> ④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(法第47条第1項)
こちらの練習問題もどうぞ!
(練習問題)
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< B >同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
<選択肢>
① 3月31日における特例退職被保険者以外の全被保険者の
② 3月31日における特例退職被保険者を含む全被保険者の
③ 9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の
④ 9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の

【解答】
<B> ④ 9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の
(法附則第3条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
R7-026 9.20
<令和6年度徴収法>雇用保険印紙からの問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、徴収法の択一式です。
★事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど、その者に係る印紙保険料を納付しなければなりません。
★印紙保険料の納付について条文で確認しましょう。
法第23条第2項、第3項 ② 印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。 ③ 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。 |
では、令和6年問9(雇用)の印紙保険料の問題をどうぞ!
①【R6年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

①【R6年出題】(雇用) 〇
★ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければなりません。
★ 「雇用保険印紙購入通帳」は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有します。
★ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければなりません。
★ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間(毎年3月1日から3月31日までの間)に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
★ 有効期間の更新を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度(更新を受けた日の翌保険年度)に限り、その効力を有します。
(則第42条)
②【R6年出題】(雇用)
事業主は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

【解答】
②【R6年出題】(雇用) 〇
★ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければなりません。
★ 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合で、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければなりません。
(則第42条、第43条)
③【R6年出題】(雇用)
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

【解答】
③【R6年出題】(雇用) 〇
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければなりません。
(則第42条第8項)
④【R6年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

【解答】
④【R6年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合は、「印紙保険料納付状況報告書」と併せて「印紙保険料納付計器使用状況報告書」を提出しなければなりません。
ちなみに、
・ 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
・ 印紙保険料納付計器を設置した事業主は、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
(則第54条、第55条)
⑤【R6年出題】(雇用)
事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。

【解答】
⑤【R6年出題】(雇用) 〇
印紙保険料納付計器を使用しなくなった場合の問題です。
(則第52条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(雇用保険法)
R7-025 9.19
<令和6年度雇用>傷病手当でよく出る問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の択一式です。
令和6年問3の「傷病手当」の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定(以下本問において「傷病の認定」という。)を受けた場合、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、傷病手当を支給しない。

【解答】
①【R6年出題】〇
★傷病手当の要件を確認しましょう。
(イ) 受給資格者であること。
(ロ) 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること 。
(ハ) 疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること。
(ニ) (ハ)の状態が (ロ )の後において生じたものであること 。
この問題のポイント!
・ 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後に、 疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給されます。
・ 待期中の日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002、53003)
②【R6年出題】
傷病手当を支給する日数は、傷病の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数に相当する日数分を限度とする。

【解答】
②【R6年出題】 〇
傷病手当を支給し得る日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
(行政手引53004)
③【R6年出題】
基本手当の支給を受ける口座振込受給資格者が当該受給期間中に疾病又は負傷により職業に就くことができなくなった場合、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、当該受給資格者は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までに傷病の認定を受けなければならない。

【解答】
③【R6年出題】 〇
傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までですが、口座振込受給資格者の場合は、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日の直前の失業の認定日までです。
(行政手引53006)
④【R6年出題】
健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が傷病の認定を受けた場合、傷病手当を支給する。

【解答】
④【R6年出題】 ×
健康保険法の傷病手当金の支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
⑤【R6年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
傷病手当の日額は、基本手当の日額と同じです。
(行政手引53005)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-024 9.18
<令和6年度労災>支給制限、受給権の保護、不正受給者からの費用徴収など【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
では、令和6年問7の問題をどうぞ!
① 【R6年出題】
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
① 【R6年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第12条の2の2第2項 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
「故意」の場合の条文と比較しましょう。
法第12条の2の2第1項 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 |
「全部又は一部を行わないことができる」と「行わない」の違いを意識してください。
②【R6年出題】
労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第16条の9第1項 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 |
「重大な過失」により死亡させた場合の給付制限はありません。
③【R6年出題】
労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。

【解答】
③【R6年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第14条の2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。 (1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 (2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(休業補償給付を行わない場合) 則第12条の4 法第14条の2の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 (1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 (2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合 |
④【R6年出題】
労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。

【解答】
④【R6年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 |
労働者が退職しても、保険給付を受ける権利は消滅しません。
⑤【R6年出題】
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第12条の3 ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 |
※事業主からではなく、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者」から徴収します。
条文の続きです。
| ② 事業主(徴収法第8条第2項又は第3項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-023 9.17
<令和6年度労基法>労働契約の問題を解いてみます
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問3】
使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

【解答】
①【R6年問3】〇
雇止めの予告の問題です。対象になる有期労働契約 (当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)に注意してください。
(有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準 H15.10.222厚生労働省告示第357号)
②【R6年出題】
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 〇
令和6年4月の改正で、労働条件の明示事項として、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」が加わりました。
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を明示するタイミングは、「労働契約の締結時」と「有期労働契約の更新時」です。
また、原則として書面の交付による明示が必要です。
(則第4条第1項第1の3号、令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生労働白書が活用できる読み方
R7-022 9.16
厚生労働白書を読んで年金の勉強に役立てましょう
厚生労働白書をチェックして、年金の勉強に役立てましょう。
ポイントを意識しながら読むと、年金制度がイメージできます。
<テーマ>
・日本の公的年金制度は世代間扶養
・年金給付は国民の老後生活の基本
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大のメリット
・マクロ経済スライド
・令和6年度の年金額改定の仕組み
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

令和6年度択一式を振り返ります(厚生年金保険法)
R7-021 9.15
<令和6年度>厚生年金保険法の問題を解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年の問題を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険の択一式です。
令和6年問10の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。

【解答】
①【R6年出題】 ×
「初診日」に厚生年金保険の被保険者で、「障害認定日」に障害等級(1級~3級)に該当する障害の状態にある場合は、「障害認定日」に障害厚生年金の受給権が発生します。
初診日・障害認定日に20歳未満であっても、受給権は20歳に達したときではなく、「障害認定日」に発生します。
(法第47条)
②【R6年出題】
障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合」に、支給されます。
障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が「治った」ことが要件です。
問題文は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中」となっていますので、障害手当金は支給されません。
(法第55条)
③【R6年出題】
年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

【解答】
③【R6年出題】 〇
年金の受給権者は、受給権者の意思で年金の受給を辞退することができます。
その場合は、「受給権者の申出」により、その「全額」の支給が停止されます。「全額」辞退することが条件です。「一部」を辞退することはできません。
ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、「停止されていない部分の額」の支給が停止されます。
(法第38条の2)
④【R6年出題】
現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
甲の年金加入歴は以下のようになります。
20歳 25歳 | 55歳 |
厚生年金保険(5年) | 第1号被保険者(保険料すべて納付) |
遺族厚生年金は、死亡した者が、次の(1)~(4)のいずれかに該当することが条件です。なお、(1)、(2)は保険料納付要件が問われます。
(1) 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
(2) 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
(3) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
(4) 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
★(1)~(3)を「短期要件」、(4)を長期要件といいます。
甲は第2号被保険者期間が5年、第1号被保険者期間で保険料をすべて納付した期間が30年ありますので、(4)の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときに該当します。
(1)~(3)には該当しません。
甲は「長期要件」に該当しますので、遺族厚生年金の額を計算するときの厚生年金保険の被保険者期間は実期間の60か月となります。
ちなみに、遺族厚生年金の額を計算するときの厚生年金保険の被保険者期間として300月が保障されるのは「短期要件」の場合です。
(法第58条、第60条)
⑤【R6年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
脱退一時金は、「厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)」で要件を満たした者に支給されます。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金は、2以上の被保険者であった期間を合算して、支給要件を判定します。
(法附則第29条、第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(国民年金法)
R7-020 9.14
<令和6年度>国民年金法は幅広い内容の出題でした。解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年の問題を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金の択一式です。
令和6年問10の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。

【解答】
①【R6年出題】 ×
遺族基礎年金を受ける要件に、「日本国内に住所を有している」はありません。
(法第37条の2)
②【R6年出題】
第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
夫と子に発生する年金を図で確認しましょう。
夫(50歳) |
| 子(16歳) |
|
| 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金
|
| 遺族基礎年金 (支給停止) |
※夫には遺族厚生年金の受給権は発生しません。
(55歳未満のため)
夫と子の両方に遺族基礎年金の受給権が発生した場合について、条文を読んでみましょう。
第41条第2項 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 |
夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
問題文の場合は、子の遺族基礎年金は支給停止、子は遺族厚生年金のみ受給します。夫は遺族基礎年金を受給します。
(第41条第2項)
③【R6年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】
③【R6年出題】 ×
保険料半額免除期間の月数は「2分の1」、保険料4分の1免除期間は「4分の3」で計算します。
問題文にあてはめると、48月×2分の1+12月×4分の3=33月です。死亡一時金の支給要件は「36月以上あること」ですので、遺族に死亡一時金は支給されません。
(法第52条の2)
④【R6年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、「所定の要件に該当」したときに受給権が発生します。ただし、支給は「請求のあった月の翌月」からとなります。請求のあった月からではありません。
(法第30条の3)
⑤【R6年出題】
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
条文で確認しましょう。
第96条第1項~3項 ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(健康保険法)
R7-019 9.13
令和6年の健保は全体的に難しかったですが解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和6年度の健康保険法択一式は、全体的に難しかったです。
その中でも押さえておくべき問題をみていきましょう。
令和6年健康保険問2の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
被保険者の総数が常時100人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込があること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。

【解答】
①【R6年出題】 〇
100人以下の企業でも、労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意すること)がなされれば、「任意特定適用事業所」となり、要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。
※100人以下は、令和6年10月から「50人以下」となります。
(参考:短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(厚生労働省))
②【R6年出題】
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
条文で確認しましょう。
法第73条 ① 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 ② 厚生労働大臣は、指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。 |
「常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。」は誤りです。
③【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払をすることができる。

【解答】
③【R6年出題】 〇
問題文の重要用語を穴埋めでチェックしましょう。
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< A >を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、< B >。
<A> 被保険者数
<B> 概算払をすることができる
(法第151条、第152条)
④【R6年出題】
協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。

【解答】
④【R6年出題】 〇
条文で確認しましょう。
法第7条の29第1項~3項 (会計監査人の監査) ① 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 ② 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 ③ 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 |
⑤【R6年出題】
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
「日雇拠出金」の問題です。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収します。加えて、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金(日雇拠出金)を徴収します。
(法第173条第1項)
また、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(「日雇関係組合」という。)は、日雇拠出金を納付する義務を負います。
(法第173条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(社会保険に関する一般常識)
R7-018 9.12
<令和6年度社一>確定給付企業年金法の問題を解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、確定給付企業年金法の択一式です。
令和6年社会保険に関する一般常識問6の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

【解答】
①【R6年出題】 ×
基金は、分割しようとするときは、「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりませんが、基金の分割は、「実施事業所の一部について行うことはできない」とされています。
(法第77条第1項、第2項)
解き方のヒント!
健康保険法にも同じような規定があります。
健康保険法第24条第1項、2項 ① 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ② 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 |
②【R6年出題】
確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない、とされています。
(法第78条第1項)
解き方のヒント!
健康保険法にも同じような規定があります。
健康保険法第25条第1項 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
★「事業主の全部」が同じです。
③【R6年出題】
基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

【解答】
③【R6年出題】 ×
基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる、です。
(法第85条第1項)
解き方のヒント!
こちらも健康保険法に同じような規定があります。
健康保険法第26条第1項 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 (1) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 (2) 健康保険組合の事業の継続の不能 (3) 厚生労働大臣による解散の命令 |
★「4分の3以上」が同じです。
④【R6年出題】
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
「事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。」とされています。
(法第89条第3項)
⑤【R6年出題】
確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
なお、確定給付企業年金法第89条第7項では、「残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。」と規定されています。
(法第89条第6項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(労働に関する一般常識)
R7-017 9.11
<令和6年度労一>労働契約法の問題を解いてみました【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働契約法の択一式です。
令和6年労働に関する一般常識の問3の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。

【解答】
①【R6年出題】 ×
労働契約は「労働者及び使用者の合意」によって成立します。合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働」すること及び「使用者がこれに対して賃金を支払う」ことです。
労働条件を詳細に定めていなかった場合であっても、労働契約そのものは成立します。
(法第6条、H24.8.10基発0810第2号)
②【R6年出題】
労働基準法第106条に基づく就業規則の「周知」は、同法施行規則第52条の2各号に掲げる、常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法のいずれかによるべきこととされているが、労働契約法第7条柱書きの場合の就業規則の「周知」は、それらの方法に限定されるものではなく、実質的に判断される。

【解答】
②【R6年出題】 〇
まず、労働契約法第7条を読んでみましょう。
| 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、 第12条に該当する場合を除き、この限りでない。 |
労働契約法第7条の「就業規則」とは、労働者が就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称をいい、労働基準法第89条の「就業規則」と同様ですが、法第7条の「就業規則」には、常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者が作成する労働基準法第89条では作成が義務付けられていない就業規則も含まれます。
法第7条の「周知」とは、例えば、
① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
② 書面を労働者に交付すること
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
等の方法により、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいいます。このように周知させていた場合には、労働者が実際に就業規則の存在や内容を知っているか否かにかかわらず、法第7条の「周知させていた」に該当します。
なお、労働基準法第106条の「周知」は、労働基準法施行規則第52条の2により、 ①から③までのいずれかの方法によるべきこととされていますが、法第7条の「周知」は、これらの3つの方法に限定されるものではなく、実質的に判断されます。
(法第7条、H24.8.10基発0810第2号)
③【R6年出題】
労働基準法第89条及び第90条に規定する就業規則に関する手続が履行されていることは、労働契約法第10条本文の、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果を生じさせるための要件ではないため、使用者による労働基準法第89条及び第90条の遵守の状況を労働契約法第10条本文の合理性判断に際して考慮してはならない。

【解答】
③【R6年出題】 ×
労働契約法第10条は、就業規則の変更により労働契約の内容である労働条件を変更することができる場合について規定しています。また、法第11条は、労働基準法において、就業規則の変更の際に必要となる手続が規定されていることを規定しています。
★ 就業規則の変更の手続については、
① 労働基準法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、変更後の就業規則を所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこと
② 労働基準法第90条により、就業規則の変更について過半数労働組合等の意見を聴かなければならず、①の届出の際に、その意見を記した書面を添付しなければならないこと
とされていいます。
★ 労働基準法第89条及び第90条の手続が履行されていることは、法第10条本文の法的効果を生じさせるための要件ではないものの、同条本文の合理性判断に際しては、就業規則の変更に係る諸事情が総合的に考慮されることから、使用者による労働基準法第89条及び第90条の遵守の状況は、合理性判断に際して考慮され得るものとされています。
(法第10条、第11条、H24.8.10基発0810第2号)
④【R6年出題】
労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、期間の定めのある労働契約(以下本問において「有期労働契約」という。)は、試みの使用期間(試用期間)を設けることが難しく、使用者は労働者の有する能力や適性を事前に十分に把握できないことがあることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、同法第16条に定めるいわゆる解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも広いと解される。

【解答】
④【R6年出題】 ×
労働契約法第17条第1項の条文を読んでみましょう。
| 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 |
有期労働契約については、契約期間中は、「やむを得ない事由があるとき」に該当しない場合は、解雇することはできません。
「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものですが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されます。
(法第17条第1項、H24.8.10基発0810第2号)
⑤【R6年出題】
労働契約法第18条第1項によれば、労働者が、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下本肢において同じ。)の契約期間を通算した期間が5年を超えた場合には、当該使用者が、当該労働者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなすこととされている。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
労働契約法第18条第1項の条文を読んでみましょう。
| 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。 |
第18条は、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)に転換させる仕組み(「無期転換ルール」という。)を設けることにより、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇用の安定を図ることとしたものです。
無期転換ルールは、「有期契約労働者が無期転換の申込み」をした場合、無期労働契約が成立する(使用者は申込みを承諾したものとみなす=断ることができない)というものです。
問題文のように、「使用者が、当該労働者に対し、現に締結している有期労働契約が満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなす」ではありません。
(法第18条、H24.8.10基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(労働保険徴収法)
R7-016 9.10
<令和6年度徴収>請負事業の一括について質問がありましたのでお答えします。【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
まず、請負事業の一括を図でイメージしましょう。
令和6年問8(労災)の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】
①【R6年出題】 〇
請負事業の一括で、元請事業に一括されるのは、「労災保険に係る保険関係」のみです。
雇用保険は一括されませんので、雇用保険は原則どおり事業ごとに適用されます。図でイメージしてください。
②【R6年出題】)
労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係はないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。

【解答】
②【R6年出題】 〇
労働保険徴収法上、請負事業が一括されたとしても、「下請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」には労働関係があります。そのため、下請負に係る事業については、「下請負人」が事業主です。
請負事業の一括により、「元請負人のみ」が「当該事業の事業主」となります。これは、元請負人は、請負に係る事業(イメージ図では、ビル建築工事の現場)については、下請負をさせた部分を含めて、工事の全てについて「事業主」として労災保険料を納付する等の義務を負うという意味です。
請負事業の一括で元請負人が事業主とされたとしても、「元請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」に労働関係が生まれるわけではありません。
図でイメージしてください。
③【R6年出題】
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
③【R6年出題】 〇
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業の分離については、厚生労働大臣の認可が必要です。
下請負事業の分離の認可については、元請負人及び下請負人が「共同で」、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
(則第8条第1項)
④【R6年出題】
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。

【解答】
④【R6年出題】 〇
③の問題の続きです。「下請負人を事業主とする認可申請書」は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出しなければなりませんが、やむを得ない理由により、期限内に提出することができなかったときは、期限後であっても提出することができます。
(則第8条第1項)
⑤【R6年出題】
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
下請負事業の概算保険料が160万円以上、「又は」、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)です。
(則第9条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
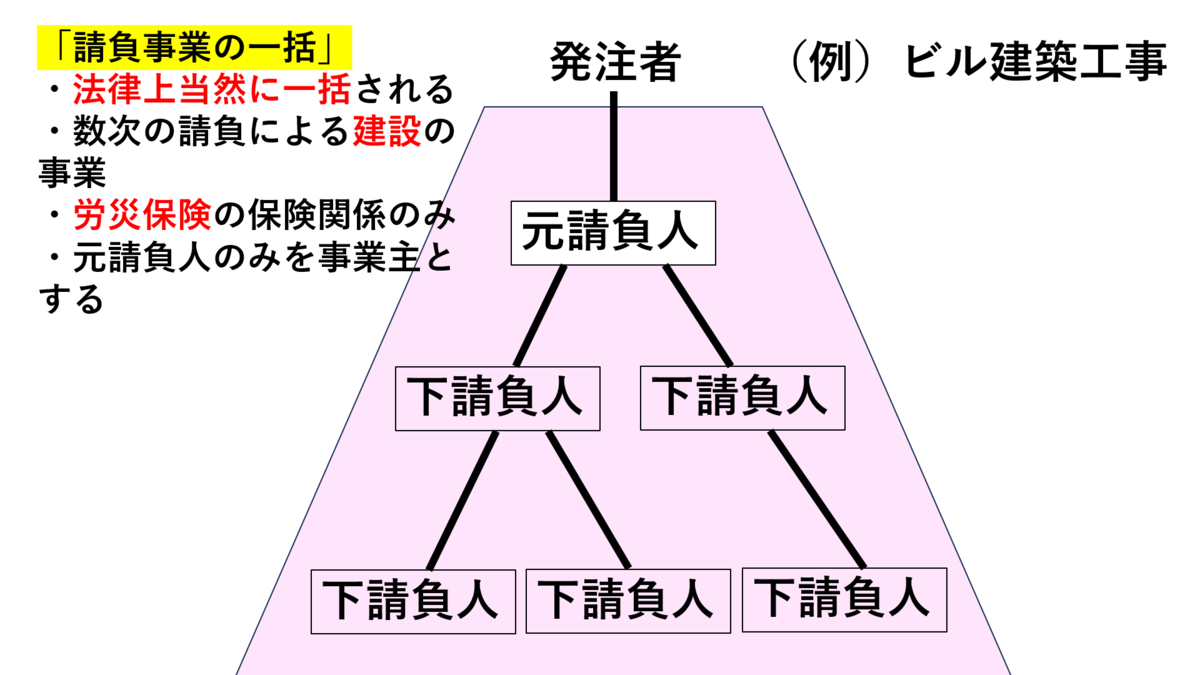
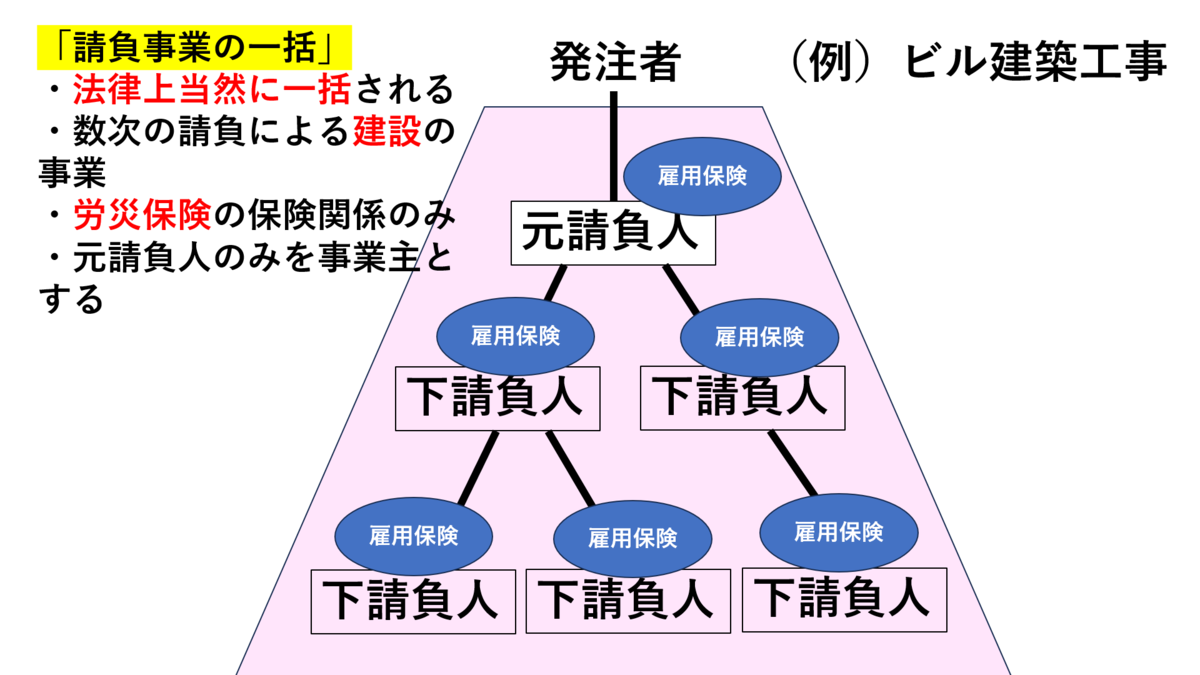
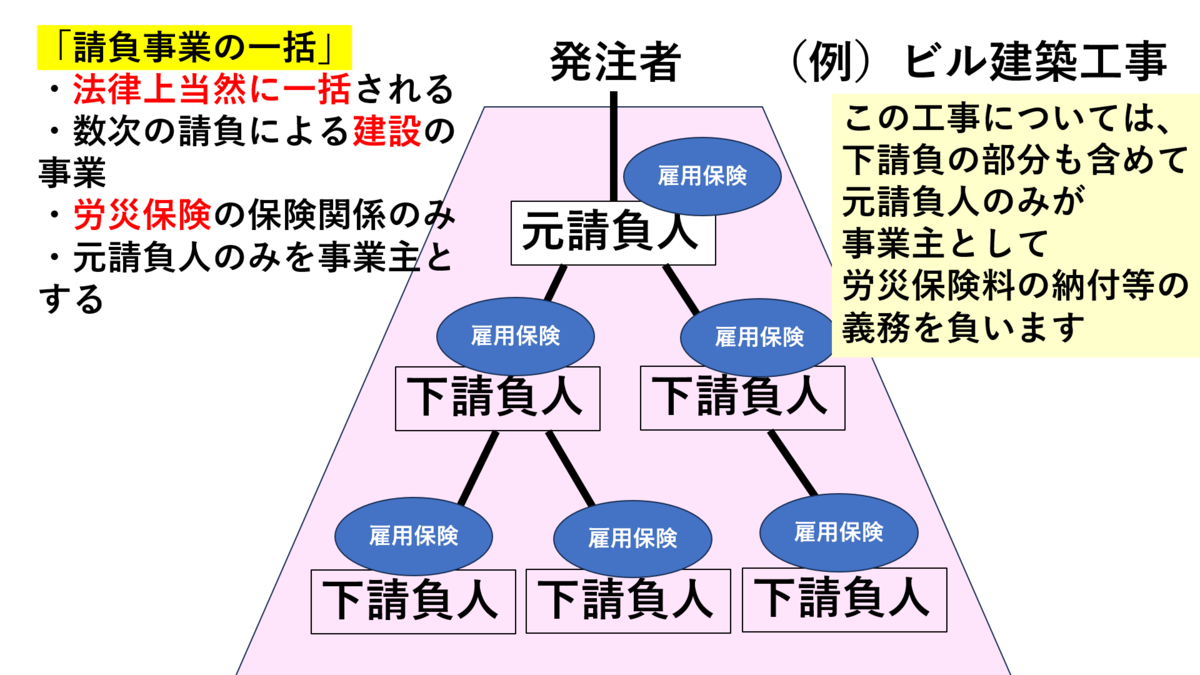
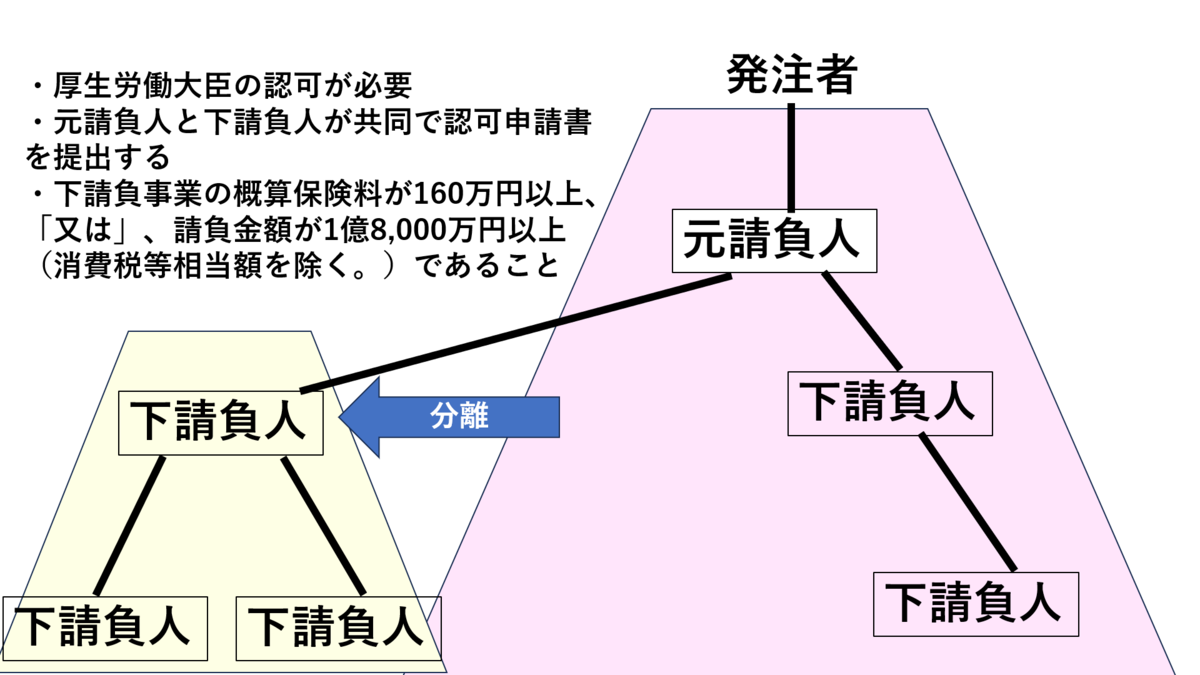
ご質問ありがとうございました
R7-015 9.9
令和6年の社労士試験を終えて勉強方法についてご質問がありましたのでお話します
勉強方法についてご質問がありましたのでお話します。
例えば、令和6年の雇用保険法は7問中5問は、
テキスト+過去問の繰り返しで解ける問題でした。
しかし、7問のうち、2問については、過去問学習では難しかったかもしれません。
具体的に雇用保険の問題を解きながらお話します。
YouTubeでお話しています。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
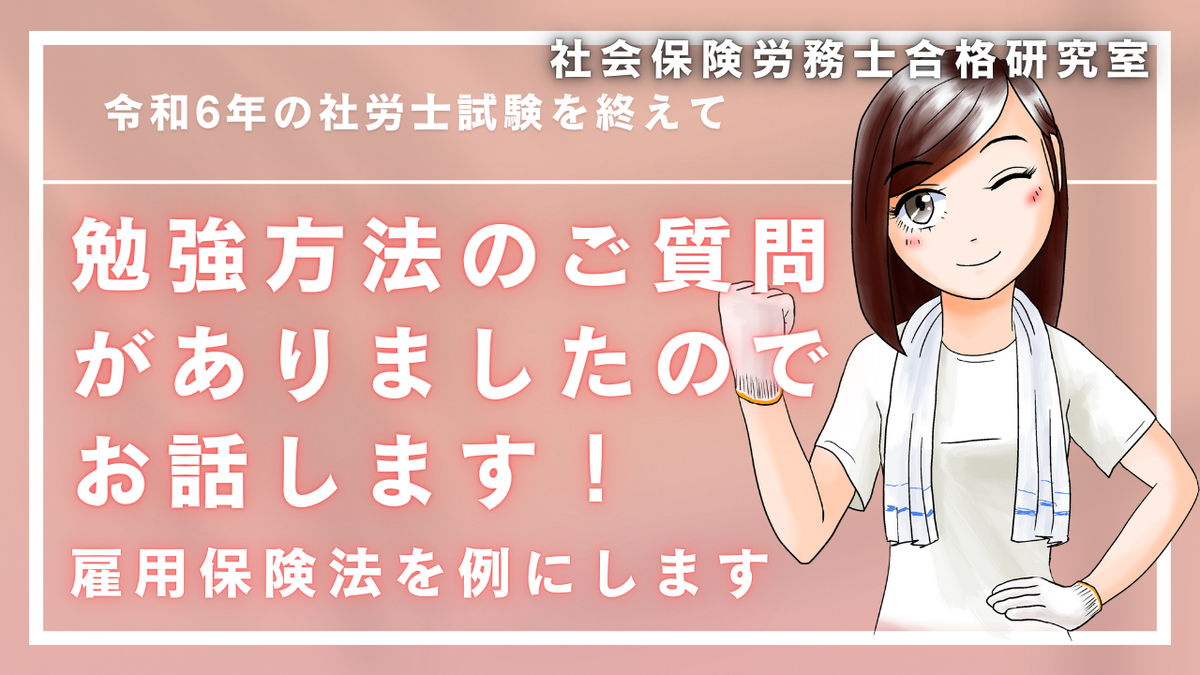
令和6年度の択一式を振り返ります(労災保険法)
R7-014 9.8
令和6年度<労災法>通勤途上の日常生活上必要な行為【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法です。
R6年労災問1の問題をどうぞ!
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
B 帰途で総菜等を購入する行為
C はり師による施術を受ける行為
D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為

【解答】
「A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、日常生活上必要な行為として、労災保険法施行規則第8条に定めるものに含まれません。
「日常生活上必要な行為」として定められている行為を確認しましょう。
則第8条(日常生活上必要な行為) 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 (1) 日用品の購入その他これに準ずる行為 (2) 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為 (4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 (5) 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |
問題文の「B 帰途で総菜等を購入する行為」は(1)に、「C はり師による施術を受ける行為」は(4)に、「D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為」は(2)に、「E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為」は(5)に該当します。
(S48.11.22基発644)
通勤途上で、逸脱・中断をしたとしても、逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、通勤と認められます。
ポイント!
ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合でも、「逸脱・中断」の間は通勤となりません。
ちなみに、「A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、「ささいな行為」となります。通常経路の途中のささいな行為は、逸脱、中断に該当しません。
他にささいな行為として、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合などがあります。
(S48.11.22基発644)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の択一式を振り返ります(労働安全衛生法)
R7-013 9.7
令和6年度<安衛法>安全衛生管理の総合問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働安全衛生法です。
R6年問8の問題をどうぞ!
次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、衛生管理者については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条)を考えないものとする。
W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。
使用する労働者数 常時30人
X市に第1工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。
・工場は1直7:00~15:00及び2直15:00~23:00の2交替で操業しており、 1グループ150人計300人の労働者が交替で就業している。
・工場には動力により駆動されるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。
Y市に第2工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。
・工場は1直7:00~15:00及び2直15:00~23:00の2交替で操業しており、1グループ40人計80人の労働者が交替で就業している。
・工場には動力により駆動されるプレス機械が5台設置され、当該機械による作業が行われている。
Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時12人(ただし、この事業場のみ、うち6人は1日4時間労働の短時間労働者)
<A>W市にある本社には、安全管理者も衛生管理者も選任する義務はない。

【解答】
<A> 〇
ポイント!
労働安全衛生法は「事業場単位」で適用されます。
管理業務を行っている本社は、労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他の業種」となります。
本社は、「その他の業種」ですので、安全管理者を選任する義務はありません。また、労働者数が常時30人ですので衛生管理者の選任義務もありません。
(法第11条、第12条、令第3項、第4条)
<B>W市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

【解答】
<B> ×
「その他の業種」で総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、常時1000人以上の労働者を使用する事業場です。
問題文の場合は、選任義務はありません。
<C>X市にある第1工場及びY市にある第2工場には、それぞれ安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならないが、X市にある第1工場には、衛生管理者を二人以上選任しなければならない。

【解答】
<C> 〇
第1工場、第2工場は、「製造業」です。
どちらも労働者数が常時50人以上ですので、安全管理者と衛生管理者の選任義務があります。
また、第1工場は、労働者数が常時300人ですので、2人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。ちなみに、第2工場は、1人以上の衛生管理者を選任しなければなりません。
(令第2条、第3条、第4条)
<D>X市にある第1工場及びY市にある第2工場には、プレス機械作業主任者を、それぞれの工場に、かつ1直2直それぞれに選任しなければならない。

【解答】
<D> 〇
「動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業」については、作業主任者を選任しなければなりません。
また、作業主任者は、「作業場所単位」で選任します。作業主任者は、労働者を直接指揮する必要があるため、作業が交替制で行われる場合は、原則として各直ごとに選任しなければなりません。
(法第14条、令第6条第7号、S48.3.19基発第145号)
<E> Z市にある営業所には、衛生推進者を選任しなければならない。

【解答】
<E> 〇
営業所は「その他の業種」です。労働者数が12人ですので、衛生推進者を選任しなければなりません。なお、労働者の人数には、短時間労働者も含みます。
(法第12条の2、則12条の2、S47.9.18基発第602号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の択一式を振り返ります(労働基準法)
R7-012 9.6
令和6年度<労基法>年次有給休暇の問題を解くポイント【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法です。
令和6年の年次有給休暇の問題をどうぞ!
①【R6年問6】
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。

【解答】
①【R6年問6】 ×
この問題のポイント!
比例付与の条件をおぼえましょう。(法第39条第3項、則第24条の3)
1週間の所定労働時間が30時間未満
かつ
1週間の所定労働日数が4日以下
※週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、
1年間の所定労働日数が216日以下
問題文は、1週間の所定労働時間は20時間ですが、1週間の所定労働日数が5日ですので、比例付与の対象になりません。
付与される年次有給休暇は、5労働日ではなく、通常の10労働日です。
②【R6年問6】
月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。
〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日 端数を切り捨てて7日

【解答 】
②【R6年問6】 ×
①の問題と同様に、比例付与の条件がポイントです。
問題文は、1週間の所定労働日数は4日ですが、1週間の所定労働時間が32時間ですので、比例付与の対象になりません。
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
③【R6年問6】
令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。

【解答】
③【R6年問6】 ×
この問題のポイント!
年次有給休暇の使用者の時季指定義務について
法定の基準日より前に、有給休暇を付与する場合の扱いについての問題です。
有給休暇の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないのが原則です。
しかし、基準日より前に10労働日以上の有給休暇を与えることとした場合は、「10労働日以上の有給休暇を与えることとした日から1年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければなりません。
令和6.4.1(入社) |
| 令和6.10.1 |
| 令和7.3.31 |
10日付与 |
| 法定の基準日 |
|
|
原則は、5日については、令和6年10月1日から1年以内(令和7年9月30日)までに、時季を定めることにより与えなければなりません。
ただし、前倒しで令和6年4月1日の入社日に付与した場合は、その日から1年以内(令和7年3月31日まで)に取得させることになります。
(法第37条第7項、則第24条の5第1項)
④【R6年問6】
使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、労働基準法第39条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、労働基準法第39条第8項の「日数」には含まれないとされている。

【解答】
④【R6年問6】 〇
この問題のポイント!
年次有給休暇の使用者の時季指定義務について
労働者自ら取得した半日年休・時間単位年休の取扱い
労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、0.5日として法第39条第8項の「日数」に含まれますので、当該日数分について使用者は時季指定を要しません。
また、労働者が時間単位で年次有給休暇を取得した日数分については、法第39条第8項の「日数」には含まれません。
(H30.12.28基発1228第15号)
⑤【R6年問6】
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、労働基準法第39条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。

【解答】
⑤【R6年問6】 ×
この問題のポイント!
出勤率の算定で、「出勤したものとみなす」期間
産前産後の女性が休業した期間は、「出勤したものとみなす」期間です。
一方、生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間は、労働基準法上出勤したものとはみなされません。
(法第39条第10項、S23.7.31基収2675)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(厚生年金保険法)
R7-011 9.5
令和6年度<厚年選択式>国庫負担・標準賞与額・受給権の保護・遺族厚生年金・障害厚生年金【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する< A >を負担するものとされている。
<選択肢>
「費用」、「費用の2分の1」、「費用の3分の1」、「費用の4分の3」

【解答】
<A> 費用
(第80条)
ポイント!
「事務の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用」は、国庫が負担します。
国庫負担の過去問をどうぞ!
【H29年出題】
厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する< F >に相当する額を負担する。
<選択肢>
「基礎年金拠出金の額の2分の1」、「基礎年金拠出金の額の3分の1」
「事務の執行に要する費用の2分の1」、「保険給付費の2分の1」

【解答】
<F> 基礎年金拠出金の額の2分の1
★厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「基礎年金拠出金の額の2分の1」は、国庫が負担します。
(法第80条第1項)
令和6年 選択問題2
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が< B >(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額。)を超えるときは、これを< B >とする。
<選択肢>
「100万円」、「150万円」、「200万円」、「250万円」

【解答】
<B> 150万円
(法第24条の4)
「標準賞与額」は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額で、上限は1か月当たり150万円です。
令和6年 選択問題3
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、< C >を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
<選択肢>
「遺族厚生年金」、「障害厚生年金」、「障害手当金」、「脱退一時金」

【解答】
<C> 脱退一時金
ポイント!
法第41条第1項では、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」となっています。
例外的に、老齢厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえの対象となります。
しかし、選択肢には「老齢厚生年金」がありません。
★附則によって、老齢厚生年金は脱退一時金と読み替えられます
法附則第29条第9項、令第14条で、「老齢厚生年金」を「脱退一時金」と読み替えるとされています。当てはめると、「ただし、脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」となります。
令和6年 選択問題4
厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により< D >を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
<選択肢>
「当該初診日から起算して3年」、「当該初診日から起算して5年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して3年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して5年」

【解答】
<D> 当該初診日から起算して5年
ポイント!
厚生年金保険の被保険者の資格喪失後(会社を退職した後)に死亡した場合でも、被保険者であった間(在職中)に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したきとは、遺族厚生年金の要件を満たします。(保険料納付要件が問われます。)
在職中(厚生年金保険の被保険者) | 退職 |
| |
▲ 初診日 |
| ▲ 死亡 | |
| 5年を経過する日前 | ||
令和6年 選択問題5
甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、< E >。
<選択肢>
「甲のみが行うことができる」
「甲も乙も行うことができない」
「甲も乙も行うことができる」
「乙のみが行うことができる」

【解答】
<E> 乙のみが行うことができる
(法第52条第7項)
解くときのチェックポイント!
・年齢
甲も乙も65歳以上(66歳)
・障害基礎年金の受給権の有無
甲は障害基礎年金の受給権を「有しない」
乙は障害基礎年金の受給権を「有する」
では、問題のポイントを図でイメージしましょう。
こちらの動画の7:28からです。
↓
https://youtu.be/B-p353mT2n0?si=2xHwJ36xd9dNXog1
条文を読んでみましょう。
法第52条第7項 障害厚生年金の額の改定の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
甲は、65歳以上かつ障害基礎年金の受給権を有しないので、額の改定請求はできません。
乙は、65歳以上ですが、障害基礎年金の受給権を有するので、額の改定請求ができます。
障害基礎年金の受給権の有無がポイントです。
詳しくは、こちらで解説しています。
↓
問題が解ける!事後重症【社労士受験対策】
https://youtu.be/vsvaK8cf1rU?si=R6U2NqkgO2jtYWDf
過去問を解いてみましょう
【R2年出題】
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

【解答】
【R2年出題】 ×
問題文の場合は、「障害基礎年金」の受給権を有するので、65歳に達した日以後に障害の程度が増進して2級の障害の状態になった場合、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。
令和6年の選択問題の「乙」がこのパターンに当たります。
(法第52条第7項)
令和6年の選択式 1つめの国庫負担は、覚えて解く問題です。 2つめの標準賞与額は、健康保険と比較しながら覚えましょう。 3つめの受給権の保護は、附則からの出題でしたので、少し戸惑われたのではないでしょうか。 4つ目の遺族厚生年金の支給要件は、覚えて解く問題です。特に起算日が注意点です。 5つ目の障害厚生年金の額の改定は、択一式で良く問われるポイントです。問題を解くポイントをうまく見つけなければならない問題です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(国民年金法)
R7-010 9.4
<令和6年度国年選択式>保険料の納付事務を行うことができる者・遺族基礎年金が支給される子・死亡一時金の遺族【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の選択式です。
令和6年 選択問題1
国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした< A >、納付事務を< B >ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを< C >という。
<選択肢>
「完全かつ効率的に行う」、「申請に基づき実施する」、「適正かつ円滑に行う」
「適正かつ確実に実施する」
「市町村(特別区を含む。)」、「実施機関」、「都道府県」、「保険者」
「指定納付受託者」、「指定代理納付者」、「納付受託者」、「保険料納付確認団体」

【解答】
<A> 市町村(特別区を含む。)
<B> 適正かつ確実に実施する
<C> 納付受託者
(法第92条の3、第92条の4)
紛らわしい用語に注意しましょう
「指定代理納付者」(第92条の2の2)
厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(←クレジットカード)
「保険料納付確認団体」(法第109条の3)
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであって、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの
・ 当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務
納付受託者のポイント!
「納付受託者」は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができます。
・国民年金基金又は国民年金基金連合会
・納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(コンビニエンスストア等)
・厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
納付受託者について過去問を解いてみましょう。
①【R1年出題】
国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
国民年金基金又は国民年金基金連合会は、国民年金基金の加入員に限って、保険料の納付に関する事務を行うことができます。
(第92条の3第1項)
②【H22年出題】
厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものの委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。

【解答】
②【H22年出題】 〇
市町村が保険料の納付事務を行うことができるのは、保険料を滞納している者で市町村から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限られます。
(第92条の3第1項)
③【H30年出題】
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
国民年金保険料納付受託記録簿は、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。
(法第92条の5、則第72条の7)
令和6年 選択問題2
遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に< D >こと」と規定されている。
<選択肢>
「婚姻をしていない」
「日本国内に住所を有している」
「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない」
「養子縁組をしていない」

【解答】
<D> 婚姻をしていない
過去問を解いてみましょう
【R4年出題】
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

【解答】
【R4年出題】 〇
図でイメージしましょう。
受給権発生 ▼ |
|
|
| 18歳年度末 ▼ |
| 20歳 ▼ |
遺族基礎年金 | ||||||
|
| ▲ 障害等級に該当し、20歳まで障害の状態にある | ||||
(法第40条第3項)
令和6年 選択問題3
遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の < E >であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
<選択肢>
「配偶者又は子」、「配偶者、子又は父母」、「配偶者、子、父母又は孫」
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」

【解答】
<E> 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

【解答】
【R1年出題】 〇
祖父母と孫では、死亡一時金を受ける順位は孫が優先します。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の順番はおぼえましょう。
(法第52条の3)
令和6年の選択式 1つめは、似たような用語が多くて、覚えにくいところです。 2つめの子の要件は、択一式でもよく出ますので、対策ができていたと思います。 3つめは、遺族の範囲と順位がポイントです。死亡一時金のみならず、死亡に関する給付についての暗記必須箇所です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(健康保険法)
R7-009 9.3
<令和6年度健保選択式>保険外併用療養費・資格喪失後の出産・家族訪問看護療養費【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、< A >、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
<選択肢>
「新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから」
「患者に対する情報提供を前提として」
「困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として」
「保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に該当するとともに」

【解答】
<A> 患者に対する情報提供を前提として
(R2.3.5保医発0305第5号)
「治験」とは?厚生労働省のホームページを参考に、お話します。
「くすりの候補」の開発の最終段階では、人での効果と安全性を調べなければなりません。その際、人の協力が必要です。
このように得られた成績を国が審査し、病気の治療に必要、かつ安全に使えると承認されたものが「くすり」となります。
人における試験を一般に「臨床試験」といい、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験は、特に「治験」と呼ばれています。
(参考:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu1.html)
令和6年 選択問題2
任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の< B >であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
<選択肢>
「資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」
「資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」
「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」
「資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」

【解答】
<B> 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
(法第104条、第106条)
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けるには、「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員であった被保険者を除く)であったこと」が必要です。
資格喪失後の出産育児一時金も同じ条件です。
任意継続被保険者の資格を喪失した後でも、要件を満たせば、継続給付や出産育児一時金が支給されます。
その場合は、任意継続被保険者の資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったことが必要です。
退職 | 取得 喪失 |
被保険者(在職中) | 任意継続被保険者 |
継続して1年以上 |
|
令和6年 選択問題3
健康保険法第111条の規定によると、被保険者の< C >が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、< D >を支給する。< D >の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に< E >の給付割合を乗じて得た額 (< E >の支給について< E >の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
<選択肢>
「家族訪問看護療養費」、「家族療養費」、「高額介護サービス費」
「高額介護合算療養費」、「高額介護サービス費」、「高額療養費」
「認定対象者」、「被扶養者」、「扶養者」
「訪問看護療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」

【解答】
<C> 被扶養者
<D> 家族訪問看護療養費
<E> 家族療養費
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、家族訪問看護療養費が支給されます。
家族訪問看護療養費の額は、指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に家族療養費の給付割合(区分に応じて100分の70、100分の80)を乗じて得た額です。
令和6年の選択式 保険外併用療養費の支給対象となる治験の条件は、難しく感じた方が多かったのではないでしょうか? 2つめの任意継続被保険者の資格を喪失した後の問題については、選択肢が紛らわしいので注意が必要です。 3つめは、問題文の中のヒントを利用しながら解く問題です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(社保一般常識)
R7-008 9.2
<令和6年度社保選択式>国民生活基礎調査・介護保険事業状況報告・目的条文【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、社会保険に関する一般常識の選択式です。
令和6年 選択問題1
厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が< A >の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
<選択肢>
「40~60%未満」、「60~80%未満」、「80~100%未満」、「100%」

【解答】
<A> 100%
「国民生活基礎調査の概況」の中の「各種世帯の所得等の状況」の「所得の種類別の状況」からの出題です。
ポイント!
各種世帯の所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合は、
・全世帯では「稼働所得」が 73.2%、「公的年金・恩給」が 20.1%。
・高齢者世帯では「公的年金・恩給」が62.8%、「稼働所得」が 25.2%。
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は 44.0%。
(2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況より)
令和6年 選択問題2
厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で< B >%となっている。
<選択肢>
「3.9」、「18.9」、「33.9」、「48.9」

【解答】
<B> 18.9
第1号被保険者に占める認定者の割合は、全国平均で18.9%です。
ちなみに、第1号被保険者数は、令和3年度末で3,589万人です。
(令和3年度介護保険事業状況報告より)
令和6年 選択問題3
国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< C >に寄与することを目的とする。」と規定している。
<選択肢>
「社会保険及び国民福祉の向上」、「社会保険及び国民保健の向上」
「社会保障及び国民福祉の向上」、「社会保障及び国民保健の向上」

【解答】
<C> 社会保障及び国民保健の向上
(法第1条)
令和6年 選択問題4
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< D >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< E >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
<選択肢>
「給付費用」、「給付割合」、「費用負担」、「負担割合」
「共助連帯」、「共同連帯」、「自助と共助」、「自助と連帯」

【解答】
<D> 共同連帯
<E> 費用負担
(法第1条)
★「後期高齢者医療」制度の対象は、原則として75歳以上の後期高齢者です。
後期高齢者医療については、公費+現役世代からの支援金で約9割が賄われています。
★「前期高齢者」は、健康保険などの医療保険に加入しています。しかし、制度によって、前期高齢者の占める割合が異なります。そのため、前期高齢者の医療費については、制度間の財政調整が行われています。
問題文の<D>「共同連帯」は、高齢者医療を社会全体で支えるということです。
<E>の、前期高齢者に係る保険者間の<費用負担>の調整は、保険者間で行う財政調整の仕組みのことです。
「目的条文」を読むと、その法律の全体像をつかむことができます。
勉強に行き詰まったら、読んでみてください。
こちらにあります。
↓
■<横断編>目的条文などを読みます!練習問題もあります。労基・安衛・労災・雇用・徴収・健保・国年・厚年
■<横断編>一般常識科目の目的条文などを読みます!労働一般常識・社保一般常識
令和6年の選択式 データから2問、目的条文から3問でした。 一般常識についても、目的条文をはじめ、条文を読むことも大切です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(労働一般常識)
R7-007 9.1
<令和6年度労一選択式>改善基準告示・労働力調査・労働協約・均等法【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働に関する一般常識の選択式です。
令和6年 選択問題1
自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあることから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい< A >及び運転時間等の基準を設け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点から、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022(令和4)年12月にその改正を行った。
<選択肢>
「拘束時間、休息期間」
「拘束時間、総実労働時間」
「手待時間、休息期間」
「手待時間、総実労働時間」

【解答】
<A> 拘束時間、休息期間
考え方のポイント!
空欄<A>の直前の「全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい」の部分がヒントです。
「労働時間」は労働基準法で規制されていますし、「手待時間」は通達で労働時間であるとされています。
そのように考えると、選択肢の中の「拘束時間、休息期間」が引き出せるかと思います。
ちなみに、「拘束時間」とは、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間=始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間のことです。
「休息期間」とは、使用者の拘束を受けない期間のことです。
(「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号))
令和6年 選択問題2
総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和4)年の女性の雇用者数は2,765万人で、雇用者総数に占める女性の割合は< B >である。
<選択肢>
「25.8%」
「35.8%」
「45.8%」
「55.8%」

<解答>
<B> 45.8%
考え方のポイント!
「だいたい半々程度で、やや男性より少ないかな?」と想像しながら解いた方が多いと思います。
しかし、厚生労働白書に出てくる数字を全て暗記するのは不可能なので、難しい問題です。
(令和5年版厚生労働白書P216 女性の雇用の状況)
令和6年 選択問題3
最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の< C >的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の< C >的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に、労働協約の< C >的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。
しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが< D >と認められる特段の事情があるときは、労働協約の < C >的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である。」
<選択肢>
「著しく不合理である」
「一部の労働者を殊更不利益に取り扱うことを目的としたものである」
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない」
「労働協約の目的を逸脱したものである」
「規範」、「強行」、「債務」、「直律」

【解答】
<C> 規範
<D> 著しく不合理である
(平成8年3月26日最高裁判所第三小法廷)
ポイント!
★規範的効力とは、個々の労働条件を規律する効力のことで、労働組合法第16条で認められています。
第16条(基準の効力) 労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする 。 |
★問題文の判例は、未組織の同種労働者に対する労働協約の一般的拘束力が一部否定された事例です。
「労働協約を未組織の同種労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、その効力を未組織の同種労働者に及ぼすことはできない」とされています。
令和6年 選択問題4
男女雇用機会均等法第9条第4項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出産後< E >を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」と定めている
<選択肢>
「30日」、「8週間」、「6か月」、「1年」

【解答】
<E> 1年
(均等法第9条)
ポイント!
第9条第4項は以下のような解釈となっています。
第9条第4項は、妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇についての民事的効力を定めたものであること。すなわち、妊娠中及び出産後1年以内に行われた解雇を、裁判で争うまでもなく無効にするとともに、解雇が妊娠、出産等を理由とするものではないことについての証明責任を事業主に負わせる効果があるものであること。
このような解雇がなされた場合には、事業主が当該解雇が妊娠・出産等を理由とする解雇ではないことを証明しない限り無効となり、労働契約が存続することとなるものであること。
(平18.10.11雇児発第1011002号)
令和6年の選択式について 出題内容は ・注目度の高い「2024年問題」 ・「女性」について「雇用状況」や「妊娠中・産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇」 ・「労働協約」の一般的拘束力についての判例 幅広い分野からの出題でした。一般常識は「広く浅い」勉強が最適です。深く考えすぎないようにしてください。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります
R7-006 8.31
<令和6年度雇用選択式>出生時育児休業給付金・個別延長給付・特例高年齢被保険者【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、雇用保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
被保険者が< A >、厚生労働省令で定めるところにより、出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、< B >回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が< C >日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
<選択肢>
「一般被保険者であるときのみ」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は短期雇用特例齢被保険者であるとき」
「一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき」
「1」、「2」、「3」、「4」
「14」、「21」、「28」、「30」

【解答】
<A> 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
<B> 2
<C> 28
ポイント!
出生時育児休業は、「産後パパ育休」と言われています。
出生時育児休業は、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度に取得できます。
★対象になる被保険者は、「一般被保険者及び高年齢被保険者」です。「短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者」は除かれます。
★出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合、次のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給されません。
(1) 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業
↓
出生時育児休業を分割で取得できるのは2回までです。
(2) 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業
↓
4週間分(28日)が限度です。
(法第61条の8)
令和6年 選択問題2
被保険者が雇用されていた適用事業所が激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により< D >日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
<選択肢>
「30」、「60」、「90」、「120」

【解答】
<D> 120
問題文の場合は、120日分延長されます。なお、所定給付日数が270日又は330日の場合は、90日分延長されます。
(法第24条の2)
個別延長給付の過去問をどうぞ!
【R2年出題】
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。

【解答】
【R2年出題】 〇
個別延長給付の対象になるのは、以下の者です。
・特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した場合に限られます)
・特定受給資格者
・就職が困難な受給資格者
(法第24条の2)
令和6年 選択問題3
令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は< E >となる。
<選択肢>
「一般被保険者」、「高年齢被保険者」、「雇用保険法の適用除外」、「短期雇用特例被保険者」

【解答】
<E> 雇用保険法の適用除外
ポイント!
1週間の所定労働時間が20時間未満ですので、どちらの会社でも、雇用保険の適用が除外されます。
また、特例高年齢被保険者になるには、本人の「申出」が必要です。問題文の場合は申出をしていませんので、被保険者になりません。
(法第6条、第37条の5)
令和6年の選択式について 5問中、3問が数字の問題です。 雇用保険は数字を中心に暗記が必要です。 被保険者の種類や、受給資格者の種類も、区別できるように勉強しましょう。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります
R7-005 8.30
<労災保険法>令和6年度選択式は併合繰上げ・未支給・遺族補償年金【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第< A >級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第< B >級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
<選択肢>
「3」、「5」、「6」、「7」、「8」、「10」、「12」、「13」

【解答】
<A> 8
<B> 5
おぼえるポイント!
★障害等級は、障害等級表(労災保険法施行規則別表第1)にあてはめて、決定されます。
↓
★同じ事由による身体障害が2つ以上ある場合は、「重い方」の障害等級が全体の障害等級になります。
↓
★ただし、13級以上の身体障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級が繰り上げられます。
・13級以上の障害が2つ以上ある場合 → 1級繰り上げ
・8級以上の障害が2つ以上ある場合 → 2級繰り上げ
・5級以上の障害が2つ以上ある場合 → 3級繰り上げ
令和6年 選択問題2
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた< C >から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、< D >の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
<選択肢>
「月」、「月の翌月」、「日」、「日の翌日」
「事業主」、「自己」、「死亡した者」、「世帯主」

【解答】
<C> 月の翌月
<D> 自己
(法第9条第1項、法第11条第1項)
おぼえるポイント!
★年金は「月」単位で支給されます。
支給すべき事由が生じた「月の翌月」から支給を受ける権利が「消滅した月」まで
★未支給の保険給付は、「自己の名」で請求します。死亡した者の名ではありません。
ちなみに、未支給の保険給付を請求できるのは、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
ただし、遺族(補償)等年金の場合は、遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族となります。
令和6年 選択問題3
最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり,遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の< E >を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条,16条の2から16条の4まで),その塡補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる< E >による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
<選択肢>
「生活基盤の喪失」、「精神的損害」、「相続財産の喪失」「被扶養利益の喪失」

【解答】
<E> 被扶養利益の喪失
(平27.3.4最高裁判所大法廷判決)
私の考えるポイント!
「生活基盤の喪失」と「被扶養利益の喪失」で迷われませんでしたか?私は迷いました。
遺族補償年金の遺族の要件は、労働者の死亡当時その収入によって「生計を維持」していたものです。
そこから、労働者の死亡によって、「被扶養利益」が喪失すると考えました。
令和6年の選択式について <A>から<D>は、択一式でよく出るところですので、過去問対策で解けます。 判例からの問題の<E>は、覚えて解く問題というより、じっくり考える問題です。 遺族補償年金の目的は?遺族補償年金の対象になる遺族は?など、様々な角度で考える問題でした。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります
R7-004 8.29
<労働安全衛生法>令和6年度選択式・定期自主検査と労働者死傷病報告【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働安全衛生法の選択式です。
令和6年 選択問題1
労働安全衛生法第45条により定期自主検査を行わなければならない機械等には、同法第37条第1項に定める特定機械等のほか< D >が含まれる。
<選択肢>
「空気調和設備」、「研削盤」、「構内運搬車」、「フォークリフト」

【解答】
<D> フォークリフト
おぼえるポイント!
★定期自主検査の対象になる機械等には、「特定機械等」が含まれています
★特定自主検査の対象になる機械等は次の5つです。
・動力により駆動されるプレス機械
・フォークリフト
・車両系建設機械
・不整地運搬車
・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
→ 特定自主検査は、「その使用する労働者で一定の資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければなりません。
特定自主検査の対象になる機械等は、「定期自主検査」の対象の機械等の中で検査が難しいものです。フォークリフトは、特定自主検査の対象ですので、当然に定期自主検査の対象にもなっています。
(法第45条、令第15条)
フォークリフトが登場する過去問をどうぞ!
【H30年出題】
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。

【解答】
【H30年出題】 ×
定期自主検査の対象になるフォークリフトに、最大荷重は規定されていません。「最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている」という規定はありません。
(令第15条)
令和6年度 選択問題2
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日以上の場合に限る。)したときは、< E >、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
<選択肢>
「7日以内に」、「14日以内に」、「30日以内に」、「遅滞なく」

【解答】
<E> 遅滞なく
おぼえるポイント!
★「労働者死傷病報告」は「遅滞なく」提出しなければなりません。
★ただし、休業の日数が4日未満の場合は
「1月から3月まで」、「4月から6月まで」、「7月から9月まで」、「10月から12月まで」のそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、提出しなければなりません。
(則第97条)
死傷病報告の過去問を1問どうぞ!
【H29年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
【H29年出題】 〇
労働者死傷病報告書は、以下の場合に提出しなければなりません。
・労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
・労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
・労働者が事業場内若しくはその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、労働者死傷病報告書の提出が必要です。
(則第97条)
労働安全衛生法の選択対策 暗記必須です。 テキストを読み込むのではなく、何度も繰り返し眺めながら、用語を頭に入れていきましょう。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります
R7-003 8.28
<労働基準法>令和6年度選択式【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の選択式です。
令和6年 選択問題1
年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、< A >、これを使用してはならない。」と定めている。

【解答】
<A> 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
労基法第56条1項の「最低年齢」からの出題です。
中学校を卒業するまでは、原則として、労働者として使用できません。
令和6年 選択問題2
最高裁判所は、労働者が始業時刻及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の< B >に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の < B >に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の< B >に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

【解答】
<B> 指揮命令下
判例の問題です。(三菱重工長崎造船所事件)
何度も出題されていますので、過去問でもおなじみの問題です。
★ポイント!
「労働基準法上の労働時間の意義」
「労働基準法上の労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。
「労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間」は、労働基準法上の労働時間に該当するとされました。
令和6年 選択問題3
最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の< C >ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。

【解答】
<C> 自由な意思に基づく
こちらも、過去問でおなじみの問題です。
ポイント!
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は「有効」とされています。
★令和6年度の労働基準法選択式 労働基準法選択式は、条文から1問、判例から2問でした。 過去問対策で、しっかり得点できる問題でした。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
これから勉強を始める方へ
R7-002 8.27
初めて社会保険労務士の勉強をする方にお話します
社労士試験を受験することを決意して、受験学校に通う方、独学で頑張る方、みなさんそれぞれの方法を選んでいると思います。
★受験学校に通う方
授業が終わったら、できるだけ時間をあけずに、授業の範囲の問題を解いてみるのが良いと思います。
問題を解くと、「ここが問われる」というポイントが分かります。
問題のポイントが分かったところで、再度、テキストに戻って復習すると、定着します。
★独学で頑張る方
どんどん過去問を解いてください。過去問=出題可能性が高いところです。
過去問で出てきたところを中心に、テキストを勉強するのが良いと思います。
★焦らずに
そのとき分からなくても、勉強が進んでいくと、「あっ、そうか」と分かることが多々あります。
「分からない」ところがあったとしても、気にせず、どんどん勉強を進めていくことをおすすめします。
いっしょに頑張りましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
