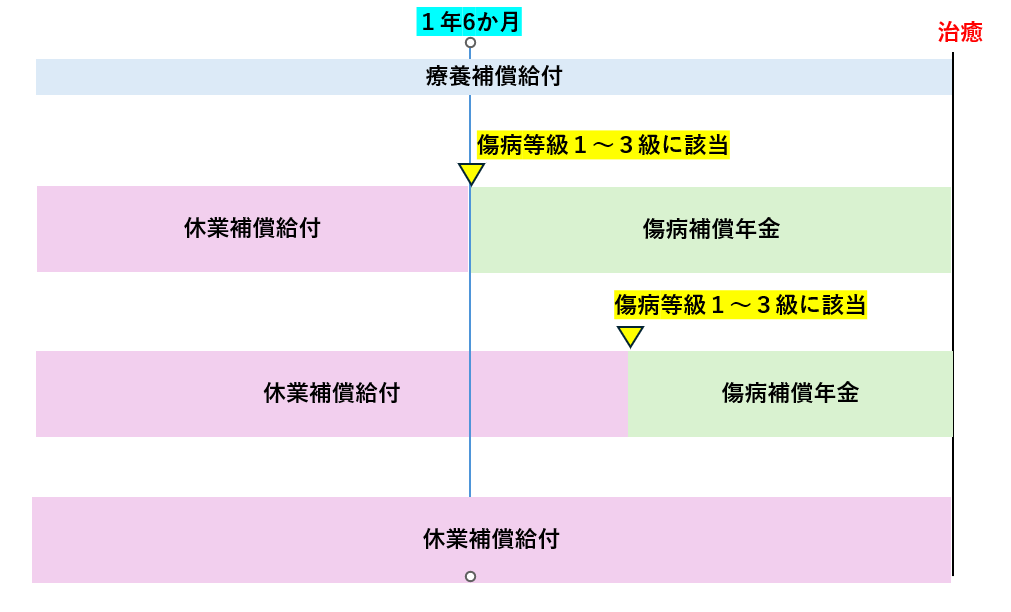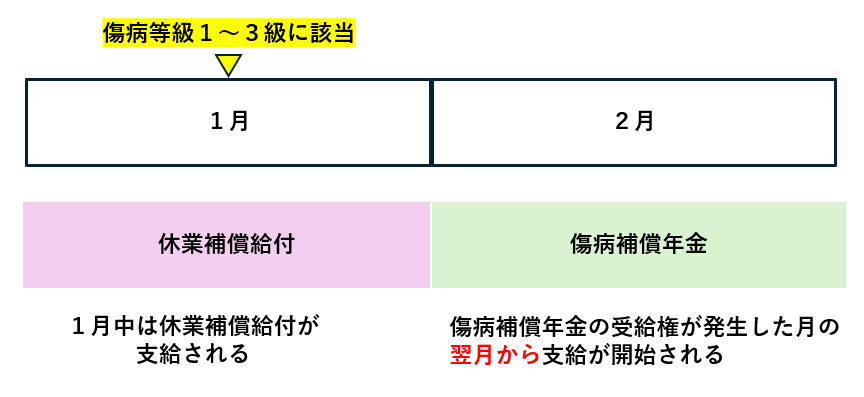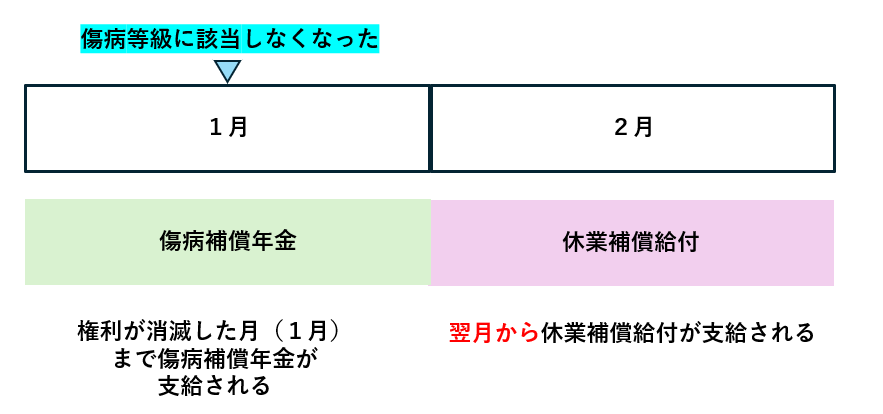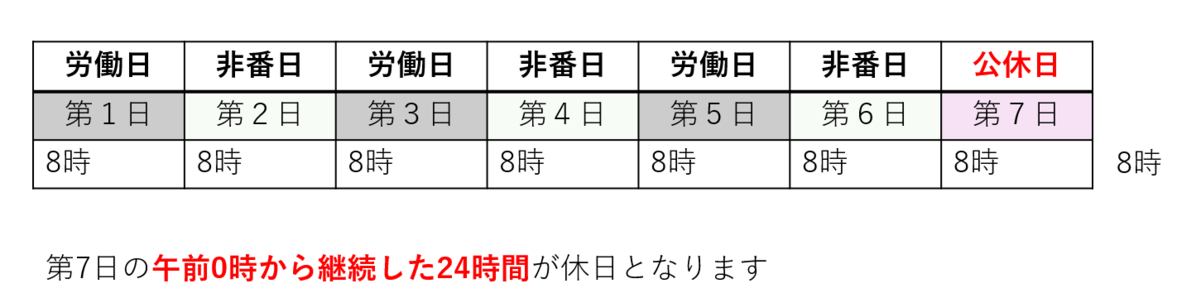合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
労災保険法「傷病補償年金」
R8-142 01.13
ポイントをお話しします|傷病補償年金
最初に、傷病補償年金について下の図①でイメージしましょう。
では、条文を読んでみましょう
法第12条の8第3項 ③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級~3級)に該当すること。
法第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 |
★傷病補償年金の額
1級 | 給付基礎日額の313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
★傷病補償年金の支給についてポイント
傷病補償年金は、他の保険給付と違い、支給の請求は不要です。
支給の決定は、請求によってではなく、政府の職権で行われます。支給事由に該当したときは、所轄労働基準監督署長が支給決定を行います。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
①【H24年出題】 〇
どちらも「治る前」の給付で、療養補償給付は治療のため、傷病補償年金は所得補償のためのものですので、併給される場合があります。
②【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも所得補償ですので、併給されません。
休業補償給付から傷病補償年金への切り替えについて下の図②でイメージしましょう
➂【H29年出題】
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】
➂【H29年出題】 〇
傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定されます。
(則第18条第2項)
④【H29年出題】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

【解答】
④【H29年出題】 〇
療養開始後1年6か月を経過した日に治っていない労働者は、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければなりません。所轄労働基準監督署長が支給事由に該当するか否か認定するためです。
(則第18条の2第1項)
※療養の開始後1年6か月を経過しても治っておらず、傷病補償年金の支給決定を受けるに至っていない場合
→ 毎年1月1日から同月末日までの間に休業補償給付を請求する際に、合わせて、「傷病の状態に関する報告書」も所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(則第19条の2)
⑤【H20年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

【解答】
⑤【H20年出題】 ×
障害の程度が重くなったときは、「変更についての請求書を提出する必要がある」の部分が誤りです。
障害の程度が、軽くなったり重くなったりして、傷病等級に変更があったときは、「請求」ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で変更に関する決定が行われます。
条文を読んでみましょう
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 則第18条の3 (傷病補償年金の変更) 所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。 |
⑥【H29年出題】
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、「傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない」です。
⑦【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅します。
ただし、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。
傷病補償年金から休業補償給付の切り替えについて、下の図③でイメージしましょう。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「休業補償給付の支給要件」
R8-141 01.12
基本をお話しします|休業補償給付が支給される要件
今回のテーマは「休業補償給付」の支給要件です。
業務上の傷病により、仕事に就けないときに支給されます。
条文を読んでみましょう
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
※部分算定日について ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |
<部分算定日の算定式>
(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×100分の60
下の図①でイメージしましょう
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】
①【R7年出題】 ×
休業給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用される時期についての問題です。
療養を開始した日から起算して「3年」ではなく「1年6か月」を経過した日以後の日から年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。
年齢については、「四半期の初日」で適用されるのもポイントです。
下の図②でイメージしましょう
②【R5年選択式】
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。
<選択肢>
① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑭ 賃金 ⑮ 通院
⑯ 能力喪失 ⑲ 療養

【解答】
<A> ⑲ 療養
<B> ⑦ 4
<C> ②100分の60
➂【H30年出題】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

【解答】
➂【H30年出題】 〇
休業の初日から第3日目までの期間は、休業補償給付は支給されません。
そのため、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主は、労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。
なお、複数業務要因災害と通勤災害については、労働基準法の補償責任が規定されていませんので、事業主による休業補償は義務付けられていません。
④【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
「休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付は支給される」とされています。
(昭58.10.13最高裁判所第一小法廷)
⑤【R7年出題】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
④の問題と同じです。
出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合でも、休業補償給付は支給されます。
⑥【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
休業補償給付は、「賃金を受けない日」について支給されます。
「賃金を受けない日」には、「全部を受けない日」と「一部を受けない日」があります。
「一部を受けない日(=一部を受ける日)」は、「全部労働不能」の場合は、「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」とされています。
問題文のように、「所定労働時間の全部労働不能」の労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合は、「賃金を受けない日」に当たりませんので、休業補償給付は支給されません。
⑦【H30年出題】※改正による修正あり
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

【解答】
⑦【H30年出題】 〇
問題文に「療養開始後1年6か月未満」とありますので、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がない前提です。
「部分算定日」の休業補償給付の額は、(「休業給付基礎日額」-「部分算定日に対して支払われる賃金の額」)×100分の60で計算します。
⑧【R2年出題】
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

【解答】
⑧【R2年出題】 ×
・休業補償給付の額は、(100%-20%)×100分の60=48%
・休業特別支給金の額は、(100%-20%)×100分の20=16%
となります。
すべて合わせても100%になりません。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
図①
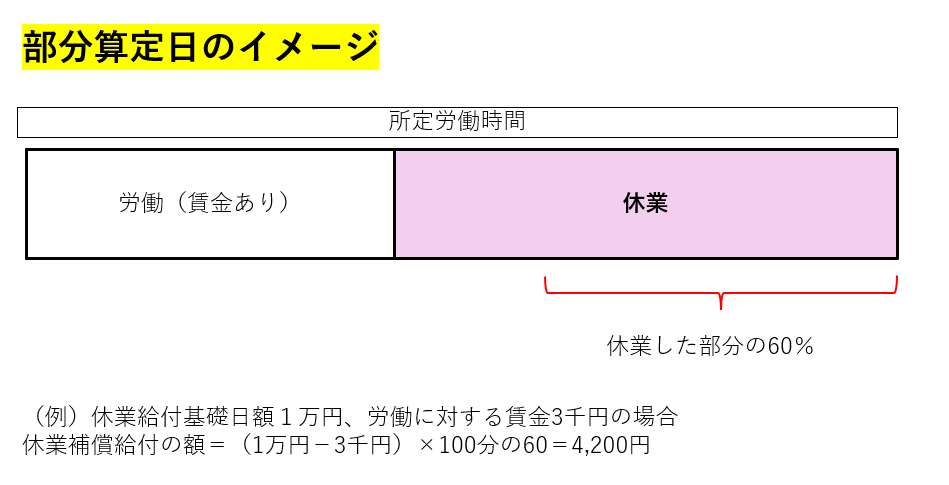
図②
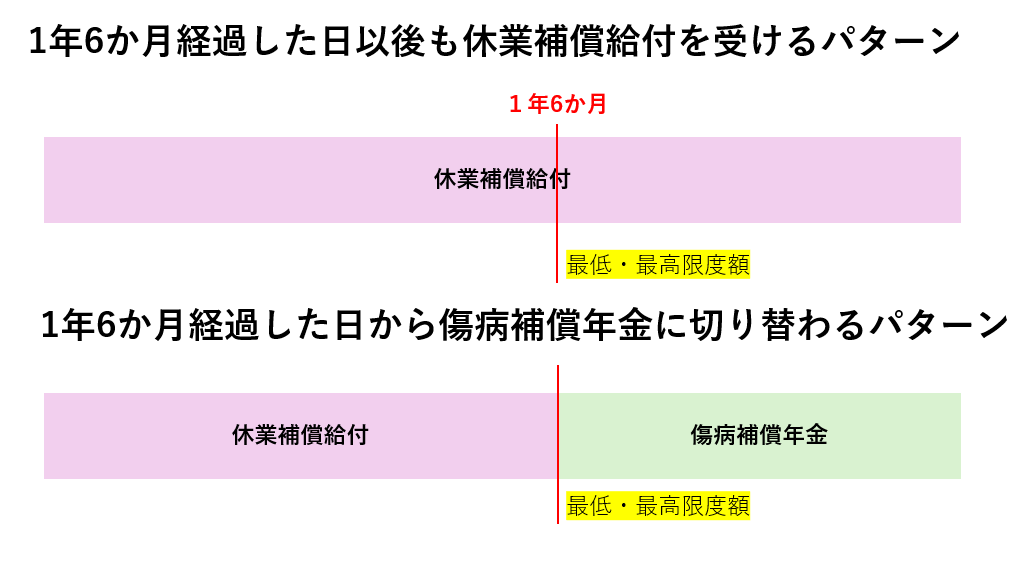
YouTubeはこちらからどうぞ!
労働基準法「割増賃金」
R8-139 01.10
時間外・休日・深夜の割増賃金の率
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
条文を読んでみましょう
法第37条第1項(時間外、休日割増賃金) ① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
法第37条第4項 (深夜割増賃金) ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
割増賃金の率を確認しましょう
時間外労働 | 法定労働時間を超えた場合 | 25%以上 |
1か月60時間を超えた場合 | 50%以上 | |
休日労働 | 法定休日に労働させた場合 | 35%以上 |
深夜労働 | 深夜の時間帯に労働させた場合 | 25%以上 |
※時間外労働と深夜労働が重なった場合 → 25%+25%=50%以上
※休日労働と深夜労働が重なった場合 → 35%+25%=60%以上
過去問で確認しましょう
【H25年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
<選択肢>
④ 午後10時から午前5時まで ⑤ 午後10時から午前6時まで
⑥ 午後11時から午前5時まで ⑦ 午後11時から午前6時まで
⑧ 時間帯 ⑬ 長さ ⑭ 密度 ⑳ 割増

【解答】
<A> ⑬ 長さ
<B> ④ 午後10時から午前5時まで
(平21.12.18最高裁判所第二小法廷 ことぶき事件)
ポイント!
・労基法の労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めている
・第37条4項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合に、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定している。
労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にする
なお、結論は、次の通りです。
・労基法41条2号の規定によって同法37条4項の適用が除外されることはない
・管理監督者に該当する労働者は深夜割増賃金を請求することができる
②【H29年出題】
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、時間外労働の割増率を合算する必要はありません。
(H11.3.31基発168号)
なお、休日労働が深夜に及んだ場合は、休日労働と深夜労働の割増率を合算した 「6割以上」となります。
(H6.1.4基発1号)
➂【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する問題です。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題A)
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】
(問題A) ×
日曜に10時間の労働があったとしても、8時間を超えた2時間は時間外労働にはなりません。
割増賃金は、深夜の時間帯でなければ、「休日労働に対する割増率」のみで計算します。
(問題B)
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】
(問題B) ×
休日は、「暦日」で考えます。
休日労働となるのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までです。
法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合、3割5分以上で計算しなければならないのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までの間に労働した部分です。
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働になるのは、日曜の午後8時から午後12時までです。
(H6.5.31基発331号)
(問題D)
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】
(問題D) ×
「法定休日の午前0時から午後12時まで」は休日割増賃金の対象になります。
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んでも、日曜の午前0時から午前3時までは、「休日割増」となり、土曜の勤務の時間外労働時間として計算されるのは、土曜の午後12時までです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「休日」
R8-138 01.09
休日の基本をお話しします
労働義務のある日を「労働日」、労働義務のない日を「休日」といいます。
労働基準法では、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられています。
では、休日について条文を読んでみましょう
法第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
第35条で規定されている休日を「法定休日」といいます。
法定休日について
原則 | 毎週少くとも1回 |
例外 | 4週間を通じ4日以上 |
図でイメージしましょう
「休日」の過去問を解いてみましょう
<4週を通じ4日以上の休日>
【H23年出題】
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

【解答】
【H23年出題】 〇
毎週少なくとも1回の休日を与えることが原則ですが、例外で、4週間を通じ4日以上の休日を与えることもできます。その場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにすることが必要です。
(則第12条の2第2項)
【H13年出題】
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】
【H13年出題】 ×
「年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。」は誤りです。
特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。
(昭23.9.20基発1384号)
<休日は暦日が原則>
【H29年出題】
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】
【H29年出題】 ×
単に24時間継続して労働義務から解放しても休日になりません。
休日は、「暦日」を意味しますので、午前0時から午後12時までの単位となります。
(昭23.4.5基発535号)
<一昼夜交替勤務の休日>
【H24年出題】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
【H24年出題】 〇
問題文のような一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間は、労働義務がないとしても、休日となりません。
(昭23.11.9基収2968号)
図でイメージしましょう
<8時間3交替制勤務の休日>
【H21年出題】
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【解答】
【H21年出題】 ×
問題文のような条件を満たす番方編成による交替制の「休日」については、暦日ではない「継続24時間」の休息を与えれば差し支えないとされています。
(昭63.3.14基発150号)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
休日の与え方<原則>
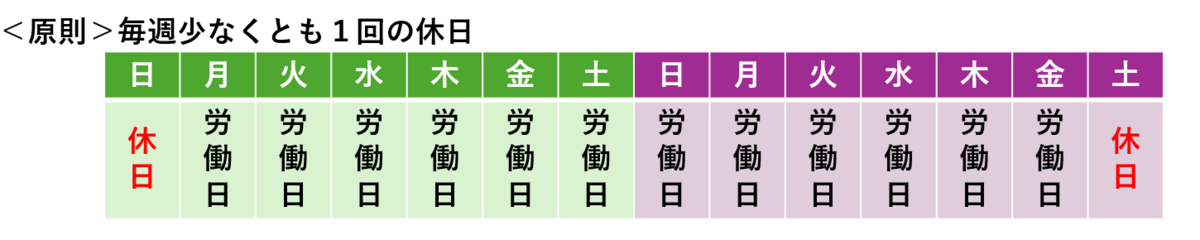
休日の与え方<例外・変形休日制>
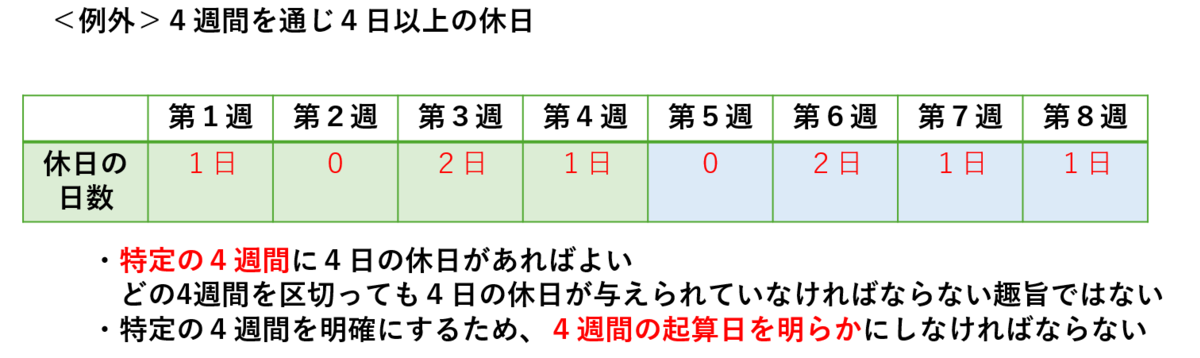
労働基準法「時間外労働」
R8-137 01.08
36協定・割増賃金が必要な「時間外労働」を整理する
◇ 労働基準法では、労働時間の上限が定められています。(法定労働時間といいます)
法定労働時間は、原則1週40時間・1日8時間で、使用者は、法定労働時間を超えて労働させることはできません。
◇ ただし、「36協定」を締結し、それを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、適法に、時間外労働をさせることができます。
なお、時間外労働させた時間については、割増賃金の支払が義務付けられています。
◇ ちなみに、ここでいう「時間外労働」とは、「法定労働時間を超える時間」のことです。
例えば、9時始業~17時終業(休憩1時間)の労働者に、18時まで残業させる場合は三六協定も割増賃金も不要です。
所定労働時間が7時間ですので、1時間延長しても、トータルの労働時間は8時間だからです。
問題を解きながら「時間外労働」を確認しましょう
<法定労働時間を超えない残業>
【H29年出題】
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

【解答】
【H29年出題】 〇
労働基準法第32条で定められている労働時間は、「実労働時間」をいいます。
遅刻をした時間分だけ終業時刻を繰り下げて労働させても、1日の実労働時間を通算して8時間を超えないときは、時間外労働に従事させたことにはなりません。36協定がない場合でも、労働基準法第32条には違反しません。
(平11.3.31基発168号)
【R4年出題】
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、労働基準法第36条第1項の協定をする必要はない。

【解答】
【R4年出題】 〇
所定労働時間が1日7時間、1週35時間の場合で、1週35時間を超えて労働時間を延長しても、1週間の実労働時間が法定労働時間以内で、各日の労働時間が8時間以内かつ休日労働を行わせない限り、36協定を締結する必要はありません。
(平11.3.31基発168号)
<労働者が時間外労働を行う義務>
【H27年出題】
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H27年出題】 ×
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容となるため、労働者は、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うとされています。
(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)
なお、「36協定」を締結し届け出た場合、使用者は適法に時間外労働をさせることができるようになります。(免罰効果が生じます。)
しかし、問題文にあるように、36協定には、私法上の権利義務を設定する効果は有りません。「労働者の民事上の義務は、36協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものである。」とされています。
<違法な時間外労働>
【R2年出題】
労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R2年出題】 〇
36協定を締結していないなど違法な時間外労働・休日労働に対しても、使用者には割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは罰則の適用は免れません。
「適法な時間外労働等について割増賃金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきである」とされています。
(昭35.7.14最高裁判所第一小法廷 小島撚糸事件)
<時間外労働が翌日に及んだ場合>
【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題です。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間
<問題>
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】 〇
「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。
ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、始業時刻の属する日である月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。
図でイメージしましょう。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
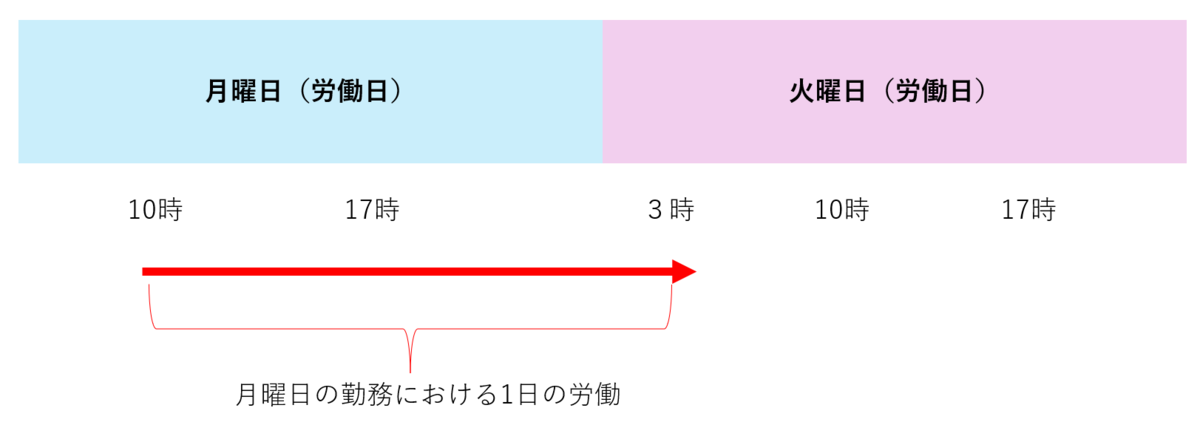
YouTubeはこちらからどうぞ!
労働基準法「労使協定」
R8-136 01.07
36協定のポイント!
★労使協定とは
使用者と
◇「事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合」
◇労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は
「労働者の過半数を代表する者」
との書面による協定のことです。
労働基準法の労働時間の上限は、原則として1週40時間、1日8時間です。
その時間を超えて労働させることは労働基準法に反しますが、「労使協定」を締結し、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、免罰効果が生じ、労働時間を延長させることができます。
条文を読んでみましょう
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
「36協定」とは、法第36条に規定されている労使協定のことです。
過去問でポイントを確認しましょう
<36協定の免罰効力が生ずる要件>
【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】
【H24年出題】 〇
36協定のポイント!
・36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になる(免罰効果が生じる)
・法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない
【R3年出題】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】
【R3年出題】 〇
36協定を締結したのみでは、免罰効果は生じません。所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になります。
有効期間が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの労使協定を締結し、これを令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合、届出日の令和3年4月9日以降は、適法に時間外労働を行わせることができます。
しかし、届出前の令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、労働基準法違反の責は免れません。
<時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務>
【H24年出題】
労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

【解答】
【H24年出題】 〇
「労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。」とされています。
労働者が、時間外又は休日労働命令に服すべき義務は、36協定から直接当然に生ずるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。
【H20年選択式】
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。

【解答】
【H20年選択式】
<A> 合理的な
・使用者が、三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た
(使用者は適法に時間外労働をさせることができる=免罰効果が生じる)
↓
・使用者が就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めている
↓
就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなす
↓
就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う
(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)
<労使協定の効力の範囲>
【H25年出題】
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

【解答】
【H25年出題】 〇
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、協定の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及びます。
(昭23.4.5基発535号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働時間」
R8-135 01.06
労働時間の基本をお話しします
「労働時間」とは、労働者が使用者の「指揮命令下」に置かれている時間のことをいいます。
「休憩時間」は、労働から解放される時間ですので、労働時間ではありません。
例えば、始業9時、終業18時、休憩12時~13時の場合の労働時間は次のようになります。
・拘束時間 → 9時間(9時~18時)
・休憩時間 → 1時間(12時~13時)
・労働時間 → 9時間-1時間=8時間
労働基準法では、労働時間の上限が定められています。
条文を読んでみましょう
法第32条(労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
<原則> 労働時間の上限は、1週40時間・1日8時間です。
<特例> 商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。
★労働基準法で定められた労働時間の上限を「法定労働時間」といいます。
★残業させる場合(法定労働時間を超える場合)の手続
使用者が、36協定(過半数労働組合又は過半数代表者との協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合 → 使用者は適法に時間外労働又は休日労働をさせることができます。
★割増賃金について
時間外、休日、深夜に労働させた場合は、使用者は、割増賃金を支払わなければなりません。
過去問を解きながら「労働時間」の考え方をみていきましょう
<特例事業場の労働時間>
【R4年出題】
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。

【解答】
【R4年出題】 ×
特例事業場については、1週間について48時間ではなく、44時間まで労働させることができます。また、1日についての上限は、原則と同じ「8時間」です。
★特例事業場も確認しましょう(赤字は略称です)
別表第1
・第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業) (商業)
・第10号(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)※映画の製作の事業を除く
(映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。))
・第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業) (保健衛生業)
・第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業) (接客娯楽業)
に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものです。
<労働時間とは?最高裁判例より>
【R6年選択式】
最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の< A >に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の< A >に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の< A >に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

【解答】
<A> 指揮命令下
(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)
ポイント!
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
【H28年出題】
労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H28年出題】 〇
労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」とされています。
(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)
<手待ち時間>
【H30年出題】
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

【解答】
【H30年出題】 ×
運転しない者が、助手席で仮眠している間は「労働時間」です。
トラックに乗り込む点で使用者の拘束を受けていること、また、万一事故が発生したときは交替運転、故障修理等を行う役割があるためです。
(昭33.10.11基収6286号)
<仮眠時間>
【R4年出題】
警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R4年出題】 〇
「従業員の職務は、もともと仮眠時間中も、必要に応じて,突発作業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、警報を聞き漏らすことは許されず、警報があったときには何らかの対応をしなければならないものであるから、何事もなければ眠っていることができる時間帯といっても、労働からの解放が保障された休憩時間であるということは到底できず、本件仮眠時間は実作業のない時間も含め、全体として被上告人の指揮命令下にある労働時間というべきである」とされています。
(平14.2.28最高裁判所第一小法廷 大星ビル管理事件)
<1日とは>
【R1年出題】
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

【解答】
【R1年出題】 〇
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは
・午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のこと
・継続勤務が2暦日にわたる場合 → 暦日が異なっていても、1勤務として取り扱う。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働となる。
(昭63.1.1基発1号)
<1週間とは>
【H30年出題】
労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

【解答】
【H30年出題】 〇
「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。」とされています。
何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることができます。
(昭63.1.1基発1号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」
R8-134 01.05
社会保険審査官及び社会保険審査会法について
今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」をみていきます。
・社会保険審査官について
→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます
厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命します
・社会保険審査会について
→ 厚生労働大臣の所轄の下に置かれます
委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します
審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されます
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときは、することができない。」となります。
(法第4条第2項)
②【R2年出題】
審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
審査請求は、「文書のみならず口頭でも」することができます。
(法第5条第1項)
➂【R7年出題】
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、審査請求の取下げは、「文書で」しなければならないとされています。
(法第12条の2)
④【R2年出題】
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限られます。
(法第5条の2)
⑤【R7年出題】
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」とされています。
(法第12条)
⑥【H29年出題】
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
「社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」とされています。
(法第2条)
⑦【R5年出題】
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます。
(法第1条、第2条)
⑧【R7年出題】
社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。

【解答】
⑧【R7年出題】 〇
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織され、合議制です。
(法第20条、第21条)
⑨【R7年出題】
社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

【解答】
⑨【R7年出題】 〇
社会保険審査会は、「公開審理」が原則です。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができます。
(法第37条)
⑩【R5年出題】
社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

【解答】
⑩【R5年出題】 〇
社会保険審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱います。
また、「審査会の合議は、公開しない。」とされています。
(法第27条、第42条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「介護保険法」
R8-132 01.03
地域包括ケアシステム|地域で包括的な支援・サービスを提供する体制
今回のテーマは「地域包括ケアシステム」です。
さっそく令和7年の問題を解いてみましょう
①【R7年出題】
いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。

【解答】
①【R7年出題】 〇
「「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。」とされています。
(参照:令和6年版厚生労働白書)
②【R7年出題】
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
要介護認定を受けようとする被保険者は、「地域包括支援センター」に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされています。
(令和6年版厚生労働白書、介護保険法第27条第1項)
なお、地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」と定義されています。(介護保険法第115条の46第1項)
過去問も解いてみましょう
【令和元年選択式】
介護保険法第115条の46第1項によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、< A >を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
<選択肢>
⑰ その地域における医療及び介護
⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進
⑲ 地域住民との身近な関係性の構築
⑳ 要介護状態の軽減又は悪化の防止

【解答】
<A> ⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「国民年金の歴史」
R8-131 01.02
国民年金の歴史|無拠出制・拠出制の実施、基礎年金の導入
年金の学習に欠かせない「国民年金の歴史」をみていきましょう
令和7年の問題を解いてみましょう
【社一R7年出題】
核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに、平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。

【解答】
【社一R7年出題】 ×
基礎年金が導入されたのは、平成元年ではなく、「昭和60(1985)年改正」です。
「当時、我が国の公的年金制度は大きく3種8制度に分立し、給付と負担の両面で制度間の格差や重複給付などが生ずるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤が不安定になるという問題が生じていた。このため、全国民共通の基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の被用者年金を基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成した。
基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。」とされています。
昭和34(1959)年 | 国民年金法制定 |
昭和34(1959)年11月 | 無拠出制の福祉年金制度の実施 |
昭和36(1961)年4月 | 拠出制の国民年金制度の実施(国民皆年金の実現) |
昭和61(1986)年4月 | 基礎年金の導入(昭和61年4月~新法) |
(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)
過去問をどうぞ!
【国年H19年出題】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
【国年H19年出題】 ×
「国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年「10月」でなく「11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。」となります。
なお、「福祉年金」については、「高齢のため受給に必要な加入期間を満たせない人や、すでに障害のある人等に対して、無拠出の老齢福祉年金、障害福祉年金及び母子福祉年金等を支給することとし、その費用は全額国庫で負担することとした。」とされています。
(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」
R8-130 01.01
高齢者医療確保法|子育てを社会全体で支援する~出産育児支援金
まず、令和7年の問題からみていきましょう
【R7年出題】
出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6年(2024)年度から導入することとした。

【解答】
【R7年出題】 〇
・子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みが導入されています。
(令和6年版厚生労働白書より)
◇◇◇もう少し詳しくみていきましょう◇◇◇
① 後期高齢者医療の被保険者は、保険料を負担しています。
「保険料率」の定め方について、条文を読んでみましょう
法第104条第3項(令和8年4月改正) 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、 第117条第2項の規定による拠出金(特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金)及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |
※少子化を克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されています。
②「支援」の流れについて条文を読んでみましょう
★ 後期高齢者医療制度で、保険者(国保・健保組合・協会けんぽ・共済組合)の出産育児一時金の費用の一部を支援するイメージで読んでください。
法第124条の2 (出産育児支援金の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」)は、第139条第1項第3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。 → 第139条第1項第3号の業務 「後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務」 → 「保険者」 全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団 ② 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。
法第124条の4 (出産育児交付金) ① 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 ② ①の出産育児交付金は、支払基金が徴収する出産育児支援金をもって充てる。
法第124条の5 (出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務) ① 支払基金は、第139条第1項第3号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。 ② 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和8年度版
毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ
厚生年金保険法(給付制限)
R8-129 12.31
違いに注意しましょう|支給停止と差し止め
・「年金たる保険給付」の全部又は一部が支給停止される場合
・「保険給付」の支払が一時差し止められる場合
をみていきましょう
条文を読んでみましょう
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3) (2)に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
法第78条 ① 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 ② 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、①の規定は、適用しない。 ※第98条第3項 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
「赤字」の部分を意識しながら読んでください。
「年金たる保険給付の受給権者」が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
②【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

【解答】
②【H30年出題】 ×
正当な理由なくして、加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、支給停止されるのではなく、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります
➂【H27年出題】
受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
※第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付ではないものとする。

【解答】
➂【H27年出題】 〇
正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず又は書類その他の物件を提出しないときは、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります。
④【R7年出題】
受給権者が、正当な理由がなく、厚生労働省令に定める事項の届出、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払いを差し止めることができる。その後、当該差止事由が消滅したときでも、差し止められた分の支給は行われない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「差し止め」については、その後、差止事由が消滅したときは、差し止められた分が遡って支給されます。
「支給停止」の場合は、支給停止された分はさかのぼって支給されませんので、違いに注意しましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法(遺族厚生年金)
R8-128 12.30
30歳未満の妻|遺族厚生年金の失権
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、「妻」については「年齢要件」はありません。また、子の有無は問われません。
ただし、夫の死亡時に「30歳未満の妻」については、特有の失権事由があります。
条文を読んでみましょう
法第63条第1号第5号 遺族厚生年金の受給権は、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときに消滅する。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき → 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 |
図でイメージしましょう
では、過去問を解いてみましょう
①【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻」は、イの「遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき」に該当します。
この場合、遺族厚生年金の受給権が消滅するのは、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して5年を経過したとき」です。
問題文の遺族厚生年金の受給権は、「妻が30歳になったとき」ではなく、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して5年を経過したとき」に消滅します。
②【R5年出題】
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

【解答】
②【R5年出題】 〇
「遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻」は「ロ」に該当します。30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅します。
「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算することがポイントです。
➂【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
➂【H29年出題】 ×
ロに該当します。
遺族厚生年金の受給権は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに消滅します。
④【R7年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して3年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
④【R7年出題】 ×
イに該当します。
遺族厚生年金の受給権は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算して「5年」を経過したときに消滅します。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
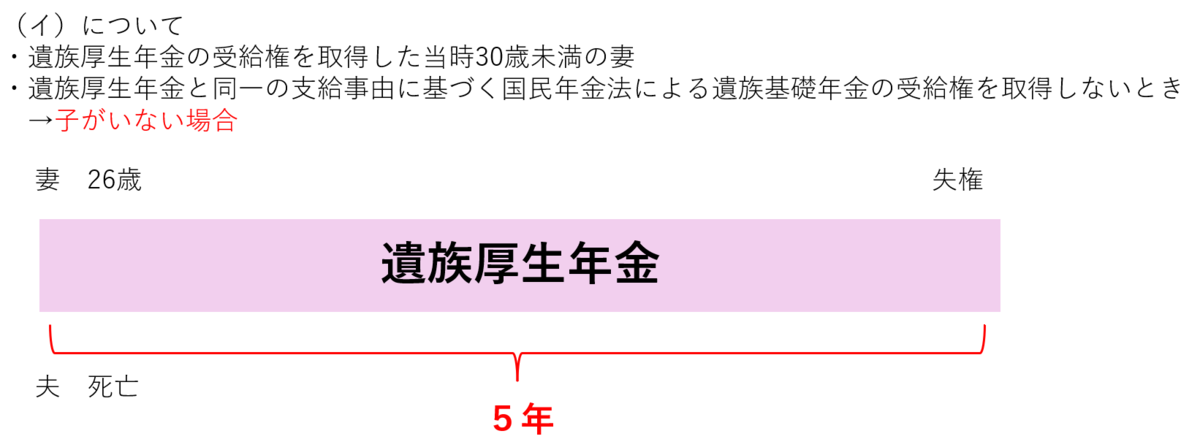
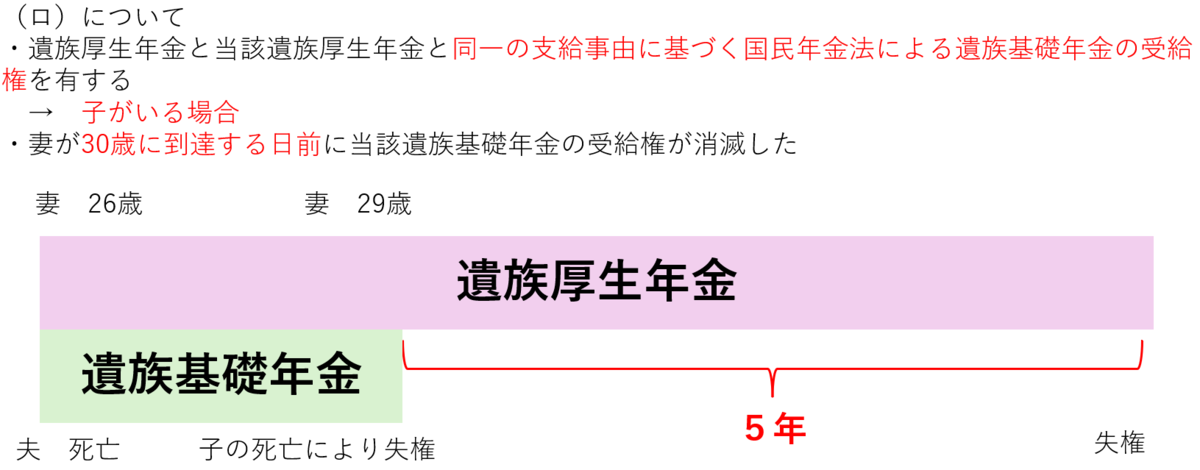
YouTubeはこちらからどうぞ!
厚生年金保険法(遺族厚生年金)
R8-127 12.29
65歳以上|遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給
65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給されます。
ただし、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は、老齢厚生年金に相当する部分の額の支給が停止されます。
下の図でイメージしましょう
条文を読んでみましょう
第64条の3 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額(法第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、同項の規定を適用しない額)に相当する部分の支給を停止する。 |
ポイント!
★ 対象は、「65歳以上」に限られています。
「65歳未満」の場合は、一人一年金が原則ですので、どちらか選択です。
では、過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます。
その場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金額は除かれることがポイントです。支給停止される額に、加給年金額は含まれません。
②【R7年出題】
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するとき、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金についてもこの規定が適用されるため、加給年金額に相当する部分も含めて、当該遺族厚生年金は支給が停止される。

【解答】
②【R7年出題】 ×
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、支給停止の対象になるのは、加給年金額が適用されない額です。
遺族厚生年金については、「老齢厚生年金の額(加給年金額は除いた額)」に相当する部分が支給停止されます。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
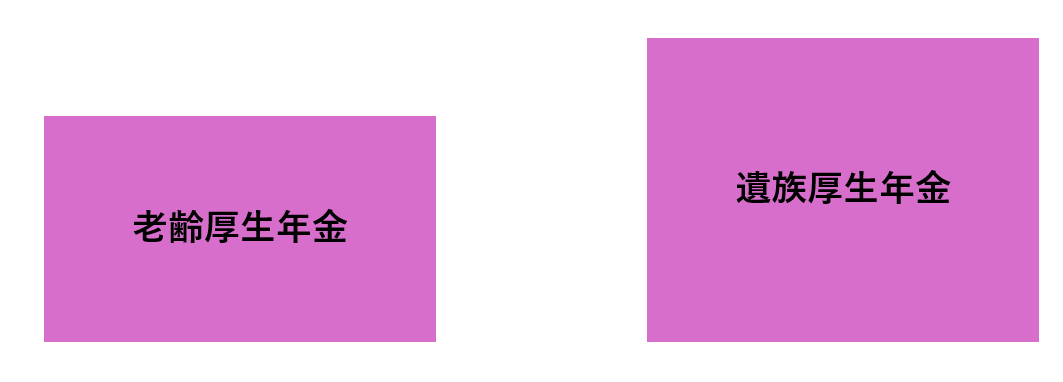
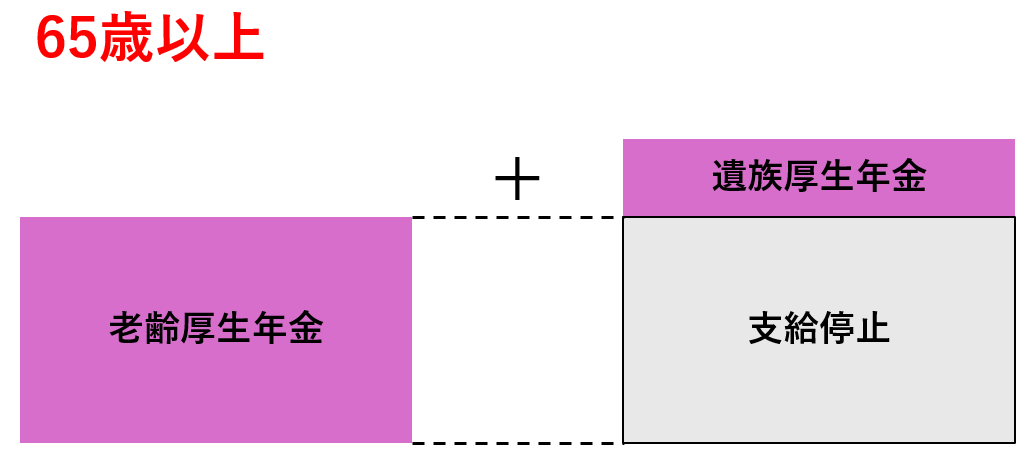
YouTubeはこちらからどうぞ!
厚生年金保険法「適用事業所」
R8-125 12.27
厚生年金保険の強制適用事業所と任意適用事業所
厚生年金保険が当然に適用される事業所を「強制適用事業所」といいます。
また、強制適用事業所に該当しない事業所は、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所になることができます。そのような事業所を「任意適用事業所」といいます。
条文を読んでみましょう
法第6条 <強制適用事業所> ① 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所又は船舶を適用事業所とする。 (1) 次に掲げる事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人事業所) イ物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ鉱物の採掘又は採取の事業 ニ電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ貨物又は旅客の運送の事業 ヘ貨物積卸しの事業 ト焼却、清掃又はと殺の事業 チ物の販売又は配給の事業 リ金融又は保険の事業 ヌ物の保管又は賃貸の事業 ル媒介周旋の事業 ヲ集金、案内又は広告の事業 ワ教育、研究又は調査の事業 カ疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ通信又は報道の事業 タ社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 レ弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 (2) 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの (3) 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶 <任意適用事業所> ➂ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外に該当する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
「強制」と「任意」についてまとめました。
| 法 人 | 個人事業所 | |
| 1人でも | 5人以上 | 5人未満 |
適用業種 | 業種問わず 強 制 | 強 制 | 任 意 |
適用業種以外 | 任 意 | 任 意 | |
※適用業種以外の業種を覚えましょう
→サービス業や農業、漁業等
では、過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】
次のアからオのうち、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主はどれか。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

【解答】
①【H28年出題】
「任意適用事業所の認可」が必要な事業主は、「アとウ」です。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
→ 旅館は「適用業種以外」ですので、個人経営の旅館は、任意適用です。
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
→「貨物積み卸し業」は「適用業種」です。個人経営で5人以上の場合は「強制適用事業所」となります。
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
→ 理容業は「適用業種以外」ですので、個人経営の理容業は、任意適用です。
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
→船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、人数に関係なく「強制適用事業所」となります。
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主
→ 学習塾(教育の事業)は「適用業種」ですので、個人経営で5人以上の場合は「強制適用事業所」となります。
②【R7年出題】
理美容の事業で、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「理美容の事業」は適用業種以外ですので、個人事業所の場合は、5人以上使用していても、強制適用事業所ではなく、「任意適用」となります。
➂【R1年出題】
常時5人以上の従業員を使用する個人経営のと殺業者である事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。

【解答】
➂【R1年出題】 ×
「と殺の事業」は「適用業種」ですので、常時5人以上使用する個人経営の事業所は、「強制適用事業所」です。
④【R4年出題】
宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
「宿泊業」は適用業種以外ですので、個人事業所の場合は、厚生年金保険の適用事業となるためには、厚生労働大臣の認可が必要です。
⑤【R1年出題】
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「畜産業」は適用業種以外ですので、個人経営の場合は、適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければなりません。
⑥【R4年出題】
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
「法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの」は強制適用事業所となります。法人の事業所の場合は、常時1人でも従業員を使用していれば、適用業種でも適用業種以外でも強制適用事業所です。
美容業の事業所が法人化した場合は、強制適用事業所となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「実施機関」
R8-124 12.26
厚生年金保険の実施機関が行う事務
被保険者の種別を確認しましょう。
①第1号厚生年金被保険者 | ②~④の被保険者以外の厚生年金保険の被保険者 |
②第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 |
➂第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 |
④第4号厚生年金被保険者 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者 |
「実施機関」を確認しましょう
①第1号厚生年金被保険者 | 厚生労働大臣 |
②第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 |
➂第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 |
④第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
(法第2条の5)
過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】
厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「政府」が管掌するとされています。
条文を読んでみましょう
法第2条(管掌) 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 |
②【R2年出題】
第2号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、実施機関としての国家公務員共済組合が行う。

【解答】
②【R2年出題】 ×
第2号厚生年金被保険者に係る拠出金の納付に関する事務は、「国家公務員共済組合連合会」が行います。
※実施機関(第2号厚生年金被保険者の場合は国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会)が行う事務
→ 被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、当該保険給付の受給権者、基礎年金拠出金の納付及び拠出金の納付、保険料その他徴収金並びに保険料に係る運用に関する事務
ただし、法第84条の5の拠出金の納付に関する事務は、「国家公務員共済組合連合会」が行うことになっています。(法第2条の5第2項)
➂【R7年出題】
第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関としては地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会があるが、厚生年金保険法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、地方公務員共済組合が行う。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
第3号厚生年金被保険者に係る事務を担当する実施機関には、「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」があります。
ただし、法第84条の5第1項の規定による拠出金の納付に関する事務は、「地方公務員共済組合連合会」が行うことになっています。(法第2条の5第2項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「2以上の種別」
R8-123 12.25
年金の事務|2以上の種別の被保険者であった期間を有する者
厚生年金保険の被保険者には、次の4つの種別があります。
①第1号厚生年金被保険者 | ②③④以外の被保険者(民間企業の会社員など) |
②第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員 |
➂第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員 |
④第4号厚生年金被保険者 | 私立学校教職員 |
例えば、国家公務員から民間企業の会社員に転職した場合は、第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者の2種の種別の被保険者であった期間を有することになります。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の事務を行う実施機関をみていきます。
年金の種類 | 年金の事務 |
老齢厚生年金 | それぞれの加入期間ごとに 各実施機関が行う |
遺族厚生年金(長期要件) | |
障害厚生年金・障害手当金 | 初診日又は死亡日に加入していた 実施機関が行う |
遺族厚生年金(短期要件) |
では、過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。

【解答】
①【R6年出題】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、「各号の厚生年金被保険者期間ごと」に適用されます。第1号、第2号、第3号、第4号それぞれで区分して計算します。
「合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして」は誤りです。
※例えば、私立学校の教職員の期間が10年、民間企業の会社員の期間が30年ある場合の老齢厚生年金についてみてみましょう。
10年 | 30年 |
第4号厚生年金被保険者期間 | 第1号厚生年金被保険者期間 |
・第4号厚生年金被保険者期間(10年分)の老齢厚生年金
→日本私立学校振興・共済事業団が支給します
・第1号厚生年金被保険者期間(30年分)の老齢厚生年金
→厚生労働大臣が支給します
条文を読んでみましょう
法第78条の26(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例) ① 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第42条の規定(受給要件)を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。 ② 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第43条の規定(年金額)を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であった全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であった期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。 |
②【H28年出題】
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【解答】
②【H28年出題】 ×
「障害認定日」ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
条文を読んでみましょう
法第78条の33第1項(障害厚生年金等に関する事務の特例) ① 障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。 |
➂【H29年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】
➂【H29年出題】 ×
「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる」が誤りです。
※障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額について
→ その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額を計算します。
(法第78条の30)
10年 | 8年 |
第1号厚生年金被保険者期間 | 第4号厚生年金被保険者期間 ▲初診日 |
・ 初診日に第4号厚生年金被保険者ですので、障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じた実施機関=日本私立学校振興・共済事業団が行います。
・ 障害厚生年金の額は、日本私立学校振興・共済事業団が、第1号厚生年金被保険者期間に基づく年金額と第4号厚生年金被保険者期間に基づく年金額を合算して計算します。
なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算します。
④【R7年出題】
障害手当金の受給権者であって、当該障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関が行う。

【解答】
④【R7年出題】 ×
障害手当金も障害厚生年金と同様に、当該障害に係る「障害認定日」ではなく、「初診日」における被保険者の種別に応じて、厚生年金保険法第2条の5第1項各号に定める実施機関が行います。
(法第78条の33第1項)
⑤【H30年出題】
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

⑤【H30年出題】 〇
この問題のポイント!
・「短期要件の遺族厚生年金」です。
→ 障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(いわゆる長期要件には該当しないものとする。)の死亡
・「短期要件の遺族厚生年金」は「障害厚生年金」と同じ仕組みです。
短期要件の遺族厚生年金の額について
→ 2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。また、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算します。
(法第78条の32第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「財政」
R8-122 12.24
厚生年金保険の財政|財政の現況及び見通しの作成・調整期間
今回は厚生年金保険の財政についてみていきます。
条文を読んでみましょう
法第2条の4 (財政の現況及び見通しの作成) ① 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。 ② 財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。 ➂ 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
法第34条 (調整期間) ① 政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。 ② 財政の現況及び見通しにおいて、調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。 ➂ 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

【解答】
①【H30年出題】 〇
「財政均衡期間」は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間です。
②【R5年出題】
政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
政府は、少なくとも5年ごとに、「財政の現況及び見通し」を作成しなければならないとされていますので、遅くとも令和7年12月末ではありません。
なお、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しが公表され、その次は、令和6年に公表されています。
➂【R5年出題】
国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、モデル年金の所得代替率が100分の50を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとされている。この所得代替率の分母の基準となる額は、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額である。

【解答】
➂【R5年出題】 〇
「所得代替率」とは、「公的年金の給付水準を示す指標」で、現役男子の平均手取り収入額に対する年金額の比率によって表されます。
所得代替率→「夫婦2人の基礎年金+夫の厚生年金」/「現役男子の平均手取り収入額」
・2024年度について
「夫婦2人の基礎年金13.4万円+夫の厚生年金9.2万円」
「現役男子の平均手取り収入額37.0万円」
で、所得代替率は61.2%でした。
(参照:厚生労働省「令和6(2024)年財政検証結果の概要」より)
所得代替率の分母の基準となる額は、「現役男子の平均手取り収入額」ですので、当該年度の前年度の男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額となります。
(平16法附則第2条第1項第3号)
④【R7年出題】
政府は、国民年金事業に関する財政の現況及び見通し又は厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に当たり、その作成年のおおむね100年後に、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第2条第1項の規定によって算出するいわゆるモデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
政府は、財政の現況及び見通しの作成に当たり、「次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に」モデル年金の所得代替率が50%を下回ることが見込まれる場合、調整期間の終了について検討を行い、その結果に基づいて調整期間の終了その他の措置を講じなければならない、となります。
(平16法附則第2条第2項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「脱退一時金」
R8-121 12.23
厚生年金保険の脱退一時金の支給要件
国民年金法・厚生年金保険法には「脱退一時金」の制度があります。
「日本国籍を有しない者」が対象です。
国民年金・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し日本を出国した場合、要件を満たせば、脱退一時金の請求をすることができます。
今回は、「厚生年金保険」の脱退一時金の支給要件をみていきます。
条文を読んでみましょう
法附則第29条第1項、第2項(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) ① 当分の間、(厚生年金保険の)被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢年金の受給資格期間 (10年間)を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有するとき。 (2) 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。 (3) 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 ② 請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R3年出題】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【解答】
①【R3年出題】 〇
脱退一時金の請求ができる要件として
・最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日から2年を経過していないこと
※国民年金の被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を経過していないこと
があります。
問題文は、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した時点ですので、脱退一時金の請求は可能です。
②【H30年出題】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求できません。
➂【R7年出題】
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
日本の永住資格を有していても、脱退一時金を請求することは可能です。
<注意点>
※永住許可を受けた者については、当該者が20歳以上60歳未満の期間に限り、昭和36年4月1日から永住許可を受けるまでの海外在住期間も受給資格期間に含めて判断される(合算対象期間)とされています。合算対象期間を入れて受給資格期間が10年以上になる場合は、脱退一時金の支給要件を満たしません。
(参照:厚生労働省「脱退一時金等について」)
④【R2年出題】
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがある」ときは脱退一時金を受けることはできません。
「障害厚生年金の支給を受けたことがある」場合は、脱退一時金の支給は受けられません。
⑤【H26年出題】
日本国籍を有しない者について、障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがある」ときは脱退一時金を受けることはできません。
「障害手当金」は、政令で定める給付の中に含まれます。
そのため、障害手当金の受給権を有したことがある場合は、脱退一時金を請求することはできません。
(令第12条)
⑥【R1年出題】
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑥【R1年出題】 ×
かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、再度、所定の要件を満たした場合は、再度、脱退一時金の支給の請求をすることができます。
⑦【R7年出題】
脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
⑥の問題と同じです。
かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、再度、所定の要件を満たした場合は、再度、脱退一時金の支給の請求をすることができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「高齢任意加入被保険者」
R8-120 12.22
高齢任意加入被保険者|適用事業所と適用事業所以外を比較
事業所に使用される「70歳以上」で、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がない者は、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険に任意で加入することができます。
高齢任意加入被保険者は次の2種類に分かれます。
①適用事業所に使用される70歳以上の者
②適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者
①と②で、加入手続き等が異なりますが、今回は「保険料」の違いをみていきます。
適用事業所 | 適用事業所以外 |
□保険料は全額を被保険者が負担 □被保険者が保険料を納付する義務を負う ※事業主が同意した場合 ・事業主が半額負担し、納付する義務を負う | □事業主が半額負担し、納付する義務を負う |
□保険料を滞納した場合 ・初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす。 ・保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。 ※保険料について事業主の同意があるときは滞納による喪失はありません。 | □保険料を滞納した場合 事業主が納付義務を負っているため、滞納による喪失はありません。 |
(法附則第4条の3、第4条の5)
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

【解答】
①【R4年出題】 ×
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」については、保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき事業主の同意がない場合は、当該被保険者は保険料の全額を負担し、かつ、保険料の納付義務は当該被保険者が負います。「当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。」は誤りです。
(法附則第4条の3第7項)
②【H29年出題】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、
「当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること」ができます。
また、「当該被保険者の同意を得て、その同意を将来に向かって撤回すること」ができるとされています。
ただし、当該被保険者が「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」であるときは、この規定は適用しないとされています。
「第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。」は誤りです。
(法附則第4条の3第10項)
➂【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
「当該保険料の納期限の属する月の末日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その被保険者の資格を喪失します。
例えば、令和7年12月分の保険料の納期限は令和8年1月末日です。
保険料を滞納し、厚生労大臣が指定した期限までに保険料を納付しないときは、令和7年12月末日に資格を喪失します。
(法附則第4条の3第6項)
④【H27年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
④【H27年出題】 ×
「当該保険料の納期限の日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その資格を喪失します。
⑤【R7年出題】
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
厚生年金保険の「適用事業所以外の事業所」に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、保険料を納付する義務は事業主が負います。
(法附則第4条の5)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「老齢厚生年金の子の加給年金額」
R8-118 12.20
障害基礎年金・老齢厚生年金|子の加算額の関係
障害基礎年金の受給権者、老齢厚生年金の受給権者については、子があり、要件を満たす場合は、子の加算額が加算されます。
ただし、受給権者が「65歳以上」の場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給されることがあります。両方の年金に「子の加算額」が加算されている場合の調整についてみていきます。
(受給権者が65歳以上の場合)
老齢厚生年金
|
子の加給年金額(支給停止) |
障害基礎年金
|
子の加算額 |
老齢厚生年金の条文を読んでみましょう
法第44条第1項 (加給年金額) ① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
障害基礎年金の子の加算が支給され、その間、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。
では、過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
子の加算額が加算された障害基礎年金と当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給される場合は、障害基礎年金の子の加算額はそのまま加算され、老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。
②【R7年出題】
障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
②【R7年出題】 〇
①の問題と同じです。
老齢厚生年金について、子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「加給年金額」
R8-117 12.19
加給年金額を比較|老齢・障害
今回のテーマは「加給年金額」です。
老齢厚生年金と障害厚生年金の加給年金額について、取扱いを比較しましょう。
まず、老齢厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう。
法第44条第1項 (加給年金額) ① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
ポイント!
・老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が「240月」以上あること
・加給年金額の対象になるのは、「配偶者」・「子」です
・受給権を取得した当時に、受給権者によって生計を維持していたこと
・受給権を取得した当時240月未満でも、在職定時改定又は退職時改定の際に240以上となった場合は、「240以上」となった当時に、受給権者によって生計を維持していれば、加給年金額の対象となります。
次は、障害厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう
第50条の2第1項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 |
ポイント!
・1級・2級の障害厚生年金が対象
3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。
・加給年金額の対象になるのは「配偶者」のみ
「子」は障害基礎年金で加算の対象になります
・受給権を取得した後で、配偶者を有することになっても、加給年金額の対象となります。
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額は加算されません。
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した後で、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合は、加給年金額は加算されません。
②【R7年出題】
老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を取得した2年後に誕生した子は、加給年金額の加算の対象となりません。
➂【H21年出題】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

【解答】
➂【H21年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権発生当時に、障害状態にない子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるときは加給年金額の対象となります。ただし、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、加給年金額の加算は終わります。
その後に、その子が19歳ではじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合でも、加給年金額は加算されません。
④【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、被保険者資格を喪失した際に(退職時改定の際に)、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
⑤【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
障害厚生年金については、その受給権を取得した日の翌日以後に、新たにその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも加給年金額が加算されます。
その場合、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
⑥【H29年出題】
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
「子」については、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「失権」
R8-116 12.18
付加年金と寡婦年金の失権事由
今回は付加年金と寡婦年金の失権事由をみていきましょう。
まずは、付加年金の失権事由を条文で読んでみましょう
法第48条 (失権) 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
★ 付加年金は、老齢基礎年金と同じ「終身年金」です。
次は寡婦年金の失権事由を条文で読んでみましょう
法第51条 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 →第40条第1項 ・ 死亡したとき。 ・ 婚姻をしたとき。 ・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 法附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
付加年金及び寡婦年金にも失権が規定されています。
②【H25年出題】
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
付加年金は老齢基礎年金にプラスして支給されますので、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。
また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。
条文を読んでみましょう。
法第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 |
★ 「全額」がポイントです。「全部又は一部」ではありません。
➂【H24年出題】
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。

➂【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、寡婦が65歳に達したときに消滅します。寡婦が老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも同様です。
④【H24年出題】
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅します。ただし、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しません。
⑤【H23年出題】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止されるのではなく、寡婦年金の受給権は「消滅」します。
⑥【H26年出題】
寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】
⑥【H26年出題】 〇
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅します。
⑦【R4年出題】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

【解答】
⑦【R4年出題】 ×
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、受給権が消滅します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R8-115 12.17
基準障害|はじめて2級による障害基礎年金
■■「はじめて2級による障害基礎年金」とは?
・既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にある(障害等級に該当しない障害)
↓
・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に
↓
・基準障害と他の障害とを併合して、初めて、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に至った場合
↓
・障害基礎年金が支給されます。
簡単に言いますと
先にあった 障害 1・2級未満 |
+ | 新たに 発生した障害 (基準障害) |
→ | 初めて 1・2級に 該当 |
→ | 障害基礎年金が 支給される |
※基準障害について、初診日要件・保険料納付要件を満たしていること
※65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が1・2級に該当していること
では、条文を読んでみましょう。
法第30条の3 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者(初診日要件を満たしている)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 保険料納付要件は、「基準傷病」の初診日の前日で判断される。 ➂ ①の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】
①【R7年出題】 〇
ポイントを確認しましょう
・基準傷病の初診日に、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)である。(初診日要件を満たしている)
・基準傷病以外の傷病により障害の状態にある
・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に
・初めて、「基準障害」と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った
・基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以降であるときに限る
②【H18年出題】
既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

【解答】
②【H18年出題】 〇
「赤字」の部分がポイントです。
既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
➂【H29年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

【解答】
➂【H29年出題】 ×
いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、その請求は、65歳に達した日以後でも行うことができます。
④【H20年出題】
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】
④【H20年出題】 ×
「支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始」が誤りです。
・ いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権が発生します。
・ 当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができます。
・ 支給は当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から開始されます。
⑤【R6年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったときに受給権が発生します。65歳以降でも請求は可能です。また、請求によって受給権が発生するのではありませんが、支給は請求があった月の翌月からとなります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法(合算対象期間)
R8-114 12.16
昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した場合の合算対象期間
国民年金法がスタートしたのは昭和36年4月1日ですが、当初、外国人は適用が除外されていました。
外国人が、国民年金に強制加入となったのは、昭和57年1月1日以降です。
S36.4.1 | S57.1.1 |
国民年金適用除外 | 強制加入 |
今回は、昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した者に関する合算対象期間をみていきます。
日本国籍の取得以後は強制加入となりますが、日本国籍を取得する前の期間については、要件を満たせば合算対象期間になります。
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第8条第5項10号・11号 (10) 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかったため国民年金の被保険者とならなかった期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。) (11) (10)に掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から当該日本の国籍を取得した日の前日までの期間に係るもの |
過去問を解いてみましょう
①【H25年出題】
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】
①【H25年出題】 ×
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していた
20歳以上60歳未満の期間のうち
国民年金の適用除外だった昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前(昭和56年12月31日まで)の期間です。
昭和57年1月1日以後は、外国人でも強制加入になったため、合算対象期間にはなりません。
「昭和61年4月1日前の期間」が誤りです。
(昭60法附則第8条第5項第10号)
②【H25年出題】
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)
20歳以上60歳未満の期間のうち
昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。
(昭60法附則第8条第5項第11号)
➂【R7年出題】
昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
合算対象期間になります。
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)
20歳以上60歳未満の期間のうち
外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。
(昭60法附則第8条第5項第11号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法(障害基礎年金)
R8-113 12.15
障害基礎年金の額の改定ルール
障害基礎年金の等級には、「1級」と「2級」があります。
障害の程度は変わることもあり、障害の程度が増進又は軽減した場合は、障害基礎年金の額の改定が行われます。
条文を読んでみましょう。
法第34条 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ➂ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ④ 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したもの(初診日要件を満たしたもの)が、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ⑤ 第30条第1項ただし書の規定(保険料納付要件)は、④の場合に準用する。 ⑥ ①の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。 |
④その他障害との併合について
(例)2級の障害基礎年金の受給権者に
↓
「その他障害」が発生した。
※「その他障害」とは、1・2級に該当しないもの(3級以下)
初診日要件や保険料納付要件を満たしている
↓
2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合
↓
2級→1級に額の改定を請求できます
※ポイント!
65歳に達する日の前日までの間に請求することが条件です。
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。

【解答】
①【R7年出題】 ×
改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する「月」ではなく「翌月」から始められます。
②【R6年出題】
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して「1年6か月」ではなく、原則として、「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。
➂【R5年出題】
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】
➂【R5年出題】 〇
「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は除かれていることにも注意してください。
④【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」に当たります。
そのため、1年を経過した日後でなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができます。
(則第33条の2の2第1項第9号)
⑤【H29年出題】
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
1級から2級への改定、2級から1級への改定は、受給権者が65歳以上でも行われます。65歳未満の場合に限られません。
⑥【H26年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

【解答】
⑥【H26年出題】 ×
2級の障害基礎年金の受給権者に
↓
3級の障害(その他障害)が発生した。
※初診日に厚生年金保険の被保険者(=国年第2号被保険者)
↓
2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合でも
↓
額の改定は請求できません。
※初診日に66歳ですので額の改定請求はできません。
その他障害との併合により額の改定請求ができるのは、「65歳に達する日の前日までの間」に増進し、かつその期間内に請求することが条件です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「任意加入被保険者」
R8-111 12.13
任意加入被保険者の資格取得日
第2号被保険者でもなく、第3号被保険者でもなく、第1号被保険者にも該当しない者は、国民年金に「任意加入」することができます。
任意加入する目的は、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たすため」、「老齢基礎年金の額を増やすため(満額にするため・満額に近づけるため)」です。
任意加入被保険者の条文を読んでみましょう
法附則第5条第1項~第3項 (任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①の(1)又は(2)に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 ➂ 任意加入の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。 |
特例による任意加入被保険者についても条文を読んでみましょう
令和7法附則第40条第1項 (任意加入被保険者の特例) 昭和50年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
★任意加入被保険者の特例は、「65歳以上70歳未満」の者が対象です。
ポイントは「昭和50年4月1日以前生まれであること」、「老齢年金の受給権を有しないことです。
老齢年金の受給権がある場合は、特例の任意加入被保険者になることはできません。そのため、老齢基礎年金の額を増やす目的の場合は、特例の任意加入はできません。
では、過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」は任意加入することができます。
問題文の場合は、日本国籍を有していますので、日本国内に住所を有していなくても、老齢基礎年金を満額にするために任意加入被保険者の申出をすることができます。
②【R2年出題】
20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
②【R2年出題】 〇
保険料半額免除期間は老齢基礎年金の額の計算上、4分の3で計算されますので、問題文の条件ですと老齢基礎年金は満額になりません。
そのため、老齢基礎年金の額を増やすために、任意加入被保険者となることができます。
➂【R6年出題】
甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

【解答】
➂【R6年出題】 ×
任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満)は、「老齢年金の受給権を有しない者」が対象です。
甲は、受給資格期間を満たし老齢基礎年金の受給権がありますので、老齢基礎年金が満額でなくても、65歳以降は任意加入できません。
④【R7年出題】
国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得します。
最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得するという規定はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金の繰下げ」
R8-110 12.12
老齢基礎年金|特例的な繰下げみなし増額
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得しても、65歳で請求をしないで、66歳以後に繰り下げて受けることができます。
老齢基礎年金の額は、繰り下げた期間に応じて増額されます。
・ 繰下げ受給するつもりで、65歳で老齢基礎年金の請求を行わなかった場合、例えば、「68歳で繰下げの申出をして増額された老齢基礎年金を受ける」こともできますし、「68歳で繰下げの申出をしないで、「65歳到達時点」の本来の老齢基礎年金をさかのぼって請求する」こともできます。
★今日のテーマは、「特例的な繰下げみなし増額制度」です。
・特例的な繰下げみなし増額制度の趣旨を確認しましょう
繰下げ上限年齢の引上げに伴い、70歳に達した日後も繰下げ待機を選択することが可能になる一方で、年金給付に係る支分権の消滅時効は5年間である。こうした中では、繰下げ上限年齢を引き上げたとしても、70歳に達した日後の繰下げ待機を選択しにくくなってしまう。このような阻害要因を緩和する観点から、70歳に達した日後に繰下げ待機していた者が、65歳時点からの本来受給を選択した場合に、増額された年金の支給が可能となるよう、改正を行う(令和5年4月1日施行)。
(令4.3.29年管管発0329第14号)
「特例的な繰下げみなし増額制度」とは?
「70歳」に達した日より後に、「65歳からの本来の老齢基礎年金」をさかのぼって受けることを請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、請求した日の「5年前の日」に繰下げの申出があったものとみなされる制度です。その場合、「繰下げによって増額」された年金が一括で支払われます。
特例的な繰下げみなし増額制度について条文を読んでみましょう
法第28条第5項 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 80歳に達した日以後にあるとき。 (2) 65歳に達した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき。 |
★「80歳以後」に請求する場合、「請求の日の5年前の日以前に障害年金や遺族年金の受給権者となった」場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。

【解答】
①【R6年出題】 〇
「70歳」に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時(=繰下げの申出をしない時)は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなされ、増額された老齢基礎年金が支給されます。
例えば、73歳で老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げの申出をしないときは、請求の5年前の68歳で繰下げの申出をしたものとみなされます。その場合、3年繰下げとなり、3年分増額された老齢基礎年金が支給されます。
なお、繰下げみなし増額制度は原則として「昭和27年4月2日以後生まれの者」が対象です。
②【R7年出題】
老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過したときに消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。

②【R7年出題】 ×
「72歳に達した時点(=70歳に達した日より後)」で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、請求の5年前(=67歳時点)に繰下げの申し出があったものとみなして、増額された老齢基礎年金が支給されます。
「繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受ける」は誤りです。
➂【R7年出題】
繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
「繰下げ待機中の受給権者が年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡し、遺族が未支給年金を請求するときは、特例増額を適用せず、支分権が時効消滅していない過去5年分に限り支給することとする。
なお、特例増額が適用される本来請求をした日以後に受給権者が死亡した場合には、未支給年金にも特例増額が適用される。」とされています。
(令4.3.29年管管発0329第14号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金」
R8-109 12.11
老齢基礎年金を繰下げ受給するための条件
老齢基礎年金の受給権は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上有する者が、65歳に達したときに、発生します。
条文を読んでみましょう
法第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 ※10年の計算には合算対象期間も合算されます。 |
老齢基礎年金は繰り下げて受給することもできます。
条文を読んでみましょう
法第28条第1項 (支給の繰下げ) 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 ※他の年金たる給付とは ・国民年金の他の年金給付(付加年金を除く) ・厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。) |
過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」、繰下げの申出はできません。
他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。
障害基礎年金は国民年金の他の年金給付に該当します。
そのため、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。
②【R6年出題】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
「遺族厚生年金」は、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」に該当します。
「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に遺族厚生年金の受給権者となった」場合は、実際には遺族厚生年金は受給しなくても、支給繰下げの申出はできません。
➂【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

【解答】
➂【R1年出題】 〇
「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」となっていますので、「老齢厚生年金」の受給権者でも老齢基礎年金の繰下げの申出をすることは可能です。
④【R7年出題】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」繰下げの申出はできません。
他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。
問題文は、「他の年金給付(加給年金を除く。)」となっていますが、加給年金ではなく付加年金です。
又、支給繰下げの申出は、「65歳に達する前」にはできません。繰下げの申出ができるのは、「66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R8-108 12.10
遺族基礎年金|失権と支給停止を整理しましょう
遺族基礎年金の「失権」事由と「支給停止」について整理しましょう。
「失権」について条文を読んでみましょう
第40条 ① 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 ② 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、遺族基礎年金の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ➂ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、①によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (2) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (3) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (4) 20歳に達したとき。 |
②について
配偶者が遺族基礎年金を受けるには、「子」と生計を同じくしていることが要件で、配偶者が受ける遺族基礎年金には必ず「子」の加算が加算されています。
「子」の数が減ると、子の数に応じて加算額も減額されます。
ただし、「子」のすべてが減額事由に該当すると、「子」がいなくなるため、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
次に「支給停止」について条文を読んでみましょう
第41条 ① 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 ② 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 (第41条の2、第42条は今回は省略します) |
では、過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【R4年出題】 〇
夫の受給する遺族基礎年金の額は、1人分の子の加算額が加算された780,900円×改定率+224,700円×改定率です。
加算の対象になっている子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の要件を満たさなくなります。
夫は「子と生計を同じくする」という要件を満たさなくなるため、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅します。
②【H30年出題】
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
(子は18歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】
②【H30年出題】 ×
・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、「子の遺族基礎年金は支給停止」となります。
→ 法第41条第2項の「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。配偶者と子に受給権が発生した場合は、配偶者が優先するためです。
・妻が再婚した場合、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
→ 法第40条第1項第2号の「婚姻をしたとき」に該当し、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
・当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、「支給停止が解除される」は誤りで、子の遺族基礎年金は「支給が停止」されます。
→ 法第41条第2項の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。
子の遺族基礎年金は、母(問題文では妻)と引き続き生計を同じくしている場合は、その間、その支給が停止されます。
➂【H30年出題】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
(子は 18 歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】
➂【H30年出題】 ×
第2号被保険者である40歳の妻が死亡し、40歳の夫と子がいる場合、以下の年金の受給権が発生します。
40歳の夫 → 遺族基礎年金のみ
(年齢要件を満たさないため、遺族厚生年金は受けられません。)
子 → 遺族基礎年金と遺族厚生年金
「遺族基礎年金」については、配偶者が優先されますので、「夫」に遺族基礎年金が支給され、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
子には、遺族厚生年金のみ支給されます。
④【R5年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
・配偶者の遺族基礎年金について
配偶者の遺族基礎年金は、子が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」は、子の加算額が減額されます。(法第39法第3項第3号)
問題文のように、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子(=配偶者以外の者の養子)となった場合は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
・子の遺族基礎年金について
「養子となったとき」は遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、「直系血族又は直系姻族の養子」となったときは失権しません。問題文の子は、直系血族又は直系姻族の養子となっていますので、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
⑤【R7年出題】
夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
遺族基礎年金の受給権を有する妻が、「直系姻族と養子縁組」しても、妻の受給権は消滅しません。
子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「時効」
R8-107 12.09
国年の時効|「基本権」と「支分権」など
国民年金法の時効には、「2年」と「5年」があります。
特に、「年金給付」と「死亡一時金」の違いに注意しましょう。
国民年金の「給付」のうち、「年金給付」の時効は5年ですが、「死亡一時金」の時効は2年です。
条文を読んでみましょう。
法第102条 ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ➂ 年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法第31条の規定を適用しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
<給付の時効について>
・年金給付を受ける権利(基本権)→ 支給すべき事由が生じた日から5年
・支分権 → 支払期月の翌月の初日から5年
・死亡一時金 →行使することができる時から2年
過去問を解いてみましょう
①【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「死亡一時金」の時効が誤りです。
・年金給付を受ける権利 → その支給すべき事由が生じた日から5年
・死亡一時金を受ける権利 → 行使することができる時から2年
②【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②【R2年出題】 〇
支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利の時効の起算点は「支払期月の翌月の初日」です。
➂【R7年出題】
保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
第102条第5項で、「保険料その他この法律の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。」と規定されています。
保険料の徴収権の時効は、納期限の翌日から2年ですが、厚生労働大臣による督促は「時効の更新の効力」を有します。時効の進行がゼロに戻りますので、2年では消滅しません。
④【R7年出題】
失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
死亡一時金の時効の起算日は、「死亡日の翌日」です。
「失踪宣告」を受けた者に係る消滅時効の起算日については、「死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日」とされています。
ただし、「死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止の考え方に立って、一定期間加入したが、年金給付を受けることなく亡くなった方に対して一定の金額を支給するものである」ことを踏まえ、「失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する」とされています。
(平26.3.27年管管発0327第2号)
⑤【R7年出題】
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない」場合で、その後に障害の程度が増進したときは、「障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に事後重症の障害基礎年金の支給を請求する」ことによって事後重症の障害基礎年金を受けることができます。
事後重症の障害基礎年金は請求によって受給権が発生します。障害認定日から5年を経過する前に行わなければならないという規定はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険料免除」
R8-106 12.08
健康保険料の免除|産休・育休中
産前産後休業期間中・育児休業期間中は、事業主が申出をすることにより、保険料が免除されます。
用語の確認をしましょう。
・産前産後休業とは
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間
※出産の日が出産の予定日後であるとき(予定日より遅れた場合)は、その分、産前休業が延びます。
(例)出産の日が出産の予定日より3日遅れた場合
出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)+3日+出産の日後56日
・育児休業等とは
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業+育児休業に準じる休業)
条文を読んでみましょう
法第159条 ① 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
★(2)について
同じ月内に、開始日と終了日の翌日がある場合、育児休業等の日数が14日以上ある場合は、その月の保険料は免除されます。
下の図の場合は、12月の保険料は免除されます。
12月 | ||
| 育児休業(14日以上) |
|
★「その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。」の部分について
「賞与」については、連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に、免除されます。
下の図の場合、12月に賞与が支払われた場合は、賞与の保険料が免除されます。
12月 | 1月 | ||
| 育児休業(1か月超) |
| |
下の図の場合、12月に賞与が支払われても、賞与の保険料は免除されません。
12月 | 1月 | ||
| 育児休業(1か月以内) |
| |
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象となる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
5月16日が出産予定日の場合、産前休業は、予定日以前42日の4月5日が開始日です。産前休業を開始した日の属する月(=4月)から免除対象です。
実際の出産日が5月10日だった場合は、産前休業は出産日以前42日の3月30日が開始日です。そのため、産前休業を開始した日の属する月(=3月)から免除対象となります。
②【R5年出題】
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
免除の対象になるのは、産前産後休業を開始した日の属する月(=令和4年12月)からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月(=令和5年3月)の前月(=令和5年2月)までです。
➂【R7年出題】
被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月16日から5月10日までは産後休業です。
令和7年3月分は、「育児休業期間中」の保険料免除の対象ではありません。
④【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
問題文は、「育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合」に該当します。
育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月(=4月・4月1日が属する月)の前月(3月)までの期間中の保険料が免除されます。
⑤【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
「育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一」ですので、保険料の免除を受けるには、「当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上」必要です。
問題文の場合、育児休業等の日数が、令和5年1月4日~16日の「13日」しかありません。そのため、令和5年1月の保険料は免除されません。(徴収されます)
⑥【R4年出題】
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

【解答】
⑥【R4年出題】 〇
育児休業期間中の保険料が免除されている期間に支払われた賞与については、当該賞与に係る保険料は徴収されません。ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額に含まれます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「特定適用事業所」
R8-104 12.06
特定適用事業所|該当したとき・該当しなくなったとき
1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」に使用され、次の3つの要件を満たした場合は、健康保険の被保険者となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 賃金が月額88,000円以上 ➂ 学生でない |
今回は、「特定適用事業所」についてみていきます。
「特定適用事業所」の要件について条文を読んでみましょう
H24法附則第46条第12項 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。 |
※特定労働者とは、厚生年金保険の被保険者資格を有する者のことです。(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号の(適用除外)いずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの)
では、過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」とは
・ 適用事業所が法人事業所の場合、法人そのものを事業主として取り扱い、同一法人格に属する全ての適用事業所を「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」として取り扱うこととする。
・ 適用事業所が個人事業所の場合、個人事業主を事業主として取り扱い、事業主が同一である適用事業所は現在の適用事業所の単位のほかに無いものとして取り扱うこととする。
(令4.9.28保保発0928第6号)
②【R7年出題】
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは、法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
特定適用事業所となったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当届」を届け出ることとされています。
(則第23条の2)
➂【R7年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合でも「遡及取消にはなりません」とされています。
(令6.1.17事務連絡)
④【R6年出題】※改正による修正あり
被保険者の総数が常時50人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込があること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。

【解答】
④【R6年出題】 〇
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得については、労使合意に基づき、申出を行うことにより可能であるとされています。
(令4.9.28保保発0928第6号)
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」によると、以下の扱いになります。
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。
(令6.1.17事務連絡)
問題文のように、常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しません。
⑥【H29年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
年収が130万円未満の短時間労働者であっても、要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかの選択はできません。
(令6.1.17事務連絡)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「資格喪失後の死亡」
R8-103 12.05
資格喪失後の死亡|埋葬料・埋葬費が支給される場合
健康保険の被保険者の資格を喪失した後に死亡した場合でも、埋葬料又は埋葬費が支給されることがあります。
本題に入る前に、「埋葬料」と「埋葬費」の違いを確認しましょう。
| 支給対象 | 金額 |
埋葬料 | 被保険者により生計を維持していた者で、埋葬を行うもの | 5万円 |
埋葬費 | 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合で、埋葬を行った者 | 5万円以内で埋葬に要した費用(実費) |
条件を条文で読んでみましょう
法第105条 (資格喪失後の死亡に関する給付) 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
死亡日が資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内の場合は、埋葬料が支給されます。
★資格喪失後の死亡について埋葬料・埋葬費が支給されるのは次の3つの場合です。
①資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
②資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
➂被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
②【R7年出題】
被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
・被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものには「埋葬料」が支給されます。
・埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。
➂【R3年出題】
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

【解答】
➂【R3年出題】 ×
「埋葬を行う者は誰でも」が誤りです。
その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができるのは、「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「届出」
R8-102 12.04
介護保険第2号被保険者|該当したとき・該当しなくなったとき
介護保険の被保険者の定義を確認しましょう。(介護保険法第9条)
① 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) ② 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) ①、②のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者となります。 |
健康保険の被保険者が介護保険第2号被保険者の場合は、健康保険の保険料と合わせて介護保険料も徴収されます。
介護保険第2号被保険者に該当した・該当しなくなった場合は、原則として届出が必要です。
条文を読んでみましょう。
則第40条 (介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出) ① 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
則第41条 (介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出) ① 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
※被保険者が任意継続被保険者であるときは、「保険者」に届け出なければならない。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

【解答】
①【R4年出題】 ×
「65歳に達した」ことにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、届け出は不要です。
②【H29年出題】
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
「40歳に達した」ことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、届出は不要です。
➂【R7年出題】
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
「被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。」とは、40歳に達したことで介護保険第2号被保険者に該当したときは、届出は不要ということです。
④【H29年出題】
50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

【解答】
④【H29年出題】 〇
事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなって介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、事業主は、被保険者に代わって届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができます。
(則第40条第3項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険外併用療養費」
R8-101 12.03
保険外併用療養費|評価療養・患者申出療養・選定療養
保険外併用療養費の内容をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第86条第1項 (保険外併用療養費) 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 法第63条第2項 ・ 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) ・ 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) ・ 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) |
★評価療養、患者申出療養、選定療養は「療養の給付」には含まれません。
例えば、「先進医療」を受けた場合、「先進医療の部分」は保険外ですので、すべて本人が負担します。一般の診療と共通する「基礎的な部分」は、「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
では、過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。

【解答】
①【R7年出題】 〇
こちらの問題文では、「評価療養の給付の対象とすべきものであるか否か」となっていますが、条文では、「療養の給付の対象とすべきものであるか否か」と定められています。
令和7年問2の問題は、アからオの選択肢のうち、「誤っているものの組み合わせ」が問われた問題でした。こちらの問題以外に明らかに「誤っているものの組み合わせ」がありました。
そのため、こちらの問題は「〇」で正解となります。
このように誤りかどうか判断に迷う問題は、明らかに誤っている(=誤りの判断が簡単につく)方を選んでください。
②【R2年出題】
患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

【解答】
②【R2年出題】 〇
「患者申出療養」制度について、厚生労働省のホームページでは以下のように案内されています。
未承認薬などをいちはやく使いたい。対象外になっているけれど治験を受けたい。
そんな患者さんたちの思いに応えるためにつくられた制度です。
患者さんからの申出を受け、医師や関連病院などが連携して、さまざまなケースについて対応できるかどうかを検討し、実施の可能性を探ります。
事前の診療計画や治療の経過などのデータは、今後多くの人が受けることのできる保険診療のために活用されます。
なお、医療法第4条の3では、「病院であって、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する一定の要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。」と規定されています。
➂【R4年選択式】
保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定されている選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が< A >の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が< B >を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
(選択肢)
⑤90日 ⑥120日 ⑧150日 ⑩180日
⑦150以上 ⑨180以上 ⑪200以上 ⑫250以上

【解答】
<A> ⑪200以上
<B> ⑩180日
④【R6年選択式】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、< A >、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
(選択肢)
②新たな医療技術、医薬品、医療器等によるものであることから
⑤患者に対する情報提供を前提として
⑨困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として
⑱保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に適合するとともに

【解答】
<A> ⑤患者に対する情報提供を前提として
(令6.3.27保発0327第10号)
⑤【H28年出題】
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
予約に基づく診察は、選定療養の対象となります。
特別料金は、全額自己負担となります。
(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条)
⑥【R4年出題】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
被保険者が支払う額は、
「保険診療30万円」×30%=9万円
+
「選定療養10万円」
=19万円です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険料額」
R8-100 12.02
<令和8年改正>一般保険料等額と介護保険料額
健康保険の被保険者に関する保険料額についてみていきます。
「介護保険第2号被保険者」と「それ以外」で保険料額が変わります。
条文を読んでみましょう。
法第156条(被保険者の保険料額) ※令和8年4月1日改正 ① 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額 (2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料等額 ② 介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 ➂ 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。 |
★令和8年4月の改正について
→ 医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料や介護保険料とあわせて、子ども・子育て支援金を徴収することになります。
健康保険法では、保険料の規定に、一般保険料率と区分して「子ども・子育て支援金率」が規定されます。
介護保険第2号被保険者である被保険者 | 介護保険第2号被保険者以外の被保険者 |
一般保険料等額 + 介護保険料額 | 一般保険料等額 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】※改正による修正あり
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

【解答】
①【R7年出題】 〇
例えば、35歳の被保険者は、介護保険第2号被保険者ではありませんので、保険料額は「一般保険料等額」のみです。
しかし、35歳の被保険者に43歳の被扶養者(=介護保険第2号被保険者に該当)がいる場合は、その35歳の被保険者(特定被保険者)に関する保険料額を、「一般保険料等額と介護保険料額との合算額」とすることができるという規定です。
「健康保険組合」限定の規定ですので、注意しましょう。
(法附則第7条)
②【R1年出題】
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

【解答】
②【R1年出題】 〇
厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合限定の規定です。
介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができます。
介護保険料額は、標準報酬月額・標準賞与額に「介護保険料率」を乗じて計算することが原則です。
問題文の「特別介護保険料額」は、原則の方法ではなく、「定額」で算定する方法です。
(法附則第8条)
➂【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
➂【H29年出題】 〇
「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と規定されています。
前月から引き続き被保険者である者が、7月26日に資格を喪失した場合、7月分の保険料は算定されません。
そのため、7月10日に賞与を30万円支給され、支給後の同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した場合は、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。
(法第156条第3項)
④【R4年出題】※改正による修正あり
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料等額とともに介護保険料額を控除することができる。

【解答】
④【R4年出題】 〇
健康保険法で一般保険料等額とともに介護保険料額が徴収されるのは、「介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)」です。
・介護保険料額の徴収の始まり
「40歳に達したとき(40歳の誕生日の前日)」から対象です。
「40歳に達した日が属する月」から介護保険料額が徴収されます。
問題文は、40歳に達した6月分から介護保険料額が徴収されますので、6月10日支払の賞与からも介護保険料額が徴収されます。
★徴収の終わりも確認しましょう。
「介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。(原則)」とされています。
「65歳に達したとき」から、介護保険第1号被保険者となります。そのため、健康保険では介護保険料額は徴収されなくなります。
例えば、12月2日が65歳の誕生日の場合は、介護保険第2号被保険者でなくなる12月1日が属する「12月分」から、保険料額は「一般保険料等額」のみとなります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「時効」
R8-099 12.01
健康保険の時効は2年/起算日にも注意
健康保険の時効をみていきます。
条文を読んでみましょう
法第93条 (時効) ① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。

【解答】
①【R6年出題】 〇
徴収権の消滅時効の起算日について確認しましょう。
・保険料 → その保険料の納期限の翌日
・保険料以外の徴収金 → 徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日
(昭3.7.6保発第514号)
②【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
現物給付については、時効の対象となりません。
➂【H27年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。

【解答】
➂【H27年出題】 〇
傷病手当金・出産手当金を受ける権利の消滅時効は2年です。
起算日は、傷病手当金は「労務不能であった日ごとにその翌日」、出産手当金は「労務に服さなかった日ごとにその翌日」です。
(昭30.9.7保険発199の2)
④【R1年出題】
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
④【R1年出題】 ×
出産手当金を受ける権利は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅します。
(昭30.9.7保険発199の2)
⑤【H30年出題】
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
コルセット装着に係る療養費については、コルセットの代金を支払った日が「療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日」です。そのためコルセットの代金を支払った日の翌日が時効起算日です。
(昭31.3.13保文発1903号)
⑥【H28年出題】※改正による修正あり
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
「高額療養費」の時効の起算日が誤りです。
(消滅時効の起算日について)
・療養費 → 療養に要した費用を支払った日の翌日
・高額療養費 → 診療月の翌月の1日
※診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日
・高額介護合算療養費 → 計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日
(昭31.3.13保文発1903号、昭48.11.7/保険発第99号/庁保険発第21号/、平21.4.30保保発第0430001号)
⑦【R7年出題】
被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解されています。
(昭31.12.24保文発第11283号)
⑧【R7年出題】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

【解答】
⑧【R7年出題】 ×
出産育児一時金の時効は、出産した日の翌日から起算して「2年」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険給付の制限」
R8-097 11.29
正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき
「正当な理由」なしに、療養に関する指示に従わない場合は、保険給付が制限されます。
条文を読んでみましょう
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 |
ポイント!
・行わないことができるのは、「全部又は一部」ではなく「一部」です。
・第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用されます。(法第122条)
過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

【解答】
①【H22年出題】 ×
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。
②【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。
➂【R2年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

【解答】
➂【R2年出題】 〇
★ 「療養の指示に従わない者」とは、次に該当する者とされています。
・ 保険者又は療養担当者の療養の指示に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)
・ 診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる者
(昭26.5.9保発第37号)
④【R7年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意思表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。

【解答】
④【R7年出題】 ×
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「損害賠償請求権」
R8-096 11.28
損害賠償請求権の代位取得と保険給付の免責
第三者の行為によって生じた事故については、「健康保険の保険給付」と「第三者からの損害賠償」が重なる不合理を避けるため、保険者の「損害賠償請求権の代位取得」と保険給付の「免責」の制度が設けられています。
条文を読んでみましょう。
法第57条 (損害賠償請求権) ①保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 |
①について(保険者が損害賠償請求権を代位取得する)
・保険者が保険給付を行った
↓
・その給付の価額の限度において、「保険給付を受ける権利を有する者」が第三者に対して有する損害賠償請求権を、保険者が代位取得する
↓
・保険者から第三者に対して損害賠償を請求する
②について(保険給付の免責)
・「保険給付を受ける権利を有する者」が第三者から損害賠償を受けた
↓
・その価額の限度において、保険者は保険給付を行う責任を免れる
では、過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「30日以内」ではなく「遅滞なく」です。
療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じた場合は、届出が必要です。
療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければなりません。
(則第65条)
②【H28年出題】
被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
保険給付を受ける権利を有する者には、「給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。」とされています。
被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できます。
➂【H27年出題】
犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。

【解答】
➂【H27年出題】 〇
「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。
また、犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際に、医療保険の保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところもあるようですが、この誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも医療保険の給付は行われます。」とされています。
(平26.3.31/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)
④【R7年出題】
自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)による給付の関係について、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として「医療保険の給付を行わないということはできない。」とされています。
「自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自賠責保険による給付の関係については、自動車事故による被害の賠償は自動車損害賠償保障法では自動車の運行供用者がその責任を負うこととしており、被害者は加害者が加入する自賠責保険によってその保険金額の限度額までの保障を受けることになっています。その際、何らかの理由により、加害者の加入する自賠責保険の保険者が保険金の支払いを行う前に、被害者の加入する医療保険の保険者から保険給付が行われた場合、医療保険の保険者はその行った給付の価額の限度において、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得し、加害者(又は加害者の加入する自賠責保険の保険者)に対して求償することになります。
一方で、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じ得ます。このような場合であっても、偶発的に発生する予測不能な傷病に備え、被保険者等の保護を図るという医療保険制度の目的に照らし、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として医療保険の給付を行わないということはできません。」とされています。
(平26.3.31/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「高額療養費」
R8-095 11.27
マイナ保険証で変わること/高額療養費の限度額適用認定証との関係
最初に、マイナ保険証についての通知を読んでみましょう。
医療保険制度においては、被保険者の所得区分に応じて自己負担限度額を設定し、医療機関等に支払う一部負担金等の金額が自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する高額療養費制度を設けている。 高額療養費については、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に、翌月以降に支給されること(償還払い)となっているところ、健康保険法施行規則第103条の2第2項等の規定に基づき、被保険者からの申請に応じて医療保険者等が交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)を医療機関等の窓口で提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっている。 この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されるといったメリットがあることを周知するため、限度額適用認定証等の様式について所要の改正を行う。 (令6.3.28保発0328第6号) |
※マイナ保険証とは、「健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード」のことです。
※「自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される」とは、自己負担限度額を超える部分は、現物給付されるということです。
では、過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。

【解答】
①【R5年出題】 ×
高額療養費は、診療報酬請求明細書(レセプト)に基づいて支給されます。
被保険者からの請求書に証拠書類を添付することについては、義務づけられていません。
(昭48.11.7保険発第99号・庁保険発第21号)
②【R7年出題】
高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。

【解答】
②【R7年出題】 〇
高額療養費の現物給付を受ける方法は次の2つです。
①医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する
②マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)により保険資格の確認を行う場合
※マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等を提示しなくても、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。
(令6.3.28保発0328第6号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「高額療養費」
R8-094 11.26
高額療養費の計算ルールを攻略しましょう/自己負担限度額の出し方がポイント!
「高額療養費」とは?
→ 医療機関の窓口で支払った一部負担金等が、月単位の高額療養費算定基準額(=自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が、事後に支給される制度です。
※現物給付される仕組みもあります。
(例)70歳未満・標準報酬月額28万円の被保険者、ある月の一部負担金が30万円
医療費(100万円) | ||
一部負担金30万円 | 保険給付(療養の給付) | |
自己負担限度額 87,430円 | 高額療養費 | |
①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は次のように計算します。
=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円
②一部負担金から高額療養費算定基準額をマイナスした額が、高額療養費として支給される額です。
高額療養費=30万円-8万7430円=21万2570円
★ポイント!
高額療養費は、暦月単位(1日から月末)で算定します。
例えば、令和7年11月27日~同年12月20日まで入院した場合は、11月27日~30日と12月1日~20日までに分けて算定します。
今回は、「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」・「高額療養費」の算定ルールをみていきましょう。
ポイントを過去問で確認しましょう
①【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「食事療養標準負担額」、「生活療養標準負担額」、「保険外併用療養に係る自己負担分(例えば差額ベッド代や先進医療にかかる費用等)」は、高額療養費の算定対象になりません。
(令第41条)
②【R7年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
同一の月に同一の保険医療機関で、「入院」と「通院」で療養を受けた場合は、同一の保険医療機関で受診したとしても、高額療養費の算定上、それぞれ「別個の保険医療機関」で受けた療養とみなされます。
(昭48.10.17保険発第95号・庁保険発第18号)
➂【H27年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】
➂【H27年出題】 ×
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、「内科」と「歯科」は、それぞれ区別して高額療養費が算定されます。
(昭48.10.17保険発第95号・庁保険発第18号)
④【H29年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

【解答】
④【H29年出題】 〇
同一月内で「全国健康保険協会管掌健康保険」から「組合管掌健康保険」に移った場合の高額療養費は、それぞれの「管掌者ごと」にその月の高額療養費の支給要件の判定が行われます。
(昭48.11.7保険発第99号・庁保険発第21号)
⑤【H27年出題】
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、「70歳未満」か「70歳以上75歳未満」で区分されます。
また、所得によっても区分されています。
問題を解くときは注意しましょう。
⑥【R2年選択式】
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。
(選択肢)
① 7,330円
② 84,430円
➂ 125,570円
④ 127,670円

【解答】
⑥【R2年選択式】
<A> ➂125,570円
ポイント!
・医薬品など評価療養に係る特別料金10万円、室料など選定療養に係る特別料金20万円は、高額療養費の算定には入りません。
医療費(70万円) | ||
一部負担金21万円 | 保険給付(療養の給付) | |
自己負担限度額 84,430円 | 高額療養費 | |
①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は次のように計算します。
=80,100円+(700,000円-267,000円)×1% = 84,430円
②一部負担金から高額療養費算定基準額をマイナスした額が、高額療養費の額です。
高額療養費=21万円-84,430円=12万5570円
⑦【R5年出題】
71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
70歳以上75歳未満の市町村民税非課税者である被保険者の外来の高額療養費算定基準額は「8,000円」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「被扶養者」
R8-093 11.25
<令和7年改正>健康保険の「被扶養者の収入要件」130万/150万/180万
健康保険の被扶養者となるための認定対象者の年間収入要件をみていきましょう。
★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
(1)認定対象者の年間収入が130万円未満
※認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)
かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) (1)の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。
★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
・認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
★扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合(改正)
→扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合は、「130万円未満」が「150万円未満」となります。なお、被保険者の「配偶者」はこの扱いから除かれます。
(R7.7.4保発0704 第1号 、年管発0704第1号)
では、過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】※改正による修正あり
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者※」という。)が日本国内に住所を有し、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
※本問の認定対象者については、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)は除く。

【解答】
①【R1年出題】 〇
認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は障害者である場合にあっては180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされます。
ただし、上記の要件を満たさなくても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないとされています。
ちなみに、認定対象者が、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者は除く。)の場合は、「130万円」は「150万円」となります。
②【R7年出題】
被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳、障害者ではない。)は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
問題文の母の年収は、遺族年金100万円+給与120万円=220万円です。
認定対象者の年収要件の「130万円未満」を満たしていませんので、母は、被保険者の被扶養者になることはできません。
③【R7年出題】
被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。

【解答】
③【R7年出題】 〇
問題文の父は、「60歳以上」で「年収180万円未満」(老齢年金の年額が130万円)の要件を満たしています。
かつ、父の年収が、認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合の要件である「被保険者からの援助による収入額より少ない」(被保険者から年額150万円の援助を受けている)要件も満たしています。
また、父は日本国内に住所を有しているため、父は、原則として被扶養者に該当します。
④【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者と同一世帯に属しておらず、日本国内に住所を有する年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。

【解答】
④【H26年出題】 ×
「その援助の額にかかわらず」が誤りです。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年収が「被保険者からの援助による収入額より少ない」ことが要件です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働に関する一般常識「労働契約法」
R8-092 11.24
「労働契約法」判例からの問題を読んでみましょう
今回は、判例をみていきます。
<テーマ>
①配置転換について労働者の同意は必要かどうか?
②在籍出向で復帰を命ずるには労働者の同意が必要かどうか?
➂在籍出向の命令には労働者の同意が必要かどうか?
では、さっそく過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。

①【R7年出題】 〇
・労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合
↓
・使用者は、労働者の個別的同意なしに合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない
と解されます。
(滋賀県社会福祉協議会事件 令和6.4.26最二小)
②【R7年出題】
「労働者が使用者(出向元)との間の雇用契約に基づく従業員たる身分を保有しながら第三者(出向先)の指揮監督の下に労務を提供するという形態の出向(いわゆる在籍出向)が命じられた場合において、その後出向元が、出向先の同意を得た上、右出向関係を解消して労働者に対し復帰を命ずるについては、原則として当該労働者の同意を得る必要があるものと解すべきである。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
②【R7年出題】 ×
使用者が労働者に対し、雇用契約上の身分を保有させながら第三者の指揮監督の下に労務を提供させる形態のいわゆる在籍出向を命じている場合に、右出向関係を解消して復帰を命ずるためには、特段の事由のない限り、「当該労働者の同意を得ることを必要としない。」とされています。
※「労働者が出向元の指揮監督の下に労務を提供するという当初の雇用契約における合意自体には何らの変容を及ぼさず、右合意の存在を前提とした上で、一時的に出向先の指揮監督の下に労務を提供する関係となっていたにすぎないものというべきであるからである。」とされています。
(古河電気工業事件 昭和60.4.5最二小)
➂【H28年出題】
いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
➂【H28年出題】 ×
「在籍出向」においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下においては、使用者は、当該労働者に対し、「個別的同意を得ることなし」に出向命令を発することができるとされています。
(新日本製鐵事件 平成15.4.18最二小)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「船員保険法」
R8-090 11.22
船員保険の行方不明手当金
船員保険法の「行方不明手当金」をみていきましょう
行方不明手当金について条文を読んでみましょう
法第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
法第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
法第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
法第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
行方不明手当金は
・被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき
・被扶養者に対し支給されます。
・行方不明の期間が1か月未満であるときは、支給されません
・行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません
②【R7年出題】
船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

【解答】
②【R7年出題】 ×
行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額です。
➂【H23年出題】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

【解答】
➂【H23年出題】 ×
行方不明となった日「の翌日」から起算して「3か月」が限度とされます。
④【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】
④【R3年選択式】
<A> 被扶養者
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働に関する一般常識「労働契約法」
R8-089 11.21
労働契約法を読んでみましょう
今日のテーマになる条文を読んでみましょう
法第3条第2項 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
法第4条 ① 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 ② 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。
法第18条第1項 (有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換) 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。)の契約期間を通算した期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。 |
★第18条について
例えば、有期労働契約の期間が1年で、更新している場合
5年 |
1年 |
無期 労働契約 | ||||
1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | ||
|
|
|
|
| 無期転換 申込み権 発生 | |
過去問を解いてみましょう
①【H27年出題】
労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。

①【H27年出題】 ×
「労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、いわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡も含まれる。同項を踏まえて、多様な正社員についていわゆる正社員との均衡を図ることが望ましい」とされています。
(H26.7.30基発0730第1号)
②【R7年出題】
労働契約法第3条第2項は、労働契約の締結又は変更に当たり、均衡を考慮することが重要であることから、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が、労働契約を締結し、又は変更する場合には、就業の実態に応じて、均衡を考慮すべきものとするという「均衡考慮の原則」を規定しているが、この考慮すべき均衡には、異なる雇用形態間の均衡も含まれる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第2項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「均衡考慮の原則」を規定していることから、多様な正社員といわゆる正社員の間の処遇の均衡にも、かかる原則は及ぶものであるとされています。
(H26.7.30基発0730第1号)
➂【R7年出題】
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と定めているが、これには労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであり、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものである。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
法第4条第1項は、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面や、労働契約が締結又は変更されて継続している間の各場面が広く含まれるものであること。これは、労働基準法第15条第1項により労働条件の明示が義務付けられている労働契約の締結時より広いものであるとされています。
(平成24.8.10基発0810第2号)
④【R6年出題】
労働契約法第18条第1項によれば、労働者が、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下本肢において同じ。)の契約期間を通算した期間が5年を超えた場合には、当該使用者が、当該労働者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなすこととされている。

【解答】
④【R6年出題】 ×
法第18条第1項は、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える有期契約労働者が、使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者が当該申込みを承諾したものとみなされ、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される無期労働契約が成立することを規定したものです。
(平成24.8.10基発0810第2号)
「使用者が、労働者に対し、期間の定めのない労働契約の申込みをしたものとみなす」規定はありません。
⑤【R7年出題】
労働契約法第18条第1項に基づき、有期契約労働者が無期労働契約への転換を申し込むことができる権利(以下本肢において「無期転換申込権」という。)が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、引き続き有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能である。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
無期転換申込権が生じている有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に無期転換申込権を行使しなかった場合であっても、再度有期労働契約が更新された場合は、新たに無期転換申込権が発生し、有期契約労働者は、更新後の有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期転換申込権を行使することが可能です。
(平成24.8.10基発0810第2号)
⑥【R3年出題】
有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、労働契約法第18条第1項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、無期労働契約への転換後も従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解されています。
(平成24.8.10基発0810第2号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「特例納付保険料」
R8-088 11.20
特例納付保険料の納付
「労働保険料」には次の種類があります。
① 一般保険料
② 第1種特別加入保険料
➂ 第2種特別加入保険料
④ 第3種特別加入保険料
⑤ 印紙保険料
⑥ 特例納付保険料
今回は「特例納付保険料」をみていきます。
「特例納付保険料」は、雇用保険法の「特例対象者」に関する保険料です。
★「特例対象者」とは
事業主が、ある人について、雇用保険の「被保険者資格取得」の届出を行わなかった場合、その人は、雇用保険に未加入となります。
未加入のままだと、例えば、その人が離職した際に、基本手当が受給できなくなる可能性もあります。
その後、資格取得の届出をし、被保険者であったことが確認された場合は、通常は2年前まで遡及して雇用保険に加入することができます。(保険料の徴収時効が2年であるため)
2年を超えた期間については遡及することができませんので、基本手当の所定給付日数の算定などについて不利益が生じることがあり得ます。
ただし、雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された場合は、2年を超えて(雇用保険料の控除が確認された時点まで)遡及して加入することができます。(=特例対象者といいます)
<流れをイメージしましょう>
・事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に適用されていなかった者について
↓
・被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合
↓
・保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い時期まで被保険者期間や所定給付日数を決定する算定基礎期間等に算入することができます。
(雇用保険法第14 条第2 項第2号、第 22条第5項)
★当該労働者を雇用していた事業主が、必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合
↓
・事業主が保険料を納付していないにもかかわらず失業等給付が支給されることになる
↓
・当該事業主は、保険料の徴収時効である2年経過後においても、保険料が納付できることになっています。(=特例納付保険料)
(徴収法第 26条)
(参照:行政手引25001)
「特例納付保険料」について条文を読んでみましょう
徴収法第26条 (特例納付保険料の納付等) ① 特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立の届出をしていなかった場合には、当該事業主(以下「対象事業主」という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が納付する義務を履行していない一般保険料(被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。 ② 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 ➂ 対象事業主は、勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。 ④ 政府は、申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。 ⑤ 対象事業主は、申出を行った場合には、期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付しなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。

【解答】
①【R7年出題】(雇用) ×
特例納付保険料を納付することができる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主です。
ただし、特例対象者は、「2年以内」ではなく、「2年を超えて」(事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された時点)遡及できる者です。
②【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。

【解答】
②【R7年出題】(雇用) 〇
概算・確定保険料の納付手続に係る規定は、特例納付保険料の納付手続には、適用されません。
➂【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】(雇用) 〇
「対象事業主は、勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。」とされています。
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければなりません。
(則第58条)
④【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。

【解答】
④【R7年出題】(雇用) 〇
労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができます。
(法第33条)
⑤【R3年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法第21条の追徴金の額を加算して求めるものとされている。

【解答】
⑤【R3年出題】(雇用) ×
特例納付保険料の納付額は、特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額を加算したものです。
法第21条の追徴金の額を加算して求めるものではありません。
(則第56条、第57条)
⑥【H27年出題】(雇用)
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。

【解答】
⑥【H27年出題】(雇用) 〇
事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、通知します。
納付書ではなく「納入告知書」による点もポイントです。
(則第38条第5項、則第59条)
⑦【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。

【解答】
⑦【R7年出題】(雇用) 〇
特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏です。
(則第38条第3項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「審査請求など」
R8-087 11.19
労働保険徴収法「不服申立て」
労働保険徴収法には、不服申立ての規定がありません。
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、「行政不服審査法」に基づいて、審査請求を行います。
図でイメージしましょう
<パターン1>
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者 | ||
| ↓ 審査請求 | |
厚生労働大臣 |
| |
↓ | ||
処分の取消しの訴え(裁判所に提訴する) | ||
<パターン2>
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者 | ||
| ↓ | |
↓ |
| |
↓ | ||
処分の取消しの訴え(裁判所に提訴する) | ||
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

【解答】
①【H28年出題】(労災) ×
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、「厚生労働大臣」に対し、「審査請求」を行うことができます。
(行政不服審査法第4条第3号)
②【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

【解答】
②【H28年出題】(労災)×
労働者災害補償保険審査官ではなく「厚生労働大臣」に対し、審査請求を行うことができます。
➂【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

【解答】
➂【H28年出題】(労災) ×
厚生労働大臣に対し、再審査請求ではなく「審査請求」を行うことができます。
④【R7年出題】(雇用)
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分について不服がある者は、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
④【R7年出題】(雇用) ×
所轄都道府県労働局の労働保険審査官ではなく「厚生労働大臣」に対して審査請求をすることができます。
⑤【R2年出題】(雇用)
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

【解答】
⑤【R2年出題】(雇用) ×
審査請求期間については以下のように規定されています。
行政不服審査法第18条 ① 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ② 処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 |
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。ただし、正当な理由があるときは、審査請求期間を超えても審査請求することができます。
「審査請求期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない」は誤りです。
⑥【R7年出題】(雇用)
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、当該処分があったことを知った日から3か月以内かつ処分の日から1年以内でなければ、取消訴訟を提起することができない。

【解答】
⑥【R7年出題】(雇用) ×
出訴期間については以下のように規定されています。
行政事件訴訟法第14条 ① 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ② 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 |
問題文の「3か月」は「6か月」となります。
⑦【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

【解答】
⑦【H28年出題】(労災) 〇
行政事件訴訟法第8条で、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。」と規定されています。
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、審査請求を経なくても、直ちにその取消しの訴えを提起することが可能です。
⑧【R7年出題】(雇用)
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経た後でなければ、当該処分の取消しの訴えを提起することができない。

【解答】
⑧【R7年出題】(雇用) ×
⑦の問題と同じです。
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経なくても、当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「任意適用事業」
R8-086 11.18
雇用保険の暫定任意適用事業
雇用保険は「労働者が雇用される事業を適用事業とする。」と規定されています。
(法第5条)
労働者を1人でも雇用すると、強制的に雇用保険の適用事業となります。
ただし、農林水産業の一部については任意適用事業となります。
条文を読んでみましょう
法附則第2条 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、任意適用事業とする。 (1) 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 (2) 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)
令附則第2条 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。 |
★ 農林水産の事業のうち常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村等及び法人の事業を除く。)は、当分の間、任意適用事業とされます。
★ 船員を雇用する事業は、農林水産業の事業であっても、原則として、強制適用事業となります。※雇用保険法施行令第2条各号に掲げる漁船(特定漁船)以外の漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除きます。
★ 暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日にその事業につき雇用保険に係る保険関係が成立します。
(行政手引20101)
では、過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)」は、任意適用事業から除かれています。
「法人」とは、私法人、公法人、特殊法人、公益法人、中間法人(協同組合等)、営利法人(会社)を問わず、法人格のある社団、財団のすべてが含まれるとされています。
そのため、公益財団法人である事業主の事務所は、任意適用事業ではありません。
(行政手引20104)
②【R7年出題】
年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
任意適用事業になるのは、「常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業」です。
「常時5人以上」とは、一の事業において雇用する労働者の数が年間を通じて5人以上であることをいいます。
したがって、ごく短期間のみ行われる事業、あるいは一定の季節にのみ行われる事業(いわゆる季節的事業)は、通常「常時5人以上」には該当しません。
問題文の、年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合は、「常時5人以上」には該当しませんので、任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができます。
(行政手引20105)
➂【R7年出題】
雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該「認可があった日(当日)」にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立します。
(徴収法附則第2条)
④【R7年出題】
常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「労働者の退職等により労働者の数が5人未満となった場合であっても、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模等からみて5人未満の状態が一時的であると認められるときは、5人以上として取り扱う。」とされています。
問題文の場合、5人未満の状態が一時的ですので、任意適用事業にはなりません。
(行政手引20105)
⑤【R7年出題】
1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「5人の計算に当たっては、法第6条第1号から第5号までに該当し法の適用を受けない労働者も含まれる。したがって、日雇労働者も含めて計算する。
ただし、「法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業については、その数のいかんにかかわらず、適用事業として取り扱う必要はない。」とされています。
問題文の場合は、雇用保険の適用が除外される1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者も5人の計算に入ります。労働者数が8人ですので、暫定任意適用事業ではありません。
(行政手引20105)
⑥【R4年出題】
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営する場合、それぞれの部門が独立した事業と認められるときであっても当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
事業主が適用事業に該当する部門と暫定任意適用事業に該当する部門とを兼営している場合は、次によって取り扱われます。
・それぞれの部門が独立した事業と認められる場合は、適用部門のみが適用事業となる。
・一方が他方の一部門にすぎず、それぞれの部門が独立した事業と認められない場合であって、主たる業務が適用部門であるときは、当該事業主の行う事業全体が適用事業となる。
(行政手引20106)
問題文のように、それぞれの部門が独立した事業と認められるときは、適用部門のみが適用事業となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「教育訓練給付」
R8-085 11.17
教育訓練給付金の支給要件・額など
「失業等給付」は、
①求職者給付
②就職促進給付
➂教育訓練給付
④雇用継続給付
で構成されています。(法第10条)
今回は、③教育訓練給付についてみていきます。
教育訓練給付金の対象になる「教育訓練」は次の3種類です。
専門実践教育訓練 | 中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練 (例)介護福祉士、看護師など |
特定一般教育訓練 | 速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練 (例)介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修など |
一般教育訓練 | 雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練 (例)社会保険労務士、Webクリエイターなど |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。

【解答】
①【R7年出題】 ×
一般教育訓練の教育訓練給付金の額の上限は10万円です。
・一般教育訓練給付金の支給額
→ 一般教育訓練の受講のために支払った費用の20%
→ 20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円
4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
・一般教育訓練給付金は一時金として支給されます。
・教育訓練経費とされるのは、指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費で最大1年分)
(行政手引58014)
②【R7年出題】
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
<教育訓練経費とされるもの>
・指定教育訓練実施者に対して支払われた入学料(対象特定一般教育訓練の受講の開始に際し当該指定教育訓練実施者に納付する入学金又は登録料)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費)として、指定教育訓練実施者が証明する額(消費税込み)
<教育訓練経費にならないもの>
・検定試験の受験料
・受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
・受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等
(行政手引58114)
➂【R7年出題】
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
問題文の場合、100分の80ではなく「100分の50」です。
・特定一般教育訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象特定一般教育訓練の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)の40%に相当する額です。
ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
・特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該特定教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者等として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用されることが困難な者を含む。)又は雇用されている者(1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して1年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者を含む。)については、特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%に相当する額となります。
ただし、その50%に相当する額が、25万円を超える場合の支給額は25万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
(行政手引58114)
④【R7年出題】
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
教育訓練給付金の受給要件について条文を読んでみましょう。
第60条の2第1項、法附則第11条、則第101条の2の5) 教育訓練給付金は、教育訓練給付金支給対象者が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が3年以上(基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものについては当分の間1年)であるときに、支給する。 (1) 当該教育訓練を開始した日(以下「基準日」という。)に一般被保険者又は高年齢被保険者である者 (2) (1)に掲げる者以外の者であって、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から厚生労働省令で定める期間内(原則1年)にあるもの |
専門実践教育訓練を開始した日前に高年齢被保険者の資格を喪失した者であっても、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から原則1年以内にある場合は、教育訓練給付金の対象になります。
⑤【R7年出題】
基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「教育訓練支援給付金」は、一定の要件を満たす専門実践教育訓練給付金の給付対象者が、当該教育訓練を受けている日のうち失業している日について支給されます。
(行政手引58501)
「基本手当が支給される期間及び待期期間、給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。」とされています。
そのため、基本手当を受給している期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。
(法附則第11条の2第4項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「訪問看護療養費など」
R8-083 11.15
訪問看護療養費の額などの算定
例えば、50歳の健康保険の被保険者が、保険医療機関に入院して療養を受けた場合、治療等については、「療養の給付」が現物給付されます。
ただし、「食事療養」は、療養の給付に含まれません。食事については、療養の給付とは別に、「入院時食事療養費」が支給されます。なお、被保険者本人は、入院時の食事については、「食事療養標準負担額」を支払います。
そのため、「入院時食事療養費」として支給されるのは、
「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から、「食事療養標準負担額」を控除した額となります。
過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
入院時食事療養費の額は、「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から「食事療養標準負担額」を控除した額です。
「食事療養標準負担額」を控除することが抜けているので誤りです。
条文を読んでみましょう
法第85条第2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |
②【H23年出題】
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。

【解答】
②【H23年出題】 ×
食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、「中央社会保険医療協議会」ではなく「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額となります。
なお、次の規定にも注意して下さい。
条文を読んでみましょう。
法第85条第3項 厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
➂【R7年出題】
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
入院時生活療養費の額は、「生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、「生活療養標準負担額」を控除した額となります。
ポイントを条文で読んでみましょう
法第85条の2第2項 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |
④【R5年出題】
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

【解答】
④【R5年出題】 ×
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、「社会保障審議会」ではなく、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとされています。
(法第85条の2第3項)
⑤【R7年出題】
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
訪問看護療養費の額は、「指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額」から、「その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(基本利用料)」を控除した額となります。
ポイントを押さえながら条文を読んでみましょう。
法第88条第4項 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分(一部負担金の区分・原則3割)に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置(減額・免除・徴収猶予の措置)が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。 |
なお、厚生労働大臣は、法第88条第4項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。(法第88条第5項)
⑥【R1年出題】
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

【解答】
⑥【R1年出題】 〇
・保険者 → 訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額を、指定訪問看護事業者に直接支払うことができます。
・被保険者 → 基本利用料(原則3割)を指定訪問看護事業者に支払います。
結果的に、訪問看護療養費は「現物給付」となります。
(法第88条第6項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「一部負担金」
R8-082 11.14
一部負担金の減額・免除・徴収猶予
療養の給付を受けた場合は、療養に要する費用の額に、原則100分の30を乗じて得た額を、「一部負担金」として、保険医療機関又は保険薬局に支払わなければなければなりません。
ただし、災害等の特別の事情がある被保険者については、特例が規定されています。
条文を読んでみましょう
法第75条の2 (一部負担金の額の特例) ① 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 (1) 一部負担金を減額すること。 (2) 一部負担金の支払を免除すること。 (3) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 ② (1)の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、(2)又は(3)の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
一部負担金の額の特例が適用されるのは、「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者」です。
厚生労働省令を読んでみましょう
則第56条の2 厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 |
②【R7年出題】
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行うものとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、「6か月以内」の期間を限って行われます。
(H18.9.14保保発0914001号)
➂【R3年出題】
保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、「審査支払機関」に請求します。
(H18.9.14保保発0914001号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「一括有期事業」
R8-081 11.13
一括有期事業のポイント!
例えば、建設現場などの「有期事業」は、有期事業ごとに、労働保険料を申告・納付します。
ただし、規模の小さい有期事業は、法律上当然に一括され、継続事業と同じ方法で、保険年度ごとに労働保険料を申告・納付します。この制度を「一括有期事業」といいます。
有期事業の一括の制度は、「労災保険」に係る保険関係のみに適用されることもポイントです。
では、条文を読んでみましょう
法第7条、則第6条 (有期事業の一括) 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、その全部を一の事業とみなす。 (1) 事業主が同一人であること。 (2) それぞれの事業が、有期事業(建設の事業・立木の伐採の事業)であること。 (3) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 ・概算保険料の額が160万円未満であること。 かつ ・ 建設の事業は、請負金額が1億8千万円未満 ・ 立木の伐採の事業は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 (4) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 (5)厚生労働省令で定める要件に該当すること。 ・それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 ・それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること。 ・それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
2以上の有期事業が有期事業の一括の対象になると、「当然に」それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用されます。労働保険料の申告、納付については、継続事業と同じく年度更新の手続きをとります。
(昭40.7.31基発901号)
②【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。

【解答】
②【R7年出題】(労災) 〇
一括有期事業を開始したときには、「初めに」、保険関係成立届を提出します。
当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はありません。
➂【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。

【解答】
➂【R7年出題】(労災) ×
一括された個々の有期事業が、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、新たに独立の有期事業としては取り扱われず、当初の一括の扱いのままとなります。
なお、当初は、単独の有期事業として成立した事業が、事業の規模の変更等で、その後、有期事業の一括のための要件を満たすにいたっても、一括の対象とはならず、単独のまま扱われます。
④【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。

【解答】
④【R7年出題】(労災) ×
請負による建設の事業の「請負金額」の算定についての問題です。
事業主が注文者から機械器具等の貸与を受けた場合には、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に「加算する」とされています。問題文の「控除する」は誤りです。
※厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合は、扱いが変わります。
(則第13条)
⑤【R3年出題】(労災)
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

【解答】
⑤【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の要件の一つは「事業主が同一人であること」です。事業主が同一人とは、その事業が同一の企業に属していることです。徴収法の事業主は、「元請負人」となり、下請負人は事業主に含まれません。
そのため、X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されません。
⑥【R7年出題】(労災)
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。

【解答】
⑥【R7年出題】(労災) ×
一括有期事業については保険年度ごとに保険料を申告・納付しますので、有期事業のメリット制ではなく、「継続事業」と同じ仕組みのメリット制が適用されます。
⑦【R4年出題】(労災)
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
⑦【R4年出題】(労災) 〇
一括有期事業については、確定保険料申告書を提出する際に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(則第34条)
⑧【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。

【解答】
⑧【R7年出題】(労災) ×
一括有期事業の事務については、「労働保険料の納付の事務を取り扱う一の事務所」の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とされます。(則第6条第3項)
「一括期事業報告書」は、その保険年度中に終了した一括有期対象事業をすべて記入し、当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(則第34条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「介護補償給付」
R8-080 11.12
介護補償給付の基本問題
介護補償給付が支給される要件を確認しましょう。
① 一定の障害の状態に該当していること
② 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること
➂ 病院または診療所に入院していないこと・障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)等に入所していないこと
条文を読んでみましょう
法第12条の8第4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (1) 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) (2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 ※厚生労働大臣が定める施設(則第18条の3の3) 1 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又 は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの 3 親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であって当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの (3) 病院又は診療所に入院している間 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。

①【R7年出題】 ×
介護補償給付の対象になる「常時介護」、「随時介護」を要する障害の状態は、厚生労働省令で定められています。
常時介護 | ① 精神神経の障害で常時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で常時介護を要するもの ➂ ①、②と同程度の介護を要する状態にあるもの |
随時介護 | ① 精神神経の障害で随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で随時介護を要するもの ➂ 障害等級1級又は傷病等級1級に該当し、常時介護を要する障害の状態に該当しないもの |
両眼を失明するととともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する場合は、常時介護の③に該当し、常時介護を要する状態となります。
問題文は、「他に障害を負っているか否かにかかわらず」の部分が誤りです。
(則別表第3)
②【R7年出題】
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
介護補償給付は、「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する」労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって「厚生労働省令で定める程度のもの」により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに支給されます。
「障害補償一時金」の支給を受けた労働者が、「加齢」で介護を要する状態となっても、介護補償給付は受けられません。
➂【R7年出題】
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
病院又は診療所に入院し、介護を受けている間は、介護補償給付は支給されません。また療養補償給付を受ける権利は、介護補償給付の支給要件ではありません。
④【R7年出題】
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
障害者支援施設に入所し、生活介護を受けている間は、介護補償給付を受けることはできません。
⑤【H24年出題】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。
⑥【R7年出題】
介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
介護補償給付は、介護の費用として支出した額(実費)が支給されます。
ただし、上限と最低保障があります。
「最低保障」が適用される要件は、「親族等による介護を受けた」ことです。
問題文のように、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合(=介護の費用を支出していない場合)であって、親族による介護を受けた日があるときは、最低保障額が支給されます。
最低保障額は、障害の程度に応じて定額とされていて、常時介護の場合は一律85,490円、随時介護の場合は42,700円です。
(則第18条の3の4)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「前借金相殺の禁止」
R8-079 11.11
労基法第17条「前借金相殺の禁止」
労働基準法では、前借金と賃金との相殺は禁止されています。
条文を読んでみましょう
法第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |
過去問を解きながらポイントを確認しましょう
①【H27年出題】
労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労働基準法第17条の目的は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することです。
(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)
②【R3年出題】
労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

【解答】
②【R3年出題】 ×
「明らかに身分的拘束を伴わないもの」は含まれません。
(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)
➂【R5年出題】
使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

【解答】
➂【R5年出題】 〇
「労働することが条件となっていないことが極めて明白」な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されません。
(昭63.3.14基発150号)
④【R7年出題】
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
法第17条には、労使協定による例外規定はありません。
賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することは禁止されています。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「在職老齢年金」
R8-078 11.10
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金とは?
★「総報酬月額相当額」+「基本月額」が、「支給停止調整額」を超える場合に、老齢厚生年金の年金額の全部又は一部の支給が停止される仕組みです。
なお、在職老齢年金は、「老齢厚生年金」の受給権者でかつ「厚生年金保険の被保険者(=在職中で厚生年金保険料を負担している)」に適用されます。
条文を読んでみましょう
法第46条第1項 (支給停止) 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、総報酬月額相当額及び基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
★用語の定義を確認しましょう
「総報酬月額相当額」
→ 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
・国会議員又は地方公共団体の議会の議員について → 標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
・70歳以上の使用される者について → 標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
「基本月額」
→ 老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く)を12で除して得た額
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
①【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される70歳以上の者に対しても、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
適用事業所に使用されていても70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料の負担はありませんが、在職老齢年金の仕組みは適用されます。
厚生年金保険の被保険者でないので、標準報酬月額と標準賞与額は、「標準報酬月額に相当する額」と「標準賞与額に相当する額」となります。
(令3条の6)
②【R7年出題】
地方公共団体の議会の議員が老齢厚生年金の受給権者であるときは、当該議員が厚生年金保険の被保険者ではないとしても、議員報酬の月額及び期末手当の額と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
「国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日が属する月」も在職老齢年金の規定が適用されます。
なお、地方公共団体の議会の議員の総報酬月額相当額は、「議員報酬の月額及び期末手当」で算定します。
(令3条の6)
➂【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
➂【H29年出題】 ×
「経過的加算額」も「繰下げ加算額」も、基本月額の計算には入りません。
なお、「経過的加算額」については、昭和60年法附則第62条で、基本月額の算定に含まない旨が規定されています。
(昭60法附則第62条)
④【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
「老齢基礎年金」も「経過的加算額」も在職老齢年金の支給停止の対象となりません。
(昭60法附則第62条)
⑤【R4年出題】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる「総報酬月額相当額」は、「標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」です。
在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されると、総報酬月額相当額も変更されます。
⑥【R7年出題】
前月から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する65歳以後の老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合は、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該総報酬月額相当額の改定が行われた月の翌月から支給される年金額が改定される。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合は、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算されます。その場合、総報酬月額相当額の改定が行われた月の「翌月」ではなく、「総報酬月額相当額の改定が行われた月」から年金額が改定されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「在職定時改定」
R8-076 11.08
在職定時改定の仕組み
「在職定時改定」は、老齢厚生年金を受けながら働いている(=厚生年金保険の被保険者である)人が対象で、在職中に、老齢厚生年金の額が再計算される制度です。
毎年9月1日(基準日)に、前年9月から当年8月までの厚生年金保険の加入期間を追加して、年金額の再計算を行い、10月分から年金額が改定されます。
なお、対象は、「65歳以上」の人です。65歳未満の人には適用されません。
条文を読んでみましょう。
法第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
65歳以上の老齢厚生年金受給権者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
①【R4年出題】 ×
在職定時改定の基準日は7月1日ではなく、「9月1日」です。
ポイントを確認しながら、問題文を読み返しましょう。
・65歳以上の老齢厚生年金受給権者が対象
・毎年基準日である9月1日において被保険者である場合(=厚生年金保険に加入している場合)
・基準日の属する月前の被保険者であった期間(前年9月~当年8月)をその計算の基礎として年金額を再計算し
・基準日の属する月の翌月(10月)から
・年金額を改定します
②【R5年出題】
厚生年金保険法第43条2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

【解答】
②【R5年出題】 〇
条文のただし以下の部分です。
具体的な日付を当てはめて読んでみましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、8月20日にA社を退職(8月21日資格喪失)し、9月10日にB社で厚生年金保険の被保険者資格を再取得した場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
在職定時改定の規定において、基準日(9月1日)が被保険者の資格を喪失した日 (8月21日)から再び被保険者の資格を取得した日(9月10日)までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合(=A社の喪失で退職時改定が行われない)は、基準日の属する月前の被保険者であった期間(8月以前の期間)を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月(10月)から年金の額を改定するものとする。
→基準日(9月1日)に被保険者ではありませんが、在職定時改定が適用され、年金額が改定されます。
➂【R7年出題】
厚生年金保険法第42条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
在職定時改定の対象は「65歳以上」で、「65歳未満」は対象外です。
老齢厚生年金を繰上げ受給していても、65歳未満の者には、在職定時改定は適用されません。
(法附則第13条の4)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「被保険者期間」
R8-075 11.07
厚生年金保険の被保険者期間の計算
「被保険者期間」は月単位で計算され、保険料の徴収や年金額の計算に使われます。
厚生年金保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されます。また、厚生年金の年金額は、原則として、平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数で計算します。
被保険者期間について条文を読んでみましょう
法第19条 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 ➂ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 ④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 ⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。 |
過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
被保険者期間は、月単位で計算します。被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
②【H30年出題】 〇
被保険者期間は、月単位で計算し、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。
問題文の場合は、資格を取得した月が「平成29年10月」、資格を喪失した月が「平成30年3月」ですので、その前月の平成30年2月までが算入されます。
被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間です。資格を喪失した月の平成30年3月は被保険者期間には算入されません。
➂【R6年出題】
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

【解答】
➂【R6年出題】 ×
(原則) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪)は、その月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
5月1日に厚生年金保険の被保険者資格取得 → 同月15日に喪失の場合、被保険者期間は原則として「1か月」として算入されます。
(例外) ただし、問題文のように、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
5月 | |
1日(取得) | 15日(喪失・種別変更) |
厚生年金保険 被保険者 |
|
| 国民年金 第1号被保険者 |
5月1日に厚生年金保険の被保険者資格取得 → 同月15日に喪失・同日に(国年)第1号被保険者に種別変更の場合、令和6年5月分については、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
令和6年5月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。
④【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
➂の問題と同じです。
平成28年3月1日に厚生年金被保険者の資格を取得 → 同月21日資格喪失・同日(国年)第1号被保険者に種別変更の場合、同年3月分は、厚生年金保険における被保険者期間に算入されず、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間となります。
⑤【R3年出題】
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
被保険者の「種別」とは、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の区別のことです。
⑥【R7年出題】
国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
被保険者期間は被保険者の種別ごとに適用されます。
第2号厚生年金被保険者(国家公務員)としての被保険者期間は、資格を喪失した月の前月(令和7年6月)までとなります。
第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間は、資格を取得した月(令和7年7月)から算入されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「合意分割」
R8-074 11.06
離婚時の厚生年金の合意分割の請求
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができます。
今回は「合意分割」をみていきます。合意分割には、平成19年4月1日以降に離婚したこと、「按分割合」を定めることなどの条件があります。
なお、他に「3号分割」もありますが、今回は触れません。
条文を読んでみましょう。
法第78条の2 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) ① 第一号改定者又は第二号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (1) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。 (2) ②の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ② ①の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 ➂ 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。 |
<用語について>
・ 第一号改定者
→ 被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。(標準報酬が多い方・渡す方)
・ 第二号改定者
→ 第一号改定者の配偶者であった者で、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。(標準報酬が少ない又はゼロの方・受ける方)
・ 離婚等
→ 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。
・ 対象期間
→ 婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。
・ 按分割合
→ 改定又は決定後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう
法第78条の3第1項 (請求すべき按分割合) 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 |
<用語について>
・ 対象期間標準報酬総額
→ 対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。
按分割合とは、第2号改定者の分割後の持ち分の割合です。
第二号改定者の対象期間標準報酬総額 |
当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額 |
按分割合は、第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定めます。
※例えば、分割前の第二号改定者の持ち分の割合が30%の場合は、按分割合は30%を超え50%以下の範囲で定めることになります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき< A >について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから< B >を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 6か月 ⑤ 按分割合 ⑥ 改定額
⑦ 改定請求額 ⑧ 改定割合

【解答】
<A> ⑤ 按分割合
<B> ② 2年
②【R7年出題】
甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に所定の事項が記載された公正証書を添えて当事者の他方による標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなされます。
問題文は、甲の死亡した日から起算して15日目に合意分割の請求を行っていますので、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされます。
(令第3条の12の7)
➂【R7年出題】
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができます。
この申立ては当事者の一方のみによってすることができます。
(法第78条の2第3項)
④【H29年出題】
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
「3か月以内」ではなく「2年以内」に行わなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第78条の4第1項 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書(離婚等をしたときから2年を経過したとき)に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 |
情報の提供の請求は、「当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合」又は「離婚等をしたときから2年を経過したとき」等は行うことができません。
⑤【R7年出題】
当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
④の解答と同じです。
標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求は、標準報酬改定請求後には行うことができません。
⑥【R7年出題】
対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
月々の標準報酬月額だけでなく、標準賞与額からも同一の保険料率で保険料が徴収され、年金の額にも反映されるようになったのは平成15年4月以降です。(総報酬制といいます。)
平成15年3月以前は、年金の額に反映するのは「標準報酬月額」のみでした。
バランスをとるために、平成15年4月1日前の対象期間については、各月の標準報酬月額に「1.3」を乗じます。
また、過去の標準報酬を現在の価値に読み替えるために使われるのが「再評価率」です。
対象期間の末日において適用される再評価率を使います。
⑦【R7年出題】
老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、「当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月」ではなく、「当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」から、年金の額が改定されます。
(法第78条の10第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「裁定」
R8-073 11.05
給付を受ける権利の裁定
例えば、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある人が65歳に達すると、老齢基礎年金の受給権が発生します。
ただし、給付を受ける権利を取得したとしても、自動的には支払われません。
給付を受けるためには、裁定請求の手続きが必要です。
給付を受ける権利を制度の運営者(国民年金の場合は厚生労働大臣)が確認することを「裁定」といい、裁定は受給権者からの請求によって行われます。
条文を読んでみましょう
法第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 |
ちなみに、国民年金の「給付」は、次のように規定されています。
法第15条 (給付の種類) この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 (1) 老齢基礎年金 (2) 障害基礎年金 (3) 遺族基礎年金 (4) 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。

【解答】
①【R7年出題】 〇
法第16条は、脱退一時金に準用されます。脱退一時金を受ける権利は、厚生労働大臣が裁定します。
(法附則第9条の3の2第7項)
また、脱退一時金の裁定請求は、「日本年金機構」に請求書を提出することによって行われます。
(則第63条)
※「法第16条(裁定)の規定による請求の受理についての厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせる」とされています。(脱退一時金についても同様です。)
(法第109条の4第1項第6号)
②【R7年出題】
市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
「国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。」と規定されています。(法第3条第3項)
市町村長が処理する事務は、国民年金法施行令第1条の2に定められています。
例えば、年金の加入歴が第1号被保険者のみの場合の老齢基礎年金の請求書は市町村に提出します。
問題文の「裁定の請求の受理・送付等」について条文を読んでみましょう。
則第64条第1項 市町村長は、令第1条の2第3号から第6号までの規定によって、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。 |
➂【R7年出題】
厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
「厚生労働大臣は、法第16条(裁定・脱退一時金に準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。」とされています。
(則第65条第1項)
また、「厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを①の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。」とされています。
(則第65条第2項)
④【R5年出題】
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

【解答】
④【R5年出題】 〇
年金の受給権の裁定をしたときは、厚生労働大臣は年金証書を交付します。
ただし、例外もあります。
「老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。」
上記の場合は、「当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす」とされています。
(則第65条第2項、第3項)
⑤【H29年出題】
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
「国民年金基金」が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「国民年金基金」が裁定します。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(法第133条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「被保険者の届出」
R8-072 11.04
第1号被保険者・第3号被保険者の届出
第1号被保険者と第3号被保険者の「届出」についてみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第12条 (届出) ・第1号被保険者について ① 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 ② 世帯主は、被保険者に代って、届出をすることができる。 ➂ 住民基本台帳法の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす。 ④ 市町村長は、届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 ・第3号被保険者 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
・第1号被保険者 → 市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない
・第3号被保険者 → 厚生労働大臣に届け出なければならない
第1号被保険者と第3号被保険者の違いがポイントです。
②【R7年出題】
被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
第1号被保険者は、厚生労働大臣ではなく「市町村長」に届け出なければなりません。
➂【R4年出題】
第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
第1号被保険者は、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければなりません。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、氏名及び住所の変更の届出は要りません。
(則第7条第、則第8条)
④【H20年出題】
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
④【H20年出題】 ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届ではなく「種別変更届」を市町村長に提出しなければなりません。
(則第6条の2)
⑤【H27年出題】
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
第2号被保険者については、国民年金法の届出の規定は適用されません。
そのため、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合は、国民年金法の届出は不要です。
(法附則第7条の4)
⑥【R7年出題】
第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
第3号被保険者については、「厚生労働大臣」に届け出なければならない点がポイントです。
⑦【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を「日本年金機構」に提出しなければなりません。
(則第1条の4第2項)
⑧【R2年出題】
20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得届の届出を要しないものとされている。

【解答】
⑧【R2年出題】 ×
20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得した場合は、当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるとしても、資格取得届の届出は必要です。
※第1号被保険者については、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、届出は要しません。
(則第1条の4第1項)
⑨【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
⑨【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができます。
ちなみに、健康保険組合に委託できるのは、事務の「一部」です。「全部又は一部」ではありませんので注意しましょう。
なお、全国健康保険協会には委託できません。
⑩【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

【解答】
⑩【R1年出題】 〇
第3号被保険者の届出については、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「被保険者」
R8-071 11.03
国民年金の被保険者の資格取得の時期
国民年金の被保険者の資格取得の時期をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第7条 (被保険者の資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 (1)第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2)第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者 (3)第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの |
法第8条 (資格取得の時期) 前条の規定による被保険者は、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 (1) 20歳に達したとき。 (2) 日本国内に住所を有するに至ったとき。 (3) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。 (4) 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 (5) 被扶養配偶者となったとき。 |
過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
第1号被保険者は、「20歳に達した日」に資格を取得します。
「20歳に達した日」は、20歳の誕生日の前日ですので、問題文の場合は、平成31年3月31日が20歳に達した日で、その日に第1号被保険者の資格を取得します。
「被保険者期間」は「被保険者の資格を取得した日の属する月」から算入されます。問題文は、「平成31年3月」から被保険者期間に算入されます。
②【H29年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
第1号被保険者と第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはその年齢要件はありません。
そのため、厚生年金保険の被保険者であれば、20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者となります。
➂【R5年出題】
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

【解答】
➂【R5年出題】 ×
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であったとしても、65歳未満の場合は、第2号被保険者となります。
※65歳以上で、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有している場合は、厚生年金保険の被保険者でも、第2号被保険者にはなりません。(法附則第3条)
④【R7年出題】
20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

【解答】
④【R7年出題】 ×
20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った「日」に、国民年金第2号被保険者の資格を取得します。翌日ではありません。
⑤【H27年出題】
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
被扶養配偶者が20歳に達した場合、第3号被保険者に該当しますので、20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得します。
⑥【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
被扶養配偶者が18歳である場合は、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは、その「被扶養配偶者」が20歳に達したときです。厚生年金保険の被保険者が20歳に達したときではありません。
⑦【H29年出題】
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
「日本国内に住所を有しない」場合は、第1号被保険者にはなりません。
そのため、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)」は、国民年金に任意加入することができます。
厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができ、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得します。
(法附則第5条第1項、第3項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R8-069 11.01
配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定
遺族基礎年金は、「配偶者」に支給される場合と「子」に支給される場合がありますが、今回は、「配偶者」に対する遺族基礎年金をみていきます。
遺族基礎年金が支給される配偶者は、「子」と生計を同じくしていることが条件です。
そのため、配偶者に対する遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算額が加算されています。
条文を読んでみましょう
法第38条 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 法第39条 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、法第38条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |
★配偶者に支給される遺族基礎年金
子が1人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率 |
子が2人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率+224,700円×改定率 |
子が3人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率 |
例えば、子が3人いる場合は、基本の額に(224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率)が加算されます。
3人の子のうち、1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の加算額が3人→2人に減額改定されます。
減額改定について条文を読んでみましょう
法第39条第3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (5) 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |
子が(1)~(8)に該当したときは、その子の分、加算額が減額されます。
ただし、「1人を除いた」の部分がポイントです。
配偶者は子があることが要件です。子が全員(1)~(8)に該当した場合は、減額ではなく、遺族基礎年金は失権します。
そのため、「減額」されて支給されるのは、1人でも子がある場合です。
では、問題を解いてみましょう
①【R2年出題】
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

【解答】
①【R2年出題】 〇
配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算額が加算されます。
②【R7年出題】
配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達したときに年金額が減額改定される。」となります。
「20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」は誤りです。
➂【R4年出題】
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
➂【R4年出題】 〇
子が1人で、その子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、子がいなくなるため、夫の遺族基礎年金は減額改定ではなく、失権します。
条文を読んでみましょう
法第40条第2項 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金」
R8-068 10.31
老齢基礎年金の額の計算
老齢基礎年金の満額は「780,900円×改定率」です。
ただし、満額の老齢基礎年金が支給されるのは、保険料納付済期間だけで「480月」ある場合です。
480月の中に、保険料免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金額が減額されます。この方式を「フルペンション減額方式」といいます。
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「学生納付特例の期間」及び「納付猶予の期間」は、老齢基礎年金の額には反映しません。なお、追納すると「保険料納付済期間」として老齢基礎年金の額に算入されます。
(法第27条第8号、平24法附則第14条)
②【R4年出題】
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

【解答】
②【R4年出題】 ×
老齢基礎年金の年金額に反映されるのは、「4分の1」ではなく「4分の3」に相当する月数です。
具体的に計算してみましょう
(その1)保険料納付済期間が480月の場合
・780,900円×改定率×480月/480月(満額)
(その2)保険料納付済期間400月、保険料半額免除期間が80月の場合
・780,900円×改定率×(400月+80月×4分の3(60月))/480月
<老齢基礎年金の額に反映する半額免除期間について>
480月 |
| ||
保険料納付済期間 | 4分の1免除期間 | 半額免除期間 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ポイント!
国庫負担は、480月が限度です。(赤色の部分)
例えば、保険料納付済期間は、老齢基礎年金の額の計算では「1」で反映します。
ただし、「1」のうち、8分の4(2分の1)は国庫負担で、本人が負担した保険料は8分の4(2分の1)です。
半額免除期間は、国庫負担8分の4(2分の1)+保険料負担(8分の2)で、4分の3(8分の6)が反映します。
480月を超えた部分は国庫負担が入りませんので、保険料負担分の8分の2(4分の1)のみが反映します。
問題文は、正しくは、「保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の 4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。」となります。
➂【R5年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】
➂【R5年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳に達した日の属する月前」の期間及び「60歳に達した日の属する月以後の期間」は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
(昭60年法附則第8条第4項)
④【R4年出題】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
④【R4年出題】 ×
老齢基礎年金の額は満額となりません。
問題文の場合、23歳から65歳までの42年間、第1号厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)です。
ただし、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間は「合算対象期間」で老齢基礎年金の年金額には反映しません。
そのため、老齢基礎年金の額に保険料納付済期間として反映するのは、23歳~60歳までの37年間です。60歳以後の5年間は合算対象期間で、老齢基礎年金の額には算入されません。
(昭60年法附則第8条第4項)
⑤【R7年出題】
昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。
第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)
第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)
第3号被保険者期間 336月

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「456月」となります。
・第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間が「保険料納付済期間」となりますので、108月です。
・第2号被保険者期間は、20歳以上60歳未満の期間ですので、12月はすべて保険料納付済期間です。
・第3号被保険者期間の336月はすべて保険料納付済期間です。
老齢基礎年金の年金額に反映するのは、108月+12月+336月=456月です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「失踪宣告・死亡の推定」
R8-067 10.30
「失踪宣告」と「死亡の推定」
「失踪宣告」と「死亡の推定」の違いを意識しましょう
■「失踪宣告」について
民法に規定されています。
・「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」とされていて、失踪の宣告を受けた者は7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなす。」とされています。
(民法第30条第1項、第31条)
生死が明らかでない者を、法律上死亡したものとみなす制度です。
■「死亡の推定」について
失踪期間の満了を待っているうちに、子が高校を卒業してしまい遺族基礎年金が受けられなくなる可能性もあります。
そのため、国民年金法では、特例を設けています。
国民年金法の条文を読んでみましょう
法第18条の3 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。 |
ポイント!
死亡の推定が適用されるのは、「船舶」の沈没等、「航空機」の墜落等の場合です。
過去問を解いてみましょう
①【H18年出題】
失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。

【解答】
①【H18年出題】 ×
失踪宣告があったときは、行方不明になってから「7年」を経過した日に死亡したものとみなされます。
②【H26年出題】
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。

②【H26年出題】 〇
失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、「生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件」については、行方不明になった日を死亡日として取り扱うことになっています。
条文を読んでみましょう
第18条の4 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金について「死亡日」とあるのは「行方不明となった日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となった当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。 |
行方不明となった日=死亡日 | 生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件 |
7年を経過した日 | 身分関係、年齢、障害の状態 |
➂【R2年出題】
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

【解答】
➂【R2年出題】 ×
遺族基礎年金の支給に関する保険料納付要件は、「死亡日の前日」で判断されます。そのため失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の保険料納付要件は、「行方不明となった日の前日」で判断されます。
④【R7年出題】
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態は、行方不明となった日ではなく、死亡したとみなされた日で判断されます。
なお、遺族基礎年金の受給権は、行方不明となった日ではなく、死亡したとみなされた日に発生します。
⑤【H26年出題】
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
「1か月間」ではなく「3か月間」です。
⑥【H22年出題】
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。

【解答】
⑥【H22年出題】 ×
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、「その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日」ではなく、「その船舶が行方不明になった日」にその者は死亡したものと推定されます。
なお、遺族基礎年金の受給権は、「船舶が沈没等をした日・航空機が墜落等をした日」に発生します。
⑦【H29年出題】
冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。

【解答】
⑦【H29年出題】 ×
冬山の登山中に行方不明になっても、死亡の推定は適用されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「傷病手当金の支給調整」
R8-066 10.29
傷病手当金と報酬等との調整
今回のテーマの1つ目は、「傷病手当金」と「報酬」との支給調整です。報酬を受けるときは、原則として傷病手当金は支給されません。
テーマの2つ目は、「傷病手当金」と「出産手当金」との支給調整です。出産手当金が優先されることがポイントです。
条文を読んでみましょう
第108条第1項 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。
法第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間」ですので、問題文の傷病手当金の支給期間は、傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から通算して1年6か月です。
報酬あり | 報酬なし |
4/25・・・・・・・・・・・・・・・・5/31 | 6/1・・・・・・・・ |
年次有給休暇 | 欠勤 |
傷病手当金 支給停止 | 支給→(通算1年6か月) |
報酬が支払われている場合、傷病手当金は支給停止されます。(なお、報酬が支払われていても待期は完成します。4月25日、26日、27日の連続した3日間で待期は完成します。)
そのため、傷病手当金は報酬を受けなくなった日(=支給停止事由がなくなった日)から支給が始まり、「支給を始めた日」から通算して1年6か月間支給されます。
(昭24.1.24保文発162)
②【H28年出題】
傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象となる。

【解答】
②【H28年出題】〇
傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されます。
「通勤手当」も報酬に当たります。支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費でも、実態は毎月の通勤に対し支給されていますので、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象となります。
(昭27.12.4保文発7241)
➂【R7年出題】
被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当する場合は、介護休業期間中でも傷病手当金又は出産手当金は支給されます。
ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合で、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われます。
(H11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)
見舞金その他名称の如何を問わず、就業規則又は労働協約等に基き、報酬支払の目的をもって支給されたとみなされるもので、その支払事由の発生以後引続き支給されるものは、「報酬」に該当します。そのため、傷病手当金との調整の対象となります。
(昭25.2.22保文発第376号)
問題文の前半は「〇」ですが、後半の見舞金は報酬に含まれますので、「×」です。
④【H30年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
出産手当金と傷病手当金はいずれか選択ではありません。
出産手当金を支給する場合は、その期間は、傷病手当金は原則として支給されません。
⑤【R4年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】
⑤【R4年出題】 〇
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間に、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、「出産手当金」の支給が優先されます。
出産手当金の額多>傷病手当金の額少の場合は、傷病手当金は支給されません。
ちなみに、出産手当金の額少<傷病手当金の額多の場合は、差額の傷病手当金が支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「傷病手当金」
R8-065 10.28
傷病手当金の支給要件
一定の要件を満たした被保険者には傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給要件について条文を読んでみましょう
法第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金は、休み始めて4日目から支給され、最初の3日間は支給されません。最初の3日間を待期といいます。なお、待期は「連続した3日間」で完成します。
では、過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 ×
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「4日」ではなく「3日」を経過した日から支給されます。
②【R1年選択式】※改正による修正あり
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B>又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。
<選択肢>
①4月1日から ②4月3日から ③4月4日から ④4月5日から
⑤日 ⑥日の2日後 ⑦日の3日後 ⑧日の翌日

【解答】
<A> ④4月5日から
<B> ⑤日
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間です。(法第99条第4項)
★<A>について
4月 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
・・・・・ |
休 | 休 | 休 | 出勤 | 休 | ・・・・・ |
4月1日~3日まで連続3日間休んでいますので、この3日間で待期は完成しています。
そのため、傷病手当金は、再び労務不能になって休業した5日から支給されます。
★<B>について
報酬あり | 報酬 | ||||||
なし | |||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
傷病手当金 支給停止 | 支給 | ||||||
報酬が支払われている場合、傷病手当金は支給停止されます。ただし、報酬が支払われていても待期は完成します。
そのため、傷病手当金は報酬を受けなくなった日(=支給停止事由がなくなった日)から支給されます。
(昭24.1.24保文発162)
➂【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

【解答】
➂【H28年出題】 〇
休日も待期期間に算入されます。問題文の場合は、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。
④【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
④【H28年出題】 ×
待期は、「労務不能の状態になった日」から起算するのが原則です。ただし、労務不能になったのが業務終了後の場合は「その翌日」から起算します。
問題文は、就業中に発症しそのまま入院していますので、その翌日ではなく、「その日」が待期期間の起算日となります。
(昭5.10.13保発52)
⑤【R7年出題】
被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「就業時間内」に労務不能になった場合は、傷病手当金の待期期間の起算日は「その翌日」ではなく「その日」(2月3日)となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たします。
⑥【R3年出題】
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

【解答】
⑥【R3年出題】 ×
一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることは要件となりません。自費診療による療養も傷病手当金の対象となります。
(昭2.2.26保発345)
⑦【R1年出題】
傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

【解答】
⑦【R1年出題】 ×
・前半について
その本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合 → 労務不能には該当しない
・後半について
本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合 → 労務不能に該当する
問題文の後半(本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事した場合等)が誤りです。
(平15.2.25保保発第0225007号/庁保険発第4号/)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「費用の負担」
R8-064 10.27
健康保険「国庫負担と国庫補助」
健康保険事業に対する「国庫負担」と「国庫補助」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。
法第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
法第153条、法附則第5条 (国庫補助) 国庫補助の対象になる給付 ・協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 ・補助の割合→ 1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間「1,000分の164」)を乗じて得た額を補助する。
第154条の2 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。 |
過去問をどうぞ!
①【H23選択式】※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。
4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E >の実施に要する費用の一部を補助することができる。

【解答】
<A> 予算
<B> 介護納付金
<C> 被保険者数
<D> 概算払い
<E> 特定健康診査等
※特定健康診査等とは
「高齢者医療確保法」の規定による40歳以上を対象とした「特定健康診査及び特定保健指導」のことです。
②【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、国庫が全額負担しています。
健康保険組合に対しても負担を行っています。
➂【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。

【解答】
➂【R6年出題】 〇
赤字の部分がポイントです。健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。
④【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
⑤【R7年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の「一部」を補助することができる。」と規定されています。「全部」ではありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R8-063 10.26
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年10月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年10月20日から25日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 健康保険組合について(健康保険法)
・ 健康保険の不服申立て~1番のポイント(健康保険法)
・ 出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度(健康保険法)
・ 育児休業が終了した際の標準報酬月額の見直し(育児休業等終了時改定)(健康保険法)
・ 日雇特例被保険者の特別療養費(健康保険法)
・ 日雇特例被保険者の保険料の納付について(健康保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「日雇特例被保険者の保険料」
R8-062 10.25
日雇特例被保険者の保険料の納付について
日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼って納付します。
納付について条文を読んでみましょう
第168条第1項 (日雇特例被保険者の保険料額) 日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする。 (1) その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額 イ 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額 ロ イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額 (2) 賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が40万円を超える場合には、40万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額 |
★日雇特例被保険者に係る保険料の負担
・日雇特例被保険者
→ イの額の2分の1及び(2)の額の2分の1の額の合算額を負担
・事業主
→ イの額の2分の1及び(1)ロの額及び(2)の額の2分の1の額の合算額を負担
法第169条第2項~第6項 ② 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。 ➂ 保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。 ④ 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。 ⑤ 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。 ⑥ 事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H23年出題】
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

【解答】
①【H23年出題】 ×
「その者を使用するすべての事業主」が誤りです。
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負います。
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「その者を使用するすべての事業主」ではなく、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。
②【R7年出題】
日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「その者を使用するそれぞれの事業主」が誤りです。
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。
なお、事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができ、その場合は、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければなりません。
➂【R4年出題】
日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
日雇特例被保険者の賃金日額は、「1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金」につき算定されます。
(法第125条第1項第6号)
問題文の場合は、初めに使用される事業所(A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所)から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所の事業主が健康保険印紙を貼り、これに消印して保険料を納付します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「日雇特例被保険者」
R8-061 10.24
日雇特例被保険者の特別療養費
日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙をはって納付します。
日雇特例被保険者が、療養の給付等を受けるには、「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
保険料納付要件は、次のいずれかに該当していることです。
・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
・療養の給付を受ける日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている
例えば、10月24日に療養の給付を受ける場合は、前2か月間(8月と9月)に通算して26日分以上納付されていれば、要件を満たします。
8月 | 9月 | 10月 |
通算して26日分以上納付 |
| |
しかし、初めて日雇特例被保険者手帳を受けた者等は、保険料納付要件を満たせません。そのため、「特別療養費」が設けられています。
条文を読んでみましょう
法第145条第1項 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。 (1) 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 ※以下(2)と(3)は今回は省略します
則第130条 (特別療養費受給票の交付) 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、全国健康保険協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための要件です。
療養の給付を受ける日において
→当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
→当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている
②【H26年出題】
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

【解答】
②【H26年出題】 〇
例えば、10月3日に、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、「日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間」=12月31日までです。
なお、月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間となります。
➂【R7年出題】
日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
こちらもチェックしましょう!
・特別療養費は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して受けます
・特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)です
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「育児休業等終了時改定」
R8-060 10.23
育児休業が終了した際の標準報酬月額の見直し(育児休業等終了時改定)
育児休業等終了時改定は、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者が対象です。
育児休業等終了時に、報酬に変動があった場合に標準報酬月額が改定されます。なお、被保険者からの申し出が必要です。
ポイント!
随時改定の要件に該当しなくても改定されます。
・1等級の差でも行われる
・固定的賃金の変動がなくてもよい
・報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、除いて算定する
条文を読んでみましょう
法第43条の2 (育児休業等を終了した際の改定) ① 保険者等は、育児・介護休業法に基づく育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 ② 改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
例えば、令和7年10月23日に育児休業等が終了した場合
令和7年 10月 |
11月 |
12月 | 令和8年 1月 |
・・・・・ |
8月 |
報酬の総額÷月数 (17日未満の月除く) | 改定 |
|
| ||
(有効期間)
育児休業等終了日の翌日(10月24日)から起算して2月を経過した日の属する月の翌月(=令和8年1月)からその年の8月まで
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはどれか。(誤りは2つ)
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 10:00
終業時刻 17:00
休憩時間 1時間
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額12,000円の日給制
給与の締切日 毎月20日
給与の支払日 毎月末日
(ア) 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(イ) 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
(ウ) 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(エ) 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
(オ) 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。

【解答】
(ア)と(イ)が誤
(ア) ×
産前産後休業中に保険料が免除される期間は、「産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までです。
問題文の場合は、産前休業を開始した日が3月7日、産後休業は出産日の翌日から56日の8月10日までです。
保険料が免除されるのは、産前産後休業を開始した日の属する月(=3月)からその産前産後休業が終了する日の翌日(8月11日)が属する月の前月(=7月)までとなります。
(法第159条の3)
(イ) ×
出産手当金の支給期間は、「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間」です。
問題文の場合は、出産の日が出産予定日より後ですので、出産予定日(6月12日)以前98日の3月7日から同年8月10日までとなります。
(法第102条)
(ウ) 〇
育児休業期間中の保険料は、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合は、「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月」まで免除されます。
なお、産前産後休業中は、「産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」が免除の期間となります。
産前産後の免除期間の終了月の翌月=育児休業等を開始した日の属する月となります。そのため、産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日(=育児休業等が終了する日の翌日)が属する月の前月までの期間について、事業主は、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができます。
(法第159条)
(エ) 〇
■6月14日に育児休業等が終了した場合
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ・・・・・ | 翌年8月 |
報酬の総額÷月数 (17日未満の月除く) | 改定 |
|
| ||
6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満の場合は、6月を除いて算定します。
7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができます。
(法第43条の2)
(オ) 〇
「育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月」までが有効期間ですが、「当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月」までとなります。
問題文の場合は、9月に改定されますので、翌年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
②【H28年出題】
産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となります。育児休業等を終了した際の改定も同様です。
➂【R7年出題】
被保険者が令和7年1月1日に職場復帰し、育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
育児休業等終了日の翌日(=令和7年1月1日)から起算して2月を経過した日の属する月(=3月)の翌月(=4月)からその年の8月までの各月の標準報酬月額となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「出産育児一時金」
R8-059 10.22
出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度
「出産育児一時金」について条文を読んでみましょう
法第101条 (出産育児一時金) 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 |
★出産育児一時金の額
政令で定める金額 →48万8千円とする。
※産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、12,000円が加算され、50万円となります。
令和7年の選択式を解いてみましょう
【R7年選択式】
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、< A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
<選択肢>
① 1 ② 2 ④ 3 ⑧ 5
⑨ 84 ⑩ 85 ⑪ 86 ⑫ 87
⑬ 46万8,000 ⑭ 47万8,000 ⑮ 48万8,000 ⑯ 49万8,000

【解答】
<A> ⑮ 48万8,000
<B> ④ 3
<C> ⑩ 85
(法第101条、令第36条)
★出産育児一時金の支払い方法には、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「償還払い制度」の3つの方法があります。
| 支給申請 | 受取り |
直接支払制度 | 医療機関等が被保険者に代わって保険者に支給申請を行う | 保険者から医療機関等に直接支払われる |
受取代理制度 | 被保険者自身が保険者に支給申請を行う | 医療機関等が被保険者に代わって受け取る |
償還払い制度 | 被保険者自身が保険者に支給申請を行う | 被保険者が自身で受け取る |
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

【解答】
①【R7年出題】 〇
<直接支払制度>
・被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結する
↓
・医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行う
(メリット)被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ります。
(参照:「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱)
②【R3年出題】
出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

【解答】
②【R3年出題】 〇
<受取代理制度>
・被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請する
↓
・医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る
(メリット)出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができます。
(参照:「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「不服申立て」
R8-058 10.21
健康保険の不服申立て~1番のポイント
健康保険の不服申立てについて条文を読んでみましょう
第189条 ① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ➂ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定(督促及び滞納処分)による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第192条 第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
過去問を解きながらポイントをつかみましょう
①【R4年出題】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前は提起できません。
図で確認しましょう(二審制です)
・資格 ・標準報酬 ・保険給付 に関する処分 |
→ 審査請求 | 社会保険審査官 |
→ 再審査請求 | 社会保険審査会 |
★「処分の取消しの訴え」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後に提起することができます。
★審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合
・社会保険審査会に再審査請求する
・社会保険審査会に再審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する
のどちらでも可能です。
②【R7年出題】
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。「一審制」で行われることがポイントです。
図で確認しましょう。(一審制です)
・保険料等の賦課若しくは徴収の処分 ・督促及び滞納処分 | → 審査請求 | 社会保険審査会 |
★保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある
・社会保険審査会に審査請求する
・社会保険審査会に審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する
のどちらも可能です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「健康保険組合」
R8-057 10.20
健康保険組合について
「健康保険」の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。
今回は、「健康保険組合」についてみていきます。
過去問を解きながら健康保険組合のポイントをおさえましょう
①【R3年出題】
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
法第8条で、「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」と規定されています。
②【R4年出題】
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

【解答】
【②【R4年出題】 〇
★ポイントを穴埋めで確認しましょう。
法第12条
① 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の< A >を得て、規約を作り、厚生労働大臣の< B >を受けなければならない。
② 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、< C >について得なければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<A>2分の1以上の同意
<B>認可
<C>各適用事業所
➂【R7年出題】
健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
組合会議員の任期が誤りです。
・健康保険組合には、議決機関として組合会が置かれます。
・組合会は、「組合会議員」をもって組織されます。
・組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選します。
(法第18条)
・組合会議員の任期は「3年を超えない範囲内で規約で定める期間」とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とされます。
(令第6条)
④【R1年出題】
健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

【解答】
④【R1年出題】 ×
最後の「事業主が選定する」が誤りです。正しくは、「理事が選挙する」です。
ちなみに、「理事長」の職務は、健康保険組合を代表し、その業務を執行することです。
・健康保険組合に、役員として理事及び監事が置かれています。
・理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選します。
・理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙します。
・監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙します。
・監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることはできません。
(法第21条)
⑤【H30年出題】
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
「被保険者の4分の3以上の多数」が誤りです。
条文を読んでみましょう
法第24条第1項 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において「組合会議員の定数の 4分の3以上の多数」により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
⑥【H25年出題】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
⑥【H25年出題】 ×
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
(法第23条第1項)
⑦【R3年出題】
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

【解答】
⑦【R3年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の< A >及びその適用事業所に使用される被保険者の< B >以上の< C >を得なければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
<A>全部
<B>2分の1
<C>同意
(法第25条第1項)
⑧【H23年出題】
健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

【解答】
⑧【H23年出題】 ×
組合会議員の定数の「2分の1」ではなく「4分の3」以上の組合会の議決です。
条文を読んでみましょう
第26条第1項、2項 ① 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 (1) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 (2) 健康保険組合の事業の継続の不能 (3) 厚生労働大臣による解散の命令 ② 健康保険組合は、(1)又は(2)に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
⑨【H29年出題】
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

【解答】
⑨【H29年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう
健康保険組合が解散により消滅した場合、< A >が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<A>全国健康保険協会
(法第26条第4項)
⑩【R3年出題】
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

【解答】
⑩【R3年出題】 〇
債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができるのは、「設立事業所の事業主」に対してです。「被保険者」には負担を求めることはできません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です
R8-056 10.19
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年10月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年10月13日から18日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・労基法「総則」(第1条~第12条)
・休業補償給付の基本問題(労災保険法)
・公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときの給付制限(雇用保険法)
・「労働保険事務組合」のよく出る問題(労働保険徴収法)
・確定拠出年金「個人型年金」のポイント!(社一)
・社会保険労務士の業務など(社会保険労務士法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」
R8-055 10.18
社会保険労務士の業務など
今回は、社会保険労務士法をみていきます。
問題を解きながらポイントをつかみましょう。
では、過去問を解いていきましょう
①【R7年出題】
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「提出に関する手続を代わつてする」=提出手続を代行することは、申請書等の提出手続の際、行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。
(昭61.10.1庁保発第40号)
②【R7年出題】
特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
社労士法第2条第1項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務を「紛争解決手続代理業務」といいます。紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限って行うことができます。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の紛争調整委員会におけるあっせんの手続、「障害者雇用促進法」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「男女雇用機会均等法」、「労働者派遣法」、「育児・介護休業法」、「短時間労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理することは、紛争解決手続代理業務の一つです。(法第2条第1項第1号の4)
また、紛争解決手続代理業務には次の事務が含まれます。(法第2条第3項)
① 第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
➂ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
➂【R7年出題】
社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
「社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会」に限りません。
条文を読んでみましょう
第25条の3の2 (懲戒事由の通知等) ① 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 ② 何人も、社会保険労務士について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |
問題文の場合、「適当な措置をとるべきことを求めることができる」のは、「何人も」となります。
④【R7年出題】
社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。」と規定されています。社会保険労務士でない者は、社会保険労務士法人の社員になることはできません。
(法第25条の8第1項)
⑤【R7年出題】
社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。」とされています。
自己若しくは第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできません。
(法第25条の18第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「確定拠出年金法」
R8-054 10.17
確定拠出年金「個人型年金」のポイント!
確定拠出年金法のポイントをみていきます。
確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。
今回は、「個人型」を重点的にみていきます。
まず、用語の定義を確認しましょう。
企業型 | 個人型 |
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する | 国民年金基金連合会が実施する |
「企業型年金加入者」→事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者 | 「個人型年金加入者」→掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者 |
「確定拠出年金運営管理業」→運営管理業務の全部又は一部を行う事業 ①記録関連業務 ②運用関連業務(運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供) | |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

【解答】
①【H21年出題】 ×
個人型年金とは、企業年金連合会ではなく「国民年金基金連合会」が実施する年金制度をいいます。
(法第2条第3項)
②【H30年出題】
第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書を参照している)

【解答】
②【H30年出題】 〇
個人型確定拠出年金の加入者の範囲は、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方となっています。(平成29年版厚生労働白書)
「個人型年金加入者」について条文を読んでみましょう。
第62条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 (1) 国民年金法の第1号被保険者 ※国民年金の保険料を免除されている者は除かれます ただし、障害基礎年金の受給権者であることにより、法定免除の適用を受けている者は加入できます (2) 国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等は除かれます) (3) 国民年金法の第3号被保険者 (4) 国民年金法の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者又は20歳以上65歳未満の海外居住者が対象) |
➂【R3年出題】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
国民年金第3号被保険者も個人型年金加入者となることができます。「国民年金基金連合会」に申し出の部分もポイントです。
(法第62条第1項)
④【R7年出題】
確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
個人型年金加入者となることはできません。
条文を読んでみましょう
法第62条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、個人型年金加入者としない。 (1) 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 (2) 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者 |
⑤【R6年出題】
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
・ 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。
・ 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更します。
(法第68条)
⑥【R7年出題】-
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
個人型年金の給付は、「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」です。
当分の間、「脱退一時金」を請求することができます。
⑦【R7年出題】
確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に「委託することができる」ではなく「委託しなければならない」です。
また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができます。
(法第60条)
⑧【R7年出題】
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
⑧【R7年出題】 〇
個人型年金加入者期間を計算する場合には、「月」によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。
(法第63条)
⑨【R7年出題】
国民年金基金連合会は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

【解答】
⑨【R7年出題】 ×
個人型年金規約の見直しは、「少なくとも10年ごと」ではなく「少なくとも5年ごと」に必要です。
(法第59条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R8-053 10.16
「労働保険事務組合」のよく出る問題
「労働保険事務組合」でよく出る問題をみていきましょう
さっそく過去問をどうぞ!
①【R7年出題】(労災)
事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。

【解答】
①【R7年出題】(労災) ×
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、「事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(労働保険事務)を処理することができます。
問題文の労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続きは、労働保険事務組合が処理することができる手続きです。
★ポイント! 労働保険事務組合に処理を委託できない手続きをおさえましょう
・印紙保険料に関する事項
・保険給付に関する請求書等の手続き
・雇用保険の二事業に係る手続き
(法第33条第1項)
②【R7年出題】(労災)
事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。

【解答】
②【R7年出題】(労災) ×
「法人」であるか否かは問われません。
なお、法人でない団体又は連合団体の場合は、「代表者の定め」があることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が定款、規約等その団体等の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確であることが必要です。
(厚生労働省「労働保険事務組合の設立と認可について」)
➂【R7年出題】(労災)
政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。

【解答】
【R7年出題】(労災) ×
督促の効果は事業主に対して「及びます」。
条文を読んでみましょう
法第34条 (労働保険事務組合に対する通知等) 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。 |
・労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、直接事業主に対してすることなく、労働保険事務組合に対してすることができます。
・通知等の効果は、事業主に及びます。
④【R7年出題】(労災)
督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。

【解答】
④【R7年出題】(労災) ×
滞納事業主が、期限までに金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、労働保険事務組合の責に帰すべき理由ではありませんので、労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負いません。
条文を読んでみましょう
法第35条 (労働保険事務組合の責任等) ① 第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ② 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ➂ 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第27条第3項の規定(国税滞納処分の規定)による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 |
・労働保険事務組合は、事業主から交付を受けた金額の限度で、政府に対して徴収金を納付する責任を負います
⑤【R7年出題】(労災)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

【解答】
⑤【R7年出題】(労災) 〇
「労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定(不正受給者からの費用徴収)及び雇用保険法第10条の4第2項の規定(返還命令等)の適用については、事業主とみなす。」とされています。
(法第35条第4項)
労災保険法第12条の3を読んでみましょう
労災保険法第12条の3 ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 ② ①の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
・問題文のように、不正受給を行った場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「給付制限」
R8-052 10.15
公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときの給付制限
法第32条の基本手当の給付制限の事例の問題です。
★公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められる場合の認定基準をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第32条(給付制限) ① 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。 (2) 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 (3) 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 (4) 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所(同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所)に紹介されたとき。 (5) その他正当な理由があるとき。 ② 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときは、給付制限は受けません。
(法第32条第1項第3号)
②【R7年出題】
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正当な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。

【解答】
②【R7年出題】 〇
「正当な理由がなく」就職することを拒否した場合、これを理由に給付制限を受けます。
(行政手引52151)
➂【R7年出題】
建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
専門の知識、技能を有しない者がそれらを必要とする業務に紹介された場合は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
(行政手引52152)
④【R7年出題】
公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

【解答】
④【R7年出題】 〇
就職先の賃金の手取額がその者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低い場合は、原則として、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
(行政手引52152)
⑤【R7年出題】
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
労働時間その他の労働条件がその地域の同種の業務について行われるものに比べて、不当である事業所に紹介された場合は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
上記は、労働条件が法令には違反しないが、その地域の同種の業務について行われる一般水準に比べて不当に悪いことを指します。
(行政手引52152)
⑥【R7年出題】
一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
給付制限を受けます。
1か月以上賃金不払(賃金の3分の1を上回る額が支払われなかった場合を含む。)の事業所(将来正当な時期に賃金が支払われるものと認められるものを除く。)に紹介された場合は、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められ、給付制限は受けません。
なお、「1か月以上賃金不払」というのは、最近の、又は紹介を受けた当時における事実を指します。しかし、その事実が一時的なものであって、近い将来正当な時期に賃金が支払われることが確実な場合は、その就職を拒む正当な理由とはなりません。
問題文は、紹介された時点で賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実ですので、「給付制限の対象になります」。
(行政手引52152)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「休業補償給付」
R8-051 10.14
休業補償給付の基本問題
今回は、休業補償給付についてみていきます。
休業補償給付について条文を読んでみましょう。
法第14条 ① 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、 1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、(以下、今回は省略します) ② 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、①の額に別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。 |
②について
国民年金・厚生年金保険の年金は、業務上、業務外問わず支給されます。
そのため、同一の事由で、労災保険の年金と「国民年金・厚生年金の年金」が支給されることがあります。
その場合は、どちらも100%支給されるのではなく、労災保険の年金が減額されます。どちらからも100%支給されると、被災前の賃金よりも高額になるためです。
「休業補償給付」を受ける労働者が、同一事由で障害基礎年金、障害厚生年金を受ける際も、休業補償給付が減額されます。その際、休業補償給付は、「障害厚生年金又は障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率」を乗じて減額された額となります。
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「3年」ではなく「1年6か月」です。
休業補償給付は、休業給付基礎日額を用いて算定します。
療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後、休業給付基礎日額には年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。
療養開始後1年6か月を経過した日から傷病補償年金に切り替わる場合がありますが、その場合は当初から年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。それに合わせて、引き続き休業補償給付を受ける場合にも、1年6か月経過した日以後は、年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されることになります。
②【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】
②【H30年出題】×
「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、支給される。」とされています。
(最高裁判所第一小法廷 昭和58.10.13)
➂【R7年出題】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
②の問題と同じです。出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない日でも休業補償給付は支給されます。
④【R7年出題】
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。

【解答】
④【R7年出題】 〇
休業補償給付の額は減額されますが、その際、「障害厚生年金又は障害基礎年金」と傷病補償年金との調整について定める率を用います。
なお、この減額に当たっては、調整された休業補償給付の額と厚生年金等の額の合計が、調整前の休業補償給付の額より低くならないように調整限度額が設けられています。
(令第1条第1項)
ちなみに、厚生年金、国民年金は減額されず、全額支給されます。
⑤【R7年出題】
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
休業特別支給金の支給の申請は、「休業補償給付の請求後」ではなく、「休業補償給付の請求と同時に」行わなければなりません。
(特別支給金則第3条第5項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「総則」
R8-050 10.13
労基法「総則」(第1条~第12条)
労働基準法の総則をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第2条 (労働条件の決定) ① 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条 (男女同一賃金の原則) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第7条 (公民権行使の保障) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
第9条 (定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
第12条 平均賃金の算出(今回は省略します) |
過去問でポイントを確認しましょう
①【R3年出題】
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合は、第1条に抵触しますが、「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由」がある場合は、抵触しません。
(昭63.3.14基発150号)
※第1条、第2条違反については、罰則の定めはありません。
②【H28年出題】
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものです。本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなりません。
(昭22.9.13発基17号)
➂【R3年出題】
労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
労働者を「有利」に取り扱うことも差別的取扱に含まれます。
④【H29年出題】
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

【解答】
④【H29年出題】 ×
労働基準法第3条で禁止しているのは、労働者の「国籍、信条、社会的身分」を理由として、労働条件について差別的取扱をすることです。第3条では、「性別」を理由とする差別的取扱については禁止していません。
⑤【H25年出題】
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
労働基準法第4条では、性別による差別のうち、「賃金」についてのみ、差別的取扱いを禁止しています。
⑥【R7年出題】
労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
第5条で禁止しているのは、使用者が「労働者の意思に反して労働を強制する」ことです。労働者が現実に労働することは必要とされません。
(昭23.3.2基発381号)
⑦【R7年出題】
労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。

【解答】
⑦【R7年出題】 〇
「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たります。
(昭23.3.2基発381号)
⑧【R7年出題】
労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

【解答】
⑧【R7年出題】 〇
使用者は、選挙権その他公民としての権利の行使や公の職務を執行するために必要な時間を、労働時間中に認めなければなりませんので、労働者が労働時間中に、必要な時間を請求した場合は、使用者はこれを拒んではなりません。「拒んだ」だけで、第7条違反となります。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます。
⑨【H29年出題】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

【解答】
⑨【H29年出題】 〇
株式会社の取締役でも業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受けます。
(昭23.3.17基発461号
⑩【R7年出題】
労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。

【解答】
⑩【R7年出題】 ×
労働基準法第9条に定める労働者は、「事業に使用される者」ですので、失業者は含みません。
なお、労働組合法の労働者は、「他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。(昭23.6.5労発基262号)
⑪【R2年出題】
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。

【解答】
⑪【R2年出題】 ×
使用者は、①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。
そのうち、①「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、「その代表取締役」ではなく、「法人そのもの」をいいます。
⑫【R7年出題】
労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。

【解答】
⑫【R7年出題】 〇
労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が行う保険料補助金は、労働基準法第11条に定める「賃金」となりません。
なお、労働者が法令の定めにより負担すべき所得税等(社会保険料等も含む。)を使用者が労働者に代わって負担する場合は、使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金となります。
(昭63.3.14基発150号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
日曜日はYouTube総集編です!
R8-049 10.12
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年10月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年10月6日から11日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 合算対象期間の基本3つ(国民年金法)
・ 労働契約期間の上限(労働基準法)
・ 労働条件の明示義務(労働基準法)
・ 賃金全額払の原則(労働基準法)
・ 割増賃金の基礎となる賃金の算出(労働基準法)
・ 就業規則に関する出題(労働基準法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「就業規則」
R8-048 10.11
就業規則に関する出題
今回は、「就業規則」の問題をみていきます。
就業規則について条文を読んでみましょう
法第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 <絶対的必要記載事項> ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ② 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ➂ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) <相対的必要記載事項> ④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 ⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 ⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 ⑦ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑩ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 ⑪ 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
法第90条(作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。
法第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。

【解答】
①【R7年出題】 〇
使用者には、「就業規則」を、労働者に周知させる義務があります。(法第106条)
周知の方法は、次の3つのうちいずれかの方法です。(則第52条の2)
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
②書面を労働者に交付すること。
➂使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
②【R7年出題】
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
②【R7年出題】 〇
従業員の金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なわれる所持品検査が許されるための要件と従業員の検査の受忍義務について判示されています。
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例です。
(西日本鉄道事件 最二小 昭43.8.2)
➂【R7年出題】
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいてはじめて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、「始業及び終業の時刻」や「休日」に関する事項などについて、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条第1号等)。
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻や休日が異なる場合には、勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻等を規定しなければなりません。
シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことになりません。
しかし、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えありません。
(令和4年1月7日 厚生労働省 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項より)
④【R7年出題】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。」と規定されています。(則第49条)
就業規則の届出に添付すべき意見書については、労働者の押印又は署名は不要です。
⑤【R7年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
労働者が、遅刻・早退をした場合、労働の提供がなかった時間について、その分、賃金を差し引いても、労基法第91条に定める減給の制裁には該当しません。
ただし、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされますので、減給の制裁の規定の適用を受けます。
(昭63.3.14基発150号)
なお、減給制裁には以下のように限度が設けられています。
・1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内
・一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額は、当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「割増賃金」
R8-047 10.10
割増賃金の基礎となる賃金の算出
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合は、1時間当たりの賃金を一定率以上で割増した割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の基礎となる賃金(1時間当たりの単価)の算出方法をみていきます。
条文を読んでみましょう
則第19条第1項 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 (1) 時間によって定められた賃金 → その金額 (2) 日によって定められた賃金 → その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 (3) 週によって定められた賃金 → その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 (4) 月によって定められた賃金 → その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 (5) 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 (6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 → その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |
★割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金(則第21条)
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

①【R7年出題】 ×
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金ですので、割増賃金の基礎となる賃金には算入しなくてもいいとされています。
ただし、問題文のように、通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合は、実際距離によらない1,000円は割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。
通 勤 手 当 | |
距離にかかわらず一律1,000円 | 実際距離に応じて支払われる |
↑
実際距離によらない1,000円は割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。
(昭23.2.20基発295号)
②【R7年出題】
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。

【解答】
②【R7年出題】 ×
手術手当は、手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金となります。
手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくても差し支えありません。
(昭23.11.22基発1681号)
➂【R7年出題】
通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
通常は事務作業に従事していても、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合は、特殊作業手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなくてはなりません。
(昭23.11.22基発1681号)
④【R7年出題】
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
賞与は割増賃金の基礎となる賃金には算入しませんが、「支給額が確定している」ものは、労働基準法の賞与とはみなされません。
そのため、毎月支払部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しません。
問題文の場合は、賞与額も含めて確定した年俸額を算定の基礎とした割増賃金の支払が必要です。
(平12.3.8基収78号)
⑤【R7年出題】
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる看護業務に従事したときに支給される夜間看護手当は、通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされています。
(昭41.4.2基収1362号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「賃金支払い5原則」
R8-046 10.09
賃金全額払の原則
賃金の支払方法には次の5つの原則があります
・通貨払いの原則
・直接払いの原則
・全額払いの原則
・毎月1回以上払いの原則
・一定期日払いの原則
条文を読んでみましょう
法第24条(賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
5つの原則とともに、例外にも注意しましょう。
今回は、「全額払の原則」についてみていきます。
賃金は「全額払」が原則です。
例外で、
・法令に別段の定めがある場合
→所得税の源泉徴収、社会保険料、雇用保険料の控除などが認められています。
・当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)がある場合
→購買代金、福利厚生施設の費用、社内預金、組合費などの控除が認められます。
過去問を解いてみましょう
①【R6年選択式】
最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の< A >ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
(選択肢)
①権利濫用に該当しない
②自由な意思に基づく
➂退職金債権放棄同意書への署名押印により行われた
④退職に接着した時期においてされた

【解答】
<A> ②自由な意思に基づく
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「有効」であるとされました。
(最高裁第二小法廷判決シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件昭和48.1.19)
②【H27年出題】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
②【H27年出題】 ×
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「有効」であるとするのが最高裁判所の判例です。
(最高裁第二小法廷判決シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件昭和48.1.19)
➂【R3年出題】
労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
「相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない」とするのが最高裁判所の判例です。
(最高裁第一小法廷判決福島県教組事件昭和44.12.18)
④【H21年選択式】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[…(略)…]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の < A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。
(選択肢)
①経済生活の安定 ②自由な意思 ③生活保障 ④同意に基づく相殺

【解答】
<A> ①経済生活の安定
(最高裁第一小法廷判決福島県教組事件昭和44.12.18)
⑤【R7年出題】
労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものですので、法第24条違反とはなりません。
(昭23.9.14基発1357号)
⑥【H23年出題】
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。

【解答】
⑥【H23年出題】 〇
5分の遅刻について、30分遅刻したとして賃金カットをすることは、労務の提供のなかった限度を超えるカットとなり、全額払の原則に反し違法です。
ただし、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として労基法第91条の制限内で行う場合には、賃金の全額払の原則に反しません。
(昭63.3.14基発150号)
⑦【H19年出題】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
⑦【H19年出題】 ×
「1日」単位で、問題文のような端数処理を行うことは、法違反となります。
割増賃金の計算の便宜上、「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされています。
(昭63.3.14基発150号)
⑧【H29年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
⑧【H29年出題】 〇
<端数処理について>
・1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合
→50円未満切り捨て、それ以上を100円に切り上げる方法は、労働基準法第24条違反にはなりません。
(昭63.3.14基発150号)
⑨【H24年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
⑨【H24年出題】 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に千円未満の端数が生じた場合
→ その額を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反にはなりません。
(昭63.3.14基発150号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働契約」
R8-045 10.08
労働条件の明示義務
労働契約の締結の際、使用者は労働条件を明示しなければなりません。
また、明示された労働条件と実際の労働条件が相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
条文を読んでみましょう
法第15条 (労働条件の明示) ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ ②の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【H16年出題】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。

【解答】
①【H16年出題】 〇
労働基準法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件は、賃金、労働時間はもちろん、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいうとされています。
一方、労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、労働基準法施行規則第5条で範囲が具体的に定められています。
②【R6年出題】
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 〇
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇入れ直後の「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示が必要です。
(則第5条第1項第1号の3)
➂【R2年出題】
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

【解答】
➂【R2年出題】 〇
賃金に関しては、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期」について書面の交付が必要です。
交付すべき書面の内容としては、就業規則の規定と併せ、前記の賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされています。
(H11.3.31基発168号)
なお、「書面の交付」については、労働者が書面の交付が必要な事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができるとされています。
(1) ファクシミリを利用してする送信の方法
(2) 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(則第5条第4項)
④【H23年出題】
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

【解答】
④【H23年出題】 〇
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
⑤【R5年出題】
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
・社宅を利用する利益が、法第11条にいう賃金である場合は、社宅を供与すべき旨の条件は、法第15条第1項の「賃金、労働時間その他の労働条件」となります。そのため、社宅を供与しなかった場合は、同条2項の労働契約の解除権を行使できます。
・社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合は、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれません。そのため、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできません。
ちなみに、労基法第15条の適用がなくても、民法第541条の規定によって契約を解除することは可能です。
(昭23.11.27基収3514号)
⑥【H28年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合は、「その解除は、将来に向かってのみその効力を生じる」とされています。
(民法第630条)
労働契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるのものではありません。
⑦【R7年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
明示された労働条件は労働契約の内容となっているため、明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働契約」
R8-044 10.07
労働契約期間の上限
労働契約には①契約期間の定めがないものと②契約期間の定めがあるものの2つがあります。
①契約期間の定めがない場合は、使用者も労働者もいつでも契約を解除することができますので、労働基準法の規制はありません。
②契約期間の定めがある(有期労働契約)の場合は、契約期間中は、原則として契約の解除ができません。そのため、労働者を長く拘束することがないように、労働基準法では、契約期間に上限(原則3年)が設けられています。
では、条文を読んでみましょう
法第14条第1項 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 (1) 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 (2) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |
過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
期間の定めのない労働契約にはなりません。
「法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年、その他のものについては3年となること。」とされています。
労働基準法第13条も読んでみましょう
| この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、その部分は無効となり、無効となった部分は、「労基法第14条第1項に規定する期間」となります。
(平15.10.22基発第1022001号)
②【H27年出題】
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

【解答】
②【H27年出題】 〇
例えば、10年で終了する「建設工事」現場の場合は、10年の労働契約を締結することができます。
➂【R2年出題】
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

【解答】
➂【R2年出題】 〇
契約期間の上限を5年にできるのは、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者」に限られています。当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合は、例外の5年は適用されませんので、契約期間の上限は原則の3年となります。
(平15.10.22基発第1022001号)
④【R4年出題】
社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められていることが必要である。

【解答】
④【R4年出題】 〇
「契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、労働者が国家資格を有していることだけでは足りず、当該国家資格の名称を用いて当該国家資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要であるものであること。」とされています。
(平15.10.22基発第1022001号)
⑤【R7年出題】
労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
「契約締結時に満60歳以上である労働者との間に締結されるものであることを要すること。」とされています。
(平15.10.22基発第1022001号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「合算対象期間」
R8-043 10.06
合算対象期間の基本3つ
老齢基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることです。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年未満でも、合算対象期間を合算して10年以上あれば、要件を満たします。
「合算対象期間」は、「カラ期間」ともいわれ、10年の計算には入りますが、老齢基礎年金の年金額の計算には入りません。
今回は、合算対象期間の基本を3つみていきます
 任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間
任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間
 海外在住邦人について
海外在住邦人について
 厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
では、合算対象期間の過去問を解いてみましょう
 <任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間>
<任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間>
①【H23年出題】
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

【解答】
①【H23年出題】 ×
昭和60年改正前の国民年金法(旧法)で、任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間となります。ただし、「20歳以上65歳未満」ではなく合算対象期間となるのは「20歳以上60歳未満」の期間です。
(昭60法附則第8条第5項第1号)
②【R5年出題】
昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
学生が国民年金に強制加入することになったのは、「平成3年4月1日」以降で、それまでは「任意加入」することができました。
そのため、合算対象期間になるのは、昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間となります。
(昭60法附則第8条第5項第1号)
★学生について
旧 法 | 新 法 | |
S36.4.1 | S61.4.1 | H3.4.1 |
任意加入 | 強制加入 | |
 <海外在住邦人について>
<海外在住邦人について>
➂【R7年出題】
日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
旧法の国民年金法では、日本国籍を有する人が海外に在住している間は国民年金の適用が除外され、任意加入もできませんでした。
そのため、日本国籍を有する人が日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間(旧法の期間)は、合算対象期間となります。20歳から60歳までの間に限られていることにも注意してください。
(昭60法附則第8条第5項第9号)
旧 法 | 新 法 |
適用除外(任意加入もできない) | 任意加入できる |
 厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
④【R7年出題】
昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。

【解答】
④【R7年出題】 〇
昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は合算対象期間です。
(昭60法附則第8条第4項)
★第2号被保険者期間について
第2号被保険者 | ||
| 20歳 | 60歳 |
合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |
なお、「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで」の間の、被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の被保険者期間についても、20歳未満・60歳以上の期間は合算対象期間となります。
(昭60法附則第8条第6項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です!
R8-042 10.05
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年9月第5週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年9月29日から10月4日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ 「外国人雇用実態調査」からの出題(労働に関する一般常識)
・ 高齢者医療確保法の基本問題を解いてみる(社会保険に関する一般常識)
・ 資格確認書の交付申請(健康保険法)
・ 一般保険料率の決定などのルール(健康保険法)
・ 事後重症による障害厚生年金の請求(厚生年金保険法)
・ 育児休業中の保険料免除~1か月以下の場合に注意(厚生年金保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「育休中の保険料免除」
R8-041 10.04
育児休業中の保険料免除~1か月以下の場合に注意
育児休業中は、厚生年金保険料は事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。(健康保険料も同様に免除されます)
免除の要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第81条の2 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例) ① 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 ② 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、「育児休業等をしている被保険者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたとき」となる。(=被保険者本人が申出を行う) |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
産前産後休業中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
産前産後休業中の保険料の免除を受けるには、実施機関に申出を行わなければなりません。
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者 → 事業主が申出
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者 → 被保険者本人が申出
※「育児休業中の保険料免除」についても同様です。
②【R6年出題】
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担及び被保険者負担分の両方が免除される。

【解答】
②【R6年出題】 〇
産前産後休業中の保険料については、事業主負担及び被保険者負担分の両方が免除されます。
※「育児休業中の保険料免除」も同様です。
➂【R7年出題】
厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
第81条の2第1項に、「その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。」とあります。育児休業等の期間が1か月以下でも、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されますが、その月の標準賞与額に係る保険料については免除されません。
④【R1年出題】
適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
事業主は、賞与を支給した場合、賞与額の届出を行わなければなりません。
産前産後休業期間中や育児休業期間中で保険料の免除が適用されている者でも、休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出が必要です。
(則第19条の5)
健康保険法の問題も解いてみましょう
①【健保R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【健保R5年出題】 〇
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合に該当します。
育児休業等を開始した日(=令和5年1月10日)の属する月(=令和5年1月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の前月までの月(=令和5年3月)までの保険料が免除されます。
②【健保R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【健保R5年出題】 ×
育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合は、その月の育児休業等の日数が14日以上あれば、その月の保険料が免除されます。
育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合、育休開始日と終了日の翌日が同一月にあり、育児休業の日数が13日しかありません。そのため、保険料は免除されません。(保険料が徴収されます)
➂【健保R6年出題】
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
➂【健保R6年出題】 ×
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合に該当します。
育児休業等を開始した日(=令和5年10月1日)の属する月(=令和5年10月)から育児休業等が終了する日の翌日(=令和6年1月1日)が属する月の前月までの月(=令和5年12月)までの保険料が免除されます。
令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は「徴収されます」。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「事後重症の障害厚生年金」
R8-040 10.03
事後重症による障害厚生年金の請求
「障害厚生年金」は、「初診日」「保険料納付要件」「障害認定日」の3つの要件を満たした場合、障害認定日に受給権が発生します。
「初診日」、「保険料納付要件」を満たしていても、障害認定日に障害等級1~3級に該当しない場合は、障害厚生年金の受給権は発生しません。
ただし、障害認定日の後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は事後重症の障害厚生年金の請求ができます。事後重症の障害厚生年金は請求によって受給権が発生します。
条文を読んでみましょう
第47条の2 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。 ② 保険料納付要件を満たしていること ➂ 請求があったときは、その請求をした者に障害厚生年金を支給する。 |
過去問を解きながらポイントを確認しましょう
①【R4年選択式】
厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後< A >までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。

【解答】
<A> 65歳に達する日の前日
②【R7年出題】
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
事後重症の障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当+その期間内(65歳に達する日の前日まで)に請求することが条件です。
➂【R7年出題】
事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
事後重症の障害厚生年金は、障害等級1級及び2級だけでなく、「3級」も対象です。
④【H29年出題】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
65歳に達した日以後は、事後重症による障害厚生年金は請求できません。
⑤【R1年出題】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、64歳であったとしても、事後重症による障害厚生年金の支給を請求することはできません。
(法附則第16条の3第1項)
⑥【R6年出題】
厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

【解答】
⑥【R6年出題】 ×
事後重症による障害厚生年金は、「請求した日の属する月の翌月」から支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「一般保険料率」
R8-039 10.02
一般保険料率の決定などのルール
健康保険の被保険者の保険料額は、次のように計算します。
(1)介護保険第2号被保険者の被保険者(介護保険料額を合わせて計算します)
一般保険料額+介護保険料額
(2)介護保険第2号被保険者ではない被保険者
一般保険料額
・一般保険料額→(標準報酬月額及び標準賞与額)×一般保険料率
・介護保険料額→(標準報酬月額及び標準賞与額)×介護保険料率
※一般保険料率とは、「基本保険料率」と「特定保険料率」とを合算した率のことです。
・特定保険料率とは
各年度において保険者が納付すべき 前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険の場合は国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合は、これを控除した額) |
総報酬額の総額の見込額 |
・基本保険料率は一般保険料率から特定保険料率を引いた率
「一般保険料率」の決定などのルールを条文で読んでみましょう
法第160条 <全国健康保険協会> ① 全国健康保険協会(以下「協会」という)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。 ② 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。 ⑤ 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が期間内に変更の認可の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
<健康保険組合> ⑬ 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定するものとする。 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
この問題のキーワードを穴埋めで確認しましょう。
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、< A >の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について< B >を受けなければならない。
解答→<A>運営委員会 <B>厚生労働大臣の認可
(法第160条第6項、第8項)
②【H24選択式】
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< A >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< B >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】
<A> 健康保険事業の収支の均衡
<B> 社会保障審議会
(法第160条第11項)
※社会保障審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項の調査審議などを行う機関です。
➂【R6年出題】
協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

【解答】
➂【R6年出題】 ×
「厚生労働大臣に届け出る」ではなく、「公表するものとする」です。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
協会は、< A >ごとに、翌事業年度以降の< B >についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の< C >を作成し、< D >ものとする。
<解答>→ <A>2年 <B>5年間 <C>収支の見通し <D>公表する
④【R7年出題】
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「社会保障審議会の議を経て」が誤りです。社会保障審議会は厚生労働大臣の諮問に応じる機関です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
10月1日は合格発表でした
10月1日は合格発表でした。
合格率は5.5%。
合格された方、おめでとうございます!
(合格のご報告いただきました皆様、ありがとうございます)
素晴らしい結果を出されたこと、本当に素晴らしいです!
もう一度頑張る方、来年初めて受験される方、どうしようか迷っている方
こちらのチャンネル・ホームページでは、問題の解き方を中心にお話ししています。
問題が解けるようになると、格段に勉強が楽しくなります。
どんどん問題を解いて、問題に慣れて、受験勉強も楽しみましょう。
健康保険法「資格確認書」
R8-038 10.01
資格確認書の交付申請
被保険者証が廃止になり、保険診療等は、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)によって受けることになります。
なお、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者については、医療機関等で資格確認を受けるための「資格確認書」を、書面又は電磁的方法により提供することとなっています。
★マイナンバーカードのICチップ等によって、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みのことをオンライン資格確認(電子資格確認)といいます。
電子資格確認を受けることができない状況にあるときの条文を読んでみましょう
法第51条の3(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) ① 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)による提供を求めることができる。この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。 ② 書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、法第63条第3項(療養の給付)等について被保険者であることの確認を受けることができる。 |
では問題を解いてみましょう
【R7年出題】
資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

【解答】
【R7年出題】 〇
・資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める場合
↓
・申請者は申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請します。
↓
・申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行います。
↓
・災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由しなくてもよい。
(則第47条第1項)
続きを条文で読んでみましょう
則第47条第2項、5項、6項、8項 ② 保険者は、資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供の申請があったときは、申請者に対し、法第51条の3第1項に規定する書面であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。 ⑤ 保険者は、申請者(任意継続被保険者を除く。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。 ⑥ 資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者(任意継続被保険者を除く。)に送付しなければならない。 ⑧ 保険者は、申請者(任意継続被保険者に限る。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者(任意継続被保険者に限る。)に送付しなければならない。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」
R8-037 9.30
高齢者医療確保法の基本問題を解いてみる
「後期高齢者医療」では、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行います。
事務を処理するため、後期高齢者医療広域連合が設けられています。
条文を読んでみましょう。
法第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 |
※保険料徴収などの窓口業務は、地域住民の身近な存在である市町村が担います。
では、問題を解いてみましょう
①【R7年出題】
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
都道府県は入りません。
条文を読んでみましょう。
法第48条 後期高齢者医療広域連合及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 |
後期高齢者医療の制度の運営は広域化を図るため、後期高齢者医療広域連合が事務を処理しますが、保険料徴収などの窓口業務は身近な市町村が行っています。
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、特別会計を設けなければなりません。
②【R7年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の者のみではありません。
条文を読んでみましょう。
法第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |
➂【R7年出題】
高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合ではなく、「市町村」の条例で定めます。
保険料の徴収の事務は「市町村」が担うことに注意しながら条文を読んでみましょう。
第104条第1項 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金及び出産育児支援金並びに感染症の予防及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 第105条 市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を納付するものとする。 第106条 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。 |
※保険料の徴収の方法には、「特別徴収」=年金から天引きする方法と「普通徴収」=個別に納付する方法があります。
第108条 ① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ➂ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 第109条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。 |
④【R7年出題】
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

【解答】
④【R7年出題】 〇
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。
⑤【R7年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
その日の翌日からではなく、「その日」からその資格を喪失します。
後期高齢者医療の被保険者の資格喪失の時期について条文を読んでみましょう。
法第53条 ① 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日若しくは第50条第2号の状態(65歳以上75歳未満で障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた)に該当しなくなった日又は第51条第2号に掲げる者(後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者)に該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者)に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働に関する一般常識「統計」
R8-036 9.29
「外国人雇用実態調査」からの出題
外国人雇用に関する問題を解いてみましょう。
「外国人雇用実態調査(厚生労働省)」からの出題です。
問題を解いてみましょう
①【R7年出題】
外国人常用労働者(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人となっており、産業別にみると、「製造業」が最も多くなっている。

【解答】
①【R7年出題】 〇
「外国人労働者(雇用保険被保険者数5人以上事業所)は約160万人。産業別にみると、「製造業」が最も多い。次いで、「サービス業(他に分類されないもの)」、「卸売業,小売業」、「建設業」となっています。
(令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省))
②【R7年出題】
外国人常用労働者の国籍・地域をみると、中国(香港、マカオ含む)が最も多く、次いで「ベトナム」、「フィリピン」の順となっている。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「外国人労働者の国籍・地域をみると、ベトナムが最も多く、次いで「中国(香港、マカオ含む)」、「フィリピン」の順となっています。
(令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省))
➂【R7年出題】
外国人常用労働者の職業をみると、「専門的・技術的職業従事者」が最も多く、次いで「生産工程従事者」、「サービス職業従事者」の順となっている。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
外国人労働者の職業をみると、生産工程従事者が最も多く、次いで「専門的・技術的職業従事者」、「サービス職業従事者」の順となっています。
(令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省))
④【R7年出題】
外国人労働者を雇用する理由(事業所計)をみると、「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」が最も多く、次いで「労働力不足の解消・緩和のため」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順となっている。

【解答】
④【R7年出題】 ×
外国人労働者を雇用する理由をみると、「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順となっています。
(令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省))
⑤【R7年出題】
外国人労働者の雇用に関する課題(事業所計)をみると、「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」が最も多く、次いで「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順となっている。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
外国人労働者の雇用に関する課題をみると、「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も多く、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順となっています。
(令和5年外国人雇用実態調査(厚生労働省))
★なお、令和7年に出題された問題は「令和5年外国人雇用実態調査」からですが、令和7年8月29日に「令和6年外国人雇用実態調査」の結果が厚生労働省から公表されています。
令和6年外国人雇用実態調査のポイントも確認しましょう。
・<外国人労働者数(雇用保険被保険者数5人以上事業所)>
約182万人(前年約160万人)。産業別にみると、「製造業」が最も多く、次いで、「サービス業(他に分類されないもの)」、「卸売業,小売業」、「建設業」の順
・<外国人労働者を雇用する理由>
「労働力不足の解消・緩和のため」が最も多く、次いで「日本人と同等またはそれ以上の活躍を期待して」、「事業所の国際化、多様性の向上を図るため」、「日本人にはない知識、技術の活用を期待して」の順
・<外国人労働者の雇用に関する課題>
「日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい」が最も多く、次いで「在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑」、「在留資格によっては在留期間の上限がある」、「文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある」の順
・<国籍・地域別>
「ベトナム」が最も多く、次いで中国(香港、マカオ含む)、フィリピンの順
・<外国人労働者の職業>
「生産工程従事者」が最も多く、次いで専門的・技術的職業従事者、サービス職業従事者の順
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です!
R8-035 9.28
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年9月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年9月22日から27日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件(厚生年金保険法)
・厚生年金の年金額の計算(給付乗率の引上げと300月保障)(厚生年金保険法)
・賃金の非常時払(非常時の出費のために)(労働基準法)
・労使協定の協定当事者の要件(労働基準法)
・労災保険の適用について(労災保険法)
・基本手当の所定給付日数・受給期間の総合問題(雇用保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「基本手当の受給期間」
R8-034 9.27
基本手当の所定給付日数・受給期間の総合問題
基本手当の「受給期間」についてみていきます。
受給期間の原則は、1年ですが、所定給付日数が330日の場合は「1年+30日」、360日の場合は「1年+60日」となります。
また、基本手当の所定給付日数は、「算定基礎期間」、「離職理由」、「年齢」などによって決まります。
では、問題を解いてみましょう
【R7年出題】
次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。
なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
➂39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難なものでなく、職業に就くことができる状態にあった。
<A> 1年
<B> 1年と30日
<C> 1年と60日
<D> 4年
<E> 4年と30日

【解答】
【R7年出題】
<B> 1年と30日
ポイントを確認しましょう。
① 20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 育児休業給付金の支給に係る休業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
→「育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある者については、これらの給付金の支給に係る休業の期間」は、算定基礎期間から除外されます。
➂39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④ 失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。 → 適用事業所XとYの間が1年以内で、かつ失業等給付を受給していないので、XとYの被保険者であった期間は通算されます。
⑤ 適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。
→ 「事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者」となり、特定受給資格者に該当します。
なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条第2項が定める就職が困難なものでなく、職業に就くことができる状態にあった。
→ 「職業に就くことができる状態」ですので、妊娠、出産、育児等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合の受給期間の延長の対象にはなりません。
・算定基礎期間は、Xの被保険者であった期間(19年-2年(育休)=17年)+Yの被保険者であった期間(6年6か月)=23年6か月です。
・離職時の年齢が45歳以上60歳未満で、算定対象期間が20年以上の特定受給資格者ですので、所定給付日数は330日です。
・受給期間は1年と30日です。
(法第20条、第22条、第23条、則第35条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「適用」
R8-033 9.26
労災保険の適用について
労災保険は、労働者を使用する事業に適用されます。
条文を読んでみましょう。
第3条 ① 労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 ② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
今回は、「出向の場合」、「労働者派遣の場合」、「就労継続支援を行う事業場の場合」、「インターンシップの実習」、「公立小学校教諭に臨時的任用された場合」の労災保険の適用をみていきます。
問題を解いてみましょう
①【R7年出題】
出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「常に出向先事業に係る保険関係による」が誤りです。
出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定することとされています。
(昭和35.11.2基発第932号)
②【R7年出題】
派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
労災保険は、労働者を使用する事業(=「労働契約関係」にある事業)を適用事業とします。そのため、派遣労働者については、労働契約関係にある「派遣元事業主」が労災保険の適用事業となります。
(昭61.6.30基発383号)
➂【R7年出題】
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者で、「雇用契約が有る」場合は労働基準法上の労働者ですので、労災保険が適用されます。しかし、「雇用契約が無い」場合は労災保険法は適用されません。
(平18.10.2障障発第1002003号)
④【R7年出題】
インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
インターンシップの実態によっては、労災保険が適用されることがあります。
一般に、インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条の労働者に該当しません。
しかし、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられますので、労災保険が適用されます。
(平9.9.18基発第636号)
⑤【R7年出題】
育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

⑤【R7年出題】 ×
非現業部分の地方公務員には「地方公務員災害補償法」、非常勤職員には、原則として、地方公務員災害補償法に基づいて定められる災害補償の条例が適用されます。
(法第3条第2項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労使協定」
R8-032 9.25
労使協定の協定当事者の要件
使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合は、労使協定の締結と届出が必要です。
労働基準法第36条に定められている労使協定を36協定といいます。
第36条を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
労使協定の労働者側の当事者は、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合」、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」です。
今回は、協定当事者になる要件などをみていきます。
過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
労働者の過半数を代表する者の選出は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。」と規定されています。
「使用者の意向に基づき選出されたものでない」ことがポイントですので、投票券等の書面を用いた方法に限定されません。
(則第6条の2第1項第2号)
②【H22年出題】
労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。

【解答】
②【H22年出題】 ×
管理監督者は労働者代表になることはできません。
労働者の過半数代表者は、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。」という要件が規定されています。
(則第6条の2第1項第1号)
➂【R7年出題】
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
36協定は、時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためものではなく、「当該事業に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのもの」と解釈されています。そのため、「労働者」の範囲には、「管理監督者」、「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などの時間外労働又は休日労働を考える余地のない者も含まれます。
(昭45.1.1845基収6206号)
④【R7年出題】
協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。

【解答】
④【R7年出題】 〇
三六協定は、それぞれの事業場ごとに締結します。しかし、協定当事者については、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能であると解されています。
(昭24.2.9基収第4234号)
⑤【R7年出題】
法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したとしても、その代表者は36協定を締結するために選任されたわけではないので、「労働者の過半数を代表する者」に当たりません。
(参照:厚生労働省ホームページ)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「非常時払」
R8-031 9.24
賃金の非常時払(非常時の出費のために)
「賃金の非常時払」とは、例えば、労働者が予期せぬ災害等で出費が必要となった場合に、賃金の支払期日前に賃金の支払を請求できる制度です。ただし、対象になるのは「既往の労働に対する賃金」です。
条文を読んでみましょう。
法第25条 (非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
則第9条 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 (1) 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 (2) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 (3) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。

【解答】
①【H29年出題】〇
「非常時」とは、「出産」、「疾病」、「災害」、「結婚」、「死亡」、「やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合」です。
「労働者本人」だけでなく、「その労働者の収入によって生計を維持する者」に係る事由も対象です。
②【R3年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由には、「労働者の収入によって生計を維持する者」の出産、疾病、災害も含まれるが、「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみならず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えないとされています。
③【R1年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
「疾病」には、業務上の疾病、負傷だけでなく、業務外のいわゆる私傷病も含まれます。なお、「災害」についても業務上、業務外は問われません。
④【R7年出題】
労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。

【解答】
④【R7年出題】 ×
労働者が非常時払を請求した場合、使用者が支払期日前に支払義務を負うのは、「既往の労働に対する賃金」です。いまだ労務の提供のない期間に対する賃金は、支払う義務はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「報酬比例部分の計算」
R8-030 9.23
厚生年金の年金額の計算(給付乗率の引上げと300月保障)
厚生年金保険の被保険者は、月々の給与(標準報酬月額)とボーナス(標準賞与額)に応じて、保険料を負担しています。
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の年金額は、「標準報酬月額と標準賞与額」と「被保険者期間(加入期間)」をベースに計算されます。
今回は厚生年金の計算式をみていきます。
※平成15年4月以降の加入期間についてみていきます。平成15年3月以前については月収ベースで計算しますので計算式が異なります。
老齢厚生年金の年金額の計算について条文を読んでみましょう。
法第43条第1項 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1,000分の 5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 ※平均標準報酬額とは? 被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。 |
<老齢厚生年金の年金額の計算式>
平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数
ポイント!
・「1000分の5.481」について
昭和21年4月1日以前に生まれた者は、生年月日に応じて1000分7.308から1000分の5.562に引上げます。
・「被保険者期間の月数」について
実際の加入期間で計算します。上限・最低保障はありません。
・「再評価率」について
過去の標準報酬月額や標準賞与額を現在の価値に再評価するための率です。
障害厚生年金の年金額の計算について条文を読んでみましょう
法第50条 ① 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例(老齢厚生年金の計算式)により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 |
ポイント!
・「1000分の5.481」について
老齢厚生年金のような生年月日による引上げはありません。
・「被保険者期間の月数」について
被保険者期間が300月未満の場合は、「300月」で計算されます。
遺族厚生年金の年金額の計算について条文を読んでみましょう
法第60条第1項 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、(1)に定める額とする。 (1) (2)以外の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例(老齢厚生年金の年金額の計算)により計算した額の4分の3に相当する額。 ただし、短期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 (2) 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → (1)に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ (1)に定める額に3分の2を乗じて得た額 ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く。)に2分の1を乗じて得た額 |
ポイント!
短期要件と長期要件で計算式が変わります。
| 給付乗率(1000分の5.481) | 被保険者期間の月数 |
短期要件 | 生年月日による引上げなし(定率) | 300月未満の場合は300月保障 |
長期要件 | 生年月日による引上げあり | 実際の加入期間 |
過去問を解いてみましょう
①【H23年選択式】
老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
①【H23年選択式】
<A> 再評価率
<B> 5.481
②【R6年出題】
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
生年月日に応じて給付乗率が引き上げられるのは昭和36年4月1日以前ではなく、「昭和21年4月1日以前」に生まれた者です。
➂【R1年出題】
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

【解答】
③【R1年出題】 〇
障害等級1級の障害厚生年金の額は、「老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数)×100分の125」です。
※被保険者期間の月数が300未満の場合は300で計算します。
④【R7年出題】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の算定式により計算した額となる。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。また、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われない。

【解答】
④【R7年出題】 〇
障害等級2級の障害厚生年金の額は、「平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」で計算した額です。被保険者期間の月数が300未満のときは、300で計算し、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われません。
⑤【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
障害等級3級の場合は障害基礎年金が支給されないため、3級の障害厚生年金には最低保障額が設けられています。最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2ではなく「4分の3」に相当する額です。
(法第50条第3項)
ちなみに、配偶者加給年金額は1級と2級の障害厚生年金には加算されますが、3級の障害厚生年金には加算されません。
⑥【R6年出題】
死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。

⑥【R6年出題】 ×
死亡した者が短期要件に該当する場合は、給付乗率の引上げは行われません。なお、被保険者期間が300月未満の場合は、300月で計算されます。
⑦【H27年出題】※改正による修正あり
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

【解答】
⑦【H27年出題】 〇
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」の死亡により支給される遺族厚生年金は「長期要件」です。死亡した者が昭和21年4月1日以前生まれの場合は、生年月日に応じ引上げられた乗率が適用されます。
⑧【R6年出題】
現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済となっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。

【解答】
⑧【R6年出題】 ×
問題文の甲は、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」に該当し、遺族厚生年金は「長期要件」となります。(短期要件には該当しません。)
長期要件ですので、遺族厚生年金の額の計算については、実際の被保険者期間の5年(60月)で計算され、300月の最低保障はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「加給年金額」
R8-029 9.22
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件
老齢厚生年金の受給権者に、「65歳未満の配偶者」又は「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)」がある場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
今回は、加給年金額が加算される要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第44条第1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項(障害基礎年金の子の加算)の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
ポイント!
<加給年金額が加算される原則の要件>
・厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算されている老齢厚生年金の受給権者であること
・受給権者が「老齢厚生年金の受給権を取得した当時」、「生計を維持」していた65歳未満の配偶者又は子が対象
では、過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
問題文の場合、配偶者に係る加給年金額は加算されません。
加算の対象になるのは、老齢厚生年金の受給権者が「その権利を取得した当時」その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者です。
受給権を取得した後で、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合は、配偶者に係る加給年金額は加算されません。
②【R7年出題】
老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
加給年金額の対象になるのは、老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の配偶者及び子です。
受給権を取得した2年後に誕生した第2子については、加給年金額の加算の対象にはなりません。
③【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満だったとしても、退職改定で被保険者期間の月数が240以上になり、240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されます。
図でイメージしましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
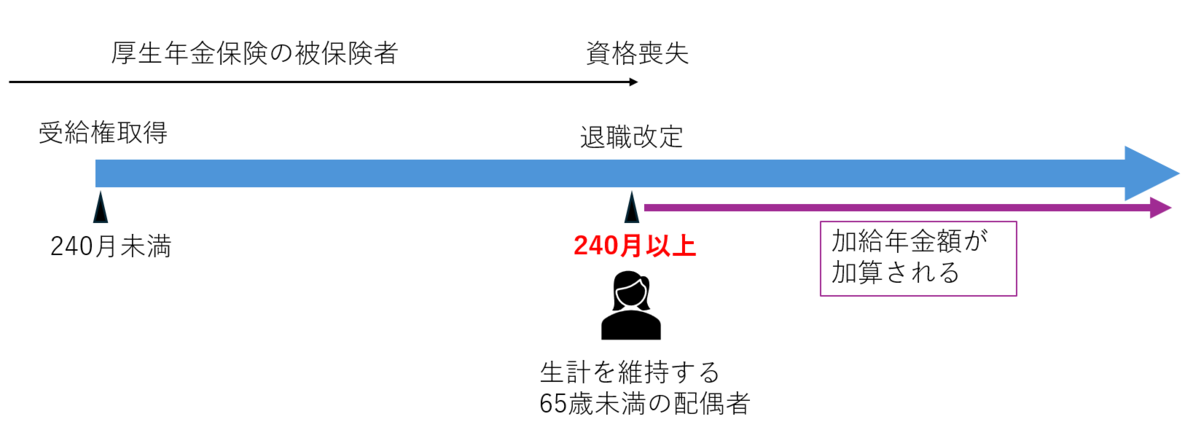
毎週日曜日はYouTube総集編です!
R8-028 9.21
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年9月第3週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年9月15日から20日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・被扶養者に該当する要件(健康保険法)
・不服申立て・審査請求と訴訟との関係(国民年金法)
・第30条の4の障害基礎年金の支給停止事由(国民年金法)
・保険料納付済期間に含む期間・含まない期間(国民年金法)
・中高齢寡婦加算について「死亡した夫の要件」(厚生年金保険法)
・厚生年金保険の被保険者資格の取得と喪失(厚生年金保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「資格の取得と喪失」
R8-027 9.20
厚生年金保険の被保険者資格の取得と喪失
厚生年金保険の被保険者資格の取得日と喪失日についてみていきます。
例えば、令和7年9月19日にA社(厚生年金保険の適用事業所)に入社し、同年11月25日に退職した場合、厚生年金保険の被保険者の資格は令和7年9月19日に取得、同年11月26日に喪失します。
では、条文を読んでみましょう。
法第13条 (資格取得の時期) ① 適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。 ② 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
法第14条 (資格喪失の時期) 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(喪失の事実があった日に更に資格を取得するに至ったとき、又は第5号(70歳に達したとき)に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき。 (2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。 (3) 任意適用事業所の脱退又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。 (4) 適用除外に該当するに至つたとき。 (5) 70歳に達したとき。 |
ポイント!
・資格取得は「当日」です。
・資格喪失は原則「翌日」です。
※同日得喪、70歳に達したときは「当日」です。
それでは問題を解いてみましょう
①【H19年出題】
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

【解答】
①【H19年出題】 〇
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日(当日)に、被保険者の資格を取得します。
②【R1年出題】
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の「翌日」ではなく「その日」に被保険者の資格を喪失します。
なお、70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日です。厚生年金保険の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失します。
③【H27年出題】
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。

【解答】
③【H27年出題】 ×
死亡したときは「その翌日」に、70歳に達したときは「その日」に被保険者資格を喪失します。
④【R5年出題】
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

【解答】
④【R5年出題】 ×
任意単独被保険者の資格喪失に際しては、事業主の同意は要りません。
★任意単独被保険者の取得と喪失を整理しましょう。
■資格取得について
・厚生労働大臣の認可があった日に取得
・事業主の同意が必要です。
(事業主が保険料を半額負担し、納付義務を負うため)
■資格喪失について
・厚生労働大臣の認可があった日の翌日に喪失
・事業主の同意は不要です。
(事業主の負担がなくなるため)
⑤【R7年出題】
適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
令和7年4月1日に甲を退職した場合、翌日の4月2日に資格を喪失するのが原則です。
ただし、同じ日に、別の適用事業所である丙に入社した場合は、甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、同じ日に丙での被保険者資格を取得します。
⑥【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
問題文のように、第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「中高齢寡婦加算」
R8-026 9.19
中高齢寡婦加算について「死亡した夫の要件」
要件を満たした夫が死亡した場合、妻の遺族厚生年金に40歳から65歳まで「中高齢寡婦加算」が加算されます。
今回は、「死亡した夫」の要件を見ていきます。
では、条文を読んでみましょう。
法第62条 ① 遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。 ② 中高齢寡婦加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。 |
★中高齢寡婦加算が加算される妻の条件を確認しましょう。
①子がいない場合
遺族厚生年金の権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの
②子がいる場合(遺族基礎年金を受けている場合)
40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子と生計を同じくしていたもの(遺族基礎年金を受けている)
→子が18歳の年度末等になり、遺族基礎年金が支給されなくなったときから65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されます。
★中高齢寡婦加算の額を確認しましょう
遺族基礎年金の額×4分の3(定額)
★では、死亡した夫の条件を確認しましょう
・遺族厚生年金は「短期要件」と「長期要件」があります。(法第58条第1項)
<短期要件>
① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
③ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
<長期要件>
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
★中高齢寡婦加算について死亡した夫の条件を確認しましょう
→ 「第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。」とされています。
→ 長期要件で支給される遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が240月以上あることが条件です。
では過去問をどうぞ!
【R7年出題】
障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。

【解答】
【R7年出題】 ×
遺族厚生年金が短期要件に該当していても、長期要件に該当していても、要件を満たした場合、中高齢寡婦加算が加算されます。
ただし、「長期要件」に該当する場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月以上あることが条件です。
問題文は、「障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫の死亡」により支給される遺族厚生年金ですので、「短期要件」です。そのため、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であっても、中高齢寡婦加算が行われます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「保険料納付済期間」
R8-025 9.18
保険料納付済期間に含む期間・含まない期間
国民年金法には、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」があります。
年金の受給資格の有無や、受給額の計算に影響します。
今回は、「保険料納付済期間」の定義をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第5条第1項 国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定(滞納処分)により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び第88条の2の規定(産前産後期間の保険料免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
<保険料納付済期間>
①第1号被保険者としての被保険者期間のうち
・納付された保険料に係るもの
・産前産後期間の保険料免除により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの
・滞納処分により徴収された保険料は保険料納付済期間に含む
・一部免除により納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものは除く
②第2号被保険者としての被保険者期間
③第3号被保険者としての被保険者期間
①+②+③の期間を保険料納付済期間といいます。
では、過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間も、「滞納処分により徴収」された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間」も、保険料納付済期間となります。
②【R3年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

【解答】
②【R3年出題】 〇
例えば半額免除の規定が適用され、免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく「保険料半額免除期間」です。
(法第5条第5項)
保険料半額免除期間
半額 納 付 |
半額 免 除 |
③【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】
③【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用されている者について、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。
(法第5条第6項)
保険料4分の1免除期間
4分の3 納 付
|
4分の1 免 除 |
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
④【H24年出題】 〇
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間ではなく「保険料納付済期間」となります。
法第94条第4項に規定されています。読んでみましょう。
| 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 |
⑤【R5年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、保険料納付済期間には算入されず、「合算対象期間」に算入されます。
(昭60法附則第8条第4項)
20歳 |
| 60歳 |
合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |
⑥【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
⑥【H24年出題】 ×
「障害基礎年金と遺族基礎年金」については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、「保険料納付済期間」となります。老齢基礎年金との違いに注意しましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第30条の4の障害基礎年金」
R8-024 9.17
第30条の4の障害基礎年金の支給停止事由
第30条の4の障害基礎年金は、20歳前傷病による障害基礎年金ともいわれます。
国民年金に加入する前(=国民年金保険料の負担をしていない)に初診日がある傷病が対象ですので、通常の障害基礎年金にはない支給停止事由が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項、第2項 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 (1) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 (2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 (3) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 (4) 日本国内に住所を有しないとき。 ② ①(1)に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が第36条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問を解きながら覚えるポイントをつかみましょう
①【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、支給が停止されます。
②【H25年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。
③【R7年出題】
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。

【解答】
③【R7年出題】 〇
■国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給が停止される事由
・恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
・少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
・日本国内に住所を有しないとき
なお、「受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき」も支給が停止されます。 次の問題で確認しましょう。
④【R7年出題】
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。

【解答】
④【R7年出題】 〇
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止されます。
なお、扶養親族等がいない場合は、
・前年の所得が472万1千円を超える場合 → 年金の全額が支給停止
・前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下の場合→ 2分の1が支給停止
となります。
⑤【R5年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1ではなく、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されます。
⑥【H27年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

【解答】
⑥【H27年出題】 ×
「受給権者の前年の所得」で判断されます。
扶養親族の所得は合算しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「不服申立て」
R8-023 9.16
国民年金法の不服申立て・審査請求と訴訟との関係
「不服申立て」について、問題を解きながらポイントをおさえましょう。
まず、「不服申立て」について条文を読んでみましょう。
第101条 ① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第14の4第1項又は第2項の規定による決定(国民年金原簿の訂正請求についての厚生労働大臣の訂正する旨又は訂正しない旨の決定)については、この限りでない。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 ⑤ ①の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。 ⑥ 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。 ⑦ 共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(審査請求と訴訟との関係) 第101条の2 前条①に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
過去問を解きながらポイントをおさえましょう
<社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる>
①【H30年出題】
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
「2か月以内」がポイントです。
<国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨の厚生労働大臣の決定>
②【H28年出題】
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
厚生労働大臣が行った国民年金原簿の訂正請求に係る訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定については、社会保険審査官に対する審査請求の対象になりません。
<審査請求と訴訟との関係>
③【H29年出題】
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審官の決定」を経た後でなければ、提起することができない、とされています。
④【R7年出題】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
①被保険者の資格に関する処分
②給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
③保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分
ポイント!
①又は②について
①又は②の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。となります。
③について
③の処分について
・社会保険審査官に審査請求をする
又は
・社会保険審査官に審査請求をせずに、処分の取消しの訴えを提起する
→ ③の処分については、「審査請求する」か「処分の取消しの訴えを提起する」を選択することが可能です。
⑤【R6年出題】
国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ提起することができない。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができない、となります。
<共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分>
⑥【R3年出題】
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)の定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることができない。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分については、社会保険審査官に対する審査請求の対象になりません。
共済組合等に係る共済各法の定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「被扶養者」
R8-022 9.15
被扶養者に該当する要件(健康保険法)
健康保険の被扶養者に該当する要件をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
法第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の三親等内の親族で(1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) (3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
■被扶養者となる条件
・日本国内に住所を有している
又は
・日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
★日本国内に住所を有していることが原則ですが、例外もあります。
例外をみていきましょう。
→ 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
★日本国内居住要件の例外として取り扱われる者を厚生労働省令で確認しましょう。
則第37条の2 法第3条第7項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 (1) 外国において留学をする学生 (2) 外国に赴任する被保険者に同行する者 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの (5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

【解答】
①【R2年出題 〇
外国に赴任する被保険者に同行する者は、国内居住要件の例外として、日本国内に生活の基礎があると認められる者として扱われます。
被扶養者の認定の際は、国内居住要件の例外に該当することを証する書類の添付が求められます。
問題文の場合は、「家族帯同ビザ」の確認で判断することが基本とされます。渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断するとされています。
(令5.6.19保保発0619第1号)
②【R7年出題】
健康保険法における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「後期高齢者医療の被保険者等である者」、「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、被扶養者になりません。
「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは、日本国籍を有さず、「特定活動(医療目的)「特定活動(長期観光)」で滞在する者です。
則第37条の3に規定されています。
① 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(医療目的)
② 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(長期観光)
問題文は、「長期観光」ですが、2年を超えない期間ではなく「1年を超えない期間」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です!
R8-021 9.14
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年9月第2週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年9月8日から13日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・平均賃金の計算(原則と最低保障額)(労働基準法)
・平均賃金を「算定すべき事由の発生した日」(労働基準法)
・ 二次健康診断等給付の基本10問(労災保険法)
・ 定年退職者等の受給期間延長(雇用保険法)
・ 労働保険料を計算してみましょう(徴収法)
・ 国民健康保険の保険給付「法定と任意」(社一・国保法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「国民健康保険法」
R8-020 9.13
国民健康保険の保険給付「法定」と「任意」
国民健康保険の保険給付には、「法定給付」と「任意給付」があります。
法定給付 | 絶対的必要給付 | 療養の給付など(必須) |
相対的必要給付 | 出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 ・国民健康保険上、「行うものとする」 ・ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 | |
任意給付 | 傷病手当金の支給その他の保険給付 ・行うことができる (給付を行うかどうか、給付内容は任意) | |
過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「移送費」は法定給付の絶対的必要給付ですので、支給は必須です。
「市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。」と規定されています。
(法第54条の4)
②【R7年出題】
国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、「移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する」となります。
③【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は必須ではなく、法定給付の相対的必要給付です。
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、「葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」となります。
(法第58条第1項)
④【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる

【解答】
④【H26年出題】 〇
傷病手当金は「任意給付」です。
傷病手当金の支給を「行うことができる」となります。
(法第58条第2項)
⑤【R1年出題】
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
出産育児一時金の支給、葬祭料の支給、葬祭の給付は、法定給付の相対的必要給付です。
(法第58条第1項)
⑥【R7年出題】
国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
→ 出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。
→ 傷病手当金の支給を行うことができる。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「概算保険料・確定保険料」
R8-019 9.12
労働保険料を計算してみましょう
概算保険料と確定保険料の額の計算してみましょう。
問題を解きながらポイントをつかみましょう。
では、さっそく過去問を解いてみましょう
【R7年出題】(労災)
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
・保険料の滞納はない。
・一般保険料以外の対象となる者はいない。
・社会保険適用事業所である。
・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円
A 令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。
B 令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。
C 当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。
D 当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
E 令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。

【解答】
<A> 〇
<B> 〇
<C> 〇
<D> ×
<E> 〇
<A>について
賃金は、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)」と定義されています。(法第2条第2項)
「使用従属関係が認められない」請負人に対して支払った報酬は、賃金総額に含みません。
<B>について
★令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料額の計算
ポイント!
・概算保険料は、「その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込み額」を使って計算するのが原則です。
ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」である場合は、「直前の保険年度の賃金総額」を使います。
・労災保険料は、全額事業主負担です。
では、計算してみましょう
・令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額
→5,000万円×1000分の3=150,000円
令和6年度の確定賃金総額を使って計算するのがポイントです。
(法第15条、則第24条)
<C>について
★概算保険料の納期限
ポイント!
事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、概算保険料申告書に添えて、
・その保険年度の6月1日から40日以内
・保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内
に納付しなければなりません。
・令和7年度の概算保険料の納付については、令和7年7月10日(その保険年度の6月1日から40日以内)までに納付しなければなりません。
<D>について
★延納の際の端数処理
ポイント!
概算保険料は延納(分割払い)ができます。
概算保険料の額を期の数で除して得た額に1円未満の端数があるときは、第1期分の概算保険料にまとめます。
・令和7年度の概算保険料を計算しましょう
→5,000万円×(1000分の3+1,000分の14.5)=875,000円
→875,000÷3=291,666.6…円(1円未満の端数がある)
第1期分 | 291,668円 |
第2期分 | 291,666円 |
第3期分 | 291,666円 |
・第2期分は291,667円ではなく、291,666円です。
<E>について
★事業主が負担する一般保険料の額
ポイント!
被保険者が負担するのは、雇用保険率のうち雇用保険二事業の保険率を減じた額の2分の1です。
・令和7年度の確定保険料を計算しましょう
→6,000万円×(1000分の3+1,000分の14.5)=1,050,000円となります。
・事業主と被保険者の負担について
労災保険率 | 雇用保険率 | ||
事業主負担 | 労働者負担 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
1,000分の3 | なし | 1,000分の9 (1,000分の5.5+1,000分の3.5) | 1,000分の5.5 |
・確定保険料のうち、被保険者が負担する一般保険料額は、6,000万円×1,000分の5.5=330,000円です。
事業主が負担する一般保険料額は、1,050,000円−330,000円=720,000円となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法「受給期間の延長」
R8-018 9.11
定年退職者等の受給期間の延長
定年等で退職した場合は、受給期間の延長が認められます。
例えば、4か月間、求職の申込みをしないことを希望した場合、原則の受給期間 (1年間)に求職の申込みをしないことを希望する期間(4か月間=猶予期間といいます)がプラスされ、受給期間は1年間+4か月となります。
なお、猶予期間は最大で1年間ですので、受給期間は最大2年間となります。
※所定給付日数が360日の就職困難者の場合は、原則の受給期間(1年+60日)が最大1年間延長されますので、受給期間の最大は2年と60日となります。
では、条文のポイントを確認しましょう。
■延長できる条件
・受給資格者であって、当該受給資格に係る離職が定年(60歳以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるもの
・離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合
・厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た
↓
・原則の受給期間(基準日の翌日から起算して1年(就職が困難なものは1年+60日)に求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間が受給期間となります。
(法第20条第2項)
では、過去問を解いてみましょう
★受給期間の延長が認められる理由
①【R7年出題】
60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。

【解答】
①【R7年出題】 〇
・受給期間の延長が認められる「定年退職者等」とは、次のいずれかの理由で離職した者です。
① 60歳以上の定年に達したこと
② 60歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
③ 船員が50歳以上の定年に達したこと
④ 船員が50歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
→ ②又は④について
・60歳(船員は50歳)以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合とは、定年制に準じる場合、すなわち、労働協約、就業規則等により、個人的な契約ではなく制度的に退職の期限(退職の期限については、不確定期限)も含まれる。)が定められている場合に限られます。
・また、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要であるので、例えば、定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、「再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、これに該当しない。」とされています。
(行政手引50281)
問題文の場合は、再雇用の期限(65歳)の到来前の、63歳の更新時に更新を希望せずに退職していますので、受給期間の延長は認められません。
②【R7年出題】
船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「船員が50歳以上の定年に達したこと」により離職した場合は、受給期間の延長が認められます。
(行政手引50281)
★受給期間の延長申請の手続
③【R7年出題】
定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。

【解答】
③【R7年出題】 ×
「1か月以内」ではなく、「2か月以内」にしなければなりません。
条文を読んでみましょう。
則第31条の3第1項、第2項 受給期間の延長の措置の申出は、受給期間延長等申請書に離職票(2枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。 ② 申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 |
④【R7年出題】
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
受給期間延長の申出は、本人が公共職業安定所に出頭した上で行うのが原則です。
ただし、疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために申請期限内に公共職業安定所に出頭することができない場合に限り、「その理由を記載した証明書を添付の上、代理人又は郵送等によって行うことができる」とされています。
(行政手引50283(3))
延長の申出を郵送により行うことは可能です。
★受給期間が延長される期間
⑤【R7年出題】
定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
・定年退職者等の受給期間の延長が認められた場合にも、法第20条第1項の受給期間の延長(疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合の延長)が認められます。
→ 定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病又は負傷等の理由により引き続き
30日以上職業に就くことができない日がある場合には「さらに受給期間の延長が認められる」とされています。
(行政手引50286(6))
⑥【R5年選択式】
60歳の定年に達した受給資格者であり、かつ、基準日において雇用保険法第22条第2項に規定する就職が困難なものに該当しない者が、定年に達したことを機に令和4年3月31日に離職し、同年5月30日に6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を管轄公共職業安定所長に申し出て受給期間の延長が認められた後、同年8月1日から同年10月31日まで疾病により引き続き職業に就くことができなかった場合、管轄公共職業安定所長にその旨を申し出ることにより受給期間の延長は令和5年< A >まで認められる。
<選択肢>
① 7月31日
② 9月30日
③ 10月31日
④ 12月31日

【解答】
<A> ③ 10月31日
(行政手引50286(6))
図で確認しましょう
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
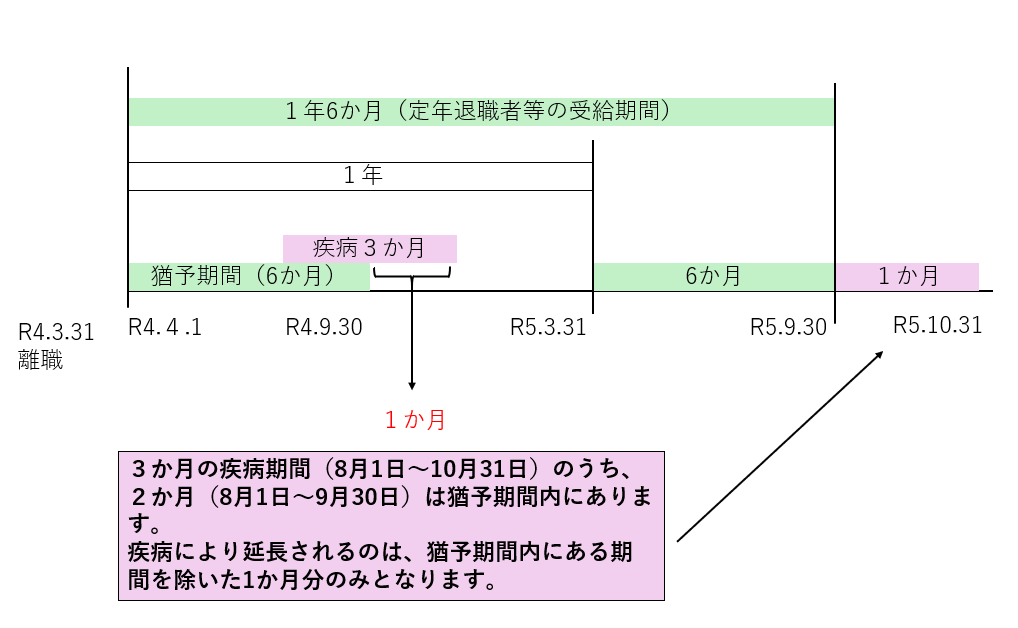
YouTubeはこちらからどうぞ!
労働者災害補償保険法「二次健康診断等給付」
R8-017 9.10
二次健康診断等給付の基本10問
・労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のものを「一次健康診断」といいます。
・一次健康診断で、脳血管疾患・心臓疾患の発生にかかわる一定の項目のいずれにも異常の所見が認められる労働者が対象です。
・二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があります。
・二次健康診断等給付は、労働者の請求に基づいて行われます。
では、条文を読んでみましょう。
法第26条 ① 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 ② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 (1) 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下「二次健康診断」という。) (2) 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。) ③ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。 |
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。

【解答】
①【R7年出題】 〇
二次健康診断等給付は、「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院)又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所」において行うとされています。
(則第11条の3、第18条の19)
②【R7年出題】
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
当該検査項目の「いずれかに」ではなく、「いずれの項目にも」異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われます。
③【H30年出題】
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
「既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する」と認められる場合は、二次健康診断等給付は行われません。
④【H30年出題】
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
④【H30年出題】 〇
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
健診給付病院等を「経由」することと、「所轄都道府県労働局長」に提出することがポイントです。所轄労働基準監督署長ではありませんので、注意しましょう。
(則第18条の19)
⑤【R7年出題】
二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
二次健康診断が受けられるのは、1年度内1回限りです。
⑥【R7年出題】
二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
特定保健指導は、医師又は保健師による面接によって行われます。内容は、「栄養指導、運動指導、生活指導」です。
⑦【H30年出題】
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

【解答】
⑦【H30年出題】 ×
特定保健指導は、「医師または歯科医師」ではなく、「医師又は保健師」による面接によって行われます。
⑧【H30年出題】
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。

【解答】
⑧【H30年出題】 〇
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われません。
⑨【H30年出題】
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。

【解答】
⑨【H30年出題】 〇
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、「医師の意見をきかなければならない。」とされています。
(法第27条、則第18条の17)
⑩【R7年出題】
特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。

【解答】
⑩【R7年出題】 〇
特別加入者は、労働安全衛生法の健康診断(一次健康診断)の対象にならないため、二次健康診断等給付の対象にもなりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「平均賃金」
R8-016 9.09
平均賃金を「算定すべき事由の発生した日」
平均賃金は、原則として、「算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」を、その期間の「総日数」で除して計算します。
今回は、「算定すべき事由の発生した日」を具体的にみていきます。
過去問をどうぞ!
★解雇予告手当について算定すべき事由の発生した日
①【H16年出題】
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

【解答】
①【H16年出題】 〇
解雇予告手当を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に「解雇の通告をした日」です。
(昭39.6.1236基収2316号)
②【R7年出題】
労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」です。その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、同様に、「当初の解雇を通告した日」とされています。
(昭39.6.1236基収2316号)
★減給制裁について算定すべき事由の発生した日
③【H25年出題】
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

【解答】
③【H25年出題】 ×
減給の制裁に関して平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」とされています。
(昭30.7.19基収5875号)
★災害補償について算定すべき事由の発生した日
④【H27年出題】
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

【解答】
④【H27年出題】 ×
「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」と規定されています。(則第48条)
★所定労働時間が二暦日にわたる場合
⑤【R7年出題】
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻に属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者について
→ 当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合は、当該勤務の始業時刻に属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされています。
(昭45.5.14基発374号)
★賃金締切日がある場合
⑥【H27年出題】
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
⑥【H27年出題】 〇
「平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。」とされています。(法第12条第2項)
ポイント!
平均賃金の条文では、「算定すべき事由の発生した日以前 3 か月間」が算定期間となっていますが、平均賃金の計算上、算定すべき事由の発生した日当日は、含めません。
そのため、7月31日に算定事由が発生したときは、前日から遡った3か月で計算します。また、賃金締切日があるため、「直前の賃金締切日」である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となります。
⑦【H27年出題】
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
⑦【H27年出題】 ×
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、平均賃金を計算する場合の「直前の賃金締切日」は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日となります。
問題文の場合、
・基本給 → 直前の賃金締切日は5月31日
・時間外手当 → 直前の賃金締切日は6月20日
となります。
(昭26.12.27基収5926号)
★雇入れ後3か月未満の場合
⑧【R7年出題】
雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。

【解答】
⑧【R7年出題】 ×
「雇入後3か月に満たない者については、平均賃金の算定期間は、雇入後の期間とする。」とされています。(法第12条第6項)
なお、雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合でも、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。
(昭23.4.22基収1065号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「平均賃金」
R8-015 9.08
平均賃金の計算(原則と最低保障額)
「平均賃金」とは、賃金の1日当たりの額のことです。
労働基準法の解雇予告手当や、休業手当などの額の計算に使われます。
今回は、平均賃金の原則の計算式と「最低保障額」をみていきましょう。
■計算式について条文を読んでみましょう。
労基法第12条第1項 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 <最低保障額> ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と(1)の金額の合算額 |
<原則の計算式>
算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額 |
その期間の総日数 |
<最低保障額>
算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額 | × | 60 |
その期間中に労働した日数 | 100 |
ポイント!
最低保障額は、「日給」「時給」「出来高払いその他の請負制」の場合に適用されます。
こちらも確認しましょう
★「その日数とその期間中の賃金」を平均賃金の計算から控除する期間
=分母からも分子からも除外する期間
・ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・ 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
・ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間
・ 試みの使用期間
★「賃金総額」に算入しない賃金
=分子からのみ除外する賃金
・ 臨時に支払われた賃金
・ 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
それでは、過去問を解いてみましょう
①【H19年出題】
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

【解答】
①【H19年出題】 〇
賃金が労働した時間によって算定される場合は、最低保障額が適用されます。
最低保障額は、「賃金の総額」÷その期間中の「労働した日数」×100分の60で計算します。
②【R7年出題】
令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払の条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。

【解答】
②【R7年出題】 〇
問題を解くポイント!
・「日給制」ですので、最低保障額が適用されます。
・ 平均賃金を算定する期間については、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。(法第12条第2項)
問題文の場合は、直前の賃金締切日(6月20日)から遡った3か月で計算します。
3月21日~4月20日、4月21日~5月20日、5月21日~6月20日までの期間で算定します。
・原則の計算式で計算すると
<原則の計算式>
(10万円+10万円+10万円)÷92日 ≒ 3260.86円
<最低保障額>
(10万円+10万円+10万円)÷30日×100分の60 = 6,000円
問題文の労働者に係る平均賃金の額は6,000円となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
日曜日はYouTube総集編です!
R8-014 9.07
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年9月第1週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年9月1日から6日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・ (R7年選択)統計からみた我が国の高齢者、パワハラ定義、最高裁判例(労働に関する一般常識)
・ (R7年選択)国年保険料納付状況・高齢者医療確保法・介護保険法・確定給付企業年金法・厚生労働白書(社会保険に関する一般常識)
・(R7年選択式) 出産育児一時金・任意適用事業所の適用取消(健康保険法)
・(R7年選択式)定時決定・再評価率の改定・3号分割・障害厚生年金(厚生年金保険法)
・ (R7年選択式)国民年金の保険料額・学生納付特例の所得要件(国民年金法)
・ (R7年選択式)判例からの出題(労働基準法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(労働基準法)から学ぶ
R8-013 9.06
R7年選択式は判例からの出題(労基法)
令和7年度の労働基準法の選択式は、
①付加金
②判例
からの出題でした。
今回は②判例の問題をみていきます。
まず過去問をどうぞ!
【H22年選択式】
賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 < A >として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 権利の濫用 ② 公序に反するもの ③ 信義に反するもの
④ 不法行為

【解答】
<A> ② 公序に反するもの
ポイント!
「従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく、従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には、それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては、「公序に反し無効である。」とされています。
(東朋学園事件 平成15.12.4最高裁判所第一小法廷)
では、令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が< C >場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。
<選択肢>
⑤ 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる
⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
⑪ 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる
⑳ 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる

【解答】
<C> ⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
裁判要旨を読んでみましょう。
| 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し、出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは、従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため、上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく、従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には、それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては、公序に反し無効である。 |
(東朋学園事件 平成15.12.4最高裁判所第一小法廷)
問題の考え方です
産前産後休業を取得すると、90%条項を満たせず、賞与を受けられなくなる可能性が高い → 「労働基準法の産前産後休業を取得する権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる」と考えましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(国民年金法)から学ぶ
R8-012 9.05
R7年選択式は国民年金の保険料額・学生納付特例の所得要件
令和7年の国民年金の選択式は、
①国民年金の保険料額
②学生納付特例の所得要件
からの出題でした。
どちらも数字の暗記が必要でした。
 国民年金の保険料額について
国民年金の保険料額について
過去問からどうぞ!
【R5年出題】
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

【解答】
【R5年出題】 ×
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)」ではなく、「17,000円」に保険料改定率を乗じて得た額となります。
なお、保険料改定率は、毎年度、名目賃金変動率に応じて改定されます。
(法第87条)
平成16年の改正で、国民年金の保険料は、毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度に引上げが完了しました。
産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことにより、令和元年度以降は、保険料額は100円引き上げられ17,000円となっています。
令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
国民年金の保険料は、< A >の年金制度改正により、< A >度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の< B >に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、< C >の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
<選択肢>
⑨ 13,300円 ⑩ 16,800円 ⑪ 16,900円 ⑫ 17,000円
⑬ 遺族基礎年金の父子家庭への支給
⑭ 産前産後期間の保険料免除制度
⑮ 年金額の特例水準の解消
⑯ 年金生活者支援給付金
⑰ 平成6年 ⑱ 平成12年 ⑲ 平成16年 ⑳ 平成24年

【解答】
<A> ⑲ 平成16年
<B> ⑪ 16,900円
<C> ⑭ 産前産後期間の保険料免除制度
 学生納付特例に係る所得要件
学生納付特例に係る所得要件
まず過去問をどうぞ!
【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
【H28年出題】 〇
学生納付特例については、「世帯主又は配偶者」の所得要件は問われないのがポイントです。
本人の所得のみで判断されます。
(法第90条の3)
令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは< D >万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき < E >万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
<選択肢>
① 32 ② 35 ③ 36 ④ 38
⑤ 103 ⑥ 106 ⑦ 128 ⑧ 168

【解答】
<D> ⑦ 128
<E> ④ 38
(令第6条の9)
・学生納付特例に係る所得要件は、扶養親族等がないときは128万円です。
・学生納付特例に係る所得要件の額と半額免除の所得要件の額は同じです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(厚生年金保険法)から学ぶ
R8-011 9.04
R7年選択式は定時決定・再評価率の改定・3号分割・障害厚生年金
令和7年の厚生年金保険の選択式は、
・定時決定
・再評価率の改定
・3号分割の対象にならない期間
・障害厚生年金のみの受給権が発生する場合
から出題されました。
 定時決定について
定時決定について
令和7年の問題をどうぞ!
①【R7年選択式】
厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が< A >(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、< B >。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
<選択肢>
① 11日 ② 12日 ③ 13日 ④ 14日 ⑤ 15日 ⑥ 16日
⑦ 17日 ⑧ 18日

【解答】
<A> ⑦ 17日
<B> ① 11日
 再評価率の改定について
再評価率の改定について
R7年の問題をどうぞ!
②【R7年選択式】
厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、< C >に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
<選択肢>
⑫ 実質賃金変動率 ⑬ 実質手取り賃金変動率 ⑮ 名目賃金変動率
⑯ 名目手取り賃金変動率

【解答】
<C> ⑯ 名目手取り賃金変動率
過去問も解いてみましょう
①【H18年選択式】※改正による修正あり
1 平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< A >(生年度別)を改定することによって毎年度自動的に行われる方式に改められた。
2 新規裁定者(< B >歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、 < C >を基準とした< A >を用い、既裁定者(< B >歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、前年の< D >(< D >が< C >を上回るときは、< C >)を基準とした< A >を用いる。
<選択肢>
① 60 ② 68 ③ 65 ④ 70
⑤ 基準年度再評価率 ⑥ 給付乗率 ⑦ 給付改定率 ⑧ 物価変動率
⑨ 名目賃金変動率 ⑩ 実質賃金変動率 ⑪ 物価上昇率
⑫ 名目手取り賃金変動率 ⑬ 消費者物価指数 ⑭ 再評価率

【解答】
<A> ⑭ 再評価率
<B> ② 68
<C> ⑫ 名目手取り賃金変動率
<D> ⑧ 物価変動率
ポイント!
新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者は「物価変動率」を基準に改定されます。
②【R5年選択式】
令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から< A >となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。
<選択肢>
① 0.1%の引下げ ② 0.2%の引下げ ③ 0.5%の引下げ ④ 据置き

【解答】
<A> ② 0.2%の引下げ
ポイント!
・既裁定者の再評価率の改定は、原則として「物価変動率」が基準となります。
ただし、「物価変動率」が「名目手取り賃金変動率」を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準とします。
問題文は、物価変動率(+0.2%)>名目手取り賃金変動率(-0.2%)ですので、「名目手取り賃金変動率」を基準に改定します。そのため、「0.2%の引き下げ」となります。
なお、基準になる名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
 3号分割標準報酬改定請求について
3号分割標準報酬改定請求について
最初に条文を読んでみましょう。
法第78条の14第1項 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していたものをいう。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。 ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 |
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

【解答】
【R1年出題】 〇
3号分割標準報酬改定請求をする場合の特定期間に係る被保険者期間については、特定被保険者の障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間は、改定又は決定の対象から除かれます。
では、令和7年の選択式をどうぞ!
③【R7年選択式】
平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から< D >までである。
<選択肢>
⑰ 令和2年8月 ⑱ 令和4年1月 ⑲ 令和4年2月 ⑳ 令和6年12月

【解答】
<D> ⑲ 令和4年2月
・特定期間について
特定期間は、特定被保険者(甲)が被保険者であった期間で、かつ、その被扶養配偶者(乙)が国民年金の第3号被保険者であった期間です。
・特定期間の一部が、甲の障害厚生年金の計算の基礎となっています。
・甲の障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間は、改定又は決定の対象から除かれます。
・障害厚生年金は、「障害認定日の属する月」までが計算の基礎となります。(法第51条)甲の障害厚生年金は、障害認定日の属する月である「令和4年2月」までが計算の基礎になっています。
・3号分割標準報酬改定請求の対象にならない期間は、障害厚生年金の計算の基礎になっている「平成23年1月から令和4年2月」までとなります。
 障害厚生年金の受給権のみ発生する場合
障害厚生年金の受給権のみ発生する場合
最初にポイントを確認しましょう!
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者です。
ただし、厚生年金保険の被保険者でも、「65歳以上で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有するもの」は第2号被保険者となりません。
(国民年金法附則第3条)
では、令和7年の問題をどうぞ!
④【R7年選択式】
厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、< E >。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
<選択肢>
⑨ 障害基礎年金と障害厚生年金である
⑩ 障害基礎年金のみである
⑪ 障害厚生年金のみである
⑭ 存在しない

【解答】
<E> ⑪ 障害厚生年金のみである
ポイント!
丙は、厚生年金保険の被保険者ですが、67歳で、かつ老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有しているため、国民年金の第2号被保険者ではありません。
・障害厚生年金について
→「初診日」に、厚生年金保険の被保険者ですので、初診日要件を満たします。
・障害基礎年金について
→「初診日」に国民年金の被保険者ではありませんので、初診日要件を満たしません。
・丙には、「障害厚生年金の受給権のみ」発生します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(健康保険法)から学ぶ
R8-010 9.03
R7年選択式は出産育児一時金・任意適用事業所の適用取消
健康保険法の令和7年選択式は、「出産育児一時金の支給要件と額」、「任意適用事業所を適用事業所でなくするときの手続き」からの出題でした。
 出産育児一時金の支給要件と額について
出産育児一時金の支給要件と額について
まず過去問からどうぞ!
①【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】
①【R5年出題】 〇
・ 出産育児一時金の額は、488,000円です。(令第36条)
・ なお、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下で、在胎週数22週に達した日以後の出産がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等の額は12,000円を加算して50万円が支給されます。
・ 胎児数に応じて支給されますので、双児の場合は50万円×2=100万円が支給されます。
(令和5.3.30保保発0330第8号)
②【H21年出題】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。

【解答】
②【H21年出題】 〇
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、「妊娠4か月以上(85日以後)」の出産が対象です。
1か月を28日で計算しますので、4か月目に入った日は、28日×3+1日=85日目となります。
(昭3.3.16保発第11号、昭27.6.16保文発2427号)
では、令和7年の選択式をどうぞ!
【R7年選択式】
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、 < A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
<選択肢>
① 1 ② 2 ④ 3 ⑧ 5
⑨ 84 ⑩ 85 ⑪ 86 ⑫ 87
⑬ 46万8,000 ⑭ 47万8,000 ⑮ 48万8,000 ⑯ 49万8,000

【解答】
<A> ⑮ 48万8,000
<B> ④ 3
<C> ⑩ 85
 任意適用事業所の脱退について
任意適用事業所の脱退について
「任意適用事業所」は、脱退することができます。
まず、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可の申請を行うときは、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意が必要です。
健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければなりません。
(則第22条第2項)
②【H28年出題】
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 ×
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めたとしても、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行う義務はありません。
令和7年の選択式をどうぞ!
【R7年選択式】
健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の< D >以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を< E >等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
<選択肢>
② 2分の1 ⑤ 3分の1 ⑥ 3分の2 ⑦ 4分の3
⑰ 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
⑱ 社会保険診療報酬支払基金又は地方校正局長
⑲ 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長

【解答】
<D> ⑦ 4分の3
<E> ⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長
(則第22条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(社会保険に関する一般常識)から学ぶ
R8-009 9.02
国年保険料納付状況・高齢者医療確保法・介護保険法・確定給付企業年金法・白書
社会保険に関する一般常識の選択式については、令和7年は、5つのテーマから出題されています。
順番にみていきましょう
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、< A >%となっている。
<選択肢>
① 53.1 ② 68.1 ③ 83.1 ④ 98.1

【解答】
<A> ③ 83.1
今回の問題は、「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」ですが、令和7年6月に「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」が公表されていますので、最新のデータを読んでみます。
「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」のポイント!
・第1号被保険者の令和6年度の最終納付率(令和4年度分保険料)は、84.5%となっています。前年度から1.5ポイント増加し、平成24年度の最終納付率(平成22年度分保険料)64.5%から20.0 ポイント増加し、12年連続で上昇しています。
・平成22年1月に発足した日本年金機構では、発足当初60%台であった最終納付率について、80%台の安定的確保とその持続的向上を目指して取組を実施した結果、最高値を更新しています。(3年連続で80%台)
解き方のヒントについて
国民年金の保険料を納付しやすい取り組みが様々行われていること(口座振替やコンビニ納付など)で、納付率を考えてみるとよいと思います。
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
高齢者医療確保法第4条第1項では、「< B >は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
<選択肢>
⑥ 国 ⑦ 後期高齢者医療広域連合 ⑮ 地方公共団体 ⑳ 保険者

【解答】
<B> ⑮ 地方公共団体
高齢者医療確保法では、「国の責務」、「地方公共団体の責務」、「保険者の責務」、「医療の担い手等の責務」が定められています。
「国」の責務のキーワードは、「国民の高齢期における医療」、「関連施策を積極的に推進しなければならない。」です。(第3条)
「地方公共団体の責務」のキーワードは、「住民の高齢期における医療」、「所要の施策を実施しなければならない。」です。(第4条)
「保険者」の責務のキーワードは、「加入者の高齢期における健康の保持」、「高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。」です。(法第5条)
なお、「後期高齢者医療広域連合」は、後期高齢者医療の事務を処理するために、設けられたものです。
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、< C >に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
<選択肢>
⑤ 医療との連携 ⑫ 事業者又は施設との連携 ⑱ 被保険者の心身の状況
⑲ 被保険者の自立した日常生活

【解答】
<C> ⑤ 医療との連携
★介護保険法第2条第2項は、平成20年に択一式でも出題されています。
介護保険法の総則の部分は毎年のように出題されていますので、択一式でも選択式でも対応できるようにしましょう。
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
確定給付企業年金法第60条第2項では、「< D >は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
<選択肢>
⑧ 最低積立基準額 ⑭ 責任準備金の額 ⑯ 積立金の額 ⑰ 積立上限額

【解答】
<D> ⑭ 責任準備金の額
用語の定義を確認しましょう。
法第59条 (積立金の積立て) 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。 法第60条 (積立金の額) ① 積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。 ② 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ③ 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 |
■責任準備金は、「今後とも年金制度を継続するとした場合に現在保有しておくべき積立金」です。(継続基準といいます)
■最低積立基準額は、「現時点で年金制度を終了させるとした場合に加入者等の給付を賄うことのできる積立金」です。(非継続基準といいます)
(参考 厚生労働省「確定給付企業年金の積立基準について」)
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「< E >」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
<選択肢>
⑨ 資産所得倍増プラン ⑩ 生涯現役計画 ⑪ 所得倍増プラン
⑬ 人生100年計画

【解答】
<E> ⑨ 資産所得倍増プラン
(令和6年厚生労働白書)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(労働に関する一般常識)から学ぶ
R8-008 9.01
統計からみた我が国の高齢者、パワハラ定義、最高裁判例
令和7年の労働に関する一般常識の選択式から学ぶことは、「問題文の中からヒントを探し出す」ことです。
 統計からみた我が国の高齢者
統計からみた我が国の高齢者
①【R7年選択式】
総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックス№142)(令和6年9月15日)」によれば、65歳以上の就業者を主な産業別にみると、「卸売業,小売業」が132万人と最も多く、次いで「< A >」が107万人で続いている。
産業別に65歳以上の就業者を10年前と比較すると、「< A >」が63万人増加し、10年前の約2.4倍となった。ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「< B >」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少している。なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、 「< B >」が52.9%と最も高くなっている。
<選択肢>
② 医療、福祉 ③ 運輸業、郵便業 ⑩ 建設業 ⑬ 宿泊業、飲食サービス業 ⑭ 生活関連サービス業、娯楽業 ⑮ 製造業 ⑰ 農業、林業
⑱ 不動産業、物品賃貸業

【解答】
<A> ② 医療、福祉
<B> ⑰ 農業、林業
(総務省「統計からみた我が国の高齢者(統計トピックス№142)(令和6年9月15日)」)
★こんなふうに考えてみるのはどうでしょう
<A>について
ヒントは「10年前の約2.4倍となった」の部分です。
高齢化が進む中で就業者が増えるといえば、「医療、福祉」でしょうか。。。
<B>について
「統計からみた我が国の高齢者」を読みますと、「ほとんどの主な産業で65歳以上の就業者が増加している一方で、「農業,林業」の65歳以上の就業者は10年前と比較して3万人減少しています。
なお、各産業の就業者に占める65歳以上の就業者の割合をみると、「農業,林業」が52.9%と最も高く、次いで「不動産業,物品賃貸業」が26.6%、「サービス業(他に分類されないもの)」が22.7%、「生活関連サービス業,娯楽業」が19.6%などとなっています。」となっています。
ヒントも見つけにくく、ちょっと難しいですね。。。
 パワハラの定義について
パワハラの定義について
②【R7年選択式】
労働施策総合推進法第30条の2第1項は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、< C >によりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めている。
<選択肢>
⑤ 客観的に合理的な理由を欠いたもの
⑥ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
⑯ 通常甘受すべき程度を著しく超えるもの
⑳ 労働関係の当事者としての権利を濫用するもの

【解答】
<C> ⑥ 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
★職場におけるパワハラは次の3つの要素をすべて満たしたものです。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③ 労働者の就業環境が害される
★客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラに該当しません。
過去問も解いてみましょう
【R3年出題】
労働施策総合推進法第30条の2第1項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。

【解答】
【R3年出題】 〇
「職場におけるパワーハラスメント対策」が大企業に対して義務化されたのは、令和2年6月1日からです。また、中小企業に対しては、令和4年4月1日から義務化されています。
 最高裁判例について
最高裁判例について
③【R7年選択式】
最高裁判所は、使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「組合結成通知を受けてからX守衛事件まで約9か月にわたり、上告人〔会社〕は、許可願の提出があれば業務に支障のない限り食堂の使用を許可していたというのであるが、そのことから直ちに上告人が組合に対し食堂の使用につき包括的に許諾をしていたものということはできず、その取扱いを変更することが許されなくなるものではない。一方、X守衛事件が起きた直後に上告人から会場使用許可願を却下されて以来、組合は、上告人所定の会場使用許可願用紙を勝手に書き変えた使用届を提出するだけで、上告人の許可なく食堂を使用するようになり、こうした無許可使用を上告人が食堂に施錠するようになるまで5か月近く続けていたのであって、これが上告人の< D >権を無視するものであり、正当な組合活動に当たらないことはいうまでもない。上告人は、組合に対し、所定の会場使用許可願を提出すること、上部団体の役員以外の外部者の入場は総務部長の許可を得ること、排他的使用をしないことを条件に、支障のない限り、組合大会開催のため食堂の使用を許可することを提案しているのであって、このような提案は、< D >者の立場からは合理的理由のあるものであり、許可する集会の範囲が限定的であるとしても、組合の拒否を見越して形式的な提案をしたにすぎないということはできない。また、上告人は組合に対し使用を拒む正当な理由がない限り食堂を使用させることとし、外部者の入場は制限すべきではないなどとする組合からの提案も、上告人の< D >権を過少に評価し、あたかも組合に食堂の利用権限があることを前提とするかのような提案であって、組合による無許可使用の繰り返しの事実を併せ考えるならば、上告人の< D >権を無視した要求であると上告人が受け止めたことは無理からぬところである。そうすると、上告人が、X守衛事件を契機として、従前の取扱いを変更し、その後、食堂使用について< D >権を前提とした合理的な準則を定立しようとして、上告人の< D >権を無視する組合に対し使用を拒否し、使用条件について合意が成立しない結果、自己の見解を維持する組合に対し食堂を使用させない状態が続いたことも、やむを得ないものというべきである。
以上によれば、本件で問題となっている施設が食堂であって、組合がそれを使用することによる上告人の業務上の支障が一般的に大きいとはいえないこと、組合事務所の貸与を受けていないことから食堂の使用を認められないと企業内での組合活動が困難となること、上告人が労働委員会の勧告を拒否したことなどの事情を考慮してもなお、条件が折り合わないまま、上告人が組合又はその組合員に対し食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって、上告人の権利の濫用であると認めるべき特段の事情があるとはいえず、< E >であるとも断じ得ないから、上告人の食堂使用の拒否が不当労働行為に当たるということはできない。」
<選択肢>
④ 管理監督 ⑪ 指揮命令 ⑫ 施設管理 ⑲ 利用許諾
① いたずらに組合秩序を混乱させようとしたもの
⑦ 組合に対する報復行為を行ったもの
⑧ 組合の施設利用権限を不利益に変更したもの
⑨ 組合の弱体化を図ろうとしたもの

【解答】
③【R7年選択式】
<D> ⑫ 施設管理
<E> ⑨ 組合の弱体化を図ろうとしたもの
(オリエンタルモーター事件・平成7.9.8最高裁判所第二小法廷)
★「使用者が労働組合に対し組合集会等のための従業員食堂の使用を許諾しない状態が続いていることをもって不当労働行為に当たるということはできない」とされた事例です。
<D>について
「食堂の使用を許諾しない」をヒントにすると、食堂=施設ですので、「施設管理」がピッタリ当てはまります。業務命令の話ではないので、「管理監督」、「指揮命令」は候補から外すことができると思います。
<E>について
「報復行為」ではありませんし、「不利益に変更」でもありませんし、「秩序を混乱させよう」でもありません。「弱体化を図ろうとした」が当てはまります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎週日曜日はYouTube総集編です!
R8-007 8.31
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年8月第4週)
毎週日曜日は総集編をお届けします。
今回は、令和7年8月27日から30日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
・ (R7年選択)労基法第114条付加金の支払(労働基準法)
・ (R7年選択)「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」と「機械等に関する規制」(労働安全衛生法)
・(R7年選択式) 遺族補償年金の遺族の障害要件と社会復帰促進等事業(労災保険法)」
・(R7年選択式)目的、高年齢求職者給付金、日雇労働求職者給付金(雇用保険法)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(雇用保険法)から学ぶ
R8-006 8.30
目的、高年齢求職者給付金、日雇労働求職者給付金
令和7年の雇用保険法の選択式は、「目的」、「高年齢求職者給付金」、「日雇労働求職者給付金」から出題されています。
令和7年の雇用保険法の選択式から学ぶことは?
・目的条文は必須です!
・同じ論点が繰り返し出題されます!
 目的条文について
目的条文について
①【R7年選択式】
雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、< B >、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
<選択肢>
① 及び労働者が子を養育するための休業
② 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
③ 並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
④ 並びに労働者が子を養育する若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
⑤ 経済的社会的地位の向上 ⑥ 産業に必要な労働力の充足
⑦ 失業の予防 ⑧ 転職の支援

【解答】
<A> ② 並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
<B> ⑦ 失業の予防
<A>について
★令和7年4月の改正箇所からの出題です。
雇用保険には、「失業等給付」と「育児休業等給付」があります。
<A>は「育児休業等給付」をあらわす用語が入ります。
「育児休業等給付」の内容を下の図で確認しましょう
改正で追加された部分からの出題でした。
 高年齢求職者給付金について
高年齢求職者給付金について
令和7年の選択式をどうぞ!
②【R7年選択式】
雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して< C >を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、< D >、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
<選択肢>
① 1か月 ② 4か月 ③ 6か月 ④ 1年
⑤ 求職の申込みをした上
⑥ 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上
⑦ 雇用保険被保険者証を提出した上
⑧ 退職証明書を提出した上

【解答】
<C> ④ 1年
<D> ⑤ 求職の申込みをした上
★ちなみに
<C>について
「1年」は平成21年の選択式でも出題されています。特例一時金の「6か月」とひっかけて出題される個所です。
<D>について
「被保険者証を提出する場面ではない」、「失業認定申告書は失業の認定日に提出するもの」というように、消去法で考えればOKです。
 日雇労働求職者給付金について
日雇労働求職者給付金について
日雇労働求職者給付金には、「普通給付」と「特例給付」があり、今回は「特例給付」の受給要件からの出題です。
まず過去問からどうぞ!
【H23年選択式】
日雇労働被保険者が失業した場合に支給される日雇労働求職者給付金には、いわゆる普通給付と特例給付の2つがあり、特例給付を受給するためには、当該日雇労働被保険者について、継続する< A >月間に、印紙保険料が各月11日分以上納付され、かつ、通算でも一定の日数分以上納付されていることが必要である。

【解答】
【H23年選択式】
<A> 6
では、令和7年の選択式をどうぞ!
③【R7年選択式】
雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して< E >分以上納付されていることを定めている。
<選択肢>
① 72日 ② 78日 ③ 84日 ④ 90日

【解答】
<E> ② 78日
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
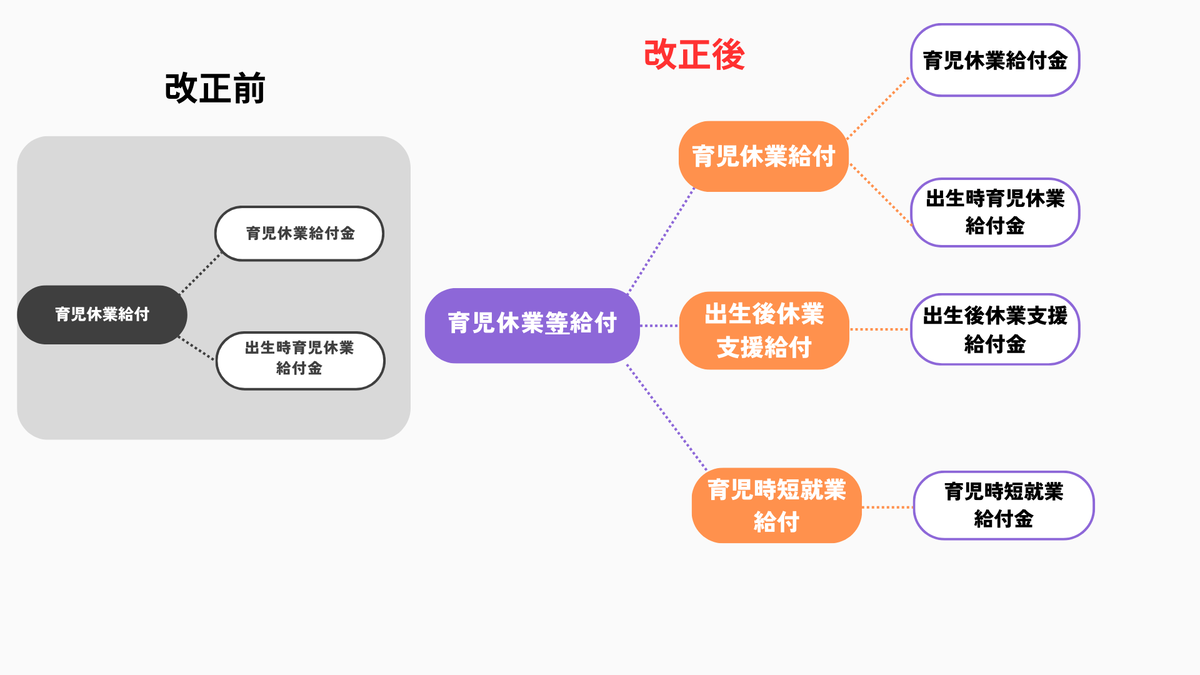
令和7年選択式(労災保険法)から学ぶ
R8-005 8.29
遺族補償年金の遺族の障害要件と社会復帰促進等事業
令和7年の選択式で出題された 「遺族補償年金の遺族の障害要件」と
「遺族補償年金の遺族の障害要件」と 「社会復帰促進等事業」をみていきましょう。
「社会復帰促進等事業」をみていきましょう。
 遺族補償年金の遺族の障害要件について
遺族補償年金の遺族の障害要件について
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」で、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。
ただし、「妻」以外は、労働者の死亡の当時、「年齢要件」か「障害要件」を満たしていることが必要です。
「障害要件」は、過去に出題されています。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】
【H19年出題】 〇
遺族の要件の一つである「厚生労働省令で定める障害の状態」のポイントは、「第5級以上」、「労働が高度の制限を受ける」の部分です。
なお、この規定は、複数事業労働者遺族年金にも準用されます。
(則第15条)
では、令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の < A >に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、< B >が高度の制限を受けるか、若しくは< B >に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
<選択肢>
① 第1級 ② 第5級以上 ③ 第8級以上 ④ 第12級以上
⑤ 日常生活 ⑥ 日常生活又は社会生活 ⑦ 労働 ⑧ 労働又は社会生活

【解答】
【R7年選択式】
<A> ② 第5級以上
<B> ⑦ 労働
 「社会復帰促進等事業」について
「社会復帰促進等事業」について
「長期家族介護者援護金」と「判例」からの出題です。
ヒントになる過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。

【解答】
①【H22年出題】 〇
特別支給金の支給の事務は所轄労働基準監督署長が行います。
条文を読んでみましょう。
則第1条第3項 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。 (1) 事業場が2以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 (2) 当該労働者災害補償保険等関係事務が複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 |
②【H29年出題】
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

【解答】
②【H29年出題】 ×
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨です。
(平15.9.4最高裁判所第一小法廷 中央労基署長(労災就学援護費)事件)
では、令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が< A >以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
<選択肢>
① 3年 ② 5年 ③ 7年 ④ 10年

【解答】
<A> ④ 10年
★「長期家族介護者援護金」の内容まで暗記するのは大変です。
過去問でもカバーできません。
「長期」をヒントに考えると、「10年かな?」と考えられると思いますが、難しいです。
【R7年選択式】
最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は,労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を< A >するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが,具体的に支給を受けるためには,< B >に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、< B >の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、< B >の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
<選択肢>
① 確保 ② 代替 ③ 補完 ④ 付加
⑤ 厚生労働大臣 ⑥ 都道府県労働局長 ⑦ 労働基準監督署長
⑧ 労働者災害補償保険審査官

【解答】
<A> ③ 補完
<B> ⑦ 労働基準監督署長
(平15.9.4最高裁判所第一小法廷 中央労基署長(労災就学援護費)事件)
判例を一字一句覚える必要はありませんが、文脈でヒントを探してみましょう
<A>について
法第2条の2で、「労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。」と定められています。
主たる事業は「保険給付」で、「社会復帰促進等事業」は附帯する事業として行うことができるという位置づけです。
試しに、選択肢を入れてみると、「保険給付を確保するため」、「保険給付を代替するため」、「保険給付を付加するため」、どれも社会復帰促進等事業の説明としてはしっくりきません。「補完」を入れると、「保険給付を補完するため」となり、ぴったりします。
<B>について
先ほどの条文で読みましたように、所轄労働基準監督署長は、「保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務」を行います。
その条文から、「労働基準監督署長」を選ぶことができますが、問題文の中に「保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定している」もヒントになります。「保険給付と同様の手続」という部分で、「労働基準監督署長」を選ぶことができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(労働安全衛生法)から学ぶ
R8-004 8.28
「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」と「機械等に関する規制」(労働安全衛生法)
令和7年の労働安全衛生法の選択式は、 「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」、
「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」、 「機械等に関する規制」から出題されました。
「機械等に関する規制」から出題されました。
 について
について
「今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について」の「基本的な考え方」からの出題でした。
平成29年の選択式が参考になります。
問題を見てみましょう。
【H29年選択式】
労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者の< A >に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。

【解答】
①【H29年選択式】
<A> 健康
労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。
★ちなみに、労働衛生の3管理とは、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和7年の問題については、問題文の中の、「労働衛生管理活動」、「作業環境管理」、「健康管理」がヒントになります。
では、令和7年の選択式をみてみましょう。
【R7年選択式】
事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、< A >及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施の徹底を図っていく必要がある。
<選択肢>
① 作業管理 ② 生産管理 ③ 有害物管理 ④ 労働時間管理

【解答】
<A> ① 作業管理
問題文のポイントは赤の部分です。
↓
事業者は、労働安全衛生法第22条に基づき、健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないが、事業場における自主的な労働衛生管理活動の促進を図るためには、総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等の選任及び職務の励行、衛生委員会の設置及び運営等の労働衛生管理体制の確立を基本とした上で、作業環境管理、< A >及び健康管理並びに労働衛生教育の総合的な実施の徹底を図っていく必要がある。
↓
★労働衛生の3管理のうち、「作業環境管理」と「健康管理」が出ていますので、残りの一つの「作業管理」が入ります。
今後における労働衛生対策の推進に関する基本方針について(平26.2.17基発0217第7号)
 について
について
「譲渡等の制限等」からの出題です。
今回は、第42条からの出題でしたが、平成22年には、第43条から選択問題が出題されています。
H22年選択式をどうぞ!
【H22年選択式】
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の < A >又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で < B >してはならない。

【解答】
【H22年選択式】
<A> 突起物
<B> 展示
では、令和7年の選択式をどうぞ!
【R7年選択式】
労働安全衛生法第42条は、「特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、< A >、又は設置してはならない。」と定めている。
<選択肢>
① 譲渡し、貸与し ② 譲渡し、展示し ③ 販売し、賃貸し
④ 販売し、販売のために展示し

【解答】
【R7年選択式】
<A> ① 譲渡し、貸与し
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(労働基準法)から学ぶ
R8-003 8.27
労基法第114条付加金の支払
令和7年度の労働基準法の選択式は、3つの穴埋めのうち、2つは第114条(付加金の支払)から、1つは判例から出題されました。
「付加金の支払」について、令和7年の選択式のポイントは
・付加金の支払を命ずるのは誰?
・「付加金」の名称そのもの
でした。
ちなみに、過去には、「付加金」を請求できる4つの場合が出題されています。
条文を読んでみましょう。
第114条 (付加金の支払) 裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項(年次有給休暇の期間又は時間)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間3年)以内にしなければならない。 |
・付加金の対象になるのは
①解雇予告手当を支払わない
②休業手当を支払わない
③割増賃金を支払わない
④年次有給休暇の期間又は時間の賃金を支払わない
の4つの場合です。
・付加金の額は、
使用者が支払わなければならない未払金の額と「同一額」です。
過去問をどうぞ!
【H24年出題】※改正による修正あり
裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇の期間又は時間の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。

【解答】
【H24年出題】 〇
付加金の支払は、「解雇予告手当」、「休業手当」、「割増賃金」、「年次有給休暇の期間又は時間の賃金」の4つを支払わない場合に適用されます。
「賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった」場合は、適用されません。
令和7年の選択式をどうぞ!
労働基準法第114条は、< A >は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の< B >の支払を命ずることができる旨規定している。
【選択肢】
① 厚生労働大臣 ② 裁判所 ③ 都道府県労働局長
④ 労働基準監督署長
⑤ 慰謝料 ⑥ 遅延損害金 ⑦ 賠償金 ⑧ 付加金

【解答】
<A> ② 裁判所
<B> ⑧ 付加金
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
YouTube総集編です
R8-002 8.26
【毎日コツコツ社労士受験】総集編(令和7年8月第3週)
毎週日曜日(今回は例外で火曜日です)は総集編をお届けします。
今回は、令和7年8月18日から24日までの動画の総集編です。
まとめて見ることができますので、ご活用ください。
☟
・<横断編>賃金の定義を確認しましょう(労基・雇用・徴収)
・短時間労働者が被保険者になる条件のポイント!<健保・厚年>
・<横断編>書類の保存期間を確認しましょう 「安衛・労災・雇用・徴収・健保・厚年」
・意外と問われる社会保険労務士法の数字(社会保険労務士法)
・覚えたことは忘れない!「元方事業者」(労働安全衛生法)
・本試験前に第1条を総ざらいしましょう!(穴埋め問題もあります)
・いよいよ当日です!社一の第1条をチェックします
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年の本試験終わりました
R8-001 8.25
昨日はお疲れさまでした
昨日はお疲れさまでした。
試験が終わって、お一人お一人、色々な思いがあると思います。
毎日、本当に忙しいですよね。
仕事もあるし、家のこともあるし、他にも気になることがたくさん。。。「時間が足りない」と思うことが多いと思います。
そんな中で、時間を作って社労士の勉強を続けて、本試験を受けた皆様、すごいです!
まずは、少し休憩して、勉強中に我慢してきたことを楽しんでくださいね。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします