合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
厚生年金保険法「脱退一時金」
R8-121 12.23
厚生年金保険の脱退一時金の支給要件
国民年金法・厚生年金保険法には「脱退一時金」の制度があります。
「日本国籍を有しない者」が対象です。
国民年金・厚生年金保険の被保険者の資格を喪失し日本を出国した場合、要件を満たせば、脱退一時金の請求をすることができます。
今回は、「厚生年金保険」の脱退一時金の支給要件をみていきます。
条文を読んでみましょう
法附則第29条第1項、第2項(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) ① 当分の間、(厚生年金保険の)被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢年金の受給資格期間 (10年間)を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有するとき。 (2) 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。 (3) 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 ② 請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R3年出題】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【解答】
①【R3年出題】 〇
脱退一時金の請求ができる要件として
・最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日から2年を経過していないこと
※国民年金の被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年を経過していないこと
があります。
問題文は、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した時点ですので、脱退一時金の請求は可能です。
②【H30年出題】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求できません。
➂【R7年出題】
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たさない等の支給要件を満たした者は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が日本の永住資格を有するときは、この限りでない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
日本の永住資格を有していても、脱退一時金を請求することは可能です。
<注意点>
※永住許可を受けた者については、当該者が20歳以上60歳未満の期間に限り、昭和36年4月1日から永住許可を受けるまでの海外在住期間も受給資格期間に含めて判断される(合算対象期間)とされています。合算対象期間を入れて受給資格期間が10年以上になる場合は、脱退一時金の支給要件を満たしません。
(参照:厚生労働省「脱退一時金等について」)
④【R2年出題】
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがある」ときは脱退一時金を受けることはできません。
「障害厚生年金の支給を受けたことがある」場合は、脱退一時金の支給は受けられません。
⑤【H26年出題】
日本国籍を有しない者について、障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがある」ときは脱退一時金を受けることはできません。
「障害手当金」は、政令で定める給付の中に含まれます。
そのため、障害手当金の受給権を有したことがある場合は、脱退一時金を請求することはできません。
(令第12条)
⑥【R1年出題】
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑥【R1年出題】 ×
かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、再度、所定の要件を満たした場合は、再度、脱退一時金の支給の請求をすることができます。
⑦【R7年出題】
脱退一時金の支給を受けた者は、その後、再び脱退一時金の支給要件を満たすことがあったとしても、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
⑥の問題と同じです。
かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、再度、所定の要件を満たした場合は、再度、脱退一時金の支給の請求をすることができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「高齢任意加入被保険者」
R8-120 12.22
高齢任意加入被保険者|適用事業所と適用事業所以外を比較
事業所に使用される「70歳以上」で、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権がない者は、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険に任意で加入することができます。
高齢任意加入被保険者は次の2種類に分かれます。
①適用事業所に使用される70歳以上の者
②適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者
①と②で、加入手続き等が異なりますが、今回は「保険料」の違いをみていきます。
適用事業所 | 適用事業所以外 |
□保険料は全額を被保険者が負担 □被保険者が保険料を納付する義務を負う ※事業主が同意した場合 ・事業主が半額負担し、納付する義務を負う | □事業主が半額負担し、納付する義務を負う |
□保険料を滞納した場合 ・初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす。 ・保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。 ※保険料について事業主の同意があるときは滞納による喪失はありません。 | □保険料を滞納した場合 事業主が納付義務を負っているため、滞納による喪失はありません。 |
(法附則第4条の3、第4条の5)
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

【解答】
①【R4年出題】 ×
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」については、保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき事業主の同意がない場合は、当該被保険者は保険料の全額を負担し、かつ、保険料の納付義務は当該被保険者が負います。「当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。」は誤りです。
(法附則第4条の3第7項)
②【H29年出題】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、
「当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること」ができます。
また、「当該被保険者の同意を得て、その同意を将来に向かって撤回すること」ができるとされています。
ただし、当該被保険者が「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」であるときは、この規定は適用しないとされています。
「第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。」は誤りです。
(法附則第4条の3第10項)
➂【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
「当該保険料の納期限の属する月の末日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その被保険者の資格を喪失します。
例えば、令和7年12月分の保険料の納期限は令和8年1月末日です。
保険料を滞納し、厚生労大臣が指定した期限までに保険料を納付しないときは、令和7年12月末日に資格を喪失します。
(法附則第4条の3第6項)
④【H27年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
④【H27年出題】 ×
「当該保険料の納期限の日」ではなく、「当該保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その資格を喪失します。
⑤【R7年出題】
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
厚生年金保険の「適用事業所以外の事業所」に使用される高齢任意加入被保険者の保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額を負担し、保険料を納付する義務は事業主が負います。
(法附則第4条の5)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「老齢厚生年金の子の加給年金額」
R8-118 12.20
障害基礎年金・老齢厚生年金|子の加算額の関係
障害基礎年金の受給権者、老齢厚生年金の受給権者については、子があり、要件を満たす場合は、子の加算額が加算されます。
ただし、受給権者が「65歳以上」の場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金が併給されることがあります。両方の年金に「子の加算額」が加算されている場合の調整についてみていきます。
(受給権者が65歳以上の場合)
老齢厚生年金
|
子の加給年金額(支給停止) |
障害基礎年金
|
子の加算額 |
老齢厚生年金の条文を読んでみましょう
法第44条第1項 (加給年金額) ① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
障害基礎年金の子の加算が支給され、その間、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。
では、過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
子の加算額が加算された障害基礎年金と当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給される場合は、障害基礎年金の子の加算額はそのまま加算され、老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。
②【R7年出題】
障害基礎年金の支給を受けている者に子の加算が行われているとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給停止されているときを除く。)に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合は、当該老齢厚生年金については、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
②【R7年出題】 〇
①の問題と同じです。
老齢厚生年金について、子について加算する額に相当する部分の支給が停止されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「加給年金額」
R8-117 12.19
加給年金額を比較|老齢・障害
今回のテーマは「加給年金額」です。
老齢厚生年金と障害厚生年金の加給年金額について、取扱いを比較しましょう。
まず、老齢厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう。
法第44条第1項 (加給年金額) ① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
ポイント!
・老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が「240月」以上あること
・加給年金額の対象になるのは、「配偶者」・「子」です
・受給権を取得した当時に、受給権者によって生計を維持していたこと
・受給権を取得した当時240月未満でも、在職定時改定又は退職時改定の際に240以上となった場合は、「240以上」となった当時に、受給権者によって生計を維持していれば、加給年金額の対象となります。
次は、障害厚生年金の加給年金額について条文を読んでみましょう
第50条の2第1項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 |
ポイント!
・1級・2級の障害厚生年金が対象
3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。
・加給年金額の対象になるのは「配偶者」のみ
「子」は障害基礎年金で加算の対象になります
・受給権を取得した後で、配偶者を有することになっても、加給年金額の対象となります。
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額は加算されません。
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した後で、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合は、加給年金額は加算されません。
②【R7年出題】
老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を取得した2年後に誕生した子は、加給年金額の加算の対象となりません。
➂【H21年出題】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

【解答】
➂【H21年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権発生当時に、障害状態にない子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるときは加給年金額の対象となります。ただし、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、加給年金額の加算は終わります。
その後に、その子が19歳ではじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合でも、加給年金額は加算されません。
④【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
被保険者である老齢厚生年金の受給権者が、被保険者資格を喪失した際に(退職時改定の際に)、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
⑤【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
障害厚生年金については、その受給権を取得した日の翌日以後に、新たにその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも加給年金額が加算されます。
その場合、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
⑥【H29年出題】
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
「子」については、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「在職老齢年金」
R8-078 11.10
在職老齢年金の仕組み
在職老齢年金とは?
★「総報酬月額相当額」+「基本月額」が、「支給停止調整額」を超える場合に、老齢厚生年金の年金額の全部又は一部の支給が停止される仕組みです。
なお、在職老齢年金は、「老齢厚生年金」の受給権者でかつ「厚生年金保険の被保険者(=在職中で厚生年金保険料を負担している)」に適用されます。
条文を読んでみましょう
法第46条第1項 (支給停止) 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、総報酬月額相当額及び基本月額との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
★用語の定義を確認しましょう
「総報酬月額相当額」
→ 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
・国会議員又は地方公共団体の議会の議員について → 標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
・70歳以上の使用される者について → 標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
「基本月額」
→ 老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く)を12で除して得た額
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
①【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される70歳以上の者に対しても、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
適用事業所に使用されていても70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料の負担はありませんが、在職老齢年金の仕組みは適用されます。
厚生年金保険の被保険者でないので、標準報酬月額と標準賞与額は、「標準報酬月額に相当する額」と「標準賞与額に相当する額」となります。
(令3条の6)
②【R7年出題】
地方公共団体の議会の議員が老齢厚生年金の受給権者であるときは、当該議員が厚生年金保険の被保険者ではないとしても、議員報酬の月額及び期末手当の額と老齢厚生年金の額に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
「国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日が属する月」も在職老齢年金の規定が適用されます。
なお、地方公共団体の議会の議員の総報酬月額相当額は、「議員報酬の月額及び期末手当」で算定します。
(令3条の6)
➂【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
➂【H29年出題】 ×
「経過的加算額」も「繰下げ加算額」も、基本月額の計算には入りません。
なお、「経過的加算額」については、昭和60年法附則第62条で、基本月額の算定に含まない旨が規定されています。
(昭60法附則第62条)
④【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
「老齢基礎年金」も「経過的加算額」も在職老齢年金の支給停止の対象となりません。
(昭60法附則第62条)
⑤【R4年出題】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
在職老齢年金の支給停止額の計算に用いる「総報酬月額相当額」は、「標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」です。
在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されると、総報酬月額相当額も変更されます。
⑥【R7年出題】
前月から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する65歳以後の老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合は、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該総報酬月額相当額の改定が行われた月の翌月から支給される年金額が改定される。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権者の総報酬月額相当額が改定された場合は、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算されます。その場合、総報酬月額相当額の改定が行われた月の「翌月」ではなく、「総報酬月額相当額の改定が行われた月」から年金額が改定されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「在職定時改定」
R8-076 11.08
在職定時改定の仕組み
「在職定時改定」は、老齢厚生年金を受けながら働いている(=厚生年金保険の被保険者である)人が対象で、在職中に、老齢厚生年金の額が再計算される制度です。
毎年9月1日(基準日)に、前年9月から当年8月までの厚生年金保険の加入期間を追加して、年金額の再計算を行い、10月分から年金額が改定されます。
なお、対象は、「65歳以上」の人です。65歳未満の人には適用されません。
条文を読んでみましょう。
法第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
65歳以上の老齢厚生年金受給権者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
①【R4年出題】 ×
在職定時改定の基準日は7月1日ではなく、「9月1日」です。
ポイントを確認しながら、問題文を読み返しましょう。
・65歳以上の老齢厚生年金受給権者が対象
・毎年基準日である9月1日において被保険者である場合(=厚生年金保険に加入している場合)
・基準日の属する月前の被保険者であった期間(前年9月~当年8月)をその計算の基礎として年金額を再計算し
・基準日の属する月の翌月(10月)から
・年金額を改定します
②【R5年出題】
厚生年金保険法第43条2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

【解答】
②【R5年出題】 〇
条文のただし以下の部分です。
具体的な日付を当てはめて読んでみましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、8月20日にA社を退職(8月21日資格喪失)し、9月10日にB社で厚生年金保険の被保険者資格を再取得した場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
在職定時改定の規定において、基準日(9月1日)が被保険者の資格を喪失した日 (8月21日)から再び被保険者の資格を取得した日(9月10日)までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合(=A社の喪失で退職時改定が行われない)は、基準日の属する月前の被保険者であった期間(8月以前の期間)を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月(10月)から年金の額を改定するものとする。
→基準日(9月1日)に被保険者ではありませんが、在職定時改定が適用され、年金額が改定されます。
➂【R7年出題】
厚生年金保険法第42条に規定する老齢厚生年金を繰上げ受給している者で65歳に達していない場合は、在職定時改定が適用されない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
在職定時改定の対象は「65歳以上」で、「65歳未満」は対象外です。
老齢厚生年金を繰上げ受給していても、65歳未満の者には、在職定時改定は適用されません。
(法附則第13条の4)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「被保険者期間」
R8-075 11.07
厚生年金保険の被保険者期間の計算
「被保険者期間」は月単位で計算され、保険料の徴収や年金額の計算に使われます。
厚生年金保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されます。また、厚生年金の年金額は、原則として、平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数で計算します。
被保険者期間について条文を読んでみましょう
法第19条 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 ➂ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 ④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 ⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。 |
過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
被保険者期間は、月単位で計算します。被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
②【H30年出題】 〇
被保険者期間は、月単位で計算し、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。
問題文の場合は、資格を取得した月が「平成29年10月」、資格を喪失した月が「平成30年3月」ですので、その前月の平成30年2月までが算入されます。
被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間です。資格を喪失した月の平成30年3月は被保険者期間には算入されません。
➂【R6年出題】
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

【解答】
➂【R6年出題】 ×
(原則) 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪)は、その月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
5月1日に厚生年金保険の被保険者資格取得 → 同月15日に喪失の場合、被保険者期間は原則として「1か月」として算入されます。
(例外) ただし、問題文のように、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
5月 | |
1日(取得) | 15日(喪失・種別変更) |
厚生年金保険 被保険者 |
|
| 国民年金 第1号被保険者 |
5月1日に厚生年金保険の被保険者資格取得 → 同月15日に喪失・同日に(国年)第1号被保険者に種別変更の場合、令和6年5月分については、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
令和6年5月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。
④【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
➂の問題と同じです。
平成28年3月1日に厚生年金被保険者の資格を取得 → 同月21日資格喪失・同日(国年)第1号被保険者に種別変更の場合、同年3月分は、厚生年金保険における被保険者期間に算入されず、国民年金第1号被保険者としての被保険者期間となります。
⑤【R3年出題】
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
被保険者の「種別」とは、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の区別のことです。
⑥【R7年出題】
国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
被保険者期間は被保険者の種別ごとに適用されます。
第2号厚生年金被保険者(国家公務員)としての被保険者期間は、資格を喪失した月の前月(令和7年6月)までとなります。
第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間は、資格を取得した月(令和7年7月)から算入されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「合意分割」
R8-074 11.06
離婚時の厚生年金の合意分割の請求
離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができます。
今回は「合意分割」をみていきます。合意分割には、平成19年4月1日以降に離婚したこと、「按分割合」を定めることなどの条件があります。
なお、他に「3号分割」もありますが、今回は触れません。
条文を読んでみましょう。
法第78条の2 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) ① 第一号改定者又は第二号改定者は、離婚等をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (1) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているとき。 (2) ②の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ② ①の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 ➂ 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。 |
<用語について>
・ 第一号改定者
→ 被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。(標準報酬が多い方・渡す方)
・ 第二号改定者
→ 第一号改定者の配偶者であった者で、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。(標準報酬が少ない又はゼロの方・受ける方)
・ 離婚等
→ 離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。
・ 対象期間
→ 婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。
・ 按分割合
→ 改定又は決定後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう
法第78条の3第1項 (請求すべき按分割合) 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 |
<用語について>
・ 対象期間標準報酬総額
→ 対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。
按分割合とは、第2号改定者の分割後の持ち分の割合です。
第二号改定者の対象期間標準報酬総額 |
当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額 |
按分割合は、第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定めます。
※例えば、分割前の第二号改定者の持ち分の割合が30%の場合は、按分割合は30%を超え50%以下の範囲で定めることになります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき< A >について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから< B >を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 6か月 ⑤ 按分割合 ⑥ 改定額
⑦ 改定請求額 ⑧ 改定割合

【解答】
<A> ⑤ 按分割合
<B> ② 2年
②【R7年出題】
甲と乙は離婚したが、合意分割の請求前に甲が死亡した。その後、乙は、甲の死亡した日から起算して15日目に、所定の事項が記載された公正証書を添えて合意分割の請求を行った。この場合、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に所定の事項が記載された公正証書を添えて当事者の他方による標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に標準報酬改定請求があったものとみなされます。
問題文は、甲の死亡した日から起算して15日目に合意分割の請求を行っていますので、甲が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされます。
(令第3条の12の7)
➂【R7年出題】
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができるが、この申立ては当事者の一方のみによってすることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
合意分割の按分割合について当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときには、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めることができます。
この申立ては当事者の一方のみによってすることができます。
(法第78条の2第3項)
④【H29年出題】
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
「3か月以内」ではなく「2年以内」に行わなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第78条の4第1項 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただし書(離婚等をしたときから2年を経過したとき)に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 |
情報の提供の請求は、「当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合」又は「離婚等をしたときから2年を経過したとき」等は行うことができません。
⑤【R7年出題】
当事者又はその一方は、原則として、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、標準報酬改定請求後にはこの請求を行うことができない。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
④の解答と同じです。
標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求は、標準報酬改定請求後には行うことができません。
⑥【R7年出題】
対象期間標準報酬総額の算定において、対象期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、同日前の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法第26条第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、当該従前標準報酬月額)及び標準賞与額に、それぞれ当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額が当該対象期間標準報酬総額とされる。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
月々の標準報酬月額だけでなく、標準賞与額からも同一の保険料率で保険料が徴収され、年金の額にも反映されるようになったのは平成15年4月以降です。(総報酬制といいます。)
平成15年3月以前は、年金の額に反映するのは「標準報酬月額」のみでした。
バランスをとるために、平成15年4月1日前の対象期間については、各月の標準報酬月額に「1.3」を乗じます。
また、過去の標準報酬を現在の価値に読み替えるために使われるのが「再評価率」です。
対象期間の末日において適用される再評価率を使います。
⑦【R7年出題】
老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月から、年金の額が改定される。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権者について、合意分割の標準報酬の改定又は決定が行われたときは、「当該標準報酬の改定又は決定が行われた日の属する月の翌月」ではなく、「当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月」から、年金の額が改定されます。
(法第78条の10第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「育休中の保険料免除」
R8-041 10.04
育児休業中の保険料免除~1か月以下の場合に注意
育児休業中は、厚生年金保険料は事業主負担分・被保険者負担分ともに免除されます。(健康保険料も同様に免除されます)
免除の要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第81条の2 (育児休業期間中の保険料の徴収の特例) ① 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に係る保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)の徴収は行わない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 ② 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料については、「育児休業等をしている被保険者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたとき」となる。(=被保険者本人が申出を行う) |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
産前産後休業中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
産前産後休業中の保険料の免除を受けるには、実施機関に申出を行わなければなりません。
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者 → 事業主が申出
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者 → 被保険者本人が申出
※「育児休業中の保険料免除」についても同様です。
②【R6年出題】
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担及び被保険者負担分の両方が免除される。

【解答】
②【R6年出題】 〇
産前産後休業中の保険料については、事業主負担及び被保険者負担分の両方が免除されます。
※「育児休業中の保険料免除」も同様です。
➂【R7年出題】
厚生年金保険法第81条の2第1項に規定される育児休業期間中の厚生年金保険料の免除の規定について、育児休業等の期間が1か月以下の場合は、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されるが、その月の標準賞与額に係る保険料についても免除される。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
第81条の2第1項に、「その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。」とあります。育児休業等の期間が1か月以下でも、その月の標準報酬月額に係る保険料は免除されますが、その月の標準賞与額に係る保険料については免除されません。
④【R1年出題】
適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
事業主は、賞与を支給した場合、賞与額の届出を行わなければなりません。
産前産後休業期間中や育児休業期間中で保険料の免除が適用されている者でも、休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出が必要です。
(則第19条の5)
健康保険法の問題も解いてみましょう
①【健保R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【健保R5年出題】 〇
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合に該当します。
育児休業等を開始した日(=令和5年1月10日)の属する月(=令和5年1月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の前月までの月(=令和5年3月)までの保険料が免除されます。
②【健保R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【健保R5年出題】 ×
育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合は、その月の育児休業等の日数が14日以上あれば、その月の保険料が免除されます。
育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合、育休開始日と終了日の翌日が同一月にあり、育児休業の日数が13日しかありません。そのため、保険料は免除されません。(保険料が徴収されます)
➂【健保R6年出題】
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
➂【健保R6年出題】 ×
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合に該当します。
育児休業等を開始した日(=令和5年10月1日)の属する月(=令和5年10月)から育児休業等が終了する日の翌日(=令和6年1月1日)が属する月の前月までの月(=令和5年12月)までの保険料が免除されます。
令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は「徴収されます」。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「事後重症の障害厚生年金」
R8-040 10.03
事後重症による障害厚生年金の請求
「障害厚生年金」は、「初診日」「保険料納付要件」「障害認定日」の3つの要件を満たした場合、障害認定日に受給権が発生します。
「初診日」、「保険料納付要件」を満たしていても、障害認定日に障害等級1~3級に該当しない場合は、障害厚生年金の受給権は発生しません。
ただし、障害認定日の後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は事後重症の障害厚生年金の請求ができます。事後重症の障害厚生年金は請求によって受給権が発生します。
条文を読んでみましょう
第47条の2 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。 ② 保険料納付要件を満たしていること ➂ 請求があったときは、その請求をした者に障害厚生年金を支給する。 |
過去問を解きながらポイントを確認しましょう
①【R4年選択式】
厚生年金保険法第47条の2によると、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において同法第47第2項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後< A >までの間において、その傷病により障害の状態が悪化し、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。なお、障害厚生年金に係る保険料納付要件は満たされているものとする。

【解答】
<A> 65歳に達する日の前日
②【R7年出題】
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
事後重症の障害厚生年金は、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当+その期間内(65歳に達する日の前日まで)に請求することが条件です。
➂【R7年出題】
事後重症の障害厚生年金の対象は、障害等級1級及び2級のみである。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
事後重症の障害厚生年金は、障害等級1級及び2級だけでなく、「3級」も対象です。
④【H29年出題】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
65歳に達した日以後は、事後重症による障害厚生年金は請求できません。
⑤【R1年出題】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、64歳であったとしても、事後重症による障害厚生年金の支給を請求することはできません。
(法附則第16条の3第1項)
⑥【R6年出題】
厚生年金保険法第47条の2に規定される事後重症による障害厚生年金は、その支給が決定した場合、請求者が障害等級に該当する障害の状態に至ったと推定される日の属する月の翌月まで遡って支給される。

【解答】
⑥【R6年出題】 ×
事後重症による障害厚生年金は、「請求した日の属する月の翌月」から支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「報酬比例部分の計算」
R8-030 9.23
厚生年金の年金額の計算(給付乗率の引上げと300月保障)
厚生年金保険の被保険者は、月々の給与(標準報酬月額)とボーナス(標準賞与額)に応じて、保険料を負担しています。
老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の年金額は、「標準報酬月額と標準賞与額」と「被保険者期間(加入期間)」をベースに計算されます。
今回は厚生年金の計算式をみていきます。
※平成15年4月以降の加入期間についてみていきます。平成15年3月以前については月収ベースで計算しますので計算式が異なります。
老齢厚生年金の年金額の計算について条文を読んでみましょう。
法第43条第1項 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1,000分の 5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 ※平均標準報酬額とは? 被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいいます。 |
<老齢厚生年金の年金額の計算式>
平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数
ポイント!
・「1000分の5.481」について
昭和21年4月1日以前に生まれた者は、生年月日に応じて1000分7.308から1000分の5.562に引上げます。
・「被保険者期間の月数」について
実際の加入期間で計算します。上限・最低保障はありません。
・「再評価率」について
過去の標準報酬月額や標準賞与額を現在の価値に再評価するための率です。
障害厚生年金の年金額の計算について条文を読んでみましょう
法第50条 ① 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定の例(老齢厚生年金の計算式)により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 |
ポイント!
・「1000分の5.481」について
老齢厚生年金のような生年月日による引上げはありません。
・「被保険者期間の月数」について
被保険者期間が300月未満の場合は、「300月」で計算されます。
遺族厚生年金の年金額の計算について条文を読んでみましょう
法第60条第1項 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、(1)に定める額とする。 (1) (2)以外の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例(老齢厚生年金の年金額の計算)により計算した額の4分の3に相当する額。 ただし、短期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 (2) 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → (1)に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ (1)に定める額に3分の2を乗じて得た額 ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く。)に2分の1を乗じて得た額 |
ポイント!
短期要件と長期要件で計算式が変わります。
| 給付乗率(1000分の5.481) | 被保険者期間の月数 |
短期要件 | 生年月日による引上げなし(定率) | 300月未満の場合は300月保障 |
長期要件 | 生年月日による引上げあり | 実際の加入期間 |
過去問を解いてみましょう
①【H23年選択式】
老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
①【H23年選択式】
<A> 再評価率
<B> 5.481
②【R6年出題】
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に、総報酬制導入以後の被保険者期間分については、平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが、昭和36年4月1日以前に生まれた者については、異なる数値が用いられる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
生年月日に応じて給付乗率が引き上げられるのは昭和36年4月1日以前ではなく、「昭和21年4月1日以前」に生まれた者です。
➂【R1年出題】
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

【解答】
③【R1年出題】 〇
障害等級1級の障害厚生年金の額は、「老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数)×100分の125」です。
※被保険者期間の月数が300未満の場合は300で計算します。
④【R7年出題】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の算定式により計算した額となる。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。また、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われない。

【解答】
④【R7年出題】 〇
障害等級2級の障害厚生年金の額は、「平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」で計算した額です。被保険者期間の月数が300未満のときは、300で計算し、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われません。
⑤【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
障害等級3級の場合は障害基礎年金が支給されないため、3級の障害厚生年金には最低保障額が設けられています。最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2ではなく「4分の3」に相当する額です。
(法第50条第3項)
ちなみに、配偶者加給年金額は1級と2級の障害厚生年金には加算されますが、3級の障害厚生年金には加算されません。
⑥【R6年出題】
死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。

⑥【R6年出題】 ×
死亡した者が短期要件に該当する場合は、給付乗率の引上げは行われません。なお、被保険者期間が300月未満の場合は、300月で計算されます。
⑦【H27年出題】※改正による修正あり
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

【解答】
⑦【H27年出題】 〇
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」の死亡により支給される遺族厚生年金は「長期要件」です。死亡した者が昭和21年4月1日以前生まれの場合は、生年月日に応じ引上げられた乗率が適用されます。
⑧【R6年出題】
現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済となっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。

【解答】
⑧【R6年出題】 ×
問題文の甲は、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者」に該当し、遺族厚生年金は「長期要件」となります。(短期要件には該当しません。)
長期要件ですので、遺族厚生年金の額の計算については、実際の被保険者期間の5年(60月)で計算され、300月の最低保障はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「加給年金額」
R8-029 9.22
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件
老齢厚生年金の受給権者に、「65歳未満の配偶者」又は「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)」がある場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
今回は、加給年金額が加算される要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第44条第1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項(障害基礎年金の子の加算)の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
ポイント!
<加給年金額が加算される原則の要件>
・厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算されている老齢厚生年金の受給権者であること
・受給権者が「老齢厚生年金の受給権を取得した当時」、「生計を維持」していた65歳未満の配偶者又は子が対象
では、過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
問題文の場合、配偶者に係る加給年金額は加算されません。
加算の対象になるのは、老齢厚生年金の受給権者が「その権利を取得した当時」その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者です。
受給権を取得した後で、新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合は、配偶者に係る加給年金額は加算されません。
②【R7年出題】
老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが、受給権を取得した2年後に第2子が誕生した。この場合、当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする。)については加給年金額の加算の対象とはならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
加給年金額の対象になるのは、老齢厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の配偶者及び子です。
受給権を取得した2年後に誕生した第2子については、加給年金額の加算の対象にはなりません。
③【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満だったとしても、退職改定で被保険者期間の月数が240以上になり、240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されます。
図でイメージしましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
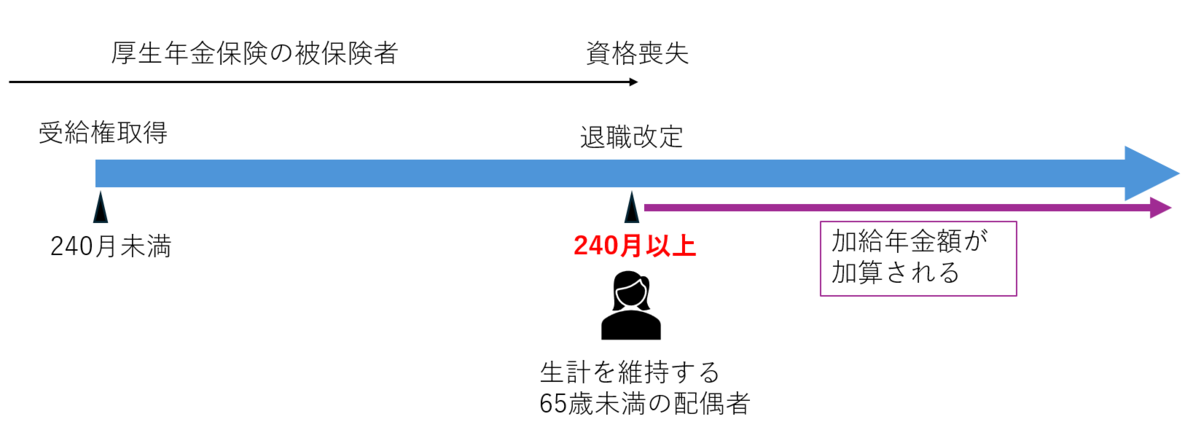
厚生年金保険法「資格の取得と喪失」
R8-027 9.20
厚生年金保険の被保険者資格の取得と喪失
厚生年金保険の被保険者資格の取得日と喪失日についてみていきます。
例えば、令和7年9月19日にA社(厚生年金保険の適用事業所)に入社し、同年11月25日に退職した場合、厚生年金保険の被保険者の資格は令和7年9月19日に取得、同年11月26日に喪失します。
では、条文を読んでみましょう。
法第13条 (資格取得の時期) ① 適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日に、被保険者の資格を取得する。 ② 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。
法第14条 (資格喪失の時期) 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(喪失の事実があった日に更に資格を取得するに至ったとき、又は第5号(70歳に達したとき)に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき。 (2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。 (3) 任意適用事業所の脱退又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。 (4) 適用除外に該当するに至つたとき。 (5) 70歳に達したとき。 |
ポイント!
・資格取得は「当日」です。
・資格喪失は原則「翌日」です。
※同日得喪、70歳に達したときは「当日」です。
それでは問題を解いてみましょう
①【H19年出題】
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

【解答】
①【H19年出題】 〇
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日(当日)に、被保険者の資格を取得します。
②【R1年出題】
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の「翌日」ではなく「その日」に被保険者の資格を喪失します。
なお、70歳に達した日とは、70歳の誕生日の前日です。厚生年金保険の被保険者資格は、70歳の誕生日の前日に喪失します。
③【H27年出題】
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。

【解答】
③【H27年出題】 ×
死亡したときは「その翌日」に、70歳に達したときは「その日」に被保険者資格を喪失します。
④【R5年出題】
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

【解答】
④【R5年出題】 ×
任意単独被保険者の資格喪失に際しては、事業主の同意は要りません。
★任意単独被保険者の取得と喪失を整理しましょう。
■資格取得について
・厚生労働大臣の認可があった日に取得
・事業主の同意が必要です。
(事業主が保険料を半額負担し、納付義務を負うため)
■資格喪失について
・厚生労働大臣の認可があった日の翌日に喪失
・事業主の同意は不要です。
(事業主の負担がなくなるため)
⑤【R7年出題】
適用事業所である甲に使用されていた被保険者乙は、令和7年4月1日に甲に使用されなくなったが、同日、別の適用事業所である丙に使用されるに至り、被保険者資格の得喪が生じた。この場合、乙の甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、乙は同日に丙での被保険者資格を取得する。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
令和7年4月1日に甲を退職した場合、翌日の4月2日に資格を喪失するのが原則です。
ただし、同じ日に、別の適用事業所である丙に入社した場合は、甲での被保険者資格は令和7年4月1日に喪失し、同じ日に丙での被保険者資格を取得します。
⑥【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
問題文のように、第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「中高齢寡婦加算」
R8-026 9.19
中高齢寡婦加算について「死亡した夫の要件」
要件を満たした夫が死亡した場合、妻の遺族厚生年金に40歳から65歳まで「中高齢寡婦加算」が加算されます。
今回は、「死亡した夫」の要件を見ていきます。
では、条文を読んでみましょう。
法第62条 ① 遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に同法第39条第3項第2号から第8号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。 ② 中高齢寡婦加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。 |
★中高齢寡婦加算が加算される妻の条件を確認しましょう。
①子がいない場合
遺族厚生年金の権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの
②子がいる場合(遺族基礎年金を受けている場合)
40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子と生計を同じくしていたもの(遺族基礎年金を受けている)
→子が18歳の年度末等になり、遺族基礎年金が支給されなくなったときから65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されます。
★中高齢寡婦加算の額を確認しましょう
遺族基礎年金の額×4分の3(定額)
★では、死亡した夫の条件を確認しましょう
・遺族厚生年金は「短期要件」と「長期要件」があります。(法第58条第1項)
<短期要件>
① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
③ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
<長期要件>
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
★中高齢寡婦加算について死亡した夫の条件を確認しましょう
→ 「第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。」とされています。
→ 長期要件で支給される遺族厚生年金の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が240月以上あることが条件です。
では過去問をどうぞ!
【R7年出題】
障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫が死亡し、子のいない妻が遺族厚生年金を受給する場合、夫死亡時の妻の年齢によっては、中高齢寡婦加算が行われることがある。ただし、当該死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満である場合は、中高齢寡婦加算は行われない。

【解答】
【R7年出題】 ×
遺族厚生年金が短期要件に該当していても、長期要件に該当していても、要件を満たした場合、中高齢寡婦加算が加算されます。
ただし、「長期要件」に該当する場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240月以上あることが条件です。
問題文は、「障害等級2級の障害厚生年金を受給する夫の死亡」により支給される遺族厚生年金ですので、「短期要件」です。そのため、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であっても、中高齢寡婦加算が行われます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(厚生年金保険法)から学ぶ
R8-011 9.04
R7年選択式は定時決定・再評価率の改定・3号分割・障害厚生年金
令和7年の厚生年金保険の選択式は、
・定時決定
・再評価率の改定
・3号分割の対象にならない期間
・障害厚生年金のみの受給権が発生する場合
から出題されました。
 定時決定について
定時決定について
令和7年の問題をどうぞ!
①【R7年選択式】
厚生年金保険法第21条第1項の規定によると、実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が< A >(厚生労働省令で定める者(被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者等)にあっては、< B >。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定するとされている。
<選択肢>
① 11日 ② 12日 ③ 13日 ④ 14日 ⑤ 15日 ⑥ 16日
⑦ 17日 ⑧ 18日

【解答】
<A> ⑦ 17日
<B> ① 11日
 再評価率の改定について
再評価率の改定について
R7年の問題をどうぞ!
②【R7年選択式】
厚生年金保険法第43条の4第1項の規定によると、調整期間における再評価率の改定については、< C >に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とするとされている。
<選択肢>
⑫ 実質賃金変動率 ⑬ 実質手取り賃金変動率 ⑮ 名目賃金変動率
⑯ 名目手取り賃金変動率

【解答】
<C> ⑯ 名目手取り賃金変動率
過去問も解いてみましょう
①【H18年選択式】※改正による修正あり
1 平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< A >(生年度別)を改定することによって毎年度自動的に行われる方式に改められた。
2 新規裁定者(< B >歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、 < C >を基準とした< A >を用い、既裁定者(< B >歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、前年の< D >(< D >が< C >を上回るときは、< C >)を基準とした< A >を用いる。
<選択肢>
① 60 ② 68 ③ 65 ④ 70
⑤ 基準年度再評価率 ⑥ 給付乗率 ⑦ 給付改定率 ⑧ 物価変動率
⑨ 名目賃金変動率 ⑩ 実質賃金変動率 ⑪ 物価上昇率
⑫ 名目手取り賃金変動率 ⑬ 消費者物価指数 ⑭ 再評価率

【解答】
<A> ⑭ 再評価率
<B> ② 68
<C> ⑫ 名目手取り賃金変動率
<D> ⑧ 物価変動率
ポイント!
新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者は「物価変動率」を基準に改定されます。
②【R5年選択式】
令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から< A >となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。
<選択肢>
① 0.1%の引下げ ② 0.2%の引下げ ③ 0.5%の引下げ ④ 据置き

【解答】
<A> ② 0.2%の引下げ
ポイント!
・既裁定者の再評価率の改定は、原則として「物価変動率」が基準となります。
ただし、「物価変動率」が「名目手取り賃金変動率」を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準とします。
問題文は、物価変動率(+0.2%)>名目手取り賃金変動率(-0.2%)ですので、「名目手取り賃金変動率」を基準に改定します。そのため、「0.2%の引き下げ」となります。
なお、基準になる名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
 3号分割標準報酬改定請求について
3号分割標準報酬改定請求について
最初に条文を読んでみましょう。
法第78条の14第1項 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していたものをいう。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。 ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 |
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

【解答】
【R1年出題】 〇
3号分割標準報酬改定請求をする場合の特定期間に係る被保険者期間については、特定被保険者の障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間は、改定又は決定の対象から除かれます。
では、令和7年の選択式をどうぞ!
③【R7年選択式】
平成2年1月生まれの甲は、平成23年1月に同い年の乙と結婚し、令和7年1月に離婚した。婚姻期間中、乙は厚生年金保険の被保険者であり、甲は国民年金の第3号被保険者であった。また、乙は、令和2年8月に初診日のある傷病により、令和4年2月の障害認定日に障害等級3級に該当しており、離婚時には、当該障害による障害厚生年金を受給していた。この事例において、3号分割標準報酬改定請求の対象とならない期間は、平成23年1月から< D >までである。
<選択肢>
⑰ 令和2年8月 ⑱ 令和4年1月 ⑲ 令和4年2月 ⑳ 令和6年12月

【解答】
<D> ⑲ 令和4年2月
・特定期間について
特定期間は、特定被保険者(甲)が被保険者であった期間で、かつ、その被扶養配偶者(乙)が国民年金の第3号被保険者であった期間です。
・特定期間の一部が、甲の障害厚生年金の計算の基礎となっています。
・甲の障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間は、改定又は決定の対象から除かれます。
・障害厚生年金は、「障害認定日の属する月」までが計算の基礎となります。(法第51条)甲の障害厚生年金は、障害認定日の属する月である「令和4年2月」までが計算の基礎になっています。
・3号分割標準報酬改定請求の対象にならない期間は、障害厚生年金の計算の基礎になっている「平成23年1月から令和4年2月」までとなります。
 障害厚生年金の受給権のみ発生する場合
障害厚生年金の受給権のみ発生する場合
最初にポイントを確認しましょう!
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者です。
ただし、厚生年金保険の被保険者でも、「65歳以上で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有するもの」は第2号被保険者となりません。
(国民年金法附則第3条)
では、令和7年の問題をどうぞ!
④【R7年選択式】
厚生年金保険の被保険者丙は、令和7年8月1日に自宅内で倒れて、病院に緊急搬送された。丙は、同日において、67歳の男性であり、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに繰下げ待機中である。この傷病によって、丙が障害認定日に、障害等級2級と認定された場合、受給権が発生する障害年金は、< E >。なお、丙に保険料滞納期間はないものとする。
<選択肢>
⑨ 障害基礎年金と障害厚生年金である
⑩ 障害基礎年金のみである
⑪ 障害厚生年金のみである
⑭ 存在しない

【解答】
<E> ⑪ 障害厚生年金のみである
ポイント!
丙は、厚生年金保険の被保険者ですが、67歳で、かつ老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有しているため、国民年金の第2号被保険者ではありません。
・障害厚生年金について
→「初診日」に、厚生年金保険の被保険者ですので、初診日要件を満たします。
・障害基礎年金について
→「初診日」に国民年金の被保険者ではありませんので、初診日要件を満たしません。
・丙には、「障害厚生年金の受給権のみ」発生します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健保・厚年>短時間労働者が被保険者になる条件
R7-356 08.19
短時間労働者が被保険者になる条件のポイント!<健保・厚年>
短時間労働者が被保険者になる要件をチェックしましょう。
★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者は、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 報酬の月額が88,000円以上であること
③ 学生でないこと
■健康保険法の問題をチェックしましょう。
(1)特定適用事業所とは
①【健保H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【健保H29年出題】 〇
「特定労働者の総数が常時50人を超える」がポイントです。
(H24法附則第46条第12項)
(2)所定労働時間について
①【健保R2年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】
①【健保R2年出題】 〇
・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)
②【健保R3年出題】
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

【解答】
②【健保R3年出題】 ×
通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満である者が被保険者として取り扱われるためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。問題文の場合は18時間ですので、被保険者になりません。
(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)
(3)報酬の月額について
①【健保R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
①【健保R4年選択式】
<A> 88,000円以上
②【健保H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
②【健保H30年出題】 ×
最低賃金法において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)
■月額88,000円の算定に含まれないもの
・ 臨時に支払われる賃金(例)結婚手当
・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例)賞与
・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例)割増賃金
・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金
→ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(4)学生でないことについて
①【健保R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
④【健保R3年出題】 ×
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
■学生でないこととして取り扱われるもの
「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。」とされています。
(R4.9.28保保発0928第6号)
■厚生年金保険法の問題もチェックしましょう
①【厚年R5年出題】※改正による修正あり
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。

【解答】
①【厚年R5年出題】 ×
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。
※特定労働者とは、「70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの」をいいます。
(H24法附則第17条第12項)
②【厚年R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
②【R2年出題】 〇
特定適用事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
(H24法附則第17条第1項)
③【R4年出題】※改正による修正あり
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
※Xは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。

【解答】
③【R4年出題】 ×
Xは、厚生年金保険の被保険者となります。
「国・地方公共団体」は、50人超えという人数が問われないことがポイントです。
Xは、「① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「② 報酬の月額が88,000円以上であること」、「③ 学生でないこと」の要件を満たし、「地方公共団体」で働いているので、厚生年金保険の被保険者となります。
(H24法附則第17条第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害厚生年金」
R7-341 08.04
障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう
障害厚生年金の事例問題を解いてみましょう。
 テーマその1
テーマその1
初診日に高齢任意加入被保険者だった場合
 テーマその2
テーマその2
3級の障害厚生年金の受給権者に新たに3級の障害が生じた場合
→「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」がポイントです
 テーマその3
テーマその3
障害厚生年金の受給権者に新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合
 テーマその4 障害厚生年金の失権
テーマその4 障害厚生年金の失権
→3級の障害厚生年金を受けていたが、63歳のときに3級に該当しなくなり障害厚生年金の支給が停止されている場合、障害厚生年金が失権するのはいつの時点?
YouTubeでお話ししています
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害手当金」
R7-335 07.29
年金給付の受給権者等には障害手当金は支給されない
以下の者には、障害手当金が支給されません。
・厚生年金保険・国民年金の年金給付(老齢・障害・遺族)の受給権者
・同一の傷病で、労災保険の障害(補償)等給付を受ける権利を有するもの
条文を読んでみましょう。
法第55条 (障害手当金の受給権者) 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
第56条 障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 (1) 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) (2) 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) (3) 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者 |
(1)(2)障害年金について
障害手当金は支給されない | 例外 | |||
1級 |
|
|
|
|
2級 |
|
|
| |
3級 |
|
| ||
3級未満 | 3年 | |||
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
障害手当金は支給されません。
障害の程度を定めるべき日において「年金たる保険給付(老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金)の受給権者には障害手当金は支給されません。
※例外
最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)は除かれます。
②【R4年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者に障害手当金は支給されない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
③【R1年出題】
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】
③【R1年出題】 ×
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、障害手当金は支給されません。
④【H28年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金は支給されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されません。
⑤【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
同一の傷病で、障害手当金の受給権と労災保険法の障害補償給付の受給権を取得した場合は、障害手当金は支給されません。
⑥【H25年出題】
障害手当金は、障害の程度を定める日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

【解答】
⑥【H25年出題】 ×
障害手当金は、障害の程度を定める日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されません。また、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者にも支給されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「遺族厚生年金」
R7-334 07.28
遺族厚生年金の事例問題を解いてみましょう
遺族厚生年金の事例問題を解きながら、遺族厚生年金のポイントをつかみましょう。
今回のテーマ
・その1 保険料納付要件(原則と特例)
※「特例」については、「前々月までの1年間」の具体例が出題されています
・その2 短期要件と長期要件について ※短期要件と長期要件は計算ルールが異なります。
短期要件と長期要件の両方に当てはまる人の事例です。
・その3 遺族の要件
※55歳の夫で子がいる場合の遺族厚生年金の注意点 ※子の遺族厚生年金の失権時期の具体例
YouTubeでお話ししています
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「70歳以上の在職老齢年金」
R7-325 07.19
70歳以上の使用される者の在職老齢年金について
厚生年金保険の被保険者になるのは「70歳未満」の者です。
70歳に達したときに厚生年金保険の被保険者資格は喪失します。
ただし、70歳以上でも、適用事業所に使用される場合は、保険料の負担はありませんが、在職老齢年金の対象になります。
70歳以上の者について条文を読んでみましょう。
法第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、又は 70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(70歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
「70歳以上の使用される者」とは、「被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの」です。
厚生労働省令定める要件は、「適用事業所に使用される者であって、かつ、法第12条各号(適用除外)に定める者に該当するものでないこと」です。
そのため、適用事業所で使用される70歳以上の者でも、適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象となりません。
(法第27条、則第10条の4)
②【R4年出題】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
②【R4年出題】 ×
70歳以上の者に対しても、在職老齢年金の仕組みは、適用されます。
③【H28年出題】
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
平成27年10月の改正で、昭和12年4月1日以前生まれの者も、在職老齢年金の対象となっています。
④【H23年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金を受給している被保険者であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。

【解答】
④【H23年出題】 〇
「70歳以上の使用される者」は、保険料を納めることはありませんが、在職老齢年金の仕組みが適用され、要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「在職老齢年金」
R7-324 07.18
在職老齢年金の仕組み
働きながら(=厚生年金保険に加入しながら)、老齢厚生年金を受給する場合は、年金がカットされることがあります。この仕組みを、在職老齢年金といいます。
条文を読んでみましょう。
法第46条第1項 (支給停止) 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、「総報酬月額相当額」及び「基本月額」との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、「支給停止基準額」に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
用語の定義を確認しましょう
★総報酬月額相当額
→ 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
★基本月額
→ 老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額
★支給停止基準額
→ 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
★支給停止調整額について → 令和7年度は51万円
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
<選択肢>
① 支給調整開始額 ② 支給調整基準額 ③ 支給停止開始額
④ 支給停止額 ⑤ 支給停止基準額 ⑥ 支給停止調整額
⑦ 総報酬月額 ⑧ 総報酬月額相当額 ⑨ 定額部分
⑩ 標準賞与月額相当額 ⑪ 平均標準報酬月額 ⑫ 報酬比例部分

【解答】
①【H28年選択式】
<A> ⑧ 総報酬月額相当額
<B> ⑥ 支給停止調整額
<C> ⑤ 支給停止基準額
②【R4年出題】
在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。

【解答】
②【R4年出題】 〇
支給停止調整額は、年度ごとに改定される場合があります。
(法第46条第3項)
③【R3年出題】
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

【解答】
③【R3年出題】 ×
基本月額は、老齢厚生年金の額を12で除して得た額ですが、「加給年金額」は除かれます。
④【R6年出題】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
★加給年金額について
・在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合でも、加給年金額は支給されます。
・在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の全部が停止される場合は、加給年金額も支給停止となります。
⑤【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となりません。
⑥【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
経過的加算額も繰下げ加算額も、基本月額の計算には入りません。
(昭60法附則第62条第1項)
⑦【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
⑦【R4年出題】 ×
老齢基礎年金は在職中でも支給停止の対象になりません。
また、経過的加算額についても在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
⑧【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】
⑧【H24年出題】 ×
60歳台後半の在職老齢年金においては、経過的加算額と老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「被保険者」
R7-307 07.01
厚生年金保険の被保険者の資格喪失事由と時期
適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然に、厚生年金保険の被保険者となります。
今回は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する事由と、喪失時期をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第14条(資格喪失の時期) 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に資格を取得するに至ったとき、又は(5)に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき。 (2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。 (3) 任意適用事業所の脱退又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき。 (4) 適用除外に該当するに至ったとき。 (5) 70歳に達したとき。(※当日喪失)
|
では過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、それに該当するに至った日の翌日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【R1年出題】 ×
適用事業所に使用される70歳未満の被保険者が70歳に達したときは、「その日」に被保険者の資格を喪失します。
年齢で喪失する場合は「当日」です。
なお、「70歳に達した日」とは、70歳の誕生日の前日です。
②【H27年出題】
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。

【解答】
②【H27年出題】 ×
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときは「その翌日」に、70歳に達したときは「その日」に被保険者資格を喪失します。
③【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書又は所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
「10日以内」ではなく「5日以内」です。
(則第22条)
④【R2年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者資格は、70歳に達した日に喪失しますが、70歳以降も引き続き当該事業所に使用される場合は、「70歳以上被用者」に該当し、厚生年金保険の保険料は徴収されませんが、在職老齢年金の対象となります。
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当する場合で、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、「70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届」を省略できます。
なお、70歳到達日の前日における標準報酬月額と「異なる」場合は、5日以内に提出しなければなりません。
(則第15条の2、則第22条)
⑤【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
⑥【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
ポイントを確認しましょう
・第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したとき
→ 被保険者の資格は翌月の1日に喪失
・遺族厚生年金の受給権
→ 死亡した日に発生
・遺族厚生年金は
→ 死亡した日の属する月の翌月から支給される
(法第36条第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「遺族厚生年金」
R7-304 06.28
30歳未満の妻の遺族厚生年金の失権
まず、遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」の要件を確認しましょう。
★遺族厚生年金の遺族の要件として、妻には年齢要件はありません。
「夫」については、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件です。
★国民年金法の遺族基礎年金の遺族となる「配偶者」については、「子」と生計を同じくすることが要件ですが、厚生年金保険の遺族厚生年金の遺族となる「配偶者」は子の有無は問われません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■夫の死亡当時30歳未満の妻については、遺族厚生年金が「5年間」の有期年金となる場合があります。
遺族基礎年金の受給権の有無(子の有無)などで、5年間の起算日が変わるのがポイントです。
では、30歳未満の妻の失権事由について条文を読んでみましょう。
法第63条第1項第5号 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときに該当するに至ったときは、消滅する。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき → 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 |
図でイメージしましょう
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権を取得した当時「30歳未満である妻」が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく「遺族基礎年金の受給権を取得しない場合」は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
5年は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算することがポイントです。
②【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該遺族厚生年金の受給権は、「当該妻が30歳になったとき」ではなく、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅します。
③【R5年出題】
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

【解答】
③【R5年出題】 〇
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、当該遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅します。
5年の起算日が、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」であることがポイントです。
④【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
④【H29年出題】 ×
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合で、当該消滅した日に妻が30歳に到達する日前であった場合は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」からではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
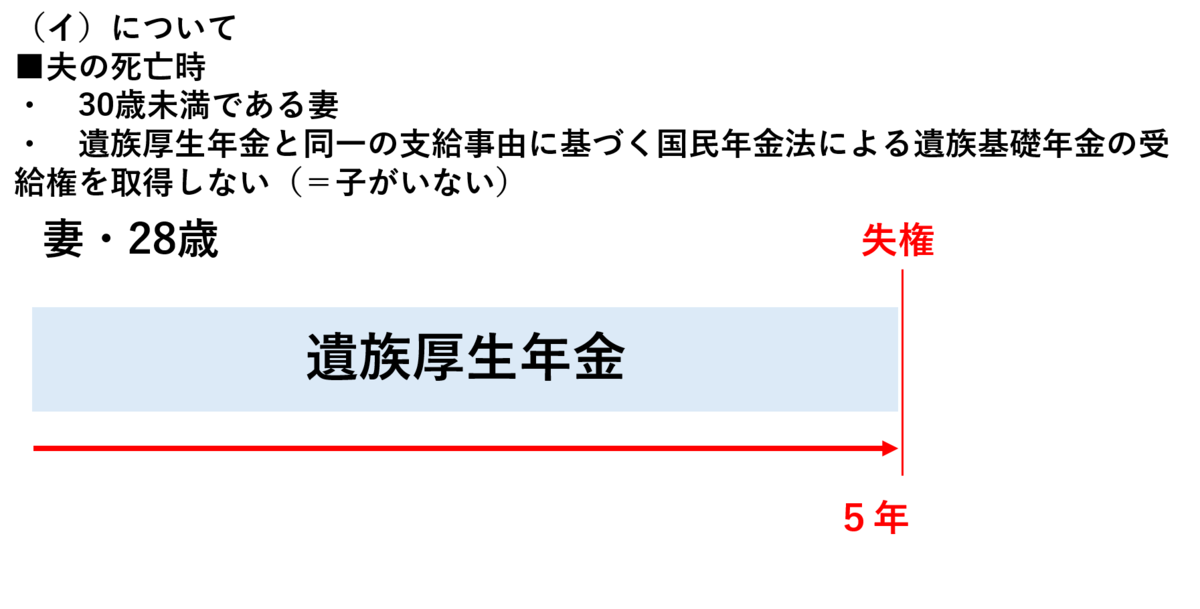
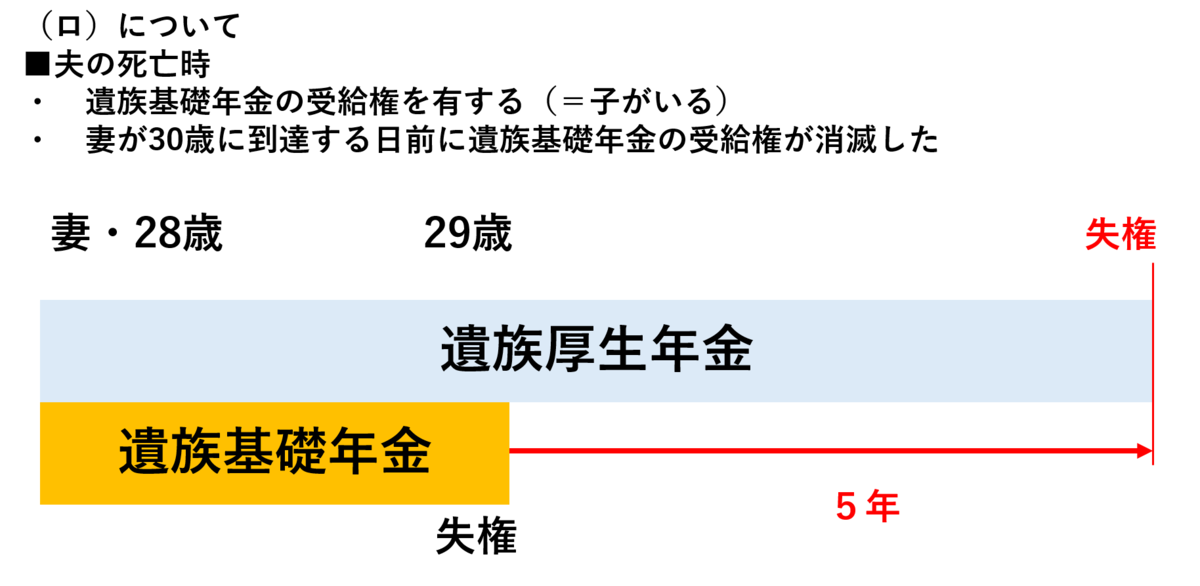
国民年金・厚生年金保険「時効」
R7-279 06.03
<国年・厚年比較>時効について
国民年金法と厚生年金保険法の「時効」を比較してみましょう。
まず、国民年金の条文を読んでみましょう。
国民年金法第102条 (時効) ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
ポイント!
「年金給付」→ 年金のみです。死亡一時金は入りません。
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
第92条 (時効) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ③ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 |
ポイント!
「保険給付」 → 障害手当金も入ります。年金のみではありません。
過去問をどうぞ!
国民年金法
①国年【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①国年【H27年出題】 ×
「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
「死亡一時金」を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
②国年【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②国年【R2年出題】 〇
「年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うもの」を「支分権」といいます。
支分権の時効についての問題です。
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は「支払期月の翌月の初日」から起算して5年を経過したときに時効によって消滅します。
厚生年金保険法
①厚年【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①厚年【H29年出題】 ×
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
国民年金の「死亡一時金」は「2年」ですので違いに注意しましょう。
②厚年【H30年出題】
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

【解答】
②厚年【H30年出題】 ×
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、「進行しない」。
③厚年【R4年出題】
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
③厚年【R4年出題】 〇
支分権の時効の問題です。
時効の起算点の「支払期月の翌月の初日」がポイントです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「特別支給の老齢厚生年金」
R7-278 06.02
特別支給の老齢厚生年金についてお話しします
本来の「老齢厚生年金」は、65歳から、老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
60歳から65歳まで支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳以上の本来の老齢厚生年金とは別の有期年金です。
・特別支給の老齢厚生年金の支給要件
・平成6年改正と平成12年改正
・生年月日や性別による支給開始年齢の違い
などを、図を使ってお話ししています。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「配偶者加給年金額」
R7-276 05.31
配偶者加給年金額(老齢厚生年金・障害厚生年金)
★まず、老齢厚生年金に加算される加給年金額をみていきましょう。
加給年金額の対象になるのは、「配偶者」と「子」です。
今回は、「配偶者」を中心にみていきます。
<加給年金額のポイント!>
・老齢厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)
→ その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であること
・加給年金額の対象になる人
→ 受給権者がその権利を取得した当時、受給権者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子
→老齢厚生年金の権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時、受給権者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子
※子の条件→ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子
★次に、障害厚生年金に加算される加給年金額をみていきましょう。
<加給年金額のポイント!>
・障害厚生年金の受給権者(加給年金額が加算される人)
→ 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当すること(3級には加給年金額は加算されません)
・加給年金額の対象になる人
→ 受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者
(受給権が発生した後で生計を維持することになった場合でも加給年金額の対象になる)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。

【解答】
①【R2年出題】 〇
・老齢厚生年金の加給年金額
配偶者 | 224,700円×改定率 |
子 | 2人目まで 224,700円×改定率 3人目以降 74,900円×改定率 |
(法第44条第2項)
②【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
被保険者資格を喪失した際に(退職時改定により)、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されるようになります。
(法第44条第1項)
③【R3年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級又は2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
法第46条第6項で、「加給年金額が加算された老齢厚生年金については、その者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。」と規定されています。
問題文は、「老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害厚生年金(1級・2級・3級)及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。」となります。
加算対象の配偶者が3級の障害厚生年金を受給している場合でも、配偶者についての加給年金額は支給停止されます。
④【R4年出題】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

【解答】
④【R4年出題】 〇
加給年金額の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合は、夫に加算されていた加給年金額は支給が停止されます。
⑤【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
⑤【H28年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は引き続き支給されます。
イメージ図をみてみましょう。
⑥【H30年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなります。
★配偶者加給年金額には「特別加算」が加算されます。
受給権者の生年月日 | 特別加算の額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円×改定率 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,300円×改定率 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,500円×改定率 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,600円×改定率 |
昭和18年4月2日~ | 165,800円×改定率 |
特別加算のポイント!
・生年月日は「老齢厚生年金の受給権者の生年月日」。加算の対象になっている配偶者の生年月日ではありません。
・特別加算が加算されるのは、「昭和9年4月2日」以降生まれ。
・生年月日が若いほど、特別加算の額が大きくなる
・昭和18年4月2日以降生まれは一律
⑦【R4年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
⑦【R4年出題】 ×
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、特別加算はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
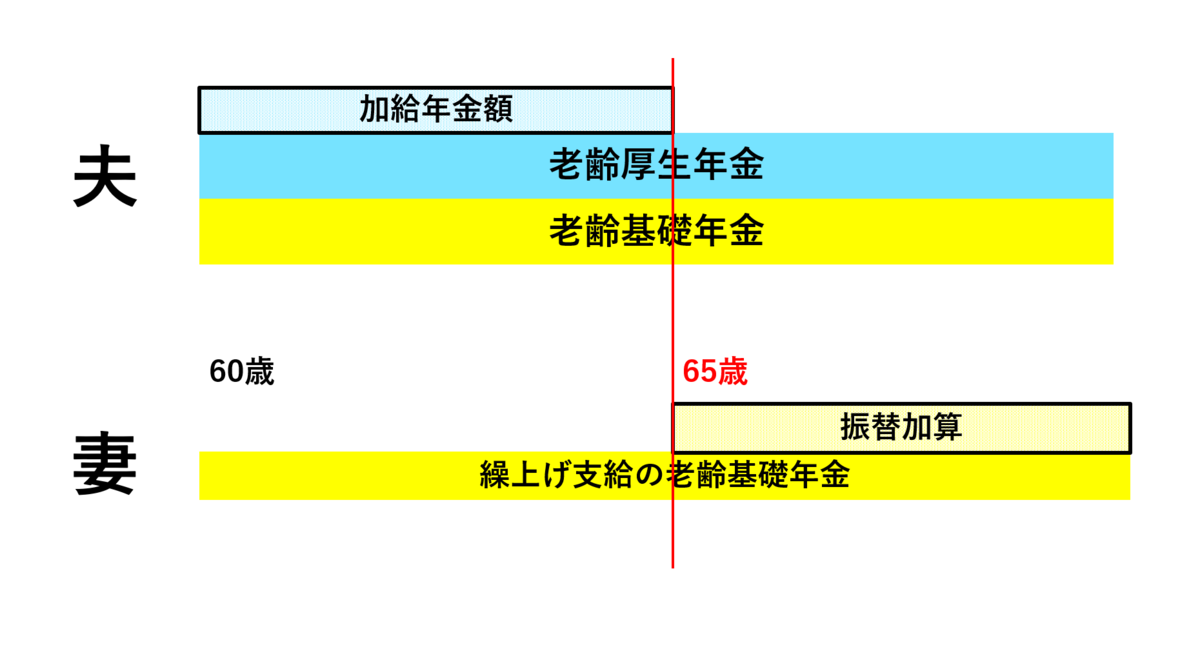
厚生年金保険法「保険給付の制限」
R7-265 05.20
厚生年金保険の給付制限事由
厚生年金保険法の保険給付が制限される条件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第73条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第73条の2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第74条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第75条 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。 ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について届出若しくは確認の請求又は訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでない。(=保険給付が行われる。)
第76条 ① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第77条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第96条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第97条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。 (3)前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
※第96条 (受給権者に関する調査) 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。 ※第97条 (診断) 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第44条第1項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
第78条 ① 受給権者が、正当な理由がなくて、第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 ② 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。 |
※「一時差し止めることができる」について
「支給停止」との違いに注意しましょう。
「支給停止」は停止事由がなくなれば、その翌月から支給が再開されますが、停止された期間分の保険給付は支払われません。
「一時差し止める」は、受給権者から届出等が行われれば、差し止められた分の保険給付が遡って支払われます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
・「故意に」 → 支給しない。
・「自己の故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」 → 保険給付の全部又は一部を行なわないことができる
②【H29年出題】
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき
→ 実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
③【R2年出題】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

【解答】
③【R2年出題】 〇
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
④【H27年出題】
保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われないが、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、この限りでないとされている。

【解答】
④【H27年出題】 〇
・ 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行われません。
ただし、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格の取得について事業主の届出があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したものであるときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付が行われます。
⑤【H27年出題】※改正による修正あり
第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
厚生年金保険法第98条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を「一時差し止めることができる」です。支給を停止するではありませんので注意しましょう。
⑥【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)は、その額の全部につき支給が停止されている場合を除き、正当な理由なくして、厚生年金保険法施行規則第35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、当該老齢厚生年金が支給停止され、その後、当該届書が提出されれば、提出された月から支給停止が解除される。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者があるものとする。)が、加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の届書を提出しないときは、「保険給付の支払を一時差し止めることができる」となります。
YouTubeはこちらです
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「離婚分割」
R7-264 05.19
3号分割についてお話しします
★3号分割制度のポイントをYouTubeでお話ししています。
・平成20年4月1日施行
・特定被保険者(第2号被保険者)と被扶養配偶者(第3号被保険者)の分割
・分割の割合は2分の1
・第2号被保険者の同意は不要
YouTubeはこちらです
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「離婚分割」
R7-262 05.17
離婚時みなし被保険者期間の扱い
「離婚時みなし被保険者期間」についてみていきます。
「離婚時みなし被保険者期間」の定義を条文で読んでみましょう。
第78条の6第3項 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。 =離婚時みなし被保険者期間という。 |
★離婚時みなし被保険者期間を図でイメージしましょう
※3号分割の「被扶養配偶者みなし被保険者期間」も同じ考え方です。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「1年以上の被保険者期間を有すること」です。この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含みません。
(法附則第17条の10)
②【H27年出題】
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

【解答】
②【H27年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは「1年以上の被保険者期間を有すること」ですが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含みません。
そのため、厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(法附則第17条の10)
③【H29年出題】
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の額の計算には算入されますが、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算には入りません。
(法附則第17条の10)
④【R3年出題】
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるための「被保険者期間の月数が240以上」の当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
(法第78条の11)
⑤【H28年出題】※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上であるものに限る。)を取得した後に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
遺族厚生年金は、「被保険者又は被保険者であった者」が要件に該当した場合に、遺族に支給されます。
「被保険者であった者」については、「長期要件に該当する場合にあっては、「離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。」とされています。
そのため、厚生年金保険の被保険者であったことがなかった者でも、「離婚時みなし被保険者期間を有する」に至り、長期要件を満たしている場合は、遺族厚生年金が支給されます。
(法第78条の11)
⑥【H19年出題】
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。

【解答】
⑥【H19年出題】 〇
⑤の問題と同じ趣旨です。
⑦【H29年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定された場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が合意分割により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額が改定されます。
ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされません。
(法第78条の10第2項)
⑧【国年H27年出題】(国民年金法の問題です)
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
⑧【国年H27年出題】(国民年金法の問題です) 〇
妻が、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金の受給権者である場合は、振替加算は行われません。
この被保険者期間の計算には、離婚時みなし被保険者期間が含まれます。
そのため、合意分割によって、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算は行われなくなります。
(昭60法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
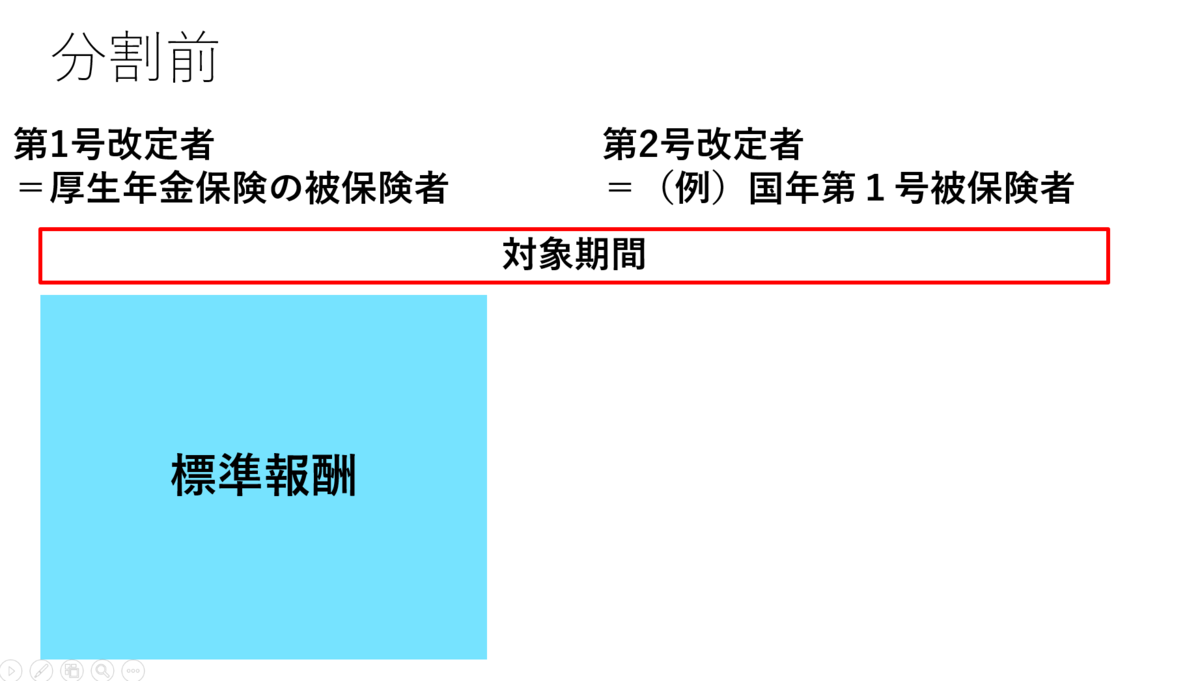
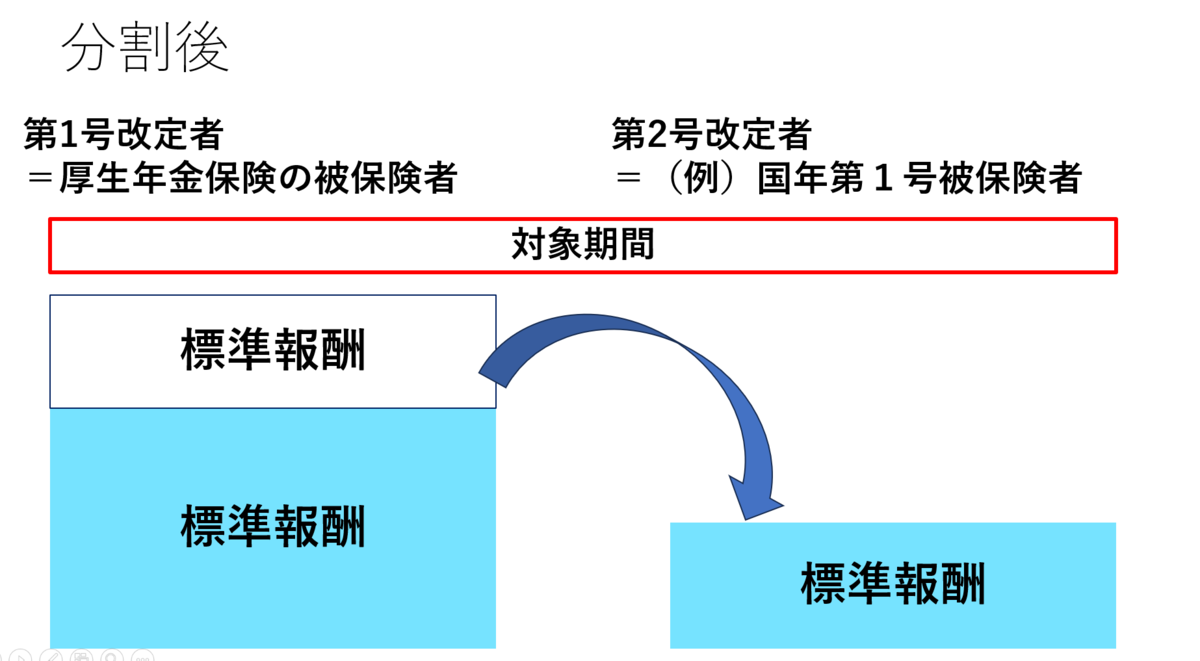
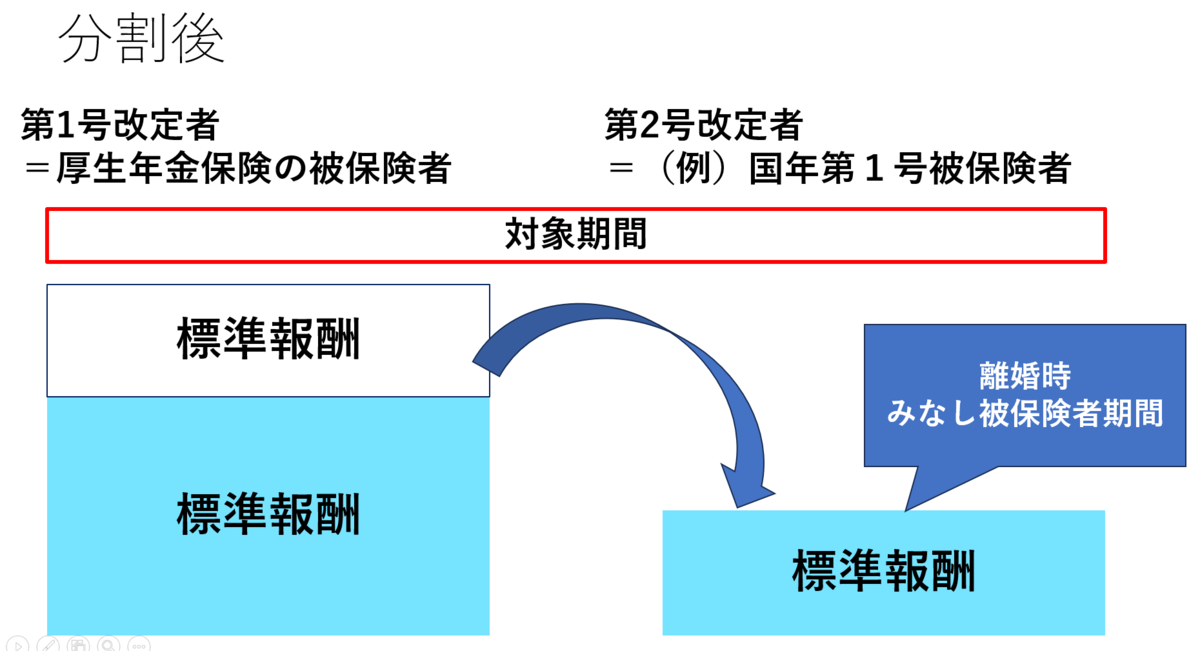
厚生年金保険法「離婚分割」
R7-261 05.16
離婚分割「合意分割制度」基本編
離婚分割には、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
今回は、「合意分割制度」をみていきます。
合意分割制度は、当事者が合意または裁判手続きにより按分割合を定め、婚姻期間中の「標準報酬月額・標準賞与額」を分割する制度です。
条文を読んでみましょう。
第78条の2 ① 第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。=標準報酬が多い方・分割する方)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。=標準報酬が少ない方・分割を受ける方)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (1) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。)について合意しているとき。 (2) 家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ② 標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 ③ 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
第78条の3 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「 按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して、標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。

【解答】
①【H21年出題】 〇
合意分割制度は、平成19年4月1日に施行されました。平成19年4月1日以後に離婚等をしたことが条件ですが、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も分割の対象です。
②【H29年選択式】
厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日< A >を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。
また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、< B >の範囲内でそれぞれ定められなければならない。
(選択肢)
① 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
② 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
④ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
⑤ から起算して6か月 ⑥ から起算して3か月
⑦ の翌日から起算して6か月 ⑧ の翌日から起算して3か月

【解答】
②【H29年選択式】
<A> ⑦ の翌日から起算して6か月
<B> ③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
(法第78条の3第1項)
按分割合とは?
「第1号改定者・第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額」に対する「第2号改定者」の持分です。
按分割合の上限は50%です。
<分割前>
第1号改定者(80%) | 第2号改定者(20%) |
按分割合は、20%を超え50%以下の範囲内で定めなければなりません。
按分割合を「50%」にした場合
↓
<分割後>
第1号改定者(50%) | 第2号改定者(50%) |
③【R2年選択式】
厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき< A >について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから< B >を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
(選択肢)
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 6か月
⑤ 按分割合 ⑥ 改定額 ⑦ 改定請求額 ⑧ 改定割合

【解答】
③【R2年選択式】
<A> ⑤ 按分割合
<B> ② 2年
④【H29年出題】
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求は、離婚等をしたときから「2年」を経過したときは、行うことができません。
(第78条の2、第78条の4)
⑤【H27年出題】
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができるのは、「家庭裁判所」です。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(第78条の2第2項)
⑥【H29年出題】
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

【解答】
⑥【H29年出題】 〇
「1か月以内」がポイントです。
(第78条の2、令3条の12の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「被保険者期間」
R7-260 05.15
厚生年金保険「被保険者期間の計算」
「被保険者期間」の計算ルールをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第19条 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 ④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 ⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。 |
ポイント!
<同月得喪(資格を取得した月にその資格を喪失した)の場合>
★(原則)被保険者期間は「1か月」で計算します。
★その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
例えば、5月1日にA社で資格を取得し同月15日に退職。同月16日にB社で資格を取得した場合
↓
B社の資格のみで、被保険者期間を1か月と計算します。
★その月に更に国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く。)の資格を取得したとき
例えば、5月1日にC社で資格を取得し同月15日に退職。その後国民年金第1号被保険者になった場合
↓
厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。5月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付します。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

①【H21年出題】 ×
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間は「被保険者であった期間」です。
②【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
②【R5年出題】 〇
被保険者期間は、「月」単位で計算します。
③【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
③【H30年出題】 〇
被保険者期間には、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。
平成30年3月30日に資格喪失した場合、資格を喪失した月である平成30年3月は被保険者期間に算入されません。
④【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
ただし、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
問題文の場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。
⑤【R6年出題】
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
令和6年5月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されません。
令和6年5月は、国民年金第1号被保険者として保険料を納付しなければなりません。
⑥【H20年出題】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。

【解答】
⑥【H20年出題】 〇
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった場合(=平成20年6月1日に資格喪失)、被保険者期間に算入されるのは、4月(資格を取得した月)と5月(資格を喪失した月の前月)です。
⑦【R3年出題】
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
⑦【R3年出題】 〇
・同一の月において被保険者の種別に変更があったとき
→その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす
・同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき
→最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「老齢厚生年金」
R7-259 05.14
老齢厚生年金「退職時改定」
働きながら(働く=厚生年金保険の被保険者という意味です。厚生年金保険料を負担していることです)受給する老齢厚生年金は、在職老齢年金といわれます。
厚生年金保険の被保険者でかつ老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の資格を喪失すると、負担した保険料を年金額に反映させるため、年金額の再計算が行われます。
このことを退職時改定といいます。
退職時改定について、条文を読んでみましょう。
第43条第3項 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 なお、第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 第14条第2号~第4号 (2) その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。(退職したとき) (3) 任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があつたとき。 (4) 適用除外に該当するに至ったとき。 |
(例)5月31日に退職した場合(6月1日資格喪失)
「退職した日」から起算して1月を経過した日の属する月=6月から年金額が改定されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】※改正による修正あり
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
<問題文のチェックポイント>
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
②【R5年出題】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

【解答】
②【R5年出題】 ×
老齢厚生年金の額の計算の基礎とされるのは、その被保険者の資格を喪失した月「以前」ではなく「前」における被保険者であった期間です。
被保険者期間は、「資格を喪失した月の前月」までで、資格を喪失した月は保険料が徴収されないからです。
また、年金の額が改定されるのは、「資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から」ですが、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき等は、その日から起算して1か月を経過した日の属する月から」です。
③【H28年出題】
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【解答】
③【H28年出題】 ×
年金の額が改定されるのは、「資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から」ですが、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき等は、その日から起算して1か月を経過した日の属する月から」です。
問題文は、1月31日付けで退職していますので、「1月31日」から起算して1か月を経過した日の属する月(=2月)から改定されます。
④【R2年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

【解答】
④【R2年出題】 ×
昭和25年7月1日生まれの者が70歳に到達するのは、「令和2年6月30日」で、その日に資格を喪失します。
年金額は、令和2年6月30日(資格を喪失した日)から起算して1か月を経過した日の属する月から改定されます。令和2年8月分ではなく「令和2年7月」から年金の額が改定されます。
⑤【H30年出題】
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
老齢厚生年金は65歳に達する前に、繰上げて受給することができます。
繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者で、繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、老齢厚生年金の額が再計算されます。
具体的には、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算に算入し、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額が改定されます。
(法附則第7条の3第5項)
⑥【H28年出題】
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
障害厚生年金には、退職時改定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害厚生年金」
R7-258 05.13
障害基礎年金との併合に基づく障害厚生年金の額の改定
1級又は2級の障害厚生年金の受給権者に、新たに障害基礎年金の受給権が発生した場合についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
図でイメージしましょう
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この場合において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。

【解答】
①【R5年出題】 〇
併合によって1級の障害基礎年金の受給権が発生した場合は、それに合わせて、障害厚生年金の額も1級に改定されます。
②【H27年出題】
障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。

【解答】
②【H27年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第52条の2第2項 障害厚生年金の受給権者(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項(その他障害による額の改定)及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
図でイメージしましょう。
・ 障害等級2級の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になった
↓
・第1号被保険者期間中に初診日がある傷病によって障害基礎年金とその他障害との併合が行われた
↓
・併合により障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された
↓
それに合わせて、障害厚生年金も障害等級1級の額に改定される
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
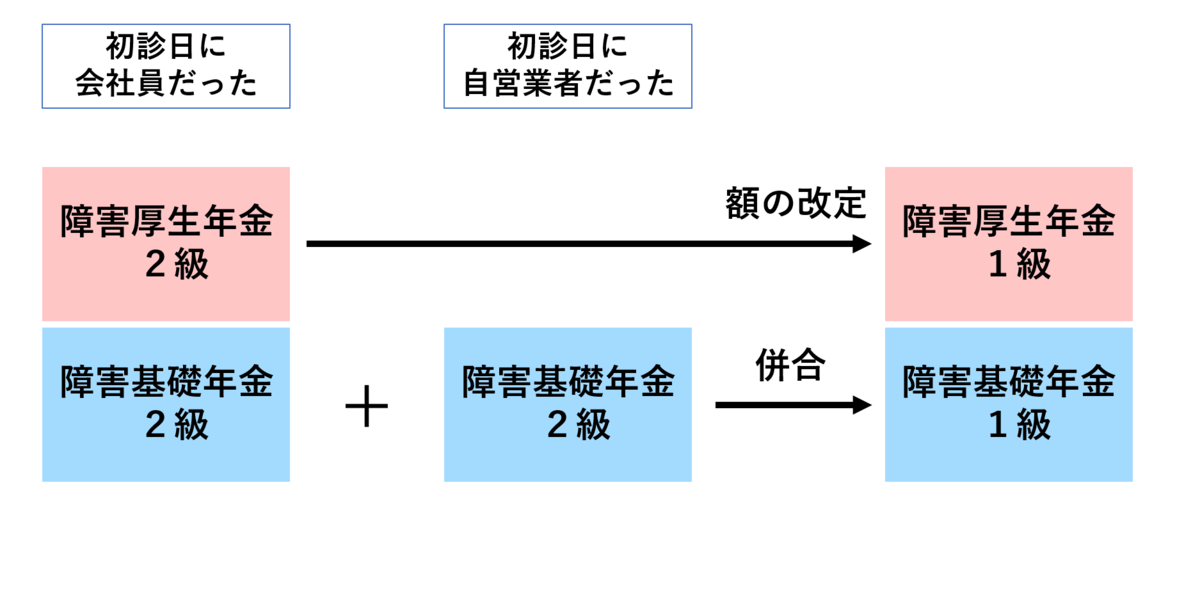
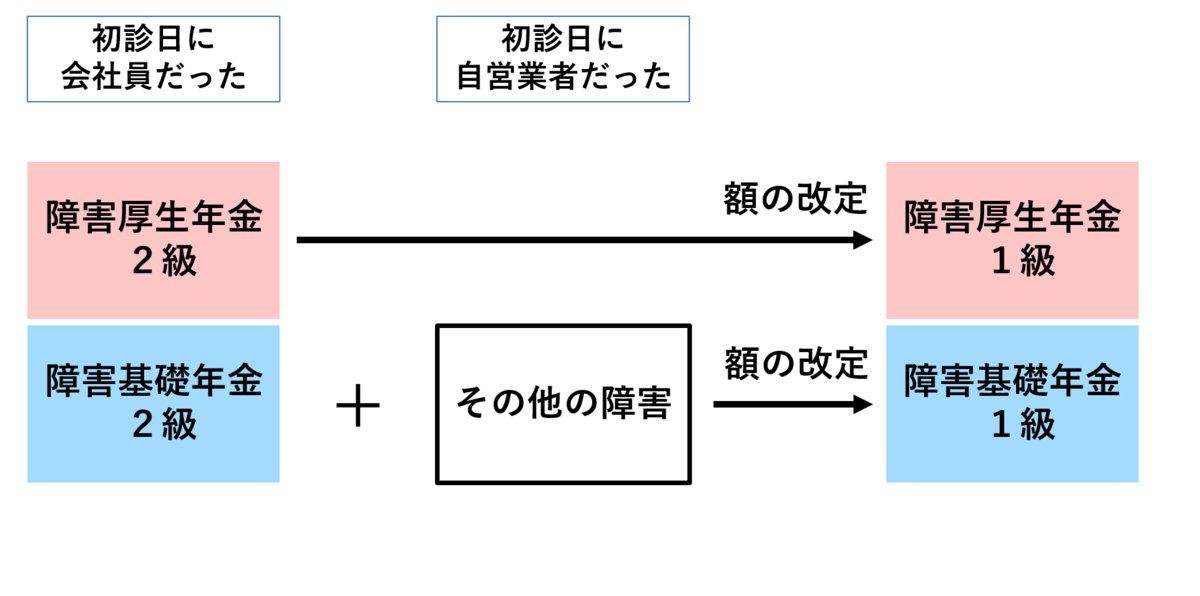
<比較>遺族基礎年金と遺族厚生年金
R7-257 05.12
【国年と厚年を比較】遺族年金の子の支給停止の違いをお話しします
遺族基礎年金と遺族厚生年金の「子」の支給停止の扱いについてお話しします。
<共通事項>
・配偶者が遺族基礎(厚生)年金の受給権を有する場合、子の年金はどうなる?
<例外>
・配偶者の年金が申し出により支給停止になった場合
・生計を同じくするその子の父・母がある場合
<応用>
・配偶者に遺族基礎年金の受給権がない場合
などお話しします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「資格の得喪の確認」
R7-223 04.08
<厚年>資格の取得・喪失は厚生労働大臣の確認で効力を生ずる
「確認」についてみていきます
★被保険者がいつ入社したのか(いつ資格取得したのか)、いつ退職したのか(いつ資格喪失したのか)を厚生労働大臣が確認します。
例えば、4月8日に社員Aが入社した場合、会社は、「資格取得届」を提出します。
↓
厚生労働大臣が、「4月8日にAが資格を取得した」と確認します。
↓
厚生労働大臣の確認によって、資格取得の効力が発生します。
・Aについて、4月分から厚生年金保険料の納付義務が発生します
・保険事故が起きた場合、年金などを受ける権利が発生します
(厚生年金保険の被保険者としての権利と義務が生まれます。)
条文を読んでみましょう。
第18条 (資格の得喪の確認) ① 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。 <確認が要らないもの> ・任意単独被保険者の資格の取得と厚生労働大臣の認可による喪失 ・高齢任意加入被保険者の資格の取得と喪失 ※適用事業所の高齢任意加入被保険者→退職・適用除外で喪失の場合は確認が必要 ※適用事業所以外の高齢任意加入被保険者→任意単独被保険者と同じ ・任意適用事業所が適用事業所でなくなったことによる資格喪失 ② 確認の方法 ・事業主による資格取得、喪失の届出 ・第31条第1項の規定による確認の請求 ・職権 ③ 確認については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。 ④ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、確認の規定は、適用しない。
第31条 (確認の請求) ① 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 ② 厚生労働大臣は、請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
確認の方法は次の3つです。
・事業主による届出
・被保険者若しくは被保険者であった者からの請求
・職権
②【R4年出題】
適用事業所に使用されている第1号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。

【解答】
②【R4年出題】 〇
被保険者(在職中)又は被保険者であった者(退職後)は、いつでも、確認を請求することができます。
③【H29年出題】
任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
任意適用事業所の適用取消しには厚生労働大臣の認可が必要で、認可があった場合全員が資格を喪失します。そのため、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認は要りません。
④【H29年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者が、「厚生労働大臣の認可」によって被保険者資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の確認は要りません。
⑤【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申出が受理された日に資格を取得しますので、厚生労働大臣の確認は不要です。
⑥【H16年出題】※改正による修正あり
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得については厚生労働大臣の確認を要しない。また、資格喪失の理由が、被保険者が事業所に使用されなくなったときや被保険者が使用される任意適用事業所の事業主が厚生労働大臣の適用取消しの認可を受けたときも確認を要しない。

【解答】
⑥【H16年出題】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の理由が、「被保険者が事業所に使用されなくなったとき」の場合は、厚生労働大臣の確認が必要です。
(令第6条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害基礎年金と障害厚生年金
R7-212 03.28
障害基礎年金と障害厚生年金の額の計算
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級、2級、3級があります。
国民年金法の条文を読んでみましょう。
国民年金法第33条 ① 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 |
(障害基礎年金の額)
1級 → 2級の額×100分の125
2級 → 78万900円×改定率
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第50条 ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 ③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
第50条③について
・障害基礎年金が支給されない障害厚生年金には最低保障額が設けられています。
最低保障額は、障害基礎年金の額(2級)×4分の3です。
※最低保障額が適用されるのは
・障害等級3級の場合(障害基礎年金が支給されないので)
・老齢年金の受給権を有する65歳以上の者が、厚生年金保険加入中に障害になった場合
(老齢年金の受給権を有する65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者にならないので、1・2級でも障害基礎年金が支給されないからです。)
では、過去問をどうぞ!
<国民年金法>
①【国年R3年出題】
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円に端数処理を行った、976,100円となる。
(注)令和3年度の給付額です。

【解答】
①【国年R3年出題】 ×
・ 障害等級2級の額は、780,900円×改定率で、端数処理は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げます。
・ 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の障害基礎年金×1.25となりますが、端数処理は、原則の方法となり50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
そのため、1級の額は780,900円×1.25=976,125円となります。(ちなみに令和3年度は1円未満の端数が出ませんでした)
<厚生年金保険法>
①【厚年R4年出題】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

【解答】
①【厚年R4年出題】 ×
2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金と同じように計算します。
・被保険者期間は、障害認定日の属する月の「前月」ではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間を基礎とします。
例えば、令和7年3月1日が障害認定日だとすると、計算に入るのは令和7年3月までの被保険者期間です。
・計算の基礎となる月数が300に満たないときは、300で計算します。
②【厚年R1年出題】
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

【解答】
②【厚年R1年出題】 〇
障害等級1級の場合は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(被保険者期間の月数が300未満のときは、300とする。)の100分の125です。
③【厚年R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】
③【厚年R2年出題】 ×
最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の「4分の3」に相当する額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「養育期間の標準報酬月額の特例」
R7-196 03.12
3歳未満の子の養育期間の従前標準報酬月額
3歳未満の子を養育している期間中に標準報酬月額が低下したとしても、将来の年金額は、子を養育する前の標準報酬月額(従前標準報酬月額)に基づいて計算される特例をみていきます。
特例が適用されるには、被保険者からの申出が必要です。
条文を読んでみましょう。
第26条第1項、第4項(3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例) ① 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。 (1) 当該子が3歳に達したとき。 (2)第14条各号のいずれかに該当するに至つたとき。 (3)当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。 (4)当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。 (5)当該被保険者に係る第81条の2第1項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。 (6)当該被保険者に係る第81条の2の2第1項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。 ④ 第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者について、①の規定を適用する場合においては、「申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。 |
★従前標準報酬月額のイメージ
→ 将来の年金額は、「従前標準報酬月額」を用いて計算されます。
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
3歳未満の子の養育期間 | ||||
従前標準報酬月額 |
|
|
|
|
ポイント!
「従前標準報酬月額」とは
・養育開始月の前月の標準報酬月額のことです。
・養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合は、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前標準報酬月額となります。
「対象となる期間」は
→ 3歳未満の子の養育を開始した月から養育する子が3歳に達したとき等に該当するに至った日の翌日の属する月の前月までです。
過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに < A >までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前< B >における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
<選択肢>
① 1年以内 ② 1年6か月以内 ③ 2年以内 ④ 6か月以内
⑤ 至った日の属する月 ⑥ 至った日の属する月の前月
⑦ 至った日の翌日の属する月 ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月

【解答】
①【H30年選択式】
<A> ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
<B> ① 1年以内
②【R3年出題】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

【解答】
②【R3年出題】 ×
「標準報酬月額」の特例が適用されるのは、特例の申出が行われた日の属する月前の月については、特例の申出が行われた日の属する月の前月までの「2年間」のうちにあるものに限られています。
★ 特例がさかのぼって適用されるのは、申出が行われた日の属する月の前月までの「2年間」です。
③【R5年出題】
本特例についての実施機関に対する申出は、第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者はその使用される事務所の事業主を経由して行い、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者は事業主を経由せずに行う。
※本特例→「厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」のことです。以下同じです。

【解答】
③【R5年出題】 〇
★本特例についての実施機関に対する申出について
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者
→その使用される事務所の事業主を経由して行います
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者
→事業主を経由せず直接行います
④【R5年出題】
本特例が適用される場合には、老齢厚生年金の額の計算のみならず、保険料額の計算に当たっても、実際の標準報酬月額ではなく、従前標準報酬月額が用いられる。

【解答】
④【R5年出題】 ×
保険料額の計算は、従前標準報酬月額ではなく、実際の標準報酬月額を用います。
⑤【R5年出題】
甲は、第1号厚生年金被保険者であったが、令和4年5月1日に被保険者資格を喪失した。その後、令和5年6月15日に3歳に満たない子の養育を開始した。さらに、令和5年7月1日に再び第1号厚生年金被保険者の被保険者資格を取得した。この場合、本特例は適用される。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
本特例は適用されません。
「従前標準報酬月額」は子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額です。
問題文の甲は、養育を開始した日の属する月の前月(=令和5年5月)は被保険者ではありません。
養育を開始した日の属する月の前月に被保険者でない場合は、「当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月」の標準報酬月額が従前標準報酬月額となります。
しかし「甲」は、「当該月(=令和5年5月)前1年以内に被保険者であった月がありません。
そのため、甲には本特例は適用されません。
⑥【H30年出題】
被保険者の配偶者が出産した場合であっても、所定の要件を満たす被保険者は、厚生年金保険法第26条に規定する3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出をすることができる。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
被保険者の配偶者が出産した場合でも、特例の申出をすることができます。
⑦【H27年出題】
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

【解答】
⑦【H27年出題】 ×
従前標準報酬月額は、子を養育することとなった日の属する月の前月(=問題文の場合は8月)の標準報酬月額です。
定時決定で改定された標準報酬月額240,000円は9月から適用されます。そのため、従前標準報酬月額は、8月の標準報酬月額の280,000円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「加給年金額」
R7-194 03.10
老齢厚生年金に加算される加給年金額についてお話しします
老齢厚生年金の受給権者に、生計を維持する「配偶者・子」がいる場合は、加給年金額が加算されます。
(今日の内容です)
・加給年金額の加算対象になる「配偶者・子」の要件
・加給年金の額と特別加算
・加給年金額が減額されるとき
・配偶者に係る加給年金額が支給停止されるとき
・子に係る加給年金額が支給停止されるとき
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「長期加入者の特例」
R7-184 02.28
厚生年金保険の被保険者期間44年以上の場合の特例
長期加入者の特例は、60歳台前半の老齢厚生年金が、「報酬比例部分」のみになる場合が対象です。
要件を満たした場合、定額部分・加給年金額が加算されます。
例えば、昭和28年4月2日生まれの男子が長期要件に該当した場合
61歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
定額部分(特例) | 老齢基礎年金 |
★長期加入者の特例が適用される要件を確認しましょう。(法附則第9条の3)
・厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けていること
・厚生年金保険の被保険者でないこと(退職していること)
・請求手続きは不要
・加給年金額の対象者がいる場合は、加給年金額も加算される
過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
(1) 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項各号に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
(2) 被保険者期間が< A >以上であるとき
(3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が< B >以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 < C >であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、< D >である。
(選択肢)
A | ① 42年 ②43年 ③44年 ④45年 |
B | ① 10年 ②15年 ③20年 ④25年 |
C | ① (1)及び(2) ② (1)、(2)及び(3) ③ (2)のみ ④ (2)及び(3) |
D | ① (1)のみ ② (1)及び(2) ③ (1)及び(3) ④ (1)、(2)及び(3) |

【解答】
①【H27年選択式】
<A> ③ 44年
<B> ② 15年
<C> ① (1)及び(2)
<D> ① (1)のみ
ポイント!
・ 報酬比例部分に定額部分が加算される特例には、(1)「障害者の特例」、(2)「長期加入者の特例」、(3)「坑内員・船員の特例」の3つのパターンがあります。
・ 「被保険者でない」という要件があるものは、(1)「障害者の特例」と(2)「長期加入者の特例」です。
・ 受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)なものは、(1)「障害者の特例」のみです。
②【R6年出題】
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
長期加入者の特例が適用される条件は、「厚生年金保険の被保険者でないこと」です。問題文は、「第1号厚生年金被保険者として在職中である」となっていますので、老齢厚生年金の額の計算に係る特例は適用されません。
③【R3年出題】
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外の被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

【解答】
③【R3年出題】 ×
44年の計算については、2以上の種別の被保険者であった期間は、合算されません。
問題文の第1号厚生年金被保険者としての4年と第2号厚生年金被保険者としての40年は合算できませんので、定額部分は加算されません。
(法附則第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険「老齢厚生年金」
R7-180 02.24
老齢厚生年金の計算についてお話しします
老齢厚生年金は、「老齢基礎年金」に上乗せされる年金です。
65歳以上で、老齢基礎年金の受給要件を満たしていて、かつ、1か月でも厚生年金保険の被保険者期間があれば、支給されます。
<今日のお話の内容です>
・総報酬制導入前、導入後の計算の違い
・在職定時改定について
・退職時改定について
よく出るポイントを中心にお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<厚生年金保険法>遺族厚生年金
R7-175 02.19
「配偶者・子」に対する遺族厚生年金の調整
遺族厚生年金の「配偶者と子」に対する支給停止事由をみていきましょう。
遺族厚生年金の遺族の順位は、「配偶者及び子」→「父母」→「孫」→「祖父母」の順です。
「配偶者と子」は同じ順位で、配偶者と子で調整されます。
原則は「配偶者」が優先しますが、例外もおさえましょう。
条文を読んでみましょう。
第66条 ① 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文(60歳未満の夫に対する支給停止、次項本文(次の②)又は次条(所在不明による支給停止)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 ② 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定(所在不明による支給停止)によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
第67条 ① 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② 配偶者又は子は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、「配偶者」が優先しますので、子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。
なお、問題文のように、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。子に対する遺族厚生年金は引き続き支給が停止されます。
「国民年金法の遺族基礎年金」との違いに注意してください。
こちらの記事と比較してください。
↓
http://www.syarogo-itonao.jp/17397987862029
「子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう」
②【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【解答】
②【R3年出題】 ×
「妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。」が誤りです。子の遺族厚生年金の支給停止は解除されず、引き続き支給停止されます。
妻が「障害基礎年金と障害厚生年金」を選択し、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」が全額支給停止となった場合でも、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金については、引き続き支給停止となります。
③【R5年出題】
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

【解答】
③【R5年出題】 〇
★ 「遺族厚生年金」については、母と同居することになったとしても、子に対する遺族厚生年金は支給停止となりません。
★ 「子に対する遺族基礎年金」は「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」は、その間、その支給が停止されます。
違いに注意しましょう。
④【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
※本問において遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。

【解答】
④【H26年出題】 〇
配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合で、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が遺族基礎年金の受給権を有するときは、配偶者の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。
下の図でイメージしましょう。
⑤【R4年選択式】
厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は、妻であるY(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが、事実上の親子関係にあった。また、Xは、Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子であるW(15歳)にも養育費を支払っていた。V及びWは、Xとは別の都道府県に在住している。この状況で、Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは、< A >である。なお、遺族厚生年金に係る保険料納付要件及び生計維持要件は満たされているものとする。
(選択肢)
① V ② W ③ Y ④ Z

【解答】
⑤【R4年選択式】
<A> ② W
それぞれに発生する年金の受給権を確認しましょう。
・Xの妻Y
→ 遺族厚生年金の受給権のみ発生
※Xの子と生計を同じくしていないため、Yには遺族基礎年金の受給権は発生しません。
・Yの先夫との子であるZ(XとZは養子縁組をしていない)
→ 遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。
「子」は死亡した者の実子か養子であることが条件です。Zは死亡したXと養子縁組をしていないので「子」になりません。
・Xの先妻であるV
→ Xの妻ではありませんので、遺族基礎年金の受給権も遺族厚生年金の受給権も発生しません。
・XとVとの子W
→ Xの子で、かつXによって生計を維持されていた(養育費の支払い)ので、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給権が発生します。
★「Xの妻Y」と「XとVとの子W」に遺族厚生年金の受給権が発生しますが、「Xの妻Y」には遺族基礎年金の受給権がありません。
「配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子が遺族基礎年金の受給権を有する」状態ですので、妻の遺族厚生年金は、その間、支給停止されます。
遺族厚生年金が最初に支給されるのは、「XとVとの子W」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
R7-159 02.03
遺族基礎年金と遺族厚生年金を比較しましょう
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を比較しましょう!
・死亡した人の要件
・遺族の範囲 を
比較してみましょう。
<今日の内容>
・ 遺族基礎年金の支給要件
・ 遺族厚生年金の支給要件
・ 遺族基礎年金の遺族の範囲
・ 遺族厚生年金の遺族の範囲
・ 遺族基礎年金の過去問
・ 遺族厚生年金の過去問
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「障害厚生年金」
R7-156 01.31
障害厚生年金に加算される加給年金額
1級、2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第50条の2 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、22万4700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを 100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
ポイント!
・3級の障害厚生年金には、加給年金額は加算されません。
・「65歳未満の配偶者」が対象です。「子」については、国民年金法の「障害基礎年金」に加算が行われます。
・加給年金額は、22万4700円×改定率で計算します。老齢厚生年金と異なり、「特別加算」はありません。
・「受給権を取得した当時」だけでなく、「権利を取得した日の翌日以後」に
配偶者を有するに至った場合でも加給年金額の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも加給年金額が加算されます。加給年金額は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加算されます。
②【H29年出題】
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

【解答】
②【H29年出題】 ×
子は、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。子は国民年金法の障害基礎年金の加算の対象となります。
③【R4年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者加給年金額には、受給権者の生年月日に応じた特別加算は行われません。
④【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。

【解答】
④【R1年出題】 〇
障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額は、以下に該当した場合は、加算が終了します。
(1) 死亡したとき。
(2) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
(3) 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
(4) 配偶者が、65歳に達したとき。
加給年金額の対象になるのは65歳未満の配偶者ですので、「配偶者が65歳に達したとき」は加算されなくなります。
また、加給年金額が加算されなくなり年金額が改定されるのは、「該当するに至った月の翌月」からとなります。
ちなみに、配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も加給年金額の対象となります。
(法第44条第4項、法第50条の2第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険
R7-153 01.27
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用についてお話しします
「1週間の所定労働時間」又は「1月間の所定労働日数」が 通常の労働者の4分の3未満でも 健康保険・厚生年金保険に加入することになる短時間労働者の条件についてお話ししています。
★基本の条件をおさえましょう。
①「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に使用されている
または
「国・地方公共団体に属する事業所」に使用されている
②次の要件をすべて満たしている
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円以上
・学生でない
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「遺族厚生年金」
R7-146 01.20
【社労士受験】遺族厚生年金の額の計算についてお話しします
遺族厚生年金の額の計算のポイントをお話ししています。
★「短期要件」と「長期要件」それぞれの要件をおさえましょう
★遺族厚生年金の計算の注意点
「短期要件」→被保険者期間に300月の最低保障があります
「長期要件」→生年月日によって給付乗率の引上げがあります
★遺族が「65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある配偶者」の場合の計算式をおさえましょう
★65歳以上で、「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の受給権がある場合は、「老齢厚生年金」が優先します
図でイメージしながらポイントをつかみましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法「年金の支払調整」
R7-144 01.18
厚生年金保険法の内払調整について
例えば、「遺族厚生年金」の受給権者が「障害厚生年金」の受給権を取得し、「障害厚生年金」の支給を受けることを選択した場合、「遺族厚生年金」の支給は停止されます。
にもかかわらず、届出が遅れたことなどによって、引き続き「遺族厚生年金」が支払われる場合があります。
その場合、遺族厚生年金を返還させ、改めて障害厚生年金を支給するのは、利便性に欠けますので、調整を簡単にするため、遺族厚生年金と障害厚生年金について「内払調整」を行います。
なお「内払」は「同一人」の年金の間の調整です。
「内払」について、図でイメージしましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第39条 (年金の支払の調整) ① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 ② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 ③ 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 |
■内払調整
①について
・乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅したにもかかわらず、翌月以後、乙年金の支払が行われた
・同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合に、翌月以後、乙年金の支払が行われた
②について
・年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われた
・年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、翌月以後も減額しない額の年金が支払われた
③について(国民年金と厚生年金保険の調整)
・同一人に対して国民年金法の年金の支給を停止して、厚生年金保険の年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合に、翌月以後の分として国民年金の年金の支払が行われた
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】 ※問題文の者は、「第1号厚生年金被保険者期間」のみを有するものとします。(改正による修正)
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が、新たに障害等級1級又は2級に該当する障害を受け、厚生年金保険法第48条第1項の規定に基づいて、前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得した場合、従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の内払とみなす。

【解答】
①【H25年出題】 〇
従前の障害厚生年金の受給権が消滅した月の翌月以後の分として、従前の障害厚生年金の支払が行われたときは、「従前の障害厚生年金の返還を求める」のではなく、その支払われた従前の障害厚生年金は、新たな障害厚生年金の「内払とみなす」となります。
②【H25年出題】※問題文の者は、「第1号厚生年金被保険者期間」のみを有するものとします。(改正による修正)
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。

【解答】
②【H25年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合、遺族厚生年金の支給が停止されますが、にもかかわらず、翌月以後も遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の「内払とみなす」となります。
③【R6年出題】
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

【解答】
③【R6年出題】 〇
同一人に対する「国民年金法による年金たる給付」と「年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)」との間の内払調整の規定です。
④【H25年出題】(※改正による修正あり)
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。

【解答】
④【H25年出題】 〇
③の問題と同じです。
※国民年金法の寡婦年金と60歳台前半の老齢厚生年金は、どちらか選択です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法・厚生年金保険法の違い
R7-135 01.09
国民年金法・厚生年金保険法の目的の異なる点
国民年金法と厚生年金保険法の違いを条文で確認しましょう。
国民年金法の第1条と第2条です。
第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 |
(参考)
日本国憲法第25条
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づいています。
厚生年金保険法第1条です。
第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
過去問をどうぞ!
①【国年H28年選択式】
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】
<A> 安定
<B> 共同連帯
②【国年R5年選択式】
国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して< A >を行うものとする。」と規定されている。
<選択肢>
① 年金支給
② 年金の給付
③ 必要な給付
④ 保険給付

【解答】
<A> ③ 必要な給付
③【国年H26年出題】
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

【解答】
③【国年H26年出題】 ×
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して「必要な保険給付」ではなく、「必要な給付」を行うものとされています。
「保険原理」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる仕組みのことですが、国民年金法の給付には、保険原理によらないものもあります。例えば、20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料の負担なく給付されるものです。
国民年金法に基づくすべての給付が保険原理により行われるものではないので、国民年金法では「保険給付」ではなく、「必要な給付」という用語を使います。
なお、厚生年金保険法では「保険給付」という用語を使います。
ちなみに法律の名称も「国民年金法」には「保険」が入っていません。「厚生年金保険法」は「保険」が入っています。
④【厚年H30年出題】
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

【解答】
④【厚年H30年出題】 ×
問題文は国民年金制度の目的条文です。国民年金はすべての国民が対象ですので、「国民」という言葉が使われています。
厚生年金保険制度は「労働者」が対象ですので、「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的」としています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法・厚生年金保険法について
R7-134 01.08
国民年金法・厚生年金保険法で最低限おさえたい歴史
国民年金法、厚生年金保険法の歴史で重要な年号をまとめました。
昭和14年 | 船員保険法制定 | ・社会保険方式による日本で最初の公的年金 ・昭和15年施行 |
昭和16年 | 労働者年金保険法制定 | ・昭和17年施行 ・昭和19年に「厚生年金保険法」に改称 |
昭和34年 | 国民年金法制定 | ・昭和34年11月福祉年金(無拠出制)開始 |
昭和36年 4月 | 国民皆年金の実施 | ・国民年金(拠出制)開始 |
昭和61年 4月 | 基礎年金の導入 | ・「基礎年金」と「報酬比例」の2階建て ・基礎年金は全国民が対象 第1号被保険者(自営業等) 第2号被保険者(会社員、公務員等) 第3号被保険者(専業主婦等) |
平成27年 10月 | 被用者年金一元化 | ・被用者の年金制度が厚生年金に統一された |
年金の歴史を図でイメージしましょう。(下の図を参照してください)
ポイント!
・昭和36年4月「国民皆年金」
・昭和61年4月「基礎年金の導入」
★昭和61年4月前の制度を「旧法」、昭和61年4月以降の制度を「新法」といいます。
過去問をどうぞ!
①【H19年出題(社一)】
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。

【解答】
①【H19年出題(社一)】 〇
国民年金法は昭和34年に制定、昭和36年4月から全面施行され、国民皆年金が実現しました。
②【H19年出題(国年)】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
②【H19年出題(国年)】 ×
国民年金法は昭和34年に制定され、同年10月ではなく「同年11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始されました。また、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立しました。
③【H15年選択式(国年)】
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
<選択肢>
① 大正15年4月1日
② 大正15年4月2日
③ 昭和2年4月1日
④ 昭和2年4月2日
⑤ 裁定日
⑥ 初診日
⑦ 障害認定日
⑧ 裁定請求日

【解答】
<A> ② 大正15年4月2日
<B> ⑦ 障害認定日
ポイント!
・ 「大正15年4月2日」以降生まれの人は、老齢基礎年金(新法の年金)の対象となります。ただし、施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった人を除きます。
・ 「障害認定日」が昭和61年4月1日以降の人は、障害基礎年金(新法の年金)の対象となります。
④【R6年出題(社一)】
日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。

【解答】
④【R6年出題(社一)】 〇
日本の公的年金制度は、「賦課方式」を基本とした仕組みで運営されていることがポイントです。
賦課方式とは、現役世代の保険料負担で、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みです。
(令和5年版厚生労働白書P256)
【R1年出題(社一)】※問題文修正あり
被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは、平成27年10月1日である。

【解答】
【R1年出題(社一)】 〇
被用者年金一元化が行われたのは、平成27年10月1日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
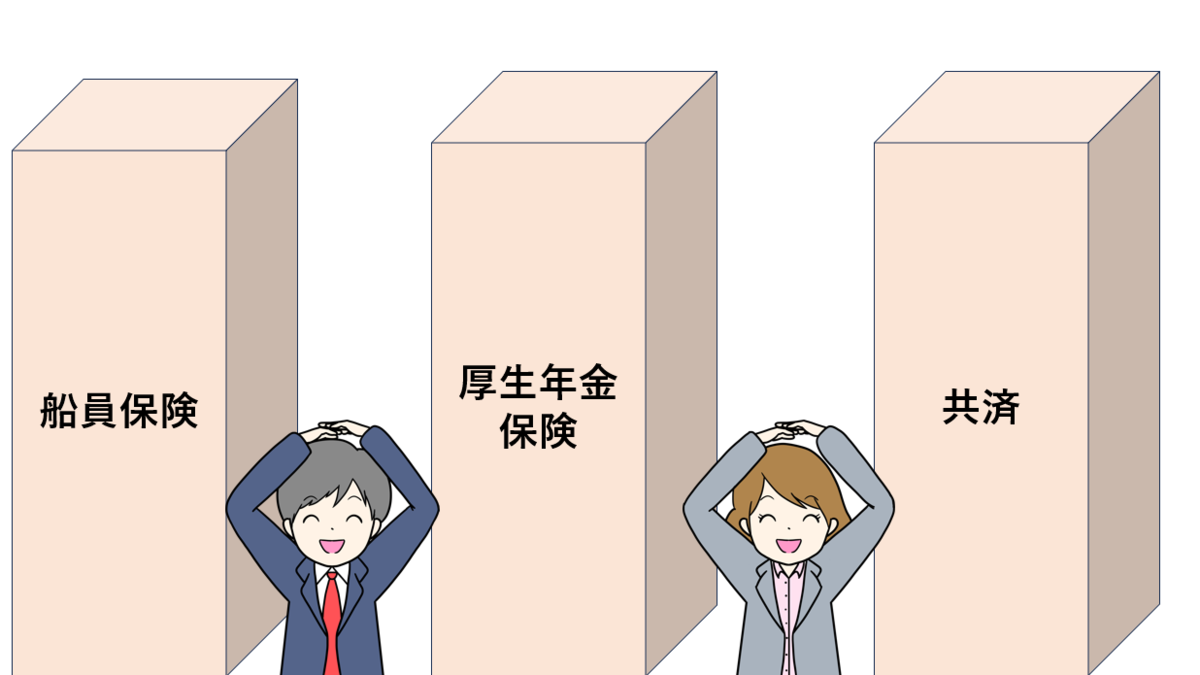
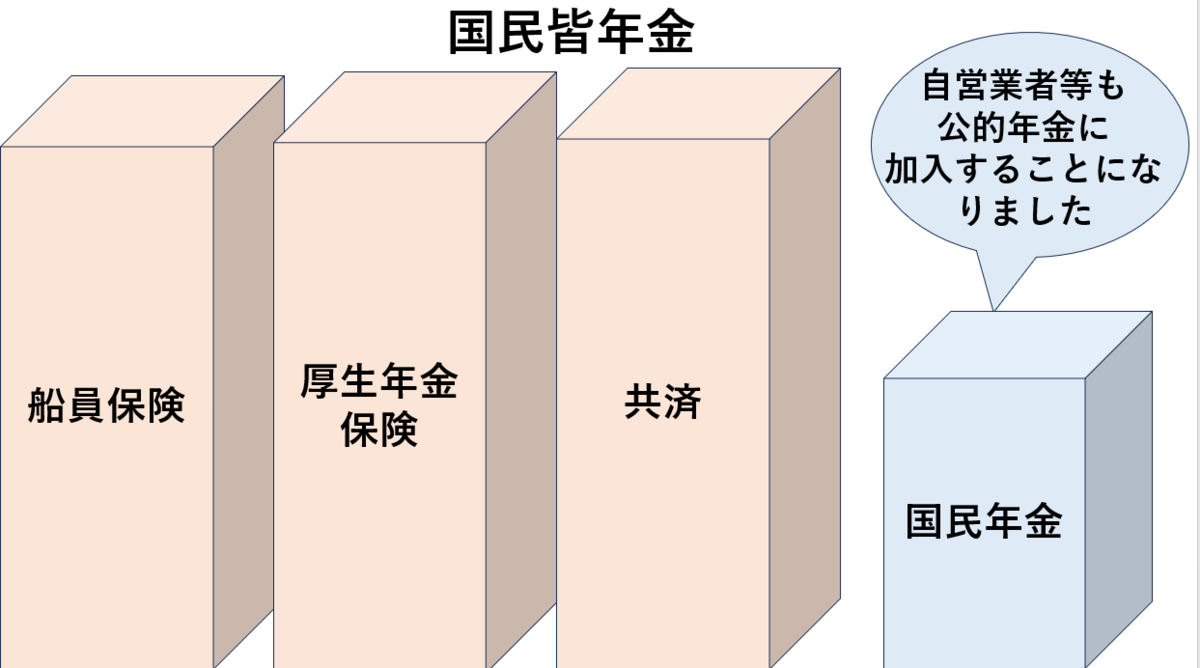
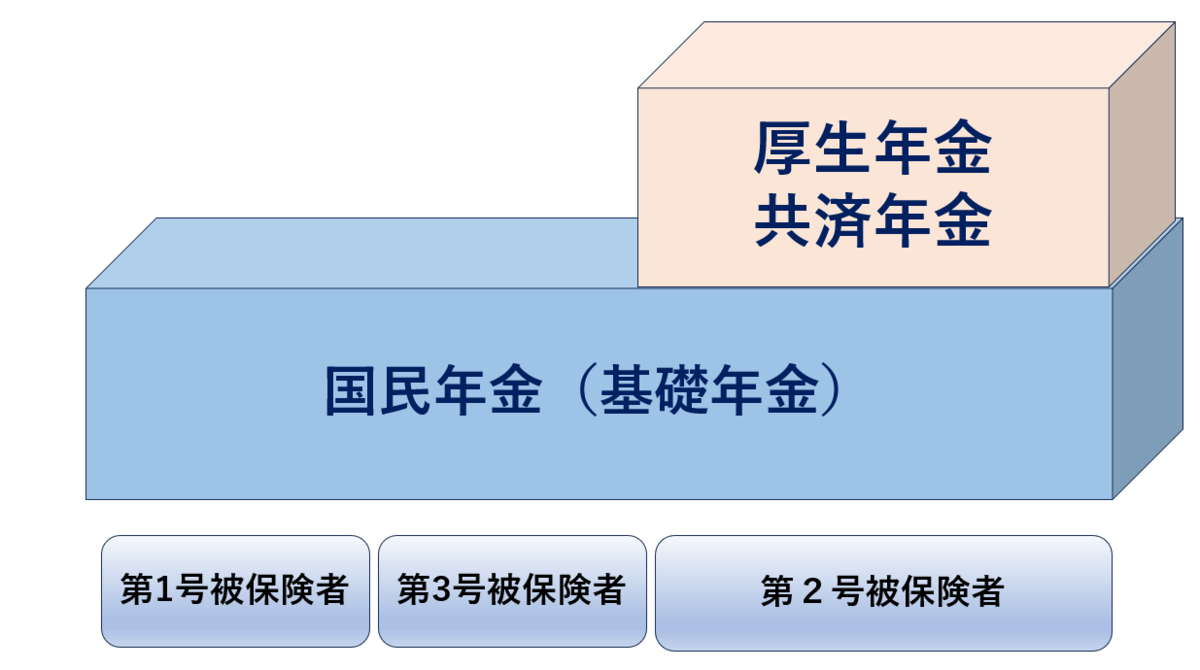
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-123 12.28
<令和6年の問題を振り返って>(厚生年金保険)資格を取得した際の標準報酬月額の決定
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
資格取得時の標準報酬月額の決定について条文を読んでみましょう。
法第22条 (被保険者の資格を取得した際の決定) ① 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 (1) 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額 (2) 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 (3) (1)、(2)によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 (4) 前3号の2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前3号の規定によって算定した額の合算額 ② 決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
(資格取得時の標準報酬月額の有効期間)
例えば、令和6年5月15日に資格を取得した場合
定時決定(7月1日現在)
△
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月~翌年8月 |
資格取得時の標月 | 資格取得時の標月 | 資格取得時の標月 | 資格取得時の標月 | 定時決定で定められた 標準報酬月額 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-B】
厚生年金保険法第22条によれば、実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。

【解答】
【R6年問7-B】 〇
月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合 → 月給制や週給制等です。
例えば、週給の場合、週給の額÷7日(その期間の総日数)×30が「報酬月額」となります。その報酬月額を標準報酬月額等級に当てはめて、その者の標準報酬月額が決定されます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

【解答】
【H30年出題】 〇
ポイントを確認しましょう。
・日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合 → 日給制や時給制など
資格を取得した月前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額=報酬月額となり、標準報酬月額が決まります。
・有効期間
資格取得時の標準報酬月額の有効期間は、資格を取得した月からその年の8月までです。9月以降は、その年の定時決定で定められた標準報酬月額となります。
ただし、6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した場合は、翌年の8月までです。
6月1日から7月1日までに資格を取得した者は、その年の定時決定を行わないからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-109 12.14
<令和6年の問題を振り返って>【厚生年金保険】未支給の保険給付
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第37条第1項、3項~5項 (未支給の保険給付) ① 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ③ 死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 ④ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。 ⑤ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
★ 年金は、後払い(例えば、12月に支給される年金は10月分と11月分です)で、受給権が消滅した月まで支給されます。
そのため、年金の受給権者が死亡した場合は、必ず未支給の年金が発生します。
★ 国民年金との違い
厚生年金保険法は「未支給の保険給付」
→ 「死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったもの」ですので、年金だけでなく一時金も対象です。
国民年金法は「未支給年金」
→ 「死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったもの」となりますので、「年金」だけが対象です。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問8-D】
未支給の保険給付の支給を請求できる遺族として、死亡した受給権者とその死亡の当時生計を同じくしていた妹と祖父がいる場合、祖父が先順位者になる。

【解答】
【R6年問8-D】 〇
未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序」とされています。妹と祖父がいる場合は、祖父が先順位者になります。
(令第3条の2)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。

【解答】
①【R4年出題】 〇
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表で請求します。
②【H23年出題】
保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。

【解答】
②【H23年出題】 ×
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給するのではなく、代表の者に全額支給されます。
③【H26年出題】
脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。

【解答】
③【H26年出題】 〇
脱退一時金も未支給の保険給付の請求の対象となります。
(法附則第29条第9項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-108 12.13
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級(健康保険との比較も)
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
法第20条第2項 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-A】
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高等級である第31級の上に第32級が追加された。第32級の標準報酬月額は65万円である。

【解答】
【R6年問7-A】 〇
令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、「第32級」です。第32級の標準報酬月額は65万円です。
「平成28年3月以降、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が、当時の最高等級(第31級:62万円)を超える状況が続き、令和2年3月末においても、全厚生年金被保険者の平均標報の2倍が62万円を超えていたことから、令和2年9月より、政令改正により標準報酬月額の上限を引き上げる(第32級(65万円)を加える)こととした。」とされています。
(厚生労働省ホームページより)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】※改正による修正あり
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第32級650,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、その年の4月1日からではなく、その年の9月1日からです。
②【R5年出題】
毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「毎年12月31日」ではなく「毎年3月31日」における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、「その年の9月1日から」、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の「改定を行わなければならない」ではなく、「改定を行うことができる。」です。
<比較>健康保険法の条文も読んでみましょう。
法第40条第2項、第3項 ② 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。 ③ 厚生労働大臣は、政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。 |
健康保険法の標準報酬月額の上限は、「第50等級1,390,000円」で、全被保険者に対する上限該当者の割合は、0.79%です。
(厚生労働省ホームページより)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-107 12.12
<令和6年の問題を振り返って>産前産後休業中の保険料免除
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第81条の2の2(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例) ① 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 ② 第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る保険料について、①の規定を適用する場合においては、「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-E】
産前産後休業をしている被保険者に係る保険料については、事業主負担分及び被保険者負担分の両方が免除される。

【解答】
【R6年問7-E】 〇
事業主負担分と被保険者負担分の両方が免除されます。
過去問をどうぞ!
①【R4年選択式】
厚生年金保険法第81条の2の2第1項の規定によると、産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、同法第81条第2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を< A >からその産前産後休業が< B >までの期間に係るものの徴収は行わないとされている。

【解答】
<A> 開始した日の属する月
<B> 終了する日の翌日が属する月の前月
②【H29年出題】
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

【解答】
②【H29年出題】 〇
産前産後休業期間中の保険料の免除の申出について
・第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者
→ 当該被保険者が使用される事業所の事業主が行う
・第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者
→ 被保険者本人が行う
③【H30年出題】
産前産後休業期間中の保険料の免除の適用を受ける場合、その期間中における報酬の支払いの有無は問われない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
産前産後休業期間中の報酬の支払いの有無は問われません。
④【R1年出題】
適用事業所の事業主は、第1号厚生年金被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
産前産後休業期間中や育児休業期間中の保険料の免除が適用されている者に対して、賞与を支給した場合でも、賞与額の届出は必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-106 12.11
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険の保険料の督促・滞納処分、延滞金
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
督促と延滞金を図でイメージしましょう。
納期限 ▼ |
| 督促状 ▼ |
| 督促状の指定期限 ▼ |
| 完納 ▼ | |
|
| 10日以上経過した日 |
|
| |||
納期限の翌日 |
|
|
|
|
| 完納又は財産差押えの日の前日 | |
条文を読んでみましょう。
法第86条 (保険料等の督促及び滞納処分) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、繰上徴収により保険料を徴収するときは、この限りでない。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 ④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 ⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。 (1) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 (2) 納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 ⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
法第87条 (延滞金) ① 督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 (1) 保険料額が1000円未満であるとき。 (2) 納期を繰り上げて徴収するとき。 (3) 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。 ② 保険料額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあった保険料額を控除した金額による。 ③ 延滞金を計算するにあたり、保険料額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 ⑤ 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
※延滞税特例基準割合(1.4%)に基づく令和6年中の延滞金の割合は以下の通りです。
・納期限の翌日から3月を経過する日までの期間 → 年2.4%
・納期限の翌日から3月を経過する日の翌日以後 → 年8.7%
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問2-B】
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われたときは、原則として延滞金が徴収されるが、納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
①【R6年問2-B】 〇
公示送達の方法によって督促したときは、延滞金は徴収されません。
②【R6年問2-C】
厚生年金保険の保険料を滞納した者に対して督促が行われた場合において、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が1,000円未満であるときは、延滞金は徴収しない。

【解答】
②【R6年問2-C】 ×
厚生年金保険法第87条第1項から第3項までの規定によって計算した額(=延滞金の金額)が1,000円未満ではなく「100円未満」であるときは、延滞金は徴収されません。
③【R6年問2-D】
保険料の納付の督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、自ら国税滞納処分の例によってこれを処分することができるほか、納付義務者の居住地等の市町村(特別区を含む。以下本肢において同じ。)に対して市町村税の例による処分を請求することもできる。後者の場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

【解答】
③【R6年問2-D】 ×
納付義務者の居住地等の市町村に対して市町村税の例による処分を請求した場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の5ではなく「100分の4」に相当する額を当該市町村に交付しなければなりません。
④【R6年問2-E】
滞納処分等を行う徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣が任命する。

【解答】
④【R6年問2-E】 ×
徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、日本年金機構の理事長が任命する、とされています。
(第100条の6第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-092 11.27
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険の脱退一時金
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
★脱退一時金は、「日本国籍を有しない者」が対象で、日本を出国した場合に請求できます。
なお、国民年金にも同じく脱退一時金の制度があります。
では、脱退一時金について条文を読んでみましょう。
法附則第29条第1項~第6項 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) ① 当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない者等は、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有するとき。 (2) 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。 (3) 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 ② 請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。 ③ 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。 ④ 支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 ⑤ 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。 ⑥ 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
★脱退一時金の計算式
「被保険者であった期間の平均標準報酬額」×「支給率」
★支給率とは
「最終月の属する年の前年10月の保険料率」×「2分の1」×「被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数」
★被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数
被保険者であった期間 | 支給率計算に用いる数 | 支給率 |
6月以上12月未満 | 6 | 0.5 |
12月以上18月未満 | 12 | 1.1 |
18月以上24月未満 | 18 | 1.6 |
24月以上30月未満 | 24 | 2.2 |
30月以上36月未満 | 30 | 2.7 |
36月以上42月未満 | 36 | 3.3 |
42月以上48月未満 | 42 | 3.8 |
48月以上54月未満 | 48 | 4.4 |
54月以上60月未満 | 54 | 4.9 |
60月以上 | 60 | 5.5 |
例えば、被保険者期間が60月以上の場合の支給率は、
1000分の183×2分の1×60≒5.5となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6問8-A】
脱退一時金の支給額は、被保険者であった期間の平均標準報酬額に支給率を乗じた額である。この支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月(最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月)の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。なお、当該政令で定める数の最大値は60である。

【解答】
【R6問8-A】 〇
脱退一時金の支給額の計算に使う「支給率」について確認しましょう。
支給率=「最終月の属する年の前年10月の保険料率」×「2分の1」×「被保険者であった期間に応じて政令で定める数」で計算します。
ちなみに、最終月は、「最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月」です。
最終月の属する年の前年「10月」の保険料率を使いますが、最終月が1月から8月までの場合は、前々年10月の保険料率を使います。
また、「被保険者であった期間に応じて政令で定める数」の最大値は60です。
(令第12条の2)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき」は、脱退一時金の支給は受けられません。
②【H30年出題】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
脱退一時金の請求要件は、「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年経過していないこと」です。また、国民年金の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過していないことです。
③【R3年出題】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【解答】
③【R3年出題】 〇
最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過していても、「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)」から起算して2年経過していない場合は、脱退一時金の請求が可能です。
問題文は、「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日から1年が経過」となっていますので、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能です。
④【H27年出題】
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。

【解答】
④【H27年出題】 ×
最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の「前年9月」ではなく「前年10月」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-091 11.26
<令和6年の問題を振り返って>厚生年金保険料の納期限
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
保険料の納期限について条文を読んでみましょう。
第82条第1項、2項(保険料の負担及び納付義務) ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 ② 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
法第83条第1項 (保険料の納付) 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問7-C】
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。

【解答】
【R6問7-C】 〇
厚生年金保険の保険料は、被保険者と事業主が、それぞれ半額を負担します。また、事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負い、納期限は翌月末日です。
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の場合は、事業主の同意がない場合、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。その場合も、保険料の納期限は翌月末日です。
(法第82条、法附則第4条の3)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日ではなく「翌月末日」までに、納付しなければなりません。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
②【H27年出題】 ×
「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者」の場合は、事業主の同意がない場合、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。
その場合の保険料の納期限は翌月末日です。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、「納期限の日」ではなく「納期限の属する月の前月の末日」に、その資格を喪失します。
(法附則第4条の3)
③【R2年出題】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は「徴収されます」。
条文を読んでみましょう。
法第19条第1項 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 法第81条第2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 |
<令和6年4月10日に資格取得、11月26日に退職(11月27日に資格喪失)の場合>
被保険者期間は、令和6年4月~10月まで、保険料の徴収も令和6年4月分から10月分までとなります。
<令和6年4月10日に資格取得、11月30日に退職(12月1日に資格喪失)の場合>
被保険者期間は、令和6年4月~11月まで、保険料の徴収も令和6年4月分から11月分までとなります。
月末退職の場合は、翌月1日が資格喪失となります。保険料は資格を喪失した月の前月まで徴収されますので、月末退職の場合、退職した日の属する月の保険料は徴収されます。
④【H22年出題】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

【解答】
④【H22年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第84条第1項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 |
事業主は、被保険者負担分の保険料を報酬から控除できますが、控除できるのは、「前月の標準報酬月額に係る保険料」です。
また、退職の場合は、「前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除することができます。
例えば、11月30日に退職した場合は、11月分まで保険料が徴収されます。
11月支払の報酬から、10月分(前月分)と11月分(当月分)の保険料を控除することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<厚生年金保険法>高齢任意加入被保険者
R7-090 11.25
厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」についてお話しします
厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」についてお話しします。
厚生年金保険の被保険者を整理してみましょう。
| 適用事業所 | 適用事業所以外の事業所 | |
| 70歳未満 | 当然被保険者 | 任意単独被保険者 |
| 70歳以上 | 高齢任意加入被保険者 | 高齢任意加入被保険者 |
・「高齢任意加入被保険者」とは、「70歳以上で老齢年金の受給権がない人」です。
・高齢任意加入被保険者には、「厚生年金保険の適用事業所」に使用される者と「適用事業所以外の事業所」に使用される者の2つのパターンがあります。
・加入の手続き、喪失事由、保険料の負担と納付義務などをおさえましょう。
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-088 11.23
<令和6年の問題を振り返って>遺族厚生年金の遺族の要件
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
遺族厚生年金の遺族について条文を読んでみましょう。
法第59条第1項、2項 ① 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 ② 父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-ウ】
厚生年金保険の被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた遺族が50歳の父と54歳の母だけであった場合、父には遺族厚生年金の受給権は発生せず、母にのみ遺族厚生年金の受給権が発生する。

【解答】
【R6問5-ウ】 ×
「父母」は、被保険者の死亡当時「55歳以上」であることが要件です。
50歳の父と54歳の母については、どちらにも遺族厚生年金の受給権は発生しません。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
生計維持関係は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時」 で判断するのが原則です。
ただし、失踪の宣告を受けた被保険者であった者については、「行方不明となった当時」の生計維持関係が問われます。
②【R1年出題】
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

【解答】
②【R1年出題】 ×
54歳の夫と21歳の子は、どちらも遺族厚生年金を受けることができる遺族ではありません。
③【R2年出題】
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
55歳以上の夫は受給権者になり得ます。子の有無は問われません。
④【R2年出題】
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。

【解答】
④【R2年出題】 〇
遺族厚生年金には転給がありません。
遺族厚生年金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。
① | 配偶者又は子 |
② | 父母 |
③ | 孫 |
④ | 祖父母 |
例えば、被保険者等の死亡当時、「配偶者又は子」がいる場合は、父母以下は遺族厚年金を受けることはできません。
問題文の場合、被保険者の子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、被保険者の父は遺族となりません。その後、子の受給権が消滅したとしても、父に受給権が転給することもありません。
⑤【R5年出題】
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
夫は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であれば遺族厚生年金の受給権者となりますが、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されます。
ただし、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金の支給停止は解除され、遺族厚生年金を受給することができます。
条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-087 11.22
<令和6年の問題を振り返って>一人一年金の原則
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
年金の併給調整について条文を読んでみましょう。
第38条第1項、法附則第17条 (併給の調整) 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金についても同様とする。 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-イ】
厚生年金保険の被保険者である甲は令和2年1月1日に死亡した。甲の死亡時に甲によって生計を維持されていた遺族は、妻である乙(当時40歳)と子である丙(当時10歳)であり、乙が甲の死亡に基づく遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた。しかし、令和6年8月1日に、乙も死亡した。乙は死亡時に厚生年金保険の被保険者であった。また、乙によって生計を維持されていた遺族は丙だけである。この場合、丙が受給権を有する遺族厚生年金は、甲の死亡に基づく遺族厚生年金と乙の死亡に基づく遺族厚生年金である。丙は、そのどちらかを選択して受給することができる。

【解答】
【R6問5-イ】 〇
1人に対して、複数の年金の受給権が発生することがあります。
問題文の丙には、「甲の死亡に基づく遺族厚生年金」と「乙の死亡に基づく遺族厚生年金」の受給権が発生していますが、同じ遺族厚生年金でも、甲の死亡に基づくものと乙の死亡に基づくものは別です。
「1人1年金の原則」に基づいて、丙は、そのどちらかを選択して受給することになります。ちなみに、選択しなかった方の年金は、支給停止されます。
(法第38条)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38条第1項及び同法附則第17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金

【解答】
①【R4年出題】
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給できない
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給できない
どちらか一方の年金の支給が停止されるもの組み合わせは、イとオの2つです。
②【H23年出題】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。
障害厚生年金は、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。
②【H26年出題】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「65歳以上」の場合、「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」は、併給することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険労務士合格研究室
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-073 11.06
<令和6年の問題を振り返って>年金の内払調整
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
今日のテーマは「内払」です。
「内払」とは、「払いすぎた額を今後支払う年金額から減額すること」です。(参照:日本年金機構のホームページ)
条文を読んでみましょう。
第39条 ① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 ② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 ③ 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。 |
(例)①について
消滅
乙年金 | 支払い |
|
|
|
| 甲年金の内払とみなす ↓ |
| ||
| 甲年金 | |||
・乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得した
↓
・そのため乙年金の受給権が消滅したにも関わらず
↓
・翌月以後の分として、乙年金の支払が行われた
↓
・払いすぎた乙年金を返還させて改めて甲年金を支払うのではなく
↓
・支払われた乙年金は、甲年金の「内払とみなす」ことになっています。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-A】
同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下本肢において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払いが行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

【解答】
【R6年問3-A】 〇
同一人に対する「国民年金法による年金たる給付」と「厚生年金保険法の年金たる保険給付」も内払の調整を行うことができます。ただし「厚生年金保険法の年金たる保険給付」は、厚生労働大臣が支給するものに限られます。
(法第39条第3項)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の支給を選択した場合において、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われたときは、その支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。

【解答】
①【H25年出題】 〇
・遺族厚生年金の受給権者が障害厚生年金の受給権を取得
↓
・障害厚生年金の支給を選択
↓
・にもかかわらず、遺族厚生年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として遺族厚生年金の支払が行われた
↓
・支払われた遺族厚生年金は、障害厚生年金の内払とみなす。
支給停止
遺族厚生年金 | 支払い |
|
|
|
| 障害厚生年金の内払とみなす ↓ |
| ||
選択→ | 障害厚生年金 | |||
(法第39条第1項)
②【H25年出題】(※改正による修正あり)
同一人に対して国民年金法による寡婦年金の支給を停止して60歳台前半の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)を支給すべき場合において、老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として寡婦年金の支払が行われたときは、その寡婦年金は、老齢厚生年金の内払とみなすことができる。

【解答】
②【H25年出題】 〇
支給停止
寡婦年金 | 支払い |
|
|
|
| 老齢厚生年金の 内払とみなすことができる。 ↓ |
| ||
選択→ | 60歳台前半の老齢厚生年金 | |||
(法第39条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-072 11.05
<令和6年の問題を振り返って>配偶者以外の者が遺族厚生年金の受給権者の場合
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給するときのルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第60条第2項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとに算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。 第61条第1項 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。 |
例えば、遺族厚生年金の受給権者が、父と母の場合、それぞれの遺族厚生年金の額は、年金の額を2で割った額となります。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-エ】
夫(70歳)と妻(70歳)は、厚生年金保険の被保険者期間を有しておらず、老齢基礎年金を受給している。また、夫妻と同居していた独身の子は厚生年金保険の被保険者であったが、3年前に死亡しており、夫妻は、それに基づく遺族厚生年金も受給している。この状況で夫が死亡し、遺族厚生年金の受給権者の数に増減が生じたときは、増減が生じた月の翌月から、妻の遺族厚生年金の年金額が改定される。

【解答】
【R6年問5-エ】 〇
遺族厚生年金の受給権者が2人(死亡した者からみると父と母)ですので、それぞれに、遺族厚生年金の額を2で割った額が支給されます。
その後、夫(父)が死亡した場合、遺族厚生年金の受給権者は2人から1人に減少します。その場合、減少が生じた月の翌月から、母(妻)の遺族厚生年金の年金額が改定されます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金額を改定する。

【解答】
①【R2年出題】 〇
増減を生じた月の「翌月から」、年金額が改定されます。「翌月から」がポイントです。
②【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権者である子が2人いる場合において、そのどちらかが死亡したときは、他の受給権者に支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定される。

【解答】
②【H26年出題】 〇
例えば、遺族厚生年金の受給権者である子がAとBの2人いる場合で、Aが死亡したときは、Bに支給される遺族厚生年金の額は、受給権者の数に減少が生じた月の翌月から改定されます。
ちなみに、Bの年金額は、Aと2分の1ずつだったものが、Aの死亡によりBが1人で受けることになりますので、Bの年金額は増額します。
③【H21年出題】
被保険者期間が300月以上である被保険者の死亡により、配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額を受給権者の数で除して得た額である。

【解答】
③【H21年出題】 〇
配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合で、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者の数で除して得た額となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族厚生年金の短期要件と長期要件のこと
R7-071 11.04
【社労士厚生年金】遺族厚生年金の短期要件と長期要件についてお話しします。
遺族厚生年金には短期要件と長期要件があります。
・短期要件とは?
・長期要件とは?
・短期要件と長期要件の両方に当てはまる場合があります
・短期要件と長期要件の計算式の違い
についてお話ししています。
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-060 10.24
<令和6年度厚年>老齢厚生年金の繰下げの条件【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
老齢厚生年金の繰下げの要件について条文を読んでみましょう。
第44条の3第1項 (支給の繰下げ) 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して 1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 |
<老齢厚生年金の繰下げの申し出の条件です>
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していないこと
・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でないこと
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていないこと
★他の年金たる給付とは?
・他の年金たる保険給付 → 障害厚生年金、遺族厚生年金
又は
・国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。) → 遺族基礎年金
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問4】
次の記述のうち、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができないものはいくつあるか。
なお、いずれも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出に係るその他の条件を満たしているものとする。
ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者。
イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者。
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者。
オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者。

【解答】
ア 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません。
イ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族厚生年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません。
ウ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに老齢基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができます。
エ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができます。
オ 老齢厚生年金の受給権を取得したときに遺族基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出はできません。
老齢厚生年金の繰下げの申出ができないのは、ア、イ、オの3つです。
過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
③ 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
④ 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
⑤ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑥ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑦ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族基礎年金
⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

【解答】
<A> ② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
<B> ⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
②【H28年出題】
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

【解答】
②【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金の受給権を有していても、条件を満たせば、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-059 10.23
<令和6年度>厚生年金保険の不服申立ての超基本問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
厚生年金保険法の審査請求・再審査請求について条文を読んでみましょう。
第90条第1項、3項、4項、5項 (審査請求及び再審査請求) ① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定(厚生年金保険原簿の訂正請求に対する措置)については、この限りでない。 ③ 審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ④ 審査請求並びに再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ⑤ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第91条第1項 ① 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第91条の3(審査請求と訴訟との関係) 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
下の図で確認しましょう。
(参考にどうぞ)
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の審査請求先も確認しましょう。
(1) 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合審査会
(2) 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合審査会
(3) 第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問1-A】
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

【解答】
①【R6年問1-A】 ×
厚生労働大臣による「被保険者の資格」に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会ではなく「社会保険審査官」に対して審査請求をすることができます。
②【R6年問1-B】
厚生労働大臣による保険料の賦課の処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
②【R6年問1-B】 ×
厚生労働大臣による「保険料の賦課」の処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
③【R6年問1-C】
厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

【解答】
③【R6年問1-C】 〇
厚生労働大臣による「脱退一時金」に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
条文を読んでみましょう。
法附則第29条第6項 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
④【R6年問1-D】
第1号厚生年金被保険者が厚生年金保険原簿の訂正請求をしたが、厚生労働大臣が訂正をしない旨の決定をした場合、当該被保険者が当該処分に不服がある場合は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
④【R6年問1-D】 ×
厚生年金保険原簿の訂正請求に対する処分は、厚生年金保険法に基づく審査請求の対象にはなりません。当該処分に不服がある場合は、行政不服審査法に基づいて、審査請求をすることができます。
⑤【R6年問1-E】
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定した場合でも、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができる。

【解答】
⑤【R6年問1-E】 ×
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。となります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に審査請求をし、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる、とされています。
②【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】
②【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求先は「社会保険審査会」です。
ちなみに、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者の審査請求先は「社会保険審査会」で正しいです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-058 10.22
<令和6年度厚年>遺族厚生年金の原則の計算式【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
遺族厚生年金の額の計算式について条文を読んでみましょう。
第60条第1項 (年金額) 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める額とする。 (1) 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項(老齢厚生年金の額)の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金(短期要件の遺族厚生年金)については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 (2) 第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 「(1)原則の遺族厚生年金の額」又は次の「イ及びロに掲げる額を合算した額」のうちいずれか多い額 イ (1)に定める額(原則の遺族厚生年金の額)に3分の2を乗じて得た額 ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額は除く。)に 2分の1を乗じて得た額 |
今日は(1)の原則の計算式を見ていきます。
遺族厚生年金の原則の計算式は、
「死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分(平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数)×4分の3」です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年5-ア】
死亡した者が短期要件に該当する場合は、遺族厚生年金の年金額を算定する際に、死亡した者の生年月日に応じた給付乗率の引上げが行われる。

【解答】
①【R6年5-ア】 ×
死亡した者が短期要件に該当する場合は、生年月日に応じた給付乗率の引上げは行われません。
短期要件と長期要件の違い
| 短期要件 | 長期要件 |
給付乗率 | 1,000分の5.481 (定率) | 生年月日に応じて 1,000分の5.562 ~ 1,000分の7.308 |
被保険者期間の月数 | 300月の最低保障あり | 実期間で計算 |
②【R6年問5-オ】
繰下げにより増額された老齢厚生年金を受給している夫(厚生年金保険の被保険者ではない。)が死亡した場合、夫によって生計を維持されていた妻には、夫の受給していた老齢厚生年金の額(繰下げによる加算額を含む。)の4分の3が遺族厚生年金として支給される。なお、妻は老齢厚生年金の受給権を有しておらず、老齢基礎年金のみを受給しているものとする。

【解答】
②【R6年問5-オ】 ×
夫の老齢厚生年金の額の4分の3が遺族厚生年金として支給されますが、繰下げによる加算額は含まれません。
ちなみに、妻は老齢厚生年金の受給権を有していないので、遺族厚生年金は原則の計算式で計算されます。
過去問をどうぞ!
【H27年出題】(改正による修正あり)
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

【解答】
【H27年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡は「長期要件」に該当しますので、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-044 10.8
<令和6年度厚年>特別支給の老齢厚生年金長期加入者の特例【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
今日は長期加入者の特例です。
・長期加入者の特例は、特別支給の老齢厚生年金が「報酬比例部分のみ」になる年代が対象です。
例えば、昭和32年4月2日生まれの男性は、63歳から報酬比例部分が支給されます。
60歳 63歳 65歳
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
|
| 老齢基礎年金 |
「長期加入者の特例」の要件に該当すると、下の図のように定額部分が加算されます。
60歳 63歳 65歳
| 報酬比例部分 | 老齢厚生年金 |
| 定額部分 | 老齢基礎年金 |
また、要件を満たせば加給年金額も加算されます。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-C】
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。

【解答】
【R6年問9-C】 ×
「在職中」は、長期加入者の特例は適用されませんので、定額部分は加算されません。
(法附則第9条の3)
★長期加入者の特例が適用される条件を確認しましょう。
・厚生年金保険の被保険者でないこと(=退職していること)
・厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
★「障害者の特例」との違い
・「障害者の特例」は、「特例の適用を請求」することが条件ですが、「長期加入者の特例」については、特例の適用を請求する必要はありません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

【解答】
①【R3年出題】 ×
長期加入者の特例の要件は「厚生年金保険の被保険者期間が44年以上」あることです。ただし、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、「44年以上」の計算は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用されます。
問題文の場合、第1号厚生年金被保険者としての4年と第2号厚生年金被保険者としての40年は合算できません。そのため長期加入者の特例の要件を満たしませんので、63歳から支給されるのは報酬比例部分のみで、定額部分は支給されません。
(法附則第9条の3、法附則第20条第2項)
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者期間30年と第2号厚生年金被保険者期間14年は合算できませんので、61歳から定額部分は支給されません。
(法附則第9条の3、法附則第20条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
在職老齢年金でよく出るところ(厚生年金保険法)
R7-043 10.7
在職老齢年金の基本をお話しします【社労士受験対策】
在職老齢年金のキーワードをおさえましょう。
・「在職老齢年金」の「在職」とは?
・総報酬月額相当額とは?
・基本月額とは?
・支給停止調整額とは?
・支給停止基準額とは?
「加給年金額」、「繰下げ加算額」、「経過的加算額」が支給停止の対象となるか、ならないかが問われるポイントです。
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族厚生年金は夫と妻で内容が異なります
R7-036 9.30
遺族厚生年金夫と妻の違い【社労士受験対策】
遺族厚生年金の夫と妻の違いについてお話します。
①受給権の発生要件 夫は55歳以上であること
②30歳未満で子のない妻
③中高齢寡婦加算
④夫の遺族基礎年金と遺族厚生年金
YouTubeでお話しています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-033 9.27
<令和6年度厚年>在職老齢年金の加給年金額【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
在職老齢年金の加給年金額のポイント!
★老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合
→ 基本月額は加給年金額を除いて計算します。
★在職老齢年金によって、老齢厚生年金が一部支給停止(=一部支給)される場合
→ 加給年金額は全額支給されます。
★在職老齢年金によって、老齢厚生年金が全額支給停止される場合
→ 加給年金額も全額支給停止されます。
(法第46条第1項)
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問8-C】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であっても、在職老齢年金の仕組みにより、自身の老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合、加給年金額は支給停止となる。

【解答】
【R6年問8-C】 ×
在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部の支給が停止される場合(=老齢厚生年金の一部が支給される場合)は、加給年金額は支給されます。
在職老齢年金の仕組みで、老齢厚生年金が全額支給停止される場合は、加給年金額も支給停止されます。
(法第46条)
過去問をどうぞ!
【R3年出題】
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

【解答】
【R3年出題】 ×
総報酬月額相当額の定義は、問題文の通りです。
基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを除く。)を12で除して得た額のことです。
(法第46条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-032 9.26
<令和6年度厚年>同月得喪の場合の被保険者期間【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
「被保険者期間」の計算について条文を読んでみましょう。
法第19条第1項、第2項 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 |
ポイント!
★被保険者期間は「月単位」で計算します。
(例1)令和6年2月21日入社・同年9月25日退職(26日喪失)の場合
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
取得 |
|
|
|
|
|
| 喪失 |
・被保険者の資格を取得した月(2月)からその資格を喪失した月(9月)の前月まで
・被保険者期間→ 2月から8月まで
(例2)令和6年2月21日入社・同年9月30日退職の場合
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
取得 |
|
|
|
|
|
|
| 喪失 |
・9月30日退職の場合、10月1日が資格喪失日です。
・被保険者の資格を取得した月(2月)からその資格を喪失した月(10月)の前月まで
・被保険者期間→ 2月から9月まで
(例3)令和6年10月3日入社・同月20日退職、その月にさらに厚生年金保険・国民年金の被保険者の資格を取得していない場合
10月 |
取得 喪失 |
・資格を取得した月に資格を喪失した場合
・被保険者期間 → 1か月
(例4)令和6年10月3日入社・同月20日退職、その月にさらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合
10月 |
取得 喪失 |
・被保険者期間に算入しない
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-D】
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

【解答】
【R6年問3-D】 ×
厚生年金保険の資格を取得した月に資格を喪失した場合は、1か月として、厚生年金保険の被保険者期間に算入されるのが原則です。
ただし、その月にさらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合は、その月は、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
問題文は、「同年5月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入しない。」となります。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の「資格を取得した月」からその「資格を喪失した月の前月」までを算入します。
②【R2年出題】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
「厚生年金保険の保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」とされています。
・ 被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば、厚生年金保険の保険料は徴収されます。例えば、9月30日に資格取得した場合でも、9月分の保険料は徴収されます。
・ 資格を喪失した月については、保険料は徴収されません。月末日で退職したときは、翌月1日が資格喪失日になりますので、「退職した日が属する月」の保険料は徴収されます。
・ 先ほどの(例2)をみてみましょう。
令和6年2月21日入社・同年9月30日退職の場合
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
取得 |
|
|
|
|
|
|
| 喪失 |
・ 9月30日退職の場合、10月1日が資格喪失日です。被保険者期間に算入されるのは、 2月から9月までですので、9月分(退職した日が属する月)の保険料が徴収されます。
(法第81条第2項)
③【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
③【H30年出題】 〇
平成29年10月1日に資格取得・平成30年3月30日に資格喪失の場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間です。
資格を喪失した月(平成30年3月)は、被保険者期間には算入されません。
④【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
平成28年3月について
1日資格取得・20日付け退職・21日に資格喪失、さらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得
→ 平成28年3月は、厚生年金保険の被保険者期間に算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-031 9.25
<令和6年度厚年>2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金額【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
老齢厚生年金に加算される加給年金額については、被保険者期間が20年(240月)以上ある者で、一定の条件を満たす配偶者や子を有する場合に、加算されます。
令和6年問2の問題を解いてみましょう。
【R6年問2-A】
甲は第1号厚生年金被保険者期間を140か月有していたが、後に第2号厚生年金被保険者期間を150か月有するに至り、それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した(これら以外の被保険者期間は有していない。)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

【解答】
【R6年問2-A】 ×
加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間が240月以上あることが条件です。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算して240月になれば、要件を満たします。
甲は第1号厚生年金被保険者期間140か月+第2号厚生年金被保険者期間150か月=
290か月ですので、加給年金額が加算される要件を満たします。
なお、加給年金額は、一の年金に加算されることになり、優先順位が決まっています。
① 一の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したもの
↓
② 最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、最も長い一の期間に基づく老齢厚生年金
↓
③ 最も長い一の期間が2以上ある場合は、次の順序
第1号厚生年金被保険者期間
↓
第2号厚生年金被保険者期間
↓
第3号厚生年金被保険者期間
↓
第4号厚生年金被保険者期間
甲の場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生しています。
そのため、加給年金額は、「最も長い一の期間」に基づく老齢厚生年金に加算されます。「第1号」厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金ではなく、長い方の「第2号厚生年金被保険者期間に基づく」老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、令3条の13)
過去問をどうぞ!
①【H28年問5-C】
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【解答】
①【H28年問5-C】 〇
第1号厚生年金被保険者期間170か月+第2号厚生年金被保険者期間130か月=300か月で、加給年金額が加算される要件を満たします。
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を同じ日に取得していますので、期間が長い方の「第1号厚生年金被保険者期間」に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、令3条の13)
②【H30年問4-エ】
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

【解答】
②【H30年問4-エ】 ×
2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なっている場合は、「遅い日」ではなく「最も早い日」に受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができます。
(法第78条の27、令3条の13)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(厚生年金保険法)
R7-030 9.24
<令和6年度厚年>2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の択一式です。
例えば、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する場合、老齢厚生年金の額は、それぞれの被保険者期間ごとに区分して計算します。
条文を読んでみましょう。
法第78条の26第2項 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、 第43条の規定(老齢厚生年金の年金額)を適用する場合においては、同条第1項に規定する被保険者であった全期間並びに同条第2項及び第3項に規定する被保険者であった期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第1項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第2項及び第3項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。 |
例えば、第2号厚生年金被保険者期間を30年、第1号厚生年金被保険者期間を10年有する場合の老齢厚生年金の支給を図でイメージしましょう。
第2号 30年 | 第1号 10年 |
国家公務員共済組合が支給 | 厚生労働大臣が支給 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-B】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、その者の2以上の種別の被保険者であった期間を合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出し計算することとされている。

【解答】
【R6年問9-B】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額は、第1号厚生年被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用して、平均標準報酬額を算出し計算します。
(第78条の26第2項)
過去問もどうぞ!
【H29年問9】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

【解答】
【H29年問9】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を「合算」するのではなく、各号の厚生年金被保険者期間ごとに、平均標準報酬額を算出します。
(法第78条の26第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(厚生年金保険法)
R7-021 9.15
<令和6年度>厚生年金保険法の問題を解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年の問題を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険の択一式です。
令和6年問10の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
厚生年金保険の被保険者であった18歳のときに初診日のある傷病について、その障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が20歳未満のときは、障害厚生年金の受給権は20歳に達したときに発生する。

【解答】
①【R6年出題】 ×
「初診日」に厚生年金保険の被保険者で、「障害認定日」に障害等級(1級~3級)に該当する障害の状態にある場合は、「障害認定日」に障害厚生年金の受給権が発生します。
初診日・障害認定日に20歳未満であっても、受給権は20歳に達したときではなく、「障害認定日」に発生します。
(法第47条)
②【R6年出題】
障害手当金は、疾病にかかり又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、保険料納付要件を満たし、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中の場合でも、5年を経過した日に政令で定める程度の障害の状態にあるときは支給される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
障害手当金は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合」に、支給されます。
障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が「治った」ことが要件です。
問題文は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間にまだその傷病が治っておらず治療中」となっていますので、障害手当金は支給されません。
(法第55条)
③【R6年出題】
年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止することとされている。ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

【解答】
③【R6年出題】 〇
年金の受給権者は、受給権者の意思で年金の受給を辞退することができます。
その場合は、「受給権者の申出」により、その「全額」の支給が停止されます。「全額」辞退することが条件です。「一部」を辞退することはできません。
ただし、厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、「停止されていない部分の額」の支給が停止されます。
(法第38条の2)
④【R6年出題】
現在55歳の自営業者の甲は、20歳から5年間会社に勤めていたので、厚生年金保険の被保険者期間が5年あり、この他の期間はすべて国民年金の第1号被保険者期間で保険料はすべて納付済みとなっている。もし、甲が現時点で死亡した場合、一定要件を満たす遺族に支給される遺族厚生年金の額は、厚生年金保険の被保険者期間を300月として計算した額となる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
甲の年金加入歴は以下のようになります。
20歳 25歳 | 55歳 |
厚生年金保険(5年) | 第1号被保険者(保険料すべて納付) |
遺族厚生年金は、死亡した者が、次の(1)~(4)のいずれかに該当することが条件です。なお、(1)、(2)は保険料納付要件が問われます。
(1) 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
(2) 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
(3) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
(4) 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
★(1)~(3)を「短期要件」、(4)を長期要件といいます。
甲は第2号被保険者期間が5年、第1号被保険者期間で保険料をすべて納付した期間が30年ありますので、(4)の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときに該当します。
(1)~(3)には該当しません。
甲は「長期要件」に該当しますので、遺族厚生年金の額を計算するときの厚生年金保険の被保険者期間は実期間の60か月となります。
ちなみに、遺族厚生年金の額を計算するときの厚生年金保険の被保険者期間として300月が保障されるのは「短期要件」の場合です。
(法第58条、第60条)
⑤【R6年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を判定する。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
脱退一時金は、「厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)」で要件を満たした者に支給されます。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金は、2以上の被保険者であった期間を合算して、支給要件を判定します。
(法附則第29条、第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(厚生年金保険法)
R7-011 9.5
令和6年度<厚年選択式>国庫負担・標準賞与額・受給権の保護・遺族厚生年金・障害厚生年金【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、厚生年金保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する< A >を負担するものとされている。
<選択肢>
「費用」、「費用の2分の1」、「費用の3分の1」、「費用の4分の3」

【解答】
<A> 費用
(第80条)
ポイント!
「事務の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用」は、国庫が負担します。
国庫負担の過去問をどうぞ!
【H29年出題】
厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する< F >に相当する額を負担する。
<選択肢>
「基礎年金拠出金の額の2分の1」、「基礎年金拠出金の額の3分の1」
「事務の執行に要する費用の2分の1」、「保険給付費の2分の1」

【解答】
<F> 基礎年金拠出金の額の2分の1
★厚生年金保険の実施者たる政府が負担する「基礎年金拠出金の額の2分の1」は、国庫が負担します。
(法第80条第1項)
令和6年 選択問題2
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が< B >(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額。)を超えるときは、これを< B >とする。
<選択肢>
「100万円」、「150万円」、「200万円」、「250万円」

【解答】
<B> 150万円
(法第24条の4)
「標準賞与額」は、賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額で、上限は1か月当たり150万円です。
令和6年 選択問題3
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、< C >を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
<選択肢>
「遺族厚生年金」、「障害厚生年金」、「障害手当金」、「脱退一時金」

【解答】
<C> 脱退一時金
ポイント!
法第41条第1項では、「保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」となっています。
例外的に、老齢厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押さえの対象となります。
しかし、選択肢には「老齢厚生年金」がありません。
★附則によって、老齢厚生年金は脱退一時金と読み替えられます
法附則第29条第9項、令第14条で、「老齢厚生年金」を「脱退一時金」と読み替えるとされています。当てはめると、「ただし、脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」となります。
令和6年 選択問題4
厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により< D >を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
<選択肢>
「当該初診日から起算して3年」、「当該初診日から起算して5年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して3年」
「被保険者の資格を喪失した日から起算して5年」

【解答】
<D> 当該初診日から起算して5年
ポイント!
厚生年金保険の被保険者の資格喪失後(会社を退職した後)に死亡した場合でも、被保険者であった間(在職中)に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したきとは、遺族厚生年金の要件を満たします。(保険料納付要件が問われます。)
在職中(厚生年金保険の被保険者) | 退職 |
| |
▲ 初診日 |
| ▲ 死亡 | |
| 5年を経過する日前 | ||
令和6年 選択問題5
甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、< E >。
<選択肢>
「甲のみが行うことができる」
「甲も乙も行うことができない」
「甲も乙も行うことができる」
「乙のみが行うことができる」

【解答】
<E> 乙のみが行うことができる
(法第52条第7項)
解くときのチェックポイント!
・年齢
甲も乙も65歳以上(66歳)
・障害基礎年金の受給権の有無
甲は障害基礎年金の受給権を「有しない」
乙は障害基礎年金の受給権を「有する」
では、問題のポイントを図でイメージしましょう。
こちらの動画の7:28からです。
↓
https://youtu.be/B-p353mT2n0?si=2xHwJ36xd9dNXog1
条文を読んでみましょう。
法第52条第7項 障害厚生年金の額の改定の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
甲は、65歳以上かつ障害基礎年金の受給権を有しないので、額の改定請求はできません。
乙は、65歳以上ですが、障害基礎年金の受給権を有するので、額の改定請求ができます。
障害基礎年金の受給権の有無がポイントです。
詳しくは、こちらで解説しています。
↓
問題が解ける!事後重症【社労士受験対策】
https://youtu.be/vsvaK8cf1rU?si=R6U2NqkgO2jtYWDf
過去問を解いてみましょう
【R2年出題】
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

【解答】
【R2年出題】 ×
問題文の場合は、「障害基礎年金」の受給権を有するので、65歳に達した日以後に障害の程度が増進して2級の障害の状態になった場合、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給されます。
令和6年の選択問題の「乙」がこのパターンに当たります。
(法第52条第7項)
令和6年の選択式 1つめの国庫負担は、覚えて解く問題です。 2つめの標準賞与額は、健康保険と比較しながら覚えましょう。 3つめの受給権の保護は、附則からの出題でしたので、少し戸惑われたのではないでしょうか。 4つ目の遺族厚生年金の支給要件は、覚えて解く問題です。特に起算日が注意点です。 5つ目の障害厚生年金の額の改定は、択一式で良く問われるポイントです。問題を解くポイントをうまく見つけなければならない問題です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法と厚生年金保険法の違い
R6-350 8.11
支給停止の違い(遺族基礎年金と遺族厚生年金)【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法と厚生年金保険法です。
受給権者本人の判断で、年金の支給停止の申出をすることができます。
まず国民年金法の条文を読んでみましょう。
国民年金法第20条の2第1項 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
厚生年金保険にも同じ規定があります。条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第38条の2第1項 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
では、国民年金の過去問をどうぞ!
【国民年金法H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
【国民年金法H28年出題】 〇
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
(法第41条第2項)
次は厚生年金保険法の過去問をどうぞ!
【厚生年金保険法H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

【解答】
【厚生年金保険法H30年出題】 ×
子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
国民年金法との違いに注意しましょう。
(法第66条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金と遺族厚生年金
R6-344 8.5
超基本!妻に支給される遺族基礎年金・遺族厚生年金【社労士受験対策】
妻に支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金の基本をお話します。
★事例1
20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(40歳)が死亡し、遺族が妻と子の場合
・遺族基礎年金の支給要件
・遺族厚生年金の支給要件
★事例2
20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(59歳)が死亡し、遺族は妻(50歳)のみの場合
・遺族基礎年金は支給されない?
・遺族厚生年金の支給要件
・中高齢寡婦加算について
★年金額について
・65歳以上、老齢厚生年金の受給権者、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける人の遺族厚生年金の計算方法
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-340 8.1
遺族厚生年金「生計維持」について【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の条文を読んでみましょう。
第59条第1項 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものであることが条件です。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
遺族厚生年金の生計維持に係る要件については、被保険者又は被保険者であった者の「死亡の当時」の生計維持関係が問われます。
ただし、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給する場合の生計維持に係る要件については、「行方不明となった当時」の失踪者との生計維持関係が問われます。
(第59条第1項)
②【H25年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
生計を維持していたものと認めらないのは、年額130万円以上ではなく、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合です。
(平成23.3.23年発0323第1号)
③【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

【解答】
③【R5年出題】 〇
前年収入が年額850万円未満であった者は、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められます。
(平成23.3.23年発0323第1号)
④【H29年出題】
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
生計維持関係は、死亡当時で認定されます。
その後、給与収入が減少しても、遺族厚生年金の受給権を得ることはできません。
(平成23.3.23年発0323第1号)
⑤【H27年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされます。
「将来に向かって」がポイントです。死亡した当時にさかのぼるのではなく、出生したときに、遺族として受給権を取得します。
(第59条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-339 7.31
在職定時改定をチェック!【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
在職定時改定について条文を読んでみましょう。
第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
★在職定時改定とは
老齢厚生年金を受給しながら働いている(=厚生年金保険料を負担している)人について、負担した厚生年金保険料が、退職前に年金額に反映される制度です。
前年9月から当年8月までの厚生年金保険料納付実績が、毎年10月からの年金額に反映します。
ポイント!
在職定時改定が適用されるのは、65歳以上70歳未満です。
65歳未満には適用されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
①【R4年出題】 ×
在職定時改定の基準日は、7月1日ではなく、9月1日です。
(第43条第2項)
②【R5年出題】
厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

【解答】
②【R5年出題】 〇
基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合
↓
基準日前に資格喪失し、1か月以内に、再び資格取得した場合、基準日に被保険者ではありませんが、在職定時改定の対象になります。例えば、8月26日に資格を喪失し、9月8日に再び被保険者の資格を取得したような場合です。
この場合は、まだ年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの期間が、在職定時改定によって再計算され、10月から老齢厚生年金の額に反映されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害手当金の支給要件、支給されない場合、額など
R6-330 7.22
障害手当金のすべてお話します【社労士受験対策】
障害手当金は、3級よりも軽い障害が対象で、一時金で支給されます。
今日の内容は次の3つです。
①支給要件
ポイントは、「5年以内」「傷病が治った」
②障害手当金が支給されない場合
よく出題されています
③障害手当金の額(最低保障額あり)
最低保障額がポイントです。
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-329 7.21
厚生年金保険の被保険者になる・ならない【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H25年出題】
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険の被保険者とならないものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合。
イ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合。
ウ 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合。
エ 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合。
オ 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。
A (アとイ)
B (アとエ)
C (イとウ)
D (ウとオ)
E (エとオ)

【解答】
【H25年出題】 E (エとオ)
アについて
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
| 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 |
ポイント!
季節的業務に使用される者は、厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、当初から継続して4か月を超えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となります。
ただし、「船舶所有者に使用される船員」の場合は、季節的業務に使用される者であっても適用除外になりませんので、被保険者となります。
(第12条第3号)
イについて
適用事業所に使用される70歳未満の者は 当然に厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者でも、以下の条件を満たせば、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険の被保険者となることができます。
・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない
・事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた
(法附則第4条の5)
ウについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。 イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの |
ポイント!
・日々雇い入れられる者は厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となります。
・2月以内の期間を定めて使用される者で、所定の期間を超えて使用されることが見込まれないものは厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となります。
ただし、「船舶所有者に使用される船員」は、臨時に使用される者でも、被保険者となります。
(第12条第1号)
エについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
| 所在地が一定しない事業所に使用される者 |
ポイント!
巡回興行などの「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、使用期間に関係なく、被保険者になりません。
(第12条第2号)
オについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。 |
ポイント!
臨時的事業の事業所に使用される者は厚生年金保険の被保険者になりません。ただし、継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
問題文は、「その者が継続して6か月を超えない期間使用される」ですので、被保険者になりません。
(第12条第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-328 7.20
<選択式>60歳台後半の在職老齢年金のポイント!【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
<選択肢>
① 支給調整開始額 ② 支給調整基準額 ③ 支給停止開始額
④ 支給停止額 ⑤ 支給停止基準額 ⑥ 支給停止調整額
⑦ 総報酬月額 ⑧ 総報酬月額相当額 ⑨ 定額部分
⑩ 標準賞与月額相当額 ⑪ 平均標準報酬月額 ⑫ 報酬比例部分

【解答】
【H28年選択式】
A ⑧ 総報酬月額相当額
B ⑥ 支給停止調整額
C ⑤ 支給停止基準額
★用語を確認しましょう。
・「総報酬月額相当額」とは
→標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
・「基本月額」とは
→老齢厚生年金の額÷12
(加給年金額・第44条の3第4項に規定する加算額(=繰下げ加算額)を除く)。
・総報酬月額相当額+基本月額が「支給停止調整額」以下の場合
→老齢厚生年金は支給停止されず全額支給される
・総報酬月額相当額+基本月額が支給停止調整額を超えるときは、「支給停止基準額」が支給停止される。
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×2分の1×12
・令和6年度の支給停止調整額は、50万円
・支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上の場合は、老齢厚生年金の全部が支給停止される。(繰下げ加算額は除く。)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。

【解答】
①【H22年出題】 〇
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である」とは、老齢厚生年金を受給しながら働いている(厚生年金保険に加入して保険料を負担している)という意味です。
②【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項)
③【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
経過的加算額と繰下げ加算額は、基本月額の計算の対象に含まれません。
「繰下げ加算額」が計算に入らないのは第46条第1項に規定されています。
「経過的加算額」が計算に入らないのは、S60法附則第62条第1項に規定されています。
④【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
老齢基礎年金も経過的加算額も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
⑤【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
経過的加算額も老齢基礎年金も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害厚生年金3つの要件と額の計算
R6-323 7.15
障害厚生年金の超基本お話します【社労士受験対策】
障害厚生年金の受給権が発生する条件を障害基礎年金と比較しながらみていきます
①初診日
②保険料納付要件
③障害認定日
障害厚生年金の被保険者=原則国民年金第2号被保険者という点も意識してください 障害厚生年金の額は報酬比例です。
1・2級には加給年金額が加算されます
3級は障害基礎年金は支給されません。加給年金額も加算されません。ただし、最低保障が設けられています。
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-318 7.10
【選択式】3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年選択式】
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに < A >までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前 < B >における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
<選択肢>
① 1年以内 ② 1年6か月以内 ③ 2年以内 ④ 6か月以内
⑤ 至った日の属する月 ⑥ 至った日の属する月の前月
⑦ 至った日の翌日の属する月 ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月

【解答】
A⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
B ① 1年以内
(第26条第1項)
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額の特例のイメージ
子を養育する期間 3歳
従前標準報酬月額
| 将来の年金額は、従前標準報酬月額を 標準報酬月額とみなして計算します |
標準報酬月額が低下 |
ポイント!
・被保険者又は被保険者であった者が、実施機関に申出をすること
・対象になる期間
→子を養育することとなった日の属する月~子が3歳に達したときに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで
・将来の年金額は、従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして計算する
・従前標準報酬月額とは
→子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額
※当該月に被保険者でない場合は、当該月前1年以内における被保険者であった月 のうち直近の月。
・申出が行われた日の属する月前の月は、申出が行われた日の属する月の前月までの 2年間のうちにあるものに限って、標準報酬月額の特例が受けられる。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

【解答】
①【H27年出題】 ×
8月 | 9月(出産) |
280,000円 | 定時決定 240,000円 |
従前標準報酬月額は、「子を養育することとなった日(9月3日)の属する月の前月の標準報酬月額」ですので、280,000円です。
(第26条第1項)
②【R3年出題】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

【解答】
②【R3年出題】 ×
さかのぼって特例が適用されるのは、特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間ではなく、「2年間」のうちにあるものに限られます。
(第26条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-317 7.9
【選択式】合意分割の請求【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
過去問からどうぞ!
①【R2年選択式】
厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき< A >について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから< B >を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 按分割合 ② 改定額 ③ 改定請求額 ④ 改定割合
⑤ 1年 ⑥ 2年 ⑦ 3年 ⑧ 6か月

【解答】
A ① 按分割合
B ⑥ 2年
(第78条の2第1項)
②【H29年選択式】
合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、< C >の範囲内でそれぞれ定められなければならない。
<選択肢>
① 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
② 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
④ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下

【解答】
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
按分割合の条文を読んでみましょう。
第78条の3第1項 按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 |
<按分割合>
第2号改定者の対象期間標準報酬総額 |
第1号改定者の対象期間標準報酬総額+第2号改定者の対象期間標準報酬総額 |
合意分割によって
・第2号改定者(分割を受ける側)の対象期間標準報酬総額(持ち分)が増えます。
・按分割合の上限は2分の1です。
択一式の過去問もどうぞ!
【H27年出題】
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

【解答】
【H27年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第78条の2第1項、2項 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) ① 第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (1) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。)について合意しているとき。 (2)家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ② 標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金
R6-316 7.8
老齢厚生年金の超基本お話します【社労士受験対策】
老齢厚生年金は65歳から老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
また、当分の間は、60歳から65歳未満の間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
それぞれの計算式や、支給要件の違いをみていきましょう。
★YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-304 6.26
<選択式>老齢厚生年金の繰下げの申出の条件【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問からどうぞ!
【R2年選択式】
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
③ 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
④ 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
⑤ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑥ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑦ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族害基礎年金
⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

【解答】
A ② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
B ⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
(第44条の3第1項)
繰下げのポイント!
★老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していないこと
★老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に「他の年金たる給付」の受給権がある場合は、繰下げの申出ができません。
※「他の年金たる給付」は、他の年金たる保険給付(=障害厚生年金、遺族厚生年金)、国民年金の年金たる給付(「老齢基礎年金及び付加年金」、「障害基礎年金」は含まれません。)です。
(例)「老齢基礎年金+付加年金」の受給権があっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができます。
(例)「障害基礎年金」の受給権があっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H19年出題】
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者でも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができます。
(第44条の3第1項)
②【H28年出題】
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

【解答】
②【H28年出題】 〇
65歳時点で、障害基礎年金の受給権者であった者でも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
(第44条の3第1項)
③【H19年出題】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。どちらか一方だけ繰り下げることもできます。
(第44条の3)
④【R4年出題】
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

【解答】
④【R4年出題】 〇
複数の種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が繰下げの申出をする場合は、すべての老齢厚生年金について、同時に繰下げの申出を行わなければなりません。
(第78条の28)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-293 6.15
<選択式>老齢厚生年金の額・再評価率など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日は選択式の過去問です。
では、過去問をどうぞ!
【H23年選択式】 ※改正による修正あり
① 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の 1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
<A> 再評価率
<B>5.481
(第43条第1項)
老齢厚生年金の額の原則は、
平均標準報酬額 × 1,000分の5.481 × 被保険者期間の月数
で計算します。
平均標準報酬額は、
計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、被保険者期間の月数で割って得た額です。
「再評価率」とは、過去の標準報酬月額と標準賞与額を現在の価値に再評価するための率です。
2 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。

【解答】
<C> 物価変動率
<D> 名目手取り賃金変動率
C、Dを入れて条文を読んでみましょう。
第43条の2第1項 再評価率については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 |
再評価率は、毎年度改定されます。
新規裁定者は、「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されます。
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(以下「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。

【解答】
<E> 3年後
C、D、Eを入れて条文を読んでみましょう。
第43条の3第1項 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。 |
既裁定者(68歳到達年度以後である受給権者)の再評価率は、「物価変動率」を基準に改定されます。
ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率が基準となります。
こちらの問題もどうぞ!
【R5年選択式】
令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から< A >となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。

【解答】
<A>0.2%の引下げ
物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」で、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ります。そのため、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」が基準となり、0.2%引き下げられます。
なお、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-292 6.14
厚生年金保険法の保険料等の督促及び滞納処分【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
督促及び滞納処分について条文を読んでみましょう。
第86条(保険料等の督促及び滞納処分) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 ④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上げ徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。 ⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。 (1) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 (2) 保険料の繰上げ徴収が認められる要件のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 ⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

【解答】
①【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促は行いません。
(第86条第1項)
②【H25年出題】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる」ではなく、「同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる」です。
(第86条第2項)
③【H25年出題】
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

【解答】
③【H25年出題】 〇
「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」の10日が覚えるポイントです。
(第86条第4項)
ちなみに、保険料の繰上徴収が認められる要件は次の通りです。
第85条 (保険料の繰上徴収) ① 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 (1) 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があつたとき。 ② 法人たる納付義務者が、解散をした場合 ③ 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 ④ 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 |
④【H25年出題】
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。

【解答】
④【H25年出題】 〇
なお、市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によって処分することができます。その場合、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4を当該市町村に交付しなければなりません。
(第86条第5項、第6項)
⑤【H25年出題】
厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の要件に該当し、納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないときは滞納処分の対象になります。
(第86条第5項第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-291 6.13
65歳以降の年金の併給ルール【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
1人に対して複数の年金の受給権が発生した場合でも、原則は「一人一年金」です。
ただし、併給が可能な組み合わせもありますので、おぼえましょう。
過去問を解きながらみていきます。
では過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
<65歳以上の老齢厚生年金について>
★併給可能な基礎年金との組み合わせ
・(老齢基礎年金+付加年金)+老齢厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
老齢厚生年金
|
|
老齢厚生年金 |
老齢基礎年金+付加年金
|
|
障害基礎年金 |
★老齢厚生年金は、遺族基礎年金とは併給できません。
(第38条、附則第17条)
②【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

【解答】
②【H24年出題】 〇
<65歳以上の遺族厚生年金について>
★併給可能な基礎年金との組み合わせ
・(老齢基礎年金+付加年金)+遺族厚生年金
・障害基礎年金+遺族厚生年金
遺族厚生年金
|
|
遺族厚生年金 |
老齢基礎年金+付加年金
|
|
障害基礎年金 |
(第38条、附則第17条)
③【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

【解答】
③【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第44条第1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金の子の加算)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
<受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給>
生計を維持している子がいる場合、老齢厚生年金も障害基礎年金も加算が行われます。その場合は、障害基礎年金に子の加算が加算され、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。
老齢厚生年金
|
子の加給年金額(支給停止) |
障害基礎年金
|
子の加算額が加算される |
④【H28年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【解答】
④【H28年出題】 〇
障害厚生年金
|
|
|
| どちらか 選択 |
老齢基礎年金 |
障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できませんので、どちらかを選択します。
遺族厚生年金
|
老齢基礎年金
|
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できます。
(第38条、附則第17条)
⑤【H26年出題】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
遺族厚生年金
|
障害基礎年金
|
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と障害基礎年金は併給できます。
(第38条、附則第17条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-280 6.2
(応用編)障害厚生年金5問【社労士受験対策】
過去問から学びます。
今日は厚生年金保険法です。
障害厚生年金の応用問題を解きながらポイントを確認しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。
しかし、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。
(第38条第1項)
②【H23年出題】
障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

【解答】
②【H23年出題】 〇
<2以上の障害が生じた場合>
★例えば、2級の障害厚生年金の受給権者に対して、更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されます。
2級 障害厚生年金 |
+ | 2級 障害厚生年金 |
= 併 合 | 1級 障害厚生年金 |
2級 障害基礎年金 | 2級 障害基礎年金 | 1級 障害厚生年金 |
この場合、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
(第48条)
問題文は、後から受給権を取得した障害厚生年金が、労働基準法の障害補償を受けるために支給停止されている場合の規定です。
その場合は、その停止すべき期間、併合した障害厚生年金ではなく、従前の障害厚生年金が支給されます。
(第49条第2項)
③【H23年出題】
障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
③【H23年出題】 〇
障害の程度が軽くなり、1級~3級の状態に該当しなくなったときは、障害不該当の届出が必要です。「速やかに」にも注意して下さい。
(則第48条)
④【H23年出題】
傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の 1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。

【解答】
④【H23年出題】 〇
障害厚生年金は、「初診日に厚生年金保険の被保険者」、「障害認定日に障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にある」、「保険料納付要件を満たしている」の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。障害認定日の年齢は関係ありません。
(第47条)
⑤【H23年出題】
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができない。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
ポイント!
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)とは、 ↓ 1度も1級、2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者のことです。 |
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができません。
下のイメージ図をご覧ください。
条文を読んでみましょう。
第52条第1項、2項、3項、7項、附則第16条の3第2項 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ⑦ ①から③までの規定は、65歳以上の者又は国民年金法の老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

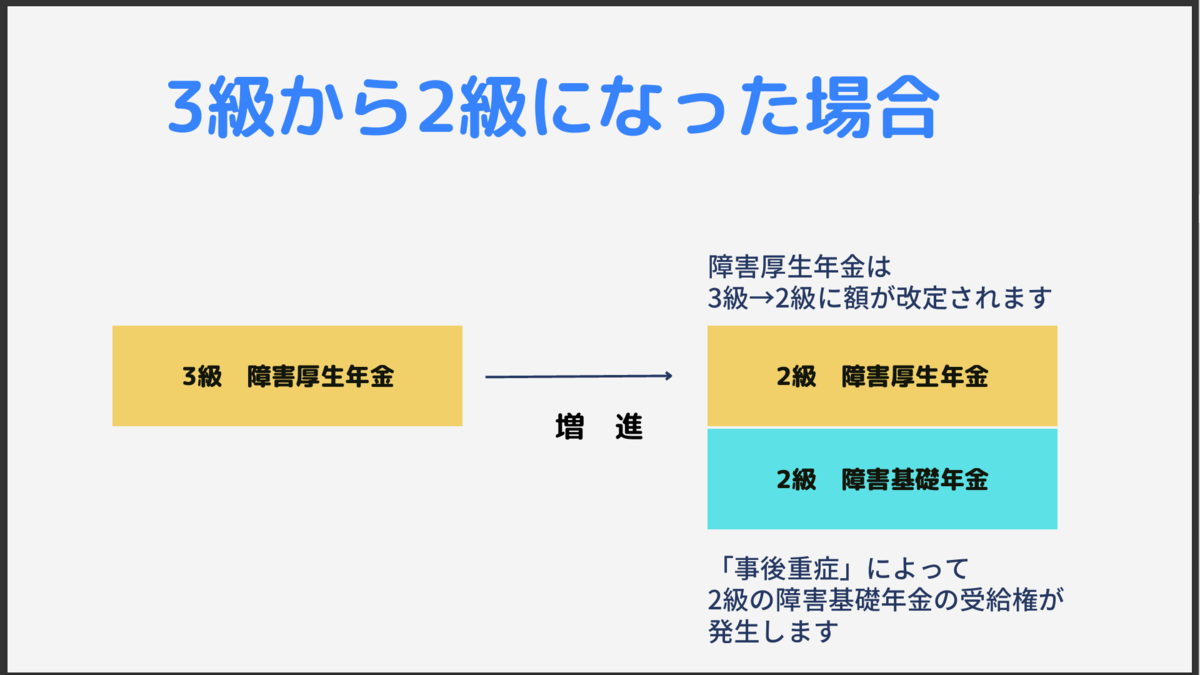
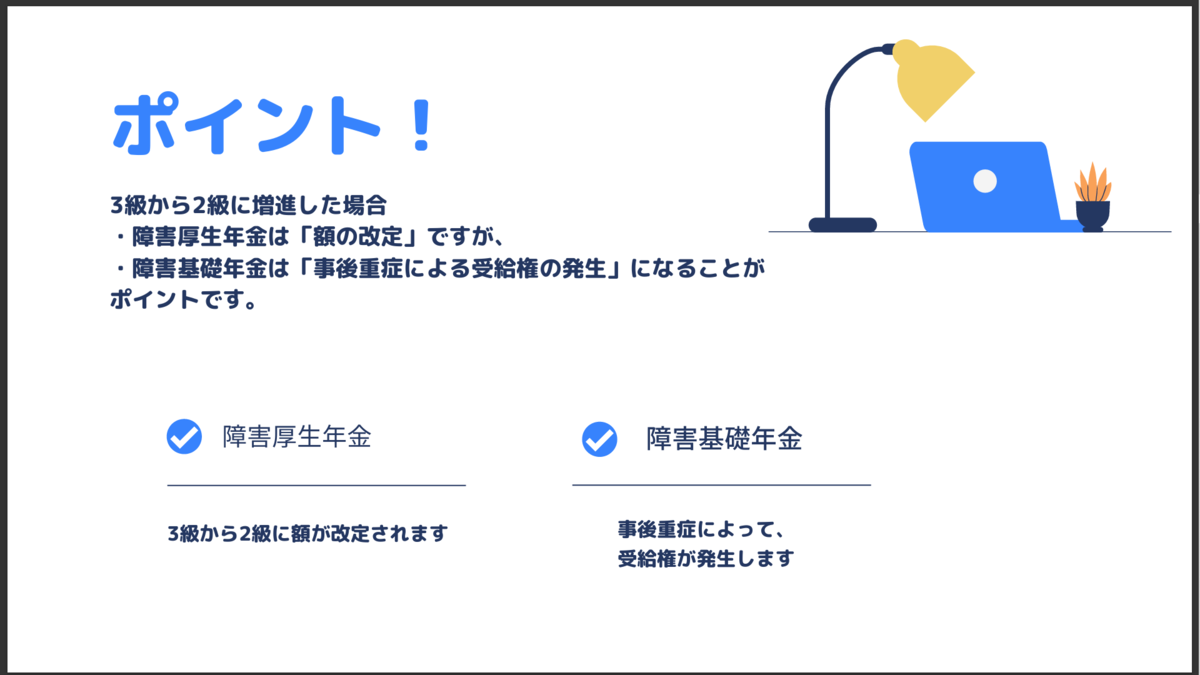
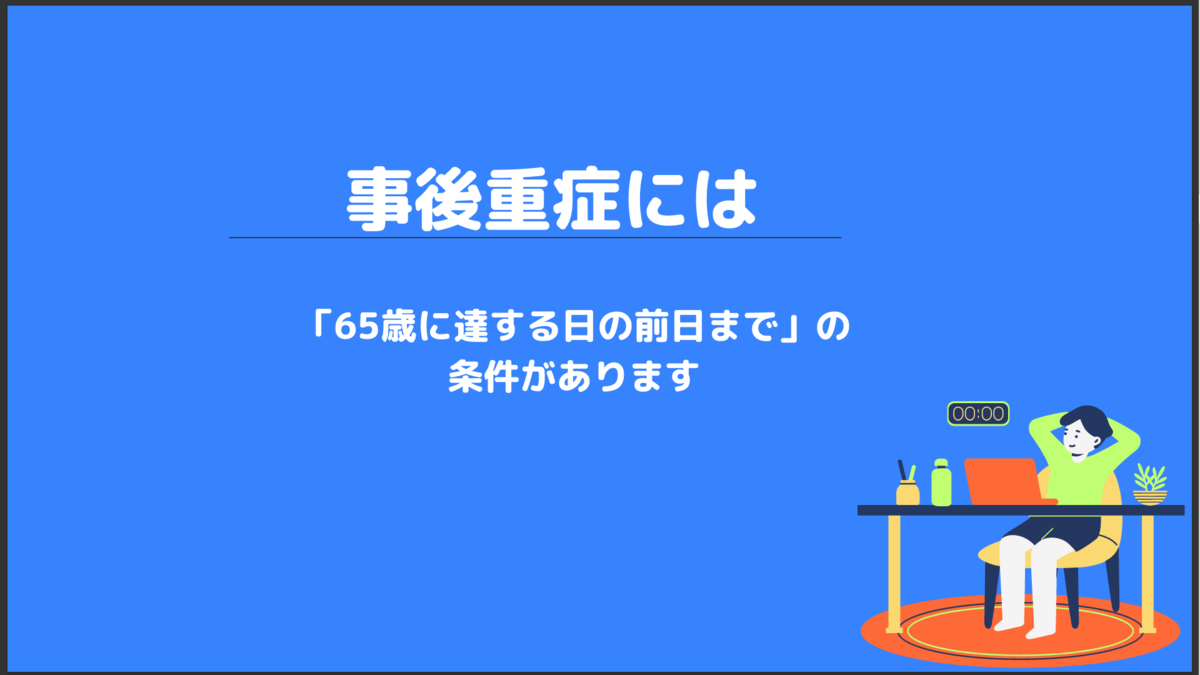
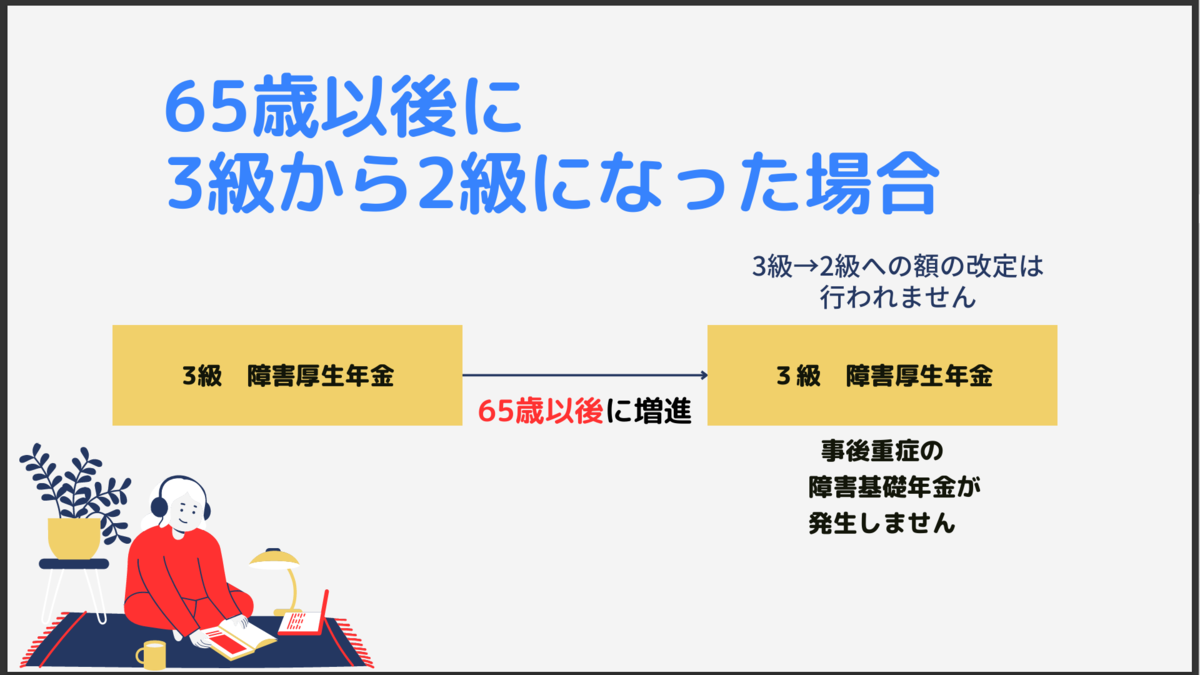
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-279 6.1
障害厚生年金重要5問【社労士受験対策】
過去問から学びます。
今日は厚生年金保険法です。
障害厚生年金の重要ポイントを確認しましょう。
まず、障害厚生年金の受給要件について条文を読んでみましょう。
第47条(障害厚生年金の受給権者) ① 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
障害厚生年金は、①「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」②「障害認定日に障害等級に該当していること」③「初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること」の3つを満たした場合は、障害認定日に受給権が発生します。
下の図でイメージしてみてください。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「軽度のものから」ではなく、「重度のものから1級、2級及び3級」です。
(第47条第2項)
ちなみに、「国民年金法」の障害等級は、「重度のものから1級及び2級」とされています。国民年金法の障害等級には3級はありません。(国民年金法第30条第2項)
②【H22年出題】※改正による修正あり
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。

【解答】
②【H22年出題】 〇
障害厚生年金の加給年金額のポイント!
★対象は65歳未満の配偶者です
「子」は障害基礎年金の加算対象になります
★加給年金額が加算されるのは1級と2級です
「3級」には加給年金額は加算されません
★障害厚生年金の権利を取得した日の翌日以後に対象になる配偶者を有するに至った場合も対象になります
→ 配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から加給年金額が加算されます
条文を読んでみましょう。
第50条の2第1項~3項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
③【H22年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

【解答】
③【H22年出題】 ×
240か月ではなく、300か月です。
条文を読んでみましょう。
第50条第1項、2項 (障害厚生年金の額) ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①の額の100分の125に相当する額とする。 |
★障害厚生年金は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額です。
★ただし、被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。
★1級は、2級の1.25倍の額です。
④【H22年出題】
障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。

【解答】
④【H22年出題】 ×
3級の障害厚生年金の額は、「2級」の額と同じです。
ただし、加給年金額は加算されません。
なお、3級の障害厚生年金には最低保障額が設定されています。
条文を読んでみましょう。
第50条第3項 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とする。 |
⑤【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。

【解答】
⑤【H22年出題】 ×
障害認定日の属する月の前月までではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とします。
条文を読んでみましょう。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
例えば障害認定日が4月に属する場合
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|
|
| 障害認定日 |
|
|
計算に入るのは4月(障害認定日の属する月)までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
年金制度の歴史をお話します
R6-274 5.27
年金制度のポイントは昭和36年と昭和61年【社労士受験対策】
年金制度の歴史をお話します。
<厚生年金保険と国民年金の誕生>
①船員保険制度
昭和14年制定、昭和15年施行
社会保険方式による日本初の公的年金制度
など
②厚生年金保険法
労働者年金保険法としてスタート
など
③国民年金法
昭和36年4月より拠出制がスタートしたことによって
国民皆年金の実現!
<旧法から新法へ>
④基礎年金の登場 昭和61年4月
・昭和61年4月1日前を「旧法」、昭和61年4月1日以後を「新法」といいます
・年金制度が2階建てになりました
・国民年金の被保険者が第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されました
⑤新法と旧法の違い
1 旧法は「縦割り」、新法は「2階建て」
2 専業主婦は旧法では任意加入、新法では第3号被保険者として強制加入です
3 船員保険は旧法では独立していましたが、新法では厚生年金に統合されました
詳しくは、YouTubeでお話ししています。
YouTubeをご覧ください
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/UMR4m6jvQr4?si=Be9bRoLQwbXNt3vy
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-266 5.19
老齢厚生年金の支給繰上げ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
老齢厚生年金の支給繰上げについて条文を読んでみましょう。
附則第7条の3第1項・2項 (老齢厚生年金の支給の繰上げ) ① 当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法の任意加入被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。 (1) 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者 (2) 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者 ※(3)と(4)は省略します。 ② 繰上げの請求は、国民年金法の老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。 |
(1)と(2)は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが完了し、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳からとなる世代です。
この世代は、60歳以上65歳未満の間に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができます。
60歳 | 65歳 |
| 老齢厚生年金
|
| 老齢基礎年金
|
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰上げと老齢基礎年金の支給繰上げの請求は同時に行わなければなりません。
(附則第7条の3第2項)
②【R4年出題】
昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

【解答】
②【R4年出題】 〇
繰り上げた老齢厚生年金の額は、政令で定める額を減じた額となります。
(附則第7条の3第4項)
減額率は、「1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」です。
問題文の場合は、1,000分の4×60か月=24%です。
(令6条の3)
なお、昭和37年4月1日以前生まれの場合は、1,000分の4ではなく「1,000分の5」で計算します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-265 5.18
障害の状態にある子の遺族厚生年金の受給権の消滅【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、「配偶者、子、父母、孫又は祖父母で、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」です。
このうち、「子、孫」については、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」が条件です。
今日は、障害状態にある子、孫の遺族厚生年金の受給権の消滅についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (2) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (3) 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
ポイント!
国民年金法と厚生年金保険法では「障害等級」の定義が異なります。
国民年金法では、「1級、2級」ですが、厚生年金保険法では「1級、2級、3級」です。
厚生年金保険法の条文では、「障害等級の1級又は2級」という表現に注意してください。厚生年金保険法の条文で単に「障害等級」と書かれていれば、1級、2級、3級です。「障害等級の1級又は2級」と書かれていれば1級と2級限定です。3級は含まれません。
(1)について
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権
※18歳年度末時点で1級・2級のときは失権しない。
(2)について
・1級・2級に該当しなくなったときは失権
※障害要件を満たさなくなっても18歳の年度末までは失権しない。
(3)について
・1級・2級でも20歳に達したときは失権
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 〇
障害の状態にあるときでも障害等級が3級の場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の遺族厚生年金の受給権は消滅します。
(第63条第2項第1号)
②【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
前半は正しいです。
遺族厚生年金の 受給権発生 ▼ | 16歳 3級に該当 ▼ | 18歳年度末 失権 ▼ |
|
|
|
後半は誤りです。
遺族厚生年金の 受給権発生(2級) ▼ | 18歳年度末 (2級) ▼(失権しない) | 19歳 3級 ▼失権 |
|
|
|
2級に該当する子が19歳のときに3級に該当した場合は、「20歳に達したとき」ではなく、1級2級に該当しなくなったとき(3級に該当したとき)に失権します。
(第63条第2項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-251 5.4
老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権を得た場合の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額を除いた額とする。)の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
★ 65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給できます。
ただし、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は「老齢厚生年金の額に相当する部分」の支給が停止されます。
■ 遺族厚生年金 > 老齢厚生年金の場合
遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額部分が支給されます。
老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
|
| 支給される |
支給される |
| 支給停止 老齢厚生年金の額に相当する部分 |
■ 遺族厚生年金 ≦ 老齢厚生年金の場合
遺族厚生年金は、全額支給停止されます。
老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
支給される |
|
|
| 支給停止
|
★ 遺族厚生年金と65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は併給できません。どちらかを選択することになります。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額よりも高い場合は、遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額部分が支給されます。
(第64条の2)
②【R3年出題】
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

【解答】
②【R3年出題】 〇
ポイント!
 「繰上げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求しなければなりません。
「繰上げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求しなければなりません。
「繰下げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方でも可能です。
 繰下げ待機中の68歳で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遡って65歳に達した月の翌月から老齢厚生年金を受給することができます。ただし、繰下げしませんので増額されません。
繰下げ待機中の68歳で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遡って65歳に達した月の翌月から老齢厚生年金を受給することができます。ただし、繰下げしませんので増額されません。
なお、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることもできます。その場合の増額率は遺族厚生年金の受給権を取得した時点で計算され、遺族厚生年金の受給権が発生した月の翌月から支給されます。
 老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができます。
老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができます。
(第44条の3、第64条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-250 5.3
65歳以上の配偶者の遺族厚生年金の額【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日は遺族厚生年金の額の算定方法をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第60条第1項、附則第17条の2 ① 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、(1)に定める額とする。 (1) 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 (2) 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき (1)に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ (1)に定める額に3分の2を乗じて得た額 ロ 遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額を除いた額とする。)に2分の1を乗じて得た額 |
(1)遺族厚生年金の額の原則の算出方法
死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額 × 4分の3
(2)老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者の場合
次のうち、どちらか高い方の額になります。
・(1)の計算方法による額
又は
・「(1)の額×3分の2」+「本人の老齢厚生年金の額×2分の1」
★具体的に計算しましょう。
例えば、夫が死亡し、65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する妻が遺族厚生年金を受ける場合で、死亡した夫の老齢厚生年金が80万円、妻の老齢厚生年金が50万円の場合の遺族厚生年金の額は①か②のどちらか高い方になります。
①死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額 × 4分の3
80万円 × 4分の3 = 60万円
②「①の額×3分の2」+「本人の老齢厚生年金の額×2分の1」
「60万円×3分の2」+「50万円×2分の1」= 65万円
遺族厚生年金の額は、高い方の②65万円になります。
※なお、遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①の額になります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
遺族厚生年金の額には、最低保障額は設定されていません。
(第60条第1項)
②【R3年出題】
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

【解答】
②【R3年出題】 ×
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)に支給される遺族厚生年金の額は、次のうちいずれか高い方です。
・ 死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額(Aとします)
・ 「Aの額に3分の2を乗じて得た額」と「配偶者の老齢厚生年金の額(加給年金額を除いた額とする。)に2分の1を乗じて得た額」を合算した額
(第60条第1項第2号、附則第17条の2第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-249 5.2
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第23条の2 (育児休業等を終了した際の改定) ① 実施機関は、育児・介護休業法に規定する育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において子であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 ② 改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 ③ 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者について、①の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。 |
《例えば、5月10日に育児休業等を終了し、3歳未満の子を養育している場合〉
★育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(5月・6月・7月)の報酬の総額をその期間の月数で除して得た額(平均額)を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。
★3月間のうち、報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月は除いて平均額を出します。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用されている事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
育児休業等を終了した際の改定も産前産後休業を終了した際の改定も、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除いて報酬月額を計算します。
(第23条の2第1項、第23条の3第1項)
②【R1年出題】
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額」で算定します。
4月20日に育児休業から復帰した場合は、「4月10日に支払った給与」、「5月10日に支払った給与」、「6月10日に支払った給与」の平均で判断します。なお、報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外して平均します。
4月 | 5月 | 6月 |
育児休業等終了日の翌日(4月20日)が属する月 |
|
|
育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間 | ||
(第23条の2第1項)
③【H29年出題】
平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

【解答】
③【H29年出題】 〇
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 育児休業等終了日の翌日(6月1日)が属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月 |
| 育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間 | 改定 | ||
5月31日に育児休業を終了し、6月1日に職場復帰した場合、育児休業等終了日の翌日(6月1日)が属する月以後3月間(6月・7月・8月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。
標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日(6月1日)から起算して2月を経過した日の属する月の翌月(9月)から改定されます。
事業主は、「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除できます。改定された9月の保険料は、10月に支給する報酬から控除することができます。
(第23条の2第2項、第84条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-231 4.14
社労士受験のための 遺族厚生年金が支給される条件
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の支給要件の条文を読んでみましょう。
第58条第1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、①又は②に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ①被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 ② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 ③ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 ④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
<保険料納付要件>
①か②の場合は、「死亡日の前日の保険料納付要件」が問われます。
・原則
死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間中に、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
・特例
令和8年4月1日前に死亡した場合(死亡日に65歳未満であること)は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないこと。(S60法附則第64条第2項)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
20歳未満でも、「厚生年金保険の被保険者」が死亡した場合は、①に該当し、遺族厚生年金の支給条件を満たします。
(第58条第1項第1号)
②【H28年出題】
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
②【H28年出題】 〇
①「厚生年金保険の被保険者が死亡したとき」の被保険者には、「失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったもの」も含まれます。
(第58条第1項第1号)
③【H28年出題】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
③【H28年出題】 〇
初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後にその傷病により、その初診日から起算して5年以内に死亡した場合は、遺族厚生年金の支給要件を満たします。「初診日」から5年以内です。「喪失日」からと間違えないようにしましょう。
(第58条第1項第2号)
④【H28年出題】※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。なお、設問の者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である。

【解答】
④【H28年出題】 〇
④には、「離婚時みなし被保険者期間を有する者」が含まれます。
国民年金の第1号被保険者期間しか有していない者でも、離婚時みなし被保険者期間を有することで、老齢厚生年金の受給権が発生します。そのような者が死亡した場合、要件を満たせば、一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
(第58条第1項第4号、第78条の11)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-230 4.13
(厚年)任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「任意適用事業所」の認可について条文を読んでみましょう。
第6条第3項、4項 ③ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
「強制適用事業所」と任意適用事業所を整理しましょう。
個人経営 | 法人 | |||
適用業種 | 非適用業種 | 業種・人数 問わず | ||
5人以上 | 5人未満 | 5人以上 | 5人未満 | |
強制 | 任意 | 任意 | 任意 | 強制 |
なお、令和4年10月から、常時5人以上の従業員を使用する士業の個人事業所(弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業)は、強制適用事業になっています。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「農業、林業、漁業」は、非適用業種ですので、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主は、適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要があります。
(第6条第3項)
②【R1年出題】
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

【解答】
②【R1年出題】 ×
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の青果商は強制適用事業所です。従業員数が4人になったとしても、任意適用事業所の認可があったとみなされ、適用事業所の資格は継続します。任意適用事業所の認可申請を行う必要はありません。
(第7条)
③【H28年出題】
その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主はどれか。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

【解答】
③【H28年出題】
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主について
「宿泊業、飲食サービス業」は非適用業種です。個人経営の旅館の事業主は、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければなりません。
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主について
「貨物積み卸し業」は、適用業種です。常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業所は強制適用事業所ですので、認可は不要です。
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主について
「理容業、美容業」、「娯楽業」は非適用業種です。個人経営の理容業の事業主は、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければなりません。
エ 常時使用している船員が5人から4人に減少した船舶所有者について
「船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶」は厚生年金保険の強制適用事業所です。人数に関係なく強制適用事業所となります。
(法第6条第1項第3号)
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主について
「教育、学習支援業」は適用業種です。常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業は強制適用事業所ですので、認可は不要です。
適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主は、 アとウです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-216
R6.3.30 加給年金額の調整(老齢厚生年金と障害基礎年金)
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「加給年金額」が加算される条件を条文で読んでみましょう。
第44条第1項 (加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法の障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
★老齢厚生年金(被保険者期間が240月(20年)以上あること)の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
(詳しくは、昨日の記事をどうぞ)
今日は、ただし以下の部分をみていきます。
65歳以上の者は、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できます。
障害基礎年金に子の加算が行われているときは、その間、老齢厚生年金の子についての加給年金額は支給停止されます。
障害基礎年金と老齢厚生年金に二重に子に対する加給年金額が加算されることを防ぐための規定です。
老齢厚生年金
| →子の加給年金額(支給停止) |
障害基礎年金
| →子の加算額が加算される |
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
65歳に達している受給権者に係る老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

【解答】
①【H24年出題】 〇
老齢厚生年金と障害基礎年金を併給する場合、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるときは、老齢厚生年金の子に対する加給年金額は支給が停止されます。
(第44条第1項)
②【H29年出題】
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
②【H29年出題】 〇
①と同じ問題です。子の加算額が加算された障害基礎年金と子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給される場合は、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。
(第44条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-215
R6.3.29 加給年金額が加算される条件
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「加給年金額」が加算される条件を条文で読んでみましょう。
第44条第1項 (加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法の障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
加給年金額が加算される要件を確認しましょう。
★老齢厚生年金(被保険者期間が240月(20年)以上あること)の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときに加給年金額が加算されます。
★老齢厚生年金の受給権を取得した当時、被保険者期間が240月未満の場合
→老齢厚生年金の受給権取得後も厚生年金保険に加入し、在職定時改定又は退職時改定で年金額が再計算されたときに240月以上になった場合は、そのときに生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
★加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間が240月(20年)以上あることが条件ですが、中高齢の資格期間短縮特例に該当する場合は、15年~19年でも要件を満たします。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
【H30年出題】 ×
被保険者資格を喪失し、年金額を再計算した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、その時点で、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されます。
(第44条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-200
R6.3.14 受給権者の申出による支給停止
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条の2第1項・3項 (受給権者の申出による支給停止) ① 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 ③ ①の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。 |
年金の支給停止を希望する受給権者は、申出により年金の「全額」を支給停止(辞退)することができます。
申出により辞退できるのは「全額」です。一部だけの辞退はできません。
また、いつでも、支給停止の撤回の申出をすることができます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。
②【H26年出題】
受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない。
③【H20年出題】
厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月から支給が開始される。

【解答】
①【R2年出題】 〇
年金がその額の一部につき支給を停止されている場合は、「停止されていない部分の額」の支給停止の申出をすることができます。
(第38条の2第1項ただし書)
②【H26年出題】 ×
老齢基礎年金と老齢厚生年金のように支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない、という規定はありません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金はそれぞれ別個に支給停止の申出ができます。
<特例があります>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は特例があります。
第78の23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第38条の2第1項に規定する年金たる保険給付についての支給停止の申出又は撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。 |
③【H20年出題】 〇
・受給権者が支給停止の申出をしたとき
→申出を行った日の属する月の翌月から支給停止されます。
・支給停止の申出を撤回したとき
→撤回の申出を行った日の属する月の翌月から支給が開始されます。
条文を確認しましょう。
第36条第2項 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-199
R6.3.13 併給可能な組み合わせ
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条第1項、附則第17条 (併給の調整) 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金 及び 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。 |
★年金は「1人1年金」が原則です。2つ以上の年金を受けることができる場合は、いずれか1つを選択し受給します。なお、選択しなかった年金は支給停止となります。
★同じ理由の年金は、基礎年金と厚生年金の2階建てで支給されます。
老齢厚生年金
|
| 障害厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
|
| 障害基礎年金 |
| 遺族基礎年金 |
★65歳以降のみ可能な組み合わせがあります。
遺族厚生年金
|
| 遺族厚生年金 |
老齢厚生年金 | ||
老齢基礎年金
|
| 老齢基礎年金 |
老齢厚生年金
|
| 遺族厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢厚生年金 | ||||
障害基礎年金
|
| 障害基礎年金 |
| 障害基礎年金 |
65歳以上の組み合わせのポイント!
老齢・遺族
|
|
老齢・障害
|
← 自身が負担した保険料を反映させるため |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
②【H23年出題】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
③【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
④【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
⑤【H26年出題】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
⑥【H28年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
⑦【R4年出題】
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38条第1項及び同法附則第17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金

【解答】
①【H30年出題】 ×
60歳で(A)「障害基礎年金+障害厚生年金」と(B)「特別支給の老齢厚生年金」の受給権がある場合は、(A)と(B)のどちらか一方を選択します。
(B)を選択した場合、障害基礎年金は併給されません。
(第38条第1項)
②【H23年出題】 ×
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。
しかし、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。
(第38条第1項)
③【H24年出題】 〇
65歳に達していても、老齢厚生年金は遺族基礎年金とは併給できません。
(第38条第1項、附則第17条)
④【H24年出題】 〇
65歳に達している場合、「(老齢基礎年金及び付加年金)+(遺族厚生年金)」又は「(障害基礎年金)+(遺族厚生年金)」の組み合わせができます。
(第38条第1項、附則第17条)
⑤【H26年出題】 〇
65歳以上の場合、遺族厚生年金と障害基礎年金は併給されます。
(第38条第1項、附則第17条)
⑥【H28年出題】 〇
65歳以上でも、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」は併給されません。
「遺族厚生年金」と「老齢基礎年金」は65歳以上の場合は併給されます。
(第38条第1項、附則第17条)
⑦【R4年出題】
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金 → 同一事由なので併給される
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給されない
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金 → 65歳以上の場合併給される
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金 → 65歳以上の場合併給される
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給されない
「どちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せ」は、イとオの2つです。
(第38条第1項、附則第17条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-185
R6.2.28 年金の支給期間と支払期月
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第36条 (年金の支給期間及び支払期月) ① 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 ② 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 ③ 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 |
年金の支給・支給停止は、月単位で行われ、「翌月」から「消滅月」までです。
3月 | 4月 | ~ | 10月 | 11月 |
受給権発生 | 開始 | 消滅 |
|
例えば、3月に年金の受給権が発生し10月に権利が消滅した場合は、年金は4月から10月まで支給されます。
年金は、6期にわけて偶数月に支払われ、後払いです。例えば、2月に支払われる年金は、12月分と1月分です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。
②【H28年出題】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
③【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする」という例外があります。例えば、さかのぼって過去の分が支払われる場合などは、奇数月に支払われることがあります。
(第36条第3項)
②【H28年出題】 ×
障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合は、「障害認定日」に障害厚生年金の受給権が発生します。そのため、障害厚生年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
障害認定日が月の初日でも、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
(第36条第1項)
③【H30年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、死亡した日の翌日(翌月の1日)に資格を喪失します
一方、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生し、遺族厚生年金は死亡した日の属する月の翌月から支給されます。
(第14条第1号、第36条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-184
R6.2.27 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
厚生年金保険の被保険者は4つの種別に分かれています。(第2条の5第1項)
第1号厚生年金被保険者
→ 第2号から第4号以外の被保険者(民間企業の会社員等)
第2号厚生年金被保険者
→ 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第3号厚生年金被保険者
→ 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第4号厚生年金被保険者
→ 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
今日は、異なる被保険者の種別に係る資格の得喪です。
条文を読んでみましょう。
第18条の2 ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日に当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者の資格が同時に適用されることはありません。「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「当日喪失」がポイントです。
(第18条の2)
②【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合は、「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「選択」することはありませんので、2以上事業所選択届の届出は不要です。
(第18条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-173
R6.2.16 老齢厚生年金の支給要件
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。 (1) 65歳以上であること。 (2) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
老齢厚生年金は、「厚生年金保険の被保険者期間」があり、「65歳以上」で、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上ある(=老齢基礎年金を受けることができる)」場合に支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
②【H30年出題】
老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
■65歳以上が対象の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、要件を満たします。
■60歳以上65歳未満が対象の特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要です。
(法第42条、法附則第8条)
②【H30年出題】 ×
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときで、その月にさらに被保険者の資格を取得していない場合は、その月は1か月として被保険者期間に算入されます。(同月得喪といいます。)
問題文は、老齢基礎年金を受給している66歳の者が、厚生年金保険の被保険者期間を1か月有することになり、要件を満たしますので、老齢厚生年金が支給されます。
(法第19条第2項、第42条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-163
R6.2.6 子・孫の遺族厚生年金の受給権の消滅
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の受給権者となる「子又は孫」の要件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。(第59条第1項第2号)
では、「子・孫」の遺族厚生年金の受給権の消滅について条文を読んでみましょう。
第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (2) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (3) 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
②【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。
③【H19年出題】
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 〇 ※改正による修正あり
子の遺族厚生年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に消滅します。ただし、障害等級1級又は2級の障害の状態にあるときは消滅しません。
問題文は、「障害等級3級の障害の状態」ですので、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。
(法第63条第2項第1号)
②【R1年出題】 ×
(前半部分)正しい
受給権発生 16歳 18歳年度末
▼ ▼ ▼
2級 | 3級 |
失権
遺族厚生年金の受給権発生時は障害等級2級でしたが、その後16歳のときに障害等級3級になりました。18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき「3級」ですので、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに受給権は消滅します。
(後半部分)誤り
受給権発生 18歳年度末 19歳
▼ ▼ ▼
2級 |
| 3級 |
失権
18歳に達した日以後の最初の3月31日では2級ですので、その時点では遺族厚生年金の受給権は消滅しません。その後19歳のときに3級になった場合は、その時点で受給権は消滅します。20歳で消滅するは誤りです。
(法第63条第2項)
③【H19年出題】 〇
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫の遺族厚生年金の受給権について
・1級又は2級に該当しなくなったとしても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは受給権は消滅しません。
・例えば、19歳で1級又は2級に該当しなくなった場合は、その時点で受給権は消滅します。
・1級又は2級のまま20歳に達したときは、その時点で受給権は消滅します。
(法第63条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-153
R6.1.27 障害手当金が支給されないとき
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
障害手当金は、以下の要件を満たした場合に支給されます。
・初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと
・初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日に、政令で定める程度の障害の状態にあること
しかし、法第56条に該当する場合は、障害手当金は支給されません。
条文を読んでみましょう。
第56条 障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 (1) 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) (2) 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) (3) 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
|
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者に障害手当金は支給されない。
②【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
③【H18年出題】
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く。)には支給しない。
④【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
①【R4年出題】 〇
障害の程度を定めるべき日に年金たる保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)の受給権者である場合は、原則として障害手当金は支給されません。
※障害の程度を定めるべき日に「国民年金法による年金たる給付の受給権者」である場合も、原則として障害手当金は支給されません。
(法第56条第1号)
②【H30年出題】 ×
障害の程度を定めるべき日に老齢厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
(法第56条第1号)
③【H18年出題】 〇
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者には、原則として支給されません。
ただし、障害厚生年金の受給権者でも、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者には、障害手当金が支給されます。
※障害基礎年金の受給権者も同じです。
(法第56条第1号)
3級未満 65歳
障害厚生年金 支給 | 3級未満(支給停止) | |
| 3年 | ※ |
障害厚生年金の受給権者 | ||
※網掛けの部分 → 障害手当金が支給されます。
④【R3年出題】 ×
障害の程度を定めるべき日に、当該傷病について労働者災害補償保険法の障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には障害手当金は支給されません。
問題文では、同じ傷病で、労災保険法の障害補償給付の受給権も取得していますので、障害手当金は支給されません。
(法第56条第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-145
R6.1.19 2以上の事業所に使用される場合の各事業主が負担する保険料の額
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第82条第3項 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
令第4条第2項 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。 |
各事業主が負担する標準賞与額に係る保険料の額は以下の通りです。
被保険者の保険料の半額 × | その月に各事業主が支払った賞与額 |
その月に当該被保険者が受けた賞与額 |
その被保険者の保険料の半額を各事業所の賞与額で按分します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。

【解答】
【R5年出題】 ×
「当該被保険者の保険料の額」ではなく、「当該被保険者の保険料の半額」に乗じて得た額とされています。
保険料は、被保険者と事業主が半額ずつ負担します。
(令第4条第2項)
では、こちらの過去問もどうぞ!
【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。

【解答】
【H28年出題】 〇
同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は以下の通りです。
被保険者の保険料の半額 × | 各事業所について算定した報酬月額 |
当該被保険者の報酬月額 |
※各事業所について算定した報酬月額とは、
各事業所について定時決定、資格取得時決定、随時改定若しくは育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定又は保険者算定の規定により算定した報酬月額です。
(令第4条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-143
R6.1.17 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
まず条文を読んでみましょう。
第63条第1項第5号 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときは、消滅する。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき → 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 |
(イについて)
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき(子がいない妻)→ 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに失権します。
夫死亡
妻26歳 30歳 31歳失権
遺族厚生年金 |
|
▲ 5年 |
|
(ロ)について
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻(子がいる妻)が30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに失権します。
夫死亡
妻27歳 28歳 30歳 33歳失権
遺族厚生年金 | |
遺族基礎年金 | ▲ 5年 |
子死亡
遺族基礎年金失権
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
②【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。
③【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻で、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合(子がいない場合)、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その遺族厚生年金の受給権は消滅します。
(法第63条第1項第5号イ)
②【R3年出題】 ×
27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該遺族厚生年金の受給権は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき」に消滅します。
(法第63条第1項第5号イ)
③【H29年出題】 ×
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻(子がある妻)で、妻が30歳に到達する日前に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。
(法第63条第1項第5号ロ)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

【解答】
【R5年出題】 〇
「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から5年を経過したときに消滅します。
(法第63条第1項第5号ロ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-142
R6.1.16 標準報酬月額等級の最高等級
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第20条第2項 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 |
厚生年金保険の標準報酬月額等級は、1等級から32等級に区分されています。
1等級の標準報酬月額は88,000円、最高等級の32等級の標準報酬月額は650,000円です。
では過去問をどうぞ!
【R1年出題】※改正による修正あり
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第32級650,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】
【R1年出題】 ×
最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、その年の4月1日からではなく、「その年の9月1日」からです。
(法第20条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
毎年3月31日(「12月31日」は誤りです。)における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる(「改定を行わなければならない」は誤りです)。
(法第20条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-141
R6.1.15 障害基礎年金との併合による障害厚生年金の改定
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
初診日 初診日
厚生年金保険の被保険者 国民年金第1号被保険者
2級 障害厚生年金 |
|
|
2級 障害基礎年金 | + 併 合 | 2級 障害基礎年金 |
↓
↓
| 1級 障害厚生年金 | 障害基礎年金に合わせて 1級に改定 |
| 1級 障害基礎年金 | 前後の障害を併合して 1級 |
さっそく令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。

【解答】
【R5年出題】 〇
先ほどの図にあてはめて確認しましょう。
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給しています。現在は、自営業を営み、国民年金に加入していますが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じました。
初診日 初診日
厚生年金保険の被保険者 国民年金第1号被保険者
2級 障害厚生年金 |
|
|
2級 障害基礎年金 | + 併 合 | 2級 障害基礎年金 |
前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定されます。
| 1級 障害厚生年金 |
|
| 1級 障害基礎年金 |
|
(法第52条の2第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-140
R6.1.14 離婚時みなし被保険者期間の扱い
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第78条の6第1項~3項 ① 実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 (1) 第1号改定者 改定前の標準報酬月額に一から改定割合( 按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た額 (2) 第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 ② 実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 (1) 第1号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額 (2) 第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 ③ 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。 |
★③が「離婚時みなし被保険者期間」です。
例えば、夫が第1号改定者、妻が第2号改定者で妻が標準報酬月額を有しない場合
夫 | 妻 |
|
標準報酬月額
|
零 | |
↓
分 割
↓
夫 | 妻 |
|
|
標準報酬月額 | 標準報酬月額 |
妻(第2号改定者)は厚生年金保険の被保険者でないのがポイントです。
しかし、離婚分割によって報酬額の記録が分割され、第2号改定者の厚生年金保険の被保険者期間であったものとみなされます。この期間を離婚時みなし被保険者期間といいます。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
②【H27年出題】
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
③【R3年出題】
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。
④【H28年出題】※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算には入りません。
なお、報酬比例部分の計算には入ります。
(法附則第17条の10)
②【H27年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間が必要ですが、「離婚時みなし被保険者期間」は1年の計算に入りません。
そのため厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみの場合は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(法附則第17条の10)
③【R3年出題】 〇
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上必要です。その被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
(法第78条の11)
④【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)は、遺族厚生年金の長期要件に該当します。
遺族厚生年金の長期要件には、「離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。」とされています。
そのため、国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより、老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)は、遺族厚生年金の長期要件を満たします。
(法第78条の11)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の「1年以上の被保険者期間」には、離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
(法附則第17条の10)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-139
R6.1.13 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
法附則第9条の2 ① 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。 ② ①の請求があったときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があった月の翌月から、年金の額を改定する。 (1) 1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額 (2) 被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額 |
「報酬比例部分」のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が対象の特例です。
要件を満たすと、障害者特例として定額部分と報酬比例部分を合わせた年金(+加給年金額)が支給されます。
要件を確認しましょう。
①報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金の受給権者であること
②3級以上の障害状態にあること(厚生年金保険で規定する障害等級は1~3級です)
③退職していること(=厚生年金保険の被保険者でないこと)
受給権者の請求が必要で、原則として請求のあった月の翌月から年金額が改定されます。(請求があったものとみなされる例外もありますが、今日は触れません。)
<イメージ図>
昭和32年4月1日生まれの男性は62歳から報酬比例部分のみが支給されます。
(62歳) (65歳)
特別支給(報酬比例部分) | 老齢厚生年金 |
| 老齢基礎年金 |
↓
障害者特例に該当した場合は定額部分が支給されます。
↓
(62歳) (65歳)
特別支給(報酬比例部分) | 老齢厚生年金 |
定額部分 | 老齢基礎年金 |
それでは、過去問をどうぞ!
【H27年選択式】
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
(1) 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
(2) 被保険者期間が< A >以上であるとき
(3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が< B >以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 < C >であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、< D >である。
<選択肢>
A | ① 42年 ②43年 ③44年 ④45年 |
B | ① 10年 ②15年 ③20年 ④25年 |
C | ① (1)及び(2) ② (1)、(2)及び(3) ③ (2)のみ ④ (2)及び(3) |
D | ① (1)のみ ② (1)及び(2) ③ (1)及び(3) ④ (1)、(2)及び(3) |

【解答】
A ③ 44年
B ② 15年
C ① (1)及び(2)
D ① (1)のみ
(法附則第9条の2第1項、第2項、法附則第9条の3第1項、法附則第9条の4第1項)
(1)は障害者特例、(2)は長期加入者特例、(3)坑内員、船員の特例です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。

【解答】
【R5年出題】 ×
障害者特例の障害の状態は、障害等級1級、2級、3級です。1級又は2級に限定されません。
(法附則第9条の2第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-138
R6.1.12 70歳以上の使用される者のポイント
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
厚生年金保険の被保険者資格は、70歳に達したときに喪失します。
そのため、70歳以降に在職中でも厚生年金保険の保険料の負担はありません。しかし、在職老齢年金の仕組みが適用される場合があります。
条文を読んでみましょう。
第27条 (届出) 適用事業所の事業主又は第10条第2項(任意単独被保険者)の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
★70歳以上の使用される者とは
70歳以上の適用事業所に使用されるもので、法第12条各号の適用除外に該当しないものをいいます。
(則第10条の4)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。
②【H28年出題】
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。
③【R4年出題】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者が在職中に70歳に達し、引き続き当該事業所に使用される場合の届出についての問題です。
70歳以上の使用される者の要件に該当する場合は、事業主は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。
ただし、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における準報酬月額と同額である場合は、届出を省略することができます。
(則第15条の2第1項)
②【H28年出題】 ×
70歳以上の使用される者に在職老齢年金の仕組みが適用されるようになったのは、平成19年4月1日ですが、その時点で70歳以上だった昭和12年4月1日以前生まれの者には在職老齢年金の仕組みは適用されませんでした。
しかし、平成27年10月の改正で、昭和12年4月1日以前生まれの者にも、在職老齢年金の仕組みが適用されるようになりました。
③【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される70歳以上の使用される者については、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
(第46条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
在職老齢年金の対象になるのは、「70歳以上の使用される者」です。
適用事業所で使用される70歳以上の者でも、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、「70歳以上の使用される者」になりません。そのため、在職老齢年金の仕組みは適用されません。
(法第46条第1項、則第10条の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-137
R6.1.11 厚生年金保険の被保険者期間の計算
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
被保険者期間について条文を読んでみましょう。
第19条 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 ④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 ⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
③【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
④【R3年出題】
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月」単位で計算される期間です。
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間は、「被保険者であった期間」のことです。
例えば、令和6年1月11日に資格を取得し、同年5月30日に資格を喪失した場合、令和6年1月11日から5月29日までが「被保険者であった期間」で、令和6年1月から4月までの4か月間が「被保険者期間」です。
(第19条第1項)
②【H30年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。平成29年10月1日に資格取得、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、資格を取得した月(平成29年10月)から資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの5か月間です。資格を喪失した月(平成30年3月)は被保険者期間には算入されません。
(第19条第1項)
③【H28年出題】 〇
同一の月に資格の取得と喪失があるときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
例外で、「ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」と規定されています。
例外その1 「その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」
→ 後から資格取得した期間によって「1か月」で算入します。
例外その2 「その月に更に国民年金の被保険者(国民年金法の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したとき」
→ 同じ月に資格取得と喪失があり、その月に更に国民年金の第1号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得した場合は、その月は厚生年金保険の被保険者期間に算入されません。
問題文のように、平成28年3月1日に第1号厚生年金被保険者の資格取得、同年3月20日付けで退職、翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった場合は、平成28年3月は、厚生年金保険の被保険者期間に算入されません。
(第19条第2項)
④【R3年出題】 〇
同一の月において被保険者の種別(第1号、第2号、第3号、第4号の厚生年金被保険者の種別の変更)に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされます。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされます。
(第19条第5項)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
【R5年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。
(第19条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
ご質問の回答です 厚生年金保険法
R6-109
R5.12.14 遺族厚生年金の「長期要件」について
12月9日の記事を読んでくださった方から、遺族厚生年金の「長期要件」についてご質問いただきました。
ご質問 例えば、自営業等で20年間国民年金保険料を納め、会社員として5年間厚生年金の被保険者であった場合、併せて25年の加入期間があるので、長期要件に該当するという考えでよろしいでしょうか? |
では、遺族厚生年金の「長期要件」について条文を読んでみましょう。
第58条第1項第4号 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき |
「長期要件」は、保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある事が条件です。
次に、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の定義を読んでみましょう。
第3条第1項第1号、2号 ①保険料納付済期間 → 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 ②保険料免除期間 → 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。 |
<国民年金法第5条の定義>
① 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(保険料一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
② 「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。
★「保険料納付済期間」は、
「第1号被保険者として保険料を納付した期間」
+
「第2号被保険者としての期間」
+
「第3号被保険者としての期間」
で算定します。
ご質問の回答です
自営業等(国民年金第1号被保険者)として20年間保険料を納付し、会社員(第2号被保険者)として5年間厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、長期要件を満たします。
「長期要件」は、厚生年金保険の期間が長いということではなく、国民年金全体で25年以上という意味です。
過去問も解いてみましょう。
【R3年出題】
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。

【解答】
【R3年出題】 〇
保険料納付済期間と保険料免除期間と「合算対象期間」も合算した期間が25年以上である場合は、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当します。
(法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-108
R5.12.13 遺族厚生年金「生計維持」の条件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第59条第1項 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって「生計を維持した」ものであることが条件です。
「生計維持」についてみていきましょう。
まず、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
②【H29年出題】
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

【解答】
①【H25年出題】 ×
生計を維持していたと認められるのは、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者です。
問題文は、年額「850万円以上」の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない、となります。年額130万円以上ではありません。
(H23.3.23年発0323第1号)
②【H29年出題】 ×
生計維持関係の認定日は、「遺族厚生年金の受給権発生日」です。その後、給与収入が年収850万円未満に減少したとしても、遺族厚生年金の受給権は得られません。
(H23.3.23年発0323第1号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

【解答】
【R5年出題】 〇
生計維持に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとされています。
① 前年の収入が年額850万円未満である
② 前年の所得が年額655.5万円未満である
③ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、①又は②に該当する
④ ①、②又は③に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる
問題文は、前年収入が年額800万円であった者ですので、①に該当し、生計を維持していたと認められます。
(H23.3.23年発0323第1号
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-107
R5.12.12 父又は母と同居することになった子の遺族厚生年金
今日は、厚生年金保険法です。
「子」に対する遺族厚生年金の支給が停止されるときをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第66条第1項 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
①前条本文 → 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する
②次項本文 → 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する
③次条 → 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
遺族厚生年金の遺族の順位では、配偶者と子は同順位です。
例えば、夫が死亡し、妻と子が遺族となった場合、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生します。
ただし、妻が遺族厚生年金の受給権を有する間は、子の遺族厚生年金は支給停止されます。(第66条第1項)
※配偶者に対する遺族厚生年金が、①、②、③によって支給停止されている間は、子に遺族厚生年金が支給されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
遺族厚生年金を受給している子が、死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、子に対する遺族厚生年金は支給停止されません。
国民年金法の遺族基礎年金の子に対する支給停止事由との違いに注意しましょう。
国民年金の遺族基礎年金については、「子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」という規定があります。
厚生年金保険法の子に対する遺族厚生年金の支給停止事由には、「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-106
R5.12.11 繰下げ加算額の算定
今日は、厚生年金保険法です。
老齢厚生年金の繰下げの申出をした者に支給される繰下げ加算額をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第44条の3第4項 支給繰下げの申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額及び在職老齢年金の規定によりその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
令第3条の5の2第1項 政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として計算した老齢厚生年金の額に平均支給率を乗じて得た額に増額率(1000分の7に受給権取得月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 |
繰下げた老齢厚生年金には、繰下げ加算額が加算されます。
・ 繰下げ加算額は「受給権取得月前被保険者期間」を基礎として計算します。
・ 在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる額は、増額の対象になりません。
・ 増額率は、「0.7%×繰下げた月数(65歳に到達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)」です。「繰り下げた月数」の上限は120ですので、増額率は最大で84%となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定めるとする。

【解答】
【R5年出題】 ×
繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月「の前月」までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額となります。
繰下げ加算額の計算は、「老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額」が基準となります。また、在職老齢年金の仕組みにより支給停止される額は、繰下げ加算額の対象になりません。
(法第44条の3第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-105
R5.12.10 特例的な繰下げみなし増額制度
今日は、令和5年度の厚生年金保険法の改正点です。
令和5年4月の改正で創設された「特例的な繰下げみなし増額制度」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第44条の3第5項 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき。 2 当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき。 |
ポイントを確認しましょう!
<改正前>
・65歳で老齢厚生年金の受給権を取得し、裁定請求しないまま73歳になりました。
73歳で老齢厚生年金を裁定請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、73歳からさかのぼって5年分の年金がまとめて支給されます。改正前は、まとめて支給される5年分には繰下げの増額分は加算されませんでした。なお、65歳から68歳までの3年分は時効で消滅します。
<改正後の変更点>
・65歳で老齢厚生年金の受給権を取得し、裁定請求しないまま73歳になりました。
73歳で老齢厚生年金を裁定請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、「請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす」ことになりました。
そのため、遡ってまとめて支給される5年分の年金には、繰下げによる増額分が加算されます。
★なお、「特例的な繰下げみなし増額制度」は、「老齢厚生年金の受給権取得日から15年経過した日以後」、「請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付(障害や遺族の年金)の受給権者であった」ときは、適用されません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

【解答】
【R5年出題】 ×
請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされますので、72歳から遡って一括支給される5年分の年金には、繰下げ加算額が加算されます。
(第44条の3第5項)
65歳 67歳 72歳
(受給権発生) (5年前) (裁定請求)
| 繰下げ加算額 |
|
繰下げ待機期間
| 5年分を一括支給 |
|
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-104
R5.12.9 遺族厚生年金 死亡した者の保険料納付要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
死亡した者の要件について条文で読んでみましょう。
第58条第1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、1又は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 3 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 4老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
★1と2には、保険料納付要件があるのがポイントです。
<保険料納付要件>
・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
※特例
・死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、「死亡日に65歳未満」で「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がない」ときも保険料納付要件を満たします。
★3と4は、保険料納付要件は問われません。
3は、障害厚生年金を受けるときに保険料納付要件を満たしているからです。
4は、長期の加入期間(保険料納付済期間+保険料免除期間=25年以上)があるからです。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
②【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
③【R1年出題】
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
上記2に当てはまりますので、「保険料納付要件を満たしている」ことが条件です。
②【R3年出題】 〇
上記2に当てはまりますので、「保険料納付要件を満たしている」ことが要件です。
原則の保険料納付要件を満たしていない場合でも、特例の保険料納付要件を満たしていれば、遺族厚生年金が支給されます。
特例の保険料納付要件は、「令和8年4月1日前に死亡した者」で、「死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないこと」、そして「死亡日に65歳未満」であることです。ちなみに、「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない」とは、「未納期間がない」という意味です。
令和3年8月1日に死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間(=令和2年7月~令和3年6月)までの間に未納期間がないとき(保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき)には、遺族厚生年金の支給対象となります。
令和2年7月 |
・・・・・・・ | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 |
| 死亡日の属する月の前々月 |
| 死亡日の 属する月 | |
死亡日の属する月の前々月までの1年間 この間に未納がないこと |
|
| ||
(S60法附則第64条第2項)
③【R1年出題】 〇
上記3に当てはまりますので、保険料納付要件は問われません。
障害厚生年金を受けるときに保険料納付要件を満たしているからです。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。

【解答】
【R5年出題】 〇
上記3に当てはまりますので、保険料納付要件は問われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-103
R5.12.8 特定適用事業所とは?
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「特定適用事業所」に使用される「短時間労働者」は、一定の要件を満たす場合は、厚生年金保険の被保険者となります。
特定適用事業所の定義を条文で読んでみましょう。
H24附則第17条第12項 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
②【R2年出題】
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
③【R2年出題】
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満の者で、特定適用事業所に使用される者は、「週の所定労働時間が20時間以上」、「厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円以上」、「学生でない」場合は、厚生年金保険の被保険者となります。
「継続して1年以上使用される見込み」という要件は、改正により現在はなくなっています。
(H24附則第17条第1項)
②【R2年出題】 ×
特定適用事業所に該当しなくなったとしても、特定4分の3未満短時間労働者の厚生年金保険の資格は継続します。
(H24附則第17条第2項)
③【R2年出題】 〇
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として、厚生年金保険の被保険者となりません。
(H24附則第17条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。

【解答】
【R5年出題】 ×
「労働者」の総数が常時100人を超えるではなく、「特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)」の総数が常時100人を超える事業所のことです。
(H24附則第17条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-102
R5.12.7 経過的寡婦加算の支給停止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
経過的寡婦加算は、遺族厚生年金を受けている65歳以上の妻に支給されるものです。
昭和31年4月1日以前生まれの妻が対象です。
条文を読んでみましょう。
S60附則第73条第1項 (遺族厚生年金の加算の特例) 中高齢寡婦加算の要件を満たした遺族厚生年金の受給権者であって昭和31年4月1日以前に生まれた者(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者であって昭和31年4月1日以前に生まれたものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額に、経過的寡婦加算を加算する。 ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(経過的寡婦加算の額) ①から②を控除して得た額 ① 中高齢寡婦加算の額 ② 老齢基礎年金の額に妻の生年月日別に定められた率を乗じて得た額 |
経過的寡婦加算が加算される妻は、次のどちらかに当てはまる場合です。
・65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(中高齢寡婦加算が加算される要件を満たしていること)
・中高齢寡婦加算が加算されていた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
※どちらも、昭和31年4月1日以前生まれの妻であることが条件です。
まず、過去問を解いてみましょう
①【R3年出題】
昭和32年4月1日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。
②【H21年出題】
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
中高齢寡婦加算は、妻が65歳に達したときは加算されなくなり、65歳以降は経過的寡婦加算が加算されます。
ただし、65歳以降、経過的寡婦加算の額が加算されるのは、昭和31年4月1日以前生まれの者に限られます。
そのため、昭和32年4月1日生まれの妻については、65歳まで中高齢寡婦加算が加算されますが、65歳以降、経過的寡婦加算額は加算されません。
(S60附則第73条第1項)
②【H21年出題】 ×
中高齢寡婦加算の額は、「遺族基礎年金の額×4分の3」で、妻の生年月日にかかわらず、定額です。
経過的寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されます。
経過的寡婦加算の額の計算式を確認しましょう。
↓
中高齢寡婦加算の額 - 老齢基礎年金の額×生年月日に応じた乗率
生年月日に応じた乗率は、例えば、昭和2年4月1日以前生まれは「0」、昭和30年4月2日生まれから昭和31年4月1日以前生まれは「480分の348」です。
経過的寡婦加算の額は、生年月日が若くなるほど少なくなるのがポイントです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金の受給権を有し、当該障害基礎年金の支給がされているときは、その間、経過的寡婦加算は支給が停止される。

【解答】
【R5年出題】 〇
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金を受給する場合は、その間、経過的寡婦加算の支給が停止されます。
障害基礎年金によって、1階部分の年金額は、満額が保障されるからです。
(S60附則第73条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-094
R5.11.29 任意適用事業所の認可
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「任意適用事業所」の認可について条文を読んでみましょう。
第6条第3項、4項、H24法附則第17条の2 ③ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条 ① 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 ② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
|
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
②【H30年出題】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

【解答】
①【R2年出題】 ×
任意適用事業所になるための認可を受けるときは、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の「2分の1」以上の同意が必要です。
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければなりませんが、その際、2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えなければなりません。
(法第6条第4項、則第13条の3)
②【H30年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の「4分の3以上」の同意が必要です。
(第8条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

【解答】
【R5年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするためには、当該事業所に使用される者の「4分の3」以上の同意を得ることが必要です。
(法第8条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-088
R5.11.23 経過的加算額のしくみ
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日のテーマは経過的加算額です。
60歳台前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分と報酬比例部分で構成されています。
65歳以降は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」で構成されます。
60歳 65歳
報酬比例部分
|
老齢厚生年金 |
定額部分 | 経過的加算額 |
老齢基礎年金 |
★ 定額部分の額の計算式を確認しましょう ★
定額部分の額は、1,628円×改定率×被保険者期間の月数です。
ただし、定額単価の1,628円は、昭和21年4月1日以前に生まれた者は、生年月日に応じた読み替えがあります。
また、被保険者期間の月数には上限があり、例えば昭和21年4月2日以降に生まれた者は480月が上限です。
★ 老齢基礎年金の計算式を確認しましょう ★
保険料納付済期間が480月の場合、老齢基礎年金の額は、満額の780,900円×改定率です。
ただし、保険料納付済期間が480月未満の場合は、免除期間や合算対象期間等の月数に応じて、老齢基礎年金の額が減額されます。
ポイント!
★ 定額部分と老齢基礎年金の計算式が異なっているのがポイントです。当分の間は、定額部分の方が老齢基礎年金より高くなります。老齢基礎年金と定額部分の差をうめるためのものが、「経過的加算額」です。
★定額部分と老齢基礎年金の違いを確認しましょう ★
| 昭和36年3月以前の期間 | 20歳未満、60歳以後の期間 |
定 額 部 分 | 計算に入る | 計算に入る |
老齢基礎年金 | 合算対象期間 | 合算対象期間 |
では、過去問をどうぞ!
【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

【解答】
【R3年出題】 ×
60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、経過的加算額の計算の基礎となります。定額部分の計算には、「60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間」が入るからです。
経過的加算額は、定額部分と老齢基礎年金の差額です。
ちなみに、経過的加算額を計算する際の老齢基礎年金は、「厚生年金保険の被保険者期間」だけで計算することがポイントです。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

【解答】
【R5年出題】 ×
甲と乙の経過的加算の額は、同額です。
★甲の経過的加算について
甲は保険料納付済期間が20歳から60歳までの480月です。
・定額部分に相当する額 → 1,628円×改定率×480月
・老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×480分の480
20歳から60歳まで全て保険料納付済期間(すべて厚生年金保険の被保険者期間)ですので、満額の老齢基礎年金が支給されます。
・経過的加算の計算式
→ (1,628円×改定率×480月)-(780,900円×改定率×480分の480)
★乙の経過的加算について
乙は、厚生年金保険に45年間(540月)加入していますが、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間は20歳から60歳までの480月で、60歳から65歳までの60月は「合算対象期間」となります。
・定額部分に相当する額 → 1,628円×改定率×480月
定額部分には、480月の上限があることに注意してください。
・老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×480分の480
20歳から60歳まで全て保険料納付済期間ですので、満額の老齢基礎年金が支給されます。合算対象期間は老齢基礎年金の年金額には反映しません。
・経過的加算の計算式
→ 甲と同じ、(1,628円×改定率×480月)-(780,900円×改定率×480分の480)です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-081
R5.11.16 中高齢寡婦加算と遺族基礎年金の調整
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「中高齢寡婦加算」は、要件を満たした妻が受ける遺族厚生年金に加算されます。
★中高齢寡婦加算が加算されるのは、次のいずれかの要件に該当する妻です。
(1) 遺族厚生年金の権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの
(2) 40歳に達した当時被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたもの(=40歳に達した当時、子と生計を同じくし遺族基礎年金を受けていたもの)
★中高齢寡婦加算が加算されるのは、40歳から65歳になるまでの間です。
★中高齢寡婦加算の額は、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額」です。
(法第62条第1項)
(例)夫の死亡当時、妻が50歳で、生計を同じくする子がいない(=遺族基礎年金を受けていない)場合、50歳から65歳まで中高齢寡婦加算が加算されます。
50歳 65歳
遺 族 厚 生 年 金
| |
中高齢寡婦加算 | 老齢基礎年金 |
| |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
②【H28年出題】
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。
③【R3年出題】
夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上あるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
夫の死亡時に、30歳以上40歳未満で子がいない妻には、中高齢寡婦加算は加算されません。
子がいない妻の場合は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満でなければなりません。
②【H28年出題】 〇
子のある妻の場合は、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金は、子が18歳になる年度の3月31日まで(障害状態にある場合は20歳になるまで)支給されますが、遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額は支給が停止されます。
条文を読んでみましょう。
第65条 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給を停止する。 |
65歳
遺族厚生年金
| ||
遺族基礎年金 | 中高齢寡婦加算 | 老齢基礎年金
|
| ||
子 18歳年度末
※遺族基礎年金を受ける間、中高齢寡婦加算は支給停止されます。
③【R3年出題】 ×
中高齢寡婦加算額は、満額の遺族基礎年金の額ではなく、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じた額」です。
妻が、夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給は停止されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止される。

【解答】
【R5年出題】 〇
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-075
R5.11.10 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から65歳になるまでの間に支給される老齢厚生年金です。
2階建てになっていて、1階が「定額部分」、2階が「報酬比例部分」となります。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) |
定額部分 | 老齢基礎年金 |
しかし、男性の場合、60歳から定額部分と報酬比例部分が支給されるのは、昭和16年4月1日以前生まれまでです。昭和16年4月2日以降生まれの男性は、定額部分の開始年齢が1歳ずつ段階的に引き上げられます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
定額部分 | 老齢基礎年金 | |
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日以前生まれの男性は、60歳から報酬比例部分のみ支給されます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 | |
昭和28年4月2日以降生まれの男性は、報酬比例部分の開始年齢が1歳ずつ引き上げられます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
昭和36年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
60歳 65歳
| 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
男性の生年月日の重要ポイントは、16年、24年、28年、36年の4つです。
定額部分の開始が61歳になる昭和16年4月2日、報酬比例部分のみになる昭和24年4月2日、報酬比例部分の開始が61歳になる昭和28年4月2日、特別支給の老齢厚生年金が支給されない昭和36年4月2日をおぼえましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
②【R3年出題】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。
③【H29年出題】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。

【解答】
①【R3年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者期間を有する女性は、特別支給の老齢厚生年金の開始年齢が男性と異なりますので注意してください。先ほどおぼえた男性の生年月日に「5」をプラスします。第1号の女性の生年月日のポイントは、21年、29年、33年、41年の4つです。
昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女性の特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみで、62歳から支給されます。同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男性の特別支給の老齢厚生年金も、報酬比例部分のみですが、64歳から支給されます。
②【R3年出題】 〇
第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間を有する女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性と同じです。
昭和35年8月22日生まれの第4号のみの女性と、同日生まれの第4号のみの男性は、報酬比例部分のみが支給され、支給開始年齢はどちらも64歳です。
③【H29年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和29年4月1日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は、以下の形になります。
60歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
定額部分 | 老齢基礎年金 | |
第1号女性の場合、定額部分の支給開始が61歳になるのは昭和21年4月2日以降生まれです。(男性の生年月日に5を足してください)
2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、21年4月2日生まれが61歳、23年4月2日生まれが62歳、25年4月2日生まれが63歳、27年4月2日生まれが64歳となります。
29年4月1日生まれは、報酬比例部分は60歳から、定額部分は64歳から支給されます。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

【解答】
【R5年出題】 〇
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は次の形になります。
60歳
報酬比例 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
報酬比例部分の支給開始年齢は、同日生まれの男性と同じ64歳です。
報酬比例部分の開始が61歳になるのが昭和28年4月2日生まれ以降です。2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、28年4月2日生まれが61歳、30年4月2日生まれが62歳、32年4月2日生まれが63歳、34年4月2日生まれが64歳です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-068
R5.11.3 5年に一度の財政検証
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第2条の4(財政の現況及び見通しの作成) ① 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。 ② 財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。 ③ 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
政府は、少なくとも5年ごとに、国民年金及び厚生年金の財政の現況及び見通しを作成しています。このことを「財政検証」といいます。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年出題】
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

【解答】
【H30年出題】 〇
「財政均衡期間」は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
財政検証は、少なくとも5年ごとに実施することになっています。
政府は、令和元年8月に、「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」を公表しています。財政検証の実施は、「少なくとも5年ごと」ですので、次は、 令和6年となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-062
R5.10.28 障害手当金の額の計算式
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第57条 (障害手当金の額) 障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 |
障害手当金の額の計算式は、以下の通りです。
↓
| 報酬比例の額(第50条第1項の規定の例により計算した額)×100分の200 |
また、障害手当金には最低保障額があります。
最低保障額の計算式は、以下の通りです。
↓
| 障害厚生年金の最低保障額(第50条第3項に定める額=2級の障害基礎年金の額× 4分の3)×2 |
参考にこちらの条文も読んでみましょう。
第50条第1項、3項 <障害厚生年金の額> ① 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 <障害厚生年金の最低保障額> ③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
②【H26年選択式】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に< A >を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

【解答】
①【H29年出題】 ×
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額です。
ただし、その額が2級の障害基礎年金の額に「4分の3を乗じて得た額」の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされます。
問題文は、「4分の3」が抜けているので誤りです。
※障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額です。
②【H26年選択式】
A 2
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。

【R5年出題】 ×
先ほどの平成29年の問題と同じく、4分の3が抜けているので誤りです。
障害手当金の最低保障額は、「障害基礎年金2級の額×4分の3」に2を乗じて得た額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-057
R5.10.23 子の遺族厚生年金の支給停止が解除されるとき
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第66条第1項 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
・前条本文(第65条の2) 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ・次項本文(第66条第2項) 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 ・次条(第67条) 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
「配偶者と子」は、遺族厚生年金の支給の順位が同順位です。配偶者と子が受給権を有する場合は、配偶者に遺族厚生年金を支給し、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
ただし、配偶者の遺族厚生年金が、第65条の2本文、第66条第2項本文、第67条の規定で支給停止されている場合は、子の遺族厚生年金の支給停止は解除され、子に遺族厚生年金が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
②【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
子の遺族厚生年金の支給停止が解除されるのは、配偶者の遺族厚生年金が、第65条の2本文、第66条第2項本文、第67条の規定で支給停止されている場合です。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止は、「解除されません」。子の遺族厚生年金は、支給停止のままです。
ちなみに、受給権者の申出による年金の支給停止は、第36条の2に規定されています。
②【R3年出題】 ×
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得し、障害基礎年金と障害厚生年金を選択しました。その場合、妻に対する遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止されます。
妻が障害の年金を選択したことにより、妻の遺族厚生年金が支給停止になった場合でも、子の遺族厚生年金の支給停止は「解除されません」。子の遺族厚生年金は支給停止のままです。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。

【解答】
【R5年出題】 ×
R3年の過去問と同じ趣旨の問題です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の受給を選択した場合は、甲に対する遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止になります。
その場合でも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は「解除されません」。甲の子の遺族厚生年金は支給停止のままです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-048
R5.10.14 任意単独被保険者の資格の取得と喪失
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第10条 (任意単独被保険者) ① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 ② 認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 |
「適用事業所」に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者は、「厚生労働大臣の認可」を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となることができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②【H27年出題】
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
ただし、保険料は任意単独被保険者が全額負担するのではありません。
事業主が保険料の半額を負担し、また、保険料を納付する義務も負います。厚生労働大臣の認可を受けるのに、事業所の事業主の「同意」が必要なのはそのためです。
②【H27年出題】 ×
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受け、その資格を喪失することができます。
厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失する際は、事業主の同意は不要です。資格喪失によって、事業主は、保険料の半額を負担する義務と納付する義務が無くなるからです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

【解答】
【R5年出題】 ×
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができます。しかし、資格喪失に際し、事業主の同意は要りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-039
R5.10.5 老齢厚生年金の退職時改定
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第43条第3項 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 |
退職などで厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合は、老齢厚生年金の年金額の見直しが行われます。
ポイントを確認しましょう。
・資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして資格を喪失した日から起算して1か月経過しました
↓
・資格を喪失した月前の被保険者であった期間を算入して、老齢厚生年金の額を再計算します
↓
・資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金額が改定されます。
※なお、「(第14条第2号)その事業所又は船舶に使用されなくなったとき」、「(第14条第3号)適用事業所でなくすることの認可を受けたとき、任意単独被保険者の資格喪失の認可を受けたとき」、「(第14条第4号)適用除外に該当するに至ったとき」は、「その日から起算」して1か月を経過した日の属する月から、年金額が改定されます。
例えば、「退職」で資格を喪失した場合は、退職日の翌月から年金額が改定されます。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【解答】
【H28年出題】 ×
退職時改定は、「資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月」から改定されるのが原則です。
しかし、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき=退職の場合」は、「その日から起算して1か月を経過した日の属する月」から、改定されます。
問題文は、1月31日付退職・2月1日に被保険者資格喪失ですので、1月31日から起算して1か月を経過した日の属する月=2月から年金額が改定されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

【解答】
【R5年出題】 ×
退職時改定で新たに老齢厚生年金の額の計算に加えるのは、「その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間」です。
その被保険者の資格を喪失した月「以前」ではありません。資格を喪失した月は含まれませんので注意しましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-030
R5.9.26 配偶者が老齢基礎年金を繰上げたときの加給年金額
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
まず過去問からどうぞ!
【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
【H28年出題】 ×
加給年金額の対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は配偶者が65歳になるまで支給されます。
 夫が老齢厚生年金の受給権者で、妻が加給年金額の対象になっている場合のイメージ図
夫が老齢厚生年金の受給権者で、妻が加給年金額の対象になっている場合のイメージ図
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼65歳
| 振替加算 |
| 老齢基礎年金 |
 妻が老齢基礎年金を繰り上げたとしても、加給年金額は65歳まで加算されます。
妻が老齢基礎年金を繰り上げたとしても、加給年金額は65歳まで加算されます。
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼60歳 ▼65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

【R5年出題】 ×
加給年金額の加算対象になっている配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとしても、当該配偶者に係る加給年金額は配偶者が65歳になるまで支給されます。
振替加算に関する国民年金の問題をどうぞ!
★国民年金法の問題です★
【国民年金法H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
【国民年金法H22年出題】 ○
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合も、振替加算額が加算されるのは、受給権者が65歳に達した日以後です。振替加算額の繰上げは行われません。
先ほどの図をもう一度みてみましょう。
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼60歳 ▼65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
加給年金額の加算対象の妻が老齢基礎年金を繰り上げた場合のポイント!
・夫の老齢厚生年金
→ 加給年金額は支給停止にはなりません。妻が65歳になるまで支給されます。
・妻の振替加算
→振替加算は繰上げされません。65歳から支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-020
R5.9.16 55歳から60歳までの夫に対する遺族厚生年金
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H27年出題】
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
②【R1年出題】
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

【解答】
①【H27年出題】 〇
★遺族年金を受けることができる夫の条件を確認しましょう。
<夫に対する遺族厚生年金>
・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であること
ただし、夫が60歳になるまでは原則として遺族厚生年金は支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
●夫に対する遺族厚生年金は、60歳に達するまでは支給停止されますが、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されません。
<夫に対する遺族基礎年金>
・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、「子と生計を同じくすること」
問題の夫に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるのが原則です。ただし、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するとき(子と生計を同じくしている場合)は、支給停止されません。
(法第59条第1項、65条の2)
②【R1年出題】 ×
夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有していますので、60歳に到達するまでの間でも、遺族厚生年金は支給停止されません。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
遺族厚生年金を受けることができる夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であることが要件です。
ただし、60歳に達するまでの期間は遺族厚生年金は支給が停止されるのが原則です。しかし、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金は支給停止されませんので、受給することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 厚生年金保険法②
R6-010
R5.9.6 厚年選択式② 事例問題・遺族厚生年金の支給停止からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は厚生年金保険法その2です。
 Cは、事例問題です。
Cは、事例問題です。
問題文を読んでみましょう。
【R5年選択式】
甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、< C >となる。
甲の年金加入歴を図にすると以下のようになります。
20歳 46歳 52歳
厚生年金保険(国民年金第2号被保険者) | 国民年金 第1号or第3号被保険者 |
▲ ▲
初診日 死亡
★甲の受給していた障害年金は、「障害基礎年金」です。
初診日がポイントです。初めて病院で診察を受けたのが「退職の3か月後」となっていますので、初診日に厚生年金保険の被保険者ではありません。そのため、障害厚生年金は受けられません。
★乙が受給できる遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」です。
・死亡した甲について
死亡した甲は、「国民年金の被保険者が死亡したとき」、「保険料納付済期間が25年以上ある者が死亡したとき」に該当しますので、遺族基礎年金の要件を満たします。
また、「厚生年金保険の被保険者であった者」で、「保険料納付済期間が25年以上ある者」の死亡ですので、遺族厚生年金の要件も満たします。
・妻(乙)と子について
<遺族基礎年金について>
妻(乙)は、「子と生計を同じくすること」の要件を満たしています。また、前年の年収が500万円ですので、生計維持要件も満たします。
妻は、子の加算が加算された遺族基礎年金を受給します。子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。
<遺族厚生年金について>
妻(乙)も子も要件を満たします。
妻(乙)が遺族厚生年金を受給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
Cには、「障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金」が入ります。
 Eは、所在不明の場合の遺族厚生年金の支給停止の問題です。
Eは、所在不明の場合の遺族厚生年金の支給停止の問題です。
条文を読んでみましょう。
第67条第1項 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
Eには、1年が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 厚生年金保険法①
R6-009
R5.9.5 厚年選択式① 権限の委任・年金額の改定からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は厚生年金保険法その1です。
厚生年金保険法は2回に分けます。
 A・Bは、権限の委任からの問題です。
A・Bは、権限の委任からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第109条の9(地方厚生局長等への権限の委任) ① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ② ①の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 |
Aは地方厚生局長、Bは地方厚生支局長が入ります。
 Dは、年金額の改定のルールからの問題です。
Dは、年金額の改定のルールからの問題です。
★年金額の改定のルールの原則 新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」 既裁定者は「物価変動率」 で改定を行うのが原則です。 |
↓
★物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」の場合 (物価>0>賃金) 賃金がマイナスになる=現役世代の負担能力が低下しているということです。そのため、既裁定者も、賃金変動に合わせ、名目手取り賃金変動率で改定されます。 新規裁定者・既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」で改定されます。 |
 問題文は、物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が-0.2%です。 物価>0>賃金ですので、賃金変動に合わせて改定されます。既裁定者の年金額は、前年度から0.2%の引下げとなります。
問題文は、物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が-0.2%です。 物価>0>賃金ですので、賃金変動に合わせて改定されます。既裁定者の年金額は、前年度から0.2%の引下げとなります。
なお、改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
Dには、0.2%の引き下げが入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-353
R5.8.15 配偶者に係る加給年金額の支給停止
配偶者に係る加給年金額が支給停止されるのはどんなときでしょう?
条文を読んでみましょう。
第46条第6項 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、配偶者について加算する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
②【R3年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。
③【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されますが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が「240か月」以上の場合に限られます。
②【R3年出題】 ×
老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されます。
障害厚生年金には3級の障害厚生年金も含まれますので、配偶者が3級の障害厚生年金を受給している間は、加給年金額は支給停止されます。
しかし、「障害手当金」を受給していても加給年金額の支給は停止されません。
(令3条の7)
③【H28年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は支給停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国年・厚年 時効
国年・厚年 時効
R5-352
R5.8.14 <比較>国年「死亡一時金」と厚年「障害手当金」の時効
国民年金の「死亡一時金」と厚生年金保険法の「障害手当金」は年金ではなく一時金で支給されます。
それぞれの時効を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
【国民年金法】 第102条第1項、第4項 ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
時効のポイント!
・年金給付を受ける権利 → 5年
・死亡一時金を受ける権利 → 2年
・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2年
【厚生年金保険法】 第92条第1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 |
時効のポイント!
・保険給付を受ける権利 → 5年
・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2年
では、過去問をどうぞ!
①国民年金法【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
②厚生年金保険法【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①国民年金法【H27年出題】 ×
年金給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
死亡一時金を受ける権利→これを行使することができる時から2年を経過したとき
に、時効によって消滅します。
「年金給付(5年)」と「死亡一時金(2年)」の時効の違いに注意してください。
②厚生年金保険法【H29年出題】 ×
保険給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
に時効によって消滅します。
「保険給付」には年金だけでなく一時金(障害手当金)も含まれます。
障害手当金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
ポイント!
同じ「一時金」でも、国民年金の「死亡一時金」の時効は2年、厚生年金保険の「障害手当金」の時効は5年です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 被保険者期間
厚生年金保険法 被保険者期間
R5-351
R5.8.13 厚生年金保険の被保険者期間
被保険者期間は、月単位で算定します。
条文を読んでみましょう。
第19条第1項、2項 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
③【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算されるのは、「被保険者であった期間」です。
②【H30年出題】 〇
平成29年10月1日に資格取得、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、資格を取得した月(平成29年10月)から資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの5か月間です。
平成30年3月は被保険者期間には算入されません。
③【H28年出題】 〇
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
ただし、問題文のように、同じ月に資格取得と資格喪失があり、その月にさらに国民年金の第1号被保険者となった場合は、その月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害手当金
厚生年金保険法 障害手当金
R5-350
R5.8.12 障害手当金が支給されない場合
「障害手当金」が支給されない場合を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第56条 障害手当金の障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) 2 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) 3 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者 |
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。
②【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
③【H18年出題】
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く。)には支給しない。
④【H28年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
障害手当金の障害の程度を定めるべき日に、「年金たる保険給付の受給権者」である場合は、障害手当金は支給されません。
遺族厚生年金=年金たる保険給付です。
②【H30年出題】 ×
老齢厚生年金=年金たる保険給付です。
障害の程度を定めるべき日に、老齢厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
③【H18年出題】 〇
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者には支給されません。
しかし、障害厚生年金の受給権者については「最後に障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した者(現に障害状態に該当しない者に限る。)」には障害手当金が支給されます。
④【H28年出題】 〇
当該傷病について「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付」を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 併合認定
厚生年金保険法 併合認定
R5-325
R5.7.18 併合認定の対象になる障害厚生年金の条件
今日は併合認定をみていみます。
条文を読んでみましょう。
第48条 (障害厚生年金の併給の調整) ① 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級の1級又は2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。 ② 障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |
障害厚生年金の受給権者に、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度の障害厚生年金が支給されます。
この併合認定の対象になる先発の障害厚生年金は、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものは除かれます。
少しの間でも、1・2級の状態にあったことがある障害厚生年金が対象です。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
②【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H29年出題】 〇
現在は3級でも、1回でも1・2級に該当したことがある障害厚生年金の受給権者に対して、新たに1・2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、併合認定の対象となります。
前後の障害を併合した障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
②【H27年出題】 ×
受給権を取得した当時から1回も障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金は、併合認定の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金の加給年金額
厚生年金保険法 障害厚生年金の加給年金額
R5-324
R5.7.17 障害厚生年金に加算される加給年金額のポイント!
1級・2級の障害厚生年金を受けることができる者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額が加算されます。
※3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。
※子については、障害基礎年金の加算対象になります。
(イメージ図)
障害等級1級・2級の場合
障害厚生年金
| (加算対象) → 配偶者 |
障害基礎年金
| (加算対象) → 子 |
条文を読んでみましょう。
第50条の2第1項~3項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを 100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
障害厚生年金の受給権を取得した時点で生計を維持している配偶者は加給年金額の対象となります。それだけでなく、受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持している配偶者を有するに至った場合も加給年金額の対象となるのが、障害厚生年金のポイントです。
※国民年金の障害基礎年金の子の加算も同じです。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
②【H24年出題】
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
1級・2級の障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、配偶者加給年金額が加算されます。
配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加算されます。
②【H24年出題】 ×
その受給権を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときも、配偶者加給年金額の加算対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害手当金の額
厚生年金保険法 障害手当金の額
R5-323
R5.7.16 障害手当金の額の計算式と最低保障額
今日は障害手当金の額の計算式を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第57条 (障害手当金の額) 障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 |
※障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額(報酬比例の年金額)×100分の200です。
※最低保障額は、(障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額)×2です。
※第50条第1項と第3項を読んでみましょう。
第50条第1項 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定(老齢厚生年金)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 第50条第3項 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。 |
※第3項は障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年選択式】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に< A >を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
②【H29年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。

【解答】
①【H26年選択式】
A 2
障害手当金の額は報酬比例の年金額×2です。
最低保障額は、3級の障害厚生年金の最低保障額×2です。
※ちなみに、3級の障害厚生年金(=障害基礎年金を受けることができない)の最低保障額は、780,900円×改定率(2級の障害基礎年金)×4分の3です。
②【H29年出題】 ×
最低保障額は、障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額に「4分の3を乗じて得た額」の2倍に相当する額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金の額の計算
厚生年金保険法 障害厚生年金の額の計算
R5-322
R5.7.15 障害厚生年金の額の計算に算入される被保険者期間
障害厚生年金は、①初診日、②保険料納付要件、③障害認定日の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。
今日は、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第50条第1項、2項 ① 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
障害厚生年金は、老齢厚生年金と同じように計算します。
・1級の場合は、1.25倍します。
・被保険者期間が300月未満の場合は、300月の最低保障があります。
・障害厚生年金の計算には、障害認定日の属する月後は算入されません。=障害認定日の属する月まで算入されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
②【H29年出題】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
③【R4年出題】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

【解答】
①【H22年出題】 ×
計算の基礎となるのは、障害認定日の属する「月」までです。
②【H29年出題】 〇
障害認定日の属する月(平成29年3月)までが計算の基礎となります。平成29年4月以後の被保険者期間は計算に入りません。
③【R4年出題】 ×
「障害認定日の属する月」までが計算の基礎となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 老齢厚生年金の加給年金額
厚生年金保険法 老齢厚生年金の加給年金額
R5-321
R5.7.14 老齢厚生年金と障害基礎年金の子の加算
今日は、65歳以上で「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を併給している場合を見ていきます。
まず、老齢厚生年金の加給年金額の条文を読んでみましょう。
第44条第1項 (加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法第33条の2第1項(障害基礎年金の子の加算)の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
老齢厚生年金の加給年金額の対象になるのは、65歳未満の配偶者と子です。
65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができます。
障害基礎年金にも老齢厚生年金にも子の加算がありますが、障害基礎年金に子の加算額が行われる場合は、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止されます。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
【H29年出題】 〇
障害基礎年金に子の加算が行われ、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金と老齢厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金と老齢厚生年金
R5-320
R5.7.13 遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整
遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある場合の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権がある場合
★遺族厚生年金が老齢厚生年金より高い場合
→老齢厚生年金との差額分の遺族厚生年金を受けることができます。
遺族厚生年金 | →受給 |
|
老齢厚生年金相当額 支給停止 |
受給→ | 老齢厚生年金
|
★遺族厚生年金が老齢厚生年金より低い場合
→遺族厚生年金は全額支給停止されます。
|
|
老齢厚生年金
|
遺族厚生年金 全額支給停止 |
受給→ |
※自身の老齢厚生年金が優先されます。
※65歳未満の場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金はどちらか選択です。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
【H29年出題】 〇
65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある場合は、老齢厚生年金が優先されます。遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、加給年金額は除きます。)に相当する部分の支給が停止されます。
老齢厚生年金より遺族厚生年金の方が高い場合は、老齢厚生年金との差額が支給されます。
(法第64条の2、第60条第1項第2号ロ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金
厚生年金保険法 障害厚生年金
R5-305
R5.6.28 障害基礎年金の併合による障害厚年金の額の改定
障害基礎年金の併合によって、障害厚生年金の額が改定されることがあります。
条文を読んでみましょう。
第52条2の第2項 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項(その他障害による額の改定)及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
図でイメージしましょう。
①会社員(厚生年金保険の被保険者)のときに初診日がある傷病で2級の障害厚生年金と障害基礎年金を受給しています。
障害厚生年金 2級 |
障害基礎年金 2級 |
②会社を退職後、自営業者になりました。(国民年金第1号被保険者となりました)
国民年金第1号被保険者のときに初診日がある傷病で「その他障害」が発生しました。
障害厚生年金 2級 |
+ |
| → | 障害厚生年金 1級 |
障害基礎年金 2級 | その他障害 | → | 障害基礎年金 1級 |
■障害基礎年金について
2級の障害基礎年金の受給権者にさらに「その他障害」が発生しました。
国民年金法第34条4項の規定により、前後の障害を併合した障害の程度が増進した場合は、額の改定を請求することができます。
その結果、障害基礎年金は1級に額が改定されます。
■障害厚生年金について
障害基礎年金が2級から1級に改定されたことに合わせて、障害厚生年金も1級に改定されます。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。

【解答】
【H27年出題】 〇
時系列で確認しましょう。
・2級の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者が
↓
・国民年金の第1号被保険者になった
↓
・第1号被保険者期間中に初診日がある傷病によって、国民年金法34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われた
↓
・併合の結果、障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された
↓
・障害厚生年金も障害等級1級の額に改定される
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 在職老齢年金
厚生年金保険法 在職老齢年金
R5-304
R5.6.27 在職老齢年金の用語の定義
在職老齢年金の用語をチェックしましょう。
過去問からどうぞ!
【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。

【解答】
A 総報酬月額相当額
B 支給停止調整額
C 支給停止基準額
用語を確認しましょう。
・総報酬月額相当額とは
→ (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
・基本月額とは
→ 老齢厚生年金の額÷12 (老齢厚生年金の月額)
※加給年金額・繰下げ加算額は除きます。
・「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額以下の場合
→ 全額支給されます。
・「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額を超える場合
→ (基本月額+総報酬月相当額-支給停止調整額)×2分の1が支給停止されます。(月額)
・支給停止基準額とは
(基本月額+総報酬月相当額-支給停止調整額)×2分の1に12をかけた額です。(支給停止される額の年額です。)
★「支給停止調整額」は毎年度見直されます。
条文を読んでみましょう。
第46条第3項 支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。)が48万円(支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。 |
支給停止調整額は令和4年度の47万円から、令和5年度は「48万円」になりました。
過去問をどうぞ!
【H25年出題】※問題文修正あり
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(480,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である20,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。

【解答】
【H25年出題】 ×
問題文は、基本月額に「老齢基礎年金」を含んでいるので、誤りです。
在職老齢年金は厚生年金保険の制度ですので、老齢基礎年金は関係ありません。
在職中でも老齢基礎年金は全額支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 3号分割(応用編)
厚生年金保険法 3号分割(応用編)
R5-286
R5.6.9 特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるとき
3号分割は、国民年金の第3号被保険者(特定被保険者の被扶養配偶者)からの請求によって行われます。
特定期間の標準報酬月額と標準賞与額を2分の1ずつ分割します。
条文を読んでみましょう。
第78条の14第1項 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法の第3号被保険者に該当していたものをいう。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。 ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 |
今回は、「当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。」の部分に注目します。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
②【H28年出題】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下「特定被保険者」という。)が、障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。
③【R1年出題】
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

【解答】
①【R3年出題】 ×
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者で、その障害厚生年金の計算に特定期間が入っている場合は、その期間は3号分割の対象になりません。
なぜなら、3号分割は第3号被保険者からの請求によって行われるからです。特定被保険者の合意がなくても行われるからです。
障害厚生年金は老齢厚生年金などと比べると保護が必要な年金です。3号分割請求により、特定被保険者が受給している障害厚生年金が合意なく減額されることを防ぐためです。
問題文のように、特定被保険者が、特定期間の「全部」をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者である場合は、3号分割標準報酬改定請求はできません。
②【H28年出題】 〇
「障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。」と規定されています。
特定被保険者が、障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれます。
(令第3条の12の11)
③【R1年出題】 〇
②の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 3号分割(基本編)
厚生年金保険法 3号分割(基本編)
R5-285
R5.6.8 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度
今日は、3号分割の基本をチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) ① 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法の第3号被保険者に該当していたものをいう。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 ② 実施機関は、①の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 ③ 実施機関は、①の請求があった場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 ④ 特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす。 ⑤ 改定され、及び決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。 |
まず、用語をおさえましょう。
・特定被保険者 → 厚生年金保険の被保険者(被保険者であった者を含む)
・特定期間 → 特定被保険者が厚生年金保険の被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間
では、過去問をどうぞ!
※「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関する問題です。
①【H26年出題】
いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
②【H26年出題】
分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。
③【H26年出題】※問題文を修正しています
実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
④【H26年出題】
老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。
⑤【H26年出題】
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
3号分割の請求ができるのは、「特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき」です。
「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合」も、3号分割の対象となります。
(則第78条の14第1号)
②【H26年出題】 〇
平成20年4月1日前の期間は、特定期間に含まれません。
3号分割の対象になるのは、平成20年4月1日以降の期間です。
(H16年法附則第46条)
③【H26年出題】 ×
特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を『特定被保険者の標準報酬月額に「2分の1」』を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定されます。
※標準賞与額についても、「2分の1」を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定されます。
3号分割は「2分の1」がポイントです。「合意した按分割合に基づいて算出した割合」ではありません。
④【H26年出題】 〇
改定され、及び決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有します。
老齢厚生年金の受給権者の年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われます。
(法第78条の18)
⑤【H26年出題】 〇
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、3号分割の請求はできません。
(則第78条の17)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金
R5-284
R5.6.7 遺族厚生年金の短期要件と長期要件
遺族厚生年金には、「短期要件」と「長期要件」があります。
条文を読んでみましょう。
第58条 ① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、1又は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 2被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 3 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 4老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
② 死亡した被保険者又は被保険者であった者が1から3までのいずれかに該当し、かつ、4にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、1から3までのいずれかのみに該当し、4には該当しないものとみなす。 |
短期要件と長期要件を確認しましょう
|
| *1 |
短期要件 | 1厚生年金保険加入中に死亡 | あり |
2厚生年金保険加入中に初診日がある傷病により資格喪失後に死亡(初診日から5年以内) | あり | |
31、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡 | なし | |
長期 | 4老齢厚生年金の受給権者(25年以上*2)が死亡 25年以上*2ある者が死亡 | なし |
*1 保険料納付要件
*2 保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上
★「長期要件」は、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上ではなく、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が25年以上です。25年以上は、国民年金全体(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)で計算します。
★「長期要件」の25年以上の計算には合算対象期間も算入します。「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る」となります。
(附則第14条)
★例えば、保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある人が、厚生年金保険の被保険者であるとき(在職中)に死亡した場合、短期要件と長期要件の両方に当てはまります。
その場合は、「その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、短期要件のいずれかのみに該当し、長期要件には該当しないもの」とみなされます。
申出がなければ、短期要件の扱いになります。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
②【H17年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。
③【H26年出題】
障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
④【R3年出題】
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
<報酬比例部分の「給付乗率について>
遺族厚生年金の原則の計算式は、報酬比例部分×4分の3です。
報酬比例部分の計算式は、平成15年4月以降の期間分については、「平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」です。
「長期要件」の場合は、死亡した者が昭和21年4月1日以前生まれの場合、給付乗率は生年月日に応じた読み替えが行われます。
なお、「短期要件」の場合は、定率(1000分の5.481(H15年4月以降)か1000分の7.125(H15年3月以前))です。
(S60年附則第59条)
②【H17年出題】 〇
「長期要件」の場合の給付乗率には、生年月日に応じた乗率が適用されます。
一方、被保険者期間の月数は「300月の最低保障」は適用されず、実際の被保険者期間で計算されます。
なお、「短期要件」の場合は、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障が適用されます。
③【H26年出題】 〇
「障害等級2級の障害厚生年金を受給する者」の死亡で支給される遺族厚生年金は、「短期要件」です。被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、300か月として計算されます。
(法第60条第1項)
| 短期要件 | 長期要件 |
給付乗率 | 定率 | 生年月日に応じた読み替えあり |
被保険者期間が300月未満 | 最低保障あり | 最低保障なし |
④【R3年出題】 ×
・ 第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡 → 短期要件
・ 保険料納付済期間が40年ある → 長期要件
申出がなければ、「短期要件」のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出され
ます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 滞納処分
厚生年金保険法 滞納処分
R5-273
R5.5.27 厚年 滞納処分
保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときの滞納処分についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第86条第5項、6項 ⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。 1 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 2 繰上徴収の要件のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
②【H25年出題】
厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
厚生労働大臣は、期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができます。
市町村が市町村税の例によって処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければなりません。
②【H25年出題】 〇
納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないときも滞納処分の対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 督促
厚生年金保険法 督促
R5-272
R5.5.26 厚生年金保険料等の督促
厚生年金保険の保険料等を滞納した者に対する督促の手続をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項~4項 (保険料等の督促) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 ④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、繰上徴収の要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
②【H25年出題】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
③【H25年出題】
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
④【R1年選択】
保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は、督促状を< A >以上を経過した日でなければならない。
(選択肢)
① 受領した日から起算して10日
② 受領した日から起算して20日
③ 発する日から起算して10日
④ 発する日から起算して20日

【解答】
①【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促状は発しません。
ちなみに、繰上徴収とは?
条文をチェックしましょう。
第85条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 2 法人たる納付義務者が、解散をした場合 3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 4 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 |
②【H25年出題】 ×
保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、「同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。」です。「代えることができる」ではありません。
③【H25年出題】 〇
督促状により指定する期限の、「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」は覚えましょう。
④【R1年選択】
A ③ 発する日から起算して10日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 厚生年金保険原簿
厚生年金保険法 厚生年金保険原簿
R5-262
R5.5.16 厚生年金保険原簿の訂正の請求
例えば、「ある会社で働いたことがあるのに、厚生年金保険の記録がない」、「標準報酬月額が違う」など、年金記録が事実と異なっていると思うときは、厚生労働大臣に年金記録の訂正を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
第28条 (記録) 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)、基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
第28条の2第1項 (訂正の請求) 第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 |
★「実施機関」は、被保険者に関する原簿を備え、一定事項を記録します。
★「厚生労働大臣」に、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるのは、第1号厚生年金被保険者である者、又は第1号厚生年金被保険者であった者です。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
②【H30年出題】
第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
③【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
④【H30年出題】
厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
この問題のチェックポイントは、訂正請求ができるのは、「第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者」であることです。
②【H30年出題】 〇
訂正請求の対象になるのは、第1号厚生年金被保険者に係る記録です。
第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合)、第4号厚生年金被保険者(日本私立学校振興・共済事業団)に係る期間は、訂正請求の対象外です。
③【H30年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者であった者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができます。
また、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者も、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができます。
④【H30年出題】 〇
条文を確認しましょう。
法第28条の3
① 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
② 厚生労働大臣は、①の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 老齢厚生年金の繰上げ
厚生年金保険法 老齢厚生年金の繰上げ
R5-261
R5.5.15 繰上げ支給の老齢厚生年金の額の改定
厚生年金保険の被保険者期間を1か月でも有し、かつ、国民年金の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上ある場合は、65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権が発生します。
老齢厚生年金は繰り上げて支給を受けることもできます。
老齢厚生年金の繰上げ受給を受けながら在職している場合の老齢厚生年金の額の改定についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
法附則第7条の3第1項~5項 ① 当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法の規定による任意加入被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が10年以上でないときは、この限りでない。 1. 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者 2. 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者 (3.、4.は省略します) ② 繰上げの請求は、国民年金法に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。 ③ 繰上げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 ④ 繰上げ支給の老齢厚生年金の額は、老齢厚生年金の額から政令で定める額を減じた額とする。 ⑤ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
・①について
1.(男子・女子(2号、3号、4号)と2.(女子(1号))は、特別支給の老齢厚生年金が支給されない人です。老齢厚生年金は65歳から支給されます。
・②について
老齢厚生年金の繰上げ請求は、老齢基礎年金と同時に行います。
・⑤について
繰上げ請求後65歳になる前に、厚生年金保険の被保険者期間を有した場合、その期間は65歳時点で、年金額に反映します。
例えば、60歳で老齢厚生年金を繰上げ受給し、その後、62歳から64歳まで厚生年金保険の被保険者だった場合は、その期間分は、65歳到達時の改定で年金額に反映します。
過去問をどうぞ!
【H30年出題】
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

【解答】
【H30年出題】 〇
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者で、繰上げの請求があった日以後に被保険者期間を有する場合は、65歳に達したときに、65歳に達した日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算に算入します。
年金額の改定は、65歳に達した日の属する月の翌月からとなります。
(法附則第7条の3第5項)
※繰上げ支給の老齢厚生年金の受給者については、65歳以降は、在職定時改定、退職改定が適用されます。
(法附則第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-260
R5.5.14 年金額の改定と加給年金額
65歳で老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、生計を維持されている配偶者又は子がいる場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
ただし、その老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上で計算されていることが条件です。(中高齢の期間短縮特例を満たしている場合は15年~19年となります)
今日は、65歳時点では20年未満だった人が、その後、在職し厚生年金保険の被保険者期間が20年になった場合の加給年金額についてみていきます。
では、条文を読んでみましょう。
第44条第1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職時改定又は退職改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
★ 被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の権利を取得した当時、受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
★ 老齢厚生年金の権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満だったとき
↓
その後在職し、「在職時改定」又は「退職改定」により240月以上となるに至った当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
※在職により被保険者期間が増え、増えた期間分が老齢厚生年金に反映されるのは、在職時改定又は退職改定のタイミングです。その際に、240月以上となり、生計維持されている配偶者又は子がいるときは、加給年金額が加算されます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
【H30年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、被保険者期間の月数が240未満であったとしても、その後在職(=厚生年金保険の被保険者として保険料を負担すること)し、被保険者資格を喪失した際の退職改定で、被保険者期間の月数が240以上になった場合は、加給年金額の加算の対象となります。
240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいて生計維持関係が認められた場合は、加給年金額が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金の支給停止
厚生年金保険法 遺族厚生年金の支給停止
R5-245
R5.4.29 子に対する遺族厚生年金の支給停止
遺族厚生年金には、いくつかの支給停止事由が設けられています。
今日は、第66条第1項の「子」に関しての支給停止の規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第66条第1項 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文(60歳までの支給停止)、次項本文(配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合)又は次条(所在不明の場合)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
例えば、厚生年金保険の被保険者が死亡し、死亡の当時、その者によって生計を維持していた配偶者と子がいる場合は、「配偶者と子」に遺族厚生年金の受給権が発生します。
配偶者と子に受給権が発生したときの調整規定です。
★「子」に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給停止されます。 → 「配偶者」が遺族厚生年金を受給します。
★次に当てはまる場合は、「子」の支給停止が解除され、子に遺族厚生年金が支給されます。
・遺族基礎年金の受給権がない夫の遺族厚生年金が60歳まで支給停止されているとき
・配偶者が遺族基礎年金の受給権を有せず、子が遺族基礎年金の受給権を有する場合で配偶者の遺族厚生年金が支給停止されているとき
・配偶者の所在が1年以上明らかでなく、配偶者の遺族厚生年金が支給停止されているとき
過去問では、「配偶者の遺族厚生年金が支給停止」されていても、子の支給停止は解除されないパターンがよく出ていますので注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
②【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
③【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。
【解答】
①【H26年出題】 〇
被保険者の死亡で、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間は、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
★妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているとき
→ 子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。(引き続き支給停止されます。)
②【H30年出題】 ×
①の問題と同じです。
★妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたとき
→ 子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。(引き続き支給停止されます。)
③【R3年出題】 ×
★妻が、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金が全額支給停止となったとき
→ 子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。(引き続き支給停止されます。)
→ ちなみに、子の「遺族基礎年金」についても、引き続き支給停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 被保険者期間
厚生年金保険法 被保険者期間
R5-232
R5.4.16 厚年被保険者期間の計算
「被保険者期間」は月単位で計算します。
条文を読んでみましょう。
第19条第1項・2項 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 |
ポイント!
★被保険者期間の計算は「月」単位です。
資格を取得した「月」から資格を喪失した月の「前月」までで計算します。
★同じ月に取得と喪失がある場合は、その月は1か月で計算します。
ただし、その月に、更に「厚生年金保険の被保険者の資格」を取得したとき、「国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者の資格」を取得したときは、先の分は被保険者期間には算入しません。
・資格を取得した月に資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格を取得したとき
1日 末日
取得 A社 喪失 | 取得 B社 |
被保険者期間は、あとのB社の期間だけで1か月となります。
A社では厚生年金保険料は徴収されません。
・資格を取得した月に資格を喪失し、さらにその月に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したとき
1日 末日
取得 A社 喪失 | 第1号被保険者 |
A社の期間は被保険者期間に算入しません。この月は、国民年金の第1号被保険者であった月となります。
A社では厚生年金保険料は徴収されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
②【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。
問題文の被保険者期間は、資格を取得した月(平成29年10月)から、資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの5か月間です。
資格を喪失した月(平成30年3月)は被保険者期間には算入されません。
②【H28年出題】 〇
平成28年3月に、厚生年金保険の被保険者の資格の取得と喪失があり、同じ月に更に国民年金の第1号被保険者となった場合、平成28年3月は、国民年金の第1号被保険者であった月となります。厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-231
R5.4.15 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金額
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金額のポイントをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第78条の27(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例) 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして加給年金額の規定を適用する。この場合において、加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。
令第3条の13第2項 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について加給年金額が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したものについて加給年金額を加算するものとする。 この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。 1.第1号厚生年金被保険者期間 2.第2号厚生年金被保険者期間 3.第3号厚生年金被保険者期間 4.第4号厚生年金被保険者期間 |
ポイント!
★加給年金額が加算される老齢厚生年金は、原則として被保険者期間が240月以上あることが条件です。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その期間を合算します。
★加給年金額が加算される年金は?
「最も早い日」に受給権を取得した老齢厚生年金に加算されます。
↓
「最も早い日」に受給権を取得した年金が2以上あるときは、「厚生年金被保険者期間が最も長い」老齢厚生年金に加算されます。
↓
「最も長い」期間が2以上あるときは、1.第1号→ 2.第2号 →3.第3号 → 4.第4号の順番となります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
②【H30年出題】
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第1号の170か月と第2号の130か月を合算して、被保険者期間が240月以上ありますので、加給年金額が加算されます。
第1号の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権と第2号に基づく老齢厚生年金の受給権を、同じ日に取得した場合は、加給年金額は、被保険者期間が長い方の第1号の被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加算されます。
②【H30年出題】 ×
2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なる場合は、加給年金額は、「早い日」に受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金にのみ加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 特別加算
厚生年金保険法 特別加算
R5-230
R5.4.14 老齢厚生年金の配偶者加給年金額に加算される特別加算
老齢厚生年金(被保険者期間が原則として240月以上)の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される「特別加算」をみていきましょう。
【加給年金額が加算される要件(原則)】
老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あること)の額には、65歳時点(又は定額部分の支給開始時点)で、生計を維持している65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算されます。
(加給年金額の額)
・ 配偶者 → 224,700円×改定率
・ 子 → 1人目、2人目 各224,700円×改定率
3人目以降 各74,900円×改定率
(法第44条第1項、2項)
では、配偶者の加給年金額に加算される「特別加算」について条文を読んでみましょう。
昭60年法附則第60条第2項 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、加給年金額の額(224,700円×改定率)に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
|
ポイント!
・「生年月日」は配偶者ではなく、老齢厚生年金の受給権者の生年月日です
・特別加算が加算されるのは、昭和9年4月2日以降生まれの受給権者です
・特別加算は、生年月日が若い方が額が多いことが特徴です
・昭和18年4月2日以後生まれの人は、一律同じ額です
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
②【H30年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。
③【H25年出題】
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者加給年金額に加算される特別加算は、「受給権者」の生年月日に応じて行われます。
配偶者の生年月日ではありません。
②【H30年出題】 ×
特別加算の額は、「受給権者の生年月日」に応じて33,200円×改定率から165,800円×改定率の範囲内で決められています。受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなります。
③【H25年出題】 〇
配偶者加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者は99,500円×改定率で、昭和18年4月2日生まれの受給権者は165,800円×改定率です。昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-219
R5.4.3 加給年金額の対象の配偶者が65歳に達したとき
所定の要件を満たした老齢厚生年金と障害厚生年金には加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第44条第1項 (老齢厚生年金の加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間が240月以上あることが原則です。ただし、中高齢の期間短縮特例に該当する場合は、その期間以上あれば対象となります。
老齢厚生年金の加給年金額の対象は、「65歳未満の配偶者」と「子」です。
第50条の2第1項 (障害厚生年金の加給年金額) 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。 |
加給年金額が加算されるのは1級・2級の障害厚生年金です。3級の場合は加給年金額は加算されません。また、加給年金額の対象は、「65歳未満の配偶者」です。「子」は障害基礎年金で加算の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
②【R1年出題】
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
加給年金額の対象になっている配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額が支給されなくなります。
なお、配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も加給年金額が加算されます。
(法第50条の2第4項)
ちなみに、老齢厚生年金も同じです。加給年金額の対象になっている配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額の加算がなくなります。
②【R1年出題】 ×
加給年金額の対象になっている配偶者が、①死亡したとき、②受給権者による生計維持の状態がやんだとき、③配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき、④配偶者が、65歳に達したときに該当したときは、その翌月から加給年金額が加算されません。
①から③に該当したときは「加給年金額対象者の不該当の届出」を10日以内に提出しなければなりません。
④については、届出は不要です。
(則第46条)
※老齢厚生年金の配偶者の加給年金額も同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 標準報酬月額
厚生年金保険法 標準報酬月額
R5-218
R5.4.2 育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定は、育児休業等が終了した日に3歳未満の子を養育している被保険者が対象です。
随時改定の要件に該当しなくても、標準報酬月額の改定が行われます。

※まず、随時改定の要件を確認してみましょう。
① 昇給又は降給等により固定的賃金が変動したこと
② 変動月から3カ月間の報酬の平均月額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
③ 報酬支払基礎日数が3か月すべて17日(短時間労働者は11日)以上であること
★育児休業等終了時改定は、
育児休業等終了時に報酬に変動があり、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3カ月間の報酬の平均額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額に、1等級以上の差が生じた場合に行われます。また、報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は除いて算定します。
では、条文を読んでみましょう。
第23条の2第1項 (育児休業等を終了した際の改定) 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という。)において子であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 |
※育児休業等終了日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始している場合は、育児休業等終了時改定による標準報酬月額の改定は行われません。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。
②【R1年出題】
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月は除いて平均を出します。
随時改定とは違い、3か月すべてが17日以上である必要はありません。
②【R1年出題】 ×
育児休業等終了時改定は、「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間」の給与の平均で判断します。問題文は、4月20日に職場復帰していますので、4月、5月、6月に支払った給与で判断されます。
4月10日払い | 給与なし(育児休業中のため) | |
5月10日払い | 17日未満 | (4月19日育休終了、20日職場復帰のため) |
6月10日払い | 17日以上 | |
17日未満の月は除いて平均を出します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 6年間支給停止
厚生年金保険法 6年間支給停止
R5-205
R5.3.20 厚生年金保険の年金と労働基準法の災害補償との調整
厚生年金保険法の保険給付は業務上・業務外を問いませんので、障害厚生年金と遺族厚生年金は、業務上の障害や死亡でも支給されます。
その障害や死亡について、労働基準法の災害補償を受ける権利がある場合の調整についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第54条第1項 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
第64条 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 |
ポイント!
労災保険法との調整ではなく、「労働基準法」の障害補償・遺族補償との調整です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
②【H28年出題】
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
障害厚生年金にも同じ趣旨の規定があります。
②【H28年出題】 ×
「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付」ではなく、同一の傷病について「労働基準法第77条の規定による障害補償」を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されます。
★ちなみに、社会保険(国民年金と厚生年金)と労災保険の年金との調整については労災保険法に規定があります。
「同一の事由」で社会保険と労災保険の年金給付が支給される場合は、労災保険の年金が減額され、社会保険の年金は全額支給されます。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、社会保険は被保険者本人が保険料を負担しているからです。
例えば、業務上の傷病で障害等級に該当する障害の状態にある場合に、同一の傷病によって、労働基準法第77条の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、支給が停止されます。
一方、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならず全額支給されます。労災保険の障害補償年金は減額されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 事後重症
厚生年金保険法 事後重症
R5-195
R5.3.10 障害厚生年金の事後重症のチェックポイント
障害厚生年金の受給権発生要件は、次の3つです。
①初診日要件
→ 初診日に厚生年金保険の被保険者であること
②障害認定日要件
→ 障害認定日に障害等級1級~3級に該当していること
③保険料納付要件
→ 初診日の前日の保険料納付状況で判断されます
初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付要件が問われます
①、②、③の要件を満たした場合は、障害認定日に障害厚生年金の受給権が発生します。
★「障害認定日」に障害等級1~3級に該当しない場合は、受給権は発生しません。
ただし、後日、1~3級に該当した場合は、「事後重症」として障害厚生年金を請求することができます。
今日は事後重症のチェックポイントをみていきましょう。
事後重症の条文を読んでみましょう。
第47条の2第1項(事後重症の障害厚生年金) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。 |
★保険料納付要件を満たしていることが前提です。
チェックポイント!
・障害認定日に1~3級に該当しなかった
↓
・障害認定日後65歳に達する日の前日までに、1~3級に該当した
↓
・その期間内(障害認定日後65歳に達する日の前日まで)に、障害厚生年金を請求すること
↓
・「請求」することによって事後重症の障害厚生年金の受給権が発生します。
※請求した日に受給権が発生します。
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始まりますので、事後重症の障害厚生年金は、請求した月の翌月から支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。
②【H26年出題】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。
③【R1年出題】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
事後重症の請求の条件は、「障害認定日後から65歳に達する日の「前日」までの間に、障害等級に該当すること」+「その期間内に請求すること」です。
問題文は「前日」が抜けているので誤りです。
②【H26年出題】 ×
事後重症の障害厚生年金は、「障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき」に請求することができます。
厚生年金保険法の「障害等級」は1級、2級、3級です。障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合でも請求することができます。
③【R1年出題】 〇
65歳に達する日の前日までの間にある場合でも、繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者や繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症の障害厚生年金の規定は適用されません。
(法附則第16条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 老齢厚生年金
厚生年金保険法 老齢厚生年金
R5-194
R5.3.9 65歳未満の老齢厚生年金と65歳以上の老齢厚生年金
 「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、65歳から支給されます。
「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、65歳から支給されます。
 「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から64歳までの間、特別に支給される老齢厚生年金です。60歳台前半の老齢厚生年金と呼ばれることもあります。
「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から64歳までの間、特別に支給される老齢厚生年金です。60歳台前半の老齢厚生年金と呼ばれることもあります。
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが支給要件です。
条文を読み比べてみましょう。
まず、通常の「老齢厚生年金」の条文です。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
「被保険者期間を有する者」の部分に注目してください。
厚生年金保険の被保険者期間は「月」単位で算定しますので、1か月でもあれば「被保険者期間を有する者」となります。
次に特別支給の老齢厚生年金の条文です。
法附則第8条 (老齢厚生年金の特例) 当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金を支給する。 1 60歳以上であること。 2 1年以上の被保険者期間を有すること。 3 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上」の厚生年金保険の被保険者期間が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
②【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
③【H28年出題】
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
④【H30年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があることが条件です。
②【H24年出題】 〇
65歳以上の老齢厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること、60歳以上65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。
③【H28年出題】 ×
2以上の種別の被保険者期間を有する場合、「1年以上の被保険者期間」については、2以上の種別の被保険者期間を合算することになっています。
問題文の場合、「第1号厚生年金被保険者期間・8か月」+「第4号厚生年金被保険者期間・10か月」=18か月で厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ありますので、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
(法附則第20条)
60歳 62歳 65歳
特別支給の老齢厚生年金(1号分) |
| |
| (4号分) |
|
| 老齢基礎年金 | |
昭和31年4月2日生まれの女性の場合、第1号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金は60歳から、第4号厚生年金被保険者期間に係る分は62歳から支給されます。
④【H30年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金は有期年金ですので、65歳に達したときに受給権が消滅します。65歳に達すると、新たに終身年金の老齢厚生年金の受給権が発生します。
そのため、特別支給の老齢厚生年金を受給していた人も、65歳で改めて老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出する必要があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金
R5-183
R5.2.26 養子になったときの遺族厚生年金の受給権
遺族厚生年金の受給権者が「養子」になった場合の受給権が今日のテーマです。
まず、遺族厚生年金の受給権の消滅事由を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第63条第1項 (遺族厚生年金の失権) 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 4 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。 |
2について
・婚姻した場合は遺族厚生年金の受給権は消滅します。事実婚でも同様です。
3について
・直系血族及び直系姻族以外の者の養子(事実上の養子も含む)となった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅します。直系血族・直系姻族の養子になっても失権しないのがポイントです。
4について
・離縁で、死亡した人との親族関係が終了した場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅します。離縁とは養子縁組の解消です。
※他に、「30歳未満の妻」の失権、「子、孫」の失権、「父母、孫、祖父母」の失権の規定もありますが、今回は省略します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
②【H29年出題】
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。
③【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
直系姻族の養子となった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
②【H29年出題】 ×
母と再婚した夫は直系姻族となります。子が母と再婚した夫の養子になっても遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
③【R3年出題】 ×
乙は丙の父の妻ですので、丙からみると乙は直系姻族です。丙が乙の養子になっても丙の遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金
R5-172
R5.2.15 遺族厚生年金・死亡した者の要件
遺族厚生年金の「死亡した者」の要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第58条第1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
(保険料納付要件) ・ ・(特例)令和8年4月1日前に死亡した者の死亡については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない場合でも保険料納付要件を満たす。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳未満である場合に限る。 |
<保険料納付要件について>
・死亡日の前日の保険料納付要件が問われるのは、 (被保険者の死亡=在職中の死亡)と
(被保険者の死亡=在職中の死亡)と (在職中に初診日がある傷病により初診日から5年以内の死亡)の場合です。
(在職中に初診日がある傷病により初診日から5年以内の死亡)の場合です。
 は障害厚生年金の裁定時に保険料納付要件を満たしているため、
は障害厚生年金の裁定時に保険料納付要件を満たしているため、 は保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)で25年以上あるため、死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。
は保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)で25年以上あるため、死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。
<短期要件と長期要件>
 から
から を「短期要件」、
を「短期要件」、 を「長期要件」といいます。今日は触れませんが、年金額の計算のルールが異なります。
を「長期要件」といいます。今日は触れませんが、年金額の計算のルールが異なります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
②【R1年出題】
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。
③【H23年出題】
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
③【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
④【R3年出題】
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。

【解答】
①【R2年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病で初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者について、「保険料納付要件を満たしていること」が条件です。
②【R1年出題】 〇
1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、保険料納付要件は問われません。
③【H23年出題】 ×
1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、保険料納付要件は問われません。しかし、3級の障害厚生年金の受給権者の死亡については、保険料納付要件を満たすことが必要です。
③【R3年出題】 〇
保険料納付要件の特例は、「令和8年4月1日前に死亡していること」、「死亡日に65歳未満」であること、「死亡日の前日に死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない(=滞納期間がない)こと」です。
甲の場合、令和和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していますが、在職中の令和3年3月15日に初診日がある傷病で初診日から5年以内の令和3年8月1日に死亡しています。
甲は、原則の保険料納付要件は満たしていませんが、保険料納付要件の特例を満たしていますので、遺族厚生年金の支給対象となります。
R2 7 月 | R2 8 月 | R2 9 月 | R2 10 月 | R2 11 月 | R2 12 月 | R3 1 月 | R3 2 月 | R3 3 月 | R3 4 月 | R3 5 月 | R3 6 月 | R3 7 月 | R3 8 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前 々月 |
| 死亡 |
死亡日の属する月の前々月までの1年間(R2年7月~R3年6月) 保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない=滞納期間がない |
|
| |||||||||||
④【R3年出題】 〇
長期要件については、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある事が必要ですが、「合算対象期間」も合算できます。合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合は、要件を満たします。
(法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 届出
厚生年金保険法 届出
R5-171
R5.2.14 70歳以上の使用される者の届出
厚生年金保険の被保険者資格は70歳に達した日に喪失します。
そのため、70歳以上の者は、在職中でも厚生年金保険の保険料の負担はありません。しかし、在職老齢年金の仕組みは適用されますので、事業主は70歳以上の使用される者についても届出が必要です。
条文を読んでみましょう。
第27条、則第10条の4 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(70歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件(適用事業所に使用される者であって、かつ適用除外に該当するものでないこと)に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。
②【H29年出題】※改正による修正あり-
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の届出をしなければならない(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、この限りでない)。
一方、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。

【解答】
①【R2年出題】 〇
被保険者が70歳に到達し、引き続き使用されることにより「70歳以上の使用される者」の要件に該当する場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出が必要です。
ただし、その者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額の場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出は省略できます。
(則第15条の2、第22条)
②【H29年出題】 ×
・70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合
(標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額の場合)
→ 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届は省略できます。
(標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる場合)
→ 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届は70歳到達日から5日以内に提出しなければなりません。
・70歳以上の者を新たに雇い入れたとき
→ 70歳以上の使用される者の該当の届出が必要です。
ポイント!70歳以上の者(適用除外に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出が必要です。在職老齢年金の仕組みが適用されるからです。
(則第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金
厚生年金保険法 障害厚生年金
R5-163
R5.2.6 障害厚生年金の失権のタイミング
障害厚生年金の失権時期を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第53条 (失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 第48条第2項 前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |
今日は2号と3号に注目しましょう。
障害厚生年金の障害等級は1級から3級まであります。
障害厚生年金の受給権の消滅は、3級に該当しなくなって3年経過したとき、又は、65歳に達したときのどちらか遅い方です。
少なくとも65歳までは失権しないのがポイントです。
★障害厚生年金の失権のタイミング
・65歳で失権(3級に該当しなくなって3年を経過している)
3級未満 ▼3年経過 ▼65歳
支給停止 |
|
▲失権
・3級に該当しなくなって3年を経過した日に失権(65歳以上)
3級未満 ▼65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
②【H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったため支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
③【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
63歳の時に障害の程度が軽減し支給停止になった場合、65歳時点ではまだ3年経過していませんので65歳に達した日には消滅しません。
3級に該当しないまま3年経過した時点で失権します。
63歳 66歳
3級未満 65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
②【H30年出題】 〇
64歳の時点で障害等級に該当しなくなって支給停止になり、その状態のまま65歳に達したとしても、3年経過していませんので、65歳時点では障害厚生年金の受給権は消滅しません。
64歳 67歳
3級未満 65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
③【R2年出題】 ×
3級に該当しなくなると障害厚生年金の支給は停止されます。その状態のまま3年が経過しても65歳までは失権しません。65歳に達する日の前日までに障害等級3級に該当した場合は、支給停止が解除され、障害厚生年金が支給されます。
<65歳に達していない場合>
3級 3級未満 3年経過 3級該当
▼ ▼ ▼ ▼
3級 支給 | 支給停止 | 3級 支給再開 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 2種類以上の被保険者であった期間
厚生年金保険法 2種類以上の被保険者であった期間
R5-155
R5.1.29 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の年金額
厚生年金保険の被保険者には第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の4つの種別があります。
例えば、民間企業の会社員と、国家公務員の経験がある人の場合は、第1号厚生年金被保険者としての期間と、第2号厚生年金被保険者としての期間の2つの種別の被保険者であった期間を有することとなります。
今日は、2つ以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の年金額の計算について確認しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
②【H29年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
③【H28年出題】
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日おいて2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
④【H30年出題】
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。
⑤【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

【解答】
①【H29年出題】 ×
例えば、第1号厚生年金被保険者期間が10年、第4号厚生年金被保険者期間が19年ある場合、合算して計算するのではなく、第1号厚生年金被保険者期間分と、第4号厚生年金被保険者期間分をそれぞれで計算します。
また、年金の支給は、10年分は厚生労働大臣から、19年分は日本私立学校振興・共済事業団から、それぞれ支給されます。
★2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金について
年金額の計算 | それぞれの種別ごとに計算 |
年金の支給事務 | それぞれの実施機関が行う |
(法第78条の26第2項)
②【H29年出題】 ×
「2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するもの」とみなして額を計算します。
(法第78条の30)
③【H28年出題】 ×
障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
(法第78条の33)
★2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金について
年金額の計算 | 2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算 |
年金の支給事務 | 初診日に加入していた実施機関が行う |
④【H30年出題】 〇
短期要件の遺族厚生年金の額は、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をします。
(法第78条の32第1項)
⑤【H28年出題】 〇
長期要件の遺族厚生年金は、各号の被保険者期間に係る被保険者期間ごとにそれぞれの実施機関から支給されます。
(法第78条の32第2項)
★2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金について
年金額の計算 | <短期要件> 2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算 <長期要件> 各被保険者期間ごとに支給される |
年金の支給事務 | <短期要件> 死亡日(又は初診日)に加入していた実施機関が行う <長期要件> それぞれの実施機関が行う |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害手当金
厚生年金保険法 障害手当金
R5-145
R5.1.19 障害手当金は症状が固定していることが条件
今日は、障害手当金の支給要件を確認しましょう。
障害手当金は、障害の状態が、障害厚生年金を受けることができる状態よりも軽いときに支給されます。
では、条文を読んでみましょう。
第55条第1項 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。 |
障害の状態は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日」でみることになります。
「初診日から5年以内に治っていること」が条件です。治っているということは症状が固定していることです。
では、過去問をどうぞ!
【R2問10-エ】
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過するまでの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。

【解答】
【R2問10-エ】 〇
障害厚生年金の障害状態は「障害認定日」で定められます。
障害認定日は、「初診日から1年6か月を経過した日」又は、「1年6か月以内に傷病が治った場合はその日」となります。傷病が治らなくても、初診日から1年6か月を経過した日に障害等級に該当する程度の状態であれば、要件を満たします。
一方、障害手当金は、初診日から起算して5年以内に、その傷病が「治っている」ことが条件ですので、治っていなければ支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金
厚生年金保険法 障害厚生年金
R5-136
R5.1.10 障害厚生年金の初診日要件
障害厚生年金は、「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」の条件を満たせば、受給権が発生します。
今日は、「初診日」の要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第47条 (障害厚生年金の受給権者) 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 |
ポイント!
「初診日」とは、傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。
「初診日」に厚生年金保険の被保険者であったことが条件です。
過去問をどうぞ!
①【R2問4-E】
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
②【R2問4-B】
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①【R2問4-E】 ×
障害厚生年金は、初診日に「厚生年金保険の被保険者」であることが条件です。
問題文の場合、初診日は国民年金の第1号被保険者ですので、障害厚生年金の初診日要件を満たしません。そのため、障害厚生年金を受給することはできません。
②【R2問4-B】 ×
障害厚生年金は、初診日に「厚生年金保険の被保険者」であることが条件で、初診日に高齢任意加入被保険者だった場合は、初診日要件を満たします。
初診日に高齢任意加入被保険者で、初診日の前日に保険料の納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-126
R4.12.31 R4択一式より 障害厚生年金の加給年金額
障害厚生年金の額には、加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第50条の2 1 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 2 加給年金額は、22万4,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
ポイント!
・加給年金額が加算されるのは1級と2級の障害厚生年金です。3級の障害厚生年金には加算されません。
・対象は65歳未満の配偶者です。子については障害基礎年金で加算が行われます。
・加給年金額は22万4,700円×改定率です。
障害等級1級又は2級 |
| 障害等級3級 |
障害厚生年金
+加給年金額(配偶者) |
|
障害厚生年金 |
障害基礎年金
+加算額(子) |
|
|
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問6-A】
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。
②【問6-B】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
①【問6-A】 ×
障害厚生年金の加給年金額の対象は、65歳未満の配偶者のみです。子は障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。
②【問6-B】 ×
障害厚生年金の額に加算される配偶者に係る加給年金額には、特別加算は行われません。
過去問をどうぞ!
【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権を取得した時点では、生計を維持している配偶者がなくても、受給権を取得した日の翌日以後に有するに至った場合は、加給年金額の対象になります。その場合は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
(法第50条の2第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-125
R4.12.30 R4択一式より 高年齢雇用継続給付と60歳台前半の老齢厚生年金
60歳台前半で在職中(=厚生年金保険の被保険者ということです。)の場合、60歳台前半の老齢厚生年金には、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
また、雇用保険からは、高年齢雇用継続給付が支給される場合があります。
高年齢雇用継続給付は、60歳時点の賃金と比べて、60歳以後の賃金が60歳時の75%未満となった場合に、支給される給付です。
60歳以降の賃金が、60歳時点と比べて61%未満になった場合は、支給対象月の賃金の15%が高年齢雇用継続給付として支給されます。61%以上75%未満の場合は、15%から逓減する率となります。
雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給される場合、在職老齢年金の支給停止基準額に加えて、60歳台前半の老齢厚生年金がカットされる仕組みになっています。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-D】
60歳以降も在職している被保険者が、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その間、60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止となる。

【解答】
【問8-D】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる間、60歳代前半の老齢厚生年金は最大で標準報酬月額の6%が支給停止されますが、「全額支給停止」とは限りません。
★60歳以降の支給対象月の賃金が60歳時点と比べて61%未満になった場合、高年齢雇用継続基本給付金は「支給対象月の賃金の15%」が支給されます。
その場合、60歳台前半の老齢厚生年金は、「標準報酬月額の6%」が支給停止されます。
雇用保険から「15」支給されると、年金が「6」停止されるイメージです。
支給対象月の賃金が61%以上75%未満の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は15%から逓減する率になりますが、その場合は老齢厚生年金の支給停止の率も6%から逓減する率となります。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。
②【H24年出題】
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の受給による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額は、最大で「標準報酬月額の6%」です。
②【H24年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合、60歳代前半の老齢厚生年金は、最大で標準報酬月額の6%に相当する部分が支給停止されます。一方、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-124
R4.12.29 R4択一式より 加給年金額の減額改定
加給年金額が加算された老齢厚生年金は、対象の配偶者や子が一定の要件に該当した場合は、加給年金額が加算されなくなります。
条文を読んでみましょう。
第44条第4項 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。 1死亡したとき。 2 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 3 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。 4 配偶者が、65歳に達したとき。 5 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 6 養子縁組による子が、離縁をしたとき。 7 子が、婚姻をしたとき。 8 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 9 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。 10 子が、20歳に達したとき。 |
例えば、加給年金額の対象になる配偶者は65歳未満という年齢要件があります。そのため、配偶者が65歳に達すると加給年金額が加算されなくなり、その翌月から減額改定されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問6-E】
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。
②【問3-B】
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。

【解答】
①【問6-E】 ×
加給年金額の対象となる配偶者は受給権者によって「生計を維持」していたことが条件です。
そのため、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合は、加給年金額は加算されなくなり、翌月から加給年金額は減額されます。
(法第44条第4項第2号)
②【問3-B】 〇
子が婚姻したときは加給年金額は加算されなくなります。18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したときでも、婚姻した月の翌月から加給年金額は減額されます。
(法第44条第4項第7号)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。
②【H26年出題】
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

【解答】
①【R3年出題】 ×
障害等級2級に該当しなくなっても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合は、加給年金額は減額されません。
問題文の場合は、17歳ですので、障害等級2級でなくなっても、その時点では加給年金額の加算の対象からは外れません。
(法第44条第4項第9号)
②【H26年出題】 ×
配偶者が、65歳に達したときは、加給年金額の対象から外れます。受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できなかったとしても加給年金額は減額されます。
※配偶者が大正15年4月1日以前生まれ(旧法対象者)の場合は、65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算されます。
(法第44条第4項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-104
R4.12.9 R4択一式より 加給年金額の支給停止
厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上ある人に、生計維持関係のある配偶者や子がいる場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
ただし、その加給年金額は、支給停止されることもあります。
条文を読んでみましょう。
第46条第6項 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
今日は、「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)」の部分を見ていきます。
加給年金額の加算対象の配偶者が、被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金の支給を受けることができる場合は、加給年金額は支給停止されます。
※原則は240月(20年)以上が対象ですが、中高齢の期間短縮特例に該当する場合は、15~19年となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-E】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

【解答】
【問9-E】 〇
加給年金額の加算の対象となっている妻が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合は、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額は支給停止となります。
★令和4年4月の改正点を確認しましょう。
<改正前>
配偶者の240月以上の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額支給停止されている場合 → 本人の老齢厚生年金に加算される加給年金額は支給されることになっていました。
<改正後>
配偶者の240月以上の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額支給停止されている場合 → 本人の老齢厚生年金に加算される加給年金額は支給停止されることになりました。(施行令第3条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-103
R4.12.8 R4択一式より 厚生年金保険の未支給保険給付
年金の受給権者が死亡した場合、必ず、未支給年金が発生します。
年金は権利が消滅した月まで支払われますので、例えば、12月20日に死亡した場合、年金は12月分まで支払われます。
年金は2か月分ずつ後払いされます。10月分と11月分が12月に支給されていますが、12月分は未支給となります。
まず、未支給保険給付の条文を読んでみましょう。
第37条 (未支給の保険給付) ① 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ③ 死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 ④ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。 ⑤ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
★ 未支給保険給付(=「保険給付」ですので、年金のみならず一時金も含まれます)が発生するのは、以下の場合です。
・ 保険給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき
・ 死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったとき
★ 未支給の保険給付を請求することができるのは、以下の遺族です。
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-E】
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

【解答】
【問10-E】 〇
未支給の保険給付を受けることができる順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦①から⑥以外の3親等内の親族です。
同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表して請求することになります。その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとなり、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとなります。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
②【H23年出題】
保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。

【解答】
①【H30年出題】 〇
未支給の保険給付は、「死亡した受給権者の名」ではなく、請求する遺族の「自己の名」で請求することがポイントです。
②【H23年出題】 ×
同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表して請求することになり、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされますので、「同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-102
R4.12.7 R4択一式より 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の繰下げ
老齢厚生年金の受給権を有する者で、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
今日は、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の、繰下げの申出についてみていきましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-D】
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

【解答】
【問9-D】 〇
第78条の28で、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、一の期間に基づく老齢厚生年金についての支給繰下げの申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない」と規定されています。
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合は、繰下げの申出は同時に行わなければなりません。
(法第78条の28)
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
問題文の場合、支給繰下げの申出は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
2つ以上の種別の老齢厚生年金を受けることができる場合は、全て同時に繰下げの申出をしなければなりません。
こちらの過去問もどうぞ!
②【H28年出題】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
③【H27年出題】
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。
老齢厚生年金のみ繰下げる又は老齢基礎年金のみ繰下げることも可能です。
(法第44条の3)
③【H27年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行う必要があります。老齢基礎年金のみ繰上げる、又は老齢厚生年金のみ繰上げることはできません。
(法附則第7条の3第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-101
R4.12.6 R4択一式より 短時間労働者の社会保険適用要件
短時間労働者の社会保険の適用条件を確認しましょう。
短時間労働者に対する適用について
◎「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」といいます。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
◎ 4分の3基準を満たさない場合でも、以下の①から④までの4つの要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
② 月額賃金が8.8万円以上であること。
③ 学生でないこと。
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(i) 特定適用事業所
(ii) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(iii) 国又は地方公共団体の適用事業所
※「特定適用事業所」の企業規模要件は、令和4年10月の改正で、500人超える企業から、「100人」を超える企業に引き下げられました。
参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-A】
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

【解答】
【問7-A】 ×
Xは、短時間労働者の社会保険適用の4つの条件に当てはまりますので、厚生年金保険の被保険者となります。
① 1週の所定労働時間が25時間 → 20時間以上
② 月額賃金が15万円 → 8.8万円以上
③ 学生でない
④ 地方公共団体に使用されている
※地方公共団体は、平成29年4月から被保険者数に関わらず、適用されます。
★なお、令和4年10月の改正で、「継続して1年以上使用されることが見込まれる」という雇用期間の要件はなくなりました。雇用期間は、通常の被保険者と同様に「2か月を超えて見込まれること」となります。
過去問をどうぞ!
【R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
【R2年出題】 〇
問題文の場合、4分の3基準を満たさない短時間労働者ですので、厚生年金保険の被保険者となるには、報酬の月額が88,000円以上あることが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-082
R4.11.17 R4択一式より 適用事業所の高齢任意加入被保険者
70歳以上の者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金など老齢又は退職を支給事由とする年金受給権を有しないものは、任意に厚生年金保険に加入することができます。
高齢任意加入被保険者には、「適用事業所に使用される者」と「適用事業所以外の事業所に使用される者」の2種類あります。
それぞれの違いが、出題ポイントです。
今日は、高齢任意加入被保険者の保険料の負担について確認しましょう。
| 保険料 |
適用事業所の 高齢任意加入被保険者 | 原則 全額自己負担 ※事業主の同意がある場合は折半で負担することもできる |
適用事業以外の事業所の 高齢任意加入被保険者 | 事業主と折半で負担 ※加入について、保険料の負担について事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受ける |
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問2-A】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下「当該被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。
②【問2-C】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下「当該被保険者」という。)が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
①【問2-A】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、かつ、保険料の納付義務も本人が負います。
なお、事業主の同意がある場合は、事業主が保険料の半額を負担し、かつ、保険料の納付義務も事業主が負います。
(附則第4条の3第7項)
②【問2-C】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までに納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の「前月の末日」に資格を喪失します。
なお、初めて納付すべき保険料を滞納し、指定の期限までに納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなされます。
また、事業主の同意がある場合は、事業主が保険料の納付義務を負いますので、保険料滞納による資格喪失はありません。
(附則第4条の3第6項)
※ちなみに、「適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上」の者は、保険料の納付義務について事業主の同意を得ることが前提ですので、滞納による資格喪失はありません。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】
【H29年出題】 ×
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、保険料を納付する義務を負うことにつき同意することができます。又、その同意を将来に向かって撤回することもできます。ただし、「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」に係る事業主には適用されません。
(法附則第4条の3第7項、8項、10項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-081
R4.11.16 R4択一式より 在職定時改定
令和4年4月に在職定時改定が導入されました。
65歳以降も働いている場合は、負担した保険料が、毎年、年金額に反映する仕組みです。
条文を読んでみましょう。
第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
★在職定時改定は、65歳以上70歳未満の受給権者が対象です。60歳台前半の老齢厚生年金には適用されません。
★毎年9月1日(基準日)に基準日の属する月前の被保険者であった期間を、老齢厚生年金の額に反映させ、基準日の属する月の翌月(10月)から年金の額を改定する仕組みです。
厚生年金保険の被保険者(在職中) | ||
| ②の期間分→令和6年10月から増額 | |
| ①の期間分→令和5年10月から増額 | |
老齢厚生年金
| ||
老齢基礎年金 | ||
65歳 ①基準日 ②基準日
(令和5年9月1日) (令和6年9月1日)
①の期間 → 65歳到達月から令和5年8月まで
②の期間 → 前年9月から令和6年8月まで
令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】
65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
【問9-B】 ×
基準日は7月1日ではなく「9月1日」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-080
R4.11.15 R4択一式より 在職老齢年金と経過的加算額
「経過的加算額」は在職老齢年金の支給停止の対象となるか?ならないかが今日のテーマです。
まず、在職老齢年金の条文を読んでみましょう。
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
★経過的加算額については法附則で規定されています。確認しましょう。
・基本月額の計算では、繰下げ加算額と同じように除外されます。
・支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときでも、繰下げ加算額は支給停止されず全額支給されますが、経過的加算額も同じように全額支給されます。
(S60年法附則第26条第1項)
令和4年の問題をどうぞ!
【問8-C】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
【問8-C】 ×
経過的加算額は在職老齢年金の支給停止の対象にはなりません。
なお、老齢基礎年金も在職老齢年金の支給停止の対象となりません。
過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
②【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
③【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
経過的加算額も繰下げ加算額も、基本月額の計算から除かれます。
②【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は、在職老齢年金の支給停止の対象になりません。老齢厚生年金が全額支給停止されても、繰下げ加算額は全額支給されます。
③【H24年出題】 ×
60歳台後半の在職老齢年金で、経過的加算額と繰下げ加算額は支給停止の対象になりませんので、全額支給されます。
なお、老齢基礎年金も支給停止の対象にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-079
R4.11.14 R4択一式より 在職老齢年金の支給停止調整額
在職老齢年金のルールを確認しましょう。
・「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円以下の場合
→ 老齢厚生年金は全額支給されます
・「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超える場合
→ 老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。
→ 支給停止額は、「(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」で計算します。
条文を読んでみましょう。
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
用語の定義をおさえましょう。
総報酬月額相当額 →標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
基本月額 →老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)÷12
支給停止基準額 →(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×2分の1×12
★「支給停止調整額」は、令和4年度は47万円です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-E】
在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。

【解答】
【問8-E】 〇
支給停止調整額は、名目賃金変動率に応じて改定されます。令和4年度は47万円ですが、年度によっては改定されることもあります。
なお、支給停止調整額を計算する際の端数処理は、5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとされています。
(法第46条第3項)
では、過去問をどうぞ!
【H28年選択】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。

【解答】
A 総報酬月額相当額
B 支給停止調整額
C 支給停止基準額
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-054
R4.10.20 R4択一式より 70歳以上の使用される者の老齢厚生年金の調整
厚生年金保険の当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者です。
厚生年金保険の被保険者資格は70歳に達したときに喪失します。そのため、70歳以上の者は、在職中でも厚生年金保険の保険料は徴収されません。
しかし、在職老齢年金の仕組みは、70歳以上の者にも適用されます。
厚生年金保険の被保険者の場合は、総報酬月額相当額は、「標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」となります。一方、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではありませんので、総報酬月額相当額は、「その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-B】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
【問8-B】 ×
適用事業所に使用される70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではなく、保険料も徴収されませんが、在職老齢年金の仕組みは適用されます。
(法第46条)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金を受給している被保険者であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者の資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。
②【H28年出題】
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

【解答】
①【H23年出題】 〇 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳以上の者には、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
②【H28年出題】 ×
当初は、70歳以上の者のうち昭和12年4月1日以前生まれの者には、在職老齢年金の仕組みは適用されていませんでした。
しかし、平成27年10月1日の改正により、昭和12年4月1日以前生まれの70歳以上の者にも、在職老齢年金の仕組みが適用されることになりました。
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることがあります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-053
R4.10.19 R4択一式より 厚生年金保険・擬制的任意適用事業所
強制適用事業所が、従業員の減少などで強制適用事業所の要件を欠いた場合は、任意適用事業所の認可を受けたものとみなされます。このことを擬制適用といいます。
擬制適用によって、その事業所で働く従業員は引き続き社会保険の適用を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
第7条 強制適用事業所が、強制適用の要件に該当しなくなったときは、その事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなす。 |
例えば、個人の事業所の従業員の数が5人未満になった、法人の事業所が個人の事業所になった場合など、強制適用事業所の要件に該当しなくなる場合があります。
その場合は、「認可があったものとみなす」扱いとなります。改めて適用事業所となるための認可の申請手続きをとらなくても、引き続き厚生年金保険の適用事業所のままです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-D】
厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。

【解答】
【問7-D】 ×
認可があったものとみなされますので、任意適用の申請をしなくても、引き続き適用事業所となります。
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

【解答】
【R1年出題】 ×
任意適用事業所の認可申請を行わなくても、適用事業所として継続します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-052
R4.10.18 R4択一式より 遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の年齢要件
今日は、遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の年齢要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第59条 (遺族厚生年金の遺族) 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
第62条 (中高齢寡婦加算) 遺族厚生年金(長期要件に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で遺族基礎年金の遺族の要件に該当するものと生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。 |
ポイント!
★遺族厚生年金の遺族の要件
妻には年齢要件・障害要件はありません。
夫、父母、祖父母には年齢要件、子、孫には年齢要件・障害要件があります。
★中高齢寡婦加算の妻の要件
対象は妻のみです。
・遺族厚生年金の受給権取得当時、生計を同じくする子がいない場合(遺族基礎年金が支給されない場合) → 夫の死亡当時、妻の年齢が40歳以上65歳未満であること
・遺族厚生年金の受給権取得当時、生計を同じくする子がいる場合(遺族基礎年金が支給される場合) → 妻が40歳に達した当時遺族基礎年金を受けていること
※中高齢寡婦加算が加算されるのは、65歳に達するまでです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-C】
被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

【解答】
【問10-C】 ×
・夫の死亡当時、子のいない38歳の妻
→ 「遺族厚生年金」は受けることができます。中高齢寡婦加算は、子がいない場合は夫の死亡当時40歳以上であることが要件ですので、中高齢寡婦加算は支給されません。
・妻の死亡した当時、子のいない38歳の夫
→ 夫は妻の死亡当時55歳以上であることが要件ですので、遺族厚生年金を受けることはできません。なお、子の有無は関係ありません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
②【H27年出題】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
21歳の子も54歳の夫も年齢要件を満たしませんので、遺族厚生年金を受けることはできません。
②【H27年出題】 〇
子のない妻は、夫の死亡当時に40歳以上65歳未満であることが条件です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-044
R4.10.10 R4択一式より 在職老齢年金「総報酬月額相当額」
在職老齢年金の計算には、「基本月額」と「総報酬月額相当額」が使われます。
今日は、「総報酬月額相当額」の計算方法がテーマです。
では、総報酬月額相当額の定義を確認しましょう。
「総報酬月額相当額」とは → 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額 です。
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。

【解答】
【問8-A】 ×
総報酬月額相当額には「その月の標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の合計」を使いますので、標準報酬月額や標準賞与額が変われば、総報酬月額相当額も変わります。
では、過去問もどうぞ!
【H27年出題】
在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。

【解答】
【H27年出題】 ×
「改定が行われた月の翌月から」が誤りです。
総報酬月額相当額が変わった月から支給停止額が再計算されます。
総報酬月額相当額が改定された場合は、「改定が行われた月」から、新たな総報酬月額相当額に基づいて年金額が改定されます。
(法第46条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-043
R4.10.9 R4択一式より 障害手当金が支給されない場合
障害手当金は「一時金」として支給される保険給付です。
今日のテーマは、支給要件に該当しても、障害手当金が支給されない場合です。
では、条文を読んでみましょう。
第56条 障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) 2 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) 3 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者 |

厚生年金保険・国民年金の「年金」の受給権者には障害手当金は支給されません。
年金は、「障害」に限定されず、「老齢」、「障害」、「遺族」が対象です。
<例外> 障害厚生年金(障害基礎年金)の受給権者でも、3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過した受給権者(現に障害状態に該当しない場合)には、障害手当金が支給されます。

同じ傷病で労災保険から障害補償給付、複数事業労働者障害給付、障害給付を受ける権利を有する者には障害手当金は支給されません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-D】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。

【解答】
【問3-D】 〇
「年金たる保険給付の受給権者(国民年金の場合は「年金たる給付」)」には、原則として障害手当金は支給されません。
「年金たる保険給付」には遺族厚生年金も含まれます。障害手当金の障害の程度を定めるべき日に遺族厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
では、過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。
②【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「同一の傷病」により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されません。「同一の傷病」がポイントです。
②【R3年出題】 ×
同一の傷病により、障害手当金の受給権と労災保険法の障害補償給付の受給権を取得した場合、両方の保険給付が支給されるのではなく、障害手当金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(厚生年金保険法)
令和4年基本問題(厚生年金保険法)
R5-029
R4.9.26 R4択一式より『障害厚生年金の額の計算』
今日のテーマは障害厚生年金の額の計算です。
条文を読んでみましょう。
第50条 (障害厚生年金の額) ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①の規定にかかわらず、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例で計算します。
ただし、老齢厚生年金は、実際の厚生年金保険の被保険者期間で計算しますが、障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合は300月で計算します。
また1級の場合は、100分の125の額となります。
障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、障害認定日の属する月までとなります。障害認定日を初診日にする問題、属する月を「属する月の前月」とする問題に注意しましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【R4問10-D】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

【解答】
【R4問10-D】 ×
障害厚生年金の額の計算には、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間が算入されます。「障害認定日の属する月の前月まで」の部分が誤りです。
では過去問もどうぞ!
①【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
②【H29年出題】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
③【H22年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

【解答】
①【H22年出題】 ×
計算の基礎になるのは、「障害認定日の属する月」までの期間です。
②【H29年出題】 〇
計算の基礎になるのは、障害認定日の属する月(平成29年3月)までの期間です。障害認定日の属する月後(平成29年4月以後)の被保険者期間はその計算の基礎となりません。
③【H22年出題】 ×
240か月ではなく、「300か月に満たないときは、これを300か月とする」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(厚生年金保険法)
令和4年択一式を解いてみる(厚生年金保険法)
R5-018
R4.9.15 R4「厚年択一」は解きやすい問題が多かったです。今日は『老齢厚生年金の支給繰下げ』
令和4年の厚生年金保険法の択一式は、全体的に解きやすかったです。
テキストの読み込みと過去問対策の大切さが分かる出題でした。
今日は、「老齢厚生年金の支給繰下げ」の問題をみていきます。
まず、老齢厚生年金の支給繰下げの条件を令和2年の選択式の問題で確認しましょう。
(復習)では令和2年選択式からどうぞ!
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

【解答】
A 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
B 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、受給権を取得してから1年待たなければなりません。
また、「老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったとき」は、支給繰下げの申出はできません。
他の年金たる給付とは、「他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)」をいいます。
「老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金」は例外になっているのがポイントです。
例えば、老齢厚生年金の受給権取得日から1年経過した日までの間に、「老齢基礎年金+付加年金」の受給権があったとしても老齢厚生年金の支給繰下げの申出は可能です。同じく、老齢厚生年金の受給権取得日から1年経過した日までの間に、「障害基礎年金」の受給権があったとしても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
では令和4年の問題をどうぞ!
①【問5-C】
68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。
②【問5-D】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。
③【問5-E】
令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。

【解答】
①【問5-C】 〇
第44条の3第3項で、「支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。」と規定されています。
68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対しては、当該申出を行った月の翌月から開始されます。
②【問5-D】 ×
「経過的加算」は、支給繰下げの申出に応じた増額の対象となります。
繰下げ加算額は、(繰下げ対象額+経過的加算額)×増額率で計算します。
(令3条の5の2第1項)
③【問5-E】 〇
令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる上限が75歳に引き上げられています。
繰下げ受給の受給率は、「繰り下げた月数×0.7%」で計算します。10年繰下げた場合、120月×0.7%=84%増額されます。
ただし、対象になるのは、①「令和4年3月31日時点で70歳未満の者(昭和27年4月2日以降生まれ)」あるいは②「老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者(老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない)」に限られます。
①、②に該当しない場合は、繰下げの申出の上限は70歳です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑧
復習しましょう/令和4年選択式⑧
R5-008
R4.9.5 令和4年「厚年選択」は択一式のような問題でした
令和4年の選択式は、「択一式」対策がそのまま「選択式」対策になるような出題でした。
 産前産後休業期間中の保険料の免除期間について
産前産後休業期間中の保険料の免除期間について
条文からの出題でした。
第81条の2の2 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 |
★「開始した日の属する月」と「終了する日の翌日が属する月の前月」が問われました。
 遺族厚生年金が最初に支給されるのは誰でしょう?
遺族厚生年金が最初に支給されるのは誰でしょう?
・ 被保険者X(50歳)と生活を共にしているのは、妻Y(45歳)とYとYの先夫との子Z(10歳)
※XとZは養子縁組をしていない。事実上の親子関係であることがポイントです。
・ Xは、Xの先妻V(50歳)とXとVの子W(15歳)に養育費を送っている
Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは誰でしょう?
①まず、遺族基礎年金の受給権が発生するのは誰でしょう?
遺族基礎年金の受給権が発生するのは、先妻との子Wです。
Z、Y、Vには遺族基礎年金の受給権は発生しません。
なぜなら、
・ZはXと養子縁組をしていないため、「事実上の親子関係」です。「事実上の親子関係の子」は、遺族基礎年金の対象になる「子」にはならないからです。
・妻Yは、死亡したXの子と生計を同じくしていないからです。
・先妻Vは、死亡したときはXの妻ではないからです。
②遺族厚生年金の受給権が発生するのは誰でしょう?
死亡した当時の妻Yと先妻との子Wです。
③妻Yと子Wは遺族厚生年金の支給順位は同順位です。どちらが優先するでしょう?
第66条第2項によります。
第66条第2項 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が所在不明による支給停止の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
配偶者Yは遺族基礎年金の受給権がなく、子Wが遺族基礎年金の受給権を有するため、配偶者Yの遺族厚生年金は、支給停止されます。
遺族厚生年金が最初に支給されるのは、「W」となります。
 65歳未満の在職老齢年金の計算
65歳未満の在職老齢年金の計算
今年の改正点からの出題です。
計算式は、(総報酬月額相当額41万円+基本月額10万円-47万円)×2分の1
=2万円です。
支給停止額は、月額2万円です。
 事後重症の障害厚生年金
事後重症の障害厚生年金
事後重症のポイントは、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った+その期間内に請求することです。
★「65歳に達する日の前日」が問われました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-365
R4.8.22 選択対策・在職時改定と退職時改定
令和4年4月から、在職時改定が導入されています。
65歳以上の者は、「在職中」であっても、毎年1回、定時に年金額の改定を行うことになりました。
資格喪失時(退職時・70歳到達時)の老齢厚生年金の額の改定(退職時改定)は、もともとありましたが、今回の改正で、退職を待たずに、就労した分が早期に年金額に反映されることになりました。
穴埋め式で条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
第43条 (年金額) 1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額 (被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、< A >を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 受給権者が毎年< B > (以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する< C >の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する< D >から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が< E >以内である場合は、基準日の属する< C >の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する< D >から、年金の額を改定する。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して< E >を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して< F >から、年金の額を改定する。 |

【解答】
A 再評価率
B 9月1日
C 月前
D 月の翌月
E 1月
F 1月を経過した日の属する月
 在職時改定について
在職時改定について
→ 第43条第2項が改正で導入された「在職時改定」です。
★在職時改定で、年金額が改定されるのは、基準日の属する月の翌月(10月分)からです。
★在職時改定が適用されるのは、「65歳以上」の老齢厚生年金の受給権者です。
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権者には在職時改定は適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
②【R2年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

【解答】
①【H28年出題】 ×
従来からある「退職時改定」の問題です。
退職時改定による老齢厚生年金の額は、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から改定されます。
ただし、第14条第2号(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき)、第3号(適用事業所でなくする認可があったとき、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき)、第4号(適用除外に該当するに至ったとき)までのいずれかに該当するに至った場合は、「その日」から起算して1月を経過した日の属する月から改定されます。
問題文の場合は、1月31日に退職(事業所に使用されなくなった)ですので、1月31日から起算して1月を経過した日(2月末日)の属する月=平成28年2月から老齢厚生年金の額が改定されます。
②【R2年出題】 ×
同じく「退職時改定」の問題です。
7月1日生まれの者が70歳になり資格を喪失するのは、70歳に達した日=6月30日です。
資格を喪失した日(6月30日)から起算して1月を経過した日(7月31日)の属する月=7月分から老齢厚生年金の額が改定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-355
R4.8.12 「厚年」被保険者期間
今回のテーマは「被保険者期間」です。
条文を読んでみましょう。
第19条 1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 |
 「被保険者期間」は「月」単位でカウントします。
「被保険者期間」は「月」単位でカウントします。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
③【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は違いますので、注意しましょう。
資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの「日単位」で計算される期間は「被保険者であった期間」です。
「被保険者期間」は、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。
②【H30年出題】 〇
H29年 10月 | 11月 | 12月 | H30年 1月 | 2月 | 3月 |
資格取得 |
|
|
|
| 資格喪失 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間です。
資格を取得した月(平成29年10月)からその資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの「月単位」で計算されます。資格を喪失した月(平成30年3月)は被保険者期間には算入されません。
③【H28年出題】 〇
平成28年3月 | |
3/1・・・・・・・・・・・3/20 | 3/21・・・・・・・・・・・・・・・・ |
厚生年金保険 被保険者 | 国民年金 第1号被保険者 |
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪といいます)は、その月は、「1箇月」として被保険者期間に算入されます。
ただし、問題文のように、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、被保険者期間には算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-340
R4.7.28 遺族厚生年金 子・孫の失権事由
遺族厚生年金の遺族となる子、孫は、被保険者等の死亡当時、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。(法第59条第1項第2号)
子・孫は一定の年齢になった、障害状態でなくなった場合は、遺族厚生年金の受給権が消滅します。
子・孫特有の失権事由を条文で確認しましょう。
法第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ① 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 ② 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 ③ 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
②【H27年出題】 ※法改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

【解答】
①【H19年出題】 〇
「18歳に達する日以後の最初の3月31日」までは、障害状態の有無は問われません。
1級又は2級の障害の状態にある子又は孫について、その事情が止んだときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは失権しません。
又、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、その状態のまま20歳に達したときは、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
②【H27年出題】 〇 ※法改正による修正あり
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態でなければ、子・孫の遺族厚生年金の受給権は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。
問題文のように、障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。
③【R1年出題】 ×
・問題文の前半について
被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、16歳で障害等級3級に該当する障害の状態になりました。18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに3級の場合は、そこで受給権は消滅します。問題文の前半は「〇」です。
・問題文の後半について
被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、19歳のときに障害等級3級の障害の状態になりました。その場合は、「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。」に該当しますので、その時点で受給権は消滅します。「20歳に達したときに当該受給権は消滅する。」の部分が「×」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-339
R4.7.27 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
遺族厚生年金の失権事由の一つに「直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき」があります。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次に該当するに至ったときは、消滅する。 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき (法第63条第1項第3号) |
・養子となった場合でも、「直系血族、直系姻族の養子」であれば、失権しないのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
②【H23年出題】
被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く。)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。
③【H29年出題】
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権は、「直系姻族の養子」となった場合は、消滅しません。
②【H23年出題】 〇
祖父は「直系血族」です。祖父の養子になっても失権しません。
③【H29年出題】 ×
被保険者等が死亡したことにより、生計を維持していた妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生しました。
その後、妻(子の母)が再婚し、子が妻(子の母)の夫の養子になりました。
子からみると、母と再婚した夫は直系姻族です。母と再婚した夫の養子になっても失権しません。
ちなみに、母(死亡した者の妻)の遺族厚生年金は、「婚姻した」ことにより、失権します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-338
R4.7.26 30歳未満の妻の遺族厚生年金
夫の死亡当時、夫によって生計を維持していた妻には、子の有無や年齢に関係なく遺族厚生年金の受給権が発生します。
今回は、夫の死亡当時30歳未満だった妻の遺族厚生年金の失権について確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに消滅する。 2 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに消滅する。 (法第63条第1項5項) |
ポイント! 夫の死亡当時30歳未満の妻について
1について
夫の死亡当時30歳未満で子がいない場合は、遺族基礎年金の受給権は取得できませんので、遺族厚生年金の受給権のみ取得します。
その場合は、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに失権します。
夫死亡
(妻27歳・子なし) 30歳
遺族厚生年金 |
← ← ← ← ← 5年 → → → → 失権
2について
夫の死亡当時子がある場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得します。
しかし、妻が30歳に到達する前に子の死亡等により、遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに失権します。
夫死亡
(妻27歳・子あり) 妻28歳
遺族厚生年金 | |
遺族基礎年金 | ← ← ← 5年 → → → 失権 |
子死亡
(遺族基礎年金失権)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。
②【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
夫の死亡の当時27歳で子のいない妻の遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときではなく、「遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき」に消滅します。
②【H29年出題】 ×
妻が30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権が消滅します。
③【H26年出題】 〇
夫の死亡当時30歳未満で、遺族基礎年金の受給権を取得しない妻の遺族厚生年金の受給権は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-337
R4.7.25 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金
今回は2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金です。
「短期要件」と「長期要件」で異なりますので、注意しましょう。
ポイントを確認しましょう。
(短期要件の場合)
・ 被保険者が、死亡したとき。
・ 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
・ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
死亡日▼
第3号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者 |
★被保険者が死亡した場合は、死亡日に加入していた実施機関が、裁定・支給事務を行います。
(長期要件の場合)
・ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
※25年の計算には合算対象期間も入ります。
★それぞれの実施機関が、それぞれの加入期間ごとに裁定・支給事務を行います。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
②【H30年出題】
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

【解答】
①【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡は長期要件に該当します。
長期要件の遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給されます。
問題文の場合、「第1号厚生年金被保険者期間」分は、第1号の実施機関から、「第3号厚生年金被保険者期間」分は、第3号の実施機関から支給されます。
(第78条の32第2項)
②【H30年出題】 〇
障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、「短期要件」の遺族厚生年金が支給されます。
2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算して、遺族厚生年金の額の計算をします。
なお、1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡による遺族厚生年金の裁定・支給の事務は、初診日に加入していた実施機関が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-336
R4.7.24 夫の遺族厚生年金
今日は、夫に支給される遺族厚生年金を見ていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
遺族厚生年金の支給対象になる「夫、父母、祖父母」については、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件です。
ただし、60歳に達するまでは支給停止され、遺族厚生年金は60歳から支給されます。
しかし、「夫」の場合は、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳未満でも遺族厚生年金は支給停止されません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。
②【H29年出題】
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 ×
夫に対する当該遺族厚生年金は、夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳までの間でも、支給停止されません。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。
②【H29年出題】 〇
妻の死亡当時の夫の状況
・夫の年齢は55歳 → 遺族厚生年金の受給権が発生します
・15歳の子と生計を同じくしている → 遺族基礎年金の受給権が発生します。
夫の遺族厚生年金は、原則は60歳までは支給停止されますが、遺族基礎年金の受給権を有しているので、60歳前でも支給停止にならず、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができます。
しかし、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金の受給権が消滅します。その際、夫はまだ60歳に達していませんので、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は、原則どおり遺族厚生年金は支給停止となります。
(妻死亡)
夫55歳
子15歳 子18歳年度末 夫60歳
遺族厚生年金 | 支給停止 | 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金 |
|
|
遺族基礎年金失権
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-335
R4.7.23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金のポイントを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第78条の30 (障害厚生年金の額の特例) 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。
第78条の31 (障害手当金の額の特例) 障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定(障害厚生年金の額の特例)を準用する。
第78条の33 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、それぞれの被保険者の種別ごとに定められた事務の実施機関が行う。 |
ポイント!
例えば、第3号厚生年金被保険者であった期間と第1号厚生年金被保険者であった期間を有し、初診日に第1号厚生年金被保険者であった場合
初診日▼
第3号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者 |
・初診日に加入していた実施機関が、年金額の計算・裁定・支給事務を行います。
・年金額の計算は、他の実施機関の加入期間分も合算して計算します。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
②【H29年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の支給に関する事務は、障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
②【H29年出題】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を「合算」し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-334
R4.7.22 2以上の障害が生じた場合の障害厚生年金の併合認定
障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金の受給権が生じた場合は、併合認定が行われます。
条文を読んでみましょう。
第48条 (障害厚生年金の併給の調整) 1 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。 2 障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |
併合認定のイメージ
・併合認定の対象になるのは、「1級又は2級に該当したことがある障害厚生年金」です。
・先発の年金が3級でも、障害基礎年金が支給停止になっている場合(短期間でも1級又は2級の障害状態にあったことがある場合)は、併合認定の対象になります。
・なお、障害基礎年金の受給権がない3級は対象外です。
2級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |
2級 | 2級 | 1級 |
3級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |
支給停止 | 2級 | 1級 |
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
②【H29年出題】
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
③【R3年出題】
厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。

【解答】
①【H27年出題】 ×
受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の場合、障害基礎年金の受給権がありません。
先発の障害が3級の障害厚生年金(受給権を取得した当時から引き続き1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)の場合は、第48条の併合認定の対象になりません。
②【H29年出題】 〇
受給権を取得した当時は2級に該当したが、現在は3級である障害厚生年金の場合は、障害基礎年金の受給権があります。
障害厚生年金の受給権を取得した当時は2級に該当したが、現在は3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、併合認定の対象になります。
第48条により、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
3級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |
支給停止 | 2級 | 1級 |
③【R3年出題】 ×
2級の障害厚生年金の受給権者が、更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、「従前の障害厚生年金の受給権は消滅」します。支給停止ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-333
R4.7.21 障害厚生年金の失権
障害厚生年金の受給権の消滅について確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第53条(失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定(二以上の障害が生じた場合の併合認定)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。 ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
障害厚生年金が失権するとき
・二以上の障害が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅します。
・受給権者が死亡したときは、受給権は消滅します。
・障害等級に該当しなくなったときは、65歳までは支給停止されます。
障害等級に該当しないまま65歳に達したときは、そこで失権します。※65歳時点で障害等級に該当しなくなった日から3年未満の場合は失権しません。
・障害等級に該当しないまま3年を経過したときはそこで失権します。※3年を経過した時点で、65歳未満の場合は失権しません。
★「障害等級に該当しなくなってから3年経過したとき」か「65歳に達したとき」のどちらか遅い方に失権します。
例えば、63歳のときに障害等級に該当しなくなったときは、65歳時点では、3年経過していないので、失権しません。障害等級に該当しなくなってから3年経過した日に失権します。
★厚生年金保険法の「障害等級」は1級から3級です。「障害等級に該当する程度の障害の状態にない」ということは、3級未満ということです。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
②【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、障害等級に該当しなくなってから3年未満の場合は失権しません。
問題文は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったのが64歳時点です。65歳の時点では3年未満ですので失権しません。
②【R2年出題】 ×
障害等級に該当しなくなった場合でも、少なくとも65歳までは支給停止で、受給権は消滅しません。
支給が停止されたまま3年経過したとしても、65歳に達する日の前日までに3級に該当した場合は、支給停止が解除され、3級の障害厚生年金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-332
R4.7.20 障害厚生年金の配偶者加給年金額
1級・2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第50条の2 1 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 2 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 3 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
ポイント!
★配偶者加給年金額が加算されるのは、1級・2級の障害厚生年金です。3級の障害厚生年金には配偶者加給年金額は加算されません。
★65歳未満の配偶者が対象です。子については障害基礎年金の方で加算が行われます。
★受給権を取得した後に、生計を維持する配偶者を有するに至った場合も、配偶者加給年金額の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
②【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
③【H24年出題】
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
子は、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。
子は、障害基礎年金の方で加算の対象になります。
②【H29年出題】 〇
受給権が発生した時点では、生計を維持している配偶者がいなかったとしても、その後、例えば結婚をして対象になる配偶者を有するに至ったときは、加給年金額が加算されます。
その場合は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額が加算されます。
③【H24年出題】 ×
障害厚生年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも、1級・2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-301
R4.6.19 60歳台前半の在職老齢年金
令和4年4月から、60歳台前半の在職老齢年金の計算式が改正されました。確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法附則第11条 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 |
用語の定義を確認しましょう。
★総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額) + (その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
★基本月額
老齢厚生年金の額(加給年金額を除く) ÷ 12
★支給停止調整額
令和4年度は47万円
① 「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円以下の場合は、全額支給されます。
② 「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超える場合は、
(「基本月額+総報酬月額相当額」-47万円)の2分の1が支給停止されます。
③ 支給停止基準額「(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×2分の1」が、老齢厚生年金の額以上の場合は、全額支給停止されます。
※上記の計算式は月額です。支給停止基準額は、正確には12を乗じた額となります。
例えば、基本月額が20万円、総報酬月額相当額が32万円の場合は、20万円+32万円=52万円で47万円を超えますので、一部が支給停止になります。
(20万円+32万円-47万円)×2分の1=2万5千円が支給停止されます。
過去問をどうぞ!
【H25年出題】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。

【解答】
【H25年出題】 ×
「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と「その月以前」の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-300
R4.6.18 65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整
今日のテーマは、65歳以上の人が「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の受給権を得た場合の調整です。
条文を読んでみましょう。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
ポイント!
 65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合
→ 本人の老齢厚生年金が支給されます。(老齢厚生年金が優先です)本人が納付した保険料を年金額に反映させるためです。
→ 遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より高い場合は、差額が受けられます。
→ 老齢厚生年金が遺族厚生年金より高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止されます。
例えば、老齢厚生年金が30万円、遺族厚生年金が40万円の場合、遺族厚生年金のうち30万円は支給停止され、差額の10万円が遺族厚生年金として支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】※改正による修正あり
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
②【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H22年出題】 〇 ※改正による修正あり
65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権があるときは、老齢厚生年金を支給し、遺族厚生年金は、「当該老齢厚生年金の額に相当する部分」の支給が停止されます。
遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ、その差額が支給されます。
また、遺族厚生年金が老齢厚生年金より低ければ、遺族厚生年金は全額支給停止となります。
②【H29年出題】 〇
老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合は、加給年金の額は除かれることに注意してください。
(法第60条第1項第2号ロ、法第64条の2)
★ポイント!
「65歳に達している」がポイントです。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」はどちらかを選択します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-299
R4.6.17 65歳以上の配偶者の遺族厚生年金
遺族厚生年金は、報酬比例部分×4分の3で計算します。※報酬比例部分は、死亡した人の被保険者期間や報酬をベースに計算します。
ただし、老齢厚生年金の受給権がある65歳以上の配偶者が受給する遺族厚生年金については、注意が必要です。
では、条文を読んでみましょう。
第60条、法附則第17条の2 (年金額) 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①に定める額とする。 ① 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金の年金額)の例により計算した額の4分の3に相当する額。 ただし、短期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 ② 遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → ①に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ ①に定める額に3分の2を乗じて得た額 ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額は除く。)に2分の1を乗じて得た額
|
ポイント!
遺族厚生年金の額は、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3」で計算するのが原則です。
ただし、65歳以上で、老齢厚生年金の受給権を有する人が、配偶者の死亡により遺族厚生年金の受給権を有する場合の年金額は、
次の①と②の額を比較し、高い方になります。
① 死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3
② 「①の計算式の額×3分の2」と「自身の老齢厚生年金(子の加給年金額は除く)の額×2分の1」を合計した額
例えば、夫(老齢厚生年金(報酬比例部分)の額が80万円)、妻(65歳以上・老齢厚生年金の額が70万円)の場合であてはめると、夫が死亡した場合の妻の遺族厚生年金の額は、以下のようになります。
① 80万円×4分の3=60万円
② 「60万円×3分の2」+「70万円×2分の1」=75万円
①と②の高い方になりますので、妻の遺族厚生年金は②の75万円となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
②【R3年出題】
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として計算した「老齢厚生年金の額の4分の3」に相当する額です。しかし、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額を最低保障とする規定はありません。
②【R3年出題】 ×
配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)の遺族厚生年金の額は①と②のどちらか多い方です。
①死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3
②①の額の3分の2+配偶者本人の老齢厚生年金の額の2分の1
 ワンポイント!
ワンポイント!
第60条第1項に、「ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①に定める額とする。」と規定されています。
65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する配偶者でも、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の支給を受けるときは、遺族厚生年金の額は①で計算します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-276
R4.5.25 障害厚生年金の計算の基礎になる期間
障害厚生年金の計算式は以下の通りです。
1級 → 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額)
2級 → 報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額)
3級 → 報酬比例の年金額(最低保障額あり)
障害厚生年金の受給権の発生以降も厚生年金保険の被保険者期間がある場合、障害厚生年金の額の計算に算入されるのはどこまででしょう?
条文を読んでみましょう。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
障害認定日の属する月「後」の被保険者であった期間は、計算に入りません。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
②【H29年出題】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
③【H28年出題】
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。

【解答】
①【H22年出題】 ×
障害認定日の属する「月の前月」までではなく、「障害認定日の属する月」までが、その計算の基礎とされます。
|
| 障害認定日 |
|
|
条文の「障害認定日の属する月後」の「後」に注目してください。計算に入れるのは障害認定日の属する月までです。
②【H29年出題】 〇
障害認定日が平成29年3月1日ですので、障害厚生年金の額の計算に入れるのは平成29年3月までです。平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎とされません。
③【H28年出題】 ×
障害厚生年金には退職時改定の仕組みはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-275
R4.5.24 障害厚生年金の最低保障額
初診日に厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)だった場合、障害等級1・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てで支給されますが、3級の場合は、障害厚生年金のみ支給されます。
障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金には最低保障額があります。
条文を読んでみましょう。
第50条 (障害厚生年金の額) 1 障害厚生年金の額は、第43条第1項(老齢厚生年金の額)の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、1項の規定にかかわらず、1項に定める額の100分の125に相当する額とする。 3 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを 100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。 |
★ 国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額は、777,800円(令和4年度)×4分の3=583,350円を端数処理(50円未満切り捨て、50円以上100円未満を100円に切り上げ)して、58万3400円です。
★ポイント1・2級でも障害基礎年金が支給されない場合があります。
「厚生年金保険の被保険者」でも、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合は、国民年金の第2号被保険者となりません。
(詳細は前回の記事をどうぞ→R4.5.23 国年の第2号被保険者)
そのため、初診日に厚生年金保険の被保険者でも国民年金の第2号被保険者でない場合は、障害等級1・2級でも、障害厚生年金のみの支給となります。
その場合でも、障害厚生年金の最低保障額が適用されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
②【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
③【H29年出題】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とする。

【解答】
①【H25年出題】 ×
最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額に「4分の3」を乗じて得た額です。
②【R2年出題】 ×
①と同じです。最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する額です。
③【H29年出題】 〇
障害厚生年金の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額×4分の3に端数処理(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)をした額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-257
R4.5.6 年金の支給開始について
年金は、その事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで、月単位で支給されます。
条文を読んでみましょう。
第36条(年金の支給期間) 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 |
5月 | 6月 | ・・・・・ | 10月 | 11月 |
支給事由 発生 |
| ・・・・・
| 権利消滅 |
|
年金の支給期間は、事由が生じた月の翌月(6月)から、権利が消滅した月(10月)までです。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
②【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「初診日要件」、「保険料納付要件」を満たし、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合は、障害認定日に受給権が発生し、障害厚生年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。障害認定日が月の初日であっても同じです。
「ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。」が誤りです。
②【H30年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合は、死亡した日の翌日に資格を喪失します。
また、遺族厚生年金の受給権は、被保険者等が死亡した日に発生し、死亡した日の属する月の「翌月」から支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-240
R4.4.19 高齢任意加入被保険者 保険料の負担編
高齢任意加入被保険者には、「適用事業所に使用される者」と「適用事業所以外の事業所に使用される者」の2種類があります。
「適用事業所以外の事業所に使用される者」は、事業主が保険料の半額を負担することと納付の義務を負うことについて同意を得ることを条件に、資格を取得します。
一方、「適用事業所に使用される者」は、事業主の同意がなくても資格を取得できます。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料負担と納付については、原則として本人の責任になりますので、滞納したときの扱いがポイントになります。
では、条文を読んでみましょう。
附則第4条の3 (適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者) ⑦ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定(保険料の源泉控除)は、適用しない。 ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
⑧ 事業主は、被保険者の同意を得て、将来に向かって同意を撤回することができる。 |
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその1
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその1
・保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う
・事業主が同意をしたとき → 事業主が保険料の半額を負担し、かつ、事業主が保険料を納付する義務を負う
・事業主は将来に向かってその同意を撤回できる(被保険者の同意が必要)
では、続きです。
附則第4条の3 ③ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす。ただし、事業主の同意がある場合は、この限りでない。
⑥ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき(ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
|
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその2
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその2
・初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、納付しないとき
→ 被保険者とならなかったものとみなす
※事業主の同意がある場合は、この規定は適用されません
・保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき
→ 保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
※事業主の同意がある場合は、この規定は適用されません。
ポイント
・「適用事業所以外の事業所に使用される」高齢任意加入被保険者は、保険料の半額負担と納付義務は事業主が負いますので、滞納の問題は生じません。
しかし、「適用事業所に使用される」高齢任意加入被保険者は、保険料負担と納付義務は本人が負いますので、滞納の場合は資格喪失のペナルティがあります。しかし、事業主の同意がある場合は、責任は事業主にあるため、滞納の問題は生じなくなります。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。ただし、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主ではないものとする)が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときはこの限りではない。
②【H29年出題】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
③【H27年出題】 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主ではないものとする)は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
①【H24年出題】 〇 ※改正による修正あり
まず、「適用事業所に使用される」の部分をチェックしましょう。「適用事業所以外の事業所」の高齢任意加入被保険者には、この規定は適用されません。
また、後半の、「事業主の同意」の部分は、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主には適用されません。
(附則第4条の3第10項)
②【H29年出題】 ×
この規定が適用されないのは、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主です。
(附則第4条の3第10項)
③【H27年出題】 ×※改正による修正あり
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、「保険料の納期限の属する月の前月の末日」に資格を喪失します。
例えば、4月分の保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、保険料の納期限(5月末日)の前月の末日(4月30日)に資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-239
R4.4.18 高齢任意加入被保険者 資格取得編
厚生年金保険の被保険者の資格は70歳に達したときに喪失します。
しかし、70歳に達しても老齢年金の受給権がない場合は、70歳以上でも受給権を取得するまで厚生年金保険に任意で加入できます。
高齢任意加入被保険者には、「適用事業所に使用される者」と「適用事業所以外の事業所に使用される者」の2種類があります。
問題文を解くときは、どちらの高齢任意加入被保険者のことなのかを意識しましょう。
条文を読んでみましょう
附則第4条の3 (適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者) ① 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。 ② 申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
附則第4条の5 (適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者) 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。 認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 |
適用事業所に使用される場合、適用事業所以外の事業所に使用される場合の共通点は、「老齢厚生年金、老齢基礎年金等老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権がないこと」です。
また、「適用事業所に使用される」場合は「実施機関に申出」、「適用事業所以外の事業所に使用される」場合は「事業主の同意+厚生労働大臣の認可」が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
②【H20年出題】 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「適用事業所以外の事業所」に使用される場合は、事業主の同意を得たうえで、「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりません。この点は任意単独被保険者と同じです。「申出」ではありませんので注意しましょう。
また、「認可を受けた日」に資格を取得します。
②【H20年出題】 〇※改正による修正あり
「適用事業所」に使用される場合は、実施機関に申し出る必要があります。事業主の同意は要りません。
次はこちらをどうぞ!
③【H21年出題】
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。

【解答】
③【H21年出題】 ×
障害給付や遺族給付の受給権者でも、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の年金の受給権を有しない場合は、高齢任意加入被保険者になることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-238
R4.4.17 任意単独被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者は、任意に厚生年金保険に加入でき、「任意単独被保険者」といいます。
では、条文を読んでみましょう。
(任意単独被保険者) 第10条 ① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 ② ①の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 |
適用事業以外の事業所の従業員でも、単独で厚生年金保険の被保険者になることができます。任意単独被保険者といいます。
加入の場合は、その事業所の事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。事業主の同意は、保険料の半額負担と納付義務を負うことの同意です。
また、厚生労働大臣の認可を受けて、資格を喪失することもできます。喪失の際は、事業主の保険料の負担等の義務が無くなるため、事業主の同意は要りません。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②【H27年出題】
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
③【H19年出題】
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

【解答】
①【H24年出題】 ×
任意単独被保険者の保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額負担します。そのため、任意単独被保険者になるには、事業主の同意が必要です。
②【H27年出題】 ×
任意単独被保険者の資格の喪失には、事業主の同意は要りません。
③【H19年出題】 〇
任意単独被保険者は、「厚生労働大臣の認可があった日」に、資格を取得します。
なお、任意単独被保険者が、厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」に資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-225
R4.4.4 厚生年金保険・国庫負担
厚生年金保険の財源は主に保険料ですが、国庫負担もあります。
今日は国庫負担がテーマです。
条文を読んでみましょう。
第80条 (国庫負担等) ① 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 ② 国庫は、①に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。 ③ 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。 |
★「国庫負担」とは、年金給付の財源として、税負担をもとに国が支出するものです。(参照:厚生労働省ホームページ)
 先に「実施機関」を確認しましょう。
先に「実施機関」を確認しましょう。
・第1号厚生年金被保険者
→ 厚生労働大臣
・第2号厚生年金被保険者
→ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
・第3号厚生年金被保険者
→ 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
・第4号厚生年金被保険者
→ 日本私立学校振興・共済事業団
 では、第80条を確認しましょう。
では、第80条を確認しましょう。
①について
厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)にも、その被扶養配偶者(第3号被保険者)にも「基礎年金」が支給されます。そのための費用として、厚生年金保険の実施者たる政府は「基礎年金拠出金」を負担しています。その基礎年金拠出金の額の2分の1を国庫が負担しています。
②について
厚生年金保険事業の事務の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用は国庫が負担する。 → 事務費は、予算の範囲内で国庫が負担しています。
③について
実施機関(厚生労働大臣を除く)が納付する「基礎年金拠出金」と実施機関(厚生労働大臣を除く。)による「事務の執行に要する費用の負担」については、厚生年金保険法に定めるもののほか、共済各法の定めるところによります。
過去問をどうぞ!
【H29年選択式】
厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する< A >に相当する額を負担する。

【解答】
A 基礎年金拠出金の額の2分の1
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-224
R4.4.3 厚生年金保険の保険料の源泉控除
事業主は、保険料の被保険者負担分を報酬から控除することができます。
条文を読んでみましょう。
第84条 (保険料の源泉控除) ① 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 ② 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 ③ 事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 |
<原則>
事業主が報酬から控除できるのは、前月分の被保険者負担分の保険料です。
<月末退職の場合>
前月分と当月分を控除できます。
例えば、4月30日退職・5月1日喪失の場合、保険料は4月分まで徴収されます。
4月の報酬から、3月分と4月分の保険料を控除できます。
<賞与の保険料>
賞与の被保険者負担分の保険料は、賞与から控除できます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
②【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
控除できるのは、原則として「前月分の保険料」のみです。ただし、月末退職のように当月分の保険料が徴収される場合は、「前月分と当月分の保険料」を控除することができます。
②【H30年出題】 〇
被保険者負担分の保険料を控除したときは、控除の計算書を作成し、控除額を被保険者に通知しなければなりません。
 ちなみに、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、法第84条の2(保険料の徴収等の特例)で、「共済各法の定めるところによる」と規定されています。
ちなみに、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、法第84条の2(保険料の徴収等の特例)で、「共済各法の定めるところによる」と規定されています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-223
R4.4.2 厚生年金保険の保険料の納付
事業主には、被保険者負担分と事業主負担分の保険料を納付する義務があります。
今回は、保険料の納付のルールを確認します。
条文を読んでみましょう。
第83条 (保険料の納付) ① 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 ② 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 ③ ②の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。 |
事業主は、厚生年金保険の保険料を翌月末日までに納付しなければなりません。例えば、4月分の保険料は5月末日までに納付することになります。
翌月下旬ごろに、保険料の「納入告知書」が事業所に届きますので、それに保険料を添えて納付します。
②は「納入告知書の額が本来納付すべき保険料額より多かった」、「納付した保険料額が本来納付すべき保険料額より多かった」場合の事務簡素化のための規定です。
6か月間の保険料を繰り上げて先に納付したものとみなすことができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。
②【H30年選択式】
厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その< A >以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。
<選択肢>
①納入の告知又は納付の日から1年
②納入の告知又は納付の日から6か月
③納入の告知又は納付の日の翌日から1年
④納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
③【H25年出題】
厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
納付期日は、当月末日ではなく、「翌月末日」までです。
②【H30年選択式】
A ④納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
③【H25年出題】 ×
第83条第3項に、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、「厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」と規定されています。「事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。」ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-222
R4.4.1 厚生年金保険の保険料の負担及び納付義務
厚生年金保険の保険料は「標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額」です。
被保険者と事業主が半額ずつ負担し、事業主が納付義務を負います。
では、条文を読んでみましょう。
第82条 (保険料の負担及び納付義務) ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 ② 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 ③ 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 ④ 第2号厚生年金被保険者についての①の規定の適用については、①の「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 ⑤ 第3号厚生年金被保険者についての①の規定の適用については、①の「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 |
例えば、標準報酬月額が41万円の場合、厚生年金保険料は7万5,030円(41万円×1000分の183)で、被保険者と事業主がそれぞれ3万7515円ずつ負担します。
事業主は、被保険者負担分と事業主負担分を合わせた7万5030円を納付する義務を負います。
 さて、今日の過去問は、「2か所以上の事業所に使用される被保険者の保険料」です。
さて、今日の過去問は、「2か所以上の事業所に使用される被保険者の保険料」です。
先に、2か所で厚生年金保険に加入している被保険者の標準報酬月額の決定のルールを確認しておきましょう。
法第24条第2項で、「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定、資格取得時の決定、随時改定、育児休業を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定又は保険者算定の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。」とされています。
例えば、A社とB社で厚生年金保険の被保険者となっている場合、A社の「報酬月額」とB社の「報酬月額」の合算額がその者の報酬月額となります。その合算した報酬月額で標準報酬月額が決定されます。
A社とB社の標準報酬月額を合算ではありませんので、注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
②【H30年出題】
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。

【解答】
①【H28年出題】 〇
被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、それぞれの事業主が負担する保険料についての問題です。
それぞれの事業所の「報酬月額」で按分します。「標準報酬月額」ではないのでご注意ください。
按分割合は「各事業所について算定した報酬月額」÷「当該被保険者の報酬月額」です。
各事業主が負担する保険料は「当該被保険者の保険料の半額」×按分割合です。
なお、各事業主が納付する保険料は、「各事業主が負担すべき保険料+これに応ずる被保険者が負担すべき保険料」となります。
(令第4条第1項)
例えば、被保険者がA事業所とB事業所で被保険者になっている場合の報酬月額は下の図のようなイメージです。
被保険者の報酬月額(A+B) | |
A事業所の報酬月額 | B事業所の報酬月額 |
A事業主の負担割合は、A÷(A+B)です。
②【H30年出題】 〇
被保険者が船舶と同時に船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付について
・当該被保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは「船舶所有者」で、「船舶所有者以外の事業主」は保険料を負担、保険料を納付する義務は負いません。
(令第4条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-221
R4.3.31 厚生年金保険の保険料
厚生年金保険は、国庫負担と保険料によって賄われています。
今回は「保険料」の勉強です。
条文を読んでみましょう。
第81条 (保険料) 1 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。(表は省略します) |
用語について
・政府等 → 政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)
・被保険者期間
→ 「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」
・保険料額
→ 標準報酬月額×保険料率、標準賞与額×保険料率
・保険料率
→ 平成29年9月以後の月分・・・1,000分の183.00
ポイントを穴埋めでチェックしましょう
問題1
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(< A >を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

【解答】
A 基礎年金拠出金
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。
②【H24年出題】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
(第1号厚生年金被保険者の保険料率について)
平成16年の年金改正で保険料水準固定方式がとられるようになりました。厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月から毎年引き上げられ(平成17年度からは9月に引き上げられています。)、平成29年9月に1000分の183になり、そこで固定されました。
(第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率について)
被用者年金一元化によって、保険料率が毎年度引き上げられ、平成30年9月にそれぞれ1,000分の183に達し、固定されています。
(第4号厚生年金被保険者の保険料率について)
保険料率は毎年度引き上げられ、令和9年4月に1,000分の183に達します。
(H24年法律第63号附則第83、84、85条)
②【H24年出題】 ×
例えば、令和4年3月31日に資格取得、令和4年9月30日に退職・10月1日に資格喪失した場合で考えてみましょう。
被保険者期間は、「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」までとなりますので、3月から9月までとなります。
3/31 取得 |
|
|
|
|
| 9/30 退職 | 10/1 喪失 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
厚生年金保険の保険料は「被保険者期間の計算の基礎となる各月」に徴収されますので、退職した日(9月30日)が属する月(9月分)の保険料は徴収されます。
ポイント!
・月末に被保険者の資格を取得した月 → 保険料が徴収される
・月の末日付けで退職したとき → 退職した日が属する月分の保険料は徴収される
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-207
R4.3.17 離婚時みなし被保険者期間と遺族厚生年金
引き続き、離婚時みなし被保険者期間のよく出るところを見ていきます。
自身が厚生年金保険の被保険者になったことがなく、離婚時みなし被保険者期間のみを有する者が死亡した場合、遺族厚生年金は支給されるでしょうか?
まず、「遺族厚生年金」の死亡した人の条件を確認しましょう。
第58条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 3 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
第78条の11 第4号に該当する場合にあっては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。 |
第4号には、「離婚時みなし被保険者期間を有する者」が含まれることがポイントです。
また、「25年以上」には、合算対象期間も合算されます。(附則第14条)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】 ※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上あるものとする)を取得した後に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
②【H19年出題】
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。

【解答】
①【H28年出題】 〇 ※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間しか有していなくても、離婚時みなし被保険者期間を有した場合は、老齢厚生年金の受給権を取得します。
そのような場合で、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡した場合は、一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金 (離婚時みなし被保険者期間のみ) |
老齢基礎年金 (第1号被保険者期間のみ(25年以上)) |
②【H19年出題】 〇
自身は厚生年金保険の被保険者になったことがなく離婚時みなし被保険者期間のみの者が死亡した場合でも、遺族に遺族厚生年金が支給されることがあります。
ただし、死亡した者の保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が原則として25年以上あることが条件です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-206
R4.3.16 離婚時みなし被保険者期間の扱いその1
「離婚時みなし被保険者期間」とは?
例えば、厚生年金保険の被保険者の夫から第3号被保険者の妻に厚生年金の分割が行われた場合、妻は厚生年金保険の被保険者ではありませんが、分割を受けたことにより、その期間は(厚生年金保険の)被保険者期間であったとみなされます。これを「みなし被保険者期間」といいます。
■合意分割
・ 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間
→ 第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。(離婚時みなし被保険者期間)
(第78条の7)
■3号分割
・ 特定期間に係る被保険者期間
→ 被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす。(被扶養配偶者みなし被保険者期間)
(第78条の15)
今日のテーマは「みなし被保険者期間」です。
「みなし被保険者期間」を算入するか算入しないかが問われるポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
②【H29年出題】
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
③【R3年出題】
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があることが条件です。みなし被保険者期間は、「1年以上」には算入されません。そのため、自身で厚生年金保険に加入したことがなく、みなし被保険者期間しか有しない場合は、特別支給の老齢厚生年金は受給できません。
(法附則第17条の10)
②【H29年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、「1,628円×改定率×厚生年金保険の被保険者期間の月数」で計算しますが、みなし被保険者期間は、この計算には算入されません。
(法附則第17条の10)
③【R3年出題】 〇
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算される要件である「被保険者期間の月数が240以上」の被保険者期間には、みなし被保険者期間は算入されません。
加給年金額が加算されるには、自身の厚生年金保険の被保険者期間が原則として240以上あることが条件です。
(法附則第17条の10)
※「被扶養配偶者みなし被保険者期間」も「離婚時みなし被保険者期間」と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-187
R4.2.25 遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額が加算されるとき
例えば、海外に居住している1級の障害厚生年金を受給中の夫(35歳)、妻(35歳)、子(10歳)の家族で、夫が死亡した場合を考えてみます。
夫は国内では第1号被保険者でしたが、日本国内に住所を有しなくなったため、国民年金の被保険者の資格を喪失しています。なお、任意加入もしていません。
夫の死亡により、遺族厚生年金と遺族基礎年金は支給されるでしょうか?
・遺族厚生年金は?
→ 「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき」に該当しますので、要件を満たせば妻と子に受給権が発生します。
・では、遺族基礎年金は?
→ 遺族基礎年金は次の4つのどれかに該当することが条件です。
(国民年金法第37条)
① 被保険者が、死亡したとき。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
③ 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
死亡した夫は4つのどれにも該当しませんので、遺族基礎年金は支給されません。
このように、遺族厚生年金は支給されても、妻と子が生計を同じくしているのに、遺族基礎年金が支給されないケースがあります。
そこで、遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額が加算される規定があります。
条文で確認しましょう。
昭和60年附則第74条 ① 配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であって、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条第1項(子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。 |
★ この規定により、先ほどのケースの妻の遺族厚生年金には、遺族基礎年金の額と子の加算額に相当する額が加算されます。
では、過去問をどうぞ
①【H29年出題】(改正による修正あり)
国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年未満であった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。
②【H18年出題】
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。

【解答】
①【H29年出題】(改正による修正あり) 〇
最初に説明したのは、妻と子の例でしたが、この問題のように遺族が「子」のみの場合でも、遺族厚生年金に遺族基礎年金の額に相当する額が加算されます。
昭和60年附則第74条第2項に次のように規定されています。
| 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条の2第1項(子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。 |
(昭和60年附則第74条第2項)
②【H18年出題】 〇
①の問題と同じです。
(昭和60年附則第74条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-186
R4.2.24 子が出生したときの父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の失権
例えば、被保険者等の死亡の当時、配偶者も子もなくて、父がいる場合は、父が遺族厚生年金の受給権者になります。
しかし、死亡当時胎児であった子が出生した場合は、子が先順位になりますので父の受給権は消滅します。
では、条文を読んでみましょう。
第63条 ③ 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。 |
★ 胎児であった子の出生で受給権が消滅するのは、子より後順位の父母、孫、祖父母です。
では、過去問です!
①【H24年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
②【R2年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
配偶者と子は、同じ順位ですので、胎児であった子が出生しても、妻の受給権は消滅しません。
②【R2年出題】 〇
①の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-185
R4.2.23 遺族厚生年金・所在不明の場合の支給停止
今回は、1年以上所在不明の場合の支給停止です。
ポイントは、支給停止のスタートと解除のタイミングです。
では、条文を読んでみましょう。
第67条 ① 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② 配偶者又は子は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。 |
★ 支給停止は、所在が明らかでなくなったときにさかのぼるのがポイントです。申請したときからではありません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。
②【R2年出題】
死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「申請の日から」ではなく、「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給を停止されます。
配偶者と子が受給権者になった場合、配偶者に遺族厚生年金を支給し、子の遺族厚生年金は支給停止になるのが原則です。しかし、配偶者が所在不明で配偶者の遺族厚生年金の支給が停止されると、子の支給停止が解除されます。
(法第66条第1項、第67条)
②【R2年出題】 〇
所在が1年以上明らかでないとき
☆「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」支給が停止されます。
所在不明になった日が属する月の翌月から支給停止されます。
☆支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができます。
支給停止が解除されるのは、「支給停止の解除の申請をした日」が属する月の翌月からです。所在が明らかになった日ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-184
R4.2.22 遺族厚生年金・配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しないとき
遺族厚生年金の受給権は配偶者と子の両方に発生、しかし遺族基礎年金の受給権は子のみに発生する場合があります。
その場合の調整が今日のテーマです。
では、条文を読んでみましょう。
第66条 ② 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条(1年以上の所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
☆この条文のシチュエーション
夫Aと妻Bの夫婦に子Cがいた。 しかし夫婦は離婚し、子Cは妻Bと生計を同じくし、夫Aは、Cの養育費を送金している。 その後、夫Aは、Dと再婚し、現在は、夫Aと妻Dが夫婦となっている。 |
そして厚生年金保険の被保険者である夫Aが死亡した場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権はどうなるでしょうか?
・ 子Cについて → 死亡した被保険者(A)と生計維持関係が認められると、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給権が発生する
・ 元妻Bについて → 死亡したAとは夫婦ではないので、遺族年金の受給権は発生しない
・ 妻Dについて → 「遺族厚生年金」の受給権が発生する。しかし、死亡したA
の子(C)と生計を同じくしていないので遺族基礎年金の受給権は発生しない
条文に当てはめると、『配偶者(妻D)に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者(夫A)の死亡について、配偶者(妻D)が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子(C)が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する』となります。
配偶者(妻D)の遺族厚生年金は支給停止されます。
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
※遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。

【解答】
【H26年出題】 〇
冒頭のシチュエーションに当てはめて問題文を読んでみてください。
妻の遺族厚生年金は支給停止され、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
(法第66条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-183
R4.2.21 遺族厚生年金・配偶者と子の支給調整
遺族厚生年金の支給順位では、配偶者と子は同順位です。配偶者と子が両方受給権者になったときの調整方法が今日のテーマです。
では、条文を見てみましょう。
第66条 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
配偶者と子が受給権者になった場合、配偶者に遺族厚生年金を支給し、子の遺族厚生年金は支給停止になるのが原則です。
例外的に、配偶者の遺族厚生年金が第65条の2(夫、父母、祖父母の支給停止)、第66条第2項(配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しないとき)、第67条(所在不明のときの支給停止)の規定で支給停止されている場合は、子に支給されます。
※「第66条第2項(配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しないとき)」は次回お話しします。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。以下同じ。)の支給が停止され、配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。
②【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
③【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
④【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【解答】
①【H22年出題】 ×
最後の「子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。」の部分が誤りです。
妻(遺族基礎年金の受給権を有する)に遺族族厚生年金を支給する間は、子の支給は停止されます。
夫の場合も同じで、夫(遺族基礎年金の受給権を有する)に遺族厚生年金を支給する間は、子の支給が停止されます。
(法第66条)
②【H26年出題】 〇
受給権者はその意思によって、年金の支給停止を申し出ることができます。
問題文のように、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
国民年金法の「遺族基礎年金」との違いに注意してください。遺族基礎年金の場合は、配偶者が申し出ることによって、配偶者の遺族基礎年金が支給停止になっている場合は、子の遺族基礎年金は支給されます。
参考 → R4.2.17 遺族基礎年金の支給停止(その3 子に対する支給停止)
(法第66条)
③【H30年出題】 ×
「子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。」が誤りです。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
(法第66条)
④【R3年出題】 ×
妻が、「障害基礎年金と障害厚生年金」を選択し、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」が全額支給停止になった場合でも、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給停止は解除されず、支給停止のままです。
(法第66条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-182
R4.2.20 遺族厚生年金・夫、父母、祖父母の支給停止
遺族厚生年金の遺族となる「夫、父母、祖父母」は、被保険者等の死亡の当時55歳以上であることが条件です。
しかし、遺族厚生年金の支給が始まるのは60歳からです。
条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
「夫、父母、祖父母」は、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件ですが、60歳までは支給停止されます。
ただし、遺族基礎年金の受給権がある「子のある夫」については、60歳までの間も支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
②【R1年出題】
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。
③【H29年出題】
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】
①【H27年出題】 〇
☆夫のポイント
・妻の死亡当時55歳以上であること
・夫が60歳に達するまでは支給停止
・夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき(子があるとき)は、支給停止されません
②【R1年出題】 ×
夫に対する当該遺族厚生年金 → 原則は60歳に達するまでは支給停止ですが、遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳前でも支給されます。
③【H29年出題】 〇
妻死亡
(夫55歳、子15歳) (子18歳年度末) (夫60歳)
▼ ▼ ▼
遺族厚生年金 | 支給停止 | 支給再開 |
遺族基礎年金 |
| |
▲遺族基礎年金失権
(夫について)
・ 子が18歳の年度末までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できる
・ 子が18歳の年度末が終了したときに遺族基礎年金は失権する
・ その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-181
R4.2.19 遺族厚生年金の遺族の優先順位
前回は、遺族の要件をみましたが、今回はその優先順位です。
では、条文を読んでみましょう。
第59条 ② 父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
③ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。 |
 最も優先順位が高いのは、「配偶者又は子」です。配偶者と子は同順位です。
最も優先順位が高いのは、「配偶者又は子」です。配偶者と子は同順位です。
そして、「配偶者又は子」がいない場合は「父母」、「配偶者、子又は父母」がいない場合は「孫」、「配偶者、子、父母又は孫」がいない場合は「祖父母」の順番になります。
順位が高い遺族がいる場合は、それ以下の人は遺族厚生年金を受けることができる遺族になりません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
②【H23年出題】
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。
③【R2年出題】
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。
④【H27年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

【解答】
①【H29年出題】 〇
生計維持されていたのが「妻、子、母」の場合、最も優先順位の高い「妻と子」に受給権が発生します。
『「父母」は、配偶者又は子が、遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。』とされていますので、問題文の場合、母は遺族厚生年金の対象の遺族にはなりません。
転給の制度もありませんので、妻が失権しても、母が遺族厚生年金の受給権を取得することはありません。
②【H23年出題】 ×
①の問題と同じです。
妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、母は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。
③【R2年出題】 〇
①、②と同じです。
子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、父は遺族厚生年金を受けることはできません。子が失権したとしても、転給されることもありません。
④【H27年出題】 〇
「将来に向かって」がポイントです。死亡当時胎児だった子は、出生以降、遺族厚生年金の対象になります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-180
R4.2.18 遺族厚生年金の遺族「配偶者、子、父母、孫、祖父母」の要件
遺族基礎年金の遺族となる「子のある配偶者」又は「子」以外に、遺族厚生年金の遺族には、子のない配偶者、父母、孫、祖父母が入ります。
では、条文を読んでみましょう。
第59条 (遺族) 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
昭和60年法附則第72条第2項 平成8年4月1日前に死亡した「夫、父母、祖父母」については、障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること。 |
遺族の条件は以下の通りです。
★被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していたこと
・妻 → 年齢要件、障害要件は問わない
・夫、父母、祖父母
→ 55歳以上であること
(平成8年4月1日前に死亡した場合は、障害等級1級、2級であれば年齢は問わない)
・子、孫
→ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、又は20歳未満で障害等級1級、2級、かつ、現に婚姻をしていない
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
②【R1年出題】
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
③【R3年出題】
85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
遺族基礎年金の遺族になる配偶者は子があることが条件ですが、遺族厚生年金の遺族の配偶者は、子の有無は問われません。
55歳以上の夫は、子がいない場合でも受給権者になり得ます。
②【R1年出題】 ×
54歳の夫と21歳の子は年齢要件に合いませんので、両方とも遺族にはなりません。
③【R3年出題】 〇
60歳の子は年齢要件に合わないので、遺族になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-163
R4.2.1 障害厚生年金の加給年金額
前回お話したように、障害基礎年金には「子」の加算額が加算されます。
「配偶者」は「障害厚生年金」の加給年金額の対象になります。
今回は、障害厚生年金の加給年金額がテーマです。
★では、条文を確認しましょう。
第52条の2 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
 ポイント!
ポイント!
・ 加給年金額が加算されるのは、1級又は2級の障害厚生年金です。
3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。
・ 対象は65歳未満の配偶者です
・ 加給年金額は「224,700円×改定率」です。老齢厚生年金の配偶者加給年金額に は、特別加算がプラスされますが、障害厚生年金の加給年金額には特別加算はつきません。
・ 受給権を取得した日の翌日以後に、対象になる配偶者を有することに至った場合でも加給年金額は加算されます
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。
②【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
①【H22年出題】 〇
加給年金額が加算される障害厚生年金は、「障害等級1級又は2級」です。対象は、「65歳未満」の配偶者です。年齢にも注意してください。
②【H29年出題】 〇
受給権を取得した日の翌日以後に対象の配偶者を有するに至った場合でも加給年金額は加算されます。その場合は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額が加算されます。
(障害基礎年金の子の加算と同じです。→ (参考)前回の記事をどうぞ)
次はこちらをどうぞ!
③【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
④【H20年出題】
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
加給年金額は、次のどれかに該当するに至ったときは、加算がなくなります。
1 死亡したとき。
2 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
4 配偶者が、65歳に達したとき。
問題文の場合は4に当てはまります。その該当するに至った月の翌月から加給年金額が加算されなくなります。
なお、「大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。」の部分もポイントです。「大正15年4月1日以前に生まれた者」は旧法の対象者で、新法の老齢基礎年金が支給されません。ですので、振替加算も行われません。
「大正15年4月1日以前に生まれた者」は、65歳以降も加給年金額の対象となります。
(法第50条の2第4項)
④【H20年出題】 ×
「配偶者の生年月日にかかわらず」が誤りです。
配偶者が「大正15年4月1日以前生まれ」の場合は、配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月からも加給年金額が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-153
R4.1.22 障害厚生年金 額の改定その3 3級から2級へ②65歳以上の場合
障害認定日に3級だったものが、その後2級に増進した場合、障害厚生年金は3級から2級に改定、障害基礎年金は事後重症になることを、前回お話しました。
しかし、3級から2級に増進したときに65歳以上だった場合は注意が必要です。今回は、65歳以上で障害の程度が増進した場合がテーマです。
では、第52条の条文を見てみましょう。
第52条 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は①の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ④から⑥は省略
⑦ ①から③まで及び前項の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
★⑦に注目してください。
「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」とは、「受給権を取得した当時から1度も障害等級1級又は2級に該当したことがない」という意味です。
65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないもの)には、1・2級への等級改定は行われません。
「障害基礎年金の事後重症」の適用は、65歳に達する日の前日までに限られています。そのため、65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進しても、事後重症の障害基礎年金の受給権は発生しません。
ですので、65歳以降は3級から1・2級への改定は行わないことになっています。1・2級の障害厚生年金だけ支給されることがないようにするためです。
では、過去問をどうぞ
①【H23年出題】
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができない。
②【H27年出題】
63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ請求した場合において、その後、当該障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
65歳以上の者だけでなく、老齢基礎年金を繰り上げて受給している者も、事後重症の障害基礎年金は請求できません。
また、「障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)」とは、受給権を取得した当時から3級で、1度も1級・2級に該当したことがないという意味です。
問題文の「老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者」は、事後重症の障害基礎年金の請求ができません。ですので、障害の程度が3級から増進しても、障害厚生年金の額の改定請求はできません。
(法第52条第7項、法附則第16条の3)
②【H27年出題】 ×
「老齢基礎年金を繰上げ請求している」かつ「3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)」は、障害の程度が増進しても、障害厚生年金の額の改定は請求できません。
(法第52条第7項、法附則第16条の3)
もう一問どうぞ!
③【R2年出題】
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
この問題は、2級の障害状態に該当していたことがあり、障害基礎年金の受給権があることがポイントです。
2級だったものが、症状が軽減して3級の程度になった場合、障害厚生年金は3級、障害基礎年金は支給停止となります。
その後、再び2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に改定、障害基礎年金は支給停止が解除され、2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
この場合は、65歳に達した日以後でも、3級から2級に額の改定が行われます。
(下の図も参考にしてください。)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
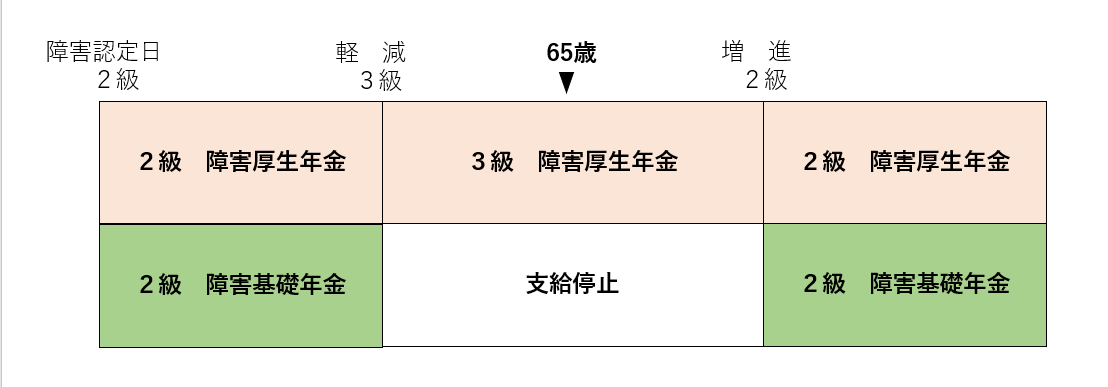
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-152
R4.1.21 障害厚生年金 額の改定その2 3級から2級への改定①
3級の障害が重くなり2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に額の改定が行われます。
その場合、「障害基礎年金」は、「事後重症」になることがポイントです。
初診日に厚生年金保険の被保険者(国民年金は第2号被保険者)で、障害認定日に3級に該当した場合、「3級の障害厚生年金」の受給権が発生しますが、障害基礎年金の受給権はありません。
その後、障害の程度が増進し2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に額の改定が行われます。一方、障害基礎年金は「障害認定日」に障害等級(1・2級)に該当しなかったものが、その後障害等級(1・2級)に該当することになり、「事後重症」となります。(下の図でご確認ください)
障害厚生年金の3級から2級への額の改定は、障害基礎年金の事後重症の要件を満たす必要があるのがポイントです。
 ここで、「国民年金法」の条文を読んでみましょう。
ここで、「国民年金法」の条文を読んでみましょう。
国民年金法第30条の2 (事後重症の障害基礎年金) ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 ④ 第①項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに①項の請求があったものとみなす。 |
★ 最後の「そのときに①項の請求があったものとみなす。」に注目してください。
事後重症の障害基礎年金は「請求」によって受給権が発生します。しかし、障害厚生年金の障害等級が3級から2級に改定された場合は、改めて請求しなくても、障害厚生年金の改定に伴い、請求が行われたとみなされます。
 では、国民年金の過去問をどうぞ!
では、国民年金の過去問をどうぞ!
①【国民年金H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
②【国民年金H22年出題】
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
①【国民年金H30年出題】 ×
障害厚生年金が3級から2級に改定された場合は、障害基礎年金は、事後重症の「請求があったものとみなす。」ことになっています。請求しなくても、事後重症の障害基礎年金の受給権が発生します。
②【国民年金H22年出題】 ×
①の問題と同じです。障害基礎年金に係る事後重症の請求をしなくても、受給権が発生します。
次回に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
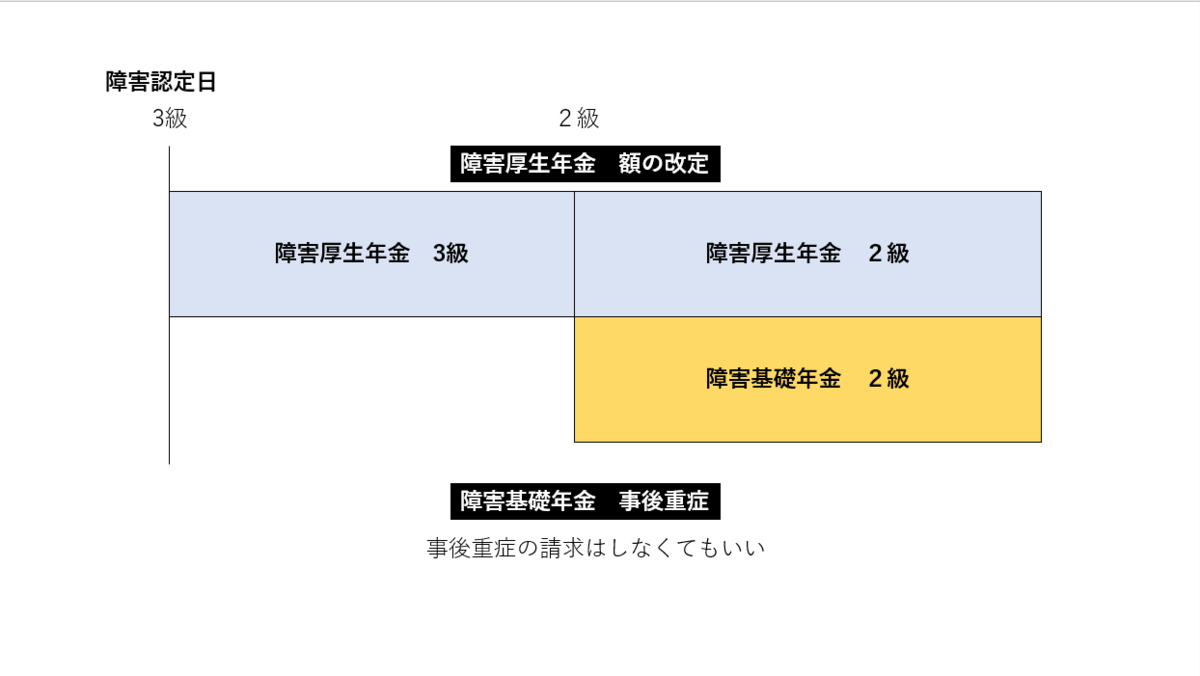
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-151
R4.1.20 障害厚生年金 額の改定 その1
障害の程度は、重くなったり軽くなったりすることがあります。その場合は、年金額が増額改定されたり、減額改定されます。又、障害等級に該当しなくなった場合は支給停止されます。
改定の方法として、「実施機関の職権による改定」、「障害の程度が増進したことによる改定請求」、「その他障害による併合改定」があります。
まず、「実施機関の職権による改定」を条文で読んでみましょう。
第52条 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 |
実施機関が障害の程度を診査して、職権で障害厚生年金の額を改定することができます。
改定が行われた場合は、改定が行われた月の翌月から、改定後の額による障害厚生年金の支給が始まります。
さて、今回は、「障害の程度が増進したことによる改定請求」をメインにお話します。
第52条の条文の続きを読んでみましょう。
第52条 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は①の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
障害の程度が増進した場合は、障害厚生年金の額の改定請求ができます。
改定請求は、原則として1年待たなければなりません。
「障害厚生年金の受給権を取得した日」
又は
「実施機関の診査を受けた日」
から起算して1年を経過した日後でなければ、行うことができません。
しかし、「障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は、例外的に1年を経過しなくても額の改定請求をすることができます。
「障害厚生年金の受給権を取得した日」又は「実施機関の診査を受けた日」のどちらか遅い日以降に、例えば、「両眼の視力の和が0.04以下のもの」に該当した場合等は、1年を経過していなくても、改定請求ができます。(施行規則第47条の2の2)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。
②【H27年出題】
40歳の障害厚生年金の受給権者が実施機関に対し障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求を行ったが、実施機関による診査の結果、額の改定は行われなかった。このとき、その後、障害の程度が増進しても当該受給権者が再度、額の改定請求を行うことはできないが、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合については、実施機関による診査を受けた日から起算して1年を経過した日後であれば、再度、額の改定請求を行うことができる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
1年6か月ではなく「1年」です。
実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後なら、再び改定の請求を行うことができます。
②【H27年出題】 ×
・その後、障害の程度が増進した場合
→ 実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後なら、再度、額の改定請求を行うことができます。(「再度、額の改定請求を行うことはできない」の部分が誤りです。)
・障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合
→ 実施機関による診査を受けた日から起算して1年を経過しなくても、額の改定請求ができます。
次回に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ⑦ 国年・厚年(旧法から新法へ)
どんな法律シリーズ⑦ 国年・厚年(旧法から新法へ)
R4-138
R4.1.7 国年・厚年その2(旧法から新法へ)
前回は、年金制度の創成期のお話をしました。
その後の経済の高度成長の中で、年金制度も充実期を迎えます。
そして、加速する高齢化、経済成長の安定化から、公的年金も大きな見直しが行われました。
昭和60年改正の大きな柱は次の3つです。
① 基礎年金の導入
② 厚生年金の給付水準の適正化
③ 女性の年金権の確立
「昭和61年4月1日」前後で年金制度が大きく変わります。昭和61年4月1日前の制度を「旧法」、それ以後を「新法」といいます。
① 基礎年金の導入について
それまでの公的年金は、自営業者等が加入する「国民年金」、民間の会社員が加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済年金」の大きく3つに分かれていました。
それぞれが独自に運営されていたので、給付面でも負担面でも制度間に格差があったこと、また、産業構造の変化に伴い財政基盤が不安定になる問題も起こっていました。
このため、登場したのが「全国民共通の基礎年金」です。
国民年金は「基礎年金」として、全国民共通の年金を担当することになりました。また、厚生年金等の被用者年金は基礎年金に上乗せされる報酬比例年金として位置づけられました。
「基礎年金」の導入によって、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金や共済年金」となる「2階建ての年金」の方式になりました。
② 厚生年金の給付水準の適正化について
加入期間が延びてもこれ以上給付水準が高くならないよう、給付乗率や定額単価も見直しが行われました。
具体的には、大正15年4月2日から昭和21年4月1日以前生まれの人の給付乗率や定額単価は、生年月日が若くなっていくほど逓減していきます。
新法施行時に40歳未満だった昭和21年4月2日以後生まれの人には新法の給付乗率や定額単価を適用しますが、40歳を過ぎていた昭和21年4月1日以前生まれの人は、旧法の水準から徐々に新法の水準に近づけていくイメージです。昭和61年4月1日を境に、給付乗率や定額単価をいきなり減らすことができないからです。
③ 女性の年金権の確立について
旧法では民間サラリーマン等の妻(専業主婦)は、国民年金には「任意で加入できる」位置づけでした。任意加入しなかった場合は、老後は、サラリーマンの夫の年金に加算される配偶者加給年金額で保障されることになっていました。
ただし、妻が任意加入していない場合は、離婚すると老齢年金が受給できない、障害になっても障害年金が受給できない問題もありました。
そのため、新法では、サラリーマン等の妻(専業主婦)も国民年金に第3号被保険者として加入することになりました。ただし、保険料は、第3号被保険者が個別に負担するのではなく、夫の加入する被用者年金制度全体で負担しています。
※妻と夫が逆の場合も同じです。
過去問をどうぞ!
【H15年選択式】
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【解答】
A 大正15年4月2日
★「基礎年金」という名称が登場するのは新法からです。
新法の「老齢基礎年金」が支給されるのは、昭和61年4月1日に60歳未満だった大正15年4月2日以降生まれの人です。ただし、大正15年4月2日以降生まれでも、昭和61年3月31日に旧法の老齢・退職給付の受給権があった場合は、そのまま旧法が適用されます。
B 障害認定日
★障害基礎年金は障害認定日に受給権が発生します。障害認定日(受給権の発生日)が昭和61年4月1日以降なら、新法の障害基礎年金が支給されます。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
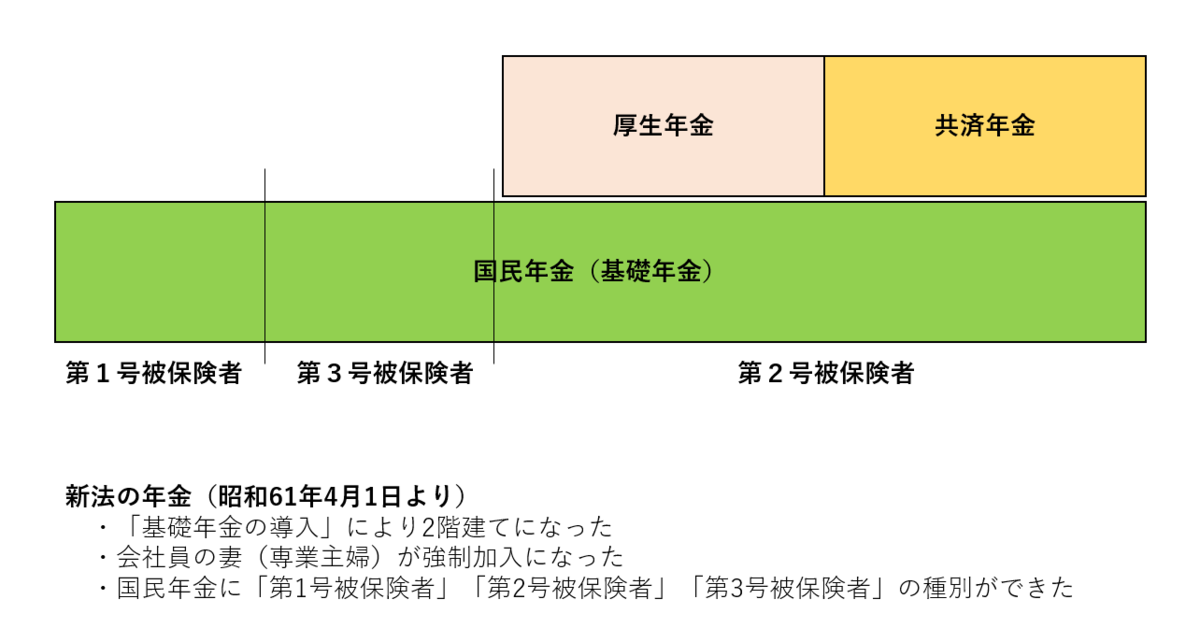
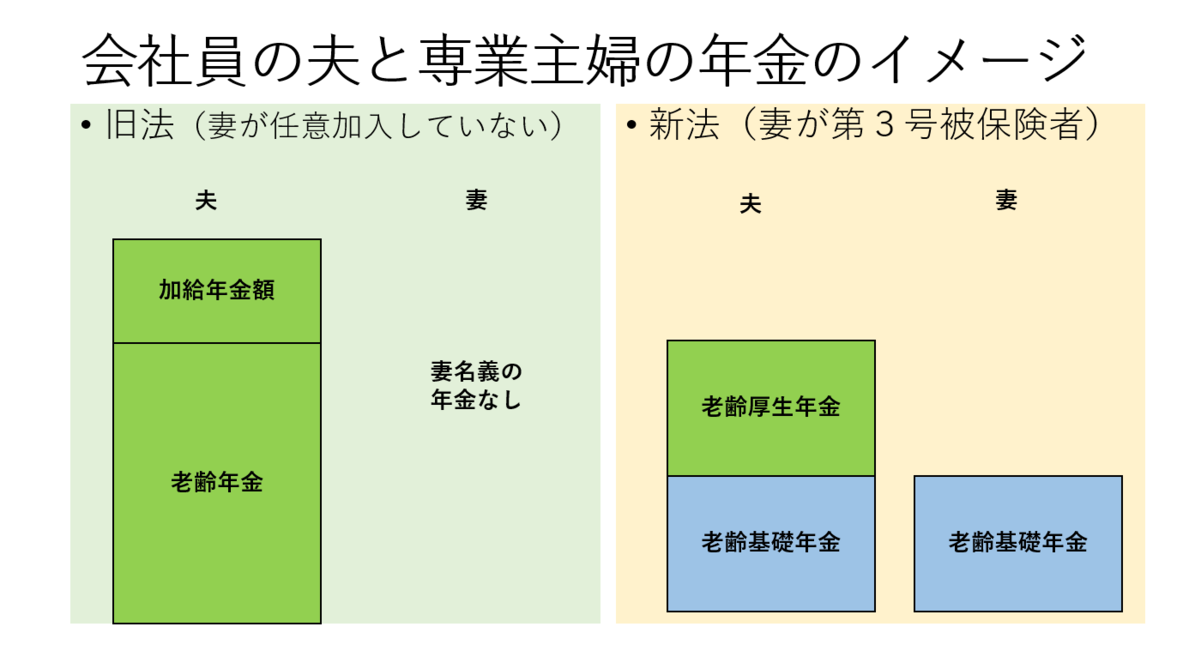
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
 どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法
どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法
R4-137
R4.1.6 国民年金法・厚生年金保険法ってどんな法律?その1
今日は、厚生年金保険法・国民年金法の創成期のお話です。
・昭和17年 労働者年金保険法発足
(昭和19年厚生年金保険法に改称)
・昭和29年 厚生年金保険法全面改正
(「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての給付方式を採用)
・昭和36年 国民年金法全面施行
(国民皆年金の実現)
★昭和17年にスタートした労働者年金は、工場等で働く男子労働者を被保険者としていました。労働力の保全強化を図ることなどが背景にありました。
昭和19年に名称が厚生年金保険法に改められ、被保険者の範囲は、事務職員や女性にも広がりました。
報酬比例部分のみだった養老年金が、「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建ての老齢年金になったのが、昭和29年の改正です。
★民間の会社員や公務員には公的な年金制度があり、老後の所得が保障されていましたが、自営業者等には、そのような制度が無いことが問題になっていました。
しかし、自営業者等にも老後の保障が必要だということで、国民年金法が制定されたのが昭和34年です。拠出制の国民年金制度が昭和36年に施行され、国民皆年金が実現しました。
「国民皆年金」とは、民間の会社員、公務員だけでなく、それ以外の自営業者等もすべての人が職業に関係なく公的年金の保護の対象になるという意味です。
なお、拠出制は昭和36年からですが、無拠出制の福祉年金制度は昭和34年からスタートしていました。
既に高齢になっている人、障害のある人等には、全額国庫負担の老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金等が支給されました。
★老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)の全てが保険料納付済期間なら満額の年金が支給されます。
しかし、大正15年4月2日から昭和16年4月1日以前生まれの人は、480月ではなく、加入可能年数×12で計算します。
なぜなら、国民年金制度が発足した昭和36年4月1日に既に20歳になっているからです。その年代の人は、昭和36年4月1日から60歳までの間の全てが保険料納付済期間なら、満額の老齢基礎年金が支給されます。
例えば大正15年4月2日~昭和2年4月1日の間に生まれた人は「25年」、昭和15年4月2日~昭和16年4月1日の間に生まれた人は39年が加入可能年数です。
20歳から60歳まで40年間加入できるのは、昭和16年4月2日以後生まれの人です。
★創成期の年金のポイントは以下の通りです。
(創成期の年金の特徴)
・「縦割り」の運営でした
制度ごとに支給要件や給付水準が設定されていて、統一されていませんでした。
・加入が「任意」な人もいました
例えば、会社員の妻などは任意加入でした。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
【H19年出題】 ×
無拠出制の福祉年金の給付の開始は、昭和34年11月からです。10月ではありません。
(法附則第1条)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
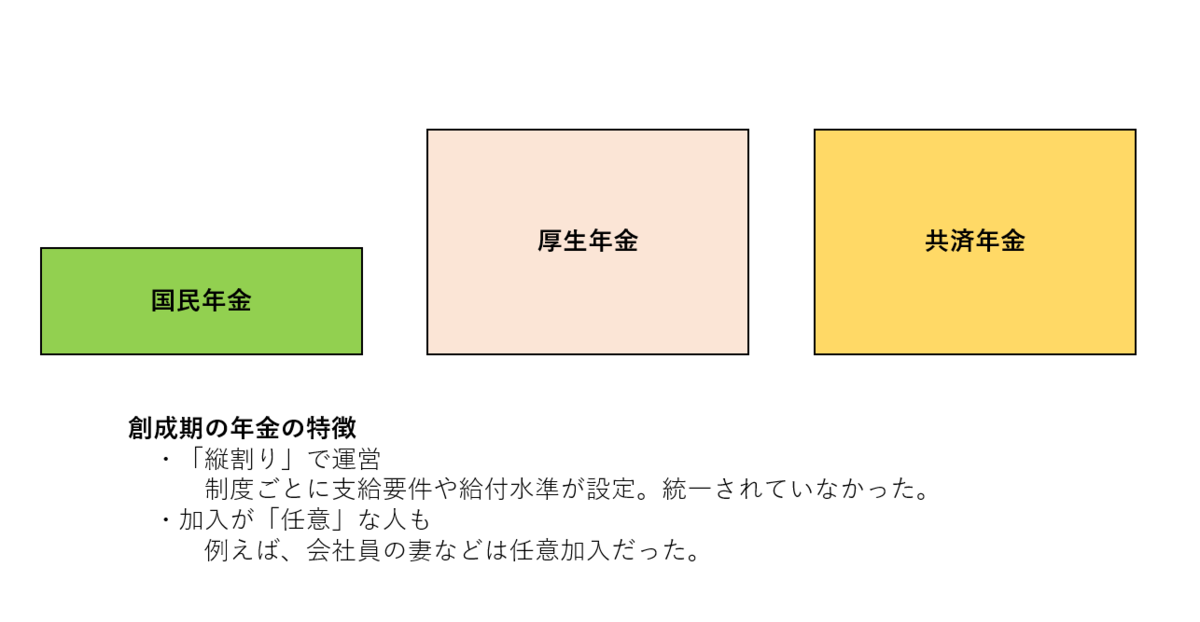
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
 「最初の一歩㉚」条文の読み方(厚生年金保険法)
「最初の一歩㉚」条文の読み方(厚生年金保険法)
R4-130
R3.12.30 「被保険者であった期間」と「被保険者期間」
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
条文を読んでみましょう。
第19条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 |
『被保険者期間』は月単位で算定されます。
例えば、12月31日に資格取得、1月31日に退職した(資格喪失は2月1日)場合は、被保険者期間は2か月です。
「被保険者期間」は、年金額の計算(平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数)や、保険料の徴収(被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収される)に使われます。
では、こちらの過去問をどうぞ
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

【解答】
①【H21年出題】 ×
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの『日単位』で計算される期間は「被保険者であった期間」のことです。12月31日資格取得、1月31日退職・2月1日資格喪失なら、被保険者であった期間は、12月31日から1月31日までの32日間です。
「被保険者期間」は、最初に書きましたように「月単位」で算定します。
次にこちらの条文を読んでみましょう。
第47条 (障害厚生年金の受給権者) 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」)において被保険者であった者が、・・・(以下略)
附則第9条の3 (長期加入者の特例) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、報酬比例部分と定額部分を合わせた年金が支給される。 |
★第47条
「被保険者であった者」に注目してください。障害厚生年金は、初診日に「被保険者」であったことが要件です。
厚生年金保険法で「被保険者であった」ということは、在職中だったという意味です。ですので、障害厚生年金は在職中に初診日があることが条件です。
★附則第9条の3
「被保険者でなく」に注目してください。
長期加入者(44年以上)に対して、報酬比例部分に定額部分が加算される特例の条件は、「被保険者でない」ことイコール退職していることです。
定額部分が加算されるには退職していることが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉓」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉓」法律によって定義が異なる用語
R4-123
R3.12.23 「障害等級」の定義(国民年金法・厚生年金保険法)その2
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、こちらの条文を読んでみましょう。
国民年金法第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」という表現に注意してください。
国民年金法の条文で単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級」のことです。
一方、国民年金法の条文で「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」と書いてある場合は、「1級・2級・3級」のことです。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H20年出題―国民年金法】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
①【H20年出題―国民年金法】 ×
「厚生年金保険法に規定する障害等級」は「3級」も入ることに注意してください。
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していても、その時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金の受給権が消滅するのは、次のどちらか遅い方です。
・3級程度の障害の状態に該当しなくなって3年経過
・65歳
少なくとも65歳までは失権しません。
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第53条(失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
|
こちらは厚生年金保険法の条文ですので、「障害等級」は、1級、2級、3級です。
消滅する時期は国民年金法と同じです。
では、厚生年金保険法の過去問も解いてみましょう。
②【H15年出題―厚生年金保険法】
障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

【解答】
②【H15年出題―厚生年金保険法】 〇
こちらは、「厚生年金保険法」ですので、単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級・3級」のことです。
消滅の時期は、国民年金の障害基礎年金と同じです。
・3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳以上のとき → その日に消滅
・3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳未満のとき → その後65歳に達した日に消滅
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉒」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉒」法律によって定義が異なる用語
R4-122
R3.12.22 「障害等級」の定義(国民年金法・厚生年金保険法)その1
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
国民年金法第30条 1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
厚生年金保険法第47条 1 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
★ 「障害基礎年金」も「障害厚生年金」も、「初診日」「保険料納付要件」「障害認定日」の3つの要件を満たすことが必要です。
★ 国民年金法の「障害等級」は、1級・2級、厚生年金保険法の「障害等級」は、1級・2級・3級です。
同じ「障害等級」という用語でも、範囲が違うことに注意しましょう。
(例1) 例えば、「初診日」に40歳・厚生年金保険の被保険者だった場合、同時に「国民年金の第2号被保険者」でもあります。
そして、障害認定日に、「1級」に該当した場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給されます。
障害厚生年金 1級 |
障害基礎年金 1級 |
(例2) 例えば、例1と同じく「初診日」に40歳・厚生年金保険の被保険者(同時に「国民年金の第2号被保険者」)だった場合。
障害認定日に「3級」に該当した場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。障害基礎年金には3級がないので、障害基礎年金は支給されません。
障害厚生年金 3級 |
では、「厚生年金保険法」の過去問を解いてみましょう。
①【H22年出題ー厚生年金保険法】
障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
①【H22年出題―厚生年金保険法】 ×
「軽度のものから」ではなく、「重度のものから1級、2級及び3級」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑯」過去問の活用(厚生年金保険法)
「最初の一歩⑯」過去問の活用(厚生年金保険法)
R4-116
R3.12.16 老齢厚生年金の計算(厚年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
さて、第43条の条文を読んでみましょう。
第43条 (年金額) 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 |
第43条は、老齢厚生年金の年金額の計算方法を規定しています。
老齢厚生年金の計算式は次の通りです。
平均標準報酬額 × 1,000分の5.481 × 被保険者期間の月数
では、過去問を解いてみましょう
①【H23年選択式】
老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
A 再評価率
B 5.481
ポイント!「平均標準報酬額」の出し方
老齢厚生年金の計算には、厚生年金保険に加入していた全期間の「標準報酬月額と標準賞与額」を使いますが、それを平均したものが「平均標準報酬額」です。
「平均標準報酬額」の計算式は、「標準報酬月額と標準賞与額の総額」÷「被保険者期間の月数」で、平均標準報酬額の計算の際、標準報酬月額と標準賞与額に「再評価率」を乗じます。
再評価率を乗じるのは、過去の標準報酬を現在の水準に読み替えるためです。
そして、再評価率は、毎年度改定されます。
例えば、昭和29年度以降生まれの人の昭和57年度の報酬は、再評価率1.472(令和3年度)を乗じることによって現在の水準に読み替えられます。
在職中の標準報酬月額や標準賞与額が高い人ほど、平均標準報酬額は高くなりますし、在職期間が長い人ほど被保険者期間が長くなるので、年金額が多くなります。
厚生年金が報酬比例といわれる理由です。
ポイント!「給付乗率」について
★平成15年4月1日に注意しましょう
なお、「平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」は、平成15年4月以降の期間の計算式です。
平成15年4月から、「総報酬制」が導入され、「賞与」からも月々の報酬(標準報酬月額)と同じ率の保険料が徴収されるようになりました。
そのため、年金額に賞与の額も反映されるようになりました。
平成15年3月までは、「賞与」から「特別保険料」が徴収されていましたが、年金額には反映されません。
平成15年3月までの被保険者期間の計算式は、「平均標準報酬月額×1,000分の7.125×被保険者期間の月数」です。
平均標準報酬月額は「標準報酬月額」だけで計算します。
なお、「1,000分の5.481」は「1,000分の7.125÷1.3」です。
年間の賞与は月々の給料の3割という考え方からです。
★昭和21年4月1日以前生まれにも注意しましょう
「給付乗率」は昭和21年4月1日以前生まれの場合は、生年月日によって読み替えがあります。
旧法から新法になった際に給付乗率が下がりました。その際、いきなり下げるのではなく、段階的に給付乗率を下げる必要があったためです。そのため、旧法に近い人(生年月日の古い人)ほど給付乗率が旧法に近いのが特徴です。
(平成15年3月までの期間)
大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の9.5
・
・
・
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の7.23
(平成15年4月以降の期間)
大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の7.308
・
・
・
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の5.562
最後に過去問をどうぞ
②【H18年選択式】
平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< C >(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

【解答】
C 再評価率
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑮」条文の読み方(厚生年金保険法)
「最初の一歩⑮」条文の読み方(厚生年金保険法)
R4-114
R3.12.15 専門用語に慣れましょう「被保険者期間を有する」(厚年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、第42条を読んでみましょう。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
第42条では、老齢厚生年金の支給要件を3つ定めています。
1 被保険者期間を有すること
2 65歳以上
3 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あること
1について
「被保険者」とは「厚生年金保険の被保険者」のこと、そして「被保険者期間」とは厚生年金保険の被保険者期間です。
被保険者期間は月単位で算定され、最短で1か月です。「被保険者期間を有する」とは、1か月でも厚生年金保険の被保険者期間を有する、という意味です。
2について
老齢厚生年金の受給権は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)に受給権が発生します。
3について
老齢基礎年金の受給資格を満たしていることという意味です。(合算対象期間も合算できます。)老齢厚生年金は、老齢基礎年金の上乗せですので、まず、老齢基礎年金の受給要件を満たしていることが前提です。
例えば、保険料納付済期間が10年(第1号被保険者としての期間が9年11か月、厚生年金保険の被保険者期間が1か月)の場合、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給できます。
老齢基礎年金の計算式は、「780,900円×改定率×480分の120」で、老齢厚生年金は1か月の被保険者期間をベースに計算されます。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
②【H30年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
65歳以上から支給される本来の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば支給されますが、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが要件です。
(法第42条、法附則第8条)
②【H30年出題】 〇
65歳からの老齢厚生年金と、特別支給の老齢厚生年金は「別物」です。
特別支給の老齢厚生年金を受けていた場合でも、65歳から支給される老齢厚生年金を受けようとする場合は、改めて、老齢厚生年金に係る裁定の請求書を提出しなければなりません。
(施行規則第30条の2)
こちらの問題もどうぞ!
③【H30年出題】
老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
問題文の場合、老齢厚生年金が支給されます。
65歳時点で厚生年金保険の被保険者期間を有していなくても、その後に被保険者期間を1か月でも有した場合は、老齢厚生年金の受給要件を満たしますので、老齢厚生年金が支給されます。
ポイント
「平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した」場合、厚生年金保険の被保険期間は1か月となります。(同月得喪といいます。)
法第19条で、「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。」と規定されている部分です。
ただし、「その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」という例外があります。
問題文の場合は、「同月に更に被保険者の資格を取得していない」とありますので、1か月の被保険者期間として算定されます。
しかし、例えば、
■令和3年12月1日入社(厚生年金保険の資格取得)
↓
■同年12月20日退職
↓
■同年12月21日 厚生年金保険資格喪失・国民年金の第1号被保険者になった
このような場合、12月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
そしてもう一つのパターンとして、令和3年12月1日に資格取得、同年12月20日付で退職し、12月中に別の会社に就職し厚生年金保険の被保険者となった場合は、後の会社の資格で厚生年金保険の被保険者期間が算定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-098
R3.11.28 2以上の種別の被保険者であった期間がある場合の中高齢寡婦加算
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「2以上の種別の被保険者であった期間がある場合の中高齢寡婦加算」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7E】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

【解答】
①【R3年問7E】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あること)が死亡した場合、遺族厚生年金は長期要件となります。
中高齢寡婦加算額は按分して支払われるのではなく、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間に基づく遺族厚生年金に加算されます。また、最も長い一の期間が2以上ある場合は、①第1号②第2号③第3号④第4号の順序で加算されます。
なお、長期要件の場合の中高齢寡婦加算は、死亡した夫の被保険者期間が240月以上あることが条件です。240月以上の計算は、2以上の種別の被保険者であった期間を合算します。
(施行令第3条の13の7)
ここもチェック!
| 2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の遺族厚生年金について | |
| 年金の決定、支払 | |
| 短期要件 | 死亡日(又は初診日)に加入していた実施機関が行う |
| 長期要件 | それぞれの加入期間ごとに各実施機関が行う |
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
③【H30年出題】
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

【解答】
②【H28年出題】 〇
第1号(15年)+第3号(18年)ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は長期要件です。長期要件の場合は、それぞれの被保険者期間に応じた遺族厚生年金が、それぞれの実施機関から支給されます。
(法第78条の32)
③【H30年出題】 〇
問題文は障害等級1級の障害厚生年金の受給権者の死亡ですので、短期要件の遺族厚生年金です。
2以上の種別に係る被保険者であった期間を合算して、1つにまとめて計算した遺族厚生年金が、初診日における被保険者の種別に応じた実施機関から支給されます。
(法78条の第32)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-097
R3.11.27 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7D】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【R3年問7D】 〇
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有したときは、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者が両方適用されるのではなく、第1号厚生年金被保険者の「資格を喪失」することに注意しましょう。
(法第18条の2)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
③【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
平成27年10月1日に、被用者年金が一元化され、国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員も厚生年金保険の被保険者となりました。
昭和20年10月2日以後に生まれた者(施行時に70歳未満)で、かつ、施行日の前日(平成27年9月30日)に共済組合の組合員や私立学校教職員共済の加入者だった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得しました。
(H24法附則第5条)
③【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失しますので、「2以上事業所選択届」を届け出ることはありません。
このような場合は、資格取得届・資格喪失届を提出することになります。
(法第18条の2)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第18条の2(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、< A >の資格を取得しない。
< A >が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、< B >に、当該< A >の資格を喪失する。

【解答】
A 第1号厚生年金被保険者
B その日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-096
R3.11.26 基準障害による障害厚生年金
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「基準障害による障害厚生年金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4ア】
厚生年金保険法第47条の3第1項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。

【解答】
①【R3年問4ア】 〇
「基準障害による障害厚生年金」は、基準障害と他の障害とを併合して初めて1級又は2級に該当したときに、併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されるものです。
初めて1級又は2級に該当したときではなく、当該障害厚生年金の「請求があった月の翌月」から始まるのがポイントです。
(法第47条の3)
ポイント!
「その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない障害厚生年金」は法第48条の併合認定の対象になる障害厚生年金からは除かれることを、ひとつ前の記事で書きました。
こちら → R3.11.25 2以上の障害が生じた場合の併合認定
受給権を取得した当時から3級の障害厚生年金は、法第48条の併合認定の対象にはなりませんが、例えば、先発の障害厚生年金が3級で、後発の障害(基準障害)と併合して初めて1級または2級に該当した場合は、第47条の3の基準障害による障害厚生年金の対象となります。
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
「基準傷病の初診日」は、基準傷病以外の傷病の初診日より後であることが条件です。併合のきっかけになるのが基準傷病ですので、一番後ろにくることになります。
(法第47条の3)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第47条の3(基準障害による障害厚生年金)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後< A >までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の < B >に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

【解答】
A 65歳に達する日の前日
B 1級又は2級
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-095
R3.11.25 2以上の障害が生じた場合の併合認定
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「2以上の障害が生じた場合の併合認定」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4イ】
厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。

【解答】
①【R3年問4イ】 ×
併合認定した場合、従前の障害厚生年金は、支給停止ではなく、「失権」します。
例えば、2級の障害厚生年金の受給権者に対して更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害が併合されます。併合の結果1級に該当した場合は、1級の障害厚生年金が支給されます。
併合の結果、1級の障害厚生年金受給権を取得した場合は、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。支給停止ではありませんので注意しましょう。
(法第48条)
ポイント!
法第48条の併合認定の対象になる障害厚生年金からは、「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るもの」は除かれます。
一度でも1級か2級の状態にあったものが併合の対象となります。
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
③【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【H29年出題】 〇
①の問題と同じです。
「障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級」ということは、障害基礎年金が支給停止中ということです。
先発の障害厚生年金が、1度でも1級又は2級に該当したことがある場合は、現在3級でも法第48条の規定による併合の対象となります。
③【H27年出題】 ×
受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金は、併合の対象になりません。
(法第48条)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第48条(障害厚生年金の併給の調整)
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の< A >に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を< B >した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
障害厚生年金の受給権者が前後の障害を< B >した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、< C >する。

【解答】
A 1級又は2級
B 併合
C 消滅
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-094
R3.11.24 3号分割/特定被保険者が障害厚生年金の受給権者のとき
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「3号分割/特定被保険者が障害厚生年金の受給権者のとき」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1E】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。

【解答】
①【R3年問1E】 ×
3号分割制度は、当事者の合意は不要です。
そのため、特定被保険者(分割される側)が障害厚生年金の受給権者で、問題文のように特定期間の全てが障害厚生年金の計算の基礎となっている場合は、特定被保険者の被扶養配偶者(分割を受ける側)は、3号分割標準報酬改定請求はできません。
(法第78条の14)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下「特定被保険者」という。)が、障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
①と同じです。
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、障害厚生年金の計算の基礎になっている被保険者期間は3号分割標準報酬改定請求の対象になりません。そのため、障害厚生年金の計算の基礎になっている被保険者期間は、改定される期間から除かれます。
(法第78条の14)
用語の定義を穴埋めで確認しましょう!
【H26年出題】※穴埋めにアレンジ
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」について、分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として< A >であった期間をいい、< B >前の期間を含まない。

【解答】
A 国民年金の第3号被保険者
B 平成20年4月1日
(法第78条の14)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-093
R3.11.23 加給年金額が支給停止されるとき
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「加給年金額が支給停止されるとき」です。
では、どうぞ!
①【R3年問8D】
老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、障害等級1級又は2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

【解答】
①【R3年問8D】 ×
加給年金額の対象の配偶者が、障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合も、加給年金額は支給停止されます。
★加給年金額の対象になる配偶者が、以下の給付を受けることができるときは、加給年金額が支給停止されます。
・ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)
・ 障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるとき
→ 障害厚生年金は、1級、2級に限定されていませんので、配偶者が3級の障害厚生年金の支給を受けるときでも、加給年金額の支給が停止されます。
→ なお、「障害手当金」については、受給していても、加給年金額は支給停止されません。
(法第46条、施行令第3条の7)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
③【H22年出題】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
④【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
①の問題と同じです。配偶者が3級の障害厚生年金を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。
(法第46条)
③【H22年出題】 〇
加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給が停止されます。
ポイント!
・ 支給停止の対象になるのは、240月以上で計算される老齢厚生年金に限られます。(中高齢期間短縮特例該当者は240月未満でも240月とみなされます。)
・ 対象になる配偶者の老齢厚生年金が「全額支給停止されている」場合は、加給年金額は支給停止されず、加算されます。
④【H28年出題】 ×
対象になる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は、配偶者が65歳になるまで加算されます。
(法第46条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-092
R3.11.22 脱退一時金の額の計算
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「脱退一時金の額の計算」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9D】
脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。

【解答】
①【R3年問9D】 〇
脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。この場合の平均標準報酬額の算出に当たって、各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率は乗じません。
(法附則第29条)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。

【解答】
②【H27年出題】 ×
前年9月ではなく、前年10月です。
支給率は、資格喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率です。
被保険者であった期間に応じた数は、「6」から「60」まで設定されています。(最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合)
例えば、被保険者であった期間が60月以上の場合の支給率は、「資格喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率×2分の1×60」ですので、1000分の183×2分の1×60で「5.5」となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)(法附則第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-091
R3.11.21 脱退一時金の支給要件のチェックポイント
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「脱退一時金の支給要件のチェックポイント」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9C】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【解答】
①【R3年問9C】 〇
この問題のチェックポイント!
■「ある日本国籍を有しない者」
→脱退一時金は「日本国籍を有しない者」が対象です。
■「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過」している。
→脱退一時金は、「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき」は支給されません。
問題文の時点では、「1年が経過」したところです。脱退一時金の請求は可能です。
■「厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上」有している
→脱退一時金は、被保険者期間が6か月以上あることが要件です。
■「障害厚生年金等の受給権を有したことがない」
→障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金は支給されません。
(法附則第29条)
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
③【H26年出題】修正あり
日本国籍を有しない者について、障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。
④【R1年出題】
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
③【H26年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したこと」がある場合は、脱退一時金は請求できません。障害手当金は、「その他政令で定める保険給付」に入っています。
(法附則第29条、施行令第12条)
④【R1年出題】 ×
脱退一時金の請求に回数は設けられていませんので、所定の要件を満たせば、再度、脱退一時金の支給を請求することもできます。
(法附則第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-090
R3.11.20 老齢厚生年金の繰下げと遡及の選択
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「老齢厚生年金の繰下げと遡及の選択」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E】
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

【解答】
①【R3年問9E】 〇
 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げはそれぞれ選択できます(同時に繰下げなくてもいい)
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げはそれぞれ選択できます(同時に繰下げなくてもいい)
問題文のように、「65歳から老齢基礎年金を受給」し、「老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する」選択も可能です。
 66歳に達した日後に他の年金を受ける権利ができた場合の選択肢は2つ
66歳に達した日後に他の年金を受ける権利ができた場合の選択肢は2つ
①他の年金が発生した時点の繰下げ増額率で、繰下げの老齢厚生年金を受給する
②65歳からの本来の老齢厚生年金を遡って請求する
問題文のように、68歳で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、②を選択し、「65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給すること」ができます。この場合は、繰下げによる増額はありません。
 遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整
遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より多い場合は、差額の遺族厚生年金が支給されます。
問題文のように、「老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給すること」ができます。
遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整は、こちらの記事で解説しています。
こちら→ R3.11.18 遺族厚生年金の額の計算
(法第44条の3)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
③【H28年出題】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。

【解答】
②【H26年出題】 ×
67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となっても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
その場合、繰下げ増額率は、遺族厚生年金の受給権ができた時点で計算されます。
なお、65歳の時点に遡って老齢厚生年金を請求することもできます。
(法第44条の3)
③【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出と、老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、それぞれ別にすることができます。
(法第44条の3)
なお、支給繰上げについては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-088
R3.11.18 遺族厚生年金の額の計算
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「遺族厚生年金の額の計算」です。
では、どうぞ!
①【R3年問8C】
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

【解答】
①【R3年問8C】 ×
問題文の遺族厚生年金の基本の額と比較する「当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額」の部分が誤りです。
遺族厚生年金の基本の計算式は、「死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額×4分の3」です。
ただし、遺族のうち「65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する配偶者」の遺族厚生年金は、次の2つのうち、どちらか多い額となります。
ⓐ 「死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額×4分の3」(上記の基本の計算式)
ⓑ ⓐの額×3分の2 + 配偶者自身の老齢厚生年金の額×2分の1
(法第60条)
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
②【H29年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合の規定で、遺族自身の老齢厚生年金を優先して受給できるようにするための調整です。
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より多い場合は、差額の遺族厚生年金が支給されます。
(法第64条の2)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
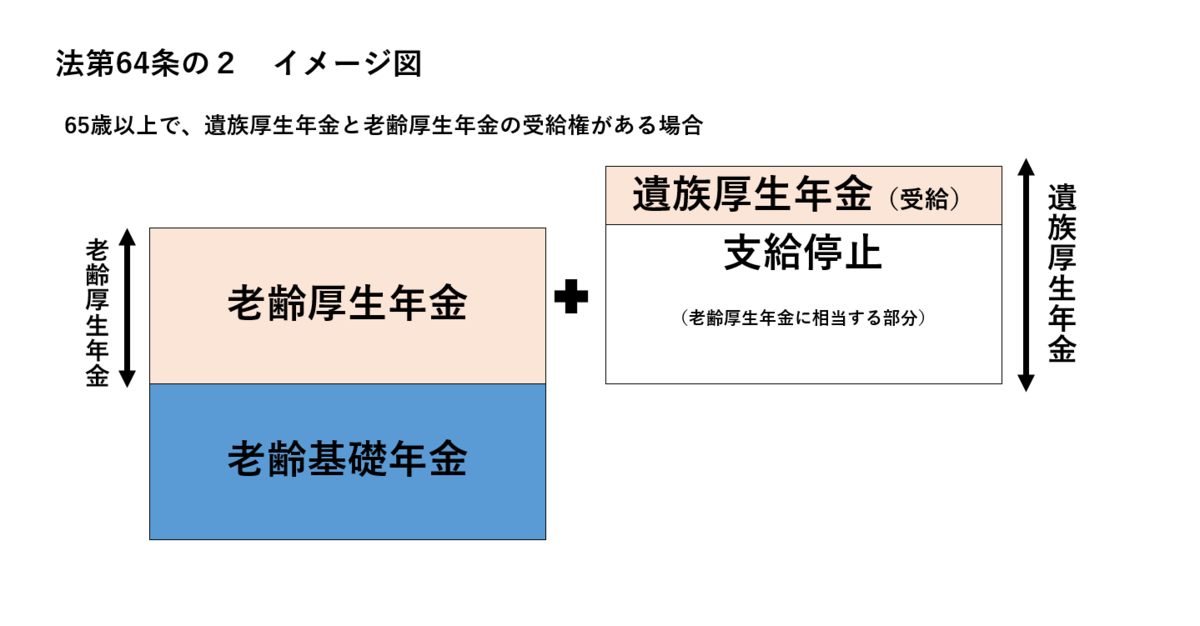
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-087
R3.11.17 遺族厚生年金の失権事由
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「遺族厚生年金の失権事由」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10E】
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

【解答】
①【R3年問10E】 ×
婚姻をしたときは、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
婚姻には、「届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」も含まれます。
問題文の母の遺族厚生年金の受給権は、「事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた」ことによって消滅します。ですので、母が受給できるのは、自身の老齢基礎年金のみとなります。
(法第63条)
★なお、「直系血族及び直系姻族以外の者の養子」となったときも、遺族厚生年金の受給権は消滅します。ここに出てくる「養子」についても、「届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者」を含みます。
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため、その受給権は消滅しない。

【解答】
②【H27年出題】 〇
妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻しても、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
(昭32.2.9保文発9485)
なお、遺族厚生年金の失権事由である「離縁による親族関係の終了」について、「離縁」とは養子縁組関係の終了のみをいいます。
(昭30.4.11保文発3441)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-086
R3.11.16 経過的寡婦加算のこと
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「経過的寡婦加算のこと」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
昭和32年4月1日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。

【解答】
①【R3年問1B】 ×
昭和32年4月1日生まれの妻には、経過的寡婦加算は加算されません。
経過的寡婦加算が加算されるのは、「昭和31年4月1日以前」に生まれた妻です。新法が施行された昭和61年4月1日に30歳以上だった人が対象です。
第3号被保険者の制度が始まったのは昭和61年4月。昭和61年4月から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金と経過的寡婦加算を合わせて 中高齢寡婦加算の額(遺族基礎年金の4分の3)と同じ額になるよう設定されています。
昭和31年4月2日以降生まれの場合、昭和61年4月から60歳に達するまですべて国民年金に加入すると「遺族基礎年金の4分の3」の額は支給されるので、経過的寡婦加算は加算されません。
(昭和60年法附則第73条)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】※改正による修正あり
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。

【解答】
②【H27年出題】 〇
ポイント!
・遺族厚生年金の受給権が発生したときに、既に妻が65歳以上でも、経過的寡婦加算が加算されます
・長期要件(保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上)の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が原則240か月以上あることが条件です。
(昭和60年法附則第73条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-069
R3.10.30 中高齢寡婦加算の額
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「中高齢寡婦加算の額」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1A】
夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上あるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【R3年問1A】 ×
中高齢寡婦加算として加算される額は、満額の遺族基礎年金ではなく、「遺族基礎年金の額×4分の3」です。
中高齢寡婦加算のポイント!
・死亡した夫について
「短期要件」でも「長期要件」でも中高齢寡婦加算は加算されますが、「長期要件」の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上あることが条件です。
・妻について
①夫の死亡当時40歳以上65歳未満
②夫の死亡当時40歳未満だった場合は、40歳当時に子と生計を同じくしていて遺族基礎年金を受給していること
・中高齢寡婦加算が加算されるのは妻が65歳に達するまで
・遺族基礎年金を受けることができる間は、中高齢寡婦加算は支給停止される
(法第62条、第65条)
こちらもどうぞ!
②【H15年出題】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当する額になっている。
③【H17年出題】
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。

【解答】
②【H15年出題】 ×
老齢基礎年金の年金額の3分の2ではなく、「遺族基礎年金」の額の「4分の3」に相当する額です。
(法第62条)
③【H17年出題】 ×
「中高齢の寡婦加算の額」は、「老齢基礎年金」ではなく「遺族基礎年金」の額の4分の3相当額です。
・中高齢寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず一定の額
中高齢寡婦加算の額の計算式
=遺族基礎年金の額×4分の3
・経過的寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使って計算する
経過的寡婦加算の額の計算式
=「中高齢寡婦加算の額」-「老齢基礎年金の満額」×「妻の生年月日に応じた率」
では、こちらもどうぞ!
④【H28年出題】
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
④【H28年出題】 〇
妻に遺族基礎年金が支給されている間は、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給は停止されます。
(法第65条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-066
R3.10.27 在老~基本月額と総報酬月額相当額
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「在老~基本月額と総報酬月額相当額」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7B】
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

【解答】
①【R3年問7B】 ×
基本月額は、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)÷12で計算します。「加給年金額」は基本月額の計算に入りません。
(法第46条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
③【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「総報酬月額相当額」は、被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額です。
★総報酬月額相当額の計算式
(その月の標準報酬月額) + (その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
(法第46条)
③【H29年出題】 ×
「経過的加算額」及び「繰下げ加算額」は、基本月額の計算に入りません。
★基本月額の計算式
老齢厚生年金の額 ÷ 12
※「加給年金額」、「繰下げ加算額」、「経過的加算額」は基本月額の計算から除かれます。
(法第46条、昭和60年法附則第62条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-058
R3.10.19 厚年「遺族厚生年金・長期要件と短期要件」
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「遺族厚生年金・長期要件と短期要件」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10A】
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

【解答】
①【R3年問10A】 ×
遺族厚生年金には、「短期要件」と「長期要件」がありますが、両方に該当する場合は、「その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときを除き、『短期要件』のいずれかのみに該当し、『長期要件』には該当しないものとみなす」とされています。 問題文は、逆になっているので×です。
問題文の場合、
・第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡 → 短期要件(在職中の死亡)
・保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上 → 長期要件
となります。別段の申出をしたときを除き、短期要件に該当する遺族厚生年金として年金額が算出されます。
(法第58条)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題(改正による修正あり)】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。

【解答】
②【H23年出題】 〇
長期要件(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上)と短期要件(被保険者が死亡)の両方に当てはまる場合は、別段の申出をした場合を除き、短期要件に該当し、長期要件には該当しないものとみなされます。
(法第58条)
こちらもどうぞ!
③【H27年出題(改正による修正あり)】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

【解答】
③【H27年出題】 〇
問題文は「長期要件」です。長期要件の場合は、給付乗率について生年月日に応じた読み替えがあります。
遺族厚生年金の原則の計算式は、老齢厚生年金と同じで「平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」です。
ただし、短期要件と長期要件でルールが違うのがポイントです。
| 短期要件 | 長期要件 | |
| 給付乗率 | 定率 | 昭和21年4月1日以前生まれ →生年月日に応じて読み替え |
| 被保険者期間の月数 | 300月の 最低保障あり | 実期間で計算 |
(法第60条)
では、長期要件と短期要件を穴埋めでチェックしましょう
1 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して< A >年を経過する日前に死亡したとき。
3 < B >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である者が、死亡したとき。

【解答】
A 5
B 障害等級の1級又は2級
C 25
★1、2、3が「短期要件」、4が「長期要件」です。
また、1と2は障害厚生年金と同じく保険料納付要件が問われます。
(法第58条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)厚生年金保険法 応用問題
R4-049
R3.10.10 厚年「特別支給の老齢厚生年金・長期加入者の特例」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は厚生年金保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問9B】
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

【解答】
①【R3年問9B】 ×
「長期加入者の特例」の問題です。
昭和16年4月2日生まれ(第1号の女子は昭和21年4月2日生まれ)以降から、特別支給の老齢厚生年金が報酬比例部分のみになる部分があります。(図を参照してください。)
長期加入者の特例とは、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上であるときは、定額部分(場合によっては加給年金額も)が支給される特例です。
昭和33年4月10日生まれの男性は、63歳から報酬比例分の支給が開始されますが、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上であるときは、定額部分も合わせて支給されます。
しかし、問題文の場合は、被保険者期間は、第1号が4年、第2号が40年となっています。「44年」をみるときは、2種以上の被保険者であった期間は、合算しないこととなっているので、問題文の場合は、要件をみたさないので、63歳から支給されるのは原則どおり報酬比例部分のみとなります。
(法附則第9条の3)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
上の問題と同じで、「44年以上」をみるときは、2種以上の期間は合算できませんので、問題文の場合は、定額部分は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
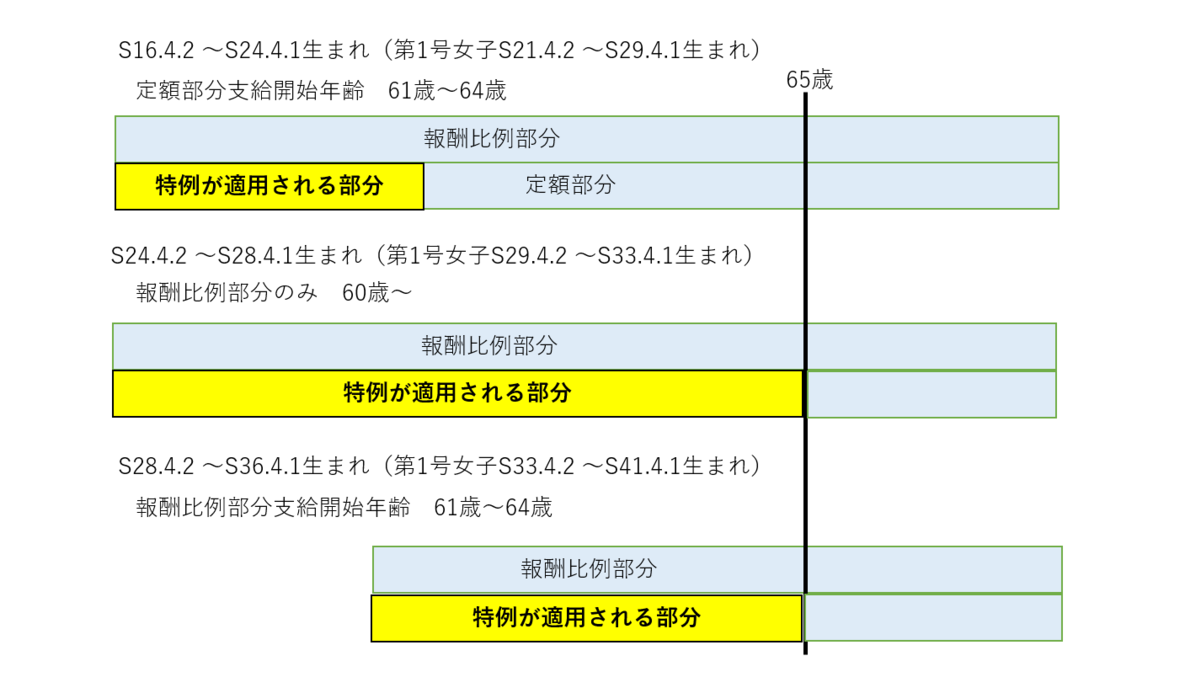
(令和3年出題より)厚生年金保険法よく出るところ
R4-039
R3.9.30 厚年「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は厚生年金保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
②【R3年問3D】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。

【解答】
①【R3年問3C】 〇
(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢)
★どちらも昭和35年8月22日生まれ、報酬比例部分のみ
・第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子 → 62歳開始
・第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子 → 64歳開始
②【R3年問3D】 〇
(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢)
★どちらも昭和35年8月22日生まれ、報酬比例部分のみ
・第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子 → 64歳
・第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子 → 64歳
ポイント!
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、
①「第1号~第4号の男子」、「第2号~第4号の女子」
②「第1号の女子」
の2つのパターンがあります。女子は、「第2号~第4号」と「第1号」で支給開始年齢が異なりますので注意してください。
★①の生年月日をおぼえましょう。節目の「昭和16年」、「昭和24年」、「昭和28年」、「昭和36年」をおさえてください。
②の節目は、プラス5年で、「昭和21年」、「昭和29年」、「昭和33年」、「昭和41年」です。
では、こちらもどうぞ!
③【H29年出題】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
④【H24年出題】(改正による修正あり)
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の支給開始年齢の読み替えに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A 男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
B 男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
C 女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
D 女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
E 女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。

【解答】
③【H29年出題】 〇
報酬比例部分→60歳から、定額部分→64歳から
④【H24年出題】(改正による修正あり)
A ×
B 〇
C 〇
D 〇
E 〇
A 男子 昭和27年4月2日生まれ → 60歳から報酬比例部分が支給
B 男子 昭和36年4月1日生まれ → 64歳から報酬比例部分が支給
C 女子(第1号)昭和33年4月2日生まれ → 61歳から報酬比例部分が支給
D 女子(第1号)昭和36年4月2日生まれ → 62歳から報酬比例部分が支給
E 女子(第1号)昭和41年4月1日生まれ → 64歳から報酬比例部分が支給
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)厚生年金保険法の定番問題
R4-029
R3.9.20 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる子の要件
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は厚生年金保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3A】
障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

【解答】
①【R3年問3A】 ×
17歳の時に障害の状態でなくなった場合でも、18歳に達した日以後の最初の3月31日までは、加給年金額の加算の対象のままです。
老齢厚生年金の加給年金額の対象になる子の条件を確認しましょう。
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
・20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子
18歳の年度末までは、障害の状態の有無は問われないのがポイントです。
(法第44条)
では、こちらもどうぞ!
②【H21問4B】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

【解答】
②【H21問4B】 ×
障害等級1級又は2級でない場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日で加給年金額の対象から外れます。その後、19歳で障害状態になったとしても、加給年金額の対象にはなりません。
(法第44条)
それでは、加給年金額の減額改定の事由を条文で確認しましょう。
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 配偶者が、65歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によって受給権者の< A >の者の養子となったとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、< B >が終了したとき。
九 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(< B >までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、< C >歳に達したとき。

【解答】
A 配偶者以外
B 18歳に達した日以後の最初の3月31日
C 20
(法第44条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・厚生年金保険法【択一】
R4-020
R3.9.11 第53回厚年(択一)より~遺族厚生年金
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 一筋縄ではいかない、ひねりの効いた問題が多かったように思います。暗記したことを組み立てたり、図を書いてみたり、今年の厚生年金保険の問題は解くのに工夫が必要です。
【R3年問5】
(問5-ア)
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。
(問5-イ)
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
(問5-ウ)
85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
(問5-エ)
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
(問5-オ)
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

【解答】
(問5-ア) 〇
「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき」は長期要件に該当します。
この「25年」に合算対象期間が含まれることがこの問題のポイントです。
問題文の通り、「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間」とを合算した期間が25年以上の場合は、長期要件に該当します。
(法第58条、附則第14条)
(問5-イ) 〇
保険料納付要件の特例の条件は、
・死亡日が令和8年4月1日前にある
・死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がない
・死亡日に65歳未満
です。
問題文の場合、
死亡日=令和3年8月1日
死亡日の属する月(令和3年8月)の前々月までの1年間(令和2年7月から令和3年6月まで)に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない」(滞納期間がない)
・死亡時に50歳
ということで、要件を満たしているので、保険料納付要件の特例が適用され遺族厚生年金の支給対象となります。
(法第58条、S60年法附則第64条)
(問5-ウ) 〇
遺族となる「子」の要件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。
問題文の場合は、年齢要件に該当しないので、遺族となりません。
(法第59条)
(問5-エ) ×
直系血族及び直系姻族以外の養子となったときは遺族厚生年金の受給権は消滅しますが、問題文の場合は、直系姻族の養子ですので、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
(法第63条)
(問5-オ) ×
30歳未満の子のいない妻の遺族厚生年金は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したときに消滅します。問題文の場合、妻が30歳になったときは、まだ5年経過していませんので、消滅しません。
(法第63条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(厚生年金保険法)
R4-009
R3.8.31 第53回選択厚年~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「厚生年金保険法」の選択式です。
問題1 賞与の定義(第3条)
迷うようなひっかけ選択肢も無いですし、ばっちり解けたと思います。
問題1 ☆☆☆ どうにか解ける
問題2 交付金(第84条の3)
■まずは「実施機関」の確認をしましょう。
第1号厚生年金被保険者 → 厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団
■「共済組合等」のキャッシュフローは、以下のようなイメージです。
・実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生年金勘定に拠出金を納付する。(厚生年金の給付に必要な費用を分担するため)
↓
・実施機関(厚生労働大臣を除く。)に係る保険給付に必要な費用(「厚生年金保険給付費等」)は、厚生年金勘定から、共済組合等に交付金として交付される。
■「厚生年金保険給付費等」とは、「実施機関(厚生労働大臣を除く。)に係る厚生年金保険法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用」をいいます。
問題2 ★★☆ やや難しい
問題3 適用事業所の一括(第8条の2)
択一式でもよく出題されるところなので、解けたと思います。
問題3 ☆☆☆ どうにか解ける
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法 選択対策
R3-358
R3.8.16 厚生年金保険法 選択問題(老齢厚生年金の額)
今日は厚生年金保険の選択対策。テーマは「老齢厚生年金の額」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
<H23年選択式 出題> ※改正による修正あり
1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。

【解答】
A 再評価率
B 5.481
C 物価変動率
D 名目手取り賃金変動率
E 3年後
(法第43条、第43条の2、第43条の3)
ポイント!
再評価率の改定基準
・新規裁定者 → 名目手取り賃金変動率を基準とする
・既裁定者 → 物価変動率を基準とする(※物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準とする)
こちらもどうぞ!
<H18年選択式 出題>
平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< F >(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

【解答】
F 再評価率
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
事後重症の障害厚生年金
R3-342
R3.7.31 障害厚生年金~事後重症のポイントをチェック
今日のテーマは、「障害厚生年金~事後重症のポイントをチェック」です。
ではどうぞ!
①<H26年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

【解答】
①<H26年出題> ×
障害等級3級も、事後重症による障害厚生年金の対象です。
(法第47条の2)
では、こちらもどうぞ!
②<H20年出題>
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。
③<H29年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

【解答】
②<H20年出題> ×
「65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる」の部分が誤り。
③<H29年出題> ×
「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる」の部分が誤り。
事後重症のポイント!
・初診日の要件を満たしている
・初診日の前日の保険料納付要件を満たしている
・障害認定日に障害等級に該当しなかった(障害認定日に受給権が発生しない)
↓
しかし、その後障害の状態が重症化した
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級(1~3級)に該当
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に「請求」する
↓
・「請求」することによって、事後重症の障害厚生年金の受給権が発生する
・請求した月の翌月から支給される
こちらもどうぞ!
④<R1年出題>
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

【解答】
④<R1年出題> 〇
老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げを受給している者は、事後重症の請求はできません。65歳以上と同じ扱いとなります。
(附則第16条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
30歳未満の妻の遺族厚生年金
R3-341
R3.7.30 30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日
今日のテーマは、「30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日」です。
ではどうぞ!
①<H19年出題>
受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。

【解答】
①<H19年出題> 〇
死亡した者に生計を維持されていた妻は、年齢問わず遺族厚生年金の対象となります。
しかし、30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
5年の起算日をおぼえましょう。
1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻
→ 遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき (子がいない場合)
→ 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年間
2 遺族厚生年金と遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき(30歳前に子の死亡などで遺族基礎年金が失権した場合)
→ 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年間
こちらもどうぞ!
②<H29年出題>
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③<H26年出題>
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】
②<H29年出題> ×
起算日が誤っています。「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算します。
・遺族厚生年金と同一の支給事由の遺族基礎年金の受給権を取得した妻
↓
・1年後に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した
↓
・消滅した日に妻は30歳前だった
↓
・「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに
遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③<H26年出題> 〇
・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻(同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない)
↓
・「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
業務上の災害と厚生年金保険の年金との関係
R3-340
R3.7.29 業務上の災害と厚生年金保険の年金との調整
今日のテーマは、「業務上の災害と厚生年金保険の年金との調整」です。
ではどうぞ!
①<H28年出題>
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。
②<H17年出題>
業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。
③<R1年出題>
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

【解答】
①<H28年出題> ×
障害厚生年金は、同一の傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する、です。
(法第54条)
なお、同一の傷病について労働者災害補償保険法の年金を受けることができる場合は、障害厚生年金は全額支給されます。その場合、労災保険法の規定により、労災保険の年金は減額されます。
②<H17年出題> 〇
①の解説と同じです。
③<R1年出題> 〇
①②と同じです。
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の遺族補償の支給が行われるときは、死亡の日から6年間、その支給が停止されます。
(法第64条)
なお、同一の事由で、遺族厚生年金と労災保険法の年金が支給される場合は、遺族厚生年金は全額支給されます。(そして、労災保険法の規定により労災保険の年金は減額されます。)
では、こちらもどうぞ!
④<H28年出題>
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金は支給されない。

【解答】
④<H28年出題> 〇
障害手当金は、当該傷病について、労災保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には支給されません。
ちなみに、当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を有する場合も、障害手当金は支給されません。
(法第56条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚年 【令和3年4月改正】脱退一時金の改正
R3-311
R3.6.30 【厚年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ
国民年金法と同じように、厚生年金保険法の脱退一時金も改正されました。
上限年数が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられています。
 国民年金法の脱退一時金の改正はこちらからどうぞ
国民年金法の脱退一時金の改正はこちらからどうぞ
→ R3.6.27 【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ
条文を穴埋めでチェックしましょう!
★空欄を埋めてください。
法附則第29条 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。
支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年< A >月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年< A >月の保険料率)に< B >を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

【解答】
A 10
B 2分の1
(法附則第29条)
 厚生年金保険の脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。
厚生年金保険の脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。
「支給率」は、『最終月の保険料率×2分の1×政令で定める数』です。
『政令で定める数』は以下の通りです。(最終月が令和3年4月以降の場合)
| 被保険者であった期間 | |
|---|---|
| 6月~12月 | 6 |
| 12月~18月 | 12 |
| 18月~24月 | 18 |
| 24月~30月 | 24 |
| 30月~36月 | 30 |
| 36月~42月 | 36 |
| 42月~48月 | 42 |
| 48月~54月 | 48 |
| 54月~60月 | 54 |
| 60月以上 | 60 |
(施行令第12条の2)
★ 例えば最終月が令和3年4月で、被保険者であった期間が60月以上の場合の支給率は、「18.3%×2分の1×60」≒5.5となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚年 【改正】標準報酬月額の上限
R3-310
R3.6.29 【厚年】標準報酬月額の最高等級の引上げ
 令和2年9月より、標準報酬月額の最高等級が引き上げられています。
令和2年9月より、標準報酬月額の最高等級が引き上げられています。
条文を穴埋めでチェックしましょう!
★空欄を埋めてください。
第20条
毎年< A >における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の< B >に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< C >から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】
A 3月31日
B 100分の200
C 9月1日
(法第20条)
ポイント!
厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級は「第32級 650,000円」になりました。
(令和2年9月より R2.8.14政令第246号)
厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級(88,000円)~第32級(650,000円)です。
ちなみに、健康保険法は 第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)です。
では、こちらもどうぞ!
<H24年出題>(修正)
被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする。

【解答】
<H24年出題>(修正) ×
厚生年金保険の標準賞与額は、『被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。』と規定されています。
厚生年金保険の標準賞与額の上限は月150万円です。
(法第24条の4)
問題文は、健康保険の標準賞与額の決定方法です。健康保険法の場合は、年度の累計で573万円までです。(健保法第45条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害 3級から2級への額の改定 その2
R3-279
R3.5.29 厚生年金保険3級から1級2級へ額の改定
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、厚生年金保険の視点で見ていきましょう。
厚生年金保険の場合、障害等級は1級から3級までありますが、3級の場合は「障害厚生年金」のみ、1級、2級の場合は「障害基礎年金+障害厚生年金」です。
3級から2級・1級に障害の程度が増進すると、障害基礎年金がプラスされます。
ということは、
・障害厚生年金 → 3級から2級・1級に改定
・障害基礎年金 → 障害等級不該当から1・2級へ(事後重症)
となります。
昨日の記事でもお話しましたが、事後重症は「65歳に達する日の前日まで」という条件がありましたよね。ここが今日のポイントです。(図1参照)
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H27年出題>
63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、その後、障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
②<H16年出題>
2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級の障害の状態になり、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。
③<R2年出題>
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①<H27年出題> ×
老齢基礎年金を繰上げ受給しているので、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定は請求できません。
障害認定日に3級だった者が、その後障害の程度が増進した場合、3級から2級、1級への額の改定請求ができます。
同時に事後重症による障害基礎年金も支給されます。(図1参照)
ただし、事後重症の条件は、「65歳に達する日の前日までに該当」すること。
そのため、65歳すぎてから障害の程度が増進しても、事後重症の障害基礎年金が支給されないので、障害厚生年金も額の改定は行われません。(図2参照)
問題のように、65歳に達するまでの間でも、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は、事後重症による障害基礎年金は支給されないので、障害厚生年金の額の改定も行われません。
(法第52条)
②<H16年出題> 〇
問題文の場合は、もともと1、2級の受給権がある(=障害基礎年金の受給権がある)ことがポイントです。
65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。なぜならば、障害基礎年金が事後重症ではないからです。
(図3参照)
③<R2年出題> ×
問題文の場合、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級の障害状態になった場合は、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。②の問題と同じです。
社労士受験のあれこれ
図1
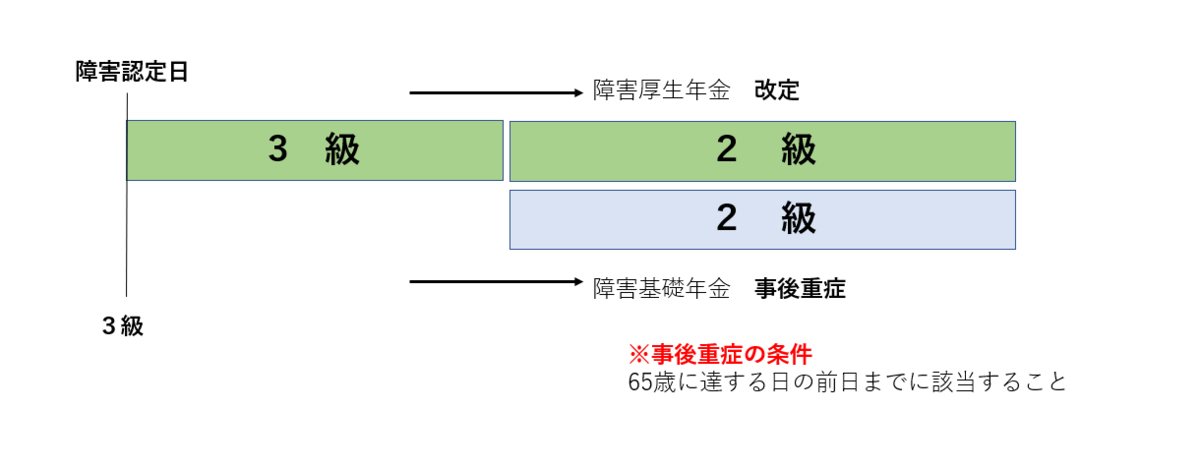
図2
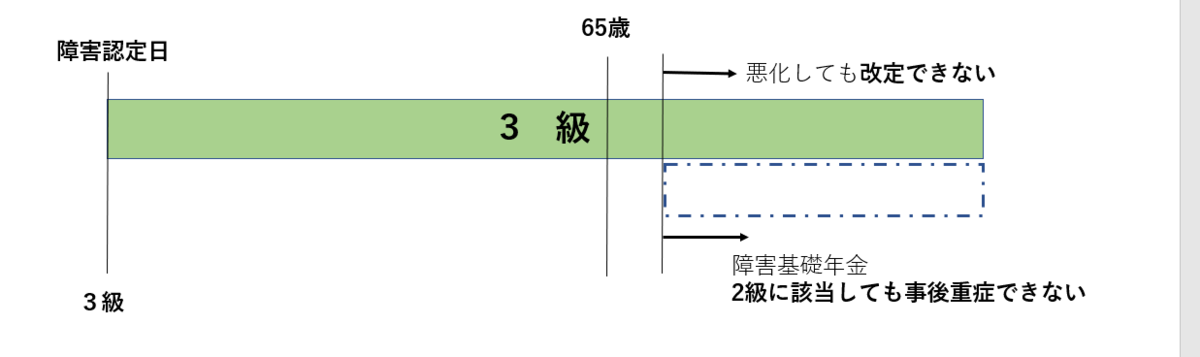
図3
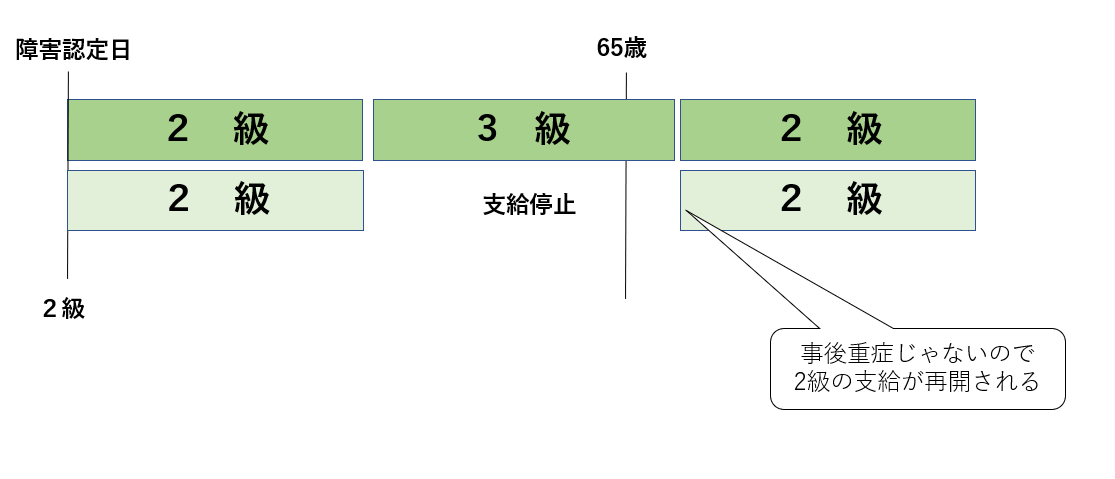
厚年 保険料率
R3-276
R3.5.26 厚生年金保険の保険料率
今日のテーマは「厚生年金保険の保険料率」です。
厚生年金保険の保険料は、「標準報酬月額×保険料率」、「標準賞与額×保険料率」 で計算します。
まずこちらからどうぞ!
①<H17年選択式>
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を< A >%に固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。

【解答】
A 18.3
平成16年改正で導入されたのが「保険料水準固定方式」です。
保険料水準固定方式とは、最終的な保険料の水準を法律で定め、その範囲内で給付を行う仕組みです。
厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられ(平成17年度からは9月に引上げ)、平成29年9月以降は、18.3%で固定されることになりました。
ではこちらをどうぞ!
②<R1年出題>
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが。上限が1000分の183に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。

【解答】
②<R1年出題> 〇
厚生年金保険の保険料率が上限の1000分の183に達するのは
・第1号厚生年金被保険者 → 平成29年9月
・第2号及び第3号厚生年金被保険者 → 平成30年9月
・第4号厚生年金被保険者 → 令和9年9月
(H24年法附則第83条から85条)
社労士受験のあれこれ
厚年 高齢任意加入被保険者
R3-274
R3.5.24 厚年 高齢任意加入被保険者のポイント
今日のテーマは、「高齢任意加入被保険者」です。
70歳になっても、老齢の年金の受給権がない人は、70歳以降も任意に厚生年金保険に加入することができます。
「高齢任意加入被保険者」には「適用事業所」に使用される人と、「適用事業所以外」の事業所に使用される人の2つのパターンがあります。それぞれの違いに注意しましょう。
まずこちらからどうぞ!
①<H26年出題>
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
②<R1年出題>
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に資格を取得する。

【解答】
①<H26年出題> ×
「厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する」の部分が誤りです。
『適用事業所以外』の高齢任意加入被保険者の場合
・『事業主の同意』を得たうえで、『厚生労働大臣の認可』を受けて、『認可があった日』に資格を取得します。
(法附則4条の5)
②<R1年出題> 〇
『適用事業所』の高齢任意加入被保険者の場合
・『実施機関に申し出』て、『実施機関への申出が受理された日』に資格を取得します。
※『適用事業所」の場合、事業主の同意は要りません。
事業主の同意は「事業主が保険料を半分負担し、かつ納付義務を負う」ためのものです。
「適用事業所以外」は事業主の保険料半分負担かつ納付義務を負うことが必須。ですので、事業主の同意も必須要件です。
一方、「適用事業所」の方は、事業主の負担が必須ではありません。そのため事業主の同意も必須ではありません。
(法附則第4条の3)
もう一問どうぞ!
③<H29年出題>
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】
③<H29年出題> ×
第4号厚生年金被保険者が誤り。この規定が適用されないのは「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者」です。
★ 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、「保険料の半額負担、かつ、保険料の納付義務を負う」ことにつき同意することができます。そして、その同意を将来に向かって撤回することもできます。
ただし、この規定は、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者には適用されません。
(法附則第4条の3)
社労士受験のあれこれ
厚年 70歳以上の使用される者
R3-273
R3.5.23 厚年 70歳以上の使用される者の届出関係
今日のテーマは、「70歳以上の使用される者」の届出関係です。
厚生年金保険の被保険者が70歳に達したときは資格を喪失しますが、70歳以後も働く場合は、厚生年金保険の被保険者ではない(=保険料は徴収されない)ものの、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
70歳以降も働く場合の手続を確認しましょう。
まずこちらからどうぞ!
①<H28年出題>
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

【解答】
①<H28年出題> ×
問題文の場合、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることがあります。
70歳以上でも適用事業所に使用される場合は、在職老齢年金のルールが適用されます。以前は、昭和12年4月1日以前生まれの者はこの適用が除外されていましたが、平成27年10月からは、昭和12年4月1日以前生まれの者にも在職老齢年金の仕組みが適用されています。
(法第46条)
こちらもどうぞ!
②<H23年出題>
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。
③<H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。
④<R2年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

【解答】
②<H23年出題> 〇
70歳以上の者を新たに使用した場合、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、在職老齢年金の規定が適用されるため、「70歳以上の使用される者の該当の届出」が必要です。
対象になるのは、「70歳以上」、「過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する」「適用事業所に使用される者で、かつ、12条各号に定める者に該当しない」者です。
(則15条の2)
③<H29年出題> ×
<被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合>
★70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる→「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出
★70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70 歳到達日の前日の標準報酬月額と同額→ 「70歳以上の使用される者の該当の届出」の提出は不要
<70歳以上の者を新たに雇い入れたとき>
★「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出
(則第15条の2)
④<R2年出題> 〇
「70歳到達日の前日以前から70歳到達日以降も引き続き 同一の適用事業所に使用」かつ、「当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である」場合は、「70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届」の提出は不要です。
(則第15条の2)
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合・遺族年金
R3-238
R3.4.18 2以上の種別の期間を有する場合~遺族厚生年金編
引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「遺族厚生年金」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H30年出題>
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

【解答】
①<H30年出題> 〇
注目ポイントは次の2つ
・ 死亡した者が「短期要件」であること(→『障害等級1級の障害厚生年金の受給権者でいわゆる長期要件には該当しない』)
・ 死亡した者が「2以上の被保険者の種別」に係る被保険者であった期間を有していたこと
■2以上の種別の被保険者期間がある場合の遺族厚生年金の計算
・短期要件の場合
→ それぞれの種別の期間を合算して計算する。(→死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする)
→ それぞれの種別の期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月で計算する
・長期要件の場合
→ それぞれの種別ごとに計算する
→ 300月の最低保障は無し
(法第78条の32、施行令第3条の13の6)
こちらもどうぞ!
②<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

【解答】
②<H28年出題> 〇
注目ポイント 問題文の遺族厚生年金は「長期要件」で2以上の種別の期間がある
問題文の場合、「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある者)」が死亡したときに該当するので長期要件です。
長期要件の遺族厚生年金は、先ほどの①の解説にも書きましたように「それぞれの種別ごとに計算」されます。また支給は、「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される」ことになります。
問題文の場合でしたら、第1号分(15年)は「厚生労働大臣」、第3号分(18年)は、「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」が行います。
なお、「短期要件」の場合の実施機関は、以下の時点で判断されます。
・被保険者の死亡 → 「死亡日」における種別
・資格喪失後の死亡(被保険者期間中に初診日ある傷病で初診日から5年以内に死亡)
→ 「初診日」における種別
・1,2級の障害厚生年金の受給権者の死亡 → 「初診日」における種別
(法第78条の32、施行令第3条の13の10)
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合・障害年金
R3-237
R3.4.17 2以上の種別の期間を有する場合~障害厚生年金編
昨日に引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「障害厚生年金」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日おいて2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【解答】
①<H28年出題> ×
当該障害に係る『障害認定日』における被保険者の種別に応じた実施機関が行うの部分の「障害認定日」が誤り。障害認定日ではなく、「初診日」です。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の当該障害厚生年金の支給に関する事務は、「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行うことになります。
例えば、20歳から10年間は第1号厚生年金被保険者で、30歳から第4号厚生年金被保険者で、第4号厚生年金被保険者である期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の支給に関する事務は、日本私立学校振興・共済事業団が行います。
(法第78条の33)
こちらもどうぞ!
②<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】
②<H29年出題> ×
障害厚生年金の受給権者で、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金の額は、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなすことになっています。
計算の基礎となるのは、「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」ではなく、それぞれを「合算」することになります。
(法第78条の30)
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合の加給年金額
R3-236
R3.4.16 2以上の種別の期間を有する場合~老齢編その2(加給年金額)
昨日に引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「加給年金額」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
②<H30年出題>
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

【解答】
①<H28年出題> 〇
問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間がある場合は、合算して240か月以上あれば加給年金額が加算されます。
第1号厚生年金被保険者分の老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者分の老齢厚生年金は、それぞれ別個に計算・支給されますが、加給年金額はどちらか一方に加算されます。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金について、加給年金額はどの老齢厚生年金に加算されるのでしょうか?加算される順番は、政令で次の通り定められています。
①最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金に加算する
↓
②同時に受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、最も長い期間で計算される老齢厚生年金に加算する
↓
③期間が同じ場合は、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間の順序で加算する
問題文の場合は、それぞれの老齢厚生年金の受給権は同じ日(平成27年10月1日)に取得していますので、期間が長い方の第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、施行令第3条の13)
②<H30年出題> ×
「遅い日」において・・・の部分が誤りです。
2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、「遅い日」ではなく「早い日」において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金にのみ加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、施行令第3条の13)
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合
R3-235
R3.4.15 2以上の種別の期間を有する場合~老齢編その1
テーマは「2以上の種別の期間を有する」場合の年金についてです。
厚生年金保険の被保険者は、4つの種別に区分されています。
第1号厚生年金被保険者(民間企業)
第2号厚生年金被保険者(国家公務員)
第3号厚生年金被保険者(地方公務員)
第4号厚生年金被保険者(私学教職員)
例えば、民間企業で勤務した後国家公務員になった場合、第1号厚生年金被保険者の期間と第2号厚生年金被保険者の期間を有することになりますが、そのような場合の年金のルールを確認していきます。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

【解答】
①<H28年出題> ×
特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する」こと」が要件です。
2以上の種別の被保険者であった期間がある場合は、合算して1年以上あればOKです。問題文の場合は、合算して18カ月あるので、特別支給の老齢厚生年金の支給要件を満たします。
問題文の女性(昭和31年4月2日生まれ)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
・60歳支給開始 → 第1号厚生年金被保険者期間分
・62歳支給開始 → 第2号厚生年金被保険者期間分
(法附則第8条、法附則第20条)
では、こちらもどうぞ!
②<R2年出題>
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。
③<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

【解答】
②<R2年出題> 〇
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は、それぞれ区分して計算され、それぞれ併給されます。
また、老齢厚生年金はそれぞれの実施機関から支給されます。(第1号厚生年金被保険者期間分は「厚生労働大臣」、第2号厚生年金被保険者期間分は「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」)
(法第78条の26)
③<H29年出題> ×
「2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して・・・」の部分が誤りです。合算して平均標準報酬額を算出するのではなく、それぞれの種別ごとに平均標準報酬額を算出します。
(第78条の26)
社労士受験のあれこれ
経過的寡婦加算
R3-234
R3.4.14 経過的寡婦加算でよく出るところ
テーマは「経過的寡婦加算」です。
『中高齢寡婦加算』と違う点を特に意識してください。
では、こちらからどうぞ!
①<H14年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。

【解答】
①<H14年出題> ×
中高齢寡婦加算の支給は65歳で終了しますが、65歳以後は、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されます。
ポイント!経過的寡婦加算は生年月日の要件あり!
「経過的寡婦加算」は、昭和31年4月1日以前に生まれた者が対象です。
★なぜ、「昭和31年4月1日以前」なの??
会社員の被扶養配偶者が「第3号被保険者」として国民年金に強制加入するようになったのは、「昭和61年4月1日」からで、その前(旧法時代)は、「国民年金は任意加入」でした。
例えば、会社員に扶養される妻が「昭和31年4月2日」以降生まれの場合を考えてみましょう。昭和31年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算は支給されません。
なぜなら、昭和61年4月1日時点で30歳未満だからです。仮に20歳から60歳まで40年間会社員に被扶される妻で、旧法時代に任意加入していなかったとしても、40年のうち30年以上は第3号被保険者となり、老齢基礎年金の額は、満額の4分の3以上(480月のうち360月以上)で計算されます。
65歳まで加算される「中高齢寡婦加算」が遺族基礎年金の4分の3なので、それと同額の老齢基礎年金が65歳から支給されます。そのため「経過的寡婦加算」でカバーする必要がないからです。
一方、「昭和31年4月1日」以前生まれの妻の場合は、同じく40年間会社員に扶養される妻だった場合、第3号被保険者の期間が30年未満となり、老齢基礎年金の額が4分の3未満となります。
経過的寡婦加算は、その4分の3未満になる部分をカバーするために加算されるものです。
(昭60年法附則第73条)
では、こちらの問題をどうぞ!
②<H15年出題(修正)>
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日に応じて最低39,070円から最高780,900円までの額として加算される。

【解答】
②<H15年出題(修正)> ×
経過的寡婦加算の額は、最低19,547円から最高585,700円までの額となります。
計算式は、次の通りです。
「中高齢の寡婦加算の額」-「満額の老齢基礎年金」×妻の生年月日に応じた乗率
乗率は、昭和2年4月1日以前生まれは「ゼロ」で生年月日が若いほど乗率は大きくなり、一番若い「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれは、「480分の348」となります。
経過的寡婦加算が中高齢寡婦加算と同額の「585,700円」になるのは、昭和2年4月1日以前生まれ。最低額の19,547円になるのは、「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれです。
若い人ほど「第3号被保険者期間」が長くなる=老齢基礎年金が多くなるので、経過的寡婦加算は逆に少なくなる仕組みです。
再度、中高齢寡婦加算との違いを確認しましょう。
・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額
・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される
(昭60年法附則第73条)
こちらもどうぞ!
③<H28年出題>
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
③<H28年出題> 〇
遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止されます。
障害基礎年金で満額保障されるので、経過的寡婦加算でカバーする必要が無いからです。
(昭60年法附則第73条)
社労士受験のあれこれ
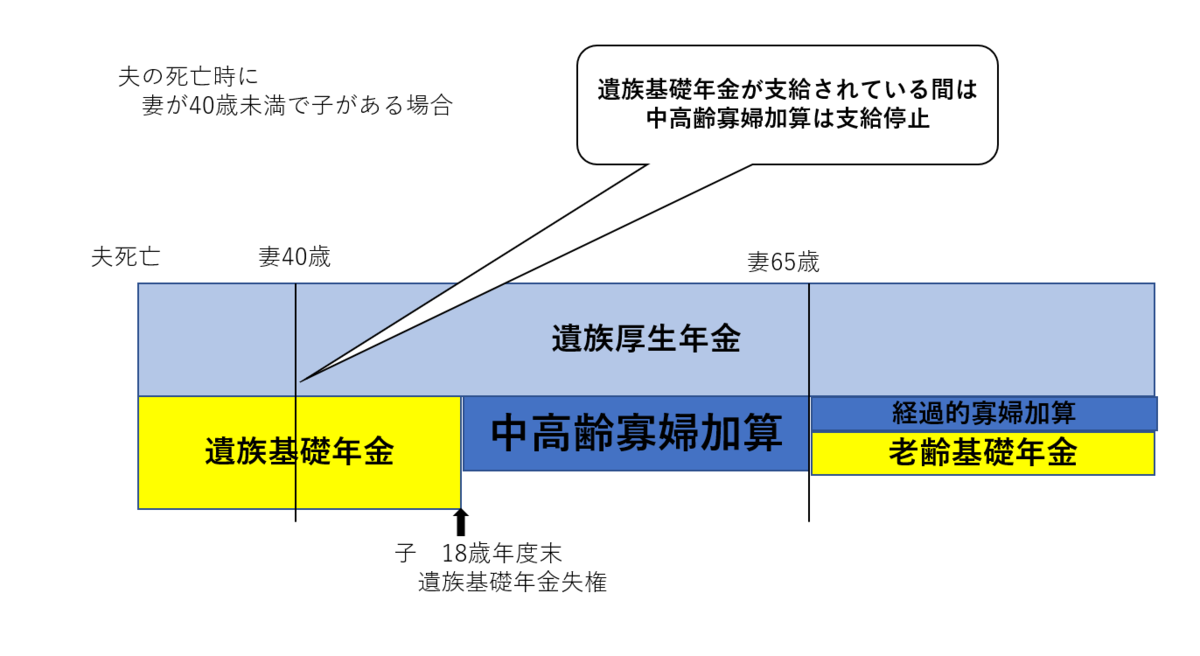
中高齢寡婦加算(その2)
R3-233
R3.4.13 中高齢寡婦加算の額
昨日に引き続き、テーマは中高齢寡婦加算です。
今日は中高齢寡婦加算の額です。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第62条
遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、
遺族厚生年金の額に< A >の額に< B >を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)を加算する。

【解答】
A 遺族基礎年金
B 4分の3
C 50円
D 100円
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額×4分の3で計算します。
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H17年出題>
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
②<H21年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

【解答】
①<H17年出題> ×
中高齢寡婦加算の額は、老齢基礎年金の額の4分の3ではなく、『遺族基礎年金』の額の4分の3です。経過的寡婦加算の額は問題文の通りです。
②<H21年出題> ×
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の説明が逆です。
・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額
・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される
※『経過的寡婦加算』については、後日、記事にします。
こちらもどうぞ!
③<H28年出題>
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻が当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
③<H28年出題> 〇
子がいる場合は「遺族厚生年金と遺族基礎年金」が支給されます。遺族基礎年金が支給されている間(子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間等)は、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止されます。
(法第65条)
社労士受験のあれこれ
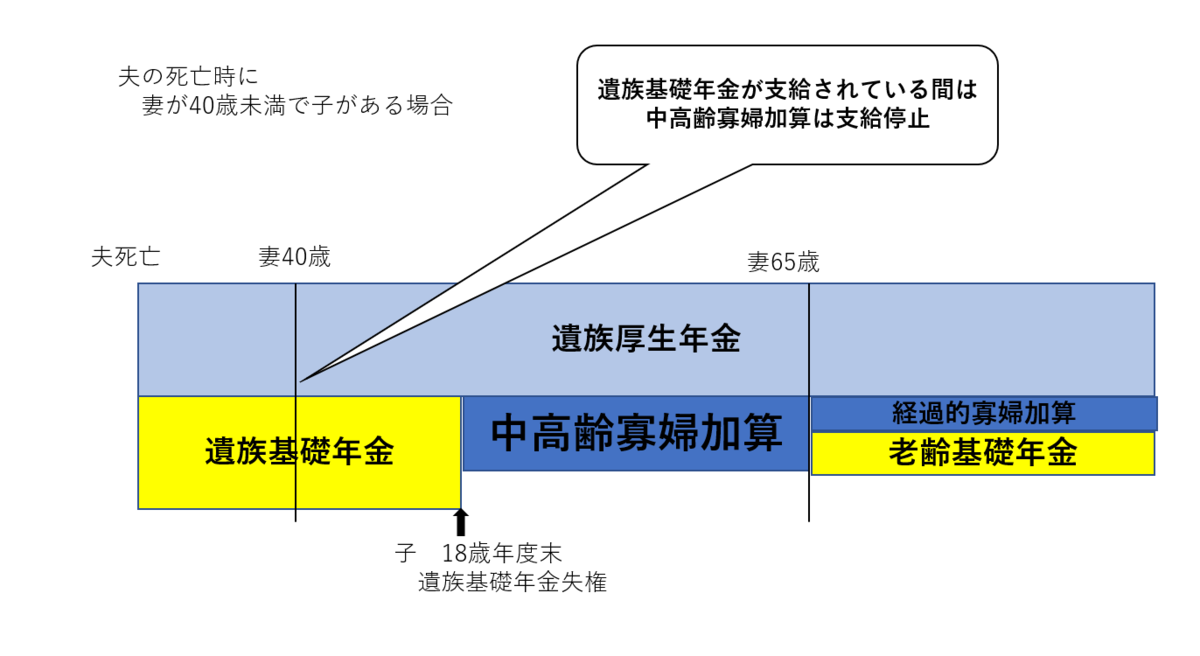
中高齢寡婦加算(その1)
R3-232
R3.4.12 中高齢寡婦加算が加算される要件
テーマは中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算が加算される要件を確認しましょう。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第62条
遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が< A >未満であるものを除く。)の受給権者である妻であって
その権利を取得した当時< B >歳以上< C >歳未満であったもの
又は< B >歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが< C >歳未満であるときは、
遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。

【解答】
A 240
B 40
C 65
ポイント!
・中高齢寡婦加算の対象は「妻」のみ
・対象になる妻の要件
①夫の死亡時に、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない
②夫の死亡時に子があり、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が年齢要件等に該当したため遺族基礎年金を受給できなくなった(夫の死亡時に40歳未満だったが40歳到達時に遺族基礎年金を受けていた)
・支給される遺族厚生年金が長期要件の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間月数が240月(中高齢の期間短縮特例に該当する場合はその期間)以上あること
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H27年出題>
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
②<H19年出題(修正)>
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者(老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上ある)が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。

【解答】
①<H27年出題> 〇
子のない妻(遺族基礎年金が支給されない)の場合は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満であることが条件です。
ちなみに、この問題は「被保険者である夫の死亡」なので遺族厚生年金は短期要件です。
②<H19年出題(修正)> 〇
①と同じく、夫の死亡当時妻が40歳未満で子がいない場合は、中高齢寡婦加算は行われません。
ちなみに、この問題は長期要件です。
★再度確認しておくと
中高齢寡婦加算が加算される妻は
①子がいない場合
夫の死亡時に40歳以上65歳未満であること
②夫の死亡時に子がある場合
夫の死亡時に40歳未満でも40歳到達時に子がいる(遺族基礎年金を受けている)こと
社労士受験のあれこれ
65歳以上の配偶者の遺族厚生年金
R3-231
R3.4.11 65歳以上の配偶者の遺族厚生年金
今日のテーマは、65歳以上の配偶者の遺族厚生年金です。
遺族厚生年金は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3で計算しますが、65歳以上の配偶者については、別の計算式があります。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第60条、附則第17条の2 (年金額)
遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、1.に定める額とする。
1. 第59条第1項に規定する遺族(2.に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金)の例により計算した額の< A >に相当する額。
ただし、短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
2.第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(< B >歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 1.に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 1.に定める額に< C >を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に < D >を乗じて得た額

【解答】
A 4分の3
B 65
C 3分の2
D 2分の1
ポイント!
★★65歳以上の配偶者の遺族厚生年金の額★★
老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
遺族厚生年金の額は、1.と2.のいずれか多い方
1.死亡した人の老齢厚生年金額の4分の3
2.1.の額の3分の2 + 自身の老齢厚生年金額の2分の1
※いずれか多い方とは → いずれかを選択する方法ではなく、多い方が遺族厚生年金の額になります。
※1.の額の3分の2は(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2)なので、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1となります。つまり、2.の額は、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1+自身の老齢厚生年金の2分の1の額です。
※この仕組みは『65歳以上』の『配偶者』だけに適用されます。
では、こちらの問題をどうぞ!
<H24年出題>
65歳に達している受給権者に支給される遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。

【解答】 ×
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせについては、「遺族厚生年金+老齢基礎年金」、「遺族厚生年金+障害基礎年金」の組み合わせが可能です。
なお、問題文の「遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する」という表現も誤りです。
先ほどの条文の2.の額(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2+自身の老齢厚生年金の2分の1の額)の方が1.の額より多い場合は2.の額が「遺族厚生年金」の額となるので、問題文の「同時に受給する」という表現にはなりません。
社労士受験のあれこれ
遺族厚生年金~短期要件と長期要件
R3-230
R3.4.10 遺族厚年 短期要件と長期要件の違い
今日のテーマは、遺族厚生年金「短期要件」と「長期要件」です。それぞれ年金額の計算に違いがあります。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第58条
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、①又は②に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に < A >がある傷病により当該< A >から起算して< B >を経過する日前に死亡したとき。
③ < C >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者が、死亡したとき。

【解答】
A 初診日
B 5年
C 障害等級の1級又は2級
D 25年
ポイント!
★①から③は短期要件
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
②厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
★④は長期要件
④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間(と合算対象期間)を合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき
保険料納付済期間と保険料免除期間(と合算対象期間)を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H27年出題(修正)>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
②<H17年出題(修正)>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者)の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。

【解答】
①<H27年出題(修正)> 〇
「長期要件」に該当するので、給付乗率は、生年月日に応じた読み替えを行います。
②<H17年出題(修正)> 〇
「長期要件」に該当するので、「300月」の最低保障は適用なし、給付乗率は生年月日に応じた読み替えが適用されます。
(法第58条、第60条、S60年法附則第59条)
ポイント!
遺族厚生年金の額の計算式(原則)
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3
※報酬比例部分→平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数(原則)
| 短期要件 | 長期要件 | |
| 給付乗率 | 定率 | 昭和21年4月1日以前生まれの者は、 生年月日に応じた読み替えあり |
| 被保険者期間の月数 | 300月の最低保障あり | 最低保障なし |
最後にこちらをどうぞ
③<H23年出題(修正)>
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。

【解答】 〇
死亡したのは、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上」の「被保険者」です。長期要件(「25年以上」)と短期要件(「被保険者」)の両方に当てはまっています。
このような場合は、どちらで計算するか選択することができますが、遺族から申出が無い場合は短期要件で計算されます。
(法第58条)
社労士受験のあれこれ
厚年・65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金
R3-229
R3.4.9 65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金の支給調整
今日のテーマは、65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合の支給調整についてです。
では、どうぞ!
<H22年出題(修正)>
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】 〇
例えば、夫婦ともに厚生年金保険の被保険者期間がある場合で夫が死亡した場合、妻は自分自身の老齢厚生年金と夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することになります。
そのような場合、65歳以後は、自分自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。
老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は当該老齢厚生年金の額に相当する部分が支給停止になります。
なお、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金よりも多い場合は、差額が遺族厚生年金として支給されます。
※夫婦を例にあげましたが、このルールは夫婦以外にも当てはまります。
社労士受験のあれこれ
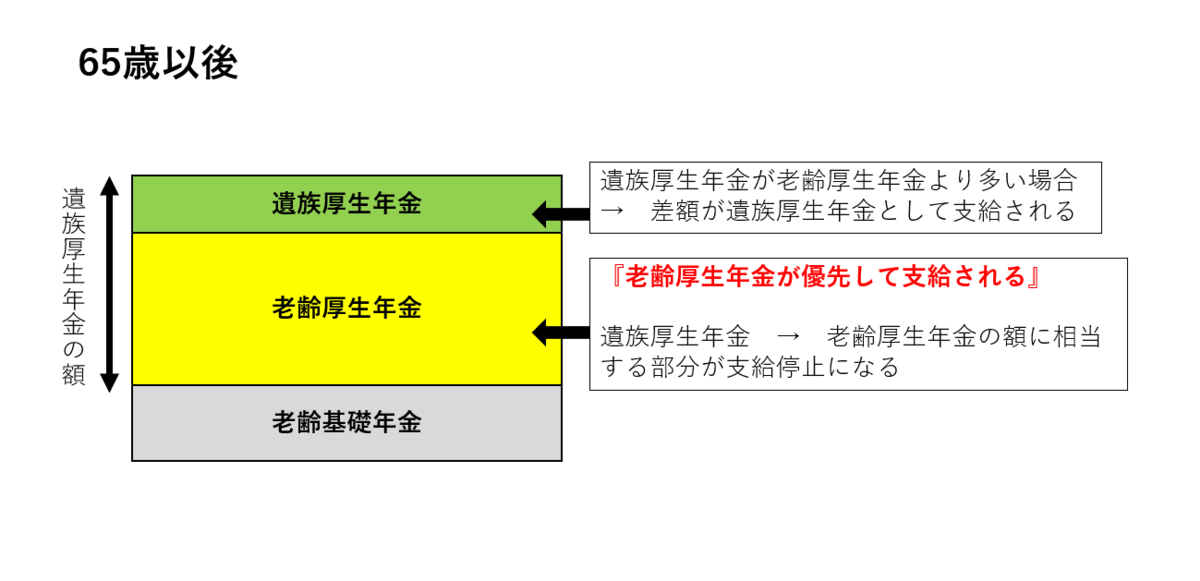
厚年・併給調整(65歳以上)
R3-228
R3.4.8 65歳以上の併給調整のルール
今日のテーマは、併給調整(65歳以上の場合)です。
では、どうぞ!
①<H23年出題>
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
①<H23年出題> ×
「障害厚生年金」と「該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金」は併給できます。
しかし、「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族基礎年金」は、障害厚生年金とは併給できません。(65歳未満でも65歳以上でも不可)
★障害厚生年金と基礎年金の組み合わせ
×老齢基礎年金(+付加年金)と障害厚生年金 → 併給不可
×遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可
〇障害基礎年金+障害厚生年金(同一支給事由の場合) → 併給できる
こちらもどうぞ!
②<H24年出題>
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
③<H24年出題>
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
④<H26年出題>
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

【解答】
②<H24年出題> 〇
★老齢厚生年金と基礎年金の組み合わせ
〇老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金 → もちろん併給できる
〇障害基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる(65歳以上の場合)
×遺族基礎年金+老齢厚生年金 → 併給不可
★「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせのイメージ
・例えば1級の障害基礎年金を受給しながら働き、その間、厚生年金保険の被保険者になっていた。
→ 65歳から①「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、②「1級の障害基礎年金と老齢厚生年金」の2つから選択できる。
③<H24年出題> 〇
★遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせ
〇老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
④<H26年出題> 〇
〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
■■組み合わせのまとめ■■
| 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | 〇 | × | 〇(65歳以上) |
| 障害基礎年金 | 〇(65歳以上) | 〇(支給事由が同一) | 〇(65歳以上) |
| 遺族基礎年金 | × | × | 〇(支給事由が同一) |
■■覚え方のポイント■■ → 「遺族厚生年金」は老齢厚生年金と同じように老後(65歳以上)の保障としての性格をもっている。
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H28年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【解答】 〇
×老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可
〇老齢基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
★「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせのイメージ
・夫婦(夫 厚生年金保険の被保険者、妻 第3号被保険者のみ)で、夫が死亡した
→ 妻は、65歳から、妻自身の老齢基礎年金と夫の死亡による遺族厚生年金を併給できる。
社労士受験のあれこれ
厚年・併給調整(65歳未満)
R3-227
R3.4.7 65歳未満の併給調整のルール
今日のテーマは、併給調整(65歳未満)です。
では、どうぞ!
①<H30年出題>
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

【解答】 ×
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給されません。
★原則は「一人一年金」です。
基礎年金と厚生年金は、支給事由が同一なら併給できます。(2階建て)
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・遺族基礎年金+遺族厚生年金
問題文の場合は、①「障害基礎年金+障害厚生年金」と②「特別支給の老齢厚生年金」のどちらかを選択することになります。
この問題は、受給権者が「65歳未満」であることがポイントです。
では、この受給権者が65歳になるとどうなるでしょうか?
65歳以上になると、①「障害基礎年金+障害厚生年金」、②「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、③「障害基礎年金+老齢厚生年金」と、選択肢が3つになります。
65歳以上は、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」が併給できることをおさえましょう。
(第38条、附則第17条)
こちらもどうぞ!
②<H12年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳未満の場合には、その者の老齢基礎年金及び付加年金は遺族厚生年金と併給されない。妻が65歳以上のときは、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されるが、付加年金は併給されない。

【解答】 ×
問題文の後段が誤りで、妻が65歳以上のときは、付加年金も併給されます。
★前段(65歳未満)のポイント
・①「(繰上げ支給の)老齢基礎年金+付加年金」と、②「遺族厚生年金」はどちら選択(併給不可)
★後段(65歳以上)のポイント
「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族厚生年金」は併給可能
(第38条、附則第17条)
『併給』のルールは、65歳未満と65歳以上で異なりますので、問題文を読む時に注意しましょう。
明日は、「65歳以上の併給ルール」をみていきます。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-203
R3.3.14 夫・妻の年金「加給年金額⑧在老との関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、在職老齢年金と加給年金額との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H24年出題>
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。
②<H27年出題>
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は105,000円(加給年金額を除く。)となる。

【解答】
①<H24年出題> ×
最後の「加給年金額を含めた」が誤り。「加給年金額は含めない」です。
ポイント! 基本月額に加給年金額は含まれない
「基本月額」の計算式は、「老齢厚生年金÷12」ですが、加給年金額は除いて計算します。
なお、支給停止額は115,000円で正しいです。
②<H27年出題> ×
ポイント! 在老で老齢厚生年金の一部が停止されても加給年金額は支給される
支給停止後の年金月額が誤りです。
この問題の場合、総報酬月額相当額は、240,000円+で600,000円÷12=290,000円です。
支給停止額は、(200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円
支給停止後の年金月額は、200,000円-105,000円=95,000円となります。
問題文の最後の(加給年金額を除く。)に注目してください。
問題文のように在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金の一部が支給停止になっていても、加給年金額は、別途全額支給されます。
★在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になった場合は、加給年金額も全額支給停止されます。
(厚生年金保険法平成6年附則第21条)
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-202
R3.3.13 夫・妻の年金「加給年金額⑦加算されるタイミング」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、加給年金額が加算されるタイミングです。
★加給年金額が加算されるタイミング★
・特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給開始年齢から
→ 定額部分がない場合は、65歳から
・65歳以後の老齢厚生年金の支給開始年齢から
※どちらも厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが条件
こちらの問題をどうぞ!
①<H30年出題>
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】 ×
「加給年金額が加算されることはない。」は誤り。加算されます。
ポイント! 受給権取得後に240月以上になった場合でも加給年金額は加算される
問題文のように、老齢厚生年金の受給権を取得した当時は240月未満であったとしても、その後厚生年金保険の被保険者として保険料を納付し、資格喪失時に240月以上になった場合、加給年金額が加算されます。
もう一問どうぞ!
②<H15年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

【解答】 ×
ポイント! 生計維持関係は240月以上となったときで確認
生計維持関係は、老齢厚生年金の受給権を取得した当時ではなく、退職時改定で240月以上となったときに確認します。
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-201
R3.3.12 夫・妻の年金「加給年金額⑥特別加算」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、配偶者加給年金額にプラスされる特別加算についてです。
★特別加算は、配偶者が65歳に達して自身の老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するためのものです。
こちらの問題をどうぞ!
①<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
②<H19年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。

【解答】
①<H28年出題> ×
ポイント! 特別加算は「受給権者」の生年月日で決まる
特別加算は、「その配偶者」の生年月日ではなく、老齢厚生年金の「受給権者」の生年月日に応じて行われます。
②<H19年出題> 〇
ポイント! 特別加算の額は、受給権者の「生年月日が若い」ほど大きい
では、こちらもどうぞ!
③<H15年出題>
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。
④<H21年出題>
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に、165,800円に改定率を乗じて得た額を加算した額とする。

【解答】
③<H15年出題> 〇
ポイント! 昭和9年と昭和18年は暗記しましょう
特別加算が加算されるのは、「昭和9年4月2日以後」生まれの受給権者
生年月日が若いほど特別加算額が大きくなりますが、「昭和18年4月2日以後」生まれからは同額となります。
④<H21年出題> ×
ポイント! 33,200円と165,800円は暗記しましょう
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日まで生まれの配偶者加給年金額に加算される特別加算は、「33,200円」に改定率を乗じて得た額です。
一番高いのは、昭和18年4月2日以後生まれで、「165,800円」に改定率を乗じて得た額となります。
特別加算は、受給権者の生年月日に応じて5段階設定されています。一番小さい「33,200円」と一番大きい「165,800円」を覚えましょう。
「33」×5=「165」と見ると覚えやすいと思います。
明日に続きます。
明日は加給年金額が加算されるタイミングです。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-200
R3.3.11 夫・妻の年金「加給年金額⑤金額は?」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、加給年金額の金額です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。
②<H28年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。

【解答】
①<H21年出題> ×
子の加給年金額の算定方法が誤りです。
1人目・2人目までは1人につき224,700円×改定率、3人目以降の子は1人につき74,900円×改定率です。
②<H28年出題> ×
所定の額×改定率の端数処理は、50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。(100円単位)
なお、令和3年度の改定率は、1.000です。
配偶者に対する加給年金額は224,700円×1.000=224,700円なので、今年度は端数処理は要りませんね。
では、もう一問どうぞ!
③<H18年出題>
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者と同様の改定率によって改定する。

【解答】 〇
「改定率」の改定基準の問題です。
基礎年金の改定率は原則として以下の基準で、毎年見直しされています。
・新規裁定者(68歳年度前) → 名目手取り賃金変動率に応じて改定
・既裁定者(68歳年度以降) → 物価変動率に応じて改定
「加給年金額」の改定率は、「新規裁定者と同様の改定率」で改定されます。受給権者本人が68歳以降になっても変わりません。
明日に続きます。
明日は配偶者加給年金額にプラスされる特別加算です。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-199
R3.3.10 夫・妻の年金「加給年金額④支給停止されるとき」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
昨日は、加給年金額の対象になる配偶者が240カ月以上の被保険者期間で計算される老齢厚生年金を受けることができるときは、その間、加給年金額が支給停止されることをお話ししました。
今日は、それ以外の支給停止理由についてです。
こちらの問題をどうぞ!
<H26年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

【解答】 ×
加給年金額の対象の配偶者が障害厚生年金(3級でも)を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。
『加給年金額が支給停止されるのはどんなとき?』
加算の対象の配偶者が、以下の給付を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給は停止されます。 ・老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。) ・障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの |
※障害厚生年金は3級も対象になります。
(厚生年金保険法第46条第6項、施行令第3条の7)
もう一問どうぞ!
<H19年出題>
加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。

【解答】 ×
さきほどの『加給年金額が支給停止されるのはどんなとき?』を見てください。
加算の対象となる妻が、障害基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額は支給停止となります。
一方、加算の対象となる妻が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていても、加給年金額の支給は停止されません。
妻が65歳前に繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていても、妻が65歳になるまで、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
このテーマは明日も続きます。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-198
R3.3.9 夫の年金・妻の年金「加給年金額のこと③共働きの場合」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件は、原則として「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」あることです。
昨日は、加給年金額の対象になる配偶者には、原則として65歳未満という年齢制限があることをお話ししました。
今日は、加給年金額の対象になる配偶者にも厚生年金保険の被保険者期間がある場合です。
こちらの問題をどうぞ!
<H28年出題>
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

【解答】 ×
ポイント! 原則として240か月以上
300か月以上が間違いです。
加給年金額の部分の支給が停止されるのは、加算対象の配偶者が受けることができる老齢厚生年金が、原則として240か月以上の被保険者期間で算定されている場合です。
(加算対象の配偶者が受けることができる老齢厚生年金の被保険者期間が240月未満(原則)の場合は、加給年金額は支給停止されません。)
(厚生年金保険法第46条第6項、施行令第3条の7)
では、もう一問どうぞ
<H22年出題>
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】 〇
ポイント! その全額が支給を停止されているものを除く。
「その全額が支給を停止されているものを除く。」に注目してください。
例えば、夫婦ともに240か月以上の厚生年金保険の被保険者期間があり、夫婦ともに加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権者である場合は、お互いに加給年金額は支給停止されます。
しかし、例えば、妻の老齢厚生年金の全額が支給停止されている場合は、夫に支給される老齢厚生年金の妻の分の加給年金額は支給停止されません。
このテーマは明日も続きます。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-197
R3.3.8 夫の年金・妻の年金「加給年金額のこと②年齢制限」
年金の仕組みを勉強しましょう。
昨日に引き続き、テーマは「加給年金額」です。
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件は、原則として「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」あることです。
加給年金額が加算されるのは、一定の条件を満たす配偶者、子がいる場合ですが、今日は加算の対象になる「配偶者」の条件を見ていきます。
こちらの問題をどうぞ!
<H26年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

【解答】 ×
ポイント! 加給年金額の対象になる配偶者は65歳未満(原則)
「当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。」が間違い。
加給年金額の対象となる配偶者は、「65歳未満」の配偶者です。そのため、加給年金額は、「配偶者が65歳に達したとき」に加算されなくなります。(配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月から加給年金額がなくなります。)
なぜなら、65歳からは、配偶者自身の老齢基礎年金を受給することができるからです。
★問題文のように、たとえ受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合であっても、65歳に達したときは加算されなくなります。
では、もう一問どうぞ
<H20年出題>
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

【解答】 ×
ポイント! 大正15年4月1日以前生まれの配偶者には年齢制限なし
「配偶者の生年月日にかかわらず」が間違いです。
配偶者が「大正15年4月1日以前生まれ」の場合は、65歳以降も引き続き加給年金額の対象となります。「大正15年4月1日以前生まれ」は旧法の対象者ですので、自身の老齢基礎年金が支給されないからです。
※この問題は「障害厚生年金の加給年金額」の問題ですが、「老齢厚生年金の加給年金額」も同じです。配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も引き続き加給年金額の対象となります。
このテーマは明日に続きます!
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-196
R3.3.7 夫の年金・妻の年金「加給年金額のこと①」
年金の仕組みを勉強しましょう。
今日のテーマは、「加給年金額」です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和3年1月22日、厚生労働省から令和3年度の年金額についてお知らせがありました。
令和3年度の新規裁定者の年金額として、
・ 国民年金 老齢基礎年金(満額)1人分 65,075 円
・ 厚生年金 夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額として220,496 円
という金額が例示されています。
厚生年金の給付水準は、平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9 万円)で 40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
片方が40年間厚生年金保険の被保険者で、もう片方が40年間国民年金(第1号被保険者か第3号被保険者)という夫婦がモデルになっています。
年金の勉強をするときは、そのようなモデルを意識してみましょう。
今日のテーマは「加給年金額」です。
例えば夫が40年間厚生年金保険の被保険者で、妻が40年間第3号被保険者だった場合、夫の年金は「老齢基礎年金+老齢厚生年金(+加給年金額)」、妻は「老齢基礎年金」となります。
といいましても、「加給年金額」が加算されるには条件があります。その条件を見ていきます。
こちらの問題をどうぞ!
<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【解答】 〇
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件は、原則として「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」あることです。
問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間がある場合は、合算して240月以上あればOKです。
この場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は日本年金機構から、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は共済組合から支給されますが、「加給年金額」はどちらの老齢厚生年金に加算されるのかが2つ目の問題です。
この点については、
・最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金
・最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間に基づく老齢厚生年金
となっています。
問題文の場合は、両方とも同時に受給権を取得していますので、被保険者期間が長い「第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」に加給年金額が加算されます。
(厚生年金保険法第44条、第78条の27、施行令第3条の13)
このテーマは明日に続きます!
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その2(創成期)
R3-191
R3.3.2 厚生年金保険法の誕生
年金の歴史についてお話しています。
現在の公的年金には、「国民年金法」と「厚生年金保険法」がありますが、先にできたのは厚生年金保険法です。
社労士試験の科目の順番が、厚生年金保険法→国民年金法と厚生年金保険法の方が先なのはそのためです。
昭和16年に「労働者年金保険法」が制定されました(昭和17年施行)。対象は、工場で働く男性労働者でした。労働力を保全し強化することによって生産力を上げるという社会的な要請があったそうです。
その労働者年金保険法が「厚生年金保険法」という名称に改められたのが昭和19年。その際、事務系の労働者や女性も対象になりました。
そして、昭和29年に厚生年金保険法が全面改正されました。実際に養老年金の受給者が生ずることへの対応です。このときの改正で、老齢年金は定額部分と報酬比例部分の2階建てになりました。また、男子の支給開始年齢が55歳だったものが段階的に60歳に引き上げられることになりました。
(参考:平成18年版、平成23年版厚生労働白書など)
★旧法と新法
昭和61年4月1日より前の年金制度を旧法、それ以降を新法といいます。
新法の厚生年金保険は国民年金(基礎年金)の2階部分という位置づけです。
例えば、65歳からの年金は、1階に老齢基礎年金があって、2階に老齢厚生年金という形です。
しかし、60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」は定額部分(1階)と報酬比例部分(2階)で、厚生年金だけで2階建てになっています。これは国民年金と厚生年金保険が別個に運営されていた旧法の形を引き継いでいます。
旧法の厚生年金保険の老齢年金の支給開始年齢は60歳で定額部分と報酬比例部分の2階建てになっていました。新法になったときに国民年金の支給開始年齢に合わせて65歳開始になりましたが、いきなり60歳から65歳に引き上げることはできません。
ですので、まずは定額部分の開始年齢を1歳ずつ引き上げ、その次に報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げることで、段階的に60歳代前半の老齢厚生年金をなくしていく方法をとっています。旧法の形を徐々になくしていくイメージで考えてみてください。
社労士受験のあれこれ
厚生年金保険法第1条(目的)
R3-189
R3.2.28 第1条チェック~厚生年金保険編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は厚生年金保険法です。
条文をチェックしましょう!
(第1条 目的)
厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 遺族
B 福祉の向上
では、こちらもどうぞ
<H30年出題>
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

【解答】×
問題文は国民年金法の目的条文です。
社労士受験のあれこれ
第三種被保険者(船員・坑内員)の被保険者期間(その2 厚年編)
R3-181
R3.2.20 第三種被保険者の被保険者期間(3分の4・5分の6)が反映するか否か?(その2 厚年編)
今日は年金です!
今日は、昨日の続きで「第3種被保険者」がテーマです。
まず、「第3種被保険者」の定義からどうぞ!
<厚年H18年出題(改)>
第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第4種被保険者以外のものをいう。

【解答】 ×
第3種被保険者は、坑内員(鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する被保険者)又は船員(船員法に規定する船員として船舶に使用される被保険者)のことで、 「第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外」のものをいいます。
問題文は、船員任意継続被保険者以外が抜けているので誤りです。
(参照:厚生年金保険法昭和60年附則第5条12号)
次は、被保険者期間の計算です
<H25年選択>
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から< A >4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に< B >を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【解答】
A 平成3年
B 5分の6
昭和61年3月以前は「3分の4」倍、昭和61年4月から平成3年3月までは「5分の6」倍です。
(参照:厚生年金保険法昭和60年附則第47条第4項)
こちらもどうぞ!
①<H20年出題>
昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。なお、他には被保険者期間がないものとする。
②<R1年出題>
船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである場合には、60歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。

【解答】
①<H20年出題> 〇
昭和21年4月1日以前生まれで、「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上」ある場合、55歳から特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が支給される特例があります。
この期間は、3分の4倍等しない「実際の期間」が15年以上あることが条件です。問題文の場合は、「3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年」しかありませんので、55歳から受けることはできません。
なお、この特例は、昭和21年4月2日以降生まれから、段階的に支給開始の年齢が引き上げられ、 例えば、昭和41年4月1日生まれの場合は、64歳からとなります。
(参照:厚生年金保険法平成6年法附則第15条)
②<R1年出題> ×
問題文の条件の場合、60歳からではなく、62歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができます。
(参照:厚生年金保険法附則第8条の2第3項)
★3分の4倍、又は5分の6倍された被保険者期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しませんが、老齢厚生年金の額の計算には反映します。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(厚年)老齢厚生年金の繰下げ
R3-178
R3.2.17 老齢厚生年金の繰下げの申し出の条件
今日は厚生年金保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

【解答】
A 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
B 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
繰下げのポイント!
① 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していないこと
→ 繰下げの申し出は、老齢厚生年金の受給権取得から1年以上待たなければならない。
② 以下の場合は繰下げの申し出はできない
・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者だった
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となった
※なぜなら、他の年金たる給付を受給しながら、老齢厚生年金を繰下げて受給額を増やすのは公平性に欠けるから。
※なお、「他の年金たる給付」とは、他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付のことです。ただし、国民年金法の年金たる給付から、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金は除かれます。(老齢基礎年金及び付加年金は、老齢厚生年金と同じく「老齢」の年金、障害基礎年金は65歳以降老齢厚生年金と併給できるので)
※まとめると、老齢厚生年金の受給権を取得したとき、またはその日から1年を経過した日までの間に、「障害厚生年金及び遺族厚生年金」、「遺族基礎年金」の受給権者となっていないこと。
こちらの問題もどうぞ!
①<H19年出題>
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。
②<H28年出題>
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

【解答】
①<H19年出題> ×
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者も、老齢厚生年金の支給繰下げの申出ができます。
②<H28年出題> 〇
老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金の受給権者であったとしても、繰下げの申し出をすることができます。(ちなみに、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間に障害基礎年金の受給権者になった場合でも繰下げの申し出ができます)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
年金額の改定(国年と厚年)
R3-176
R3.2.15 国年と厚年を比較・年金額改定
まずは国民年金法です!
令和2年度の問題をどうぞ!(国年)
<問2-選択・国年>
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

【解答】
A 国民の生活水準
B 改定
国民年金は、老齢、障害、死亡を保障するための制度です。
「国民の生活水準」に著しい変動があれば、速やかに年金額の改定が行われます。
(国民年金法第4条)
こちらの問題もどうぞ!
<厚生年金保険法 年金額の改定>
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、< C >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】
C 賃金
厚生年金保険法の場合は、「賃金」という用語が入るのが特徴です。厚生年金保険は被用者のための年金制度だからです。
(厚生年金保険法第2条の2)
・国民年金 → 国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合
・厚生年金保険 → 国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合
こちらの問題もどうぞ!(厚生年金保険)
<H30年出題・厚年>
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】 ×
冒頭の「厚生年金保険法に基づく保険料率」が誤りです。この条文は、保険料率ではなく、「年金たる保険給付」の改定のルールです。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(厚年)4分の3基準
R3-160
R3.1.30 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が4分の3以上
今日は厚年法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-D>
特定適用事業所以外の適用事業所においては、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うことされている。

【解答】 ×
直近6か月ではなく、直近2カ月です。
~~この問題でおさえておきたいところ~~
※短時間労働者の厚生年金保険の加入要件
■1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上
→ 被保険者となる
※1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数とは?
→ 就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数のこと。
※雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき
→ 4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った → 実際の労働時間又は労働日数が直近2か月で4分の3基準を満たしている → 今後も同様の状態が続くことが見込まれる → 4分の3基準を満たしているものとして取り扱う
(参照:H28.5.13 保保発0513第1号/年管管発0513第1号/)
では、こちらの問題をどうぞ
<H29年出題>
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】 ×
「通常の労働者の4分の3以上」の要件を満たしている場合は、学生でも厚生年金保険の被保険者となります。
※ 通常の労働者の4分の3未満の場合は、「特定適用事業所に使用」「20時間以上」「1年以上使用見込」「88,000円以上」など他の適用基準を満たしていても、「学生でないこと」という要件があるので、学生は適用除外です。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(厚年)特定適用事業所と短時間労働者
R3-159
R3.1.29 特定適用事業所と短時間労働者について
今日は厚年法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
 <問7-ア>
<問7-ア>
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
 <問7-イ>
<問7-イ>
特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
※短時間労働者の厚生年金保険の加入要件
■1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上
→ 被保険者となる
■1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満
→ 原則として適用除外
※ただし、4分の3未満でも一定の要件を満たせば、厚生年金保険の被保険者となる
<要件>
①週の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上使用されることが見込まれる
③厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円以上
④学生でない
⑤特定適用事業所に使用される
※「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと
 <問7-ア> 〇
<問7-ア> 〇
報酬の月額が88,000円未満の場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
 <問7-イ> 〇
<問7-イ> 〇
当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
(厚生年金保険法第12条5号)
では、こちらの問題をどうぞ
 <問7-エ>
<問7-エ>
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
 <問7-エ> ×
<問7-エ> ×
常時500人を超えなくなった場合でも、引き続き特定適用事業所とみなすこととされているので、そのまま厚生年金保険の被保険者となります。
(厚生年金保険法附則(平成24年)第17条)
最後にもう一問どうぞ!
 <問7-ウ>
<問7-ウ>
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
 <問7-ウ> 〇
<問7-ウ> 〇
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者
↓
厚生年金保険の被保険者とならない。
※ただし、特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、所定の労働組合等の同意を得て、「任意特定適用事業所」の申し出を行うことができます。
(厚生年金保険法附則(平成24年)第17条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(年金)3号分割標準報酬改定請求
R3-134
R3.1.4 3号分割~当事者の一方が死亡した場合
令和2年度の問題をどうぞ!
<問3-イ>
特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

【解答】 ×
「当該特定被保険者が『死亡した日』に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。」の部分、死亡した日ではなく、『死亡した日の前日』です。(死亡した日には請求できないので、前日)
■ 特定被保険者が死亡したとしても、死亡後1か月以内なら、3号分割改定を請求できます。
※「特定被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者と被保険者であった者のこと。
※「被扶養配偶者」とは、特定被保険者の配偶者として国民年金法の第3号被保険者だった者のこと。
こちらの問題もどうぞ!
<H28年出題>
離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

【解答】 〇
令和2年度と同じ趣旨の問題です。
3号分割について、こちらもどうぞ!
 <H26年出題>
<H26年出題>
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して、分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して、いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
 <H26年出題>
<H26年出題>
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して、原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

【解答】
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
■ 特定期間 → 特定被保険者が厚生年金保険の被保険者で、かつ、その被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者であった期間のこと。
ただし、この制度が施行された平成20年4月1日以降が対象です。それより前の期間は特定期間に含まれません。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
事実婚関係だった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者だった場合は分割の対象になります。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年です。
社労士受験のあれこれ
(年金)退職時改定
R3-128
R2.12.29 資格喪失→保険料が年金額に反映するのはいつから?
令和2年度の問題をどうぞ!
<厚年 問9-A>
被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎なり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

【解答】 ×
問題文の場合
・資格喪失日 → 令和2年6月30日(70歳に達した日=誕生日の前日)
・被保険者期間 → 令和2年5月まで(喪失した月の前月まで)
 <退職時改定>令和2年5月までの期間も入れて、老齢厚生年金の額を再計算する。
<退職時改定>令和2年5月までの期間も入れて、老齢厚生年金の額を再計算する。
・年金額の改定 → 資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から
資格喪失日は6月30日。「資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月」は令和2年7月。老齢厚生年金は、令和2年8月からではなく、「令和2年7月」から改定されます。
こちらの問題もどうぞ!
 <H26年出題>
<H26年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
 <H28年出題>
<H28年出題>
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【解答】
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
老齢厚生年金の額の計算のルールは、「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」とされています。
受給権を取得した時点の年金額には、受給権を取得した月は含みません。
※ ちなみに・・・
厚生年金保険法で、「被保険者である」というのは、「在職中」という意味。在職中とはすなわち厚生年金保険料を負担しているという意味です。
問題文の「老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった」とは、老齢厚生年金の受有権を取得した月に在職中だった(=厚生年金保険の保険料を負担していた)という意味です。
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
平成28年3月からではなく、平成28年2月から年金額が改定されます。
<退職時改定のルール>
・ 被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月経過した
↓
・ 被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とする
↓
・ 資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
※起算日に注意しましょう!
「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。(退職)」は、その翌日に資格を喪失しますが、退職時改定による年金額の改定は、「退職日」から起算して1か月を経過した日の属する月からとなります。
問題文の場合、平成28年1月31日付退職、同年2月1日に被保険者資格を喪失ですので、退職時改定の起算日は退職日の平成28年1月31日となります。
年金額の改定は、資格喪失日(退職の場合は退職日)から起算して1か月を経過した日の属する月からなので、平成28年2月から年金額が改定されることになります。
社労士受験のあれこれ
(年金)滞納処分のルール
R3-125
R2.12.26 厚生労働大臣が滞納処分を行う場合のルール
令和2年の問題をどうぞ!
 <厚年 問3-ウ >
<厚年 問3-ウ >
厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
 <厚年 問3-エ >
<厚年 問3-エ >
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

【解答】
 <厚年 問3-ウ > 〇
<厚年 問3-ウ > 〇
厚生労働大臣は、督促を受けた者が指定の期限までに保険料等を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる
↓
滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること等の事情があるため、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき
↓
財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
※納付義務者が滞納処分を免れるため財産を隠ぺいしているおそれがあるようなときは、財務大臣(国税のトップ)に、必要な情報を提供したうえで、滞納処分等の権限の全部又は一部を委任できる。
 <厚年 問3-エ > 〇
<厚年 問3-エ > 〇
国税滞納処分の例による処分の厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。
↓
<日本年金機構が滞納処分等を行う場合>
・あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける
・「滞納処分等実施規程」に従い徴収職員に行わせる
こちらもどうぞ!
<厚年 H30年出題>
厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。

【解答】 〇
厚生労働大臣は、市町村に、その処分を請求することができる
↓
処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によって処分した
↓
厚生労働大臣は、徴収金の100の4に相当する額を当該市町村に交付する
社労士受験のあれこれ
(年金)被保険者期間のカウント
R3-124
R2.12.25 厚年 保険料が徴収される月されない月
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問3-ア >
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

【解答】 ×
月末日で退職したとき →退職した日が属する月の保険料は徴収されます。
例えば、退職日が12月31日の場合、翌日の1月1日に資格を喪失します。
資格を喪失した月(1月)は保険料は徴収されませんが、退職月(12月)は保険料が徴収されます。
もし、退職日が12月25日なら、翌日の12月26日に資格を喪失します。
この場合、資格を喪失した月が12月ですので、保険料が徴収されるのは11月まで。12月は保険料は徴収されません。
こちらもどうぞ!
 <厚年 H21年出題>
<厚年 H21年出題>
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
 <厚年 H20年出題>
<厚年 H20年出題>
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。
 <厚年 H28年出題>
<厚年 H28年出題>
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
 <厚年 H21年出題> ×
<厚年 H21年出題> ×
問題文のように日単位となるのは「被保険者であった期間」です。
「被保険者期間」は、「月単位」で計算します。「資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」までとなります。
 <厚年 H20年出題> 〇
<厚年 H20年出題> 〇
被保険者期間は、「資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」まで。
問題文の場合は、4月(4月30日)に資格取得・6月(6月1日)に資格喪失ですので、被保険者期間は4月、5月の2か月となります。保険料も、4月分と5月分の2か月分が徴収されます。
 <厚年 H28年出題> 〇
<厚年 H28年出題> 〇
同月得喪の問題です。
(原則)
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は1か月の被保険者期間としてカウントします。
(例外)
資格を取得した月に資格を喪失し、その月に更に厚生年金保険の被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者以外)の資格を取得したときは、先に喪失した厚生年金保険は被保険者期間としてカウントしません。
問題文の場合、平成28年3月1日に資格取得、同月20日退職・翌21日に資格喪失ですので、厚生年金保険は同月得喪。引き続き同月21日に国民年金の第1号被保険者となっています。
このパターンは上記(例外)に当たりますので、3月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。(厚生年金保険の保険料も徴収されません。)
社労士受験のあれこれ
(年金)受給権者の申出による支給停止
R3-123
R2.12.24 年金の支給停止の申出について
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1-B >
年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。

【解答】 〇
受給権者の意思で、年金の支払いを辞退するための規定です。
辞退できるのは「全額」です。(一部だけの辞退はできない)
問題文にもあるように、年金の一部が既に支給停止されている場合は、残りの部分(支給停止されていない部分)を辞退することになります。
こちらもどうぞ!
 <厚年 H19年出題>
<厚年 H19年出題>
年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。
 <国年 H24年出題>
<国年 H24年出題>
受給権者の申出による年金の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

【解答】
 <厚年 H19年出題> ×
<厚年 H19年出題> ×
辞退できるのは「全額」についてです。一部だけ辞退は不可。
受給権者の申出により「その全額又は一部の支給を停止」は間違いで、「全額」が支給停止されます。同様に、停止されていない部分の「全額又は一部の支給を停止」も間違いで、こちらも残りの部分が「全額」支給停止されます。
 <国年 H24年出題> ×
<国年 H24年出題> ×
受給権者の申出による年金の支給停止は、いつでも撤回することができますが、「過去に遡って」が間違いで、「将来に向かって」撤回することができます。
・支給停止 → 申出をした日の属する月の翌月分から支給停止
・支給停止の解除 → 申出をした日の属する月の翌月分から支給停止の解除
社労士受験のあれこれ
(年金)2以上の種別の被保険者であった期間
R3-122
R2.12.23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問5-C >
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。

【解答】 〇
厚生年金保険の被保険者は、第1号から第4号まで4つの種別に分けられています。
例えば、民間企業の会社員と国家公務員の経験がある人は、問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有することになります。
このような場合
・老齢厚生年金の受給権の有無 → それぞれの被保険者期間ごとにみる
・老齢厚生年金の年金額 → それぞれの被保険者期間ごとに計算する
1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は、それぞれで計算し、併給されます。
こちらもどうぞ!
 <H29年出題>
<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
 <H28年出題>
<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【解答】
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
「2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して・・・平均標準報酬額を算出する。」が間違いです。
年金額は、それぞれの種別の被保険者期間ごとに計算します。
 <H28年出題> 〇
<H28年出題> 〇
加給年金額が加算されるには、原則として240月以上の被保険者期間が必要です。この場合は、2以上の種別の被保険者期間を合算します。問題文の場合は、第1号厚生年金被保険者期間170か月、第2号厚生年金被保険者期間130か月で合計300月ありますので、加給年金額が加算されます。
なお、加算については、それぞれの厚生年金被保険者期間のうち一の期間の老齢厚生年金の額に加算されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)老齢基礎年金の受給資格
R3-119
R2.12.20 厚年第3種被保険者の被保険者期間の特例
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問9‐D>
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】 ×
老齢基礎年金の受給資格を満たしているので、65歳以上の特例の任意加入被保険者になることはできません。
★ 厚生年金保険の第3種被保険者とは、「坑内員・船員」である被保険者のことです。過酷な労働だったため、受給資格期間を計算する際の特例が設けられています。
| 昭和61年3月まで | 平成3年3月まで | 平成3年4月以降 |
| 3分の4倍 | 5分の6倍 | 実期間 |
問題文の場合、平成3年3月までの実期間が72月、平成3年4月以降が36月。72月は5分の6倍で計算しますので、老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たします。
そのため、65歳以上の特例による任意加入はできません。
こちらもどうぞ!
<厚年 H25年選択>
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から< A >4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に< B >を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【解答】
A 平成3年
B 5分の6
社労士受験のあれこれ
(年金)厚生年金・加給の対象
R3-118
R2.12.19 (厚年)老齢・障害・遺族の加給対象者
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐E>
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。

【解答】 〇
老齢厚生年金の加給年金額の対象は、「配偶者」「子」です。
こちらもどうぞ!
 <H29年出題>
<H29年出題>
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
 <R1年出題>
<R1年出題>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。

【解答】
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
1級又は2級の障害厚生年金の加給年金額の対象は「配偶者」のみで、「子」は対象になっていません。
※「子」は、障害基礎年金の方で加算対象となります。
 <R1年出題> ×
<R1年出題> ×
遺族厚生年金には加給年金額はありません。
【厚生年金加給年金額の対象者】
| 配偶者 | 子 | |
| 老齢厚生年金(原則240月以上) | 〇 | 〇 |
| 障害厚生年金(1級・2級) | 〇 | なし |
| 遺族厚生年金 | なし | なし |
社労士受験のあれこれ
(年金)遺族厚生年金の保険料納付要件
R3-117
R2.12.18 遺族厚生年金・保険料納付要件が必要なパターンは?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問10‐ア>
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】 〇
★この問題のポイント!
死亡した者が保険料納付要件を満たしていることが条件であること。
<保険料納付要件>
・ 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
・ 死亡日が令和8年4月1日前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと(死亡日が65歳未満であること)
ちなみに、遺族厚生年金には死亡した人の要件が4つありますが、保険料納付要件が必要なのはその中の2つです。(後で書きます。)
こちらもどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。
 <H23年出題>
<H23年出題>
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。

【解答】
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の保険料納付要件は問われません。(障害厚生年金を受給する際に、既に保険料納付要件を満たしているので)
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
遺族厚生年金の死亡した者の要件に、「3級の障害厚生年金の受給権者」は入っていません。1級・2級とは違います。
3級の障害厚生年金の受給権者だからという理由で、保険料納付要件が問われない、ということはありません。
では、こちらで選択の練習をどうぞ!
<遺族厚生年金 死亡した者の要件>
① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に < A >がある傷病により当該< A >から起算して< B >を経過する日前に死亡したとき。
③ 障害等級の< C >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者が、死亡したとき。

【解答】
A 初診日
B 5年
C 1級又は2級
D 25年
上記①~④のうち、保険料納付要件が問われるのは①(在職中の死亡)と②(初診日から5年以内の死亡)です。
③(1,2級の障害厚生年金の受給権者)と④(25年満たしている)は保険料納付要件は問われません。
社労士受験のあれこれ
(年金)障害厚生年金の支給要件
R3-112
R2.12.13 障害厚生年金・初診日要件
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問4‐E>
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

【解答】 ×
障害厚生年金の要件は、「初診日に厚生年金保険の被保険者」であることです。
問題文の場合は初診日に「国民年金第1号被保険者」ですので、障害厚生年金は受給できません。
こちらもどうぞ!
<H26年出題>
厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

【解答】 〇
初診日に「厚生年金保険の被保険者」ですので、障害厚生年金を受給することができます。
社労士受験のあれこれ
(年金)3級の障害厚生年金のこと
R3-110
R2.12.11 3級の障害厚生年金のポイントは?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問4‐D>
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】 ×
3級の障害厚生年金の最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3です。
★なお、「障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されない」の部分は「〇」です。(1級・2級の障害厚生年金には配偶者加給年金額が加算されます。)
また、3級の場合は、1階部分の障害基礎年金は支給されません。
ちなみに・・・
3級の障害厚生年金に最低保障額が設定されているのは、障害基礎年金が無いからです。でも、1級・2級でも障害基礎年金が支給されない場合があり、その場合は、1級・2級でも最低保障額が適用されます。
★では、1級・2級で障害基礎年金が支給されない場合とは?
初診日に「厚生年金保険の被保険者」ではあるが、「国民年金第2号被保険者ではない」場合です。
★具体的には、65歳以上で老齢基礎年金等の受給権を有する者です。
65歳以降、在職中(厚生年金保険に加入中)に障害になった場合、初診日に厚生年金保険の被保険者であるものの、老齢基礎年金等の受給権がある場合は国民年金の第2号被保険者ではありません。そのため、障害厚生年金は支給されますが、障害基礎年金は支給されません。
このような場合は、1級・2級であっても、3級の障害厚生年金の最低保障額と同額が保障されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)代表取締役の被保険者資格
R3-109
R2.12.10 代表取締役は厚生年金保険の被保険者となる?ならない?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問6‐E>
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

【解答】 ×
★ 代表取締役も被保険者となります。
法人の理事、監事、取締役等法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は被保険者になります。
ちなみに、事業主1人で経営している法人は、強制適用事業所となります。
また、個人事業主は、個人事業主本人が事業主体となるので、厚生年金保険の被保険者にはなりません。
では、こちらもどうぞ!(健康保険法の問題です)
 健保 H22年出題
健保 H22年出題
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
 健保 H29年出題
健保 H29年出題
従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。

【解答】
 健保 H22年出題 ×
健保 H22年出題 ×
法人役員は、法人(事業主)から、労務の対償として報酬を受けている者として、被保険者の資格を取得します。(厚生年金保険と同じです。)
 健保 H29年出題 ×
健保 H29年出題 ×
個人事業所の事業主は、本人が事業主なので、被保険者となることはできません。(こちらも厚生年金保険と同じです。)
では、次は「雇用保険法」の問題をどうぞ!
 雇用保険 H30年出題
雇用保険 H30年出題
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
 雇用保険 H24年出題
雇用保険 H24年出題
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

【解答】
 雇用保険 H30年出題 〇
雇用保険 H30年出題 〇
なお、問題文のような人が失業した場合は基本手当を受けることができますが、基本手当の基になる賃金には、取締役としての地位に基づく役員報酬は含まれません。あくまでも労働の対償としての賃金で計算されます。
 雇用保険 H24年出題 〇
雇用保険 H24年出題 〇
株式会社の代表取締役は、雇用関係にないので、失業することも考えられませんよね。株式会社の代表取締役は被保険者になることはありません。
社労士受験のあれこれ
(年金)失踪宣告と生計維持
R3-108
R2.12.9 失踪宣告を受けた場合の生計維持関係はどの時点でみる?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐C>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】 〇
★ 行方不明となった人の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所は失踪宣告をすることができ、行方不明から7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。
遺族厚生年金等については、「行方不明となった日」を「死亡日」として取り扱い、生計維持関係や保険料納付要件等をみることになります。
ただし、遺族厚生年金等の受給権は、失踪宣告が確定した日に発生し、受給権者の身分関係、年齢、障害状態は、失踪宣告による死亡日(7年後)で判断します。
この問題は、「生計維持に係る要件」についてですので、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われます。
では、こちらもどうぞ!
 国年 H18年出題
国年 H18年出題
失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。
 国年 H26年出題
国年 H26年出題
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
 国年 R2出題
国年 R2出題
失踪の宣告を受けたことにより死亡とみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

【解答】
 国年 H18年出題 ×
国年 H18年出題 ×
「5年」ではなく、7年を経過した日に死亡したものとみなされます。
 国年 H26年出題 〇
国年 H26年出題 〇
・ 生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件 → 行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
・ 受給権者の身分関係、年齢、障害状態 → 失踪宣告による死亡日(7年後)で判断
 国年 R2出題 ×
国年 R2出題 ×
保険料納付要件は、「死亡日の前日」で判断します。失踪宣告の場合は、「行方不明となった日」を「死亡日」としますので、保険料納付要件は「行方不明となった日の前日」で判断することになります。
社労士受験のあれこれ
(年金)遺族厚生年金の失権の届出
R3-107
R2.12.8 遺族厚生年金の失権事由と届出の関係
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐A>
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 〇
この問題のポイントは、「失権の届出が必要なとき、不要なときを区別すること」です。
★「子、孫」特有の遺族厚生年金の失権事由は3つありますが、届出が必要なのは②のみです。
①と③は「年齢」による失権です。年齢は日本年金機構で把握できるので、届出は要りません。
一方、②については「障害の事情がやんだ」事実は把握できていませんので、届出が必要なのです。今回の問題は②に該当します。
「子、孫」特有の遺族厚生年金の失権事由と失権届
| 「子、孫」の失権事由 | 失権届 | |
| ① | 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 (ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。) | 不要 |
| ② | 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。 (ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 | 要 |
| ③ | 子又は孫が、20歳に達したとき。 | 不要 |
では、こちらもどうぞ!
<H23年出題>
遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る。)であるとき、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したときは、10日以内に失権の届書を日本年金機構に提出しなくてはならない。

【解答】 ×
上の表の①に該当します。年齢に達したことにより失権ですので、届書の提出は不要です。
もう1問どうぞ!
<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
「年齢」に達したことによる不該当の届書の提出は不要です。
★ 加給年金額対象者が要件に該当しなくなった場合は、老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額対象者不該当の届出を10日以内に提出しなければなりません。
ただし、対象者が「年齢」に達したことにより不該当になった場合は、届書の提出は不要です。
届書が不要になるのは次の3つです。
・ 配偶者が、65歳に達したとき。
・ 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
・ 子が、20歳に達したとき。
社労士受験のあれこれ
(年金)障害の程度の審査のための診断書
R3-104
R2.12.5 障害基礎年金・障害の現状に関する届出
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問6‐C>
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の状況に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
障害状態確認届(診断書)の作成期間は、指定日前1か月以内から、令和元年8月から「指定日前3か月以内」に拡大されています。
★「障害状態確認届」とは → 厚生労働大臣が指定した年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するためのもの
では、こちらもどうぞ!
<厚生年金保険 障害の現状に関する届出 (参考)H21年出題>
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の額の全部につき支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 〇
国民年金同様、厚生年金保険も「3か月」です。
また、全部につき支給停止されている場合は、診断書の提出は不要です。(国年も同様)
社労士受験のあれこれ
(年金)「生計維持」の認定
R3-103
R2.12.4 生計維持要件850万円について
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問1‐ウ>
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。

【解答】 ×
定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)の収入が年額850万円未満(又は所得が年額655.5万円未満)となると認められるときは、収入の認定要件に該当します。
★『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕』より
■生計維持認定対象者は?
| 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
|---|---|
| 老齢基礎年金の振替加算等の対象者 | 老齢厚生年金の加給年金額の対象の配偶者及び子 |
| 障害基礎年金の加算額の対象の子 | 障害厚生年金の加給年金額の対象の配偶者 |
| 遺族基礎年金の受給権者 | 遺族厚生年金の受給権者 |
| 寡婦年金の受給権者 |
■収入に関する認定要件は、「厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外」とされています。
■具体的には、
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
※障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者の場合は、「エ」が「ア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。」となります。
では、こちらもどうぞ!
 <厚生年金 H18年出題>
<厚生年金 H18年出題>
老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については、維持関係があるとは認定されない。
 <厚生年金 H27年出題>
<厚生年金 H27年出題>
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

【解答】
 <厚生年金 H18年出題> ×
<厚生年金 H18年出題> ×
 <厚生年金 H27年出題> ×
<厚生年金 H27年出題> ×
生計維持の要件は、「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者」とされています。
前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が年額850万円未満(前年の所得(前年の所得が確定しない場合は前々年の所得)が年額655.5万円未満)でなかったとしても、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められれば、認定要件に該当します。
社労士受験のあれこれ
(厚年)脱退一時金の請求条件
R3-100
R2.12.1 脱退一時金と障害の年金との関係
令和2年の問題をどうぞ!
<問9‐E>
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

【解答】 ×
脱退一時金は、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは支給されません。
問題文のように、現在は障害の状態が軽減していたとしても、受給権を有したことがあれば支給されません。
なお、脱退一時金とは、外国人が対象です。日本で、年金に結び付かない短い期間、厚生年金保険料を納付した外国人が帰国する際に請求できます。
こちらもどうぞ!
※国民年金法の過去問です!
 <国年 H24年出題>
<国年 H24年出題>
脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。
 <国年 H30年出題>
<国年 H30年出題>
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

【解答】
 <国年 H24年出題> 〇
<国年 H24年出題> 〇
厚生年金保険法と同じです。障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されません。
 <国年 H30年出題> ×
<国年 H30年出題> ×
厚生年金保険法と同じです。障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されません。現在、障害基礎年金の支給を停止されてても、脱退一時金は請求できません。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(厚年)
R3-090
R2.11.21 <R2出題>覚える「遺族厚生年金・受給権者の順位」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問2-E>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

【解答】 〇
まず、遺族の順位を確認しましょう。
ポイントは、①年金を受給できる順位が決まっていること、②先順位の人が受給権を得ると、後の人は遺族とならないこと
| 順位 | |
| 1 | 配偶者又は子 |
| 2 | 父母 (配偶者、子がいないとき) |
| 3 | 孫 (配偶者、子、父母がいないとき) |
| 4 | 祖父母 (配偶者、子、父母、孫がいないとき) |
例えば、被保険者の死亡の当時、生計維持関係のある配偶者又は子が無く、生計を維持されていた父がいた場合、父が遺族厚生年金の受給権者となります。
しかし、その後、被保険者の死亡の当時胎児であった子(第1順位)が出生した場合は、父の受給権は消滅します。
一方、被保険者の死亡の当時、生計維持関係のあった妻がいて、妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、その後、被保険者の死亡の当時胎児であった子が出生しても、妻の受給権は消滅しません。(配偶者と子は同順位なので)
では、関連問題をどうぞ!
 H24年出題
H24年出題
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
 H27年出題
H27年出題
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

【解答】
 H24年出題 〇
H24年出題 〇
R2年の問題と同じ主旨です。子より後順位の父母、孫、祖父母と、子と同順位の妻との違いに注意してください。
 H27年出題 〇
H27年出題 〇
死亡の当時胎児であった子は、出生したときに、遺族となります。「将来に向かって」の部分がポイントです。死亡時にさかのぼるのではなく、出生したときから遺族となります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(厚年)
R3-080
R2.11.11 <R2出題>問題の意図「特支の老厚/1年要件」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問10-イ>
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第1号厚生年金被保険者期間が9か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。

【解答】 〇
問題の意図は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件の「1年以上の被保険者期間」は、異なる種別でも合算できる?です。
 厚生年金保険の被保険者には、第1号から第4号まで4つの種別があります。
厚生年金保険の被保険者には、第1号から第4号まで4つの種別があります。
特別支給の老齢厚生年金には、「1年以上の被保険者期間」という支給要件がありますが、種別が異なっていても、合算できます。
問題文では、第1号厚生年金被保険者期間(9か月)と第3号厚生年金被保険者(3か月)を合算して1年になりますので、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たします。
関連問題をどうぞ!
 問題<R1年出題>
問題<R1年出題>
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
 問題<H28年出題>
問題<H28年出題>
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

【解答】
 問題<R1年出題> 〇
問題<R1年出題> 〇
特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間」を有していることが要件です。
ちなみに、65歳からの本来の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月でもあればOKです。
 問題<H28年出題> ×
問題<H28年出題> ×
第1号厚生年金被保険者期間(8か月)と第4号厚生年金被保険者期間(10か月)の合算で特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たします。
問題文の場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
なお、60歳から支給されるのは第1号厚生年金被保険者期間の分です。第4号の期間分の支給は、62歳からです。
女性の場合、第1号厚生年金被保険者期間分の支給開始年齢が他と違うことも意識してください。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(厚年)
R3-069
R2.10.31 R2出題【選択練習】在職老齢年金の計算
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>を埋めてください。
令和2年8月において、総報酬月額相当額が220,000円の64歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が120,000円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月< A >円の当該老齢厚生年金が支給停止される。
(参考:問10ウ)

【解答】
A 30,000
計算手順
①基本月額(120,000円)+総報酬月額相当額(220,000円)が28万円を超えるので、支給停止が行われる
↓
②基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下なので、(基本月額+総報酬月額相当額)の28万円を超えた部分の2分の1が支給停止になる。
計算式は、
(120,000円+220,000円-280,000円)×2分の1=30,000円
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(厚年)
R3-060
R2.10.22 R2出題・厚年~所在不明のときの支給停止
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問8より
死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。

【解答】 〇
この問題のチェックポイントは、「いつから」支給停止されるのか?という部分です。
「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されます。他の受給権者の申請があったときからではありません。
 問題文のように、遺族厚生年金の受給権者が2人の子(例えばAとB)である場合、1人当たりの額は、遺族厚生年金を「2」で割った額となります。
問題文のように、遺族厚生年金の受給権者が2人の子(例えばAとB)である場合、1人当たりの額は、遺族厚生年金を「2」で割った額となります。
そのうちの1人(A)が行方不明になり、残りの1人(B)の申出によりAの年金が支給停止になった場合、Bの年金額が増額されることになります。(それまでは2分の1ずつだったのがB1人で全額受けることになるので)
こちらもどうぞ!
<R1年出題>
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。

【解答】 ×
支給停止は申請の日からではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(厚年)
R3-050
R2.10.12 R2出題・難問解決策「障害等級3級不該当と65歳」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問3より>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【解答】 ×
3級の障害厚生年金が支給されます。
★「失権」と「支給停止」
まずは、「失権」と「支給停止」の違いを意識してください。
「失権」とは受給権の消滅、すなわち受給権そのものがなくなること。復活はありません。
一方、「支給停止」とは、何らかの理由で支給が止まること。停止理由がなくなれば支給停止は解除され再び支給されます。
★問題文の考え方
障害等級3級に該当しなくなった
↓
障害厚生年金は支給停止
↓
その状態のまま3年が経過
↓
その後、65歳に達する日の前日までに障害等級3級の障害の状態になった
↓
支給停止は解除。障害厚生年が支給される
★ポイント!
3級に該当しないまま3年経過しても、65歳に達するまでは失権せず、支給停止のまま。再び3級に該当すれば支給停止は解除され、障害厚生年金が支給されます。
少なくとも65歳までは失権しないのがポイントです。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H27年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。

【解答】 ×
障害厚生年金は、3級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき、又は、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過したとき、のどちらか遅い方に失権します。
問題文の場合、3級に該当しなくなったのが63歳の時。65歳に達した日にはまだ3年たっていません。ですので、65歳に達した日には消滅しません。
では、選択の練習をどうぞ!
(障害厚生年金の失権)
障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定(併合認定)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
1 死亡したとき。
2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、< A >歳に達したとき。ただし、< A >歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく< B >年を経過していないときを除く。
3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく< B >年を経過したとき。ただし、< B >年を経過した日において、当該受給権者が< A >歳未満であるときを除く。

【解答】
A 65
B 3
ちなみに、「障害等級」は厚生年金保険法の場合は「1級、2級、3級」です。
国民年金法の「障害等級」は「1級、2級」です。
社労士受験のあれこれ
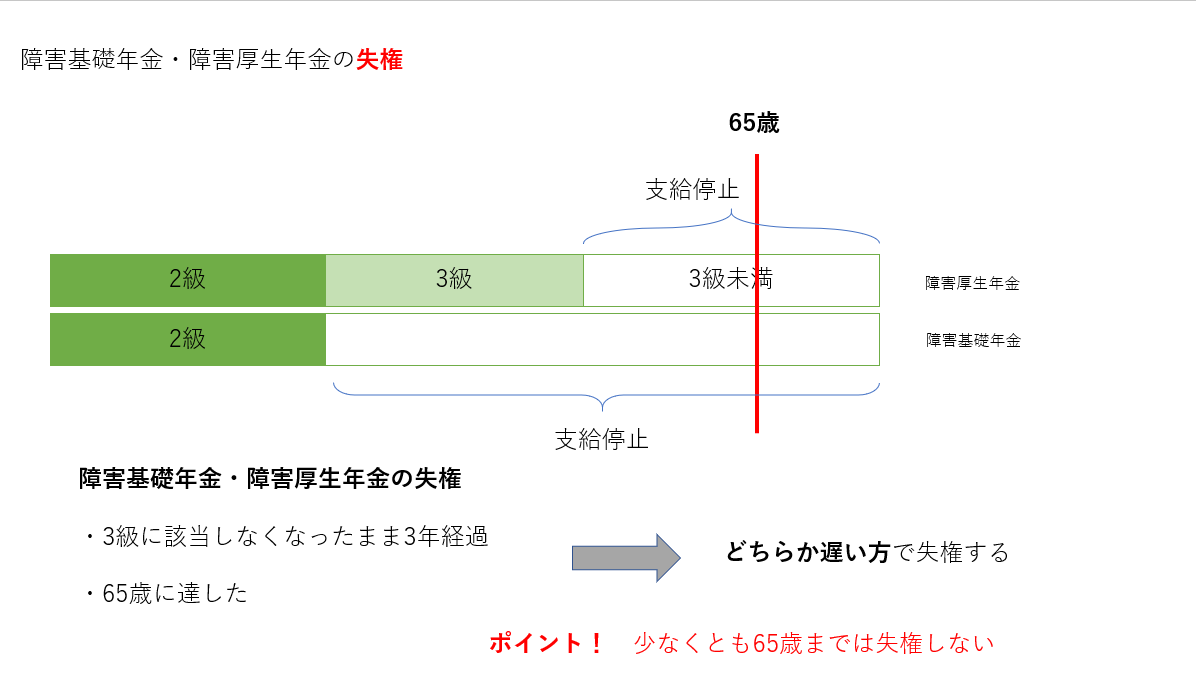
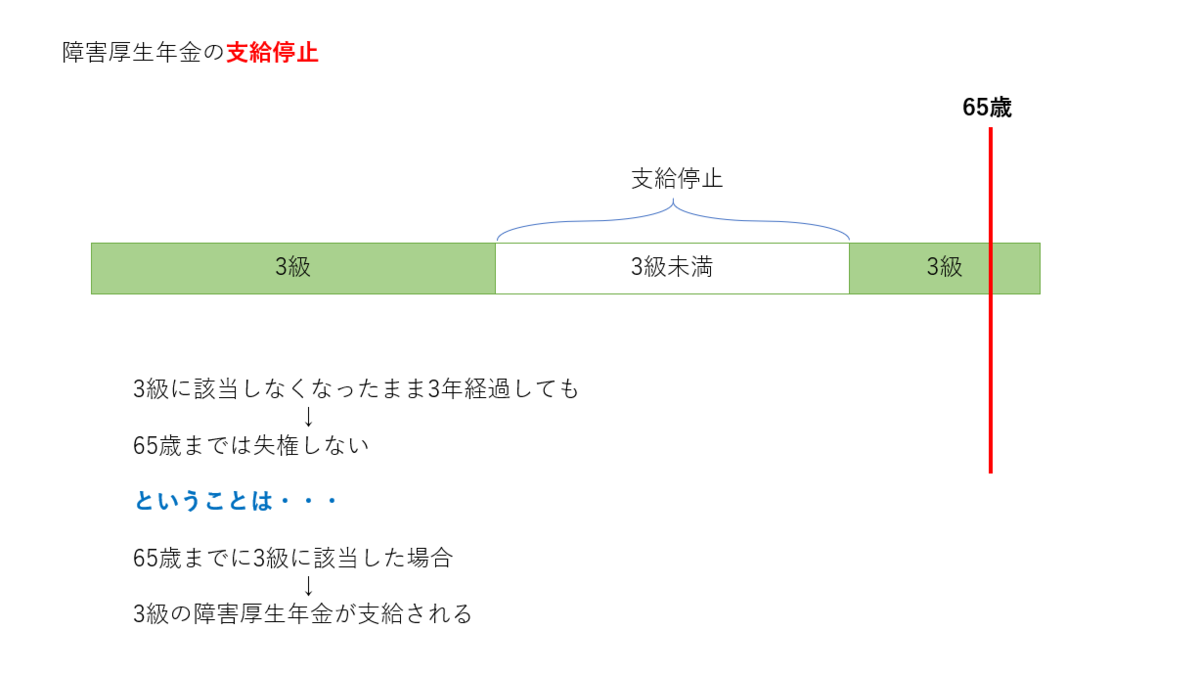
R2年問題から~厚生年金保険法
R3-040
R2.10.2 R2出題・遺族厚生年金をうけることができる遺族
<遺族厚生年金を受けることができる遺族>
→ 被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。
→ 妻以外の者は、次に掲げる要件に該当した場合に限る
・ 夫、父母又は祖父母 → 55歳以上
・ 子又は孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない
遺族厚生年金
<R2年問5B>
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。

【解答】 〇
遺族厚生年金には転給がないことがポイントです。(労災保険の遺族(補償)年金には転給があります。)
遺族厚生年金をうけることができる遺族は、上記のとおりです。
ただし、「父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」とされています。
①年金を受給できる順位が決まっていること、②先順位の人が受給権を得ると、後の人は遺族とならないことをおさえてください。
| 順位 | |
| 1 | 配偶者又は子 |
| 2 | 父母 (配偶者、子がいないとき) |
| 3 | 孫 (配偶者、子、父母がいないとき) |
| 4 | 祖父母 (配偶者、子、父母、孫がいないとき) |
問題文の場合、死亡の当時、のこされたのは10歳の子と父。
子の方が順位が上なので、遺族厚生年金を受けることができる遺族は「子」です。父は遺族になりません。
その後、子が18歳年度末で受給権を失った場合でも、父が遺族になることはありません。
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<H29年出題>
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

【解答】 〇
配偶者と子がいるので、母は遺族にはなりません。配偶者の受給権がなくなっても、母が遺族になることはありません。
遺族厚生年金の問題をもう一問どうぞ
R2問10オ
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。

【解答】 ×
遺族厚生年金の場合、夫は「55歳以上」であることが要件ですが、子の有無は要件になっていません。55歳以上の夫は、子がいなくても遺族厚生年金の受給権者になり得ます。
「夫」の遺族厚生年金についてもう一問どうぞ
<H27年出題>
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

【解答】 〇
例えば、妻の死亡時55歳の夫の場合
子が いない | 遺族厚生年金のみ | 60歳まで支給停止 |
子が いる | 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金の受給権を有する場合は、 60歳未満でも遺族厚生年金は支給停止されない |
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(厚生年金保険法)
R3-030
R2.9.22 過去の論点は繰り返す(R2・厚年「障害手当金・治っていなければ?」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
障害手当金「治っていなければ?」
問題<H27年出題>
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。

【解答】 〇
障害手当金は「傷病が治っていること」が要件です。
条文を確認してみると、
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
※初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていることが条件
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問10エ>
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。

【解答】 〇
| 障害厚生年金 | 障害認定日(※) | 1級、2級、3級 |
| 障害手当金 | 初診日から起算して5年を経過する日までの間に おけるその傷病の治った日 | 3級よりも軽い |
※障害認定日とは
・初診日から起算して1年6月を経過した日
又は
・初診日から1年6月以内にその傷病が治った日があるときは、その治った日
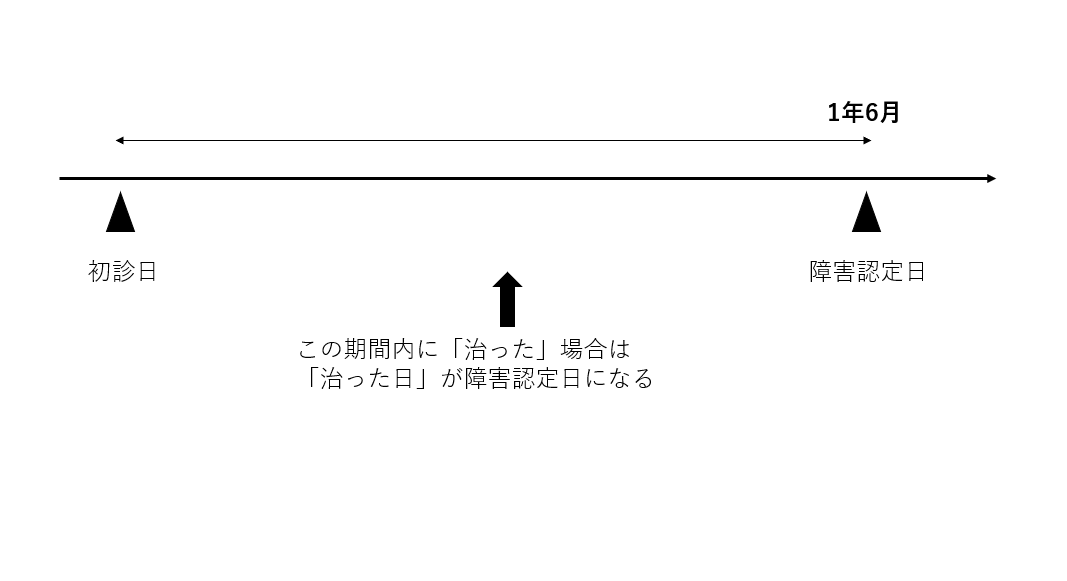
初診日から1年6月以内に傷病が治った場合は、その日が障害認定日になりますが、その傷病が治らなくても、初診日から1年6か月を経過した日に、障害等級に該当する程度の状態なら、障害厚生年金の支給要件を満たします。
障害厚生年金は治らなくても、支給要件は満たせます。
一方、障害手当金は「治った」ことが要件です。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(厚生年金保険法)
R3-021
R2.9.13 第52回試験・択一厚年の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 厚年 択一式
問題の文章は長いですが、テキストと過去問の論点をしっかり勉強していれば、解ける問題でした。
勉強の成果が出せる問題だと思いました。
 なるべく単純に覚える。
なるべく単純に覚える。
例えば、問2の問題。
・事業主の届出の提出期限は「5日以内」がほとんどです。
まずは基本的に事業主の届け出=「5日以内」を覚える。
そして、例えば「報酬月額変更の届出」のように「速やかに」届出るものは例外的に覚える。
「例外」を覚えて、それ以外は5日という覚え方が効率的です。
・船舶の届出の提出期限は「10日以内」がほとんどです。
私は、船は海の上なので距離がある。だから5日の2倍の10日と覚えています。
・被保険者の届出の提出期限は「10日以内」がほとんどです。
こちらも「速やかに」を例外的に覚える方法で大丈夫です。
 問題文は「ポイント」だけ読む
問題文は「ポイント」だけ読む
例えば、問4の問題
Aについて
障害厚生年金の「初診日」の要件は、「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」
↓
高齢任意加入被保険者も厚生年金保険の被保険者。
↓
高齢任意加入被保険者期間中に初診日がある場合は、初診日要件は満たしている
↓
保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金は支給される
Eも同じです。
障害厚生年金の要件は「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」
初診日に国民年金の第1号被保険者で、その後、厚生年金保険の被保険者になってから障害等級3級になったとしても
↓
障害厚生年金は受給できない。(初診日に厚生年金保険の被保険者でないので)
全体的に できるだけ単純に考える。ポイントをつかむ勉強を。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(厚生年金保険法)
R3-011
R2.9.3 第52回試験・選択(厚年)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 厚年 選択式
1 被保険者に対する情報の提供からの出題
「理解」を増進させるのはわかるけれど「誰の理解」を増進させるのか?が論点の問題です。
この条文は、後半の『「被保険者」に対し』と『「当該被保険者の保険料納付の実績・・・』の部分がクローズアップされることが多いので、今回の論点は意外な部分でした。
2 老齢厚生年金の繰下げについての出題
ヒントは次の2点です。
・繰下げの申出までは受給権を取得してから1年待たなければならない
・65歳以上の老齢厚生年金は、障害基礎年金と併給できる
3 離婚分割についての出題
基本的な個所からの出題。迷わずに。
ポイント! 勉強は繰り返し繰り返し。繰り返すことで見えてくる。
社労士受験のあれこれ
目的条文check 2 社保編
2 社保編
R2-261
R2.8.18 健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック
目的条文は要チェック!
本日は、「健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「健康保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(基本的理念)
第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< C >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< D >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< E >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

【解答】
A 業務災害
B 福祉の向上
C 高齢化
D 後期高齢者医療制度
E 常に
問2 「国民年金法」
(国民年金制度の目的)
第1条 国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(管掌)
第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、 < C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた< D >(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< E >が行うこととすることができる。

【解答】
A 日本国憲法第25条第2項
B 健全な国民生活
C 全国市町村職員共済組合連合会
D 日本私立学校振興・共済事業団
E 市町村長(特別区の区長を含む。)
問3 「厚生年金保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の< A >の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(管掌)
第2条 厚生年金保険は、< C >が、管掌する。

【解答】
A 生活
B 福祉の向上
C 政府
社労士受験のあれこれ
横断編(不服申立て)
R2-259
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「審査請求を棄却したものとみなすことができる」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
A 3か月
問2 「雇用保険法」
① 資格取得・喪失の確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して < B >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
B 3か月
問3 「健康保険法」
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
審査請求をした日から< C >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
C 2月
D 社会保険審査会
問4 「国民年金法」
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は< E >その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
審査請求をした日から< F >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
E 保険料
F 2月
問5 「厚生年金保険法」
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
② ①の審査請求をした日から< G >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< H >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
G 2月
H 社会保険審査会
| 棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
では、こちらをどうぞ!
①<国民年金 H30年出題>
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
②<厚生年金保険法 H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】
①<国民年金 H30年出題> 〇
「2か月」がポイントです!
②<厚生年金保険法 H29年出題> ×
・第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行います。
・脱退一時金については、「社会保険審査会」で〇です。
(国民年金も「脱退一時金」は、「社会保険審査会」に対して審査請求ができます。
社労士受験のあれこれ
横断編(公課の禁止)
R2-258
R2.8.15 横断編/課税されるもの、されないもの
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「課税されるもの、されないもの」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
<H24年出題>
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

【解答】 〇
労災保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」と規定されています。
※ 労災保険の保険給付には、「現金給付」と「現金給付」があるので「金品」
問2 「雇用保険法」
<H28年出題>
租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

【解答】 ×
雇用保険法では「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とされています。
常用就職支度手当は失業等給付の中に入っていますので、課税できません。
※雇用保険法には現物給付がないので「金銭」となっています。
なお、雇用保険二事業の助成金等は失業等給付ではありませんので、公課を課することができます。
問3 「健康保険法」
<H18年出題>
出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

【解答】 〇
健康保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされています。
保険給付(もちろん出産手当金出産育児一時金も含まれます。)は、課税されません。
問4 「国民年金法」
<H25年出題>
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

【解答】 〇
国民年金法のルールは、以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、公課を課することができる。
問5 「厚生年金保険法」
障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。

【解答】 〇
厚生年金保険法のルールは以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、公課を課することができる。
※ 「老齢厚生年金」は課税されますが、障害厚生年金は課税されません。
社労士受験のあれこれ
横断編(療養に関する指示に従わないとき)
R2-257
R2.8.14 横断編/療養に関する指示に従わないときの制限
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「療養に関する指示に従わないときの制限」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が故意の犯罪行為若しくは< A >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの< B >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の< C >。

【解答】
A 重大な過失
B 原因
C 全部又は一部を行わないことができる
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< D >。

【解答】
D 一部を行わないことができる
 「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその< F >となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< G >。
自己の故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその< F >となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

【解答】
E 重大な過失
F 原因
G 全部又は一部を行わないことができる
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは< H >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの< I >となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の< J >。
障害厚生年金の受給権者が、< K >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
H 重大な過失
I 原因
J 全部又は一部を行わないことができる
K 故意
こちらもどうぞ!
 問1労災保険法
問1労災保険法
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
 問2 健康保険法
問2 健康保険法
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
 問3 国民年金法(R元年出題)
問3 国民年金法(R元年出題)
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題)
問4 厚生年金保険法(R元年出題)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
 問1労災保険法 ×
問1労災保険法 ×
キーワードは、「故意に」「直接の原因」。
全部又は一部を行わないことができるではなく、「保険給付を行わない」です。
 問2 健康保険法 ×
問2 健康保険法 ×
キーワードは、「闘争、泥酔又は著しい不行跡」。
行わないではなく、「全部又は一部を行わないことができる」です。
 問3 国民年金法(R元年出題) 〇
問3 国民年金法(R元年出題) 〇
キーワードは、「故意に」。
故意に死亡させた者には支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
故意に障害 → 障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
重大な過失 → 保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士受験のあれこれ
横断編(支給制限~全部制限)
R2-256
R2.8.13 横断編/支給制限「行わない」のはどんなとき?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「支給制限「行わない」のはどんなとき?」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】
A 故意に
B 直接の原因
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< C >により、又は< D >給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

【解答】
C 自己の故意の犯罪行為
D 故意に
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
< E >障害又はその< F >となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < E >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によっ遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を< E >死亡させた者についても、同様とする。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< E >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
E 故意に
F 直接の原因
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< G >、障害又はその< H >となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< G >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< G >死亡させた者についても、同様とする。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< G >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
G 故意に
H 直接の原因
社労士受験のあれこれ
横断編(受給権の保護)
R2-255
R2.8.12 横断編/受給権の保護
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「受給権の保護」です。
では、どうぞ!
「労災保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外あり)
年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・国年、厚年も同様)
「雇用保険法」
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外なし)
「健康保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外なし)
「国民年金法」
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、厚年も同様)
・ 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢基礎年金、付加年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
「厚生年金保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、国年も同様)
・ 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢厚生年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
 では、問題をどうぞ!
では、問題をどうぞ!
 労災保険法<H24年出題>
労災保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
 雇用保険法<H23年出題>
雇用保険法<H23年出題>
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
 健康保険法<H24年出題>
健康保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。
 国民年金法<H28年出題>
国民年金法<H28年出題>
給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H26年出題>
厚生年金保険法<H26年出題>
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、< A >に行わせるものとされている。

【解答】
 労災保険法<H24年出題> 〇
労災保険法<H24年出題> 〇
 雇用保険法<H23年出題> 〇
雇用保険法<H23年出題> 〇
 健康保険法<H24年出題> ×
健康保険法<H24年出題> ×
保険給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押さえ、すべてできません。
 国民年金法<H28年出題> 〇
国民年金法<H28年出題> 〇
脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
※厚生年金保険でも、脱退一時金は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
 厚生年金保険法<H26年出題> ×
厚生年金保険法<H26年出題> ×
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押えの対象にはなりません。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
A 独立行政法人福祉医療機構
社労士受験のあれこれ
横断編(60・65・70・75歳)その1
R2-253
R2.8.10 横断編/年齢再確認!60・65・70・75歳その1
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「年齢再確認!60・65・70・75歳 その1」です。
では、どうぞ!
 国民年金法
国民年金法
空欄を埋めてください。
<任意加入被保険者>
次の1から3のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
2 日本国内に住所を有する< A >の者
3 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >のもの
<特例による任意加入被保険者>
昭和< C >年4月1日以前に生まれた者であって、次の1,2のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
ただし、その者が国民年金法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
1 日本国内に住所を有する< D >の者
2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< D >のもの

【解答】

A 60歳以上65歳未満
B 20歳以上65歳
C 40
D 65歳以上70歳未満
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 昭和40年4月1日以前に生まれた者
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
空欄を埋めてください。
<任意単独被保険者>
適用事業所以外の事業所に使用される< E >の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< F >を得なければならない。
<高齢任意加入被保険者>
適用事業所に使用される< G >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に< H >て、被保険者となることができる。
適用事業所以外の事業所に使用される< I >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、< J >を受けて、被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< K >を得なければならない。

【解答】
E 70歳未満
F 事業主の同意
G 70歳以上
H 申し出
I 70歳以上
J 厚生労働大臣の認可
K 事業主の同意
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 国民年金の「特例による任意加入被保険者」と違い、生年月日の要件がない
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと
・ 「適用事業所」と「適用事業所以外」で要件が違うので、注意。
こちらもどうぞ!
<国民年金 H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】 〇
原則 → 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者
ただし、厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合は、第2号被保険者にはならない。
問題文の場合、「在職老齢年金を受給する」「65歳以上70歳未満の被保険者」ということで、「老齢年金の受給権がある+65歳以上」ですので、厚生年金保険の被保険者なのですが、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
一方、第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが条件です。
問題文の場合は、第2号被保険者の配偶者に当たりませんので、第3号被保険者にはなりません。
なお、厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」は、「国民年金の第2号被保険者」です。なぜなら、「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない」からです。
社労士受験のあれこれ
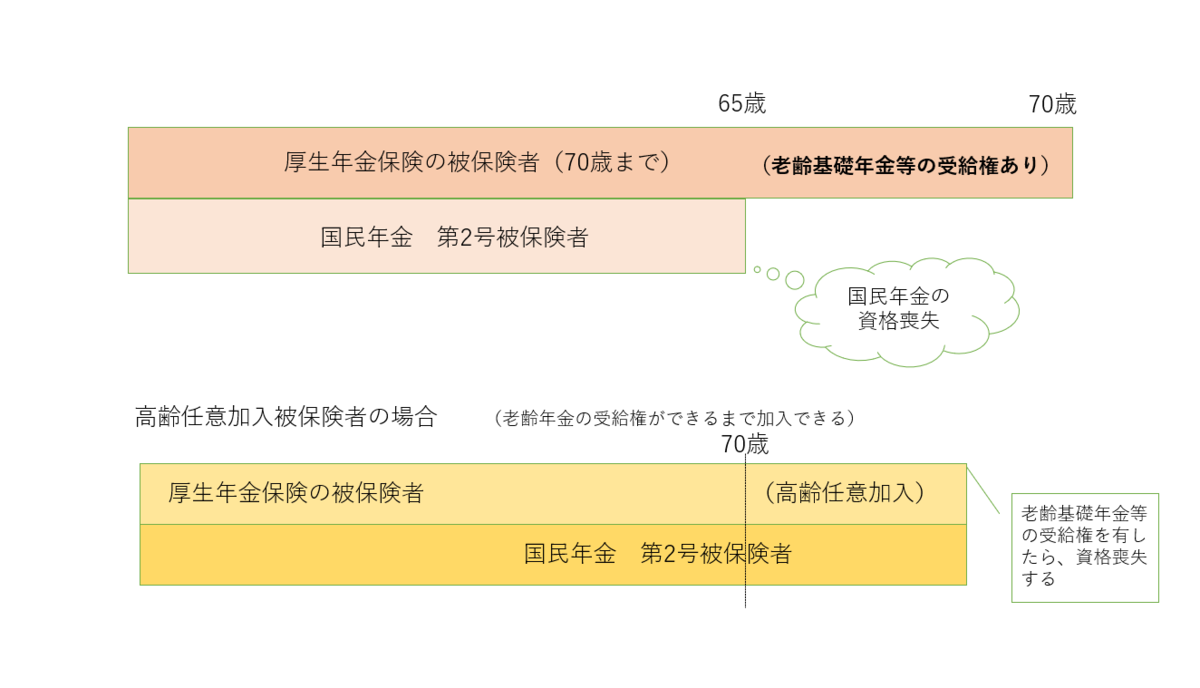
横断編(標準賞与額・健保と厚年)
R2-252
R2.8.9 横断編/健保と厚年~標準賞与額どう違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「健保と厚年~標準賞与額どう違う?」です。
では、どうぞ!
まずは「健康保険法」から
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】

A 1,000
B 573万
 健康保険<H27年出題>
健康保険<H27年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。

【解答】 ×
・ 標準賞与額の累計額は、「年度」で573万円が限度。
(3月までと4月以降では年度が違う。3月分の賞与は4月以降分と累計しない。)
・ 標準賞与額の累計は「保険者」単位で行う。
(A社(協会けんぽ)、B社(健保組合)の賞与は累計しない。)
この問題の場合は、12月の標準賞与額は「100万円」となります。
次は、厚生年金保険です!
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< C >円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
この場合において、当該標準賞与額が< D >円を超えるときは、これを < D >円とする。

【解答】

C 1,000
D 150万
厚生年金保険の標準所与額は、月150万円が上限です。
社労士受験のあれこれ
横断編(標準報酬月額・健保厚年を比較)
R2-251
R2.8.8 横断編/標準報酬月額・健保と厚年の違いは??
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「標準報酬月額・健保と厚年の違いは??」です。
では、どうぞ!
まずは「健康保険法」から
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
健康保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、
最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 58,000
B 50
C 1,390,000
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
毎年< D >における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が< E >を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< F >から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の< D >において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が< G >を下回ってはならない。

【解答】
D 3月31日
E 100分の1.5
F 9月1日
G 100分の0.5
次は、厚生年金保険です!
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
厚生年金保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、
最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 88,000
B 31
C 620,000
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
毎年< D >における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の < E >に相当する額が標準報酬月額等級の< F >の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< G >から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該< F >の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】

D 3月31日
E 100分の200
F 最高等級
G 9月1日
社労士受験のあれこれ
横断編(未支給の保険給付・給付)
R2-249
R2.8.6 横断編/未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?」です。
では、どうぞ!
問 題
 雇用保険<H29年出題>
雇用保険<H29年出題>
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。

【解答】
 〇
〇
ポイント!
★未支給の失業等給付を受けることができる範囲と順序を覚えましょう。
・死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」(順序もこのとおり)
★「失業」の認定を受けなければならない
受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当の支給を請求する者 → 当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
★請求期間がある
未支給給付請求者は、死亡した受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、請求しなければならない。
次は労災、どうぞ!
 労災保険<H22年出題>
労災保険<H22年出題>
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

【解答】
 C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
ポイント!
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順序を覚えましょう。
労災保険からもう一問!
 労災保険法<H30年出題>
労災保険法<H30年出題>
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
未支給の遺族(補償)年金の支給を請求できるのは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」です。
では、国民年金法です!
 国民年金法<R元年出題>
国民年金法<R元年出題>
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。

【解答】 〇
ポイント!
国民年金の未支給年金を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
最後は厚生年金保険です!
 厚生年金保険<H30年出題>
厚生年金保険<H30年出題>
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
厚生年金保険の未支給の保険給付を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
→ 国民年金と同じです。
なお、国民年金の未支給の対象は「年金給付」、厚生年金保険は「保険給付」です。
社労士受験のあれこれ
横断編(障害等級・労災、国年、厚年)
R2-248
R2.8.5 横断編/それぞれの障害等級~労災、国年、厚年
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「障害等級・労災、国年、厚年」です。
では、どうぞ!
問 題
 傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
 ×
×
「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。
ポイント!
ちなみに、傷病補償年金の支給要件として、「当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」があります。
厚生労働省令で定める傷病等級は「第1級~第3級」です。
第1級 → 常時介護を要する状態
第2級 → 随時介護を要する状態
第3級 → 常態として労働不能
★ 傷病等級は、「治っていない傷病」です。
次どうぞ!
 障害(補償)給付
障害(補償)給付
空欄に埋めてください。
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は < A >とする。

【解答】
 A 障害補償一時金
A 障害補償一時金
ポイント!
障害等級第1級~第7級 → 障害補償年金
障害等級第8級~第14級 → 障害補償一時金
★ 障害等級は、「負傷し又は疾病にかかり治った」ときです。
 傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
第1級 → 給付基礎日額の313日分
第2級 → 給付基礎日額の277日分
第3級 → 給付基礎日額の245日分
 障害基礎年金(国民年金法)
障害基礎年金(国民年金法)
空欄を埋めてください。
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の①、②のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して< B >を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、< C >であること。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから< D >とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
B 1年6月
C 60歳以上65歳未満
D 1級及び2級
ポイント!
障害基礎年金の障害等級は、重いほうから1級、2級
1級の年金額は、2級の年金額×100分の125
 障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金・障害手当金
(障害手当金の受給権者)
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して< E >を経過する日までの間におけるその< F >日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

【解答】
E 5年
F 傷病の治った(障害手当金は「治っている」ことが要件です。)
ポイント!
厚生年金には、「障害厚生年金」と「障害手当金」があります。
障害厚生年金 → 障害等級1級~3級
障害手当金 → 3級よりも軽い状態
社労士受験のあれこれ
横断編(遺族の範囲その3「厚年」)
R2-247
R2.8.4 横断編/「厚生年金」遺族の範囲は国年とどう違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「遺族の範囲その3「厚年」」です。
国民年金法の遺族基礎年金は、子のための年金で、受給できるのは、父子、母子、子に限定されています。
一方、厚生年金保険の遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母と受給できる範囲が広くなります。
「妻」に対する加算(中高齢寡婦加算など)が行われるのも特徴です。
では、どうぞ!
問 題
 遺族厚生年金<R元年出題>
遺族厚生年金<R元年出題>
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

【解答】
 ×
×
夫も子も遺族の範囲に入りません。
遺族厚生年金を受けることができる遺族のポイント!
・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は入りません)
・妻 → 年齢・障害要件なし
・夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(60歳までは原則支給停止(若年停止)
・子、孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない
次どうぞ!
 遺族厚生年金<H23年出題>
遺族厚生年金<H23年出題>
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

【解答】
 ×
×
遺族の中で、支給順位が決まっています。妻が受給権を取得した場合は、母は受給権は取得できず、転給の制度もありません。
支給順位のポイント!
① 配偶者、子
② 父母
③ 孫
④ 祖父母
例えば、①の配偶者、子がいれば、②以下は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。
社労士受験のあれこれ
横断編(健保・厚年の「船員」)
R2-244
R2.8.1 横断編/健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ」です。
では、どうぞ!
問 題
 <健康保険法>
<健康保険法>
船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、日雇特例被保険者となる場合を除き、健康保険の被保険者となることができない。
 <厚生年金保険法>
<厚生年金保険法>
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

【解答】
 <健康保険法> 〇
<健康保険法> 〇
船員保険の被保険者は、健康保険の被保険者にはなりません。なぜなら、職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産については「船員保険」から保険給付が受けられるからです。
なお、船員保険の疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者となることができるので注意してください。
 <厚生年金保険法> 〇
<厚生年金保険法> 〇
船員は厚生年金保険の被保険者となります。
<参考>船員保険について
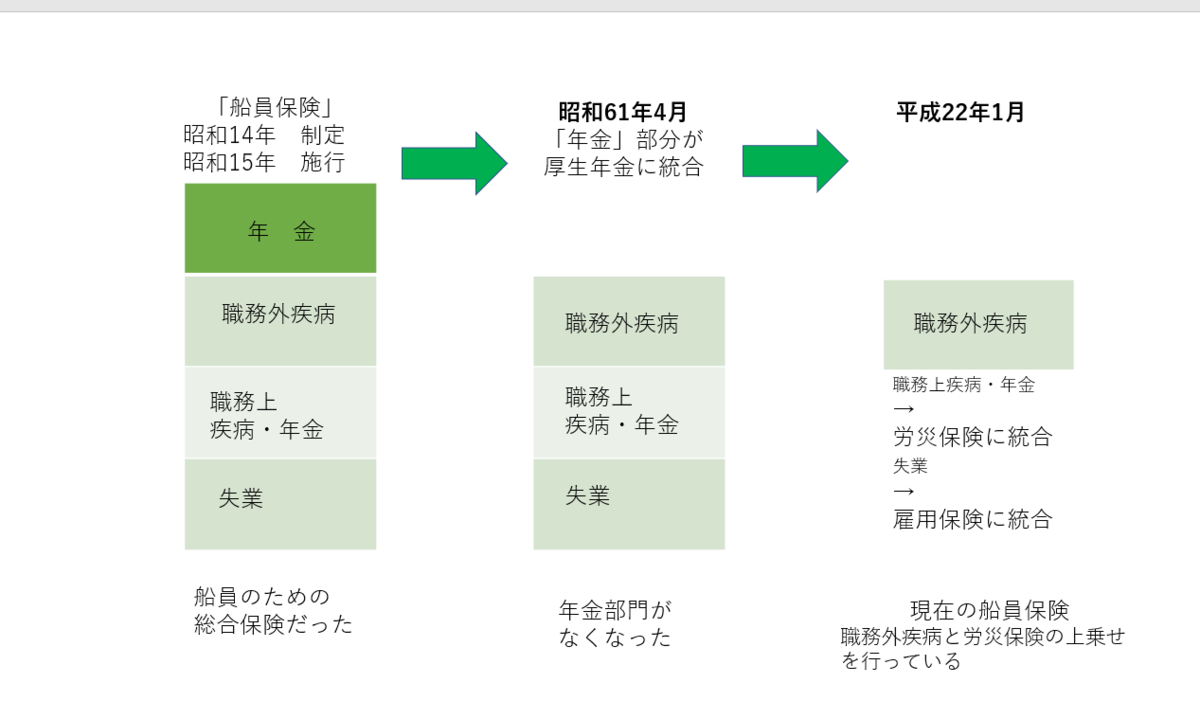
こちらもどうぞ!
①<厚生年金保険法・H30年出題>
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。
②<厚生年金保険法・H25年出題>
船舶使用者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
①<厚生年金保険法・H30年出題> ×
「当該期間を超えて使用されないとき」でも、厚生年金保険の被保険者となる。
・通常
2月以内の期間を定めて使用される者 → 厚生年金保険の被保険者にならない
※ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となる
・船員
「2月以内の期間」の定めであっても、当初から被保険者となる。(所定の期間を超えなくてもOK)
②<厚生年金保険法・H25年出題> ×
船員の場合は、継続して4か月を超えない季節的業務に使用されても、厚生年金保険の被保険者となります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-239
R2.7.27 選択式の練習/実施機関のことなど
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「実施機関のことなど」です。
では、どうぞ!
問 題
 厚生年金保険は、< A >が、管掌する。
厚生年金保険は、< A >が、管掌する。
 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。
【選択肢】
① 厚生労働大臣 ② 実施機関 ③ 政府 ④ 実施機関等

【解答】
 A ③ 政府
A ③ 政府
 B ② 実施機関
B ② 実施機関
ちなみに、
実施機関は、
被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、当該保険給付の受給権者、基礎年金拠出金の負担(納付)、拠出金の納付(第2号、第3号、第4号厚生年金金被保険者)、保険料その他この法律の規定による徴収金並びに保険料に係る運用に関する事務を行います。
実施機関は、被保険者の種別に応じて定められています。
↓
<実施機関>
第1号厚生年金被保険者 → 厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済第組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団
こちらもどうぞ!
問題
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る< C >における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
【選択肢】
① 障害認定日 ② 初診日 ③ 初診日の前日

【解答】
C ② 初診日
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】 ×
※ 障害認定日に2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金の額
(公務員と民間企業勤務経験があるような場合)
↓
2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」が計算の基礎となるのではありません。
また、障害厚生年金の裁定・支給事務は、初診日に加入していた実施機関が、他の実施機関の加入期間分も含めて行います。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-229
R2.7.17 選択式の練習/遺族厚生年金の支給停止
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「遺族厚生年金の支給停止」です。
では、どうぞ!
問 題
(遺族厚生年金の支給停止)
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について < A >の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から< B >年間、その支給を停止する。
< C >に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、< D >に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、< D >が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
【選択肢】
① 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金
② 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付
③ 労働基準法の規定による遺族補償
④ 5 ⑤ 6 ⑥ 10
⑦ 配偶者、父母又は祖父母 ⑧ 夫、父母又は祖父母
⑨ 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹
⑩ 妻 ⑪ 配偶者 ⑫ 夫

【解答】
A ③ 労働基準法の規定による遺族補償
B ⑤ 6
 労働者が業務上死亡した場合は、使用者は労働基準法の規定により遺族補償を行います。労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡の日から6年間、遺族厚生年金は支給停止となります。
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は労働基準法の規定により遺族補償を行います。労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡の日から6年間、遺族厚生年金は支給停止となります。
 しかし、実際、業務上死亡した場合は、労災保険法から遺族補償年金が支給されます。(通勤災害の場合は遺族年金が支給されます)
しかし、実際、業務上死亡した場合は、労災保険法から遺族補償年金が支給されます。(通勤災害の場合は遺族年金が支給されます)
同一人の死亡に対し、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)と遺族厚生年金が支給される場合は、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)が減額され、遺族厚生年金は調整されず全額支給されます。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、厚生年金保険の保険料は労使折半です。本人も保険料を負担している厚生年金は減額せず、本人負担のない労災保険の方を減額して調整しています。
C ⑧ 夫、父母又は祖父母
D ⑫ 夫
 被保険者の死亡の当時55歳以上の夫、父母又は祖父母については遺族厚生年金の遺族の範囲に入ります。しかし、受給権があったとしても60歳までは遺族厚生年金は支給停止されます。
被保険者の死亡の当時55歳以上の夫、父母又は祖父母については遺族厚生年金の遺族の範囲に入ります。しかし、受給権があったとしても60歳までは遺族厚生年金は支給停止されます。
ただし、夫については、夫が遺族基礎年金の受給中の場合は、60歳未満でも合わせて遺族厚生年金が支給されます。
こちらもどうぞ!
<H29年出題>
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。
なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】〇
妻の死亡当時、夫55歳以上で子がいる場合、夫に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生します。
その場合、夫が60歳未満でも、遺族厚生年金は支給停止にならず、遺族基礎年金受給中は、遺族厚生年金も支給されます。
問題文の場合、夫が60歳になる前に、子が18歳の年度末を迎えるので、その時点で遺族基礎年金は失権します。
遺族基礎年金が失権してから60歳になるまでは、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。
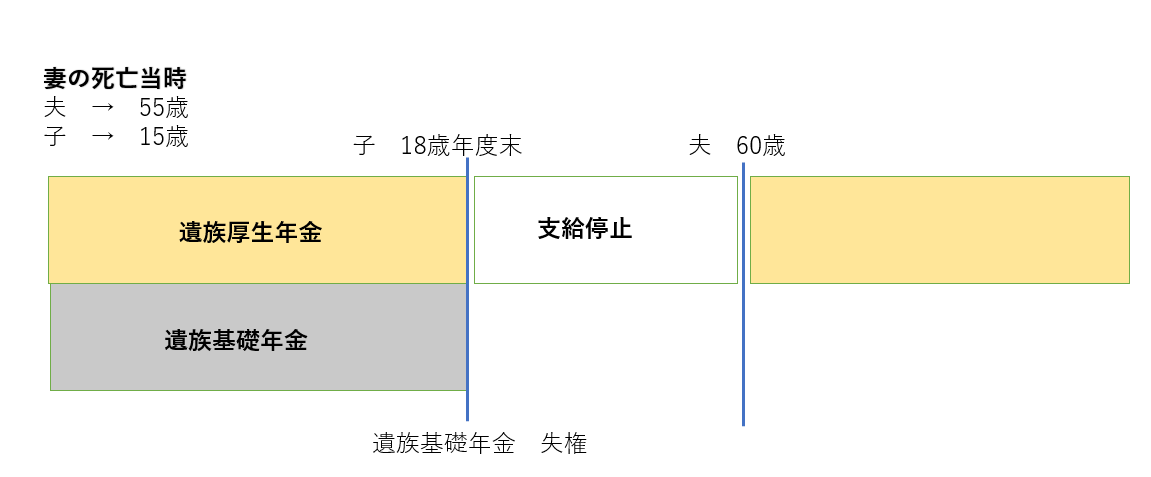
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-219
R2.7.7 選択式の練習/65歳未満の在職老齢年金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「65歳未満の在職老齢年金」です。
「在職老齢年金」の問題は、65歳以上か65歳未満か、まずは年齢を確認してくださいね。
ではどうぞ!
問 題
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が200,000円であり、その者の総報酬月額相当額が300,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は< A >円となる。
なお、加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、基本月額は加給年金額を< B >ものである。
【選択肢】
① 110,000 ② 90,000 ③ 15,000
④ 含めた ⑤ 除いた

【解答】
A ① 110,000
<1月当たりの支給停止額の計算>
(30万円+20万円-28万円)×2分の1
B ⑤ 除いた
基本月額=老齢厚生年金の額÷12
(老齢厚生年金の額から加給年金額は除く。)
こちらもどうぞ!
<H27年アレンジ>
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は< C >円(加給年金額を除く。)となる。
【選択肢】
① 105,000 ② 95,000 ③ 10,000 ④ 190,000

【解答】
C ② 95,000
計算の手順
1.まず、総報酬月額相当額を計算する
240,000円 + (600,000円÷12) = 290,000円
2.基本月額+総報酬月額相当額を計算する
200,000円 + 290,000円 = 490,000円
280,000円を超えているので、在老の仕組みで支給停止される。
3.1月当たりの支給停止額を計算する
基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下の計算式を使う
(200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円
4.支給停止後の年金月額を計算する
200,000円-105,000円=95,000円
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-209
R2.6.27 選択式の練習/厚生年金の費用はどのように負担する?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「厚生年金の費用はどのように負担する?」です。
★ 厚生年金保険は、「国庫負担」(税金)と保険料で賄われています。
国庫は、どの部分にどの程度、負担しているのか?等が今日のテーマです。
ではどうぞ!
まずは国庫負担からどうぞ!
(国庫負担等)
国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する< A >に相当する額を負担する。
【選択肢】
① 基礎年金拠出金の額の2分の1 ② 保険給付に要する額の2分の1 ③ 年金たる保険給付に要する額の2分の1

【解答】
A ① 基礎年金拠出金の額の2分の1
国民年金の基礎年金は、第1号被保険者のみならず、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)も対象です。
第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金に充てる費用のため、厚生年金保険から国民年金に対して「基礎年金拠出金」を拠出していますが、その基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額は国庫が負担します。
では、こちらもどうぞ!
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の< B >(基礎年金拠出金の負担に関する< B >を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
実施機関(厚生労働大臣を除く。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の< B >の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
① 業務 ② 事務 ③ 事業

【解答】
B ② 事務
次は保険料です!
(保険料)
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(< C >を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
【選択肢】
① 事務費 ② 第3号被保険者に係る費用 ③ 基礎年金拠出金

【解答】
C ③ 基礎年金拠出金
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H15年出題>
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

【解答】 〇
保険料は「月単位」で徴収されます。
例えば、
・6月30日に資格取得した → たとえ1日でも6月分の保険料は徴収される
・6月29日退職、6月30日資格喪失した → 資格喪失月の6月分の保険料は徴収されない
・6月30日退職、7月1日資格喪失した → 月末まで被保険者だった6月分の保険料は徴収される
 最後についでにもう一問!
最後についでにもう一問!
<H28年出題>
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者の資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】 〇
★「同月得喪」をおさえましょう。
「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する」のが原則です。
例えば、令和2年6月1日に資格取得し、同月20日退職、21日資格喪失の場合は、6月は1か月の被保険者期間としてカウントされます。
 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない、という例外規定があります。
ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない、という例外規定があります。
先ほどの続きで、6月21日に国民年金の第1号被保険者又は第3号被保険者となったときは、6月は国民年金の1号又は3号であった月となり、厚生年金保険の被保険者期間にはカウントされません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-199
R2.6.17 選択式の練習/遺族厚生年金の受給権の消滅(30歳未満の妻)
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「遺族厚生年金の受給権の消滅(30歳未満の妻)」です。
ではどうぞ!
問題
 遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時< A >未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、< B >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時< A >未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、< B >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
 遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が< A >に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、< C >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が< A >に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、< C >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
【選択肢】
① 40歳 ② 60歳 ③ 30歳
④ 30歳に達した日 ⑤ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
⑥ 夫の死亡した日の翌日
⑦ 子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
⑧ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
⑨ 当該遺族基礎年金の受給権を取得した日

【解答】
A ③ 30歳
B ⑤ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
C ⑧ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
 について
について
夫の死亡当時30歳未満の妻
子なし(遺族基礎年金の受給権なし)
↓
遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年で遺族厚生年金の受給権は消滅
(夫の死亡時30歳未満の妻で子がいない場合、遺族厚生年金は5年で失権)
 について
について
夫の死亡当時、30歳未満の妻
子あり(遺族基礎年金の受給権あり)
↓
妻が30歳になる前に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した
↓
遺族基礎年金の受給権が消滅した日か5年で遺族厚生年金の受給権は消滅
(妻が30歳未満で遺族基礎年金が失権した場合は、遺族基礎年金の失権から5年で遺族厚生年金は失権)
こちらもどうぞ!
H29年出題
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】 ×
遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年」です。
 に当てはまるパターンです。
に当てはまるパターンです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-189
R2.6.7 選択式の練習/厚年・財政の現況及び見通しの作成
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「財政の現況及び見通しの作成」です。
 平成16年の年金改正で、「保険料水準固定方式」が導入されました。
平成16年の年金改正で、「保険料水準固定方式」が導入されました。
この方式のポイントは、
・ 最終的な保険料(保険料率)の水準を法律で定める
・ 給付はその負担の範囲内で行う
ことです。
そのため、給付水準は、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて、毎年度自動的に調整されています。
また、定期的にその時点の長期的な財政調整の見通しを作成し、給付水準の調整の必要の有無などを検証すること(財政検証)も平成16年の改正で導入された制度です。
ではどうぞ!
問題
(財政の現況及び見通しの作成)
政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び< A >の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね< B >とする。
政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、< C >、これを公表しなければならない。
(調整期間)
政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、< D >の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
(調整期間の開始年度)
調整期間の開始年度は、< D >とする。
【選択肢】
① 国庫補助 ② 積立金 ③ 国庫負担
④ 10年間 ⑤ 100年間 ⑥ 25年間
⑦ 遅滞なく ⑧ 10日以内に ⑨ 年度末までに
⑩ 保険料 ⑪ 保険給付 ⑫ 基礎年金拠出金
⑬ 平成16年度 ⑭ 平成17年度 ⑮ 平成18年度

【解答】
A ③ 国庫負担
B ⑤ 100年間
C ⑦ 遅滞なく
D ⑪ 保険給付
E ⑭ 平成17年度
こちらの問題もどうぞ!
この法律による< F >の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
【選択肢】
① 保険料 ② 年金たる保険給付 ③ 国庫負担

【解答】
F ② 年金たる保険給付
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-179
R2.5.28 選択式の練習/配偶者加給年金額の特別加算
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「配偶者加給年金額の特別加算」です。
一定の要件を満たした場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
加給年金額の対象になるのは、生計維持関係のある65歳未満の配偶者又は子ですが、配偶者加給年金額には、特別加算がプラスされることもあります。
「特別加算」がプラスされる要件は?
ではどうぞ!
問題1
< A >年4月2日以後に生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が加算される。
【選択肢】
① 大正15 ② 昭和9 ③ 昭和4

【解答】② 昭和9
配偶者加給年金額に特別加算が行われるのは、生年月日が昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者です。
問題2
< B >に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、165,800円に改定率を乗じて得た額である。
【選択肢】
① 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間
② 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間
③ 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間
④ 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間
⑤ 昭和18年4月2日以後

【解答】
B ⑤ 昭和18年4月2日以後
ポイント!
昭和18年4月2日以後生まれの老齢厚生年金の受給権者の配偶者加給年金額の特別加算は、生年月日に関係なく一律165,800円×改定率です。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれの受給権者の特別加算の額は、33,200円×改定率で、段階的に多くなります。昭和18年4月2日以後生まれからの額が一番多いのがポイントです。
こちらもどうぞ
<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】 ×
特別加算は、配偶者の生年月日ではなく、受給権者の生年月日に応じて加算されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-169
R2.5.18 選択式の練習/障害厚生年金の最低保障額
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害厚生年金の最低保障額」です。
障害厚生年金の額は、
平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 被保険者期間の月数
で計算します。
 被保険者期間の月数が300に満たないとき → 300で計算する
被保険者期間の月数が300に満たないとき → 300で計算する
 障害等級1級の障害厚生年金の額 → 100分の125に相当する額となる
障害等級1級の障害厚生年金の額 → 100分の125に相当する額となる
 障害等級1級又は2級 → 受給権者により生計を維持している65未満の配偶者がある → 加給年金額が加算される
障害等級1級又は2級 → 受給権者により生計を維持している65未満の配偶者がある → 加給年金額が加算される
 今日のテーマ
今日のテーマ
障害厚生年金に最低保障額が適用されるのはどんなときでしょう?
ではどうぞ!
問 題
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に< A >を乗じて得た額(その額に< B >ものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【選択肢】
① 2分の1 ② 3分の2 ③ 4分の3
④ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
⑤ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる
⑥ 5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる

【解答】
障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額についての問題です。
A ③ 4分の3
B④ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
ポイント
障害基礎年金を受けることができない場合は、障害厚生年金の額に最低保障額が適用されます。
→ → 障害基礎年金を受けることができない場合は次の2つです。
・ 障害等級3級の場合
・ 初診日に「厚生年金保険の被保険者だけど、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がある」場合、障害厚生年金は受給できます。しかし、初診日に国民年金の第2号被保険者ではないので、障害等級1級・2級でも障害基礎年金は受給できません。
こちらの問題もどうぞ!
 令和2年度障害厚生年金の最低保障額は?
令和2年度障害厚生年金の最低保障額は?
計算式
↓
< C >円 × 4分の3 = < D >円
【選択肢】
① 780,900 ② 977,125 ③ 781,700
④ 585,700 ⑤ 732,800 ⑥ 586,300

【解答】
C ③ 781,700
D ⑥ 586,300
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-159
R2.5.8 選択式の練習/老厚・報酬比例部分の計算ルール
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「老齢厚生年金の報酬比例部分」のルールです。
ではどうぞ!
問 題
老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式
被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の< A >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
【選択肢】
①5.125 ②5.481 ③7.125 ④7.5

【解答】
A ②5.481
※給付乗率の1000分の5.481は、昭和21年4月1日以前生まれの者は、生年月日に応じた読み替えがあります。(生年月日が古い方が乗率が高く設定されています。)
こちらの問題もどうぞ
報酬比例部分の「平均標準報酬額」とは?
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、< B >を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
【選択肢】
①改定率 ②再評価率 ③調整率 ④マクロ経済スライド率

【解答】 ②再評価率
平均標準報酬額とは、簡単に言うと、新入社員時代から退職までの在職中の標準報酬月額と標準賞与額を全部合算して、厚年に加入した月数で割った額のことです。
しかし、例えば同じ10,000円でも、40年前の新入社員時代と現在では価値がちがいます。過去の賃金を現在の水準に読み替えるために使う率のことを「再評価率」といいます。
再評価率は、性年度別に設定されていて、毎年度自動的に改定されます。
もう一問どうぞ!
再評価率の改定の仕組み(H18年出題)
※調整期間以外の期間
■新規裁定者(< C >歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、原則として< D >を基準とした再評価率を用い、既裁定者(< C >歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として前年の< E >を基準とした再評価率を用いる。
【選択肢】
①消費者物価指数 ②名目手取り賃金変動率 ③実質賃金変動率
④名目賃金変動率 ⑤物価変動率 ⑥65 ⑦68 ⑧70

【解答】
C ⑦68 D ②名目手取り賃金変動率 E ⑤物価変動率
参 考
国民年金の基礎年金は、毎年度「改定率」を改定することによって、年金額を見直しますが、国民年金の「改定率」と厚生年金保険の「再評価率」の改定の仕組みは同じです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-149
R2.4.28 選択式の練習/在職老齢年金の計算
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、問題です。
※平成27年択一式を選択式にアレンジしています。
問 題
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は< A >円(加給年金額を除く。)となる。
<選択肢>
①105,000 ②10,000 ③190,000 ④95,000

【解答】 ④95,000
「特別支給の老齢厚生年金」ですので、60歳代前半の在老の計算式を使います。
問題文の条件だと、
・基本月額+総報酬月額相当額>28万円で、
基本月額≦28万円、総報酬月額相当額≦47万円です。
支給停止基準額の計算式は
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1となります。
実際に数字を当てはめましょう。
総報酬月額相当額は24万円+(60万円÷12)=29万円です。
支給停止月額は、
(29万円+20万円-28万円)×2分の1=105,000円となります。
支給停止後の年金月額は、200,000円-105,000円=95,000円となります。
※支給停止される額と、支給される額を間違えないようにしましょう。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H24年出題>
60歳代前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。

【解答】 ×
基本月額は老齢厚生年金の額÷12で計算しますが、その際加給年金額は除いて計算します。
在老の仕組みで老齢厚生年金が一部カットされても、加給年金額はそのまま加算されます。(老齢厚生年金が全額支給停止の場合は、加給年金額も全額支給停止になります。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-139
R2.4.18 遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の「死亡した者」の要件は次の4つです。
 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

 、
、 の場合は、保険料納付要件を満たす必要があります。
の場合は、保険料納付要件を満たす必要があります。
 (H28年出題)当時の問題文を改正に合わせて改定しています。
(H28年出題)当時の問題文を改正に合わせて改定しています。
次の記述のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるものはいくつあるか。
ア 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。
イ 保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。
ウ 国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算してが25年以上あるものとする)。
エ 保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
オ 63歳の厚生年金保険の被保険者が令和2年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満であるが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。

【解答】 5つとも○
 アについて
アについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
厚生年金保険の被保険者だったら、年齢は関係ありません。
 イについて
イについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
「被保険者の死亡」には「失踪の宣告を受けた者であって、行方不明となった当時被保険者であったもの」も含みます。
なお、失踪宣告を受けた場合、保険料納付要件、生計維持関係、被保険者資格は、行方不明になった日を死亡日として取り扱うことになっています。
問題文の場合、行方不明になった時点で「保険料納付要件を満たしている被保険者」ですので、要件を満たしています。
 ウについて
ウについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
厚生年金保険の被保険者になったことがなくても、離婚時みなし被保険者期間のみで老齢厚生年金の受給権を得ることがあります。
そのような人が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金が支給されることがあります。
 エについて
エについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
初診日から起算して5年を経過する日前に死亡がポイントです。
「資格喪失日から5年」に間違えないようにしてくださいね。
 オについて
オについて
問題文の注目ポイントは
・ 63歳の厚生年金保険の被保険者が死亡した →  に該当する
に該当する
・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満である → 25年未満なので には当てはまらない
には当てはまらない
 の場合、保険料納付要件を満たす必要があります。
の場合、保険料納付要件を満たす必要があります。
問題文の場合、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満、となっていますので、原則の保険料納付要件は満たしていません。
しかし、現在63歳で、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者である、とのことなので、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないことになるので、特例が適用できます。(令和8年4月1日前、かつ65歳未満)
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

【解答】 ○
 に当てはまります。
に当てはまります。
保険料納付要件は問われません。(既に障害厚生年金の受給資格を満たしているので、遺族厚生年金の保険料納付要件は問わない。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-129
R2.4.6 加給年金額と老齢基礎年金の繰上げとの関係
例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合、その加給年金額は、妻が65歳に達するまで加算されます。
しかし、その妻が65歳前に繰上げ支給の老齢基礎年金の支給をうけたとしたら、夫の老齢厚生年金に加算されている加給年金額はどうなりますか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】 ×
加給年金額の対象の配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとしても、加給年金額に相当する部分は、その配偶者が65歳に達するまで支給されます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-119
R2.3.22 加給年金額の支給が停止されるとき
 例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合を考えてみましょう。
例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合を考えてみましょう。
もし妻が老齢厚生年金の支給を受けることができるとき、夫の老齢厚生年金に加算された加給年金額はどうなりますか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

【解答】 ×
300か月以上ではなく、240か月以上です。
加算対象になっている配偶者が単に老齢厚生年金を受けることができるだけでは、加給年金額は支給停止になりません。
その配偶者の受けることができる老齢厚生年金が、何カ月の被保険者期間で計算されているのかがポイントです。
加給年金額が停止されるのは、その配偶者が受けることができる老齢厚生年金が被保険者期間が原則として240月以上で計算されている場合に限られます。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H22年出題>
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-109
R2.3.8 審査請求と再審査請求(厚年)
 第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある場合、社会保険審査官に審査請求ができますが、、、
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある場合、社会保険審査官に審査請求ができますが、、、
 (H28年出題)
(H28年出題)
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】 ○
穴埋め式でポインを確認しましょう。
 【厚生年金保険法第90条、第91条】
【厚生年金保険法第90条、第91条】
 厚生労働大臣による被保険者の資格、< A >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
厚生労働大臣による被保険者の資格、< A >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 審査請求をした日から< B >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
審査請求をした日から< B >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
 資格、< A >又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< C >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
資格、< A >又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< C >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は督促・滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は督促・滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。
 【社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項、32条第1項】
【社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項、32条第1項】
(審査請求期間)
 審査請求は、被保険者若の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して< E >を経過したときは、することができない。
審査請求は、被保険者若の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して< E >を経過したときは、することができない。
(再審査請求期間)
 厚生年金保険法第90条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< F >を経過したときは、することができない。
厚生年金保険法第90条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< F >を経過したときは、することができない。

【解答】
A 標準報酬 B 2月 C 審査請求に対する社会保険審査官
D 社会保険審査会 E 3月 F 2月
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-99
R2.2.17 2以上の種別の被保険者であった期間を有する障害厚生年金
 厚生年金保険の被保険者には、第1号、第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の4つの種別があります。
厚生年金保険の被保険者には、第1号、第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の4つの種別があります。
例えば、民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)と国家公務員(第2号厚生年金被保険者)の2つの種別の被保険者であった期間を有する者が、障害厚生年金の支給を受ける場合、支給に関する事務はどの実施機関が行うのでしょうか?
 H28年出題
H28年出題
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【解答】 ×
障害認定日における被保険者の種別ではなく、「初診日」における被保険者の種別で決まります。初診日にあてはまっていた被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】 ×
「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」で計算するのではなく、2以上の被保険者の種別の被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。
初診日に加入していた種別の実施機関が、他の種別の実施機関で加入していた期間分も合算して年金額の計算をし、支給事務を行うことになります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-89
R2.1.31 老齢厚生年金の繰上げと繰下げ
★ 老齢厚生年金の繰上げ、繰下げのルールを確認しましょう。
 H27年出題
H27年出題
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】 ○
老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、同時にしなければなりません。
 では、老齢厚生年金の繰下げはどうでしょう?
では、老齢厚生年金の繰下げはどうでしょう?
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H28年出題>
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。

【解答】 ○
老齢厚生年金の繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時でなくても構いません。
 <番外編>もどうぞ。
<番外編>もどうぞ。
<H30年出題>
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

【解答】 ○
<2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の繰下げ>
→ 一の期間に基づく老齢厚生年金の繰下げの申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金の繰下げの申出と同時に行うこと。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚年法)
R2-79
R2.1.14 65歳以上の在老のルール(厚年)
今日は、いただいたご質問にお答えします。
テーマ「65歳以上の在職老齢年金のルール」
~~「経過的加算額と繰下げ加算額」の扱いについて~~
ポイント
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、老齢厚生年金の全額が支給停止される。
ただし、経過的加算額と繰下げ加算額は支給停止にはならずに、全額支給される。
このポイントを押さえたうえで、次の問題を解いてみてください。
 H22年出題
H22年出題
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。

【解答】 ○
<ご質問内容>
問題文で、「(繰下げ加算額を除く。)」となっていますが、経過的加算額も支給停止の対象から除かれるはず。
この問題は、「経過的加算額」が入っていないのに、なぜ「○」なのでしょうか?
<解説>
 まず、「経過的加算額」は、法附則で規定されている制度で、あくまでも「当分の間」の措置です。(ということは、いずれ無くなるかもしれない)
まず、「経過的加算額」は、法附則で規定されている制度で、あくまでも「当分の間」の措置です。(ということは、いずれ無くなるかもしれない)
 60歳台後半の在職老齢年金の条文(法第46条)では、「繰下げ加算額を除く」と規定されていて、「経過的加算額」には触れられていません。
60歳台後半の在職老齢年金の条文(法第46条)では、「繰下げ加算額を除く」と規定されていて、「経過的加算額」には触れられていません。
だたし、法附則によって、当分の間、法第46条の在職老齢年金は、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と読み替えることが規定されています。
 本来は「繰下げ加算額を除く」でOKですが、当分の間、経過的加算額が加算されている人については、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と附則で読み替えているということです。
本来は「繰下げ加算額を除く」でOKですが、当分の間、経過的加算額が加算されている人については、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と附則で読み替えているということです。
 ですので、平成22年の問題は、附則ではなく、本来のルールが問われていると考えて、「○」になるということです。
ですので、平成22年の問題は、附則ではなく、本来のルールが問われていると考えて、「○」になるということです。
ちなみに。。。
この問題は、平成22年(問2)で、「誤っているもの」を選ぶ問題でした。
問2のAからEのうち、「A」の肢が明らかに誤っている問題でした。
もし、判断に迷ったら、よりはっきり誤っている方を選ぶ、というテクニックも必要かもしれません。
 では、次の問題はどうでしょう?
では、次の問題はどうでしょう?
【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】 ×
60歳台後半の在職老齢年金では、経過的加算額は支給停止の対象にならないので「×」です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-69
R1.12.27 R1厚年/加給年金額の対象者である配偶者が65歳になったとき
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年法「加給年金額の対象者である配偶者が65歳になったとき」についてです。
 R1厚年法(問6)より
R1厚年法(問6)より
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

【解答】 ×
この場合の届書の提出は不要です。
ポイント★
加給年金額対象者の不該当の届出は、10日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。
ただし、配偶者が65歳に達したときの不該当届の提出は不要です。(対象者の「年齢」は、把握できているから)
ちなみに、不該当の事由が、加給年金額対象者が死亡した、生計維持の状態がやんだ、離婚又は婚姻の取消をしたというときは、不該当届を提出しなければなりません。
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
不該当の事由が「年齢」の場合は、不該当届の提出は不要です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-59
R1.12.8 R1厚年/特別支給の老齢厚生年金の要件
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年法「特別支給の老齢厚生年金の要件」についてです。
 R1厚年法(問1)より
R1厚年法(問1)より
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。

【解答】 ○
特別支給の老齢厚生年金(=60歳代前半の老齢厚生年金)は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。

【解答】 ○
65歳から支給される老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月あれば支給されます。特別支給の老齢厚生年金とは違う点です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-49
R1.11.14 R1厚年/擬制的任意適用事業所
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「擬制的任意適用事業所」についてです。
 R1厚年法(問4)より
R1厚年法(問4)より
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

【解答】 ×
 「任意適用事業所の認可申請」は不要です。
「任意適用事業所の認可申請」は不要です。
個人経営・青果商・常時5人以上の従業員の場合は、強制適用事業所ですが、従業員数が4人になると、強制適用事業所ではなくなります。
しかし、従業員にとっては厚生年金保険の資格が存続する方が有利です。ですので、任意適用事業所の認可申請をしなくても、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、そのまま適用事業所として継続されます。このことを擬制的任意適用事業所といいます。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H19年出題>
強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。

【解答】 ○
擬制的任意適用事業所についての問題です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-38
R1.10.27 R1厚年/障害手当金と障害厚生年金
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年「障害手当金と障害厚生年金」についてです。
 R1厚年法(問10)より
R1厚年法(問10)より
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】 ×
 障害厚生年金と障害手当金は原則として併給できません。
障害厚生年金と障害手当金は原則として併給できません。
★ 障害の程度を定めるべき日において次のいずれかに該当する場合は、障害手当金は支給されません。
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③ 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
 この問題の場合、①に該当するので障害手当金は支給されません。ちなみに①の年金たる保険給付とは「老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金」のことです。
この問題の場合、①に該当するので障害手当金は支給されません。ちなみに①の年金たる保険給付とは「老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金」のことです。

厚生年金保険の年金(老齢、障害、遺族)・国民年金の年金(老齢、障害、遺族)・労災保険の障害補償給付、障害給付の受給権者には、「障害手当金」は支給されません。

ただし、障害厚生年金(障害基礎年金)の受給権者の場合は、例外があります。

 こんな問題も出題されています。
こんな問題も出題されています。
【H18年出題】
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。

【解答】 ○
障害厚生年金の受給権者でも、最後に障害等級に該当しなくなった日から障害状態に該当することなく3年を経過した者(現に障害状態に該当しない者に限る。)には、障害手当金が支給されることがあります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-28
R1.10.12 R1厚年法/強制適用事業所と任意適用事業所
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「強制適用事業所と任意適用事業所」についてです。
 R1厚年法(問4)より
R1厚年法(問4)より
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

【解答】 ×
「法人」の事業所の場合は、常時1人でも従業員を使用すれば業種関係なく今日背適用事業所となりますが、「個人経営」の事業所の場合は、「業種」と「5人以上」か「5人未満」かで変わりますので注意しましょう。
問題文ですと、業種が「農林水産業」の個人経営ですので、常時5人以上でも強制適用事業所にはなりません。
適用事業所となるには、厚生労働大臣の認可が必要です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-18
R1.9.24 R1厚年/遺族厚生年金・夫の要件
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「遺族厚生年金・夫の要件」についてです。
 R1厚年(問2)より
R1厚年(問2)より
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

【解答】 ×
54歳の夫は遺族厚生年金を受けることはできません。
夫は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、55歳以上であることが要件です。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(厚生年金保険法)
R2-9
R1.9.10 R1選択式(厚生年金保険法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第8回目は、「厚生年金保険法 選択式」です。
 AとBは「督促、滞納処分」についての出題です。
AとBは「督促、滞納処分」についての出題です。
★Aは、督促状に指定する期限についてですが、よく出題されるところです。
<参考 H25年出題>
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
(解答) ○
★Bも平成26年に出題実績があります。
厚生労働大臣から財務大臣に、滞納処分等に係る権限を委任することができます。
委任の要件の中に、「納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること」、「滞納保険料等の額が5000万円以上あること」等があります。
 Cは、「財政の現況及び見通しの作成」についての出題です。
Cは、「財政の現況及び見通しの作成」についての出題です。
「保険料水準固定方式」をとっているので、調整するのは「保険給付の額」の方と考えればスムーズだと思います。
 DとEは「年金の端数処理」からの出題です。
DとEは「年金の端数処理」からの出題です。
こちらの記事をどうぞ。(国民年金法ですが、内容は同じです。)

社労士受験のあれこれ
【選択式対策】厚年・在職老齢年金の計算
R1.8.21 【選択式対策】70歳以上の在老計算問題
本日のcheckは厚生年金保険法です。
(H27年択一式のアレンジ問題です)
70歳以上の老齢厚生年金(基本月額150,000円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360,000円であり、その月以前1年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は< A >円となる。

【解答】 A 20,000
計算式 (15万円+36万円-47万円)×2分の1
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社会保険分野】目的条文
R1.8.17 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックです。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
厚年・配偶者加給年金額の特別加算
R1.7.26 配偶者加給年金額の加算のよく出る問題
過去問をどうぞ
<H12年出題>
老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。

【解答】 ○
配偶者の加給年金額に特別加算が行われるのは、昭和9年4月2日以降生まれの受給権者が対象です。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】 ×
特別加算は、配偶者の生年月日ではなく、受給権者本人の生年月日に応じて行われます。
もう一問どうぞ!
<H25年出題>
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

【解答】 ○
特別加算は、受給権者の生年月日が若い方が高額です。(老齢厚生年金本体の計算式は早く生まれた人の方が有利ですよね?その逆です。)
最後にもう一問
<H15年出題>
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。

【解答】 ○
昭和18年4月2日以後は一律165,800円×改定率です。
社労士受験のあれこれ
60歳代前半の老齢厚生年金(在老)
R1.7.24 在老/支給停止調整開始額
過去問をどうぞ
<H20年出題>
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が28万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。

【解答】 ○
総報酬月額相当額+老齢厚生年金の基本月額が28万円以下のときは、60歳台前半の老齢厚生年金はカットされず全額支給されます。
なお、厚生年金保険法の「被保険者である」とは在職中という意味です。「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である」とは年金受給中かつ在職中ということです。
もう一問どうぞ
<H22年出題>
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
質問へのお返事です。
R1.6.24 老齢厚生年金の繰上げの問題で質問いただきました。
こちらの問題に質問いただきました。
【H29年本試験・厚生年金保険法問7C】
被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
【解答】 ○
 ご質問の内容は、『60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件として老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているのかが設問で言及されていない。これで正解としていいのか?』というものです。
ご質問の内容は、『60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件として老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているのかが設問で言及されていない。これで正解としていいのか?』というものです。
この問題は、問題文の2行目から3行目にあるように、繰上げ請求をしたときの「老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率」を問うものなので、老齢基礎年金の受給資格は満たしているという前提で問題文を読んでいいと思います。
この問題に限らず、本試験で、このような疑問にぶつかった場合は、他の選択肢に明らかな誤りがないか探してみてください。
例えば、今回取り上げた問題は、5つの選択肢のうちの一つが、「事後重症を請求できる期間」の問題で明らかに「×」を付けられる問題でした。
実際の問題は一問一答ではなく5つの中から正解を選ぶ問題ですので、迷ったら○×を判断しやすい問題から解いていくのもいいのでは?と思います。
この問題の解説はコチラ → H30.1.16 H29年問題より「老齢厚生年金の繰上げ減額率」
社労士受験のあれこれ
中高齢寡婦加算【厚生年金保険法】
R1.5.22 中高齢寡婦加算のポイントは?
 今日のテーマは厚生年金保険の中高齢寡婦加算です!
今日のテーマは厚生年金保険の中高齢寡婦加算です!
では、過去問をどうぞ
<H27年出題>
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。

【解答】○
子のない妻(遺族基礎年金を受けられない妻)の場合は、夫の死亡当時40歳以上であることが、中高齢寡婦加算の要件です。
こちらもどうぞ
<H15年出題>
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当する額になっている。

【解答】 ×
「老齢基礎年金」×「3分の2」ではなく、「遺族基礎年金」の額×「4分の3」です。
社労士受験のあれこれ
老齢厚生年金と障害基礎年金の併給(厚年法)
R1.5.1 老齢(厚)+障害(基)、子の加給年金額はどうなる?
まず過去問をどうぞ
<H24年出題>
老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

【解答】 ○
65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能です。
生計維持関係のある子がいる場合、障害基礎年金も老齢厚生年金も子の加算があります。しかし、両方に加算するわけにはいきませんので、その場合は、老齢厚生年金の方の子に対する加給年金額をストップ(支給停止)します。
社労士受験のあれこれ
基礎年金と厚生年金の組み合わせ(厚生年金保険法)
H31.4.24 老齢、遺族、障害 併給できる組み合わせは?
さっそく、過去問をどうぞ
<H24年出題>
(前提)65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される年金
【問題1】
老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
【問題2】
遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

【解答】
【問題1】 ○
65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金」の組み合わせはもちろんですが、「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせもOKです。
しかし、遺族基礎年金と老齢厚生年金の併給は不可です。
【問題2】 ○
65歳以後、「老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金」の組み合わせ、「障害基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせ、どちらもOKです。
ポイント! 付加年金の受給権がある場合、付加年金は老齢基礎年金と一心同体で支給されます。惑わされないように注意してください。
社労士受験のあれこれ
(厚生年金保険法)夫に対する遺族厚生年金
H31.4.17 「夫」に支給される遺族厚生年金を整理する
遺族厚生年金の「遺族」となるのは、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母」で、死亡の当時、その者に生計を維持していたことが条件です。※「妻」以外は年齢要件、障害要件がつきます。
 今日は、「夫」に支給される遺族厚生年金について確認しましょう。
今日は、「夫」に支給される遺族厚生年金について確認しましょう。
・夫は55歳以上であることが条件
・ただし、60歳までは支給停止。しかし夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき(=子がある場合)は、60歳未満でも支給される。
では、過去問をどうぞ
<H27年出題>
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

【解答】 ○
例えば、妻の死亡当時、夫55歳、子10歳で夫と子が生計を同じくしている場合、夫には遺族基礎年金の受給権も発生し、夫が60歳未満でも夫に対する遺族厚生年金は支給停止されずに支給されます。※遺族基礎年金と遺族厚生年金の2階建てで支給されます。
もう一問どうぞ
<H29年出題>
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】 ○
遺族基礎年金の受給権がある間(子が18歳の年度末まで)は、遺族基礎年金と遺族厚生年金は2階建てで支給されますが、遺族基礎年金が失権すると、夫の遺族厚生年金は原則通り60歳までは支給停止となります。
社労士受験のあれこれ
併給調整/厚生年金保険
H31.4.1 「障害厚生年金」と併給されるもの・されないもの
まず過去問をどうぞ
<H23年出題>
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】 ×
「障害厚生年金」は、「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金」とは併給できます。
「老齢基礎年金及び付加年金」並びに「遺族基礎年金」とは併給されません。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【解答】○
ポイント
⓵ 障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できない。いずれか一方のみを受給できる。
② 遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できる。(65歳以上であることが条件)
社労士受験のあれこれ
事後重症の障害厚生年金
H31.2.14 事後重症の請求
⓵初診日に厚生年金保険の被保険者だった
②初診日の前日に保険料納付要件を満たしていた
③障害認定日に障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にある
この3つの要件を満たせば、障害認定日に障害厚生年金の受給権が発生します。

もし、③の障害認定日に障害等級に該当しなければ受給権は発生しません。

しかし、障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当した場合は

請求することによって障害厚生年金の受給権が発生します。
 では、事後重症の障害厚生年金の請求のルールを確認しましょう。
では、事後重症の障害厚生年金の請求のルールを確認しましょう。
過去問をどうぞ
<H29年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求することができる。

【解答】 ×
事後重症の障害厚生年金は、65歳に達する日の前日までに請求することが条件です。
ポイント!
事後重症の障害厚生年金は請求日となります。支給は、請求日の属する月の翌月から開始です。
社労士受験のあれこれ
年金の支給期間/厚生年金保険法
H31.2.13 年金の支給期間
年金の支給期間は次のように規定されています。

年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
過去問をどうぞ
<H28年出題>
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月分から支給される。

【解答】 ×
年金は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月分から支給されますので、障害認定日が月の初日であったとしても、支給は障害認定日の属する月の翌月分からです。
社労士受験のあれこれ
比較してみましょう/厚生年金保険法
H31.2.12 老齢厚生年金と障害厚生年金を比べてみましょう。
昨日の記事のポイント
老齢厚生年金の受給権を取得した以後も働く場合(厚生年金保険の被保険者となる場合)、受給権を取得した時点の老齢厚生年金の額には、「受給権を取得した月」は含まない。
昨日の記事はコチラ H31.2.11 老齢厚生年金の受給権取得時の年金額
H31.2.11 老齢厚生年金の受給権取得時の年金額
 では、「障害厚生年金」の場合は、どこまでを年金の額の計算に入れるのか?が本日のテーマです。
では、「障害厚生年金」の場合は、どこまでを年金の額の計算に入れるのか?が本日のテーマです。
なお、⓵初診日の要件、②保険料納付要件を満たし、③障害認定日に障害等級に該当する場合は、障害認定日に受給権が発生します。
過去問をどうぞ
<⓵ H29年出題>
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

【解答】 〇
障害厚生年金の額の計算は、「障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。」と規定されています。「以後ではなく『後』であることがポイントです」
額の計算に算入するのは、「障害認定日の属する月まで(問題の場合だと、平成29年3月まで)」です。「障害認定日の属する月後(問題の場合だと、平成29年4月~)」は算入されません。
★老齢厚生年金と比較してください★ 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 (以後がポイントです。) |
もう一問どうぞ
<②平成28年出題>
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。

【解答】×
障害厚生年金には退職時改定はありません。
社労士受験のあれこれ
昨日の補足/厚生年金保険法
H31.2.11 老齢厚生年金の受給権取得時の年金額
昨日の記事は「退職時改定」の仕組みでした。
昨日の記事はコチラ H31.2.10 老齢厚生年金「退職時改定」の仕組み
H31.2.10 老齢厚生年金「退職時改定」の仕組み
 老齢厚生年金の受給権を取得した後も、在職して「厚生年金保険の被保険者」だった場合。受給権を取得した以後の厚生年金保険の被保険者期間(=保険料を負担していた)を入れて、老齢厚生年金の額を再計算することを退職時改定といいます。
老齢厚生年金の受給権を取得した後も、在職して「厚生年金保険の被保険者」だった場合。受給権を取得した以後の厚生年金保険の被保険者期間(=保険料を負担していた)を入れて、老齢厚生年金の額を再計算することを退職時改定といいます。
 今日は、「老齢厚生年金」の受給権を取得した以後も厚生年金保険の被保険者である場合、「受給権を取得した」時点の老齢厚生年金には、どこまでが算入されるのかを確認していきます。
今日は、「老齢厚生年金」の受給権を取得した以後も厚生年金保険の被保険者である場合、「受給権を取得した」時点の老齢厚生年金には、どこまでが算入されるのかを確認していきます。
過去問をどうぞ
<H26年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。

【解答】 ×
受給権を取得した時点の年金額には、受給権を取得した月は含まれません。受給権を取得した月の前月までで計算します。
★ 条文を確認すると
法43条第2項
老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 (以後がポイントです。)
権利を取得した月以後の被保険者であった期間は、退職時改定の際に年金の計算に算入されます。
社労士受験のあれこれ
ご質問ありがとうございます!/厚生年金保険法
H31.2.10 老齢厚生年金「退職時改定」の仕組み
「退職時改定」の仕組みについてご質問がありました。
ご質問ありがとうございます。
 例えば3月31日退職(4月1日喪失)の場合
例えば3月31日退職(4月1日喪失)の場合
・保険料は → 3月分まで
・退職時改定は退職日から起算してして1月経った日の属する月から=4月から
★ ご質問は、4月改定では3月までの納付分が年金に反映されますか?ということですが、「反映されます」。
| 2月 | 3月 | 4月 | |
| ▲3月31日退職 | ▲4月1日喪失 | ||
| 保険料 | 〇 | 〇 | |
| 年金額改定 |
条文を確認しますと
↓
(法43条第3項)
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の⓵資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき、適用事業所でなくなること又は任意単独被保険者の資格喪失について厚生労働大臣の認可を受けたとき、適用除外に該当するに至ったときは ②その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
・ 退職時改定に反映されるのは①の部分(資格を喪失した月前における被保険者であった期間)ですので、例の場合ですと3月分までとなります。3月分までを入れて年金額が再計算されます。
・ 年金額の改定は、②の部分です。事業所に使用されなくなったとき(退職日)は、その日から起算して1月を経過した日の属する月からとなりますので、3月31日から1月を経過した日の属する月=4月から年金額の改定となります。
過去問もどうぞ
<H28年出題>
在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1カ月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【解答】 ×
年金額が改定されるのは、平成28年2月からです。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)
H31.1.14 H30年出題/年金額の改定
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「年金額の改定」です。
H30年 厚生年金保険法(問7B)
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】 ×
「保険料率」ではなく、「年金たる保険給付の額」の改定のルールです。
穴埋め式でも確認しておきましょう。
(年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、< A >、< B >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】
A 国民の生活水準 B 賃金
ちなみに、国民年金法にも「年金額の改定」の規定があります。
↓
「この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」
※ 「賃金」という用語がないのが厚生年金保険法との違いです。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)
H31.1.11 H30年出題/目的条文の比較(厚年と国年)
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「目的条文」です。
H30年 厚生年金保険法(問7D)
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

【解答】 ×
問題文は、厚生年金保険の目的ではなく、「国民年金法」の目的です。
国民年金は全国民共通の年金ですが、厚生年金保険は「労働者」の老齢、障害、死亡について保険給付を行うものです。
では、ここで、「国民年金」と「厚生年金保険」のそれぞれの目的条文を穴埋め式で確認しておきましょう。
<国民年金法>
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって< A >の安定がそこなわれることを< B >によって防止し、もって健全な< A >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
<厚生年金保険法>
この法律は、< C >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < C >及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【解答】
A 国民生活 B 国民の共同連帯 C 労働者
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)
H31.1.10 H30年出題/2以上の種別がある者の加給年金額
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「2以上の種別がある者の加給年金額」です。
H30年 厚生年金保険法(問4エ)
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

【解答】 ×
「遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ」が誤りです。
加給年金額は、原則として被保険者期間の月数が240以上あることが要件ですが、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の加給年金額は、第1号から第4号までの各種別の被保険者期間を合算して240月以上あればOKです。
この場合、加給年金額は、第1号から第4号の厚生年金被保険者期間のうち、どれか一つの種別の老齢厚生年金にだけ加算されることになります。
では、どの老齢厚生年金に加算されるのか?がこの問題のポイントです。
問題文のように、2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なる場合は、遅い日において受給権を取得した種別の老齢厚生年金ではなく、「最も早い日に受給権を取得した」ものに、加給年金額が加算されます。
それでは、同時に受給権を取得した場合はどうなるのでしょう?
過去問で確認してみましょう。
<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【解答】 〇
同時に取得した場合は、「最も長い期間」の種別の老齢厚生年金に加算されます。
問題文の場合は、最も長い期間が第1号厚生年金被保険者期間ですので、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されることになります。
ちなみに、最も長い期間が2以上ある場合は、①第1号厚生年金被保険者期間、②第2号厚生年金被保険者期間、③第3号厚生年金被保険者期間、④第4号厚生年金被保険者期間の順番で決められます。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)
H30.12.28 H30年出題/加給年金額が加算される条件
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「加給年金額が加算される条件」です。
H30年 厚生年金保険法(問10C)
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】 ×
被保険者資格を喪失し、退職時改定によって240以上となった場合は、そこから加給年金額が加算されます。
流れを見てみましょう。
・受給権を取得した当時、配偶者がいたが、被保険者期間の月数が240未満だったので加給年金額は加算されなかった。
↓
・在職中だったので、その後も厚生年金保険の被保険者として保険料を負担した。
↓
・厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。
↓
・退職時改定により、被保険者の資格を喪失した月前の被保険者期間を老齢厚生年金の計算に入れる。
↓
・その結果、月数が240以上になった。
↓
・240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいれば加給年金額が加算される。
【過去問もどうぞ】
<H15年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

【解答】 ×
生計維持関係は、受給権を取得した当時ではなく、退職時改定で240月以上となるに至った当時で確認します。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)
H30.12.26 H30年出題/2以上の種別がある者の老齢厚生年金の繰下げ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」です。
※ 今日は、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の繰下げ」です。
H30年 厚生年金保険法(問10B)
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

【解答】 ○
例えば、第1号厚生年金被保険者期間(民間企業勤務)が10年、第2号厚生年金被保険者期間(国家公務員)が30年ある場合、老齢厚生年金は、それぞれの実施機関が裁定し、支払いを行います。
また、老齢厚生年金の繰下げの申出をする場合は、問題文にあるように、それぞれの実施機関に、同時に申出を行わなければなりません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)
H30.12.7 H30年出題/障害厚生年金の受給権の消滅時期
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「障害厚生年金の受給権の消滅時期」です。
H30年 厚生年金保険法(問4ウ)
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。

【解答】 ○
設問の場合、
65歳の時点で → 障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過していない → 65歳時点では受給権は消滅しない
では、設問の場合は、いつ受給権が消滅するのでしょうか?
障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過したとき → 受給権は消滅する(この時点で65歳を過ぎていることがポイントです!)
【過去問もどうぞ】
<H27年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。

【解答】 ×
65歳に達した時点では、障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年経過していませんので、65歳では受給権は消滅しません。
障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった63歳から3年間は失権しません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法)
H30.11.20 H30年出題/加給年金額の特別加算
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生年金保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「加給年金額に加算される特別加算の額について」です。
H30年 厚生年金保険法(問1C)
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

【解答】 ×
受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなるではなく、「受給権者の生年月日が遅いほど特別加算の額は大きくなる」、です。
★特別加算の額は、受給権者の生年月日が若くなるほど、多くなります。
なぜでしょうか?
老齢厚生年金は、生年月日が早い人の方が、定額部分の月数の上限や、報酬比例の給付乗率が有利に設定されていますよね?
そのため、せめて特別加算の額については、生年月日が若い人の方を有利に設定しましょう、ということです。
【こちらの過去問もどうぞ】
<平成28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
【解答】 ×
配偶者の生年月日ではなく、特別加算の額は「受給権者」の生年月日に応じて決まります。
★特別加算の問題のチェックポイント★
・配偶者の生年月日ではなく「受給権者」の生年月日
・特別加算額が行われるのは、「昭和9年4月2日」以後生まれ
・ 受給権者の生年月日が若い方が額が多い。
・「昭和18年4月2日」以後生まれからは一律165,800円×改定率で計算する
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法 基礎編)
H30.10.29 H30年出題/併給調整のルール
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
厚生年金保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「併給調整のルール」です。
H30年 厚生年金保険法(問5D)
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

【解答】 ×
★ 特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されません。
【年齢に注意!】特別支給の老齢厚生年金は60歳以上65歳未満であることに注意してください。
65歳までは①と②のどちらか選択となります。
①障害基礎年金 + 障害厚生年金
②特別支給の老齢厚生年金
*65歳以降は、障害基礎年金+老齢厚生年金の組み合わせを選択することもできます。
【 過去問もチェックしましょう】
過去問もチェックしましょう】
<H26年出題>
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

【解答】 ○
★ 65歳以後の障害基礎年金は次の併給が可能です。

・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法 基礎編)
H30.10.11 H30年出題/厚生年金保険法の目的条文と管掌
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
厚生年金保険法の「基礎」を確認しましょう。
厚生年金保険法の問題を2つ解いてください。
① H30年厚生年金保険法(問7D)
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。
② H30年厚生年金保険法(問7E)
厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

【解答】
① ×
問題文は、「国民年金法」の目的です。
厚生年金保険法は、「労働者」の老齢、障害、死亡について保険給付を行う、「労働者」及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することが目的です。
ポイント
国民年金は、職業に関係なくすべての「国民」が対象、厚生年金保険は、会社員や公務員等、労働者が対象の保険です。
② ×
実施機関が管掌するのではなく、「政府」が管掌します。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生年金保険法 選択編)
H30.9.19 <H30年選択>厚生年金保険法振り返ります
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、厚生年金保険法の選択式です。
A 保険料の納付より
「6か月」は覚えていても、「当日」か「翌日」で迷った方も多かったのではないでしょうか?
<同じ論点の過去問・平成25年出題>
厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
【解答】 ×
1年ではなく、「6か月」です。
B・C 運用の目的より
厚生年金保険の「保険料」を負担しているのは誰なのか?を意識して、読んでみてください。
(考え方)
積立金は、「厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部」であり、将来の保険給付の貴重な財源となるもの。
↓ だから
専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行う
D・E 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例より
■養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
⇒ 3歳未満の子の子育てのために時短勤務等で働き、それによって標準報酬月額が下がった場合でも、子どもが生まれる前の標準報酬月額で年金額が計算される仕組みのこと。
■対象期間 ⇒ 子を養育することとなった日の属する月から子が3歳に達したときに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで
■従前標準報酬月額 ⇒ 子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額のこと。(原則)
※ 子を養育することとなった日の属する月の前月において被保険者でない場合は、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月の標準報酬月額
<参考にどうぞ 過去問・平成17年出題>
3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】基本の条文(社会保険編)
H30.8.21 【選択式対策】基本条文チェック!(健保、国年、厚年)
 テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。
テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。
本試験の最中、「ここ、テキストのあのページの右上に書いてあった!」となったときに、目を閉じれば、そのページの映像が頭の中に浮かび上がるように。
■■
おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【健康保険法】
(基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< A >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< B >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< C >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける< D >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
【国民年金法】
(用語の定義)
・ 「政府及び実施機関」とは、< E >及び実施機関たる共済組合等をいう。
・ この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< F >をいう。
【厚生年金保険法】
(障害厚生年金の受給権者)
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して < G >(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに< H >があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の< I >に満たないときは、この限りでない。

【解答】
A 高齢化 B 後期高齢者医療 C 常に D 医療の質の向上
E 厚生年金保険の実施者たる政府 F 日本私立学校振興・共済事業団
G 1年6月を経過した日 H 国民年金の被保険者期間 I 3分の2
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社会保険分野】目的条文
H30.8.16 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)
 ご質問いただきました。
ご質問いただきました。
★「一般常識の勉強方法」
・ 労働分野 → 労働経済の数字(例えば、完全失業率やら労働力率etc)を、小数点以下まで覚える必要はありませんが、「用語の意味」はおさえてください。例えば、「完全失業率」=「労働力人口に占める完全失業者の割合」というように。
・ 社会保険分野 → 得点しやすい分野です。今年は、国民健康保険法の改正個所、確定拠出年金法の「数字」あたりに力を入れてほしいです。(まだ10日もあります!間に合います)
★「予備校の選び方」
これは相性などもあり、人によって全く違うと思うので、「○○が良い」とは言えなくて、申し訳ないです。
まずは、各学校の無料体験講座などを受けてみて、比較してみるのもいいのでは?と思います。
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・厚生年金保険法】遺族厚生年金の支給要件
H30.8.6 【選択式対策】遺族厚生年金(改正点に注意)
 試験直前。情報量が多いと混乱してしまいます。人のアドバイスよりも、今までの自分の努力と「勘」を信じましょう!
試験直前。情報量が多いと混乱してしまいます。人のアドバイスよりも、今までの自分の努力と「勘」を信じましょう!
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法」です。
<遺族厚生年金>
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< A >年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< B >年以上である者が、死亡したとき。

【解答】
A 25 B 25
(どちらも25年です。)
※ 「10年」ではないので注意してください。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・厚生年金保険法】遺族厚生年金の遺族
H30.7.12 【選択式対策】遺族厚生年金を受けることができる遺族
 頭の中がごちゃごちゃしてきたら、一度、原点に戻って基本事項を確認してみるのもいいかもしれません。
頭の中がごちゃごちゃしてきたら、一度、原点に戻って基本事項を確認してみるのもいいかもしれません。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法」です。
<遺族>
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は< A >であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。ただし、< B >以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫、父母又は祖父母については、< C >歳以上であること。
2 < D >については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で< E >に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が< F >歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による< G >の受給権を有するときは、この限りでない。

【解答】
A 祖父母 B 妻 C 55 D 子又は孫
E 障害等級の1級若しくは2級 F 60 G 遺族基礎年金
 <G>について
<G>について
平成26年4月から「子のある夫」に遺族基礎年金が支給されるようになっています。
遺族厚生年金の遺族となる「夫」は55歳以上という年齢要件があり、また、60歳までは支給停止されます。
「子のある55歳以上の夫」の場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されますが、その場合、60歳になるまでの遺族厚生年金の支給停止はありません。(60歳前でも遺族厚生年金が支給されます。)
過去問もどうぞ
(H23年出題)
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

【解答】 ×
遺族厚生年金には転給はありません。
→ 「妻」が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、「母」は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。
 遺族の順位も覚えておきましょう
遺族の順位も覚えておきましょう
①配偶者、子 ②父母 ③孫 ④祖父母
父母は、「配偶者又は子」がいるときは遺族とならない
孫は、「配偶者、子又は父母」がいるときは遺族とならない
祖父母は、「配偶者、子、父母又は孫」がいるときは遺族にならない。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・厚生年金保険法】老齢厚生年金の繰下げ
H30.6.14 【選択式対策】老齢厚生年金繰下げの要件を知る
 毎日、少しでもいいので、勉強に没頭する時間を作ってみましょう。
毎日、少しでもいいので、勉強に没頭する時間を作ってみましょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法・支給の繰下げ」です。
(支給の繰下げ)
老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して < A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに< B >を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、支給繰下げの申出をすることはできない。

【解答】
A 1年を経過した日 B 障害基礎年金
★★過去問もチェック
(平成28年出題)
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

【解答】 ○
ポイント! 老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、繰下げの申出ができる。
※65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるため
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・厚生年金保険法】遺族厚生年金
H30.5.17 【選択式対策】遺族厚生年金の受給権の消滅
 本試験まであと3か月と少し。焦らずいきましょう!
本試験まであと3か月と少し。焦らずいきましょう!
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「厚生年金保険法」です。
第63条 (遺族厚生年金・失権)
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三 < A >の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して < B >年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時< C >歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき
→ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が< C >歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき
→ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が< D >に該当する障害の状態にあるときを除く。
二 < D >に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、< E >歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。

【解答】
A 直系血族及び直系姻族以外
※ 直系血族及び直系姻族以外の養子になった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
「祖父の養子になった場合」というのが過去に出題されていますが、祖父は直系血族ですので、祖父の養子になったことによる遺族厚生年金の受給権消滅はありません。
B 5
C 30
D 障害等級の1級又は2級
E 20
※ Dについて 1級又は2級だけが対象です。3級は含みません
★★平成27年には↓以下のような問題が出題されています。
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、この有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
<解答> ○
障害等級1級又は2級であれば、18歳に達した日以後の最初の3月31日では失権しません(障害状態にあれば最長20歳まで)が、3級の場合は、原則通り、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権します。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・厚生年金保険】老齢厚生年金の受給資格と年金額
H30.4.23 【選択式対策】老齢厚生年金の受給資格と年金額
平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は厚生年金保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
第42条 (受給権者)
老齢厚生年金は、< A >を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
一 65歳以上であること。
二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< B >以上であること。
第43条 (年金額)
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の< C >(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該< D >で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に< D >を乗じて得た額とする。

【解答】
A 被保険者期間 B 10年 C 平均標準報酬額 D 被保険者期間の月数
おさえるポイント★
A → 「被保険者期間」 65歳からの老齢厚生年金は、被保険者期間が1か月でもあれば、受給資格ができます。「被保険者期間」は月単位、最小期間は1か月ですので、「被保険者期間を有する」とは、「被保険者期間が最低でも1か月以上はある」という意味です。
B → 「10年」 老齢厚生年金の受給資格を得るには、「国民年金」の保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)が10年以上あることが必要。
C → 「平均標準報酬額」 平均標準報酬額とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で割った額のこと。(簡単に言うと、在職中の給料(賞与含む)の1月当たりの平均額)なお、標準報酬月額と標準賞与額には「再評価率」をかけます。過去の報酬を現在の賃金や物価の水準に読み替えるためです。
D → 「被保険者期間の月数」 老齢厚生年金の額は、「被保険者であった全期間の平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」で計算します。
※ 「1000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前生まれの場合は、生年月日によって読み替えがあります。
また、平成15年3月以前の被保険者期間がある場合は、ボーナスを含まない「平均標準報酬月額」を使って計算し、乗率も変わります。
社労士受験のあれこれ
加給年金額(障害厚生年金)
H30.3.31 H29年問題より「障害厚生年金の加給年金額」
H29年本試験【厚生年金保険法問5C】を解いてみてください。
障害等級第1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】 ○
★ ポイント!
障害厚生年金の額には、受給権者によって生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額が加算されます。
「受給権を取得した当時」に生計維持関係のある65歳未満の配偶者がいる場合はもちろん、受給権を取得した日の「翌日以後」(簡単に言うと受給権を取得した後から)に有することになった場合でも、加給年金額が加算されることがポイントです。
★ 比較しましょう。
遺族厚生年金の場合は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時にその者に「生計を維持」していたことが条件です。
社労士受験のあれこれ
厚年・不服申立て
H30.3.1 H29年問題より「厚生年金保険・不服申立て」
H29年本試験【厚生年金保険法問2C】を解いてみてください。
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】 ×
★ 第1号厚生年金被保険者の保険料の滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官ではなく、「社会保険審査会」に対して審査請求をすることができます。
※ 第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金については、問題文の通り、社会保険審査会で○です。
★ 「不服申立て」の条文を確認しておきましょう。条文の空欄を埋めてください。
(審査請求及び再審査請求)
厚生労働大臣による被保険者の< A >、< B >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
厚生労働大臣による< C >その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

【解答】
A 資格 B 標準報酬 C 保険料
★ なお、第1号厚生年金被保険者以外の審査請求先は以下の通りです。
・ 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合審査会
・ 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合審査会
・ 第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
社労士受験のあれこれ
60歳代後半の在職老齢年金
H30.2.5 H29年問題より「60歳代後半の在職老齢年金」
H29年本試験【厚生年金保険法問10D】を解いてみてください。
平成29年4月において、総報酬月額相当額が480,000円の66歳の被保険者(第1号厚生年金保険被保険者期間のみを有し、前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者とする。)が、基本月額が100,000円の老齢厚生年金を受給することができる場合、在職老齢年金の仕組みにより月額60,000円の老齢厚生年金が支給停止される。

【解答】 ○
★ 「66歳の被保険者」ですので、60歳代後半の在老のルールを適用します。
★ なお、平成29年度の支給停止調整額は46万円です。(平成30年度も同じ46万円です。)
★ 60歳代後半の在老のルール
| 基本月額 + 総報酬月額相当額 → 46万円以下 | 支給停止なし(全額支給) |
| 基本月額 + 総報酬月額相当額 → 46万円超える | 合計額が46万円を超えた部分の2分の1が支給停止 |
★ 問題文の場合は、
10万円(基本月額)と48万円(総報酬月額相当額)を足すと58万円です。
合計額が46万を超えていますよね。
合計額58万円から46万円を引いた額=12万円(46万円を超えた部分)の2分の1が支給停止になりますので、すなわち月額6万円が支給停止されることになります。
★ ポイント
「支給停止調整額=46万円」は必ず覚えましょう。
社労士受験のあれこれ
老齢厚生年金の繰上げ
H30.1.16 H29年問題より「老齢厚生年金の繰上げ減額率」
H29年本試験【厚生年金保険法問7C】を解いてみてください。
被保険者期間の月数を12月以上有する昭和31年4月2日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。

【解答】 ○
★ 「62歳に達する日の属する月の前月までの月数」の62歳がポイントです!
★ 設問の昭和31年4月2日生まれの男性(被保険者期間の月数が12月以上)の場合、62歳から報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給されます。
★ 設問の男性のように報酬比例部分のみが61歳から64歳までに支給される人の老齢厚生年金の繰上げのポイントを確認すると・・・
◆ 老齢厚生年金の繰上げを請求できるのは、60歳から報酬比例部分の支給開始年齢到達前まで
◆ 繰上げ減額率は、「繰上げ請求月から報酬比例部分の支給開始年齢到達月の前月までの月数」×一定率
→ 設問の男性は報酬比例部分の支給開始年齢が62歳なので、老齢厚生年金支給の繰上げの請求をした場合の減額率は、「繰上げ請求月から62歳到達月の前月までの月数」×一定率となります。
本来の報酬比例部分支給開始年齢から何カ月早く繰り上げたかで計算します。
★ ちなみに
この場合、老齢基礎年金も併せて繰上げ請求をしなければなりません。老齢基礎年金の繰上げ減額率は、「繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数」×一定率となります。
老齢基礎年金は本来65歳から支給されるので、繰上げ減額率は本来の65歳から何カ月早く繰り上げたかで計算されます。
社労士受験のあれこれ
基本の問題その7(厚生年金保険法)
H29.12.26 H29年問題より「基本」を知ろう・厚生年金保険法
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
任意単独被保険者の資格の得喪
「任意単独被保険者」は、厚生労働大臣の認可によって資格の取得・喪失ができる
★ 法律上当然に、厚生年金保険の被保険者になれるのは、「適用事業所」に使用される70歳未満の者です。
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者の場合は、厚生労働大臣の認可を受ければ(事業主の同意も必要)、厚生年金保険の被保険者(任意単独被保険者)になることができます。
★ 任意単独被保険者は、「任意」で厚生年金保険の被保険者になれるので、同じく
「任意」で資格を喪失することもできます。その際も厚生労働大臣の認可が必要です。
★ 通常、被保険者の資格の取得・喪失は「厚生労働大臣の確認」で効力が生じます。誰が、いつ、入社したか、退職したか等を、一人一人「確認」することによって、厚生年金保険の被保険者としての権利や義務が発生します。
ただし、任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可によって、資格を取得、喪失した場合は、厚生労働大臣の確認は要りません。なぜなら、厚生労働大臣の認可によって取得・喪失ができているので、入社日や退職日などについて確認する必要がないからです。
では、平成29年【問3】アを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問3】ア)
適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

<解答> ×
厚生労働大臣の認可によって喪失する場合は、確認はいりません。
社労士受験のあれこれ
定番問題その18(厚生年金保険法)
H29.12.7 H29年問題より「定番」を知る・厚生年金保険法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (障害厚生年金の計算)
「障害認定日」の属する月後の被保険者であった期間は、障害厚生年金の計算に入らない。
★ 障害認定日に障害等級の状態にあれば、障害厚生年金の受給権は障害認定日に発生します。
障害厚生年金の額には、「障害認定日」の属する月後(以後ではない)の被保険者であった期間は入りません。言い換えると、障害認定日の属する月まで計算に入れるということです。
ちなみに、「初診日」ではありませんので注意してください。障害認定日と初診日を入れ替えた問題にひっかからないで。
これを覚えると、平成29年【問7】Eが解けます。
★問題です。
(平成29年【問7】E)
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。

<解答> 〇
障害厚生年金の額の計算の基礎となるのは、障害認定日の属する月すなわち平成29年3月まで。障害認定日の属する月後(平成29年4月以降)は、計算の基礎になりません。
社労士受験のあれこれ
定番問題その8(厚生年金保険法)
H29.11.7 H29年問題より「定番」を知る・厚生年金保険法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (事後重症の請求)
事後重症は、65歳に達する日の前日までに請求すること
★ 障害厚生年金は、①初診日の要件、②保険料納付要件、③障害認定日の要件の3つのが揃えば、「障害認定日」に受給権が発生します。
★ 「障害認定日」に障害等級(厚生年金の場合は1級、2級、3級)に該当しない場合は、受給権は発生しませんが、その後悪化し障害等級に該当した場合、請求をすることによって受給権が発生します。(事後重症による障害厚生年金です。)
★ 「事後重症」による障害厚生年金は、「65歳までに」請求することで受給権が発生します。
<条件>
・ 障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し
・ 障害認定日後65歳に達する日の前日までに請求すること
※ 「請求」した日に受給権が発生します。
これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問7】D)
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

<解答> ×
★ 「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。」の部分が×です。請求は、「65歳に達する日の前日までの間に」することが要件です。
社労士受験のあれこれ
覚えれば解ける問題その8(厚生年金保険法)
H29.10.19 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・厚生年金保険法
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (時効)
「保険給付」を受ける権利の時効は「5年」
★ 保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
注目してほしいのは、「保険給付」という用語。
★ 厚生年金保険法の「保険給付」として、
① 老齢厚生年金
② 障害厚生年金及び障害手当金
③ 遺族厚生年金
が規定されています。「保険給付」には年金だけでなく障害手当金(一時金)も含まれていることに注意しましょう。
★ 「保険給付」を受ける権利の時効は5年と規定されています。一時金である障害手当金も「保険給付」ですので、時効は5年です。
★ 余裕のある方はこちらの記事もどうぞ。
↓
これを覚えると、平成29年【問5】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】)
障害手当金の給付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

<解答> ×
障害手当金の時効は5年です。
★ ちなみに、国民年金の「死亡一時金」の時効は2年ですので、間違えないように気を付けましょう。
社労士受験のあれこれ
まずは原則!その10(厚生年金保険法)
H29.10.6 H29年問題より原則を学ぶ・障害厚生年金の加給年金額
なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(障害厚生年金・加給年金額)
1・2級の障害厚生年金には、「配偶者」加給年金額がプラスされる
障害厚生年金には、1級、2級、3級の等級がありますが、要件を満たせば、1級、2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
「子」については、「障害基礎年金」の方で加算されます。
【年金の加算について】
| 配偶者の加算 | 子の加算 | ||
|---|---|---|---|
| 障害 | 障害基礎年金 | なし | 〇 |
| 障害厚生年金(1・2級) | 〇 | なし |
◆◆ ちなみに、「老齢」の場合、「老齢厚生年金」には、「配偶者」と「子」について加給年金額が加算されます。「老齢基礎年金」には、配偶者、子ともに加算はありません。
この原則で、平成29年【問8】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問8】D)
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。

<解答> ×
◆ 障害厚生年金の加給年金額の対象になるのは子ではなく「配偶者」です。
社労士受験のあれこれ
平成29年度選択式を解きました。(厚生年金保険編)
H29.9.13 平成29年度選択式(厚生年金保険編)~次につなげるために~
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「厚生年金保険法」です。
【A】
「国庫負担」からの出題です。
皆さましっかりチェックしていた箇所だと思います。
【B】
「中高齢寡婦加算の額」からの出題です。
これもできた方が多かったのでは?
【C】
「3号分割・特定期間」からの出題です。
離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割の2つのパターンがあります。ケアレスミスを防ぐためにも、どちらのパターンの問題なのかきちんと確認しましょう。
この問題は3号分割です。合意分割との違いを押さえておけば、迷わず解けます。
【D】
「標準報酬改定請求の請求期限」からの出題です。
厚生年金保険法施行規則第78条の3に規定されています。
ここまでチェックしていた方は少ないのではないでしょうか?分からなくても仕方ありません。気にしなくていいです。
【E】
「合意分割」の按分割合からの出題です。
平成21年択一式で出題されている箇所です。
「按分割合」とは、第1号改定者と第2号改定者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合のことです。
合意分割するにあたって、第2号改定者の割合が増えるということ、ただし、その割合は2分の1が限度、というルールをおさえていれば解ける問題だと思います。
今後の勉強のポイント!
★ よく出る基本的な箇所はきちんと覚える
基本的な箇所は必ず暗記して落ち着いて解きましょう。問題の読み間違いや早とちりには注意。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)
H29.8.1 目的条文のチェック(社会保険編)
8月になりました!
ここからの頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。
目的条文のチェック(労働編)はコチラです。
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

<解答>
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
※ 業務災害→ 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
ココもポイント!
第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。
コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
★★憲法第25条第2項も見ておきましょう。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H29.1.20 必ず出る改正点(厚年編9)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度の本試験を振り返って、改正点がどのように出題されたのかを検証しています。
本日は平成28年度厚生年金保険法問7のエです。被用者年金一元化からの出題です。
<問題文>
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

【答】 ×
★ 長期加入者の特例については、2以上の種別の被保険者期間は合算されません。
種別ごとに44年以上あることが要件です。
★ 長期加入者の特例のポイント
→ 被保険者でないこと+被保険者期間が44年以上あること
例えば、問題の昭和29年10月2日生まれの男性は、61歳から報酬比例部分が支給されますが、長期加入者の特例の要件を満たせば、定額部分もプラスされます。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H29.1.13 必ず出る改正点(厚年編8)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度の本試験を振り返って、改正点がどのように出題されたのかを検証しています。
本日は平成28年度厚生年金保険法問5のCです。被用者年金一元化からの出題です。
<問題文>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【答】 ○
★ ポイントその1 <240以上の判定>
加給年金額が加算されるには、被保険者期間の月数が240以上あることが要件です。この場合、2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は、合算して240以上あれば、要件を満たします。
★ ポイントその2 <どちらの老齢厚生年金に加算されるか?>
この問題の男性の場合は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を同時に取得しているので、加給年金額は、被保険者期間が長い方の第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加算されます。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H29.1.12 必ず出る改正点(厚年編7)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
改正点がストレートに問われるパターンが多いので、得点しやすいです。
本日は平成28年度厚生年金保険法問6のDです。被用者年金の一元化からの問題です。
<問題文>
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【答え】 ×
★ 障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う → 障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行うです。
例えば、国家公務員(第2号厚生年金被保険者)と民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)の期間があり、民間企業に在職中に初診日がある場合は、厚生労働大臣(日本年金機構)が、支給に関する事務を行います。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.19 必ず出る改正点(厚年編6)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度厚生年金保険法問6のCです。被用者年金一元化からの問題です。
<問題文>
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

【答え】 ×
ポイント
★ 第1号厚生年金被保険者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を取得した場合
→ その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
<ということは、>
・ 第1号が第4号の資格を取得 → 第1号の資格を喪失 → 第1号と第4号が二重になることはない → 選択届を届け出る場面はありません。
<ちなみに、>
・ 第1号厚生年金被保険者が2つ以上の事業所に使用され、管轄の年金事務所が2つ以上になった場合は、自身に関する事務を行う年金事務所を選択します。その場合は、「2以上事業所選択届」を提出することになります。
★★根拠★★
第18条の2
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
→ 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者が同時に第1号厚生年金被保険者になることはない。
2 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
→ 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の資格を有することになったときは、その日に第1号の資格は喪失。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.15 必ず出る改正点(厚年編5)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度厚生年金保険法問7のオです。在職老齢年金の改正からの問題です。
<問題文>
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

【答え】 ×
ポイント!
★ 70歳以上で在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、昭和12年4月2日以降生まれまでが対象でしたが、平成27年10月の改正で、昭和12年4月1日以前生まれの人も対象になっています。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.14 必ず出る改正点(厚年編4)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度厚生年金保険法問8のAです。退職時改定の改正からの問題です。
<問題文>
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【答え】 × 平成28年3月からではなく平成28年2月から年金額が改定される。
ポイント!
★ 「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき(簡単に言うと「退職」したとき)は、その翌日に資格を喪失します。
平成27年10月の改正で、退職時の年金額の改定については、「喪失日」からではなく、「退職した日」から起算することになりました。
問題文のように、1月31日退職・2月1日喪失の場合は、退職日である1月31日から起算して1月を経過した日の属する月から(=2月から)年金額が改定されます。
★★こちらのページもどうぞ → H28.3.24 退職時改定の起算日
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.13 必ず出る改正点(厚年編3)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度厚生年金保険法問9のAです。被用者年金一元化からの出題です。
<問題文>
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

【答え】 ○
ポイント!
★ 「老齢厚生年金の受給権者が死亡」=「長期要件」の遺族厚生年金であることがポイントです。
長期要件の遺族厚生年金は、「老齢厚生年金」と同じで、「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給」されます。
問題の要件の場合は、第1号厚生年金被保険者期間の15年分は厚生労働大臣から、第3号厚生年金被保険者期間の18年分は、地方公務員共済組合等から支給されます。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.12 必ず出る改正点(厚年編2)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度厚生年金保険法問7のイです。「不服申し立て」の改正点からの出題です。
<問題文>
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【答え】 ○
ポイント!
★ 「棄却したものとみなす」のは、「2か月」以内に決定がないとき。2か月がポイントです。(「3か月」なのか「2か月」なのかをきちんと押さえるべき個所です。今はまだ覚える必要はありませんが、試験までには整理しておきましょう。ちなみにこの辺りは横断学習が効果的なところです。参考までに→横断のページはこちらです。)
★ 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の審査請求についてはこちらのページをどうぞ → H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.2 必ず出る改正点(厚年編)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
改正点がストレートに問われるパターンが多いので、得点しやすいです。
本日は平成28年度厚生年金保険法問7のウです。被用者年金の一元化からの問題です。
<問題文>
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上でないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

【答え】 ×
★ 特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要ですが、2以上の種別の期間がある場合は合算して1年以上あればOKです。
問題文の女性は、第1号厚生年金被保険者期間8か月プラス第4号厚生年金被保険者期間10か月で1年以上となりますので、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
社労士受験のあれこれ
ひっかけ問題(引っかかってはいけない)
H28.10.10 シリーズひっかけ(厚年・老齢厚生年金)
次の問題を解いてみてください。
<平成20年出題>
65歳以上の者であって、厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の者は、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるときであっても、老齢厚生年金を請求することはできない。

<解答> ×
65歳以上の老齢厚生年金は、「被保険者期間を有する者」で、保険料納付済期間と保険料免除済期間とを合算した期間が25年以上あることが条件です。
★ 被保険者期間は月単位で算定されるので、「被保険者期間を有する者」とは、最低1月は被保険者期間がある者、ということです。
ということは、65歳以上の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば支給されるので、「厚生年金保険の被保険者期間が1年未満の場合は請求できない」というのは誤りです。

ちなみに、65歳未満の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること・保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あることが要件です。
社労士受験のあれこれ
年金教室第2回目
H28.9.12 年金教室② 「厚生年金保険」の誕生
年金教室第1回目では、船員のための年金(船員保険)が昭和14年に創設されたことを勉強しました。
第1回目はコチラからどうぞ→年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?
今日は、厚生年金保険法の始まりをお話しします。

★「労働者年金保険法」
現在の厚生年金保険は「労働者年金保険法」という名称で、昭和16年に制定されました。対象は工場で働く男子労働者でした。(平成23年版の厚生労働白書によると制定当時は「産業戦士の恩給制度」とも呼ばれていたそうです。)
★「厚生年金保険」へ
厚生年金保険と名称が改められたのは昭和19年です。その際に、事務職員や女子労働者にも適用されるようになりました。

厚生年金保険(労働者年金保険法)が制定されたのは、75年も前なのです。
社会も激変しました。
戦後 → 高度経済成長 → 安定成長 → 少子高齢化社会と、社会情勢の変化に伴って年金制度も改正が繰り返されています。
社労士受験のあれこれ
年金教室 第1回目
H28.9.7 年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?
今日から年金教室を始めます。
年金制度は生活や経済に密着しているものなので、社会の変動に合わせて、改正が繰り返されています。そして改正のたびにどんどん複雑に難しくなってしまい、勉強しないといけないことが増える一方です。
そんな年金ですが、少しでも勉強が楽になるよう、今日から「年金教室」と題しまして、基本事項からちょっと難しいところまで、解説していきます。年金はわかると面白いです!
「年金教室」は不定期に書いていきます。どうぞよろしくお願いします!
今日のタイトルは、「「社会保険方式」の一番古い公的年金は?」です。

まず、「保険」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる制度で、社会保険というのは、国が責任をもって運営している保険という意味です。
★★「保険」とは、保険料を負担すればいざというときそれに応じた給付が受けられるもの。もし保険料を払わなかった場合は、給付が受けられなくなる可能性もある、ということ。
健康保険などの医療保険、年金、介護保険、雇用保険などは「社会保険」方式で運営されています。
例えば、「年金保険」の場合は、老齢、障害、死亡というリスクに備えて保険料を払う(強制加入)。そして実際に老齢(65歳)になると、保険料を払った期間等に応じた年金が支払われるという仕組み。
さて、日本で一番古い「社会保険方式」による公的年金は「船員保険」です。
船員保険の創設は昭和14年です。
戦時体制下で船員の確保が必要だったからだそうです。(平成23年版厚生労働白書より)
当時の船員保険は、年金だけでなく、「健康保険相当部分(職務外の疾病部門)」「労災相当部分(職務上疾病・年金部門)」「雇用保険相当部分(失業部門)」の分野もカバーする総合保険でした。
しかし、被保険者数の減少や高齢化等のため財政が悪化し、基礎年金制度が始まった昭和61年4月に船員保険の年金部門は、厚生年金保険に統合され、船員保険から年金部門はなくなりました。
★ちなみに、「労災相当部分」、「雇用保険相当部分」は、平成22年1月に、「労災保険法」、「雇用保険法」に統合されました。
★現在の船員保険は、「健康保険相当部分」と「船員独自の上乗給付」を行っています。
過去問もチェック!
① H16年出題
船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。
② H22年出題
船員保険法は大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。
【解答】
① H16年出題 ○
② H22年出題 ×
大正14年ではなく昭和14年制定。
「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。
社労士受験のあれこれ
H28年度選択式を解きました。その5(年金編)
H28.9.6 平成28年度選択式(年金編)~次につなげるために~
平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。
★労基・安衛編はコチラから。
→ H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
★労災・雇用編はコチラから。
→ H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~
★一般常識編はコチラから。
→ H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~
★健康保険編はコチラから
→ H28.9.5 平成28年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~
ラストは、厚生年金保険法・国民年金法です。
<厚生年金保険法>
【A】、【B】、【C】
60歳台後半の在職老齢年金の問題です。
最初は数字を入れる問題?と思いましたが、用語を入れる問題でした。
選択肢に似たような用語が並んでいるので、きっちり覚えていないと選ぶのが大変なところです。
在老の問題は、毎年のように出題されますが、今年のように「用語」に焦点を当てるパターンは珍しいです。この問題を見て、条文を読んで重要用語をおさえていくことも必要だと思いました。
【D】、【E】
「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置」からの出題です。
【D】については、平成23年の国民年金法の選択式で同じ個所が出題されています。(やはり繰り返されています。)
【E】も頻出事項です。まぎらわしい選択肢もなかったので、できた方が多かったと思います。
<国民年金法>
【A】、【B】
目的条文からの出題です。
「社労士受験のあれこれ」でも取り上げました。
こちらからどうぞ。 → H28.8.2 目的条文のチェック(社会保険編)
【C】
保険料の免除期間の問題です。
例えば、平成26年10月分の保険料の納付期限は平成26年12月1日(月)です。(平成26年11月30日が日曜日のため)。
平成26年10月分の保険料の免除を受けるには、平成26年12月1日から2年後の平成28年12月1日までの免除申請をすることになります。
★通常は翌月末日が納付期限ですが、曜日の関係で納付期限が翌月になる場合もあります。そのようなときは、2年2カ月前までが免除の対象になります。
【D】、【E】
財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任についての問題です。
難しいです・・・。
ここまでチェックしていた方はすごい!と思います。
平成28年度の選択肢の検証はこれで終わります。
択一式についても、ボチボチ検証していきたいと思っています。
社労士受験のあれこれ
【直前】「厚生年金保険法」の選択対策
H28.8.22 直前!「厚生年金保険法」の選択対策
無理せず、焦らず。
ひとつひとつ固めていきましょう。
今日は厚生年金保険法の選択問題です。
<国庫負担等>
1. 国庫は、毎年度、< A >が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
2. 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の< B >(基礎年金拠出金の負担に関する< B >を含む。次項において同じ。)の執行(< C >(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
3 < C >(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び< C >による厚生年金保険事業の< B >の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。

【解答】
A 厚生年金保険の実施者たる政府 B 事務 C 実施機関
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)
H28.8.2 目的条文のチェック(社会保険編)
いよいよ8月です!
8月の頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。
目的条文のチェック(労働編)はコチラです。
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

<解答>
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
ココもポイント!
第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。
コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
★ 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づいています。第25条第1項ではありませんので注意してくださいね。
★★憲法も見ておきましょう。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
★厚生年金保険は「保険給付」といいますが、国民年金は「給付」で保険給付とはいいません。
この違いについてはコチラ → H28.1.28 国民年金と厚生年金保険の違い
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その2
H28.7.29 金曜日は横断 (不服申し立て その2)
金曜日は「横断」です。
今週は、「不服申し立ての横断整理その2」で、テーマは「処分の取消しの訴え」です。
その1はこちら → 「審査請求」と「再審査請求」の期限
厚年一元化に伴う改正点はこちら → H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
※雇用保険の解答を修正しました。(H28.8.1)
では問題です。空欄を埋めてください。
【労災保険法】
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【健康保険法】
ⅰ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
ⅱ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
Ⅲ < A >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<A>に入るのは次のどちらでしょう?
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分
【国民年金法】
ⅰ 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ ⅰに規定する処分(< B >(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<B>に入るのは次のどちらでしょう。
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分
【厚生年金保険法】
ⅰ 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
ⅲ < C >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<C>に入るのはどちらでしょう?
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分

【解答】
【労災保険法】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<労働者災害補償保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、労働者災害補償保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<雇用保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「①確認、②失業等給付に関する処分、③不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴え」をするには、雇用保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
※審査請求と雇用保険審査官が入れ替わっていましたので訂正しました。(H28.8.1)
【健康保険法】
<A>には、「① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることが可能です。
【国民年金法】
<B>には、「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分」が入ります。
★「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)」について処分取消しの訴えをするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」については、社会保険審査官に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
【厚生年金保険法】
<C>には、「① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
社労士受験のあれこれ
【改正】厚生年金保険法練習問題
H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。
今週は不服申立てです。
空欄を埋めてください。
(審査請求及び再審査請求)
① < A >による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、< B >に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
一 第2号厚生年金被保険者 → < C >
二 第3号厚生年金被保険者 → < D >
三 第4号厚生年金被保険者 → < E >
(審査請求)
① < A >による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は保険料等の督促及び滞納処分の規定による処分に不服がある者は、< B >に対して審査請求をすることができる。
② 第2号厚生年金被保険者、第3号被保険者に関する保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、それぞれ< C >、< D >に対して審査請求をすることができる。
③ 第4号被保険者に関する保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、< E >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
A 厚生労働大臣 B 社会保険審査会
C 国家公務員共済組合審査会 D 地方公務員共済組合審査会
E 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
第1号厚生年金被保険者以外の審査機関は、名称だけ押さえておきましょう。
| 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合審査会 |
| 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合審査会 |
| 第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 |
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その1
H28.7.22 金曜日は横断 (不服申し立て その1)
金曜日は「横断」です。
今週から、「不服申し立て」の横断整理に入ります。(何回かに分けてUPします。)
今週は、「審査請求」と「再審査請求」の期限を整理しましょう。
以下の問題の空欄を埋めてください。
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して < >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
<参考>
次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
| 1 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合審査会 |
| 2 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合審査会 |
| 3 第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 |

<解答>
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から <3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して<3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、脱退一時金に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
ポイント!
★労災保険・雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険 <共通>
審査請求 → 3カ月
再審査請求 → 2カ月
★労災保険・雇用保険
棄却したものとみなす → 3カ月
★健康保険・国民年金・厚生年金保険
棄却したものとみなす → 2カ月
社労士受験のあれこれ
【改正】厚生年金保険法練習問題
H28.7.18 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。
では、問題です。選択肢から選んでください。
(第80条 国庫負担等)
1 国庫は、毎年度、< A >が負担する< B >の額の2分の1に相当する額を負担する。
2 国庫は、1項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(< B >の負担に関する事務を含む。3項において同じ。)の執行(< C >(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
3 < C >(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する< B >及び< C >による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
<選択肢>
① 実施機関 ② 保険給付 ③ 厚生年金保険の実施者たる政府 ④ 国家公務員共済組合連合会 ⑤ 保険者 ⑥ 保険者等 ⑦ 日本私立学校振興・共済事業団 ⑧ 国庫納付金 ⑨ 厚生年金保険の管掌者たる政府 ⑩ 消費税 ⑪ 地方公務員共済組合連合会 ⑫ 基礎年金拠出金

<解答>
1 国庫は、毎年度、<A ③厚生年金保険の実施者たる政府>が負担する<B ⑫基礎年金拠出金>の額の2分の1に相当する額を負担する。
→ 厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の2分の1が国庫負担で賄われている
2 国庫は、1項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(<B ⑫基礎年金拠出金>の負担に関する事務を含む。3項において同じ。)の執行(<C ①実施機関>(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
3 <C ①実施機関>(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する<B ⑫基礎年金拠出金>及び<C ①実施機関>による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
基礎年金拠出金についてはこちらの記事もどうぞ
→ <国民年金>H28.5.22 基礎年金拠出金の負担と納付
社労士受験のあれこれ
【横断】資格取得届
H28.7.15 金曜日は横断 (資格取得届)
金曜日は「横断」です。
(2日遅れの更新で申し訳ないです。)
今週は、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法の「資格取得届」でよく出るところを横断的に整理しましょう。
※ ちなみに、労災保険法には「資格取得届」はありません。
では、問題です。
【雇用保険法】
① 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【健康保険法】
②(平成22年出題) 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
【国民年金法】
③(平成20年出題) 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
④ 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
【厚生年金保険法】
⑤ 法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から10日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとする。

【解答】
【雇用保険法】
① ×
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで」です。
【健康保険法】
②(平成22年出題) ×
①新規適用事業所の届出と②被保険者の資格取得の届出は5日以内ですが、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出は、「速やかに」です。
★健康保険法の事業主の行う届出の提出期限は原則として「5日以内」です。
「5日以内」ではないものを覚えていくのがポイントです。
★提出期限が「速やかに」の届出
「報酬月額の変更の届出(随時改定)」、「育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出」、「産前産後休業を終了した際の報酬月額の変更の届出」
【国民年金法】
③(平成20年出題) ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、資格取得届ではなく「種別変更届」を提出しなければなりません。(期限は14日以内、提出先は市町村長です。)
④ ○
第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出の経由先について
・ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者の場合 → その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由(経由の事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる)
・ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者の場合 → その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由
【厚生年金保険法】
⑤ ×
当該事実があった日から10日以内ではなく「5日以内」です。(船員被保険者は10日以内)
※ 法第27条は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者については、適用されません。
社労士受験のあれこれ
【改正】厚生年金保険法練習問題
H28.7.11 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。
今週は「積立金の管理運用」です。
【問題】
第79条の2(運用の目的)
積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「< A >」という。)及び実施機関(< B >を除く。次条③において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(< C >の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「< D >」という。)をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
第79条の3(積立金の運用)
① < A >の運用は、< B >が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、< A >を寄託することにより行うものとする。
② < B >は、①の規定にかかわらず、①の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に< A >を預託することができる。
③ < D >の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、< D >の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。

<解答>
第79条の2(運用の目的)
積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「<A 特別会計積立金>」という。)及び実施機関(<B 厚生労働大臣>を除く。次条③において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(<C 基礎年金拠出金>の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「<D 実施機関積立金>」という。)をいう。以下同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
第79条の3(積立金の運用)
① <A 特別会計積立金>の運用は、<B 厚生労働大臣>が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、<A 特別会計積立金>を寄託することにより行うものとする。
② <B 厚生労働大臣>は、①の規定にかかわらず、①の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に<A 特別会計積立金>を預託することができる。
③ <D 実施機関積立金>の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、<D 実施機関積立金>の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。
★第79条の2(運用の目的)の重要用語
・特別会計積立金 → 年金特別会計の厚生年金勘定の積立金
・実施機関積立金 → 実施機関(厚生労働大臣を除く。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分
★第79条の3(積立金の運用)のポイント
・特別会計積立金の運用 → 厚生労働大臣が行う。
・実施機関積立金の運用 → 実施機関(厚生労働大臣を除く)が行う。
社労士受験のあれこれ
【改正】厚年 / 在職老齢年金
H28.7.6 在老改正 「資格喪失月まで」→「退職月まで」に変更
H28.3.26にUPした記事ですが、内容に言葉が足りない部分がありましたので、修正し、再度UPいたします。
受験生の皆様にはご迷惑をかけますが、もう一度お読みいただければ幸いです。
在職老齢年金(在老)とは、
厚生年金保険料を負担しながら、受け取る老齢厚生年金のことです。
年金の月額と報酬との合算によっては、年金が停止になる制度です。(場合によっては、年金が全額支給されることもあるし、逆に年金が全額支給停止になることもあります。
さて、在職老齢年金の年金の停止額は「月単位」で算定されます。
在職老齢年金の条文は以下の通りですが、かなり長文なので、「どの月が在老の対象で支給停止になるのか」というポイントだけ読んでみてください。
(支給停止)
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

在老の規定が適用される月は、「被保険者である日が属する月」です。
ただし、要件は、「前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。」とされています。
例えば、老齢厚生年金の受給権者が再就職して厚生年金保険の被保険者になった(前月以前から引き続いて被保険者の資格を有していないものとする)場合、再就職後の在老の規定が適用されるのは、資格取得月の翌月からとなります。

*では、退職し資格を喪失した場合の扱いはどうでしょう?
上記改正条文の(厚生労働省令で定める日を除く。)の部分に注目してください。
この「厚生労働省令で定める日」は施行規則第32条の2で以下のように規定されています。
『法第46条第1項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第14条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した場合に限る。)とする。』→ 簡単に言うと、「被保険者の資格を喪失した日」は、「被保険者である日」としないということ
●改正前は、「被保険者の資格を喪失した日」は、「被保険者である日」と扱われていたので、在老の規定は「資格を喪失した日の属する月」まで適用されていました。そのため、月末退職(翌月1日が資格喪失日)の場合は、退職月の翌月まで在老の規定が適用されていました。
●しかし、改正後は、「被保険者の資格を喪失した日」は「被保険者である日」と扱われなくなりました。
すると、月末退職の場合翌月1日が資格喪失日なので、退職月の翌月は「被保険者である日が属する月」ではありませんよね。被保険者である日が属するのは「退職月」までとなるので、在老の規定も「退職月」までということになります。(前月から引き続いて被保険者であるという前提・次の再就職は考えずに)
<例> 前月から引き続いて被保険者であるという前提・次の再就職は考えずに
| ◆7月31日退職・8月1日資格喪失の場合 | 在老の適用は退職月の7月まで |
| ◆7月6日退職・7月7日資格喪失の場合 | 在老の適用は退職月の7月まで (改正前も7月までだった) |
★★改正のポイント! 月末退職でも、在老の適用は「退職月まで」となったこと | |
科目別 厚生年金保険法はこちら
【改正】厚生年金保険法練習問題
H28.7.4 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。
【問題1】
老齢厚生年金の受給権者が、平成28年4月6日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同年7月31日に退職しその後再就職しなかった場合、在職老齢年金の仕組みが適用されるのは、7月までである。
【問題2】
1か月以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する昭和38年4月1日生まれの男子が、60歳になった場合、その者が、老齢厚生年金の受給資格を満たし、かつ国民年金の任意加入被保険者でないときは、65歳に達する前に、実施機関に当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。(坑内員、船員、特定警察職員等には該当しないものとする。)
【問題3】
実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。

<解答>
【問題1】 ○
在職老齢年金は、「被保険者である日が属する月」が対象です。改正で、「資格を喪失した日」は、「被保険者である日」とされなくなりました。
設問の場合、7月31日退職・8月1日喪失(その後再就職なし)ですので、8月は「被保険者である日がない」ので、在職老齢年金の規定は適用されず、退職月の7月までが在老の対象です。
★★お詫びとお知らせ★★
在職老齢年金についてUPした平成28年3月26日の記事の説明に不備がありました。現在非公開にしていますが、後日訂正の上再度UPいたします。
受験勉強中の皆様にはご迷惑をおかけします。申し訳ございません。
【問題2】 ○
「65歳に達する前に」がポイントです。65歳に達する前に、繰上げの請求をすることができるのは、老齢厚生年金の支給が65歳からの者(60歳台前半の老齢厚生年金が支給されない世代)であることに注意しましょう。
ポイント!
★65歳に達する前に実施機関に繰上げの請求ができる者★
① 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和36年4月2日以後生まれ(③及び④を除く。)
② 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和41年4月2日以後生まれ(③及び④を除く。)
③ 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上である者であって、昭和41年4月2日以後生まれ(④を除く。)
④ 特定警察職員等である者で昭和42年4月2日以後生まれ
【問題3】 ○
改正で、主語が厚生労働大臣から「実施機関」に変わりました。
社労士受験のあれこれ
【改正】厚生年金保険法練習問題
H28.6.27 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。
【問題1】
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは在職老齢年金と呼ばれるが、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日が属する月についても在職老齢年金の仕組みが適用されることになった。
【問題2】
63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職したことによりその被保険者の資格喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。
【問題3】(H23年出題改)
在職老齢年金の支給停止調整額は、法律上、賃金等の変動に応じて改定する仕組みとなっている。平成28年度の在職老齢年金の支給停止調整額については、47万円から46万円に改定された。

<解答>
【問題1】 ○
国会議員・地方公共団体の議会の議員も在職老齢年金の対象になりました。
なお、国会議員又は地方公共団体の議会の議員の総報酬月額相当額は、「その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」と規定されています。
★こちらの記事もどうぞ → H28.3.27 国会議員、地方公共団体の議会議員も在老の対象に
【問題2】 ×
退職時改定は、「資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに至った日にあってはその日)から起算して1月を経過した日の属する月」から、行われることになりました。
適用事業所に使用されなくなったとき(第14条第2号)は、翌日に資格を喪失しますが、退職時改定は「使用されなくなった日」から起算して1月を経過した日の属する月からとなります。
例えば9月30日に退職した場合は10月1日に資格を喪失しますが、退職時改定は、9月30日から1月を経過した日の属する月である10月に行われます。
★こちらの記事もどうぞ → H28.3.24 退職時改定の起算日
【問題3】(H23年出題改) ×
平成28年度の支給停止調整額は、平成27年度と同じ47万円です。
ちなみに、60歳代前半の支給停止調整開始額28万円、支給停止調整変更額47万円も変更ありません。
社労士受験のあれこれ
【改正】厚生年金保険法 練習問題
H28.6.20 月曜日は厚生年金保険法改正個所の練習問題
毎週月曜日は、改正厚生年金保険法からの練習問題です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう。
【問題1】
60歳台前半の老齢厚生年金は、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上あり、1年以上の被保険者期間を有する者に支給されるが、2以上の種別に係る被保険者であった期間を有する者の場合、合算して1年以上あれば要件を満たす。
【問題2】
昭和41年4月2日以後生まれの女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【問題3】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子の支給開始年齢の読み替えに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
B 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
C 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
D 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
E 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。

<解答>
【問題1】 ○
60歳台前半の老齢厚生年金の要件の「1年以上の被保険者期間」は、2以上の種別に係る被保険者であった期間を有する場合は、合算して1年以上あればOKです。
【問題2】 ○
★老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳以上になる者(60歳代前半の老齢厚生年金が支給されない)の生年月日はおさえておきましょう。
・ 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。) → 昭和36年4月2日以後生まれ
・ 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)→ 昭和41年4月2日以後生まれ
・ 坑内員、船員の特例 → 昭和41年4月2日以後生まれ
・ 特定警察職員等 → 昭和42年4月2日以後生まれ
【問題3】 Aが誤り 61歳以上ではなく「60歳以上」です
支給開始年齢の引き上げの生年月日は必ず覚えておきましょう。
「男子又は女子(第2号、第3号、第4号)」の生年月日をまず押さえて、「女子(第1号)」はプラス5年で覚えましょう。
女子については2パターンあることがポイント。!
パターン①「第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。」とパターン②「第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。」に分かれています。
長文ですが、赤字の部分<①女子「第2号、第3号、第4号」と②女子「第1号」>だけしっかり見てくださいね。一字一句読まなくてもいいです。
詳しくはこちらをクリック
国・地方公共団体の扱い
H28.6.17 金曜日は横断 (国・地方公共団体の扱い)
金曜日は横断です。
国・地方公共団体の扱いについて過去の出題ポイントを集めました。
【労災保険法】
① H11年記述
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業や< A >の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、適用されない。
② H20年出題
労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(行政執行法人を除く。)の職員には適用される。
【雇用保険法】
③ H22年出題
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
④ H27年出題
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
【健康保険法】
⑤ H14年出題
健康保険法の適用される法人の事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。
⑥ H20年出題
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
【厚生年金保険法】
⑦
適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。

<解答>
【労災保険法】
① H11年記述 A 官公署
労働者を1人でも使用する事業は業種関係なく原則として労災保険法の適用事業となります。
ただし、国の直営事業(現在当てはまる事業はありません)、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)= 非現業の官公署のことは、労災保険法から除外されています。国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法で保護されるからです。
さらにポイント!
都道府県、市町村の現業部門は、労災保険法上では適用除外になっていませんが、「常勤職員」は地方公務員災害補償法の規定で労災保険法の適用が除外されています。
また、都道府県、市町村の現業部門の「非常勤職員」は、地方公務員災害補償法の適用が受けられないので、労災保険法の適用を受けることになります。
さらにさらにポイント!!
労災保険法は「国」の事業は全面的に適用除外ですが、「都道府県、市町村」の事業の場合は、「現業部門の非常勤職員」に労災保険法が適用されます。
労働保険徴収法で「二元適用事業」になるのは、「都道府県及び市町村の行う事業」で、国の行う事業は二元適用事業にはなりませんよね。「国」の行う事業は、そもそも労災保険が成立することがないからです。
② H20年出題 ○
行政執行法人の職員 → 国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用除外
行政執行法人以外の独立行政法人の職員 → 労災保険法適用
【雇用保険法】
③ H22年出題 ×
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、原則として雇用保険法の適用事業です。
④ H27年出題 ○
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業には雇用保険が適用されます。しかし、公務員が離職した場合は、法令、条例、規則等で確実な保障が設けられているため、その諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められ、一定の要件を満たした者は、雇用保険の適用は除外されます。
<適用除外されるもの>
■国又は行政執行法人の事業に雇用される者(非常勤職員で国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものを除く。)
■都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
■市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
ポイント!
「都道府県等」と「市町村等」は、雇用保険の適用除外の「承認を受けること」が要件です。
【健康保険法】
⑤ H14年出題 ×
国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所に含まれます。
⑥ H20年出題 ×
先ほどの問題でも勉強したように、国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所です。そして、国や地方公共団体に使用される者は、健康保険法上適用除外になっていないので、法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となります。
ただし、健康保険法第200条(共済組合に関する特例)で、「共済組合の組合員に対しては、この法律による保険給付は行わない」と規定されているため、実際は健康保険給付の保険給付(保険料の徴収も)は行われません。
<まとめ>
共済組合の組合員(国家公務員、地方公務員)は適用除外されていないため、健康保険法の被保険者となります。ただし、保険給付は行われないし、保険料も徴収されません。
私立学校教職員共済制度の加入者も同じ扱いです。
【厚生年金保険法】
⑦ ×
私立学校教職員共済制度の加入者は厚生年金保険の第4号厚生年金被保険者となります。
◆厚生年金保険の被保険者は4種類
1.2.から4.までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者 → 第1号厚生年金被保険者
2.国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第2号厚生年金被保険者
3.地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第3号厚生年金被保険者
4.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者 → 第4号厚生年金被保険者
社労士受験のあれこれ
【改正】厚生年金保険法 練習問題
H28.6.13 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、厚生年金保険法の改正箇所からの練習問題の日です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう!
【問題1】
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、実施機関が定める。
【問題2】
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。
【問題3】
空欄を埋めてください。
政府は、第2条の4第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第79条の2に規定する< A >をいう。)を< B >が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
【問題4】
保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。
【問題5】
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払うが、支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
【問題6】
一定の要件を満たした老齢厚生年金には加給年金額が加算されるが、加給年金額は、配偶者については224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とし、子については1人につき74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。

【解答】
【問題1】 ×
現物給与の価額は、実施機関ではなく厚生労働大臣が定める。(変更なし)
【問題2】 ×
厚生労働大臣ではなく「実施機関」が裁定する。
【問題3】 A 実施機関積立金 B 政府等
※「政府等」は第32条(保険給付の種類)で登場します。
この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政府等」という。)が行う。
1. 老齢厚生年金
2. 障害厚生年金及び障害手当金
3. 遺族厚生年金
※「実施機関積立金」は第79条の2(運用の目的)で登場します。
積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
【問題4】 ×
端数処理は1円単位です。「50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる」です。
ちなみに、「保険給付の額を計算する過程」の端数処理は、令3条で「保険給付の額を計算する過程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。」と定められています。
【問題5】 ×
年金は年6期に分けて偶数月に前月までの2カ月分が支給されますが、支払期月ごとの支払額の端数は「1円未満切り捨て」です。
ちなみに、毎年3月から翌年2月までの切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数は切り捨てた額)は、翌年2月の支払期月の年金額に加算されることになりました。
【問題6】 ×
加給年金額は100円単位の端数処理です。50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。
例えば平成28年度の配偶者の加給年金額は、224,700円×0.999(改定率)=224475.3≒224,500円となります。
社労士受験のあれこれ
書類の保存期間 2年3年4年5年
H28.6.10 金曜日は横断 書類の保存期間
書類の保存期間は2年、3年、4年、5年、それ以外と各法律さまざまです。
でも、覚えておけば得点できます。どんどん覚えましょう。
では、過去問をどうぞ。
① 労働基準法(H22年出題)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
② 労働安全衛生法(H22年出題)
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
③ 労働安全衛生法(H19年出題)
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。
④ 労働安全衛生法(H21年出題)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
⑤ 労災保険法
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管しなければならない。
⑦ 徴収法(H19年出題)
事業主もしくは事業主であった者又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。
⑧ 徴収法(H22年出題)
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は4年である。
⑨ 健康保険法(H22年出題)
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題)
事業主は、厚生年金保険法に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

【解答】
① 労働基準法(H22年出題) ○
ポイント
・ その他労働関係に関する重要な書類 → タイムカード等の記録、残業命令書等が該当する
・ 企画業務型裁量労働制の実施状況にかかる労働者ごとの記録 → 決議の有効期間中+その満了後3年間)
② 労働安全衛生法(H22年出題) ○
・ 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育のうち、保存義務があるのは特別教育のみ。
・ 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議事で重要なものに係る記録も保存期間は3年
③ 労働安全衛生法(H19年出題) ○
④ 労働安全衛生法(H21年出題) ○
・ 保存期間が5年のもの → 健康診断個人票、面接指導の結果の記録(長時間労働、ストレスチェック)
⑤ 労災保険法 ×
2年間ではなく、3年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題) ○
・ 雇用保険に関する書類(雇用保険二事業及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。) → 2年間
・ 被保険者に関する書類 → 4年間
⑦ 徴収法(H19年出題) ×
⑧ 徴収法(H22年出題) ○
・ 労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類 →その完結の日から3年間
・ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 → 4年間
ポイント
・ 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿もおさえておきましょう。
① 労働保険事務等処理委託事業主名簿
② 労働保険料等徴収及び納付簿
③ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
①と②は3年間、③は4年間保存
⑨ 健康保険法(H22年出題) ×
5年間ではなく「2年間」保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題) ×
厚生年金保険法に関する書類 → その完結の日から2年間保存
健康保険法と同じなのでおぼえやすいです。
【改正】厚生年金保険法 練習問題
H28.6.6 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、厚生年金保険法の改正箇所からの練習問題の日です。
問題を解きながら改正ポイントを身につけましょう!
【問題1】
同一の適用事業所において使用される被保険者について、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別に変更があった場合は、資格の取得と喪失の規定は、被保険者の種別ごとに適用される。
【問題2】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日の翌日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
【問題3】
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失についても、資格の得喪についての確認の規定が、適用される。
【問題4】
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失し、その月に更に国民年金法に規定する第3号被保険者の資格を取得した場合には、その月は1月の被保険者期間として算入される。

■■アドバイス■■
種別ごとに管理されるというイメージで解いてもらえば大丈夫だと思います。
<解答>
【問題1】 ○
例えば、同一の適用事業所で、ある被保険者について、常勤職員(第2号厚生年金被保険者)から短時間勤務職員(第1号厚生年金被保険者)に変更があった場合は、第2号厚生年金被保険者の資格を喪失し、第1号厚生年金被保険者の資格を取得することになります。
同一の適用事業所でも取得・喪失の規定が適用(2号喪失・1号取得)されることがポイントです。
【問題2】 ×
「翌日」ではなく「その日」です。
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者が、同時に第1号厚生年金被保険者の資格を有することはありません。(2号、3号、4号と1号が重複することはない)
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
ここもポイント!
厚生年金保険の「被保険者期間」は、被保険者の種別ごとに適用されます。
・ 第1号厚生年金被保険者であった期間 → 第1号厚生年金被保険者期間
・ 第2号厚生年金被保険者であった期間 → 第2号厚生年金被保険者期間
・ 第3号厚生年金被保険者であった期間 → 第3号厚生年金被保険者期間
・ 第4号厚生年金被保険者であった期間 → 第4号厚生年金被保険者期間
【問題3】 ×
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、資格の得喪の確認は不要です。
【問題4】 ×
この場合、厚生年金保険の被保険者期間は0箇月となります。
厚生年金保険法第19条第2項では、「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」と規定されています。
<原則> 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき
→ 1箇月として被保険者期間に算入
<例外>
・その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき
→ 後の分のみを被保険者期間に算入
・その月に更に国民年金の被保険者(第1号被保険者、第3号被保険者)の資格を取得したときは
→ 被保険者期間には算入しない(0箇月) <改正点>
★参考★
以前の記事はコチラ → 被保険者期間の計算(同一月内の取得と喪失)
社労士受験のあれこれ
横断 国民年金と厚生年金保険の時効
H28.6.3 金曜日は横断 /国年と厚年
国民年金法、厚生年金保険法の時効として「2年」と「5年」があります。
国民年金と厚生年金保険の違う点を意識してください。
では、まず国民年金法から。
(国民年金法)
(時効)
年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
<問題 H18年出題>
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
【解答】 ×
「給付」を受ける権利ではなく「年金給付」を受ける権利の時効は5年です。
★★注意しましょう★★
国民年金の「給付」は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金。「給付」の内容には「年金」と「一時金」があります。
「給付」と「年金給付」では範囲が違うことに注意してください。
給付のうち、「年金給付」の時効は5年、「死亡一時金」の時効は2年です。
次は厚生年金保険です。
(厚生年金保険法)
(時効)
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
<問題 H23年出題>
保険給付を受ける権利は、5年を経過したとき、時効により消滅する。
【解答】 ○
★★ポイント★★
「保険給付」を受ける権利の時効は5年です。「保険給付」ですので、年金も一時金も両方とも時効は5年です。
<国年と厚年の時効の比較>
| 2年 | 5年 | |
| 国民年金法 | 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利 死亡一時金を受ける権利 | 年金給付を受ける権利 |
| 厚生年金法 | 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利 | 保険給付を受ける権利 |
科目別 国民年金法
科目別 厚生年金保険法
社労士受験のあれこれ
【改正】厚生年金保険法 練習問題 第1回目
H28.5.30 毎週月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
毎週月曜日は、厚生年金保険法の今年の改正個所から作成した問題を出します。
1年目はさらりと基本事項が出題されることが多いので、本試験に改正個所が出たらlucky★です。
【選択式】
①第2条 厚生年金保険法は、 A が管掌する。
②第2条の5 厚生年金保険法の実施機関は、被保険者の種別ごとに次のように定められています。
「第1号厚生年金被保険者」に係る事務 → B
「第2号厚生年金被保険者」に係る事務 → 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
「第3号厚生年金被保険者」に係る事務 → 地方公務員共済組合、 C 及び地方公務員共済組合連合会
「第4号厚生年金被保険者」に係る事務 → D
③附則第4条の3
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、 E 。
<Eの選択肢>
ⅰ 厚生労働大臣の認可を受ける必要がある
ⅱ 実施機関に申し出る必要がある
【択一式】
適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。

【解答】
①A 政府
★ここは改正されていません。財政面・管理運営面で責任を負うのは国(厚生労働省)です。「実施機関」ではありませんー。
②B 厚生労働大臣
C 全国市町村職員共済組合連合会
D 日本私立学校振興・共済事業団
③ ⅱ 実施機関に申し出る必要がある
★厚生労働大臣に申し出から実施機関に申し出に改正されました。
「適用事業所」なので、事務を担当する実施機関が存在するからです。
ちなみに、任意単独被保険者、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は「厚生労働大臣の認可」で変更はありません。
そもそも厚生年金保険に加入していない「適用事業所以外」なので実施機関は関係ないですよね。
【択一式】 ×
平成18年に出題された問題で、当時は「○」でしたが、現在は「×」です。
改正前は、共済組合の組合員、私学教職員共済制度の加入者は、厚生年金保険は適用除外でしたが、現在は、被用者年金一元化で厚生年金保険の被保険者となっています。
社労士受験のあれこれ
厚生年金と労災保険 併給調整その3
H28.5.26 厚年「障害手当金」と労災保険の保険給付
社会保険と労災保険の調整のルールを2回お話ししました。
第1回目はコチラ → 同一事由で国年・厚年と労災保険から給付を受けられるとき
第2回目はコチラ → 第30条の4の障害基礎年金と労災保険の調整
★第3回目は、厚生年金保険法の「障害手当金」と労災保険の障害(補償)給付等の併給調整についてです。
まず、厚生年金保険法をチェックしてみましょう。
障害の程度を定めるべき日において次の①~③のいずれかに該当する者には、障害手当金の支給要件を満たしていても、障害手当金は支給されません。
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③ 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

③に注目してください。
同じ傷病が原因で、労働基準法の障害補償、労働者災害補償保険法の障害(補償)給付を受ける権利がある場合は、障害手当金は支給されない、と規定されています。

では、次の過去問を解いてみましょう。
H25年出題(厚年)
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

【解答】×
労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者にも、支給されません。

ついでにここもチェック
先ほどの①と②についてもついでに見ておきましょう
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
→ 厚生年金保険の年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)の受給権者には障害手当金は支給しない、ということ。
<例外> 障害厚生年金の受給権者でも、最後に障害状態に該当しなくなってから3年経過している者には、要件に合えば障害手当金が支給される
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
→ 厚生年金保険の年金と同じ考え方。国民年金の年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者には障害手当金は支給しない、ということ。
例外の考え方も同じです。
社労士受験のあれこれはコチラ
国年・厚年と労災保険 併給調整その1
H28 .5.18 同一事由で国年・厚年と労災保険から給付を受けられるとき
まず、労災保険、国民年金、厚生年金保険の目的を確認してみるとこんな感じになります。
| 労災保険 | 国民年金 | 厚生年金保険 |
業務上・通勤による 負傷、疾病、障害、死亡等 | 老齢、障害、死亡 (業務上外は問わない) | 老齢、障害、死亡 (業務上外は問わない)
|
例えば、民間企業のサラリーマンが業務上や通勤により死亡した場合は、労災保険と国民年金と厚生年金保険から、遺族に対して遺族年金が支給されることになります。が、すべて100%ずつ支給されるわけではありません。
ポイント!
「同一の事由」で労災保険の年金給付と社会保険(国民年金・厚生年金保険)が支給される場合は、労災保険の年金給付が減額されます。
※社会保険は本人が保険料を負担しているので減額するのは問題ありです。一方、労災保険の保険料は全額事業主負担(本人負担なし)なので労災保険の方を減額しましょうという考え方です。
ということでポイントは
| 「同一事由」による労災保険の年金給付と社会保険(国年・厚年)の調整 |
| 労災保険の年金給付 → 減額支給 |
| 社会保険(国年・厚年) → 全額支給 |

では、問題を解いてみましょう!
① H14年出題(労災)
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金又は遺族年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
② H12年出題(労災)
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることになる。
③ H12年出題(労災)
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。
④ H26出題(国年)
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
⑤ H12年出題(国年)
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

【解答】
① H14年出題(労災) ○
「同一の事由」で社会保険(国年・厚年)の年金と労災保険の年金給付が支給される場合は、労災の年金給付が減額調整されるので○です。
なお、国民年金法の寡婦年金も「死亡」によって支給される年金ですので忘れないでくださいね。
② H12年出題(労災) ○
休業補償給付(休業給付)と厚生年金保険法の障害厚生年金又は国民年金法の障害基礎年金が同一事由で支給されることもあり得ます。その場合は、休業補償給付(休業給付)が減額調整されます。
労災保険は年金給付だけでなく、休業補償給付(休業給付)も減額調整の対象ですので押さえてくださいね。
③ H12年出題(労災) ○
労災保険の年金給付が減額調整されるのは「同一事由」の社会保険(国年・厚年)の年金です。老齢厚生年金・老齢基礎年金と同一事由の労災保険の年金給付はありませんので、同時に受ける労災の年金給付も減額調整されません。
④ H26出題(国年) ○
同一事由で、遺族基礎年金と労災保険法の遺族補償年金を受けることができる場合は、労災保険法の遺族補償年金が減額調整され、遺族基礎年金は全額支給されます。
⑤ H12年出題(国年) ○
労災保険の年金給付との調整と間違えないようにしてくださいね。
併給調整その2に続きます!
社労士受験のあれこれはこちら
遺族の失権 ~国年・厚年~
H28.5.4 子(孫)の失権の時期■国年・厚年
遺族基礎年金(国年)、遺族厚生年金(厚年)の子、孫(孫は厚年のみ)の失権の時期をチェックしましょう。
ちなみに労災保険の遺族(補償)年金の子、孫、兄弟姉妹の失権時期はこちらから → ★
では、遺族基礎年金の子、遺族厚生年金の子、孫の要件から確認してみることにしましょう。
<国民年金>
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
<厚生年金保険>
子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
※ ちなみに国民年金法では「障害等級」と表現されますが、厚生年金保険法では「障害等級の1級又は2級」と表現されます。厚生年金保険法の場合、「障害等級」は「1級から3級」までですよね。3級は含まない「1級又は2級」限定という意味です。
子(又は孫)の要件に該当しなくなったときに遺族基礎(厚生)年金の受給権が消滅します。
<国民年金>
① 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
→ 原則は高校卒業の年度末で失権。ただし、そのときに障害状態にある場合は失権しない。
② 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
→ 障害状態に該当しなくなっても高校卒業の年度末までは失権しない。
③ 20歳に達したとき。
→ 遺族基礎年金は20歳で失権(20歳以降は、本人に30条の4(20歳前にあ初診日がある)の障害基礎年金が支給される)
※厚生年金保険は「子、孫」、「障害等級の1級又は2級」に読み替えてください。

では、問題を解いてみましょう。
①国年H16年出題
遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。
②厚年H22年出題
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①国年H16年出題 ○
被保険者等の死亡当時に障害状態になく、その後障害状態になった場合でも18歳年度末に障害状態にあれば20歳まで遺族基礎年金を受給できます。
比較してみましょう!
労災保険は、死亡当時に障害状態にあれば障害状態にある限り受給できます。違いに注意してくださいね。労災保険はこちら→ ★
②厚年H22年出題 ○
18歳年度末に障害状態(1級又は2級)にあれば20歳まで受給できますが、3級の場合は原則どおり18歳年度末で失権です。
社労士受験のあれこれはこちら
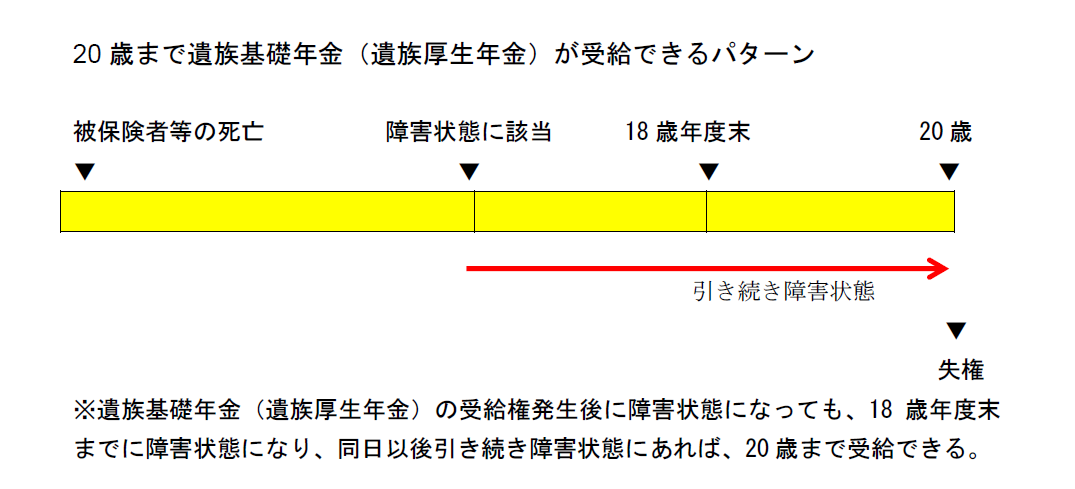
横断 労災保険法と厚生年金保険法の遺族
H28.4.20 転給 → 労災(有)、厚年(無)
労災保険 遺族(補償)年金 | 厚生年金保険 遺族厚生年金 |
労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 (妻以外の者は、一定の年齢要件又は障害要件に該当すること)
| 被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は入らない) (妻以外の者は、一定の年齢要件に該当すること) (注)H8.4.1前に死亡した者の夫、父母、祖父母の場合は死亡当時一定の障害状態に該当していれば遺族となっていた |
| ○共通点○ 「妻」には、年齢要件も障害要件もつかない | |
「受給資格者」のうち最先順位者が「受給権者」となる。 受給権者が失権した場合、転給の制度がある。(転給=受給資格者の中で受給権が移っていく制度) | 最先順位者のみ受給権を取得。 後順位者は遺族の範囲に入らない。(遺族厚生年金は受けられない。) 転給制度なし。 |
問題を解いてみましょう。
<労災保険法>
①H17年出題
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当するものに限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。
②H18年出題
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。
<厚生年金保険法>
③H16年出題
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となることはできない。
④H23年出題
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

【解答】
<労災保険法>
①H17年出題 ○
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(受給資格者)の要件
・ 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(妻以外は、一定の年齢要件又は障害要件あり)
・ 労働者の死亡の当時生計を維持されていたこと
②H18年出題 ○
受給資格者の内の順位です。
受給資格者の中で最先順位者が受給権者(年金を受ける権利がある者)となります。
例えば、死亡当時生計を維持されていた妻と母(60歳)がいる場合、受給資格者は妻と母の2人です。受給資格者の内の順位は①妻、②母となり、「受給権者」は最先順位の妻となります。
その後、妻の受給権が失権した場合は、次の順位の母に受給権が移ります。このことを転給といいます。
ポイント!
受給資格者のうち、最先順位者が受給権者となります。
<厚生年金保険法>
③H17年出題 ○
死亡当時子と母がいた場合、先順位の子だけが遺族厚生年金の受給権者になり、後順位の母は遺族厚生年金の対象にはなりません。転給の制度もないので、子が失権した後に母が受給権者になることもありません。
④H23年出題 ×
上の③H16年の問題と同じです。死亡当時妻と母がいた場合、妻が遺族厚生年金の受給権者になり、母は遺族厚生年金の対象にはなりません。転給の制度もありませんので、母に受給権が移ることもありません。
ポイント!
厚生年金保険法第59条2項
「父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」
遺族厚生年金の順位は、①配偶者又は子、②父母、③孫、④祖父母です。
例えば「①配偶者又は子」が受給権を取得したら、②父母③孫④祖父母は遺族厚生年金の対象から外れるということです。
社労士受験のあれこれはこちら
横断 国民年金と厚生年金保険の任意加入
H28.4.12 老齢年金の受給権を有しない者の任意加入
国民年金、厚生年金には、老齢年金の受給権のない者の任意加入の制度があります。
国民年金と厚生年金の主な違いは次の点です。
<老齢年金の受給権がない者の任意加入>
| 国民年金(特例任意加入被保険者) | 厚生年金(高齢任意加入被保険者) | |
| 生年月日 | 昭和40年4月1日以前生まれ | 要件なし |
| 年齢 | 65歳以上70歳未満 | 70歳以上 |

過去問でチェックしてみましょう。
<国民年金>H27年出題
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
<厚生年金>H20年出題
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。
<厚生年金>H26年出題
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

<国民年金>H27年出題 ×
昭和30年4月1日以前ではなく「昭和40年4月1日以前」生まれが対象
<厚生年金>H20年出題 ○
<厚生年金>H26年出題 ×
「適用事業所以外」の場合は、厚生労働大臣に申し出ではなく厚生労働大臣の「認可」を受け、「認可があった日」に資格を取得する。
ポイント!
厚生年金・高齢任意加入被保険者は、「適用事業所」か「適用事業所以外」かで違う。どちらの問題なのか確認してから解答しましょう!
| 適用事業所の高齢任意加入被保険者 | 適用事業所以外の高齢任意加入被保険者 |
実施機関に申し出る *事業主の同意はなくてもよい | 厚生労働大臣の認可を受ける 事業主の同意を得る |
| 申出が受理された日に資格を取得 | 認可があった日に資格を取得 |
横断 保険料の納付期限
H28.4.10 健・国年・厚年の保険料納付期限
健康保険・国民年金・厚生年金の保険料の納付期限を整理しましょう。
表は、左から「納付義務者」「納付期限」「負担義務」です。
健康保険
| 事業主 | 翌月末日 | (原則)事業主と被保険者が 2分の1ずつ負担 |
任意継続被保険者 | 当月10日 (初回分は保険者が指定する日) *前納制度あり (前納に係る期間の初月の前月末日) | 全額任意継続被保険者が負担 |
国民年金
第1号被保険者 任意加入被保険者 特例任意加入被保険者 | 翌月末日 *前納制度あり | 世帯主・配偶者の一方は 被保険者の保険料を連帯して納付する義務あり |
厚生年金保険
事業主 当然被保険者 任意単独被保険者 高齢任意加入被保険者 (適用事業書・事業主の同意あり) 高齢任意加入被保険者 (適用事業所以外) | 翌月末日 | 事業主と被保険者が2分の1ずつ負担 |
高齢任意加入被保険者 (適用事業所・事業主の同意なし) | 翌月末日 *前納制度 なし | 全額被保険者が負担 |

過去問で練習してみましょう
<健保H13年出題>
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を前納することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。
<健保H15年出題>
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
<国年H18年出題>
毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。
<厚年H21年出題>
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。

【解答】
<健保H13年出題> ×
前納の場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
<健保H15年出題> ○
任意継続被保険者は、保険料の納付は本人の義務。保険料も本人が全額負担する。
<国年H18年出題> ×
任意加入被保険者も保険料の納付期限は翌月末日。
<厚年H21年出題> ×
適用事業所の高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者も、保険料の納付期限は翌月末日。
【改正】厚生年金保険法
H28.3.27 国会議員、地方公共団体の議会議員も在老の対象に
昨日、在老の改正についてお話ししました。
昨日の記事はこちら → 資格喪失月の在職老齢年金
「在職老齢年金」は「厚生年金の被保険者」でありかつ「老齢厚生年金の受給権者」が対象です。
ただし、70歳になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますが、一定の要件に該当する場合は、「70歳以上の使用される者」(被保険者とは言わないので注意)として在老の適用を受けます。
★それに加えて、改正により、「国会議員、地方公共団体の議会の議員」も、在職老齢年金の対象になりました。
昨日と同じく第46条を載せます。今日は、「国会議員、地方公共団体の議会の議員」の部分だけ読んでみてください。
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は70歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第27条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とし、70歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
【改正】厚生年金保険法
H28.3.24 退職時改定の起算日 ◆追記あり(H29.3.23)◆
※ 訂正しました(H29.3.23)
説明に紛らわしい点がありました。
赤字で追記しております。
ご迷惑をおかけして申し訳なく思っております。
何卒よろしくお願いいたします。
(平成29年3月23日)
働きながら(=厚生年金保険料を負担する)受給する老齢厚生年金のことを在職老齢年金といいますが、働きながら納付していた保険料は、退職して厚生年金保険の資格を喪失したときに、老齢年金額に反映される仕組みになっています。
このたびの改正で、退職時改定の起算日が変わりました。
まずは、条文を確認してみましょう。
(第43条)
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
※第14条第2号から4号とは?
当然被保険者又は任意単独被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第5号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
三 第8条第1項(任意適用事業所の取消)又は第11条(任意単独被保険者の資格喪失)の認可があつたとき。
四 第12条(適用除外)の規定に該当するに至つたとき。
五 70歳に達したとき。

例えば、3月24日に退職した場合、3月25日が資格喪失日です。(これは変わりません。)
改正前は、3月25日(資格喪失日)から1月を経過した日の属する月(=4月)から、退職時改定により年金額が改定されていましたが、改正により3月24日(退職日)から起算することに変わりました。(どちらにしても改定は4月からです)
では、3月31日に退職した場合は?
4月1日が資格喪失日です。(これも変わりません。)
改正前は、資格を喪失した日(4月1日)から起算して1月を経過した日の属する月(=5月)から退職時改定により年金額が改定されていました。
今回の改正で、「資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。」と変わりました。(青字の部分に注目してください。)
つまり、3月31日に退職の場合は、「その日(=3月31日)」から起算して1月を経過した日の属する月(=4月)から、年金の額を改定することになります。
なお、在職老齢金の支給停止期間も改正されています。
こちらについても後日お話ししますね。
「確認」
H28.3.22 健・厚・雇にはあるが、国、労災にはない
厚生年金保険法では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる」と規定されています。(ただし例外有)
健康保険法、雇用保険法にも「確認」について規定があります。
厚生年金保険法・健康保険法・雇用保険法の共通点は、資格の取得や喪失について、事業主に「届出」が義務づけられている点です。
何月何日に誰が入社して、何月何日に誰が退職したのかをチェックするのが確認です。
一方、「国民年金法」、「労災保険法」には確認の規定はありません。
国民年金法、労災保険法には、資格の得喪について事業主からの届出義務はありませんよね。労災保険は、労働者なら誰でも保護が受けられるので、個人ごとに得喪を届け出る必要はありません。
【改正】厚生年金保険法
H28.3.10 2つ以上の厚生年金被保険者期間がある場合の年金の計算
例えば、サラリーマンだった期間と地方公務員だった期間がある人の場合、被保険者であった期間が2種類になります。(第1号厚生年金被保険者期間と第3号厚生年金被保険者期間)
このように2以上の種別の被保険者であった期間がある場合の年金の計算のルールは以下のとおりです。
■老齢厚生年金■
第1号から第4号まで、それぞれの厚生年金被保険者期間ごとに年金額を計算する
※例えば、第1号厚生年金被保険者期間が10年、第2号厚生年金被保険者期間が15年の場合は、日本年金機構から10年分、国家公務員共済組合から15年分が計算されます。
■障害厚生年金・障害手当金■
合算して年金額を計算する
※例えば、初診日に第1号厚生年金被保険者で、ほかに第2号厚生年金被保険者期間もある場合は、初診日の実施機関である日本年金機構が第2号厚生年金被保険者期間の分も合算して年金を計算します。
■遺族厚生年金■
短期要件 → 合算して年金額を計算する
(障害厚生年金と同じ。初診日を死亡日に読み替える)
長期要件 → 第1号から第4号まで、それぞれの厚生年金被保険者期間ごとに年金額を計算する
【改正】厚生年金保険法
H28.3.2 保険給付の端数処理
厚生年金保険法第35条です。空欄を埋めてください。
保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に A 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 A 以上 B 未満の端数が生じたときは、これを B に切り上げるものとする。

【解答】
A 50銭 B 1円
改正前は50円と100円でしたよね。改正前は100円単位でしたが、改正後は1円単位で裁定、改定されます。
※ 改正後の端数処理は、平成27年10月以後に裁定・改定された保険給付に適用されます。
※ 国民年金法も同様に端数処理方法が改正されています。
※ ただし、老齢基礎年金の満額(780,900円×改定率)などは、50円未満切り捨て50円以上100円未満は100円に切り上げる端数処理(100円単位)です。気をつけてくださいね。
年金制度の歴史
H28.2.29 厚生年金、共済年金、いつからスタートしたの?
平成27年10月より、被用者年金が一元化されています。
一元化された厚生年金、共済年金など、これまでの年金の歴史をおさえておきましょう。
被用者(会社員、船員など)
| 昭和14年 | 船員保険法制定 ・昭和15年6月施行 ・昭和61年4月 厚生年金保険法に統合 |
| 昭和16年 | 労働者年金保険法制定 ・昭和17年6月施行 ・昭和19年 厚生年金保険法に改称 |
被用者(公務員など)
| 昭和23年 | 国家公務員共済組合法制定 ・昭和23年7月施行 |
| 昭和28年 | 私立学校教職員共済法制定(当時の名称は私立学校教職員共済組合法) ・昭和29年1月施行 |
| 昭和37年 | 地方公務員等共済組合法制定 ・昭和37年12月施行 |
自営業者など
| 昭和34年 | 国民年金法制定 ・昭和34年11月 無拠出制スタート ・昭和36年 4月 拠出制スタート |
今日のポイント!
被用者年金(厚生年金、共済年金)のほうが、国民年金よりも歴史が古い。
条文の読み方 ~厚生年金保険法~
H28.2.27 障害厚生年金の受給権者
厚生年金保険法第47条では、障害厚生年金の受給要件が規定されています。
アンダーラインの①被保険者と②国民年金の被保険者の違いを考えてみましょう。
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において①被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに②国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

国民年金法でも厚生年金保険法でも、保険に加入している人のことを「被保険者」といいます。
・ 国民年金法で「被保険者」といえば、国民年金に加入している人のこと
↓
(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、国民年金の任意加入被保険者)
・厚生年金保険法で「被保険者」といえば、厚生年金に加入している人のこと
↓
(会社員や公務員など)
◇ポイント
同じ「被保険者」という用語でも、国民年金法と厚生年金保険法では定義が違う

さて、冒頭の条文は、「厚生年金保険法」第47条です。
「①被保険者」は厚生年金保険法で定義されている被保険者のこと(会社員や公務員など)です。
「②国民年金の被保険者」期間については、「国民年金の」被保険者とわざわざ書いていますので、厚生年金だけでなく「国民年金」の被保険者期間全体をさしています。

ということは、
障害厚生年金の受給の要件は、「初診日」に「厚生年金保険の被保険者である」こと、「保険料納付要件」は国民年金の被保険者期間があるときは、「国民年金全体の保険料納付状況で判断される」ことがポイントです。

今日のポイント
障害厚生年金は、初診日に「厚生年金保険に加入」していることが条件
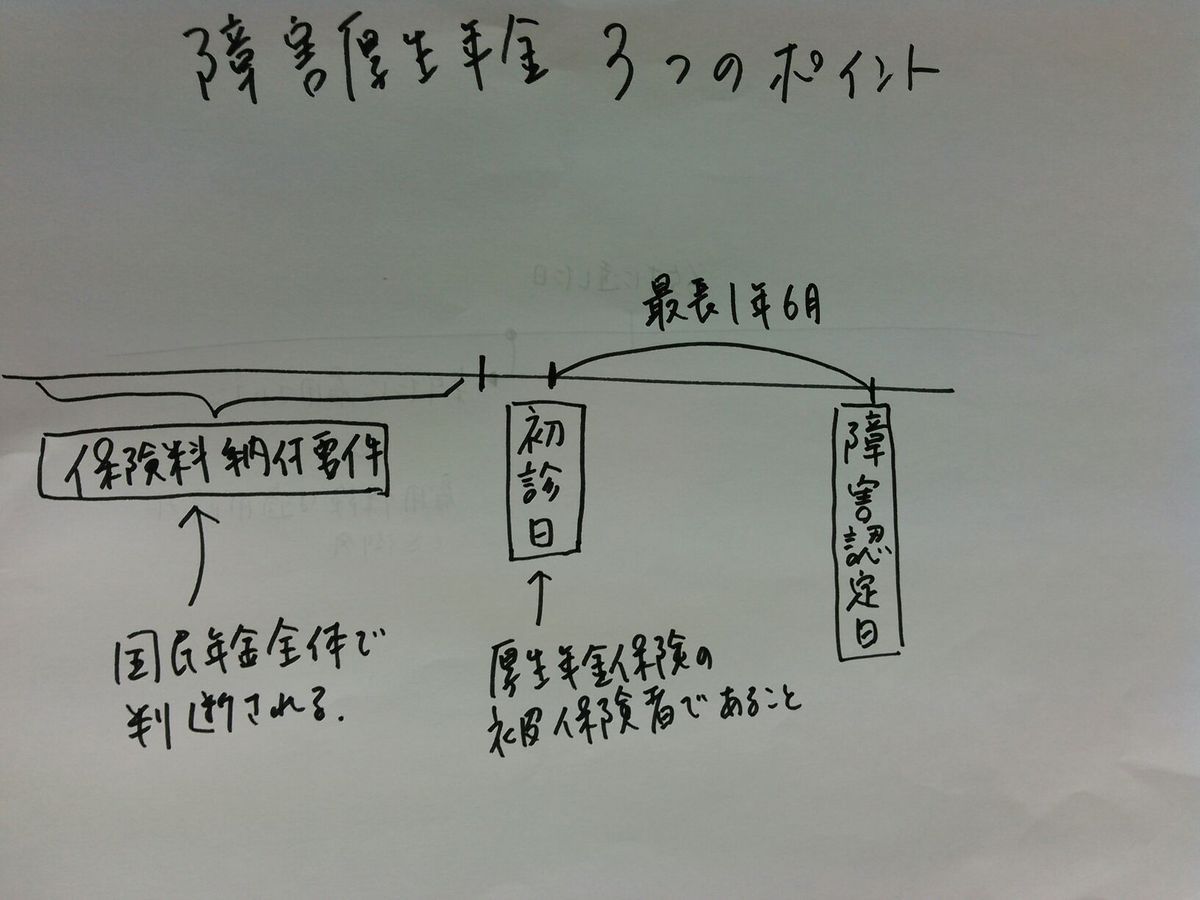
H28.2.10 強制適用事業所(健康保険と厚生年金の違い)
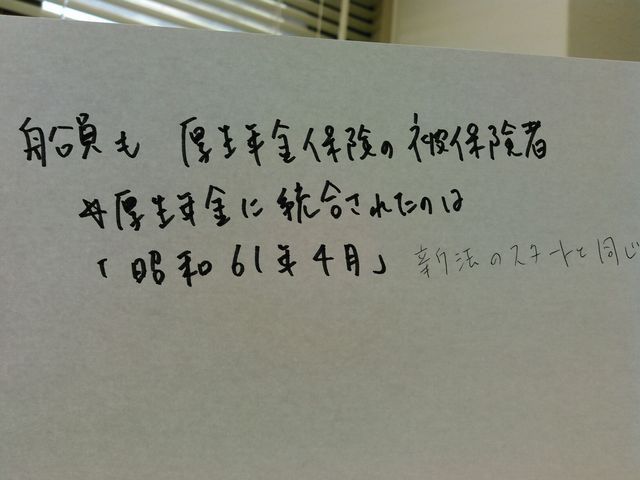
【健康保険法 強制適用事業所】
1 法定16業種で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
2 国・地方公共団体・法人の事業所で常時従業員を使用するもの
【厚生年金保険法 強制適用事業所】
1 法定16業種で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
2 国・地方公共団体・法人の事業所で常時従業員を使用するもの
3 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されるものが乗り組む船舶
■厚生年金は「船舶」が強制適用■
厚生年金の場合、船員が乗り組む「船舶」が強制適用事業所になることがポイントです。
■船員法第1条の船員は、船員保険法の被保険者■
船員法第1条に規定する船員は、「船員保険法」の対象です。
船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行います。
アンダーラインの部分に注目してください。船員法第1条の船員は職務外の傷病等については船員保険法で保障されています。そのため健康保険法は適用除外となります。
一方の年金について。公的年金の歴史で一番古い制度は、実は船員保険法です。かつては、船員は船員保険法で老後の年金などが保障されていました。が、船員の数の減少などにより昭和61年4月に船員保険法から年金部門がなくなり、年金部門は厚生年金保険法に統合されました。
そのため、現在の船員保険法には年金部門がありません。船員は会社員と同様に厚生年金保険に加入することになっています。船員法第1条に規定する船員が乗り組む船舶が厚生年金の強制適用事業所となっているのはそのためです。
ポイント
船員 → 職務外の疾病等は「船員保険法」、老齢・障害・死亡は「厚生年金保険法」
ちなみに・・・
船員保険法には、「労働者災害補償保険法と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う」という目的もありますが、この点はまた別の機会にお話しします。
H28.2.5 特別支給の老齢厚生年金
(二以上の種別の被保険者であった期間を有する場合)
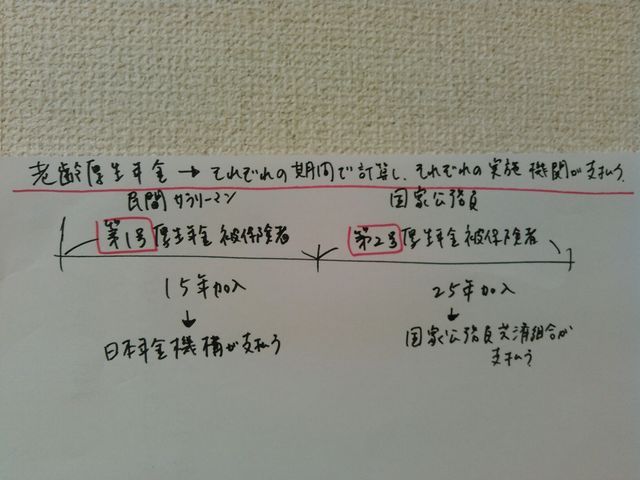
今日は、特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金)についてお話ししますね。
■■4つの種別の厚生年金被保険者■■
被用者年金の一元化により、厚生年金保険の被保険者は、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の4つの種別に分けられるようになりました。
例えば、民間企業のサラリーマンと国家公務員の両方を経験した場合は、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者の2つの種別の厚生年金被保険者期間があることになります。
■■2つ以上の種別の厚生年金被保険者期間がある場合の特別支給の老齢厚生年金■■
特別支給の老齢厚生年金の要件のひとつに、「1年以上の被保険者期間を有すること」があります。
2つ以上の種別の厚生年金被保険者期間がある場合は、合算して「1年以上」あれば、要件を満たします。
■■特別支給の老齢厚生年金額の計算■■
それぞれの種別の厚生年金被保険者期間ごとに計算し、それぞれの実施機関から支給されます。
H28.1.28 国民年金と厚生年金保険の違い
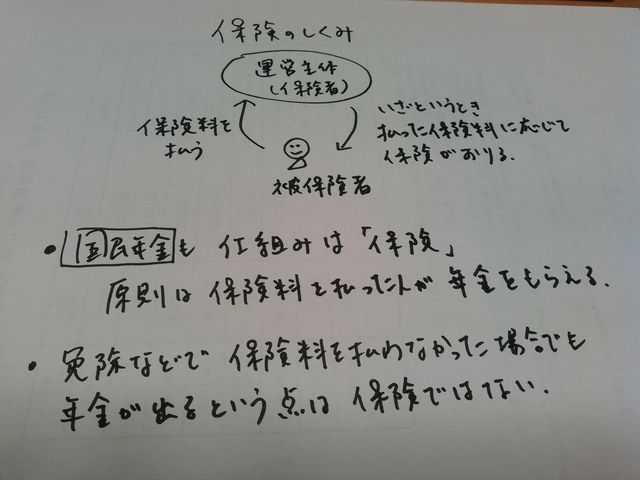
国民年金法と厚生年金保険法という法律の名称。厚生年金保険は「保険」という用語が入っていますが、国民年金は国民年金保険とは言いません。
また、厚生年金は、「保険給付」と言いますが、国民年金は「給付」でやはり保険給付とは言いません。
国民年金法も、原則は、保険料を払った人だけが払った分に応じて年金を受け取る、一方保険料を払わなかった人には年金は出ないという「保険」の仕組みをとっています。
でも、国民年金には、免除などで保険料を払わなかった人に対しても年金が支払われるという面があり、保険ではない部分もあります。
ですので、国民年金保険、保険給付とは言わず「国民年金法」「給付」という用語が使われています。
※とはいっても、国民年金も「被保険者」、「保険料」という用語は使います。国民年金も基本は「保険」です。
H28.1.27 賃金・報酬、賞与
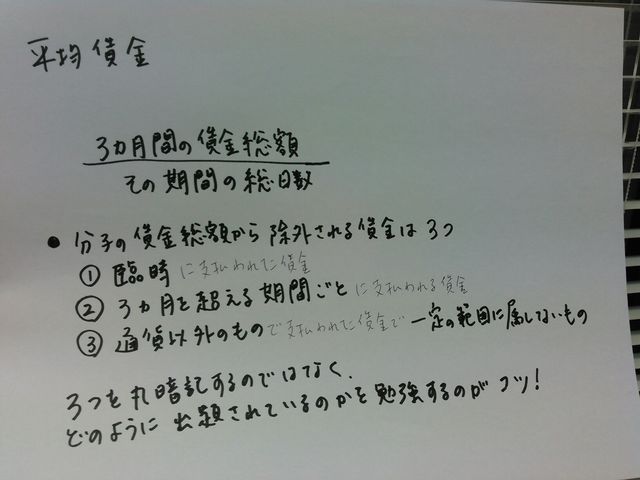
■労働の対償→賃金・報酬、賞与
「労働の対償として受けるもの」は一般的に言うと給料ですが、受験勉強では、まず法律ごとの呼び方を押さえることから始めます。
・労働基準法、雇用保険法、労働保険徴収法では、「賃金」といいます。
*例えば、雇用保険法の基本手当の日額や、徴収法の労働保険料は「賃金」を基に計算します。
・健康保険法、厚生年金保険法では、「報酬、賞与」といいます。
*例えば、厚生年金保険法では会社員として支払う厚生年金保険料や将来受けとる年金額は、「報酬、賞与」を基に計算します。
■ポイント
・「賃金」、「報酬、賞与」は「労働の対償」として支払われるもの
・しかし、保険料や給付額の計算に賃金の全てを算入するわけではない
*例えば、労働基準法の平均賃金は賃金をもとに計算しますが、賃金を全て算入するのではなく、夏・冬のボーナスなど平均賃金の計算から除外される賃金があります。
どの科目でも現物給与、臨時に支払われるものの扱いなどは頻出事項です。過去問で練習して慣れていきましょう。
H28.1.17 年金額の改定
年金は、日々の生活を保障するために支給されるもの。
国民の生活水準は、上がったり下がったりと変動があります。年金の額も、生活水準が上がればアップ、下がればダウンさせる必要があります。
国民年金法、厚生年金保険法、それぞれに年金額の改定についての規定がありますが、国民年金法と厚生年金保険法で違う点、分かりますか?
<国民年金法>
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
<厚生年金保険法>
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金は「国民の生活水準」ですが、厚生年金保険は「国民の生活水準、賃金」となっていますよね。
厚生年金保険法は「労働者」が対象の年金制度なので、賃金の変動も、年金額の改定に影響します。
また、国民年金は「年金」、厚生年金保険法は「年金たる保険給付」となっています。この違いはまた別の日にお話しします。
H28.1.16 国民年金法と厚生年金保険法の目的条文
国民年金法と厚生年金保険法の目的条文の空欄を埋めてください。
<国民年金法第1条>
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって A 生活の安定がそこなわれることを A の共同連帯によって防止し、もって健全な A 生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
<厚生年金保険法第1条>
この法律は、 B の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、
B 及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金は全国民が対象の年金制度なので、空欄Aには「国民」が入ります。
厚生年金保険は、会社員や公務員など雇われて働く人が対象なので、空欄Bには「労働者」が入ります。
H28.1.14 被保険者期間の計算(同一月内の取得と喪失)
「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」
アンダーライン部分が改正箇所です。
■被保険者期間は月単位で計算
例えば、1月14日(資格取得)~5月25日(資格喪失)の場合、被保険者期間は資格を取得した月(1月)から喪失した月の前月(4月)までの4か月間です。資格喪失月は被保険者期間の計算に入らないのが原則です。
■同一月に資格取得と喪失がある場合は1か月で計算
被保険者期間は資格を喪失した月の前月までで計算するのが原則ですが、例えば、1月14日(資格取得)~1月25日(喪失)のように同一月に取得と喪失がある場合は1か月で計算され1か月分の保険料を納付しなければなりません。(ほんの数日だけ働いた場合でも1か月分の保険料がかかるということです。)
同一月 | ||
| 取得 喪失 |
|
・被保険者期間は1か月として計算する
<例外 同一月にさらに厚生年金保険の資格を取得した場合>
被保険者期間は、あとの事業所の期間で1か月で計算します。
同一月 | |
A事業所(取得・喪失) | B事業所(取得) |
・被保険者期間はB事業所の期間で1か月として計算する
<例外 平成27年10月の改正点>
同一月に国民年金第1号被保険者、第3号被保険者の資格を取得した場合の取り扱い
<改正前>
同一月 | |
厚生年金保険(取得・喪失) | 国民年金第1号被保険者 |
・厚生年金保険料・国民年金保険料ともに納付する必要があった
↓
<改正後>
同一月 | |
厚生年金保険(取得・喪失) | 国民年金第1号被保険者 |
・この月は国民年金保険料のみ納付すればよいことになった
【改正のポイント】
同じ月に厚生年金保険の資格取得と喪失があり、その後同じ月内に国民年金(第1号被保険者、第3号被保険者)の資格を取得した場合
- 改正前 → 厚生年金保険の被保険者期間は1か月で計算
(保険料がかかった)
- 改正後 → 厚生年金保険の被保険者期間は計算されない
(保険料もかからない)
H28.1.13 年齢
60歳、65歳、70歳、75歳。法律によって年齢の基準が違うので頭の中がごちゃごちゃしませんか?
次の空欄を埋めて整理してみてください。
■雇用保険法
<高年齢継続被保険者>
同一の事業主の適用事業に ① 歳に達した日の前日から引き続いて ② 歳に達した日以後の日において雇用されているもの
■徴収法
<雇用保険料の免除の対象になる高年齢労働者>
保険年度の初日に ③ 歳以上の労働者
■健康保険法
<一部負担金>
1 ④ 歳に達する日の属する月以前 → 100分の30
2 ⑤ 歳に達する日の属する月の翌月以後 (3の場合を除く。)
→100分の20
3 ⑥ 歳に達する日の属する月の翌月以後の一定以上所得者
→ 100分の30
■厚生年金保険法
<被保険者>
適用事業所に使用される ⑦ 歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
■高齢者の医療の確保に関する法律
<後期高齢者医療の被保険者>
1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑧ 歳以上の者
2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑨ 歳以上 ⑩ 歳未満の者で、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
■介護保険法
<介護保険の被保険者>
・第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑪ 歳以上の者
・第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑫ 歳以上 ⑬ 歳未満の医療保険加入者
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解答】
①65 ②65 ③64 ④70 ⑤70 ⑥70 ⑦70 ⑧75 ⑨65 ⑩75 ⑪65 ⑫40 ⑬65
H28.1.3 老齢厚生年金の失権
附則第10条
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は、死亡により消滅するほか、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
第45条
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
老齢厚生年金は、60歳から65歳まで支給される「60歳台前半の老齢厚生年金」、65歳から支給される「本来の老齢厚生年金」の2種類があります。
それぞれルールが違う(ということは、そこでひっかける問題は作りやすい)ので、問題文を読むときはどちらの老齢厚生年金なのか確認することがまずはポイントです。
65歳からの「本来の老齢厚生年金」は「終身年金」なので失権事由は「死亡」のみです。(死ぬまで支給されるということ)
60歳台前半の老齢厚生年金は「有期年金」なので、死亡で失権するだけではなく、65歳に達したときに失権します。
【ポイント】
60歳台前半の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金は、「別のもの」です。
60歳台前半の老齢厚生年金の支給を受けるときには「裁定請求」することにより支給が始まりますが65歳で受給権が消滅します。
65歳になると、本来の老齢厚生年金の受給権が発生しますが、改めて本来の老齢厚生年金について「裁定請求」が必要です。
60歳代前半の老齢厚生年金を受けるときと、65歳からの本来の老齢厚生年金を受けるときの2回、裁定請求が必要です。
H28.1.2 裁定
「保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。」
改正前は、「厚生労働大臣」でしたが、一元化により「実施機関」となりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、老齢厚生年金は、原則として①厚生年金保険の被保険者期間が1月以上、②保険料納付済期間と免除期間が合わせて25年以上、③65歳以上という条件が揃えば、自動的に受給権が発生します。(基本権といいます。)
でも、受給権者は毎日毎日星の数ほど発生します。実施機関でそれを全て把握して年金を支給するのは不可能です。
年金は受給権ができても自動的に支給されるわけではないのです。何もしなければいつまでたっても年金は支給されません。
受給権が発生した場合は、受給権者本人から「受給権ができたので年金を支給してください」と請求し、それを実施機関が確認して初めて年金が支給されます。このことを「裁定」といいます。
裁定は「実施機関」が行います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【実施機関】
第1号厚生年金被保険者 → 厚生労働大臣(日本年金機構)
第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会
及び 地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団
H27.12.30 厚生年金保険の被保険者
被用者年金一元化により、平成27年10月より、公務員や私立学校教職員も厚生年金保険の被保険者になりました。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の4つに区分されています。
① 第1号厚生年金被保険者 → 2号から4号以外の被保険者
(民間企業のサラリーマンやOL)
② 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合の組合員
③ 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合の組合員
④ 第4号厚生年金被保険者 → 私立学校教職員共済制度の加入者
民間企業のサラリーマンは、「国民年金」では「第2号被保険者」、「厚生年金保険」では「第1号厚生年金被保険者」です。名称が似ているので読み間違えないように注意がいりますね。
【改正前】 被用者年金は、大きく分けて厚生年金と共済年金の2つ
| 厚生年金 | 共済年金 (国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済) | |
国民年金(基礎年金) | ||

【改正後】 被用者年金は厚生年金のみ
厚生年金 (第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者) |
| 国民年金(基礎年金) |
