合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和6年度版
毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ
過去問から学ぶ社労士 kindle版です。
令和5年度に出題された問題の勉強方法を、毎日更新しています。
令和6年1月5日までの記事をまとめた電子書籍を販売しました。
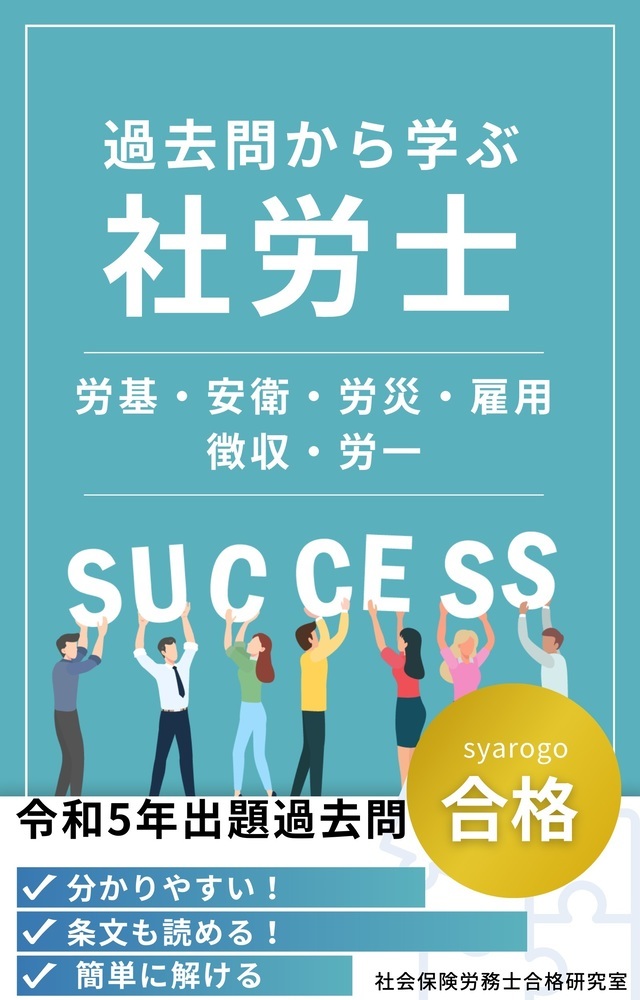
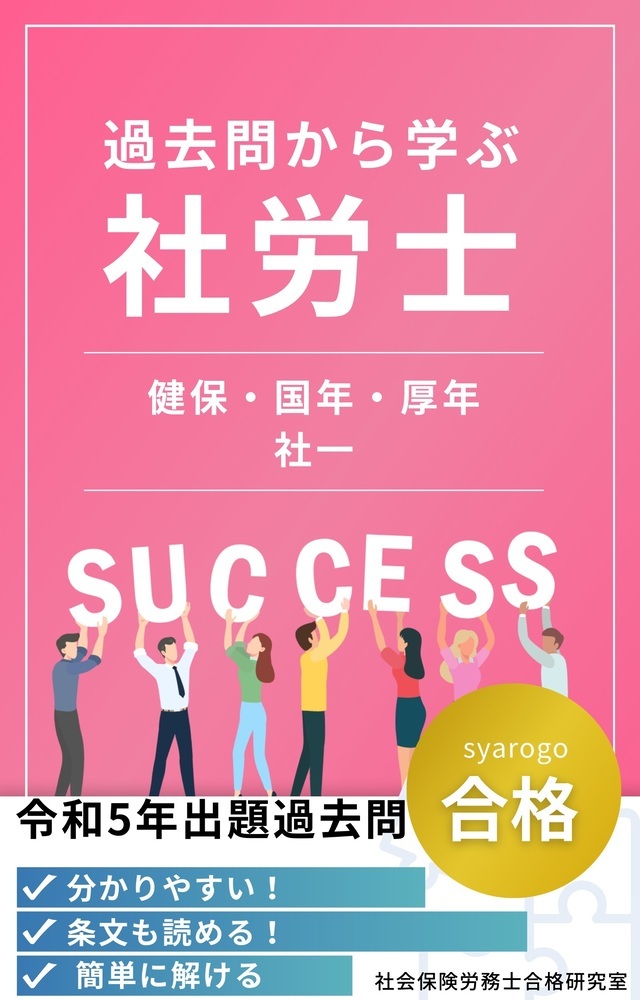
昨日はお疲れさまでした
R7-001 8.26
猛暑の中、本当にお疲れさまでした。
昨日は、本試験お疲れさまでした。
猛暑の中の追い込みで、本当に大変だったと思います。
まずは、ゆっくり体を休めてください。
いつも、ホームページとYouTubeを見ていただき、ありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/aGONkLRQ170?si=9ydjvLTm3Yffm82q
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
いよいよ当日です。合格を祈ります!
R6-364 8.25
最後に社会保険労務士法をチェックしましょう【社労士受験対策】
いよいよ本番です。
社会保険労務士法の条文のポイントを確認しましょう。
第1条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2 (社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第2条第2項、第3項
② 「紛争解決手続代理業務」は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
③ 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
(1)第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。) について相談に応ずること。
(2)紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
(3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
第15条 (不正行為の指示等の禁止)
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第16条 (信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第19条 (帳簿の備付け及び保存)
① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
② 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から 2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。
第25条 (懲戒の種類)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
(1) 戒告
(2) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
(3) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒)
① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
今日は長い1日ですが、頑張りましょう!
応援しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
横断 労働一般常識・社保一般常識
R6-363 8.24
<横断編>一般常識科目の目的条文などを読みます!【社労士受験対策】
一般常識科目の目的条文などをチェックしましょう。
★障害者の雇用の促進等に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
★労働契約法
第1条 (目的)
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。
★雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
第2条 (基本的理念)
① この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
② 事業主並びに国及び地方公共団体は、基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。
★育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
★短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
★憲法
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
★労働組合法
第1条第1項 (目的)
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
★社会保険労務士法
第1条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
★国民健康保険法
第1条 (この法律の目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民健康保険)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
★児童手当法
第1条 (目的)
この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
★高齢者の医療の確保に関する法律
第1条 (目的)
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (基本的理念)
① 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
第3条 (国の責務)
国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条第 (地方公共団体の責務)
① 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
② 住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。
第5条 (保険者の責務)
保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
★船員保険法
第1条 (目的)
この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★介護保険法
第1条 (目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (介護保険)
① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
② 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
★確定拠出年金法
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★確定給付企業年金法
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【横断】労基・安衛・労災・雇用・徴収・健保・国年・厚年
R6-362 8.23
<横断編>目的条文などを読みます!練習問題もあります【社労士受験対策】
目的条文などをチェックしましょう。
練習問題もあります。
条文を読んでみましょう。
★労働基準法 第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
★労働安全衛生法 第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
★労災保険法 第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
★雇用保険法 第1条 (目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 第2条(管掌) ① 雇用保険は、政府が管掌する。 ② 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 第3条 (雇用保険事業) 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
★労働保険徴収法 第1条 (趣旨) この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。
★健康保険法 第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 第2条 (基本的理念) 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
★国民年金法 第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 第3条 (管掌) ① 国民年金事業は、政府が、管掌する。 ② 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。 ③ 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。
★厚生年金保険法 第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 第2条 (管掌) 厚生年金保険は、政府が、管掌する。 |
過去問をどうぞ!
★労働基準法
①【H27年出題】
労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとしている。
②【H28年出題】
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
「人たるに値する生活」がポイントです。
②【H28年出題】 〇
労働基準法第1条は、労働基準法の基本理念を宣明したものです。
(昭22.9.13発基17号)
★労働安全衛生法
①【H24年選択式】
労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< A >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< B >を促進することを目的とすると規定している。
②【H29年出題】
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

【解答】
①【H24年選択式】
<A> 危害防止基準
<B> 快適な職場環境の形成
②【H29年出題】 〇
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあります。
(昭47.9.18発基第91号)
★労災保険法
条文の穴埋め問題です。
第2条の2
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して< A >を行うほか、< B >を行うことができる。

【解答】
<A> 保険給付
<B> 社会復帰促進等事業
★雇用保険法
【H28年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< A >を図るとともに、< B >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< C >を図ることを目的とする。」と規定されている。

【解答】
<A> 生活及び雇用の安定
<B> 求職活動
<C> 福祉の増進
★労働保険徴収法
【R2年出題】(雇用)
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

【R2年出題】(雇用) 〇
労働保険徴収法第1条からの問題です。
★健康保険法
【H30年選択式】
健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、< A >、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の < B >、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の< C >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。」と規定している。

【解答】
<A> 疾病構造の変化
<B> 運営の効率化
<C> 質の向上
★国民年金法
①【H28年選択式】
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
②【R5年選択式】
国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して< C >を行うものとする。」と規定されている。

【解答】
①【H28年選択式】
<A> 安定
<B> 共同連帯
②【R5年選択式】
<C> 必要な給付
★厚生年金保険法
条文の穴埋め問題です。
第1条
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について< A >を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

【解答】
<A> 保険給付
<B> 福祉の向上
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
横断 労災・雇用・徴収・健保・厚年
R6-361 8.22
<横断編>書類の保存期間【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
条文で確認しましょう。
★労災保険法 則第51条 (書類の保存義務) 労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
★雇用保険法 則第143条 (書類の保管義務) 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。
★労働保険徴収法 則第72条 (書類の保存義務) 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
★健康保険法 則第34条 (事業主による書類の保存) 事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。
★厚生年金保険法 則第28条 (書類の保存) 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
★労災保険法
【R1年出題】
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。

【解答】
【R1年出題】 ×
労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。
(則第51条)
★雇用保険法
【R4年出題】
事業主は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)のうち被保険者に関する書類を4年間保管しなければならない。

【解答】
【R4年出題】 〇
雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は同法施行規則による書類を除く。)は、その完結の日から2年間(被保険者に関する書類は、4年間)保管しなければなりません。
★労働保険徴収法
【H28年出題】(雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】
【H28年出題】(雇用) 〇
その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければなりません。
(則第72条)
★健康保険法
【H25年出題】
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より3年間、保存しなければならない。

【解答】
【H25年出題】 ×
その完結の日より「2年間」、保存しなければなりません。
(則第34条)
★厚生年金保険法
【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。

【解答】
【H29年出題】 ×
事業主は、厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければなりません。5年間という例外はありません。
(則第28条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-360 8.21
傷病補償年金と特別支給金の重要10問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
傷病補償年金の条文を読んでみましょう。
第12条の8第3項 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 則第18条 (傷病等級) ① 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。 ② 障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。 別表2
第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。
下の図でイメージしてください。
②【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
②【H24年出題】 〇
「療養補償給付」も「傷病補償年金」も治ゆするまでの給付です。
療養補償給付は治療についての給付ですので、傷病補償年金と併給されます。
③【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されません。
④【H29年出題】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。

【解答】
④【H29年出題】 〇
傷病補償年金は、労働者の請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で支給決定されることがポイントです。
そのため、療養開始後1年6か月を経過した日に治っていないときは、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させることになっています。
(則第18条の2第2項、第3項)
⑤【H29年出題】
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
「6か月以上」がポイントです。
⑥【H29年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。

【解答】
⑥【H29年出題】 〇
「打切補償を支払ったものとみなされる」=解雇することができます。
下の図でイメージしてください。
⑦【H20年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

【解答】
⑦【H20年出題】 ×
傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行いますが、傷病補償年金の傷病等級の変更も、所轄労働基準監督署長の職権で行われます。
(則第18条の3)
⑧【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

⑧【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合は、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。自動的に休業補償給付が支給されるのではなく、休業補償給付は「請求」が必要です。
⑨【H28年出題】
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

【解答】
⑨【H28年出題】 〇
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されます。
ただし、当分の間、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされています。
(特別支給金規則第5条の2、昭56.6.27基発第393号)
★保険給付と特別支給金のイメージ図です
傷病特別年金 | →ボーナス特別支給金 |
傷病特別支給金 | →一般の特別支給金 |
傷病補償年金 | 保険給付 |
⑩【R1年出題】
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

【解答】
⑩【R1年出題】 〇
「傷病特別支給金」は、傷病等級に応じて「定額」であることがポイントです。
(特別支給金規則第5条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
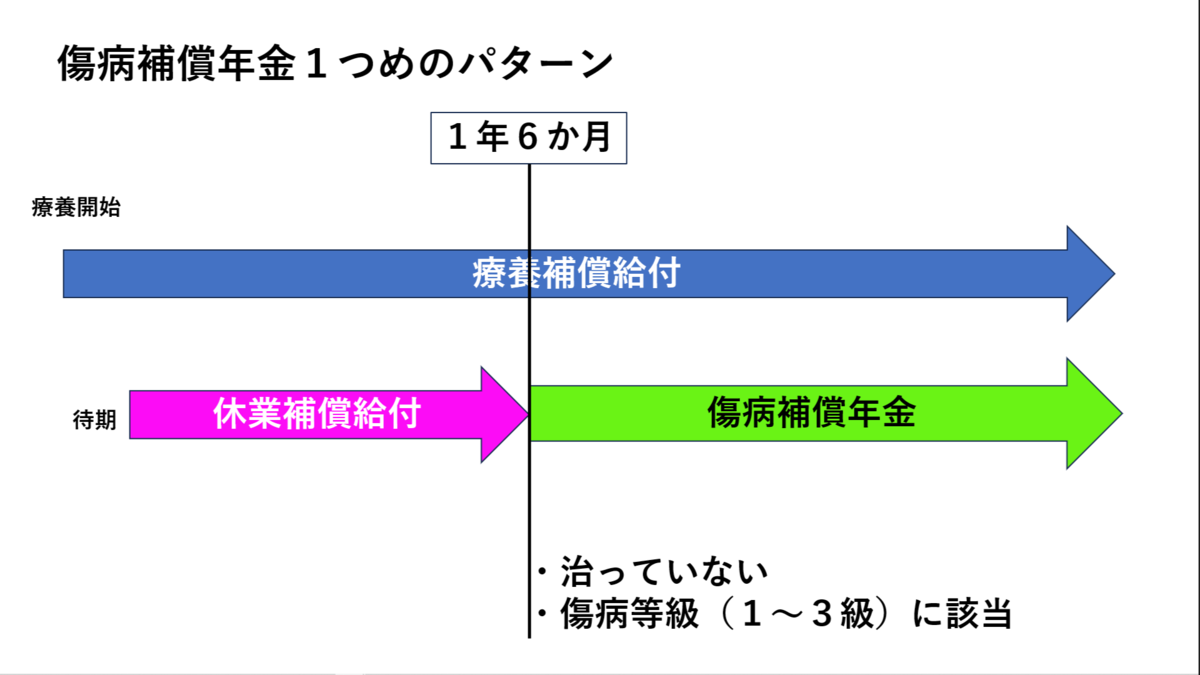
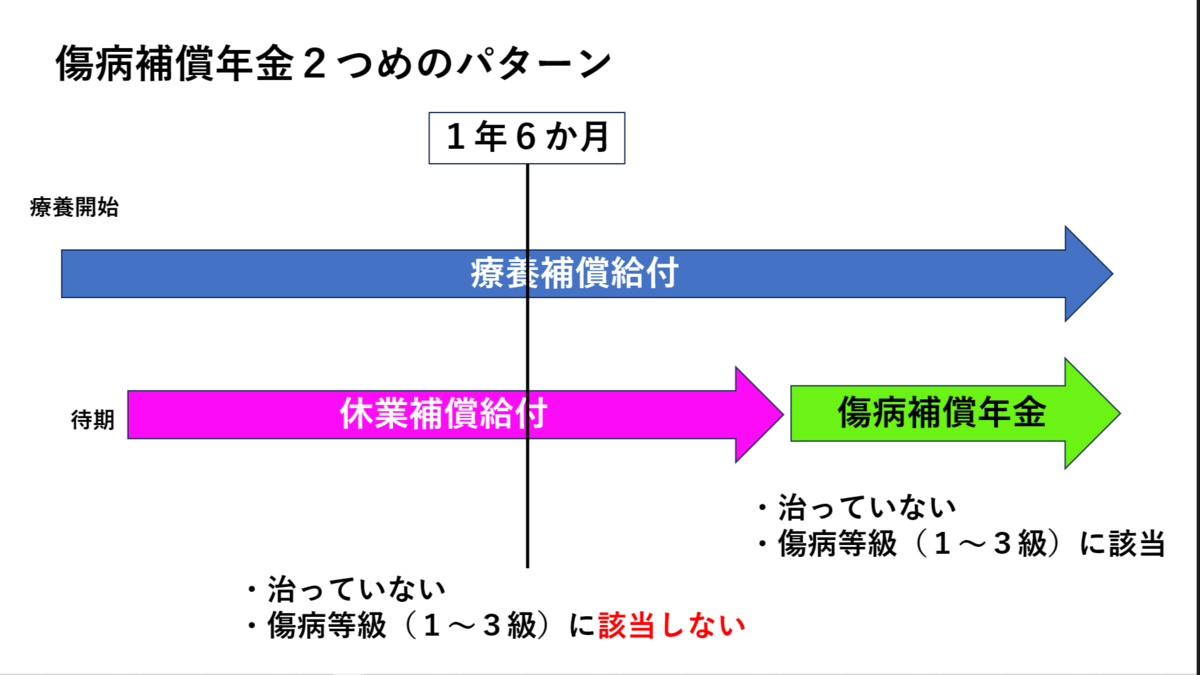
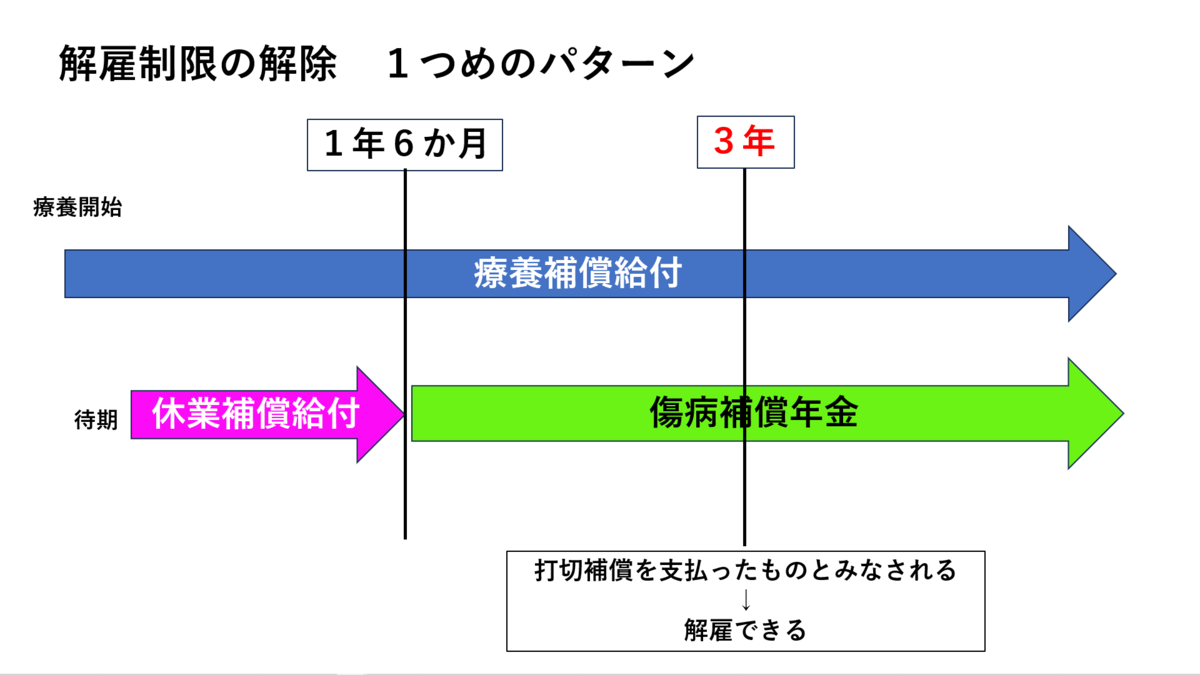
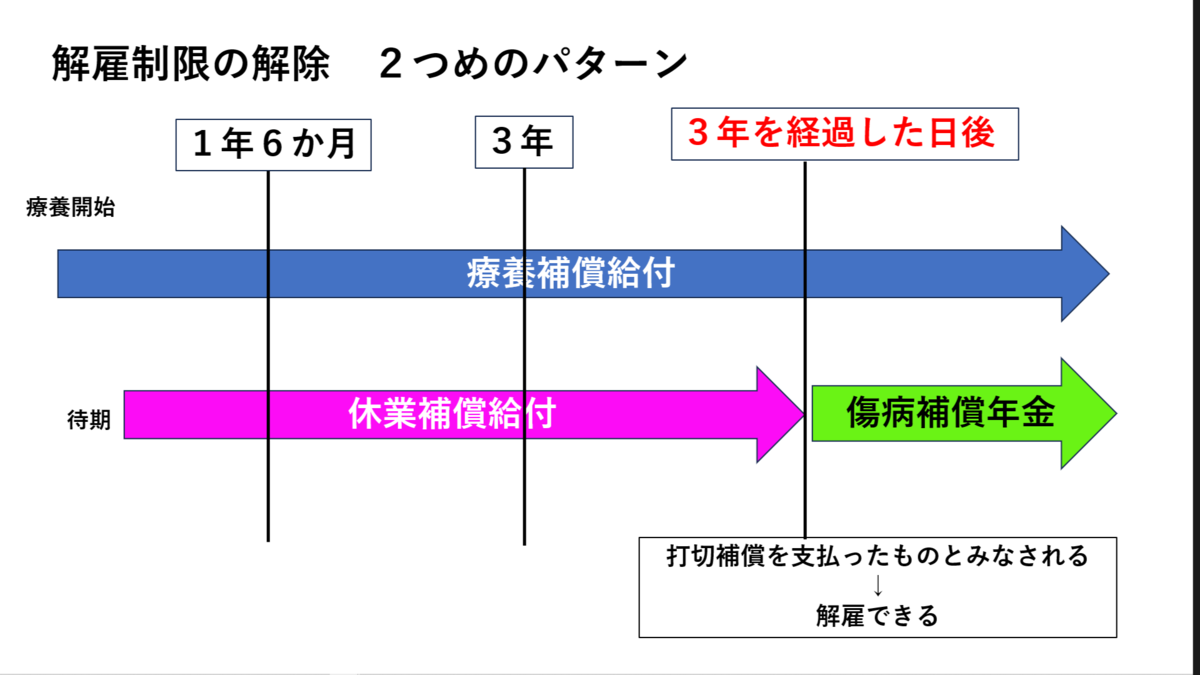
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-359 8.20
労働安全衛生法の派遣労働者への適用5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働安全衛生法の派遣労働者に対する適用についてみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

【解答】
①【H27年出題】 〇
ポイント!
「衛生管理者」の選任義務のある事業場の労働者の人数
派遣労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」の双方の人数に含まれます。
②【H27年出題】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

【解答】
②【H27年出題】 ×
ポイント!
「雇入れ時」の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられます。
労働契約関係にあるのは、派遣元だからとイメージしてください。
③【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

【解答】
③【H27年出題】 ×
ポイント!
派遣労働者に対する「特別の教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者のみに課せられています。
特別教育は、危険・有害業務を行う現場でとイメージしてください。
④【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

【解答】
④【H27年出題】 ×
ポイント!
・一般健康診断の実施義務は「派遣元」の事業者
・特殊健康診断の実施義務は「派遣先」の事業者
⑤【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

⑤【H27年出題】 ×
第66条の8第1項の医師による面接指導は、「派遣元事業場」の事業者に実施義務が課せられています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<超基本>20歳前傷病による障害基礎年金
R6-358 8.19
<超基本>20歳前傷病による障害基礎年金についてお話します【社労士受験対策】
20歳前傷病による障害基礎年金の超基本をお話します。
今日の内容です
・20歳前傷病による障害基礎年金とは?
・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権発生日2つ
・20歳前傷病による障害基礎年金独自の支給停止の規定
・20歳前傷病による障害基礎年金に対する国庫負担
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 健康保険法
R6-357 8.18
<健保>短時間労働者の重要問題5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
短時間労働者の問題をチェックしましょう。
 特定適用事業所とは
特定適用事業所とは
①【H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「特定労働者の総数が常時100人を超える」がポイントです。
(H24法附則第46条第12項)
★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者で、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として健康保険の被保険者となります。 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 報酬の月額が88,000円以上であること ③ 学生でないこと |
 報酬の月額について
報酬の月額について
②【R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
②【R4年選択式】
<A> 88,000円以上
③【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
③【H30年出題】 ×
最低賃金において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)
 学生でないことについて
学生でないことについて
④【R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
④【R3年出題】 ×
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
(R4.9.28保保発0928第6号)
 任意特定適用事業所について
任意特定適用事業所について
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下でも、所定労働組合等の同意を得て、任意特定適用事業所の申出を行うことができます。
(H24法附則第46条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<横断>労基・雇用・徴収
R6-356 8.17
<横断編>労基・雇用・徴収の賃金の定義を比べる【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
「賃金」の定義を横断で確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
★労働基準法 第11条 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
★雇用保険法 第3条第4項、第5項 ④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 法第4条第4項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
★労働保険徴収法 第2条第2項、第3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 |
過去問をどうぞ!
★労働基準法
①【労基H23年出題】
労働基準法に定める賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者又は顧客が労働者に支払うすべてのものをいう。

【解答】
①【労基H23年出題】 ×
「使用者又は顧客が」ではなく、「使用者が労働者に支払うすべてのもの」です。
(法第11条)
②【労基H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
②【労基H27年出題】 〇
退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金となりません。
但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは賃金となります。
(昭22.9.43発基第17号)
★雇用保険法
①【雇用H21年出題】
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。

【解答】
①【雇用H21年出題】 ×
「通貨以外のもので支払われるもの(=現物給付)で、厚生労働省令で定める範囲」のものは賃金に含まれます。
(法第4条第4項、則第2条第1項)
②【雇用H26年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

【解答】
②【雇用H26年出題】 ×
「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲」は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによるとされています。
食事、被服、住居の利益は、公共職業安定所長が定めるまでもなく、賃金の範囲に算入されます。
問題文の住居の利益は、賃金となります。
(則第2条第1項、行政手引50403、行政手引50501)
★労働保険徴収法
①【徴収H24年出題】(労災)
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

【解答】
①【徴収H24年出題】(労災) 〇
労働基準法第26条の休業手当は賃金に含まれます。
労働基準法第20条の解雇予告手当は賃金に含まれません。
(法第2条第2項、昭25.4.10基収950号、昭23.8.18基収2520号)
②【徴収H19年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むとされている。

【解答】
②【徴収H19年出題】(雇用) 〇
労働保険徴収法の「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含みます。
(法第2条第2項、則第3条第1項)
③【徴収R5年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服、住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

【解答】
③【徴収R5年出題】(雇用) ×
労働保険徴収法における「賃金」のうち、通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、「厚生労働大臣」が定めることとされています。
(法第2条第3項)
④【徴収H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
④【徴収H26年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、賃金となりません。
(昭25.2.16基発127号)
⑤【徴収H24年出題】(労災)
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。

【解答】
⑤【徴収H24年出題】(労災) 〇
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されません。
(平15.10.1基徴発1001001号)
ちなみに、在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、賃金総額に算入されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-355 8.16
特別加入者と労働者の異なる点でよく出るところ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者は労災保険法に特別加入することによって、労働者と同じ保護が受けられます。
ただし、労働者と特別加入者で違う点もありますので、ポイントを確認しましょう。
①二次健康診断等給付について
特別加入者は、二次健康診断等給付は対象になりません。労働者と違い、健康診断が義務づけられていないからです。
②社会復帰促進等事業について
特別加入者は、労働者と同じように社会復帰促進等事業が適用されます。
ただし、「特別支給金」の中の「ボーナス特別支給金」は、特別加入者には支給されません。
例えば、労働者については、傷病補償年金に特別支給金として、傷病特別支給金と傷病特別年金がプラスされます。しかし、特別加入者には、ボーナス特別支給金の傷病特別年金は支給されません。
傷病特別年金 | → ボーナス特別支給金 |
傷病特別支給金 | → 一般の特別支給金 |
傷病補償年金 | 保険給付 |
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

【解答】
【H28年出題】 〇
特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されません。なお、一般の特別支給金は支給されます。
(特別支給金規則第19条)
③通勤災害について
特別加入者にも通勤災害は適用されます。ただし、一人親方等の一部については、住居と就業の場所との間の往復が明確でないため、通勤災害が適用されません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
②【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
特別加入者である家内労働者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
④給付基礎日額について
特別加入者には賃金がないため、給付基礎日額は、厚生労働大臣の定めた額から、申請に基づき決定した額となります。
過去問をどうぞ!
【H30年選択式】
(特別加入者の)給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< A >である。

【解答】
A 25,000円
(則第46条の20第1項)
⑤特別加入者の支給制限
次の場合は、特別加入者の保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」とされています。
<中小事業主等について>
・ 事故が、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
・ 業務災害の原因である事故が中小の事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき
<一人親方等について>
・ 事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
<海外派遣者について>
・ 事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
過去問をどうぞ!
【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
【R3年出題】 ×
「保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」の部分が誤りです。
事業主から費用徴収するのではなく、保険給付が支給制限されます。
「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
(法第34条第1項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【横断】労災・雇用・健保・国年・厚年
R6-353 8.14
<横断編>法律ごとに「時効」を確認しましょう【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
★労災保険法
時効には、「2年」と「5年」があります。
療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、葬祭料(複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付)、介護(補償)等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
ポイント
療養(補償)等給付は、「療養の費用の支給を受ける権利」です。
障害・遺族の「前払一時金」は「2年」です。
障害(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。
遺族(補償)等給付 →年金も一時金も「5年」です。
障害(補償)年金差額一時金は「5年」です。
※傷病(補償)等年金は、時効の問題は生じません
★雇用保険法
失業等給付等の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
★健康保険法
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
★国民年金法
・ 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
・ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
ポイント
年金は「5年」、死亡一時金は「2年」です
★厚生年金保険法
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
ポイント
「保険給付」には障害手当金が含まれます。障害手当金の時効は5年です
過去問をどうぞ!
★労災保険法
【H27年出題】※改正による修正あり
障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、複数事業労働者介護給付、障害給付、遺族給付及び介護給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
【H27年出題】 ×
介護補償給付(複数事業労働者介護給付、介護給付)を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年ではなく「2年」を経過したときは、時効によって消滅します。
(法第42条第1項)
★雇用保険法
①【H28年出題】※改正による修正あり
失業等給付等を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

①【H28年出題】 〇
失業等給付等を受ける権利、その返還を受ける権利の時効は2年です。
(法第74条第1項)
②【R4年出題】
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合に政府が納付すべきことを命じた金額を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅する。

②【R4年出題】 〇
政府が返還命令等の規定により納付すべきことを命じた金額を徴収する権利の時効は、2年です。
(法第74条第1項)
★健康保険法
①【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「現物給付」である「療養の給付」には、時効はありません。
②【R5年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】
②【R5年出題】 ×
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年ですが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日ではなくその「翌日」です。
時効の起算日にも注意しましょう。
(昭30.9.7保険発199号の2)
★国民年金法
①【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
死亡一時金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したとき
時効によって消滅します。
年金給付と死亡一時金の違いに注意しましょう。
(法第102条)
②【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②【R2年出題】 〇
支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点となります。
(法第102条)
★厚生年金保険法
①【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【H29年出題】 ×
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
(第92条第1項)
②【R4年出題】
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②【R4年出題】〇
支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」が時効の起算点です。
(法第92条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【横断】労災・健保・国年・厚年
R6-353 8.14
<横断編>法律で異なる生計維持の要件について【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
★労災保険法★
「遺族補償年金」について
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
ポイント!
もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。
(昭41.1.31基発第73号)
★健康保険法★
「被扶養者」の認定について
①主としてその被保険者により生計を維持するもの(同一世帯になくてもよい)
直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫、兄弟姉妹
②被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
・被保険者の3親等内の親族で①以外のもの
・被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子
・上記の配偶者の死亡後におけるその父母及び子
ポイント!
① 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合
(1) 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。
② 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(昭52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
埋葬料について
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給する。
ポイント!
生計を維持していた者には、被保険者により生計の全部又は大部分を維持した者のみに限らず一部分を維持していた者も含みます。
(昭8.8.7保発第502号)
★国民年金法・厚生年金保険法
生計維持の認定要件
① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者は除く。)→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
② 障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者
→ 次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
(平23.3.23年発0323第2号)
★障害基礎年金、障害厚生年金は、受給権が発生した後でも、結婚や出生などで加算の要件を満たした場合は、その翌月から加算が行われます。
では、過去問をどうぞ!
★労災保険法
【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

【解答】
【H28年出題】 ×
遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部又は一部を営んでいた関係が認められる限り、遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものと認めて差し支えないとされています。
問題文の場合は、生計維持関係があったものとされ、遺族補償年金を受けることができます。
(昭41.10.22基発1108号)
★健康保険法
※注意 問題文の被扶養者は、すべて日本国内に住所を有しています。
①【H27年出題】
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年間100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合は、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
問題文の母は被扶養者になることができません。
母の収入が、100万円の遺族厚生年金+パートの給与120万円=年間220万円あるためです。
②【R1年出題】
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

【解答】
②【R1年出題】 〇
年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが原則ですが、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、「被保険者の年間収入を上回らない場合」は、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当します。
③【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

【解答】
③【H24年出題】 〇
埋葬料の支給要件の「その者により生計を維持していた者」には、生計の一部を維持していた者も含まれます。
(昭8.8.7保発第502号)
★国民年金法・厚生年金保険法
①【国民年金R2年出題】
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。

【解答】
①【国民年金R2年出題】 ×
前年の収入が年額850万円以上でも、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められる場合は、収入に関する認定要件に該当します。
②【厚生年金保険法H27年出題】
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

【解答】
②【厚生年金保険法H27年出題】 ×
①の問題と同じです。問題文の場合は、生計維持関係が認定されます。
③【厚生年金保険法H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
③【厚生年金保険法H29年出題】 〇
配偶者を有するに至った日の属する月の「翌月」から、加給年金額が加算されるのがポイントです。
障害基礎年金と障害厚生年金は、「受給権を取得した日の翌日以後」にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者(障害基礎年金の場合は子)を有するに至ったときでも、加算の対象になります。
条文を読んでみましょう。
国民年金法第33条の2第2項 障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。
厚生年金保険法第50条の2第3項 障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【横断】労災・健保・国年・厚年
R6-352 8.13
<横断編>支給制限「故意」「故意の犯罪行為」「重大な過失」など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は横断編です。
条文を読んでみましょう。
特に赤字の部分に注意してください。
★労災保険法 第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 ② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
★健康保険法 第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。 第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。 第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
★国民年金法 第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。 第71条 ① 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
★厚生年金保険法 第73条 被保険者又は被保険者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。 第73条の2 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。 第74条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。 第76条 ① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 ② 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 |
過去問をどうぞ!
★労災保険法
①【H26年出題】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
キーワードは、「故意に」と「保険給付を行わない」です。
(法第12条の2の2第1項)
②【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
②【R2年出題】×
「故意の犯罪行為」によって生じた場合は、「政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる」。
(法第12条の2の2第2項)
③【R2年出題】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
③【R2年出題】 〇
「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合」、政府は、保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」。
(法第12条の2の2第2項)
★健康保険法
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
自己の故意の犯罪行為、又は故意に給付事由を生じさせたときは、「保険給付は、行わない」です。
(法第116条)
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。

【解答】
②【H23年出題】 ×
闘争、泥酔、著しい不行跡については、「その全部又は一部を行わないことができる」
(法第117条)
③【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の「一部」を行わないことができる。
よく出る箇所ですので注意してください。
(法第119条)
★国民年金法
①【R5年出題】
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「故意に」障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は「支給しない」。
(法第69条)
②【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

【解答】
②【R1年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
(法第71条第2項)
③【H26年選択式】
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。

【解答】
A 療養に関する指示に従わない
B 全部又は一部を行わない
(法第70条)
★厚生年金保険法
①【R1年出題】
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「故意に」のときは「支給されない」。
「重大な過失」のときは「全部又は一部を行わないことができる」。
(法第73条、第73条の2)
②【H29年出題】
実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
キーワードは、障害厚生年金の受給権者が、「故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ことにより、その「障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき」です。
(法第74条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
未支給年金のこと
R6-351 8.12
国民年金の未支給年金についてお話します【社労士受験対策】
未支給年金についてお話します
★年金の受給権者が死亡した場合、必ず未支給年金があります。
年金は後払いだからです。
★未支給年金は自己の名で請求します。
★未支給年金が請求できる遺族の範囲と順位
★未支給年金を請求できる同順位者が2人以上あるとき
★遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合、受給権者の子ではないけれど、子とみなして未支給年金が請求する場合
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
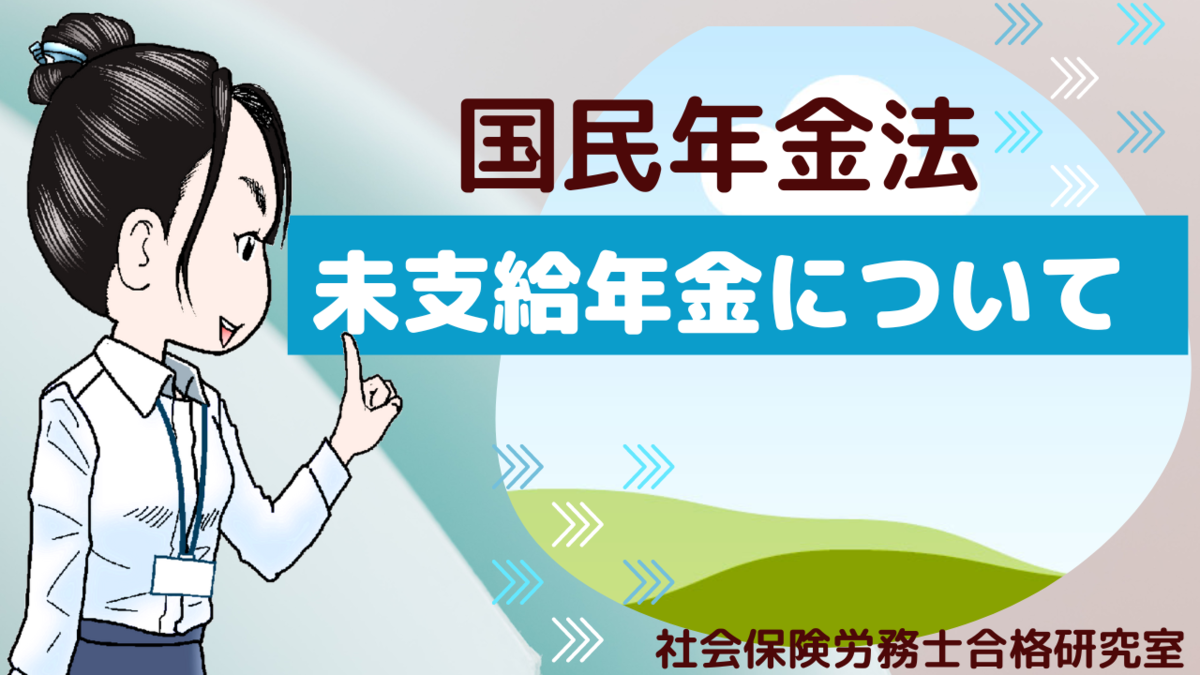
過去問から学ぶ 国民年金法と厚生年金保険法の違い
R6-350 8.11
支給停止の違い(遺族基礎年金と遺族厚生年金)【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法と厚生年金保険法です。
受給権者本人の判断で、年金の支給停止の申出をすることができます。
まず国民年金法の条文を読んでみましょう。
国民年金法第20条の2第1項 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
厚生年金保険にも同じ規定があります。条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第38条の2第1項 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
では、国民年金の過去問をどうぞ!
【国民年金法H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
【国民年金法H28年出題】 〇
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
(法第41条第2項)
次は厚生年金保険法の過去問をどうぞ!
【厚生年金保険法H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

【解答】
【厚生年金保険法H30年出題】 ×
子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
国民年金法との違いに注意しましょう。
(法第66条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-349 8.10
令和6年度の国民年金保険料など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年出題】※令和6年度に合わせて問題修正しています。
令和6年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,980円である。

【解答】
【H30年出題】 〇
令和6年度の国民年金保険料の月額は、
17,000円×保険料改定率(0.999)≒16,980円です。
(法第87条第3項)
★令和元年度以後の保険料は、17,000円×保険料改定率で計算します。
端数は、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。
★保険料改定率について
保険料改定率は、前年度の保険料改定率×名目賃金変動率です。
保険料について過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
★3月31日に死亡した場合、被保険者の資格は、死亡した日の翌日(4月1日)に喪失します。
★被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までですので、3月までです。
・保険料は2月分までではなく「3月分」まで納付しなければなりません。
(第11条第1項、第87条第2項)
②【H28年出題】
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
市町村長ではなく、「厚生労働大臣」から、通知が行われます。
(法第92条第1項)
③【H26年出題】
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】
③【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第88条第2項、3項 ② 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
④【R5年出題】
厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

【解答】
④【R5年出題】 ×
「その納付が確実と認められるときに限り」ではありません。
条文を読んでみましょう。
第92条の2 厚生労働大臣は、被保険者から、保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-348 8.9
国民年金基金の基本10問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
国民年金基金の基本問題10問です。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」は、第1号被保険者とみなされ、国民年金基金の加入員となることができます。
(法附則第5条第11項)
②【R5年出題】
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【R5年出題】 ×
国民年金保険料を納付することを要しないものとされたとき及びその一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、国民年金基金の加入員の資格を喪失します。「該当するに至った日の翌日」ではなく、「当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」に加入員の資格を喪失します。
(第127条第3項第3号)
③【H29年出題】
国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
国民年金基金の掛金の上限は、額の上限の特例に該当する場合を除き1か月につき68,000円です。
(基金令第34条)
④【R3年出題】
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

【解答】
④【R3年出題】 ×
国民年金基金には障害に関する一時金はありません。
条文を読んでみましょう。
第128条第1項 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 |
⑤【R4年出題】
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
「老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。」が誤りです。
条文を読んでみましょう。
第129条第1項 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。 |
⑥【H22年出題】
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

【解答】
⑥【H22年出題】 ×
国民年金基金の支給する一時金の額にも下限が決められています。
国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない、とされています。
(法第130条第3項)
⑦【R1年出題】
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。

【解答】
⑦【R1年出題】 ×
400円ではなく「200円」です。
条文を読んでみましょう。
第131条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。(←支給を停止することができる。) |
⑧【H27年出題】
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

【解答】
⑧【H27年出題】 〇
遺族基礎年金と間違えないようにしましょう。「死亡一時金」がポイントです。
(法第129条第3項)
⑨【H29年出題】
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】
⑨【H29年出題】 〇
「国民年金基金」が裁定するがポイントです。
(法第133条)
⑩【H30年出題】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

【解答】
⑩【H30年出題】 ×
「基金の加入員期間の年数にかかわらず」が誤りです。
中途脱退者とは、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が15年に満たないものをいいます。
(法第137条の17、基金令第45条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-347 8.8
健康保険の保険者についての問題【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の保険者について条文を読んでみましょう。
第4条 (保険者) 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) ① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。 ② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第6条 (組合管掌健康保険) 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
全国健康保険協会の定款の変更は、「厚生労働大臣の認可」を受けなければ、その効力を生じません。
ただし、「事務所の所在地の変更」などの変更は、「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出」なければならないとされています。
(法第7条の6第2項、第3項、則第2条の3)
②【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
②【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
令第16条第1項 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
ちなみに、全国健康保険協会の条文も読んでみましょう。
法第7条の27 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
③【H24年出題】
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第7条の34 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
④【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
穴埋めでポイントを確認しましょう。
令第24条 健康保険組合は、毎年度終了後< A >以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
<解答>
A 6か月
⑤【H21年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

【解答】
⑤【H21年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
(法第123条第1項)
⑥【H22年出題】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

【解答】
⑥【H22年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の業務のうち、確認や保険料の徴収など厚生年金保険とセットになる業務は、厚生労働大臣が行います。(任意継続被保険者に係るものを除く。)の部分も注意して下さい。
(第5条第2項)
⑦【H29年出題】
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

【解答】
⑦【H29年出題】 ×
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。
保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行います。
(第5条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-346 8.7
労災保険暫定任意適用事業・雇用保険暫定任意適用事業【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
農林水産業の一部は、労災保険、雇用保険の適用が当分の間、任意となっています。
※労災保険と雇用保険では、暫定任意適用事業の範囲が異なります。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年問9】(労災)
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

【解答】
①【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業については、厚生労働大臣の認可があった日に、保険関係が成立します。
労災の任意加入については労働者の同意は不要です。労災保険料は、事業主が全額負担するからです。
(整備法第5条第1項)
②【H21年問9】(労災)
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。

【解答】
②【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業は、事業主が保険関係の消滅の申請を行えば、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。
ただし、消滅の申請には次の要件が必要です。
① 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
② 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
③ 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、特別保険料を徴収する期間を経過していること。
(整備法第8条第2項)
③【H21年問9】(労災)
労災保険にかかる保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

【解答】
③【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業が加入する際は労働者の同意は要りませんが、保険関係の消滅には、「労働者の過半数の同意」が必要です。そのため、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければなりません。
(整備法第8条第2項、令第3条)
④【H21年問9】(労災)
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

【解答】
④【H21年問9】(労災) ×
「2分の1」ではなく「4分の3以上」の同意です。
雇用保険暫定任意適用事業の手続について
・加入の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
★申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要
・消滅の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
★申請には、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要
(法附則第2条、第4条)
⑤【H21年問9】(労災)
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。

【解答】
⑤【H21年問9】(労災) 〇
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければなりません。
この規定に違反した事業主には罰則が定められています。
(法附則第2条第3項、第7条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-345 8.6
一般被保険者の基本手当以外の求職者給付5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
一般被保険者の基本手当以外の求職者給付をみていきます。
「失業等給付」について条文を読んでみましょう。
第10条 ① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 ② 求職者給付は、次のとおりとする。 (1) 基本手当 (2) 技能習得手当 (3) 寄宿手当 (4) 傷病手当 ③ 高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。 ④ 就職促進給付は、次のとおりとする。 (1) 就業促進手当 (2) 移転費 (3) 求職活動支援費 ⑤ 教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。 ⑥ 雇用継続給付は、次のとおりとする。 (1) 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(「高年齢雇用継続給付」という。) (2) 介護休業給付金 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
受給資格者Xは、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後、交通事故による負傷のために職業に就くことができなくなり、そのため基本手当の支給を受けられなくなったが、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、Xに対して傷病手当が支給されることはない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
交通事故により、自動車損害賠償保障法に基づく保険金の支給を受けることができる場合には、傷病手当を支給して差し支えないとされています。
(S53.9.22雇保発32)
なお、健康保険の傷病手当金などの支給を受けることができる場合は、傷病手当は支給されません。
条文を読んでみましょう。
法第37条第8項 認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法第99条の規定による傷病手当金、労働基準法第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令(法令の規定に基づく条例又は規約を含む。)により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。 |
②【H24年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。

【解答】
②【H24年出題】 〇
延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
(行政手引53004)
③【H24年出題】
技能習得手当には、受講手当、通所手当及び寄宿手当の3種類がある。

【解答】
③【H24年出題】 ×
技能習得手当は、「受講手当」及び「通所手当」です。
(則第56条)
★一般被保険者の求職者給付
(1) 基本手当
(2) 技能習得手当→(受講手当、通所手当)
(3) 寄宿手当
(4) 傷病手当
④【H24年出題】
寄宿手当は、公共職業訓練等受講開始前の寄宿日については支給されることはない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
寄宿手当は、公共職業訓練等受講期間中の日についてのみ支給されます。公共職業訓練等受講開始前の寄宿日又は受講終了後の寄宿日については支給されません。
(行政手引52901)
⑤【H28年出題】
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。

【解答】
⑤【H28年出題】 ×
「公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ」、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ」、「被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した」ことにより基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない、とされています。
(第36条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金と遺族厚生年金
R6-344 8.5
超基本!妻に支給される遺族基礎年金・遺族厚生年金【社労士受験対策】
妻に支給される遺族基礎年金と遺族厚生年金の基本をお話します。
★事例1
20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(40歳)が死亡し、遺族が妻と子の場合
・遺族基礎年金の支給要件
・遺族厚生年金の支給要件
★事例2
20歳から厚生年金保険の被保険者である夫(59歳)が死亡し、遺族は妻(50歳)のみの場合
・遺族基礎年金は支給されない?
・遺族厚生年金の支給要件
・中高齢寡婦加算について
★年金額について
・65歳以上、老齢厚生年金の受給権者、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける人の遺族厚生年金の計算方法
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
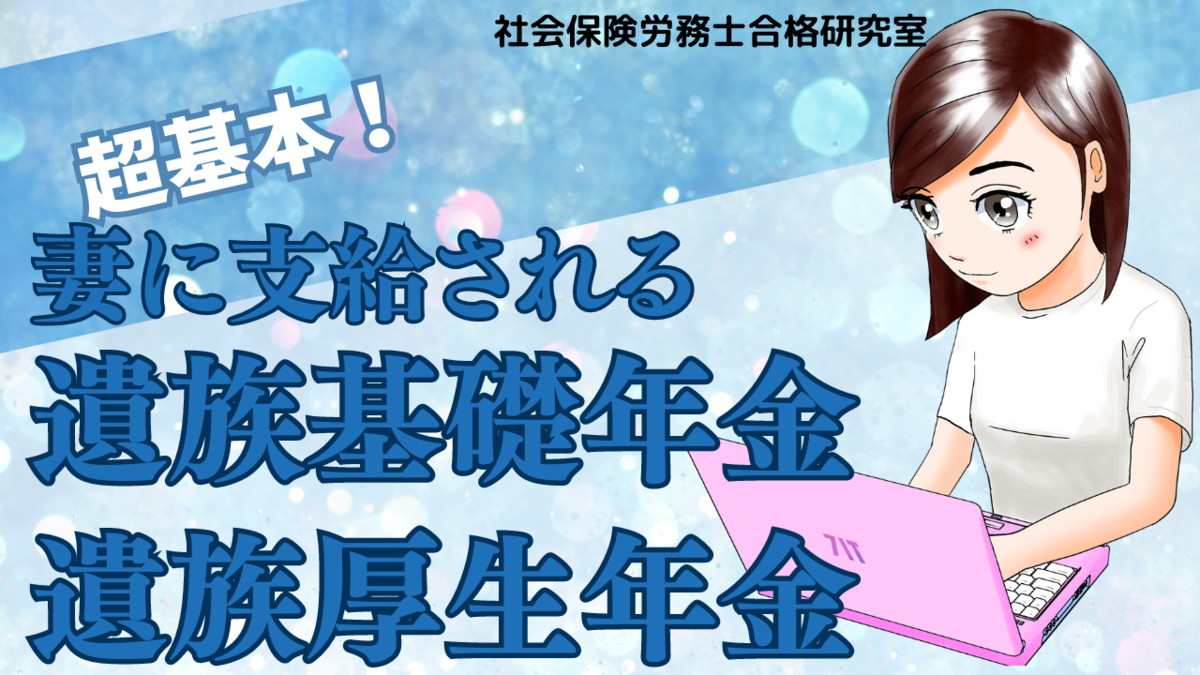
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-343 8.4
障害補償給付「準用」「加重」「併合繰上げ」「変更」【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
障害補償給付の重要ポイントを過去問でチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H21年問6】
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。

【解答】
①【H21年問6】 〇
<障害等級の準用>
障害等級表には、類型的な身体障害が掲げられています。障害等級表に掲げられていない障害は、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる障害に準じて障害等級が認定されます。
(則第14条第1項、第4項)
②【H21年問6】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】
②【H21年問6】 ×
<加重障害>
既に身体障害のあった者が、新たな業務災害により、同一の部位について障害の程度が加重した場合は、加重した障害等級に応ずる障害補償給付となります。
加重する前も加重した後も年金の等級の場合、その額は、現在の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額となります。
なお、既存の障害に係る従前の障害補償年金は、引き続き支給されます。
(則第14条第5項)
※下のイメージ図もご覧ください。
③【H21年問6】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合 第7級
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
③第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

【解答】
③【H21年問6】 〇
<併合・併合繰上げ>
障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級によるのが原則です。
ただし、一定の場合は等級が繰り上げられます。
問題文を例にしてみましょう。
①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合
↓
第13級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を1級繰り上げ7級となります。
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合
↓
第5級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を3級繰り上げて1級となります。
③第6級及び第8級の2障害がある場合
↓
第8級以上に該当する障害が2以上あるので重い方を2級繰り上げて4級となります。
(則第14条第3項)
④【H21年問6】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

【解答】
④【H21年問6】 〇
<加重障害>
②と同じです。
ただし、加重前が一時金で加重後が年金の場合の給付額は、新たな等級の年金額から既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額となります。
(則第14条第5項)
⑤【H21年問6】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】
⑤【H21年問6】 〇
<変更>
障害の程度が自然的な経過により増進し、又は軽減した場合の規定です。
例えば、3級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が、自然的経過により5級に軽減した場合は、新たに該当することとなった5級の障害補償年金が支給され、その後は、従前の3級の障害補償年金は支給されません。
この規定は、障害補償年金から障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)への変更です。
もともとが障害補償一時金の場合は、適用されません。
(第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-342 8.3
安全委員会・衛生委員会のチェックポイント【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
安全委員会、衛生委員会についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第17条 (安全委員会) ① 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。 (3) 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項 ② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 安全管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。 ④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 ⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第18条 (衛生委員会) ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 産業医のうちから事業者が指名した者 (4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 ④ 前条第3項から第5項までの規定は、衛生委員会について準用する。
第19条第1項 (安全衛生委員会) 事業者は、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。

【解答】
①【R4年出題】 ×
衛生委員会は、政令で定める規模の「事業場ごと」に設置義務があります。
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」に設置しなければなりません。
(第18条第1項、令第9号)
②【R4年出題】
安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務づけられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。

【解答】
②【R4年出題】 〇
衛生委員会は全業種が対象ですが、安全委員会は、安全管理者の選任義務がある業種が対象です。
事業場の規模は、常時50人以上か常時100人以上の2つがあります。
(第17条第1項、令第8条)
③【H21年出題】
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

【解答】
③【H21年出題】 〇
衛生委員会は、「全業種・50人以上」の事業場が対象ですので、安全委員会を設けなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。
(第17条第1項、第18条第1項、令第8条、令第9条)
安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。
④【H21年出題】
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。

【解答】
④【H21年出題】 〇
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
(則第23条)
ちなみに、委員会の開催に要する時間は、「労働時間」となります。
⑤【H21年出題】
事業者は、安全委員会を開催したときは、遅滞なく、当該安全委員会の議事の概要を所定の方法によって労働者に周知させなければならない。

【解答】
④【H21年出題】 〇
事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を所定の方法で労働者に周知させなければなりません。
(則第23条第3項)
※事業者は、委員会の開催の都度、所定の事項を記録し、3年間保存しなければなりません。
⑤【H16年出題】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【解答】
⑤【H16年出題】 ×
衛生委員会の委員として産業医を指名しなければなりません。専属の産業医に限られませんので、産業医が嘱託の場合でも、指名しなければなりません。
(昭63.9.16基発第601号の1)
⑥【H12年出題】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

【解答】
⑥【H12年出題】 〇
作業環境測定士は、「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。
(第18条第3項)
⑦【H26年出題】
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

【解答】
⑦【H26年出題】 ×
「その委員の半数」が誤りです。
「第1号の委員以外の委員の半数」となります。ちなみに第1号の委員は、議長となる委員です。
(第17条第4項、5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-341 8.2
労働基準法の賃金になるもの・ならないもの【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
労働基準法の賃金の定義を条文で読んでみましょう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
労働基準法の賃金となるもの・ならないものを過去問でみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する部分は、労働者が法律上当然生ずる義務を免れるため、「賃金」となります。
※ちなみに、労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに、企業が保険料の補助を行う場合は、福利厚生のために使用者が負担するものとなり、賃金とは認められません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H30年出題】
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
ストック・オプション制度から得られる利益は、労働の対償ではなく、賃金には当たりません。
(平9.6.1基発412号)
③【R1年出題】
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

【解答】
③【R1年出題】 ×
社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は、実費弁償であり、「賃金」に当たりません。
(昭63.3.14基発150号)
④【H26年出題】
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

【解答】
④【H26年出題】 ×
解雇予告手当は賃金ではありません。
(昭23.8.18基収2520号)
⑤【H22年出題】
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

【解答】
⑤【H22年出題】 ×
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞等の恩恵的給付は、原則として賃金とはみなされません。
ただし、結婚手当等で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、賃金となります。
(昭22.9.13発基17号)
⑥【H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
⑥【H27年出題】 〇
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、「臨時の賃金等」に当たります。
(昭22.9.13発基17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-340 8.1
遺族厚生年金「生計維持」について【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の条文を読んでみましょう。
第59条第1項 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものであることが条件です。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
遺族厚生年金の生計維持に係る要件については、被保険者又は被保険者であった者の「死亡の当時」の生計維持関係が問われます。
ただし、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給する場合の生計維持に係る要件については、「行方不明となった当時」の失踪者との生計維持関係が問われます。
(第59条第1項)
②【H25年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
生計を維持していたものと認めらないのは、年額130万円以上ではなく、年額850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合です。
(平成23.3.23年発0323第1号)
③【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

【解答】
③【R5年出題】 〇
前年収入が年額850万円未満であった者は、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められます。
(平成23.3.23年発0323第1号)
④【H29年出題】
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
生計維持関係は、死亡当時で認定されます。
その後、給与収入が減少しても、遺族厚生年金の受給権を得ることはできません。
(平成23.3.23年発0323第1号)
⑤【H27年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなされます。
「将来に向かって」がポイントです。死亡した当時にさかのぼるのではなく、出生したときに、遺族として受給権を取得します。
(第59条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-339 7.31
在職定時改定をチェック!【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
在職定時改定について条文を読んでみましょう。
第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
★在職定時改定とは
老齢厚生年金を受給しながら働いている(=厚生年金保険料を負担している)人について、負担した厚生年金保険料が、退職前に年金額に反映される制度です。
前年9月から当年8月までの厚生年金保険料納付実績が、毎年10月からの年金額に反映します。
ポイント!
在職定時改定が適用されるのは、65歳以上70歳未満です。
65歳未満には適用されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
①【R4年出題】 ×
在職定時改定の基準日は、7月1日ではなく、9月1日です。
(第43条第2項)
②【R5年出題】
厚生年金保険法第43条第2項の在職定時改定の規定において、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定するものとする。

【解答】
②【R5年出題】 〇
基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合
↓
基準日前に資格喪失し、1か月以内に、再び資格取得した場合、基準日に被保険者ではありませんが、在職定時改定の対象になります。例えば、8月26日に資格を喪失し、9月8日に再び被保険者の資格を取得したような場合です。
この場合は、まだ年金額に反映されていない前年9月から当年8月までの期間が、在職定時改定によって再計算され、10月から老齢厚生年金の額に反映されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-338 7.30
<10問で分かる>繰上げ支給の老齢基礎年金【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
老齢基礎年金の繰上げのよく出る問題をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ請求はできません。
(法附則第9条の2)
②【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されませんし、任意加入被保険者になることもできません。
(法附則第9条の2の3)
③【H23年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。

【解答】
③【H23年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった「日」に発生します。(翌日ではありません。)そして、受給権発生日の属する月の翌月から支給されます。
(法附則第9条の2第3項)
④【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】
④【H26年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
(法附則第9条の2第2項)
⑤【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
⑤【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。振替加算額は、65歳に達した日以後でなければ加算されません。
(S60法附則第14条)
⑥【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、65歳に達した日の属する月の翌月から加算されます。
なお、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げられますが、振替加算には繰下げによる増額はありません。
(S60法附則第14条)
⑦【H24年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑦【H24年出題】 〇
事後重症の障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までの間、請求できます。
ただし、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前でも、事後重症による障害基礎年金の請求はできません。
(法附則第9条の2の3)
⑧【H26年出題】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】
⑧【H26年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅します。
⑨【H19年出題】
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。

【解答】
⑨【H19年出題】 ×
付加年金は、老齢基礎年金に連動していますので、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合は、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されます。また、その際、減額率、増額率も同じように適用されます。
(法附則第9条の2第6項)
⑩【H27年出題】
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
⑩【H27年出題】 〇
ポイントその1
振替加算は、妻自身の老齢基礎年金に加算される年金です。夫の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止されていた場合でも、要件を満たせば、加算が行われます。
ポイントその2
老齢基礎年金の支給を繰り上げていても、振替加算は繰り上げられませんので、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算されます。
(S60法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
「事後重症」について国年・厚年両方の視点でお話します
R6-337 7.29
問題が解ける!事後重症【社労士受験対策】
「事後重症」について国民年金・厚生年金保険、それぞれの視点でお話します。
<今日の内容>
・事後重症の条件
キーワードは、
障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること
請求で受給権が発生すること
・事後重症の障害基礎年金でも請求が不要な場合
障害厚生年金が3級から2級に改定になった場合
★65歳に達した日の前日までの条件を忘れないようにすることがポイントです。
・「障害厚生年金」の受給権者でも、障害基礎年金の受給権は無いことがあります。
★1度も1・2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者
→ 障害基礎年金の受給権はありません
★2級だったが障害状態が軽減して現在3級の場合
→ 3級の間は障害基礎年金の支給は停止されますが、障害基礎年金の受給権はあります
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
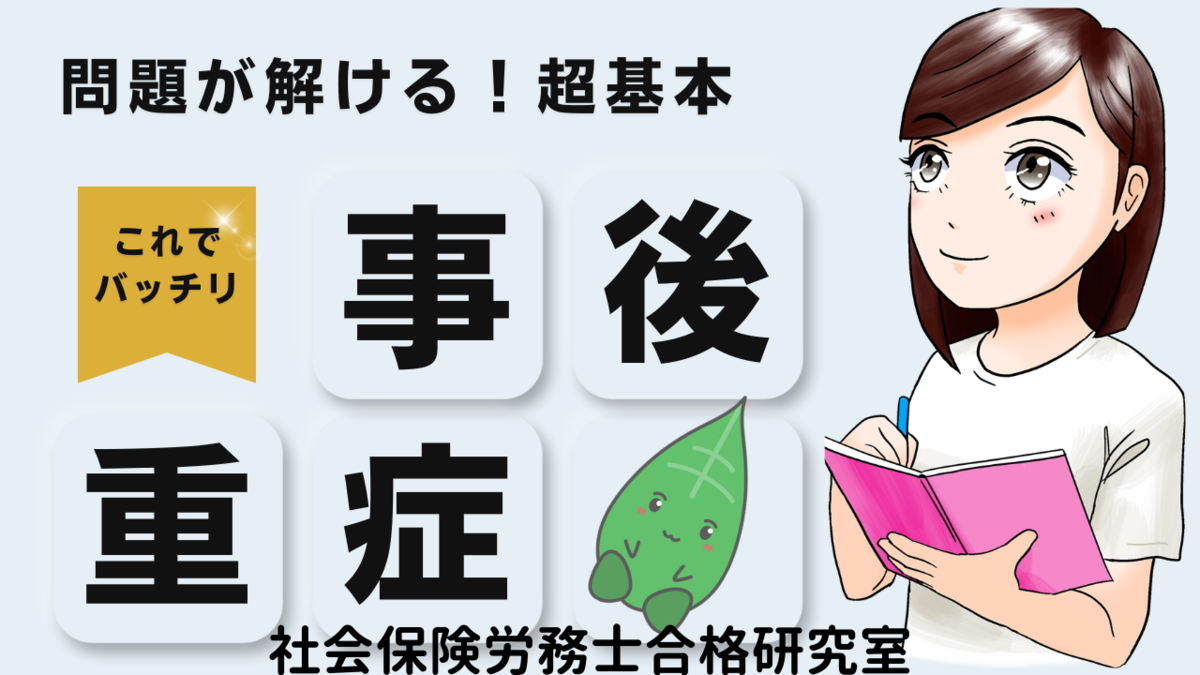
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-336 7.28
<選択式>高額療養費の支給要件【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
高額療養費の支給要件を条文で読んでみましょう。
第115条第1項 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 |
高額療養費のイメージ(療養の給付の場合)
一部負担金 |
療養の給付 | |
高額療養費 算定基準額 | 高額療養費 | |
(例)
56歳・標準報酬月額が41万円の被保険者
1か月の医療費が100万円(一部負担金30万円)
・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、
8万100円+(100万円-26万7千円)×1%=8万7430円です。
・高額療養費は、
30万円-8万7430円=21万2570円です。
選択式の過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。
<選択肢>
①7,330円
②84,430円
③125,570円
④123,670円

【解答】
A ③125,570円
ポイント!
★評価療養に係る特別料金、選定療養に係る特別料金は計算に入れません。
★「高額療養費算定基準額」は自己負担限度額、「高額療養費」は支給される額です。
問われているのは、「高額療養費」です。間違えないようにしましょう。
「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」
80,100円+(療養に要した費用(70万円)-267,000円)×1%=84,430円
「高額療養費」
21万円-84,430円=125,570円
(令42条)
②【H28年選択式】
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- < B >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は < C >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< D >となる。
<選択肢>
①40,070円
②42,980円
③44,100円
④44,400円
⑤45,820円
⑥80,100円
⑦93,000円
⑧140,100円
⑨267,000円
⑩558,000円
⑪670,000円
⑫842,000円

【解答】
B ⑫842,000円
C ⑤45,820円
D ⑧140,100円
(令第42条)
ポイント!
★Bについて
70歳未満・標準報酬月額83万円以上の高額療養費算定基準額
252,600円+(療養に要した費用-842,000円)×1%
252,600円は、842,000円の30%です。一部負担金として252600円支払っているということは、医療費が842,000円以上かかっているということです。
★Cについて
問われているのは、「高額療養費」です。
高額療養費算定基準額は
252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
高額療養費は
300,000円-254,180円=45,820円
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額、入院時食事療養に係る食事療養標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額は高額療養費の算定対象となりません。
(令第41条)
②【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】
②【R5年出題】 ×
食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は算定対象になりません。
(令第41条)
③【H27年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】
③【H27年出題】 ×
歯科診療と歯科診療以外の診療については、それぞれ別個の保険医療機関とみなされます。
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、高額療養費の算定上、別個の病院で受けた療養とみなされます。
(令第43条第9項)
④【H23年出題】
高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。

【解答】
④【H23年出題】 〇
同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、高額療養費の支給要件の取扱いではそれぞれ区別されます。
(令第43条第10項)
⑤【H24年出題】
被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
高額療養費は、暦月単位で計算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-335 7.27
一元適用事業・二元適用事業【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険徴収法には、「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。
労災保険と雇用保険の適用や保険料納付の手続などを一元化して処理する「一元適用事業」が原則です。
特例で、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして二元的に処理する事業は、「二元適用事業」といいます。
「二元適用事業」に当たる事業をおぼえましょう。それ以外は一元適用事業です。
では、二元適用事業について条文を読んでみましょう。
第39条第1項 (適用の特例) 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 則第70条 (適用の特例を受ける事業) 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 (1) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 (2) 港湾労働法の港湾運送の行為を行う事業 (3) 農林水産の事業 (4) 建設の事業 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

【解答】
①【H26年出題】(雇用) 〇
都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業です。
(第39条第1項)
②【H24年出題】(労災)
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

【解答】
②【H24年出題】(労災) ×
「国」の行う事業は二元適用事業ではないので、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」ではなく「都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」となります。
(第39条第1項)
③【H26年出題】(雇用)
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

【解答】
③【H26年出題】(雇用) 〇
国の行う事業は、二元適用事業ではありません。
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)は、労災保険の適用が除外で、労災保険が成立しないからです。
(第39条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-334 7.26
<選択式>雇用保険の被保険者となるもの【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
さっそく、選択式の過去問をどうぞ!
【R2年選択式】
1 雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
2 事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< C >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する< D >に提出しなければならない。
雇用保険法第38条に規定する短期雇用特例被保険者については、< E >か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して< E >か月を超えない場合には、被保険者資格を取得しない。
<選択肢>
① 1 ② 4 ③ 6 ④ 10 ⑤ 12 ⑥ 15
⑦ 20 ⑧ 30 ⑨ 20時間以上 ⑩ 21時間以上
⑪ 30時間以上 ⑫ 31時間以上 ⑬ 28日以上
⑭ 29日以上 ⑮ 30日以上 ⑯ 31日以上
⑰ 公共職業安定所長
⑱ 公共職業安定所長又は都道府県労働局長 ⑲ 都道府県労働局長
⑳ 労働基準監督署長

【解答】
A ⑨ 20時間以上
B ⑯ 31日以上
C ④ 10
D ⑰ 公共職業安定所長
E ② 4
(第4条第1項、第6条、第38条第1項、則第6条第1項)
★Eについて
「短期雇用特例被保険者」の定義から確認しましょう。
第38条第1項 (短期雇用特例被保険者) 被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち次の各号のいずれにも該当しない者(第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「短期雇用特例被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、特例一時金を支給する。 (1) 4か月以内の期間を定めて雇用される者 (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数 (30時間)未満である者 |
<4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者の扱い>
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得します。
例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得します。
ただし、当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても、当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4か月を超えない場合には、被保険者資格は取得しません。
(行政手引20555)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除く。)は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第2号)
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
②【H27年出題】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。

【解答】
②【H27年出題】 〇
学生・生徒は、雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第4号)
ただし、次の場合は、被保険者となります。
1 卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの
2 休学中の者
3 定時制の課程に在学する者
4 前3号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの
(則第3条の2)
休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となります。
③【H27年出題】
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。

【解答】
③【H27年出題】 〇
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は雇用保険の適用が除外されます。
(第6条第6号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-333 7.25
<選択式>休業補償給付の支給額について【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
まず、選択式の過去問をどうぞ!
【R5年選択式】
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。
<選択肢>
① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失
⑪ 療養

【解答】
A ⑪ 療養
B ⑦ 4
C ② 100分の60
★部分算定日とは
・療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
・一部について賃金が支払われる休暇(例えば、時間単位の年次有給休暇を取得した場合など)
<部分算定日の休業補償給付の額の出し方を確認しましょう>
午前中は労働し、午後は通院のため休業した場合
※給付基礎日額は10,000円、午前中の労働に対する賃金が3000円の場合
休業補償給付の額
↓
給付基礎日額(10,000円)から部分算定日に対して支払われる賃金の額(3,000円)を控除して得た額の100分の60=4,200円
午前 | 午後 |
労働(3,000円)) | 通院のため休業 |
| (10,000円-3,000円)×60%=4,200円 |
給付基礎日額10,000円 | |
択一式の過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
休業の初日から第3日目までは待期期間となり、休業補償給付は支給されません。その間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。
なお、複数業務要因災害、通勤災害には、事業主の労働基準法の休業補償を行う義務はありません。
(第14条第1項、労基法第76条)
②【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
会社の所定休日も、休業補償給付は支給されます。
③【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
所定労働時間の全部労働不能で、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日は、「賃金を受けない日」として休業補償給付が支給されます。
問題文の場合は、休業中に平均賃金の6割以上の金額を受けていますので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため休業補償給付は支給されません。
(昭40.9.15基災発第14号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-332 7.24
<選択式>雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働者を新たに雇い入れた場合、作業内容を変更した場合は、安全衛生教育を行わなければなりません。
雇入時、作業内容変更時の安全衛生教育の条文を読んでみましょう。
第59条第1項、2項 ① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
則第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 (1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 (2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 (3) 作業手順に関すること。 (4) 作業開始時の点検に関すること。 (5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 (6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 (7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。 (8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項 ② 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。 |
ポイント!
令和6年4月1日改正
特定の業種(安全管理者の選任義務がない非工業的業種)で認められていた教育項目の一部省略が、改正で廃止されました。
では、選択式の過去問をどうぞ!
【R4年選択式】
労働安全衛生法第59条において、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならないが、この教育は、< A >についても行わなければならないとされている。
<選択肢>
① 労働者が90日以上欠勤等により業務を休み、その業務に復帰したとき
② 労働者が再教育を希望したとき
③ 労働者が業務災害により30日以上休業し、元の業務に復帰したとき
④ 労働者の作業内容を変更したとき

【解答】
A ④ 労働者の作業内容を変更したとき
択一式の過去問もどうぞ!
①【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

【解答】
①【H17年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育の対象は、「全労働者」です。常時使用する労働者だけではありません。
雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。
違いに注意してください。
(第59条、則第35条、則第43条)
②【R2年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるとことにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育は、「全労働者」が対象です。
常時使用する労働者だけでなく、臨時に使用する労働者についても、雇入れ時の安全衛生教育を行うことが義務づけられています。
(第59条、則第35条)
③【R2年出題】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

【解答】
③【R2年出題】 〇
作業内容を変更したときにも、新規に雇い入れたときと同様に、全労働者に対して安全衛生教育を行わなければなりません。
④【H27年出題】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。

【解答】
④【H27年出題】 ×
派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、派遣先ではなく、「派遣元」の事業者に課せられています。
なお、作業内容変更時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」、「派遣先」の両方の事業者に課せられています。
ちなみに、「特別教育」「職長教育」の実施義務は、「派遣先」の事業者に課せられています。
(労働者派遣法第45条)
⑤【R2年出題】
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育は、所定労働時間内に行なうのが原則です。安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものとされています。
(昭47.9.18基発第602号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-331 7.23
労基法で派遣労働者についてよく出るところ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「労働者派遣」について、「派遣労働者」・「派遣元事業主」・「派遣先事業主」の関係を確認しましょう。
下の図を見てください。
労働基準法上の義務は、労働契約関係にある派遣元事業主が負うのが原則ですが、一部、派遣先事業主が負う場合もあります。
過去問でチェックしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
派遣先の事業に適用される規定もありますので、派遣先の指揮命令権者が使用者になることもあります。
(派遣法第44条動労基準法の適用に関する特例)
②【H30年出題】
派遣先の使用者が、派遣中の労働者に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる直接払の原則に違反しない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
派遣労働者に賃金を支払う義務があるのは、派遣元です。派遣元からの賃金を、派遣先が手渡すことだけであれば、直接払の原則に違反しません。
(昭61.6.6基発333号)
③【H18年出題】
労働者派遣中の労働者の休業手当について労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。

【解答】
③【H18年出題】 〇
休業の際、休業手当を支払う義務は、派遣元にあります。
派遣労働者の休業手当について使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。派遣元の使用者について、派遣労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断します。
(昭61.6.6基発333号)
④【H29年出題】
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

【解答】
④【H29年出題】 ×
派遣労働者に対する労働条件(労働時間、休憩、休日等も含めて)の明示は、労働契約を締結する際に「派遣元」の使用者が行います。
なお、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により「派遣先の事業のみ」を派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされています。
(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)
⑤【H17年出題】
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

【解答】
⑤【H17年出題】 ×
派遣先の使用者が、派遣労働者に時間外・休日労働を行わせる場合は、「派遣元」の事業場で、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)
⑥【H25年出題】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

【解答】
⑥【H25年出題】 〇
派遣労働者については、「派遣元」で36協定を締結しますので、派遣元の労働者には派遣労働者が含まれます。
問題文は、「派遣先」ですので、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含みません。
(昭61.6.6基発333号)
⑦【H16年出題】
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。

【解答】
⑦【H16年出題】 〇
派遣労働者については、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、「派遣元」の事業についてなされます。
代替労働者の派遣の可能性も含めて、「派遣元」の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することになります。
(昭61.6.6基発333号)
⑧【H25年出題】
派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

【解答】
⑧【H25年出題】 〇
派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、「派遣元」の使用者です。常時10人以上の人数には、派遣中の労働者も含みます。
(昭61.6.6基発333号)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
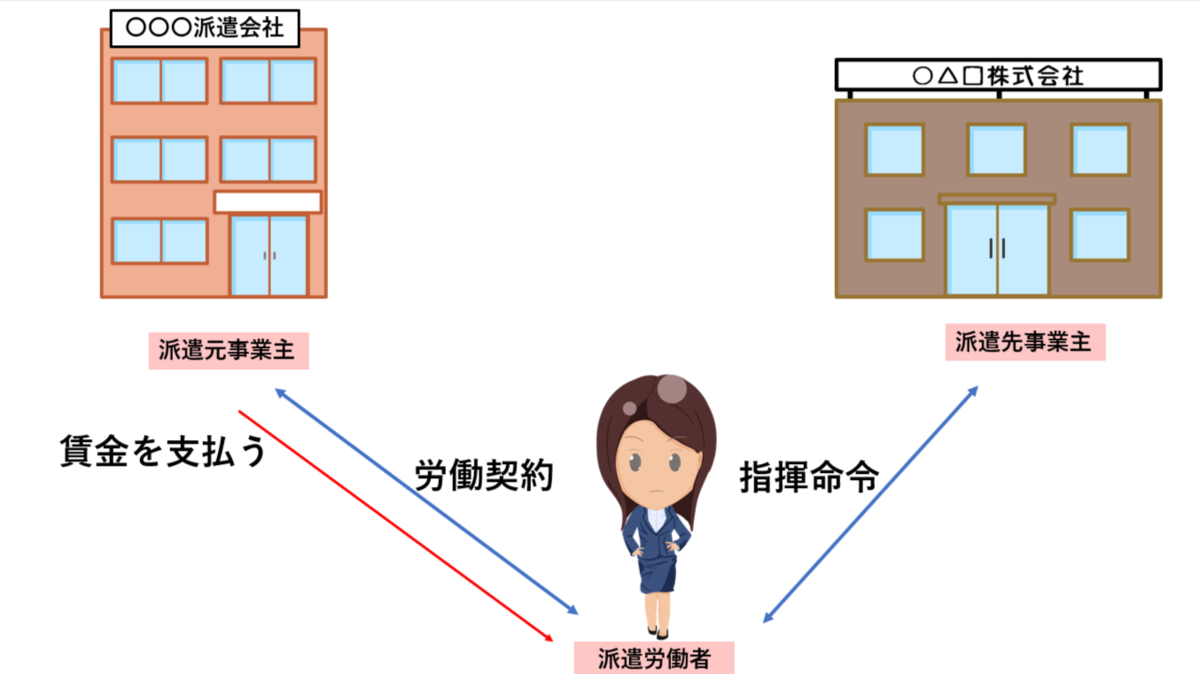
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
障害手当金の支給要件、支給されない場合、額など
R6-330 7.22
障害手当金のすべてお話します【社労士受験対策】
障害手当金は、3級よりも軽い障害が対象で、一時金で支給されます。
今日の内容は次の3つです。
①支給要件
ポイントは、「5年以内」「傷病が治った」
②障害手当金が支給されない場合
よく出題されています
③障害手当金の額(最低保障額あり)
最低保障額がポイントです。
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-329 7.21
厚生年金保険の被保険者になる・ならない【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H25年出題】
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険の被保険者とならないものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合。
イ 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合。
ウ 船舶所有者に臨時に使用される船員であって、その者が引き続き1か月未満の期間日々雇い入れられる場合。
エ 巡回興行などの所在地が一定しない事業所に使用される者であって、その者が引き続き6か月以上使用される場合。
オ 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。
A (アとイ)
B (アとエ)
C (イとウ)
D (ウとオ)
E (エとオ)

【解答】
【H25年出題】 E (エとオ)
アについて
次に該当する者は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
| 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して4か月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。 |
ポイント!
季節的業務に使用される者は、厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、当初から継続して4か月を超えて使用される予定の場合は、当初から被保険者となります。
ただし、「船舶所有者に使用される船員」の場合は、季節的業務に使用される者であっても適用除外になりませんので、被保険者となります。
(第12条第3号)
イについて
適用事業所に使用される70歳未満の者は 当然に厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者でも、以下の条件を満たせば、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険の被保険者となることができます。
・老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない
・事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた
(法附則第4条の5)
ウについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であって、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては1月を超え、ロに掲げる者にあっては定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。 イ 日々雇い入れられる者 ロ 2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの |
ポイント!
・日々雇い入れられる者は厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、被保険者となります。
・2月以内の期間を定めて使用される者で、所定の期間を超えて使用されることが見込まれないものは厚生年金保険の被保険者となりません。ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となります。
ただし、「船舶所有者に使用される船員」は、臨時に使用される者でも、被保険者となります。
(第12条第1号)
エについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
| 所在地が一定しない事業所に使用される者 |
ポイント!
巡回興行などの「所在地が一定しない事業所」に使用される者は、使用期間に関係なく、被保険者になりません。
(第12条第2号)
オについて
次に該当する場合は、厚生年金保険の被保険者から除外されます。
臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合。 |
ポイント!
臨時的事業の事業所に使用される者は厚生年金保険の被保険者になりません。ただし、継続して6か月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となります。
問題文は、「その者が継続して6か月を超えない期間使用される」ですので、被保険者になりません。
(第12条第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-328 7.20
<選択式>60歳台後半の在職老齢年金のポイント!【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。
<選択肢>
① 支給調整開始額 ② 支給調整基準額 ③ 支給停止開始額
④ 支給停止額 ⑤ 支給停止基準額 ⑥ 支給停止調整額
⑦ 総報酬月額 ⑧ 総報酬月額相当額 ⑨ 定額部分
⑩ 標準賞与月額相当額 ⑪ 平均標準報酬月額 ⑫ 報酬比例部分

【解答】
【H28年選択式】
A ⑧ 総報酬月額相当額
B ⑥ 支給停止調整額
C ⑤ 支給停止基準額
★用語を確認しましょう。
・「総報酬月額相当額」とは
→標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
・「基本月額」とは
→老齢厚生年金の額÷12
(加給年金額・第44条の3第4項に規定する加算額(=繰下げ加算額)を除く)。
・総報酬月額相当額+基本月額が「支給停止調整額」以下の場合
→老齢厚生年金は支給停止されず全額支給される
・総報酬月額相当額+基本月額が支給停止調整額を超えるときは、「支給停止基準額」が支給停止される。
支給停止基準額=(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×2分の1×12
・令和6年度の支給停止調整額は、50万円
・支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上の場合は、老齢厚生年金の全部が支給停止される。(繰下げ加算額は除く。)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者について、支給される年金額を調整する仕組みは、在職老齢年金と呼ばれる。

【解答】
①【H22年出題】 〇
「老齢厚生年金の受給権者が被保険者である」とは、老齢厚生年金を受給しながら働いている(厚生年金保険に加入して保険料を負担している)という意味です。
②【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項)
③【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
経過的加算額と繰下げ加算額は、基本月額の計算の対象に含まれません。
「繰下げ加算額」が計算に入らないのは第46条第1項に規定されています。
「経過的加算額」が計算に入らないのは、S60法附則第62条第1項に規定されています。
④【R4年出題】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
老齢基礎年金も経過的加算額も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
⑤【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
経過的加算額も老齢基礎年金も在職老齢年金の支給停止の対象になりません。
(第46条第1項、S60法附則第62条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-327 7.19
10問で分かる!死亡一時金【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
支給要件の条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項、2項 (支給要件) ① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 ② 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 (1) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 (2) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。「第2号被保険者、第3号被保険者」としての被保険者期間は対象とされません。
(第43条、第49条、第52条の2)
②【H23年出題】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

【解答】
②【H23年出題】 ×
65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、「死亡一時金、脱退一時金」については、第1号被保険者とみなされます。しかし、寡婦年金については、第1号被保険者とみなされません。
(H6法附則第11条第9項、H16法附則第23条第9項)
★ちなみに、65歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金について第1号被保険者とみなされます。
(法附則第5条第9項)
★「付加保険料」については、65歳未満の任意加入被保険者は、第1号被保険者とみなされ付加保険料を納付できます。65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、付加保険料は納付できません。
| 寡婦年金 | 死亡一時金 | 脱退一時金 | 付加保険料 | |
| 任意加入被保険者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特例の任意加入被保険者 | × | 〇 | 〇 | × |
③【R1年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】
③【R1年出題】 〇
保険料4分の1免除期間は、「4分の3」相当ですので、48月×4分の3=36月となります。要件を満たしますので、死亡一時金が支給されます。
(第52条の2第1項)
④【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

【解答】
④【H24年出題】 ×
「保険料全額免除期間」は、保険料を全く納付していませんので、計算に入りません。
(第52条の2第1項)
⑤【R2年出題】
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
(原則)
死亡した者の死亡日に、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません。
(例外)
ただし、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金は支給されます。
例えば、18歳に達した日以後の最初の3月に遺族基礎年金の受給権が発生しても、同じ月に受給権が消滅し、結局遺族基礎年金は支給されません。その場合は、死亡一時金が支給されます。
次に遺族の範囲について条文を読んでみましょう。
第52条の3 (遺族の範囲及び順位等) ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
⑥【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

【解答】
⑥【R1年出題】 〇
遺族の順位は決まっていて、祖父母と孫では、孫が優先します。
(第52条の3)
死亡一時金の額についての過去問をどうぞ!
⑦【H26年出題】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。

【解答】
⑦【H26年出題】 ×
死亡一時金の額は、6段階で設定されていて、32万円が最高です。32万円支給されるのは、420月以上の場合です。
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
月数は、以下の月数を合算します。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における
保険料納付済期間の月数
+
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
+
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
+
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
(第52条の4第1項)
⑧【H29年出題】
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。

【解答】
⑧【H29年出題】 〇
付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族の死亡一時金の額には、8,500円が加算されます。
(第52条の4第2項)
支給の調整について条文を読んでみましょう。
第52条の6(支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
過去問をどうぞ!
⑨【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
⑨【H24年出題】×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、その者の選択によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。
例えば、死亡一時金を選択した場合は、死亡一時金が支給され、寡婦年金は支給されません。
(第52条の6)
⑩【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
⑩【R3年出題】 〇
・1人1年金の原則
遺族厚生年金と寡婦年金はどちらか選択です。
・寡婦年金を選択した場合
死亡一時金は支給されません
・遺族厚生年金を選択した場合
死亡一時金も支給されます。
(第20条、第52条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-326 7.18
<選択式>健康保険の国庫負担など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
今日は、健康保険の費用の負担です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H23年選択式】 ※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。
4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E>の実施に要する費用の一部を補助することができる。
<選択肢>
① 一般保険料率 ② 一般保険料率の10% ③ 介護納付金
④ 概算払い ⑤ 組合間で調整 ⑥ 高額療養費の財政調整
⑦ 後期高齢者医療 ⑧ 児童手当拠出金 ⑨ 所要保険料率の50%
⑩ 精算払い ⑪ 退職者給付拠出金 ⑫ 調整保険料
⑬ 特定健康診査等 ⑭ 被保険者数 ⑮ 被保険者数及び被扶養者数
⑯ 分割払い ⑰ 保険外併用療養費 ⑱ 保険料収入
⑲ 保険料収入の25% ⑳ 予算

【解答】
A ⑳ 予算
B ③ 介護納付金
C ⑭ 被保険者数
D ④ 概算払い
E ⑬ 特定健康診査等
(第151条、152条、154条の2)
令和6年4月1日改正
★流行初期医療確保拠出金とは?
全国健康保険協会及び健康保険組合は「流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金)」を納付する義務を負うことになりました。
(内容)
「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により一般医療の提供を制限して、流行初期の感染患者への医療の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、財政的な支援を行います。(流行初期医療確保措置)事業実施主体は、「都道府県」で、措置に関する費用は、公費と保険者で負担することになっています。
★「出産育児交付金等」が導入されました。
出産育児一時金を全世代で支えあう制度です。
条文を読んでみましょう。
第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。 |
下のイメージ図をご覧ください。
選択式の練習をどうぞ!
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の< A >については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により< B >が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
<選択肢>
① 全部 ② 全部又は一部 ③ 一部
④ 政府 ⑤ 社会保険診療報酬支払基金 ⑥ 厚生労働大臣

【解答】
A ③ 一部
B ⑤ 社会保険診療報酬支払基金
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、健康保険組合に対しても負担を行っています。
(第151条)
②【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等には国庫補助が行われます。しかし、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
(第153条)
③【H30年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の「全部」ではなく、「一部」を補助することができる、です。
(第154条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-325 7.17
滞納処分と延滞金の注意点【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
第28条第1項 (延滞金) ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
※令和6年度中の延滞金の割合 ・年8.7パーセント (納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、年2.4パーセント) |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
延滞金は、「指定した期限の翌日」からではなく、「法定納期限の翌日」から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算します。
(第28条第1項)
納期限
▼ |
| 督促状の 指定期限 ▼ |
|
| 完納
▼ |
| 納期限の 翌日 |
|
| 完納の 前日 |
|
|
|
| |||
②【H29年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
②【H29年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、事業主が督促状に指定された期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されません。
延滞金が徴収されない場合を条文で読んでみましょう。
第28条第5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 |
③【H26年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
③【H26年出題】(雇用) ×
「追徴金」について
追徴金は、労働保険料ではないことに注意してください。
・ 督促の対象は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」ですので、追徴金も督促の対象になります。
(第27条第3項)
・ 延滞金は、「労働保険料の納付を督促」したときに徴収されます。追徴金は労働保険料ではありませんので、追徴金は延滞金の対象になりません。
(第28条第1項)
④【H22年出題】(雇)
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

【解答】
④【H22年出題】(雇) ×
追徴金は、国税滞納処分の例によって処分される対象になります。
(第27条第3項)
追徴金の額については、延滞金の対象になりません。
(第28条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-324 7.16
<選択式>雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
雇用保険の被保険者の資格を喪失したときの手続をみていきます。
選択式の過去問をどうぞ!
【R4年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12ある時は、 < A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,700円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,746円とする。
(選択肢)
A ① 最後の完全な6賃金月 ② 最初の完全な6賃金月
③ 中間の完全な6賃金月 ④ 任意の完全な6賃金月
B ① 雇用保険被保険者資格取得届 ② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 雇用保険被保険者証 ④ 雇用保険被保険者離職票
C ①1,350円 ②1,373円 ③ 2,160円 ④ 2,196円

【解答】
A ① 最後の完全な6賃金月
B ④ 雇用保険被保険者離職票
C ④ 2,196円
Bについて
離職票には賃金額が記載されています。
Cについて
令和5年8月1日からの賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,700円、最低賃金日額が2,746円ですので、「最低賃金日額の2,746円」が令和5年8月1日以後の賃金日額の下限となります。
算定した賃金日額が2,500円ですので、下限が適用され、基本手当日額は、
2,746円×80%=2,196円
となります。
(第16条、第17条、第18条、行政手引50601)
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【R4年出題】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【解答】
①【R4年出題】 ×
雇用保険被保険者資格喪失届は、事実のあった日の属する月の翌月10日までではなく、「当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に提出しなければなりません。
被保険者資格を喪失する理由としては、離職、死亡などがあります。
例えば、「離職」した場合は、「離職の翌日」が資格喪失日(事実のあった日)となりますので、資格喪失届は、離職日の翌々日から10日以内に提出しなければなりません。
(則第7条第1項)
②【H26年出題】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
則第7条第3項 事業主は、資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。 |
ポイント!
■資格喪失の原因が「離職」である場合は、資格喪失届に「離職証明書」の添付が必要
ただし
■被保険者が、「離職票」の交付を希望しないときは、離職証明書は添付しなくてもよい
ただし、
■離職日に59歳以上の被保険者については、離職票の交付を希望しないときでも、離職証明書を添付しなければならない
★離職証明書と離職票を区別してください。
離職証明書は3枚1組で、事業主控と離職票が付いています。
離職証明書は公共職業安定所に提出するもので、離職票は、離職者に交付されるものです。
③【H18年出題】
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。

【解答】
③【H18年出題】 ×
離職により被保険者でなくなった者に対して事業主が離職証明書を交付することもあります。
(則第16条)
離職票は、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付した場合に交付されることが通常です。
このほかに、離職者が公共職業安定所に直接離職票の交付を請求して交付される場合があります。
離職者がこの請求を行う場合には、原則として事業主から離職者に対して交付された離職証明書を提出しなければなりません。事業主は、このような場合は、離職者から離職証明書の交付を求められることになります。
(行政手引21453)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害厚生年金3つの要件と額の計算
R6-323 7.15
障害厚生年金の超基本お話します【社労士受験対策】
障害厚生年金の受給権が発生する条件を障害基礎年金と比較しながらみていきます
①初診日
②保険料納付要件
③障害認定日
障害厚生年金の被保険者=原則国民年金第2号被保険者という点も意識してください 障害厚生年金の額は報酬比例です。
1・2級には加給年金額が加算されます
3級は障害基礎年金は支給されません。加給年金額も加算されません。ただし、最低保障が設けられています。
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 労災保険法
R6-322 7.14
<選択式>療養補償給付のポイント【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
過去問で療養補償給付のポイントをみていきます。
では、選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
労災保険法第13条第2項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。
<選択肢>
① 治療材料 ② 薬剤 ③ リハビリ用品 ④ 療養の費用

【解答】
A ④ 療養の費用
第13条の条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 (1) 診察 (2) 薬剤又は治療材料の支給 (3) 処置、手術その他の治療 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 (6) 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
則第11条の2 (療養の費用を支給する場合) 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。 |
★療養補償給付の原則は「療養の給付(=現物給付)」です。
★ただし、「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、療養の費用の支給(=現金給付)が行われます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H21年出題】
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
療養の給付は、指定病院等で行われます。
指定病院等とは、
・社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(=労災病院のこと)
又は
・都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
です。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院でも、労災保険の指定病院等でない場合は、療養の給付は行われません。
(則第11条第1項)
②【H21年出題】
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
療養の給付に代えて療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合」のほか、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」です。
「労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合」では、療養の費用は支給されません。
(則第11条の2)
③【H21年出題】
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。

【解答】
③【H21年出題】 ×
療養の給付の範囲は、①~⑥の「ほか」政府が療養上相当と認めるものではありません。①~⑥の「なか」で政府が必要と認めるものに限られます。
(第13条第2項)
④【H21年出題】
療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

【解答】
④【H21年出題】 ×
指定病院等を変更しようとするときは、届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を「経由」して「所轄労働基準監督署長」に提出しなければなりません。
提出先は、都道府県労働局長ではなく「所轄労働基準監督署長」です。また、承認を受ける必要はありません。
指定病院等を「経由」することにも注意してください。
(則第12条第3項)
⑤【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
症状が残っていてもそれが安定して、医療効果が期待しえない状態になった場合は、療養の必要がなくなったものとされ、療養の給付は行われなくなります。
(昭23.1.13基災3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-321 7.13
<選択式>事業者等の責務【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
では、選択式の過去問をどうぞ!
①【H18年選択式】
労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。
<選択肢>
① 職場における安全衛生水準の向上に努め
② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
③ 危険及び健康障害を防止するようにし
④ 労働災害の防止を図ら

【解答】
A ② 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
②【R4年選択式】
労働安全衛生法において、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、< B >と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」と規定されている。
<選択肢>
① 快適な職場環境の実現 ② より高度な基準の自主設定
③ 労働災害の撲滅に向けた活動 ④ 労働災害の防止に関する新たな情報の活用

<解答>
B ① 快適な職場環境の実現
第3条第1項で定められているのは、事業者の責務です。
事業者は、単に労働災害防止のためにこの法律で定められた最低基準を守るだけでなく、さらに快適な職場環境の実現と賃金、労働時間等の労働条件の改善を通じて、労働者の安全と健康を確保すべき責務を有していることを明らかにしています。
(昭47.9.18発基第91号)
③【H17年選択式】
労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を< C >し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の< C >、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< D >なければならない。」旨の規定が置かれている。
<選択肢>
① 譲渡 ② 設計 ③ 設置 ④ 発注
⑤ に資するように努め ⑥ に配慮し ⑦ のための必要な措置を講じ
⑧ を図るように努め

【解答】
C ② 設計
D ⑤ に資するように努め
第3条第2項の条文を読んでみましょう。
| 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 |
①機械等の設計者・製造者・輸入者
②原材料の製造者・輸入者
③建設物の建設者・設計者
は、それぞれの立場で労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。
(昭47.9.18発基第91号)
では択一式の過去問もどうぞ!
①【H26年出題】
労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。

【解答】
①【H26年出題】 〇
建設工事の注文者等の責務についての規定です。
労働安全衛生法第3条第3項の条文を読んでみましょう。
第3条第3項 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 |
②【H26年出題】
労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。

【解答】
②【H26年出題】 〇
機械等の設計者・製造者・輸入者の責務についての問題です。
(第3条第2項)
③【H29年出題】
労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めることを求めている。

【解答】
③【H29年出題】 〇
原材料の製造者・輸入者の責務についての問題です。
(第3条第2項)
④【R2年出題】
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

【解答】
④【R2年出題】 〇
「機械等の設計者、製造者又は輸入者」、「原材料の製造者又は輸入者」、「建設物の建設者又は設計者」、「建設工事の注文者等」についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有しています。
(昭47.9.18発基第91号)
なお、「労働者」にも責務の規定が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-320 7.12
賃金の重要問題5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「賃金」の重要ポイントを過去問でみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
健康診断の結果に基づいて、医師の証明の範囲内で、使用者が休業を命じた場合には、使用者は労務の提供のなかった限度で賃金を支払わなくても差し支えないとされています。
問題文の休業を命じた日については「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H23年出題】
労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
②【H23年出題】 ×
・労働者が、業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したこと
↓
債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえない
・使用者が、業務命令を事前に発したということは
↓
その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべき
・労働者が提供した内勤業務については
↓
労務を受領したものとはいえない
・使用者は、労働者に対し内勤業務に従事した時間に対する賃金の支払義務は負わない
(昭和60年3月7日最高裁判所第1小法廷)
③【H23年出題】
労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
③【H23年出題】 ×
80%条項は、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定する限りにおいては、有効です。
しかし、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎としている点は、公序に反し無効とされています。
労働基準法又は労働組合法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせることになるからです。
(平成元年12月14日最高裁判所第一小法廷)
④【H23年出題】
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。

【解答】
④【H23年出題】 〇
5分の遅刻で、30分遅刻したものとして賃金カットをすることは、全額払違反となります。
ただし、第91条の減給制裁の制限内で行う場合は全額払い違反にはなりません。
(第91条 昭63.3.14基発150号)
⑤【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に含めないことが原則です。
ただし、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎となる賃金に含めなければなりません。
(第37条 昭22.11.5基発231号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-319 7.11
おさえておきたい解雇のルール5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「解雇」のルールを過去問でチェックしていきます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができませんが、労働者が自由な判断で同意した場合は、取り消すことができるとされています。ただし、解雇予告の意思表示の取消しに対して労働者の同意がない場合は、取り消すことはできません。
問題文は、労働者は、解雇の取り消しの申出に同意せず、それに応じなかったため、予告どおりに解雇となります。任意退職にはなりません。
(昭33.2.13基発90号)
②【H24年出題】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

【解答】
②【H24年出題】 ×
即時解雇の効力が発生する日は、「即時解雇の意思表示をした日」or「解雇予告除外認定のあった日」どちらの日でしょうか?
解雇予告除外認定は、解雇の意思表示をする前に受けるのが原則です。
解雇予告除外認定は、除外事由に該当する事実があるか否かを確認する処分です。
認定されるべき事実がある場合は、使用者は有効に即時解雇することができます。
そのため、即時解雇の意思表示をした後に、解雇予告除外認定を受けた場合は、解雇の効力は、「使用者が即時解雇の意思表示をした日」に発生します。
(昭63.3.14基発150号)
③【H24年出題】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 〇
解雇予告について確認しましょう。
★30日前に予告する
例えば、8月31日に解雇する場合は、遅くとも8月1日には解雇予告をしなければなりません。
解雇の予告をした日は、予告期間に算入されないことがポイントです。
★即時解雇の場合は、解雇予告手当を支払う
即時解雇をする場合は、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払わなければなりません。
★予告期間と予告手当を組み合わせて30日にする
8月31日をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をした場合、予告期間は16日です。(解雇の予告をした日は算入しません。)そのため、解雇予告手当は、平均賃金の14日分以上が必要です。
(第20条第1項)
④【H24年出題】
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。

【解答】
④【H24年出題】 ×
解雇の予告期間中に、業務上の負傷をし療養のため休業した場合、たとえ休業期間が1日~2日の軽度のものでも労働基準法第19条が適用されますので、その後30日間は解雇できません。解雇の効力は、当初の予告どおりの日には発生しません。
(昭26.6.25基収2609号)
⑤【H24年出題】
労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等、労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
解雇も「退職」のひとつで、「退職」には、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等があります。
(第89条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-318 7.10
【選択式】3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年選択式】
厚生年金保険法第26条第1項の規定によると、3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から当該子が3歳に達したときに該当するに < A >までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前 < B >における被保険者であった月のうち直近の月。以下「基準月」という。)の標準報酬月額(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなすとされている。
<選択肢>
① 1年以内 ② 1年6か月以内 ③ 2年以内 ④ 6か月以内
⑤ 至った日の属する月 ⑥ 至った日の属する月の前月
⑦ 至った日の翌日の属する月 ⑧ 至った日の翌日の属する月の前月

【解答】
A⑧ 至った日の翌日の属する月の前月
B ① 1年以内
(第26条第1項)
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額の特例のイメージ
子を養育する期間 3歳
従前標準報酬月額
| 将来の年金額は、従前標準報酬月額を 標準報酬月額とみなして計算します |
標準報酬月額が低下 |
ポイント!
・被保険者又は被保険者であった者が、実施機関に申出をすること
・対象になる期間
→子を養育することとなった日の属する月~子が3歳に達したときに該当するに至った日の翌日の属する月の前月まで
・将来の年金額は、従前標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして計算する
・従前標準報酬月額とは
→子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額
※当該月に被保険者でない場合は、当該月前1年以内における被保険者であった月 のうち直近の月。
・申出が行われた日の属する月前の月は、申出が行われた日の属する月の前月までの 2年間のうちにあるものに限って、標準報酬月額の特例が受けられる。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
9月3日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000円から240,000円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000円に改定された。この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000円である。

【解答】
①【H27年出題】 ×
8月 | 9月(出産) |
280,000円 | 定時決定 240,000円 |
従前標準報酬月額は、「子を養育することとなった日(9月3日)の属する月の前月の標準報酬月額」ですので、280,000円です。
(第26条第1項)
②【R3年出題】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子を養育することとなった日の属する月から当該子が3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月において、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間のうちにあるものに限られている。

【解答】
②【R3年出題】 ×
さかのぼって特例が適用されるのは、特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の申出が行われた日の属する月の前月までの3年間ではなく、「2年間」のうちにあるものに限られます。
(第26条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-317 7.9
【選択式】合意分割の請求【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
過去問からどうぞ!
①【R2年選択式】
厚生年金保険法第78条の2第1項の規定によると、第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき< A >について合意しているときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができるとされている。ただし、当該離婚等をしたときから< B >を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 按分割合 ② 改定額 ③ 改定請求額 ④ 改定割合
⑤ 1年 ⑥ 2年 ⑦ 3年 ⑧ 6か月

【解答】
A ① 按分割合
B ⑥ 2年
(第78条の2第1項)
②【H29年選択式】
合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、< C >の範囲内でそれぞれ定められなければならない。
<選択肢>
① 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
② 第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
④ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下

【解答】
③ 第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下
按分割合の条文を読んでみましょう。
第78条の3第1項 按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。 |
<按分割合>
第2号改定者の対象期間標準報酬総額 |
第1号改定者の対象期間標準報酬総額+第2号改定者の対象期間標準報酬総額 |
合意分割によって
・第2号改定者(分割を受ける側)の対象期間標準報酬総額(持ち分)が増えます。
・按分割合の上限は2分の1です。
択一式の過去問もどうぞ!
【H27年出題】
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

【解答】
【H27年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第78条の2第1項、2項 (離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) ① 第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であった者であって、標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。)をした場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。 (1) 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。)について合意しているとき。 (2)家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。 ② 標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金
R6-316 7.8
老齢厚生年金の超基本お話します【社労士受験対策】
老齢厚生年金は65歳から老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
また、当分の間は、60歳から65歳未満の間に、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
それぞれの計算式や、支給要件の違いをみていきましょう。
★YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
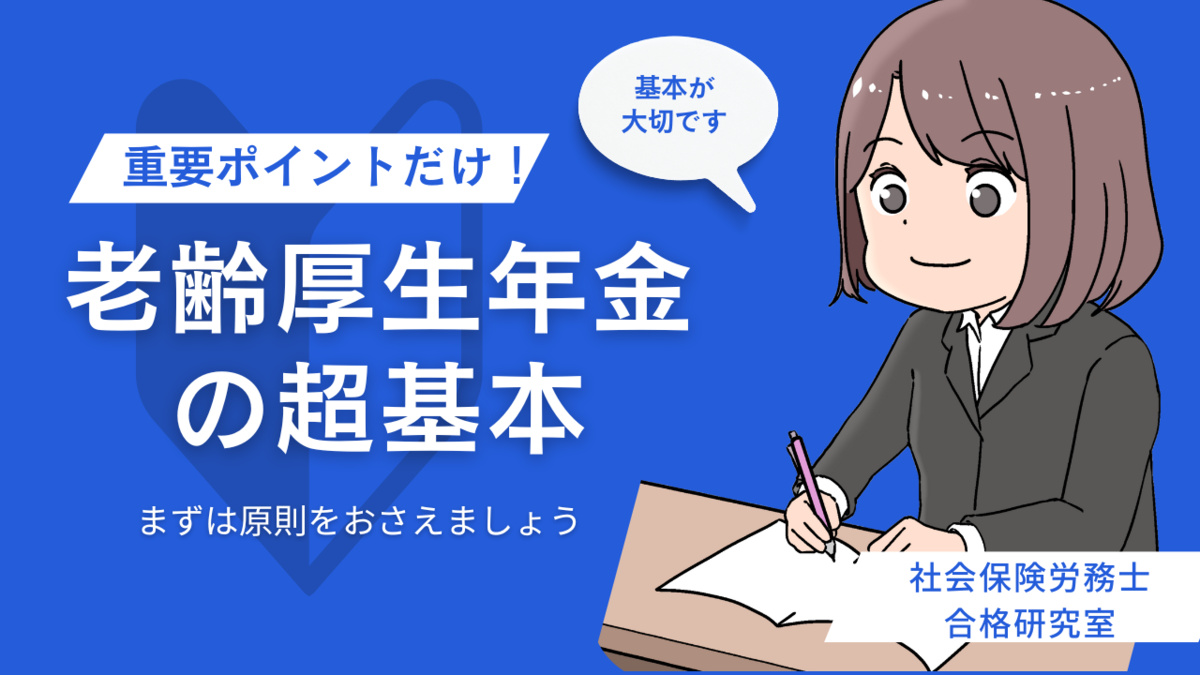
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-315 7.7
国民年金の被保険者期間の計算【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
被保険者期間の計算について条文を読んでみましょう。
第11条 (被保険者期間の計算) ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 |
被保険者期間は月単位で計算します。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
平成11年4月1日生まれの者は平成31年3月31日に20歳に達し、その日に資格を取得します。被保険者期間に算入されるのは、資格を取得した日の属する月からですので、平成31年3月からです。
(第11条)
②【H26年出題】
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

【解答】
②【H26年出題】 ×
昭和29年4月1日生まれの場合、60歳に達するのは、平成26年3月31日です。被保険者期間に算入されるのは、「資格を喪失した日の属する月の前月」までですので、平成26年2月までです。
(第11条)
③【H29年出題】
平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

【解答】
③【H29年出題】 〇
同じ月に取得と喪失がある場合は、その月は1か月として、被保険者期間に算入されます。
(第11条)
④【H26年出題】
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
④【H26年出題】〇
・ 4月1日に資格取得・4月30日に資格喪失の場合は1か月が被保険者期間に算入されます。
・ 4月1日に資格取得・同年5月31日に資格喪失の場合、資格を喪失した日の属する月の前月が4月ですので、1か月が被保険者期間に算入されます。
(第11条)
⑤【R5年出題】
被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間を2か月として被保険者期間に算入する。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
同じ月に、資格取得と資格喪失があるときは、その月は1か月として被保険者期間に算入されますが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、「後の被保険者期間」で1か月として被保険者期間に算入されます。「前後を合算」は誤りです。
(第11条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-314 7.6
<選択式>学生納付特例のチェックポイント【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
<選択肢>
① 1年2か月 ② 1年6か月 ③ 2年2か月 ④ 2年6か月

【解答】
A ③ 2年2か月
免除される期間は、「厚生労働大臣の指定する期間」です。
具体的にみてみましょう。
1.申請免除及び納付猶予の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間
2.学生納付特例の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間
(平成26年厚生労働省告示第191号)
国民年金保険料の免除がさかのぼって申請できるのは、保険料の納期限から2年を経過していない期間です。
例えば、令和4年8月分の保険料の納付期限は令和4年9月30日です。令和6年9月30日までに免除の申請をすれば、2年1か月前の分まで遡って免除されます。
※「2年2か月」遡及できる場合
なお、保険料の納期限は翌月末日ですが、その日が土日等の場合は、翌々月の第1営業日が納付期限になります。
例えば、令和4年6月の保険料は、7月31日が日曜日だったため、8月1日が納期限となります。そのため、令和4年6月分の免除申請の期限は令和6年8月1日となります。この場合は2年2月前の分まで遡って免除されます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
学生納付特例の適用を受けるには所得要件がありますが、世帯主又は配偶者の所得は問われず、本人の所得要件のみが問われるのがポイントです。
(第90条の3第1項)
所得要件を確認しましょう
| 本人 | 世帯主 | 配偶者 |
申請免除(全額・一部) | 〇 | 〇 | 〇 |
学生納付特例 | 〇 | ― | ― |
納付猶予 | 〇 | ― | 〇 |
②【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

【解答】
②【R3年出題】 ×
納付猶予制度は法附則に規定される時限措置で、有効期間は令和12年6月までです。
(H26年法附則第14条の3)
学生納付特例制度は、国民年金法本則に規定される恒久的な制度で、時限措置ではありません。
(第90条の3)
③【H28年出題】
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

【解答】
③【H28年出題】 〇
学生等は、申請全額免除・一部免除・納付猶予の対象から除外されています。
ただし、法定免除は学生等にも適用されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-313 7.5
<選択式>国民年金の給付制限【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、選択式からどうぞ!
【H26年選択式】
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。
<選択肢>
① 医師の診療を拒んだ ② 全額の支給を停止する
③ 全部を一時差し止める ④ 全部又は一部を一時差し止める
⑤ 全部又は一部を行わない ⑥ 当該職員の指導に従わない
⑦ 当該職員の診断を拒んだ ⑧ 療養に関する指示に従わない

【解答】
A ⑧ 療養に関する指示に従わない
B ⑤ 全部又は一部を行わない
「全部又は一部を行わないことができる」の条文を読んでみましょう。
第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。 |
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【R5年出題】
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「障害基礎年金は支給しない」です。
「支給しない」の条文を読んでみましょう。
第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 |
「故意」の場合は、「全部又は一部を行わないことができる」ではなく「支給しない」です。
②【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

【解答】
②【R1年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権が「消滅する」条文を読んでみましょう。
第71条第2項 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 |
③【R1年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべきものを故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

【解答】
③【R1年出題】 〇
「支給しない」条文を読んでみましょう。
第71条第1項 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 |
④【R2年出題】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「支給を停止する」ではなく、「年金給付の支払を一時差し止めることができる」です。
差止めの場合、届出を提出すれば、差止められていた年金がさかのぼって支払われます。
「一時差し止めることができる」の条文を読んでみましょう。
第73条 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 |
⑤【R1年出題】
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
差し止めと違い、支給停止の場合は、停止された年金は支払われません。
条文を読んでみましょう。
第72条 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。 |
⑥【R4年出題】
国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
受診命令に従わず、職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
(第72条第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-312 7.4
<選択式>保険外併用療養費のよく出るところ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、保険外併用療養費について条文を読んでみましょう。
第86条第1項 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 |
「評価療養」とは
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
「患者申出療養」とは
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
「選定療養」とは
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
では、過去問をどうぞ!
【R4年選択式】
保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定されている選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が< A >の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が< B >を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
<選択肢>
① 90日 ② 120日 ③ 150日 ④ 180日
⑤ 150以上 ⑥ 200以上 ⑦ 180以上 ⑧ 250以上

【解答】
A ⑥ 200以上
B ④ 180日
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
択一式の過去問もどうぞ!
①【R4年出題】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

【解答】
①【R4年出題】 ×
イメージ図をご覧ください。
「選定療養」の部分は全額患者負担になるのがポイントです。
「保険外併用療養費」は、通常は「療養の給付」に当たる部分です。
保険診療 | 選定療養(保険適用外) | |
30万円 | 10万円 | |
一部負担金9万円 | 保険外併用療養費 | |
被保険者は保険診療の自己負担額(30万円の3割)と、選定療養に要した費用(10万円)を合わせて19万円を支払います。
(第86条第2項)
②【H28年出題】
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
予約診療は、保険外併用療養費制度の選定療養の対象となります。
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
③【H26年出題】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

【解答】
③【H26年出題】 ×
選定療養の対象になるのは、100床以上ではなく、200床以上の病院です。
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-311 7.3
労働保険料の被保険者負担について【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H22年出題】(雇用)
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。

【解答】
①【H22年出題】(雇用) ×
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額は、事業主が全額負担します。労働者の負担はありません。
(第31条第3項)
②【H22年出題】(雇用)※改正による修正あり
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。

【解答】
②【H22年出題】(雇用) 〇
一般保険料には、「労災保険料」と「雇用保険料」があり、「雇用保険料」には、「二事業」分が含まれます。
雇用保険の被保険者が負担するのは、「雇用保険料」から「二事業」分を引いた額の2分の1です。雇用保険料全体の2分の1ではありませんので、注意してください。
なお、二事業の分は、事業主が全額負担します。
例えば、令和6年度の一般事業の雇用保険料率は、1000分の15.5で、そのうち二事業の率は1000分の3.5です。
被保険者が負担するのは、(1000分の15.5-1000分の3.5)×2分の1=1000分の6です。
事業主が負担するのは、(1000分の15.5-1000分の3.5)×2分の1+1000分の3.5=1000分の9.5です。
(第31条第1項第1号)
③【H22年出題】(雇用)
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。

【解答】
③【H22年出題】(雇用) ×
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額と、一般保険料を負担しなければなりません。
日雇労働被保険者は、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1」と「印紙保険料の額の2分の1」を負担します。
(第31条第3項)
④【H22年出題】(雇用)
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。

【解答】
④【H22年出題】(雇用) ×
第3種特別加入保険料は、労災保険料ですので、事業主が全額負担します。
(第31条第3項)
⑤【H25年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。

【解答】
⑤【H25年出題】(雇用) 〇
控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。月給制の場合は、毎月賃金を支払う都度控除しなければなりませんので、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできません。
条文を読んでみましょう。
第32条第1項(賃金からの控除) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
則第60条 (賃金からの控除) ① 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。 ② 事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
|
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-310 7.2
<選択式>日雇労働者の基本問題【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
雇用保険法第42条は、同法第3章4節において< A >とは、< B >又は < C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
<選択肢>
① 2か月 ② 4か月 ③ 4か月以内の期間を定めて雇用される者
④ 6か月 ⑤ 7日 ⑥ 11日 ⑦ 13日 ⑧ 15日
⑨ 18日 ⑩ 26日 ⑪ 28日 ⑫ 30日 ⑬ 31日
⑭ 31日以上雇用されることが見込まれない者 ⑮ 季節的に雇用される者
⑯ 短期雇用特例被保険者 ⑰ 特定受給資格者 ⑱ 特例受給資格者
⑲ 日々雇用される者 ⑳ 日雇労働者

<解答>
A ⑳ 日雇労働者
B ⑲ 日々雇用される者
C ⑫ 30日
D ⑨ 18日
E ⑬ 31日
(第42条)
★日雇労働者とは★
・日々雇用される者
・30日以内の期間を定めて雇用される者
をいいます。
ただし、以下の場合は、日雇労働者とはされません。
・連続する前2月の各月において18日以上同一事業主の適用事業に雇用されたとき
(2月は「暦月」です。)
・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたとき
※なお、雇用保険法第43条第2項の認可を受けた場合は、引き続き日雇労働被保険者として取り扱われます。
②【H29年選択式】
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
<選択肢>
① 2月 ② 3月 ③ 4月 ④ 6月
⑤ 11日 ⑥ 16日 ⑦ 18日 ⑧ 20日

【解答】
A ① 2月
B ⑦ 18日
(第43条第2項)
★日雇労働被保険者になる者★
被保険者である日雇労働者で、次の各号のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。
(1) 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
(2) 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
(3) 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
(4) (1)から(3)のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者=任意加入の認可を受けた者
択一式の過去問もどうぞ!
①【H24年出題】
日雇労働被保険者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、法令で定める適用事業に雇用されるに至った日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第25号)に必要に応じ所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
日雇労働被保険者資格取得届のポイント!
★事実のあった日から起算して「5日以内」に提出します。
↓
10日以内ではありませんので注意しましょう。
★管轄公共職業安定所の長に提出します。
↓
その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所です。
(則第71条第1項)
②【H20年出題】
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。

【解答】
②【H20年出題】 ×
管轄公共職業安定所の長から交付されるのは、「日雇労働被保険者手帳」です。
雇用保険被保険者証は交付されません。
(則第73条第1項)
③【H29年出題】
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
日雇労働被保険者には、確認の制度は適用されません。
(第43条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金のことお話します
R6-309 7.1
遺族基礎年金の額についてもう少し詳しくお話します【社労士受験対策】
先日は、遺族基礎年金の3つの基本をお話しました。
↓
https://youtu.be/4cv6AR25kZk?si=ziNHPLdWhmSHUjQC
今回は、遺族基礎年金の額についてもう少し詳しくお話します。
★遺族基礎年金の額
・配偶者が受給する場合
・子が受給する場合
★死亡当時胎児だった子が生まれた場合
★子の数が減った場合
★配偶者の遺族基礎年金が失権するとき
★応用編
・ すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合の遺族基礎年金の受給権
YouTubeでお話しています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
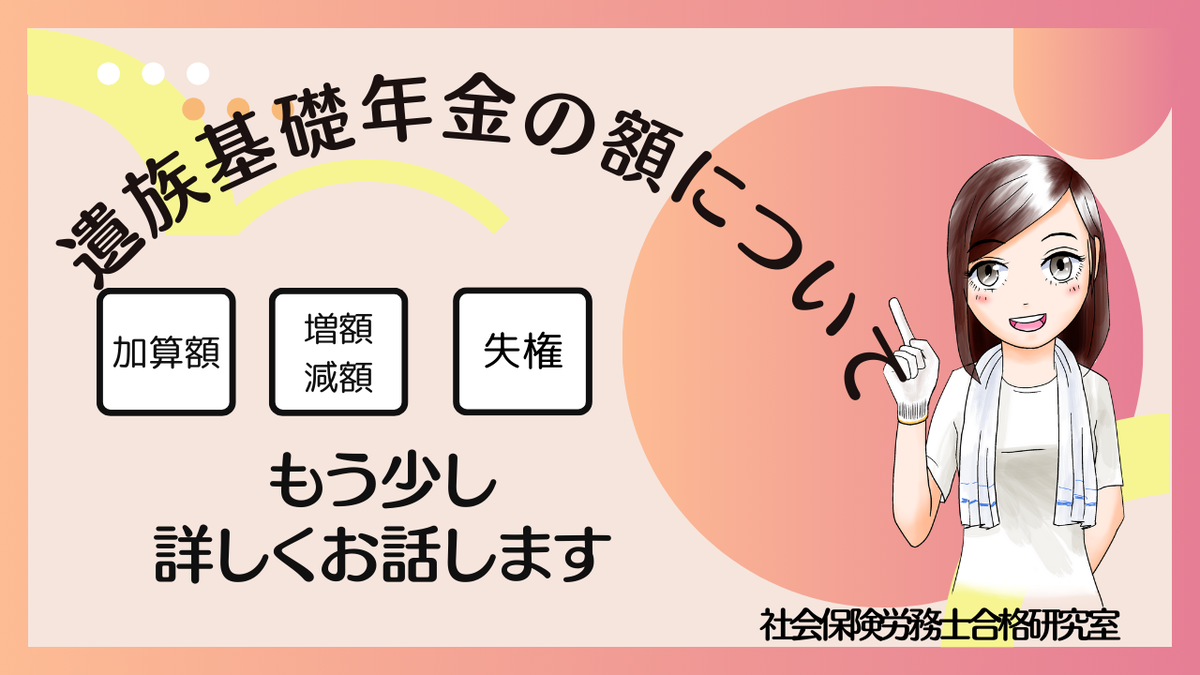
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-308 6.30
遺族補償一時金の重要ポイント【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
「遺族補償給付」には「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今日は「遺族補償一時金」のお話です。
遺族補償一時金は、次の場合に支給されます。
①遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合
又は
②遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合に、支給された年金と前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
では、条文を読んでみましょう。
第16条の6第1項 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 (1) 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 (2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において給付基礎日額の 1000日分に満たないとき |
(1)例えば、労働者の死亡の当時、障害状態にない50歳の夫のみだった場合
↓
遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1000日分
(2)給付基礎日額の1000日分は、年金の最低保障額のイメージです。
↓
遺族補償一時金の額は、支給された(年金+前払一時金)と給付基礎日額の1000日分との差額
遺族補償一時金を受けることができる遺族と順位は、次の通りです。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子→父母→孫→祖父母
3 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子→父母→孫→祖父母
4 兄弟姉妹
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
①【H25年出題】 〇
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、生計を維持していた場合でも、生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
②【H28年出題】 〇
兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
③【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
③【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
★遺族補償年金の受給資格者になるには、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなければなりません。
★遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の2、第16条の7)
④【H10年出題】
遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。

【解答】
④【H10年出題】 〇
死亡労働者の妻が再婚をした場合、遺族補償年金の受給権は消滅します。支払われた遺族補償年金+前払一時金が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合は、差額が遺族補償一時金として支給されます。
「死亡した労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の身分は、労働者の死亡の当時の身分によります。
再婚したとしても、労働者の死亡当時の妻は、遺族補償一時金の請求権を有することがあります。
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
⑤【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

【解答】
⑤【H28年出題】×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることはあり得ます。(④の問題のような場合です。)
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-307 6.29
<選択式>「元方事業者」の定義、講ずべき措置等【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
<選択肢>
① 一の場所 ② 現場 ③ 作業場 ④ 事業場

【解答】
①【H19年選択式】
A ① 一の場所
「一の場所」とは、例えばビル建設工事なら、工事の作業場の全域です。
(昭47.9.18基発第602号)
ちなみに、元方事業者のうち、建設業・造船業(特定事業)を行う者を、特定元方事業者」といいます。
②【H13年選択式】
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な< B >を行なわなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、< C >適用され、一の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、< B >の義務を負わせることとしたものである。
<選択肢>
① 援助 ② 勧告 ③ 指示 ④ 命令
⑤ 業種の如何にかかわらず ⑥ 建設業についてのみ
⑦ 特定業種(建設業及び造船業)についてのみ ⑧ 製造業についてのみ

【解答】
②【H13年選択式】
B ③ 指示
C ⑤ 業種の如何にかかわらず
第29条の「元方事業者の講ずべき措置等」は、業種の如何にかかわらず適用されることがポイントです。
「関係請負人又はその労働者」は、元方事業者がする是正のために必要な指示に従わなければなりません。(第29条第3項)
第29条の条文を読んでみましょう。
第29条 (元方事業者の講ずべき措置等) ① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 ② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 ③ 指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 |
択一式も解いてみましょう
①【H18年出題】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

【解答】
①【H18年出題】 〇
第29条は、「業種のいかんを問わず」、適用されます。
(第29条第1項)
②【H22年出題】
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
指導及び指示の対象は、「関係請負人及び関係請負人の労働者」です。関係請負人の労働者に対しても、指導及び指示を直接行うことができます。
ちなみに、製造業のみならず、業種のいかんを問わず元方事業者に適用される規定です。
(第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-306 6.28
<選択式>最高裁判所の判例からの問題【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H21年選択式】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の< A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 経済生活の安定 ② 生活保障 ③ 最低賃金の保障
④ 不利益の補償

【解答】
①【H21年選択式】
A ① 経済生活の安定
★過払調整について
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法第24条第1項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。
この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。
(昭44.12.18最高裁判所第一小法廷)
②【H21年選択式】
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< B >という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の< B >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度で負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。」としている。
<選択肢>
① 経済生活の安定 ② 生活保障 ③ 最低賃金の保障
④ 不利益の補償

【解答】
②【H21年選択式】
B ② 生活保障
★休業手当と民法536条第2項との関係について
「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条第2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
(昭62.7.17最高裁判所第二小法廷)
③【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< C >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< C >というべきである。」
<選択肢>
① 影響を与えない ② 影響を与えるもの ③ 含まれない
④ 含まれるもの

【解答】
③【H26年選択式】
C ④ 含まれるもの
★労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日について
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
(平25.6.6最高裁判所第一小法廷)
④【H22年選択式】
賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 < D >として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 権利の濫用 ② 公序に反するもの ③ 信義に反するもの
④ 不法行為

【解答】
D ② 公序に反するもの
★出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする場合の出勤率の算定で、産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて
・ 従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,90%条項で賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きい
・従業員が産前産後休業等を取得した場合には,それだけで90%条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高い
・産前産後休業の取得の権利を保障した趣旨を実質的に失わせるというべきであるから、公序に反し無効である。
(平15.12.4最高裁判所第一小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-305 6.27
<選択式>労働組合のことなど【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働組合法などです。
さっそく過去問をどうぞ!
【H21年選択式】
1 日本国憲法第28条において、「勤労者の団結する権利及び< A >その他の < B >をする権利は、これを保障する。」と定められている。また、労働組合法第1条第2項には「刑法(明治40年法律第45号)第35条の規定は、< C >の< A >その他の行為であつて前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、< C >の正当な行為と解釈されてはならない。」と定められている。
2 労働関係調整法第7条において、「この法律において< D >とは、同盟罷業、怠業、< E >その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。」と定められている。
<選択肢>
① 工場封鎖 ② 個別交渉 ③ 作業所閉鎖 ④ 事業所封鎖
⑤ 事務所閉門 ⑥ 示威行動 ⑦ 従業員組合 ⑧ 集団交渉
⑨ 集団行動 ⑩ 職業組合 ⑪ 職業別組合 ⑫ 争議行為
⑬ 大衆行動 ⑭ 対等交渉 ⑮ 団体交渉 ⑯ 団体行動
⑰ 敵対行為 ⑱ 不当行為 ⑲ 労働組合 ⑳ 労働争議

【解答】
A ⑮ 団体交渉
B ⑯ 団体行動
C ⑲ 労働組合
D ⑫ 争議行為
E ③ 作業所閉鎖
★A・Bについて
「日本国憲法第28条」は、勤労者の団結権です。
こちらもどうぞ!
労働組合法第1条第1項の条文も穴埋めで読んでみましょう。
第1条第1項 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより< A >を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< B >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< C >を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |

【解答】
A 労働者の地位
B 団体行動
C 労働協約
択一式もどうぞ!
【H25年出題】
使用者が組合員の賃金から組合費を控除しそれを労働組合に引き渡す旨の、労働組合と使用者との間の協定(いわゆるチェック・オフ協定)は、それに反対する組合員にチェック・オフを受忍する義務を負わせるものではなく、組合員はいつでも使用者にチェック・オフの中止を申し入れることができるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H25年出題】 〇
労働基準法第24条では、賃金の全額払の原則が定められていますが、労使協定を締結すれば、例えば組合費などを賃金から控除することができます。
労使協定の締結によって、賃金全額払の原則の例外となりますが、所定の罰則の適用を受けないという効力を有するにすぎません。
それが労働協約の形式により締結された場合でも、当然に使用者がチェック・ オフをする権限を取得するものでないことはもとより、組合員がチェック・オフを 受忍すべき義務を負うものではないと解すべきである、とされています。
(平成5年3月25日最高裁判所第一小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-304 6.26
<選択式>老齢厚生年金の繰下げの申出の条件【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
さっそく過去問からどうぞ!
【R2年選択式】
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。
<選択肢>
① 受給権を取得した日から起算して1か月を経過した日
② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
③ 受給権を取得した日から起算して5年を経過した日
④ 受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日
⑤ 付加年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑥ 老齢基礎年金及び障害基礎年金並びに遺族基礎年金
⑦ 老齢基礎年金及び付加年金並びに遺族害基礎年金
⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金

【解答】
A ② 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
B ⑧ 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
(第44条の3第1項)
繰下げのポイント!
★老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していないこと
★老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に「他の年金たる給付」の受給権がある場合は、繰下げの申出ができません。
※「他の年金たる給付」は、他の年金たる保険給付(=障害厚生年金、遺族厚生年金)、国民年金の年金たる給付(「老齢基礎年金及び付加年金」、「障害基礎年金」は含まれません。)です。
(例)「老齢基礎年金+付加年金」の受給権があっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができます。
(例)「障害基礎年金」の受給権があっても、老齢厚生年金の繰下げの申出ができます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H19年出題】
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者でも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができます。
(第44条の3第1項)
②【H28年出題】
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

【解答】
②【H28年出題】 〇
65歳時点で、障害基礎年金の受給権者であった者でも、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
(第44条の3第1項)
③【H19年出題】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。どちらか一方だけ繰り下げることもできます。
(第44条の3)
④【R4年出題】
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

【解答】
④【R4年出題】 〇
複数の種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が繰下げの申出をする場合は、すべての老齢厚生年金について、同時に繰下げの申出を行わなければなりません。
(第78条の28)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-303 6.25
<選択式>年金額の改定・財政の現況及び見通しの作成【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
<選択肢>
① 国民生活の現況 ② 国民生活の状況 ③ 国民の生活水準
④ 国民生活の安定 ⑤ 改定 ⑥ 所要 ⑦ 是正 ⑧ 訂正

【解答】
A ③ 国民の生活水準
B ⑤ 改定
(法第4条)
年金額の改定の規定です。
②【H26年選択式】
政府は、少なくとも< A >年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び< B >期間における見通しを作成しなければならない。
この< B >期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね < C >年間とする。
<選択肢>
① 3 ② 5 ③ 7 ④ 10 ⑤ 25 ⑥ 30
⑦ 50 ⑧ 100 ⑨ 財政均衡 ⑩ 財政計画
⑪ 収支均衡 ⑫ 将来推計

【解答】
A ② 5
B ⑨ 財政均衡
C ⑧ 100
(第4条の3第1項)
年金の財政は、有限均衡方式がとられています。長期的な財政の均衡が義務づけられています。
条文を読んでみましょう。
第4条の2 (財政の均衡) 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 |
財政均衡期間は約100年で、この期間で給付と負担のバランスを図ることになっています。
政府は、給付と負担のバランスを確認するため、少なくとも5年ごとに財政検証を行っています。
③【R3年選択式】
国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に< A >ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を< B >するものとし、政令で、給付額を< B >する期間の < C >を定めるものとする。
<選択肢>
① 給付額に不足が生じない ② 給付の支給に支障が生じない
③ 財政窮迫化をもたらさない ④ 財政収支が保たれる
⑤ 改定 ⑥ 減額 ⑦ 調整 ⑧ 変更
⑨ 開始年度 ⑩ 終了年度 ⑪ 開始年度及び終了年度 ⑫ 年限

【解答】
A ② 給付の支給に支障が生じない
B ⑦ 調整
C ⑨ 開始年度
(第16条の2第1項)
調整期間とは、マクロ経済スライドが適用される期間のことです。
政均衡期間に均衡を保つことができないと見込まれる場合には、給付額を調整するため、マクロ経済スライドを行い、給付水準を調整します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金の基本について
R6-302 6.24
遺族基礎年金の3つの基本をお話します。【社労士受験対策】
遺族基礎年金の3つの基本をお話しします。
①死亡した人の要件
・短期要件と長期要件があります。
・保険料納付要件が必要な場合と、不要な場合があります。
②遺族基礎年金を受けることができる遺族
死亡した者に生計を維持されていた「配偶者又は子」です。
ただし、配偶者は、「子と生計を同じくすること」が条件です。
③遺族基礎年金の額
「配偶者」に支給される場合と、「子」に支給される場合で分けて、おさえましょう。
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
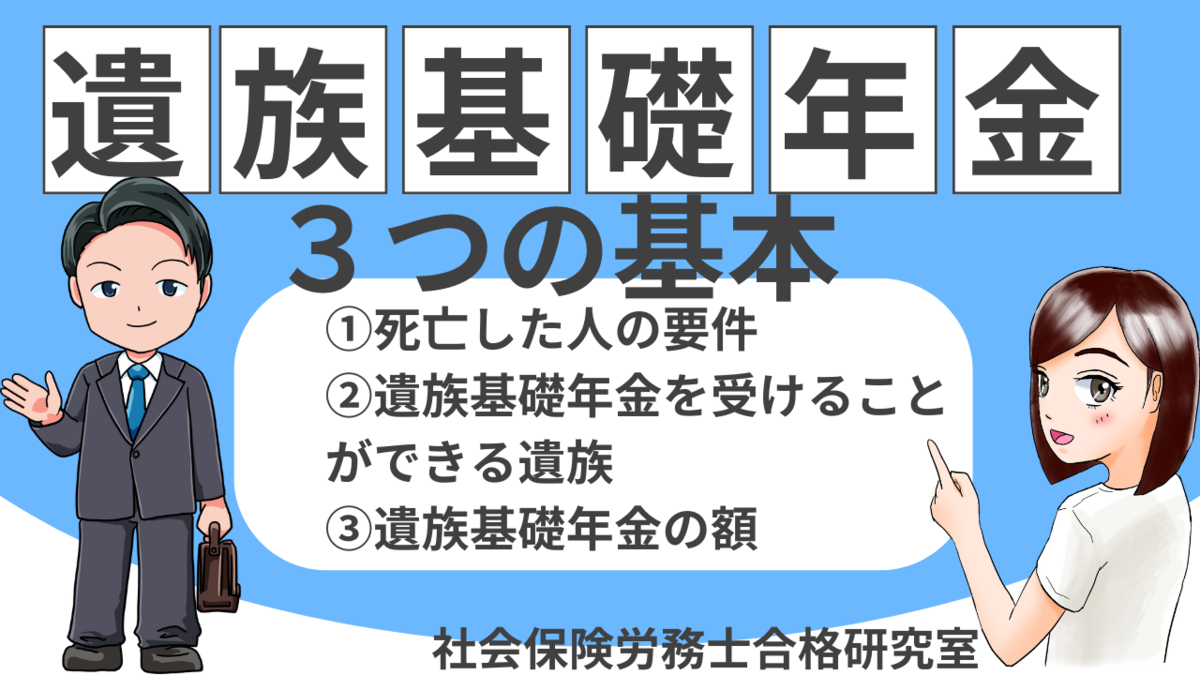
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-301 6.23
<選択式>任意継続被保険者の保険料の前納など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
任意継続被保険者は、保険料を全額負担し、納付する義務も負います。
条文を読んでみましょう。
第161条第1項、第3項 ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第164条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
第157条第1項 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。 |
例えば、6月24日に退職した場合、任意継続被保険者になるのは、6月25日からです。6月分から任意継続被保険者として保険料を納付します。
5月 | 6月 任意継続被保険者と なった月 |
事業主と2分の1ずつ負担 事業主が納付する | 全額負担 本人が納付する |
では、選択式の過去問をどうぞ!
①【H22年選択式】※問題文修正しています
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
①【H22年選択式】
A 各月の初日
B 初月の前月末日
C 年4分の利率
D 5月
※Dについて条文を読んでみましょう。
令第48条 保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。 (第165条、令第48条、第49条、則第139条第1項) |
②【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< E >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
<選択肢>
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
③ 9月30日における健康保険の
④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

【解答】
E ④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
択一式の過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料の前納の単位は、「4月から9月まで」・「10月から翌年3月まで」の6か月間又は「4月から翌年3月まで」の12か月間が原則です。
しかし、6か月又は12か月の間に、任意継続被保険者の資格を取得した場合は、「資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間」、資格を喪失することが明らかな場合は、「その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間」の保険料について前納を行うことができます。
(令第48条)
②【R4年出題】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定されます。
(第3条第4項、第157条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-300 6.22
<選択式>全国健康保険協会の一般保険料率【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の被保険者の保険料額の条文を読んでみましょう。
第156条第1項(被保険者の保険料額) 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料額と介護保険料額との合算額 ※一般保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額 ※介護保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額 (2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料額 |
「全国健康保険協会」の「一般保険料率」を選択式の過去問でみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H24年選択式】 ※改正による修正あり
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として < B >が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、< C >についての健康保険の事業の収支の見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< D >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< E >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
<選択肢>
① 1000分の30から1000分の130 ② 1000分の30から1000分の164
③ 1000分の60から1000分の90 ④ 1000分の60から1000分の120
⑤ 運営委員会 ⑥健康保険組合との収支の均衡
⑦ 健康保険事業の収支の均衡 ⑧ 厚生労働大臣
⑨ 国民健康保険との収支の均衡 ⑩ 社会保障審議会
⑪ 全国健康保険協会 ⑫ 地方厚生(支)局長
⑬ 中央社会保険医療協議会 ⑭ 当該事業年度以降3年間
⑮ 中央社会保険医療協議会 ⑯ 都道府県の支部長
⑰ 被保険者の家計収入との均衡 ⑱ 毎事業年度
⑲ 翌事業年度以降3年間 ⑳ 翌事業年度以降5年間

【解答】
A ① 1000分の30から1000分の130
B ⑪ 全国健康保険協会
C ⑳ 翌事業年度以降5年間
D ⑦ 健康保険事業の収支の均衡
E ⑩ 社会保障審議会
(第160条第1項、第5項、第10条、第11条)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

【解答】
①【H26年出題】 〇
全国健康保険協会の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内で、「支部被保険者を単位」として「全国健康保険協会が決定」します。
なお、支部被保険者とは、「各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者・当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者」をいいます。
支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。
(第160条第1項、第2項)
②【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
第160条第6項~第8項 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、< A >が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< B >の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、上記の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、< A >に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、< A >は、その変更について厚生労働大臣の< C >を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、上記の< C >をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 |

【解答】
A 理事長
B 運営委員会
C 認可
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。」が誤りです。
条文を読んでみましょう
第160条第10項、第11項 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が上記の期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 |
厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、都道府県単位保険料率を変更することができるとされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-299 6.21
<選択式>基本手当の日額と賃金日額【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
選択式の過去問をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H18年選択式】
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲と定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。
<選択肢>
① 30 ② 40 ③ 45 ④ 50 ⑤ 55 ⑥ 60
⑦ 70 ⑧ 80 ⑨ 180 ⑩ 合算対象期間 ⑪ 算定対象期間
⑫ 支給基礎期間 ⑬ 支給要件期間 ⑭ 受給期間 ⑮ 受給資格期間
⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数 ⑰ 当該最後の6か月間の所定労働日数
⑱ 当該最後の6か月間の総日数 ⑲ 被保険者期間
⑳ みなし被保険者期間

【解答】
A ③ 45
B ⑪ 算定対象期間
C ⑲ 被保険者期間
D ⑯ 当該最後の6か月間に労働した日数
E ⑦ 70
(第16条、第17条)
ポイント!
★基本手当の日額 = 賃金日額×一定の率
一定の率 → 原則 100分の80から100分の50までの範囲
60歳以上65歳未満 100分の80から100分の45までの範囲
★賃金日額の計算式
<原則>
算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 180
賃金総額から除外される賃金 → 臨時に支払われる賃金、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
<最低保障>
日給、時間給、出来高払制その他の請負制の場合
最後の6か月間に支払われた賃金の総額 ÷ 当該最後の6か月間に労働した日数×100分の70
択一式の過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法の傷病手当金は、健康保険の給付金のため賃金ではありません。また、傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となり、賃金ではありません。
(行政手引50502)
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。

【解答】
②【H30年出題】 〇
接客係等が客からもらうチップは賃金ではありませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものは賃金となります。
(行政手引50502)
③【H30年出題】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。

【解答】
③【H30年出題】 ×
月給者が月の中途で退職する場合で、その月分の給与が全額支払われた場合、退職日の翌日以後の分は賃金日額の算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503)
④【H30年出題】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、原則の計算式(被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額が、最低保障額(最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70の額)に満たない場合は、最低保障額が賃金日額となります。
(第17条)
⑤【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
未払賃金のある月は、未払額を含めて賃金額を算定します。
(行政手引50609)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-298 6.20
<選択式>業務上の疾病の範囲・通勤による疾病の範囲【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
選択式の過去問をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H18年選択式】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、< B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。
<選択肢>
① 業務上の事故による疾病 ② 業務上の負傷に起因する疾病
③ 業務と因果関係のある疾病 ④ 業務に起因することの明らかな疾病
⑤ 業務に起因する疾病 ⑥ 通勤 ⑦ 通勤上の事由
⑧ 通勤上の事由による疾病 ⑨ 通勤と因果関係のある疾病
⑩ 通勤途上の事故 ⑪ 通勤途上の負傷
⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病 ⑬ 通勤による疾病
⑭ 通勤による負傷 ⑮ 通勤による負傷に起因する疾病
⑯ 労働安全衛生規則 ⑰ 労働基準法施行規則
⑱ 労働基準法施行令 ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則
⑳ 労働者災害補償保険法施行令

【解答】
A ⑰ 労働基準法施行規則
B ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則
C ④ 業務に起因することの明らかな疾病
D ⑭ 通勤による負傷
E ⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病
こちらの過去問もどうぞ!
①【H19年出題】
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
「業務上の負傷に起因する疾病」は、別表第1の2第1号で定められていて、業務上の疾病に含まれます。
ちなみに、別表第1の2は職業病リストとよばれていて、業務上の疾病の範囲を明確にしています。
(労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2)
②【H19年出題】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

【解答】
②【H19年出題】 〇
業務上の疾病と認められるには、労働基準法施行規則別表第1の2(職業病リスト)で定められている疾病に該当しなければなりません。
なお、第1号から第10号までのリストには、業務と疾病の間に因果関係が確立している疾病が示されています。
示されていない疾病については、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」として業務と疾病の因果関係が認められた場合は、業務上の疾病として認められます。
③【H19年出題】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

【解答】
③【H19年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第22条第1項 療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
則第18条の4(通勤による疾病の範囲) 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。 |
通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。
④【H21年出題】
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

【解答】
④【H21年出題】 ×
通勤による疾病は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。業務上の疾病と異なり、具体的な疾病の種類は挙げられていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-297 6.19
<選択式>産業医の職務【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
選択式の過去問をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H21年選択式】※改正による修正あり
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< A >をすることができる。」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、所定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< B >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と定められている。
<選択肢>
① 意見 ② 勧告 ③ 指導 ④ 助言
⑤ 作業環境 ⑥ 作業場所 ⑦ 作業方法 ⑧ 設備

【解答】
A ② 勧告
B ⑦ 作業方法
(第13条第5項、則第15条第1項)
練習問題もどうぞ!
<問題1>
① 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
② 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
③ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
④ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< A >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
⑤ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< B >をすることができる。この場合において、事業者は、当該< B >を< C >しなければならない。
⑥ 事業者は、< B >を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該< B >の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

【解答】
<A> 労働時間
<B> 勧告
<C> 尊重
(第13条)
<問題2>
法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 産業医を選任すべき事由が発生した日から< D >以内に選任すること。(2) 次に掲げる者(イ及びロにあっては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあっては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあっては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
(3) 常時< E >人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時 < F >人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に< G >の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、 鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、 砒ひ素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗 化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
(4) 常時< H >人をこえる労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。

【解答】
<D> 14日
<E> 1,000
<F> 500
<G> 専属
<H> 3,000
(則第13条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-296 6.18
<選択式>監督又は管理の地位にある者の範囲【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
選択式の過去問をみていきます。
【H24年選択式】
労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について< A >の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方による。
(1) 原則
労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2) 適用除外の趣旨
〔略〕
(3) 実態に基づく判断
〔略〕
(4) 待遇に対する留意
管理監督者であるかの判定に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、< B >待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
(5) スタッフ職の取扱い
【略】
【選択肢】
① 課長相当職以上の ②経営者と一体的な立場にある者
③ 事業主のために行為をするすべての者
④ 使用者の利益を代表するすべての者
⑤ その地位にふさわしい ⑥ 取締役に近い
⑦ 部下の割増賃金を上回る ⑧ 複数の部下を持ち指揮命令を行っている者

【解答】
A ② 経営者と一体的な立場にある者
B ⑤ その地位にふさわしい
ポイント!
適用除外の趣旨を確認しましょう。
「職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。」とされています。
★「『監督若しくは管理の地位にある者』とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。
★「定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある」とされています。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害基礎年金の受給権発生要件の基本
R6-295 6.17
障害基礎年金の受給権3つのポイントについてお話をします【社労士受験対策】
障害基礎年金発生の3つの要件を確認しましょう。
①初診日
・初診日とは?
・初診日の要件
②保険料納付要件
・初診日の前日
・初診日の属する月の前々月
・特例が適用される条件
③障害認定日
・1年6か月と治った日
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-294 6.16
<選択式>老齢基礎年金の繰上げと繰下げ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
今日は選択式の過去問です。
では、過去問をどうぞ!
【H21年選択式】※改正による修正あり
① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

【解答】
<A> 60歳以上65歳未満
<B> 任意加入被保険者
<C> 65歳
(法附則第9条の2第1項)
繰上げのポイント!
★繰上げ請求ができるのは、60歳から65歳になるまでの間です
★任意加入被保険者は繰上げ請求できません
② 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】
<D> 付加年金
<E> 老齢
(第28条第1項)
繰下げのポイント!
★66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない
★65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない
★65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない
「他の年金たる給付」とは
↓
(国民年金法の)他の年金給付(付加年金を除く。)
又は
厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
こちらの問題もどうぞ!
①【R1年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

【解答】
①【R1年出題】 ×
老齢基礎年金の支給の繰上げは、国民年金法附則で当分の間の措置として規定されています。
老齢基礎年金の支給繰下げは、国民年金法第28条で規定されています。
(第28条、附則第9条の2)
②【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
②【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者となったときは、繰下げの申出はできません。
※他の年金たる給付は、簡単に書きますと、障害や遺族の年金です。
問題文のように、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、「障害基礎年金」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることができません。
(第28条第1項)
③【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

③【R1年出題】 〇
「66歳前に老齢基礎年金を請求していない」、「65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない」、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない」場合は、老齢基礎年金の繰下げの申出ができます。
「他の年金たる給付」から、老齢厚生年金は除かれますので、問題文の場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができます。
(第28条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-293 6.15
<選択式>老齢厚生年金の額・再評価率など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日は選択式の過去問です。
では、過去問をどうぞ!
【H23年選択式】 ※改正による修正あり
① 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の 1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
<A> 再評価率
<B>5.481
(第43条第1項)
老齢厚生年金の額の原則は、
平均標準報酬額 × 1,000分の5.481 × 被保険者期間の月数
で計算します。
平均標準報酬額は、
計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じて得た額の総額を、被保険者期間の月数で割って得た額です。
「再評価率」とは、過去の標準報酬月額と標準賞与額を現在の価値に再評価するための率です。
2 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。

【解答】
<C> 物価変動率
<D> 名目手取り賃金変動率
C、Dを入れて条文を読んでみましょう。
第43条の2第1項 再評価率については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 |
再評価率は、毎年度改定されます。
新規裁定者は、「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されます。
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(以下「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。

【解答】
<E> 3年後
C、D、Eを入れて条文を読んでみましょう。
第43条の3第1項 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)を基準とする。 |
既裁定者(68歳到達年度以後である受給権者)の再評価率は、「物価変動率」を基準に改定されます。
ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率が基準となります。
こちらの問題もどうぞ!
【R5年選択式】
令和X年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和X年度の既裁定者(令和X年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から< A >となる。なお、令和X年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。

【解答】
<A>0.2%の引下げ
物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」で、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ります。そのため、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」が基準となり、0.2%引き下げられます。
なお、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-292 6.14
厚生年金保険法の保険料等の督促及び滞納処分【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
督促及び滞納処分について条文を読んでみましょう。
第86条(保険料等の督促及び滞納処分) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 ④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上げ徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。 ⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法の指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。 (1) 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 (2) 保険料の繰上げ徴収が認められる要件のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。 ⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

【解答】
①【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促は行いません。
(第86条第1項)
②【H25年出題】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる」ではなく、「同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる」です。
(第86条第2項)
③【H25年出題】
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。

【解答】
③【H25年出題】 〇
「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」の10日が覚えるポイントです。
(第86条第4項)
ちなみに、保険料の繰上徴収が認められる要件は次の通りです。
第85条 (保険料の繰上徴収) ① 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 (1) 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があつたとき。 ② 法人たる納付義務者が、解散をした場合 ③ 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 ④ 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 |
④【H25年出題】
厚生労働大臣は、督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法に規定される指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。

【解答】
④【H25年出題】 〇
なお、市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によって処分することができます。その場合、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4を当該市町村に交付しなければなりません。
(第86条第5項、第6項)
⑤【H25年出題】
厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の要件に該当し、納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないときは滞納処分の対象になります。
(第86条第5項第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-291 6.13
65歳以降の年金の併給ルール【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
1人に対して複数の年金の受給権が発生した場合でも、原則は「一人一年金」です。
ただし、併給が可能な組み合わせもありますので、おぼえましょう。
過去問を解きながらみていきます。
では過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
<65歳以上の老齢厚生年金について>
★併給可能な基礎年金との組み合わせ
・(老齢基礎年金+付加年金)+老齢厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
老齢厚生年金
|
|
老齢厚生年金 |
老齢基礎年金+付加年金
|
|
障害基礎年金 |
★老齢厚生年金は、遺族基礎年金とは併給できません。
(第38条、附則第17条)
②【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。

【解答】
②【H24年出題】 〇
<65歳以上の遺族厚生年金について>
★併給可能な基礎年金との組み合わせ
・(老齢基礎年金+付加年金)+遺族厚生年金
・障害基礎年金+遺族厚生年金
遺族厚生年金
|
|
遺族厚生年金 |
老齢基礎年金+付加年金
|
|
障害基礎年金 |
(第38条、附則第17条)
③【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

【解答】
③【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第44条第1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定(障害基礎年金の子の加算)により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
<受給権者が65歳に達している場合の老齢厚生年金と障害基礎年金の併給>
生計を維持している子がいる場合、老齢厚生年金も障害基礎年金も加算が行われます。その場合は、障害基礎年金に子の加算が加算され、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。
老齢厚生年金
|
子の加給年金額(支給停止) |
障害基礎年金
|
子の加算額が加算される |
④【H28年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【解答】
④【H28年出題】 〇
障害厚生年金
|
|
|
| どちらか 選択 |
老齢基礎年金 |
障害厚生年金と老齢基礎年金は併給できませんので、どちらかを選択します。
遺族厚生年金
|
老齢基礎年金
|
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給できます。
(第38条、附則第17条)
⑤【H26年出題】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
遺族厚生年金
|
障害基礎年金
|
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と障害基礎年金は併給できます。
(第38条、附則第17条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-290 6.12
保険料納付済期間や保険料免除期間のことなど【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。

【解答】
①【H24年出題】 〇
第91条で、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」とされています。
ただし、翌月末日が、日曜日、休日、土曜日等の場合は、その翌日が期限となります。
例えば、令和6年5月分の国民年金の保険料の納期限は、翌月末日(令和6年6月30日)が日曜日ですので、その翌日(令和6年7月1日)となります。
(第91条、国税通則法第10条第2項)
②【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
②【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、障害基礎年金の要件では、「保険料納付済期間」となります。
<第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間>
★老齢基礎年金★
「合算対象期間」となります。
受給資格期間の計算には入りますが、年金額には反映しません。
★障害基礎年金・遺族基礎年金★
「保険料納付済期間」となります。
(第5条第1項)
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

【解答】
③【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
「督促及び滞納処分により保険料が納付された期間」も保険料納付済期間に含まれます。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
④【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第3項 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※「納付猶予」の期間も保険料全額免除期間に含まれます。(H16法附則第19条) |
保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間から除かれ、保険料納付済期間とされます。
⑤【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まれない。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
例えば、保険料4分の1免除をうけた場合、残りの4分の3は納付する義務があります。
残りの4分の3を納付した期間は、「保険料納付済期間」ではなく、「保険料4分の1免除期間」となります。
条文を読んでみましょう。
第5条第6項 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-289 6.11
障害基礎年金重要5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
では過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「事後重症」の問題です。
「その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。」が誤りです。
条文を読んでみましょう。
第30条の2第1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 |
事後重症の障害基礎年金は、「65歳に達する日の前日までの間」に、請求することができます。
★事後重症のポイント!
・初診日の要件を満たしていること
・初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること
・障害認定日に障害等級に不該当であること(=障害基礎年金の受給権は発生しない)
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当したこと
・65歳に達する日の前日までの間に請求すること
↓
事後重症の障害基礎年金は、「請求」によって受給権が発生します。
②【H21年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
「子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。」が誤りです。
障害基礎年金に加算される額は、以下の額です。
1人目、2人目の子は、1人につき224,700円×改定率
3人目以降は、1人につき74,900円×改定率
(第33条の2第1項)
③【H23年出題】
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
受給権を取得した日の翌日以後に子を有するに至った場合でも、加算が行われます。
条文を読んでみましょう。
第33条の2第2項 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |
④【H21年出題】
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。

【解答】
④【H21年出題】 ×
初診日の要件、障害認定日の要件、保険料納付要件を満たしていれば、障害認定日に65歳を超えていても、障害基礎年金の受給権は発生します。
ちなみに「初診日」の要件は、初診日に次のどちらかに該当していることです。
(1) 被保険者であること。
(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
問題文は初診日に(2)の要件を満たしていますので、障害認定日が65歳を超えていても、障害基礎年金が支給されます。
(第30条)
⑤【H21年出題】
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。

【解答】
⑤【H21年出題】 〇
旧国民年金法の「障害福祉年金」とは、拠出制の障害年金の要件に該当しない場合などに支給された年金で、費用は全額国庫負担でした。
昭和61年3月31日に、障害福祉年金の受給権を有していた者が、昭和61年4月1日に障害等級1、2級に該当する場合は、障害福祉年金ではなく「障害基礎年金」として支給されます。
なお、支給される障害基礎年金は、「第30条の4の障害基礎年金=20歳前に初診日がある障害基礎年金」です。
(昭60法附則第25条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
老齢基礎年金の計算式のすべて
R6-288 6.10
老齢基礎年金の額の計算について原則のお話をします【社労士受験対策】
老齢基礎年金の額の計算の原則のお話をします。
・老齢基礎年金の満額の額は?
・満額支給されるのはどのような場合?
→20歳から60歳までの480月すべてが保険料納付済期間であること
・保険料納付済期間とは?
第1号被保険者期間+第2号被保険者期間+第3号被保険者期間
→第1号被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されるのは?
→第2号被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されるのは?
・老齢基礎年金が減額される例
→未納期間がある場合
・保険料免除期間がある場合
→免除の種類によって老齢基礎年金の額に反映される割合が決まります
・過去問を解いてみましょう
→学生納付特例期間と納付猶予期間の扱い
→第2号被保険者期間のうち老齢基礎年金の額に反映される期間
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

過去問から学ぶ 健康保険法
R6-287 6.9
埋葬料と埋葬費【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
埋葬料と埋葬費の違いを意識しながら条文を読んでみましょう。
第100条、令第35条 ① 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
| 対象者 | 金額 | 時効の起算日 |
埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 | 死亡日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った者 | 5万円の範囲内で 埋葬に要した費用 | 埋葬を行った日の翌日 |
埋葬料は、「生計を維持されていた者で埋葬を行うべき者」に支給されます。
埋葬費は、「実際に埋葬を行った者」に支給されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
埋葬料の対象者は、被保険者と同一世帯であったか否かは問われません。
なお、民法上の親族又は遺族であることも要しませんし、被保険者が世帯主であるか否かも問われません。
(昭7.4.25保規129)
②【H25年出題】
事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「いかなる理由があろうとも」が誤りです。
「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」とされています。(則第33条)
正当な理由がある場合は拒むことができます。
③【H25年出題】
埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者の続柄を記載する必要はない。

【解答】
③【H25年出題】 ×
埋葬料の申請書には、「被保険者と申請者との続柄」を記載しなければなりません。
(則第85条第1項第3号)
④【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

【解答】
④【H24年出題】 〇
被保険者により生計の一部を維持していた者も、埋葬料の支給対象になります。
(昭8.8.7保発502)
⑤【H25年出題】
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。

【解答】
⑤【H25年出題】 ×
死亡した被保険者により生計を維持されていたものがいない場合は、実際に埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。
死亡した被保険者に生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合は、埋葬費が支給されます。
(昭26.6.28保文発162)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-286 6.8
増加概算保険料のすべて【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
「増加概算保険料」の要件は次の2つです。
① 労働者の人数が増える等で、賃金総額の見込額が増加した場合
↓
増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の 100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上になった
(則第25条第1項)
② 労災保険の保険関係又は雇用保険の保険関係のみが成立していた事業が両保険の保険関係が成立する事業になったため、一般保険料率が変更した場合
↓
変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上になった
(法附則第5条、則附則第4条第1項)
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。

【解答】
①【H23年出題】(労災) 〇
継続事業も有期事業も、増加概算保険料の申告・納付の期限は同じです。
「賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内」に申告・納付を行わなければなりません。「増加が見込まれた日から」がポイントです。実際に2倍を超えるに至った日ではありませんので注意してください。
(第16条)
②【H23年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。

【解答】
②【H23年出題】(労災) 〇
この場合は、「一般保険料率が変更された日から30日以内」に申告・納付しなければなりません。また、翌日起算であることにも注意してください。令和4年に、「一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に(解答〇)」で出題されています。
(法附則第5条、則附則第4条)
③【H23年出題】(労災)
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

【解答】
③【H23年出題】(労災) ×
増加概算保険料には、「認定決定」はありません。
④【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。

【解答】
④【H23年出題】(労災) 〇
賃金総額の見込額が増加したけれども、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合は、確定保険料の申告・納付の際に精算することになります。
⑤【H23年出題】(労災)
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

【解答】
⑤【H23年出題】(労災) ×
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
日本銀行又は労働基準監督を経由して行うことができますが、年金事務所は経由できません。
(則第38条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-285 6.7
基本手当の受給手続【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
過去問を解きながら、基本手当の受給手続を確認しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
失業の認定日に提出するものは離職票ではありません。
失業認定申告書に受給資格者証を添えて(マイナンバーカード利用者の場合はマイナンバーカードによる認証を行って)提出した上、職業の紹介を求めなければなりません。
(行政手引50201)
条文を読んでみましょう。
則第22条第1項 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示しない)ことができる。 |
②【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接する」場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
証明書による失業の認定を受けることができるのは、次の4つの理由です。
第15条第4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 (1) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 (2)公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (3) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 (4) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 |
「民間の職業紹介事業者の紹介」ではなく、公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するための場合は、証明書による失業の認定を受けることができます。
③【H25年出題】
公共職業安定所の長は、受給資格者証を提出した受給資格者に対して失業の認定を行った後、正当な理由があるときは、受給資格者証を返付しないことができる。

【解答】
③【H25年出題】 ×
「管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行ったときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)しなければならない。」とされています。
受給資格者証を返付しないことができるという規定はありません。
(則第22条第2項)
④【H25年出題】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。

【解答】
④【H25年出題】 〇
基本手当の支給は、口座振込の方法で行われるのが原則です。ただし、受給資格者の申出によりやむを得ない事由がある場合に限り、現金で支給することができます。
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その「代理人」が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができます。
(則第46条第1項)
⑤【H25年出題】※改正による修正あり
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を提出しなければならない。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
受給期間内に再就職した場合の手続です。
「受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、受給期間内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。」とされています。
(則第20条第1項、第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-284 6.6
通勤災害「療養給付」の基本【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
通勤災害の保険給付の基本をみていきましょう。
通勤災害に関する保険給付には、次の保険給付があります。(第21条)
(1) 療養給付 (2) 休業給付 (3) 障害給付 (4) 遺族給付 (5) 葬祭給付 (6) 傷病年金 (7) 介護給付 |
業務災害とは違い、名称に「補償」が入らないのがポイントです。
業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償の使用者責任を代行するものです。しかし、通勤災害には使用者の責任はありません。そのため、業務災害に関する保険給付とは異なるルールがあります。
条文を読んでみましょう。
第31条第2項、3項 ② 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ③ 政府は、②の労働者から徴収する一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
則第44条の2(一部負担金) ① 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 (2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 (3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ② 一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。 ③ 控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「療養給付」を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがあります。「通勤災害」には使用者の責任がないため、労働者にも一部負担してしてもらおうという趣旨です。
「療養補償給付」、「複数事業労働者療養給付」には、一部負担金はありません。
(第31条第2項)
②【H24年出題】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。

【解答】
②【H24年出題】 〇
療養給付を受ける労働者が徴収される一部負担金は、200円です。※健康保険法の日雇特例被保険者である労働者は100円です。
ただし、現に療養に要した費用の総額が200円(又は100円)に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額が徴収されます。
(則第44条の2第2項)
③【H24年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

【解答】
③【H24年出題】 〇
一部負担金は、休業給付の額から控除できます。
(則第44条の2第3項)
④【R1年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給される休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から一部負担金の額に相当する額を控除することにより行われる。

【解答】
④【R1年出題】 〇
療養給付を受ける労働者に支給する休業給付で最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、一部負担金の額が控除された額になります。
(第22条の2第3項)
⑤【H24年出題】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者については、一部負担金は徴収されません。
(則第44条の2第1項第1号)
⑥【H25年出題】
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。

【解答】
⑥【H25年出題】 ×
「療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者」については、一部負担金は徴収されません。休業給付が支給されないので、一部負担金が控除できないためです。
(則第44条の2第1項第1号)
⑦【H25年出題】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。

【解答】
⑦【H25年出題】 〇
同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者については、一部負担金は徴収されません。
(則第44条の2第1項第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-283 6.5
安全衛生管理体制の基本5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
安全衛生管理体制では、業種の分け方がポイントです。
3つのグループ分けをおぼえましょう。
A | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 |
B
| 製造業(物の加工業を含む。)、 電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、 各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業、 自動車整備業、機械修理業 |
C | その他の業種 |
(令第2条)
過去問を解きながら覚えるポイントをチェックしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場においては総括安全衛生管理者を選任しなければならないが、総括安全衛生管理者は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
 総括安全衛生管理者を選任する義務がある事業場
総括安全衛生管理者を選任する義務がある事業場
A | 常時100人以上 |
B | 常時300人以上 |
C | 常時1,000人以上 |
常時500人の労働者を使用する製造業の事業場は、総括安全衛生管理者の選任義務があります。
 巡視義務
巡視義務
総括安全衛生管理者には作業場等を巡視する義務はありません。
(第10条、令第2条、則第3条の2)
②【H23年出題】
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場においては安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
 安全管理者を選任する義務がある事業場
安全管理者を選任する義務がある事業場
A B | 常時50人以上
|
C | 選任義務なし |
常時80人の労働者を使用する建設業の事業場は、安全管理者の選任義務があります。
 巡視義務
巡視義務
安全管理者は作業場等を巡視する義務はありますが、頻度は決められていません。
(第11条、令第3条、則第6条)
③【H23年出題】
常時60人の労働者を使用する自動車整備業の事業場においては産業医を選任しなければならないが、産業医は少なくとも毎年1回作業場等を巡視しなければならない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
 産業医を選任する義務がある事業場
産業医を選任する義務がある事業場
A B C |
常時50人以上
|
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、産業医の選任義務があります。
 巡視義務
巡視義務
産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視する義務があります。ただし、産業医が、事業者から、毎月1回以上、情報の提供を受けている場合で、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回となります。
(第13条、令第5条、則第15条)
④【H23年出題】
常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。

【解答】
④【H23年出題】 ×
 安全衛生推進者等を選任する義務がある事業場
安全衛生推進者等を選任する義務がある事業場
A |
常時10人以上50人未満 |
安全衛生推進者 |
B | ||
C | 衛生推進者 |
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者等の選任義務があります。
 巡視義務
巡視義務
安全衛生推進者等には、作業場等を巡視する義務はありません。
(第13条、令第5条、則第12条の2)
⑤【H23年出題】
常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
 衛生管理者を選任する義務がある事業場
衛生管理者を選任する義務がある事業場
A B C |
常時50人以上
|
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、全業種で、衛生管理者の選任義務があります。
 巡視義務
巡視義務
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視する義務があります。
(第12条、令第4条、則第11条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-282 6.4
解雇の基本5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「解雇」の基本をみていきます。
なお、「解雇」とは、使用者が一方的に労働契約を終了させることです。
「労働契約法」では、「客観的に合理的な理由」がなく、社会通念上「相当と認められない」場合は、労働者を解雇することはできないことが定められています。
「労働基準法」では、解雇する際のルールとして、「解雇予告」、「解雇制限」が定められています。
過去問を解きながら基本を確認しましょう。
まず、第20条の条文を読んでみましょう。
第20条 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ② 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 第1項但書の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
労働者を解雇する場合は、少くとも30日前に予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
また、予告期間は、1日について平均賃金を支払った場合は、日数を短縮できます。例えば、10日分の平均賃金を支払った場合は、20日前に予告することになります。
また、次の場合は、解雇予告は要りません。
1天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
2労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
ただし、1も2もその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受ける必要があります。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。

【解答】
①【H23年出題】 ×
労働者の一方的な労働契約の解約(任意退職)には、労働基準法第20条の規定は適用されません。
②【H23年出題】
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処せられる。

【解答】
②【H23年出題】 ×
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇」をしたとしても、労働基準法の罰則の対象にはなりません。
なお、解雇の民事的効力については、労働基準法ではなく、「労働契約法」に定められています。
労働契約法第16条 (解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
有効・無効の判断は、労働基準監督署ではなく、裁判所が行います。
③【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者に、適用されることがあります。
条文を読んでみましょう。
第21条 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(1)に該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、(2)若しくは(3)に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は(4)に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 (1) 日日雇い入れられる者 (2) 2か月以内の期間を定めて使用される者 (3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 (4) 試の使用期間中の者 |
試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、予告期間、予告手当が適用されます。
④【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。

【解答】
④【H23年出題】 ×
第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者にも適用されます。期間の途中で解雇する場合には、解雇の予告が必要です。
(第21条)
⑤【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」となった場合は、予告手当を支払うことなく、即時に解雇することができますが、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要です。
(第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
休憩時間のすべてお話します
R6-281 6.3
休憩とは?条文読んでみましょう、過去問も!
・休憩時間とはどんな時間のことでしょう?
・労働時間がちょうど6時間の場合の休憩時間は?
・休憩付与の3つの原則は「途中付与」、「一斉付与」、「自由利用」です
・条文(第34条)を読んでみましょう
・過去問も解いてみましょう
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
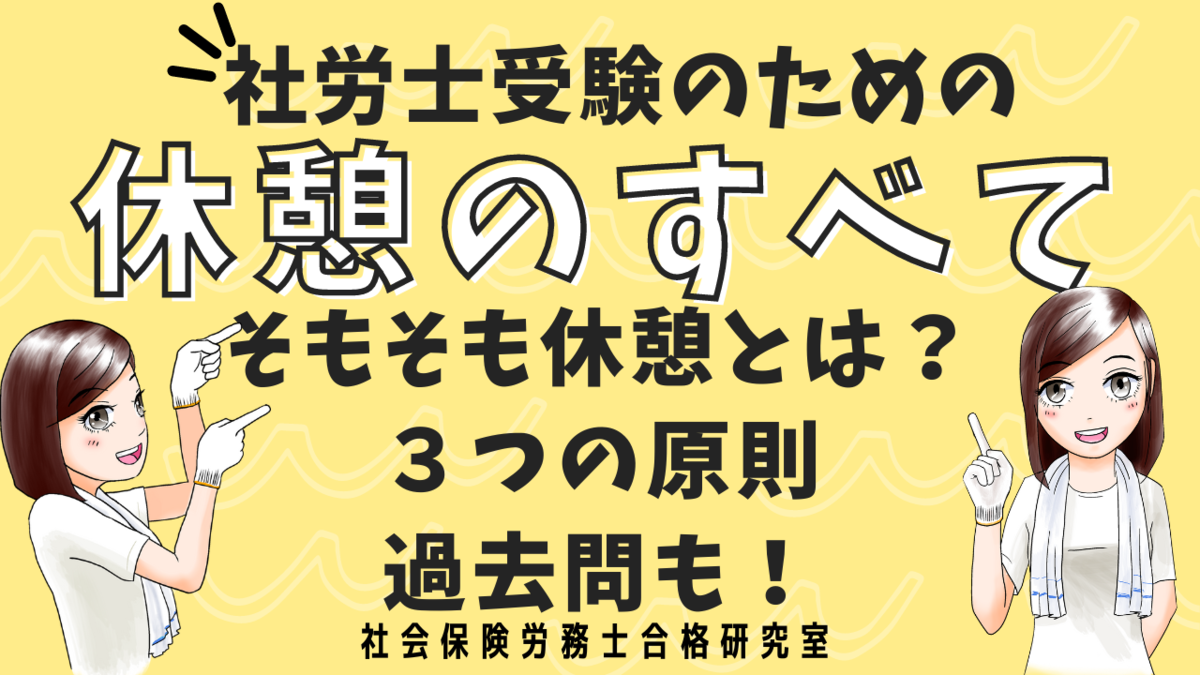
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-280 6.2
(応用編)障害厚生年金5問【社労士受験対策】
過去問から学びます。
今日は厚生年金保険法です。
障害厚生年金の応用問題を解きながらポイントを確認しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。
しかし、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。
(第38条第1項)
②【H23年出題】
障害厚生年金(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く。以下本肢において同じ。)の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が、労働基準法第77条の規定に定める障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。

【解答】
②【H23年出題】 〇
<2以上の障害が生じた場合>
★例えば、2級の障害厚生年金の受給権者に対して、更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合は、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されます。
2級 障害厚生年金 |
+ | 2級 障害厚生年金 |
= 併 合 | 1級 障害厚生年金 |
2級 障害基礎年金 | 2級 障害基礎年金 | 1級 障害厚生年金 |
この場合、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
(第48条)
問題文は、後から受給権を取得した障害厚生年金が、労働基準法の障害補償を受けるために支給停止されている場合の規定です。
その場合は、その停止すべき期間、併合した障害厚生年金ではなく、従前の障害厚生年金が支給されます。
(第49条第2項)
③【H23年出題】
障害厚生年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
③【H23年出題】 〇
障害の程度が軽くなり、1級~3級の状態に該当しなくなったときは、障害不該当の届出が必要です。「速やかに」にも注意して下さい。
(則第48条)
④【H23年出題】
傷病の初診日において65歳未満の被保険者であり、障害認定日において障害等級の 1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり、かつ保険料納付要件を満たしているときは、当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても、障害厚生年金を支給する。

【解答】
④【H23年出題】 〇
障害厚生年金は、「初診日に厚生年金保険の被保険者」、「障害認定日に障害等級の1級、2級又は3級に該当する程度の障害の状態にある」、「保険料納付要件を満たしている」の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。障害認定日の年齢は関係ありません。
(第47条)
⑤【H23年出題】
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができない。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
ポイント!
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっていないものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)とは、 ↓ 1度も1級、2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者のことです。 |
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができません。
下のイメージ図をご覧ください。
条文を読んでみましょう。
第52条第1項、2項、3項、7項、附則第16条の3第2項 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ⑦ ①から③までの規定は、65歳以上の者又は国民年金法の老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

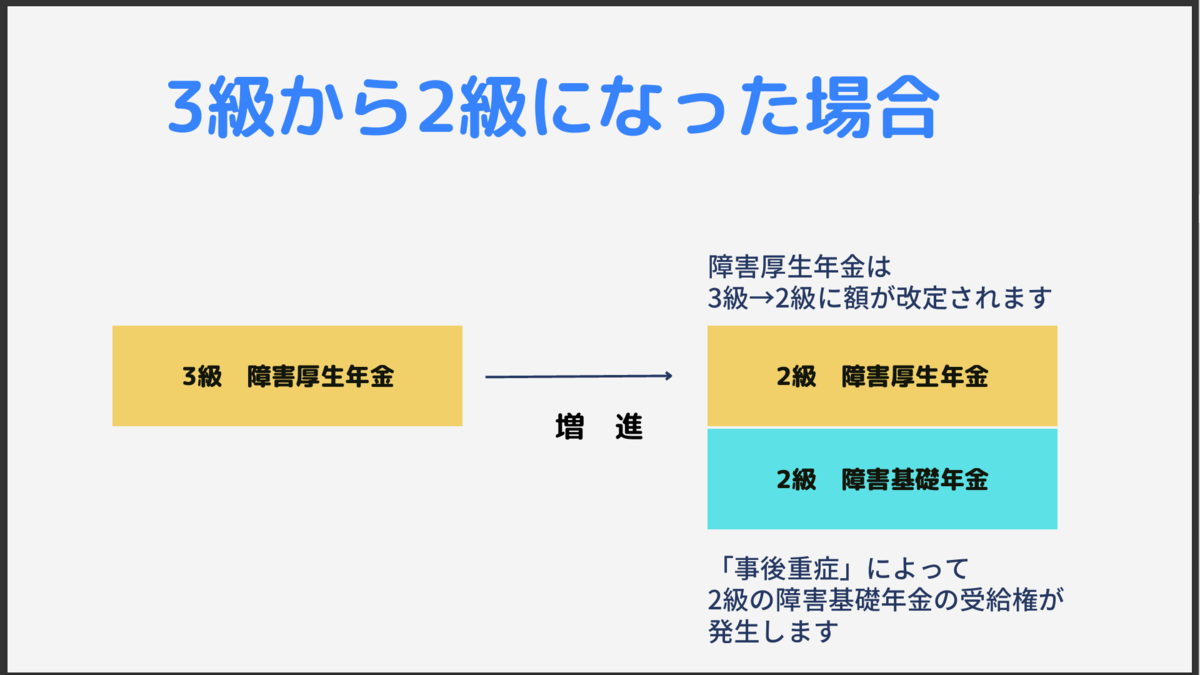
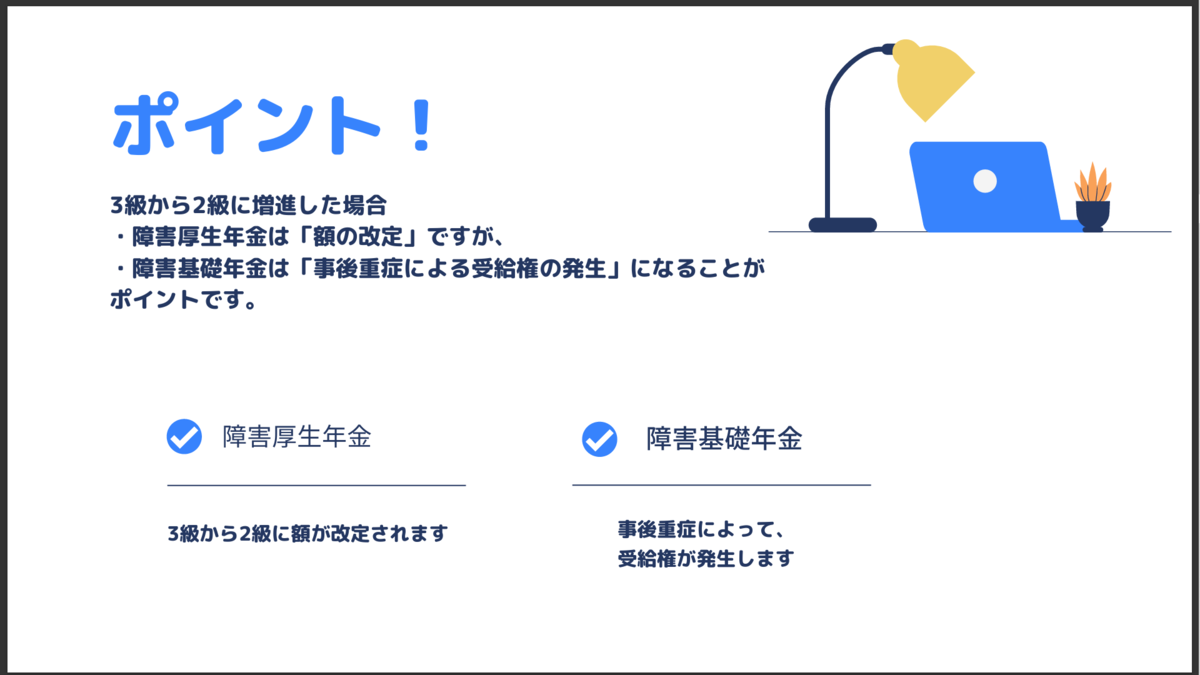
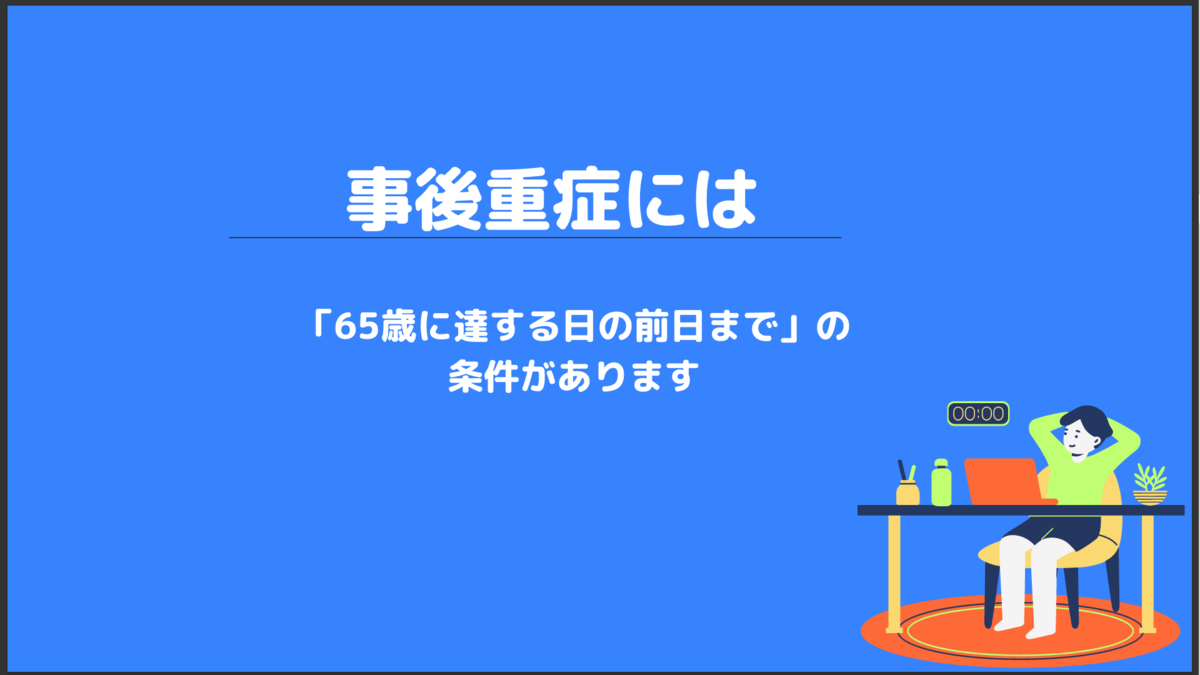
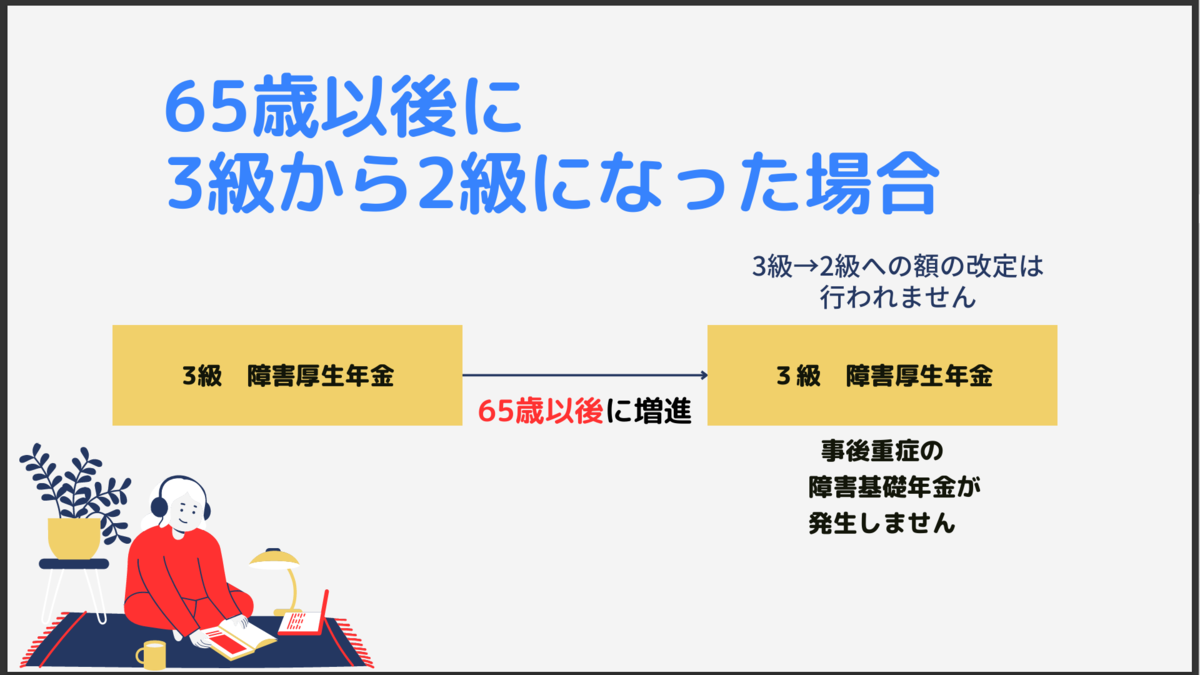
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-279 6.1
障害厚生年金重要5問【社労士受験対策】
過去問から学びます。
今日は厚生年金保険法です。
障害厚生年金の重要ポイントを確認しましょう。
まず、障害厚生年金の受給要件について条文を読んでみましょう。
第47条(障害厚生年金の受給権者) ① 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
障害厚生年金は、①「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」②「障害認定日に障害等級に該当していること」③「初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること」の3つを満たした場合は、障害認定日に受給権が発生します。
下の図でイメージしてみてください。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「軽度のものから」ではなく、「重度のものから1級、2級及び3級」です。
(第47条第2項)
ちなみに、「国民年金法」の障害等級は、「重度のものから1級及び2級」とされています。国民年金法の障害等級には3級はありません。(国民年金法第30条第2項)
②【H22年出題】※改正による修正あり
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。

【解答】
②【H22年出題】 〇
障害厚生年金の加給年金額のポイント!
★対象は65歳未満の配偶者です
「子」は障害基礎年金の加算対象になります
★加給年金額が加算されるのは1級と2級です
「3級」には加給年金額は加算されません
★障害厚生年金の権利を取得した日の翌日以後に対象になる配偶者を有するに至った場合も対象になります
→ 配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から加給年金額が加算されます
条文を読んでみましょう。
第50条の2第1項~3項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
③【H22年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

【解答】
③【H22年出題】 ×
240か月ではなく、300か月です。
条文を読んでみましょう。
第50条第1項、2項 (障害厚生年金の額) ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①の額の100分の125に相当する額とする。 |
★障害厚生年金は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額です。
★ただし、被保険者期間の月数が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。
★1級は、2級の1.25倍の額です。
④【H22年出題】
障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。

【解答】
④【H22年出題】 ×
3級の障害厚生年金の額は、「2級」の額と同じです。
ただし、加給年金額は加算されません。
なお、3級の障害厚生年金には最低保障額が設定されています。
条文を読んでみましょう。
第50条第3項 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とする。 |
⑤【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。

【解答】
⑤【H22年出題】 ×
障害認定日の属する月の前月までではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とします。
条文を読んでみましょう。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
例えば障害認定日が4月に属する場合
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|
|
| 障害認定日 |
|
|
計算に入るのは4月(障害認定日の属する月)までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-278 5.31
寡婦年金よく出る5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、寡婦年金の条文を読んでみましょう。
第49条第1項、3項(支給要件) ① 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 ③ 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
ポイント!
第1号被保険者だけでなく「任意加入被保険者」の期間も含みます。特例任意加入被保険者は含まれません。
夫の死亡時に60歳未満の妻については、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。寡婦年金が支給されるのは、60歳から65歳になるまでです。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H24年出題】 〇
65歳に達したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
寡婦年金の失権について条文を読んでみましょう。
第51条(失権) 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (第40条第1項) (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときも、寡婦年金の受給権は消滅します。 附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |
②【H24年出題】
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

【解答】
②【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅しますが、直系血族又は直系姻族の養子となったときは除かれます。そのため、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはありません。
(第51条)
③【H24年出題】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。

【解答】
③【H24年出題】 ×
寡婦年金の額には、付加保険料の納付分は反映しません。
寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)の期間で計算した老齢基礎年金の4分の3です。
条文を読んでみましょう。
第50条 (年金額) 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
④【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
寡婦年金の額の算定には、第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は反映しません。
(第50条)
⑤【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、寡婦年金が優先されるのではありません。寡婦年金と死亡一時金のどちらか選択となります。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 (支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金を選択した場合は、寡婦年金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-277 5.30
振替加算の基本5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、振替加算の条件を確認しましょう。
下のイメージ図をご覧ください。
なお、振替加算が支給されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
の人に限られることにも注意しましょう。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】
①【H21年出題】 ×
遺族基礎年金には振替加算額は加算されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金の額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるもの (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(1級又は2級) |
振替加算は「老齢基礎年金の額」に加算されます。
遺族基礎年金を選択した場合は、振替加算相当額は加算されません。
②【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
障害基礎年金の全額が支給停止されている場合は、振替加算に相当する部分は支給停止されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第16条第1項 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間振替加算に相当する部分の支給を停止する。 |
障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、振替加算は支給停止されます。
障害基礎年金が全額支給停止されている(=受けることができない)場合は、支給停止されません。
③【H21年出題】
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

【解答】
③【H21年出題】 ×
合算対象期間と学生納付特例期間のみで10年以上の場合でも、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。しかし、どちらも老齢基礎年金の額には反映しませんので、老齢基礎年金の額はゼロになります。
老齢基礎年金の額自体はゼロでも、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給されます。
問題文の場合は、老齢基礎年金の額に反映する期間が1月以上1年未満ありますので、振替加算相当額のみではなく、1月以上1年未満の分が反映された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
(昭60年附則第15条第1項)
④【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

【解答】
④【H21年出題】 〇
配偶者と離婚しても、振替加算は支給停止されません。
⑤【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】
⑤【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されます。しかし、増額はされません。
(昭60年附則第14条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-276 5.29
健康保険の現金給付5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険には、現物給付と現金給付があります。
現物給付の代表例は「療養の給付」(=病院等で治療そのものを受ける)、現金給付の代表例は「傷病手当金」(=現金で給付される)です。
現金給付の5問をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができなかったときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」とされています。
「療養のため」の療養とは、保険給付として受ける療養に限らないのがポイントです。自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても「療養のため」に該当しますので、傷病手当金が支給されます。
ただし、「健康保険で診療を受けることができる範囲の療養」であることが必要ですので、美容整形手術などの療養については、傷病手当金は支給されません。
(第99条、昭2.2.26保発345)
②【H23年出題】※改正による修正あり
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。
なお、報酬と出産手当金の支給を受けることはできない場合とする。

【解答】
②【H23年出題】 ×
傷病手当金ではなく、「障害厚生年金」が優先されます。
なお、障害年金の日額は、年金額÷360で計算します。
★傷病手当金は支給されません
|
障害厚生年金の 日額 |
傷病手当金
|
★差額の傷病手当金が支給されます
差額 |
|
傷病手当金
| 障害厚生年金の 日額 |
条文を読んでみましょう。
第108条第3項、則第89条 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。 (1) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 → 障害年金の額 (2) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 → 出産手当金の額(当該額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 (3) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 → 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 (4) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 → 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び出産手当金の額の合算額(当該合算額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 |
③【H23年出題】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。

【解答】
③【H23年出題】 〇
日雇特例被保険者の傷病手当金は、「療養の給付」等を受けていることが条件です。
問題①でみました一般被保険者の傷病手当金は、「自費診療で受けた療養」でも対象になりますが、日雇特例被保険者の傷病手当金は、「療養の給付」等を受けていることが条件です。
そのため、日雇特例被保険者の傷病手当金は、「自費診療で受けた療養」では支給されません。
ただし、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しません。
(第135条第1項、平15.2.25庁保発2944)
④【H23年出題】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。

【解答】
④【H23年出題】 〇
介護休業期間中でも、支給要件に該当する場合は、傷病手当金が支給されます。
同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整が行われます。
(第99条、平11.3.31保険発46・庁保険発9)
⑤【H23年出題】
被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、提出しなければなりません。
なお、医師又は歯科医師の意見書には、「移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)」、「移送経路、移送方法及び移送年月日」を記載することになっています。
(則第82条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-275 5.28
納付書と納入告知書の問題5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
徴収法では、「納付書」と「納入告知書」を区別することがポイントです。
条文を読んでみましょう。
則第38条第4項 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならない。 |
労働保険料等の納付は、「納付書」で行うことが原則です。
試験対策としては、「納入告知書」によって行われるものをおぼえましょう。おぼえたもの以外は「納付書」です。
(納入告知書によるもの) ・有期事業のメリット制の適用に伴う確定保険料の差額 ・認定決定された確定保険料と追徴金 ・認定決定された印紙保険料と追徴金 ・特例納付保険料 (則第38条第5項) |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用保険) ×
概算保険料の認定決定の通知は、納入告知書ではなく「納付書」で行われます。
確定保険料の認定決定との違いに注意しましょう。
概算保険料の認定決定 | 確定保険料の認定決定 |
納付書 | 納入告知書 |
追徴金なし | 追徴金あり |
(則第38条第4項、5項)
②【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
②【H25年出題】(雇用保険) 〇
確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
③【H25年出題】(雇用保険)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
③【H25年出題】(雇用保険) 〇
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われます。
(則第38条第4項、5項)
ちなみに、印紙保険料の認定決定が行われた場合は、認定決定した印紙保険料の額の100分の25の追徴金が徴収されます。
認定決定による印紙保険料と追徴金は「現金」で納付します。雇用保険印紙で納付するのではありませんので注意しましょう。
④【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。

【解答】
④【H25年出題】(雇用) 〇
追加徴収の概算保険料の納付は、納付書によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
⑤【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
⑤【H25年出題】(雇用) 〇
追徴金の額等の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
年金制度の歴史をお話します
R6-274 5.27
年金制度のポイントは昭和36年と昭和61年【社労士受験対策】
年金制度の歴史をお話します。
<厚生年金保険と国民年金の誕生>
①船員保険制度
昭和14年制定、昭和15年施行
社会保険方式による日本初の公的年金制度
など
②厚生年金保険法
労働者年金保険法としてスタート
など
③国民年金法
昭和36年4月より拠出制がスタートしたことによって
国民皆年金の実現!
<旧法から新法へ>
④基礎年金の登場 昭和61年4月
・昭和61年4月1日前を「旧法」、昭和61年4月1日以後を「新法」といいます
・年金制度が2階建てになりました
・国民年金の被保険者が第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されました
⑤新法と旧法の違い
1 旧法は「縦割り」、新法は「2階建て」
2 専業主婦は旧法では任意加入、新法では第3号被保険者として強制加入です
3 船員保険は旧法では独立していましたが、新法では厚生年金に統合されました
詳しくは、YouTubeでお話ししています。
YouTubeをご覧ください
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
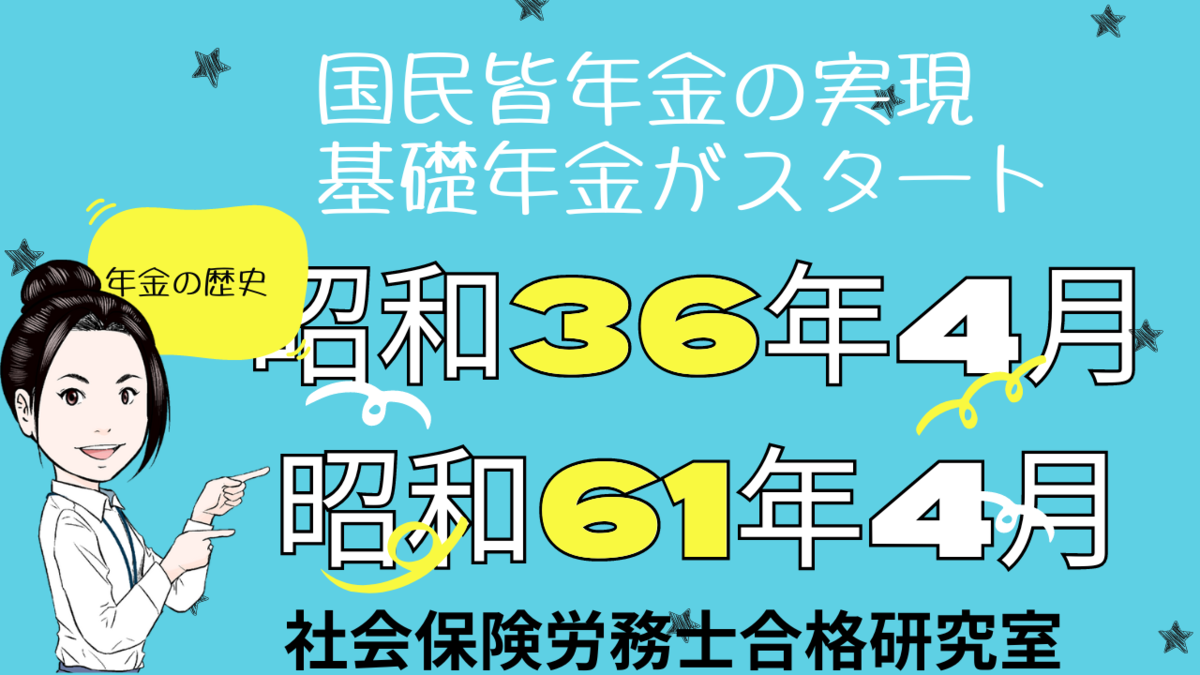
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-273 5.26
基本手当重要問題5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「基本手当」に関する過去問を解きながら重要ポイントをチェックしていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
AとBの間が1年以内で、Bの離職により基本手当又は特例一時金の支給を受けていない場合は、Bの期間は、今回の基本手当の算定基礎期間として通算されます。
問題文の「現実にそれらの支給を受けていない」がポイントです。Bで基本手当又は特例一時金の受給資格を取得していても、現実に支給を受けていない場合は、算定基礎期間は通算されます。
事業主B | 3か月 基本手当、特例一時金を 受けていない |
事業主A |
条文で読んでみましょう。
第22条第3項 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 |
この問題のポイント!
(1) 前の会社と今回の会社の間の空白が1年を超えている場合は、前の会社の被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
(2) 前に、基本手当又は特例一時金の支給を現実に受けたことがある場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る被保険者であった期間は、算定基礎期間から除かれます。
②【H21年出題】
受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た額である。

【解答】
②【H21年出題】 ×
基本手当の日額は、
賃金日額×(100分の80から100分の50までの範囲で厚生労働省令で定める率)
で計算します。
100分の80から100分の60までではなく、100分の80から100分の50までの範囲です。
なお、離職の日に60歳以上65歳未満の場合は、「100分の80から100分の45」までの範囲となります。
(第16条)
③【H21年出題】
雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の場合、その者が当該受給資格に係る離職日において満40歳であれば、算定基礎期間の長さや離職理由にかかわらず、基本手当の所定給付日数は300日となる。

【解答】
③【H21年出題】 ×
「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に該当する受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間の長さ(「1年以上」か「1年未満」か)、「年齢」(「45歳未満」か「45歳以上65歳未満」か)で決まります。離職理由は関係ありません。
<就職が困難な者の所定給付日数>
| 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 |
150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
離職日に満40歳の場合は、算定基礎期間が1年未満の場合は150日、1年以上の場合は300日となります。
④【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。

【解答】
④【H21年出題】 〇
<受給期間内に再就職して再び離職した場合>
①新たに受給資格を取得した場合 →前の受給期間は消滅し、前の受給資格に係る基本手当は支給されません。
②再び離職した際に、新たに受給資格を取得しなかった場合 → 前の受給期間内なら前の受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することができます。
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
問題文は、新たに高年齢受給資格を取得していますので、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできません。
(行政手引50251)
⑤【H21年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額が賃金日額の100分の80に相当する額に達しなければ、当該収入の基礎となった日数分の基本手当の支給に当たり、支給額は減額されない。

【解答】
⑤【H21年出題】 ×
失業の認定に係る期間中に自己の労働による収入を得た場合、基本手当は、「全額支給」、「減額支給」、「支給されない」の3つに分かれます。
(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」との合計額(=「合計額」といいます)と比較します。
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超えない場合 → 基本手当は全額支給されます
・「合計額」が賃金日額の100分の80を超える場合 → 超過額が基本手当の日額から控除されます。
・超過額が基本手当の日額以上の場合 → 基本手当は支給されません。
問題文は、「その収入の1日分に相当する額」となっていますが、「(「その収入の1日分に相当する額」から「控除額」を控除した額)と「基本手当の日額」」との合計額で比較します。
(第19条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-272 5.25
業務災害・通勤災害の範囲【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
業務災害、通勤災害の範囲をみていきます。
まず、業務災害、通勤災害の定義を条文で読んでみましょう。
第7条第1項 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 (1) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 (2) 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。) (3) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 (4) 二次健康診断等給付 |
業務災害とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」、通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

【解答】
①【H25年出題】 ×
「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところを指します。
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないとされています。
「反復・継続性」とは、おおむね「1か月に1回以上」の往復行為又は移動がある場合に認められます。
(平18.3.31基発第0331042号、平18.3.31/基労管発第0331001号/基労補発第0331003号/)
②【H25年出題】
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。

【解答】
②【H25年出題】 〇
出張の機会を利用して出張期間内に、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われます。
(平18.3.31/基労管発第0331001号/基労補発第0331003号/)
③【H25年出題】
通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。

【解答】
③【H25年出題】 ×
「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。
通勤の途中で、自動車にひかれた、電車が急停車したため転倒して受傷した、駅の階段から転落した、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった等、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められます。
問題文は、通勤による災害と認められます。
(平18.3.31基発第0331042号)
④【H25年出題】
通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

【解答】
④【H25年出題】 ×
被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではありませんので、通勤災害とは認められません。
(平18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-271 5.24
通勤に該当する例・該当しない例【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
まず、「通勤」の定義を条文で読んでみましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 (1) 住居と就業の場所との間の往復 (2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 (3) (1)に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
★「就業に関し」について
「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示しています。つまり、通勤と認められるには、移動行為が業務と密接な関連をもって行われることを要します。
★「合理的な経路及び方法」について
「合理的な経路及び方法」とは、移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいいます。
★「業務の性質を有するもの」について
「業務の性質を有するもの」とは、移動による災害が業務災害と解されるものをいいます。
(平18.3.31基発第0331042号)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があるとされています。
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合でも、通勤に該当することはあります。
(平18.3.31基発第0331042号)
②【H24年出題】
運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。

【解答】
②【H24年出題】 ×
運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、
① 午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合
② 第2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻に出勤する場合
には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるものと考えられるので、就業との関連性はないと認められます。そのため、通勤に該当しません。
(平18.3.31基発第0331042号)
③【H24年出題】
日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に該当しない。

【解答】
③【H24年出題】 〇
日々雇用される労働者について、公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、未だ就職できるかどうか確実でない段階であり、職業紹介を受けるための行為であって、就業のための出勤行為であるとはいえないとされています。
ちなみに、日々雇用される労働者について
・継続して同一の事業に就業している場合は、就業することが確実であり、その際の出勤は、就業との関連性が認められます。
・公共職業安定所等でその日の紹介を受けた後に、紹介先へ向う場合で、その事業で就業することが見込まれるときも、就業との関連性を認めることができます。
(平18.3.31基発第0331042号)
④【H24年出題】
昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。

【解答】
④【H24年出題】 ×
通勤は1日について1回のみしか認められないものではありませんので、昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、昼休みについていえば、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられますので、その往復行為は就業との関連性を認められ、通勤に該当します。
(平18.3.31基発第0331042号)
⑤【H24年出題】
業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えないとされています。
問題文の場合は通勤に該当することもあります。
(平18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-270 5.23
建設工事現場の安全衛生管理【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
下請負事業者が混在している建設工事現場の安全衛生管理体制をみていきましょう。
まず、建設現場の安全管理体制のイメージを確認しましょう。(記事の下の図をご覧ください)
さっそく過去問からどうぞ!
【R1年出題】
次に示す建設工事現場における安全衛生管理に関する問題です。
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題①】
乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

【解答①】 〇

乙社は、特定元方事業者です
・元方事業者とは?
一の場所において行う事業の仕事の一部を関係請負人に請け負わせているものです。
・特定元方事業者とは?
特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者を特定元方事業者といいます。

統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業者は?
「特定元方事業者」は、一の場所の規模に応じ、統括安全衛生責任者を選任します。
統括安全衛生責任者の選任が必要な規模は、原則として労働者数が常時50人以上の場所です。(工事の種類によっては30人以上となります)
問題文は、一の場所の労働者数が、乙社+丙社+丁社=60人ですので、乙社は特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

統括安全衛生責任者には、「元方安全衛生管理者の指揮」をさせなければなりません。
なお元方安全衛生管理者の選任義務があるのは、統括安全衛生責任者を選任した「建設業」の事業を行うものです。造船業には選任義務はありません。
(第15条、令7条)
【問題②】
丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。

【解答②】 〇
「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。」とされています。
下請負人である丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければなりません。
(第16条第1項)
【問題③】
丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

【解答③】 ×
「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」とされています。
関係請負人丁社の労働者が、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社ではなく、元方事業者の乙社に課せられます。
(第29条第2項)
【問題④】
乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。

【解答④】 〇
「特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。」とされていて、そのうちの一つが「協議組織の設置及び運営を行うこと。」です。
特定元方事業者である乙社は、協議組織を設置しなければなりません。
また、協議組織の設置、運営については、以下のように定められています。
則第635条(協議組織の設置及び運営) ① 特定元方事業者は、協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。 (1) 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。 (2) 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。 ② 関係請負人は、特定元方事業者が設置する協議組織に参加しなければならない。 |
関係請負人の丙社及び丁社は協議組織に参加しなければなりません。
(第30条第1項第1号、則第635条)
【問題⑤】
乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。

【解答⑤】 〇
・乙社、丙社、丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負います。
(第21条第2項)
・乙社は丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負います。
(第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
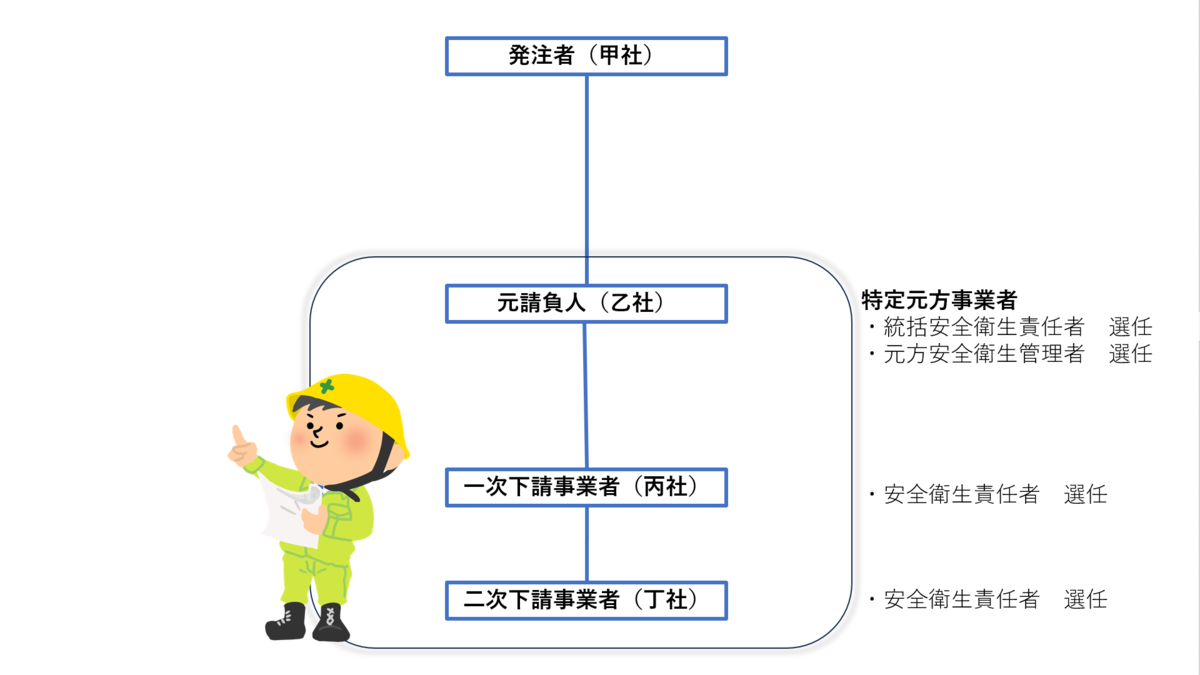
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-269 5.22
絶対的必要記載事項の具体的な内容【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
就業規則には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
「絶対的必要記載事項」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
今回は、絶対的必要記載事項の内容をみていきます。
まず、「絶対的必要記載事項」を確認しましょう。
絶対的必要記載事項は次の3つです。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (2)賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (第89条第1号~3号) |
では、具体的な内容をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、絶対的必要記載事項です。
ちなみに、「臨時の賃金等」は、相対的必要記載事項です。
(第89条第1号)
②【H26年出題】
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法第89条第1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則で、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定め」をすれば、「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務の要件を満たします。
また、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項も「始業及び終業の時刻」に関する事項ですので、就業規則に記載しなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
③【H28年出題】
労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」にも第89条は適用されます。そのため、就業規則には、始業及び終業の時刻を定めなければなりません。
(S23.12.25基収4281号)
④【R1年出題】
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、例えば「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めることで差し支えない。

【解答】
④【R1年出題】 ×
労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、「勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻」を規定しなければなりません。
「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めるだけでは足りません。
(H11.3.31基発168号)
⑤【H30年出題】
就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
絶対的必要記載事項の「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれます。
育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間を就業規則に記載する必要があります。
なお、対象者、申出手続、育児休業期間等は育児介護休業法に具体的に定められていますので、「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定め」があれば記載義務は満たしている、とされています。
(H11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-268 5.21
労働基準法の労働者の具体例7問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
まず労働基準法の「労働者」の定義を条文で読んでみましょう。
第9条 (定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
①事業に「使用」される者で、②その対償に「賃金」が支払われる者は、労働基準法の労働者となります。
今回は、労働者に該当するか否かの具体例をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。

【解答】
①【R4年出題】 ×
法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではありません。
(H11.3.31基発168号)
②【H29年出題】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

【解答】
②【H29年出題】 〇
株式会社の取締役でも、工場長、部長等職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働者として労働基準法の適用を受けます。
(S23.3.17基発461号)
③【R4年出題】
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

【解答】
③【R4年出題】 〇
事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者となります。そのような場合は、明確な契約関係がなくても労働基準法が適用されます。
④【H29年出題】
医科大学付属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

【解答】
④【H29年出題】 ×
研修医が、医療行為等に従事することは、「教育的な側面を強く有するもの」ではなく「病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなる」のであり、「病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価できる」限り、研修医は労働基準法第9条所定の「労働者に当たる」ものというべきである、とされています。
(H17.6.3最高裁判所第二小法廷)
⑤【H27年出題】
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
請負契約と労働契約は異なります。
「請負」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」です。(民法632条)
請負は、業務を自己の業務として相手方から独立して処理するものです。(S23.1.9基発14号)
しかし、請負契約の形式をとっていても、使用従属関係の実体が認められるときは、その関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法の「労働者」に当たります。
⑥【H29年出題】
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多いです。しかし、請負契約によらず雇用契約によってその事業主と大工との間に使用従属関係が認められる場合は、労働者となり、労働基準法の適用を受けます。
大工が労働者に該当し、労働基準法が適用されることもあります。
(H11.3.31基発168号)
⑦【R1年出題】
いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。

【解答】
⑦【R1年出題】 〇
次の4つの全てに該当する芸能タレントは、労働基準法の労働者にはなりません。
①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている
②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない
③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない
④契約形態が雇用契約ではない
(S63.7.30基収355号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
条文の読み方をお話します
R6-267 5.20
条文の読み方 以上・超える、以下・未満【社労士受験対策】
条文の読み方をお話します。
テーマは、 「以上・超える、 以下・未満」です。
100人以上 → 100人を含む
100人を超える →100人を含まない
100人以下 → 100人を含む
100人未満 → 100人を含まない
「有期事業が一括される要件」と「下請負事業分離の認可の要件」を例にお話しています。(過去問もあります。)
宜しければ、YouTubeでご覧ください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-266 5.19
老齢厚生年金の支給繰上げ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
老齢厚生年金の支給繰上げについて条文を読んでみましょう。
附則第7条の3第1項・2項 (老齢厚生年金の支給の繰上げ) ① 当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法の任意加入被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第42条第2号に該当しないときは、この限りでない。 (1) 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者 (2) 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者 ※(3)と(4)は省略します。 ② 繰上げの請求は、国民年金法の老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。 |
(1)と(2)は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが完了し、老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳からとなる世代です。
この世代は、60歳以上65歳未満の間に、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができます。
60歳 | 65歳 |
| 老齢厚生年金
|
| 老齢基礎年金
|
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰上げと老齢基礎年金の支給繰上げの請求は同時に行わなければなりません。
(附則第7条の3第2項)
②【R4年出題】
昭和38年4月1日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60歳0か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24パーセントとなる。

【解答】
②【R4年出題】 〇
繰り上げた老齢厚生年金の額は、政令で定める額を減じた額となります。
(附則第7条の3第4項)
減額率は、「1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率」です。
問題文の場合は、1,000分の4×60か月=24%です。
(令6条の3)
なお、昭和37年4月1日以前生まれの場合は、1,000分の4ではなく「1,000分の5」で計算します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-265 5.18
障害の状態にある子の遺族厚生年金の受給権の消滅【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、「配偶者、子、父母、孫又は祖父母で、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」です。
このうち、「子、孫」については、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」が条件です。
今日は、障害状態にある子、孫の遺族厚生年金の受給権の消滅についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (2) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (3) 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
ポイント!
国民年金法と厚生年金保険法では「障害等級」の定義が異なります。
国民年金法では、「1級、2級」ですが、厚生年金保険法では「1級、2級、3級」です。
厚生年金保険法の条文では、「障害等級の1級又は2級」という表現に注意してください。厚生年金保険法の条文で単に「障害等級」と書かれていれば、1級、2級、3級です。「障害等級の1級又は2級」と書かれていれば1級と2級限定です。3級は含まれません。
(1)について
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに失権
※18歳年度末時点で1級・2級のときは失権しない。
(2)について
・1級・2級に該当しなくなったときは失権
※障害要件を満たさなくなっても18歳の年度末までは失権しない。
(3)について
・1級・2級でも20歳に達したときは失権
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 〇
障害の状態にあるときでも障害等級が3級の場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の遺族厚生年金の受給権は消滅します。
(第63条第2項第1号)
②【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
前半は正しいです。
遺族厚生年金の 受給権発生 ▼ | 16歳 3級に該当 ▼ | 18歳年度末 失権 ▼ |
|
|
|
後半は誤りです。
遺族厚生年金の 受給権発生(2級) ▼ | 18歳年度末 (2級) ▼(失権しない) | 19歳 3級 ▼失権 |
|
|
|
2級に該当する子が19歳のときに3級に該当した場合は、「20歳に達したとき」ではなく、1級2級に該当しなくなったとき(3級に該当したとき)に失権します。
(第63条第2項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-264 5.17
第2号・第3号被保険者は保険料の納付義務なし【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
第1号被保険者は、国民年金の保険料を納付しなければなりませんが、第2号被保険者と第3号被保険者には保険料の納付義務はありません。
条文を読んでみましょう。
第94条の6 (第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例) 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
第2号被保険者、第3号被保険者にも、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されますが、給付に必要な費用は、「基礎年金拠出金」を通して行われます。
そのため、第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付する必要はありません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
第1号被保険者と任意加入被保険者には国民年金保険料の納付義務があります。
第2号被保険者及び第3号被保険者には国民年金保険料の納付義務はありません。
(第88条第1項、第94条の6)
②【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
国民年金保険料の納付義務があるのは「第1号被保険者」です。第2号被保険者と第3号被保険者は国民年金保険料を納付することを要しません。
(第88条第1項、第94条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
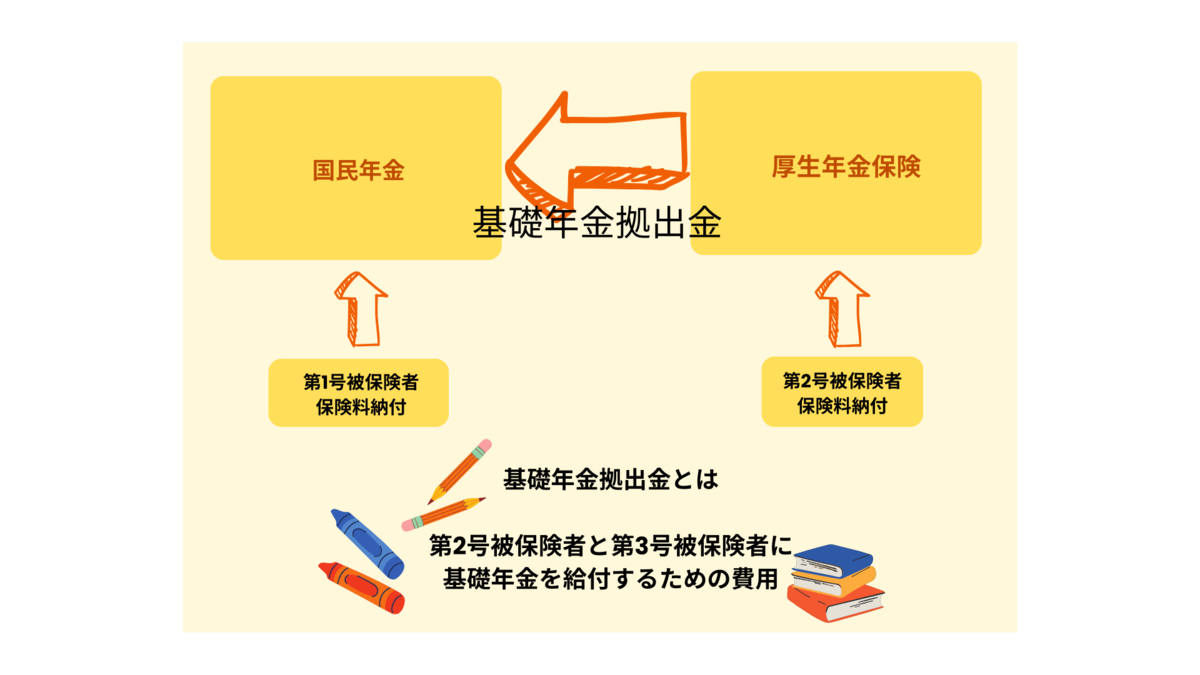
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-263 5.16
付加年金と死亡一時金の加算額に対する国庫負担【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
第1号被保険者は、付加保険料(月額400円)を納付することができます。以下の給付には、付加保険料の納付が反映されます。
★付加年金
老齢基礎年金に上乗せして「付加年金」が支給されます。
付加年金は200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で計算します。
★死亡一時金の加算額
死亡した者の付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある場合、死亡一時金に8500円が加算されます。
今回は、付加年金と死亡一時金の加算額の費用に対する国庫負担をみていきます。
条文を読んでみましょう。
S60年法附則第34条第1項第1号 (国民年金事業に要する費用の負担の特例) 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。 |
★付加年金の給付に要する費用、死亡一時金の加算額に要する費用の「4分の1」を国庫が負担します。
※第52条の4第1項に定める額とは、12万円から32万円まで6段階で設定されている死亡一時金の額のことです。
その額は「除く」としていますので、4分の1の国庫負担が行われるのは、死亡一時金に加算される額(=8500円)に対してです。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

【解答】
①【R4年出題】 〇
「付加年金の給付に要する費用」と「死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)=死亡一時金に加算される額(8500円)のこと」の総額の4分の1に相当する額を国庫が負担します。
(S60年法附則第34条第1項第1号)
②【H26年出題】
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の額の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。

【解答】
②【H26年出題】 〇
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に死亡一時金に加算される額(8,500円)の給付に要する費用については、4分の1を国庫が負担します。
(S60年法附則第34条第1項第1号)
③【H26年出題】
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。

【解答】
③【H26年出題】 ×
付加年金の給付に要する費用の国庫負担は、3分の1ではなく「4分の1」です。
(S60年法附則第34条第1項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-262 5.15
一時帰休に伴う休業手当と随時改定【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、随時改定の条文を読んでみましょう。
第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
随時改定の3つの要件を確認しましょう。
① 昇給・降給、給与体系の変更等で固定的賃金の変動があった。
② 固定的賃金の変動月からの3か月間の報酬の平均月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3カ月間の各月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上である。
改定が行われるのは、「その著しく高低を生じた月の翌月から」です。具体的には、固定的賃金の変動月から4か月目からです。
例えば、4月に固定的賃金の変動があった場合、4月・5月・6月の3か月間の報酬の平均をとり、標準報酬月額は7月から改定されます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 変動 |
|
| 改定 |
|
|
|
|
|
今回は、「一時帰休に伴う休業手当」と随時改定についてみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
①【R3年出題】 〇
一時帰休に伴い、低額な休業手当が支払われる状態が継続して3か月を超える場合は、随時改定の対象になります。
(令和5.6.27事務連絡)
②【R3年出題】
賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払が行われ、5月1日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

【解答】
②【R3年出題】 ×
一時帰休に伴い、低額な休業手当が支払われる状態が継続して3か月を超える場合は、随時改定の対象になりますが、3か月は月単位で計算します。
月末締め月末払いの事業所で、2月19日から一時帰休が開始された場合は、5月1日に「3か月を超える場合」に該当します。
2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降に随時改定が行われます。
ただし、5月1日時点で一時帰休の状態が解消している場合は、「3か月を超える」に該当しないので、随時改定は行われません。
問題文は、随時改定の対象になりません。
(令和5.6.27事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-261 5.14
労働保険料の算定と納付【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【R3年出題】(雇用)
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。
保険関係成立年月日:令和元年7月10日
事業の種類:食料品製造業
令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6
令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9
令和元年度の確定賃金総額:4,000万円
令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円
令和2年度の確定賃金総額:7,600万円
令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円
【問題】
A 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3期に分けて納付することが認められ、第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。

【解答】
A ×
ポイント! 年度の中途に保険関係が成立した場合の延納について
4月・5月に成立 → 3期に分けて延納できる
6月~9月に成立 → 2期に分けて延納できる
10月以降に成立 → 延納できない
7月10日に成立した場合は、当該年度の保険料は「2期」に分けて納付することが認められます。
最初の期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内ですので、令和元年8月29日です。翌日起算がポイントです。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 (7月10日~11月30日)
納付期日 8月29日 | 第2期 (12月1日~3月31日)
納付期日1月31日 (労働保険事務組合に委託) 2月14日 | |||||||
(則第27条)
【問題】
B 令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111万円とされた。
7,400万円×1000分の15=111万円

【解答】
B ×
概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額で計算するのが原則です。
ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下の場合は、「直前の保険年度の賃金総額」で計算します。
令和2年度の賃金総額の見込額は7,400万円ですが、令和元年度の確定賃金総額4,000万円の100分の50以上100分の200以下の範囲に入ります。そのため、令和2年度の概算保険料は、令和元年度の確定賃金総額で計算します。
令和2年度の概算保険料は、4,000万円×1000分の15=60万円です。
令和元年度 | 令和2年度 |
確定賃金総額4,000万円 | 賃金総額の見込額7,400万円 ※令和2年度の概算保険料は、 令和元年度の確定賃金総額で計算します |
(第15条、則第24条)
【問題】
C 令和3年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を3,600万円で算定し、延納を申請した。また、令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第1期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
3,600万円×1000分の15÷3=18万円‥………………………①
(令和2年度の確定保険料)-(令和2年度の概算保険料)……②
第1期分の保険料=①+②

【解答】
C 〇
 令和3年度の概算保険料は、賃金総額の見込額の3,600万円で算定します。
令和3年度の概算保険料は、賃金総額の見込額の3,600万円で算定します。
令和2年度の確定賃金総額7,600万円の100分の50未満だからです。
 令和3年度の概算保険料の額は3600万円×1000分の15=54万円です。3期に分けて延納でき、1回当たりの額は、54万円÷3=18万円です。
令和3年度の概算保険料の額は3600万円×1000分の15=54万円です。3期に分けて延納でき、1回当たりの額は、54万円÷3=18万円です。
 確定保険料は延納できませんので、1期目で全額納付します。
確定保険料は延納できませんので、1期目で全額納付します。
 第1期分として7月10日までに納付する額は以下の額です。
第1期分として7月10日までに納付する額は以下の額です。
令和3年度第1期分概算保険料18万円 |
+
確定精算のために納付する令和2年度分の確定保険料 (納付済の令和2年度の概算保険料と確定保険料の差額) |
(第15条、第19条、則第27条)
【問題】
D 令和3年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3,600万円から6,000万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。

【解答】
D ×
増加概算保険料の要件は、「増加後の賃金総額の見込額が増加前の賃金総額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である」ことです。
見込額が3,600万円から6,000万円に増加しても、100分の200は超えていませんので、増加概算保険料の納付は不要です。
(第16条、則第25条)
【問題】
E 令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。

【解答】
E ×
認定決定された概算保険料も、延納の申請が可能です。
(則第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
条文の読み方をお話します
R6-260 5.13
条文の読み方「みなす」・「推定する」【社労士受験対策】
「みなす」と「推定する」の違いについてお話します。
★「みなす」について
労働基準法の専門業務型裁量労働制は、「労使協定で定める時間労働したものとみなす」と」規定されています。
実際の労働時間に関係なく、「労使協定で定める時間」労働したと確定的に決められます。
★「推定する」について
例えば、国民年金法では船舶が沈没した際現にその船舶に乗っていた者者の生死が 3か月間分らない場合は、その船舶が沈没した日に、その者は、「死亡したものと推定する。」となっています。
推定するとは「一応死亡したものとしておく」という意味ですので、覆る可能性があります。なお「みなす」の場合は覆ることはありません。
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-259 5.12
2年前の日より前に被保険者となったとみなして算定基礎期間を算定【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
前回に引き続き、「算定基礎期間」の算定についてお話します。
前回の記事はこちらです。
条文を読んでみましょう。
第22条第4項、5項 ④ 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。 ⑤ 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(第1号に規定する事実を知っていた者を除く。)については、「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。 (1) その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。 (2) 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があつた日の2年前の日より前に徴収法の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。 |
★事業主が雇用保険の資格取得届を提出していなかった場合
■(原則)確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行います。遡って加入できるのは原則2年以内です。
■2年を超えて遡及できる場合
・給与明細等の確認書類により
↓
・資格取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである時期がある
↓
・給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日に
↓
・被保険者となったものとみなして算定基礎期間の算定を行います
(行政手引50302)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前については、給与明細等の確認書類により、雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日に被保険者となったものとみなされます。
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前については、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれません。
(第22条第4項、5項、行政手引23501)
②【H27年出題】
厚生労働大臣が職権で12年前から被保険者であったことを遡及的に確認した直後に、基準日において40歳の労働者が離職して特定受給資格者となった場合であって、労働保険徴収法第32条第1項の規定により労働者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかでないとき、所定給付日数は240日となる。

【解答】
②【H27年出題】 ×
確認のあった日の2年前の日より前に遡及できるのは、給与明細等により被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に被保険者の負担すべき雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合です。
賃金から控除されていたことが明らかでない場合は、「確認のあった日の2年前の日に被保険者となったもの」とみなされます。
問題文の場合は、「被保険者の負担すべき雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない」となっていますので、算定基礎期間は12年ではなく「2年」です。
40歳の特定受給資格者で、算定基礎期間が2年ですので、所定給付日数は150日となります。
(第22条第4項、5項、行政手引23501)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-258 5.11
算定基礎期間から除かれる期間【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
基本手当の所定給付日数は、特定受給資格者、特定理由離職者になるかどうか、就職困難者であるかどうか、離職日の年齢、算定基礎期間で決まります。
その中の一つ「算定基礎期間」をみていきます。
算定基礎期間は、原則として、離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業所に雇用された期間のことです。
では、条文を読んでみましょう。
第22条第3項、第61条の7第9項 ③ 算定基礎期間は、受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。 (1) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間 (2) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間 (3) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間 |
★算定基礎期間は、「引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間」です。
ただし、別の会社で被保険者であったことがある場合は、算定基礎期間に通算されます。
A社 | 1年以内 基本手当受給しない | B社 |
A社とB社の間が1年以内で基本手当を受給していませんので、B社の被保険者であった期間にA社の被保険者であった期間が通算されます。
★通算されない場合もみてみましょう。
A社 | 1年超え 基本手当受給しない | B社 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、通算されません。
A社 | 1年以内 基本手当受給した | B社 |
A社とB社の間は1年以内ですが、基本手当を受給しているので、通算されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。

【解答】
①【R3年出題】 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず被保険者となり、当該期間は算定基礎期間に算入されます。
(行政手引20352)
②【R3年出題】
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
育児休業給付金を受けた期間は、算定基礎期間から除外されます。
ちなみに、出生時育児休業給付金の支給を受けた期間も、算定基礎期間から除外されます。
(第61条の7第9項、第61条の8第6項)
③【H29年出題】
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
介護休業給付金を受けた期間は、算定基礎期間に含まれます。(除外されません。)
④【R3年出題】
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合は、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、算定基礎期間に含まれません。
(第22条第3項)
⑤【R3年出題】
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格者に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、その受給資格又は特例受給資格者に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、基本手当の算定基礎期間に含まれません。
(第22条第3項)
⑥【H27年出題】
事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は5年となる。

【解答】
⑥【H27年出題】 〇
A社 3年間 | 2年間 基本手当受給しない | B社 5年間 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、A社の被保険者であった期間は通算されません。算定基礎期間はB社のみで算定し5年となります。
(第22条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-257 5.10
特別加入者に対する支給制限【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者は、労災保険に特別加入できます。
特別加入すると、労働者とみなされ、労働者と同じ補償が受けられます。
ただし、労働者とは異なる規定もありますので、注意しましょう。
今回は、労働者と異なる規定のひとつ「支給制限」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条第1項第4号 中小事業主等の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。
第35条第1項第7号 一人親方等及び特定作業従事者の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
第36条第1項第3号 海外派遣者の事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
★特別加入者の支給制限について
・中小事業主等のみに規定されているもの
中小事業主等の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・中小事業主等、一人親方等、海外派遣者共通で規定されているもの
事故が特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
★★「労働者」の場合と比較してみましょう。
① 事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故
② 事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故
③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
(第31条第1項)
①②③については、事業主に非があるため、「事業主からの費用徴収」の対象になります。労働者に対する保険給付は全額支給され、支給制限は行われません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
特別加入している中小事業主等の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」です。
事業主から費用を徴収するのではなく、「支給制限」が行われます。
(第34条第1項第4号)
②【H26年出題】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる(=費用徴収)。」ではなく、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(=支給制限)」となります。
(第34条第1項第4号)
③【H26年出題】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
③【H26年出題】 ×
②の問題と同じです。第二種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故については、費用徴収ではなく、支給制限となります。
(第35条第1項第7号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-256 5.9
リスクアセスメントの実施【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
「リスクアセスメントの実施」について、条文を読んでみましょう。
第28条の2第1項 (事業者の行うべき調査等) 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。 |
★ 職場に潜在的に存在している危険性、有害性を見つけ出し、リスクを見積もり、そのリスクを低減するための措置をとることをリスクアセスメントといいます。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は< A >危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第2項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されている。

【解答】
A 作業行動その他業務に起因する
(第28条の2第1項
②【H29年選択式】
労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する< B >(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による< B >を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。

【解答】
B 危険性又は有害性等
③【R3年出題】
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。

【解答】
③【R3年出題】 ×
調査の時期について条文を読んでみましょう。
則第24条の11(危険性又は有害性等の調査) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。 (1) 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 (2) 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 (3) 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 (4) 前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 |
作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するときは、危険性又は有害性等の調査を行うものとされていますが、「1か月以内に」とは規定されていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-255 5.8
第91条制裁規定の制限【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
今日は「制裁規定」をみていきます。
「制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を就業規則に記載しなければなりません。(相対的必要記載事項です)
制裁の種類は、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇等がありますが、制裁の種類及び程度については、労働基準法上の制限はありません。
ただし、「減給の制裁」については、労働基準法上の制限が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
減給制裁の制限
・1回の事案について
→ 減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければなりません
※例えば、平均賃金が1万円なら、1回の事案で減給できるのは5千円までです
・一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額について
→当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければなりません
※例えば、当該賃金支払期の賃金総額が25万円なら、減給の総額は2万5千円以内です。5件の事案が発生した場合は、5千円×5回=2万5千円まで減給できます。
※事案が6件になった場合は、2万5千円を超えた部分は次期賃金支払期に延ばさなければなりません。
(昭23.9.20基収1789号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
「一賃金支払期における賃金の総額」は、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいいます。
欠勤や遅刻等で賃金総額がカットされたときは、カットされた賃金総額を基礎として10分の1を計算します。
(昭25.9.8基収1338号)
②【R2年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。

【解答】
②【R2年出題】 ×
遅刻・早退・欠勤で労働の提供がなかった時間分の賃金を差し引くことは、減給制裁に当たりませんので、労働基準法第91条による制限は受けません。
※ただし、遅刻早退の時間分の賃金額を超える減給は制裁とみなされ、第91条の制限を受けます。
(昭63.3.14基発150号)
③【R3年出題】
就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めても、減給制裁に当たらないとされています。
(昭26.3.31基収938号)
④【H28年出題】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。

【解答】
④【H28年出題】 ×
出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、出勤停止の当然の結果となり、減給制裁に当たりません。
(昭23.7.3基収2177号)
⑤【H30年出題】
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
「制裁事由発生日(行為時)」ではなく、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
(昭30.7.19基収5875号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-254 5.7
必要記載事項の一部を記載しない就業規則の効力【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
就業規則の作成について条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 (1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (2)賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (4)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 (5) 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 (6) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 (7) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (8) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (9) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (10) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 (11) 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
(1)から(3)は必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」、(4)から(11)は定めをする場合は記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「退職手当」に関する事項は相対的必要記載事項です。退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項を、就業規則に規定しておかなければなりません。
不支給事由又は減額事由は、退職手当の決定、計算の方法に該当しますので、就業規則に記載する必要があります。
(H12.3.31基発168号)
②【H30年出題】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「制裁の定め」は相対的必要記載事項です。制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければなりません。制裁を定めをしない場合は、記載義務はありませんので、その旨を記載する義務もありません。
(第89条第9号)
③【H26年出題】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。

【解答】
③【H26年出題】 ×
絶対的必要記載事項の一部、又は、相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則も、その効力発生について他の要件を具備する限り有効とされています。「無効となる」は誤りです。
ただし、第89条違反の責を免れません。
(H11.3.31基発168号)
④【R3年出題】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることができるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効ですが、同条違反の責任は「免れない」とされています。
(H11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
条文の読み方をお話します
R6-253 5.6
条文の読み方「及び」と「並びに」【社労士受験対策】
「及び」、「並びに」どちらも「and」です。
使い分けをみていきましょう。
★「及び」の例
労働基準法第2条第2項
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
★「及び」「並びに」の例
労働基準法第12条第4項
賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
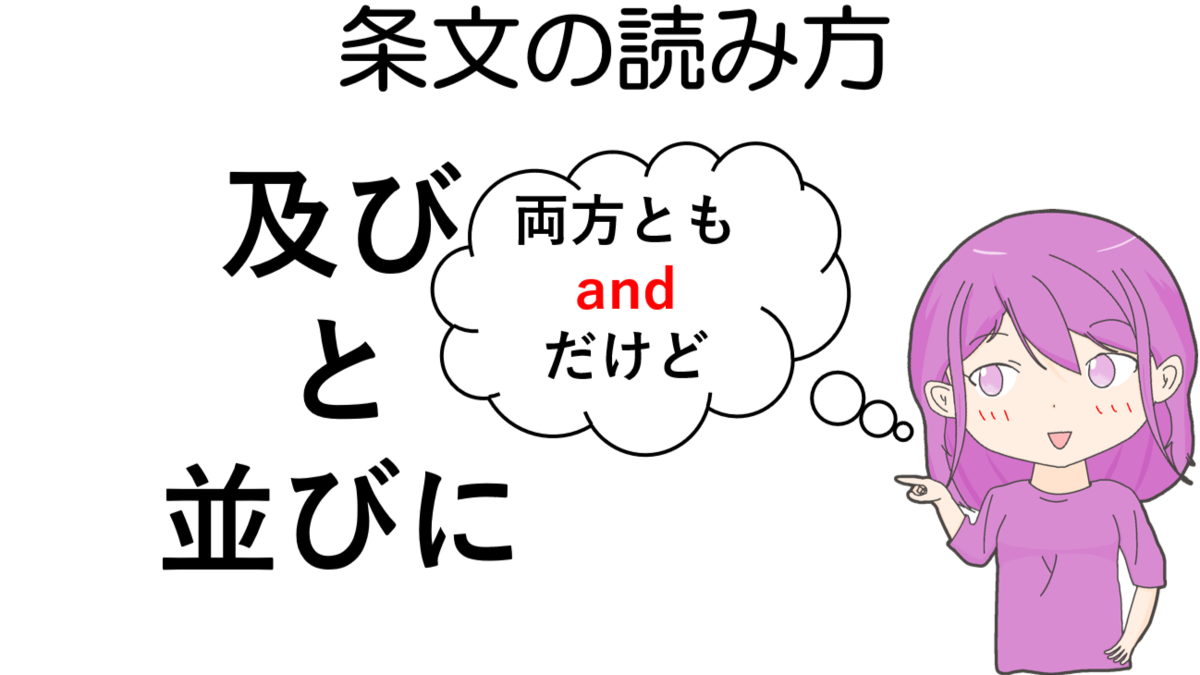
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-252 5.5
休業手当の支払義務【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「休業手当」の条文を読んでみましょう。
第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
使用者が本条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「休日」については、休業手当を支給する義務はありません。
(S24.3.22基収4077号)
②【R3年出題】
就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、更に当該休職者に対しその休職期間中の賃金は月額の2分の1を支給する旨規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限りにおいては、使用者に本条の休業手当の支払義務は生じない。

【解答】
②【R3年出題】 ×
就業規則に、問題文のような規則を定めていても、定めていなくても、使用者の責に帰すべき事由による休業に対しては、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
「会社の業務の都合」が使用者の責に帰すべき事由に該当する場合は、賃金規則に平均賃金の100分の60に満たない額の賃金を支給することを規定しても無効である、とされています。
(S23.7.12基発1031号)
③【R3年出題】
親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は本条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
問題文の事由は「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。資材資金の不足による休業は、使用者の責任です。
(S12.6.11基収1998号)
④【R3年出題】
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。

【解答】
④【R3年出題】 〇
新規学卒者の採用内定については、一般的には、企業の例年の入社時期を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられます。
そのような場合に、企業の都合で就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間については、休業手当を支給すべきものと解されています。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-251 5.4
老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権を得た場合の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額を除いた額とする。)の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
★ 65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金は併給できます。
ただし、老齢厚生年金は全額支給されますが、遺族厚生年金は「老齢厚生年金の額に相当する部分」の支給が停止されます。
■ 遺族厚生年金 > 老齢厚生年金の場合
遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額部分が支給されます。
老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
|
| 支給される |
支給される |
| 支給停止 老齢厚生年金の額に相当する部分 |
■ 遺族厚生年金 ≦ 老齢厚生年金の場合
遺族厚生年金は、全額支給停止されます。
老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
支給される |
|
|
| 支給停止
|
★ 遺族厚生年金と65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は併給できません。どちらかを選択することになります。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額よりも高い場合は、遺族厚生年金は、老齢厚生年金との差額部分が支給されます。
(第64条の2)
②【R3年出題】
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

【解答】
②【R3年出題】 〇
ポイント!
 「繰上げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求しなければなりません。
「繰上げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上げ請求しなければなりません。
「繰下げ」は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらか一方でも可能です。
 繰下げ待機中の68歳で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遡って65歳に達した月の翌月から老齢厚生年金を受給することができます。ただし、繰下げしませんので増額されません。
繰下げ待機中の68歳で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遡って65歳に達した月の翌月から老齢厚生年金を受給することができます。ただし、繰下げしませんので増額されません。
なお、老齢厚生年金の繰下げの申出をすることもできます。その場合の増額率は遺族厚生年金の受給権を取得した時点で計算され、遺族厚生年金の受給権が発生した月の翌月から支給されます。
 老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができます。
老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができます。
(第44条の3、第64条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-250 5.3
65歳以上の配偶者の遺族厚生年金の額【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日は遺族厚生年金の額の算定方法をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第60条第1項、附則第17条の2 ① 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、(1)に定める額とする。 (1) 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額の4分の3に相当する額。ただし、短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 (2) 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき (1)に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ (1)に定める額に3分の2を乗じて得た額 ロ 遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額を除いた額とする。)に2分の1を乗じて得た額 |
(1)遺族厚生年金の額の原則の算出方法
死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額 × 4分の3
(2)老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の配偶者の場合
次のうち、どちらか高い方の額になります。
・(1)の計算方法による額
又は
・「(1)の額×3分の2」+「本人の老齢厚生年金の額×2分の1」
★具体的に計算しましょう。
例えば、夫が死亡し、65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する妻が遺族厚生年金を受ける場合で、死亡した夫の老齢厚生年金が80万円、妻の老齢厚生年金が50万円の場合の遺族厚生年金の額は①か②のどちらか高い方になります。
①死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額 × 4分の3
80万円 × 4分の3 = 60万円
②「①の額×3分の2」+「本人の老齢厚生年金の額×2分の1」
「60万円×3分の2」+「50万円×2分の1」= 65万円
遺族厚生年金の額は、高い方の②65万円になります。
※なお、遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①の額になります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
遺族厚生年金の額には、最低保障額は設定されていません。
(第60条第1項)
②【R3年出題】
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

【解答】
②【R3年出題】 ×
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)に支給される遺族厚生年金の額は、次のうちいずれか高い方です。
・ 死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額(Aとします)
・ 「Aの額に3分の2を乗じて得た額」と「配偶者の老齢厚生年金の額(加給年金額を除いた額とする。)に2分の1を乗じて得た額」を合算した額
(第60条第1項第2号、附則第17条の2第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-249 5.2
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第23条の2 (育児休業等を終了した際の改定) ① 実施機関は、育児・介護休業法に規定する育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において子であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 ② 改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 ③ 第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者について、①の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。 |
《例えば、5月10日に育児休業等を終了し、3歳未満の子を養育している場合〉
★育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(5月・6月・7月)の報酬の総額をその期間の月数で除して得た額(平均額)を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。
★3月間のうち、報酬支払基礎日数が17日未満の月があるときは、その月は除いて平均額を出します。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用されている事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
育児休業等を終了した際の改定も産前産後休業を終了した際の改定も、報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月は除いて報酬月額を計算します。
(第23条の2第1項、第23条の3第1項)
②【R1年出題】
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間に受けた報酬の総額」で算定します。
4月20日に育児休業から復帰した場合は、「4月10日に支払った給与」、「5月10日に支払った給与」、「6月10日に支払った給与」の平均で判断します。なお、報酬支払基礎日数が17日未満の月は除外して平均します。
4月 | 5月 | 6月 |
育児休業等終了日の翌日(4月20日)が属する月 |
|
|
育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間 | ||
(第23条の2第1項)
③【H29年出題】
平成28年5月31日に育児休業を終えて同年6月1日に職場復帰した3歳に満たない子を養育する被保険者が、育児休業等終了時改定に該当した場合、その者の標準報酬月額は同年9月から改定される。また、当該被保険者を使用する事業主は、当該被保険者に対して同年10月に支給する報酬から改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除することができる。

【解答】
③【H29年出題】 〇
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| 育児休業等終了日の翌日(6月1日)が属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月 |
| 育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間 | 改定 | ||
5月31日に育児休業を終了し、6月1日に職場復帰した場合、育児休業等終了日の翌日(6月1日)が属する月以後3月間(6月・7月・8月)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。
標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日(6月1日)から起算して2月を経過した日の属する月の翌月(9月)から改定されます。
事業主は、「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料」を報酬から控除できます。改定された9月の保険料は、10月に支給する報酬から控除することができます。
(第23条の2第2項、第84条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-248 5.1
第3号被保険者となる要件【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「第3号被保険者」について条文を読んでみましょう。
第7条第1項第3号 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
則第1条の3 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 (1) 外国において留学をする学生 (2) 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (4) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの (5) 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
第3号被保険者のポイントは?
■第2号被保険者に扶養される配偶者
■20歳以上60歳未満
■日本国内に住所を有する(原則)
※外国において留学する学生、外国に赴任する第2号被保険者に同行する者などは、国内居住要件の例外が認められます
なお、日本国籍を有しない者で、「医療滞在」や「観光等を目的とするロングステイ」の場合は、第1号被保険者・第3号被保険者から除外されます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
★国籍要件について
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、全て、「国籍要件」はありません。
★年齢要件(20歳以上60歳未満)について
第1号被保険者、第3号被保険者は年齢要件があります。
第2号被保険者は年齢要件はありません。
★国内居住要件について
第1号被保険者は、「国内居住要件」があります。
第2号被保険者は、「国内居住要件」はありません。
第3号被保険者は、原則は「国内居住要件」がありますが、例外もあります。
(第7条第1項)
②【H17年出題】※改正による修正あり
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。

【解答】
②【H17年出題】 ×
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でも、要件を満たせば第3号被保険者となります。
なお、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は第1号被保険者からは除外されます。
(第7条第1項)
③【R3年出題】
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
第3号被保険者は、国内居住が原則ですが、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、海外特例により第3号被保険者として認定されます。第3号被保険者の資格は喪失しません。
(第7条第1項、則第1条の3)
④【R3年出題】
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

【解答】
④【R3年出題】 〇
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する場合は、海外特例により、第3号被保険者となることができます。
(第7条第1項、則第1条の3第3号)
⑤【H27年出題】
第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
「日本年金機構」が行うの部分がポイントです。
(令第4条)
⑥【R3年出題】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
 「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者ではないことがポイントです!
「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者ではないことがポイントです!
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者です。
ただし、「65歳以上」で「老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権」を有する場合は、第2号被保険者となりません。
問題の「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は第2号被保険者ではありません。
 第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。問題の配偶者は第2号被保険者の配偶者ではないので、第3号被保険者になりません。
第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。問題の配偶者は第2号被保険者の配偶者ではないので、第3号被保険者になりません。
(第7条、附則第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
ご質問に答えます 国民年金法
R6-247 4.30
1号から除外される厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者とは?【社労士受験対策】
国民年金の第1号被保険者から除外される「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」についてご質問がありました。
まず、第1号被保険者の定義を条文で読んでみましょう。
第7条第1項第1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。) |
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、第1号被保険者から除外されます。
 20歳以上60歳未満で、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とは、どんな人でしょう?
20歳以上60歳未満で、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とは、どんな人でしょう?
例えば、昭和15年4月1日以前生まれで一定の要件を満たした女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、「55歳から59歳まで」の間でした。
早ければ55歳から特別支給の老齢厚生年金を受けることができました。その場合、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる」者になりますので、第1号被保険者から除外されます。
他に、坑内員、船員も一定要件を満たせば、早ければ55歳から老齢厚生年金を受けることができました。
注意しましょう
「受給資格期間を満たしている者」ではありませんので、注意してください。
例えば、現在、55歳の人で保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上ある場合は、受給資格期間を満たしています。しかし、実際に老齢厚生年金を「受けることはできない」ので、第1号被保険者からは除外されません。
 「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は国民年金に「任意加入」できます。
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は国民年金に「任意加入」できます。
条文を読んでみましょう。
附則第5条第1項 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
第1号被保険者から除外される「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、(1)の規定で国民年金に任意加入できます。
先ほどの例の昭和15年4月1日以前生まれの女性で、「55歳から59歳まで」の間に特別支給の老齢厚生年金を受けることができたとしても、65歳からの老齢基礎年金は満額支給されるとは限りません。
老齢基礎年金を満額にしたい又は満額に近づけたい場合は、国民年金に任意加入して保険料を納付することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
条文の読み方をお話します
R6-246 4.29
条文の読み方「又は」と「若しくは」【社労士受験対策】
「又は」と「若しくは」の使い方をお話します。
どちらも英語ではorです。
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
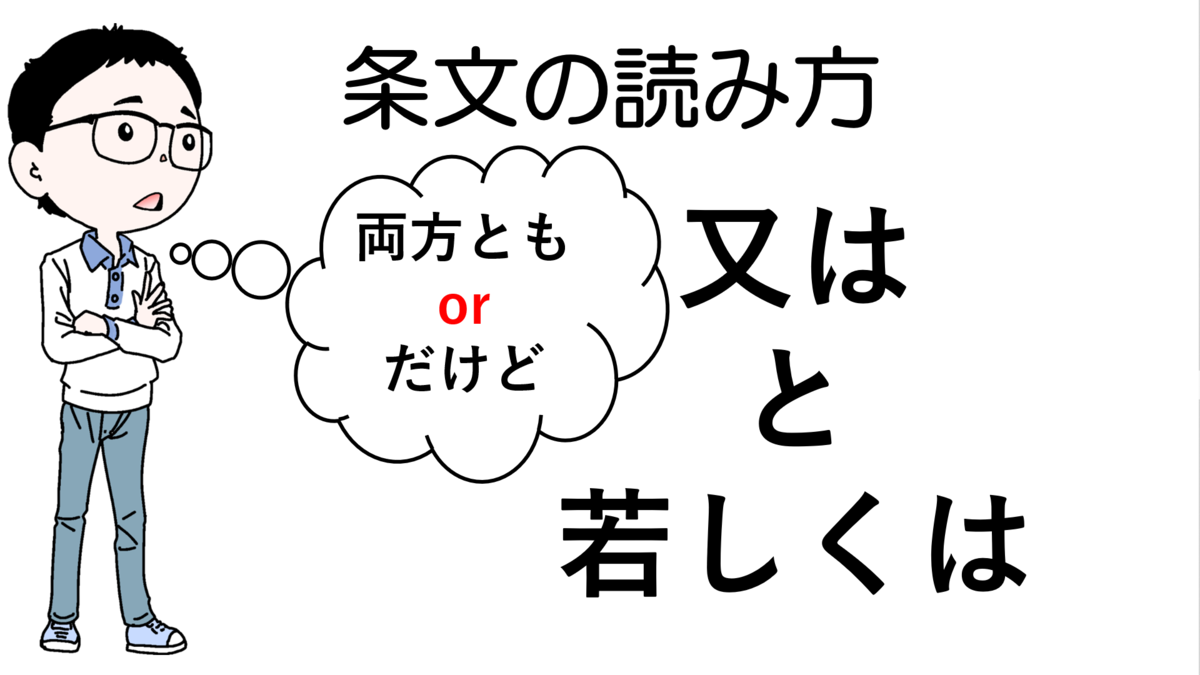
YouTubeで解説しています。
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-245 4.28
<指定の更新>保険医療機関又は保険薬局【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
保険医療機関・保険薬局となるには、厚生労働大臣の指定を受けなければなりませんが、指定の効力には有効期間があります。
今日は、指定の更新などをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 ② 保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなす。
第79条 (保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消) ① 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 ② 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 |
保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年を経過すると消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

【解答】
①【H29年出題】 〇
ポイント!
・保険医療機関又は保険薬局の指定 → 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が指定します。
・指定の効力 → 指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失います。
(第68条第1項)
②【H28年出題】
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
保険医療機関・保険薬局の指定の効力は6年ですので、指定の更新の手続が必要です。
しかし、保険医個人が開設する診療所の場合は、更新手続きは不要です。そのため、更新しない場合は、指定の効力を失う前に、その旨の申出が必要です。
・有効期間の更新をしない場合 → その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、申出が必要です。
・上記の期間内に申出がない場合 → 指定の申請があったものとみなされ、更新申請をしなくても、有効期間が更新されます。
なお、この規定は、「病院及び病床を有する診療所」には適用されません。
問題文は、「病床の有無に関わらず」が誤りです。病床を有する診療所には適用されません。
(第68条第2項)
③【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退、保険医又は保険薬剤師の登録の抹消、どちらも予告期間は「14日以上」ではなく「1月以上」です。
なお、保険医、保険薬剤師について、条文を読んでみましょう。
第64条 (保険医又は保険薬剤師) 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。 第71条第1項 (保険医又は保険薬剤師の登録) 保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-244 4.27
保険医療機関又は保険薬局の指定【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
保険医療機関とは、被保険者証を持って行けば、誰でも、健康保険を使って診察等を受けることができる病院、診療所のことです。
では、条文を読んでみましょう。
第63条第3項 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとする。 (1)厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。) (2)特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの (3)健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 |
健康保険の療養の給付を受けることができる医療機関は次の3つです。
(1) 保険医療機関又は保険薬局
(2) 保険者が指定する病院、診療所、薬局
(事業主が開設した病院等)
(3) 健康保険組合が開設した病院、診療所、薬局
(健康保険組合が開設した病院等)
今日は(1)保険医療機関又は保険薬局についてみていきます。
では、次に保険医療機関又は保険薬局の指定について条文を読んでみましょう。
第65条 ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 ② その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。 ③ 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしないことができる。 ※1号から6号は省略します。 ④ 厚生労働大臣は、病院又は診療所について申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、指定を行うことができる。 ※1号から4号は省略します |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険組合が開設した病院でも、保険医療機関として指定を受けた場合は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行わなければなりません。
(S32.9.2保険発第123号)
②【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
②【H29年出題】 〇
※地方社会保険医療協議会に諮問するもの
・保険医療機関、保険薬局の指定
・保険医療機関、保険薬局の指定の取消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取消し
ちなみに・・・
★保険医療機関・保険薬局は「指定」ですが、保険医・保険薬剤師は「登録」という用語を使っています。
③【R1年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合、第65条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する場合は、指定をしないことができます。
問題文は、第3号に該当しますので、厚生労働大臣は指定をしないことができます。
(第65条第3項第3号)
④【R3年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。

【解答】
④【R3年出題】 〇
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法だけでなく、他の医療保険各法、高齢者医療確保法に係る療養も担当することになっています。
(第70条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-243 4.26
法人の役員である被保険者等の保険給付の特例【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険法の目的条文を読んでみましょう。
第1条 (目的) 健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
健康保険の保険給付は、労災保険法の業務災害以外の傷病等に対して行われます。
例えば、健康保険の被保険者が副業として行う請負業務中に負傷したとしても、「請負」は労働関係ではありませんので、業務中といえども労災保険の保険給付は受けられません。
請負業務中の負傷など労災保険の業務災害に当たらない業務上の負傷等は、原則として健康保険の保険給付の対象になります。
(平25.8.14事務連絡)
ただし、「役員」の業務上の負傷等については特例が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第53条の2(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例) 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
則第52条の2 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 |
(原則)
被保険者、被扶養者が法人の役員である場合、その法人の役員としての業務に起因する傷病等は、原則として健康保険の保険給付の対象外となります。
使用者側の責めに帰すべきものですので、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられるからです。
(特例)
「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等で、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険の保険給付の対象となります。
(平25.8.14事務連絡)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
労災保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付の対象になります。
(法第1条、平25.8.14事務連絡)
②【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
②【H30年出題】 〇
被保険者、被扶養者が法人の役員である場合、その法人の役員としての業務に起因する傷病等は、健康保険の保険給付の対象外となるのが原則です。
ただし、5人未満の適用事業所の法人の代表者は、業務遂行の過程で業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があります。対象になる業務は、従業員が従事する業務と同一であると認められるものです。
(第53条の2、則第52条の2、平25.8.14事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-242 4.25
保険関係の消滅と確定保険料申告書【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険の保険関係の消滅について条文を読んでみましょう。
第5条 (保険関係の消滅) 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
事業が廃止又は終了した場合は、その日の翌日に、保険関係は当然に消滅します。
なお、廃止は「継続事業」、終了は「有期事業」に用いられます。
第19条第1項、2項(確定保険料申告書) ① 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から 40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。 ② 有期事業については、その事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。 |
保険関係が消滅した場合は確定保険料申告書を提出し、労働保険料の精算を行います。
<確定保険料申告書提出期限>
★継続事業、一括有期事業の場合
通常 (保険年度ごとに精算します)
→ 次の保険年度の6月1日から40日以内
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合
→ 保険関係が消滅した日から50日以内
★有期事業の場合
→ 保険関係が消滅した日から50日以内
ちなみに、「保険年度の6月1日」も「消滅した日」も午前0時から始まりますので、どちらも当日起算です。
・継続事業、一括有期事業が保険年度の中途に保険関係が消滅した場合
4月1日 3月31日
| 廃止 | 消滅 |
|
|
| 消滅した日から50日以内 |
|
・有期事業の保険関係が消滅した場合
開始 |
| 終了 | 消滅 |
消滅した日から50日以内
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。

【解答】
①【H29年出題】(労災) ×
事業が廃止された場合は、廃止の日の翌日に、自動的に保険関係は消滅します。
「保険関係廃止届」なるものはありませんし、届出によって消滅するものでもありません。
(第5条)
②【R3年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。

【解答】
②【R3年出題】(労災) 〇
暫定任意適用事業も適用事業と同じく、事業が廃止された場合は、廃止の日の翌日に、自動的に保険関係は消滅します。
ただし、暫定任意適用事業は、厚生労働大臣の認可を受けて保険関係を消滅させることもできます。その場合は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、保険関係が消滅します。
(整備法第8条第1項)
③【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

【解答】
③【R5年出題】(雇用) ×
継続事業の保険関係が保険年度の中途に消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
令和4年10月31日に事業を廃止した場合、保険関係の消滅は同年11月1日です。
確定保険料申告書の提出期限は、11月1日から起算して50日以内ですので、「12月20日」までとなります。
(第19条第1項)
④【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

【解答】
④【H26年出題】(雇用) ×
第19条第3項で以下のように定められています。
| 事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときはその不足額を、確定保険料申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。 |
問題文の場合は、不足額は、確定保険料申告書に添えて、納付しなければなりません。期限は、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)です。
(第19条第3項)
⑤【H26年出題】(雇用)
請負金額50億円、事業期間5年の建設事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

【解答】
⑤【H26年出題】(雇用) ×
有期事業は事業が終了した日の翌日に保険関係が消滅します。
有期事業は、保険年度ごとではなく、事業が開始したときに概算保険料を申告・納付し、事業が終了したときに確定精算を行います。
有期事業の確定保険料の申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
(第19条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-241 4.24
労働保険の成立手続(保険関係成立届)【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険の成立と届出について条文を読んでみましょう。
第3条 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。
第4条 雇用保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
第4条の2第1項 (保険関係の成立の届出等) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 |
労災保険・雇用保険の保険関係は、その事業が開始された日に成立します。
労働保険の適用事業になった場合は、「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。(則第4条第2項)
★「当日起算」、「翌日起算」に注意しましょう
起算日は、原則として「翌日」です。
保険関係成立届の提出期限は、「その成立した日から10日以内」ですが、起算日は「翌日」です。労働保険が成立した日は、午前0時から始まらないからです。
ちなみに、継続事業の概算保険料の申告期限は、「保険年度の6月1日から40日以内」ですが、起算日は「当日」です。保険年度の6月1日は午前0時から始まるからです。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【H27年出題】(労災) 〇
保険関係成立届の提出期限は、「保険関係が成立した日の翌日から起算」して10日以内です。「その成立した日から10日以内」は翌日から起算することがポイントです。
(第4条の2第1項)
②【R1年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

【解答】
②【R1年出題】(労災) 〇
届け出なければならない事項は、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項です。
有期事業については、事業の予定される期間も届出の事項に含まれます。
(第4条の2第1項、則第4条第1項第5号)
③【H25年出題】(労災)
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

【解答】
③【H25年出題】(労災) ×
労働者を使用した場合は、当然に労災保険・雇用保険の適用事業となります。
労働保険の保険関係は、保険関係成立届を提出することによって成立するのではなく、事業が開始された日(適用事業になった日)に、自動的に成立します。
(第3条、第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-240 4.23
特例高年齢被保険者と高年齢求職者給付金【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「高年齢被保険者」について条文を読んでみましょう。
第37条の2第1項 (高年齢被保険者) 65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢被保険者」という。)が失業した場合には、高年齢求職者給付金を支給する。 |
65歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」といいます。
高年齢被保険者が失業した場合は、高年齢求職者給付金が支給されます。
「特例高年齢被保険者」について条文を読んでみましょう。
第3条の5第1項、則第65条の7 (高年齢被保険者の特例) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。 (1) 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 (2) 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 (3) 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。 |
特例高年齢被保険者とは?
・2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者
・2つの事業所の労働時間を合計し、所定労働時間が20時間以上であること
※1つの事業所の所定労働時間は5時間以上20時間未満であること
・特例高年齢被保険者となるには、本人からの「申出」が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者に係る適用事業は、異なる事業主であることが必要です。
事業所が別であっても同一の事業主(同じ会社)であるときは、特例高年齢被保険者となることができません。
(第37条の5第1項、行政手引1070)
②【R4年出題】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
第37条の5第2項で、「特例高年齢被保険者となった者は、要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。」と定められています。
1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、申出が必要です。
(第37条の5第2項)
③【R4年出題】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。

【解答】
③【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、『当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ』で算定されます。
(第37条の6第2項)
④【R4年出題】
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。

【解答】
④【R4年出題】 〇
特例高年齢被保険者には、賃金日額の下限の規定は適用されません。
(第37条の6第2項、行政手引2140)
⑤【R4年出題】
特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
特例高年齢被保険者にも、離職理由による給付制限は適用されます。
ただし、同じ日に2の事業所を離職した場合で、その離職理由が異なっている場合は、給付制限の取扱いは、離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して支給されます。
問題文の場合は、「倒産により離職」に一本化されますので、離職理由による給付制限は行われません。
(行政手引2270)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
条文の読み方をお話します
R6-239 4.22
社労士受験のための 条文の読み方「その他」と「その他の」の違い
条文の読み方をお話します。
今回は、「その他」と「その他の」の違いです。
(例)
★使用者の定義
事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
↓
「その他」の前後の言葉が、並んでいる関係です。
★明示すべき労働条件
賃金、労働時間その他の労働条件
↓
「その他の」の前の言葉が、「その他の」の後の言葉の中に含まれています。
労働条件の中に、賃金、労働時間が含まれています。
YouTubeでお話しました。
良かったらご覧ください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-238 4.21
社労士受験のための 業務災害の認定の具体例
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
「業務災害」とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」のことです。
業務上と認められるには、
①業務遂行性が認められること(労働者が労働関係にあること)
↓
②業務起因性が成立していること(業務と傷病との間に因果関係があること)
が必要です。
「業務上」と認められるか否かの具体例をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
道路清掃工事の日雇い労働者が、正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷と認められる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
★ポイント! 休憩時間中の災害について
休憩時間中の災害が、私的行為によって発生した場合は、業務起因性は認められませんので、業務災害になりません。
しかし、就業中なら業務行為に含まれてるような行為(例えば、トイレなどの生理的行為など)は、事業主の支配下で「業務に付随する行為」として取り扱われます。
問題文の場合は、道路が作業場で、しかも、常に自動車などによる交通危険にさらされている場所で休憩せざるを得なかった事情にありました。このような事情のため生じた負傷は、業務上の負傷となります。
(昭25.6.8基災収1252号)
②【H26年出題】
明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

【解答】
②【H26年出題】 ×
★ポイント! 出張中の災害について
出張中は、全般的に業務遂行性があり、その間の災害には業務起因性が認められ、一般的に業務上と認められます。ただし、積極的な私的行為や恣意的行為で自ら災害を発生させた場合などは業務上と認められません。
出張については、自宅を出てから自宅に帰るまでが出張途上にあると考えられます。問題文のように、出張の順路の一部が、通常の通勤経路と重複していたとしても、出張業務遂行中とみられます。
「通勤災害」ではなく、「業務災害」となります。
(昭34.7.15基収第2980号)
③【H27年出題】
会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。

【解答】
③【H27年出題】 〇
★ポイント! 運動会、宴会などの行事に参加中の災害について
全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いとされるような会社主催の行事に参加する場合等は業務となります。
参加が推奨されているが任意である社内の親睦野球大会での負傷は、業務上の負傷に該当しません。
(平成18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-237 4.20
社労士受験のための
(定義)労働災害・労働者・事業者・化学物質・作業環境測定
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 労働災害 → 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 (2) 労働者 → 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 (3) 事業者 → 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 (4) 化学物質 → 元素及び化合物をいう。 (5) 作業環境測定 → 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
労働災害とは、労働者の業務上の災害のことです。
そのため、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではありません。
(第2条第1号)
②【R2年出題】
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

【解答】
②【R2年出題】 〇
労働安全衛生法の労働者は、労働基準法の労働者と同じです。「同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者」、「家事使用人」は労働者に該当しませんので、労働安全衛生法は適用されません。
(昭47.9.18発基第91号)
③【H26年出題】
労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

【解答】
③【H26年出題】 ×
問題文は労働基準法の「使用者」の定義です。労働安全衛生法の「事業者」と労働基準法の「使用者」は違いますので注意しましょう。
労働安全衛生法の「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいいます。法人の場合は法人そのもの、個人企業の場合は事業主個人を指します。
(第2条第3号、昭47.9.18発基第91号)
④【H28年出題】
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

【解答】
④【H28年出題】 〇
労働安全衛生法の「事業者」は、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。労働基準法第10条の「使用者」とはその概念が異なります。
「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)と同じです。
(第2条第2号、第3号、昭47.9.18発基第91号)
⑤【H30年選択式】
労働安全衛生法で定義される作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行う< A >、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

【解答】
⑤【H30年選択式】
(A) デザイン
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-236 4.19
社労士受験のための
割増賃金②割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
例えば、時間外労働をさせた場合、「通常の労働時間」の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
通常の労働時間の賃金の計算式は、「月によって定められた賃金」については、「その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」と定められています。
詳しくはこちらの記事をどうぞ
なお、基本給と手当が支払われている場合は、手当も含めて計算します。
しかし、割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当が定められていますので、確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第37条第5項 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
則第21条 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 (1) 別居手当 (2) 子女教育手当 (3) 住宅手当 (4) 臨時に支払われた賃金 (5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当は、頭文字をとって「か・つ・べ・し・ん・いち・の住宅」です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】
①【H26年出題】 〇
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づくものですので、割増賃金の基礎となる賃金から除外されます。
(則第21条)
②【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
家族手当も、通勤手当と同じく、労働とは直接関係のない個人的事情に基づくものですので、割増賃金の基礎となる賃金から除外されます。
しかし、「家族手当」といっても、扶養家族数に関係なく一律に支給される手当や、独身者に対しても一定額が支払われている場合は、「家族手当」とはみなされません。
そのため、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含めなければなりません。
(S23.11.5基発231号)
③【H19年出題】
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
「住宅手当」は、家族手当、通勤手当と同じく、労働とは直接関係のない個人的事情に基づくものですので、割増賃金の基礎となる賃金から除外されます。
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、「住宅に要する費用」に応じて算定される手当をいいます。
問題文のように、「住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当」や、「全員に一律に定額で支給される手当」は、除外される「住宅手当に該当しません」ので、割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しなければなりません。
(則第21条、H11.3.31基発170号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-235 4.18
社労士受験のための 割増賃金①通常の労働時間1時間当たりの賃金額
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第37条第1項、4項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) ① 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
割増賃金の率を確認しましょう。
・ 時間外に労働させた場合 →2割5分以上
1か月60時間を超えた場合 →超えた分は5割以上
・ 休日に労働させた場合 → 3割5分以上
・ 深夜に労働させた場合 → 2割5分以上
例えば、時間外労働を5時間させた場合は、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」×1.25×5時間で計算します。
「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」の計算についてみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数:240日
計算の基礎となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間
(A)300,000円÷(21×7)
(B)300,000円÷(21×8)
(C)300,000円÷(30÷7×40)
(D)300,000円÷(240×7÷12)
(E)300,000円÷(365÷7×40÷12)

【解答】
(D)300,000円÷(240×7÷12)
通常の労働時間の賃金の計算式は、「月給制(月によって定められた賃金)」の場合は、
「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」と定められています。 (則第19条第1項第4号)
原則は、「月給÷その月の所定労働時間数」ですが、月によって所定労働時間数が異なる場合には、「月給÷1年間における1月平均所定労働時間数」で計算します。
問題文は、月によって所定労働時間数が異なりますので、月給を、「1年間における 1月平均所定労働時間数」で除します。
「1年間における1月平均所定労働時間数」は、年間の所定労働時間数のトータル(年間所定労働日数×1日の所定労働時間数)を1年間の月数(12か月)で除して計算できます。
問題文では、年間所定労働日数は240日、1日の所定労働時間数は7時間です。(拘束時間8時間から休憩1時間を引いた時間です)
「1年間における1月平均所定労働時間数」の計算式は、240日×7時間÷12か月です。
通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式は、
300,000円÷(240×7÷12)となります。
(則第19条第1項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-234 4.17
社労士受験のための 国民健康保険法 法定給付と任意給付
過去問から学びましょう。
今日は国民健康保険法です。
国民健康保険法の保険給付は、「法定給付」と「任意給付」に分かれています。
また、「法定給付」には、必ず行わなければならない「絶対的必要給付」と、特別な理由がある場合は全部又は一部を行なわないことができる「相対的必要給付」があります。
法定給付 | 絶対的必要給付 |
相対的必要給付 | |
任意給付 |
|
「相対的必要給付」と「任意給付」について条文を読んでみましょう。
第58条第1項、2項 ① 市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 ② 市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。 |
①出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付は、「行うものとする」とされていますが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる「相対的必要給付」です。
②傷病手当金その他の保険給付(出産手当金)は「行うことができる」となっています。行うかどうかや給付の内容は、市町村及び組合が決定できる「任意給付」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「移送費」は法定給付の絶対的必要給付です。
被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給します。
移送費は、必ず行わなければならない「絶対的必要給付」で、給付内容も法令で定められています。
(第54条の4)
②【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる

【解答】
②【H26年出題】 〇
傷病手当金は、条例又は規約の定めるところにより行うことができる「任意給付」です。
(第58条第2項)
③【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
「死亡」に関しては、『「葬祭費の支給又は葬祭の給付」を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。』とされています。
「絶対的必要給付」ではなく、「相対的必要給付」です。
④【R1年出題】
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
④【R1年出題】 〇
出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は、相対的必要給付です。
(第58条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-233 4.16
社労士受験のための 労働契約法 労働者の安全への配慮
過去問から学びましょう。
今日は労働契約法です。
条文を読んでみましょう。
第5条 (労働者の安全への配慮) 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |
第5条の趣旨は、以下の通りです。
通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかになっていないところである。
このため、法第5条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものであること。
(平成24.8.10基発0810第2号より)
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。

【解答】
①【H30年出題】 〇
法第5条の「労働契約に伴い」の内容です。
(平成24.8.10基発0810第2号)
②【H28年出題】
労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を求めているが、その内容は一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。

【解答】
②【H28年出題】〇
「必要な配慮」の内容です。
なお、労働安全衛生法をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されているところであり、これらは当然に遵守されなければならないものであること、とされています。
ちなみに、「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。
(平成24.8.10基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
何から覚えればよいでしょう?
R6-232 4.15
社労士受験のための 勉強の手順をお話します
社労士受験を決意しました!
初めて見るテキストは、「なんだか難しい」と感じますよね。
勉強の手順をお話します。
①テキストを読む
↓
②問題を解く・ポイントとコツをつかむ
↓
③再度テキストを読んで、自分のものにする
がんばりましょう。
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
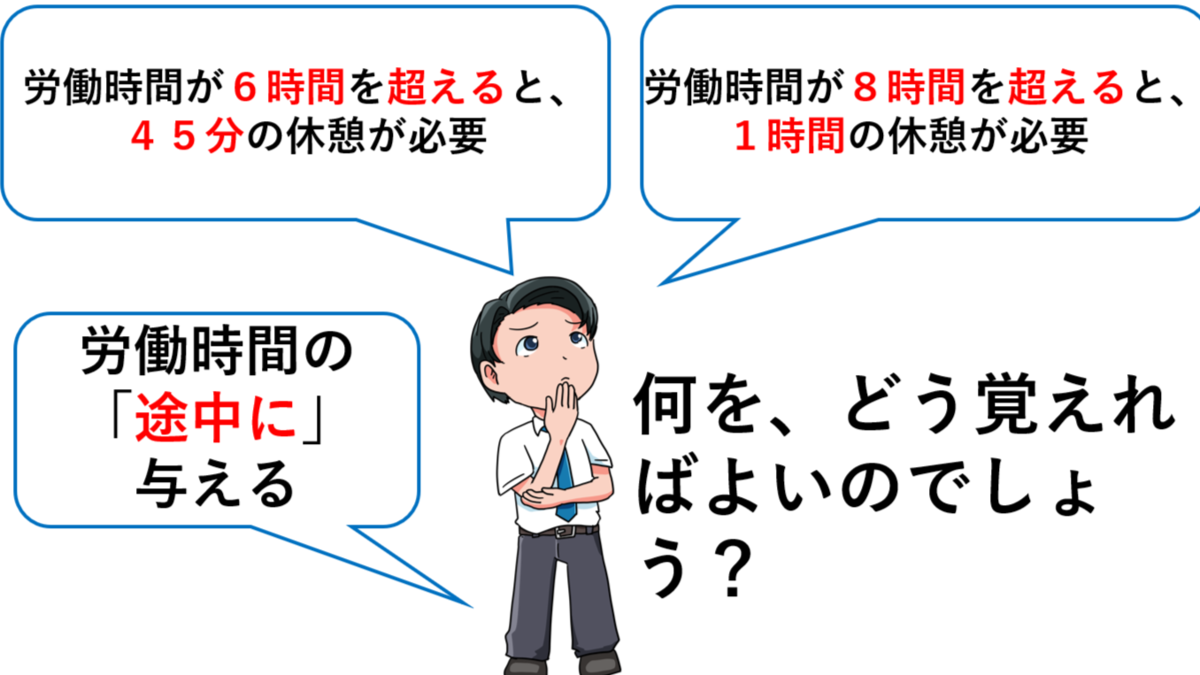
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-231 4.14
社労士受験のための 遺族厚生年金が支給される条件
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の支給要件の条文を読んでみましょう。
第58条第1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、①又は②に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ①被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 ② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 ③ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 ④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
<保険料納付要件>
①か②の場合は、「死亡日の前日の保険料納付要件」が問われます。
・原則
死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間中に、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上あること。
・特例
令和8年4月1日前に死亡した場合(死亡日に65歳未満であること)は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がないこと。(S60法附則第64条第2項)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
20歳未満でも、「厚生年金保険の被保険者」が死亡した場合は、①に該当し、遺族厚生年金の支給条件を満たします。
(第58条第1項第1号)
②【H28年出題】
保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
②【H28年出題】 〇
①「厚生年金保険の被保険者が死亡したとき」の被保険者には、「失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったもの」も含まれます。
(第58条第1項第1号)
③【H28年出題】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
③【H28年出題】 〇
初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後にその傷病により、その初診日から起算して5年以内に死亡した場合は、遺族厚生年金の支給要件を満たします。「初診日」から5年以内です。「喪失日」からと間違えないようにしましょう。
(第58条第1項第2号)
④【H28年出題】※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。なお、設問の者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である。

【解答】
④【H28年出題】 〇
④には、「離婚時みなし被保険者期間を有する者」が含まれます。
国民年金の第1号被保険者期間しか有していない者でも、離婚時みなし被保険者期間を有することで、老齢厚生年金の受給権が発生します。そのような者が死亡した場合、要件を満たせば、一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
(第58条第1項第4号、第78条の11)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-230 4.13
(厚年)任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「任意適用事業所」の認可について条文を読んでみましょう。
第6条第3項、4項 ③ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条(適用除外)に規定する者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
「強制適用事業所」と任意適用事業所を整理しましょう。
個人経営 | 法人 | |||
適用業種 | 非適用業種 | 業種・人数 問わず | ||
5人以上 | 5人未満 | 5人以上 | 5人未満 | |
強制 | 任意 | 任意 | 任意 | 強制 |
なお、令和4年10月から、常時5人以上の従業員を使用する士業の個人事業所(弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業)は、強制適用事業になっています。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「農業、林業、漁業」は、非適用業種ですので、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主は、適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要があります。
(第6条第3項)
②【R1年出題】
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

【解答】
②【R1年出題】 ×
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の青果商は強制適用事業所です。従業員数が4人になったとしても、任意適用事業所の認可があったとみなされ、適用事業所の資格は継続します。任意適用事業所の認可申請を行う必要はありません。
(第7条)
③【H28年出題】
その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主はどれか。
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主
エ 常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主

【解答】
③【H28年出題】
ア 常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主について
「宿泊業、飲食サービス業」は非適用業種です。個人経営の旅館の事業主は、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければなりません。
イ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主について
「貨物積み卸し業」は、適用業種です。常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業所は強制適用事業所ですので、認可は不要です。
ウ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主について
「理容業、美容業」、「娯楽業」は非適用業種です。個人経営の理容業の事業主は、その事業所を適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければなりません。
エ 常時使用している船員が5人から4人に減少した船舶所有者について
「船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶」は厚生年金保険の強制適用事業所です。人数に関係なく強制適用事業所となります。
(法第6条第1項第3号)
オ 常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主について
「教育、学習支援業」は適用業種です。常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業は強制適用事業所ですので、認可は不要です。
適用事業所にするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主は、 アとウです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-229 4.12
申請のあった日以後保険料全額免除期間に算入することができる
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「申請全額免除」の条文を読んでみましょう。
第90条第1項 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の3免除、半額免除期、4分の1免除期間の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 (1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 (2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 (3) 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。 (4) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 |
保険料の全額免除の申請をした場合は、「申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる」という部分に注目してください。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H28年出題】 ×
障害基礎年金の受給権は発生しません。初診日の前日の「保険料納付要件」を満たしていないからです。
★保険料が免除される期間は、「厚生労働大臣が指定する期間」です。
厚生労働大臣が指定する期間は、申請免除の場合、「申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間」となります。
→遡って保険料の免除を申請することができるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間です。
★ただし、保険料全額免除期間に算入されるのは、「申請のあった日以後」です。
★障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」で判断されます。
22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請をして、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となったとしても、「保険料全額免除期間」に算入されるのは、申請のあった日以後です。
初診日の前日の時点では、すべての期間が「滞納」で保険料納付要件を満たしませんので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
(法第30条第1項、第90条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-228 4.11
社労士受験のための 任意加入被保険者と口座振替納付
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
国民年金の任意加入被保険者は、原則として、口座振替で保険料を納付しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
附則第5条第1項、2項(任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①(1)又は(2)に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 |
★ (3)日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは、口座振替の申出をする必要はありません。
★ 特例による任意加入被保険者も、原則として口座振替で保険料を納付しなければなりません。(H6附則第11条第2項)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】※改正による修正あり
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
日本国内に住所を有する者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合は、「口座振替納付を希望する旨の申出」または「口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出」が必要です。
(附則第5条第2項)
②【H28年出題】
日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
日本国内に住所を有する任意加入被保険者は口座振替納付が原則ですが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができます。
(則第2条の2第2号)
③【H21年出題】
国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない

【解答】
③【H21年出題】 ×
日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない者(海外に在住している場合)は、口座振替納付を希望する旨の申出は不要です。
(附則第5条第2項)
④【R2年出題】
60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

【解答】
④【R2年出題】 ×
特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付できないので、誤りです。
なお、任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が、65歳に達した日に、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合は、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされます。
(H16附則第23条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-227 4.10
社労士受験のための 傷病手当金の待期期間
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
傷病手当金の待期期間をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第99条第1項 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。
傷病手当金が支給されない最初の3日間を「待期」といいます。待期の完成は、傷病手当金が支給される条件の一つです。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

【解答】
①【H28年出題】 〇
労務に服することができない状態が3日間連続していれば、待期は完成します。
金 | 土 所定休日 | 日 所定休日 | 月 | 火 |
労務不能 | 労務不能 | 労務不能 | 労務不能 | 労務不能 |
所定休日も通算されますので、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。
(S32.1.31保発2の2)
②【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
資格喪失日前に労務不能の日が3日間継続しているのみでは、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は、4日目以後に支給されるので、3日目に退職した場合は資格喪失の際に、傷病手当金を受けられる状態になっていないからです。
(第104条、S32.1.31保発2の2)
③【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
③【H28年出題】 ×
待期期間は、「労務不能になった日」から起算します。ただし、「業務終了後」に労務不能になった場合は、翌日から起算します。
問題文は、就業中に労務不能になっていますので、「入院した日の翌日」ではなく、「入院した日」が待期期間の起算日となります。
(S5.10.13保発52)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-226 4.9
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主の範囲
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険事務組合は、中小事業主から委託を受けて、事業主の代理人として労働保険事務を処理します。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる「中小事業主」の範囲を確認しましょう。
★労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主
・ 労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主 ・ 団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるもの (第33条第1項則第62条第1項) |
★委託できる事業主の規模
・ 金融業、保険業、不動産業、小売業を主たる事業とする事業主 →常時50人以下の労働者を使用する事業主 ・ 卸売業、サービス業を主たる事業とする事業主 →常時100人以下の労働者を使用する事業主 ・ 上記以外の事業主 →常時300人以下の労働者を使用する事業主 (則第62条第2項) |
※常時使用する労働者の人数は、事業場単位ではなく、「企業単位」で算定します。
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

【解答】
①【R5年出題】(労災) 〇
労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる事業主の地域的範囲の制限はありません。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主だけでなく、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、委託できます。
(第33条)
②【R1年出題】(雇用)
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【解答】
②【R1年出題】(雇用) 〇
金融業を主たる事業とする事業主は、常時使用する労働者が50人以下の場合は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができます。
(則第62条第2項)
委託できる事業主の規模はしっかりおぼえましょう。
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 常時50人以下 |
卸売業、サービス業 | 常時100人以下 |
その他 | 常時300人以下 |
③【R5年出題】(労災)
清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。

【解答】
③【R5年出題】(労災) 〇
使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人、100人、50人を超えることとなった場合でも、常態として300人、100人、50以下ならば、労働保険事務組合に委託することができます。
(参照 労働保険事務組合事務処理手引)
④【R3年出題】(雇用)
労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。

【解答】
④【R3年出題】(雇用) 〇
事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主でも、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、委託することができます。
(則第62条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
私が社会保険労務士になるまでのお話
R6-225 4.8
社会保険労務士との出会いから合格まで
私が社会保険労務士試験に合格するまでのお話です。 平成7年合格ですので、ちょっと(かなり?)前のお話ですが、何かの参考になれば。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
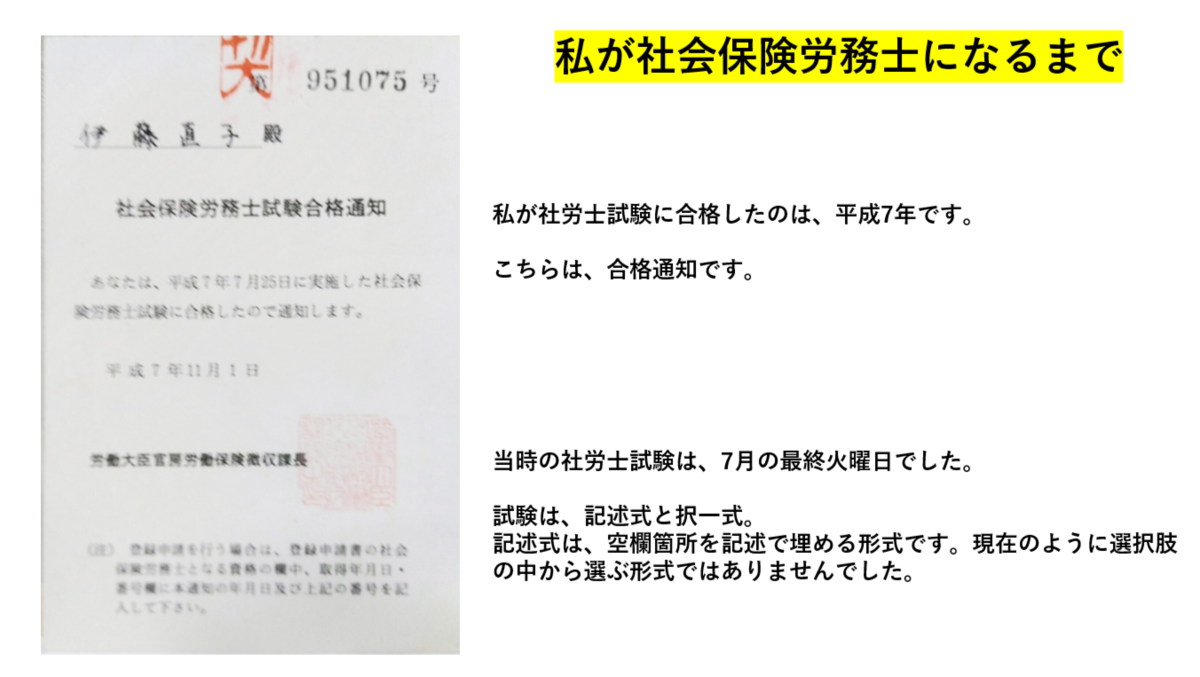
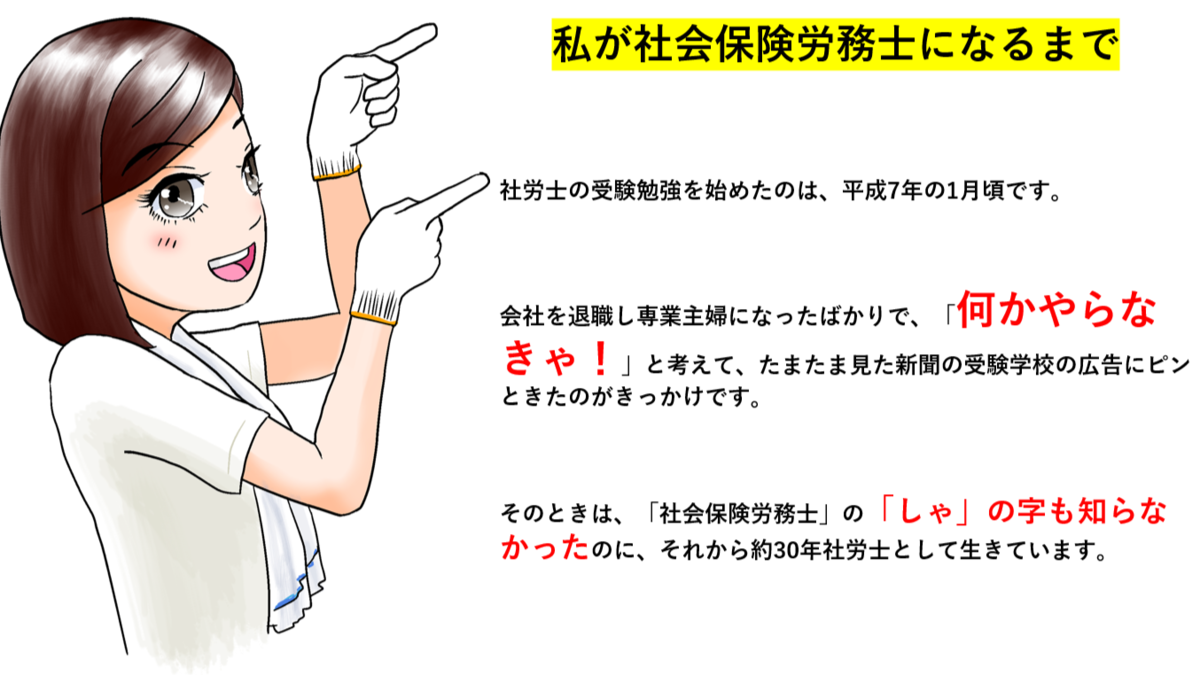
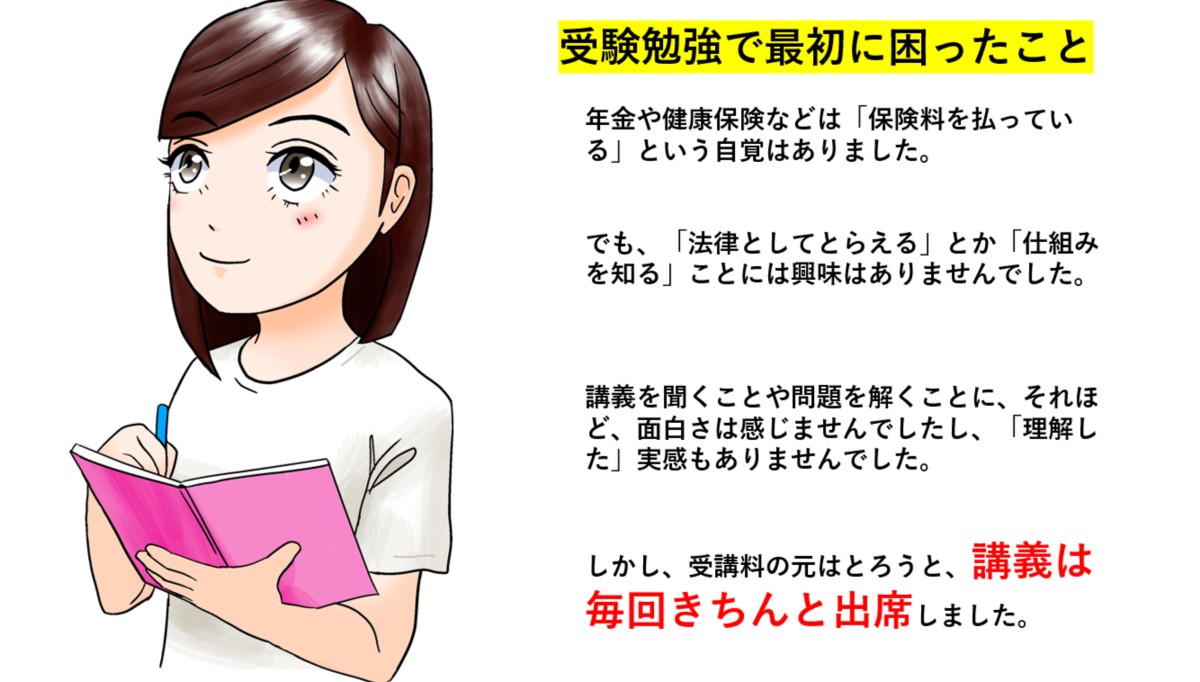
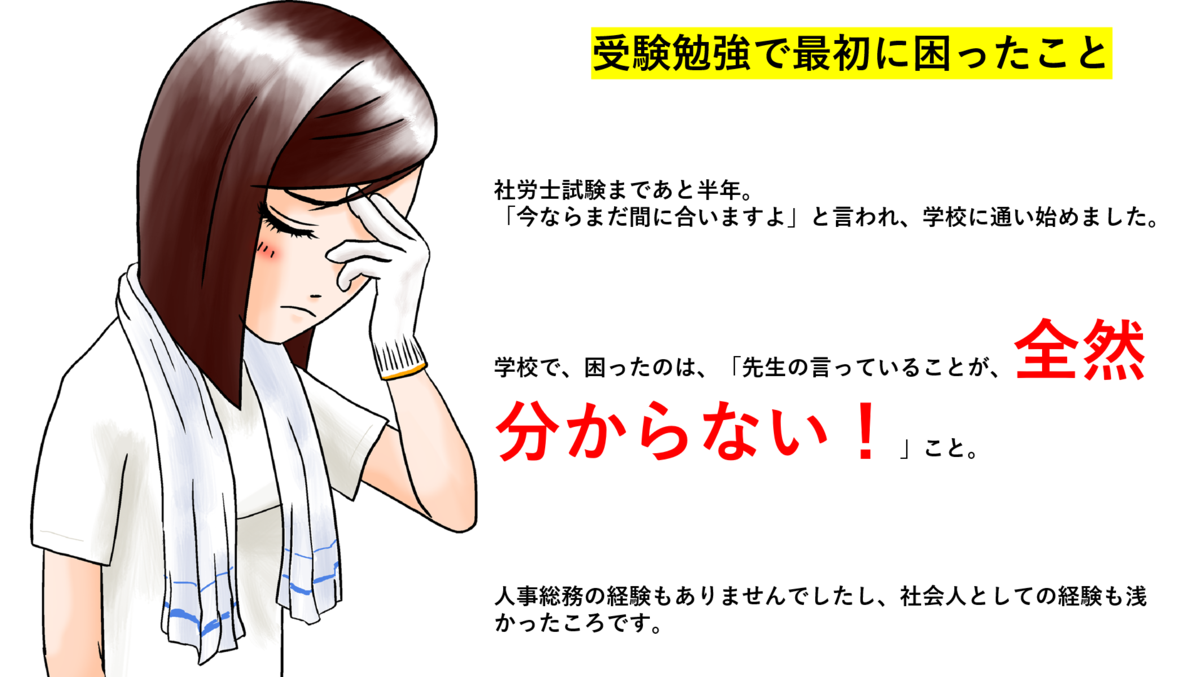
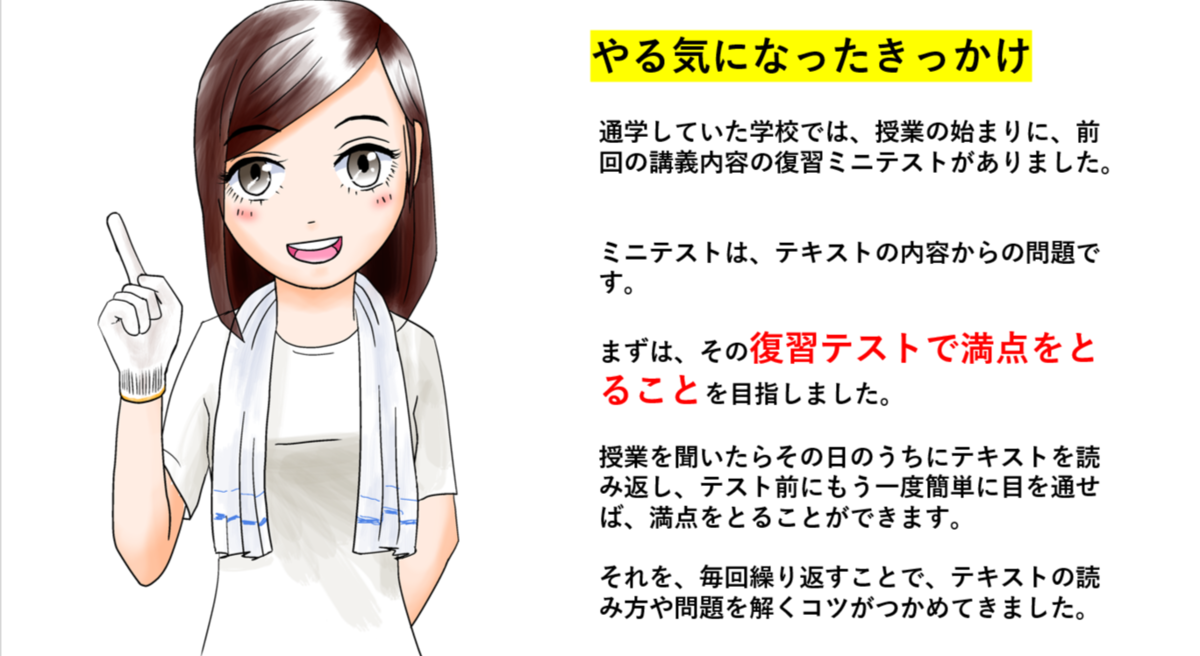
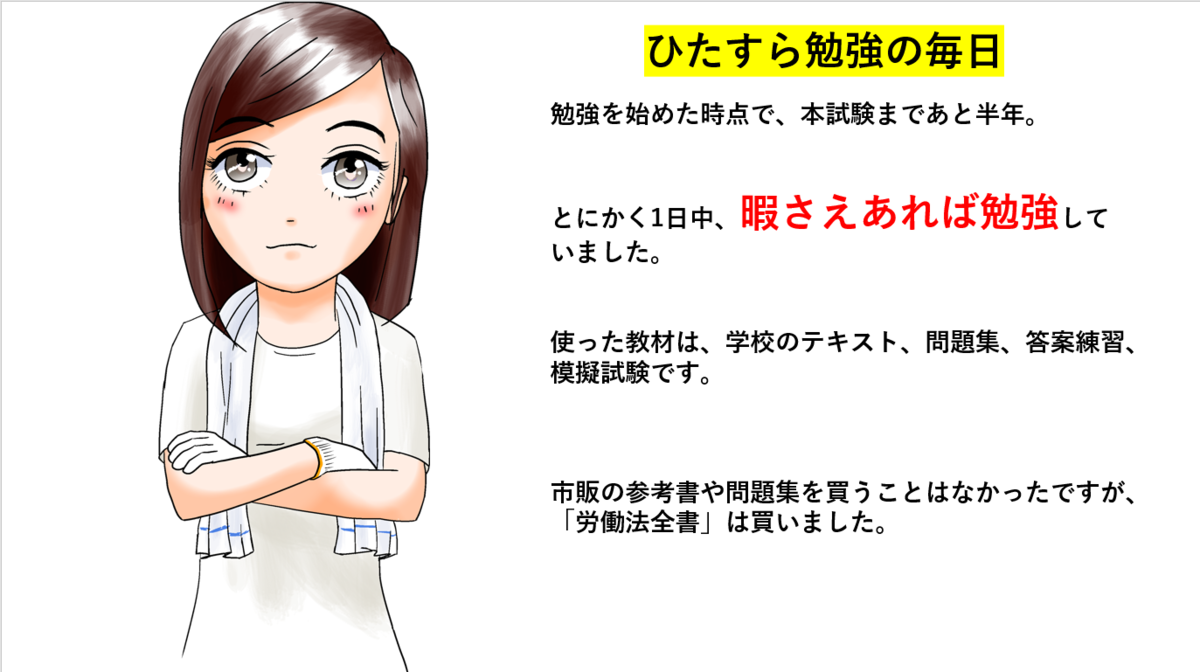

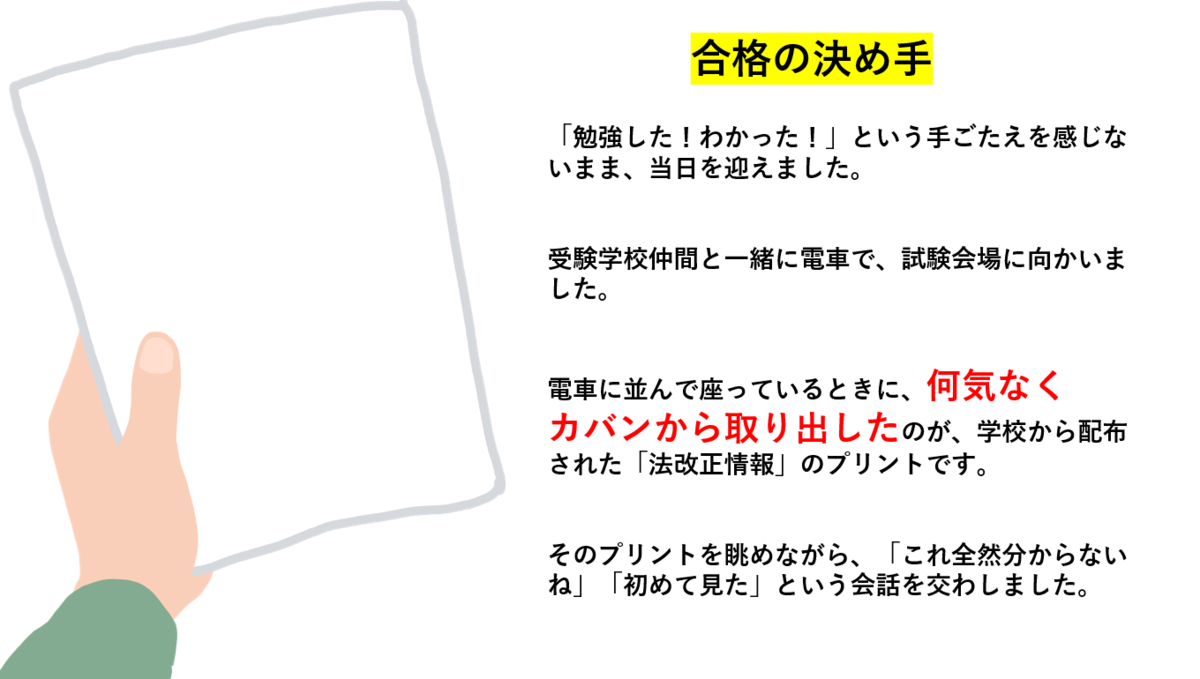
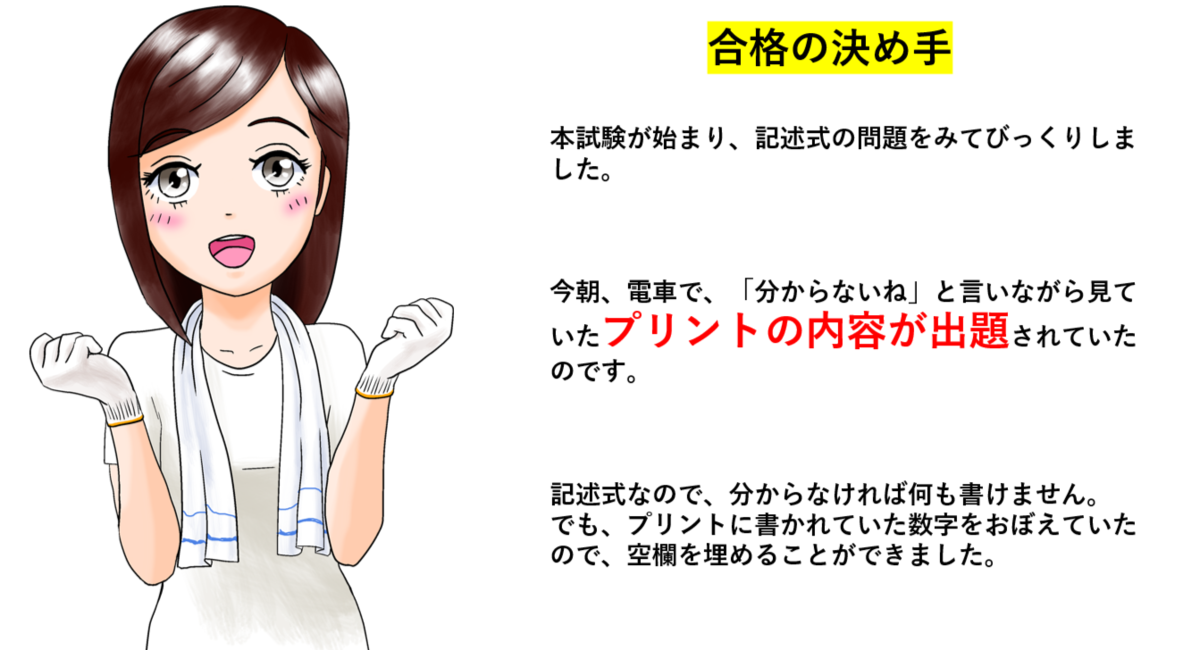

過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-224 R6.4.7
社労士受験のための 受給期間中に再就職して再び離職した場合
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「受給期間」とは、基本手当を受けることができる有効期間です。受給期間内に再就職・再離職し新しい基本手当の受給資格ができた場合をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
★新しい受給資格ができた場合は、新しい受給資格が優先されます。前の受給資格に基づく基本手当は、受給期間内であっても支給されなくなります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
受給期間内に再就職して再び離職し、再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間は消滅します。再離職の日の翌日から新しい受給期間が始まりますので、前の受給資格に基づく基本手当は受給できません。
★ちなみに、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職で受給資格を取得できなかったときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができます。
(行政手引50251)
②【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。

【解答】
②【H21年出題】 〇
①と同じ趣旨の問題です。
(行政手引50251)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-223 R6.4.6
社労士受験のための 受給期間の原則
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
「受給期間」とは、基本手当を受けることができる有効期間です。基本手当は受給期間内に受けなければなりませんが、一定の場合は、受給期間を延長することができます。
では、「受給期間」について条文を読んでみましょう。
第20条第1項 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。 (1) (2)及び(3)に掲げる受給資格者以外の受給資格者 → 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下「基準日」という。)の翌日から起算して1年 (2) 就職困難者のうち基準日において45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の受給資格者 → 基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間 (3) 特定受給資格者のうち基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上である者 → 基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間 |
受給期間は原則として離職日の翌日から起算して1年間です。
ただし、(2)所定給付日数が360日の場合は、「1年+60日」、(3)所定給付日数が330日の場合は、「1年+30日」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

【解答】
①【H28年出題】 〇
45歳以上65歳未満・就職が困難な者・算定基礎期間が1年以上の場合、所定給付日数は360日、受給期間は基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間です。
(法第20条第1項第2号)
②【H26年出題】
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日、受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間です。
(法第20条第1項第3号)
③【H22年選択式】
63歳で定年に達したことにより離職した受給資格者の場合、その離職に係る基本手当は、原則として、当該離職の日の翌日から起算して< A >の期間内における < B >について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給される。当該受給資格者が上記期間内に疾病により引き続き30日以上職業に就くことができず、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、 < A >に当該理由により職業に就くことができない日数が加算されるが、その加算された合計の期間が< C >を超えるときは、< C >が上限となる。
なお、本問の受給資格者は雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらず、また、上記疾病については傷病手当の支給を受ける場合を除くものとする。

【解答】
③【H22年選択式】
A 1年
B 失業している日
C 4年
(第20条第1項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-222 4.5
社労士受験のための 離職理由による基本手当の給付制限
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
離職理由による給付制限について条文を読んでみましょう。
第33条第1項 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
給付制限が行われるのは、離職理由が、「自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合」、「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
離職理由による給付制限期間中は、基本手当は支給されませんので、この間については、「失業の認定を行う必要はない」とされています。
(行政手引52205)
②【H26年出題】
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
正当な理由があるので、離職理由による給付制限は行われません。
(行政手引52203)
③【H29年出題】
従業員として当然守らなければならない事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇として給付制限を受ける。

【解答】
③【H29年出題】 〇
事業所の機密を漏らしたことによって解雇されることは、自己の責に帰すべき重大な理由による解雇となり、給付制限を受けます。
(行政手引52203)
④【H26年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

【解答】
④【H26年出題】 〇
第33条第1項で、「ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない(給付制限が行われない)。」とされていますので、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、給付制限は行われません。他の要件を満たす限り基本手当が支給されます。
(行政手引522053)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-221 4.4
社労士受験のための 労災 未支給の保険給付の請求
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
未支給の保険給付について条文を読んでみましょう。
第11条 ① 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ② 死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 ③ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、①に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、複数事業労働者遺族年金については第20条の6第3項において準用する第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。 ④ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
★ 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金、遺族年金については、転給があるため、未支給の保険給付を請求できる遺族の範囲が違います。
★ 保険給付の請求をしていない者が死亡した場合は、①に規定する者が、自己の名で保険給付を請求できます。
★ 「年金」の受給権者が死亡した場合は、必ず未支給年金が発生します。年金は死亡した月まで支給され、「後払い」だからです。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】※改正による修正あり
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
★ 未支給の保険給付を請求することができるのは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
★ 遺族補償年金については、未支給の遺族補償年金を請求できるのは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族です(複数事業労働者遺族年金、遺族年金も同じです。)。
(第11条第1項)
②【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】
②【H30年出題】 〇
例えば、遺族補償年金を受ける権利を有する者が4月20日に死亡した場合、4月分が未支給になります。未支給の遺族補償年金は、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」が、自己の名で、請求できます。
(第11条第1項)
③【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。

【解答】
③【H30年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合で、「その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかった」ときは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」が、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができます。
(第11条第2項)
④【H30年出題】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

【解答】
④【H30年出題】 〇
手続を簡素化するための規定です。未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人(代表者)がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人(代表者)に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます。
(第11条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-220 4.3
社労士受験のための 衛生委員会の設置
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項~3項、令第9条 (衛生委員会) ① 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 (1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。 (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項 ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 (1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 (2) 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 (3) 産業医のうちから事業者が指名した者 (4) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 |
ポイント!
★衛生委員会は、全業種の常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。
★(1)の委員が、委員会の議長となります。(第17条第4項)
★「(1)委員会の議長となる委員以外」の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。 (第17条第4項)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。

【解答】
①【R4年出題】 ×
衛生委員会は、「常時50人以上の労働者を使用する事業場ごと」に設置しなければなりません。
「企業全体で常時50人以上」ではありませんし、「企業全体を統括管理する事業場」だけでもありません。
(第18条第1項、令第9条)
②【H21年出題】
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

【解答】
②【H21年出題】 〇
安全委員会は、安全管理者を選任しなければならない業種で、区分に応じて常時50人以上又は常時100人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。
衛生委員会は、「全業種」で常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置義務があります。そのため、安全委員会を設けなければならない事業場では、衛生委員会も設けなければなりません。
(法第17条、18条、令第8条、第9条)
③【H26年出題】
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
推薦に基づき指名しなければならないのは、「その委員の半数」ではなく、「委員会の議長となる委員以外」の委員の半数です。
この規定は、衛生委員会にも準用されます。
(法第17第4項、第18条第4項)
④【H12年出題】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

【解答】
④【H12年出題】 〇
作業環境測定士は、衛生委員会の委員として「指名することができる」と任意になっている点がポイントです。
(法第18条第3項)
⑤【R4年出題】
事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
衛生委員会のメンバーには、必ず「産業医」を入れなければなりません。安全衛生委員会も同じです。
(法第18条第2項)
⑥【H16年出題】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【解答】
⑥【H16年出題】 ×
産業医は必ず衛生委員会の委員として指名しなければなりません。産業医は専属の産業医に限られませんので、嘱託の場合でも指名が必要です。
(昭63.9.16基発第601号の1)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-219
R6.4.2 休業手当の重要ポイント
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
休業手当について条文を読んでみましょう。
第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
【H27年出題】
労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
問題①
使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。

【解答】
問題① ×
★テーマ 休日に休業手当の支給義務はない
就業規則や労働協約で「休日」と定められている日には、休業手当を支給する義務がありません。問題文の場合は、土日が休日ですので、使用者は、5日分の休業手当を支払わなければなりません。
(昭24.3.22基収4077号)
問題②
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

【解答】
問題② 〇
★ テーマ 休業期間が一労働日に満たない場合の休業手当の額
現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
問題文は、所定労働時間が4時間に短縮され、現実に就労した時間に対して7,500円の支払がなされています。平均賃金10,000円の100分の60以上ですので、賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法となりません。
(昭27.8.7基収3445号)
問題③
就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。

【解答】
問題③ 〇
★ テーマ 休日に休業手当の支給義務はない
日曜日の休日をあらかじめ振り替えて水曜日とした場合、水曜日は休日になりますので、休業手当を支払う義務は生じません。
(昭24.3.22基収4077号)
問題④
休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

【解答】
問題④ 〇
★テーマ 「休業」の定義
「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれます。
問題⑤
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
問題⑤ 〇
★テーマ 休電による休業には原則として休業手当の支払義務はない
休電による休業は、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないので、休業手当を支払わなくても第26条違反になりません。
(昭26.10.11基発696号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-218
R6.4.1 国民健康保険法の保険者
過去問から学びましょう。
今日は国民健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第3条 (保険者) ① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 ② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】
①【R4年出題】 ×
・国民健康保険組合の設立には、「都道府県知事の認可」を受けなければなりません。この部分は正しいです。
・認可の申請は、10人ではなく「15人」以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人ではなく「300人」以上の同意を得て行うものとされています。
(第17条第1項、2項)
②【R1年選択式】
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、< A >、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
(選択肢)
①安定的な財政運営 ②国民健康保険の運営方針の策定
③事務の標準化及び広域化の促進 ④地域住民との身近な関係性の構築

【解答】
②【R1年選択式】
A ①安定的な財政運営
③【R3年出題】
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った「日」又は第6条各号(適用除外規定)のいずれにも該当しなくなった「日」から、その資格を取得します。「翌日」ではありません。
(第7条)
④【R3年出題】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】
④【R3年出題】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、適用除外です。被保険者になりません。
(第6条第9号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-217
R6.3.31 労働組合法の「労働者」
過去問から学びましょう。
今日は労働組合法です。
労働組合法の「労働者」の定義を条文で読んでみましょう。
第3条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 |
通達を確認しましょう。
本条にいう「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。 (昭23.6.5労発第262号) |
なお、労働基準法の労働者は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」ですので、失業者は含まれません。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

【解答】
①【H23年出題】 〇
労働組合法の「労働者」については、現に就業していると否とを問わないため、失業者も含むのがポイントです。
(昭23.6.5労発第262号)
労働基準法の労働者の定義もみておきましょう。違いに注意してください。
労働基準法第9条 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
②【H23年出題】
使用者は、その雇用する労働者が加入している労働組合であっても、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とは、団体交渉を行う義務を負うことはない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」は、不当労働行為として禁止されています。
その雇用する労働者が加入している労働組合で、当該企業の外部を拠点に組織されている労働組合(いわゆる地域合同労組など)とも、団体交渉を行う義務があります。
(第7条第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-216
R6.3.30 加給年金額の調整(老齢厚生年金と障害基礎年金)
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「加給年金額」が加算される条件を条文で読んでみましょう。
第44条第1項 (加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法の障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
★老齢厚生年金(被保険者期間が240月(20年)以上あること)の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
(詳しくは、昨日の記事をどうぞ)
今日は、ただし以下の部分をみていきます。
65歳以上の者は、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給できます。
障害基礎年金に子の加算が行われているときは、その間、老齢厚生年金の子についての加給年金額は支給停止されます。
障害基礎年金と老齢厚生年金に二重に子に対する加給年金額が加算されることを防ぐための規定です。
老齢厚生年金
| →子の加給年金額(支給停止) |
障害基礎年金
| →子の加算額が加算される |
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
65歳に達している受給権者に係る老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。

【解答】
①【H24年出題】 〇
老齢厚生年金と障害基礎年金を併給する場合、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるときは、老齢厚生年金の子に対する加給年金額は支給が停止されます。
(第44条第1項)
②【H29年出題】
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
②【H29年出題】 〇
①と同じ問題です。子の加算額が加算された障害基礎年金と子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給される場合は、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。
(第44条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-215
R6.3.29 加給年金額が加算される条件
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「加給年金額」が加算される条件を条文で読んでみましょう。
第44条第1項 (加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法の障害基礎年金の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
加給年金額が加算される要件を確認しましょう。
★老齢厚生年金(被保険者期間が240月(20年)以上あること)の受給権を取得した当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときに加給年金額が加算されます。
★老齢厚生年金の受給権を取得した当時、被保険者期間が240月未満の場合
→老齢厚生年金の受給権取得後も厚生年金保険に加入し、在職定時改定又は退職時改定で年金額が再計算されたときに240月以上になった場合は、そのときに生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
★加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間が240月(20年)以上あることが条件ですが、中高齢の資格期間短縮特例に該当する場合は、15年~19年でも要件を満たします。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
【H30年出題】 ×
被保険者資格を喪失し、年金額を再計算した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、その時点で、加給年金額の対象となる配偶者がいた場合は、加給年金額が加算されます。
(第44条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-214
R6.3.28 付加保険料の7つのポイント
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「付加保険料」の納付について条文を読んでみましょう。
第87条の2 ① 第1号被保険者(法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除を受けている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。 ② 付加保険料の納付は、国民年金保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後期間の免除により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 ③ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 ④ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、③の申出をしたものとみなす。 |
第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付することができます。付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金に付加年金がプラスされます。
過去問をどうぞ!
これまで過去問①②の次に解答①②としてきましたが、リクエストを頂きましたので、今回から過去問①解答①→過去問②解答②の順番にします。 |
①【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
「任意加入被保険者」は付加保険料の納付については第1号被保険者とみなされ、付加保険料を納付できます。
なお、特例任意加入被保険者は付加保険料を納付できません。
(法附則第5条第9項)
②【R1年出題】
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
産前産後期間の保険料免除の期間は、付加保険料を納付することができます。
(第87条の2第2項)
③【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
保険料の免除(法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除)を受けている者は、付加保険料は納付できません。
(第87条の2第1項)
④【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

【解答】
④【H26年出題】 ×
追納によって保険料が納付されたものとみなされた月は、付加保険料は納付できません。
(法第87条の2第1項)
⑤【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
そのため、付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
(法第87条の2第4項)
⑥【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
付加保険料の納付は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、納付をやめることができます。
やめることができるのは、その申し出をした日の属する月以後の各月ではなく、申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)です。
(法第87条の2第3項)
ちなみに、付加保険料の納付を始めるときは、「その申出をした日の属する月以後の各月」からとなります。
⑦【H26年出題】
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

【解答】
⑦【H26年出題】 ×
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合でも、納付を辞退したものとはみなされません。
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合でも、国民年金の保険料と同様、納期限から2年以内は納付することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-213
R6.3.27 健康保険 被保険者資格の取得と喪失の確認
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
入社した日に健康保険の被保険者資格を取得し、退職した日の翌日に資格を喪失するのが一般的です。例えば、健康保険の被保険者の資格を取得すると、保険料を負担する義務や、保険給付を受ける権利などが生まれます。
被保険者資格の取得や喪失は、保険者等の確認によって効力が発生します。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項、2項(資格の得喪の確認) ① 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失(任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失)並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 ② 確認は、「事業主からの届出」、「被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求」、「職権」で行うものとする。 |
★「被保険者の資格の取得及び喪失」は、保険者等の確認によって、その効力を生じます。
※保険者等とは
・ 協会が管掌する健康保険の被保険者の場合 → 厚生労働大臣
・ 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者の場合 → 当該健康保険組合
★確認が要らないもの
・ 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失
→ 任意適用事業所の適用取消しの厚生労働大臣の認可を受けた場合、それに伴い被保険者資格も喪失します。あらためて資格喪失の確認は要らないからです。
・ 任意継続被保険者の資格の取得及び喪失
→ 任意継続被保険者は事業主との関係がなくなっていて、入社日・退職日の確認が要らないからです。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
②【H26年出題】
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
③【H30年出題】
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が、それぞれ確認することによってその効力を生じます。
任意継続被保険者の被保険者資格の取得・喪失については保険者等の確認は行われません。特例退職被保険者も任意継続被保険者とみなされ、被保険者資格の取得・喪失については保険者等の確認は行われません。
(法第39条第1項、法附則第3条第6項)
②【H26年出題】 ×
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認は不要です。
(法第39条第1項)
③【H30年出題】 ×
「任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失」、「任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失」については、保険者等の確認は不要です。
(法第39条第1項、法附則第3条第6項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-212
R6.3.26 概算保険料の追加徴収
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
概算保険料の追加徴収について条文を読んでみましょう。
第17条 ① 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。 ② 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
則第26条 (概算保険料の追加徴収) 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 (1) 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 (2) 納期限 |
保険年度の中途から保険料率が引き上げられた場合、既に納付した概算保険料と保険料率が引き上げられた後の概算保険料の差額が追加で徴収されます。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
②【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることになっている。
③【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
④【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、延納することはできない。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収は、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」、行われることがポイントです。増加概算保険料との違いに注意してください。
(第17条)
②【H30年出題】(労災) ×
保険年度の中途に、保険料率が引き下げられた場合でも、還付する規定はありません。
③【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収される概算保険料の納付は「納付書」により行われます。
(則第26条、則第38条第4項)
④【H30年出題】(労災) ×
追加徴収される概算保険料は、延納することができます。
概算保険料について延納が認められていること、通知により指定された期限までに延納の申請をすることが条件です。
(則第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-211
R6.3.25 雇用保険 賃金日額の算定
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
基本手当の日額は、「賃金日額」×給付率で算定します。
給付率の原則は、50%~80%ですが、60歳以上65歳未満は45%~80%です。
今日は、基本手当の日額のもとになる「賃金日額」をみていきます。
「賃金日額」の定義を条文で読んでみましょう。
第17条第1条 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
賃金日額の原則の算定式は以下の通りです。
最後の6か月間に支払われた賃金の総額 | ÷ | 180 |
※賃金総額から、「臨時」の賃金及び「3か月を超える期間ごと」の賃金は除かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
②【H30年出題】
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
③【H26年出題】
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢にかかわりなく一律である。
④【R4年選択式】※改正による修正あり
雇用保険法第13条の算定対象期間において、完全な賃金月が例えば12あるときは、< A >に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。賃金日額の算定は< B >に基づいて行われるが、同法第17条第4項によって賃金日額の最低限度額及び最高限度額が規定されているため、算定した賃金日額が2,500円のときの基本手当日額は< C >となる。
なお、同法第18条第1項、第2項の規定による賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は、2,700円、同法同条第3項の規定による最低賃金日額は2,746円とする。
(選択肢)
A | ①最後の完全な6賃金月 ②最初の完全な6賃金月 ③中間の完全な6賃金月 ④任意の完全な6賃金月 |
B | ①雇用保険被保険者資格取得届 ②雇用保険被保険者資格喪失届 ③雇用保険被保険者証 ④雇用保険被保険者離職票 |
C | ①1,350円 ②1,373円 ③2,160円 ④2,196円 |

【解答】
①【H22年出題】 〇
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金で計算します。
(第17条第1項)
②【H30年出題】 ×
(原則)
賃金日額は、原則として、「被保険者期間として計算された最後の6か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額です。
(最低保障)
ただし、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合は最低保障があります。
最低保障は、「最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」です。
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数などによっては最低保障が適用される場合があります。
(第17条第2項)
③【H26年出題】 〇
賃金日額には、最高限度額と最低限度額が規定されています。
最高限度額は、「30歳未満」、「30歳以上45歳未満」、「45歳以上60歳未満」、「60歳以上65歳未満」の4段階で設定されていて、最も高いのが「45歳以上60歳未満」です。
最低限度額は年齢にかかわりなく一律です。
(第17条第4項)
④【R4年選択式】※改正による修正あり
A ①最後の完全な6賃金月
「賃金月」とは、同一の事業主のもとにおける賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、その期間が満1か月であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」といいます。
(行政手引50601)
B ④雇用保険被保険者離職票
C ④2,196円
令和5年8月1日以後の賃金日額の最低限度額(自動変更対象額)は2,700円、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に 20 を乗じて7で除して得た額)は2,746円です。
自動変更対象額が最低賃金日額を下回るので、最低賃金日額の2,746円が賃金日額の最低限度額となります。
問題文では、算定した賃金日額が2,500円となっていますので、最低限度額が適用され、賃金日額は2,746円になります。
基本手当日額は、2,746円×給付率(80%)=2,196円です。
ちなみに、賃金日額に最低限度額が適用される場合、給付率は80%です。
(第16条、第17条、則第28条の5)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-210
R6.3.24 障害補償年金の自然的経過による変更
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
障害の程度が自然的経過により変更した場合の規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
障害補償年金を受ける労働者が対象です。(障害補償一時金は対象になりません。)
障害の程度が、自然的経過により変更(増進・軽減)した場合、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。
(例)
・5級の障害補償年金を受けていた労働者の障害の程度が、自然的経過により3級に増進した場合
↓
3級の障害補償年金が支給され、その後は5級の障害補償年金は支給されません。
・7級の障害補償年金を受けていた労働者の障害の程度が、自然的経過により9級に軽減した場合
↓
9級の障害補償一時金が支給され、その後は7級の障害補償年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「障害補償年金」を受ける者の障害の程度が、自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)が支給されます。その後は、従前の障害補償年金は支給されません。
(第15条の2)
②【H30年出題】 〇
「障害補償一時金」を受けた者については、障害の程度が自然的経過により変更しても、障害補償給付の変更は行われません。
(第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-209
R6.3.23 労働者死傷病報告の注意点
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
労働者死傷病報告について条文を読んでみましょう。
則第97条 (労働者死傷病報告) ① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ② 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、労働者死傷病報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②【H25年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③【H30年出題】
派遣元事業者は、派遣労働者が労働災害に被災したことを把握した場合、派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
労働者死傷病報告書は、「労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき」に提出しなければなりません。労働災害でなくても、事業場内における負傷により休業した場合は、提出が必要です。
(則第97条)
②【H25年出題】 ×
★ 休業4日以上の場合
→労働者死傷病報告書は「遅滞なく」提出しなければなりません。
★ 休業4日未満の場合
→ 期間ごとにまとめて提出します。
1月から3月までの分・・・4月末日までに提出
4月から6月までの分・・・7月末日までに提出
7月から9月までの分・・・10月末日までに提出
10月から12月までの分・・・1月末日までに提出
問題文は、休業日数が2日ですので、「遅滞なく」は誤りです。
(則第97条)
③【H30年出題】 〇
派遣労働者の労働者死傷病報告は、派遣元・派遣先の両方に提出義務があります。
<派遣先事業者>
派遣労働者が労働災害に被災した場合は、労働者死傷病報告を作成し、派遣先の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。
また、当該労働者死傷病報告の写しを、遅滞なく、派遣元事業者に送付します。
<派遣元事業者>
派遣先事業者から送付された所轄労働基準監督署長に提出した労働者死傷病報告の写しを踏まえて労働者死傷病報告を作成し、派遣元の事業場を所轄する労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(H27.9.30基発0930第5号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-208
R6.3.22 年次有給休暇⑥計画的付与
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
計画的に有給休暇の取得日を定めることを、計画的付与といいます。
条文を読んでみましょう。
第39条第6項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。 |
計画的付与の導入によって、気がねなく年次有給休暇を取得できるなどの効果が期待できます。
計画的付与の導入には、労使協定が必要です。
また、計画的付与の対象になるのは、有給休暇の日数のうち、5日を超える部分です。労働者が個人的な事由で有給休暇を取得できるよう、5日は残しておく必要があります。
例えば、有給休暇の日数が20日の場合、計画的付与の対象にできるのは、15日までです。
過去問をどうぞ!
①【H15年出題】
いわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法第39条第6項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が生じたときには、使用者は、相当程度の時間的余裕をもって行えば、当該労働者について、時季変更権を行使することができる。
②【H26年出題】
労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められていない。

【解答】
①【H15年出題】 ×
計画的付与については、労働者の時季指定権も使用者の時季変更権も行使できません。
(H22.5.18基発0518第1号)
②【H26年出題】 〇
有給休暇の計画的付与として、時間単位年休を与えることは認められていません。
(H21.5.29基発0529001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-207
R6.3.21 年次有給休暇⑤時季指定権と時季変更権
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第5項 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 |
年次有給休暇は、「労働者の請求する時季」に与えることが原則です。(時季指定権)
しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」は、使用者は、時季を変更することができます。(時季変更権)
過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第30条第5項(当時は第3項)に定める使用者による時季変更権の行使の有効性が争われた事件において、次のように判示した。「労基法39条3項〔現行5項〕ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、< A >配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して< A >を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより< A >が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところである〔‥…〕から、勤務割を変更して< A >を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の目的いかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。」
②【R5年出題】
労働基準法第30条第5項にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H27年選択式】
A 代替勤務者
(最高二小S62.7.10)
ポイント!
勤務割(シフト制)の事業場で、使用者が、通常の配慮をすれば、シフトを変更して代替勤務者を配置することが可能な状況であるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできない。
シフトを変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の目的によってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
②【R5年出題】 〇
①の判例と同じです。
(最高二小S62.7.10)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-206
R6.3.20 年次有給休暇④時間単位付与
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第4項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、(1)に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、有給休暇の日数のうち(2)に掲げる日数については、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 (1) 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 (2) 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) (3) その他厚生労働省令で定める事項 |
時間単位年休のポイント!
・労使協定の締結が必要です
・時間単位で年次有給休暇を与えることができるのは、年に5日以内です。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。
②【H28年出題】
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。
③【H25年出題】
労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

【解答】
①【H22年出題】 ×
年次有給休暇の時間単位付与は、「就業規則の定めを置くこと」ではなく「労使協定を締結すること」を要件に、「年10日」ではなく「年5日」の範囲内で認められています。
(第39条第4項)
②【H28年出題】 〇
週の所定労働時間が1日8時間から4時間に変更になった場合、時間単位で取得できる時間数はどうなるのかという問題です。
所定労働時間が変更になる前の残余は10日と5時間です。
時間の部分の残余は8時間のうちの5時間ということで、8分の5と考えます。
所定労働時間が4時間になると、所定労働時間に比例して時間の部分の残余は、4時間×8分の5≒3時間となります。(1時間未満の端数は切り上げます。)
所定労働時間が4時間に変更になった後に取得できる年次有給休暇は、日数の10日は変更になりませんが、時間数の方は5時間から3時間に変更されます。
ちなみに、日数は10日で変わりませんが、1日当たりの時間数は、変更前は8時間、変更後は4時間です。
(H21.10.5基発1005号第1号)
③【H25年出題】 〇
時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象となります。
ただし、労働者が時間単位の取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位の取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められません。
(H21.5.29 基発0529001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-205
R6.3.19 年次有給休暇③出勤率の算定「出勤したものとみなす」
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
年次有給休暇の権利は、次の2つの要件を満たせば、法律上当然に発生します。
①雇入れの日から 6か月継続勤務 |
| ②全労働日の 8割以上出勤 |
出勤率は、「全労働日」に対する「出勤した日」の割合です。
実際は出勤していなくても、出勤したと「みなす」日があります。
条文を読んでみましょう。
第39条第10項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、出勤したものとみなす。 |
・業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
・育児休業又は介護休業をした期間
・産前産後の女性が休業した期間
は、出勤率については「出勤」として算定されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。
②【H28年出題】
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

【解答】
①【H18年出題】 ×
子の看護休暇を取得した期間は、出勤したものとみなす扱いにはなりません。
(法第39条第10項)
②【H28年出題】 〇
年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして取り扱います。
(H6.3.31基発181号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-204
R6.3.18 年次有給休暇②出勤率の算定「全労働日」
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
年次有給休暇の権利は、次の2つの要件を満たせば、法律上当然に発生します。
①雇入れの日から 6か月継続勤務 |
| ②全労働日の 8割以上出勤 |
年次有給休暇の権利の発生要件である「出勤率」は、「全労働日」に対する「出勤した日」の割合です。
「全労働日」とは、労働義務のある日のことで、暦日数から所定の休日を除いた日数のことです。
「全労働日」についての通達を確認しましょう。
1 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、2に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。 2 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。 (1) 不可抗力による休業日 (2) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 (3) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 (平25.7.10基発0710第3号) |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
②【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >というべきである。」

【解答】
①【H28年出題】 ×
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいいます。
所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものとされています。
(平25.7.10基発0710第3号)
②【H26年選択式】
A 含まれるもの
★「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」の扱いについて
※不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等は、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれます。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日など、「労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日」は、出勤日数に算入すべきものとして「全労働日に含まれるもの」とされます。
解雇の日から解雇無効が確定するまでの期間について、その期間の労働日を全労働日に含めた上でその全部を出勤日として取り扱うことで、年次有給休暇の成立要件を満たしているものということができます。
(平25.6.6第一小法廷判決 平25.7.10基発0710第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-203
R6.3.17 年次有給休暇①権利の発生
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項・2項 (年次有給休暇) ① 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、1年6か月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日(以下「6か月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、①の日数に、次の表の上欄に掲げる6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 ただし、継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
|
年次有給休暇の付与日数を確認しましょう。
継続 勤務 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
付与 日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年次有給休暇の発生要件は、次の2つです。
①雇入れの日から 6か月継続勤務 |
| ②全労働日の 8割以上出勤 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりのある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数以上の有給休暇を与えることにある。
②【H20年出題】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
③【R4年出題】
年次有給休暇の権利は、「労基法39条1項、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまって始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
④【H24年出題】
労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところであり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
「休日のほかに毎年一定日数以上の有給休暇を与える」の部分がポイントです。
「休日」は、「労働義務がない日」です。
年次有給休暇の「休暇」は「労働義務が免除される日」ですので、休暇は労働義務のある「労働日」に取得します。そのため、年次有給休暇は1労働日、2労働日と算定します。
②【H20年出題】 〇
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利です。
労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく、「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないとされています。
(最高裁第二小法廷 昭和48年3月2日 白石営林署事件)
③【R4年出題】 ×
年次有給休暇の権利は、「労基法39条1項、2項の要件が充足されることによって「法律上当然に労働者に生ずる権利」であって、「労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく」、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、「労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』」の観念を容れる余地はない」とされています。
ポイント!
・年次有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に労働者に生ずる権利で、労働者からの請求をまって生ずるものではありません。
(最高裁第二小法廷 昭和48年3月2日 白石営林署事件)
④【H24年出題】 〇
年次有給休暇をどのように利用するかは、労働者の自由です。
病気療養のために年次有給休暇を利用することもできます。
(昭24.12.28基発第1456号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-202
R6.3.16 児童手当法のあれこれ
過去問から学びましょう。
今日は児童手当法です。
まず、児童手当法の「児童」の定義を条文で読んでみましょう。
第3条第1項 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
②【R2年出題】
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
③【R2年出題】
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
④【R2年出題】
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
⑤【R2年出題】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による

【解答】
①【R2年出題】 〇
「児童」の定義についての問題です。
(第3項第1項)
ちなみに、「支給要件児童」という用語もあります。
「支給要件児童」は、
・15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。「中学校修了前の児童」という。)
・中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
をいいます。
(第4条第1項第1号)
②【R2年出題】 ×
児童手当は、原則として、毎年「2月、6月及び10月」の3期に、それぞれの前月までの分を支払います。
(第8条第4項)
③【R2年出題】 〇
例えば2人目以降の子が生まれた場合、児童手当の増額改定は、その改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。
(第9条第1項)
ちなみに、「児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至っ場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から」行われます。
(第9条第3項)
④【R2年出題】 〇
「未支払の児童手当」についての問題です。
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合は、未支払の児童手当は中学校修了前の児童であった者に支払われます。
(第12条第1項)
⑤【R2年出題】 〇
児童手当法の罰則規定です。
(第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-201
R6.3.15 パートタイム・有期雇用労働法第8条と第9条
過去問から学びましょう。
今日はパートタイム・有期雇用労働法です。
まず、「短時間労働者」と「有期雇用労働者」の定義を条文で確認しましょう。
第2条第1項・2項 ① この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。 ② この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。 |
★短時間労働者とは
→ 1週間の所定労働時間が、同じ会社で雇用される「通常の労働者」と比較して短い労働者
★有期雇用労働者とは
→ 会社と「有期雇用」(1年や3年などの期間が定められている)の労働契約を結んでいる労働者
パートタイム・有期雇用労働法第8条では、同一企業の通常の労働者と短時間労働者及び有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差を禁止しています。
条文を読んでみましょう。
第8条 (不合理な待遇の禁止) 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。 |
第9条では、通常の労働者と同視すべき短時間労働者・有期雇用労働者に対する差別的取扱いを禁止しています。
条文を読んでみましょう。
第9条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 |
では、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(H30.12.28厚生労働省告示第 430 号)」からの問題をみてみましょう。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。
②【R4年出題】
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
ガイドラインでは、「通常の労働者」と「短時間労働者・有期雇用労働者」との間に待遇の相違がある場合に、どのような相違が不合理で、どのような相違が不合理でないかの原則となる考え方と具体例が示されています。
★パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関して原則となる考え方
・基本給であって、労働者の能力又は経験に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。また、能力又は経験に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた基本給を支給しなければならない。
問題文の事例は、「問題とならない例」となっています。「許されない」は誤りです。
(H30.12.28厚生労働省告示第 430 号)
②【R4年出題】 〇
★パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関して原則となる考え方
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならない。
また、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。
問題文は、「賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するもの」についての原則となる考え方です。
(H30.12.28厚生労働省告示第 430 号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-200
R6.3.14 受給権者の申出による支給停止
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条の2第1項・3項 (受給権者の申出による支給停止) ① 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 ③ ①の申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができる。 |
年金の支給停止を希望する受給権者は、申出により年金の「全額」を支給停止(辞退)することができます。
申出により辞退できるのは「全額」です。一部だけの辞退はできません。
また、いつでも、支給停止の撤回の申出をすることができます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。
②【H26年出題】
受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止について、この申出は、老齢基礎年金と老齢厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない。
③【H20年出題】
厚生年金保険法第38条の2に規定される受給権者の申出による年金たる保険給付の支給停止は、申出を行った日の属する月の翌月から支給停止される。また、支給停止の申出を撤回したときは、その旨の申出を行った日の属する月の翌月から支給が開始される。

【解答】
①【R2年出題】 〇
年金がその額の一部につき支給を停止されている場合は、「停止されていない部分の額」の支給停止の申出をすることができます。
(第38条の2第1項ただし書)
②【H26年出題】 ×
老齢基礎年金と老齢厚生年金のように支給事由が同一の年金がある場合には同時に行わなければならない、という規定はありません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金はそれぞれ別個に支給停止の申出ができます。
<特例があります>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合は特例があります。
第78の23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第38条の2第1項に規定する年金たる保険給付についての支給停止の申出又は撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。 |
③【H20年出題】 〇
・受給権者が支給停止の申出をしたとき
→申出を行った日の属する月の翌月から支給停止されます。
・支給停止の申出を撤回したとき
→撤回の申出を行った日の属する月の翌月から支給が開始されます。
条文を確認しましょう。
第36条第2項 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-199
R6.3.13 併給可能な組み合わせ
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条第1項、附則第17条 (併給の調整) 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金 及び 遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。 |
★年金は「1人1年金」が原則です。2つ以上の年金を受けることができる場合は、いずれか1つを選択し受給します。なお、選択しなかった年金は支給停止となります。
★同じ理由の年金は、基礎年金と厚生年金の2階建てで支給されます。
老齢厚生年金
|
| 障害厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
|
| 障害基礎年金 |
| 遺族基礎年金 |
★65歳以降のみ可能な組み合わせがあります。
遺族厚生年金
|
| 遺族厚生年金 |
老齢厚生年金 | ||
老齢基礎年金
|
| 老齢基礎年金 |
老齢厚生年金
|
| 遺族厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢厚生年金 | ||||
障害基礎年金
|
| 障害基礎年金 |
| 障害基礎年金 |
65歳以上の組み合わせのポイント!
老齢・遺族
|
|
老齢・障害
|
← 自身が負担した保険料を反映させるため |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。
②【H23年出題】
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
③【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
④【H24年出題】
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
⑤【H26年出題】
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。
⑥【H28年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。
⑦【R4年出題】
次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38条第1項及び同法附則第17条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金

【解答】
①【H30年出題】 ×
60歳で(A)「障害基礎年金+障害厚生年金」と(B)「特別支給の老齢厚生年金」の受給権がある場合は、(A)と(B)のどちらか一方を選択します。
(B)を選択した場合、障害基礎年金は併給されません。
(第38条第1項)
②【H23年出題】 ×
障害厚生年金は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できます。
しかし、「老齢基礎年金及び付加年金」、「遺族基礎年金」とは併給できません。
(第38条第1項)
③【H24年出題】 〇
65歳に達していても、老齢厚生年金は遺族基礎年金とは併給できません。
(第38条第1項、附則第17条)
④【H24年出題】 〇
65歳に達している場合、「(老齢基礎年金及び付加年金)+(遺族厚生年金)」又は「(障害基礎年金)+(遺族厚生年金)」の組み合わせができます。
(第38条第1項、附則第17条)
⑤【H26年出題】 〇
65歳以上の場合、遺族厚生年金と障害基礎年金は併給されます。
(第38条第1項、附則第17条)
⑥【H28年出題】 〇
65歳以上でも、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」は併給されません。
「遺族厚生年金」と「老齢基礎年金」は65歳以上の場合は併給されます。
(第38条第1項、附則第17条)
⑦【R4年出題】
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金 → 同一事由なので併給される
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給されない
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金 → 65歳以上の場合併給される
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金 → 65歳以上の場合併給される
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給されない
「どちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せ」は、イとオの2つです。
(第38条第1項、附則第17条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-198
R6.3.12 基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者数
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
今日のテーマは「基礎年金拠出金」の算定です。
・厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
・実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
(第94条の2第1項、2項)
条文を読んでみましょう。
第94条の3第1項、2項 ① 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 ※政府及び実施機関に係る被保険者の総数とは ・ 厚生年金保険の実施者たる政府 →第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ・ 実施機関たる共済組合等 → 当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者 ■国家公務員共済組合連合会 →当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ■地方公務員共済組合連合会 →当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ■日本私立学校振興・共済事業団 →第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ② 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
令第11条の3 法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする |
基礎年金拠出金の額の出し方
基礎年金の給付に 要する費用 | × | 第2号被保険者+第3号被保険者 |
国民年金の被保険者の総数 |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。
②【R4年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。
③【H30年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

【解答】
①【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について
・第1号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者 → 20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者 → すべての者
「第2号被保険者にあってはすべての者」は誤りです。
(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)
②【R4年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者」の総数です。
保険料の負担がない保険料全額免除期間は入りません。
(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)
③【H30年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者」の総数です。
保険料全額免除期間、保険料未納期間は入りません。
(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-197
R6.3.11 死亡一時金と寡婦年金の調整
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「死亡一時金」と「寡婦年金」の両方の受給権を取得した場合の調整のルールをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第52条の6(支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けることはできません。「その者の選択」により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、どちらか一つが支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
③【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
①【H18年出題】 〇
同一人の死亡で、死亡一時金と寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを受給します。
(第52条の6)
②【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、「その者の選択」により、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つが支給されます。
寡婦年金が優先されるわけではありません。
(第52条の6)
③【R3年出題】 〇
遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった場合の調整についての問題です。
★ポイント1 「一人一年金の原則」
2つ以上の年金の受給権が発生した場合は、原則として、一つの年金を選択し受給します。
遺族厚生年金と寡婦年金は併給できませんので、どちらか一つを選択します。
(第20条)
★ポイント2 「寡婦年金と死亡一時金は選択」
寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択します。寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。死亡一時金を選択した場合は、寡婦年金は支給されません。
(第52条の6)
・寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
・遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されます。(遺族厚生年金と死亡一時金には調整規定がないからです。)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-196
R6.3.10 死亡一時金と遺族基礎年金の関係
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2 第2項 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 (1) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 (2) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |
同一の死亡で遺族基礎年金が支給される場合は、死亡一時金は原則として支給されません。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】
【R2年出題】 ×
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません。
ただし、例外的に、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金が支給されます。
例えば、子が18歳に達した日の属する年度の年度末(3月)に被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金の受給権は発生しますが、同一月に受給権が消滅するため、結局遺族基礎年金は支給されません。
そのため、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金を支給する例外が設けられています。
(第52条の2第2項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-195
R6.3.9 健康保険の被扶養者となる要件
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第3条第7項 健康保険法において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の3親等内の親族で(1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) (3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
★後期高齢者医療の被保険者等その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被扶養者となりません。
★養父母と養子は、父母と子に含まれます。
★被扶養者として認定されるには、「国内居住要件」を満たす必要があります。
■国内居住要件の考え方は以下の通りです。
・住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たす
・ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、保険者において、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断して差し支えない
■国内居住要件の例外について
外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱うとされています。
例外事由は以下の通りです。
| ①外国において留学をする学生 |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
| ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの |
| ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
(則第37条の2、令1.11.13保保発1113第1号)
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。
②【H30年出題】(改正による修正あり)
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。なお、被扶養者の国内居住要件等は満たしているものとする。
③【R2年出題】
被保険者(海外に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
④【R2年出題】
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

【解答】
①【R4年出題】 ×
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子は、その被保険者と「同一の世帯」に属し、主としてその被保険者により生計が維持されていれば、被扶養者となります。世帯を別にしている場合は、被扶養者になりません。
(第3条第7項第3号)
②【H30年出題】 〇
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡し、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定されます。
(第3条第7項第4号)
③【R2年出題】 ×
被保険者の被扶養者である配偶者の父が被扶養者となるには、「被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する」ことが条件です。問題文の場合は、同一世帯要件を満たしていません。また、国内居住要件も満たしていません。
(第3条第7項第2号)
④【R2年出題】 〇
「外国に赴任する被保険者に同行する者」は、国内居住要件の例外として取り扱われます。
「外国に赴任する被保険者に同行する者」の確認は、「家族帯同ビザ」の確認により判断することを基本とします。
(令1.11.13保保発1113第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-194
R6.3.8 請負事業の一括のポイント!②分離編
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
引き続き「請負事業の一括のポイント」をチェックします。
昨日は、「一括編」でしたが、今日は「分離編」です。
ポイントをチェックしましょう!
・下請負事業を分離させることができます
・一括は「法律上当然に」行われますが、分離の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。なお、認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。
・分離する下請負事業は、一定以上の規模でなければなりません。
・分離の認可申請は、元請負人と下請負人が共同で行います。
条文を読んでみましょう。
第8条第2項 請負事業が一括された場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して下請負人をその請負に係る事業主とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして適用する。
則第8条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請) 下請負事業の分離の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、定められた事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
則第9条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準) 下請負事業の分離の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号に該当する事業(有期事業の一括の要件に該当する事業)以外の事業でなければならない。 |
★下請負事業の分離の認可を受けるための要件を確認しましょう。
下請負事業の規模が、
・概算保険料が160万円以上
又は
請負金額が1億8千万円以上
であることが必要です。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】(労災)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。
②【H27年出題】(労災)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

【解答】
①【H27年出題】(労災) ×
厚生労働省令で定める事業とは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」です。(則第7条)
元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の事業の規模が、「概算保険料の額に相当する額が160万円以上」、又は、「請負金額が1億8千万円以上」でなければなりません。
なお、請負金額から消費税額は除かれます。
(第8条第2項、則第7条、第9条)
②【H27年出題】(労災) ×
下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出します。ただし、「そのいずれかが単独で」ではなく、「元請負人及び下請負人が共同で」提出しなければなりません。
(則第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-193
R6.3.7 請負事業の一括のポイント!①一括編
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
今日は、「請負事業の一括」のポイントをチェックします。
まずポイントからどうぞ!
・対象は「建設の事業」です。(立木の伐採の事業は対象外です)
・建設の事業が数次の請負によって行われる場合、労災保険は下請負事業を元請負事業に一括して、保険関係が成立します。
・法律上当然に一括され、元請負人のみが適用事業主となります。
・一括されるのは労災保険の保険関係のみで、雇用保険の保険関係は一括されません。雇用保険の保険関係は、個別に成立します。
★建設の事業が数次の請負によって行われる場合のイメージ
<労災保険の保険関係> <雇用保険の保険関係>
元請負事業に一括されます 個別に成立します
元請負事業(成立) |
| 元請負事業(成立) |
↓ |
| ↓ |
下請負事業その1 |
| 下請負事業その1(成立) |
↓ |
| ↓ |
下請負事業その2 |
| 下請負事業その2(成立) |
↓ |
| ↓ |
下請負事業その3 |
| 下請負事業その3(成立) |
条文を読んでみましょう。
第8条第1項、則第7条 (請負事業の一括) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
②【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
③【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。
④【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。
⑤【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】(労災) ×
請負事業の一括の対象は「建設の事業」です。「立木の伐採の事業」は請負事業の一括の対象になりません。
(第8条第1項、則第7条)
②【R2年出題】(労災保険) ×
請負事業の一括は、「法律上当然に」行われます。「所轄労働基準監督署長に届け出ることによって」は誤りです。
(第8条第1項)
③【R2年出題】(労災保険) 〇
請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係」のみです。「雇用保険に係る保険関係」は一括されず、個別に適用されます。
(第8条第1項、則第7条)
④【R2年出題】(労災保険) ×
請負事業の一括が行われ元請負人のみが当該事業の事業主とされると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負います。
しかし、「労働関係の当事者」として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となることはありません。
(第8条第1項)
⑤【R2年出題】(労災保険) ×
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負います。
そのため、元請負人がこれを納付しないときでも、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、保険料を納付するよう請求することはできません。
(第8条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-192
R6.3.6 雇用保険法の違反行為に対する罰則
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第83条から第85条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
雇用保険法には、事業主に対する罰則(第83条)、労働保険事務組合に対する罰則(第84条)、被保険者、受給資格者等に対する罰則(第85条)があります。
雇用保険法の規定に違反する行為があった場合、行為者本人が罰せられるのはもちろんですが、「その法人又は人」に対しても罰金刑が科されます。両罰規定といいます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。
②【H24年出題】
「人」の代理人、使用人その他の従業者が、その「人」の業務に関して、雇用保険法第83条から第85条までの各号に掲げる違反行為をしたとき、行為者が罰せられるほか、その「人」に対しても雇用保険法第83条から第85条までに掲げる懲役刑が科せられることがある。

【解答】
①【R2年出題】 ×
雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(法第83条)
行為者を罰するだけでなく、「その法人又は人の業務」ですので、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。
(第86条)
②【H24年出題】 ×
行為者が罰せられるほか、その「法人又は人」に対しても「罰金刑」が科せられることがあります。
法人又は人に対しては、「懲役」ではなく「罰金」であることがポイントです。
(第86条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-191
R6.3.5 遺族補償年金の受給資格者と受給権者
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
★遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。
ただし、「妻」以外の者は、労働者の死亡の当時、「年齢要件」か「障害条件」に該当した場合に限られます。
要件に該当する者が「受給資格者」となります。
受給資格者には順位があり、年金を受けることができるのは受給資格者の中の最先順位者です。年金を受ける者を「受給権者」といいます。
順位は以下の通りです。
① | 妻(年齢要件、障害要件はありません) 夫(60歳以上又は一定の障害) |
② | 子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は一定の障害) |
③ | 父母(60歳以上又は一定の障害) |
④ | 孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は一定の障害) |
⑤ | 祖父母(60歳以上又は一定の障害) |
⑥ | 兄弟姉妹(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は60歳以上又は一定の障害) |
⑦ | 夫(55歳以上60歳未満) |
⑧ | 父母(55歳以上60歳未満) |
⑨ | 祖父母(55歳以上60歳未満) |
⑩ | 兄弟姉妹(55歳以上60歳未満) |
(第16条の2第1項、3項、昭40年法附則43条)
★転給とは?
最先順位者が失権した場合に、次の順位の者が受給権者になることです。
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。
②【R2年出題】
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。
③【H19年出題】
遺族補償年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
④【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「夫」は、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
「障害の状態にない50歳の夫」は、どちらにも当てはまりませんので、遺族補償年金の受給資格者になりません。
(第16条の2第1項)
②【R2年出題】 ×
「子」は「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
19歳の大学生は、年齢要件を満たしませんので、一定の障害状態にない場合は、受給資格者になりません。
17歳の高校生は、年齢要件を満たしますので、一定の障害状態になくても、受給資格者になります。
(第16条の2第1項)
③【H19年出題】 〇
「第5級以上」、「労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度」がキーワードです。
(則第15条)
④【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
「遺族補償年金」は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければなりません。
一方、「遺族補償一時金」は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなくても、受けられる可能性があります。
(第16条の2第1項、第16条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-190
R6.3.4 衛生管理者の資格要件
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第12条第1項 (衛生管理者) 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者の統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
令第4条 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
則第7条第3号 衛生管理者は次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 ①農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 ↓ ・第1種衛生管理者免許を有する者 ・衛生工学衛生管理者免許を有する者 ・第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) ② その他の業種 ↓ ・第1種衛生管理者免許を有する者 ・第2種衛生管理者免許を有する者 ・衛生工学衛生管理者免許を有する者 ・第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等) |
では、過去問をどうぞ!
①【令和1年選択式】
衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか< A >などが定められている。
(選択肢)
① 衛生管理士 ② 看護師 ③ 作業環境測定士
④ 労働衛生コンサルタント
②【H24年出題】
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。

【解答】
①【令和1年選択式】
A ④ 労働衛生コンサルタント
(則第10条3号)
②【H24年出題】 ×
先ほどの、①の業種と②の業種をもう一度確認しましょう。
「第2種衛生管理者免許」では、①の業種の衛生管理者には選任できません。
「製造業」は①の業種ですので、第2種衛生管理者免許を有する労働者でも他に資格等を有していない場合は、衛生管理者に選任することはできません。
ちなみに②のその他の業種の場合は、第2種衛生管理者免許を有する者を衛生管理者に選任できます。
(則第10条3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-189
R6.3.3 平均賃金のポイント!
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第12条第1項・2項 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と(1)の金額の合算額 ② 平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
★平均賃金の原則の計算式
3か月間に支払われた賃金の総額 |
その期間の総日数(暦日数) |
★平均賃金の最低保障額(賃金の全部が日給制、時間給制、出来高払制の場合)
賃金の総額 | × | 60 |
労働した日数 | 100 |
第12条第3項・4項 ③ 平均賃金の算定期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除する。 (1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 (2) 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 (3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 (4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間 (5) 試みの使用期間 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 |
★③は「分子」(賃金総額)からも、「分母」(総日数)からも控除します
★④は、「分子」(賃金総額)からのみ控除します。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
②【H27年出題】
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
③【H27年出題】
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
④【H27年出題】
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
⑤【H27年出題】
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
賃金の総額に算入しない賃金は、
・臨時に支払われた賃金
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金(現物給与)で一定の範囲に属しないもの
です。
「通勤手当及び家族手当」は賃金総額に含みます。
(第12条第4項)
②【H27年出題】 ×
「公民権の行使により休業した期間」は、休業した期間の日数も賃金も平均賃金の計算に算入します。
賃金総額・その期間の日数の両方から控除されるのは以下の期間です。
(1) 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
(2) 産前産後の女性の休業期間
(3) 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
(4) 育児休業、介護休業期間
(5) 試用期間
(第12条第4項)
③【H27年出題】 ×
労働基準法施行規則第48条で、「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」と定められていますので、「死亡した日」は誤りです。
(則第48条)
④【H27年出題】 〇
「平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。」と規定されています。
賃金締切日が毎月月末で、7月31日に算定事由が発生した場合は、直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となります。
(第12条第2項)
⑤【H27年出題】 ×
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、それぞれの賃金ごとの賃金締切日から起算します。
6月25日に算定事由が発生した場合、
基本給(毎月月末締め)は、5月31日から遡った3か月
時間外手当(毎月20日締め)は、6月20日から遡った3か月
となります。
(S26.12.27基収5926号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-188
R6.3.2 国民健康保険法 保険料を滞納した場合
過去問から学びましょう。
今日は国民健康保険法です。
条文を読んでみましょう
第9条第3項、6項、則第5条の6 市町村は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 |
※ 世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付します。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除かれます。(第9条第6項)
※国民健康保険組合にも準用されます。(第22条)
第63条の2第1項、3項、則第32条の2 ① 市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 ③ 市町村及び組合は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。
②【R1年出題】
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。
③【R1年出題】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
④【R2年出題】
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

【解答】
①【H28年選択式】
A 1年間
B 被保険者資格証明書
★流れをおさえましょう。
保険料を1年間滞納した
↓
市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求める
↓
被保険者証を返還する
↓
市町村は被保険者資格証明書を交付する
(第9条第3項、6項、則第5条の6)
②【R1年出題】 ×
1年間保険料を滞納し、被保険者証を返還すると、被保険者資格証明書が交付されます。
しかし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(問題文の場合は15歳の子)には、「有効期間を6か月とする被保険者証」が交付されます。
(第9条第6項)
③【R1年出題】 ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養費ではなく「特別療養費」が支給されます。
被保険者資格証明書で療養を受けた場合は、病院等の窓口で医療費を全額支払い、後から一部負担金を引いた分が支給されます。これを特別療養費といいます。
(第54条の3)
④【R2年出題】 〇
★流れを確認しましょう。
・納期限から1年6か月以上保険料を滞納している
↓
・市町村は保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める
↓
・なお滞納している保険料を納付しない
↓
・市町村は一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができる
(第63条の2第1項、3項、則第32条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-187
R6.3.1 就労条件総合調査 労働時間制度
過去問から学びましょう。
今日は労働に関する一般常識です。
令和5年「就労条件総合調査」の結果より、「労働時間制度」をみていきましょう。
(週休制) 主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 85.4%(令和4年調査 83.5%)となっており、さらに「完全週休2日制」を採用している企業割合は 53.3%(同48.7%)となっている。 「完全週休2日制」を採用している企業割合を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 68.1%、「300~999 人」が 60.0%、「100~299 人」が 52.2%、 「30~99 人」が 52.5%となっている。
(変形労働時間制の採用状況) 変形労働時間制を採用している企業割合は 59.3%(令和4年調査 64.0%)となっており、これを企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 77.3%、「300~999 人」が 68.6%、「100~299 人」が 67.9%、「30~99 人」が 55.3%となっている。 また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 31.5%、「1か月単位の変形労働時間制」が 24.0%、「フレックスタイム制」が 6.8%となっている。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
②【R4年出題】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超えるようになった。
③【R4年出題】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」よりも多くなっている。
④【H28年出題】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【解答】
①【H28年出題】 ×
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えています。
完全週休2日制は、30~99人規模の企業では「52.5%」ですので、「3割にとどまっている」は誤りです。
②【R4年出題】 ×
企業規模計でみると、完全週休2日制を採用している企業割合は53.3%で、6割は超えていません。
③【R4年出題】 〇
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している企業の割合は59.3%です。
変形労働時間制の種類(複数回答)別では、「1年単位の変形労働時間制」が31.5%、「1か月単位の変形労働時間制」が24.0%です。
④【H28年出題】 ×
フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.8%です。3割は超えていません。
参照 厚生労働省 令和5年就労条件総合調査 結果の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-186
R6.2.29 就労条件総合調査 年次有給休暇の取得状況
過去問から学びましょう。
今日は労働に関する一般常識です。
令和5年「就労条件総合調査」の結果より、「年次有給休暇の取得状況」をみていきましょう。
令和4年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1 人平均は 17.6 日、このうち労働者が取得した日数は 10.9 日で、取得率は 62.1%となっており、昭和 59 年以降過去最高となっている。 取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が 74.8%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 49.1%と最も低くなっている。 (令和5年「就労条件総合調査」の結果より) |
企業規模別の取得率もみておきましょう。
企業規模 | 労働者1人 平均取得率 |
令和5年調査計 | 62.1% |
1,000人以上 | 65.6% |
300~999人 | 61.8% |
100~299人 | 62.1% |
30~ 99人 | 57.1% |
(令和5年「就労条件総合調査」の結果より)
過去問と練習問題をどうぞ!
①過去問【R2年選択式】※問題文修正しています
我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには雇用動向調査、年次有給休暇の取得率を知るには< A >、男性の育児休業取得率を知るには雇用均等基本調査が使われている。
②【練習問題】
令和5年「就労条件総合調査」によると、労働者1 人平均の年次有給休暇の取得率は < B >%となっており、昭和 59 年以降過去最高となっている。
(選択肢)
① 53.1 ② 62.1 ③ 73.3 ④ 81.2

【解答】
①過去問【R2年選択式】
A 就労条件総合調査
②【練習問題】
B ② 62.1
参照 厚生労働省 令和5年就労条件総合調査 結果の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/23/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-185
R6.2.28 年金の支給期間と支払期月
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第36条 (年金の支給期間及び支払期月) ① 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 ② 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 ③ 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 |
年金の支給・支給停止は、月単位で行われ、「翌月」から「消滅月」までです。
3月 | 4月 | ~ | 10月 | 11月 |
受給権発生 | 開始 | 消滅 |
|
例えば、3月に年金の受給権が発生し10月に権利が消滅した場合は、年金は4月から10月まで支給されます。
年金は、6期にわけて偶数月に支払われ、後払いです。例えば、2月に支払われる年金は、12月分と1月分です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
年金は、年6期に分けて偶数月にそれぞれの前月分までが支払われることとなっており、前支払期月に支払うべきであった年金についても次の偶数月に支払われ、奇数月に支払われることはない。
②【H28年出題】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
③【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする」という例外があります。例えば、さかのぼって過去の分が支払われる場合などは、奇数月に支払われることがあります。
(第36条第3項)
②【H28年出題】 ×
障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合は、「障害認定日」に障害厚生年金の受給権が発生します。そのため、障害厚生年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
障害認定日が月の初日でも、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。
(第36条第1項)
③【H30年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、死亡した日の翌日(翌月の1日)に資格を喪失します
一方、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生し、遺族厚生年金は死亡した日の属する月の翌月から支給されます。
(第14条第1号、第36条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-184
R6.2.27 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
厚生年金保険の被保険者は4つの種別に分かれています。(第2条の5第1項)
第1号厚生年金被保険者
→ 第2号から第4号以外の被保険者(民間企業の会社員等)
第2号厚生年金被保険者
→ 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第3号厚生年金被保険者
→ 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
第4号厚生年金被保険者
→ 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
今日は、異なる被保険者の種別に係る資格の得喪です。
条文を読んでみましょう。
第18条の2 ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日に当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者の資格が同時に適用されることはありません。「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「当日喪失」がポイントです。
(第18条の2)
②【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合は、「その日」に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。「選択」することはありませんので、2以上事業所選択届の届出は不要です。
(第18条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-183
R6.2.26 振替加算その2 振替加算が支給停止されるとき
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
昨日は、「振替加算が行われないとき」をみましたが、今日は振替加算の支給停止をみていきます。
★ 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止されます。 (第16条第1項) |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
②【R1年出題】
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで第2号被保険者期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。
③【R3年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H30年出題】 〇
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金等を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止されます。
ただし、障害基礎年金、障害厚生年金等が全額支給停止になっている場合は、振替加算は支給停止されません。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第28条)
②【R1年出題】 〇
障害基礎年金を受給している間は、振替加算は支給停止されます。
ただし、障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合は、障害基礎年金は全額支給停止になりますので、老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第28条)
③【R3年出題】 ×
振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときでも、振替加算は支給停止されません。
(昭60年法附則第14条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-182
R6.2.25 振替加算その1 振替加算が行われないとき
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
振替加算が行われる者の条件を確認しましょう。
・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 ・配偶者の年金の加給年金額の対象になっていたこと (配偶者が次の年金の受給権者であること(加給年金額が加算されるもの)) (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。=1・2級) ・振替加算の額 224,700円×改定率×その者の生年月日に応じて政令で定める率 |
今日は、「振替加算が行われないとき」のルールをみていきます。
★ 老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は加算されません。
(昭60年法附則第14条第1項)
加給年金額と振替加算のイメージ図
(例)夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算され、妻に振替加算が加算される場合
(63歳) (65歳)
夫 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金(240月以上) | |
|
| 老齢基礎年金 | |
|
| 加給年金額 |
|
|
|
| 65歳 |
妻 |
|
| 老齢厚生年金 |
|
|
| 老齢基礎年金 |
|
|
| 振替加算 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題 】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
②【H27年出題】
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
①【H30年出題 】 〇
老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は加算されません。
政令で定められている老齢厚生年金は、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上(20年以上)あるものです。
なお、中高齢の期間短縮特例を満たす場合は、15~19年となります。
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第25条)
②【H27年出題】 〇
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
この期間には、「離婚時みなし被保険者期間」も算入します。
離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第25条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-181
R6.2.24 <健保>正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき(横断もあり)
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
第122条 第116条、第117条、第118条第1項及び第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。 |
ポイント!
「全部又は一部」ではなく、「一部」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
②【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
③【R2年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「一部」を行わないことができる」です。
(第119条)
②【H30年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる」です。全部ではありません。
被扶養者にも準用されます。
(第119条、第122条)
③【R2年出題】 〇
「療養の指示に従わない者」とは
(1)保険者又は療養担当者の療養の指示に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者
(2)診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる者
とされています。
(昭26.5.9保発第37号)
(横断編) 他の科目の過去問もどうぞ!
<労災保険H26年出題>
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
<国民健康保険R3年出題>
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

【解答】
<労災保険H26年出題> 〇
「正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる」です。「全部又は一部」がポイントです。
条文を読んでみましょう。
労災保険法第12条の2の2第2項 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
<国民健康保険R3年出題> 〇
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の「一部」を行わないことができる」です。健康保険法と同じく「一部」がポイントです。
条文を読んでみましょう。
国民健康保険法第62条 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
ご質問のお返事です 労働保険徴収法
R6-180
R6.2.23 メリット制が適用された場合の労災保険率
今日は、いただきましたご質問のお返事です。
ご質問の内容です。
| 継続事業にかかるメリット制が適用された場合の労災保険率の引き上げ、引き下げの意味がよくわかりません。 |
労災保険率は、労災発生のリスクによって「事業の種類」ごとに、1000分の2.5から1000分の88の範囲で決められています。
ただし、事業の種類が同じでも、労災が発生する会社もあれば、発生しない会社もあります。
例えば、大きな労働災害が発生した事業場(=労災保険から保険給付が行われた)も、労働災害が発生しなかった事業場(=労災保険から保険給付を受けていない)も、「事業の種類」が同じなら、労災保険率も同じです。
しかし、メリット制が適用されると、災害率が高い場合は、労災保険率が引き上げられ、逆に低い場合は、労災保険率が引き下げられますので、保険料負担の公平性が保たれます。
■では、継続事業と一括有期事業にメリット制が適用される条件を確認しましょう。
①事業の継続性を満たすこと
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)に労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していること
②事業の規模を満たすこと
連続する3保険年度中の各保険年度に次の(A)~(C)のいずれかに該当する事業であること
(A) 100人以上の労働者を使用する事業
(B) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、災害度係数が0.4以上であるもの
(C) 一括有期事業は、各保険年度において確定保険料の額が40万円以上
■次に、メリット制が適用される時期を確認しましょう。
・基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から適用されます。
①年度 | ②年度 | ③年度 | ④年度 | ⑤年度 |
連続する3保険年度 (収支率を算定) |
| メリット制適用 | ||
|
| ③年度の3/31(基準日) |
|
|
■「収支率」を確認しましょう。
メリット収支率は、簡単に言いますと、連続する3保険年度中の「保険料に対する保険給付の割合」です。
メリット収支率は、保険料も保険給付も「業務災害」に関する部分で計算するのがポイントです。
保険給付+特別支給金 |
保険料 |
★メリット収支率が85%超える場合
→ 保険給付の割合が高い=災害発生率が高いということです。継続事業では、労災保険率が最大で40%引き上げられます。
★メリット収支率が75%以下の場合
→ 保険給付の割合が小さいので、継続事業では労災保険率が最大で40%引き下げられます。
★メリット収支率が75%超え85%以下の場合
→労災保険率の引上げ引き下げはありません。
■メリット制が適用された場合の労災保険率を確認しましょう。
例えば、労災保険率が1000分の9の場合、そのうち1000分の0.6は非業務災害率で、1000分の8.4が業務災害に当たる率です。なお、非業務災害率は、全事業共通です。
メリット制で引上げ引き下げの対象になるのは、「業務災害」に当たる部分の率です。
例えば、業務災害が起こらなかった事業(労災の保険給付が行われなかった事業)の場合、メリット収支率は0となり、労災保険率のうち、非業務災害率を除いた率が40%引き下げられます。
9-0.6 | × | 100-40 | + | 0.6 |
1000 | 100 |
| 1000 | |
↑ 非業務災害率を除いた率 |
| ↑ 40%減 |
| ↑ 非業務災害率 |
基準日の属する保険年度の次の次の保険年度からの労災保険率は、1000分の5.64になります。非業務災害率はメリット制の対象になりませんが、労災保険率には入りますので、注意しましょう。
では、次にメリット収支率が180%の場合です。労災保険率のうち、非業務災害率を除いた率が40%引き上げられます。
9-0.6 | × | 100+40 | + | 0.6 |
1000 | 100 |
| 1000 | |
↑ 非業務災害率を除いた率 |
| ↑ 40%増 |
| ↑ 非業務災害率 |
基準日の属する保険年度の次の次の保険年度からの労災保険率は、1000分の12.36になります。
では、過去問もどうぞ!
①【R2年出題(労災)】
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引上げ引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
②【R2年出題(労災)】
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
③【R2年出題(労災)】
労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。

【解答】
①【R2年出題(労災)】 〇
雇用保険率には、メリット制はありません。
(第12条第3項)
②【R2年出題(労災)】 〇
メリット収支率の分子は、業務災害に係る保険給付ですが、「特別支給金で業務災害に係るもの」も含みます。
(第12条第3項)
③【R2年出題(労災)】 〇
メリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となります。
(第12条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-179
R6.2.22 介護休業給付金の基本問題
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう
第61条の4 第1項、第6項(介護休業給付金) ① 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族を介護するための休業(以下「介護休業」という。)をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間(原則)に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
⑥ 被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。 (1) 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業 (2) 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業 |
※ 介護休業給付金は、介護休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
「2年間」が原則ですが、当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)となります。
過去問をどうぞ!
【H30年出題】
本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
① 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
② 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
③ 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
④ 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

【解答】
【H30年出題】
① ×
同一の対象家族について取得した介護休業は、「93日」を限度に「3回」まで介護休業給付金の対象になります。
例えば、60日間介護休業を取得した後復帰し、同一の対象家族について2回目の介護休業を取得した場合は、33日が限度となります。
介護休業 (1回目) |
| 介護休業 (2回目) |
60日 |
| 33日 |
同一の対象家族について当該被保険者が「4回以上」の介護休業をした場合における「4回目」以後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。
(第61条の4第6項、行政手引59802)
※介護休業給付金の支給額は、「支給単位期間」単位で計算します。
※「支給単位期間」とは、介護休業開始日から1か月ごとに区切った期間で、介護休業を開始した日から起算して3か月を経過する日までの期間に限られます。介護休業給付金の対象になる1回の休業期間は、最長で3か月です。
② ×
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれます。
■介護休業は、「対象家族」を介護するための休業です。「対象家族」を確認しましょう。
・ 被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母(実父母のみならず養父母を含む。)、子(実子のみならず養子を含む。)、配偶者の父母(実父母のみならず養父母を含む。)
・被保険者の、祖父母、兄弟姉妹、孫
(第61条の4第1項、行政手引59802)
③ ×
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が「93日」に達した日後の介護休業については、介護休業給付金は支給されません。
(第61条の4、第6項)
④ 〇
例えば「父」の介護で介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰した後、他の対象家族(母)に対する介護休業を取得する場合、他の対象家族(母)に係る介護休業開始日に受給資格を満たせば、他の対象家族(母)に係る介護休業給付金を受給することができます。その場合、先行する対象家族(父)に係る介護休業取得回数は関係ありません。
(行政手引59861)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働者災害補償保険法
R6-178
R6.2.21 心理的負荷による精神障害の認定基準について
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
仕事が原因のストレス(業務による心理的負荷)で発病した精神障害については、労災認定の基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。
要件を満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
ちなみに、労働基準法施行規則別表第1の2第9号は、「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
②【H30年出題】
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。
③【H30年出題】
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。
④【H30年出題】
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
認定基準においては、「ハラスメントやいじめのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

【解答】
①【H30年出題】 〇
★精神障害の認定要件について
精神障害の認定の要件は①、②、③のいずれも満たすことです。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
②【H30年出題】 ×
★業務による強い心理的負荷の有無の判断について
精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価するとされています。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
③【H30年出題】 ×
★業務による心理的負荷評価表について
「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分されます。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
④【H30年出題】 ×
★長時間労働等の心理的負荷の評価について
発病直前の1か月におおむね「160」時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とするとされています。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
⑤【H30年出題】 ×
★業務による心理的負荷の評価期間について
業務による心理的負荷の評価期間は発病前おおむね6か月です。
しかし、心理的負荷を的確に評価するため、ハラスメントやいじめのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、「開始時からのすべての行為」を評価の対象とするとされています。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-177
R6.2.20 定期自主検査について
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第45条第1項、2項 (定期自主検査) ① 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 ② 事業者は、①の機械等で政令で定めるものについて特定自主検査を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。 |
① 定期自主検査が義務づけられている機械は、施行令第15条第1項に定められています。なお、「特定機械等」も定期自主検査の対象です。
② 特に検査が技術的に難しい機械には「特定自主検査」が義務づけられています。特定自主検査は、一定の資格を有する労働者又は検査業者が実施しなければなりません。
「特定自主検査」の対象は、以下の機械です。(施行令第15条第2項)
・フォークリフト
・車両系建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
・不整地運搬車
・作業床の高さが2メートル以上の高所作業車
・動力により駆動されるプレス機械
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。
②【H30年出題】
事業者は、現に使用しているフォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、最大荷重が1トン未満のフォークリフトは除かれている。
③【H30年出題】
屋内作業場において、有機溶剤中毒予防規則に定める第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等を用いて行う印刷の業務に労働者を従事させている事業者は、当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置について、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければならない。
④【H30年出題】
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
⑤【H30年出題】
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
動力プレスは、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行わなければなりません。「加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレス」は除かれていません。
(施行令第15条第1項第2号、則第134条の3)
②【H30年出題】 ×
フォークリフトについては、1年を超えない期間ごとに1回、定期に自主検査を行わなければなりません。「最大荷重が1トン未満のフォークリフト」は除かれていません。
(則第151条の21)
③【H30年出題】 〇
当該有機溶剤作業を行っている場所で稼働させている局所排気装置については、1年以内ごとに1回、定期に、定められた事項について自主検査を行わなければなりません。
(有機溶剤中毒予防規則第20条)
④【H30年出題】 ×
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の対象です。特定自主検査は、「その使用する労働者で一定の資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければなりません。
(第45条第2項)
⑤【H30年出題】 ×
定期自主検査の結果の記録は、「3年間」保存しなければなりません。
(則第135条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-176
R6.2.19 1週間の労働時間を44時間とする特例
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について 8時間を超えて、労働させてはならない。
則第25条の2第1項 (法第40条) 使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。 第8号 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業) 第10号 映画・演劇業(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業) 第13号保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業) 第14号接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業) |
法定労働時間が1週間44時間となる特例が適用されるのは、以下の業種です。
常時10人未満の
・商業
・映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)
・保健衛生業
・接客娯楽業
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。
②【H18年出題】
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
労働時間の特例は、1週間について「44時間」、1日について「8時間」までです。
(法第32条、40条、則第25条の2第1項)
②【H18年出題】 〇
物品の販売の事業は、法別表第1第8号の事業です。常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。
(法第32条、40条、則第25条の2第1項)
こちらもチェックしましょう。
・ 「1か月単位の変形労働時間制」と「フレックスタイム制」には、44時間の特例が適用されます。
例えば、1か月単位の変形労働時間制の変形期間の労働時間の総枠を計算する場合、特例対象の事業の場合は、44時間×変形期間の暦日数/7で計算します。
・ 「1年単位の変形労働時間制」と「1週間単位の非定型的変形労働時間制」には、44時間の特例は適用されません。
(H11.3.31基発170号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-175
R6.2.18 障害者雇用促進法 障害者に対する差別の禁止等
過去問から学びましょう。
今日は障害者雇用促進法です。
条文を読んでみましょう。
第34条 (障害者に対する差別の禁止) 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
第35条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
第36条の2(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置) 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
第36条の3 事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
②【R1年出題】
事業主は、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。
③【R3年出題】
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。
④【R4年出題】
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「全ての事業主は、法第34条及び第35条の規定に基づき、労働者の募集及び採用について、障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。)に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならず、また、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。」とされています。
(平27.3.25厚生労働省告示第116号)
②【R1年出題】 〇
「事業主と障害者の相互理解の観点から、事業主は、応募しようとする障害者から求人内容について問合せ等があった場合には、当該求人内容について説明することが重要である。また、募集に際して一定の能力を有することを条件としている場合、当該条件を満たしているか否かの判断は過重な負担にならない範囲での合理的配慮(法第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置をいう。)の提供を前提に行われるものであり、障害者が合理的配慮の提供があれば当該条件を満たすと考える場合、その旨を事業主に説明することも重要である。」とされています。
(第36条の2、平27.3.25厚生労働省告示第116号)
③【R3年出題】 〇
「合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない」とされています。
(平27.3.25厚生労働省告示第117号)
④【R4年出題】 〇
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当しません。
(平27.3.25厚生労働省告示第116号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険労務士法
R6-174
R6.2.17 紛争解決手続代理業務について
過去問から学びましょう。
今日は社会保険労務士法です。
条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。 ③ 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 (1) 紛争解決手続について相談に応ずること。 (2) 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 (3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< A >を行うことが含まれている。
ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < B >に合格し、かつ社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< C >社会保険労務士に限られる。
<選択肢>
①あっせん ②裁判所への提訴 ③和解の交渉 ④調停
⑤紛争解決手続代理業務試験 ⑥特定社会保険労務士試験 ⑦特認紛争解決業務試験 ⑧紛争解決手続業務試験 ⑨上級 ⑩特定 ⑪特認 ⑫上席
②【H23年出題】
具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。
③【R1年出題】
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

【解説】
①【H19年選択式】
A ③和解の交渉
B ⑤紛争解決手続代理業務試験
C ⑩特定
(法第2条)
②【H23年出題】 ×
法第2条第3項第1号に規定する「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の「相談」です。
このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことはできません。
(平成19.3.26/厚生労働省基発第0326009号/庁文発第0326011号/)
③【R1年出題】 ×
紛争調整委員会におけるあっせんの手続について相談に応じること、あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができるのは、「特定社会保険労務士」に限られます。
(法第2条第2項、3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-173
R6.2.16 老齢厚生年金の支給要件
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。 (1) 65歳以上であること。 (2) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
老齢厚生年金は、「厚生年金保険の被保険者期間」があり、「65歳以上」で、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上ある(=老齢基礎年金を受けることができる)」場合に支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
②【H30年出題】
老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
■65歳以上が対象の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、要件を満たします。
■60歳以上65歳未満が対象の特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要です。
(法第42条、法附則第8条)
②【H30年出題】 ×
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときで、その月にさらに被保険者の資格を取得していない場合は、その月は1か月として被保険者期間に算入されます。(同月得喪といいます。)
問題文は、老齢基礎年金を受給している66歳の者が、厚生年金保険の被保険者期間を1か月有することになり、要件を満たしますので、老齢厚生年金が支給されます。
(法第19条第2項、第42条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-172
R6.2.15 遺族基礎年金の保険料納付要件
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第37条 (支給要件) 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、(1)又は(2)に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 (1) 被保険者が、死亡したとき。 (2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。 (3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 (4) 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
★遺族基礎年金の保険料納付要件
(1)か(2)に該当する場合は、保険料納付要件が問われます。
(原則)
死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
(特例) S60法附則第20条第2項
・死亡日が令和8年4月1日前にあること
・死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと
・死亡日において65歳未満であること
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
②【R4年出題】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
問題文は、保険料納付要件の特例を満たします。
■死亡日が令和8年4月1日前にあること
↓
死亡日は平成30年4月2日
■死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと
↓
平成30年4月1日(死亡日の前日)に、平成29年3月から平成30年2月までの期間(死亡日の属する月の前々月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料の未納期間がない)
H30年4月 | H30年3月 | H30年2月 | ~~~~~~ | H29年3月 |
死亡 |
| 死亡日の属する月の前々月までの1年間 | ||
■死亡日において65歳未満であること
↓
第1号被保険者が死亡(死亡日に20歳以上60歳未満)
(S60法附則第20条第2項)
②【R4年出題】 ×
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者の場合は、第37条の(4)の条件を満たします。
(3)、(4)に該当する場合は、保険料納付要件は問われませんので、死亡日の前日に、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合でも、遺族基礎年金は支給されます。
(第37条第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-171
R6.2.14 資格喪失後の出産育児一時金
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付) 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |
資格喪失後の出産について、出産育児一時金を受けることができる条件は次のとおりです。
・資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと
・資格を喪失した日後6月以内に出産したこと
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給できることとなる。
②【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
③【H30年出題】
被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
例えば、ある人が会社を退職した後、会社員の夫の健康保険の被扶養者となりました。
資格喪失後6か月以内に出産した場合、被保険者本人としての出産育児一時金を受けるか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受けるかは、請求者の選択によります。
(昭48.117保険発99号)
②【H28年出題】 ×
1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者が、第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給が行われます。
なお、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける場合には、国民健康保険の保険者は出産育児一時金の支給を行いません。
(平23.6.3保保発0603第2号/保国発0603第2号/)
③【H30年出題】 ×
まず、条文を読んでみましょう。
第107条 (船員保険の被保険者となった場合) 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。 |
資格喪失後に船員保険の被保険者になった場合は、資格喪失後の出産育児一時金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-170
R6.2.13 継続事業の一括のポイント!
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
★「継続事業の一括」のイメージは?
例えば、株式会社A銀行には、東京本社、北海道支店、大阪支店、福岡支店があります。
労働保険徴収法は、それぞれで適用されるのが原則です。
ただし、厚生労働大臣の認可を受けた場合は、保険関係を指定事業に一括することができます。
例えば、本社で支店の給料計算もまとめて行っている場合に、本社を指定事業として、支店の分も一括して労働保険料の申告手続きができるようになります。
条文を読んでみましょう。
第9条 (継続事業の一括) 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(労災)
事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。
②【R5年出題】(労災)
継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない。
③【R5年出題】(労災)
継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
④【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(「指定事業」という。)以外の事業にかかる保険関係は、消滅する。
⑤【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

【解答】
①【R5年出題】(労災) 〇
ポイント!
「継続事業の一括」は、当然に行われるのではなく「厚生労働大臣の認可」が必要です。
(第9条)
なお、継続事業の一括に係る厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。(則第76条)
②【R5年出題】(労災) 〇
継続事業の一括の要件として、以下の要件があります。
■それぞれの事業が、次の①から③までのいずれか一のみに該当するものであること。
①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
②雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
問題文は、①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業ですので、一括されません。
(則第10条第1項第1号)
③【R5年出題】(労災) ×
継続事業の一括の要件として、「それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくすること」があります。
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についても、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要があります。
(則第10条第1項第2号)
④【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、保険関係は、指定事業に一括され、すべての労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされます。
そのため、指定事業以外の事業にかかる保険関係は、消滅します。
指定事業以外の事業は、保険関係の消滅により、労働保険料の確定精算の手続が必要になります。
(第9条)
⑤【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括が行われ保険関係が一括されても、労災保険給付の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は一括されません。
労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、それぞれの事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-169
R6.2.12 特定受給資格者の範囲
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう
第23条第2項 特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く。)をいう。 (1) 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (2) 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 |
「特定受給資格者」には(1)倒産等により離職した者、(2)解雇等により離職した者があります。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
②【H30年出題】
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
③【H30年出題】
離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
④【H30年出題】
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当する。
⑤【H30年出題】
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
⑥【R3年出題】
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
⑦【R3年出題】
常時介護を必要とする親族と同居する労働者が、概ね往復5時間以上を要する遠隔地に転勤を命じられたことにより離職した場合、当該転勤は労働者にとって通常甘受すべき不利益であるから、特定受給資格者に該当しない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第5号ホ)
②【H30年出題】 〇
「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号)
③【H30年出題】 ×
次のいずれかに該当する場合は、特定受給資格者に該当します。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由に離職した者。
・ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことを理由に離職した者。
問題文は、どちらにも該当しませんので、特定受給資格者に該当しません。
(則第36条第5号ロ、ハ)
④【H30年出題】 〇
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第35条第2号)
⑤【H30年出題】 〇
★「期間の定めのある労働契約」について、以下のどちらかに該当する場合は特定受給資格者に該当します。
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。
(則第36条第7号)
⑥【R3年出題】 ×
事業所の廃止に伴い離職した者は特定受給資格者に該当します。
ただし、「事業所の廃止」については、「当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。」とされていますので、問題文の場合は、特定受給資格者に該当しません。
(則第35条第3号)
⑦【R3年出題】 ×
家庭的事情(常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等の事情がある場合をいいます。)を抱える労働者が、遠隔地(往復所要時間が概ね4時間以上)に転勤を命じられた等を理由に離職した場合は、特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号、行政手引50305)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-168
R6.2.11 休業補償給付の基本問題
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
休業補償給付の条文を読んでみましょう。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。・・・(※以下省略します。) |
休業補償給付は、以下の要件を満たした場合に支給されます。
・「業務上」の傷病による療養のため
↓
・労働することができないため
↓
・賃金を受けない
休業補償給付の額は、1日当たり給付基礎日額の100分の60で、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
②【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
③【H30年出題】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
④【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
⑤【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
療養補償給付は、療養中に受けられる治療等のことです。休業補償給付は療養中に受けられる所得補償です。目的が違いますので同時に受けることができます。
(法第13条、第14条)
②【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも療養中に受けられる所得補償ですので、同時に支給されることはありません。
(法第18条第2項)
※ 年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。
例えば、1月に傷病補償年金を支給すべき事由が生じた場合は、傷病補償年金は2月から支給され、1月中は「休業補償給付」が支給されます。
③【H30年出題】 〇
労働基準法では、業務災害について補償を行うことを使用者に義務付けています。(災害補償といいます)
労働基準法第76条第1項では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。」と規定されています。
なお、労働基準法の災害補償の事由について、労働者災害補償保険法から労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれる場合は、使用者は災害補償を行う責を免れます。(労働基準法第84条)
そのため、労災保険から休業補償給付が行われるときは、事業主は、労働基準法の休業補償を行う義務はなくなります。
ただし、休業の初日から第3日目までの期間は、労災保険の休業補償給付が行われませんので、事業主は労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。
(労基法第76条、第84条)
ちなみに、通勤災害、複数業務要因災害には、労働基準法の災害補償責任はありません。
④【H30年出題】 ×
休業補償給付は、会社の所定休日にも支給されます。
⑤【H30年出題】 〇
「平均賃金の100分の60以上の金額」が支払われている場合は、「休業する日」に該当しません。
所定労働時間の全部労働不能の労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、「休業する日」に該当しないので、休業補償給付は支給されません。
(昭40.9.15基災発第14号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-167
R6.2.10 定期健康診断のポイント!
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
「定期健康診断」について条文を読んでみましょう。
則第44条第1項 (定期健康診断) 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 (1) 既往歴及び業務歴の調査 (2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 (3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 (4) 胸部エックス線検査及び 喀痰 検査 (5) 血圧の測定 (6) 貧血検査 (7) 肝機能検査 (8) 血中脂質検査 (9) 血糖検査 (10) 尿検査 (11) 心電図検査 |
ポイント!
全労働者が対象ではなく「常時使用する労働者」が対象です。
なお、健康診断には、労働者一般が対象の「一般健康診断」と、特定の有害な業務に従事する労働者が対象の「特殊健康診断」があります。
則第44条の定期健康診断は一般健康診断です。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
②【R1年出題】
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
③【H27年出題】
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
④【R1年出題】
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
パート労働者等は、次の(1)と(2)の両方に当てはまる場合は、「常時使用する労働者」として一般健康診断の対象になります。
(1)期間の定めのない契約により使用される
※「期間の定めのある契約」により使用される者については、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者は(1)に該当します。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である
問題文は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働き、「1年限り(=1年以上)」の契約ですので、(1)と(2)の両方に該当し、一般健康診断の対象となります。
(平19.10.1基発第1001016号)
②【R1年出題】 〇
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「4分の3以上」の場合に課せられます。
ただし、1週間の労働時間数が当該事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の「おおむね2分の1以上」である者に対しても実施することが望ましいとされています。
(平19.10.1基発第1001016号)
③【H27年出題】 〇
★健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて
・労働者一般が対象の「一般健康診断」は労働時間になりません。
→ 一般的な健康の確保をはかることを目的としています。業務遂行との関連において行なわれるものではありませんので、受診のために要した時間は、当然には事業者の負担すべきものとされていません。
・特定の有害な業務に従事する労働者が対象の「特殊健康診断」は「労働時間」となります。
→ 事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のもので、所定労働時間内に行なわれるのを原則とします。また、特殊健康診断の実施に要する時間は「労働時間」と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない、とされています。
(昭47.9.18基発第602号)
④【R1年出題】 ×
法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものとされています。
(昭47.9.18基発第602号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-166
R6.2.9 1か月単位の変形労働時間制の採用ルール
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
1か月単位の変形労働時間制について条文を読んでみましょう。
第32条の2 ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間・特例44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間(特例44時間)又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
★ 1か月単位の変形労働時間制は、「1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間・特例44時間)を超えない」ことが条件です。
変形期間の所定労働時間の総枠は、次のように計算します。この範囲内なら平均すると1週間当たりの労働時間は、法定労働時間以内になります。
1週間の法定労働時間 (40時間・特例44時間) |
× | 変形期間の暦日数 |
7 |
例えば、法定労働時間が40時間の事業場で、変形期間を1か月とし暦日数が31日の場合の総枠は、40時間×31日/7=177.1時間となります。
1か月の総労働時間が177.1時間以内なら、特定された週に40時間又は特定された日に8時間を超えて労働させることができます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。
③【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
④【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。
⑤【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」又は「労使協定」のどちらかで採用できます。
ちなみに、10人以上の事業場は、就業規則の作成義務がありますので、「就業規則に準ずるもの」では採用できません。10人以上の事業場は、「就業規則」又は「労使協定」のどちらかになります。
「その他これに準ずるもの」は10人未満の事業場のみに適用されます。
また、10人以上でも10人未満でも、1か月単位の変形労働時間制を「労使協定」で採用する場合は、協定を所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。届出義務はありますが、届出をしなくても効力は発生します。そのため、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。」は誤りです。
(法第32条の2)
②【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、その期間の起算日を定める必要があります。
変形期間を1か月とする場合、毎月1日から月末までの暦月という要件はありません。
ちなみに、変形期間は1か月以内なら、例えば、2週間、4週間なども可能です。
(則第12条の2)
③【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、変形期間の所定労働時間の合計が40(又は44)×変形期間の暦日数/7の範囲内となることが条件です。
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度や1週間の労働時間の限度は定められていません。
(S63.1.1基発第1号)
④【R1年出題】 〇
★1か月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間です。
①1日について
→ 就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週間について
→ 就業規則その他これに準ずるものにより40時間(特例44時間)を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間(特例44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③ 変形期間について
→ 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
問題文の場合、「1日6時間」の日ですので、①の「それ以外の日」に当たり、時間外労働となるのは、「8時間を超えて労働した時間」です。その日の労働時間は8時間ですので、延長した2時間は時間外労働にはなりません。
(S63.1.1基発第1号)
⑤【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者には適用されません。
(第60条)
「育児を行う者」については「適用しない」ではなく、「配慮をしなければならない」となっています。
条文を読んでみましょう。
則第12条の6 使用者は、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-165
R6.2.8 介護保険法の被保険者
過去問から学びましょう。
今日は介護保険法です。
介護保険の被保険者には、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」があります。
条文を読んでみましょう。
第9条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
※なお、介護保険の保険者は、「市町村及び特別区」です。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
②【H23年出題】
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
③【R4年出題】
介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
④【H29年出題】
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
⑤【R1年出題】
A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。
⑥【R1年出題】
A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
介護保険の第1号被保険者は、「市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者」です。
(第9条第1項)
②【H23年出題】 ×
介護保険の第2号被保険者は、「市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。
(第9条第2項)
③【R4年出題】 ×
介護保険の第2号被保険者は「医療保険加入者」であることが条件ですので、医療保険加入者でなくなった場合は資格を喪失します。
「医療保険加入者でなくなった日の翌日」からではなく、「医療保険加入者でなくなった日」から、その資格を喪失します。
(法第11条第2項)
④【H29年出題】 ×
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失します。第2号被保険者の資格を継続する制度はありません。
⑤【R1年出題】 〇
第2号被保険者は「医療保険加入者」であることが条件ですので、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない60歳の者は、介護保険の被保険者となりません。
A県A市に住所を有する65歳の者は、医療保険加入者でなくても介護保険の第1号被保険者となります。
(第9条)
⑥【R1年出題】 ×
住民票のある市町村の被保険者になることが原則です。
しかし、住所地特例という例外があります。
B県B市の介護保険施設に入所することによりB県B市に住民票を異動させた場合でも、もともとA県A市に住所を有していた場合は、「A県A市」が行う介護保険の被保険者となります。
介護保険施設などが多い市町村に、被保険者が偏ってしまうことを防ぐためです。
(第13条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-164
R6.2.7 労働契約法の「懲戒」
過去問から学びましょう。
今日は労働契約法です。
「懲戒」について条文を読んでみましょう。
第15条 (懲戒) 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、その権利を濫用したものとして、無効とされることがある。
②【R1年出題】
労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。
③【H30年出題】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
④【H26年出題】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H24年出題】 〇
使用者が労働者を懲戒することができる場合でも、その懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には権利を濫用したとして無効とされます。
権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び態様その他の事情が考慮されることを規定したものです。
(H24.8.10基発0810第2号)
②【R1年出題】 〇
法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義です。
労働基準法第89条第9号によると、「表彰及び制裁」については、定めをする場合はその種類及び程度に関する事項を就業規則に記載しなければならない相対的必要記載事項です。
(H24.8.10基発0810第2号)
③【H30年出題】 ×
最高裁判所の判例のポイントは、次の2点です。
1 使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと
2 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていること
周知させる手続が採られていない場合は、拘束力は生じません。
(H15.10.10最高裁判所第二小法廷 フジ興産事件)
④【H26年出題】 〇
使用者が労働者を懲戒するためには、「あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと」が必要です。
(H15.10.10最高裁判所第二小法廷 フジ興産事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-163
R6.2.6 子・孫の遺族厚生年金の受給権の消滅
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
遺族厚生年金の受給権者となる「子又は孫」の要件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。(第59条第1項第2号)
では、「子・孫」の遺族厚生年金の受給権の消滅について条文を読んでみましょう。
第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (2) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (3) 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
②【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。
③【H19年出題】
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 〇 ※改正による修正あり
子の遺族厚生年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に消滅します。ただし、障害等級1級又は2級の障害の状態にあるときは消滅しません。
問題文は、「障害等級3級の障害の状態」ですので、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。
(法第63条第2項第1号)
②【R1年出題】 ×
(前半部分)正しい
受給権発生 16歳 18歳年度末
▼ ▼ ▼
2級 | 3級 |
失権
遺族厚生年金の受給権発生時は障害等級2級でしたが、その後16歳のときに障害等級3級になりました。18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき「3級」ですので、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに受給権は消滅します。
(後半部分)誤り
受給権発生 18歳年度末 19歳
▼ ▼ ▼
2級 |
| 3級 |
失権
18歳に達した日以後の最初の3月31日では2級ですので、その時点では遺族厚生年金の受給権は消滅しません。その後19歳のときに3級になった場合は、その時点で受給権は消滅します。20歳で消滅するは誤りです。
(法第63条第2項)
③【H19年出題】 〇
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫の遺族厚生年金の受給権について
・1級又は2級に該当しなくなったとしても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までは受給権は消滅しません。
・例えば、19歳で1級又は2級に該当しなくなった場合は、その時点で受給権は消滅します。
・1級又は2級のまま20歳に達したときは、その時点で受給権は消滅します。
(法第63条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-162
R6.2.5 国民年金基金の給付について
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、国民年金基金の業務について条文を読んでみましょう。
第128条第1項 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 |
★基金の年金について
・基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない、とされています。
(法第129条第1項)
★基金の一時金について
・基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない、とされています。
(法第129条第3項)
給付の支給のルールについて条文を読んでみましょう。
第130条 ① 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。 ② 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 ③ 基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。
第131条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。
②【R4年出題】
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。
③【H22年出題】
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。
④【R1年出題】
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。
⑤【R3年出題】
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の「死亡」に関し、一時金の支給を行うものとされています。
「障害」に関する支給はありません。
(第128条第1項)
②【R4年出題】 ×
国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、「老齢基礎年金の受給権を取得したとき」には、支給されるものでなければならない、と規定されています。老齢基礎年金の受給権を取得した時点には限られません。
(法第129条第1項)
③【H22年出題】 ×
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければなりません。
また、国民年金基金の支給する一時金の額にも下限が定められています。
基金が支給する一時金の額は、「8,500円」を超えるものでなければなりません。
(法第130条第3項)
④【R1年出題】 ×
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することはできません。
ただし、当該年金の額のうち、「200円」に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、支給を停止することができます。
(法第131条)
⑤【R3年出題】 〇
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金額は、200円に増額率を乗じて得た額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければなりません。
(法第130条第2項、基金令第24条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-161
R6.2.4 全国健康保険協会について
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2つがあります。
今回は、「全国健康保険協会」についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) ① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。 ② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第7条の2(設立及び業務) ① 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。 ② 協会は、次に掲げる業務を行う。 (1) 保険給付及び日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務 (2) 保健事業及び福祉事業に関する業務 (3) 前2号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの (4)~(6)は省略します ③ 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
第123条 ① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。 ② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
過去問をどうぞ!
①【R5年選択式】
健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、< A >が行う。
②【H29年出題】
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
③【R1年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

【解答】
①【R5年選択式】
A 厚生労働大臣
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)、これらに附帯する業務は厚生労働大臣が行います。
全国健康保険協会管掌健康保険の資格の得喪、標準報酬月額などの決定、保険料の徴収の業務は、厚生年金保険とセットで、厚生労働大臣が行います。
任意継続被保険者は厚生年金保険に加入しませんので、除かれます。
②【H29年出題】 ×
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。
「保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う」の部分は正しいです。
条文で確認しましょう。
第155条 (保険料) ① 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 ② 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。 |
③【R1年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会です。
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。
(法第123条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-160
R6.2.3 賃金総額を正確に算定することが困難なものの特例
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第11条 (一般保険料の額) ① 一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 ② 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 ③ 厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
則第12条 (賃金総額の特例) 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 (1) 請負による建設の事業 (2) 立木の伐採の事業 (3) 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。) (4) 水産動植物の採捕又は養殖の事業 |
・一般保険料の額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
・「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する「すべての労働者に支払う賃金の総額」をいいますが、厚生労働省令で定める事業(上記(1)から(4))については、労災保険料を計算するに当たり、賃金総額の特例が設けられています。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(雇用)
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
②【R1年出題】(労災)
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
③【R4年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。
④【R4年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

【解答】
①【H30年出題】(雇用) ×
「請負による建設の事業」、「立木の伐採の事業」、「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」は、賃金総額の特例が認められていますが、常に認められるのではなく、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」に限定されています。
(則第12条)
②【R1年出題】(労災) ×
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業は、賃金総額を「請負金額×労務費率」とすることができます。
事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算するのが原則です。
(則第13条第2項第1号)
③【R4年出題】(労災) 〇
賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を使います。
(則第13条第2項)
④【R4年出題】(労災) ×
「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」で賃金総額の特例が認められた場合は、「その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」が賃金総額となります。
(則第15条)
なお、「立木の伐採の事業」の場合は、「所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額」が賃金総額となります。
(則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-159
R6.2.2 高年齢雇用継続基本給付金のポイント
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」がありますが、今日は、「高年齢雇用継続基本給付金」を中心にみていきます。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の方が対象です。原則として60歳以降の賃金が、60歳時点の75%未満になった場合に、支給されます。
条文を読んでみましょう。
第61条第1項 (高年齢雇用継続基本給付金) 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)に対して支給対象月に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなして算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1) 当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。)を基準日とみなして算定基礎期間に相当する期間が、5年に満たないとき。 (2) 当該支給対象月に支払われた賃金の額が、370,452円以上であるとき。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
②【R4年出題】
60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。
③【R4年出題】
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。
④【R1年出題】
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
⑤【H27年出題】
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。
⑥【R4年出題】
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した日に、被保険者であった期間(算定基礎期間に相当する期間)が5年以上あることが条件です。
要件を満たせば、60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月まで支給されます。
60歳時点で算定基礎期間に相当する期間が5年未満の場合は、60歳時点では受給資格はできません。ただし、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年以上になった場合に、受給資格ができます。
その場合は、算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
(行政手引59011)
②【R4年出題】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格を見る際の「算定基礎期間に相当する期間」は、基本手当の算定基礎期間の扱いと同じです。
例えば、A社からB社に転職した場合、A社の被保険者であった期間とB社の被保険者であった期間の間が1年を超えている場合は、通算できません。
問題文のように、57歳から59歳まで20か月被保険者でなかった場合は、基本手当等を受けていなくても、前の被保険者であった期間は通算されません。
そのため、60歳時点の被保険者期間は5年以上になりませんので、60歳から高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
(行政手引59011)
A社 被保険者であった期間 | 空白 (20か月) | B社 被保険者であった期間 |
A社とB社の間が1年を超えていますので、A社の被保険者であった期間とB社の被保険者であった期間は通算できません。
③【R4年出題】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者の資格を喪失した後、基本手当の支給を受けずに1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者となり得ます。
(行政手引59311)
④【R1年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月の賃金が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額(原則として60歳時点の賃金月額のことです)の75%未満になることが条件です。
★高年齢雇用継続基本給付金として支給される額は、支給対象月の賃金が60歳時点の賃金月額の61%未満の場合は、支給対象月の賃金の額の15%となります。
★支給対象月の賃金が60歳時点の賃金月額の61%以上の場合は、15%から一定の割合で逓減された率を、支給対象月の賃金の額に乗じます。
★ちなみに、(高年齢雇用継続基本給付金の額として計算した額+支給対象月の賃金)が支給限度額(370,452円)を超えるときは、(支給限度額(370,452円)-支給対象月の賃金の額)が高年齢雇用継続基本給付金の額となります。
(行政手引59014)
⑤【H27年出題】 〇
「支給対象月」の要件を条文で読んでみましょう。
第61条第2項 「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
★支給対象月とは、60歳到達月から65歳到達月までの「暦月」です。
60歳 到達月 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 65歳 到達月 |
支給対象月 | 支給対象月 |
高年齢雇用継続給付は、「一般被保険者」が対象ですが、「65歳に達した月」については高年齢被保険者も対象になります。
★支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者である」ことが条件です。
初日から末日まで被保険者として継続して雇用されている「暦月」が支給対象月となりますので、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象となりません。
(行政手引59013)
⑥【R4年出題】 ×
支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る」とされています。
支給対象月の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合は、高年齢雇用継続基本給付金を受けることはできません。
(行政手引59013)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-158
R6.2.1 派遣労働者に係る労災保険給付
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
★労働者派遣の「派遣元」「派遣先」「派遣労働者」の三者間の関係を確認しましょう。
① 派遣元と派遣労働者との間 → 労働契約関係にあります。
② 派遣元と派遣先との間 → 労働者派遣契約を締結し、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣します。
③ 派遣先 → 派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令します。
★労働者派遣事業に対する労働者災害補償保険は、派遣元事業主の事業が適用事業となります。
(参考 S61.6.30発労徴41号、基発第383号)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。
②【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。
③【R1年出題】
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。
④【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
⑤【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

【解答】
①【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る業務災害の認定について
・派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある
・派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある
↓
業務遂行性があります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
②【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る業務災害の認定について
・派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為は、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば
↓
業務遂行性があります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
③【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る通勤災害の認定について
・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となります。そのため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
④【R1年出題】 〇
★派遣労働者の保険給付の請求について
・当該派遣労働者の「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することになっ ています。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
⑤【R1年出題】 ×
★派遣労働者の保険給付の請求について
・保険給付請求書の事業主の証明は「派遣元事業主」が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-157
R6.1.31 フォークリフト 1トン未満と1トン以上の違い
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第59条第3項 (特別教育) 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
第61条第1項 (就業制限) 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 |
★「特別教育」とは?
危険又は有害な業務に労働者をつかせるときに行わなければならない安全又は衛生のための特別の教育です。
★「就業制限」とは?
クレーンの運転等の就業制限業務に従事できるのは、「都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者」、「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者」、「その他厚生労働省令で定める資格を有する者」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
②【H27年選択式】
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないが、労働安全衛生法施行令第20条で定めるものには、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務、つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。)の運転の業務、 < A >などがある。
(Aの選択肢)
①アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
②エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
③最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
④チェーンソーを用いて行う立木の伐採の業務

【解答】
①【R2年出題】 〇
最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、「特別教育」の対象です。
(則第36条第5号)
②【H27年選択式】
A ③最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
(令第20条第11号)
最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、「就業制限業務」です。
ポイント!
「特別教育」の対象業務と「就業制限業務」の対象業務をいくつか確認しましょう。
特別教育 | 就業制限業務 |
1トン未満のフォークリフト 5トン未満のクレーン 小型ボイラー | 1トン以上のフォークリフト 5トン以上のクレーン ボイラー(小型ボイラーを除く。) |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-156
R6.1.30 就業規則の作成・届出の義務
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 (1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (2) 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (4) 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 (5) 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 (6) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 (7) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (8) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (9) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (10) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 (11) 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 |
ポイント!
第89条の(1)、(2)、(3)は就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項です。
(4)から(11)は、定めをする場合は記載しなければならない相対的必要記載事項です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。
②【R2年出題】
1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
③【R2年出題】
慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
④【R3年出題】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。
⑤【H26年出題】
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議することまで使用者に要求しているものではない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成・届け出義務があります。
派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上使用する派遣元の使用者は、就業規則の作成・届出義務を負います。
派遣労働者の就業規則は、「派遣元使用者」が作成・届出義務を負うことに注意して下さい。
(S61.6.6基発333号)
②【R2年出題】 ×
労働基準法は、企業単位ではなく事業場単位で適用されます。
1つの企業が2つの工場をもっている場合は、それぞれの工場で労働基準法が適用されます。どちらの工場も使用している労働者が10人未満の場合は、就業規則の作成・届出義務はありません。
③【R2年出題】 ×
慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合、その旨を就業規則に記載するかどうかは、当事者の自由です。
(S23.10.30基発1575号)
④【R3年出題】 ×
同一事業場で、当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成することは可能です。
その場合、3割の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部です。
そのため、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合等の意見を聴くだけでは、労働基準法第90条による意見聴取を行ったことにはなりません。
(S63.3.14基発150号)
⑤【H26年出題】 〇
労働基準法第90条に定める意見を聴取する義務は、労働者の団体的意見を求めるということで、協議までは要求していません。
就業規則についての意見を聴けば、労働基準法違反になりません。
(S25.3.15基収525号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-155
R6.1.29 介護保険法 介護保険料の徴収
過去問から学びましょう。
今日は介護保険法です。
条文を読んでみましょう。
第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
市町村(特別区を含む。)は、第1号被保険者から保険料を徴収します。
保険料の徴収方法には、「特別徴収」(年金から天引きする方法)と「普通徴収」があり、特別徴収が原則です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
②【R3年出題】
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村(特別区を含む。)が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
③【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
市町村は、第2号被保険者からは、保険料を徴収しません。
(法第129条第4項)
★第2号被保険者の介護保険料の流れ
市町村 |
③ ↑ |
社会保険診療報酬支払基金 |
② ↑ |
① 医療保険者 |
①医療保険者が医療保険の保険料と介護保険料を一括して徴収します。
②医療保険者は、徴収した介護保険料を、社会保険診療報酬支払基金に納付します。
③徴収した納付金は、社会保険診療報酬支払基金から、市町村に交付します。
(法第125条、126条、150条)
②【R3年出題】 ×
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
条文を読んでみましょう。
① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
③【H30年選択式】
(A)3年
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働に関する一般常識
R6-154
R6.1.28 労働契約法 就業規則の変更による労働条件の変更
過去問から学びましょう。
今日は労働契約法です。
条文を読んでみましょう。
第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 |
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。
②【R3年出題】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法第10条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち、「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく、少数労働組合が含まれるが、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体は含まれない。
③【H30年出題】
就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。

【解答】
①【H23年出題】 〇
法第10条は、「就業規則の変更」という方法で、「労働条件を変更する場合」に、使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させ」たこと及び「就業規則の変更」が「合理的なものである」ことという要件を満たした場合に、労働契約の変更についての「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じることを規定したものです。
また、法第10条は、就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となる場合に適用されるものです。
(平成24年8月10日基発0810第2号)
②【R3年出題】 ×
労働者で構成されその意思を代表する親睦団体も含まれます。
法第10条本文の「労働組合等との交渉の状況」は、労働組合等事業場の労働者の意思を代表するものとの交渉の経緯、結果等をいうものです。
「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者のほか、少数労働組合や、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体等労働者の意思を代表するものが広く含まれます。
(平成24年8月10日基発0810第2号)
③【H30年出題】 〇
就業規則の変更が法第10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負います。
(平成24年8月10日基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 厚生年金保険法
R6-153
R6.1.27 障害手当金が支給されないとき
過去問から学びましょう。
今日は厚生年金保険法です。
障害手当金は、以下の要件を満たした場合に支給されます。
・初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと
・初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日に、政令で定める程度の障害の状態にあること
しかし、法第56条に該当する場合は、障害手当金は支給されません。
条文を読んでみましょう。
第56条 障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 (1) 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) (2) 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) (3) 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
|
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者に障害手当金は支給されない。
②【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
③【H18年出題】
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く。)には支給しない。
④【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
①【R4年出題】 〇
障害の程度を定めるべき日に年金たる保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)の受給権者である場合は、原則として障害手当金は支給されません。
※障害の程度を定めるべき日に「国民年金法による年金たる給付の受給権者」である場合も、原則として障害手当金は支給されません。
(法第56条第1号)
②【H30年出題】 ×
障害の程度を定めるべき日に老齢厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
(法第56条第1号)
③【H18年出題】 〇
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者には、原則として支給されません。
ただし、障害厚生年金の受給権者でも、最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者には、障害手当金が支給されます。
※障害基礎年金の受給権者も同じです。
(法第56条第1号)
3級未満 65歳
障害厚生年金 支給 | 3級未満(支給停止) | |
| 3年 | ※ |
障害厚生年金の受給権者 | ||
※網掛けの部分 → 障害手当金が支給されます。
④【R3年出題】 ×
障害の程度を定めるべき日に、当該傷病について労働者災害補償保険法の障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には障害手当金は支給されません。
問題文では、同じ傷病で、労災保険法の障害補償給付の受給権も取得していますので、障害手当金は支給されません。
(法第56条第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-152
R6.1.26 年金の内払調整
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第21条 ① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
③ 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。 |
①について
例えば、寡婦年金の受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したため、寡婦年金の受給権が消滅しました。しかし、寡婦年金の受給権が消滅した日の属する月の翌月以降の分として、寡婦年金の支払が行われました。その場合、支払われた寡婦年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金の内払とみなされます。
消滅
寡婦年金(乙年金) | 内払 |
↓
繰上支給の老齢基礎年金(甲年金) |
寡婦年金を返還して、改めて老齢基礎年金を支給するのではなく、内払調整によって支払われた寡婦年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金の内払とみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
②【R2年出題】
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
③【R3年出題】
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

【解答】
①【H20年出題】 〇
年金の支給を停止すべき事由が生じました。
↓
にもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われました。
↓
支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができます。
(法第21条第2項)
②【R2年出題】 〇
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じました。
↓
にもかかわらず、翌月以降も減額しない額の遺族基礎年金が支払われました
↓
減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができます。
(法第21条第2項)
③【R3年出題】 〇
障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を受けていた者が、その後、老齢基礎年金を受けることを選択した場合、障害厚生年金は支給停止されます。
しかし、翌月以降も障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は老齢基礎年金の内払とみなすことができます。
(法第21条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-151
R6.1.25 標準賞与額の決定と保険料の徴収
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう
第45条第1項 (標準賞与額の決定) 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
第167条第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円です。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
②【R1年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。
③【R3年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
その月の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額が、その月の標準賞与額となります。
ただし、その年度の標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合は、累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とされます。
「540万円」が誤りです。
(法第45条)
②【R1年出題】 〇
賞与の累計は、「保険者単位」とされています。
同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、同一の保険者である期間に支払われた賞与で累計します。
全国健康保険協会管掌健康保険の事業所の賞与が7月150万円、健康保険組合管掌健康保険の事業所の賞与が12月250万円、翌年3月200万円の場合は、全国健康保険協会管掌健康保険の分が7月150万円、健康保険組合管掌健康保険の分が12月250万円、3月200万円となります。
(H18.8.18 事務連絡)
③【R3年出題】 〇
前月から引き続き被保険者の場合、資格を喪失した月の賞与は、保険料の徴収の対象になりません。
ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額には含まれます。
(平成19年5月1日庁保険発第0501001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-150
R6.1.24 有期事業の一括のポイントを全てチェック!
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第7条 (有期事業の一括) 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 (1) 事業主が同一人であること。 (2) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 (3) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 (4) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
則第6条 (有期事業の一括) ① 法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 (1) 概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること。 (2) 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満であること。 ② 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 (1) それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 (2) それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること。 (3) それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 ③ 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項(3)の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。 |
ポイント!
★一括の対象になる事業の規模をおさえましょう。
<建設の事業>
概算保険料が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満
<立木の伐採の事業>
概算保険料が160万円未満かつ素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
★有期事業の一括で一括されるのは、「労災保険」の保険関係のみです。雇用保険は一括されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】(労災)
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。
②【H30年出題】(労災)
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
③【R3年出題】(労災)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
④【R3年出題】(労災)
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
⑤【H28年出題】(労災)
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象とされる。
⑥【R3年出題】(労災)
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。
⑦【R3年出題】(労災)
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。
⑧【R3年出題】(労災)
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。
⑨【H28年出題】(労災)
有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

【解答】
①【H24年出題】(労災) 〇
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるのがポイントです。申請や承認などの手続は不要です。
(S40.7.31基発901号)
②【H30年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の対象になると、原則としてその全体が継続事業として取り扱われます。労働保険料の申告や納付は、継続事業と同じように年度更新で行います。
(S40.7.31基発901号)
③【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の対象になるのは、建設の事業・立木の伐採の事業です。また、労災保険に係る保険関係のみが対象です。
④【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額が160万円未満でなければなりません。
(則第6条第1項第1号)
⑤【H28年出題】(労災) ×
独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が縮小し有期事業の一括のための要件を満たしたとしても、有期事業の一括の対象にはなりません。
ちなみに、有期事業の一括の対象になっていた事業の規模が拡大し要件を満たさなくなったとしても、一括の対象からは除外されません。
⑥【R3年出題】(労災) ×
「それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表による事業の種類をいう。)を同じくすること。」が、有期事業の一括の要件です。労災保険率が同じでも、事業の種類が異なっている場合は、有期事業の一括は適用されません。
(則第6条第2項第2号)
⑦【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の条件の一つに、「事業主が同一人であること」があります。「事業主が同一人」とは、「同一企業」ということです。同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合は、事業主が同一人であることに該当しないので、有期事業の一括は行われません。
(法第7条第1号)
⑧【R3年出題】(労災) 〇
数次の請負による建設の事業の場合、徴収法上の事業主は、原則として元請負人になります。(法第8条)
そのため、X会社がY会社の下請として施工する建設の事業では、X会社は下請負人で、徴収法上は事業主になりません。
X会社がY会社の下請負人として施工する事業は、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されません。元請のY会社の工事に一括されます。
(法第7条)
⑨【H28年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の対象となった事業の労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となります。
(則第6条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 雇用保険法
R6-149
R6.1.23 被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定
過去問から学びましょう。
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第6条第1号 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)には、雇用保険は、適用しない。 |
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、原則として雇用保険の被保険者になりません。
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます。(行政手引20303)
今日は、「所定労働時間」の算定についてみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
②【R3年出題】
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
③【R3年出題】
1週間の所定労働時間算定に当たって、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき、1週間の所定労働時間は、それらの加重平均により算定された時間とする。
④【R3年出題】
労使協定等において「1年間の所定労働時間の総枠は〇〇時間」と定められている場合のように、所定労働時間が1年間の単位で定められている場合は、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合であっても、1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。
⑤【R3年出題】
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。

【解答】
①【R3年出題】 〇
●1週間の所定労働時間が定まっていない場合・シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合
→ 勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定します。
(行政手引20303)
②【R3年出題】 〇
●所定労働時間が1か月の単位で定められている場合
→ 当該時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります
例えば、1か月の所定労働時間が109時間の場合は、109時間×12か月÷52週=25.1で、1週間の所定労働時間は25時間6分です。
(行政手引20303)
③【R3年出題】 〇
●4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないとき
→ それらの加重平均により算定された時間が1週間の所定労働時間となります。
(行政手引20303)
④【R3年出題】 ×
●所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合
→ 1年間の所定労働時間の総枠を52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
●所定労働時間が1年間の単位で定められている場合であっても、さらに、週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合
→ 当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により、1週間の所定労働時間を算定します。
(行政手引20303)
⑤【R3年出題】 〇
●雇用契約書等による1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合
→ 乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間で判断します。
(行政手引20303)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-148
R6.1.22 支給制限(労働者へのペナルティ)
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 ② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
労働者に非がある場合は、労災の保険給付の支給制限が行われます。
①「故意に」は「行わない(絶対)」、②「故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」は「全部又は一部を行わないことができる(裁量)」です。違いに注意しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
②【H26年出題】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
③【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
④【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
⑤【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
⑥【H26年出題】
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
⑦【H28年選択式】
労災保険法第13条第2項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< B >に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「故意」とは、自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容することをいいます。
(労災保険法第12条の2の2第1項、S40.7.31基発901号)
②【H26年出題】 〇
労働者が「故意に」自らの負傷を生じさせたときは、「政府は保険給付を行わない。」
(労災保険法第12条の2の2第1項)
③【H26年出題】 〇
労働者が「故意に」自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は「保険給付を行わない。」
(労災保険法第12条の2の2第1項)
④【H26年出題】 〇
「故意の犯罪行為」により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意によるものです。
(労災保険法第12条の2の2第2項、S40.7.31基発901号)
⑤【R2年出題】 〇
労働者が「重大な過失」により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
「重大でない過失」の場合は、保険給付の全部又は一部を行わないことはできません。
(労災保険法第12条の2の2第2項)
⑥【H26年出題】 〇
労働者が「正当な理由なく療養に関する指示に従わない」ことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
(労災保険法第12条の2の2第2項)
⑦【H28年選択式】
A 療養の費用
B 療養に関する指示
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働安全衛生法
R6-147
R6.1.21 労働安全衛生法の適用単位
過去問から学びましょう。
今日は労働安全衛生法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じである。
②【H28年出題】
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
③【R3年出題】
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

【解答】
①【R2年出題】 〇
労働安全衛生法は、事業場単位で適用されます。「事業場」の適用単位の考え方は、労働基準法の考え方と同じです。
事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のような一定の場所で相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいいます。
一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定されます。同一場所にあるものは原則として一の事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされます。
★例えば
〇〇株式会社
本社 (大阪) |
| 工場 (姫路) |
| 営業所 (神戸) |
| 店舗 (西宮) |
労働安全衛生法は企業単位(〇〇株式会社単位)ではなく、「事業場単位」(本社、工場、営業所、店舗それぞれ)で適用されます。
(S47.9.18発基第91号)
②【H28年出題】 〇
労働安全衛生法の事業場の業種の区分は、その業態によって個別に決まります。
たとえば、製鉄所は「製造業」ですが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業ではなく、「その他の業種」となります。
(S47.9.18発基第91号)
③【R3年出題】 ×
総括安全衛生管理者も「事業場単位」で適用されます。
第10条で、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。」と規定されています。
「企業全体における労働者数」ではなく「事業場の労働者数」を基準として、「事業場」の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられています。
(S47.9.18発基第91号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-146
R6.1.20 許されるべき相殺 最高裁判例より
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第24条 ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
第24条では、賃金支払5原則が定められています。
賃金支払の5つの原則を確認しましょう。
・通貨払いの原則
・直接払いの原則
・全額払いの原則
・毎月一回以上払いの原則
・一定期日払いの原則
今日は「全額払」の原則に関する問題です。
賃金は労働した分を「全額」支払うのが原則です。ただし、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができます。
今日は、賃金の過払があった場合などに相殺が許される要件をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。
②【H27年出題】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H29年出題】
賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
④【H21年選択式】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の < A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【R3年出題】 〇
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺」は、労働基準法第24条第1項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではない」とされています。
過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないなど、『労働者の経済生活の安定』をおびやかすおそれのない場合は、労働基準法第24条第1項に違反しません。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
②【H27年出題】 ×
金額が少額であるということだけで相殺が許されるものではありません。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
③【H29年出題】 ×
「過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされる」ことも、相殺が許される条件の一つです。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
④【H21年選択式】
A 経済生活の安定
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-145
R6.1.19 2以上の事業所に使用される場合の各事業主が負担する保険料の額
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第82条第3項 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
令第4条第2項 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。 |
各事業主が負担する標準賞与額に係る保険料の額は以下の通りです。
被保険者の保険料の半額 × | その月に各事業主が支払った賞与額 |
その月に当該被保険者が受けた賞与額 |
その被保険者の保険料の半額を各事業所の賞与額で按分します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の額に乗じて得た額とされている。

【解答】
【R5年出題】 ×
「当該被保険者の保険料の額」ではなく、「当該被保険者の保険料の半額」に乗じて得た額とされています。
保険料は、被保険者と事業主が半額ずつ負担します。
(令第4条第2項)
では、こちらの過去問もどうぞ!
【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。

【解答】
【H28年出題】 〇
同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は以下の通りです。
被保険者の保険料の半額 × | 各事業所について算定した報酬月額 |
当該被保険者の報酬月額 |
※各事業所について算定した報酬月額とは、
各事業所について定時決定、資格取得時決定、随時改定若しくは育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定又は保険者算定の規定により算定した報酬月額です。
(令第4条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-144
R6.1.18 過誤払いの年金の返還金債権への充当
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第21条の2 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
則第86条の2 年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 (1) 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 (2) 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき |
(1)の例をみてみましょう。
例えば、老齢基礎年金を受給している夫が令和6年1月18日に死亡しました。老齢基礎年金は受給権が消滅した月(令和6年1月)まで支給されますが、死亡の翌月以後も、老齢基礎年金が過誤払されました。この場合、過誤払いされた年金は、本来なら妻が返還しなければなりません。しかし、夫の死亡により妻に遺族基礎年金が支給される場合は、妻に支払う遺族基礎年金の金額を過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。
死亡
夫 | 老齢基礎年金 | 過誤払 |
↑返還金債権の金額に充当できる
妻 |
| 遺族基礎年金 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
②【H29年出題】
遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
妻に支払う「老齢基礎年金」の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することはできません。
充当することができるのは、「年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者」です。夫の死亡に伴う遺族基礎年金が妻に支払われる場合は、充当の対象になります。
(則第86条の2第1号)
②【H29年出題】 ×
過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができるのは、「他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う」場合です。
婚姻で受給権が消滅した場合は、充当の対象になりません。
(則第86条の2第2号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
「その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。」が誤りです。
「当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。」となります。
「死亡」によって受給権が消滅したにもかかわらず、翌月以降も年金が過誤払された場合に、過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付で調整する場合は、内払ではなく「充当」という用語を使います。
「充当」は死亡した人と残された人の年金との調整ですが、「内払」は1人の年金間での調整です。
(法第21条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-143
R6.1.17 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
まず条文を読んでみましょう。
第63条第1項第5号 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したときは、消滅する。 イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき → 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日 ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日 |
(イについて)
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻が遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき(子がいない妻)→ 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに失権します。
夫死亡
妻26歳 30歳 31歳失権
遺族厚生年金 |
|
▲ 5年 |
|
(ロ)について
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻(子がいる妻)が30歳前に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに失権します。
夫死亡
妻27歳 28歳 30歳 33歳失権
遺族厚生年金 | |
遺族基礎年金 | ▲ 5年 |
子死亡
遺族基礎年金失権
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。
②【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。
③【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻で、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合(子がいない場合)、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その遺族厚生年金の受給権は消滅します。
(法第63条第1項第5号イ)
②【R3年出題】 ×
27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該遺族厚生年金の受給権は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき」に消滅します。
(法第63条第1項第5号イ)
③【H29年出題】 ×
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻(子がある妻)で、妻が30歳に到達する日前に、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、「当該遺族厚生年金の受給権を取得した日」ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権は消滅します。
(法第63条第1項第5号ロ)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。

【解答】
【R5年出題】 〇
「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から5年を経過したときに消滅します。
(法第63条第1項第5号ロ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-142
R6.1.16 標準報酬月額等級の最高等級
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第20条第2項 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 |
厚生年金保険の標準報酬月額等級は、1等級から32等級に区分されています。
1等級の標準報酬月額は88,000円、最高等級の32等級の標準報酬月額は650,000円です。
では過去問をどうぞ!
【R1年出題】※改正による修正あり
厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第1級88,000円から第32級650,000円まで区分されており、この等級区分については毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】
【R1年出題】 ×
最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるのは、その年の4月1日からではなく、「その年の9月1日」からです。
(法第20条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
毎年12月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
毎年3月31日(「12月31日」は誤りです。)における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる(「改定を行わなければならない」は誤りです)。
(法第20条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-141
R6.1.15 障害基礎年金との併合による障害厚生年金の改定
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至ったときは、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と当該障害基礎年金の支給事由となった障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
初診日 初診日
厚生年金保険の被保険者 国民年金第1号被保険者
2級 障害厚生年金 |
|
|
2級 障害基礎年金 | + 併 合 | 2級 障害基礎年金 |
↓
↓
| 1級 障害厚生年金 | 障害基礎年金に合わせて 1級に改定 |
| 1級 障害基礎年金 | 前後の障害を併合して 1級 |
さっそく令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は、自営業を営み、国民年金に加入しているが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定される。

【解答】
【R5年出題】 〇
先ほどの図にあてはめて確認しましょう。
甲は、厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給しています。現在は、自営業を営み、国民年金に加入していますが、仕事中の事故によって、新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため、甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じました。
初診日 初診日
厚生年金保険の被保険者 国民年金第1号被保険者
2級 障害厚生年金 |
|
|
2級 障害基礎年金 | + 併 合 | 2級 障害基礎年金 |
前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合、新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに、障害厚生年金の額も改定されます。
| 1級 障害厚生年金 |
|
| 1級 障害基礎年金 |
|
(法第52条の2第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-140
R6.1.14 離婚時みなし被保険者期間の扱い
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第78条の6第1項~3項 ① 実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 (1) 第1号改定者 改定前の標準報酬月額に一から改定割合( 按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た額 (2) 第2号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 ② 実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において、第1号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。 (1) 第1号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額 (2) 第2号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあっては、零)に、第1号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額 ③ 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。 |
★③が「離婚時みなし被保険者期間」です。
例えば、夫が第1号改定者、妻が第2号改定者で妻が標準報酬月額を有しない場合
夫 | 妻 |
|
標準報酬月額
|
零 | |
↓
分 割
↓
夫 | 妻 |
|
|
標準報酬月額 | 標準報酬月額 |
妻(第2号改定者)は厚生年金保険の被保険者でないのがポイントです。
しかし、離婚分割によって報酬額の記録が分割され、第2号改定者の厚生年金保険の被保険者期間であったものとみなされます。この期間を離婚時みなし被保険者期間といいます。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
②【H27年出題】
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
③【R3年出題】
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。
④【H28年出題】※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H29年出題】 〇
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算には入りません。
なお、報酬比例部分の計算には入ります。
(法附則第17条の10)
②【H27年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間が必要ですが、「離婚時みなし被保険者期間」は1年の計算に入りません。
そのため厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみの場合は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
(法附則第17条の10)
③【R3年出題】 〇
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上必要です。その被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
(法第78条の11)
④【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)は、遺族厚生年金の長期要件に該当します。
遺族厚生年金の長期要件には、「離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。」とされています。
そのため、国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより、老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)は、遺族厚生年金の長期要件を満たします。
(法第78条の11)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは、1年以上の被保険者期間を有することであるが、この被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の「1年以上の被保険者期間」には、離婚時みなし被保険者期間は含まれません。
(法附則第17条の10)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-139
R6.1.13 特別支給の老齢厚生年金の障害者特例
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
法附則第9条の2 ① 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分が計算されているものに限る。)の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。 ② ①の請求があったときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があった月の翌月から、年金の額を改定する。 (1) 1,628円に改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が480を超えるときは、480とする。)を乗じて得た額 (2) 被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額 |
「報酬比例部分」のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が対象の特例です。
要件を満たすと、障害者特例として定額部分と報酬比例部分を合わせた年金(+加給年金額)が支給されます。
要件を確認しましょう。
①報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金の受給権者であること
②3級以上の障害状態にあること(厚生年金保険で規定する障害等級は1~3級です)
③退職していること(=厚生年金保険の被保険者でないこと)
受給権者の請求が必要で、原則として請求のあった月の翌月から年金額が改定されます。(請求があったものとみなされる例外もありますが、今日は触れません。)
<イメージ図>
昭和32年4月1日生まれの男性は62歳から報酬比例部分のみが支給されます。
(62歳) (65歳)
特別支給(報酬比例部分) | 老齢厚生年金 |
| 老齢基礎年金 |
↓
障害者特例に該当した場合は定額部分が支給されます。
↓
(62歳) (65歳)
特別支給(報酬比例部分) | 老齢厚生年金 |
定額部分 | 老齢基礎年金 |
それでは、過去問をどうぞ!
【H27年選択式】
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の老齢厚生年金について、報酬比例部分の支給開始年齢は62歳であり、定額部分の支給は受けられないが、
(1) 厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び第5項に規定する、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
(2) 被保険者期間が< A >以上であるとき
(3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が< B >以上であるとき
のいずれかに該当する場合には、60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる。
上記(1)から(3)のうち、「被保険者でない」という要件が求められるのは、 < C >であり、定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要(請求があったものとみなされる場合を含む。)であるのは、< D >である。
<選択肢>
A | ① 42年 ②43年 ③44年 ④45年 |
B | ① 10年 ②15年 ③20年 ④25年 |
C | ① (1)及び(2) ② (1)、(2)及び(3) ③ (2)のみ ④ (2)及び(3) |
D | ① (1)のみ ② (1)及び(2) ③ (1)及び(3) ④ (1)、(2)及び(3) |

【解答】
A ③ 44年
B ② 15年
C ① (1)及び(2)
D ① (1)のみ
(法附則第9条の2第1項、第2項、法附則第9条の3第1項、法附則第9条の4第1項)
(1)は障害者特例、(2)は長期加入者特例、(3)坑内員、船員の特例です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。

【解答】
【R5年出題】 ×
障害者特例の障害の状態は、障害等級1級、2級、3級です。1級又は2級に限定されません。
(法附則第9条の2第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-138
R6.1.12 70歳以上の使用される者のポイント
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
厚生年金保険の被保険者資格は、70歳に達したときに喪失します。
そのため、70歳以降に在職中でも厚生年金保険の保険料の負担はありません。しかし、在職老齢年金の仕組みが適用される場合があります。
条文を読んでみましょう。
第27条 (届出) 適用事業所の事業主又は第10条第2項(任意単独被保険者)の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
★70歳以上の使用される者とは
70歳以上の適用事業所に使用されるもので、法第12条各号の適用除外に該当しないものをいいます。
(則第10条の4)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。
②【H28年出題】
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。
③【R4年出題】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者が在職中に70歳に達し、引き続き当該事業所に使用される場合の届出についての問題です。
70歳以上の使用される者の要件に該当する場合は、事業主は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。
ただし、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における準報酬月額と同額である場合は、届出を省略することができます。
(則第15条の2第1項)
②【H28年出題】 ×
70歳以上の使用される者に在職老齢年金の仕組みが適用されるようになったのは、平成19年4月1日ですが、その時点で70歳以上だった昭和12年4月1日以前生まれの者には在職老齢年金の仕組みは適用されませんでした。
しかし、平成27年10月の改正で、昭和12年4月1日以前生まれの者にも、在職老齢年金の仕組みが適用されるようになりました。
③【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される70歳以上の使用される者については、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
(第46条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
在職老齢年金の対象になるのは、「70歳以上の使用される者」です。
適用事業所で使用される70歳以上の者でも、厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、「70歳以上の使用される者」になりません。そのため、在職老齢年金の仕組みは適用されません。
(法第46条第1項、則第10条の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-137
R6.1.11 厚生年金保険の被保険者期間の計算
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
被保険者期間について条文を読んでみましょう。
第19条 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 ④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 ⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月)とみなす。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
③【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
④【R3年出題】
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月」単位で計算される期間です。
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間は、「被保険者であった期間」のことです。
例えば、令和6年1月11日に資格を取得し、同年5月30日に資格を喪失した場合、令和6年1月11日から5月29日までが「被保険者であった期間」で、令和6年1月から4月までの4か月間が「被保険者期間」です。
(第19条第1項)
②【H30年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。平成29年10月1日に資格取得、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、資格を取得した月(平成29年10月)から資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの5か月間です。資格を喪失した月(平成30年3月)は被保険者期間には算入されません。
(第19条第1項)
③【H28年出題】 〇
同一の月に資格の取得と喪失があるときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
例外で、「ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」と規定されています。
例外その1 「その月に更に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」
→ 後から資格取得した期間によって「1か月」で算入します。
例外その2 「その月に更に国民年金の被保険者(国民年金法の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したとき」
→ 同じ月に資格取得と喪失があり、その月に更に国民年金の第1号被保険者又は第3号被保険者の資格を取得した場合は、その月は厚生年金保険の被保険者期間に算入されません。
問題文のように、平成28年3月1日に第1号厚生年金被保険者の資格取得、同年3月20日付けで退職、翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった場合は、平成28年3月は、厚生年金保険の被保険者期間に算入されません。
(第19条第2項)
④【R3年出題】 〇
同一の月において被保険者の種別(第1号、第2号、第3号、第4号の厚生年金被保険者の種別の変更)に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされます。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなされます。
(第19条第5項)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
【R5年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。
(第19条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-136
R6.1.10 健康保険法の時効の起算日
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「時効」について条文を読んでみましょう。
第193条 (時効) ① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |
今日は、時効の起算日をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
②【H30年出題】
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
③【H27年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。
④【R1年出題】
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
⑤【H28年出題】※改正による修正あり
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「療養の給付」は現物給付ですので、時効はありません。
②【H30年出題】 ×
療養費の請求権の消滅時効は、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日から起算されます。例えば、コルセット装着については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日は、「コルセットを装着した日」ではなく、「コルセットの代金を支払った日」です。消滅時効は、「コルセットの代金を支払った日の翌日」から起算されます。
(S31.3.13保文発第1903号)
③【H27年出題】 〇
傷病手当金の請求権は「労務不能日」に発生しこれを行使し得るものです。そのため、傷病手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。
(S30.9.7保険発第199号)
④【R1年出題】 ×
出産手当金を受ける権利は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算されます。
なお、出産育児一時金は、「出産した日の翌日から」起算されます。
(S30.9.7保険発第199号)
⑤【H28年出題】 ×
高額療養費は診療月の末日ではなく、診療月の翌月の1日が起算日です。
★時効の起算日を確認しましょう。
<療養費>
療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日(療養に要した費用を支払った日)の翌日
(S31.3.13保文発第1903号)
<高額療養費>
診療月の翌月の1日。傷病が月の途中で治ゆした場合も同様。
ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日。
(S48.11.7/保険発第99号/庁保険発第21号/)
<高額介護合算療養費>
計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日
(H21.4.30保保発第0430001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】
【R5年出題】 ×
労務不能であった日ごとにその「翌日」です。
(S30.9.7保険発第199号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-135
R6.1.9 健康保険の擬制的任意適用事業所
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第32条 強制適用事業所が、第3条第3項各号(強制適用事業所の要件)に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可(任意適用の認可)があったものとみなす。 |
例えば、個人事業所の従業員の数が5人未満になった場合、17業種以外の法人の事業所が個人事業になった場合のように、強制適用事業所が、強制適用の要件に該当しなくなったときの取扱いです。
「任意適用の認可があったものとみなす。」とされていますので、改めて任意適用の認可を受けなくても、自動的に適用事業所の資格が継続します。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

【解答】
【H27年出題】 ×
強制適用事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、自動的に、任意適用の認可があったものとみなされます。被保険者の希望があってもなくても、任意適用事業所の認可の申請は不要です。
(第32条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合でも、自動的に適用事業所のままでいられますので、任意適用の認可の申請は不要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-134
R6.1.8 健康保険の強制適用事業所
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険の強制適用事業所について、条文を読んでみましょう。
第3条第3項 健康保険法において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 ①次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人事業) (1) 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 (2) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 (3) 鉱物の採掘又は採取の事業 (4) 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 (5) 貨物又は旅客の運送の事業 (6) 貨物積卸しの事業 (7) 焼却、清掃又はと殺の事業 (8) 物の販売又は配給の事業 (9) 金融又は保険の事業 (10) 物の保管又は賃貸の事業 (11) 媒介周旋の事業 (12) 集金、案内又は広告の事業 (13) 教育、研究又は調査の事業 (14) 疾病の治療、助産その他医療の事業 (15) 通信又は報道の事業 (16) 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 (17)弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 ②①に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの |
強制適用事業所になる事業所は以下の通りです。
| 法人 | 個人事業 |
業種・人数 | 業種問わず、常時1人以上 | 17業種で、常時5人以上 |
※個人事業で、健康保険の適用が任意になる事業所は以下の通りです。
・個人事業で「17業種以外(農林水産業やサービス業など)」の事業所は、5人以上でも5人未満でも人数に関係なく任意です。
・個人事業で「17業種」の事業所でも、5人未満の場合は任意です。
※国、地方公共団体の事業所は、健康保険の強制適用事業所です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
②【H23年出題】
常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
③【R1年出題】
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
法人の代表者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
代表者が1人の法人の事業所で、代表者以外に従業員を雇用していないものでも、強制適用事業所となります。
(昭和24.7.28保発第74号)
②【H23年出題】 〇
飲食業は「17業種以外」ですので、常時10人の従業員を使用していても、個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはなりません。
「法人である事業所」は業種関係なく、常時1人でも使用していれば強制適用事業所となりますので、「常時3人の従業員を使用している法人の土木、建築等の事業所」は強制適用事業所です。
③【R1年出題】 〇
国、地方公共団体は、健康保険の強制適用事業所です。
そのため、国、地方公共団体に使用される者は健康保険の被保険者です。しかし、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものには、健康保険法による保険給付は行われません。共済で給付が受けられるからです。
条文を確認しましょう。
第200条 (共済組合に関する特例) ① 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない。 ② 共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。

【解答】
【R5年出題】 ×
令和4年10月1日から、「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業」が強制適用になる業種に加わりました。
なお、「政令で定める業務」は、「公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士に関する政令第1条に規定する沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士」です。(施行令第1条)
「外国法事務弁護士」は適用の対象となる事業に含まれます。
(令第1条第9号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 労災保険法
R6-133
R6.1.7 複数業務要因災害に係る労災保険給付額
まず、用語の定義を確認しましょう。
★複数事業労働者とは
事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者のことです。(法第1条)
★複数業務要因災害とは
複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のことです。(法第7条)
複数業務要因災害の対象になる傷病は、脳・心臓疾患、精神障害などです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社1年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4か月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月間の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(A) 甲会社につき算定した給付基礎日額である。
(B) 甲会社・乙会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
(C) 甲会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
(D) 甲会社・丙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
(E) 甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。

【解答】 E
■ 複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、「当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額とする。ただし、第9条第1項第5号の規定は、適用しない。」と」規定されています。(則第9条の2の2第1号)
■ 複数事業労働者の平均賃金相当額の算定期間と算定方法の「原則」を確認しましょう。
複数事業労働者に係る平均賃金相当額の原則的な算定期間は、傷病等の発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)以前3か月間であり、平均賃金相当額を算定すべき各事業場において賃金締切日がある場合は事業場ごとに算定事由発生日から直近の賃金締切日より起算すること。 (令和2年8月21日基発0821第2号) |
次に「複数業務要因災害」の場合を確認しましょう。
複数業務要因災害は原則として脳・心臓疾患及び精神障害を想定しています。
複数業務要因災害として認定される場合、どの事業場においても業務と疾病等との間に相当因果関係は認められません。
・遅発性疾病等の診断が確定した日にいずれかの事業場に使用されている場合は、当該事業場について当該診断確定日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月に支払われた賃金により平均賃金相当額を算定します。
・遅発性疾病等の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、遅発性疾病等の診断が確定した日までの間に他の事業場から賃金を受けている場合は、当該事業場の平均賃金相当額について、直前の賃金締切日以前3か月間において支払われた賃金により算定します
(令和2年8月21日基発0821第2号)
|
| 4か月前 ▼ |
| 3か月前 ▼ | 死亡 ▼ |
甲会社 |
|
| |||
乙会社 |
|
| |||
丙会社 |
|
|
| ||
丁会社 |
|
|
| ||
遅発性疾病等の診断が確定した日に使用されている「甲会社」、「乙会社」、「丁会社」で診断確定日以前3か月間(賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日以前3か月間)に支払われた賃金で平均賃金相当額を算定します。
丙会社は、「3か月前の日を始期として、遅発性疾病等の診断が確定した日までの間」に賃金を受けていませんので、計算に入りません。
(令和2年8月21日基発0821第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-132
R6.1.6 第19条解雇制限が適用される条件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
条文の「休業する期間」に注目してください。解雇制限が適用されるのは「休業する期間」です。
まず、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
②【R1年出題】
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
解雇制限を受けるのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために「休業する期間」及びその後30日間ですので、労働者が業務上の傷病により治療中だったとしても、休業しないで就労している場合は、解雇制限は受けません。
(第19条)
②【R1年出題】 〇
6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定だとしても、女性労働者が産前休業を請求しないで引き続き就労している場合は、解雇制限は受けません。
(S25.6.16基収1526号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。

【解答】
【R5年出題】 〇
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、解雇制限は適用されません。しかし、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされています。
(第19条、S25.6.16基収1526号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-131
R6.1.5 第2号被保険者期間の合算対象期間
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
S60年附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条(老齢基礎年金の支給要件)及び第27条(老齢基礎年金の年金額)並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
例えば、18歳から63歳まで厚生年金保険の被保険者だった場合、その間はすべて国民年金第2号被保険者となります。ただし、老齢基礎年金の適用については、20歳前の期間と60歳以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」に算入されます。
18歳 20歳 60歳 63歳
厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者) | ||
合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
②【R4年出題】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。
③【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間・60歳以後の期間は、合算対象期間(カラ期間)となり、老齢基礎年金の支給要件の「10年以上」の期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。
(S60年附則第8条第4項)
②【R4年出題】 ×
60歳から65歳までの期間が「合算対象期間」になるため、老齢基礎年金は満額になりません。
20歳 23歳 60歳 65歳
未加入 | 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者) | |
保険料納付済期間(37年間) | 合算対象期間 | |
老齢基礎年金の額に反映するのは、23歳から60歳までの期間です。
(S60附則第8条第4項)
③【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間が「合算対象期間」になるのは、「老齢基礎年金」のみです。
障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、「保険料納付済期間」となります。ちなみに、遺族基礎年金も同様に保険料納付済期間となります。
(S60附則第8条第4項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】
【R5年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては「合算対象期間」に算入され、保険料納付済期間には算入されません。
(S60附則第8条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-130
R6.1.4 老齢基礎年金の支給要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第26条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
老齢基礎年金の受給権は、「保険料納付済期間+保険料免除期間」を10年以上有する者が65歳に達したときに発生します。
条文では、「保険料免除期間」が2か所出てきます。
1つめの「保険料免除期間」からは、「学生納付特例及び納付猶予」の期間が除かれています。学生納付特例期間と納付猶予期間は、老齢基礎年金の年金額に反映しないからです。
2つめの「保険料免除期間」では、学生納付特例期間と納付猶予期間は除外されていません。そのため、10年以上の計算には、学生納付特例期間と納付猶予期間が含まれます。
また、附則第9条第1項で、老齢基礎年金の支給要件の特例が規定されています。
特例により、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年未満でも、「合算対象期間」を合算した期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の要件を満たします。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
②【R4年出題】
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)を合算した期間を7年、合算対象期間を5年有している場合は、65歳に達したときに、老齢基礎年金の受給権が発生します。
(法第26条、附則第9条)
②【R4年出題】 ×
納付猶予期間も学生納付特例期間も、保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されません。
(第27条、H16附則第19条第4項、H26附則第14条第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。

【解答】
【R5年出題】 〇
老齢基礎年金の支給を受けるには、保険料納付済期間と保険料免除期間と、合算対象期間を合算した期間が10年以上必要です。
(法第26条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-129
R6.1.3 国民年金の年金と厚生年金保険の年金の組み合わせ
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第20条第1項、附則第9条の2の4 年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。 |
ポイント!
年金は、「一人一年金」が原則です!
例外的に「併給できる」パターンをおさえましょう。
過去問でみていきましょう。
①【H21年出題】
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
②【R4年出題】
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。
③【R4年出題】
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
④【H26年出題】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
⑤【H30年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
国民年金の年金には、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「付加年金」があります。
★同時に2つ以上の年金の受給権を取得することもあります。
その場合は、「一人一年金の原則」が適用され、一つの年金を選択して受給します。その際、選択しなかった年金は、「支給停止」となります。「失権」ではありませんので、注意しましょう。
★例外で、「付加年金」は、「老齢基礎年金」と併給できます。
→問題文は、「遺族基礎年金」、「老齢基礎年金」、「付加年金」の受給権を取得しています。一人一年金の原則で、「遺族基礎年金」か「老齢基礎年金」のいずれか一方を選択して受給します。
老齢基礎年金を選択した場合は「付加年金」も支給されます。
遺族基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金が支給停止になりますので、付加年金も支給停止となります。
②【R4年出題】 〇
老齢基礎年金、障害基礎年金、付加年金の受給権を取得した場合で、「障害基礎年金」の受給を選択したときは、「老齢基礎年金と付加年金」は、障害基礎年金を受給する間、支給が停止されます。
③【R4年出題】 〇
「基礎年金」と「厚生年金」は同一の支給事由の場合は併給されます。
老齢厚生年金
|
| 障害厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
| 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
付加年金は老齢基礎年金と併給できます。そのため、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給されます。
④【H26年出題】 ×
「基礎年金」と「厚生年金」の支給事由が異なっていても、65歳以上の場合は、併給できる場合があります。
65歳以上の「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」
65歳以上の「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」
65歳以上の「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」
★65歳以上に限って併給できるパターン
遺族厚生年金
|
| 老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
| 障害基礎年金 | 障害基礎年金 |
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給することができます。老齢基礎年金を受給する場合は、付加年金も併給できます。
⑤【H30年出題】 〇
65歳以降は、「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を併給することができます。
ただし、65歳前は併給できません。そのため、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択して受給することになります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、併給できます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-128
R6.1.2 学生納付特例と保険料の納付猶予
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
まず、過去問からどうぞ!
【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

【解答】
【R3年出題】 ×
「学生納付特例制度」は、法第90条の3に規定されていて、時限的な措置ではなく恒久的な措置です。
一方、「保険料の納付猶予制度」は、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されている「令和12年6月まで」の時限的な措置です。
なお、保険料の納付猶予制度は、50歳に達する日の属する月の前月までが対象です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

【解答】
【R5年出題】 ×
学生納付特例制度は、本則(第90条の3)に規定されています。
保険料の納付猶予制度は、本則ではなく、法附則(平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条)に規定されている時限措置です。「令和12年6月まで」にも注意しましょう。年度末の3月まではなく、6月までがポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 国民年金法
R6-127
R6.1.1 老齢基礎年金の額と国庫負担
今日は国民年金法です。
国庫負担と老齢基礎年金の額との関係をみていきます。
さっそく、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。

【解答】
【R5年出題】 ×
・保険料納付済期間の月数は、老齢基礎年金の年金額には「1」で反映されますが、そのうち「2分の1」は国庫負担です。
保険料 |
国庫負担 |
・保険料全額免除期間は、老齢基礎年金の年金額には原則「2分の1」で反映されます。
免除 |
国庫負担 |
→ 問題文の、「保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているから」の部分です。
※ちなみに、学生納付特例・50歳未満の納付猶予期間には国庫負担がありませんので、年金額には反映しません。
なお、「国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられた」のは、「平成21年4月1日」以降です。「平成15年4月1日以降」の部分が誤りです。
全額免除期間は、平成21年4月以降は、年金額には「2分の1」が反映しますが、平成21年3月までは「3分の1」が反映します。
(第27条、H16法附則第9条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 国民年金法
R6-126
R5.12.31 国民年金保険料の額の改定
今日は国民年金法です。
保険料の額の改定についてみていきます。
★「令和元年度以後」の年度に属する月の保険料は、
「17,000円」に保険料改定率を乗じて得た額となります。
(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げます。)
(第87条第3項)
★保険料改定率は、「前年度の保険料改定率」×「名目賃金変動率」で計算します。
なお、「名目賃金変動率」の内訳は、「物価変動率」×「実質賃金変動率」です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

【解答】
【R5年出題】 ×
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「令和元年度以後」の年度に属する月の月分の保険料として定められている「17,000円」に「保険料改定率」を乗じて得た額となります
保険料改定率は、「前年度の保険料改定率」×「名目賃金変動率」で計算します。
令和5年度の保険料改定率は、以下の計算式で計算します。
・前年度の保険料改定率 → 0.976
・物価変動率 → 0.998
・実質賃金変動率 → 0.998
保険料改定率は、0.976×名目賃金変動率(0.998×0.998)=0.972です。
令和5年度の保険料額は、17,000円×保険料改定率(0.972) ≒ 16,520円です。
★ 計算の基礎となる保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成29年度まで毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降は月額16,900円で固定されることになっていました。
しかし、産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴って、令和元年度以降の計算の基礎となる保険料の額は100円引き上げられ、月額17,000円となっています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-125
R5.12.30 20歳前傷病による障害基礎年金の「所得」による支給停止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第36条の3第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
第36条の4第1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。 |
「第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)」は、「受給権者の所得」による支給停止があります。
「20歳前傷病による障害基礎年金」には、所得による支給停止以外に、以下の事由による支給停止があります。
① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
④ 日本国内に住所を有しないとき。
通常の障害基礎年金にはない支給停止事由ですので、注意しましょう。
今日は「所得による支給停止」をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
②【H30年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が472万1千円を超えるときは全額が、その年の10月から翌年の9月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。
③【H25年出題】
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
所得は、「受給権者の前年の所得」で判断します。「所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出」の部分が誤りです。
(第36条の3第1項)
②【H30年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止のポイント
★前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下のとき(扶養親族等がいないとき)
→ 2分の1が支給停止される
★前年の所得が472万1千円を超えるとき(扶養親族等がいないとき)
→ 全額が支給停止される
★支給停止期間は「その年の10月から翌年の9月まで」
全額支給
|
|
全額支給停止 |
2分の1支給停止
|
(370万4千円) (472万1千円)
(令第5条の4)
③【H25年出題】 ×
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災等の災害で、住宅、家財等の財産について被害金額がその価格のおおむね「2分の1」以上の損害を受けた場合は、所得を理由とする支給停止は行われません。
3分の1ではなく「2分の1」です。
(第36条の4第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。
②【R5年出題】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「全部又は3分の1」ではなく、「全部又は2分の1」です。
(第36条の3第1項)
②【R5年出題】 〇
チェックポイントは、「2分の1以上」、その損害を受けた月から「翌年の9月まで」です。
(第36条の4第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-124
R5.12.29 傷病手当金の支給期間
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項、4項 ① 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ④ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。 |
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

【解答】
【H28年出題】 〇
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日」から支給されます。
3日を経過した日とは、第4日目以降という意味です。
継続した3日間の待期を満たす必要があり、待期は休日も含んでカウントします。
問題文の待期は、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で完成します。
(S32.1.31保発第2号の2)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
②【R5年出題】
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「4日」を経過した日からではなく、「3日」を経過した日からです。
例えば、金曜日から労務不能になった場合は、金曜日・土曜日・日曜日の連続した3日間で待期期間が完成し、4日目の月曜日から傷病手当金が支給されます。
| 金 | 土 | 日 | 月 |
| 休 | 休 | 休 | 休 |
②【R5年出題】 ×
被保険者が死亡した場合は、死亡した日の翌日に被保険者資格を喪失しますので、死亡日当日までは、健康保険の被保険者です。
そのため、傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合は、被保険者である死亡日当日分まで支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-123
R5.12.28 産休中・育休中の保険料免除
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「育児休業期間中」の保険料免除について条文を読んでみましょう。
第159条第1項 育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定(産前産後休業中の保険料免除)の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 1 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 2 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
育児休業期間中の保険料の免除について確認しましょう。
1 「育児休業等を開始した日の属する月」から「終了する日の翌日が属する月の前月」までの保険料が免除されます。
2 開始した日と終了する日の翌日が同月内にある場合
→ 14日以上の育児休業を取得した場合はその月の保険料が免除されます。
※「賞与」については、賞与を支払った月の末日を含む1か月を超える育児休業等が免除の対象になります。
「産前産後休業期間中」の保険料免除について条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

【解答】
【H26年出題】 〇
「産前産後休業を開始した日の属する月」から「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間、保険料が免除されます。
ちなみに、「当該被保険者に関する保険料を徴収しない」とは、事業主負担分も被保険者負担分も免除されるという意味です。
(法第159条の3)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
②【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
③【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月(令和4年12月)からその産前産後休業が終了する日の翌日(令和5年3月9日)が属する月の前月(令和5年2月)までです。
令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |
12月10日 (開始日) |
|
| 3月9日 (終了日の翌日) |
免除 | 免除 | 免除 |
|
②【R5年出題】 〇
免除されるのは、その育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)からその育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の前月(令和5年3月)までです。
令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 | 令和5年4月 |
1月10日 (開始日) |
| 3月31日 (終了日) | 4月1日 (終了日の翌日) |
免除 | 免除 | 免除 |
|
③【R5年出題】 ×
育児休業等開始日(1月4日)と終了日の翌日(1月17日)が同一月にあるのがポイントです。
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一の場合、保険料の免除については育児休業等の日数が14日以上あることが条件です。
問題文の場合は、1月4日から1月16日までで、13日しかありません。そのため、令和5年1月の保険料は免除されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-122
R5.12.27 健康保険の被保険者とならないもの
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう
第3条第1項 健康保険法において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。) 2臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1か月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。) イ日々雇い入れられる者 ロ2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 3事業所で所在地が一定しないものに使用される者 4季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く。) 5臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く。) 6国民健康保険組合の事業所に使用される者 7後期高齢者医療の被保険者等 8厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。) 9 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者 (1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。)又はその1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 ロ 報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が、8万8千円未満であること。 ハ 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 |
※(補足)9について
同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が4分の3未満でも、次の要件に当てはまる場合は、健康保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり8万8千円以上
③学生でない
④特定適用事業所又は任意特定適用事業所に使用されている
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用期間が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。
②【R2年出題】
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
③【R2年出題】
所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。
④【H26年出題】
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
⑤【R4年選択】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
①【H22年出題】 〇
「2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、健康保険の被保険者になりませんが、例外で、「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」は、被保険者となります。
問題文の場合は、所定の期間が60日間ですので、当初は健康保険の被保険者になりません。しかし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った61日目から被保険者の資格を取得します。
(第3条第1項第2号ロ、S5.8.6保規第344号)
②【R2年出題】 ×
「季節的業務に使用される者」は健康保険の被保険者になりませんが、例外的に、当初から「4か月を超えて使用される」予定の場合は、当初から被保険者になります。
問題文のように、季節的業務に使用される者で、「当初4か月以内の期間」の予定が、業務の都合で、継続して4か月を超えたとしても、被保険者になりません。
(第3条第1項第4号)
③【R2年出題】 ×
所在地が一定しない事業所に使用される者は、被保険者になりません。例外規定はありません。
(第3条第1項第3号)
④【H26年出題】 〇
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、被保険者になりません。
(第3条第1項第6号)
⑤【R4年選択】
A88,000円以上
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。

【解答】
【R5年出題】 〇
問題文のように、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」は被保険者となります。
最初の雇用契約が2か月以内でも、雇用契約の開始時に2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者資格を取得します。
(第3項第1項第2号ロ、R4.9.9保保発0909第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-121
R5.12.26 療養費の支給
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第87条第1項 (療養費) 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 |
療養費は、「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」又は「保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合に、保険者がやむを得ないものと認めるとき」に「療養の給付等」に代えて、「現金」で支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
②【R1年出題】
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。
③【H21年出題】
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。
④【R3年出題】
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【解答】
①【H27年出題】 〇
無医村で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合は、「療養の給付を行うことが困難であると認めるとき」として、療養費が支給されます。
(S13.8.20社庶第1629号)
②【R1年出題】 ×
療養費の対象になるのは、「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」の支給を行うことが困難であると認めるときです。訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費の対象になりません。
③【H21年出題】 ×
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、「その受領は事業主等が代理して行う」ものとし、「国外への送金は行わない」ことになっています。「療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金する」は誤りです。
なお、海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
(S56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
④【R3年出題】 〇
療養費の額は、
療養について算定した費用の額 - 一部負担金の割合を乗じて得た額
+
食事療養(又は生活療養)について算定した費用 - 食事療養標準負担額(又は生活療養標準負担額)
を基準として、保険者が定めます。
(第87条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
単に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。
②【R5年出題】
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
単に保険診療が不評だからとの理由で、保険診療を回避した場合は、療養費の支給は認められません。
また、緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた時には、療養費は支給しないこととされています。
(S24.6.6保文発第1017号)
②【R5年出題】 〇
問題文にプラスして、以下の点もポイントです。
・現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行う。
・海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。
(S56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-120
R5.12.25 標準報酬月額の有効期間
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第42条第3項 (被保険者の資格を取得した際の決定) 被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第41条第2項 (定時決定) 定時決定の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
第43条第2項 (随時改定) 随時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の3第2項 (産前産後休業を終了した際の改定) 産前産後休業を終了した際の改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の2第2項 (育児休業等を終了した際の改定) 育児休業等を終了した際の改定の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
|
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
②【H24年出題】
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。
③【R3年出題】
その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
資格取得時に決定された標準報酬月額は、1月1日から5月31日までに資格を取得した者は、「その年の8月」まで、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した者は、「翌年の8月」までの各月の標準報酬月額となります。
(法第42条第2項)
②【H24年出題】 ×
7月1日に被保険者資格を取得した者は、標準報酬月額の定時決定を行いません。
資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として「翌年の8月」まで用います。
(法第42条第2項)
③【R3年出題】 〇
・1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
↓
原則として、「その年の8月」までの標準報酬月額となります。
・7月から12月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
↓
原則として、「翌年の8月」までの標準報酬月額となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。

【解答】
【R5年出題】 〇
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額の有効期間は、「産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月まで」です。
※当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までとなります。
例えば、12月25日に産前産後休業が終了した場合は、「産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月」は、2月です。
産前産後休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は3月からその年の8月までが有効期間となります。
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
~ | 8月 |
産休終了翌日 |
| 2か月経過月 | 改定 |
|
(第43条の3第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-119
R5.12.24 任意継続被保険者の保険料の前納
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) ① 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 |
「前納」のポイントを穴埋めでチェックしましょう
 令第48条 (保険料の前納期間)
令第48条 (保険料の前納期間)
任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。
ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する< A >以降の期間又はその資格を喪失する日の属する< B >までの期間の保険料について前納を行うことができる。
 令第49条 (前納の際の控除額)
令第49条 (前納の際の控除額)
法第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。
 則第139条第1項 (任意継続被保険者の保険料の前納)
則第139条第1項 (任意継続被保険者の保険料の前納)
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< D >までに払い込まなければならない。

【解答】
A 月の翌月
B 月の前月
C 年4分
D 初月の前月末日
過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
②【H22年選択式】
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< A >である。

【解答】
①【H26年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料を前納する期間は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間が単位です。
6か月又は12か月の間に、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかな場合は、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料を前納することができます。
(令第48条)
②【H22年選択式】
(A) 5月
6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者は、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。
(令第48条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
【R5年出題】 〇
「各月の初日が到来したとき」がポイントです。
(第165条)
※国民年金との違いを確認しましょう。
国民年金の第1号被保険者も保険料を前納することができます。国民年金の場合は、「前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。」となります。違いに注意しましょう。(国民年金法第93条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-118
R5.12.23 国又は地方公共団体負担の医療と健康保険の調整
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第55条第4項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 |
同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において療養の給付等は行われません。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
②【H16年出題】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
災害救助法の目的は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」です。
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われません。
②【H16年出題】 〇
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付では、健康保険による保険給付が優先されます。
費用のうち健康保険の保険給付が及ばない部分(自己負担分)が、生活保護法の医療扶助の対象となります。
(生活保護法第4条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

【解答】
【R5年出題】 〇
同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行われません。
(第55条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-117
R5.12.22 少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁されたときの保険給付
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第118条 ① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 ② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 |
少年院等に収容されたとき、刑事施設、労役場に拘禁されたときは、公費負担で療養が行われますので、健康保険の保険給付は制限されます。
制限されるのは、「疾病、負傷、出産」で、死亡については制限はありません。
また、傷病手当金、出産手当金の支給について制限が行われるのは、厚生労働省令で定める場合に限ります。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
②【H29年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。
③【H22年出題】
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
保険者は、被保険者が少年院等に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行いません。しかし、被保険者がそのようなときでも、被扶養者に係る保険給付は行われます。
(第118条第1項、2項)
②【H29年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場等に拘禁された場合でも、被扶養者に対する保険給付は行われます。
(第118条第2項)
③【H22年出題】 ×
第118条の規定は、「被扶養者」について準用されます。その場合、「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えます。
(第122条)
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、その期間に係る保険給付はすべて行わないではなく、「その期間に係る当該被扶養者に係る保険給付は行わない」となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

【解答】
【R5年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、少年院等に収容されたとき又は刑事施設、労役場等に拘禁された場合でも、その被扶養者に係る保険給付は行われます。
(第118条第1項、2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-116
R5.12.21 特定長期入院被保険者が療養の給付と併せて受けた生活療養
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「特定長期入院被保険者」の定義を確認しましょう。
「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のこと。 (第63条第2項第1号) |
では、「入院時生活療養費」の条文を読んでみましょう。
第85条の2第1項~3項 (入院時生活療養費) ① 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 ② 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、生活療養標準負担額を控除した額とする。 ③ 厚生労働大臣は、②の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
過去問をどうぞ!
【H26年選択式】
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

【解答】
A 介護保険法
「生活療養標準負担額」の定義についての問題です。
生活療養標準負担額は、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
(第85条の2第2項)
入院時生活療養費は、「生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から、「生活療養標準負担額」を控除した額です。
生活療養標準負担額は、一般の所得の場合は、食費(1食460円又は420円)+居住費(1日370円)です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
②【R5年出題】
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用については、入院時食事療養費ではなく「入院時生活療養費」が支給されます。
(第85条の2第1項)
②【R5年出題】 ×
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会ではなく、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとされています。
(第85条の2第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-115
R5.12.20 療養の給付に含まれないもの
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第63条第1項、2項 (療養の給付) ① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ② 次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く。以下「食事療養」という。) 2 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) イ 食事の提供である療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 3 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療 養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) 4 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) 5 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) |
「食事療養」、「生活療養」、「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」は療養の給付の対象になりません。
「食事療養」を受けた場合は「入院時食事療養費」、「生活療養」を受けた場合は「入院時生活療養費」、「評価療養、患者申出療養、選定療養」を受けた場合は「保険外併用療養費」の対象になります。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】※改正による修正あり
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

【解答】
【H28年出題】 〇
「患者申出療養」は療養の給付の対象にはなりません。
患者申出療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。
(第63条第2項、第86条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

【解答】
【R5年出題】 ×
『食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)』は、「食事療養」として、「入院時食事費療養」が支給されます。「食事療養」は療養の給付には含まれません。
(イメージ図)
入院療養 | 療養の給付 | 一部負担金 |
+
食事療養 | 入院時食事療養費 | 食事療養標準負担額 |
ちなみに、「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者」のことを、「特定長期入院被保険者」といいます。
特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用については、「入院時生活療養費」が支給されます。
※生活療養とは
・食事の提供である療養
・温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
のことです。
(第63条第2項、第85条、第85条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-114
R5.12.19 徴収法の「賃金」の定義
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
|
通貨以外のもので支払われるもの(現物給付)も、厚生労働省令で定める範囲内のものは賃金に含まれます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】(労災保険)
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
②【R1年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
③【H19年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
④【H26年出題】(労災保険)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
①【H24年出題】(労災保険) 〇
労働基準法の「休業手当」は賃金ですが、「解雇予告手当」は賃金となりません。
(S25.4.10 基収950号、S23.8.18基収2520号)
②【R1年出題】(雇用保険) 〇
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされています。
(則第3条)
③【H19年出題】(雇用保険) 〇
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。
①食事、②被服、③住居の利益、④所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも、「通貨以外のもので支払われる賃金」として、賃金に算入されます。
(則第3条)
④【H26年出題】(労災保険) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約などで事業主に支給が義務づけられていても、労働保険料の算定基礎となる賃金にはなりません。
(S25.2.16基発127号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

【解答】
【R5年出題】(雇用保険) ×
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされています。
(第2条第3項)
ポイント!
「範囲」と「評価」に注意しましょう
・通貨以外のもので支払われる賃金の範囲 → 食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
・賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価 → 厚生労働大臣が定める
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法
R6-113
R5.12.18 失業の認定日が就職日の前日である場合
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は雇用保険法です。
失業の認定日について条文を読んでみましょう。
第15条第1項、3項 ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。 |
失業の認定は、原則として、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
②【H28年出題】
公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
失業の認定は、4週間に1回ずつ「直前の28日」の各日について行われます。前回の認定日以後~当該認定日の前日までの期間について行われます。
②【H28年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
(則第24条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
失業の認定日が就職日の前日である場合、当該認定日において就労していない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定をすることができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
失業の認定は、前回の認定日以後当該認定日の前日までの期間について行うのが原則です。
しかし、認定日が就職日の前日である場合は、前回の認定日から当該認定日を含めた期間について認定をすることができます。
「認定日の翌日まで」ではありません。
(行政手引51251)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-112
R5.12.17 退職時の証明
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第22条第1項 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 |
退職時の証明書の法定記載事項は、「使用期間」、「業務の種類」、「その事業における地位」、「賃金」、「退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)」です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。
②【R4年出題】
労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記載しなければならない。
③【H22年出題】
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「退職」の事由には、自己都合、会社の勧奨、定年、契約期間の満了、解雇などがあります。
退職時の証明書は、退職理由を問わず交付する義務がありますので、労働者が自己都合による退職をした場合でも、労働者が証明書を請求した場合は、交付する義務があります。
②【R4年出題】 ×
第22条第3項で、「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」と規定されています。
労働者が法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合は、請求があった事項だけを記載することになります。
③【H22年出題】 ×
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合は、解雇の事実のみを記載する義務があります。
第22条第3項で、「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」と規定されていますので、請求されていない解雇の理由を証明書に記載してはなりません。
(H11.1.29基発45号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数について制限はない。

【解答】
【R5年出題】 〇
退職時の証明を求める回数について制限はありません。
(H11.3.31基発169号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-111
R5.12.16 年次有給休暇の時季変更権
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第5項 使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 |
労働者には時季指定権があり、年次有給休暇を取得する時季は労働者が指定できます。
また、使用者には時季変更権があり、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、時季変更権を行使できます。
今日は、「時季変更権」についてみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年選択】
最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど< A >に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[…(略)…]労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…(略)…]使用者にある程度の < B >の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右< B >は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右< B >が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項[現5項]ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」
②【H22年選択】
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、[…(略)…]事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との< A >を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者が、これを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…(略)…]使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H29年選択】
A 事業の正常な運営
B 裁量的判断
ポイント!
・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期のものであればあるほど、事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなる。
・ 労働者が、事前の調整を経ることなく、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、使用者の時季変更権の行使については、使用者にある程度の裁量的判断の余地が認められる。
・ 裁量的判断が、労働基準法39条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、その行使は違法となる。
(平成4.6.23最高裁判所第三小法廷)
②【H22年選択】
A 事前の調整
ポイント!
・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、それが長期のものであればあるほど、事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。
(平成4.6.23最高裁判所第三小法廷)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第39条第5項にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R5年出題】 〇
勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されない、とされています。
(昭和62.7.10最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-110
R5.12.15 労基法第15項第1項の労働条件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
労働契約締結の際に、使用者は、労働者に対して「賃金、労働時間その他の労働条件」を明示する義務があります。
明示事項には、「必ず明示しなければならない事項」と「定めをしている場合は明示しなければならない事項」の2種類があります。
まず、過去問からどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
②【H24年出題】
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
③【H23年出題】
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
④【R4年出題】
労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。

【解答】
①【H16年出題】 〇
第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件は、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎などに関する条件を含む労働者の職場における一切の待遇のことです。
一方、第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、施行規則第5条で具体的に決められています。
第1条及び第2条の「労働条件」と第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、異なります。
②【H24年出題】 ×
「表彰に関する事項」は、それに関する定めをする場合は、労働契約の締結に際し、明示しなければならない事項です。
(則第5条)
③【H23年出題】 〇
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除できます。
④【R4年出題】 ×
「契約解除の日から14日以内」は、民法の期間計算の原則によります。
9月1日に労働契約を解除した場合は、解除当日ではなく解除の翌日から数えて14日をいいます。契約解除の日から14日以内は、9月2日から数えて、9月15日までをいいます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

【解答】
【R5年出題】 〇
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合は、社宅を供与する旨の条件は第15条第1項の「労働条件」に含まれません。そのため、社宅を供与しなかったときでも、労働者は即時に労働契約を解除することはできません。
ちなみに、社宅を利用する利益が、第11条にいう賃金である場合は、第15条第1項の「賃金、労働時間その他の労働条件」に該当しますので、社宅を供与しなかった場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
(S23.11.27基収3514号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
ご質問の回答です 厚生年金保険法
R6-109
R5.12.14 遺族厚生年金の「長期要件」について
12月9日の記事を読んでくださった方から、遺族厚生年金の「長期要件」についてご質問いただきました。
ご質問 例えば、自営業等で20年間国民年金保険料を納め、会社員として5年間厚生年金の被保険者であった場合、併せて25年の加入期間があるので、長期要件に該当するという考えでよろしいでしょうか? |
では、遺族厚生年金の「長期要件」について条文を読んでみましょう。
第58条第1項第4号 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき |
「長期要件」は、保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある事が条件です。
次に、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の定義を読んでみましょう。
第3条第1項第1号、2号 ①保険料納付済期間 → 国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間をいう。 ②保険料免除期間 → 国民年金法第5条第2項に規定する保険料免除期間をいう。 |
<国民年金法第5条の定義>
① 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(保険料一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。
② 「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。
★「保険料納付済期間」は、
「第1号被保険者として保険料を納付した期間」
+
「第2号被保険者としての期間」
+
「第3号被保険者としての期間」
で算定します。
ご質問の回答です
自営業等(国民年金第1号被保険者)として20年間保険料を納付し、会社員(第2号被保険者)として5年間厚生年金保険の被保険者期間がある場合は、長期要件を満たします。
「長期要件」は、厚生年金保険の期間が長いということではなく、国民年金全体で25年以上という意味です。
過去問も解いてみましょう。
【R3年出題】
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。

【解答】
【R3年出題】 〇
保険料納付済期間と保険料免除期間と「合算対象期間」も合算した期間が25年以上である場合は、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当します。
(法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-108
R5.12.13 遺族厚生年金「生計維持」の条件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第59条第1項 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって「生計を維持した」ものであることが条件です。
「生計維持」についてみていきましょう。
まず、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた子であっても、年額130万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない。
②【H29年出題】
被保険者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたが、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができる。

【解答】
①【H25年出題】 ×
生計を維持していたと認められるのは、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者です。
問題文は、年額「850万円以上」の収入を将来にわたって有すると認められる場合は、その者によって生計を維持していたとは認められず、遺族厚生年金を受けることができる遺族になることはない、となります。年額130万円以上ではありません。
(H23.3.23年発0323第1号)
②【H29年出題】 ×
生計維持関係の認定日は、「遺族厚生年金の受給権発生日」です。その後、給与収入が年収850万円未満に減少したとしても、遺族厚生年金の受給権は得られません。
(H23.3.23年発0323第1号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者で、前年収入が年額800万円であった者は、定期昇給によって、近い将来に収入が年額850万円を超えることが見込まれる場合であっても、その被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

【解答】
【R5年出題】 〇
生計維持に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとされています。
① 前年の収入が年額850万円未満である
② 前年の所得が年額655.5万円未満である
③ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、①又は②に該当する
④ ①、②又は③に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる
問題文は、前年収入が年額800万円であった者ですので、①に該当し、生計を維持していたと認められます。
(H23.3.23年発0323第1号
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-107
R5.12.12 父又は母と同居することになった子の遺族厚生年金
今日は、厚生年金保険法です。
「子」に対する遺族厚生年金の支給が停止されるときをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第66条第1項 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
①前条本文 → 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する
②次項本文 → 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する
③次条 → 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
遺族厚生年金の遺族の順位では、配偶者と子は同順位です。
例えば、夫が死亡し、妻と子が遺族となった場合、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生します。
ただし、妻が遺族厚生年金の受給権を有する間は、子の遺族厚生年金は支給停止されます。(第66条第1項)
※配偶者に対する遺族厚生年金が、①、②、③によって支給停止されている間は、子に遺族厚生年金が支給されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
配偶者と離別した父子家庭の父が死亡し、当該死亡の当時、生計を維持していた子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、当該子が死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、当該子に対する遺族厚生年金は支給停止とはならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
遺族厚生年金を受給している子が、死亡した父の元配偶者である母と同居することになったとしても、子に対する遺族厚生年金は支給停止されません。
国民年金法の遺族基礎年金の子に対する支給停止事由との違いに注意しましょう。
国民年金の遺族基礎年金については、「子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」という規定があります。
厚生年金保険法の子に対する遺族厚生年金の支給停止事由には、「生計を同じくするその子の父若しくは母があるとき」はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-106
R5.12.11 繰下げ加算額の算定
今日は、厚生年金保険法です。
老齢厚生年金の繰下げの申出をした者に支給される繰下げ加算額をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第44条の3第4項 支給繰下げの申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額及び在職老齢年金の規定によりその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
令第3条の5の2第1項 政令で定める額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月(以下「受給権取得月」という。)の前月までの被保険者期間(以下「受給権取得月前被保険者期間」という。)を基礎として計算した老齢厚生年金の額に平均支給率を乗じて得た額に増額率(1000分の7に受給権取得月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)を乗じて得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 |
繰下げた老齢厚生年金には、繰下げ加算額が加算されます。
・ 繰下げ加算額は「受給権取得月前被保険者期間」を基礎として計算します。
・ 在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる額は、増額の対象になりません。
・ 増額率は、「0.7%×繰下げた月数(65歳に到達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)」です。「繰り下げた月数」の上限は120ですので、増額率は最大で84%となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に支給する繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定めるとする。

【解答】
【R5年出題】 ×
繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月「の前月」までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額と在職老齢年金の仕組みによりその支給を停止するものとされた額を勘案して、政令で定める額となります。
繰下げ加算額の計算は、「老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額」が基準となります。また、在職老齢年金の仕組みにより支給停止される額は、繰下げ加算額の対象になりません。
(法第44条の3第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 厚生年金保険法
R6-105
R5.12.10 特例的な繰下げみなし増額制度
今日は、令和5年度の厚生年金保険法の改正点です。
令和5年4月の改正で創設された「特例的な繰下げみなし増額制度」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第44条の3第5項 老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に当該老齢厚生年金を請求し、かつ、当該請求の際に繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して15年を経過した日以後にあるとき。 2 当該請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付の受給権者であったとき。 |
ポイントを確認しましょう!
<改正前>
・65歳で老齢厚生年金の受給権を取得し、裁定請求しないまま73歳になりました。
73歳で老齢厚生年金を裁定請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、73歳からさかのぼって5年分の年金がまとめて支給されます。改正前は、まとめて支給される5年分には繰下げの増額分は加算されませんでした。なお、65歳から68歳までの3年分は時効で消滅します。
<改正後の変更点>
・65歳で老齢厚生年金の受給権を取得し、裁定請求しないまま73歳になりました。
73歳で老齢厚生年金を裁定請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、「請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす」ことになりました。
そのため、遡ってまとめて支給される5年分の年金には、繰下げによる増額分が加算されます。
★なお、「特例的な繰下げみなし増額制度」は、「老齢厚生年金の受給権取得日から15年経過した日以後」、「請求をした日の5年前の日以前に他の年金たる給付(障害や遺族の年金)の受給権者であった」ときは、適用されません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
65歳到達時に老齢厚生年金の受給権が発生していた者が、72歳のときに老齢厚生年金の裁定請求をし、かつ、請求時に繰下げの申出をしない場合には、72歳から遡って5年分の年金給付が一括支給されることになるが、支給される年金には繰下げ加算額は加算されない。

【解答】
【R5年出題】 ×
請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされますので、72歳から遡って一括支給される5年分の年金には、繰下げ加算額が加算されます。
(第44条の3第5項)
65歳 67歳 72歳
(受給権発生) (5年前) (裁定請求)
| 繰下げ加算額 |
|
繰下げ待機期間
| 5年分を一括支給 |
|
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-104
R5.12.9 遺族厚生年金 死亡した者の保険料納付要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
死亡した者の要件について条文で読んでみましょう。
第58条第1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、1又は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 3 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 4老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
★1と2には、保険料納付要件があるのがポイントです。
<保険料納付要件>
・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
※特例
・死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、「死亡日に65歳未満」で「死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に未納期間がない」ときも保険料納付要件を満たします。
★3と4は、保険料納付要件は問われません。
3は、障害厚生年金を受けるときに保険料納付要件を満たしているからです。
4は、長期の加入期間(保険料納付済期間+保険料免除期間=25年以上)があるからです。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
②【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
③【R1年出題】
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
上記2に当てはまりますので、「保険料納付要件を満たしている」ことが条件です。
②【R3年出題】 〇
上記2に当てはまりますので、「保険料納付要件を満たしている」ことが要件です。
原則の保険料納付要件を満たしていない場合でも、特例の保険料納付要件を満たしていれば、遺族厚生年金が支給されます。
特例の保険料納付要件は、「令和8年4月1日前に死亡した者」で、「死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないこと」、そして「死亡日に65歳未満」であることです。ちなみに、「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない」とは、「未納期間がない」という意味です。
令和3年8月1日に死亡した場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間(=令和2年7月~令和3年6月)までの間に未納期間がないとき(保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき)には、遺族厚生年金の支給対象となります。
令和2年7月 |
・・・・・・・ | 令和3年6月 | 令和3年7月 | 令和3年8月 |
| 死亡日の属する月の前々月 |
| 死亡日の 属する月 | |
死亡日の属する月の前々月までの1年間 この間に未納がないこと |
|
| ||
(S60法附則第64条第2項)
③【R1年出題】 〇
上記3に当てはまりますので、保険料納付要件は問われません。
障害厚生年金を受けるときに保険料納付要件を満たしているからです。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
遺族厚生年金は、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときにも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるが、その支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない。

【解答】
【R5年出題】 〇
上記3に当てはまりますので、保険料納付要件は問われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-103
R5.12.8 特定適用事業所とは?
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「特定適用事業所」に使用される「短時間労働者」は、一定の要件を満たす場合は、厚生年金保険の被保険者となります。
特定適用事業所の定義を条文で読んでみましょう。
H24附則第17条第12項 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所をいう。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
②【R2年出題】
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
③【R2年出題】
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3未満の者で、特定適用事業所に使用される者は、「週の所定労働時間が20時間以上」、「厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円以上」、「学生でない」場合は、厚生年金保険の被保険者となります。
「継続して1年以上使用される見込み」という要件は、改正により現在はなくなっています。
(H24附則第17条第1項)
②【R2年出題】 ×
特定適用事業所に該当しなくなったとしても、特定4分の3未満短時間労働者の厚生年金保険の資格は継続します。
(H24附則第17条第2項)
③【R2年出題】 〇
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、原則として、厚生年金保険の被保険者となりません。
(H24附則第17条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時100人を超える事業所のことである。

【解答】
【R5年出題】 ×
「労働者」の総数が常時100人を超えるではなく、「特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)」の総数が常時100人を超える事業所のことです。
(H24附則第17条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-102
R5.12.7 経過的寡婦加算の支給停止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
経過的寡婦加算は、遺族厚生年金を受けている65歳以上の妻に支給されるものです。
昭和31年4月1日以前生まれの妻が対象です。
条文を読んでみましょう。
S60附則第73条第1項 (遺族厚生年金の加算の特例) 中高齢寡婦加算の要件を満たした遺族厚生年金の受給権者であって昭和31年4月1日以前に生まれた者(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の妻であった者に限る。)がその権利を取得した当時65歳以上であったとき、又は中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者であって昭和31年4月1日以前に生まれたものが65歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額に、経過的寡婦加算を加算する。 ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(経過的寡婦加算の額) ①から②を控除して得た額 ① 中高齢寡婦加算の額 ② 老齢基礎年金の額に妻の生年月日別に定められた率を乗じて得た額 |
経過的寡婦加算が加算される妻は、次のどちらかに当てはまる場合です。
・65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(中高齢寡婦加算が加算される要件を満たしていること)
・中高齢寡婦加算が加算されていた遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
※どちらも、昭和31年4月1日以前生まれの妻であることが条件です。
まず、過去問を解いてみましょう
①【R3年出題】
昭和32年4月1日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。
②【H21年出題】
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
中高齢寡婦加算は、妻が65歳に達したときは加算されなくなり、65歳以降は経過的寡婦加算が加算されます。
ただし、65歳以降、経過的寡婦加算の額が加算されるのは、昭和31年4月1日以前生まれの者に限られます。
そのため、昭和32年4月1日生まれの妻については、65歳まで中高齢寡婦加算が加算されますが、65歳以降、経過的寡婦加算額は加算されません。
(S60附則第73条第1項)
②【H21年出題】 ×
中高齢寡婦加算の額は、「遺族基礎年金の額×4分の3」で、妻の生年月日にかかわらず、定額です。
経過的寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されます。
経過的寡婦加算の額の計算式を確認しましょう。
↓
中高齢寡婦加算の額 - 老齢基礎年金の額×生年月日に応じた乗率
生年月日に応じた乗率は、例えば、昭和2年4月1日以前生まれは「0」、昭和30年4月2日生まれから昭和31年4月1日以前生まれは「480分の348」です。
経過的寡婦加算の額は、生年月日が若くなるほど少なくなるのがポイントです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金の受給権を有し、当該障害基礎年金の支給がされているときは、その間、経過的寡婦加算は支給が停止される。

【解答】
【R5年出題】 〇
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、障害基礎年金を受給する場合は、その間、経過的寡婦加算の支給が停止されます。
障害基礎年金によって、1階部分の年金額は、満額が保障されるからです。
(S60附則第73条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-101
R5.12.6 受給権の保護と公課の禁止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
「受給権の保護」について条文を読んでみましょう。
第24条 (受給権の保護) 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 |
★国民年金の給付を受ける権利は、保護されていて、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。
例外的に、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができます。
次は、「公課の禁止」について条文を読んでみましょう。
第25条 (公課の禁止) 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 |
★国民年金の給付は、原則として課税されません。
例外的に、老齢基礎年金及び付加年金は課税対象となります。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には、公課を課することができる。
②【R3年選択式】
国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、< A >として、課することができない。ただし、< B >については、この限りでない。」と規定している。

【解答】
①【H25年出題】 〇
老齢基礎年金及び付加年金は、課税対象となります。
②【R3年選択式】
A 給付として支給を受けた金銭を標準
B 老齢基礎年金及び付加年金
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

【解答】
【R5年出題】 ×
国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。
例外的に、「老齢基礎年金又は付加年金」を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることはできますが、「担保に供する」ことはできません。
また、遺族基礎年金については、例外なく、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-100
R5.12.5 保険料の繰上徴収
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第172条(保険料の繰上徴収) 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 2 法人である納付義務者が、解散をした場合 3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 |
健康保険の保険料の納付期限は翌月末日です。しかし、要件に該当した場合、納期前でも保険料を徴収することができる場合があります。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
②【H23年出題】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
③【H30年出題】
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険料の繰上徴収が認められます。
②【H23年出題】 〇
被保険者の使用されている事業所が廃止された場合は、保険料の繰上徴収が認められます。
③【H30年出題】 ×
工場または事業場の譲渡によって事業主が変更した場合は、「事業所の廃止」に含まれますので、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当します。
(S5.11.5保理513)
令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
②【R5年出題】
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

【解答】
①【R5年出題】 〇
納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険料の繰上徴収が認められます。
②【R5年出題】 ×
国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるときは、保険料の繰上徴収が認められます。
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料を納期前であってもすべて徴収することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-099
R5.12.4 雇用保険率 事業主負担と被保険者負担
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
令和5年度の雇用保険率は以下の通りです。
・一般の事業 1000分の15.5
・農林水産、清酒製造の事業 1000分の17.5
・建設の事業 1000分の18.5
労災保険料は事業主が全額負担しますが、雇用保険料は、事業主負担分と被保険者負担分に分けられるのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(雇用)
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

【解答】
【R2年出題】(雇用) ×
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料の額は、「労災保険料の額+雇用保険料の額」です。
労災保険料は事業主が全額負担しますので、労働者負担はありません。
雇用保険料については、二事業分は事業主が全額負担し、二事業以外の部分を事業主と被保険者が折半で負担します。
被保険者が負担するのは、「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額となります。
問題文は、「当該事業に係る一般保険料の額」となっています。労災保険と雇用保険が成立している場合、一般保険料には労災保険料も含まれますので、誤りです。
雇用保険率 | ||
二事業率 | 二事業率以外※ | |
事業主 | 事業主(2分の1) | 被保険者(2分の1) |
※二事業率以外の率は、「失業等給付・育児休業給付の保険料率」です。
(法第31条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) 〇
先ほどの図に数字を入れてみましょう。
雇用保険率 1,000分の15.5 | ||
二事業率 1000分の3.5 | 二事業率以外※ 1,000分の12 | |
事業主 1,000分の3.5 | 事業主(2分の1) 1,000分の6 | 被保険者(2分の1) 1,000分の6 |
事業主負担 → 1,000分の3.5+1,000分の6=1,000分の9.5
被保険者負担 → 1,000分の6
となります。
(法第31条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-098
R5.12.3 第6条 中間搾取の排除
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
②【H26年出題】
労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「何人も」とは、労働基準法の適用を受ける事業主に限定されません。その規制対象は、個人、団体又は公人、私人を問いません。そのため、公務員も規制対象となります。
(S23.3.2基発381号)
②【H26年出題】 ×
処罰対象は、個人、団体又は公人、私人を問いません。業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員だけではありません。
(S23.3.2基発381号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人の為に違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。

【解答】
【R5年出題】 ×
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、法人の為に違反行為を計画し、かつ実行した従業員が現実に利益を得ていない場合でも、法人の従業員について第6条違反が成立します。
(S34.2.1633基収8770号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-097
R5.12.2 賃金直接払の原則
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
賃金支払五原則の条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金支払の原則は次の5つです。
1 通貨払い
2 直接払い
3 全額払い
4 毎月1回以上払い
5 一定期日払い
今日は「直接払いの原則」をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
②【H28年出題】
労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H30年出題】
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
労働基準法第24条第1項は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止しています。そのため、労働者の親権者その他の法定代理人に賃金を支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは、第24条違反となります。
労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことはできません。
(S63.3.14基発150号)
②【H28年出題】 〇
労働者が賃金債権を他に譲渡した場合でも、労働基準法第24条の直接払いの原則は適用されますので、使用者は、直接労働者に対し賃金を支払わなければなりません。譲受人に対して賃金を支払うことはできません。
(最高三小43.3.12)
③【H30年出題】 〇
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、賃金直接払の原則には違反しません。
(S61.6.6基発333号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働者の親権者その他法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うこと、どちらも直接払の原則に違反します。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 労働基準法
R6-096
R5.12.1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
今日は労働基準法です。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のポイントをみていきます。
まず、ガイドラインの趣旨を読んでみましょう。
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。 (労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインより) |
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録しなければなりませんが、その原則的な方法をみていきます。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。

【解答】
【R5年出題】 〇
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいず
れかの方法によることとされています。
①使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
② タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録すること。
なお、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者
の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。
(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定))
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-095
R5.11.30 労働者の過半数を代表する者の要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
「労使協定」の労働者側の当事者は、
・事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
・労働者の過半数を代表する者
となります。
「労働者の過半数を代表する者」の条件を条文を読んでみましょう。
則第6条の2第1項、3項 ① 労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第41条第2項に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
②【H13年出題】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
③【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
労働者側の当事者である過半数を代表する者については、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」が条件です。
いわゆる管理監督者に当たる者は、過半数を代表する者になることはできません。
(則第6条の2第1項第1号)
②【H13年出題】 ×
監督又は管理の地位にある者は、「労働者の過半数を代表する者」になることはできません。
しかし、監督又は管理の地位にある者も「労働者」には該当します。そのため、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、監督又は管理の地位にある者も含みます。
(S46.1.1845基収6206号)
③【H22年出題】 ×
「協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」が条件ですので、「投票券等の書面を用いた労働者による投票」に限定されることはありません。
なお、「投票、挙手等」の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当事者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当する、とされています。
(H11.3.31基発169号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。

【解答】
【R5年出題】 ×
「労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと」という要件と、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」という要件を満たす必要があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-094
R5.11.29 任意適用事業所の認可
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「任意適用事業所」の認可について条文を読んでみましょう。
第6条第3項、4項、H24法附則第17条の2 ③ 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ④ 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第8条 ① 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 ② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
|
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の3分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えて、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければならない。
②【H30年出題】
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

【解答】
①【R2年出題】 ×
任意適用事業所になるための認可を受けるときは、当該事業所に使用される者(厚生年金保険法第12条に規定する者及び特定4分の3未満短時間労働者を除く。)の「2分の1」以上の同意が必要です。
任意適用事業所の認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用申請書を日本年金機構に提出しなければなりませんが、その際、2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添えなければなりません。
(法第6条第4項、則第13条の3)
②【H30年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の「4分の3以上」の同意が必要です。
(第8条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けることにより当該事業所を適用事業所でなくすることができるが、このためには、当該事業所に使用される者の全員の同意を得ることが必要である。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当する者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

【解答】
【R5年出題】 ×
任意適用事業所を適用事業所でなくするためには、当該事業所に使用される者の「4分の3」以上の同意を得ることが必要です。
(法第8条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-093
R5.11.28 厚生年金保険の被保険者は(原則)国民年金第2号被保険者
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金第2号被保険者です。
条文を読んでみましょう。
第7条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者は国民年金の被保険者とする。(「第2号被保険者」という。) 法附則第3条 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。 |
厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者となります。
ただし、当分の間は、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。
★65歳以上の厚生年金保険の被保険者でも、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は、第2号被保険者となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。
③【R3年出題】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者です。20歳未満でも厚生年金保険の被保険者であれば国民年金の第2号被保険者です。
第1号被保険者と第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」という年齢枠がありますが、第2号被保険者には「20歳以上60歳未満」の年齢枠がないのがポイントです。
②【R4年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者であったとしても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
③【R3年出題】 〇
「第3号被保険者」になるには、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。
「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は、厚生年金保険の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではありません。
問題文の55歳の配偶者は、第2号被保険者の配偶者ではありませんので、第3号被保険者になりません。
(法第7条第1項第3号)
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者でも、65歳未満の場合は、第2号被保険者になります。問題文は、「62歳」の特別支給の老齢厚生年金の受給権者ですので、第2号被保険者です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-092
R5.11.27 準備金の積立
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「準備金」について条文を読んでみましょう。
第160条の2 (準備金) 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
令第46条、令附則第5条 (準備金の積立て) ① 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の 2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
② 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 |
★保険者は、準備金を積み立てなければなりません。
・全国健康保険協会は、「保険給付」と「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の1=1か月分」の準備金を積み立てなければなりません。
・健康保険組合は、「保険給付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)=当分の間2か月分」と、「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の1=1か月分」の準備金を積み立てなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。
②【R1年選択式】
全国健康保険協会は、毎事業年度末において、< A >において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の< B >に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
全国健康保険協会の準備金の問題です。
準備金として積み立てなければならないのは、保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」です。3分の1ではありません。
また、保険給付に要した費用の額は、「前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除く。)」となります。
(令第46条第1項)
②【R1年選択式】
①と同じく全国健康保険協会の準備金の問題です。
<A> 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
<B>12分の1
(令第46条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の 1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
健康保険組合の準備金の問題です。
前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額です。12分の2ではありません。
(令第46条第2項、令附則第5条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-091
R5.11.26 労働保険料 年度更新の手続
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
今日は継続事業の労働保険料の年度更新手続きをみていきます。
継続事業の労働保険料は、「保険年度」単位で計算します。
保険年度ごとに、「賃金総額の見込額」で計算した「概算保険料」を申告・納付し、保険年度が終わってから、確定した賃金総額で計算した「確定保険料」で保険料のプラスマイナスを精算する仕組みです。
毎保険年度6月1日から40日以内に、「概算保険料」を申告・納付し、同時に、前年度の保険料を精算するために、「確定保険料」を申告・納付します。この手続きを「年度更新」といいます。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
②【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇 (雇用)
継続事業は、保険年度単位で労働保険料を計算します。
★概算保険料 → その保険年度の賃金総額の見込額で計算し、6月1日から40日以内に概算で保険料を申告・納付します。
★確定保険料 → その保険年度が終わってから確定した賃金総額で計算し、次の保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付し、納付済みの概算保険料を精算します。
なお、一括有期事業も継続事業と同じように、保険年度単位で労働保険料を計算します。
(法第15条、第19条)
②【H26年出題】(雇用) ×
継続事業(一括有期事業を含む。)の確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものは、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければなりません。
納付した概算保険料の額が足りないときは、その不足額を、「確定保険料申告書に 添えて」に納付しなければなりません。確定保険料の納付期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じですので、「確定保険料申告書の提出期限の翌日から40日以内」は誤りです。
(法第19条第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) 〇
令和4年6月1日に、継続事業の労働保険の保険関係が成立した場合、令和4年度末までの賃金総額の見込額で計算した概算保険料を、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付します。
令和4年度終了後に、確定した賃金総額で令和4年度の労働保険料を確定し、既に納付している概算保険料を精算します。この確定保険料の申告・納付手続は、令和5年6月1日から40日以内に行います。
同時に、賃金総額の見込額で計算した令和5年度の概算保険料を、令和5年6月1日から40日以内に申告・納付します。
令和5年度の概算保険料の申告・納付手続と令和4年度の確定保険料の申告・納付手続の期限が同じですので、令和5年度の保険年度に同一の用紙で一括して行うことができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 雇用保険法
R6-090
R5.11.25 移転費の支給要件
今日は雇用保険法です。
「移転費」の位置づけを条文で確認しましょう。
第10条第1項、4項 ① 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
④ 就職促進給付は、次のとおりとする。 1 就業促進手当 2 移転費 3 求職活動支援費 |
「失業等給付」は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」で構成されています。
その中の「就職促進給付」には、「就業促進手当」、「移転費」、「求職活動支援費」があります。
では、「移転費」について条文を読んでみましょう。
第58条 (移転費) ① 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。 ② 移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
則第86条 (移転費の支給要件) 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であって、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が1年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。 1 待期又は給付制限(法第32条第1項、第2項又は第52条第1項の規定による給付制限に限る。)の期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなった場合であって、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。 2 当該就職又は公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主、訓練等施設の長その他の者(以下「就職先の事業主等」という。)から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。 |
移転費は、要件を満たした「受給資格者等」に支給されます。
「受給資格者等」を確認しましょう。
・基本手当に係る受給資格者
・高年齢受給資格者
(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していない者を含む。)
・特例受給資格者
(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)
・日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。
②【H28年選択式】
雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、< A >の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。
③【H30年出題】
基本手当の受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くためその住所を変更する場合、移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、当該受給資格者は移転費を受給することができない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
移転費は、受給資格者等が「公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就くため」、又は「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため」、その住所又は居所を変更する場合に支給されます。
②【H28選択式】
A 受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族
③【H30年出題】 〇
移転費は、就職支度費が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないときに支給されます。
移転費の額を超える就職支度費が就職先の事業主から支給されるときは、移転費は支給されません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所の紹介した雇用期間が1年未満の職業に就くためその住居又は居所を変更する場合、移転費を受給することができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
雇用期間が1年未満の場合は、移転費は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-089
R5.11.24 第5条 強制労働の禁止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
労働者の意思に反して「労働を強制すること」を禁止する規定です。労働者が現実に「労働」することは必要ではなく、労働することを「強要」したなら、第5条違反となります。
(S23.3.2基発381号)
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
②【R3年出題】
労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
③【H29年出題】
労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。

【解答】
①【R2年出題】 〇
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」を用いて「労働を強制」した場合は、第5条違反となります。その手段の正当であるか不当であるかによって第5条違反が決定されます。
(S63.3.14基発150号)
②【R3年出題】 〇
「脅迫」とは、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足ります。
(S63.3.14基発150号)
③【H29年出題】 〇
「強制労働の禁止」に違反した使用者には、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という労働基準法で最も重い刑罰が科せられます。
(法第117条)
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
「監禁」とは、一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことにより、労働者の身体の自由を拘束することをいい、必ずしも物質的障害もってを手段とする必要はありません。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-088
R5.11.23 経過的加算額のしくみ
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
今日のテーマは経過的加算額です。
60歳台前半に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、定額部分と報酬比例部分で構成されています。
65歳以降は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」で構成されます。
60歳 65歳
報酬比例部分
|
老齢厚生年金 |
定額部分 | 経過的加算額 |
老齢基礎年金 |
★ 定額部分の額の計算式を確認しましょう ★
定額部分の額は、1,628円×改定率×被保険者期間の月数です。
ただし、定額単価の1,628円は、昭和21年4月1日以前に生まれた者は、生年月日に応じた読み替えがあります。
また、被保険者期間の月数には上限があり、例えば昭和21年4月2日以降に生まれた者は480月が上限です。
★ 老齢基礎年金の計算式を確認しましょう ★
保険料納付済期間が480月の場合、老齢基礎年金の額は、満額の780,900円×改定率です。
ただし、保険料納付済期間が480月未満の場合は、免除期間や合算対象期間等の月数に応じて、老齢基礎年金の額が減額されます。
ポイント!
★ 定額部分と老齢基礎年金の計算式が異なっているのがポイントです。当分の間は、定額部分の方が老齢基礎年金より高くなります。老齢基礎年金と定額部分の差をうめるためのものが、「経過的加算額」です。
★定額部分と老齢基礎年金の違いを確認しましょう ★
| 昭和36年3月以前の期間 | 20歳未満、60歳以後の期間 |
定 額 部 分 | 計算に入る | 計算に入る |
老齢基礎年金 | 合算対象期間 | 合算対象期間 |
では、過去問をどうぞ!
【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず、60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢厚生年金における経過的加算額の計算の基礎とされない。

【解答】
【R3年出題】 ×
60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は、経過的加算額の計算の基礎となります。定額部分の計算には、「60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間」が入るからです。
経過的加算額は、定額部分と老齢基礎年金の差額です。
ちなみに、経過的加算額を計算する際の老齢基礎年金は、「厚生年金保険の被保険者期間」だけで計算することがポイントです。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について、20歳に達した日の属する月から60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した甲と、20歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加入した乙とでは、老齢厚生年金における経過的加算の額は異なる。

【解答】
【R5年出題】 ×
甲と乙の経過的加算の額は、同額です。
★甲の経過的加算について
甲は保険料納付済期間が20歳から60歳までの480月です。
・定額部分に相当する額 → 1,628円×改定率×480月
・老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×480分の480
20歳から60歳まで全て保険料納付済期間(すべて厚生年金保険の被保険者期間)ですので、満額の老齢基礎年金が支給されます。
・経過的加算の計算式
→ (1,628円×改定率×480月)-(780,900円×改定率×480分の480)
★乙の経過的加算について
乙は、厚生年金保険に45年間(540月)加入していますが、老齢基礎年金の計算上、保険料納付済期間は20歳から60歳までの480月で、60歳から65歳までの60月は「合算対象期間」となります。
・定額部分に相当する額 → 1,628円×改定率×480月
定額部分には、480月の上限があることに注意してください。
・老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×480分の480
20歳から60歳まで全て保険料納付済期間ですので、満額の老齢基礎年金が支給されます。合算対象期間は老齢基礎年金の年金額には反映しません。
・経過的加算の計算式
→ 甲と同じ、(1,628円×改定率×480月)-(780,900円×改定率×480分の480)です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-087
R5.11.22 付加保険料納付済期間を有していた場合
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の4 (死亡一時金の額) ① 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次に定める額とする。
② 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。 |
・死亡一時金の額は、「保険料納付済期間の月数」+「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3」+「保険料半額免除期間の月数の2分の1」+「保険料4分の3免除期間の月数の4分の1」を合算した月数に応じて12万円から32万円まで6段階設定されています。
・付加保険料納付済期間が3年以上ある者の場合は、死亡一時金の額に8,500円が加算されます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
②【H29年出題】
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
③【R2年出題】
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
④【H21年出題】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

【解答】
①【H24年出題】 ×
死亡一時金の支給要件と死亡一時金の額の計算には、「保険料全額免除期間」は入りません。
死亡一時金は保険料が掛け捨てになることを防ぐための給付です。そのため、一部免除の期間は計算に入りますが、全額免除の期間は計算に入りません。
(法第52条の2)
②【H29年出題】 〇
付加保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算されます。
③【R2年出題】 〇
保険料納付済期間が36月間で、併せて付加保険料を36月間(3年間)納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円+8,500円で128,500円となります。
④【H21年出題】 ×
夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していたとしても、寡婦年金の額には加算はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。

【解答】
【R5年出題】 ×
夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合でも、寡婦年金の額には加算はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-086
R5.11.21 健康保険の被保険者資格
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険法では、『「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。』と定義されています。(法第3条第1項)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。
②【H26年出題】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は、被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日」に取得します。(法第35条)
「適用事業所に使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生した日です。事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、「事実の日にさかのぼって」資格を取得します。資格取得日を「調査の日」とするのは誤りです。
(昭和5.11.6保規第522号)
②【H26年出題】 ×
試用期間が定められていたとしても、被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日=雇入れの当初」から取得します。試用期間中も被保険者となります。「試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる」は誤りです。
(昭和13.10.22社庶第229号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。
②【R5年出題】
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
<健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則等により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合>
・ 例えば病気休職等の場合は、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しません。
・ なお、被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込みがない場合又は公務に就任しこれに専従する場合等においては被保険者資格を喪失させるのが妥当とされています。
(昭和26.3.9保文発第619号)
②【R5年出題】 ×
事業主が休業手当を支給する期間中は、被保険者資格を継続させること、とされていますので、問題文の被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失しません。
(昭和25.4.14保発第20号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-085
R5.11.20 労働保険料その他徴収金を納付しない場合の具体例
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 |
まず過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(雇用)
労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。
②【H22年出題】(雇用)
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。

【解答】
①【R1年出題】(雇用) 〇
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない場合」の具体例として、「保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料」の完納がない場合があります。
②【H22年出題】(雇用) 〇
「認定決定に係る概算保険料」について完納がない場合も、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない場合」の具体例です。事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、督促が行われます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) ×
概算保険料、確定保険料を納期限までに申告しない場合は、政府が認定決定をし、事業主に通知します。 事業主は、認定決定された労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければなりません。
督促が行われるのは、認定決定の通知があったにもかかわらず、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しない場合です。
認定決定と同時に督促が行われるのではなく、認定決定に係る確定保険料をその期限までに完納しない場合に、督促が行われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法
R6-084
R5.11.19 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給額は、一般教育訓練の受講のために支払った費用の20%です。ただし、上限は10万円です。また、4千円を超えない場合は、支給されません。
今日は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請の手続をみていきます。
条文を読んでみましょう。
則第101条の2の11(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続) ① 教育訓練給付対象者は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 1 一般教育訓練修了証明書 2 当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の受講のために支払った費用の額を証明することができる書類 3 第101条の2の6第2号に掲げる費用の額を証明することができる書類及び当該一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書 4 その他職業安定局長が定める書類 ② 教育訓練給付対象者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第4号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。
②【H27年出題】
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲は、入学料、受講料及び交通費である。
③【H25年出題】
教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。
④【H27年出題】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して3か月以内に申請しなければならない。
⑤【H25年出題】
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。

【解答】
①【R3年出題】 〇
一般教育訓練給付金は、一時金で支給されます。
教育訓練経費の20%に相当する額ですが、上限は10万円です。
(行政手引58014)
②【H27年出題】 ×
交通費は、教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲に入りません。
(行政手引58014)
教育訓練給付金の支給の対象となる費用の範囲を確認しましょう。
1 入学料及び受講料(最大1年分)
2 一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタントが行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
③【H25年出題】 ×
教育訓練給付金の額として算定された額が「4,000円」を超えないときは教育訓練給付金は、支給されません。問題文は算定された額が5,000円ですので、支給されます。
(法第60条の2第5項 則第101条の2の9)
④【H27年出題】 ×
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。
(則第101条の2の11)
⑤【H25年出題】 〇
管轄公共職業安定所の長は、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して「7日以内」に教育訓練給付金を支給する、とされています。
(則第101条の2の13)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることその他やむを得ない理由がなくとも社会保険労務士により支給申請を行うことができる。
②【R5年出題】
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該教育訓練給付金の支給に係る一般教育訓練の修了予定日の1か月前までに教育訓練給付金支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
支給申請は、疾病又は負傷そのたやむを得ない理由(在職中であること)があると認められない限り、代理人(提出代行を行う社会保険労務士を含む。)、又は郵送によって行うことができない、とされています。
(行政手引58015
②【R5年出題】 ×
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請は、一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内にしなければなりません。「修了予定日の1か月前までに」ではありません。
(則第101条の2の11)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-083
R5.11.18 労災保険と「厚生年金保険・国民年金」との調整
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労災保険法です。
労災保険の保険給付と、「国民年金・厚生年金保険」の年金は、併給できます。
ただし、「同一の事由」で支給される場合は、「労災保険」の年金たる保険給付が減額されます。同一事由による補償が二重になることを防ぐためです。労災年金は減額されますが、「国民年金・厚生年金」は全額支給されます。「国民年金・厚生年金」は、本人が保険料を負担することにより、支給されるものだからです。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】(修正あり)
労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額が全額支給される。
②【H12年出題】
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。
③【H12年出題】
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。

【解答】
①【H18年出題】 ×
労災年金と「同一の事由」により厚生年金保険の年金又は国民年金の年金が支給される場合は、労災年金は、「減額」して支給されます。
(法別表第1)
②【H12年出題】 〇
休業補償給付を受ける労働者が「同一の事由」について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、休業補償給付の額が減額されます。
(法第14条第2項)
同一の事由で厚生年金・国民年金が支給される場合に調整される労災保険の保険給付は、年金だけでなく休業補償給付も対象になります。
③【H12年出題】 〇
同時に厚生年金保険法の老齢厚生年金又は国民年金法の老齢基礎年金を受けることができる場合でも、労災年金は、全額支給されます。給付事由が異なるためです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
(ア)
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額とする。
(イ)
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
(ウ)
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
(エ)
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
(オ)
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
(ア) 〇
「同一の事由」により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金は減額され、障害補償年金の額は、調整率を乗じて得た額となります。問題文の場合、調整率は「0.73」です。
(別表第1)
政令で定める率の一覧表(施行令第2条~第7条)
| 厚生年金 + 国民年金 |
厚生年金のみ |
国民年金のみ |
障害補償年金 複数事業労働者障害年金 障害年金 | 障害厚生年金 +障害基礎年金 0.73 | 障害厚生年金
0.83 | 障害基礎年金
0.88 |
傷病補償年金 複数事業労働者傷病年金 傷病年金 | 障害厚生年金 +障害基礎年金 0.73 | 障害厚生年金
0.88 | 障害基礎年金
0.88 |
遺族補償年金 複数事業労働者遺族年金 遺族年金 | 遺族厚生年金 +遺族基礎年金 又は寡婦年金 0.80 | 遺族厚生年金
0.84 | 遺族基礎年金 又は寡婦年金
0.88 |
※休業補償給付の額を調整する場合は、傷病補償年金と同じ調整率を使います。
(イ) ×
既に受給している障害基礎年金と、新たに受け取る障害補償年金は、支給事由が異なります。そのため、障害補償年金の額は調整されず、全額が支給されます。
(ウ) ×
障害基礎年金と遺族補償年金は支給事由が異なりますので、遺族補償年金は全額支給されます。
(エ) 〇
同一の事由により遺族補償年金と「遺族厚生年金及び遺族基礎年金」を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80を乗じて得た額となります。
(オ) ×
遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は、全額支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-082
R5.11.17 天災その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
第20条第1項、3項 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 |
★解雇が制限される期間は次の2つです。
① 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業する期間+その後30日間
② 産前産後の女性が休業する期間+その後30日間
(例外)
・打切補償を支払う場合
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
★解雇しようとする場合は、予告が必要です。
・少なくとも30日前に予告をする又は30日分以上の平均賃金を支払う(予告期間と平均賃金を併用することもできます)
(例外)
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
②【R2年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
③【H30年出題】
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
例外が認められる第19条、20条の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」、第20条の「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません。使用者の一方的な判断で例外が適用されることを防ぐためです。
②【R2年出題】 ×
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由です。「事業場が火災により焼失した場合」はやむを得ない事由に該当しますが、事業主の故意又は過失に基づく場合は除かれます。
問題文の「使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合」はやむを得ない事由に含まれません。
(S63.3.14基発150号)
③【H30年出題】 ×
税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合は、「やむを得ない事由」に該当しません。その場合は、産前産後休業中の女性労働者は解雇できません。
(S63.3.14基発150号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。

【解答】
【R5年出題】 〇
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しません。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-081
R5.11.16 中高齢寡婦加算と遺族基礎年金の調整
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「中高齢寡婦加算」は、要件を満たした妻が受ける遺族厚生年金に加算されます。
★中高齢寡婦加算が加算されるのは、次のいずれかの要件に該当する妻です。
(1) 遺族厚生年金の権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの
(2) 40歳に達した当時被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたもの(=40歳に達した当時、子と生計を同じくし遺族基礎年金を受けていたもの)
★中高齢寡婦加算が加算されるのは、40歳から65歳になるまでの間です。
★中高齢寡婦加算の額は、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額」です。
(法第62条第1項)
(例)夫の死亡当時、妻が50歳で、生計を同じくする子がいない(=遺族基礎年金を受けていない)場合、50歳から65歳まで中高齢寡婦加算が加算されます。
50歳 65歳
遺 族 厚 生 年 金
| |
中高齢寡婦加算 | 老齢基礎年金 |
| |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
②【H28年出題】
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。
③【R3年出題】
夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上あるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
夫の死亡時に、30歳以上40歳未満で子がいない妻には、中高齢寡婦加算は加算されません。
子がいない妻の場合は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満でなければなりません。
②【H28年出題】 〇
子のある妻の場合は、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金は、子が18歳になる年度の3月31日まで(障害状態にある場合は20歳になるまで)支給されますが、遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額は支給が停止されます。
条文を読んでみましょう。
第65条 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給を停止する。 |
65歳
遺族厚生年金
| ||
遺族基礎年金 | 中高齢寡婦加算 | 老齢基礎年金
|
| ||
子 18歳年度末
※遺族基礎年金を受ける間、中高齢寡婦加算は支給停止されます。
③【R3年出題】 ×
中高齢寡婦加算額は、満額の遺族基礎年金の額ではなく、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じた額」です。
妻が、夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給は停止されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止される。

【解答】
【R5年出題】 〇
中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者である妻が、遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢寡婦加算は支給が停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-080
R5.11.15 付加年金の支給要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第87条の2第1項 第1号被保険者(法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、保険料一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金の保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。
第43条 (付加年金の支給要件) 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 (付加年金の年金額) 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
|
・付加保険料(月400円)を納付することができるのは、第1号被保険者のみです。なお、65歳未満の任意加入被保険者も付加保険料を納付できます。
・保険料の免除を受けている者は付加保険料を納付できません。
・国民年金基金の加入員も付加保険料を納付できません。
・付加年金は、付加保険料の保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
・付加年金の年金額は、「200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
②【R4年出題】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。
第2号被保険者、第3号被保険者としての被保険者期間は対象になりません。
②【R4年出題】 ×
付加保険料に係る納付済期間を60月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される付加年金の額は、年額で、「200円」に60月を乗じて得た額です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。

【解答】
【R5年出題】 ×
付加保険料の額は月400円で、付加年金の額は「200円」×付加保険料に係る納付済期間の月数で計算します。付加年金は、月400円の付加保険料を納付していることが前提です。
そのため、付加年金は、「付加保険料」の保険料納付済期間を有する者(=付加保険料を納付した者)が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加保険料の納付済期間の月数に応じて支給されます。
なお、第2号被保険者、第3号被保険者は付加保険料を納付することはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-079
R5.11.14 傷病手当金の継続給付
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
第108条第5項 傷病手当金の継続給付を受けるべき者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者でないこととする。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
傷病手当金の継続給付を受ける者が、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の支給を受けることができるときは、原則として、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるとき、「傷病手当金」は支給されません。
ただし、老齢退職年金給付÷360(1日当たり単価です)が、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
(則第89条第2項)
②【H27年出題】 〇
老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受ける者に限られます。「適用事業所に使用される被保険者」=在職中の者は、傷病手当金と「老齢基礎年金及び老齢厚生年金」との調整は行われません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

【解答】
【R5年出題】 ×
傷病手当金の継続給付と「老齢基礎年金・老齢厚生年金等」との調整のポイント!
★ 日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者は、傷病手当金の継続給付と「老齢基礎年金・老齢厚生年金等」との調整の対象から除かれます。「傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。」は誤りです。
★ 「傷病手当金」は原則として支給されませんが、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の方が少ないときは差額が支給されます。差額が支給されることもありますので、「打ち切られる」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-078
R5.11.13 第2種特別加入保険料の算定
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つがあり、保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。
特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。
なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、別表第5)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。

【解答】
【R5年出題】 〇 (労災)
給付基礎日額が12,000円の場合、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、12,000円×365=4,380,000円です。
また、第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて、1000分の3から1000分の52の範囲です。
最高の率の1,000分の52で計算すると、4,380,000円×1000分の52=227,760円となり、事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間の第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 雇用保険法
R6-077
R5.11.12 育児休業給付金の支給単位期間
今日は雇用保険法です。
まず、「支給単位期間」について条文を読んでみましょう。
第61条の7第5項 「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあっては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 |
例えば、令和5年11月12日に子を出産し、令和6年1月7日まで産後休業を取得し、令和6年1月8日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得した場合の支給単位期間をみてみましょう。
「育児休業を開始した日」は1月8日で、休業開始応当日は各月の8日です。
支給単位期間は、育児休業を開始した日(1月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(2月7日)までの1か月、次が、休業開始応当日(2月8日)から翌月の休業開始応当日の前日(3月7日)の1か月で、以降も同じように休業開始応当日(各月8日)から翌月の休業開始応当日の前日までの1か月ごとに区切っていきます。
育児休業を終了した日の属する月の支給単位期間は令和6年11月8日から11月10日までとなります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
(A) 0か月
(B) 3か月
(C) 4か月
(D) 5か月
(E) 6か月

【解答】
(D) 5か月
問題文の場合、同一の子について、育児休業を3回取得しているのがポイントです。
1回目 2月4日~5月3日
2回目 6月10日~8月9日
3回目 11月9日~12月8日
★3回目の育児休業は、原則として、育児休業給付金の対象になりません。
条文を読んでみましょう。
第61条の7第2項 被保険者が育児休業について育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、育児休業給付金は、支給しない。 |
3回目の育児休業(11月9日~12月8日)は、「厚生労働省令で定める場合に該当しない」と問題文にありますので、育児休業給付金の対象になりません。
そのため、支給単位期間は、5か月となります。
1回目の育児休業の支給単位期間
↓
「2月4日~3月3日」、「3月4日~4月3日」、「4月4日~5月3日」の3か月
2回目の育児休業の支給単位期間
↓
「6月10日~7月9日」、「7月10日~8月9日」の2か月
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-076
R5.11.11 副業・兼業の休憩について
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第38条第1項 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 |
第38条第1項の規定により、複数の事業場における労働時間は通算されます。
また、事業主が異なっていても(会社が違っていても)、労働時間は通算されます。
(S23.5.14基発769)
まず、過去問をどうぞ
【H26年出題】
労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も通算される。

【解答】
【H26年出題】 〇
例えば、A株式会社の大阪支店と神戸営業所で労働した場合は、労働時間は通算されます。また、A株式会社の事業場とB株式会社の事業場で労働するような場合(事業主を異にする事業場において労働する場合)も労働時間は通算されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働者が、事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、第32条・第40条に定める法定労働時間は通算されます。
しかし、「休憩(法第 34 条)、休日(法第 35 条)、年次有給休暇(法第 39 条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されないこと。」とされています。
問題文の「第34条に定める休憩」の適用については、通算されません。
(R2.9.1基 発 0 901 第 3 号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-075
R5.11.10 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から65歳になるまでの間に支給される老齢厚生年金です。
2階建てになっていて、1階が「定額部分」、2階が「報酬比例部分」となります。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) |
定額部分 | 老齢基礎年金 |
しかし、男性の場合、60歳から定額部分と報酬比例部分が支給されるのは、昭和16年4月1日以前生まれまでです。昭和16年4月2日以降生まれの男性は、定額部分の開始年齢が1歳ずつ段階的に引き上げられます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
定額部分 | 老齢基礎年金 | |
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日以前生まれの男性は、60歳から報酬比例部分のみ支給されます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 | |
昭和28年4月2日以降生まれの男性は、報酬比例部分の開始年齢が1歳ずつ引き上げられます。
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
昭和36年4月2日以降生まれの男性は、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
60歳 65歳
| 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
男性の生年月日の重要ポイントは、16年、24年、28年、36年の4つです。
定額部分の開始が61歳になる昭和16年4月2日、報酬比例部分のみになる昭和24年4月2日、報酬比例部分の開始が61歳になる昭和28年4月2日、特別支給の老齢厚生年金が支給されない昭和36年4月2日をおぼえましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
②【R3年出題】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。
③【H29年出題】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。

【解答】
①【R3年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者期間を有する女性は、特別支給の老齢厚生年金の開始年齢が男性と異なりますので注意してください。先ほどおぼえた男性の生年月日に「5」をプラスします。第1号の女性の生年月日のポイントは、21年、29年、33年、41年の4つです。
昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女性の特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分のみで、62歳から支給されます。同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男性の特別支給の老齢厚生年金も、報酬比例部分のみですが、64歳から支給されます。
②【R3年出題】 〇
第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間を有する女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性と同じです。
昭和35年8月22日生まれの第4号のみの女性と、同日生まれの第4号のみの男性は、報酬比例部分のみが支給され、支給開始年齢はどちらも64歳です。
③【H29年出題】 〇
第1号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和29年4月1日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は、以下の形になります。
60歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
定額部分 | 老齢基礎年金 | |
第1号女性の場合、定額部分の支給開始が61歳になるのは昭和21年4月2日以降生まれです。(男性の生年月日に5を足してください)
2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、21年4月2日生まれが61歳、23年4月2日生まれが62歳、25年4月2日生まれが63歳、27年4月2日生まれが64歳となります。
29年4月1日生まれは、報酬比例部分は60歳から、定額部分は64歳から支給されます。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。

【解答】
【R5年出題】 〇
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性の特別支給の老齢厚生年金は次の形になります。
60歳
報酬比例 | 老齢厚生年金(報酬比例部分) | |
| 老齢基礎年金 |
報酬比例部分の支給開始年齢は、同日生まれの男性と同じ64歳です。
報酬比例部分の開始が61歳になるのが昭和28年4月2日生まれ以降です。2年刻みで1歳ずつ引き上げられますので、28年4月2日生まれが61歳、30年4月2日生まれが62歳、32年4月2日生まれが63歳、34年4月2日生まれが64歳です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-074
R5.11.9 死亡一時金の遺族の範囲
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 (死亡一時金の支給要件) 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
第52条の3(遺族の範囲及び順位等) ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金(①ただし書に規定するものを除く。)を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と「生計を同じくしていた」ものです。
また、受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
②【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これらの者以外の三親等内の親族は、死亡一時金の遺族になりません。
②【R1年出題】 〇
祖父母と孫では、死亡一時金を受ける順位は孫が優先します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金をうけることができる遺族はいないものとする。

【解答】
【R5年出題】 ×
死亡した甲の妹は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていた場合は、生計を維持していなくても死亡一時金の支給を受けることができます。
「生計維持」の要件には「収入要件」がありますが、「生計同一」には収入要件はありません。
死亡一時金の対象になる遺族は、「生計を同じくしていること」ですので、生計維持要件は問われません。
(参照:H23.3.23年発0323第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-073
R5.11.8 随時改定「固定的賃金の変動」の具体例
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
今日は随時改定です。
条文を読んでみましょう。
第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 随時改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
★随時改定の要件は次の3つです。
ⅰ 昇給や降給で固定的賃金が変動した
ⅱ 変動した月から3か月間の報酬の平均による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
ⅲ 3か月間の全ての月の報酬支払基礎日数が17日以上である。(短時間労働者は11日以上)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
②【R4年出題】
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
産前産後休業中に、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合は、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないので、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象となりません。
(R4.9.5事務連絡より)
随時改定の要件の一つに、「固定的賃金の変動」があります。
給与体系の変更は固定的賃金の変動に当たりますが、「給与体系の変更に当たらない」事例の問題です。
②【R4年出題】 ×
単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変更として取り扱います。
ガソリン単価を月単位で見直し、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合は、随時改定の対象となります。
(R4.9.5事務連絡より)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
ポイント!
★在宅勤務手当の考え方
・実費弁償分 → 「報酬等」に含まれません。例えばパソコンの購入や通信に要する費用などです。
・実費弁償に当たらないもの(労働の対償として支払われる性質のもの) → 「報酬等」に含まれます。例えば、毎月5000円を渡し切りで支給するものです。
★在宅勤務手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないため、随時改定の対象になりません。
(R4.9.5事務連絡より)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-072
R5.11.7 第3種特別加入保険料の算定
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の 3つがあります。
保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。
特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。
なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(労災)※改正による修正あり
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和5年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。
②【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
①【H26年出題】(労災) ×
令和5年度の第3種特別加入保険料率は事業の種類にかかわらず一律に 「1000分の3」とされています。
第3種特別加入保険料率は、「一律」で定められているのがポイントです。
(第14条の2、則第24条の3)
なお、第1種特別加入保険料率は、「当該事業に適用される労災保険率と同一の率」で、第2種特別加入保険料率は、1000分の3から1000分の52の範囲で、事業又は作業の種類ごとに定められていています。
②【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、別表第5)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者における給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円とする。

【解答】
【R5年出題】(労災) ×
「第3種特別加入保険料の額」は、保険料算定基礎額の総額(給付基礎日額×365)×第3種特別加入保険料率で算定します。
問題文にあてはめると、(12,000円×365)×1000分の3=13,140円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法
R6-071
R5.11.6 賃金日額の算定基礎に算入されるもの・されないもの
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は雇用保険法です。
まず、雇用保険法の「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
第4条第4項 「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。 |
雇用保険法の「賃金」とは、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてものをいいます。ただし、「通貨以外のもの=現物給付」で支払われるものであって、則第 2条で定める範囲外のものは賃金となりません。
次に「賃金日額」の条文を読んでみましょう。
第17条第1項 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
「臨時」に支払われる賃金、「3か月を超える期間ごと」に支払われる賃金は、賃金日額の算定の基礎となる賃金から除外されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
③【H26年出題】
月あたり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
④【H26年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金は、健康保険の給付金ですので、「賃金とは認められません」。
その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、「恩恵的給付」となり、「賃金とは認められません」。
(行政手引50502 「賃金と解されないものの例」)
②【H30年出題】 〇
チップは接客係等が客からもらうもので、賃金とは認められません。
ただし、一度事業主の手を経て再分配されるものは「賃金と認められます」。
(行政手引50502 「賃金と解されないものの例」)
③【H26年出題】 ×
賃金とは、「事業主が労働者に支払ったものであること」、「労働の対償として支払ったものであること」の要件があります。
定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は、「労働の対償として支払われるもの」となり、「賃金に含まれます」。
④【H26年出題】 ×
「住居の利益」は賃金となりますので、賃金日額の算定対象に「含まれます」。
通貨以外のもので支払われる賃金(=現物給与)の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによります。食事、被服及び住居の利益は公共職業安定所長が定めるまでもなく賃金の範囲に算入されます。
(行政手引50403「賃金の範囲に算入される現物給与」、行政手引50501「賃金と解されるものの例」)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
退職金相当額の全部又は一部を労働者の在職中に給与に上乗せする等により支払う、いわゆる「前払い退職金」は、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金に該当する場合を除き、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれる。

【解答】
【R5年出題】 〇
いわゆる「前払い退職金」は、、原則として、賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲に含まれます。
なお、労働者の退職後に一時金又は年金として支払われる退職金は、賃金日額算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-070
R5.11.5 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働の適用について
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
災害等による臨時の必要がある場合は、使用者は行政官庁の許可を受けて、時間外労働・休日労働をさせることができます。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働) 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 |
「年少者」の適用について条文を読んでみましょう。
第60条第1項 第32条の2から第32の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。 |
第32条の2から第32の5(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、 1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第36条(36協定による時間外・休日労働)、第40条(労働時間及び休日の特例)、第41条の2(高度プロフェッショナル制度)は、年少者には適用されません。
次に、「妊産婦」の適用について条文を読んでみましょう。
第66条第2項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 |
第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)、第36条第1項(36協定による場合)でも、 妊産婦は、時間外労働・休日労働をしないことを請求することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
②【H25年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
18歳未満の者には、第36条(36協定による時間外・休日労働)の規定は、適用されません。そのため、36協定があっても時間外労働を行わせることはできません。
第33条(災害等による臨時の必要がある場合)の規定は、18歳未満の者にも適用されます。災害等による臨時の必要がある場合は、満18歳未満の者でも時間外労働・休日労働をさせることができます。
②【H25年出題】 〇
妊産婦が請求した場合は、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合、36協定による場合でも、時間外労働・休日労働はさせられません。妊産婦全員ではなく、「妊産婦が請求した場合」に禁止されることに注意してください。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。

【解答】
【R5年出題】 〇
第33条第1項「災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等」の規定について
・年少者には適用されます。災害等により臨時の必要がある場合は年少者に時間外労働等をさせることができます。
・「妊産婦が請求」した場合は、災害等により臨時の必要がある場合でも、時間外労働等をさせることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労働に関する一般常識
R6-069
R5.11.4 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知と意向確認
今日は育児介護休業法です。
令和4年4月の改正で、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知と意向確認が義務化されました。
条文を読んでみましょう。
第21条 (妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) ① 事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。 ② 事業主は、労働者が申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
則第69条の3 育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 育児休業に関する制度 2 育児休業申出等の申出先 3 雇用保険法に規定する育児休業給付に関すること。 4 労働者が育児休業期間及び出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い |
※個別周知・意向確認の方法
ⅰ 面談
ⅱ 書面の交付
ⅲ ファクシミリ
ⅳ 電子メール等
(ⅲ及びⅳについては、労働者が希望する場合に限ります。)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
労働者から、本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、当該労働者に対して、育児休業制度等(出生時育児休業も含みます。)について周知するとともに、制度の取得意向を確認するための措置を実施する必要があります。
※取得を控えさせるような形での個別の周知と意向確認は認められません。
(令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&Aより)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-068
R5.11.3 5年に一度の財政検証
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第2条の4(財政の現況及び見通しの作成) ① 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。 ② 財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする。 ③ 政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 |
政府は、少なくとも5年ごとに、国民年金及び厚生年金の財政の現況及び見通しを作成しています。このことを「財政検証」といいます。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年出題】
財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とされている。

【解答】
【H30年出題】 〇
「財政均衡期間」は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
政府は、令和元年8月に、国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを公表した。そのため、遅くとも令和7年12月末までには、新たな国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しを作成しなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
財政検証は、少なくとも5年ごとに実施することになっています。
政府は、令和元年8月に、「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通し」を公表しています。財政検証の実施は、「少なくとも5年ごと」ですので、次は、 令和6年となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-067
R5.11.2 法定免除の対象になる月
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第89条第1項 被保険者(産前産後の保険料免除及び保険料一部免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 1 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 2 生活保護法による生活扶助を受けるとき。 3 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき。 |
★法定免除から除外される被保険者
・産前産後免除の要件を満たしている場合は、法定免除の対象から除外されます。産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるからです。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けている間は、法定免除の対象から除外されます。
★法定免除が適用される期間
法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月
~
該当しなくなる日の属する月まで
・例えば、11月2日に法定免除の要件に該当した場合は、前月(10月)から免除されます。10月の保険料納期限は11月末で、まだ期限が到来していないからです。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
②【R2年出題】
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
法定免除事由に該当すれば、当然に保険料を納付する義務がなくなります。法定免除には所得要件はありません。
②【R2年出題】 〇
保険料の法定免除事由に該当した場合、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から当然に保険料が免除になります。ただし、「届出」が必要です。法定免除事由に該当した日から14日以内に届書を市町村に提出しなければなりません。なお、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は要りません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。

【解答】
【R5年出題】 〇
学生納付特例の適用を受けている第1号被保険者が、法定免除の要件に該当した場合は、法定免除の対象になります。法定免除の期間は、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-066
R5.11.1 家族出産育児一時金のポイント
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第114条 (家族出産育児一時金) 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。 |
被扶養者が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。
被扶養者ではなく「被保険者」に対し支給されるのがポイントです。
家族出産育児一時金の額は、出産育児一時金と同額です。
「出産育児一時金」の額は、令和5年4月1日に改正されています。
・産科医療補償制度に加入する医療機関等で、妊娠週数22週以降に出産した場合は、 1児につき「50万円」が支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合・産科医療補償制度に加入する医療機関等でも妊娠週数22週未満で出産した場合は、「48万8千円」となります。
(令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
②【H23年出題】
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。
③【H27出題】※改正による修正あり
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50万円、それ以外のときには 48万8千円である。

【解答】
①【R3年出題】 ×
家族出産育児一時金は、「被保険者の被扶養者」が出産したときに支給されます。配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合も対象です。
②【H23年出題】 〇
「家族」に関する保険給付は、「被保険者に対して」支給されるのがポイントです。
「被扶養者に対して支給する」となっていると誤りです。
③【H27出題】※改正による修正あり 〇
出産育児一時金として政令で定める金額は、48万8千円です。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)の場合は、1万2千円が加算され50万円となります。
(令第36条、令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】
【R5年出題】 〇
1児あたり50万円ですので、双子の場合は100万円となります。
(昭16.7.23社発第991号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-065
R5.10.31 雇用保険印紙の買戻し
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
則第43条第2項、3項 ② 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、3.に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。 1. 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 3. 雇用保険印紙が変更されたとき。 ③ 事業主は、1.又は2.に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。 |
1.2.3.に該当するときは、雇用保険印紙の買戻しの申出をすることができます。
買戻しの条件に注意しましょう。
| 買戻し期間 | 公共職業安定所長の 確認 |
1.雇用保険に係る保険関係が消滅 | なし | 受けなければならない |
2.日雇労働被保険者を使用しなくなった | なし | 受けなければならない |
3.雇用保険印紙が変更 | 6月間 | 不要 |
過去問をどうぞ!
【H18年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から 6か月間である。

【解答】
【H18年出題】(雇用) 〇
雇用保険印紙が変更された場合は、買戻しの期間が決められているのがポイントです。期間は、「雇用保険印紙が変更された日から6か月間」です。なお、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要はありません。
ちなみに、「雇用保険に係る保険関係が消滅したとき」、「日雇労働被保険者を使用しなくなったとき」は、買戻しの期間は決められていませんが、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けることが必要です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙が変更されたときに、買戻しを申し出ることができるのは、その変更された日から「6か月間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 雇用保険法
R6-064
R5.10.30 賃金日額の最高額、最低額
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項・2項 (基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更) ① 厚生労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)が、直近の自動変更対象額が変更がされた年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 ② 変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 |
基本手当の日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて、変更されます。
令和4年度の平均給与額は、令和3年度と比べて、約1.6%上昇しています。
そのため、令和5年8月1日以降の賃金日額・基本手当の日額の最高額は以下の通りになりました。
| 賃金日額の上限 | 給付率 | 基本手当の日額の上限 |
60歳以上65歳未満 | 16,210 | 45% | 7,294 |
45歳以降60歳未満 | 16,980 | 50% | 8,490 |
30歳以上45歳未満 | 15,430 | 50% | 7,715 |
30歳未満 | 13,890 | 50% | 6,945 |
なお、賃金日額・基本手当の日額の最低額は以下の通りです。
| 賃金日額の下限 | 給付率 | 基本手当の日額の下限 |
年齢関係なく | 2,746 | 80% | 2,196 |
では、過去問どうぞ!
【R1年出題】
厚生労働大臣は、4月1日からの年度の平均給与額が、平成27年4月1日から始まる年度(自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。

【解答】
【R1年出題】 〇
ポイント!
・自動変更対象額は、毎年度の平均給与額の変動に応じて、変更されます。
・自動変更対象額は、翌年度の8月1日から変更になります。
令和4年度の平均給与額は、令和3年度と比べて、約1.6%上昇していますが、その比率に応じて自動変更対象額が変更されるのは、令和5年8月1日からです。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
雇用保険法第18条第3項に規定する最低賃金日額は、同条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とされる。

【解答】
【R5年出題】 〇
毎年度の平均給与額の変動に応じて変更された最低額が、「最低賃金日額」を下回る場合は、最低賃金日額が最低額となります。
条文を読んでみましょう。
法第18条第3項 法第18条第1項及び第2項の規定により算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の4月1日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法に規定する地域別最低賃金)をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とする。
則第28条の5 (最低賃金日額の算定方法) 最低賃金日額は、法第18条第1項及び第2項の規定により変更された自動変更対象額が適用される年度の4月1日に効力を有する最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。 |
最低賃金日額は、地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額です。
「20」は、週所定労働時間が20時間の労働者を想定して算出されています。
「7」は、1週間の日数です。
(参考)
令和5年8月1日以降の最低額は、最低賃金日額が適用されています。
961円×20÷7×80%で、基本手当の日額の最低額は、2,196円となります。
・961円→令和5年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額です。
・961円×20÷7が最低賃金日額です。
・80%は給付率です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-063
R5.10.29 産前産後休業
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第65条第1項、2項 (産前産後) ① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
ポイント!
①産前休業
・女性労働者からの「請求」が要件です。
・産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)です。
②産後休業
・産後休業は8週間です。請求は要件ではありません。
・6週間を経過した後は、女性労働者が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
②【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
③【H25年出題】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
④【R3年出題】
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
⑤【R3年出題】
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
「出産」の範囲は妊娠4か月以上で、1か月は28日として計算します。そのため、 4か月以上とは、85日以上となります。
(S23.12.23基発1885号)
②【R3年出題】 ×
「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩ですので、生産のみならず死産も含まれます。妊娠中絶も妊娠4か月以後に行った場合は、対象になります。
(S26.4.2婦発113号)
③【H25年出題】 ×
妊娠85日以上の場合は、労働基準法第65条が適用されます。妊娠100日目の女性が流産した場合は、産後休業を与えなければなりません。
(S23.12.23基発1885号)
④【R3年出題】 〇
出産当日は、産前6週間に含まれます。
(S25.3.31基収4057号)
⑤【R3年出題】 〇
6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、女性労働者からの請求が産前休業の条件です。女性労働者から請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

【解答】
【R5年出題】 〇
産前6週間は、自然の出産予定日を基準に計算し、産後8週間は、現実の出産日を基準に計算します。
妊娠中絶については、産前6週間の休業の問題は発生しません。
しかし、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後に妊娠中絶を行った場合は、産後休業が適用されます。
(S26.4.2婦発113号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-062
R5.10.28 障害手当金の額の計算式
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第57条 (障害手当金の額) 障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 |
障害手当金の額の計算式は、以下の通りです。
↓
| 報酬比例の額(第50条第1項の規定の例により計算した額)×100分の200 |
また、障害手当金には最低保障額があります。
最低保障額の計算式は、以下の通りです。
↓
| 障害厚生年金の最低保障額(第50条第3項に定める額=2級の障害基礎年金の額× 4分の3)×2 |
参考にこちらの条文も読んでみましょう。
第50条第1項、3項 <障害厚生年金の額> ① 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 <障害厚生年金の最低保障額> ③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
②【H26年選択式】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に< A >を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。

【解答】
①【H29年出題】 ×
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額です。
ただし、その額が2級の障害基礎年金の額に「4分の3を乗じて得た額」の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされます。
問題文は、「4分の3」が抜けているので誤りです。
※障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額です。
②【H26年選択式】
A 2
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。

【R5年出題】 ×
先ほどの平成29年の問題と同じく、4分の3が抜けているので誤りです。
障害手当金の最低保障額は、「障害基礎年金2級の額×4分の3」に2を乗じて得た額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-061
R5.10.27 保険料免除期間の定義
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
法第5条第2項~6項 ② 「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。 ③ 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ④ 「保険料4分の3免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑤ 「保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑥ 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
ポイント!
・保険料免除期間は、「第1号被保険者」のみに適用されます。
・保険料免除期間には、以下の期間があります。
保険料全額免除期間
保険料4分の3免除期間
保険料半額免除期間
保険料4分の1免除期間
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
②【R3年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)を含みます。
②【R3年出題】 〇
例えば半額免除については、保険料の半額は免除されますが、残りの部分(半額)は納付義務があります。残りの部分(半額)を納付すると、「保険料半額免除期間」となります。
保険料の一部免除については、免除されていない残りの部分が納付されることにより、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間となります。
③【H24年出題】 〇
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間となります。
保険料納付済期間にはなりません。
④【H24年出題】 〇
保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間は、保険料を追納することができます。
追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされ、「保険料納付済期間」となります。
問題文のように、保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
(第94条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】
【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用され、免除されないその残余の4分の3の部分が納付又は徴収された場合は、その期間は、「保険料4分の1免除期間」となります。保険料納付済期間ではありません。
なお、免除された4分の1を追納により納付した場合は、保険料納付済期間となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-060
R5.10.26 任意継続被保険者の資格喪失
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第48条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(④から⑥までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 ① 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 ② 死亡したとき。 ③ 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 ④ 被保険者となったとき。 ⑤ 船員保険の被保険者となったとき。 ⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 ⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
|
★「翌日」喪失が原則ですが、④から⑥に当てはまる場合は、「その日」に資格を喪失します。
★⑦について
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合は、「その申出が受理された日の属する月の末日の翌日=申出が受理された日の属する月の翌月1日」に資格を喪失します。
例えば、4月6日に資格喪失の申出が受理された場合は、5月1日が資格喪失日となります。その場合、4月分の保険料の納付が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
②【H30年出題】
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
③【H29年出題】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に資格を喪失します。
②【H30年出題】 ×
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になったときは、2年経過していなくても、その日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
③【H29年出題】 〇
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、「その月の10日」です。
保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、「納付期日の翌日」に任意継続被保険者の資格を喪失します。
なお、初めて納付すべき保険料の納付期日は、「保険者が指定する日」までです。
また、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、「任意継続被保険者とならなかったもの」とみなされます。
(法第37条第2項、第164条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

【解答】
【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をした場合は、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
しかし、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前で、その月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、その月の保険料の「納付期日の翌日」に資格を喪失します。
(令和3.11.10事務連絡「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労働安全衛生法
R6-059
R5.10.25 健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
今日は労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第66条の4(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
健康診断の結果(異常の所見があると診断された労働者に限ります。)について医師又は歯科医師の意見を聴くことが、事業者に義務付けられています。
なお、医師等からの意見聴取については、厚生労働省令で以下のように定められています。
則第51条の2第1項 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 健康診断の結果に基づく医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 ① 健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3か月以内に行うこと。 ② 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
意見聴取の対象は、「健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。」の部分がポイントです。
こちらの関連過去問もどうぞ!
【H26年選択式】
労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の< A >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。

【解答】
A 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
第66条の5健康診断実施後の措置からの出題です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-058
R5.10.24 年少者、妊産婦等の坑内労働
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
「坑内労働」について条文を読んでみましょう。
第63条 (坑内労働の禁止) 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
第64条の2(坑内業務の就業制限) 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 ① 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 ↓ 坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 ↓ 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの |
★満18歳未満の者の坑内労働は禁止されています。
★妊産婦について
・妊娠中の女性は、坑内業務に就かせられません。
・産後1年を経過しない女性は、「本人が申し出た場合」のみ、坑内業務に就かせられません。
★上記の妊産婦以外の満18歳以上の女性について
・人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、就かせられません。
・女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事することができます。
では、過去問をどうぞ!
【H20年出題】
使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

【解答】
【H20年出題】 ×
「妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」以外の女性については、坑内の管理、監督業務等に従事することができます。しかし、人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、従事できませんので、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることはできません。
(参照:H18.10.11基発第1011001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないのは、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た「産後1年を経過しない」女性です。
問題文は、「産後1年を経過しない」が抜けているので誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-057
R5.10.23 子の遺族厚生年金の支給停止が解除されるとき
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第66条第1項 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
・前条本文(第65条の2) 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。 ・次項本文(第66条第2項) 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。 ・次条(第67条) 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
「配偶者と子」は、遺族厚生年金の支給の順位が同順位です。配偶者と子が受給権を有する場合は、配偶者に遺族厚生年金を支給し、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
ただし、配偶者の遺族厚生年金が、第65条の2本文、第66条第2項本文、第67条の規定で支給停止されている場合は、子の遺族厚生年金の支給停止は解除され、子に遺族厚生年金が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
②【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
子の遺族厚生年金の支給停止が解除されるのは、配偶者の遺族厚生年金が、第65条の2本文、第66条第2項本文、第67条の規定で支給停止されている場合です。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止は、「解除されません」。子の遺族厚生年金は、支給停止のままです。
ちなみに、受給権者の申出による年金の支給停止は、第36条の2に規定されています。
②【R3年出題】 ×
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得し、障害基礎年金と障害厚生年金を選択しました。その場合、妻に対する遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止されます。
妻が障害の年金を選択したことにより、妻の遺族厚生年金が支給停止になった場合でも、子の遺族厚生年金の支給停止は「解除されません」。子の遺族厚生年金は支給停止のままです。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
夫の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得した。甲が障害厚生年金の受給を選択すれば、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていた甲の子(現在10歳)に遺族厚生年金が支給されるようになる。

【解答】
【R5年出題】 ×
R3年の過去問と同じ趣旨の問題です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給していた甲が、新たに障害厚生年金の受給権を取得し、障害厚生年金の受給を選択した場合は、甲に対する遺族基礎年金と遺族厚生年金は支給停止になります。
その場合でも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は「解除されません」。甲の子の遺族厚生年金は支給停止のままです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-056
R5.10.22 国民年金保険料の追納の要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第94条第1項 (保険料の追納) 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
★ポイントを確認しましょう。
・老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
・承認を受けた月の前10年以内の期間内に限って追納することができます。
・「一部免除」の期間については、免除の部分以外が納付されていなければ、追納できません。例えば、半額免除の場合は、免除されていない残りの半額が納付されていることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
②【H29年出題】
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有する者、遺族基礎年金の受給権を有する者でも、追納は可能です。障害基礎年金、遺族基礎年金は、支給停止や失権する可能性があるためです。
なお、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
②【H29年出題】 〇
例えば、4分の3免除は、残りの4分の1を納付することにより、保険料4分の3免除期間となります。4分の1を納付しない場合は、保険料4分の3免除期間には算入されません。
追納についても、一部免除の保険料については、その残余の額が納付されていないときは、追納はできません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
老齢基礎年金の受給権者は、保険料の追納はできません。
老齢基礎年金を請求していなくても、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-055
R5.10.21 日雇特例被保険者の保険料納付要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければりません。
★ 保険料納付要件を確認しましょう。
・ 保険給付を受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
又は
・ 保険給付を受ける日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること
例えば、10月23日に療養の給付を受ける場合は、
・8月1日から9月30日までの間に、通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
・4月1日から9月30日までの間に、通算して78日分以上の保険料が納付されている
ことが必要です。
(法第129条第2項など)
★ 被保険者の出産については、保険料納付要件が緩和されるのがポイントです。
(「出産育児一時金」、「出産手当金」の要件)
・ 出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
(法第137条)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
②【H30年出題】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に、事業主が印紙をはり、消印を行う方法で行います。
②【H30年出題】 ×
その出産の日の属する月の前4か月間に通算して「30日分」以上ではなく、「26日分」以上の保険料がその者について納付されていなければなりません。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
日雇特例被保険者の被扶養者の出産については、保険料納付要件は緩和されません。
原則の保険料納付要件(「前2か月間に通算して26日分以上」又は「前6か月間に通算して78日分以上」)を満たさなければなりません。
(法第144条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-054
R5.10.20 雇用保険印紙購入通帳と雇用保険印紙の購入
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
則第42条第1項~5項 (雇用保険印紙購入通帳) ① 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 ② 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。 ③ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。 ④ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 |
★雇用保険印紙を購入するときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければなりません。
則第43条第1項 (雇用保険印紙の購入) 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
②【H20年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。
③【R2年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳の有効期間満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。

【解答】
①【H23年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けるために提出するのは、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」です。雇用保険印紙の購入申込書ではありません。
②【H20年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、「その交付の日の属する保険年度」に限ります。
③【R2年出題】(雇用) 〇
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前(3月1日)から当該期間が満了する日(3月31日)までの間に、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

【解答】
【R5年出題】 × (雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく、「所轄公共職業安定所長」に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けます。
 ポイント!
ポイント!
雇用保険印紙購入通帳の交付 → 所轄公共職業安定所長
雇用保険印紙の購入 → 日本郵便株式会社の営業所
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 雇用保険法
R6-053
R5.10.19 雇用保険の被保険者の範囲の具体例
今日は雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
第4条第1項 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、第6条各号に掲げる者(適用除外になる者)以外のものをいう。
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 |
 労働者が雇用される事業は、業種に関わらず、全て雇用保険の適用事業となります。※農林水産業の一部は、当分の間は任意適用事業(暫定任意適用事業)です。
労働者が雇用される事業は、業種に関わらず、全て雇用保険の適用事業となります。※農林水産業の一部は、当分の間は任意適用事業(暫定任意適用事業)です。
適用事業に雇用される労働者は、適用除外に該当する者以外は、雇用保険の被保険者となります。
適用事業に雇用される労働者は、雇用保険の被保険者となりますが、「雇用される労働者」に該当しない場合は、被保険者となりません。今日は、被保険者の範囲に関する具体例をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
②【H30年出題】
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
③【H30年出題】
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかな場合であっても被保険者となることはない。
④【H30年出題】
労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
株式会社の代表取締役は、被保険者になりません。労働者でないからです。
(行政手引20351)
②【H30年出題】 〇
株式会社の取締役は、原則として被保険者になりません。しかし、同時に会社の部長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者で、雇用関係があると認められるものに限って、被保険者となります。
(行政手引20351)
③【H30年出題】 ×
特定非営利活動法人(NPO法人)の役員は、雇用関係が明らかでない限り被保険者となりません。雇用関係が明らかな場合は、被保険者となることがあります。
(行政手引20351)
④【H30年出題】 〇
在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合は、原則として被保険者となります。
(行政手引20351)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
名目的に就任している監査役であって、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となる。
②【R5年出題】
専ら家事に従事する家事使用人は、被保険者とならない。
③【R5年出題】
個人事業の事業主と同居している親族は、当該事業主の業務上の指揮命令を受け、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われ、取締役等に該当しない場合には、被保険者となる。
④【R5年出題】
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。
⑤【R5年出題】
日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」、「技能実習2号イ」及び「技能実習2号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う者は被保険者とならない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
監査役は、会社法上従業員との兼職禁止規定がありますので、被保険者となりません。
ただし、名目的に就任している監査役で、常態的に従業員として事業主との間に明確な雇用関係があると認められる場合は、被保険者となります。
(行政手引20351)
②【R5年出題】 〇
家事使用人は、被保険者となりません。
(行政手引20351)
③【R5年出題】 〇
個人事業の事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
しかし、「事業主の業務上の指揮命令を受けている」、「就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている」、「事業主と利益を一にする地位(取締役等)に該当しない」場合には、被保険者となります。
(行政手引20351)
④【R5年出題】 〇
ワーキング・ホリデー制度による入国者は、主として休暇を過ごすことを目的に入国します。その付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められるものですので、被保険者となりません。
(行政手引20352)
⑤【R5年出題】 ×
技能実習生として受け入れられ、講習を経て技能等の修得をする活動を行う場合は、受け入れ先の事業主と雇用関係にありますので、被保険者となります。
(行政手引20352)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労災保険法
R6-052
R5.10.18 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
今日は、労災保険法です。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」の基本的な考え方を確認しましょう。
・業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があります。そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱われます。
・脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積が考慮されます。
・業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表される業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断する必要があります。
次に、「認定要件」を確認しましょう。
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱われます。
(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
※(1)「発症前の長期間」とは、発症前おおむね6か月間をいいます
(2)「発症に近接した時期」とは、発症前おおむね1週間をいいます。
(参照:令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。
②【R4年出題】
心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。
③【R4年出題】
急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。

【解答】
①【R4年出題】 〇
「短期間の過重業務と発症との関連性」を時間的にみた場合、業務による過重な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられます。次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断することとされています。
① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
②【R4年出題】 ×
心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされています。
心理的負荷を伴う業務については、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しても、負荷の程度を評価する視点による検討、評価の対象になります。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
③【R4年出題】 ×
異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされていますので、評価期間は、「発症直前から前日までの間」とされています。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914 第1 号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。
ア 狭心症
イ 心停止(心臓性突然死を含む。)
ウ 重篤な心不全
エ くも膜下出血
オ 大動脈解離

【解答】
【R5年出題】 5つ
なお、認定基準で対象疾病として取り扱われる脳・心臓疾患は以下の通りです。
< 脳血管疾患>
(1) 脳内出血(脳出血)
(2) くも膜下出血
(3) 脳梗塞
(4) 高血圧性脳症
< 虚血性心疾患等>
(1) 心筋梗塞
(2) 狭心症
(3) 心停止(心臓性突然死を含む。)
(4) 重篤な心不全
(5) 大動脈解離
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労働安全衛生法
R6-051
R5.10.17 事業者の指定した医師等の健康診断を受けることを希望しない場合
今日は、労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
第66条第5項 労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
★労働者には、事業者が行う健康診断を受ける義務があります。
ただし、労働者が事業者の指定した医師等による健康診断を受けることを希望しない場合は、別の医師等による健康診断を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することが認められています。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

【解答】
【R5年出題】 ×
事業者の指定した医師又は歯科医師による健康診断を受けることを希望しない場合は、「他の医師又は歯科医師の行なう健康診断」を受け、「その結果を証明する書面」を事業者に提出しなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-050
R5.10.16 労働者と使用者
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
「事業主」とは、その事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
②【R4年出題】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
③【H29年出題】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
④【R2年出題 】
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
使用者には、「事業主」、「事業の経営担当者」、「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」の3つがあります。
そのうち、「事業主」とは、その事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役ではなく「法人そのもの」をいいます。
②【R4年出題】 ×
法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者のような、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は、労働者になりません。
株式会社の代表取締役は、労働基準法の労働者ではありません。
(S23.1.9基発14号)
③【H29年出題】 〇
株式会社の取締役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者となります。
(S23.3.17基発461号)
④【R2年出題 】 ×
「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれません。各事業において、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限が与えられているか否かによります。
「係長」でも、与えられている責任と権限の有無によっては、係長が「使用者」になることもあります。
(S22.9.13発基第17号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
使用者となるか否かは、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限が与えられているか否かで判断します。企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものではありません。
例えば、課長は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」という面では、労働基準法の労働者です。一方、その課長に、ある事項について権限と責任が与えられている場合は、その事項については、その課長は使用者となります。
「労働者」に該当する者が、同時に「使用者」に該当することは、あり得ます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 社会保険に関する一般常識
R6-049
R5.10.15 確定拠出年金法 個人型年金加入者の掛金
今日は、確定拠出年金法です。
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。
今日は、個人型年金加入者の掛金をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第68条 (個人型年金加入者掛金) ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
第70条 (個人型年金加入者掛金の納付) ① 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会に納付するものとする。 ② 第2号加入者(=厚生年金保険の被保険者)は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 ③ ②の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。 ④ 国民年金基金連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
【H22年選択式】 ※修正あり
確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)に納付することになっている。ただし、第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を< A >に通知しなければならない。

【解答】
【H22年選択式】 ※修正あり
A 個人型記録関連運営管理機関
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。
②【R5年出題】
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
年2回以上ではなく、「年1回以上」です。
②【R5年出題】 ×
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を「国民年金基金連合会」に納付します。
こちらの過去問もどうぞ!
【R2年選択式】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】
(A)48,000
国民年金第1号被保険者の掛金の上限は68,000円です。
ただし、付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月は、68,000円から付加保険料又は国民年金基金の掛金の額を控除した額が上限となります。
問題文の場合、確定拠出年金の掛金は、68,000円-基金の掛金20,000円= 48,000円まで拠出できます。
(令第36条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-048
R5.10.14 任意単独被保険者の資格の取得と喪失
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第10条 (任意単独被保険者) ① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 ② 認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 |
「適用事業所」に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者は、「厚生労働大臣の認可」を受けることにより、厚生年金保険の被保険者となることができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②【H27年出題】
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
ただし、保険料は任意単独被保険者が全額負担するのではありません。
事業主が保険料の半額を負担し、また、保険料を納付する義務も負います。厚生労働大臣の認可を受けるのに、事業所の事業主の「同意」が必要なのはそのためです。
②【H27年出題】 ×
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受け、その資格を喪失することができます。
厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失する際は、事業主の同意は不要です。資格喪失によって、事業主は、保険料の半額を負担する義務と納付する義務が無くなるからです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
厚生年金保険の任意単独被保険者となっている者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができるが、資格喪失に際しては、事業主の同意を得る必要がある。

【解答】
【R5年出題】 ×
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができます。しかし、資格喪失に際し、事業主の同意は要りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-047
R5.10.13 寡婦年金 死亡した夫の要件
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第49条第1項 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 |
★死亡した夫の要件を確認しましょう。
・夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上あること
※学生納付特例・納付猶予の期間は年金額には反映しません
・夫が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けたことがあるときは、寡婦年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。
②【H28年出題】
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
③【R2年出題】
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。
④【H28年出題】
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
⑤【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
死亡した夫は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あることが条件です。ただし、その期間に、合算対象期間は算入できません。
問題文は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が5年あるだけですので、寡婦年金は支給されません。
②【H28年出題】 〇
★任意加入被保険者は付加保険料が納付できます。また、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
(法附則第5条第9項)
★なお、特例による任意加入被保険者は、付加保険料は納付できません。また、寡婦年金については、第1号被保険者としての被保険者期間とはみなされません。
死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
(H16法附則第23条第9項)
③【R2年出題】 ×
年金の支給は、受給権を取得した月の翌月から始まります。
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合は、その夫は、老齢基礎年金を「受けていません」。そのため、要件を満たした妻に寡婦年金が支給されます。
④【H28年出題】 ×
寡婦年金の額について条文を読んでみましょう。
第50条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の老齢基礎年金の額の規定例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
問題文は、「4分の3」が抜けているので誤りです。
なお、「第1号被保険者としての被保険者期間」だけで計算することがポイントです。
⑤【H24年出題】 〇
寡婦年金の額の算定には、「第1号被保険者」としての被保険者期間のみが反映します。第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は反映されません。
(法第50条)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。

【解答】
【R5年出題】 〇
寡婦年金の支給要件は「第1号被保険者期間」のみで判断されます。第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年のみの場合は、寡婦年金の支給要件を満たしません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-046
R5.10.12 訪問看護療養費の支給要件
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第88条第1項・2項 (訪問看護療養費) ① 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 ② 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
則第67条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
則第68条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】※改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
②【H24年出題】
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
③【H25年出題】
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
④【R3年出題】
指定看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

【解答】
①【H28年選択式】※改正による修正あり
A 保険者
B 自己
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給されます。
②【H24年出題】 ×
訪問看護は、「看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」が行います。
「医師、歯科医師」は入らないのがポイントです。
③【H25年出題】 ×
「保険医療機関等」又は「介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院」によるものは、訪問看護から除かれます。
「保険医療機関の看護師」から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、療養の給付の対象となります。
④【R3年出題】 〇
キーワードを穴埋めで確認しましょう。
★指定看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(< A >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する< B >若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。
A 主治の医師
B 介護老人保健施設
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたものである。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。

【解答】
【R5年出題】 〇
チェックポイントは以下の2点です。
・保険者が必要と認める場合に限り、支給する
・看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-045
R5.10.11 労働保険事務組合の責任
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第34条 (労働保険事務組合に対する通知等) 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
第35条第1項~3項 (労働保険事務組合の責任等) ① 事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ② 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ③ 政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 |
★労働保険事務組合・委託事業主・政府の関係のイメージです。
(政府からの通知等)
政 府 |
↓納入の告知その他の通知等 |
労働保険事務組合 |
↓通知等の効果は委託事業主に及ぶ |
委託事業主 |
(労働保険料の納付)
政 府 |
↑労働保険料を納付 |
労働保険事務組合 |
↑金銭を交付 |
委託事業主 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
②【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
③【H25年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
④【H25年出題】(雇用)
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。
⑤【H29年出題】(雇用)
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) 〇
政府は、通知等を、事業主ではなく労働保険事務組合に対してすることができます。
また、その通知は委託事業主に対してなされたものとみなされます。
(法第34条)
②【H25年出題】(雇用) ×
通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、委託事業主に及びます。当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容には関係ありません。
(法第34条)
③【H25年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合は、「事業主から交付された金額の限度で」、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負います。「当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない」という規定はありません。
(法第35条第1項)
④【H25年出題】(雇用) ×
政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合に、その徴収について「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負います。
問題文は、労働保険事務組合の責に帰すべき理由がありますので、「当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。」は誤りです。
(法第35条第2項)
⑤【H29年出題】(雇用) ×
政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限って、その残余の額を、直接、当該事業主から徴収することができます。
(法第35条第3項)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

【解答】
【R5年出題】(労災) ×
問題文の場合、追徴金の徴収について「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」があります。その場合は、労働保険事務組合が、政府に対して、追徴金の納付の責めを負います。
(法第35条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法
R6-044
R5.10.10 就業手当の支給要件と支給額
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、雇用保険法です。
「就業手当」の対象者を条文を読んでみましょう。
第56条の3第1項第1号イ 職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの |
<就業手当の要件>
・職業に就いた受給資格者
(高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者は対象外です)
・安定した職業に就いた者ではないこと(=再就職手当の対象にならないこと)
・就業開始日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること
※上記以外にも要件がありますが、今回は触れません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。
②【H23年出題】
就業手当の支給申請手続は、基本手当の受給のための失業の認定とは無関係であり、当該就業した日が属する月の末日の翌日から起算して1か月以内に、就業手当支給申請書を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
就業手当の対象から、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」は除かれます。
問題文は、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者」とありますので、就業手当は支給されません。
★「就業手当」と「再就職手当」の支給要件を比較しましょう。
(就業手当) 第56条の3第1項第1号イ
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるもの
(再就職手当) 第56条の3第1項第1号ロ
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるもの
②【H23年出題】 ×
就業手当の支給申請手続は、「失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日」にしなければなりません。失業の認定に合わせて原則として4週間に1回、支給申請を行う必要があります。
(則第82条の5第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上のものに対して支給される就業促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を乗じて得た額である。

【解答】
【R5年出題】 〇
「安定した職業に就いた者を除く」、「基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」とありますので、「就業手当」についての問題です。
就業手当の額は、基本手当日額に10分の3を乗じて得た額です。
(第56条の3第3項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労災保険法
R6-043
R5.10.9 労災不服申立てのポイント!
今日は、労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条 ① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をしている者は、審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第40条 第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。
②【R5年出題】
審査請求をした日から起算して1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
③【R5年出題】
処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を行うことができます。都道府県労働局長ではありません。
②【R5年出題】 ×
審査請求をした日から起算して「3か月」を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる、です。1か月ではありません。
③【R5年出題】 ×
「処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する『労働者災害補償保険審査官の決定』を経た後でなければ、提起することができない。」です。
労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合は、
①「労働保険審査会に再審査請求」→「処分の取消しの訴えを提起する」
②労働保険審査会に再審査請求をしないで、「処分の取消しの訴えを提起する」
のどちらでも選択することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法
R6-042
R5.10.8 健康診断結果報告のポイント!
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
まず、条文を読んでみましょう。
則第52条 (健康診断結果報告) ① 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条又は第45条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ② 事業者は、第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
①について
定期健康診断(則第44条)、特定業務従事者の健康診断(則第45条)(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく、「定期健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。なお、対象は常時50人以上の労働者を使用する事業者です。
②について
②の「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」は、令和4年10月1日の改正で、常時使用する労働者の数にかかわらず、全ての事業場に報告が義務づけられました。
過去問をどうぞ!
<H25年選択式>
労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、< A >を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(選択肢)
①労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断
②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
③労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断
④労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便

【解答】
<H25年選択式>
A ②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
定期健康診断結果報告書の対象になるのは、②労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、所定の様式の定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
定期健康診断結果報告書の提出が義務づけられているのは、常時50人以上の労働者を使用する事業者です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労働基準法
R6-041
R5.10.7 賃金支払五原則の一つ 一定期日払いの原則
今日は、労働基準法です。
賃金支払5原則の条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金支払の原則は次の5つです。
1 通貨払い
2 直接払い
3 全額払い
4 毎月1回以上払い
5 一定期日払い
今日は、5つ目の「一定期日払い」の原則をみていきます。
賃金は、「毎月1回以上・一定期日を定めて」支払うのが原則です。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金は、毎月1回以上払いの原則・一定期日払いの原則について例外が認められています。
※「その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は、①1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、②1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、③1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当、です。(則第8条)
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

【解答】
【R1年出題】 ×
「一定の期日」の支払は、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではありません。例えば、「月の末日」、「土曜日」等とすることも可能です。
しかし、「毎月第2土曜日」のような定めは許されません。「第2土曜日」は例えば 9月なら9日、10月なら14日となり、月によって変動があるためです。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めるだけでなく、その支払日を繰下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。

【解答】
【R5年出題】 〇
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることも、支払日を繰下げることもどちらも可能です。どちらでも一定期日払に違反しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識
R6-040
R5.10.6 船員保険の行方不明手当金
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、船員保険法です。
条文を読んでみましょう。
第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。
第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
まず過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
②【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
③【H23年出題】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。
④【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】
①【R2年出題】 ○
行方不明手当金は、船員保険独自の給付です。
1か月以上の行方不明が行方不明手当金の対象です。
また、「職務上の事由」、「被扶養者」がキーワードです。
②【H28年出題】 ○
被保険者の行方不明の間に報酬が支払われている場合は、行方不明手当金はその差額となります。
③【H23年出題】 ×
行方不明手当金の支給期間は被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して 「3か月」を限度とします。なお、行方不明が3か月以上となったときは、「死亡の推定」により「行方不明となった日」に死亡したものと推定されます。
④【R3年選択式】
A被扶養者
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

【解答】
【R5年出題】 ×
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3か月」が限度です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-039
R5.10.5 老齢厚生年金の退職時改定
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
条文を読んでみましょう。
第43条第3項 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。 |
退職などで厚生年金保険の被保険者資格を喪失した場合は、老齢厚生年金の年金額の見直しが行われます。
ポイントを確認しましょう。
・資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして資格を喪失した日から起算して1か月経過しました
↓
・資格を喪失した月前の被保険者であった期間を算入して、老齢厚生年金の額を再計算します
↓
・資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金額が改定されます。
※なお、「(第14条第2号)その事業所又は船舶に使用されなくなったとき」、「(第14条第3号)適用事業所でなくすることの認可を受けたとき、任意単独被保険者の資格喪失の認可を受けたとき」、「(第14条第4号)適用除外に該当するに至ったとき」は、「その日から起算」して1か月を経過した日の属する月から、年金額が改定されます。
例えば、「退職」で資格を喪失した場合は、退職日の翌月から年金額が改定されます。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【解答】
【H28年出題】 ×
退職時改定は、「資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月」から改定されるのが原則です。
しかし、「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき=退職の場合」は、「その日から起算して1か月を経過した日の属する月」から、改定されます。
問題文は、1月31日付退職・2月1日に被保険者資格喪失ですので、1月31日から起算して1か月を経過した日の属する月=2月から年金額が改定されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月以前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

【解答】
【R5年出題】 ×
退職時改定で新たに老齢厚生年金の額の計算に加えるのは、「その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間」です。
その被保険者の資格を喪失した月「以前」ではありません。資格を喪失した月は含まれませんので注意しましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-038
R5.10.4 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権発生日
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 |
20歳前に初診日がある場合(=国民年金加入前の傷病という意味です。)の障害基礎年金の受給権の発生日を確認しましょう。
★①★障害認定日が20歳前にある場合
初診日 | 障害認定日 |
| 20歳 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「20歳に達した日」に障害基礎年金の受給権が発生します
★②★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H26年出題】 ×
まず、「障害認定日」の定義を確認しましょう。
障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」となるので、障害認定日が1年6か月より早くなる可能性もあります。
しかし、問題文は、25歳時点で「継続して治療中(治っていない)」です。そのため、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」が障害認定日です。
初診日が19歳の時なので、障害認定日は、20歳に達した日後になります。
先ほどの図の②に該当します。
★②★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
受給権は、20歳に達した日ではなく、「障害認定日」に障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に発生します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。

【解答】
【R5年出題】 ○
初診日が19歳で継続して治療中ですので、障害認定日は、20歳に達した日後となります。障害認定日に障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、障害認定日に受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-037
R5.10.3 資格喪失後の傷病手当金の継続給付
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
資格喪失後に継続して傷病手当金を受給するには、「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」、「資格喪失時に傷病手当金の支給を受けていること(又は受けられる状態にあること)」が必要です。
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
【H28年出題】 ○
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるには、資格喪失時に傷病手当金の支給を受けていること(又は受けられる状態にあること)が必要です。
また、傷病手当金は、待期期間(継続3日の労務不能日)を満たせば、4日目以降に支給が開始されます。
労務不能となった日から3日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受けられる状態にありません。そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。
(S32.1.31保発第2号の2)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
甲は、資格喪失時に傷病手当金を受けられる状態にありませんので、傷病手当金の継続給付を受けることができません。
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 |
休 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 喪失 |
待期期間を満たしていませんので、傷病手当金の支給要件を満たしていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-036
R5.10.2 労働保険事務組合とは
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項、第2項 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、①の業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
労働保険事務組合は、中小事業主の委託を受けて、労働保険料の納付などの労働保険事務の処理を行います。
労働保険事務組合として業務を行おうとする団体等は、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。
②【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。

【解答】
①【H19年出題】(雇用) ○
団体等は、法人でなくても構いませんが、法人でない団体等は、代表者の定めがあることが要件です。(団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法等が定款等において明確に定められ、団体性が明確であることも要します。)
②【H19年出題】(雇用) ×
認可の要件の一つに、「団体等は本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上であること。」があります。
その団体の事業の一環で労働保険事務を行うことになりますので、「専業で行わなければならない」は誤りです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。

【解答】
【R5年出題】(労災) ○
労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではありません。既存の事業主団体と労働保険事務組合は同一の組織です。
既存の事業主の団体等はその事業の一環で、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 雇用保険法
R6-035
R5.10.1 3年以内に就業促進手当を受けたことがあるとき
今日は、雇用保険法です。
再就職手当・常用就職支度手当の支給要件について条文を読んでみましょう。
第56条の3第2項、則第82条の4 受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(「受給資格者等」という。)が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当又は常用就職支度手当は、支給しない。 |
★ 再就職手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
★ 常用就職支度手当は、就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないことが条件です。
■■就業促進手当の「就業手当」、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の違いを確認しましょう。
<就業手当>
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)
対象→受給資格者
<再就職手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者
対象→受給資格者
<常用就職支度手当>
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者で、就職が困難な者
対象→受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。

【解答】
【R5年出題】 ○
受給資格者が「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた」場合に支給されるのは、再就職手当です。
また、「厚生労働省令で定める安定した職業に就いた」ことにより支給される就業促進手当は、「再就職手当又は常用就職支度手当」です。
受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年以内に再就職手当又は就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、再就職手当を受給することはできません。
「厚生労働省令で定める安定した職業」を確認しておきましょう。
「再就職手当」
則第82条の2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であって、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
「常用就職支度手当」
則第82条の3 1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-034
R5.9.30 労働者の死亡当時胎児であった子が出生したとき
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項、第2項 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 |
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが条件です。
また、妻以外の者は、労働者の死亡当時、「年齢要件」か、「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。

【解答】
【H19年出題】 ×
労働者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、生まれたときから遺族補償年金の受給資格者となります。
労働者の死亡の当時胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされます。
しかし、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとはみなされません。そのため、そのような子の遺族補償年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働者の死亡当時、胎児であった子は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子」とみなされます。出生以後は遺族補償年金の受給資格者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法
R6-033
R5.9.29 雇入れ時の健康診断の項目の省略
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
条文を読んでみましょう。
則第43条 (雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 |
なお、雇入れ時の健康診断は、全労働者ではなく「常時使用する労働者」が対象になるのがポイントです。
では、過去問をどうぞ
【R1年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

【解答】
【R1年出題】 ×
「6か月」ではなく「3か月」です。
医師による健康診断を受けた後3か月以内の者を雇い入れる場合で、その者が健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、その項目は省略することができます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

【解答】
【R5年出題】 ×
6月ではなく「3月」です。
こちらの問題もどうぞ!
【H23年選択式 】
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

【解答】
【H23年選択式 】
A 常時使用する
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-032
R5.9.28 労働基準法違反の労働契約
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第13条 (労働基準法違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
労働基準法に違反する労働条件が含まれる労働契約は、契約全てが無効になるのではなく、「基準に達しない」部分だけが無効になることがポイントです。
例えば、「法定時間外労働に対する割増賃金は支払わない」という労働条件が定められていた場合は、その部分だけが無効になります。
そして、無効になった部分は、労働基準法の基準で埋められ、「法定時間外労働については割増賃金を支払う」となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H30年出題】
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

【解答】
①【H25年出題】 ○
労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効(空白)となり、空白となった部分は、労働基準法の基準で補充されます。
②【H30年出題】 ×
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、特例でその期間の上限が5年となっています。
その契約期間に違反した場合、労働基準法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年ではなく「5年」となります。
(平成15.10.22基発第1022001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号(高度の専門的知識等を有する労働者)及び第2号(満60歳以上の労働者)については5年、その他のものについては3年となります。
「期間の定めのない労働契約となる」は誤りです。
(平成15.10.22基発第1022001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識
R6-031
R5.9.27 介護保険法の基本問題
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、介護保険法です。
まず過去問からどうぞ!
①【H18年出題】
介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
②【R1年出題】
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
③【H24年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村(特別区を含む。)をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

【解答】
①【H18年出題】 ○
介護保険の保険者は、「市町村及び特別区」です。
(法第3条)
②【R1年出題】 ○
要介護状態や要支援状態になった場合は、介護保険からサービスを受けることができます。
介護給付を受ける場合は、「要介護者に該当すること」・「その該当する要介護状態区分」について、市町村の認定(=「要介護認定」といいます。)を受けなければなりません。
市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知することになります。
要介護認定の効力は、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
(法第27条第8項)
③【H24年出題】 ○
要介護状態区分には、要介護1から要介護5まで5つの区分があります。
状態が変化し、要介護状態区分が変化したと認めるときは、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
(法第29条第1項)
④【R3年出題】 ○
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができます。
また、介護保険審査会は、「各都道府県」に置かれます。
(法第183条、第184条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
②【R5年出題】
要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が当該認定をした日からその効力を生ずる。
③【R5年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R5年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
介護保険の保険者は、市町村(特別区を含む。)です。
国や都道府県は、市町村を重層的に支える立場です。
②【R5年出題】 ×
要介護認定の効力は、市町村が当該認定をした日からではなく、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
③【R5年出題】 ○
状態が変化した場合は、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
④【R5年出題】 ×
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」の部分が誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-030
R5.9.26 配偶者が老齢基礎年金を繰上げたときの加給年金額
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
まず過去問からどうぞ!
【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
【H28年出題】 ×
加給年金額の対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は配偶者が65歳になるまで支給されます。
 夫が老齢厚生年金の受給権者で、妻が加給年金額の対象になっている場合のイメージ図
夫が老齢厚生年金の受給権者で、妻が加給年金額の対象になっている場合のイメージ図
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼65歳
| 振替加算 |
| 老齢基礎年金 |
 妻が老齢基礎年金を繰り上げたとしても、加給年金額は65歳まで加算されます。
妻が老齢基礎年金を繰り上げたとしても、加給年金額は65歳まで加算されます。
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼60歳 ▼65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の加算対象となる配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者に係る加給年金額は支給が停止される。

【R5年出題】 ×
加給年金額の加算対象になっている配偶者が、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとしても、当該配偶者に係る加給年金額は配偶者が65歳になるまで支給されます。
振替加算に関する国民年金の問題をどうぞ!
★国民年金法の問題です★
【国民年金法H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
【国民年金法H22年出題】 ○
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合も、振替加算額が加算されるのは、受給権者が65歳に達した日以後です。振替加算額の繰上げは行われません。
先ほどの図をもう一度みてみましょう。
夫
▼65歳
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
加給年金額 |
|
妻
▼60歳 ▼65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
加給年金額の加算対象の妻が老齢基礎年金を繰り上げた場合のポイント!
・夫の老齢厚生年金
→ 加給年金額は支給停止にはなりません。妻が65歳になるまで支給されます。
・妻の振替加算
→振替加算は繰上げされません。65歳から支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-029
R5.9.25 老齢基礎年金繰上げの注意点
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
法附則第9条の2第5項 (老齢基礎年金の支給の繰上げ) 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
法附則第9条の2の3 第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条(任意加入被保険者)の規定は、当分の間、繰上げ支給の老齢齢基礎年金の受給権者については、適用しない。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。
②【H23年出題】
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止される。
③【H19年出題】
国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。

【解答】
①【R4年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
②【H23年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は「支給停止される」のではなく「受給権が消滅」します。
③【H19年出題】 ○
<国民年金の任意加入と老齢基礎年金の繰上げとの関係>
・国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求はできません。 (法附則第9条の2第1項)
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

【解答 】
【R5年出題】 ○
老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合は、寡婦年金の受給権は消滅しますので、寡婦年金は支給されません。
また、老齢基礎年金の支給繰上げをした場合は、国民年金の任意加入被保険者になることもできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-028
R5.9.24 傷病手当金の待期について
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金を受けるには、連続3日間の待期期間を満たすことが必要です。
過去問をどうぞ!
【H21年出題】
傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能となった場合は待期の適用は行われない。

【解答】
【H21年出題】 ○
待期は最初に1回満たせば良く、その後労務に服した後再び同じ疾病又は負傷につき労務不能となった場合には、待期は不要です。
(昭2.3.11保理1085)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期の適用がない。

【解答】
【R5年出題】 ○
待期は、同じ疾病又は負傷につき、1回満たせば要件を満たします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 徴収法
R6-027
R5.9.23 第1種特別加入保険料の計算
今日は、第1種特別加入保険料の計算です。
特別加入者の保険料の計算に使う「保険料算定基礎額」は、給付基礎日額×365です。 例えば、給付基礎日額が12,000円の場合は、保険料算定基礎額は438万円となります。
第1種特別加入保険料は、保険料算定基礎額×第1種特別加入保険料率で計算します。 |
※なお、年度の中途に特別加入者となった場合又は特別加入者でなくなった場合は、保険料算定基礎額は月割計算となります。
例えば給付基礎日額が12,000円、その年度の加入月数が6か月の場合は、保険料算定基礎額は、438万円×(6か月/12か月)=219万円となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。

【解答】
【R5年出題】(労災) ○
ポイント!
・保険料算定基礎額は、12,000円×365=438万円です。
・第1種特別加入保険料率は、当該事業に適用される労災保険率と同一の率ですので、1,000分の4です。
・令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は
438万円×1,000分の4=17,520円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法
R6-026
R5.9.22 求職活動を行った実績の回数
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、雇用保険法です。
条文を読んでみましょう。
法第15条第5項 (失業の認定) 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
【R3年選択式】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日ついて、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が< A >回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ < B >を行った場合
ニ < C >における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
<選択肢>
| A ①1 ②2 ③3 ④4 |
B ①求人情報の閲覧 ②求人への応募書類の郵送 ③職業紹介機関への登録 ④知人への紹介依頼 |
| C ①巡回職業相談所 ②都道府県労働局 ③年金事務所 ④労働基準監督署 |

【解答】
【R3年選択式】
<A> ①1
<B> ②求人への応募書類の郵送
<C> ①巡回職業相談所
※なお、単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
(行政手引51254)
★求職活動実績の基準を確認しましょう。
(原則)基本手当の支給を受けるためには、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、求職活動実績が原則2回以上必要です。
ただし、法第33条に定める給付制限※(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後については、「給付制限期間」と「給付制限満了後の認定対象期間」をあわせた期間に、原則3回以上の求職活動実績が必要です。
※法第33条に定める給付制限とは、離職理由による給付制限です。離職理由は、「自己の責に帰すべき重大な理由による解雇」又は「正当な理由のない自己都合退職」です。
※給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上の求職活動実績が必要です。
(行政手引51254)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

【解答】
【R5年出題】 ○
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満の場合は、求職活動を行った実績が1回以上あれば、失業の認定が行われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-025
R5.9.21 遺族補償年金の受給資格者になる夫の要件
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 (3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 (4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが条件です。
また、妻以外の者は、年齢要件か障害要件を満たすことが条件です。
なお、昭和40年法附則第43条の遺族補償年金に関する特例により、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものは、遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。
では、過去問をどうぞ!
【R3年選択式】
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)、父母又は祖父母については、< A >歳以上であること。
2 子又は孫については、< B >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、< B >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は< A >歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

【解答】
A60
B18
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。

【解答】
【R5年出題】 ×
夫は、年齢要件か障害要件のどちらかを満たす必要がありますので、妻の死亡当時、障害の状態にない50歳の夫は、遺族補償年金の受給資格者になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法
R6-024
R5.9.20 健康診断の結果の通知
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第66条の6(健康診断の結果の通知) 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断(一般健康診断、特殊健康診断、臨時の健康診断)を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
則第51条の4(健康診断の結果の通知) 事業者は、法第66条第4項又は第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
【解答】
【R1年出題】 ×
事業者は、すべての労働者の健康診断の結果を記録し、5年間保存する義務があります。
また、健康診断の受診結果の通知も、全ての労働者に対して行う義務があります。異常所見が認められた労働者だけではありません。
(法第66条の3、66条の6、則第51条の、則第51条の4)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
事業者は、労働安全衛生規則第44条の定期健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)を通知しなければならない。
【解答】
【R5年出題】 ×
事業者の健康診断の結果の通知義務は、異常の所見があると診断された労働者に限らず、全ての労働者に適用されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労働基準法
R6-023
R5.9.19 休憩時間のポイント!
今日は休憩時間のポイントを見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条 (休憩) ① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
休憩の3原則を確認しましょう。
①途中に与える
②一斉に与える
③自由に利用させる
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
休憩時間は、労働基準法第34条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。
②【R5年出題】
一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、労働基準法第34条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。
③【R5年出題】
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも労働基準法第34条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。
④【R5年出題】
労働基準法第34条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。
⑤【R5年出題】
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
【解答】
①【R5年出題】 ×
休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定がある場合は、一斉に与えなくてもよいことになります。
なお、以下の業種には一斉付与の原則が適用されませんので、労使協定は不要です。
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業 通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。) (施行規則第31条) |
「道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業」には、一斉付与の原則が適用されます。
②【R5年出題】 ×
一昼夜交替制勤務でも、労働基準法上は、労働時間の途中に法第34条第1項の休憩を与えればよい、とされています。
(S23.5.10基収1582号)
③【R5年出題】 ○
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、「事業場内で自由に休息し得る」場合には、必ずしも違法にはなりません。
(S23.10.30基発1575号)
④【R5年出題】 ○
一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味で、6時間を超えた時点で45分という意味ではありません。
(S35.5.10基収1582号)
⑤【R5年出題】 ○
休憩時間には、単に作業に従事しない手待ち時間は含まれません。休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。
昼食休憩時間に来客当番として待機させた時間は、手待ち時間になり、休憩時間ではなく労働時間となります。
(S32.9.13発基17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働に関する一般常識
R6-022
R5.9.18 社会保険労務士法 報酬の基準の明示・帳簿備付け義務
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、社会保険労務士法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H27年出題】
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
②【H24年選択式】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

【解答】
①【H27年出題】 ○
条文を読んでみましょう。
則第12条の10(報酬の基準を明示する義務) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、それぞれ次の各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。 1 社会保険労務士 → 法第2条第1項各号に掲げる事務並びに法第2条の2第1項に規定する出頭及び陳述に関する事務 2 社会保険労務士法人 → 法第2条第1項第1号から第1号の3まで、第2号及び第3号に掲げる事務、法第25条の9第1項各号に掲げる業務に関する事務並びに法第25条の9の2の規定により委託される事務 |
②【H24年選択式】
<A>2年間
<B>100万円以下の罰金
(法第19条、第33条)
令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼しようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。
②【R5年出題】
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
社会保険労務士は、法第2条の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合は、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示す義務があります。
②【R5年出題】 ×
1年間ではなく「2年間」保存しなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識
R6-021
R5.9.17 高齢者医療確保法のよく出るところ
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、高齢者医療確保法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H28年出題】
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
②【H30年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
③【H29年出題】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入して設けられる。
④【R1年出題】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。
条文を読んでみましょう。
第118条第1項 社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。 |
②【H30年出題】 ×
「5年ごとに、5年を1期」ではなく「6年ごとに、6年を1期」です。
条文を読んでみましょう。
第9条第1項 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。 |
③【H29年出題】 ○
条文を読んでみましょう。
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 |
④【R1年出題】 ×
「あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて」が誤りです。
「条例の定めるところにより」行われます。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
では令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
②【R5年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
③【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
④【R5年出題】
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。
②【R5年出題】 ○
「6年ごとに、6年を1期」がポイントです。
③【R5年出題】 ×
都道府県ではなく「市町村」です。
④【R5年出題】
都道府県ではなく「後期高齢者医療広域連合」、高齢者医療確保法の定めるところによりではなく、「条例の定めるところにより」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 厚生年金保険法
R6-020
R5.9.16 55歳から60歳までの夫に対する遺族厚生年金
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、厚生年金保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H27年出題】
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
②【R1年出題】
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

【解答】
①【H27年出題】 〇
★遺族年金を受けることができる夫の条件を確認しましょう。
<夫に対する遺族厚生年金>
・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であること
ただし、夫が60歳になるまでは原則として遺族厚生年金は支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
●夫に対する遺族厚生年金は、60歳に達するまでは支給停止されますが、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されません。
<夫に対する遺族基礎年金>
・被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、「子と生計を同じくすること」
問題の夫に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるのが原則です。ただし、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するとき(子と生計を同じくしている場合)は、支給停止されません。
(法第59条第1項、65条の2)
②【R1年出題】 ×
夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有していますので、60歳に到達するまでの間でも、遺族厚生年金は支給停止されません。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ、60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも、55歳から遺族厚生年金を受給することはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
遺族厚生年金を受けることができる夫については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時55歳以上であることが要件です。
ただし、60歳に達するまでの期間は遺族厚生年金は支給が停止されるのが原則です。しかし、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金は支給停止されませんので、受給することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-019
R5.9.15 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
まず、過去問からどうぞ!
★今日の過去問は「厚生年金保険法」です。
①【H28年出題(厚生年金保険)】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
②【H19年出題(厚生年金保険法)】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

【解答】
①【H28年出題(厚生年金保険)】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなくても構いません。別々に繰下げの申出をすることができます。
(厚生年金保険法第44条の3)
②【H19年出題(厚生年金保険法)】 ×
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
★国民年金法です。
【R5年出題】
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
老齢基礎年金の支給繰下げの申出と、老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、同時に行う必要はありません。
(法第28条)
比較しましょう こちらの過去問もどうぞ!
【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】
【H26年出題】 〇
支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
(附則第9条の2第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-018
R5.9.14 高額療養費の算定対象に含まれないもの
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

【解答】
【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象になりません。
条文を読んでみましょう。
第115条第1項 (高額療養費) 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 |
高額療養費は、一部負担金等の額が著しく高額なときに支給されます。
「食事療養及び生活療養を除く。」の部分がポイントです。食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費の算定に含まれません。
なお、保険外併用療養に係る自己負担分(差額ベッド代や先進医療にかかる費用など)も対象になりません。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】
【R5年出題】 ×
食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は、算定の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 徴収法
R6-017
R5.9.13 労働保険料の申告・納付
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、徴収法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【H29年出題】(労災)
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
③【H29年出題】(労災)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。

【解答】
①【H26年出題】(雇用) 〇
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
6月30日に事業を廃止した場合は、翌日の7月1日に保険関係が消滅します。
保険関係が消滅した日の当日から起算するのがポイントです。確定保険料申告書は、7月1日から50日以内の8月19日までに提出しなければなりません。
(法第19条)
②【H29年出題】(労災) ×
継続事業・一括有期事業の延納の条件を確認しましょう。
★概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業は、20万円)以上のもの
又は
★労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
※当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは延納できません。
※延納の申請が必要です。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている場合は、概算保険料の額を問わず延納できます。
(則第27条)
③【H29年出題】(労災) 〇
平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の有期事業は、
第1期 6月15日~11月30日
第2期 12月1日~翌年3月31日
第3期 4月1日~6月5日
の3期に分けて納付することができます。
第1期の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内です。6月16日から20日以内の7月5日となります。
(則第28条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
②【R5年出題】(雇用)
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
③【R5年出題】(雇用)
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
令和4年10月31日で事業を廃止した場合、翌日の11月1日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書の提出期限は11月1日から起算して50日以内ですので、12月20日となります。
②【R5年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、概算保険料の額を問わず延納できますので、納付すべき概算保険料の額が10万円であっても、延納の申請を行うことができます。
③【R5年出題】(雇用) ×
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの有期事業は、6期に分けて延納することができます。
第1期 5月1日~7月31日
第2期 8月1日~11月30日
第3期 12月1日~翌年3月31日
第4期 4月1日~7月31日
第5期 8月1日~11月30日
第6期 12月1日~翌年2月28日
120万円の6分の1ずつ納付しますので、第1期に納付すべき概算保険料の額は20万円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 雇用保険法
R6-016
R5.9.12 訓練延長給付のよく出るところ
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、雇用保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H22年出題】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
②【H14年出題】
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。
③【R1年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

【解答】
①【H22年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象です。
(法第24条第1項)
②【H14年出題】 〇
公共職業訓練等を受け終わった後も要件を満たせば、30日を限度として訓練延長給付が行われます。
(法第24条第2項、令第5条)
③【R1年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」について行うものとされています。
(則第24条第1項)
★訓練延長給付について
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。
なお、公共職業訓練等の期間は2年以内のものが対象です。
①公共職業訓練等を受講するために待期している期間
→公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日の期間内
②受講している期間
→公共職業訓練等を受け終わる日までの間
③受講終了後の一定期間
→公共職業安定所長が当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者が対象
公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数が30日に満たない者が対象
支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日おいて受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで失業の認定を受けることはない。
②【R5年出題】
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日は、訓練延長給付の支給対象とならない。
③【R5年出題】
公共職業安定所長がその指示した公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であると認めた者は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数の訓練延長給付を受給することができる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)」に行われます。
受講証明書は所定の認定日のつど提出することになります。
(行政手引52354)
②【R5年出題】 ×
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間も訓練延長給付の支給対象となります。
③【R5年出題】 〇
受講後の延長給付は、30日から当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数(30日に満たない場合に限る。)を差し引いた日数となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-015
R5.9.11 障害補償給付 併合と併合繰上げ
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H30年出題】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級

【解答】
【H30年出題】 ×
①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 → 「8級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の5級が2級繰り上がって「3級」となります。
②第4級、第5級の2障害がある場合 → 「5級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の4級が3級繰り上がって「1級」となります。
※問題文の2級は誤りです。
③第8級、第9級の2障害がある場合 → 「13級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の8級が1級繰り上がって「7級」となります。
・ 障害等級は、別表第一に定めるところによります。
・ 障害が2以上あるときは、重い方の障害等級に該当する障害等級になるのが原則です。
・ 13級以上の障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害の該当する障害等級を 1級から3級繰り上げます。
①第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を1級繰り上げ
②第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を2級繰り上げ
③第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を3級繰り上げ
(例外)9級と13級の障害の場合は、障害補償一時金の額は、繰り上げられた8級(503日分)ではなく、9級(391日分)と13級(101日分)の合算額(492日分)となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12条の6)、かつ四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級

【解答】 C
12級と14級の障害があるときは、併合して、重い方の障害等級12級が全体の障害等級となります。
なお、「13級以上の障害が2以上ある」には該当しないので、繰上げはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働安全衛生法
R6-014
R5.9.10 特定機械等の種類
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働安全衛生法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H25年出題】
次の機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)のうち、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないものとして正しいものはどれか。
A フォークリフト
B 作業床の高さが2メートルの高所作業車
C 不整地運搬車
D 直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置
E つり上げ荷重が5トンの移動式クレーン

【解答】 E
特定機械等は、特に危険な作業を必要とする機械等です。特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
特定機械等の種類は覚えましょう。
施行令第12条 (特定機械等) (1) ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。) (2) 第一種圧力容器(小型圧力容器並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法、高圧ガス保安法、ガス事業法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の適用を受けるものを除く。) (3) つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン (4) つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン (5) つり上げ荷重が2トン以上のデリツク (6) 積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のエレベーター (7) ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路。)の高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。) (8) ゴンドラ |
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
労働安全衛生法第37条第1項の「特定機械等」(特に危険な作業を必要とする機械であって、これを製造しようとする者はあらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならないもの)として、労働安全衛生法施行令に掲げられていないものはどれか。ただし、いずれも本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除くものとする。
A 「ボイラー(小型ボイラー並びに船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法(昭和39年法律第170号)の適用を受けるものを除く。)」
B 「つり上げ荷重が3トン以上(スタツカー式クレーンにあつては、1トン以上)のクレーン」
C 「つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン」
D 「積載荷重(エレベーター(簡易リフト及び建設用リフトを除く。以下同じ。)、簡易リフト又は建設用リフトの構造及び材料に応じて、これらの搬器に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。以下同じ。)が1トン以上のエレベーター」
E 「機体重量が3トン以上の車両系建設機械」

【解答】 E
車両系建設機械は特定機械等ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-013
R5.9.9 一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業の日の休業手当
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働基準法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H27年出題】
当該労働者の労働条件は次のとおりである。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
(問題)
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
【解答】 〇
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日は平均賃金の100分の60に相当する金額を支払う義務があります。
現実の労働時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合は、その差額を支払わなければなりません。
(S27.8.7基収3445号)
問題文の1日当たりの休業手当は、10,000円×100分の60=6,000円です。
使用者の責に帰すべき事由で労働時間が4時間になり、その労働時間に対し7,500円が支払われています。
現実の労働時間に対する賃金が平均賃金の100分の60以上ですので、賃金の支払に加えて休業手当を支払う必要はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
賃 金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円
A 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
7,000円-5,000円=2,000円
B 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
C 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
10,000円×0.6-5,000円=1,000円
D 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000円-5,000円)×0.6=1,200円
E 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。
【解答】 E
ポイント!
★1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、平均賃金の100分の60に相当する金額を支払う義務があります。
★現実の労働時間に対する賃金は5,000円で、平均賃金の100分の60(7,000円×100分の60)以上です。そのため、使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しません。
正しい記述はEです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 社会保険に関する一般常識
R6-012
R5.9.8 社一選択式 船員保険法・高齢者医療確保法・確定給付企業年金法・児童手当法・白書からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は社会保険に関する一般常識です。
 Aは、船員保険法の傷病手当金の問題です。
Aは、船員保険法の傷病手当金の問題です。
条文を読んでみましょう。
第69条第5項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。 |
Aには3年が入ります。
船員保険法は健康保険法と比較して、異なる点をチェックしてください。
 Bは、高齢者医療確保法の特定健康診査の問題です。
Bは、高齢者医療確保法の特定健康診査の問題です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
第19条第1項 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。
第20条 (特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。(以下省略) |
Bには40歳が入ります。
 Cは確定給付企業年金法の掛金の額の基準の問題です。
Cは確定給付企業年金法の掛金の額の基準の問題です。
条文を読んでみましょう。
第57条 (掛金の額の基準) 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 |
Cには、財政の均衡を保つことが入ります。
 Dは、児童手当法の児童手当の額の問題です。
Dは、児童手当法の児童手当の額の問題です。
小学校修了後中学校修了前の児童(中学生)については、一律1か月1万円です。
Dには10,000円が入ります。
 Eは、令和4年版厚生労働白書から高齢化の問題です。
Eは、令和4年版厚生労働白書から高齢化の問題です。
問題文を読んでみましょう。
高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< E >人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
Eには、5.5が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 労働に関する一般常識
R6-011
R5.9.7 労一選択式 判例・派遣法・最低賃金法からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働に関する一般常識です。
 A・Bは、判例問題です。
A・Bは、判例問題です。
問題の判例のポイントは3つです。
① 大学卒業予定者の採用内定により、就労の始期を大学卒業直後とする解約権留保付労働契約が成立したものと認められました
→「企業において、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることを予定していなかったなど、判示の事実関係のもとにおいては、企業の求人募集に対する大学卒業予定者の応募は労働契約の申込であり、これに対する企業の採用内定通知は右申込に対する承諾であって、誓約書の提出とあいまつて、これにより、大学卒業予定者と企業との間に、就労の始期を大学卒業の直後とし、それまでの間誓約書記載の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したものと認めるのが相当である」
② 留保解約権に基づく大学卒業予定者採用内定の取消事由
→「採用内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる」
③ 留保解約権に基づく大学卒業予定者採用内定の取消が解約権の濫用にあたるとして無効とされた
Aは「本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることを予定していなかった」
Bは「知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって」
が入ります。
(昭和54年7月20日最高裁判所第二小法廷)
 Cは、労働者派遣法の労働者派遣の期間からの問題です。
Cは、労働者派遣法の労働者派遣の期間からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第35条の3 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない。 |
Cには、「3」が入ります。
 D・Eは最低賃金法からの問題です。
D・Eは最低賃金法からの問題です。
★Dは罰則の問題です。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法第40条の罰則が適用されます。
条文を読んでみましょう。
第40条 第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。 |
特定(産業別)最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法ではなく、労働基準法の罰則(第24条違反)が適用されます。
Dには労働基準法が入ります。
★Eは、最低賃金の減額の特例の問題です。
条文を読んでみましょう。
第7条 (最低賃金の減額の特例) 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 2 試の使用期間中の者 3 職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの 4 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 |
Eには都道府県労働局長が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 厚生年金保険法②
R6-010
R5.9.6 厚年選択式② 事例問題・遺族厚生年金の支給停止からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は厚生年金保険法その2です。
 Cは、事例問題です。
Cは、事例問題です。
問題文を読んでみましょう。
【R5年選択式】
甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、< C >となる。
甲の年金加入歴を図にすると以下のようになります。
20歳 46歳 52歳
厚生年金保険(国民年金第2号被保険者) | 国民年金 第1号or第3号被保険者 |
▲ ▲
初診日 死亡
★甲の受給していた障害年金は、「障害基礎年金」です。
初診日がポイントです。初めて病院で診察を受けたのが「退職の3か月後」となっていますので、初診日に厚生年金保険の被保険者ではありません。そのため、障害厚生年金は受けられません。
★乙が受給できる遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」です。
・死亡した甲について
死亡した甲は、「国民年金の被保険者が死亡したとき」、「保険料納付済期間が25年以上ある者が死亡したとき」に該当しますので、遺族基礎年金の要件を満たします。
また、「厚生年金保険の被保険者であった者」で、「保険料納付済期間が25年以上ある者」の死亡ですので、遺族厚生年金の要件も満たします。
・妻(乙)と子について
<遺族基礎年金について>
妻(乙)は、「子と生計を同じくすること」の要件を満たしています。また、前年の年収が500万円ですので、生計維持要件も満たします。
妻は、子の加算が加算された遺族基礎年金を受給します。子に対する遺族基礎年金は支給停止されます。
<遺族厚生年金について>
妻(乙)も子も要件を満たします。
妻(乙)が遺族厚生年金を受給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
Cには、「障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金」が入ります。
 Eは、所在不明の場合の遺族厚生年金の支給停止の問題です。
Eは、所在不明の場合の遺族厚生年金の支給停止の問題です。
条文を読んでみましょう。
第67条第1項 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 |
Eには、1年が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 厚生年金保険法①
R6-009
R5.9.5 厚年選択式① 権限の委任・年金額の改定からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は厚生年金保険法その1です。
厚生年金保険法は2回に分けます。
 A・Bは、権限の委任からの問題です。
A・Bは、権限の委任からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第109条の9(地方厚生局長等への権限の委任) ① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ② ①の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 |
Aは地方厚生局長、Bは地方厚生支局長が入ります。
 Dは、年金額の改定のルールからの問題です。
Dは、年金額の改定のルールからの問題です。
★年金額の改定のルールの原則 新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」 既裁定者は「物価変動率」 で改定を行うのが原則です。 |
↓
★物価変動率が「+」、名目手取り賃金変動率が「-」の場合 (物価>0>賃金) 賃金がマイナスになる=現役世代の負担能力が低下しているということです。そのため、既裁定者も、賃金変動に合わせ、名目手取り賃金変動率で改定されます。 新規裁定者・既裁定者ともに「名目手取り賃金変動率」で改定されます。 |
 問題文は、物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が-0.2%です。 物価>0>賃金ですので、賃金変動に合わせて改定されます。既裁定者の年金額は、前年度から0.2%の引下げとなります。
問題文は、物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が-0.2%です。 物価>0>賃金ですので、賃金変動に合わせて改定されます。既裁定者の年金額は、前年度から0.2%の引下げとなります。
なお、改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
Dには、0.2%の引き下げが入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 国民年金法
R6-008
R5.9.4 国年選択式は国民年金事業の円滑な実施・国民年金の給付・被保険者の要件からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は国民年金法です。
 AからCは、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置からの問題です。
AからCは、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第74条第1項 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1) 教育及び広報を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。 (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 |
令和5年度は、A 教育及び広報、B 相談その他の援助、C 利便の向上が入ります。
なお、平成23年に同じ問題が出題されています。
【H23年選択式】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) <A 教育及び広報>を行うこと。
(2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、 <B 相談その他の援助>を行うこと。
(3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する<C 情報>その他の被保険者等の利便の向上に資する<C 情報>を提供すること。
★★選択式も過去問対策が大切です。
 Dは、国民年金の給付からの問題です。
Dは、国民年金の給付からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 |
Dは「必要な給付」が入ります。保険給付ではありませんので注意しましょう。
過去問を確認しましょう。
【H26年出題】
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
【解答】 ×
必要な保険給付ではなく、「必要な給付」です。
保険原理とは、負担した保険料に応じた保険給付が行われるというものです。国民年金法の給付には、例えば、保険料の負担が求められない20歳前の障害基礎年金など、保険原理によらないものもあります。
そのため、国民年金は「保険給付」ではなく、「必要な給付」とされています。
なお、厚生年金保険法は、「保険給付」となります。
 Eは被保険者の要件の問題です。
Eは被保険者の要件の問題です。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の共通点は、「国籍要件」が問われない点です。
Eには、国籍が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 健康保険法
R6-007
R5.9.3 健保選択式は協会けんぽの業務・高額療養費多数回該当・出産手当金からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は健康保険法です。
 Aは全国健康保険協会の業務に関する問題です。
Aは全国健康保険協会の業務に関する問題です。
条文を読んでみましょう。
第5条第2項 (全国健康保険協会管掌健康保険) 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
全国健康保険協会が管掌する業務のうち、①資格の取得・喪失の確認、②標準報酬月額・標準賞与額の決定、③保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)、④①~③に附帯する業務は、「厚生労働大臣」が行います。厚生年金保険と一体化している業務だからです。
なお、全国健康保険協会の任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく、全国健康保険協会が行います。任意継続被保険者は厚生年金保険に加入していないからです。
Aには「厚生労働大臣」が入ります。
 BからDは、高額療養費多数回該当の問題です。
BからDは、高額療養費多数回該当の問題です。
高額療養費多数回該当とは、療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合をいいます。
70歳未満で標準報酬月額が83万円以上の場合、高額療養費算定基準額は252,600円+(医療費-842,000円)×1%ですが、多数回該当の場合は、140,100円となります。
なお、高額療養費は、管掌する保険者が変わった場合は、高額療養費の支給回数は通算されません。
Bは「12か月」、Cは「140,100円」、Dは「通算されない」が入ります。
 Eは出産手当金の問題です。
Eは出産手当金の問題です。
条文を読んでみましょう。
第102条 (出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
Eには、「98」が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 雇用保険法
R6-006
R5.9.2 雇用選択式は技能習得手当・日雇労働求職者給付金・定年退職者等の受給期間の延長からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は雇用保険法です。
 A・Bは技能習得手当の問題です。
A・Bは技能習得手当の問題です。
失業等給付には、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」があります。
一般被保険者の求職者給付は、「基本手当」、「技能習得手当」、「寄宿手当」、「傷病手当」で構成されています。
技能習得手当について条文を読んでみましょう。
第36条第1項 技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。
則第56条 (技能習得手当の種類) 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
則第57条 (受講手当) ① 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第19条第1項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について、40日分を限度として支給するものとする。 ② 受講手当の日額は、500円とする。 |
技能習得手当には、「受講手当」と「通所手当」があります。
「受講手当」はお弁当代をイメージしてください。日額500円で40日分を限度として支給されます。
Aは通所手当、Bは40日が入ります。
 C・Dは、日雇労働求職者給付金の問題です。
C・Dは、日雇労働求職者給付金の問題です。
日雇労働求職者給付金には、普通給付と特例給付があります。
★日雇労働求職者給付金(普通給付)は、日雇労働被保険者が失業した場合に、失業の日の属する月の前2月間に、その者について、通算して26日分以上の印紙保険料が納付されていることが条件です。
Cには、通算して26日が入ります。
★特例給付は、基礎期間(資格期間)が6か月、受給期間は、基礎期間に引き続く4か月間となります。
Dは、特例給付の受給期間の問題です。
条文を読んでみましょう。
則第54条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる期間及び日数は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度とする。 |
Dには、通算して60日が入ります。
 Eは定年退職者等の受給期間の延長の問題です。
Eは定年退職者等の受給期間の延長の問題です。
離職の理由が、
・定年(60歳以上の定年に限る。)に達したこと
・60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこと
による場合は、受給期間の延長の申出ができます。
受給期間の延長が認められた場合は、受給期間に、「求職の申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(最大1年間)」が加算されます。
例えば、6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出た場合は、受給期間の1年間に6か月が加算されます。
← ← ← ← ←1年 → → → → → | 6か月加算 | |
6か月(猶予期間) |
|
|
| ▲離職 | ||
問題文の原則の受給期間は令和4年4月1日から1年間です。6か月間求職の申込みをしないことを希望する旨を申し出ていますので、原則の受給期間に6か月が加算されます。なお、猶予期間は、4月1日から9月30日となります。
また、定年退職者等の受給期間とされた期間内に、疾病・負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合は、更に受給期間の延長が認められます。
定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間の日数です。
ただし、その期間の全部又は一部が猶予期間内にあるときは、疾病・負傷等の理由で職業に就くことができない期間のうち「猶予期間内にない期間分の日数」となります。
(参考:行政手引50286)
問題文の場合、疾病で職業に就くことができない期間は、8月1日から10月31日です。猶予期間(4月1日から9月30日)にない期間分の日数は、31日です。
問題文の受給期間を確認しましょう。
原則の受給期間は、令和4年4月1日~令和5年3月31日です。
↓
定年退職者等の受給期間の延長により原則の受給期間に6か月加算され、受給期間は令和5年9月30日までとなります。
↓
さらに、疾病により職業に就くことができない期間のうち31日が加算され、令和5年10月31日までとなります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 労災保険法
R6-005
R5.9.1 労災選択式は休業補償給付と社会復帰促進等事業からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労災保険法です。
 A~Cは休業補償給付の問題です。
A~Cは休業補償給付の問題です。
条文を読んでみましょう。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による「(A)療養」のため労働することができないために賃金を受けない日の第「(B)4」日目から支給されます。
休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の「(C)100分の60」に相当する額です。
※部分算定日(労働者が所定労働時間のうちその一部分のみ労働する日など)の休業補償給付の額について確認しましょう。
・休業補償給付の額は、(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)の100分の60です。
・年齢階層別の最高限度額が適用されている場合は、最高限度額の適用がないものとした給付基礎日額で算定します。
・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)が最高限度額を超える場合は、最高限度額の100分の60となります。
 D・Eは、社会復帰促進等事業の問題です。
D・Eは、社会復帰促進等事業の問題です。
条文を読んでみましょう。
第29条第1項 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 |
今回は、(D)健康診断と(E)賃金が問われました。
<賃金の支払の確保を図るために必要な事業とは?>
賃金の支払の確保等に関する法律で、「未払賃金立替払制度」が設けられています。
この制度により、企業が倒産したことで賃金が支払われずに退職した労働者に対して、未払賃金の立替払が行われます。
未払賃金の立替払事業は、社会復帰促進等事業の一環で行われています。
労災保険は、業務災害に対する使用者責任を国が代行する目的で作られた保険です。
未払賃金の立替払制度は、賃金支払に対する使用者責任を国が代行するもので、労災保険の目的と共通するからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 労働安全衛生法
R6-004
R5.8.31 安衛選択式は重量表示と病者の就業禁止からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働安全衛生法です。
 Dは重量表示の問題です。
Dは重量表示の問題です。
条文を読んでみましょう。
第35条 (重量表示) 一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
過去に出題されていますので見てみましょう。
【H24年出題】
重量が1つで0.5トンである貨物を発送しようとする者は、所定の除外事由に該当する場合を除き、当該貨物に見やすく、かつ、容易に消滅しない方法でその重量を表示しなければならない。
【解答】 ×
0.5トンではなく1トンです。
過去問から、重量の1トンがポイントになることが分かります。
今回の「D」には、「1トン」が入ります。
 Eは、病者の就業禁止の問題です。
Eは、病者の就業禁止の問題です。
条文を読んでみましょう。
第68条 (病者の就業禁止) 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 |
今回の「E」には、「その就業を禁止」が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和5年度選択式振り返り 労働基準法
令和5年度選択式振り返り 労働基準法
R6-003
R5.8.30 労働基準法選択式は時効と判例からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働基準法です。
 Aは時効の問題です。
Aは時効の問題です。
条文を読んでみましょう。
第115条 (時効) この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 附則第143条第3項 当分の間、「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。 |
★労働基準法の時効について確認しましょう。
・賃金(退職手当を除く) → 5年間(当分の間3年間)
・退職手当 → 5年間
・災害補償その他の請求権 → 2年間
Aは、災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)の時効ですので、「2年」となります。
 Bは、年次有給休暇の時季変更権の判例の問題です。
Bは、年次有給休暇の時季変更権の判例の問題です。
労働者が指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに、使用者が時季変更権を行使した場合の効力についてです。
判例では、「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。」とされています。
(昭和57年3月18日最高裁判所第一小法廷)
Bは、「客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権行使があったものとしてその効力を認める」から、「遅滞なく」が入ります。
 Cは、「労働時間」についての問題です。
Cは、「労働時間」についての問題です。
同じ論点の問題が過去に出題されていますので確認しましょう。
【H22年出題】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
解答は「〇」です。
判例では、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法32条の労働時間に当たる。」とされています。
(平成14年2月28日最高裁判所第一小法廷)
今回のCの問題は、別の判例からの出題ですが、「不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」とされています。
Cには、「労働からの解放」が入ります。
(平成19年10月19日最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 毎日コツコツ。継続は力なり。
毎日コツコツ。継続は力なり。
R6-002
R5.8.29 毎日コツコツ。継続は力なり!社会保険労務士合格研究室
社会保険労務士合格研究室は、ホームページもYouTubeチャンネルも、合言葉は「毎日コツコツ。継続は力なり。」です。

今年の社労士試験は、8月27日でした。
今年はゴールデンウィークも、夏休みも、お盆休みも返上して勉強していた方が大半だと思います。
勉強は「頑張って、しなければならない」ものだと、疲れますよね?
「毎日の習慣」にしてしまうと、気分的に楽になると思います。
5分でもいいので、毎日少しでも勉強するというのはいかがでしょう?
疲れて何もしたくない日でも、とりあえず必ず2~3問は解いてみるとか。
勉強は(勉強に限らないかもしれませんが)、2~3日休んでしまうと、どんどん休みたくなりませんか?

私は、何度かフルマラソンを走った経験があります。
とても遅いので、毎回6時間近くかかってしまいます。
少しずつでもゴールに近づいている!と自分を励ましながら、1歩1歩足を前に出している感じです。
脚は痛いし、疲れるし、途中で何回も脚が止まります。
でも、脚を止めても楽にならず・・・むしろ、次の1歩の出だしが辛くなります。

勉強はもっと長丁場ですが、少しずつでもいいので、止まらずに毎日続けて、1歩ずつ合格に近づけばいいなーと思っています。
明日から、また、令和6年度に向けて配信していきます。
今後ともよろしくお願いします。
社会保険労務士合格研究室 伊藤直子
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 昨日はお疲れさまでした
昨日はお疲れさまでした
R6-001
R5.8.28 昨日はお疲れさまでした!
皆様
昨日はお疲れ様でした。
力を出し切った方
勉強が足りなかったかな?とちょっと後悔している方
色々いらっしゃると思います。
まずは、体をゆっくり休めてください。
暑すぎた夏もそろそろ終わりです。
夏の終わりの空気を味わいながら、
美味しいものを食べたり、
行きたかったところに出かけたりしてください。
本当にお疲れさまでした。
また、更新します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
