合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
国民年金法「時効」
R8-107 12.09
国年の時効|「基本権」と「支分権」など
国民年金法の時効には、「2年」と「5年」があります。
特に、「年金給付」と「死亡一時金」の違いに注意しましょう。
国民年金の「給付」のうち、「年金給付」の時効は5年ですが、「死亡一時金」の時効は2年です。
条文を読んでみましょう。
法第102条 ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 年金給付を受ける権利の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ➂ 年金給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については、会計法第31条の規定を適用しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
<給付の時効について>
・年金給付を受ける権利(基本権)→ 支給すべき事由が生じた日から5年
・支分権 → 支払期月の翌月の初日から5年
・死亡一時金 →行使することができる時から2年
過去問を解いてみましょう
①【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「死亡一時金」の時効が誤りです。
・年金給付を受ける権利 → その支給すべき事由が生じた日から5年
・死亡一時金を受ける権利 → 行使することができる時から2年
②【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②【R2年出題】 〇
支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利の時効の起算点は「支払期月の翌月の初日」です。
➂【R7年出題】
保険料を滞納している者の保険料納付義務は、厚生労働大臣による督促があったとしても、2年で消滅する。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
第102条第5項で、「保険料その他この法律の規定による徴収金についての督促は、時効の更新の効力を有する。」と規定されています。
保険料の徴収権の時効は、納期限の翌日から2年ですが、厚生労働大臣による督促は「時効の更新の効力」を有します。時効の進行がゼロに戻りますので、2年では消滅しません。
④【R7年出題】
失踪の宣告を受けた者に係る消滅時効の起算日は、死亡したとみなされた日の翌日であり、死亡したとみなされた日の翌日から2年を経過した後に、死亡一時金の請求権は時効によって消滅するため、死亡一時金は支給されない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
死亡一時金の時効の起算日は、「死亡日の翌日」です。
「失踪宣告」を受けた者に係る消滅時効の起算日については、「死亡とみなされた日(原則失踪の7年後)の翌日」とされています。
ただし、「死亡一時金については、いわゆる掛け捨て防止の考え方に立って、一定期間加入したが、年金給付を受けることなく亡くなった方に対して一定の金額を支給するものである」ことを踏まえ、「失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する」とされています。
(平26.3.27年管管発0327第2号)
⑤【R7年出題】
年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するため、障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で、その後に障害の程度が増進したときでも、障害基礎年金の請求は、当該障害認定日から5年を経過する前に行わなければならない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「障害認定日において、当該障害が、障害等級に該当する程度の障害の状態にない」場合で、その後に障害の程度が増進したときは、「障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その期間内に事後重症の障害基礎年金の支給を請求する」ことによって事後重症の障害基礎年金を受けることができます。
事後重症の障害基礎年金は請求によって受給権が発生します。障害認定日から5年を経過する前に行わなければならないという規定はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険料免除」
R8-106 12.08
健康保険料の免除|産休・育休中
産前産後休業期間中・育児休業期間中は、事業主が申出をすることにより、保険料が免除されます。
用語の確認をしましょう。
・産前産後休業とは
出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間
※出産の日が出産の予定日後であるとき(予定日より遅れた場合)は、その分、産前休業が延びます。
(例)出産の日が出産の予定日より3日遅れた場合
出産の予定日以前42日(多胎妊娠の場合98日)+3日+出産の日後56日
・育児休業等とは
3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業+育児休業に準じる休業)
条文を読んでみましょう
法第159条 ① 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
★(2)について
同じ月内に、開始日と終了日の翌日がある場合、育児休業等の日数が14日以上ある場合は、その月の保険料は免除されます。
下の図の場合は、12月の保険料は免除されます。
12月 | ||
| 育児休業(14日以上) |
|
★「その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。」の部分について
「賞与」については、連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に、免除されます。
下の図の場合、12月に賞与が支払われた場合は、賞与の保険料が免除されます。
12月 | 1月 | ||
| 育児休業(1か月超) |
| |
下の図の場合、12月に賞与が支払われても、賞与の保険料は免除されません。
12月 | 1月 | ||
| 育児休業(1か月以内) |
| |
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象となる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
5月16日が出産予定日の場合、産前休業は、予定日以前42日の4月5日が開始日です。産前休業を開始した日の属する月(=4月)から免除対象です。
実際の出産日が5月10日だった場合は、産前休業は出産日以前42日の3月30日が開始日です。そのため、産前休業を開始した日の属する月(=3月)から免除対象となります。
②【R5年出題】
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
免除の対象になるのは、産前産後休業を開始した日の属する月(=令和4年12月)からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月(=令和5年3月)の前月(=令和5年2月)までです。
➂【R7年出題】
被保険者が令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月分から健康保険法第159条に規定される育児休業期間中の保険料免除の対象となり、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
令和7年3月15日に出産した場合、令和7年3月16日から5月10日までは産後休業です。
令和7年3月分は、「育児休業期間中」の保険料免除の対象ではありません。
④【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
問題文は、「育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合」に該当します。
育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月(=4月・4月1日が属する月)の前月(3月)までの期間中の保険料が免除されます。
⑤【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
「育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一」ですので、保険料の免除を受けるには、「当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上」必要です。
問題文の場合、育児休業等の日数が、令和5年1月4日~16日の「13日」しかありません。そのため、令和5年1月の保険料は免除されません。(徴収されます)
⑥【R4年出題】
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

【解答】
⑥【R4年出題】 〇
育児休業期間中の保険料が免除されている期間に支払われた賞与については、当該賞与に係る保険料は徴収されません。ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額に含まれます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「特定適用事業所」
R8-104 12.06
特定適用事業所|該当したとき・該当しなくなったとき
1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」に使用され、次の3つの要件を満たした場合は、健康保険の被保険者となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上 ② 賃金が月額88,000円以上 ➂ 学生でない |
今回は、「特定適用事業所」についてみていきます。
「特定適用事業所」の要件について条文を読んでみましょう
H24法附則第46条第12項 特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。 |
※特定労働者とは、厚生年金保険の被保険者資格を有する者のことです。(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号の(適用除外)いずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの)
では、過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」とは
・ 適用事業所が法人事業所の場合、法人そのものを事業主として取り扱い、同一法人格に属する全ての適用事業所を「事業主が同一である1又は2以上の適用事業所」として取り扱うこととする。
・ 適用事業所が個人事業所の場合、個人事業主を事業主として取り扱い、事業主が同一である適用事業所は現在の適用事業所の単位のほかに無いものとして取り扱うこととする。
(令4.9.28保保発0928第6号)
②【R7年出題】
初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律に規定する「特定適用事業所」となった適用事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、①適用事業所の名称及び所在地、②特定適用事業所となった年月日、③事業主が法人であるときは、法人番号を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
特定適用事業所となったときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当届」を届け出ることとされています。
(則第23条の2)
➂【R7年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得要件について、常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合は遡及取消となる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
常時50人を超えると見込んで特定適用事業所該当届を提出して適用された後、実際には常時50人を超えなかった場合でも「遡及取消にはなりません」とされています。
(令6.1.17事務連絡)
④【R6年出題】※改正による修正あり
被保険者の総数が常時50人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込があること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。

【解答】
④【R6年出題】 〇
特定適用事業所以外の適用事業所に使用される短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得については、労使合意に基づき、申出を行うことにより可能であるとされています。
(令4.9.28保保発0928第6号)
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」によると、以下の扱いになります。
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。
(令6.1.17事務連絡)
問題文のように、常時50人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しません。
⑥【H29年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が130万円未満の場合、被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかを選択することができる。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
年収が130万円未満の短時間労働者であっても、要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
被保険者になるか、被保険者になることなく被保険者である配偶者の被扶養者になるかの選択はできません。
(令6.1.17事務連絡)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「資格喪失後の死亡」
R8-103 12.05
資格喪失後の死亡|埋葬料・埋葬費が支給される場合
健康保険の被保険者の資格を喪失した後に死亡した場合でも、埋葬料又は埋葬費が支給されることがあります。
本題に入る前に、「埋葬料」と「埋葬費」の違いを確認しましょう。
| 支給対象 | 金額 |
埋葬料 | 被保険者により生計を維持していた者で、埋葬を行うもの | 5万円 |
埋葬費 | 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合で、埋葬を行った者 | 5万円以内で埋葬に要した費用(実費) |
条件を条文で読んでみましょう
法第105条 (資格喪失後の死亡に関する給付) 資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
死亡日が資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内の場合は、埋葬料が支給されます。
★資格喪失後の死亡について埋葬料・埋葬費が支給されるのは次の3つの場合です。
①資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき
②資格喪失後の傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したとき
➂被保険者の資格を喪失した日後3月以内に死亡したとき
②【R7年出題】
被保険者の資格を喪失した後も引き続き傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受けなくなった日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは埋葬料の支給を受けることができるが、当該埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者が、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を受けることができる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
・被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものには「埋葬料」が支給されます。
・埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます。
➂【R3年出題】
傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

【解答】
➂【R3年出題】 ×
「埋葬を行う者は誰でも」が誤りです。
その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができるのは、「被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「届出」
R8-102 12.04
介護保険第2号被保険者|該当したとき・該当しなくなったとき
介護保険の被保険者の定義を確認しましょう。(介護保険法第9条)
① 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) ② 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) ①、②のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者となります。 |
健康保険の被保険者が介護保険第2号被保険者の場合は、健康保険の保険料と合わせて介護保険料も徴収されます。
介護保険第2号被保険者に該当した・該当しなくなった場合は、原則として届出が必要です。
条文を読んでみましょう。
則第40条 (介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出) ① 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したときは、この限りでない。
則第41条 (介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出) ① 被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。
※被保険者が任意継続被保険者であるときは、「保険者」に届け出なければならない。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより、介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

【解答】
①【R4年出題】 ×
「65歳に達した」ことにより、介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、届け出は不要です。
②【H29年出題】
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して日本年金機構又は健康保険組合に届け出なければならない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
「40歳に達した」ことにより介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、届出は不要です。
➂【R7年出題】
被保険者は、介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
「被保険者又はその被扶養者が40歳に達したときは、この限りでない。」とは、40歳に達したことで介護保険第2号被保険者に該当したときは、届出は不要ということです。
④【H29年出題】
50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

【解答】
④【H29年出題】 〇
事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなって介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、事業主は、被保険者に代わって届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができます。
(則第40条第3項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険外併用療養費」
R8-101 12.03
保険外併用療養費|評価療養・患者申出療養・選定療養
保険外併用療養費の内容をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第86条第1項 (保険外併用療養費) 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 法第63条第2項 ・ 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) ・ 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) ・ 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) |
★評価療養、患者申出療養、選定療養は「療養の給付」には含まれません。
例えば、「先進医療」を受けた場合、「先進医療の部分」は保険外ですので、すべて本人が負担します。一般の診療と共通する「基礎的な部分」は、「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
では、過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいう。

【解答】
①【R7年出題】 〇
こちらの問題文では、「評価療養の給付の対象とすべきものであるか否か」となっていますが、条文では、「療養の給付の対象とすべきものであるか否か」と定められています。
令和7年問2の問題は、アからオの選択肢のうち、「誤っているものの組み合わせ」が問われた問題でした。こちらの問題以外に明らかに「誤っているものの組み合わせ」がありました。
そのため、こちらの問題は「〇」で正解となります。
このように誤りかどうか判断に迷う問題は、明らかに誤っている(=誤りの判断が簡単につく)方を選んでください。
②【R2年出題】
患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

【解答】
②【R2年出題】 〇
「患者申出療養」制度について、厚生労働省のホームページでは以下のように案内されています。
未承認薬などをいちはやく使いたい。対象外になっているけれど治験を受けたい。
そんな患者さんたちの思いに応えるためにつくられた制度です。
患者さんからの申出を受け、医師や関連病院などが連携して、さまざまなケースについて対応できるかどうかを検討し、実施の可能性を探ります。
事前の診療計画や治療の経過などのデータは、今後多くの人が受けることのできる保険診療のために活用されます。
なお、医療法第4条の3では、「病院であって、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する一定の要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。」と規定されています。
➂【R4年選択式】
保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定されている選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が< A >の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が< B >を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
(選択肢)
⑤90日 ⑥120日 ⑧150日 ⑩180日
⑦150以上 ⑨180以上 ⑪200以上 ⑫250以上

【解答】
<A> ⑪200以上
<B> ⑩180日
④【R6年選択式】
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、< A >、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
(選択肢)
②新たな医療技術、医薬品、医療器等によるものであることから
⑤患者に対する情報提供を前提として
⑨困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として
⑱保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に適合するとともに

【解答】
<A> ⑤患者に対する情報提供を前提として
(令6.3.27保発0327第10号)
⑤【H28年出題】
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
予約に基づく診察は、選定療養の対象となります。
特別料金は、全額自己負担となります。
(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条)
⑥【R4年出題】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
被保険者が支払う額は、
「保険診療30万円」×30%=9万円
+
「選定療養10万円」
=19万円です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険料額」
R8-100 12.02
<令和8年改正>一般保険料等額と介護保険料額
健康保険の被保険者に関する保険料額についてみていきます。
「介護保険第2号被保険者」と「それ以外」で保険料額が変わります。
条文を読んでみましょう。
法第156条(被保険者の保険料額) ※令和8年4月1日改正 ① 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料等額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)と子ども・子育て支援金率とを合算した率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額 (2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料等額 ② 介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。ただし、その月に再び介護保険第2号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 ➂ 前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。 |
★令和8年4月の改正について
→ 医療保険者は、医療保険制度上の給付に係る保険料や介護保険料とあわせて、子ども・子育て支援金を徴収することになります。
健康保険法では、保険料の規定に、一般保険料率と区分して「子ども・子育て支援金率」が規定されます。
介護保険第2号被保険者である被保険者 | 介護保険第2号被保険者以外の被保険者 |
一般保険料等額 + 介護保険料額 | 一般保険料等額 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】※改正による修正あり
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当していない場合であっても、規約で定めるところにより、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、当該被保険者(「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料等額と介護保険料額との合算額とすることができる。

【解答】
①【R7年出題】 〇
例えば、35歳の被保険者は、介護保険第2号被保険者ではありませんので、保険料額は「一般保険料等額」のみです。
しかし、35歳の被保険者に43歳の被扶養者(=介護保険第2号被保険者に該当)がいる場合は、その35歳の被保険者(特定被保険者)に関する保険料額を、「一般保険料等額と介護保険料額との合算額」とすることができるという規定です。
「健康保険組合」限定の規定ですので、注意しましょう。
(法附則第7条)
②【R1年出題】
政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

【解答】
②【R1年出題】 〇
厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合限定の規定です。
介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料等額と特別介護保険料額との合算額とすることができます。
介護保険料額は、標準報酬月額・標準賞与額に「介護保険料率」を乗じて計算することが原則です。
問題文の「特別介護保険料額」は、原則の方法ではなく、「定額」で算定する方法です。
(法附則第8条)
➂【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
➂【H29年出題】 〇
「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と規定されています。
前月から引き続き被保険者である者が、7月26日に資格を喪失した場合、7月分の保険料は算定されません。
そのため、7月10日に賞与を30万円支給され、支給後の同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した場合は、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。
(法第156条第3項)
④【R4年出題】※改正による修正あり
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料等額とともに介護保険料額を控除することができる。

【解答】
④【R4年出題】 〇
健康保険法で一般保険料等額とともに介護保険料額が徴収されるのは、「介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)」です。
・介護保険料額の徴収の始まり
「40歳に達したとき(40歳の誕生日の前日)」から対象です。
「40歳に達した日が属する月」から介護保険料額が徴収されます。
問題文は、40歳に達した6月分から介護保険料額が徴収されますので、6月10日支払の賞与からも介護保険料額が徴収されます。
★徴収の終わりも確認しましょう。
「介護保険第2号被保険者である被保険者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料等額とする。(原則)」とされています。
「65歳に達したとき」から、介護保険第1号被保険者となります。そのため、健康保険では介護保険料額は徴収されなくなります。
例えば、12月2日が65歳の誕生日の場合は、介護保険第2号被保険者でなくなる12月1日が属する「12月分」から、保険料額は「一般保険料等額」のみとなります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「時効」
R8-099 12.01
健康保険の時効は2年/起算日にも注意
健康保険の時効をみていきます。
条文を読んでみましょう
法第93条 (時効) ① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
徴収権の消滅時効の起算日は、保険料についてはその保険料の納期限の翌日、保険料以外の徴収金については徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日である。

【解答】
①【R6年出題】 〇
徴収権の消滅時効の起算日について確認しましょう。
・保険料 → その保険料の納期限の翌日
・保険料以外の徴収金 → 徴収金を徴収すべき原因である事実の終わった日の翌日
(昭3.7.6保発第514号)
②【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
現物給付については、時効の対象となりません。
➂【H27年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。

【解答】
➂【H27年出題】 〇
傷病手当金・出産手当金を受ける権利の消滅時効は2年です。
起算日は、傷病手当金は「労務不能であった日ごとにその翌日」、出産手当金は「労務に服さなかった日ごとにその翌日」です。
(昭30.9.7保険発199の2)
④【R1年出題】
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
④【R1年出題】 ×
出産手当金を受ける権利は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅します。
(昭30.9.7保険発199の2)
⑤【H30年出題】
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
コルセット装着に係る療養費については、コルセットの代金を支払った日が「療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日」です。そのためコルセットの代金を支払った日の翌日が時効起算日です。
(昭31.3.13保文発1903号)
⑥【H28年出題】※改正による修正あり
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
「高額療養費」の時効の起算日が誤りです。
(消滅時効の起算日について)
・療養費 → 療養に要した費用を支払った日の翌日
・高額療養費 → 診療月の翌月の1日
※診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日
・高額介護合算療養費 → 計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日
(昭31.3.13保文発1903号、昭48.11.7/保険発第99号/庁保険発第21号/、平21.4.30保保発第0430001号)
⑦【R7年出題】
被保険者が資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後の継続給付を受ける権利の一部が既に時効により消滅している場合、時効未完成の期間については同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
資格喪失後何らの手続をとることなく相当期間を経過したため、受給資格期間は満たしているが、資格喪失後継続給付を受ける権利の一部がすでに時効により消滅している事例については、「継続して」に該当せず、時効未完成の期間についても、資格喪失後継続給付を受けることはできないものと解されています。
(昭31.12.24保文発第11283号)
⑧【R7年出題】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産したときは、出産した日の翌日から起算して5年を経過する日までの間、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

【解答】
⑧【R7年出題】 ×
出産育児一時金の時効は、出産した日の翌日から起算して「2年」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険給付の制限」
R8-097 11.29
正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき
「正当な理由」なしに、療養に関する指示に従わない場合は、保険給付が制限されます。
条文を読んでみましょう
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 |
ポイント!
・行わないことができるのは、「全部又は一部」ではなく「一部」です。
・第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用されます。(法第122条)
過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。

【解答】
①【H22年出題】 ×
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。
②【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」です。
➂【R2年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

【解答】
➂【R2年出題】 〇
★ 「療養の指示に従わない者」とは、次に該当する者とされています。
・ 保険者又は療養担当者の療養の指示に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)
・ 診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる者
(昭26.5.9保発第37号)
④【R7年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。療養に関する指示に従わないときとは、保険者又は療養担当者の療養の指揮に関する明白な意思表示があったにもかかわらず、これに従わない者(作為又は不作為の場合を含む。)等をいう。

【解答】
④【R7年出題】 ×
保険者は、被保険者又は被保険者であった者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、「当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる。」となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「損害賠償請求権」
R8-096 11.28
損害賠償請求権の代位取得と保険給付の免責
第三者の行為によって生じた事故については、「健康保険の保険給付」と「第三者からの損害賠償」が重なる不合理を避けるため、保険者の「損害賠償請求権の代位取得」と保険給付の「免責」の制度が設けられています。
条文を読んでみましょう。
法第57条 (損害賠償請求権) ①保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 ② 前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 |
①について(保険者が損害賠償請求権を代位取得する)
・保険者が保険給付を行った
↓
・その給付の価額の限度において、「保険給付を受ける権利を有する者」が第三者に対して有する損害賠償請求権を、保険者が代位取得する
↓
・保険者から第三者に対して損害賠償を請求する
②について(保険給付の免責)
・「保険給付を受ける権利を有する者」が第三者から損害賠償を受けた
↓
・その価額の限度において、保険者は保険給付を行う責任を免れる
では、過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、30日以内に、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「30日以内」ではなく「遅滞なく」です。
療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じた場合は、届出が必要です。
療養の給付に係る事由等が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、届出に係る事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)及び被害の状況を記載した届書を保険者に提出しなければなりません。
(則第65条)
②【H28年出題】
被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
保険給付を受ける権利を有する者には、「給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。」とされています。
被保険者の被扶養者が第三者の行為により死亡し、被保険者が家族埋葬料の給付を受けるときは、保険者は、当該家族埋葬料の価額の限度において当該被保険者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第三者に対して求償できます。
➂【H27年出題】
犯罪の被害を受けたことにより生じた傷病は、一般の保険事故と同様に、健康保険の保険給付の対象とされており、犯罪の被害者である被保険者は、加害者が保険者に対し損害賠償を負う旨を記した誓約書を提出しなくとも健康保険の保険給付を受けられる。

【解答】
➂【H27年出題】 〇
「犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています。
また、犯罪の被害によるものなど、第三者の行為による傷病について医療保険の給付を行う際に、医療保険の保険者の中には、その第三者行為の加害者が保険者に対し損害賠償責任を負う旨を記した加害者の誓約書を、被害者である被保険者に提出させるところもあるようですが、この誓約書があることは、医療保険の給付を行うために必要な条件ではないことから、提出がなくとも医療保険の給付は行われます。」とされています。
(平26.3.31/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)
④【R7年出題】
自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)による給付の関係について、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じるので、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であることから医療保険の給付を行わない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として「医療保険の給付を行わないということはできない。」とされています。
「自動車事故による被害を受けた場合の医療保険の給付と自賠責保険による給付の関係については、自動車事故による被害の賠償は自動車損害賠償保障法では自動車の運行供用者がその責任を負うこととしており、被害者は加害者が加入する自賠責保険によってその保険金額の限度額までの保障を受けることになっています。その際、何らかの理由により、加害者の加入する自賠責保険の保険者が保険金の支払いを行う前に、被害者の加入する医療保険の保険者から保険給付が行われた場合、医療保険の保険者はその行った給付の価額の限度において、被保険者が有する損害賠償請求権を代位取得し、加害者(又は加害者の加入する自賠責保険の保険者)に対して求償することになります。
一方で、加害者が不明のひき逃げ等の場合や自賠責保険の補償の範囲を超える賠償義務が発生した場合には、被害者の加入する医療保険の保険者が給付を行ったとしても、その保険者は求償する相手先がないケースや結果的に求償が困難なケースが生じ得ます。このような場合であっても、偶発的に発生する予測不能な傷病に備え、被保険者等の保護を図るという医療保険制度の目的に照らし、医療保険の保険者は、求償する相手先がないことや結果的に求償が困難であること等を理由として医療保険の給付を行わないということはできません。」とされています。
(平26.3.31/保保発0331第1号/保国発0331第2号/保高発0331第12号/)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「高額療養費」
R8-095 11.27
マイナ保険証で変わること/高額療養費の限度額適用認定証との関係
最初に、マイナ保険証についての通知を読んでみましょう。
医療保険制度においては、被保険者の所得区分に応じて自己負担限度額を設定し、医療機関等に支払う一部負担金等の金額が自己負担限度額を超えた場合に、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する高額療養費制度を設けている。 高額療養費については、各月について支払った一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合に、翌月以降に支給されること(償還払い)となっているところ、健康保険法施行規則第103条の2第2項等の規定に基づき、被保険者からの申請に応じて医療保険者等が交付する限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)を医療機関等の窓口で提示した場合には、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されることとなっている。 この自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけでなく、マイナ保険証により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されるといったメリットがあることを周知するため、限度額適用認定証等の様式について所要の改正を行う。 (令6.3.28保発0328第6号) |
※マイナ保険証とは、「健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード」のことです。
※「自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される」とは、自己負担限度額を超える部分は、現物給付されるということです。
では、過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
高額療養費の支給は、償還払いを原則としており、被保険者からの請求に基づき支給する。この場合において、保険者は、診療報酬請求明細書(家族療養費が療養費払いである場合は当該家族療養費の支給申請書に添付される証拠書類)に基づいて高額療養費を支給するものであり、法令上、請求書に証拠書類を添付することが義務づけられている。

【解答】
①【R5年出題】 ×
高額療養費は、診療報酬請求明細書(レセプト)に基づいて支給されます。
被保険者からの請求書に証拠書類を添付することについては、義務づけられていません。
(昭48.11.7保険発第99号・庁保険発第21号)
②【R7年出題】
高額療養費制度において、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いの免除については、限度額適用認定証等を提示した場合だけではなく、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)により保険資格の確認を行う場合についても対象となっており、マイナ保険証を利用する場合には、医療機関等の窓口において、限度額適用認定証等を提示せずとも、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除される。

【解答】
②【R7年出題】 〇
高額療養費の現物給付を受ける方法は次の2つです。
①医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示する
②マイナ保険証(健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカード)により保険資格の確認を行う場合
※マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等の窓口で、限度額適用認定証等を提示しなくても、自己負担限度額を超える一部負担金の支払いが免除されます。
(令6.3.28保発0328第6号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「高額療養費」
R8-094 11.26
高額療養費の計算ルールを攻略しましょう/自己負担限度額の出し方がポイント!
「高額療養費」とは?
→ 医療機関の窓口で支払った一部負担金等が、月単位の高額療養費算定基準額(=自己負担限度額)を超えた場合、超えた額が、事後に支給される制度です。
※現物給付される仕組みもあります。
(例)70歳未満・標準報酬月額28万円の被保険者、ある月の一部負担金が30万円
医療費(100万円) | ||
一部負担金30万円 | 保険給付(療養の給付) | |
自己負担限度額 87,430円 | 高額療養費 | |
①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は次のように計算します。
=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1% = 87,430円
②一部負担金から高額療養費算定基準額をマイナスした額が、高額療養費として支給される額です。
高額療養費=30万円-8万7430円=21万2570円
★ポイント!
高額療養費は、暦月単位(1日から月末)で算定します。
例えば、令和7年11月27日~同年12月20日まで入院した場合は、11月27日~30日と12月1日~20日までに分けて算定します。
今回は、「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」・「高額療養費」の算定ルールをみていきましょう。
ポイントを過去問で確認しましょう
①【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「食事療養標準負担額」、「生活療養標準負担額」、「保険外併用療養に係る自己負担分(例えば差額ベッド代や先進医療にかかる費用等)」は、高額療養費の算定対象になりません。
(令第41条)
②【R7年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
同一の月に同一の保険医療機関で、「入院」と「通院」で療養を受けた場合は、同一の保険医療機関で受診したとしても、高額療養費の算定上、それぞれ「別個の保険医療機関」で受けた療養とみなされます。
(昭48.10.17保険発第95号・庁保険発第18号)
➂【H27年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】
➂【H27年出題】 ×
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、「内科」と「歯科」は、それぞれ区別して高額療養費が算定されます。
(昭48.10.17保険発第95号・庁保険発第18号)
④【H29年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

【解答】
④【H29年出題】 〇
同一月内で「全国健康保険協会管掌健康保険」から「組合管掌健康保険」に移った場合の高額療養費は、それぞれの「管掌者ごと」にその月の高額療養費の支給要件の判定が行われます。
(昭48.11.7保険発第99号・庁保険発第21号)
⑤【H27年出題】
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、「70歳未満」か「70歳以上75歳未満」で区分されます。
また、所得によっても区分されています。
問題を解くときは注意しましょう。
⑥【R2年選択式】
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。
(選択肢)
① 7,330円
② 84,430円
➂ 125,570円
④ 127,670円

【解答】
⑥【R2年選択式】
<A> ➂125,570円
ポイント!
・医薬品など評価療養に係る特別料金10万円、室料など選定療養に係る特別料金20万円は、高額療養費の算定には入りません。
医療費(70万円) | ||
一部負担金21万円 | 保険給付(療養の給付) | |
自己負担限度額 84,430円 | 高額療養費 | |
①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は次のように計算します。
=80,100円+(700,000円-267,000円)×1% = 84,430円
②一部負担金から高額療養費算定基準額をマイナスした額が、高額療養費の額です。
高額療養費=21万円-84,430円=12万5570円
⑦【R5年出題】
71歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
70歳以上75歳未満の市町村民税非課税者である被保険者の外来の高額療養費算定基準額は「8,000円」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「被扶養者」
R8-093 11.25
<令和7年改正>健康保険の「被扶養者の収入要件」130万/150万/180万
健康保険の被扶養者となるための認定対象者の年間収入要件をみていきましょう。
★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
(1)認定対象者の年間収入が130万円未満
※認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)
かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(2) (1)の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。
★ 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
・認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。
(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
★扶養認定日が令和7年10月1日以降の場合(改正)
→扶養認定を受ける人が19歳以上23歳未満の場合は、「130万円未満」が「150万円未満」となります。なお、被保険者の「配偶者」はこの扱いから除かれます。
(R7.7.4保発0704 第1号 、年管発0704第1号)
では、過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】※改正による修正あり
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者※」という。)が日本国内に住所を有し、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
※本問の認定対象者については、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者を除く。)は除く。

【解答】
①【R1年出題】 〇
認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は障害者である場合にあっては180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとされます。
ただし、上記の要件を満たさなくても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が「60歳以上」又は「障害者」の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないとされています。
ちなみに、認定対象者が、19歳以上23歳未満の者(被保険者の配偶者は除く。)の場合は、「130万円」は「150万円」となります。
②【R7年出題】
被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳、障害者ではない。)は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
問題文の母の年収は、遺族年金100万円+給与120万円=220万円です。
認定対象者の年収要件の「130万円未満」を満たしていませんので、母は、被保険者の被扶養者になることはできません。
③【R7年出題】
被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。

【解答】
③【R7年出題】 〇
問題文の父は、「60歳以上」で「年収180万円未満」(老齢年金の年額が130万円)の要件を満たしています。
かつ、父の年収が、認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合の要件である「被保険者からの援助による収入額より少ない」(被保険者から年額150万円の援助を受けている)要件も満たしています。
また、父は日本国内に住所を有しているため、父は、原則として被扶養者に該当します。
④【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者と同一世帯に属しておらず、日本国内に住所を有する年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。

【解答】
④【H26年出題】 ×
「その援助の額にかかわらず」が誤りです。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年収が「被保険者からの援助による収入額より少ない」ことが要件です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「訪問看護療養費など」
R8-083 11.15
訪問看護療養費の額などの算定
例えば、50歳の健康保険の被保険者が、保険医療機関に入院して療養を受けた場合、治療等については、「療養の給付」が現物給付されます。
ただし、「食事療養」は、療養の給付に含まれません。食事については、療養の給付とは別に、「入院時食事療養費」が支給されます。なお、被保険者本人は、入院時の食事については、「食事療養標準負担額」を支払います。
そのため、「入院時食事療養費」として支給されるのは、
「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から、「食事療養標準負担額」を控除した額となります。
過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
入院時食事療養費の額は、「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から「食事療養標準負担額」を控除した額です。
「食事療養標準負担額」を控除することが抜けているので誤りです。
条文を読んでみましょう
法第85条第2項 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |
②【H23年出題】
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。

【解答】
②【H23年出題】 ×
食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、「中央社会保険医療協議会」ではなく「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額となります。
なお、次の規定にも注意して下さい。
条文を読んでみましょう。
法第85条第3項 厚生労働大臣は、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
➂【R7年出題】
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)を控除した額である。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
入院時生活療養費の額は、「生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、「生活療養標準負担額」を控除した額となります。
ポイントを条文で読んでみましょう
法第85条の2第2項 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額及び同項第2号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 |
④【R5年出題】
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

【解答】
④【R5年出題】 ×
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、「社会保障審議会」ではなく、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとされています。
(法第85条の2第3項)
⑤【R7年出題】
訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に健康保険法第74条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
訪問看護療養費の額は、「指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額」から、「その額に一部負担金の割合を乗じて得た額(基本利用料)」を控除した額となります。
ポイントを押さえながら条文を読んでみましょう。
法第88条第4項 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第74条第1項各号に掲げる場合の区分(一部負担金の区分・原則3割)に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第75条の2第1項各号の措置(減額・免除・徴収猶予の措置)が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。 |
なお、厚生労働大臣は、法第88条第4項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。(法第88条第5項)
⑥【R1年出題】
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

【解答】
⑥【R1年出題】 〇
・保険者 → 訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額を、指定訪問看護事業者に直接支払うことができます。
・被保険者 → 基本利用料(原則3割)を指定訪問看護事業者に支払います。
結果的に、訪問看護療養費は「現物給付」となります。
(法第88条第6項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「一部負担金」
R8-082 11.14
一部負担金の減額・免除・徴収猶予
療養の給付を受けた場合は、療養に要する費用の額に、原則100分の30を乗じて得た額を、「一部負担金」として、保険医療機関又は保険薬局に支払わなければなければなりません。
ただし、災害等の特別の事情がある被保険者については、特例が規定されています。
条文を読んでみましょう
法第75条の2 (一部負担金の額の特例) ① 保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 (1) 一部負担金を減額すること。 (2) 一部負担金の支払を免除すること。 (3) 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 ② (1)の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、(2)又は(3)の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
一部負担金の額の特例が適用されるのは、「災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者」です。
厚生労働省令を読んでみましょう
則第56条の2 厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 |
②【R7年出題】
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行うものとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、「6か月以内」の期間を限って行われます。
(H18.9.14保保発0914001号)
➂【R3年出題】
保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、「審査支払機関」に請求します。
(H18.9.14保保発0914001号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「傷病手当金の支給調整」
R8-066 10.29
傷病手当金と報酬等との調整
今回のテーマの1つ目は、「傷病手当金」と「報酬」との支給調整です。報酬を受けるときは、原則として傷病手当金は支給されません。
テーマの2つ目は、「傷病手当金」と「出産手当金」との支給調整です。出産手当金が優先されることがポイントです。
条文を読んでみましょう
第108条第1項 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。
法第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間」ですので、問題文の傷病手当金の支給期間は、傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から通算して1年6か月です。
報酬あり | 報酬なし |
4/25・・・・・・・・・・・・・・・・5/31 | 6/1・・・・・・・・ |
年次有給休暇 | 欠勤 |
傷病手当金 支給停止 | 支給→(通算1年6か月) |
報酬が支払われている場合、傷病手当金は支給停止されます。(なお、報酬が支払われていても待期は完成します。4月25日、26日、27日の連続した3日間で待期は完成します。)
そのため、傷病手当金は報酬を受けなくなった日(=支給停止事由がなくなった日)から支給が始まり、「支給を始めた日」から通算して1年6か月間支給されます。
(昭24.1.24保文発162)
②【H28年出題】
傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されるが、当該支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費であっても、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象となる。

【解答】
②【H28年出題】〇
傷病手当金は、その支給期間に一部でも報酬が支払われていれば支給額が調整されます。
「通勤手当」も報酬に当たります。支給期間以前に支給された通勤定期券の購入費でも、実態は毎月の通勤に対し支給されていますので、傷病手当金の支給期間に係るものは調整の対象となります。
(昭27.12.4保文発7241)
➂【R7年出題】
被保険者が、介護休業期間中に私傷病により傷病手当金を受給する場合には、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われる。なお、傷病手当金との調整の対象とされる報酬には、就業規則に基づき報酬支払の目的をもって支給された見舞金は含まれない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
傷病手当金及び出産手当金の支給要件に該当する場合は、介護休業期間中でも傷病手当金又は出産手当金は支給されます。
ただし、傷病手当金又は出産手当金が支給される場合で、その期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について介護休業手当等との調整が行われます。
(H11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)
見舞金その他名称の如何を問わず、就業規則又は労働協約等に基き、報酬支払の目的をもって支給されたとみなされるもので、その支払事由の発生以後引続き支給されるものは、「報酬」に該当します。そのため、傷病手当金との調整の対象となります。
(昭25.2.22保文発第376号)
問題文の前半は「〇」ですが、後半の見舞金は報酬に含まれますので、「×」です。
④【H30年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
出産手当金と傷病手当金はいずれか選択ではありません。
出産手当金を支給する場合は、その期間は、傷病手当金は原則として支給されません。
⑤【R4年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】
⑤【R4年出題】 〇
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間に、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、「出産手当金」の支給が優先されます。
出産手当金の額多>傷病手当金の額少の場合は、傷病手当金は支給されません。
ちなみに、出産手当金の額少<傷病手当金の額多の場合は、差額の傷病手当金が支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「傷病手当金」
R8-065 10.28
傷病手当金の支給要件
一定の要件を満たした被保険者には傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給要件について条文を読んでみましょう
法第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金は、休み始めて4日目から支給され、最初の3日間は支給されません。最初の3日間を待期といいます。なお、待期は「連続した3日間」で完成します。
では、過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 ×
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「4日」ではなく「3日」を経過した日から支給されます。
②【R1年選択式】※改正による修正あり
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B>又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。
<選択肢>
①4月1日から ②4月3日から ③4月4日から ④4月5日から
⑤日 ⑥日の2日後 ⑦日の3日後 ⑧日の翌日

【解答】
<A> ④4月5日から
<B> ⑤日
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間です。(法第99条第4項)
★<A>について
4月 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
・・・・・ |
休 | 休 | 休 | 出勤 | 休 | ・・・・・ |
4月1日~3日まで連続3日間休んでいますので、この3日間で待期は完成しています。
そのため、傷病手当金は、再び労務不能になって休業した5日から支給されます。
★<B>について
報酬あり | 報酬 | ||||||
なし | |||||||
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
傷病手当金 支給停止 | 支給 | ||||||
報酬が支払われている場合、傷病手当金は支給停止されます。ただし、報酬が支払われていても待期は完成します。
そのため、傷病手当金は報酬を受けなくなった日(=支給停止事由がなくなった日)から支給されます。
(昭24.1.24保文発162)
➂【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

【解答】
➂【H28年出題】 〇
休日も待期期間に算入されます。問題文の場合は、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。
④【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
④【H28年出題】 ×
待期は、「労務不能の状態になった日」から起算するのが原則です。ただし、労務不能になったのが業務終了後の場合は「その翌日」から起算します。
問題文は、就業中に発症しそのまま入院していますので、その翌日ではなく、「その日」が待期期間の起算日となります。
(昭5.10.13保発52)
⑤【R7年出題】
被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「就業時間内」に労務不能になった場合は、傷病手当金の待期期間の起算日は「その翌日」ではなく「その日」(2月3日)となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たします。
⑥【R3年出題】
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

【解答】
⑥【R3年出題】 ×
一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることは要件となりません。自費診療による療養も傷病手当金の対象となります。
(昭2.2.26保発345)
⑦【R1年出題】
傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。

【解答】
⑦【R1年出題】 ×
・前半について
その本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合 → 労務不能には該当しない
・後半について
本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合 → 労務不能に該当する
問題文の後半(本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事した場合等)が誤りです。
(平15.2.25保保発第0225007号/庁保険発第4号/)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「費用の負担」
R8-064 10.27
健康保険「国庫負担と国庫補助」
健康保険事業に対する「国庫負担」と「国庫補助」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。
法第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
法第153条、法附則第5条 (国庫補助) 国庫補助の対象になる給付 ・協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 ・補助の割合→ 1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合(当分の間「1,000分の164」)を乗じて得た額を補助する。
第154条の2 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。 |
過去問をどうぞ!
①【H23選択式】※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。
4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E >の実施に要する費用の一部を補助することができる。

【解答】
<A> 予算
<B> 介護納付金
<C> 被保険者数
<D> 概算払い
<E> 特定健康診査等
※特定健康診査等とは
「高齢者医療確保法」の規定による40歳以上を対象とした「特定健康診査及び特定保健指導」のことです。
②【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、国庫が全額負担しています。
健康保険組合に対しても負担を行っています。
➂【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。

【解答】
➂【R6年出題】 〇
赤字の部分がポイントです。健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払いをすることができる。
④【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
⑤【R7年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の「一部」を補助することができる。」と規定されています。「全部」ではありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「日雇特例被保険者の保険料」
R8-062 10.25
日雇特例被保険者の保険料の納付について
日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼って納付します。
納付について条文を読んでみましょう
第168条第1項 (日雇特例被保険者の保険料額) 日雇特例被保険者に関する保険料額は、1日につき、次に掲げる額の合算額とする。 (1) その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額 イ 標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額 ロ イに掲げる額に100分の31を乗じて得た額 (2) 賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が40万円を超える場合には、40万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額 |
★日雇特例被保険者に係る保険料の負担
・日雇特例被保険者
→ イの額の2分の1及び(2)の額の2分の1の額の合算額を負担
・事業主
→ イの額の2分の1及び(1)ロの額及び(2)の額の2分の1の額の合算額を負担
法第169条第2項~第6項 ② 事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。 ➂ 保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。 ④ 日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。 ⑤ 事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。 ⑥ 事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H23年出題】
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するすべての事業主。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

【解答】
①【H23年出題】 ×
「その者を使用するすべての事業主」が誤りです。
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負います。
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「その者を使用するすべての事業主」ではなく、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。
②【R7年出題】
日雇特例被保険者を使用する事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合においては、その者を使用するそれぞれの事業主)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。事業主は、この規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「その者を使用するそれぞれの事業主」が誤りです。
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合は、「初めにその者を使用する事業主」が納付する義務を負います。
なお、事業主は、保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができ、その場合は、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければなりません。
➂【R4年出題】
日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
日雇特例被保険者の賃金日額は、「1日において2以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金」につき算定されます。
(法第125条第1項第6号)
問題文の場合は、初めに使用される事業所(A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所)から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、A健康保険組合管掌健康保険の適用事業所の事業主が健康保険印紙を貼り、これに消印して保険料を納付します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「日雇特例被保険者」
R8-061 10.24
日雇特例被保険者の特別療養費
日雇特例被保険者の保険料は、日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙をはって納付します。
日雇特例被保険者が、療養の給付等を受けるには、「保険料納付要件」を満たさなければなりません。
保険料納付要件は、次のいずれかに該当していることです。
・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
・療養の給付を受ける日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている
例えば、10月24日に療養の給付を受ける場合は、前2か月間(8月と9月)に通算して26日分以上納付されていれば、要件を満たします。
8月 | 9月 | 10月 |
通算して26日分以上納付 |
| |
しかし、初めて日雇特例被保険者手帳を受けた者等は、保険料納付要件を満たせません。そのため、「特別療養費」が設けられています。
条文を読んでみましょう
法第145条第1項 次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して3月(月の初日に該当するに至った者については、2月)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。 (1) 初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者 ※以下(2)と(3)は今回は省略します
則第130条 (特別療養費受給票の交付) 日雇特例被保険者は、特別療養費受給票の交付を申請しようとするときは、全国健康保険協会又は委託市町村に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための要件です。
療養の給付を受ける日において
→当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
→当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている
②【H26年出題】
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

【解答】
②【H26年出題】 〇
例えば、10月3日に、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、「日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間」=12月31日までです。
なお、月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間となります。
➂【R7年出題】
日雇特例被保険者又はその被扶養者は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して、特別療養費の支給を受けることができる。特別療養費受給票は、特別療養費の支給を受けることのできる日雇特例被保険者で、初めて特別療養費の支給に係る日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)を経過していない者等の申請により、保険者が交付する。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
こちらもチェックしましょう!
・特別療養費は、保険者より交付された特別療養費受給票を保険医療機関等に提出して受けます
・特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については、2か月)です
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「出産育児一時金」
R8-059 10.22
出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度
「出産育児一時金」について条文を読んでみましょう
法第101条 (出産育児一時金) 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 |
★出産育児一時金の額
政令で定める金額 →48万8千円とする。
※産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は、12,000円が加算され、50万円となります。
令和7年の選択式を解いてみましょう
【R7年選択式】
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、< A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
<選択肢>
① 1 ② 2 ④ 3 ⑧ 5
⑨ 84 ⑩ 85 ⑪ 86 ⑫ 87
⑬ 46万8,000 ⑭ 47万8,000 ⑮ 48万8,000 ⑯ 49万8,000

【解答】
<A> ⑮ 48万8,000
<B> ④ 3
<C> ⑩ 85
(法第101条、令第36条)
★出産育児一時金の支払い方法には、「直接支払制度」、「受取代理制度」、「償還払い制度」の3つの方法があります。
| 支給申請 | 受取り |
直接支払制度 | 医療機関等が被保険者に代わって保険者に支給申請を行う | 保険者から医療機関等に直接支払われる |
受取代理制度 | 被保険者自身が保険者に支給申請を行う | 医療機関等が被保険者に代わって受け取る |
償還払い制度 | 被保険者自身が保険者に支給申請を行う | 被保険者が自身で受け取る |
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

【解答】
①【R7年出題】 〇
<直接支払制度>
・被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結する
↓
・医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行う
(メリット)被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ります。
(参照:「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱)
②【R3年出題】
出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

【解答】
②【R3年出題】 〇
<受取代理制度>
・被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請する
↓
・医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る
(メリット)出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等であっても、直接支払制度と同様に、被保険者等の経済的負担の軽減を図ることができます。
(参照:「出産育児一時金等の受取代理制度」実施要綱)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「不服申立て」
R8-058 10.21
健康保険の不服申立て~1番のポイント
健康保険の不服申立てについて条文を読んでみましょう
第189条 ① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ➂ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第180条の規定(督促及び滞納処分)による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
第192条 第189条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
過去問を解きながらポイントをつかみましょう
①【R4年出題】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前は提起できません。
図で確認しましょう(二審制です)
・資格 ・標準報酬 ・保険給付 に関する処分 |
→ 審査請求 | 社会保険審査官 |
→ 再審査請求 | 社会保険審査会 |
★「処分の取消しの訴え」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後に提起することができます。
★審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合
・社会保険審査会に再審査請求する
・社会保険審査会に再審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する
のどちらでも可能です。
②【R7年出題】
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。この不服申立てに対する審査は一審制で行われる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服のある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。「一審制」で行われることがポイントです。
図で確認しましょう。(一審制です)
・保険料等の賦課若しくは徴収の処分 ・督促及び滞納処分 | → 審査請求 | 社会保険審査会 |
★保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある
・社会保険審査会に審査請求する
・社会保険審査会に審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起する
のどちらも可能です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「健康保険組合」
R8-057 10.20
健康保険組合について
「健康保険」の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。
今回は、「健康保険組合」についてみていきます。
過去問を解きながら健康保険組合のポイントをおさえましょう
①【R3年出題】
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
法第8条で、「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」と規定されています。
②【R4年出題】
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

【解答】
【②【R4年出題】 〇
★ポイントを穴埋めで確認しましょう。
法第12条
① 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の< A >を得て、規約を作り、厚生労働大臣の< B >を受けなければならない。
② 2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、< C >について得なければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<A>2分の1以上の同意
<B>認可
<C>各適用事業所
➂【R7年出題】
健康保険組合は、議決機関として組合会が置かれている。組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。組合会議員の任期は5年とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とする。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
組合会議員の任期が誤りです。
・健康保険組合には、議決機関として組合会が置かれます。
・組合会は、「組合会議員」をもって組織されます。
・組合会議員の定数は偶数で、その半数は設立事業所の事業主及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選します。
(法第18条)
・組合会議員の任期は「3年を超えない範囲内で規約で定める期間」とし、補欠の組合会議員の任期は、前任者の残任期間とされます。
(令第6条)
④【R1年出題】
健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。

【解答】
④【R1年出題】 ×
最後の「事業主が選定する」が誤りです。正しくは、「理事が選挙する」です。
ちなみに、「理事長」の職務は、健康保険組合を代表し、その業務を執行することです。
・健康保険組合に、役員として理事及び監事が置かれています。
・理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選します。
・理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙します。
・監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙します。
・監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることはできません。
(法第21条)
⑤【H30年出題】
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
「被保険者の4分の3以上の多数」が誤りです。
条文を読んでみましょう
法第24条第1項 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において「組合会議員の定数の 4分の3以上の多数」により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
⑥【H25年出題】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
⑥【H25年出題】 ×
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
(法第23条第1項)
⑦【R3年出題】
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。

【解答】
⑦【R3年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の< A >及びその適用事業所に使用される被保険者の< B >以上の< C >を得なければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
<A>全部
<B>2分の1
<C>同意
(法第25条第1項)
⑧【H23年出題】
健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。

【解答】
⑧【H23年出題】 ×
組合会議員の定数の「2分の1」ではなく「4分の3」以上の組合会の議決です。
条文を読んでみましょう
第26条第1項、2項 ① 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 (1) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 (2) 健康保険組合の事業の継続の不能 (3) 厚生労働大臣による解散の命令 ② 健康保険組合は、(1)又は(2)に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
⑨【H29年出題】
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

【解答】
⑨【H29年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう
健康保険組合が解散により消滅した場合、< A >が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<A>全国健康保険協会
(法第26条第4項)
⑩【R3年出題】
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

【解答】
⑩【R3年出題】 〇
債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができるのは、「設立事業所の事業主」に対してです。「被保険者」には負担を求めることはできません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「一般保険料率」
R8-039 10.02
一般保険料率の決定などのルール
健康保険の被保険者の保険料額は、次のように計算します。
(1)介護保険第2号被保険者の被保険者(介護保険料額を合わせて計算します)
一般保険料額+介護保険料額
(2)介護保険第2号被保険者ではない被保険者
一般保険料額
・一般保険料額→(標準報酬月額及び標準賞与額)×一般保険料率
・介護保険料額→(標準報酬月額及び標準賞与額)×介護保険料率
※一般保険料率とは、「基本保険料率」と「特定保険料率」とを合算した率のことです。
・特定保険料率とは
各年度において保険者が納付すべき 前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険の場合は国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合は、これを控除した額) |
総報酬額の総額の見込額 |
・基本保険料率は一般保険料率から特定保険料率を引いた率
「一般保険料率」の決定などのルールを条文で読んでみましょう
法第160条 <全国健康保険協会> ① 全国健康保険協会(以下「協会」という)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。 ② 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。 ⑤ 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が期間内に変更の認可の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
<健康保険組合> ⑬ 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定するものとする。 健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
この問題のキーワードを穴埋めで確認しましょう。
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、< A >の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について< B >を受けなければならない。
解答→<A>運営委員会 <B>厚生労働大臣の認可
(法第160条第6項、第8項)
②【H24選択式】
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< A >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< B >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】
<A> 健康保険事業の収支の均衡
<B> 社会保障審議会
(法第160条第11項)
※社会保障審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項の調査審議などを行う機関です。
➂【R6年出題】
協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

【解答】
➂【R6年出題】 ×
「厚生労働大臣に届け出る」ではなく、「公表するものとする」です。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
協会は、< A >ごとに、翌事業年度以降の< B >についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の< C >を作成し、< D >ものとする。
<解答>→ <A>2年 <B>5年間 <C>収支の見通し <D>公表する
④【R7年出題】
健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、決定する。健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「社会保障審議会の議を経て」が誤りです。社会保障審議会は厚生労働大臣の諮問に応じる機関です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「資格確認書」
R8-038 10.01
資格確認書の交付申請
被保険者証が廃止になり、保険診療等は、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)によって受けることになります。
なお、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある者については、医療機関等で資格確認を受けるための「資格確認書」を、書面又は電磁的方法により提供することとなっています。
★マイナンバーカードのICチップ等によって、オンラインで資格情報の確認ができる仕組みのことをオンライン資格確認(電子資格確認)といいます。
電子資格確認を受けることができない状況にあるときの条文を読んでみましょう
法第51条の3(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等) ① 被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。)による提供を求めることができる。この場合において、当該保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。 ② 書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、法第63条第3項(療養の給付)等について被保険者であることの確認を受けることができる。 |
では問題を解いてみましょう
【R7年出題】
資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める被保険者(以下本肢において「申請者」という。)は、申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号等を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うが、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

【解答】
【R7年出題】 〇
・資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供を求める場合
↓
・申請者は申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請します。
↓
・申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行います。
↓
・災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由しなくてもよい。
(則第47条第1項)
続きを条文で読んでみましょう
則第47条第2項、5項、6項、8項 ② 保険者は、資格確認書の書面による交付又は電磁的方法による提供の申請があったときは、申請者に対し、法第51条の3第1項に規定する書面であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して5年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。 ⑤ 保険者は、申請者(任意継続被保険者を除く。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。 ⑥ 資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者(任意継続被保険者を除く。)に送付しなければならない。 ⑧ 保険者は、申請者(任意継続被保険者に限る。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者(任意継続被保険者に限る。)に送付しなければならない。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「被扶養者」
R8-022 9.15
被扶養者に該当する要件(健康保険法)
健康保険の被扶養者に該当する要件をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
法第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の三親等内の親族で(1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) (3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
■被扶養者となる条件
・日本国内に住所を有している
又は
・日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの
★日本国内に住所を有していることが原則ですが、例外もあります。
例外をみていきましょう。
→ 外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
★日本国内居住要件の例外として取り扱われる者を厚生労働省令で確認しましょう。
則第37条の2 法第3条第7項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 (1) 外国において留学をする学生 (2) 外国に赴任する被保険者に同行する者 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (4) 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの (5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

【解答】
①【R2年出題 〇
外国に赴任する被保険者に同行する者は、国内居住要件の例外として、日本国内に生活の基礎があると認められる者として扱われます。
被扶養者の認定の際は、国内居住要件の例外に該当することを証する書類の添付が求められます。
問題文の場合は、「家族帯同ビザ」の確認で判断することが基本とされます。渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断するとされています。
(令5.6.19保保発0619第1号)
②【R7年出題】
健康保険法における被扶養者とは、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りではない。厚生労働省令で定める者とは、日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において2年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものをいう。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「後期高齢者医療の被保険者等である者」、「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、被扶養者になりません。
「健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは、日本国籍を有さず、「特定活動(医療目的)「特定活動(長期観光)」で滞在する者です。
則第37条の3に規定されています。
① 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(医療目的)
② 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(長期観光)
問題文は、「長期観光」ですが、2年を超えない期間ではなく「1年を超えない期間」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(健康保険法)から学ぶ
R8-010 9.03
R7年選択式は出産育児一時金・任意適用事業所の適用取消
健康保険法の令和7年選択式は、「出産育児一時金の支給要件と額」、「任意適用事業所を適用事業所でなくするときの手続き」からの出題でした。
 出産育児一時金の支給要件と額について
出産育児一時金の支給要件と額について
まず過去問からどうぞ!
①【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】
①【R5年出題】 〇
・ 出産育児一時金の額は、488,000円です。(令第36条)
・ なお、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下で、在胎週数22週に達した日以後の出産がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等の額は12,000円を加算して50万円が支給されます。
・ 胎児数に応じて支給されますので、双児の場合は50万円×2=100万円が支給されます。
(令和5.3.30保保発0330第8号)
②【H21年出題】
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。

【解答】
②【H21年出題】 〇
出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、「妊娠4か月以上(85日以後)」の出産が対象です。
1か月を28日で計算しますので、4か月目に入った日は、28日×3+1日=85日目となります。
(昭3.3.16保発第11号、昭27.6.16保文発2427号)
では、令和7年の選択式をどうぞ!
【R7年選択式】
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、 < A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
<選択肢>
① 1 ② 2 ④ 3 ⑧ 5
⑨ 84 ⑩ 85 ⑪ 86 ⑫ 87
⑬ 46万8,000 ⑭ 47万8,000 ⑮ 48万8,000 ⑯ 49万8,000

【解答】
<A> ⑮ 48万8,000
<B> ④ 3
<C> ⑩ 85
 任意適用事業所の脱退について
任意適用事業所の脱退について
「任意適用事業所」は、脱退することができます。
まず、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。事業主がこの申請を行うときは、健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の3分の2以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
任意適用事業所の事業主が適用事業所でなくするための認可の申請を行うときは、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意が必要です。
健康保険任意適用取消申請書に、被保険者の「3分の2」ではなく「4分の3」以上の同意を得たことを証する書類を添付しなければなりません。
(則第22条第2項)
②【H28年出題】
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 ×
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めたとしても、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行う義務はありません。
令和7年の選択式をどうぞ!
【R7年選択式】
健康保険法第31条第1項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の< D >以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。認可の申請は、事業主の氏名及び住所並びに事業所の名称及び所在地を記載した申請書を< E >等に提出することによって行う。この申請書には、被保険者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
<選択肢>
② 2分の1 ⑤ 3分の1 ⑥ 3分の2 ⑦ 4分の3
⑰ 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会
⑱ 社会保険診療報酬支払基金又は地方校正局長
⑲ 日本年金機構又は国民健康保険団体連合会
⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長

【解答】
<D> ⑦ 4分の3
<E> ⑳ 日本年金機構又は地方厚生局長
(則第22条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健保・厚年>短時間労働者が被保険者になる条件
R7-356 08.19
短時間労働者が被保険者になる条件のポイント!<健保・厚年>
短時間労働者が被保険者になる要件をチェックしましょう。
★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者は、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として被保険者となります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 報酬の月額が88,000円以上であること
③ 学生でないこと
■健康保険法の問題をチェックしましょう。
(1)特定適用事業所とは
①【健保H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【健保H29年出題】 〇
「特定労働者の総数が常時50人を超える」がポイントです。
(H24法附則第46条第12項)
(2)所定労働時間について
①【健保R2年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】
①【健保R2年出題】 〇
・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
・ 所定労働時間が1か月の単位で定められている場合で、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間が1週間の所定労働時間となります。
(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)
②【健保R3年出題】
同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以上であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。

【解答】
②【健保R3年出題】 ×
通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満である者が被保険者として取り扱われるためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であることが条件です。問題文の場合は18時間ですので、被保険者になりません。
(平成24法附則第46条第1項、令4.9.28保保発0928第6号)
(3)報酬の月額について
①【健保R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
①【健保R4年選択式】
<A> 88,000円以上
②【健保H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
②【健保H30年出題】 ×
最低賃金法において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)
■月額88,000円の算定に含まれないもの
・ 臨時に支払われる賃金(例)結婚手当
・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例)賞与
・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例)割増賃金
・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金
→ 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
(4)学生でないことについて
①【健保R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
④【健保R3年出題】 ×
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
■学生でないこととして取り扱われるもの
「卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっている者、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととするが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とする。」とされています。
(R4.9.28保保発0928第6号)
■厚生年金保険法の問題もチェックしましょう
①【厚年R5年出題】※改正による修正あり
特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。

【解答】
①【厚年R5年出題】 ×
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。
※特定労働者とは、「70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のもの」をいいます。
(H24法附則第17条第12項)
②【厚年R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
②【R2年出題】 〇
特定適用事業所に使用される者で、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
(H24法附則第17条第1項)
③【R4年出題】※改正による修正あり
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
※Xは、厚生年金保険法第12条第1号から第4号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。

【解答】
③【R4年出題】 ×
Xは、厚生年金保険の被保険者となります。
「国・地方公共団体」は、50人超えという人数が問われないことがポイントです。
Xは、「① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること」、「② 報酬の月額が88,000円以上であること」、「③ 学生でないこと」の要件を満たし、「地方公共団体」で働いているので、厚生年金保険の被保険者となります。
(H24法附則第17条第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「資格喪失後の継続給付」
R7-332 07.26
資格喪失後に傷病手当金と出産手当金が継続給付される要件
健康保険の被保険者資格を喪失した後も、継続して傷病手当金・出産手当金を受けることができます。
資格喪失後も継続して傷病手当金・出産手当金が支給される要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
下の図でイメージしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
資格喪失後の傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者でなければなりませんが、この被保険者期間は、同一の保険者でなくても構いません。
②【R1年出題】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

【解答】
②【R1年出題】 〇
資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。
転職等で異なった保険者における被保険者期間を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たします。ただし、1日の空白もなく継続していることが必要です。
③【R4年出題】
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
資格喪失後の継続給付の要件の1つは、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことです。
ただし、「1年以上」の計算から、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
問題文の場合は、「共済組合の組合員としての6か月間」は計算に入らないことがポイントです。資格喪失日の前日まで、A健康保険組合の被保険者であった期間が、「7か月」+「3か月」の10か月しかないため、資格喪失後の傷病手当金は支給されません。
④【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。(3日間の待期を満たす必要があります。)
資格喪失後の傷病手当金を受けるには、その資格を喪失した際に傷病手当金を受けていることが必要ですが、労務不能となった日から3日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていません。
そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。
1日目 | 2日目 | 3日目 |
休 | 休 | 休 退 職 ※傷病手当金を 受けられる状態にない |
(昭27.6.12保文発3367)
⑤【R5年出題】
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
退職日に傷病手当金を受ける要件を満たしていませんので、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 |
休 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 退職 |
⑥【H26年出題】
5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】
⑥【H26年出題】 ×
出産手当金は、出産の日又は出産の予定日以前42日に至った日に受給権が発生します。
5月25日が出産予定日で同年3月20日に退職している場合は、退職日に出産手当金を受ける状態にありません。(出産手当金の受給権が発生していません)
そのため、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることはできません。
⑦【H23年出題】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

【解答】
⑦【H23年出題】 ×
資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たしていれば、傷病手当金の継続給付を受けることができます。
⑧【H27年出題】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

【解答】
⑧【H27年出題】 〇
資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
(法附則第3条第5項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
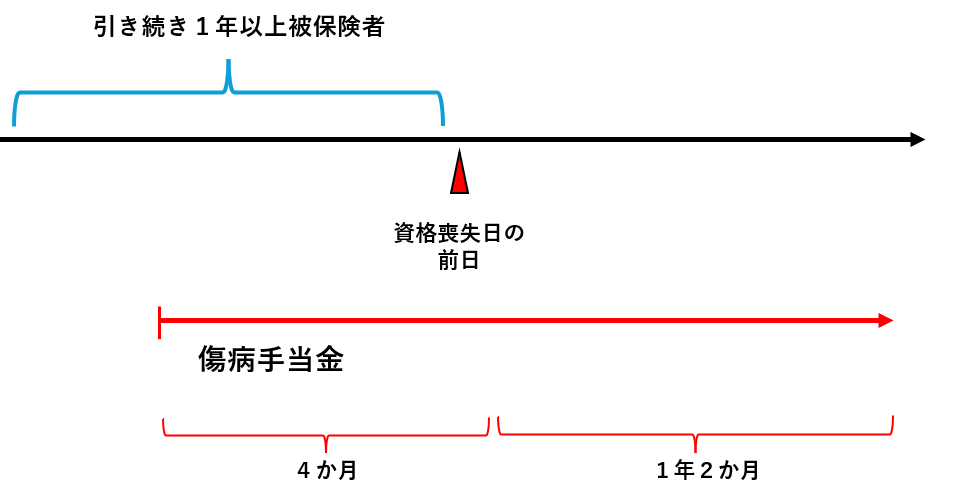
健康保険法「保険医」
R7-331 07.25
保険医・保険薬剤師の登録
保険医療機関・保険薬局は厚生労働大臣の「指定」を受けますが、保険医・保険薬剤師は、厚生労働大臣の「登録」を受けます。
条文を読んでみましょう。
法第64条 (保険医又は保険薬剤師) 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。
法第71条 ① 保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 ② 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる。 (1) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。 ((2)~(4)省略) ③ 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき
・保険医療機関、保険薬局の指定を取り消そうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしないこととするとき
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録をしないこととするとき
②【H29年出題】
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、健康保険法第63条第3項第1号の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

【解答】
②【H29年出題】 〇
個人の診療所、個人の薬局についての保険医療機関又は保険薬局のみなし指定の規定です。
問題文のように保険医の登録をした個人開業医の診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされますので、指定の手続きは必要ありません。
条文を読んでみましょう。
法第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。 |
③【H19年出題】
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から10年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
申請者が、保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき等は、厚生労働大臣は、登録をしないことができる、とされています。10年ではありません。
④【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】
④【H29年出題】 ×
保険医療機関又は保険薬局は、「1月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、「1月以上」の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる、とされています。
(法第79条)
⑤【R6年出題】
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
保険医等の登録には、有効期間はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険医療機関」
R7-330 07.24
保険医療機関・保険薬局の指定
厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所又は薬局を「保険医療機関」又は「保険薬局」といいます。
保険医療機関、保険薬局では、すべての人が必要な診療等を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
法第65条 (保険医療機関又は保険薬局の指定) ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 ② その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。 ③ 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができる。 (1) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。 (2) 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。 (以下(3)~ (6)省略) ④ 厚生労働大臣は、病院又は病床を有する診療所について申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、指定を行うことができる。 (1) 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、医療法に規定する厚生労働省令で定める員数及び厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。 (以下(2)~(4)省略) |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき
・保険医療機関、保険薬局の指定を取り消そうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしないこととするとき
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき
・保険医、保険薬剤師の登録をしないこととするとき
②【R6年出題】
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

【解答】
②【R6年出題】 〇
・ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。
・ 申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるとされています。
・ 厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければなりません。
③【R1年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる、とされています。
(法第65条第3項第3号)
④【R2年選択式】
健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、< A >するものとされている。

【解答】
④【R2年選択式】
<A> 地方社会保険医療協議会に諮問する
⑤【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年です。
(法第69条第1項)
⑥【H28年出題】
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
法第68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 ② 保険医療機関(病院又は病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなす。 |
指定の有効期間は6年ですので、指定の更新が必要です。
ただし、保険医個人が開設する診療所は、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申請があったものとみなされます。この規定は、「病院又は病床を有する診療所」には、適用されないのがポイントです。
⑦【R6年出題】
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

【解答】
⑦【R6年出題】 ×
「病院及び病床を有する診療所」には適用されません。
⑧【H22年出題】
保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。

【解答】
⑧【H22年出題】 ×
保険医療機関または保険薬局は、「3か月以上」ではなく「1か月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができるとされています。
なお、「登録の抹消」は、「保険医又は保険薬剤師」に対応する用語です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「傷病手当金」
R7-323 07.17
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第99条第4項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。 |
|
|
| 支 給 |
|
|
| 支 給 |
| 支 給 |
待期 | 欠 勤 | 出 勤 | 欠 勤 | 出 | 欠 勤 | ||||
| ▲支給開始 |
|
|
|
| ||||
| ↓ |
| ↓ |
| ↓ | ||||
通算して1年6か月
過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】 ※改正による修正あり
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。
<選択肢>
①4月1日から ②4月3日から ③4月4日から ④4月5日から
⑤日 ⑥日の2日後 ⑦日の3日後 ⑧日の翌日

【解答】
①【R1年選択式】
<A> ④4月5日から
<B> ⑤日
②【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

【解答】
②【H26年出題】 ×
傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6か月間」です。
問題文の場合は、傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から通算して1年6か月間です。
③【R5年出題】
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。

【解答】
③【R5年出題】 ×
健康保険の被保険者資格は、死亡したときはその翌日に喪失します。
死亡した日は被保険者の資格は有効ですので、傷病手当金は当該被保険者の死亡日の当日分まで支給されます。
④【R4年出題】
傷病手当金の支給を受けている間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。

【解答】
④【R4年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
則第84条の2第7項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第99条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。 |
後の傷病に係る待期期間の経過した日を「後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日」として額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額が支給されます。
この場合、後の傷病に係る傷病手当金の「支給を始める日」が確定するため、前の傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病手当金について再度額を算定する必要はありません。
(H27.12.18事務連絡)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険給付の制限など」
R7-314 07.08
少年院に収容された場合等の給付制限と保険料免除
被保険者又は被保険者であった者が、少年院に収容されたときや刑事施設に拘禁されている場合は、公費で療養等が行われるので、健康保険の保険給付は行われません。また、保険給付が行われないため、保険料が免除されます。
条文を読んでみましょう。
第118条 ① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 (1) 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 (2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 ② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 |
ポイント!
・給付制限の対象になるのは、「疾病、負傷、出産」です。
「死亡」については給付制限の対象ではありません。死亡の場合は、埋葬料(埋葬費)が支給されます。
少年院に収容された場合などは、保険給付が制限されますので、保険料も徴収されません。
条文を読んでみましょう。
法第158条 (保険料の徴収の特例) 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。 ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。(→該当するに至ったときと該当しなくなったときが同じ月にある場合は、保険料が徴収されます) |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されていても、被扶養者に係る保険給付は行われます。
②【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
被扶養者に係る保険給付は行われます。
③【H27年出題】
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、保険料が徴収されないのは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間です。
④【H29年出題】
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
刑事施設に拘禁されていても、「任意継続被保険者」には保険料免除の規定は適用されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「他の法令との調整」
R7-311 07.05
他の法令による保険給付と健康保険の保険給付の調整
他の法令による保険給付を受けることができる場合の健康保険の調整規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第55条 (他の法令による保険給付との調整) ① 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 ③ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 ④ 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
健康保険では、「労働者災害補償保険法に規定する業務災害」以外の疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行います。
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、健康保険の給付が行われます。
(H25.8.14事務連絡)
②【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「被保険者に係る療養の給付等は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。」となります。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法に基づく給付を受けることができる場合は、健康保険の埋葬料は支給されません。
③【H29年出題】
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われません。
④【H22年出題】
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

【解答】
④【H22年出題】 ×
「同一の疾病、負傷または死亡について」の部分が誤りです。「同一の疾病又は負傷について」となります。
介護保険法には、「死亡」に関する給付がありません。
「死亡」については、介護保険の給付と調整されませんので、健康保険の給付が行われます。
⑤【R5年出題】
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
「被保険者に係る療養の給付等は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。」となります。
⑥【H30年出題】
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
災害救助法の目的は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」です。
同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において健康保険の保険給付は行われません。
⑦【H16年出題】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

【解答】
⑦【H16年出題】 〇
健康保険による保険給付は、生活保護法による医療扶助に優先して行われます。
健康保険による保険給付が及ばない部分が、生活保護法による医療扶助の対象となります。
(生活保護法第4条第2項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「一時帰休」
R7-303 06.27
資格取得時、定時決定、随時改定の際の休業手当の扱い
「一時帰休」の際に支払われる休業手当等の扱いを過去問でみていきましょう。
さっそく過去問です!
①【R4年出題】
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

【解答】
①【R4年出題】 〇
ポイント!
■新たに使用されることとなった者が、当初から自宅待機とされた場合
→ 雇用契約が成立しており、かつ、休業手当等が支払われるときは、その休業手当等の支払の対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する
■自宅待機に係る者の被保険者資格取得時における標準報酬の決定について
→ 現に支払われる休業手当等に基づき報酬月額を算定し、標準報酬を決定する
→ 休業手当等をもつて標準報酬を決定した後に自宅待機の状況が解消したときは、随時改定の対象とする
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
②【R1年出題】
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
②【R1年出題】 〇
ポイント!
■定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休が解消しているかどうかは、「7月1日」で判断する
■7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う
→ 例えば、4月及び5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う
(令5.6.27事務連絡)
③【R6年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

【解答】
③【R6年出題】 〇
ポイント!
■標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合
→ その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。
→ 例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定する
■標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合
→ 定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する
→ 「9月以降において受けるべき報酬」とは?
→ 7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出する。
→ 例えば4・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行う
(令5.6.27事務連絡)
④【R3年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
④【R3年出題】 〇
ポイント!
■一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合
→ これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とする
→ ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限る
■休業手当等をもつて標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したとき → 随時改定の対象とする
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「日雇特例被保険者」
R7-302 06.26
健康保険の日雇特例被保険者の保険料納付要件
日雇特例被保険者が、療養の給付を受ける際の流れをおさえましょう。
・日雇特例被保険者は、厚生労働大臣から「日雇特例被保険者手帳」の交付を受ける
↓
・療養の給付を受けるとき
所定の保険料が納付されていることを日雇特例被保険者手帳によって証明して申請する
↓
・保険者は、これを確認したことを表示した「受給資格者票」を発行し、又は既に発行した「受給資格者票」にこれを確認したことを表示する
↓
・日雇特例被保険者は、「受給資格者票」を保険医療機関等に提出して療養の給付を受ける
日雇特例被保険者の「療養の給付」の受給要件を条文で読んでみましょう。
法第129条 (療養の給付) ① 日雇特例被保険者の疾病又は負傷に関しては、療養の給付を行う。 ② 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号のいずれかに該当していなければならない。ただし、第2号に該当する場合においては、第1号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病又は負傷及びこれにより発した疾病以外の疾病又は負傷については、療養の給付を行わない。 (1) 当該日の属する月の前2月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。 (2) 前号に該当することにより当該疾病又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日から1年(結核性疾病に関しては、5年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く。)。 ③ 保険者は、日雇特例被保険者が、①第1号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。 ④ 日雇特例被保険者が療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を保険医療機関等のうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。 |
ポイント!
「前2月間」、「前6月間」は暦月で計算します。
(例)6月26日に療養の給付を受けようとする場合
4月 | 5月 | 6月 |
通算して26日分以上納付 |
| |
又は
12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
通算して78日分以上納付 |
| |||||
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための保険料納付要件
・療養の給付を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上
又は
・療養の給付を受ける日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上
の保険料が納付されていること
日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、原則として、上記の保険料納付要件を満たさなければなりません。
②【H30年出題】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「日雇特例被保険者が出産」した場合の保険料納付要件に注意しましょう。
・出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることが要件です。
「出産育児一時金」、「出産手当金」に適用されます。
(法第137条、第138条)
③【R5年出題】
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

【解答】
③【R5年出題】 〇
日雇特例被保険者本人が出産した場合の保険料納付要件は、「出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料」が納付されていることです。
また、日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときの保険料納付要件は、原則通りです。出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることが要件です。
(法第144条)
④【H26年出題】
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)である。

【解答】
④【H26年出題】 〇
日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後、療養の給付を受けるために、原則2か月ほど必要です。
そのため、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者等に対しては、「特別療養費」が支給されます。
特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)です。
例えば、6月26日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は8月31日までです。
7月1日に日雇特例被保険者手帳を受けた場合は、特別療養費の支給期間は8月31日までです。
(法第145条)
⑤【R1年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「全国健康保険協会」ではなく、「厚生労働大臣」が行います。
条文を読んでみましょう。
第123条 ① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とする。 ② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「時効」
R7-293 06.17
健康保険の時効と起算日
健康保険の時効について条文を読んでみましょう。
法第193条 (時効) ① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |
健康保険の時効は「2年」です。
また、「時効」が適用されないもの、「時効の起算日」にも注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「現物給付」については、時効は適用されません。
②【H30年出題】
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。

【解答】
②【H30年出題】 ×
療養費の時効の起算日は、「療養に要した費用を支払った日の翌日」です。
問題文の場合は、「コルセットを装着した日の翌日」ではなく、「コルセットの代金を支払った日の翌日」から起算します。
コルセットを装着しただけで費用を支払っていない場合は、「療養費請求の権利を行使し得ない」からです。
(昭和31.3.13保文発第1903号)
③【H28年出題】※改正による修正あり
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

【解答】
③【H28年出題】 ×
高額療養費の時効の起算日が誤りです。
<消滅時効の起算日について>
・療養費 → 療養に要した費用を支払った日の翌日
・高額療養費 → 診療月の翌月1日
※診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日
・高額介護合算療養費 → 計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日
(昭和48.11.7庁保険発第21号、保険発第99号、平成21.4.30保保発第430001号)
④【R5年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】
④【R5年出題】 ×
傷病手当金を受ける権利の時効の起算日は労務不能であった日ごとにその「当日」ではなく「労務不能であった日ごとにその「翌日」」です。
(昭和30.9.7保険発第199-2号)
⑤【R1年出題】
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
出産手当金を受ける権利は、「出産した日の翌日」からではなく、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算します。傷病手当金の時効の起算日と同じ考え方です。
なお、「出産育児一時金」の時効については、「出産した日の翌日」から起算します。
(昭和30.9.7保険発第199-2号)
⑥【H26年出題】
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

【解答】
⑥【H26年出題】 〇
埋葬料と埋葬費の起算日の違いに注意しましょう。
埋葬料 → 実際に埋葬を行ったかどうかは関係ないため、時効の起算日は保険事故発生の日(死亡した日)の翌日
埋葬費 → 埋葬を行った事実に対して支払われるので、時効の起算日は保険事故発生日(埋葬した日)の翌日
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「入院時食事療養費」
R7-292 06.16
入院時食事療養費についてお話しします
入院時食事療養費は、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、支給されます。
<入院時食事療養費の額>
「食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から「食事療養標準負担額」を控除した額です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「介護保険料率」
R7-290 06.14
「介護保険料率」の定め方
健康保険の被保険者の保険料額は以下の通りです。
① 介護保険第2号被保険者である被保険者
→ 一般保険料額と介護保険料額との合算額
② 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者
→ 一般保険料額
★一般保険料額とは?
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額
★介護保険料額とは?
標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額
今回は、「介護保険料率」の定め方をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第160条第16条 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 |
★介護保険料率について
介護納付金の額 ÷ 介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)の総報酬額総額の見込
で計算します。
★介護納付金とは
健康保険の保険者は、介護保険第2号被保険者から介護保険料を徴収し、「介護納付金」として社会保険診療報酬支払基金に納付します。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】※改正による修正あり
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
介護保険料率は、「介護納付金の額」÷「介護保険第2号被保険者の総報酬額総額の見込」で計算します。
②【R4年出題】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

【解答】
②【R4年出題】 ×
「全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を「当該年度」における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の「総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。」となります。
ちなみに「総報酬額」とは、標準報酬月額と標準賞与額を合算した額です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「訪問看護療養費」
R7-282 06.06
訪問看護療養費のポイント
訪問看護療養費は、居宅で療養している人が対象です。
主治医の指示により、訪問看護ステーションの看護師等から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に支給されます。
条文を読んでみましょう。
法第88条(訪問看護療養費) ① 被保険者が、指定訪問看護事業者から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 ② 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 ③ 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。 ④ 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、一部負担金に相当する額を控除した額とする。 ⑤ 厚生労働大臣は、④の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】※改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

①【H28年選択式】
【解答】
<A> 保険者
<B> 自己
②【H25年出題】
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるもの」は訪問看護療養費の対象から除かれています。
「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、「療養の給付」の対象となります。
③【H24年出題】
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

【解答】
③【H24年出題】 ×
訪問看護を行うものに、「医師、歯科医師」は入りません。
(則第68条)
④【R5年出題】
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたものである。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。

【解答】
④【R5年出題】 〇
・訪問看護療養費は、保険者が必要と認める場合に限り支給する
・指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたもの
・看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
(則第67条、第68条)
⑤【R1年出題】
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
保険者は、被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用を、被保険者に代わり、指定訪問看護事業者に支払うことができます。
これによって、訪問看護療養費は、現物給付となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「適用事業所」
R7-269 05.24
健康保険の強制適用事業所と任意適用事業所
健康保険は、個人ごとではなく事業所ごとに適用されます。健康保険に加入している事業所のことを適用事業所といいます。
法律上強制的に加入する事業所を「強制適用事業所」、任意に認可を受けて加入した事業所のことを「任意適用事業所」といいます。
条文を読んでみましょう。
法第3条第3項 「強制適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 (1) 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人経営) イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 ハ 鉱物の採掘又は採取の事業 ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 ホ 貨物又は旅客の運送の事業 ヘ 貨物積卸しの事業 ト 焼却、清掃又はと殺の事業 チ 物の販売又は配給の事業 リ 金融又は保険の事業 ヌ 物の保管又は賃貸の事業 ル 媒介周旋の事業 ヲ 集金、案内又は広告の事業 ワ 教育、研究又は調査の事業 カ 疾病の治療、助産その他医療の事業 ヨ 通信又は報道の事業 タ 社会福祉法に定める更生保護事業 レ 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 (2) 国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの(=常時従業員が1人でもいれば強制適用事業) |
<強制適用事業所になるもの>
| 17業種 | サービス業・農業・漁業等 | |
| 5人以上 | 5人未満 |
|
個人経営 | 強制 | (任意) | (任意) |
法 人 | 1人でもいれば強制 | ||
次に、任意適用事業所について条文を読んでみましょう
法第31条 ① 強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 ② 認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
法第33条 ① 任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 ② 脱退の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 |
擬制的任意適用事業について条文を読んでみましょう
法第32条 強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、その事業所について任意加入の認可があったものとみなす。(=擬制的任意適用事業) |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
法人の事業所は、常時1人でも従業員を使用する場合は強制適用事業所となります。
また、法人の代表者でも、法人から「労務の対償」として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
そのため、代表者が1人の法人の事業所でも、強制適用事業所となります。
②【H23年出題】
常時10人以上の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人以上の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。

【解答】
②【H23年出題】 〇
飲食業は法定17業種以外の業種ですので、個人経営の場合は、人数に関係なく強制適用事業所となりません。
また、法人の場合は、常時1人でも従業員を使用していれば、業種関係なく、強制適用事業所となります。
③【R5年出題】
令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
外国法事務弁護士は対象となります。
なお、対象になるのは、弁護士、公認会計士その他政令で定める者ですが、政令で定めるものは以下の通りです。
・ 公証人
・ 司法書士
・ 土地家屋調査士
・ 行政書士
・ 海事代理士
・ 税理士
・ 社会保険労務士
・ 沖縄弁護士
・ 外国法事務弁護士
(令第1条)
④【R2年出題】
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

【解答】
④【R2年出題】 ×
任意適用事業所で被保険者の4分の3以上の申出があった場合でも、事業主は適用事業所でなくするための認可の申請をする義務はありません。
⑤【R5年出題】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
強制適用事業所が、強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、「任意加入の認可があったものとみなす」とされていますので、事業主は認可の申請をする必要はありません。自動的に健康保険の適用が継続されます。
YouTubeはこちらです
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「任意継続被保険者」
R7-237 04.22
任意継続被保険者の保険料の前納
任意継続被保険者は、保険料を、その月の10日までに納付しなければなりません。
なお、初めて納付すべき保険料は、保険者が指定する日までに納付しなければなりません。
例えば、4月27日に退職したとすると、4月28日に被保険者資格を喪失します。
任意継続被保険者となった場合は、4月28日に任意継続被保険者の資格を取得します。任意継続被保険者としての保険料は、4月分から徴収されます。
任意継続被保険者の保険料は前納することができます。
条文を読んでみましょう。
第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) ① 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 ④ 保険料の前納の手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
<保険料の納付期日>
・一般の被保険者の保険料は、翌月末日
・任意継続被保険者の保険料は、その月の10日(ただし、初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定する日」まで)
「任意継続被保険者の資格取得の申出をした日」は誤りです。
(法第164条第1項)
②【R2年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

【解答】
②【R2年出題】 ×
前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額となります。
③【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

【解答】
③【H26年出題】 〇
★任意継続被保険者の保険料の前納期間の単位について
(原則)
4月から9月までの6か月間 10月から翌年3月までの6か月間 |
4月から翌年3月までの12か月間 |
当該6か月又は12か月の間に、 「任意継続被保険者の資格を取得した者」 | その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間について前納できる |
当該6か月又は12か月の間に、 「その資格を喪失することが明らかである者」 | その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間について前納できる |
(令第48条)
④【H30年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間のみを単位として行わなければならない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
「4月から翌年3月までの12か月間」の単位もあります。
また、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者についての例外もあります。
③の問題をご覧ください。
⑤【R5年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
なお、国民年金の保険料の前納との違いに注意しましょう。
国民年金は、「前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。」となります。(国民年金法第93条)
⑥【H22年選択式】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納をおこなうことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
<A> 各月の初日
<B> 初月の前月末日
<C> 年4分の利率
<D> 5月
★<D>について
6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。
問題文は、4月に資格を取得していますので、5月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。
(則第139条、令第48条、令第49条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「資格喪失後の出産」
R7-234 04.19
資格喪失後の「出産育児一時金」の条件
退職後(被保険者の資格喪失後)に、出産した場合、要件を満たせば、最後の保険者から出産育児一時金を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付) 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 ※1年以上被保険者であった者 → 「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者
※支給額 → 1児につき48万8千円(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合は50万円) |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することとなる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合についての問題です。
「被保険者本人としての出産育児一時金」、「被扶養者としての家族出産育児一時金」の受給資格ができますが、どちらを受給するかは請求者の選択によります。
(昭48.11.7保険発99・庁保険発21)
②【R2年出題】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
要件を満たしたもの者が資格喪失後6か月以内に出産した場合、資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が対象者に対して出産育児一時金の支給を行います。
そのため、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができます。
(平23.6.3保保発0603第2号)
③【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
その者が健康保険法の規定に基づく資格喪失後の出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができます。②の問題と同じです。
④【H30年出題】
被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第107条 (船員保険の被保険者となった場合) 前3条の規定(「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」)にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。 |
資格喪失後の出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合は、船員保険法から支給を受けることができますので、健康保険法の出産育児一時金は支給されません。「いずれかを選択して受給することができる」は誤りです。
⑤【H26年出題】
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」及び「資格喪失後の出産育児一時金の給付」は行われません。船員保険から支給を受けることができるからです。
⑥【R6年選択式】
任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金を受けることができるのは、< A >であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
<選択肢>
① 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
② 資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
③ 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を含む。)
④ 資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)

【解答】
<A> ① 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
図でイメージしましょう。
退職 | ・資格喪失 = ・任継取得 | ~ | 任継喪失 |
引き続き1年以上被保険者 | 任意継続被保険者 | ||
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「療養費」
R7-232 04.17
【健保】療養費(現金給付)が支給されるとき
健康保険は、『現物給付』が原則です。
しかし、現物給付を行うことが困難であると認めるときなどは、その費用について、現金で「療養費」が支給されます。
「療養費」が支給される要件などをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第87条第1項、第2項 (療養費) ① 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 ② 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 |
「療養費」が支給されるのは以下の2つの場合です。
① 「療養の給付等」を行うことが困難であると保険者が認めるとき
② 被保険者が保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合で、保険者がやむを得ないものと認めるとき
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【解答】
①【R3年出題】 〇
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を「基準として、保険者が定める。」の部分がポイントです。
②【R1年出題】
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
療養費が支給されるのは、「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき」、又は「被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき」です。
「訪問看護療養費の支給を行うことが困難」であるのは、どちらにも該当しませんので、療養費は支給されません。
③【H27年出題】
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。

【解答】
③【H27年出題】 〇
無医村で応急措置として緊急に売薬を服用した場合は、「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当しますので、療養費の支給を受けることができます。
(昭13.8.20社庶1629)
④【R5年出題】
現に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
「その地方に保険医がいない場合又は保険医はいても、その者が傷病等のために、診療に従事することができない場合」等には、療養費の支給が認められます。
・緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた時には、療養費は支給されません。
・現に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められません。
(昭24.6.6保文発1017号)
⑤【R5年出題】
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
★海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について
・療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
・療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
・現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこととされています。
・現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこととされています。
・ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いることとされています。
(昭56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
⑥【H27年出題】
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。

【解答】
⑥【H27年出題】 ×
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされています。
その支給は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて換算されます。その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこととされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「産前産後・育児休業等」
R7-231 04.16
【健保】出産・育児に関する総合問題を解いてみましょう
産前産後、育児休業等について、以下の内容をみていきます。
・産前産後休業期間中の保険料免除
・出産手当金の支給期間
・育児休業期間中の保険料免除
・育児休業等終了時改定の申出
・育児休業等終了時改定の有効期間
さっそく過去問をどうぞ!
【H27年出題】
被保険者が多胎妊娠し(出産予定日は6月12日)、3月7日から産前休業に入り、6月15日に正常分娩で双子を出産した。産後休業を終了した後は引き続き育児休業を取得し、子が1歳に達した日をもって育児休業を終了し、その翌日から職場復帰した。産前産後休業期間及び育児休業期間に基づく報酬及び賞与は一切支払われておらず、職場復帰後の労働条件等は次のとおりであった。なお、職場復帰後の3か月間は所定労働日における欠勤はなく、育児休業を終了した日の翌日に新たな産前休業に入っていないものとする。この被保険者に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。
【職場復帰後の労働条件等】
始業時刻 10:00
終業時刻 17:00
休憩時間 1時間
所定の休日 毎週土曜日及び日曜日
給与の支払形態 日額12,000円の日給制
給与の締切日 毎月20日
給与の支払日 毎月末日
(ア) 事業主は出産した年の3月から8月までの期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(イ) 出産手当金の支給期間は、出産した年の5月2日から同年8月10日までである。
(ウ) 事業主は産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間の終了月の翌月から、子が1歳に達した日の翌日が属する月の前月までの期間について、育児休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができる。
(エ) 出産した年の翌年の6月末日に支払われた給与の支払基礎日数が17日未満であるため、同年7月末日及び8月末日に受けた給与の総額を2で除した額に基づく標準報酬月額が、従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができる。
(オ) 職場復帰後に育児休業等終了時改定に該当した場合は、改定後の標準報酬月額がその翌年の8月までの各月の標準報酬月額となる。なお、標準報酬月額の随時改定には該当しないものとする。
A(アとイ) B(アとオ) C(イとウ) D(ウとエ) E(エとオ)

【解答】
A(アとイ)

(ア) ×
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
問題文の場合、産前産後休業の開始が3月7日、終了が8月10日です。
事業主は出産した年の3月から「7月まで」の期間について、産前産後休業期間中における健康保険料の免除を申し出ることができます。

(イ) ×
条文を読んでみましょう。
第102条第1条(出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
問題文を条文に当てはめると、出産の日が出産の予定日より後で、多胎妊娠ですので、出産手当金が支給されるのは、出産予定日(6月12日)以前98日(=3月7日)から出産の日後56日(=8月10日)までの間において労務に服さなかった期間です。

(ウ) 〇
条文を読んでみましょう。
第159条 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業中の保険料免除を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
問題文の場合、産前産後休業期間中における健康保険料の免除期間は、「3月~7月」です。
育児休業期間中の保険料が免除される期間は、
・育児休業等を開始した日の属する月(=産前産後休業期間中の保険料免除期間の終了月の翌月=8月)
から
・育児休業等が終了する日の翌日(1歳に達した日の翌日=6月15日)が属する月の前月(=5月)
までとなります。

(エ) 〇
条文を読んでみましょう。
第43条の2第1項 保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業等を終了した被保険者が、育児休業等終了日において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 |
<随時改定と比較しましょう>
随時改定 | 育児休業等を終了した際の改定 |
固定的賃金に変動があった | 固定的賃金に変動がなくても対象になる |
2等級以上の差が生じた | 1等級以上の差が生じた |
3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上) | 報酬払基礎日数が17日未満の月は除く (短時間労働者は11日未満) |
問題文のポイントです。
6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
育児休業等終了日の翌日 |
|
|
|
算入しない | (7月+8月)÷2 |
| |
従前の標準報酬月額と比べて1等級以上の差がある場合には育児休業等終了時改定を申し出ることができます。

(オ) 〇
条文を読んでみましょう。
第43条の2第2項 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ~ | 翌年8月 |
育児休業等終了日の翌日 |
|
|
|
|
|
算入しない | (7月+8月)÷2 | 改定 |
|
| |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「家族療養費など」
R7-225 04.10
被扶養者に関する健康保険の給付
「被扶養者」に関する給付として以下の給付があります。
・家族療養費 (療養の給付、療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費に当たります) ・家族訪問看護療養費 ・家族移送費 ・家族埋葬料 ・家族出産育児一時金 |
「家族療養費」の給付割合について
①6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である被扶養者 | 100分の70 |
②6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被扶養者 | 100分の80 |
③70歳に達する日の属する月の翌月以後である被扶養者 (④を除く) | 100分の80 |
④70歳以上の現役並所得者である被保険者の70歳以上の被扶養者 | 100分の70 |
ポイント!
被扶養者に関する給付は、「被保険者に」支給されることがポイントです。
例えば、法第110条第1項では、
「被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。」と規定されています。
「被扶養者に対し、家族療養費を支給する」という問題は誤りです。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
被保険者に対して「入院時生活療養費」ではなく、「家族療養費」が支給されます。
(法第110条第1項)
②【H30年出題】
被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額である。

【解答】
②【H30年出題】 ×
被扶養者が6歳の年度末以前の場合、家族療養費の給付割合は、「100分の80」です。
(法第110条第2項)
③【H29年出題】
68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

【解答】
③【H29年出題】 ×
★被扶養者が70歳以上の場合の家族療養費の給付割合
・100分の80
・ただし、被保険者が70歳以上で現役並所得者の場合(=一部負担金の割合が100分の30)は、70歳以上の被扶養者の家族療養費の割合も100分の70になります。
問題文の場合は、被保険者が70歳未満ですので、被保険者の収入の額に関係なく、70歳以上の家族療養費の給付割合は80%です。
(法第110条第2項)
④【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
第114条で、「被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する。」と規定されています。
「被扶養者」が出産した場合に支給されますので、被扶養者である配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合にも支給されます。
(法第114条)
⑤【H29年出題】
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、「被扶養者」でなく、「被保険者」に対しその指定訪問看護に要した費用について、「訪問看護療養費」ではなく「家族訪問看護療養費」を支給する、となります。
(法第111条)
⑥【H30年出題】
被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
「家族療養費」は、「被保険者」に対して支給されます。
そのため、被保険者が死亡し被保険者の資格を喪失すると、家族療養費は支給されません。
(法第110条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「不正利得の徴収」
R7-220 04.05
<健保>偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた場合
詐欺など不正行為で保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者から不正行為によって受けた分のすべてを徴収することできます。
条文を読んでみましょう。
第58条 (不正利得の徴収等) ① 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。 ② ①の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 ③ 保険者は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用等の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。 |
②について
事業主、保険医、主治の医師が不正行為に絡んでいる場合は、保険者は保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
③について
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者が不正の行為で診療報酬の支払いを受けたときは、その額につき返還させるほか、返還させる額の100分の40を支払わせることができます。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、その場合の「全部又は一部」とは、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることが考えられるので、全部又は一部とされたものであって、偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨である。

【解答】
①【H25年出題】 〇
偽りその他不正行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
★「全部又は一部」の意味について
↓
偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることがあるため
↓
偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという意味です。
(昭32.9.2保険発123)
②【R6年出題】
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である。

【解答】
②【R6年出題】 ×
全部又は一部という意味は、偽りその他不正行為によって受けた分が保険給付の一部であることがあるためです。偽りその他不正行為によって受けた分はすべて徴収することができるという趣旨です。
①の問題と同じです。
③【H29年出題】
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。

【解答】
③【H29年出題】 ×
事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、事業主に対しても保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができます。
④【R3年出題】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪問看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

【解答】
④【R3年出題】 〇
指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができます。
⑤【H26年出題】
保険者は、指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって訪問看護療養費の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額についてのみ返還させることができ、その返還額に一定割合を乗じて得た額を支払わせることはできない。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
その支払った額について返還させるほか、その返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「一部負担金」
R7-211 03.27
療養の給付を受ける場合の一部負担金
療養の給付を受ける場合は一部負担金を支払わなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第74条第1項 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に、当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 (1) 70歳に達する日の属する月以前である場合→ 100分の30 (2) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) → 100分の20 (3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき(現役並み所得者) → 100分の30
令第34条第1項 (一部負担金の割合が100分の30となる場合) 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。 |
(70歳未満の場合)
療養に要する費用の額(100万円) | |||||
一部負担金
|
療養の給付 | ||||
30万円 |
|
|
|
|
|
では、過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の< A >以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
<選択肢>
① 前月の標準報酬月額が28万円
② 前月の標準報酬月額が34万円
③ 標準報酬月額が28万円
④ 標準報酬月額が34万円

【解答】
<A> ③ 標準報酬月額が28万円
②【H27年選択式】
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< A >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< B >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
<選択肢>
① 70歳に達する日 ② 70歳に達する日の属する月
③ 70歳に達する日の属する月の翌月 ④ 70歳に達する日の翌日
⑤ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑥ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑧ 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

【解答】
<A> ③ 70歳に達する日の属する月の翌月
<B> ⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
<B>について条文を読んでみましょう。
令第34条 (一部負担金の割合が100分の30となる場合) ① 法第74条第1項第3号の政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬月額とし、同号の政令で定める額は28万円とする。 ② 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 (1) 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者 (2) 被保険者(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当するものをいう。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が 520万円に満たない者 |
★なお、令第34条第2項の規定の適用を受けようとする場合は、申請が必要です。
被保険者が70歳以上の場合
■療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上(現役並み所得者)の場合は、一部負担金の割合は「100分の30」です。
ただし、以下の場合は、申請によって「100分の20」となります。
(1)
・ 被保険者と70歳以上の被扶養者を合算した収入が520万円未満
・ 70歳以上の被扶養者がいない場合は、被保険者のみの収入が383万円未満
(2)
・ 被扶養者が後期高齢者医療の被保険者になったため被扶養者でなくなり、70歳以上の被扶養者がいなくなった場合は、その被扶養者であった者の収入を合算して520万円未満
★問題文について
標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者は、一部負担金の割合は3割です。
ただし、「被保険者のみの収入の額が383万円未満」の場合は、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となります。
なお、収入を合算できるのは70歳以上の被扶養者のみです。問題では、被扶養者が67歳の妻のみですので、被扶養者の収入は合算できません。
③【H24年出題】
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。

【解答】
③【H24年出題】 〇
70歳以上・標準報酬月額28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、一部負担金は申請により2割負担となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「労災との調整」
R7-210 03.26
健康保険と労災保険の保険給付の調整
健康保険と労災保険との調整について条文を読んでみましょう。
法第55条第1項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
例えば、労災保険で通勤災害の保険給付を受けることができる場合は、健康保険の保険給付は行われません。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
通勤災害については労災保険からの給付が優先されます。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法の給付が行われる場合は、健康保険の埋葬料は支給されません。
②【H26年出題】
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。

【解答】
②【H26年出題】 ×
「労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害については、それが、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険で給付する」とされています。
ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われません。
(昭48.12.1保険発105・庁保発24)
③【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】
③【H28年出題】 〇
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が行われます。
(H25.8.14事務連絡)
④【R4年出題】
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。

【解答】
④【R4年出題】 ×
「健康保険は、業務外の疾病や負傷等に対して保険給付を行い、労災保険は、業務上の疾病や負傷等に対し保険給付を行います。その条件に当てはまるかどうかは、それぞれの保険者が自らの判断により行うものであるため、労災保険の認定が確定していないことを理由に、健康保険の保険給付の申請を受理しないことは認められないことになります。」
「労災保険給付の請求が行われている場合であっても、健康保険の被保険者は、健康保険の保険者に保険給付の申請を行うことが可能です。」
とされていますので、問題文の場合は、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合でも、健康保険の保険給付の申請は可能です。
(平成24.6.20事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「被扶養者」
R7-209 03.25
健康保険の被扶養者の範囲と要件
健康保険法の「被扶養者」となる範囲と要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の3親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
ポイント!
被扶養者の要件を整理しましょう。
① | ・直系尊属 ・配偶者(事実婚を含む。) ・子 ・孫 ・兄弟姉妹 | 主として被保険者により生計を維持するもの (別居でも可) |
② | ・3親等内の親族(①以外) ・事実婚の配偶者の父母及び子 ・事実婚の配偶者の死亡後の父母及び子 | 被保険者と同一の世帯に属している + 主として被保険者により生計を維持するもの |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】 ※改正による修正あり
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。なお、当該63歳の母は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「被保険者の配偶者の母」が被扶養者となるには、「被保険者と同一世帯」+「生計維持」の要件を満たさなければなりません。
「被保険者と別居」している場合は、被扶養者になりません。
②【R1年出題】 ※改正による修正あり
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。なお、認定対象者は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
②【R1年出題】 〇
「被扶養者としての届出に係る者が被保険者と同一世帯に属している」場合の認定基準を確認しましょう。
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する ② ①の条件に該当しない場合でも、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない (S52.4.6保発第9号・庁保発第9号) |
③【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず、その他の要件を満たす限り、被扶養者に該当する。なお、当該父は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
③【H26年出題】 ×
「認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合」の認定基準を確認しましょう。
| 認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する |
被保険者の父は、被保険者と同一世帯に属していなくても、要件を満たせば被扶養者に該当しますが、父の年収が被保険者からの援助による収入額より少ないことが条件です。
「その援助の額にかかわらず」は誤りです。
(S52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
④【H27年出題】 ※改正による修正あり
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年間100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合は、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、当該母は、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
④【H27年出題】 ×
58歳で障害者ではない母の年収が100万円の遺族厚生年金+パート労働による給与120万円=220万円ですので、母は被扶養者になることはできません。
⑤【R3年出題】
被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
被扶養者の収入の確認に当たり、「被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むもの」とされています。
(令2.4.10事務連絡)
⑥【R2年出題】
被保険者(外国に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

【解答】
⑥【R2年出題】 ×
被保険者の配偶者の父は、「生計維持」にプラスして「被保険者と同一世帯」に属していることが要件です。
問題文の場合、当該父は日本国外に居住し同一世帯にありませんので、被扶養者にはなりません。
⑦【H28年出題】※改正による修正あり
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。なお、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
⑦【H28年出題】 〇
後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「法人の役員である被保険者等の保険給付」
R7-206 03.22
法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例
法人の役員である被保険者については、その法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷、死亡に対しては、健康保険から保険給付は行われないのが原則です。
ただし例外もあります。
条文を読んでみましょう。
第53条の2 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
則第52条の2 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 |
ポイント!
法人の役員としての業務でも、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務で、従業員が従事する業務と同一であると認められる業務に起因する疾病、負傷、死亡については、保険給付が行われます。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
法人の理事、監事、取締役、代表社員等であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。
(昭24.7.28保発74号)
②【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
②【H30年出題】 〇
・被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者について
・業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合がある
・対象になる業務は、当該法人の従業員が従事する業務と同一であると認められるもの
③【R4年出題】
被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
「5人以上」ではなく「5人未満」です。
「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。」となります。
「傷病手当金」も支給されることがポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「随時改定」
R7-205 03.21
随時改定の3つの要件
「随時改定」とは、固定的賃金の変動があった場合に標準報酬月額を見直すことです。
随時改定に当てはまる要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上(短時間労働者の場合は11日以上)でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 随時改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
★随時改定は次の3つの要件を満たした場合に行われます。
① 昇給や降給などで、固定的賃金に変動があったこと。
② 固定的賃金が変動した月からの3か月間に支払われた報酬の平均月額とこれまでの標準報酬月額に2等級以上の差が生じたこと。
③ 継続した3か月の報酬支払基礎日数が各月とも17日以上(短時間労働者は11日以上)あること。
★著しく高低を生じた月の翌月から改定されます
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 固定的賃金の変動 |
| 著しく 高低を生じた月 | 標準報酬月額 改定 |
|
|
|
|
|
例えば、3月に昇給で固定的賃金が変動し、3月、4月、5月の報酬の平均月額と、これまでの標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合、「6月」から随時改定により、標準報酬月額が改定されます。
「著しく高低を生じた月の翌月」とは「固定的賃金の変動があった月から4か月目」です。
★定時決定との違いに注意しましょう。
「定時決定」→ 17日未満(短時間労働者は11日未満)の月がある場合は、その月を除いて平均を出します。
「随時改定」→ 継続した3か月間に17日未満(短時間労働者は11日未満)の月がある場合は行われません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
・特定適用事業所において被保険者である短時間労働者について
「定時決定」は、報酬支払基礎日数が11日未満の月があるときは、その月を除いて行う。「随時改定」は、継続した3か月間で、各月とも報酬支払基礎日数が11日以上でなければ行わない。
(法第41条第1項、第43条第1項)
②【H26年出題】
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「昇給及び降給が遡及したため、それに伴う差額支給によって報酬月額に変動が生じた場合」は、随時改定されるべき月以降において受けるべき報酬月額で算定されます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|
| 昇給差額 |
|
| 改 定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (5月+6月+7月の報酬-昇給差額)÷3 |
| ||
・3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた
↓
・随時改定の対象になるのは「5月、6月、7月の3か月間に受けた報酬の総額」÷3の額
ポイント!
「昇給差額」は除いて計算すること
差額が支払われた5月が起算月となること
↓
標準報酬月額が改定されるのは8月から
(法第43条、R5.6.27事務連絡)
③【R3年出題】
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。

【解答】
③【R3年出題】 〇
時給単価の変動はないが、契約時間が変わった場合は、固定的賃金の変動に該当します。
(R5.6.27事務連絡)
④【R4年出題】
被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

【解答】
④【R4年出題】 ×
減給制裁は固定的賃金の変動には当たりません。そのため、随時改定の対象になりません。
(R5.6.27事務連絡)
⑤【H28年出題】
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
「産休等により通勤手当が不支給となっている場合で、通勤の実績がないことにより不支給となっている場合には、手当自体が廃止された訳ではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象とはならない。」とされています。
(令3.4.1事務連絡)
⑥【H30年出題】
標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
随時改定の要件は、原則として2等級以上の差が生じることです。
ただし、49級→50級、1級→2級、50級→49級、2級→1級の場合、1等級の差でも随時改定が行われることがあります。
<49級→50級、50級→49級>
片方の月額が1,415,000円以上
もう片方の月額が1,295,000円以上1,355,000円未満(49級)
<1級→2級、2級→1級>
片方の月額が53,000円未満
もう片方の月額が63,000円以上73,000円未満(2級)
問題文は、標準報酬月額等級第49級にあったものが、昇給で1,415,000円になっていますので、1等級でも随時改定の対象になり、50等級に改定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「保険料の免除」
R7-204 03.20
育児休業等期間中・産前産後休業中の健康保険料が免除される期間
育児休業等の期間中、産前産後休業中は、健康保険料が免除されます。
★育児休業等とは、「育児休業及び育児休業に準じる休業」のことで、3歳に満たない子を養育するための休業です。
育児休業等期間の免除について条文を読んでみましょう。
第159条第1項 育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
ポイント!
■標準報酬月額に係る保険料の免除について
(1) 「育児休業等開始日」の属する月と「育児休業等終了日」の翌日が属する月が異なる場合
↓
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月
<例>
育児休業等開始日3月20日、育児休業等終了日が6月20日の場合
3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
3月~5月までの保険料が免除されます。
(2) 育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月とが同一の場合
↓
当該月における育児休業等の日数が14日以上(ただし、当該被保険者が出生時育児休業を取得する場合には、事業主が当該被保険者を就業させる日数を除く。)である場合は、当該月の保険料が免除されます。
<例>
3月4日に開始、同月25日に終了した場合
3月 | 4月 |
育児休業等開始日 育児休業等終了日の翌日 |
|
3月の育児休業等の日数が14日以上ですので、3月の保険料が免除されます。
■標準賞与額に係る保険料の免除について
「1か月を超える」育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。
<例1>
・3月5日~4月25日まで育児休業等を取得し、3月に賞与が支払われた場合
↓
1か月を超える育児休業等を取得しているので、賞与の保険料が免除されます。
<例2>
・3月14日~4月2日まで育児休業等を取得し、3月に賞与が支払われた場合
↓
1か月以内ですので、賞与の保険料は免除されません。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【R5年出題】- 〇
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和5年1月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月(令和5年3月)
令和5年1月から令和5年3月までの保険料が免除されます。
②【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「育児休業等開始日の属する月と育児休業等終了日の翌日が属する月」が同一で、育児休業等の期間が14日未満ですので、保険料は免除されません(保険料が徴収されます)。
③【R6年出題】
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
③【R6年出題】 ×
令和5年10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 |
育児休業等開始日の属する月 |
|
| 育児休業等終了日の翌日の属する月 |
(免除期間の始期)育児休業等開始日の属する月(令和5年10月)
(免除期間の終期)育児休業等終了日の翌日の属する月の前月(令和5年12月)
令和5年10月から12月までの保険料が免除され、令和6年1月分の保険料は免除されません(徴収されます)。
★産前産後休業期間中の免除の問題です
④【R5年出題】
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
問題文の場合、「産前産後休業を開始した日の属する月=令和4年12月」から、「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月=令和5年2月」までの保険料が免除されます。
⑤【R1年出題】
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象となる。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
産前産後休業は、多胎妊娠でない場合は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日から出産の日後56日までの間で、妊娠または出産を理由として労務に服さなかった期間です。
出産予定日が5月16日の場合は、産前休業は出産予定日以前42日の4月5日から開始されます。そのため、保険料免除の対象は4月分からとなります。
しかし、問題文のように出産予定日より前の5月10日に出産した場合、産前休業の開始日は、出産日以前42日の3月30日に変更されます。
被保険者は3月25日から出産のため休業していますので、3月分から免除対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「定時決定」
R7-203 03.19
標準報酬月額の定時決定
「定時決定」とは、標準報酬月額を毎年見直すことです。
定時決定について条文を読んでみましょう。
第41条 (定時決定) ① 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ② 定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする ③ 定時決定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定、又は産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 |
<例1>
4月 報酬 249,800円(報酬支払基礎日数20日)
5月 報酬 275,920円(報酬支払基礎日数22日)
6月 報酬 257,430円(報酬支払基礎日数21日)
(249,800円+275,920円+257,430円)÷3≒261,050円(報酬月額)
報酬月額(261,050円)を標準報酬月額等級に当てはめ、
標準報酬月額は、26万円となります。
<例2>
4月 報酬 249,800円(報酬支払基礎日数20日)
5月 報酬 163,800円(報酬支払基礎日数15日)
6月 報酬 257,430円(報酬支払基礎日数21日)
(249,800円+257,430円)÷2≒253,615円(報酬月額)
標準報酬月額は、26万円となります。
ポイント!
17日未満の月は除いて計算しますので、分母は「3」とは限りません。「2」、「1」の場合もあります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされています。
① 月給者については、各月の暦日数によること。
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。
③ 日給者については、各月の出勤日数によること。
問題文の場合、「その月における暦日の数から」ではなく、「就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。
(平18.5.12庁保険発第0512001号)
②【H19年出題】
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)

【解答】
②【H19年出題】 〇
4~6月に支払った賃金で算定します。
問題文の場合、定時決定は、
4月15日支払(3月1日~31日)
+
5月15日支払(4月1日~30日)
+
6月15日支払(5月1日~31日)
で、算定します。
③【R3年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
③【R3年出題】 ×
短時間労働者は、「11日未満」の月を除いて算定します。
問題文は、報酬支払の基礎となった日数が「11日以上」の月である4月、5月、6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行います。
④【H29年出題】
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
6月1日に被保険者資格を取得した者についても、その年の定時決定は行われません。
⑤【H24年出題】
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として「翌年の6月30日までの1年間」ではなく、「翌年の8月」まで用います。
ちなみに、資格取得時に決定された標準報酬月額は、「被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額となります。
(法第42条)
⑥【R3年出題】
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

【解答】
⑥【R3年出題】 ×
7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合も、その年の標準報酬月額の定時決定は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険法>任意継続被保険者
R7-192 03.08
任意継続被保険者の資格取得と喪失
健康保険の資格を喪失した後も、任意で健康保険に加入することができます。
「任意継続被保険者」の資格取得と喪失をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第3条第4項 「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。ただし、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
第37条 ① 任意継続被保険者となる申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 ② 申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。
第38条 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 (1) 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 (2) 死亡したとき。 (3) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 (4) 被保険者となったとき。 (5) 船員保険の被保険者となったとき。 (6) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 (7) 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
保険者は、「正当な理由があると認めるとき」は、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができるとされています。
②【R4年出題】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
例えば、3月8日退職、翌日の9日に資格を喪失した場合で考えてみましょう。
・任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日(=3月8日)まで継続して2か月以上被保険者であることが条件です。
・任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月(=3月)から算定されます。
(法第157条第1項)
③【R3年出題】
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。

【解答】
③【R3年出題】 ×
任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。
ただし、「その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたとき」は、任意継続被保険者となることができます。
④【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

【解答】
④【H27年出題】 ×
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、納付期日の翌日に資格を喪失します。
なお、任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「その月の10日」ですので、保険料の納付期日までに納付しなかったときは、11日に資格を喪失します。
⑤【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。
⑥【R6年出題】
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑥【R6年出題】 ×
「その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」は、その翌日から、任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
例えば、3月8日に資格喪失の申出が受理された場合は、4月1日が資格喪失日となり、3月分の保険料の納付が必要です。
⑦【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合、法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失します。
(令3.12.27事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「出産手当金」
R7-182 02.26
出産手当金の支給期間・支給額など
出産手当金について条文を読んでみましょう。
第102条 ① 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 ② 第99条第2項及び第3項の規定(傷病手当金の額)は、出産手当金の支給について準用する。
第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額(傷病手当金の額)より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 |
出産手当金が支給される期間をイメージしましょう。
|
| 出産日 | 出産の 翌日 |
|
|
|
産前休業 42日(多胎妊娠98日) | 産後休業 56日 | |||||
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)< A >(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日< B >までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。

【解答】
①【H30年選択式】
<A> 以前42日
<B> 後56日
②【H18年出題】
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。

【解答】
②【H18年出題】 〇
出産予定日より遅れて出産した場合は、その分、産前休業の期間が延長されます。
|
| 出産 予定日 |
| 出産日 | 出産の 翌日 |
|
|
|
42日 | 5日 | 56日 | ||||||
産前休業 | 産後休業 | |||||||
問題文の場合は、産前休業は42日+5日=47日、産後休業は、出産の翌日から56日となります。
(昭31.3.14保文発1956号)
③【R2年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

【解答】
③【R2年出題】 ×
出産手当金が支給されるのは、「労務に服さなかった期間」です。
「通常の労務に服している期間」は、出産手当金は支給されません。
④【R4年出題】
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

【解答】
④【R4年出題】 〇
出産手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中でも出産手当金が支給されます。
なお、出産手当金が支給される場合で、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額が調整されます。
(平11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)
⑤【R4年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることができる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】
⑤【R4年出題】 〇
出産手当金の支給要件と傷病手当金の支給要件を、同時に満たした場合は、出産手当金の支給が優先されます。
・出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている
→ 傷病手当金は支給されません。
・出産手当金の額が傷病手当金の額より少ない
→差額の傷病手当金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険法>保険料
R7-170 02.14
(健保)標準賞与額に係る保険料
「標準賞与額」に係る保険料を確認しましょう。
「賞与」の定義を条文で読んでみましょう。
法第3条第6項 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
★年3回以下支給されるボーナス等が該当します。
「標準賞与額の決定」について条文を読んでみましょう。
法第45条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 |
★健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円です。
★「標準賞与額」に係る保険料
標準賞与額×毎月の保険料と同じ保険料率で計算します。
「保険料の源泉控除」について条文を読んでみましょう。
法第167条第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
その年度における標準賞与額の累計額が540万円ではなく、「573万円」です。
②【R1年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

【解答】
②【R1年出題】 〇
賞与の累計は、「保険者単位」で行います。
同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、「同一の保険者である期間」に支払われた賞与について累計します。
(H18.8.18事務連絡)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
全国健康保険協会管掌健康保険 | |||||||||||
|
|
| 150 万円 |
|
|
| 250 万円 |
|
|
| 173万円 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
全国健康保険協会管掌健康保険 | 健康保険組合管掌健康保険 | ||||||||||
|
|
| 150 万円 |
|
|
| 250 万円 |
|
|
| 200 万円 |
③【R4年出題】
育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

【解答】
③【R4年出題】 〇
育児休業期間中などの保険料免除期間中に支払われた賞与についても、標準賞与額として決定し、年間累計額に含みます。
(H18.8.18事務連絡)
④【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
④【H29年出題】 〇
法第156条第3項で、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と定められています。
そのため、前月から引き続き被保険者で、7月10日賞与支給、同月25日退職、同月26日被保険者資格喪失の場合、7月の賞与に係る保険料を納付する義務はありません。
⑤【R3年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
前月から引き続き被保険者である場合、資格喪失月に支払われた賞与については保険料を納付する義務はありません。
ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額には含まれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険法>傷病手当金
R7-169 02.13
傷病手当金の支給要件
病気やケガで仕事に就くことができない場合は、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第99条第1項・第4項 ① 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ④ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。 |
<傷病手当金の支給要件を確認しましょう>
① 業務外の事由による傷病の療養のために労務に服することができないこと
② 連続して3日間労務不能であること(待期完成)
③ 労務不能の期間について報酬の支払いがないこと
過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】※改正による修正あり
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >通算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から通算されることになる。
<選択肢>
① 4月1日から ② 4月3日から ③ 4月4日から ④ 4月5日から
⑤ 日 ⑥ 日の2日後 ⑦ 日の3日後 ⑧ 日の翌日

【解答】
<A> ④ 4月5日から
<B> ⑤ 日
ポイント!
傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。
<A> 4月1日に労務不能となり3日間休業→同月4日通常どおり出勤→翌5日から再び労務不能となって休業した場合→傷病手当金は4月5日から支給されます。
4月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 |
休 | 休 | 休 | 出勤 | 休 |
待期完成 |
| 支給開始 | ||
<B> 報酬があったために、その当初から傷病手当金が支給停止されていた場合
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
有給 | 有給 | 有給 | 有給 | 有給 | 無給 | 無給 |
待期完成 | 停止 | 停止 | 支給開始 |
| ||
②【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
・就業時間中に傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合
→ その日の報酬の全部又は一部を受けると否とを問わず、その日は待期3日に含まれます。
・業務終了後に、傷病の療養のため労務に服することができなくなった場合
→待期は、翌日から起算します。
問題文は、就業中に労務不能になっていますので、待期期間の起算日は、「入院の日」となります。
(昭5.10.13保発52)
③【R3年出題】
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
一般の被保険者の場合、「療養」は、保険医から療養の給付を受けることに限られません。自費診療による療養も、傷病手当金の対象となります。
(昭2.2.26保発345)
④【R5年出題】
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期の適用がない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
待期期間を完成させなければならないのは、最初に療養のため労務不能となった場合のみです。その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期は不要です。
(昭2.3.11保理1085)
⑤【R2年出題】
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合は、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より小さい場合は、差額の傷病手当金が支給されます。そのため、「傷病手当金が支給されることはない」は誤りです。
(昭33.7.8保険発95の2)
⑥【H26年出題】※改正による修正あり
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から通算して1年6か月間である。

【解答】
⑥【H26年出題】 ×
傷病手当金の支給期間は、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。問題文の場合、支給期間は、4月28日からではなく、傷病手当金の支給が始まった日=「6月1日」から通算して1年6か月間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険
R7-153 01.27
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用についてお話しします
「1週間の所定労働時間」又は「1月間の所定労働日数」が 通常の労働者の4分の3未満でも 健康保険・厚生年金保険に加入することになる短時間労働者の条件についてお話ししています。
★基本の条件をおさえましょう。
①「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」に使用されている
または
「国・地方公共団体に属する事業所」に使用されている
②次の要件をすべて満たしている
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円以上
・学生でない
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「国庫負担等」
R7-142 01.16
健康保険の「国庫負担」と「国庫補助」
健康保険の事業を運営するための費用には、保険給付に要する費用、事務の執行に要する費用などがあります。
今回は、国庫が負担する費用、国庫が補助する部分をみていきます。
「国庫負担」の条文を読んでみましょう。
法第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。 |
事務の執行に要する費用(事務費)については、国庫が全額負担します。
過去問をどうぞ!
①【H23年選択式】※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。

【解答】
<A> 予算
<B> 介護納付金
<C> 被保険者数
<D> 概算払い
★介護納付金のイメージ
| 介護保険第2号被保険者 (40歳以上65歳未満) |
|
|
|
|
↓(介護保険料)
|
|
|
|
| 健康保険組合・全国健康保険協会 |
|
|
|
|
↓(介護納付金)
|
|
|
|
| 社会保険診療報酬支払基金 |
|
|
|
|
↓
|
|
|
|
| 介護保険 |
|
|
|
②【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、全国健康保険協会に対しても、健康保険組合に対しても、国庫が負担しています。
②【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払をすることができる。

【解答】
②【R6年出題】 〇
国庫は、健康保険組合に対しても、事務費を負担しています。健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数が基準となっています。「被扶養者数や標準報酬月額」などは基準に入っていませんので、注意してください。
また、その国庫負担金は、概算払をすることができることになっています。
次は、「国庫補助」についての過去問です。
【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】
【R3年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の療養の給付などの支給に要する費用等の1000分の164について、国庫補助が行われています。
ただし、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
(法第153条)
最後に、特定健康診査等についての過去問です。
【H30年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】
【H30年出題】 ×
費用の全部ではなく、「費用の一部」です。
条文を読んでみましょう。
第154条の2 国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法「療養の給付」
R7-141 01.15
健康保険の「療養の給付」を受けようとする場合
「療養の給付」は、健康保険の代表的な給付です。
療養の給付は「現物給付」で、病気で医療機関に行くと、診察等を受けて、かかった費用の原則3割の一部負担金を医療機関に支払います。
「療養の給付」が受けられる医療機関をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第63条第3項 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとする。 (1) 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(第65条の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。) (2) 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの (3) 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 |
それぞれをイメージしてみましょう。
(1)保険医療機関・保険薬局(誰でも行くことができる一般の病院など)
(2)事業主医局(健康保険組合管掌健康保険の事業主が開設する病院)など
(3)健康保険組合が開設する病院など
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「保険医療機関」は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うもので、一部の被保険者及び被扶養者に限定することはできません。
「保険医療機関として指定を受けた」場合は、健康保険組合が開設した病院でも、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することはできません。
(昭32.9.2保険発123号)
②【R6年出題】
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局は、保険医療機関としての指定を受けなくとも当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うことができる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
健康保険組合である保険者の開設する病院若しくは診療所又は薬局が、当該健康保険組合以外の保険者の被保険者の診療を行うには、「保険医療機関の指定」を受けなければなりません。
(昭32.9.2保険発123号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法について
R7-133 01.07
日本最初の社会保険「健康保険法」についてお話しします
<健康保険の歴史>
健康保険法は労働者を対象にした保険で、大正11年に制定された日本で最初の社会保険です。
しかし、大正12年に関東大震災が発生したため、全体が施行されたのは、昭和2年です。
当初の健康保険は業務上の傷病等も保険給付の対象になっていました。当時は、業務上、業務外を判別することが難しかったからです。ただし、昭和22年に労災保険法がスタートし、業務災害は労災保険の対象になりました。
ちなみに、日本で最初の社会保険方式の公的年金は、昭和14年に制定された船員保険制度の年金です。
国民皆保険が実現したのは、国民皆年金と同じ昭和36年4月です。
国民皆保険のイメージ
健 康 保 険 |
船 員 保 険 |
国家公務員共済組合 |
地方公務員共済組合 |
私立学校教職員共済 |
国民健康保険 |
後期高齢者医療(原則75歳以上) |
健康保険法の第1条を読んでみましょう。
第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式(社一)】
世界初の社会保険は、< A >で誕生した。当時の< A >では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、 < A >に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、< B >に「健康保険法」を制定した。
<選択肢>
① アメリカ
② イギリス
③ ドイツ
④ フランス
⑤ 昭和13年
⑥ 昭和16年
⑦ 大正11年
⑧ 大正15年

【解答】
<A> ③ ドイツ
<B> ⑦ 大正11年
(平成23年版厚生労働白書P35)
②【H21年出題】
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。

【解答】
②【H21年出題】 ×
健康保険法は、大正11年に制定された日本で最初の社会保険に関する法ですが、制定と同時に施行されたのではありません。
施行は大正15年(保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年)です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-122 12.27
<令和6年の問題を振り返って>保険医・保険薬剤師の登録
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
保険医、保険薬剤師とは?
厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師を「保険医」、薬剤師を「保険薬剤師」といいます。
保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、保険医又は保険薬剤師でなければなりません。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-ウ】
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師(以下本肢において「保険医等」という。)でなければならない。当該登録の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その登録の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医等の申請があったものとみなす。

【解答】
【R6年問9-ウ】 ×
保険医等の登録には、有効期間がありませんので誤りです。
なお、保険医療機関・保険薬局の指定には、6年間の有効期間がありますので違いに注意して下さい。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は、保険医療機関の指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所は、第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

①【H29年出題】 〇
「保険医療機関又は保険薬局のみなし指定」の規定です。
条文を読んでみましょう。
第69条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について保険医又は保険薬剤師の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。 |
「保険医」として登録を受けた個人の開業医が開設した診療所で、かつ、開設者である医師のみが診療に従事している場合は、保険医療機関の指定の申請をしなくても、「保険医療機関」の指定があったものとみなされます。
②【H19年出題】
保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、健康保険の診療又は調剤のほか健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤を担当する。

【解答】
②【H19年出題】 〇
保険医又は保険薬剤師は、健康保険法以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤も担当します。
(法第72条)
③【H19年出題】
保険医等の登録の申請があった場合において、以前に登録を取り消されたことがあり、その取消された日から10年を経過しない者であるとき、その他著しく不適当と認められるときは、登録されない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
以前に登録を取り消されたことがあり、その取消の日から「5年」を経過しない者であるときは、厚生労働大臣は登録しないことができるとされています。
(法第71条第2項)
④【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
④【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定
・保険医療機関、保険薬局の指定の取り消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取り消し
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしない
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)
・保険医、保険薬剤師の登録をしない
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-121 12.26
<令和6年の問題を振り返って>保険医療機関・保険薬局の指定
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
保険医療機関、保険薬局とは?
→ 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。)又は薬局のこと
※保険医療機関、保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。
※保険医療機関で健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局で健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師でなければなりません。
→ 「保険医」・「保険薬剤師」といいます。
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問9-ア】
厚生労働大臣により保険医療機関の指定を受けた病院及び病床を有する診療所は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失うが、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。

【解答】
①【R6年問9-ア】 ×
保険医療機関・保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年です。6年を経過したときは、効力を失います。
ただし、「その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の申請があったものとみなす。」扱いがあります。ただし、この規定から、「病院又は病床を有する診療所」は除かれています。
この規定が適用されるのは、個人開業医です。
個人開業医については、「指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間」に、「更新しない」旨の申出をしなければ、保険医療機関の申請があったものとみなされ、指定が更新されます。
(法第68条)
②【R6年問9-イ】
厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるときは、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができるが、厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

【解答】
②【R6年問9-イ】 〇
・ 厚生労働大臣による保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行われます。
(法第65条第1項)
・ 厚生労働大臣は、申請があった場合、法第65条第3項第1号~第6号のいずれかに該当するときは、指定をしないことができます。
「申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき」は、第1号に該当しますので、厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定をしないことができます。
(法第65条第3項第1号)
・ 厚生労働大臣は、指定をしないこととするときは、「地方社会保険医療協議会」の議を経なければならないとされています。「中央社会保険医療協議会」と間違えないようにしてください。
(法第67条)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
問題文は、法第65条第3項第3号に該当しますので、厚生労働大臣は、指定をしないことができます。
②【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】
②【H29年出題】 ×
予告期間は、14日以上ではなく「1月以上」です。
法第79条 ① 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 ② 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 |
③【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
③【H29年出題】 〇
<地方社会保険医療協議会に諮問する>(法第82条第2項)
・保険医療機関、保険薬局の指定
・保険医療機関、保険薬局の指定の取り消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取り消し
<地方社会保険医療協議会の議を経なければならない>(法第67条、第71条)
・保険医療機関、保険薬局の指定をしない
・病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)
・保険医、保険薬剤師の登録をしない
④【R2年選択式】
健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、< A >ものとされている。
<選択肢>
① 中央社会保険医療協議会に諮問する
② 地方社会保険医療協議会に諮問する
③ 社会保障審議会の意見を聴く
④ 都道府県知事の意見を聴く

【解答】
<A> ②地方社会保険医療協議会に諮問する
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-120 12.25
<令和6年の問題を振り返って>日雇特例被保険者に関する問題
和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、健康保険法の択一式です。
日雇特例被保険者の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
条文を読んでみましょう。
第123条 ① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とする。 ② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
★ 日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収は、「厚生労働大臣」が行います。
では、「日雇拠出金」について条文を読んでみましょう。
第173条 (日雇拠出金の徴収及び納付義務) ① 厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。 ② 日雇関係組合は、「日雇拠出金」を納付する義務を負う。 |
日雇関係組合 ・日雇特例被保険者を使用する 事業主の設立する健康保険組合 | →→→→→→→→→ 日雇拠出金 | 厚生労働大臣 |
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、「保険料の徴収」と、「日雇関係組合から拠出金の徴収」を行います。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問2-E】
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。

【解答】
【R6年問2-E】 〇
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収します。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

【解答】
①【H21年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
②【R1年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

【解答】
②【R1年出題】 ×
全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。
③【R4年出題】
日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負います。
ただし、日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合は、初めにその者を使用する事業主が、保険料を納付する義務を負います。
問題文の場合は、午前と午後で2か所の事業所に使用されていますが、午前に働いた適用事業所(初めにその者を使用する事業主)から受ける賃金額で標準賃金日額を決定し、保険料の納付も、午前に働いた適用事業所(初めにその者を使用する事業主)が健康保険印紙を貼り、消印して行います。
(第169条第2項、第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-100 12.05
<令和6年の問題を振り返って>全国健康保険協会の一般保険料率
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
全国健康保険協会の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内で、支部被保険者を単位として協会が決定します。
支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といい、その支部被保険者に適用されます。
条文を読んでみましょう。
法第160条第5項 協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問3-オ】
協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。

【解答】
【R6問3-オ】 ×
健康保険事業の収支の見通しを作成し、「厚生労働大臣に届け出る」ではなく、「公表するものとする。」です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

【解答】
①【H26年出題】 〇
協会の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130までの範囲内」で、支部被保険者を単位として「協会」が決定します。支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいいます。
(法第160条第1項)
②【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
条文で確認しましょう。
「登場人物」に特に注意してください。
法第160条第6項~9項 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 |
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率を変更することができます。
条文を読んでみましょう。
法第160条第10項、11項 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 |
④【H24年選択式】
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として < B >が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、< C >についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< D >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< E >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】
④【H24年選択式】
<A>1,000分の30から1,000分の130
<B> 全国健康保険協会
<C> 翌事業年度以降5年間
<D> 健康保険事業の収支の均衡
<E> 社会保障審議会
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-099 12.04
<令和6年の問題を振り返って>全国健康保険協会の事業
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第7条の28 第1項、2項 (財務諸表等) ① 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。 ② 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第2項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第7条の29第1項~3項 (会計監査人の監査) ① 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 ② 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 ③ 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
第7条の30(各事業年度に係る業績評価) ① 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。 ② 厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問2-D】
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。

【解答】
①【R6問2-D】 〇
全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければなりません。
会計監査人は厚生労働大臣が選任し、また、会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければなりません。
②【R6問1-A】
全国健康保険協会は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。

【解答】
②【R6問1-A】 ×
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について評価を行い、遅滞なく、協会に対し、「評価の結果を通知」するとともに、これを「公表」しなければなりません。
評価の結果を公表するのは厚生労働大臣です。全国健康保険協会ではありません。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
協会の毎事業年度の決算は翌事業年度の5月31日までに完結しなければなりません。
また、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。
②【H30年出題】
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行う
↓
評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表する
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-086 11.21
<令和6年の問題を振り返って>資格喪失後の傷病手当金の継続給付
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
資格喪失後の継続給付について条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6問4-E】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日以後に傷病手当金の継続給付の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、その資格を喪失した日の前日において当該被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を傷病手当金の額の算定の基礎に用いる。

【解答】
【R6問4-E】 〇
資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、被保険者の資格を喪失した日の前日において被保険者であった者が属していた保険者等により定められた直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額が、傷病手当金の額の算定の基礎に用いられます。
(法第84条の2)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるための要件に、「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」があります。
転職等で異なった保険者における被保険者期間だったとしても、合算して1年になれば、要件を満たします。なお、1日の空白もなく継続していなければなりません。
また、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含みません。
(法第104条)
②【R4年出題】
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
②【R4年出題】 ×
図にしてみましょう。
退職
共済組合 6か月 | A健康保険組合 10か月 | |
|
| 傷病手当金 |
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、「資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」が必要です。「1年以上」には、共済組合の組合員であった期間は含みません。
問題文は、A健康保険組合の期間が10か月しかありませんので、傷病手当金の継続給付は受けられません。
(法第104条)
③【H27年出題】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

【解答】
③【H27年出題】 〇
・資格喪失後に任意継続被保険者になった場合
→ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができます。
・資格喪失後に特例退職被保険者となった場合
→ 資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
(法第104条、法附則第3条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-085 11.20
<令和6年の問題を振り返って>健康保険の資格取得と喪失
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
【R6問1-C】
一般労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか遅い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は被保険者資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではない。

【解答】
【R6問1-C】 ×
派遣労働者の社会保険は、雇用関係にある「派遣元事業主(派遣会社)」で、適用されます
★登録型派遣労働者の適用
→ 派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させないこととして差し支えないとされています。
★被保険者資格の喪失手続等
→ 登録型派遣労働者について、1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させるものではないこととされています。
問題文では、その雇用契約が締結されないことが確実になった日又は当該1か月を経過した日のいずれか「遅い日をもって」、の部分が誤りです。
ちなみに、「一般労働者派遣事業(許可制)」と「特定労働者派遣事業(届出制)」の区別は廃止されています。すべての労働者派遣事業が「許可制」となっています。
(H27.9.30保保発0930第9号、年管管発0930第11号)
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
被保険者は、「適用事業に使用されるに至った日」から資格を取得します。
試用期間だとしても、適用事業に使用されていますので、試用期間を経過した日の翌日からではなく、入社した日に資格を取得します。
(法第35条)
②【R2年出題】
新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされている。

【解答】
②【R2年出題】 〇
当初から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立している、かつ、休業手当が支払われているときは、休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得します。
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
③【R5年出題】
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。

【解答】
③【R5年出題】 ×
一時帰休中の者の被保険者資格については、休業手当が支払われるときは、被保険者の資格は存続するものとされています。
(昭50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
④【H27年出題】
被保険者が解雇され(労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除く。)、事業主から資格喪失届が提出された場合、労使双方の意見が対立し、当該解雇について裁判が提起されたときにおいても、裁判において解雇無効が確定するまでの間は、被保険者の資格を喪失したものとして取り扱われる。

【解答】
④【H27年出題】 〇
解雇行為が労働法規又は労働協約に違反することが明らかな場合を除いて、事業主から被保険者資格喪失届の提出があったときは、裁判が提起されたときでも、一応資格を喪失したものとしてこれを受理し、被保険者証の回収等、所定の手続をなすこととされています。
(昭25.10.9保発第68号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<健康保険>任意継続被保険者
R7-084 11.18
【社労士受験】任意継続被保険者のすべてお話しします
任意継続被保険者のすべてをお話しします。
①任意継続被保険者の要件
「申出」の期限は?
②任意継続被保険者の資格の喪失
「翌日喪失」or「当日喪失」がポイント
任意継続被保険者をやめる申出
③任意継続被保険者の標準報酬月額
④任意継続被保険者の保険料
保険料を納付期日までに納付しなかったとき
前納について
⑤任意継続被保険者の保険給付
傷病手当金、出産手当金の扱い
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-069 11.02
<令和6年の問題を振り返って>育児休業期間中の保険料の免除【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
育児休業期間の保険料免除について条文を読んでみましょう。
第159条第1項 育児休業等をしている被保険者(産前産後休業期間の保険料免除の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 (1) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 (2) その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
★(1)について(開始日の属する月と終了する日の翌日が属する月が異なる)
開始日 |
|
|
| 終了日の翌日 |
免 除 | 免 除 | 免 除 | 免 除 |
|
★(2)について(開始日の属する月と終了する日の翌日が属する月が同一)
| 開始日 終了日の翌日 |
|
| 14日以上 免 除 |
|
★賞与について
育児休業等の期間が1か月以下の場合は、「標準報酬月額」に係る保険料に限って免除されます。賞与の保険料は、1か月を超える育児休業等を取得している場合に限り、免除の対象となります。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問10-C】
被保険者乙の配偶者が令和5年8月8日に双生児を出産したことから、被保険者乙は令和5年10月1日から令和5年12月31日まで育児休業を取得した。この場合、令和6年1月分の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
【R6問10-C】 ×
保険料が徴収されないのは、育児休業等を開始した日の属する月(令和5年10月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和6年1月1日)が属する月の前月(令和5年12月)までの月です。
令和6年1月分の保険料は、免除されません(=徴収されます)
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)から育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の前月(令和5年3月)までの月の保険料は徴収されません。
②【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一の場合は、育児休業等の日数が14日以上あることが必要です。
問題文の育児休業期間は、令和5年1月4日~16日で13日しかありません。
そのため、令和5年1月分の保険料は免除されません(徴収されます)。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-068 11.01
<令和6年の問題を振り返って>健康保険の保険料の負担と納付義務【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
保険料について条文を読んでみましょう。
第161条第1項~3項(保険料の負担及び納付義務) ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ② 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 ③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第162条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例) 健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
第164条第1項 (保険料の納付) 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問7-A】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増減することができる。

【解答】
【R6問7-A】 ×
一般保険料額又は介護保険料額は、被保険者と事業主が2分の1ずつ負担するのが原則です。
ただし、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき割合を「増減」ではなく「増加」することができます。
ポイント!
・「増加」できるのは、事業主の負担割合です。被保険者の負担割合は増加できません。
・規約で「増加」できるのは、「健康保険組合」のみです。全国健康保険協会には、適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
重要キーワードは、「健康保険組合」、「事業主の負担割合」、「増加」です。
②【H30年出題】
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
②【H30年出題】×
任意継続被保険者の初めて納付すべき保険料は、「保険者が指定する日」までに納付しなければなりません。
表にまとめました。
| 負担割合 | 納付義務 | 納付期日 |
一般の被保険者 | 2分の1 | 事業主 | 翌月末日 |
任意継続被保険者 | 全 額 | 自 己 | その月の10日 初めて納付すべき保険料は、 「保険者が指定する日」 |
③【R1年出題】
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込みがない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

【解答】
③【R1年出題】 〇
被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、使用関係は存続しているため、保険料を負担しなければなりません。事業主及び被保険者は保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負います。
(昭和26.3.9保文発第619号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-067 10.31
<令和6年の問題を振り返って>労災と出産育児一時金の関係【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
出産育児一時金の条文を読んでみましょう。
第101条 (出産育児一時金) 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。 |
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の額は、
★産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合
↓
1児につき50万円
★産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合
↓
1児につき48万8千円
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問8-B】
被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

【解答】
【R6問8-B】 〇
業務中に転倒強打したことに対して、労災保険法から補償が行われたとしても、健康保険法に規定される保険事故(出産)として、出産育児一時金が支給されます。
(昭24.3.26保文発523)
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、「出産」に対して、健康保険から出産育児一時金の支給が行われます。
なお、流産でも妊娠4か月以上の場合は、健康保険法の出産となります。
(昭24.3.26保文発523)
②【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】
②【R5年出題】 〇
産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に出産した場合は、出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、1児につき50万円支給されます。双子の場合は100万円となります。
また、家族出産育児一時金は、被扶養者ではなく、「被保険者に対し」支給されることにも注意して下さい。
(法第101条、104条、令第36条、令和5.3.30保保発0330第8号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-052 10.16
<令和6年度健保>療養の給付に含まれないもの【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
「療養の給付」について条文を読んでみましょう。
第63条第1項、第2項 ① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 (1) 診察 (2) 薬剤又は治療材料の支給 (3) 処置、手術その他の治療 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ② 次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。 (1) 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) (2) 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) イ 食事の提供である療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 (3) 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) (4) 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) (5) 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問4-A】
入院時の食事の提供に係る費用、特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用、評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用、正常分娩及び単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはならない。

【解答】
【R6年問4-A】 〇
・入院時の食事の提供に係る費用→「入院時食事療養費」
・特定長期入院被保険者に係る生活療養に係る費用→「入院時生活療養費」
・評価療養・患者申出療養・選定療養に係る費用→「保険外併用療養費」
の対象となります。
単に経済的理由による人工妊娠中絶に係る費用は、療養の給付の対象とはなりません。
(S27.9.29保発第56号)
医師の手当を必要とする異常分娩は療養の給付の対象ですが、正常分娩は療養の給付の対象になりません。
(S17.2.27社発第206号)
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
入院療養と併せて行う食事の提供は、療養の給付には含まれません。「入院時食事療養費」の対象になります。
(法第63条第2項第1号)
②【H28年出題】(改正による修正あり)
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

【解答】
②【H28年出題】 〇
患者申出療養は、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。
(法第63条第2項第4号、法第86条)
③【H28年出題】
定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
健康診断は療養の給付の対象になりませんが、精密検査は療養の給付の対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-051 10.15
<令和6年度健保>任意継続被保険者の資格喪失【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
任意継続被保険者の資格喪失について条文を読んでみましょう。
第38条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(④から⑥までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 ① 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 ② 死亡したとき。 ③ 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 ④ 被保険者となったとき。 ⑤ 船員保険の被保険者となったとき。 ⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 ⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問1-B】
任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申し出た日の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【R6年問1-B】 ×
「その申し出た日」ではなく、「その申出が受理された日」の属する月の末日が到来するに至ったときは、その翌日から任意継続被保険者の資格を喪失します。
保険者が申出書を受理した日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
(法第38条第7号)
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前で、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失することになります。
(令和3年12月27日事務連絡)
②【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

【解答】
②【H27年出題】 ×
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、「納付期日の翌日」にその資格を喪失します。納付期日はその月の10日ですので、翌日の11日に資格を喪失します。
(法第38条第3号)
ちなみに、初めて納付すべき保険料を納付しなかったときは、「任意継続被保険者とならなかったものとみなす」とされています。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りではありません。
(法第37条第2項)
③【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。

【解答】
③【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった「日」からその資格を喪失します。翌日ではありません。
(法第38条第6号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-041 10.5
<令和6年度健保>定時決定の対象月に休業手当が支払われた場合【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-D】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

【解答】
【R6年問6-D】 〇
定時決定の算定対象月(4月・5月・6月)に休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定します。
★ちなみに、休業手当等が支払われた月のみで決定するわけではありません。
例えば、定時決定の対象月である4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与の支払を受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定した上で、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。
ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定します。(次の問題で解説します)
(令和5年6月27日事務連絡)
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
【R1年出題】 〇
一時帰休の状態が解消しているかどうかは、7月1日時点で判断します。
7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要がありますので、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出します。
例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行います。
6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行います。
(令和5年6月27日事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(健康保険法)
R7-027 9.21
<令和6年度健保>任意継続被保険者・特例退職被保険者の標準報酬月額【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問1】
健康保険組合において、任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額が、当該被保険者の属する健康保険組合の全被保険者における前年度の9月30日の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額を超える場合は、規約で定めるところにより、資格喪失時の標準報酬月額をその者の標準報酬月額とすることができる。

【解答】
①【R6年問1】 〇
「任意継続被保険者」の標準報酬月額について、条文を読んでみましょう。
第47条 (任意継続被保険者の標準報酬月額) ① 任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 (1) 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 (2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
② 保険者が健康保険組合である場合においては、(1)に掲げる額が(2)に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、(1)に掲げる額(当該健康保険組合が(2)に掲げる額を超え(1)に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。 |
問題文は、第47条第2項からの出題です。
(法第47条第2項)
②【R6年問3】
特例退職被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第41条から同法第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額となる。

②【R6年問3】 ×
当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における「特例退職被保険者以外の全被保険者」の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額、となります。
(法附則第3条第4項)
こちらの過去問もどうぞ!
【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、原則として、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
<選択肢>
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
③ 9月30日における健康保険の
④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

【解答】
<A> ④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(法第47条第1項)
こちらの練習問題もどうぞ!
(練習問題)
特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条から第44条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< B >同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
<選択肢>
① 3月31日における特例退職被保険者以外の全被保険者の
② 3月31日における特例退職被保険者を含む全被保険者の
③ 9月30日における特例退職被保険者を含む全被保険者の
④ 9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の

【解答】
<B> ④ 9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の
(法附則第3条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(健康保険法)
R7-019 9.13
令和6年の健保は全体的に難しかったですが解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の択一式です。
令和6年度の健康保険法択一式は、全体的に難しかったです。
その中でも押さえておくべき問題をみていきましょう。
令和6年健康保険問2の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
被保険者の総数が常時100人以下の企業であっても、健康保険に加入することについての労使の合意(被用者の2分の1以上と事業主の合意)がなされた場合、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、月額賃金が8.8万円以上であること、2か月を超える雇用の見込があること、学生でないことという要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で健康保険の被保険者となる。

【解答】
①【R6年出題】 〇
100人以下の企業でも、労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主の方が厚生年金保険・健康保険に加入することについて合意すること)がなされれば、「任意特定適用事業所」となり、要件をすべて満たす短時間労働者は、企業単位で厚生年金保険・健康保険に加入できます。
※100人以下は、令和6年10月から「50人以下」となります。
(参考:短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(厚生労働省))
②【R6年出題】
保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。厚生労働大臣は、この指導をする場合において、常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
条文で確認しましょう。
法第73条 ① 保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 ② 厚生労働大臣は、指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。 |
「常に厚生労働大臣が指定する診療又は調剤に関する学識経験者を立ち会わせなければならない。」は誤りです。
③【R6年出題】
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、概算払をすることができる。

【解答】
③【R6年出題】 〇
問題文の重要用語を穴埋めでチェックしましょう。
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担することになっており、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< A >を基準として、厚生労働大臣が算定する。また、その国庫負担金は、< B >。
<A> 被保険者数
<B> 概算払をすることができる
(法第151条、第152条)
④【R6年出題】
協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。

【解答】
④【R6年出題】 〇
条文で確認しましょう。
法第7条の29第1項~3項 (会計監査人の監査) ① 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 ② 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。 ③ 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。 |
⑤【R6年出題】
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、健康保険法第155条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金を徴収する。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
「日雇拠出金」の問題です。
厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収します。加えて、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合から拠出金(日雇拠出金)を徴収します。
(法第173条第1項)
また、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(「日雇関係組合」という。)は、日雇拠出金を納付する義務を負います。
(法第173条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(健康保険法)
R7-009 9.3
<令和6年度健保選択式>保険外併用療養費・資格喪失後の出産・家族訪問看護療養費【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、健康保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
保険外併用療養費の支給対象となる治験は、< A >、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
<選択肢>
「新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから」
「患者に対する情報提供を前提として」
「困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として」
「保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に該当するとともに」

【解答】
<A> 患者に対する情報提供を前提として
(R2.3.5保医発0305第5号)
「治験」とは?厚生労働省のホームページを参考に、お話します。
「くすりの候補」の開発の最終段階では、人での効果と安全性を調べなければなりません。その際、人の協力が必要です。
このように得られた成績を国が審査し、病気の治療に必要、かつ安全に使えると承認されたものが「くすり」となります。
人における試験を一般に「臨床試験」といい、「くすりの候補」を用いて国の承認を得るための成績を集める臨床試験は、特に「治験」と呼ばれています。
(参考:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu1.html)
令和6年 選択問題2
任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の< B >であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
<選択肢>
「資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」
「資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」
「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」
「資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」

【解答】
<B> 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
(法第104条、第106条)
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けるには、「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員であった被保険者を除く)であったこと」が必要です。
資格喪失後の出産育児一時金も同じ条件です。
任意継続被保険者の資格を喪失した後でも、要件を満たせば、継続給付や出産育児一時金が支給されます。
その場合は、任意継続被保険者の資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったことが必要です。
退職 | 取得 喪失 |
被保険者(在職中) | 任意継続被保険者 |
継続して1年以上 |
|
令和6年 選択問題3
健康保険法第111条の規定によると、被保険者の< C >が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、< D >を支給する。< D >の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に< E >の給付割合を乗じて得た額 (< E >の支給について< E >の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
<選択肢>
「家族訪問看護療養費」、「家族療養費」、「高額介護サービス費」
「高額介護合算療養費」、「高額介護サービス費」、「高額療養費」
「認定対象者」、「被扶養者」、「扶養者」
「訪問看護療養費」、「保険外併用療養費」、「療養費」

【解答】
<C> 被扶養者
<D> 家族訪問看護療養費
<E> 家族療養費
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、家族訪問看護療養費が支給されます。
家族訪問看護療養費の額は、指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に家族療養費の給付割合(区分に応じて100分の70、100分の80)を乗じて得た額です。
令和6年の選択式 保険外併用療養費の支給対象となる治験の条件は、難しく感じた方が多かったのではないでしょうか? 2つめの任意継続被保険者の資格を喪失した後の問題については、選択肢が紛らわしいので注意が必要です。 3つめは、問題文の中のヒントを利用しながら解く問題です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-357 8.18
<健保>短時間労働者の重要問題5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
短時間労働者の問題をチェックしましょう。
 特定適用事業所とは
特定適用事業所とは
①【H29年出題】※改正による修正あり
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時100人を超えるものの各適用事業所のことをいう。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「特定労働者の総数が常時100人を超える」がポイントです。
(H24法附則第46条第12項)
★特定適用事業所に使用され、1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の者で、次の①~③の全ての要件に該当する場合は、短時間労働者として健康保険の被保険者となります。 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 報酬の月額が88,000円以上であること ③ 学生でないこと |
 報酬の月額について
報酬の月額について
②【R4年選択式】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
②【R4年選択式】
<A> 88,000円以上
③【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
③【H30年出題】 ×
最低賃金において算入しないことを定める賃金は、報酬に含みません。精皆勤手当、家族手当・通勤手当は、報酬に含めません。
(則第23条の4第6号、R4.9.28保保発0928第6号)
 学生でないことについて
学生でないことについて
④【R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
④【R3年出題】 ×
「その他これらに準ずる者」とは、事業主との「雇用関係を存続した上で」事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)とされています。
(R4.9.28保保発0928第6号)
 任意特定適用事業所について
任意特定適用事業所について
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
短時間労働者を使用する特定適用事業所の被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下になり、特定適用事業所の要件に該当しなくなった場合であっても、事業主が所定の労働組合等の同意を得て、当該短時間労働者について適用除外の規定の適用を受ける旨の申出をしないときは、当該短時間労働者の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
被保険者の総数(短時間労働者を除く。)が常時100人以下でも、所定労働組合等の同意を得て、任意特定適用事業所の申出を行うことができます。
(H24法附則第46条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-347 8.8
健康保険の保険者についての問題【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の保険者について条文を読んでみましょう。
第4条 (保険者) 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) ① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。 ② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第6条 (組合管掌健康保険) 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
全国健康保険協会は、事務所の所在地の変更に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
全国健康保険協会の定款の変更は、「厚生労働大臣の認可」を受けなければ、その効力を生じません。
ただし、「事務所の所在地の変更」などの変更は、「遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出」なければならないとされています。
(法第7条の6第2項、第3項、則第2条の3)
②【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度、事業計画及び予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
②【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
令第16条第1項 健康保険組合は、毎年度、収入支出の予算を作成し、当該年度の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
ちなみに、全国健康保険協会の条文も読んでみましょう。
法第7条の27 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 |
③【H24年出題】
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第7条の34 全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
④【H24年出題】
健康保険組合は、毎年度終了後6か月以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
穴埋めでポイントを確認しましょう。
令第24条 健康保険組合は、毎年度終了後< A >以内に、厚生労働省令に定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
<解答>
A 6か月
⑤【H21年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

【解答】
⑤【H21年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」のみです。
(法第123条第1項)
⑥【H22年出題】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

【解答】
⑥【H22年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の業務のうち、確認や保険料の徴収など厚生年金保険とセットになる業務は、厚生労働大臣が行います。(任意継続被保険者に係るものを除く。)の部分も注意して下さい。
(第5条第2項)
⑦【H29年出題】
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

【解答】
⑦【H29年出題】 ×
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。
保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行います。
(第5条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-336 7.28
<選択式>高額療養費の支給要件【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
高額療養費の支給要件を条文で読んでみましょう。
第115条第1項 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 |
高額療養費のイメージ(療養の給付の場合)
一部負担金 |
療養の給付 | |
高額療養費 算定基準額 | 高額療養費 | |
(例)
56歳・標準報酬月額が41万円の被保険者
1か月の医療費が100万円(一部負担金30万円)
・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)は、
8万100円+(100万円-26万7千円)×1%=8万7430円です。
・高額療養費は、
30万円-8万7430円=21万2570円です。
選択式の過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。
<選択肢>
①7,330円
②84,430円
③125,570円
④123,670円

【解答】
A ③125,570円
ポイント!
★評価療養に係る特別料金、選定療養に係る特別料金は計算に入れません。
★「高額療養費算定基準額」は自己負担限度額、「高額療養費」は支給される額です。
問われているのは、「高額療養費」です。間違えないようにしましょう。
「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」
80,100円+(療養に要した費用(70万円)-267,000円)×1%=84,430円
「高額療養費」
21万円-84,430円=125,570円
(令42条)
②【H28年選択式】
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- < B >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は < C >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< D >となる。
<選択肢>
①40,070円
②42,980円
③44,100円
④44,400円
⑤45,820円
⑥80,100円
⑦93,000円
⑧140,100円
⑨267,000円
⑩558,000円
⑪670,000円
⑫842,000円

【解答】
B ⑫842,000円
C ⑤45,820円
D ⑧140,100円
(令第42条)
ポイント!
★Bについて
70歳未満・標準報酬月額83万円以上の高額療養費算定基準額
252,600円+(療養に要した費用-842,000円)×1%
252,600円は、842,000円の30%です。一部負担金として252600円支払っているということは、医療費が842,000円以上かかっているということです。
★Cについて
問われているのは、「高額療養費」です。
高額療養費算定基準額は
252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
高額療養費は
300,000円-254,180円=45,820円
択一式の過去問もどうぞ!
①【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額、入院時食事療養に係る食事療養標準負担額、保険外併用療養費に係る自己負担額は高額療養費の算定対象となりません。
(令第41条)
②【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】
②【R5年出題】 ×
食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は算定対象になりません。
(令第41条)
③【H27年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】
③【H27年出題】 ×
歯科診療と歯科診療以外の診療については、それぞれ別個の保険医療機関とみなされます。
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したときは、高額療養費の算定上、別個の病院で受けた療養とみなされます。
(令第43条第9項)
④【H23年出題】
高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。

【解答】
④【H23年出題】 〇
同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、高額療養費の支給要件の取扱いではそれぞれ区別されます。
(令第43条第10項)
⑤【H24年出題】
被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、高額療養費は3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
高額療養費は、暦月単位で計算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-326 7.18
<選択式>健康保険の国庫負担など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
今日は、健康保険の費用の負担です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H23年選択式】 ※改正による修正あり
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、< B >並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。
4 国庫は、< A >の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、< E>の実施に要する費用の一部を補助することができる。
<選択肢>
① 一般保険料率 ② 一般保険料率の10% ③ 介護納付金
④ 概算払い ⑤ 組合間で調整 ⑥ 高額療養費の財政調整
⑦ 後期高齢者医療 ⑧ 児童手当拠出金 ⑨ 所要保険料率の50%
⑩ 精算払い ⑪ 退職者給付拠出金 ⑫ 調整保険料
⑬ 特定健康診査等 ⑭ 被保険者数 ⑮ 被保険者数及び被扶養者数
⑯ 分割払い ⑰ 保険外併用療養費 ⑱ 保険料収入
⑲ 保険料収入の25% ⑳ 予算

【解答】
A ⑳ 予算
B ③ 介護納付金
C ⑭ 被保険者数
D ④ 概算払い
E ⑬ 特定健康診査等
(第151条、152条、154条の2)
令和6年4月1日改正
★流行初期医療確保拠出金とは?
全国健康保険協会及び健康保険組合は「流行初期医療確保拠出金等(流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金)」を納付する義務を負うことになりました。
(内容)
「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により一般医療の提供を制限して、流行初期の感染患者への医療の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間、財政的な支援を行います。(流行初期医療確保措置)事業実施主体は、「都道府県」で、措置に関する費用は、公費と保険者で負担することになっています。
★「出産育児交付金等」が導入されました。
出産育児一時金を全世代で支えあう制度です。
条文を読んでみましょう。
第152条の2 (出産育児交付金) 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。 |
下のイメージ図をご覧ください。
選択式の練習をどうぞ!
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。)の< A >については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第124条の4第1項の規定により< B >が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
<選択肢>
① 全部 ② 全部又は一部 ③ 一部
④ 政府 ⑤ 社会保険診療報酬支払基金 ⑥ 厚生労働大臣

【解答】
A ③ 一部
B ⑤ 社会保険診療報酬支払基金
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、健康保険組合に対しても負担を行っています。
(第151条)
②【R3年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等には国庫補助が行われます。しかし、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われません。
(第153条)
③【H30年出題】
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の「全部」ではなく、「一部」を補助することができる、です。
(第154条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-312 7.4
<選択式>保険外併用療養費のよく出るところ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、保険外併用療養費について条文を読んでみましょう。
第86条第1項 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 |
「評価療養」とは
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
「患者申出療養」とは
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
「選定療養」とは
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
では、過去問をどうぞ!
【R4年選択式】
保険外併用療養費の対象となる選定療養とは、「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定されている選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。
そのうち第4号によると、「病床数が< A >の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が< B >を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」と規定されている。
<選択肢>
① 90日 ② 120日 ③ 150日 ④ 180日
⑤ 150以上 ⑥ 200以上 ⑦ 180以上 ⑧ 250以上

【解答】
A ⑥ 200以上
B ④ 180日
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
択一式の過去問もどうぞ!
①【R4年出題】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

【解答】
①【R4年出題】 ×
イメージ図をご覧ください。
「選定療養」の部分は全額患者負担になるのがポイントです。
「保険外併用療養費」は、通常は「療養の給付」に当たる部分です。
保険診療 | 選定療養(保険適用外) | |
30万円 | 10万円 | |
一部負担金9万円 | 保険外併用療養費 | |
被保険者は保険診療の自己負担額(30万円の3割)と、選定療養に要した費用(10万円)を合わせて19万円を支払います。
(第86条第2項)
②【H28年出題】
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
予約診療は、保険外併用療養費制度の選定療養の対象となります。
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
③【H26年出題】
被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院はその者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

【解答】
③【H26年出題】 ×
選定療養の対象になるのは、100床以上ではなく、200床以上の病院です。
(平18.9.12厚生労働省告示第495号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-301 6.23
<選択式>任意継続被保険者の保険料の前納など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
任意継続被保険者は、保険料を全額負担し、納付する義務も負います。
条文を読んでみましょう。
第161条第1項、第3項 ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 ③ 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第164条 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
第157条第1項 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。 |
例えば、6月24日に退職した場合、任意継続被保険者になるのは、6月25日からです。6月分から任意継続被保険者として保険料を納付します。
5月 | 6月 任意継続被保険者と なった月 |
事業主と2分の1ずつ負担 事業主が納付する | 全額負担 本人が納付する |
では、選択式の過去問をどうぞ!
①【H22年選択式】※問題文修正しています
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
①【H22年選択式】
A 各月の初日
B 初月の前月末日
C 年4分の利率
D 5月
※Dについて条文を読んでみましょう。
令第48条 保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。 (第165条、令第48条、第49条、則第139条第1項) |
②【R1年選択式】
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< E >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
<選択肢>
① 3月31日における健康保険の
② 3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
③ 9月30日における健康保険の
④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

【解答】
E ④ 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
択一式の過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料の前納の単位は、「4月から9月まで」・「10月から翌年3月まで」の6か月間又は「4月から翌年3月まで」の12か月間が原則です。
しかし、6か月又は12か月の間に、任意継続被保険者の資格を取得した場合は、「資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間」、資格を喪失することが明らかな場合は、「その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間」の保険料について前納を行うことができます。
(令第48条)
②【R4年出題】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定されます。
(第3条第4項、第157条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-300 6.22
<選択式>全国健康保険協会の一般保険料率【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険の被保険者の保険料額の条文を読んでみましょう。
第156条第1項(被保険者の保険料額) 被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 (1) 介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料額と介護保険料額との合算額 ※一般保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額 ※介護保険料額とは、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額 (2) 介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料額 |
「全国健康保険協会」の「一般保険料率」を選択式の過去問でみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H24年選択式】 ※改正による修正あり
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として < B >が決定する。その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、< C >についての健康保険の事業の収支の見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。
2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における< D >を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。厚生労働大臣は、全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、< E >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
<選択肢>
① 1000分の30から1000分の130 ② 1000分の30から1000分の164
③ 1000分の60から1000分の90 ④ 1000分の60から1000分の120
⑤ 運営委員会 ⑥健康保険組合との収支の均衡
⑦ 健康保険事業の収支の均衡 ⑧ 厚生労働大臣
⑨ 国民健康保険との収支の均衡 ⑩ 社会保障審議会
⑪ 全国健康保険協会 ⑫ 地方厚生(支)局長
⑬ 中央社会保険医療協議会 ⑭ 当該事業年度以降3年間
⑮ 中央社会保険医療協議会 ⑯ 都道府県の支部長
⑰ 被保険者の家計収入との均衡 ⑱ 毎事業年度
⑲ 翌事業年度以降3年間 ⑳ 翌事業年度以降5年間

【解答】
A ① 1000分の30から1000分の130
B ⑪ 全国健康保険協会
C ⑳ 翌事業年度以降5年間
D ⑦ 健康保険事業の収支の均衡
E ⑩ 社会保障審議会
(第160条第1項、第5項、第10条、第11条)
択一式の過去問もどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

【解答】
①【H26年出題】 〇
全国健康保険協会の一般保険料率は、「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内で、「支部被保険者を単位」として「全国健康保険協会が決定」します。
なお、支部被保険者とは、「各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者・当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者」をいいます。
支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。
(第160条第1項、第2項)
②【R4年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
第160条第6項~第8項 ⑥ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、< A >が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< B >の議を経なければならない。 ⑦ 支部長は、上記の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、< A >に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 ⑧ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、< A >は、その変更について厚生労働大臣の< C >を受けなければならない。 ⑨ 厚生労働大臣は、上記の< C >をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 |

【解答】
A 理事長
B 運営委員会
C 認可
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。」が誤りです。
条文を読んでみましょう
第160条第10項、第11項 ⑩ 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 ⑪ 厚生労働大臣は、協会が上記の期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 |
厚生労働大臣は、協会が期間内に申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、都道府県単位保険料率を変更することができるとされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-287 6.9
埋葬料と埋葬費【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
埋葬料と埋葬費の違いを意識しながら条文を読んでみましょう。
第100条、令第35条 ① 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、5万円を支給する。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
| 対象者 | 金額 | 時効の起算日 |
埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 | 死亡日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った者 | 5万円の範囲内で 埋葬に要した費用 | 埋葬を行った日の翌日 |
埋葬料は、「生計を維持されていた者で埋葬を行うべき者」に支給されます。
埋葬費は、「実際に埋葬を行った者」に支給されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
埋葬料の対象者は、被保険者と同一世帯であったか否かは問われません。
なお、民法上の親族又は遺族であることも要しませんし、被保険者が世帯主であるか否かも問われません。
(昭7.4.25保規129)
②【H25年出題】
事業主は、埋葬料の支給を受けようとする者から、厚生労働省令の規定による証明書を求められたときには、いかなる理由があろうとも、拒むことができない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「いかなる理由があろうとも」が誤りです。
「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」とされています。(則第33条)
正当な理由がある場合は拒むことができます。
③【H25年出題】
埋葬料の支給を受けようとする者は、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であるから、埋葬料の申請書には当該被保険者と申請者の続柄を記載する必要はない。

【解答】
③【H25年出題】 ×
埋葬料の申請書には、「被保険者と申請者との続柄」を記載しなければなりません。
(則第85条第1項第3号)
④【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。

【解答】
④【H24年出題】 〇
被保険者により生計の一部を維持していた者も、埋葬料の支給対象になります。
(昭8.8.7保発502)
⑤【H25年出題】
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。

【解答】
⑤【H25年出題】 ×
死亡した被保険者により生計を維持されていたものがいない場合は、実際に埋葬を行った者に埋葬費が支給されます。
死亡した被保険者に生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合は、埋葬費が支給されます。
(昭26.6.28保文発162)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-276 5.29
健康保険の現金給付5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険には、現物給付と現金給付があります。
現物給付の代表例は「療養の給付」(=病院等で治療そのものを受ける)、現金給付の代表例は「傷病手当金」(=現金で給付される)です。
現金給付の5問をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができなかったときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。」とされています。
「療養のため」の療養とは、保険給付として受ける療養に限らないのがポイントです。自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても「療養のため」に該当しますので、傷病手当金が支給されます。
ただし、「健康保険で診療を受けることができる範囲の療養」であることが必要ですので、美容整形手術などの療養については、傷病手当金は支給されません。
(第99条、昭2.2.26保発345)
②【H23年出題】※改正による修正あり
傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の傷病により障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金が優先して支給される。ただし、その障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由により障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より多いときは、その差額を支給する。
なお、報酬と出産手当金の支給を受けることはできない場合とする。

【解答】
②【H23年出題】 ×
傷病手当金ではなく、「障害厚生年金」が優先されます。
なお、障害年金の日額は、年金額÷360で計算します。
★傷病手当金は支給されません
|
障害厚生年金の 日額 |
傷病手当金
|
★差額の傷病手当金が支給されます
差額 |
|
傷病手当金
| 障害厚生年金の 日額 |
条文を読んでみましょう。
第108条第3項、則第89条 傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。 (1) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 → 障害年金の額 (2) 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 → 出産手当金の額(当該額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 (3) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 → 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額(当該額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 (4) 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 → 当該受けることができる報酬の全部又は一部の額及び出産手当金の額の合算額(当該合算額が傷病手当金の額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額 |
③【H23年出題】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。

【解答】
③【H23年出題】 〇
日雇特例被保険者の傷病手当金は、「療養の給付」等を受けていることが条件です。
問題①でみました一般被保険者の傷病手当金は、「自費診療で受けた療養」でも対象になりますが、日雇特例被保険者の傷病手当金は、「療養の給付」等を受けていることが条件です。
そのため、日雇特例被保険者の傷病手当金は、「自費診療で受けた療養」では支給されません。
ただし、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しません。
(第135条第1項、平15.2.25庁保発2944)
④【H23年出題】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。

【解答】
④【H23年出題】 〇
介護休業期間中でも、支給要件に該当する場合は、傷病手当金が支給されます。
同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整が行われます。
(第99条、平11.3.31保険発46・庁保険発9)
⑤【H23年出題】
被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、提出しなければなりません。
なお、医師又は歯科医師の意見書には、「移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)」、「移送経路、移送方法及び移送年月日」を記載することになっています。
(則第82条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-262 5.15
一時帰休に伴う休業手当と随時改定【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、随時改定の条文を読んでみましょう。
第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
随時改定の3つの要件を確認しましょう。
① 昇給・降給、給与体系の変更等で固定的賃金の変動があった。
② 固定的賃金の変動月からの3か月間の報酬の平均月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
③3カ月間の各月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上である。
改定が行われるのは、「その著しく高低を生じた月の翌月から」です。具体的には、固定的賃金の変動月から4か月目からです。
例えば、4月に固定的賃金の変動があった場合、4月・5月・6月の3か月間の報酬の平均をとり、標準報酬月額は7月から改定されます。
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 変動 |
|
| 改定 |
|
|
|
|
|
今回は、「一時帰休に伴う休業手当」と随時改定についてみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
①【R3年出題】 〇
一時帰休に伴い、低額な休業手当が支払われる状態が継続して3か月を超える場合は、随時改定の対象になります。
(令和5.6.27事務連絡)
②【R3年出題】
賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払が行われ、5月1日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

【解答】
②【R3年出題】 ×
一時帰休に伴い、低額な休業手当が支払われる状態が継続して3か月を超える場合は、随時改定の対象になりますが、3か月は月単位で計算します。
月末締め月末払いの事業所で、2月19日から一時帰休が開始された場合は、5月1日に「3か月を超える場合」に該当します。
2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降に随時改定が行われます。
ただし、5月1日時点で一時帰休の状態が解消している場合は、「3か月を超える」に該当しないので、随時改定は行われません。
問題文は、随時改定の対象になりません。
(令和5.6.27事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-245 4.28
<指定の更新>保険医療機関又は保険薬局【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
保険医療機関・保険薬局となるには、厚生労働大臣の指定を受けなければなりませんが、指定の効力には有効期間があります。
今日は、指定の更新などをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第68条 (保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 ② 保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、指定の申請があったものとみなす。
第79条 (保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消) ① 保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 ② 保険医又は保険薬剤師は、1月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 |
保険医療機関又は保険薬局の指定の効力は、指定の日から起算して6年を経過すると消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。

【解答】
①【H29年出題】 〇
ポイント!
・保険医療機関又は保険薬局の指定 → 病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が指定します。
・指定の効力 → 指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失います。
(第68条第1項)
②【H28年出題】
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
保険医療機関・保険薬局の指定の効力は6年ですので、指定の更新の手続が必要です。
しかし、保険医個人が開設する診療所の場合は、更新手続きは不要です。そのため、更新しない場合は、指定の効力を失う前に、その旨の申出が必要です。
・有効期間の更新をしない場合 → その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、申出が必要です。
・上記の期間内に申出がない場合 → 指定の申請があったものとみなされ、更新申請をしなくても、有効期間が更新されます。
なお、この規定は、「病院及び病床を有する診療所」には適用されません。
問題文は、「病床の有無に関わらず」が誤りです。病床を有する診療所には適用されません。
(第68条第2項)
③【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退、保険医又は保険薬剤師の登録の抹消、どちらも予告期間は「14日以上」ではなく「1月以上」です。
なお、保険医、保険薬剤師について、条文を読んでみましょう。
第64条 (保険医又は保険薬剤師) 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。 第71条第1項 (保険医又は保険薬剤師の登録) 保険医又は保険薬剤師の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-244 4.27
保険医療機関又は保険薬局の指定【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
保険医療機関とは、被保険者証を持って行けば、誰でも、健康保険を使って診察等を受けることができる病院、診療所のことです。
では、条文を読んでみましょう。
第63条第3項 療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付を受けるものとする。 (1)厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。) (2)特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの (3)健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 |
健康保険の療養の給付を受けることができる医療機関は次の3つです。
(1) 保険医療機関又は保険薬局
(2) 保険者が指定する病院、診療所、薬局
(事業主が開設した病院等)
(3) 健康保険組合が開設した病院、診療所、薬局
(健康保険組合が開設した病院等)
今日は(1)保険医療機関又は保険薬局についてみていきます。
では、次に保険医療機関又は保険薬局の指定について条文を読んでみましょう。
第65条 ① 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 ② その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、病床の種別ごとにその数を定めて行うものとする。 ③ 厚生労働大臣は、申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしないことができる。 ※1号から6号は省略します。 ④ 厚生労働大臣は、病院又は診療所について申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、指定を行うことができる。 ※1号から4号は省略します |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険組合が開設した病院でも、保険医療機関として指定を受けた場合は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行わなければなりません。
(S32.9.2保険発第123号)
②【H29年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとされている。

【解答】
②【H29年出題】 〇
※地方社会保険医療協議会に諮問するもの
・保険医療機関、保険薬局の指定
・保険医療機関、保険薬局の指定の取消し
・保険医、保険薬剤師の登録の取消し
ちなみに・・・
★保険医療機関・保険薬局は「指定」ですが、保険医・保険薬剤師は「登録」という用語を使っています。
③【R1年出題】
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合、第65条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する場合は、指定をしないことができます。
問題文は、第3号に該当しますので、厚生労働大臣は指定をしないことができます。
(第65条第3項第3号)
④【R3年出題】
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。

【解答】
④【R3年出題】 〇
保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法だけでなく、他の医療保険各法、高齢者医療確保法に係る療養も担当することになっています。
(第70条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-243 4.26
法人の役員である被保険者等の保険給付の特例【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、健康保険法の目的条文を読んでみましょう。
第1条 (目的) 健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
健康保険の保険給付は、労災保険法の業務災害以外の傷病等に対して行われます。
例えば、健康保険の被保険者が副業として行う請負業務中に負傷したとしても、「請負」は労働関係ではありませんので、業務中といえども労災保険の保険給付は受けられません。
請負業務中の負傷など労災保険の業務災害に当たらない業務上の負傷等は、原則として健康保険の保険給付の対象になります。
(平25.8.14事務連絡)
ただし、「役員」の業務上の負傷等については特例が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第53条の2(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例) 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
則第52条の2 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 |
(原則)
被保険者、被扶養者が法人の役員である場合、その法人の役員としての業務に起因する傷病等は、原則として健康保険の保険給付の対象外となります。
使用者側の責めに帰すべきものですので、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当でないと考えられるからです。
(特例)
「被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等で、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者」については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険の保険給付の対象となります。
(平25.8.14事務連絡)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
労災保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付の対象になります。
(法第1条、平25.8.14事務連絡)
②【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
②【H30年出題】 〇
被保険者、被扶養者が法人の役員である場合、その法人の役員としての業務に起因する傷病等は、健康保険の保険給付の対象外となるのが原則です。
ただし、5人未満の適用事業所の法人の代表者は、業務遂行の過程で業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があります。対象になる業務は、従業員が従事する業務と同一であると認められるものです。
(第53条の2、則第52条の2、平25.8.14事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-227 4.10
社労士受験のための 傷病手当金の待期期間
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
傷病手当金の待期期間をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第99条第1項 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給されます。
傷病手当金が支給されない最初の3日間を「待期」といいます。待期の完成は、傷病手当金が支給される条件の一つです。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

【解答】
①【H28年出題】 〇
労務に服することができない状態が3日間連続していれば、待期は完成します。
金 | 土 所定休日 | 日 所定休日 | 月 | 火 |
労務不能 | 労務不能 | 労務不能 | 労務不能 | 労務不能 |
所定休日も通算されますので、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。
(S32.1.31保発2の2)
②【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
資格喪失日前に労務不能の日が3日間継続しているのみでは、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は、4日目以後に支給されるので、3日目に退職した場合は資格喪失の際に、傷病手当金を受けられる状態になっていないからです。
(第104条、S32.1.31保発2の2)
③【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】
③【H28年出題】 ×
待期期間は、「労務不能になった日」から起算します。ただし、「業務終了後」に労務不能になった場合は、翌日から起算します。
問題文は、就業中に労務不能になっていますので、「入院した日の翌日」ではなく、「入院した日」が待期期間の起算日となります。
(S5.10.13保発52)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-213
R6.3.27 健康保険 被保険者資格の取得と喪失の確認
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
入社した日に健康保険の被保険者資格を取得し、退職した日の翌日に資格を喪失するのが一般的です。例えば、健康保険の被保険者の資格を取得すると、保険料を負担する義務や、保険給付を受ける権利などが生まれます。
被保険者資格の取得や喪失は、保険者等の確認によって効力が発生します。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項、2項(資格の得喪の確認) ① 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、第36条第4号に該当したことによる被保険者の資格の喪失(任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失)並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 ② 確認は、「事業主からの届出」、「被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求」、「職権」で行うものとする。 |
★「被保険者の資格の取得及び喪失」は、保険者等の確認によって、その効力を生じます。
※保険者等とは
・ 協会が管掌する健康保険の被保険者の場合 → 厚生労働大臣
・ 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者の場合 → 当該健康保険組合
★確認が要らないもの
・ 任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失
→ 任意適用事業所の適用取消しの厚生労働大臣の認可を受けた場合、それに伴い被保険者資格も喪失します。あらためて資格喪失の確認は要らないからです。
・ 任意継続被保険者の資格の取得及び喪失
→ 任意継続被保険者は事業主との関係がなくなっていて、入社日・退職日の確認が要らないからです。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
②【H26年出題】
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
③【H30年出題】
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が、それぞれ確認することによってその効力を生じます。
任意継続被保険者の被保険者資格の取得・喪失については保険者等の確認は行われません。特例退職被保険者も任意継続被保険者とみなされ、被保険者資格の取得・喪失については保険者等の確認は行われません。
(法第39条第1項、法附則第3条第6項)
②【H26年出題】 ×
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認は不要です。
(法第39条第1項)
③【H30年出題】 ×
「任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失」、「任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失」については、保険者等の確認は不要です。
(法第39条第1項、法附則第3条第6項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-206
R6.3.20 年次有給休暇④時間単位付与
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第4項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、(1)に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、有給休暇の日数のうち(2)に掲げる日数については、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 (1) 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 (2) 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) (3) その他厚生労働省令で定める事項 |
時間単位年休のポイント!
・労使協定の締結が必要です
・時間単位で年次有給休暇を与えることができるのは、年に5日以内です。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
年次有給休暇の時間単位での取得は、労働者の多様な事情・希望に沿いながら年次有給休暇の消化率を高める効果を持ち得るものであるため、労働基準法第39条第4項所定の事項を記載した就業規則の定めを置くことを要件に、年10日の範囲内で認められている。
②【H28年出題】
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。
③【H25年出題】
労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

【解答】
①【H22年出題】 ×
年次有給休暇の時間単位付与は、「就業規則の定めを置くこと」ではなく「労使協定を締結すること」を要件に、「年10日」ではなく「年5日」の範囲内で認められています。
(第39条第4項)
②【H28年出題】 〇
週の所定労働時間が1日8時間から4時間に変更になった場合、時間単位で取得できる時間数はどうなるのかという問題です。
所定労働時間が変更になる前の残余は10日と5時間です。
時間の部分の残余は8時間のうちの5時間ということで、8分の5と考えます。
所定労働時間が4時間になると、所定労働時間に比例して時間の部分の残余は、4時間×8分の5≒3時間となります。(1時間未満の端数は切り上げます。)
所定労働時間が4時間に変更になった後に取得できる年次有給休暇は、日数の10日は変更になりませんが、時間数の方は5時間から3時間に変更されます。
ちなみに、日数は10日で変わりませんが、1日当たりの時間数は、変更前は8時間、変更後は4時間です。
(H21.10.5基発1005号第1号)
③【H25年出題】 〇
時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象となります。
ただし、労働者が時間単位の取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位の取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められません。
(H21.5.29 基発0529001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-195
R6.3.9 健康保険の被扶養者となる要件
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第3条第7項 健康保険法において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 (1) 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの (2) 被保険者の3親等内の親族で(1)に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (3) 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの (4) (3)の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
★後期高齢者医療の被保険者等その他健康保険法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、被扶養者となりません。
★養父母と養子は、父母と子に含まれます。
★被扶養者として認定されるには、「国内居住要件」を満たす必要があります。
■国内居住要件の考え方は以下の通りです。
・住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たす
・ただし、住民票が日本国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、保険者において、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断して差し支えない
■国内居住要件の例外について
外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者については、日本国内に住所がないとしても、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱うとされています。
例外事由は以下の通りです。
| ①外国において留学をする学生 |
| ②外国に赴任する被保険者に同行する者 |
| ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
| ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの |
| ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
(則第37条の2、令1.11.13保保発1113第1号)
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。
②【H30年出題】(改正による修正あり)
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定される。なお、被扶養者の国内居住要件等は満たしているものとする。
③【R2年出題】
被保険者(海外に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。
④【R2年出題】
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。

【解答】
①【R4年出題】 ×
被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の父母及び子は、その被保険者と「同一の世帯」に属し、主としてその被保険者により生計が維持されていれば、被扶養者となります。世帯を別にしている場合は、被扶養者になりません。
(第3条第7項第3号)
②【H30年出題】 〇
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡し、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持される当該父母及び子は被扶養者に認定されます。
(第3条第7項第4号)
③【R2年出題】 ×
被保険者の被扶養者である配偶者の父が被扶養者となるには、「被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する」ことが条件です。問題文の場合は、同一世帯要件を満たしていません。また、国内居住要件も満たしていません。
(第3条第7項第2号)
④【R2年出題】 〇
「外国に赴任する被保険者に同行する者」は、国内居住要件の例外として取り扱われます。
「外国に赴任する被保険者に同行する者」の確認は、「家族帯同ビザ」の確認により判断することを基本とします。
(令1.11.13保保発1113第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-181
R6.2.24 <健保>正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき(横断もあり)
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
第122条 第116条、第117条、第118条第1項及び第119条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。この場合において、これらの規定中「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えるものとする。 |
ポイント!
「全部又は一部」ではなく、「一部」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
②【H30年出題】
保険者は、被保険者の被扶養者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の全部を行わないことができる。
③【R2年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「一部」を行わないことができる」です。
(第119条)
②【H30年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、当該被扶養者に係る保険給付の「一部」を行わないことができる」です。全部ではありません。
被扶養者にも準用されます。
(第119条、第122条)
③【R2年出題】 〇
「療養の指示に従わない者」とは
(1)保険者又は療養担当者の療養の指示に関する明白な意志表示があったにもかかわらず、これに従わない者
(2)診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付費の増加をもたらすと認められる者
とされています。
(昭26.5.9保発第37号)
(横断編) 他の科目の過去問もどうぞ!
<労災保険H26年出題>
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
<国民健康保険R3年出題>
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

【解答】
<労災保険H26年出題> 〇
「正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる」です。「全部又は一部」がポイントです。
条文を読んでみましょう。
労災保険法第12条の2の2第2項 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
<国民健康保険R3年出題> 〇
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の「一部」を行わないことができる」です。健康保険法と同じく「一部」がポイントです。
条文を読んでみましょう。
国民健康保険法第62条 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-171
R6.2.14 資格喪失後の出産育児一時金
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付) 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |
資格喪失後の出産について、出産育児一時金を受けることができる条件は次のとおりです。
・資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと
・資格を喪失した日後6月以内に出産したこと
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給できることとなる。
②【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
③【H30年出題】
被保険者の資格喪失後の出産により出産育児一時金の受給資格を満たした被保険者であった者が、当該資格喪失後に船員保険の被保険者になり、当該出産について船員保険法に基づく出産育児一時金の受給資格を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
例えば、ある人が会社を退職した後、会社員の夫の健康保険の被扶養者となりました。
資格喪失後6か月以内に出産した場合、被保険者本人としての出産育児一時金を受けるか、被扶養者としての家族出産育児一時金を受けるかは、請求者の選択によります。
(昭48.117保険発99号)
②【H28年出題】 ×
1年以上健康保険法の規定による被保険者であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、当該被保険者であった者が、第106条の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給が行われます。
なお、健康保険の保険者から出産育児一時金の支給を受ける場合には、国民健康保険の保険者は出産育児一時金の支給を行いません。
(平23.6.3保保発0603第2号/保国発0603第2号/)
③【H30年出題】 ×
まず、条文を読んでみましょう。
第107条 (船員保険の被保険者となった場合) 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金の給付」の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。 |
資格喪失後に船員保険の被保険者になった場合は、資格喪失後の出産育児一時金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-161
R6.2.4 全国健康保険協会について
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合の2つがあります。
今回は、「全国健康保険協会」についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険) ① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。 ② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第7条の2(設立及び業務) ① 健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。 ② 協会は、次に掲げる業務を行う。 (1) 保険給付及び日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務 (2) 保健事業及び福祉事業に関する業務 (3) 前2号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第5条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの (4)~(6)は省略します ③ 協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
第123条 ① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。 ② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
過去問をどうぞ!
①【R5年選択式】
健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、< A >が行う。
②【H29年出題】
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
③【R1年出題】
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

【解答】
①【R5年選択式】
A 厚生労働大臣
全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定、保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)、これらに附帯する業務は厚生労働大臣が行います。
全国健康保険協会管掌健康保険の資格の得喪、標準報酬月額などの決定、保険料の徴収の業務は、厚生年金保険とセットで、厚生労働大臣が行います。
任意継続被保険者は厚生年金保険に加入しませんので、除かれます。
②【H29年出題】 ×
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく、「全国健康保険協会」が行います。
「保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う」の部分は正しいです。
条文で確認しましょう。
第155条 (保険料) ① 保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金並びに健康保険組合においては、日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 ② 協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。 |
③【R1年出題】 ×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会です。
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。
(法第123条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 健康保険法
R6-151
R6.1.25 標準賞与額の決定と保険料の徴収
過去問から学びましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう
第45条第1項 (標準賞与額の決定) 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
第167条第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
健康保険の標準賞与額の上限は、年度の累計額573万円です。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
②【R1年出題】
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。
③【R3年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
その月の賞与額から千円未満の端数を切り捨てた額が、その月の標準賞与額となります。
ただし、その年度の標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合は、累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とされます。
「540万円」が誤りです。
(法第45条)
②【R1年出題】 〇
賞与の累計は、「保険者単位」とされています。
同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、同一の保険者である期間に支払われた賞与で累計します。
全国健康保険協会管掌健康保険の事業所の賞与が7月150万円、健康保険組合管掌健康保険の事業所の賞与が12月250万円、翌年3月200万円の場合は、全国健康保険協会管掌健康保険の分が7月150万円、健康保険組合管掌健康保険の分が12月250万円、3月200万円となります。
(H18.8.18 事務連絡)
③【R3年出題】 〇
前月から引き続き被保険者の場合、資格を喪失した月の賞与は、保険料の徴収の対象になりません。
ただし、標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額には含まれます。
(平成19年5月1日庁保険発第0501001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-136
R6.1.10 健康保険法の時効の起算日
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「時効」について条文を読んでみましょう。
第193条 (時効) ① 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 ② 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 |
今日は、時効の起算日をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
②【H30年出題】
療養費の請求権の消滅時効については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日より起算される。例えば、コルセット装着に係る療養費については、コルセットを装着した日にコルセットの代金を支払わず、その1か月後に支払った場合、コルセットを装着した日の翌日から消滅時効が起算される。
③【H27年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその翌日である。
④【R1年出題】
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。
⑤【H28年出題】※改正による修正あり
健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「療養の給付」は現物給付ですので、時効はありません。
②【H30年出題】 ×
療養費の請求権の消滅時効は、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日の翌日から起算されます。例えば、コルセット装着については、療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日は、「コルセットを装着した日」ではなく、「コルセットの代金を支払った日」です。消滅時効は、「コルセットの代金を支払った日の翌日」から起算されます。
(S31.3.13保文発第1903号)
③【H27年出題】 〇
傷病手当金の請求権は「労務不能日」に発生しこれを行使し得るものです。そのため、傷病手当金の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算されます。
(S30.9.7保険発第199号)
④【R1年出題】 ×
出産手当金を受ける権利は、「労務に服さなかった日ごとにその翌日」から起算されます。
なお、出産育児一時金は、「出産した日の翌日から」起算されます。
(S30.9.7保険発第199号)
⑤【H28年出題】 ×
高額療養費は診療月の末日ではなく、診療月の翌月の1日が起算日です。
★時効の起算日を確認しましょう。
<療養費>
療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日(療養に要した費用を支払った日)の翌日
(S31.3.13保文発第1903号)
<高額療養費>
診療月の翌月の1日。傷病が月の途中で治ゆした場合も同様。
ただし、診療費の自己負担分を、診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日。
(S48.11.7/保険発第99号/庁保険発第21号/)
<高額介護合算療養費>
計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日
(H21.4.30保保発第0430001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金を受ける権利の消滅時効は2年であるが、その起算日は労務不能であった日ごとにその当日である。

【解答】
【R5年出題】 ×
労務不能であった日ごとにその「翌日」です。
(S30.9.7保険発第199号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-135
R6.1.9 健康保険の擬制的任意適用事業所
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第32条 強制適用事業所が、第3条第3項各号(強制適用事業所の要件)に該当しなくなったときは、その事業所について前条第1項の認可(任意適用の認可)があったものとみなす。 |
例えば、個人事業所の従業員の数が5人未満になった場合、17業種以外の法人の事業所が個人事業になった場合のように、強制適用事業所が、強制適用の要件に該当しなくなったときの取扱いです。
「任意適用の認可があったものとみなす。」とされていますので、改めて任意適用の認可を受けなくても、自動的に適用事業所の資格が継続します。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなったとき、被保険者の2分の1以上が希望した場合には、事業主は厚生労働大臣に任意適用事業所の認可を申請しなければならない。

【解答】
【H27年出題】 ×
強制適用事業所が強制適用事業所の要件に該当しなくなったときは、自動的に、任意適用の認可があったものとみなされます。被保険者の希望があってもなくても、任意適用事業所の認可の申請は不要です。
(第32条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
強制適用事業所が、健康保険法第3条第3項各号に定める強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合において、当該事業所の被保険者の2分の1以上が任意適用事業所となることを希望したときは、当該事業所の事業主は改めて厚生労働大臣に任意適用の認可を申請しなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
強制適用事業所の要件に該当しなくなった場合でも、自動的に適用事業所のままでいられますので、任意適用の認可の申請は不要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-134
R6.1.8 健康保険の強制適用事業所
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険の強制適用事業所について、条文を読んでみましょう。
第3条第3項 健康保険法において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。 ①次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの(個人事業) (1) 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 (2) 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 (3) 鉱物の採掘又は採取の事業 (4) 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 (5) 貨物又は旅客の運送の事業 (6) 貨物積卸しの事業 (7) 焼却、清掃又はと殺の事業 (8) 物の販売又は配給の事業 (9) 金融又は保険の事業 (10) 物の保管又は賃貸の事業 (11) 媒介周旋の事業 (12) 集金、案内又は広告の事業 (13) 教育、研究又は調査の事業 (14) 疾病の治療、助産その他医療の事業 (15) 通信又は報道の事業 (16) 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 (17)弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業 ②①に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの |
強制適用事業所になる事業所は以下の通りです。
| 法人 | 個人事業 |
業種・人数 | 業種問わず、常時1人以上 | 17業種で、常時5人以上 |
※個人事業で、健康保険の適用が任意になる事業所は以下の通りです。
・個人事業で「17業種以外(農林水産業やサービス業など)」の事業所は、5人以上でも5人未満でも人数に関係なく任意です。
・個人事業で「17業種」の事業所でも、5人未満の場合は任意です。
※国、地方公共団体の事業所は、健康保険の強制適用事業所です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
②【H23年出題】
常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
③【R1年出題】
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
法人の代表者であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得します。
代表者が1人の法人の事業所で、代表者以外に従業員を雇用していないものでも、強制適用事業所となります。
(昭和24.7.28保発第74号)
②【H23年出題】 〇
飲食業は「17業種以外」ですので、常時10人の従業員を使用していても、個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはなりません。
「法人である事業所」は業種関係なく、常時1人でも使用していれば強制適用事業所となりますので、「常時3人の従業員を使用している法人の土木、建築等の事業所」は強制適用事業所です。
③【R1年出題】 〇
国、地方公共団体は、健康保険の強制適用事業所です。
そのため、国、地方公共団体に使用される者は健康保険の被保険者です。しかし、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものには、健康保険法による保険給付は行われません。共済で給付が受けられるからです。
条文を確認しましょう。
第200条 (共済組合に関する特例) ① 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない。 ② 共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和4年10月1日より、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業に該当する個人事業所のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所は、健康保険の適用事業所となったが、外国法事務弁護士はこの適用の対象となる事業に含まれない。

【解答】
【R5年出題】 ×
令和4年10月1日から、「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業」が強制適用になる業種に加わりました。
なお、「政令で定める業務」は、「公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士に関する政令第1条に規定する沖縄弁護士、外国法事務弁護士、弁理士」です。(施行令第1条)
「外国法事務弁護士」は適用の対象となる事業に含まれます。
(令第1条第9号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-124
R5.12.29 傷病手当金の支給期間
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項、4項 ① 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ④ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。 |
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。

【解答】
【H28年出題】 〇
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日」から支給されます。
3日を経過した日とは、第4日目以降という意味です。
継続した3日間の待期を満たす必要があり、待期は休日も含んでカウントします。
問題文の待期は、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で完成します。
(S32.1.31保発第2号の2)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が業務外の疾病により労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して4日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
②【R5年出題】
傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合、当該傷病手当金は当該被保険者の死亡日の前日分まで支給される。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「4日」を経過した日からではなく、「3日」を経過した日からです。
例えば、金曜日から労務不能になった場合は、金曜日・土曜日・日曜日の連続した3日間で待期期間が完成し、4日目の月曜日から傷病手当金が支給されます。
| 金 | 土 | 日 | 月 |
| 休 | 休 | 休 | 休 |
②【R5年出題】 ×
被保険者が死亡した場合は、死亡した日の翌日に被保険者資格を喪失しますので、死亡日当日までは、健康保険の被保険者です。
そのため、傷病手当金の支給期間中に被保険者が死亡した場合は、被保険者である死亡日当日分まで支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-123
R5.12.28 産休中・育休中の保険料免除
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「育児休業期間中」の保険料免除について条文を読んでみましょう。
第159条第1項 育児休業等をしている被保険者(第159条の3の規定(産前産後休業中の保険料免除)の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が1か月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る。)は、徴収しない。 1 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 → その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月 2 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合 → 当該月 |
育児休業期間中の保険料の免除について確認しましょう。
1 「育児休業等を開始した日の属する月」から「終了する日の翌日が属する月の前月」までの保険料が免除されます。
2 開始した日と終了する日の翌日が同月内にある場合
→ 14日以上の育児休業を取得した場合はその月の保険料が免除されます。
※「賞与」については、賞与を支払った月の末日を含む1か月を超える育児休業等が免除の対象になります。
「産前産後休業期間中」の保険料免除について条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

【解答】
【H26年出題】 〇
「産前産後休業を開始した日の属する月」から「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間、保険料が免除されます。
ちなみに、「当該被保険者に関する保険料を徴収しない」とは、事業主負担分も被保険者負担分も免除されるという意味です。
(法第159条の3)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
被保険者甲の産前産後休業開始日が令和4年12月10日で、産前産後休業終了日が令和5年3月8日の場合は、令和4年12月から令和5年2月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
②【R5年出題】
被保険者乙の育児休業等開始日が令和5年1月10日で、育児休業等終了日が令和5年3月31日の場合は、令和5年1月から令和5年3月までの期間中の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
③【R5年出題】
被保険者丙の育児休業等開始日が令和5年1月4日で、育児休業等終了日が令和5年1月16日の場合は、令和5年1月の当該被保険者に関する保険料は徴収されない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
免除される期間は、産前産後休業を開始した日の属する月(令和4年12月)からその産前産後休業が終了する日の翌日(令和5年3月9日)が属する月の前月(令和5年2月)までです。
令和4年12月 | 令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 |
12月10日 (開始日) |
|
| 3月9日 (終了日の翌日) |
免除 | 免除 | 免除 |
|
②【R5年出題】 〇
免除されるのは、その育児休業等を開始した日の属する月(令和5年1月)からその育児休業等が終了する日の翌日(令和5年4月1日)が属する月の前月(令和5年3月)までです。
令和5年1月 | 令和5年2月 | 令和5年3月 | 令和5年4月 |
1月10日 (開始日) |
| 3月31日 (終了日) | 4月1日 (終了日の翌日) |
免除 | 免除 | 免除 |
|
③【R5年出題】 ×
育児休業等開始日(1月4日)と終了日の翌日(1月17日)が同一月にあるのがポイントです。
育児休業等を開始した日の属する月と育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一の場合、保険料の免除については育児休業等の日数が14日以上あることが条件です。
問題文の場合は、1月4日から1月16日までで、13日しかありません。そのため、令和5年1月の保険料は免除されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-122
R5.12.27 健康保険の被保険者とならないもの
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう
第3条第1項 健康保険法において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。 1船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。) 2臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては1か月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。) イ日々雇い入れられる者 ロ2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 3事業所で所在地が一定しないものに使用される者 4季節的業務に使用される者(継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く。) 5臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除く。) 6国民健康保険組合の事業所に使用される者 7後期高齢者医療の被保険者等 8厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。) 9 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者 (1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。)又はその1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 ロ 報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が、8万8千円未満であること。 ハ 高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。 |
※(補足)9について
同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間又は1か月の所定労働日数が4分の3未満でも、次の要件に当てはまる場合は、健康保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり8万8千円以上
③学生でない
④特定適用事業所又は任意特定適用事業所に使用されている
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
60日間の期間を定めて雇用される者が、その期間中に負傷し休業のまま引き続き60日を超えて使用期間が存在し、負傷の治癒後に労務に服することが見込まれるときは、61日目から被保険者の資格を取得する。
②【R2年出題】
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
③【R2年出題】
所在地が一定しない事業所に使用される者で、継続して6か月を超えて使用される場合は、その使用される当初から被保険者になる。
④【H26年出題】
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。
⑤【R4年選択】
健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)が1か月当たり< A >であることとされている。

【解答】
①【H22年出題】 〇
「2か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は、健康保険の被保険者になりませんが、例外で、「所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合」は、被保険者となります。
問題文の場合は、所定の期間が60日間ですので、当初は健康保険の被保険者になりません。しかし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った61日目から被保険者の資格を取得します。
(第3条第1項第2号ロ、S5.8.6保規第344号)
②【R2年出題】 ×
「季節的業務に使用される者」は健康保険の被保険者になりませんが、例外的に、当初から「4か月を超えて使用される」予定の場合は、当初から被保険者になります。
問題文のように、季節的業務に使用される者で、「当初4か月以内の期間」の予定が、業務の都合で、継続して4か月を超えたとしても、被保険者になりません。
(第3条第1項第4号)
③【R2年出題】 ×
所在地が一定しない事業所に使用される者は、被保険者になりません。例外規定はありません。
(第3条第1項第3号)
④【H26年出題】 〇
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、被保険者になりません。
(第3条第1項第6号)
⑤【R4年選択】
A88,000円以上
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
適用事業所に臨時に使用される者で、当初の雇用期間が2か月以内の期間を定めて使用される者であっても、就業規則や雇用契約書その他の書面において、その雇用契約が更新される場合がある旨が明示されていることなどから、2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者となる。

【解答】
【R5年出題】 〇
問題文のように、「2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合」は被保険者となります。
最初の雇用契約が2か月以内でも、雇用契約の開始時に2か月以内の雇用契約が更新されることが見込まれる場合には、最初の雇用契約期間の開始時から被保険者資格を取得します。
(第3項第1項第2号ロ、R4.9.9保保発0909第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-121
R5.12.26 療養費の支給
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第87条第1項 (療養費) 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 |
療養費は、「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」又は「保険医療機関等以外の病院等から診療等を受けた場合に、保険者がやむを得ないものと認めるとき」に「療養の給付等」に代えて、「現金」で支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。
②【R1年出題】
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。
③【H21年出題】
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。
④【R3年出題】
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【解答】
①【H27年出題】 〇
無医村で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合は、「療養の給付を行うことが困難であると認めるとき」として、療養費が支給されます。
(S13.8.20社庶第1629号)
②【R1年出題】 ×
療養費の対象になるのは、「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費」の支給を行うことが困難であると認めるときです。訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費の対象になりません。
③【H21年出題】 ×
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、「その受領は事業主等が代理して行う」ものとし、「国外への送金は行わない」ことになっています。「療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金する」は誤りです。
なお、海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用います。
(S56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
④【R3年出題】 〇
療養費の額は、
療養について算定した費用の額 - 一部負担金の割合を乗じて得た額
+
食事療養(又は生活療養)について算定した費用 - 食事療養標準負担額(又は生活療養標準負担額)
を基準として、保険者が定めます。
(第87条第2項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
単に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。
②【R5年出題】
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
単に保険診療が不評だからとの理由で、保険診療を回避した場合は、療養費の支給は認められません。
また、緊急疾病で他に適当な保険医が居るにかかわらず、好んで保険医以外の医師について診療又は手当を受けた時には、療養費は支給しないこととされています。
(S24.6.6保文発第1017号)
②【R5年出題】 〇
問題文にプラスして、以下の点もポイントです。
・現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行う。
・海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる。
(S56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-120
R5.12.25 標準報酬月額の有効期間
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第42条第3項 (被保険者の資格を取得した際の決定) 被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第41条第2項 (定時決定) 定時決定の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
第43条第2項 (随時改定) 随時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の3第2項 (産前産後休業を終了した際の改定) 産前産後休業を終了した際の改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
第43条の2第2項 (育児休業等を終了した際の改定) 育児休業等を終了した際の改定の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
|
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。
②【H24年出題】
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。
③【R3年出題】
その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
資格取得時に決定された標準報酬月額は、1月1日から5月31日までに資格を取得した者は、「その年の8月」まで、6月1日から12月31日までの間に資格を取得した者は、「翌年の8月」までの各月の標準報酬月額となります。
(法第42条第2項)
②【H24年出題】 ×
7月1日に被保険者資格を取得した者は、標準報酬月額の定時決定を行いません。
資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として「翌年の8月」まで用います。
(法第42条第2項)
③【R3年出題】 〇
・1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
↓
原則として、「その年の8月」までの標準報酬月額となります。
・7月から12月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
↓
原則として、「翌年の8月」までの標準報酬月額となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月までの各月の標準報酬月額とされる。当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までの各月の標準報酬月額とする。なお、当該期間中に、随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けないものとする。

【解答】
【R5年出題】 〇
産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額の有効期間は、「産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月まで」です。
※当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年8月までとなります。
例えば、12月25日に産前産後休業が終了した場合は、「産前産後休業終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月」は、2月です。
産前産後休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は3月からその年の8月までが有効期間となります。
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
~ | 8月 |
産休終了翌日 |
| 2か月経過月 | 改定 |
|
(第43条の3第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-119
R5.12.24 任意継続被保険者の保険料の前納
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) ① 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 |
「前納」のポイントを穴埋めでチェックしましょう
 令第48条 (保険料の前納期間)
令第48条 (保険料の前納期間)
任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。
ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する< A >以降の期間又はその資格を喪失する日の属する< B >までの期間の保険料について前納を行うことができる。
 令第49条 (前納の際の控除額)
令第49条 (前納の際の控除額)
法第165条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円として計算する。)を控除した額とする。
 則第139条第1項 (任意継続被保険者の保険料の前納)
則第139条第1項 (任意継続被保険者の保険料の前納)
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< D >までに払い込まなければならない。

【解答】
A 月の翌月
B 月の前月
C 年4分
D 初月の前月末日
過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
②【H22年選択式】
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< A >である。

【解答】
①【H26年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料を前納する期間は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間が単位です。
6か月又は12か月の間に、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかな場合は、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料を前納することができます。
(令第48条)
②【H22年選択式】
(A) 5月
6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者は、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料について前納を行うことができます。
(令第48条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができるが、前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
【R5年出題】 〇
「各月の初日が到来したとき」がポイントです。
(第165条)
※国民年金との違いを確認しましょう。
国民年金の第1号被保険者も保険料を前納することができます。国民年金の場合は、「前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。」となります。違いに注意しましょう。(国民年金法第93条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-118
R5.12.23 国又は地方公共団体負担の医療と健康保険の調整
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第55条第4項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 |
同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において療養の給付等は行われません。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
②【H16年出題】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
災害救助法の目的は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」です。
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われません。
②【H16年出題】 〇
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付では、健康保険による保険給付が優先されます。
費用のうち健康保険の保険給付が及ばない部分(自己負担分)が、生活保護法の医療扶助の対象となります。
(生活保護法第4条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

【解答】
【R5年出題】 〇
同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行われません。
(第55条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-117
R5.12.22 少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁されたときの保険給付
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第118条 ① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 ② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 |
少年院等に収容されたとき、刑事施設、労役場に拘禁されたときは、公費負担で療養が行われますので、健康保険の保険給付は制限されます。
制限されるのは、「疾病、負傷、出産」で、死亡については制限はありません。
また、傷病手当金、出産手当金の支給について制限が行われるのは、厚生労働省令で定める場合に限ります。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
②【H29年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。
③【H22年出題】
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
保険者は、被保険者が少年院等に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行いません。しかし、被保険者がそのようなときでも、被扶養者に係る保険給付は行われます。
(第118条第1項、2項)
②【H29年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場等に拘禁された場合でも、被扶養者に対する保険給付は行われます。
(第118条第2項)
③【H22年出題】 ×
第118条の規定は、「被扶養者」について準用されます。その場合、「保険給付」とあるのは、「当該被扶養者に係る保険給付」と読み替えます。
(第122条)
被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、その期間に係る保険給付はすべて行わないではなく、「その期間に係る当該被扶養者に係る保険給付は行わない」となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたときのいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行わないが、その被扶養者に係る保険給付も同様に行わない。

【解答】
【R5年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、少年院等に収容されたとき又は刑事施設、労役場等に拘禁された場合でも、その被扶養者に係る保険給付は行われます。
(第118条第1項、2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-116
R5.12.21 特定長期入院被保険者が療養の給付と併せて受けた生活療養
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「特定長期入院被保険者」の定義を確認しましょう。
「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者のこと。 (第63条第2項第1号) |
では、「入院時生活療養費」の条文を読んでみましょう。
第85条の2第1項~3項 (入院時生活療養費) ① 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 ② 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、生活療養標準負担額を控除した額とする。 ③ 厚生労働大臣は、②の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
過去問をどうぞ!
【H26年選択式】
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

【解答】
A 介護保険法
「生活療養標準負担額」の定義についての問題です。
生活療養標準負担額は、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
(第85条の2第2項)
入院時生活療養費は、「生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額」から、「生活療養標準負担額」を控除した額です。
生活療養標準負担額は、一般の所得の場合は、食費(1食460円又は420円)+居住費(1日370円)です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の被保険者)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
②【R5年出題】
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会に諮問するものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用については、入院時食事療養費ではなく「入院時生活療養費」が支給されます。
(第85条の2第1項)
②【R5年出題】 ×
厚生労働大臣は、入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を定めようとするときは、社会保障審議会ではなく、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとされています。
(第85条の2第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-115
R5.12.20 療養の給付に含まれないもの
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第63条第1項、2項 (療養の給付) ① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ② 次に掲げる療養に係る給付は、療養の給付に含まれないものとする。 1 食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く。以下「食事療養」という。) 2 次に掲げる療養であって入院療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) イ 食事の提供である療養 ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 3 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療 養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) 4 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) 5 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) |
「食事療養」、「生活療養」、「評価療養」、「患者申出療養」、「選定療養」は療養の給付の対象になりません。
「食事療養」を受けた場合は「入院時食事療養費」、「生活療養」を受けた場合は「入院時生活療養費」、「評価療養、患者申出療養、選定療養」を受けた場合は「保険外併用療養費」の対象になります。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】※改正による修正あり
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

【解答】
【H28年出題】 〇
「患者申出療養」は療養の給付の対象にはなりません。
患者申出療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給されます。
(第63条第2項、第86条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)は、療養の給付に含まれる。

【解答】
【R5年出題】 ×
『食事の提供である療養であって入院療養と併せて行うもの(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者に係るものを除く。)』は、「食事療養」として、「入院時食事費療養」が支給されます。「食事療養」は療養の給付には含まれません。
(イメージ図)
入院療養 | 療養の給付 | 一部負担金 |
+
食事療養 | 入院時食事療養費 | 食事療養標準負担額 |
ちなみに、「療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者」のことを、「特定長期入院被保険者」といいます。
特定長期入院被保険者が、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用については、「入院時生活療養費」が支給されます。
※生活療養とは
・食事の提供である療養
・温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
のことです。
(第63条第2項、第85条、第85条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-100
R5.12.5 保険料の繰上徴収
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第172条(保険料の繰上徴収) 保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 2 法人である納付義務者が、解散をした場合 3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 |
健康保険の保険料の納付期限は翌月末日です。しかし、要件に該当した場合、納期前でも保険料を徴収することができる場合があります。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であってもすべての保険料を徴収することができる。
②【H23年出題】
被保険者の使用されている事業所が廃止されたとき、納期前であっても保険料はすべて徴収することができる。
③【H30年出題】
工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険料の繰上徴収が認められます。
②【H23年出題】 〇
被保険者の使用されている事業所が廃止された場合は、保険料の繰上徴収が認められます。
③【H30年出題】 ×
工場または事業場の譲渡によって事業主が変更した場合は、「事業所の廃止」に含まれますので、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当します。
(S5.11.5保理513)
令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
健康保険法第172条によると、保険料は、納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
②【R5年出題】
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料の納期が到来したときに初めて強制的に保険料を徴収することができる。

【解答】
①【R5年出題】 〇
納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険料の繰上徴収が認められます。
②【R5年出題】 ×
国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるときは、保険料の繰上徴収が認められます。
保険料の納付義務者が、国税、地方税その他の公課の滞納により、滞納処分を受けるときは、保険者は、保険料を納期前であってもすべて徴収することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-092
R5.11.27 準備金の積立
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
「準備金」について条文を読んでみましょう。
第160条の2 (準備金) 保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
令第46条、令附則第5条 (準備金の積立て) ① 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の 2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
② 健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。 |
★保険者は、準備金を積み立てなければなりません。
・全国健康保険協会は、「保険給付」と「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の1=1か月分」の準備金を積み立てなければなりません。
・健康保険組合は、「保険給付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)=当分の間2か月分」と、「高齢者拠出金等の納付」の費用の支出に備えるため、「1事業年度当たりの平均額の12分の1=1か月分」の準備金を積み立てなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の3分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。
②【R1年選択式】
全国健康保険協会は、毎事業年度末において、< A >において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の< B >に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
全国健康保険協会の準備金の問題です。
準備金として積み立てなければならないのは、保険給付に要した費用の額の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」です。3分の1ではありません。
また、保険給付に要した費用の額は、「前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除く。)」となります。
(令第46条第1項)
②【R1年選択式】
①と同じく全国健康保険協会の準備金の問題です。
<A> 当該事業年度及びその直前の2事業年度内
<B>12分の1
(令第46条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が法第63条第3項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の12分の3(当分の間、12分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の 1事業年度当たりの平均額の12分の2に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
健康保険組合の準備金の問題です。
前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1事業年度当たりの平均額の「12分の1」に相当する額です。12分の2ではありません。
(令第46条第2項、令附則第5条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-086
R5.11.21 健康保険の被保険者資格
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
健康保険法では、『「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。』と定義されています。(法第3条第1項)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。
②【H26年出題】
適用事業所に期間の定めなく採用された者について、就業規則に2か月の試用期間が定められている場合は、その間は、被保険者とならず、試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日」に取得します。(法第35条)
「適用事業所に使用されるに至った日」とは、事実上の使用関係の発生した日です。事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、「事実の日にさかのぼって」資格を取得します。資格取得日を「調査の日」とするのは誤りです。
(昭和5.11.6保規第522号)
②【H26年出題】 ×
試用期間が定められていたとしても、被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日=雇入れの当初」から取得します。試用期間中も被保険者となります。「試用期間を経過した日の翌日から被保険者となる」は誤りです。
(昭和13.10.22社庶第229号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止された場合、例えば病気休職であって実務に服する見込みがあるときは、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しない。
②【R5年出題】
事業所の休業にかかわらず、事業主が休業手当を健康保険の被保険者に支給する場合、当該被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
<健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則等により雇用関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合>
・ 例えば病気休職等の場合は、賃金の支払停止は一時的なものであり使用関係は存続するものとみられるため、被保険者資格は喪失しません。
・ なお、被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込みがない場合又は公務に就任しこれに専従する場合等においては被保険者資格を喪失させるのが妥当とされています。
(昭和26.3.9保文発第619号)
②【R5年出題】 ×
事業主が休業手当を支給する期間中は、被保険者資格を継続させること、とされていますので、問題文の被保険者の健康保険の被保険者資格は喪失しません。
(昭和25.4.14保発第20号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-079
R5.11.14 傷病手当金の継続給付
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
第108条第5項 傷病手当金の継続給付を受けるべき者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者でないこととする。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
傷病手当金の継続給付を受ける者が、老齢基礎年金や老齢厚生年金等の支給を受けることができるときは、原則として、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるとき、「傷病手当金」は支給されません。
ただし、老齢退職年金給付÷360(1日当たり単価です)が、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
(則第89条第2項)
②【H27年出題】 〇
老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受ける者に限られます。「適用事業所に使用される被保険者」=在職中の者は、傷病手当金と「老齢基礎年金及び老齢厚生年金」との調整は行われません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金の継続給付を受けている者(傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。)に、老齢基礎年金や老齢厚生年金等が支給されるようになったときは、傷病手当金は打ち切られる。

【解答】
【R5年出題】 ×
傷病手当金の継続給付と「老齢基礎年金・老齢厚生年金等」との調整のポイント!
★ 日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者は、傷病手当金の継続給付と「老齢基礎年金・老齢厚生年金等」との調整の対象から除かれます。「傷病手当金を受けることができる日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む。」は誤りです。
★ 「傷病手当金」は原則として支給されませんが、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の方が少ないときは差額が支給されます。差額が支給されることもありますので、「打ち切られる」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-073
R5.11.8 随時改定「固定的賃金の変動」の具体例
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
今日は随時改定です。
条文を読んでみましょう。
第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 随時改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
★随時改定の要件は次の3つです。
ⅰ 昇給や降給で固定的賃金が変動した
ⅱ 変動した月から3か月間の報酬の平均による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
ⅲ 3か月間の全ての月の報酬支払基礎日数が17日以上である。(短時間労働者は11日以上)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が産前産後休業をする期間について、基本給は休業前と同様に支給するが、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないことから、賃金体系の変更にはあたらず、標準報酬月額の随時改定の対象とはならない。
②【R4年出題】
自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
産前産後休業中に、通勤の実績がないことにより、通勤手当が支給されない場合は、その事業所の通勤手当の制度自体が廃止されたわけではないので、賃金体系の変更にはあたらず、随時改定の対象となりません。
(R4.9.5事務連絡より)
随時改定の要件の一つに、「固定的賃金の変動」があります。
給与体系の変更は固定的賃金の変動に当たりますが、「給与体系の変更に当たらない」事例の問題です。
②【R4年出題】 ×
単価の変動が月ごとに生じる場合でも、固定的賃金の変更として取り扱います。
ガソリン単価を月単位で見直し、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合は、随時改定の対象となります。
(R4.9.5事務連絡より)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
X事業所では、新たに在宅勤務手当を設けることとしたが、当該手当は実費弁償分であることが明確にされている部分とそれ以外の部分があるものとなった。この場合には、当該実費弁償分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。また、当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象にはならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
ポイント!
★在宅勤務手当の考え方
・実費弁償分 → 「報酬等」に含まれません。例えばパソコンの購入や通信に要する費用などです。
・実費弁償に当たらないもの(労働の対償として支払われる性質のもの) → 「報酬等」に含まれます。例えば、毎月5000円を渡し切りで支給するものです。
★在宅勤務手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないため、随時改定の対象になりません。
(R4.9.5事務連絡より)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-066
R5.11.1 家族出産育児一時金のポイント
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第114条 (家族出産育児一時金) 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、政令で定める金額を支給する。 |
被扶養者が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。
被扶養者ではなく「被保険者」に対し支給されるのがポイントです。
家族出産育児一時金の額は、出産育児一時金と同額です。
「出産育児一時金」の額は、令和5年4月1日に改正されています。
・産科医療補償制度に加入する医療機関等で、妊娠週数22週以降に出産した場合は、 1児につき「50万円」が支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合・産科医療補償制度に加入する医療機関等でも妊娠週数22週未満で出産した場合は、「48万8千円」となります。
(令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。
②【H23年出題】
被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、その被保険者に対して政令で定める金額を支給する。
③【H27出題】※改正による修正あり
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50万円、それ以外のときには 48万8千円である。

【解答】
①【R3年出題】 ×
家族出産育児一時金は、「被保険者の被扶養者」が出産したときに支給されます。配偶者だけでなく、被保険者の被扶養者である子が出産した場合も対象です。
②【H23年出題】 〇
「家族」に関する保険給付は、「被保険者に対して」支給されるのがポイントです。
「被扶養者に対して支給する」となっていると誤りです。
③【H27出題】※改正による修正あり 〇
出産育児一時金として政令で定める金額は、48万8千円です。ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)の場合は、1万2千円が加算され50万円となります。
(令第36条、令和5.3.30保保発 0330 第 13 号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】
【R5年出題】 〇
1児あたり50万円ですので、双子の場合は100万円となります。
(昭16.7.23社発第991号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-060
R5.10.26 任意継続被保険者の資格喪失
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第48条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(④から⑥までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 ① 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 ② 死亡したとき。 ③ 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 ④ 被保険者となったとき。 ⑤ 船員保険の被保険者となったとき。 ⑥ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 ⑦ 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
|
★「翌日」喪失が原則ですが、④から⑥に当てはまる場合は、「その日」に資格を喪失します。
★⑦について
任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、保険者に申し出た場合は、「その申出が受理された日の属する月の末日の翌日=申出が受理された日の属する月の翌月1日」に資格を喪失します。
例えば、4月6日に資格喪失の申出が受理された場合は、5月1日が資格喪失日となります。その場合、4月分の保険料の納付が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
②【H30年出題】
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
③【H29年出題】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【H26年出題】 ×
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に資格を喪失します。
②【H30年出題】 ×
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になったときは、2年経過していなくても、その日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
③【H29年出題】 〇
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、「その月の10日」です。
保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、「納付期日の翌日」に任意継続被保険者の資格を喪失します。
なお、初めて納付すべき保険料の納付期日は、「保険者が指定する日」までです。
また、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、「任意継続被保険者とならなかったもの」とみなされます。
(法第37条第2項、第164条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をしたが、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前であり、当該月の保険料をまだ納付していなかった場合、健康保険法第38条第3号の規定に基づき、当該月の保険料の納付期日の翌日から資格を喪失する。

【解答】
【R5年出題】 〇
任意継続被保険者が任意の資格喪失の申出をした場合は、申出が受理された日の属する月の翌月1日に資格を喪失します。
しかし、申出のあった日が保険料納付期日の10日より前で、その月の保険料を納付期日までに納付しなかった場合は、その月の保険料の「納付期日の翌日」に資格を喪失します。
(令和3.11.10事務連絡「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-055
R5.10.21 日雇特例被保険者の保険料納付要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は健康保険法です。
日雇特例被保険者が保険給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければりません。
★ 保険料納付要件を確認しましょう。
・ 保険給付を受ける日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
又は
・ 保険給付を受ける日の属する月の前6月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていること
例えば、10月23日に療養の給付を受ける場合は、
・8月1日から9月30日までの間に、通算して26日分以上の保険料が納付されている
又は
・4月1日から9月30日までの間に、通算して78日分以上の保険料が納付されている
ことが必要です。
(法第129条第2項など)
★ 被保険者の出産については、保険料納付要件が緩和されるのがポイントです。
(「出産育児一時金」、「出産手当金」の要件)
・ 出産の日の属する月の前4月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていること
(法第137条)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
②【H30年出題】
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前4か月間に通算して30日分以上の保険料がその者について納付されていなければ、出産育児一時金が支給されない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に、事業主が印紙をはり、消印を行う方法で行います。
②【H30年出題】 ×
その出産の日の属する月の前4か月間に通算して「30日分」以上ではなく、「26日分」以上の保険料がその者について納付されていなければなりません。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

【解答】
【R5年出題】 〇
日雇特例被保険者の被扶養者の出産については、保険料納付要件は緩和されません。
原則の保険料納付要件(「前2か月間に通算して26日分以上」又は「前6か月間に通算して78日分以上」)を満たさなければなりません。
(法第144条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-046
R5.10.12 訪問看護療養費の支給要件
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第88条第1項・2項 (訪問看護療養費) ① 被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。 ② 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
則第67条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。
則第68条 法第88条第1項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】※改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
②【H24年出題】
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
③【H25年出題】
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
④【R3年出題】
指定看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

【解答】
①【H28年選択式】※改正による修正あり
A 保険者
B 自己
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給されます。
②【H24年出題】 ×
訪問看護は、「看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士」が行います。
「医師、歯科医師」は入らないのがポイントです。
③【H25年出題】 ×
「保険医療機関等」又は「介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護医療院」によるものは、訪問看護から除かれます。
「保険医療機関の看護師」から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、療養の給付の対象となります。
④【R3年出題】 〇
キーワードを穴埋めで確認しましょう。
★指定看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(< A >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する< B >若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。
A 主治の医師
B 介護老人保健施設
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。指定訪問看護を受けられる者の基準は、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者であって、主治医が訪問看護の必要性について、被保険者の病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要する状態に適合すると認めたものである。なお、看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士をいう。

【解答】
【R5年出題】 〇
チェックポイントは以下の2点です。
・保険者が必要と認める場合に限り、支給する
・看護師等とは、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-037
R5.10.3 資格喪失後の傷病手当金の継続給付
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
資格喪失後に継続して傷病手当金を受給するには、「被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと」、「資格喪失時に傷病手当金の支給を受けていること(又は受けられる状態にあること)」が必要です。
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
【H28年出題】 ○
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるには、資格喪失時に傷病手当金の支給を受けていること(又は受けられる状態にあること)が必要です。
また、傷病手当金は、待期期間(継続3日の労務不能日)を満たせば、4日目以降に支給が開始されます。
労務不能となった日から3日目に退職した場合は、退職日に傷病手当金を受けられる状態にありません。そのため、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることはできません。
(S32.1.31保発第2号の2)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年4月1日に被保険者の資格を喪失した甲は、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)期間を有する者であった。甲は、令和5年3月27日から療養のため労務に服することができない状態となったが、業務の引継ぎのために令和5年3月28日から令和5年3月31日までの間は出勤した。この場合、甲は退職後に被保険者として受けることができるはずであった期間、傷病手当金の継続給付を受けることができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
甲は、資格喪失時に傷病手当金を受けられる状態にありませんので、傷病手当金の継続給付を受けることができません。
3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 |
休 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 喪失 |
待期期間を満たしていませんので、傷病手当金の支給要件を満たしていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-028
R5.9.24 傷病手当金の待期について
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金を受けるには、連続3日間の待期期間を満たすことが必要です。
過去問をどうぞ!
【H21年出題】
傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能となった場合は待期の適用は行われない。

【解答】
【H21年出題】 ○
待期は最初に1回満たせば良く、その後労務に服した後再び同じ疾病又は負傷につき労務不能となった場合には、待期は不要です。
(昭2.3.11保理1085)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
傷病手当金の待期期間について、疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能となった場合のみ待期が適用され、その後労務に服し同じ疾病又は負傷につき再度労務不能となった場合は、待期の適用がない。

【解答】
【R5年出題】 ○
待期は、同じ疾病又は負傷につき、1回満たせば要件を満たします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 健康保険法
R6-018
R5.9.14 高額療養費の算定対象に含まれないもの
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、健康保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。

【解答】
【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象になりません。
条文を読んでみましょう。
第115条第1項 (高額療養費) 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 |
高額療養費は、一部負担金等の額が著しく高額なときに支給されます。
「食事療養及び生活療養を除く。」の部分がポイントです。食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費の算定に含まれません。
なお、保険外併用療養に係る自己負担分(差額ベッド代や先進医療にかかる費用など)も対象になりません。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
高額療養費は公的医療保険による医療費だけを算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象とされている。

【解答】
【R5年出題】 ×
食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、保険外併用療養に係る自己負担分は、算定の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 健康保険法
R6-007
R5.9.3 健保選択式は協会けんぽの業務・高額療養費多数回該当・出産手当金からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は健康保険法です。
 Aは全国健康保険協会の業務に関する問題です。
Aは全国健康保険協会の業務に関する問題です。
条文を読んでみましょう。
第5条第2項 (全国健康保険協会管掌健康保険) 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。 |
全国健康保険協会が管掌する業務のうち、①資格の取得・喪失の確認、②標準報酬月額・標準賞与額の決定、③保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)、④①~③に附帯する業務は、「厚生労働大臣」が行います。厚生年金保険と一体化している業務だからです。
なお、全国健康保険協会の任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく、全国健康保険協会が行います。任意継続被保険者は厚生年金保険に加入していないからです。
Aには「厚生労働大臣」が入ります。
 BからDは、高額療養費多数回該当の問題です。
BからDは、高額療養費多数回該当の問題です。
高額療養費多数回該当とは、療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合をいいます。
70歳未満で標準報酬月額が83万円以上の場合、高額療養費算定基準額は252,600円+(医療費-842,000円)×1%ですが、多数回該当の場合は、140,100円となります。
なお、高額療養費は、管掌する保険者が変わった場合は、高額療養費の支給回数は通算されません。
Bは「12か月」、Cは「140,100円」、Dは「通算されない」が入ります。
 Eは出産手当金の問題です。
Eは出産手当金の問題です。
条文を読んでみましょう。
第102条 (出産手当金) 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
Eには、「98」が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 給付制限
健康保険法 給付制限
R5-362
R5.8.24 健康保険給付制限 最終チェック!
健康保険の給付制限をチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
第121条 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
③【H22年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
④【H28年出題】
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
①【R3年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、『自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき』は、当該給付事由に係る保険給付は、行わない、です。
「重過失」は入りません。
②【H23年出題】 ×
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、『その全部又は一部を行わないことができる』です。
「給付の全部について行わないものとする。」は誤りです。
③【H22年出題】 ×
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、『保険給付の一部』を行わないことができる、です。
「保険給付の全部または一部」は誤りです。
④【H28年出題】 〇
正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の『全部又は一部』を行わないことができる、です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 国庫負担
健康保険法 国庫負担
R5-346
R5.8.8 健康保険事業の事務の執行
健康保険の事務費についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。 |
健康保険の事務費については、国が負担しています。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
②【H23年選択式】
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに< B >の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、全国健康保険協会だけでなく、健康保険組合に対しても、国庫が負担しています。
②【H23年選択式】
A 予算
B 介護納付金
C 被保険者数
D 概算払い
★介護納付金とは?
介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料は、医療保険料と一体的に各医療保険者が徴収します。
↓
徴収した介護保険料は、「介護納付金」として社会保険診療報酬支払基金に納付します。
↓
社会保険診療報酬支払基金から、各市町村に交付されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 保険医療機関・保険薬局
健康保険法 保険医療機関・保険薬局
R5-345
R5.8.7 保険医療機関・保険薬局の指定
今日は、保険医療機関・保険薬局の指定をみていきます。
★厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所 → 保険医療機関
★厚生労働大臣の指定を受けた薬局 → 保険薬局
条文を読んでみましょう。
第65条第1項 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
②【H28年出題】
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
③【H22年出題】
保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
・保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行います。
※「厚生労働大臣の指定」の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されています。(第205条、則第159条第1項)
・指定の効力は6年間です。
(法第68条)
②【H28年出題】 ×
「病床の有無に関わらず」が誤りです。
「保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。」のは、保険医個人が開設する診療所です。「病院又は病床を有する診療所」は除かれます。
(法第68条第2項)
③【H22年出題】 ×
保険医療機関又は保険薬局は、「1月以上の予告期間」を設けて、その指定を辞退することができます。
(法第79条第1項)
ちなみに、保険医又は保険薬剤師は、「1月以上の予告期間」を設けて、その登録の抹消を求めることができます。
(法第79条第2項)
保険医療機関・保険薬局は、「指定」、「辞退」
保険医・保険薬剤師は、「登録」、「抹消」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 報酬支払基礎日数
健康保険法 報酬支払基礎日数
R5-344
R5.8.6 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数
定時決定の条文を読んでみましょう。
第41条第1項 (定時決定) 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 |
今日は、報酬支払の基礎となった日数をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

【解答】
【H28年出題】 ×
4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされています。
① 月給者については、各月の暦日数による。
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による。
③ 日給者については、各月の出勤日数による。
問題文の場合は、その月における暦日の数から欠勤日数を控除した日数ではなく、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数が、支払基礎日数となります。
(H18.5.12庁保険発第0512001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 埋葬料と埋葬費
健康保険法 埋葬料と埋葬費
R5-343
R5.8.5 埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合
今日は、埋葬料と埋葬費をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第100条 ① 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、①の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
①埋葬料のポイント!
→被保険者により生計を維持していた者に支給されます。
実際に埋葬を行うことが条件ではありません。
②埋葬費のポイント!
→被保険者により生計を維持していた者がいないとき(=埋葬料の支給を受けるべき者がいないとき)は、実際に「埋葬を行った者」に、5万円の範囲内で埋葬に要した費用(実費)が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
②【H25年出題】
埋葬を行う者とは、埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
③【H28年出題】
被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

【解答】
①【H24年出題】 〇
埋葬料の支給要件の「その者により生計を維持していた者」には、生計の一部を維持していた者も含まれます。
(S8.8.7保発502)
②【H25年出題】 ×
埋葬料は、埋葬を行った事実により支給されるのではなく、被保険者の死亡により支給されるものです。
埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者ではありません。埋葬を行うべき者のことですので、被保険者が死亡し社葬を行った場合で、その被保険者に配偶者がいた場合は、配偶者に埋葬料が支給されます。
③【H28年出題】 〇
被保険者が死亡し、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に実費が支給されます。
別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合は、実際に埋葬を行った弟に、埋葬料の金額の範囲内でその埋葬に要した費用(実費)が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 延滞金
健康保険法 延滞金
R5-342
R5.8.4 健康保険 延滞金の計算
今日は、延滞金の計算についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第181条 ① 督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 1 徴収金額が1000円未満であるとき。 2 納期を繰り上げて徴収するとき。 3 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。 ② 徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。 ③ 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は延滞金の金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 ⑤ 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
②【H27年選択】※改正による修正あり
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。令和5年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.4%とされたため、令和5年における延滞税特例基準割合は年1.4%となった。このため、令和5年における延滞金の割合の特例は、< A >までの期間については年< B >%とされ、< A >の翌日以後については年< C >%とされた。

【解答】
①【H28年出題】 〇
延滞金は、「納期限の翌日」から「徴収金完納又は財産差押えの日の前日」までの期間の日数に応じて算定されます。
問題文の場合は、「納期限の翌日=6月1日」から「完納の日の前日=7月30日」までの日数によって計算します。
②【H27年選択】※改正による修正あり
A 納期限の翌日から3か月を経過する日
B2.4
C8.7
※延滞金の割合の特例の条文を読んでみましょう。
附則第9条 (延滞金の割合の特例)
第181条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
令和5年における延滞税特例基準割合は年1.4%です。
令和5年の延滞金の割合の特例は、
3か月を経過する日までの期間→1.4%+1%=2.4%
3か月を経過する日の翌日以後の期間→1.4%+7.3%=8.7%
となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 標準賞与額
健康保険法 標準賞与額
R5-314
R5.7.7 健保 標準賞与額のポイント
今日は、健康保険の「標準賞与額」をみていきましょう。
なお、賞与とは、「3か月を超える期間ごとに受けるもの」です。
条文を読んでみましょう。
第45条 (標準賞与額の決定) 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 |
則第27条 (賞与額の届出) 被保険者の賞与額に関する届出は、賞与を支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 |
第167条第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
②【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
③【R4年出題】
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
540万円ではなく、「573万円」です。
ポイント!
・標準賞与額は、賞与額から1000円未満を切り捨てた額です。
・年度の累計は、573万円です。累計が573万円に達した後も賞与が支給された場合は、それ以降の標準賞与額は0円となります。
②【H29年出題】 〇
前月から引き続き被保険者だった者が資格を喪失した場合、資格を喪失した月に支給された賞与については、保険料は徴収されません。
※保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月でも、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額の573万円には算入されます。
(H19.5.1庁保険発第0501001号)
③【R4年出題】 〇
資格を取得した月に支給された賞与は、保険料の徴収の対象となります。
6月25日に介護保険の第2号被保険者となった場合は、6月に支給された賞与から、一般保険料額と介護保険料額を控除することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 保険料免除
健康保険法 保険料免除
R5-299
R5.6.22 保険料免除(少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された場合)
少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された期間は、健康保険料は免除されます。
条文を読んでみましょう。
第158条 (保険料の徴収の特例) 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。 ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
※第118条第1項 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 |
少年院に収容された場合等は、公費で医療が行われますので、健康保険の疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われず、また、保険料は徴収されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
②【H29年出題】
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
・ 前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合等
→ 免除される期間は、「該当した月」から該当しなくなった月の「前月」まで
※問題文は、「その翌月以後、拘禁されなくなった月まで」となっているので誤りです。
・ 資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合等
→ 免除される期間は、該当した月の「翌月」から該当しなくなった月の「前月」まで
・ 拘禁された、拘禁されなくなったのが同じ月にある場合
→ 保険料は免除されません。
②【H29年出題】 ×
任意継続被保険者は、刑事施設に拘禁されたとき等でも、保険料の免除はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 給付制限
健康保険法 給付制限
R5-298
R5.6.21 少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された場合の給付制限
さっそく条文を読んでみましょう。
第118条 ① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 ② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 |
ポイントその1
少年院に収容された場合等は、公費で医療が行われますので、健康保険の疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われません。
「死亡」については、健康保険の保険給付が行われます。
ポイントその2
被保険者が少年院、刑事施設、労役場に収容・拘禁されたとき等でも、被扶養者がそれに該当しない場合は、被扶養者に対する保険給付は行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
②【H29年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
被保険者が少年院等に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行われません。
被扶養者については、被扶養者がそのような状態にない場合は、被扶養者に係る保険給付は行われます。
②【H29年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合でも、被扶養者に対する保険給付は行われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金の支給
健康保険法 傷病手当金の支給
R5-297
R5.6.20 傷病手当金と老齢年金の調整
傷病手当金と老齢基礎年金・老齢厚生年金は同時に受けられるでしょうか?
条文を読んでみましょう。
法第108条第5項 傷病手当金の支給を受けるべき者(資格喪失後の継続給付により傷病手当金を受けるべき者に限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
則第89条第2項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
ポイントその1!
老齢退職年金給付と調整されるのは、「資格喪失後の継続給付により傷病手当金を受ける者」に限られます。
老齢退職年金給付を受けることができる者には、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、原則として支給されません。退職後に、老齢年金と傷病手当金の両方が支給されると、所得保障が重複してしまうからです。
ポイントその2!
ただし、「老齢退職年金給付の額÷360」が、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるとき、「老齢退職年金給付は支給されない」ではなく、「傷病手当金は支給されない」です。
ただし、「老齢退職年金給付の額÷360」が、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
②【H27年出題】 〇
「適用事業所に使用される被保険者」=在職中に傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 被保険者の届出
健康保険法 被保険者の届出
R5-281
R5.6.4 同時に2以上の事業所に使用される場合
被保険者が、同時に2以上の事業所に使用される場合の届出をみていきます。
条文を読んでみましょう。
則第1条の2 (選択) ① 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。 ② 当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、①の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
則第2条第1項 (選択の届出) 選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、一定の事項を記載した届書を全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 |
同時に2か所以上の適用事業に使用される場合、被保険者は、10日以内に選択の届出が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。
②【R4年選択式】
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から < A >日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を全国健康保険協会を選択しようとするときは< B >に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
(選択肢)
① 5 ② 7 ③ 10 ④ 14
⑤ 厚生労働大臣 ⑥ 全国健康保険協会の都道府県支部
⑦ 全国健康保険協会の本部 ⑧ 地方厚生局長

【解答】
①【H27年出題】 ×
被保険者が同時に2つの事業所に使用される場合で、それぞれの適用事業所の保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出します。
その場合、2つの事業所の保険者がどちらも全国健康保険協会であっても、管轄する年金事務所が異なる場合は、当該被保険者に関する事務を行う年金事務所を選択することになります。
②【R4年選択式】
A ③ 10
B ⑤ 厚生労働大臣
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 指定健康保険組合
健康保険法 指定健康保険組合
R5-270
R5.5.24 指定健康保険組合による健全化計画の作成
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第28条 (指定健康保険組合による健全化計画の作成) ① 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ② 承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。 ③ 厚生労働大臣は、承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
②【H25年選択式】
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下、「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする< A >の計画とする。
(選択肢)
① 2年間 ② 3年間 ③ 4年間 ④ 5年間

【解答】
①【H30年出題】 ×
「健康保険組合が準用する第7条の39第1項(監督)の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定(健全化計画に従い事業を行わなければならない)に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求め(健全化計画の変更の求め)に応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。」と規定されています。(第29条第2項)
健全化計画に従わない場合は、厚生労働大臣は「当該健康保険組合の解散を命ずることができる」です。
②【H25年選択式】
A ② 3年間
健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3年間」の計画とされています。
(令第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 全国健康保険協会
健康保険法 全国健康保険協会
R5-253
R5.5.7 全国健康保険協会の事業計画や業績評価など
今日は、全国健康保険協会の事業計画や業績評価などをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第7条の27(事業計画等の認可) 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第7条の28(財務諸表等) ① 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。 ② 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第7条の30(各事業年度に係る業績評価) ① 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。 ② 厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
②【H30年出題】
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
③【H23年出題】
全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
毎事業年度の決算は、翌事業年度の5月31日までに完結します。
財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。
②【H30年出題】 〇
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行います。評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければなりません。
③【H23年出題】 ×
全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、評価の結果を通知し、公表しなければならないのは、「全国健康保険協会の理事長」ではなく「厚生労働大臣」です。
また、評価の結果を通知するのは、全国健康保険協会に対してです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 国や地方公共団体の負担との調整
健康保険法 国や地方公共団体の負担との調整
R5-243
R5.4.27 国や地方公共団体が医療費を負担する場合の調整
例えば、災害時などに、国や地方公共団体が医療費を負担する場合があります。
そのような場合の健康保険の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第55条第4項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 |
まず、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。
②【H30年出題】
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
③【H16年出題】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

【解答】
①【R3年出題】 〇
例えば水質汚濁等の公害で病気になった場合は、公害補償法の制度で療養の給付などの補償が行われます。
公害補償法で、補償給付の支給がされた場合は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、健康保険による保険給付は行わない、とされています。
(公害補償法第14条、昭50.12.8保険発第110号・庁保険発第20号)
②【H30年出題】 〇
災害救助法の目的は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」です。
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われません。
③【H16年出題】 〇
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類の保護があります。
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付では、健康保険による保険給付が優先されます。
費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分は、医療扶助の対象となります。
健康保険からの保険給付 | 自己負担分 (医療扶助の給付対象) |
(生活保護法第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 介護保険との関係
健康保険法 介護保険との関係
R5-242
R5.4.26 健康保険と介護保険の給付との調整
介護保険には、医療を提供するサービスもあります。
健康保険と介護保険の医療の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第55条第3項 (他の法令による保険給付との調整) 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
同一の病気やけがについて、介護保険から給付を受けることができる場合は、健康保険の給付は行われません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
②【H22年出題】
被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
③【R4年出題】
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る療養については、医療保険から行うものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
同一の傷病で、介護保険の給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われません。
②【H22年出題】 ×
同一の「疾病、負傷または死亡」の「死亡」の部分が誤りです。介護保険には死亡に関する給付がありませんので、死亡については介護保険との調整は行われません。
③【R4年出題】 〇
介護保険適用病床に入院している要介護者である患者が、急性憎悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合は、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則です。
しかし、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のある場合は、当該病床で療養の給付又は医療が行われることは可能です。
この場合の緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされています。
(H12.3.31保険発第55号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 労災との関係
健康保険法 労災との関係
R5-241
R5.4.25 健康保険と労災保険の調整について
健康保険では、被保険者と被扶養者の「疾病、負傷、死亡、出産」について保険給付を行います。
ただし、労災保険法に規定する「業務災害」にあたるものは、健康保険の対象から除外されます。
「通勤災害」については、健康保険からは除外されていませんが、労災保険から給付を受けることができる場合は、調整が行われます。
では、条文を読んでみましょう。
第55条 第1項(他の法令による保険給付との調整) 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
例えば、通勤途上で事故にあい、労災保険の通勤災害に関する保険給付の受給権を得た場合は、健康保険法からの給付は行われません。
労災保険と健康保険の調整が行われるのは、労災保険法に基づく給付を「受けることができる」ときです。「受けたとき」ではありませんので、労災保険の給付の受給権があれば調整の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
②【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
③【R1年出題】
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険により給付する。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われない。
④【R3年出題】
被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「同一の疾病、負傷又は死亡」について、労働者災害補償保険法の規定により給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われません。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合は、健康保険の埋葬料は支給されません。
②【H28年出題】 〇
請負で働く場合は労働契約関係にないので、労災保険の対象にはなりません。そのため、請負業務中に負傷しても労災保険から保険給付が行われません。そのような場合は、健康保険の給付が行われます。
(平成25.8.14事務連絡)
③【R1年出題】 〇
・事業所について、労災保険が適用されるべきであるにもかかわらず、その適用が行われていない場合、その間に発生した通勤災害については、遡って労災保険から給付されます。
・労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害については、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものは、健康保険から給付が行われます。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われません。
(S48.12.1保険発第105号・庁保険発第24号)
④【R3年出題】 〇
労災保険法における業務災害は、健康保険の給付の対象外です。
また、労災保険法における通勤災害は、労災保険からの給付が優先されます。
そのため、保険者は、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができます。
(平成25.8.14事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 健康保険組合
健康保険法 健康保険組合
R5-227
R5.4.11 健康保険組合の合併・分割・設立事業所の増減・解散の手続
健康保険組合の合併、分割、設立事業所の増減、解散に関しての手続をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第23条第1項 (合併) 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第24条第1項~2項 (分割) ① 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ② 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
第25条第1項 (設立事業所の増減) 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
第26条 (解散) ① 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 1.組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 2.健康保険組合の事業の継続の不能 3.厚生労働大臣による解散の命令 ② 健康保険組合は、前項1.又は2.に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ③ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 ④ 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②【H30年出題】
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
③【R3年出題】
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
④【H23年出題】
健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
⑤【H29年出題】
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
⑥【R3年出題】
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

【解答】
①【H25年出題】 ×
合併の場合は、組合会において組合会議員の定数の「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
②【H30年出題】 ×
分割の場合は、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
③【R3年出題】 〇
健康保険組合に新しく適用事業所が加入する、又は、健康保険組合に加入している設立事業所が分離するときの手続です。
そのような場合は、その増加又は減少に係る適用事業所の「事業主の全部」及びその適用事業所に使用される「被保険者の2分の1以上の同意」を得なければなりません。
④【H23年出題】 ×
健康保険組合の解散の理由は、①組合会議員の定数の「4分の3」以上の多数による組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、の3つです。
なお、①と②は「厚生労働大臣の認可」が必要です。③は厚生労働大臣の命令による強制解散ですので、認可は要りません。
⑤【H29年出題】 〇
解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、「全国健康保険協会」が承継します。
⑥【R3年出題】 〇
健康保険組合が解散する場合に、健康保険組合の財産をもって債務を完済できないときは、「設立事業所の事業主」に対し、債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができます。
健康保険組合と事業主との連帯責任の規定ですので、「被保険者」に対しては負担を求めることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 60歳以上の被保険者
健康保険法 60歳以上の被保険者
R5-214
R5.3.29 60歳以上の被保険者が退職・再雇用される場合
60歳以上の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合の手続をみていきます。
60歳以上の人が退職し再雇用された場合、例えば、正社員から嘱託社員に変わったり、退職金の支払いがあったとしても、1日の空白も無ければ、健康保険の被保険者の資格は継続します。
再雇用後に嘱託社員に変わった場合、報酬が下がることがあります。
通常は、報酬が下がった場合は、随時改定によって標準報酬月額が見直されます。随時改定の場合、標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動(報酬が下がった月)から 4か月目からになります。
そこで、60歳以上の被保険者については、退職し1日の空白も無く再雇用された場合は、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出することができます。
それによって、再雇用された月から、再雇用後の報酬に応じた標準報酬月額に決定されます。
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

【解答】
【R1年出題】 〇
この取扱いは、「60歳」以降に退職後継続して再雇用されるものに対して適用されます。高齢者の継続雇用の支援が目的です。
(H25.1.25保保発0125第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金
健康保険法 傷病手当金
R5-213
R5.3.28 傷病手当金の待期期間
傷病手当金の待期期間をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日」から支給されます。言い換えると、第4日目から支給されます。
傷病手当金が出るまでの3日間のことを待期といいます。
待期は、休業が連続3日で完成します。
例えば、
休 | 休 | 休 | 休 | 出 | 休 |
3日連続して休んでいますので、傷病手当金は4日目から支給されます。
休 | 休 | 休 | 出 | 休 |
3日連続して休んでいるので待期は完成しています。傷病手当金は5日目から支給されます。
休 | 出 | 休 | 休 |
休みが3日連続していないので待期は完成していません。
(参照:S32.1.31保発2号の2)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
②【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。
③【R1年選択】
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から起算されることになる。
<選択肢>
① 4月1日から ② 4月3日から ③ 4月4日から ④ 4月5日から
⑤ 日 ⑥ 日の2日後 ⑦ 日の3日後 ⑧ 日の翌日

【解答】
①【H28年出題】 ×
待期は「労務に服することができなくなった日」から起算します。
ただし、労務に服することができなくなったのが『業務終了後』の場合は「翌日」から起算します。
問題文は、労務に服することができなくなったのが就業中ですので、翌日ではなく「その日」が傷病手当金の待期期間の起算日となります。
(S5.10.13保発52号)
②【H28年出題】 〇
金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
待期は、労務不能の日が連続3日で完成します。所定休日も待期に算入されます。
そのため、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。
③【R1年選択】
A ④4月5日から
B ⑤日
★支給期間の起算日
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
休 | 休 | 休 | 出 | 休 |
1日から3日まで連続3日間休業していますので、待期期間が完成しています。傷病手当金は、再び休業した5日から支給されます。
傷病手当金の支給期間は、「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。問題文の傷病手当金の支給期間は、4月5日から起算します。
★報酬があったため傷病手当金が支給停止されていた場合
報酬を受けることができる場合は、その間は傷病手当金は支給されません。
報酬を受けなくなれば傷病手当金が支給されますので、その場合の傷病手当金の支給期間は、「報酬をうけなくなった日又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった日」から起算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 共済組合の組合員
健康保険法 共済組合の組合員
R5-203
R5.3.18 共済組合の組合員と健康保険の関係
健康保険の強制適用事業所は、以下の通りです。
・常時5人以上の従業員を使用する個人経営の法定17業種の事業の事業所 ・国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの |
★ 国、地方公共団体の事業所も、健康保険の強制適用事業所になることがポイントです。
強制適用事業所に使用される従業員は、当然、健康保険の被保険者となります。そのため、国、地方公共団体に使用される人も健康保険の被保険者となります。
国や地方公共団体に使用される人は、健康保険の被保険者ですが、同時に共済組合の組合員でもあります。
両方から保険給付が行われることのないように、健康保険法では共済組合に関する特例が規定されています。
条文を読んでみましょう。
第200条 (共済組合に関する特例) 1 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない。 2 共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。 |
共済組合の組合員に対しては、健康保険の保険給付は行われません。
※特例の対象になるのは、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者です。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
②【R1年出題】
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】
①【H20年出題】 ×
共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者と「なります」。
しかし、健康保険法からの保険給付は行われません。
②【R1年出題】 〇
「共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。」と規定されています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 保険料免除
健康保険法 保険料免除
R5-192
R5.3.7 産前産後休業中の保険料免除
産前産後の休業期間中は、健康保険の保険料が免除されます。
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
ポイント!
・免除の要件
→ 事業主が保険者等に申出をすること
・免除される期間
→休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
②【R1年出題】
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は 3月分から免除対象となる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
免除されるのは、産前産後休業を開始した日の「属する月」からその産前産後休業が終了する日の「翌日が属する月の前月」までです。
「属する月」と「前月」がチェックポイントです。
ちなみに、事業主負担分、被保険者負担分ともに免除されます。
②【R1年出題】 〇
産前産後休業は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日です。
・5月16日が出産予定日で3月25日から休業していました。
5月16日が出産予定日の場合、出産日以前42日は4月5日~ですので、産前産後休業を開始した日の属する月の「4月」から保険料が免除されます。
・しかし、実際は、予定日より前の5月10日に出産しました。
その場合は、実際の出産日以前42日は、3月30日からとなります。
3月25日から休業していますので、保険料免除の開始は、産前産後休業を開始した日の属する月の「3月」に変更されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 短時間労働者
健康保険法 短時間労働者
R5-181
R5.2.24 短時間労働者の報酬支払基礎日数
健康保険の被保険者となる「短時間労働者」の範囲を確認しましょう。
同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が4分の3未満で、次の要件に当てはまる人です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金の月額が8.8万円以上
③学生でない
④特定適用事業所又は任意特定適用事業所に使用されている
では、定時決定の条文を読んでみましょう。
第41条第1項 (定時決定) 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 |
定時決定は、4月、5月、6月の報酬の平均をとるのが原則です。ただし、その中に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月は除かれます。
短時間労働者の場合は、17日が「11日」となります。短時間労働者の定時決定は、「11日未満の月」を除いて平均を出します。
※随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定についても、短時間労働者は「11日」となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
※本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。
②【R3年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
①【H29年出題】 〇
・短時間労働者の定時決定
→ 報酬支払いの基礎となった日数が11日未満の月は、除きます。
・短時間労働者の随時改定
→ 継続した3か月間の各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、随時改定は行われません。
②【R3年出題】 ×
短時間労働者の定時決定では、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満の月は除いて行われます。
問題文の場合、4月は11日、5月は15日、6月は16日で、すべて11日以上ですので、4月・5月・6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 高額介護合算療養費
健康保険法 高額介護合算療養費
R5-169
R5.2.12 高額介護合算療養費のポイント!
高額介護合算療養費制度とは?
→ 健康保険と介護保険の自己負担の合算額が、限度額を超えた場合に、限度額を超えた額が支給される制度です。
・毎年8月1日から翌年7月31日の1年間が計算期間です。
まず、高額介護合算療養費の条文を読んでみましょう。
第115条の2第1項 (高額介護合算療養費) 一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。
②【H30年出題】
高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
③【R2年出題】
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
④【H25年選択】
高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超えた場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は< A >円である。
70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は < B >円である。

【解答】
①【H25年出題】 ×
高額介護合算療養費は、健康保険の被保険者とその被扶養者で個別にするのではなく、健康保険上の世帯単位(被保険者とその被扶養者)で算定します。
(令43条の2)
②【H30年出題】 ×
高額介護合算療養費は、健康保険法の高額療養費が支給されていることは条件ではありません。なお、高額療養費が支給されている場合は、一部負担金等の額から高額療養費は控除されます。
(令43条の2)
③【R2年出題】 〇
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前と変更後の自己負担額は合算されます。
(令43条の2)
④【H25年選択】
<A>500
<B>670,000
★高額介護合算療養費が支給されるのは、
「介護合算一部負担金等世帯合算額」が「介護合算算定基準額+支給基準額(500円)を超えた場合です。
「支給基準額」とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
高額介護合算療養費が支給されるのは、「介護合算一部負担金等世帯合算額」から「介護合算算定基準額」を控除した額が500円を超える場合に限ります。
(H20年厚生労働省告示225号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金
健康保険法 傷病手当金
R5-161
R5.2.4 労務に服することができないとき
傷病手当金の支給要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
 傷病手当金の支給要件は次の3つです。
傷病手当金の支給要件は次の3つです。
・療養中であること
・労務に服することができないこと
・連続3日間の待期期間を満たしていること
今日は、要件の1つ「労務に服することができない」をみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。
②【R2年出題】
伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。
③【H25年出題】
傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたい」とされています。
・被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能でも、職場転換などで就労可能な他の比較的軽微な労務に服して相当額の報酬を得ている場合
→ 労務不能には該当しません。
・本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業や内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することで賃金を得る場合等
→ 労務不能に「該当します」。
問題文の後半が誤りです。
(H15.2.25保保発第0225007号/庁保険発第4号)
②【R2年出題】 〇
自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解されます。病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となります。
(S29.10.25保険発第261号)
③【H25年出題】 〇
傷病が休業を要する程度でなくても、病院が遠隔地で、通院のため事実上働けない場合には、傷病手金が支給されます。
(S2.5.10保理2211)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 適用除外
健康保険法 適用除外
R5-152
R5.1.26 健保・季節的業務に使用される者
健康保険の適用事業所に使用される者は、被保険者となります。
しかし、一定の者は、健康保険の適用が除外されています。
除外されるものの一つに「季節的業務に使用される者」があります。
「季節的業務に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。」とされています。季節的業務に使用される者は、健康保険の一般の被保険者からは除外されます。
しかし、「継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く。」という例外があります。季節的業務でも当初から継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から一般の被保険者となります。
(法第3条第1項第4号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
②【H25年出題】
季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
季節的業務に当初4か月以内の予定で使用された場合は、一般の被保険者から除外されます。業務の都合等で継続して4か月を超えたとしても一般の被保険者にはなりません。
(S9.4.17保発191)
②【H25年出題】 ×
季節的業務に当初4か月未満の予定で使用された場合は、業務の都合で、継続して4か月以上使用されることになった場合でも被保険者にはなりません。
(S9.4.17保発191)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 被扶養者
健康保険法 被扶養者
R5-143
R5.1.17 被扶養者は原則国内に居住していることが条件
健康保険の被扶養者として認定されるには、原則として、国内に居住していることが条件です。
条文を読んでみましょう。
第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2 被保険者の3親等内の親族で1に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4 3の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
被扶養者の認定基準として、原則として「日本国内に住所を有すること」という条件があります。例外として、日本国内に住所がない場合でも、「外国に一時的に留学する学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる者」があります。
過去問をどうぞ!
①【R2問9-A】
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。
②【R2問3-オ】
被保険者(海外に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

【解答】
①【R2問9-A】 〇
まず、「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」を確認しましょう。
施行規則第37条の2で次のように定められています。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められるもの
⑤ そのほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
問題文は、②外国に赴任する被保険者に同行する者に該当します。
「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とします。
(令元11.13保保発1113 第 1 号)
②【R2問3-オ】 ×
配偶者の父母が被扶養者となるには、生計維持関係があることと、同一世帯に属することが条件です。
問題文の場合、被保険者は国内に居住していて、配偶者の父は国外に居住しているので、同一世帯要件を満たしていません。また問題文の父は、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものにも該当していません。
(則第37条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金
健康保険法 傷病手当金
R5-134
R5.1.8 傷病手当金と休業補償給付の調整
労働者災害補償保険法の休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、業務外の傷病を併発し、その傷病についても労務不能の場合、労災の休業補償給付と、健康保険の傷病手当金は併給できるでしょうか?
では、過去問をどうぞ
【R2問10-A】
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

【解答】
【R2問10-A】 ×
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によっても労務不能の状態になった場合は、原則として、傷病手当金は支給されません。休業補償給付も傷病手当金も生活保障が目的で、両方併せて受けると、就労して受ける収入よりも多くなってしまうからです。
ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額分は支給されます。差額分の傷病手当金が支給されることがあるので、「休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。」が誤りです。
(昭和33年7月8日保険発第95号の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-119
 R4.12.24
R4.12.24 R4択一式より 減給制裁と随時改定の関係
R4択一式より 減給制裁と随時改定の関係
減給制裁が行われた場合、随時改定の対象になるでしょうか?
まず、随時改定の条文を読んでみましょう。
第43条 (随時改定) 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 |
随時改定の要件は次の3つです。
①昇給や降給等で固定的賃金に変動があったこと。
②変動月からの3カ月間の報酬(残業手当等の非固定的賃金を含みます)の平均に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと。
③3カ月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であること。
※要件を満たした場合、報酬が変動した月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

【解答】
【問8-A】 ×
減給制裁は固定的賃金の変動に当たりませんので、随時改定の対象とはなりません。随時改定の手続はできません。
(厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-118
R4.12.23 R4択一式より 夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定
令和元年に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されました。
今日は、上記の附帯決議を踏まえた令和3年の通知で、「夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定」をみていきましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-C】
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。

【解答】
【問4-C】 ×
「健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方」ではなく、「被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする、とされています。
(令和3年4月30日保保発 0430 第 2 号)
改正前は昭和60年通知が基準になっていましたが、現在は令和3年通知に基づきます。
昭和60年通知と令和3年通知を比較してみましょう。
令和3年通知 | 昭和60年通知(廃止) |
被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする。
夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 | 年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること |
※昭和60年通知は廃止されました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-117
R4.12.22 R4択一式より 保険外併用療養費の額
まず、「保険外併用療養費」の制度を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 (保険外併用療養費) 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
第63条第2項3号~5号 ・「評価療養」とは → 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの (例 先進医療など) ・「患者申出療養」とは → 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの ・「選定療養」とは → 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養 (例 差額ベッドなど) |
例えば、自己負担割合3割の被保険者が先進医療を受け、トータルの医療費が80万円でそのうち先進医療に係る費用が30万円だった場合で考えてみましょう。
保険診療 50万円 | 先進医療 30万円 |
・保険給付される部分(保険外併用療養費) 35万円 ・一部負担金に当たる額 15万円 |
全額自己負担 |
通常の治療なら「療養の給付」として支給される部分が、「保険外併用療養費」として支給されます。
本人は、15万円+30万円=45万円を負担します。
ちなみに、保険診療の一部負担金に当たる部分は、高額療養費の対象となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-D】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

【解答】
【問4-D】 ×
保険診療と選定療養を併せて受けた場合は保険外併用療養費の対象となります。
保険診療30万円のうち自己負担額は3割の9万円で、21万円が保険外併用療養費として支給されます。また、選定療養の10万円は全額自己負担です。
被保険者が保険医療機関に支払う額は、9万円+10万円=19万円です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
②【H28年出題】
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用については保険外併用療養費が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
予約診療は選定療養の対象となります。
特別料金は全額自己負担です。通常の治療の部分は、一部負担金に相当する部分は本人が負担しますが、残りは保険外併用療養費として保険給付が行われます。
②【H28年出題】 〇
患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象にはなりません。療養の給付と同じ範囲の部分は、保険外併用療養費として支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-116
R4.12.21 R4択一式より 都道府県単位保険料率の変更の手続
全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130の範囲で支部被保険者を単位として協会が決定します。
※ 支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいいます。
※ 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率のことを「都道府県単位保険料率」といいます。
今日は、都道府県単位保険料率の変更の手続を見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第160条第6項、7項、8項 6 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 7 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
支部長 | 意見を求められた場合 都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合 | 予め評議会の意見を聴く |
↓ | 理事長に対し意見の申出を行う | |
理事長 | 支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経る | |
↓ | 保険料率の変更について認可を申請する | |
厚生労働大臣 | 保険料率の変更について認可する | |
★運営委員会 → 事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に置かれます。
★評議会 → 都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに設けられます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-ウ】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
【問3-ウ】 〇
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときのプロセスです。
①あらかじめ、理事長が支部長の意見を聴く
↓
②運営委員会の議を経る
↓
③理事長は、変更について厚生労働大臣の認可を受ける
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
②【H23年出題】
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

【解答】
①【H26年出題】※改正による修正あり 〇
協会が管掌する健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲で、都道府県ごとに設定されます。
②【H23年出題】 ×
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、「×運営委員会 → 〇理事長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、「×理事長に対しその変更について意見の申出を行う →〇運営委員会の議を経なければならない」となります。
③【R1年出題】 ×
「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。」が誤りです。
法第160条第10項と11項で以下のように定められています。
第10項 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第11条 厚生労働大臣は、協会が10項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-115
R4.12.20 R4択一式より 使用されるに至った日から自宅待機とされた場合
入社することになったものの、入社日から自宅待機となった場合、健康保険の被保険者の資格はどのように扱われるのでしょうか?
資格取得日について条文を読んでみましょう。
第35条 (資格取得の時期) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。 |
 「適用事業所に使用されるに至った日」、「事業所が適用事業所となった日」、「適用除外に該当しなくなった日」に被保険者の資格を取得します。
「適用事業所に使用されるに至った日」、「事業所が適用事業所となった日」、「適用除外に該当しなくなった日」に被保険者の資格を取得します。
適用事業所に入社した場合は、その日に健康保険の被保険者の資格を取得します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-B】
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

【解答】
【問2-B】 〇
当初から自宅待機でも健康保険の被保険者の資格は取得します。
・休業手当は報酬ですので、休業手当の支払いの対象となった日の初日に資格を取得します。
・資格取得時の標準報酬月額は、現に支払われる休業手当等に基づき決定されます。
・休業手当で標準報酬月額が決定した後に、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象となります。
(S50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
過去問をどうぞ!
【R3年出題 】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
【R3年出題 】 〇
★一時帰休に伴って低額な休業手当等が支払われることになった場合
→ 固定的賃金の変動とみなして、随時改定の対象となります。※ただし、報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限ります。
★休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消し、通常の報酬が支払われるようになったとき
→ 随時改定の対象となります。
(S50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-114
R4.12.19 R4択一式より 健康保険組合の設立要件
健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立の2種類ありますが、本日は任意設立を見ていきます。
条文を読んでみましょう。
第11条 1 一又は二以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3000人以上でなければならない。
第12条 1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、同意は、各適用事業所について得なければならない。 |
 健康保険組合は、1社単独で設立する単一組合と、2社以上が共同で設立する総合組合があります。人数要件があり、単独で設立する場合は常時700人以上、共同で設立する場合は常時3000人以上の被保険者が必要です。
健康保険組合は、1社単独で設立する単一組合と、2社以上が共同で設立する総合組合があります。人数要件があり、単独で設立する場合は常時700人以上、共同で設立する場合は常時3000人以上の被保険者が必要です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

【解答】
【問5-B】 〇
健康保険組合を設立するときは、「被保険者の2分の1以上の同意」が必要です。また、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
2以上の適用事業所で健康保険組合を設立する場合、それぞれの適用事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意を得なければなりません。
なお、健康保険組合は、「設立の認可を受けた時に成立」します。(法第15条)
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
②【R3年出題】
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
第205条で、「健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。」と規定されています。しかし、健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長には委任されていません。
ちなみに、健康保険組合の設立の認可の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して行います。(則第3条第2項)
②【R3年出題】 ×
第8条で、「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」と規定されています。特例退職被保険者ではなく、任意継続被保険者です。
ちなみに、「日雇特例被保険者」は入りませんので注意してください。日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会のみだからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-097
R4.12.2 R4択一式より 資格喪失後の継続給付の条件
資格喪失後に、継続して傷病手当金・出産手当金を受けることができます。その条件として、「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった」ことがあります。
今日は、1年の算定ルールを確認しましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 法附則第3条第6項 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが条件です。ただし、この「1年以上被保険者であった」の被保険者には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが条件です。ただし、この「1年以上被保険者であった」の被保険者には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
では、令和4年の問題をどうぞ
【問9-C】
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
【問9-C】 ×
資格喪失後の傷病手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが必要です。ただし、この期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
問題文の場合は、資格喪失の日の前日までの被保険者であった期間は、共済組合の組合員の期間を除くと、10か月しかありません。そのため、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。
②【H23年出題】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
③【H27年出題】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
保険者が異なっていても、資格喪失日の前日まで1日の空白も無く1年以上被保険者であった場合は、資格喪失後も継続して傷病手当金を受けることができます。
②【H23年出題】 ×
資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、要件を満たせば、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができます。
③【H27年出題】 〇
資格喪失後に任意継続被保険者となった場合は、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができます。
一方、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
(法附則第3条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-096
R4.12.1 R4択一式より 介護休業期間中の出産手当金
介護休業期間中でも、出産手当金は支給されるでしょうか?
まず、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

【解答】
【問9-B】 〇
出産手当金の支給要件に該当すると認められる者には、介護休業期間中でも、出産手当金が支給されます。
※ちなみに、「傷病手当金」も同じです。支給要件に該当すれば、介護休業期間中でも、傷病手当金が支給されます。
(H11.3.31保険発46・庁保険発9)
では、次の条文を読んでみましょう。
第108条 (傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) ① 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。 ② 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合は、その期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
報酬の全部又は一部を受けることができる場合は、その期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
出産手当金も同じ扱いです。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。
②【H23年出題】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。

【解答】
①【H27年出題】 〇
要件に該当すれば、介護休業期間中でも出産手当金が支給されます。また、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額について報酬(介護休業手当)との調整が行われます。
(H11.3.31保険発46・庁保険発9)
②【H23年出題】 〇
要件に該当すれば、介護休業期間中でも傷病手当金が支給されます。また、その期間に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について報酬(介護休業手当等)との調整が行われます。
(H11.3.31保険発46・庁保険発9)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-095
R4.11.30 R4択一式より 健保「報酬」の定義
保険料の額や傷病手当金・出産手当金は「標準報酬月額」を使って計算します。
「標準報酬月額」は、「報酬月額」に基づいて決まります。報酬月額は1月当たりの報酬の額のことです。
今日のテーマは、「報酬」の定義です。
では、条文を読んでみましょう。
第3条 5 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 6 健康保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
「報酬」とは → 労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの
※「臨時」に受けるもの、「3月を超える期間ごと」に受けるものは、報酬から除かれます。
「3月を超える期間ごとに受けるもの」とは、年3回以下の賞与などのことです。
「賞与」とは → 「3月を超える期間ごと」に受けるもの
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-B】
健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

【解答】
【問7-B】 〇
3か月を超える期間ごとに受けるものは報酬から除外されます。
3か月を超える期間ごとに受ける報酬に該当するものは、年間を通じ4回以上支給される報酬以外の報酬となります。ですので、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、『年間を通じ4回以上』支給される場合は、報酬に該当します。
(S36.1.26保発第5号)
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
②【R1年出題】
保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
通勤手当は、「報酬」に含まれます。
②【R1年出題】 〇
通勤手当は6か月ごとに支給されても、実態は毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に当てられるものですので、報酬となります。
(昭和27.12.4保文発7241)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-094
R4.11.29 R4択一式より 健康保険組合の役員
今日のテーマは、健康保険組合の役員です。
まず、「組合会」について条文を読んでみましょう。
第18条 (組合会) 1 健康保険組合に、組合会を置く。 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。
|
組合会は、健康保険組合の議決機関で、組合会議員で組織されています。
組合会議員の定数は偶数で、事業主が選定する選定議員と被保険者である組合員が互選する互選議員がそれぞれ半数ずつです。
次に「役員」について条文を読んでみましょう。
第21条 (役員) 1 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。 4 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 5 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。 |
 健康保険組合には、役員として理事及び監事を置くことになっています。
健康保険組合には、役員として理事及び監事を置くことになっています。
理事は組合の執行機関、監事は監査機関です。
理事の定数は、偶数で、事業主の選定した選定議員が半数、被保険者である組合員の互選した互選議員が半数です。
理事長は健康保険組合の代表者です。事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事の選挙で決められます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-C】
健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙で選出する。なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

【解答】
【問5-C】 〇
健康保険組合の監事の任務は、「健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査」することです(第22条第4項)
事業主の選定した選定議員と被保険者である組合員の互選した互選議員のうちから、それぞれ1人が選出されます。
監事には中立が求められるため、理事又は健康保険組合の職員と兼務できません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。
②【H22年出題】
健康保険組合の監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙することになっており、監事のうち一人は理事または健康保険組合の職員を兼ねることができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
健康保険組合の理事は、事業主の選定した組合会議員と被保険者である組合員の互選した組合会議員が半々で構成されています。代表者である理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、「理事が選挙」します。「事業主が選定」は誤りです。
②【H22年出題】 ×
中立的な立場が求められる監事については、理事または健康保険組合の職員を兼ねることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-068
R4.11.3 R4択一式より 資格喪失後の出産手当金の継続給付
出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間について支給されます。
資格喪失時に、出産手当金を受けている(又は受ける条件を満たしている)場合は、要件を満たせば退職後も継続して出産手当金を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
※被保険者の資格を喪失した日まで1年以上被保険者であった者で、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの(又は支給要件を満たしているもの)は、退職後も、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金の給付を受けることができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-D】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。

【解答】
【問5-D】 ×
出産手当金の支給を受けることはできません。「その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」という要件を満たしていないからです。
過去問をどうぞ!
【H24年出題】
被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

【解答】
【H24年出題】 ×
資格喪失後の出産手当金の継続給付は、「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」ことが条件です。問題文のような「資格喪失後6か月以内に出産」だけでは要件は満たしません。
★なお、資格喪失後6月以内に出産した場合は、要件を満たせば、『出産育児一時金』の支給が受けられます。
条文を読んでみましょう。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付) 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |
最後の保険者から受けることができるのは、出産手当金ではなく、「出産育児一時金」ですので注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-067
R4.11.2 R4択一式より 介護保険料率の定め方
まず、健康保険の被保険者に関する保険料額を確認しましょう
・介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料額と介護保険料額との合算額
・介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料額
※「一般保険料額」は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率+特定保険料率)を乗じて得た額です。
※「介護保険料額」は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額です。
(法第156条)
今日のテーマは「介護保険料率」の定め方です。
条文を読んでみましょう。
第160条第16条 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 |
介護保険第2号被保険者は、介護保険法で、40歳以上65歳未満の医療保険加入者と定義されています。介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者は、健康保険料といっしょに介護保険料を徴収されます。
そのため、介護保険料率は、「介護保険第2号被保険者」である被保険者の総報酬額の総額をもとに定められます。
では令和4年の問題をどうぞ!
【問4-C】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

【解答】
【問4-C】 ×
介護保険料率は、「介護納付金」÷「当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額」で得た率を基準として、保険者が定めます。
分子は、前年度の実績ではなく、「当該年度」における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の「見込額」となります。
なお、「総報酬額」とは、「標準報酬月額及び標準賞与額の合計額」です。
※介護保険第2号被保険者の介護保険料の流れを確認しましょう。
介護保険第2号被保険者 |
↓介護保険料 |
健康保険 |
↓介護納付金 |
社会保険診療報酬支払基金 |
↓介護給付費交付金 |
市町村 |
介護保険第2号被保険者の介護保険料は、医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通して、市町村に交付されます。
なお、介護保険第1号被保険者の保険料は、介護保険法のルールによって、市町村が徴収します。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】※改正による修正あり
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

【解答】
【H29年出題】※改正による修正あり 〇
介護保険料率は、毎年度、決定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-066
R4.11.1 R4択一式より 出産手当金と傷病手当金の調整
「出産手当金」と「傷病手当金」の両方の支給要件を満たした場合、どちらの支給が優先されるでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) 1 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 |
出産手当金と傷病手当金の両方を受給できる期間は、出産手当金を優先し、出産手当金が支給され、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金と出産手当金は、支給を始める日が違いますので、1日あたりの支給額が異なる場合があります。その場合、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-C】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】
【問2-C】 〇
出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件を満たした期間は、出産手当金の支給が優先されます。
・出産手当金の額 > 傷病手当金の額 → その期間中の傷病手当金は支給されません
・出産手当金の額 < 傷病手当金の額 → 差額が支給されます
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。
②【H30年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
傷病手当金と出産手当金が逆です。
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、「出産手当金」の支給が優先され、その期間中は「傷病手当金」の支給は停止されます。
②【H30年出題】 ×
出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件を満たした期間は出産手当金が優先されます。選択制ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-065
R4.10.31 R4択一式より 法人の役員に係る保険給付の特例
健康保険の保険給付は「労災保険法の規定による業務災害」以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して行われます。労災保険からの給付が受けられない場合は、健康保険の給付が受けられます。
なお、労災保険は労働者を保護するための保険ですので、法人の役員としての業務に起因する傷病等については、労災保険からは保険給付が行われません。
しかし、被保険者等が法人の役員である場合は、法人の役員としての業務に起因する負傷等は、健康保険の保険給付でも対象外となっています。
法人の役員の業務上の負傷は、使用者側の責に帰すべきものなので、労使折半の健康保険から保険給付を行うことが適当でないと考えられるからです。
(参考:H25.8.14事務連絡 全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
では、条文を読んでみましょう。
第53条の2(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例) 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。 |
 被保険者等(被扶養者も含みます)が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外となります。
被保険者等(被扶養者も含みます)が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外となります。
ただし例外に注意してください。「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務で厚生労働省令で定めるもの」は保険給付の対象になります。
ちなみに、厚生労働省令で定めるものは、『厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。』とされています。(則第52条の2)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-A】
被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

【解答】
【問2-A】 ×
法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して健康保険から保険給付が行われるのは、被保険者の数が「5人未満」である適用事業所に使用される場合です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
②【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
①【H26年出題】 〇
傷病手当金も保険給付の対象になるのがポイントです。
②【H30年出題】 〇
役員の業務内容が、当該法人の従業員が従事する業務と同一であると認められない場合は、健康保険の給付対象にはなりません。
(H25.8.14事務連絡 全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-051
R4.10.17 R4択一式より 任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者は健康保険の保険料を納付する義務があります。
今日は、任意継続被保険者の保険料をみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第157条 (任意継続被保険者の保険料) 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
第161条 (保険料の負担及び納付義務) 1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第164条 (保険料の納付) 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
|
例えば、健康保険の被保険者が10月17日に退職した場合、その翌日に資格を喪失します。資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であって、資格を喪失した日から20日以内に保険者に申出をした場合、10月18日に任意継続被保険者の資格を取得します。
その場合、任意継続被保険者の保険料は、10月から算定されます。初めて納付すべき保険料(10月分)の納期限は、保険者が指定する日です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-D】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

【解答】
【問2-D】 〇
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定されます。
例えば10月17日に退職した場合は、在職中の保険料は資格喪失月の前月の9月分まで徴収され、任意継続被保険者としての保険料は10月分からとなります。
過去問をどうぞ!
【H30年出題】
一般の被保険者に関する保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
【H30年出題】 ×
任意継続被保険者に関する保険料について、初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定した日」までに納付しなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-037
R4.10.4 R4択一式より『健康保険法・審査請求と訴訟との関係』
今日のテーマは、健康保険法・審査請求と訴訟との関係です。
では、条文を読んでみましょう。
第189条 (審査請求及び再審査請求) ① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第192条 (審査請求と訴訟との関係) 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
第190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
 今日は、「審査請求と訴訟との関係」に注目します。
今日は、「審査請求と訴訟との関係」に注目します。
・第189条について
「被保険者の資格」、「標準報酬」、「保険給付」に関する処分に不服がある場合は→社会保険審査官に審査請求→社会保険審査会に再審査請求という流れになっています。
・第192条について
「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」となっていて、審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合は、再審査請求をしないで、「処分の取り消しの訴え」を提起することができます。
・ちなみに第190条について
「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」とされています。こちらは、社会保険審査会に審査請求をしないで、直接、処分の取り消しの訴えを提起することができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-C】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

【解答】
【問7-C】 ×
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後」でなければ、提起することができません。
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定の後は、「社会保険審査会に再審査請求」をすることもできますが、再審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起することもできます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-036
R4.10.3 R4択一式より『健康保険と介護保険の関係』
同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定による給付を受けることができるときは、健康保険の給付は行われません。
今日は、健康保険と介護保険の調整を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第55条第3項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
「介護保険法」の給付が優先されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
②【H22年出題】
被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
同一の傷病について、介護保険法の給付を受けることができる場合には、介護保険が優先し、健康保険の療養の給付は行われません。
②【H22年出題】 ×
問題文の「同一の疾病、負傷または死亡」に注目してください。介護保険法には、「死亡」に関する給付がありませんので、死亡については健康保険との調整は行われません。
では令和4年の問題をどうぞ!
【問1-D】
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る療養については、医療保険から行うものとされている。

【解答】
【問1-D】 〇
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則です。
しかし、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により,患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合については,当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものであること、とされています。
(平成18年4月28日 老老発第0428001号・保医発第0428001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(健康保険法)
令和4年基本問題(健康保険法)
R5-027
R4.9.24 R4択一式より『移送費として支給される額』
今日のテーマは「移送費」です。
さっそく条文を読んでみましょう。
第97条 ① 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 ② 移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
則第80条 (移送費の額) 法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
則第81条 (移送費の支給が必要と認める場合) 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 1 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 3 緊急その他やむを得なかったこと。 |
★移送費とは?
負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、その経済的な出費について補填を行い、必要な医療が受けられることを可能にするとの考え方から、現金により支給されます。
なお、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはなりません。
参照:H6.9.9保険発第119号・庁保険発第9号
令和4年の問題をどうぞ!
【R4問3-イ】
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない。

【解答】
【R4問3-イ】 ×
移送費には一部負担金はありませんので、「3割の患者自己負担分を差し引いた」の部分が誤りです。
なお、移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用に基づいて算定した額の範囲での実費が支給されます。
では、過去問もどうぞ!
【H24年出題】
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

【解答】
【H24年出題】 〇
移送費の金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(健康保険法)
令和4年択一式を解いてみる(健康保険法)
R5-017
R4.9.14 R4「健保択一」は長文が多く12ページのボリューム。今日は『被保険者証』
令和4年の健康保険の択一式は、長文問題が多く12ページのボリュームでした。
問題文を読むときは、まず「キーワード」を見つけ出すことが大切です。
では、今日は、「被保険者証」の問題を解いてみましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
則第47条(被保険者証の交付) 1 協会は、厚生労働大臣から、被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。 2 健康保険組合は被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 3 保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 4 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 5 保険者は、任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。 |
被保険者の資格取得の確認を行ったときは、協会(又は健康保険組合)は、被保険者証を被保険者に交付します。
被保険者証は「保険者から事業主に送付」→「事業主から被保険者に送付」の流れが原則です。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から直接、被保険者に送付することもできます。(テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能とするため、令和3年に改正されました。)
また、任意継続被保険者については、保険者から直接任意継続被保険者に送付されます。
則第51条 (被保険者証の返納) 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。 4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 |
資格喪失の場合は、事業主は遅滞なく被保険者証を回収し、保険者に返納します。この場合、被保険者は5日以内に被保険者証を事業主に提出しなければなりません。
任意継続被保険者の場合は、本人が、5日以内に保険者に返納します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【R4年問1-C】
事業主は、被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。
②【R4年問2-E】
保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

【解答】
①【R4年問1-C】 ×
(被保険者証の返納の問題)
資格喪失の場合は、事業主が遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければなりません。返納の場合は、後半部分の「被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。」という例外規定はありません。
②【R4年問2-E】 〇
(被保険者証の交付の問題)
被保険者証の交付については、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑦
復習しましょう/令和4年選択式⑦
R5-007
R4.9.4 令和4年「健保選択」は、数字の暗記が決め手
令和4年の健康保険の選択式は、4つが数字でした。
 短時間労働者に対する適用について
短時間労働者に対する適用について
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が平成28年10月1日より実施されています。
◎「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」といいます。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
◎ 4分の3基準を満たさない場合でも、以下の①から⑤までの5つの要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
② 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
③ 月額賃金が8.8万円以上であること。
④ 学生でないこと。
⑤ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(i) 特定適用事業所
(ii) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(iii) 国又は地方公共団体の適用事業所
 令和4年10月以降の改正について
令和4年10月以降の改正について
※②の雇用期間要件が廃止されます。
※「特定適用事業所」の企業規模要件が、500人超える企業から、「100人」を超える企業に引き下げられます。
参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
★令和4年は、「88,000円以上」が問われました。
 保険外併用療養費について
保険外併用療養費について
保険外併用療養費は、評価療養、患者申出療養、選定療養を受けたときが対象です。
令和4年の選択式では、厚生労働省告示に掲げられている第1号から第11号までの選定療養のうち、4号と7号からの出題でした。
4号は「病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」、7号は、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」です。
★「200以上」と「180日」が問われました。
 同時に2以上の事業所に使用される場合の手続きについて
同時に2以上の事業所に使用される場合の手続きについて
被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合の手続の問題です。
保険者が2以上ある場合は、被保険者は、被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければなりません。
その場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に提出します。提出先は、全国健康保険協会を選択しようとするときは「厚生労働大臣」に、健康保険組合を選択しようとするときは、「健康保険組合」です。
全国健康保険協会の適用と徴収の業務は、厚生年金保険とセットになりますので、「厚生労働大臣」が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-363
R4.8.20 任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者の資格喪失を確認しましょう。
条文の空欄を埋めてみましょう。
第38条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して< A >を経過したとき。 2 死亡したとき。 3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 4 被保険者となったとき。 5 < B >の被保険者となったとき。 6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 7 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、< C >が到来したとき。 |

【解答】
A 2年
B 船員保険
C その申出が受理された日の属する月の末日
ポイント!
※第7号は改正で追加されました。
任意継続被保険者本人の申出により、資格を喪失することが可能になりました。
保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときの「翌日」(=受理された日の翌月1日)に資格を喪失します。
例えば、8月20日に資格喪失の申出が受理された場合は、9月1日が資格喪失日となります。
※「翌日」喪失が原則ですが、第4号から第6号に該当した場合は、「当日」に資格を喪失します。
・ 被保険者となったとき。→ 当日喪失
・ 船員保険の被保険者となったとき。 → 当日喪失
・ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 → 当日喪失
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
②【H30年出題】
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
③【H29年出題】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
④【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

【解答】
①【H26年出題】 ×
後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に任意継続被保険者の資格を喪失します。
②【H30年出題】 ×
任意継続被保険者が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に任意継続被保険者の資格を喪失します。2年を経過していなくても、任意継続被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となります。
③【H29年出題】 〇
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
なお、任意継続被保険者の保険料の納付期日は、その月の10日です。
※初めて納付すべき保険料について
「初めて納付すべき保険料」の納付期日は、「保険者が指定する日」です。
「初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。」とされています。
④【H27年出題】 ×
「督促状により指定する期限の翌日」ではなく、納付期日(その月の10日)の翌日に資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-353
R4.8.10 任意継続被保険者の保険料前納
任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)です。
今回は、任意継続被保険者の保険料の「前納」を確認しましょう。
第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) 1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
令48条 (保険料の前納期間) 任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
令第49条 (前納の際の控除額) 法第65条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。
②【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
③【H22年選択式】 ※修正あり
1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
①【R2年出題】 ×
前納の場合、保険料の割引があります。
②【H26年出題】 〇
前納の期間の単位は、「4月から9月まで」、「10月から翌年3月まで」の6か月間又は「4月から翌年3月まで」の12か月間です。
しかし、例外もあります。
・途中で任意継続被保険者の資格を取得した者
→ 資格を取得した日の属する月の翌月分からの期間
・資格を喪失することが明らかである者
→ 資格を喪失する日の属する月の前月分までの期間
③【H22年選択式】 ※修正あり
A 各月の初日
B 初月の前月末日 (則第139条第1項)
C 年4分の利率
D 5月
Aについて
前納された保険料は、前納期間の「各月の初日」にその月分の保険料が納付されたとみなされます。
※国民年金の場合は、「各月が経過した際」に、その月分の保険料が納付されたとみなされます。
Bについて
「4月から9月までの6か月間」、「4月から翌年3月までの12か月間」の期限は、3月末日、「10月から翌年3月までの6か月間」の期限は、9月末日です。
Dについて
途中で資格取得した場合は、前納できるのは、資格を取得した日の属する月の翌月分からの期間となりますので、初月は5月となります。期間は、「5月から9月まで」又は、「5月から翌年3月まで」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-324
R4.7.12 法定免除の要件
今回のテーマは「法定免除」です。
対象者を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第89条 被保険者(産前産後免除及び保険料の一部免除の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 ② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ③ 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定するもの)に入所しているとき。 |
ポイント!
★法定免除の対象は、
・障害基礎年金、1級・2級の障害厚生年金等の受給権者
→ただし、厚生年金保険法の障害等級(3級)に該当しなくなってから3年を経過した者は、法定免除の対象外になります。
・生活保護法の生活扶助を受ける人
・国立ハンセン病療養所等に入所している人
過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。
②【H27年出題】
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。

【解答】
①【H16年出題】 ×
法定免除は、障害基礎年金の受給権があることが条件です。1・2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者には、法定免除は適用されません。
②【H27年出題】 ×
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの種類の扶助があります。
法定免除の対象になるのは、そのうちの「生活扶助」を受ける場合です。
医療扶助のみを受ける場合は法定免除の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-323
R4.7.11 収入がある者についての被扶養者の認定
被扶養者の認定には、次のような基準があります。
★「認定対象者」(被扶養者としての届出に係る者)が被保険者と同一世帯に属している場合
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する。
② ①の条件に該当しない場合でも、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。
①について
被扶養者の収入 |
|
|
被保険者の年間収入 |
| |
▲2分の1
②について
被扶養者の収入 |
| |
被保険者の年間収入 |
| |
▲2分の1
★認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合には180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する。
被扶養者の収入 |
|
被保険者からの援助 | |
(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】 ※改正による修正あり
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が 130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
(なお、認定対象者は、日本国内に住所を有している)
②【H27年出題】 ※改正による修正あり
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。(なお、母は日本国内に住所を有している。)
③【H22年出題】 ※改正による修正あり
被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年間100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。(なお、父は日本国内に住所を有している。)

【解答】
①【R1年出題】 〇
認定対象者と被保険者が同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが、被扶養者となる条件です。
しかし、被保険者の年間収入の2分の1以上でも、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合で、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する者として差し支えないとされています。
※ちなみに、令和2年4月から被扶養者については「日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」という要件が追加されています。
②【H27年出題】 ×
認定要件の年収には、年金や給与も含まれます。
問題文の58歳の母の年間収入は、100万円の遺族厚生年金+120万円のパート労働による給与=220万円です。年間収入130万円以上ですので、被扶養者となりません。
③【H22年出題】 ×
被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合には180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ないことが条件です。
問題文の父の年間収入は、被保険者からの援助額より多いので、被扶養者に該当しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-322
R4.7.10 短時間労働者の社会保険の適用
★1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の「4分の3以上」の場合は、健康保険、厚生年金保険の被保険者として取り扱われます。
★「4分の3未満の場合」
・平成28年10月から
特定適用事業所(被保険者数が常時501人以上の企業)に、厚生年金保険・健康保険が適用されました。
・平成29年4月から
任意特定適用事業所(被保険者数が常時500人以下の企業の事業所で、短時間労働者が社会保険に加入することについて労使合意を行った事業所)にも、厚生年金保険・健康保険が適用されるようになりました。
「4分の3未満」でも適用される要件を確認しましょう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である者で、次の①から④の全てに該当するもの ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ② 継続して1年以上使用されることが見込まれること。 ③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が 8万8千円以上であること。 ④ 学生でないこと |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
②【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
③【R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
特定適用事業所とは、「常時501人以上」の企業の各適用事業所です。
(H24年法附則第46条第12項)
②【H30年出題】 ×
短時間労働者の適用条件の1つである「報酬」は、法第3条第1項9号で「報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額」とされています。
除外される報酬は以下の通りです。
・ 臨時に支払われる賃金 (結婚手当等)
・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
・ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (割増賃金等)
・ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
・ 深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
(則第23条の4、R4.3.18保保発0318第1号)
問題文の「家族手当」と「通勤手当」はともに報酬に含まないで算定します。
③【R3年出題】 ×
「事業主との雇用関係の有無にかかわらず」の部分が誤りです。
「「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)」とされています。
(R4.3.18保保発0318第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-293
R4.6.11 毎年7月1日の定時決定
「標準報酬月額」は、保険料の計算、傷病手当金などの計算に使われます。
標準報酬月額は、毎年7月1日に見直しをします。「定時決定」といいます。
★「報酬」、「報酬月額」、「標準報酬月額」と似たような用語が登場します。
「報酬」は、労働の対償として受けるもののことで、時給制の人もいれば、月給制の人もいて様々です。
報酬を月ベースになおしたものを「報酬月額」といいます。
報酬月額を1等級から50等級まで50段階に区分したものを「標準報酬月額」といいます。
では、条文を読んでみましょう。
第41条 (定時決定) ① 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ② ①の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ③ ①の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 |
定時決定のポイント!
★毎年7月1日現在で行います
★「4月+5月+6月の報酬の総額÷その期間の月数」で計算した額が「報酬月額」です。
・ ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者の場合は11日)未満の月は除いて計算します。分母の「その期間の月数」は「3」と限りません。「2」になることも「1」になることもありますので注意しましょう。
・ 例えば、4月、5月、6月の報酬(報酬支払基礎日数は17日以上)が、それぞれ、188,500円、196,200円、182,300円だったとすると、(188,500円+196,200円+182,300円)÷3で、「報酬月額」は189,000円です。この額を標準報酬月額等級表にあてはめ、「標準報酬月額」は190,000円となります。
★決定された標準報酬月額の有効期間は、その年の9月から翌年の8月までです。
★定時決定を行わない者
・ 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
・ 7月から9月までのいずれかの月に随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定が行われる者
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)
②【H29年出題】
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
③【R3年出題】
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

【解答】
①【H19年出題】 〇
定時決定は、4月・5月・6月に支払われた報酬で算定します。
問題文のように、毎月末日締め、翌月15日支払いの場合は、4月15日払い(3月分)、5月15日払い(4月分)、6月15日払い(5月分)で算定します。
②【H29年出題】 ×
6月1日から7月1日に資格を取得したものは、その年の定時決定の対象から除外されます。問題文の6月1日に被保険者資格を取得した者は、その年の定時決定は行いません。
③【R3年出題】 ×
定時決定の届出の提出期限は、7月10日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-273
R4.5.22 健保・保険料の源泉控除
事業主は被保険者負担分の保険料を、報酬から控除できます。
控除のルールを条文で読んでみましょう。
第167条 (保険料の源泉控除) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 |
ポイント!
被保険者の当月分の給料から控除できるのは、前月分の被保険者負担分の保険料です。
ただし、被保険者が月末に退職し、当月分の保険料が徴収される場合は、前月分と当月分を控除することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。
②【R1年出題】
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。
③【H26年出題】
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間にかかるもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
保険料は、資格を取得した月から徴収されますので、5月23日に被保険者資格を取得した場合は5月分から徴収されます。
給与から控除できるのは、前月分です。
月給制で、毎月20日締め、当月末日払いの場合、6月に支給される最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で前月分の5月分の保険料を控除できます。
しかし、毎月末日締め、当月25日払いの場合、当月の5月に支給される最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では保険料を控除できません。翌月の6月に支給される給与から控除します。
②【R1年出題】 ×
7月30日退職の場合は、翌日の7月31日に資格を喪失します。
第156条で、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない」と規定されていますので、資格喪失月は保険料が生じないのがポイントです。
7月30日に退職した場合、保険料が生じるのは6月分までです。7月25日支払いの給与(6月16日から7月15日までの期間に係るもの)で、6月分の保険料を控除します。
③【H26年出題】 〇
5月31日退職の場合は、資格喪失日が6月1日で、保険料は5月分まで生じます。
末日退職の場合の健康保険料の源泉控除は、前月分と当月分を控除できますので、毎月末日締め、当月25日払いの場合、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間にかかるもの)で前月の4月分と当月の5月分の保険料を控除することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-272
R4.5.21 資格喪失月の賞与の保険料は?
賞与の保険料額の計算式は、以下の通りです。
・介護保険第2号被保険者
→ 「標準賞与額×一般保険料率」+「標準賞与額×介護保険料率」
・介護保険第2号被保険者以外
→ 「標準賞与額×一般保険料率」
★ 事業主と被保険者が2分の1ずつ負担します。事業主は、被保険者の負担分を賞与から控除できます。条文を読んでみましょう。
第167条 (保険料の源泉控除) ② 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。
②【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
③【R3年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
事業主は、賞与から、被保険者の負担する標準賞与額に係る保険料を控除することができます。
②【H29年出題】 〇
資格を喪失した月の保険料については、第156条第3項で次のように定められています。
「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」
問題文のように、前月から引き続き被保険者である者が、7月25日に退職し26日に資格を喪失した場合は、7月分の保険料は算定されませんので、事業主は納付する義務はありません。
資格喪失月に支給された賞与についても、保険料は算定されませんので、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。
(法第156条第3項)
③【R3年出題】 〇
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与が支給され、同月20日に退職した場合、当該賞与に係る保険料は徴収されません。
しかし、「保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月であっても、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額に算入する。被保険者資格の喪失月であり資格喪失日の前日までに支払われる賞与額についても被保険者賞与支払届の提出を徹底すること。標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。」とされています。
(H19.5.1庁保険発第0501001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-271
R4.5.20 健康保険/保険料の負担
健康保険の保険料は、原則として被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担します。
また、保険料の納付義務を負うのは、事業主です。
条文を読んでみましょう。
第161条 (保険料の負担及び納付義務) 1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第162条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例) 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。 |
ポイント!
任意継続被保険者は、本人が保険料の全額を負担し、保険料の納付義務も本人が負います。
では、過去問をどうぞ!
①【H15年出題】
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
②【H30年出題】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
③【H19年出題】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。

【解答】
①【H15年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料は、本人が納付義務を負います。
②【H30年出題】 〇
保険料額は、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担するのが原則ですが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担割合を増加することができます。
ポイント!
・健康保険組合だけの特例です。全国健康保険協会には適用されません。
・負担割合を増加できるのは「事業主の負担分」です。被保険者の負担割合は増加できません。
③【H19年出題】 〇
「健康保険組合」は、規約で定めるところにより、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-255
R4.5.4 高額介護合算療養費
高額介護合算療養費とは??
「健康保険」の一部負担金と「介護保険」の利用者負担額を合算して、「介護合算算定基準額+支給基準額」を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。超えた金額は、健康保険と介護保険の自己負担額の比率で按分して支給されます。
計算期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日)です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は< A >円である。
70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は < B >円である。
②【H25年出題】
高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。
③【H28年出題】
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
④【H30年出題】
高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

【解答】
①【H25年選択式】
A 500
B 670,000
(平成20年厚生労働省告示第225号、令43条の3)
高額介護合算療養費は、「介護合算一部負担金等世帯合算額-介護合算算定基準額」が、500円を超える場合に限り、支給されます。
②【H25年出題】 ×
「個別に」算定ではなく、「世帯」単位で算定します。
(H21.4.30保保発0430001)
③【H28年出題】 ×
高額介護合算療養費を算定する場合も、70歳未満の21,000円未満のものは算定対象から除かれます。
(H21.4.30保保発0430001)
④【H30年出題】 ×
「健康保険法に基づく高額療養費が支給されていること」は要件ではありません。
なお、合算する場合は、健康保険の一部負担金等の額から高額療養費は除かれ、また、介護保険の利用者負担額から高額介護サービス費は除かれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-254
R4.5.3 月の途中で後期高齢者医療の被保険者になった場合の高額療養費
75歳になり後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した場合、健康保険の資格は喪失します。
今日のテーマは、月の途中で後期高齢者医療の被保険者になった場合の高額療養費の自己負担限度額についてです。
月の途中(2日~末日)に、後期高齢者医療の被保険者になった月は、その月に受けた療養は、「健康保険」、「後期高齢者医療」の自己負担限度額をそれぞれ「2分の1」にして、支給要件を見ることになります。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。
②【R1年出題】
標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400円である者が、月の初日以外の日において75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円とされている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
★月の初日以外の日に75歳に達した場合のポイント!
・健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用される
・個人単位で両制度のいずれも通常の基準額の2分の1の額を設定する
②【R1年出題】 〇
健康保険と後期高齢者医療でそれぞれ2分の1の高額療養費算定基準額が適用されるので、問題文の場合は、外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-253
R4.5.2 (高額療養費)長期高額疾病の特例
長期間にわたり高額な医療費がかかる特定疾病については、自己負担限度額の特例が設けられています。負担軽減のためです。
特定疾病については施行令第41条第9項で以下の要件が定められています。
1 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
2 1の治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
要件に基づき、指定されているのが次の3つです。
① 人工腎臓を実施する慢性腎不全 (人工透析)
② 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害及び先天性血液凝固第Ⅸ因子障害 (血友病)
③ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(血液製剤に起因するHIV感染症)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は10,000円とされている。
②【H28年出題】
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。

【解答】
①【R2年出題】 ×
★長期高額疾病(特定疾病)に係る自己負担限度額の特例
・自己負担限度額は月額1万円です。※限度額を超える分は高額療養費が現物給付で支給されます。
・ただし、「慢性腎不全」のうち「70歳未満」の「上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」については自己負担限度額は2万円です。
問題文の高額療養費算定基準額は1万円ではなく「2万円」です。
(昭59.9.28厚告156)
②【H28年出題】 ×
2万円ではなく「1万円」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-252
R4.5.1 多数回該当・高額療養費
高額療養費に該当する月以前12か月間に、高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。自己負担を軽減するためです。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
②【H28年選択式】
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- < A >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は < B >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< C >となる。
③【H18年出題】
転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合であっても、高額療養費の算定にあたっての支給回数は通算される。

【解答】
①【H26年出題】 ×
多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいいます。4か月目からは高額療養費算定基準額が「多数回該当」の上限額になります。
②【H28年選択式】
A 842,000円
B 45,820円
C 140,100円
■70歳未満の被保険者(標準報酬月額83万円)の場合
(高額療養費算定基準額)
・252,600円+(医療費-842,000円)×1%
・多数回該当の場合 140,100円
ポイント!
842,000円について → 842,000円の30%が252,600円です。
計算式!
・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
252,600円+(100万円-84万2千円)×1% = 25万4,180円
・高額療養費
30万円 - 25万4,180円 = 4万5,820円
③【H18年出題】 ×
健康保険組合の被保険者から協会健保の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合は、支給回数は通算されないことになっています。
(昭59.9.29保険発第74号・庁保険発第18号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-251
R4.4.30 高額療養費/世帯合算
高額療養費は、「1人単位」で計算するのが原則ですが、同一世帯で、複数人が医療機関にかかった場合は、一部負担金等を合算して計算することができます。
また、同一人物でも、高額療養費は医療機関ごとに計算するのが原則ですが、同一人物が同一月に複数の医療機関にかかった場合も、世帯合算が適用されます。
合算の対象になるのは、「70歳未満」の場合は21,000円以上の自己負担額です。「70歳以上」の場合は、合算の対象に制限はありませんので、すべての自己負担額を合算できます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。

【解答】
【H30年出題】 ×
夫婦がともに被保険者の場合は、70歳未満、70歳以上関係なく、世帯合算の対象になりません。
世帯合算の単位は、「被保険者+その被扶養者」のまとまりです。
<計算事例>
・70歳未満の被保険者A(標準報酬月額32万円)
→ 医療費20万円(一部負担金 6万円)
・70歳未満の被扶養者B
→ 医療費3万円(窓口負担 9千円)
・70歳未満の被扶養者C
→ 医療費100万円(窓口負担 30万円)
世帯合算の対象になるのは「2万1千円以上」の被保険者Aと被扶養者Cの負担分です。被扶養者Bは2万1千円未満なので、世帯合算されません。
①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
8万100円+(120万円-26万7千円)×1% = 8万9430円
②高額療養費
36万円 - 8万9430円 = 27万570円
となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-250
R4.4.29 高額療養費の要件
例えば、病気で入院し、1か月間で医療費が100万円かかった場合、一部負担金は3割の30万円となります。
このうちの自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として払い戻されます。(限度額適用認定証を提示し、払い戻しではなく現物給付として受ける方法もあります。)
 70歳未満の被保険者(標準報酬月額28万円)、医療費100万円の場合の高額療養費
70歳未満の被保険者(標準報酬月額28万円)、医療費100万円の場合の高額療養費
①自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
8万100円+(100万円-26万7千円)×1% = 8万7430円
②高額療養費
30万円-8万7430円 = 21万2570円
→ 21万2570円が高額療養費として払い戻されます。
医療費総額 100万円 | ||
療養の給付
70万円 | 一部負担金 30万円 | |
自己負担限度額 8万7430円 | 高額療養費 21万2570円 | |
条文を読んでみましょう
第115条 (高額療養費) ① 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 ② 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。 |
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
②【H23年出題】
高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。
③【H27年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、高額療養費の計算には入りません。
★高額療養費の算定対象とならない負担
・食事療養標準負担額
・生活療養標準負担額
・保険外のもの
保険外併用療養費に係る自費負担分など
②【H23年出題】 〇
★高額療養費の支給要件の取扱いポイント
・暦月単位で計算
例えば、3月15日から4月10日まで入院療養を受けた場合は、「3月15日から3月31日まで」と「4月1日から4月10日まで」に区別します。
・1人ずつ計算
・医療機関ごとに計算
・医科、歯科別で計算
・入院と通院はそれぞれで計算
問題文のように、同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、それぞれ区別します。
③【H27年出題】 ×
内科と歯科は、それぞれ区別して算定します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-236
R4.4.15 療養の給付 一部負担金
保険医療機関や保険薬局で治療などを受けた場合、70歳未満の場合は、かかった医療費の3割を一部負担金として支払います。
今回のテーマは一部負担金です。
条文を読んでみましょう。
第74条 (一部負担金) 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 1 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30 2 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(3に掲げる場合を除く。) 100分の20 3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30 |
一部負担金の割合は以下の通りです。
①70歳未満 → 100分の30 (←誤っていたので修正しました)
②70歳以上(③を除く) → 100分の20
③70歳以上の現役並所得者 → 100分の30
では、過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の< A >以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
<選択肢>
① 前月の標準報酬月額が28万円
② 前月の標準報酬月額が34万円
③ 標準報酬月額が28万円
④ 標準報酬月額が34万円

【解答】
A ③ 標準報酬月額が28万円
70歳以上の現役並み所得者の一部負担金の割合は100分の30です。
現役並み所得については、施行令第34条で、「療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上」と規定されています。
(令第34条)
つぎはこちらをどうぞ!
②【H27年選択式】
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< B >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< C >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
<選択肢>
① 70歳に達する日 ②70歳に達する日の属する月
③ 70歳に達する日の属する月の翌月 ④ 70歳に達する日の翌日
⑤ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑥ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑧ 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

【解答】
②【H27年選択式】
B ③ 70歳に達する日の属する月の翌月
C ⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
★Bについて
一部負担金の割合が2割か3割になる「70歳以上」とは、「70歳に達する日の属する月の翌月」からとなります。
★Cについて
70歳以上で、標準報酬月額が28万円以上の場合は、原則として一部負担金の割合は3割です。
ただし、標準報酬月額が28万円以上でも、
・「被保険者」と「その被扶養者(70歳以上の場合に限る。)」の収入が合わせて520万円未満
・当該被扶養者がいない場合は、「被保険者」の収入が383万円未満
の場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。
問題文の場合は、被扶養者である妻が70歳未満ですので、被扶養者の収入は合算しません。「被保険者のみ」の収入が383万円未満の場合は、申請により一部負担金の額が2割となります。
(施行令第34条)
最後にもう一問どうぞ!
③【H24年出題】※改正による修正あり
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。

【解答】
③【H24年出題】 〇 ※改正による修正あり
70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上でも、被保険者と70歳以上の被扶養者の収入を合わせて520万円未満の場合、申請により2割負担となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-217
R4.3.27 資格喪失後の傷病手当金と老齢退職年金給付
資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができる場合は、どちらが優先されるでしょう?
では、条文を読んでみましょう。
第108条第5項 傷病手当金の支給を受けるべき者(資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者に限る。)が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
則第89条第2項 法第108条第5項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。老齢退職年金給付が優先されます。
ただし、老齢退職年金給付の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
なお、傷病手当金の額は「日単位」ですが、年金の額は「年単位」です。老齢退職年金給付は360で割った日額で傷病手当金と比較します。365ではありませんので注意してください。
老齢退職年金給付÷360が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
③【H17年出題】
適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。

【解答】
①【H23年出題】 ×
老齢退職年金給付が優先されますので、「傷病手当金は支給されない」となります。
②【H27年出題】 〇
傷病手当金と老齢退職年金給付が調整されるのは、「資格喪失後の継続給付の傷病手当金」の場合です。退職していることが前提です。
問題文は、「適用事業所に使用される被保険者」です。在職中の傷病手当金は、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われません。
③【H17年出題】 ×
②と同様に、③も「適用事業所に使用される常勤職員」ですので、「傷病手当金」と「老齢基礎年金・老齢厚生年金」の調整は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-201
R4.3.11 出産手当金その2 報酬との調整・傷病手当金との調整
報酬と出産手当金との調整のルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第108条 (出産手当金と報酬との調整) ② 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
報酬を受けることができる場合 → 出産手当金は支給されません
ただし、報酬の額が、出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
②【H27年出題】
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
報酬が出産手当金より少ないときは、差額が支給されます。
②【H27年出題】 〇
介護休業期間中でも、要件に該当する場合は、傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
傷病手当金又は出産手当金が支給される場合で、同じ期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整が図られます。
(平成11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)
次に、出産手当金と傷病手当金の支給調整を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。 |
出産手当金と傷病手当金の両方が支給される場合は、出産手当金が優先され、その期間は傷病手当金は支給されません。
ただし、出産手当金の額が、傷病手当金より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
では、過去問をどうぞ!
③【H24年出題】
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。
④【H30年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
③【H24年出題】 ×
出産手当金が優先されます。
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給が優先され、その期間中は傷病手当金の支給は停止されます。
④【H30年出題】 ×
③の問題と同じです。選択制ではなく、出産手当金が優先されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-200
R4.3.10 出産手当金その1 支給要件
被保険者が出産した場合、産前産後の休業中は健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給要件を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第102条 (出産手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
出産手当金が支給されるのは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日です。
 「出産日当日」は産前?産後?
「出産日当日」は産前?産後?
条文の「出産の日以前42日」と「出産の日後56日」に注目してください。42日には「出産の日」を含み、56日は出産の日の翌日からとなります。出産当日は「産前」に入ります。
 「出産予定日」より出産が遅れた場合は?
「出産予定日」より出産が遅れた場合は?
産前休業は、出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。
条文の『出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日』の部分に注目してください。
出産が予定日よりも遅れた場合は、出産予定日以前42日から出産日後56日が支給期間となるので、遅れた日数分も出産手当金が支給されます。
予定日以前42日 | 遅れた日数分 | 出産の日後56日間 | |||||||
|
| 予定日 |
|
| 出産日 |
|
|
|
|
 「任意継続被保険者」には支給される?
「任意継続被保険者」には支給される?
任意継続被保険者には出産手当金は支給されません。
なお、同様に、特例退職被保険者にも出産手当金は支給されません。(附則第3条)
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)< A >(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日< B >までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。
②【R2年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。
③【H18年出題】
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。

【解答】
①【H30年選択式】
A 以前42日
B 後56日
「前」ではなく「以前」、「以後」ではなく「後」なのがポイントです。
出産日当日は、「産前」に含まれることに注意してください。
②【R2年出題】 ×
出産手当金が支給されるのは、「労務に服さなかった期間」です。
問題文の「通常の労務に服している期間」があった場合は、その間は出産手当金は支給されません。
③【H18年出題】 〇
予定日より遅れた日数分も支給されます。
問題文のように予定日より5日遅れて出産した場合、支給期間は、産前は42日+5日、産後は出産の翌日から56日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!健康保険法
ここを乗り越えよう!健康保険法
R4-172
R4.2.10 入院時食事療養費
入院の場合、診察や手術などは「療養の給付」として現物給付が行われます。そして入院時の食事についても現物給付が行われます。
今日は、入院時の食事がテーマです。
診察や手術については、療養に要した費用の原則100分の30を一部負担金として本人が負担し、残りが療養の給付として健康保険から現物給付されます。
一部負担金 | 療養の給付 |
食事については、食費の一部を「食事療養標準負担額」として本人が負担し、残りが「入院時食事療養費」として健康保険から現物給付されます。
食事療養標準負担額 | 入院時食事療養費 |
では、「入院時食事療養費」を条文で確認しましょう。
第85条 (入院時食事療養費) 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。 |
「療養の給付」と併せて受けた食事療養に要した費用の部分がポイントです。入院時食事療養費は療養の給付とセットになります。
また、「特定長期入院被保険者」は、入院時の食事は「入院時生活療養費」として給付が行われますので、入院時食事療養費の対象から除かれています。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
本当なら、被保険者本人が食事療養に要した費用を病院に支払い、そして入院時食事療養費は、保険者から被保険者に支給すべきものです。
しかし、実際は、入院時食療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度で、被保険者に代わって保険者から病院等に支払う方式をとっています。そして、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされ、結果として現物給付になる、という仕組みです。
(法第85条第5項、第6項)
次に、入院時食事療養費の額を確認しましょう。
第85条 ② 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 ③ 厚生労働大臣は、②の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
★入院時食事療養費の計算式は以下の通りです。
入院時食事療養費の額 =
厚生労働大臣が定める食事療養の費用の額* - 食事療養標準負担額
*厚生労働大臣が定める額より実費の方が少ない場合は実費
では、過去問をどうぞ!
②【H23年出題】
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
③【H27年出題】(改正による修正あり)
入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。

【解答】
②【H23年出題】 ×
中央社会保険医療協議会が定める基準ではなく、「厚生労働大臣」が定める基準です。
③【H27年出題】(改正による修正あり) 〇
食事療養標準負担額は、平均的な家計の食費の状況、特定介護保険施設等の食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定めることになっています。
食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円です。内容は、食材費相当額プラス調理費相当額です。
しかし、「所得の状況」その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に額が定められていて、問題文のような「住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者」は、1食につき100円となっています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!健康保険法
ここを乗り越えよう!健康保険法
R4-161
R4.1.30 法人の役員である被保険者又はその被扶養者の保険給付の特例
健康保険法の保険給付は、「業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産」に関して行われます。
「業務災害以外の」がポイントです。
例えば、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合、労働者でないため労災保険法の業務災害にはなりません。そのような労災保険の給付の対象にならない負傷は、原則として健康保険の給付が受けられます。
では、例えば社長が業務中に負傷した場合はどうでしょう?
社長の場合、特別加入していなければ労災保険の給付は受けられません。健康保険の目的条文をそのまま適用すると、「労災保険法の業務災害以外の負傷」ということで健康保険の保険給付の対象になってしまいます。
しかし、社長は業務災害については補償責任を負う立場です。また、健康保険の保険料は労使折半です。そのため、社長の業務上の負傷等について健康保険から保険給付を行うのは適当でないということから、健康保険の給付は行わないことになっています。
★条文を読んでみましょう。
第52条の2 (法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例) 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
則第52条の2(法第53条の2の厚生労働省令で定める業務) 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 |
法人の役人については、原則として、その法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡については健康保険の保険給付は行われません。
なお、法人の役員としての業務とは、法人の役員がその法人のために行う業務全般を指します。
ただし、「法人の役員の業務」から「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるもの」は除かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
②【H26年出題】
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
③【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
①【H28年出題】 〇
労災保険の業務災害にならない請負業務中の負傷等については、原則として健康保険の給付が行われます。
(法第1条、平成25.8.14事務連絡)
②【H26年出題】 〇
法人の役人については、原則として、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については健康保険の保険給付は行われません。
しかし、例外で、被保険者が5人未満の適用事業所の法人の役員については、業務遂行の過程で業務に起因して生じた傷病についても健康保険の保険給付の対象になります。
傷病手当金も支給されます。
(平成25.8.14事務連絡)
③【H30年出題】 〇
健康保険の給付対象となる業務は、「当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるもの」と定められています。(則第52条の2)
役員の業務内容が当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められない場合には健康保険の給付対象になりません。
(平成25.8.14事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!健康保険法
ここを乗り越えよう!健康保険法
R4-147
R4.1.16 健康保険の強制適用事業所
健康保険は、個人ごとに加入するのではなく、「事業所単位」で適用を受けます。
健康保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」といい、強制的に適用される「強制適用事業所」と、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用を受ける「任意適用事業所」があります。
強制でも任意でも「適用事業所」に使用される者は、健康保険の被保険者となります。
今日は、「強制適用事業所」の要件をみていきます。
強制適用事業所は、法第3条で以下のように規定されています。
① 法定16業種の事業を行っている事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの (個人経営の事業所) ② 国、地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用するもの |
問題を解くときに最初にチェックするポイントは「個人経営」?それとも「法人」?です。
「法人」なら、業種関係なく、常時1人でも従業員がいれば強制適用事業所です。
「個人経営」なら、法定16業種か否か、5人以上か5人未満で、適用が変わります。
| 個人経営 | 法人 | ||
従業員数 | 5人以上 | 5人未満 | 1人以上 | |
業種 | 法定16業種 | 〇 | × | 〇 |
法定16業種以外 | × | × | 〇 | |
〇の事業所が強制適用事業所です。
×の事業所は強制適用ではありませんが、任意で加入することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
②【R1年出題】
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
③【H24年出題】
健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
・常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所
→飲食業は法定16業種以外の業種ですので、個人経営の場合は人数に関係なく、強制適用事業所になりません。
・常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所
→法人の場合は、業種に関係なく、常時従業員が1人でもいれば、強制適用事業所です。
(法第3条)
②【R1年出題】 ×
法人の代表者は、法人に使用される者として、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。
法人の場合は、常時1人以上の従業員がいれば強制適用です。代表者1人の法人でも強制適用事業所になります。
(昭24.7.28保発第74号)
③【H24年出題】 ×
適用除外の規定で被保険者になることができない者でも、常時雇用されている者なら、「常時5人以上」の人数に算入されます。
(昭18.4.5保発905号)
もう1問どうぞ!
④【R1年出題】
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
健康保険法第3条では、「国、地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用するもの」は強制適用事業所です。
国、地方公共団体も健康保険の強制適用事業所になることに注意してください。
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。(適用除外されていません。)
ただし、法第200条で、「国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。」と規定されています。
共済組合と健康保険の両方から二重に保険給付を受けるのではなく、共済組合の組合員には健康保険の保険給付を行わないことになっています。なお、保険料も徴収されません。
(法第200条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ⑤ 健康保険法
どんな法律シリーズ⑤ 健康保険法
R4-136
R4.1.5 健康保険法ってどんな法律?
健康保険法・・・大正11年制定、大正15年7月施行、昭和2年1月全面施行
(制定から全面施行までの期間が長いのがポイントです)
「保険料を負担」することによって「保険給付を受けられる」ことが保険の仕組みです。
「保険者」とは、保険の運営主体のことで、健康保険法の場合は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。
「被保険者」とは保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利がある人のことです。
被保険者は「保険料」を納付することによって、保険事故(業務災害以外の負傷、疾病若しくは死亡又は出産)の際は、保険給付を受けることができます。
ケガや病気の場合は、保険医療機関で診察や薬を受けたり、場合によっては入院や手術のこともありますが、それも保険給付の1つで「療養の給付」といいます。
さて、健康保険は、個人で加入するのではなく、「事業所」単位で加入するのがポイントです。
法律上当然に健康保険の適用を受ける事業所を「強制適用事業所」、厚生労働大臣の認可を受けて任意に加入した事業所を「任意適用事業所」といいます。
強制でも任意でも健康保険の「適用事業所」で使用される者は、健康保険の被保険者となります。(ただし、被保険者になるには、一定の条件があります。)
よく出るポイントを過去問で確認しましょう。
①【H18年出題】
船員保険の被保険者及び疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができない。
②【H20年出題】
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。

【解答】
①【H18年出題】 ×
「船員保険」は船員を対象とした医療保険ですので、「船員保険の被保険者」は健康保険の被保険者から除外されます。しかし、疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができます。
(法第3条)
②【H20年出題】 ×
後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被保険者から除外されますので、健康保険の資格は喪失します。
(法第3条)
★日本は「国民皆保険制度」をとっていますので、すべての人が公的な医療保険で治療を受けることができます。
医療保険には、「健康保険」、「船員保険」、「共済組合(国家公務員、地方公務員)」、「私立学校教職員共済」、「国民健康保険」があり、健康保険がその中心になっています。
また、原則として75歳以上の人は「後期高齢者医療」の被保険者となりますので、各医療保険からは除外されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉘」条文の読み方(健康保険法)
「最初の一歩㉘」条文の読み方(健康保険法)
R4-128
R3.12.28 「行わない」と「行わないことができる」の違い
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 |
第116条の「行わない」は絶対的給付制限で、「絶対に支給しない」という意味です。保険者の裁量で、「行う」、「行わない」を決めることはできません。
第117条は、「その全部又は一部を行わないことができる」で保険者が適用するか否かを決めます。「行う」、「行わない」又は「全部」なのか「一部」なのかは保険者が判断します。
第119条は、「行わないことができる」ですが、「全部又は一部」ではなく「一部」になっているのがポイントです。「全部を停止する」ことはできません。
では、過去問をどうぞ
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
③【H22年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
絶対的給付制限が適用されるのは、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき」です。「重過失」は含まれません。
②【H23年出題】 ×
「闘争、泥酔、著しい不行跡」の場合は、「全部について行わない」ではなく、「その全部又は一部を行わないことができる」です。
③【H22年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わない」ときは、「全部または一部」ではなく、保険給付の「一部」を行わないことができる、です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑫」過去問の活用(健康保険法)
「最初の一歩⑫」過去問の活用(健康保険法)
R4-112
R3.12.12 報酬の範囲(健保編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、昨日の復習から始めましょう。
次の「報酬」の定義について、条文の空欄を埋めてください。
第3条第5項(報酬の定義)
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、< A >として受けるすべてのものをいう。ただし、< B >に受けるもの及び< C >を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

【解答】
A 労働の対償
B 臨時
C 3か月
今日は、報酬に含まれるもの、含まれないものを過去問から具体的に学びましょう
①【H24年出題】
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
②【H26年出題】
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
③【R1年出題】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。

【解答】
①【H24年出題】 ×
「通勤手当」は報酬に当たります。
なお、通勤手当が3か月ごとや6か月ごとに支給されているとしても、実態は、毎月の通勤に対し支給されるもので、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているものなので、報酬となります。
(昭27.12.4保文発2741)
②【H26年出題】 〇
「労働基準法に基づく解雇予告手当」、「退職を事由に支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの」は、報酬又は賞与には含まれません。
(昭24.6.24保文発1175号、平15.10.1保保発第1001002号/庁保険発第1001001号)
③【R1年出題】 〇
今日のポイント(退職金)
・退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの
→報酬又は賞与には該当しません
・在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合
→報酬又は賞与に該当します。(労働の対償としての性格が明確で、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有するから)
(平15.10.1保保発第1001002号/庁保険発第1001001号)
次に、「現物給与」の過去問を解いてみましょう
④【H28年出題】
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。

【解答】
④【H28年出題】 ×
都道府県知事ではなく、「厚生労働大臣」が定めます。
「通貨以外のもの」(現物給与)も報酬又は賞与に含まれます。
現物給与の価額は、その地方の時価によって「厚生労働大臣」が定めることになっていますが、健康保険組合は、規約で別の定めをすることができます。
(法第46条)
最後に「現物給与の価額」の条文を穴埋めで確認しましょう。
第46条 (現物給与の価額)
① 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、< A >が定める。
② < B >は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

【解答】
A 厚生労働大臣
B 健康保険組合
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑪」条文の読み方(健康保険法)
「最初の一歩⑪」条文の読み方(健康保険法)
R4-111
R3.12.11 報酬の定義(健保編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文で用語の定義を読んでみましょう。
第3条 ⑤ この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
⑥ この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
報酬は、保険料の計算や傷病手当金、出産手当金の基になり、また、賞与も保険料の計算の基になります。
「報酬」は、「労働の対償として受けるすべてのもの」と定義されていて、通勤手当、住宅手当なども報酬となります。
しかし、「臨時に受けるもの」と「3月を超える期間ごとに受けるもの」は報酬から除外されます。
「臨時に受けるもの」は、大入り袋など常態として受ける報酬以外のもの、「3月を超える期間ごとに受けるもの」は、年3回以下の回数で支給される賞与のことです。
なお、「報酬」、「報酬月額」、「標準報酬月額」の違いにも注意しましょう。
「報酬」は労働の対償として受けるすべてのもの、「報酬月額」はそれを月ベースに換算したもの、「標準報酬月額」は、報酬月額を標準報酬月額等級(健康保険の場合1級から50級)にあてはめて簡単な数字にしたものです。
次に「賞与」は、「3月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されていて、年3回以下の賞与のことです。もし、賞与が年間を通して4回以上支給されている場合は「報酬」に入ります。
「標準賞与額」は、「賞与額」の1,000円未満を切り捨てた額です。
ただし、年度の賞与額の累計額は573万円が上限です。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H23年出題】
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
②【H22年出題】 ※改正による修正あり
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。
③【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「臨時に受けるもの」及び「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は、報酬に含まれないのがポイントです。
②【H22年出題】 〇
標準報酬月額は、50等級に区分されていて、最低は第1級の58,000円、最高は第50級の1,390,000円です。
(法第42条)
③【H28年出題】 ×
年度の上限は、540万円ではなく、「573万円」です。
標準賞与額のポイント
・賞与額の1,000円未満の端数は切り捨てて、その月の標準賞与額を決定します
・その年度(毎年4月1日~翌年3月31日まで)の標準賞与額の累計額の上限は573万円です
・573万円を超えることとなる場合は、累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度はその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額はゼロ円になります。
 ちょっと話は変わりますが・・・
ちょっと話は変わりますが・・・
「労働基準法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」では、「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」は「賃金」といいます。
労働基準法を例にとりますと、 「臨時の賃金」、「3か月を超える期間ごとの賃金」も「賃金」に含まれます。
しかし、平均賃金を算定するときは、 「臨時の賃金」、「3か月を超える期間ごとの賃金(年3回以下の賞与)」は、賃金の総額から控除します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法
R4-067
R3.10.28 訪問看護療養費のこと
令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。
今日は「訪問看護療養費のこと」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1E】
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

【解答】
①【R3年問1E】 〇
「訪問看護事業」の定義についての問題です。
この問題文のポイントを、穴埋めで見てみましょう。空欄を埋めてください。
『訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、< A >において継続して療養を受ける状態にある者(< B >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の< A >において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(< C >等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

【解答】
A 居宅
B 主治の医師
C 保険医療機関
(法第88条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
③【H24年出題】
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
④【H28年選択式】改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、「療養の給付」の対象となります。
法第88条で、「保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるもの」は、訪問看護事業から除かれています。
保険医療機関等によるものは「療養の給付」の対象、介護保険法の介護老人保健施設、介護医療院によるものは介護保険の対象です。
(法第88条)
③【H24年出題】 ×
訪問看護は、「療養上の世話又は必要な診療の補助」ですので、医師、歯科医師は入りません。
(法第88条、則第68条)
④【H28年選択式】改正による修正あり
A 保険者
B 自己
(法第88条)
最後に穴埋め問題をどうぞ!
訪問看護は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< D >が行う。

【解答】
D 言語聴覚士
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法
R4-064
R3.10.25 傷病手当金「療養」の意味
令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。
今日は「傷病手当金「療養」の意味」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9D】
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

【解答】
①【R3年問9D】 ×
傷病手当金は、「療養のため」労務に服することができないときに支給されます。
この「療養」とは、保険医から療養の給付を受けることだけでなく、自費診療による療養も含まれます。
(S2.2.26保発345)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

【解答】
②【H23年出題】 〇
「自費診療で受けた療養」、「自宅での療養」、「病後の静養」についても、傷病手当金の要件である「療養」に該当するので、傷病手当金の支給対象となります。
※美容整形手術による療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲には入りませんので、傷病手当金も支給されません。
(S2.2.26保発345)
比較しましょう/日雇特例被保険者の傷病手当金
③【H23年出題】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。

【解答】
③【H23年出題】 〇
一般の被保険者の傷病手当金は、療養の給付を受けていることが要件ではなく自費療でも対象になりますが、日雇特例被保険者の傷病手当金の場合は、「療養の給付を受けていること」が要件で、自費診療等の場合は傷病手当金は支給されません。
ただし、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていればよく、労務不能期間のすべてに療養の給付を受けていることを要しない、とされています。
(H15.2.25庁保発1)
条文を穴埋めで確認しましょう
第99条 (傷病手当金)
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため< A >ができないときは、その< A >ができなくなった日から起算して< B >を経過した日から < A >ができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】
A 労務に服すること
B 3日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法
R4-056
R3.10.17 健保「資格喪失後の出産手当金の継続給付」
令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。
今日は資格喪失後の出産手当金の継続給付です。
では、どうぞ!
①【R3年問9B】
1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

【解答】
①【R3年問9B】 ×
「退職日において通常勤務していた」の部分がポイントです。 退職日に勤務したときは、資格喪失後の出産手当金は支給されません。
「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」ことが、出産手当金の継続給付の要件です。なお、実際に支給を受けていなくても「受ける条件」を満たしている場合は、「支給を受けている」こととなります。
出産手当金は「労務に服さなかった」ことが条件です。退職日に勤務していたということは、その条件を満たしていません。
そのため、資格喪失後の出産手当金は支給されません。
(法第104条)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。
③【H24年出題】
被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
出産手当金(多胎妊娠ではない。)は、出産予定日以前42日からが対象です。
5月25日が出産予定日の場合は4月14日~となり、3月20日に退職した場合は、資格喪失時に出産手当金を受ける条件を満たしていないので、資格喪失後に出産手当金の継続給付は受けられません。
(法第104条)
③【H24年出題】 ×
資格喪失後6月以内の出産の規定は、資格喪失後の「出産育児一時金」が当てはまります。
★確認しましょう。(資格喪失後の出産育児一時金)
「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」
(法第106条)
条文を穴埋めでチェックしましょう!
第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して< A >からその給付を受けることができる。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付)
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後< B >以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を< C >から受けることができる。

【解答】
A 同一の保険者
B 6月
C 最後の保険者
★第106条の「1年以上被保険者であった者」は、第104条の条件と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)健保法 応用問題
R4-047
R3.10.8 健保「健康保険と労災保険の関係」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は健康保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E】
被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

【解答】
①【R3年問9E】 〇
被保険者が副業として行う請負業務中の負傷や、被扶養者の請負業務やインターンシップ中の負傷などのように、労災保険の給付が受けられない場合は、原則として健康保険の給付が行われます。
問題文のテーマは、「業務災害・通勤災害と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、健康保険の保険者は、まずは労災保険への請求を促し、健康保険の給付を留保することができるか?」というものです。
回答は、
・ 労災保険法の業務災害については健康保険の給付の対象外であり、また、労災保険法における通勤災害については労災保険からの給付が優先される。そのため、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができる。
・ ただし、保険者において、健康保険の給付を留保するに当たっては、関係する医療機関等に連絡を行うなど、十分な配慮を行うこと。
とされています。
(法第1条 平成25.8.1事務連絡)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
③【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

【解答】
②【H28年出題】 〇
請負業務中に負傷した場合、「業務」ではあっても労働者ではないので労災保険の給付の対象にはなりません。このような労災保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われます。
(法第1条 平成25.8.1事務連絡)
③【H30年出題】 ×
「通勤災害」は健康保険の対象ですが、労災保険からの給付が優先されます。労災保険の給付を受けることができる場合には、健康保険の保険給付は行われませんので、問題文の場合は、埋葬料は支給されません。
(法第55条)
穴埋めで条文を確認しましょう!
第1条 (目的)
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(< A >第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第55条 (他の法令による保険給付との調整)
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の< B >について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

【解答】
A 労働者災害補償保険法
B 疾病、負傷又は死亡
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)健康保険法よく出るところ
R4-037
R3.9.28 健保「資格喪失月の賞与」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は健康保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1D】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
①【R3年問1D】 〇
ポイント!
(資格喪失月に支払われた賞与について)
・原則として保険料は徴収されません
・標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額に算入されます
法第156条、(H19.5.1 庁保険発第0501001号)
では、こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
③【H25年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
③【H25年出題】 〇
資格喪失月に支給された賞与について、原則として保険料を納付する義務はありません。
※年度の標準賞与額の累計額には算入されます。
では、最後にこちらをどうぞ!
第45条 (標準賞与額の決定)
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >万円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】
A 1,000
B 573
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)健康保険法の定番問題
R4-027
R3.9.18 休業手当と随時改定
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は健康保険です。
では、どうぞ!
①【R3年問1A】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
①【R3年問1A】 〇
低額な休業手当が支払われることとなった場合は、随時改定の対象となります。ただし、固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限られます。
ちなみに、休業手当等をもって標準報酬月額の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象となります。
(S50.3.29保険発25・H15.2.25庁保険発3)
では、こちらもどうぞ!
②【R3問1B】
賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払が行われ、5月1日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

【解答】
②【R3問1B】 ×
①の問題の解説にも書きましたように、一時帰休に伴う随時改定は、低額な休業手当等の支払が継続して『3か月を超える』場合に行われます。
この『3か月』は「暦日単位」ではなく「月単位」で計算します。
問題文の場合は、一時帰休の開始が2月19日ですので、2、3、4月で3か月です。5月1日が「3か月を超える場合」に該当し、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行います。
しかし、問題文では、「5月1日に一時帰休の状態が解消している」ということですので、3か月を超えません。そのため随時改定は行いません。
(参照:H29.6.2付け厚生労働省年金局事業管理課長 事務連絡)
では、随時改定の条文を確認しましょう。
① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、< A >日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を< B >で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった < C >に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を< C >として、その著しく高低を生じた月の< D >から、標準報酬月額を改定することができる。
② ①の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(< E >までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

【解答】
A 17
B 3
C 報酬月額
D 翌月
E 7月から12月
(法第43条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・健康保険法【択一】
R4-019
R3.9.10 第53回健保(択一)より~複合問題
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 細かい知識を問われる問題が目立ちました。しかし、テキストや過去問で強調されているところをおさえていれば、問題は解けます。難問に引きずられることがないよう、基本で勝負できるようにしましょう。
【R3年問10】
(問10-A)
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。
(問10-B)
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。
(問10-C)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
(問10-D)
倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。
(問10-E)
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【解答】
(問10-A) 〇
時間給の単価に変動はない、しかし、勤務体系に変更(1日の所定労働時間が8時間から6時間になった)があった場合、「固定的賃金の変動に該当」し、随時改定の対象となります。
(参照:「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕 R3.4.1事務連絡)
(問10-B) ×
7月から9月までのいずれかの月から、「随時改定」、「育児休業を終了した際の改定」、「産前産後休業を終了した際の改定」が行われた場合は、その年の定時決定は行われません。
(法第41条)
(問10-C) 〇
保険料控除のポイント
①「前月分」の保険料を報酬から控除することができる
②被保険者がその事業所に使用されなくなった場合(退職の場合)
→前月分と当月分の保険料を報酬から控除することができる
※月の途中で退職した場合 → 前月分のみ控除することができる
※月末に退職した場合 → 前月分と今月分の2か月分を控除することができる
(法第167条)
(問10-D) 〇
・国民健康保険には、倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度があります。
・そのため、失業後に、任意継続被保険者となった場合よりも、国民健康保険の保険料が低くなる場合もあります。
・しかし、任意継続被保険者が保険料を前納した場合、前納に係る期間の経過前には、その資格を喪失したとき(他の健康保険の被保険者となったとき、死亡したとき等)以外は、前納された保険料を還付する取扱いはありません。
・このため、特定受給資格者等である任意継続被保険者が、保険料を前納した後に国民健康保険の軽減制度について知った場合は、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることによって、前納を初めからなかったものとすることができるようになっています。
(参照:H22.3.24 保保発0324第2号)
(問10-E) 〇
療養費として支給される額は、「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)」に基づいて計算した額」から、「一部負担金の割合を乗じて得た額」を差し引いた額となります。「実際に支払った額」が基準になるわけではないので注意してください。また、食事療養や生活療養を受けた場合も同じように計算します。
(法第87条)
■この問題のポイントを穴埋めでチェックしておきましょう。
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を< A >。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、< B >が定める。

【解答】
A 除く
B 保険者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(健康保険法)
R4-008
R3.8.30 第53回選択健保~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「健康保険法」の選択式です。
問題1 一般保険料率(第156条、第160条)
第156条では、保険料額について、介護保険第2号被保険者は、「一般保険料額+介護保険料額」、介護保険第2号被保険者以外は「一般保険料額」とされています。
「一般保険料額」は、標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ「一般保険料率」を乗じて計算します。
「一般保険料率」の内訳は、「基本保険料率+特定保険料率」となります。
特定保険料率は、後期高齢者医療制度への支援金等に充てるための保険料率で、特定保険料率の計算式は、
「(前期高齢者納付金等の額、後期高齢者支援金等の額)÷総報酬額の総額の見込額」で得た率を基準として、保険者が定めることになっています。
協会けんぽの場合、分子は(前期高齢者納付金等の額、後期高齢者支援金等の額-国庫補助額)となります。
ちなみに、
国庫補助額を「控除」か「加算」かで迷いませんでしたか?保険者は国庫補助額の分、負担が減ると考えると「控除」が選べます。
「総報酬額」か「総報酬額の総額」かで迷いませんでしたか?「総報酬額」は個別の標準報酬月額と標準賞与額の合計です。保険者全体の総額を使うので、「総報酬額の総額」となります。
問題1 ★☆☆ 暗記が肝心
問題2 標準報酬月額(第40条)
この問題は、ばっちり解けると思います。
問題2 ☆☆☆ どうにか解ける
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法 選択対策
R3-356
R3.8.14 健康保険法 選択問題(保険料率)
今日は健康保険の選択対策。テーマは保険料率です!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
第160条(保険料率)
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >までの範囲内において、< B >を単位として< C >が決定するものとする。
5 全国健康保険協会は、< D >ごとに、翌事業年度以降の< E >年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、 < F >の議を経なければならない。
10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
11 厚生労働大臣は、協会が第10項の期間内に申請をしないときは、< G >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】
A 1,000分の30から1,000分の130
B 支部被保険者
※支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
C 全国健康保険協会
D 2年
E 5
F 運営委員会
G 社会保障審議会
(健康保険法第160条第1項、5項、6項、10項、11項)
では、過去問もどうぞ!
①<H26年出題>
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
②<H29年出題>
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

【解答】
①<H26年出題> 〇
「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内、「支部被保険者を単位」、「協会が決定」がポイントです。
(法第160条第1項)
なお、第2項では、「支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する」と規定されています。
②<H29年出題> 〇
「介護保険第2号被保険者」、「保険者が定める」の部分がポイントです。
(法第160条第16項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 埋葬料と埋葬費
R3-334
R3.7.23 埋葬料と埋葬費の違い
今日は、健康保険法「埋葬料と埋葬費の違い」です。
では、条文からどうぞ!
空欄を埋めてください
第100条 埋葬料
1 被保険者が死亡したときは、その者により< A >者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 1の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< B >者に対し、1の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

【解答】
A 生計を維持していた
B 埋葬を行った
| 対 象 | 金 額 | |
| 埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った者 (埋葬料の支給を受けるべき者がない場合) | 埋葬に要した費用 (5万円の範囲内) |
では、こちらをどうぞ!
①<H24年出題>
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
②<H25年出題>
埋葬を行う者とは、埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
③<H25年出題>
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。

【解答】
①<H24年出題> 〇
「生計の一部を維持していた者」も埋葬料の対象になります。被扶養者とは別の概念です。
(参照 昭8.8.7保発502)
②<H25年出題> ×
埋葬を行う者とは、「社会通念上」埋葬を行うべき人のことで、実際に埋葬を行うかどうかではありません。問題文の場合は、配偶者は埋葬料の支給対象となり得ます。
③<H25年出題> ×
生計を維持されていなかった兄弟姉妹が実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の支給対象となります。
(参照 昭26.6.28保文発162)
こちらもどうぞ!
④<H26年出題>
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

【解答】
④<H26年出題> 〇
ポイント!
・埋葬料 → 埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付される
保険事故発生の日は「死亡した日」
・埋葬費 → 死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されない
保険事故発生の日は「埋葬した日」
★時効の起算日(保険事故発生の日の翌日)
| 埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
出産育児一時金
R3-333
R3.7.22 出産育児一時金のポイントチェック
今日は、「出産育児一時金」のポイントをチェックします!
では、問題をどうぞ!
①<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
②<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。
③<H26年出題>
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

【解答】
①<H21年出題> 〇
私生児の出産でも支給されます。なぜなら、主として「母体を保護する」ことが、出産に関する給付の目的だからです。
(参照 昭2.3.17保理792)
②<H21年出題> 〇
出産に関する給付は、妊娠4か月以上の出産が対象です。
1月は28日で計算するので、28日×3月+1日=85日。85日目が4か月目に入った日になるため、妊娠85日以降が出産に関する給付の対象となります。
(参照 昭3.3.16保発11)
また、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を問いません。
(参照 昭27.6.16保文発2427)
③<H26年出題> ×
労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、出産育児一時金の支給は行われます。
(参照 昭24.3.26保文発第523号)
こちらもどうぞ!
④<H27年出題>
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
⑤<H21年出題>
被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
⑥<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。

【解答】
④<H27年出題> 〇
出産育児一時金の額は一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は40万4千円)です。
(施行令第36条)
⑤<H21年出題> ×
妊娠4か月以降の死産の場合は出産育児一時金は支給されます。しかし、死産児は被扶養者ではないので、家族埋葬料は支給されません。
(参照 昭23.12.2保文発898)
⑥<H21年出題> 〇
例えば、双子の場合は42万円×2=84万円となります。(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は404,000円×2=808,000円)
(参照 平20.12.17保保発1217004)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 入院時生活療養費
R3-332
R3.7.21 入院時生活療養費~選択対策~
「入院時生活療養費」は選択式で出題実績があります。
チェックしておきましょう!
では、問題をどうぞ!
①<H19選択>
療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を < A >といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち< B >から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、< C >として現物で支給する。< C >の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して< D >が定めた基準により算定した額から< E >を控除した額とする。

【解答】
A 特定長期入院被保険者
B 自己の選定するもの
C 入院時生活療養費
D 厚生労働大臣
E 生活療養標準負担額
(法第85条の2)
ポイント!
・入院時生活療養費は「現物」で支給される
・「厚生労働大臣の算出基準による生活療養費」から、「生活療養標準負担額」を控除したものが「入院時生活療養費」として現物給付されます。
次はこちらをどうぞ!
②<H26選択>改正による修正あり
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
(1)下記(2)(3)以外の者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(2)病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者 → 1日につき< D >円と1食につき260円との合計額

【解答】
A 介護保険法
B 370
C 460
D 0
★生活療養標準負担額は、「居住費(光熱水費)」と「食費」の合計です。
※生活療養標準負担額(低所得者以外)
| 生活療養標準負担額 | ||
(1) (2)(3)以外 | 居住費(1日) 370円 | 食費(1食) 460円又は420円 ※管理栄養士等を配置している保険医機関の場合は460円となる。 |
(2)病状の程度が重篤な者等 | 同上 | 同上 |
| (3)指定難病の患者 | 0円 | 1食 260円 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 被保険者証のこと
R3-306
R3.6.25 健保 被保険者証のフロー
今日のテーマは、被保険者証のフローです。
従業員が入社した場合、事業主は資格取得届を提出します。
提出先は、「全国健康保険協会」(協会けんぽ)の場合は日本年金機構へ、「健康保険組合」の場合は「健康保険組合」です。
昨日お話しましたように、資格取得届が提出されると、協会けんぽの場合、厚生労働大臣が確認を行います。協会けんぽは、その情報の提供を受けて、被保険者証を交付します。
健康保険組合の場合は、健康保険組合で資格取得の確認を行い、被保険者証を交付します。
まずはこちらからどうぞ!
①<H23年出題>
厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期間を定めて交付するものとする。
②<H26年出題>
被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

【解答】
①<H23年出題> 〇
ポイント! 「被保険者資格証明書」は協会けんぽのみ。健保組合にはありません
「協会けんぽ」の場合、年金機構に資格取得届を提出して、厚生労働大臣が確認→協会けんぽに情報提供→協会けんぽから被保険者証を交付、という流れになるので、被保険者証の交付まで時間がかかります。
「被保険者資格証明書」は、被保険者証が交付されるまでの間に病院で療養を受ける必要がある場合、事業主又は被保険者からの求めがあった場合に交付されます。
被保険者資格証明書は、協会けんぽではなく「厚生労働大臣」が交付する点にも注意してください。
(則第50条の2)
②<H26年出題> 〇
被保険者資格証明書は、被保険者証の交付を受けたときなどは使えなくなるので、返納します。返納は、事業主を経由することがポイントです。
(則第50条の2)
こちらもどうぞ!
③<R1年出題>
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。
④<H27年出題>
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。

【解答】
③<R1年出題> 〇
施行規則第50条で、「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。」と規定されています。
④<H27年出題> ×
3年ごとではなく「毎年一定の期日を定め」です。被扶養者が就職するなどで扶養の状況は変化することもあるので、現に扶養に該当するかどうかチェックできるという仕組みです。
(則第50条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 資格得喪の確認
R3-305
R3.6.24 健保 資格の得喪の確認
今日のテーマは、資格得喪の確認です。
ところで、健康保険には「確認」の制度がありますが、労災保険には「確認」はありません。
なぜなら、労災保険は「労働者」であれば全て保護されるからです。そのため、労災保険には資格取得届もありません。
(ちなみに、国民年金にも「確認」という制度はありません。)
まずは穴埋めで確認しましょう!
第39条 資格得喪の確認
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては< A >、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる。
ただし、任意適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
確認は、資格の取得及び喪失の届出若しくは被保険者又は被保険者であった者からの請求により、又は職権で行うものとする。

【解答】
A 厚生労働大臣
この条文で「保険者等」とは厚生労働大臣と健康保険組合を指します。厚生労働大臣は保険者ではないので、「等」がついています。
(法第39条、附則第3条)
★例えば、6月24日に入社しても、事業主が届出をしないままだと、保険者等は入社の事実を知らないので、健康保険の資格は取得できません。
「確認」とは、事業主からの届出等によって入社の事実を保険者等に知ってもらい、それによって、健康保険の被保険者としての効力が発生するというものです。(退職の場合も同じ)
確認の方法は、①事業主からの届出、②被保険者又は被保険者であった者からの請求、③職権の3つです。
★「任意適用の取消しによる被保険者の資格の喪失」の場合は、任意適用取消しの厚生労働大臣の認可があった日の翌日に資格を喪失すると決まっているので、確認の必要はありません。
また、任意継続被保険者と特例退職被保険者は、資格得喪の理由が入社や退職ではないので、こちらも確認はいりません。
こちらもどうぞ!
①<H21年出題>
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
②<H26年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
③<H30年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

【解答】
①<H21年出題> ×
全国健康保険協会の被保険者の確認は全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。(上の穴埋めの部分です。)
法第5条で、『全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。』と規定されています。
※なぜ「厚生労働大臣」が出てくるのか?
適用事業所に入社した場合、健康保険と厚生年金保険はセットで加入します。厚生年金保険と健康保険で重なる事務は、厚生年金保険の事務を行う厚生労働大臣がまとめて行うということです。
( )で、任意継続被保険者が除かれているのは、任意継続被保険者は、退職しているため厚生年金保険とセットで加入することが無いからです。
②<H26年出題> ×
確認は要りません。
③<H30年出題> ×
同じく、保険者等の確認は要りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 任意継続被保険者の標準報酬月額
R3-304
R3.6.23 任意継続被保険者の標準報酬月額
今日のテーマは、「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。
ではどうぞ!
①<R1選択>
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

【解答】
A 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(法第47条)
※令和3年度の、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は令和2年度と同じ30万円です。(令和2年9月30日時点の標準報酬月額の平均額は290,274円だそうです。)
こちらもどうぞ!
②<H15年出題>
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
③<H30年出題>
一般の被保険者に関する保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
②<H15年出題> 〇
★在職中
| 保険料の負担 | 被保険者と事業主は、それぞれ2分の1を負担 |
| 納付義務 | 事業主が負う |
★退職後(任意継続被保険者)
| 保険料の負担 | 任意継続被保険者が全額負担 |
| 納付義務 | 任意継続被保険者が負う |
(法第161条)
③<H30年出題> ×
初めて納付すべき保険料の期限が誤りです。
★保険料の納期限
| 在職中 | 翌月末日 |
| 任意継続被保険者 | その月の10日 ※初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日 例えば、6月23日に任意継続被保険者の資格を取得した場合、6月から任意継続被保険者として保険料が徴収されるが、既に6月10日を過ぎているから。 |
(法第164条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法 標準賞与額に係る保険料
R3-264
R3.5.14 (健保)標準賞与額に係る保険料
今日は、標準賞与額に係る保険料です。
「賞与」の定義からどうぞ!
①<R1年出題>
保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

【解答】
①<R1年出題> 〇
賞与の定義は「3か月を超える期間ごと」に受けるものです。
なお、「臨時に」受けるものは、報酬にも賞与にも入りません。
「3か月を超える期間ごと」に受けるものとは、年3回以下の回数で支給されるいわゆるボーナスのことです。
6か月ごとに支給される通勤手当は、支払の便宜上6か月間を一括して支給するものですので、賞与ではなく報酬となります。
(法第3条、昭26.9.18保文発3603、昭40.8.4庁保険発38)
次は「標準賞与額」をどうぞ!
②<R1年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

【解答】
②<R1年出題> 〇
標準賞与額とは
・賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額
・上限あり → 年度(4月1日~翌年3月31日)の標準賞与額の累計額が573万円を超える場合は、累計額が573万円となるよう決定される
ポイント!賞与の累計は、保険者単位で行われます
問題文の前段は、年度の累計が573万円になるよう、3月は173万円となります。
後段は、年度の途中で保険者が変わっているので、賞与の累計は保険者単位となります。全国健康保険協会管掌健康保険分は、7月150万円、健康保険組合管掌健康保険分は、12月250万円、3月200万円となります。
(法第45条、H18年8月18日付け事務連絡)
最後に、こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。
④<H29年出題>
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
③<H24年出題> 〇
被保険者負担分の標準賞与額に係る保険料を賞与から控除することができます。
(法第167条第2項)
④<H29年出題> 〇
資格を喪失した月は、標準賞与額に係る保険料についても納付する義務はありません。
なお、資格を喪失した月は、保険料徴収の必要はありませんが、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額573万円に算入されます。
(法第156条、H19.5.1庁保険発第0501001号)
社労士受験のあれこれ
健康保険法 家族療養費
R3-263
R3.5.13 (健保)家族療養費でよく出るところ
今日は、家族療養費です。
こちらからどうぞ!
①<R1年出題>
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

【解答】
①<R1年出題> ×
被保険者に対して支給されるのは、入院時生活療養費ではなく「家族療養費」です。
(法第110条)
| ★被扶養者に関する給付 | 被保険者に関する給付 |
| 家族療養費 | 療養の給付 療養費 入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 |
| 家族訪問看護療養費 | 訪問看護療養費 |
| 家族移送費 | 移送費 |
| 家族埋葬料 | 埋葬料 |
| 家族出産育児一時金 | 出産育児一時金 |
こちらもどうぞ!
②<H19年出題>
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
③<H23年出題>
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。

【解答】
②<H19年出題> 〇
家族療養費は「被保険者」に対して支給されるのがポイントです。「被扶養者に対して」ではありません。
(法第110条)
③<H23年出題> ×
家族訪問看護療養費は、「当該被扶養者に対して」ではなく、「被保険者に対して」支給されます。
(法第111条)
ポイント!
被扶養者に関する給付(家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金)は、被保険者に対して支給されます。(被扶養者に対してではありません。)
では、こちらもどうぞ!
④<H24年出題>
被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。

【解答】
④<H24年出題> ×
「当日から」支給されない、ではなく「翌日から」支給されなくなります。
家族療養費は、被保険者に対して支給されるので、被保険者が死亡した場合は家族療養費は支給されなくなります。
被保険者が死亡した場合、資格の喪失は死亡日の翌日です。ですので、家族療養費が支給されなくなるのは、死亡の日の翌日からとなります。
社労士受験のあれこれ
健康保険法 現物給付と現金給付
R3-262
R3.5.12 (健保)現物給付と現金給付
今日は、「現物給付」と「現金給付」です。
健康保険法の保険給付の代表「療養の給付」。例えば、病気で病院に行き、診察を受ける、注射を打ってもらう、入院する、手術を受ける等々は「現物給付」です。現金が支給されるわけではありません。
一方、「療養費」は現金給付です。近くに保険医療機関がないなどの理由で、保険医療機関等以外で治療などを受けた場合は、現物給付ではなく、費用が支払われます。
「現物給付」と「現金給付」についての問題をみていきましょう。
こちらからどうぞ!
①<H29年出題>
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
②<H24年出題>(修正)
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医用機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
③<R1年出題>
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

【解答】
①<H29年出題> 〇
入院時食事療養費は第85条で第1項で、「療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。」と定められていますが、実際は現物給付となっています。
同条第5項で、「保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。」とされているからです。
第5項を解体して流れを書きますと、被保険者が療養の給付と併せて食事療養を受けた場合、
・ 本来は被保険者が病院又は診療所に食事療養に要した費用を支払う
↓
・ 保険者から被保険者に対して食事療養の費用を入院時食事療養費として支給する
ここまでだと現金給付になるのですが、
↓
・ 保険者は、「入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度で、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」、とされていて、保険者から病院等に食事に要した費用を直接支払うことによって、結果として現物給付になるという仕組みです。
(法第85条)
②<H24年出題>(修正) 〇
保険外併用療養費も「現物給付」で行われます。
先ほどの入院時食事療養費と同じです。
第86条第1項では、「その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。」となっているのですが、実際は、保険者から保険医療機関等に、直接費用を払うことができるので、結果として現物給付となっています。
(法第86条)
③<R1年出題> 〇
訪問看護療養費も、第88条第1項で、「被保険者が指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。」と規定されています。
しかし、同条第6項で保険者が被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる、とされていて、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者に直接費用を支払うことによって、結果として現物給付になっています。
(法第88条)
では、現金給付の問題もどうぞ!
④<H24年出題>
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

【解答】
④<H24年出題> 〇
移送費は「現金給付」です。
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用の範囲内で算定されます。(ただし、実費を超えることはできません。)
(法第97条)
社労士受験のあれこれ
健保・報酬支払基礎日数など
R3-223
R3.4.3 報酬支払基礎日数と翌月払いの賃金
引き続き健康保険法です。
今日のテーマは、報酬支払基礎日数と翌月払いの賃金です。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)

【解答】 〇
定時決定は、支払月が4月、5月、6月の賃金で行います。
問題文の場合、定時決定に用いる報酬は、3月分、4月分、5月分の賃金となります。
3月分(3月1日~31日)→4月15日支払い
4月分(4月1日~30日)→5月15日支払い
5月分(5月1日~31日)→6月15日支払い
では、報酬支払基礎日数の問題もどうぞ
②<H25年出題>
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
③<H28年出題>
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

【解答】
②<H25年出題> 〇
③<H28年出題> ×
「暦日の数」から当該欠勤日数を控除した日数が誤りです。
★報酬支払基礎日数の算定については以下のように取り扱います。
① 月給者 → 各月の暦日数による
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合 → 就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による
③ 日給者 → 各月の出勤日数による
(平18.5.12庁保険発第0512001号)
社労士受験のあれこれ
定時決定・休職給を受けた場合
R3-222
R3.4.2 定時決定~休職給の扱いなど
引き続き健康保険法です。
定時決定は毎年7月1日時点に行われますが、その際休職している場合などはどうするの?が今日のテーマです。
では、どうぞ!
①<H30年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。

【解答】 〇
報酬月額を算定する際に「低額の休職給を受けた月を除く」のがポイントです。
例えば、4月に低額の休職給を受けた場合は、5月と6月の報酬で報酬月額を算定します。
(昭和37.6.28保険発第71号)
なお、4月、5月、6月すべての月が低額の休職給だった場合は、従来の報酬月額をそのまま用います。
では、こちらの問題もどうぞ
②<H16年出題>
被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。

【解答】 ×
休職期間中の給与による標準報酬月額ではなく、休職前の標準報酬月額によります。
(昭和27.1.25保文発420号)
こちらもどうぞ!
③<H20年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
④<R1年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

【解答】
③<H20年出題> 〇
④<R1年出題> 〇
介護休業中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定します。
(育児休業中も同様です)
(平11.3.31保険発46・庁保険発9)
社労士受験のあれこれ
再雇用時の標準報酬月額
R3-221
R3.4.1 60歳以降再雇用されたときの標準報酬月額について
今日は健康保険法です。
60歳以上で定年になり、引き続き再雇用されたとき、報酬が下がることが一般的に多いです。
今日は、そのような場合の標準報酬月額の決定方法がテーマです。
では、どうぞ!
<R1年出題>
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

【解答】 〇
定年退職後引き続き再雇用する際に、報酬を下げる会社が一般的に多くみられます。
その際、健康保険の資格は継続しますので、報酬が下がった場合は、固定的賃金の変動として本来なら随時改定の対象です。
しかし随時改定の場合、標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動から4か月目からです。そうなるとしばらく定年退職前の高い報酬による標準報酬月額が続くことなります。
この問題のポイントは、対象が「60歳以降に退職後継続して再雇用」される人であることです。
使用関係が一旦中断したものとみなし、随時改定ではなく「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を提出することによって、下がった報酬による標準報酬月額がすぐに適用される点でメリットがあります。高齢者の継続雇用を支援するための仕組みです。
(H25.1.25保保発0125第1号)
社労士受験のあれこれ
健康保険法第1条(目的)
R3-187
R3.2.26 第1条チェック~健康保険法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は健康保険法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 目的>
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害
『労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産』とは?
労働者が業務上負傷した場合、業務災害として労災保険の保険給付が受けられます。
一方、例えば、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務中に負傷した場合は、業務であったとしても「労働者」ではないので、労災保険の対象になりません。
このように労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の保険給付が受けられます。
(参照:平成25.8.14事務連絡 全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
では、こちらもどうぞ
①<H21年出題>
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
②<H28年選択(社一)>
世界初の社会保険は、< B >で誕生した。当時の< B >では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から < B >に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、< C >に「健康保険法」を制定した。

【解答】
①<H21年出題> ×
健康保険法は、大正11年に制定されましたが、全面施行は昭和2年です。
なお、「日本で最初の社会保険」の部分は正しいです。健康保険のポイントです。
②<H28年選択(社一)>
B ドイツ
C 大正11年
日本の社会保障制度には大きく分けて「社会保険方式」と「公的扶助方式」があります。健康保険は「保険」の仕組みで運営されている「社会保険方式」です。
なお、財源が公費である「公的扶助方式」の代表例は生活保護です。
(参照:平成23年版 厚生労働白書)
社労士受験のあれこれ
(健保)高額療養費
R3-175
R3.2.14 高額療養費の計算問題
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。

【解答】
A 125,570円
【高額療養費の計算問題のチェックポイント!】
●年齢 → 70歳未満か70歳以上かで高額療養費算定基準額が違うので
●標準報酬月額 → 同じく高額療養費算定基準額が違うので
●高額療養費の計算に入れないもの
・特別料金(評価療養、患者申出療養、選定療養)
・食事療養標準負担額
・生活療養標準負担額
●問題文では、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)・高額療養費、どちらを問われているのか?
問題文の場合
年齢50歳、標準報酬月額41万円
高額療養費の対象→保険診療に要した費用70万円(一部負担金相当額21万円)
※評価療養に係る特別料金10万円、選定療養に係る特別料金20万円は対象外
<高額療養費算定基準額(自己負担限度額)の算定式>
80,100円+(700,000円(療養に要した費用)-267,000円)×1%
= 84,430円(自己負担限度額)
<高額療養費>
210,000円-84,430円 = 125,570円
この問題では「高額療養費」が問われているので、答えは125,570円です。
こちらの問題もどうぞ!
①<H27年出題>
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
②<H27年出題>
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%
③<H28年選択>
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-< A >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は< B >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< C >となる。

【解答】
①<H27年出題> 〇
特別料金(評価療養、患者申出療養、選定療養)、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象となりません。
②<H27年出題> 〇
ちなみに、558,000円の30%が167,400円です。
③<H28年選択>
A 842,000円
B 45,820円
C 140,100円
Aの額 → 252,600円÷0.3=842,000円
・当該被保険者の一部負担金
1,000,000円×0.3=300,000円
・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
・高額療養費
300,000円-254,180円=45,820円
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(健保)短時間労働者の適用
R3-172
R3.2.11 短時間労働者~所定労働時間のカウント
今日は健康保険です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-D>
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】 〇
★1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の場合は、原則として健康保険は適用除外です。
ただし、4分の3未満でも一定の要件を満たせば、被保険者となります。
<被保険者になる要件>
①週の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上使用されることが見込まれる
③報酬の月額が88,000円以上
④学生でない
⑤特定適用事業所に使用される(事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと)
①「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」という要件がありますが、例えば、所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間は「1ヵ月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して算出することとなっています。
・1年間を 52 週、1ヵ月を 12 分の 52 週とする → 1か月の所定労働時間を12 分の 52 で除すことで1週間の所定労働時間を算出できる。
問題文の「特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められている」とは、例えば、夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められているような場合です。そのような場合、『当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を 12 分の52で除して』1週間の所定労働時間を算出します。
(参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」)
こちらの問題もどうぞ!
①<H30年出題その1>
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。
②<H30年出題その2>
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
①<H30年出題その1> 〇
令和2年度と同様、所定労働時間20時間以上のカウントについての問題です。
問題文の「1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない」とは、例えば、4週5休制等のような場合です。そのような場合は、『当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間』を1週間の所定労働時間として算定します。
②<H30年出題その2> ×
「報酬の月額が88,000円以上」の算定のルールです。
88,000円は、基本給と諸手当で算定します。
ただし、次の①から④までの賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
※④のように、最低賃金に算入されない賃金は88,000円に含みません。ですので、問題文の場合、家族手当も通勤手当も算定の対象にはなりません。
(参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(健保)療養の指示に従わない場合
R3-151
R3.1.21 療養の指示に従わない場合の給付制限
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-D>
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

【解答】 〇
問題文が長いですが、キーワードは 『正当な理由なしに』『療養の指示』『従わない』です。このような場合は、『保険給付の一部を行わないことができる』です。
(健康保険法第119条)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
 <H28年出題>
<H28年出題>
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
令和2年度の問題と同じです。
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の『一部を行わないことができる』です。「全部又は一部」ではないので注意しましょう。
(健康保険法第119条)
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
『闘争、泥酔又は著しい不行跡』の場合は、『全部又は一部を行わないことができる』です。問題文の「全部について行わない」は間違いです。
(健康保険法第117条)
 <H28年出題> 〇
<H28年出題> 〇
文書の提出等の命令に従わない、答弁や受診を拒んだ、そんなときは、『全部又は一部を行わないことができる』です。
(健康保険法第121条)
穴埋めで条文もチェック!
<第116条> 被保険者又は被保険者であった者が、自己の< A >により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
<第117条> 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< B >。
<第119条> 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< C >。
<第120条> 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、< D >以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< E >を経過したときは、この限りでない。
<第121条> 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の< G >。

【解答】
A 故意の犯罪行為 (第116条)
B 全部又は一部を行わないことができる (第117条)
C 一部を行わないことができる (第119条)
D 6月 (第120条)
E 1年 (第120条)
F 全部又は一部を行わないことができる (第121条)
社労士受験のあれこれ
説明動画を作ってみました。よかったらどうぞ。
(健保)療養費~海外で療養を受けた場合
R3-150
R3.1.20 療養費支給申請書に添付する証拠書類
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問8-E>
被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。

【解答】 〇
海外で療養等を受けた場合は、療養費の対象になります。
療養費の申請手続の添付書類が外国語で記載されていたら・・・『日本語の翻訳文を添付してください、何か問い合わせすることがあるかもしれないので、翻訳者の氏名及び住所を記載してください』という感じで読んでみてください。
(参照:昭和56年2月25日 保険発第10号・庁保険発第2号)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H21年出題>
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。

【解答】 ×
最後の「保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。」が間違いです。『その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。』ことになっています。
支給申請や受領を、海外にいる被保険者と保険者が直接やり取りするのは、効率が悪いからです。
なお、この問題文には他にもポイントがあります。
・ 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせること (支給申請は原則事業主経由)
・ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること
(療養を受けた日、申請をした日ではないので注意しましょう。)
(参照:昭和56年2月25日 保険発第10号・庁保険発第2号)
条文もチェック!
<療養費>
保険者は、療養の給付等を行うことが< A >であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者が< B >ものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

【解答】
A 困難
B やむを得ない
(健康保険法第87条)
社労士受験のあれこれ
(健保)報酬から控除する保険料
R3-149
R3.1.19 支払う報酬が無いときの保険料の負担
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-オ>
事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

【解答】 〇
たとえ、被保険者に支払う報酬が無くて保険料を控除できない場合であっても、事業主には、被保険者負担分の保険料を保険者に納付する義務があります。(会社から受け取る報酬が無くても、被保険者は健康保険料を負担する義務があるということ)
(参照:昭和2年2月18日 保理第578号)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。

【解答】
 <H25年出題> ×
<H25年出題> ×
令和2年度の問題と同じように考えればいいと思います。
報酬から控除した保険料の額が、本来、被保険者の負担すべき額に足りなかったとしても、事業主には保険料の全額を納付する義務があります。
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
この問題も同じです。報酬がなくて保険料を控除できなくても、事業主には、保険料(事業主負担分+被保険者負担分)を納付する義務があります。
では、こちらもどうぞ!
 <H26年出題>
<H26年出題>
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間にかかるもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。

【解答】 〇
報酬から控除できる被保険者負担分の保険料は、「前月の標準報酬月額に係る」保険料のみです。
ただし、例外的に、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合(退職の場合)は、前月と当月の2か月分の保険料を控除できます。
例外が当てはまるのは、問題文のような月末退職の場合です。5月31日退職の場合、6月1日資格喪失となり、保険料は5月分まで徴収されます。
そのため、5月支払の給与から、4月分(前月分)と5月分(当月分)の2か月分の保険料を控除することができます。
(参照:健康保険法第167条)
社労士受験のあれこれ
(健保)任意継続被保険者の申出
R3-148
R3.1.18 任意継続被保険者申出期限
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-イ>
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。

【解答】 ×
「いかなる理由がある場合においても」が誤り。
例外として、『正当な理由があると認めるとき』は、保険者は期限を経過した後の申出ででも、受理することができます。
(参照:健康保険法第37条)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。
 <H23年出題>
<H23年出題>
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。

【解答】
 <H25年出題> 〇
<H25年出題> 〇
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
問題文にあるように、「法律の不知」という主張は、正当な理由にあたりません。「知りませんでした」ではダメということ。
なお、「正当な理由」とされるのは、「天災事変」「交通ストライキ」等です。
(判例:昭和36年2月24日 最高裁判所第二小法廷)
 <H23年出題> 〇
<H23年出題> 〇
任意継続被保険者の初回分の保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。(正当な理由がある場合以外)
(健康保険法第37条)
※ついでにこちらもチェック!
・ 2回目以降の保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日に資格を喪失します。
・ 任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「当月10日」です。初回分は、「保険者が指定する日」です。
(健康保険法第38条、第164条)
社労士受験のあれこれ
(健保)訪問看護療養費
R3-147
R3.1.17 指定訪問看護の利用回数の限度は?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問3-イ>
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。

【解答】 ×
原則として、週3日が限度です。
なお、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者については、週4日以上の訪問看護が可能です。
(参照:令和2年3月5日 保発0305第3号)
こちらの問題もどうぞ!
~訪問看護事業の定義を穴埋めで確認しましょう。~
訪問看護事業とは、
・疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(< A >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、
・その者の居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< B >が行う療養上の< C >又は必要な診療の< D >を行う事業のこと
・< E >等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは< F >によるものを除く

【解答】
A 主治の医師
B 言語聴覚士
C 世話
D 補助
E 保険医療機関
F 介護医療院
(参照:健康保険法第88条、施行規則第68条)
もう一問どうぞ!
<H19年出題>
70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。

【解答】 〇
指定訪問看護を受けた被保険者は、基本利用料(厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額)を負担します。
また、基本利用料のほか、その他の利用料を負担することもあります。
その他の利用料とは?
・ 訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護
・ 交通費、おむつ代等に要する費用(実費)
(参照)
・令和2年3月5日 保発0305第3号
・指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(H12.3.31厚生省令第80号)
社労士受験のあれこれ
(健保)特定の法人の電子申請の義務
R3-146
R3.1.16 電子申請の義務がある法人の規模と届出の種類
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問8-A>
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

【解答】 〇
■■おさえるポイントは電子申請の義務がある法人の規模と届出の種類
【電子申請が義務となる『特定法人』とは?】
・事業年度開始の時の資本金等が1億円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
【対象の届出は3つ】
・報酬月額算定基礎届(定時決定)
・報酬月額変更届(随時改定)
・賞与支払届
※参照条文:健康保険法施行規則第25条、第26条、第27条
ちなみに、厚生年金保険法も同様です。
こちらの問題もどうぞ!
<H30年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

【解答】 〇
覚えるポイントは期限。「5日以内」です。
なお、賞与支払届の提出は、特定法人(資本金1億円を超える法人等)は、原則として電子申請で行わなければなりません。
(健保法施行規則第27条)
社労士受験のあれこれ
(健保)病気休職中の保険料
R3-145
R3.1.15 傷病手当金終了後休職が続いている場合の健康保険料
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-B>
被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければならない。

【解答】 〇
傷病手当金の受給終了後も引き続き休業し、報酬の支払いが無かったとしても、健康保険の被保険者である間は、保険料(事業主&被保険者ともに)を負担する義務があります。(産前産後休業や育児休業中は保険料の免除制度があるけれど、病気やケガなどの休業については免除の制度が無い。)
こちらの問題もどうぞ!
 <H24年出題>
<H24年出題>
被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。
 <R1年出題>
<R1年出題>
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

【解答】
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
病気休職中でも保険料は免除されませんので、事業主負担分、被保険者負担分ともに負担義務があります。
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
この問題も同じです。
病気休職中でも、事業主も被保険者も保険料を負担する義務はあります。また、その際の保険料は、賃金支給停止前の標準報酬に基づき算定されます。
では、こちらもどうぞ!
 <H27年出題>
<H27年出題>
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

【解答】
 <H27年出題> ×
<H27年出題> ×
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われなくなり、保険料も徴収されません。
また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、保険料を徴収されない期間は、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間です。問題文中の徴収されない期間が誤りです。
例えば、令和2年3月に被保険者の資格を取得、刑事施設に拘禁されたのが令和2年4月、拘禁されなくなったのが8月の場合、保険料を徴収しない期間は、4月から7月までとなります。
ちなみに・・・
被保険者がその資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合は、その翌月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間となります。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
産前産後休業、育児休業の保険料の免除の期間を確認しておきましょう。
| 開始 | 終了 | |
| 産前産後休業 | 開始した日の属する月から | 終了する日の翌日が属する月の前月まで |
| 育児休業 | 開始した日の属する月から | 終了する日の翌日が属する月の前月まで |
(例)産前産後休業の場合
出産日5月1日、産前休業3月21日~5月1日、産後休業5月2日~6月26日の場合、保険料が免除される期間は、3月から5月までとなります。
社労士受験のあれこれ
(健保)資格取得時の標準報酬月額
R3-144
R3.1.14 資格取得時の賃金に算定誤りがあった場合
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-D>
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

【解答】 〇
<被保険者資格を取得した際の標準報酬月額>
・ 固定的賃金の算定誤り等があった → 訂正できる
・ 残業代のような非固定的賃金の見込みが当初の算定額より増減した → 訂正できない
こちらの問題もどうぞ!
<H27年出題>
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

【解答】 ×
その期間における『所定労働日数』ではなく、その期間の『総日数』で除します。
例えば、週給制の場合は、週給÷7(1週間の総日数)×30が報酬月額となります。
資格取得時決定の条文を穴埋めで確認しておきましょう
(被保険者の資格を取得した際の決定)
保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の< A >で除して得た額の< B >倍に相当する額
② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前< C >月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
③ ①、②の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前< C >月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
④ ①、②、③のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、①、②、③の規定によって算定した額の合算額
決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の< D >月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の< D >月)までの各月の標準報酬月額とする。

【解答】
A 総日数
B 30
C 1
D 8
社労士受験のあれこれ
(健保)随時改定のタイミング
R3-143
R3.1.13 育児休業中の昇給~随時改定はいつ?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-C>
育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

【解答】 ×
(問題の要旨)
育児休業に昇給があった → しかし育児休業中は一切給与の支払いがない → このような場合、随時改定はどうなるのか?
問題文では、「標準報酬月額の随時改定が行われることはない。」となっていますが、そこが誤りです。
(答)
産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合 → 実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として随時改定の対象となります。
こちらの問題もどうぞ!
<H26年出題>
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。

【解答】 〇
随時改定は、『固定的賃金の変動が報酬に反映された月』を起算とします。
問題文の場合、昇給分が実際に報酬に反映されたのは5月なので、5月、6月、7月の3か月間で要件をみます。また、3か月の平均をとる際は、昇給差額分は除外されます。
随時改定の条文を穴埋めで確認しておきましょう
(随時改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した< A >月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を< A >で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった< B >に比べて、< C >を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を< B >として、その< C >を生じた月の < D >から、標準報酬月額を改定することができる。

【解答】
A 3
B 報酬月額
C 著しく高低
D 翌月
社労士受験のあれこれ
(健保)定時決定のルール
R3-142
R3.1.12 給与の締め日を変更した場合、定時決定はどうする?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-B>
給与の支払方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。

【解答】 〇
(問題の要旨)
4月から、給与の締め日が、毎月20日締め(末日払い)から25日締めに変更になった。
締め日が変更された4月は、給与計算期間が3月21日から4月25日までとなってしまう。このままだと支払い基礎日数が暦日よりも多くなってしまう。
定時決定の際は、どのように扱えばいいのか?
(答)
3月21日~4月25日までの報酬で算定すると、通常よりも多くなってしまうので、『超過分の報酬を除外』し、その他の月の報酬との平均を算出して、標準報酬月額を保険者算定する。
問題文の通り、超過分の3月21日~3月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与の計算期間(3月26日~4月25日)で算出された報酬を4月の報酬とする。
ちなみに、支払基礎日数が減少した場合はどうする?
・給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合
→ 支払基礎日数が17日以上なら、通常の定時決定の方法で算定する。
→ 支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外して報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定する。
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】 〇
まず、一時帰休の際に支払われる休業手当は「報酬」ですので、休業手当が支払われた日は、支払基礎日数に含まれることに注意してくださいね。
この問題のポイントは、「7月1日の時点で一時帰休の状況が解消」(=現在、低額な休業手当は支払われていないということ)している点です。このような場合、休業手当はどのように扱うのでしょうか?
→ 7月1日時点で元に戻っている。なので、低額な休業手当を除いて標準報酬月額を決定する。
→ 問題文のように、4月と5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当という場合は、6月分を除いて4月と5月の報酬月額を平均して定時決定を行う。
※ちなみに、7月1日現在で一時帰休の状況が解消していない場合は?
→ 例えば、4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当が支払われた場合には、6月分の休業手当を含めて、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。
社労士受験のあれこれ
(健保)任意適用事業所の要件
R3-141
R3.1.11 任意適用事業所と被保険者の申出
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-C>
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

【解答】 ×
被保険者から任意適用事業所の脱退を希望する申出があったとしても、事業主には脱退の申請をする義務はありません。
こちらの問題もどうぞ!
 <H28年出題>
<H28年出題>
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。
 <H24年出題>
<H24年出題>
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とすべき義務が生じる。

【解答】
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
令和2年度の出題と同じ趣旨です。事業主には任意適用取消しの申請をする義務はありません。
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
被保険者となるべき者の希望があったとしても、事業主には適用事業所とすべき義務はありません。
比較してみましょう!
| 加入の義務 | 脱退の義務 | |
|---|---|---|
労災保険 | あり 過半数の希望があった場合 | なし |
雇用保険 | あり 2分の1以上の希望があった場合 | |
健康保険 厚生年金保険 | なし | なし |
社労士受験のあれこれ
(健保)協会けんぽ/短期借入金など
R3-140
R3.1.10 協会けんぽ・厚生労働大臣の認可?承認?報告?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-B>
全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

【解答】 〇
・ 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
・ 短期借入金は、その事業年度内に償還しなければならない。
・ 資金の不足のため償還できないときは、その金額に限って、厚生労働大臣の認可を受けて、借り換えができる。
・ 借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
コチラの問題もどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 <H24年出題>
<H24年出題>
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
短期借入金をするとき → 厚生労働大臣の認可
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
財務諸表、事業報告書等 → 厚生労働大臣の承認
 <H24年出題>
<H24年出題>
重要な財産の譲渡、担保 → 厚生労働大臣の認可(報告ではない)
社労士受験のあれこれ
(健保)出産手当金の支給要件
R3-139
R3.1.9 出産手当金の支給は労務に服さなかった期間
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-E>
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

【解答】 ×
出産手当金は、「労務に服さなかった」期間支給されます。
問題文は、「通常の労務に服している」期間の話ですので、出産手当金は支給されません。
出産手当金の条文を穴埋めで確認しましょう
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が< A >後であるときは、< A >))以前42日(多胎妊娠の場合においては、< B >日)から出産の日後56日までの間において< C >期間、出産手当金を支給する。

【解答】
A 出産の予定日
B 98
C 労務に服さなかった
コチラの問題もどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
 <H27年出題>
<H27年出題>
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

【解答】
 <H23年出題> 〇
<H23年出題> 〇
出産手当金のルール
・ 報酬の全部又は一部を受けることができる場合 → 出産手当金は支給しない
※報酬の額が、出産手当金の額より少ないとき → 差額を支給する
 <H27年出題> 〇
<H27年出題> 〇
事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているとき → 出産手当金の支給額は介護休業手当との調整が行われる。(上記H23年出題の問題と同じ趣旨です。)
社労士受験のあれこれ
(健保)休業補償給付と傷病手当金の関係
R3-138
R3.1.8 休業補償給付と傷病手当金は併給できる?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-A>
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

【解答】 ×
「労災保険の休業補償給付」、「健康保険の傷病手当金」の目的はどちらも「生活保障」。仮に、両方同時に受給すると、働いて得る賃金を超えてしまいます。
ですので、労災保険法による休業補償給付を受けている間に、業務外の事由で労務不能になったとしても、傷病手当金は支給されません。
ただし、労災の休業補償給付の額が、傷病手当金の額に満たない場合は差額が支給されます。
この問題のポイント!
労災の休業補償給付の額より、健保の傷病手当金の額の方が高い場合は、差額の傷病手当金が支給されます。問題文の「傷病手当金が支給されることはない。」が間違い。差額の傷病手当金が支給されることがあるからです。
社労士受験のあれこれ
(健保)一部負担金の減免
R3-137
R3.1.7 健保一部負担金の減免はどのようなときに行われる?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問8-D>
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。

【解答】 〇
災害等の特別の事情があり、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して、保険者は次の3つの措置を採ることができます。
① 一部負担金の減額
② 一部負担金の支払の免除
③ 一部負担金の徴収の猶予
こちらの問題もどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を採ることができる。①一部負担金を減額すること、②一部負担金の支払を免除すること、③保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
 <H25年出題>
<H25年出題>
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者はその徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。

【解答】
 <H23年出題> 〇
<H23年出題> 〇
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
 <H25年出題> 〇
<H25年出題> 〇
一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとするときは、あらかじめ申請が必要。
→ 徴収猶予又は減免の決定をした場合、保険者は速やかに証明書を交付する
→ 療養の給付等を受けようとするときは、「証明書」を健康保険被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出する。
社労士受験のあれこれ
(健保)任意継続被保険者の前納
R3-136
R3.1.6 任継の保険料は前納できるが、その額は?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-E>
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

【解答】 ×
任意継続被保険者の前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の「合計額」ではなく、合計額から「割引」があります。(詳しくは下の問題でどうぞ)
こちらの問題もどうぞ!
<H22年選択>
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納をおこなうことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
A 各月の初日
※国民年金の前納は、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされるのは、「各月が経過した際」です。区別して覚えましょう。
B 初月の前月末日
※例えば、4月分から9月分までの6か月分を前納する場合は、納付期限は「前納に係る期間の初月の前月末日」=3月末日までとなります。
C 年4分の利率
※前納については割引があります。
D 5月
※前納の期間は、
- ・4月から9月までの6か月間
- ・10月から翌年3月までの6か月間
- ・4月分から翌年3月分までの12か月間
- ですが、その途中で任意継続被保険者となった場合は、その資格取得した月の翌月以降の期間について前納することができます。
- 問題文の場合、4月に任意継続被保険者の資格を取得していますので、翌月の5月から9月までの期間または翌年3月までの期間で前納できます。
社労士受験のあれこれ
(健保)資格喪失後の傷病手当金
R3-135
R3.1.5 資格喪失後に特例退職被保険者になった。傷手は継続給付される?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-A>
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

【解答】 ×
資格喪失後に「特例退職被保険者」になった場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けられません。
※「特例退職被保険者」といえば、定年退職後で老齢厚生年金を受けている世代なので、二重の保障は不要と考えてみてください。
こちらの問題もどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

【解答】
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、傷病手当金の継続給付を受けることはできます。
資格喪失後の傷病手当金の継続給付
・任意継続被保険者になった場合 → 受けられる
・特例退職被保険者になった場合 → 受けられない
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
資格喪失後に船員保険の被保険者となったとき
→ 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金」→ の給付は行われない。
※船員保険法の方で給付が行われるからです。
社労士受験のあれこれ
(年金)代表取締役の被保険者資格
R3-109
R2.12.10 代表取締役は厚生年金保険の被保険者となる?ならない?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問6‐E>
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

【解答】 ×
★ 代表取締役も被保険者となります。
法人の理事、監事、取締役等法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は被保険者になります。
ちなみに、事業主1人で経営している法人は、強制適用事業所となります。
また、個人事業主は、個人事業主本人が事業主体となるので、厚生年金保険の被保険者にはなりません。
では、こちらもどうぞ!(健康保険法の問題です)
 健保 H22年出題
健保 H22年出題
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
 健保 H29年出題
健保 H29年出題
従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。

【解答】
 健保 H22年出題 ×
健保 H22年出題 ×
法人役員は、法人(事業主)から、労務の対償として報酬を受けている者として、被保険者の資格を取得します。(厚生年金保険と同じです。)
 健保 H29年出題 ×
健保 H29年出題 ×
個人事業所の事業主は、本人が事業主なので、被保険者となることはできません。(こちらも厚生年金保険と同じです。)
では、次は「雇用保険法」の問題をどうぞ!
 雇用保険 H30年出題
雇用保険 H30年出題
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
 雇用保険 H24年出題
雇用保険 H24年出題
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

【解答】
 雇用保険 H30年出題 〇
雇用保険 H30年出題 〇
なお、問題文のような人が失業した場合は基本手当を受けることができますが、基本手当の基になる賃金には、取締役としての地位に基づく役員報酬は含まれません。あくまでも労働の対償としての賃金で計算されます。
 雇用保険 H24年出題 〇
雇用保険 H24年出題 〇
株式会社の代表取締役は、雇用関係にないので、失業することも考えられませんよね。株式会社の代表取締役は被保険者になることはありません。
社労士受験のあれこれ
(健保)高額介護合算療養費
R3-098
R2.11.29 高額介護合算療養費・計算期間途中に保険者が変更した
令和2年の問題をどうぞ!
<問2‐B>
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

【解答】 〇
高額介護合算療養費の計算期間の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前と変更後の自己負担額は合算されます。
★高額介護合算療養費とは?
計算期間(毎年8月~1年間)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計した額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
こちらもどうぞ!
 <H28年出題>
<H28年出題>
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
 <H25選択>
<H25選択>
高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は< A >円である。
70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は
< B >円である。

【解答】
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
70歳未満の場合、高額療養費と同様に、21,000円未満のものは算定対象から除かれます。
 <H25選択>
<H25選択>
A 500
B 670,000
Aについて → 高額介護合算療養費は、自己負担合算額が介護合算算定基準額を超えた場合に支給されますが、支給基準額(500円)を超えない場合は、支給されません。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(健保)
R3-088
R2.11.19 <R2出題>覚える「4か月以内の季節的業務」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問5-ウ>
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

【解答】 ×
季節的業務の場合、業務の都合で4か月を超えて使用された場合でも、一般の被保険者にはなりません。
★ 季節的業務とは → 例えば、清酒の醸造、製茶、製氷など
季節的業務のポイント!
・当初から4か月を超える予定で使用された → 当初から一般被保険者になる
・当初は4か月以内の予定 → 業務の都合でたまたま4か月を超えた場合でも → 一般の被保険者にならない。
では、関連問題をどうぞ!
<H19年出題>
臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。

【解答】 〇
2か月以内の雇用契約で使用される場合は、一般被保険者にはならず、原則として日雇特例被保険者となります。
ただし、所定の期間(当初の契約期間=問題文の場合は5週間)を超えて引き続き使用されるようになった場合は、そのときから一般被保険者となります。
では、選択式の練習をどうぞ!
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 < A >の被保険者(< A >法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては < B >を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ < C >以内の期間を定めて使用される者
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して< D >を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者等
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

【解答】
A 船員保険
B 1月
C 2月
D 6月
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(健保)
R3-078
R2.11.9 <R2出題>問題の意図「資格喪失後の出産育児一時金他の制度との調整」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問4-C>
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

【解答】 〇
問題の意図は、資格喪失後国民健康保険の被保険者になり、出産した場合の、健保の資格喪失後の出産育児一時金と国民健康保険の出産育児一時金の調整方法です。(両方から受けるのは不可です。)
★対象者の意思表示で決まります。
・健康保険法の出産育児一時金の支給を受ける旨の
・意思表示をしたとき → 健康保険法の出産育児一時金の支給を受けることができる。(国民健康保険からは支給しない)
・意思表示をしないとき → 国民健康保険から支給が受けられる
こちらもどうぞ!
 H28年出題
H28年出題
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
 H25年出題
H25年出題
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給できることとなる。
 H26年出題
H26年出題
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

【解答】
 H28年出題 ×
H28年出題 ×
★資格喪失後に国民健康保険の被保険者になった場合
上記の令和2年の問題と同じ意図の問題です。「健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない」は誤り。健康保険の出産育児一時金を受ける旨の意思表示をすれば、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
 H25年出題 〇
H25年出題 〇
★資格喪失後に被扶養者になった場合
被保険者本人としての出産育児一時金か被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかは本人の選択によります。
 H26年出題 〇
H26年出題 〇
★資格喪失後に船員保険の被保険者になった場合
資格喪失後に船員保険の被保険者となったときは船員保険を優先。
(健康保険の「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金」の給付は行われない。)
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(健保)
R3-067
R2.10.29 R2出題【選択練習】日雇特例被保険者の保険料納付要件
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>を埋めてください。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して< A >日分以上又は当該日の属する月の前6か月に通算して< B >日分以上の保険料が納付されていなければならない。
(参考:問7A)

【解答】
A 26
B 78
 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければなりません。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければなりません。
例えば、2020年11月に療養の給付を受けるには、2020年9月・10月の2か月間で通算26日分以上納付されているか、2020年5月~10月ので6か月間で通算78日分以上の納付が必要です。
なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙を貼付し消印する方法で行われます。
関連問題をどうぞ!
<日雇特例被保険者の出産>
空欄< C >を埋めてください。
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前< C >月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

【解答】
C 4
出産の場合は、前4月間に通算して26日分以上でOKです。出産直前まで労働して保険料を納付するのは大変なので、前4か月間に条件が緩和されます。
では、もう一問どうぞ
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して< D >か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については< E >か月間)である。
(参考:H26年択一式問題)

【解答】
D 3
E 2
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、前2月間に26日分以上の保険料が必要なので、初めて日雇特例被保険者手帳を交付されたときは、まだ療養の給付が受けられません。
そのため、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)は特別療養費が支給されます。
★例えば
・10月29日に交付を受けた場合はその年の12月31日まで支給される
・11月1日に交付を受けた場合はその年の12月31日まで支給される
最低暦月で2月あれば療養の給付が受けられるので、特別療養費はその間の保障だと考えてください。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(健保)
R3-058
R2.10.20 R2出題・当初から自宅待機の場合の健保資格取得日
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問4より
新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされている。

【解答】 〇
被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日」に取得します。
使用されるに至った日とは、事実上の使用関係に入った日のことですので、自宅待機で出社していなくても、休業手当(給料)の支払いの対象になった日から、健康保険の被保険者の資格を取得します。
では、類似問題をどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。
 <H30年出題>
<H30年出題>
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。

【解答】
 <H25年出題> 〇
<H25年出題> 〇
 <H30年出題> ×
<H30年出題> ×
上記で解説しましたように、適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日です。
事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、「すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべき」ものとされますので、調査の日を資格取得日とするのは誤りです。
では、最後にもう一問どうぞ!
<H22年出題>
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用される者については適用されない。

【解答】 ×
試みの使用される者にも適用されます。
たとえ試用期間であったとしても、雇用関係に入っているからです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(健保)
R3-048
R2.10.10 R2出題・難問解決策「自己の故意の犯罪行為と埋葬料」
一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問6より>
被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。

【解答】 〇
まず、第116条の条文を見てみましょう。
「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」
↓
無免許運転は、道路交通法違反で処罰される行為ですが、
・死亡は最終的1回限りの絶対的な事故であること
・埋葬を行う者に対する救済または弔意を目的として支給するものであること
から、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給されることになっています。
同じ論点の問題をどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
 <H25年出題>
<H25年出題>
被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。

【解答】
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
自殺は最終的1回限りの絶対的な事故のため、埋葬料は支給されます。
 <H25年出題> ×
<H25年出題> ×
上記R2年度の問題と同じです。埋葬料は支給されます。
では、こちらもどうぞ。
<H29年出題>
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。

【解答】 〇
自殺未遂による傷病については、療養の給付、傷病手当金は支給されません。
ただし、精神疾患等に起因する場合は、故意に給付事由を生じさせたとはいえないので、保険給付の対象となります。
では、選択の練習をどうぞ!
被保険者又は被保険者であった者が、自己の< A >により、又は < B >に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< C >。

【解答】
A 故意の犯罪行為
B 故意
C 全部又は一部を行わないことができる
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~健康保険法
R3-038
R2.9.30 R2出題・資格取得前の傷病(健保)
 今日のテーマは
今日のテーマは
入社する前(健康保険の資格を取得する前)からの傷病の場合、傷病手当金の支給は受けられる?受けられない?
<R2年問2E>
被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

【解答】 ×
入社前から治療を受けていた傷病についても、保険給付の対象となります。
資格取得前の傷病でも、療養の給付、傷病手当金ともに支給されます。
★適正に資格を取得したならば、健康保険の保障が受けられると考えてください。
では、同じパターンの問題をどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病又は負傷については、6か月以内のものに限り保険給付を行う。
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。

【解答】
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
6か月以内という制限はありません。
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
傷病手当金も支給されます。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(健康保険法)
R3-028
R2.9.20 過去の論点は繰り返す(R2・健保「地域型健康保険組合」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
地域型健康保険組合
 問題<H21年出題>
問題<H21年出題>
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、一定の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
 問題<H21年出題>
問題<H21年出題>
地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。

【解答】
 問題<H21年出題> ×
問題<H21年出題> ×
3か年度ではなく「5か年度」です。
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限って、不均一の一般保険料率の設定が認められています。
 問題<H21年出題> ×
問題<H21年出題> ×
2分の1以上ではなく、「3分の2」以上です。
不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、組合会で組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決が必要。
 「地域型健康保険組合」ときたら数字です!「5か年度」と「3分の2」
「地域型健康保険組合」ときたら数字です!「5か年度」と「3分の2」
「地域型健康保険組合」→ 同一都道府県内の健康保険組合の再編・統合の受け皿。企業・業種を超えての設立が認められている。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問1E>
地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

【解答】 〇
平成21年と同じ問題です。
「数字」がポイントだと知っていれば、問題文を全部読む必要ありません。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(健康保険法)
R3-020
R2.9.12 第52回試験・択一健保の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 健保 択一式
感想を一言で表すと、「難しかった!」。
テキストで「見たことない」と焦った方も多かったと思います。
「テキストで見たことない」記述は、「もしかしたら、そんな規定もあるかもしれない」と思ってしまうので、本当に難しいですね。
しかし、難しい中にも、探せばヒントは隠れています。

例えば、高額長期疾病(「人工透析」「血友病」「後天性免疫不全症候群」の3つ)は負担軽減のため、自己負担限度額が1万円となっていますが、「人工透析」のみ、70歳未満・標準報酬月額53万円以上の者は2万円となっています。
過去にも出題されたポイントですので、ここが分かれば、問4は解けます。

ア 被扶養者の要件について、「被保険者が世帯主であることは要しない」
イ 任意継続被保険者の申出は資格を喪失した日から20日以内。ただし、正当な理由があるときは期間経過後でも受理できるという例外あり。
ウ 4カ月以内の季節的業務に使用される者は、たまたま業務の都合で4か月を超えても被保険者にはならない。
アイウが×と判断できるので、問5は解けます。

資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、「特例退職被保険者」には支給されない。この規定も過去に出題されたポイントです。これが分かれば問6も解けます。

任意継続被保険者は保険料の前納ができます。前納の額は、「年4分の利率による複利現価法により、前納期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額」です。「割引」はよく出題されるポイントです。
「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」ではなく、割引があることをおさえていれば問7も解けます。
過去問の基本事項だけでも4問は解けました。
全体的に 勉強はまんべんなく。重箱の隅はほっておく。基本事項をおさえていれば、合格ラインに届く。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(健康保険法)
R3-010
R2.9.2 第52回試験・選択(健保)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 健保 選択式
1 社会保険医療協議会への諮問からの出題
「地方社会保険医療協議会」「中央社会保険医療協議会」の役割の違いをおさえていればOKな問題でした。
 「中央社会保険医療協議会」→ 厚生労働省に置く
「中央社会保険医療協議会」→ 厚生労働省に置く
 「地方社会保険医療協議会」→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置く。
「地方社会保険医療協議会」→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置く。
※ 地方社会保険医療協議会は、『保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議することができる。』
2 一部負担金の割合についての出題
70歳以上の一部負担金の割合の問題ですが、5年前の平成27年にも選択式で出題されていました。
70歳以上の一部負担金の規定はポイントになる数字が多いので、選択式の問題が作りやすい。このような規定は、定期的に出題される可能性が高いと思います。
3 高額療養費の計算についての出題
この問題のポイントは、
・「高額療養費」と「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」を間違えない
・評価療養や選定療養は、高額療養費の対象外となる
4 資格喪失届の提出についての出題
令和2年1月1日施行の改正からの問題でした。
・資格取得の届出→所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由できる
・資格喪失の届出→所轄公共職業安定所長を経由できる
5 協会による広報及び保険料の納付の勧奨等についての出題
条文そのままの問題ですが、丸暗記は無理。このような問題は、前後の文脈、言葉の意味などを考えて当てはめてゆく方法で。
ポイント! テキストは「ポイント」を意識しながら読む。日々の積み重ねが大事。
社労士受験のあれこれ
目的条文check 2 社保編
2 社保編
R2-261
R2.8.18 健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック
目的条文は要チェック!
本日は、「健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「健康保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(基本的理念)
第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< C >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< D >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< E >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

【解答】
A 業務災害
B 福祉の向上
C 高齢化
D 後期高齢者医療制度
E 常に
問2 「国民年金法」
(国民年金制度の目的)
第1条 国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(管掌)
第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、 < C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた< D >(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< E >が行うこととすることができる。

【解答】
A 日本国憲法第25条第2項
B 健全な国民生活
C 全国市町村職員共済組合連合会
D 日本私立学校振興・共済事業団
E 市町村長(特別区の区長を含む。)
問3 「厚生年金保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の< A >の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(管掌)
第2条 厚生年金保険は、< C >が、管掌する。

【解答】
A 生活
B 福祉の向上
C 政府
社労士受験のあれこれ
横断編(不服申立て)
R2-259
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「審査請求を棄却したものとみなすことができる」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
A 3か月
問2 「雇用保険法」
① 資格取得・喪失の確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して < B >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
B 3か月
問3 「健康保険法」
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
審査請求をした日から< C >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
C 2月
D 社会保険審査会
問4 「国民年金法」
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は< E >その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
審査請求をした日から< F >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
E 保険料
F 2月
問5 「厚生年金保険法」
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
② ①の審査請求をした日から< G >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< H >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
G 2月
H 社会保険審査会
| 棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
では、こちらをどうぞ!
①<国民年金 H30年出題>
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
②<厚生年金保険法 H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】
①<国民年金 H30年出題> 〇
「2か月」がポイントです!
②<厚生年金保険法 H29年出題> ×
・第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行います。
・脱退一時金については、「社会保険審査会」で〇です。
(国民年金も「脱退一時金」は、「社会保険審査会」に対して審査請求ができます。
社労士受験のあれこれ
横断編(公課の禁止)
R2-258
R2.8.15 横断編/課税されるもの、されないもの
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「課税されるもの、されないもの」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
<H24年出題>
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

【解答】 〇
労災保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」と規定されています。
※ 労災保険の保険給付には、「現金給付」と「現金給付」があるので「金品」
問2 「雇用保険法」
<H28年出題>
租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

【解答】 ×
雇用保険法では「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とされています。
常用就職支度手当は失業等給付の中に入っていますので、課税できません。
※雇用保険法には現物給付がないので「金銭」となっています。
なお、雇用保険二事業の助成金等は失業等給付ではありませんので、公課を課することができます。
問3 「健康保険法」
<H18年出題>
出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

【解答】 〇
健康保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされています。
保険給付(もちろん出産手当金出産育児一時金も含まれます。)は、課税されません。
問4 「国民年金法」
<H25年出題>
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

【解答】 〇
国民年金法のルールは、以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、公課を課することができる。
問5 「厚生年金保険法」
障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。

【解答】 〇
厚生年金保険法のルールは以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、公課を課することができる。
※ 「老齢厚生年金」は課税されますが、障害厚生年金は課税されません。
社労士受験のあれこれ
横断編(療養に関する指示に従わないとき)
R2-257
R2.8.14 横断編/療養に関する指示に従わないときの制限
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「療養に関する指示に従わないときの制限」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が故意の犯罪行為若しくは< A >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの< B >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の< C >。

【解答】
A 重大な過失
B 原因
C 全部又は一部を行わないことができる
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< D >。

【解答】
D 一部を行わないことができる
 「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその< F >となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< G >。
自己の故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその< F >となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

【解答】
E 重大な過失
F 原因
G 全部又は一部を行わないことができる
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは< H >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの< I >となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の< J >。
障害厚生年金の受給権者が、< K >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
H 重大な過失
I 原因
J 全部又は一部を行わないことができる
K 故意
こちらもどうぞ!
 問1労災保険法
問1労災保険法
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
 問2 健康保険法
問2 健康保険法
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
 問3 国民年金法(R元年出題)
問3 国民年金法(R元年出題)
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題)
問4 厚生年金保険法(R元年出題)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
 問1労災保険法 ×
問1労災保険法 ×
キーワードは、「故意に」「直接の原因」。
全部又は一部を行わないことができるではなく、「保険給付を行わない」です。
 問2 健康保険法 ×
問2 健康保険法 ×
キーワードは、「闘争、泥酔又は著しい不行跡」。
行わないではなく、「全部又は一部を行わないことができる」です。
 問3 国民年金法(R元年出題) 〇
問3 国民年金法(R元年出題) 〇
キーワードは、「故意に」。
故意に死亡させた者には支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
故意に障害 → 障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
重大な過失 → 保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士受験のあれこれ
横断編(支給制限~全部制限)
R2-256
R2.8.13 横断編/支給制限「行わない」のはどんなとき?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「支給制限「行わない」のはどんなとき?」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】
A 故意に
B 直接の原因
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< C >により、又は< D >給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

【解答】
C 自己の故意の犯罪行為
D 故意に
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
< E >障害又はその< F >となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < E >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によっ遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を< E >死亡させた者についても、同様とする。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< E >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
E 故意に
F 直接の原因
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< G >、障害又はその< H >となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< G >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< G >死亡させた者についても、同様とする。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< G >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
G 故意に
H 直接の原因
社労士受験のあれこれ
横断編(受給権の保護)
R2-255
R2.8.12 横断編/受給権の保護
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「受給権の保護」です。
では、どうぞ!
「労災保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外あり)
年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・国年、厚年も同様)
「雇用保険法」
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外なし)
「健康保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外なし)
「国民年金法」
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、厚年も同様)
・ 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢基礎年金、付加年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
「厚生年金保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、国年も同様)
・ 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢厚生年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
 では、問題をどうぞ!
では、問題をどうぞ!
 労災保険法<H24年出題>
労災保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
 雇用保険法<H23年出題>
雇用保険法<H23年出題>
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
 健康保険法<H24年出題>
健康保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。
 国民年金法<H28年出題>
国民年金法<H28年出題>
給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H26年出題>
厚生年金保険法<H26年出題>
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、< A >に行わせるものとされている。

【解答】
 労災保険法<H24年出題> 〇
労災保険法<H24年出題> 〇
 雇用保険法<H23年出題> 〇
雇用保険法<H23年出題> 〇
 健康保険法<H24年出題> ×
健康保険法<H24年出題> ×
保険給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押さえ、すべてできません。
 国民年金法<H28年出題> 〇
国民年金法<H28年出題> 〇
脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
※厚生年金保険でも、脱退一時金は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
 厚生年金保険法<H26年出題> ×
厚生年金保険法<H26年出題> ×
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押えの対象にはなりません。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
A 独立行政法人福祉医療機構
社労士受験のあれこれ
横断編(標準賞与額・健保と厚年)
R2-252
R2.8.9 横断編/健保と厚年~標準賞与額どう違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「健保と厚年~標準賞与額どう違う?」です。
では、どうぞ!
まずは「健康保険法」から
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】

A 1,000
B 573万
 健康保険<H27年出題>
健康保険<H27年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。

【解答】 ×
・ 標準賞与額の累計額は、「年度」で573万円が限度。
(3月までと4月以降では年度が違う。3月分の賞与は4月以降分と累計しない。)
・ 標準賞与額の累計は「保険者」単位で行う。
(A社(協会けんぽ)、B社(健保組合)の賞与は累計しない。)
この問題の場合は、12月の標準賞与額は「100万円」となります。
次は、厚生年金保険です!
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< C >円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
この場合において、当該標準賞与額が< D >円を超えるときは、これを < D >円とする。

【解答】

C 1,000
D 150万
厚生年金保険の標準所与額は、月150万円が上限です。
社労士受験のあれこれ
横断編(標準報酬月額・健保厚年を比較)
R2-251
R2.8.8 横断編/標準報酬月額・健保と厚年の違いは??
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「標準報酬月額・健保と厚年の違いは??」です。
では、どうぞ!
まずは「健康保険法」から
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
健康保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、
最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 58,000
B 50
C 1,390,000
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
毎年< D >における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が< E >を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< F >から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の< D >において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が< G >を下回ってはならない。

【解答】
D 3月31日
E 100分の1.5
F 9月1日
G 100分の0.5
次は、厚生年金保険です!
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
厚生年金保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、
最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 88,000
B 31
C 620,000
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
毎年< D >における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の < E >に相当する額が標準報酬月額等級の< F >の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< G >から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該< F >の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】

D 3月31日
E 100分の200
F 最高等級
G 9月1日
社労士受験のあれこれ
横断編(日雇労働者の定義)
R2-250
R2.8.7 横断編/「日雇労働者」の定義は雇用保険と健康保険で違う
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「「日雇労働者」の定義は雇用保険と健康保険で違う」です。
では、どうぞ!
「雇用保険法」の日雇労働者の定義
 雇用保険
雇用保険
空欄を埋めてください。
日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
一 < A >雇用される者
二 < B >以内の期間を定めて雇用される者
ただし、前2月の各月において< C >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< D >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)は、日雇労働者とならない。

【解答】

A 日々
B 30日
C 18日
D 31日
では、「日雇労働被保険者」とは?
被保険者である日雇労働者であって、①から④のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。
日雇労働被保険者が失業した場合には、日雇労働求職者給付金が支給されます。
① 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③ 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
④ ①~③のほか、公共職業安定所長の認可を受けた者
次は健康保険法の「日雇労働者」です
 健康保険
健康保険
健康保険法において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
二 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
 さらに!
さらに!
「日雇特例被保険者」 → 適用事業所に使用される日雇労働者
※ ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者、又は次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、除外されます。
・ 引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
・任意継続被保険者であるとき。
・その他特別の理由があるとき。
ちなみに、健保「日雇特例被保険者」でおさえておきたいのはこの問題!
問題<H15年出題>
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。

【解答】 ×
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者で組織され、日雇特例被保険者は入りません。
日雇特例被保険者の「保険者」は全国健康保険協会のみだからです。
社労士受験のあれこれ
横断編(健保・厚年の「船員」)
R2-244
R2.8.1 横断編/健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ」です。
では、どうぞ!
問 題
 <健康保険法>
<健康保険法>
船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、日雇特例被保険者となる場合を除き、健康保険の被保険者となることができない。
 <厚生年金保険法>
<厚生年金保険法>
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

【解答】
 <健康保険法> 〇
<健康保険法> 〇
船員保険の被保険者は、健康保険の被保険者にはなりません。なぜなら、職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産については「船員保険」から保険給付が受けられるからです。
なお、船員保険の疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者となることができるので注意してください。
 <厚生年金保険法> 〇
<厚生年金保険法> 〇
船員は厚生年金保険の被保険者となります。
<参考>船員保険について
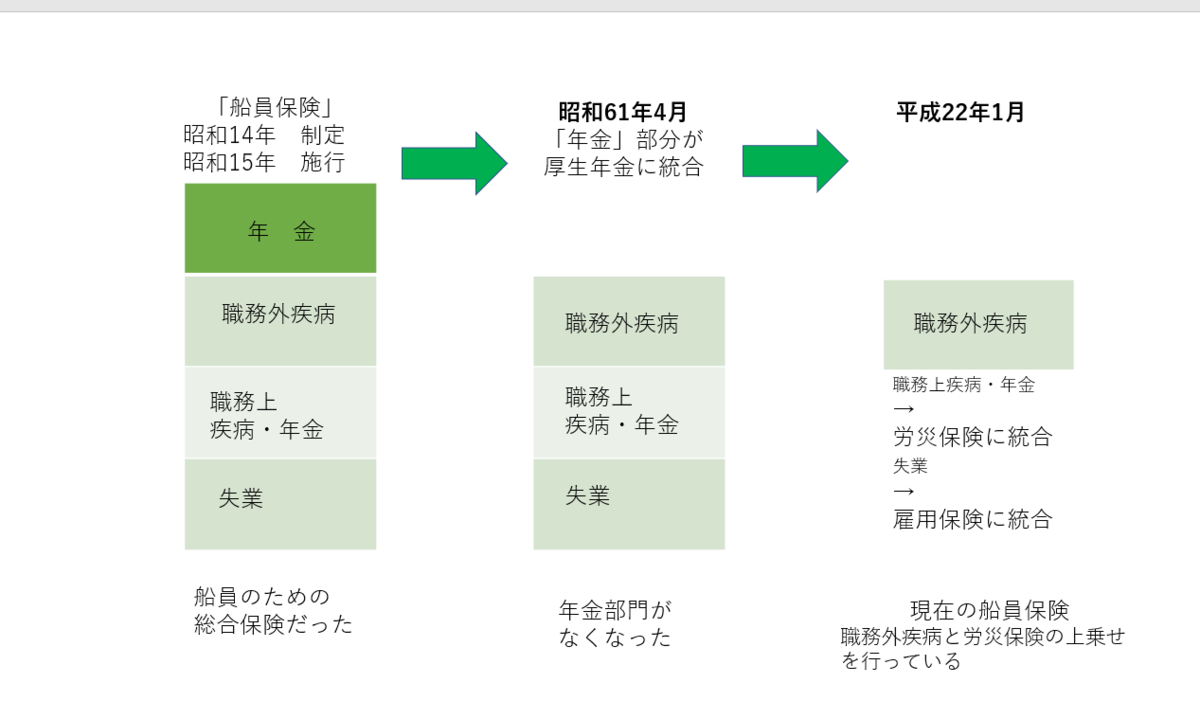
こちらもどうぞ!
①<厚生年金保険法・H30年出題>
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。
②<厚生年金保険法・H25年出題>
船舶使用者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
①<厚生年金保険法・H30年出題> ×
「当該期間を超えて使用されないとき」でも、厚生年金保険の被保険者となる。
・通常
2月以内の期間を定めて使用される者 → 厚生年金保険の被保険者にならない
※ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となる
・船員
「2月以内の期間」の定めであっても、当初から被保険者となる。(所定の期間を超えなくてもOK)
②<厚生年金保険法・H25年出題> ×
船員の場合は、継続して4か月を超えない季節的業務に使用されても、厚生年金保険の被保険者となります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-237
R2.7.25 選択式の練習/協会けんぽの一般保険料率
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「協会けんぽの一般保険料率」です。
では、どうぞ!
問 題1
協会 → 全国健康保険協会のことです。
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、< A >までの範囲内において、< B >(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。
【選択肢】
① 1000分の10から1000分の120 ② 1000分の20から1000分の130
③ 1000分の30から1000分の130 ④ 支部被保険者
⑤ 協会被保険者 ⑥ 都道府県被保険者

【解答】
A ③ 1000分の30から1000分の130
※健康保険組合管掌の一般保険料率も1000分の30から1000分の130までの範囲内で、健康保険組合ごとに決定します。
B ④ 支部被保険者
※支部被保険者単位で決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。
問 題2
協会は、< C >ごとに、翌事業年度以降の< D >間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
【選択肢】
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 4年 ⑤ 5年 ⑥ 6年

【解答】
C ② 2年
D ⑤ 5年
※協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間について
・被保険者数
・総報酬額の見通し
・保険給付に要する費用の額
・保険料の額
・その他
の収支の見通しを公表するものとされています。
問 題3
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< E >の議を経なければならない。
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について< F >。
【選択肢】
① 評議会 ② 運営委員会 ③ 社会保障審議会
④ 地方社会保険医療協議会の議を経なければならない
⑤ 厚生労働大臣の承認を得なければならない
⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない

【解答】
E ② 運営委員会
※ 「運営委員会」は協会に置かれる
「評議会」は支部ごとに設けられる
※ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするとき→事前に理事長は各支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければなりません。
F ⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。

【解答】 ×
あらかじめ、「理事長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、「運営委員会の議を経なければならない」です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-227
R2.7.15 選択式の練習/定時決定について
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「定時決定について」です。
では、どうぞ!
問 題
<定時決定>
保険者等は、被保険者が毎年< A >現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を< B >で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の< C >までの各月の標準報酬月額とする。
定時決定は、< D >までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により < E >までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
【選択肢】
① 6月1日 ② 4月1日 ③ 7月1日
④ 6 ⑤ その期間の月数 ⑥ 12
⑦ 9月から翌年の8月 ⑧ 10月から翌年の9月 ⑨ 8月から翌年の7月
⑩ 5月1日から6月1日 ⑪ 6月1日から7月1日 ⑫ 7月1日から8月1日
⑬ 5月から8月 ⑭ 6月から9月 ⑮ 7月から9月

【解答】
A ③ 7月1日
B ⑤ その期間の月数
C ⑦ 9月から翌年の8月
D ⑪ 6月1日から7月1日
E ⑮ 7月から9月
こちらもどうぞ!
<H29年出題>
特定事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
※ 短時間労働者とは
1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のこと

【解答】 〇
定時決定、随時改定、育児休業を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定については、報酬支払の基礎となった日数が17日以上か17日未満かがポイントになりますが、短時間労働者の場合は17日ではなく11日となります。
こちらもどうぞ!
<H24年出題>
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

【解答】 ×
7月1日に被保険者資格を取得した者 → 定時決定は行わない。
資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の8月31日まで用いる。
「翌年の6月30日までの1年間用いる」が誤りです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-217
R2.7.5 選択式の練習/全国健康保険協会のこと
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「全国健康保険協会のこと」です。
健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。
今日は、「全国健康保険協会」について。
ではどうぞ!
問 題
全国健康保険協会について(以下「協会」という。)
協会に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。
理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。
理事長及び監事は、< A >が任命する。
理事は、理事長が任命する。
事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に< B >を置く。
< B >の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、< A >が各同数を任命する。
【選択肢】
① 内閣総理大臣 ② 厚生労働大臣 ③ 社会保障審議会
④運営委員会 ⑤ 評議会 ⑥ 理事会

【解答】
A ② 厚生労働大臣
B ④運営委員会
協会に置かれるのが「運営委員会」、支部ごとに設けられるのが「評議会」です。
引き続きこちらも!
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、 < C >。これを変更しようとするときも、同様とする。
協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の< D >までに完結しなければならない。
協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後< E >以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
【選択肢】
① 厚生労働大臣に届け出なければならない
② 厚生労働大臣の許可を受けなければならない
③ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない
④ 4月30日 ⑤ 5月31日 ⑥ 6月30日
⑦ 1か月 ⑧ 2か月 ⑨ 3か月

【解答】
C ③ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない
B ⑤ 5月31日
C ⑧ 2か月
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】 ×
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
★評価をするのは厚生労働大臣。評価を行ったら、協会にフィードバックし、公表する。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-207
R2.6.25 選択式の練習/埋葬料と埋葬費どこが違う?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「埋葬料と埋葬費どこが違う?」です。
★埋葬料と埋葬費の違いをしっかり確認しましょう。
ではどうぞ!
問題
① 被保険者が死亡したときは、< A >であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、< B >円を支給する。
② ①により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< C >に対し、< B >円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【選択肢】
① その者と生計を同じくしていた者 ② 被扶養者
③ その者により生計を維持していた者
④ 30万 ⑤ 10万 ⑥ 5万
⑦ 埋葬を行うべき者 ⑧ 埋葬を行った者 ⑨ 埋葬を行おうとする者

【解答】
A ③ その者により生計を維持していた者
B ⑥ 5万
C ⑧埋葬を行った者
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として、政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

【解答】 〇
埋葬料 → 政令で定める金額(定額5万円)
埋葬費 → 5万円以内で実際に埋葬にかかった費用
 では、もう一問
では、もう一問
<H28年出題>
被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

【解答】 〇
死亡した被保険者により生計を維持していた者がいない場合、「埋葬料の支給を受けるべき者」がいませんので、実際に埋葬を行った者に5万円以内で実費が支給されます。問題文の場合は、別に生計をたてている実弟が実際に埋葬を行っていますので、その弟に埋葬費が支給されます。
ちなみに、埋葬料も埋葬費も時効は2年ですが、起算日が異なります。
埋葬料 → 被保険者の「死亡」に対して支給される。時効の起算日は、「死亡日の翌日」
埋葬費 → 実際に埋葬を行ったことに対して支給される。時効の起算日は、「埋葬を行った日の翌日」
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-197
R2.6.15 選択式の練習/短時間労働者の健康保険の適用
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「短時間労働者の健康保険の適用」です。
・ 平成28年10月1日→ 特定適用事業の短時間労働者に対する適用のルール
・ 平成29年4月1日 → 任意特定適用事業所のルール
がそれぞれ始まりました。
ではどうぞ!
問題
<健康保険の被保険者資格の取得基準>
短時間労働者については、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の< A >以上である者は、健康保険の被保険者として取り扱う。
【選択肢】
① 2分の1 ② 3分の2 ③ 4分の3

【解答】
A ③ 4分の3
「4分の3基準」といいます。
こちらもどうぞ!
<4分の3基準を満たさない者について>
4分の3基準を満たさない者でも、次の①から⑤までの5つの要件を満たすものは、健康保険の被保険者として取り扱う。
① 1週間の所定労働時間が< B >時間以上であること
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が
< C >円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所に使用されていること
【選択肢】
① 10 ② 20 ③ 25
④ 58,000 ⑤ 88,000 ⑥ 98,000

【解答】
B ② 20
C ⑤ 88,000
では、こちらもどうぞ!
「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時< D >人を超えるものの各適用事業所をいう。
【選択肢】
① 300 ② 500 ③ 1,000

【解答】
D ② 500
ちなみに
「任意特定適用事業所」とは?
★ 被保険者数が常時 500 人以下でも、労使の合意に基づき申出をすることによって適用を受けることができます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-187
R2.6.5 選択式の練習/任意継続被保険者の保険料の前納
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「任意継続被保険者の保険料の前納」です。
任意継続被保険者は保険料を前納することができます。
前納のルールは?
ではどうぞ!
問題
1. 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2・ 前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< A >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
3・ 前納された保険料については、前納に係る期間の< B >ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【選択肢】
① 年5分の利率 ② 年4分の利率 ③ 年3分の利率
④ 各月の初日が到来した ⑤ 各月が経過した
⑥ 各月10日が到来した

【解答】
A ② 年4分の利率
B ④ 各月の初日が到来した
こちらの問題もどうぞ!
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< C >までに払い込まなければならない。
【選択肢】
① 初月の前月末日 ② 初月の末日 ③ 初月の10日

【解答】
C ① 初月の前月末日
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-177
R2.5.26 選択式の練習/健保・国庫負担
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「健保・国庫負担」です。
ではどうぞ!
問 題
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の< A >(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する< A >を含む。)の執行に要する費用を負担する。
< B >に対して交付する国庫負担金は、各< B >における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
< B >に対して交付する国庫負担金については、概算払をすることができる。
【選択肢】
① 業務 ② 事務 ③ 職務
④ 健康保険組合 ⑤ 全国健康保険協会 ⑥ 市町村

【解答】
A ② 事務
B ④ 健康保険組合
健康保険の事業運営のための「事務費」については、予算の範囲内で、国庫が負担しています。(全国健康保険協会、健康保険組合を問わず、事務費は国庫が負担します。)
健康保険組合に対する国庫負担金は、被保険者数を基準に算定します。
こちらの問題もどうぞ!
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数と総報酬額の総額を基準として、厚生労働大臣が算定する。

【解答】 ×
算定の基準は、「被保険者数と総報酬額の総額」ではなく、「被保険者数」です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-167
R2.5.16 選択式の練習/(改正)被扶養者の認定要件
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「被扶養者の認定要件」です。
令和2年4月1日改正です。
ではどうぞ!
問 題
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者(省略)で、< A >を有するもの又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
【選択肢】
① 日本国内に所得 ② 日本国内に住所 ③ 日本国内で職業

【解答】
A ② 日本国内に住所
ポイント
令和2年4月1日より、被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加になりました。
 例 外
例 外
海外に居住していても、留学中の学生など日本国内に生活の基礎があると認められる者は、被扶養者として認められる例外があります。
↓
(海外居住でも例外的に被扶養者と認められる者)
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
⑤ ①から④までの他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
こちらの問題もどうぞ!
<H28年出題アレンジ>
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、日本国内に住所を有し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。

【解答】 ○
後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者にはなりません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-157
R2.5.6 選択式の練習/入院時食事療養費について
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、健康保険法「入院時食事療養費」です。
★平成27年の択一式をアレンジしています。
ではどうぞ。
問 題
入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき < A >円※とされているが、被保険者及び被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき< B >円とされている。
※難病、小児慢性特定疾病の患者は除く
【選択肢】
①100 ②160 ③210 ④260 ⑤360 ⑥460

【解答】
A ⑥460 B ①100
食事療養標準負担額 → 入院した際の食費のうち、被保険者本人が負担するもの。
こちらの問題もどうぞ
<H23年出題>
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。

【解答】 ×
中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額ではなく、「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額です。
※厚生労働大臣は、基準を定めようとするときは、「中央社会保険医療協議会に諮問」するとされています。
ポイント!
入院時食事療養費は、食費について定めた「基準額」から、被保険者が負担する「食事療養標準負担額」を控除した額です。
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

【解答】 ○
ポイント!
入院時食事療養費は、現物給付です。
※ 本来は、被保険者が病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用を、保険者が被保険者に代わって病院又は診療所に直接支払う方式です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-147
R2.4.26 選択式の練習/健保・保険給付の制限
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、問題です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る< A >。
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、< B >。
【選択肢】
①保険給付は行わない ②保険給付を行わないことができる
③保険給付の一部を行わないことができる
④保険給付の全部又は一部を行わないことができる

【解答】
A ①保険給付は行わない
B ④保険給付の全部又は一部を行わないことができる
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H22年出題>
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 ×
全部又は一部を行わないことができる、ではなく、「一部」を行わないことができる、です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-137
R2.4.16 産前産後休業を終了した際の改定
産前産後休業を終了したときに、例えば、子育てのため残業が無くなったなどの理由で以前より報酬が下がることがあります。
このような場合、標準報酬月額の改定の対象になるでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。

【解答】 ○
産前産後休業を終了した際の改定(育児休業等を終了した際の改定も)については、固定的賃金の変動は必須要件ではありません。
<比較>随時改定は、固定的賃金が変動することが条件です。残業手当の減少だけでは対象になりません。
| 随時改定 | 育児休業等終了時の改定 産前産後休業終了時の改定 |
| 固定的賃金が変動した | 固定的賃金の変動がなくてもOK |
| 原則として2等級以上の差が生じた | 1等級でもOK |
| 報酬支払基礎日数17日以上の月が3月継続している | 17日未満の月は除く |
こちらの問題もどうぞ!
<H25年出題>
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

【解答】 ×
17日未満の月がある場合は、その月を除いて平均を出し、改定を行います。
随時改定と比較しておさえてくださいね。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-127
R2.4.2 労災保険の給付を受けられない業務上の傷病等について
健康保険法の保険給付は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して行います。
労災保険の業務災害以外の傷病等とはどんなものなのか、イメージしてみてください。
 (H28年出題)
(H28年出題)
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】 ○
考え方の流れは以下の通りです。
とある会社員(健康保険の被保険者)が、副業として請負業務を行っている。
↓
その人が、もし請負業務中に負傷した場合、業務中であっても労働者ではないので、労災保険の給付は受けられない。
↓
原則として、健康保険の保険給付が受けられる。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-117
R2.3.19 任意適用事業所の取消し
 任意適用事業所の被保険者から、任意適用からの脱退を求められた場合、事業主は任意適用事業所の取消しの申請をする義務はあるのでしょうか?
任意適用事業所の被保険者から、任意適用からの脱退を求められた場合、事業主は任意適用事業所の取消しの申請をする義務はあるのでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

【解答】 ×
任意適用事業所に使用される被保険者から、任意適用取消の申請の希望があったとしても、事業主は取消しの申請をする義務はありません。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H24年出題>
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。

【解答】 ×
従業員から「任意適用事業所にしてほしい」と希望があったとしても、事業主には任意適用事業所とするべき義務はありません。
 任意適用事所となって健康保険に加入する、任意適用事業所を脱退する、どちらも、従業員からの希望があったとしても、事業主にはその申請をする義務は生じません。
任意適用事所となって健康保険に加入する、任意適用事業所を脱退する、どちらも、従業員からの希望があったとしても、事業主にはその申請をする義務は生じません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-107
R2.3.4 特定健康診査&特定保健指導
 特定健康診査とは
特定健康診査とは
・生活習慣病の予防が目的
・40歳から74歳までの人が対象のメタボリックシンドロームに着目した健診のこと
 (H28年出題)
(H28年出題)
健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。

【解答】 ×
「行うように努めなければならない」努力義務ではなく、「行うものとする」義務規定です。
高齢者医療確保法の規定
・厚生労働大臣が「特定健康診査等基本指針」を定める
↓
・保険者は、特定健康診査等基本指針に即して6年ごとに6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定める
↓
・保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行う
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-97
R2.2.15 保険医療機関又は保険薬局のみなし指定
 厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所、薬局のことを「保険医療機関又は保険薬局」といい、療養の給付を担当します。
厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所、薬局のことを「保険医療機関又は保険薬局」といい、療養の給付を担当します。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院又若しくは診療所又は薬局の開設者の申請によって行いますが、例外もあります。
 H29年出題
H29年出題
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

【解答】 ○
保険医療機関又は保険薬局のみなし指定からの出題です。みなし指定の対象は個人開業医と個人薬局のみなのがポイントです。
個人開業医と個人薬局の場合、保険医又は保険薬剤師の登録をすれば、保健医療機関又は保険薬局の指定の手続をしなくても指定があったとみなされます。
ここもポイント
保険医又は保険薬剤師 → 登録
保険医療機関又は保険薬局 → 指定
「登録」と「指定」の使い分けにも注意です。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H29年出題>
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】 ×
保険医療機関又は保険薬局の指定の辞退 → 1か月以上の予告期間
保険医又は保険薬剤師の登録の抹消 → 1か月以上の予告期間
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-87
R2.1.27 傷病手当金の待期の起算日
★ 傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給されます。
では、もし、就業中に労務不能になった場合の起算日は?
 H28年出題
H28年出題
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該翌日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】 ×
待期は、労務に服することができない状態に置かれた日から起算します。
問題の場合は入院した日(=労務に服することができない状態に置かれた日)から起算しますので、翌日を起算とするのが誤りです。
※ なお、労務に服することができない状態に置かれたときが業務終了後の場合は、翌日から起算します。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H25年出題>
傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健保法)
R2-77
R2.1.10 健康保険と後期高齢者医療の関係(健保)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H28 健保法(問10)より
H28 健保法(問10)より
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。

【解答】 ○
後期高齢者医療の被保険者は、健康保険の対象から除かれます。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H20年出題】
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。

【解答】 ×
後期高齢者医療の被保険者は、健康保険の対象から除かれますので、健康保険の被保険者資格は喪失します。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-67
R1.12.24 R1健保/全国健康保険協会の決算
和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「全国健康保険協会の決算」についてです。
 R1健保法(問1)より
R1健保法(問1)より
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これを当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

【解答】 ○
全国健康保険協会(協会)の決算のルールです。
財務諸表等をいつまでに(決算完結後2か月以内)、どこに(厚生労働大臣に)提出し、何が必要か(承認を受ける)をチェックしてください。
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H22年出題>
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後1か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。

【解答】 ×
決算完結後1か月以内ではなく、「2か月以内」です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-57
R1.12.4 R1健保/強制適用事業所について
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「強制適用事業所」についてです。
 R1健保法(問4)より
R1健保法(問4)より
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とならない。

【解答】 ×
法人の事業所は、業種を問わず、従業員1人だけでも強制適用です。
健康保険(厚生年金保険も)の場合、社長も「法人に雇われる者」として、強制加入となりますので、社長1人だけで他に従業員がいない法人でも強制適用事業所となります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-47
R1.11.10 R1健保/共済組合の組合員と健康保険
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健康保険法「共済組合の組合員と健康保険」についてです。
 R1健保法(問3)より
R1健保法(問3)より
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】 ○
 共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。共済組合からの保険給付と健康保険の保険給付が二重になるのを避けるため、共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法の保険給付を行わないことになっています。
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。共済組合からの保険給付と健康保険の保険給付が二重になるのを避けるため、共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法の保険給付を行わないことになっています。
なお、健康保険法の保険料も徴収されません。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H20年出題>
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。

【解答】 ×
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-36
R1.10.24 R1健保/出産手当金の時効
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「出産手当金の時効」についてです。
 R1健保法(問4)より
R1健保法(問4)より
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】 ×
 出産手当金の時効は2年ですが、時効の起算日は「出産した日の翌日から」は誤り。正しくは「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。
出産手当金の時効は2年ですが、時効の起算日は「出産した日の翌日から」は誤り。正しくは「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。
出産手当金は、「労務に服さなかった日」に対して支給されるからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-26
R1.10.8 R1健保法/被扶養者に関する保険給付
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健康保険法「被扶養者に関する保険給付」についてです。
 R1健保法(問2)より
R1健保法(問2)より
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

【解答】 ×
典型的なひっかけ問題です。慌てて解答しないようにしてくださいね。
67歳の「被扶養者」が生活療養を受けた場合は、被保険者に対し、入院時生活療養費ではなく、「家族療養費」が支給されます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/ご質問いただきました(健保)
R2-16
R1.9.22 R1健康保険法/被扶養者の認定
和元年の問題を振り返っています。
健康保険法の「被扶養者の認定」についてご質問がありました。ありがとうございます。
今日はその問題を解いてみます。
 R1健康保険法(問5)より
R1健康保険法(問5)より
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

【解答】 ○
認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の2分の1未満であれば原則として被扶養者に該当することになっています。
 この問題は、年収が被保険者の2分の1未満という要件が抜けているので誤りではないか?というご質問を頂きました。
この問題は、年収が被保険者の2分の1未満という要件が抜けているので誤りではないか?というご質問を頂きました。
認定対象者の年収が被保険者の2分の1以上の場合は、原則として被扶養者には該当しません。
しかし、被保険者の収入の2分の1以上でも一定の場合は、被扶養者に該当するものとして差し支えないという例外も設けられています。(一定の場合というのが問題文にある〝当該世帯の生計の状況を総合的に勘案し・・・〟の部分です。)
受験対策としては、「例外」がある、ということをおさえておけばいいかと思います。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(健康保険法)
R2-8
R1.9.9 R1選択式(健康保険法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第7回目は、「健康保険法 選択式」です。
 Aは「任意継続被保険者の標準報酬月額」についての出題です。
Aは「任意継続被保険者の標準報酬月額」についての出題です。
「任意継続被保険者」に関するルールは、どこをとっても問題が作りやすいので、「確実に出る」ことを前提に勉強するのがポイントです。
今回の箇所は、択一式でもよく出題されています。H24年には、今回の選択式と全く同じ論点で出題されています。
<参考 H24年出題>
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
(解答) ×
3月31日ではなく「9月30日」です。
 BとCは、「傷病手当金の支給を始める日」についての出題です。
BとCは、「傷病手当金の支給を始める日」についての出題です。
ポイント!
・ Bについて
休休休出休 → 連続3日休んでいるので待期は完成している。5日目から傷病手当金が支給されます。
・ Cについて
こちらの記事をどうぞ。

 DとEは「準備金」からの出題です。
DとEは「準備金」からの出題です。
保険者は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならないことになっています。(予測がつかない支出に備えるため)
協会の保険給付費については、準備金の積立金の基準は「12分の1」(1か月相当分)となります。
平成28年択一式でも出題されています。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社会保険分野】目的条文
R1.8.17 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックです。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
老齢退職年金給付と傷病手当金との調整/健康保険法
R1.6.18 老齢退職年金給付と傷病手当金は同時に受けられるか?
★★まずは過去問をどうぞ
<H27年出題>
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

【解答】 ○
「適用事業所に使用される被保険者」(=在職中)の部分がポイントです。
老齢退職年金給付と調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金(退職後に継続して給付される傷病手当金)です。
もう一問どうぞ
<H23年出題>
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。

【解答】 ×
老齢退職年金給付を受給している者には、資格喪失後の継続給付の傷病手当金は支給されません。(老齢退職年金給付が優先です。)
例外 → 老齢退職年金給付の額÷360が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
社労士受験のあれこれ
資格喪失月の賞与(健保)
R1.6.16 資格喪失月に支払われた賞与。保険料は?
過去問をどうぞ
<H25年出題>
前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】 ○
資格喪失月は、通常の保険料と同様に賞与の保険料も徴収されません。
※ ただし、資格喪失日の前日までに払われた賞与は、標準賞与額として決定され、標準賞与額の年度の累計額(573万円)に含まれます。
社労士受験のあれこれ
短時間労働者の報酬支払基礎日数(健保)
R1.6.5 (健保)短時間労働者のポイントは?
まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

【解答】○
「定時決定」、「随時改定」は通常は「17日」が基準ですが、短時間労働者の場合は、「11日」となります。育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定も同様です。
社労士受験のあれこれ
資格喪失後の出産育児一時金(健保)
R1.6.4 資格喪失後に「被扶養者」になった場合
まずは過去問をどうぞ
<H25年出題>
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給することになる。

【解答】○
例えば、会社員が退職後、夫の被扶養者になり出産した場合、被扶養者としての家族出産育児一時金の対象となります。と同時に、要件(資格喪失後6月以内に出産・引き続き1年以上被保険者だった)に合えば資格喪失後の出産育児一時金を受けることもできます。
しかし両方受けることはできません。請求者の選択によることになります。
社労士受験のあれこれ
高額療養費算定基準額(健康保険)
R1.5.18 【健保】高額療養費算定基準額・数字
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
< A >円+(療養に要した費用-< B >)×1%

【解答】
※平成27年択一式で出題された問題を選択式にアレンジしました。
A 167,400 B 558,000
ちなみに558,000円×100分の30が167,400円。
167,400円÷3×10が558,000円。
どちらかの数字を覚えていればOKです。
社労士受験のあれこれ
【前納】国民年金と健康保険の違い
R1.5.16 国民年金と健康保険の前納、どこが違う??
 条文の空欄を埋めてください。
条文の空欄を埋めてください。
【健康保険法】 (任意継続被保険者の保険料の前納)
1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料については、前納に係る期間の< A >ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【国民年金法】 (保険料の前納)
1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の< B >際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
【健康保険法】 A 各月の初日が到来した
【国民年金法】 B 各月が経過した
社労士受験のあれこれ
資格得喪の確認(健保)
R1.5.13 資格の取得・喪失は保険者等の確認で効力が発生するが。。。
健康保険法第39条では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によってその効力を生ずる」と規定されています。
ただし、例外もあります。今日は例外を確認しましょう。
まず過去問からどうぞ
<H26年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

【解答】 ×
→ なぜ保険者等の確認が必要なのでしょう?
一般的に「入社日=資格取得」、「退職日=翌日に資格喪失」ですので、保険者等が「入社日」と「退職日」を確認して初めて健康保険の資格取得、喪失の効力が発生します。
任意適用事業所が厚生労働大臣の認可を受けた場合は、認可の翌日に全員被保険者の資格を喪失するので、確認する必要がないということです。
なお、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失も確認は要りません。
任意継続被保険者は、法律で資格の取得事由と喪失事由が決まっていて、それに該当することによって資格を取得・喪失するからです。
もう一問どうぞ
<H30年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

【解答】 ×
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失、任意継続被保険者(特例退職被保険者も任意継続被保険者とみなす)の資格の喪失は保険者等の確認は不要です。
社労士受験のあれこれ
延滞金の日数の計算(健康保険法)
R1.5.9 健保・「延滞金」いつからいつまで?
まず過去問からどうぞ
<H28年出題>
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。

【解答】 ○
延滞金は、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの前日までの期間の日数にに応じて計算されます。
・ 延滞金は納期限の「翌日」から計算する。(納期限の当日は計算に入れない。)
・ 完納した当日は計算に入れないので、延滞金は完納の「前日」までで計算する。
★よくあるひっかけ問題
「督促状の指定期限(問題文では6月20日)の翌日から」とするパターンは間違いです。
ポイント!
督促状の指定期限までに納付した場合は、延滞金は徴収されません。
社労士受験のあれこれ
健康保険・一部負担金
H31.4.19 70歳以上の一部負担金の割合は?
さっそく、過去問をどうぞ
<H24年出題>
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担(平成26年3月31日までは1割負担)となる。

【解答】 ○
70歳以上の被保険者の一部負担金は2割ですが、70歳以上でも現役並み所得者(標準報酬月額が28万円以上)は3割となります。ただし、70歳以上の被保険者と被扶養者の年収が年収が520万円未満の場合は、申請によって2割負担となります。※平成26年3月31日までに70歳になっている人(昭和19年4月1日以前生まれの人)は、1割負担となります。
もう一問どうぞ
<H27年出題>
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< A >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和23年9月1日生まれ)が、平成31年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< B >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
■■選択肢■■
⓵70歳に達する日 ②70歳に達する日の属する月 ③70歳に達する日の属する月の翌月 ④70歳に達する日の翌日
⑤被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑥被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑦被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑧被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

【解答】
A ③70歳に達する日の属する月の翌月
B ⑦被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
※被保険者の収入と合算できるのは、70歳以上の被扶養者の収入です。設問の被扶養者の妻は67歳ですので収入の合算できません。そのため被保険者のみの収入で算定し、被保険者の収入が383万円未満であることが要件となります。
社労士受験のあれこれ
療養の給付/健康保険法
H31.4.9 資格取得前の傷病でも療養の給付等は受けられる?
さっそく過去問をどうぞ
<H23年出題>
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。

【解答】 ×
入社前の病気やケガも保険給付の対象ですので、療養の給付も傷病手当金も受けられます。
社労士受験のあれこれ
移送費/健康保険法
H31.4.8 移送費に一部負担金はある?orない?
さっそく過去問をどうぞ
<H21年出題>
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。

【解答】 ×
移送費は、「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された金額」の範囲内での実費が支給されます。
問題文の「3割の一部負担を差し引いた」の部分が誤りです。移送費には一部負担金はありません。
もう一問どうぞ
<H24年出題>
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

【解答】 ○
移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された金額の範囲内での実費です。「現に移送に要した費用の金額を超えることができない」がこの問題のポイントです。
社労士受験のあれこれ
傷病手当金・待期
H31.3.26 傷病手当金の待期の起算日は?
まずは過去問からどうぞ
<H28年出題>
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】 ×
待期は「労務に服することができなくなった日」から起算します。(※労務に服することができなくなったのが業務終了後の場合は、翌日から起算。)
問題文の場合は、業務中に労務不能になっているので当日から起算した3日間が待期期間です。
社労士受験のあれこれ
傷病手当金の継続給付
H31.3.25 資格喪失後の傷病手当金の要件
先日、資格喪失後の継続給付の条文を穴埋め式で確認しました。
その日の記事はコチラをどうぞ → H31.3.6 穴埋めで確認・資格喪失後の継続給付
今日は、その条文についての過去問をどうぞ。
<H23年出題>
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

【解答】 ×
資格喪失後に任意継続被保険者になったとしても、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けることができます。
【注意】資格喪失後に特例退職被保険者になった場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けられません。
社労士受験のあれこれ
老齢退職年金給付と傷病手当金との調整/健康保険法
※訂正あり
H31.3.21 老齢退職年金給付と傷病手当金は同時に受けられるか?※訂正あり
★★まずは過去問をどうぞ
<H27年出題>
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

【解答】 ○
「適用事業所に使用される被保険者」(=在職中)の部分がポイントです。
老齢退職年金給付と調整が行われるのは、資格喪失後の傷病手当金(退職後に継続して給付される傷病手当金)です。
もう一問どうぞ
<H23年出題>
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。

【解答】 ×
解説に誤りがありましたので、解説を削除しました。
訂正したものをこちらに載せました。
ご迷惑をおかけしたこと申し訳なく思っております。
社労士受験のあれこれ
健康保険法/訪問看護療養費
H31.3.19 「訪問看護事業」とは?
 「訪問看護療養費」とは?
「訪問看護療養費」とは?
疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者が、指定訪問看護事業者の看護師等に訪問してもらって療養上の世話又は必要な診療の補助を受けた場合に、「訪問看護療養費」として現物給付されます。
過去問をどうぞ
⓵指定訪問看護事業者について
<H25年出題>
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
②訪問看護事業について
<H24年出題>
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。

【解答】
⓵ ×
訪問看護療養費は、「指定訪問看護事業者」から訪問看護を受けたときに支給されます。「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けた場合は、訪問看護療養費ではなく「療養の給付」の対象となります。
なお、保険医療機関等だけでなく、介護保険法の介護老人保健施設若しくは介護医療院による療養上の世話も訪問看護療養費の対象にはなりません。
② ×
訪問看護を実施するのは、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士です。医師、歯科医師は含まれません。
社労士受験のあれこれ
社会保障制度の沿革を知ろう
H31.3.13 最低限おさえておきたい年金制度の沿革②
 昨日は、年金制度の沿革のポイントを選択式で学びました。
昨日は、年金制度の沿革のポイントを選択式で学びました。
今日は、年金だけでなく健康保険の沿革もまとめて確認しましょう。
過去問をどうぞ
<⓵ 国年H19年出題>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
<② 健保H21年出題>
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。

【解答】
⓵ ×
無拠出制の福祉年金の給付が始まったのは、昭和34年10月からではなく昭和34年11月からです。
福祉年金とは、制度の発足時点で既に70歳以上の人等が対象でした。保険料の納付が前提になっていない点が特徴の年金です。
老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金があります。
 ついでに厚生年金保険の沿革も。
ついでに厚生年金保険の沿革も。
昭和16年に工場の男子労働者を対象に「労働者年金保険法」が公布(昭和17年施行)されました。その後昭和19年に女子労働者や事務職員などにも適用されるようになり、名称が「厚生年金保険法」に改定されました。
② ×
健康保険法の制定は大正11年ですが、翌年に関東大震災が発生したので、大正15年(ただし、保険給付及び費用に関する規定は昭和2年)から施行されました。
社労士受験のあれこれ
健康保険法/資格喪失後の継続給付
H31.3.6 穴埋めで確認・資格喪失後の継続給付
 傷病手当金、出産手当金は、被保険者の資格を喪失した後も継続して給付を受けられることがあります。
傷病手当金、出産手当金は、被保険者の資格を喪失した後も継続して給付を受けられることがあります。
その際の要件を穴埋め式で確認しましょう。
【問題】
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで< A >被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、< B >であった期間、継続して< C >からその給付を受けることができる。

【解答】
A 引き続き1年以上 B 被保険者として受けることができるはず
C 同一の保険者
社労士受験のあれこれ
健康保険法/傷病手当金の支給期間
H31.2.28 傷病手当金、いつからいつまで支給される?
 傷病手当金は、■療養のため労務に服することができないとき、■労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、支給されます。
傷病手当金は、■療養のため労務に服することができないとき、■労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間、支給されます。
 支給期間は、支給を始めた日から起算して最長で1年6か月です。
支給期間は、支給を始めた日から起算して最長で1年6か月です。
 傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、この3日間のことを待期と言います。では、この3日間に有休休暇を取った場合、待期は完成するのでしょうか?
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、この3日間のことを待期と言います。では、この3日間に有休休暇を取った場合、待期は完成するのでしょうか?
過去問をどうぞ。
<H20年出題>
被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため入院療養となり、有給休暇が終了した後も入院のため欠勤(報酬の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。

【解答】 ×
「有給休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から」が間違い。有給休暇が終了した日の翌日から支給されます。有給休暇をとって報酬が支払われても待期は完成することがこの問題のポイントです。
1 日 | 2 日 | 3 日 | 4 日 | 5 日 | 6 日 | 7 日 | 8 日 | 9 日 | 10 日 | 11 日 | 12 日 |
有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 有 休 | 欠勤 | 欠勤 |
| 入 院 | |||||||||||
5日、6日、7日の3日間で待期は完成しますが、8日から10日は有給休暇で報酬が支払われていますので、傷病手当金は、有給休暇終了の翌日(報酬が支払われなくなった日)である11日から支給されます。
 傷病手当金は最長で1年6か月支給されますが、起算日は「支給を始めた日から」です。
傷病手当金は最長で1年6か月支給されますが、起算日は「支給を始めた日から」です。
過去問をどうぞ。
<H26年出題>
被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。

【解答】 ×
「4月28日から起算して1年6か月」ではなく、実際に傷病手当金の支給が始まった「6月1日」から起算して1年6か月です。
社労士受験のあれこれ
健康保険法/費用の負担
H31.2.25 事務費の財源
 今日のテーマは、健康保険事業の運営費のうちの「事務費」について。事務費の財源について確認しましょう。
今日のテーマは、健康保険事業の運営費のうちの「事務費」について。事務費の財源について確認しましょう。
まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】 ×
健康保険事業の運営費のうち、事務費については、全国健康保険協会だけでなく、健康保険組合に対しても全額国庫による負担が行われています。
もう一問どうぞ
<H13年出題>
健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。

【解答】 ×
健康保険組合の国庫負担金の算定の基準にするのは「被保険者数と標準報酬月額の総額」ではなく、「被保険者数」です。
★ポイントを穴埋め式でどうぞ。
1 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における
< A >を基準として、< B >が算定する。
2 1の国庫負担金については、< C >をすることができる。

【解答】
A 被保険者数 B 厚生労働大臣 C 概算払
社労士受験のあれこれ
健康保険法/労災休業補償給付と傷病手当金の調整
H31.2.24 休業補償給付と傷病手当金は同時に受けられる?受けられない?
 今日のテーマ
今日のテーマ
労災保険の休業補償給付を受けている間に、業務外の傷病にかかってしまった。その場合、傷病手当金も受けられるかどうか?です。
まずは過去問をどうぞ
<H24年出題>
労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって、労務不能の状態になった場合には、それぞれが別の保険事故であるため、休業補償給付及び傷病手当金は、それぞれ全額支給される。

【解答】 ×
労災保険法の休業補償給付を受給中に、さらに業務外の病気やけがで労務不能になった場合は、傷病手当金は支給されません。労災保険の休業補償給付が優先です。
ただし、傷病手当金の額が休業補償給付の額より多いときは、差額分だけ支給されます。
社労士受験のあれこれ
健康保険法/定時決定
H31.2.21 4・5・6月の報酬の平均
 まずは定時決定のルールからどうぞ
まずは定時決定のルールからどうぞ
・被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所で行う
・同日前3月間に受けた報酬の総額÷その期間の月数

報酬月額

標準報酬月額を決定する。
※ 通常は、4月、5月、6月の3か月間の報酬の総額を3で割って平均(=報酬月額)を出しますが、「3」が「2」や「1」になることもあります。
なぜなら、平均を出す期間は、「その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く」からです。
例えば、4月と5月の報酬支払基礎日数が20日で6月が15日の場合は、4月と5月の報酬の総額を「2」で割って平均を出すことになります。17日未満の6月は除かれます。
今日のポイント
ただし、「短期間労働者」の場合は、「17日」を「11日」と読み替えます。
ということで過去問をどうぞ!
<H29年出題>
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

【解答】 ○
短時間労働者の場合、継続した3月間で11日未満の月がある場合は「随時改定」は行いません。
社労士受験のあれこれ
健康保険組合の組織
H31.2.16 健康保険組合の組織
健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。
今日は、「健康保険組合の組織」を確認しましょう。
それではさっそく過去問をどうぞ
<平成15年出題>
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。

【解答】×
「日雇特例被保険者」が入っているので×です。日雇特例被保険者の保険者は「全国健康保険協会」で、健康保険組合に日雇特例被保険者は入りません。
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者で組織されます。任意継続被保険者を忘れないように注意してください。
もう一問どうぞ
<H21年出題>
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。

【解答】×
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」の一つだけです。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H31.1.30 H30年出題/健康保険と後期高齢者医療の関係
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「健康保険と後期高齢者医療の関係」です。
H30年 健康保険法(問10E)
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。

【解答】 ×
任意継続被保険者になってから2年経っていなくても、後期高齢者医療の被保険者になったときは、任意継続被保険者の資格は喪失します。(当日喪失)
★ 75歳になったら「後期高齢者医療」の被保険者になり、それまで入っていた健康保険からは適用除外の扱いとなります。任意継続被保険者だったとしても同じ考え方です。
過去問もどうぞ
<H20年出題>
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。

【解答】 ×
「健康保険の被保険者資格を有したまま」は誤り。健康保険の被保険者資格は喪失です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H31.1.29 H30年出題/保険給付の制限
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「保険給付の制限」です。
H30年 健康保険法(問6D)
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6か月以内の期間を定め、その者に支給すべき療養費の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、偽りその他不正の行為があった日から3年を経過したときは、この限りではない。

【解答】 ×
よく出題される規定です。
誤り箇所を穴埋め式で確認しましょう。

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6月以内の期間を定め、その者に支給すべき< A >の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< B >を経過したときは、この限りでない。
【解答】A 傷病手当金又は出産手当金 B 1年
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H31.1.28 H30年出題/任意継続被保険者の保険料の納付期日
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「任意継続被保険者の保険料の納付期日」です。
H30年 健康保険法(問5ウ)
一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなけれなならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】 ×
任意継続被保険者の毎月の保険料は、「その月の10日までに納付」は〇ですが、初めて納付すべき保険料の納付期日は、「保険者が指定する日」です。
例えば、1月27日に会社を退職し28日に資格を喪失した場合、要件を満たせば任意継続被保険者の資格取得日は1月28日となり、1月分から任意継続被保険者としての保険料が徴収されます。
初めて納付すべき保険料(任意継続被保険者となった月)の納付期日は「保険者が指定する日」までです。
過去問もどうぞ
<平成22年出題>
被保険者に関する毎月の保険料は、翌月の末日までに、納付しなければならないが、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までに納付しなければならない。

【解答】 ×
任意継続被保険者に関する保険料については、その月の末日ではなく「その月の10日」です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H31.1.26 H30年出題/被扶養者の要件
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「被扶養者の要件」です。
H30年 健康保険法(問10B)
被保険者の配偶者の63歳の母が、遺族厚生年金を150万円受給しており、それ以外の収入が一切ない場合、被保険者がその額を超える仕送りをしていれば、被保険者と別居していたとしても被保険者の被扶養者に該当する。

【解答】 ×
「配偶者の母」は被保険者と同一世帯にあることが条件です。別居している場合は被扶養者にはなれません。
過去問もどうぞ
<平成29年出題>
被保険者の兄姉は、主として被保険者により生計を維持している場合であっても、被保険者と同一世帯でなければ被扶養者とはならない。

【解答】 ×
「被保険者の兄弟姉妹」は、主として被保険者に生計を維持されていれば被扶養者となります。同一世帯要件はありません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H31.1.24 H30年出題/督促状により指定する期限
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「督促状により指定する期限」です。
H30年 健康保険法(問5ウ)
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。

【解答】 ×
14日以上が誤りです。督促状を発する日から起算して10日以上経過した日です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H31.1.23 H30年出題/資格喪失後の傷病手当金
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「資格喪失後の傷病手当金」です。
H30年 健康保険法(問9A)
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際、その資格を喪失した日の前日以前から傷病手当金を受けている者は、その資格を喪失した日から1年6か月間、継続して同一の保険者から当該傷病手当金を受給することができる。

【解答】 ×
「その資格を喪失した日から1年6か月間」が誤りです。「支給を始めた日から1年6か月間」です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H31.1.8 H30年出題/任意継続被保険者の届出関係
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「任意継続被保険者の届出関係」です。
H30年 健康保険法(問4C)
全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、事業主を経由して全国健康保険協会に提出しなければならない。

【解答】 ×
「事業主を経由して」が誤りです。
任意継続被保険者は既に退職しているので、事業主は経由せず直接保険者(協会又は組合)に提出します。
過去問もどうぞ
被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。

【解答】 ○
在職中の被保険者は、「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」に提出します。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H30.12.24 H30年出題/協会けんぽの業績評価
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」です。
※ 今日は、「協会けんぽの業績評価」です。
H30年 健康保険法(問1オ)
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】 ○
業績評価をするのは誰なのか?がポイントです。
【では過去問をどうぞ】
<H23年出題>
全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】 ×
評価をするのは全国健康保険協会の理事長ではなく「厚生労働大臣」、評価の結果は厚生労働大臣ではなく「全国健康保険協会」に対して通知します。
【選択式の練習です】
<事業計画等>
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、 < A >を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
<財務諸表等>
協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後< B >以内に厚生労働大臣に提出し、その< C >を受けなければならない。

【解答】
A 厚生労働大臣の認可 B 2月 C 承認
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H30.12.3 H30年出題/定時決定(休職給の取扱い)
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「健康保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「定時決定(休職給の取扱い)」です。
H30年 健康保険法(問3D)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。

【解答】 ○
定時決定の際は、4月・5月・6月の報酬の平均を出します。計算の際に、低額の休職給を受けた月を入れると平均が下がってしまいますので、その月は除いて平均を計算します。
例えば、5月に低額の休職給を受けた場合は、4月と6月の2か月間の平均を報酬月額とします。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法)
H30.11.13 H30年出題/災害救助法との調整
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、健康保険法「災害救助法との調整」です。
H30年 健康保険法(問3A)
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。

【解答】 ○
災害救助法により、大規模災害の際に都道府県知事が応急的な救助を行うことになっています。
災害救助法の救助が行われる場合は、健康保険の保険給付よりもそちらが優先されます。
【過去問もチェック!】
<H16年出題>
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

【解答】 ○
健康保険と生活保護法による医療扶助の場合は、健康保険が優先します。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法 基礎編)
H30.10.26 H30年出題/通勤途上の事故と健康保険
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「通勤途上の事故と健康保険との関係」です。
H30年 健康保険法(問2E)
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

【解答】 ×
★ 労災保険法に基づく給付が行われる場合は、健康保険法の埋葬料は支給されません。
【もう少し詳しくみると・・・】
■ まずは、労災保険と健康保険の保険給付の内容を確認しましょう。
・ 労災保険 → 業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等について保険給付を行う。
・ 健康保険 → 労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産について保険給付を行う。
■ 「通勤途上」の負傷、疾病、死亡については、労災保険の対象でもあるし、健康保険の対象でもあります。
■ どちらが優先するのか?
労災保険の通勤災害の給付の受給権がある場合は、健康保険の給付は行いません。(労災保険法が優先)
 【過去問もチェックしましょう】
【過去問もチェックしましょう】
<H26年出題>
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。

【解答】 ×
前半の「通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われない」の部分は○です。
後半が誤り。「勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合」は、健康保険の保険給付は行われます。
→ 労災保険の保険給付が受けられる場合は、健康保険は行わない。逆に労災保険が適用されず労災の保険給付が受けられない場合は、健康保険が使えます。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法 基礎編)
H30.10.7 H30年出題/保険医療機関
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
健康保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 「保険医療機関」として指定を受けるということは?
H30年健康保険法(問2A)
保険医療機関として指定を受けた病院であっても、健康保険組合が開設した病院は、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することができる。

【解答】 ×
ポイント!
療養の給付が受けられる病院、診療所又は薬局には次の3種類があります。
① 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所(保険医療機関)又は薬局(保険薬局)
② 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの (事業主医局)
③ 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局(健康保険組合直営病院)
①の保険医療機関・保険薬局として指定を受けた場合は、すべての被保険者が診療の対象です。健康保険組合直営の病院であっても、保険医療機関として指定を受けたなら、診療の対象者をその組合員である被保険者及び被扶養者のみに限定することはできません。
ついでにこちらの過去問もチェック!
【H20年出題】
健康保険組合である保険者が当該組合の被保険者のために開設する病院若しくは診療所又は薬局については、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要はない。ただし、その他の被保険者の診療を行うためには、保険医療機関又は保険薬局としての指定を受ける必要がある。
【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(健康保険法 選択編)
H30.9.17 <H30年選択>健康保険法振り返ります
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、健康保険法の選択式です。
A・B・C 基本的理念より
「基本的理念」については、こちらの記事で取り上げていました。
この条文、どこを空欄にしても問題文が作れそうなくらい、重要単語でいっぱいです。
↓
H30.8.21 【選択式対策】基本条文チェック!(健保、国年、厚年)
<過去問チェック・平成21年出題>
健康保険制度は、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて5年ごとに検討が加えられることになっている。
【解答】 ×
5年ごとではなく「常に」検討が加えられる、です。
D・E 出産手当金より
「出産の日」当日が、どちらに入るか覚えていればOKです。
<過去問チェック・平成24年出題>
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金が支給される。
【解答】 ○
「出産の日」は産前休業に含まれます。「以前」と「後」がポイントです。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】基本の条文(社会保険編)
H30.8.21 【選択式対策】基本条文チェック!(健保、国年、厚年)
 テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。
テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。
本試験の最中、「ここ、テキストのあのページの右上に書いてあった!」となったときに、目を閉じれば、そのページの映像が頭の中に浮かび上がるように。
■■
おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【健康保険法】
(基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< A >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< B >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< C >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける< D >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
【国民年金法】
(用語の定義)
・ 「政府及び実施機関」とは、< E >及び実施機関たる共済組合等をいう。
・ この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< F >をいう。
【厚生年金保険法】
(障害厚生年金の受給権者)
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して < G >(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに< H >があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の< I >に満たないときは、この限りでない。

【解答】
A 高齢化 B 後期高齢者医療 C 常に D 医療の質の向上
E 厚生年金保険の実施者たる政府 F 日本私立学校振興・共済事業団
G 1年6月を経過した日 H 国民年金の被保険者期間 I 3分の2
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社会保険分野】目的条文
H30.8.16 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)
 ご質問いただきました。
ご質問いただきました。
★「一般常識の勉強方法」
・ 労働分野 → 労働経済の数字(例えば、完全失業率やら労働力率etc)を、小数点以下まで覚える必要はありませんが、「用語の意味」はおさえてください。例えば、「完全失業率」=「労働力人口に占める完全失業者の割合」というように。
・ 社会保険分野 → 得点しやすい分野です。今年は、国民健康保険法の改正個所、確定拠出年金法の「数字」あたりに力を入れてほしいです。(まだ10日もあります!間に合います)
★「予備校の選び方」
これは相性などもあり、人によって全く違うと思うので、「○○が良い」とは言えなくて、申し訳ないです。
まずは、各学校の無料体験講座などを受けてみて、比較してみるのもいいのでは?と思います。
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・健康保険法】給付制限
H30.7.31 【選択式対策】給付制限
 いよいよ7月も最終日です!試験まで、体調管理にも気を付けてくださいね。
いよいよ7月も最終日です!試験まで、体調管理にも気を付けてくださいね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
【給付制限】
<問題1>
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、< A >。
<問題2>
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、< B >。
<問題3>
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< C >。
<問題4>
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、< D >以内の期間を定め、その者に支給すべき< E >又は< F >の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< G >を経過したときは、この限りでない。

【解答】
<問題1> A 行わない。
<問題2> B その全部又は一部を行わないことができる。
<問題3> C 一部を行わないことができる。
<問題4> D 6月 E 傷病手当金 F 出産手当金 G 1年
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・健康保険法】協会の一般保険料率
H30.7.9 【選択式対策】協会けんぽ・一般保険料率
 西日本に想像を絶するほどの大雨が降りました。ニュースを見ると、胸が痛くなります。
西日本に想像を絶するほどの大雨が降りました。ニュースを見ると、胸が痛くなります。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
<一般保険料率>
■ 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、< A >から< B >までの範囲内において、< C >(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。
■ 協会は、< D >ごとに、翌事業年度以降の< E >についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
■ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、 < F >が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< G >の議を経なければならない。

【解答】
A 1000分の30 B 1000分の130 C 支部被保険者
D 2年 E 5年間 F 理事長 G 運営委員会
※ 「理事長」→ 協会を代表し、その業務を執行する。
「運営委員会」→ 事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・健康保険法】訪問看護療養費
H30.6.11 【選択式対策】登場人物いろいろ・訪問看護療養費
 参考書やテキストをたくさん読んで、予想問題もたくさん解いている。。。でも、それで「あやふやな知識」が増えていませんか?本番で「どっちだったっけ?」と迷うのは損。少しずつでもいいので、確実に覚えていきましょう。
参考書やテキストをたくさん読んで、予想問題もたくさん解いている。。。でも、それで「あやふやな知識」が増えていませんか?本番で「どっちだったっけ?」と迷うのは損。少しずつでもいいので、確実に覚えていきましょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
今日のテーマは、「訪問看護療養費」です。
(訪問看護療養費)
被保険者が、< A >が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病又は負傷により、< B >において継続して療養を受ける状態にある者(< C >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の < B >において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(< D >等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する< E >によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

【解答】
A 厚生労働大臣 B 居宅 C 主治の医師 D 保険医療機関
E 介護医療院
ついでにチェック
居宅において療養上の世話又は必要な診療の補助を行うのは
看護師、保健師、< F >、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< G >

【解答】
F 助産師 G 言語聴覚士
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・健康保険法】数字のチェック
H30.5.15 【選択式対策】健康保険は数字で勝負
 急に暑くなりましたね!
急に暑くなりましたね!
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「健康保険法」です。
~~択一式の問題を選択式にアレンジしてみました。~~
問題1(H29年問2Bをアレンジ)
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第< A >級の < B >円までの等級区分となっている。
問題2(H28問2Bをアレンジ)
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く < C >か年度に限り、1,000分の30から1,000分の< D >までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

【解答】
A 50 B 1,390,000 C 5 D 130
※ 問題2は、地域型健康保険組合からの出題です。
ついでにこちらもチェック
次の空欄を埋めましょう。
(健康保険・標準賞与額の決定)
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< E >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が < F >万円を超えることとなる場合には、当該累計額が< F >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする

【解答】 E 1,000 F 573
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・健康保険】健康保険組合の解散
H30.4.18 【選択式対策】健康保険組合の解散
平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は健康保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
第26条(健康保険組合の解散)
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
① 組合会議員の定数の< A >の多数による組合会の議決
② 健康保険組合の< B >
③ 厚生労働大臣による解散の命令
2 健康保険組合は、前項①又は②に掲げる理由により解散しようとするときは、< C >を受けなければならない。
3 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。
4 < D >は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

【解答】
A 4分の3以上 B 事業の継続の不能 C 厚生労働大臣の認可
D 協会
ちょっとポイント★
「企業の健康保険組合の解散が相次ぐ見通し」であることがニュースになっています。高齢者の医療費への仕送りの負担が重くなっていることが理由として挙げられていました。
今日は、「健康保険組合の解散」のルールを確認しておきましょう。
★ 健康保険組合の解散の理由は、①組合会の議決によって、②倒産などで健康保険組合の事業の継続が不能になったことによって、③厚生労働大臣からの解散命令によって、の3つが定められています。
★ 理由①と②の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。(③の場合は厚生労働大臣が強制的に解散命令を出していますので、認可はいりません。)
★ 健康保険組合が解散する場合に、その財産をもって債務を完済できないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、「連帯責任で費用を負担してください」と請求することができます。
★ 健康保険組合が解散した場合は、協会(全国健康保険協会)が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継します。(健康保険組合から協会けんぽに移る)
社労士受験のあれこれ
移送費の要件
H30.3.23 H29年問題より「健康保険・移送費について」
H29年本試験【健康保険法問5D】を解いてみてください。
移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養をうけたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。

【解答】 ○
★ 通院などは移送費の対象にならないことがポイントです。
★ 移送費の条件を確認しておきましょう。以下の条文の空欄を埋めてください。
則第81条
< A >は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。
一 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。
二 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが< B >であったこと。
三 < C >その他やむを得なかったこと。

【解答】
A 保険者 B 著しく困難 C 緊急
社労士受験のあれこれ
健保・国庫負担
H30.2.26 H29年問題より「健康保険・国庫負担」
H29年本試験【健康保険法問4ウ】を解いてみてください。
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。

【解答】 ×
★ 全国健康保険協会・健康保険組合ともに、「事務の執行に要する費用」は、予算の範囲内で全額国庫が負担することになっています。
★ 「健康保険組合」への国庫負担金の算定方法をおさえておきましょう。条文の空欄を埋めてください。
① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< A >を基準として、< B >が算定する。
② ①の国庫負担金については、< C >をすることができる。

【解答】
A 被保険者数 B 厚生労働大臣 C 概算払
社労士受験のあれこれ
任意継続被保険者に係る業務
H30.1.31 H29年問題より「任継の保険料徴収業務」
H29年本試験【健康保険法問1C】を解いてみてください。
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

【解答】 ×
★ 「保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い」の部分が誤り。
★ 健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の二つです。
★ 「全国健康保険協会」が管掌する健康保険の業務のうち、次の4つについては、「厚生労働大臣」が行う業務とされています。
① 被保険者の資格の取得及び喪失の確認
② 標準報酬月額及び標準標準賞与額の決定
③ 保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)
④ ①~③に附帯する業務
★ なぜなら、「健康保険」の適用や保険料の徴収は「厚生年金」とセットで行われるからです。そのため、協会けんぽの場合、厚生年金と共通している業務については、厚生労働大臣が行うことになっています。
★ ただし、任意継続被保険者に係るものは、厚生労働大臣の行う業務からは除かれています。
任意継続被保険者は退職していますので、セットとなる厚生年金がありません。そのため、任意継続被保険者の保険料の徴収は、厚生労働大臣ではなく「全国健康保険協会」の業務として行われます。
社労士受験のあれこれ
任意継続被保険者の保険料滞納
H30.1.11 H29年問題より「任意継続被保険者が保険料を滞納した場合」
H29年本試験【健康保険法問2E】を解いてみてください。
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

【解答】 ○
★ 任意継続被保険者は、本人が責任をもって保険料を納めなければなりません。保険料を納めなかった場合は資格を喪失します。
任意継続被保険者の保険料の納付期日と保険料を納めなかった場合の扱いは以下の通りです。
| 初回分の保険料 | 2回目以降の保険料 | |
| 納付期日 | 保険者が指定する日 | その月の10日 |
| 納めなかった場合 | 任意継続被保険者とならなかったものとみなす | 納付期日の翌日に資格を喪失する |
※ 納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは除かれます。
社労士受験のあれこれ
基本の問題その5(健康保険法)
H29.12.21 H29年問題より「基本」を知ろう・健康保険法
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
傷病手当金の支給要件
傷病手当金は、「療養のため」労務に服することができない場合に支給される。
★ 傷病手当金の支給要件として、健康保険法第99条で「被保険者が療養のため労務に服することができないときは、・・・」と定められています。
「療養のため」とは、保険給付としての療養の給付を受けていなくても傷病手当金は支給され得る、という意味です。例えば、治療を自費診療で受けた場合などでも傷病手当金の対象となります。
ただし、もともと健康保険の保険給付の対象にならない美容整形の手術などで労務不能になった場合は、傷病手当金は支給されません。
★ 「日雇特例被保険者」の要件と比較してみましょう
日雇特例被保険者にも傷病手当金が支給されます。
ただし、日雇特例被保険者の場合は、傷病手当金の支給要件は「療養の給付を受けている場合」と定められています。日雇特例被保険者は、現に「療養の給付」を受けていなければ傷病手当金は支給されませんので、自費診療の療養は、傷病手当金の支給対象外となります。
では、平成29年【問8】Aを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問8】A)
傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養については、療養の給付に係る保険医の意見書を必要とするため、自費診療で療養を受けた場合は、傷病手当金が支給されない。

<解答> ×
社労士受験のあれこれ
定番問題その16(健康保険法)
H29.11.30 H29年問題より「定番」を知る・健康保険法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (資格喪失月の保険料は?)
保険料は「月単位」。前月から引き続き被保険者である者が資格を喪失した場合は、その月分の保険料は徴収されない。
★ 例えば
・前月から引き続き被保険者である者が11月17日に退職した場合
→ 11月18日が資格喪失日。資格喪失した11月分の保険料は徴収されない。
・前月から引き続き被保険者である者が11月30日に退職した場合
→ 12月1日が資格喪失日。11月分の保険料は徴収される。
・11月5日に資格取得し、11月20日に退職した場合(同一月に取得と喪失)
→ 11月分の保険料は徴収される。
★ 賞与について
・原則の考え方は上と同じです。
例えば、前月から引き続き被保険者であった者に、12月10日に賞与の支払があり、その者が12月20日に退職した場合、12月は資格喪失月ですので、賞与の保険料も徴収されません。
これを覚えると、平成29年【問10】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問10】C)
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
定番問題その6(健康保険法)
H29.11.2 H29年問題より「定番」を知る・健康保険法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (健康保険と介護保険、どちらが優先か?)
同一の疾病又は負傷について、介護保険法から給付を受けることができる場合は、介護保険が優先
★ 介護保険には要介護者等に対する医療系サービスがあります。介護保険から医療系サービスを受けられる場合は、そちらを優先し、その傷病については健康保険の療養の給付等は行われません。
★ <参考>健康保険法第55条2項
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
これを覚えると、平成29年【問4】イが解けます。
★問題です。
(平成29年【問4】イ)
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。

<解答> 〇
介護保険法から給付が受けられる場合は、健康保険からの給付は行われません。
社労士受験のあれこれ
覚えれば解ける問題その6(健康保険法)
H29.10.17 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・健康保険法
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (健康保険組合が解散した場合)
「全国健康保険協会」が、権利義務を承継する。
★ 健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。
※「全国健康保険協会」は、健康保険組合の組合員でない被保険者の保険を管掌することになっています。
★ 「健康保険組合」は次の3つのいずれかの理由により解散します。
①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決
②健康保険組合の事業の継続の不能
③厚生労働大臣の解散命令
★ 「健康保険組合」が解散した場合、その後はどうなるのでしょう?
解散で消滅した健康保険組合の権利義務は、「全国健康保険協会」が承継します。(解散した健康保険組合に加入していた人は、全国健康保険協会に引き継がれます。)
これを覚えると、平成29年【問1】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問1】D)
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
まずは原則!その8(健康保険法)
H29.10.4 H29年問題より原則を学ぶ・健康保険
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(被扶養者に関する給付は「被保険者」に支給する)
被扶養者に対する保険給付には、「家族療養費」、「家族訪問看護療養費」、「家族移送費」、「家族埋葬料」、「家族出産育児一時金」があります。
よく出るポイントは、被扶養者に対する保険給付は、「被扶養者」ではなく、「被保険者」に支給すること。
保険料を負担する義務、保険給付を受ける権利は、被保険者にあるからです。
この原則で、平成29年【問7】Cが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】C)
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対しその指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

<解答> ×
「「被保険者」に対し「家族訪問看護療養費」を支給する」です。
◆ 定番の問題です。「被扶養者」が療養等を受けたときは、「被扶養者」ではなく、「被保険者」に対して家族療養費等が支給されます。
このタイプの問題は、「被扶養者」に対し支給する、となっていたら誤りです。まずはそこをチェックしてください。
社労士受験のあれこれ
平成29年度選択式を解きました。(健康保険編)
H29.9.12 平成29年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「健康保険法」です。
【A】
「現物給与」からの出題です。
「食事」については以下の流れを押さえましょう。
・ 「食事」が現物で支給された場合も「報酬」に入る
↓
・ 「食事」については、都道府県ごとに標準価額が決められている
↓
・ 標準価額の3分の2以上を被保険者が負担している場合は「報酬」に入らない
※ 負担が3分の2未満の場合は、標準価額から負担分を引いたものが「現物給与」の価額となる
【B、C】
第160条「保険料率」からの出題です。
協会けんぽの一般保険料率は、支部単位で決められています。
ただし、都道府県間で、年齢構成(年齢構成が高いと医療費がかかる)や所得水準(保険料の収入額に影響する)に差がありますので、支部間で調整する仕組みがとられています。
【B】の文章は「療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡」とあるので、医療費に影響するということでヒントは「年齢」。
【C】の文章は「財政力の不均衡」とあるのでヒントは所得。選択肢の「所得階級別の・・・」と「総報酬額の平均額」。どちらか迷った方も多かったのでは?
協会が把握できるのは「報酬」で、所得は把握できないなーと考えてみるのはどうでしょう?
【D】
「指定訪問看護事業者の責務」からの出題です。
テキストにはあまり出てこない箇所で、「こんなの見たことない!」と思ってしまったかもしれませんね。
指定訪問看護事業者が指定訪問看護を提供するに当たって、保険者や保険医療機関などの指示に基づいて、というのも変だな、と考えてみると答が出せるかと思います。
【E】
「健康保険組合の設立」からの出題です。
人数要件が、久しぶりに出ました。
皆さんばっちりできたところだと思います。
今後の勉強のポイント!
★ 択一式が選択式に生まれ変わる
「択一式」を勉強するときは、「キーワード」を意識しながら。択一式のポイントが選択に生まれ変わって出題されることも多い。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】選択式の練習(健康保険法)
H29.8.10 選択式の練習(健康保険法)
選択式の練習問題です。
本日は、健康保険法の改正個所からです。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
第41条(定時決定)
保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、< A >日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
則第24条の2(法第41条第1項の厚生労働省令で定める者)
法第41条第1項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の< B >である同条に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の< B >である短時間労働者とする。

<解答>
A 11 B 4分の3未満
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)
H29.8.1 目的条文のチェック(社会保険編)
8月になりました!
ここからの頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。
目的条文のチェック(労働編)はコチラです。
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

<解答>
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
※ 業務災害→ 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
ココもポイント!
第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。
コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
★★憲法第25条第2項も見ておきましょう。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
社労士受験のあれこれ
退職後の傷病手当金(続き)
H29.3.29 健康保険法・傷病手当金の継続給付その2
その1では、退職後の傷病手当金の継続給付の要件について勉強しました。
今日はその続きです。
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けるには、退職時に傷病手当金を「支給を受け得る状態」であることが要件です。
例えば、3月29日から休み始めて3月31日に退職した場合は、退職後に傷病手当金の継続給付は受けられるでしょうか?
↓
★ 傷病手当金の支給は「3日間の待期」を満たしていることが要件です。
3月31日は休み始めて3日目ですので、3月31日の退職日には未だ待期が完成していません。=傷病手当金の要件を満たしていない。
↓
傷病手当金は支給されません。
 過去問をどうぞ
過去問をどうぞ
<H28年出題>
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者が傷病により労務不能となり、当該労務不能となった日から3日目に退職した場合には、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けることはできない。

<解答> 〇
退職日に待期が完成していないので、資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は受けられません。(休業3日目に退職した場合は要件を満たさない)
社労士受験のあれこれ
退職後の傷病手当金
H29.3.28 健康保険法・傷病手当金の継続給付
退職すると、その翌日に健康保険の被保険者の資格は喪失します。
例えば、在職中に病気になり傷病手当金の給付を受けていた場合、退職後はその傷病手当金はどうなるのでしょう?
健康保険法では、傷病手当金の「継続給付」の規定が設けられていて、要件を満たせば、退職後も引き続いて傷病手当金を受けることができます。
今日は、「傷病手当金の継続給付」を勉強しましょう。
 傷病手当金の継続給付の要件
傷病手当金の継続給付の要件
① 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったこと
→ 平成29年3月28日に退職した場合、翌日の29日に被保険者の資格を喪失します。資格喪失の前日(3月28日)まで引き続いて1年以上健康保険の被保険者だったことが条件です。
② 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていること
→ 報酬との調整で傷病手当金が支給停止されていた場合(「支給を受け得る」状態)でも要件は満たします。
↓
↓
★ 要件を満たせば
被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
→ 傷病手当金は、支給を始めた日から1年6か月受けることができますよね。
例えば、在職中に6か月間支給を受けた場合は、退職後引き続きあと1年間受けることができます。
※ また、在職中は報酬との調整で傷病手当金が支給停止されていた場合は、退職後報酬がなくなった日から傷病手当金が支給されます。
 過去問をどうぞ
過去問をどうぞ
<H24年出題>
一定の要件を満たした者が、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受領することができるが、退職日まで有給扱いで全額賃金が支給されていても、資格喪失後の傷病手当金は受給することができる。

<解答> 〇
退職日まで有給扱いだったため傷病手当金は停止されていたとしても、「傷病手当金を受けられる」状態であれば、資格喪失後の傷病手当金は支給されます。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.27 必ず出る改正点(健保編4)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年健康保険法問3のDです。
<問題文>
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

【答え】 ○
★ 平成28年4月1日の改正で創設された「患者申出療養」からの出題です。
「療養を受けようとする者の申出に基づく」がキーワードです。
★ 患者申出療養は、「療養の給付」ではなく、「保険外併用療養費」の対象になることもポイントです。
なお、「保険外併用療養費」の対象になるものは次の3つです。
1 評価療養
2 患者申出療養
3 選定療養
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.26 必ず出る改正点(健保編3)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年健康保険法問4のCです。標準賞与額の改正からの問題です。
<問題文>
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【答え】 ×
★ 平成28年4月1日の改正で、上限の額が540万円から「573万円」になりました。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.11.29 必ず出る改正点(健保編2)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
改正点を直球で出してくるパターンが多いので、得点しやすいです。
本日は平成28年度健康保険法問9のイです。平成28年4月の改正からの問題です。
<問題文>
出産手当金の額は、1日につき、出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。ただし、その期間が12か月間に満たない場合は、出産手当金の支給を始める日の属する月の標準報酬月額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額とする。

【答え】 ×
★ 問題文の前半は「○」ですが、後半の12カ月未満の部分の「支給を始める日の属する月の標準報酬月額」が「×」です。
<12か月間ある場合>
※ 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額
※ 例えば、平成28年11月29日に支給を開始した場合
| H27.12 | H28.1 | H28.2 | H28.3 | H28.4 | H28.5 | H28.6 | H28.7 | H28.8 | H28.9 | H28.10 | H28.11 |
| H27年12月から平成28年11月までの各月の標準報酬月額を合算して平均をとる | |||||||||||
<12か月間に満たない場合>
※ ①と②のどちらか少ない額が算定の基礎になる
| ① 支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額 |
| ② 支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日の全被保険者の標準報酬月額を平均した額 |
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.11.24 必ず出る改正点(健保編)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
改正点を直球で出してくるパターンが多いので、得点しやすいです。
本日は平成28年度健康保険法問2のCです。
<問題文>
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

【答え】 × 「100分の1」ではなく「100分の0.5」
★ 上限改定のルール
① 毎年3月31日における
最高等級該当者数の被保険者総数に占める割合 → 100分の1.5を超える
↓
② その年の9月1日から
当該最高等級の上に更に等級を加える等級区分の改定を行うことができる
↓
③ ただし、その年の3月31日において
改定後の最高等級該当者数の被保険者総数に占める割合 → 100分の0.5を下回らないこと
※ 平成28年4月1日に「100分の1」が「100分の0.5」に改正されていて、そこからの出題でした。
社労士受験のあれこれ
日本最初の社会保険は?
H28.10.13 健康保険法制定
日本の社会保障制度は、① 社会保険、 ② 社会福祉、 ③ 公的扶助、 ④ 保険医療・公衆衛生の4つに分類され、現在の社会保障の中心は、「①社会保険」です。
健康保険などの医療保険や、年金制度、介護保険などが「社会保険」です。
「保険」ですので、「保険料を拠出することによって→保険給付が受けられる」という形式で運営されています。
それでは、日本で最初の社会保険について、次の問題を解いてみましょう。
<平成21年出題>
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。

(解答) ×
健康保険法は大正11年に制定されましたが、翌年の関東大震災発生によって施行が延期されました。施行は、大正15年(保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年から)です。

ちなみに、日本で最初の公的年金制度は「船員保険」です。
コチラの記事をどうぞ
社労士受験のあれこれ
ひっかけ問題(引っかかってはいけない)
H28.10.5 シリーズひっかけ(健康保険・日雇特例被保険者)
次の問題を解いてみてください。
<平成19年出題>
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

<解答> ×
「日雇特例被保険者手帳」ではなく、保険医療機関等に「受給資格者票」を提出して療養の給付等を受けることになります。
ポイント!
日雇特例被保険者の保険料の納付は、「日雇特例日保険者手帳」に「印紙」をはり消印することによって行う。
★「日雇特例被保険者手帳」は印紙を貼付するものです。保険医療機関等では手帳ではなく「受給資格者票」を提出します。
(第129条)
保険者は、日雇特例被保険者が、前項第1号(前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上の印紙が貼付されている)に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
社労士受験のあれこれ
H28年度選択式を解きました。その4(健康保険編)
H28.9.5 平成28年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~
平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。
★労基・安衛編はコチラから。
→ H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
★労災・雇用編はコチラから。
→ H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~
★一般常識編はコチラから。
→ H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~
今日は、「健康保険法」です。
<健康保険法>
【A】、【B】、【C】
去年改正された高額療養費からの出題です。
高額療養費については、とにかく数字を覚えることが最も大事です。
「社労士受験のあれこれ」でも取り上げています。
コチラの記事もどうぞ → H28.4.14 所得段階別の高額療養費算定基準額
【D】、【E】
訪問看護療養費からの問題です。
訪問看護療養費については、平成15年にこんな問題が出ています。
「指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、主治の医師が指定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。」
答えは「×」です。どこの指定訪問看護事業者を選ぶのは、主治の医師が指定するではなく、「自己の選定」です。
このように、択一式のポイントがそのまま選択式で出題されることは多々あります。
知っておくと要領よく勉強ができます!
次回は、年金です。
社労士受験のあれこれ
【直前】「健康保険法」の選択対策
H28.8.18 直前!「健康保険法」の選択対策
あと10日。まだまだ、巻き返しできます!
試験中に、「あーーーこれ見たことあるけど、どっちだったっけ?」と思うのは非常に悔しいので、気になった箇所は、しっかり見直しをしておきましょう。
今日は健康保険法の選択問題です。
雇用保険同様、健康保険も「数字」のチェックが必須です!
①標準賞与額の決定
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
②入院時食事療養費
入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して< C >が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して< C >が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
■食事療養標準負担額■
| 対象者の区分 | 食事療養標準負担額 | ||||
| a | b,c,dのいずれにも該当しない者 | 1食につき460 円 (ただし、平成28 年4月1日から平成30 年3月31 日までの間においては、1食につき < D > 円) | |||
| b | c,dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 | 1食につき< E >円 | |||
| c | 低所得者Ⅱ | 過去1年間の入院期間が90日以下 | 1食につき210 円 | ||
| 過去1年間の入院期間が90 日超 | 1食につき160 円 | ||||
| d | 低所得者Ⅰ | 1食につき100円 | |||
③特例退職被保険者の標準報酬月額
特例退職被保険者の標準報酬月額については、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< F >の特例退職被保険者< G >全被保険者の同月の標準報酬月額を< H >を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
【選択肢】
① 3月31日 ② 9月30日 ③ 4月1日 ④ 10月1日
⑤ を含む ⑥ 以外の
⑦ 平均した額の範囲内においてその規約で定めた額
⑧ 平均した額の範囲内において政令で定めた額
⑨ 平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の2分の1に相当する額の範囲内において規約で定めた額
⑩ 平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額に相当する額の範囲内において規約で定めた額

<解答>
A 1,000 B 573万
C 厚生労働大臣 D 360 E 260
F ② 9月30日 G ⑥ 以外の H ⑦ 平均した額の範囲内においてその規約で定めた額
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)
H28.8.2 目的条文のチェック(社会保険編)
いよいよ8月です!
8月の頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。
目的条文のチェック(労働編)はコチラです。
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

<解答>
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
ココもポイント!
第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。
コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
★ 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づいています。第25条第1項ではありませんので注意してくださいね。
★★憲法も見ておきましょう。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
★厚生年金保険は「保険給付」といいますが、国民年金は「給付」で保険給付とはいいません。
この違いについてはコチラ → H28.1.28 国民年金と厚生年金保険の違い
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その2
H28.7.29 金曜日は横断 (不服申し立て その2)
金曜日は「横断」です。
今週は、「不服申し立ての横断整理その2」で、テーマは「処分の取消しの訴え」です。
その1はこちら → 「審査請求」と「再審査請求」の期限
厚年一元化に伴う改正点はこちら → H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
※雇用保険の解答を修正しました。(H28.8.1)
では問題です。空欄を埋めてください。
【労災保険法】
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【健康保険法】
ⅰ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
ⅱ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
Ⅲ < A >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<A>に入るのは次のどちらでしょう?
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分
【国民年金法】
ⅰ 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ ⅰに規定する処分(< B >(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<B>に入るのは次のどちらでしょう。
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分
【厚生年金保険法】
ⅰ 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
ⅲ < C >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<C>に入るのはどちらでしょう?
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分

【解答】
【労災保険法】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<労働者災害補償保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、労働者災害補償保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<雇用保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「①確認、②失業等給付に関する処分、③不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴え」をするには、雇用保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
※審査請求と雇用保険審査官が入れ替わっていましたので訂正しました。(H28.8.1)
【健康保険法】
<A>には、「① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることが可能です。
【国民年金法】
<B>には、「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分」が入ります。
★「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)」について処分取消しの訴えをするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」については、社会保険審査官に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
【厚生年金保険法】
<C>には、「① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
社労士受験のあれこれ
選択対策/健康保険法
H28.7.27 水曜日は選択式対策!(健康保険法)
今週は健康保険法です。
【問題①】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< A >。
【問題②】
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、< B >以内の期間を定め、その者に支給すべき< C >の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< D >を経過したときは、この限りでない。
【問題③】
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書その他の物件の提出若しくは提示命令に従わず、又は職員の質問若しくは診断に対して答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の< E >。
【問題④】
1. < F >は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2. < F >は、協会が1.の期間内に申請をしないときは、< G >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】
【問題①】A 一部を行わないことができる
ポイント! 「全部又は一部」ではない、「行わない」ではない。
【問題②】B 6月 C 傷病手当金又は出産手当金 D 1年
【問題③】E 全部又は一部を行わないことができる
問題①②③の解説はコチラの記事をどうぞ
↓ ↓ ↓
H28.5.5 全部?全部又は一部?一部?(健保・給付制限)
【問題④】 F 厚生労働大臣 G 社会保障審議会
ヒント!
アンダーラインの「都道府県単位保険料率の変更の認可」の部分がヒントです。都道府県単位保険料率を変更しようとするときは「厚生労働大臣の認可」が必要ですよね。
ここもポイント!
協会管掌の健康保険の一般保険料率は、支部被保険者を単位として協会が決定します。支部被保険者を単位として決定する一般保険料率を都道府県単位保険料率といいます。
(第160条)
1. 協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものとする。
※支部被保険者 → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者
2. 1.の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その1
H28.7.22 金曜日は横断 (不服申し立て その1)
金曜日は「横断」です。
今週から、「不服申し立て」の横断整理に入ります。(何回かに分けてUPします。)
今週は、「審査請求」と「再審査請求」の期限を整理しましょう。
以下の問題の空欄を埋めてください。
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して < >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
<参考>
次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
| 1 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合審査会 |
| 2 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合審査会 |
| 3 第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 |

<解答>
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から <3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して<3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、脱退一時金に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
ポイント!
★労災保険・雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険 <共通>
審査請求 → 3カ月
再審査請求 → 2カ月
★労災保険・雇用保険
棄却したものとみなす → 3カ月
★健康保険・国民年金・厚生年金保険
棄却したものとみなす → 2カ月
社労士受験のあれこれ
【横断】資格取得届
H28.7.15 金曜日は横断 (資格取得届)
金曜日は「横断」です。
(2日遅れの更新で申し訳ないです。)
今週は、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法の「資格取得届」でよく出るところを横断的に整理しましょう。
※ ちなみに、労災保険法には「資格取得届」はありません。
では、問題です。
【雇用保険法】
① 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【健康保険法】
②(平成22年出題) 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
【国民年金法】
③(平成20年出題) 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
④ 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
【厚生年金保険法】
⑤ 法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から10日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとする。

【解答】
【雇用保険法】
① ×
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで」です。
【健康保険法】
②(平成22年出題) ×
①新規適用事業所の届出と②被保険者の資格取得の届出は5日以内ですが、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出は、「速やかに」です。
★健康保険法の事業主の行う届出の提出期限は原則として「5日以内」です。
「5日以内」ではないものを覚えていくのがポイントです。
★提出期限が「速やかに」の届出
「報酬月額の変更の届出(随時改定)」、「育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出」、「産前産後休業を終了した際の報酬月額の変更の届出」
【国民年金法】
③(平成20年出題) ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、資格取得届ではなく「種別変更届」を提出しなければなりません。(期限は14日以内、提出先は市町村長です。)
④ ○
第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出の経由先について
・ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者の場合 → その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由(経由の事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる)
・ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者の場合 → その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由
【厚生年金保険法】
⑤ ×
当該事実があった日から10日以内ではなく「5日以内」です。(船員被保険者は10日以内)
※ 法第27条は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者については、適用されません。
社労士受験のあれこれ
選択対策/健康保険法(療養の給付)
H28.7.13 水曜日は選択式対策!(健康保険法)
今週は健康保険法です。
(療養の給付)
1 療養の給付の範囲
① 診察
② 薬剤又は治療材料の支給
③ 処置、手術その他の治療
④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2療養の給付に含まれないもの
① 「食事療養」
食事の提供である療養であって前項第⑤号(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に掲げる療養)と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものを除く。)
② 「生活療養」
次に掲げる療養であって前項第⑤号(病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に掲げる療養)に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
③ 「評価療養」
厚生労働大臣が定める< A >を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から< B >を行うことが必要な療養(次号の< C >を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの
④ 「< C >」
< A >を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から< B >を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの
⑤ 「< D >」
被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養

<解答>
A 高度の医療技術 B 評価 C 患者申出療養 D 選定療養
ここもチェック!
①「食事療養」
療養の給付と併せて受けた食事療養 → 「入院時食事療養費」を支給する
※入院時の食事は療養の給付(診療等)とは別に「入院時食事療養費」として支給(現物給付)される。
②「生活療養」
療養の給付と併せて受けた生活療養 → 「入院時生活療養費」を支給する(現物給付)
③「評価療養」④「患者申出療養」⑤ 選定療養」
評価療養、患者申出療養、選定療養を受けたとき → 「保険外併用療養費」を支給する
※ 通常の治療と共通する部分(保険診適用される部分)が「保険外併用療養費」として現物給付され、保険診適用されていない部分は「自費」負担となる
社労士受験のあれこれ
横断・日雇労働者
H28.7.8 金曜日は横断 (日雇労働者/労基・雇用・健保)
金曜日は横断です。
「日雇労働者」について過去の出題ポイントを集めました。
<労働基準法>
問題①(H11年出題)
日々雇入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。
問題②(H13年出題)
日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
<雇用保険法>
問題③(H25年選択式)
雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において<A >とは、<B >又は<C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
問題④(H20年出題)
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
問題⑤(H20年出題)
日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。
問題⑥(H20年出題)
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
<健康保険法>
問題⑦
健康保険法の「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては< A >を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる< B >を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ < C >以内の期間を定めて使用される者
2. 季節的業務に使用される者(継続して< D >を超えて使用されるべき場合を除く。)
3. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して< E >を超えて使用されるべき場合を除く。)
問題⑧(H19年出題)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

<解答>
<労働基準法>
問題①(H11年出題) ×
日々雇入れられる者でも労働契約締結時に絶対的明示事項(昇給に関する事項は除く)は書面の交付が必要です。
なお、日々雇入れられる者は、「労働者名簿の調製」は不要です。
問題②(H13年出題) ×
日々雇入れられる者については、解雇予告の規定は原則として除外されます。
ただし、日々雇入れられる者でも「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」は、解雇の予告が必要です。
<雇用保険法>
問題③(H25年選択式)
A 日雇労働者 B 日々雇用される者 C 30日 D 18日 E 31日
問題④(H20年出題) ○
次の①又は②に該当した場合は、日雇労働者でなくなります。
①前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 |
※ ただし、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができます。
問題⑤(H20年出題) ×
10日以内ではなく「5日以内」です。ちなみに提出先は管轄公共職業安定所長です。
問題⑥(H20年出題) ×
日雇労働被保険者には、雇用保険被保険証は交付されません。
管轄公共職業安定所長は日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき、任意加入の認可をしたときは、「日雇労働被保険者手帳」を交付しなければならないと規定されています。
ここもポイント!
日雇労働被保険者には「確認」の制度は適用されません。
<健康保険法>
問題⑦
A 1月 B 所定の期間 C 2月 D 4月 E 6月
問題⑧(H19年出題) ×
保険医療機関等に提出するのは、「受給資格者票」です。
社労士受験のあれこれ
国・地方公共団体の扱い
H28.6.17 金曜日は横断 (国・地方公共団体の扱い)
金曜日は横断です。
国・地方公共団体の扱いについて過去の出題ポイントを集めました。
【労災保険法】
① H11年記述
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業や< A >の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、適用されない。
② H20年出題
労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(行政執行法人を除く。)の職員には適用される。
【雇用保険法】
③ H22年出題
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
④ H27年出題
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
【健康保険法】
⑤ H14年出題
健康保険法の適用される法人の事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。
⑥ H20年出題
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
【厚生年金保険法】
⑦
適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。

<解答>
【労災保険法】
① H11年記述 A 官公署
労働者を1人でも使用する事業は業種関係なく原則として労災保険法の適用事業となります。
ただし、国の直営事業(現在当てはまる事業はありません)、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)= 非現業の官公署のことは、労災保険法から除外されています。国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法で保護されるからです。
さらにポイント!
都道府県、市町村の現業部門は、労災保険法上では適用除外になっていませんが、「常勤職員」は地方公務員災害補償法の規定で労災保険法の適用が除外されています。
また、都道府県、市町村の現業部門の「非常勤職員」は、地方公務員災害補償法の適用が受けられないので、労災保険法の適用を受けることになります。
さらにさらにポイント!!
労災保険法は「国」の事業は全面的に適用除外ですが、「都道府県、市町村」の事業の場合は、「現業部門の非常勤職員」に労災保険法が適用されます。
労働保険徴収法で「二元適用事業」になるのは、「都道府県及び市町村の行う事業」で、国の行う事業は二元適用事業にはなりませんよね。「国」の行う事業は、そもそも労災保険が成立することがないからです。
② H20年出題 ○
行政執行法人の職員 → 国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用除外
行政執行法人以外の独立行政法人の職員 → 労災保険法適用
【雇用保険法】
③ H22年出題 ×
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、原則として雇用保険法の適用事業です。
④ H27年出題 ○
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業には雇用保険が適用されます。しかし、公務員が離職した場合は、法令、条例、規則等で確実な保障が設けられているため、その諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められ、一定の要件を満たした者は、雇用保険の適用は除外されます。
<適用除外されるもの>
■国又は行政執行法人の事業に雇用される者(非常勤職員で国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものを除く。)
■都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
■市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
ポイント!
「都道府県等」と「市町村等」は、雇用保険の適用除外の「承認を受けること」が要件です。
【健康保険法】
⑤ H14年出題 ×
国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所に含まれます。
⑥ H20年出題 ×
先ほどの問題でも勉強したように、国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所です。そして、国や地方公共団体に使用される者は、健康保険法上適用除外になっていないので、法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となります。
ただし、健康保険法第200条(共済組合に関する特例)で、「共済組合の組合員に対しては、この法律による保険給付は行わない」と規定されているため、実際は健康保険給付の保険給付(保険料の徴収も)は行われません。
<まとめ>
共済組合の組合員(国家公務員、地方公務員)は適用除外されていないため、健康保険法の被保険者となります。ただし、保険給付は行われないし、保険料も徴収されません。
私立学校教職員共済制度の加入者も同じ扱いです。
【厚生年金保険法】
⑦ ×
私立学校教職員共済制度の加入者は厚生年金保険の第4号厚生年金被保険者となります。
◆厚生年金保険の被保険者は4種類
1.2.から4.までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者 → 第1号厚生年金被保険者
2.国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第2号厚生年金被保険者
3.地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第3号厚生年金被保険者
4.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者 → 第4号厚生年金被保険者
社労士受験のあれこれ
書類の保存期間 2年3年4年5年
H28.6.10 金曜日は横断 書類の保存期間
書類の保存期間は2年、3年、4年、5年、それ以外と各法律さまざまです。
でも、覚えておけば得点できます。どんどん覚えましょう。
では、過去問をどうぞ。
① 労働基準法(H22年出題)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
② 労働安全衛生法(H22年出題)
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
③ 労働安全衛生法(H19年出題)
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。
④ 労働安全衛生法(H21年出題)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
⑤ 労災保険法
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管しなければならない。
⑦ 徴収法(H19年出題)
事業主もしくは事業主であった者又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。
⑧ 徴収法(H22年出題)
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は4年である。
⑨ 健康保険法(H22年出題)
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題)
事業主は、厚生年金保険法に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

【解答】
① 労働基準法(H22年出題) ○
ポイント
・ その他労働関係に関する重要な書類 → タイムカード等の記録、残業命令書等が該当する
・ 企画業務型裁量労働制の実施状況にかかる労働者ごとの記録 → 決議の有効期間中+その満了後3年間)
② 労働安全衛生法(H22年出題) ○
・ 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育のうち、保存義務があるのは特別教育のみ。
・ 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議事で重要なものに係る記録も保存期間は3年
③ 労働安全衛生法(H19年出題) ○
④ 労働安全衛生法(H21年出題) ○
・ 保存期間が5年のもの → 健康診断個人票、面接指導の結果の記録(長時間労働、ストレスチェック)
⑤ 労災保険法 ×
2年間ではなく、3年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題) ○
・ 雇用保険に関する書類(雇用保険二事業及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。) → 2年間
・ 被保険者に関する書類 → 4年間
⑦ 徴収法(H19年出題) ×
⑧ 徴収法(H22年出題) ○
・ 労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類 →その完結の日から3年間
・ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 → 4年間
ポイント
・ 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿もおさえておきましょう。
① 労働保険事務等処理委託事業主名簿
② 労働保険料等徴収及び納付簿
③ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
①と②は3年間、③は4年間保存
⑨ 健康保険法(H22年出題) ×
5年間ではなく「2年間」保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題) ×
厚生年金保険法に関する書類 → その完結の日から2年間保存
健康保険法と同じなのでおぼえやすいです。
「H28選択式」/傷病手当金(健康保険法)
H28.6.8 水曜日は選択式対策(傷病手当金)
毎週水曜日は選択式の練習です。
今日は傷病手当金です。改正事項ですので、完璧におぼえましょう。
次のAからHまでに入る語句を選択肢の中から選んでください。
1 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して A を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、 B 日の属する月以前の直近の継続した C 間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、 D ものとする。)の E に相当する金額(その金額に、 F ものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が C に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか G 額の E に相当する金額(その金額に、 F ものとする。)とする。
(1) B 日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、 D ものとする。)
(2) B 日の属する年度の前年度の H における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、 D ものとする。)
<選択肢>
① 100分の60 ② 6月 ③ 少ない ④ 10月31日 ⑤ 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる ⑥ 4日 ⑦ 多い ⑧ 50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる ⑨ 10円未満を切り捨てる ⑩ 傷病手当金の支給を始める ⑪ 1円未満を切り捨てる⑫ 9月30日 ⑬ 3日 ⑭ 12月 ⑮ 9月1日 ⑯ 4月1日 ⑰ 療養を開始した ⑱ 50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる ⑲ 3分の2 ⑳ 資格を取得した ㉑ 7月1日

【解答】
A ⑬ 3日 B ⑩ 傷病手当金の支給を始める C ⑭ 12月 D ⑤ 5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる E ⑲ 3分の2 F ⑱ 50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる G ③ 少ない H ⑫ 9月30日
以前の記事もどうぞ。改正事項の解説です。
社労士受験のあれこれ
【横断】「死亡(葬儀等)」の給付
H28.5.15 労災(葬祭料)・健保(埋葬料)比較
死亡したときの給付として、労災保険には葬祭料(葬祭給付)、健康保険には埋葬料(埋葬費)があります。
健康保険の埋葬料は「埋葬」の費用ですが、労災保険の葬祭料(葬祭給付)は、埋葬だけでなく葬式全般の費用を補償するものなので、労災保険の方が手厚い額になります。
では、比べてみましょう。
【労災保険・葬祭料(葬祭給付)】
| 額 | 受給者 | 時効 |
315,000円+給付基礎日額30日分 (最低保障 給付基礎日額60日分) | 葬祭を行う者 | 2年 |
【健康保険・埋葬料、埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)、家族埋葬料】
| 額 | 受給者 | 時効 | |
| 埋葬料 | 5万円 | 生計を維持していた者であって埋葬を行う者 | 2年 |
| 埋葬費 | 埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用 | 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合 埋葬を行った者 | 2年 |
| 家族埋葬料 | 5万円 (被扶養者が死亡したとき) | 被保険者 | 2年 |

では、過去問を解いてみましょう。
①労災(H12年出題)
葬祭料は、遺族補償給付を受けることができる遺族のうち最先順位の者に支給される。
②労災(H14年出題)
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。
③健保(H25年出題)
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
④健保(H26年出題)
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

【解答】
①労災(H12年出題) ×
葬祭料は、「葬祭を行う者」に支給されます。遺族補償給付を受けることができる遺族とイコールになるとは限りません。
②労災(H14年出題) ×
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効→死亡した日の翌日から進行
葬祭料(葬祭給付)は「葬祭を行った」ことに支給されるのではなく、「死亡」したことに対して支給されるからです。
③健保(H25年出題) ×
親族でも、生計を維持されていなかった場合は「埋葬料」の対象にはなりません。が、実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の対象になります。
④健保(H26年出題) ○
埋葬料→「死亡」について給付。(実際に埋葬しなくても給付される)
埋葬費→「埋葬を行った」ことについて給付。
時効の起算日も、埋葬料は死亡した日の翌日、埋葬費は埋葬した日の翌日となります。
社労士受験のあれこれはコチラ
任意継続被保険者チェック (健保)
H28.5.12 任継のポイントはココ!
任意継続被保険者の条文の空欄を埋めてみてください。
第3条第4項
「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第1項ただし書に該当するに至った(適用除外に該当した)ため被保険者( A を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで B して C 月以上被保険者( A 、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、 D に申し出て、 B して当該 D の被保険者となった者をいう。ただし、 E 又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
第37条
第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から F 日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
過去問も解いてみましょう。(H22年出題)
任意継続被保険者は、①任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき、②死亡したとき、③保険料を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)、④被保険者となったとき、⑤船員保険の被保険者となったとき、⑥後期高齢者医療の被保険者等となったときのいずれかに該当するに至ったときは、その日からその資格を喪失する。

【解答】
A 日雇特例被保険者
B 継続 (「通算」ではありません)
C 2
D 保険者
E 船員保険の被保険者
F 20
ここもポイント!
任意継続被保険者は、適用事業所を退職した、又は適用除外に該当したため資格を喪失した者が対象です。
任意適用事業所の認可の取り消しで資格を喪失した場合は、任意継続被保険者にはなれません。
H22年過去問 ×
①②③に該当したときはその日ではなく「翌日」に資格を喪失します。(④⑤⑥はその日に資格を喪失します。)
④の例 (例えば5月12日付で大阪支社から東京本社に転勤になった場合)
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
| 大阪 | 大阪 | 大阪 喪失 東京 取得 | 東京 | 東京 |
12日に東京の適用事業所で資格を取得し、その日(12日)に大阪の資格を喪失します。
大阪の資格が翌日喪失(13日喪失)になると、12日の資格が大阪と東京で重複してしまうからです。
社労士受験のあれこれはこちら
給付制限 ~健康保険編~
H28.5.5 全部?全部又は一部?一部?(健保・給付制限)
どの科目でも給付制限の問題はしっかり覚えておけば得点源です。
これは慣れるが勝ちです!
今日は健康保険法の給付制限に慣れましょう。
さっそく、問題を解いてみましょう!

① H11年出題
被保険者の死亡の原因が自殺である場合、故意に事故を起こしたものとして、埋葬料は支給されない。
② H23年出題
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
③ オリジナル
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書その他の物件の提出若しくは提示命令に従わず、又は職員の質問若しくは診断に対して答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付は、行わない。
④ H22年出題
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
⑤ H14年出題
保険者は、偽りその他の不正の行為によって保険給付を受け又は受けようした者に対して、保険給付の全部又は一部を6か月間以内の期間において不支給とすることができるとされているが、この給付制限は傷病手当金と出産手当金に限られ、また、偽りその他の不正の行為があった日から1年を経過したときは不支給の対象とはならない。

【解答】
① H11年出題 ×
★故意の犯罪行為又は故意 → 保険給付は行わない(絶対的給付制限)
ポイント
・ 自殺の場合 → 自殺は故意に基づく事故。しかし、埋葬料は支給される。
・ 自殺未遂の場合 → 精神疾患等が原因の場合は、「故意」には当たらないので保険給付は行われる。
② H23年出題 ×
「全部について行わない」ではなく、「全部又は一部を行わないことができる」
★闘争、泥酔、著しい不行跡 →全部又は一部を行わないことができる
給付制限をする・しないなどは保険者が任意に決めることができる。
③ オリジナル ×
「保険給付は行わない(絶対的給付制限)」ではなく、「全部又は一部を行わないことができる」
★命令に従わない場合等 → 全部又は一部を行わないことができる
④ H22年出題 ×
「全部または一部」ではなく「一部」を行わないことができる。
★療養に関する指示に従わない → 一部を行わないことができる
療養の指示に従わず治癒を遅らせた場合等は、保険者は保険給付の一部の給付制限はできるが、全部の給付制限はできない。
⑤ H14年出題 ○
★不正行為 → 傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部の給付制限ができる
偽りその他の不正の行為に対する給付制限のチェックポイント
・ 支給制限の対象は「傷病手当金と出産手当金」
・ 不支給の期間は「6か月間以内」
・ 支給制限の決定ができるのは、偽りその他の不正の行為があった日から1年以内
社労士受験のあれこれはこちら
横断 前納(健保・国年)
H28.4.26 健保(任継)・国年の前納比較
健康保険法の任意継続被保険者と国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者含む)には前納制度があります。
比較してみましょう。空欄を埋めてください。
<健康保険法 ・ 任意継続被保険者の保険料の前納>
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
前納された保険料については、前納に係る期間の A ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の B までに払い込まなければならない。
<国民年金法 ・ 前納>
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の C 際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
A 各月の初日が到来した B 初月の前月末日 C 各月が経過した

ここもチェック!
→ 割引額は年利4%の複利原価法によって計算される(共通)
→ 前納期間の原則
<健保> 4月~9月まで若しくは10月~翌年3月までの6か月間
4月~翌年3月までの12か月間
<国年> 6月又は年単位
・・・・ただし例外あり。過去問でチェック!・・・・・
(健保 H26年出題)
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
<解答> ○
6月又は12月の間に、
・任意継続被保険者の資格を取得した → 6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料を前納できる
(例)4月に資格を取得した場合、5月~9月又は5月~翌年3月までの期間で前納可
・資格を喪失することが明らか → 6月間又は12月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料を前納できる
(例)9月に資格を喪失することが明らかな場合、4月~8月までの期間で前納可
(国年 H26年出題)
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(すでに前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。
<解答> ○
社労士受験のあれこれはこちら
高額療養費でおぼえること
H28.4.14 所得段階別の高額療養費算定基準額
額療養費の計算問題も気になりますが、まずは、所得段階別の高額療養費算定基準額の数字を覚えることが先決です。

ちなみに・・・
「高額療養費算定基準額」と「高額療養費」は似た名称ですので注意してください。
「高額療養費算定基準額」は「自己負担限度額」のこと。自分で負担する額の上限です。
「高額療養費」は窓口負担のうち自己負担限度額を超えた部分。償還払い(一定の場合は現物給付)される額のことです。

では、次の問題を解いてみてください。
① 平成19年出題(改)
70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額が28万円の被保険者又はその被扶養者が、同一の月にそれぞれ1つの保険医療機関から受けた療養に係る一部負担金等のうち、21,000円以上のものを世帯で合算した額が、80,100円+((医療費-267,000円)×1%)を超えたときは、その超過額が高額療養費として支給される(高額療養の多数該当の場合を除く。)。
②
70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、所得区分により設定されている。このうち、標準報酬月額83万円以上で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は、252,600円+(医療費-A円)×B%である。
③ H19年出題
70歳未満の被保険者で、療養の給付を行った月の属する年度分の市区町村民税を免除されている者については、原則として、当該給付に係る一部負担金の限度額(高額療養費算定基準額)は24,600円である。

【解答】
① 平成19年出題 → ○
チェックポイント!
・「年齢」チェック70歳未満
* 70歳以上になると高額療養費算定基準額(自己負担限度額)が別に設定されている。
・ 「標準報酬月額」チェック28万円
* 標準報酬月額が28万円以上53万円未満の区分で答える
・ 「一部負担金等の額が21,000円以上」チェック
* 70歳未満の場合、世帯合算の対象になる一部負担金等は21,000円以上のもののみ。70歳以上の場合は、額を問わず合算される。
② <解答> A 842,000 B 1
Aの額は、252,600円×3分の10で計算できます。
医療費全体が842,000円で、その3割の252,600円が一部負担金という関係です。
※ とすると、一部負担金から医療費全体の額を計算するときは、一部負担金×3分の10で計算できるということです。一部負担金の額から医療費全体の額を計算させる問題もあるので押さえておいてください。
③ H19年出題 → ×
市町村民税が非課税の者の高額療養費算定基準額は原則として35,400円。多数該当に該当する場合は「24,600円」です。
横断 保険料の納付期限
H28.4.10 健・国年・厚年の保険料納付期限
健康保険・国民年金・厚生年金の保険料の納付期限を整理しましょう。
表は、左から「納付義務者」「納付期限」「負担義務」です。
健康保険
| 事業主 | 翌月末日 | (原則)事業主と被保険者が 2分の1ずつ負担 |
任意継続被保険者 | 当月10日 (初回分は保険者が指定する日) *前納制度あり (前納に係る期間の初月の前月末日) | 全額任意継続被保険者が負担 |
国民年金
第1号被保険者 任意加入被保険者 特例任意加入被保険者 | 翌月末日 *前納制度あり | 世帯主・配偶者の一方は 被保険者の保険料を連帯して納付する義務あり |
厚生年金保険
事業主 当然被保険者 任意単独被保険者 高齢任意加入被保険者 (適用事業書・事業主の同意あり) 高齢任意加入被保険者 (適用事業所以外) | 翌月末日 | 事業主と被保険者が2分の1ずつ負担 |
高齢任意加入被保険者 (適用事業所・事業主の同意なし) | 翌月末日 *前納制度 なし | 全額被保険者が負担 |

過去問で練習してみましょう
<健保H13年出題>
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を前納することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。
<健保H15年出題>
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
<国年H18年出題>
毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。
<厚年H21年出題>
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。

【解答】
<健保H13年出題> ×
前納の場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
<健保H15年出題> ○
任意継続被保険者は、保険料の納付は本人の義務。保険料も本人が全額負担する。
<国年H18年出題> ×
任意加入被保険者も保険料の納付期限は翌月末日。
<厚年H21年出題> ×
適用事業所の高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者も、保険料の納付期限は翌月末日。
選択式の練習 ~健康保険法~
H28.4.5 全国健康保険協会の事業計画等
次の文章の空欄を埋めてください。
※「協会」とは全国健康保険協会のことです。
<第7条の27>
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、 A に、厚生労働大臣
B 。これを変更しようとするときも、同様とする。
■選択肢■
①当該事業年度開始後 ②当該事業年度開始前 ③に届け出なければならない
④の認可を受けなければならない

<第7条の28>
協会は、毎事業年度の決算を C に完結しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下「事業報告書等」という。)を添え、監事及び7条の29第2項の規定により選任された D の意見を付けて、 E に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
<第7条の29>
協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、 D の監査を受けなければならない。
2 D は、厚生労働大臣が選任する。
■選択肢■
①翌事業年度の5月31日まで ②事業年度終了後6月以内
③会計監査人 ④理事長 ⑤役員
⑥決算完結後2月以内 ⑦決算完結後1月以内 ⑧決算完結後6月以内
<第7条の30>
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、 F に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
■選択肢■
①政府 ②協会 ③日本年金機構

【解答】
A ②当該事業年度開始前 B ④の認可を受けなければならない
C ①翌事業年度の5月31日まで D ③会計監査人 E ⑥決算完結後2月以内
F ②協会
期限など数字は暗記が必要です。
※「健康保険組合」の規定と混同しないように注意してくださいね。
資格の得喪の確認 ~健康保険法~
H28.4.2 保険者等の「等」がポイント
健康保険法の保険者の定義は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。
が、資格の得喪の確認は「保険者等」が行います。「等」とは??
第39条では次のように規定されています。
(資格の得喪の確認)
第39条 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる。
★協会が管掌する健康保険の被保険者 → 厚生労働大臣
★健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者 → 当該健康保険組合
協会の場合は、厚生年金保険とセットで厚生労働大臣が確認するというイメージです。
厚生労働大臣は保険者ではありませんので、「保険者等」という表現になります。

ちなみに、先ほどの第39条第1項には、例外的に確認が不要とされるパターンがあります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
ただし、第36条第4号(任意適用事業所の適用の取消について厚生労働大臣の認可を受けた)に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
<例外 得喪の確認がいらないパターン>
★任意適用事業所の適用の取消について厚生労働大臣の認可を受けたことによる被保険者の資格の喪失
→ 厚生労働大臣の認可を受けて任意適用事業所ごと脱退するので、重ねて確認はいらないから。
★任意継続被保険者の資格の取得及び喪失
→ 事業主との関係が終了しているので、入社日・退社日でもめることがないから。
過去問を解いてみましょう。
①平成21年出題
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については、保険者等の確認は行われない。
②平成26年出題
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。

【解答】
①平成21年出題 → ×
全国健康保険協会の被保険者の確認は、全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が確認する。後半は正しい。特例退職被保険者も任意継続被保険者と同じ考え方。
②平成26年出題 → ×
任意適用事業所の適用取消で資格を喪失する場合は確認は不要。
ただし、任意適用事業所の適用の認可を受けて資格を取得する場合は確認は必要。
「確認」
H28.3.22 健・厚・雇にはあるが、国、労災にはない
厚生年金保険法では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる」と規定されています。(ただし例外有)
健康保険法、雇用保険法にも「確認」について規定があります。
厚生年金保険法・健康保険法・雇用保険法の共通点は、資格の取得や喪失について、事業主に「届出」が義務づけられている点です。
何月何日に誰が入社して、何月何日に誰が退職したのかをチェックするのが確認です。
一方、「国民年金法」、「労災保険法」には確認の規定はありません。
国民年金法、労災保険法には、資格の得喪について事業主からの届出義務はありませんよね。労災保険は、労働者なら誰でも保護が受けられるので、個人ごとに得喪を届け出る必要はありません。
【改正】健康保険法
H28.3.18 傷病手当金と出産手当金は同額とは限らなくなる
傷病手当金と出産手当金が同時に支給される場合は、「出産手当金が優先」され、出産手当金を支給する期間は、傷病手当金は支給しない、という論点が過去に何回も出題されています。
平成28年3月までは、傷病手当金と出産手当金の単価は同額ですが、平成28年4月からは、「支給を始める日の属する月以前直近12カ月」の平均で計算しますので、支給開始月が違う場合、傷病手当金と出産手当金の単価が異なる可能性があります。
改正の解説はこちらから(3/17の記事)

そのため、傷病手当金と出産手当金の調整方法が以下のように改正されています。
(第103条 出産手当金と傷病手当金との調整)
出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項(傷病手当金の額)の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。
例外が改正のポイント!
原則 → 出産手当金を支給する場合、その期間傷病手当金は支給しない
例外 → 出産手当金が傷病手当金より少ない場合はその差額が支給される
■■傷病手当金 > 出産手当金 → 差額が支給される
【改正】健康保険法 H28年4月~
H28.3.17 傷病手当金・出産手当金の日額の計算式
<平成28年3月までの傷病手当金・出産手当金の日額>
「標準報酬日額(標準報酬月額×30分の1)」×3分の2



<平成28年4月からの傷病手当金・出産手当金の日額>
「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額×30分の1」×3分の2
ポイント 支給開始月以前12カ月の標準報酬月額の平均で計算されるようになった。
支給開始月以前12カ月の標準報酬月額の平均で計算されるようになった。
・・・・・・・・・・
ちなみに、支給開始月以前に12カ月未満の場合は、①と②のどちらか少ない方になります。
① 「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額×30分の1」×3分の2
② 「前年度の9月30日の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額×30分の1」×3分の2
ここもポイント!
・ 「支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間」と「以前」とあるので、支給を始める日の属する月も入れて12カ月間の平均をとります。
例えば、平成28年7月1日に支給開始で12カ月ある場合は、平成27年8月から平成28年7月までの平均額です。
・ 標準賞与額は計算には入りません。
・ 端数処理の方法
「傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額×30分の1」①×3分の2②
→ ①で5円未満切り捨て、5円以上10円未満10円に切り上げ
→ ②で50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満1円に切り上げ
選択式の練習 ~健康保険法~
H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
次の空欄A~Dに入るものを選択肢の中から選んでください。
(基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、 A の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び B 制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して C 検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の D 並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
<選択肢>
① 適正化 ② 少子高齢化 ③ 減少 ④ 2年ごとに ⑤ 介護保険
⑥ 人口減少 ⑦ 超高齢化 ⑧ 5年ごとに ⑨ 後期高齢者医療
⑩ 高齢化 ⑪ 軽減化 ⑫ 随時 ⑬ 国民健康保険 ⑭ 常に
⑮ 労働者災害補償保険 ⑯ 抑制

【解答】
A ⑩ 高齢化 *少子高齢化ではない
B ⑨ 後期高齢者医療
C ⑭ 常に
D ① 適正化
健康保険法改正 (平成28年4月)
H28.2.24 【改正】標準報酬月額の等級区分
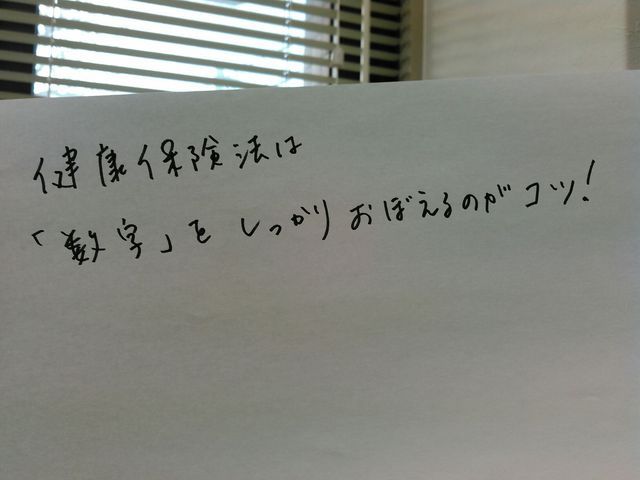
◆平成28年4月より、標準報酬月額の等級区分が、47等級から50等級に改正されます。
最高等級は第50級(標準報酬月額139万円)に引き上げられます。
◆等級区分の改定のルールも改正されます。次の空欄をチェックしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が A を下回ってはならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】 A 100分の0.5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆標準賞与額の上限も改正されます。
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が B 円を超えることとなる場合には、当該累計額が B 円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】 B 573万
改正点は、その年の本試験に出題される!と思って覚えてください。改正点が出たらラッキーです。
健康保険法改正 (平成28年4月)
H28.2.18 【改正】一般保険料率の上限の引き上げ
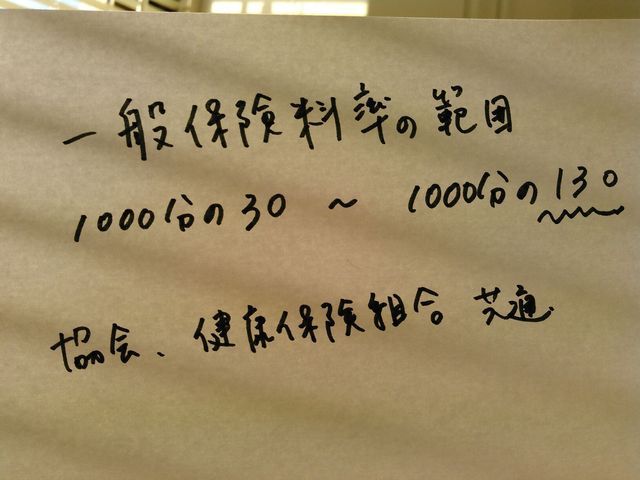
次の空欄を埋めてください。
<健康保険法第160条>
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1000分の A から1000分の B までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。
2 前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】A 30 B 130
<改正点> 一般保険料率の上限が1000分の120から1000分の130に引き上げられます。(平成28年4月より)
<ここもポイント!>
健康保険組合の一般保険料率の上限も同じく改正され、1000分の30から1000分の130までの範囲内で決定されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに、
平成28年2月10日に平成28年度の都道府県単位保険料率が発表されています。
一番高いのは佐賀県の1000分の103.3、一番低いのは新潟県の1000分の97.9です。(覚えなくていいです。参考まで)
H28.2.10 強制適用事業所(健康保険と厚生年金の違い)
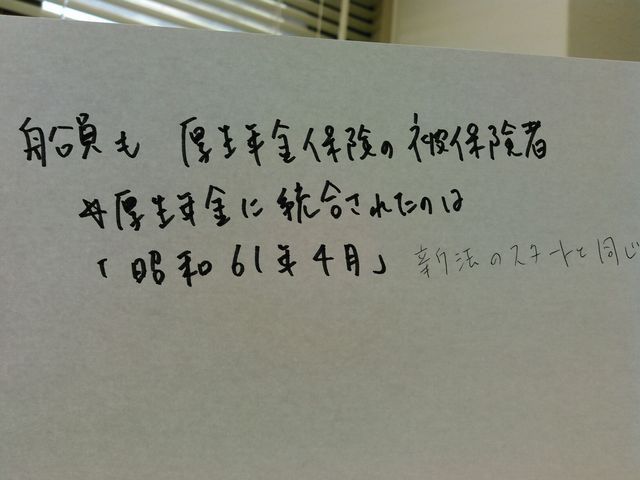
【健康保険法 強制適用事業所】
1 法定16業種で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
2 国・地方公共団体・法人の事業所で常時従業員を使用するもの
【厚生年金保険法 強制適用事業所】
1 法定16業種で常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所
2 国・地方公共団体・法人の事業所で常時従業員を使用するもの
3 船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されるものが乗り組む船舶
■厚生年金は「船舶」が強制適用■
厚生年金の場合、船員が乗り組む「船舶」が強制適用事業所になることがポイントです。
■船員法第1条の船員は、船員保険法の被保険者■
船員法第1条に規定する船員は、「船員保険法」の対象です。
船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行います。
アンダーラインの部分に注目してください。船員法第1条の船員は職務外の傷病等については船員保険法で保障されています。そのため健康保険法は適用除外となります。
一方の年金について。公的年金の歴史で一番古い制度は、実は船員保険法です。かつては、船員は船員保険法で老後の年金などが保障されていました。が、船員の数の減少などにより昭和61年4月に船員保険法から年金部門がなくなり、年金部門は厚生年金保険法に統合されました。
そのため、現在の船員保険法には年金部門がありません。船員は会社員と同様に厚生年金保険に加入することになっています。船員法第1条に規定する船員が乗り組む船舶が厚生年金の強制適用事業所となっているのはそのためです。
ポイント
船員 → 職務外の疾病等は「船員保険法」、老齢・障害・死亡は「厚生年金保険法」
ちなみに・・・
船員保険法には、「労働者災害補償保険法と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行う」という目的もありますが、この点はまた別の機会にお話しします。
H28.1.27 賃金・報酬、賞与
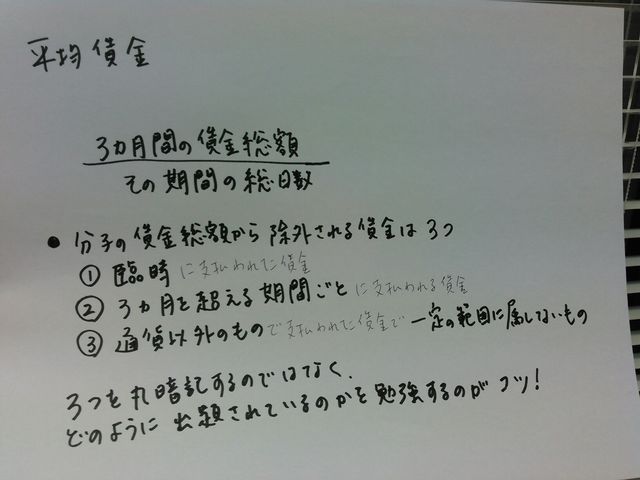
■労働の対償→賃金・報酬、賞与
「労働の対償として受けるもの」は一般的に言うと給料ですが、受験勉強では、まず法律ごとの呼び方を押さえることから始めます。
・労働基準法、雇用保険法、労働保険徴収法では、「賃金」といいます。
*例えば、雇用保険法の基本手当の日額や、徴収法の労働保険料は「賃金」を基に計算します。
・健康保険法、厚生年金保険法では、「報酬、賞与」といいます。
*例えば、厚生年金保険法では会社員として支払う厚生年金保険料や将来受けとる年金額は、「報酬、賞与」を基に計算します。
■ポイント
・「賃金」、「報酬、賞与」は「労働の対償」として支払われるもの
・しかし、保険料や給付額の計算に賃金の全てを算入するわけではない
*例えば、労働基準法の平均賃金は賃金をもとに計算しますが、賃金を全て算入するのではなく、夏・冬のボーナスなど平均賃金の計算から除外される賃金があります。
どの科目でも現物給与、臨時に支払われるものの扱いなどは頻出事項です。過去問で練習して慣れていきましょう。
H28.1.25 日雇労働者の定義(雇用保険法・健康保険法)
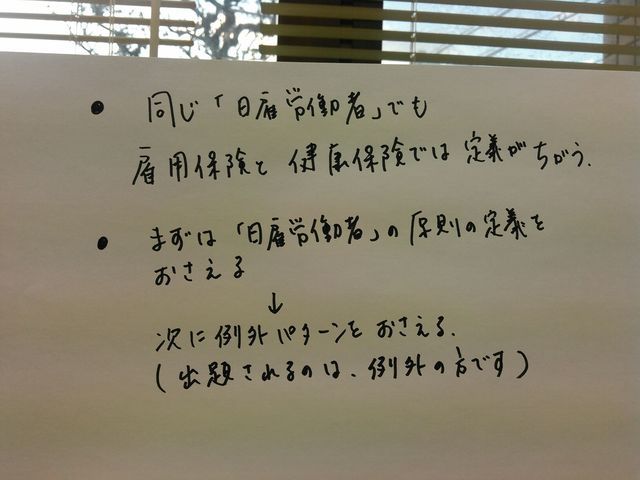
雇用保険法、健康保険法には「日雇労働者」という区分があり、「印紙保険料」など一般の労働者とは別の扱いが規定されています。
しかし、同じ「日雇労働者」という用語を使っていますが、雇用保険法と健康保険法では定義が違うのがやっかいなところです。
まずは、それぞれの法律の「日雇労働者」の定義の違いをおさえてみましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(雇用保険法・日雇労働者)
日雇労働者とは、次のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(次条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。
1 A 雇用される者
2 B 以内の期間を定めて雇用される者
(健康保険法・日雇労働者)
この法律において「日雇労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
1 C に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては1月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ D 雇い入れられる者
ロ E 以内の期間を定めて使用される者
2 F 業務に使用される者(継続して G を超えて使用されるべき場合を除く。)
3 H 事業の事業所に使用される者(継続して I を超えて使用されるべき場合を除く。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解答】
A日々 B30日 C臨時 D日々 E2月 F季節的 G4月 H臨時的 I6月
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【さらにアドバイス】
日雇労働者の定義の原則をおさえたら、例外もきちんとチェックしましょう。
条文で「除く」となっている部分が例外です。例外規定の方がよく出題されますが、まずは原則をおさえてから「例外」にいきましょう。
「例外規定」の方は、過去問を解いてみると、ポイントがよく分かりますので、また日を改めて、解説しますね。
H28.1.18 健康保険法「保険者」
「健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
保険者とは保険の運営主体のこと。保険料の徴収や保険給付を行います。健康保険の保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合の2つがあります。
が、カッコ内で(日雇特例被保険者の保険を除く。)とありますよね。
日雇特例被保険者の保険の保険者は、「全国健康保険協会」一つです。健康保険組合はありません。
過去に繰り返し出題されているポイントです。
例えば、平成17年の問題はこんな感じです。
「健康保険の保険者には全国健康保険協会と健康保険組合があるが、日雇特例被保険者の保険の保険者は全国健康保険協会のみである。」
答えはもちろん○です。
H28.1.13 年齢
60歳、65歳、70歳、75歳。法律によって年齢の基準が違うので頭の中がごちゃごちゃしませんか?
次の空欄を埋めて整理してみてください。
■雇用保険法
<高年齢継続被保険者>
同一の事業主の適用事業に ① 歳に達した日の前日から引き続いて ② 歳に達した日以後の日において雇用されているもの
■徴収法
<雇用保険料の免除の対象になる高年齢労働者>
保険年度の初日に ③ 歳以上の労働者
■健康保険法
<一部負担金>
1 ④ 歳に達する日の属する月以前 → 100分の30
2 ⑤ 歳に達する日の属する月の翌月以後 (3の場合を除く。)
→100分の20
3 ⑥ 歳に達する日の属する月の翌月以後の一定以上所得者
→ 100分の30
■厚生年金保険法
<被保険者>
適用事業所に使用される ⑦ 歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
■高齢者の医療の確保に関する法律
<後期高齢者医療の被保険者>
1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑧ 歳以上の者
2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑨ 歳以上 ⑩ 歳未満の者で、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
■介護保険法
<介護保険の被保険者>
・第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑪ 歳以上の者
・第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑫ 歳以上 ⑬ 歳未満の医療保険加入者
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解答】
①65 ②65 ③64 ④70 ⑤70 ⑥70 ⑦70 ⑧75 ⑨65 ⑩75 ⑪65 ⑫40 ⑬65
