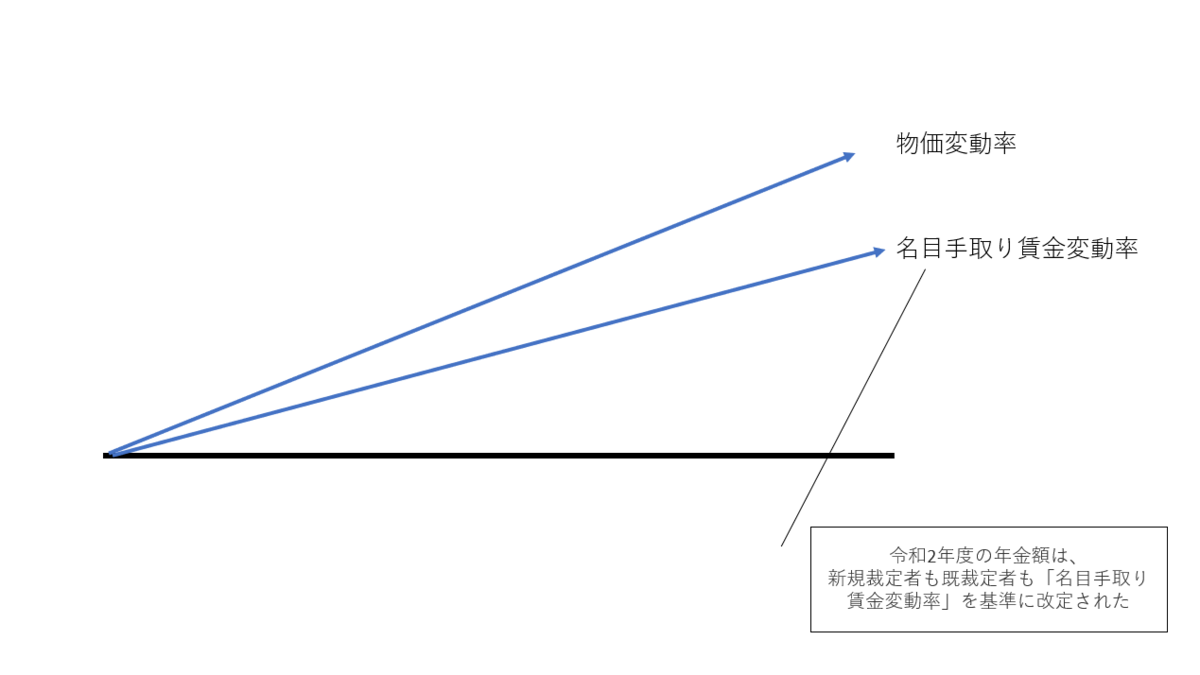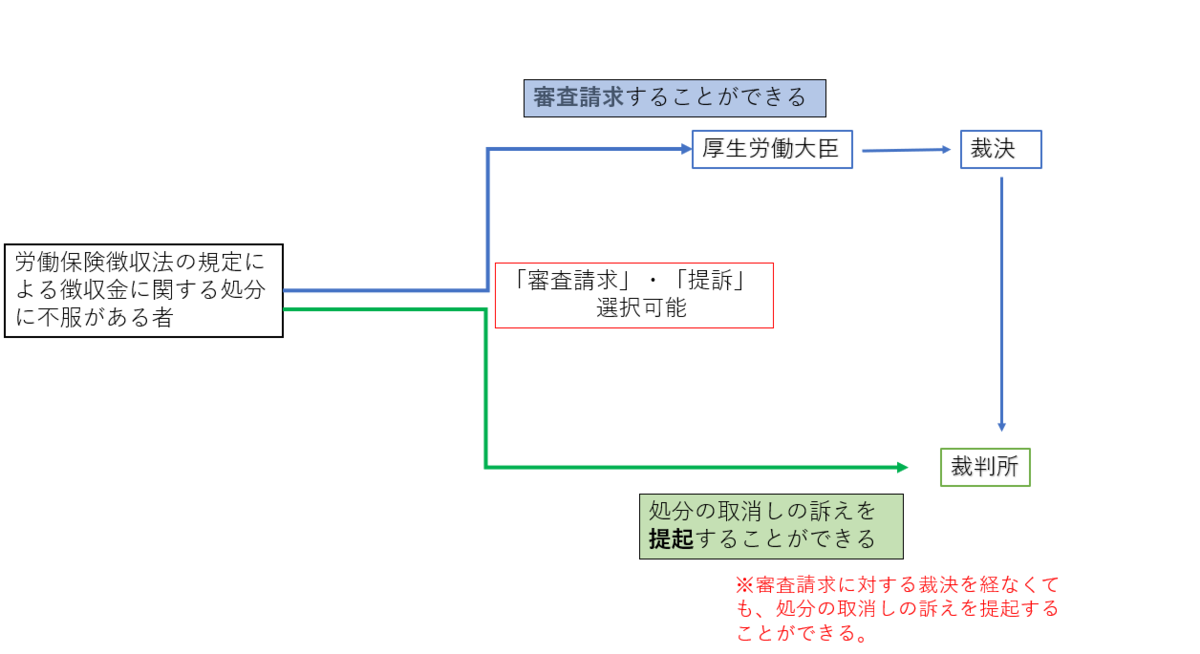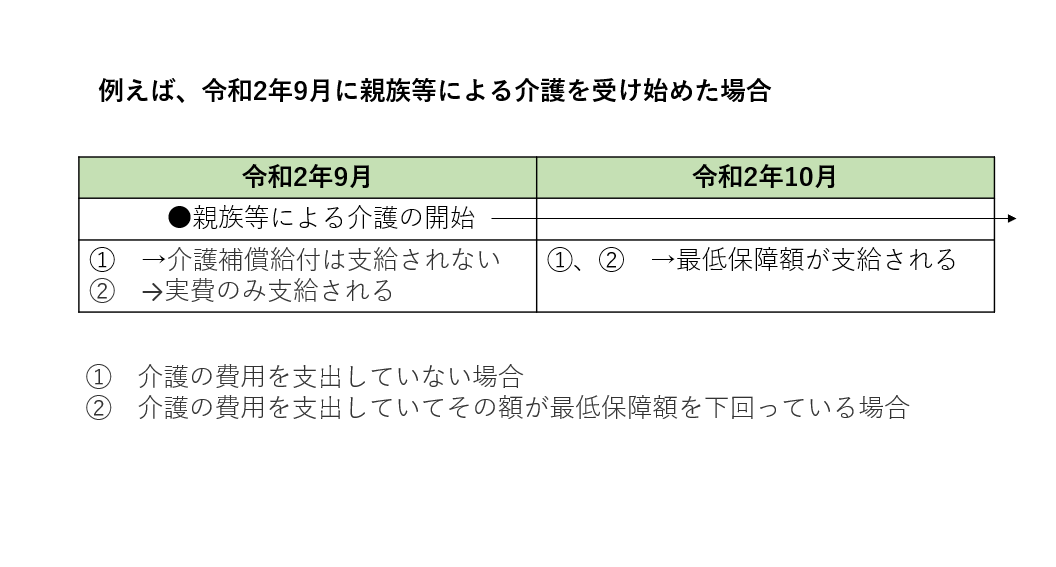合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和3年度版
毎日コツコツ。
社労士受験のあれこれ (過去記事)
このページは令和3年度版です。
お疲れ様でした。
R3-364
R3.8.22 本日はお疲れさまでした。
コロナ禍。日常生活の変化に対応しなければならないなか、受験勉強を続けること、とても大変だったと思います。
本当にお疲れさまでした。今日はのんびり過ごしてください。
また、明日。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎年恒例/第1条チェック!(第3弾)
R3-363
R3.8.21 第1条チェック・介護保険、確定拠出年金、確定給付企業年金
絶対合格! 実力を発揮できますように! |
今日は毎年恒例の第1条チェックの第3弾です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
【介護保険法】
第1条 (目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< A >を保持し、その有する能力に応じ < B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< D >を図ることを目的とする。
【確定拠出年金法】
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が< E >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る < F >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
第1条 (目的)
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< G >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< H >を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【解答】
【介護保険法】
A 尊厳
B 自立した日常生活
C 共同連帯
D 福祉の増進
【確定拠出年金法】
E 自己の責任
F 自主的な努力
【確定給付企業年金法】
G 給付の内容
H 自主的な努力
ワンポイント!
介護保険法 平成12年4月施行
確定拠出年金法 平成13年10月施行
確定給付企業年金法 平成14年4月施行
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎年恒例/第1条チェック!(第2弾)
R3-362
R3.8.20 第1条チェック・健保、国年、厚年、社労士法
今日は毎年恒例の第1条チェックの第2弾です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
【健康保険法】
第1条 (目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
第1条 (国民年金制度の目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを< C >によって防止し、もって< D >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
第1条 (目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< E >の生活の安定と< F >に寄与することを目的とする。
【社会保険労務士法】
第1条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< G >と労働者等の< H >に資することを目的とする。

【解答】
【健康保険法】
A 業務災害
B 福祉の向上
【国民年金法】
C 国民の共同連帯
D 健全な国民生活
【厚生年金保険法】
E 遺族
F 福祉の向上
【社会保険労務士法】
G 健全な発達
H 福祉の向上
こちらもどうぞ!
①健康保険法
第2条 (基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< A >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< B >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
②国民年金法<H19年出題アレンジ>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年< C >月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
③厚生年金保険法<R1年社一出題アレンジ>
被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
→ この改正の施行日は? <平成〇〇年〇〇月〇日>
④社会保険労務士法
第1条の2 (社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する< D >に精通して、 < E >で、誠実にその業務を行わなければならない。

【解答】
①健康保険法
A 後期高齢者医療制度
B 常に
(健康保険法第2条)
②国民年金法
C 11
無拠出制の福祉年金の開始は昭和34年11月からです。
(国民年金法附則第1条)
③厚生年金保険法
平成27年10月1日
被用者年金一元化は平成27年10月1日です。
④社会保険労務士法
D 法令及び実務
E 公正な立場
(社会保険労務士法第1条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
毎年恒例/第1条チェック!(第1弾)
R3-361
R3.8.19 第1条チェック・労基、安衛、雇用、労災、労契、労組
今日は毎年恒例の第1条チェックの第1弾です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
【労働基準法】
第1条 労働条件の原則
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、< B >。
第2条 労働条件の決定
① 労働条件は、労働者と使用者が、< C >において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その< D >しなければならない。
【労働安全衛生法】
第1条 目的
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< E >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< F >を確保するとともに、 < G >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< H >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< H >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >の確保等を図り、もって労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
第1条 目的
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< K >の休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< L >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。
【労働契約法】
第1条 目的
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< N >により成立し、又は変更されるという< N >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< O >の安定に資することを目的とする。
【労働組合法】
第1条 目的
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< P >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための< Q >をすること及びその手続を助成することを目的とする。

【解答】
【労働基準法】
A 人たるに値する生活
B その向上を図るように努めなければならない
C 対等の立場
D 義務を履行
【労働安全衛生法】
E 自主的活動の促進
F 安全と健康
G 快適な職場環境の形成
【労働者災害補償保険法】
H 複数事業労働者
Ⅰ 安全及び衛生
J 福祉の増進
【雇用保険法】
k 子を養育するため
L 生活及び雇用の安定
M 福祉の増進
【労働契約法】
N 合意
O 個別の労働関係
【労働組合法】
P 団体行動
Q 団体交渉
こちらもどうぞ!
①労基法(H13年出題)
労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
②安衛法(H29年出題>
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。
③労災保険法
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< B >を行うことができる。
④雇用保険法
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< C >を行うほか、< D >及び能力開発事業を行うことができる。

【解答】
①労基法(H13年出題) 〇
労働基準法第1条(労働条件の原則)、第2条(労働条件の決定)には罰則の定めはありません。
②安衛法(H29年出題> 〇
『労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にある』の部分がポイントです。
(昭和47.9.18 発基第91号)
③労災保険法
A 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因
B 社会復帰促進等事業
(労災保険法第2条の2)
④雇用保険法
C 育児休業給付
D 雇用安定事業
(雇用保険法第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和2年版厚生労働白書より
R3-360
R3.8.18 「地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度」より
今日は「令和2年版厚生労働白書」からの問題です。
第7章「国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現」の第4節「地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度」から抜粋しています。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
( 介護保険制度の現状と目指す姿)
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月には149万人であったサービス利用者数は、2019(平成31)年4月には< A > になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してきている。
高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< B >人に 1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「< C >」の実現を目指している。「< C >」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護保険料は、現在約5,900円になっており、2025年には約< D >円になると見込まれている。
(医療・介護の連携の推進)
地域包括ケア強化法において、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設を
「< E >」として 2018(平成 30)年4月に創設した。2020(令和2)年3月末現在、 < E >は 343施設(21,738療養床)となっている。

【解答】
A 487万人と、約3.3倍
B 5.5
C 地域包括ケアシステム
D 7,200
E 介護医療院
こちらもどうぞ!
第2条
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 1の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、< A >との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 1の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の< B >に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 1の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その< C >において、その有する能力に応じ< D >を営むことができるように配慮されなければならない。

【解答】
A 医療
B 選択
C 居宅
D 自立した日常生活
(介護保険法第2条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労一 中高年者縦断調査より
R3-359
R3.8.17 第15回中高年者縦断調査(厚生労働省)より
今日は「第15回 中高年者縦断調査(厚生労働省)」をみていきましょう。
・調査の目的
この調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して、調査し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的としています。
平成17年度を初年として実施しています。
・調査の対象
平成17年10月末時点で 50~59 歳であった全国の男女を対象とし、そのうち、第 13回調査又は第14回調査において協力を得られた者を調査客体としています。第15回調査における対象者の年齢は、64~73 歳です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
(就業状況の変化)
第1回調査から 14年間の就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は、第1回38.5%から第15回4.1%と減少している。
一方、「パート・アルバイト」は、< A >。
【選択肢】 ① ほぼ横ばいの状況である ② 10ポイント以上減少した ③ 10ポイント以上増加した |
(就業希望と求職の状況)
第15回調査で「仕事をしていない」者について、就業希望の有無をみると、「仕事をしたい」者の割合は16.3%、「仕事をしたくない」者は80.9%となっている。また、「仕事をしたい」が求職活動を「何もしていない」者の割合は 12.2%となっている。
求職活動をしていない理由別にみると、「< B >」の 19.3%が最も高く、次いで「希望する仕事がありそうにない」の 17.4%となっている。
【選択肢】 ① 知識、能力に自信がない ② 病気・けがのため |
(これからの生活設計)
第15回調査時のこれからの仕事の希望をみると、「仕事をしたい」は「65~69 歳の仕事」では 56.4%、「70 歳以降の仕事」では 39.0%となっている。
これからの仕事について、「仕事をしたい」理由では「< C >」と答えた者が 51.2%と最も高く、次いで「条件が合う仕事があるならしたい」の 19.1%となっている。
【選択肢】 ① 生活費を稼ぐため、仕事をしなければならない ② 企業への貢献や生きがいのため、 ぜひ仕事をしたい |

【解答】
(就業状況の変化)
A ① ほぼ横ばいの状況である
★「パート・アルバイト」は、第1回16.8%から第15回16.9%と、ほぼ横ばいの状況である。
(就業希望と求職の状況)
B ② 病気・けがのため
(これからの生活設計)
C ① 生活費を稼ぐため、仕事をしなければならない
★「仕事をしたい」者が希望している仕事のかたちは、「65~69 歳の仕事」、「70 歳以降の仕事」のいずれの年齢でも、「雇われて働く(パートタイム)」が 24.9%、14.7%と最も高く、次いで「自営業主」が 10.5%、9.2%となっている。
参照 → 厚生労働省「第 15 回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生年金保険法 選択対策
R3-358
R3.8.16 厚生年金保険法 選択問題(老齢厚生年金の額)
今日は厚生年金保険の選択対策。テーマは「老齢厚生年金の額」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
<H23年選択式 出題> ※改正による修正あり
1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 < A >については、毎年度、厚生年金保険法第43条の2第1項第1号に掲げる率(以下「< C >」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「< D >」という。)を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
3 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の< E >の年の4月1日の属する年度以後において適用される< A >(「基準年度以後< A >」という。)の改定については、上記2の規定にかかわらず、< C >(< C >が < D >を上回るときは、< D >)を基準とする。

【解答】
A 再評価率
B 5.481
C 物価変動率
D 名目手取り賃金変動率
E 3年後
(法第43条、第43条の2、第43条の3)
ポイント!
再評価率の改定基準
・新規裁定者 → 名目手取り賃金変動率を基準とする
・既裁定者 → 物価変動率を基準とする(※物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準とする)
こちらもどうぞ!
<H18年選択式 出題>
平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< F >(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

【解答】
F 再評価率
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法 選択対策
R3-357
R3.8.15 国民年金法 選択問題(老齢基礎年金の繰上げと繰下げ)
今日は国民年金の選択対策。テーマは「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」です!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
<H21年選択式 出題> ※改正による修正あり
1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が、< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】
A 60歳以上65歳未満
B 任意加入被保険者
C 65歳
D 付加年金
E 老齢
(法附則第9条の2、法第28条)
では、過去問もどうぞ!
①<H23年出題>
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
②<H26年出題>
任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。
③<H23年出題>
繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】
①<H23年出題> ×
繰上げ支給は、「国民年金法の附則において当分の間の措置」として規定されています。一方、繰下げ支給は、附則ではなく本則で規定されています。
繰上げ → 法附則9条の2
繰下げ → 法第28条
②<H26年出題> 〇
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求はできません。
(法附則第9条の2)
③<H23年出題> ×
「支給停止」が誤り。寡婦年金の受給権は「消滅」します。
寡婦年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰上げの請求をして、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
(法附則第9条の2第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健康保険法 選択対策
R3-356
R3.8.14 健康保険法 選択問題(保険料率)
今日は健康保険の選択対策。テーマは保険料率です!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
第160条(保険料率)
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、 < A >までの範囲内において、< B >を単位として< C >が決定するものとする。
5 全国健康保険協会は、< D >ごとに、翌事業年度以降の< E >年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
6 全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、 < F >の議を経なければならない。
10 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
11 厚生労働大臣は、協会が第10項の期間内に申請をしないときは、< G >の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

【解答】
A 1,000分の30から1,000分の130
B 支部被保険者
※支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
C 全国健康保険協会
D 2年
E 5
F 運営委員会
G 社会保障審議会
(健康保険法第160条第1項、5項、6項、10項、11項)
では、過去問もどうぞ!
①<H26年出題>
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
②<H29年出題>
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

【解答】
①<H26年出題> 〇
「1,000分の30から1,000分の130」までの範囲内、「支部被保険者を単位」、「協会が決定」がポイントです。
(法第160条第1項)
なお、第2項では、「支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する」と規定されています。
②<H29年出題> 〇
「介護保険第2号被保険者」、「保険者が定める」の部分がポイントです。
(法第160条第16項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法 選択対策
R3-355
R3.8.13 雇用保険法 選択問題(特定受給資格者の定義)
今日は雇用保険の選択対策。特定受給資格者の定義をチェックしましょう。
「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。
一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職)
二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職)
今日は、ニ(解雇等による離職)を穴埋めでチェックしていきます。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
法第23条第2項第2号(解雇等による離職)の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 解雇(< A >によるものを除く。)
二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が< B >と著しく相違したこと。
三 賃金(退職手当を除く。)の額を< C >で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかったこと。
四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなったこと。
イ 離職の日の属する月以後6月のうちいずれかの月に支払われる賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなったこと。
ロ 離職の日の属する月の6月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前6月のうちいずれかの月の賃金の額に100分の85を乗じて得た額を下回ったこと。
五 次のいずれかに該当することとなったこと。
イ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< D >か月以上の期間において労働基準法に規定する限度時間に相当する時間数を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり< E >時間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した< F >か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと。
ニ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったこと。
ホ 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として< G >をしたこと。
六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと。
七 期間の定めのある労働契約の更新により< H >年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
七の二 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが < I >された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から< J >が著しく害されるような言動を受けたこと。
九 事業主から退職するよう< K >を受けたこと。
十 事業所において< L >事由により行われた休業が引き続き< M >か月以上となったこと。
十一 事業所の業務が法令に違反したこと。

【解答】
A 自己の責めに帰すべき重大な理由
B 事実
C 3
D 3
E 100
F 2
G 不利益な取扱い
H 3
I 明示
J 就業環境
K 勧奨
L 使用者の責めに帰すべき
M 3
(雇用保険法施行規則第36条)
では、過去問もどうぞ!
<H30年出題>
次のうち、特定受給資格者に該当する者として誤っているものはどれか?
A 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者。
B 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者。
C 離職の日の属する月の前6月のいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
D 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者。
E 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者。

【解答】
A 〇 施行規則第36条5号ホに該当するので、特定受給資格者に該当します。
B 〇 施行規則第36条6号に該当するので、特定受給資格者に該当します。
C × 施行規則第36条5号ロ、ハに該当しないので、特定時給資格者になりません。
ロ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり100時 間以上、時間外労働及び休日労働が行われたこと
ハ 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し一月当たり80 時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたこと
D 〇 施行規則第35条2号に該当するので、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。
E 〇 施行規則第36条7号に該当するので、特定受給資格者に該当します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法 選択対策
R3-354
R3.8.12 労災保険法 選択問題~改正点など
今日は、労災保険法の選択対策です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① 総則
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< B >に寄与することを目的とする。
第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、 < A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< C >を行うことができる。
問題②
第7条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< D >」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。)
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付
問題③
法第20条の3
複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
労災保険法施行規則第18条の3の6(複数業務要因災害による疾病の範囲)
法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他< E >ことの明らかな疾病とする。

【解答】
問題①
A 複数事業労働者
B 福祉の増進
C 社会復帰促進等事業
(法第1条、第2条の2)
問題②
D 複数業務要因災害
(法第7条)
★ポイント!労災保険の目的の改正
・今般の改正により、労災保険の目的として、「複数事業労働者」の二以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)につ いても保険給付を行うことが加えられた。
・労災法第2条の2において、第1条の目的を達成するため、保険給付を行う場合について複数業務要因災害が加えられた。
・複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない。そのため、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わない。
参照 → R2.8.21 基発0821第1号
問題③
E 二以上の事業の業務を要因とする
(則第18条の3の6)
★ポイント!複数業務要因災害の範囲
複数業務要因災害による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている。
参照 → R2.8.21 基発0821第1号
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働安全衛生法 選択対策
R3-353
R3.8.11 安衛法選択問題~過去問より
今日は、安衛法の選択対策です。過去問をどうぞ!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① H19年出題
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。
問題② H20年出題
労働者の健康保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。
また、事業者が講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。
問題③ H21年出題(改正による修正あり)
労働安全衛生法では、常時50人以上の労働者を使用する事業場の事業者は、産業医を選任しなければならないとされ、同法第13条第5項では、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な< D >をすることができる」と定められている。また、労働安全衛生規則第15条第1項では、「産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、一定の情報の提供を受けている場合であって、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、< E >又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている。

【解答】
問題①
A 一の場所
(安衛法第15条)
問題②
B 健康教育及び健康相談
C 利用
(安衛法第69条)
問題③
D 勧告
E 作業方法
(安衛法第13条、則第15条)
こちらもどうぞ!
問題④ (法第13条)
第2項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
第3項 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する< F >に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
第4項 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の< G >に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
第5項 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を< H >しなければならない。
問題⑤ (則第15条)
(産業医の定期巡視)
産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であって、事業者の< I >を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
二 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であって、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

【解答】
問題④ 法第13条
F 知識
G 労働時間
H 尊重
問題⑤ 則第15条
Ⅰ 同意
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法 選択対策
R3-352
R3.8.10 労基法選択問題~過去問より
今日は、労働基準法の選択対策です。過去問をどうぞ!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① H20年出題
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法[・・・・・]32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔・・・・・〕」というのが最高裁判所の判例である。
問題② H23年出題
「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を< B >として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
問題③ H22年出題
「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間[当該期間]の満了により右雇用契約[当該雇用契約]が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間[当該期間]は契約の存続期間ではなく、< C >であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
問題①
A 合理的な
参照→最高一小H3.11.28
問題②
B 解除条件
参照→最高二小S48.3.2
問題③
C 試用期間
参照→最高三小H2.6.5
関連過去問もどうぞ!
④<H27年出題>
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。
⑤<H22年出題>
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
④<H27年出題> ×
当該就業規則の規定の内容が「合理的なもの」である限り、それが具体的労働契約の内容をなす。なので、その就業規則の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、「労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」ことになります。
参照→最高一小H3.11.28
⑤<H22年出題> ×
年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はない、とされています。
参照→最高二小S48.3.2
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和2年版男女共同参画白書(内閣府)より
R3-351
R3.8.9 令和2年版男女共同参画白書(内閣府)より
今日は、「令和2年男女共同参画白書(内閣府)」を参照しています。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
(女性の年齢階級別労働力率(M字カーブ)の状況)
女性の年齢階級別労働力率について昭和54(1979)年からの変化を見ると、現在も「M字カーブ」を描いているものの、そのカーブは以前に比べて浅くなっている。
M字の底となる年齢階級も上昇している。昭和54(1979)年は< A >及び30~34歳がM字の底となっていたが、< A >の労働力率は次第に上がり、令和元(2019)年では85.1%と、年齢階級別で最も高くなっている。なお、令和元(2019)年には30~34歳及び35~39歳がM字の底となっている。
【選択肢】 ①20~24歳 ②25~29歳 |
問題②
(女性の就業希望者)
総務省「労働力調査(詳細集計)」によると、令和元(2019)年における女性の非労働力人口2,657万人のうち、231万人が就業を希望している。就業を希望しているにも関わらず、現在求職していない理由としては、「< B >」が最も多い。
【選択肢】 ①出産・育児のため ②適当な仕事がありそうにない |
問題③
(所定内給与における男女間格差等の推移)
一般労働者における男女の所定内給与額の格差は,長期的に見ると< C >傾向にあるが、令和元(2019)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は< D >と、前年に比べ1ポイント縮小した。
【選択肢】 ①拡大 ②縮小 ③74.3 ④89.0 |

【解答】
問題①
A ②25~29歳
★昭和54(1979)年のM字の底
25~29歳(48.2%)及び30~34歳(47.5%)
★令和元(2019)年
25~29歳の労働力率は85.1%、年齢階級別で最も高くなっている
★令和元(2019)年のM字の底
30~34歳(77.5%)及び35~39歳(76.7%)
問題②
B ①出産・育児のため
★「出産・育児のため」が最も多く、31.1%となっている
問題③
C ②縮小
D ③74.3
★一般労働者における男女の所定内給与額の格差は、長期的に見ると縮小傾向
★令和元(2019)年の男性一般労働者の給与水準を100としたときの女性一般労働者の給与水準は74.3。
参照→ 男女共同参画白書 令和2年版 第2章第1節 就業をめぐる状況
(内閣府ホームページより)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和2年労働災害発生状況の分析等より
R3-350
R3.8.8 令和2年労働災害発生状況の分析等より
今日は、「令和2年労働災害発生状況の分析等」(厚生労働省)がテーマです。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
(死亡者数)
令和2年の労働災害による死亡者数は 802 人と3年連続で< A >となった。
【選択肢】 ①過去最少 ②過去最多 |
問題②
(死傷者数 事故の型別)
事故の型別では、特に死傷者数の最も多い事故の型である「< B >」、「動作の反動・無理な動作」で増加した。< B >災害は、全体の23.6%を占め、そのうちの 60.8%が休業1か月以上となった。
【選択肢】 ①交通事故( 道路 ) ②転倒 |
問題③
(死傷者数 年齢別)
年齢別では、20歳未満を除く全ての年代で増加し、全死傷者数の約4分の1を占める「< C >」では 34,928 人となった。
【選択肢】 ①60歳~ ②50歳~59歳 |
問題④
(業種別の労働災害発生状況 製造業の労働災害発生状況)
製造業における死傷災害(休業4日以上)の事故の型別では、< D >が最も多く、「転倒」がそれに続いている。
【選択肢】 ①はさまれ・巻き込まれ ②墜落・転落 |

【解答】
問題①
A ①過去最少
★令和2年の労働災害による死亡者数は802人(前年比43 人・5.1%減、平成29年比 176人・18.0%減)で3年連続で過去最少。
問題②
B ②転倒
★特に死傷者数の最も多い事故の型である「転倒」(前年比 943 人・3.1%増、平成 29 年比 2,619 人・9.3%増)、「動作の反動・無理な動作」(同 1,412人・8.0%増・同 2,944人 18.2%増)で増加。
★「死傷者数」→労働災害による休業4日以上の死傷者数
問題③
C ①60歳~
★年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占めている。
問題④
D ①はさまれ・巻き込まれ
★製造業の労働災害発生状況 長期的には減少傾向であるものの、依然として死亡者数、死傷者数ともに機械等への「はさまれ・巻き込まれ」が最多。
参照→ 令和2年の労働災害発生状況を公表(厚生労働省ホームページ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況より その2
R3-349
R3.8.7 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査よりその2
今日も昨日に引き続き、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(厚生労働省)がテーマです。
この調査には、「事業所調査」と「個人調査」があり、昨日は「事業所調査」、今日は「個人調査」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
(正社員以外の労働者の仕事に対する意識)
・現在の就業形態を選んだ理由
就業形態別にみると、「契約社員(専門職)」では「< A >」が 49.9% と最も高く、次いで「正社員として働ける会社がなかったから」が 23.9%、「嘱託社員(再雇用者))」では「< A >」が 45.6%と最も高く、次いで「家計の補助、学費等を得たいから」が 24.6%、「パートタイム労働者」では「< B >」が 45.4%と最も高く、次いで「家庭の事情(家事・育児・介護等)と両立しやすいから」が 36.7%、「臨時労働者」では「< B >」が 39.5%と最も高く、次いで「専門的な資格・技能を活かせるから」が 29.5%、「派遣労働者」では「< C >」が 31.1%と最も高く、次いで「自分の都合のよい時間に働けるから」が 20.9% となっている。
【選択肢】 ①自分の都合のよい時間に働けるから ②専門的な資格・技能を活かせるから ③正社員として働ける会社がなかったから |
問題②
(現在の職場での満足度)
仕事の内容・やりがいや賃金など 11 の項目と職業生活全体について、「満足」又は「やや満足」とする労働者割合から「不満」又は「やや不満」とする労働者割合を差し引いた満足度D.I.を正社員と正社員以外の労働者で比較してみると、「< D >」(正社員 61.4 ポイント、正社員以外の労働者 33.1 ポイント)、「< E >」(正社員 58.8 ポイント、正社員以外の労働者 57.5 ポ イント)、「正社員以外の労働者との人間関係、コミュニケーション」(同 50.5 ポイント、同 50.7 ポ イント)となっている。
「< D >」は、正社員の満足度D.I.が最も高いが、正社員以外の労働者では低い。
「賃金」(同 21.7 ポイント、同 6.7 ポイント)、「教育訓練・能力開発のあり方」(同 19.1 ポイント、同 4.2 ポイント)、「人事評価・処遇のあり方」(同 16.2 ポイント、同 16.5 ポイン ト)などは両者ともに低い。
【選択肢】 ①仕事の内容・やりがい ②雇用の安定性 |

【解答】
問題①
A ②専門的な資格・技能を活かせるから
B ①自分の都合のよい時間に働けるから
C ③正社員として働ける会社がなかったから
★現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで)
「契約社員(専門職)」、「嘱託社員(再雇用者)」
→ 「専門的な資格・技能を活かせるから」が最も高い
「 パートタイム労働者」、「臨時労働者」
→ 「自分の都合のよい時間に働けるから」が最も高い
「派遣労働者」
→ 「正社員として働ける会社がなかったから」が最も高い
問題②
D ②雇用の安定性
E ①仕事の内容・やりがい
★現在の職場での満足度D.I.について
・「正社員」 → 「雇用の安定性」が 高い
・「正社員以外の労働者」 → 「仕事の内容・やりがい」が高い
調査の概要より
<調査の目的> 正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。
参照→ 厚生労働省 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況より
R3-348
R3.8.6 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査より
今日のテーマは、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(厚生労働省)です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。枠内の選択肢から選んでください。
問題①
(正社員以外の労働者を活用する理由 )
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)を みると、「< A >」とする事業所割合が 38.1%(前回 27.2%)と最も高く、前回に比べて上昇している。次いで、「< B >」が 31.7%(前回 32.9%)、「< C >」が 31.1%(前回 38.6%)となっており、これらの理由の事業所割合は、前回に比べて低下している。
【選択肢】 ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため ②正社員を確保できないため ③賃金の節約のため |
問題②
(正社員以外の労働者を活用する理由 )
「契約社員」では「< D >」54.4% (前回 49.3%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」35.8%(前回 36.0%)、 「嘱託社員」では「< E >」80.0%(前回 77.1%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」44.3%(前回 37.8%)、「パートタイム労働者」では「< F >」37.4%(前回 39.2%)が最も高く、次いで「賃金の節約のため」34.8%(前回 41.1%)、「派遣労働者」では「< G >」47.8%(前回 32.5%)が最も高く、次いで「即戦力・能力のある人材を確保するため」33.3%(前回 33.9%) となっている。
【選択肢】 ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため ②正社員を確保できないため ③高年齢者の再雇用対策のため ④専門的業務に対応するため |
問題③
(正社員以外の労働者を活用する上での問題点)
正社員以外の労働者がいる事業所について、正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)をみると、「良質な人材の確保」56.8%が最も高く、次いで「< H >」が52.5%、「仕事に対する責任感」が46.0%などとなっている。
【選択肢】 ①チームワーク ②定着性 ③正社員との人間関係 |

【解答】
問題①
A ②正社員を確保できないため
B ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため
C ③賃金の節約のため
★正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)
・正社員を確保できないため(38.1%)
・1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため(31.7%)
・賃金の節約のため(31.1%)
問題②
D ④専門的業務に対応するため
E ③高年齢者の再雇用対策のため
F ①1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため
G ②正社員を確保できないため
★正社員以外の労働者を活用する理由(正社員以外の就業形態別)
・「契約社員」 → 「専門的業務に対応するため」が最も高い
・ 「嘱託社員」 →「高年齢者の再雇用対策のため」が最も高い
・「パートタイム労働者」 → 「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が最も高い
・「派遣労働者」 → 「正社員を確保できないため」が最も高い
問題③
H ②定着性
★正社員以外の労働者を活用する上での問題点(複数回答)
「良質な人材の確保」(56.8%)
「定着性」( 52.5%)
「仕事に対する責任感」(46.0%)
調査の概要より
<調査の目的> 正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。
参照→ 厚生労働省 令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
「令和元年度雇用均等基本調査」の結果より
R3-347
R3.8.5 「令和元年度雇用均等基本調査」企業調査の結果より
今日のテーマは、「令和元年度雇用均等基本調査」(企業調査の結果)です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題①
(管理職に占める女性の割合)
課長相当職以上の管理職に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は 11.9%、係長相当職以上の女性管理職割合は13.7%となっている。
それぞれの役職に占める女性管理職割合は、部長相当職では 6.9%、課長相当職では10.9%、係長相当職では17.1%となっており、役員を除く各管理職で調査開始以来最も<A ①高く ②低く>なっている。
問題②
(管理職に占める女性の割合)
課長相当職以上の女性管理職割合を産業別にみると、< B >(54.4%)が突出して高くなっており、教育,学習支援業(19.2%)、生活関連サービス業,娯楽業(18.1%)、宿泊業, 飲食サービス業(16.9%)と続いている。
問題③
(セクシュアルハラスメントを防止するための対策の取組内容)
セクシュアルハラスメントを防止するための対策に取り組んでいる企業の取組内容(複数回答)をみると、「就業規則・労働協約等の書面で内容及び、< C >を明確化し、周知している」が 64.8%と最も高く、次いで、「当事者等のプライバシー保護に必要な措置を講じ、周知している」が 53.2%、「相談・苦情対応窓口を設置している」が 52.7%、「行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、周知している」が51.8%となっている。

【解答】
問題①
A ①高く
『課長相当職以上の管理職に占める女性の割合(以下、「女性管理職割合」という。)は 11.9% と、前回調査(平成30年度 11.8%)より 0.1 ポイント上昇、係長相当職以上の女性管理職割合は 13.7%と、前回調査(同 13.5%)より 0.2ポイント上昇した。それぞれの役職に占める女性管理職割合は、部長相当職では 6.9%(同 6.7%)、課長相当職では 10.9%(同 9.3%)、係長相当職では17.1%(同16.7%)となっており、役員を除く各管理職で調査開始以来最も高くなっている。』
細かい数字までは覚えなくてもいいので、全体の雰囲気だけつかんでください。
問題②
B 医療,福祉
問題③
C あってはならない旨の方針
調査の概要より
<調査の目的> 本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ることを目的とする。
参照→ 厚生労働省「「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要」]]
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和2年版厚生労働白書
R3-346
R3.8.4 令和2年版厚生労働白書「女性のライフコースの変化と男女の働き方」
今日のテーマは、令和2年版厚生労働白書より、「女性のライフコースの変化と男女の働き方」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題①
女性の就労に関しては、結婚・出産に伴う離職を示すいわゆるM字カーブ問題が指摘 されるが、25~29歳、30~34歳、35~39歳女性の就業率の上昇により、就業率のグラフは< A >に近づいており、M字カーブ問題は< B >に向かっている。この背景としては、1990年代においては主に未婚率の上昇が、2000年代以降は主に < C >の上昇が影響していると考えられる。
問題②
1989(平成元)年における女性の就業者の約3割は家族従業者と自営業者であったが、我が国の経済社会全体における自営業の減少に応じてこれらは減少し、 2019(令和元)年には雇用者が約< D >割を占めるようになっている。雇用者の増加の中では、週間就業時間15~34時間など比較的短時間の働き方が増加している 。
問題③
労働者が非正規雇用に就いた理由については、従来より自発的なものと非自発的なものがあることが指摘されているが、こうした構造は2019年においても変わっていない。男性の25~34歳、35~44歳、45~54歳では「正規の職員・従業員の仕事がないから」が、65歳以上では「自分の都合のよい時間に働きたいから」が多い。女性についてはどの年齢階級においても「< E >から」の割合が比較的高く、35~ 44歳においては「家事・育児・介護等と両立しやすいから」、45~54歳においては「家計の補助・学費等を得たいから」も多くなっている。

【解答】
問題①
A 台形
B 解消
C 有配偶女性の就業率
「令和2年版厚生労働白書(女性の就業率のいわゆるM字カーブ問題は解消に向かっている)」より
問題②
D 9
「令和2年版厚生労働白書(女性の就労形態は、家族従業者等から雇用者へとシフトし、比較的短時間の働き方を中 心に増加してきた)」より
問題③
E 自分の都合のよい時間に働きたい
「令和2年版厚生労働白書(増加の背景には、働く側の意識とともに、雇用者側での人件費の抑制志向、人材確保の ための短時間労働者としての活用等の事情が存在)」より
参照→ 令和2年版厚生労働白書「第1章 平成の30年間と、2040年にかけての社会の変容 第3節 労働力と働き方の動向」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働一般常識(統計)
R3-345
R3.8.3 令和2年就労条件総合調査 結果の概況より その2
今日のテーマは、「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」その2です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題①
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、令和元年11月分の常用労働者1人平均所定内賃金は319.7千円となっており、そのうち諸手当は47.5千円、所定内賃金に占める諸手当の割合は14.9%となっている。
また、所定内賃金に占める諸手当の割合を企業別にみると、規模が<A ①小さい ② 大きい >ほど高くなっている。
問題②
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、令和元年11月分の諸手当を支給した企業割合を諸手当の種類別(複数回答)にみると、「<B ①通勤手当 ②精皆勤手当>など」が92.3%で最も高く、次いで「役付手当など」86.9%、「家族手当、扶養手当、育児支援手当など」68.3%などとなっている。

【解答】
問題①
A ①小さい
所定内賃金に占める諸手当の割合は、1,000人以上規模では13.8%、30~99人規模では16.6%です。
問題②
B ①通勤手当
ちなみに、「精皆勤手当、出勤手当など」は25.5%です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働一般常識(統計)
R3-344
R3.8.2 令和2年就労条件総合調査 結果の概況より その1
今日のテーマは、「令和2年就労条件総合調査 結果の概況」です。
ではどうぞ!
問題①
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
問題②
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、年次有給休暇の取得率は、男女ともに50%を下回っている。
問題③
令和2年就労条件総合調査(厚生労働省)によると、企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、30~99人規模の企業の方が1,000人以上規模の企業より高くなっている。

【解答】
問題① ×
フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.1%です。(3割は超えていません。)
なお、変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%。種類別にみると、1年単位の変形労働時間制が33.9%、1か月単位の変形労働時間制が23.9%、フレックスタイム制が6.1%です。
問題② ×
年次有給休暇の取得率は、男性53.7%、女性60.7%で、ともに50%を超えています。
問題③ ×
企業規模計の年次有給休暇取得率は56.3%で、取得率は過去最高となっています。 また、企業規模別でみると、1,000人以上規模の企業が63.1%、30~99人規模の企業が51.1%で、1,000人以上規模の企業の方が、30~99人規模の企業より高くなっています。
参照 → 厚生労働省ホームページ「令和2年就労条件総合調査の概況」
こちらもどうぞ!
・就労条件総合調査の目的
この調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。
・調査の根拠法令
統計法に基づく< A ①一般統計調査 ②基幹統計調査>

【解答】
A ①一般統計調査
参照 → 厚生労働省 令和2年就労条件総合調査 結果の概況:調査の概要
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働一般常識(統計)
R3-343
R3.8.1 令和2年労働組合基礎調査の概況より
今日のテーマは、「令和2年労働組合基礎調査の概況」です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
・ 労働組合及び労働組合員の状況
令和2年6月30 日現在における単一労働組合の労働組合数は23,761 組合、労働組合員数は 1,011 万 5 千人で、前年に比べて労働組合数は 296 組合(1.2%)減、労働組合員数は 2 万 8 千人(0.3 %)増加している。
また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は <A ①17.1 ②20.2 >%で、前年より0.4 ポイント上昇している。
女性の労働組合員数は 343 万 5 千人で、前年に比べ 5万人(1.5%)の <B ①増 ②減 >、推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は12.8%となっており、前年より0.4ポイント上昇している。

【解答】
A ①17.1 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は17.1%
B ①増 女性の労働組合員数は343万5千人で前年比5万人増加
次は、こちらを!
・パートタイム労働者の状況
労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると137万5 千人となっており、前年に比べて 4 万2千人(3.1%)の<C ①増 ②減 >、全労働組合員数に占める割合は13.7%で、前年より0.4ポイント上昇している。 また、推定組織率は8.7%で、前年より0.6 ポイント上昇している。

【解答】
C ①増 パートタイム労働者の労働組合員数は137万5千人
前年より4万2千人(3.1%)増加
参照 → 厚生労働省ホームページ 「令和2年労働組合基礎調査の概況」
こちらもどうぞ!
・労使関係総合調査(労働組合基礎調査)の目的
この調査は、労働組合、労働組合員の産業、企業規模及び加盟上部組合別の分布等、労働組合組織の実態を明らかにすることを目的に、我が国におけるすべての労働組合を対象として、昭和22年以降、毎年実施している< D ①一般統計調査 ②基幹統計調査>である。

【解答】
D 一般統計調査
参照 → 厚生労働省ホームページ「労使関係総合調査(労働組合基礎調査):調査の概要」
こちらも!
<H28年選択式>
政府は、毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し、労働組合組織率を発表している。この組織率は、通常、推定組織率と言われるが、その理由は、組織率算定の分母となる雇用労働者数として「< E >」の結果を用いているからである。

【解答】
E 労働力調査
★推定組織率 → 雇用者数に占める労働組合員数の割合
労働組合員数÷総務省統計局実施の「労働力調査」の雇用者数で計算します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
事後重症の障害厚生年金
R3-342
R3.7.31 障害厚生年金~事後重症のポイントをチェック
今日のテーマは、「障害厚生年金~事後重症のポイントをチェック」です。
ではどうぞ!
①<H26年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。

【解答】
①<H26年出題> ×
障害等級3級も、事後重症による障害厚生年金の対象です。
(法第47条の2)
では、こちらもどうぞ!
②<H20年出題>
傷病の初診日において被保険者であった者について、障害認定日には障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、同日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になり、かつ、初診日において保険料納付要件を満たしているときは、65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる。
③<H29年出題>
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、障害認定日に障害等級に該当しなかった者が障害認定日後65歳に達する日の前日までに当該傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態となり、初診日の前日において保険料納付要件を満たしている場合は、65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる。

【解答】
②<H20年出題> ×
「65歳以後であっても障害等級に該当した日から3年を経過していなければ、障害厚生年金の支給を請求することができる」の部分が誤り。
③<H29年出題> ×
「65歳に達した日以後であっても障害厚生年金の支給を請求できる」の部分が誤り。
事後重症のポイント!
・初診日の要件を満たしている
・初診日の前日の保険料納付要件を満たしている
・障害認定日に障害等級に該当しなかった(障害認定日に受給権が発生しない)
↓
しかし、その後障害の状態が重症化した
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級(1~3級)に該当
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に「請求」する
↓
・「請求」することによって、事後重症の障害厚生年金の受給権が発生する
・請求した月の翌月から支給される
こちらもどうぞ!
④<R1年出題>
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

【解答】
④<R1年出題> 〇
老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げを受給している者は、事後重症の請求はできません。65歳以上と同じ扱いとなります。
(附則第16条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
30歳未満の妻の遺族厚生年金
R3-341
R3.7.30 30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日
今日のテーマは、「30歳未満の妻の遺族厚生年金の「5年」の起算日」です。
ではどうぞ!
①<H19年出題>
受給権を取得した当時30歳未満である妻に対する遺族厚生年金は、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する者について30歳に達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合はその日から起算して5年を経過したときに、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない者については当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに、それぞれ受給権が消滅する。

【解答】
①<H19年出題> 〇
死亡した者に生計を維持されていた妻は、年齢問わず遺族厚生年金の対象となります。
しかし、30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は、5年間の有期給付となります。
5年の起算日をおぼえましょう。
1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満の妻
→ 遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないとき (子がいない場合)
→ 遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年間
2 遺族厚生年金と遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき(30歳前に子の死亡などで遺族基礎年金が失権した場合)
→ 遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年間
こちらもどうぞ!
②<H29年出題>
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③<H26年出題>
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】
②<H29年出題> ×
起算日が誤っています。「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から起算ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算します。
・遺族厚生年金と同一の支給事由の遺族基礎年金の受給権を取得した妻
↓
・1年後に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した
↓
・消滅した日に妻は30歳前だった
↓
・「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに
遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③<H26年出題> 〇
・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻(同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない)
↓
・「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したときに、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
業務上の災害と厚生年金保険の年金との関係
R3-340
R3.7.29 業務上の災害と厚生年金保険の年金との調整
今日のテーマは、「業務上の災害と厚生年金保険の年金との調整」です。
ではどうぞ!
①<H28年出題>
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。
②<H17年出題>
業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。
③<R1年出題>
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。

【解答】
①<H28年出題> ×
障害厚生年金は、同一の傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する、です。
(法第54条)
なお、同一の傷病について労働者災害補償保険法の年金を受けることができる場合は、障害厚生年金は全額支給されます。その場合、労災保険法の規定により、労災保険の年金は減額されます。
②<H17年出題> 〇
①の解説と同じです。
③<R1年出題> 〇
①②と同じです。
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の遺族補償の支給が行われるときは、死亡の日から6年間、その支給が停止されます。
(法第64条)
なお、同一の事由で、遺族厚生年金と労災保険法の年金が支給される場合は、遺族厚生年金は全額支給されます。(そして、労災保険法の規定により労災保険の年金は減額されます。)
では、こちらもどうぞ!
④<H28年出題>
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金は支給されない。

【解答】
④<H28年出題> 〇
障害手当金は、当該傷病について、労災保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には支給されません。
ちなみに、当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を有する場合も、障害手当金は支給されません。
(法第56条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金基金のこと
R3-339
R3.7.28 国民年金基金の給付について
今日のテーマは「国民年金基金の給付」です。
では条文をチェックしましょう!
空欄を埋めてください。
第115条 (基金の給付)
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の< A >に関して必要な給付を行なうものとする。
第128条 (基金の業務)
基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の< B >に関し、一時金の支給を行なうものとする。

【解答】
A 老齢
B 死亡
(法第115条、第128条)
では、こちらをどうぞ!
①<H15年出題>
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。
②<H29年出題>
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】
①<H15年出題> 〇
国民年金基金は、老齢に関して「年金」、死亡に関して「一時金」の給付を行います。障害や脱退に関する給付は行いません。
②<H29年出題> 〇
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、「国民年金基金」が裁定するのがポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(法第133条)
では、こちらもどうぞ
③<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。
④<H16年出題>
基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
⑤<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

【解答】
③<H22年出題> 〇
基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が『老齢基礎年金の受給権を取得したとき』には、その者に支給されるものでなければならない、とされています。
また、老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該『老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない』とされています。
老齢基礎年金の上乗せのイメージです。
(法第129条)
④<H16年出題> ×
「死亡一時金又は遺族基礎年金」ではなく、『その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない』とされています。
(法第129条)
⑤<H22年出題> ×
一時金の額については下限が定められていて、『基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない』とされています。
(法第130条)
最後にポイントを穴埋めでチェックしましょう
第129条 (基金の給付の基準)
1 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が< A >の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
2 < A >の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該< A >の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
3 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が< B >を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
第130条
1 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、< C >円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3 基金が支給する一時金の額は、< D >円を超えるものでなければならない。

【解答】
A 老齢基礎年金
B 死亡一時金
C 200
D 8,500
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
20歳前傷病による障害基礎年金その3
R3-338
R3.7.27 20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止ルール②
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。
昨日の続きです。
ではこちらからどうぞ!
①<H25年出題>
国民年金法第34条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
②<H27年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

【解答】
①<H25年出題> ×
支給停止されるのは、「全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1」ではなく、「全部又は2分の1」に相当する部分です。
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★所得による支給制限がある
前年の所得額(扶養親族等がいない場合)
4,621,000円を超える → 年金の全額が支給停止
3,604,000円を超え4,621,000円以下 → 2分の1の年金額が支給停止
3,604,000円以下 → 全額支給される(支給停止なし)
(法第36条の3)
②<H27年出題> ×
「受給権者」の前年の所得で判断されます。扶養親族の所得は合算しません。
では、こちらもどうぞ
③<H25年出題>
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
③<H25年出題> ×
3分の1以上ではなく「2分の1」以上です。
20歳前傷病による障害基礎年金は、所得による支給制限がありますが、被災し、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わないことになっています。
(法第36条の4)
最後にこちらをどうぞ
④<H17年出題>
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。

【解答】
④<H17年出題> ×
20歳前に初診日があっても、初診日に第2号被保険である場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金ではなく、一般の障害基礎年金が支給されます。ですので、所得による支給停止はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
20歳前傷病による障害基礎年金その2
R3-337
R3.7.26 20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止ルール①
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。
ではこちらからどうぞ!
①<H25年出題>
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】
①<H25年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★日本国内に住所を有しないときは支給停止
(一般の障害基礎年金は、日本国内に住所を有しなくても支給停止にはなりません。)
(法第36条の2)
次はこちらをどうぞ
②<H30年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。

【解答】
②<H30年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」、「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給停止
(一般の障害基礎年金は、このような施設に収容されていても支給停止になりません。)
(法第36条の2、則第34条の4)
次はこちらを!
③<R1年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
④<H25年出題>
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
⑤<H20年出題>
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

【解答】
③<R1年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは支給停止
(一般の障害基礎年金はこの理由では支給停止になりません)
④<H25年出題> 〇
③の問題でみたように、「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは20歳前の傷病による障害基礎年金は支給停止になります。しかし、労災保険法の年金たる給付が全額支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は原則として支給停止されません。
⑤<H20年出題> 〇
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、労災保険法の障害補償年金を受けることができるときでも、その支給は停止されません。
明日も続きます!
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
20歳前傷病による障害基礎年金その1
R3-336
R3.7.25 20歳前傷病の障害基礎年金の受給要件
今日のテーマは、「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給要件です。
では条文チェックからどうぞ!
空欄を埋めてください。
第32条の4第1項(20歳前傷病による障害基礎年金)
疾病にかかり、又は負傷し、その< A >において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは< B >において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその< C >において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

【解答】
A 初診日
B 20歳に達した日
C 障害認定日
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント!
●初診日に20歳未満である=国民年金の被保険者でない
●受給権の発生
・ 障害認定日以後に20歳に達した
→ 20歳に達した日に1級または2級の障害状態にあれば20歳に達した日
・ 障害認定日が20歳に達した日後
→ 障害認定日に1級または2級の障害状態にあれば障害認定日
では、こちらをどうぞ!
①<H26年出題>
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
②<H30年出題>
傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
③<H22年出題>
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

【解答】
①<H26年出題> ×
問題文の場合、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」です。
「20歳に達した日」、「障害認定日」どちらが後に来るかがポイントです。
「障害認定日」は初診日から1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は治った日)です。
問題文の場合、25歳現在、「継続して治療している」状況なので、障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日となります。
そして、初診日に19歳なので、障害認定日は20歳に達した日よりも後になります。
ですので、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権が発生します。
②<H30年出題> ×
「初診日」に19歳であったこと(国民年金の被保険者ではない)がポイントです。
「初診日に国民年金の被保険者でない」、「障害認定日に障害等級1級、2級に該当している」ので、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。
第1号被保険者の資格を取得した後、全て未納期間であったことは関係ありません。
③<H22年出題> ×
「障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降」の部分が誤りです。
初診日が20歳未満でも、その初診日において「厚生年金保険の被保険者」だったことがポイントです。
初診日に厚生年金保険の被保険者(=国民年金の第2号被保険者)ですので、障害認定日に障害等級に該当していれば、「障害認定日」に障害基礎年金と障害厚生年金の受給権が発生します。
初診日に国民年金の被保険者ですので、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。
★明日は、「通常の障害基礎年金」と「20歳前の傷病による障害基礎年金」の違いをお話しします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金第2号被保険者のこと
R3-335
R3.7.24 厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者(原則)
厚生年金保険の被保険者は、国民年金法の第2号被保険者です。
第2号被保険者のポイントは以下の3つです。
・国籍要件なし
・国内居住要件なし
・年齢要件(20歳以上60歳未満)なし
ではどうぞ!
①<H29年出題>
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②<H20年出題>
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①<H29年出題> 〇
第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件(20歳以上60歳未満)がありますが、第2号被保険者にはそれがないので、20歳未満でも厚生年金保険の被保険者なら国民年金の第2号被保険者です。
(法第7条)
②<H20年出題> ×
第2号被保険者は60歳に達しても資格は喪失しません。
★第1号被保険者と第3号被保険者は、60歳に達した日に資格を喪失します。
では、こちらをどうぞ!
③<H25年出題>改正による修正あり
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住所を有する配偶者(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
④<H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
★厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される「70歳未満」の者です。
といっても、厚生年金保険の被保険者すべてが国民年金の第2号被保険者となるわけではありません。
厚生年金保険の被保険者が第2号被保険者になる要件として、「65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限る。」という規定が法附則第3条にありますので注意してください。
③<H25年出題> 〇
ポイントその1
★厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(70歳以上)は国民年金の第2号被保険者。
なぜなら、「老齢基礎年金、老齢厚生年金等」の受給権がないから。
ポイントその2
第3号被保険者は「第2号被保険者」の配偶者。
問題文の場合、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満ですので、第3号被保険者となります。
④<H27年出題> 〇
問題文の場合、年齢が「65歳以上」で「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する」(老齢の年金の受給権がある)ため、第2号被保険者ではありません。
ですので、生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者でも、「第2号被保険者」の被扶養配偶者ではないので、第3号被保険者とはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 埋葬料と埋葬費
R3-334
R3.7.23 埋葬料と埋葬費の違い
今日は、健康保険法「埋葬料と埋葬費の違い」です。
では、条文からどうぞ!
空欄を埋めてください
第100条 埋葬料
1 被保険者が死亡したときは、その者により< A >者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 1の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< B >者に対し、1の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

【解答】
A 生計を維持していた
B 埋葬を行った
| 対 象 | 金 額 | |
| 埋葬料 | 生計を維持していた者であって、埋葬を行うもの | 5万円 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った者 (埋葬料の支給を受けるべき者がない場合) | 埋葬に要した費用 (5万円の範囲内) |
では、こちらをどうぞ!
①<H24年出題>
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
②<H25年出題>
埋葬を行う者とは、埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
③<H25年出題>
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。

【解答】
①<H24年出題> 〇
「生計の一部を維持していた者」も埋葬料の対象になります。被扶養者とは別の概念です。
(参照 昭8.8.7保発502)
②<H25年出題> ×
埋葬を行う者とは、「社会通念上」埋葬を行うべき人のことで、実際に埋葬を行うかどうかではありません。問題文の場合は、配偶者は埋葬料の支給対象となり得ます。
③<H25年出題> ×
生計を維持されていなかった兄弟姉妹が実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の支給対象となります。
(参照 昭26.6.28保文発162)
こちらもどうぞ!
④<H26年出題>
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

【解答】
④<H26年出題> 〇
ポイント!
・埋葬料 → 埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付される
保険事故発生の日は「死亡した日」
・埋葬費 → 死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されない
保険事故発生の日は「埋葬した日」
★時効の起算日(保険事故発生の日の翌日)
| 埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
出産育児一時金
R3-333
R3.7.22 出産育児一時金のポイントチェック
今日は、「出産育児一時金」のポイントをチェックします!
では、問題をどうぞ!
①<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
②<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)妊娠85日以後の出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産を問わず、支給される。
③<H26年出題>
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

【解答】
①<H21年出題> 〇
私生児の出産でも支給されます。なぜなら、主として「母体を保護する」ことが、出産に関する給付の目的だからです。
(参照 昭2.3.17保理792)
②<H21年出題> 〇
出産に関する給付は、妊娠4か月以上の出産が対象です。
1月は28日で計算するので、28日×3月+1日=85日。85日目が4か月目に入った日になるため、妊娠85日以降が出産に関する給付の対象となります。
(参照 昭3.3.16保発11)
また、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、早産を問いません。
(参照 昭27.6.16保文発2427)
③<H26年出題> ×
労災保険法の療養補償給付を受けたとしても、出産育児一時金の支給は行われます。
(参照 昭24.3.26保文発第523号)
こちらもどうぞ!
④<H27年出題>
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには42万円、それ以外のときには40万4千円である。
⑤<H21年出題>
被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
⑥<H21年出題>
(出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関する問題)双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。

【解答】
④<H27年出題> 〇
出産育児一時金の額は一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は40万4千円)です。
(施行令第36条)
⑤<H21年出題> ×
妊娠4か月以降の死産の場合は出産育児一時金は支給されます。しかし、死産児は被扶養者ではないので、家族埋葬料は支給されません。
(参照 昭23.12.2保文発898)
⑥<H21年出題> 〇
例えば、双子の場合は42万円×2=84万円となります。(産科医療補償制度の対象外の出産の場合は404,000円×2=808,000円)
(参照 平20.12.17保保発1217004)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 入院時生活療養費
R3-332
R3.7.21 入院時生活療養費~選択対策~
「入院時生活療養費」は選択式で出題実績があります。
チェックしておきましょう!
では、問題をどうぞ!
①<H19選択>
療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を < A >といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち< B >から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、< C >として現物で支給する。< C >の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して< D >が定めた基準により算定した額から< E >を控除した額とする。

【解答】
A 特定長期入院被保険者
B 自己の選定するもの
C 入院時生活療養費
D 厚生労働大臣
E 生活療養標準負担額
(法第85条の2)
ポイント!
・入院時生活療養費は「現物」で支給される
・「厚生労働大臣の算出基準による生活療養費」から、「生活療養標準負担額」を控除したものが「入院時生活療養費」として現物給付されます。
次はこちらをどうぞ!
②<H26選択>改正による修正あり
入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について< A >に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。
(1)下記(2)(3)以外の者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(2)病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 → 1日につき< B >円と1食につき< C >円又は420円との合計額
(3)難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者 → 1日につき< D >円と1食につき260円との合計額

【解答】
A 介護保険法
B 370
C 460
D 0
★生活療養標準負担額は、「居住費(光熱水費)」と「食費」の合計です。
※生活療養標準負担額(低所得者以外)
| 生活療養標準負担額 | ||
(1) (2)(3)以外 | 居住費(1日) 370円 | 食費(1食) 460円又は420円 ※管理栄養士等を配置している保険医機関の場合は460円となる。 |
(2)病状の程度が重篤な者等 | 同上 | 同上 |
| (3)指定難病の患者 | 0円 | 1食 260円 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 認定決定でおさえたいところ②
R3-331
R3.7.20 印紙保険料の認定決定と追徴金
認定決定でおさえたいところ第2弾!
今日は印紙保険料の認定決定です。
概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定はこちらをどうぞ!
では、問題をどうぞ!
①<H24年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
②<H25年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①<H24年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
・ 認定決定された印紙保険料は「現金」で納付する(印紙ではないので注意)
・ 「日本銀行」又は「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付する
(則第38条)
②<H25年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われる。
(則第38条)
では、追徴金の問題をどうぞ!
③<H28年出題(雇用保険)>
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】
③<H28年出題(雇用保険)> ×
印紙保険料の追徴金の割合は「100分の25」。一般保険料の場合の追徴金の割合である100分の10より高いのがポイントです。
追徴金が徴収されるのは、印紙保険料の納付を怠ったことについて、「正当な理由」がないと認められるときです。
(法第25条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 認定決定でおさえたいところ①
R3-330
R3.7.19 概算保険料の認定決定・確定保険料の認定決定
認定決定が行われるのは、
・概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき
・確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき
です。
では、問題をどうぞ!
①<H25年出題(雇用保険)>
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②<H23年出題(労災)>
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
③<R1年出題(労災)>
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

【解答】
①<H25年出題(雇用保険)> ×
「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われます。
ポイント!
・概算保険料の認定決定 → 納付書
・確定保険料の認定決定 → 納入告知書
②<H23年出題(労災)> ×
増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しなくても、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときでも、認定決定は行われません。
③<R1年出題(労災)> ×
「30日以内」が誤りです。
通知を受けた日から「15日以内」です。なお、この場合は翌日起算となるので、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。
通知を受けた日は、午前0時ではなく、受けた時から始まるので翌日起算です。
では、追徴金の問題をどうぞ!
④<H26年出題(雇用保険)>
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
③<H26年出題(雇用保険)> ×
「概算保険料」の認定決定の場合は、追徴金は課されません。
ポイント!
「確定保険料」の認定決定の場合は、追徴金が課されます。
追徴金の計算式は、納付すべき額(1,000円未満の端数切り捨て)×100分の10です。
追徴金の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 賃金について
R3-329
R3.7.18 徴収法 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲
徴収法では、保険料の算定のもとになるのは「賃金」です。
まず「賃金」の定義をどうぞ!
徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
今日は、通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)の扱いについてみていきましょう。
では、問題をどうぞ!
①<R1年出題(雇用保険)>
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
②<H19年出題(雇用保険)>
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。

【解答】
①<R1年出題(雇用保険)> 〇
②<H19年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
・ 賃金は「通貨」だけでなく、通貨以外のもので支払われるものも含まれる。
・ その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
・ なお、「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」ことになっています。
「範囲」と「評価」を区別して読んでください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 不服申立て
R3-328
R3.7.17 徴収法の処分に不服のあるときは?
徴収法の処分に不服のある場合は、行政不服審査法によって行います。
ではどうぞ!
H28年 労災問9より
①<ア>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
②<イ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
③<ウ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
④<エ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
⑤<オ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

【解答】
ポイント!
徴収法には、不服申し立ての規定がありません。労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する処分については、行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになります。
①<ア> ×
異議申立てではなく「審査請求をすることができる」です。
また、審査請求先は、「厚生労働大臣」です。
★不服申立ての種類は、原則として「審査請求」とされています。
(行政不服審査法第2条、第4条)
②<イ> ×
<ア>と同じで、「厚生労働大臣に審査請求をすることができる」です。
③<ウ> ×
<ア><イ>と同じで「厚生労働大臣」に対し、再審査請求ではなく「審査請求」を行うことができる、です。
④<エ> 〇
行政事件訴訟法第8条によって、「直ちにその取消しの訴えを提起すること」ができます。
審査請求をしないで直ちに提起する、という選択もできることをおさえましょう。
(行政事件訴訟法第8条)
⑤<オ> ×
「審査請求は代理人によってすることができる」と規定されています。
(行政不服審査法第12条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
所定給付日数と受給期間
R3-327
R3.7.16 覚えましょう。所定給付日数と受給期間
覚えれば解ける所定給付日数。しっかり暗記しましょう。
ではどうぞ!
①<H26年出題>
雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては < A >とされている。

【解答】
①<H26年出題>
A 360日
就職困難者の所定給付日数は、算定基礎期間が1年未満の場合は、年齢に関係なく150日。1年以上の場合は、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日です。
次は受給期間の問題をどうぞ!
②<H28年出題>
基本手当の受給資格に係る離職の日において55歳であって算定基礎期間が25年である者が特定受給資格者である場合、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
③<H23年出題>
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。
④<H28年出題>
定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。

【解答】
②<H28年出題> 〇
55歳・算定基礎期間が25年・特定受給資格者の場合、所定給付日数は330日で、受給期間は「1年+30日」です。
★受給期間
原 則 → 1年
所定給付日数360日 → 1年+60日
所定給付日数330日 → 1年+30日
③<H23年出題> 〇
「妊娠、出産、育児等」の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合 → 受給期間の延長が認められます。
問題文の場合、所定給付日数が270日なので受給期間は1年、それに「出産及び育児」のため職業に就くことができない180日をプラスして、受給期間は「1年+180日」となります。
④<H28年出題> ×
定年に達したことで受給期間の延長が認められた場合でも、疾病又は負傷等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときは、受給期間はさらに延長が認められます。
ただし、この場合でも受給期間は最長4年間です。
(行政手引50286)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
定年後の受給期間の延長
R3-326
R3.7.15 60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと
今日のテーマは、「60歳以上の定年後の受給期間の延長のこと」です。
ではどうぞ!
①<H24年出題>
60歳以上で定年退職した者に対する雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間の延長は、1年を限度とする。
②<H24年出題>
60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。
③<H28年出題>
60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定の期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。

【解答】
①<H24年出題> 〇
定年退職者等が「少しゆっくりしてから求職活動を始めよう」という場合は、受給期間の延長の申出をすることができます。
求職申し込みをしないことを希望するとして申し出た期間(猶予期間)は、 1 年が限度です。例えば、猶予期間を4か月と希望した場合、受給期間が4か月延長されます。
(法第20条、則31条の2、行政手引50282)
②<H24年出題> 〇
「2か月以内」がポイントです。
(則第31条の3)
③<H28年出題> ×
「60歳以上の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている」場合、当該期限が到来したことにより離職した場合は受給期間の延長の対象となります。
問題文のように、1 年更新の再雇用制度で雇用されて、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、受給期間の延長は認められません。
(行政手引50281)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険の被保険者
R3-325
R3.7.14 雇用保険の被保険者になる?ならない?
今日のテーマは、「雇用保険の被保険者になる?ならない?」です。
ではどうぞ!
①<H25年出題>
同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
②<H30年出題>
労働日の全部又はその大部分において事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者と同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

【解答】
①<H25年出題> 〇
・同時に2以上の雇用関係にある労働者の場合
→ 一の雇用関係についてのみ被保険者となるので、同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはありません。なお、被保険者となるのは、原則として、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係のみです。
(行政手引20352)
②<H30年出題> 〇
・在宅勤務者の場合
→ 事業所勤務労働者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。
※事業所勤務労働者との同一性とは、簡単に書くと、所属事業所で勤務する他の労働者と同一の就業規則等の諸規定が適用されることです。
(行政手引20351)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【改正労災】複数事業労働者(特別加入者編)
R3-324
R3.7.13 複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)
今日のテーマは、「複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)」です。
以下のような場合も「複数事業労働者」となります。
・ある会社では「労働者」として働く一方、他の仕事で「特別加入」している
・複数の仕事で「特別加入」している
このような場合の給付基礎日額の算定についてみていきましょう。
では特別加入者の給付基礎日額のポイントからどうぞ!
穴埋めで確認しましょう。
(平成30年選択式より)
・中小事業主等の特別加入の給付基礎日額 → 当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は、
< A >である。

【解答】
A 25,000円
特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から最高25,000円まで、16段階の設定があります。また、家内労働者については、それにプラスして「2,000円、2,500円、3,000円」の設定もあります。
 特別加入者の給付基礎日額のポイント
特別加入者の給付基礎日額のポイント
| 自動変更対象額 | 適用なし |
| 年齢階層別の最高・最低限度額 | |
| スライド制 | 適用される |
では、複数事業労働者の場合の給付基礎日額は?
①労働者であって、かつ、特別加入者である場合
労働者としての給付基礎日額 + 特別加入者としての給付基礎日額
※労働者としての給付基礎日額 → 合算前に自動変更対象額、スライド制、年齢階層別最高・最低限度額を適用し算定
※特別加入者としての給付基礎日額 → 合算前に、スライド制のみ適用し算定
②複数の特別加入を行っている場合
特別加入者としての各給付基礎日額を合算 → 合算した額にスライド制のみ適用し算定
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【労災】特別加入者の範囲
R3-323
R3.7.12 令和3年4月改正 特別加入者の範囲その2
今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その2です!
特別加入者は、3つに分かれています。
第1種特別加入者 → 中小事業主等
第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者
第3種特別加入者 → 海外派遣者
今日は、「特定作業従事者」の範囲を確認しましょう。
では穴埋めでどうぞ!
【特定作業従事者の範囲】
1 農業における一定の作業
2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業
3 家内労働者及びその補助者が行う一定の作業
4 労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業
5 介護関係業務に係る一定の作業及び家事支援に係る一定の作業
令和3年4月より追加された作業
↓
6 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における< A >の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
7 < B >の制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

【解答】
A 音楽、演芸その他の芸能
B アニメーシヨン
(則第46条の18)
★令和3年4月から追加されたのは次の2つです。
■芸能従事者
・芸能実演家(俳優、舞踊家、音楽家、演芸家、スタント等)
・芸能製作作業従事者(監督、撮影、衣装、メイク等)
■アニメーション制作作業従事者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【労災】特別加入者の範囲
R3-322
R3.7.11 令和3年4月改正 特別加入者の範囲その1
今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その1です!
特別加入者は、3つに分かれています。
第1種特別加入者 → 中小事業主等
第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者
第3種特別加入者 → 海外派遣者
令和3年4月より改正された「一人親方等」の範囲を確認しましょう。
では穴埋めでどうぞ!
【一人親方等の範囲】
1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
(例)個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
(例)大工、左官、とび職人
3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売の事業
6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7 船員法第1条に規定する船員が行う事業
8 < A >法第2条に規定する< A >が行う事業
9 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する< B >その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する< C >に係る< B >その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

【解答】
A 柔道整復師
B 委託契約
C 社会貢献事業
(則第46条の17)
★8と9が令和3年4月から追加された事業です。
9は、先日書きました「【改正】70歳までの就業確保措置」によって「創業支援等措置」に基づく事業を行う人が対象です。
★ 明日は特定作業従事者です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【安衛法】元方事業者の講ずべき措置等
R3-321
R3.7.10 元方事業者と関係請負人
今日のテーマは「元方事業者と関係請負人」です。
では条文を穴埋めでどうぞ!
法第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)
1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< A >を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な < B >を行なわなければならない。
3 2の< B >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< B >に従わなければならない。

【解答】
A 指導
B 指示
業種を限定していませんので、すべての業種の「元方事業者」に適用される規定です。
「指導」と「指示」が出てきますが、「指示」の方は、「違反していると認めるとき」、「従わなければならない」のように使われていますので、指導より指示の方が重いイメージです。
では、こちらもどうぞ!
①<H18年出題>
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
②<H22年出題>
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
③<H26年出題>
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

【解答】
①<H18年出題> 〇
最大のポイントは、「業種のいかんを問わず」の部分です。この規定は、業種を問わず元方事業者に適用されます。
(法第29条)
②<H22年出題> ×
関係請負人のみならず、関係請負人の労働者に対しても指導及び指示をしなければなりません。
(法第29条)
③<H26年出題> ×
この規定には、罰則はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【安衛法】統括安全衛生責任者
R3-320
R3.7.9 統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ
今日のテーマは「統括安全衛生責任者でおさえておきたいところ」です。
ではどうぞ!
法第15条 (統括安全衛生責任者)
事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため、その者が2以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)のうち、建設業又は< A >に属する事業(以下「特定事業」という。)を行う者(以下「< B >」という。)は、その労働者及びその請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という。)の労働者が当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第30条第1項各号の事項を統括管理させなければならない。

【解答】
A 造船業
B 特定元方事業者
ポイント!
用語をおさえておきましょう。
・元方事業者 → 一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの
・特定事業 → 建設業、造船業
・特定元方事業者 → 元方事業者のうち特定事業を行うもの(建設業と造船業の元方事業者)
では、こちらもどうぞ!
①<H20年出題>
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が同一の場所で混在して仕事をすることによって生ずる労働災害を防止するため、労働安全衛生法施行令第7条第2項で定める仕事の区分により統括安全衛生責任者を選任しなければならないが、この場合、その労働者及び関係請負人の労働者が常時40人のずい道の建設の仕事については、統括安全衛生責任者を選任する必要はない。
②<H20年出題>
労働安全衛生法第15条第2項は、「統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。
③<H22年出題>
建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。

【解答】
①<H20年出題> ×
常時40人のずい道の建設の仕事は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。※ずい道の建設の仕事の場合、常時30人以上で選任義務があります。
(統括安全衛生責任者の選任について)
・選任が必要な業種 → 特定事業(建設業、造船業)
・規模
(原則)特定元方事業者の労働者+関係請負人の労働者数が常時50人以上
※「ずい道等の建設」、「圧気工法による作業」、「一定の橋梁の建設」
→ 常時30人以上
②<H20年出題> ×
「作業場所を巡視すること」に関する措置を講ずることは、統括安全衛生責任者が統括管理する項目の中に含まれます。
③<H22年出題> 〇
「元方安全衛生管理者」は「統括安全衛生責任者」の部下のようなイメージです。「建設業に属する事業」の元方事業者で、統括安全衛生責任者を選任した事業者が選任します。「建設業」のみが対象で、造船業には元方安全衛生管理者の選任義務はありません。
(法第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【安衛法】事業者の責務など
R3-319
R3.7.8 安衛~事業者の責務など
今日のテーマは事業者の責務などです。
ではどうぞ!
①<H18年選択>
労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。
②<H12年出題>
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。
③
労働安全衛生法第3条第2項の規定においては、「機械、器具その他の設備を < B >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< B >する者は、これらの物の< B >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止< C >なければならない。」と規定されている。
④
労働安全衛生法第3条第3項の規定においては、「建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように< D >しなければならない。」と規定されている。

【解答】
①<H18年選択>
A 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
★ 事業主が労働安全衛生法に定める労働災害の防止のための最低基準を守ることは当然。さらに、職場環境、労働条件を改善し、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない、と規定されています。
②<H12年出題> 〇
★ 労働者にも「労働災害を防止するため必要な事項を守る」こと、「事業者等が実施する労働災害の防止に関する措置に協力する」ことが求められています。語尾が「努めなければならない」と努力義務であることがポイントです。
(法第4条)
③
B 設計
C に資するように努め
★ 対象は、①機械、器具その他の設備を設計する者、製造する者、輸入する者、②原材料を製造する者、輸入する者、③建設物を建設する者、設計する者です。
例えば、機械の設計者は、機械の設計の段階で、その機械を使用する際の労働災害を防止するための措置を講ずることが求められています。努力義務ですので注意してください。
④
D 配慮
★ 対象は、建設工事の注文者等です。例えば、工事を発注する際に、安全に工事が行われるように、施工方法や工期等の条件に配慮してください、という規定です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【労基法】フレックスタイム制
R3-318
R3.7.7 清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制
今日のテーマはフレックスタイム制です。
本題の前にフレックスタイム制を導入の要件を確認しておきましょう。
① 就業規則その他これに準ずるものに規定する
・「始業及び終業の時刻」をその労働者の決定に委ねること
② 労使協定で一定事項を定める
「清算期間」とは?
清算期間とは → その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、< A >以内の期間に限るものとする。

【解答】
A 3か月
フレックスタイム制の清算期間の上限は3か月です。
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、一定のルールがあります。そのルールを次の問題で確認しましょう。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

【解答】
①<R1年出題> 〇
 フレックスタイム制の時間外労働は?
フレックスタイム制の時間外労働は?
フレックスタイム制の時間外労働は、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた部分です。
例えば、清算期間が1か月の場合は1か月単位で労働時間を清算します。
1か月の法定労働時間の総枠は、暦日数が31日の月でしたら177.1時間です。もし、1か月でトータルした実際の労働時間が総枠を超えていれば、その枠を超えた時間が時間外労働となります。
 では、清算期間を3か月とした場合は?
では、清算期間を3か月とした場合は?
清算期間を3か月にした場合は、3か月単位で清算します。
暦日数が92日だとすると、法定労働時間の総枠は525.7時間(労働時間の週平均が40時間)となり、実際の労働時間のトータルが総枠を超えれば、超えた分が時間外労働となります。
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、『1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと』というルールがあります。
ですので、問題文のように、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当し、36協定の締結と届出、清算期間の途中でも割増賃金を支払う必要があります。
(法第32条の3)
★もう一つ注意★ 特例事業場の場合、清算期間が1か月以内なら「44時間」の特例が適用されますが、清算期間が1か月を超える場合は、特例は適用されませんので原則の40時間が適用されます。
こちらもどうぞ!
②<R2年出題>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

【解答】
②<R2年出題> ×
フレックスタイム制の労使協定
・清算期間が1か月以内 → 届出不要
・清算期間が1か月を超える → 届け出なければならない
(法第32条の3)
ついでに「労使協定の有効期間」もチェックしましょう。
清算期間が1か月を超える → 有効期間の定めをすること
(則第12条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【改正】障害者雇用促進法
R3-317
R3.7.6 令和3年3月からの障害者雇用率
令和3年3月1日から、法定雇用率が変わりました。
まずは、こちらをどうぞ
<H25年選択(修正)>
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定率以上になるよう義務づけている。この法定雇用率は令和3年3月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、< A >人以上に拡大された。< A >人以上の企業には、< B >を選任するよう努力することが求められている。

【解答】
A 43.5
B 障害者雇用推進者
(法第43条)
 令和3年3月1日からの法定雇用率
令和3年3月1日からの法定雇用率
| 民間企業 | 2.3% |
| 特殊法人 | 2.6% |
| 国、地方公共団体 | 2.6% |
| 教育委員会 | 2.5% |
 一般の民間企業の場合
一般の民間企業の場合
★雇用する労働者が常時43.5人以上の場合
・障害者の雇用義務が発生する
・障害者の雇用状況の報告義務がある
・障害者雇用推進者を選任する努力が求められる
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【改正】確定給付企業年金法
R3-316
R3.7.5 【改正】確定給付企業年金~支給開始年齢
昨日、高年齢者雇用安定法の改正「70歳までの就業確保措置」の努力義務についてお話しました。
確定給付企業年金法も改正で70歳までの拡大が行われています。
まずは、こちらをどうぞ
<H30年選択(修正)>
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1)< A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2)政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】
A 60歳以上70歳以下(←今回の改正点です)
B 50歳未満
(法第36条、施行令28条)
 確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢
確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢
(1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき
(2)50歳以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき(※規約で当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)
では、こちらもどうぞ!
①<H30選択>
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < C >
②<H26年出題>
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
③<H26年出題>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】
①<H30選択>
C 脱退一時金
★確定給付企業年金では、「老齢給付金」と「脱退一時金」の給付を行います。
また、規約で定めるところにより、それらの給付に加え、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付を行うことができます。
(法第29条)
②<H26年出題> 〇
老齢給付金の支給要件は、20年を超えてはならない、とされています。
(法第36条)
③<H26年出題> 〇
老齢給付金を年金で支給する場合は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給するものでなければなりません。
(法第33条)
※老齢給付金は、原則として年金として支給。ただし、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合は、一時金として支給することができます。(法第38条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【改正】高年齢者雇用安定法
R3-315
R3.7.4 【改正】70歳までの就業確保措置
今日のテーマは「70歳までの就業確保措置」です。(令和3年4月~)
 70歳定年を義務付けるものではないので、注意してください。
70歳定年を義務付けるものではないので、注意してください。
まずは、ポイントをチェックしましょう
★ 第9条では、「高年齢者雇用確保措置」が義務づけられています。こちらは、もとからある規定です。
定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
1 当該定年の引上げ
2 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
3 当該定年の定めの廃止
高年齢者雇用確保措置のポイント!
・65歳までの「雇用確保」
・義務

 ★ 上記の「65歳までの雇用確保の義務」にプラスして、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」が新しく加わりました。
★ 上記の「65歳までの雇用確保の義務」にプラスして、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」が新しく加わりました。
高年齢者就業確保措置のポイント!比較してみましょう!
・65歳から70歳までの「就業確保」(雇用ではなく「就業」であることに注意)
・努力義務
では、新しくできた「高年齢者就業確保措置」をチェックしましょう
<努力義務の対象になる事業主>
・定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主
・継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主
<高年齢者就業確保措置>努力義務
1 当該定年の引上げ
2 65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入
3 当該定年の定めの廃止
4 創業支援等措置(雇用によらない措置)
※ なお、4の「創業支援等措置」の導入については、過半数労働組合等の同意を得ることが条件となっています。
また、「創業支援等措置」とは雇用によらない措置であることがポイントです。
「創業支援等措置」の内容は70歳まで継続的に「業務委託契約を締結する制度」、「①事業主が自ら実施する社会貢献事業、②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業、に従事できる制度」です。
(法第10条の2)
まとめ 比較表を作ってみました。
| 高年齢者雇用確保措置 | 高年齢者就業確保措置 |
| 65歳まで | 70歳まで |
| 義務 | 努力義務 |
| 創業支援等措置OK(雇用によらない措置) | |
継続雇用できる事業主の範囲 ・自社 ・特殊関係事業主 | 継続雇用できる事業主の範囲 ・自社 ・特殊関係事業主 ・特殊関係事業主以外の他社 |
では、こちらもどうぞ!
<H26年出題>
高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。

【解答】 ×
「定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。」と規定されているので、原則として60歳を下回ることはできません。(例外あり)
定年を65歳以上とすることは義務付けられていません。
(法第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働施策総合推進法その2
R3-314
R3.7.3 【改正】中途採用比率の公表の義務化
今日のテーマは「中途採用比率の公表の義務化」です。(令和3年4月~)
中途採用に関する環境整備を推進することが目的です。
まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう
第27条の2
常時雇用する労働者の数が< A >人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。

【解答】
A 300
中途採用比率の公表が義務づけられたのは、常時雇用される労働者数が300人を超える(301人以上)の企業です。
★ 労働者の職業選択に資するよう、正規雇用労働者の中途採用比率を定期的に公表しなければならないことになりました。
★ なお、「正規雇用労働者の中途採用比率」の情報公表は、頻度はおおむね1年に1回以上、方法はインターネットの利用その他の方法とされています。
(参照)令和3.2.9職発0209 第3号
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働施策総合推進法
R3-313
R3.7.2 パワハラ防止措置の義務
今日のテーマは「パワハラ防止措置の義務」です。
まずは、条文を穴埋めでチェックしましょう
第32条の2 (雇用管理上の措置等)
1 事業主は、職場において行われる< A >を背景とした言動であって、 < B >な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の< C >が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が1の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して< D >をしてはならない。

【解答】
A 優越的な関係
B 業務上必要かつ相当
C 就業環境
D 解雇その他不利益な取扱い
令和2年6月に改正されました。
令和2年厚生労働省告示第5号では、『職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。』とされていて、また、『客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については 、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。』とされています。
事業主はパワーハラスメン防止対策について、雇用管理上必要な措置を講じなければならないことが義務づけられました。
なお、中小事業主は、令和4年4月から義務化されますので、それまでは努力義務となっています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国年 令和3年度の年金額
R3-312
R3.7.1 令和3年度の年金額の改定について
老齢基礎年金の満額は、780,900円×改定率です。
令和3年度の改定率は「1.000」ですので、令和3年度の年金額は、780,900円×1.000=780,900円となります。
今日のテーマは、改定率が「1.000」になった根拠です。
まずは、こちらからどうぞ!
<R2年出題>
年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。

【解答】 ×
改定の基準が逆です。正しくは次の通りです。
・68歳に到達する年度前(新規裁定者)→ 名目手取り賃金変動率
・68歳に到達した年度以後(既裁定者) → 物価変動率
(法第27条の2)

今回の指標は、
・ 物価変動率 → 0.0%
・ 名目手取り賃金変動率 → ▲0.1%
となりました。賃金がマイナスになっていることに注目してください。
ポイント!
既裁定者は原則として「物価変動率」が基準ですが、令和3年4月より、『物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、「名目手取り賃金変動率」を基準とする。』と改正されています。(法第27条の3)
今回は、「名目手取り賃金変動率がマイナス0.1%、物価変動率は0.0%」です。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っていますので上の条件に当てはまり、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されています。
つまり、令和3年度は、新規裁定者・既裁定者とも、『名目手取り賃金変動率(▲0.1%)』を基準に改定されています。
令和2年度の改定率が「1.001」でしたので、そこからマイナス0.1%して、今年度の改定率は「1.000」です。
ちなみに、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚年 【令和3年4月改正】脱退一時金の改正
R3-311
R3.6.30 【厚年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ
国民年金法と同じように、厚生年金保険法の脱退一時金も改正されました。
上限年数が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられています。
 国民年金法の脱退一時金の改正はこちらからどうぞ
国民年金法の脱退一時金の改正はこちらからどうぞ
→ R3.6.27 【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ
条文を穴埋めでチェックしましょう!
★空欄を埋めてください。
法附則第29条 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。
支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。)の属する年の前年< A >月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年< A >月の保険料率)に< B >を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

【解答】
A 10
B 2分の1
(法附則第29条)
 厚生年金保険の脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。
厚生年金保険の脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。
「支給率」は、『最終月の保険料率×2分の1×政令で定める数』です。
『政令で定める数』は以下の通りです。(最終月が令和3年4月以降の場合)
| 被保険者であった期間 | |
|---|---|
| 6月~12月 | 6 |
| 12月~18月 | 12 |
| 18月~24月 | 18 |
| 24月~30月 | 24 |
| 30月~36月 | 30 |
| 36月~42月 | 36 |
| 42月~48月 | 42 |
| 48月~54月 | 48 |
| 54月~60月 | 54 |
| 60月以上 | 60 |
(施行令第12条の2)
★ 例えば最終月が令和3年4月で、被保険者であった期間が60月以上の場合の支給率は、「18.3%×2分の1×60」≒5.5となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚年 【改正】標準報酬月額の上限
R3-310
R3.6.29 【厚年】標準報酬月額の最高等級の引上げ
 令和2年9月より、標準報酬月額の最高等級が引き上げられています。
令和2年9月より、標準報酬月額の最高等級が引き上げられています。
条文を穴埋めでチェックしましょう!
★空欄を埋めてください。
第20条
毎年< A >における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の< B >に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< C >から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】
A 3月31日
B 100分の200
C 9月1日
(法第20条)
ポイント!
厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級は「第32級 650,000円」になりました。
(令和2年9月より R2.8.14政令第246号)
厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級(88,000円)~第32級(650,000円)です。
ちなみに、健康保険法は 第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)です。
では、こちらもどうぞ!
<H24年出題>(修正)
被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする。

【解答】
<H24年出題>(修正) ×
厚生年金保険の標準賞与額は、『被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。』と規定されています。
厚生年金保険の標準賞与額の上限は月150万円です。
(法第24条の4)
問題文は、健康保険の標準賞与額の決定方法です。健康保険法の場合は、年度の累計で573万円までです。(健保法第45条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和3年度の国民年金保険料
R3-309
R3.6.28 【国年】令和3年度の保険料の計算根拠
令和3年度の国民年金保険料の計算根拠が今日のテーマです。
まずはこちらをどうぞ!
令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料の額は、< A >に保険料改定率を乗じて得た額(その額に< B >円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< B >円以上< C >円未満の端数が生じたときは、これを< C >円に切り上げるものとする。)とする。

【解答】
A 17,000
B 5
C 10
令和元年度以後の保険料は、「17,000円×保険料改定率」で計算します。
端数は、5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。(保険料額は10円単位まで)
さて、令和3年度の保険料改定率は「0.977」ですので、
令和3年度の国民年金の保険料は、17,000円×0.977
10円未満を四捨五入で端数処理して、「16,610円」です。
★「保険料改定率」の改定基準は?
保険料改定率は、「前年度保険料改定率 × 名目賃金変動率」となります。
名目賃金変動率は、簡単に言うと「物価変動率 × 実質賃金変動率」です。
 保険料の改定は「保険料改定率」。保険料改定率は、名目賃金変動率を基準にしています。
保険料の改定は「保険料改定率」。保険料改定率は、名目賃金変動率を基準にしています。
一方、年金額の改定は「改定率」。改定率は、原則として、新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者は「物価変動率」が基準になります。
名目手取り賃金変動率は、簡単に言うと、「物価変動率 × 実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」です。
「名目賃金変動率」と「名目手取り賃金変動率」は違うので注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国年 【令和3年4月改正】脱退一時金の改正
R3-308
R3.6.27 【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ
令和3年4月の脱退一時金の改正が今日のテーマです。
脱退一時金の支給額の計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
特定技能1号の創設で期限付きの在留期間の最長期間が5年となったこと、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等による見直しです。
まずは条文の穴埋めをどうぞ!
附則第9条の3の2 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第3項 脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に< A >を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。

【解答】
A 2分の1
◇脱退一時金の額の計算式
基準月の保険料額×2分の1×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数
政令で定める数は施行令14条の3の2に次のように規定されています。
| 6月以上12月未満 | 6 |
| 12月以上18月未満 | 12 |
| 18月以上24月未満 | 18 |
| 24月以上30月未満 | 24 |
| 30月以上36月未満 | 30 |
| 36月以上42月未満 | 36 |
| 42月以上48月未満 | 42 |
| 48月以上54月未満 | 48 |
| 54月以上60月未満 | 54 |
| 60月以上 | 60 |
 6の倍数なので覚えやすいです。
6の倍数なので覚えやすいです。
★例えば、基準月が令和3年度にあり、保険料納付済期間等の月数が60月の場合の脱退一時金の額は、
16,610円(令和3年度の保険料額)×2分の1×60=498,300円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国年 【令和3年4月改正】寡婦年金
R3-307
R3.6.26 寡婦年金の改正されたところをチェック
今日は、「寡婦年金」の改正点をチェックしましょう。
まずは条文の穴埋めをどうぞ!
第49条 寡婦年金の支給要件
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が < A >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< A >年以上継続した< B >の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、老齢基礎年金又は< C >の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。

【解答】
A 10
B 65歳未満
C 障害基礎年金
令和3年4月の改正点は?
・改正前
死亡した夫が、「障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は寡婦年金は支給されない
↓
・改正後
「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したとき」は寡婦年金は支給されない
◇改正で、死亡した夫の障害基礎年金の受給状況の条件が、老齢基礎年金と同じになりました。
◇改正前は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、実際に障害基礎年金を受けていなくても、寡婦年金は支給されませんでした。(夫が障害基礎年金の受給権者であったというだけで寡婦年金は支給されなかった)
改正後は、夫に障害基礎年金の受給権があったとしても、実際に障害基礎年金を受けていない場合は、寡婦年金は支給されることになりました。
ちなみに、「障害基礎年金の受給権があるが、実際に障害基礎年金を受けていない」ってどんなとき? → 『障害基礎年金の受給権発生日と死亡日が同じ月』のときです。
こちらもどうぞ!
①<H20年出題>
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
②<H20年出題>
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。

【解答】
①<H20年出題> ×
「60歳以上65歳未満の妻」ではなく「65歳未満の妻」が対象です。
妻が60歳未満の場合は、60歳から寡婦年金が支給されます。(②の問題)
(法第49条)
②<H20年出題> 〇
寡婦年金は60歳から65歳まで支給される有期年金です。
年金は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から、「権利が消滅した日の属する月」まで支給されます。
寡婦年金は夫の死亡によって支給されるので、60歳以上の妻の場合は、「夫の死亡した日の属する月の翌月」から支給されます。夫の死亡当時に妻が60歳未満の場合は、「妻が60歳に達した日の属する月の翌月」から支給を始める、と規定されています。
そして寡婦年金は65歳で失権しますので、最大で「65歳に達した日の属する月」まで支給されます。
(法第18条、第49条3項、51条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 被保険者証のこと
R3-306
R3.6.25 健保 被保険者証のフロー
今日のテーマは、被保険者証のフローです。
従業員が入社した場合、事業主は資格取得届を提出します。
提出先は、「全国健康保険協会」(協会けんぽ)の場合は日本年金機構へ、「健康保険組合」の場合は「健康保険組合」です。
昨日お話しましたように、資格取得届が提出されると、協会けんぽの場合、厚生労働大臣が確認を行います。協会けんぽは、その情報の提供を受けて、被保険者証を交付します。
健康保険組合の場合は、健康保険組合で資格取得の確認を行い、被保険者証を交付します。
まずはこちらからどうぞ!
①<H23年出題>
厚生労働大臣は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、健康保険法施行規則の規定による被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期間を定めて交付するものとする。
②<H26年出題>
被保険者資格証明書の交付を受けた全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般被保険者が、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

【解答】
①<H23年出題> 〇
ポイント! 「被保険者資格証明書」は協会けんぽのみ。健保組合にはありません
「協会けんぽ」の場合、年金機構に資格取得届を提出して、厚生労働大臣が確認→協会けんぽに情報提供→協会けんぽから被保険者証を交付、という流れになるので、被保険者証の交付まで時間がかかります。
「被保険者資格証明書」は、被保険者証が交付されるまでの間に病院で療養を受ける必要がある場合、事業主又は被保険者からの求めがあった場合に交付されます。
被保険者資格証明書は、協会けんぽではなく「厚生労働大臣」が交付する点にも注意してください。
(則第50条の2)
②<H26年出題> 〇
被保険者資格証明書は、被保険者証の交付を受けたときなどは使えなくなるので、返納します。返納は、事業主を経由することがポイントです。
(則第50条の2)
こちらもどうぞ!
③<R1年出題>
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効である。
④<H27年出題>
健康保険法施行規則においては、保険者は3年ごとに一定の期日を定め、被扶養者に係る確認をすることができることを規定している。

【解答】
③<R1年出題> 〇
施行規則第50条で、「保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。」と規定されています。
④<H27年出題> ×
3年ごとではなく「毎年一定の期日を定め」です。被扶養者が就職するなどで扶養の状況は変化することもあるので、現に扶養に該当するかどうかチェックできるという仕組みです。
(則第50条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 資格得喪の確認
R3-305
R3.6.24 健保 資格の得喪の確認
今日のテーマは、資格得喪の確認です。
ところで、健康保険には「確認」の制度がありますが、労災保険には「確認」はありません。
なぜなら、労災保険は「労働者」であれば全て保護されるからです。そのため、労災保険には資格取得届もありません。
(ちなみに、国民年金にも「確認」という制度はありません。)
まずは穴埋めで確認しましょう!
第39条 資格得喪の確認
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては< A >、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。)の確認によって、その効力を生ずる。
ただし、任意適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。
確認は、資格の取得及び喪失の届出若しくは被保険者又は被保険者であった者からの請求により、又は職権で行うものとする。

【解答】
A 厚生労働大臣
この条文で「保険者等」とは厚生労働大臣と健康保険組合を指します。厚生労働大臣は保険者ではないので、「等」がついています。
(法第39条、附則第3条)
★例えば、6月24日に入社しても、事業主が届出をしないままだと、保険者等は入社の事実を知らないので、健康保険の資格は取得できません。
「確認」とは、事業主からの届出等によって入社の事実を保険者等に知ってもらい、それによって、健康保険の被保険者としての効力が発生するというものです。(退職の場合も同じ)
確認の方法は、①事業主からの届出、②被保険者又は被保険者であった者からの請求、③職権の3つです。
★「任意適用の取消しによる被保険者の資格の喪失」の場合は、任意適用取消しの厚生労働大臣の認可があった日の翌日に資格を喪失すると決まっているので、確認の必要はありません。
また、任意継続被保険者と特例退職被保険者は、資格得喪の理由が入社や退職ではないので、こちらも確認はいりません。
こちらもどうぞ!
①<H21年出題>
被保険者の資格の取得及び喪失は、健康保険組合の被保険者については当該健康保険組合が、全国健康保険協会の被保険者については全国健康保険協会が、それぞれ確認することによってその効力を生ずるが、任意継続被保険者及び特例退職被保険者の被保険者資格の得喪については保険者等の確認は行われない。
②<H26年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる。
③<H30年出題>
任意適用事業所の適用の取消しによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者及び特例退職被保険者の資格の喪失の要件に該当した場合は、被保険者が保険者等に資格喪失の届書を提出しなければならず、当該資格喪失の効力は、保険者等の確認によって生ずる。

【解答】
①<H21年出題> ×
全国健康保険協会の被保険者の確認は全国健康保険協会ではなく「厚生労働大臣」が行います。(上の穴埋めの部分です。)
法第5条で、『全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。』と規定されています。
※なぜ「厚生労働大臣」が出てくるのか?
適用事業所に入社した場合、健康保険と厚生年金保険はセットで加入します。厚生年金保険と健康保険で重なる事務は、厚生年金保険の事務を行う厚生労働大臣がまとめて行うということです。
( )で、任意継続被保険者が除かれているのは、任意継続被保険者は、退職しているため厚生年金保険とセットで加入することが無いからです。
②<H26年出題> ×
確認は要りません。
③<H30年出題> ×
同じく、保険者等の確認は要りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
健保 任意継続被保険者の標準報酬月額
R3-304
R3.6.23 任意継続被保険者の標準報酬月額
今日のテーマは、「任意継続被保険者の標準報酬月額」です。
ではどうぞ!
①<R1選択>
任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の< A >全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

【解答】
A 9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する
(法第47条)
※令和3年度の、協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は令和2年度と同じ30万円です。(令和2年9月30日時点の標準報酬月額の平均額は290,274円だそうです。)
こちらもどうぞ!
②<H15年出題>
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
③<H30年出題>
一般の被保険者に関する保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
②<H15年出題> 〇
★在職中
| 保険料の負担 | 被保険者と事業主は、それぞれ2分の1を負担 |
| 納付義務 | 事業主が負う |
★退職後(任意継続被保険者)
| 保険料の負担 | 任意継続被保険者が全額負担 |
| 納付義務 | 任意継続被保険者が負う |
(法第161条)
③<H30年出題> ×
初めて納付すべき保険料の期限が誤りです。
★保険料の納期限
| 在職中 | 翌月末日 |
| 任意継続被保険者 | その月の10日 ※初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日 例えば、6月23日に任意継続被保険者の資格を取得した場合、6月から任意継続被保険者として保険料が徴収されるが、既に6月10日を過ぎているから。 |
(法第164条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 延滞金の割合の特例
R3-303
R3.6.22 徴収法の延滞金(延滞金の割合の特例)
今日のテーマは、「延滞金の割合の特例」です。
まずは条文から確認しましょう。
徴収法第28条第1項 (延滞金)
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその< A >までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から < B >月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が< C >円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

【解答】
A 完納又は財産差押えの日の前日
B 2
C 1,000
(徴収法第28条)
延滞金の割合については特例があります
<延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合について>
各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、
・ 年14.6%の割合 → 延滞税特例基準割合+年7.3%
・ 年7.3%の割合 → 延滞税特例基準割合+年1%(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)
とすることになっています。
(附則第12条)
さて、令和3年の「延滞税特例基準割合」は、1.5%です。
ですので、令和3年の延滞金の割合は、年8.8%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。
※ 1.5+7.3=8.8%、1.5+1=2.5%です。
★ ちなみに、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法では、年8.8%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。2月ではなく「3月」ですのでご注意ください。
練習問題をどうぞ
『徴収法 延滞金の割合の特例について』
令和3年の延滞金の割合は年< D >%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年< E >%)となる。

【解答】
D 8.8
E 2.5
こちらもどうぞ!
①<H29年出題(雇用)>
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
②<H25年出題(雇用)>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

【解答】
①<H29年出題(雇用)> 〇
督促状に指定された期限までに徴収金を完納すれば、延滞金は徴収されません。
(法第28条)
②<H25年出題(雇用)> ×
督促状の「指定した期限の翌日」ではなく、本来の「納期限の翌日」から計算されます。よく出るひっかけ問題ですので注意してください。
(法第28条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 令和2年9月改正 その2
R3-302
R3.6.21 (改正)メリット収支率の算定
労災保険法の改正で「複数業務要因災害」が加わりましたが、「メリット収支率」の算定には算入する?しない?が今日のテーマです。
メリット収支率とは?
メリット収支率とは、簡単に言うと、「保険料の額」に対する「保険給付の額(特別支給金含む。)」の割合です。政府から見ると、収入(保険料)に対する支出(保険給付+特別支給金)の割合です。そして、どちらも「業務災害」に係る額であることがポイントです。
この割合が高い(=労働災害の発生率が高い)場合、具体的には100分の85を超えると、保険料率が上がります。
逆にこの割合が低い(=労働災害の発生率が低い)場合、具体的には100分の75以下の場合は、保険料率が下がります。
※メリット制が適用されるには、継続性(3年)、規模(100人以上など)の要件もあります。(継続事業(一括有期事業を含む)の場合)
では、「複数事業労働者」、「複数業務要因災害」とメリット制の関係は?
★複数業務要因災害 → メリット収支率の計算には算入しません
「複数業務要因災害」の場合は、どの事業場においても業務と疾病等との間に相当因果関係が認められないからです。
→ 通勤災害、二次健康診断等給付も今まで通り、算入しません。メリット収支率は「業務災害」で算定します。
★複数事業労働者の業務災害 → 「災害発生事業場における賃金額」をもとに算定した額に相当する額のみを算入します。
こちらもどうぞ!
①<H24年出題(労災)>
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。
②<H24年出題(労災)>
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③ 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
③<H25年出題(労災)>
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

【解答】
①<H24年出題(労災)> 〇
メリット制のポイント! その1 継続性の要件
連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日に、労災保険の保険関係の成立後3年以上経過していること
(法第12条)
②<H24年出題(労災)> 〇
メリット制のポイント! その2 規模の要件
連続する3保険年度中の各保険年度において、
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100未満の労働者を使用する事業であって所定の要件(災害度係数が0.4以上)を満たすもの
③ 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
(法第12条)
③<H25年出題(労災)> ×
メリット制のポイント! その3 収支率の要件
メリット制が適用されるのは、メリット収支率が85%を超え、又は75%以下であるとき
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 令和2年9月改正
R3-301
R3.6.20 (改正)労働保険徴収法~労災保険率の決定の基準
労災保険法の改正に伴い、徴収法では労災保険率の決定の基準が改正されています。
まずは、条文を確認しましょう。
徴収法第12条 (一般保険料に係る保険料率)
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び< A >に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去< B >年間の業務災害、< C >及び通勤災害に係る災害率並びに< D >に要した費用の額、< A >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【解答】
A 社会復帰促進等事業
B 3
C 複数業務要因災害
D 二次健康診断等給付
ポイント!
労災保険率を決定する基準に、「複数業務要因災害」が加わりました。
こちらもどうぞ!
①<H24年出題(労災)>
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。
②<H26年出題(労災)>
個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
③<H24年出題(労災)>
労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。

【解答】
①<H24年出題(労災)> ×
最高は、「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」の1000分の88です。1000分の100は超えていません。
ちなみに、最低は1000分の2.5です。
(則第16条、則別表第1)
②<H26年出題(労災)> ×
個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、②その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する、とされています。
事業の単位については、継続事業については、「同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業」として取り扱われます。
問題文の場合、「業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている」ので、それぞれが別個の事業として取り扱われます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
③<H24年出題(労災)> 〇
労働者派遣事業における事業の種類は、「派遣労働者の派遣先」での作業実態に基づき決定されます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法 令和2年10月改正
R3-300
R3.6.19 (改正)雇用保険~「給付制限期間」の短縮
正当な理由がなく、自己都合による退職をした場合の給付制限期間が短縮されています。令和2年10月1日以降の離職が対象です。
まずは、条文を確認しましょう。
雇用保険法第33条
被保険者が< A >によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で< B >の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、< B >の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

【解答】
A 自己の責めに帰すべき重大な理由
B 公共職業安定所長
ポイント!
| 離職理由 | 給付制限期間 | |
| ・自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された | 3か月 | |
| ・正当な理由なく自己の都合により退職した | R2年10月1日前 | 3か月 |
R2年10月1日 以降 | 2か月 ※ 5年間のうち 2回まで | |
※退職した日から遡って5年間のうちに2回以上( 離職日を基準とする )、正当な理由 なく自己の都合により退職(令和2年10月1日以降のものに限る)した者の給付制限期間は3か月となります。
※ 自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合の給付制限期間は、3か月となります。(従来通り)
(法第33条、 行政手引52205)
こちらもどうぞ!
①<H28年出題>
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
②<H23年出題>
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く)は、基本手当が支給されない。

【解答】
①<H28年出題> ×
基本手当が支給されないので、この間は失業の認定を行う必要ない、とされています。
(行政手引52205)
②<H23年出題> ×
給付制限期間の起算は、「当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日」ではなく「待期期間の満了後」です。 待期の満了の日の翌日から起算します。
(法第33条)
こちらもどうぞ!
③<R26年出題>
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。
④<R22年出題>
正当な理由がなく自己の都合によって退職したため、基本手当について離職理由に基づく給付制限を受けている受給資格者であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることとなった場合においては、当該公共職業訓練等を受ける期間について、技能習得手当を受給することができる。

【解答】
③<R26年出題> 〇
離職理由に基づく給付制限が行われる場合でも、公共職業安定所長の指示した公共職 業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は、 給付制限は行われないことになっています。そのため、公共職業訓練等の受講開始日以後は、 給付制限は行われず、基本手当が支給されます。
(法第33条、行政手引52205)
④<R22年出題> 〇
③の問題と同じです。離職理由に基づく給付制限中、基本手当が支給されない場合は技能習得手当も支給されません。
しかし、公共職業訓練等の受給開始日以後は、給付制限が解除され、基本手当が支給されます。その場合は、技能習得手当も支給されます。
(法第33条、第36条)
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
雇用保険法 令和2年8月改正
R3-299
R3.6.18 (改正)雇用保険~被保険者期間
「基本手当」を受給するには、原則として算定対象期間(離職の日以前2年間)に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること(特定受給資格者又は特定理由離職者は離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上)が条件です。
今回、「被保険者期間」のカウント方法が改正されました。
これまで、被保険者期間に算入される基準は「日数」だけでしたが、改正により、「労働時間」による基準も設定されました。
まずは、条文を確認しましょう。
雇用保険法第14条 (被保険者期間)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が < A >日以上であるものに限る。)を1か月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が< B >日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。
被保険者期間が12か月(特定受給資格者又は特定理由離職者については6か月)に満たない場合については、「賃金の支払の基礎となった日数が< A >日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が< C >時間以上であるものに限る。」とする。

【解答】
A 11
B 15
C 80
※離職日が令和2年8月以降であることが条件です。
・被保険者として雇用された期間を、資格の喪失の日の前日からさかのぼって 1か月ごとに区切り、区切られた 1 か月の期間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以ある月、又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上ある月を1か月として計算します。
また、このように区切ることによって、1か月未満の期間が生ずることがあります。その場合は、その1 か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が 80 時間以上あるときは、その期間を2分の1か月の被保険者期間として計算します。
(法第14条、 行政手引50103)
こちらもどうぞ!
①<H23年出題>
被保険者が平成23年7月31日に離職し、同年7月1日から7月31日までの期間に賃金支払いの基礎となった日数が13日あった場合、当該期間は1か月として被保険者期間に算入される。
②<H26年出題>
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

【解答】
①<H23年出題> 〇
問題文の場合、8月1日が資格の喪失日となります。(喪失応当日が各月の1日です。)
被保険者期間は、資格の喪失の日の前日からさかのぼって1か月ごとに区切りますので、7月31日~7月1日、6月30日~6月1日・・・と区切っていきます。
問題文の場合、7月1日から7月31日までの期間に賃金支払い基礎日数が13日あるので、1か月の被保険者期間として算入します。
(法第14条)
②<H26年出題> ×
問題文の場合、9月26日が資格の喪失日で、喪失応当日が各月の26日です。
9月25日~8月26日、8月25日~7月26日・・・と区切っていき、最後は4月25日~4月1日となります。
最後の1か月未満の期間は、その1か月未満の期間の日数が15 日以上、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11 日以上あれば、「2分の1か月」として計算しますので、「4月1日から4月25日までの期間」は2分の1か月となります。
※離職日が令和2年8月1日以降の場合は、「賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上」となります。
(法第14条)
こちらもどうぞ!
③<R1年出題>
一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。
④<H29年出題>
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

【解答】
③<R1年出題> ×
労働基準法第26条の規定による休業手当は「賃金」となります。問題文の場合、賃金の支払の基礎となった日数が17日となるので、被保険者期間に算入されます。
(行政手引50501)
④<H29年出題> ×
年次有給休暇に対して支払われた給与も「賃金」となります。問題文の場合は、賃金の支払の基礎となった日数が22日となりますので、被保険者期間として算入されます。
(行政手引50501)
社労士受験のあれこれ
労災保険法 令和2年9月改正その4
R3-298
R3.6.17 複数事業労働者の給付基礎日額~具体例
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
複数事業労働者とは → R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
複数業務要因災害とは → R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
複数事業労働者の給付基礎日額 → R3.6.16 複数事業労働者の給付基礎日額の算定について
今日のテーマは、複数事業労働者の給付基礎日額の具体例です。
まずは、労働基準法の平均賃金の出し方を確認しましょう。
労働基準法第12条
1.労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前< A >か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の< B >で除した金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下ってはならない。
① 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に< C >で除した金額の< D >
② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と①の金額の合算額
2. 1.の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

【解答】
A 3
B 総日数
C 労働した日数
D 100分の60
<原則>
算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(※就労日数ではなく、暦日数です)
<最低保障額> 時間額や日額、出来高給の場合
算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ 労働日数 × 100分の60
※注意点
・算定事由発生日の前日から遡ります。
・賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡ります。
複数事業労働者の給付基礎日額の注意点
<労働基準法の平均賃金の最低保障について>
・複数事業労働者の給付基礎日額相当額
→ 時給や日給制等の場合、労基法の規定では、平均賃金の算定について最低保障の適用があります。しかし、労災保険法では、特例により、労基法の規定による最低保障は適用しない金額を給付基礎日額相当額とする、とされています。
(具体例)
A社とB社の2社で就業している場合
A社 → 月給15万円
B社 → 日給1万円で月9日勤務
直近3カ月の総日数は90日
■計算式■
A社 → 15万円×3か月÷90日 = 5,000円
B社 → 1万円×9日×3か月÷90日 = 3,000円※
給付基礎日額は、A社(5,000円)+B社(3,000円)=8,000円となります。
※B社は日給制なので、労働基準法では平均賃金の最低保障額が適用されます。
最低保障は、(10,000円×9日)×3か月÷(9日×3か月)×100分の60 = 6,000円となります。しかし、労災則第9条第1項第4号に基づく給付基礎日額相当額の特例として、労基法第12 条第1項ただし書の規定(最低保障)の適用を受けないものとした場合の金額を、給付基礎日額相当額とすることになります。
ちなみに・・・
各事業場の「平均賃金の最低保障額」が「合算後の額」より高い場合
→各事業の平均賃金の最低保障額のうち、最も高い額が給付基礎日額となります。
参照:労災保険法第8条、則9条の2の2、令和2.8.21基発0821第2号
社労士受験のあれこれ
労災保険法 令和2年9月改正その3
R3-297
R3.6.16 複数事業労働者の給付基礎日額の算定について
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
今日のテーマは、複数事業労働者の給付基礎日額です。
複数事業労働者とは → R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
複数業務要因災害とは → R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
条文を確認しましょう。
第8条
① 給付基礎日額は、労働基準法第12条の< A >に相当する額とする。この場合において、< A >を算定すべき事由の発生した日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって< B >が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
② 労働基準法第12条の< A >に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、①の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。
③ ①、②の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者(葬祭を行う者)に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、①、②に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を< C >した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。

【解答】
A 平均賃金
B 疾病の発生
C 合算
ポイント!
給付基礎日額 = 労働基準法の平均賃金に相当する額
算定事由発生日 = ・負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日
・診断によって疾病の発生が確定した日
※複数事業労働者の給付基礎日額(原則)のポイント
複数事業労働者の業務上の事由による傷病等 (業務災害) | 複数事業労働者を使用する全事業における賃金をもとに給付基礎日額を算定する |
複数事業労働者(複数事業労働者に類する者を含む。)の2以上の事業の業務を要因とする事由による傷病等(複数業務要因災害) | |
| 複数事業労働者の通勤による傷病等(通勤災害) |
※複数事業労働者は複数の事業で働くことによって生計を立てているため、労災保険の保険給付もすべての事業の賃金を合算して算定するという考え方です。
※ 複数事業労働者に関する保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額(以下「給付基礎日額相当額」という。)を合算した額を基礎として算定します。
(令和2.8.21基発0821第2号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
労災保険法 令和2年9月改正その2
R3-296
R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
労災保険法の主たる事業は「保険給付」で、それに付随するものとして「社会復帰促進等事業」があります。
労災保険法の改正によって、「保険給付」は4つに分かれることになりました。
<保険給付の種類>
| 業務災害に関する保険給付 |
| 複数業務要因災害に関する保険給付 |
| 通勤災害に関する保険給付 |
| 二次健康診断等給付 |
今日は、新しく加わった「複数業務要因災害」がテーマです。
では、どうぞ!
空欄を埋めてください。
第7条
労災保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 < A >(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< B >」という。)に関する保険給付(1の業務災害を除く。)
3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
4 二次健康診断等給付

【解答】
A 複数事業労働者
B 複数業務要因災害
ポイント! 複数業務要因災害とは?
複数業務要因災害 → 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のこと。ただし、「業務災害」の場合は除かれます。
★さらにポイント
・複数業務要因災害の範囲 → 対象の傷病は「脳・心臓疾患、精神障害」
複数業務要因災害による疾病の範囲は、則第18条の3の6で、『労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(「脳・心臓疾患、精神障害」)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病』と規定されています。現時点で想定されているのは、脳・心臓疾患、精神障害です。
★複数業務要因災害のポイント色々
・複数業務要因災害に関する保険給付
「業務災害」は、1つの事業の業務上の負荷(労働時間やストレス)だけで労災認定をします。
このたび新しく加わった「複数業務要因災害」は、単独の事業場の負荷だけでは労災認定されなくても、複数の事業の業務上の負荷を総合的に評価することによって、労災認定されるものです。
「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡の間に因果関係が認められることをいいます。
・労働基準法の災害補償責任
1つの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないので、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負いません。
(令和2.8.21基発0821第1号)
★複数業務要因災害に関する保険給付の種類
1 複数事業労働者療養給付
2 複数事業労働者休業給付
3 複数事業労働者障害給付
4 複数事業労働者遺族給付
5 複数事業労働者葬祭給付
6 複数事業労働者傷病年金
7 複数事業労働者介護給付
(法第20条の2)
 ちなみに、これまでは、業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、療養(補償)給付のように略称していました。今後は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するそうです。
ちなみに、これまでは、業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、療養(補償)給付のように略称していました。今後は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するそうです。
(令和2.8.21基発0821第1号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
労災保険法 令和2年9月改正その1
R3-295
R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
<改正のポイント>
・複数事業労働者に関する保険給付について
→ すべての事業場の賃金を合算した額を基礎として給付基礎日額を決定する
・1つの事業における業務上の負荷(労働時間やストレス等)のみでは業務と疾病等の間に因果関係が認められない場合
→ すべての事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断する
では、どうぞ!
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

【解答】
A 複数事業労働者
ポイント! 複数事業労働者とは?
複数事業労働者 → 事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のこと
簡単に言うと、算定事由発生日にA社とB社というように、複数の事業場で働いている労働者のことです。
★さらにポイント
労災法第7条第1項第2号で、複数事業労働者には「これに類する者も含む」とされています。
「これに類する者」の範囲は、則第5条で「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」と定められています。
注目ポイントは、傷病等の発生時ではなく、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点」に2以上の事業に同時に使用されていたという点です。
複数業務要因災害の対象である複数事業労働者について、傷病等が発症した時点で、複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあるからです。これは、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症時期がずれることがあるためです。
例えば、傷病等が発症した時点では、「A社」だけで働いていたが、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時期」に、「A社」と「B社」で就業していたような場合も複数事業労働者になるということです。
★もう一つポイント
『「労働者」であってかつ他の事業場で「特別加入をしている者」』及び『複数の事業場において特別加入をしている者』も複数事業労働者として保護の対象となります。
(令和2.8.21基発0821 第1号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
労災 療養補償給付その2
R3-294
R3.6.13 療養補償給付よく出るところ その2
昨日に引き続き、労災保険の「療養補償給付」です。
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等という。」において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
②<H21年出題>
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

【解答】
①<R1年出題> 〇
ポイント! 療養の給付(現物給付)は、指定病院等で
療養の給付が受けられるのは「指定病院等」です。
指定病院等とは
・ 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院のこと)
・ 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者 (労災保険指定医療機関・薬局等)
です。
指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われません。
(則第11条)
②<H21年出題> ×
ポイント! 療養の給付が原則、療養の費用の支給は例外
療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とされていて、例えば、近くに指定病院等がないような場合です。
問題文のように、指定病院等でない病院等での療養を望んだとしても、それだけでは療養の費用の支給の対象にはなりません。
(則11条の2、昭41.1.31基発第73号)
こちらもどうぞ!
③<H27年出題>
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
④<H22年出題>(改正あり)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
A ①~⑧
B ②~⑧
C ③~⑧
D ③、④
E ③、④、⑦

【解答】
③<H27年出題> ×
請求書の提出について
療養の給付 → 指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出
療養の費用の支給 → 直接、所轄労働基準監督署長に提出
(則第12条)
④<H22年出題>(改正あり) D
事業主の証明を受けなければならないものは、「③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況」です。
※令和2年9月の改正により
・証明を受ける事業主から「非災害発生事業場の事業主」は除かれます。
・「⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨」が加わりました。
(則第12条の2)
社労士受験のあれこれ
労災 療養補償給付その1
R3-293
R3.6.12 療養補償給付よく出るところ その1
労災保険の「療養補償給付」には
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<H21年出題>
傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
②<H28年出題>
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
③<H27年出題>
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

【解答】
①<H21年出題> 〇
ポイント!
療養補償給付、療養給付は「治ゆ」するまで
療養補償給付(療養給付)は、治療の必要がなくなるまで行われます。
例えばケガの場合は、傷口が治った状態をイメージしてください。治ゆとは、「症状固定」の状態をいいます。「傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合」です。
(昭23.1.13基災発第3号)
②<H28年出題> ×
いったん、症状固定(治ゆ)が認められれば療養補償給付(療養給付)は終了しますが、再び発症し一定の要件を満たせば、「再発」となり、療養補償給付(療養給付)が再開されます。
③<H27年出題> ×
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になれば、療養の給付は終了します。
では、こちらもどうぞ!
④<H24年出題>
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
⑤<H24年出題>
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
④<H24年出題> 〇
療養補償給付も休業補償給付も「治ゆする前」の給付です。治療で休んでいる間は、療養補償給付と休業補償給付の両方を受けることができます。
⑤<H24年出題> 〇
傷病補償年金も「治ゆする前」の給付ですので、治療を受けながら(療養補償給付を受けながら)、受給することができます。
最後に条文を確認しましょう。
空欄を埋めてください。
第13条
① 療養補償給付は、療養の給付とする。
② ①の療養の給付の範囲は、次の各号(< A >が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 < B >
③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて< C >することができる。

【解答】
A 政府
B 移送
C 療養の費用を支給
社労士受験のあれこれ
安衛 労働者死傷病報告書
R3-292
R3.6.11 労働者死傷病報告書よく出るところ
労働者が労働災害等により死亡又は休業した場合、事業者には労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出する義務があります。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②<H20年出題>
事業者は、労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③<H25年出題>
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①<H29年出題> 〇
労働者死傷病報告書の提出が必要なのは、「労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業」したときです。
その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも、事業場内における負傷の場合は、労働者死傷病報告書を提出しなければなりません。
(則第97条)
②<H20年出題> 〇
「労働者が事業場内において負傷、窒息又は急性中毒」より休業した場合は、労働者死傷病報告書の提出が必要です。
③<H25年出題> ×
休業日数が2日の場合は、「遅滞なく」は誤りです。
■労働者死傷病報告書の提出
ポイント! 「4日以上」と「4日未満」で提出期限が違います。
・休業4日以上の場合 → 遅滞なく
・休業4日未満の場合
1月~3月 → 4月末日
4月~6月 → 7月末日
7月~9月 → 10月末日
10月~12月 → 1月末日
穴埋めで確認しましょう!
(労働者死傷病報告)
① 事業者は、労働者が< A >その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、< B >又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、 < C >、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
② ①の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の < D >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
A 労働災害
B 窒息
C 遅滞なく
D 翌月末日
(則第97条)
社労士受験のあれこれ
安衛 作業主任者
R3-291
R3.6.10 「作業主任者」でおさえておきたいところ
「作業主任者」は、事業場単位ではなく作業場所単位で選任します。
作業主任者は、一定の危険、有害な作業を行う現場で、作業の指揮や設備等の管理を行います。
では、どうぞ!
①<H22年出題>
事業者は、高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業に限る。)については作業主任者を選任しなければならないが、当該作業主任者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高圧室内作業主任者技能講習を修了したものでなければならない。

【解答】
①<H22年出題> ×
高圧室内作業主任者は、技能講習の修了ではなく「免許」が要件です。
ポイント!
★作業主任者の資格には、①都道府県労働局長の免許を受けた者、②都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、の2種類があります。
(法第14条)
ついでに、こちらもどうぞ!
「作業主任者」について空欄を埋めてください。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により< A >させなければならない

【解答】
A 関係労働者に周知
作業主任者を選任したときは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」を関係労働者に周知する義務があります。
<ポイント>
・ 作業主任者の場合、選任の期限や労働基準監督署長への選任報告義務はありません。
・ 周知するのは、「作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項」です。
ちなみに、安全衛生推進者、衛生推進者の場合は、周知するのは「氏名」(「その者に行なわせる事項」は入っていない)です。
(則第18条)
罰則もチェック✔
施行令第6条で定める作業について、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行わせなかった事業者に対して、 < B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 ②50万円以下の罰金 >に処する。

【解答】
B ①6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
作業主任者を選任しなかった場合の罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」。懲役の可能性もあることがポイントです。
一方、総括安全衛生管理者、安全管理者、産業医等については、選任しなかった場合の罰則は、「50万円以下の罰金」。懲役はつきません。
(法第119条)
社労士受験のあれこれ
安衛 常時50人未満の事業場
R3-290
R3.6.9 産業医を選任すべき事業場以外の事業場
常時50人以上の事業場は、業種を問わず、産業医を選任する義務があります。
今日は50人未満の事業場=産業医の選任義務がない事業場がテーマです。
では、どうぞ!
①H26年出題のアレンジです。空欄を埋めてください。
事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働安全衛生法第13条第1項に定める労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する< A >に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

【解答】
A 保健師
■産業医の選任義務のない事業場(常時50人未満)
・労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師
又は
・労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師
に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
※努力義務なのでその点にも注意してください。
(法第13条の2、則第15条の2)
ついでに、こちらもどうぞ!
②保健指導等
事業者は、一般健康診断又は深夜業に従事する労働者の自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は< B >による < C >を行うように努めなければならない。

【解答】
B 保健師
C 保健指導
(法第66条の7)
社労士受験のあれこれ
労働基準法 切り上げ切捨て
R3-289
R3.6.8 労基法・端数処理どこまで認められる?
今日は、労働基準法の端数処理はどこまで認めらるのか?がテーマです。
労働基準法には、「全額払いの原則」(労働した分は100%支払う)がありますが、計算の便宜上、一定のラインまでは端数処理が認められています。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
②<H25年出題>
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
①<H19年出題> ×
「1日」ごとに設問のような端数処理を行うのは、全額払いに原則に反します。
違反とならない端数処理は、
「1か月」の時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計の1時間未満の端数 → 30分未満切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
(昭63.3.14基発150号)
②<H25年出題> ×
問題文の最初の「1日」が誤りです。
時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、「1日」単位は不可、「1か月」ならOKです。(①の問題と同じ)
問題の後半は〇です。
・ 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額の円未満の端数
→ 50銭未満切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
・ 1か月の時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端 数 → 50銭未満切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
こちらも、どうぞ!
③<H29年出題>
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。
④<H24年出題>
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
③<H29年出題> 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)の100円未満の端数 → 50円未満切り捨て、それ以上を100円に切り上げる(OK)
④<H24年出題> 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)の千円未満の端数 → 翌月の賃金支払日に繰り越して支払う(OK)
③と④は、現金払いのときに封筒の中で小銭がジャラジャラたくさんにならないように、というイメージで覚えてください。
社労士受験のあれこれ
労働基準法 休業手当
R3-288
R3.6.7 休業手当の支払義務がある日・ない日
今日は、労働基準法「休業手当」です。
休業手当の支払義務が発生する日はどんな日なのでしょうか?
では、どうぞ!
<H27年出題>
■■問題文の労働者の労働条件■■
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
A 使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日間の休業手当を支払わなければならない。
B 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
C 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
D 休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労総契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。
E 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
A ×
ポイント!
「休日」=労働する義務のない日。もともと労働の予定のない日なので、休業手当を支払う義務はありません。
問題文の場合、所定休日の土曜日と日曜日には休業手当を支払う義務はありませんので、5日間の休業手当を支払うことになります。
(昭24.3.22基収4077号)
B 〇
ポイント!
一労働日の一部だけ休業した場合は、全体として平均賃金の100分の60まで支払わなければならない。
問題文の場合、労働基準法で義務付けられるのは、平均賃金(10,000円)×100分の60=6,000円以上です。
4時間の労働で7,500円の支払がなされているので、休業手当をプラスして支払う必要はありません。
しかし、例えば、使用者の責に帰すべき事由でその日の労働時間が1時間に短縮され、その日の賃金が1,875円の場合は、休業手当として6,000円との差額(4,125円)を支払わなければなりません。
(昭27.8.7 基収3445号)
C 〇
ポイント!
「休日」は休業手当の支払義務はありません。(Aと同じです。)
問題文の場合、振替によって、日曜日が「労働日」、水曜日が「休日」となっているので、水曜日に休ませても休業手当の支払義務はありません。
(昭24.3.22基収4077号)
D 〇
ポイント!
特定の労働者に対して、その意思に反して就業を拒否する場合も、「休業手当」の支払義務の対象です。
ちなみに、「休業」は丸一日とは限りません。Bの問題のように1日の一部だけ休業する場合も含まれます。
E 〇
ポイント!
休電による休業については、原則としての使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しません。
休業手当を支払わなくても、26条違反にはなりません。
(昭26.10.11基発696号)
社労士受験のあれこれ
出来高払い制の保障給
R3-287
R3.6.6 労基法・出来高払いの保障給は何に対する保障なの?
今日は、労働基準法第27条「出来高払い制の保障給」です。
では、どうぞ!
①<R1年選択>
労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。

【解答】
A 労働時間
出来高払制の労働者の場合、本人は出勤していても、材料などが不足していると出来高が上がらず、そうすると賃金が支払われなくなります。
そのようなことのないよう、「労働時間」に応じ、一定額の保障をしなければならないことになっています。
ですので、労働者が労働者の責に帰すべき事由で「就業しなかった」(=労働時間が無い)場合は、保障給も支払う必要はありません。
(法第27条、昭23.11.11基発1639号)
では、こちらをどうぞ!
②<H26年出題>
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障することにある。
③<H28年出題>
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

【解答】
②<H26年出題> ×
「その出来高や成果」ではなく、「労働時間」に応じた賃金の支払を保障することが趣旨です。
③<H28年出題> 〇
「労働時間に応じた」一定額の賃金の保障が必要なので、原則は時間給となります。
「実労働時間の長短と関係なく」1か月について一定額を保障するものは、保障給とはいえません。
最後はこちらを
④<H13年出題>
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

【解答】
④<H13年出題> ×
出来高払制の保障給は「労働時間」に応じた保障を義務付けています。問題文のように休業している場合は、保障する必要はありません。
ただし、問題文のように「使用者の責に帰すべき事由によって休業」する場合は、「休業手当」を支払う義務があります。
社労士受験のあれこれ
国民健康保険法
R3-286
R3.6.5 国民健康保険 保険料を滞納したとき
今日は、国民健康保険法「保険料を滞納したとき」です。
滞納期間によって対応が変化します。
では、どうぞ!
①<H28年選択>
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。

【解答】
A 1年間
B 被保険者資格証明書
(法第9条)
ポイント!
1年間滞納 → 被保険者証の返還 → 被保険者資格証明書が交付される
次はこちらをどうぞ
②<R2年出題>
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

【解答】
②<R2年出題> 〇
ポイント!
・ 1年6か月滞納 → 保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止め
・ なお滞納している保険料を納付しない → 一時差し止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除できる
(法第63条の2)
では、最後にこちらをどうぞ!
③<R1年出題>
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
④<R1年出題>
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

【解答】
③<R1年出題> ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養費ではなく、「特別療養費」が支給されます。
療養の給付等の現物給付ではなく、いったん、全額自己負担し、後から保険給付分が償還払いされます。
(法第54条の3)
④<R1年出題> ×
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(問題文では15歳の子)には、被保険者資格証明書ではなく、有効期間が6か月の被保険者証が交付されます。
(法第9条)
社労士受験のあれこれ
社一 確定拠出年金法
R3-285
R3.6.4 確定拠出年金法の脱退一時金
今日は、確定拠出年金法の脱退一時金がテーマです。
では、どうぞ!
①<H20年出題>
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
①<H20年出題> 〇
~~給付の種類~~
・老齢給付金
・障害給付金
・死亡一時金
・脱退一時金(当分の間)
(法第28条、附則第2条の2、3条)
では、脱退一時金をどうぞ!
★企業型
当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。
1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
2. 個人別管理資産の額が< A >以下であること。
3. 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して< B >か月を経過していないこと。
★個人型
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
1. 国民年金の保険料免除者であること。
2. < C >の受給権者でないこと。
3. 通算拠出期間が1月以上< D >年以下であること又は個人別管理資産の額が < E >円以下であること。
4. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < F >年を経過していないこと。
5. 企業型の脱退一時金の支給を受けていないこと。

【解答】
A 15,000円
B 6
C 障害給付金
D 5
E 25万
F 2
※Dについて
改正により、1月以上3年以下から1月以上5年以下になりました。
(附則第2条の2、第3条、施行令第60条)
では、「確定給付企業年金法」と比較してみましょう!
確定給付企業年金法 (給付の種類)
① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
1 老齢給付金
2 < G >
② 事業主等は、規約で定めるところにより、①に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
1 障害給付金
2 < H >

【解答】
G 脱退一時金
H 遺族給付金
★確定給付企業年金の給付
・基本 → 老齢給付金、脱退一時金
・任意 → 障害給付金、遺族給付金
(法第29条)
社労士受験のあれこれ
社一 医療費適正化計画と介護保険事業計画
R3-284
R3.6.3 比較してみましょう・医療費適正化計画と介護保険事業計画
「医療費適正化計画」は高齢者医療確保法、「介護保険事業計画」は介護保険法で出てきます。
それぞれの計画のサイクルを覚えましょう。
では、どうぞ!
【高齢者医療確保法】
(医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画)
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定めるとともに、 < A >年ごとに< B >年を1期として、全国医療費適正化計画を定めるものとする。
(都道府県医療費適正化計画)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、< A >年ごとに、< B >年を1期として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとする。
(特定健康診査等基本指針)
厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
(特定健康診査等実施計画)
< C >(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、< A >年ごとに、< B >年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。
(特定健康診査)
< C >は、特定健康診査等実施計画に基づき、< D >歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。
【介護保険法】
(基本指針)
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(「基本指針」という。)を定めるものとする。
(市町村介護保険事業計画)
市町村は、基本指針に即して、< E >年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画という。)を定めるものとする。
(都道府県介護保険事業支援計画)
都道府県は、基本指針に即して、< E >年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。

【解答】
A 6
B 6
C 保険者
保険者 → 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う「全国健康保険協会」、「健康保険組合」、「都道府県及び市町村(特別区を含む。」、「国民健康保険組合」、「共済組合」、「日本私立学校振興・共済事業団」
D 40
E 3
では、こちらもどうぞ!
①<H30年出題>
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
②<H24年出題>
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
③<R1年出題>
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

①<H30年出題> 〇
「公表するよう努める」努力規定に注意しましょう。
(高齢者医療確保法第9条)
②<H24年出題> 〇
(高齢者医療確保法第10条)
③<R1年出題> 〇
「市町村介護保険事業計画」の問題です。
(介護保険法第117条)
社労士受験のあれこれ
労一 労働災害発生状況の分析等(厚生労働省)
R3-283
R3.6.2 令和2年労働災害発生状況の分析より
社労士試験では、平成30年に「平成28年労働災害発生状況の分析等」から出題されています。
今日は令和3年4月30日に公表された令和2年の労働災害発生状況を見ていきましょう。
では、どうぞ!
①死亡者数 概況
令和2年の労働災害による死亡者数は802人と3年連続 で< A ①過去最大 ②過去最少 >となった。 労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「第13次労働災害防止計画」(平成30年度~令和4年度)では、死亡者数を平成29年と比較して、令和4年までに15%以上減少させることとしているが、死亡者数は、同計画の目標を超えた減少となった。
②死傷者数 概況
令和2年の労働災害による休業4日以上の死傷者数は 131,156人となった。新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害は 6,041人となり、これを除くと 125,115 人となった。13次防では、死傷者数を平成29年と比較して、令和4年までに5%以上減少させることを目標としているが、13次防の重点業種で< B ①増加 ②減少 >し、全体では 8.9%の< B ①増加 ②減少 >となっており、同計画の目標<C ①を達成している ②の達成が困難な >状況となっている。
③死傷者数 年齢別
年齢別では、20歳未満を除く全ての年代で増加し、全死傷者数の約4分の1を占める「< D ①20歳~29歳 ②60 歳~ >」では 34,928人(前年比 1,213 人・3.6%増、平成29年比 4,901 人・16.3%増)となった。 なお、新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除くと、「50 歳 ~59 歳」(同 659 人・2.2%増・同 2,322 人・8.1%増)及び「60 歳~」(同 528 人・1.6%増・同 4,216 人・14.0%増)で増加した。

【解答】
①死亡者数 概況
A ②過去最少
令和2年1月~12月までの労働災害による死亡者数は、802人(前年比43人・5.1%減、平成29年比176人・18.0%減)と3年連続で過去最少となっています。
★「第13次労働災害防止計画」(平成30年度~令和4年度)では、死亡者数を平成29年と比較して、令和4年までに15%以上減少させることとしていて、死亡者数は、目標を超えた減少となっています。
ポイント! 死亡者数は3年連続過去最少
②死傷者数 概況
B ①増加
C ②の達成が困難な
令和2年の労働災害による休業4日以上の死傷者数 → 131,156 人(前年比 5,545 人・4.4%増、平成29年比10,696人・8.9%増)、新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害6,041人を除くと125,115 人(前年比 496 人・0.4%減、平成29年比 4,655 人・3.9%増)
★「第13次労働災害防止計画」では、死傷者数を平成29年と比較して、令和4年までに5%以 上減少させることを目標としていますが、「第13次労働災害防止計画」の重点業種※で増加し、全体では 8.9%の増加となっており、同計画の目標の達成が困難な状況となっています。
※死傷災害では、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店を重点事業としている。
ポイント! 休業4日以上の死傷者数は増加
③死傷者数 年齢別
D ②60歳~
・ 20歳未満を除く全ての年代で増加
・ 全死傷者数の約4分の1を占める「60歳~」では 34,928人(前年比 1,213 人・3.6%増、平成29年比 4,901 人・16.3%増)
・ 新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除くと、「50 歳 ~59 歳」(同 659 人・2.2%増・同 2,322 人・8.1%増)及び「60 歳~」(同 528 人・1.6%増・同 4,216 人・14.0%増)で増加
令和2年の労働災害発生状況はこちらをどうぞ(厚生労働省HP)
令和2年の労働災害発生状況を公表
社労士受験のあれこれ
労一 次世代育成支援対策推進法
R3-282
R3.6.1 子育てサポート企業といえば、くるみん、プラチナくるみん
「くるみん」とは
→ 「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた企業のマークです。
では、どうぞ!
①<H26年選択式>
一般雇用主であって、常時雇用する労働者が< A >以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。

【解答】
A 101人
常時雇用する労働者数が 101人以上の企業の義務
・一般事業主行動計画を策定(従業員の仕事と子育ての両立を図るため)
・一般への公表
・従業員への周知
・厚生労働大臣への届出
※100人以下の企業は努力義務です。
★ 一般事業主行動計画を策定したら
一定の基準を満たした企業は、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。その認定を受けた企業は「くるみんマーク」を取得できます。
さらに高い水準の取組を行っている企業は、「プラチナくるみんマーク」を受けることができます。
社労士受験のあれこれ
労一 障害者雇用促進法「もにす」
R3-281
R3.5.31 障害者雇用に取り組む優良中小事業主「もにす」
「もにす」とは
→ 障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度のマークです。
では、どうぞ!
①障害者雇用促進法
第77条(基準に適合する事業主の認定)
厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時< A >以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

【解答】
A 300人
中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下)が対象の制度です。
認定事業主になると、「障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにす)が使用できる」、「厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのホームページに掲載され、社会的認知度を高めることができる」などのメリットがあります。
ちなみに、「もにす」とは「共に進む」(ともにすすむ)という言葉からとったそうです。
社労士受験のあれこれ
障害 3級から2級への額の改定 その3
R3-280
R3.5.30 事後重症のポイント(国民年金)その2
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、国民年金の視点に戻ります。
事後重症は「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当、その期間内に請求するという条件がポイントでした。
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H22年出題>
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。
②<H30年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】
①<H22年出題> ×
問題文の場合、障害基礎年金に係る事後重症の請求は要りません。
障害の程度が増進し障害厚生年金の額が改定されたときは、そのときに事後重症の請求があったものとみなすことになっているからです。ですので、事後重症の請求をしなくても障害基礎年金が支給されます。(図1参照)
(法第30条の2)
②<H30年出題> ×
①の問題と同じく「障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない」の部分が誤りです。
障害厚生年金が3級から2級に改定されたときに、事後重症の請求をしたものとみなされます。
(法第30条の2)
社労士受験のあれこれ
図1
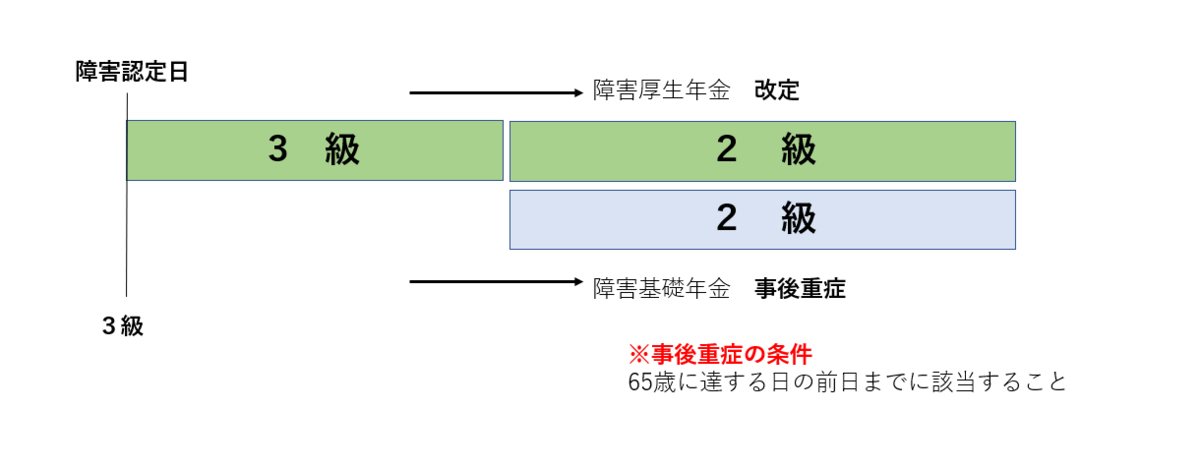
障害 3級から2級への額の改定 その2
R3-279
R3.5.29 厚生年金保険3級から1級2級へ額の改定
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、厚生年金保険の視点で見ていきましょう。
厚生年金保険の場合、障害等級は1級から3級までありますが、3級の場合は「障害厚生年金」のみ、1級、2級の場合は「障害基礎年金+障害厚生年金」です。
3級から2級・1級に障害の程度が増進すると、障害基礎年金がプラスされます。
ということは、
・障害厚生年金 → 3級から2級・1級に改定
・障害基礎年金 → 障害等級不該当から1・2級へ(事後重症)
となります。
昨日の記事でもお話しましたが、事後重症は「65歳に達する日の前日まで」という条件がありましたよね。ここが今日のポイントです。(図1参照)
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H27年出題>
63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合において、その後、障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
②<H16年出題>
2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、その後、3級の障害の状態になり、65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が支給される。
③<R2年出題>
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①<H27年出題> ×
老齢基礎年金を繰上げ受給しているので、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定は請求できません。
障害認定日に3級だった者が、その後障害の程度が増進した場合、3級から2級、1級への額の改定請求ができます。
同時に事後重症による障害基礎年金も支給されます。(図1参照)
ただし、事後重症の条件は、「65歳に達する日の前日までに該当」すること。
そのため、65歳すぎてから障害の程度が増進しても、事後重症の障害基礎年金が支給されないので、障害厚生年金も額の改定は行われません。(図2参照)
問題のように、65歳に達するまでの間でも、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合は、事後重症による障害基礎年金は支給されないので、障害厚生年金の額の改定も行われません。
(法第52条)
②<H16年出題> 〇
問題文の場合は、もともと1、2級の受給権がある(=障害基礎年金の受給権がある)ことがポイントです。
65歳以降に再び障害の程度が増進して2級の障害の状態になったとき、2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。なぜならば、障害基礎年金が事後重症ではないからです。
(図3参照)
③<R2年出題> ×
問題文の場合、65歳以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級の障害状態になった場合は、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。②の問題と同じです。
社労士受験のあれこれ
図1
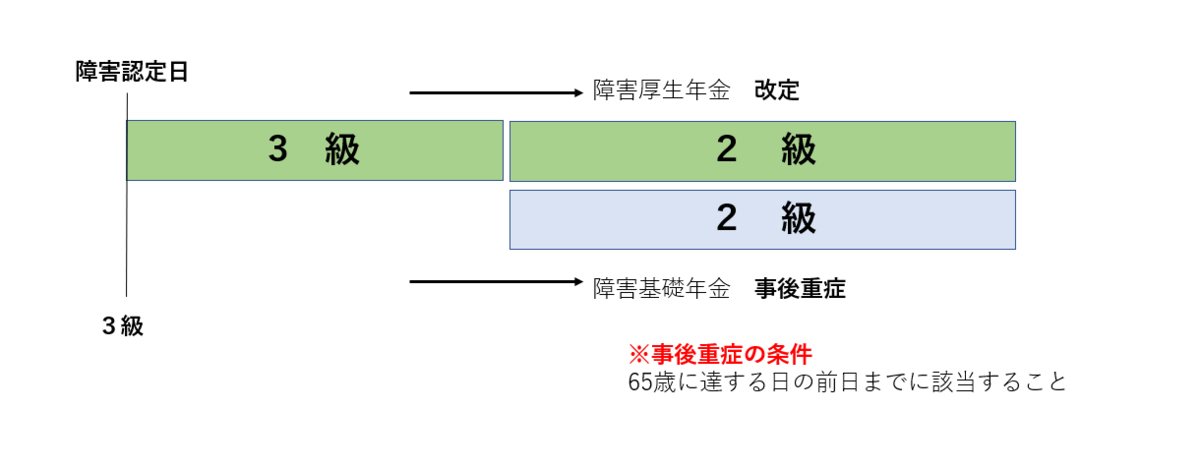
図2
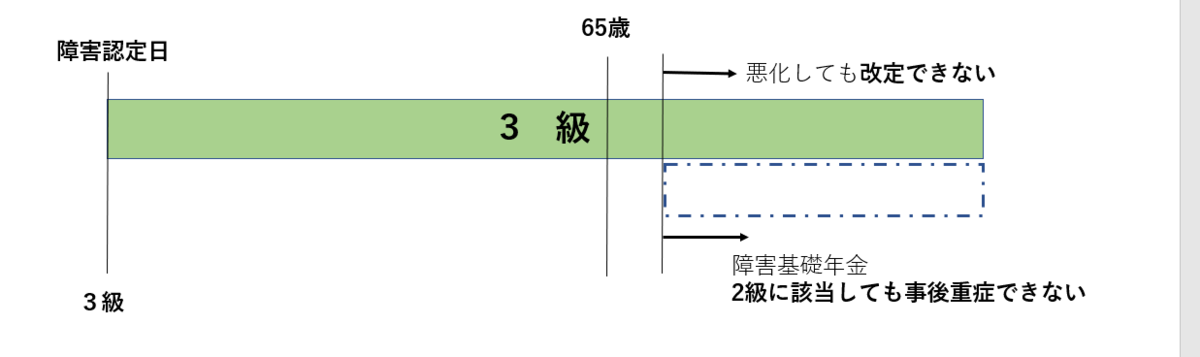
図3
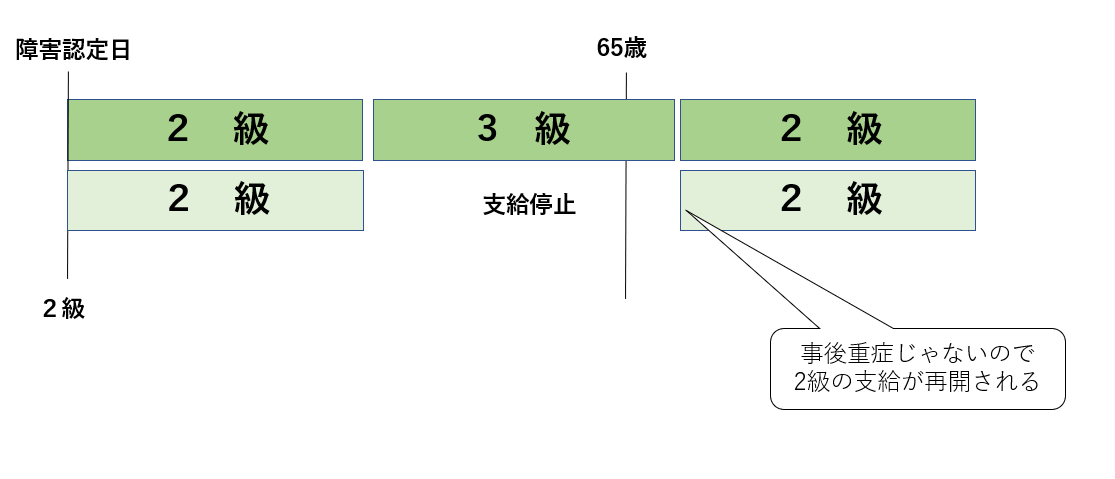
障害 3級から2級への額の改定 その1
R3-278
R3.5.28 事後重症のポイント(国民年金)その1
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、国民年金の視点で見ていきましょう。
国民年金の場合、「障害認定日に障害等級に該当していない」その後「障害等級に該当した」ということで「事後重症」になります。
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H18年出題>
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日おいて障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
②<H21年出題>
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
③<R1年出題>
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

【解答】
①<H18年出題> 〇
 この問題の事後重症のポイント!
この問題の事後重症のポイント!
■65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに
・障害の程度が2級以上の状態に該当すること
・請求すること
(法第30条の2)
②<H21年出題> ×
「その者の年齢に関わりなく」が誤りです。
事後重症の障害基礎年金は、障害認定日後『65歳に達する日の前日まで』の間に請求することが条件です。
③<R1年出題> 〇
受給権が発生する日をおさえましょう。
(通常の障害基礎年金)障害認定日に障害等級に該当 → 障害認定日に受給権発生
事後重症の障害基礎年金 → 支給請求日に受給権発生
※事後重症の障害基礎年金は、請求日に受給権が発生し、請求日が属する月の翌月分から支給されます。請求が遅れると、支給開始時期も遅くなります。
(法第30条の2)
社労士受験のあれこれ
国年 受給権者の届出(住基ネットとの関係)
R3-277
R3.5.27 受給権者の届出と機構保存本人確認情報
今日のテーマは国民年金「受給権者の届出と機構保存本人確認情報の関係」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H24年出題>
厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

【解答】 ×
「年金の支払期月の前月」ではなく「毎月」行います。
住所や氏名の異動情報の取得を、月に1回行っています。
(則第18条)
次はこちらを
②<H25年出題>
老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。

【解答】
②<H25年出題> 〇
年金の受給権者は、氏名又は住所を変更したときは、14日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければなりません。
しかし、氏名変更届、住所変更届については、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はありません。
(則第19条、20条)
こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。
④<H27年出題>
老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方の機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。

【解答】
③<H24年出題> 〇
受給権者が死亡した場合は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければなりません。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができ、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は不要です。
(法第105条、則第24条)
④<H27年出題> ×
「年金受給権者死亡届」の提出は省略できますが、「未支給年金請求書」の提出は省略できません。
(則第24条、25条)
社労士受験のあれこれ
厚年 保険料率
R3-276
R3.5.26 厚生年金保険の保険料率
今日のテーマは「厚生年金保険の保険料率」です。
厚生年金保険の保険料は、「標準報酬月額×保険料率」、「標準賞与額×保険料率」 で計算します。
まずこちらからどうぞ!
①<H17年選択式>
平成16年の改正では、厚生年金保険の最終的な保険料水準を< A >%に固定し、その範囲内で給付費を賄うことを基本に、給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。

【解答】
A 18.3
平成16年改正で導入されたのが「保険料水準固定方式」です。
保険料水準固定方式とは、最終的な保険料の水準を法律で定め、その範囲内で給付を行う仕組みです。
厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月から毎年0.354%ずつ引き上げられ(平成17年度からは9月に引上げ)、平成29年9月以降は、18.3%で固定されることになりました。
ではこちらをどうぞ!
②<R1年出題>
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが。上限が1000分の183に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。

【解答】
②<R1年出題> 〇
厚生年金保険の保険料率が上限の1000分の183に達するのは
・第1号厚生年金被保険者 → 平成29年9月
・第2号及び第3号厚生年金被保険者 → 平成30年9月
・第4号厚生年金被保険者 → 令和9年9月
(H24年法附則第83条から85条)
社労士受験のあれこれ
国年 年金の支給期間
R3-275
R3.5.25 国年 年金の支給期間は、いつからいつまで?
今日のテーマは「年金の支給期間」です。
まず条文の確認からどうぞ!
法第18条 (年金の支給期間及び支払期月)
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の< A >から始め、権利が消滅した日の< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の < A >からその事由が消滅した日の< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

【解答】
A 属する月の翌月
B 属する月
C 前月
※年金は、月単位で支給されます。
ではこちらをどうぞ!
①<H27年出題>
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。
②<H23年出題>
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。

【解答】
①<H27年出題> ×
婚姻した日の属する月の前月分までの部分が誤りです。
年金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで支給されます。
婚姻で遺族基礎年金が失権した場合は、『婚姻した日の属する月』分までの遺族基礎年金が支給されます。
(法第18条)
②<H23年出題> ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、『繰上げ請求のあった日』に発生します。翌日に発生の部分が誤りです。
なお、支給は「受給権発生日の属する月の翌月から」で合ってます。
(法第18条)
こちらもどうぞ!
③<H29年出題>
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
④<H29年出題>
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。

【解答】
③<H29年出題> ×
1月分と2月分の年金の部分が誤りです。
平成29年2月27日に死亡した場合、年金は「権利が消滅した日の属する月」までですので、2月分まで支給されます。
また年金は、「年6期、偶数月、後払い」と覚えましょう。問題文の場合、平成29年2月に12月分と1月分が支払われています。
未支給年金請求者が請求できるのは、2月分のみとなります。
(法第18条、第19条)
④<H29年出題> 〇
未支給年金として請求できるのは、夫が受けるはずだった『65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分』までとなります。
未支給年金のポイントを穴埋め式で確認しましょう
第19条 (未支給年金)
1 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の< A >であって、その者の死亡の当時その者と< B >ものは、< C >で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 1の場合において死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、1に規定する者は、< C >で、その年金を請求することができる。

【解答】
A 三親等内の親族
B 生計を同じくしていた
C 自己の名
社労士受験のあれこれ
厚年 高齢任意加入被保険者
R3-274
R3.5.24 厚年 高齢任意加入被保険者のポイント
今日のテーマは、「高齢任意加入被保険者」です。
70歳になっても、老齢の年金の受給権がない人は、70歳以降も任意に厚生年金保険に加入することができます。
「高齢任意加入被保険者」には「適用事業所」に使用される人と、「適用事業所以外」の事業所に使用される人の2つのパターンがあります。それぞれの違いに注意しましょう。
まずこちらからどうぞ!
①<H26年出題>
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
②<R1年出題>
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(厚生年金保険法第12条各号に該当する者を除く。)が高齢任意加入の申出をした場合は、実施機関への申出が受理された日に資格を取得する。

【解答】
①<H26年出題> ×
「厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する」の部分が誤りです。
『適用事業所以外』の高齢任意加入被保険者の場合
・『事業主の同意』を得たうえで、『厚生労働大臣の認可』を受けて、『認可があった日』に資格を取得します。
(法附則4条の5)
②<R1年出題> 〇
『適用事業所』の高齢任意加入被保険者の場合
・『実施機関に申し出』て、『実施機関への申出が受理された日』に資格を取得します。
※『適用事業所」の場合、事業主の同意は要りません。
事業主の同意は「事業主が保険料を半分負担し、かつ納付義務を負う」ためのものです。
「適用事業所以外」は事業主の保険料半分負担かつ納付義務を負うことが必須。ですので、事業主の同意も必須要件です。
一方、「適用事業所」の方は、事業主の負担が必須ではありません。そのため事業主の同意も必須ではありません。
(法附則第4条の3)
もう一問どうぞ!
③<H29年出題>
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】
③<H29年出題> ×
第4号厚生年金被保険者が誤り。この規定が適用されないのは「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者」です。
★ 高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、「保険料の半額負担、かつ、保険料の納付義務を負う」ことにつき同意することができます。そして、その同意を将来に向かって撤回することもできます。
ただし、この規定は、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者には適用されません。
(法附則第4条の3)
社労士受験のあれこれ
厚年 70歳以上の使用される者
R3-273
R3.5.23 厚年 70歳以上の使用される者の届出関係
今日のテーマは、「70歳以上の使用される者」の届出関係です。
厚生年金保険の被保険者が70歳に達したときは資格を喪失しますが、70歳以後も働く場合は、厚生年金保険の被保険者ではない(=保険料は徴収されない)ものの、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
70歳以降も働く場合の手続を確認しましょう。
まずこちらからどうぞ!
①<H28年出題>
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

【解答】
①<H28年出題> ×
問題文の場合、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることがあります。
70歳以上でも適用事業所に使用される場合は、在職老齢年金のルールが適用されます。以前は、昭和12年4月1日以前生まれの者はこの適用が除外されていましたが、平成27年10月からは、昭和12年4月1日以前生まれの者にも在職老齢年金の仕組みが適用されています。
(法第46条)
こちらもどうぞ!
②<H23年出題>
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。
③<H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。
④<R2年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

【解答】
②<H23年出題> 〇
70歳以上の者を新たに使用した場合、厚生年金保険の被保険者にはなりませんが、在職老齢年金の規定が適用されるため、「70歳以上の使用される者の該当の届出」が必要です。
対象になるのは、「70歳以上」、「過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する」「適用事業所に使用される者で、かつ、12条各号に定める者に該当しない」者です。
(則15条の2)
③<H29年出題> ×
<被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合>
★70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる→「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出
★70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70 歳到達日の前日の標準報酬月額と同額→ 「70歳以上の使用される者の該当の届出」の提出は不要
<70歳以上の者を新たに雇い入れたとき>
★「70歳以上の使用される者の該当の届出」を提出
(則第15条の2)
④<R2年出題> 〇
「70歳到達日の前日以前から70歳到達日以降も引き続き 同一の適用事業所に使用」かつ、「当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である」場合は、「70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届」の提出は不要です。
(則第15条の2)
社労士受験のあれこれ
国年 前納について②
R3-272
R3.5.22 保険料「前納」でよく出るところ その2
引き続き、国民年金保険料の前納のルールを見ていきましょう。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。

【解答】
①<H27年出題> 〇
保険料が前納された後、前納期間の経過前に保険料の額の引上げがあった場合は、前納保険料のうち未経過分については、引上げ後に納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当されます。
(令第8条の2)
こちらもどうぞ!
②<H21年出題>
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
③<H25年出題>
保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

【解答】
②<H21年出題> 〇
前納期間の途中で、資格を喪失した場合や第2号被保険者、第3号被保険者になった場合は、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、未経過期間分が還付されます。
(令第9条)
③<H25年出題> 〇
保険料を前納した後、途中で保険料の免除を受けた場合も、未経過期間分が還付の対象となります。
(令第9条)
社労士受験のあれこれ
国年 前納について①
R3-271
R3.5.21 保険料「前納」でよく出るところ その1
国民年金保険料の前納のルールを見ていきましょう。
前納とは、まとめて前払いをする制度です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
②<H27年出題>
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。

【解答】
①<R1年出題> ×
平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは可能です。
保険料の前納は、「6月」単位又は「年」単位で行うのが原則です。
ただし、例外もあり、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合は、6月又は年以外の単位も可能です。
6月又は年以外の単位の場合は、任意の月分から当年度末または翌年度末までの期間となりますが、問題文の昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者は、60歳に達する令和元年8月1日に資格を喪失するので、平成31年4月から令和元年7月分までの4か月間をまとめることができます。
(令7条)
②<H27年出題> 〇
2年前納は口座振替でできます。また、口座振替のみならず、現金・クレジットカード納付でも2年前納ができます。
(令7条)
では、こちらもどうぞ
③<H21年出題>
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
④<H24年出題>
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

【解答】
③<H21年出題> 〇
割引があるのが前納のメリットです。割引額は年利4%の複利現価法で計算します。4分という利率を覚えておきましょう。
(令8条)
④<H24年出題> ×
国民年金保険料を1年間分前納する場合、現金よりも口座振替による支払の方が割引率は高くなります。
(参考) 令和3年度の国民年金保険料は月16,610円ですが、1年分前納した場合、「現金」、「クレジットカード」だと195,780円(3,540円割引)、「口座振替」だと195,140円(4,180円割引)となります。
(令8条)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H30年出題>
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】
⑤<H30年出題> ×
「前納に係る期間の各月の初日が到来したとき」が誤りです。
『「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす』です。
(法第93条)
社労士受験のあれこれ
学生納付特例 その2
R3-270
R3.5.20 学生納付特例のポイントその2
引き続き、テーマは「学生納付特例」です。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【解答】
①<H29年出題> 〇
学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の10年以上の計算には入りますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されないのがポイントです。納付猶予の期間も同じです。
(法第26条、第27条)
こちらもどうぞ!
②<H30年出題>
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
③<R1年出題>
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

【解答】
②<H30年出題> 〇
学生納付特例期間は老齢基礎年金の額の計算には反映されませんが、追納すれば保険料納付済期間となり年金の額が増えます。
なお、追納できるのは、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に限れられることにも注意してください。
(法第94条)
③<R1年出題> ×
「学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない」が誤りです。
学生納付特例期間(納付猶予も含む)は、老齢基礎年金の額に反映されませんので、一部につき追納する場合は、まず学生納付特例期間(納付猶予)を優先し、それ以外の免除を古い順番に行うのが原則です。
ただし、問題文のように学生納付特例より前に納付義務が生じた保険料があるときは、古い保険料から追納することができます。
問題文の場合
・ 平成27年6月分から平成28年3月分 保険料全額免除期間
・ 平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間
・ 平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間
となっていますので、学生納付特例の期間よりも古い平成27年6月分から平成28年3月分の保険料全額免除期間の保険料を先に追納することができます。
(法第94条)
最後にこちらもどうぞ!
国民年金制度創設当初は、学生は任意加入だったが、< A >4月1日から強制加入に改められた。

【解答】
A 平成3年
社労士受験のあれこれ
学生納付特例 その1
R3-269
R3.5.19 学生納付特例のポイントその1
テーマは「学生納付特例」です。
では、どうぞ!
①<H28年出題>
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
②<H28年出題>
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①<H28年出題> 〇
申請全額免除は、学生には適用されません。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除も学生には適用されません。
・「法定免除」は、学生にも適用されます。
(法第90条)
②<H28年出題> 〇
学生納付特例は、学生本人の前年の所得のみで判断されます。世帯主や配偶者の前年の所得は関係ありません。
(法第90条の3)
こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。
④<H23年出題>
学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。
⑤<H27年出題>
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

【解答】
③<H24年出題> 〇
退学等の理由で学生でなくなった場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければなりません。なお、卒業の場合は提出不要です。
(則第77条の9)
④<H23年出題> ×
学生納付特例事務法人は、保険料の納付に関する事務はできません。
学生納付特例事務法人とは、学生が学生納付特例の手続きをしやすくするために、大学等が学生の委託を受けて、申請の代行を行う制度のことです。
(法第109条の2の2)
⑤<H27年出題> 〇
「学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をした日」がポイントです。
学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない、とされています。
(法第109条の2の2)
社労士受験のあれこれ
国年 国民年金原簿
R3-268
R3.5.18 国民年金原簿 よく出るところ
まず、国民年金法第14条を確認しておきましょう。
第14条 (国民年金原簿)
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
では、どうぞ!
①<H28年出題>
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。

【解答】
①<H28年出題> 〇
当分の間、第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録管理は行われていません。
(法第14条、附則第7条の5)
次はこちらをどうぞ!
②<H30年出題>
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

【解答】
②<H30年出題> 〇
「年金記録が事実と異なる」と思う場合は、厚生労働大臣に年金記録の訂正請求ができます。例えば、国民年金の保険料を納付していたのに記録がない、とか、会社で働いていた期間の厚生年金保険の記録がない、などの場合です。
訂正請求ができるのは、本人(被保険者又は被保険者であった者)で、自己の特定国民年金原簿記録についてですが、本人が死亡している場合は、遺族が請求できます。
※ただし、本人の死亡に伴う未支給年金または遺族年金等を受けることができる人に限定されています。
寡婦年金の場合は、「妻」が「死亡した夫」に係る特定国民年金原簿記録について、国民年金原簿の訂正請求をすることができます。
ちなみに、特定国民年金原簿記録とは、「被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容」です。
(法第14条の2)
では、こちらをどうぞ!
③<R2年出題>
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。

【解答】
③<R2年出題> ×
社会保険審査会ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければならない、です。
なお、「社会保険審査会」は行政不服審査を行う機関で、「社会保障審議会」は厚生労働大臣の諮問機関です。
(法第14条の2)
最後はこちらを
④<H27年選択式>
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は< A >に委任されており、 < A >が決定しようとするときは、あらかじめ< B >に諮問しなければならない。

【解答】
A 地方厚生局長又は地方厚生支局長
B 地方年金記録訂正審議会
(法第14条の4、第109条の9、令11条の12の2)
※地方厚生(支)局長が、年金記録の訂正請求に対して、その訂正(不訂正)の決定を行うときは、あらかじめ地方年金記録訂正審議会に諮問しなければなりません。
社労士受験のあれこれ
国年 種別変更
R3-267
R3.5.17 第1号、第2号、第3号被保険者~種別変更
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの
種別があります。
例えば、40歳の会社員が退職して自営業を始めた場合、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者に種別が変わります。
この場合のポイントは、第2号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者の資格を取得するのではなく、第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」となる点です。
では、どうぞ!
①<H22年出題>
被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
②<H30年出題>
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
③<H24年出題>
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者になった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

【解答】
①<H22年出題> 〇
★被保険者の種別に変更があった月★
・変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
・同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
(法第11条の2)
②<H30年出題> ×
同一月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者への種別の変更があった場合、その月は「最後の種別の被保険者であった月」とみなすので、当該月は第3号被保険者であった月とみなします。
(法第11条の2)
③<H24年出題> ×
第1号被保険者から第3号被保険者になった月は、第3号被保険者であった月とみなします。すでに第1号被保険者としての保険料が納付されていても、関係ありません。
(法第11条の2)
では、こちらもどうぞ
④<H20年出題>
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
④<H20年出題> ×
「資格取得届」が誤りです。
第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」ですので、「種別変更の届出」を、当該事実があった日から14日以内に市町村長に提出しなければなりません。
(則第6条の2)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H27年出題>
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

【解答】
⑤<H27年出題> ×
第2号被保険者には、国民年金法の届出の規定は適用されません。
ですので、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合の種別変更の届出は不要です。
(法附則第7条の4)
社労士受験のあれこれ
国年 第3号被保険者届出いろいろ その2
R3-266
R3.5.16 第3号被保険者の届出
引き続き、第3号被保険者の届出いろいろです。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①<H29年出題> 〇
ポイント! 第3号被保険者の資格取得の届出 → 提出期限(14日以内)と提出先(日本年金機構)がポイントです。
次はこちらをどうぞ
②<H27年出題>
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

【解答】
②<H27年出題> 〇
第2号被保険者の夫と第3号被保険者の妻が離婚した場合
・「第1号被保険者の種別の変更の届出」を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出
・「被扶養配偶者非該当届」を離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へを提出
★「被扶養配偶者非該当届」のポイント
・「全国健康保険協会管掌」の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった者については、被扶養配偶者非該当届の提出は不要。
・ 配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合は、被扶養配偶者非該当届の提出は不要
・ 被扶養配偶者非該当届の提出が必要なのは、(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合、(2)離婚した場合です。
(H26年11月1日 年管管発1101第1号)
社労士受験のあれこれ
国年 第3号被保険者届出いろいろ
R3-265
R3.5.15 第3号被保険者(平成17年4月1日前と以後)
今日は、第3号被保険者の届出色々です。
現在は、会社員や公務員の被扶養配偶者(第3号被保険者)に該当した場合は、第2号被保険者の事業主等を経由して届け出を行うので、届出もれは基本的にありません。
しかし、事業主経由で第3号被保険者の届出を行うようになったのは平成14年4月からです。
第3号被保険者制度ができた昭和61年4月から平成14年3月までは、自分自身で市町村に届出を提出しなければならず、その届出をしなかった人が多数存在しました。
届出をしなかった期間は、未納期間となり、年金の受給資格ができない、あるいは受給額が減るという不利益が生じてしまいます。
今日は、このような人たちを救済するための特例がテーマです。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
②<H22年出題>
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
③<H29年出題>
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

【解答】
この問題のポイント!
<第3号被保険者の取得の届出が遅れた場合の取扱い>
★平成17年4月1日前
第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)
↓
届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる
※届出の遅滞の理由の有無は問わない
★平成17年4月1日以後
第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)
↓
届出の遅滞がやむを得ないと認められるとき
↓
届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる
①<H19年出題> 〇
「平成17年4月1日以後の期間」がポイントです。
第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞によって保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間については、届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、その旨の届出をすることができます。
届出が行われた日以後、届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されます。
(法附則第7条の2)
②<H22年出題> 〇
平成17年4月1日以後については、第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間は、原則として保険料納付済期間に算入されません。(届け出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、届出をすることができます。)
ちなみに、「届出をした日の属する月の前々月までの2年間」は保険料納付済期間に算入されます。
(疑問その1 届け出をした日の属する月の前月はどうなるのか?)
例えば、2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合、2021年4月は保険料納付済期間となります。
国民年金の保険料の納期限は翌月末日です。2021年4月分は5月末までに納付すればいいので、3号の取得も5月14日に届け出れば、2021年4月は保険料納付済期間に算入できるという理屈です。
(疑問その2 なぜ2年間なのか?)
保険料の納付の時効の期間に合わせた扱いです。
2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合は、2021年3月までの2年間も保険料納付済期間となります。
(法附則第7条の2)
③<H29年出題> 〇
資格取得日 → 平成26年4月1日
資格取得の届出 → 平成29年4月13日
・ 届け出をした日の属する月の前々月までの2年間は「保険料納付済期間」となる。(平成27年3月~平成29年2月まで、平成29年3月も)
・ 平成26年4月から平成27年2月までの期間は、届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるとき → その旨を届け出れば → 届出日以後、保険料納付済期間に算入される。
(法附則第7条の2)
社労士受験のあれこれ
健康保険法 標準賞与額に係る保険料
R3-264
R3.5.14 (健保)標準賞与額に係る保険料
今日は、標準賞与額に係る保険料です。
「賞与」の定義からどうぞ!
①<R1年出題>
保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

【解答】
①<R1年出題> 〇
賞与の定義は「3か月を超える期間ごと」に受けるものです。
なお、「臨時に」受けるものは、報酬にも賞与にも入りません。
「3か月を超える期間ごと」に受けるものとは、年3回以下の回数で支給されるいわゆるボーナスのことです。
6か月ごとに支給される通勤手当は、支払の便宜上6か月間を一括して支給するものですので、賞与ではなく報酬となります。
(法第3条、昭26.9.18保文発3603、昭40.8.4庁保険発38)
次は「標準賞与額」をどうぞ!
②<R1年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

【解答】
②<R1年出題> 〇
標準賞与額とは
・賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額
・上限あり → 年度(4月1日~翌年3月31日)の標準賞与額の累計額が573万円を超える場合は、累計額が573万円となるよう決定される
ポイント!賞与の累計は、保険者単位で行われます
問題文の前段は、年度の累計が573万円になるよう、3月は173万円となります。
後段は、年度の途中で保険者が変わっているので、賞与の累計は保険者単位となります。全国健康保険協会管掌健康保険分は、7月150万円、健康保険組合管掌健康保険分は、12月250万円、3月200万円となります。
(法第45条、H18年8月18日付け事務連絡)
最後に、こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。
④<H29年出題>
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
③<H24年出題> 〇
被保険者負担分の標準賞与額に係る保険料を賞与から控除することができます。
(法第167条第2項)
④<H29年出題> 〇
資格を喪失した月は、標準賞与額に係る保険料についても納付する義務はありません。
なお、資格を喪失した月は、保険料徴収の必要はありませんが、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額573万円に算入されます。
(法第156条、H19.5.1庁保険発第0501001号)
社労士受験のあれこれ
健康保険法 家族療養費
R3-263
R3.5.13 (健保)家族療養費でよく出るところ
今日は、家族療養費です。
こちらからどうぞ!
①<R1年出題>
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

【解答】
①<R1年出題> ×
被保険者に対して支給されるのは、入院時生活療養費ではなく「家族療養費」です。
(法第110条)
| ★被扶養者に関する給付 | 被保険者に関する給付 |
| 家族療養費 | 療養の給付 療養費 入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 |
| 家族訪問看護療養費 | 訪問看護療養費 |
| 家族移送費 | 移送費 |
| 家族埋葬料 | 埋葬料 |
| 家族出産育児一時金 | 出産育児一時金 |
こちらもどうぞ!
②<H19年出題>
被扶養者が保険医療機関において評価療養を受けた場合には、被保険者に対して家族療養費が支給される。
③<H23年出題>
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被扶養者に対して、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費が支給される。

【解答】
②<H19年出題> 〇
家族療養費は「被保険者」に対して支給されるのがポイントです。「被扶養者に対して」ではありません。
(法第110条)
③<H23年出題> ×
家族訪問看護療養費は、「当該被扶養者に対して」ではなく、「被保険者に対して」支給されます。
(法第111条)
ポイント!
被扶養者に関する給付(家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金)は、被保険者に対して支給されます。(被扶養者に対してではありません。)
では、こちらもどうぞ!
④<H24年出題>
被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。

【解答】
④<H24年出題> ×
「当日から」支給されない、ではなく「翌日から」支給されなくなります。
家族療養費は、被保険者に対して支給されるので、被保険者が死亡した場合は家族療養費は支給されなくなります。
被保険者が死亡した場合、資格の喪失は死亡日の翌日です。ですので、家族療養費が支給されなくなるのは、死亡の日の翌日からとなります。
社労士受験のあれこれ
健康保険法 現物給付と現金給付
R3-262
R3.5.12 (健保)現物給付と現金給付
今日は、「現物給付」と「現金給付」です。
健康保険法の保険給付の代表「療養の給付」。例えば、病気で病院に行き、診察を受ける、注射を打ってもらう、入院する、手術を受ける等々は「現物給付」です。現金が支給されるわけではありません。
一方、「療養費」は現金給付です。近くに保険医療機関がないなどの理由で、保険医療機関等以外で治療などを受けた場合は、現物給付ではなく、費用が支払われます。
「現物給付」と「現金給付」についての問題をみていきましょう。
こちらからどうぞ!
①<H29年出題>
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
②<H24年出題>(修正)
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医用機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。
③<R1年出題>
被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。この支払いがあったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

【解答】
①<H29年出題> 〇
入院時食事療養費は第85条で第1項で、「療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。」と定められていますが、実際は現物給付となっています。
同条第5項で、「保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。」とされているからです。
第5項を解体して流れを書きますと、被保険者が療養の給付と併せて食事療養を受けた場合、
・ 本来は被保険者が病院又は診療所に食事療養に要した費用を支払う
↓
・ 保険者から被保険者に対して食事療養の費用を入院時食事療養費として支給する
ここまでだと現金給付になるのですが、
↓
・ 保険者は、「入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度で、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる」、とされていて、保険者から病院等に食事に要した費用を直接支払うことによって、結果として現物給付になるという仕組みです。
(法第85条)
②<H24年出題>(修正) 〇
保険外併用療養費も「現物給付」で行われます。
先ほどの入院時食事療養費と同じです。
第86条第1項では、「その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。」となっているのですが、実際は、保険者から保険医療機関等に、直接費用を払うことができるので、結果として現物給付となっています。
(法第86条)
③<R1年出題> 〇
訪問看護療養費も、第88条第1項で、「被保険者が指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。」と規定されています。
しかし、同条第6項で保険者が被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる、とされていて、保険者が被保険者に代わって、指定訪問看護事業者に直接費用を支払うことによって、結果として現物給付になっています。
(法第88条)
では、現金給付の問題もどうぞ!
④<H24年出題>
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

【解答】
④<H24年出題> 〇
移送費は「現金給付」です。
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用の範囲内で算定されます。(ただし、実費を超えることはできません。)
(法第97条)
社労士受験のあれこれ
徴収法~保険関係の一括③
R3-261
R3.5.11 徴収法~継続事業の一括
引き続き、徴収法の「保険関係の一括」です。
今日は、「継続事業の一括」です。
継続事業の一括とは?
例えば、同一の企業に、本店、A支店、B営業所がある場合、保険料の申告・納付は本店、A支店、B営業所でそれぞれ行うのが原則です。
しかし、「継続事業の一括」の認可を受けることにより、保険料の申告・納付を一つにまとめることもできます。
こちらからどうぞ!
①<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
②<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。

【解答】
①<H21年出題(雇用)> 〇
「継続事業の一括」は、法律上当然に一括されるのではなく、厚生労働大臣の認可(認可の権限は都道府県労働局長に委任されている)が必要です。
認可されると保険関係が一括され、保険料の申告・納付は、指定事業でまとめて行います。
「継続事業一括申請書」は指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出することがポイントです。
(法第9条、則第10条)
②<H21年出題(雇用)> ×
継続事業の一括は、労災保険率表による事業の種類を同じくすることが要件です。雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業でも同様に、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要があります。
(則第10条)
こちらもどうぞ!
③<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
④<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労使保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。

【解答】
③<H21年出題(雇用)> ×
「保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。」の部分が誤り。そもそも保険関係消滅申請書というものはありません。
継続事業の一括の認可があったときは、すべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、労働保険料の申告・納付は指定事業で一括して行われます。
そして、指定事業以外の事業の保険関係は消滅しますが、この場合は、「確定保険料申告書」を提出して保険関係の消滅に伴う保険料の確定精算を行うことになります。
(法第9条)
④<H21年出題(雇用)> ×
継続事業の一括の認可を受けても、労災保険び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務は一括されません。原則どおり、事業場単位となります。事務を行うのは、「指定事業の所在地」ではなく、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長です。
(法第9条)
社労士受験のあれこれ
徴収法~保険関係の一括②
R3-260
R3.5.10 徴収法~請負事業の一括
引き続き、徴収法の「保険関係の一括」です。
今日は、「請負事業の一括」です。
請負事業の一括のポイント
★建設の事業が数次の請負によって行われるとき
・ 下請負事業では、それぞれ独立した事業としての保険関係は成立しない
・ 数次の下請負事業は元請負事業に一括され、元請負人のみを適用事業主として保険関係が成立する
・ 一括は法律上当然に行われる
・ 労災保険に係る保険関係のみ適用される
★下請負事業を分離させることもできる
・ 下請負事業を元請負事業から分離して保険関係を成立させることもできる
・ 分離には、一定の規模の要件がある
・ 分離には政府の認可が必要
こちらからどうぞ!
①<H26年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
②<H26年出題(労災)>
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
③<H26年出題(労災)>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】
①<H26年出題(労災)> ×
請負事業の一括は「法律上当然」に一括されるので、認可申請も厚生労働大臣の認可も不要です。
(法第8条)
②<H26年出題(労災)> ×
請負事業の一括の対象になるのは「建設の事業」です。立木の伐採の事業は請負事業の一括は行われません。
(法第8条、則第7条)
③<H26年出題(労災)> 〇
請負事業の一括で一括されるのは、「労災保険の保険関係」のみです。
「雇用保険の保険関係」は一括されませんので、それぞれの下請負人ごとに労働保険徴収法が適用されます。
(法第8条、則第7条)
次は、こちらをどうぞ!(下請負事業の分離)
④<H27年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。
⑤<H27年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

【解答】
④<H27年出題(労災)> ×
下請負事業の分離の認可を受けるには、事業の規模が、「概算保険料の額が160万円以上、又は、請負金額が1億8千万円以上」であることが条件です。
有期事業の一括の対象にならない規模と覚えておきましょう。
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業を分離させるためには、規模の要件を満たすことと、「下請負事業の分離の認可」の手続きが必要です。
(法第8条、則第9条)
⑤<H27年出題(労災)> ×
「そのいずれかが単独で」の部分が誤りです。
認可申請書は、元請負人及び下請負人が共同で申請しなければなりません。
期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。
(法第8条、則第8条)
社労士受験のあれこれ
徴収法~保険関係の一括①
R3-259
R3.5.9 徴収法~有期事業の一括
今日は徴収法の「保険関係の一括」です。
保険関係の一括には、「有期事業の一括」、「請負事業の一括」、「継続事業の一括」の3つがあります。
今日は、「有期事業の一括」です。
有期事業の一括のポイント
対象:建設の事業、立木の伐採の事業
・ 規模の小さい(一定の要件あり)有期事業であること
・ 法律上当然に一括される
・ 労働保険は、継続事業と同様の方法で適用される
・ 労災保険に係る保険関係のみ適用される
こちらからどうぞ!
①<H28年出題(労災)>
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
②<H28年出題(労災)>
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

【解答】
①<H28年出題(労災)> ×
「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」が誤りです。
有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」又は「立木の伐採の事業」です。
(則第6条)
ポイント!
一括されるのは「労災保険」に係る保険関係のみです。「雇用保険」は一括されません。
②<H28年出題(労災)> ×
有期事業の一括の対象となる事業の要件
「建設の事業」 → 請負金額(消費税相当額を除く)が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満
「立木の伐採の事業」 → 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満、かつ、概算保険料額が160万円未満
概算保険料の額が160万円未満であることは共通しています。しかし、一括の要件に労働者数は関係ありません。
(則第6条)
次は、こちらをどうぞ!
③<H24年出題(労災)>
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。

【解答】
③<H24年出題(労災)> 〇
有期事業の一括は、一定の要件に該当する場合には当然に行われます。承認や認可を受けるなどの手続きは要りません。
(法第7条)
最後にこちらを
④<H30年出題(労災)>
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
⑤<H23年出題(雇用)>
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
④<H30年出題(労災)> 〇
単独の有期事業でしたら、例えば工事現場の場合、工事が開始したときに「概算保険料」を申告・納付し、工事終了時に「確定保険料」で精算します。それを各工事ごとに行うことになります。
一方、一括有期事業の場合は、それぞれの有期事業ごとではなく、その全体が継続事業として取り扱われることになり、継続事業と同じように年度ごとに労働保険料の概算、確定手続きを行うことになります。
(法第7条)
⑤<H23年出題(雇用)> 〇
ポイント!
一括有期事業報告書は、「確定保険料申告書」に加えて提出します。
期限は、「次の保険年度の6月1日から起算して40日以内」又は「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。
(則第34条)
社労士受験のあれこれ
雇用保険法~過去の選択問題
R3-258
R3.5.8 雇用保険法・過去の選択式から学ぶ
今日のテーマは、雇用保険法「過去の選択問題から学ぼう」です。
ではどうぞ!
①<H19年選択>
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、< A >を有するにもかかわらず、< B >ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、< C >が終了することをいう。

【解答】
A 労働の意思及び能力
B 職業に就く
C 事業主との雇用関係
(法第4条)
★「用語」の定義からの出題です。用語の定義は選択式で問われても自信をもって解けるようしっかり覚えましょう。
条文からもう一問どうぞ!
(就職への努力)
求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ< D >の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、< E >ように努めなければならない。

【解答】
D 職業能力
E 職業に就く
(第10条の2)
次は、こちらをどうぞ!
②<H18年選択>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< A >までの範囲で定められている。
賃金日額は、原則として< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が、労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の100分の< E >に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる。

【解答】
A 45
B 算定対象期間
C 被保険者期間
D 当該最後の6か月間に労働した日数
E 70
★「総日数」と「労働した日数」の違いに注意しましょう。
例えば、5月の「総日数」は暦の日数ですので31日ですが、「労働した日数」の場合は、休日の日数は入りません。
最後にこちらを!
③<H30年出題>
賃金が出来高払制によって定められている場合の賃金日額は、労働した日数と賃金額にかかわらず、被保険者期間として計算された最後の3か月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を90で除して得た額となる。
④<H22年出題>
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。

【解答】
③<H30年出題> ×
★日給、時給、出来高払制その他の請負制の場合の賃金日額
<原則>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」
<最低保障>
「被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額」
→ <原則>の額と<最低保障>の額のどちらか高い方の額となります。
(法第17条)
④<H22年出題> 〇
★基本手当の日額は、「賃金日額×給付率」で計算します。
給付率は、60歳未満は80%から50%、60歳以上65歳未満は80%から45%です。
年齢に関わらず、賃金日額×100分の80を乗じて得た額を超えることはありません。
(法第16条)
社労士受験のあれこれ
雇用保険法~届出その2
R3-257
R3.5.7 雇用保険・被保険者資格喪失届
引き続き、雇用保険法の届出をみていきましょう。
今日は、「雇用保険被保険者資格喪失届」です。
【確認しましょう】「雇用保険の被保険者資格を喪失する日」について
被保険者資格を喪失する日
→(原則)離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する 。
→ ・被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合 ・ 被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合
それぞれ当該事実のあった日に被保険者資格を喪失する。
(行政手引20601)
では「資格喪失届」の穴埋めをどうぞ!
(被保険者でなくなったことの届出)
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して< A >日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が< B >であるときは、当該資格喪失届に、< C >を添えなければならない。
事業主は、資格喪失届を提出する際に被保険者が< D >の交付を希望しないときは、< C >を添えないことができる。ただし、離職の日において< E >歳以上である被保険者については、この限りでない。

【解答】
A 10
B 離職
C 雇用保険被保険者離職証明書
D 雇用保険被保険者離職票
E 59
(則第7条)
ポイント!
離職証明書の添付が必要なのは、被保険者でなくなったことの理由が「離職」の場合です。例えば、被保険者でなくなったことの理由が「死亡」の場合は、離職証明書は添付しません。(基本手当を受給することがないから)
離職証明書と離職票
・離職証明書 → 公共職業安定所に提出
・離職票 → 離職した本人に交付される(基本手当の受給手続きに必要)
では、こちらをどうぞ!
①<H20年出題>
雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②<H21年出題>
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならない。
③<H18年出題>
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。
④<H26年出題>
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者については、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも離職証明書を添えなければならない。

【解答】
①<H20年出題> 〇
雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内です。
「当該事実のあった日」とは、被保険者資格を喪失する日のことで、例えば離職の場合は、離職した日の翌日、死亡の場合は死亡した日の翌日です。
5月7日が離職日の場合は、8日が資格喪失日になり、資格喪失届は5月9日から10日以内(5月18日)までに提出します。
(則第7条)
②<H21年出題> 〇
被保険者が離職票の交付を希望した場合は、年齢に関係なく、資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
(則第7条)
③<H18年出題> 〇
被保険者が離職票の交付を希望しない場合は、資格喪失届に離職証明書を添付しないことができます。ただし59歳未満に限られるので注意しましょう。
(則第7条)
④<H26年出題> 〇
離職日に59歳以上の場合は、離職票の交付の希望の有無にかかわらず、必ず離職証明書を添えなければなりません。
(則第7条)
最後にもう一問どうぞ!
⑤<H18年出題>
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。

【解答】
⑤<H18年出題> ×
離職証明書は、事業主が資格喪失届に添付して公共職業安定所長に提出することが一般的ですが、事業主から離職により被保険者でなくなった者に対して、離職証明書を交付することもあります。
例えば、被保険者が離職時に離職票の交付を希望しなかったので、事業主が資格喪失届に離職証明書を添付しなかった。しかし、その後、離職した者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、事業主は離職証明書をその者に交付しなければならない、とされています。
(則第16条)
社労士受験のあれこれ
雇用保険法~届出
R3-256
R3.5.6 雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険法の届出をみていきましょう。
今日は、「雇用保険被保険者資格取得届」です。
ではどうぞ!
①<R2年選択>
事業主は、雇用保険法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月< A >日までに、雇用保険被保険者資格取得届をその事業所の所在地を管轄する < B >に提出しなければならない。

【解答】
A 10
B 公共職業安定所長
(則第6条)
同じ問題をどうぞ。
②<H24年出題>
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【解答】 〇
「提出期限」と「提出先」がポイントです。
(参考)
★なお、雇用保険被保険者資格取得届は、労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することもできます。
★資格取得届に所定の書類の添付が必要な場合はどんな場合?
1 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
2 提出期限を超えて資格取得届を提出する場合
3 提出期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(不正受給による失業等給付の返還命令の連帯規定)(育児休業給付に準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があったと認められる場合
4 そのほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となったことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
(則第6条)
こちらもどうぞ!
③<H29年出題>
公共職業安定所長は、一般被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証を交付しなければならないが、この場合、被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。

【解答】 〇
「雇用保険被保険者証」は、被保険者本人に交付されるもので、事業主を通じて交付することができます。「雇用保険被保険者証」を事業主が保管するのは間違いなので、注意してください。
(則第10条)
(参考:確認の通知)
公共職業安定所長は、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。
当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
(則第9条)
★ 雇用保険の被保険者資格の取得をした場合は、被保険者に対して、「資格取得確認通知書(被保険者通知用)」によりその旨が通知され、また、雇用保険被保険者証が交付されます。
資格取得確認通知書(被保険者通知用)、被保険者証の交付は、事業主を通じて行うことができることになっています。
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-255
R3.5.5 「心理的負荷による精神障害の認定基準」その2
引き続き、今日も「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。
(認定基準について)
1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
1 対象疾病を発病している。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
ではどうぞ!
①<H24年出題>
認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。
②<H30年出題>
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

【解答】
①<H24年出題> 〇
・ 心理的負荷(ストレス)が非常に強い → 個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こる
・ 脆弱性が大きい → 心理的負荷(ストレス)が小さくても破綻が生ずる
※心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件 → 対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があること + 当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること
(H23.12.26 基発1226 第1号)
②<H30年出題> ×
「主観的にどう受け止めたかという観点」が誤りです。
強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものである、とされています。( 「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者のこと。)
(H23.12.26 基発1226 第1号)
こちらもどうぞ!
③<H30年出題>
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

【解答】
③<H30年出題> ×
「強」、「弱」の二段階ではなく、「強」、「中」、「弱」の三段階に区分されています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
最後にこちらをどうぞ
④<H30年出題>
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
⑤<H24年出題>
認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。

【解答】
④<H30年出題> ×
120時間ではなく「160時間」を超える時間外労働を行った場合等です。
⑤<H24年出題> 〇
発病前おおむね6か月の間に、「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。
特別な出来事には、「心理的負荷が極度のもの」と 「極度の長時間労働」の2つ類型があります。
そのうち、「極度の長時間労働」とは、 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)とされています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-254
R3.5.4 「心理的負荷による精神障害の認定基準」その1
今日のテーマは「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。
(認定基準について)
1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
1 対象疾病を発病している。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
ではどうぞ!
①<H30年出題>
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

【解答】
①<H30年出題> 〇
穴埋め式でポイントをおさえましょう!
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、< B >が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

【解答】
A 6か月
B 業務による強い心理的負荷
(H23.12.26 基発1226 第1号)
では、こちらもどうぞ
②<H30年出題>
認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

【解答】
②<H30年出題> ×
問題文の最後の「発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする」が誤りです。
いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすることとされています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-253
R3.5.3 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 その2
引き続き、テーマは「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 」です。
(認定基準について)
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した 脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り 扱う。
(1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る 異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」とい う。)に就労したこと。
(3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下 「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(H13.12.12 基発第1063号)
ではどうぞ!
①<H28年選択>
厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。
業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。
「発症前の長期間とは、発症前おおむね< A >をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前< B >におおむね100時間又は発症前< C >にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

【解答】
①<H28年選択>
A 6か月間
B 1か月間
C 2か月間ないし6か月間
ポイント!
★ 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間
★ 労働時間(疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる)に着目
→ その時間が長いほど、業務の過重性が増す
→ 発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合 → 業務と発症との関連性が弱い
おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど → 業務と発症との関 連性が徐々に強まると評価できる
② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる → 業務と発症との関連性が強いと評価できる
(H13.12.12 基発第1063号)
こちらもどうぞ
②<H22年出題>
厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)では、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間について、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間としている。

【解答】 ×
■過重負荷の評価期間■
「異常な出来事」 → 発症直前から前日までの間
「短期間の過重業務」 → 発症前おおむね1週間
「長期間の過重業務」 → 発症前おおむね6か月間
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-252
R3.5.2 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 その1
今日のテーマは、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H18年選択>
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

【解答】
①<H18年選択>
A 労働基準法施行規則
B 労働者災害補償保険法施行規則
C 業務に起因することの明らかな疾病
ポイント!
業務上の疾病の範囲 → 労働基準法施行規則
通勤による疾病の範囲 → 労働者災害補償保険法施行規則
で定められている。
労働基準法施行規則別表第1の2を見てみましょう
★空欄を埋めてください。
別表第一の二
一 業務上の< D >に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
(省略)
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
(省略)
四 化学物質等による次に掲げる疾病
(省略)
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
(省略)
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
(省略)
八 < E >にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他< F >ことの明らかな疾病

【解答】
D 負傷
E 長期間
F 業務に起因する
労働基準法施行規則別表第一の二(「職業病リスト」)の1号から10号で、一定の疾病が例示列挙されています。
また、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」は、例示列挙されている疾病以外に業務に起因したと認められる疾病が発生した場合に、当てはめるためのものです。
★ なお、「業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患」は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱われます。
要件は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」によります。明日から、こちらの通達をみていきます。
こちらの問題もどうぞ!
②<H28年出題>
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

【解答】
②<H28年出題> 〇
「業務上の疾病」と認められるには、労働基準法施行規則別表第一の二の1号から11号のどれかに該当することが要件です。
社労士受験のあれこれ
雇入れ時の健康診断
R3-251
R3.5.1 雇入れ時の健康診断でよく出るところ
今日のテーマは、「雇入れ時の健康診断」です。よく出るところをチェックしましょう!
まずこちらからどうぞ!
①<H23年選択>
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。

【解答】
①<H23年選択>
A 常時使用する
「すべての労働者」とすると間違いなので注意しましょう。常時使用する労働者が対象です。
(則第43条)
こちらの問題もどうぞ!
②<H27年出題>
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

【解答】
②<H27年出題> ×
契約期間が1年の労働者は、実施義務の対象です。
■■対象になる労働者■■
「常時使用する労働者とは?」 → ①と②の両方の要件を満たす者
①「期間の定めのある労働契約」であっても、1年以上使用される予定の者 (一定の有害業務に従事する者は6月以上使用される予定の者)
②同種の業務に従事する労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
※4分の3未満の労働者でも、概ね2分の1以上である者に対しても健康診断の実施が望ましいとされている
(平成19年10月1日基発第1001016号)
最後にもう一問どうぞ
③<H17年出題>
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

【解答】
③<H17年出題> ×
雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、「すべての労働者」です。
(第59条)
★条文を比較してみると
(雇入れ時の健康診断)則第43条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(雇入れ時の安全衛生教育) 第59条
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
※第59条(安全衛生教育)は、常時使用する労働者に限定されていません。
社労士受験のあれこれ
安全委員会・衛生委員会
R3-250
R3.4.30 安全委員会・衛生委員会の会議
今日のテーマは、「安全委員会と衛生委員会」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H21年出題>
安全委員会を設けなければならない事業場においては、衛生委員会を設けなければならない。

【解答】
①<H21年出題> 〇
安全委員会は、一定の業種及び規模(50人以上又は100人以上)の事業場ごとに、 一方、衛生委員会は、全業種・50人以上の事業場ごとに設置が義務付けられています。
安全委員会の設置義務がある事業場は、衛生委員会も設置しなければなりません。
なお、安全委員会と衛生委員会を設置しなければならないときは、合わせて「安全衛生委員会」を設置することができます。
(法第17条、第18条、第19条)
こちらの問題もどうぞ!
②<H21年出題>
衛生委員会を設けなければならない事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
③<H20年出題>
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
②<H21年出題> 〇
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければならない、とされています。
(則第23条)
③<H20年出題> ×
委員会の開催状況を所轄労働基準監督署長に報告する義務はありません。
なお、以下の点は義務付けられています。
・委員会開催の都度、遅滞なく、委員会の議事の概要を労働者に周知させる
・委員会開催の都度、一定事項を記録し、3年間保存する
(則第23条)
最後にもう一問どうぞ
④<H26年出題>
安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

【解答】
④<H26年出題> 〇
「関係労働者の意見を聴くための機会を設ける」とは、安全衛生の委員会、労働者の常会、職場懇談会等労働者の意見を聴くための措置を講ずることをいうものである、とされています。
(則第23条の2、昭47.9.18基発第601号の1)
ちなみに。。。
「安全・衛生委員会は一定規模等の事業場に設置義務があり、事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策の推進について事業者が必要な意見を聴取し、その協力を得るために設置運営されるもの。したがって、安全・衛生委員会の活動は労働時間内に行なう」のが原則とされています。
(昭47.9.18発基第91号)
安全・衛生委員会の会議の時間は「労働時間」となり、法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金の支払が必要です。
(昭47.9.18基発602号)
社労士受験のあれこれ
労基法上の「休日」
R3-249
R3.4.29 労働基準法上「休日」とは?
今日のテーマは、労働基準法の「休日」です。
まず、労働基準法の「休日」の与え方について確認してみましょう。
<原則> 毎週少くとも1回
<例外> 4週間を通じ4日以上
では、どうぞ!
①<H29年出題>
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
②<H13年出題>
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。
③<H24年出題>
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
①<H29年出題> ×
連続24時間、労働義務から解放しても「休日」を与えたことにはなりません。
原則として、労働基準法の「休日」は、午前零時から午後12時までの暦日を指します。起算時点は、午前零時です。
(昭23.4.5基発535号)
②<H13年出題> ×
休日は、原則として、午前零時から午後12時までの暦日ですが、例えば8時間3交替連続作業の場合などは、例外的に2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることも認められています。
(昭63.3.14基発150号)
③<H24年出題> 〇
一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日とは認められません。
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 〇 | 非番 | 〇 | 非番 | 〇 | 非番 | 休日 | 〇 |
8時 |  8時 8時 | 8時 |  8時 8時 | 8時 |  8時 8時 | 8時 |
※非番は休日とはならない。「休日」は原則どおり午前零時から午後12時までの暦日でなければなりません。
(昭23.11.9 基収2968号)
こちらの問題もどうぞ!
④<H23年出題>
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。
⑤<H13年出題>
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】
④<H23年出題> 〇
休日は「毎週1回」が原則。例外的に「4週間を通じ4日以上の休日」(変形休日制)が認められています。
変形休日制の場合、4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものおいて明らかにする必要があります。
(昭22.9.13発基17号、則第12条の2)
⑤<H13年出題> ×
変形休日制の場合、特定の4週間に4日の休日があればOKです。
どの4週間を区切っても、4日の休日がなければならないという意味ではありません。
④の問題で見たように、起算日を明らかにしなければならないのは、特定の4週間を明確にするためです。
(昭23.9.20基発1384号)
社労士受験のあれこれ
平均賃金
R3-248
R3.4.28 平均賃金~算定すべき事由の発生した日
労働基準法の「平均賃金」は、原則として『算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額』÷『その期間の総日数』で計算します。
今日のテーマは、「算定すべき事由の発生した日」についてです。
なお、「平均賃金」は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給制裁の際に使われます。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
②<H25年出題>
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
③<H30年出題>
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
④<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

【解答】
①<H27年出題> ×
災害補償の場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」となります。
(施行規則第48条)
②<H25年出題> ×
③<H30年出題> ×
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
(昭30.7.19 29基収5875号)
④<H16年出題> 〇
解雇予告手当を算定する場合の「算定すべき事由の発生した日」は、労働者に解雇の通告をした日です。
(昭39.6.12 36基収2316号)
こちらの問題もどうぞ!
⑤<H27年出題>
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】 〇
ポイント!
①条文では、「算定すべき事由の発生した日以前3か月間」となっていますが、事由の発生した日の前日から遡ると解されています。
問題文の場合、7月31日に算定事由が発生していますので、前日の7月30日から遡ります。
②ただし、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算することになっています。問題文の場合、7月30日の直前の賃金締切日は6月30日となります。
(第12条)
社労士受験のあれこれ
労働条件の変更(労働契約法)
R3-247
R3.4.27 労働契約法・就業規則による労働契約の内容の変更など
「労働条件」を変更することはできるのでしょうか?
就業規則の変更によって労働条件を不利益に変更することは認められるのでしょうか?
そんな観点で労働契約法を読んでみましょう。
<労働契約の内容の変更>
①<H24年出題>
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。

【解答】
①<H24年出題> 〇
労働契約法第8条では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とされています。
■ポイント■
・労働契約の変更についての基本原則である「合意の原則」を確認したもの
・労働契約の内容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより変更される。労働契約の変更の要件として、変更内容について書面を交付することまでは求められない。
(参照 H24.8.10基発0810第2号)
<就業規則の変更による労働契約の内容の変更>
②<H23年出題>
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。

【解答】
②<H23年出題> 〇
法第10条からの出題です。
法第10条は、就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となる場合に適用されます。
「就業規則の変更」という方法によって「労働条件を変更する場合」において、
・使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知」させたこと
・「就業規則の変更」が「合理的なものである」こと
という要件を満たした場合
↓
労働契約の変更についての「合意の原則」の例外として、
「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じることを規定しています。
また、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況」は、就業規則の変更が合理的なものであるか否かを判断するに当たっての考慮要素として例示されたものです。
(参照 H24.8.10基発0810第2号)
<就業規則の変更に係る手続>
③<H29年出題>
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、労働契約法第11条に定める就業規則の変更に係る手続を履行されていることは、労働契約の内容である労働条件が、変更後の就業規則に定めるところによるという法的効果を生じさせるための要件とされている。

【解答】
③<H29年出題> ×
法第11条からの出題です。法第11条では、「就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによる。」と規定されています。
■■ポイント■■
労働基準法第89条及び第90条に規定する就業規則に関する手続は、法第10条本文の法的効果を生じさせるための要件ではないものの、就業規則の内容の合理性に資するものとなります。就業規則の変更の手続は、労働基準法第89条及び第90条の定めるところによることを規定し、それらの手続が重要であることを明らかにしたものです。
(参照 H24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
中高年者縦断調査(厚生労働省)
R3-246
R3.4.26 第15回中高年者縦断調査の結果より
平成27年の選択式では、中高年者縦断調査(厚生労働省)からの出題がありました。
今日は、「第15回中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査)の概況」を見てみましょう。
<調査の目的>
この調査は、団塊の世代を含む全国の中高年者世代の男女を追跡して調査し、高齢者対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることが目的。
平成 17 年度を初年として実施している。
<調査の対象及び客体>
平成17年10 月末時点で 50~59 歳であった全国の男女が対象。そのうち、第1 回調査又は 第14回調査で協力を得られた者を調査客体(20,903人)としている。 第15回調査における対象者の年齢は、64~73 歳。
ではどうぞ!
第1回調査から 14 年間の就業状況の変化をみると、「正規の職員・従業員」は、第1回 38.5%から第 15 回4.1%と減少している。一方、「パート・アルバイト」は、第1回 16.8%から第15 回< A >。
①28.2%と、10ポイント以上増加した
②16.9%と、ほぼ横ばいの状況である
③8.3%と、ほぼ半減した

【解答】
A ②16.9%と、ほぼ横ばいの状況である
※この14年間で、「正規の職員・従業員」の割合は減少、「パート・アルバイト」の割合はほぼ横ばいとなっています。
社労士受験のあれこれ
労基法、安衛法、労働契約法の違い
R3-245
R3.4.25 使用者の定義(労基法・安衛法・労契法)
今日のテーマは、「使用者」の定義です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法の違いをチェックしましょう。
では労働基準法からからどうぞ!
①<労働基準法 H21年選択>
労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする< A >をいう。
②<労働基準法 H26年出題>
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

【解答】
①<労働基準法 H21年選択>
A すべての者
労働基準法の使用者
・事業主
・事業の経営担当者
・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
②<労働基準法 H26年出題> ×
労働基準法の使用者は、「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。
次は労働安全衛生法です!
③<安衛法 H28年出題>
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
④<安衛法 H26年出題>
労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

【解答】
③<安衛法 H28年出題> 〇
労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念を異にしています。
「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。
労働基準法上の義務主体である「使用者」と違い、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。
(法第2条、昭47.9.18発基91号)
④<安衛法 H26年出題> ×
労働安全衛生法第2条で、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されています。
事業者の意味づけは③で解説している通りです。
最後は労働契約法をどうぞ!
⑤<労働契約法 H29年出題>
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

【解答】
⑤<労働契約法 H29年出題> ×
「労働基準法第10条の「使用者」と同義である。」が誤りです。
労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。
したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであり、これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当し、労働基準法の「使用者」より狭い概念であること、とされています。
(法第2条、H24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
労基法、安衛法、労働組合法、労働契約法の相違
R3-244
R3.4.24 労働者の定義(労基・安衛・労組・労契)
今日のテーマは、「労働者」の定義です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、労働契約法の違いをチェックしましょう。
ではこちらからどうぞ!
①<労働基準法>
労基法第9条(定義)
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、< A >をいう。
第116条(適用除外)
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び< B >については、適用しない。
②<安衛法 H28年出題>
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
③<労働組合法 H23年出題>
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
④<労働契約法 H24年出題>
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

【解答】
①<労働基準法>
A 賃金を支払われる者
B 家事使用人
②<安衛法 H28年出題> 〇
労働安全衛生法の労働者の定義は、「労働基準法第9条の労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」をいうとされています。
(安衛法第2条)
③<労働組合法 H23年出題> 〇
労働組合法では、「「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。
(労組法第3条、昭和23年6月5日労発第262号)
④<労働契約法 H24年出題> 〇
労働契約法の「労働者」には、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」のすべてが含まれます。そのため、その要件に該当すれば家事使用人にも労働契約法は適用されます。
なお、労働契約法第21条(適用除外)では、労働契約法の適用について、①国家公務員及び地方公務員については、適用しない。②使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
とされていて、家事使用人は適用除外に入っていません。
(法第2条、第21条、平24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
最低賃金法
R3-243
R3.4.23 最低賃金の定め方など
今日のテーマは、最低賃金の定め方などです。
最低賃金法によって、賃金の最低限度額が定められています。
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類がありますが、その額以上の賃金を支払わなければなりません。
ではこちらからどうぞ!
①<H21年出題>
法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められている。
②<H21年出題>
法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。
③<H21年出題>
法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。
④<H21年出題>
法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められ、法第39条において、法第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。
⑤<R1年出題>
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

【解答】
①<H21年出題> ×
最低賃金額は、「時間」によって定められています。「日」単位では定められていません。
賃金額を時間当たりに換算した額と、最低賃金額と比べます。
②<H21年出題> ×
考慮されるのは、「企業収益」ではなく「通常の事業の賃金支払能力」です。
なお、「地域別最低賃金」は、各都道府県ごとに定められていて、全部で47件設定されています。
もう一つの「特定最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
③<H21年出題> 〇
使用者には、最低賃金の概要を労働者に周知する義務があります。概要は次の3点です。
1 適用を受ける労働者の範囲及びこれらの労働者に係る最低賃金額
2 最低賃金に算入しない賃金
3 効力発生年月日
また、周知義務に違反した場合は罰則があります。
④<H21年出題> ×
都道府県労働局長、労働基準監督署長又は「公共職業安定所長」ではなく、「都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官」です。
(最低賃金法に違反する事実がある場合)
・第34条 → 監督機関(都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官)に対して申告ができる
・第34条第2項 → 申告をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止
・第39条 → 不利益取扱いの禁止の規定に違反した場合の罰則規定
⑤<R1年出題> 〇
派遣労働者に適用されるのは、「派遣先」の最低賃金です。
※派遣労働者の賃金を支払うのは「派遣元」です。
では、選択式もどうぞ!
<H24選択>
最低賃金法は、その第1条において、「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、< A >ことを目的とする。」と規定している。
また、同法における< B >別最低賃金は、中央最低賃金審議会が出した引上げ額の目安を受けて、地方最低賃金審議会が< B >の実情を踏まえた審議、答申をした後、異議申出に関する手続を経て< C >が決定する。
< B >別最低賃金は、同法によれば< B >における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の< D >を総合的に勘案して定められなければならないとされており、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、< E >に係る施策との整合性に配慮するものとされている。

【解答】
A 国民経済の健全な発展に寄与する
B 地域
C 都道府県労働局長
D 賃金支払能力
E 生活保護
※地域別最低賃金審議の流れ
・中央最低賃金審議会
「目安審議」を行う
↓
・地方最低賃金審議会
引上げ額の目安を受けて、地域の実情を踏まえた審議・答申を得て、異議申出に関する手続を経て都道府県労働局長により決定される。
社労士受験のあれこれ
労働組合法
R3-242
R3.4.22 労働組合法の目的と労働組合の定義
今日のテーマは、労働組合法の目的と労働組合の定義です。
穴埋めで条文checkしましょう
第1条(目的)
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために< A >に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する < B >を締結するための< C >をすること及びその手続を助成することを目的とする。
第2条(労働組合)
労働組合法で「労働組合」とは、労働者が主体となって< A >に労働条件の維持改善その他< D >の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、次の各号に該当するものは除く。
1 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ< E >にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する< E >にある労働者その他< F >を代表する者の参加を許すもの
2 団体の運営のための経費の支出につき使用者の< G >を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
3 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
4 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

【解答】
A 自主的
B 労働協約
C 団体交渉
D 経済的地位
E 監督的地位
F 使用者の利益
G 経理上の援助
では、こちらもどうぞ!
①<H26年出題>
労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。
②<R2年出題>
労働組合が、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けていても、労働組合法上の労働組合の要件に該当するとともに、使用者の支配介入として禁止される行為には該当しない。

【解答】
①<H26年出題> ×
政治運動や社会運動そのものは禁止されていませんが、主として政治運動又は社会運動が目的になっているものは、労働組合とは認められません。
労働組合の目的は、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることです。
②<R2年出題> 〇
団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるものは、労働組合とは認められませんが、使用者から最小限の広さの事務所の供与を受けることは、経理上の援助に当たりません。
社労士受験のあれこれ
年齢問題~介護保険法、高齢者医療確保法
R3-241
R3.4.21 何歳から?(介護保険、後期高齢者医療)
今日のテーマは、介護保険、後期高齢者医療制度の対象になる年齢です。
まずは、「高齢者医療確保法」からどうぞ!
①<H22年出題>
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

【解答】
①<H22年出題> ×
「年齢」が誤り。70歳ではなく75歳です。
<後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者>
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
・65歳以上75歳未満の者で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
(法第50条)
※「後期高齢者医療広域連合」とは?次の問題を解いてください。
②<H22年出題>
市町村(特別区を含む。以下同じ)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】
②<H22年出題> 〇
「後期高齢者医療広域連合」は、都道府県ごとに設けられています。
(法第48条)
なお、後期高齢者医療の事務から、「保険料の徴収の事務」が除かれていることに注意しましょう。保険料を徴収するのは、後期高齢者医療広域連合ではなく「市町村」です。
次は「介護保険法」をどうぞ!
③<H24年出題>
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
④<H23年出題>
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
⑤<H29年出題>
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

【解答】
③<H24年出題> 〇
④<H23年出題> ×
「20歳以上65歳未満」ではなく「40歳以上65歳未満」です。
⑤<H29年出題> ×
第2号被保険者は、「医療保険加入者」であることが要件なので、医療保険加入者でなくなった場合は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失します。
※介護保険の被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類です。
1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 → 「第1号被保険者」
2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
→ 「第2号被保険者」
(法第9条、第11条)
社労士受験のあれこれ
介護保険法
R3-240
R3.4.20 介護給付を受けようとするときの手続き
今日のテーマは、介護給付を受けるときの手続きです。
①介護給付を受けるには認定を受けなければならない
①<H24年出題>
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

【解答】
①<H24年出題> ×
厚生労働大臣の認定ではなく、「市町村又は特別区」の認定を受けなければなりません。
(法第19条)
<認定の流れ>
・要介護認定の申請
↓
・認定調査
↓
・主治医の意見
↓
・介護認定審査会による審査判定
↓
・認定
②認定の効力はいつから発生する?
②<R1年出題>
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

【解答】
②<R1年出題> 〇
「申請のあった日」までさかのぼるのがポイントです。
(法第27条第8項)
③認定結果が出るのはいつ?
③<H29年出題>
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

【解答】
③<H29年出題> 〇
認定の結果が通知されるのは、原則として申請から30日以内とされています。
(法第27条第11項)
④要介護認定の有効期間
④<H24年出題>
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
⑤<H29年出題>
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村又は特別区に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

【解答】
④<H24年出題> 〇
要介護認定には、有効期間があります。
⑤<H29年出題> 〇
有効期間満了後も要介護状態の場合は更新申請ができます。
社労士受験のあれこれ
社会保険労務士法
R3-239
R3.4.19 社労士法~紛争解決手続代理業務
今日はのテーマは、紛争解決手続代理業務です。
では、まずは選択問題からどうぞ!
<H19年選択>
1 社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。」と規定されている。
2 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< C >を行うことが含まれている。
3 ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < D >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< E >社会保険労務士に限られる。

【解答】
A 発達 (※発展ではなく「発達」です。注意しましょう。)
B 福祉の向上
C 和解の交渉
D 紛争解決手続代理業務試験
E 特定
(法第1条、第2条)
こちらもどうぞ!
①<R1年出題>
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

【解答】 ×
紛争解決手続代理業務ができるのは「特定社会保険労務士」だけです。「すべての社会保険労務士」が誤りです。
・「紛争解決手続代理業務」に含まれる事務
① 紛争解決手続について相談に応ずること。
② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
③ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合・遺族年金
R3-238
R3.4.18 2以上の種別の期間を有する場合~遺族厚生年金編
引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「遺族厚生年金」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H30年出題>
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

【解答】
①<H30年出題> 〇
注目ポイントは次の2つ
・ 死亡した者が「短期要件」であること(→『障害等級1級の障害厚生年金の受給権者でいわゆる長期要件には該当しない』)
・ 死亡した者が「2以上の被保険者の種別」に係る被保険者であった期間を有していたこと
■2以上の種別の被保険者期間がある場合の遺族厚生年金の計算
・短期要件の場合
→ それぞれの種別の期間を合算して計算する。(→死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする)
→ それぞれの種別の期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月で計算する
・長期要件の場合
→ それぞれの種別ごとに計算する
→ 300月の最低保障は無し
(法第78条の32、施行令第3条の13の6)
こちらもどうぞ!
②<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

【解答】
②<H28年出題> 〇
注目ポイント 問題文の遺族厚生年金は「長期要件」で2以上の種別の期間がある
問題文の場合、「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある者)」が死亡したときに該当するので長期要件です。
長期要件の遺族厚生年金は、先ほどの①の解説にも書きましたように「それぞれの種別ごとに計算」されます。また支給は、「それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される」ことになります。
問題文の場合でしたら、第1号分(15年)は「厚生労働大臣」、第3号分(18年)は、「地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会」が行います。
なお、「短期要件」の場合の実施機関は、以下の時点で判断されます。
・被保険者の死亡 → 「死亡日」における種別
・資格喪失後の死亡(被保険者期間中に初診日ある傷病で初診日から5年以内に死亡)
→ 「初診日」における種別
・1,2級の障害厚生年金の受給権者の死亡 → 「初診日」における種別
(法第78条の32、施行令第3条の13の10)
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合・障害年金
R3-237
R3.4.17 2以上の種別の期間を有する場合~障害厚生年金編
昨日に引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「障害厚生年金」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日おいて2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【解答】
①<H28年出題> ×
当該障害に係る『障害認定日』における被保険者の種別に応じた実施機関が行うの部分の「障害認定日」が誤り。障害認定日ではなく、「初診日」です。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の当該障害厚生年金の支給に関する事務は、「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行うことになります。
例えば、20歳から10年間は第1号厚生年金被保険者で、30歳から第4号厚生年金被保険者で、第4号厚生年金被保険者である期間に初診日がある場合は、障害厚生年金の支給に関する事務は、日本私立学校振興・共済事業団が行います。
(法第78条の33)
こちらもどうぞ!
②<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】
②<H29年出題> ×
障害厚生年金の受給権者で、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金の額は、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなすことになっています。
計算の基礎となるのは、「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」ではなく、それぞれを「合算」することになります。
(法第78条の30)
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合の加給年金額
R3-236
R3.4.16 2以上の種別の期間を有する場合~老齢編その2(加給年金額)
昨日に引き続き、「2以上の種別の期間を有する」場合の年金がテーマです。
今日は「加給年金額」です。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
②<H30年出題>
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

【解答】
①<H28年出題> 〇
問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間がある場合は、合算して240か月以上あれば加給年金額が加算されます。
第1号厚生年金被保険者分の老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者分の老齢厚生年金は、それぞれ別個に計算・支給されますが、加給年金額はどちらか一方に加算されます。
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金について、加給年金額はどの老齢厚生年金に加算されるのでしょうか?加算される順番は、政令で次の通り定められています。
①最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金に加算する
↓
②同時に受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、最も長い期間で計算される老齢厚生年金に加算する
↓
③期間が同じ場合は、第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間、第4号厚生年金被保険者期間の順序で加算する
問題文の場合は、それぞれの老齢厚生年金の受給権は同じ日(平成27年10月1日)に取得していますので、期間が長い方の第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、施行令第3条の13)
②<H30年出題> ×
「遅い日」において・・・の部分が誤りです。
2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、「遅い日」ではなく「早い日」において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金にのみ加給年金額が加算されます。
(法第78条の27、施行令第3条の13)
社労士受験のあれこれ
厚年 2以上の種別の期間を有する場合
R3-235
R3.4.15 2以上の種別の期間を有する場合~老齢編その1
テーマは「2以上の種別の期間を有する」場合の年金についてです。
厚生年金保険の被保険者は、4つの種別に区分されています。
第1号厚生年金被保険者(民間企業)
第2号厚生年金被保険者(国家公務員)
第3号厚生年金被保険者(地方公務員)
第4号厚生年金被保険者(私学教職員)
例えば、民間企業で勤務した後国家公務員になった場合、第1号厚生年金被保険者の期間と第2号厚生年金被保険者の期間を有することになりますが、そのような場合の年金のルールを確認していきます。
では、こちらからどうぞ!
①<H28年出題>
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

【解答】
①<H28年出題> ×
特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する」こと」が要件です。
2以上の種別の被保険者であった期間がある場合は、合算して1年以上あればOKです。問題文の場合は、合算して18カ月あるので、特別支給の老齢厚生年金の支給要件を満たします。
問題文の女性(昭和31年4月2日生まれ)の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
・60歳支給開始 → 第1号厚生年金被保険者期間分
・62歳支給開始 → 第2号厚生年金被保険者期間分
(法附則第8条、法附則第20条)
では、こちらもどうぞ!
②<R2年出題>
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。
③<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。

【解答】
②<R2年出題> 〇
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は、それぞれ区分して計算され、それぞれ併給されます。
また、老齢厚生年金はそれぞれの実施機関から支給されます。(第1号厚生年金被保険者期間分は「厚生労働大臣」、第2号厚生年金被保険者期間分は「国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会」)
(法第78条の26)
③<H29年出題> ×
「2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して・・・」の部分が誤りです。合算して平均標準報酬額を算出するのではなく、それぞれの種別ごとに平均標準報酬額を算出します。
(第78条の26)
社労士受験のあれこれ
経過的寡婦加算
R3-234
R3.4.14 経過的寡婦加算でよく出るところ
テーマは「経過的寡婦加算」です。
『中高齢寡婦加算』と違う点を特に意識してください。
では、こちらからどうぞ!
①<H14年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるときは、その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので、中高齢寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。

【解答】
①<H14年出題> ×
中高齢寡婦加算の支給は65歳で終了しますが、65歳以後は、遺族厚生年金に経過的寡婦加算が加算されます。
ポイント!経過的寡婦加算は生年月日の要件あり!
「経過的寡婦加算」は、昭和31年4月1日以前に生まれた者が対象です。
★なぜ、「昭和31年4月1日以前」なの??
会社員の被扶養配偶者が「第3号被保険者」として国民年金に強制加入するようになったのは、「昭和61年4月1日」からで、その前(旧法時代)は、「国民年金は任意加入」でした。
例えば、会社員に扶養される妻が「昭和31年4月2日」以降生まれの場合を考えてみましょう。昭和31年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算は支給されません。
なぜなら、昭和61年4月1日時点で30歳未満だからです。仮に20歳から60歳まで40年間会社員に被扶される妻で、旧法時代に任意加入していなかったとしても、40年のうち30年以上は第3号被保険者となり、老齢基礎年金の額は、満額の4分の3以上(480月のうち360月以上)で計算されます。
65歳まで加算される「中高齢寡婦加算」が遺族基礎年金の4分の3なので、それと同額の老齢基礎年金が65歳から支給されます。そのため「経過的寡婦加算」でカバーする必要がないからです。
一方、「昭和31年4月1日」以前生まれの妻の場合は、同じく40年間会社員に扶養される妻だった場合、第3号被保険者の期間が30年未満となり、老齢基礎年金の額が4分の3未満となります。
経過的寡婦加算は、その4分の3未満になる部分をカバーするために加算されるものです。
(昭60年法附則第73条)
では、こちらの問題をどうぞ!
②<H15年出題(修正)>
遺族厚生年金に加算される経過的寡婦加算額は、妻の生年月日に応じて最低39,070円から最高780,900円までの額として加算される。

【解答】
②<H15年出題(修正)> ×
経過的寡婦加算の額は、最低19,547円から最高585,700円までの額となります。
計算式は、次の通りです。
「中高齢の寡婦加算の額」-「満額の老齢基礎年金」×妻の生年月日に応じた乗率
乗率は、昭和2年4月1日以前生まれは「ゼロ」で生年月日が若いほど乗率は大きくなり、一番若い「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれは、「480分の348」となります。
経過的寡婦加算が中高齢寡婦加算と同額の「585,700円」になるのは、昭和2年4月1日以前生まれ。最低額の19,547円になるのは、「昭和30年4月2日~昭和31年4月1日」生まれです。
若い人ほど「第3号被保険者期間」が長くなる=老齢基礎年金が多くなるので、経過的寡婦加算は逆に少なくなる仕組みです。
再度、中高齢寡婦加算との違いを確認しましょう。
・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額
・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される
(昭60年法附則第73条)
こちらもどうぞ!
③<H28年出題>
経過的寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権者が国民年金法による障害基礎年金の支給を受ける場合には、遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
③<H28年出題> 〇
遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止されます。
障害基礎年金で満額保障されるので、経過的寡婦加算でカバーする必要が無いからです。
(昭60年法附則第73条)
社労士受験のあれこれ
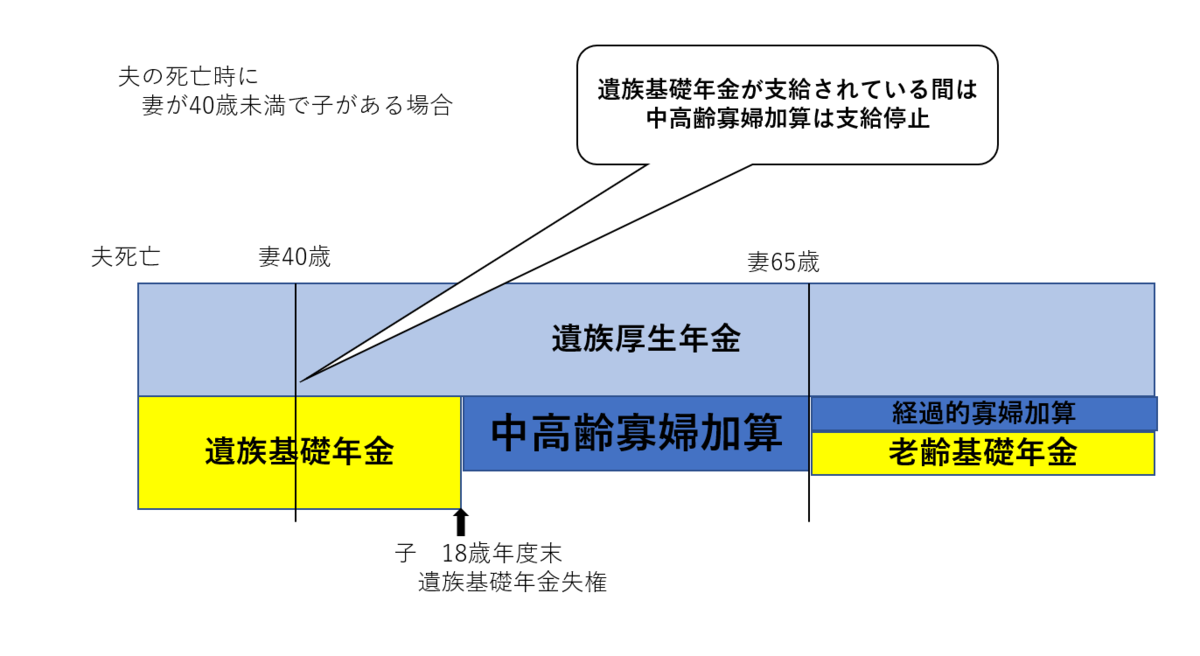
中高齢寡婦加算(その2)
R3-233
R3.4.13 中高齢寡婦加算の額
昨日に引き続き、テーマは中高齢寡婦加算です。
今日は中高齢寡婦加算の額です。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第62条
遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、
遺族厚生年金の額に< A >の額に< B >を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)を加算する。

【解答】
A 遺族基礎年金
B 4分の3
C 50円
D 100円
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額×4分の3で計算します。
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H17年出題>
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。
②<H21年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使用し算出されるが、経過的寡婦加算の額は、当該妻の生年月日にかかわらず、一定の金額とされている。

【解答】
①<H17年出題> ×
中高齢寡婦加算の額は、老齢基礎年金の額の4分の3ではなく、『遺族基礎年金』の額の4分の3です。経過的寡婦加算の額は問題文の通りです。
②<H21年出題> ×
中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算の説明が逆です。
・中高齢寡婦加算の額は → 妻の生年月日にかかわらず一定の金額
・経過的寡婦加算の額は → 妻の生年月日に応じた率を使用し算出される
※『経過的寡婦加算』については、後日、記事にします。
こちらもどうぞ!
③<H28年出題>
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻が当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
③<H28年出題> 〇
子がいる場合は「遺族厚生年金と遺族基礎年金」が支給されます。遺族基礎年金が支給されている間(子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間等)は、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止されます。
(法第65条)
社労士受験のあれこれ
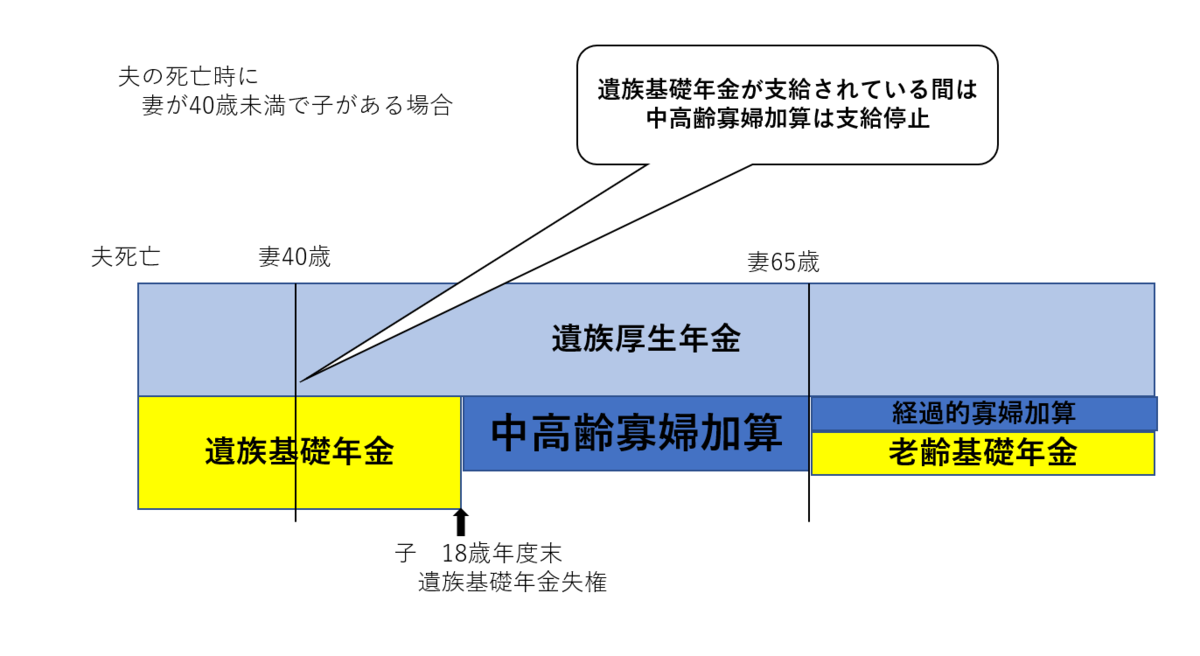
中高齢寡婦加算(その1)
R3-232
R3.4.12 中高齢寡婦加算が加算される要件
テーマは中高齢寡婦加算です。
中高齢寡婦加算が加算される要件を確認しましょう。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第62条
遺族厚生年金(第58条第1項第4号(長期要件)に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が< A >未満であるものを除く。)の受給権者である妻であって
その権利を取得した当時< B >歳以上< C >歳未満であったもの
又は< B >歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で国民年金法第37条の2第1項に規定する要件に該当するものと生計を同じくしていたものが< C >歳未満であるときは、
遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。

【解答】
A 240
B 40
C 65
ポイント!
・中高齢寡婦加算の対象は「妻」のみ
・対象になる妻の要件
①夫の死亡時に、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない
②夫の死亡時に子があり、遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していたが、子が年齢要件等に該当したため遺族基礎年金を受給できなくなった(夫の死亡時に40歳未満だったが40歳到達時に遺族基礎年金を受けていた)
・支給される遺族厚生年金が長期要件の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間月数が240月(中高齢の期間短縮特例に該当する場合はその期間)以上あること
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H27年出題>
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。
②<H19年出題(修正)>
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者(老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上ある)が死亡した場合において、死亡した者の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した当時、遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず、かつ、当該妻がその当時40歳未満であった場合、当該妻の遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が行われることはない。

【解答】
①<H27年出題> 〇
子のない妻(遺族基礎年金が支給されない)の場合は、夫の死亡時に40歳以上65歳未満であることが条件です。
ちなみに、この問題は「被保険者である夫の死亡」なので遺族厚生年金は短期要件です。
②<H19年出題(修正)> 〇
①と同じく、夫の死亡当時妻が40歳未満で子がいない場合は、中高齢寡婦加算は行われません。
ちなみに、この問題は長期要件です。
★再度確認しておくと
中高齢寡婦加算が加算される妻は
①子がいない場合
夫の死亡時に40歳以上65歳未満であること
②夫の死亡時に子がある場合
夫の死亡時に40歳未満でも40歳到達時に子がいる(遺族基礎年金を受けている)こと
社労士受験のあれこれ
65歳以上の配偶者の遺族厚生年金
R3-231
R3.4.11 65歳以上の配偶者の遺族厚生年金
今日のテーマは、65歳以上の配偶者の遺族厚生年金です。
遺族厚生年金は、原則として老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3で計算しますが、65歳以上の配偶者については、別の計算式があります。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第60条、附則第17条の2 (年金額)
遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、1.に定める額とする。
1. 第59条第1項に規定する遺族(2.に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金)の例により計算した額の< A >に相当する額。
ただし、短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。
2.第59条第1項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(< B >歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
→ 1.に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 1.に定める額に< C >を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に < D >を乗じて得た額

【解答】
A 4分の3
B 65
C 3分の2
D 2分の1
ポイント!
★★65歳以上の配偶者の遺族厚生年金の額★★
老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき
遺族厚生年金の額は、1.と2.のいずれか多い方
1.死亡した人の老齢厚生年金額の4分の3
2.1.の額の3分の2 + 自身の老齢厚生年金額の2分の1
※いずれか多い方とは → いずれかを選択する方法ではなく、多い方が遺族厚生年金の額になります。
※1.の額の3分の2は(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2)なので、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1となります。つまり、2.の額は、死亡した人の老齢厚生年金の2分の1+自身の老齢厚生年金の2分の1の額です。
※この仕組みは『65歳以上』の『配偶者』だけに適用されます。
では、こちらの問題をどうぞ!
<H24年出題>
65歳に達している受給権者に支給される遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。

【解答】 ×
受給権者が65歳以上の場合、遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせについては、「遺族厚生年金+老齢基礎年金」、「遺族厚生年金+障害基礎年金」の組み合わせが可能です。
なお、問題文の「遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する」という表現も誤りです。
先ほどの条文の2.の額(死亡した人の老齢厚生年金の4分の3×3分の2+自身の老齢厚生年金の2分の1の額)の方が1.の額より多い場合は2.の額が「遺族厚生年金」の額となるので、問題文の「同時に受給する」という表現にはなりません。
社労士受験のあれこれ
遺族厚生年金~短期要件と長期要件
R3-230
R3.4.10 遺族厚年 短期要件と長期要件の違い
今日のテーマは、遺族厚生年金「短期要件」と「長期要件」です。それぞれ年金額の計算に違いがあります。
では、こちらからどうぞ!
<穴埋め問題>
第58条
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、①又は②に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に < A >がある傷病により当該< A >から起算して< B >を経過する日前に死亡したとき。
③ < C >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者が、死亡したとき。

【解答】
A 初診日
B 5年
C 障害等級の1級又は2級
D 25年
ポイント!
★①から③は短期要件
①厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
②厚生年金保険の被保険者であった間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
③障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
★④は長期要件
④老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間(と合算対象期間)を合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したとき
保険料納付済期間と保険料免除期間(と合算対象期間)を合算した期間が25年以上である者が死亡したとき
では、こちらの問題をどうぞ!
①<H27年出題(修正)>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
②<H17年出題(修正)>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者)の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。

【解答】
①<H27年出題(修正)> 〇
「長期要件」に該当するので、給付乗率は、生年月日に応じた読み替えを行います。
②<H17年出題(修正)> 〇
「長期要件」に該当するので、「300月」の最低保障は適用なし、給付乗率は生年月日に応じた読み替えが適用されます。
(法第58条、第60条、S60年法附則第59条)
ポイント!
遺族厚生年金の額の計算式(原則)
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額の4分の3
※報酬比例部分→平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数(原則)
| 短期要件 | 長期要件 | |
| 給付乗率 | 定率 | 昭和21年4月1日以前生まれの者は、 生年月日に応じた読み替えあり |
| 被保険者期間の月数 | 300月の最低保障あり | 最低保障なし |
最後にこちらをどうぞ
③<H23年出題(修正)>
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。

【解答】 〇
死亡したのは、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上」の「被保険者」です。長期要件(「25年以上」)と短期要件(「被保険者」)の両方に当てはまっています。
このような場合は、どちらで計算するか選択することができますが、遺族から申出が無い場合は短期要件で計算されます。
(法第58条)
社労士受験のあれこれ
厚年・65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金
R3-229
R3.4.9 65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金の支給調整
今日のテーマは、65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合の支給調整についてです。
では、どうぞ!
<H22年出題(修正)>
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】 〇
例えば、夫婦ともに厚生年金保険の被保険者期間がある場合で夫が死亡した場合、妻は自分自身の老齢厚生年金と夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することになります。
そのような場合、65歳以後は、自分自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。
老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は当該老齢厚生年金の額に相当する部分が支給停止になります。
なお、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金よりも多い場合は、差額が遺族厚生年金として支給されます。
※夫婦を例にあげましたが、このルールは夫婦以外にも当てはまります。
社労士受験のあれこれ
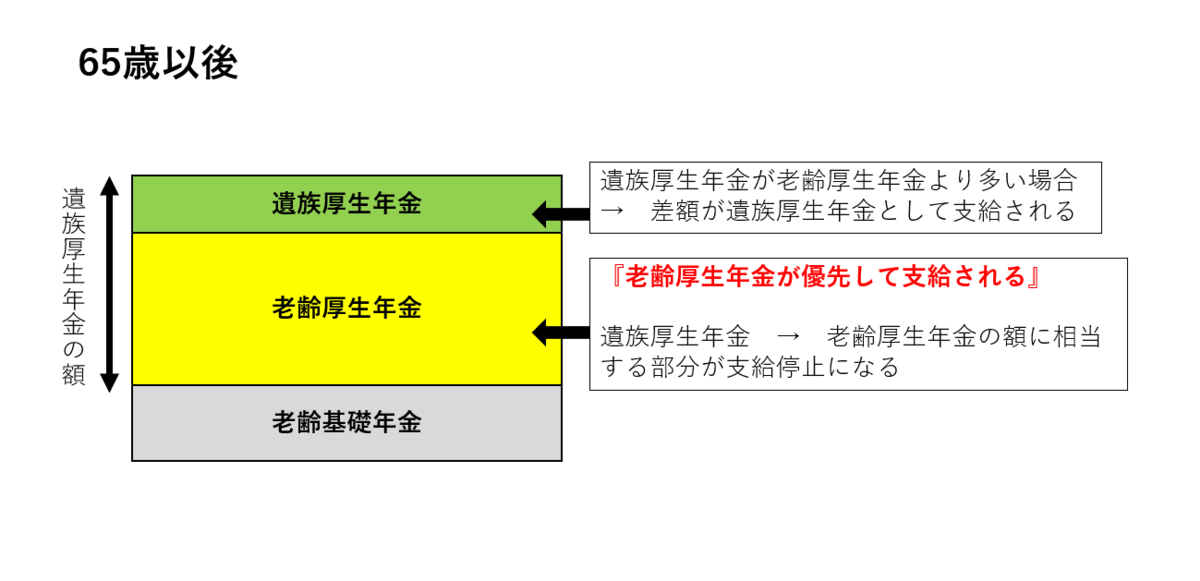
厚年・併給調整(65歳以上)
R3-228
R3.4.8 65歳以上の併給調整のルール
今日のテーマは、併給調整(65歳以上の場合)です。
では、どうぞ!
①<H23年出題>
障害厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。

【解答】
①<H23年出題> ×
「障害厚生年金」と「該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金」は併給できます。
しかし、「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族基礎年金」は、障害厚生年金とは併給できません。(65歳未満でも65歳以上でも不可)
★障害厚生年金と基礎年金の組み合わせ
×老齢基礎年金(+付加年金)と障害厚生年金 → 併給不可
×遺族基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可
〇障害基礎年金+障害厚生年金(同一支給事由の場合) → 併給できる
こちらもどうぞ!
②<H24年出題>
受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。
③<H24年出題>
受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。
④<H26年出題>
障害基礎年金の受給権者である男性が65歳で遺族厚生年金の受給権を得た場合、それぞれを併給することができる。

【解答】
②<H24年出題> 〇
★老齢厚生年金と基礎年金の組み合わせ
〇老齢基礎年金(+付加年金)と老齢厚生年金 → もちろん併給できる
〇障害基礎年金と老齢厚生年金 → 併給できる(65歳以上の場合)
×遺族基礎年金+老齢厚生年金 → 併給不可
★「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせのイメージ
・例えば1級の障害基礎年金を受給しながら働き、その間、厚生年金保険の被保険者になっていた。
→ 65歳から①「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、②「1級の障害基礎年金と老齢厚生年金」の2つから選択できる。
③<H24年出題> 〇
★遺族厚生年金と基礎年金の組み合わせ
〇老齢基礎年金(+付加年金)と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
④<H26年出題> 〇
〇障害基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
■■組み合わせのまとめ■■
| 老齢厚生年金 | 障害厚生年金 | 遺族厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | 〇 | × | 〇(65歳以上) |
| 障害基礎年金 | 〇(65歳以上) | 〇(支給事由が同一) | 〇(65歳以上) |
| 遺族基礎年金 | × | × | 〇(支給事由が同一) |
■■覚え方のポイント■■ → 「遺族厚生年金」は老齢厚生年金と同じように老後(65歳以上)の保障としての性格をもっている。
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H28年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したとしても、それらは併給されないため、いずれか一方のみを受給することができるが、遺族厚生年金の受給権者が65歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、それらの両方を受給することができる。

【解答】 〇
×老齢基礎年金と障害厚生年金 → 併給不可
〇老齢基礎年金と遺族厚生年金 → 併給できる(65歳以上)
★「老齢基礎年金と遺族厚生年金」の組み合わせのイメージ
・夫婦(夫 厚生年金保険の被保険者、妻 第3号被保険者のみ)で、夫が死亡した
→ 妻は、65歳から、妻自身の老齢基礎年金と夫の死亡による遺族厚生年金を併給できる。
社労士受験のあれこれ
厚年・併給調整(65歳未満)
R3-227
R3.4.7 65歳未満の併給調整のルール
今日のテーマは、併給調整(65歳未満)です。
では、どうぞ!
①<H30年出題>
障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

【解答】 ×
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給されません。
★原則は「一人一年金」です。
基礎年金と厚生年金は、支給事由が同一なら併給できます。(2階建て)
・老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+障害厚生年金
・遺族基礎年金+遺族厚生年金
問題文の場合は、①「障害基礎年金+障害厚生年金」と②「特別支給の老齢厚生年金」のどちらかを選択することになります。
この問題は、受給権者が「65歳未満」であることがポイントです。
では、この受給権者が65歳になるとどうなるでしょうか?
65歳以上になると、①「障害基礎年金+障害厚生年金」、②「老齢基礎年金+老齢厚生年金」、③「障害基礎年金+老齢厚生年金」と、選択肢が3つになります。
65歳以上は、「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」が併給できることをおさえましょう。
(第38条、附則第17条)
こちらもどうぞ!
②<H12年出題>
遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳未満の場合には、その者の老齢基礎年金及び付加年金は遺族厚生年金と併給されない。妻が65歳以上のときは、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給されるが、付加年金は併給されない。

【解答】 ×
問題文の後段が誤りで、妻が65歳以上のときは、付加年金も併給されます。
★前段(65歳未満)のポイント
・①「(繰上げ支給の)老齢基礎年金+付加年金」と、②「遺族厚生年金」はどちら選択(併給不可)
★後段(65歳以上)のポイント
「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族厚生年金」は併給可能
(第38条、附則第17条)
『併給』のルールは、65歳未満と65歳以上で異なりますので、問題文を読む時に注意しましょう。
明日は、「65歳以上の併給ルール」をみていきます。
社労士受験のあれこれ
国年・付加年金
R3-226
R3.4.6 付加年金でよく出るところ
今日のテーマは、付加年金のよく出るところです。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第43条(支給要件)
付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が< A >の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条(年金額)
付加年金の額は、< B >円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
A 老齢基礎年金
B 200
では、こちらをどうぞ
①<H19年出題>
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

【解答】 ×
「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」は、「第1号被保険者」としての被保険者期間が対象です。第2号被保険者、第3号被保険者としての被保険者期間は対象になりません。
こちらもどうぞ!
②<H27年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

【解答】 〇
付加年金の額は、200円×300か月=年額60,000円で計算します。
なお、この場合納付した付加保険料は400円×300か月=120,000円です。付加年金を2年間受給したら、納付した付加保険料と同額となります。
(第44条(年金額))
では、こちらをどうぞ
③<H19年出題>
政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。
④<H29年出題>
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

【解答】
③<H19年出題> ×
(付加年金を含む。)が誤り。付加年金は除かれます。
④<H29年出題> ×
付加年金の額には、改定率による改定はありません。
(第16条の2)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H19年出題>
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。
⑥<H25年出題>
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

【解答】
⑤<H19年出題> ×
減額率、増額率は、付加年金も老齢基礎年金と同じように適用されます。
※老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる場合
→ 付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給され、減額率、増額率も同じように適用されます。
(第46条、附則第9条の2)
⑥<H25年出題> 〇
第47条で「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」と定められています。
「全額」に注意してください。「全部又は一部」と出題されたら誤りです。
第48条で「付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。」と定められていて、老齢基礎年金同様付加年金も終身年金です。
社労士受験のあれこれ
国年・付加保険料のこと②
R3-225
R3.4.5 付加保険料の納付の辞退
引き続き、付加保険料のことです。
今日のテーマは、付加保険料の納付の辞退です。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第87条の2
第3項
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する< A >以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により< B >されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】
A 月の前月
B 前納
では、こちらをどうぞ
①<H30年出題>
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】 ×
「申出をした日の属する月以後」ではなく、「申出をした日の属する月の前月以後」です。
例えば、4月5日に申出をした場合は、納付の辞退は、3月分からです。
3月分の納期限は4月末日。申出時点ではまだ期限が来ていないからです。
また、既に納付されたもの、前納されたものは除かれます。
こちらもどうぞ!
②<H26年出題>
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

【解答】 ×
「辞退したものとみなされる。」が誤りです。
平成26年3月までは、納期限までに付加保険料を納付しなかった場合は、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされ、以後納付できなくなっていました。
しかし、平成26年4月以降は、『辞退の申出をしたものとみなさない』ことになっていて、現在は、納期限を経過しても、2年間は付加保険料を納付することができます。
では、最後にこちらをどうぞ
③<H27年出題>
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
④<R1年出題>
平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される

【解答】
③<H27年出題> 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できないので、国民年金基金の加入員になったときは、加入員になった日に付加保険料納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
(第87条の2第4項)
④<R1年出題> ×
「令和元年7月分以後」が誤りです。
令和元年8月に国民年金基金の加入員になった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされます。
しかし、問題文の「平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納」していた点に注目してください。
第87条の2第3項では、付加保険料の辞退の対象から、『既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。』とされています。
令和元年7月分は前納されているので、辞退できません。
国民年金基金の加入員となった日の属する月以後(令和元年8月以後)は付加保険料を納付できないので、辞退の対象となります。
社労士受験のあれこれ
国年・付加保険料のこと①
R3-224
R3.4.4 付加保険料を納付できる場合、できない場合
今日は国民年金法です。
今日のテーマは、付加保険料を納付できる場合とできない場合です。
★付加年金
付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第87条の2
第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び< A >を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、< B >円の保険料を納付する者となることができる。

【解答】
A 国民年金基金の加入員
→(付加保険料と国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せという目的が同じなので、国民年金基金の加入員は付加保険料は納付できません)
B 400
★ 保険料の免除を受けている者、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
では、こちらをどうぞ
①<R1年出題>
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
②<H29年出題>
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
③<H26年出題>
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
④<H23年出題>
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。

【解答】
①<R1年出題> ×
産前産後期間の保険料免除の期間の各月については、付加保険料を納付することができます。
★付加保険料を納付できる月
・国民年金の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)
・産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月
(第87条の2第2項)
②<H29年出題> ×
半額免除期間は付加保険料の納付はできません。
★以下の保険料免除期間は付加保険料の納付はできません。
・法定免除
・申請全額免除
・学生納付特例、納付猶予期間
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除
(第87条の2第1項)
③<H26年出題> ×
保険料の追納を行った月は、付加保険料を納付することはできません。
(第87条の2第2項)
④<H23年出題> 〇
独立行政法人農業者年金基金法第17条で以下のように定められています。
「農業者年金の被保険者のうち国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料(付加保険料)を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付する者となる。」
社労士受験のあれこれ
健保・報酬支払基礎日数など
R3-223
R3.4.3 報酬支払基礎日数と翌月払いの賃金
引き続き健康保険法です。
今日のテーマは、報酬支払基礎日数と翌月払いの賃金です。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)

【解答】 〇
定時決定は、支払月が4月、5月、6月の賃金で行います。
問題文の場合、定時決定に用いる報酬は、3月分、4月分、5月分の賃金となります。
3月分(3月1日~31日)→4月15日支払い
4月分(4月1日~30日)→5月15日支払い
5月分(5月1日~31日)→6月15日支払い
では、報酬支払基礎日数の問題もどうぞ
②<H25年出題>
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規定等に基づき、事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。
③<H28年出題>
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

【解答】
②<H25年出題> 〇
③<H28年出題> ×
「暦日の数」から当該欠勤日数を控除した日数が誤りです。
★報酬支払基礎日数の算定については以下のように取り扱います。
① 月給者 → 各月の暦日数による
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合 → 就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による
③ 日給者 → 各月の出勤日数による
(平18.5.12庁保険発第0512001号)
社労士受験のあれこれ
定時決定・休職給を受けた場合
R3-222
R3.4.2 定時決定~休職給の扱いなど
引き続き健康保険法です。
定時決定は毎年7月1日時点に行われますが、その際休職している場合などはどうするの?が今日のテーマです。
では、どうぞ!
①<H30年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者について、標準報酬月額の定時決定に際し、4月、5月、6月のいずれかの1か月において休職し、事業所から低額の休職給を受けた場合、その休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する。

【解答】 〇
報酬月額を算定する際に「低額の休職給を受けた月を除く」のがポイントです。
例えば、4月に低額の休職給を受けた場合は、5月と6月の報酬で報酬月額を算定します。
(昭和37.6.28保険発第71号)
なお、4月、5月、6月すべての月が低額の休職給だった場合は、従来の報酬月額をそのまま用います。
では、こちらの問題もどうぞ
②<H16年出題>
被保険者の休職期間中に、給与の支給がなされる場合、標準報酬月額はその給与に基づき算定する。

【解答】 ×
休職期間中の給与による標準報酬月額ではなく、休職前の標準報酬月額によります。
(昭和27.1.25保文発420号)
こちらもどうぞ!
③<H20年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。
④<R1年出題>
介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

【解答】
③<H20年出題> 〇
④<R1年出題> 〇
介護休業中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定します。
(育児休業中も同様です)
(平11.3.31保険発46・庁保険発9)
社労士受験のあれこれ
再雇用時の標準報酬月額
R3-221
R3.4.1 60歳以降再雇用されたときの標準報酬月額について
今日は健康保険法です。
60歳以上で定年になり、引き続き再雇用されたとき、報酬が下がることが一般的に多いです。
今日は、そのような場合の標準報酬月額の決定方法がテーマです。
では、どうぞ!
<R1年出題>
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

【解答】 〇
定年退職後引き続き再雇用する際に、報酬を下げる会社が一般的に多くみられます。
その際、健康保険の資格は継続しますので、報酬が下がった場合は、固定的賃金の変動として本来なら随時改定の対象です。
しかし随時改定の場合、標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動から4か月目からです。そうなるとしばらく定年退職前の高い報酬による標準報酬月額が続くことなります。
この問題のポイントは、対象が「60歳以降に退職後継続して再雇用」される人であることです。
使用関係が一旦中断したものとみなし、随時改定ではなく「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を提出することによって、下がった報酬による標準報酬月額がすぐに適用される点でメリットがあります。高齢者の継続雇用を支援するための仕組みです。
(H25.1.25保保発0125第1号)
社労士受験のあれこれ
請負による建設業の賃金総額
R3-220
R3.3.31 賃金総額算定のルール(請負の建設業)
今日は徴収法です。
一般保険料は、「賃金総額」×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)で計算します。
「賃金総額」は、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額ですが、特例もあります。
今日は賃金総額の特例を確認します。
では、どうぞ!
①<H26年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。

【解答】 〇
特例による賃金総額の算出が認められているのは、
1 請負による建設の事業
2 立木の伐採の事業
3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
4 水産動植物の採捕又は養殖の事業
例えば、請負による建設の事業の場合、労災保険の保険関係は元請の事業主に一括され、元請の事業主が下請事業の労働者の分も一括して保険料を納付しなければなりません。しかし、その際、元請の事業主が、下請事業の労働者の賃金の総額を正確に把握することが困難な場合があります。そのため、賃金総額の特例が設けられています。
(徴収法第11条、施行規則第12条)
では、こちらをどうぞ!
②<H30年出題(雇)>
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

【解答】 ×
「常に」が誤りです。
賃金総額の特例が認められるのは、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」です。
では、こちらの問題もどうぞ!
③<H21年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
④<R1年出題(災)>
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

【解答】
③<H21年出題(災)> 〇
請負による建設の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難なものの賃金総額は、『請負金額×労務費率』で計算します。
(施行規則第12条、第13条)
④<R1年出題(災)> ×
請負金額イコール請負代金とは限りません。また最後の「含まれない」が誤りです。
(原則)
注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等 → 請負代金に加算する
(例外)
「機械装置の組立て又は据付けの事業」 → 機械装置の価額は請負代金から除外する
※消費税は請負金額から除きます。
(施行規則第13条)
社労士受験のあれこれ
自己の労働による収入
R3-219
R3.3.30 失業の認定期間中に自己の労働による収入があった場合
今日も引き続き雇用保険法です。
失業の認定期間中に自己の労働による収入があった場合、基本手当の日額はどうなるでしょう?
では、どうぞ!
①<R1年出題>
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
②<H26年出題>
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない

【解答】
①<R1年出題> 〇
失業の認定を受けるべき期間中に、「就職した日」があるときは、就職した日は失業の認定は行わないことを、昨日お話しました。
今日のテーマは、「就職」ではなく、「自己の労働によって収入を得た場合」です。そのような場合は、その収入の額に応じて基本手当が減額される場合があります。
「自己の労働」とは、問題文にあるように原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいいます。
(行政手引51255)
②<H26年出題> 〇
失業認定申告書によって届け出ることになっています。
では、こちらの問題もどうぞ!
③<H26年出題>
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。

【解答】 ×
「基本手当の日額に100分の80を乗じ」の部分が誤り。100分の80は乗じず、問題文の場合は、基本手当の日額をそのまま計算に使います。
自己の労働による収入があった場合の基本手当の日額については、3つおさえておきましょう。
※ 収入から控除する額(雇用保険法第19条第2項に定める額)は、1,312円(令和2年8月~)です。
| 1 全額支給 | 『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%以内 → 基本手当の日額は全額支給される |
| 2 減額支給 | 『(収入-1,312円)+基本手当の日額』が賃金日額の80%を超える → 超える額の分だけ基本手当の日額が減額される |
| 3 不支給 | 『収入-1,312円』が賃金日額の80%を超える → 基本手当は支給されない |
問題文は1に該当します。
社労士受験のあれこれ
失業の認定
R3-218
R3.3.29 失業の認定の条件
今日は、雇用保険の「失業の認定」です。
請負業務に従事した日は、失業の認定は行われる?行われない?
では、どうぞ!
①<H27年出題>
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。

【解答】 ×
問題文の場合は、「就職」に当たるので、失業の認定は行われません。
基本手当の支給を受けるには、失業の認定を受けなければなりません。「失業」とは、「労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態 にあること」をいいます。
★「就職した日」は失業の認定は行われません。
行政手引51255によると、雇用関係に入ることはもちろん「就職」ですが、請負、委任、自営業を開始した場合等も就職に含まれます。 原則として1日の労働時間が4時間以上のもの (4時間未満でも被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無は問われません。
では、こちらの問題もどうぞ!
②<H28年出題>
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。

【解答】 〇
行政手引51256からの出題です。
受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用 契約期間が「就職」していた期間となります。
最後にもう一問どうぞ!
③<H25年出題>
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

【解答】 ×
失業の認定日は「失業認定申告書( 則様式第14号)」に「 受給資格者証」を添えて 提出します。 (施行規則第22条第1項)
社労士受験のあれこれ
特定受給資格者or特定理由離職者
R3-217
R3.3.28 雇止めによる離職
今日は、雇用保険の「特定受給資格者と特定理由離職者」です。
雇止めによる離職は、どちらに該当するのでしょうか?
では、どうぞ!
①<H30年出題>
期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は、特定受給資格者に該当する。

【解答】 〇
特定受給資格者の範囲は、雇用保険法施行規則第36条に定められています。「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」もその一つです。
また行政手引 50305(5)では、上記の特定受給資格者は、 次のいずれにも該当する場合に適用するとされています。
・ 期間の定めがある労働契約が 1 回以上更新され、雇用された時点から継続して 3 年以上雇用されている場合
・ 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
この問題では、1回以上契約が更新され「3年以上」雇用されていている点がキーになります。
では、「3年未満」で雇止めの場合はどうなるのでしょうか。
上記3年以上の条件に当てはまらない場合、同じ則36条で定められている「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと」による離職の場合は、「特定受給資格者」に当たります。
「更新されることが明示されている」というのは、更新の確約がある場合です。
更新の確約があり、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合は、3年未満でも特定受給資格者となります。
(行政手引 50305(5))
では、こちらの問題もどうぞ!
②<H22年出題>
契約期間を1年とし、期間満了に当たり契約を更新する場合がある旨を定めた労働契約を、1回更新して2年間引き続き雇用された者が、再度の更新を希望したにもかかわらず、使用者が更新に合意しなかったため、契約期間の満了により離職した場合は、特定理由離職者に当たる。

【解答】 〇
引き続き雇用された期間が「2年間」であることと、『期間満了に当たり契約を更新する場合がある』旨を定めていた点がポイントです。
「更新する場合がある」という示し方は「更新の確約」はないということ、また雇用期間も2年なので、特定受給資格者には当たりません。
問題文の条件の場合は「特定理由離職者」に該当します。
特定理由離職者は次のいずれにも該当する場合とされています。
・当該労働契約の更新がないため離職した(更新の確約まではない場合)
・労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
(行政手引50305-2)
社労士受験のあれこれ
労災~休業補償給付
R3-216
R3.3.27 休業補償給付 一部のみ労働する日②
昨日に引き続き、テーマは「休業補償給付」です。
今日は「一部のみ労働する日」の休業補償給付(その2)です。
では、どうぞ!
<H16年出題>
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。

【解答】 〇
所定労働時間の一部分だけ労働した日の休業補償給付は、「(給付基礎日額-実際に労働した部分の賃金額)×60%」で計算することは、前回お話しました。
今回の問題は、労働しなかった時間について、事業主が金額を支払った場合の取り扱いです。
休業補償給付は賃金を受けない日に支給されますが、一部労働不能の場合は、①「その労働不能の時間について全く賃金を受けない日」、②「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか受けない日」が「賃金を受けない日」に該当します。
問題文は②に当たりますので、「賃金を受けない日」となり、休業補償給付が支給されます。
例えば、給付基礎日額が10,000円、実際に労働した部分の賃金が4,000円の場合で、労働しなかった時間に対して事業主から2,000円支払われた場合を考えてみましょう。
平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額が6,000円で、事業主からの2,000円はその60%未満です。
ですので、「賃金を受けない日」として、休業補償給付が3,600円((10,000円-4,000円)×60%)が支給されます。
(労災保険法第14条 昭40.7.31基発901号)
社労士受験のあれこれ
労災~休業補償給付
R3-215
R3.3.26 休業補償給付 一部のみ労働する日①
昨日に引き続き、テーマは「休業補償給付」です。
今日は「一部のみ労働する日」の休業補償給付(その1)です。
では、どうぞ!
①<H16年出題>
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。

【解答】 〇
所定労働時間の一部分だけ労働した日(=一部分だけ休業した日)も休業(補償)給付の対象になります。
そのような一部休業日の休業補償給付は、「(給付基礎日額 - 実際に労働した部分の賃金額)×60%」で計算します。
例えば、給付基礎日額(通常通り労働した場合の1日あたりの賃金額)が10,000円、実際に労働した部分の賃金が4,000円の場合、その日の休業(補償)給付は、(10,000円-4,000円)×60%=3,600円となります。
(労災保険法第14条)
こちらもどうぞ!
②<H13年出題>
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
③<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

【解答】
②<H13年出題> 〇
③<H30年出題> 〇
①の問題と同じです。
一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、「給付基礎日額」と「実際に労働した部分の賃金額」の差額の100分の60です。
なお、療養開始後1年6か月経過すると、給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。
②の問題のかっこ書き(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の部分は最高限度額が適用されたときのルールで、③の問題は「療養開始後1年6か月未満」なので最高限度額は適用されていないという前提です。
年齢別の最高限度額が適用されている場合のルールは第14条に規定されていますが、過去にそこが論点になったことがないので、今回は触れないでおきます。
(参考:労災保険法第14条)
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
社労士受験のあれこれ
労災~休業補償給付
R3-214
R3.3.25 休業補償給付 全部労働不能の場合
今日は労災保険法です。
テーマは「休業補償給付」です。
今日は「全部労働不能」の場合の休業補償給付です。
では、どうぞ!
<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】 〇
休業補償給付は、『労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給する』と規定されています。
この問題のポイントは、「賃金を受けない日」の定義です。
通達では、全部労働不能であって「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」を賃金を受けない日と定義づけています。(例えば、事業主から平均賃金の50%の金額を受けた場合は、「賃金を受けない日」に該当するため、休業補償給付は全額支給される。)
問題文のように、休業中に、事業主が「平均賃金の6割以上」を支払っている場合は、賃金を受けない日に該当しないので、休業補償給付は支給されません。
(労災保険法第14条、昭40.7.31基発第901号)
もう一問どうぞ!
<H16年出題>
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

【解答】 〇
上の問題と同じです。平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、「賃金を受けない日」に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は支給されません。
穴埋め式で条文を確認しましょう
第14条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために< A >日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。

【解答】
A 賃金を受けない
B 4
C 100分の60
★明日は、一部のみ労働する日についてです。
社労士受験のあれこれ
割増賃金の算定
R3-213
R3.3.24 どこからどこまで?時間外労働・休日労働
今日は労働基準法です。
時間外労働は原則として2割5分以上、休日労働は3割5分以上の割増率で、賃金を計算しなければなりません。
今日は、日をまたがって残業したときなど、様々な事例の問題を解いてみましょう。
では、どうぞ!
<H30年出題>
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
①<H30年出題>
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
②<H30年出題>
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
③<H30年出題>
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
④<H30年出題>
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
⑤<H30年出題>
日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払いの義務の対象労働になる。

【解答】
①<H30年出題> ×
★8時間を超えた2時間に対して時間外労働の割増率を加算する必要はありません。
法定休日には、時間外労働という概念がありませんので、法定休日の日曜に10時間労働した場合は、その10時間は休日労働の割増率だけで計算します。(深夜業に該当する場合は深夜割増を加算します。)
(労基法第37条、平11.3.31基発168号)
②<H30年出題> ×
★月曜の午前0時から3時までは休日ではありません。
法定休日は原則として暦日単位となり、問題文の場合は、日曜の午前0時から午後12時までの24時間が「休日」です。
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働は、日曜の午後8時から午後12時までです。
(平6.5.31基発331号)
③<H30年出題> 〇
問題文の場合、月曜の始業から火曜の午前3時までを1日の労働として扱うことになります。
通達(昭63.1.1基発1号)では、「継続勤務が二暦日にわたる場合はたとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする、とされています。
(昭63.1.1基発1号)
④<H30年出題> ×
★土曜の時間外労働は土曜の午後12時まで
②の問題と同じで、日曜の午前0時からは法定休日です。
問題文の場合、日曜の午前0時から3時までは休日労働で計算します。
(平6.5.31基発331号)
⑤<H30年出題> ×
★時間外労働は「1日単位」でも見なければならない
時間外労働となるのは、1日8時間を超えた部分ですので、まずは木曜2時間、そして金曜2時間です。
金曜日の時点で、法定労働時間内の労働が34時間、時間外労働が4時間です。
土曜日に10時間労働していますが、そのうち6時間までは週の法定労働時間以内の労働で、残りの4時間が時間外労働となります。
(労働基準法第32条)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 残業(法定時間内) | 2 | 2 | |||||
| 時間外労働 | 2 | 2 | 4 |
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-212
R3.3.23 夫・妻の年金「振替加算⑧加算のタイミング(応用編)」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算がつくタイミング「応用編」です。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
②<H27年出題>
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】
①<H27年出題> 〇
(この問題のポイント)
・妻が60歳で老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算は繰上げされないので、振替加算の加算は65歳以後。
・在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になると、配偶者加給年金額も支給停止となる。
・配偶者加給年金額が支給停止されていた場合でも、妻が65歳になると振替加算が加算される
・振替加算は、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算。翌月分からの部分がポイントです。
②<H27年出題> ×
妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されないではなく「加算されます」。
(問題文の妻の現状)
・65歳時点で、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった
・65歳以後、特例による任意加入被保険者として保険料を納付した
・67歳で老齢基礎年金の受給権を取得した
この妻は振替加算の要件を満たしているので、67歳から受給する老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(昭和60年国民年金法附則第18条)
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-211
R3.3.22 夫・妻の年金「振替加算⑦加算のタイミング(基礎編)」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算がつくタイミング(基礎編)です。
まずこちらからどうぞ!
①<H18年出題>
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。

【解答】 ×
例えば、夫が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)の受給権を取得した当時、妻が65歳未満なら、夫の老齢厚生年金に妻が65歳になるまで加給年金額が加算され、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
問題文のように、夫が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)の受給権を取得した当時、妻が65歳以上で振替加算の要件を満たしている場合は、夫の老齢厚生年金には加給年金額は加算されず、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(昭和60年国民年金法附則第14条第2項)
では、こちらをどうぞ!
②<H27年出題>
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】 〇
退職時改定で、夫が初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、妻が65歳未満なら夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されますが、問題文のように妻が66歳の場合は、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
なお、問題文のように、妻が65歳になった後に、夫が240月(原則)の要件を満たした場合は、振替加算の要件を満たしているか確認を受けるために、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
(昭和60年国民年金法附則第14条第2項)
社労士受験のあれこれ
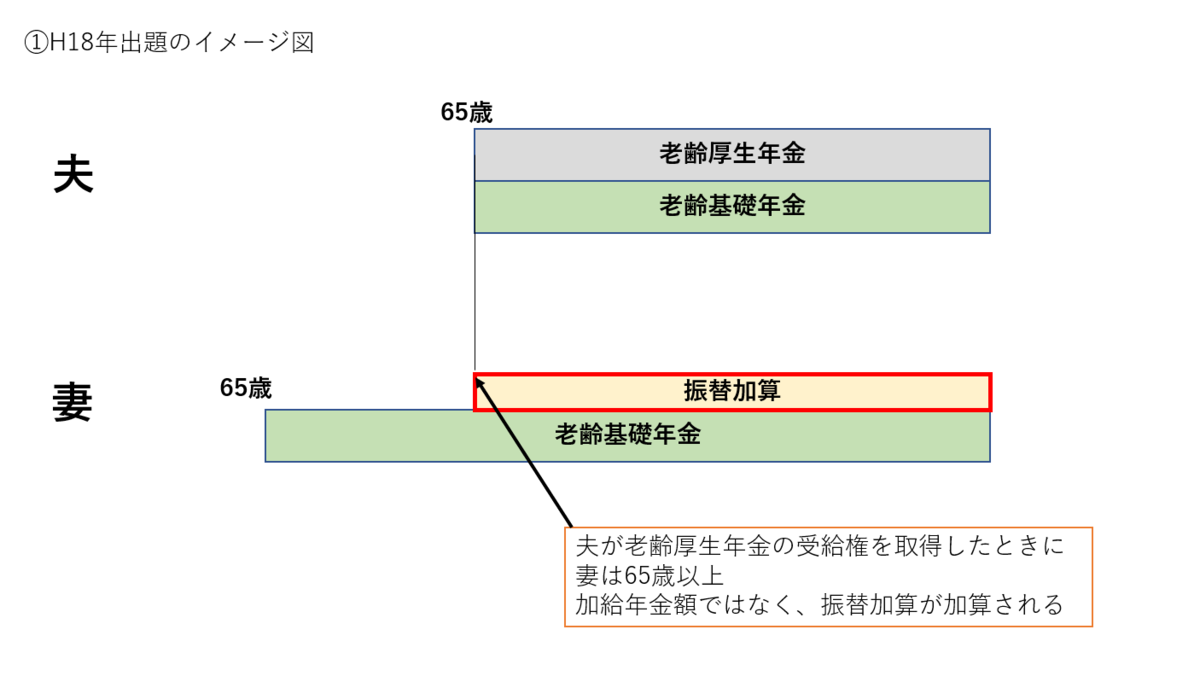
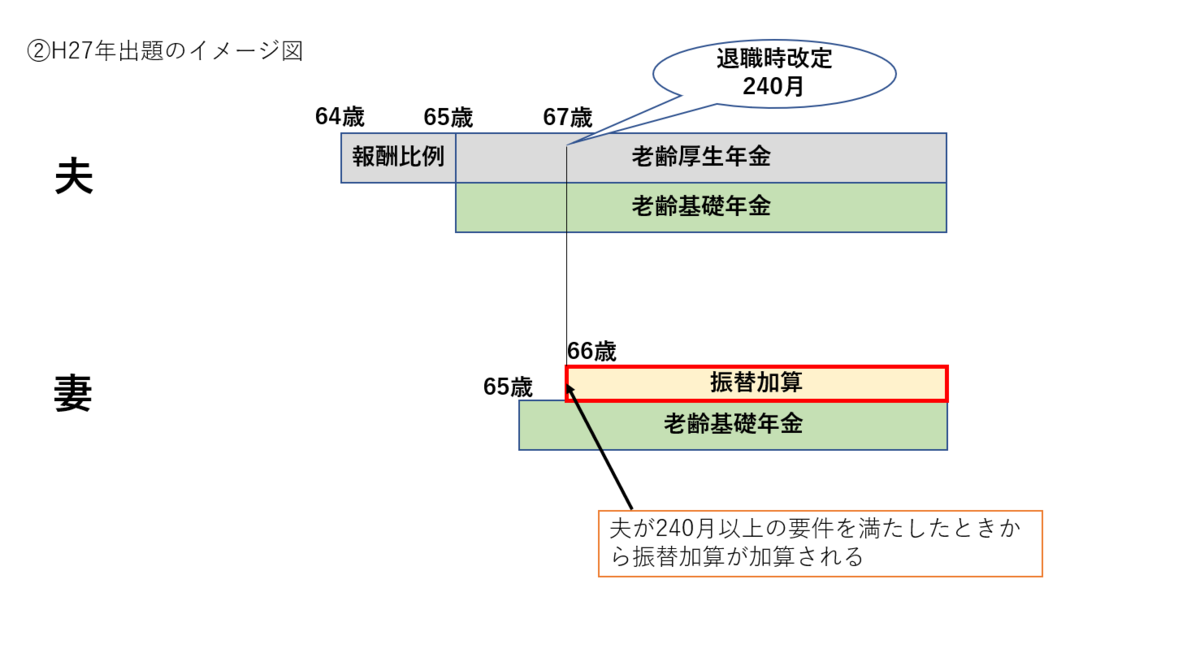
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-210
R3.3.21 夫・妻の年金「振替加算⑥振替加算のみの老齢基礎年金」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算だけの老齢基礎年金です。
まずこちらからどうぞ!
①<R1年出題>
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

【解答】 〇
老齢基礎年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上あれば受給資格ができます。
ただし、保険料全額免除期間のうち、「学生納付特例期間」と「納付猶予期間」は注意が必要です。
「学生納付特例期間」と「納付猶予期間」は受給資格の10年以上の計算には入りますが、老齢基礎年金の額の計算は「ゼロ」となります。(合算対象期間と同じ扱いです。)
問題文のように、「学生納付特例の期間及び納付猶予の期間だけで10年以上」の場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金の計算はゼロとなりますので支給されません。
(国民年金法第26条)
先ほどの問題をおさえたら、こちらをどうぞ!
②<H20年出題(修正)>
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が10年あり、かつ、それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】 〇
「合算対象期間+学生納付特例」のみで10年の場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金はゼロとなります。
しかし、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算相当額の老齢基礎年金」(=振替加算のみの老齢基礎年金)が支給されます。
(昭和60年国民年金法附則第15条)
なお、良く出題される典型的な問題として、例えば『「保険料納付済期間が1か月+合算対象期間で10年以上ある場合」は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給される』というパターンがあります。これは「×」です。
このような場合は、保険料納付済期間1か月で計算した老齢基礎年金に振替加算が加算されることになりますので、注意しましょう。
ではこちらも!
③<H27年出題>
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】 〇
問題文の場合、甲は40年間すべて合算対象期間ですので、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金の額はゼロです。
しかし、振替加算の要件に該当していますので、65歳から「振替加算相当額の老齢基礎年金」が支給されます。
最後にもう一問どうぞ!
④<R1年出題>
合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。

【解答】 〇
振替加算のみの老齢基礎年金は繰下げできません。
(昭和60年国民年金法附則第15条第4項)
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-209
R3.3.20 夫・妻の年金「振替加算⑤障害年金との関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、障害年金との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
②<H30年出題>
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】
①<H21年出題> 〇
②<H30年出題> 〇
どちらの問題も同じです。
振替加算は、『障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの』の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分は支給停止となります。
(昭和60年国民年金法附則第16条)
では、もう一問どうぞ!
③<H21年出題>
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

【解答】 ×
最後が誤りで、「振替加算に相当する部分の支給は停止されない」です。
先ほどの問題で、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等障害を支給事由とする年金を受けることができる場合は、その間、振替加算に相当する部分は支給停止になることを勉強しました。
では、その障害基礎年金等が支給停止になっている場合は、振替加算はどうなるのか?というのがこの問題のテーマです。
障害基礎年金等が全額支給停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。
(昭和60年国民年金法附則第16条)
最後にもう一問どうぞ!
④<R1年出題>
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで第2号被保険者期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

【解答】 〇
66歳の女性の現状
・障害基礎年金を受給中
・配偶者に生計維持されている。65歳に達するまで配偶者の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されていた。
・障害等級が3級程度に軽減し、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した
この女性が、障害基礎年金を受給している間は、振替加算は支給停止です。しかし、障害の程度が3級程度に軽減すると、障害基礎年金は全額支給停止となり、振替加算は支給停止ではなくなります。
この女性は、老齢基礎年金を受給することに変更するのですが、その場合、65歳時点で配偶者に生計維持されており、他の振替加算の要件も満たしているので、老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-208
R3.3.19 夫・妻の年金「振替加算④振替加算の額」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算の額です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H18年出題>
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。
②<H28年出題>
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

【解答】
①<H18年出題> ×
振替加算の額は、「224,700円×改定率」×「生年月日に応じて定められた率」で計算しますが、「生年月日」は「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者」の生年月日です。
②<H28年出題> ×
振替加算の額は、「老齢基礎年金の額」ではなく「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額となります。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
★もう少し詳しくみましょう。
振替加算の額は「224,700円×改定率」×「老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた率」で計算します。
「224,700円×改定率」は「加給年金額」と同じですが、その額がそのまま振替加算になるのではなく、その額に「生年月日に応じて定められた率」を乗じるのがポイントです。
「生年月日に応じて定められた率」が一番大きい「1.000」になるのは「大正15年4月2日~昭和2年4月1日まで」生まれで、生年月日が若くなるほど率は小さくなり、一番小さくなるのが「昭和40年4月2日~昭和41年4月1日まで」生まれの「0.067」となります。
振替加算は、旧法時代に任意加入だった「カラ期間」をカバーするための制度です。
第3号被保険者制度ができた「昭和61年4月1日」に、20歳に近いほど第3号被保険者期間が長い(カラ期間が少ない)ので、振替加算が少なくなり、「昭和61年4月1日」に60歳に近いほどカラ期間は多い(第3号被保険者期間が短い)ので振替加算が多くなります。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-207
R3.3.18 夫・妻の年金「振替加算③繰上げ・繰下げとの関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、老齢基礎年金の繰上げ・繰下げとの関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
②<H22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
①<H21年出題> ×
老齢基礎年金を繰下げた場合は振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算については増額されません。
②<H22年出題> 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算については繰上げされません。振替加算の加算は、受給権者が65歳に達した日以後となります。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
もう一問どうぞ
③<H30年出題>
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】 ×
「老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算」の部分が誤りです。
(振替加算が加算される時期)
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 振替加算は申出のあった日の属する月の翌月から加算
(振替加算も繰下げて支給される)
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 65歳に達した日の属する月の翌月から加算
(振替加算は繰上げされない)
社労士受験のあれこれ
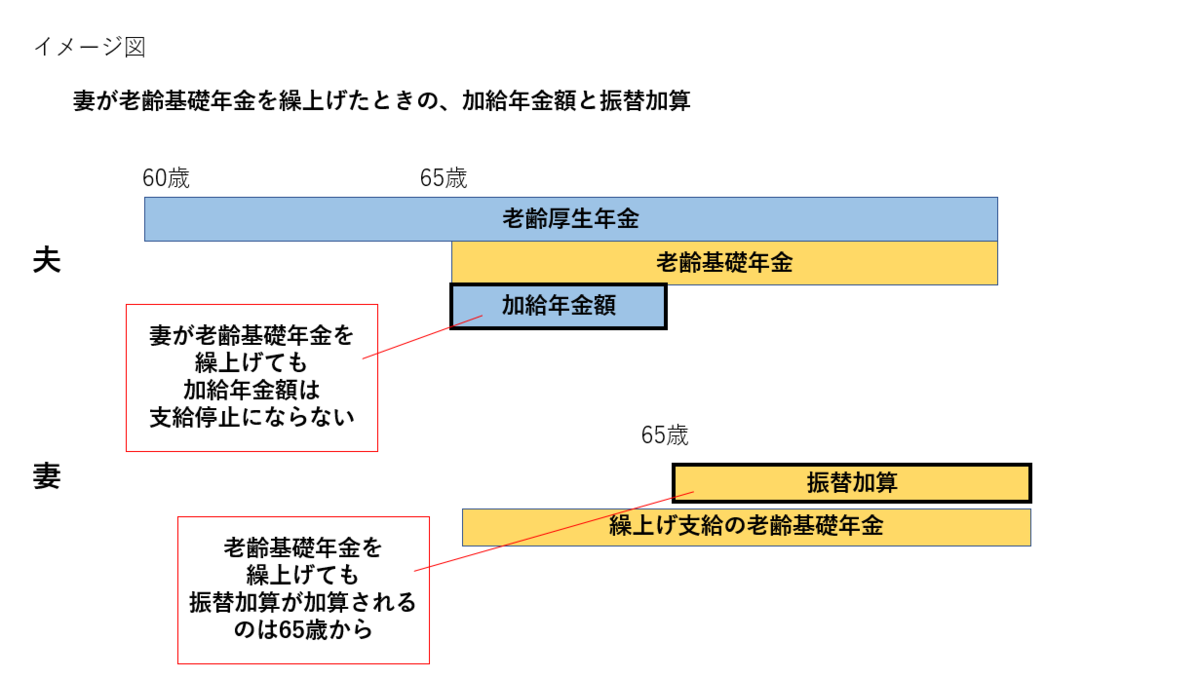
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-206
R3.3.17 夫・妻の年金「振替加算②老齢厚生年金との関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、老齢厚生年金との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H30年出題>
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】 〇
この問題のテーマは、「老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができるときに、振替加算は加算されるのか?」です。
問題文のポイントは、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の「月数が240以上」であることです。
振替加算が加算されないのは、被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金を受けることができるときです。
単に老齢厚生年金を受けることができる、ではなく、240月以上(中高齢期間短縮特例の場合は15~19年)で計算される老齢厚生年金であることに注意してください。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
もう一問どうぞ
②<厚生年金保険 H24年出題>
(離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について)
振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる。
③<H27年出題>
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
②<厚生年金保険 H24年出題> 〇
「みなし被保険者期間」も含んで算定した厚生年金保険の被保険者期間が240月以上の場合、振替加算は行われません。「みなし被保険者期間」も含まれるのがポイントです。
(厚生年金保険法平成24年の出題です。)
③<H27年出題> 〇
上の②と同じです。「みなし被保険者期間」も含んで算定した厚生年金保険の被保険者期間が240月以上になった場合は、振替加算は行われなくなります。
では、こちらもどうぞ!
④<H21年出題>
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】 ×
遺族基礎年金と老齢基礎年金の両方の受給権が発生したときは、どちらかを選択することになり、遺族基礎年金を選択した場合は、振替加算は加算されません。振替加算は老齢基礎年金に加算されるものだからです。
最後にこちらもどうぞ!
⑤<H21年出題>
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

【解答】 〇
振替加算は老齢基礎年金と同様、受給権者本人の権利に基づいているので、離婚したとしても支給停止にはなりません。
明日も振替加算です。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-205
R3.3.16 夫・妻の年金「振替加算①対象になる生年月日」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、「振替加算の対象となる生年月日」です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H22年出題>
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。

【解答】 〇
「老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例」とは振替加算のことです。
老齢厚生年金、障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額は、配偶者が65歳に達したときに加算されなくなります。
65歳に達したときに、配偶者自身が老齢基礎年金の受給権を取得し、今まで相手の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額が振り替わって、自身の老齢基礎年金に加算される仕組みになっています。
ポイント! 振替加算の対象は「大正15年4月2日~昭和41年4月1日以前生まれ」
振替加算の対象は、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれです。
◆なぜ大正15年4月2日生まれ以降?
振替加算は「老齢基礎年金(新法)」に加算されるものだからです。新法の対象者が大正15年4月2日~生まれだからです。
大正15年4月1日以前生まれの場合は旧法の対象となるので、65歳以降も、相手の老齢年金に加給年金額が加算され続けます。
◆なぜ昭和41年4月1日以前まで?
昭和41年4月2日以降生まれには振替加算はつきません。なぜなら「第3号被保険者」の制度ができた「昭和61年4月1日」に20歳未満だったからです。
仮に20歳から60歳までの40年間被扶養配偶者だった場合、その間ずっと第3号被保険者で、65歳から満額の老齢基礎年金が受給できるので、振替加算でカバーする必要がないからです。
昭和41年4月1日以前生まれの場合は、「昭和61年4月1日」に20歳を過ぎています。同じように40年間被扶養配偶者だった場合、「任意加入」だった旧法時代にカラ期間ができてしまい、満額の老齢基礎年金が受給できない場合があります。
振替加算はそのようなカラ期間をカバーするための制度です。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
では、もう一問どうぞ
②<H30年出題>
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】 〇
この問題のチェックポイント!
<夫(老齢厚生年金の受給権者)の要件>
◆夫の生年月日
大正15年4月2日以降生まれであること(新法の対象者であること)
→旧法の対象者だと旧法のルールが適用され、配偶者が65歳になっても加給年金額が加算されるからです。
◆夫の老齢厚生年金が加給年金額が加算される要件を満たしていること
原則として被保険者期間が240月以上あることが条件ですが、昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの場合は、40歳以降の第1号厚生年金被保険者期間が19年以上あればOKです。
<妻(振替加算の対象)の要件>
◆妻の生年月日
大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれであること
◆65歳に達した日に夫に生計を維持されていること
→65歳に達した日の前日に、夫の年金の加給年金額の対象になっていたこと
(対象になる夫の年金)
・老齢厚生年金又は退職共済年金(被保険者期間の月数が原則として240月以上)
・障害厚生年金又は障害共済年金(1級又は2級)
「振替加算」は、夫婦とも新法の対象であるときに行われます。片方が旧法の場合は、旧法のルール(配偶者が65歳になっても引き続き加給年金額が加算される)が適用されるので、振替加算は行われません。
明日も振替加算です。
社労士受験のあれこれ
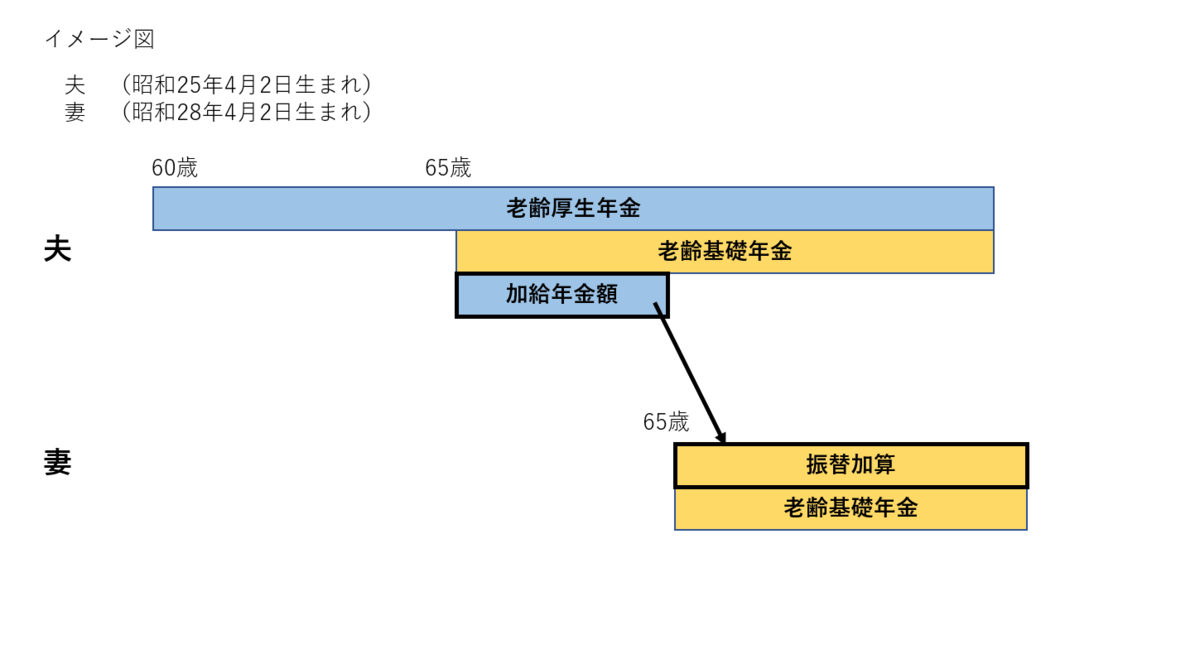
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-204
R3.3.15 夫・妻の年金「加給年金額⑨届出について」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、「届出」についてです。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
問題文の場合、不該当の届出は要りません。
ポイント! 加給年金額対象者の不該当の理由が「年齢」の場合は届出不要
配偶者又は子が、加給年金額の対象から外れるのは次のいずれかに該当した場合です。
1 死亡したとき。
2 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
4 配偶者が、65歳に達したとき。
5 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。
6 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
7 子が、婚姻をしたとき。
8 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
9 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
10 子が、20歳に達したとき。
★ 加給年金額対象者が不該当になった場合は、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりませんが、不該当の事由が「年齢」の場合(上記4、8、10の場合)は、届出は要りません。
例えば、配偶者が離婚した場合は届け出が必要です。(届け出がないと、日本年金機構は、誰がいつ離婚したかを把握できないからです)
(厚生年金保険法第44条第4項、施行規則第32条)
では、こちらの問題をどうぞ
②<H18年出題>
老齢厚生年金の受給権者であって、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者については、その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が加算されなくなり、振替加算も行われない。

【解答】 ×
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が65歳に達したときは、加給年金額が加算されなくなるという部分は正しいです。
しかし、その配偶者が大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの場合は、その配偶者の老齢基礎年金に振替加算が行われます。
今日で加給年金額のお話は終わります。明日からのテーマは「振替加算」です。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-203
R3.3.14 夫・妻の年金「加給年金額⑧在老との関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、在職老齢年金と加給年金額との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H24年出題>
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。
②<H27年出題>
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は105,000円(加給年金額を除く。)となる。

【解答】
①<H24年出題> ×
最後の「加給年金額を含めた」が誤り。「加給年金額は含めない」です。
ポイント! 基本月額に加給年金額は含まれない
「基本月額」の計算式は、「老齢厚生年金÷12」ですが、加給年金額は除いて計算します。
なお、支給停止額は115,000円で正しいです。
②<H27年出題> ×
ポイント! 在老で老齢厚生年金の一部が停止されても加給年金額は支給される
支給停止後の年金月額が誤りです。
この問題の場合、総報酬月額相当額は、240,000円+で600,000円÷12=290,000円です。
支給停止額は、(200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円
支給停止後の年金月額は、200,000円-105,000円=95,000円となります。
問題文の最後の(加給年金額を除く。)に注目してください。
問題文のように在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金の一部が支給停止になっていても、加給年金額は、別途全額支給されます。
★在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になった場合は、加給年金額も全額支給停止されます。
(厚生年金保険法平成6年附則第21条)
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-202
R3.3.13 夫・妻の年金「加給年金額⑦加算されるタイミング」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、加給年金額が加算されるタイミングです。
★加給年金額が加算されるタイミング★
・特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」の支給開始年齢から
→ 定額部分がない場合は、65歳から
・65歳以後の老齢厚生年金の支給開始年齢から
※どちらも厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが条件
こちらの問題をどうぞ!
①<H30年出題>
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】 ×
「加給年金額が加算されることはない。」は誤り。加算されます。
ポイント! 受給権取得後に240月以上になった場合でも加給年金額は加算される
問題文のように、老齢厚生年金の受給権を取得した当時は240月未満であったとしても、その後厚生年金保険の被保険者として保険料を納付し、資格喪失時に240月以上になった場合、加給年金額が加算されます。
もう一問どうぞ!
②<H15年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について、その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合には、老齢厚生年金の受給権を取得した当時の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される。

【解答】 ×
ポイント! 生計維持関係は240月以上となったときで確認
生計維持関係は、老齢厚生年金の受給権を取得した当時ではなく、退職時改定で240月以上となったときに確認します。
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-201
R3.3.12 夫・妻の年金「加給年金額⑥特別加算」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、配偶者加給年金額にプラスされる特別加算についてです。
★特別加算は、配偶者が65歳に達して自身の老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するためのものです。
こちらの問題をどうぞ!
①<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
②<H19年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。

【解答】
①<H28年出題> ×
ポイント! 特別加算は「受給権者」の生年月日で決まる
特別加算は、「その配偶者」の生年月日ではなく、老齢厚生年金の「受給権者」の生年月日に応じて行われます。
②<H19年出題> 〇
ポイント! 特別加算の額は、受給権者の「生年月日が若い」ほど大きい
では、こちらもどうぞ!
③<H15年出題>
老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である。
④<H21年出題>
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、224,700円に改定率を乗じて得た額に、165,800円に改定率を乗じて得た額を加算した額とする。

【解答】
③<H15年出題> 〇
ポイント! 昭和9年と昭和18年は暗記しましょう
特別加算が加算されるのは、「昭和9年4月2日以後」生まれの受給権者
生年月日が若いほど特別加算額が大きくなりますが、「昭和18年4月2日以後」生まれからは同額となります。
④<H21年出題> ×
ポイント! 33,200円と165,800円は暗記しましょう
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日まで生まれの配偶者加給年金額に加算される特別加算は、「33,200円」に改定率を乗じて得た額です。
一番高いのは、昭和18年4月2日以後生まれで、「165,800円」に改定率を乗じて得た額となります。
特別加算は、受給権者の生年月日に応じて5段階設定されています。一番小さい「33,200円」と一番大きい「165,800円」を覚えましょう。
「33」×5=「165」と見ると覚えやすいと思います。
明日に続きます。
明日は加給年金額が加算されるタイミングです。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-200
R3.3.11 夫・妻の年金「加給年金額⑤金額は?」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、加給年金額の金額です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び1人目の子については224,700円に、2人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である。
②<H28年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。

【解答】
①<H21年出題> ×
子の加給年金額の算定方法が誤りです。
1人目・2人目までは1人につき224,700円×改定率、3人目以降の子は1人につき74,900円×改定率です。
②<H28年出題> ×
所定の額×改定率の端数処理は、50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げます。(100円単位)
なお、令和3年度の改定率は、1.000です。
配偶者に対する加給年金額は224,700円×1.000=224,700円なので、今年度は端数処理は要りませんね。
では、もう一問どうぞ!
③<H18年出題>
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額、老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については、受給権者本人が68歳以降になっても、基礎年金の新規裁定者と同様の改定率によって改定する。

【解答】 〇
「改定率」の改定基準の問題です。
基礎年金の改定率は原則として以下の基準で、毎年見直しされています。
・新規裁定者(68歳年度前) → 名目手取り賃金変動率に応じて改定
・既裁定者(68歳年度以降) → 物価変動率に応じて改定
「加給年金額」の改定率は、「新規裁定者と同様の改定率」で改定されます。受給権者本人が68歳以降になっても変わりません。
明日に続きます。
明日は配偶者加給年金額にプラスされる特別加算です。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-199
R3.3.10 夫・妻の年金「加給年金額④支給停止されるとき」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
昨日は、加給年金額の対象になる配偶者が240カ月以上の被保険者期間で計算される老齢厚生年金を受けることができるときは、その間、加給年金額が支給停止されることをお話ししました。
今日は、それ以外の支給停止理由についてです。
こちらの問題をどうぞ!
<H26年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

【解答】 ×
加給年金額の対象の配偶者が障害厚生年金(3級でも)を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。
『加給年金額が支給停止されるのはどんなとき?』
加算の対象の配偶者が、以下の給付を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給は停止されます。 ・老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。) ・障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの |
※障害厚生年金は3級も対象になります。
(厚生年金保険法第46条第6項、施行令第3条の7)
もう一問どうぞ!
<H19年出題>
加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。

【解答】 ×
さきほどの『加給年金額が支給停止されるのはどんなとき?』を見てください。
加算の対象となる妻が、障害基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額は支給停止となります。
一方、加算の対象となる妻が、繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていても、加給年金額の支給は停止されません。
妻が65歳前に繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていても、妻が65歳になるまで、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
このテーマは明日も続きます。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-198
R3.3.9 夫の年金・妻の年金「加給年金額のこと③共働きの場合」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件は、原則として「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」あることです。
昨日は、加給年金額の対象になる配偶者には、原則として65歳未満という年齢制限があることをお話ししました。
今日は、加給年金額の対象になる配偶者にも厚生年金保険の被保険者期間がある場合です。
こちらの問題をどうぞ!
<H28年出題>
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

【解答】 ×
ポイント! 原則として240か月以上
300か月以上が間違いです。
加給年金額の部分の支給が停止されるのは、加算対象の配偶者が受けることができる老齢厚生年金が、原則として240か月以上の被保険者期間で算定されている場合です。
(加算対象の配偶者が受けることができる老齢厚生年金の被保険者期間が240月未満(原則)の場合は、加給年金額は支給停止されません。)
(厚生年金保険法第46条第6項、施行令第3条の7)
では、もう一問どうぞ
<H22年出題>
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】 〇
ポイント! その全額が支給を停止されているものを除く。
「その全額が支給を停止されているものを除く。」に注目してください。
例えば、夫婦ともに240か月以上の厚生年金保険の被保険者期間があり、夫婦ともに加給年金額が加算された老齢厚生年金の受給権者である場合は、お互いに加給年金額は支給停止されます。
しかし、例えば、妻の老齢厚生年金の全額が支給停止されている場合は、夫に支給される老齢厚生年金の妻の分の加給年金額は支給停止されません。
このテーマは明日も続きます。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-197
R3.3.8 夫の年金・妻の年金「加給年金額のこと②年齢制限」
年金の仕組みを勉強しましょう。
昨日に引き続き、テーマは「加給年金額」です。
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件は、原則として「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」あることです。
加給年金額が加算されるのは、一定の条件を満たす配偶者、子がいる場合ですが、今日は加算の対象になる「配偶者」の条件を見ていきます。
こちらの問題をどうぞ!
<H26年出題>
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

【解答】 ×
ポイント! 加給年金額の対象になる配偶者は65歳未満(原則)
「当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。」が間違い。
加給年金額の対象となる配偶者は、「65歳未満」の配偶者です。そのため、加給年金額は、「配偶者が65歳に達したとき」に加算されなくなります。(配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月から加給年金額がなくなります。)
なぜなら、65歳からは、配偶者自身の老齢基礎年金を受給することができるからです。
★問題文のように、たとえ受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合であっても、65歳に達したときは加算されなくなります。
では、もう一問どうぞ
<H20年出題>
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

【解答】 ×
ポイント! 大正15年4月1日以前生まれの配偶者には年齢制限なし
「配偶者の生年月日にかかわらず」が間違いです。
配偶者が「大正15年4月1日以前生まれ」の場合は、65歳以降も引き続き加給年金額の対象となります。「大正15年4月1日以前生まれ」は旧法の対象者ですので、自身の老齢基礎年金が支給されないからです。
※この問題は「障害厚生年金の加給年金額」の問題ですが、「老齢厚生年金の加給年金額」も同じです。配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も引き続き加給年金額の対象となります。
このテーマは明日に続きます!
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-196
R3.3.7 夫の年金・妻の年金「加給年金額のこと①」
年金の仕組みを勉強しましょう。
今日のテーマは、「加給年金額」です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
令和3年1月22日、厚生労働省から令和3年度の年金額についてお知らせがありました。
令和3年度の新規裁定者の年金額として、
・ 国民年金 老齢基礎年金(満額)1人分 65,075 円
・ 厚生年金 夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額として220,496 円
という金額が例示されています。
厚生年金の給付水準は、平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9 万円)で 40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
片方が40年間厚生年金保険の被保険者で、もう片方が40年間国民年金(第1号被保険者か第3号被保険者)という夫婦がモデルになっています。
年金の勉強をするときは、そのようなモデルを意識してみましょう。
今日のテーマは「加給年金額」です。
例えば夫が40年間厚生年金保険の被保険者で、妻が40年間第3号被保険者だった場合、夫の年金は「老齢基礎年金+老齢厚生年金(+加給年金額)」、妻は「老齢基礎年金」となります。
といいましても、「加給年金額」が加算されるには条件があります。その条件を見ていきます。
こちらの問題をどうぞ!
<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【解答】 〇
老齢厚生年金に加給年金額が加算される要件は、原則として「老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上」あることです。
問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間がある場合は、合算して240月以上あればOKです。
この場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は日本年金機構から、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は共済組合から支給されますが、「加給年金額」はどちらの老齢厚生年金に加算されるのかが2つ目の問題です。
この点については、
・最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金
・最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間に基づく老齢厚生年金
となっています。
問題文の場合は、両方とも同時に受給権を取得していますので、被保険者期間が長い「第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金」に加給年金額が加算されます。
(厚生年金保険法第44条、第78条の27、施行令第3条の13)
このテーマは明日に続きます!
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その6(旧法のしくみ)
R3-195
R3.3.6 旧法の老齢年金の支給開始年齢は何歳だった?
年金の歴史についてお話しています。
今日は、旧法の「老齢年金」です。
既にお話していますように、昭和61年3月までの旧制度では、「国民年金」「厚生年金保険」「共済年金」がそれぞれ独立して運営されていました。
例えば、「老齢年金」の支給要件や支給開始年齢は、旧国民年金法と旧厚生年金保険法では以下のように異なっていました。
・旧国民年金法の場合
→支給要件(保険料納付済期間+免除期間が原則として25年以上ある)を満たした者に、65歳から「老齢年金」を支給
・旧厚生年金保険法の場合
→支給要件(原則として被保険者期間が20年以上ある)を満たした者に、60歳から「老齢年金」を支給(ただし、女性と坑内員は55歳から支給)
では一旦ここで旧法の話は終わりまして、国民年金法(新法)の「第1号被保険者」の定義をみてみましょう。
第1号被保険者とは ① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者 ② 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない ③ 厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等)を受けることができる者は除く。 ④ 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。 |
③に注目してください。「(厚生年金保険法に基づく老齢給付等)を受けることができる者」は第1号被保険者から除外されます。
20歳以上60歳未満でそのような人がいるんですか?とよく聞かれますが、旧法では、女性や坑内員などのように55歳から老齢年金を受けることができる人がいて、新法になってからも経過措置として残っていました。
60歳前から老齢給付等を受けられる場合は、もう第1号被保険者として保険料を納付する必要はないので除外とされています。
※「受給資格期間を満たした」と「受けることができる」は違いますので注意してください。
※ちなみに・・・
日本国内に住所を有し20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第1号被保険者からは除外されますが、「任意加入」することはできます。
こちらの問題をどうぞ!
<H17年出題>
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。

【解答】 ×
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でも、被扶養配偶者の場合は第3号被保険者となります。
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」が除外されるのは、第1号被保険者の場合です。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その5(第3号被保険者)
R3-194
R3.3.5 旧法から新法へ(会社員等の被扶養配偶者)
年金の歴史についてお話しています。
旧法では、「会社員の夫と専業主婦の妻」が年金モデルになっていて、老後は夫が老齢年金を受給し、夫の年金に妻の加給年金額が加算されるという仕組みでした。そして、妻は国民年金への加入は任意でした。
旧法のポイント会社員等に扶養される配偶者は、国民年金の加入は任意だった
しかし、妻が任意加入しなかった場合、老後に妻名義の年金が支給されない点などが問題になっていました。
そのため、昭和61年4月1日からは「第3号被保険者」として、会社員等の被扶養配偶者も国民年金に強制加入することになりました。ただし、個別に保険料を負担するのではなく、会社員等が加入する厚生年金保険や共済組合で負担することになりました。
例えば、昭和29年4月2日生まれの女性で、20歳から60歳まで会社員の夫に扶養されていた場合
■昭和49年4月(20歳)~昭和61年3月まで
・国民年金は任意加入
国民年金に任意加入していなかった場合 → 合算対象期間
■昭和61年4月~平成26年3月まで
・国民年金は強制加入(第3号被保険者) → 保険料納付済期間
こちらの問題をどうぞ!
①<H23年出題>
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
②<H26年出題>
昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。

【解答】
①<H23年出題> ×
20歳以上「65歳未満」ではなく、20歳以上「60歳未満」です。
先ほど書きました会社員等の被扶養配偶者がこの規定に該当します。任意加入できるけれど任意加入しなかった期間は合算対象期間となりますが、「20歳以上60歳未満」という枠がありますので注意してください。
また「昭和60年改正前の国民年金法」の期間は、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間です。
(昭和60年法附則第8条第5項)
②<H26年出題> 〇
国民年金の任意加入被保険者になっていたが、保険料を滞納していた期間については、合算対象期間となります。(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その4(基礎年金の導入)
R3-193
R3.3.4 旧法から新法へ(基礎年金の誕生)
年金の歴史についてお話しています。
旧法の年金には大きく分けて3つのグループがありました。
①厚生年金保険・船員保険(民間企業の従業員等)
②共済組合(公務員等)
③国民年金(自営業者等)
この3つの制度が、縦割りでばらばらに運営されていたのが旧法の特徴です。
<旧法のイメージ図>
厚生年金 船員保険 | 共済年金 | ||||
| 国民年金 | |||||
昭和36年4月1日に国民皆年金が実現しましたが、その後、第一次産業が衰退するなど産業構造の変化もあり国民年金の財政は不安定になり、また各制度間の格差も問題になっていました。
そこで、昭和60年に国民年金法が大改正されました。旧法では自営業者等だけを対象にしていた国民年金は、昭和61年4月1日以降、基礎年金として全国民共通の年金制度に生まれ変わりました。
厚生年金保険と共済年金は、基礎年金の上乗せという形式になりました。(このときに船員保険は厚生年金保険に統合されました。)
<新法のイメージ図>
| 厚生年金 | 共済年金 | ||||
国民年金(基礎年金) | |||||
国民年金の被保険者が、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類になったのも新法からです。
こちらの問題をどうぞ!
<H15年選択>
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【解答】
A 大正15年4月2日
B 障害認定日
★「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」。基礎年金という名称は新法から使われています。
★「老齢基礎年金」の対象は、新法施行時に60歳未満だった「大正15年4月2日以降生まれ」の者です。
ただし、問題文に「施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。」とあるように、新法施行日に旧法の老齢・退職給付の受給権のあった者は、引き続き旧法の対象となるので、そのまま旧制度の年金を受けます。
★障害基礎年金は「障害認定日」に受給権が発生します。昭和61年4月1日以降に障害認定日があれば、新法の障害基礎年金の対象になります。
例えば、初診日が昭和61年4月1日前にあっても、障害認定日がそれ以降の場合は新法の対象です。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その3(創成期)
R3-192
R3.3.3 国民年金の誕生(国民皆年金の実現)
年金の歴史についてお話しています。
民間企業の会社員や公務員の老齢については、厚生年金保険、共済年金でカバーできていましてが、自営業者や農林水産業に従事する人たちの年金制度はありませんでした。
しかし、老齢人口が増える。核家族化が進み子が親を扶養する力も弱まっていく。老齢者の生活は国が保障するべきではないかという機運が高まる。そんな時代背景の中、自営業者等を対象とする国民年金が誕生しました。
国民年金の創設により、すべての国民が、「国民年金」「厚生年金保険」「共済」のどれかの制度に加入することになりました。このことを「国民皆年金」といいます。
こちらの問題をどうぞ!
①<H19年出題(社一)>
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。

【解答】 〇
国民年金法は、昭和34年制定、昭和36年4月施行です。
もともと被用者のための年金制度(厚生年金保険、共済年金)は存在していて、国民年金ができたことによって、「国民皆年金」が実現したことがポイントです。
では、こちらもどうぞ!
②<H19年出題(社一)>
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。
③<H19年出題(国年)>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
②<H19年出題(社一)> 〇
国民皆保険と国民皆年金。どちらも「昭和36年4月」に実現しました。
③<H19年出題(国年)> ×
無拠出制の福祉年金の給付が開始されたのは昭和34年11月からです。(10月が間違い)
「福祉年金」とは、保険料の負担なしで支給される年金で、「老齢福祉年金」「障害福祉年金」「母子(準母子)福祉年金」があります。例えば、「老齢福祉年金」は国民年金が成立したときに既に高齢になっていた人が対象です。
「福祉年金」の今
老齢福祉年金はそのまま支給されていますが、障害福祉年金と母子(準母子)福祉年金は、新法施行日(昭和61年4月1日)以降、それぞれ障害基礎年金、遺族基礎年金に裁定替えされています。
(昭60年法附則第25条、第28条)
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その2(創成期)
R3-191
R3.3.2 厚生年金保険法の誕生
年金の歴史についてお話しています。
現在の公的年金には、「国民年金法」と「厚生年金保険法」がありますが、先にできたのは厚生年金保険法です。
社労士試験の科目の順番が、厚生年金保険法→国民年金法と厚生年金保険法の方が先なのはそのためです。
昭和16年に「労働者年金保険法」が制定されました(昭和17年施行)。対象は、工場で働く男性労働者でした。労働力を保全し強化することによって生産力を上げるという社会的な要請があったそうです。
その労働者年金保険法が「厚生年金保険法」という名称に改められたのが昭和19年。その際、事務系の労働者や女性も対象になりました。
そして、昭和29年に厚生年金保険法が全面改正されました。実際に養老年金の受給者が生ずることへの対応です。このときの改正で、老齢年金は定額部分と報酬比例部分の2階建てになりました。また、男子の支給開始年齢が55歳だったものが段階的に60歳に引き上げられることになりました。
(参考:平成18年版、平成23年版厚生労働白書など)
★旧法と新法
昭和61年4月1日より前の年金制度を旧法、それ以降を新法といいます。
新法の厚生年金保険は国民年金(基礎年金)の2階部分という位置づけです。
例えば、65歳からの年金は、1階に老齢基礎年金があって、2階に老齢厚生年金という形です。
しかし、60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」は定額部分(1階)と報酬比例部分(2階)で、厚生年金だけで2階建てになっています。これは国民年金と厚生年金保険が別個に運営されていた旧法の形を引き継いでいます。
旧法の厚生年金保険の老齢年金の支給開始年齢は60歳で定額部分と報酬比例部分の2階建てになっていました。新法になったときに国民年金の支給開始年齢に合わせて65歳開始になりましたが、いきなり60歳から65歳に引き上げることはできません。
ですので、まずは定額部分の開始年齢を1歳ずつ引き上げ、その次に報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げることで、段階的に60歳代前半の老齢厚生年金をなくしていく方法をとっています。旧法の形を徐々になくしていくイメージで考えてみてください。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史(創成期)
R3-190
R3.3.1 社会保険方式の年金制度はいつ始まった?
今日から年金の歴史を勉強しましょう。
20歳で国民年金に加入 → 40年保険料を納付 → 65歳から老齢年金を受給 → 人生100年と考えると年金を受ける期間は約40年近くなる。
考えてみたら、年金との付き合いは「被保険者」+「受給権者」で約80年という期間なのですね。
その間、社会や経済はどんどん変化していくので、それに合わせて年金も法改正が行われます。
年金の勉強に必要なのは、そんな変化の歴史です。
本日は、年金の創成期のお話です。
まずはこちらをどうぞ!
<社一 H22年出題>
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

【解答】 ×
船員保険法の制定は大正14年ではなく、昭和14年です。(昭和15年から施行)
また、年金等給付を含む総合保険で、「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。
★船員保険は、日本で最初の社会保険方式による「公的年金」★
創成期の船員保険は、船員を対象とする「年金」、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」、「健康保険に相当する疾病給付」を総合的に行う保険でした。
戦時体制下で、物資の海上輸送を担う船員の確保が急務だった頃です。
その後の船員保険は?
船員保険の「年金」は、昭和61年4月1日に、厚生年金保険法に統合されました。被保険者の減少や著しい高齢化で年金財政が悪化し、船員保険のみでは存続が厳しくなったからです。
また、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」は、平成22年からそれぞれ労災保険法、雇用保険法に統合されました。
現在の船員保険は、「職務外の疾病等に関する給付(健康保険に相当する部分)」と労災についての船員独自の上乗せの給付を行っています。
(参考:厚生労働白書平成23年版)
社労士受験のあれこれ
厚生年金保険法第1条(目的)
R3-189
R3.2.28 第1条チェック~厚生年金保険編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は厚生年金保険法です。
条文をチェックしましょう!
(第1条 目的)
厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 遺族
B 福祉の向上
では、こちらもどうぞ
<H30年出題>
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

【解答】×
問題文は国民年金法の目的条文です。
社労士受験のあれこれ
国民年金法第1条(目的)
R3-188
R3.2.27 第1条チェック~国民年金法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は国民年金法です。
条文をチェックしましょう!
<H28年選択>
(第1条 目的)
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】
A 安定
B 共同連帯
★国民年金は「日本国憲法第25条第2項に規定する理念」に基づいています。
(参考)憲法第25条
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金は第2項の「国の社会保障的義務」の理念に基づきます。(第1項ではないので注意してください。)
では、こちらもどうぞ
<H26年出題>
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

【解答】×
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な「保険給付」ではなく「給付」を行います。
厚生年金保険法では「保険給付」といいますが、国民年金は「給付」といいます。
法律の名称も、「厚生年金保険法」と「国民年金法」。
国民年金には「保険」という用語が入っていません。
国民年金も保険方式で運営されるものの、例えば、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金や、保険料の全額免除期間のように、保険料の負担と給付が結び付かない給付があるからです。
ですので、「すべての給付は保険原理により行われる」の部分も誤り。保険原理でない給付も存在します。
(参考)国民年金法第2条
国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(保険給付ではなく「必要な給付」となっています。)
社労士受験のあれこれ
健康保険法第1条(目的)
R3-187
R3.2.26 第1条チェック~健康保険法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は健康保険法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 目的>
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害
『労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産』とは?
労働者が業務上負傷した場合、業務災害として労災保険の保険給付が受けられます。
一方、例えば、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務中に負傷した場合は、業務であったとしても「労働者」ではないので、労災保険の対象になりません。
このように労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の保険給付が受けられます。
(参照:平成25.8.14事務連絡 全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
では、こちらもどうぞ
①<H21年出題>
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
②<H28年選択(社一)>
世界初の社会保険は、< B >で誕生した。当時の< B >では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から < B >に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、< C >に「健康保険法」を制定した。

【解答】
①<H21年出題> ×
健康保険法は、大正11年に制定されましたが、全面施行は昭和2年です。
なお、「日本で最初の社会保険」の部分は正しいです。健康保険のポイントです。
②<H28年選択(社一)>
B ドイツ
C 大正11年
日本の社会保障制度には大きく分けて「社会保険方式」と「公的扶助方式」があります。健康保険は「保険」の仕組みで運営されている「社会保険方式」です。
なお、財源が公費である「公的扶助方式」の代表例は生活保護です。
(参照:平成23年版 厚生労働白書)
社労士受験のあれこれ
労働保険徴収法第1条(趣旨)
R3-186
R3.2.25 第1条チェック~徴収法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は徴収法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 趣旨>
(R2年問8D(雇))
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

【解答】 〇
徴収法第1条(趣旨)からの出題です。
「労働保険の事業の効率的な運営」がキーワードです。
労災保険と雇用保険の事業を効率的に運営するために、保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付の手続等のルールを定めた法律です。
また、事業主の代理人として労働保険の事務を処理する団体が、労働保険事務組合です。
では、こちらもどうぞ
<H12年出題>
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。

【解答】 ×
国の行う事業は二元適用事業ではありません。
「国」の行う事業は労災保険が成立しないからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考に、労災保険法第3条第2項を見てみると、「国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、労災保険法は、適用しない。」と規定されています。ちなみに官公署の事業とは、非現業の官公署のことです。
=国の行う事業は労災保険は全面的に適用除外
→なお、「都道府県、市町村」については、「現業の非常勤職員」には労災保険法が適用されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労働保険の事業の効率的な運営を趣旨とする徴収法では、「一元適用事業」(労災保険と雇用保険の保険料の申告や納付等を一本化して行う)が、原則です。
労災保険と雇用保険の適用の範囲等が違う事業は、「二元適用事業」として、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に行います。
試験対策としては、「二元適用事業」に該当する事業を暗記して、それ以外は「一元適用事業」と覚えればOKです。
「二元適用事業の種類」
・都道府県及び市町村が行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものが行う事業
・港湾運送の行為を行う事業
・農林・水産の事業
・建設の事業
(参照:徴収法第39条、施行規則第70条)
社労士受験のあれこれ
雇用保険法第1条(目的)
R3-185
R3.2.24 第1条チェック~雇用保険法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は雇用保険法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 目的>
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について< A >が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< B >をした場合に必要な給付を行うことにより、 労働者の< C >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

【解答】
A 雇用の継続
B 子を養育するための休業
C 生活及び雇用の安定
<雇用保険の体系図>
| 雇用保険 | 失業等給付 | ①求職者給付 | 失業した場合 |
| ②就職促進給付 | 失業した場合 | ||
| ③教育訓練給付 | 自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 | ||
| ④雇用継続給付 | 雇用の継続が困難となる事由が生じた場合 | ||
| 育児休業給付 | |||
| 雇用保険二事業 | |||
■雇用保険は雇用に関する総合的機能を有する制度■
1.失業等給付 → 労働者が失業した場合等に支給(生活及び雇用の安定並びに就職を促進するため)
2.育児休業給付 → 労働者が子を養育するための休業をした場合に支給(生活及び雇用の安定のため)
3.雇用保険二事業 → 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るために行う
■雇用保険法の成り立ち■
「失業」に対する保険として、昭和22年に「失業保険法」という名称で制定されました(その後失業保険法は廃止)。現在の「雇用保険法」は昭和49年に制定され昭和50年に施行されました。
では、こちらもどうぞ
<H13年選択より>※改訂済
再就職手当は< D >の一つであり、受給資格者が< E >職業に就き、かつ一定の要件に該当する場合に、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の< F >以上であることを条件として支給される。
(選択肢)
①求職者給付 ②雇用継続給付 ③就職促進給付
④安定した ⑤離職前の ⑥継続的な
⑦2分の1 ⑧3分の1 ⑨3分の2

【解答】
D ③就職促進給付
B ④安定した
C ⑧3分の1
雇用保険には似たような名称の「給付」や「手当」がたくさんあります。体系図を頭に入れながら各用語をしっかりおさえましょう。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
労災保険法第1条(目的)~令和2年9月1日改正
R3-184
R3.2.23 第1条チェック~労災保険法編(改正)
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は労災保険法です。
労災保険法の第1条は、令和2年9月1日に改正されています。
条文をチェックしましょう!
<第1条>
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の< A >を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の< A >を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務
今回の改正で、『複数事業労働者』という用語が加わりました。
『複数事業労働者』とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のことです。労働災害が起こった時に、複数の会社と労働契約関係にあった労働者などが該当します。
複数事業労働者についてのポイントは以下の通りです。
①給付基礎日額 → 全ての会社の賃金を合算した額をもとに算定する
②脳・心臓疾患、精神障害 → 全ての会社での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価する
<労災保険法の体系>
労災保険法のメインは「保険給付」で、それに付帯する事業として「社会復帰促進等事業」があります。
「保険給付」の種類は、改正前は「業務災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」「二次健康診断等給付」の3つでしたが、このたびの改正で、「複数業務要因災害に関する保険給付」が入り4種類になりました。
では、こちらの条文もどうぞ
第7条
労働者災害補償保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 < B >(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< C >」という。)に関する保険給付(前号(業務災害)に掲げるものを除く。)
3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
4 二次健康診断等給付

【解答】
B 複数事業労働者
C 複数業務要因災害
<労働者災害補償保険法の成り立ち>
労災保険法は、労働基準法とともに昭和22年に施行されました。
労働基準法では、労働者の業務災害に対して、使用者に災害補償の義務を課しています。ただ、使用者だけで災害補償を完全に履行するのはハードルが高いのが現実です。
そこで、業務災害にあった労働者を保護し、使用者の負担を軽減するために、相互扶助の精神によってできたのが労災保険法です。保険料は全額使用者が負担し、保険給付は直接労働者に支払う形式です。労災保険は、使用者が行うべき災害補償を代行する役目をもつ保険です。
その後、昭和48年の法改正で、「通勤災害」が保険給付の対象に加わりました。
「二次健康診断等給付」が施行されたのは、平成13年です。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
労働安全衛生法第1条(目的)
R3-183
R3.2.22 第1条チェック~労働安全衛生法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
まずは、労働安全衛生法です。
選択式からどうぞ!
<H24年選択>
労働安全衛生法第1条は、労働災害の防止のための< A >の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< B >を促進することを目的とすると規定している。

【解答】
A 危害防止基準
B 快適な職場環境の形成
<労働安全衛生法の成り立ち>
昭和22年に制定された労働基準法。その中の第5章が「安全及び衛生」でした。
戦後四半世紀を経た昭和47年に、「安全及び衛生」の部分が労働基準法から分離され、単独法として「労働安全衛生法」が制定されました。
では、もう一問どうぞ
①<H15年選択>
労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の< C >の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と< C >についての一般法である労働基準法とは< D >関係に立つものである、とされている。

【解答】
C 労働条件
D 一体としての
(参照:昭47年9月18日 発基第91号)
この通達によると、労働安全衛生法と労働基準法の関係は、「この法律は、形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、・・・(中略)・・・この法律と労働条件についての一般法である労働基準法とは、一体としての関係に立つものであることが明らかにされている。」とされています。
では、過去問をどうぞ!
①<H12年出題>
労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
②<H29年出題>
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

【解答】
①<H12年出題> 〇
「労働災害の防止のための危害防止基準の確立」、「責任体制の明確化」、「自主的活動の促進の措置を講ずる」等の手段によって、
↓
①職場における労働者の安全と健康を確保
②快適な職場環境の形成を促進
することを目的としています。
②<H29年出題> 〇
先ほどの問題でも出ていたように、労働安全衛生法と労働基準法は、一体としての関係に立っています。
ですので、労働基準法の労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本とされます。
また、通達では、「賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まつて、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。」とされています。
(参照:昭47年9月18日 発基第91号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
労働基準法第1条(労働条件の原則)
R3-182
R3.2.21 第1条チェック~労働基準法編
今日から、各法律の第1条をチェックしていきます。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
まずは、労働基準法です。
選択式からどうぞ!
<H19年選択>
労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

【解答】
A が人たるに値する生活を営む
「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」からきているものです。労働基準法で定める労働条件は「健康で文化的」な生活を送るための最低限の基準。そんな考えを意識しながら、労働基準法を読んでみてください。
では、過去問をどうぞ
①<H25年出題>
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。
②<H28年出題>
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】
①<H25年出題> 〇
労働基準法の定める労働条件は最低基準です。この最低基準を標準とするのではなく、労働関係の当事者は、さらに「向上」を図るように努めましょう、という感じで読んでみてください。
②<H28年出題> 〇
労働基準法が制定されたのは昭和22年ですが、その際の通達(昭和22年9月13日発基第17号)では、第1条について次のように記されています。
「本条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであって本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。」
労働基準法の各条文の基本観念です。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
第三種被保険者(船員・坑内員)の被保険者期間(その2 厚年編)
R3-181
R3.2.20 第三種被保険者の被保険者期間(3分の4・5分の6)が反映するか否か?(その2 厚年編)
今日は年金です!
今日は、昨日の続きで「第3種被保険者」がテーマです。
まず、「第3種被保険者」の定義からどうぞ!
<厚年H18年出題(改)>
第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第1号厚生年金被保険者に限る。)であって、第4種被保険者以外のものをいう。

【解答】 ×
第3種被保険者は、坑内員(鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する被保険者)又は船員(船員法に規定する船員として船舶に使用される被保険者)のことで、 「第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外」のものをいいます。
問題文は、船員任意継続被保険者以外が抜けているので誤りです。
(参照:厚生年金保険法昭和60年附則第5条12号)
次は、被保険者期間の計算です
<H25年選択>
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から< A >4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に< B >を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【解答】
A 平成3年
B 5分の6
昭和61年3月以前は「3分の4」倍、昭和61年4月から平成3年3月までは「5分の6」倍です。
(参照:厚生年金保険法昭和60年附則第47条第4項)
こちらもどうぞ!
①<H20年出題>
昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。なお、他には被保険者期間がないものとする。
②<R1年出題>
船員たる被保険者であった期間が15年以上あり、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者であって、その者が昭和35年4月2日生まれである場合には、60歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができる。

【解答】
①<H20年出題> 〇
昭和21年4月1日以前生まれで、「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上」ある場合、55歳から特別支給の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)が支給される特例があります。
この期間は、3分の4倍等しない「実際の期間」が15年以上あることが条件です。問題文の場合は、「3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年」しかありませんので、55歳から受けることはできません。
なお、この特例は、昭和21年4月2日以降生まれから、段階的に支給開始の年齢が引き上げられ、 例えば、昭和41年4月1日生まれの場合は、64歳からとなります。
(参照:厚生年金保険法平成6年法附則第15条)
②<R1年出題> ×
問題文の条件の場合、60歳からではなく、62歳から定額部分と報酬比例部分を受給することができます。
(参照:厚生年金保険法附則第8条の2第3項)
★3分の4倍、又は5分の6倍された被保険者期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しませんが、老齢厚生年金の額の計算には反映します。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(年金)第三種被保険者(船員・坑内員)の被保険者期間(その1国年編)
R3-180
R3.2.19 第三種被保険者の被保険者期間(3分の4・5分の6)が反映するか否か?(その1国年編)
今日は年金です!
令和2年度の出題振り返りは、いったん、終了します。
今日は、質問を頂きましたので、そちらのお返事です。
<質問の内容> 『平成24年の国民年金問題1で、厚生年金保険の第三種被保険者の納付済期間と老齢基礎年金の計算が違う点について』 |
厚生年金保険には「第三種被保険者」という種別があり、「坑内員・船員」が該当します。
労働が過酷だったため、厚生年金保険の被保険者期間は、昭和61年3月以前は「第3種被保険者であった期間×3分の4」、昭和61年4月から平成3年3月までは「第3種被保険者であった期間×5分の6」でカウントします。
3分の4倍又は5分の6倍した被保険者期間が、反映するものと反映しないものがあります。今日はそのお話です。
では、(国年)平成24年出題の問題をどうぞ!
<国年H24年出題>
国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

【解答】 ×
国民年金の「保険料納付済期間」には、旧法の厚生年金保険の被保険者期間も含まれます。その際、第三種被保険者期間は3分の4倍でカウントされます。
ただし、「老齢基礎年金」の額の計算をする際の「保険料納付済期間」については、第三種被保険者期間は、3分の4倍又は5分の6倍しない「実期間」となります。
なぜなら、老齢基礎年金は「780,900円×改定率」が満額なので、3分の4倍(又は5分の5倍)して計算してもそれほどメリットが無いからではないか?と私は思っています。
ですので、平成24年の問題は、「その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。」の部分が誤りで、老齢基礎年金の額は、3分の4を乗じない「実期間」を保険料納付済期間として計算することになります。
<第三種被保険者であった期間のポイント>
・老齢基礎年金の受給資格を見る場合の保険料納付済期間
→ 3分の4倍又は5分の6倍した期間が適用
・老齢基礎年金の額を計算する場合の保険料納付済期間
→ 実期間で計算(3分の4倍、5分の6倍しない)
(参照:国民年金 昭和60年改正法附則第8条第2項、第3項)
★第三種被保険者のテーマは、明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働者について
R3-179
R3.2.18 労働者性の判断(最高裁判例より)
今日は労働基準法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、< A >の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、< B >等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」

【解答】
A 時間的、場所的な拘束
B 報酬の支払方法、公租公課の負担
★ 「横浜南労基署長事件(平成8年11月28日最高裁)」からの出題です。判決では、労働者性は認められていません。
<キーワード>
・時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やか
・報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、 上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない
→ 「 報酬は、運賃表により出来高が支払われていた」
「所得税の源泉徴収並びに社会保険及び雇用保険の保険料の控除はされておらず、上告人は、報酬を事業所得として確定申告をした」
<参考>
『昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告 (労働基準法の「労働者」の判断基準について)』によると、
「実質的な使用従属性」を労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働に関する判断基準
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無
ニ 代替性の有無
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
ハ その他
(2)専属性の程度
(3)その他
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。

【解答】 〇
芸能タレントの「労働者性」についての行政通達です。
人気の程度、就業の実態、収入の形態等からみて判断されます。
(昭63.7.30 基収355号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(厚年)老齢厚生年金の繰下げ
R3-178
R3.2.17 老齢厚生年金の繰下げの申し出の条件
今日は厚生年金保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

【解答】
A 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
B 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
繰下げのポイント!
① 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していないこと
→ 繰下げの申し出は、老齢厚生年金の受給権取得から1年以上待たなければならない。
② 以下の場合は繰下げの申し出はできない
・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者だった
・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となった
※なぜなら、他の年金たる給付を受給しながら、老齢厚生年金を繰下げて受給額を増やすのは公平性に欠けるから。
※なお、「他の年金たる給付」とは、他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付のことです。ただし、国民年金法の年金たる給付から、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金は除かれます。(老齢基礎年金及び付加年金は、老齢厚生年金と同じく「老齢」の年金、障害基礎年金は65歳以降老齢厚生年金と併給できるので)
※まとめると、老齢厚生年金の受給権を取得したとき、またはその日から1年を経過した日までの間に、「障害厚生年金及び遺族厚生年金」、「遺族基礎年金」の受給権者となっていないこと。
こちらの問題もどうぞ!
①<H19年出題>
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。
②<H28年出題>
障害基礎年金の受給権者が65歳になり老齢厚生年金の受給権を取得したものの、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかった場合、その者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。なお、その者は障害基礎年金、老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権者となったことがないものとする。

【解答】
①<H19年出題> ×
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者も、老齢厚生年金の支給繰下げの申出ができます。
②<H28年出題> 〇
老齢厚生年金の受給権を取得したときに、障害基礎年金の受給権者であったとしても、繰下げの申し出をすることができます。(ちなみに、老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間に障害基礎年金の受給権者になった場合でも繰下げの申し出ができます)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労災)通勤の定義
R3-177
R3.2.16 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
今日は労災保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、< A >な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、< B >に伴い、当該< B >の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該< B >の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、< C >にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を< D >すること。
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(< E >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情

【解答】
A 合理的
B 転任
C 要介護状態
D 介護
E 18
★ 通勤には次の3つの移動があります。
①住居と就業の場所との間の往復
(通常の家と職場の往復)
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(終業後に副業先に向かうための移動など)
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(単身赴任者の赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動)
令和2年の選択式は、③に該当するための要件からの出題です。
やむを得ない事情により ⅰ「配偶者と別居した」、ⅱ「配偶者がない労働者が子と別居した」、Ⅲ「配偶者も子もない労働者が同居介護していた要介護状態にある父母又は親族と別居することになった」場合等が対象です。
令和2年度は、「配偶者」と別居することになったやむを得ない事情(介護、子の養育、配偶者の就業など)からの出題です。
(労災保険法第7条、施行規則第7条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H29年出題>
労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。
②<H25年出題>
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

【解答】
①<H29年出題> ×
「住居」と認められます。配偶者と別居することになったやむを得ない事情の中に、「配偶者が、引き続き就業すること」という要件があります。
(労災保険法施行規則第7条)
②<H25年出題> ×
「反復・継続性」とは、おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められます。
なお、「家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋は、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えない」の部分は〇です。
(H18.3.31基発第 0331042号、基労管発第0331001号、基労補発第0331003号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
年金額の改定(国年と厚年)
R3-176
R3.2.15 国年と厚年を比較・年金額改定
まずは国民年金法です!
令和2年度の問題をどうぞ!(国年)
<問2-選択・国年>
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

【解答】
A 国民の生活水準
B 改定
国民年金は、老齢、障害、死亡を保障するための制度です。
「国民の生活水準」に著しい変動があれば、速やかに年金額の改定が行われます。
(国民年金法第4条)
こちらの問題もどうぞ!
<厚生年金保険法 年金額の改定>
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、< C >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】
C 賃金
厚生年金保険法の場合は、「賃金」という用語が入るのが特徴です。厚生年金保険は被用者のための年金制度だからです。
(厚生年金保険法第2条の2)
・国民年金 → 国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合
・厚生年金保険 → 国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合
こちらの問題もどうぞ!(厚生年金保険)
<H30年出題・厚年>
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】 ×
冒頭の「厚生年金保険法に基づく保険料率」が誤りです。この条文は、保険料率ではなく、「年金たる保険給付」の改定のルールです。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(健保)高額療養費
R3-175
R3.2.14 高額療養費の計算問題
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円+(療養に要した費用-267,000円)×1%」であるので、高額療養費は< A >となる。

【解答】
A 125,570円
【高額療養費の計算問題のチェックポイント!】
●年齢 → 70歳未満か70歳以上かで高額療養費算定基準額が違うので
●標準報酬月額 → 同じく高額療養費算定基準額が違うので
●高額療養費の計算に入れないもの
・特別料金(評価療養、患者申出療養、選定療養)
・食事療養標準負担額
・生活療養標準負担額
●問題文では、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)・高額療養費、どちらを問われているのか?
問題文の場合
年齢50歳、標準報酬月額41万円
高額療養費の対象→保険診療に要した費用70万円(一部負担金相当額21万円)
※評価療養に係る特別料金10万円、選定療養に係る特別料金20万円は対象外
<高額療養費算定基準額(自己負担限度額)の算定式>
80,100円+(700,000円(療養に要した費用)-267,000円)×1%
= 84,430円(自己負担限度額)
<高額療養費>
210,000円-84,430円 = 125,570円
この問題では「高額療養費」が問われているので、答えは125,570円です。
こちらの問題もどうぞ!
①<H27年出題>
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
②<H27年出題>
70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%
③<H28年選択>
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円-< A >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は< B >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< C >となる。

【解答】
①<H27年出題> 〇
特別料金(評価療養、患者申出療養、選定療養)、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象となりません。
②<H27年出題> 〇
ちなみに、558,000円の30%が167,400円です。
③<H28年選択>
A 842,000円
B 45,820円
C 140,100円
Aの額 → 252,600円÷0.3=842,000円
・当該被保険者の一部負担金
1,000,000円×0.3=300,000円
・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
252,600円+(1,000,000円-842,000円)×1%=254,180円
・高額療養費
300,000円-254,180円=45,820円
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(社一)確定拠出年金の掛金
R3-174
R3.2.13 確定拠出年金~掛金拠出限度額
今日は確定拠出年金法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】
A 48,000
確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」があります。
国民年金の第1号被保険者が加入できるのは「個人型」ですが、その場合の掛金の拠出限度額は、68,000円(月額)です。
ただし、付加保険料又は国民年金基金の掛金を納付している場合は、それらを合算して68,000円以内となります。
問題文では、国民年金基金の掛金を20,000円納付しているので、確定拠出年金の掛金は48,000円までとなります。
(確定拠出年金法施行令36条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H21年出題>
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
②<H29年出題>
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。
③<H20年出題>
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。

【解答】
①<H21年出題> ×
「企業年金連合会」が誤り。
「確定拠出年金」には、企業型年金及び個人型年金があり、「個人型年金」とは、「国民年金基金連合会」が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいいます。
なお、「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいいます。
(法第2条)
②<H29年出題> 〇
個人型年金加入者になることができるのは以下の通り。
・ 国民年金の第1号被保険者
・ 60歳未満の厚生年金保険の被保険者 (企業型年金加入者の場合は、企業型年金規約で個人型への加入が認められている場合に限る。)
・ 国民年金の第3号被保険者
(法第62条)
③<H20年出題> ×
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。
(法第68条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(雇用保険)雇用保険法の適用
R3-173
R3.2.12 雇用保険の被保険者になる要件
今日は雇用保険です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

【解答】
A 20時間以上
B 31日以上
雇用保険法第6条で、「1週間の所定労働時間が20時間未満の者」、「同一の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」は、原則として雇用保険法が適用されないことになっています。
上記の適用除外に該当しない人(1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用されることが見込まれる)は、雇用保険の被保険者となります。
(雇用保険法第6条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H23年出題>
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。
②<H22年出題>
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。
③<H27年出題>
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

【解答】
①<H23年出題> 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、原則として雇用保険は適用除外です。
ただし、「日雇労働被保険者に該当」する者は被保険者となります。また、日雇労働 者で、前 2 月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は被保険者となります。
(第6条第2号)
②<H22年出題> 〇
1 週間の所定労働時間が 20 時間未満の者は、原則として雇用保険は適用除外。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満でも日雇労働被保険者に該当する場合は、雇用保険が適用されます。
(第6条第1号)
③<H27年出題> 〇
当初は31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(健保)短時間労働者の適用
R3-172
R3.2.11 短時間労働者~所定労働時間のカウント
今日は健康保険です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-D>
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件である「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の算定において、短時間労働者の所定労働時間が1か月の単位で定められ、特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは、当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とする。

【解答】 〇
★1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の場合は、原則として健康保険は適用除外です。
ただし、4分の3未満でも一定の要件を満たせば、被保険者となります。
<被保険者になる要件>
①週の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上使用されることが見込まれる
③報酬の月額が88,000円以上
④学生でない
⑤特定適用事業所に使用される(事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと)
①「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」という要件がありますが、例えば、所定労働時間が1ヵ月単位で定められている場合、1週間の所定労働時間は「1ヵ月の所定労働時間を 12 分の 52 で除して算出することとなっています。
・1年間を 52 週、1ヵ月を 12 分の 52 週とする → 1か月の所定労働時間を12 分の 52 で除すことで1週間の所定労働時間を算出できる。
問題文の「特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められている」とは、例えば、夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められているような場合です。そのような場合、『当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を 12 分の52で除して』1週間の所定労働時間を算出します。
(参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」)
こちらの問題もどうぞ!
①<H30年出題その1>
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、1週間の所定労働時間が20時間以上であることの算定において、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない場合は、当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を1週間の所定労働時間として算定することとされている。
②<H30年出題その2>
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。

【解答】
①<H30年出題その1> 〇
令和2年度と同様、所定労働時間20時間以上のカウントについての問題です。
問題文の「1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでない」とは、例えば、4週5休制等のような場合です。そのような場合は、『当該周期における1週間の所定労働時間の平均により算定された時間』を1週間の所定労働時間として算定します。
②<H30年出題その2> ×
「報酬の月額が88,000円以上」の算定のルールです。
88,000円は、基本給と諸手当で算定します。
ただし、次の①から④までの賃金は算入しません。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対する賃金(割増賃金等)
④ 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
※④のように、最低賃金に算入されない賃金は88,000円に含みません。ですので、問題文の場合、家族手当も通勤手当も算定の対象にはなりません。
(参考:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集」)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労災保険法)労災保険の罰則規定
R3-171
R3.2.10 労災保険~事業主等に関する罰則
今日は労災保険です!
令和2年度の問題をどうぞ!
①問4-ア
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
②問4-イ
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
③問4-ウ
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
④問4-エ
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
⑤問4-オ
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

【解答】
①問4-ア 〇 報告をしなかった場合
②問4-イ 〇 文書の提出をしなかった場合
③問4-ウ 〇 虚偽の記載をした文書を提出した場合
④問4-エ 〇 虚偽の陳述をした場合
⑤問4-オ 〇 検査を拒んだ場合
<労災保険法の罰則規定>
・事業主等に関する罰則(事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者、労働保険事務組合又は特別加入に係る団体)
→ 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・事業主等以外の者に関する罰則(労働者や保険給付を受ける者などが対象)
→ 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
令和2年度の問題は、事業主に対する罰則です。
事業主に対する罰則を確認しましょう。次の2つです。
① 第46条の規定による行政庁の報告命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は行政庁の文書提出命令に対し、文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
② 第48条第1項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
①、②に該当した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(労災保険法第51条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H30年出題その1>
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
②<H30年出題その2>
行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

【解答】
①<H30年出題その1> 〇
第46条の「使用者に対する報告、出頭命令」の規定です。
対象になるのは、労働者を使用する者、労働保険事務組合、特別加入に係る団体、派遣先の事業主、船員派遣の役務の提供を受ける者です。
(労災保険法第46条)
②<H30年出題その2> 〇
第48条の「立ち入り検査」の規定です。
対象は、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは特別加入に係る団体の事務所、派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場です。
(労災保険法第48条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)請負関係と労働関係
R3-170
R3.2.9 「請負契約」と「労働契約」の違い
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-D>
下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。

【解答】 〇
それぞれの関係を整理すると、下請負人と注文主は「請負関係」、下請負人とその雇用する労働者とは「雇用関係」にあります。
「請負」とは、 ① 請負事業主が、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること、② 請負事業主が、業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することの2つの要件を満たすことが必要です。
問題文はどちらも満たしているので、労働者ではなく事業主となります。
(参考:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号))
こちらの問題もどうぞ!
①<H27年出題>
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。
②<H29年出題>
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

【解答】
①<H27年出題> 〇
労働契約の場合は、『使用者の指揮命令に従って労務を提供する→賃金が支払われる』という関係ですが、請負契約の場合は、『注文主から受けた仕事を完成させる→報酬が支払われる』という関係です。請負契約の場合は、注文主から指揮命令を受けないのがポイントです。
ですので、「その実体において使用従属関係が認められるとき」は、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たります。
②<H29年出題> ×
工場と大工が、請負契約ではなく雇用契約を結ぶことにより使用従属関係になることもあります。その場合は、大工は労働基準法第9条の労働者に該当します。
(昭23.12.25基収4281号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)金品の返還
R3-169
R3.2.8 労働者が退職した場合の金品の返還
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-オ>
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

【解答】 〇
労基法第23条は、労働者の退職の際に、労働者の金品を迅速に返還すべきことを規定した条文です。足止め策に利用することなどを防止するためです。
例えば、退職した労働者から賃金支払いの請求があった場合は、所定の賃金支払い日前でも、請求日から7日以内に支払わなければなりません。
ちなみに、「権利者」とは、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は相続人です。
また、賃金又は金品に関して争いがある(賃金の額などについて労使で争いがある)場合は、異議のない部分を7日以内に支払うこととなっています。
(昭22.9.13基発17号)
こちらの問題もどうぞ!
①<H30年出題>
労働基準法第20条第1項に定める解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
②<H12年出題>
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
①<H30年出題> 〇
解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」とされています。
(昭23.3.17基発464号)
②<H12年出題> ×
退職手当は、通常の賃金とは扱いが異なり、「予め就業規則等で定められた支払時期」に支払えばよいとされています。
(昭26.12.27基収5483号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)就業規則の記載事項
R3-168
R3.2.7 就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-A>
慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。

【解答】 ×
就業規則へ記載するか否か、当事者の自由です。
(昭23.10.30基発1575号)
就業規則には、必ず記載しなければならない事項『絶対的必要記載事項』と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 『相対的必要記載事項』があり、以下のように定められています。
<絶対的必要記載事項>
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
<相対的必要記載事項>
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰及び制裁に関する事項
⑧ その他、当該事業場の労働者すべてに適用される定めに関する事項
問題文の「労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする」という事項は、絶対的必要記載事項でも相対的必要記載事項でも当てはまらないので、就業規則の記載は任意となります。
こちらの問題もどうぞ!
①<H25年出題>
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
②<H14年出題>
休職に関する事項は、使用者がこれに関する定めをする場合には、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条第1項の規定により、労働契約の締結に際し労働者に対して明示しなければならない労働条件とされており、また、それが当該事業場の労働者すべてに適用される定めであれば、同法第89条に規定する就業規則の必要記載事項でもある。

【解答】
①<H25年出題> 〇
「従来の慣習」を就業規則に規定しなければならないか?がテーマです。
問題文の、従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用される」の部分がポイントです。
相対的必要記載事項の最後の「そのほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当するので、就業規則に規定しなければなりません。
(昭23.10.30基発1575号)
②<H14年出題> 〇
「休職に関する事項」について
労働契約の際 → 「休職」については、労基法施行規則第5条で「定めをする場合は明示しなければならない」事項に掲げられているので、休職に関する事項の定めがある場合は明示しなければなりません。
就業規則 → 「休職」に関する事項が、「当該事業場の労働者すべてに適用される定め」であれば、就業規則の相対的必要記載事項として記載しなければなりません。
(労基法第15条第1項、第89条、同法施行規則第5条第1項)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働時間の定義
R3-167
R3.2.6 「労働時間」とはどんな時間のこと?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-A>
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。

【解答】 〇
運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間でも、万一の場合は運転を交替したり、故障個所を修理することもあり得ます。労働から解放されていないので、労働時間に当たります。
(昭33.10.11基発6286号)
こちらの問題もどうぞ!
①<H26年出題>
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。
②<H21年出題>
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。

【解答】
①<H26年出題> 〇
令和2年の問題と同じです。
「労働」の概念をつかみましょう。『一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。」の部分がポイントです。
②<H21年出題> ×
来客当番として事務所に待機させた時間は、労働時間となります。問題文の場合は来客当番の時間を入れると法定労働時間を超えるので、割増賃金を支払う義務があります。
(昭23.4.7基収1196号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)解雇予告の意思表示
R3-166
R3.2.5 解雇予告の意思表示は取り消すことができるか?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-ウ>
使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。

【解答】 〇
いったん解雇を告げた後に、「やっぱり解雇は取り消したい」と言えるかどうかですが、解雇予告の意思表示を取り消すことは、一般的にはできません。
ただし、労働者が自らの判断で取消しに同意した場合は、取り消すことができるという解釈です。
(昭33.2.13基発90号)
こちらの問題もどうぞ!
①<H16年出題>
ある労働者を解雇しようと思い、労働基準法第20条の規定に従って、5月1日に、30日前の予告を行った。しかし、その後になって思い直し、同月10日、当該労働者に対し、「考え直した結果、やはり辞めてほしくないので、このままわが社にいてくれないか。」と申し出てみたが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。その場合、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は自己退職(任意退職)したこととなる。
②<H24年出題>
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

【解答】
①<H16年出題> ×
②<H24年出題> ×
どちらの問題も、解雇を予告した後、「やはり引き続きわが社にいてほしい」と解雇の取り消しを申し出ていますが、労働者は、解雇の取り消しに同意せずそれに応じていません。
その場合、「予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。」は誤りです。
行政解釈では、「解雇予告の意思表示の取り消しに対して、労働者の同意がない場合は、自己都合退職の問題は生じない」となっていて、このような場合は、自己都合退職ではなく、予告期間を経過した日に「解雇」ということになります。
(昭33.2.13基発90号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)解雇予告の除外
R3-165
R3.2.4 解雇予告除外認定の要件など
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-エ>
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。

【解答】 ×
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力かつ突発的な事由という意味です。
「事業場が火災により焼失した場合」は「やむを得ない事由」に該当しますが、「使用者の重過失による火災で事業場が焼失」した場合は除かれます。
(労基法第20条 昭63.3.14基発150号)
解雇予告の条文をチェック!
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。)
(解雇予告除外認定)
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。)
こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。

【解答】 〇
①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
②労働者の責に帰すべき事由
→所轄労働基準監督署長の認定を条件として、予告・予告手当なしで解雇することができます。
では、もう一問どうぞ!
<H18年出題>
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇予告除外認定」という。)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。

【解答】 〇
原則は、「解雇予告除外認定」は解雇の意思表示をなす前に受けるべきもの。
では、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、解雇の効力いつ発生するのでしょうか?
問題文にあるように、『解雇予告除外事由に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得る』とされます。
この問題のポイントは、そのような事実がある場合には、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する、の部分です。
平成24年には、即時解雇の効力は認定のあった日に発生するという出題がありましたが、それは誤りです。認定のあった日ではなく即時解雇の意思表示をした日に発生します。
(昭63.3.14基発150号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働条件の明示
R3-164
R3.2.3 書面の交付等による明示義務
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-イ>
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

【解答】 〇
労働者を雇い入れる際に、「賃金」に関する事項は、書面等による明示が必要です。
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(昇給については書面でなくてもよい)
※基本給の額等を具体的に書面に記載するのが原則。
しかし、就業規則に規定されている賃金等級で労働者が賃金を確定できるのならば、等級を明確に示す方法でも可。
問題文のように、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。(ただし、就業規則が周知されていることが前提)
(労働基準法第15条、施行規則第5条、昭51.9.28基発第690号)
では、こちらの問題をどうぞ
①<H9年出題>
使用者は、労働契約の締結に際し、賃金に関する事項については、書面により明示しなければならないこととされているが、採用時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に周知されていれば、この書面による明示がなされていると解してよい。
②<H12年出題>
労働契約の締結に際し書面を交付して明示すべき労働条件のうち、退職に関する事項については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないが、明示事項の内容が膨大なものとなる場合は、労働者の利便性をも考慮し、適用される就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足りる。

【解答】
①<H9年出題> 〇
令和2年度の問題と同じです。
②<H12年出題> 〇
例えば、『定年、退職の手続き、解雇の事由及び手続「詳細は、就業規則第21条~25条」による』という記載でもよい。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働契約の契約期間
R3-163
R3.2.2 労働契約の契約期間の上限は?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-ア>
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

【解答】 〇
高度の専門的知識等を有する労働者との間の労働契約 → 上限5年まで可能
※ただし高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る。(高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合は、上限3年まで)
労働契約は、次の2つに分けられます。
・期間の定めのない契約(労基法上規制なし)
・期間の定めのある契約(規制あり)
【期間の定めのある契約について)
原則 → 3年以内
例外その1(3年を超える期間が可能)
・建設工事などの有期事業(その事業の終わりまでの契約が可能)
・職業訓練(訓練期間が長期にわたる場合)
例外その2(上限5年まで)
・高度の専門的知識等を有する労働者をそのような高度の専門的知識等が必要な業務に就かせる場合
・満60歳以上の労働者との労働契約
(労働基準法第14条)
では、こちらの問題をどうぞ
①<H25年出題>
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
②<H27年出題>
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
③<H18年選択式出題>
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が < A >ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。

【解答】
①<H25年出題> 〇
満60歳以上の労働者との契約期間は上限5年です。
②<H27年出題> 〇
例えば、4年で完成する建設現場に、4年の契約期間で雇い入れるような場合です。
③<H18年選択式出題>
A 1,075万円を下回らない
高度の専門的な知識、技術又は経験については、告示で限定列挙されていて、そのうちの一つです。
(労働基準法第14条 H15.10.22厚労告356号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)派遣の仕組み
R3-162
R3.2.1 労基法の使用者は、派遣元?派遣先?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-E>
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

【解答】 ×
派遣労働者に関する労働基準法は、原則として、労働契約関係にある派遣元(派遣会社)が、使用者としての責任を負います。
ただし、 一部の規定については、派遣労働者の指揮命令権者である派遣先が、使用者としての責任を負うことになっています。
では、こちらの問題をどうぞ
①<H9年出題>
派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
②<H17年出題>
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

【解答】
①<H9年出題> 〇
第33条「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働・休日労働」について、事前に行政官庁の許可を受ける、又は事後に遅滞なく届出をする義務は「派遣先」が負います。
(昭61.6.6基発333号)
②<H17年出題> ×
36協定は「派遣元」で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ます。
(昭61.6.6基発333号)
ちなみに・・・
※派遣労働者については、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして労働時間に係る規定を適用しています。
・労働時間の把握は?
派遣労働者に係る労働時間を適正に把握する義務は「派遣先」にある。
・36協定に基づく時間外労働等
派遣先が時間外労働等を行わせる場合は、36 協定の範囲内であること。もし、その範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合には、派遣先は労基法違反となる。
(労働者派遣法第44条 労働基準法の適用に関する特例)
では、最後にこちらもどうぞ!
<H16年出題>
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。

【解答】 〇
事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、「派遣元」の事業でなされます。
(昭61.6.6基発333号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(徴収法)労働保険料の口座振替
R3-161
R3.1.31 労働保険料の口座振替を希望する場合
今日は徴収法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-A(雇)>
事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。

【解答】 〇
書面の提出先は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」です。
(徴収法第21条の2、徴収法施行規則第38条の2)
では、こちらの問題をどうぞ
<H30年出題>
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

【解答】 ×
「納付が確実と認められれば」必ずではなく、『その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り』、その申出を承認することができる、とされています。
(徴収法第21条の2)
では、最後にこちらもどうぞ!
<H24年出題その1>
労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
<H24年出題その2>
いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

【解答】
<H24年出題その1> 〇
<H24年出題その2> 〇
■口座振替ができるのは
納付書によって行われる
・概算保険料(延納する場合も口座振替ができる)
・確定保険料
■口座振替できないもの
増加概算保険料、認定決定された概算保険料、追徴金
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(厚年)4分の3基準
R3-160
R3.1.30 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が4分の3以上
今日は厚年法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-D>
特定適用事業所以外の適用事業所においては、1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である者を被保険者として取り扱うこととされているが、雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき、4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間又は労働日数が直近6か月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱うことされている。

【解答】 ×
直近6か月ではなく、直近2カ月です。
~~この問題でおさえておきたいところ~~
※短時間労働者の厚生年金保険の加入要件
■1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上
→ 被保険者となる
※1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数とは?
→ 就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数のこと。
※雇用契約書における所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化しているとき
→ 4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った → 実際の労働時間又は労働日数が直近2か月で4分の3基準を満たしている → 今後も同様の状態が続くことが見込まれる → 4分の3基準を満たしているものとして取り扱う
(参照:H28.5.13 保保発0513第1号/年管管発0513第1号/)
では、こちらの問題をどうぞ
<H29年出題>
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】 ×
「通常の労働者の4分の3以上」の要件を満たしている場合は、学生でも厚生年金保険の被保険者となります。
※ 通常の労働者の4分の3未満の場合は、「特定適用事業所に使用」「20時間以上」「1年以上使用見込」「88,000円以上」など他の適用基準を満たしていても、「学生でないこと」という要件があるので、学生は適用除外です。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(厚年)特定適用事業所と短時間労働者
R3-159
R3.1.29 特定適用事業所と短時間労働者について
今日は厚年法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
 <問7-ア>
<問7-ア>
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
 <問7-イ>
<問7-イ>
特定適用事業所に使用される者は、その1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満であって、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
※短時間労働者の厚生年金保険の加入要件
■1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上
→ 被保険者となる
■1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、又は1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満
→ 原則として適用除外
※ただし、4分の3未満でも一定の要件を満たせば、厚生年金保険の被保険者となる
<要件>
①週の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上使用されることが見込まれる
③厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円以上
④学生でない
⑤特定適用事業所に使用される
※「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のこと
 <問7-ア> 〇
<問7-ア> 〇
報酬の月額が88,000円未満の場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
 <問7-イ> 〇
<問7-イ> 〇
当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。
(厚生年金保険法第12条5号)
では、こちらの問題をどうぞ
 <問7-エ>
<問7-エ>
特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
 <問7-エ> ×
<問7-エ> ×
常時500人を超えなくなった場合でも、引き続き特定適用事業所とみなすこととされているので、そのまま厚生年金保険の被保険者となります。
(厚生年金保険法附則(平成24年)第17条)
最後にもう一問どうぞ!
 <問7-ウ>
<問7-ウ>
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
 <問7-ウ> 〇
<問7-ウ> 〇
特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者
↓
厚生年金保険の被保険者とならない。
※ただし、特定適用事業所以外の適用事業所の事業主は、所定の労働組合等の同意を得て、「任意特定適用事業所」の申し出を行うことができます。
(厚生年金保険法附則(平成24年)第17条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(労基法)36協定~時間外労働の限度時間
R3-158
R3.1.28 36協定で協定する事項は?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-C>
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

【解答】 〇
36協定には、対象期間の、「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの期間の労働時間を延長して労働させることができる時間(時間外労働の時間)を協定することになっています。
その時間は、労基法に以下のように規定されています。
・1か月45時間、1年360時間
・1年単位の変形労働時間(対象期間が3か月を超える期間を定めている場合)は、1か月42時間、1年320時間
(労基法第36条)
では、第36条を穴埋めで確認しましょう!
第36条 時間外及び休日の労働
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は第35条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
【協定で定めること】
① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
② 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間。1年間に限るものとする。)
③ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
④ 対象期間における< A >、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
※ ④の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
※ 限度時間は、1か月について< B >時間及び1年について< C >時間とする。
1年単位の変形労働時間制の対象期間として< D >を超える期間を定め労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とする。
それ以外に
・有効期間の定め、対象期間の起算日など
・通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合(特別条項)

【解答】
A 1日
B 45
C 360
D 3か月
(労基法第36条)
最後にもう一問どうぞ!
<H24年出題>
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】 〇
36協定は、「所轄労働基準監督署長に届出」をすることによって免罰効果が生まれることがポイントです。
単に「36協定を締結しました(届け出してません)」では、効果はありません。
(労基法第36条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(労基法)労基法上の「使用者」とは
R3-157
R3.1.27 労基法上使用者とはどのような立場の人?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-B>
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。

【解答】 ×
労働基準法には様々な義務規定がありますが、使用者は、その履行の責任者となります。
部長や課長という名称ではなくて、労働基準法の義務について実質的に一定の権限を与えられている場合は、労働基準法の使用者として責任を問われることになります。
問題の場合、「係長」という名称でも、責任と権限があれば労働基準法の使用者になります。
参照:(昭和22.9.13発基第17号)
では、令和2年の問題からもう一問どうぞ!
<問1-C>
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。

【解答】 ×
一問目と同じです。
課長という役職であっても、権限がなく、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、労働基準法の使用者にはなりません。
参照:(昭和22.9.13発基第17号)
では、もう一問どうぞ!
<H24年出題>
労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう。

【解答】 ×
「事業主のために行為をするすべての者」です。管理監督者以上に限定されていません。
穴埋め式で条文check!
第10条 使用者の定義
この法律で使用者とは、< A >又は事業の< B >その他その事業の労働者に関する事項について、< C >をいう。

【解答】
A 事業主
B 経営担当者
C 事業主のために行為をするすべての者
(労基法第10条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(労基法)労基法の適用単位
R3-156
R3.1.26 労基法は場所単位で適用される
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-D>
1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。

【解答】 ×
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務があります。
「10人」は、企業単位で数えるのか、それとも事業場単位で数えるのか?というのがこの問題のテーマです。
労働基準法は、事業単位(「場所的観念」)で適用されます。
ですので、この問題の場合、工場単位で数えます。どちらも10人未満ですので、就業規則の作成義務はありません。
(労基法第89条)
★労働基準法は、企業単位ではなく、原則として場所的観念で適用されることを思い出してください。
では、こちらの問題もどうぞ!
<H26年出題>
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

【解答】 ×
「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない。主として場所的観念によって決定すべきもの、とされています。
問題文の記述は逆になっています。
穴埋め式で条文check!
第9条 労働者の定義
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(「事業」という。)に使用される者で、< A >者をいう。

【解答】
A 賃金を支払われる
(労基法第9条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(徴収法)労働保険料の労働者負担
R3-155
R3.1.25 労働保険料、労働者の負担分は?
今日は徴収法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-C(雇)>
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

【解答】 ×
一般保険料の額は、賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)で計算します。
労災保険料は全額事業主負担ですが、問題文の表現だと、それが労働者負担になってしまうので、誤りとなります。
労災保険と雇用保険が成立している事業の被保険者が負担する労働保険料の額は、
『一般保険料の額のうち雇用保険率に係る部分の額』から『その額に二事業率を乗じて得た額』を減じた額の2分の1です。
例えば、令和2年度の雇用保険率は、一般の事業は「1,000分の9」です。
1000分の9の内訳は
・失業等給付と育児休業給付 → 1,000分の6
・雇用保険二事業 → 1,000分の3
となります。
そのうち、被保険者が負担する率は、「1,000分の9から1,000分の3」を減じた額の2分の1なので「1,000分の3」となります。
残りの労働保険料は事業主が負担します。
事業主の負担
・労災保険料 → 全額
・雇用保険料 → 「失業等給付と育児休業給付」×2分の1
雇用保険二事業(全て)
(徴収法第31条)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。
 <H22年出題>
<H22年出題>
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。

【解答】
 <H22年出題> 〇
<H22年出題> 〇
令和2年度の問題と同じ趣旨です。
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主が全額負担します。
(徴収法第31条)
雇用保険率の内訳
雇用保険率1000分の9のうち、「1,000分の3」が二事業分ですが、残りの「1000分の6」の内訳は、次の通りです。
1000分の4 → 育児休業給付
1000分の2 → 失業等給付
(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号))
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(雇用保険)給付制限~日雇労働被保険者
R3-154
R3.1.24 日雇労働被保険者の給付制限の例外
今日は雇用保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-A>
日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。

【解答】 〇
日雇労働被保険者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒否した場合は、給付制限の対象になりますが、例外的に、日雇労働求職者給付金が支給される場合もあります。
(例外)
① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
③ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 → 「同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所」
④ その他正当な理由があるとき。
問題文は、例外の③に該当しますので、給付制限は受けません。
(雇用保険法第52条)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H25年出題>
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

【解答】 ×
給付制限の期間は、就職を拒否した日から起算して7日間です。
(雇用保険法第52条、行政手引90702 (2))
穴埋めで条文もチェック!
(日雇労働求職者給付金 給付制限)
第52条 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して< A >間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
③ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
④ その他正当な理由があるとき。
(基本手当 給付制限)
第32条 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して< B >間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
① 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。
② 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。
③ 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。
④ 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。
⑤ その他正当な理由があるとき。

【解答】
A 7日
B 1か月
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基)割増賃金の支払義務
R3-153
R3.1.23 違法な時間外労働に対する割増賃金
今日は労働基準法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-D>
労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】 〇
<読み方>
・時間外労働、休日労働については、第33条、第36条の条件を満たすことが必要
↓
・第37条では、条件を満たした適法な時間外労働や休日労働について、割増賃金の支払を義務付けている
↓
・では、第33条、第36条の条件を満たしていない違法な時間外労働や休日労働の場合は、割増賃金は支払わなくてもいいのか?
↓
・一層強い理由でその支払義務があるものと解すべき
(参照:労働基準法第37条 昭35.7.14最高裁一小 小島撚糸事件)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

【解答】 〇
令和2年度の問題と同じです。
穴埋めで条文もチェック!
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条
① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、< B >のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< C >届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、< D >ことができる。
③ < E >のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

【解答】
A 許可
B 事態急迫
C 事後に遅滞なく
D 命ずる
E 公務
社労士受験のあれこれ
(労基)就業規則の作成義務
R3-152
R3.1.22 就業規則~常時10人の数え方
今日は労働基準法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-C>
派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。

【解答】 ×
就業規則の作成・届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です。
派遣元の使用者の場合、「派遣労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上」になると、派遣労働者にも適用される就業規則を作成する義務があります。
参照:労働基準法第89条
基発第0331010号 平成21.3.31(派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
 <H26年出題>
<H26年出題>
労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が1年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。

【解答】
 <R1年出題> ×
<R1年出題> ×
労働基準法第89条では、単に常時10人以上の「労働者」と規定されているだけです。ですので、短時間労働者かそうでないかには関係なく1人でカウントします。
(労働基準法第89条)
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
「常時10人以上」とは、たまに10人未満になることがあったとしても、通常、10人以上いる状態だと考えてください。
問題文は、通常8人、たまに10人以上になるということなので、労働基準法第89条でいう「常時10人以上」には当たりません。
(労働基準法第89条)
穴埋めで条文もチェック!
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、< A >並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く。)決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに< B >に関する事項
③ 退職に関する事項(< C >を含む。)
④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
⑦ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑩ 表彰及び< D >の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑪ その他、当該事業場の< E >に適用される定めをする場合においては、これに関する事項

【解答】
A 休暇
B 昇給
C 解雇の事由
D 制裁
E 労働者のすべて
社労士受験のあれこれ
(健保)療養の指示に従わない場合
R3-151
R3.1.21 療養の指示に従わない場合の給付制限
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-D>
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに診療担当者より受けた診断書、意見書等により一般に療養の指示と認められる事実があったにもかかわらず、これに従わないため、療養上の障害を生じ著しく給付の増加をもたらすと認められる場合には、保険給付の一部を行わないことができる。

【解答】 〇
問題文が長いですが、キーワードは 『正当な理由なしに』『療養の指示』『従わない』です。このような場合は、『保険給付の一部を行わないことができる』です。
(健康保険法第119条)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
 <H28年出題>
<H28年出題>
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
令和2年度の問題と同じです。
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき」は、保険給付の『一部を行わないことができる』です。「全部又は一部」ではないので注意しましょう。
(健康保険法第119条)
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
『闘争、泥酔又は著しい不行跡』の場合は、『全部又は一部を行わないことができる』です。問題文の「全部について行わない」は間違いです。
(健康保険法第117条)
 <H28年出題> 〇
<H28年出題> 〇
文書の提出等の命令に従わない、答弁や受診を拒んだ、そんなときは、『全部又は一部を行わないことができる』です。
(健康保険法第121条)
穴埋めで条文もチェック!
<第116条> 被保険者又は被保険者であった者が、自己の< A >により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
<第117条> 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< B >。
<第119条> 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< C >。
<第120条> 保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、< D >以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から< E >を経過したときは、この限りでない。
<第121条> 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の< G >。

【解答】
A 故意の犯罪行為 (第116条)
B 全部又は一部を行わないことができる (第117条)
C 一部を行わないことができる (第119条)
D 6月 (第120条)
E 1年 (第120条)
F 全部又は一部を行わないことができる (第121条)
社労士受験のあれこれ
(健保)療養費~海外で療養を受けた場合
R3-150
R3.1.20 療養費支給申請書に添付する証拠書類
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問8-E>
被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させることとされている。

【解答】 〇
海外で療養等を受けた場合は、療養費の対象になります。
療養費の申請手続の添付書類が外国語で記載されていたら・・・『日本語の翻訳文を添付してください、何か問い合わせすることがあるかもしれないので、翻訳者の氏名及び住所を記載してください』という感じで読んでみてください。
(参照:昭和56年2月25日 保険発第10号・庁保険発第2号)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H21年出題>
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。

【解答】 ×
最後の「保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。」が間違いです。『その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。』ことになっています。
支給申請や受領を、海外にいる被保険者と保険者が直接やり取りするのは、効率が悪いからです。
なお、この問題文には他にもポイントがあります。
・ 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせること (支給申請は原則事業主経由)
・ 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること
(療養を受けた日、申請をした日ではないので注意しましょう。)
(参照:昭和56年2月25日 保険発第10号・庁保険発第2号)
条文もチェック!
<療養費>
保険者は、療養の給付等を行うことが< A >であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者が< B >ものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

【解答】
A 困難
B やむを得ない
(健康保険法第87条)
社労士受験のあれこれ
(健保)報酬から控除する保険料
R3-149
R3.1.19 支払う報酬が無いときの保険料の負担
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-オ>
事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

【解答】 〇
たとえ、被保険者に支払う報酬が無くて保険料を控除できない場合であっても、事業主には、被保険者負担分の保険料を保険者に納付する義務があります。(会社から受け取る報酬が無くても、被保険者は健康保険料を負担する義務があるということ)
(参照:昭和2年2月18日 保理第578号)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者資格を喪失した者に係る保険料で、その者に支払う報酬がないため控除できない場合は、事業主は被保険者負担相当分を除いた額を納付する。

【解答】
 <H25年出題> ×
<H25年出題> ×
令和2年度の問題と同じように考えればいいと思います。
報酬から控除した保険料の額が、本来、被保険者の負担すべき額に足りなかったとしても、事業主には保険料の全額を納付する義務があります。
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
この問題も同じです。報酬がなくて保険料を控除できなくても、事業主には、保険料(事業主負担分+被保険者負担分)を納付する義務があります。
では、こちらもどうぞ!
 <H26年出題>
<H26年出題>
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間にかかるもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。

【解答】 〇
報酬から控除できる被保険者負担分の保険料は、「前月の標準報酬月額に係る」保険料のみです。
ただし、例外的に、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合(退職の場合)は、前月と当月の2か月分の保険料を控除できます。
例外が当てはまるのは、問題文のような月末退職の場合です。5月31日退職の場合、6月1日資格喪失となり、保険料は5月分まで徴収されます。
そのため、5月支払の給与から、4月分(前月分)と5月分(当月分)の2か月分の保険料を控除することができます。
(参照:健康保険法第167条)
社労士受験のあれこれ
(健保)任意継続被保険者の申出
R3-148
R3.1.18 任意継続被保険者申出期限
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-イ>
任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならず、保険者は、いかなる理由がある場合においても、この期間を経過した後の申出は受理することができない。

【解答】 ×
「いかなる理由がある場合においても」が誤り。
例外として、『正当な理由があると認めるとき』は、保険者は期限を経過した後の申出ででも、受理することができます。
(参照:健康保険法第37条)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならないが、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても受理することができる。なお、判例によると「法律の不知」によるという主張は、この場合の正当な理由にあたらないものと解されている。
 <H23年出題>
<H23年出題>
任意継続被保険者の資格取得の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。なお、その申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めない限り、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。

【解答】
 <H25年出題> 〇
<H25年出題> 〇
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
問題文にあるように、「法律の不知」という主張は、正当な理由にあたりません。「知りませんでした」ではダメということ。
なお、「正当な理由」とされるのは、「天災事変」「交通ストライキ」等です。
(判例:昭和36年2月24日 最高裁判所第二小法廷)
 <H23年出題> 〇
<H23年出題> 〇
任意継続被保険者の初回分の保険料を納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなされます。(正当な理由がある場合以外)
(健康保険法第37条)
※ついでにこちらもチェック!
・ 2回目以降の保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日に資格を喪失します。
・ 任意継続被保険者の保険料の納付期日は、「当月10日」です。初回分は、「保険者が指定する日」です。
(健康保険法第38条、第164条)
社労士受験のあれこれ
(健保)訪問看護療養費
R3-147
R3.1.17 指定訪問看護の利用回数の限度は?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問3-イ>
指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。

【解答】 ×
原則として、週3日が限度です。
なお、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者については、週4日以上の訪問看護が可能です。
(参照:令和2年3月5日 保発0305第3号)
こちらの問題もどうぞ!
~訪問看護事業の定義を穴埋めで確認しましょう。~
訪問看護事業とは、
・疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(< A >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、
・その者の居宅において看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< B >が行う療養上の< C >又は必要な診療の< D >を行う事業のこと
・< E >等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは< F >によるものを除く

【解答】
A 主治の医師
B 言語聴覚士
C 世話
D 補助
E 保険医療機関
F 介護医療院
(参照:健康保険法第88条、施行規則第68条)
もう一問どうぞ!
<H19年出題>
70歳未満の被保険者が訪問看護を受けたとき、厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額と、当該被保険者の選定に基づいて提供された指定訪問看護等に要する平均的な時間を超える指定訪問看護等及び指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護等の利用料がある場合はその費用とを負担しなければならない。

【解答】 〇
指定訪問看護を受けた被保険者は、基本利用料(厚生労働大臣が定める基準により算定した指定訪問看護の費用から訪問看護療養費支給額を差し引いた額)を負担します。
また、基本利用料のほか、その他の利用料を負担することもあります。
その他の利用料とは?
・ 訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護
・ 交通費、おむつ代等に要する費用(実費)
(参照)
・令和2年3月5日 保発0305第3号
・指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(H12.3.31厚生省令第80号)
社労士受験のあれこれ
(健保)特定の法人の電子申請の義務
R3-146
R3.1.16 電子申請の義務がある法人の規模と届出の種類
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問8-A>
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届の届出は、事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

【解答】 〇
■■おさえるポイントは電子申請の義務がある法人の規模と届出の種類
【電子申請が義務となる『特定法人』とは?】
・事業年度開始の時の資本金等が1億円を超える法人
・保険業法に規定する相互会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
【対象の届出は3つ】
・報酬月額算定基礎届(定時決定)
・報酬月額変更届(随時改定)
・賞与支払届
※参照条文:健康保険法施行規則第25条、第26条、第27条
ちなみに、厚生年金保険法も同様です。
こちらの問題もどうぞ!
<H30年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

【解答】 〇
覚えるポイントは期限。「5日以内」です。
なお、賞与支払届の提出は、特定法人(資本金1億円を超える法人等)は、原則として電子申請で行わなければなりません。
(健保法施行規則第27条)
社労士受験のあれこれ
(健保)病気休職中の保険料
R3-145
R3.1.15 傷病手当金終了後休職が続いている場合の健康保険料
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-B>
被保険者が同一疾病について1年6か月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は保険料を負担する義務を負わなければならない。

【解答】 〇
傷病手当金の受給終了後も引き続き休業し、報酬の支払いが無かったとしても、健康保険の被保険者である間は、保険料(事業主&被保険者ともに)を負担する義務があります。(産前産後休業や育児休業中は保険料の免除制度があるけれど、病気やケガなどの休業については免除の制度が無い。)
こちらの問題もどうぞ!
 <H24年出題>
<H24年出題>
被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され事業主負担分のみ納付する義務を負う。
 <R1年出題>
<R1年出題>
被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

【解答】
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
病気休職中でも保険料は免除されませんので、事業主負担分、被保険者負担分ともに負担義務があります。
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
この問題も同じです。
病気休職中でも、事業主も被保険者も保険料を負担する義務はあります。また、その際の保険料は、賃金支給停止前の標準報酬に基づき算定されます。
では、こちらもどうぞ!
 <H27年出題>
<H27年出題>
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

【解答】
 <H27年出題> ×
<H27年出題> ×
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われなくなり、保険料も徴収されません。
また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合、保険料を徴収されない期間は、その月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間です。問題文中の徴収されない期間が誤りです。
例えば、令和2年3月に被保険者の資格を取得、刑事施設に拘禁されたのが令和2年4月、拘禁されなくなったのが8月の場合、保険料を徴収しない期間は、4月から7月までとなります。
ちなみに・・・
被保険者がその資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合は、その翌月以後、拘禁されなくなった月の前月までの期間となります。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
産前産後休業、育児休業の保険料の免除の期間を確認しておきましょう。
| 開始 | 終了 | |
| 産前産後休業 | 開始した日の属する月から | 終了する日の翌日が属する月の前月まで |
| 育児休業 | 開始した日の属する月から | 終了する日の翌日が属する月の前月まで |
(例)産前産後休業の場合
出産日5月1日、産前休業3月21日~5月1日、産後休業5月2日~6月26日の場合、保険料が免除される期間は、3月から5月までとなります。
社労士受験のあれこれ
(健保)資格取得時の標準報酬月額
R3-144
R3.1.14 資格取得時の賃金に算定誤りがあった場合
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-D>
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

【解答】 〇
<被保険者資格を取得した際の標準報酬月額>
・ 固定的賃金の算定誤り等があった → 訂正できる
・ 残業代のような非固定的賃金の見込みが当初の算定額より増減した → 訂正できない
こちらの問題もどうぞ!
<H27年出題>
月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

【解答】 ×
その期間における『所定労働日数』ではなく、その期間の『総日数』で除します。
例えば、週給制の場合は、週給÷7(1週間の総日数)×30が報酬月額となります。
資格取得時決定の条文を穴埋めで確認しておきましょう
(被保険者の資格を取得した際の決定)
保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
① 月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の< A >で除して得た額の< B >倍に相当する額
② 日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前< C >月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
③ ①、②の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前< C >月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
④ ①、②、③のうち2以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、①、②、③の規定によって算定した額の合算額
決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の< D >月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の< D >月)までの各月の標準報酬月額とする。

【解答】
A 総日数
B 30
C 1
D 8
社労士受験のあれこれ
(健保)随時改定のタイミング
R3-143
R3.1.13 育児休業中の昇給~随時改定はいつ?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-C>
育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。

【解答】 ×
(問題の要旨)
育児休業に昇給があった → しかし育児休業中は一切給与の支払いがない → このような場合、随時改定はどうなるのか?
問題文では、「標準報酬月額の随時改定が行われることはない。」となっていますが、そこが誤りです。
(答)
産休等の無給期間中に固定的賃金に変動があった場合 → 実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として随時改定の対象となります。
こちらの問題もどうぞ!
<H26年出題>
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。

【解答】 〇
随時改定は、『固定的賃金の変動が報酬に反映された月』を起算とします。
問題文の場合、昇給分が実際に報酬に反映されたのは5月なので、5月、6月、7月の3か月間で要件をみます。また、3か月の平均をとる際は、昇給差額分は除外されます。
随時改定の条文を穴埋めで確認しておきましょう
(随時改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した< A >月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を< A >で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった< B >に比べて、< C >を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を< B >として、その< C >を生じた月の < D >から、標準報酬月額を改定することができる。

【解答】
A 3
B 報酬月額
C 著しく高低
D 翌月
社労士受験のあれこれ
(健保)定時決定のルール
R3-142
R3.1.12 給与の締め日を変更した場合、定時決定はどうする?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-B>
給与の支払方法が月給制であり、毎月20日締め、同月末日払いの事業所において、被保険者の給与の締め日が4月より20日から25日に変更された場合、締め日が変更された4月のみ給与計算期間が3月21日から4月25日までとなるため、標準報酬月額の定時決定の際には、3月21日から3月25日までの給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日まで)で算出された報酬を4月の報酬とする。

【解答】 〇
(問題の要旨)
4月から、給与の締め日が、毎月20日締め(末日払い)から25日締めに変更になった。
締め日が変更された4月は、給与計算期間が3月21日から4月25日までとなってしまう。このままだと支払い基礎日数が暦日よりも多くなってしまう。
定時決定の際は、どのように扱えばいいのか?
(答)
3月21日~4月25日までの報酬で算定すると、通常よりも多くなってしまうので、『超過分の報酬を除外』し、その他の月の報酬との平均を算出して、標準報酬月額を保険者算定する。
問題文の通り、超過分の3月21日~3月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与の計算期間(3月26日~4月25日)で算出された報酬を4月の報酬とする。
ちなみに、支払基礎日数が減少した場合はどうする?
・給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合
→ 支払基礎日数が17日以上なら、通常の定時決定の方法で算定する。
→ 支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外して報酬の平均を算出し、標準報酬月額を算定する。
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】 〇
まず、一時帰休の際に支払われる休業手当は「報酬」ですので、休業手当が支払われた日は、支払基礎日数に含まれることに注意してくださいね。
この問題のポイントは、「7月1日の時点で一時帰休の状況が解消」(=現在、低額な休業手当は支払われていないということ)している点です。このような場合、休業手当はどのように扱うのでしょうか?
→ 7月1日時点で元に戻っている。なので、低額な休業手当を除いて標準報酬月額を決定する。
→ 問題文のように、4月と5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当という場合は、6月分を除いて4月と5月の報酬月額を平均して定時決定を行う。
※ちなみに、7月1日現在で一時帰休の状況が解消していない場合は?
→ 例えば、4・5・6月のうち、4・5月は通常の給与、6月のみ一時帰休による休業手当が支払われた場合には、6月分の休業手当を含めて、4・5・6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。
社労士受験のあれこれ
(健保)任意適用事業所の要件
R3-141
R3.1.11 任意適用事業所と被保険者の申出
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-C>
任意適用事業所において被保険者の4分の3以上の申出があった場合、事業主は当該事業所を適用事業所でなくするための認可の申請をしなければならない。

【解答】 ×
被保険者から任意適用事業所の脱退を希望する申出があったとしても、事業主には脱退の申請をする義務はありません。
こちらの問題もどうぞ!
 <H28年出題>
<H28年出題>
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。
 <H24年出題>
<H24年出題>
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とすべき義務が生じる。

【解答】
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
令和2年度の出題と同じ趣旨です。事業主には任意適用取消しの申請をする義務はありません。
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
被保険者となるべき者の希望があったとしても、事業主には適用事業所とすべき義務はありません。
比較してみましょう!
| 加入の義務 | 脱退の義務 | |
|---|---|---|
労災保険 | あり 過半数の希望があった場合 | なし |
雇用保険 | あり 2分の1以上の希望があった場合 | |
健康保険 厚生年金保険 | なし | なし |
社労士受験のあれこれ
(健保)協会けんぽ/短期借入金など
R3-140
R3.1.10 協会けんぽ・厚生労働大臣の認可?承認?報告?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-B>
全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

【解答】 〇
・ 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合は、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
・ 短期借入金は、その事業年度内に償還しなければならない。
・ 資金の不足のため償還できないときは、その金額に限って、厚生労働大臣の認可を受けて、借り換えができる。
・ 借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
コチラの問題もどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
全国健康保険協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、運営委員会の議を経て短期借入金をすることができる。その場合、理事長はあらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
 <H24年出題>
<H24年出題>
全国健康保険協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供したときは、厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
短期借入金をするとき → 厚生労働大臣の認可
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
財務諸表、事業報告書等 → 厚生労働大臣の承認
 <H24年出題>
<H24年出題>
重要な財産の譲渡、担保 → 厚生労働大臣の認可(報告ではない)
社労士受験のあれこれ
(健保)出産手当金の支給要件
R3-139
R3.1.9 出産手当金の支給は労務に服さなかった期間
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-E>
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。

【解答】 ×
出産手当金は、「労務に服さなかった」期間支給されます。
問題文は、「通常の労務に服している」期間の話ですので、出産手当金は支給されません。
出産手当金の条文を穴埋めで確認しましょう
被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が< A >後であるときは、< A >))以前42日(多胎妊娠の場合においては、< B >日)から出産の日後56日までの間において< C >期間、出産手当金を支給する。

【解答】
A 出産の予定日
B 98
C 労務に服さなかった
コチラの問題もどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
 <H27年出題>
<H27年出題>
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

【解答】
 <H23年出題> 〇
<H23年出題> 〇
出産手当金のルール
・ 報酬の全部又は一部を受けることができる場合 → 出産手当金は支給しない
※報酬の額が、出産手当金の額より少ないとき → 差額を支給する
 <H27年出題> 〇
<H27年出題> 〇
事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているとき → 出産手当金の支給額は介護休業手当との調整が行われる。(上記H23年出題の問題と同じ趣旨です。)
社労士受験のあれこれ
(健保)休業補償給付と傷病手当金の関係
R3-138
R3.1.8 休業補償給付と傷病手当金は併給できる?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-A>
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

【解答】 ×
「労災保険の休業補償給付」、「健康保険の傷病手当金」の目的はどちらも「生活保障」。仮に、両方同時に受給すると、働いて得る賃金を超えてしまいます。
ですので、労災保険法による休業補償給付を受けている間に、業務外の事由で労務不能になったとしても、傷病手当金は支給されません。
ただし、労災の休業補償給付の額が、傷病手当金の額に満たない場合は差額が支給されます。
この問題のポイント!
労災の休業補償給付の額より、健保の傷病手当金の額の方が高い場合は、差額の傷病手当金が支給されます。問題文の「傷病手当金が支給されることはない。」が間違い。差額の傷病手当金が支給されることがあるからです。
社労士受験のあれこれ
(健保)一部負担金の減免
R3-137
R3.1.7 健保一部負担金の減免はどのようなときに行われる?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問8-D>
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払を免除することができる。

【解答】 〇
災害等の特別の事情があり、一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対して、保険者は次の3つの措置を採ることができます。
① 一部負担金の減額
② 一部負担金の支払の免除
③ 一部負担金の徴収の猶予
こちらの問題もどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる者に対して、次の措置を採ることができる。①一部負担金を減額すること、②一部負担金の支払を免除すること、③保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
 <H25年出題>
<H25年出題>
災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。保険者はその徴収猶予又は減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。

【解答】
 <H23年出題> 〇
<H23年出題> 〇
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
 <H25年出題> 〇
<H25年出題> 〇
一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けようとするときは、あらかじめ申請が必要。
→ 徴収猶予又は減免の決定をした場合、保険者は速やかに証明書を交付する
→ 療養の給付等を受けようとするときは、「証明書」を健康保険被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出する。
社労士受験のあれこれ
(健保)任意継続被保険者の前納
R3-136
R3.1.6 任継の保険料は前納できるが、その額は?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-E>
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

【解答】 ×
任意継続被保険者の前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の「合計額」ではなく、合計額から「割引」があります。(詳しくは下の問題でどうぞ)
こちらの問題もどうぞ!
<H22年選択>
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納をおこなうことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
A 各月の初日
※国民年金の前納は、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなされるのは、「各月が経過した際」です。区別して覚えましょう。
B 初月の前月末日
※例えば、4月分から9月分までの6か月分を前納する場合は、納付期限は「前納に係る期間の初月の前月末日」=3月末日までとなります。
C 年4分の利率
※前納については割引があります。
D 5月
※前納の期間は、
- ・4月から9月までの6か月間
- ・10月から翌年3月までの6か月間
- ・4月分から翌年3月分までの12か月間
- ですが、その途中で任意継続被保険者となった場合は、その資格取得した月の翌月以降の期間について前納することができます。
- 問題文の場合、4月に任意継続被保険者の資格を取得していますので、翌月の5月から9月までの期間または翌年3月までの期間で前納できます。
社労士受験のあれこれ
(健保)資格喪失後の傷病手当金
R3-135
R3.1.5 資格喪失後に特例退職被保険者になった。傷手は継続給付される?
今日は健康保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-A>
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者が、その資格を喪失後に特例退職被保険者の資格を取得した場合、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

【解答】 ×
資格喪失後に「特例退職被保険者」になった場合は、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は受けられません。
※「特例退職被保険者」といえば、定年退職後で老齢厚生年金を受けている世代なので、二重の保障は不要と考えてみてください。
こちらの問題もどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

【解答】
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、傷病手当金の継続給付を受けることはできます。
資格喪失後の傷病手当金の継続給付
・任意継続被保険者になった場合 → 受けられる
・特例退職被保険者になった場合 → 受けられない
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
資格喪失後に船員保険の被保険者となったとき
→ 「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金」→ の給付は行われない。
※船員保険法の方で給付が行われるからです。
社労士受験のあれこれ
(年金)3号分割標準報酬改定請求
R3-134
R3.1.4 3号分割~当事者の一方が死亡した場合
令和2年度の問題をどうぞ!
<問3-イ>
特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る。)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。

【解答】 ×
「当該特定被保険者が『死亡した日』に3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす。」の部分、死亡した日ではなく、『死亡した日の前日』です。(死亡した日には請求できないので、前日)
■ 特定被保険者が死亡したとしても、死亡後1か月以内なら、3号分割改定を請求できます。
※「特定被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者と被保険者であった者のこと。
※「被扶養配偶者」とは、特定被保険者の配偶者として国民年金法の第3号被保険者だった者のこと。
こちらの問題もどうぞ!
<H28年出題>
離婚をし、その1年後に、特定被保険者が死亡した場合、その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬改定請求があったときは、当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

【解答】 〇
令和2年度と同じ趣旨の問題です。
3号分割について、こちらもどうぞ!
 <H26年出題>
<H26年出題>
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して、分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して、いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
 <H26年出題>
<H26年出題>
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関して、原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

【解答】
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
■ 特定期間 → 特定被保険者が厚生年金保険の被保険者で、かつ、その被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者であった期間のこと。
ただし、この制度が施行された平成20年4月1日以降が対象です。それより前の期間は特定期間に含まれません。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
事実婚関係だった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者だった場合は分割の対象になります。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年です。
社労士受験のあれこれ
(年金)被保険者期間のカウント
R3-133
R3.1.3 第1号被保険者の資格取得・喪失と保険料
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-B>
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

【解答】 〇
■ 平成12年1月1日生まれの場合、令和元年12月31日に20歳に達するので、その日に第1号被保険者の資格を取得します。なお、その後ずっと第1号被保険者だった場合、60歳に達した日(令和41年12月31日)に資格を喪失します。
■ 被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までですので、問題文の場合、令和元年12月から令和41年11月までとなります。
■ 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されます。
こちらの問題もどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
 <H26年出題>
<H26年出題>
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
 <H29年出題>
<H29年出題>
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

【解答】
 <R1年出題> ×
<R1年出題> ×
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達するのは平成31年3月31日です。被保険者期間に算入されるのは、平成31年3月からです。
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
昭和29年4月1日生まれの者が60歳に達して資格を喪失するのは平成26年3月31日です。被保険者期間は、資格を喪失した日の属する月の前月ですので、被保険者期間に算入されるのは平成26年2月までです。
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
第1号被保険者が平成29年3月31日に死亡した場合、翌日の平成29年4月1日に資格を喪失します。被保険者期間は同年3月までで、保険料の納付義務も3月分までです。
社労士受験のあれこれ
(年金)老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
R3-132
R3.1.2 支給繰下げの申出があったものとみなされるのはいつ?
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-D>
老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70歳達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。

【解答】 〇
この問題のポイントは
・ 66歳~70歳までの間に遺族厚生年金の受給権を取得した
・ 支給繰下げの申出をしたのが70歳
この場合、『遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日』に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
・66歳に達した日後に次の①又は②に掲げる者が支給繰下げの申出をしたときは、次の①又は②に定める日において、支給繰下げの申出があったものとみなす。
① 70に達する日前に他の年金たる給付(※)の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付(※)を支給すべき事由が生じた日
(※)他の年金たる給付とは? → 他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
② 70歳に達した日後にある者(①該当する者を除く。)
→ 70歳に達した日
問題文の場合①に該当します。70歳に達する前に他の年金たる給付(問題文の場合、遺族厚生年金)の受給権者となっているので、「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」に繰下げの申出があったものとみなされます。
 ちなみに、このような場合
ちなみに、このような場合
<繰下げの増額率の計算は?>
①の場合は、「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」、②の場合は、「70歳に達した日」の時点で、増額率が計算されます。
<繰下げた老齢基礎年金はいつから支給される?>
①の場合は、「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」の属する月の翌月から、②の場合は、「70歳に達した日」の属する月の翌月から、支給されます。
問題文の場合は、増額率は「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」の時点で計算し、支給は「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」の属する月の翌月からとなります。
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】 〇
以下の場合は、繰下げの申出はできません。
・65歳に達したときに、他の年金たる給付(※)の受給権者であったとき
・65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付(※)の受給権者となったとき
※他の年金たる給付 → 他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。
問題文では、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となった」とあるので、繰下げの申出はできません。
社労士受験のあれこれ
(年金)追納できる期間
R3-131
R3.1.1 追納できるのはいつからいつまで?
あけましておめでとうございます! 今年も「社会保険労務士合格研究室」をよろしくお願いします。 合言葉の「毎日コツコツ」頑張りましょう! |
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-エ>
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

【解答】 〇
追納できるのは、「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るもの」に限られています。
アンダーライン部分「以前10年」ではなく「前10年」なのがポイント。承認を受けた月は入りません。
問題文の場合、追納の承認を受けたのが令和2年4月なので、その前月から10年以内が対象です。
令和2年3月からさかのぼって10年以内にあるのは平成22年4月ですので、追納の対象は平成22年4月から平成28年3月までとなります。
こちらの問題もどうぞ!
<H30年出題>
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

【解答】 〇
老齢基礎年金の受給権者は追納できないことにも注意してください。
ちなみに、「障害基礎年金の受給権者は追納できるか否か」という問題が過去に出題されていますが、「障害基礎年金の受給権者は追納できます」。
障害基礎年金は、障害の状態によっては支給停止になる可能性もありますよね?追納して老齢基礎年金の受給額を増やす選択もできるのです。
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

【解答】 〇
一部免除の期間も追納できます。
例えば、4分の1免除は、「4分の1」は免除されますが、残りの4分の3は納付しなければなりません。
4分の3を納付してこその「4分の1免除期間」であり、その免除された4分の1を追納することは可能です。
一方、4分の3を納付していなければ未納期間です。問題文にあるように4分の3を納付していないときは、追納もできません。
社労士受験のあれこれ
(年金)脱退一時金(日本から出国する外国人が対象)
R3-130
R2.12.31 脱退一時金を受けた後のこと
今年も1年ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年を。
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-ウ>
日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、平成7年4月から平成9年3月までの2年間、国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成23年4月から日本に居住することになり、60歳までの8年間、第1号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】 ×
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている」が間違いで、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしません。
脱退一時金には、「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。」という規定があります。
問題文でいうと、脱退一時金の計算の基礎となった「平成7年4月から平成9年3月までの2年間」は、被保険者でなかったことになります。(合算対象期間にもならない)
再び日本国内に居住し8年間保険料を納付しても、受給資格期間の10年に満たないので老齢基礎年金の受給資格はできません。
こちらの問題もどうぞ!
<H20年出題>
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

【解答】 〇
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
ちなみに。。。
日本と「年金通算の社会保障協定」を締結している国の場合、一定の要件を満たすと、年金の加入期間を通算することができます。
ただし、脱退一時金を受けた場合は、その計算の基礎となった期間は通算されなくなります。
社労士受験のあれこれ
(年金)法定免除と保険料納付
R3-129
R2.12.30 法定免除に該当していても保険料は納付できる?
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-イ>
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。

【解答】 〇
法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。
将来の老齢基礎年金を増やしたい場合は、本人の申出によって、法定免除の期間の保険料を納付することもできます。
こちらの問題もどうぞ!
<H29年出題>
国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

【解答】 〇
もう一問どうぞ!
<H16年出題>
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。

【解答】 ×
法定免除の対象になるのは、障害基礎年金、障害厚生年金等(1・2級)の受給権者です。
障害厚生年金の受給権者でも3級(一度も2級以上に該当していない)は、法定免除の対象になりません。
ちなみに、過去に1・2級の障害年金を受けていたが、障害の程度が軽くなり、現在3級に該当している場合は、法定免除の対象となります。
※ なお、3級に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した場合は、法定免除の対象から除かれます。(保険料の納付義務が発生する)
社労士受験のあれこれ
(年金)退職時改定
R3-128
R2.12.29 資格喪失→保険料が年金額に反映するのはいつから?
令和2年度の問題をどうぞ!
<厚年 問9-A>
被保険者である老齢厚生年金の受給者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎なり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

【解答】 ×
問題文の場合
・資格喪失日 → 令和2年6月30日(70歳に達した日=誕生日の前日)
・被保険者期間 → 令和2年5月まで(喪失した月の前月まで)
 <退職時改定>令和2年5月までの期間も入れて、老齢厚生年金の額を再計算する。
<退職時改定>令和2年5月までの期間も入れて、老齢厚生年金の額を再計算する。
・年金額の改定 → 資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から
資格喪失日は6月30日。「資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月」は令和2年7月。老齢厚生年金は、令和2年8月からではなく、「令和2年7月」から改定されます。
こちらの問題もどうぞ!
 <H26年出題>
<H26年出題>
老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。
 <H28年出題>
<H28年出題>
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。

【解答】
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
老齢厚生年金の額の計算のルールは、「受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない」とされています。
受給権を取得した時点の年金額には、受給権を取得した月は含みません。
※ ちなみに・・・
厚生年金保険法で、「被保険者である」というのは、「在職中」という意味。在職中とはすなわち厚生年金保険料を負担しているという意味です。
問題文の「老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった」とは、老齢厚生年金の受有権を取得した月に在職中だった(=厚生年金保険の保険料を負担していた)という意味です。
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
平成28年3月からではなく、平成28年2月から年金額が改定されます。
<退職時改定のルール>
・ 被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月経過した
↓
・ 被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とする
↓
・ 資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
※起算日に注意しましょう!
「その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。(退職)」は、その翌日に資格を喪失しますが、退職時改定による年金額の改定は、「退職日」から起算して1か月を経過した日の属する月からとなります。
問題文の場合、平成28年1月31日付退職、同年2月1日に被保険者資格を喪失ですので、退職時改定の起算日は退職日の平成28年1月31日となります。
年金額の改定は、資格喪失日(退職の場合は退職日)から起算して1か月を経過した日の属する月からなので、平成28年2月から年金額が改定されることになります。
社労士受験のあれこれ
(年金)法定免除について
R3-127
R2.12.28 法定免除→いつから免除になる?手続きは?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問10-オ >
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】 〇
この問題のチェックポイントはこちら!
 「法定免除」の事由に該当している?
「法定免除」の事由に該当している?
「生活保護法による生活扶助を受けるようになった」→ 法定免除事由に該当する
生活保護には、「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8つの扶助がありますが、保険料の法定免除の対象になるのは、そのうちの「生活扶助」です。
 いつから免除される?
いつから免除される?
■法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になる。
例えば、12月に該当した場合は、11月から免除になります。(11月分の納期限が12月末なので)
■既に納付された保険料は免除にならない。
 手続きは?
手続きは?
法定免除事由に該当した日から14日以内に届書を市町村に提出しなければならない。(厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、提出不要)
★法定免除の効果は要件に該当すれば当然に発生します。届出の有無は効果に関係ありませんが、該当した事実を確認するために必要です。
こちらもどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
 <H27年出題>
<H27年出題>
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
 <H26年出題>
<H26年出題>
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

【解答】
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
法定免除は、要件に該当すれば当然に免除の対象になるため、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得は関係ありません。
また、法定免除の期間(その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで)もしっかりおさえてください。
 <H27年出題> ×
<H27年出題> ×
法定免除の対象は「生活扶助」のみです。生活扶助以外の扶助は、申請免除の対象になり得ます。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
老齢基礎年金の額を増やすために、法定免除期間中、本人から保険料を納付する旨の申出があった場合、その期間の保険料を納付することができます。
社労士受験のあれこれ
(年金)死亡一時金の額+α
R3-126
R2.12.27 死亡一時金の算定と付加保険料
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問2-A >
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】 〇
この問題のポイント!
 死亡一時金の額は「定額」・保険料を納付した月数によって、6段階
死亡一時金の額は「定額」・保険料を納付した月数によって、6段階
<死亡一時金の額>
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における次の月数を合算した月数に応じて定められています。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
・保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
・保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
| 月数 | 金額 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 | |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 | +25,000 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 | +25,000 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 | +50,000 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 | +50,000 |
| 420月以上 | 320,000円 | +50,000 |
 付加保険料の納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円加算される
付加保険料の納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円加算される
こちらもどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
 <H24年出題>
<H24年出題>
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
 <H24年出題>
<H24年出題>
死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。
 <H24年出題>
<H24年出題>
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。

【解答】
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
保険料4分の1免除期間は「4分の3」で計算しますので、問題文の場合、48月×4分の3=36月です。
死亡一時金は合算した月数(令和2年度の解説をご確認ください。)が36月以上あることが条件ですので、要件を満たします。
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
保険料全額免除期間は36月の計算に入れません。(保険料を全く納めていないので)
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
死亡一時金の額は、6段階の定額です。
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
付加保険料の納付は、寡婦年金の額には反映しません。付加保険料が反映するのは死亡一時金のみです。
社労士受験のあれこれ
(年金)滞納処分のルール
R3-125
R2.12.26 厚生労働大臣が滞納処分を行う場合のルール
令和2年の問題をどうぞ!
 <厚年 問3-ウ >
<厚年 問3-ウ >
厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため、保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
 <厚年 問3-エ >
<厚年 問3-エ >
日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

【解答】
 <厚年 問3-ウ > 〇
<厚年 問3-ウ > 〇
厚生労働大臣は、督促を受けた者が指定の期限までに保険料等を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる
↓
滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること等の事情があるため、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき
↓
財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
※納付義務者が滞納処分を免れるため財産を隠ぺいしているおそれがあるようなときは、財務大臣(国税のトップ)に、必要な情報を提供したうえで、滞納処分等の権限の全部又は一部を委任できる。
 <厚年 問3-エ > 〇
<厚年 問3-エ > 〇
国税滞納処分の例による処分の厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。
↓
<日本年金機構が滞納処分等を行う場合>
・あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける
・「滞納処分等実施規程」に従い徴収職員に行わせる
こちらもどうぞ!
<厚年 H30年出題>
厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。

【解答】 〇
厚生労働大臣は、市町村に、その処分を請求することができる
↓
処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によって処分した
↓
厚生労働大臣は、徴収金の100の4に相当する額を当該市町村に交付する
社労士受験のあれこれ
(年金)被保険者期間のカウント
R3-124
R2.12.25 厚年 保険料が徴収される月されない月
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問3-ア >
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

【解答】 ×
月末日で退職したとき →退職した日が属する月の保険料は徴収されます。
例えば、退職日が12月31日の場合、翌日の1月1日に資格を喪失します。
資格を喪失した月(1月)は保険料は徴収されませんが、退職月(12月)は保険料が徴収されます。
もし、退職日が12月25日なら、翌日の12月26日に資格を喪失します。
この場合、資格を喪失した月が12月ですので、保険料が徴収されるのは11月まで。12月は保険料は徴収されません。
こちらもどうぞ!
 <厚年 H21年出題>
<厚年 H21年出題>
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
 <厚年 H20年出題>
<厚年 H20年出題>
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする。)の保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される。
 <厚年 H28年出題>
<厚年 H28年出題>
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
 <厚年 H21年出題> ×
<厚年 H21年出題> ×
問題文のように日単位となるのは「被保険者であった期間」です。
「被保険者期間」は、「月単位」で計算します。「資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」までとなります。
 <厚年 H20年出題> 〇
<厚年 H20年出題> 〇
被保険者期間は、「資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」まで。
問題文の場合は、4月(4月30日)に資格取得・6月(6月1日)に資格喪失ですので、被保険者期間は4月、5月の2か月となります。保険料も、4月分と5月分の2か月分が徴収されます。
 <厚年 H28年出題> 〇
<厚年 H28年出題> 〇
同月得喪の問題です。
(原則)
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は1か月の被保険者期間としてカウントします。
(例外)
資格を取得した月に資格を喪失し、その月に更に厚生年金保険の被保険者又は国民年金の被保険者(第2号被保険者以外)の資格を取得したときは、先に喪失した厚生年金保険は被保険者期間としてカウントしません。
問題文の場合、平成28年3月1日に資格取得、同月20日退職・翌21日に資格喪失ですので、厚生年金保険は同月得喪。引き続き同月21日に国民年金の第1号被保険者となっています。
このパターンは上記(例外)に当たりますので、3月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。(厚生年金保険の保険料も徴収されません。)
社労士受験のあれこれ
(年金)受給権者の申出による支給停止
R3-123
R2.12.24 年金の支給停止の申出について
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1-B >
年金たる保険給付は、厚生年金保険法の他の規定又は同法以外の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されている場合は、その受給権者の申出により、停止されていない部分の額の支給を停止することとされている。

【解答】 〇
受給権者の意思で、年金の支払いを辞退するための規定です。
辞退できるのは「全額」です。(一部だけの辞退はできない)
問題文にもあるように、年金の一部が既に支給停止されている場合は、残りの部分(支給停止されていない部分)を辞退することになります。
こちらもどうぞ!
 <厚年 H19年出題>
<厚年 H19年出題>
年金たる保険給付(厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額又は一部の支給を停止するものとし、すでに厚生年金保険法の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の全額又は一部の支給を停止する。
 <国年 H24年出題>
<国年 H24年出題>
受給権者の申出による年金の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

【解答】
 <厚年 H19年出題> ×
<厚年 H19年出題> ×
辞退できるのは「全額」についてです。一部だけ辞退は不可。
受給権者の申出により「その全額又は一部の支給を停止」は間違いで、「全額」が支給停止されます。同様に、停止されていない部分の「全額又は一部の支給を停止」も間違いで、こちらも残りの部分が「全額」支給停止されます。
 <国年 H24年出題> ×
<国年 H24年出題> ×
受給権者の申出による年金の支給停止は、いつでも撤回することができますが、「過去に遡って」が間違いで、「将来に向かって」撤回することができます。
・支給停止 → 申出をした日の属する月の翌月分から支給停止
・支給停止の解除 → 申出をした日の属する月の翌月分から支給停止の解除
社労士受験のあれこれ
(年金)2以上の種別の被保険者であった期間
R3-122
R2.12.23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問5-C >
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は併給される。

【解答】 〇
厚生年金保険の被保険者は、第1号から第4号まで4つの種別に分けられています。
例えば、民間企業の会社員と国家公務員の経験がある人は、問題文のように、第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有することになります。
このような場合
・老齢厚生年金の受給権の有無 → それぞれの被保険者期間ごとにみる
・老齢厚生年金の年金額 → それぞれの被保険者期間ごとに計算する
1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は、それぞれで計算し、併給されます。
こちらもどうぞ!
 <H29年出題>
<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
 <H28年出題>
<H28年出題>
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

【解答】
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
「2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して・・・平均標準報酬額を算出する。」が間違いです。
年金額は、それぞれの種別の被保険者期間ごとに計算します。
 <H28年出題> 〇
<H28年出題> 〇
加給年金額が加算されるには、原則として240月以上の被保険者期間が必要です。この場合は、2以上の種別の被保険者期間を合算します。問題文の場合は、第1号厚生年金被保険者期間170か月、第2号厚生年金被保険者期間130か月で合計300月ありますので、加給年金額が加算されます。
なお、加算については、それぞれの厚生年金被保険者期間のうち一の期間の老齢厚生年金の額に加算されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)基礎年金拠出金
R3-121
R2.12.22 基礎年金拠出金は第2号と第3号の基礎年金の費用
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 選択式>
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。

【解答】
A 実施機関たる共済組合等
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に保険料を納付していませんが、基礎年金を受けることができます。
第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用のため、厚生年金保険から国民年金に「基礎年金拠出金」を支払っています。
こちらもどうぞ!
 <H28年出題>
<H28年出題>
実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。
 <H24年出題>
<H24年出題>
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。

【解答】
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
日本年金機構ではなく、「国民年金の管掌者たる政府」に納付します。
 <H24年出題> 〇
<H24年出題> 〇
第2号被保険者と第3号被保険者からは国民年金の保険料は徴収しません。第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付の費用は、基礎年金拠出金が使われます。
社労士受験のあれこれ
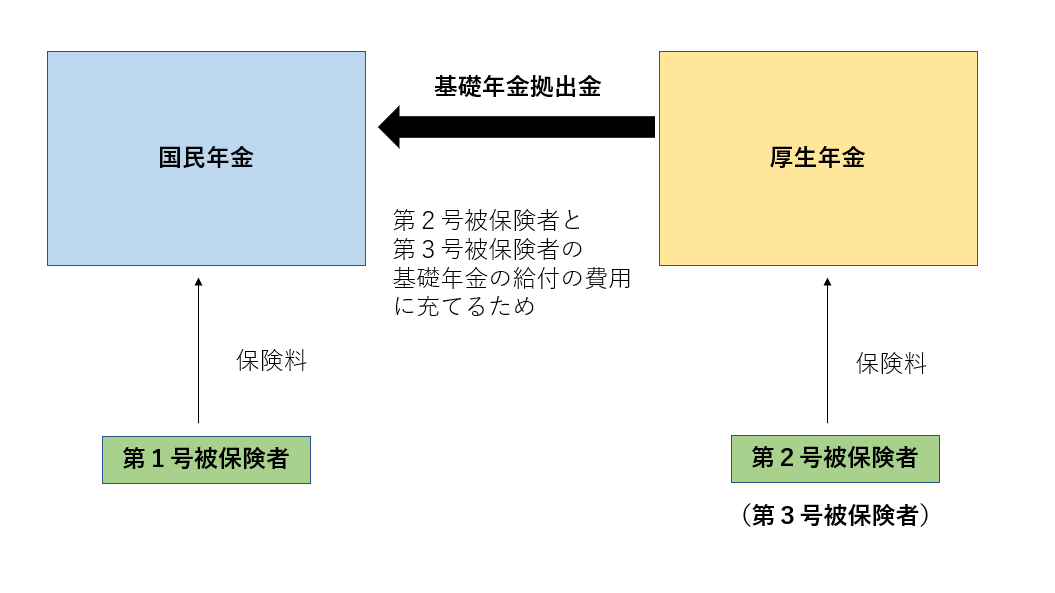
(年金)基準障害(前後の障害を併合して初めて障害等級に該当)
R3-120
R2.12.21 基準障害~初診日・保険料納付要件はどこでみる?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問3‐A>
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

【解答】 ×
「基準傷病による障害基礎年金」は、「はじめて2級以上に該当したことによる障害基礎年金」とも言われます。
既に先発の傷病による障害(単独では2級に満たない)があったところに、新たに傷病(基準傷病)が発生し、先発障害と基準障害を併合して初めて1・2級に該当した場合の規定です。
基準傷病(基準障害)は、後から新しく発生した傷病で、1・2級に該当するきっかけになる傷病のことです。
「初診日要件」と「保険料納付要件」は、「基準傷病」で判断するのがポイントです。
問題文の場合、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合でも、基準傷病に係る初診日に被保険者であれば初診日要件を満たします。
こちらもどうぞ!
 <H18年出題>
<H18年出題>
既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
 <H29年出題>
<H29年出題>
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
 <H20年出題>
<H20年出題>
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】
 <H18年出題> 〇
<H18年出題> 〇
令和2年の出題と同じ趣旨です。
「初診日要件」と「保険料納付要件」は、「基準傷病」で判断するのがポイントです。
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
請求は、65歳に達した日以後でもできます。
 <H20年出題> ×
<H20年出題> ×
基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件(基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当)に該当すれば受給権が発生します。
65歳に達した日以後でも請求できますが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月からではなく、「請求があった月の翌月」から開始されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)老齢基礎年金の受給資格
R3-119
R2.12.20 厚年第3種被保険者の被保険者期間の特例
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問9‐D>
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】 ×
老齢基礎年金の受給資格を満たしているので、65歳以上の特例の任意加入被保険者になることはできません。
★ 厚生年金保険の第3種被保険者とは、「坑内員・船員」である被保険者のことです。過酷な労働だったため、受給資格期間を計算する際の特例が設けられています。
| 昭和61年3月まで | 平成3年3月まで | 平成3年4月以降 |
| 3分の4倍 | 5分の6倍 | 実期間 |
問題文の場合、平成3年3月までの実期間が72月、平成3年4月以降が36月。72月は5分の6倍で計算しますので、老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たします。
そのため、65歳以上の特例による任意加入はできません。
こちらもどうぞ!
<厚年 H25年選択>
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から< A >4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に< B >を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【解答】
A 平成3年
B 5分の6
社労士受験のあれこれ
(年金)厚生年金・加給の対象
R3-118
R2.12.19 (厚年)老齢・障害・遺族の加給対象者
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐E>
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,700円に、3人目以降の子については1人につき74,900円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)である。

【解答】 〇
老齢厚生年金の加給年金額の対象は、「配偶者」「子」です。
こちらもどうぞ!
 <H29年出題>
<H29年出題>
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
 <R1年出題>
<R1年出題>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その妻の有する遺族厚生年金に当該子の加給年金額が加算される。

【解答】
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
1級又は2級の障害厚生年金の加給年金額の対象は「配偶者」のみで、「子」は対象になっていません。
※「子」は、障害基礎年金の方で加算対象となります。
 <R1年出題> ×
<R1年出題> ×
遺族厚生年金には加給年金額はありません。
【厚生年金加給年金額の対象者】
| 配偶者 | 子 | |
| 老齢厚生年金(原則240月以上) | 〇 | 〇 |
| 障害厚生年金(1級・2級) | 〇 | なし |
| 遺族厚生年金 | なし | なし |
社労士受験のあれこれ
(年金)遺族厚生年金の保険料納付要件
R3-117
R2.12.18 遺族厚生年金・保険料納付要件が必要なパターンは?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問10‐ア>
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。

【解答】 〇
★この問題のポイント!
死亡した者が保険料納付要件を満たしていることが条件であること。
<保険料納付要件>
・ 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
・ 死亡日が令和8年4月1日前の場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がないこと(死亡日が65歳未満であること)
ちなみに、遺族厚生年金には死亡した人の要件が4つありますが、保険料納付要件が必要なのはその中の2つです。(後で書きます。)
こちらもどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。
 <H23年出題>
<H23年出題>
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。

【解答】
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、死亡した者の保険料納付要件は問われません。(障害厚生年金を受給する際に、既に保険料納付要件を満たしているので)
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
遺族厚生年金の死亡した者の要件に、「3級の障害厚生年金の受給権者」は入っていません。1級・2級とは違います。
3級の障害厚生年金の受給権者だからという理由で、保険料納付要件が問われない、ということはありません。
では、こちらで選択の練習をどうぞ!
<遺族厚生年金 死亡した者の要件>
① 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
② 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に < A >がある傷病により当該< A >から起算して< B >を経過する日前に死亡したとき。
③ 障害等級の< C >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
④ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< D >以上である者が、死亡したとき。

【解答】
A 初診日
B 5年
C 1級又は2級
D 25年
上記①~④のうち、保険料納付要件が問われるのは①(在職中の死亡)と②(初診日から5年以内の死亡)です。
③(1,2級の障害厚生年金の受給権者)と④(25年満たしている)は保険料納付要件は問われません。
社労士受験のあれこれ
(年金)国年保険料の前納
R3-116
R2.12.17 一部免除の保険料は前納できる?できない?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問2‐D>
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

【解答】 ×
一部免除の保険料も、前納は適用されます。
こちらもどうぞ!
<H30年出題>
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】 ×
「各月の初日が到来」が×です。
前納に係る期間の「各月が経過した」際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
もともと、国民年金の保険料は、翌月末日が納期限(後払い)であることを思えば、納得だと思います。
では、こちらで横断の練習をどうぞ!
【国民年金】 保険料の前納
前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の< A >した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【健康保険】 任意継続被保険者の保険料の前納
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
前納された保険料については、前納に係る期間の< B >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
A 各月が経過
B 各月の初日
※健康保険の任意継続被保険者の保険料は、通常は「当月10日」が納期限です。それをヒントに考えるといいと思います。
社労士受験のあれこれ
(年金)振替加算の生計維持の認定
R3-115
R2.12.16 振替加算の加算事由と生計維持の認定
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問7‐B>
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

【解答】 〇
例えば、妻(振替加算の対象)が65歳になった後に、夫が240月(原則)以上で計算された老齢厚生年金を受けられるようになった場合は、そこで、生計維持関係を確認することになります。
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】 〇
問題文の場合、退職時改定によって加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たすことになりますが、妻が既に66歳になっていますので加給年金額は加算されません。
夫の厚生年金保険の資格喪失日から妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
その際、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することが必要です。(身分関係や生計維持関係の確認のためです)
社労士受験のあれこれ
(年金)保険料全額免除期間の定義
R3-114
R2.12.15 保険料全額免除期間に入るもの、入らないもの
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問5‐B>
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

【解答】 ×
「産前産後期間の保険料免除」は全額免除期間には入りません。
※ 「産前産後期間の保険料免除」は保険料納付済期間に入ります。
こちらもどうぞ!
 <H24年出題>
<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
 <令和元年出題>
<令和元年出題>
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。

【解答】
 <H24年出題> 〇
<H24年出題> 〇
保険料の全額免除を受けたとしても、「追納」で保険料を納付した場合は、保険料納付済期間となります。
ちなみに、「追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたもの」とみなされます。追納した日に、その月分が保険料免除期間から保険料納付済期間に変わるイメージで。
 <令和元年出題> ×
<令和元年出題> ×
産前産後期間の免除の期間
| 免除の届出をした後に出産した場合 | 出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで ※多胎妊娠の場合 出産予定月の3か月前~出産予定月の翌々月まで |
| 免除の届出を行う前に出産した場合 | 出産月の前月~出産月の翌々月まで ※多胎妊娠の場合 出産月の3か月前~出産月の翌々月まで |
問題文の場合、保険料免除の届出をした後の出産ですので、「出産予定日」を基準にします。免除期間は、出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで。令和元年9月分から令和元年12月分となります。
なお、免除期間は4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)です。
届け出後の出産は「出産予定日」、届け出前の出産は「出産日」が基準です。
社労士受験のあれこれ
(年金)任意加入被保険者と国民年金基金
R3-113
R2.12.14 任意加入被保険者は国民年金基金に加入できる?できない?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問2‐C>
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

【解答】 〇
任意加入被保険者のうち、国民年金基金に加入できるのは、
・ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
・ 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
の2つです。
→ ちなみに、
「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」、65歳以上70歳未満の「特例による任意加入被保険者」は基金に加入できませんので注意しましょう。
こちらもどうぞ!
 <H29年出題>
<H29年出題>
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
 <H29年出題>
<H29年出題>
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
 <H27年出題>
<H27年出題>
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員になることができます。(令和2年の問題と同じ)
 <H29年出題> 〇
<H29年出題> 〇
農業者年金の被保険者は基金に加入できません。翌日ではなく「その日」に、加入員の資格を喪失することにも注意してください。
 <H27年出題> 〇
<H27年出題> 〇
喪失日の「その月の初日」にも気を付けてください。
社労士受験のあれこれ
(年金)障害厚生年金の支給要件
R3-112
R2.12.13 障害厚生年金・初診日要件
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問4‐E>
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

【解答】 ×
障害厚生年金の要件は、「初診日に厚生年金保険の被保険者」であることです。
問題文の場合は初診日に「国民年金第1号被保険者」ですので、障害厚生年金は受給できません。
こちらもどうぞ!
<H26年出題>
厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

【解答】 〇
初診日に「厚生年金保険の被保険者」ですので、障害厚生年金を受給することができます。
社労士受験のあれこれ
(年金)国民年金の時効
R3-111
R2.12.12 国年時効の起算日は?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問7‐D>
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】 〇
※年金の支分権の時効についての問題です。
■年金には、
・基本権 → 年金を受ける権利
・支分権 → 支払い期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利
の2つがあり、支分権の時効の起算日は、年金の支払期月の翌月の初日です。
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】 ×
★ 「年金」と「保険料、死亡一時金」の時効の違いに注意しましょう。
| 年金給付を受ける権利 | その支給すべき事由が生じた日から5年 |
・保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 ・死亡一時金を受ける権利 | これらを行使することができる時から2年 |
穴埋めで練習しましょう!
年金給付を受ける権利は、< A >から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する< B >から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び< C >を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
A その支給すべき事由が生じた日
B 支払期月の翌月の初日
C 死亡一時金
社労士受験のあれこれ
(年金)3級の障害厚生年金のこと
R3-110
R2.12.11 3級の障害厚生年金のポイントは?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問4‐D>
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】 ×
3級の障害厚生年金の最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3です。
★なお、「障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されない」の部分は「〇」です。(1級・2級の障害厚生年金には配偶者加給年金額が加算されます。)
また、3級の場合は、1階部分の障害基礎年金は支給されません。
ちなみに・・・
3級の障害厚生年金に最低保障額が設定されているのは、障害基礎年金が無いからです。でも、1級・2級でも障害基礎年金が支給されない場合があり、その場合は、1級・2級でも最低保障額が適用されます。
★では、1級・2級で障害基礎年金が支給されない場合とは?
初診日に「厚生年金保険の被保険者」ではあるが、「国民年金第2号被保険者ではない」場合です。
★具体的には、65歳以上で老齢基礎年金等の受給権を有する者です。
65歳以降、在職中(厚生年金保険に加入中)に障害になった場合、初診日に厚生年金保険の被保険者であるものの、老齢基礎年金等の受給権がある場合は国民年金の第2号被保険者ではありません。そのため、障害厚生年金は支給されますが、障害基礎年金は支給されません。
このような場合は、1級・2級であっても、3級の障害厚生年金の最低保障額と同額が保障されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)代表取締役の被保険者資格
R3-109
R2.12.10 代表取締役は厚生年金保険の被保険者となる?ならない?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問6‐E>
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。

【解答】 ×
★ 代表取締役も被保険者となります。
法人の理事、監事、取締役等法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は被保険者になります。
ちなみに、事業主1人で経営している法人は、強制適用事業所となります。
また、個人事業主は、個人事業主本人が事業主体となるので、厚生年金保険の被保険者にはなりません。
では、こちらもどうぞ!(健康保険法の問題です)
 健保 H22年出題
健保 H22年出題
法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
 健保 H29年出題
健保 H29年出題
従業員が3人の任意適用事業所で従業員と同じような仕事に従事している個人事業所の事業主は、健康保険の被保険者となることができる。

【解答】
 健保 H22年出題 ×
健保 H22年出題 ×
法人役員は、法人(事業主)から、労務の対償として報酬を受けている者として、被保険者の資格を取得します。(厚生年金保険と同じです。)
 健保 H29年出題 ×
健保 H29年出題 ×
個人事業所の事業主は、本人が事業主なので、被保険者となることはできません。(こちらも厚生年金保険と同じです。)
では、次は「雇用保険法」の問題をどうぞ!
 雇用保険 H30年出題
雇用保険 H30年出題
株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。
 雇用保険 H24年出題
雇用保険 H24年出題
株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

【解答】
 雇用保険 H30年出題 〇
雇用保険 H30年出題 〇
なお、問題文のような人が失業した場合は基本手当を受けることができますが、基本手当の基になる賃金には、取締役としての地位に基づく役員報酬は含まれません。あくまでも労働の対償としての賃金で計算されます。
 雇用保険 H24年出題 〇
雇用保険 H24年出題 〇
株式会社の代表取締役は、雇用関係にないので、失業することも考えられませんよね。株式会社の代表取締役は被保険者になることはありません。
社労士受験のあれこれ
(年金)失踪宣告と生計維持
R3-108
R2.12.9 失踪宣告を受けた場合の生計維持関係はどの時点でみる?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐C>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】 〇
★ 行方不明となった人の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所は失踪宣告をすることができ、行方不明から7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。
遺族厚生年金等については、「行方不明となった日」を「死亡日」として取り扱い、生計維持関係や保険料納付要件等をみることになります。
ただし、遺族厚生年金等の受給権は、失踪宣告が確定した日に発生し、受給権者の身分関係、年齢、障害状態は、失踪宣告による死亡日(7年後)で判断します。
この問題は、「生計維持に係る要件」についてですので、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われます。
では、こちらもどうぞ!
 国年 H18年出題
国年 H18年出題
失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。
 国年 H26年出題
国年 H26年出題
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
 国年 R2出題
国年 R2出題
失踪の宣告を受けたことにより死亡とみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

【解答】
 国年 H18年出題 ×
国年 H18年出題 ×
「5年」ではなく、7年を経過した日に死亡したものとみなされます。
 国年 H26年出題 〇
国年 H26年出題 〇
・ 生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件 → 行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
・ 受給権者の身分関係、年齢、障害状態 → 失踪宣告による死亡日(7年後)で判断
 国年 R2出題 ×
国年 R2出題 ×
保険料納付要件は、「死亡日の前日」で判断します。失踪宣告の場合は、「行方不明となった日」を「死亡日」としますので、保険料納付要件は「行方不明となった日の前日」で判断することになります。
社労士受験のあれこれ
(年金)遺族厚生年金の失権の届出
R3-107
R2.12.8 遺族厚生年金の失権事由と届出の関係
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐A>
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 〇
この問題のポイントは、「失権の届出が必要なとき、不要なときを区別すること」です。
★「子、孫」特有の遺族厚生年金の失権事由は3つありますが、届出が必要なのは②のみです。
①と③は「年齢」による失権です。年齢は日本年金機構で把握できるので、届出は要りません。
一方、②については「障害の事情がやんだ」事実は把握できていませんので、届出が必要なのです。今回の問題は②に該当します。
「子、孫」特有の遺族厚生年金の失権事由と失権届
| 「子、孫」の失権事由 | 失権届 | |
| ① | 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 (ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。) | 不要 |
| ② | 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。 (ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 | 要 |
| ③ | 子又は孫が、20歳に達したとき。 | 不要 |
では、こちらもどうぞ!
<H23年出題>
遺族厚生年金の受給権者が子(障害等級に該当しないものに限る。)であるとき、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了して受給権を失権したときは、10日以内に失権の届書を日本年金機構に提出しなくてはならない。

【解答】 ×
上の表の①に該当します。年齢に達したことにより失権ですので、届書の提出は不要です。
もう1問どうぞ!
<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
「年齢」に達したことによる不該当の届書の提出は不要です。
★ 加給年金額対象者が要件に該当しなくなった場合は、老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額対象者不該当の届出を10日以内に提出しなければなりません。
ただし、対象者が「年齢」に達したことにより不該当になった場合は、届書の提出は不要です。
届書が不要になるのは次の3つです。
・ 配偶者が、65歳に達したとき。
・ 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
・ 子が、20歳に達したとき。
社労士受験のあれこれ
(年金)老齢基礎年金繰下げの増額率
R3-106
R2.12.7 繰下げ増額率の計算式
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問10‐ア>
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.9%を乗じて得た額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。

【解答】 ×
増額率は、25.2%(1,000分の7×36月)です。
■ 老齢基礎年金の繰下げについては、繰下げた月数分、老齢基礎年金が増額されます。月数は、「受給権取得月~繰下げの申出をした日の属する月の前月まで」です。
■ 問題文の場合、65歳に到達した平成29年4月に受給権を取得し、令和2年4月に繰下げの申出を行っていますので、平成29年4月から令和2年3月までの月数である36月で増額率を出します。
■ 付加年金は老齢基礎年金と一心同体なので、増額率、支給開始月ともに老齢基礎年金と同じです。
では、こちらもどうぞ!
 空欄を埋めてください
空欄を埋めてください
昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は< A >に当該年金の受給権を取得した日の< B >から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の< C >までの月数(当該月数が< D >を超えるときは、< D >)を乗じて得た率をいう。
 <H22年出題>
<H22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。
 <H29年出題>
<H29年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

【解答】 〇

A 1,000分の7
B 属する月
C 属する月の前月
D 60
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
申出を行った日の属する月ではなく、申出を行った日の属する月の前月までの月数です。
 <H29年出題> 〇
<H29年出題> 〇
ポイント!
老齢基礎年金を繰下げた場合、付加年金についても繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
もう一つ。繰上げの場合も同様です。老齢基礎年金を繰り上げた場合、付加年金も繰り上げられ老齢基礎年金と同じ率で減額されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)障害の程度が変わった場合の年金額の改定
R3-105
R2.12.6 障害が増進したことによる改定請求
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問1‐エ>
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】 〇
障害基礎年金については、障害の程度(障害等級)に変更があった場合、額の改定が行われます。
厚生労働大臣の職権による改定と、障害の程度が増進したことによる受給権者からの改定請求による方法がありますが、今回の出題は、受給権者からの改定請求についてです。
短期間のうちに、何回も「障害の程度が変わった」という請求を避けるため、原則として、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年待たなければ、額の改定請求はできません。
ただし、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」は、1年経過しなくても請求することができます。
「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については、厚生労働省令で具体的に定められていて、問題文の「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着」するに至ったこともその一つです。
つまり、人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合は、受給権取日から1年経過していなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求ができます。
では、こちらもどうぞ!
★空欄を埋めてください。
【障害の程度が変わった場合の年金額の改定】
1 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が< A >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 2の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が< A >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して < B >でなければ行うことができない。

【解答】 〇
A 増進
B 1年を経過した日後
社労士受験のあれこれ
(年金)障害の程度の審査のための診断書
R3-104
R2.12.5 障害基礎年金・障害の現状に関する届出
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問6‐C>
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の状況に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
障害状態確認届(診断書)の作成期間は、指定日前1か月以内から、令和元年8月から「指定日前3か月以内」に拡大されています。
★「障害状態確認届」とは → 厚生労働大臣が指定した年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するためのもの
では、こちらもどうぞ!
<厚生年金保険 障害の現状に関する届出 (参考)H21年出題>
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の額の全部につき支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 〇
国民年金同様、厚生年金保険も「3か月」です。
また、全部につき支給停止されている場合は、診断書の提出は不要です。(国年も同様)
社労士受験のあれこれ
(年金)「生計維持」の認定
R3-103
R2.12.4 生計維持要件850万円について
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問1‐ウ>
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。

【解答】 ×
定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)の収入が年額850万円未満(又は所得が年額655.5万円未満)となると認められるときは、収入の認定要件に該当します。
★『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕』より
■生計維持認定対象者は?
| 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
|---|---|
| 老齢基礎年金の振替加算等の対象者 | 老齢厚生年金の加給年金額の対象の配偶者及び子 |
| 障害基礎年金の加算額の対象の子 | 障害厚生年金の加給年金額の対象の配偶者 |
| 遺族基礎年金の受給権者 | 遺族厚生年金の受給権者 |
| 寡婦年金の受給権者 |
■収入に関する認定要件は、「厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外」とされています。
■具体的には、
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
※障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者の場合は、「エ」が「ア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。」となります。
では、こちらもどうぞ!
 <厚生年金 H18年出題>
<厚生年金 H18年出題>
老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については、維持関係があるとは認定されない。
 <厚生年金 H27年出題>
<厚生年金 H27年出題>
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

【解答】
 <厚生年金 H18年出題> ×
<厚生年金 H18年出題> ×
 <厚生年金 H27年出題> ×
<厚生年金 H27年出題> ×
生計維持の要件は、「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者」とされています。
前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が年額850万円未満(前年の所得(前年の所得が確定しない場合は前々年の所得)が年額655.5万円未満)でなかったとしても、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められれば、認定要件に該当します。
社労士受験のあれこれ
(社一)船員保険法の一般保険料率
R3-102
R2.12.3 船員保険の一般保険料率は、疾病保険料率+災害保健福祉保険料率
令和2年の問題をどうぞ!
<問10‐C>
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合計した率を乗じて算定される。

【解答】 ×
「後期高齢者医療制度」の被保険者であることがポイントです。後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、災害保健福祉保険料率のみで、疾病保険料率は合算されません。
<船員保険法の「一般保険料率」について>
■ 船員保険一般保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて計算します。
■ 一般保険料率とは、「疾病保険料率」と「災害保健福祉保険料率」の合計です。
・一般保険料率 → 職務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産に関する保険給付等に充てる(健康保険の保険給付に相当する部分)
・災害保健福祉保険料率 → 職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷に関する給付に充てる(労災保険の上乗せの部分)
■ 後期高齢者医療制度の被保険者の場合、業務外の疾病等の「医療」については後期高齢者医療制度の対象になるため、船員保険では行いません。そのため保険料についても、疾病保険料率はかけずに、災害保健福祉保険料率のみで算定します。
では、こちらもどうぞ!
 <H30年出題その1>
<H30年出題その1>
一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。
 <H30年出題その2>
<H30年出題その2>
疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとされている。
 <H30年出題その3>
<H30年出題その3>
災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、協会が決定するものとされている。

【解答】
 <H30年出題その1> ×
<H30年出題その1> ×
一般保険料率の内訳は、疾病保険料率+災害保健福祉保険料率です。一般保険料率に介護保険料率は含まれていません。
(介護保険第2号被保険者の場合は、一般保険料額と介護保険料額を合算した額が保険料になります。)
なお、後半の「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者は、災害保健福祉保険料率のみ」の部分は令和2年の問題と同じ主旨ですので後半は「〇」です。
 <H30年出題その2> ×
<H30年出題その2> ×
疾病保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内です。
 <H30年出題その3> ×
<H30年出題その3> ×
災害保健福祉保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内です。
社労士受験のあれこれ
(労一)平成30年労働安全衛生調査より
R3-101
R2.12.2 産業医を選任している事業所の割合
令和2年の問題をどうぞ!
<問2‐B>
産業医を選任している事業所の割合は約3割となっており、産業医の選任義務がある事業所規模50人以上でみると、ほぼ100%となっている。

【解答】 ×
産業医を選任している事業所の割合は29.3%です。約3割なので、前半は〇です。
また、産業医の選任義務がある事業所規模 50人以上でみると、84.6%ですので、後半の「ほぼ100%」が×です。
では、こちらもどうぞ!
産業医に提供している労働者に関する情報(複数回答)をみると、 「< A >」が 74.6%と最も多くなっている。
<選択肢>
①労働者の業務に関する情報で、産業医が必要と認めるもの
②健康診断等の結果を踏まえた就業上の措置の内容等

【解答】
A ②健康診断等の結果を踏まえた就業上の措置の内容等
社労士受験のあれこれ
(厚年)脱退一時金の請求条件
R3-100
R2.12.1 脱退一時金と障害の年金との関係
令和2年の問題をどうぞ!
<問9‐E>
障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

【解答】 ×
脱退一時金は、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは支給されません。
問題文のように、現在は障害の状態が軽減していたとしても、受給権を有したことがあれば支給されません。
なお、脱退一時金とは、外国人が対象です。日本で、年金に結び付かない短い期間、厚生年金保険料を納付した外国人が帰国する際に請求できます。
こちらもどうぞ!
※国民年金法の過去問です!
 <国年 H24年出題>
<国年 H24年出題>
脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。
 <国年 H30年出題>
<国年 H30年出題>
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

【解答】
 <国年 H24年出題> 〇
<国年 H24年出題> 〇
厚生年金保険法と同じです。障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されません。
 <国年 H30年出題> ×
<国年 H30年出題> ×
厚生年金保険法と同じです。障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されません。現在、障害基礎年金の支給を停止されてても、脱退一時金は請求できません。
社労士受験のあれこれ
(国年)任意加入被保険者の申出
R3-099
R2.11.30 国年/任意加入被保険者の要件
令和2年の問題をどうぞ!
<問9‐B>
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】 ×
日本国籍を有していれば、日本国内に住所を有していなくても任意加入できます。
任意加入被保険者の申出ができる要件は次の通りです。
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
※ただし、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当する場合は、任意加入できません。
問題文の場合は、③に当てはめて考えてみてください。
なお、老齢基礎年金を増やすことは「任意加入」の目的の一つです。
問題文のように特別支給の老齢厚生年金を受給していても、老齢基礎年金を満額にするために65歳まで任意加入することは可能です。
ちなみに、65歳以上70歳未満の「特例」の任意加入被保険者の場合は、老齢基礎年金を増やす目的では任意加入できません。受給資格期間を満たせない人だけを対象にしています。
こちらもどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
 <H27年出題>
<H27年出題>
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

【解答】
 <H25年出題> ×
<H25年出題> ×
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、国籍問わず、任意加入できます。
 <H27年出題> ×
<H27年出題> ×
65歳以上70歳未満を対象とする特例による任意加入被保険者の条件のポイントは、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない」ことと、「昭和40年4月1日以前生まれ」であることです。
問題文の「昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り」が間違いです。
社労士受験のあれこれ
(健保)高額介護合算療養費
R3-098
R2.11.29 高額介護合算療養費・計算期間途中に保険者が変更した
令和2年の問題をどうぞ!
<問2‐B>
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

【解答】 〇
高額介護合算療養費の計算期間の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前と変更後の自己負担額は合算されます。
★高額介護合算療養費とは?
計算期間(毎年8月~1年間)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計した額が、自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。
こちらもどうぞ!
 <H28年出題>
<H28年出題>
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
 <H25選択>
<H25選択>
高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は< A >円である。
70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は
< B >円である。

【解答】
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
70歳未満の場合、高額療養費と同様に、21,000円未満のものは算定対象から除かれます。
 <H25選択>
<H25選択>
A 500
B 670,000
Aについて → 高額介護合算療養費は、自己負担合算額が介護合算算定基準額を超えた場合に支給されますが、支給基準額(500円)を超えない場合は、支給されません。
社労士受験のあれこれ
(徴収法)継続事業の概算保険料の延納
R3-097
R2.11.28 継続事業・年度途中で成立した場合の延納
令和2年の問題をどうぞ!
<問8‐A(雇)>
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。

【解答】 〇
年度途中で保険関係が成立した場合の延納についてはしっかり覚えましょう!
| 保険関係成立日 | 回数 | 最初の期 |
|---|---|---|
| 4月1日から5月31日 | 3回 | 保険関係成立日から7月31日まで |
| 6月1日から9月30日 | 2回 | 保険関係成立日から11月30日まで |
| 10月1日以降 | 延納不可 | 保険関係成立日から3月31日 |
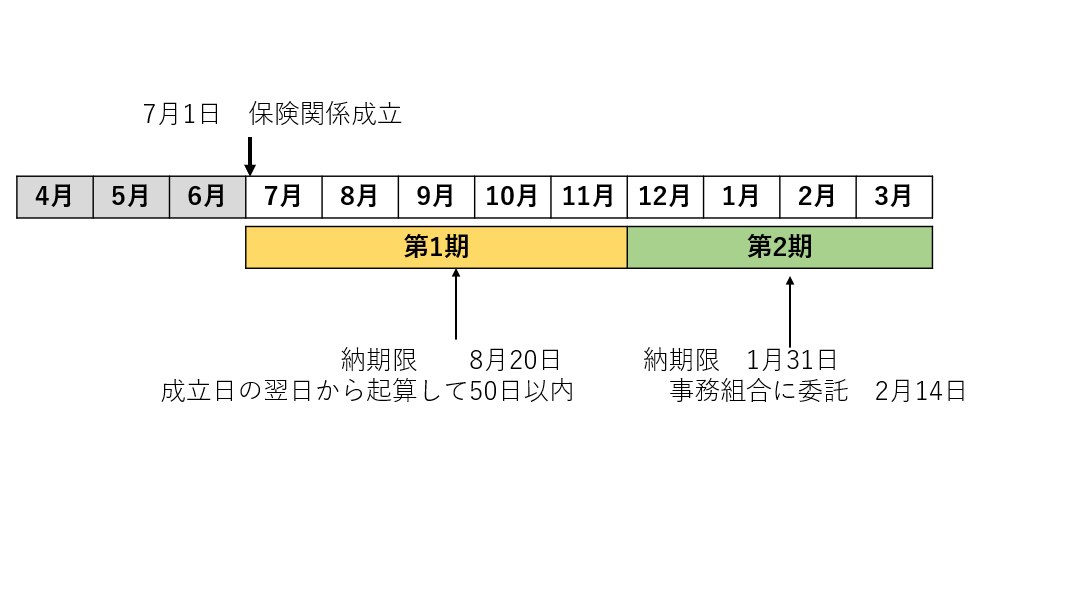
こちらの問題もどうぞ!
<H29年出題>
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

【解答】 〇
10月1日に保険関係が成立した場合は延納できませんので、3月31日までの分を1回で納付します。
納期限は、保険関係成立日の翌日(10月2日)から50日以内なので、11月20日となります。
社労士受験のあれこれ
(雇用保険)資格取得届と資格喪失届
R3-096
R2.11.27 資格取得と資格喪失・事実がないと認めるとき
令和2年の問題をどうぞ!
<問1‐B>
公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。

【解答】 ×
最後が誤り。「被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者」に対しても通知しなければなりません。
・資格取得届又は資格喪失届の提出があった
↓
・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるとき
↓
・公共職業安定所長は、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該該届出をした事業主に通知しなければならない。
本人にも会社にもその旨通知してください、ということです。
では、もう一問どうぞ!
<H20年出題>
厚生労働大臣は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者による請求がなくても、職権によって、労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認を行うことができる。

【解答】 〇
被保険者の資格取得と喪失は、厚生労働大臣の確認によって効力が生じます。
被保険者になったこと又は被保険者でなくなったことの事実、そしてそれがいつなのか?を厚生労働大臣が確認することによって、保険料を負担する義務や失業等給付を受ける権利が発生します。
確認の方法は3つです。
①第7条の規定による届出(資格取得届、資格喪失届
②被保険者又は被保険者であった者からの請求
③厚生労働大臣の職権
※厚生労働大臣の権限は公共職業安定所長に委任されています。
では、次はこちらを
<H29年出題>
公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。

【解答】 〇
<確認の通知の手順>
・被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をした
↓
・「確認に係る者」と「事業主」に通知しなければならない
※雇用保険被保険者資格取得確認通知書、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書で通知する
※確認に係る者への通知は事業主を通じて行うことができる
★「確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために通知をすることができない場合」が上記の問題です。
そのような場合は、公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければなりません。
社労士受験のあれこれ
労災「第三者行為災害の調整」
R3-095
R2.11.26 第三者行為災害・保険給付と特別支給金の違い
令和2年の問題をどうぞ!
<問7-C>
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。

【解答】 〇
第三者の損害賠償と労災保険の保険給付が二重にならないよう、損害賠償と保険給付の間で調整が行われます。
しかし、特別支給金の場合は、損害賠償との調整は行われず、損害賠償を受けていても特別支給金は支給されます。
特別支給金は社会復帰促進等事業として行われているからです。
特別支給金と保険給付とで違う点は意識していてくださいね。
では、もう一問どうぞ!
<R2年出題>
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。

【解答】〇
同一の事由で、労災保険法の保険給付と、社会保険(国民年金・厚生年金保険)の年金給付が支給される場合、労災保険の支給額が減額されることになっています。両方100%支給されると保障が過分になるからです。
ただし、減額されるのは保険給付で、特別支給金は減額されずに100%支給されます。
社労士受験のあれこれ
安衛「健康診断に出てくる数字」
R3-094
R2.11.25 健康診断・3月、6月、1年、3年、5年???
令和2年の問題をどうぞ!
<R年選択>
事業者は、労働者を本邦外の地域に< A >以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

【解答】
A 6月
関連問題をどうぞ!
 (雇入時の健康診断)
(雇入時の健康診断)
事業者は、< B >を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、< C >を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
 (特定業務従事者の健康診断)
(特定業務従事者の健康診断)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び< D >以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を行わなければならない。
 (健康診断結果の記録の作成)
(健康診断結果の記録の作成)
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を< E >保存しなければならない。

【解答】
B 常時使用する労働者
C 3月
D 6月
E 5年間
社労士受験のあれこれ
労基法「天災事変その他やむを得ない事由」とは?
R3-093
R2.11.24 「天災事変その他やむを得ない事由」に含まれる?
令和2年の問題をどうぞ!
<問5-エ>
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。

【解答】 ×
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度の不可抗力そして突発的な事由。経営者として如何ともなし難い状況。
「事業場が火災により焼失した場合」は、通常は「やむを得ない」事由となりますが、「事業主の故意又は重大な過失」による場合は除かれます。
問題文は、「使用者の重過失による火災」なので、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には含まれません。
ちなみに、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は第19条(解雇制限)の条文にも登場しますが、同じ解釈です。
では、関連問題をどうぞ!
<H23年出題>
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。

【解答】〇
行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要です。使用者の勝手な判断による濫用を防止するためです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(社一)
R3-092
R2.11.23 <R2出題>覚える「社労士違反するおそれがあると認めるとき」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問5-エ>
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

【解答】 ×
第25条の33(注意勧告)からの出題です。
「会則の定めにかかわらず」ではなく、「会則の定めるところにより」です。
穴埋めで確認しましょう!
第25条の33(注意勧告)
< A >は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に< B >があると認めるときは、< C >の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

【解答】
A 社会保険労務士会
B 違反するおそれ
C 会則
では、関連問題をどうぞ!
<R1年出題>
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】 ×
「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる」ではなく、「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(労一)
R3-091
R2.11.22 <R2出題>覚える「労働の実態~統計調査」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<R2年選択式>
我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには< A >、年次有給休暇の取得率を知るには< B >、男性の育児休業取得率を知るには< C >が使われている。

【解答】
A 雇用動向調査
B 就労条件総合調査
C 雇用均等基本調査
★雇用動向調査の目的
全国の主要産業の事業所の入職者数・離職者数、入職者・離職者の性・年 齢階級、離職理由等の状況を明らかにすること
★就労条件総合調査の目的
主要産業の企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業の就労条件の現状を明らかにすること
★雇用均等基本調査の目的
男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握し、雇用均等行政の成果測定や方向性の検討を行う上での基礎資料を得ること
では、練習問題をどうぞ!
 2019年(令和元年)雇用動向調査結果の概況より
2019年(令和元年)雇用動向調査結果の概況より
令和元年 1 年間の入職率と離職率を性、年齢階級別にみると、男女ともに入職率は < A >が他の年齢階級に比べて高くなっている。
【選択肢】 ①24 歳以下 ②60歳以上
 令和2年就労条件総合調査の概況より
令和2年就労条件総合調査の概況より
平成31年・令和元年(又は平成30会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は労働者1人平均18.0日、そのうち労働者が取得した日数は10.1日で、取得率は56.3%となっており、< B >となった。
【選択肢】
①取得日数は過去最少(昭和59年以降)、取得率は過去最低(昭和59年以降)
②取得日数は過去最多(昭和59年以降)、取得率は過去最高(昭和59年以降)
 「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要より
「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要より
平成29年10月1日から平成30年9月30 日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和元年10 月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を 含む。)の割合は< C > と、前回調査より 1.32 ポイント上昇した。
【選択肢】
①83.0%
②7.48%

【解答】
 2019年(令和元年)雇用動向調査結果の概況より
2019年(令和元年)雇用動向調査結果の概況より
A ①24 歳以下
参照:厚生労働省-2019 年(令和元年)雇用動向調査結果の概況-
 令和2年就労条件総合調査の概況より
令和2年就労条件総合調査の概況より
B ②取得日数は過去最多(昭和59年以降)、取得率は過去最高(昭和59年以降)
 「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要より
「令和元年度雇用均等基本調査」の結果概要より
C ②7.48%
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(厚年)
R3-090
R2.11.21 <R2出題>覚える「遺族厚生年金・受給権者の順位」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問2-E>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

【解答】 〇
まず、遺族の順位を確認しましょう。
ポイントは、①年金を受給できる順位が決まっていること、②先順位の人が受給権を得ると、後の人は遺族とならないこと
| 順位 | |
| 1 | 配偶者又は子 |
| 2 | 父母 (配偶者、子がいないとき) |
| 3 | 孫 (配偶者、子、父母がいないとき) |
| 4 | 祖父母 (配偶者、子、父母、孫がいないとき) |
例えば、被保険者の死亡の当時、生計維持関係のある配偶者又は子が無く、生計を維持されていた父がいた場合、父が遺族厚生年金の受給権者となります。
しかし、その後、被保険者の死亡の当時胎児であった子(第1順位)が出生した場合は、父の受給権は消滅します。
一方、被保険者の死亡の当時、生計維持関係のあった妻がいて、妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合、その後、被保険者の死亡の当時胎児であった子が出生しても、妻の受給権は消滅しません。(配偶者と子は同順位なので)
では、関連問題をどうぞ!
 H24年出題
H24年出題
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
 H27年出題
H27年出題
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

【解答】
 H24年出題 〇
H24年出題 〇
R2年の問題と同じ主旨です。子より後順位の父母、孫、祖父母と、子と同順位の妻との違いに注意してください。
 H27年出題 〇
H27年出題 〇
死亡の当時胎児であった子は、出生したときに、遺族となります。「将来に向かって」の部分がポイントです。死亡時にさかのぼるのではなく、出生したときから遺族となります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(国年)
R3-089
R2.11.20 <R2出題>覚える「第3号被保険者の届出」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問6-B>
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。

【解答】 ×
第3号被保険者は「厚生労働大臣」に届出なければなりません。
なお、第1号被保険者は「市町村長」に届出します。
では、関連問題をどうぞ!
 H20年出題
H20年出題
第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。
 R1年出題
R1年出題
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
 H23年出題
H23年出題
健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。

【解答】
 H20年出題 〇
H20年出題 〇
第3号被保険者の届出は、第2号被保険者を使用する事業主や共済組合等を経由して行います。
平成14年3月までは、第3号被保険者が自ら市町村長に届出をすることになっていましたが届け出漏れが多かったため、平成14年4月から事業主等を経由することになりました。
 R1年出題 〇
R1年出題 〇
第2号被保険者を使用する事業主(共済組合等)が届出を受理した=そのときに厚生労働大臣に届出があったとみなされます。
 H23年出題 ×
H23年出題 ×
健康保険組合に委託できるのは「一部」です。「全部」委託することはできません。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(健保)
R3-088
R2.11.19 <R2出題>覚える「4か月以内の季節的業務」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問5-ウ>
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

【解答】 ×
季節的業務の場合、業務の都合で4か月を超えて使用された場合でも、一般の被保険者にはなりません。
★ 季節的業務とは → 例えば、清酒の醸造、製茶、製氷など
季節的業務のポイント!
・当初から4か月を超える予定で使用された → 当初から一般被保険者になる
・当初は4か月以内の予定 → 業務の都合でたまたま4か月を超えた場合でも → 一般の被保険者にならない。
では、関連問題をどうぞ!
<H19年出題>
臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。

【解答】 〇
2か月以内の雇用契約で使用される場合は、一般被保険者にはならず、原則として日雇特例被保険者となります。
ただし、所定の期間(当初の契約期間=問題文の場合は5週間)を超えて引き続き使用されるようになった場合は、そのときから一般被保険者となります。
では、選択式の練習をどうぞ!
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 < A >の被保険者(< A >法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては < B >を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ < C >以内の期間を定めて使用される者
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して< D >を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者等
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)

【解答】
A 船員保険
B 1月
C 2月
D 6月
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(徴収法)
R3-087
R2.11.18 <R2出題>覚える「日雇労働被保険者手帳」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問9-C(雇)>
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。

【解答】 ×
★ 「日雇労働被保険者手帳」によって、印紙保険料の納付や日雇労働求職者給付金の支給などが行われます。日雇労働被保険者手帳は被保険者のみならず事業主や政府にとっても重要です。
徴収法第23条では、「事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。」と規定されています。
問題文は、「使用期間が終了するまで返還してはならない。」が誤りで、請求があったときは、これを返還しなければなりません。事業主が被保険者手帳の返還を拒否することは、職業選択の自由の阻害につながるからです。
では、関連問題をどうぞ!
<H24年出題(雇用保険)>
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。

【解答】 ×
「追徴金を徴収されることはない」が誤りで、追徴金を徴収されることもあります。
★ 日雇労働被保険者を使用する場合、事業主には日雇労働被保険者手帳を提出させる義務があります。(徴収法第23条)
追徴金は、正当な理由があると認められるときは徴収されませんが、問題文のように「事業主が日雇労働被保険者手帳の提出を求めなかった → 日雇労働被保険者が手帳を提出しなかった → 雇用保険印紙の貼付がなされなかった」場合は正当な理由にならないので、追徴金の対象となります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(雇用保険)
R3-086
R2.11.17 <R2出題>覚える「個別延長給付の対象者」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問3-B>
特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当しない受給資格者は、個別延長給付を受けることができない。

【解答】 〇
★個別延長給付の対象になるのは、特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者です。
それぞれ要件がありますので、確認しましょう。
●「特定受給資格者」 又は 「特定理由離職者※ 」
・次 のア~ウのいずれかに該当すること
ア 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
イ 雇用されていた適用事業が激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって 、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
ウ 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者(イに該当する者を除く。)
・かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること
●就職困難者である受給資格者
上記イに該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること
※個別延長給付の対象になる特定理由離職者は、「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」に限られます。
では、令和2年度の問題よりもう一問どうぞ!
<問3-C>
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。

【解答】 ×
1.5倍ではなく2倍です。
最後に「全国延長給付」の過去問をどうぞ!
<H25年出題>
全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。

【解答】 ×
要件は、「100分の4」を超えることです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(労災)
R3-085
R2.11.16 <R2出題>覚える「労災・給付制限」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
 <問1-B>
<問1-B>
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
 <問1-C>
<問1-C>
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
 <問1-B> ×
<問1-B> ×
負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
「行わないとすることはできない」が誤りです。
 <問1-C> 〇
<問1-C> 〇
保険給付の全部又は一部を行わないことができるのは、単なる過失ではなく「重大な過失」による場合です。
では、選択練習問題をどうぞ!
① 労働者が、< A >に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは< C >により、又は正当な理由がなくて< D >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
A 故意
B 直接の原因
C 重大な過失
D 療養に関する指示
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(安衛)
R3-084
R2.11.15 <R2出題>覚える「総括安全衛生管理者の要件」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問9-C>
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。

【解答】 〇
総括安全衛生管理者は、事業場の労働者のトップが選任されるイメージです。仕事は事業場の統括管理が仕事なので、一般的に工場長や部長などが該当します。
問題文にあるように、安全管理者の資格及び衛生管理者の資格などは要りません。
では、こちらもどうぞ!
 H19年出題①
H19年出題①
総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しなければならない。
 H19年出題②
H19年出題②
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。

【解答】
 H19年出題① ×
H19年出題① ×
総括安全衛生管理者は、問題文のような要件はありません。総括安全衛生管理者は、統括管理する者(権限や責任がある人)を充てます。
 H19年出題② ×
H19年出題② ×
「これに準ずる者」は総括安全衛生管理者として選任できません。
では、選択練習問題をどうぞ!
(総括安全衛生管理者)
1. 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、 次の業務を< A >させなければならない。
① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
2. 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を< A >する者をもって充てなければならない。
3. < B >は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に< C >することができる。

【解答】
A 統括管理
B 都道府県労働局長
C 勧告
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(労基)
R3-083
R2.11.14 <R2出題>覚える「危険有害業務の就業制限」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問3-A>
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

【解答】 〇
★女性を「妊婦」「産婦」「その他の女性」の3つにグループ分けしています。
妊産婦については、母性保護のため、その妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならないとされています。
また、妊産婦以外のその他の女性も妊娠、出産機能に有害な業務の就業が制限されています。
★ 妊産婦等の就業制限の業務として24業務が規定されています。
妊婦 → 24のすべての業務に「就かせてはならない」
産婦 → 「就かせてはならない」業務が3、「申し出た場合就かせてはならない」業務が19、「就かせても差し支えない」業務が2
その他の女性 → 「重量物を取り扱う業務」、「有害物を発散する場所における業務」の2つについては「就かせてはならない」、それ以外の22の業務は「就かせても差し支えない」
★すべての女性の就業が禁止される「重量物を取り扱う業務」、「有害物を発散する場所における業務」の2つは覚えておきましょう。
では、こちらも
<問3-B>
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

【解答】 ×
「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」は、「妊婦」と「産婦」は就かせてはならない業務ですが、その他の女性は「就かせても差し支えない業務です。
では、選択練習問題をどうぞ!
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3
① 使用者は、< A >を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

【解答】
A 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(社一)
R3-082
R2.11.13 <R2出題>問題の意図「後期高齢者医療の自己負担」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問10-D>
単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定額以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。

【解答】 ×
★後期高齢者医療の自己負担割合は原則として1割ですが、現役並所得者は3割です。
この問題の意図は、「被保険者による申請」が要るか要らないか?です。
対象となる市町村課税標準額が145万円以上の場合は、現役並所得者として、自己負担割合が3割となります。
ただし、市町村課税標準額が145万円以上でも、収入が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、1割負担となります。この場合は申請が必要です。→ここがこの問題のポイントです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(労一)
R3-081
R2.11.12 <R2出題>問題の意図「ロックアウトの正当性」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問4-E>
いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)は、個々の具体的な労働争議における労使間の交渉態度、経過、組合側の争議行為の態様、それによって使用者側の受ける打撃の程度等に関する具体的諸事情に照らし、衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当と認められる場合には、使用者の正当な争議行為として是認され、使用者は、いわゆるロックアウト(作業所閉鎖)が正当な争議行為として是認される場合には、その期間中における対象労働者に対する個別的労働契約上の賃金支払義務を免れるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】 〇
★「ロックアウト(作業所閉鎖)」とは、使用者側の争議対抗手段のひとつです。
「水島水門事件」からの出題です。ポイントは、「衡平の見地から見て労働者側の争議行為に対する対抗防衛手段として相当」と認められる → 「その期間中の賃金支払義務を免れる」の部分です。
「労働関係調整法」より
空欄を埋めてください。
■労働関係調整法
第6条
この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために< A >が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。
第7条
この法律において< A >とは、同盟罷業、怠業、< B >その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいう。

【解答】
A 争議行為
B 作業所閉鎖
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(厚年)
R3-080
R2.11.11 <R2出題>問題の意図「特支の老厚/1年要件」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問10-イ>
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第1号厚生年金被保険者期間が9か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。

【解答】 〇
問題の意図は、特別支給の老齢厚生年金の支給要件の「1年以上の被保険者期間」は、異なる種別でも合算できる?です。
 厚生年金保険の被保険者には、第1号から第4号まで4つの種別があります。
厚生年金保険の被保険者には、第1号から第4号まで4つの種別があります。
特別支給の老齢厚生年金には、「1年以上の被保険者期間」という支給要件がありますが、種別が異なっていても、合算できます。
問題文では、第1号厚生年金被保険者期間(9か月)と第3号厚生年金被保険者(3か月)を合算して1年になりますので、特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たします。
関連問題をどうぞ!
 問題<R1年出題>
問題<R1年出題>
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
 問題<H28年出題>
問題<H28年出題>
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

【解答】
 問題<R1年出題> 〇
問題<R1年出題> 〇
特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上の厚生年金保険の被保険者期間」を有していることが要件です。
ちなみに、65歳からの本来の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月でもあればOKです。
 問題<H28年出題> ×
問題<H28年出題> ×
第1号厚生年金被保険者期間(8か月)と第4号厚生年金被保険者期間(10か月)の合算で特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たします。
問題文の場合は、60歳から特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
なお、60歳から支給されるのは第1号厚生年金被保険者期間の分です。第4号の期間分の支給は、62歳からです。
女性の場合、第1号厚生年金被保険者期間分の支給開始年齢が他と違うことも意識してください。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(国年)
R3-079
R2.11.10 <R2出題>問題の意図「被保険者期間がない者の障害基礎年金」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問2-イ>
初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。

【解答】 ×
問題の意図は、「初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者に障害基礎年金は支給されるか?」です。
国民年金に加入してすぐ初診日があるような場合です。
例えば、令和2年11月8日に20歳に達して第1号被保険者の資格を取得して、同年11月20日に初診日がある人の場合、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がありません。
障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある」場合に適用されます。
前々月までに被保険者期間がない場合は、滞納が無いということで、保険料納付要件は問わず、障害基礎年金が支給されます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(健保)
R3-078
R2.11.9 <R2出題>問題の意図「資格喪失後の出産育児一時金他の制度との調整」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問4-C>
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。

【解答】 〇
問題の意図は、資格喪失後国民健康保険の被保険者になり、出産した場合の、健保の資格喪失後の出産育児一時金と国民健康保険の出産育児一時金の調整方法です。(両方から受けるのは不可です。)
★対象者の意思表示で決まります。
・健康保険法の出産育児一時金の支給を受ける旨の
・意思表示をしたとき → 健康保険法の出産育児一時金の支給を受けることができる。(国民健康保険からは支給しない)
・意思表示をしないとき → 国民健康保険から支給が受けられる
こちらもどうぞ!
 H28年出題
H28年出題
引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者がその被保険者の資格を喪失し、国民健康保険組合(規約で出産育児一時金の支給を行うこととしている。)の被保険者となった場合、資格喪失後6か月以内に出産したときには、健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない。
 H25年出題
H25年出題
引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)を有し、資格喪失後6か月以内に出産した者が、健康保険の被扶養者になっている場合、請求者の選択により被保険者本人としての出産育児一時金、又は被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかを受給できることとなる。
 H26年出題
H26年出題
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。

【解答】
 H28年出題 ×
H28年出題 ×
★資格喪失後に国民健康保険の被保険者になった場合
上記の令和2年の問題と同じ意図の問題です。「健康保険の保険者がその者に対して出産育児一時金を支給することはない」は誤り。健康保険の出産育児一時金を受ける旨の意思表示をすれば、健康保険から出産育児一時金が支給されます。
 H25年出題 〇
H25年出題 〇
★資格喪失後に被扶養者になった場合
被保険者本人としての出産育児一時金か被扶養者としての家族出産育児一時金のいずれかは本人の選択によります。
 H26年出題 〇
H26年出題 〇
★資格喪失後に船員保険の被保険者になった場合
資格喪失後に船員保険の被保険者となったときは船員保険を優先。
(健康保険の「傷病手当金又は出産手当金の継続給付」、「資格喪失後の死亡に関する給付」、「資格喪失後の出産育児一時金」の給付は行われない。)
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(徴収法)
R3-077
R2.11.8 <R2出題>問題の意図「メリット収支率に入れるもの入れないもの」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<労災問9-C>
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。

【解答】 〇
問題の意図は、「特別支給金は、メリット収支率の計算に入るか否か」です。
★メリット収支率の分母は「保険料」、分子は「保険給付等の額」です。保険料に対する保険給付等の割合なので、率が大きいということは業務災害が多かったということです。
具体的には、収支率が100分の85を超えると労災保険率がup し、収支率が100分の75以下になると労災保険率はdown
し、収支率が100分の75以下になると労災保険率はdown します。
します。
★また、収支率の計算は分母・分子ともに「業務災害」に係るもので計算します。なぜなら事業主の努力で防ぐことができるのは業務災害だけだからです。
★「特別支給金」は保険給付の上乗せですので、収支率の計算に入れることになっています。
こちらもどうぞ!
 H25年出題
H25年出題
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
 H22年出題
H22年出題
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。

【解答】
 H25年出題 ×
H25年出題 ×
特別支給金もメリット収支率の計算に含まれます。(ただし、業務災害に係る特別支給金でも収支率の計算に入れないものもあります。)
 H22年出題 〇
H22年出題 〇
特別加入の承認を受けた海外派遣者については、分母・分子ともに収支率の計算には入りません。分母・分子ともに日本国内の分で計算されます。
★ちなみに、特別加入の承認を受けた中小事業主等については、分母・分子ともに計算に入ります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(雇用保険)
R3-076
R2.11.7 <R2出題>問題の意図「雇用保険の適用除外」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問2-C>
雇用保険の被保険者が国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められるものであって雇用保険法施行規則第4条に定めるものに該当するに至ったときは、その日の属する月の翌月の初日から雇用保険の被保険者資格を喪失する。

【解答】 ×
「その日の属する月の翌月の初日から」ではなく、適用除外の手続がなされた場合は、その手続開始の日(適用除外申請書が提出された日)から雇用保険法が適用されなくなります。
<適用除外の手続き>
・ 国その他これに準ずるものの事業に雇用される者 → 手続きすることなく適用除外となる
・都道府県又はこれに準ずるものの事業に雇用される者 → 厚生労働大臣に適用除外申請をし、その承認を受けなければならない
・市町村又はこれに準ずるものの事業に雇用される者 → 都道府県労働局長に適用除外申請をし、その承認を受けなければならない
<適用除外になる理由>
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業は、法令、条例、規則等によって退職手当に関する制度が確立されています。求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与が、退職後に支払われることが確実だからです。
こちらもどうぞ!
 H22年出題
H22年出題
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
 H27年出題
H27年出題
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
 H24年出題
H24年出題
都道府県の長が、当該都道府県の事業に雇用される者について、雇用保険法を適用しないことについて厚生労働大臣による承認の申請を行い、その承認を受けたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日の翌日から雇用保険法は適用されない。

【解答】
 H22年出題 ×
H22年出題 ×
国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業も労働者を1人でも雇用していれば雇用保険の適用事業となります。
 H27年出題 〇
H27年出題 〇
国その他これに準ずるものの事業に雇用される者の場合は、承認不要です。
 H24年出題 ×
H24年出題 ×
承認の申請がなされた日の翌日からではなく、承認の申請がなされた日から、雇用保険法は適用されません。
社労士受験のあれこれ
本日合格発表でした。
R3-075
R2.11.6 第52回社労士試験合格発表
第52回社労士試験の合格発表でした。
合格率6.4%と厳しい中で、合格された方、おめでとうございます!
残念だった方。
合格を手に入れるまで、毎日コツコツ勉強を積み重ねましょう。
「継続は力なり」
続けていれば、必ず合格できます。
いっしょに頑張りましょう。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(労災)
R3-074
R2.11.5 <R2出題>問題の意図「解雇制限と労災保険の関係」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問6-B>
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

【解答】 ×
「3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り」の「限り」の部分が×です。
「労働基準法第81条の規定による打切補償を支払った」ものとみなされる日が2つあることを知ってくださいというのがこの問題の意図です。
★「打切補償を支払った」ものとみなされ、解雇制限が解除される日は次の2つのどちらかです。
①開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合はその日
又は
②療養開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は傷病補償年金を受けることとなった日
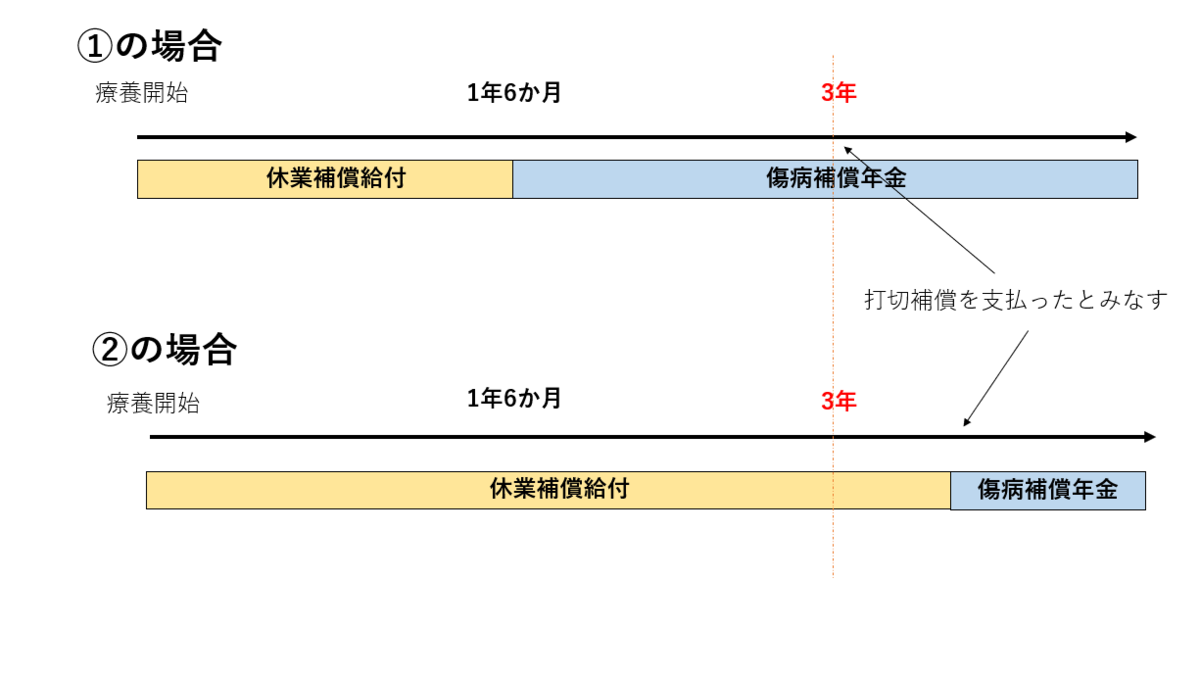
まず、労働基準法では「業務上の負傷又は疾病で療養のため休業する期間」は解雇できないことになっているので、治ゆする前に解雇はできません。
ただし、「療養の開始後3年を経過していること」、「打切補償を支払うこと」によって、解雇制限が解除される例外があります。
労災保険法では、①療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている、又は②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合は打切補償を支払ったとみなし、解雇できることになっています。
単に傷病補償年金を受けているだけではなく、療養開始後3年経過していることがポイントです。
ちなみに、休業補償給付から傷病補償年金の切り替えは、一番早くて療養の開始後1年6か月を経過した日ですが、1年6か月経過した日後に切り替わることもあり得るので注意してください。
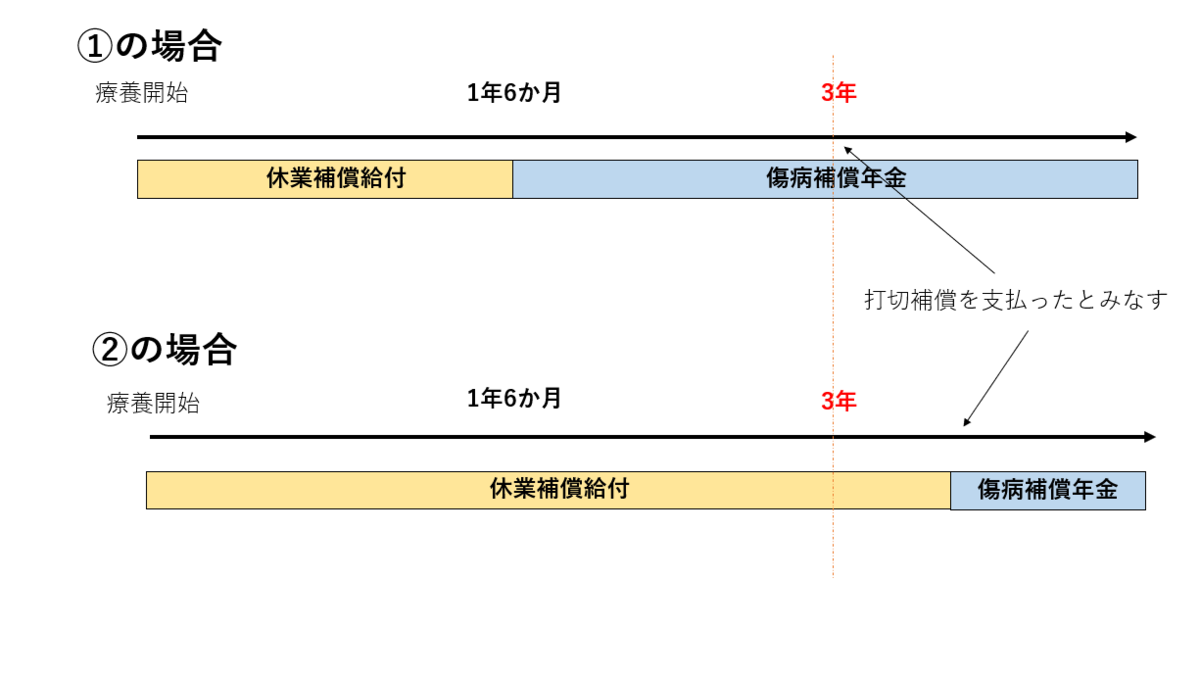
まず、労働基準法では「業務上の負傷又は疾病で療養のため休業する期間」は解雇できないことになっているので、治ゆする前に解雇はできません。
ただし、「療養の開始後3年を経過していること」、「打切補償を支払うこと」によって、解雇制限が解除される例外があります。
労災保険法では、①療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている、又は②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合は打切補償を支払ったとみなし、解雇できることになっています。
単に傷病補償年金を受けているだけではなく、療養開始後3年経過していることがポイントです。
ちなみに、休業補償給付から傷病補償年金の切り替えは、一番早くて療養の開始後1年6か月を経過した日ですが、1年6か月経過した日後に切り替わることもあり得るので注意してください。
R2年問題から~問題の意図を考える(安衛)
R3-073
R2.11.4 <R2出題>問題の意図「安全衛生教育は労働時間?」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問10-C>
安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払わなければならない。

【解答】 〇
安全衛生教育は、業務上のケガや病気を防ぐために事業主の責任で行われます。所定労働時間内に実施すべきものですが、問題文のように、法定労働時間外に行われた場合は、割増賃金が必要です。
★この問題の意図は、安全衛生教育の時間は労働時間になるか否か。労働時間なら事業主に賃金支払い義務がありますので、法定時間外に行った場合は、割増賃金も発生します。
では、こちらもどうぞ <労働時間になる?ならない?>
<H27年出題>
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものと解されている。

【解答】 〇
一般健康診断は、一般的な健康管理のためのものなので、その時間の賃金は負担しなくも良い。しかし、賃金を支払うことが望ましい。という考え方です。
特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する労働者のためのもので業務遂行に関連するので労働時間と解されます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(労基)
R3-072
R2.11.3 <R2出題>問題の意図「減給制裁」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問7-E>
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。

【解答】 ×
「ノーワークノーペイの法則」
例えば1時間遅刻した分として1時間分の賃金を控除することは減給制裁になりません。
しかし、1時間の遅刻に対して、例えば3時間分の賃金を控除してしまうと、働いた2時間分まで引かれてしまうことになり、そこは労基法第91条の制限を受けます。
この問題の意図は、「ノーワークノーペイ」(労働していない分は賃金は発生しない)と「減給制裁」(ペナルティとして労働した時間分まで控除してしまう)の違いです。
減給制裁の条文をどうぞ
第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の< A >を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の< B >を超えてはならない。

【解答】
A 半額
B 10分の1
<減給制限>
・1回の額 → 平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
・総額 → 一賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
※減給については労基法で制限がかかっています。ペナルティだとしても、賃金の大部分を減給されてしまうと、労働者の生活が成り立たないからです。
では、こちらの問題をどうぞ!
<H28年出題>
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。

【解答】 ×
出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、「制裁としての出勤停止」の当然の結果なので、91条違反にはなりません。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(社一)
R3-071
R2.11.2 R2出題【選択練習】社会保険労務士法・紛争解決手続代理業務
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄を埋めてください。
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は< A >万円とされている。
(参照:問5ア)

【解答】
A 120
★紛争の目的の価額が120万円を超える場合は、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限られます。
★個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものとして、社会保険労務士会が設置している社労士会労働紛争解決センターなどがあります。
さらにこちらもどうぞ
<H19年選択式>
・ 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< B >を行うことが含まれる。
・ ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < C >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< D >社会保険労務士に限られる。

【解答】
B 和解の交渉
C 紛争解決手続代理業務試験
D 特定
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(労一)
R3-070
R2.11.1 R2出題【選択練習】労働安全衛生調査(実態調査)より
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄を埋めてください。
参照:平成30年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果(厚生労働省)
 傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は< A >%である。
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は< A >%である。
【選択肢】 ①28.8 ②55.8 ③87.8
 受動喫煙対策に取り組んでいる事業所の割合は< B >%となっている。
受動喫煙対策に取り組んでいる事業所の割合は< B >%となっている。
【選択肢】 ①32.5 ②57.5 ③88.5
(参考:問2A、D)

【解答】
A ②55.8
B ③88.5
どちらも令和2年の択一式で出題されました。
 について → 択一式では、治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は3割と出題されて「誤り」の問題でした。小数点まで覚える必要はありません。治療と仕事の両立支援を行っている事業所割合は5割少し超えるくらいだな程度でOKです。
について → 択一式では、治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は3割と出題されて「誤り」の問題でした。小数点まで覚える必要はありません。治療と仕事の両立支援を行っている事業所割合は5割少し超えるくらいだな程度でOKです。
 について → 択一式では、「約6割にとどまっている」と出題されて「誤り」の問題でした。こちらも小数点まで覚える必要はありません。受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 88.5%。9割近いなと思う程度でOKです。
について → 択一式では、「約6割にとどまっている」と出題されて「誤り」の問題でした。こちらも小数点まで覚える必要はありません。受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 88.5%。9割近いなと思う程度でOKです。
さらにこちらもどうぞ
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立でき るような取組を行っている事業所の割合は 55.8%となっている。
治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所について、取組内容(複数回答)をみると、「< C >」が 90.5%と最も多く、次いで「< D >」が 28.0%となっている。
【選択肢】
①通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整等)
②両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)

【解答】
C ①通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整等)
D ②両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)
 今日の問題は、『平成30年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果(厚生労働省)』を参照しています。
今日の問題は、『平成30年「労働安全衛生調査(実態調査)」の結果(厚生労働省)』を参照しています。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(厚年)
R3-069
R2.10.31 R2出題【選択練習】在職老齢年金の計算
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>を埋めてください。
令和2年8月において、総報酬月額相当額が220,000円の64歳の被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有し、当該老齢厚生年金における基本月額が120,000円の場合、在職老齢年金の仕組みにより月< A >円の当該老齢厚生年金が支給停止される。
(参考:問10ウ)

【解答】
A 30,000
計算手順
①基本月額(120,000円)+総報酬月額相当額(220,000円)が28万円を超えるので、支給停止が行われる
↓
②基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下なので、(基本月額+総報酬月額相当額)の28万円を超えた部分の2分の1が支給停止になる。
計算式は、
(120,000円+220,000円-280,000円)×2分の1=30,000円
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(国年)
R3-068
R2.10.30 R2出題【選択練習】年金額改定の基準
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>を埋めてください。
年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、< A >を基準として、また68歳に到達した年度以後は< B >を基準として行われる。
【選択肢】 ①物価変動率 ②名目手取り賃金変動率 ③名目賃金変動率
(参考:問6A)

【解答】
A ②名目手取り賃金変動率
B ①物価変動率
 年金の額は、毎年度、賃金や物価の動向に合わせて改定されています。
年金の額は、毎年度、賃金や物価の動向に合わせて改定されています。
 新規裁定者(68歳到達年度前)は、まだ現役に近いので働く人の生活水準(名目手取り賃金変動率)に合わせる、既裁定者(68歳到達年度以後)は、引退世代の生活水準(物価変動率)に合わせる、と考えてみてください。
新規裁定者(68歳到達年度前)は、まだ現役に近いので働く人の生活水準(名目手取り賃金変動率)に合わせる、既裁定者(68歳到達年度以後)は、引退世代の生活水準(物価変動率)に合わせる、と考えてみてください。
ちなみに・・・
令和2年度は、
・物価変動率 → +0.5%
・名目手取り賃金変動率 → +0.3%
でした。
「物価」「名目手取り賃金」が両方とも「+」で「物価」の方が上回っています。このような場合は、既裁定者は「物価」ではなく「名目手取り賃金変動率」を基準とします。
なぜなら「年金」は世代間扶養だから。年金は現役世代の保険料で支えられています。既裁定者の方が新規裁定者よりも年金額の伸びが大きくなるのは、理屈に合わないからです。
令和2年度の年金額は、新規裁定者も既裁定者も「名目手取り賃金変動率」を基準に改定が行われました。
(名目手取り賃金変動率「+0.3%」にスライド調整率「̠̠0.1%」がかかりました。)
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(健保)
R3-067
R2.10.29 R2出題【選択練習】日雇特例被保険者の保険料納付要件
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>を埋めてください。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して< A >日分以上又は当該日の属する月の前6か月に通算して< B >日分以上の保険料が納付されていなければならない。
(参考:問7A)

【解答】
A 26
B 78
 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければなりません。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、保険料納付要件を満たさなければなりません。
例えば、2020年11月に療養の給付を受けるには、2020年9月・10月の2か月間で通算26日分以上納付されているか、2020年5月~10月ので6か月間で通算78日分以上の納付が必要です。
なお、日雇特例被保険者の保険料の納付は、日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙を貼付し消印する方法で行われます。
関連問題をどうぞ!
<日雇特例被保険者の出産>
空欄< C >を埋めてください。
日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前< C >月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

【解答】
C 4
出産の場合は、前4月間に通算して26日分以上でOKです。出産直前まで労働して保険料を納付するのは大変なので、前4か月間に条件が緩和されます。
では、もう一問どうぞ
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者に対する特別療養費の支給期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して< D >か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については< E >か月間)である。
(参考:H26年択一式問題)

【解答】
D 3
E 2
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、前2月間に26日分以上の保険料が必要なので、初めて日雇特例被保険者手帳を交付されたときは、まだ療養の給付が受けられません。
そのため、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月間(月の初日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者については2か月間)は特別療養費が支給されます。
★例えば
・10月29日に交付を受けた場合はその年の12月31日まで支給される
・11月1日に交付を受けた場合はその年の12月31日まで支給される
最低暦月で2月あれば療養の給付が受けられるので、特別療養費はその間の保障だと考えてください。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(雇保)
R3-066
R2.10.28 R2出題【選択練習】不服申立て(雇用保険)
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です。
空欄< A >を埋めてください。
失業等給付に関する処分について審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
(参考:問6D)

【解答】
A 3か月
横断的に覚えるのがコツです!
| 棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
 コチラの記事にまとめています。よかったらどうぞ。
コチラの記事にまとめています。よかったらどうぞ。
↓
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
では、もう一問どうぞ!
第9条の規定による確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等(これらの規定を第61条の6第2項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、< B >に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、< C >に対して再審査請求をすることができる。

【解答】
B 雇用保険審査官
C 労働保険審査会
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(労災)
R3-065
R2.10.27 R2出題・【選択練習】特別支給金~算定基礎年額
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>、<C>を埋めてください。
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前< A >間(雇入後< A >に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の< B >期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が< C >円を超えることはない。
(参考:問7A)

【解答】
A 1年
B 3か月を超える
C 150万
 特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類がありますが、「算定基礎年額」は、ボーナス特別支給金の計算の基になるものです。
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類がありますが、「算定基礎年額」は、ボーナス特別支給金の計算の基になるものです。
算定基礎年額とは、簡単に言うと、年間のボーナスの総額ですが、あまり高くならないように上限が設定されています。
<手順>
まず、(ア)と(イ)を比較して算定基礎年額を出します。
(ア)負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者、雇入後の期間)の特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額
(イ)給付基礎日額×365×20%
(ア)と(イ)のどちらか低い方となります。
ただし、(ア)と(イ)が150万円を超える場合は、算定基礎年額は150万円となります。
関連問題をどうぞ!
<H28出題>
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】 〇
なぜ、休業特別支給金の支給申請の際に、「特別給与の総額」を記載するのか?
解説はこちらの記事をどうぞ
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(安衛)
R3-064
R2.10.26 R2出題・【選択練習】面接指導80時間or100時間
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄< A >を埋めてください。
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり< A >時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
(参考:R2問8C)

【解答】 A 100
★ ちなみに、「健康管理時間」は、労働基準法第41条の2第3項で、「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」を合計した時間と規定されています。
(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、その決議に係る時間を除いた時間となります。)
解説はこちらの記事をどうぞ
↓
①R2.9.16 過去の論点は繰り返す(R2安衛法・長時間労働者の面接指導)
②R2.9.26 R2出題・労働時間の状況を把握しなければならない労働者の範囲
| ■長時間労働者に対する面接指導 |
| 時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積 労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない |
| ■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導 |
| 時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
| ■高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導 |
| 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
関連問題をどうぞ!
<高度プロフェッショナル制度の対象労働者の面接指導>
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、< B >の変更、有給休暇(労働基準法第39条の有給休暇を除く)の付与、< C >が短縮されるための配慮等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

【解答】
B 職務内容
C 健康管理時間
面接指導は、①長時間労働者、②研究開発業務、③高度プロフェッショナル制度の3種類があります。
事後措置のキーワードがそれぞれ違うので注意してください。
面接指導の事後措置のキーワードはこちら。
↓
| ■長時間労働者に対する面接指導 |
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等 |
| ■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導 |
就業場所の変更、職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等 |
| ■高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導 |
職務内容の変更、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康管理時間が短縮されるための配慮等 |
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(労基)
R3-063
R2.10.25 R2出題・【選択練習】中間搾取の排除
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄< A >を埋めてください。
労働基準法第6条に定める「< A >も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
(参考:問4C)

【解答】 A 何人
労働基準法第6条(公民権行使の保障)の主体は「何人も」です。個人、団体、公人、私人たるとを問いません。
関連問題をどうぞ!
<H28出題>
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

【解答】 ×
他人の就業に介入して利益を得る(中間搾取)行為は、団体・個人、公人・私人関係なく禁止されています。もちろん公務員であってもこのような行為は禁止されています。
最後にもう一問どうぞ
<H23年出題>
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

【解答】 ×
第6条は「法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」となっていますので、「法律によって許される場合」もあります。問題文は、「他の法律の定め如何にかかわらず」の部分が誤りです。
なお、法律に基づいて許される場合とは、職業安定法などの規定による場合です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(社一)
R3-062
R2.10.24 R2出題・【よく出る】児童手当の支給
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問8より
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

【解答】 ×
支払期月は、毎年2月、6月、10月の3期です。
・それぞれの前月までの分を支払います。
もう一問どうぞ!
<H29選択>
児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、< A >の認定を受けなければならない。
なお、本問において一般受給資格者は、法人でないものとする。

【解答】 住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)
最後にもう一問どうぞ
児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の < B >における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

【解答】 B 6月1日
毎年6月1日~6月30日までの間に提出しなければなりません。
★実は、毎年のように出題されている児童手当法。出題箇所はほぼ決まっているので、しっかり過去問を勉強していれば大丈夫です!
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(労一)
R3-061
R2.10.23 R2出題・障害者雇用率の算定
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問3より
障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。

【解答】 ×
短時間労働者は、原則として、1人を0.5人としてカウントします。
※ただし、短時間重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウントします。
| 週所定労働時間 | 30時間以上 | 20時間以上30時間未満 (短時間労働者) |
|---|---|---|
| 身体障害者 | 1人 | 0.5人 |
| 重度 | 2人 | 1人 |
| 知的障害者 | 1人 | 0.5人 |
| 重度 | 2人 | 1人 |
| 精神障害者 | 1人 | 0.5人 |
ちなみに。。。
民間企業の障害者雇用率は現在2.2%ですが、令和3年3月1日から2.3%となります。
それにともなって、障害者を雇用しなければならない民間企業の規模が45.5人以上から43.5人以上に広がります。
<45.5人以上(令和3年3月~43.5人以上)の民間企業の義務>
① 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない
② 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(厚年)
R3-060
R2.10.22 R2出題・厚年~所在不明のときの支給停止
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問8より
死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。

【解答】 〇
この問題のチェックポイントは、「いつから」支給停止されるのか?という部分です。
「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されます。他の受給権者の申請があったときからではありません。
 問題文のように、遺族厚生年金の受給権者が2人の子(例えばAとB)である場合、1人当たりの額は、遺族厚生年金を「2」で割った額となります。
問題文のように、遺族厚生年金の受給権者が2人の子(例えばAとB)である場合、1人当たりの額は、遺族厚生年金を「2」で割った額となります。
そのうちの1人(A)が行方不明になり、残りの1人(B)の申出によりAの年金が支給停止になった場合、Bの年金額が増額されることになります。(それまでは2分の1ずつだったのがB1人で全額受けることになるので)
こちらもどうぞ!
<R1年出題>
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。

【解答】 ×
支給停止は申請の日からではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(国年)
R3-059
R2.10.21 R2出題・死亡一時金と年金との関係
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問1より
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】 ×
死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金は支給されます。
★遺族基礎年金と死亡一時金の関係
(原則)
死亡した者の死亡日にその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。 → 死亡一時金は支給されない。
(例外)
死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 死亡一時金は支給される。
例えば、被保険者の死亡時に、子が18歳の年度末(3月)だった場合、遺族基礎年金の受給権は発生しますが、同月中に受給権は消滅してしまいます。 そのため、結局、受給権はできても遺族基礎年金は受給できません。 この場合は、例外規定の「死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき」に該当しますので、死亡一時金が支給されます。 |
では、類似問題をどうぞ!
<H24年出題>
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】 ×
死亡一時金の支給を受ける者が、夫の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、どちらか一方を支給し、他方は支給しない、とされています。寡婦年金が優先されるわけではありません。
ポイント! 死亡一時金と寡婦年金のどちらを受けるかは、受給権者が選択する
問題文は、寡婦年金を優先しているので間違いです。
寡婦年金と死亡一時金では、寡婦年金の方が額が多いと考えがちですが、そうとも限りません。
例えば、65歳近くなって寡婦年金の受給権ができたとしたら、死亡一時金の方が額が多くなる可能性がありますので。
では、穴埋め問題をどうぞ!
1 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が< B >月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は< C >の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2 1の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
① 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により< D >を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該< D >の受給権が消滅したときを除く。
② 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により < D >を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該< D >の受給権が消滅したときを除く。

【解答】
A 前月
B 36
C 障害基礎年金
D 遺族基礎年金
最後にもう一問どうぞ!
<H28年出題>
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。

【解答】 ×
上記の穴埋め問題でも出てきましたように、死亡した者が、「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある」ときは、死亡一時金は支給されません。
一方、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときでも、要件を満たせば遺族に死亡一時金が支給されます。
「死亡一時金」は掛け捨て防止が目的です。
老齢基礎年金や障害基礎年金をうけたことがあるなら国民年金の保険料は掛け捨てにはなりませんよね。だから、老齢基礎年金や障害基礎年金をうけたことがある者が死亡した場合は、死亡一時金は支給されません。
一方、遺族基礎年金を受けたことがある者が死亡したときは、要件を満たせば死亡一時金は支給されます。遺族基礎年金の場合、受ける本人の保険料納付要件ではなく、死亡した人の保険料納付要件が反映されるからです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(健保)
R3-058
R2.10.20 R2出題・当初から自宅待機の場合の健保資格取得日
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問4より
新たに適用事業所に使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格については、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われているときは、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得するものとされている。

【解答】 〇
被保険者資格は、「適用事業所に使用されるに至った日」に取得します。
使用されるに至った日とは、事実上の使用関係に入った日のことですので、自宅待機で出社していなくても、休業手当(給料)の支払いの対象になった日から、健康保険の被保険者の資格を取得します。
では、類似問題をどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。
 <H30年出題>
<H30年出題>
適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。

【解答】
 <H25年出題> 〇
<H25年出題> 〇
 <H30年出題> ×
<H30年出題> ×
上記で解説しましたように、適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日です。
事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、「すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべき」ものとされますので、調査の日を資格取得日とするのは誤りです。
では、最後にもう一問どうぞ!
<H22年出題>
被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、①適用事業所に使用されるに至った日、②その使用される事業所が適用事業所となった日、③適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当した日から、被保険者の資格を取得するが、①の場合、試みに使用される者については適用されない。

【解答】 ×
試みの使用される者にも適用されます。
たとえ試用期間であったとしても、雇用関係に入っているからです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(徴収法)
R3-057
R2.10.19 R2出題・特別加入保険料率について
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
 R2災問10より
R2災問10より
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
 R2災問10より
R2災問10より
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
 R2災問10より 〇
R2災問10より 〇
一般の労働者の労災保険率は、過去3年間の「業務災害」「通勤災害」の災害率、「二次健康診断等給付」に要した費用、「社会復帰促進等事業」の内容等をもとに決められます。
一方、特別加入者は二次健康診断等給付の対象外です。そのため、第1種別加入保険料率は、「二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮した率を減じた率となります。
ただし、現在は、その率はゼロですので、結果として第1種特別加入保険料率は、その事業に適用される労災保険率と同率となります。
 R2災問10より ×
R2災問10より ×
事業又は作業の種類ごとに、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲で、18段階で設定されています。
では、特別加入保険料率の問題をどうぞ!
<H26年出題>
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和2年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

【解答】 ×
第3種特別加入保険料率は、1000分の3です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(雇用保険)
R3-056
R2.10.18 R2出題・訓練延長給付よく出るところ
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2年問3Aより
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

【解答】 〇
公共職業安定所長の指示で公共職業訓練等を受ける場合は、所定給付日数を超えて基本手当が支給されることがありますが、その日額は、本来の基本手当の日額と同じ額です。
訓練延長給付によって、所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお、公共職業訓練等を受講するために待期している期間、受講している期間、受講終了後の一定期間、基本手当が支給されます。
では、訓練延長給付の問題をどうぞ!
<22年出題>
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。

【解答】 ×
待期している期間も、訓練延長給付の対象です。
穴埋め式で確認しましょう
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が< A >以内のものに限られている。
公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては、 当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く< B >間の 期間内の失業している日について、当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて 基本手当を支給する。
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、< C >を限度として訓練延長給付が行われ得る。

【解答】
A 2年
B 90日
C 30日
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(労災)
R3-055
R2.10.17 R2出題・不正受給者からの費用徴収
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
 R2年問2Cより
R2年問2Cより
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
 R2年問2Dより
R2年問2Dより
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

【解答】
 R2年問2Cより 〇
R2年問2Cより 〇
なお、「保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部」とは、受けた保険給付のうち不正受給した部分をさしています。不正受給した部分は全部回収されます。
例えば、保険給付をまるごと全部不正受給した場合は全部回収されます。また、保険給付の一部を不正受給した場合は、不正受給した部分は全部回収されます。回収されるのは、「不正受給した金額の全部又は一部」ではありません。
 R2年問2Dより 〇
R2年問2Dより 〇
不正受給に事業主が加担している場合は、事業主にも責任を負わせる趣旨です。
では、選択練習問題もどうぞ!
① < A >により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
② ①の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と < B >して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

【解答】
A 偽りその他不正の手段
B 連帯
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(安衛)
R3-054
R2.10.16 R2出題・職長教育のポイント!
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
<R2問10より>
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

【解答】 〇
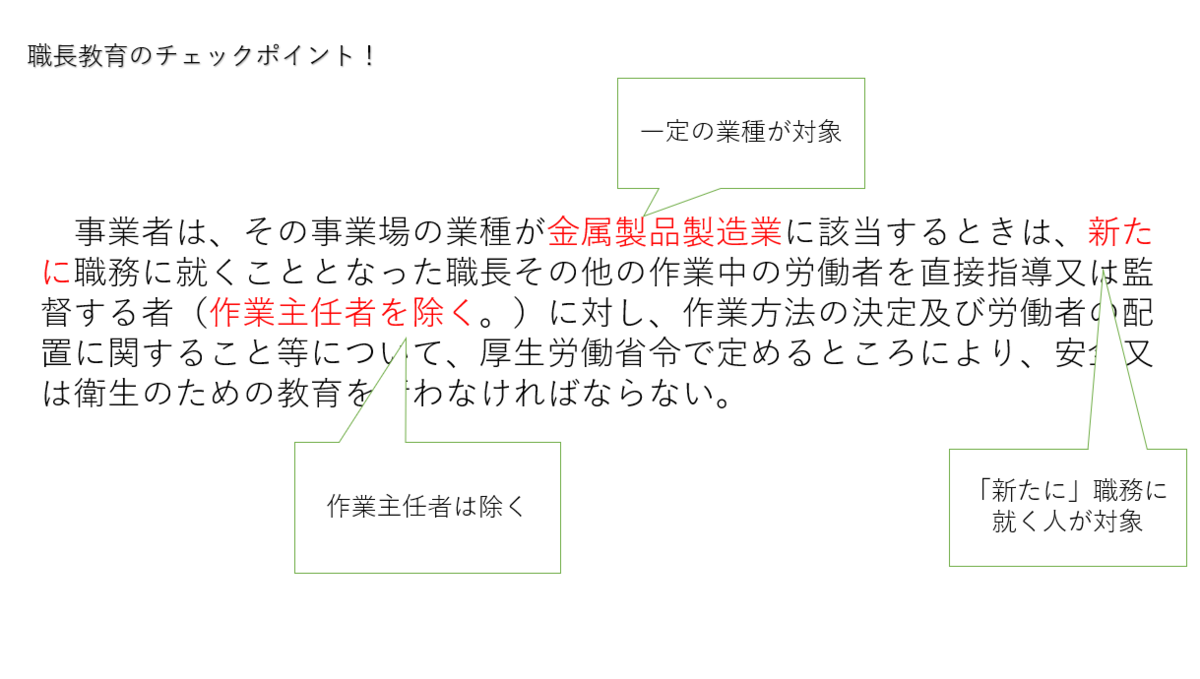
他の職長教育の問題をどうぞ!
<H22年出題>
運送業の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること等について安全衛生教育を行わなければならない。

【解答】 ×
職長教育の対象になる業種は、「建設業、製造業(一定のものを除く。)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業」です。運送業は対象になっていません。
では、もう一問!
<H13年出題>
事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

【解答】 ×
職長教育は、「新たに職務につく」こととなったときが対象です。「その職務内容を変更したとき」は、職長教育は義務付けられていません。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(労基)
R3-053
R2.10.15 R2出題・年次有給休暇の時季指定義務
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
<R2問6より>
使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

【解答】 〇
労働基準法施行規則第24条の6からの出題です。
イメージはこのような感じです。
使用者 : 「年次有給休暇ですが、いつ取りたいですか?」(取得時季について当該労働者の意見を聴かなければならない)
労働者 : 「10月23日に取得したいです。」
使用者 : 「それでは、10月23日に休んでください。」(聴取した意見を尊重するよう努めなければならない)
 労働基準法第39条第7項では、年5日の有給休暇の付与が使用者に義務付けられています。
労働基準法第39条第7項では、年5日の有給休暇の付与が使用者に義務付けられています。
労働基準法第39条第7項を穴埋め式で確認しましょう。
【問題です】
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が< A >労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち< B >日については、< C >(継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間の初日をいう。)から< D >年以内の期間に、労働者ごとにその< E >を定めることにより与えなければならない。

【解答】
A 10
B 5
C 基準日
D 1
E 時季
なお、「労働者自身の時季指定」又は「計画的付与」によって有給休暇を与えた場合は、その日数分、使用者の時季指定義務の5日から控除することができます。
例えば、労働者が自ら時季指定して2日間有給休暇を取得した場合は、使用者が時季指定しなければならない日数は3日間となります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(社一)
R3-052
R2.10.14 R2出題・難問解決策「児童手当法の所得制限」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問10より>
10歳と11歳の子を監護し、かつ、この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額1万円(10歳の子の分として月額5千円、11歳の子の分として月額5千円)が支給されることになる。

【解答】 ×
児童手当には所得制限があり、所得が所得制限以上の場合は、当分の間、月額5千円の「特例給付」が支給されています。
なお、所得制限額は、 主たる生計者のみの所得で判断し、世帯合算はしません。
父と母の所得を合算すると所得制限額以上だとしても、主たる生計者の所得が所得制限額を超えていなければ、特例給付ではなく、通常の児童手当が支給されます。
ここで、児童手当の額を確認しましょう。
| 支給対象児童 | 1人当たりの月額 |
|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
| 3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降15,000円) |
| 中学生 | 10,000円(一律) |
「特例給付」は、児童1人当たり5,000円です。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H30年選択>
11歳、8歳、5歳の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき< A >である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

【解答】 A 35,000円
3歳~小学校修了前の児童は1人10,000円ですが、第3子以降は15,000円となるので、合計35,000円となります。
では、選択の練習をどうぞ!
児童手当法において「児童」とは、< A >に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の < B >で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

【解答】
A 18歳
B 内閣府令
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(労一)
R3-051
R2.10.13 R2出題・難問解決策「同一労働同一賃金」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問3より>
パートタイム・有期雇用労働法が適用される企業において、同一の能力又は経験を有する通常の労働者であるXと短時間労働者であるYがいる場合、XとYに共通して適用される基本給の支給基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。

【解答】 ×
話題の「同一労働同一賃金」がテーマの問題。
難しいですね。解けなくても気にしないでください。
「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(同一労働同一賃金ガイドライン)からの出題です。
このガイドラインには、「通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例」が示されています。
ガイドラインによると、「基本給」で労働者の「能力又は経験」に応じて支給するものについて、次のように記載されています。
・ 通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者 → 能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならない。
・ 能力又は経験に一定の相違がある → その相違に応じた基本給を支給しなければならない。
また、(問題とならない例)、(問題となる例)として具体例がいくつか示されています。
(問題とならない例)の中に、「A社においては、同一の能力又は経験を有する通常の労働者である Xと短時間労働者であるYがいるが、XとYに共通して適用される基準を設定し、就業の時間帯や就業日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「土日祝日」という。)か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けている。」が示されています。
簡単に言うと、「基本給」で労働者の「能力又は経験」に応じて支給するものについては、通常の労働者と同一の能力又は経験を有する短時間・有期雇用労働者には、能力又は経験に応じた部分につき、通常の労働者と同一の基本給を支給しなければならないが、就業日や就業の時間帯が土日祝日か否か等の違いにより、時間当たりの基本給に差を設けることは問題とならない、ということです。
ですので、上記問題文については、「時間当たりの基本給に差を設けることは許されない。」が誤りということになります。
では選択練習問題をどうぞ!
短時間・有期雇用労働法第8条において、事業主は、短時間・有期雇用労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、< A >と認められる相違を設けてはならないこととされている。
また、短時間・有期雇用労働法第9条において、事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、待遇のそれぞれについて、< B >をしてはならないこととされている。

【解答】
A 不合理
B 差別的取扱い
★同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)からの抜粋です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(厚年)
R3-050
R2.10.12 R2出題・難問解決策「障害等級3級不該当と65歳」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問3より>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【解答】 ×
3級の障害厚生年金が支給されます。
★「失権」と「支給停止」
まずは、「失権」と「支給停止」の違いを意識してください。
「失権」とは受給権の消滅、すなわち受給権そのものがなくなること。復活はありません。
一方、「支給停止」とは、何らかの理由で支給が止まること。停止理由がなくなれば支給停止は解除され再び支給されます。
★問題文の考え方
障害等級3級に該当しなくなった
↓
障害厚生年金は支給停止
↓
その状態のまま3年が経過
↓
その後、65歳に達する日の前日までに障害等級3級の障害の状態になった
↓
支給停止は解除。障害厚生年が支給される
★ポイント!
3級に該当しないまま3年経過しても、65歳に達するまでは失権せず、支給停止のまま。再び3級に該当すれば支給停止は解除され、障害厚生年金が支給されます。
少なくとも65歳までは失権しないのがポイントです。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H27年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。

【解答】 ×
障害厚生年金は、3級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき、又は、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から3年を経過したとき、のどちらか遅い方に失権します。
問題文の場合、3級に該当しなくなったのが63歳の時。65歳に達した日にはまだ3年たっていません。ですので、65歳に達した日には消滅しません。
では、選択の練習をどうぞ!
(障害厚生年金の失権)
障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定(併合認定)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
1 死亡したとき。
2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、< A >歳に達したとき。ただし、< A >歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく< B >年を経過していないときを除く。
3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく< B >年を経過したとき。ただし、< B >年を経過した日において、当該受給権者が< A >歳未満であるときを除く。

【解答】
A 65
B 3
ちなみに、「障害等級」は厚生年金保険法の場合は「1級、2級、3級」です。
国民年金法の「障害等級」は「1級、2級」です。
社労士受験のあれこれ
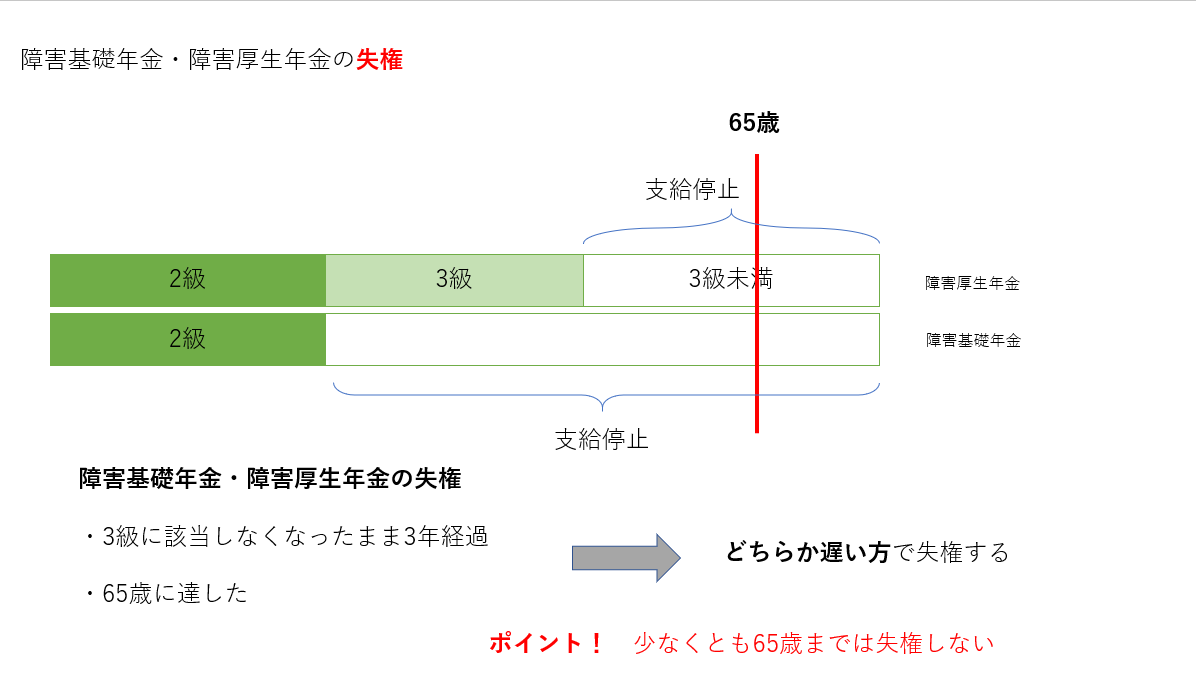
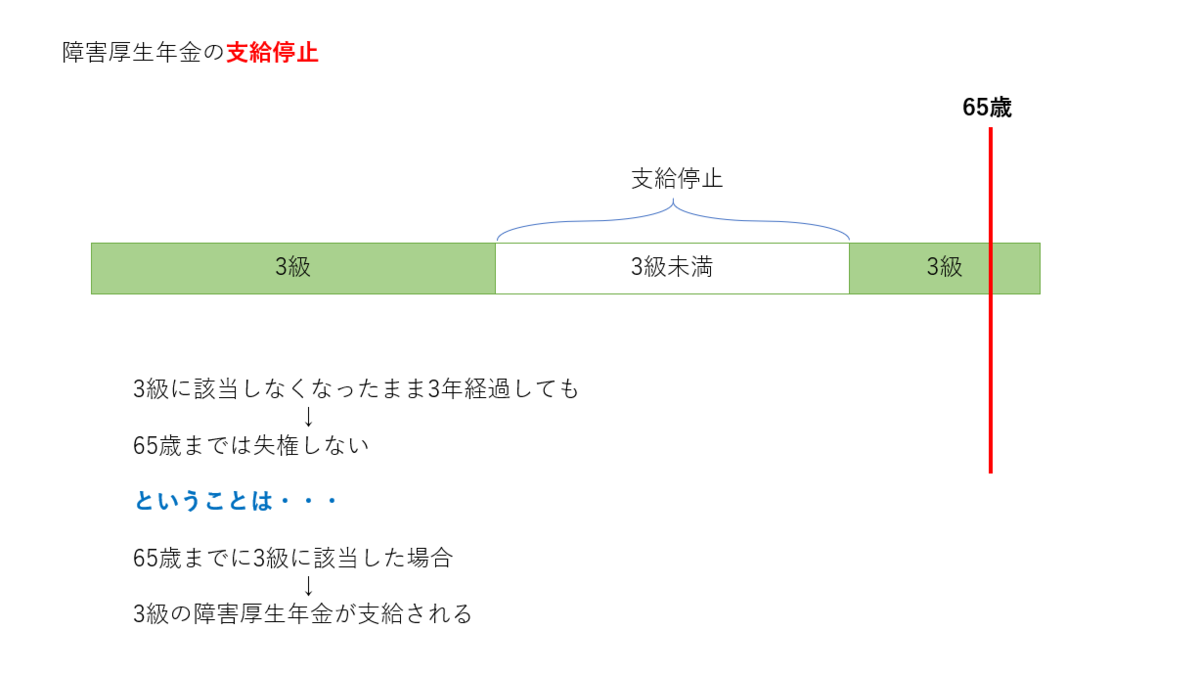
R2年問題から~難問の解決方法(国年)
R3-049
R2.10.11 R2出題・難問解決策「寡婦年金の支給要件」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問4より>
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。

【解答】 ×
寡婦年金の条文を読んでみると、死亡した夫の要件として、
「夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は、寡婦年金は支給しないとあります。
老齢基礎年金の「支給を受けていた」ときは寡婦年金は支給されませんが、受給権があったとしても「支給を受けていない」場合なら、寡婦年金は支給されます。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H14年出題>
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。

【解答】 〇
死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給されません。
ではこちらもどうぞ!
<H18年出題>
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給をうけたことがなければ寡婦年金は支給される。

【解答】 ×
死亡した夫が、「障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は、寡婦年金は支給されません。
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、実際に支給をうけていなくても寡婦年金は支給されません。
老齢基礎年金との違いに注意してください。
ちなみに、行政解釈では、夫が障害基礎年金の受給権者であった場合とは、現実の年金の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさす、とされています。
では、選択の練習をどうぞ!
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が < A >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< B >年以上継続した < C >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が< D >の受給権者であったことがあるとき、又は < E >の支給を受けていたときは、この限りでない。

【解答】
A 10
B 10
C 65
D 障害基礎年金
E 老齢基礎年金
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(健保)
R3-048
R2.10.10 R2出題・難問解決策「自己の故意の犯罪行為と埋葬料」
一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問6より>
被保険者が道路交通法違反である無免許運転により起こした事故のため死亡した場合には、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給される。

【解答】 〇
まず、第116条の条文を見てみましょう。
「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」
↓
無免許運転は、道路交通法違反で処罰される行為ですが、
・死亡は最終的1回限りの絶対的な事故であること
・埋葬を行う者に対する救済または弔意を目的として支給するものであること
から、所定の要件を満たす者に埋葬料が支給されることになっています。
同じ論点の問題をどうぞ!
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。
 <H25年出題>
<H25年出題>
被保険者が道路交通法規違反によって処罰されるべき行為中に起こした事故により死亡した場合、健康保険法第116条に定める給付制限事由に該当するものとして、埋葬料は支給されない。

【解答】
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
自殺は最終的1回限りの絶対的な事故のため、埋葬料は支給されます。
 <H25年出題> ×
<H25年出題> ×
上記R2年度の問題と同じです。埋葬料は支給されます。
では、こちらもどうぞ。
<H29年出題>
被保険者が、故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は行われないこととされているが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、故意に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付の対象となる。

【解答】 〇
自殺未遂による傷病については、療養の給付、傷病手当金は支給されません。
ただし、精神疾患等に起因する場合は、故意に給付事由を生じさせたとはいえないので、保険給付の対象となります。
では、選択の練習をどうぞ!
被保険者又は被保険者であった者が、自己の< A >により、又は < B >に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その< C >。

【解答】
A 故意の犯罪行為
B 故意
C 全部又は一部を行わないことができる
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(徴収法)
R3-047
R2.10.9 R2出題・難問解決策「請負事業の一括の効果」
一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2(労災)問8より>
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。

【解答】 ×
「労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる」の部分が誤りです。
元請負人が事業主とされるとは、下請負も含めたすべてについて保険料の納付等の義務を負うということ。
下請負人やその使用する労働者と元請負人に労働関係はありません。
こちらもどうぞ!
<H26年出題(労災)>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】 〇
雇用保険に係る保険関係は、元請負人に一括されません。
雇用保険は、原則通り「事業」単位で適用されるので、元請負人は元請負人、下請負人は下請負人とそれぞれの事業ごとに徴収法が適用されます。
では、こちらも!
<H28年出題(雇用)>
請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

【解答】 ×
先ほどの問題で勉強したように、雇用保険に係る保険関係は、元請負人に一括されません。
下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、下請負人が納付義務を負います。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(雇用保険)
R3-046
R2.10.8 R2出題・難問解決策「労働の意思」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問2より>
 自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
 雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

【解答】
 ×
×
 ×
×
考えるポイント!
行政手引51254によると、「受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるため」には、「単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけではなく、真に就職への意欲をもち、かつ、精神的、肉体的、環境的に労働の能力を有していることが必要」とされています。
「自営の開業に先行する準備行為に専念する者」や「雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者」がその要件に該当するかどうか考えてみると、答えが出るのではないでしょうか?
行政手引では、
・ 求職条件として短時間就労を希望する者については
→ 雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者に限り労働の意思を有する 者と推定される。
(私見:例えば、1週間に2時間だけ働きたいという人は、労働の意思があるとは推定されないということ)
・ 内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については
→ 労働の意思を有する者として扱うことはできない。
ただし、求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては、その者が 自営の準備に専念するものではなく、安定所の職業紹介に応じられる場合には、労働の意思を有する者と扱うことが可能であるので慎重に取り扱うこと。
ちなみに「労働の意思」とは?
★労働の意思 (行政手引 51202)
労働の意思とは、就職しようとする積極的な意思をいう。すなわち、安定所に出頭し て求職の申込みを行うのはもちろんのこと、受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとするものである。
選択式の練習もどうぞ!
この法律において「離職」とは、被保険者について、< A >することをいう。
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、< B >を有するにもかかわらず、< C >ができない状態にあることをいう。

【解答】
A 事業主との雇用関係が終了
B 労働の意思及び能力
C 職業に就くこと
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(労災)
R3-045
R2.10.7 R2出題・難問解決策「傷病特別支給金・傷病特別年金の申請」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2・問7より>
特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。

【解答】 〇

保険給付の傷病(補償)年金は、職権で支給決定されるので、請求は不要です。

特別支給金(傷病特別支給金、傷病特別年金)は、「申請」が必要です。
この「申請」が今回の問題のテーマです。
まず、この問題の解説に入る前に、「休業特別支給金」のことについて少しだけ
「休業(補償)給付」には特別支給金として「休業特別支給金」が上乗せされます。
また、休業(補償)給付には、ボーナス特別支給金はありません。
しかし、休業特別支給金の申請の際は、届書に「特別給与(ボーナス)の総額」を記載することになっています。
なぜなら、最初の休業特別支給金の申請時に特別給与の総額を届出しておけば、後で、障害特別年金、障害特別一時金、傷病特別年金、遺族特別年金、遺族特別一時金の申請を行う場合に、特別給与の総額を記載する必要がなくなるからです。
そこでこの問題に戻ると
・原則 特別支給金の支給の申請は、関連する保険給付の支給の請求と同時に行う
・傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、
→ 傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、所定の申請を行ったものとして取り扱う。(休業特別支給金の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除く)
同じ論点の問題をどうぞ!
①H24年出題
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
②H28年出題
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③H28年出題
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

【解答】
①H24年出題 〇
休業特別支給金の支給の申請は、休業(補償)給付の請求と同時に行う。
※ 休業特別支給金の申請書と休業(補償)給付の支給請求書は、一本の様式になっている。
②H28年出題 〇
③H28年出題 〇
社労士受験のあれこれ
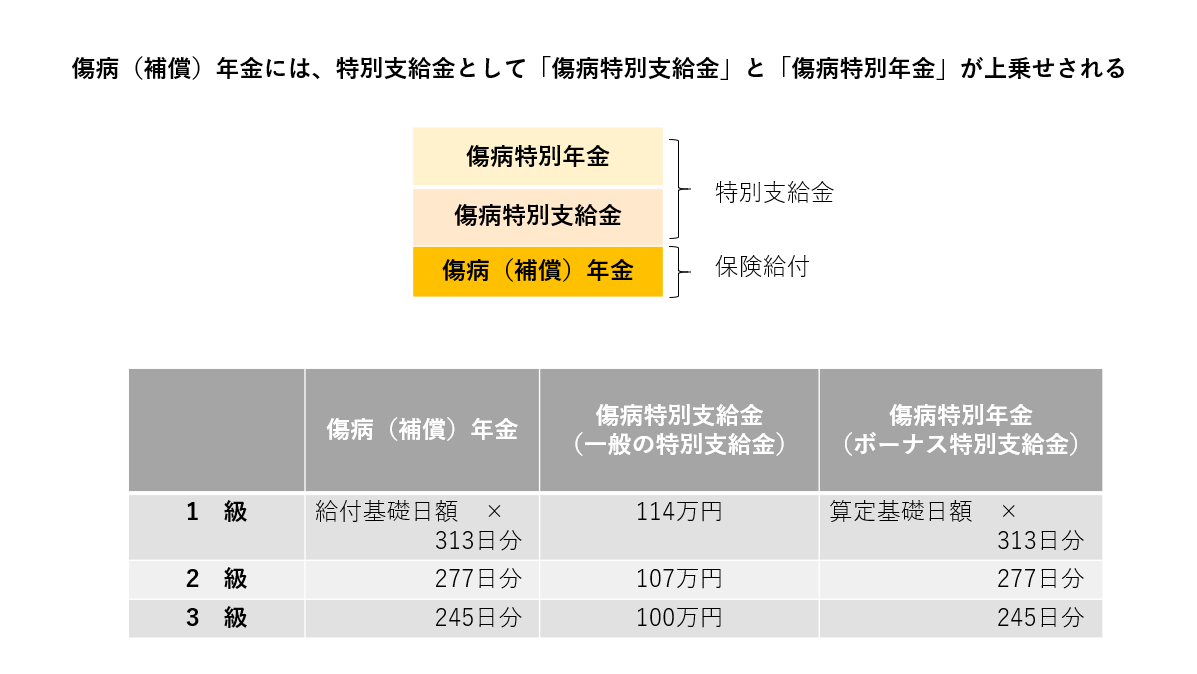
R2年問題から~難問の解決方法(安衛)
R3-044
R2.10.6 R2出題・難問解決策「安衛法・両罰規定」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2・問9より>
労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。

【解答】 ×
法人の従業者が違反行為をしたときは、当該従業者は罰則の対象となります。
・・・・・・・
こちらの条文を読んでみましょう。
第122条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

条文に「行為者を罰する」と書いてあります。ここから、法令違反行為を行った従業者本人が罰則の対象になるのは明らかです。
また、従業者を指揮命令する立場である法人又は人(事業者)にも罰金刑が課されます。(両罰規定といいます)
同じ論点の問題をどうぞ!
<H29年出題>
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。

【解答】 ×
違反行為を行った従業者は、処罰の対象となります。
では、穴埋め問題に挑戦しましょう!
第122条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、< A >を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の< B >を科する。

【解答】
A 行為者
B 罰金刑
・Bについて
労働安全衛生法の罰則には、懲役と罰金がありますが、両罰規定で法人又は人に科せられるのは「罰金刑」です。法人に懲役刑は科せられないからです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(労基)
R3-043
R2.10.5 R2出題・難問解決策「食事の供与は賃金になる?」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2・問4より>
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものとして認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

【解答】 〇
令和2年労基法問4の問題です。
問4は「誤っているもの」を解く問題ですが、「公民権行使の保障」の肢が明らかに間違っていたので、問4そのものは解きやすい問題でした。
今回取り上げた問題は、一字一句覚える必要はありません。参考程度にとどめてください。
おさえておきたいポイントは「食事の供与」が「賃金」なのか、それとも「福利厚生」なのかという論点です。
「食事の供与」が「福利厚生」として取り扱われるポイントが3つあるというのが問題文から分かります。「賃金」=「労働の対償」であることが大前提。この3つに当てはまったら労働の対償とは言えないということです。
ちなみに、行政通達によると、現物給与について「賃金」となるか否かについて、「労働者から代金を徴収するものは原則として賃金ではない」となっていますが、「その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分」については賃金とみなされることになっています。
参考程度に。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~社保一般常識
R3-042
R2.10.4 R2・社会保険審査官及び社会保険審査会法
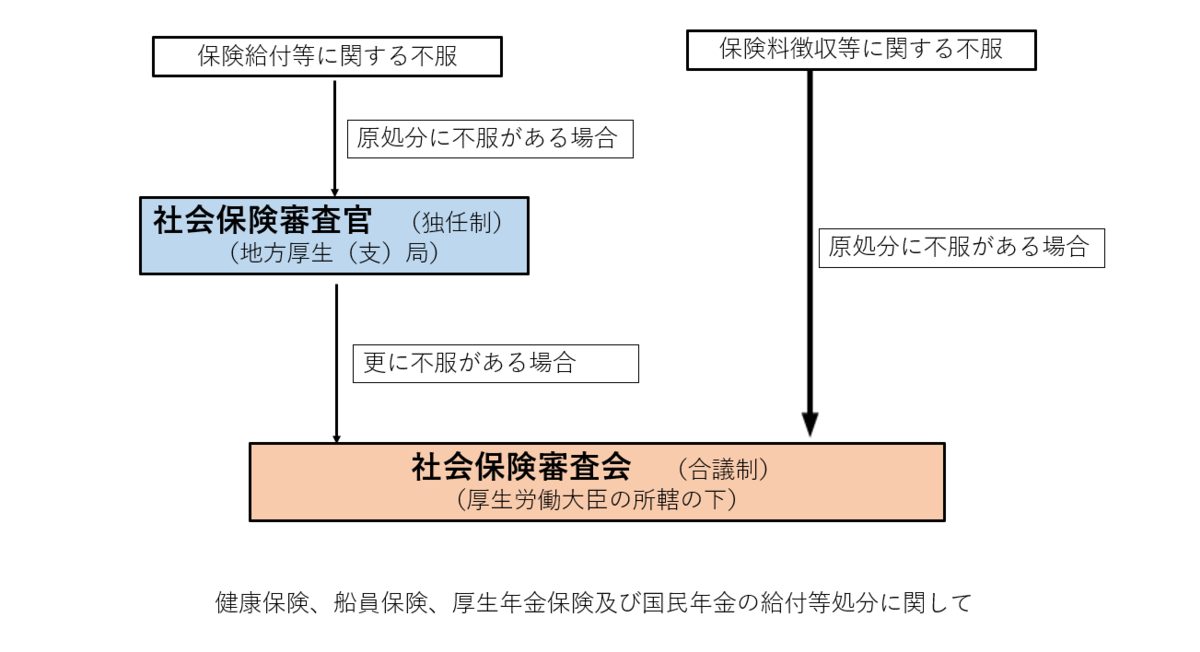
今日のテーマは、「社会保険審査官と社会保険審査会」です。
 <R2年問9A>
<R2年問9A>
審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。
 <R2年問9D>
<R2年問9D>
審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。

【解答】
 <R2年問9A> 〇
<R2年問9A> 〇
審査請求は、文書でも口頭でもできます。
 <R2年問9D>
<R2年問9D>
審査請求の取下げは、文書でしなければなりません。口頭ではできません。
では、こちらもどうぞ!
 <H21年出題・改>
<H21年出題・改>
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同条第2項及び第6項を除く。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条(同法第138条において準用する場合を含む。)並びに年金給付遅延加算金支給法第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。
 <H21年出題>
<H21年出題>
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

【解答】
 <H21年出題・改> 〇
<H21年出題・改> 〇
社会保険審査官は、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれるのがポイントです。
 <H21年出題> 〇
<H21年出題> 〇
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれるのがポイントです。委員長および委員5人をもって組織され、合議制となっています。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~労働一般常識
R3-041
R2.10.3 R2出題「H30年労働安全衛生調査」より
「平成30年労働安全衛生調査(実態調査)(常用労働者10人以上の民営事業所を対象)(厚生労働省)より
★調査の目的
事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすること
(厚生労働省HP 平成30年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況より)
問題をどうぞ!
<R2年問2E>
現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者について、その内容(主なもの3つ以内)をみると、「仕事の質・量」、「仕事の失敗、責任の発生等」、「顧客、取引先等からのクレーム」が上位3つを占めている。

【解答】 ×
「仕事の質・量」が 59.4%で最も多い。「仕事の失敗、責任の発生等」が 34.0%、「対人関係(セク ハラ・パワハラを含む。)」が 31.3%となっています。
ちなみに、「顧客、取引先等からのクレーム」は13.1%です。
なお、現在の仕事や職業生活に関することで、強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者の割合は 58.0% です。
参照:(厚生労働省HP 平成30年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況より)
相談できる人の有無
★ 仕事や職業生活に関する不安、悩み、ストレスについて相談できる人の有無等
現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレスについて相談できる人がいる労働者の割合は 92.8%となっているそうです。
誰に相談する?
では、相談できる相手(複数回答)でみたときに、最も多い相手は分かりますか?
↓
↓
↓
↓
「家族・友人」が 79.6%で最も多いそうです。
次が「上司・同僚」の77.5% です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~厚生年金保険法
R3-040
R2.10.2 R2出題・遺族厚生年金をうけることができる遺族
<遺族厚生年金を受けることができる遺族>
→ 被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持したものとする。
→ 妻以外の者は、次に掲げる要件に該当した場合に限る
・ 夫、父母又は祖父母 → 55歳以上
・ 子又は孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない
遺族厚生年金
<R2年問5B>
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。

【解答】 〇
遺族厚生年金には転給がないことがポイントです。(労災保険の遺族(補償)年金には転給があります。)
遺族厚生年金をうけることができる遺族は、上記のとおりです。
ただし、「父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」とされています。
①年金を受給できる順位が決まっていること、②先順位の人が受給権を得ると、後の人は遺族とならないことをおさえてください。
| 順位 | |
| 1 | 配偶者又は子 |
| 2 | 父母 (配偶者、子がいないとき) |
| 3 | 孫 (配偶者、子、父母がいないとき) |
| 4 | 祖父母 (配偶者、子、父母、孫がいないとき) |
問題文の場合、死亡の当時、のこされたのは10歳の子と父。
子の方が順位が上なので、遺族厚生年金を受けることができる遺族は「子」です。父は遺族になりません。
その後、子が18歳年度末で受給権を失った場合でも、父が遺族になることはありません。
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<H29年出題>
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。

【解答】 〇
配偶者と子がいるので、母は遺族にはなりません。配偶者の受給権がなくなっても、母が遺族になることはありません。
遺族厚生年金の問題をもう一問どうぞ
R2問10オ
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。

【解答】 ×
遺族厚生年金の場合、夫は「55歳以上」であることが要件ですが、子の有無は要件になっていません。55歳以上の夫は、子がいなくても遺族厚生年金の受給権者になり得ます。
「夫」の遺族厚生年金についてもう一問どうぞ
<H27年出題>
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。

【解答】 〇
例えば、妻の死亡時55歳の夫の場合
子が いない | 遺族厚生年金のみ | 60歳まで支給停止 |
子が いる | 遺族厚生年金 + 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金の受給権を有する場合は、 60歳未満でも遺族厚生年金は支給停止されない |
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~国民年金法
R3-039
R2.10.1 R2・任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違い
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金の強制被保険者ですが、それに当てはまらない人でも、任意で加入できる制度があります。
任意加入には次の2つパターンがあります。
1.任意加入被保険者
2.特例による任意加入被保険者
今日のテーマは、1.と2.の違いです。
 付加保険料
付加保険料
<R2年問3E>
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】 〇
「任意加入被保険者」も第1号被保険者と同じように付加保険料を納付できます。
では、「特例による任意加入被保険者」は付加保険料を納付できるでしょうか?
こちらの問題をどうぞ
<H15年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。

【解答】 〇
特例による任意加入被保険者の目的は、「老齢基礎年金の受給資格を得るため」で、増やすためではありません。
一方、「付加保険料」の目的は増やすため。
目的が合致しないため、特例による任意加入被保険者は付加保険料の納付はできません。
 「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違い
「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違い
| 任意加入被保険者 | 特例による 任意加入被保険者 | |
|---|---|---|
| 付加保険料 | 〇 納付できる | × 納付できない |
| 寡婦年金 | 〇 算入される | × 算入されない |
| 死亡一時金 | 〇 算入される | 〇 算入される |
| 脱退一時金 | 〇 算入される | 〇 算入される |
 寡婦年金
寡婦年金
<R2年問9A>
68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。

【解答】 ×
寡婦年金は支給されません。
特例による任意加入被保険者としての期間は、寡婦年金の期間には算入されないからです。(上の表を参照)
では、こちらをどうぞ!
<H28年出題>
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

【解答】 〇
上の表を参照してください。「特例による任意加入被保険者」と比較しておさえてください。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~健康保険法
R3-038
R2.9.30 R2出題・資格取得前の傷病(健保)
 今日のテーマは
今日のテーマは
入社する前(健康保険の資格を取得する前)からの傷病の場合、傷病手当金の支給は受けられる?受けられない?
<R2年問2E>
被保険者資格を取得する前に初診日がある傷病のため労務に服することができず休職したとき、療養の給付は受けられるが、傷病手当金は支給されない。

【解答】 ×
入社前から治療を受けていた傷病についても、保険給付の対象となります。
資格取得前の傷病でも、療養の給付、傷病手当金ともに支給されます。
★適正に資格を取得したならば、健康保険の保障が受けられると考えてください。
では、同じパターンの問題をどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
被保険者の資格取得が適正である場合、その資格取得前の疾病又は負傷については、6か月以内のものに限り保険給付を行う。
 <H23年出題>
<H23年出題>
被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。

【解答】
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
6か月以内という制限はありません。
 <H23年出題> ×
<H23年出題> ×
傷病手当金も支給されます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~徴収法
R3-037
R2.9.29 R2・労働保険徴収法の規定による処分に不服がある場合
・ 徴収法には不服申立ての規定がありません。不服がある場合は、行政不服審査法の規定で行います。
不服申立て
<R2年雇用問10B>
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

【解答】 ×
「正当な理由があるときは、この限りでない。」という例外規定が設けられているので、「当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。」が誤りです。
徴収法の不服申立てでおさえておきたいポイント!
「徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。(「厚生労働大臣」「審査請求をすることができる」がポイントです。)
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<H28年出題>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

【解答】 ×
『「労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。』です。(行政不服審査法)
問題文の「その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立て」が誤り。「厚生労働大臣に審査請求をすることができる。」です。
もう一問どうぞ!
<H28年出題>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

【解答】 〇
厚生労働大臣に審査請求をすることもできますが、直ちに処分の取消しの訴えを提起すること(裁判所に提訴)もできます。
R2年問題から~雇用保険法
R3-036
R2.9.28 R2出題・傷病手当の支給要件
雇用保険の傷病手当の目的は??
求職の申込みをした後(←ここが今日の最大のポイント)
↓
疾病又は負傷のために職業に就くことができない
↓
疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日に
↓
基本手当の日額と同じ額の傷病手当を支給することによって
↓
傷病期間中の生活を保障することが目的
問題をどうぞ!
<R2年問4A>
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

【解答】 ×
★傷病手当の対象になるのは、次の要件に該当した場合です。
① 受給資格者である
②求職の申込みをしている
③疾病又は負傷のため職業に就くことができない
④ 「疾病又は負傷のため職業に就くことができない」状態が「求職の申込み」後に生じた
問題文のように、「疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が離職前から継続している」場合には、傷病手当は支給されません。
また、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が離職後に生じた場合で も、求職の申込みを行う前に生じその後も継続しているものであるときは、傷病手当 の支給対象にはなりません。(行政手引53002)
では、こちらもどうぞ!
 <H28出題>
<H28出題>
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
 <H22出題>
<H22出題>
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

【解答】
 <H28出題> 〇
<H28出題> 〇
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない期間が継続して15日未満のとき
→ 証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができる
傷病手当は支給されない
 <H22出題> ×
<H22出題> ×
求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合は、傷病手当は受給できません。
なお、求職の申込みを行う以前に 疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある者は傷病手当は受給できませんが、受給期間の延長の申出は可能です。
受給期間の延長は、疾病又は負傷により職業に就くことができない状態が30日以上継続した場合に認められます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~労災保険法
R3-035
R2.9.27 R2出題・介護補償給付の最低保障額
労災保険の「介護(補償)給付」は、
親族又はこれに準ずる者の介護を
・受けていない
・受けている
の2つに分けることができます。
 今日のポイントは、
今日のポイントは、
「親族又はこれに準ずる者の介護を受けている」場合は、
「最低保障額」が適用されることです。
介護補償給付の問題
<R2年問6E>
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】 ×
「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」が誤りです。
親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は、介護費用の支出がなくても、最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給されます。
(注)翌月からです。(後述)
【最低保障額が適用されるパターン】
★ 親族又はこれに準ずる者(友人・知人)の介護を受けている(これが大前提)
かつ
①介護の費用を支出していない
→ 最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給される
②介護の費用を支出していて、その額が最低保障額を下回っている
→ 最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給される
③介護の費用を支出していて、その額が最低保障額を上回る
→ 実費が支給される(ただし、上限(常時166,950円、随時83,480円)あり
 最低保障額は「親族又はこれに準ずる者介護を受けている」ことが大前提です。親族等の介護の負担を補うためだと考えてください。
最低保障額は「親族又はこれに準ずる者介護を受けている」ことが大前提です。親族等の介護の負担を補うためだと考えてください。
ですので、問題文の「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合」(=すべて親族等で介護したので費用がかかっていない場合)でも、親族等の負担を鑑み、最低保障額が支給されます。
では、こちらの問題もどうぞ!
<H25出題>
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支給された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】 〇
介護補償給付は、「月単位」で支給されます。
問題文の「支給すべき事由が生じた月」がポイントです。支給すべき事由が生じた月は、最低保障額は適用されません。
★支給すべき事由が生じた月は、親族等による介護を受けていても
①介護の費用を支出していない場合 → 介護補償給付は支給されない
②介護の費用を支出していてその額が最低保障額を下回っている場合 → 実費のみ
この問題文は②に該当するので、「当該介護に要する費用として支出された額(実費)」のみが支給されます。
R2年問題から~労働安全衛生法
R3-034
R2.9.26 R2出題・労働時間の状況を把握しなければならない労働者の範囲
労働安全衛生法第66条の8の3で、「事業者は、面接指導を実施するため、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。」とされています。
今日のテーマは、「労働時間の状況を把握しなければならない」労働者の範囲です。
 ちなみに労働時間の状況の把握の方法は?
ちなみに労働時間の状況の把握の方法は?
タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とされています。
<R2年問8D>
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

【解答】 ×
事業者は、面接指導を実施するため、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
労働時間の状況を把握しなければならない労働者の範囲から除かれるのは、「労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)」です。
問題文の「労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者」は、労働時間の状況の把握が必要です。
※労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者(管理監督者等)= 労働時間の状況を把握しなければならない
「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」について
高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、「健康管理時間」を把握する必要があります。(労働基準法)
「健康管理時間」とは → 対象労働者が事業場内にいた時間と事業場外において労働した時間との合計の時間
「健康管理時間」が一定時間を超えた者については、面接指導が必要です。(安衛法)
では、その問題をどうぞ!
<R2年問8Cより>
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

【解答】 〇
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~労働基準法
R3-033
R2.9.25 R2出題・労使協定届出いる?いらない?
労働基準法には、11の労使協定が規定されています。
大きく分けると、所轄労働基準監督署長に届出がいる労使協定、届出しなくていい労使協定の2つのパターンがあります。
令和2年度の問題で確認しましょう!
フレックスタイム制の労使協定
<R2年問6B>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

【解答】 ×
フレックスタイム制の労使協定は
清算期間が
・1か月を超える場合 → 届け出がいる
・1か月以内の場合 → 届け出はいらない
問題文の「清算期間の長さにかかわらず」の部分が誤りです。
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<R1出題>
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

【解答】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定は、
労使協定で定める時間が
・法定労働時間を超える → 労使協定の届出がいる
・法定労働時間以下 → 労使協定の届出はいらない
 労働基準法上の労使協定について、届出がいる・いらないは、おさえておきましょう。
労働基準法上の労使協定について、届出がいる・いらないは、おさえておきましょう。
 こちらもどうぞ「労使協定の効果って?」
こちらもどうぞ「労使協定の効果って?」
労働基準法上の労使協定の効力は、
その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつもの
(例えば、「36協定」を締結して、所轄労働基準監督署長に届け出をすれば、時間外労働、休日労働させても、労働基準法には違反しないという免罰効果が生まれる)
↓
しかし、労使協定からは、「労働者の民事上の義務」は、直接生じない。
↓
「労働者の民事上の義務」は労働協約、就業規則等の根拠が必要
(例えば、なぜ労働者には「時間外労働をしなければならない義務」があるのか?この義務は36協定から生まれているのではなく、就業規則などに「残業義務」についてルールがあるから。)
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(社保一般常識)
R3-032
R2.9.24 過去の論点は繰り返す(R2・確定給付企業年金法)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
確定給付企業年金法
 <H26年出題>
<H26年出題>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
 <H28年出題>
<H28年出題>
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによる。
・終身また5年以上、毎年1回以上定期的に支給すること
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
老齢給付金は、年金として支給するのが原則。
規約で定めた場合は、その全部又は一部を一時金として支給できる。
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
「毎月、翌月末までに」が誤り。
掛金の拠出は「年1回以上、定期的に」です。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
 <R2問6B>
<R2問6B>
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
 <R2問6C>
<R2問6C>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
 <R2問6E>
<R2問6E>
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】
 <R2問6B> ×
<R2問6B> ×
「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」です。
加入者が掛金の全部を負担することはできません。
 <R2問6C> ×
<R2問6C> ×
「終身又は10年以上」ではなく「終身又は5年以上」です。
 <R2問6E> ×
<R2問6E> ×
老齢給付金の受給権は、消滅は次の3つです。
1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
老齢給付金は「一時金」として支給されることもあるので、「3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。」も消滅事由としておさえてください。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(労働一般常識)
R3-031
R2.9.23 過去の論点は繰り返す(R2・メンタルヘルスケア対策)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
メンタルヘルスケア対策
<H26年出題>
「平成24年労働者健康状況調査(厚生労働省)」参照
メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合は半数近くに達しており、事業所規模別にみると、300人以上の規模では9割を超えている。

【解答】 ○
解答は「〇」ですが、データが平成24年のもので、数字も変化しているので覚えなくていいです。「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所の割合」が問われたということだけおさえていればOKです。
なお、「労働者健康状況調査」は平成24年をもって廃止されています。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問2C>
※「平成30年労働安全衛生調査(実態調査)(常用労働者10人以上の民営事業所を対象)(厚生労働省)」の概況を参照
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は約6割となっている。

【解答】 〇
労働安全衛生調査(実態調査)は平成25年から始まっています。
平成30年労働安全衛生調査(実態調査)によると、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 59.2%です。
ちなみに、取組内容(複数回答)は、
・ストレスチェックが 62.9%で最も多い。次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が 56.3%。
シリーズ・歴史は繰り返す(厚生年金保険法)
R3-030
R2.9.22 過去の論点は繰り返す(R2・厚年「障害手当金・治っていなければ?」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
障害手当金「治っていなければ?」
問題<H27年出題>
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。

【解答】 〇
障害手当金は「傷病が治っていること」が要件です。
条文を確認してみると、
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
※初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていることが条件
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問10エ>
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。

【解答】 〇
| 障害厚生年金 | 障害認定日(※) | 1級、2級、3級 |
| 障害手当金 | 初診日から起算して5年を経過する日までの間に おけるその傷病の治った日 | 3級よりも軽い |
※障害認定日とは
・初診日から起算して1年6月を経過した日
又は
・初診日から1年6月以内にその傷病が治った日があるときは、その治った日
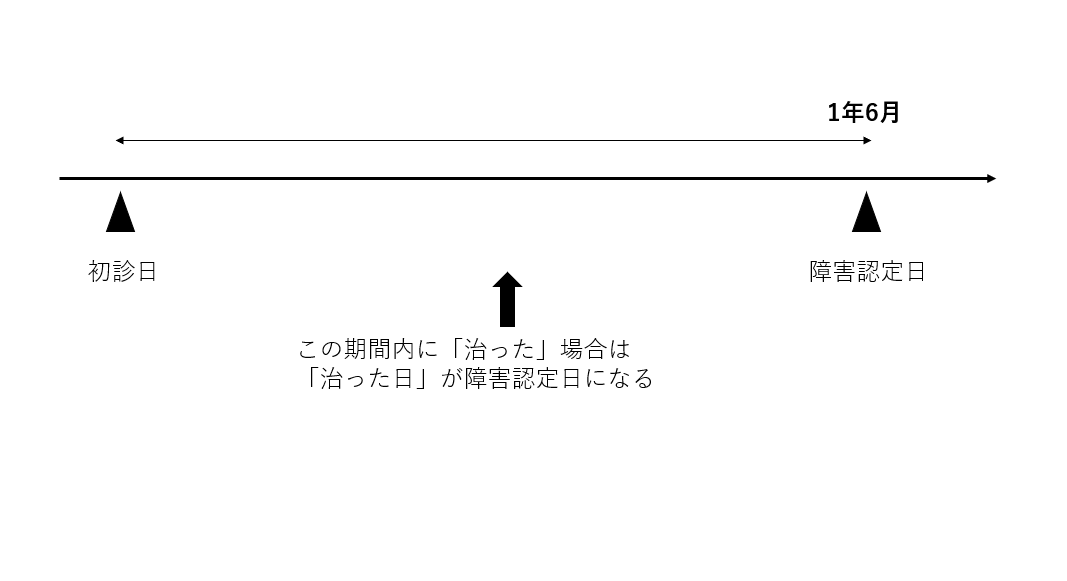
初診日から1年6月以内に傷病が治った場合は、その日が障害認定日になりますが、その傷病が治らなくても、初診日から1年6か月を経過した日に、障害等級に該当する程度の状態なら、障害厚生年金の支給要件を満たします。
障害厚生年金は治らなくても、支給要件は満たせます。
一方、障害手当金は「治った」ことが要件です。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(国民年金法)
R3-029
R2.9.21 過去の論点は繰り返す(R2・国年「死亡一時金の要件」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
死亡一時金の要件
問題<H24年出題>
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

【解答】 ×
全額免除期間は、36月の月数の計算には入りません。
全額免除期間は、保険料の負担が「ゼロ」だった期間。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のためのものなので、保険料の負担のなかった期間(=全額免除期間)は計算に入りません。
<死亡一時金の支給要件>
・死亡日の前日の保険料納付要件
・死亡日の前月まででみる(前々月ではない)
| 保険料納付済期間の月数 | 1 |
| 保険料4分の1免除期間の月数 | 4分の3 |
| 保険料半額免除期間の月数 | 2分の1 |
| 保険料4分の3免除期間の月数 | 4分の1 |
・合算して36月以上あること
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問3D>
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】 ×
死亡一時金の保険料納付要件は、36月。
問題文の場合、18か月+24か月×2分の1=30月となります。(全額免除期間は計算に入れません)
要件を満たさないので、死亡一時金は支給されません。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(健康保険法)
R3-028
R2.9.20 過去の論点は繰り返す(R2・健保「地域型健康保険組合」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
地域型健康保険組合
 問題<H21年出題>
問題<H21年出題>
合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合に該当する組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3か年度に限り、一定の範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
 問題<H21年出題>
問題<H21年出題>
地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。

【解答】
 問題<H21年出題> ×
問題<H21年出題> ×
3か年度ではなく「5か年度」です。
合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限って、不均一の一般保険料率の設定が認められています。
 問題<H21年出題> ×
問題<H21年出題> ×
2分の1以上ではなく、「3分の2」以上です。
不均一の一般保険料率の決定の認可を受けようとするときは、組合会で組合会議員の定数の3分の2以上の多数による議決が必要。
 「地域型健康保険組合」ときたら数字です!「5か年度」と「3分の2」
「地域型健康保険組合」ときたら数字です!「5か年度」と「3分の2」
「地域型健康保険組合」→ 同一都道府県内の健康保険組合の再編・統合の受け皿。企業・業種を超えての設立が認められている。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問1E>
地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

【解答】 〇
平成21年と同じ問題です。
「数字」がポイントだと知っていれば、問題文を全部読む必要ありません。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(徴収法)
R3-027
R2.9.19 過去の論点は繰り返す(R2・徴収「有期事業の延納」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
有期事業の延納
 問題<H22年出題>
問題<H22年出題>
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
 問題<H29年出題>
問題<H29年出題>
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。

【解答】
 問題<H22年出題> 〇
問題<H22年出題> 〇
「最初の期」の取り方と納期限が問われている問題です。
 問題<H29年出題> 〇
問題<H29年出題> 〇
平成22年の問題と同じですが、さらに延納回数も問われています。
図で確認しましょう。
有期事業の延納は、「最初の期」の取り方が肝心です。
まずは基本形を書いてみて、「保険関係成立の日」の日を置いてみてください。
保険関係成立の日からその日の属する期の末日まで、「2月超える」なのか「2月以内」なのかがポイントです。
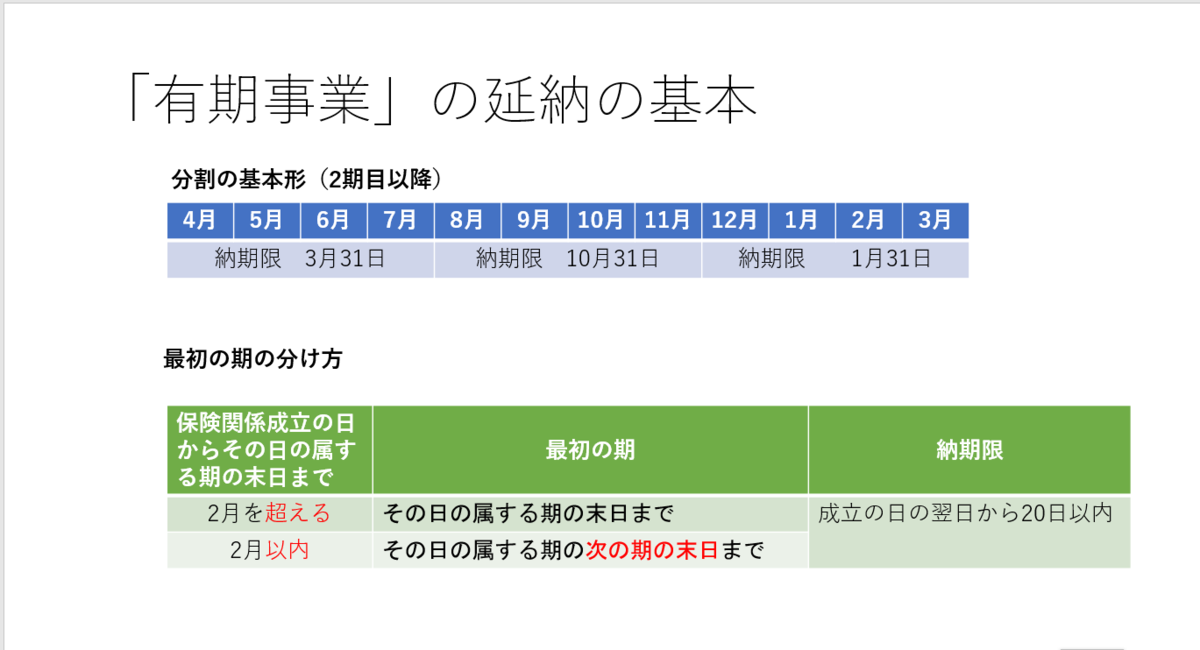
平成22年の問題は、保険関係成立の日が「7月1日」。
その日の属する期の末日まで2月以内なので、次の期の末日までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(7月2日)から20日以内なので、「7月21日」です。
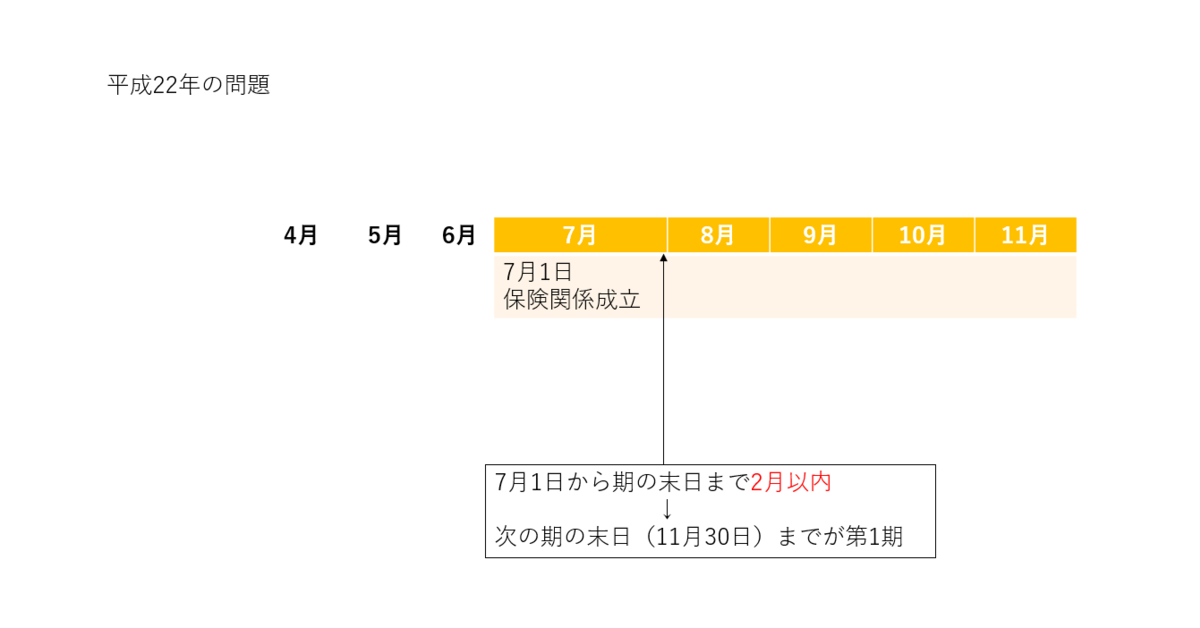
次は平成29年の問題。
こちらは、保険関係成立の日が「6月15日」。
その日の属する期の末日まで2月以内なので、次の期の末日までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(6月16日)から20日以内なので、「7月5日」です。
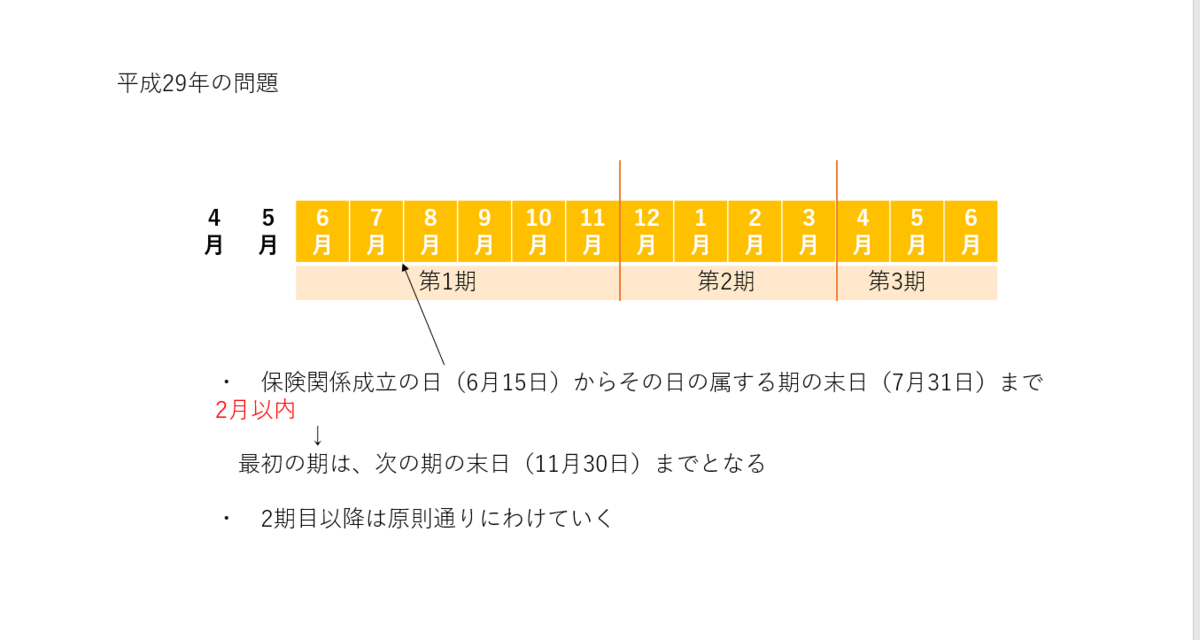
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2雇用問8B>
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。

【解答】 〇
保険関係成立の日が「6月1日」。
その日の属する期の末日(7月31日)まで2月以内なので、次の期の末日(11月30日)までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(6月2日)から20日以内なので、「6月21日」です。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(雇用保険法)
R3-026
R2.9.18 過去の論点は繰り返す(R2・雇用「不正受給による給付制限」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
不正受給による給付制限
 問題<H23年出題>
問題<H23年出題>
受給資格者が偽りの理由によって不正に広域求職活動費の支給を受けようとしたときには、その受けようとした日以後、当該受給資格に係る基本手当は原則として支給されないが、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
 問題<H26年出題>
問題<H26年出題>
偽りその他不正な行為により就職促進給付を受けたことにより処分を受けた者が、給付を受けた日以後新たに受給資格を取得した場合には、その受給資格に基づく就職促進給付を受けることができる。

【解答】
 問題<H23年出題> 〇
問題<H23年出題> 〇
まず条文を確認してみましょう。
第34条
1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。
2 1に規定する者が1に規定する日以後新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。
 勉強の手順
勉強の手順
①「何」の給付を不正受給したら、「何」の給付が制限されるの?
・求職者給付又は就職促進給付を不正受給
↓
基本手当を支給しない
②やむを得ない理由がある場合は?
↓
基本手当の全部又は一部を支給することができる
③新たな受給資格ができた場合は?
↓
新たに取得した受給資格に基づく基本手当は支給される
★この問題は、上記手順の②に該当します。
 問題<H26年出題> 〇
問題<H26年出題> 〇
条文を確認すると、
第60条
1 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
2 1に規定する者が1に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
上記の の手順で条文を読むと、
の手順で条文を読むと、
①求職者給付又は就職促進給付を不正受給
↓
就職促進給付を支給しない
②やむを得ない理由がある場合は?
↓
就職促進給付の全部又は一部を支給することができる
③新たな受給資格等ができた場合は?
↓
新たに取得した受給資格等に基づく就職促進給付は支給される
★この問題は上記手順の③に該当します。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
 <R2問5B>
<R2問5B>
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。
 <R2問5D>
<R2問5D>
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。
 <R2問5E>
<R2問5E>
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由として基本手当の給付制限を受けない。

【解答】
 <R2問5B> 〇
<R2問5B> 〇
平成23年の過去問の 勉強の手順で解けます。
勉強の手順で解けます。
手順③に該当します。
 <R2問5D> ×
<R2問5D> ×
第61条の8より
 手順
手順
① 育児休業給付金を不正受給
↓
以後、育児休業給付金を支給しない
② やむを得ない理由がある場合は?
↓
育児休業給付金の全部又は一部を支給することができる。
③ 新たに育児休業給付金の支給を受けることができる者となった場合は?
↓
新たな受給資格に係る育児休業給付金を支給できる
★手順③に該当します。
新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができるので「×」です。
 <R2問5E> 〇
<R2問5E> 〇
第61条の3より
① 高年齢雇用継続基本給付金を不正受給
↓
高年齢雇用継続基本給付金は支給しない
② やむを得ない理由がある場合は?
↓
高年齢雇用継続基本給付金の全部又は一部を支給することができる
★ 手順①によると、偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者が制限される給付は「高年齢雇用継続基本給付金」です。基本手当の給付制限はありません。
ちなみに、「高年齢再就職給付金」についても確認しておくと
①「高年齢再就職給付金」又は「当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付」を不正受給した場合は
↓
高年齢再就職給付金は支給されない
②やむを得ない理由がある場合は、
↓
高年齢再就職給付金の全部又は一部を支給することができる
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(労災法)
R3-025
R2.9.17 過去の論点は繰り返す(R2・労災「加重障害」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
障害/加重
問題<H30年出題>
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。

【解答】 〇
例えば、既に7級の身体障害があり、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度が4級に加重した場合は、
↓
新しい障害等級(4級)の障害補償生年金の額から、もともとの障害等級(7級)の障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給されることになります。
簡単に言うと、4級と7級の差額の障害補償年金が支給される、ということです。
↓
なお、既存の障害は、業務上、業務外を問いません。
問題文のように、既存の障害が業務上だった場合は、既存の障害補償年金(7級)は継続して支給されます。
差額の年金と既存の年金の2本立で支給されます。
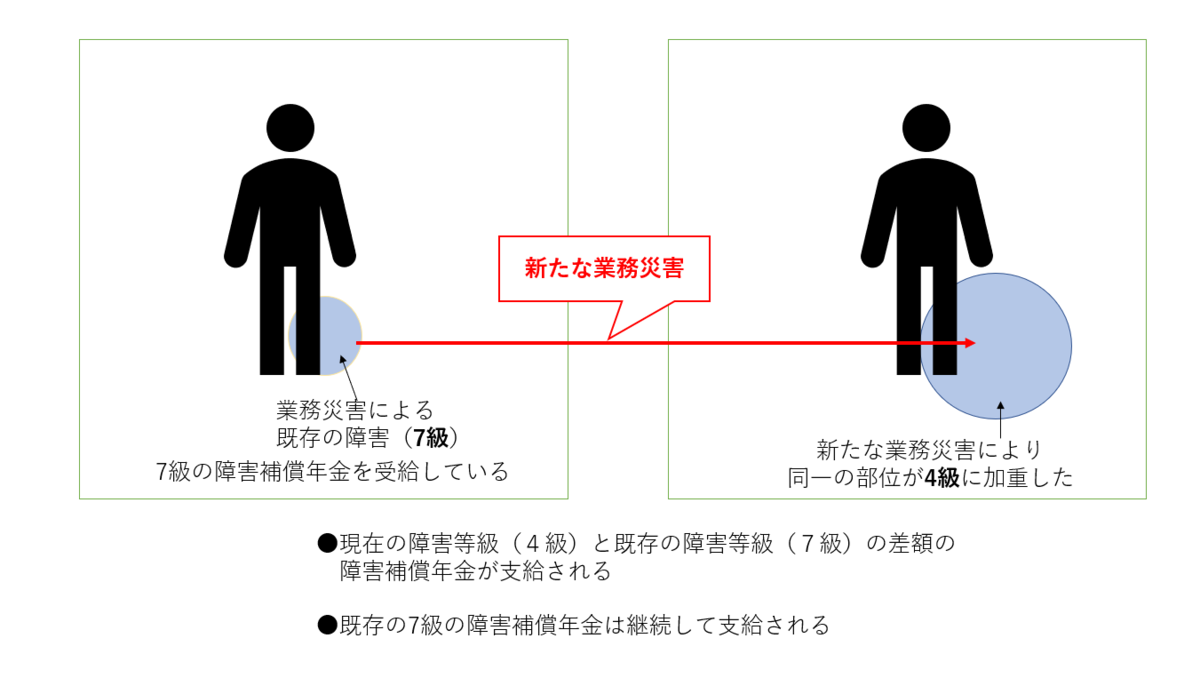
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2年問5より>
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11条の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 給付基礎日額の67日分
B 給付基礎日額の156日分
C 給付基礎日額の189日分
D 給付基礎日額の223日分
E 給付基礎日額の379日分

【解答】 A 給付基礎日額の67日分
先ほどの過去問と同じ考え方です。
新しい等級(11級)と既存の等級(12級)の差額が支給されます。
223日分 - 156日分 = 67日分です。
12級も11級も「一時金」ですので、67日分の一時金が支給されます。
 では、既存の等級が「一時金」、現在の等級が「年金」の場合は?
では、既存の等級が「一時金」、現在の等級が「年金」の場合は?
<H21年出題>
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

【解答】 〇
加重前の等級は「一時金」、加重後の等級が「年金」に該当するパターンです。
この場合も、「差額」となりますが、「差額」の出し方がポイントです。
例えば、加重前の等級が10級、加重後の等級が5級の場合、差額は、5級の年金額から10級の一時金の額の25分の1を差し引いて算出します。
 ポイントは、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1であること。
ポイントは、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1であること。
一時金は、25年分の年金をまとめて1回で支払った額とされていますので、一時金を25で割ることによって1年分の額が計算できるのです。
問題文の場合、新たな等級の障害補償年金から既存の等級の障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額が支給されます。
「加重障害」の問題はパターンが3つ
| 加重前 | 加重後 | 過去問 |
| 年金(7級以上) | 年金(7級以上) | H30年 |
| 一時金(8級以下) | 年金(7級以上) | H21年 |
| 一時金(8級以下) | 一時金(8級以下) | R2年 |
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(安衛法)
R3-024
R2.9.16 過去の論点は繰り返す(R2安衛法・長時間労働者の面接指導)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
長時間労働者に対する面接指導
問題<H21年出題(改)>
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。

【解答】 ×
「本人の申出の有無にかかわらず」の部分が誤り。
長時間労働者に対する面接指導は、「労働者の申出」により行います。
 「労働者からの申出の有無」が論点になることをおさえてください。
「労働者からの申出の有無」が論点になることをおさえてください。
では、令和2年度の問題から2問どうぞ!
 <R2年問8Bより>
<R2年問8Bより>
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
 <R2年問8Cより>
<R2年問8Cより>
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

【解答】
 <R2年問8Bより> ×
<R2年問8Bより> ×
「研究開発業務に従事する労働者の面接指導」
労働者の申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならないのは、80時間ではなく「100時間超」です。
 <R2年問8Cより> 〇
<R2年問8Cより> 〇
「高度プロフェッショナル制度の対象の労働者に対する面接指導」
「100時間超」と「申出の有無にかかわらず」がポイントです。
まとめ
| ■長時間労働者に対する面接指導 |
| 時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積 労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない |
| ■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導 |
| 時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
| ■高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導 |
| 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える 労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない |
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(労基法)
R3-023
R2.9.15 過去の論点は繰り返す(R2労基・法令等の周知義務)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
労働基準法第106条 法令等の周知義務
問題<H16年出題>
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。

【解答】 ×
労働基準法及びこれに基づく命令 → 要旨を周知すれば足りる
就業規則 → 全文の周知が必要(要旨だけではダメ)
 条文を確認しましょう。
条文を確認しましょう。
第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項(貯蓄金の管理)、第24条第1項ただし書(賃金の一部控除)、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の3第1項(フレックスタイム制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)、第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外)、第36条第1項(三六協定)、第37条第3項(代替休暇)、第38条の2第2項(事業場外労働のみなし労働時間制)、第38条の3第1項(専門業務型裁量労働制)並びに第39条第4項(時間単位年休)、第6項(有給休暇の計画的付与)及び第9項ただし書(有給休暇の賃金)に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(企画業務型裁量労働制)(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項(高度プロフェッショナル制度)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
なお、就業規則だけでなく、労使協定、労使委員会の決議も全文を周知する必要があります。
労使協定、労使委員会の決議で周知が義務付けられるのは、「労働基準法に規定する」労使協定、労使委員会の決議です。
では、令和2年度の問題から2問どうぞ!
 <R2年問2Aより>
<R2年問2Aより>
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
 <R2年問2Bより>
<R2年問2Bより>
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

【解答】
 <R2年問2Aより> ×
<R2年問2Aより> ×
就業規則は、全文の周知が必要
 <R2年問2Bより> ×
<R2年問2Bより> ×
周知義務は、対象労働者に対してのみではなく、すべてが対象。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(国民年金法)
R3-022
R2.9.14 第52回試験・択一国年の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 国年 択一式
厚生年金保険と同様に、テキストと過去問で対応できる問題で、これなら勉強の成果が出せると思いました。
ただ、テキストや過去問の記載そのままではありませんので、丸暗記ではちょっと厳しい。
テキストのアンダーライン部分、過去問で「誤り」とされた部分の言わんとする意味を知っておく必要があります。
背景や理由を知っておくと勉強が格段に楽になります。
 遺族基礎年金は「子」のための年金
遺族基礎年金は「子」のための年金
問2 E
「遺族基礎年金」を受給できる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者又は子
↓
「配偶者」については、「子と生計を同じくすること」が要件
↓
言い方を変えると、遺族基礎年金を受給できる「配偶者」には必ず子がいる
↓
ということは、配偶者の受給する遺族基礎年金には、子の数に応じた加算額が必ず加算されている
ですので、問2E「被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。」は「〇」です。
遺族基礎年金は「子」のための年金だということを意識してください。
 付加保険料は、老齢基礎年金の上乗せを目的に納付する保険料
付加保険料は、老齢基礎年金の上乗せを目的に納付する保険料
問3 E
「付加保険料」は老齢基礎年金の上乗せを目的として、国民年金保険料に付加して支払うもの
↓
対象は第1号被保険者のみ
(第2号、第3号被保険者はそもそも国民年金保険料を負担していないので不可)
↓
では、任意加入被保険者は、付加保険料を支払うことができるか??
↓
(一般の)任意加入被保険者は、「老齢基礎年金」を増やす目的でも加入できるので、付加保険料も納付できる
↓
しかし、特例の任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)は、老齢基礎年金を増やす目的ではなく、「受給資格」を得るための加入なので、付加保険料は納付できない
ですので、問3E「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。」は「〇」です。
(特例ではない一般の任意加入被保険者なので、付加保険料の納付OK)
全体的に 何にでも「理由」がある。「理由」を意識すると丸暗記はいらない。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(厚生年金保険法)
R3-021
R2.9.13 第52回試験・択一厚年の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 厚年 択一式
問題の文章は長いですが、テキストと過去問の論点をしっかり勉強していれば、解ける問題でした。
勉強の成果が出せる問題だと思いました。
 なるべく単純に覚える。
なるべく単純に覚える。
例えば、問2の問題。
・事業主の届出の提出期限は「5日以内」がほとんどです。
まずは基本的に事業主の届け出=「5日以内」を覚える。
そして、例えば「報酬月額変更の届出」のように「速やかに」届出るものは例外的に覚える。
「例外」を覚えて、それ以外は5日という覚え方が効率的です。
・船舶の届出の提出期限は「10日以内」がほとんどです。
私は、船は海の上なので距離がある。だから5日の2倍の10日と覚えています。
・被保険者の届出の提出期限は「10日以内」がほとんどです。
こちらも「速やかに」を例外的に覚える方法で大丈夫です。
 問題文は「ポイント」だけ読む
問題文は「ポイント」だけ読む
例えば、問4の問題
Aについて
障害厚生年金の「初診日」の要件は、「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」
↓
高齢任意加入被保険者も厚生年金保険の被保険者。
↓
高齢任意加入被保険者期間中に初診日がある場合は、初診日要件は満たしている
↓
保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金は支給される
Eも同じです。
障害厚生年金の要件は「初診日に厚生年金保険の被保険者であること」
初診日に国民年金の第1号被保険者で、その後、厚生年金保険の被保険者になってから障害等級3級になったとしても
↓
障害厚生年金は受給できない。(初診日に厚生年金保険の被保険者でないので)
全体的に できるだけ単純に考える。ポイントをつかむ勉強を。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(健康保険法)
R3-020
R2.9.12 第52回試験・択一健保の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 健保 択一式
感想を一言で表すと、「難しかった!」。
テキストで「見たことない」と焦った方も多かったと思います。
「テキストで見たことない」記述は、「もしかしたら、そんな規定もあるかもしれない」と思ってしまうので、本当に難しいですね。
しかし、難しい中にも、探せばヒントは隠れています。

例えば、高額長期疾病(「人工透析」「血友病」「後天性免疫不全症候群」の3つ)は負担軽減のため、自己負担限度額が1万円となっていますが、「人工透析」のみ、70歳未満・標準報酬月額53万円以上の者は2万円となっています。
過去にも出題されたポイントですので、ここが分かれば、問4は解けます。

ア 被扶養者の要件について、「被保険者が世帯主であることは要しない」
イ 任意継続被保険者の申出は資格を喪失した日から20日以内。ただし、正当な理由があるときは期間経過後でも受理できるという例外あり。
ウ 4カ月以内の季節的業務に使用される者は、たまたま業務の都合で4か月を超えても被保険者にはならない。
アイウが×と判断できるので、問5は解けます。

資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、「特例退職被保険者」には支給されない。この規定も過去に出題されたポイントです。これが分かれば問6も解けます。

任意継続被保険者は保険料の前納ができます。前納の額は、「年4分の利率による複利現価法により、前納期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額」です。「割引」はよく出題されるポイントです。
「前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額」ではなく、割引があることをおさえていれば問7も解けます。
過去問の基本事項だけでも4問は解けました。
全体的に 勉強はまんべんなく。重箱の隅はほっておく。基本事項をおさえていれば、合格ラインに届く。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(社保一般常識)
R3-019
R2.9.11 第52回試験・択一社一の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 社保一般常識 択一式
問6 確定給付企業年金法
問7 船員保険法
問8 児童手当法
問9 社会保険審査官及び社会保険審査会法
問10 社会保険制度の費用の負担及び保険料等
白書等からの出題は無く、すべて法令からの出題でした。
問6 確定給付企業年金法
テキストの基本事項をおさえていればOK。
特に、確定拠出年金法との横断的な整理は必須です。
問7 船員保険法
一般の会社員が加入する「健康保険法」と比べると、船員が加入する「船員保険法」は、給付内容が手厚く設計されています。
健康保険法の給付内容と比較しながら、「違う点」を意識して勉強するのがポイントです。
問8 児童手当法
対策は、テキストの基本事項と過去問で大丈夫です。
問9 社会保険審査官及び社会保険審査会法
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法の不服申し立ての勉強でカバーできたと思います。
問10 社会保険制度の費用の負担及び保険料等
テキストと過去問の勉強でOKです。
全体的に 「横断」学習が効果的。「同じところ」「違うところ」を意識しながら。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(労働の一般常識)
R3-018
R2.9.10 第52回試験・択一労一の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 労働の一般常識 択一式
問1 「平成30年若年者雇用実態調査」
問2 「平成30年労働安全衛生調査」
問3 労働関係法規
問4 労働組合法等
問5 社会保険労務士法
問1
若年者雇用実態調査は、平成17年、平成21年、平成25年、平成30年に実施されています。(ほぼ4~5年おき)
若年者雇用実態調査は厚生労働省のホームページで公開されています。
コチラ→ 厚生労働省「雇用の構造に関する実態調査(若年者雇用実態調査)」
平成25年調査の結果は、平成28年の本試験で丸ごと5問出題されています。調査が4~5年おきなので、出題もそれくらいの頻度になると予測して、このサイトでも、2回にわたって取り上げました。
ご参考にどうぞ。
平成28年の出題パターンとほぼ同じでした。労働一般常識も過去問は必須ですね。
問3
正解の肢は単体で見ると難しい。が、消去法でなんとか解ける。
問5
社労士法。「社一」ではなく「労一」で登場。
明らかな数字誤り(60万円×)はOK。が、もう一つは迷ったのでは?
社会保険労務士会の注意勧告の条文は昨年も出題されていたところ。「会則の定めにかかわらず」の部分が「ナンカアヤシイ」とピンとくれば、大丈夫だったと思いますが。。。
全体的に 「統計」問題も過去問対策は必要。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(徴収法)
R3-017
R2.9.9 第52回試験・択一徴収法の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 徴収法 択一式
基本に忠実かつ過去の出題傾向に沿った問題で、解きやすかったと思います。
徴収法は過去問中心の勉強で大丈夫。
問10(雇用)に不服申し立ての問題がありました。
徴収法には不服申し立ての規定がありませんので、処分に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。
審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。ただし、「正当な理由があるときは、この限りでない。」という例外が設けられています。
問題文は、「当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない」となっているので「×」です。
全体的に 徴収法はブレずに過去問。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(雇用保険法)
R3-016
R2.9.8 第52回試験・択一雇保の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 雇用保険 択一式
各問題の主題をまとめるとこのようになります。
↓
問1 被保険者資格の得喪と届出
問2 失業の認定
問3 基本手当の延長給付
問4 傷病手当
問5 給付制限
問6 雇用保険制度
問7 能力開発事業
↓
雇用継続給付や教育訓練給付、今年の改正点からの出題はありませんでした。
通常のテキストではあまり見たことのない部分からの出題も多かったので、難しかったのではないでしょうか?
それでも、例えば「傷病手当」は「求職の申し込みをした後」に傷病のため職業に就くことができなくなった人が対象であるという条件をつかんでいれば、それをヒントに考えることはできるように思います。
全体的に 一見難しそうな問題でもどこかにヒントあり。あきらめないで。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(労災保険法)
R3-015
R2.9.7 第52回試験・択一労災の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 労災 択一式
問3の特別加入することができる「厚生労働省令で定める種類の作業」は、少々難しい。問4の罰則規定も完璧には覚えられない部分です。
それ以外は、だいたい大丈夫だと思います。と言いましても、丸暗記で解ける問題ではなく、覚えていたことを頭の中で論理的に組み立てながら問題を解く感じになったと思います。
問1は支給制限の問題ですが、「故意の犯罪行為」の場合、「全部又は一部を行わないことができる。」です。が、問題文は「全部又は一部を行わないとすることはできない」となっているので、文章をひっくり返して読まないといけない。「えーと」と考えるのに少し時間がかかってしまいました。
問4は、「D」が正解ですが、同一の災害で身体障害が2以上ある場合に、重いほうの障害等級となる。それは「一方の障害が第14級」に該当するときという部分がポイントです。
13級以上の障害が2以上ある場合は、重いほうを1級~3級繰り上げることになるので。
問7は、「休業特別支給金」の申請は「5年」じゃなくて2年というポイントをおさえていれば、自動的に「D」が選べたと思います。
全体的に きちんと勉強した方にとっては、解きやすい良い問題だったと思います
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(労働安全衛生法)
R3-014
R2.9.6 第52回試験・択一安衛法の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 安衛法 択一式
超マニアックな難問が無かった。テキストや過去問をきちんと勉強していた方には、解きやすかったと思います。
 問8のポイント → 「80時間」と「100時間」の違いと「申出の有無」
問8のポイント → 「80時間」と「100時間」の違いと「申出の有無」
■長時間労働者に対する面接指導
時間外・休日労働が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積
労働者からの申出があった場合 → 面接指導を行わなければならない
■新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導
時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える
労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない
■高度プロフェッショナル制度により労働者に対する面接指導
1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1月当たり100時間を超える
労働者からの申出の有無にかかわらず → 面接指導を行わなければならない
 問9
問9
A~Dまで明らかな間違いがないので、「E」が選べる。消去法方式。
 問10
問10
Aが明らかに誤り。臨時の労働者に対しても安全衛生教育は努力義務ではなく、義務なので。
全体的に 難問が無かったので、落ち着いて解けたと思います。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(労働基準法)
R3-013
R2.9.5 第52回試験・択一労働基準法の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 労基法 択一式
一肢ずつ見ると、「あまり見たことない・・・?」ような肢があって、それが答えになっている問題が多いように感じました。
でも、基本的な肢をつかって消去法で解いていくと、正解にたどりつく出題でした。
例えば、問1で考えると、
A 事業主の定義
株式会社の場合、事業主は「法人そのもの」のことで代表取締役ではない
B 使用者の定義
使用者に当たるか否かは、役職名ではなく、与えられた責任と権限の有無によるので、係長が使用者になることもあり得る
C 使用者の定義
Bと同様。役職が課長でも、権限外の事項を単に伝達しただけでは、使用者とはみなされない
E 労働者派遣の使用者
指揮命令関係にある派遣先も、労働基準法の使用者として責任を問われる部分がある。
消去法で、解答は「D」となります。
全体的に 労働基準法でかなりの部分を占める「労働時間」に関する問題が1問しかなかった。。。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(国民年金法)
R3-012
R2.9.4 第52回試験・選択(国年)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 国年 選択式
1 年金額の改定からの出題
年金額の改定のルールで、よく注意して見ていた条文だったと思います。
2 遺族基礎年金についての出題
遺族基礎年金には、「短期要件」と「長期要件」がありますが、保険料納付要件が問われる短期要件からの出題でした。
3 基礎年金拠出金についての出題
「実施機関たる共済組合等」。いつも思いますが、覚えにくい用語ですね。。。
ただ、選択肢の中からは選びやすかったと思います。
ポイント! 基本を大切に
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(厚生年金保険法)
R3-011
R2.9.3 第52回試験・選択(厚年)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 厚年 選択式
1 被保険者に対する情報の提供からの出題
「理解」を増進させるのはわかるけれど「誰の理解」を増進させるのか?が論点の問題です。
この条文は、後半の『「被保険者」に対し』と『「当該被保険者の保険料納付の実績・・・』の部分がクローズアップされることが多いので、今回の論点は意外な部分でした。
2 老齢厚生年金の繰下げについての出題
ヒントは次の2点です。
・繰下げの申出までは受給権を取得してから1年待たなければならない
・65歳以上の老齢厚生年金は、障害基礎年金と併給できる
3 離婚分割についての出題
基本的な個所からの出題。迷わずに。
ポイント! 勉強は繰り返し繰り返し。繰り返すことで見えてくる。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(健康保険法)
R3-010
R2.9.2 第52回試験・選択(健保)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 健保 選択式
1 社会保険医療協議会への諮問からの出題
「地方社会保険医療協議会」「中央社会保険医療協議会」の役割の違いをおさえていればOKな問題でした。
 「中央社会保険医療協議会」→ 厚生労働省に置く
「中央社会保険医療協議会」→ 厚生労働省に置く
 「地方社会保険医療協議会」→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置く。
「地方社会保険医療協議会」→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置く。
※ 地方社会保険医療協議会は、『保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもって答申するか、自ら厚生労働大臣に、文書をもって建議することができる。』
2 一部負担金の割合についての出題
70歳以上の一部負担金の割合の問題ですが、5年前の平成27年にも選択式で出題されていました。
70歳以上の一部負担金の規定はポイントになる数字が多いので、選択式の問題が作りやすい。このような規定は、定期的に出題される可能性が高いと思います。
3 高額療養費の計算についての出題
この問題のポイントは、
・「高額療養費」と「高額療養費算定基準額(自己負担限度額)」を間違えない
・評価療養や選定療養は、高額療養費の対象外となる
4 資格喪失届の提出についての出題
令和2年1月1日施行の改正からの問題でした。
・資格取得の届出→所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由できる
・資格喪失の届出→所轄公共職業安定所長を経由できる
5 協会による広報及び保険料の納付の勧奨等についての出題
条文そのままの問題ですが、丸暗記は無理。このような問題は、前後の文脈、言葉の意味などを考えて当てはめてゆく方法で。
ポイント! テキストは「ポイント」を意識しながら読む。日々の積み重ねが大事。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(社保一般常識)
R3-009
R2.9.1 第52回試験・選択(社一)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 社保一般常識 選択式
1 平成29年社会保障費用統計からの出題です。
「120兆円」という数字は、新聞やネットで見かけた方も多いと思いますが、100兆、140兆、160兆と並んでいると、迷ってしまうかもしれません。
社会保障給付費の中で「年金」の占める割合が最も高いという部分は、解きやすかったのではないでしょうか?
例えば、会社員でも「健康保険」より「厚生年金」の保険料の方が高いので。(年金の方がお金がかかる)
2 介護保険料の滞納についての出題
介護保険料の滞納対応としての「保険給付の支払いの一時差し止め」のルールについてですが、択一式でも同じテーマの問題が出ていました。
「1年」「1年6カ月」を区別して覚えていればOKな問題です。
3 国民健康保険組合についての出題
そういえばあまり意識していなかった部分ですが、なんとなく選択できる問題です。
4 個人型確定拠出年金の掛金についての出題
国民年金第1号被保険者の掛金の上限(68,000円)は、国民年金基金との合算枠なのを覚えていればOKな問題でした。
ポイント! 択一式で出るような論点は選択式でも出る
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(労働一般常識)
R3-008
R2.8.31 第52回試験・選択(労一)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 労働一般常識 選択式
最近の出題傾向からみて、「統計調査は出そうだな」と思っていた方もいたのでは?
私もそう思っていました。
しかし、思ったよりも範囲が広かったです。
やはり、労働一般常識は「広く浅く」です。
今後の労働経済の勉強方法としては、単に数字の動きを見るだけでなく、その数字の出典となる「統計」のこと(名称や実施方法、実施機関など)も知っておく必要があると思います。
 よろしければご参考に。
よろしければご参考に。
R2.7.28 選択式の練習/平成31年就労条件総合調査より
R2.7.18 選択式の練習/労働力調査(令和元年平均)より
ポイント! 「統計」の目的や方法なども意識して
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(雇用保険)
R3-007
R2.8.30 第52回試験・選択(雇用保険)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 雇用保険 選択式
基本的な問題ばかりなのに、ドキドキするのは、「数字」の問題だから。
雇用保険法は、出てくる数字が多く、一つ間違うと、それにつながるものすべて間違えてしまうという怖さがあると思います。
雇用保険は数字が勝負だと思っています。
AとBは、雇用保険の「被保険者」の要件です。
こちらの記事(R2.6.23 選択式の練習/雇用保険の被保険者とならないもの)でも数字を取り上げましたが、例えば、20時間未満なら除外、逆に見ると20時間以上ならOKというように裏表をみないといけないパターンが多く、そこが雇用保険法の奥深いところのように思います。
CとDは、「資格取得届」の提出期限と提出先です。
これはバッチリですよね。
Eは「短期雇用特例被保険者」です。
これも数字がポイントになる問題です。
ポイント! 雇用保険はやっぱり数字
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(労災保険)
R3-006
R2.8.29 第52回試験・選択(労災保険)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 労災 選択式
「通勤」の定義からの出題です。
通勤の定義については定番問題ですが、単身赴任者の「住居間の移動」の要件の細かい部分からの出題は珍しいです。
住居間の移動の要件は、労働者災害補償保険法施行規則第7条に規定されています。
「なんとなく見たことがある」と思った方も多いのでは?
前後の文章の流れで空欄を埋めていくタイプの問題でした。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(安衛)
R3-005
R2.8.28 第52回試験・選択(労働安全衛生法)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 選択式(安衛)
D 海外派遣労働者の健康診断からの出題です。
基本的な部分なので、正解を選べたと思います。
ついつい、今まで出たことがない分野や、新しめの条文に目が行ってしまいますが、このように健康診断の基本部分が出題されることが多いです。
基本分野も疎かにしてはいけないと感じました。(自戒を込めて)
ポイント!基本事項も手を抜かず
E 労働安全衛生規則第526条(昇降するための設備の設置等)からの出題です。
ちょっと難しいです。マニアックです。
ここまできちんと覚えていた人は、いらっしゃらないのでは?
これは、解けなくても仕方ないと思います。
ポイント!難問に振り回されないように
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(労基)
R3-004
R2.8.27 第52回試験・選択労基
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 労基選択式
1 第96条の2の寄宿舎についての「監督上の行政措置」からの出題でした。
ちょっと意外な個所からの出題です。
「計画」なので、前もって届け出が必要、と考えると、2つまでは絞れます。「14日前まで」と自信をもって選べたかどうかでしょうか?
なお、平成21年に同じ論点の問題が択一式で出題されています。「工事着手30日前までに届け出」で「誤」の問題でした。
ポイント! 択一式の論点は、数年後に選択式で出題されることが多い
2 労基法上の「労働者性」についての最高裁判例からの出題です。
労働基準法第9条で「労働者」の定義が規定されています。
しかし、現実は、働き方が多様化していて、「労働者」に当たるか否か、判断に迷う事例が多々あります。
ですので、古典的ではあるものの、非常に今日的な論点の問題だと思いました。
でも、「C」の選択肢は難しいです。
明日は安衛法です。
社労士受験のあれこれ
1日何時間勉強する?
R3-003
R2.8.26 「思い」の強さを合格につなげる
「1日どれくらい勉強すればいいですか?」
よく聞かれる質問です。
もちろん、勉強時間は多ければ多いほど、合格に近づくはずです。
ただ、社労士受験を考えている方は社会人が圧倒的に多く、勉強ばかりに時間を割くのは無理という方が大半だと思います。
なので、冒頭の質問には、私は「1日24時間体制」と答えています。
机に向かって本を開いている時間だけをカウントするのではなく、ちょっと手が空いたら数字や条文を思い浮かべるとか、テキストは肌身離さず持っていて、気になることがあればパッとひらいてすぐ確認するとか・・・。「24時間体制で勉強を意識する」という方法です。
「思ったことや口に出したことは現実になる」と思いませんか?
いつも合格を意識して過ごしたら、絶対にそうなると思います。
社労士受験のあれこれ
時間の流れと継続
R3-002
R2.8.25 継続は力なり
去年の社労士試験から今年の社労士試験までの1年間。
あっという間に感じませんでしたか?
特に今年はコロナで、これまでの習慣や常識が急激に変わっていって。それでも受験勉強を続けてきたこと、素晴らしいと思います。
私がこのホームページを立ち上げたのは、平成27年秋で、もうすぐ5年になります。
最初のころは「社労士受験のあれこれ」を毎日更新していましたが、途中から、2~3日に1回ペースになっていました。
でも、今年の4月からは、毎日、更新しています。
なぜなら、「合格」をつかむには、毎日コツコツ勉強を続けるしかないから。
だから、受験勉強を応援する私も、毎日コツコツ発信しようと決めたのです。
あとは、何があっても続けるだけ。
「継続は力なり」という言葉がありますよね。
過去記事もありますので、良かったら見てください。
(当時の情報のままです。法改正で変わっている部分もありますので注意してください。)
社労士受験のあれこれ
コロナと酷暑の中で
R3-001
R2.8.24 本試験お疲れさまでした!
一夜明けました。
本試験、お疲れさまでした。
コロナと酷暑の中での試験は、本当に負担だったと思います。
とりあえず、ゆっくりしてくださいね。
試験問題の感想なども書いていきますので、またお読みください。
社労士受験のあれこれ