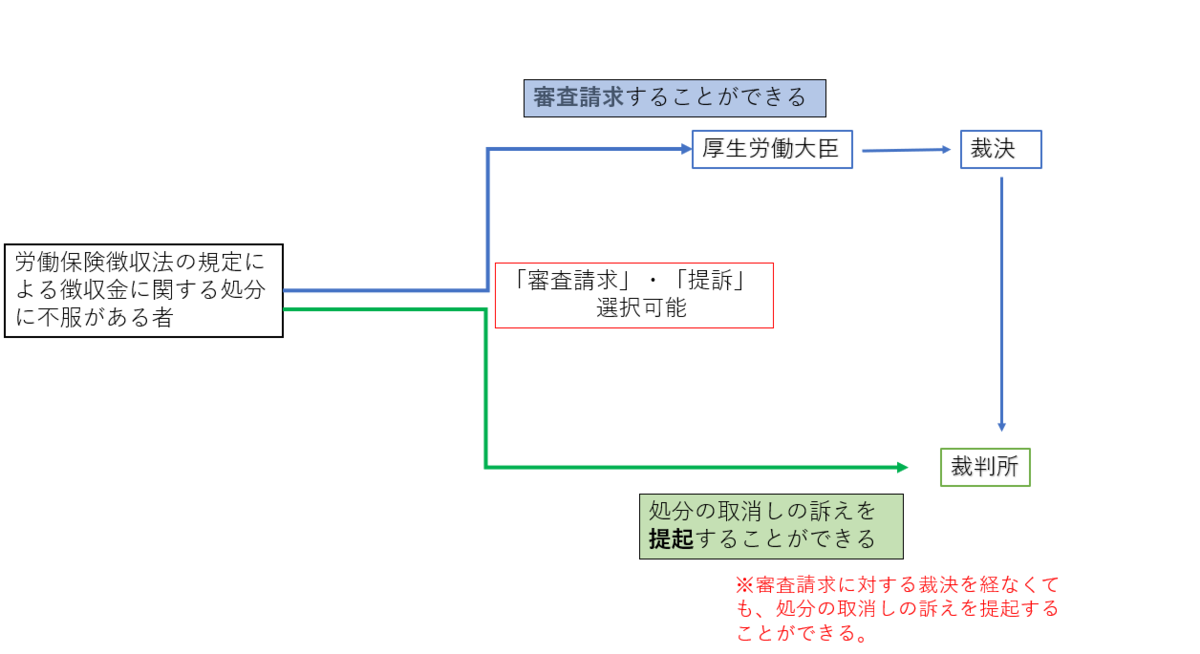合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
労働保険徴収法「特例納付保険料」
R8-088 11.20
特例納付保険料の納付
「労働保険料」には次の種類があります。
① 一般保険料
② 第1種特別加入保険料
➂ 第2種特別加入保険料
④ 第3種特別加入保険料
⑤ 印紙保険料
⑥ 特例納付保険料
今回は「特例納付保険料」をみていきます。
「特例納付保険料」は、雇用保険法の「特例対象者」に関する保険料です。
★「特例対象者」とは
事業主が、ある人について、雇用保険の「被保険者資格取得」の届出を行わなかった場合、その人は、雇用保険に未加入となります。
未加入のままだと、例えば、その人が離職した際に、基本手当が受給できなくなる可能性もあります。
その後、資格取得の届出をし、被保険者であったことが確認された場合は、通常は2年前まで遡及して雇用保険に加入することができます。(保険料の徴収時効が2年であるため)
2年を超えた期間については遡及することができませんので、基本手当の所定給付日数の算定などについて不利益が生じることがあり得ます。
ただし、雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された場合は、2年を超えて(雇用保険料の控除が確認された時点まで)遡及して加入することができます。(=特例対象者といいます)
<流れをイメージしましょう>
・事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことにより、雇用保険に適用されていなかった者について
↓
・被保険者資格の確認を行う日の2年前の日よりも前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合
↓
・保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い時期まで被保険者期間や所定給付日数を決定する算定基礎期間等に算入することができます。
(雇用保険法第14 条第2 項第2号、第 22条第5項)
★当該労働者を雇用していた事業主が、必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合
↓
・事業主が保険料を納付していないにもかかわらず失業等給付が支給されることになる
↓
・当該事業主は、保険料の徴収時効である2年経過後においても、保険料が納付できることになっています。(=特例納付保険料)
(徴収法第 26条)
(参照:行政手引25001)
「特例納付保険料」について条文を読んでみましょう
徴収法第26条 (特例納付保険料の納付等) ① 特例対象者を雇用していた事業主が、雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、保険関係成立の届出をしていなかった場合には、当該事業主(以下「対象事業主」という。)は、特例納付保険料として、対象事業主が納付する義務を履行していない一般保険料(被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日から当該特例対象者の離職の日までの期間に係るものであつて、その徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の額(雇用保険率に応ずる部分の額に限る。)のうち当該特例対象者に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に厚生労働省令で定める額を加算した額を納付することができる。 ② 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。 ➂ 対象事業主は、勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。 ④ 政府は、申出を受けた場合には、特例納付保険料の額を決定し、厚生労働省令で定めるところにより、期限を指定して、これを対象事業主に通知するものとする。 ⑤ 対象事業主は、申出を行った場合には、期限までに、厚生労働省令で定めるところにより、特例納付保険料を納付しなければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。

【解答】
①【R7年出題】(雇用) ×
特例納付保険料を納付することができる事業主は、特例対象者を雇用していた事業主です。
ただし、特例対象者は、「2年以内」ではなく、「2年を超えて」(事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された時点)遡及できる者です。
②【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。

【解答】
②【R7年出題】(雇用) 〇
概算・確定保険料の納付手続に係る規定は、特例納付保険料の納付手続には、適用されません。
➂【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】(雇用) 〇
「対象事業主は、勧奨を受けた場合においては、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、書面により申し出ることができる。」とされています。
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければなりません。
(則第58条)
④【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。

【解答】
④【R7年出題】(雇用) 〇
労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができます。
(法第33条)
⑤【R3年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付額は、労働保険徴収法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た同法第21条の追徴金の額を加算して求めるものとされている。

【解答】
⑤【R3年出題】(雇用) ×
特例納付保険料の納付額は、特例納付保険料の基本額に、当該特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額を加算したものです。
法第21条の追徴金の額を加算して求めるものではありません。
(則第56条、第57条)
⑥【H27年出題】(雇用)
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。

【解答】
⑥【H27年出題】(雇用) 〇
事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、通知します。
納付書ではなく「納入告知書」による点もポイントです。
(則第38条第5項、則第59条)
⑦【R7年出題】(雇用)
特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。

【解答】
⑦【R7年出題】(雇用) 〇
特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏です。
(則第38条第3項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「審査請求など」
R8-087 11.19
労働保険徴収法「不服申立て」
労働保険徴収法には、不服申立ての規定がありません。
労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、「行政不服審査法」に基づいて、審査請求を行います。
図でイメージしましょう
<パターン1>
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者 | ||
| ↓ 審査請求 | |
厚生労働大臣 |
| |
↓ | ||
処分の取消しの訴え(裁判所に提訴する) | ||
<パターン2>
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者 | ||
| ↓ | |
↓ |
| |
↓ | ||
処分の取消しの訴え(裁判所に提訴する) | ||
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

【解答】
①【H28年出題】(労災) ×
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、「厚生労働大臣」に対し、「審査請求」を行うことができます。
(行政不服審査法第4条第3号)
②【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。

【解答】
②【H28年出題】(労災)×
労働者災害補償保険審査官ではなく「厚生労働大臣」に対し、審査請求を行うことができます。
➂【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。

【解答】
➂【H28年出題】(労災) ×
厚生労働大臣に対し、再審査請求ではなく「審査請求」を行うことができます。
④【R7年出題】(雇用)
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分について不服がある者は、所轄都道府県労働局の労働保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
④【R7年出題】(雇用) ×
所轄都道府県労働局の労働保険審査官ではなく「厚生労働大臣」に対して審査請求をすることができます。
⑤【R2年出題】(雇用)
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

【解答】
⑤【R2年出題】(雇用) ×
審査請求期間については以下のように規定されています。
行政不服審査法第18条 ① 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ② 処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 |
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。ただし、正当な理由があるときは、審査請求期間を超えても審査請求することができます。
「審査請求期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない」は誤りです。
⑥【R7年出題】(雇用)
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、当該処分があったことを知った日から3か月以内かつ処分の日から1年以内でなければ、取消訴訟を提起することができない。

【解答】
⑥【R7年出題】(雇用) ×
出訴期間については以下のように規定されています。
行政事件訴訟法第14条 ① 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 ② 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 |
問題文の「3か月」は「6か月」となります。
⑦【H28年出題】(労災)
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

【解答】
⑦【H28年出題】(労災) 〇
行政事件訴訟法第8条で、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。」と規定されています。
概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、審査請求を経なくても、直ちにその取消しの訴えを提起することが可能です。
⑧【R7年出題】(雇用)
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経た後でなければ、当該処分の取消しの訴えを提起することができない。

【解答】
⑧【R7年出題】(雇用) ×
⑦の問題と同じです。
概算保険料額の認定決定の処分がなされ、当該処分に不服がある場合、審査請求の裁決を経なくても、当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「一括有期事業」
R8-081 11.13
一括有期事業のポイント!
例えば、建設現場などの「有期事業」は、有期事業ごとに、労働保険料を申告・納付します。
ただし、規模の小さい有期事業は、法律上当然に一括され、継続事業と同じ方法で、保険年度ごとに労働保険料を申告・納付します。この制度を「一括有期事業」といいます。
有期事業の一括の制度は、「労災保険」に係る保険関係のみに適用されることもポイントです。
では、条文を読んでみましょう
法第7条、則第6条 (有期事業の一括) 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、その全部を一の事業とみなす。 (1) 事業主が同一人であること。 (2) それぞれの事業が、有期事業(建設の事業・立木の伐採の事業)であること。 (3) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 ・概算保険料の額が160万円未満であること。 かつ ・ 建設の事業は、請負金額が1億8千万円未満 ・ 立木の伐採の事業は、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満 (4) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 (5)厚生労働省令で定める要件に該当すること。 ・それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 ・それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること。 ・それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
2以上の有期事業が有期事業の一括の対象になると、「当然に」それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用されます。労働保険料の申告、納付については、継続事業と同じく年度更新の手続きをとります。
(昭40.7.31基発901号)
②【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用による一括有期事業を開始したときには、初めに保険関係成立届を提出することとなるが、この届を一度提出しておけば、以後何年でもこの一括有期事業が継続している限り、当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はない。

【解答】
②【R7年出題】(労災) 〇
一括有期事業を開始したときには、「初めに」、保険関係成立届を提出します。
当該一括有期事業に含まれる個々の事業については、その都度保険関係成立届を提出する必要はありません。
➂【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用により一括された個々の有期事業について、その後、事業の規模の変更等があった場合には、当初の一括の扱いとされず、新たに独立の有期事業として取り扱われる。

【解答】
➂【R7年出題】(労災) ×
一括された個々の有期事業が、その後、事業の規模の変更等があった場合でも、新たに独立の有期事業としては取り扱われず、当初の一括の扱いのままとなります。
なお、当初は、単独の有期事業として成立した事業が、事業の規模の変更等で、その後、有期事業の一括のための要件を満たすにいたっても、一括の対象とはならず、単独のまま扱われます。
④【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされるための要件として、立木の伐採の事業以外の事業にあっては請負金額の上限が定められているが、当該請負金額を計算するに当たって、事業主が注文者からその事業に使用する機械器具等の貸与を受けた場合には、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業を除き、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除することとされている。

【解答】
④【R7年出題】(労災) ×
請負による建設の事業の「請負金額」の算定についての問題です。
事業主が注文者から機械器具等の貸与を受けた場合には、当該機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に「加算する」とされています。問題文の「控除する」は誤りです。
※厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合は、扱いが変わります。
(則第13条)
⑤【R3年出題】(労災)
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

【解答】
⑤【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の要件の一つは「事業主が同一人であること」です。事業主が同一人とは、その事業が同一の企業に属していることです。徴収法の事業主は、「元請負人」となり、下請負人は事業主に含まれません。
そのため、X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されません。
⑥【R7年出題】(労災)
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用される場合であって、労働保険徴収法施行規則第17条第3項で定める規模の事業のとき、同法第20条に規定するいわゆる有期事業のメリット制の適用対象とされる。

【解答】
⑥【R7年出題】(労災) ×
一括有期事業については保険年度ごとに保険料を申告・納付しますので、有期事業のメリット制ではなく、「継続事業」と同じ仕組みのメリット制が適用されます。
⑦【R4年出題】(労災)
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
⑦【R4年出題】(労災) 〇
一括有期事業については、確定保険料申告書を提出する際に、「一括有期事業報告書」を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(則第34条)
⑧【R7年出題】(労災)
労働保険徴収法第7条の適用により一括有期事業とみなされた場合、概算保険料申告書、確定保険料申告書は当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、一括有期事業報告書は一括された事業ごとに作成し、各事業の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官にそれぞれ提出しなければならない。

【解答】
⑧【R7年出題】(労災) ×
一括有期事業の事務については、「労働保険料の納付の事務を取り扱う一の事務所」の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とされます。(則第6条第3項)
「一括期事業報告書」は、その保険年度中に終了した一括有期対象事業をすべて記入し、当該一括有期事業に係る労働保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(則第34条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R8-053 10.16
「労働保険事務組合」のよく出る問題
「労働保険事務組合」でよく出る問題をみていきましょう
さっそく過去問をどうぞ!
①【R7年出題】(労災)
事業主は、労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続について、労働保険事務組合に処理を委託することができない。

【解答】
①【R7年出題】(労災) ×
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、「事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(労働保険事務)を処理することができます。
問題文の労災保険の特別加入の申請、変更届、脱退申請等に関する手続きは、労働保険事務組合が処理することができる手続きです。
★ポイント! 労働保険事務組合に処理を委託できない手続きをおさえましょう
・印紙保険料に関する事項
・保険給付に関する請求書等の手続き
・雇用保険の二事業に係る手続き
(法第33条第1項)
②【R7年出題】(労災)
事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理できる労働保険事務組合とは、労働保険徴収法第33条に規定する団体等であって法人でなければならない。

【解答】
②【R7年出題】(労災) ×
「法人」であるか否かは問われません。
なお、法人でない団体又は連合団体の場合は、「代表者の定め」があることのほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法(総会、執行機関、財産の管理運営方法等)等が定款、規約等その団体等の基本となる規則において明確に定められ、団体性が明確であることが必要です。
(厚生労働省「労働保険事務組合の設立と認可について」)
➂【R7年出題】(労災)
政府が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料等についての督促状による督促を、直接当該事業主に対してすることなく当該労働保険事務組合に対して行った場合、その効果は当該事業主に対して及ばない。

【解答】
【R7年出題】(労災) ×
督促の効果は事業主に対して「及びます」。
条文を読んでみましょう
法第34条 (労働保険事務組合に対する通知等) 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。 |
・労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、直接事業主に対してすることなく、労働保険事務組合に対してすることができます。
・通知等の効果は、事業主に及びます。
④【R7年出題】(労災)
督促状による督促があった旨の通知を労働保険事務組合から受けた滞納事業主が、労働保険事務処理規約等に規定する期限までに労働保険料の納付のための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、当該労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負う。

【解答】
④【R7年出題】(労災) ×
滞納事業主が、期限までに金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったために延滞金を徴収される場合、労働保険事務組合の責に帰すべき理由ではありませんので、労働保険事務組合は延滞金の納付責任を負いません。
条文を読んでみましょう
法第35条 (労働保険事務組合の責任等) ① 第33条第1項の委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ② 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ➂ 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して第27条第3項の規定(国税滞納処分の規定)による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 |
・労働保険事務組合は、事業主から交付を受けた金額の限度で、政府に対して徴収金を納付する責任を負います
⑤【R7年出題】(労災)
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に使用されていた者が、前年に当該労働保険事務組合の虚偽の届出により労災保険の保険給付を不正に受給していた場合、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができる。

【解答】
⑤【R7年出題】(労災) 〇
「労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定(不正受給者からの費用徴収)及び雇用保険法第10条の4第2項の規定(返還命令等)の適用については、事業主とみなす。」とされています。
(法第35条第4項)
労災保険法第12条の3を読んでみましょう
労災保険法第12条の3 ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 ② ①の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
・問題文のように、不正受給を行った場合に、それが労働保険事務組合の虚偽の届出によるものであるときは、政府は当該労働保険事務組合に対して、当該不正受給者と連帯し、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを命ずることができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「概算保険料・確定保険料」
R8-019 9.12
労働保険料を計算してみましょう
概算保険料と確定保険料の額の計算してみましょう。
問題を解きながらポイントをつかみましょう。
では、さっそく過去問を解いてみましょう
【R7年出題】(労災)
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
保険関係成立年月日:令和3年8月5日
事業の種類:小売業
労働保険関係の概要:
・保険料の滞納はない。
・一般保険料以外の対象となる者はいない。
・社会保険適用事業所である。
・令和7年度の概算保険料の額は875,000円である。
令和6年度及び7年度の労災保険率:1000分の3
令和6年度の雇用保険率:1000分の15.5
令和7年度の雇用保険率:1000分の14.5
令和7年度の雇用保険二事業の保険率:1000分の3.5
令和6年度の確定賃金総額:5,000万円
令和7年度に支払いが見込まれる賃金総額:6,000万円
A 令和6年度中に請負契約を締結し、使用従属関係が認められない労務提供を行った請負人に対して支払った報酬額は、令和6年度の確定賃金総額に含まれていない。
B 令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額は150,000円であり、当該事業主がすべて負担しなければならない。
C 当該事業主は令和7年度の概算保険料の納付に当たって、口座振替による場合を除き、概算保険料を概算保険料申告書に添えて令和7年7月10日までに納付しなければならない。
D 当該事業主が令和7年度の概算保険料の延納を申請して認められた場合、第2期分として納付する概算保険料の額は291,667円となる。
E 令和7年度の確定賃金総額が6,000万円となった場合の確定保険料のうち、当該事業主が負担することとなる一般保険料の額は総額720,000円となる。

【解答】
<A> 〇
<B> 〇
<C> 〇
<D> ×
<E> 〇
<A>について
賃金は、「賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)」と定義されています。(法第2条第2項)
「使用従属関係が認められない」請負人に対して支払った報酬は、賃金総額に含みません。
<B>について
★令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料額の計算
ポイント!
・概算保険料は、「その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込み額」を使って計算するのが原則です。
ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」である場合は、「直前の保険年度の賃金総額」を使います。
・労災保険料は、全額事業主負担です。
では、計算してみましょう
・令和7年度の概算保険料のうち、労災保険の保険料の額
→5,000万円×1000分の3=150,000円
令和6年度の確定賃金総額を使って計算するのがポイントです。
(法第15条、則第24条)
<C>について
★概算保険料の納期限
ポイント!
事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、概算保険料申告書に添えて、
・その保険年度の6月1日から40日以内
・保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内
に納付しなければなりません。
・令和7年度の概算保険料の納付については、令和7年7月10日(その保険年度の6月1日から40日以内)までに納付しなければなりません。
<D>について
★延納の際の端数処理
ポイント!
概算保険料は延納(分割払い)ができます。
概算保険料の額を期の数で除して得た額に1円未満の端数があるときは、第1期分の概算保険料にまとめます。
・令和7年度の概算保険料を計算しましょう
→5,000万円×(1000分の3+1,000分の14.5)=875,000円
→875,000÷3=291,666.6…円(1円未満の端数がある)
第1期分 | 291,668円 |
第2期分 | 291,666円 |
第3期分 | 291,666円 |
・第2期分は291,667円ではなく、291,666円です。
<E>について
★事業主が負担する一般保険料の額
ポイント!
被保険者が負担するのは、雇用保険率のうち雇用保険二事業の保険率を減じた額の2分の1です。
・令和7年度の確定保険料を計算しましょう
→6,000万円×(1000分の3+1,000分の14.5)=1,050,000円となります。
・事業主と被保険者の負担について
労災保険率 | 雇用保険率 | ||
事業主負担 | 労働者負担 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
1,000分の3 | なし | 1,000分の9 (1,000分の5.5+1,000分の3.5) | 1,000分の5.5 |
・確定保険料のうち、被保険者が負担する一般保険料額は、6,000万円×1,000分の5.5=330,000円です。
事業主が負担する一般保険料額は、1,050,000円−330,000円=720,000円となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「延滞金」
R7-328 07.22
延滞金の徴収
労働保険料を滞納した場合は、「延滞金」が徴収されることがあります。
今回は、延滞金の額や、延滞金が徴収されない場合をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第28条 (延滞金) ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ② 労働保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。 ③ 延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 |
<延滞金の割合の特例について>
令和7年中の延滞金の割合は、
「年14.6%」→「年8.7%」
「年7.3%」→「年2.4%」
となります。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
延滞金は、「指定した期限の翌日から」ではなく、「納期限の翌日」から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算されます。
納期限 | 納期限の 翌日 |
|
| 督促状の 指定期限 | 完納の 前日 | 完納 |
▲ | ▲ |
|
| ▲ | ▲ | ▲ |
|
|
| ||||
②【H29年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
②【H29年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、督促状に指定された期限までに完納したときは、延滞金は徴収されません。
③【R1年出題】(雇用)
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

【解答】
③【R1年出題】(雇用) 〇
労働保険料の額が1,000円未満である、又は、延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
④【H29年出題】(雇用)
認定決定された確定保険料に対しては追徴金が徴収されるが、滞納した場合には、この追徴金を含めた額に対して延滞金が徴収される。

【解答】
④【H29年出題】(雇用) ×
延滞金の対象になるのは、「労働保険料」のみです。追徴金は労働保険料ではありませんので、追徴金には延滞金は課されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R7-315 07.09
労働保険事務組合が行う手続き(まとめ)
労働保険事務組合が行う手続きをまとめました。
条文を読んでみましょう。
法第33条 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、①に規定する業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ③ 認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ④ 厚生労働大臣は、労働保険事務組合が労働保険関係法令規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、認可を取り消すことができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 則第63条 (認可の申請) ① 法第33条第2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、所定の事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ② 申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 (1) 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。) (2) 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類 (3) 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
則第64条 (委託等の届出) ① 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 ② 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、所定の事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
則第65条 (変更の届出) 労働保険事務組合は、認可申請書又は添付書類の(1)、(2)に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
則第66条 (業務の廃止の届出) 業務の廃止の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】(雇用)
労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。

【解答】
①【H28年出題】(雇用) 〇
次に掲げる厚生労働大臣の権限は、「都道府県労働局長に委任する」とされています。
(1)法第8条第2項の規定による認可(下請負事業の分離の認可)に関する権限
(2)法第9条の規定による認可及び指定(継続事業の一括の認可と指定)に関する権限
(3)法第33条第2項の規定による認可(労働保険事務組合の認可)、同条第3項の規定による届出の受理(労働保険事務組合の業務廃止の届出)及び同条第4項の規定による認可の取消し(労働保険事務組合の認可の取消し)に関する権限
(4) 法第26条(特例納付保険料)第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
(則第76条)
②【R3年出題】雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
②【R3年出題】(雇用) ×
労働保険事務の処理の委託があったときは、「委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に」ではなく、「遅滞なく」届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
③【H20年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
③【H20年出題】(雇用) 〇
労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
④【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

【解答】
④【R1年出題】(雇用) ×
「厚生労働大臣」ではなく、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」に提出しなければなりません。
⑤【H20年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
⑤【H20年出題】(雇用) 〇
労働保険事務組合は、「労働保険事務組合認可申請書」又は「労働保険事務組合認可申請書」に添付された「定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)」、「労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類」の記載に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければなりません。
⑥【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
⑥【R1年出題】(雇用) ×
労災二元適用事業に係るものは、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」ではなく、「所轄労働基準監督署長」を経由して都道府県労働局長に提出します。
⑦【H23年出題】(労災)
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
⑦【H23年出題】(労災) ×
「労働保険事務等処理委託解除届」ではなく、「労働保険事務組合業務廃止届」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「延納」
R7-309 07.03
有期事業の延納
概算保険料は延納(分割納付)することができます。
今回は、有期事業の延納をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
則第28条 ① 有期事業であって納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期に分けて納付することができる。 ※期の中途に保険関係が成立した事業について → 保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。 ② 延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない。 |
有期事業の延納のポイント!
・「最初の期の取り方と納付期限」に注意しましょう。
・継続事業と一括有期事業は、「年度単位」で保険料を算定しますので、3期に分けるのが原則です。
有期事業は、「全期間」を通して算定しますので、3期に限りません。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】(労災)
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

【解答】
①【R3年出題】(労災) 〇
問題文の有期事業は延納の申請をすることにより、概算保険料を分割納付できます。
★有期事業の延納の要件を確認しましょう。
①・概算保険料の額が75万円以上
又は
・労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
②事業の全期間が6月以内でない
問題文の「事業の全期間が200日」、「概算保険料の額が80万円」の有期事業は、概算保険料を分割納付できます。
②【R5年出題】(雇用)
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

【解答】
②【R5年出題】(雇用) ×
★期の分け方の基本!
全期間を通じて、毎年「4月1日から7月31日」まで、「8月1日から11月30日」まで「12月1日から翌年3月31日」までの各期に分けることができます。
| 4月1日~ 7月31日 | 8月1日~ 11月30日 | 12月1日~ 3月31日 |
納期限 | 3月31日 | 10月31日 | 1月31日 |
★最初の期について
・保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるとき
→ 保険関係成立の日からその日の属する期の末日まで
・保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月以内のとき
→ 保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日まで
を最初の期とする。
■問題文は保険関係成立の日が5月1日です。
5月1日の属する期の末日(7月31日)までの期間が「2月を超え」ます。
そのため、最初の期は、保険関係成立の日からその日の属する期の末日(7月31日)までとなります。
基本の分け方に当てはめます。
R4.5.1 ~ R4.7.31 | R4.8.1 ~ R4.11.30 | R4.12.1 ~ R5.3.31 | R5.4.1 ~ R5.7.31 | R5.8.1 ~ R5.11.30 | R5.12.1 ~ R6.2.28 |
1期目 | 2期目 | 3期目 | 4期目 | 5期目 | 6期目 |
6期に分けることができますので、第1期に納付する概算保険料は
「120万円」÷6=20万円です。
③【H29年出題】(労災)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。

【解答】
③【H29年出題】(労災) 〇
■最初の期について
保険関係成立の日(6月15日)からその日の属する期の末日(7月31日)までの期間が2月以内ですので、保険関係成立の日(6月15日)からその日の属する期の次の期の末日(11月30日)までが第1期となります。
6月15日 ~ 11月30日 | 12月1日 ~ 3月31日 | 4月1日 ~ 6月5日 |
1期目 | 2期目 | 3期目 |
■最初の期の納期限について
最初の期の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内です。
6月15日の翌日から起算して20日以内ですので、第1期の納期限は平成29年7月5日です。
④【H27年出題】(雇用)
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

【解答】
④【H27年出題】(雇用) 〇
有期事業(一括有期事業を除く。)については、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、納期限の延長はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R7-252 05.07
労働保険事務組合の責任など
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料の申告・納付などの労働保険事務を処理します。
今回は、「労働保険事務組合に対する通知」、「労働保険事務組合の責任」、「帳簿の備付け」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第34条 (労働保険事務組合に対する通知等) 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
第35条 (労働保険事務組合の責任等) ① 委託に基づき、事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ② 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ③ 政府は、前2項の規定により労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 ④ 労働保険事務組合は、労災保険法第12条の3第2項の規定(不正受給者からの費用徴収)及び雇用保険法第10条の4第2項(不正受給者に対する返還命令等)の規定の適用については、事業主とみなす。
第36条 (帳簿の備付け) 労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 則第68条 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。 (1)労働保険事務等処理委託事業主名簿 (2)労働保険料等徴収及び納付簿 (3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) 〇
委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、法律上当然に、通知の効果が委託事業主に及ぶことになります。
政 府
|
→ 通知等 |
労働保険 事務組合 |
→ 通知の効果が 当然に及ぶ |
委託事業主 |
②【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。

【解答】
②【H25年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合に対してなされた通知等は、法律上当然に、その通知等の効果が委託事業主に及びます。
労働保険事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容には関係ありません。
③【H25年出題】(雇用)
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。

【解答】
③【H25年出題】(雇用) ×
第35条第2項で、「その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」とされています。
問題文の場合は、労働保険事務組合が、延滞金の納付の責任を負います。
④【H29年出題】(雇用)
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

【解答】
④【H29年出題】(雇用) ×
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、「当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる」ではなく、「その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」ものとなります。
労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合は、「その残余の額を当該事業主から徴収することができる」とされています。
金銭を労働保険事務組合に交付したとしても、事業主は、全責任を免れるわけではありません。
⑤【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

【解答】
⑤【R5年出題】(労災) ×
第35条第2項で、「その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずる」とされています。
問題文の場合は、労働保険事務組合は政府に対して追徴金の納付責任を負います。
⑥【R3年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿を事務所に備えておかなければならない。

【解答】
⑥【R3年出題】(雇用) 〇
労働保険事務組合が備えなければならない帳簿をおぼえましょう。
(1)労働保険事務等処理委託事業主名簿
(2)労働保険料等徴収及び納付簿
(3)雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
⑦【H28年出題】(雇用)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類を、その完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】
⑦【H28年出題】(雇用) 〇
労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類は、その完結の日から3年間保存しなければなりません。ただし、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿」は4年間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「労働保険事務組合」
R7-230 04.15
労働保険事務組合に委託できる事務の範囲
「労働保険事務組合」とは、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等です。
認可で新しい団体が設立されるのではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものです。
労働保険事務組合について条文を読んでみましょう。
第33条第1項、第2項 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務の処理を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
則第62条第1項(委託事業主の範囲) 法第33条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
委託できる事業主の範囲
|
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。

【解答】
①【H19年出題】(雇用) ×
厚生労働大臣の認可を受けて労働保険事務組合となった団体は、「その事業の一環として」、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理します。専業で行わなければならないものではありません。
②【R1年出題】(雇用)
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【解答】
②【R1年出題】(雇用) 〇
「金融業」を主たる事業とする事業主で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは、「常時使用する労働者が50人以下」の場合です。「50人」を超える場合は、委託できません。
③【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

【解答】
③【R5年出題】(労災) 〇
令和2年4月より、労働保険事務組合に委託する事業主の所在地の制限がなくなっています。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができます。
④【H23年出題】(雇用)
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
<A> 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
<B> 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
<C> 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
<D> 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
<E> 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務

【解答】
④【H23年出題】(雇用)
誤り → <B>
「印紙保険料に関する事項」は、労働保険事務組合に処理を委託することができる労働保険事務の範囲から除かれています。
<B>印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務は、労働保険事務組合に委託して処理させることはできません。
⑤【R1年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。

【解答】
⑤【R1年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合は、「労災の保険給付に関する請求の事務」を行うことはできません。
★労働保険事務組合に委託できない事務
・印紙保険料に関する事項
・保険給付に関する請求書等の事務手続
・雇用保険の二事業に係る事務手続
⑥【H19年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【解答】
⑥【H19年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができ、また、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務も「処理することができる」となります。
⑦【R3年出題】(雇用)
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

【解答】
⑦【R3年出題】(雇用) 〇
「保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行」、「雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行」、「印紙保険料に関する事項」は、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「督促及び滞納処分等」
R7-219 04.04
労働保険徴収法の「督促・滞納処分」、「延滞金」のポイント!
労働保険料を滞納した場合などの扱いについて、条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
第28条 (延滞金) ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ② 労働保険料の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を控除した額とする。 ③ 延滞金の計算において、労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ⑤ 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
法附則第12条 (延滞金の割合の特例) 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、 年14.6%の割合 → 延滞税特例基準割合+年7.3% 年7.3%の割合 → 延滞税特例基準割合+年1%(当該加算した割合が7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合) とされます。 |
下の図でイメージしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。

【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
概算保険料・確定保険料について所定の期限までに申告しなかった場合は、政府が認定決定をし、事業主に通知します。その場合、督促が行われるのは、「通知があってもなお、法定納期限(通知を受けた日から15日以内)までに納付しないときに限られます。
(法第27条)
②【R1年出題】(雇用)
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。

【解答】
②【R1年出題】(雇用) 〇
督促・滞納処分の対象になる「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」については、「労働保険料」だけではありません。
労働保険料ではない「追徴金」も督促・滞納処分の対象になっていることに注意してください。
(昭55.6.5発労徴40号)
③【H29年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
③【H29年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、事業主が督促状に指定された期限までに完納したときは、延滞金は徴収されません。
④【R1年出題】(雇用)
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。

【解答】
④【R1年出題】(雇用) ×
延滞金の期間の日数は、「督促状で指定した期限の翌日」ではなく「納期限の翌日」からその完納又は財産差押えの日の前日までです。
ちなみに、延滞金の割合は、「年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)です。
⑤【R1年出題】(雇用)
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。

【解答】
⑤【R1年出題】(雇用) 〇
労働保険料の額が1,000円未満であるとき・延滞金の額が100円未満であるときは、延滞金は徴収されません。
⑥【H26年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
⑥【H26年出題】(雇用) ×
・督促、滞納処分は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない」場合に行われます。
・延滞金は、「労働保険料の納付を督促したとき」に徴収されます。
延滞金の対象になるのは「労働保険料」のみです。
追徴金は労働保険料ではありませんので、延滞金の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
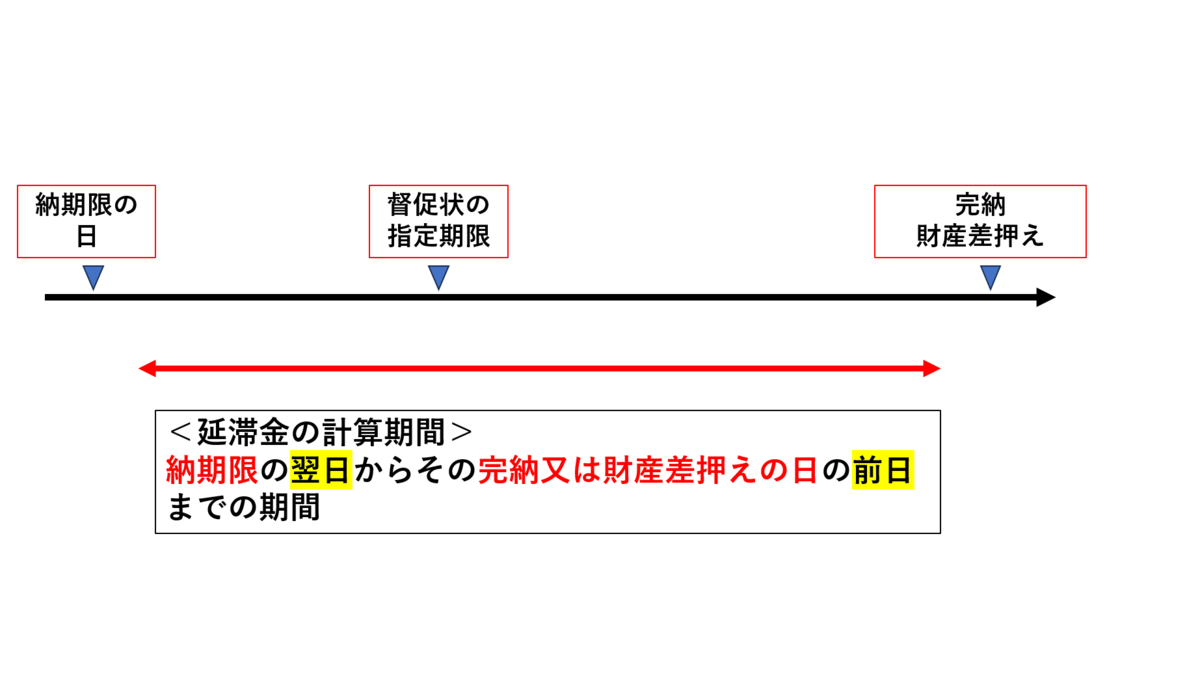
労働保険徴収法「特別加入保険料」
R7-217 04.02
特別加入保険料の算定
特別加入保険料の計算方法を確認しましょう。
・第1種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第1種特別加入保険料率 ・第2種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第2種特別加入保険料率 ・第3種特別加入保険料の額 「特別加入保険料算定基礎額の総額」×第3種特別加入保険料率 |
「特別加入保険料算定基礎額」は、原則として、「給付基礎日額×365」で計算します。
一般の労働者でいうと、個々の労働者の1年間の賃金の額です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。

【解答】
①【R2年出題】(労災) 〇
特別加入者には、二次健康診断等給付が適用されませんので、第1種特別加入保険料率は、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」を減じた率となります。
ただし、「厚生労働大臣の定める率」は、「零」ですので、第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業の労災保険率と同一の率となります。
(法第13条)
②【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
②【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類によって、1000分の3から1000分の52の範囲で、それぞれ定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、則別表5)
③【H26年出題】(労災)※改正による修正あり
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和7年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

【解答】
③【H26年出題】(労災) ×
第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に「1000分の3」です。
(法第14条の2、則第23条の3)
④【R2年出題】(労災)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。

【解答】
④【R2年出題】(労災) ×
当該月数に1月未満の端数があるときは「その月数を切り捨てる」ではなく、「これを1月とする。」となります。
★ 「継続事業」で、保険年度の中途に特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額」について
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)÷12」×「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
「特別加入者とされた期間の月数」に1月未満の端数があるときは、1月とします。
・保険年度の中途に新たに特別加入者となった者
→ 特別加入申請の承認日の属する月を「1月」と算定します
・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者
→ 特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を「1月」と算定します
★例えば、特別加入の承認が6月30日、消滅日が翌年2月18日の場合
6月と翌年2月は「1月」で算定しますので、特別加入者とされた期間の月数は9か月となります。
(則第21条第1項、H7.3.30労徴発28号)
⑤【R5年出題】(労災)
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
「有期事業」の場合
「特別加入保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)÷12」×「特別加入者とされた期間の月数」で計算します。
端数処理は、継続事業と異なるので注意してください。
有期事業についての特別加入期間のすべてで端数処理をします。
例えば、有期事業の全期間が「12か月11日」の場合は、端数の11日を1月で算定し、13か月となります。
(則第21条第2項、H7.3.30労徴発28号)
⑥【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。

【解答】
⑥【R5年出題】(労災) 〇
第1種特別加入保険料は、「12,000円×365」×1,000分の4=17,520円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働保険徴収法>確定保険料
R7-191 03.07
労働保険料の精算(確定保険料の申告と納付)
労働保険料は、「申告制」で納付することになっています。
■継続事業・一括有期事業の場合
労働保険料は、「保険年度」単位で、申告・納付することになっています。
保険年度の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、保険年度の終了後に、「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。
■有期事業の場合
労働保険料は、事業の初めに「概算」で保険料を申告・納付し、事業終了後に「確定」で保険料を申告し、保険料の過不足を精算します。
今回は、「確定保険料」の申告と納付の手続きをみていきます。
条文を読んでみましょう。
★継続事業・一括有期事業の確定保険料(一般保険料について) 第19条第1項 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から 40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。 (一般保険料の額) ・その保険年度に使用したすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定する
★有期事業の確定保険料(一般保険料について) 第19条第2項 有期事業については、その事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。 (一般保険料の額) ・当該保険関係に係る全期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定する |
「賃金総額」の違いを確認しましょう。
★概算保険料
「賃金総額の見込額」で計算します。
★確定保険料
実際に支払った「賃金総額」で計算します。
過不足の精算について条文を読んでみましょう。
第19条 ③ 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した概算保険料がないときは確定保険料を、確定保険料申告書に添えて、「継続事業・一括有期事業」にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。
⑥ 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額を超える場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(雇用)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】(雇用) 〇
申告書の提出先は、所轄都道府県労働局歳入徴収官です。
納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、確定保険料申告書の提出は必要です。
(則第38条)
②【R6年出題】(雇用)
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合には同年5月10日までに提出しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】(雇用) ×
・前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の確定保険料について
「次の保険年度の6月1日から40日以内」に提出しなければなりません。
「当日」起算ですので、「7月10日」が提出期限です。
・保険年度の中途に保険関係が消滅した場合
「保険関係が消滅した日から50日以内」に提出しなければなりません。
こちらも「当日」起算です。
問題文の場合、「3月31日」に事業が廃止されているので、翌日の「4月1日」に保険関係が消滅します。
4月1日(当日)から起算して50日以内ですので、期限は、5月10日ではなく「5月20日」です。
(法第19条)
③【R6年出題】(雇用)
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
③【R6年出題】(雇用) ×
有期事業の確定保険料申告書は、「保険関係が消滅した日から50日以内」に提出しなければなりません。なお、「当日」起算です。
3月31日に事業が終了した場合、翌日の4月1日に保険関係が消滅します。
4月1日(当日)から起算して50日以内ですので、期限は5月20日となります。
(法第19条)
④【H26年出題】(雇用)
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
④【H26年出題】(雇用) 〇
6月30日に事業が廃止された場合、翌日の7月1日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書は、7月1日(当日)から起算して50日以内ですので、その年の8月19日が期限となります。
(法第19条)
⑤【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

【解答】
⑤【R5年出題】(雇用) ×
事業の廃止が10月31日の場合、保険関係は11月1日に消滅します。
確定保険料申告書は、11月1日(当日)から起算して50日以内ですので、12月20日が期限です。
(法第19条)
⑥【R1年出題】(労災)
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
⑥【R1年出題】(労災) ×
労働保険料還付請求書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく、「官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出しなければなりません。
還付を受ける場合は、請求が必要です。
・ 確定保険料申告書を提出する際に、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)はその超過額を還付します。
・ 還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他徴収金に充当します。
(則第36条、第37条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「概算保険料の追加徴収」
R7-181 02.25
保険年度の中途で保険料率の引上げを行ったときの「追加徴収」
今回は、概算保険料の追加徴収です。
条文を読んでみましょう。
法第17条 (概算保険料の追加徴収) ① 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。 ② 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
則第26条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 (1) 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 (2) 納期限 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
政府が、保険年度の中途に保険料率の引上げを行ったときの追加徴収は、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」行われることがポイントです。
②【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。

【解答】
②【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収される概算保険料の納付は、「納付書」によって行われます。納入告知書ではありません。
(則第38条)
③【R4年出題】(雇用)
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

【解答】
③【R4年出題】(雇用) 〇
追加徴収される概算保険料は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなります。
事業主は、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はありません。
④【H22年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。

【解答】
④【H22年出題】(労災) ×
追加徴収の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
⑤【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、延納することはできない。

【解答】
⑤【H30年出題】(労災) ×
追加徴収される概算保険料は、延納することができます。
ただし、元々の概算保険料の延納を行う事業主に限られています。
(則第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働保険徴収法>延納
R7-168 02.12
延納(継続事業・一括有期事業の場合)
「概算保険料」は延納(分割払)をすることができます。
今回は、継続事業・一括有期事業の延納をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第18条 (概算保険料の延納) 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が概算保険料(認定決定も含みます)、増加概算保険料、概算保険料の追加徴収により納付すべき労働保険料を延納させることができる。 |
ポイント!
「確定保険料」は延納できません。
<延納の条件>
・概算保険料の額が40万円以上
(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上
又は
・労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
・保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは延納できません。
・事業主が概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合
(原則)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | |||||||||
7月10日 (保険年度の6月1日から起算して40日以内) | 10月31日 ・労働保険事務組合に委託 →11月14日 | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 | |||||||||
(年度途中に保険関係が成立した場合)
★4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業
第1期 | 第2期 | 第3期 |
保険関係成立の日 ~ 7月31日 | 8月1日 ~ 11月30日 | 12月1日 ~ 3月31日 |
保険関係成立の日の 翌日から起算して 50日以内 | 10月31日 ・労働保険事務組合に委託 →11月14日 | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 |
★6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業
第1期 | 第2期 |
保険関係成立の日 ~ 11月30日 | 12月1日 ~ 3月31日 |
保険関係成立の日の 翌日から起算して 50日以内 | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 |
★10月1日以降に保険関係が成立した事業は延納できません。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。

【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託」している事業主は、概算保険料の額に関係なく延納できます。問題文の場合は、延納の申請を行うことができます。
②【R2年出題】(雇用)
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。

【解答】
②【R2年出題】(雇用) 〇
7月1日に保険関係が成立した場合は、2回に分けて納付することができます。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 | 第2期 | |||||||
保険関係成立の日の翌日から起算して 50日以内 (8月20日) | 1月31日 ・労働保険事務組合に委託 →2月14日 | |||||||
③【H29年出題】(労災)
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

【解答】
③【H29年出題】(労災) 〇
10月1日以降に保険関係が成立したときはその年度は延納できませんので、一括で納付しなければなりません。
保険年度の中途に保険関係が成立した場合、当該保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)に納付しなければなりませんので、納付期限は、平成29年11月20日となります。
(法第15条、則第27条)
④【H27年出題】(雇用)
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

【解答】
④【H27年出題】(雇用) 〇
第1期の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても、延長されません。
(則第27条第2項)
⑤【H29年出題】(労災)
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

【解答】
⑤【H29年出題】(労災) ×
1円未満の端数は、「第1期分」にまとめます。
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合は、第1期の納付額は56,668円、第2期及び第3期の納付額は各56,666円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働保険徴収法「一般保険料」
R7-154 01.28
労働者の労働保険料「一般保険料」の額の計算
労働保険料には6つの種類があります。
① 一般保険料
② 第1種特別加入保険料(中小事業主等が特別加入したときの保険料)
③ 第2種特別加入保険料(一人親方等が特別加入したときの保険料)
④ 第3種特別加入保険料(海外派遣者が特別加入したときの保険料)
⑤ 印紙保険料(日雇労働被保険者の雇用保険料。印紙で納付する。)
⑥ 特例納付保険料(雇用保険法の特例対象者の保険料)
今回は一般保険料の計算についてお話しします。
一般保険料は、一般の労働者の保険料で、原則として、労災保険料+雇用保険料です。
★一般保険料の額の計算について
「賃金総額」×「一般保険料率(一般保険料に係る保険料率)」で計算します。
■「賃金総額」とは→ 事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。
■一般保険料率
①労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業
→「労災保険率」+「雇用保険率」
②労災保険に係る保険関係のみが成立している事業
→「労災保険率」
③雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
→「雇用保険率」
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(労災)
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

【解答】
①【R1年出題】(労災) ×
労働保険料は、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、「特例納付保険料」の計6種類です。
(法第10条第2項)
②【H30年出題】(雇用)
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。

【解答】
②【H30年出題】(雇用) ×
二元適用事業は、「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」を別個の事業とみなして徴収法を適用します。そのため、一般保険料額も、「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」を別々に計算します。
一元適用事業の一般保険料額は、「賃金総額」×「一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)」で算定します。
ただし、雇用保険法の適用を受けない者がいる場合は、「労災保険」と「雇用保険」で賃金総額が異なります。そのため、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することになります。
(整備省令第17条第1項)
★下の図でイメージしましょう。
③【R4年出題】(雇用)
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

【解答】
③【R4年出題】(雇用) 〇
一元適用事業で、二元適用事業に準じ、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する場合でも、二元適用事業ではありませんので、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様です。
(整備省令第17条第1項、第2項)
④【H30年出題】(雇用)
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されるが、当該労働者が属する事業場に係る労災保険料は、徴収・納付の便宜を考慮して、当該労働者に支払われる賃金を算定の基礎となる賃金総額から除外して算定される。

【解答】
④【H30年出題】(雇用) ×
1日30分未満しか働かない労働者に対しても労災保険は適用されます。
保険料の計算のもとになる「賃金総額」は事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。そのため、1日30分未満しか働かない労働者に支払われる賃金も、賃金総額に含まれます。
(法第11条第2項)
⑤【R4年出題】(雇用)
A及びBの2つの適用事業主に雇用される者XがAとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあるときは、XはAとの雇用関係においてのみ労働保険の被保険者資格が認められることになり、労働保険料の算定は、AにおいてXに支払われる賃金のみをAの賃金総額に含めて行い、BにおいてXに支払われる賃金はBの労働保険料の算定における賃金総額に含めない。

【解答】
⑤【R4年出題】(雇用) ×
Xは、A及びBの2つの適用事業主に雇用され、Aとの間で主たる賃金を受ける雇用関係にあります。
★雇用保険料について
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする=問題文の場合はA)についてのみ被保険者となります。(行政手引20352)
そのため、雇用保険料の算定は、問題文の通り、「A」の雇用保険料は、Xに支払われる賃金を賃金総額に含めて行います。「B」の雇用保険料には、Xに支払われる賃金は賃金総額には含まれません。
★労災保険料について
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、それぞれで労災保険の適用を受けます。そのため、Aの労災保険料は、AにおいてXに支払われる賃金は賃金総額に含まれ、また、Bの労災保険料もBにおいてXに支払われる賃金が賃金総額に含まれます。
⑥【H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
⑥【H26年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主にその支給が義務づけられていても、労働保険徴収法では「賃金として取り扱わない」ことになっています。
そのため、労働保険料の算定基礎となる賃金総額には含みません。
(昭25.2.16基発127号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
R7-116 12.21
<令和6年の問題を振り返って>追徴金の額・納期限など
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
「追徴金」について条文を読んでみましょう。
法第21条第1項、2項 (追徴金) ① 政府は、事業主が認定決定された確定保険料又は不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。 ② 認定決定された確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。
法第25条第1項、2項 ① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、①により認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
★追徴金が徴収される場合
確定保険料の額を認定決定した場合 | 100分の10 |
印紙保険料の額を認定決定した場合 | 100分の25 |
※「概算保険料の額」を認定決定した場合は、追徴金は徴収されません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問10-E(雇用)】
労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

【解答】
【R6年問10-E(雇用)】 ×
追徴金の納期限は、「事業主が通知を受けた日」から起算して30日ではなく「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
また、追徴金は、「納付書」ではなく「納入告知書」で通知することもポイントです。
(法第21条第3項、則第26条)
★認定決定された保険料の納期限について
認定決定された概算保険料(納付書) | その通知を受けた日から15日以内 |
認定決定された確定保険料(納入告知書) |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題(雇用)】
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
①【H26年出題(雇用)】 ×
認定決定された概算保険料については、追徴金は徴収されません。
②【R4年出題(労災)】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。

【解答】
②【R4年出題(労災)】 〇
以下の場合は、追徴金は徴収されません。
■事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合
■認定決定された確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるとき
→「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいいます。「法令の不知、営業の不振、資金難等」は含まれません。
問題文のように「事業主が法令の改正を知らなかった」場合は、追徴金が徴収されます。
③【H28年出題(雇用)】
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】
③【H28年出題(雇用)】 ×
追徴金は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10ではなく「100分の25」です。
④【H25年出題(雇用)】
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
④【H25年出題(雇用)】 〇
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(法第25条、則第38条第5項)
⑤【H28年出題(雇用)】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
⑤【H28年出題(雇用)】 ×
認定決定された印紙保険料と追徴金は、雇用保険印紙ではなく、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に「現金」で納付します。日本銀行に納付することもできます。
(則第38条第3項第2号)
⑥【H26年出題(雇用)】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
⑥【H26年出題(雇用)】 ×
追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促します。ただし、追徴金については、延滞金は徴収されません。
(法第27条、第28条)
条文を読んでみましょう。
法第27条第1項 労働保険料その他この法律の規定による徴収金(→追徴金も含まれます)を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 法第28条 政府は、労働保険料(→追徴金は含まれません)の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(徴収法)
R7-048 10.12
<令和6年出題徴収>保険関係の成立と消滅など【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問8-A(雇用)】
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当する日に至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

【解答】
①【R6年問8-A(雇用)】 ×
労災保険・雇用保険の保険関係は、「その事業が開始された日」に、事業主の意思に関係なく強行的に成立します。
また、雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が、雇用保険法の適用事業に該当するに至った場合は、「その該当する日」に保険関係が強行的に成立します。
なお、保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければなりません。
「保険関係成立届」を提出することによって保険関係が成立するのではありません。
(法第3条、4条の2、法附則第3条)
②【R6年問8-B(雇用)】
都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続きを一元的に処理する事業として定められている。

【解答】
②【R6年問8-B(雇用)】 ×
「都道府県及び市町村の行う事業」、「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、「二元適用事業」ですので、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係は、別個の事業とみなして徴収法を適用します。
ちなみに、「国の行う事業」は、二元適用事業とされていません。国の行う事業は、労災保険に係る保険関係が成立しないからです。
(法第39条、則第70条)
③【R6年問8-C(雇用)】
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
③【R6年問8-C(雇用)】 〇
「名称、所在地等変更届」の問題です。
名称、所在地等に変更があったときは、変更を生じた日の「翌日から起算」して「10日以内」に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
(法第4条の2第2項、則第5条)
④【R6年問8-D(雇用)】
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得て、その者が当該保険関係の消滅の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

【解答】
④【R6年問8-D(雇用)】 ×
雇用保険暫定任意適用事業については、任意に保険関係を消滅させることができます。その場合は、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要です。
保険関係の消滅の申請をした場合、「厚生労働大臣の認可があった日の翌日」に、その事業についての当該保険関係が消滅します。「厚生労働大臣の認可があった日」ではありません。
(法附則第4条第2項)
⑤【R6年問8-E(雇用)】
雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

【解答】
⑤【R6年問8-E(雇用)】 ×
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、「その翌日」に消滅します。
(法第5条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
R7-038 10.2
<令和6年度徴収>労働保険料の申告について【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問10-A(雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、保険年度の7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないが、当該事業が3月31日に廃止された場合は同年5月10日までに提出しなければならない。

【解答】
①【R6年問10-A(雇用)】 ×
継続事業の確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内(7月10日までに)提出しなければなりません。
なお、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
継続事業の保険関係は、事業が廃止されたときは、その翌日に消滅します。
3月31日に廃止された場合は、4月1日に保険関係が消滅します。確定保険料申告書の期限は保険関係が消滅した日から50日以内(当日起算)ですので、5月20日までに提出しなければなりません。
(法第19条)
②【R6年問10-B(雇用)】
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
②【R6年問10-B(雇用)】 ×
3月31日に事業が終了した有期事業の保険関係は4月1日に消滅します。
有期事業の確定保険料申告書の期限は、「保険関係が消滅した日から50日以内」(当日起算)ですので、5月20日までに提出しなければなりません。
(法第19条第2項)
③【R6年問10-C(雇用)】
2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
③【R6年問10-C(雇用)】 ×
一括有期事業についての報告書は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に提出しなければなりません。確定保険料申告書を提出する際に提出します。
当該事業が継続している場合は、7月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(則第34条)
④【R6年問10-D(雇用)】
前保険年度より保険関係が引き続く継続事業の事業主は、前保険年度の3月31日に賃金締切日があり当該保険年度の4月20日に当該賃金を支払う場合、当該賃金は前保険年度の確定保険料として申告すべき一般保険料の額を算定する際の賃金総額に含まれる。

【解答】
④【R6年問10-D(雇用)】 〇
確定保険料の算定基礎となる賃金総額には、その保険年度中に使用した労働者に支払うことが確定した賃金であれば、その保険年度間に現実に支払われていないものも含まれます。
前保険年度の3月31日に賃金締切日があり、当該保険年度の4月20日に支払う賃金も前保険年度の確定保険料を算定する際の賃金総額に含まれます。
(昭24.10.5基災収5178号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働保険徴収法)
R7-026 9.20
<令和6年度徴収法>雇用保険印紙からの問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、徴収法の択一式です。
★事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど、その者に係る印紙保険料を納付しなければなりません。
★印紙保険料の納付について条文で確認しましょう。
法第23条第2項、第3項 ② 印紙保険料の納付は、事業主が、雇用保険法第44条の規定により当該日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。 ③ 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料納付計器を、厚生労働大臣の承認を受けて設置した場合には、当該印紙保険料納付計器により、日雇労働被保険者が所持する日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができる。 |
では、令和6年問9(雇用)の印紙保険料の問題をどうぞ!
①【R6年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限りその効力を有するが、有効期間の更新を受けた当該雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。

①【R6年出題】(雇用) 〇
★ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければなりません。
★ 「雇用保険印紙購入通帳」は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有します。
★ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければなりません。
★ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間(毎年3月1日から3月31日までの間)に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
★ 有効期間の更新を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度(更新を受けた日の翌保険年度)に限り、その効力を有します。
(則第42条)
②【R6年出題】(雇用)
事業主は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。

【解答】
②【R6年出題】(雇用) 〇
★ 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければなりません。
★ 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書がなくなった場合で、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければなりません。
(則第42条、第43条)
③【R6年出題】(雇用)
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。

【解答】
③【R6年出題】(雇用) 〇
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければなりません。
(則第42条第8項)
④【R6年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合、労働保険徴収法施行規則第54条に定める印紙保険料納付状況報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況及び毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。

【解答】
④【R6年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙と印紙保険料納付計器を併用して印紙保険料を納付する場合は、「印紙保険料納付状況報告書」と併せて「印紙保険料納付計器使用状況報告書」を提出しなければなりません。
ちなみに、
・ 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
・ 印紙保険料納付計器を設置した事業主は、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
(則第54条、第55条)
⑤【R6年出題】(雇用)
事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならず、当該都道府県労働局歳入徴収官による当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を受けることとなる。

【解答】
⑤【R6年出題】(雇用) 〇
印紙保険料納付計器を使用しなくなった場合の問題です。
(則第52条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(労働保険徴収法)
R7-016 9.10
<令和6年度徴収>請負事業の一括について質問がありましたのでお答えします。【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働保険徴収法の択一式です。
まず、請負事業の一括を図でイメージしましょう。
令和6年問8(労災)の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業であって、数次の請負によって行われる場合、雇用保険に係る保険関係については、元請事業に一括することなく事業としての適用単位が決められ、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】
①【R6年出題】 〇
請負事業の一括で、元請事業に一括されるのは、「労災保険に係る保険関係」のみです。
雇用保険は一括されませんので、雇用保険は原則どおり事業ごとに適用されます。図でイメージしてください。
②【R6年出題】)
労働保険徴収法第8条に規定する請負事業の一括について、下請負に係る事業については下請負人が事業主であり、元請負人と下請負人の使用する労働者の間には労働関係はないが、同条第2項に規定する場合を除き、元請負人は当該請負に係る事業について下請負をさせた部分を含め、そのすべての労働者について事業主として保険料の納付等の義務を負う。

【解答】
②【R6年出題】 〇
労働保険徴収法上、請負事業が一括されたとしても、「下請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」には労働関係があります。そのため、下請負に係る事業については、「下請負人」が事業主です。
請負事業の一括により、「元請負人のみ」が「当該事業の事業主」となります。これは、元請負人は、請負に係る事業(イメージ図では、ビル建築工事の現場)については、下請負をさせた部分を含めて、工事の全てについて「事業主」として労災保険料を納付する等の義務を負うという意味です。
請負事業の一括で元請負人が事業主とされたとしても、「元請負人」と「下請負人が使用する労働者の間」に労働関係が生まれるわけではありません。
図でイメージしてください。
③【R6年出題】
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
③【R6年出題】 〇
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業の分離については、厚生労働大臣の認可が必要です。
下請負事業の分離の認可については、元請負人及び下請負人が「共同で」、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に「下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
(則第8条第1項)
④【R6年出題】
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、天災その他不可抗力等のやむを得ない理由により、同法施行規則第8条第1項に定める期限内に「下請負人を事業主とする認可申請書」を提出することができなかったときは、期限後であっても当該申請書を提出することができる。

【解答】
④【R6年出題】 〇
③の問題の続きです。「下請負人を事業主とする認可申請書」は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出しなければなりませんが、やむを得ない理由により、期限内に提出することができなかったときは、期限後であっても提出することができます。
(則第8条第1項)
⑤【R6年出題】
労働保険徴収法第8条第2項に定める下請負事業の分離に係る認可を受けるためには、当該下請負事業の概算保険料が160万円以上、かつ、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)であることが必要とされている。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
下請負事業の概算保険料が160万円以上、「又は」、請負金額が1億8,000万円以上(消費税等相当額を除く。)です。
(則第9条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
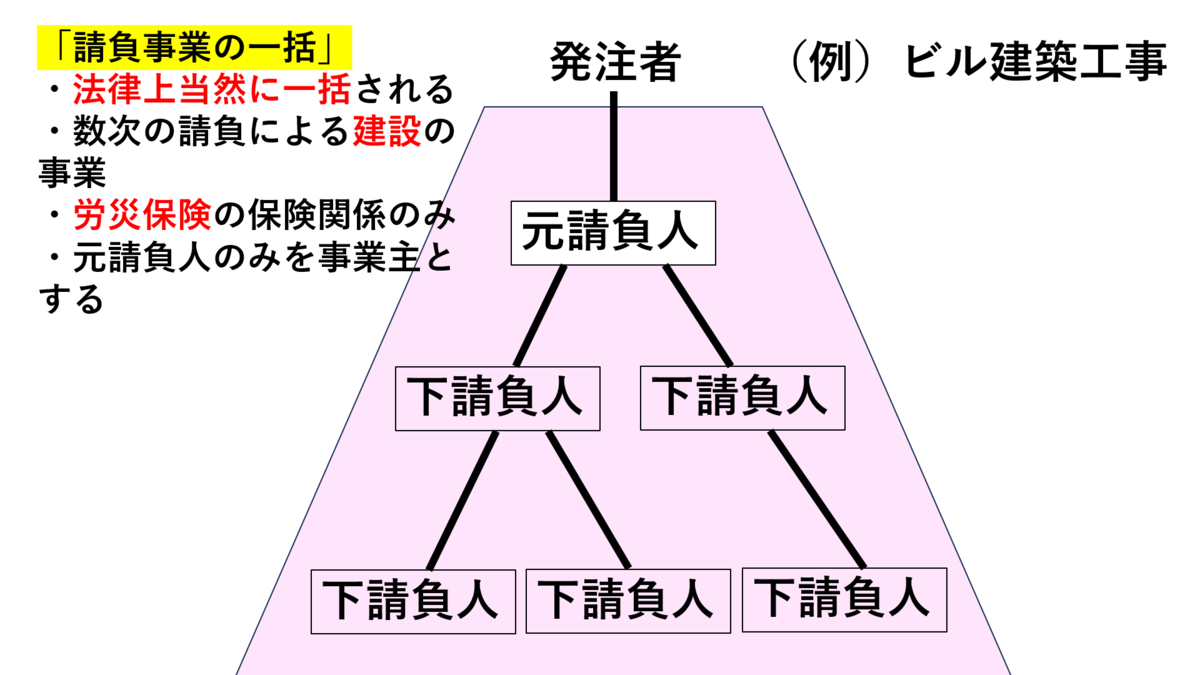
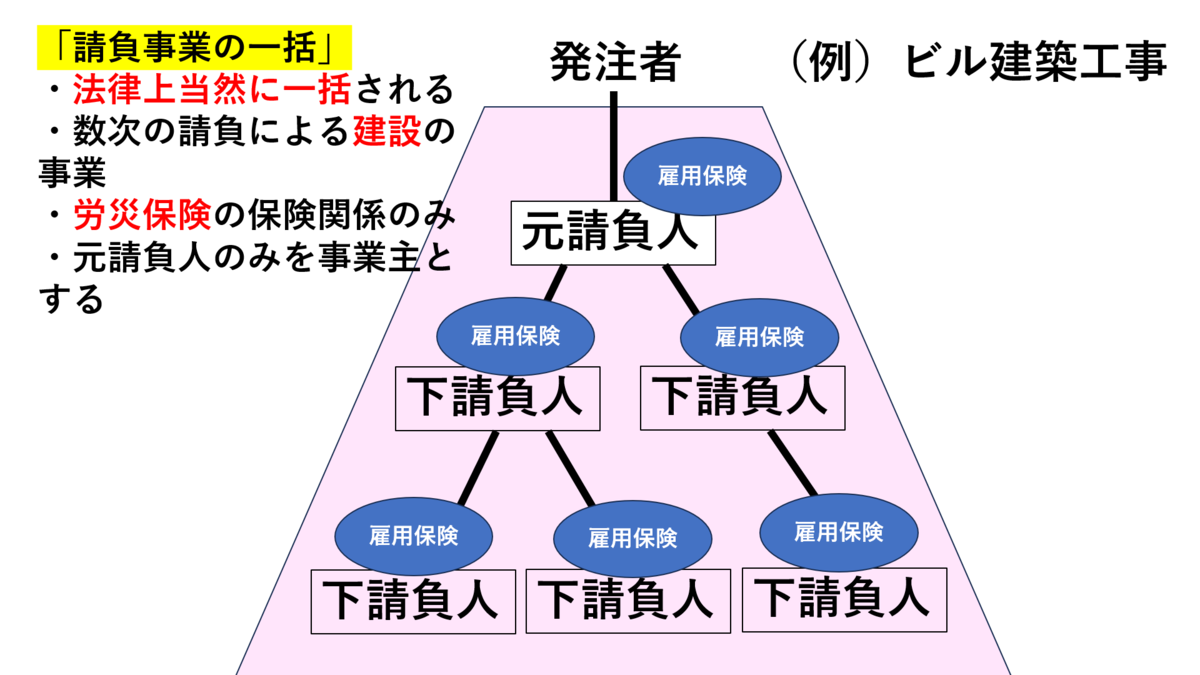
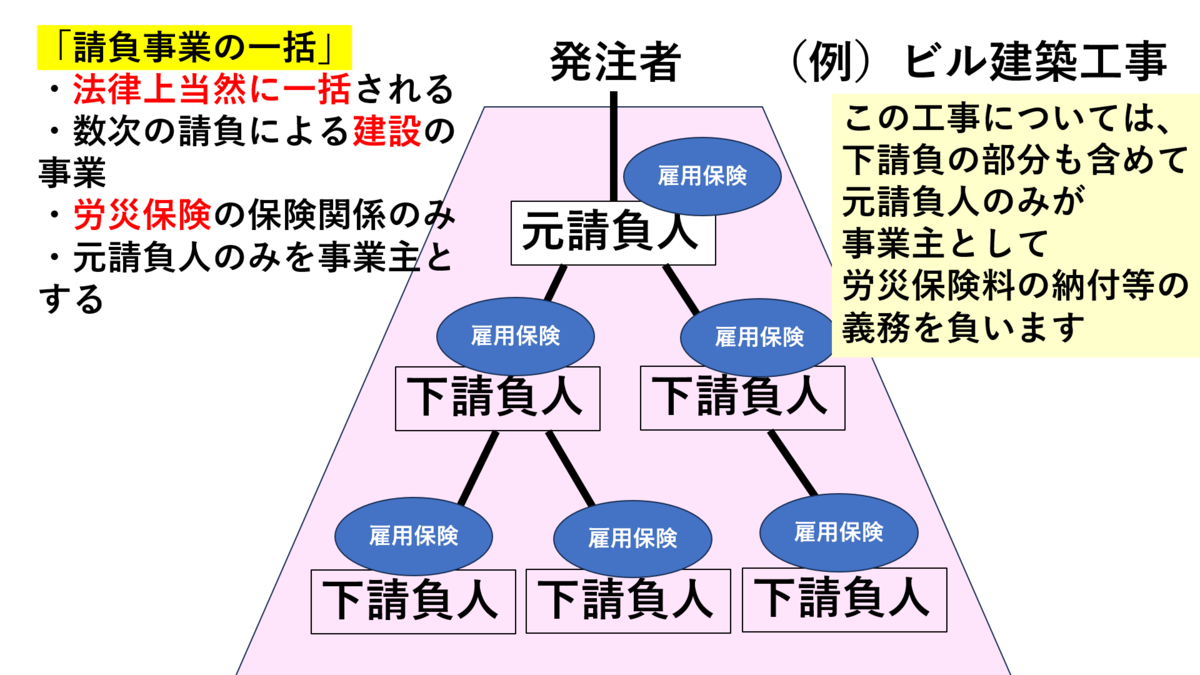
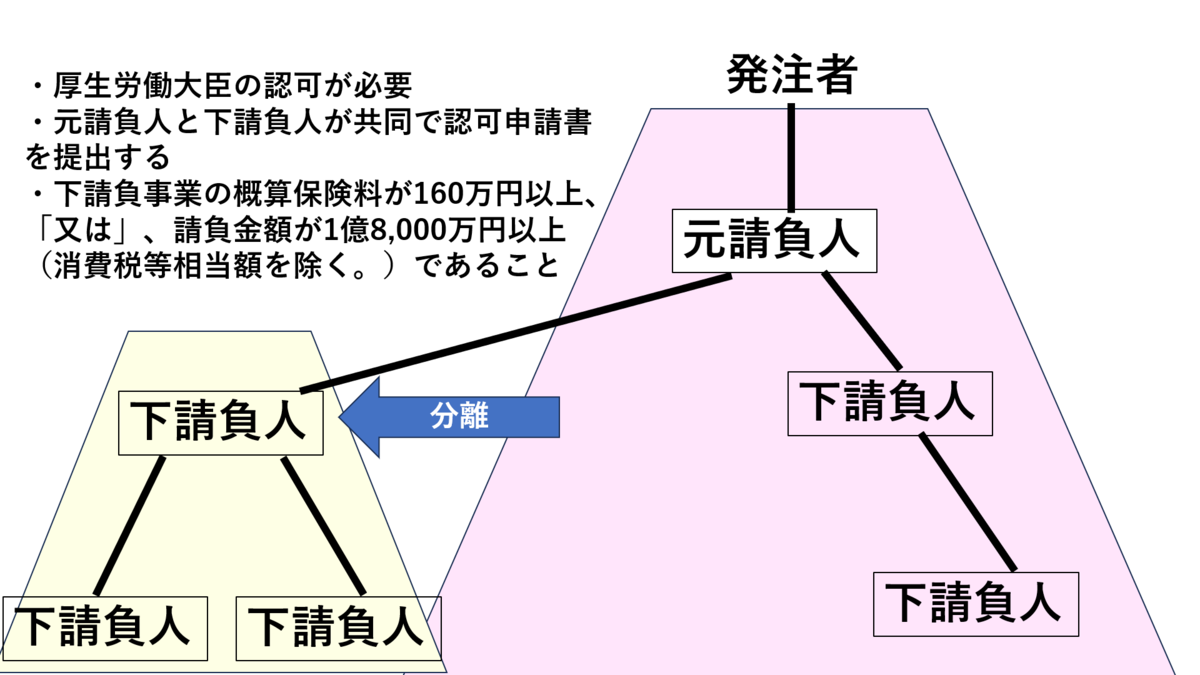
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-346 8.7
労災保険暫定任意適用事業・雇用保険暫定任意適用事業【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
農林水産業の一部は、労災保険、雇用保険の適用が当分の間、任意となっています。
※労災保険と雇用保険では、暫定任意適用事業の範囲が異なります。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年問9】(労災)
労災保険暫定任意適用事業の事業主については、労災保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。この場合において、当該申請書には、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

【解答】
①【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業については、厚生労働大臣の認可があった日に、保険関係が成立します。
労災の任意加入については労働者の同意は不要です。労災保険料は、事業主が全額負担するからです。
(整備法第5条第1項)
②【H21年問9】(労災)
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。

【解答】
②【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業は、事業主が保険関係の消滅の申請を行えば、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅します。
ただし、消滅の申請には次の要件が必要です。
① 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。
② 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、当該保険関係が成立した後1年を経過していること。
③ 特例による保険給付が行われることとなった労働者に係る事業にあっては、特別保険料を徴収する期間を経過していること。
(整備法第8条第2項)
③【H21年問9】(労災)
労災保険にかかる保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書には、当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

【解答】
③【H21年問9】(労災) 〇
労災保険暫定任意適用事業が加入する際は労働者の同意は要りませんが、保険関係の消滅には、「労働者の過半数の同意」が必要です。そのため、労働者の過半数の同意を得たことを証明することができる書類を添付しなければなりません。
(整備法第8条第2項、令第3条)
④【H21年問9】(労災)
雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の事業主が、当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。この場合において、当該申請書は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要がある。

【解答】
④【H21年問9】(労災) ×
「2分の1」ではなく「4分の3以上」の同意です。
雇用保険暫定任意適用事業の手続について
・加入の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
★申請には、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意が必要
・消滅の場合
★雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。
★申請には、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意が必要
(法附則第2条、第4条)
⑤【H21年問9】(労災)
労働保険徴収法では、雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならないとされており、この規定に違反した事業主に対する罰則が定められている。

【解答】
⑤【H21年問9】(労災) 〇
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が雇用保険の加入を希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければなりません。
この規定に違反した事業主には罰則が定められています。
(法附則第2条第3項、第7条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-335 7.27
一元適用事業・二元適用事業【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険徴収法には、「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。
労災保険と雇用保険の適用や保険料納付の手続などを一元化して処理する「一元適用事業」が原則です。
特例で、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして二元的に処理する事業は、「二元適用事業」といいます。
「二元適用事業」に当たる事業をおぼえましょう。それ以外は一元適用事業です。
では、二元適用事業について条文を読んでみましょう。
第39条第1項 (適用の特例) 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。 則第70条 (適用の特例を受ける事業) 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。 (1) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業 (2) 港湾労働法の港湾運送の行為を行う事業 (3) 農林水産の事業 (4) 建設の事業 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

【解答】
①【H26年出題】(雇用) 〇
都道府県及び市町村の行う事業は、二元適用事業です。
(第39条第1項)
②【H24年出題】(労災)
労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。」とされている。

【解答】
②【H24年出題】(労災) ×
「国」の行う事業は二元適用事業ではないので、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」ではなく「都道府県及び市町村の行う事業その他・・・」となります。
(第39条第1項)
③【H26年出題】(雇用)
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

【解答】
③【H26年出題】(雇用) 〇
国の行う事業は、二元適用事業ではありません。
国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)は、労災保険の適用が除外で、労災保険が成立しないからです。
(第39条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-325 7.17
滞納処分と延滞金の注意点【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
第28条第1項 (延滞金) ① 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1,000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。
※令和6年度中の延滞金の割合 ・年8.7パーセント (納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は、年2.4パーセント) |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
延滞金は、「指定した期限の翌日」からではなく、「法定納期限の翌日」から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算します。
(第28条第1項)
納期限
▼ |
| 督促状の 指定期限 ▼ |
|
| 完納
▼ |
| 納期限の 翌日 |
|
| 完納の 前日 |
|
|
|
| |||
②【H29年出題】(雇用)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

【解答】
②【H29年出題】(雇用) 〇
督促状が発せられた場合でも、事業主が督促状に指定された期限までに徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されません。
延滞金が徴収されない場合を条文で読んでみましょう。
第28条第5項 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、(4)の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。 (1) 督促状に指定した期限までに労働保険料その他この法律の規定による徴収金を完納したとき。 (2) 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。 (3) 延滞金の額が100円未満であるとき。 (4) 労働保険料について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。 (5) 労働保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。 |
③【H26年出題】(雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
③【H26年出題】(雇用) ×
「追徴金」について
追徴金は、労働保険料ではないことに注意してください。
・ 督促の対象は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」ですので、追徴金も督促の対象になります。
(第27条第3項)
・ 延滞金は、「労働保険料の納付を督促」したときに徴収されます。追徴金は労働保険料ではありませんので、追徴金は延滞金の対象になりません。
(第28条第1項)
④【H22年出題】(雇)
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

【解答】
④【H22年出題】(雇) ×
追徴金は、国税滞納処分の例によって処分される対象になります。
(第27条第3項)
追徴金の額については、延滞金の対象になりません。
(第28条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-311 7.3
労働保険料の被保険者負担について【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H22年出題】(雇用)
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。

【解答】
①【H22年出題】(雇用) ×
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額は、事業主が全額負担します。労働者の負担はありません。
(第31条第3項)
②【H22年出題】(雇用)※改正による修正あり
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。

【解答】
②【H22年出題】(雇用) 〇
一般保険料には、「労災保険料」と「雇用保険料」があり、「雇用保険料」には、「二事業」分が含まれます。
雇用保険の被保険者が負担するのは、「雇用保険料」から「二事業」分を引いた額の2分の1です。雇用保険料全体の2分の1ではありませんので、注意してください。
なお、二事業の分は、事業主が全額負担します。
例えば、令和6年度の一般事業の雇用保険料率は、1000分の15.5で、そのうち二事業の率は1000分の3.5です。
被保険者が負担するのは、(1000分の15.5-1000分の3.5)×2分の1=1000分の6です。
事業主が負担するのは、(1000分の15.5-1000分の3.5)×2分の1+1000分の3.5=1000分の9.5です。
(第31条第1項第1号)
③【H22年出題】(雇用)
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。

【解答】
③【H22年出題】(雇用) ×
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額と、一般保険料を負担しなければなりません。
日雇労働被保険者は、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1」と「印紙保険料の額の2分の1」を負担します。
(第31条第3項)
④【H22年出題】(雇用)
海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料については、当該海外派遣者と派遣元の事業主とで当該第3種特別加入保険料の額の2分の1ずつを負担することとされている。

【解答】
④【H22年出題】(雇用) ×
第3種特別加入保険料は、労災保険料ですので、事業主が全額負担します。
(第31条第3項)
⑤【H25年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険の被保険者が負担すべき労働保険料相当額を被保険者の賃金から控除することが認められているが、この控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができるものとされているので、例えば、月給制で毎月賃金を支払う場合に、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできない。

【解答】
⑤【H25年出題】(雇用) 〇
控除は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる額についてのみ行うことができます。月給制の場合は、毎月賃金を支払う都度控除しなければなりませんので、1年間分の被保険者負担保険料額全額をまとめて控除することはできません。
条文を読んでみましょう。
第32条第1項(賃金からの控除) 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
則第60条 (賃金からの控除) ① 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。 ② 事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
|
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-286 6.8
増加概算保険料のすべて【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
「増加概算保険料」の要件は次の2つです。
① 労働者の人数が増える等で、賃金総額の見込額が増加した場合
↓
増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の 100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上になった
(則第25条第1項)
② 労災保険の保険関係又は雇用保険の保険関係のみが成立していた事業が両保険の保険関係が成立する事業になったため、一般保険料率が変更した場合
↓
変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上になった
(法附則第5条、則附則第4条第1項)
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。

【解答】
①【H23年出題】(労災) 〇
継続事業も有期事業も、増加概算保険料の申告・納付の期限は同じです。
「賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内」に申告・納付を行わなければなりません。「増加が見込まれた日から」がポイントです。実際に2倍を超えるに至った日ではありませんので注意してください。
(第16条)
②【H23年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。

【解答】
②【H23年出題】(労災) 〇
この場合は、「一般保険料率が変更された日から30日以内」に申告・納付しなければなりません。また、翌日起算であることにも注意してください。令和4年に、「一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に(解答〇)」で出題されています。
(法附則第5条、則附則第4条)
③【H23年出題】(労災)
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。

【解答】
③【H23年出題】(労災) ×
増加概算保険料には、「認定決定」はありません。
④【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなったが、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合には、確定保険料の申告・納付の際に精算する必要がある。

【解答】
④【H23年出題】(労災) 〇
賃金総額の見込額が増加したけれども、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至らなかった場合は、確定保険料の申告・納付の際に精算することになります。
⑤【H23年出題】(労災)
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないとされているが、一定の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。

【解答】
⑤【H23年出題】(労災) ×
増加概算保険料申告書は所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
日本銀行又は労働基準監督を経由して行うことができますが、年金事務所は経由できません。
(則第38条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-275 5.28
納付書と納入告知書の問題5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
徴収法では、「納付書」と「納入告知書」を区別することがポイントです。
条文を読んでみましょう。
則第38条第4項 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならない。 |
労働保険料等の納付は、「納付書」で行うことが原則です。
試験対策としては、「納入告知書」によって行われるものをおぼえましょう。おぼえたもの以外は「納付書」です。
(納入告知書によるもの) ・有期事業のメリット制の適用に伴う確定保険料の差額 ・認定決定された確定保険料と追徴金 ・認定決定された印紙保険料と追徴金 ・特例納付保険料 (則第38条第5項) |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用保険) ×
概算保険料の認定決定の通知は、納入告知書ではなく「納付書」で行われます。
確定保険料の認定決定との違いに注意しましょう。
概算保険料の認定決定 | 確定保険料の認定決定 |
納付書 | 納入告知書 |
追徴金なし | 追徴金あり |
(則第38条第4項、5項)
②【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
②【H25年出題】(雇用保険) 〇
確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
③【H25年出題】(雇用保険)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
③【H25年出題】(雇用保険) 〇
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われます。
(則第38条第4項、5項)
ちなみに、印紙保険料の認定決定が行われた場合は、認定決定した印紙保険料の額の100分の25の追徴金が徴収されます。
認定決定による印紙保険料と追徴金は「現金」で納付します。雇用保険印紙で納付するのではありませんので注意しましょう。
④【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第17条第1項の規定に基づき概算保険料の追加徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官は事業主に対して追加徴収する概算保険料の額の通知を行うが、当該徴収金の納付は、納付書によって行われる。

【解答】
④【H25年出題】(雇用) 〇
追加徴収の概算保険料の納付は、納付書によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
⑤【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第21条第1項の規定に基づき追徴金の徴収が行われる場合に、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う追徴金の額等の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
⑤【H25年出題】(雇用) 〇
追徴金の額等の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第4項、5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 徴収法
R6-261 5.14
労働保険料の算定と納付【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【R3年出題】(雇用)
次に示す業態をとる事業についての労働保険料に関する記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、保険料の滞納はないものとし、また、一般保険料以外の対象となる者はいないものとする。
保険関係成立年月日:令和元年7月10日
事業の種類:食料品製造業
令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6
令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9
令和元年度の確定賃金総額:4,000万円
令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円
令和2年度の確定賃金総額:7,600万円
令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円
【問題】
A 令和元年度の概算保険料を納付するに当たって概算保険料の延納を申請した。当該年度の保険料は3期に分けて納付することが認められ、第1期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内の令和元年8月29日までとされた。

【解答】
A ×
ポイント! 年度の中途に保険関係が成立した場合の延納について
4月・5月に成立 → 3期に分けて延納できる
6月~9月に成立 → 2期に分けて延納できる
10月以降に成立 → 延納できない
7月10日に成立した場合は、当該年度の保険料は「2期」に分けて納付することが認められます。
最初の期分の保険料の納付期日は保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内ですので、令和元年8月29日です。翌日起算がポイントです。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 (7月10日~11月30日)
納付期日 8月29日 | 第2期 (12月1日~3月31日)
納付期日1月31日 (労働保険事務組合に委託) 2月14日 | |||||||
(則第27条)
【問題】
B 令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111万円とされた。
7,400万円×1000分の15=111万円

【解答】
B ×
概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額で計算するのが原則です。
ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下の場合は、「直前の保険年度の賃金総額」で計算します。
令和2年度の賃金総額の見込額は7,400万円ですが、令和元年度の確定賃金総額4,000万円の100分の50以上100分の200以下の範囲に入ります。そのため、令和2年度の概算保険料は、令和元年度の確定賃金総額で計算します。
令和2年度の概算保険料は、4,000万円×1000分の15=60万円です。
令和元年度 | 令和2年度 |
確定賃金総額4,000万円 | 賃金総額の見込額7,400万円 ※令和2年度の概算保険料は、 令和元年度の確定賃金総額で計算します |
(第15条、則第24条)
【問題】
C 令和3年度の概算保険料については、賃金総額の見込額を3,600万円で算定し、延納を申請した。また、令和2年度の確定保険料の額は同年度の概算保険料の額を上回った。この場合、第1期分の保険料は下記の算式により算定した額とされた。
3,600万円×1000分の15÷3=18万円‥………………………①
(令和2年度の確定保険料)-(令和2年度の概算保険料)……②
第1期分の保険料=①+②

【解答】
C 〇
 令和3年度の概算保険料は、賃金総額の見込額の3,600万円で算定します。
令和3年度の概算保険料は、賃金総額の見込額の3,600万円で算定します。
令和2年度の確定賃金総額7,600万円の100分の50未満だからです。
 令和3年度の概算保険料の額は3600万円×1000分の15=54万円です。3期に分けて延納でき、1回当たりの額は、54万円÷3=18万円です。
令和3年度の概算保険料の額は3600万円×1000分の15=54万円です。3期に分けて延納でき、1回当たりの額は、54万円÷3=18万円です。
 確定保険料は延納できませんので、1期目で全額納付します。
確定保険料は延納できませんので、1期目で全額納付します。
 第1期分として7月10日までに納付する額は以下の額です。
第1期分として7月10日までに納付する額は以下の額です。
令和3年度第1期分概算保険料18万円 |
+
確定精算のために納付する令和2年度分の確定保険料 (納付済の令和2年度の概算保険料と確定保険料の差額) |
(第15条、第19条、則第27条)
【問題】
D 令和3年度に支払いを見込んでいた賃金総額が3,600万円から6,000万円に増加した場合、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額を増加概算保険料として納付しなければならない。

【解答】
D ×
増加概算保険料の要件は、「増加後の賃金総額の見込額が増加前の賃金総額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である」ことです。
見込額が3,600万円から6,000万円に増加しても、100分の200は超えていませんので、増加概算保険料の納付は不要です。
(第16条、則第25条)
【問題】
E 令和3年度の概算保険料の納付について延納を申請し、定められた納期限に従って保険料を納付後、政府が、申告書の記載に誤りがあったとして概算保険料の額を決定し、事業主に対し、納付した概算保険料の額が政府の決定した額に足りないと令和3年8月16日に通知した場合、事業主はこの不足額を納付しなければならないが、この不足額については、その額にかかわらず、延納を申請することができない。

【解答】
E ×
認定決定された概算保険料も、延納の申請が可能です。
(則第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-242 4.25
保険関係の消滅と確定保険料申告書【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険の保険関係の消滅について条文を読んでみましょう。
第5条 (保険関係の消滅) 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
事業が廃止又は終了した場合は、その日の翌日に、保険関係は当然に消滅します。
なお、廃止は「継続事業」、終了は「有期事業」に用いられます。
第19条第1項、2項(確定保険料申告書) ① 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料申告書を、次の保険年度の6月1日から 40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。 ② 有期事業については、その事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければならない。 |
保険関係が消滅した場合は確定保険料申告書を提出し、労働保険料の精算を行います。
<確定保険料申告書提出期限>
★継続事業、一括有期事業の場合
通常 (保険年度ごとに精算します)
→ 次の保険年度の6月1日から40日以内
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合
→ 保険関係が消滅した日から50日以内
★有期事業の場合
→ 保険関係が消滅した日から50日以内
ちなみに、「保険年度の6月1日」も「消滅した日」も午前0時から始まりますので、どちらも当日起算です。
・継続事業、一括有期事業が保険年度の中途に保険関係が消滅した場合
4月1日 3月31日
| 廃止 | 消滅 |
|
|
| 消滅した日から50日以内 |
|
・有期事業の保険関係が消滅した場合
開始 |
| 終了 | 消滅 |
消滅した日から50日以内
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。

【解答】
①【H29年出題】(労災) ×
事業が廃止された場合は、廃止の日の翌日に、自動的に保険関係は消滅します。
「保険関係廃止届」なるものはありませんし、届出によって消滅するものでもありません。
(第5条)
②【R3年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係の消滅を申請しようとする労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、当該事業についての保険関係が消滅する。

【解答】
②【R3年出題】(労災) 〇
暫定任意適用事業も適用事業と同じく、事業が廃止された場合は、廃止の日の翌日に、自動的に保険関係は消滅します。
ただし、暫定任意適用事業は、厚生労働大臣の認可を受けて保険関係を消滅させることもできます。その場合は、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、保険関係が消滅します。
(整備法第8条第1項)
③【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

【解答】
③【R5年出題】(雇用) ×
継続事業の保険関係が保険年度の中途に消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
令和4年10月31日に事業を廃止した場合、保険関係の消滅は同年11月1日です。
確定保険料申告書の提出期限は、11月1日から起算して50日以内ですので、「12月20日」までとなります。
(第19条第1項)
④【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

【解答】
④【H26年出題】(雇用) ×
第19条第3項で以下のように定められています。
| 事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときはその不足額を、確定保険料申告書に添えて、有期事業以外の事業にあっては次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、有期事業にあっては保険関係が消滅した日から50日以内に納付しなければならない。 |
問題文の場合は、不足額は、確定保険料申告書に添えて、納付しなければなりません。期限は、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)です。
(第19条第3項)
⑤【H26年出題】(雇用)
請負金額50億円、事業期間5年の建設事業について成立した保険関係に係る確定保険料の申告書は、事業が終了するまでの間、保険年度ごとに、毎年、7月10日までに提出しなければならない。

【解答】
⑤【H26年出題】(雇用) ×
有期事業は事業が終了した日の翌日に保険関係が消滅します。
有期事業は、保険年度ごとではなく、事業が開始したときに概算保険料を申告・納付し、事業が終了したときに確定精算を行います。
有期事業の確定保険料の申告書は、保険関係が消滅した日から50日以内に提出しなければなりません。
(第19条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-241 4.24
労働保険の成立手続(保険関係成立届)【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険の成立と届出について条文を読んでみましょう。
第3条 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。
第4条 雇用保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
第4条の2第1項 (保険関係の成立の届出等) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 |
労災保険・雇用保険の保険関係は、その事業が開始された日に成立します。
労働保険の適用事業になった場合は、「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。(則第4条第2項)
★「当日起算」、「翌日起算」に注意しましょう
起算日は、原則として「翌日」です。
保険関係成立届の提出期限は、「その成立した日から10日以内」ですが、起算日は「翌日」です。労働保険が成立した日は、午前0時から始まらないからです。
ちなみに、継続事業の概算保険料の申告期限は、「保険年度の6月1日から40日以内」ですが、起算日は「当日」です。保険年度の6月1日は午前0時から始まるからです。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【H27年出題】(労災) 〇
保険関係成立届の提出期限は、「保険関係が成立した日の翌日から起算」して10日以内です。「その成立した日から10日以内」は翌日から起算することがポイントです。
(第4条の2第1項)
②【R1年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。

【解答】
②【R1年出題】(労災) 〇
届け出なければならない事項は、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項です。
有期事業については、事業の予定される期間も届出の事項に含まれます。
(第4条の2第1項、則第4条第1項第5号)
③【H25年出題】(労災)
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

【解答】
③【H25年出題】(労災) ×
労働者を使用した場合は、当然に労災保険・雇用保険の適用事業となります。
労働保険の保険関係は、保険関係成立届を提出することによって成立するのではなく、事業が開始された日(適用事業になった日)に、自動的に成立します。
(第3条、第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-226 4.9
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主の範囲
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労働保険事務組合は、中小事業主から委託を受けて、事業主の代理人として労働保険事務を処理します。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる「中小事業主」の範囲を確認しましょう。
★労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる事業主
・ 労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主 ・ 団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるもの (第33条第1項則第62条第1項) |
★委託できる事業主の規模
・ 金融業、保険業、不動産業、小売業を主たる事業とする事業主 →常時50人以下の労働者を使用する事業主 ・ 卸売業、サービス業を主たる事業とする事業主 →常時100人以下の労働者を使用する事業主 ・ 上記以外の事業主 →常時300人以下の労働者を使用する事業主 (則第62条第2項) |
※常時使用する労働者の人数は、事業場単位ではなく、「企業単位」で算定します。
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主のほか、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託することができる。

【解答】
①【R5年出題】(労災) 〇
労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる事業主の地域的範囲の制限はありません。
労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主だけでなく、他の都道府県に主たる事務所を持つ事業の事業主についても、委託できます。
(第33条)
②【R1年出題】(雇用)
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【解答】
②【R1年出題】(雇用) 〇
金融業を主たる事業とする事業主は、常時使用する労働者が50人以下の場合は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができます。
(則第62条第2項)
委託できる事業主の規模はしっかりおぼえましょう。
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 常時50人以下 |
卸売業、サービス業 | 常時100人以下 |
その他 | 常時300人以下 |
③【R5年出題】(労災)
清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることとなった場合でも、常態として300人以下であれば労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができる。

【解答】
③【R5年出題】(労災) 〇
使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人、100人、50人を超えることとなった場合でも、常態として300人、100人、50以下ならば、労働保険事務組合に委託することができます。
(参照 労働保険事務組合事務処理手引)
④【R3年出題】(雇用)
労働保険徴収法第33条第1項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる。

【解答】
④【R3年出題】(雇用) 〇
事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主でも、労働保険事務の処理を委託することが必要であると認められる事業主は、委託することができます。
(則第62条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-212
R6.3.26 概算保険料の追加徴収
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
概算保険料の追加徴収について条文を読んでみましょう。
第17条 ① 政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。 ② 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき労働保険料の額を通知しなければならない。
則第26条 (概算保険料の追加徴収) 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 (1) 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 (2) 納期限 |
保険年度の中途から保険料率が引き上げられた場合、既に納付した概算保険料と保険料率が引き上げられた後の概算保険料の差額が追加で徴収されます。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
②【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われることになっている。
③【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
④【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、延納することはできない。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収は、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」、行われることがポイントです。増加概算保険料との違いに注意してください。
(第17条)
②【H30年出題】(労災) ×
保険年度の中途に、保険料率が引き下げられた場合でも、還付する規定はありません。
③【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収される概算保険料の納付は「納付書」により行われます。
(則第26条、則第38条第4項)
④【H30年出題】(労災) ×
追加徴収される概算保険料は、延納することができます。
概算保険料について延納が認められていること、通知により指定された期限までに延納の申請をすることが条件です。
(則第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-194
R6.3.8 請負事業の一括のポイント!②分離編
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
引き続き「請負事業の一括のポイント」をチェックします。
昨日は、「一括編」でしたが、今日は「分離編」です。
ポイントをチェックしましょう!
・下請負事業を分離させることができます
・一括は「法律上当然に」行われますが、分離の場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。なお、認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。
・分離する下請負事業は、一定以上の規模でなければなりません。
・分離の認可申請は、元請負人と下請負人が共同で行います。
条文を読んでみましょう。
第8条第2項 請負事業が一括された場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して下請負人をその請負に係る事業主とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして適用する。
則第8条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請) 下請負事業の分離の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、定められた事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
則第9条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準) 下請負事業の分離の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号に該当する事業(有期事業の一括の要件に該当する事業)以外の事業でなければならない。 |
★下請負事業の分離の認可を受けるための要件を確認しましょう。
下請負事業の規模が、
・概算保険料が160万円以上
又は
請負金額が1億8千万円以上
であることが必要です。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】(労災)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。
②【H27年出題】(労災)
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

【解答】
①【H27年出題】(労災) ×
厚生労働省令で定める事業とは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業」です。(則第7条)
元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の事業の規模が、「概算保険料の額に相当する額が160万円以上」、又は、「請負金額が1億8千万円以上」でなければなりません。
なお、請負金額から消費税額は除かれます。
(第8条第2項、則第7条、第9条)
②【H27年出題】(労災) ×
下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出します。ただし、「そのいずれかが単独で」ではなく、「元請負人及び下請負人が共同で」提出しなければなりません。
(則第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-193
R6.3.7 請負事業の一括のポイント!①一括編
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
今日は、「請負事業の一括」のポイントをチェックします。
まずポイントからどうぞ!
・対象は「建設の事業」です。(立木の伐採の事業は対象外です)
・建設の事業が数次の請負によって行われる場合、労災保険は下請負事業を元請負事業に一括して、保険関係が成立します。
・法律上当然に一括され、元請負人のみが適用事業主となります。
・一括されるのは労災保険の保険関係のみで、雇用保険の保険関係は一括されません。雇用保険の保険関係は、個別に成立します。
★建設の事業が数次の請負によって行われる場合のイメージ
<労災保険の保険関係> <雇用保険の保険関係>
元請負事業に一括されます 個別に成立します
元請負事業(成立) |
| 元請負事業(成立) |
↓ |
| ↓ |
下請負事業その1 |
| 下請負事業その1(成立) |
↓ |
| ↓ |
下請負事業その2 |
| 下請負事業その2(成立) |
↓ |
| ↓ |
下請負事業その3 |
| 下請負事業その3(成立) |
条文を読んでみましょう。
第8条第1項、則第7条 (請負事業の一括) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
②【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
③【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。
④【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。
⑤【R2年出題】(労災保険)
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】(労災) ×
請負事業の一括の対象は「建設の事業」です。「立木の伐採の事業」は請負事業の一括の対象になりません。
(第8条第1項、則第7条)
②【R2年出題】(労災保険) ×
請負事業の一括は、「法律上当然に」行われます。「所轄労働基準監督署長に届け出ることによって」は誤りです。
(第8条第1項)
③【R2年出題】(労災保険) 〇
請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係」のみです。「雇用保険に係る保険関係」は一括されず、個別に適用されます。
(第8条第1項、則第7条)
④【R2年出題】(労災保険) ×
請負事業の一括が行われ元請負人のみが当該事業の事業主とされると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負います。
しかし、「労働関係の当事者」として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となることはありません。
(第8条第1項)
⑤【R2年出題】(労災保険) ×
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負います。
そのため、元請負人がこれを納付しないときでも、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、保険料を納付するよう請求することはできません。
(第8条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
ご質問のお返事です 労働保険徴収法
R6-180
R6.2.23 メリット制が適用された場合の労災保険率
今日は、いただきましたご質問のお返事です。
ご質問の内容です。
| 継続事業にかかるメリット制が適用された場合の労災保険率の引き上げ、引き下げの意味がよくわかりません。 |
労災保険率は、労災発生のリスクによって「事業の種類」ごとに、1000分の2.5から1000分の88の範囲で決められています。
ただし、事業の種類が同じでも、労災が発生する会社もあれば、発生しない会社もあります。
例えば、大きな労働災害が発生した事業場(=労災保険から保険給付が行われた)も、労働災害が発生しなかった事業場(=労災保険から保険給付を受けていない)も、「事業の種類」が同じなら、労災保険率も同じです。
しかし、メリット制が適用されると、災害率が高い場合は、労災保険率が引き上げられ、逆に低い場合は、労災保険率が引き下げられますので、保険料負担の公平性が保たれます。
■では、継続事業と一括有期事業にメリット制が適用される条件を確認しましょう。
①事業の継続性を満たすこと
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)に労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上経過していること
②事業の規模を満たすこと
連続する3保険年度中の各保険年度に次の(A)~(C)のいずれかに該当する事業であること
(A) 100人以上の労働者を使用する事業
(B) 20人以上100人未満の労働者を使用する事業で、災害度係数が0.4以上であるもの
(C) 一括有期事業は、各保険年度において確定保険料の額が40万円以上
■次に、メリット制が適用される時期を確認しましょう。
・基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から適用されます。
①年度 | ②年度 | ③年度 | ④年度 | ⑤年度 |
連続する3保険年度 (収支率を算定) |
| メリット制適用 | ||
|
| ③年度の3/31(基準日) |
|
|
■「収支率」を確認しましょう。
メリット収支率は、簡単に言いますと、連続する3保険年度中の「保険料に対する保険給付の割合」です。
メリット収支率は、保険料も保険給付も「業務災害」に関する部分で計算するのがポイントです。
保険給付+特別支給金 |
保険料 |
★メリット収支率が85%超える場合
→ 保険給付の割合が高い=災害発生率が高いということです。継続事業では、労災保険率が最大で40%引き上げられます。
★メリット収支率が75%以下の場合
→ 保険給付の割合が小さいので、継続事業では労災保険率が最大で40%引き下げられます。
★メリット収支率が75%超え85%以下の場合
→労災保険率の引上げ引き下げはありません。
■メリット制が適用された場合の労災保険率を確認しましょう。
例えば、労災保険率が1000分の9の場合、そのうち1000分の0.6は非業務災害率で、1000分の8.4が業務災害に当たる率です。なお、非業務災害率は、全事業共通です。
メリット制で引上げ引き下げの対象になるのは、「業務災害」に当たる部分の率です。
例えば、業務災害が起こらなかった事業(労災の保険給付が行われなかった事業)の場合、メリット収支率は0となり、労災保険率のうち、非業務災害率を除いた率が40%引き下げられます。
9-0.6 | × | 100-40 | + | 0.6 |
1000 | 100 |
| 1000 | |
↑ 非業務災害率を除いた率 |
| ↑ 40%減 |
| ↑ 非業務災害率 |
基準日の属する保険年度の次の次の保険年度からの労災保険率は、1000分の5.64になります。非業務災害率はメリット制の対象になりませんが、労災保険率には入りますので、注意しましょう。
では、次にメリット収支率が180%の場合です。労災保険率のうち、非業務災害率を除いた率が40%引き上げられます。
9-0.6 | × | 100+40 | + | 0.6 |
1000 | 100 |
| 1000 | |
↑ 非業務災害率を除いた率 |
| ↑ 40%増 |
| ↑ 非業務災害率 |
基準日の属する保険年度の次の次の保険年度からの労災保険率は、1000分の12.36になります。
では、過去問もどうぞ!
①【R2年出題(労災)】
メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引上げ引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
②【R2年出題(労災)】
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
③【R2年出題(労災)】
労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。

【解答】
①【R2年出題(労災)】 〇
雇用保険率には、メリット制はありません。
(第12条第3項)
②【R2年出題(労災)】 〇
メリット収支率の分子は、業務災害に係る保険給付ですが、「特別支給金で業務災害に係るもの」も含みます。
(第12条第3項)
③【R2年出題(労災)】 〇
メリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となります。
(第12条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-170
R6.2.13 継続事業の一括のポイント!
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
★「継続事業の一括」のイメージは?
例えば、株式会社A銀行には、東京本社、北海道支店、大阪支店、福岡支店があります。
労働保険徴収法は、それぞれで適用されるのが原則です。
ただし、厚生労働大臣の認可を受けた場合は、保険関係を指定事業に一括することができます。
例えば、本社で支店の給料計算もまとめて行っている場合に、本社を指定事業として、支店の分も一括して労働保険料の申告手続きができるようになります。
条文を読んでみましょう。
第9条 (継続事業の一括) 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】(労災)
事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、労働保険徴収法施行規則第10条で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることを継続事業の一括という。
②【R5年出題】(労災)
継続事業の一括に当たって、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業とは、一括できない。
③【R5年出題】(労災)
継続事業の一括に当たって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
④【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(「指定事業」という。)以外の事業にかかる保険関係は、消滅する。
⑤【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

【解答】
①【R5年出題】(労災) 〇
ポイント!
「継続事業の一括」は、当然に行われるのではなく「厚生労働大臣の認可」が必要です。
(第9条)
なお、継続事業の一括に係る厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。(則第76条)
②【R5年出題】(労災) 〇
継続事業の一括の要件として、以下の要件があります。
■それぞれの事業が、次の①から③までのいずれか一のみに該当するものであること。
①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
②雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
問題文は、①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業と、③一元適用事業であって労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立している事業ですので、一括されません。
(則第10条第1項第1号)
③【R5年出題】(労災) ×
継続事業の一括の要件として、「それぞれの事業が、労災保険率表による事業の種類を同じくすること」があります。
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業についても、それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要があります。
(則第10条第1項第2号)
④【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、保険関係は、指定事業に一括され、すべての労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされます。
そのため、指定事業以外の事業にかかる保険関係は、消滅します。
指定事業以外の事業は、保険関係の消滅により、労働保険料の確定精算の手続が必要になります。
(第9条)
⑤【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括が行われ保険関係が一括されても、労災保険給付の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は一括されません。
労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、それぞれの事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-160
R6.2.3 賃金総額を正確に算定することが困難なものの特例
過去問から学びましょう。
今日は徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第11条 (一般保険料の額) ① 一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 ② 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 ③ 厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
則第12条 (賃金総額の特例) 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 (1) 請負による建設の事業 (2) 立木の伐採の事業 (3) 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。) (4) 水産動植物の採捕又は養殖の事業 |
・一般保険料の額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
・「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用する「すべての労働者に支払う賃金の総額」をいいますが、厚生労働省令で定める事業(上記(1)から(4))については、労災保険料を計算するに当たり、賃金総額の特例が設けられています。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(雇用)
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
②【R1年出題】(労災)
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
③【R4年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。
④【R4年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

【解答】
①【H30年出題】(雇用) ×
「請負による建設の事業」、「立木の伐採の事業」、「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」は、賃金総額の特例が認められていますが、常に認められるのではなく、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」に限定されています。
(則第12条)
②【R1年出題】(労災) ×
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業は、賃金総額を「請負金額×労務費率」とすることができます。
事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算するのが原則です。
(則第13条第2項第1号)
③【R4年出題】(労災) 〇
賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を使います。
(則第13条第2項)
④【R4年出題】(労災) ×
「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」で賃金総額の特例が認められた場合は、「その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」が賃金総額となります。
(則第15条)
なお、「立木の伐採の事業」の場合は、「所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額」が賃金総額となります。
(則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働保険徴収法
R6-150
R6.1.24 有期事業の一括のポイントを全てチェック!
過去問から学びましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第7条 (有期事業の一括) 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 (1) 事業主が同一人であること。 (2) それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 (3) それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 (4) それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 (5) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。
則第6条 (有期事業の一括) ① 法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 (1) 概算保険料の額に相当する額が160万円未満であること。 (2) 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であり、建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満であること。 ② 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。 (1) それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 (2) それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること。 (3) それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 ③ 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項(3)の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。 |
ポイント!
★一括の対象になる事業の規模をおさえましょう。
<建設の事業>
概算保険料が160万円未満かつ請負金額が1億8,000万円未満
<立木の伐採の事業>
概算保険料が160万円未満かつ素材の見込生産量が1,000立方メートル未満
★有期事業の一括で一括されるのは、「労災保険」の保険関係のみです。雇用保険は一括されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】(労災)
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。
②【H30年出題】(労災)
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
③【R3年出題】(労災)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
④【R3年出題】(労災)
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
⑤【H28年出題】(労災)
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象とされる。
⑥【R3年出題】(労災)
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。
⑦【R3年出題】(労災)
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。
⑧【R3年出題】(労災)
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。
⑨【H28年出題】(労災)
有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

【解答】
①【H24年出題】(労災) 〇
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるのがポイントです。申請や承認などの手続は不要です。
(S40.7.31基発901号)
②【H30年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の対象になると、原則としてその全体が継続事業として取り扱われます。労働保険料の申告や納付は、継続事業と同じように年度更新で行います。
(S40.7.31基発901号)
③【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の対象になるのは、建設の事業・立木の伐採の事業です。また、労災保険に係る保険関係のみが対象です。
④【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額が160万円未満でなければなりません。
(則第6条第1項第1号)
⑤【H28年出題】(労災) ×
独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が縮小し有期事業の一括のための要件を満たしたとしても、有期事業の一括の対象にはなりません。
ちなみに、有期事業の一括の対象になっていた事業の規模が拡大し要件を満たさなくなったとしても、一括の対象からは除外されません。
⑥【R3年出題】(労災) ×
「それぞれの事業が、事業の種類(労災保険率表による事業の種類をいう。)を同じくすること。」が、有期事業の一括の要件です。労災保険率が同じでも、事業の種類が異なっている場合は、有期事業の一括は適用されません。
(則第6条第2項第2号)
⑦【R3年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の条件の一つに、「事業主が同一人であること」があります。「事業主が同一人」とは、「同一企業」ということです。同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合は、事業主が同一人であることに該当しないので、有期事業の一括は行われません。
(法第7条第1号)
⑧【R3年出題】(労災) 〇
数次の請負による建設の事業の場合、徴収法上の事業主は、原則として元請負人になります。(法第8条)
そのため、X会社がY会社の下請として施工する建設の事業では、X会社は下請負人で、徴収法上は事業主になりません。
X会社がY会社の下請負人として施工する事業は、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されません。元請のY会社の工事に一括されます。
(法第7条)
⑨【H28年出題】(労災) 〇
有期事業の一括の対象となった事業の労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となります。
(則第6条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-114
R5.12.19 徴収法の「賃金」の定義
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
則第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
|
通貨以外のもので支払われるもの(現物給付)も、厚生労働省令で定める範囲内のものは賃金に含まれます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】(労災保険)
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
②【R1年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
③【H19年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
④【H26年出題】(労災保険)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
①【H24年出題】(労災保険) 〇
労働基準法の「休業手当」は賃金ですが、「解雇予告手当」は賃金となりません。
(S25.4.10 基収950号、S23.8.18基収2520号)
②【R1年出題】(雇用保険) 〇
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の「範囲」は、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされています。
(則第3条)
③【H19年出題】(雇用保険) 〇
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるものに限られません。
①食事、②被服、③住居の利益、④所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも、「通貨以外のもので支払われる賃金」として、賃金に算入されます。
(則第3条)
④【H26年出題】(労災保険) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約などで事業主に支給が義務づけられていても、労働保険料の算定基礎となる賃金にはなりません。
(S25.2.16基発127号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用保険)
労働保険徴収法における「賃金」のうち、食事、被服及び住居の利益の評価に関し必要な事項は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定めることとされている。

【解答】
【R5年出題】(雇用保険) ×
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めることとされています。
(第2条第3項)
ポイント!
「範囲」と「評価」に注意しましょう
・通貨以外のもので支払われる賃金の範囲 → 食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
・賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価 → 厚生労働大臣が定める
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-099
R5.12.4 雇用保険率 事業主負担と被保険者負担
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
令和5年度の雇用保険率は以下の通りです。
・一般の事業 1000分の15.5
・農林水産、清酒製造の事業 1000分の17.5
・建設の事業 1000分の18.5
労災保険料は事業主が全額負担しますが、雇用保険料は、事業主負担分と被保険者負担分に分けられるのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(雇用)
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

【解答】
【R2年出題】(雇用) ×
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料の額は、「労災保険料の額+雇用保険料の額」です。
労災保険料は事業主が全額負担しますので、労働者負担はありません。
雇用保険料については、二事業分は事業主が全額負担し、二事業以外の部分を事業主と被保険者が折半で負担します。
被保険者が負担するのは、「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額となります。
問題文は、「当該事業に係る一般保険料の額」となっています。労災保険と雇用保険が成立している場合、一般保険料には労災保険料も含まれますので、誤りです。
雇用保険率 | ||
二事業率 | 二事業率以外※ | |
事業主 | 事業主(2分の1) | 被保険者(2分の1) |
※二事業率以外の率は、「失業等給付・育児休業給付の保険料率」です。
(法第31条第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
一般の事業について、雇用保険率が1,000分の15.5であり、二事業率が1,000分の3.5のとき、事業主負担は1,000分の9.5、被保険者負担は1,000分の6となる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) 〇
先ほどの図に数字を入れてみましょう。
雇用保険率 1,000分の15.5 | ||
二事業率 1000分の3.5 | 二事業率以外※ 1,000分の12 | |
事業主 1,000分の3.5 | 事業主(2分の1) 1,000分の6 | 被保険者(2分の1) 1,000分の6 |
事業主負担 → 1,000分の3.5+1,000分の6=1,000分の9.5
被保険者負担 → 1,000分の6
となります。
(法第31条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-091
R5.11.26 労働保険料 年度更新の手続
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
今日は継続事業の労働保険料の年度更新手続きをみていきます。
継続事業の労働保険料は、「保険年度」単位で計算します。
保険年度ごとに、「賃金総額の見込額」で計算した「概算保険料」を申告・納付し、保険年度が終わってから、確定した賃金総額で計算した「確定保険料」で保険料のプラスマイナスを精算する仕組みです。
毎保険年度6月1日から40日以内に、「概算保険料」を申告・納付し、同時に、前年度の保険料を精算するために、「確定保険料」を申告・納付します。この手続きを「年度更新」といいます。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の労働保険料(印紙保険料を除く。)は、当該保険料の算定の対象となる期間が終わってから確定額で申告し、当該確定額と申告・納付済みの概算保険料との差額(納付した概算保険料がないときは当該確定額)を納付する仕組みをとっており、この確定額で申告する労働保険料を確定保険料という。
②【H26年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、納付した概算保険料の額が法所定の計算により確定した額に足りないときは、その不足額を、確定保険料申告書提出期限の翌日から40日以内に納付しなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇 (雇用)
継続事業は、保険年度単位で労働保険料を計算します。
★概算保険料 → その保険年度の賃金総額の見込額で計算し、6月1日から40日以内に概算で保険料を申告・納付します。
★確定保険料 → その保険年度が終わってから確定した賃金総額で計算し、次の保険年度の6月1日から40日以内に申告・納付し、納付済みの概算保険料を精算します。
なお、一括有期事業も継続事業と同じように、保険年度単位で労働保険料を計算します。
(法第15条、第19条)
②【H26年出題】(雇用) ×
継続事業(一括有期事業を含む。)の確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものは、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければなりません。
納付した概算保険料の額が足りないときは、その不足額を、「確定保険料申告書に 添えて」に納付しなければなりません。確定保険料の納付期限は、確定保険料申告書の提出期限と同じですので、「確定保険料申告書の提出期限の翌日から40日以内」は誤りです。
(法第19条第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
令和4年6月1日に労働保険の保険関係が成立し、継続して交通運輸事業を営んできた事業主は、概算保険料の申告及び納付手続と確定保険料の申告及び納付手続とを令和5年度の保険年度において同一の用紙により一括して行うことができる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) 〇
令和4年6月1日に、継続事業の労働保険の保険関係が成立した場合、令和4年度末までの賃金総額の見込額で計算した概算保険料を、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付します。
令和4年度終了後に、確定した賃金総額で令和4年度の労働保険料を確定し、既に納付している概算保険料を精算します。この確定保険料の申告・納付手続は、令和5年6月1日から40日以内に行います。
同時に、賃金総額の見込額で計算した令和5年度の概算保険料を、令和5年6月1日から40日以内に申告・納付します。
令和5年度の概算保険料の申告・納付手続と令和4年度の確定保険料の申告・納付手続の期限が同じですので、令和5年度の保険年度に同一の用紙で一括して行うことができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-085
R5.11.20 労働保険料その他徴収金を納付しない場合の具体例
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 |
まず過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(雇用)
労働保険徴収法第27条第1項は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。」と定めているが、この納付しない場合の具体的な例には、保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料の完納がない場合がある。
②【H22年出題】(雇用)
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。

【解答】
①【R1年出題】(雇用) 〇
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない場合」の具体例として、「保険年度の6月1日を起算日として40日以内又は保険関係成立の日の翌日を起算日として50日以内に(延納する場合には各々定められた納期限までに)納付すべき概算保険料」の完納がない場合があります。
②【H22年出題】(雇用) 〇
「認定決定に係る概算保険料」について完納がない場合も、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない場合」の具体例です。事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、督促が行われます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) ×
概算保険料、確定保険料を納期限までに申告しない場合は、政府が認定決定をし、事業主に通知します。 事業主は、認定決定された労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しなければなりません。
督促が行われるのは、認定決定の通知があったにもかかわらず、その通知を受けた日から15日以内(翌日起算)に納付しない場合です。
認定決定と同時に督促が行われるのではなく、認定決定に係る確定保険料をその期限までに完納しない場合に、督促が行われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-078
R5.11.13 第2種特別加入保険料の算定
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つがあり、保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。
特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。
なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、別表第5)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。

【解答】
【R5年出題】 〇 (労災)
給付基礎日額が12,000円の場合、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、12,000円×365=4,380,000円です。
また、第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に応じて、1000分の3から1000分の52の範囲です。
最高の率の1,000分の52で計算すると、4,380,000円×1000分の52=227,760円となり、事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間の第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-072
R5.11.7 第3種特別加入保険料の算定
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
労災保険の特別加入には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の 3つがあります。
保険料は、それぞれ、「第1種特別加入保険料」、「第2種特別加入保険料」「第3種特別加入保険料」となります。
特別加入保険料は、特別加入者それぞれの給付基礎日額に応じて定められる保険料算定基礎額の総額×特別加入保険料率で算定します。
なお、保険年度1年間の保険料算定基礎額の総額は、給付基礎日額×365です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(労災)※改正による修正あり
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和5年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。
②【R2年出題】(労災)
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
①【H26年出題】(労災) ×
令和5年度の第3種特別加入保険料率は事業の種類にかかわらず一律に 「1000分の3」とされています。
第3種特別加入保険料率は、「一律」で定められているのがポイントです。
(第14条の2、則第24条の3)
なお、第1種特別加入保険料率は、「当該事業に適用される労災保険率と同一の率」で、第2種特別加入保険料率は、1000分の3から1000分の52の範囲で、事業又は作業の種類ごとに定められていています。
②【R2年出題】(労災) ×
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類に「応じて」、1000分の3から1000分の52の範囲で定められています。同一の率ではありません。
(則第23条、別表第5)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の9であり、当該中小事業主等に雇用される者が労災保険法第36条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者における給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第3種特別加入保険料の額は39,420円とする。

【解答】
【R5年出題】(労災) ×
「第3種特別加入保険料の額」は、保険料算定基礎額の総額(給付基礎日額×365)×第3種特別加入保険料率で算定します。
問題文にあてはめると、(12,000円×365)×1000分の3=13,140円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-065
R5.10.31 雇用保険印紙の買戻し
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
則第43条第2項、3項 ② 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、3.に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。 1. 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。 2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。 3. 雇用保険印紙が変更されたとき。 ③ 事業主は、1.又は2.に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。 |
1.2.3.に該当するときは、雇用保険印紙の買戻しの申出をすることができます。
買戻しの条件に注意しましょう。
| 買戻し期間 | 公共職業安定所長の 確認 |
1.雇用保険に係る保険関係が消滅 | なし | 受けなければならない |
2.日雇労働被保険者を使用しなくなった | なし | 受けなければならない |
3.雇用保険印紙が変更 | 6月間 | 不要 |
過去問をどうぞ!
【H18年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更されたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から 6か月間である。

【解答】
【H18年出題】(雇用) 〇
雇用保険印紙が変更された場合は、買戻しの期間が決められているのがポイントです。期間は、「雇用保険印紙が変更された日から6か月間」です。なお、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受ける必要はありません。
ちなみに、「雇用保険に係る保険関係が消滅したとき」、「日雇労働被保険者を使用しなくなったとき」は、買戻しの期間は決められていませんが、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けることが必要です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。

【解答】
【R5年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙が変更されたときに、買戻しを申し出ることができるのは、その変更された日から「6か月間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-054
R5.10.20 雇用保険印紙購入通帳と雇用保険印紙の購入
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
則第42条第1項~5項 (雇用保険印紙購入通帳) ① 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 ② 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。 ③ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。 ④ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、所定の事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 |
★雇用保険印紙を購入するときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければなりません。
則第43条第1項 (雇用保険印紙の購入) 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
②【H20年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。
③【R2年出題】(雇用)
雇用保険印紙購入通帳の有効期間満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。

【解答】
①【H23年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けるために提出するのは、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」です。雇用保険印紙の購入申込書ではありません。
②【H20年出題】(雇用) ×
雇用保険印紙購入通帳の有効期間は、「その交付の日の属する保険年度」に限ります。
③【R2年出題】(雇用) 〇
雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前(3月1日)から当該期間が満了する日(3月31日)までの間に、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(雇用)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、労働保険徴収法施行規則第42条第1項に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。

【解答】
【R5年出題】 × (雇用)
所轄都道府県労働局歳入徴収官ではなく、「所轄公共職業安定所長」に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けます。
 ポイント!
ポイント!
雇用保険印紙購入通帳の交付 → 所轄公共職業安定所長
雇用保険印紙の購入 → 日本郵便株式会社の営業所
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-045
R5.10.11 労働保険事務組合の責任
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、労働保険徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第34条 (労働保険事務組合に対する通知等) 政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなす。
第35条第1項~3項 (労働保険事務組合の責任等) ① 事業主が労働保険関係法令の規定による労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ② 労働保険関係法令の規定により政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとする。 ③ 政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。 |
★労働保険事務組合・委託事業主・政府の関係のイメージです。
(政府からの通知等)
政 府 |
↓納入の告知その他の通知等 |
労働保険事務組合 |
↓通知等の効果は委託事業主に及ぶ |
委託事業主 |
(労働保険料の納付)
政 府 |
↑労働保険料を納付 |
労働保険事務組合 |
↑金銭を交付 |
委託事業主 |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
公共職業安定所長が雇用保険法第9条第1項の規定による労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認をしたときの、委託事業主に対してする通知が、労働保険事務組合に対してなされたときは、当該通知は当該委託事業主に対してなされたものとみなされる。
②【H25年出題】(雇用)
労働保険徴収法第19条第4項の規定により委託事業主に対してする認定決定の通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容によっては当該委託事業主に及ばないことがある。
③【H25年出題】(雇用)
労働保険事務組合は、概算保険料の納期限が到来しているにもかかわらず、委託事業主が概算保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しない場合、当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない。
④【H25年出題】(雇用)
労働保険料の納付義務者である委託事業主に係る督促状を労働保険事務組合が受けたが、当該労働保険事務組合が当該委託事業主に対して督促があった旨の通知をしないため、当該委託事業主が督促状の指定期限までに納付できず、延滞金を徴収される場合、当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。
⑤【H29年出題】(雇用)
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) 〇
政府は、通知等を、事業主ではなく労働保険事務組合に対してすることができます。
また、その通知は委託事業主に対してなされたものとみなされます。
(法第34条)
②【H25年出題】(雇用) ×
通知が労働保険事務組合に対してなされた場合、その通知の効果については、委託事業主に及びます。当該労働保険事務組合と当該委託事業主との間の委託契約の内容には関係ありません。
(法第34条)
③【H25年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合は、「事業主から交付された金額の限度で」、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負います。「当該概算保険料を立て替えて納付しなければならない」という規定はありません。
(法第35条第1項)
④【H25年出題】(雇用) ×
政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合に、その徴収について「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責任を負います。
問題文は、労働保険事務組合の責に帰すべき理由がありますので、「当該委託事業主のみが延滞金の納付の責任を負う。」は誤りです。
(法第35条第2項)
⑤【H29年出題】(雇用) ×
政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限って、その残余の額を、直接、当該事業主から徴収することができます。
(法第35条第3項)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合事務処理規約に規定する期限までに、確定保険料申告書を作成するための事実を事業主が報告したにもかかわらず、労働保険事務組合が労働保険徴収法の定める申告期限までに確定保険料申告書を提出しなかったため、所轄都道府県労働局歳入徴収官が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することとした場合、当該事業主が当該追徴金を納付するための金銭を当該労働保険事務組合に交付しなかったときは、当該労働保険事務組合は政府に対して当該追徴金の納付責任を負うことはない。

【解答】
【R5年出題】(労災) ×
問題文の場合、追徴金の徴収について「労働保険事務組合の責めに帰すべき理由」があります。その場合は、労働保険事務組合が、政府に対して、追徴金の納付の責めを負います。
(法第35条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働保険徴収法
R6-036
R5.10.2 労働保険事務組合とは
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、徴収法です。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項、第2項 (労働保険事務組合) ① 中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)を処理することができる。 ② 事業主の団体又はその連合団体は、①の業務を行なおうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
労働保険事務組合は、中小事業主の委託を受けて、労働保険料の納付などの労働保険事務の処理を行います。
労働保険事務組合として業務を行おうとする団体等は、厚生労働大臣の認可を受けることが必要です。
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。
②【H19年出題】(雇用)
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。

【解答】
①【H19年出題】(雇用) ○
団体等は、法人でなくても構いませんが、法人でない団体等は、代表者の定めがあることが要件です。(団体等の事業内容、構成員の範囲、その他団体等の組織、運営方法等が定款等において明確に定められ、団体性が明確であることも要します。)
②【H19年出題】(雇用) ×
認可の要件の一つに、「団体等は本来の事業目的をもって活動し、その運営実績が2年以上であること。」があります。
その団体の事業の一環で労働保険事務を行うことになりますので、「専業で行わなければならない」は誤りです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
労働保険事務組合は労働保険徴収法第33条第2項に規定する厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではなく、既存の事業主の団体等がその事業の一環として、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。

【解答】
【R5年出題】(労災) ○
労働保険事務組合は厚生労働大臣の認可を受けることによって全く新しい団体が設立されるわけではありません。既存の事業主団体と労働保険事務組合は同一の組織です。
既存の事業主の団体等はその事業の一環で、事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 徴収法
R6-027
R5.9.23 第1種特別加入保険料の計算
今日は、第1種特別加入保険料の計算です。
特別加入者の保険料の計算に使う「保険料算定基礎額」は、給付基礎日額×365です。 例えば、給付基礎日額が12,000円の場合は、保険料算定基礎額は438万円となります。
第1種特別加入保険料は、保険料算定基礎額×第1種特別加入保険料率で計算します。 |
※なお、年度の中途に特別加入者となった場合又は特別加入者でなくなった場合は、保険料算定基礎額は月割計算となります。
例えば給付基礎日額が12,000円、その年度の加入月数が6か月の場合は、保険料算定基礎額は、438万円×(6か月/12か月)=219万円となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】(労災)
中小事業主等が行う事業に係る労災保険率が1,000分の4であり、当該中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者に係る給付基礎日額が12,000円のとき、令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は17,520円となる。

【解答】
【R5年出題】(労災) ○
ポイント!
・保険料算定基礎額は、12,000円×365=438万円です。
・第1種特別加入保険料率は、当該事業に適用される労災保険率と同一の率ですので、1,000分の4です。
・令和5年度の保険年度1年間における第1種特別加入保険料の額は
438万円×1,000分の4=17,520円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 徴収法
R6-017
R5.9.13 労働保険料の申告・納付
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、徴収法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H26年出題】(雇用)
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【H29年出題】(労災)
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。
③【H29年出題】(労災)
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。

【解答】
①【H26年出題】(雇用) 〇
保険年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
6月30日に事業を廃止した場合は、翌日の7月1日に保険関係が消滅します。
保険関係が消滅した日の当日から起算するのがポイントです。確定保険料申告書は、7月1日から50日以内の8月19日までに提出しなければなりません。
(法第19条)
②【H29年出題】(労災) ×
継続事業・一括有期事業の延納の条件を確認しましょう。
★概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業は、20万円)以上のもの
又は
★労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの
※当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものは延納できません。
※延納の申請が必要です。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている場合は、概算保険料の額を問わず延納できます。
(則第27条)
③【H29年出題】(労災) 〇
平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の有期事業は、
第1期 6月15日~11月30日
第2期 12月1日~翌年3月31日
第3期 4月1日~6月5日
の3期に分けて納付することができます。
第1期の納期限は、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内です。6月16日から20日以内の7月5日となります。
(則第28条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。
②【R5年出題】(雇用)
令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
③【R5年出題】(雇用)
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの期間で道路工事を行う事業について、事業主が納付すべき概算保険料の額が120万円であったとき、延納の申請により第1期に納付すべき概算保険料の額は24万円とされる。

【解答】
①【R5年出題】(雇用) ×
令和4年10月31日で事業を廃止した場合、翌日の11月1日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書の提出期限は11月1日から起算して50日以内ですので、12月20日となります。
②【R5年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、概算保険料の額を問わず延納できますので、納付すべき概算保険料の額が10万円であっても、延納の申請を行うことができます。
③【R5年出題】(雇用) ×
令和4年5月1日から令和6年2月28日までの有期事業は、6期に分けて延納することができます。
第1期 5月1日~7月31日
第2期 8月1日~11月30日
第3期 12月1日~翌年3月31日
第4期 4月1日~7月31日
第5期 8月1日~11月30日
第6期 12月1日~翌年2月28日
120万円の6分の1ずつ納付しますので、第1期に納付すべき概算保険料の額は20万円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 賃金
労働保険徴収法 賃金
R5-361
R5.8.23 徴収法上の賃金となるもの・ならないもの
徴収法の「賃金」の定義を条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
徴収法上の賃金には、通貨だけでなく、一定の範囲の現物給付も入ります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(労災)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
②【H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
③【H26年出題】(労災)
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。
④【H29年出題】(労災)
労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
⑤【H29年出題】(労災)
住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
【解答】
①【H29年出題】 〇(労災)
前払退職金は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されます。
※なお、退職を事由として支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等で退職前に一時金として支払われるものは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しません。
(平成15.10.1基徴発1001001号)
②【H26年出題】 〇(労災)
祝金、見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等で事業主に支給義務があったとしても、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含まれません。
(昭和25.2.16基発127号)
③【H26年出題】 〇(労災)
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金となり、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めます。
(昭和51.3.31労徴発12号)
④【H29年出題】 〇(労災)
会社が全額負担する生命保険の掛金は、賃金になりません。
(昭30.3.31基災1239号)
⑤【H29年出題】 〇(労災)
則第3条で「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」と規定されていますので、住居の利益は賃金になります。
ただし、問題文のように、住居施設等を無償で供与される場合で、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金となりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 有期事業の一括
徴収法 有期事業の一括
R5-341
R5.8.3 有期事業の一括のポイント!
今日は、「有期事業の一括」のポイントをみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第7条、則第6条 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 1 事業主が同一人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 3 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 ・ 概算保険料に相当する額が160万円未満 かつ ・ 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満 ・ 建設の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満 4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。 ・ それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 ・ それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること。 ・ それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 |
2以上の有期事業が要件に該当する場合は、徴収法上、その全部が一の事業とみなされます。
労働保険料の申告・納付については、継続事業と同じように、年度更新の手続を行います。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
②【H28年出題】
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
③【H28年出題】
労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
④【H28年出題】
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
⑤【H28年出題】
有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」であり、又は「立木の伐採の事業」であることとされています。
②【H28年出題】 ×
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件は、それぞれの事業の規模が、
「概算保険料の額が160万円未満」であることです。
かつ
・立木の伐採の事業は、素材の見込生産量が1000立方メートル未満
・建設の事業は請負金額が1億8000万円未満
であることが要件です。
「労働者数」は一括の要件に入っていません。
③【H28年出題】 ×
要件を満たす事業は、自動的に有期事業の一括が行われます。届出によって行われるのではありません。
④【H28年出題】 ×
・ 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至っても、有期事業の一括の対象にはなりません。
・ また、当初は一括の対象になっていた事業が、その後、事業の規模が増加し要件の規模以上になったとしても、一括の対象からは除外されません。
⑤【H28年出題】 〇
有期事業の一括が行われると、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われます。
労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 印紙保険料
徴収法 印紙保険料
R5-340
R5.8.2 徴収法 印紙保険料のポイント!
今日は印紙保険料の出題ポイントをみていきましょう。
過去問からどうぞ!
①【H28年出題】
請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。
②【H28年出題】
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。
③【H28年出題】
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
④【H28年出題】
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
⑤【H28年出題】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
建設の事業が数次の請負で行われる場合は、請負事業の一括により元請負人のみが事業主とされます。
一括の対象になるのは、「労災保険に係る保険関係」です。
「雇用保険に係る保険関係」は、元請負人に一括されませんので、それぞれの事業ごとに適用されます。
そのため、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、元請負人ではなく、その日雇労働被保険者を使用する「下請負人」が納付しなければなりません。
(法第23条)
②【H28年出題】 ×
日雇労働被保険者についても「一般保険料」の対象となります。
日雇労働被保険者を使用する事業主は、一般保険料+印紙保険料を負担することになります。
(法第31条)
③【H28年出題】 〇
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主の義務
→毎月の雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに報告しなければなりません。
→日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月も、報告義務があります。
(則第54条)
④【H28年出題】 ×
認定決定された印紙保険料の追徴金の割合は、納付すべき印紙保険料額の「100分の25」です。
確定保険料の額が認定決定された場合の追徴金よりも高いことに注意してください。
(法第25条)
⑤【H28年出題】 ×
認定決定に係る印紙保険料と追徴金は、印紙ではなく現金で納付します。
所轄都道府県労働局収入官吏だけでなく、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することもできます。
(則第38条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 不服申立て
労働保険徴収法 不服申立て
R5-313
R5.7.6 徴収法 行政不服審査法による審査請求
労働保険徴収法の徴収金に関する処分に不服がある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に審査請求を行います。
では、さっそく過去問をどうぞ!
★平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服がある事業主が行うことができる措置についての問題です。
①【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
②【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
③【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
④【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
⑤【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「厚生労働大臣」に対し、「審査請求」行うことができる、です。
(行政不服審査法第4条)
②【H28年出題】 ×
①と同じく、「厚生労働大臣」に対し、「審査請求」行うことができる、です。
(行政不服審査法第4条)
③【H28年出題】 ×
①と同じく、厚生労働大臣に対し、「審査請求」行うことができる、です。
(行政不服審査法第4条)
④【H28年出題】 〇
行政事件訴訟法第8条で、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」と規定されています。
問題文の認定決定については、厚生労働大臣の裁決を経なくても、直ちにその取消しの訴えを提起することができます。
⑤【H28年出題】 ×
行政不服審査法第12条で、「審査請求は、代理人によってすることができる。」と定められています。事業主は当該認定決定について、代理人によって審査請求を行うことができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 印紙保険料
労働保険徴収法 印紙保険料
R5-296
R5.6.19 印紙保険料の認定決定と追徴金
日雇労働被保険者を使用する事業主は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することによって、印紙保険料を納付します。
事業主が印紙保険料の納付を怠ったときについて条文を読んでみましょう。
第25条第1項、2項 (印紙保険料の決定及び追徴金) ① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の 100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行います。納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用保険)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H28年出題】(雇用保険)
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
③【H28年出題】(雇用)
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
①【H25年出題】(雇用保険) 〇
印紙保険料の認定決定の通知は、納入告知書によって行われます。
(則第38条第5項)
②【H28年出題】(雇用保険) ×
徴収される追徴金は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の「100分の25」です。
③【H28年出題】(雇用) ×
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、「日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)」又は、「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付しなければなりません。
雇用保険印紙ではなく、現金で納付するのがポイントです。
(則第38条第3項第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 有期事業
労働保険徴収法 有期事業
R5-280
R5.6.3 有期事業の成立と消滅
労働保険徴収法には、「継続事業」と「有期事業」という分け方があります。
徴収法の有期事業は、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」で、労災保険のみの取扱いです。雇用保険には「有期事業」の扱いはありません。
また、有期事業以外は、「継続事業」となります。
では、「有期事業」の成立と消滅について条文を読んでみましょう。
第3条 (保険関係の成立) 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
第4条の2 (保険関係の成立の届出等) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
第5条 (保険関係の消滅) 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
③【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
④【H27年出題】(労災)
複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
保険関係成立届は、成立の日の翌日から起算して10日以内に提出します。「翌日起算」がポイントです。
保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長ですが、「一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業を除く。)」と「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業」は、「所轄労働基準監督署長」に提出します。
(則第1条、4条)
②【H27年出題】 〇
有期事業の概算保険料の申告・納付の期限は、「成立した日の翌日から起算して20日以内」です。「翌日起算」と「20日以内」がポイントです。
(法第15条の2)
③【H27年出題】 〇
有期事業の確定保険料の申告・納付の期限は、「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。ここは、「当日起算」となります。保険関係が消滅するのは、事業が廃止又は終了した日の翌日です。
(法第19条第2項、3項)
④【H27年出題】 〇
有期事業の賃金総額は、当該保険関係に係る「全期間」で算定します。保険年度単位ではありません。
(法第15条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 保険関係の消滅
徴収法 保険関係の消滅
R5-269
R5.5.23 事業が廃止又は終了したときは保険関係は翌日に消滅
今日は、保険関係の消滅についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第5条 (保険関係の消滅) 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
「廃止」は継続事業、「終了」は有期事業です。
廃止・終了の日の翌日に、当然に保険関係は消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
②【H27年出題】(労災)
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
③【H23年出題】(労災)
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
事業を廃止したときは、保険関係はその翌日に自動的に消滅します。
保険関係廃止届は存在しません。
なお、継続事業の場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出して労働保険料の精算を行わなければなりません。ちなみに、50日以内は「当日起算」です。
(法第19条)
②【H27年出題】 ×
暫定任意適用事業も、事業を廃止した場合には、保険関係はその翌日に自動的に消滅します。保険関係の消滅の申請は不要です。
ちなみに、労災保険も雇用保険も暫定任意適用事業の場合は、加入は事業主の任意ですので、脱退も任意です。
暫定任意適用事業が脱退する場合は、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限が委任されています。)が必要で、保険関係は、認可があった日の翌日に消滅します。
③【H23年出題】 ×
暫定任意適用事業がその事業を廃止した場合は、自動的に保険関係が消滅しますので、保険関係消滅申請書の提出は不要です。
また、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一でも、確定保険料申告書は提出しなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 受給権の保護
労災保険法 受給権の保護
R5-267
R5.5.21 労災保険給付の受給権の保護
労災保険の保険給付を受ける権利は保護されています。
条文を読んでみましょう。
第12条の5 ① 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 ② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
②【H24年出題】
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
③【R1年出題】
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労働者が退職したとしても、労災保険給付を受ける権利は変わりません。
②【H24年出題】 〇
保険給付を受ける権利は、譲渡、担保に供すること、差押えは禁止されています。
③【R1年出題】 ×
「保険給付」と「社会復帰促進等事業の一環として行われる特別支給金」との違いに注意しましょう。
譲渡、差押えの規定は特別支給金には準用されませんので、特別支給金については譲渡、差押えは禁止されていません。
(特別金支給規則第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 労働保険事務組合
徴収法 労働保険事務組合
R5-252
R5.5.6 労働保険事務組合 報奨金の支給要件
事業主から委託を受け、労働保険料を正しく納付することが、労働保険事務組合の重要な役割です。
労働保険料の納付状況が著しく良好な労働保険事務組合には、報奨金が支給されます。
今日は、報奨金の支給要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令)第1条第1項 労働保険事務組合が委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して労働保険料に係る報奨金を交付する。 1. 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。 2. 前年度の労働保険料等について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないこと。 3. 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(雇用)
労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。
②【H30年出題】(雇用)
納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。
③【H30年出題】(雇用)
労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
④【H30年出題】(雇用)
労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。

【解答】
①【H30年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合が報奨金の交付を受ける要件として、前年度の労働保険料について国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがあります。
前年度の労働保険料については、当該労働保険料に係る「追徴金及び延滞金」が含まれます。
②【H30年出題】(雇用) ×
確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合は、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていることが条件です。
納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、は誤りです。
③【H30年出題】(雇用) ×
労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、「所轄都道府県労働局長」に提出しなければなりません。
なお、申請書は10月15日までに提出しなければなりません。
(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条)
④【H30年出題】(雇用) ×
労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、次のいずれか低い額以内とされています。
・1,000万円
・常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額
労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下ではなく、「1千万円以下の額」とされています。
(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 口座振替
労働保険徴収法 口座振替
R5-240
R5.4.24 労働保険料の口座振替について
事業主が、労働保険料を口座振替で納付することを希望した場合のポイントを見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第21条の2第1項 (口座振替による納付等) 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
則第38条の2 口座振替による納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない。 則第38条の4 口座振替による納付の対象は、納付書によって行われる概算保険料及び延納する場合における概算保険料並びに確定保険料の不足額とする。 |
では、過去問をどうぞ!
なお、問題文の「労働保険料」から印紙保険料は除きます。
①【H30年出題】(労災)
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
②【H30年出題】(労災)
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。
③【H30年出題】(労災)
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
④【H30年出題】(労災)
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
⑤【H30年出題】(労災)
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

【解答】
①【H30年出題】(労災) ×
延納される概算保険料も口座振替による納付の対象です。
②【H30年出題】(労災) ×
口座振替による労働保険料の納付が承認されたからといって、労働基準監督署を経由できなくなることはありません。
一定の場合は、労働基準監督署を経由することもできます。
③【H30年出題】(労災) ×
増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となりません。
④【H30年出題】(労災) ×
その納付が確実と認められ、「かつ」、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って、事業主からの申出を承認することができます。承認することができる、ですので、法律上、必ず行われるものではありません。
⑤【H30年出題】(労災) 〇
追徴金の納付については、口座振替による納付の対象となりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 継続事業の一括
労働保険徴収法 継続事業の一括
R5-226
R5.4.10 継続事業の一括の効果
継続事業の一括について条文を読んでみましょう。
法第9条 (継続事業の一括) 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 |
ポイント!
・継続事業(=有期事業以外の事業)に限られます。
・継続事業の一括には厚生労働大臣の認可が必要です。なお、認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。
・通常、保険関係は、それぞれの事業ごとに成立しています。厚生労働大臣の認可を受けることによって、それぞれの保険関係を一つにまとめて事務処理を行うことになります。
・保険関係は、指定事業に一括され、指定事業以外の事業の保険関係は消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(「指定事業」という。)以外の事業にかかる保険関係は、消滅する。
②【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、指定事業に保険関係が一括されますので、指定事業以外の事業にかかる保険関係は、消滅します。
この場合、「指定事業以外の事業」は保険関係の消滅について、労働保険料の確定精算を行うことになります。
「指定事業」は、増加概算保険料の納付の手続が必要になることがあります。
②【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括が行われても、労災保険や雇用保険の給付に関する事務や、雇用保険の被保険者に関する事務は一括されません。
被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、被一括事業のぞれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 確定保険料
労働保険徴収法 確定保険料
R5-212
R5.3.27 納付した概算保険料が確定保険料より多い場合
継続事業と一括有期事業は、保険年度単位で保険料を申告納付します。
保険年度の初めに概算保険料を申告・納付し、年度終了後に確定保険料で精算する仕組みです。
今日は、納付した概算保険料が確定保険料より多かった場合の手続です。
条文を読んでみましょう。
法第19条第6項 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
則第36条第1項 (労働保険料の還付) 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。
則第37条 (労働保険料の充当) 1 還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額又は法第 20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金をいう。)等に充当するものとする。 2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、1の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 |
ポイント!
★納付した概算保険料の額が、確定保険料の額をこえる場合
→政府は、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料等に「充当」、又は「還付」します。
・還付について
→ 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、超過額の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付します。
・充当について
→ 還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料等に充当します。
→ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当したときは、その旨を事業主に通知しなければなりません。
※充当が行われるのは、還付請求がない場合です。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(労災)
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【R4年出題】(労災)
概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。
③【H24年出題】(雇用)
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
④【H29年出題】(雇用)
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
労働保険料還付請求書は、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出します。
②【R4年出題】 〇
既に納付した概算保険料の額が、認定決定された確定保険料の額を超えるときは、事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができます。
③【H24年出題】 〇
所轄都道府県労働局歳入徴収官が、超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当するのは、還付請求が行われないときです。
④【H29年出題】 ×
所轄都道府県労働局歳入徴収官が超過額を充当した場合、「当該事業主による充当についての承認」は不要です。しかし、「当該事業主への充当後の通知」は必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 概算保険料
労働保険徴収法 概算保険料
R5-202
R5.3.17 概算保険料の計算式
継続事業と一括有期事業は、保険年度単位で労働保険料を申告・納付します。
概算保険料は、保険年度の6月1日から40日以内に、申告・納付します。
今日は、概算保険料の計算式を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条、則第24条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。 ・その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の見込額(当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合にあっては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 ※特別加入者がいない場合の条文です。 |
ポイント!
・ 概算保険料(原則)=その保険年度の賃金総額の見込額×一般保険料率です。
・ 概算保険料は、その保険年度の賃金総額の「見込額」を使って計算するのが原則です。
ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」の場合は、「直前の保険年度の賃金総額」を使います。
・ 保険年度の中途に保険関係が成立した場合は、成立日から保険年度の末日までの賃金総額の見込額で計算します。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(労災)
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料にかかる保険料率を乗じて算定する。
②【R3年出題】(雇用)
(前提条件)
保険関係成立年月日:令和元年7月10日
事業の種類:食料品製造業
令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6
令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9
令和元年度の確定賃金総額:4,000万円
令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円
令和2年度の確定賃金総額:7,600万円
令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円
(問題)
令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111万円とされた。
7,400万円×1000分の15=111万円

【解答】
①【R1年出題】 〇
概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度の賃金総額に一般保険料料率を乗じて算定します。
また、賃金総額については、1,000円未満切捨てです。
②【R3年出題】 ×
令和2年度の賃金総額の見込額は7,400万円で、直前の保険年度(令和元年度)の確定賃金総額4,000万円の100分の50以上100分の200以下の範囲内です。
そのため、令和2年度の概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額ではなく、直前の保険年度の賃金総額で算定します。
算式は、4,000万円×1000分の15=60万円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 賃金総額の特例
労働保険徴収法 賃金総額の特例
R5-191
R5.3.6 賃金総額の特例が認められる請負による建設の事業
労働保険料には、
・一般保険料
・第1種特別加入保険料
・第2種特別加入保険料
・第3種特別加入保険料
・印紙保険料
・特例納付保険料
があります。
通常の労働者の労働保険料が「一般保険料」です。
一般保険料の額について、条文を読んでみましょう。
第11条 (一般保険料の額) 1 一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
|
「一般保険料」の額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。
ただし、「賃金総額」には特例があります。(第3項)
条文を読んでみましょう。
則第12条 (賃金総額の特例) 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2 立木の伐採の事業 3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。) 4 水産動植物の採捕又は養殖の事業 |
ポイント!
特例が認められるのは、
・労災保険料
・賃金総額を正確に算定することが困難なもの
ですので注意してください。
今日は、「請負による建設の事業」の特例をみていきます。
請負による建設の事業の労災保険料は、下請負人の労働者も含めて賃金総額を算定しなければなりません。
しかし、元請負人が、下請負人の労働者も含めた賃金総額を正確に算定することが困難な場合があるので、特例が認められています。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題(雇用)】
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
②【R1年出題(労災)】
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
③【R4年出題(労災)】
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

【解答】
①【H30年出題(雇用)】 ×
賃金総額の特例が認められるのは、賃金総額を正確に算定することが困難なものです。
請負による建設の事業だから認められるものではありません。
②【R1年出題(労災)】 ×
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業は、「請負金額×労務費率」が賃金総額となります。
請負金額とは、
①事業主が注文者からその事業に使用する工事用の資材の支給を受けたり、又は機械器具等の貸与を受けた場合
→ 支給された物の価格(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額に加算します。
②機械装置の組み立て又は据付けの事業の場合
→機械装置の価額(消費税等相当額を除く。)は請負代金に加算しません。
請負代金に機械装置の価額(消費税等相当額を除く。)が含まれている場合は、その価額を控除します。
問題文の場合は、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等を請負代金に加算します。
(則第13条)
③【R4年出題(労災)】 〇
消費税を含まない請負金額を用いて計算します。
(則第13条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 認定決定
労働保険徴収法 認定決定
R5-180
R5.2.23 概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定
今日は、概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定をみていきます。
それぞれの違いに注意しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条第3項(概算保険料の認定決定) 政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
法第19条第4項(確定保険料の認定決定) 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 |
 認定決定は、申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに行われます。
認定決定は、申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題(労災)】
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
②【H25年出題(雇用)】
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
③【H25年出題(雇用)】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
④【R3年出題(労災)】
事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
⑤【H26年出題(雇用)】
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
①【R3年出題(労災)】 〇
概算保険料の認定決定についての問題です。
認定決定を行うのは都道府県労働局歳入徴収官です。
②【H25年出題(雇用)】 ×
概算保険料の認定決定の通知は、納入告知書ではなく「納付書」によって行われます。
(則第38条第4項)
③【H25年出題(雇用)】 〇
確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第5項)
★「納付書」と「納入告知書」について
則第38条第4項で以下のように定められています。
「労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならない。」
★原則は「納付書」です。例外の「納入告知書」によって行われるものをおぼえましょう。
「納入告知書」で行われるものは次の4つです。
①有期事業のメリット制の差額徴収、②認定決定された確定保険料とその追徴金、③印紙保険料の認定決定とその追徴金、④特例納付保険料
上記以外は「納付書」で行われます。
④【R3年出題(労災)】 〇
認定決定された概算保険料の不足額の納期限は、通知を受けた日から15日以内です。翌日から起算するのがポイントです。
(法第15条第4項)
ちなみに、認定決定された確定保険料の不足額の納期限も同じです。
(法第19条第5項)
⑤【H26年出題(雇用)】 ×
概算保険料の認定決定の場合は、追徴金は徴収されません。
「確定保険料」の認定決定については、追徴金が徴収されます。
(法第21条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 延納
労働保険徴収法 延納
R5-168
R5.2.11 継続事業(一括有期事業)の概算保険料の延納
今日は、概算保険料の延納の制度をみていきましょう。
継続事業と一括有期事業の労働保険料は、保険年度ごとに算定します。概算保険料は、7月10日が納期限ですが、事業主が申請することにより、延納することができます。
今日のテーマは、継続事業と一括有期事業の延納です。単独の有期事業の延納は別のルールがあります。
条文を読んでみましょう。
第18条 (概算保険料の延納) 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が 第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。 |
 延納のポイント!
延納のポイント!
■事業主の申請が必要です。
■延納できる概算保険料
・年度の概算保険料、保険関係成立当初の概算保険料
・認定決定による概算保険料
・増加概算保険料
・追加徴収による概算保険料
※確定保険料は延納できません。
■概算保険料の額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円以上)
又は
労働保険事務組合に労働保険事務を委託している
■10月1日以降に成立した事業は、延納できません。
<延納回数をみてみましょう>
■保険関係が前年度以前に成立している場合
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
期間 | 4月1日~7月31日 | 8月1日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
納期限 | 7月10日 | 10月31日 ※11月14日 | 1月31日 ※2月14日 |
※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、第2期と第3期の納期限が14日延長されます。
■年度の中途に保険関係が成立した場合
・4月1日~5月31日に成立した場合→3回の延納が可能です。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
期間 | 成立日~7月31日 | 8月1日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
納期限 | 成立した日の 翌日から50日以内 | 10月31日 ※11月14日 | 1月31日 ※2月14日 |
・6月1日~9月30日に成立した場合→2回の延納が可能です。
| 第1期 | 第2期 |
期間 | 成立日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
納期限 | 成立した日の翌日から 50日以内 | 1月31日 ※2月14日 |
・10月1日以降に成立した場合 → 延納できません。一括して納付します。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問8-A(雇用)】
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。
②【R2問8-C(雇用)】
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

【解答】
①【R2問8-A(雇用)】 〇
7月1日に保険関係が成立した場合、2回に分けて納付することができます。最初の期分の納付期限は、7月1日の翌日から起算して50日以内ですので、8月20日となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|
|
| 成立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1期 納付期限 8月20日 | 第2期 納付期限 1月31日 ※2月14日 | |||||||
②【R2問8-C(雇用)】 〇
概算保険料の延納が認められている事業主は、申請することにより、増加概算保険料も延納することができます。
増加概算保険料の延納は、見込額が増加した日以後、「4月1日から7月31日まで」、「8月1日から11月30日まで」、「12月1日から翌年3月31日」までの各期に分けて納付できます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | |||||||||
問題文では第1期に属する7月1日に増加が見込まれていますので、3等分にして延納することができます。
最初の期分の納付期限は、7月1日の翌日から起算して30日以内ですので7月31日となります。
8月1日から11月30日までの分は10月31日(11月14日)、12月1日から翌年3月31日までの分は1月31日(2月14日)までに納付します。
(則第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 特別加入者の保険料
労働保険徴収法 特別加入者の保険料
R5-160
R5.2.3 特別加入保険料の月割計算
特別加入者の保険料の額は、保険料算定基礎額に、特別加入保険料率を乗じて計算します。
例えば中小事業主等の特別加入者で給付基礎日額が10,000円の場合、保険料算定基礎額は、3,650,000円(10,000円×365)で、その額に第1種特別加入保険料率を乗じて計算します。
今日は、保険料算定基礎額の月割計算の方法をみていきましょう。
・保険年度の中途に新たに特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者
→ 保険料算定基礎額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
・有期事業について
→ 保険料算定基礎額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該特別加入に係る期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
②【H24年出題】(労災) ※改正による修正あり
個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。
なお、事業の種類等は次のとおりである。
・事業の種類 飲食店
・当該事業に係る労災保険率 1000分の3
・中小事業主等の特別加入に係る承認日 令和4年12月15日
・給付基礎日額 8千円
・特別加入保険料算定基礎額 292万円
(A)8千円×107日×1000分の3
(B)8千円×108日×1000分の3
(C)292万円×12分の1×3か月×1000分の3
(D)292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3
(E)292万円×12分の1×4か月×1000分の3

【解答】
①【R2年出題】(労災)×
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった場合の保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額÷12×当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数となります。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数は1月に切り上げます。
★「月割計算」するのがポイントです。例えば、令和5年2月3日に特別加入した場合は、特別加入とされた期間の月数は、2月と3月の「2か月」となります。
②【H24年出題】(労災) E
E 「292万円×12分の1×4か月×1000分の3」で算定します。
292万円は8千×365です。
月割計算の際、1月未満の端数は1月に切り上げるのがポイントですので、12月から3月までの4か月となります。
保険年度の中途に新しく特別加入者となった場合は、特別加入申請の承認日の属する月を1月に切り上げ、また、保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者は、特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を、1月に切り上げます。
例えば、以下のような場合は、6月と1月をそれぞれ1月に切り上げます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|
| 加入 |
|
|
|
|
|
| 脱退 |
|
|
※有期事業の場合
有期事業についての特別加期間のすべてにおいての端数処理となります。
例えば、有期事業全体で6か月と10日の場合は、10日の端数を1か月に切り上げ、 7か月となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 雇用保険印紙購入通帳
労働保険徴収法 雇用保険印紙購入通帳
R5-151
R5.1.25 雇用保険印紙購入通帳の交付と印紙の購入
日雇労働被保険者を使用した場合、事業主は、「その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。」とされています。(則第40条)
雇用保険印紙は、第1級、第2級、第3級の3種類で、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)で販売されています。(則第41条)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、「雇用保険印紙購入通帳の交付」を受けなければなりません。(則第42条第1項)
雇用保険印紙購入通帳によって、日本郵便株式会社の営業所から必要な枚数を購入することになります。
「雇用保険印紙購入通帳」には有効期間があります。条文を読んでみましょう。
則第42条 ② 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。 ③ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。 ④ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 ⑧ 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。 |
有効期間があるのは、「雇用保険印紙購入通帳」です。印紙そのものには有効期間はありませんので注意してください。
雇用保険印紙購入通帳の更新手続きは、「有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間」です。具体的には、3月1日から3月31日までの間です。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(雇用保険)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
②【18年出題】(雇用保険)
事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。
③【H20年出題】(雇用保険)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。
④【R2年出題】(雇用保険)
雇用保険印紙購入通帳の有効期間満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。

【解答】
①【H23年出題】(雇用保険) ×
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けるために提出するのは、雇用保険印紙の購入申込書ではなく、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」です。
(様式第9号、則第42条)
②【18年出題】(雇用保険) ×
雇用保険印紙は、①「あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける」→②「総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)にて雇用保険印紙を購入する」という流れで購入します。
印紙は、公共職業安定所ではなく、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)で販売されます。
(則第41条、42条、43条)
③【H20年出題】(雇用保険) ×
雇用保険印紙購入通帳は、「その交付の日の属する保険年度」に限り、その効力を有する、です。
(則第42条)
④【R2年出題】(雇用保険) 〇
雇用保険印紙購入通帳の更新手続きは、有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、行います。
(則第42条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 日雇労働被保険者
労働保険徴収法 日雇労働被保険者
R5-142
R5.1.16 日雇労働被保険者の労働保険料の負担
雇用保険の日雇労働被保険者が失業した場合は、日雇労働求職者給付金が支給されます。
日雇労働求職者給付金には、印紙保険料の納付要件があります。
事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど印紙保険料を納付しなければなりません。印紙保険料は、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印して行われます。
雇用保険印紙には、第1級(176円)、第2級(146円)、第3級(96円)があり、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担します。
労働保険料の被保険者負担分を確認しましょう。
労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」があります。
「労災保険」の保険料は、事業主が全額負担します。
「雇用保険」の保険料は、賃金総額×雇用保険率で計算します。そのうち、被保険者が負担するのは、賃金総額×「雇用保険率-二事業率」×2分の1で計算します。
さらに、日雇労働被保険者については、「印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)」を負担します。
(第31条第1項、第2項)
過去問をどうぞ!
①【R2問10-C(雇用)】
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。
②【R2問10-D(雇用)】
日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担するものとする。

【解答】
①【R2問10-C(雇用)】 ×
労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料率は、「労災保険率+雇用保険率」です。
「労災保険率」の部分は全額事業主が負担します。
雇用保険の被保険者の負担分は、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額となります。
被保険者負担分=(雇用保険率-二事業率)×2分の1です。
②【R2問10-D(雇用)】 〇
日雇労働被保険者は、①の問題文の被保険者負担分「(雇用保険率-二事業率)×2分の1」のほかに、印紙保険料の額の2分の1を負担します。
日雇労働被保険者は、一般被保険者と同じ雇用保険料額を負担し、さらに、印紙保険料の2分の1を負担します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 請負事業の一括
労働保険徴収法 請負事業の一括
R5-133
R5.1.7 請負事業の一括の出題ポイント
「請負事業の一括」の出題ポイントを確認しましょう。
例えば、ビルの工事現場では、元請A社の労働者、下請B社の労働者、孫請C社の労働者がいっしょに仕事をしています。労災保険は、A社、B社、C社それぞれで成立するのではなく、その工事現場で成立します。その際、労災保険の保険関係は、元請負人A社に一括されるのがポイントです。
条文を読んでみましょう。
第8条第1項 (請負事業の一括) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 |
 下請負事業が元請負事業に法律上当然に一括され、徴収法上の事業主は、元請負人のみとなります。
下請負事業が元請負事業に法律上当然に一括され、徴収法上の事業主は、元請負人のみとなります。
第8条第2項(下請負事業の分離) 元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して事業主として適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして適用する。 |
 下請負事業を元請負事業から分離させ、独立させることもできます。その場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。※認可の権限は都道府県労働局長に委任されています。
下請負事業を元請負事業から分離させ、独立させることもできます。その場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。※認可の権限は都道府県労働局長に委任されています。
★認可申請の手続き
・元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、申請書を所轄都道府県労働局長に提出する
・下請負事業の事業の規模が、「概算保険料が160万円以上」又は「請負金額が1億8千万円以上」であることが必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問8-A労災】
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
②【R2問8-B労災 】
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
③【R2問8-C労災】
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。
④【R2問8-D労災】
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。
⑤【R2問8-E労災】
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。

【解答】
①【R2問8-A労災】 ×
請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」です。「立木の伐採の事業」には適用されません。
②【R2問8-B労災 】 ×
請負事業の一括は、法律上当然に行われます。届出や申請など手続きは不要です。
③【R2問8-C労災】 〇
一の事業とみなして元請負人のみが事業主とされるのは、「労災保険に係る保険関係」のみです。「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については一括されませんので、雇用保険については、原則通り、元請、下請それぞれの事業ごとに適用されます。
④【R2問8-D労災】 ×
請負事業の一括が行われると、元請負人が、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、事業主として保険料の納付の義務を負います。
しかし、だからといって、労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となることはありません。
⑤【R2問8-E労災】 ×
元請負人が保険料を納付しないときに下請負人に対して保険料の請求ができる、という規定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-113
R4.12.18 R4択一式より 概算保険料の追加徴収
保険年度の中途から保険料率の引き上げを実施した場合、政府は、引き上げによって増加した労働保険料を追加徴収します。
条文を読んでみましょう。
第17条 (概算保険料の追加徴収) 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。
則第26条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 2 納期限 |
増加概算保険料は、一定の基準以上の増加があった場合に適用されますが、追加徴収は額の多少を問わず徴収されるのがポイントです。
令和4年の問題をどうぞ!
【問9-E】(雇用)
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

【解答】
【問9-E】(雇用) 〇
ポイントは以下の2点です。
・納入告知書ではなく、「納付書」で納付することになります。
・所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収する概算保険料の増加額を通知します。事業主は、申告書を提出する必要はありません。
(則第38条第4項、5項)
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
②【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
③【H22年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収のポイントは、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」行われることです。
②【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収される概算保険料は、納入告知書ではなく、「納付書」により行われます。
③【H22年出題】(労災) ×
納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-112
R4.12.17 R4択一式より 増加概算保険料の納期限
増加概算保険料の納付要件を確認しましょう。
①事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が増加した場合
要件 → 増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額に基づく概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上
(法第16条、則第25条)
②「労災保険に係る保険関係のみ」が成立している事業又は「雇用保険に係る保険関係のみ」が成立している事業が「労災保険及び雇用保険に係る保険関係」が成立している事業に該当するに至ったため一般保険料率が変更した場合
要件 → 変更後の一般保険料率に基づく概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上
(法附則第5条、則附則第4条)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】(雇用)
事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

【解答】
【問9-B】(雇用) 〇
労災保険のみが成立している事業の一般保険料率は労災保険率のみですが、労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至った場合は、一般保険料率は「労災保険率+雇用保険率」に上がります。
その際、変更後の一般保険料率に基づく概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上になった場合は、差額を納付しなければなりません。
納期限は、「一般保険料率が変更された日から30日以内」ですが、翌日起算ですので、「一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内」となります。
(法附則第5条)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
②【H23年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。

【解答】
①【H23年出題】(労災) 〇
継続事業も有期事業も、増加概算保険料の納期限は、当該賃金総額の「増加が見込まれた日」から30日以内です。「実際に支払った賃金総額が既に納付した賃金総額の見込額の2倍を超えるに至った日」ではなく、「増加が見込まれた日」からであることがポイントです。なお、起算日は、翌日起算です。
(法第16条)
②【H23年出題】(労災) 〇
納期限は、一般保険料率が変更された日から30日以内です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-093
R4.11.28 R4択一式より 徴収法上の賃金
「賃金」は「労働の対償」として、「事業主が労働者」に支払うものをいいます。
賃金は、徴収法では、労働保険料の計算に使われます。
では、賃金の定義を条文で確認しましょう。
第2条 2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
★賃金には、一定の現物給付も含まれます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問10-E(労災)】
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。
②【問10-D(労災)】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
①【問10-E(労災)】 〇
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、賃金と認められます。ただし、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は、賃金とは認められません。
(S24.6.14基災収3850号)
②【問10-D(労災)】 〇
健康保険法の傷病手当金は、賃金ではありません。
標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合で、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額について → 恩恵的給付と認められる場合には、賃金とは認められず、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含みません。
(S27.5.10基収2244号)
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題(労災)】
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
②【H24年出題(労災)】
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

【解答】
①【H26年出題(労災)】 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金などの個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約などで支払いが事業主に義務付けられていても、賃金としては取り扱われません。
(S25.2.16基発127号)
②【H24年出題(労災)】 〇
労働基準法の「休業手当」は賃金です。(S25.4.10基収950号)解雇予告手当は賃金ではありません。(S23.8.18基収2520号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-092
R4.11.27 R4択一式より 法人の取締役の労災保険料
一般保険料の額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
今日のテーマは、法人の取締役の賃金が賃金総額に含まれるか否かについてです。
では、条文を読んでみましょう。
第11条 (一般保険料の額) ① 一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 ② 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
第12条 (一般保険料に係る保険料率) 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、労災保険率 3 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、雇用保険率 |
一般保険料額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
一般保険料率は、以下の通りです。
① 労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業
→ 労災保険率+雇用保険率
② 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業
→ 労災保険率
③ 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
→ 雇用保険率
また、計算に使う「賃金総額」は、「すべての『労働者』に支払う賃金の総額」です。
では、令和4年の問題をどうぞ。
【問10-A(労災)】
法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

【解答】
【問10-A(労災)】 〇
法人の取締役でも、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合は、「労働者」として労災保険が適用されます。
そのため、労災保険料を計算する場合は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)は、賃金総額に含まれます。
(S61.3.14基発141号)
なお、雇用保険については、「株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。」とされています。(行政手引20351)
過去問もどうぞ!
【H24年出題(雇用)】
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。

【解答】
【H24年出題(雇用)】 〇
一元適用事業は、「賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)」のように、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係をまとめて、一般保険料を計算します。
二元適用事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定することになっていますので、「賃金総額×労災保険率+賃金総額×雇用保険率」で計算します。
ただし、一元適用事業でも、労災保険が適用される労働者の範囲と雇用保険が適用される労働者の範囲が異なることがあります。そのような場合は、それぞれの保険で賃金総額が変わりますので、二元適用事業と同じように、「労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして」一般保険料の額を算定することになります。
(法第39条、整備令第17条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-064
R4.10.30 R4択一式より 徴収法「名称・所在地等変更届」
今日のテーマは、「名称・所在地等変更届」です。
保険関係が成立した場合は、保険関係が成立した日から10日以内に「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
また、事業の名称や所在地等に変更があった場合は届け出が必要です。
条文を読んでみましょう。
第4条の2第2項 保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
則第5条 (変更事項の届出) 1 法第4条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 ① 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ② 事業の名称 ③ 事業の行われる場所 ④ 事業の種類 ⑤ 有期事業にあっては、事業の予定される期間 2 法第4条の2第2項の規定による届出は、1の各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 ① 労働保険番号 ② 変更を生じた事項とその変更内容 ③ 変更の理由 ④ 変更年月日 |
★ 名称・所在地等変更届は、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-C(雇用)】
事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定される期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。

【問10-C(雇用)】 〇
有期事業は、「事業の予定される期間」に変更があったときは、名称・所在地等変更届の提出が必要です。
過去問をどうぞ!
【H25年出題(労災)】
名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更を生じた日の当日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

【解答】
【H25年出題(労災)】 ×
名称、所在地等変更届の提出期限は、変更を生じた日の「当日」からではなく「翌日」から起算して10日以内です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-063
R4.10.29 R4択一式より 有期事業のメリット制の適用条件
労災保険率は、事業の種類ごとに定められています。しかし、事業の種類が同じでも、事業主の災害防止に対する努力によって、企業ごとの災害発生率には差が生じます。
メリット制とは、業務災害の発生が多ければ労災保険率(又は労災保険料)を引き上げる、逆に発生が少なければ労災保険率(又は労災保険料)を引き下げる制度です。
今日は、「有期事業」のメリット制の適用要件を確認します。
徴収法で、有期事業とは、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」です。
有期事業でメリット制の適用を受ける事業の規模は以下の通りです。
有期事業のメリット制の対象になる事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が40万円以上であること。 2 建設の事業にあっては請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。 |
★1か2のいずれかに該当することが条件です。
「いずれか」がポイントです。
1 確定保険料の額が40万円以上
又は
2 建設の事業 → 請負金額が1億1千万円以上
立木の伐採の事業 → 素材の生産量が1,000立方メートル以上
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-C(労災)】
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。

【解答】
【問9-C(労災)】 ×
メリット制の適用を受けるのは、「見込生産量」ではなく「生産量」が1000立方メートル以上のときです。見込ではなく確定した生産量です。
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業で、その事業の素材の生産量が1000立方メートル以上のときは、労災保険のメリット制の適用対象となります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題(労災)】
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
②【H22年出題(労災)】
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

【解答】
①【H28年出題(労災)】 ×
「有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度」の部分が誤りです。
継続事業と一括有期事業のメリット制は、問題文の通り、一定の範囲内で労災保険率を上げ下げする制度です。
「有期事業」の場合は、労災保険率を上下させるのではなく、「確定保険料の額」を一定の範囲で上げ下げする制度です。
②【H22年出題(労災)】 〇
有期事業のメリット制が適用されると、確定保険料の額は上げ下げされます。確定保険料の額が引き上げられた場合は、差額が徴収されます。
引き上げられた場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、引き上げられた確定保険料の額と既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収します。その場合、「納入告知書」によって、通知されるのがポイントです。
(則第35条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-050
R4.10.16 R4択一式より 確定保険料の認定決定と追徴金
「確定保険料申告書」を提出しなかったとき、申告書の記載に誤りがあるときは、政府が職権で確定保険料の額を決定(認定決定)し、事業主に通知することになっています。その際、追徴金が課されます。
では、条文を読んでみましょう。
第19条第4項、第5項 4 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 5 認定決定の通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の認定決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の認定決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
第21条 (追徴金) 1 政府は、事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。 2 認定決定された確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。 |
ポイント!
確定保険料の認定決定は、「事業主が確定保険料申告書を提出しないとき」、又は「その申告書の記載に誤りがあると認めるとき」に行われます。
なお、政府が認定決定した確定保険料の額について事業主に通知する場合は、「納入告知書」によって行います。
では、令和4年の問題をどうぞ
【問8-D(労災)】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。

【解答】
【問8-D(労災)】 〇
「天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合」には、追徴金は徴収されません。
「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知、営業の不振、資金難等は含まれない」(昭56.9.25労徴発68号)とされています。
問題文は、法令の不知によるものですので、追徴金が徴収されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題(労災)】
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
②【H26年出題(雇用)】
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。

【解答】
①【R1年出題(労災)】 ×
認定決定された確定保険料は、「通知を受けた日から15日以内」に納付しなければなりません。なお、起算日は翌日です。「通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」に納付しなければなりません。
②【H26年出題(雇用)】 ×
「天災その他やむを得ない理由」の場合は追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、営業の不振等」はそれに含まれません。そのため、「法令の不知、営業の不振等」の理由の場合は、追徴金が徴収されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-034
R4.10.1 R4択一式より『一括有期事業報告書の提出』
一括有期事業については、確定保険料申告書を提出する際に、「一括有期事業報告書」を提出しなければなりません。
一括有期事業報告書は、請負金額から賃金総額を算定するためのもので、前年4月から当年3月31日までに終了した事業の具体的実施内容を記載します。
今日のテーマは一括有期事業報告書です。
条文を読んでみましょう。
則第34条 (一括有期事業についての報告) 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1 日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、所定の事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |
★ 確定保険料申告書と同時に提出します。提出期限・提出先は確定保険料申告書と同じです。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題(労災)】
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
②【H23年出題(雇用)】
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①【H30年出題(労災)】 〇
労働保険料の申告、納付については一般の継続事業と同じように年度更新の手続きがとられます。
(昭40.7.31基発901号)
②【H23年出題(雇用)】 〇
一括有期事業報告書は、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するものです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-C(労災)】
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
【問8-C(労災)】 〇
なお、提出期限は、「次の保険年度の6月1 日から起算して40日以内」又は「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(徴収法)
令和4年基本問題(徴収法)
R5-024
R4.9.21 R4択一式より『雇用保険暫定任意適用事業』
労働者を1人でも雇用する事業は、当然に雇用保険の適用事業です。
しかし、一部の農林水産業は、当分の間、雇用保険の適用は任意となります。
今日は、令和4年の択一式から、雇用保険暫定任意適用事業を見ていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
<雇用保険法> 第5条 (適用事業) 雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 附則第2条 (暫定任意適用事業) 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。 1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。) 施行令第2条 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。 |
★雇用保険の暫定任意適用事業は、民間の個人経営の農林水産の事業で5人未満の労働者を雇用するものです。
なお、船員を雇用する事業は、原則として強制適用事業となります。
<徴収法> 附則第2条 (雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置) ① 雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 ② 任意加入の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない。 ③ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。 ④ 雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす。 |
① 雇用保険暫定任意適用事業の場合、雇用保険に係る保険関係が成立するのは、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日です。※厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。
② 労働者の2分の1以上の同意が必要なのは、労働者にも保険料の負担があるためです。なお、認可があれば、同意しなかった者も含めてその事業に雇用される者全員に雇用保険が適用されます。★「その事業に使用される労働者の2分の1」とは、労働者総数の2分の1以上ではなく、適用除外となる労働者を除いた労働者の2分の1以上の者をいう、とされています。 (行政手引20154)
③ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければなりません。
④ 例えば、5人未満の農業の法人が個人経営になったなどのように、強制適用事業から暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に任意加入の認可があったものとみなされます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問10-A(雇用)】
雇用保険法第6条に該当する者を含まない4人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。
②【問10-B(雇用)】
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。

【解答】
①【問10-A(雇用)】 〇
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければなりません。雇用される労働者4人の場合は、2人以上が加入を希望した場合となります。
なお、労災保険の暫定任意の場合は、「過半数」が希望したとき、となります。労働者が4人の場合、過半数は3人以上です。
②【問10-B(雇用)】 ×
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされます。法律上当然に認可を受けたとみなされますので、任意加入の認可の手続きを行う必要はありません。後半部分の「事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を・・・」の部分が誤りです。
(行政手引20157)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(徴収法)
令和4年択一式を解いてみる(徴収法)
R5-014
R4.9.11 R4「徴収択一」は長文問題が多かったです。今日は『賃金総額の特例』
令和4年の徴収法の択一は長文問題が多くみられました。
今日は、「賃金総額の特例」の問題を見てみましょう。
一般保険料の額は、「賃金総額」×一般保険料に係る保険料率で計算します。
「賃金総額」は、原則として、「事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額」ですが、「厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。」(法第11条第3項)という特例があります。
令和4年は、この「賃金総額の特例」が出題されました。
まず、「厚生労働省令で定める事業」を読んでみましょう。
則第12条(賃金総額の特例) 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2 立木の伐採の事業 3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。) 4 水産動植物の採捕又は養殖の事業 |
賃金総額の特例が認められる条件は1~4に当てはまる事業で、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」ですので、注意してください。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【R4年問10-B】労災
労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
②【R4年問10-C】労災
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

【解答】
①【R4年問10-B】労災 ×
『造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)』、『水産動植物の採捕又は養殖の事業』については、『その事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。』とされています。
★賃金総額=(平均賃金に相当する額×それぞれの労働者の使用期間の総日数)の合算額
なお、『立木の伐採の事業』については、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。』とされています。
★賃金総額
=素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額×生産するすべての素材の材積
(則第14条、第15条)
②【R4年問10-C】労災 〇
『請負による建設の事業』については、『その事業の種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする』とされています。
また、請負金額に、「消費税等相当額を含まない」のがポイントです。
では、過去問もどうぞ!
③【H26年出題】労災
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
④【H30年出題】雇用
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

【解答】
③【H26年出題】労災 〇
特例による賃金総額の算出が認められているのは、「請負による建設の事業」、「立木の伐採の事業」、「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」です。
④【H30年出題】雇用 ×
請負による建設の事業だから、常に、特例が認められるのではなく、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」に限られています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-362
R4.8.19 「追徴金」の注意点
今日は、「追徴金」の注意点を確認しましょう。
「追徴金」が徴収されるのは、
・「政府が確定保険料の額を認定決定したとき」と
・「政府が印紙保険料額を認定決定したとき」です。
次に、「滞納処分」と「延滞金」の条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) 1労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 3 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
第28条 (延滞金) 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ※令和4年の延滞金の割合は、年14.6%→年8.7%、年7.3%→年2.4%です。 |
 第27条の「督促と滞納処分」は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」が対象、第28条の「延滞金」は「労働保険料」のみが対象になっていることに注目してください。
第27条の「督促と滞納処分」は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」が対象、第28条の「延滞金」は「労働保険料」のみが対象になっていることに注目してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題(雇用保険)】
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
②【H22年出題(雇用保険)】
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
③【H26年出題(雇用保険)】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
①【R1年出題(雇用保険)】 〇
「追徴金」が入っている点がポイントです。
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」とは、「労働保険料」と「その他この法律の規定による徴収金」です。
「追徴金」は労働保険料ではありませんが、「その他この法律の規定による徴収金」として、督促、滞納処分の対象になります。
(昭55.6.5発労徴40号)
②【H22年出題(雇用保険)】 ×
追徴金を納付しないときは、「国税滞納処分の例によって処分」されることはありますが、延滞金が徴収されることはありません。
第28条の延滞金が徴収されるのは、「労働保険料の納付を督促したとき」に限られます。追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しなかったとしても延滞金は徴収されません。
③【H26年出題(雇用保険)】 ×
追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しない場合でも延滞金は徴収されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-352
R4.8.9 納付書と納入告知書
徴収法では、「納付書」と「納入告知書」の区別が問われます。
「納入告知書」によるものを覚えておきましょう。
・有期事業に係るメリット制の差額の徴収 ・認定決定に係る確定保険料と追徴金 ・認定決定に係る印紙保険料と追徴金 ・特例納付保険料 |
納入告知書に係るもの以外は、「納付書」によります。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H22年出題】(労災)
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
③【H27年出題】(雇用)
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
④【H25年出題】(雇用)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
「認定決定された概算保険料」の額の通知は、納入告知書ではなく、「納付書」で行われます。
なお、「認定決定された確定保険料」の額の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条)
②【H22年出題】(労災) 〇
有期事業のメリット制が適用され、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、引き上げられた確定保険料の額と既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収します。
問題文では触れられていませんが、この通知は、「納入告知書」によって行われます。
(法第20条、則第38条)
③【H27年出題】(雇用) 〇
特例納付保険料の額と納期限の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(法第26条、則第38条、59条)
④【H25年出題】(雇用) 〇
認定決定による印紙保険料と追徴金の通知は「納入告知書」によって行われます。
この場合は、事業主は、雇用保険印紙ではなく、現金で納付することになります。
(法第25条、則第38条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-321
R4.7.9 印紙保険料の追徴金
日雇労働被保険者を使用する事業主は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することにより、印紙保険料を納付します。
事業主が印紙保険料の貼付を怠った場合は、政府は、認定決定を行います。
では、条文を読んでみましょう。
第25条 (印紙保険料の決定及び追徴金) ① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
★ 追徴金は、納付すべき印紙保険料額の100分の25です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題(雇用)】
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H28年出題(雇用)】
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
③【H24年出題(雇用)】
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。
④【H28年出題(雇用)】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
①【H25年出題(雇用)】 〇
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」により行われます。
(則第38条第5項)
②【H28年出題(雇用)】 ×
100分の10ではなく、「100分の25」です。
印紙保険料以外の労働保険料の追徴金の「100分の10」よりも高いことがポイントです。
③【H24年出題(雇用)】 ×
「事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった」ときは、正当な理由に当たりません。
そのため、追徴金の対象になります。
なお、「雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった」場合は、罰則規定が適用され、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
(法第46条第1号)
④【H28年出題(雇用)】 ×
認定決定に係る印紙保険料と追徴金は、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付します。
雇用保険印紙ではなく、現金で納付します。
問題文の「日本銀行に納付することはできず」が誤りです。
(則第38条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-320
R4.7.8 雇用保険料率と被保険者負担分
雇用保険料は、賃金総額×雇用保険料率で計算します。
令和4年度は、年度途中で雇用保険料率が変わります。
例えば、「一般の事業」の場合、
令和4年4月1日から9月30日まで → 1000分の9.5
令和4年10月1日から令和5年3月31日まで → 1000分の13.5
となります。
内訳は、
前半の1000分の9.5については
→ 被保険者負担が1000分の3、事業主負担が1000分の6.5
後半の1000分の13.5については
→ 被保険者負担が1000分の5、事業主負担が1000分の8.5
となります。
過去問をどうぞ!
【R2年出題(雇用)】
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

【解答】
【R2年出題(雇用)】 ×
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業の場合、「労災保険」に係る保険料は全額事業主負担となります。
問題文のように「当該事業に係る一般保険料の額」と書くと、労災保険と雇用保険が成立している事業の場合は、労災保険料も含まれてしまうので注意してください。
被保険者が負担するのは、「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から「当該事業に係る雇用保険率に応ずる部分の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1となります。
例えば、令和4年度前半の「一般の事業」の雇用保険率は1000分の9.5で、そのうち1000分の3.5が二事業率です。二事業率の部分は、全額事業主負担です。
「1000分の9.5」から「二事業の1000分の3.5」を減じた額の2分の1が被保険者が負担する部分です。被保険者負担分は1000分の3となります。
(法第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-292
R4.6.10 下請負事業の分離
建設の事業が数次の請負で行われている場合は、下請負事業が元請負事業に一括され、徴収法上、元請負人のみが事業主として取り扱われます。
しかし、一定規模以上の下請負事業は、元請負人の請負に係る事業から分離し、保険関係を独立させることができます。
条文を読んでみましょう。
第8条 (請負事業の一括) ① 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
② ①に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して①の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして①の規定を適用する。
則第8条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請) 法第8条第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
則第9条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準) 法第8条第2項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号(有期事業の一括の要件)に該当する事業以外の事業でなければならない。 |
下請負事業の分離のポイント!
・請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負人を分離させる場合は、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限が委任されています)の認可が必要です。
・有期事業の一括の要件に該当しない規模のものが分離の対象です。
分離の要件=概算保険料が160万円以上、又は請負金額が1億8千万円以上であること
過去問をどうぞ!
①【H27年出題(労災)】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。
②【H27年出題(労災)】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。
③【H27年出題(労災)】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【H27年出題(労災)】 ×
「厚生労働省令で定める事業」とは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」のことです。
下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の事業の規模が、概算保険料が160万円以上、又は、請負金額が1億8千万円以上でなければなりません。
②【H27年出題(労災)】 ×
下請負事業の分離の認可は、いずれかが単独で行うことはできません。元請負人と下請負人が共同で、「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
③【H27年出題(労災)】 〇
「下請負人を事業主とする認可申請書」は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
しかし、例外で、「やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。」と定められています。
やむを得ない理由とは、「天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等」とされています。
(昭47.11.24労徴発41号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-291
R4.6.9 請負事業の一括
建設の事業が数次の請負で行われている場合は、下請負事業が元請負事業に一括され、徴収法上、元請負人のみが事業主として取り扱われます。
条文を読んでみましょう。
第8条 (請負事業の一括) 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 則第7条 法第8条第1項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする |
請負事業の一括のポイント!
一括の対象になるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」です。
法律上当然に一括されます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題(労災)】
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
②【R2年出題(労災)】
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
③【H26年出題(労災)】
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
④【R2年出題(労災)】
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。

【解答】
①【R2年出題(労災)】 ×
請負事業の一括が適用されるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」が数次の請負によって行われるものです。「立木の伐採」の事業には適用されません。
(則第7条)
②【R2年出題(労災)】 ×
請負事業の一括は、法律上当然に行われます。「届け出」や「認可」などの手続きは要りません。
(法第8条)
③【H26年出題(労災)】 〇
「雇用保険」に係る保険関係は一括されません。それぞれの「事業単位」で、労働保険徴収法が適用されます。
④【R2年出題(労災)】 ×
請負事業の一括が行われた場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含めて、事業主として保険料の納付の義務を負います。
しかし、労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となることはありません。
 次回は、下請負事業の分離の要件です。
次回は、下請負事業の分離の要件です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-270
R4.5.19 増加概算保険料
労働保険の保険料は、保険年度当初に概算で申告・納付し、保険年度が終了してから確定精算する仕組みになっています。(継続事業の場合)
しかし、年度の途中で、事業規模が拡大したなどの理由で、賃金総額の見込額が増加し、一定の要件に当てはまった場合は、「増加概算保険料」を申告・納付することになっています。
今回のテーマは「増加概算保険料」です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H23年出題(労災)】
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
②【H23年出題(労災)】
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
③【H22年出題(労災)】
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料を延納していないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。

【解答】
①【H23年出題(労災)】 〇
増加概算保険料の申告・納付の要件は、以下の2つです。
1 労働者数の増加等によって、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が増加した
→ 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である
2 労災保険に係る保険関係のみ成立している事業又は雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業が労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため一般保険料率が変更した
→ 変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であることとする。
問題文は2に該当しますので、増加概算保険料の申告・納付が必要です。
(法第16条、則第25条、法附則第5条、則附則第4条)
②【H23年出題(労災)】 〇
増加概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業も有期事業も同じです。賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内です。
(法第16条)
③【H22年出題(労災)】 ×
増加概算保険料も延納できますが、もともとの概算保険料を延納していることが条件です。問題文のように、増加前の概算保険料を延納していないときは、増加概算保険料の延納はできません。
(則第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-235
R4.4.14 徴収法で「賃金」と解されるもの、解されないもの
労災保険の保険料、雇用保険の保険料は、事業主が労働者に支払う「賃金」の総額を基礎に計算されます。
今回は、保険料の基になる「賃金」の定義を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第2条 (定義) ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
則第3条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 |
通貨以外のもので支払われるのもの(現物給与)も賃金に含まれます。
現物給与として賃金に算入されるものは、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものです。
通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めます。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
②【H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
③【H24年出題】(労災)
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。
④【H29年出題】(労災)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。

【解答】
①【H19年出題】(雇用) 〇
なお、通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めます。
②【H26年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主に支給が義務付けられていても賃金としては取り扱いません。
問題文のような就業規則で定められた慶弔見舞金であっても、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含まれません。
(昭25.2.16基発127号)
③【H24年出題】(労災) 〇
退職を事由として支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額には算入されません。
(平15.10.1基徴発1001001号)
④【H29年出題】(労災) 〇
「前払い退職金」について
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確で、労働者の通常の生計に充てられる経常的な収入としての意義があるため、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されます。
(平15.10.1基徴発1001001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-216
R4.3.26 督促及び滞納処分
納期限を過ぎても労働保険料が納付されない場合、督促状が送付されます。
また、滞納した保険料を納付しない場合は、滞納処分が行われます。
条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 |
滞納処分とは、滞納金を強制的に徴収するためのもので、滞納者の財産を差し押さえ、それを換価した代金を滞納金に充てる行政処分です。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】(雇用)
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。
②【R1年出題】(雇用)
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
③【H22年出題】(雇用)
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

【解答】
①【H22年出題】(雇用) 〇
概算保険料・確定保険料を、所定の納期限までに申告しなかった場合は、政府は認定決定を行います。認定決定の納期限までに納付しない場合は、督促が行われます。
②【R1年出題】(雇用) 〇
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、「追徴金」が含まれているのがポイントです。
③【H22年出題】(雇用) ×
「追徴金」は、国税滞納処分の例によって処分されることはありますが、延滞金の対象にはなりません。問題文は逆になっています。
第27条(督促及び滞納処分)は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」を納付しない場合が対象ですが、第28条(延滞金)は、「労働保険料の納付」を督促したときが対象です。
第28条(延滞金)は「労働保険料」だけが対象になっているのがポイントです。
「追徴金」は労働保険料ではありませんので、延滞金の対象にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-199
R4.3.9 概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定
労働保険料の申告書を納期限までに提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときは、認定決定が行われます。
「概算」で申告納付する概算保険料と「実績」で申告納付する確定保険料では、同じ認定決定でもルールに違いがあります。
条文を読んでみましょう。
第15条第3項(概算保険料) 政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
第19条第4項(確定保険料) 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 |
政府が職権で、事業主が納付しなければならない労働保険料の額を決定し、通知することを認定決定といいます。
「申告書を提出しないとき」、「申告書の記載に誤りがあるとき」に行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用保険) ×
概算保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われます。
②【H25年出題】(雇用保険) 〇
確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
★ 労働保険料の納付は、「納入告知書」に係るものを除き「納付書」によって行わなければならないとされていますので、原則は「納付書」によって行われます。
「納入告知書」によるものは限られていますので、納入告知書によるものの方を覚えておきましょう。
■■納入告知書によるもの■■
「確定保険料の認定決定と追徴金」、「有期事業のメリット制の差額徴収」、「印紙保険料の認定決定と追徴金」、「特例納付保険料」
(則第38条第5項)
また、確定保険料の認定決定が行われた場合は、「追徴金」が徴収されます。
条文を読んでみましょう。
第21条 (追徴金) ① 政府は、事業主が認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。 ② 納付すべき確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。 |
追徴金は懲罰的な金銭です。認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、追徴金が徴収されます。また、追徴金は「納入告知書」で納付します。
一方、概算保険料は概算的に前払いする保険料ですので、認定決定に係る概算保険料には、追徴金は賦課されません。
では、過去問をどうぞ!
③【H26年出題】(雇用保険)
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
③【H26年出題】(雇用保険) ×
概算保険料の認定決定には、追徴金は徴収されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-171
R4.2.9 継続事業・一括有期事業の確定保険料(その2精算)
前回の続きです。
年度終了後に、確定した賃金総額で保険料を算定し、概算で納付した保険料とのプラスマイナスを調整することになります。
今回は、その精算の手続きがテーマです。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R1年出題(労災)】
事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。

【解答】
①【R1年出題(労災)】×
既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で過不足がないとき=納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料申告書は、日本銀行は経由できません。
※納付すべき労働保険料がある場合の確定保険料申告書は、日本銀行を経由することができます。
 次は、納付した概算保険料よりも確定保険料のほうが少ない場合の手続きを条文で確認しましょう。
次は、納付した概算保険料よりも確定保険料のほうが少ない場合の手続きを条文で確認しましょう。
則第36条 (労働保険料の還付) 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。
則第37条 (労働保険料の充当) 第36条の還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金をいう。)等に充当するものとする。 |
ポイント!
★既に納付した概算保険料が確定保険料よりも多い場合の超過額について
「還付」か「充当」です。
還付 → 還付請求が必要
充当 → 還付請求がない場合は充当される
では、過去問をどうぞ!
②【R1年出題(労災)】
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
③【H24年出題(雇用)】
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
④【H29年出題(雇用)】
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

【解答】
②【R1年出題(労災)】 ×
提出先が誤りです。
事業主は、超過額の還付を請求できますが、労働保険料還付請求書は、「官署支出官」又は「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出しなければなりません。
(則第36条)
③【H24年出題(雇用)】 〇
超過額の還付請求が行われないときは、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」は、超過額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当します。
(則第37条)
④【H29年出題(雇用)】 ×
超過額を概算保険料等に充当した場合は、「その旨を事業主に通知しなければならない」とされています。(則第37条第2項)「事業主による充当についての承認」は要しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-170
R4.2.8 継続事業・一括有期事業の確定保険料(その1期限)
継続事業・一括有期事業の労働保険料は年度単位(4月1日から翌年3月31日まで)で計算します。
保険料は保険年度の最初に、概算で申告・納付し、保険年度が終了し賃金総額が確定した後でプラスマイナスを精算することになります。
毎年度6月1日から40日以内に、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と今年度の概算保険料の申告・納付を行います。この手続きを「年度更新」といいます。
今日は、年度終了後の確定保険料がテーマです。
では、条文で確認しましょう。
第19条 (確定保険料) ① 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。 ③ 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは確定保険料を、申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、納付しなければならない。 |
確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければなりません。なお、6月1日当日から起算します。納付している概算保険料が確定保険料の額に足りないときは不足額も納付します。
また、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合も、労働保険料の精算のため確定保険料の申告・納付が必要です。期限は、保険関係が消滅した日から50日以内です。こちらも保険関係が消滅した日、当日から起算します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題(雇用)】
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【R1年出題(労災)】
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
③【H23年出題(労災)】
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。
④【H30年出題(雇用)】
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①【H26年出題(雇用)】 〇
平成26年6月30日に事業が廃止された場合、その翌日(7月1日)に保険関係が消滅します。
年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。起算日は当日ですので、7月1日から起算して50日の8月19日が期限となります。
②【R1年出題(労災)】 〇
第1種特別加入保険料についても年度の中途で承認が取り消された場合は、保険料の精算が必要です。
保険年度の中途に承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料、第3種特別加入保険料については、それぞれ当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
(法第19条)
③【H23年出題(労災)】 〇
一括有期事業の労働保険料も継続事業と同じように年度更新を行います。保険年度の中途で保険関係が消滅した場合も同じです。
(法第19条)
④【H30年出題(雇用)】 〇
納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、確定保険料申告書の提出は必要です。
(則第38条)
次回、過不足の具体的な精算手続きに続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-160
R4.1.29 特別加入保険料率
労災保険法の特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つの種類があります。
特別加入者の保険料は、原則として、『「保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)」×特別加入保険料率』で計算します。
なお、保険年度の中途で加入・脱退した場合は月割計算、有期事業の場合は全期間で計算します。
今日は、保険料の算定に使う特別加入保険料率を確認します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題(労災)】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
②【R2年出題(労災)】
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
③【H26年出題(労災)】
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和4年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

【解答】
①【H26年出題(労災)】 ×
第1種特別加入保険料率は、「中小事業主等」の保険料率です。
考慮されるのは、「通勤災害に係る災害率」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。特別加入者は二次健康診断等給付の対象外だからです。
なお、「厚生労働大臣の定める率」は、零ですので、結果として、第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率と同じです。
(法第13条、則第21条の2)
★穴埋めで確認しましょう★
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 < A >年間の< B >に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
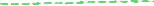
<解答>
A 3
B 二次健康診断等給付
②【R2年出題(労災)】 ×
第2種特別加入保険料率は、「一人親方等」の保険料率です。
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類によって違います。範囲は、最低1000分の3から最高1000分の52まであります。
(則第23条、別表第5)
③【H26年出題(労災)】 ×
第3種特別加入保険料率は、「海外派遣者」の保険料率です。
第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に「1000分の3」です。
(則第23条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-146
R4.1.15 メリット制の収支率の考え方 (過去問編)
前回からの続きです。
今回は、「収支率」のよく出るところを過去問で確認します。
さて、メリット収支率は、保険料に対する保険給付の割合です。
もう少し詳しく書くと、
(分母)「連続する3保険年度中の確定保険料×第1種調整率」
に対する
(分子)「保険給付等(業務災害に係る保険給付及び特別支給金)」
の割合です。
ポイント!
「分母」も「分子」も、「業務災害」に関するものだけ
収支率の計算に入るもの、入らないものを過去問で確認しましょう。
ではどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
②【H22年出題】(労災)
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。
③【H18年出題】(労災)
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。

【解答】
①【R2年出題】(労災) 〇
「特別支給金」も収支率の計算に入ります。
分子は、「業務災害として支給した保険給付+特別支給金」です。
(則18条の2)
②【H22年出題】(労災) 〇
「海外派遣者」は国内の使用者の指揮命令下にないので、海外派遣者の保険料、保険給付等の額ともに、収支率の計算に入りません。
★特別加入している「中小事業主」については、分母(保険料)、分子(保険給付)ともに収支率の計算に含まれます。
(則18条の2)
③【H18年出題】(労災) 〇
業務災害に対する保険給付のうち、以下のものは収支率の計算に入れません。
・ 遺族補償一時金(年金が失権した場合に支給される遺族補償一時金との差額)
・ 障害補償年金差額一時金
・ 特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額
・ 海外派遣者に対する保険給付の額
※なお、特別支給金も同じ扱いです。
★「分母」もみておきましょう。
・ 収支率の「分母」は保険料。「一般保険料の額」+「第1種特別加入保険料の額」です。
あくまでも「業務災害」に関する保険料ですので、「非業務災害率」の部分は除外されることに注意してください。
「非業務災害率」は、一律1,000分の0.6です。
例えば、労災保険率が1,000分の3なら、業務災害の部分が「1,000分の2.4」、非業務災害の部分が「1,000分の0.6」です。
収支率の計算に入れるのは1,000分の2.4の部分です。
・ 分子と調整するために、分母の保険料の額には「第1種調整率」を乗じます。第1種調整率は、一般の事業は100分の67です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-145
R4.1.14 メリット制の収支率の考え方(制度の仕組み編)
労災保険率は、事業の種類ごとに決められています。
事業の種類によって労働災害が発生するリスクが異なるからです。
しかし、同じ種類の事業でも、作業環境の改善を行うなど個々の事業主の企業努力で災害発生率は変わります。
メリット制は、企業努力で労働災害を抑えた場合はその企業の労災保険率を引き下げる、逆に労働災害が多い場合はその企業の労災保険率を引き上げて、労働災害の防止のための努力を促す制度です。
継続事業、一括有期事業、単独有期事業のそれぞれでメリット制が設けられていますが、今日は、「継続事業」のメリット制のお話です。
メリット制適用の条件として、次の3点があります。
① 事業の継続性
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)に労災保険に係る保険関係成立後3年以上経過していること
② 事業の規模
連続する3保険年度中の各保険年度に次の A か B のどちらかを満たしていること
A100 人以上の労働者を使用した事業
B20 人以上 100 人未満の労働者を使用した事業で、災害度係数が 0.4 以上
③収支率
収支率が100分の85を超え又は100分の75以下になることが必要です。
「収支率」が今日のテーマです。
★収支率とは?
「収支率」は、労災保険料に対する保険給付の割合です。政府から見ると労災保険料が収入、保険給付が支出です。労働災害が多いと、割合が高くなります。
★メリット制が適用される収支率の範囲は?
メリット収支率が低い(具体的には75パーセント以下)の場合は、労災保険率が低くなります。(最大で、40%割り引かれます)
逆にメリット収支率が高い(具体的には85%を超える)場合は、労災保険率が高くなります。(最大で40%割増されます。)
なお、75%を超え85%以下の時は、メリット制は適用されませんので、労災保険率の増減はありません。
ポイントは、メリット制に関係するのは「業務災害」だけという点です。
非業務災害(通勤災害や二次健康診断等給付)は、企業の努力でどうにかなるものではないからです。
次回に続きます。
次回は、メリット収支率の問題を解きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑩」過去問の活用(徴収法)
「最初の一歩⑩」過去問の活用(徴収法)
R4-110
R3.12.10 保険関係の成立と消滅(徴収法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
保険関係の成立の条文を読んでみましょう。
第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 |
なお、労災保険法第3条第1項は、「労働者を使用する事業を適用事業とする」、雇用保険法第5条第1項は、「労働者が雇用される事業を適用事業とする」としています。
労働者を使用(雇用)するようになった日に労働保険の保険関係が成立します。
例えば、令和3年12月10日に初めて労働者を雇い入れたが、その日にその労働者が業務上の負傷をしてしまった。そのような場合でも、令和3年12月10日に労災保険の保険関係が成立しているので、労災保険の保険給付の対象となります。
同時に労働保険料を納付する義務も発生します。
では、過去問をどうぞ。
①【H25年出題(労災)】
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

【解答】
①【H25年出題(労災)】 ×
「保険関係成立届を提出することによって成立する」の部分が誤りです。
保険関係は、仮に保険関係成立届を提出しなかったとしても、「事業が開始された日」に自動的に成立します。
次は、保険関係の消滅の条文を読んでみましょう。
第5条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
継続事業の場合は「廃止」、有期事業の場合は「終了」という用語を使いますが、いずれにしても、保険関係はその翌日に消滅します。
では、過去問を解いてみましょう。
②【H29年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
③【H26年出題(雇用)】
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
②【H29年出題(労災)】 ×
ポイントその1
「保険関係廃止届」なるものは存在しません。
ポイントその2
届出によって消滅するのではなく、廃止又は終了したときは、自動的にその翌日に保険関係関係が消滅します。
③【H26年出題(雇用)】 〇
事業を廃止した場合は、労働保険料を精算するために、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
確定保険料申告書の提出期限は、保険関係が消滅した日から50日以内です。消滅した日は午前零時から始まりますので、当日から起算するのがポイントです。
平成26年6月30日に事業を廃止した場合は、その翌日の7月1日に保険関係が消滅します。7月1日から起算して50日以内ですので、その年の8月19日が期限となります。
(法第19条)
最後に確定保険料申告書の納期限を条文で確認しましょう。
第19条 (確定保険料)
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から< A >日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から< B >日以内)に提出しなければならない。
有期事業については、その事業主は、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日から< B >日以内に提出しなければならない。

【解答】
A 40
B 50
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑨」条文の読み方(徴収法)
「最初の一歩⑨」条文の読み方(徴収法)
R4-109
R3.12.9 専門用語に慣れましょう(当日起算・翌日起算)(徴収法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第4条の2 (保険関係の成立の届出) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 |
「10日以内」の起算日が、「当日起算」か「翌日起算」かがポイントです。
初日の扱いについては、民法第140条で、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と規定されています。
「期間の初日は、算入しない」ので原則は翌日起算です。しかし、例外的に「その期間が午前零時から始まるとき」は、初日から起算することになります。
保険関係成立届は、「成立した日から10日以内」に提出しますが、起算日は、原則どおり翌日となります。
保険関係が成立した日とは、初めて労働者を雇い入れた日です。始業が9時だとするとその日は既に9時間過ぎていて丸一日ありません。そのため、初日は算入せず、翌日起算となります。
では、過去問を解いてみましょう。
①【R1年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
②【H27年出題(労災)】
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題(労災)】 〇
「その成立した日から10日以内」で正しいです。
起算日は翌日です。
②【H27年出題(労災)】 〇
「成立した日の翌日から起算して10日以内」で正しいです。
★ ①の問題の「その成立した日から10日以内」は「翌日起算」ですので、②の問題の「成立した日の翌日から起算して10日以内」と同じ意味です
では、次の条文を読んでみましょう。
第15条 (概算保険料の納付) 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。 (途中省略あり) |
その保険年度の6月1日から40日以内の起算日は、「初日の6月1日」です。その保険年度の6月1日は午前零時から始まり丸一日ありますので、当日起算です。
納期限は6月1日から40日で、7月10日です。
一方、保険年度の中途に保険関係が成立したものは、「保険関係が成立した日から50日以内」ですが、こちらは翌日起算です。保険関係が成立した日は、丸一日ないからです。
過去問を解いてみましょう
③【H30年出題(雇用)】
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

【解答】
③【H30年出題(雇用)】 〇
・継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料の納期限
→ 保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日まで
(午前零時から始まる。当日起算)
・保険年度の中途で保険関係が成立した事業
→保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
(午前零時に始まらないので、翌日起算)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ徴収法
R4-063
R3.10.24 有期事業の概算保険料の延納
令和3年の問題から徴収法を学びましょう。
今日は「有期事業の概算保険料の延納」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9B(労災保険)】
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

【解答】
①【R3年問9B(労災保険)】 〇
(有期事業(一括有期事業を除く。)の延納の条件)
■概算保険料の額が75万円以上
又は
労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している
■事業の全期間が6か月を超える
問題文は、事業の全期間が200日、概算保険料の額が80万円ですので、申請により分割納付をすることができます。
(則第28条)
こちらもどうぞ!
②【H22年出題(労災)】
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
③【H29年出題(労災)】
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
④【H27年出題(雇用)】
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

【解答】
②【H22年出題(労災)】 〇
ポイント!有期事業の延納は、全期間を通じ、「4月1日~7月31日」「8月1日~11月30日」「12月1日~翌年3月31日」の各期に分けられます。
★有期事業の延納の「最初の期」のとり方と納期限をおさえましょう。
保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が
・2月を超えるとき
→ 保険関係成立日からその日の属する期の末日までが「最初の期」
・2月以内のとき
→ 保険関係成立日からその日の属する期の次の期の末日までが「最初の期」
保険関係成立日が7月1日の場合、保険関係成立日の属する期は「4月1日~7月31日」の期です。
保険関係成立日からその期の末日(7月31日)までは2月以内ですので、最初の期は、保険関係成立日(7月1日)からその日の属する期の次の期の末日(11月30日)までとなります。
また最初の期の納期限は、成立日の翌日から20日以内ですので、7月21日となります。
(則28条)
③【H29年出題(労災)】 〇
| 4月~7月 | 8月~11月 | 12月~3月 | 4月~7月 |
| 6月15日成立 | 6月5日終了 | ||
第1期 (6月15日~11月30日) | 第2期 (12月1日~3月31日) | 第3期 (4月1日~6月5日) | |
ポイント!
★第1期は6月15日~11月30日まで
※6月15日から6月15日の属する期の末日(7月31日)まで2月以内なので、次の期とつながります。
★最初の期の納期限は、保険関係成立日の翌日から20日以内
(則第28条)
④【H27年出題(雇用)】 〇
★有期事業の延納の納期限について
・最初の期 → 保険関係成立日の翌日から20日以内
・第2期以降
4月1日~7月31日 → 3月31日
8月1日~11月30日 → 10月31日
12月1日~3月31日 → 翌年1月31日
ポイント!
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても納期限は延長されません
・4月1日~7月31日の期の納期限は「3月31日」です。
(則第28条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ徴収法
R4-055
R3.10.16 徴収「労働保険事務組合の届出」
令和3年の問題から徴収法を学びましょう。
今日は労働保険事務組合の届出です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E(雇用)】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【R3年問9E(雇用)】 ×
「14日以内」が誤りです。
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、「遅滞なく」、労働保険事務等処理委託届を提出しなければなりません。
なお、委託の解除の時も同じく、「遅滞なく」、労働保険事務等処理委託解除届を提出しなければなりません。
ポイント!
「労働保険事務等処理委託届」「労働保険事務等処理委託解除届」の提出は、「遅滞なく」
(則第64条)
こちらもどうぞ!
②【H20年出題(雇用)】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
③【R1出題(雇用)】
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
④【H23年出題(労災)】
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
②【H20年出題(雇用)】 〇
「労働保険事務等処理委託解除届」のチェックポイントは、「遅滞なく」と「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。
(則第64条)
③【R1出題(雇用)】 ×
提出先は、「厚生労働大臣」ではなく、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。
ポイント!
「変更の届出」のチェックポイントは、「14日以内」と「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。
★ 労働保険事務組合の認可を受けるときは、「申請書」に「①定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)、②労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類、③最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」を添付します。
↓
申請書又は添付書類の①若しくは②に記載された事項に変更を生じた場合に、「変更の届出」が必要です。③に変更があっても届出は要りません。
(則第65条)
④【H23年出題(労災)】 ×
業務の廃止の場合は、労働保険事務等処理委託解除届ではなく、「労働保険事務組合業務廃止届」を提出します。
「労働保険事務組合業務廃止届」は、「60日前までに」がチェックポイントです。
(則第66条)
もう一問どうぞ!
⑤【R1年出題(雇用)】
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
⑤【R1年出題(雇用)】 ×
「労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」がポイントで、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由」が誤りです。
原則として、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由しますが、第64条の規定により行う届書(労働保険事務等処理委託届)のうち労災二元適用事業等に係るものは、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して行います。
(則第78条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)徴収法 応用問題
R4-046
R3.10.7 徴収「特例納付保険料」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8D(雇用)】
労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。

【解答】
①【R3年問8D(雇用)】 〇
「特例納付保険料」は労働保険料の1つです。
「督促及び滞納処分」は労働保険料その他徴収金を納付しないとき、「延滞金」は、労働保険料を納付しない場合の規定で、労働保険料である特例納付保険料もその対象となります。
★ 「特例納付保険料」とは、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きを行った労働者について、本来納付すべきであった労働保険料を納付することができる制度です。
事業主は、厚生労働大臣の納付勧奨を受けて、納付の申出を行い、本来納付すべきであった雇用保険料に相当する額に10%をプラスした額を、特例納付保険料として納付することができます。
(法第26条)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
③【H27年出題】
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。

【解答】
②【H27年出題】 〇
特例納付保険料は、「基本額」+「加算額(基本額×100分の10)」で計算します。
(法第26条)
③【H27年出題】 〇
特例納付保険料の納付は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」を納期限とすること、「納入告知書」によることがポイントです。
(法第26条、則第38条、則第59条)
穴埋めで確認しましょう!
則第59条 (特例納付保険料に係る通知)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して< A >日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特例納付保険料の額
二 納期限

【解答】
A 30
では、こちらの条文も確認しましょう!
第10条 (労働保険料)
1 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2 1の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
① 一般保険料
② 第一種特別加入保険料
③ 第二種特別加入保険料
④ 第三種特別加入保険料
⑤ 印紙保険料
⑥ < B >

【解答】
B 特例納付保険料
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)徴収法よく出るところ
R4-036
R3.9.27 徴収法「暫定任意適用事業の保険関係の消滅」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8E(労災)】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

【解答】
①【R3年問8E(労災)】 ×
厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅するので、当該保険関係の消滅に同意しなかった者も含めて、全労働者の保険関係が消滅します。
(整備省令第3条)
★暫定任意適用事業は、保険関係の成立が「任意」ですので、保険関係を任意に消滅させることもできます。
★その場合、暫定任意適用事業の成立は「厚生労働大臣の認可があった日」、消滅は「厚生労働大臣の認可があった日の翌日」です。
では、こちらもどうぞ!
②【H29年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
③【H23年出題(労災)】
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。

【解答】
②【H29年出題(労災)】 ×
労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で違いがあります。
| 暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請要件 | |
労災保険 暫定任意適用事業 | ・労働者の過半数の同意を得る ・保険関係成立後1年以上経過している ・特例給付が行われる事業の場合は特別保険料を徴収する一定期間を経過している |
雇用保険 暫定任意適用事業 | ・労働者の4分の3以上の同意を得る |
③【H23年出題(労災)】 ×
雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる要件は、4分の3以上の同意です。また、1年経過の要件はありません。
では、最後にこちらをどうぞ!
④【H27年出題(労災)】
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

【解答】
④【H27年出題(労災)】 ×
適用事業でも暫定任意適用事業でも、事業の廃止又は終了の日の翌日に、法律上当然に保険関係が消滅します。
問題文の場合、事業の廃止によってその翌日に保険関係が消滅するので、保険関係の消滅の申請は要りません。
(法第5条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)徴収法の定番問題
R4-026
R3.9.17 労働保険事務組合が処理できない事務
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問9C(雇用)】
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

【解答】
①【R3年問9C(雇用)】 〇
労働保険事務組合は、中小事業主から委託を受けて、労働保険事務の処理を行います。
しかし、労働保険事務組合に委託できない事務処理もあります。
(労働保険事務組合に委託できない事務)
・印紙保険料に関する事項(法第33条で除外されている)
・保険給付に関する請求書等の事務手続
・雇用保険二事業に係る事務手続
(法第33条)
では、こちらもどうぞ!
②【R1問9D(雇用)】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
③【H18問10C(雇用)】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。
④【H19問8E(雇用)】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【解答】
②【R1問9D(雇用)】 ×
労働保険事務組合は、労災保険の保険給付に関する請求の事務は、処理できません。
③【H18問10C(雇用)】 ×
印紙保険料に関する事項は除かれています。
④【H19問8E(雇用)】 ×
雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務は、処理できます。
最後に、労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主の規模を確認しましょう。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、その使用する労働者数が常時< A >人(金融業若しくは保険業、< B >又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又は< C >を主たる事業とする事業主については100人)以下の事業主である。

【解答】
A 300
B 不動産業
C サービス業
(則第62条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労働保険徴収法【択一】
R4-015
R3.9.6 第53回徴収(択一)より~有期事業の一括
第53回試験を振り返ってみましょう。
★☆☆ 数字を中心に過去問の基本事項をしっかり押さえていれば、しっかり対応できたと思います。
【R3年問10(労災)】
(問10-A)
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
(問10-B)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
(問10-C)
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。
(問10-D)
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。
(問10-E)
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

【解答】
(問10-A) 〇
有期事業の一括には、規模の要件があります。
①概算保険料の額が160万円未満
かつ
②建設の事業 → 請負金額が1億8千万円未満
立木の伐採の事業 → 素材の見込生産量が1000立方メートル未満
■建設の事業でも、立木の伐採の事業でも、概算保険料が160万円未満であることが要件です。
(法第7条、則第6条)
(問10-B) 〇
それぞれの事業が、建設の事業に該当するか、又は立木の伐採の事業に該当することが要件です。また、一括されるのは「労災保険」のみであることにも注意しましょう。雇用保険は一括されません。
(法第7条、則第6条)
(問10-C) ×
一括の要件として、「それぞれの事業が事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること」があります。「労災保険率表」に掲げる事業の種類を同じくすることが要件なので、『事業の種類が異なって』いる場合は、労災保険率が同じでも一括されません。
(則第6条)
(問10-D) 〇
「事業主が同一人であること」とは、その事業が同じ企業に属していることをいいます。
(問10-E) 〇
建設の請負事業の場合は、徴収法上、「元請負人」のみが事業主となります。ですので、X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、元請のY会社の工事に一括されます。X会社が元請として施工する有期事業とは一括されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 認定決定でおさえたいところ②
R3-331
R3.7.20 印紙保険料の認定決定と追徴金
認定決定でおさえたいところ第2弾!
今日は印紙保険料の認定決定です。
概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定はこちらをどうぞ!
では、問題をどうぞ!
①<H24年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされており、この場合、当該事業主は、現金により、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は所轄都道府県労働局収入官吏に、その納付すべき印紙保険料を納付しなければならない。
②<H25年出題(雇用保険)>
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①<H24年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
・ 認定決定された印紙保険料は「現金」で納付する(印紙ではないので注意)
・ 「日本銀行」又は「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付する
(則第38条)
②<H25年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」で行われる。
(則第38条)
では、追徴金の問題をどうぞ!
③<H28年出題(雇用保険)>
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】
③<H28年出題(雇用保険)> ×
印紙保険料の追徴金の割合は「100分の25」。一般保険料の場合の追徴金の割合である100分の10より高いのがポイントです。
追徴金が徴収されるのは、印紙保険料の納付を怠ったことについて、「正当な理由」がないと認められるときです。
(法第25条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 認定決定でおさえたいところ①
R3-330
R3.7.19 概算保険料の認定決定・確定保険料の認定決定
認定決定が行われるのは、
・概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき
・確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるとき
です。
では、問題をどうぞ!
①<H25年出題(雇用保険)>
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②<H23年出題(労災)>
増加概算保険料の納付の要件に該当するに至っている場合であって、事業主が増加概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は増加概算保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知しなければならない。
③<R1年出題(労災)>
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

【解答】
①<H25年出題(雇用保険)> ×
「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われます。
ポイント!
・概算保険料の認定決定 → 納付書
・確定保険料の認定決定 → 納入告知書
②<H23年出題(労災)> ×
増加概算保険料については、事業主が増加概算保険料申告書を提出しなくても、又はその申告書の記載に誤りがあると認められるときでも、認定決定は行われません。
③<R1年出題(労災)> ×
「30日以内」が誤りです。
通知を受けた日から「15日以内」です。なお、この場合は翌日起算となるので、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。
通知を受けた日は、午前0時ではなく、受けた時から始まるので翌日起算です。
では、追徴金の問題をどうぞ!
④<H26年出題(雇用保険)>
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
③<H26年出題(雇用保険)> ×
「概算保険料」の認定決定の場合は、追徴金は課されません。
ポイント!
「確定保険料」の認定決定の場合は、追徴金が課されます。
追徴金の計算式は、納付すべき額(1,000円未満の端数切り捨て)×100分の10です。
追徴金の納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 賃金について
R3-329
R3.7.18 徴収法 通貨以外のもので支払われる賃金の範囲
徴収法では、保険料の算定のもとになるのは「賃金」です。
まず「賃金」の定義をどうぞ!
徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
今日は、通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)の扱いについてみていきましょう。
では、問題をどうぞ!
①<R1年出題(雇用保険)>
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
②<H19年出題(雇用保険)>
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。

【解答】
①<R1年出題(雇用保険)> 〇
②<H19年出題(雇用保険)> 〇
ポイント!
・ 賃金は「通貨」だけでなく、通貨以外のもので支払われるものも含まれる。
・ その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる
・ なお、「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める」ことになっています。
「範囲」と「評価」を区別して読んでください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 不服申立て
R3-328
R3.7.17 徴収法の処分に不服のあるときは?
徴収法の処分に不服のある場合は、行政不服審査法によって行います。
ではどうぞ!
H28年 労災問9より
①<ア>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
②<イ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
③<ウ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
④<エ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
⑤<オ>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

【解答】
ポイント!
徴収法には、不服申し立ての規定がありません。労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金に関する処分については、行政不服審査法に基づいて不服申立てを行うことになります。
①<ア> ×
異議申立てではなく「審査請求をすることができる」です。
また、審査請求先は、「厚生労働大臣」です。
★不服申立ての種類は、原則として「審査請求」とされています。
(行政不服審査法第2条、第4条)
②<イ> ×
<ア>と同じで、「厚生労働大臣に審査請求をすることができる」です。
③<ウ> ×
<ア><イ>と同じで「厚生労働大臣」に対し、再審査請求ではなく「審査請求」を行うことができる、です。
④<エ> 〇
行政事件訴訟法第8条によって、「直ちにその取消しの訴えを提起すること」ができます。
審査請求をしないで直ちに提起する、という選択もできることをおさえましょう。
(行政事件訴訟法第8条)
⑤<オ> ×
「審査請求は代理人によってすることができる」と規定されています。
(行政不服審査法第12条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 延滞金の割合の特例
R3-303
R3.6.22 徴収法の延滞金(延滞金の割合の特例)
今日のテーマは、「延滞金の割合の特例」です。
まずは条文から確認しましょう。
徴収法第28条第1項 (延滞金)
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその< A >までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から < B >月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が< C >円未満であるときは、延滞金を徴収しない。

【解答】
A 完納又は財産差押えの日の前日
B 2
C 1,000
(徴収法第28条)
延滞金の割合については特例があります
<延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合について>
各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、
・ 年14.6%の割合 → 延滞税特例基準割合+年7.3%
・ 年7.3%の割合 → 延滞税特例基準割合+年1%(加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)
とすることになっています。
(附則第12条)
さて、令和3年の「延滞税特例基準割合」は、1.5%です。
ですので、令和3年の延滞金の割合は、年8.8%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。
※ 1.5+7.3=8.8%、1.5+1=2.5%です。
★ ちなみに、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法では、年8.8%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年2.5%)となります。2月ではなく「3月」ですのでご注意ください。
練習問題をどうぞ
『徴収法 延滞金の割合の特例について』
令和3年の延滞金の割合は年< D >%(納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年< E >%)となる。

【解答】
D 8.8
E 2.5
こちらもどうぞ!
①<H29年出題(雇用)>
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。
②<H25年出題(雇用)>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

【解答】
①<H29年出題(雇用)> 〇
督促状に指定された期限までに徴収金を完納すれば、延滞金は徴収されません。
(法第28条)
②<H25年出題(雇用)> ×
督促状の「指定した期限の翌日」ではなく、本来の「納期限の翌日」から計算されます。よく出るひっかけ問題ですので注意してください。
(法第28条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 令和2年9月改正 その2
R3-302
R3.6.21 (改正)メリット収支率の算定
労災保険法の改正で「複数業務要因災害」が加わりましたが、「メリット収支率」の算定には算入する?しない?が今日のテーマです。
メリット収支率とは?
メリット収支率とは、簡単に言うと、「保険料の額」に対する「保険給付の額(特別支給金含む。)」の割合です。政府から見ると、収入(保険料)に対する支出(保険給付+特別支給金)の割合です。そして、どちらも「業務災害」に係る額であることがポイントです。
この割合が高い(=労働災害の発生率が高い)場合、具体的には100分の85を超えると、保険料率が上がります。
逆にこの割合が低い(=労働災害の発生率が低い)場合、具体的には100分の75以下の場合は、保険料率が下がります。
※メリット制が適用されるには、継続性(3年)、規模(100人以上など)の要件もあります。(継続事業(一括有期事業を含む)の場合)
では、「複数事業労働者」、「複数業務要因災害」とメリット制の関係は?
★複数業務要因災害 → メリット収支率の計算には算入しません
「複数業務要因災害」の場合は、どの事業場においても業務と疾病等との間に相当因果関係が認められないからです。
→ 通勤災害、二次健康診断等給付も今まで通り、算入しません。メリット収支率は「業務災害」で算定します。
★複数事業労働者の業務災害 → 「災害発生事業場における賃金額」をもとに算定した額に相当する額のみを算入します。
こちらもどうぞ!
①<H24年出題(労災)>
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制は、連続する3保険年度中の各保険年度においてその適用を受けることができる事業であって、当該連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。
②<H24年出題(労災)>
継続事業(一括有期事業を含む。)に係るいわゆるメリット制の適用を受けることができる事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において、少なくとも次のいずれかに該当する事業であることが必要である。
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすもの
③ 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
③<H25年出題(労災)>
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

【解答】
①<H24年出題(労災)> 〇
メリット制のポイント! その1 継続性の要件
連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日に、労災保険の保険関係の成立後3年以上経過していること
(法第12条)
②<H24年出題(労災)> 〇
メリット制のポイント! その2 規模の要件
連続する3保険年度中の各保険年度において、
① 100人以上の労働者を使用する事業
② 20人以上100未満の労働者を使用する事業であって所定の要件(災害度係数が0.4以上)を満たすもの
③ 規模が、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であるもの
(法第12条)
③<H25年出題(労災)> ×
メリット制のポイント! その3 収支率の要件
メリット制が適用されるのは、メリット収支率が85%を超え、又は75%以下であるとき
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法 令和2年9月改正
R3-301
R3.6.20 (改正)労働保険徴収法~労災保険率の決定の基準
労災保険法の改正に伴い、徴収法では労災保険率の決定の基準が改正されています。
まずは、条文を確認しましょう。
徴収法第12条 (一般保険料に係る保険料率)
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び< A >に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受ける全ての事業の過去< B >年間の業務災害、< C >及び通勤災害に係る災害率並びに< D >に要した費用の額、< A >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【解答】
A 社会復帰促進等事業
B 3
C 複数業務要因災害
D 二次健康診断等給付
ポイント!
労災保険率を決定する基準に、「複数業務要因災害」が加わりました。
こちらもどうぞ!
①<H24年出題(労災)>
労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1000分の100を超えている。
②<H26年出題(労災)>
個々の事業に対する労災保険率の適用は、事業主が同一人であって業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている場合には、常時使用される労働者の数が最も多い部門の業種に応ずる労災保険率を適用する。
③<H24年出題(労災)>
労災保険率を決定する際の事業の種類に関し、労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の派遣先での作業実態に基づき決定され、必ずしも「その他の各種事業」になるものではない。

【解答】
①<H24年出題(労災)> ×
最高は、「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業」の1000分の88です。1000分の100は超えていません。
ちなみに、最低は1000分の2.5です。
(則第16条、則別表第1)
②<H26年出題(労災)> ×
個々の事業に対する労災保険率の適用については、①事業の単位、②その事業が属する事業の種類、③その事業の種類に係る労災保険率の順に決定する、とされています。
事業の単位については、継続事業については、「同一場所にあるものは分割することなく一の事業とし、場所的に分離されているものは別個の事業」として取り扱われます。
問題文の場合、「業種が異なる二以上の部門が場所的に分かれ、それぞれ独立した運営が行われている」ので、それぞれが別個の事業として取り扱われます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
③<H24年出題(労災)> 〇
労働者派遣事業における事業の種類は、「派遣労働者の派遣先」での作業実態に基づき決定されます。
(平成12.2.24 労働省発徴第12号/基発第94号)
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
徴収法~保険関係の一括③
R3-261
R3.5.11 徴収法~継続事業の一括
引き続き、徴収法の「保険関係の一括」です。
今日は、「継続事業の一括」です。
継続事業の一括とは?
例えば、同一の企業に、本店、A支店、B営業所がある場合、保険料の申告・納付は本店、A支店、B営業所でそれぞれ行うのが原則です。
しかし、「継続事業の一括」の認可を受けることにより、保険料の申告・納付を一つにまとめることもできます。
こちらからどうぞ!
①<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書を指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
②<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可については、労災保険率表による事業の種類を同じくすることがその要件とされているが、雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の場合は、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要はない。

【解答】
①<H21年出題(雇用)> 〇
「継続事業の一括」は、法律上当然に一括されるのではなく、厚生労働大臣の認可(認可の権限は都道府県労働局長に委任されている)が必要です。
認可されると保険関係が一括され、保険料の申告・納付は、指定事業でまとめて行います。
「継続事業一括申請書」は指定事業として指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出することがポイントです。
(法第9条、則第10条)
②<H21年出題(雇用)> ×
継続事業の一括は、労災保険率表による事業の種類を同じくすることが要件です。雇用保険に係る保険関係が成立している二元適用事業でも同様に、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要があります。
(則第10条)
こちらもどうぞ!
③<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可があったときは、当該二以上の事業に使用されるすべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業の保険関係は消滅する。この場合、保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。
④<H21年出題(雇用)>
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労使保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。

【解答】
③<H21年出題(雇用)> ×
「保険関係消滅申請書を提出することにより、労働保険料の確定精算の手続はすべて終了する。」の部分が誤り。そもそも保険関係消滅申請書というものはありません。
継続事業の一括の認可があったときは、すべての労働者が指定事業に使用される労働者とみなされ、労働保険料の申告・納付は指定事業で一括して行われます。
そして、指定事業以外の事業の保険関係は消滅しますが、この場合は、「確定保険料申告書」を提出して保険関係の消滅に伴う保険料の確定精算を行うことになります。
(法第9条)
④<H21年出題(雇用)> ×
継続事業の一括の認可を受けても、労災保険び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務は一括されません。原則どおり、事業場単位となります。事務を行うのは、「指定事業の所在地」ではなく、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長です。
(法第9条)
社労士受験のあれこれ
徴収法~保険関係の一括②
R3-260
R3.5.10 徴収法~請負事業の一括
引き続き、徴収法の「保険関係の一括」です。
今日は、「請負事業の一括」です。
請負事業の一括のポイント
★建設の事業が数次の請負によって行われるとき
・ 下請負事業では、それぞれ独立した事業としての保険関係は成立しない
・ 数次の下請負事業は元請負事業に一括され、元請負人のみを適用事業主として保険関係が成立する
・ 一括は法律上当然に行われる
・ 労災保険に係る保険関係のみ適用される
★下請負事業を分離させることもできる
・ 下請負事業を元請負事業から分離して保険関係を成立させることもできる
・ 分離には、一定の規模の要件がある
・ 分離には政府の認可が必要
こちらからどうぞ!
①<H26年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合において、労災保険の保険関係に関し当該事業を一の事業とすることについて元請負人の認可申請があり、厚生労働大臣の認可があったときは、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
②<H26年出題(労災)>
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。
③<H26年出題(労災)>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】
①<H26年出題(労災)> ×
請負事業の一括は「法律上当然」に一括されるので、認可申請も厚生労働大臣の認可も不要です。
(法第8条)
②<H26年出題(労災)> ×
請負事業の一括の対象になるのは「建設の事業」です。立木の伐採の事業は請負事業の一括は行われません。
(法第8条、則第7条)
③<H26年出題(労災)> 〇
請負事業の一括で一括されるのは、「労災保険の保険関係」のみです。
「雇用保険の保険関係」は一括されませんので、それぞれの下請負人ごとに労働保険徴収法が適用されます。
(法第8条、則第7条)
次は、こちらをどうぞ!(下請負事業の分離)
④<H27年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。
⑤<H27年出題(労災)>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

【解答】
④<H27年出題(労災)> ×
下請負事業の分離の認可を受けるには、事業の規模が、「概算保険料の額が160万円以上、又は、請負金額が1億8千万円以上」であることが条件です。
有期事業の一括の対象にならない規模と覚えておきましょう。
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負事業を分離させるためには、規模の要件を満たすことと、「下請負事業の分離の認可」の手続きが必要です。
(法第8条、則第9条)
⑤<H27年出題(労災)> ×
「そのいずれかが単独で」の部分が誤りです。
認可申請書は、元請負人及び下請負人が共同で申請しなければなりません。
期限は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。
(法第8条、則第8条)
社労士受験のあれこれ
徴収法~保険関係の一括①
R3-259
R3.5.9 徴収法~有期事業の一括
今日は徴収法の「保険関係の一括」です。
保険関係の一括には、「有期事業の一括」、「請負事業の一括」、「継続事業の一括」の3つがあります。
今日は、「有期事業の一括」です。
有期事業の一括のポイント
対象:建設の事業、立木の伐採の事業
・ 規模の小さい(一定の要件あり)有期事業であること
・ 法律上当然に一括される
・ 労働保険は、継続事業と同様の方法で適用される
・ 労災保険に係る保険関係のみ適用される
こちらからどうぞ!
①<H28年出題(労災)>
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
②<H28年出題(労災)>
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

【解答】
①<H28年出題(労災)> ×
「土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業」が誤りです。
有期事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」又は「立木の伐採の事業」です。
(則第6条)
ポイント!
一括されるのは「労災保険」に係る保険関係のみです。「雇用保険」は一括されません。
②<H28年出題(労災)> ×
有期事業の一括の対象となる事業の要件
「建設の事業」 → 請負金額(消費税相当額を除く)が1億8千万円未満、かつ、概算保険料額が160万円未満
「立木の伐採の事業」 → 素材の見込生産量が1,000立方メートル未満、かつ、概算保険料額が160万円未満
概算保険料の額が160万円未満であることは共通しています。しかし、一括の要件に労働者数は関係ありません。
(則第6条)
次は、こちらをどうぞ!
③<H24年出題(労災)>
有期事業の一括は法律上一定の要件に該当する場合には当然に行われるものであり、事業主からの申請、都道府県労働局長による承認は不要である。

【解答】
③<H24年出題(労災)> 〇
有期事業の一括は、一定の要件に該当する場合には当然に行われます。承認や認可を受けるなどの手続きは要りません。
(法第7条)
最後にこちらを
④<H30年出題(労災)>
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
⑤<H23年出題(雇用)>
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
④<H30年出題(労災)> 〇
単独の有期事業でしたら、例えば工事現場の場合、工事が開始したときに「概算保険料」を申告・納付し、工事終了時に「確定保険料」で精算します。それを各工事ごとに行うことになります。
一方、一括有期事業の場合は、それぞれの有期事業ごとではなく、その全体が継続事業として取り扱われることになり、継続事業と同じように年度ごとに労働保険料の概算、確定手続きを行うことになります。
(法第7条)
⑤<H23年出題(雇用)> 〇
ポイント!
一括有期事業報告書は、「確定保険料申告書」に加えて提出します。
期限は、「次の保険年度の6月1日から起算して40日以内」又は「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。
(則第34条)
社労士受験のあれこれ
請負による建設業の賃金総額
R3-220
R3.3.31 賃金総額算定のルール(請負の建設業)
今日は徴収法です。
一般保険料は、「賃金総額」×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)で計算します。
「賃金総額」は、その事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額ですが、特例もあります。
今日は賃金総額の特例を確認します。
では、どうぞ!
①<H26年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。

【解答】 〇
特例による賃金総額の算出が認められているのは、
1 請負による建設の事業
2 立木の伐採の事業
3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
4 水産動植物の採捕又は養殖の事業
例えば、請負による建設の事業の場合、労災保険の保険関係は元請の事業主に一括され、元請の事業主が下請事業の労働者の分も一括して保険料を納付しなければなりません。しかし、その際、元請の事業主が、下請事業の労働者の賃金の総額を正確に把握することが困難な場合があります。そのため、賃金総額の特例が設けられています。
(徴収法第11条、施行規則第12条)
では、こちらをどうぞ!
②<H30年出題(雇)>
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

【解答】 ×
「常に」が誤りです。
賃金総額の特例が認められるのは、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」です。
では、こちらの問題もどうぞ!
③<H21年出題(災)>
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額(一定の場合には、所定の計算方法による)に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。
④<R1年出題(災)>
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。

【解答】
③<H21年出題(災)> 〇
請負による建設の事業で、賃金総額を正確に算定することが困難なものの賃金総額は、『請負金額×労務費率』で計算します。
(施行規則第12条、第13条)
④<R1年出題(災)> ×
請負金額イコール請負代金とは限りません。また最後の「含まれない」が誤りです。
(原則)
注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等 → 請負代金に加算する
(例外)
「機械装置の組立て又は据付けの事業」 → 機械装置の価額は請負代金から除外する
※消費税は請負金額から除きます。
(施行規則第13条)
社労士受験のあれこれ
労働保険徴収法第1条(趣旨)
R3-186
R3.2.25 第1条チェック~徴収法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は徴収法です。
条文をチェックしましょう!
<第1条 趣旨>
(R2年問8D(雇))
労働保険徴収法は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めている。

【解答】 〇
徴収法第1条(趣旨)からの出題です。
「労働保険の事業の効率的な運営」がキーワードです。
労災保険と雇用保険の事業を効率的に運営するために、保険関係の成立・消滅、労働保険料の納付の手続等のルールを定めた法律です。
また、事業主の代理人として労働保険の事務を処理する団体が、労働保険事務組合です。
では、こちらもどうぞ
<H12年出題>
国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。

【解答】 ×
国の行う事業は二元適用事業ではありません。
「国」の行う事業は労災保険が成立しないからです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
参考に、労災保険法第3条第2項を見てみると、「国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、労災保険法は、適用しない。」と規定されています。ちなみに官公署の事業とは、非現業の官公署のことです。
=国の行う事業は労災保険は全面的に適用除外
→なお、「都道府県、市町村」については、「現業の非常勤職員」には労災保険法が適用されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労働保険の事業の効率的な運営を趣旨とする徴収法では、「一元適用事業」(労災保険と雇用保険の保険料の申告や納付等を一本化して行う)が、原則です。
労災保険と雇用保険の適用の範囲等が違う事業は、「二元適用事業」として、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に行います。
試験対策としては、「二元適用事業」に該当する事業を暗記して、それ以外は「一元適用事業」と覚えればOKです。
「二元適用事業の種類」
・都道府県及び市町村が行う事業
・都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものが行う事業
・港湾運送の行為を行う事業
・農林・水産の事業
・建設の事業
(参照:徴収法第39条、施行規則第70条)
社労士受験のあれこれ
(徴収法)労働保険料の口座振替
R3-161
R3.1.31 労働保険料の口座振替を希望する場合
今日は徴収法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問9-A(雇)>
事業主は、概算保険料及び確定保険料の納付を口座振替によって行うことを希望する場合、労働保険徴収法施行規則に定める事項を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって、その申出を行わなければならない。

【解答】 〇
書面の提出先は、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」です。
(徴収法第21条の2、徴収法施行規則第38条の2)
では、こちらの問題をどうぞ
<H30年出題>
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。

【解答】 ×
「納付が確実と認められれば」必ずではなく、『その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り』、その申出を承認することができる、とされています。
(徴収法第21条の2)
では、最後にこちらもどうぞ!
<H24年出題その1>
労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
<H24年出題その2>
いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

【解答】
<H24年出題その1> 〇
<H24年出題その2> 〇
■口座振替ができるのは
納付書によって行われる
・概算保険料(延納する場合も口座振替ができる)
・確定保険料
■口座振替できないもの
増加概算保険料、認定決定された概算保険料、追徴金
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(徴収法)労働保険料の労働者負担
R3-155
R3.1.25 労働保険料、労働者の負担分は?
今日は徴収法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-C(雇)>
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

【解答】 ×
一般保険料の額は、賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)で計算します。
労災保険料は全額事業主負担ですが、問題文の表現だと、それが労働者負担になってしまうので、誤りとなります。
労災保険と雇用保険が成立している事業の被保険者が負担する労働保険料の額は、
『一般保険料の額のうち雇用保険率に係る部分の額』から『その額に二事業率を乗じて得た額』を減じた額の2分の1です。
例えば、令和2年度の雇用保険率は、一般の事業は「1,000分の9」です。
1000分の9の内訳は
・失業等給付と育児休業給付 → 1,000分の6
・雇用保険二事業 → 1,000分の3
となります。
そのうち、被保険者が負担する率は、「1,000分の9から1,000分の3」を減じた額の2分の1なので「1,000分の3」となります。
残りの労働保険料は事業主が負担します。
事業主の負担
・労災保険料 → 全額
・雇用保険料 → 「失業等給付と育児休業給付」×2分の1
雇用保険二事業(全て)
(徴収法第31条)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <H22年出題>
<H22年出題>
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業については、雇用保険の被保険者は、一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から、その額に二事業率を乗じて得た額を減じた額の2分の1を負担することとされている。
 <H22年出題>
<H22年出題>
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主及び労働者が2分の1ずつを負担することとされている。

【解答】
 <H22年出題> 〇
<H22年出題> 〇
令和2年度の問題と同じ趣旨です。
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
一般保険料の額のうち労災保険率に応ずる部分の額については、事業主が全額負担します。
(徴収法第31条)
雇用保険率の内訳
雇用保険率1000分の9のうち、「1,000分の3」が二事業分ですが、残りの「1000分の6」の内訳は、次の通りです。
1000分の4 → 育児休業給付
1000分の2 → 失業等給付
(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号))
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(徴収法)継続事業の概算保険料の延納
R3-097
R2.11.28 継続事業・年度途中で成立した場合の延納
令和2年の問題をどうぞ!
<問8‐A(雇)>
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。

【解答】 〇
年度途中で保険関係が成立した場合の延納についてはしっかり覚えましょう!
| 保険関係成立日 | 回数 | 最初の期 |
|---|---|---|
| 4月1日から5月31日 | 3回 | 保険関係成立日から7月31日まで |
| 6月1日から9月30日 | 2回 | 保険関係成立日から11月30日まで |
| 10月1日以降 | 延納不可 | 保険関係成立日から3月31日 |
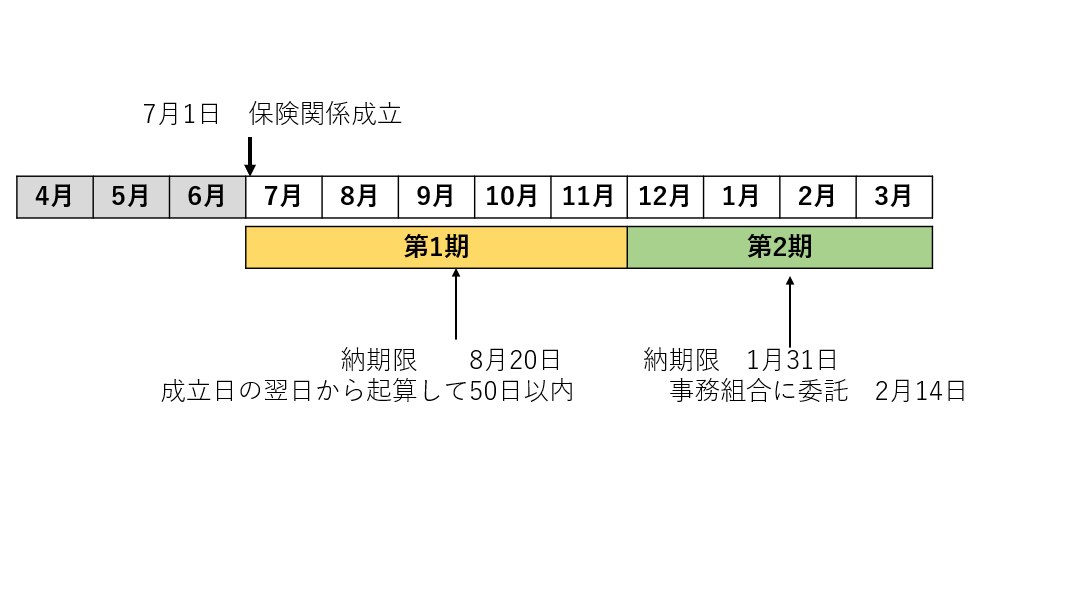
こちらの問題もどうぞ!
<H29年出題>
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

【解答】 〇
10月1日に保険関係が成立した場合は延納できませんので、3月31日までの分を1回で納付します。
納期限は、保険関係成立日の翌日(10月2日)から50日以内なので、11月20日となります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(徴収法)
R3-087
R2.11.18 <R2出題>覚える「日雇労働被保険者手帳」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問9-C(雇)>
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者手帳へ雇用保険印紙を貼付して消印又は納付印の押印によって行うため、事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならず、使用期間が終了するまで返還してはならない。

【解答】 ×
★ 「日雇労働被保険者手帳」によって、印紙保険料の納付や日雇労働求職者給付金の支給などが行われます。日雇労働被保険者手帳は被保険者のみならず事業主や政府にとっても重要です。
徴収法第23条では、「事業主は、日雇労働被保険者を使用する場合には、その者の日雇労働被保険者手帳を提出させなければならない。その提出を受けた日雇労働被保険者手帳は、その者から請求があったときは、これを返還しなければならない。」と規定されています。
問題文は、「使用期間が終了するまで返還してはならない。」が誤りで、請求があったときは、これを返還しなければなりません。事業主が被保険者手帳の返還を拒否することは、職業選択の自由の阻害につながるからです。
では、関連問題をどうぞ!
<H24年出題(雇用保険)>
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。

【解答】 ×
「追徴金を徴収されることはない」が誤りで、追徴金を徴収されることもあります。
★ 日雇労働被保険者を使用する場合、事業主には日雇労働被保険者手帳を提出させる義務があります。(徴収法第23条)
追徴金は、正当な理由があると認められるときは徴収されませんが、問題文のように「事業主が日雇労働被保険者手帳の提出を求めなかった → 日雇労働被保険者が手帳を提出しなかった → 雇用保険印紙の貼付がなされなかった」場合は正当な理由にならないので、追徴金の対象となります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(徴収法)
R3-077
R2.11.8 <R2出題>問題の意図「メリット収支率に入れるもの入れないもの」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<労災問9-C>
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。

【解答】 〇
問題の意図は、「特別支給金は、メリット収支率の計算に入るか否か」です。
★メリット収支率の分母は「保険料」、分子は「保険給付等の額」です。保険料に対する保険給付等の割合なので、率が大きいということは業務災害が多かったということです。
具体的には、収支率が100分の85を超えると労災保険率がup し、収支率が100分の75以下になると労災保険率はdown
し、収支率が100分の75以下になると労災保険率はdown します。
します。
★また、収支率の計算は分母・分子ともに「業務災害」に係るもので計算します。なぜなら事業主の努力で防ぐことができるのは業務災害だけだからです。
★「特別支給金」は保険給付の上乗せですので、収支率の計算に入れることになっています。
こちらもどうぞ!
 H25年出題
H25年出題
特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
 H22年出題
H22年出題
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。

【解答】
 H25年出題 ×
H25年出題 ×
特別支給金もメリット収支率の計算に含まれます。(ただし、業務災害に係る特別支給金でも収支率の計算に入れないものもあります。)
 H22年出題 〇
H22年出題 〇
特別加入の承認を受けた海外派遣者については、分母・分子ともに収支率の計算には入りません。分母・分子ともに日本国内の分で計算されます。
★ちなみに、特別加入の承認を受けた中小事業主等については、分母・分子ともに計算に入ります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(徴収法)
R3-057
R2.10.19 R2出題・特別加入保険料率について
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
 R2災問10より
R2災問10より
第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率である。
 R2災問10より
R2災問10より
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。

【解答】
 R2災問10より 〇
R2災問10より 〇
一般の労働者の労災保険率は、過去3年間の「業務災害」「通勤災害」の災害率、「二次健康診断等給付」に要した費用、「社会復帰促進等事業」の内容等をもとに決められます。
一方、特別加入者は二次健康診断等給付の対象外です。そのため、第1種別加入保険料率は、「二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮した率を減じた率となります。
ただし、現在は、その率はゼロですので、結果として第1種特別加入保険料率は、その事業に適用される労災保険率と同率となります。
 R2災問10より ×
R2災問10より ×
事業又は作業の種類ごとに、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲で、18段階で設定されています。
では、特別加入保険料率の問題をどうぞ!
<H26年出題>
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和2年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

【解答】 ×
第3種特別加入保険料率は、1000分の3です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(徴収法)
R3-047
R2.10.9 R2出題・難問解決策「請負事業の一括の効果」
一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2(労災)問8より>
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。

【解答】 ×
「労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる」の部分が誤りです。
元請負人が事業主とされるとは、下請負も含めたすべてについて保険料の納付等の義務を負うということ。
下請負人やその使用する労働者と元請負人に労働関係はありません。
こちらもどうぞ!
<H26年出題(労災)>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】 〇
雇用保険に係る保険関係は、元請負人に一括されません。
雇用保険は、原則通り「事業」単位で適用されるので、元請負人は元請負人、下請負人は下請負人とそれぞれの事業ごとに徴収法が適用されます。
では、こちらも!
<H28年出題(雇用)>
請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。

【解答】 ×
先ほどの問題で勉強したように、雇用保険に係る保険関係は、元請負人に一括されません。
下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料は、下請負人が納付義務を負います。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~徴収法
R3-037
R2.9.29 R2・労働保険徴収法の規定による処分に不服がある場合
・ 徴収法には不服申立ての規定がありません。不服がある場合は、行政不服審査法の規定で行います。
不服申立て
<R2年雇用問10B>
労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内であれば、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。ただし、当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。

【解答】 ×
「正当な理由があるときは、この限りでない。」という例外規定が設けられているので、「当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない。」が誤りです。
徴収法の不服申立てでおさえておきたいポイント!
「徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。(「厚生労働大臣」「審査請求をすることができる」がポイントです。)
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<H28年出題>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

【解答】 ×
『「労働保険徴収法の規定による処分に不服がある者」→ 厚生労働大臣に審査請求をすることができる。』です。(行政不服審査法)
問題文の「その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立て」が誤り。「厚生労働大臣に審査請求をすることができる。」です。
もう一問どうぞ!
<H28年出題>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。

【解答】 〇
厚生労働大臣に審査請求をすることもできますが、直ちに処分の取消しの訴えを提起すること(裁判所に提訴)もできます。
シリーズ・歴史は繰り返す(徴収法)
R3-027
R2.9.19 過去の論点は繰り返す(R2・徴収「有期事業の延納」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
有期事業の延納
 問題<H22年出題>
問題<H22年出題>
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
 問題<H29年出題>
問題<H29年出題>
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。

【解答】
 問題<H22年出題> 〇
問題<H22年出題> 〇
「最初の期」の取り方と納期限が問われている問題です。
 問題<H29年出題> 〇
問題<H29年出題> 〇
平成22年の問題と同じですが、さらに延納回数も問われています。
図で確認しましょう。
有期事業の延納は、「最初の期」の取り方が肝心です。
まずは基本形を書いてみて、「保険関係成立の日」の日を置いてみてください。
保険関係成立の日からその日の属する期の末日まで、「2月超える」なのか「2月以内」なのかがポイントです。
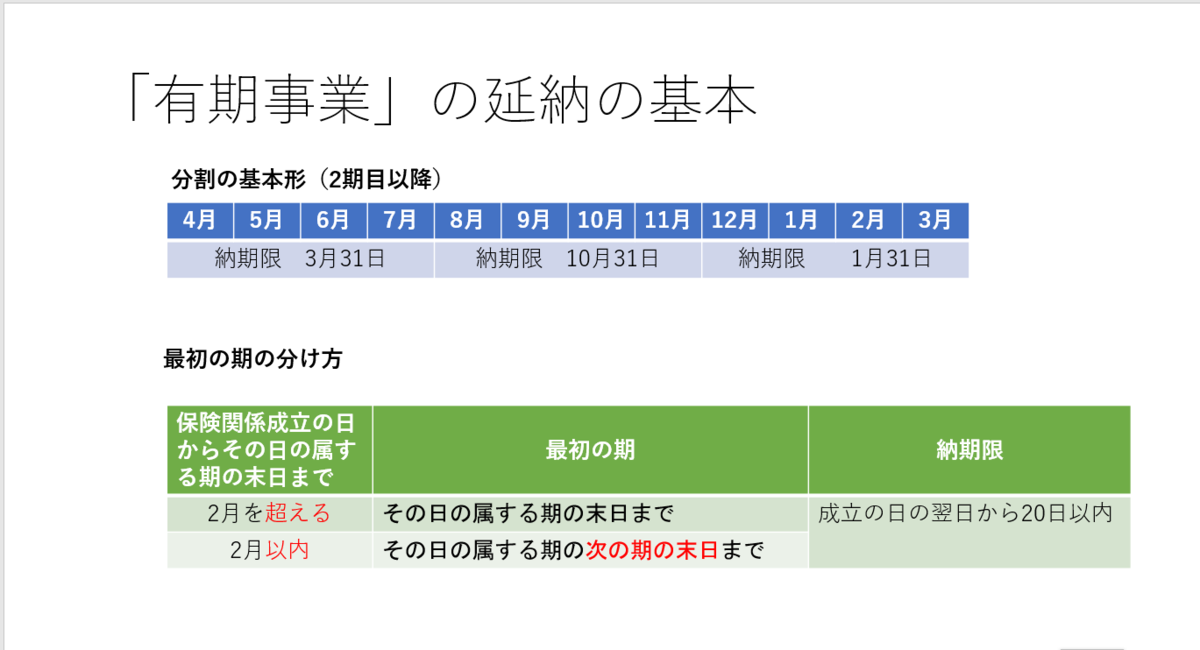
平成22年の問題は、保険関係成立の日が「7月1日」。
その日の属する期の末日まで2月以内なので、次の期の末日までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(7月2日)から20日以内なので、「7月21日」です。
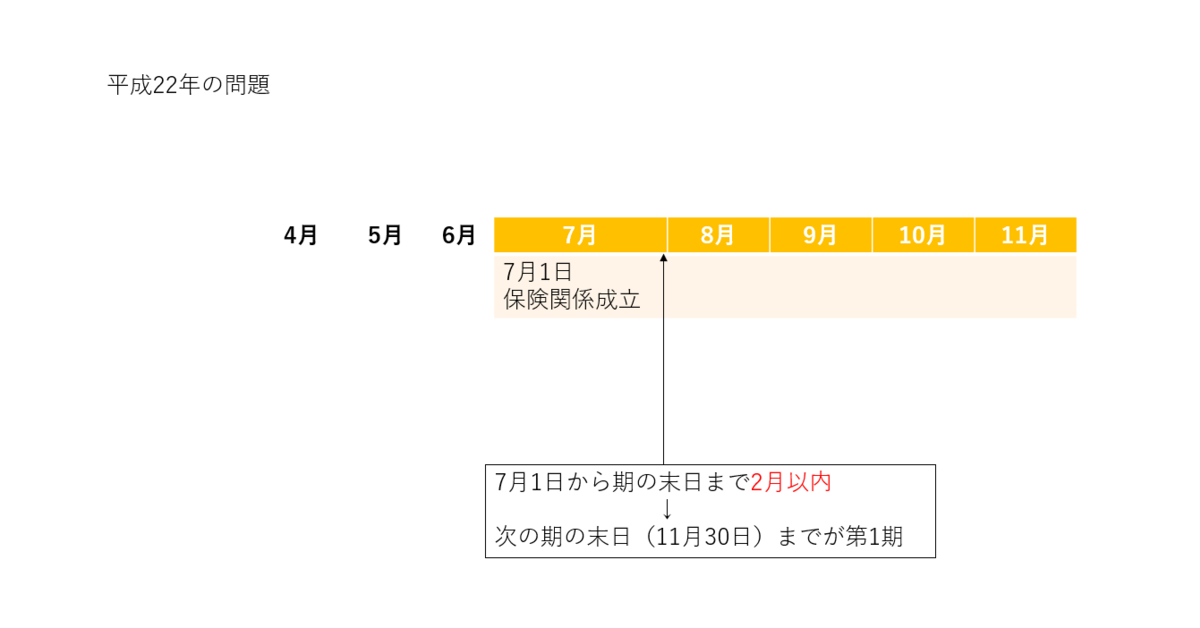
次は平成29年の問題。
こちらは、保険関係成立の日が「6月15日」。
その日の属する期の末日まで2月以内なので、次の期の末日までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(6月16日)から20日以内なので、「7月5日」です。
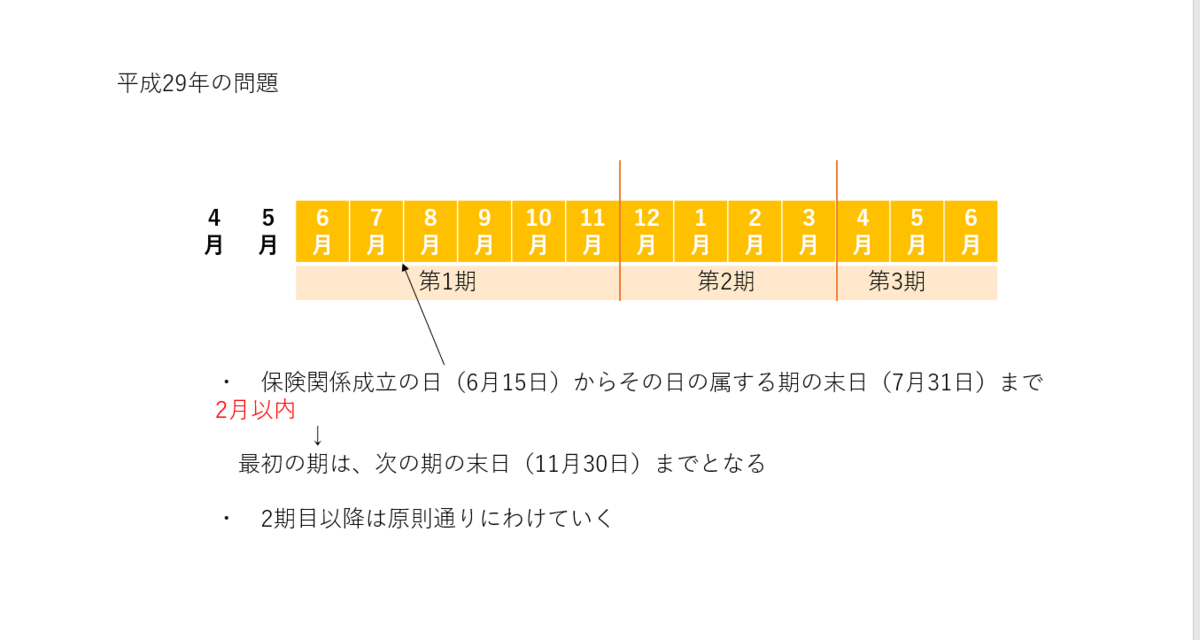
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2雇用問8B>
概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。

【解答】 〇
保険関係成立の日が「6月1日」。
その日の属する期の末日(7月31日)まで2月以内なので、次の期の末日(11月30日)までが最初の期となります。
最初の期の納期限は保険関係成立の日の翌日(6月2日)から20日以内なので、「6月21日」です。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(徴収法)
R3-017
R2.9.9 第52回試験・択一徴収法の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 徴収法 択一式
基本に忠実かつ過去の出題傾向に沿った問題で、解きやすかったと思います。
徴収法は過去問中心の勉強で大丈夫。
問10(雇用)に不服申し立ての問題がありました。
徴収法には不服申し立ての規定がありませんので、処分に不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、厚生労働大臣に審査請求をすることができます。
審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。ただし、「正当な理由があるときは、この限りでない。」という例外が設けられています。
問題文は、「当該期間を超えた場合はいかなる場合も審査請求できない」となっているので「×」です。
全体的に 徴収法はブレずに過去問。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-236
R2.7.24 迷わないために覚えておく数字@徴収法
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「迷わないために覚えておく数字@徴収法」です。
では、どうぞ!
問題 1
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込み生産量が1000立方メートル未満、又は概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

【解答】 ×
又はではなく「かつ」です。
有期事業の一括の対象になる事業の規模は、
・ 立木の伐採の事業 → 素材の見込み生産量が1000立方メートル未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満
・ 建設の事業 → 請負金額が1億8千万円未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満
問題 2
<H27年出題>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

【解答】 ×
下請負事業の分離の認可の規模の要件は、
概算保険料の額に相当する額が160万円以上、又は、請負金額が1億8000万円以上
問題 3
<H27年出題>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

【解答】 ×
「請負事業の一括」の対象は建設の事業だけです。
立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象ではないので、下請負事業の分離の対象にもなりません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-226
R2.7.14 徴収法でよく出る端数処理
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「徴収法でよく出る端数処理」です。
切り上げ?切り捨て?
1円単位?10円単位?1000円単位?
この機会に覚えてしまいましょう!
では、どうぞ!
問題 1
<H17年出題>
賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。

【解答】 〇
概算保険料は、「賃金総額の見込額 × 一般保険料率」で計算します。
端数処理は
・賃金総額 → 1,000円未満切り捨て
・概算保険料の額又は確定保険料の額 → 1円未満切り捨て
となります。
問題 2
<H24年出題>
個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。
なお、事業の種類等は次のとおりである。
・事業の種類 飲食店
・当該事業に係る労災保険率 1000分の3
・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 令和元年12月15日
・給付基礎日額 8千円
・特別加入保険料算定基礎額 292万円
| A | 8千円×107日×1000分の3 |
| B | 8千円×108日×1000分の3 |
| C | 292万円×12分の1×3か月×1000分の3 |
| D | 292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3 |
| E | 292万円×12分の1×4か月×1000分の3 |

【解答】 E
ポイント! 保険年度の途中で特別加入した又は中途脱退した場合は「月割計算」
特別加入期間の月数に1か月未満の端数があるときは、1か月としてカウントします。
・保険年度の中途に特別加入者になった
承認日の属する月 → 1か月でカウントする
・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった
地位の消滅の前日の属する月 → 1か月でカウントする
問題文の場合、特別加入の承認を受けたのは令和元年12月15日。12月は1か月でカウントします。令和元年度の特別加入期間の月数は、令和元年12月から令和2年3月までの4か月となります。
(注意)有期事業の場合は端数処理の方法が異なります。有期事業についての特別加入期間を全期間で端数処理しますので、注意してください。
問題 3
<H29年出題>
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

【解答】 ×
ポイント! 1円未満の端数は、1期分でまとめます。
170,000円÷3=56666.6666
第1期 → 56,668円
第2期、第3期 → 56,666円
問題 4
延滞金は、労働保険料の額が100円未満であるとき又は延滞金の額が10円未満であるときは、徴収されない。

【解答】 ×
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-216
R2.7.4 第1種特別加入保険料率の決め方
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「第1種特別加入保険料率の決め方」です。
中小事業主が労災保険に特別加入した場合の労災保険率は?
では、どうぞ!
問題
<H26年出題>
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される保険料率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。

【解答】 ×
「通勤災害に係る災害率」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。
特別加入者には、「二次健康診断等給付」は行われませんよね?
ですので、「二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率となります。
※なお、「二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」は現在ゼロなので、第1種特別加入保険料率は、通常の労災保険料率と同じ率です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-206
R2.6.24 追徴金でよく出るところ
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「追徴金でよく出るところ」です。
確定保険料の額を認定決定した場合、印紙保険料の額を認定決定した場合、それぞれ追徴金が徴収されます。
今日は「追徴金」がテーマです!
では、どうぞ!
問題
①<H25年出題>
事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた場合等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
②<H28年出題>
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】
①<H25年出題> 〇
②<H28年出題> × 100分の10ではなく100分の25
★追徴金の率がポイント!
確定保険料の認定決定 → 100分の10
印紙保険料の認定決定 → 100分の25
どちらも、納付すべき額の1,000円未満の端数は切り捨てです。
印紙保険料の認定決定についてもう一問どうぞ!
<H25年出題>
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】 〇
「納入告知書」がポイントです。(納付書ではありません。)
さらに、ポイントです!
認定決定された印紙保険料の追徴金は、印紙ではなく現金で納付しなければならないことにも注意しましょう。
こちらもどうぞ!
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】 ×
延滞金がかかるのは「労働保険料」のみです。追徴金は労働保険料ではないので、延滞金はかかりません。
ポイント!
「追徴金」は「労働保険料」ではありません。
 督促及び滞納処分
督促及び滞納処分
・労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
・ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
↓
★ 追徴金は、「その他この法律の規定による徴収金」に該当しますので、「督促」「国税滞納処分の例による処分」は、追徴金も対象となります。
 延滞金
延滞金
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
↓
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」ではなく、「労働保険料」になっていることに注目してください。延滞金の対象は「労働保険料」のみで、その他この法律の規定による徴収金は対象外です。ですので、追徴金も延滞金の対象にはなりません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-196
R2.6.14 労災保険率の決定
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「労災保険率の決定」です。
労災保険率は、事業の種類ごとに、1000分の2.5~1000分の88の間で定められています。今日のテーマは、労災保険率の決定ルールです。
では、どうぞ!
問題
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【解答】 ×
「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。
こちらもどうぞ!
非業務災害率とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。

【解答】 〇
非業務災害率には、「通勤災害」の災害率と二次健康診断等給付の費用が反映されています。
労災保険率のうち、1000分の0.6が非業務災害率となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-186
R2.6.4 徴収法上の賃金
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「徴収法上の賃金」です。
労働者の労災保険、雇用保険の保険料は、労働者に支払う「賃金」をもとに計算します。
保険料の計算ベースになる「賃金」の定義を確認しましょう。
では、どうぞ!
問題
労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいうが、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金には含まれない。

【解答】 ×
労働基準法で定める休業手当は賃金ですので、労働保険料を計算する際の賃金総額に算入します。
問題2
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲)
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、< A >の定めるところによる。
【選択肢】
① 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
② 厚生労働大臣

【解答】 A ① 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
賃金には、「通貨以外のもの(現物給与のこと)であって、厚生労働省令で定めるもの」も含まれます。
算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)の範囲は、徴収法施行規則で、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」と規定されています。
現物給与で賃金に算入されるのは、①食事の利益、②被服の利益、③住居の利益、④所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるもの、です。
問題3
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

【解答】 〇
現物給与の評価額は、「厚生労働大臣」が定めることになっています。
ちなみに、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化推進のため、
健康保険法でも「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。」となっています。(健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。)
厚生年金保険法も同様に現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることになっています。
(参考)雇用保険法はちょっと違います。
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
雇用保険法では、評価額は公共職業安定所長が定めるとされています。さらっと読むだけでOKです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-176
R2.5.25 令和2年度の雇用保険率
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「令和2年度の雇用保険率」です。
では、どうぞ!
問題
①<H26年出題(アレンジ)>
雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、令和2年度の雇用保険率は、一般の事業では、1000分の8とされている。
②<H30年出題(アレンジ)>
建設の事業における令和2年度の雇用保険率は、令和元年度と同じく、1000分の11である。

【解答】
①<H26年出題(アレンジ)> ×
一般の事業の令和2年度の雇用保険率は、1000分の9です。(令和元年度と同率)
②<H30年出題(アレンジ)> ×
建設の事業の令和2年度の雇用保険率は、1000分の12です。(令和元年度と同率)
こちらもどうぞ!
<R1年出題>
一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。

【解答】 ×
雇用保険料率は、①一般の事業、②農林水産、清酒製造業、③建設の事業の3つのグループに分けて設定されています。
問題文の「園芸サービスの事業」は一般の事業のグループに入りますので、この問題は×となります。
ポイント!
園芸サービス、⽜⾺の育成、酪農、養鶏、養豚、内⽔⾯養殖、特定の船員を雇用する 事業 → 一般の事業の雇用保険率(1000分の9)が適⽤されます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-166
R2.5.15 労働保険事務組合の責任
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「労働保険事務組合の責任」です。
労働保険事務組合の責任についてテーマごとに確認しましょう。
問題1
<テーマ>
労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主が、
↓
労働保険料等の納付のため、
↓
金銭を事務組合に交付した
↓
そのときの事務組合の責任は??
<H17年出題>
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。

【解答】 ○
事業主は労働保険料納付のための金銭を事務組合に委託した。事務組合は委託された金額の限度で、政府にその労働保険料を納付する責任がある、ということです。
「その交付を受けた金額の限度で」の部分がポイントです。
問題2
<テーマ>
例えば、確定保険料を申告するにあたり、事業主は事務組合に賃金総額などを報告していた
↓
にもかかわらず、事務組合は確定保険料申告書を提出していなかった
↓
その結果、政府が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することになった
↓
そのときの事務組合の責任は??
<H15年出題>
事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。

【解答】 ×
この問題の場合、追徴金が徴収されるのは、事業主が賃金等の報告をしなかったことが原因。事務組合にはその責めに帰すべき理由がない、と問題文に書かれていますので、事務組合は追徴金納付の責は負いません。
(事務組合の責に帰すべき理由がある場合は、納付の責を負います。)
問題3
<テーマ>
では、労働保険料その他の徴収金納付の金銭を事務組合に交付した事業主は
↓
その後は全ての責任を免れるのでしょうか?
<H29年出題>
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

【解答】 ×
上の2問で勉強したように、「事業主が労働保険料納付のための金銭を事務組合に交付した」、「事務組合の責に帰すべき理由によって追徴金や延滞金が課された」。このような場合、事務組合が納付の責を負います。
しかし、事務組合に滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限って、事業主も納付の責任を負うことがあります。
なお、問題文の「当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる」という規定はありません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-156
R2.5.5 請負事業の一括
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
問題
<H26年出題>
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

【解答】 ×
「請負事業の一括」の対象は、建設の事業のみ。立木の伐採の事業は対象外です。
ポイント
元請負人→下請け→孫請け・・・と数次の請負で行われる建設の事業の保険関係は、元請負人のみを適用事業主として成立します。
下請負人の保険関係は、元請負人に当然に一括されます。(認可などの手続きは要りません。)
★下請負事業の分離については「認可」が必要。こちらの記事をどうぞ
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H26年出題>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】 ○
請負事業の一括は、労災保険の保険関係だけが対象です。
雇用保険の保険関係については一括されず、原則通り、各事業ごと(元請けは元請けで、下請けは下請けで、孫請けは孫請けで)に適用されます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-146
R2.4.25 労働保険料の還付請求と充当
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
問題
<H29年出題>
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

【解答】 ×
事業主による充当についての承認は不要ですが、当該事業主への充当後の通知は必要です。
ポイント
概算保険料 > 確定保険料の場合
・事業主が還付請求をした場合 → 還付
・事業主が還付請求をしない場合 → 充当
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
①<H24年出題>
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
②<R1年出題>
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①<H24年出題> ○
還付請求が行われないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が充当します。
②<R1年出題> ×
労働保険料還付請求書の提出先は、「官署支出官」又は「所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(所轄都道府県労働局資金前渡官吏)です。
ちなみに、充当するは、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-136
R2.4.15 労働保険/有期事業とは?
徴収法には、「継続事業」と「有期事業」という概念が登場します。
改めて、「有期事業」の定義を確認しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

【解答】 ×
徴収法上の有期事業は、建設の事業と立木の伐採の事業です。ビルが建ったらそこで事業が終了する建設現場などを想像していただければOKです。
なお、有期事業は労災保険の保険関係だけのもので、雇用保険の保険関係には有期事業の考え方はありません。
こちらの問題もどうぞ!
<H28年出題>
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

【解答】 ×
有期事業の一括の要件に、労働者数は入っていませんので、「かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満」の部分が誤りです。
なお、概算保険料が160万円未満は共通要件ですが、さらに、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満であることも要件です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-126
R2.4.1 暫定任意適用事業・保険関係消滅について
暫定任意適用事業の場合は、事業主の申請によって、保険関係を消滅させることができます。
その申請要件について、労災保険と雇用保険で違いはあるでしょうか?
 (H29年出題)
(H29年出題)
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

【解答】 ×
労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業では手続きが異なります。
<労災保険暫定任意適用事業>
・労働者の過半数の同意
・保険関係成立後1年経過している
・特別保険料を徴収する期間が経過している
<雇用保険暫定任意適用事業>
・労働者の4分の3以上の同意
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H21年出題>
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。

【解答】 ○
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H27年出題>
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

【解答】 ×
事業を廃止した場合は、法律上当然に、廃止の日の翌日に保険関係が消滅します。
ですので、消滅の申請、所轄都道府県労働局長の認可、ともに不要です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-116
R2.3.17 メリット制の適用
 継続事業と有期事業、メリット制の違いは?
継続事業と有期事業、メリット制の違いは?
 (H28年出題)
(H28年出題)
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。

【解答】 ×
「有期事業を含め」の部分が間違いです。
継続事業(一括有期事業含む)の場合、収支率が85%超になれば、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から労災保険率が引き上げられ、収支率が75%以下になれば引き下げられます。
事業が継続的に続くので、労災保険率を上下させることによって、メリット制を適用させます。
一方、有期事業の場合は、事業が終了してしまうので、労災保険率を上下させるのではなく、確定保険料を増減させることによってメリット制を適用します。
 では、こちらの問題もどうぞ
では、こちらの問題もどうぞ
<H25年出題>
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

【解答】 ×
メリット制が適用されるのは、収支率がメリット収支率が85%を超え、又は75%以下である場合です。問題文の100%は間違いです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-106
R2.3.2 徴収法/書類の保存期間
 徴収法の規定による書類の保存期間は?
徴収法の規定による書類の保存期間は?
 (H28年出題)
(H28年出題)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】 ○
徴収法の書類の保存期間は基本的に3年ですが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿だけは、4年ですので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-96
R2.2.13 概算保険料延納の際の納期限
 概算保険料は、一定の要件を満たせば延納(分割納付)が可能です。労働保険事務組合に事務処理を委託している場合の納期限は?
概算保険料は、一定の要件を満たせば延納(分割納付)が可能です。労働保険事務組合に事務処理を委託している場合の納期限は?
 H27年出題
H27年出題
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

【解答】 ○
継続事業(一括有期事業含む)の延納の場合は、労働保険事務組合に委託している場合、第2期分と第3期分の納期限が14日延長して設定されていますが、単独の有期事業の場合は、そのような取り扱いはありません。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H27年出題>
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

【解答】 ○
継続事業(一括有期事業を含む。)で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも、4月1日から7月31日までの期分(第1期分)の納期限は延長されず、原則通りの7月10日となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-86
R2.1.26 日雇労働被保険者の一般保険料(徴収法)
★ 事業主は、使用する日雇労働被保険者については印紙保険料を納付しなければなりません。が、印紙保険料だけ?というのが今日のテーマです。
 H28年出題
H28年出題
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。

【解答】 ×
事業主は、印紙保険料だけでなく、一般保険料も負担しなければなりません。
日雇労働被保険者については、一般保険料にプラスして印紙保険料がかかります。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H22年出題>
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。

【解答】 ×
先ほどの問題は、「事業主」の負担でしたが、こちらは「日雇労働被保険者」の負担についての問題です。
日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1にプラスして、一般保険料の被保険者負担分も負担する必要があります。
★ちなみに
一般保険料は、労災保険料+雇用保険料です。
一般保険料のうち、労災保険料は全額事業主負担なので、労働者の負担はありません。
雇用保険料は、賃金総額×(雇用保険率-二事業に係る率)の2分の1が被保険者負担分です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-76
R2.1.8 下請負事業の分離の条件(徴収法)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H27 徴収法(労災問10)より
H27 徴収法(労災問10)より
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

【解答】 ×
厚生労働省令で定める事業(=労災保険の保険関係が成立している建設の事業)が数次の請負で行われる場合、労災保険の保険関係は、元請負事業に一括されます。(下請負事業の分も含めてすべて元請負事業にまとめられるということ。=請負事業の一括)
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、そこから下請負事業を分離させることもできます。ただし、その場合は法律上当然ではなく、「認可」が必要です。
上記は、下請負事業を分離させるときの認可の条件についての問題です。
下請負事業の分離の認可を受けるには、「元請負及び下請負人」が申請することが条件です(共同で申請しなければならない)。上記の問題は、「そのいずれかが単独で」の部分が間違っています。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H27年出題】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書は、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】 ○
下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出するのが原則です。(やむを得ない理由の場合は、期限後でも提出できる例外があります。)
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-66
R1.12.23 R1徴収/保険関係成立届の提出先
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「保険関係成立届の提出先」についてです。
 R1徴収法(労災問10)より
R1徴収法(労災問10)より
一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。

【解答】 ○
一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業の保険関係成立届は
→ 所轄労働基準監督署長に提出
→ ただし、雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、所轄公共職業安定所長に提出
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H28年出題>
① 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
② 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

【解答】
① ○
一元適用事業・労働保険事務組合に委託なし(雇用保険のみが成立している事業を除く。)
→ 所轄労働基準監督署長
② ○
一元適用事業・労働保険事務組合に委託あり
→ 所轄公共職業安定所長
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-56
R1.11.29 R1徴収/認定決定の納期限
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「認定決定の納期限」についてです。
 R1徴収法(労災問9)より
R1徴収法(労災問9)より
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

【解答】 ×
確定保険料の認定決定の通知を受けた場合の納期限は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。(概算保険料の認定決定も同じです。)
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、 事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-46
R1.11.9 R1徴収/労働保険事務組合
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「労働保険事務組合」についてです。
 R1徴収法(雇用問9)より
R1徴収法(雇用問9)より
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【解答】 ○
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる中小事業主の範囲は覚えておきましょう。
「金融業」の場合、委託できるのは常時使用する労働者が50人以下の事業主です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-35
R1.10.23 R1徴収/労働保険料の種類
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「労働保険料の種類」についてです。
 R1徴収法(労災問8)より
R1徴収法(労災問8)より
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

【解答】 ×
一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料の6種類です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-25
R1.10.5 R1徴収法/労災保険暫定任意適用事業の保険関係消滅
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「労災保険暫定任意適用事業の保険関係消滅」についてです。
 R1徴収法(労災問10)より
R1徴収法(労災問10)より
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

【解答】 ×
「労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。」の部分が誤りです。
労災保険暫定任意適用事業の場合、そもそも労災保険の加入が任意ですので、申請によって保険関係を消滅させることができます。
しかし、労働者の立場から見ると、労災保険の保護が無くなることになるので、事業主は保険関係消滅申請書に労働者の同意書を添付しなければなりません。
※なお、労災保険に任意加入するときは、同意書は要りません。労働者が労災保険料を負担する必要が無いからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-15
R1.9.21 R1徴収法/概算保険料の延納
令和元年の問題を振り返っています。
今日は徴収法の基本的な問題を解いてみます。
 R1徴収法(労災問8)より
R1徴収法(労災問8)より
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれている。

【解答】 ×
継続事業、一括有期事業の場合、延納の対象から除外されるのは、当該保険年度の「10月1日」以降に保険関係が成立した場合です。
ちなみに、保険関係成立日が4月1日から5月31日までの場合は3回、6月1日から9月30日までの場合は2回に分けて延納できます。
社労士受験のあれこれ
第1種特別加入保険料率(徴収法)
R1.5.29 特別加入保険料率の決め方(第1種特別加入保険料率)
空欄を埋めてください
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の< A >を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
【選択肢】
① 過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率
② 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額

【解答】 ② 過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額
※平成26年出題の択一式を穴埋めにアレンジした問題です。
過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を減じるのは、特別加入者には二次健康診断等給付が行われないからです。
なお、「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率」は、現在は「ゼロ」です。
社労士受験のあれこれ
概算保険料申告書を提出しなかった場合(徴収法)
R1.5.27 「追徴金」のよく出る問題(徴収法)
まず、過去問をどうぞ
<H26年出題>
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】×
「概算保険料」については、認定決定されたとしても追徴金は課せられません。
こちらもどうぞ
<H22年出題>
事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。

【解答】 ○
確定保険料が認定決定された場合の追徴金に係る割合は100分の10ですが、認定決定された印紙保険料の追徴金に係る割合は100分の25です。
社労士受験のあれこれ
単独有期事業の概算保険料の額の出し方(徴収法)
H31.4.18 単独有期事業の概算保険料の計算のポイントは?
さっそく、過去問をどうぞ
<H27年出題>
複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。

【解答】 ○
単独の有期事業の場合、賃金総額は「全期間」の見込額で計算することがポイント。
継続事業(一括有期事業も)は、賃金総額の見込額は「保険年度単位」で計算するので、ひっかからないようにしましょう。
社労士受験のあれこれ
延滞金/徴収法
H31.3.28 延滞金の対象となるものは?
まずは過去問からどうぞ
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】 ×
「未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。」の部分が誤りです。
■ 督促の対象は、「労働保険料その他この法律による徴収金」です。「その他この法律による徴収金」には追徴金も含まれますので、追徴金も督促の対象です。
■ 一方、延滞金は「労働保険料」の納付を督促したときに徴収されます。延滞金は「労働保険料」のみが対象で「その他この法律による徴収金」は対象外です。追徴金に延滞金は課せられません。
もう一問どうぞ
<H22年出題>
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

【解答】×
追徴金を滞納した場合、「督促」と「国税滞納処分」の対象になります。
しかし追徴金について、延滞金は徴収されません。
社労士受験のあれこれ
保険関係成立届/徴収法
H31.3.22 保険関係成立届の提出先
★★まずは過去問をどうぞ
<H28年出題>
⓵ 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
② 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

【解答】
⓵ ○
② ○
★ 一元適用事業の場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しているか否かで提出先が変わります。
こちらもどうぞ
<H27年出題>
建設業の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】 ○
・ 二元適用事業の労災保険の成立は所轄労働基準監督署長に提出します。
・ 保険関係成立届は、保険関係が成立した日から10日以内に提出しますが、「翌日起算」がポイントです。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(徴収法)
H31.2.7 H30年出題/労災保険率の定め方
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」です。
※ 今日は、「労災保険率の定め方」です。
H30年 徴収法(雇用保険問8E)
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去5年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【解答】 ×
「過去5年間」ではなく「過去3年間」の実績を考慮します。
ポイント
過去3年間の実績が考慮されますが、何の実績を考慮するのかを1つずつおさえましょう。穴埋め式で確認しましょう。
空欄を埋めてください。

労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに< A >に要した費用の額、< B >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
【解答】 A 二次健康診断等給付 B 社会復帰促進等事業
こちらもどうぞ
労災保険率は、保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業の種類及び内容を考慮して定められる。

【解答】 × 「二次健康診断等給付に要した費用の額」が抜けています。
★ 労災保険法の保険給付は①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付の3つです。
二次健康診断等給付も忘れずに。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(徴収法)
H31.1.7 H30年出題/確定保険料申告書の提出
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」です。
※ 今日は、「確定保険料申告書の提出」です。
H30年 徴収法(雇用保険問9イ)
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】 ○
確定保険料の額が申告済みの概算保険料より多くても、少なくても、確定保険料申告書の提出は必要です。
★ では、既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合の手続きを確認しましょう。
過去問でどうぞ
(H18年出題)
既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主が充当の申出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当され、充当の申出のない場合は超過額が還付される。

【解答】 ×
ポイント
【還付請求をすれば還付される】
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、超過額の還付を請求したとき
↓
官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、超過額を還付する
【還付請求がない場合は充当される】
事業主から還付請求がない場合
↓
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等に充当する
↓
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(徴収法)
H30.12.20 H30年出題/印紙保険料の額
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」を確認しましょう。
※ 今日は、「印紙保険料の額」です。
H30年 徴収法(雇用保険問8A)
賃金の日額が、11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に1.5%を乗じて得た額である。

【解答】 ×
印紙保険料の日額は、第1級→176円(賃金の日額が、11,300円以上のとき)、第2級→146円(賃金の日額が8,200円以上11,300円未満のとき)、第3級→96円(賃金の日額が8,200円未満のとき)の3パターンで定額です。
問題文は賃金の日額が11,300円以上ですので、印紙保険料は第1級176円です。
【では過去問をどうぞ】
①H21年出題
賃金の日額が11,300円以上である日雇労働被保険者に係る印紙保険料の額は、その労働者に支払う賃金の日額に雇用保険率を乗じて得た額である。
②H22年出題
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。
③H12年出題
日雇労働被保険者を使用する事業主が当該日雇労働被保険者について負担すべき保険料は、印紙保険料の2分の1のみである。

【解答】
① × 印紙保険料の額は、176円(第1級)となります。
② × 日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額だけでなく、一般保険料(雇用保険料の被保険者負担分)も負担しなければなりません。
③ × 日雇労働被保険者を使用する事業主は、印紙保険料の額の2分の1のみでなく、一般保険料(労災保険料(全額事業主負担)と雇用保険料(事業主負担分))も負担しなければなりません。
ポイント!
日雇労働被保険者は印紙保険料のみではありません。
一般保険料(労災保険料+雇用保険料)も必要ですので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(徴収法)
H30.12.2 H30年出題/継続事業一括の効果
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「徴収法」を確認しましょう。
※ 今日は、「継続事業が一括された場合の注意点」です。
H30年 徴収法(労災問8B)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所管に応じて行う。

【解答】 ○
例えば、本社を指定事業として継続事業の一括の認可を受けると、本社で被一括事業(支店や営業所など)の保険料を一括して申告納付することになります。
ただし、支店や営業所など(被一括事業)の労災保険給付の請求手続きなどは本社に一括されませんので、それぞれの事業場で行います。
【同じ論点の過去問です】
<平成21年出題>
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。

【解答】 ×
指定事業の所在地を管轄ではなく、「被一括事業の所在地を管轄」する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して行います。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(徴収法 基礎編)
H30.11.12 H30年出題/一般保険料の納付に関する事務
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
徴収法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、徴収法「一般保険料の納付に関する事務」です。
H30年 徴収(雇用保険)法(問9オ)
雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。

【解答】 ○
公共職業安定所では、労働保険料の申告・納付に関する事務は扱っていません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(徴収法 基礎編)
H30.10.24 H30年出題/労働保険・口座振替できるもの・できないもの
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
徴収法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「口座振替」できるもの、できないものです。
① H30年 徴収法(労災問10A)
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
② H30年 徴収法(労災問10C)
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
③ H30年 徴収法(労災問10E)
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

【解答】 ① × ② × ③ ○
★ 口座振替の対象になるのは次の二つです。(どちらも「納付書」によるもの)
・ 概算保険料、延納する場合における概算保険料
・ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付
※ 問題①について
「延納する場合を除く。」が誤りです。延納の概算保険料も口座振替の対象です。
※ 問題②について
「増加概算保険料」は口座振替の対象にはなりません。
※ 問題③について
「追徴金」も口座振替の対象にはなりません。
 【過去問もチェックしましょう】
【過去問もチェックしましょう】
<H24年出題>
① 労働保険徴収法第18条の規定により延納する場合における概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
② 労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
③ いわゆる認定決定された概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
④ 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付については、口座振替による納付の対象とならない。
⑤ 労働保険徴収法第21条の規定による追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

【解答】
① ○ 延納する場合における概算保険料の納付は口座振替できる。
② ○ 増加概算保険料の納付は、口座振替できない。
③ ○ 認定決定された概算保険料と認定決定された確定保険料の納付は、口座振替できない。
④ × 確定保険料の額から既に納付した概算保険料の額を控除した不足額の納付は、口座振替できる。
⑤ ○ 追徴金の納付は、口座振替できない。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(徴収法 基礎編)
H30.10.6 H30年出題/概算保険料の納付期限
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
徴収法の「基礎」を確認しましょう。
※ 「概算保険料」の納付期限の問題。気を付ける点はどこでしょう?
H30年雇用保険法(徴収法問9ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。
【解答】 ○
ポイント!
<継続事業(一括有期事業を含む。)の場合>
・ 前保険年度から保険関係が引き続いている場合
→ 保険年度の6月1日から起算して40日以内(当日起算なので7月10日まで)
・ 保険年度の中途で保険関係が成立した場合
→ 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
★「50」と「40」を間違えないように。当日起算、翌日起算を区別してくださいね。
例えば、10月6日に初めて労働者を雇い入れた場合、10月6日に保険関係が成立します。しかし、労働者が「よろしくお願いします」とやって来るのは、午前9時。10月6日は丸一日ありません。ですので、翌日起算になると考えてください。
ついでにこちらの過去問もチェック!
【有期事業の場合 H27年出題】
※ 「建設の有期事業」とは、一括有期事業として一括される個々の有期事業を除いたものをいう。
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
【解答】 ○
有期事業の概算保険料の申告・納付期限のポイントは、「20」と「翌日起算」です。
→ 成立した日の翌日から起算して20日以内
社労士受験のあれこれ
【徴収法】有期事業・期限
H30.7.30 徴収法 有期事業・期限について
 今日の神戸の最高気温は34.5℃。それでも涼しく感じます。
今日の神戸の最高気温は34.5℃。それでも涼しく感じます。
■■
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
平成27年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。
空欄を埋めてください。
① 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して< A >以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
② 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して< B >以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
③ 建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して< C >以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

【解答】 A 10日 B 20日 C 50日
社労士受験のあれこれ
【徴収法】有期事業の延納
H30.7.5 徴収法 有期事業・延納について
 7月5日。関西は一日中大雨でした。
7月5日。関西は一日中大雨でした。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
① 平成22年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。
空欄を埋めてください。(空欄には「○月○日」という日付が入ります。)
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から< A >までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、< B >が納期限となる。

【解答】 A 11月30日 B 7月21日
■ 有期事業の場合、全期間を通じて、毎年「4月1日~7月31日」、「8月1日~11月30日」、「12月1日~翌年3月31日」までの各期に分けることができます。
■ 最初の期の分け方
保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が
・2月を超えるとき → その日の属する期の末日までが最初の期
・2月以内のとき → 次の期の末日までが最初の期
■ 問題の要件の場合、「保険関係成立日」が7月1日。その日の属する期の末日(7月3日)まで2月以内なので、次の期の末日(11月30日)までが最初の期となります。
また、最初の期の納期限は、保険関係成立の日の「翌日」から起算して20日以内ですので、「7月21日」が納期限となります。
では、もう一問いきます!
H18年の択一式の問題を穴埋めにアレンジしました。同じように空欄に○月○日と入れてください。
工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が< C >までであり、以後、12月1日から翌年< D >までの期分が翌年1月31日まで、その次の期分は< E >までとなる。

【解答】 C 6月28日 D 3月31日 E 3月31日
■ 最初の期分は保険関係成立の日の翌日から20日以内
■ 2期目以降は
「4月1日~7月31日」 → 3月31日まで
「8月1日~11月30日」→ 10月31日まで
「12月1日~翌年3月31日」 → 翌年1月31日まで
社労士受験のあれこれ
【徴収法】一括有期事業/提出期限
H30.6.5 一括有期事業/提出期限など
 6月。お住まいの地域は、もう梅雨入りしましたか?
6月。お住まいの地域は、もう梅雨入りしましたか?
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
条文の空欄を埋めてください。
①一括有期事業開始届
一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、< A >に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②一括有期事業報告書
一括有期事業の事業主は、次の保険年度の< B >から起算して < C >以内又は保険関係が消滅した日から起算して< D >に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
A その開始の日の属する月の翌月10日まで B 6月1日 C 40
D 50日
もう少し詳しく
「一括有期事業開始届」とは
・ 毎月、個々の有期事業を開始したときに提出するもの。所轄労働基準監督署長が、工事等の実施状況を把握するため。
・ちなみに、「保険関係成立届」は、一括有期事業を開始したときに一度だけ提出する。個々の事業の開始ごとに提出しなくてもいい。
「一括有期事業報告書」とは
・ 確定保険料を提出するときに提出するもの。その年度中に終了した一括有期事業の内容を記載する。
ついでにこちらもチェック
<一括される事業の規模の要件>
① 概算保険料の額に相当する額が< E >万円未満であること。
かつ、
② 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が< F >立方メートル未満、建設の事業にあつては、請負金額(消費税等相当額を除く。)が< G >円未満であること。

【解答】
E 160 F 1,000 G 1億8000万
社労士受験のあれこれ
【徴収法】労災保険率の改正
H30.5.13 労災保険率の改定のルールをチェック
 5月。風が心地よいですね。
5月。風が心地よいですね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「徴収法」です。
選択式で徴収法は出題されませんが、穴埋め方式で要点をcheckしましょう。
平成30年4月1日より、労災保険率が改定されています。
労災保険率の改定のルールを確認しておきましょう。
条文の空欄を埋めてください。
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び< A >に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去< B >の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに< C >に要した費用の額、< A >として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【解答】
A 社会復帰促進等事業 B 3年間 C 二次健康診断等給付
※ 労災保険率は、3年ごとに改定されます。
ついでにこちらもチェック
労災保険率は、最高1000分の< D >、最低1000分の< E >

【解答】 D 88 E 2.5
※ 1000分の88が適用される事業の種類は、「金属鉱業、非金属鉱業(石炭石鉱業又はドロマイド鉱業を除く)又は石炭鉱業」
社労士受験のあれこれ
暫定任意適用事業(労災)
H30.3.26 H29年問題より「労災・暫定任意適用事業について」
H29年本試験【労災保険法問9C】を解いてみてください。
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならず、この申請をしないときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

【解答】 × 罰則規定はありません。
★ 労災保険、雇用保険ともに、労働者が一人でも雇えば、強行的に保険関係が成立するのが原則です。
ただし、農林水産業の一部は、保険の適用は任意となります(暫定任意適用事業)。事業主の任意加入の申請+厚生労働大臣の認可で、保険関係が成立します。
★ 労働者から加入の希望があった場合
労災保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の過半数が希望するとき」、雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望するとき」は、事業主に任意加入の申請をする義務が生じます。
★ 希望があった。でも任意加入の申請をしなかった場合
雇用保険暫定任意適用事業の場合は「労働者の2分の1以上が希望」したにもかかわらず、任意加入の申請をしなかった事業主に対しては、罰則が設けられています。(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
「労働者の過半数が希望」したにもかかわらず、労災保険の任意加入の申請をしなかった場合についての罰則規定は設けられていません。
社労士受験のあれこれ
延納の条件
H30.2.22 H29年問題より「延納の条件」
H29年本試験【徴収法(労災)問10オ】を解いてみてください。
労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。

【解答】 ×
★ 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合は、概算保険料の額に関係なく延納できます。
<継続事業(一括有期事業含む)の延納の条件>
概算保険料の額が40万円以上 (労災保険又は雇用保険どちらかのみ成立している事業は20万円以上) | 又は | 労働保険事務の処理を労働保険事組合に委託していること |
| 当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものでないこと | ||
| 事業主が延納の申請をしたこと | ||
社労士受験のあれこれ
労働保険料の額
H30.1.29 H29年問題より「労働保険料の額の出し方」
H29年本試験【雇用保険法問8エ】を解いてみてください。
有期事業(一括有期事業を除く。)について、事業主が確定保険料として申告すべき労働保険料の額は、特別加入者がいない事業においては一般保険料の額となり、特別加入者がいる事業においては第1種又は第3種特別加入者がいることから、これらの者に係る特別加入保険料の額を一般保険料の額に加算した額とする。

【解答】 ×
★ 「第3種特別加入者がいる」の部分が誤りです。
★ 第3種特別加入者とは、「海外派遣者の特別加入」のことです。
国内の有期事業からは海外派遣者の特別加入はできませんので、国内の有期事業に海外派遣者がいることはあり得ません。
この問題は有期事業についてのものですので、「第3種特別加入者に係る特別加入保険料が加算される」の部分が×です。
社労士受験のあれこれ
労働保険事務組合
H30.1.10 H29年問題より「労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した場合」
H29年本試験【雇用保険法問10E】を解いてみてください。
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

【解答】 ×
★ 労働保険事務組合は、労働保険料の申告や納付等の事務を、委託事業主に代って処理します。
ですので、労働保険事務組合は、労働保険料等の納付のため委託事業主から預かった金銭を、その金額の限度で、労働保険事務組合の責任で政府に納付します。
また、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由で、追徴金や延滞金が徴収される場合、労働保険事務組合は、その限度で、政府に対して納付の責めを負います。
★ とはいっても、問題文にあるように、委託事業主が労働保険事務組合に金銭を交付したら「滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該委託事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。」ということはありません。
徴収法第35条3項では、「労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる」と規定されています。
社労士受験のあれこれ
基本の問題その4(徴収法)
H29.12.20 H29年問題より「基本」を知ろう・徴収法
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
継続事業(一括有期事業)の延納の要件
10月1日以降に保険関係が成立した場合は、その年度は延納できない
★ 概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方だけ成立している場合は20万円以上)または、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合(この場合は、概算保険料の額は問いません)は、申請することによって、概算保険料を延納(分割納付)することができます。
ただし、10月1日以降に保険関係が成立した場合は、その年度は延納できません。
では、平成29年【労災問10】ウを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【労災問10】ウ)
継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

<解答> ○
10月1日に成立した場合は延納できませんので一括納付となります。保険年度の中途に保険関係が成立した場合の概算保険料の申告・納付期限は、保険関係が成立した日(翌日起算)から50日以内です。この問題の場合、平成29年10月2日から50日以内の平成29年11月20日が期限となります。
社労士受験のあれこれ
定番問題その15(徴収法)
H29.11.28 H29年問題より「定番」を知る・徴収法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (退職金の扱い)
「退職金」賃金総額に算入する・しない?
★ 退職時に支払われる「退職金」や会社の都合で退職前に一時金で支払われる「退職金」は、一般保険料を計算する際の賃金総額には算入しません。(労働保険料はかからない)
★ ただし、在職中に、月々の給料や賞与に上乗せして前払いされる退職金(前払い退職金といわれるもの)については、一般保険料を計算する際の賃金総額に算入されます。
これを覚えると、平成29年【労災問8】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【労災問8】A)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入される。

<解答> 〇
★ 前払い退職金は、保険料の計算に算入されます。
社労士受験のあれこれ
定番問題その5(徴収法)
H29.11.1 H29年問題より「定番」を知る・徴収法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (延納の場合の端数処理)
分割したときの1円未満の端数は、第1期分に加算する
★ 概算保険料を延納する場合、余り(1円未満の端数が.3333…の場合は1円、.66666…の場合は2円)が出ることがあります。その場合の余りは第1期分に加算します。
★ 例えば、概算保険料が80万円で3期に分けて納付する場合
800,000円÷3=266,666.6666円となり、2円余ります。
その場合の各期の納付額は、
第1期分 266,668円 →(余りの2円は第1期分に加算する)
第2期分 266,666円
第3期分 266,666円
となります。
これを覚えると、平成29年【労災問10】アが解けます。
★問題です。
(平成29年【労災問10】ア)
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

<解答> ×
170,000円÷3=56,666.666…ですので、2円余ります。
余った2円は1期に加算します。第1期56,668円、第2期と第3期は各56,666円となります。
社労士受験のあれこれ
覚えれば解ける問題その5(徴収法)
H29.10.16 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・徴収法
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (事業廃止のときの手続き)
「保険関係成立届」はあるが、「保険関係廃止届」はありません。
★ <保険関係が成立したときの手続き>
事業主は、成立した日から10日以内(翌日起算)に、「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
★ <保険関係が消滅したときの手続き>
事業主は、労働保険料の「確定額」を申告し精算します。
ポイント 事業の廃止の際の「保険関係廃止届」というものが社労士試験に出題されたことがありますが、そういった届出は存在しません。
これを覚えると、平成29年【労災問9】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【労災問9】A)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る保険関係が消滅する。

<解答> ×
保険関係は、事業が廃止された日の翌日に法律上当然に消滅します。
保険関係廃止届の受理によって消滅するものではありませんし、そもそも保険関係廃止届なるものも実在しません。
社労士受験のあれこれ
まずは原則!その5(徴収法)
H29.9.29 H29年問題より原則を学ぶ・徴収法
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(徴収法)
督促状の指定期限までに完納すれば延滞金は徴収されない
◆ 事業主が、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を、法定納期限までに納付しない場合、政府は、期限を指定して督促しなければなりません。
◆ 督促は、督促状を発することによって行いますが、督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない、とされています。
◆ 督促状が発せられた場合でも、「督促状に指定された期限」までに、徴収金を完納した場合は、延滞金は徴収されません。
(督促状に指定された期限までに納付しない場合は、延滞金が徴収されます。)
この原則で、平成29年【雇用問9】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【雇用問9】A)
事業主が労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を法定納期限までに納付せず督促状が発せられた場合でも、当該事業主が督促状に指定された期限までに当該徴収金を完納したときは、延滞金は徴収されない。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
労働保険料について
H29.6.8 徴収法「労働保険料」
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」を総称したものです。
労災保険も雇用保険も「保険」ですので、「保険料」を納付しなければなりません。
 労働保険のための保険料を「労働保険料」といいます。本日は労働保険料の勉強です。
労働保険のための保険料を「労働保険料」といいます。本日は労働保険料の勉強です。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第10条 労働保険料)
1 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2 1項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
① 一般保険料
② 第一種特別加入保険料
③ 第二種特別加入保険料
④ 第三種特別加入保険料
⑤ < A >
⑥ < B >

(解答) A 印紙保険料 B 特例納付保険料
★ 労働保険料は6種類ありますので、覚えましょう。
→ 「印紙保険料」とは、雇用保険の日雇労働被保険者にかかるもので、1級(176円)、2級(146円)、3級(96円)の3種類があります。
日雇労働被保険者の場合、「一般保険料」にプラスして「印紙保険料」がかかります。
→ 「特例納付保険料」は、雇用保険に2年を超えて遡及加入した被保険者にかかる保険料です。(一定の要件がありますが、ここでは割愛します。)
 では、過去問です。
では、過去問です。
<H20年出題>
労働保険徴収法第10条によれば、政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収するとされ、当該保険料とは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料である。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
H29年度の雇用保険率
H29.4.5 平成29年度の雇用保険率は引き下げ
雇用保険率は、「一般の事業」、「農林水産・清酒製造の事業」、「建設の事業」と、事業の種類によって3パターン設定されています。
平成29年度の雇用保険率は昨年度より引き下げられていて、4月1日から適用されています。
 試験対策として、まずは「一般の事業」の平成29年度の雇用保険率を押さえましょう。「一般の事業」の平成29年度の雇用保険率は、「1000分の9」となりました。(*平成28年度は1000分の11でした)
試験対策として、まずは「一般の事業」の平成29年度の雇用保険率を押さえましょう。「一般の事業」の平成29年度の雇用保険率は、「1000分の9」となりました。(*平成28年度は1000分の11でした)
★ 雇用保険率の「1000分の9」は、①「雇用保険二事業以外(失業等給付)」に係る部分と②「雇用保険二事業」に係る部分に分けられます。
平成29年度は、①は1,000分の6、②は1,000分の3となります。(ちなみに引き下げられたのは①の部分で、②の部分は昨年度と同じ率です。)
 労働者と事業主の負担についても押さえましょう。
労働者と事業主の負担についても押さえましょう。
①の部分は労働者と事業主が折半で負担し、②の部分は事業主が全額負担します。
負担割合は↓の表のようになります。
雇用保険率
| 事業主負担 | 労働者負担 |
1000分の9 (内1000分の3が二事業分) | 1000分の6 | 1000分の3 |
 ついでに、「就職支援法事業」に要する費用はどちらに入るのかも確認しておきましょう。
ついでに、「就職支援法事業」に要する費用はどちらに入るのかも確認しておきましょう。
①の部分は失業等給付の費用に充てる部分ですが、「就職支援法事業」の費用も①に含まれます。②の部分は雇用保険二事業(雇用安定事業と能力開発事業)の費用に充てる部分ですが「就職支援法事業」は除かれます。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.22 必ず出る改正点(徴収法編)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度徴収法(労災)問9のアです。不服申し立てからの問題です。
<問題文>
平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服のある事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。

【答え】 ×
★ 平成28年4月の行政不服審査法の改正で異議申立ては廃止されました。
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に関する処分について不服がある者は、行政不服審査法の規定によって、厚生労働大臣に審査請求することができます。
(厚生労働大臣に審査請求をせずに、直ちに処分取消しの訴えを提起することもできます。)
社労士受験のあれこれ
ひっかけ問題(引っかかってはいけない)
H28.10.6 シリーズひっかけ(徴収・保険関係成立届)
次の問題を解いてみてください。
<平成25年出題>
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

<解答> ×
労働保険の保険関係は、「保険関係成立届」を提出することにより成立するのではありません。
事業が開始された日(労働者を使用(雇用)するようになった日)に、自動的に保険関係が成立します。
★ 例えば、平成28年10月6日に、初めて労働者を雇い入れた場合、保険関係成立届を提出した、しないに関係なく、平成28年10月6日に、当然に労働保険の保険関係が成立します。(保険関係が成立するということは、保険料を納付する義務、保険給付を請求する権利が発生するということです。)
しかし、日本全国いつどこで保険関係が成立しているのか、政府は把握できません。事業主からの「保険関係成立届」の提出によって把握できると考えてください。
社労士受験のあれこれ
労働保険事務組合のよく出るところ
H28.7.28 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(労働保険事務組合)
労働者を一人でも雇うと、原則として労災保険・雇用保険は強制加入となり、毎年度労働保険料の申告・納付の手続きが必要となります。
ただ、人手のない中小零細企業の場合は、毎年度の申告・納付を自身で行うのはかなりの重荷です。
労働保険事務組合とは、中小事業主から委託を受けて、労働保険事務の処理をすることができる団体のことです。
【問題①】労働保険事務組合とは?
<H19年(雇)出題>
厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合となった団体は、労働保険事務を専業で行わなければならない。
【問題②】労働保険事務組合に事務委託できる事業主の範囲
空欄を埋めてください。
| 金融業、< A >、< B >、小売業 | 常時< D >人以下 |
| 卸売業、< C > | 常時< E >人以下 |
| 上記以外 | 常時300人以下 |
【問題③】労働保険事務組合に委託するメリットは?
<H13年(雇)出題>
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。
<H15年(雇)出題>
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。
<H17年(雇)出題>
有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を労働保険事務組合(以下「事務組合」という。)に委託している事業主であっても、納付期限は事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。
【問題④】委託できないもの
<H23年(雇)出題>
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事
務
【問題⑤】よく出る「期限」
NO1 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、解除があった日の翌日から起算して14日以内に、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
NO2 労働保険事務組合は、労働保険事務組合認可申請書に添付された定款の記載に変更を生じた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない。
NO3 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、30日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
【問題⑥】労働保険事務組合の役割等(政府と中小事業との橋渡し役のイメージ)
<H18年(雇)出題>
政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が委託事業主に及ばないことがある。

◆◆解答◆◆
【問題①】労働保険事務組合とは?
<H19年(雇)出題> ×
労働保険事務組合は、既に事業の実績のある団体が、厚生労働大臣の認可を受けることによって、事業の一環で労働保険事務の処理ができるというものです。専業で行わなければならないという規定はありません。
【問題②】
| 金融業、<A保険業>、<B不動産業>、小売業 | 常時<D50>人以下 |
| 卸売業、<Cサービス業> | 常時<E100>人以下 |
| 上記以外 | 常時300人以下 |
労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲はよく出ます。こればかりは覚えておかないと解けないので、しっかり覚えておきましょう。
【問題③】労働保険事務組合に委託するメリットは?
<H13年(雇)出題> ○
概算保険料の額の如何にかかわらず延納できることは、労働保険事務組合に委託するメリットです。
<H15年(雇)出題> ×
納期限が14日延長されることも労働保険事務組合に委託するメリットで、2期目(納期限10月31日)と3期目(納期限1月31日)は、それぞれ11月14日、2月14日となります。ただし、1期目の納期限は延長されません。
<H17年(雇)出題> ○
有期事業の場合は、労働保険事務組合に委託していても納期限は延長されません。
ここもポイント!
中小事業主等は、労働保険事務組合に委託することによって、労災保険に特別加入することができます。
【問題④】委託できないもの
<H23年(雇)出題> B
印紙保険料に関する事務や労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、委託できません。
【問題⑤】よく出る「期限」
NO1 ×
労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託があったときや委託解除があったときの届出は「遅滞なく」です。
NO2 ×
定款の記載に変更を生じた場合の届出は、変更があった日の翌日から「14日以内」です。
★ちなみに、
労働保険事務組合認可申請書には、①定款、規約等、②労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類、③最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類を添付することになっています。
ただし、③最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類については、変更があっても届出はいりません。
NO3 ×
業務を廃止しようとするときは「60日前まで」です。
【問題⑥】労働保険事務組合の役割等(政府と中小事業との橋渡し役のイメージ)
<H18年(雇)出題> ×
「政府が労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知等は、事業主に対してしたこととみなす」とされているので、委託契約の内容に関係なく告知等の効果は委託事業主に及びます。
社労士受験のあれこれ
一括有期事業開始届と一括有期事業報告書(徴収法)
H28.6.16 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(徴収法・一括有期事業)
「一括有期事業」とは、規模の小さい有期事業の労働保険料の納付・申告をまとめて継続事業と同様に保険年度ごとに行う仕組みです。
<手続き>
■ 有期事業の一括が始まるとき ■
「保険関係成立届」(成立した日(翌日起算)から10日以内)と「概算保険料申告書」を提出します。
■ 毎月の手続き ■
どこでどのような有期事業が行われているかを行政が把握する必要があるので、一括有期事業の対象になる有期事業が開始されたら、毎月、「一括有期事業開始届」を提出することになっています。(その月に始まった有期事業を翌月10日までに届け出ます。
■ 確定精算のとき(年度更新・一括有期事業の終了で保険関係が消滅するとき)
前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業を報告するため、「一括有期事業報告書」を提出することになっています。期限は「確定保険料申告書」と同じで、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内、又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内です。
★★「一括有期事業開始届」と「一括有期事業報告書」。名称が似ているので間違えないでくださいね。
では、過去問を解いてみましょう。
①H17年出題
一括される有期事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日から10日以内に、一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②H23年出題
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①H17年出題 ×
10日以内ではなく「開始の日の属する月の翌月10日まで」です。一括有期事業開始届はよく出題されていますが、すべて「期限」を問う問題でした。覚えてしまいましょう。
②H23年出題 ○
「確定保険料申告書」と一緒に提出するので、期限・提出先は「確定保険料申告書」と同じです。
社労士受験のあれこれ
書類の保存期間 2年3年4年5年
H28.6.10 金曜日は横断 書類の保存期間
書類の保存期間は2年、3年、4年、5年、それ以外と各法律さまざまです。
でも、覚えておけば得点できます。どんどん覚えましょう。
では、過去問をどうぞ。
① 労働基準法(H22年出題)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
② 労働安全衛生法(H22年出題)
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
③ 労働安全衛生法(H19年出題)
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。
④ 労働安全衛生法(H21年出題)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
⑤ 労災保険法
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管しなければならない。
⑦ 徴収法(H19年出題)
事業主もしくは事業主であった者又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。
⑧ 徴収法(H22年出題)
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は4年である。
⑨ 健康保険法(H22年出題)
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題)
事業主は、厚生年金保険法に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

【解答】
① 労働基準法(H22年出題) ○
ポイント
・ その他労働関係に関する重要な書類 → タイムカード等の記録、残業命令書等が該当する
・ 企画業務型裁量労働制の実施状況にかかる労働者ごとの記録 → 決議の有効期間中+その満了後3年間)
② 労働安全衛生法(H22年出題) ○
・ 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育のうち、保存義務があるのは特別教育のみ。
・ 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議事で重要なものに係る記録も保存期間は3年
③ 労働安全衛生法(H19年出題) ○
④ 労働安全衛生法(H21年出題) ○
・ 保存期間が5年のもの → 健康診断個人票、面接指導の結果の記録(長時間労働、ストレスチェック)
⑤ 労災保険法 ×
2年間ではなく、3年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題) ○
・ 雇用保険に関する書類(雇用保険二事業及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。) → 2年間
・ 被保険者に関する書類 → 4年間
⑦ 徴収法(H19年出題) ×
⑧ 徴収法(H22年出題) ○
・ 労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類 →その完結の日から3年間
・ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 → 4年間
ポイント
・ 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿もおさえておきましょう。
① 労働保険事務等処理委託事業主名簿
② 労働保険料等徴収及び納付簿
③ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
①と②は3年間、③は4年間保存
⑨ 健康保険法(H22年出題) ×
5年間ではなく「2年間」保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題) ×
厚生年金保険法に関する書類 → その完結の日から2年間保存
健康保険法と同じなのでおぼえやすいです。
徴収法 現物給与の範囲と評価
H28.4.30 賃金には、現物給与も含まれる
労働保険徴収法でいう「賃金」には、「通貨以外のもの」で支払われるもの(現物給与)も含まれます。
さっそくですが「通貨以外のもの」で支払われる賃金の範囲について、次の問題を解いてみてください。
H19年出題
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。

【解答】 ○
「現物給与の範囲」についての問題です。
食事、被服、住居の利益は当然に賃金の範囲に入りますが、それ以外に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも現物給与の範囲に含まれるということです。
ここもポイント!
「現物給与の評価」についてもおさえておきましょう。
「賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。」
「現物給与の範囲」 → 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
「現物給与の評価」 → 厚生労働大臣
社労士受験のあれこれはこちら
雇用保険料率
H28.4.4 H28年度の雇用保険料率
平成28年4月より雇用保険料率は以下のように引き下げられます。
| 雇用保険料率 | 労働者負担 | 事業主負担 | |||
| 一般の事業 | 1000分の11 | 1000分の4 | 1000分の7 (雇用保険二事業分) 1000分の3 | ||
農林水産 清酒製造の事業 | 1000分の13 | 1000分の5 | 1000分の8 (雇用保険二事業分) 1000分の3 | ||
| 建設の事業 | 1000分の14 | 1000分の5 | 1000分の9 (雇用保険二事業分) 1000分の4 | ||
<ポイント>
一般の事業の場合、雇用保険料率は1000分の11です。
1000分の11のうち、「1000分の3」は雇用保険二事業の保険料率で、事業主が負担します。残りの1000分の8を、労働者と事業主で1000分の4ずつ負担します。
雇用保険料率(1000分の11)を労使で折半するのではありません。雇用保険料率のうち二事業分は全額事業主負担です。
労災保険率 ~徴収法~
H28.3.31 労災保険率の決定方法
労災保険率の決定のルールです。空欄を埋めてください。
労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び A に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 B 年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに C に要した費用の額、 A として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して D が定める。

【解答】
A 社会復帰促進等事業 B 3 C 二次健康診断等給付 D 厚生労働大臣
労災保険率は過去3年間の災害率などを考慮して、3年ごとに見直されています。
問題を解くポイントは、労災保険の事業の枠組みをしっかり把握しておくことです。
労災保険は、「保険給付」と「社会復帰促進等事業」の二つの事業を行っています。メインの事業は「保険給付」です。
そして、「保険給付」としては、1業務災害に関する保険給付、2通勤災害に関する保険給付、3二次健康診断等給付の3つがあります。
| 労災保険 | 保険給付(メイン)・・・1 業務災害に関する保険給付 2 通勤災害に関する保険給付 3 二次健康診断等給付 |
社会復帰促進等事業・・・1 社会復帰促進事業 2 被災労働者等援護事業 3 安全衛生確保等事業 |
平成24年には次のような問題が出題されています。
労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。
先ほどの空欄部分の用語をチェックしながら解いてください。
答は「○正しい」です。
当日?翌日? ~労働保険徴収法~
H28.3.7 保険関係の成立と消滅(強制適用事業)
<強制適用事業の保険関係の成立>
第3条・第4条
労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。
雇用保険法第五条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
ポイント!
労災保険も雇用保険も労働者を一人でも使用(雇用)すれば、原則として自動的に保険関係が成立します。
例えば、3月7日に初めて労働者を一人雇った場合、初日に業務上のケガをするかもしれませんよね。保険関係は、労働者を初めて使用(雇用)した「当日」に成立します。ですので、その日から保険給付を受けることができます。(保険料も当然その日から計算されます。)
<強制適用事業の保険関係の消滅>
第5条
保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。
ポイント!
保険関係は、廃止(継続事業)又は終了(有期事業)の「翌日」に消滅します。例えば、廃止又は終了の日(最終日)はまだ業務をしていて、その日いっぱいは保険関係が存在している。なので消滅は「翌日」と考えればしっくりきます。

★★出題ポイント★★
保険関係が成立した場合は、「保険関係成立届」を提出する義務がありますが、「保険関係消滅届」なるものはありません。
消滅の場合は、「確定保険料申告書」を提出し、消滅した日までの労働保険料を精算しなければなりません。「保険関係消滅届」を提出するとひっかける問題が、何度も出題されていますので注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ 過去記事はこちらから
H28.1.27 賃金・報酬、賞与
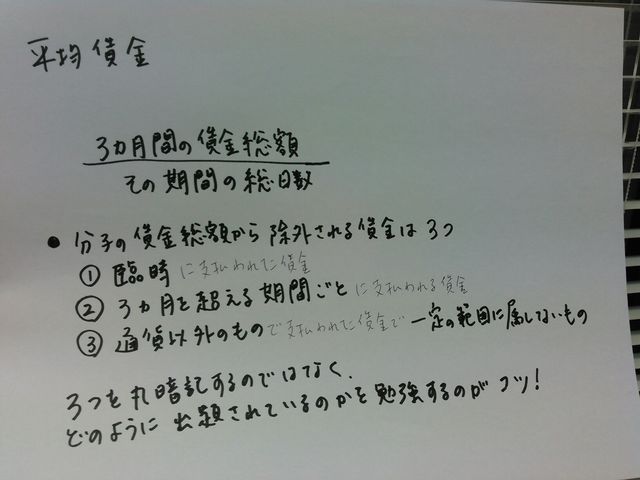
■労働の対償→賃金・報酬、賞与
「労働の対償として受けるもの」は一般的に言うと給料ですが、受験勉強では、まず法律ごとの呼び方を押さえることから始めます。
・労働基準法、雇用保険法、労働保険徴収法では、「賃金」といいます。
*例えば、雇用保険法の基本手当の日額や、徴収法の労働保険料は「賃金」を基に計算します。
・健康保険法、厚生年金保険法では、「報酬、賞与」といいます。
*例えば、厚生年金保険法では会社員として支払う厚生年金保険料や将来受けとる年金額は、「報酬、賞与」を基に計算します。
■ポイント
・「賃金」、「報酬、賞与」は「労働の対償」として支払われるもの
・しかし、保険料や給付額の計算に賃金の全てを算入するわけではない
*例えば、労働基準法の平均賃金は賃金をもとに計算しますが、賃金を全て算入するのではなく、夏・冬のボーナスなど平均賃金の計算から除外される賃金があります。
どの科目でも現物給与、臨時に支払われるものの扱いなどは頻出事項です。過去問で練習して慣れていきましょう。
H28.1.13 年齢
60歳、65歳、70歳、75歳。法律によって年齢の基準が違うので頭の中がごちゃごちゃしませんか?
次の空欄を埋めて整理してみてください。
■雇用保険法
<高年齢継続被保険者>
同一の事業主の適用事業に ① 歳に達した日の前日から引き続いて ② 歳に達した日以後の日において雇用されているもの
■徴収法
<雇用保険料の免除の対象になる高年齢労働者>
保険年度の初日に ③ 歳以上の労働者
■健康保険法
<一部負担金>
1 ④ 歳に達する日の属する月以前 → 100分の30
2 ⑤ 歳に達する日の属する月の翌月以後 (3の場合を除く。)
→100分の20
3 ⑥ 歳に達する日の属する月の翌月以後の一定以上所得者
→ 100分の30
■厚生年金保険法
<被保険者>
適用事業所に使用される ⑦ 歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
■高齢者の医療の確保に関する法律
<後期高齢者医療の被保険者>
1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑧ 歳以上の者
2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑨ 歳以上 ⑩ 歳未満の者で、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
■介護保険法
<介護保険の被保険者>
・第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑪ 歳以上の者
・第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑫ 歳以上 ⑬ 歳未満の医療保険加入者
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解答】
①65 ②65 ③64 ④70 ⑤70 ⑥70 ⑦70 ⑧75 ⑨65 ⑩75 ⑪65 ⑫40 ⑬65