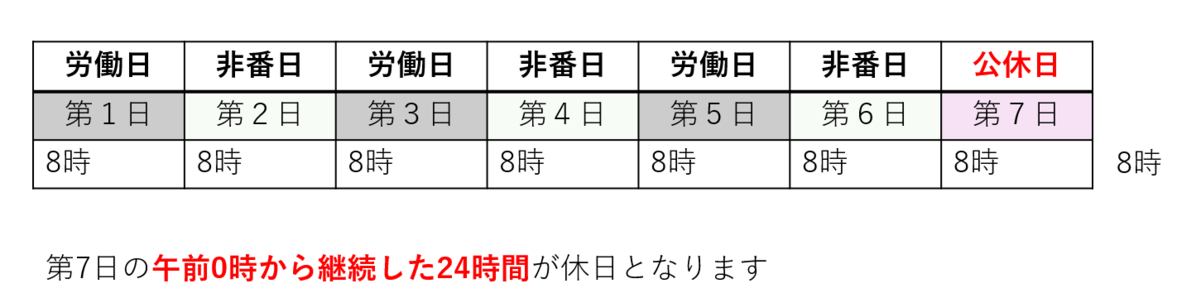合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
労働基準法「割増賃金」
R8-139 01.10
時間外・休日・深夜の割増賃金の率
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
条文を読んでみましょう
法第37条第1項(時間外、休日割増賃金) ① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
法第37条第4項 (深夜割増賃金) ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
割増賃金の率を確認しましょう
時間外労働 | 法定労働時間を超えた場合 | 25%以上 |
1か月60時間を超えた場合 | 50%以上 | |
休日労働 | 法定休日に労働させた場合 | 35%以上 |
深夜労働 | 深夜の時間帯に労働させた場合 | 25%以上 |
※時間外労働と深夜労働が重なった場合 → 25%+25%=50%以上
※休日労働と深夜労働が重なった場合 → 35%+25%=60%以上
過去問で確認しましょう
【H25年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
<選択肢>
④ 午後10時から午前5時まで ⑤ 午後10時から午前6時まで
⑥ 午後11時から午前5時まで ⑦ 午後11時から午前6時まで
⑧ 時間帯 ⑬ 長さ ⑭ 密度 ⑳ 割増

【解答】
<A> ⑬ 長さ
<B> ④ 午後10時から午前5時まで
(平21.12.18最高裁判所第二小法廷 ことぶき事件)
ポイント!
・労基法の労働時間に関する規定の多くは、その長さに関する規制について定めている
・第37条4項は、使用者が原則として午後10時から午前5時までの間において労働させた場合に、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定している。
労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にする
なお、結論は、次の通りです。
・労基法41条2号の規定によって同法37条4項の適用が除外されることはない
・管理監督者に該当する労働者は深夜割増賃金を請求することができる
②【H29年出題】
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、時間外労働の割増率を合算する必要はありません。
(H11.3.31基発168号)
なお、休日労働が深夜に及んだ場合は、休日労働と深夜労働の割増率を合算した 「6割以上」となります。
(H6.1.4基発1号)
➂【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する問題です。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題A)
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】
(問題A) ×
日曜に10時間の労働があったとしても、8時間を超えた2時間は時間外労働にはなりません。
割増賃金は、深夜の時間帯でなければ、「休日労働に対する割増率」のみで計算します。
(問題B)
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】
(問題B) ×
休日は、「暦日」で考えます。
休日労働となるのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までです。
法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合、3割5分以上で計算しなければならないのは、法定休日(問題文の場合は日曜)の午前0時から午後12時までの間に労働した部分です。
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働になるのは、日曜の午後8時から午後12時までです。
(H6.5.31基発331号)
(問題D)
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】
(問題D) ×
「法定休日の午前0時から午後12時まで」は休日割増賃金の対象になります。
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んでも、日曜の午前0時から午前3時までは、「休日割増」となり、土曜の勤務の時間外労働時間として計算されるのは、土曜の午後12時までです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「休日」
R8-138 01.09
休日の基本をお話しします
労働義務のある日を「労働日」、労働義務のない日を「休日」といいます。
労働基準法では、原則として、毎週少なくとも1回の休日を与えることが義務付けられています。
では、休日について条文を読んでみましょう
法第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
第35条で規定されている休日を「法定休日」といいます。
法定休日について
原則 | 毎週少くとも1回 |
例外 | 4週間を通じ4日以上 |
図でイメージしましょう
「休日」の過去問を解いてみましょう
<4週を通じ4日以上の休日>
【H23年出題】
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

【解答】
【H23年出題】 〇
毎週少なくとも1回の休日を与えることが原則ですが、例外で、4週間を通じ4日以上の休日を与えることもできます。その場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにすることが必要です。
(則第12条の2第2項)
【H13年出題】
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】
【H13年出題】 ×
「年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。」は誤りです。
特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。
(昭23.9.20基発1384号)
<休日は暦日が原則>
【H29年出題】
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】
【H29年出題】 ×
単に24時間継続して労働義務から解放しても休日になりません。
休日は、「暦日」を意味しますので、午前0時から午後12時までの単位となります。
(昭23.4.5基発535号)
<一昼夜交替勤務の休日>
【H24年出題】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
【H24年出題】 〇
問題文のような一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間は、労働義務がないとしても、休日となりません。
(昭23.11.9基収2968号)
図でイメージしましょう
<8時間3交替制勤務の休日>
【H21年出題】
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【解答】
【H21年出題】 ×
問題文のような条件を満たす番方編成による交替制の「休日」については、暦日ではない「継続24時間」の休息を与えれば差し支えないとされています。
(昭63.3.14基発150号)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
休日の与え方<原則>
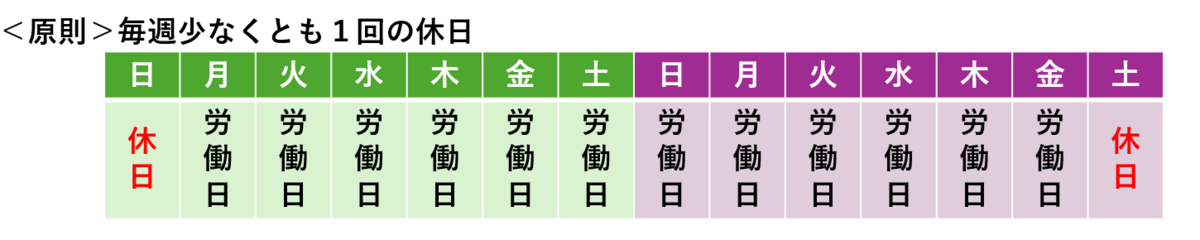
休日の与え方<例外・変形休日制>
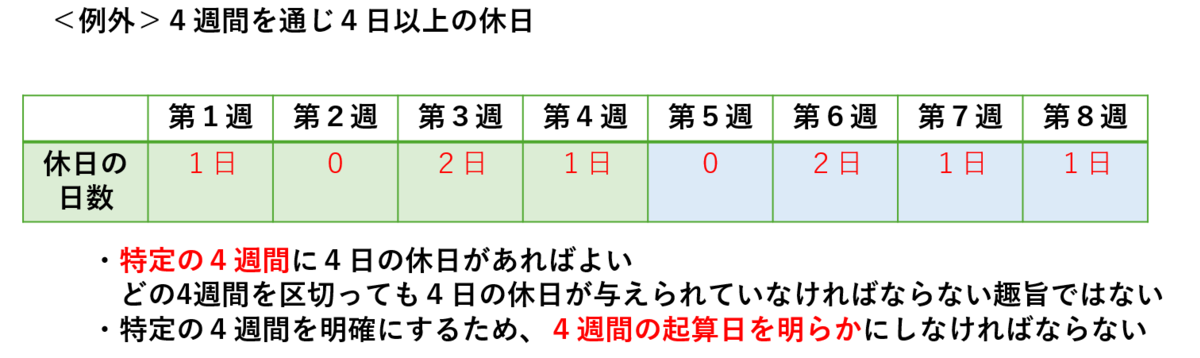
労働基準法「時間外労働」
R8-137 01.08
36協定・割増賃金が必要な「時間外労働」を整理する
◇ 労働基準法では、労働時間の上限が定められています。(法定労働時間といいます)
法定労働時間は、原則1週40時間・1日8時間で、使用者は、法定労働時間を超えて労働させることはできません。
◇ ただし、「36協定」を締結し、それを所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、適法に、時間外労働をさせることができます。
なお、時間外労働させた時間については、割増賃金の支払が義務付けられています。
◇ ちなみに、ここでいう「時間外労働」とは、「法定労働時間を超える時間」のことです。
例えば、9時始業~17時終業(休憩1時間)の労働者に、18時まで残業させる場合は三六協定も割増賃金も不要です。
所定労働時間が7時間ですので、1時間延長しても、トータルの労働時間は8時間だからです。
問題を解きながら「時間外労働」を確認しましょう
<法定労働時間を超えない残業>
【H29年出題】
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

【解答】
【H29年出題】 〇
労働基準法第32条で定められている労働時間は、「実労働時間」をいいます。
遅刻をした時間分だけ終業時刻を繰り下げて労働させても、1日の実労働時間を通算して8時間を超えないときは、時間外労働に従事させたことにはなりません。36協定がない場合でも、労働基準法第32条には違反しません。
(平11.3.31基発168号)
【R4年出題】
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、労働基準法第36条第1項の協定をする必要はない。

【解答】
【R4年出題】 〇
所定労働時間が1日7時間、1週35時間の場合で、1週35時間を超えて労働時間を延長しても、1週間の実労働時間が法定労働時間以内で、各日の労働時間が8時間以内かつ休日労働を行わせない限り、36協定を締結する必要はありません。
(平11.3.31基発168号)
<労働者が時間外労働を行う義務>
【H27年出題】
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H27年出題】 ×
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容となるため、労働者は、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うとされています。
(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)
なお、「36協定」を締結し届け出た場合、使用者は適法に時間外労働をさせることができるようになります。(免罰効果が生じます。)
しかし、問題文にあるように、36協定には、私法上の権利義務を設定する効果は有りません。「労働者の民事上の義務は、36協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものである。」とされています。
<違法な時間外労働>
【R2年出題】
労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R2年出題】 〇
36協定を締結していないなど違法な時間外労働・休日労働に対しても、使用者には割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは罰則の適用は免れません。
「適法な時間外労働等について割増賃金支払義務があるならば、違法な時間外労働等の場合には一層強い理由でその支払義務あるものと解すべきは事理の当然とすべきである」とされています。
(昭35.7.14最高裁判所第一小法廷 小島撚糸事件)
<時間外労働が翌日に及んだ場合>
【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題です。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間
<問題>
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】 〇
「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。
ただし、継続勤務が2暦日にわたる場合は、暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、始業時刻の属する日である月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。
図でイメージしましょう。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
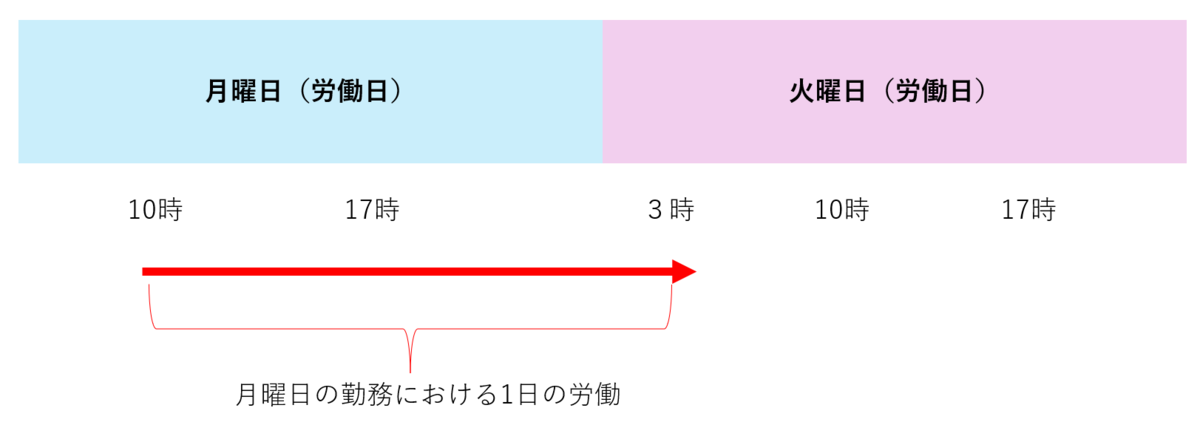
YouTubeはこちらからどうぞ!
労働基準法「労使協定」
R8-136 01.07
36協定のポイント!
★労使協定とは
使用者と
◇「事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合」
◇労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は
「労働者の過半数を代表する者」
との書面による協定のことです。
労働基準法の労働時間の上限は、原則として1週40時間、1日8時間です。
その時間を超えて労働させることは労働基準法に反しますが、「労使協定」を締結し、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、免罰効果が生じ、労働時間を延長させることができます。
条文を読んでみましょう
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
「36協定」とは、法第36条に規定されている労使協定のことです。
過去問でポイントを確認しましょう
<36協定の免罰効力が生ずる要件>
【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】
【H24年出題】 〇
36協定のポイント!
・36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になる(免罰効果が生じる)
・法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない
【R3年出題】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】
【R3年出題】 〇
36協定を締結したのみでは、免罰効果は生じません。所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になります。
有効期間が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの労使協定を締結し、これを令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合、届出日の令和3年4月9日以降は、適法に時間外労働を行わせることができます。
しかし、届出前の令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、労働基準法違反の責は免れません。
<時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務>
【H24年出題】
労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

【解答】
【H24年出題】 〇
「労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであり、労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要なものであること。」とされています。
労働者が、時間外又は休日労働命令に服すべき義務は、36協定から直接当然に生ずるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。
【H20年選択式】
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。

【解答】
【H20年選択式】
<A> 合理的な
・使用者が、三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た
(使用者は適法に時間外労働をさせることができる=免罰効果が生じる)
↓
・使用者が就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めている
↓
就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなす
↓
就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う
(平3.11.28最高裁判所第一小法廷 日立製作所武蔵工場事件)
<労使協定の効力の範囲>
【H25年出題】
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

【解答】
【H25年出題】 〇
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合と使用者が36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、協定の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及びます。
(昭23.4.5基発535号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働時間」
R8-135 01.06
労働時間の基本をお話しします
「労働時間」とは、労働者が使用者の「指揮命令下」に置かれている時間のことをいいます。
「休憩時間」は、労働から解放される時間ですので、労働時間ではありません。
例えば、始業9時、終業18時、休憩12時~13時の場合の労働時間は次のようになります。
・拘束時間 → 9時間(9時~18時)
・休憩時間 → 1時間(12時~13時)
・労働時間 → 9時間-1時間=8時間
労働基準法では、労働時間の上限が定められています。
条文を読んでみましょう
法第32条(労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
<原則> 労働時間の上限は、1週40時間・1日8時間です。
<特例> 商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)、保健衛生業、接客娯楽業の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。
★労働基準法で定められた労働時間の上限を「法定労働時間」といいます。
★残業させる場合(法定労働時間を超える場合)の手続
使用者が、36協定(過半数労働組合又は過半数代表者との協定)を締結し、労働基準監督署長に届け出た場合 → 使用者は適法に時間外労働又は休日労働をさせることができます。
★割増賃金について
時間外、休日、深夜に労働させた場合は、使用者は、割増賃金を支払わなければなりません。
過去問を解きながら「労働時間」の考え方をみていきましょう
<特例事業場の労働時間>
【R4年出題】
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。

【解答】
【R4年出題】 ×
特例事業場については、1週間について48時間ではなく、44時間まで労働させることができます。また、1日についての上限は、原則と同じ「8時間」です。
★特例事業場も確認しましょう(赤字は略称です)
別表第1
・第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業) (商業)
・第10号(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)※映画の製作の事業を除く
(映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。))
・第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業) (保健衛生業)
・第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業) (接客娯楽業)
に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものです。
<労働時間とは?最高裁判例より>
【R6年選択式】
最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の< A >に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の< A >に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の< A >に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

【解答】
<A> 指揮命令下
(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)
ポイント!
労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。
【H28年出題】
労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H28年出題】 〇
労働基準法32条の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である」とされています。
(平12.3.9最高裁判所第一小法廷 三菱重工業長崎造船所事件)
<手待ち時間>
【H30年出題】
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

【解答】
【H30年出題】 ×
運転しない者が、助手席で仮眠している間は「労働時間」です。
トラックに乗り込む点で使用者の拘束を受けていること、また、万一事故が発生したときは交替運転、故障修理等を行う役割があるためです。
(昭33.10.11基収6286号)
<仮眠時間>
【R4年出題】
警備員が実作業に従事しない仮眠時間について、当該警備員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに対応することが義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情が存しないなどの事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として警備員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労働基準法第32条の労働時間に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R4年出題】 〇
「従業員の職務は、もともと仮眠時間中も、必要に応じて,突発作業、継続作業、予定作業に従事することが想定され、警報を聞き漏らすことは許されず、警報があったときには何らかの対応をしなければならないものであるから、何事もなければ眠っていることができる時間帯といっても、労働からの解放が保障された休憩時間であるということは到底できず、本件仮眠時間は実作業のない時間も含め、全体として被上告人の指揮命令下にある労働時間というべきである」とされています。
(平14.2.28最高裁判所第一小法廷 大星ビル管理事件)
<1日とは>
【R1年出題】
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

【解答】
【R1年出題】 〇
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは
・午前0時から午後12時までのいわゆる暦日のこと
・継続勤務が2暦日にわたる場合 → 暦日が異なっていても、1勤務として取り扱う。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働となる。
(昭63.1.1基発1号)
<1週間とは>
【H30年出題】
労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

【解答】
【H30年出題】 〇
「1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。」とされています。
何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることができます。
(昭63.1.1基発1号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「前借金相殺の禁止」
R8-079 11.11
労基法第17条「前借金相殺の禁止」
労働基準法では、前借金と賃金との相殺は禁止されています。
条文を読んでみましょう
法第17条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |
過去問を解きながらポイントを確認しましょう
①【H27年出題】
労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労働基準法第17条の目的は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することです。
(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)
②【R3年出題】
労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

【解答】
②【R3年出題】 ×
「明らかに身分的拘束を伴わないもの」は含まれません。
(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発90号)
➂【R5年出題】
使用者が労働者からの申出に基づき、生活必需品の購入等のための生活資金を貸付け、その後この貸付金を賃金から分割控除する場合においても、その貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合的に判断して労働することが条件となっていないことが極めて明白な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されない。

【解答】
➂【R5年出題】 〇
「労働することが条件となっていないことが極めて明白」な場合には、労働基準法第17条の規定は適用されません。
(昭63.3.14基発150号)
④【R7年出題】
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
法第17条には、労使協定による例外規定はありません。
賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することは禁止されています。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「総則」
R8-050 10.13
労基法「総則」(第1条~第12条)
労働基準法の総則をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
第2条 (労働条件の決定) ① 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条 (男女同一賃金の原則) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第7条 (公民権行使の保障) 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
第9条 (定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
第12条 平均賃金の算出(今回は省略します) |
過去問でポイントを確認しましょう
①【R3年出題】
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合は、第1条に抵触しますが、「社会経済情勢の変動等他に決定的な理由」がある場合は、抵触しません。
(昭63.3.14基発150号)
※第1条、第2条違反については、罰則の定めはありません。
②【H28年出題】
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものです。本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなりません。
(昭22.9.13発基17号)
➂【R3年出題】
労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
労働者を「有利」に取り扱うことも差別的取扱に含まれます。
④【H29年出題】
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

【解答】
④【H29年出題】 ×
労働基準法第3条で禁止しているのは、労働者の「国籍、信条、社会的身分」を理由として、労働条件について差別的取扱をすることです。第3条では、「性別」を理由とする差別的取扱については禁止していません。
⑤【H25年出題】
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。

【解答】
⑤【H25年出題】 〇
労働基準法第4条では、性別による差別のうち、「賃金」についてのみ、差別的取扱いを禁止しています。
⑥【R7年出題】
労働基準法第5条に定める「労働者の意思に反して労働を強制する」とは、不当な手段を用いることによって、使用者が労働者の意識ある意思を抑圧し、その自由な発現を妨げて、労働すべく強要することをいい、必ずしも労働者が現実に労働することを必要としない。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
第5条で禁止しているのは、使用者が「労働者の意思に反して労働を強制する」ことです。労働者が現実に労働することは必要とされません。
(昭23.3.2基発381号)
⑦【R7年出題】
労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たる。

【解答】
⑦【R7年出題】 〇
「業として利益を得る」とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続することをいい、1回の行為であっても、反復継続して利益を得る意思があれば、これに当たります。
(昭23.3.2基発381号)
⑧【R7年出題】
労働審判員や裁判員としての職務は労働基準法第7条にいう「公の職務」に該当するため、労働者が労働時間中に、これらの職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、使用者はこれを拒んではならないが、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

【解答】
⑧【R7年出題】 〇
使用者は、選挙権その他公民としての権利の行使や公の職務を執行するために必要な時間を、労働時間中に認めなければなりませんので、労働者が労働時間中に、必要な時間を請求した場合は、使用者はこれを拒んではなりません。「拒んだ」だけで、第7条違反となります。ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます。
⑨【H29年出題】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

【解答】
⑨【H29年出題】 〇
株式会社の取締役でも業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受けます。
(昭23.3.17基発461号
⑩【R7年出題】
労働基準法第9条に定める「労働者」とは、他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。

【解答】
⑩【R7年出題】 ×
労働基準法第9条に定める労働者は、「事業に使用される者」ですので、失業者は含みません。
なお、労働組合法の労働者は、「他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいい、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。(昭23.6.5労発基262号)
⑪【R2年出題】
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。

【解答】
⑪【R2年出題】 ×
使用者は、①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。
そのうち、①「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、「その代表取締役」ではなく、「法人そのもの」をいいます。
⑫【R7年出題】
労働者が自己を被保険者として生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が保険料の補助を行う場合、その保険料補助金は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条に定める「賃金」とは認められない。

【解答】
⑫【R7年出題】 〇
労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに企業が行う保険料補助金は、労働基準法第11条に定める「賃金」となりません。
なお、労働者が法令の定めにより負担すべき所得税等(社会保険料等も含む。)を使用者が労働者に代わって負担する場合は、使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金となります。
(昭63.3.14基発150号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「就業規則」
R8-048 10.11
就業規則に関する出題
今回は、「就業規則」の問題をみていきます。
就業規則について条文を読んでみましょう
法第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 <絶対的必要記載事項> ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 ② 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 ➂ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) <相対的必要記載事項> ④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 ⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 ⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 ⑦ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 ⑩ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 ⑪ 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
法第90条(作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。
法第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
就業規則を作成した使用者は、当該就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すこと等により、労働者が必要なときに容易に確認できる状態にする必要がある。

【解答】
①【R7年出題】 〇
使用者には、「就業規則」を、労働者に周知させる義務があります。(法第106条)
周知の方法は、次の3つのうちいずれかの方法です。(則第52条の2)
①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
②書面を労働者に交付すること。
➂使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
②【R7年出題】
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
②【R7年出題】 〇
従業員の金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なわれる所持品検査が許されるための要件と従業員の検査の受忍義務について判示されています。
使用者がその従業員に対して金品の不正隠匿の摘発・防止のために行なう所持品検査は、これを必要とする合理的理由に基づいて、一般的に妥当な方法と程度で、しかも制度として、職場従業員に対して画一的に実施されるものでなければならず、このようなものとしての所持品検査が就業規則その他明示の根拠に基づいて行なわれるときは、従業員は、個別的な場合にその方法や程度が妥当を欠く等特段の事情がない限り、検査を受忍すべき義務があるとするのが、最高裁判所の判例です。
(西日本鉄道事件 最二小 昭43.8.2)
➂【R7年出題】
労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいてはじめて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態(シフト制)の労働者に関する労働基準法第89条第1項第1号に係る事項の就業規則への記載に際して、「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことにならないが、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、「始業及び終業の時刻」や「休日」に関する事項などについて、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条第1号等)。
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻や休日が異なる場合には、勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻等を規定しなければなりません。
シフト制労働者に関して、就業規則上「個別の労働契約による」、「シフトによる」との記載のみにとどめた場合、就業規則の作成義務を果たしたことになりません。
しかし、基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定めることは差し支えありません。
(令和4年1月7日 厚生労働省 いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項より)
④【R7年出題】
労働基準法第90条第2項の規定により就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、この者の押印もなければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。」と規定されています。(則第49条)
就業規則の届出に添付すべき意見書については、労働者の押印又は署名は不要です。
⑤【R7年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないものであるから、その時間分の減給は、労働基準法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けないが、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、同条に定める規定の適用を受ける。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
労働者が、遅刻・早退をした場合、労働の提供がなかった時間について、その分、賃金を差し引いても、労基法第91条に定める減給の制裁には該当しません。
ただし、遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされますので、減給の制裁の規定の適用を受けます。
(昭63.3.14基発150号)
なお、減給制裁には以下のように限度が設けられています。
・1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内
・一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額は、当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「割増賃金」
R8-047 10.10
割増賃金の基礎となる賃金の算出
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合は、1時間当たりの賃金を一定率以上で割増した割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の基礎となる賃金(1時間当たりの単価)の算出方法をみていきます。
条文を読んでみましょう
則第19条第1項 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 (1) 時間によって定められた賃金 → その金額 (2) 日によって定められた賃金 → その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 (3) 週によって定められた賃金 → その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 (4) 月によって定められた賃金 → その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 (5) 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 (6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 → その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |
★割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金(則第21条)
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

①【R7年出題】 ×
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金ですので、割増賃金の基礎となる賃金には算入しなくてもいいとされています。
ただし、問題文のように、通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合は、実際距離によらない1,000円は割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。
通 勤 手 当 | |
距離にかかわらず一律1,000円 | 実際距離に応じて支払われる |
↑
実際距離によらない1,000円は割増賃金の基礎となる賃金に算入されます。
(昭23.2.20基発295号)
②【R7年出題】
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。

【解答】
②【R7年出題】 ×
手術手当は、手術手当の与えられる勤務時間が法定の割増賃金を支払うべき時間に該当する場合にのみ割増賃金の基礎となる賃金となります。
手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくても差し支えありません。
(昭23.11.22基発1681号)
➂【R7年出題】
通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
通常は事務作業に従事していても、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合は、特殊作業手当を割増賃金の基礎となる賃金に算入して計算した割増賃金を支払わなくてはなりません。
(昭23.11.22基発1681号)
④【R7年出題】
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
賞与は割増賃金の基礎となる賃金には算入しませんが、「支給額が確定している」ものは、労働基準法の賞与とはみなされません。
そのため、毎月支払部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しません。
問題文の場合は、賞与額も含めて確定した年俸額を算定の基礎とした割増賃金の支払が必要です。
(平12.3.8基収78号)
⑤【R7年出題】
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる看護業務に従事したときに支給される夜間看護手当は、通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされています。
(昭41.4.2基収1362号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「賃金支払い5原則」
R8-046 10.09
賃金全額払の原則
賃金の支払方法には次の5つの原則があります
・通貨払いの原則
・直接払いの原則
・全額払いの原則
・毎月1回以上払いの原則
・一定期日払いの原則
条文を読んでみましょう
法第24条(賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
5つの原則とともに、例外にも注意しましょう。
今回は、「全額払の原則」についてみていきます。
賃金は「全額払」が原則です。
例外で、
・法令に別段の定めがある場合
→所得税の源泉徴収、社会保険料、雇用保険料の控除などが認められています。
・当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)がある場合
→購買代金、福利厚生施設の費用、社内預金、組合費などの控除が認められます。
過去問を解いてみましょう
①【R6年選択式】
最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の< A >ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。
(選択肢)
①権利濫用に該当しない
②自由な意思に基づく
➂退職金債権放棄同意書への署名押印により行われた
④退職に接着した時期においてされた

【解答】
<A> ②自由な意思に基づく
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「有効」であるとされました。
(最高裁第二小法廷判決シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件昭和48.1.19)
②【H27年出題】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
②【H27年出題】 ×
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「有効」であるとするのが最高裁判所の判例です。
(最高裁第二小法廷判決シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件昭和48.1.19)
➂【R3年出題】
労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
「相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、労働基準法24条1項の規定に違反しない」とするのが最高裁判所の判例です。
(最高裁第一小法廷判決福島県教組事件昭和44.12.18)
④【H21年選択式】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[…(略)…]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の < A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。
(選択肢)
①経済生活の安定 ②自由な意思 ③生活保障 ④同意に基づく相殺

【解答】
<A> ①経済生活の安定
(最高裁第一小法廷判決福島県教組事件昭和44.12.18)
⑤【R7年出題】
労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものですので、法第24条違反とはなりません。
(昭23.9.14基発1357号)
⑥【H23年出題】
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。

【解答】
⑥【H23年出題】 〇
5分の遅刻について、30分遅刻したとして賃金カットをすることは、労務の提供のなかった限度を超えるカットとなり、全額払の原則に反し違法です。
ただし、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として労基法第91条の制限内で行う場合には、賃金の全額払の原則に反しません。
(昭63.3.14基発150号)
⑦【H19年出題】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
⑦【H19年出題】 ×
「1日」単位で、問題文のような端数処理を行うことは、法違反となります。
割増賃金の計算の便宜上、「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされています。
(昭63.3.14基発150号)
⑧【H29年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
⑧【H29年出題】 〇
<端数処理について>
・1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合
→50円未満切り捨て、それ以上を100円に切り上げる方法は、労働基準法第24条違反にはなりません。
(昭63.3.14基発150号)
⑨【H24年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
⑨【H24年出題】 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に千円未満の端数が生じた場合
→ その額を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反にはなりません。
(昭63.3.14基発150号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働契約」
R8-045 10.08
労働条件の明示義務
労働契約の締結の際、使用者は労働条件を明示しなければなりません。
また、明示された労働条件と実際の労働条件が相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
条文を読んでみましょう
法第15条 (労働条件の明示) ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ ②の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
では、過去問を解いてみましょう
①【H16年出題】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。

【解答】
①【H16年出題】 〇
労働基準法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件は、賃金、労働時間はもちろん、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいうとされています。
一方、労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、労働基準法施行規則第5条で範囲が具体的に定められています。
②【R6年出題】
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 〇
すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇入れ直後の「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示が必要です。
(則第5条第1項第1号の3)
➂【R2年出題】
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

【解答】
➂【R2年出題】 〇
賃金に関しては、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期」について書面の交付が必要です。
交付すべき書面の内容としては、就業規則の規定と併せ、前記の賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされています。
(H11.3.31基発168号)
なお、「書面の交付」については、労働者が書面の交付が必要な事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができるとされています。
(1) ファクシミリを利用してする送信の方法
(2) 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
(則第5条第4項)
④【H23年出題】
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

【解答】
④【H23年出題】 〇
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができます。
⑤【R5年出題】
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
・社宅を利用する利益が、法第11条にいう賃金である場合は、社宅を供与すべき旨の条件は、法第15条第1項の「賃金、労働時間その他の労働条件」となります。そのため、社宅を供与しなかった場合は、同条2項の労働契約の解除権を行使できます。
・社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合は、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれません。そのため、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできません。
ちなみに、労基法第15条の適用がなくても、民法第541条の規定によって契約を解除することは可能です。
(昭23.11.27基収3514号)
⑥【H28年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合は、「その解除は、将来に向かってのみその効力を生じる」とされています。
(民法第630条)
労働契約の効力を遡及的に消滅させ、契約が締結されなかったのと同一の法律効果を生じさせるのものではありません。
⑦【R7年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができるにとどまり、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することはできない。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
明示された労働条件は労働契約の内容となっているため、明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は、明示されたとおりの労働条件の履行を使用者に要求することができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働契約」
R8-044 10.07
労働契約期間の上限
労働契約には①契約期間の定めがないものと②契約期間の定めがあるものの2つがあります。
①契約期間の定めがない場合は、使用者も労働者もいつでも契約を解除することができますので、労働基準法の規制はありません。
②契約期間の定めがある(有期労働契約)の場合は、契約期間中は、原則として契約の解除ができません。そのため、労働者を長く拘束することがないように、労働基準法では、契約期間に上限(原則3年)が設けられています。
では、条文を読んでみましょう
法第14条第1項 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 (1) 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 (2) 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |
過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
期間の定めのない労働契約にはなりません。
「法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号及び第2号に掲げるものについては5年、その他のものについては3年となること。」とされています。
労働基準法第13条も読んでみましょう
| この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、その部分は無効となり、無効となった部分は、「労基法第14条第1項に規定する期間」となります。
(平15.10.22基発第1022001号)
②【H27年出題】
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

【解答】
②【H27年出題】 〇
例えば、10年で終了する「建設工事」現場の場合は、10年の労働契約を締結することができます。
➂【R2年出題】
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

【解答】
➂【R2年出題】 〇
契約期間の上限を5年にできるのは、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者」に限られています。当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合は、例外の5年は適用されませんので、契約期間の上限は原則の3年となります。
(平15.10.22基発第1022001号)
④【R4年出題】
社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められていることが必要である。

【解答】
④【R4年出題】 〇
「契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することができるのは、労働者が国家資格を有していることだけでは足りず、当該国家資格の名称を用いて当該国家資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要であるものであること。」とされています。
(平15.10.22基発第1022001号)
⑤【R7年出題】
労働基準法第14条第1項第2号は、満60歳以上である労働者との労働契約(同条同項第1号に掲げる労働契約を除く。)は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならないと定めているが、満60歳以上であるかどうかは当該労働契約締結時の年齢で判断される。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
「契約締結時に満60歳以上である労働者との間に締結されるものであることを要すること。」とされています。
(平15.10.22基発第1022001号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労使協定」
R8-032 9.25
労使協定の協定当事者の要件
使用者が労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合は、労使協定の締結と届出が必要です。
労働基準法第36条に定められている労使協定を36協定といいます。
第36条を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
労使協定の労働者側の当事者は、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合」、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」です。
今回は、協定当事者になる要件などをみていきます。
過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
労働者の過半数を代表する者の選出は、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。」と規定されています。
「使用者の意向に基づき選出されたものでない」ことがポイントですので、投票券等の書面を用いた方法に限定されません。
(則第6条の2第1項第2号)
②【H22年出題】
労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。

【解答】
②【H22年出題】 ×
管理監督者は労働者代表になることはできません。
労働者の過半数代表者は、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。」という要件が規定されています。
(則第6条の2第1項第1号)
➂【R7年出題】
協定当事者である「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、労働基準法第41条第2号の「管理監督者」、同条第3号の「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などのような、時間外労働又は休日労働を考える余地のない者を含む全ての労働者と解すべきであるとされている。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
36協定は、時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためものではなく、「当該事業に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのもの」と解釈されています。そのため、「労働者」の範囲には、「管理監督者」、「監視、断続的労働従事者で行政官庁の許可を受けた者」、満18歳に満たない者などの時間外労働又は休日労働を考える余地のない者も含まれます。
(昭45.1.1845基収6206号)
④【R7年出題】
協定当事者である使用者は、労働基準法第10条の「使用者」であるから、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能である。

【解答】
④【R7年出題】 〇
三六協定は、それぞれの事業場ごとに締結します。しかし、協定当事者については、各事業場の長ではなく、株式会社の社長自らが協定当事者となることも可能であると解されています。
(昭24.2.9基収第4234号)
⑤【R7年出題】
法人の役員を含む全従業員により構成されており、その目的・活動内容に照らし労働組合とは認められない親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したにすぎない場合、当該代表者は、「労働者の過半数を代表する者」に当たらないとされている。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
親睦団体の代表者が自動的に協定を締結したとしても、その代表者は36協定を締結するために選任されたわけではないので、「労働者の過半数を代表する者」に当たりません。
(参照:厚生労働省ホームページ)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「非常時払」
R8-031 9.24
賃金の非常時払(非常時の出費のために)
「賃金の非常時払」とは、例えば、労働者が予期せぬ災害等で出費が必要となった場合に、賃金の支払期日前に賃金の支払を請求できる制度です。ただし、対象になるのは「既往の労働に対する賃金」です。
条文を読んでみましょう。
法第25条 (非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
則第9条 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 (1) 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 (2) 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 (3) 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。

【解答】
①【H29年出題】〇
「非常時」とは、「出産」、「疾病」、「災害」、「結婚」、「死亡」、「やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合」です。
「労働者本人」だけでなく、「その労働者の収入によって生計を維持する者」に係る事由も対象です。
②【R3年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由には、「労働者の収入によって生計を維持する者」の出産、疾病、災害も含まれるが、「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみに限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
「労働者の収入によって生計を維持する者」とは、労働者が扶養の義務を負っている親族のみならず、労働者の収入で生計を営む者であれば、親族でなく同居人であっても差し支えないとされています。
③【R1年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由のうち、「疾病」とは、業務上の疾病、負傷をいい、業務外のいわゆる私傷病は含まれない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
「疾病」には、業務上の疾病、負傷だけでなく、業務外のいわゆる私傷病も含まれます。なお、「災害」についても業務上、業務外は問われません。
④【R7年出題】
労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。

【解答】
④【R7年出題】 ×
労働者が非常時払を請求した場合、使用者が支払期日前に支払義務を負うのは、「既往の労働に対する賃金」です。いまだ労務の提供のない期間に対する賃金は、支払う義務はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「平均賃金」
R8-016 9.09
平均賃金を「算定すべき事由の発生した日」
平均賃金は、原則として、「算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額」を、その期間の「総日数」で除して計算します。
今回は、「算定すべき事由の発生した日」を具体的にみていきます。
過去問をどうぞ!
★解雇予告手当について算定すべき事由の発生した日
①【H16年出題】
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

【解答】
①【H16年出題】 〇
解雇予告手当を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に「解雇の通告をした日」です。
(昭39.6.1236基収2316号)
②【R7年出題】
労働基準法第20条に基づく解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」であり、その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を通告した日とするものとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
解雇予告手当を算定する際の平均賃金算定事由発生日は、「労働者に解雇の通告をした日」です。その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、同様に、「当初の解雇を通告した日」とされています。
(昭39.6.1236基収2316号)
★減給制裁について算定すべき事由の発生した日
③【H25年出題】
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

【解答】
③【H25年出題】 ×
減給の制裁に関して平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」とされています。
(昭30.7.19基収5875号)
★災害補償について算定すべき事由の発生した日
④【H27年出題】
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。

【解答】
④【H27年出題】 ×
「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」と規定されています。(則第48条)
★所定労働時間が二暦日にわたる場合
⑤【R7年出題】
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻に属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされている。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
所定労働時間が二暦日にわたる勤務を行う労働者について
→ 当該勤務の二暦日目に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合は、当該勤務の始業時刻に属する日に当該事由が発生したものとして取り扱うこととされています。
(昭45.5.14基発374号)
★賃金締切日がある場合
⑥【H27年出題】
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
⑥【H27年出題】 〇
「平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。」とされています。(法第12条第2項)
ポイント!
平均賃金の条文では、「算定すべき事由の発生した日以前 3 か月間」が算定期間となっていますが、平均賃金の計算上、算定すべき事由の発生した日当日は、含めません。
そのため、7月31日に算定事由が発生したときは、前日から遡った3か月で計算します。また、賃金締切日があるため、「直前の賃金締切日」である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となります。
⑦【H27年出題】
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
⑦【H27年出題】 ×
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、平均賃金を計算する場合の「直前の賃金締切日」は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日となります。
問題文の場合、
・基本給 → 直前の賃金締切日は5月31日
・時間外手当 → 直前の賃金締切日は6月20日
となります。
(昭26.12.27基収5926号)
★雇入れ後3か月未満の場合
⑧【R7年出題】
雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。

【解答】
⑧【R7年出題】 ×
「雇入後3か月に満たない者については、平均賃金の算定期間は、雇入後の期間とする。」とされています。(法第12条第6項)
なお、雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定すべき事由が発生した場合でも、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。
(昭23.4.22基収1065号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「平均賃金」
R8-015 9.08
平均賃金の計算(原則と最低保障額)
「平均賃金」とは、賃金の1日当たりの額のことです。
労働基準法の解雇予告手当や、休業手当などの額の計算に使われます。
今回は、平均賃金の原則の計算式と「最低保障額」をみていきましょう。
■計算式について条文を読んでみましょう。
労基法第12条第1項 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 <最低保障額> ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と(1)の金額の合算額 |
<原則の計算式>
算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額 |
その期間の総日数 |
<最低保障額>
算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額 | × | 60 |
その期間中に労働した日数 | 100 |
ポイント!
最低保障額は、「日給」「時給」「出来高払いその他の請負制」の場合に適用されます。
こちらも確認しましょう
★「その日数とその期間中の賃金」を平均賃金の計算から控除する期間
=分母からも分子からも除外する期間
・ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・ 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
・ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間
・ 試みの使用期間
★「賃金総額」に算入しない賃金
=分子からのみ除外する賃金
・ 臨時に支払われた賃金
・ 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
それでは、過去問を解いてみましょう
①【H19年出題】
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

【解答】
①【H19年出題】 〇
賃金が労働した時間によって算定される場合は、最低保障額が適用されます。
最低保障額は、「賃金の総額」÷その期間中の「労働した日数」×100分の60で計算します。
②【R7年出題】
令和7年1月1日から、賃金が日給1万円、毎月20日締切、当月25日支払の条件で雇われている労働者について、同年7月15日に平均賃金を算定すべき事由が発生した。当該労働者に支払われていた賃金は、1月支払分から6月支払分までいずれも労働日数は月10日で支払額は各月10万円であり、本条第3項各号に掲げられている業務上負傷し療養のために休業した期間等の控除期間がなかった。この場合の当該労働者に係る平均賃金の額は6,000円である。

【解答】
②【R7年出題】 〇
問題を解くポイント!
・「日給制」ですので、最低保障額が適用されます。
・ 平均賃金を算定する期間については、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。(法第12条第2項)
問題文の場合は、直前の賃金締切日(6月20日)から遡った3か月で計算します。
3月21日~4月20日、4月21日~5月20日、5月21日~6月20日までの期間で算定します。
・原則の計算式で計算すると
<原則の計算式>
(10万円+10万円+10万円)÷92日 ≒ 3260.86円
<最低保障額>
(10万円+10万円+10万円)÷30日×100分の60 = 6,000円
問題文の労働者に係る平均賃金の額は6,000円となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(労働基準法)から学ぶ
R8-013 9.06
R7年選択式は判例からの出題(労基法)
令和7年度の労働基準法の選択式は、
①付加金
②判例
からの出題でした。
今回は②判例の問題をみていきます。
まず過去問をどうぞ!
【H22年選択式】
賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 < A >として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 権利の濫用 ② 公序に反するもの ③ 信義に反するもの
④ 不法行為

【解答】
<A> ② 公序に反するもの
ポイント!
「従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく、従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には、それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては、「公序に反し無効である。」とされています。
(東朋学園事件 平成15.12.4最高裁判所第一小法廷)
では、令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
最高裁判所は、就業規則として定める給与規程における、出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の条項(以下本問において「本件90%条項」という。)の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めが労働基準法(平成9年法律第92号による改正前のもの)65条等に反するか等が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法65条は、産前産後休業を定めているが、産前産後休業中の賃金については何らの定めを置いていないから、産前産後休業が有給であることまでも保障したものではないと解するのが相当である。〔…(略)…〕したがって、産前産後休業を取得し〔…(略)…〕た労働者は、その間就労していないのであるから、労使間に特段の合意がない限り、その不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、当該不就労期間を出勤として取り扱うかどうかは原則として労使間の合意にゆだねられているというべきである。
ところで、従業員の出勤率の低下防止等の観点から、出勤率の低い者につきある種の経済的利益を得られないこととする措置ないし制度を設けることは、一応の経済的合理性を有するものである。上告人の給与規程は、賞与の支給の詳細についてはその都度回覧にて知らせるものとし、回覧に具体的な賞与支給の詳細を定めることを委任しているから、本件各回覧文書〔本件90%条項の適用に関し、産前産後休業については、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に算入し、出勤した日数には含めない旨を定めた文書〕は、給与規程と一体となり、本件90%条項等の内容を具体的に定めたものと解される。本件各回覧文書によって具体化された本件90%条項は、労働基準法65条で認められた産前産後休業を取る権利〔…(略)…〕に基づく不就労を含めて出勤率を算定するものであるが、上述のような労働基準法65条〔…(略)…〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が< C >場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である」。
<選択肢>
⑤ 使用者に労働者の仕事と生活の調和にも配慮することを規定している趣旨を実質的に失わせるものと認められる
⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
⑪ 同法等に違反する行為に罰則を設けている意味を没却させる
⑳ 労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとしている意味を没却させる

【解答】
<C> ⑥ 上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる
裁判要旨を読んでみましょう。
| 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者としこれに満たない者には賞与を支給しないこととする旨の就業規則条項の適用に関し、出勤率算定の基礎とする出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し、出勤した日数に上記日数及び育児を容易にするための措置により短縮された勤務時間分を含めない旨を定めた就業規則の付属文書の定めは、従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため、上記条項により賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きく、従業員が産前産後休業を取得し又は勤務時間短縮措置を受けた場合には、それだけで上記条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高いという事情の下においては、公序に反し無効である。 |
(東朋学園事件 平成15.12.4最高裁判所第一小法廷)
問題の考え方です
産前産後休業を取得すると、90%条項を満たせず、賞与を受けられなくなる可能性が高い → 「労働基準法の産前産後休業を取得する権利を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる」と考えましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(労働基準法)から学ぶ
R8-003 8.27
労基法第114条付加金の支払
令和7年度の労働基準法の選択式は、3つの穴埋めのうち、2つは第114条(付加金の支払)から、1つは判例から出題されました。
「付加金の支払」について、令和7年の選択式のポイントは
・付加金の支払を命ずるのは誰?
・「付加金」の名称そのもの
でした。
ちなみに、過去には、「付加金」を請求できる4つの場合が出題されています。
条文を読んでみましょう。
第114条 (付加金の支払) 裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項(年次有給休暇の期間又は時間)の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から5年(当分の間3年)以内にしなければならない。 |
・付加金の対象になるのは
①解雇予告手当を支払わない
②休業手当を支払わない
③割増賃金を支払わない
④年次有給休暇の期間又は時間の賃金を支払わない
の4つの場合です。
・付加金の額は、
使用者が支払わなければならない未払金の額と「同一額」です。
過去問をどうぞ!
【H24年出題】※改正による修正あり
裁判所は、労働基準法第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金(年次有給休暇の期間又は時間の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しては適用されない。

【解答】
【H24年出題】 〇
付加金の支払は、「解雇予告手当」、「休業手当」、「割増賃金」、「年次有給休暇の期間又は時間の賃金」の4つを支払わない場合に適用されます。
「賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった」場合は、適用されません。
令和7年の選択式をどうぞ!
労働基準法第114条は、< A >は、同法第37条の規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、同条の規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の< B >の支払を命ずることができる旨規定している。
【選択肢】
① 厚生労働大臣 ② 裁判所 ③ 都道府県労働局長
④ 労働基準監督署長
⑤ 慰謝料 ⑥ 遅延損害金 ⑦ 賠償金 ⑧ 付加金

【解答】
<A> ② 裁判所
<B> ⑧ 付加金
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「年次有給休暇」
R7-310 07.04
年次有給休暇の比例付与
所定労働日数が少ない労働者にも年次有給休暇の権利が発生します。
ただし、比例付与の対象となり、年次有給休暇の付与日数が少なくなることがあります。
では、条文を読んでみましょう。
法第39条第3項、則第24条の3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が30時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 (1) 1週間の所定労働日数が4日以下の労働者 (2) 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1年間の所定労働日数が216日以下の労働者 |
★比例付与の対象になるのは
・週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
※週以外の期間によって労働日数が定められる場合
・年間所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
ポイント!
1週間の所定労働時間が30時間以上の者は比例付与の対象になりません
★比例付与の日数の計算
比例付与の有休の日数は、通常の労働者の週所定労働日数(5.2日)との比率で計算されます。
例えば、6か月間継続勤務した週所定労働日数が4日の労働者に付与される日数は、
10日×4日/5.2日≒7日(1未満切り捨て)となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R6年出題】
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。

【解答】
①【R6年出題】 ×
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者です。
問題文の場合は、週5日労働ですので、1週間の所定労働時間が20時間でも比例付与の対象になりません。
6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
②【R6年出題】
月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。
〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日 端数を切り捨てて7日

【解答】
②【R6年出題】 ×
比例付与の対象になるのは、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者ですので、1週間の所定労働時間が32時間の労働者は、週4日労働でも比例付与の対象になりません。
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
③【H17年出題】
1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。

【解答】
③【H17年出題】 〇
年次有給休暇の権利は、基準日に発生します。
基準日に予定されている所定労働日数に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものとされています。
問題文の場合、雇入れの日から起算して6か月継続勤務した時点で、「週4日勤務・ 1日の所定労働時間8時間」ですので、比例付与の対象ではありません。
そのため、10日の年次有給休暇を付与しなければなりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「休日の振替」
R7-285 06.09
休日の振替についてお話しします。代休との違いに注意しましょう(労働基準法)
「休日の振替」についてお話しします。
ポイント!
・代休との違い
・休日の振替とは、あらかじめ「休日」と「労働日」を入れ替えること
・場合によっては、「時間外労働」の割増賃金が必要になることもあります
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「退職手当」
R7-283 06.07
労基法の「退職手当」に関する出題
労働基準法の「退職手当」に関する出題を集めました。
テーマは以下の通りです。
・退職手当は労働基準法の「賃金」に当たるか否か
・賃金支払い5原則の例外
・退職手当は、就業規則の相対的必要記載事項
・金品の返還
・退職金に関する判例
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労働基準法では、退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこととされています。
ただし、退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものは賃金とされます。
(昭22.9.13発基第17号)
②【R3年出題】
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。

【解答】
②【R3年出題】 ×
賃金は、「通貨払い」が原則です。
例外的に、「労働者の同意」を得た場合は、「当該労働者の預金又は貯金への振込み」によることができます。また、退職手当については、「銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付する」ことによることができます。
③【H12年出題】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
③【H12年出題】 ×
退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。
退職手当は、「予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足りる」とされています。
(法第23条、昭26.12.27基収5483号)
④【H28年出題】
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。

【解答】
④【H28年出題】 ×
「退職手当」は、就業規則の相対的必要記載事項です。
退職手当の制度を設ける場合は、就業規則に、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を定めなければなりません。
退職手当についての不支給事由又は減額事由は、退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当します。そのため、就業規則に記載しなければなりません。
(法第89条、H11.3.31基発168号)
⑤【H27年出題】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
「全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。」とされています。
労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示の効力は、肯定されています。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷)
⑥【H30年選択式】
最高裁判所は、同業他社への転職者に対する退職金の支給額を一般の退職の場合の半額と定めた退職金規則の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
「原審の確定した事実関係のもとにおいては、被上告会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもつて直ちに社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、したがつて、被上告会社がその退職金規則において、右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、その点を考慮して、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、本件退職金が< A >的な性格を併せ有することにかんがみれば、合理性のない措置であるとすることはできない。」
<選択肢>
① 功労報償 ② 就業規則を遵守する労働者への生活の補助
③ 成果給 ④ 転職の制約に対する代償措置

【解答】
⑥【H30年選択式】
<A> ① 功労報償
「この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、所論の同法3条、16条、24条及び民法90条等の規定にはなんら違反するものではない。」とされています。
(昭和52.8.9最高裁判所第二小法廷)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「1週間単位の非定型的労働時間制」
R7-247 05.02
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の導入
「労使協定」の締結によって、1週間単位で労働時間を弾力的に設定することができる制度です。
対象になるのは、規模30人未満の小売業、旅館、料理、飲食店の事業に限られます。
条文を読んでみましょう。
第32条の5 ① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、1日について10時間まで労働させることができる。 ② 使用者は、1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
則第12条の5 ① 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。 ② 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。 ③ 法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。 |
※1週間単位の非定型的変形労働時間制には、「1週間44時間」の特例は適用されません。
そのため、1週40時間・1日10時間以内で設定しなければなりません。
(則第25条の2)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
いわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、「小売業、旅館、料理店若しくは飲食店」の事業で、「常時使用する労働者の数が30人未満」の事業場です。
「いずれか1つに該当する事業場」ではなく事業の種類と労働者数の両方に該当しなければなりません。
②【H22年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限は「10時間」と定められています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「過半数代表者」
R7-246 05.01
労働基準法の「労働者の過半数を代表する者」とは
労働者の過半数を代表する者とは、当該事業場のすべての労働者の過半数を超える者によって代表者とされた者です。
「労使協定」などの際に登場します。
例えば、第36条の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」が協定当事者となります。
「労働者の過半数で組織する労働組合」がない場合とは、「そもそも労働組合がない」又は「労働組合があっても当該事業場の労働者の過半数で組織されていない」場合です。
では、過半数代表者の条件について条文を読んでみましょう。
則第6条の2 ① 労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 (2) 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 |
では過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」が誤りです。
「投票、挙手等の方法による手続」としては、労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当します。
(平11.3.31基発169号)
②【R5年出題】
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」という要件も満たさなければなりません。
③【H25年出題】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトは含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

【解答】
③【H25年出題】 〇
労働基準法第36条の協定は、当該事業において法律上又は事実上時間外労働又は休日労働の対象となる労働者の過半数の意思を問うためのものではなく、当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数の意思を問うためのものです。
そのため、労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイトも含まれます。
なお、派遣労働者は、「派遣元」の人数に含まれます。
(平11.3.31基発168号)
④【H13年出題】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

【解答】
④【H13年出題】 ×
「第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者」も労働基準法の「労働者」です。そのため、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者も含まれます。
なお、「第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者」は、「労働者の過半数を代表する者」にはなれません。
⑤【H23年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者ではなかったとしても、当該協定を行政官庁に届け出て行政官庁がこれを受理した場合には、当該協定は有効であり、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
いわゆる36協定を締結した労働者側の当事者が労働者の過半数を代表する者でない場合は、当該協定は有効とは認められないとするのが最高裁判所の判例です。その場合、労働者は使用者の時間外労働命令に従う義務はありません。
(最高裁平成13年6月22日第二小法廷判決)
⑥【H19年出題】
使用者は、労働者が労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【解答】
⑥【H19年出題】 〇
過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならないこととしたものです。
「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれます。
(平11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「就業規則」
R7-245 04.30
就業規則作成の手続
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません。変更した場合も、同様に、行政官庁に届け出なければなりません。
今回は、就業規則作成・変更の際の手続をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

【解答】
①【H20年出題】 ×
「同意を得なければならない」ではなく「意見を聴かなければならない」です。
同意を得ることまで義務付けられていません。意見を聴けば労働基準法違反になりません。
②【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

【解答】
②【H21年出題】 〇
就業規則の作成だけでなく、その変更についても、意見を聴かなければなりません。
③【H26年出題】
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
就業規則の作成又は変更については、協議をすることまで使用者に要求していません。
(昭25.3.15基収525号)
④【R3年出題】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

【解答】
④【R3年出題】 ×
同一事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成することは差し支えありません。
ただし、当該一部の労働者に適用される就業規則は、当該事業場の就業規則の一部です。
そのため、その作成または変更については、当該事業場の「全労働者」の過半数で組織する労働組合又は「全労働者」の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数ではありません。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【H30年出題】
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則のみ行えば足りる。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるのではなく、パートタイム労働者についての就業規則は、就業規則の本則の一部となります。
そのため、当該事業場の「全労働者」の過半数で組織する労働組合又は「全労働者」の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「端数処理」
R7-244 04.29
全額払いの原則と端数処理
賃金は労働の対償ですので、使用者は、労働者にその全額を支払わなければなりません。
ただし、賃金の支払額については、便宜上、端数処理が認められています。
★遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理について
5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払いの原則に反し、違法とされています。
なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しません。
(昭63.3.14基発150号)
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
①【H19年出題】 ×
1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、「法違反」となります。
★なお、「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められますので、違反になりません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H25年出題】
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、法違反になりませんが、「1日」単位では法違反になります。
後半は、正しいです。以下の処理は、法違反になりません。
「1時間当たり」の賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
「1か月」における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、上記と同様に処理すること
③【H29年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。

【解答】
③【H29年出題】 〇
1か月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことは、法違反として取り扱わないとされています。
(昭63.3.14基発150号)
④【H24年出題】
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
④【H24年出題】 〇
1か月の賃金支払額に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、法違反としては取り扱わないこととされています。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【H27年出題】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
「過払いした賃金を精算・調整するため、後に支払われるべき賃金から控除すること」
↓
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、第24条第1項項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。
この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。」
とされています。
「その金額が少額」であればよいということではありません。
(昭和44年12月18日最高裁第一小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「割増賃金の単価」
R7-241 04.26
割増賃金の1時間当たりの賃金額の算出
割増賃金は以下のように計算します。
1時間当たりの賃金額 × 時間外労働の時間数 × 割増率
(休日労働の時間数・深夜労働の時間数)
「1時間あたりの賃金額」の算出について条文を読んでみましょう。
則第19条第1項 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第33条若しくは法第36条第1項の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 (1) 時間によって定められた賃金については、その金額 (2) 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 (3) 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 (4) 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 (6) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 |
基本給以外の「手当」も、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
ただし、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる手当は除外することができます。
条文を読んでみましょう。
則第21条(割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金) 家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 (1) 別居手当 (2) 子女教育手当 (3) 住宅手当 (4) 臨時に支払われた賃金 (5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数:240日
計算の基礎となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間
(A) 300,000円÷(21×7)
(B) 300,000円÷(21×8)
(C) 300,000円÷(30÷7×40)
(D) 300,000円÷(240×7÷12)
(E) 300,000円÷(365÷7×40÷12)

①【H28年出題】
【解答】
(D) 300,000円÷(240×7÷12)
月給制の場合は、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」は、
「月給」÷月の所定労働時間数
で計算します。
ただし、月によって所定労働時間数が異る場合は、「月給」÷「1か月の平均所定労働時間数」となります。
問題文の場合、年間の所定労働日数が240日で、対象月の所定労働日数が21日です。
月によって所定労働時間数が異なるので、「1か月の平均所定労働時間数」で割ることになります。
1か月の平均所定労働時間数は、240日×7時間÷12か月で計算します。
※7時間=拘束時間8時間(午前9時から午後5時)-休憩1時間です。
②【H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法の第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「通勤手当」は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。
③【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
家族手当でも、「家族数に関係なく」一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎に含めなければなりません。
(昭22.11.5基発231号)
④【H19年出題】
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】
④【H19年出題】 ×
住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、除外される住宅手当には該当しません。
問題文のように、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当しません。そのため、割増賃金の計算の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(平11.3.31基発170号)
⑤【H18年出題】
賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項又は第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足りる。

【解答】
⑤【H18年出題】 〇
賃金が出来高払制その他の請負制の場合は、「出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額」÷「総労働時間数」で計算します。
所定労働時間ではなく「総労働時間数」で計算するのがポイントです。総労働時間には、時間外労働時間も含まれます。
⑥【H17年出題】
年間賃金を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。

【解答】
⑥【H17年出題】 〇
年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は「賞与」に該当しません。
そのため、割増賃金の支払いは、「月例給与に賞与部分を含めた年俸額」を基礎として支払わなければなりません。
(平12.3.8基収78号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「割増賃金」
R7-240 04.25
時間外、休日、深夜労働の割増率
時間外労働、休日労働、深夜労働させた場合は、割増賃金を支払わなければなりません。
今回は、「割増率」をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第37条第1項、第4項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) ① 使用者が、第33条(災害等による臨時の必要がある場合)又は第36条第1項の規定(36協定)により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金率(第37条、時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)
・深夜労働と時間外又は休日労働が重なる場合 則第20条 ① 時間外労働が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合は、 5割以上(その時間の労働のうち、1か月について60時間を超える時間外労働に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ② 休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合は、6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
休日労働が、8時間を超えても、深夜業に該当しない場合は、休日労働のみの割増率(3割5分増)となります。時間外労働の割増率は合算する必要はありません。
(H11.3.31基発168号)
②【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間
<A> 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】
<A> ×
日曜の10時間の労働については、深夜業に該当しなければ、時間外労働の割増率は加算する必要はありません。8時間を超えた2時間も含めて、休日労働に対する割増率のみで構いません。
(H11.3.31基発168号)
<B> 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】
<B> ×
「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。
そのため、問題文の場合、休日割増賃金の対象になるのは、日曜日の午後12時までです。月曜の午前0時以降は、休日割増賃金を支払う義務はありません。
(H6.5.31基発331号)
0時 | |
日曜(法定休日) 休日割増 | 月曜(平日) |
<C> 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】
<C> 〇
時間外労働が引き続き翌日の所定労働時間に及んだ場合は、「翌日の所定労働時間の始期までの超過時間に対して、割増賃金を支払えば法第37条の違反にならない」とされています。
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、日付が変わっても月曜の超過勤務時間となります。
<D> 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】
<D> ×
「法定休日」の割増賃金率は、「暦日単位」で適用されます。
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前0時以降は休日労働の割増賃金で計算しなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
<E> 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

【解答】
<E> ×
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
|
|
|
| 2時間 | 2時間 |
4時間 |
|
8時間 |
8時間 | ||||||
6時間 |
6時間 |
6時間
|
6時間 |
木曜 → 時間外労働2時間(8時間を超えた分)
金曜 → 時間外労働2時間(8時間を超えた分)
土曜 → 時間外労働4時間(週の通算労働時間が44時間(木・金のそれぞれ2時間の時間外は除きます)となるので、40時間を超えた分)
③【H23年出題】
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

【解答】
③【H23年出題】〇
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ない時間外又は休日労働は違法です。
ただし、法定労働時間を超えた場合、又は休日労働させた場合は割増賃金を支払わなければならないため、違法な時間外労働・休日労働をさせた場合でも、使用者は、割増賃金の支払義務は免れません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「休日」
R7-224 04.09
労基法第35条「休日の与え方」
「休日」とは労働義務のない日のことです。
まず、休日について条文を読んでみましょう。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
■休日の与え方
<原則>毎週少なくとも1回
<例外>4週間を通じ4日以上の休日
★休日のイメージ
<原則 毎週1回>
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
休 | 休 | 休 | 休 |
<例外 4週4休>
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 |
休休 | 休休 |
|
※就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとされています。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

【解答】
①【H23年出題】 〇
休日は、「毎週1回」与えるのが原則ですが、例外で、「4週間を通じ4日以上」の休日を与えることもできます。
4週4休日の場合は、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしなければなりません。
(法第35条、則第12条の2)
②【H13年出題】
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】
②【H13年出題】 ×
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制については、特定の4週間に4日の休日があればよいとされています。
どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならない趣旨ではありません。
特定の4週間を明確にするため、就業規則等で起算日を明らかにすることとされています。
(昭和23.9.20基発1384号)
③【H29年出題】
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】
③【H29年出題】 ×
「休日」とは、単に連続24時間の休業ではありません。
「休日」とは「暦日」を指し、午前0時から午後12時までの休業のことをいいます。
(昭23.4.5基発535号)
④【H21年出題】
①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。

【解答】
④【H21年出題】 ×
8時間3交替制勤務で、要件に該当する場合は、「継続24時間」の休息を与えれば、暦日でなくても労働基準法第35条の休日を与えたことになります。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【H13年出題】
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。

【解答】
⑤【H13年出題】 ×
④の問題のように、要件に該当する8時間3交替制の場合は、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることが認められています。
⑥【H24年出題】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
⑥【H24年出題】 〇
労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 労働日 8:00 | 非番日 8:00 | 公休日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第7日の午前0時から継続した24時間は「休日」となります。
非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日を与えたものとは認められません。
(昭23.11.9基収2968号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法第41条
R7-197 03.13
労働時間・休憩・休日に関する規定の適用除外(労基法第41条)
労基法第41条に定められた労働者には、「労働時間・休憩・休日」に関する規定が適用されません。
条文を読んでみましょう。
第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外) 労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 (1) 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者 →農業の事業・水産の事業に従事する者 (2) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 (3) 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの |
ポイント!
★適用除外になるのは、「労働時間・休憩・休日」に関する規定です。
「深夜業」、「年次有給休暇」については適用されます。
★「林業」については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されます。
★監視又は断続的労働に従事する者については、所轄労働基準監督署長の許可が必要です。
過去問をどうぞ!
①【H23年選択式】
労働基準法第4章に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、農業又は畜産、養蚕、水産の事業に従事する労働者については適用されないが、これらの事業においても、< A >及び年次有給休暇に関する規定は適用される。
(選択肢)
① 深夜業 ② 事業場外のみなし労働時間制
③ フレックスタイム制 ④ 労働時間の通算

【解答】
<A> ① 深夜業
②【H22年出題】
労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。

【解答】
②【H22年出題】 〇
監督若しくは管理の地位にある者とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者です。
ただし、管理監督者に該当するか否かは、地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断されます。
(昭63.3.14基発150号)
③【H27年出題】
労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは、必ずしも機密書類を取り扱う者を意味するものではなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

【解答】
③【H27年出題】 〇
「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいいます。
(昭22.9.13発基17号)
④【R4年出題】
使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、労働基準法第36条第1項の協定がなくとも、休日に日直をさせることができる。

【解答】
④【R4年出題】 〇
宿直又は日直勤務を断続的勤務として許可を受けた場合は、その宿直又は日直の勤務については、労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されません。
そのため、使用者が労働基準法施行規則第23条によって日直を断続的勤務として許可を受けた場合には、36協定がなくても、休日に日直をさせることができます。
(昭23.1.13基発33号)
⑤【H26年選択式】
小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)として取り扱われるなど不適切な事案もみられるところであることから、平成20年9月9日付け基発0909001号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、< A >において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する< B >となる。」ことがあげられている。
(選択肢)
① 時間単価に換算した賃金額 ② 総賃金額 ③ 平均賃金額
④ 役職手当額 ⑤ 考慮要素 ⑥ 重要な要素 ⑦ 参考 ⑧ 補強要素

【解答】
<A> ① 時間単価に換算した賃金額
<B> ⑥ 重要な要素
(平成20年9月9日基発第0909001号 )
⑥【H25年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当する労働者が、使用者に、同法第37条第3項(現行同条第4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができるかという点をめぐって、次のように判示した。
「労基法(労働基準法)における労働時間に関する規定の多くは、その< A >に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。他方、同条3項は、使用者が原則として< B >の間において労働させた場合においては、その時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならない旨を規定するが、同項は、労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働に関し一定の規制をする点で、労働時間に関する労基法中の他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
また、労基法41条は、同法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、同条各号の一に該当する労働者については適用しないとし、これに該当する労働者として、同条2号は管理監督者等を、同条1号は同法別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者を定めている。一方、同法第6章中の規定であって年少者に係る深夜業の規制について定める61条をみると、同条4項は、上記各事業については同条1項ないし3項の深夜業の規制に関する規定を < C >旨別途規定している。こうした定めは、同法41条にいう「労働時間、休憩及び休日に関する規定」には、深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。
以上によれば、労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく、管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。」
(選択肢)
① 時間帯 ② 長さ ③ 密度 ④ 割増
⑤ 午後10時から午前5時まで ⑥ 午後10時から午前6時まで
⑦ 午後11時から午前5時まで ⑧ 午後11時から午前6時まで
⑨ 行政官庁の許可を受けた場合に限り適用する
⑩ 厚生労働省令で定める ⑪ 適用する ⑫ 適用しない

【解答】
<A> ② 長さ
<B> ⑤ 午後10時から午前5時まで
<C> ⑫ 適用しない
「管理監督者に該当する労働者は,深夜割増賃金を請求することができる」という点がポイントです。
(平成21年12月18日最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働基準法>解雇制限
R7-188 03.04
解雇が制限される期間と例外
労働基準法では、解雇が禁止される期間を設けています。
条文を読んでみましょう。
法第19条 ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
★解雇制限期間と例外を確認しましょう。
解雇が禁止される期間 | 例外で解雇できる場合 |
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間+その後30日間 | ・打切補償を支払う場合(行政官庁の認定不要) ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定を受けること) |
②産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間+その後30日間 | ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(行政官庁の認定を受けること) |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
就業規則に定めた定年制が労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ、従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっていて、それが従業員にも徹底している場合には、その定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
・就業規則で定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めている。
・従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然労働関係が終了する慣行になっている。
↓
定年による雇用関係の終了は解雇ではないので、労働基準法第19条第1項に抵触しません。
(昭26.8.9基収3388号)
②【H29年出題】
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
業務上の傷病により治療中でも、休業しないで就労している場合は、解雇は制限されません。
解雇が制限されるのは「休業する期間+30日間」です。
(昭24.4.12基収1134号)
③【R1年出題】
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
③【R1年出題】 〇
産前の休業を請求しないで就労している場合は、解雇は制限されません。
(昭25.6.16基収1526号)
④【H26年出題】
労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。

【解答】
④【H26年出題】 〇
産前産後の女性の解雇が制限されるのは、「第65条の規定によって休業する期間+その後30日間」です。
第65条で規定される産後の休業は、「産後8週間」です。
そのため、産後8週間を超えて休業している期間は、解雇は制限されません。
産後8週間を超えて休業していても、解雇が制限されるのは、「産後8週間及びその後の30日間」となります。
⑤【H30年出題】
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
「税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合」は、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には当たりません。
(昭63.3.14基発150号)
⑥【R5年出題】
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。

【解答】
⑥【R5年出題】 〇
「従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合」は、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に当たりません。
(昭63.3.14基発150号)
⑦【H28年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第19条第1項の解雇制限が解除されるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法〔労働基準法〕において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法〔労災保険法〕に基づく保険給付が行われている場合とで、同項〔労働基準法第19条第1項〕ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には< A >として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が< A >の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後< B >を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による< A >の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。」

【解答】
<A> 打切補償
<B> 3年
(最高二小平27.6.8)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労働基準法>妊産婦
R7-176 02.20
妊産婦の「変形労働時間制の適用」・「時間外労働・休日労働・深夜労働」
母性保護のため、妊産婦については、「変形労働時間制の適用」が制限され、「時間外労働・休日労働・深夜労働」が禁止されています。
ただし、「妊産婦が請求した場合」に限られていることがポイントです。個人差に配慮したためです。
では、条文を読んでみましょう。
第66条 ① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の規定にかかわらず、1週間についての法定労働時間、1日についての法定労働時間を超えて労働させてはならない。 ② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、「災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合」及び「公務のため臨時の必要がある場合」並びに「36協定による場合」にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
①について
→「フレックスタイム制」は制限されません。
→「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」及び「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の適用を禁止する意味ではありません。
制限される時間は、変形労働時間制によって、1日又は1週間の法定労働時間を超える時間です。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

【解答】
①【H25年出題】 〇
妊産婦が請求した場合は、第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項の規定(36協定による場合)にかかわらず、時間外労働・休日労働は禁止されます。
②【R3年出題】
労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

【解答】
②【R3年出題】 ×
監督又は管理の地位にある者には、労働時間に関する規定が適用されません。
妊産婦で監督又は管理の地位にある者についても、労働時間に関する規定は適用されません。
そのため、妊産婦から請求があった場合でも、監督又は管理の地位にある者の場合は、「労働時間に関する規定」は適用されません。
★妊産婦で監督又は管理の地位にある者には、「妊産婦の労働時間に関する規定(「変形労働時間制の適用の制限」、「時間外労働・休日労働の禁止」)は適用されません。
(昭61.3.20基発第151号)
③【H19年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。

【解答】
③【H19年出題】 ×
第66条第2項の規定は、第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦には適用されません。
(昭61.3.20基発第151号)
④【H17年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【解答】
④【H17年出題】 ×
監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働をさせることはできます。
ただし、「深夜」の規定は監督又は管理の地位にある者にも適用されます。そのため、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があった場合は、深夜業をさせることはできません。
(昭61.3.20基発第151号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「労働契約」
R7-157 02.01
労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約
労働基準法では、労働条件の最低基準が定められています。
今回は、労働基準法の基準を下回る労働契約についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
・ 労働基準法で定められている1日の労働時間の上限は8時間です。
↓
・ ある労働契約で1日の労働時間を10時間と定めました。(労働基準法の基準を下回っている)
↓
・ 労働契約全体が無効になるのではなく、「労働基準法で定める基準に達しない」部分のみ無効になります。
↓
・ 法第13条により、「1日8時間」とする労働契約に修正されます。
★労働協約・就業規則との効力の力関係も確認しましょう。
労働基準法 | > | 労働協約 | > | 就業規則 | > | 労働契約 |
強い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・弱い
ポイント!
・使用者が一方的に定めた就業規則よりも、労働組合と使用者が対等の立場で約束した「労働協約」の方が強い
・個々の労働者ごとに締結した労働契約より、職場のルールである就業規則の方が強い。
・労働協約、就業規則、労働契約は、労働基準法の基準は守らなければならない。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
無効となるのは、労働基準法で定める基準に「達しない」(=不利な)労働条件を定める部分です。労働基準法で定める基準より労働者に「有利」なものは有効です。
②【R5年出題】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

【解答】
②【R5年出題】 ×
法第14条第1項に規定する期間(「高度の専門的知識等を有する労働者」及び「満60歳以上の労働者」については5年、その他のものについては「3年」)を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、その部分は無効となります。
その場合、労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項に規定する期間(5年又は3年)となります。
(平成15.10.22基発第1022001号)
③【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。

【解答】
③【H25年出題】 〇
労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約については、その部分は無効となり、無効となった部分は、労働基準法所定の基準で補充されます。
④【H27年出題】
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

【解答】
④【H27年出題】 〇
労働組合法と労働基準法の異なる点を確認しましょう。
・労働組合法第16条
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。」
・労働基準法第13条
「労働基準法で定める基準に達しない(=不利な)労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法「賃金支払い5原則」
R7-147 01.21
賃金の通貨払いの原則と例外
賃金は、「労働の対償」として支払われるものです。
労働者が、労働した分の賃金を、間違いなく受け取ることができるよう、労働基準法では、賃金の支払いについて5つの原則を定めています。
賃金支払い5原則は次のとおりです。
① 通貨払い
② 直接払い
③ 全額払い
④ 毎月1回以上払い
⑤ 一定期日払い
条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
今回は、「通貨払いの原則とその例外」をみていきます。
原則 → 賃金は通貨(例えば、1万円札や100円硬貨など)で支払わなければなりません。
例外 → 通貨以外で支払うことができる場合もあります。
・ 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
・ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

【解答】
①【R1年出題】 ×
賃金を「通貨以外のもの」で支払うことができるのは、「法令に別段の定めがある場合又は「労使協定」がある場合」ではなく、「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」です。
「労働協約」と「労使協定」の違いに注意しましょう。
★「労働協約」とは
↓
労働組合(労働者側)と使用者又はその団体(使用者側)との間の労働条件等に関する約束のことです。労働者側が「労働組合」であることがポイントです。労働組合がない事業場では、労働協約は締結できません。
★「労使協定」とは
↓
・事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
・労働者の過半数を代表する者
との書面による協定です。労働組合がなくても労使協定は締結できます。
労使協定は、事業場全体に効力が及びます。
②【H29年出題】
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
労働協約は、締結当事者である「使用者」と「労働組合とその構成員」のみに適用されます。
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。労働協約の適用を受けない労働者については、通貨以外のもので支払うことはできません。
(昭63.3.14基発150号)
③【H28年出題】
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない限り得られているものと解されている。

【解答】
③【H28年出題】 〇
労働者の「同意」を得た場合は、賃金を口座振込みで支払うことができます。
「同意」については、労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問われません。
労働者が、賃金の振込み対象として労働者本人名義の預貯金口座の指定を行えば、原則として、同意が得られているものと解されます。
(則第7条の2、昭63.1.1基発1号)
④【R3年出題】
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。

【解答】
④【R3年出題】 ×
退職手当の支払についても、労働者の預金又は貯金への振込みで支払う場合は、「労働者の同意」が必要です。
また、通常の賃金とは違い、退職手当は、小切手を労働者に交付することによって支払うことができますが、この場合も「労働者の同意」が必要です。
(則第7条の2第2項)
⑤【R6年出題】 ※問題文を修正しています
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払方法として、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)のうち労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動によることができる(いわゆる賃金のデジタル払い)が、賃金の支払いに係る資金移動を行う口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が500万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が500万円を超えた場合に当該額を速やかに500万円以下とするための措置を講じていることが、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号に定められている。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
いわゆる賃金のデジタル払いの要件の一つに「賃金の支払に係る資金移動を行う口座残高上限額を100万円以下に設定又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。」があります。
問題文は500万円になっているので誤りです。
(則第7条の2第1項第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法第23条金品の返還
R7-136 01.10
退職時の金品の返還義務
労働者が死亡又は退職した際に、権利者の請求があった場合、使用者は請求があった日から7日以内に金品を返還しなければなりません。
労働者の足止め策に利用させないようにするためです。
第23条 (金品の返還)
① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② 賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、①の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 |
請求する権利がある「権利者」は、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は遺産相続人です。一般債権者は含まれません。
(昭22.9.13発基17号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
労働者の死亡又は退職の際に
・ 権利者の請求があった場合 → 7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません
ただし、
・賃金又は金品に関して争いがある場合 → 異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければなりません
②【H30年出題】
労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」です。
労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたりません。
(昭23.3.17基発464号)
③【H12年出題】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
③【H12年出題】 ×
退職手当は、通常の賃金の場合と異なります。
退職手当は、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば足ります。
(昭26.12.27基収5483号)
④【R6年出題】
労働基準法第23条は、労働の対価が完全かつ確実に退職労働者又は死亡労働者の遺族の手に渡るように配慮したものであるが、就業規則において労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定しているときには、権利者からの請求があっても、7日以内に賃金を支払う必要はない。

【解答】
④【R6年出題】 ×
通常の賃金は、「一定期日払い」の原則がありますが、第23条はその特例で、権利者の請求があれば7日以内に支払うことを強行的に義務付けています。
そのため、就業規則で労働者の退職又は死亡の場合の賃金支払期日を通常の賃金と同一日に支払うことを規定していたとしても、請求があれば7日以内に賃金を支払わなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法第1条
R7-127 01.01
労働基準法第1条を読んでみましょう!
労働基準法第1条を読んでみましょう。
法第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
<第1条のポイント!>
・ 第1条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働条件を保障することを宣明したものです。労働基準法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならないものです。
・ 労働者が人たるに値する生活を営むためにはその標準家族の生活をも含めて考えることとされます。
・ 第2項については労働条件の低下がこの法律の基準を理由としているか否かに重点を置いて認定されます。経済諸条件の変動に伴うものは本条に抵触するものとされません。
(昭和22.9.13発基第17号)
過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

【解答】
①【H19年選択式】
<A> が人たるに値する生活を営む
②【H25年出題】
労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、労働者の職場に関する一切の待遇をいいますので、賃金、労働時間、解雇、災害補償等だけでなく、安全衛生、寄宿舎等の条件も含まれます。
③【H28年出題】
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】
③【H28年出題】 〇
労働基準法第1条は、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されます。
(昭和22.9.13発基第17号)
④【H25年出題】
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。

【解答】
④【H25年出題】 〇
労働基準法で定める労働条件の最低基準が標準とならないように、この最低基準を理由として労働条件を低下させることは禁止され、その向上を図るように努めることが労働関係の当事者に義務づけられています。
⑤【R3年出題】
労働基準法第1条第2項にいう「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
「この基準を理由として」とは、労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を低下させている場合をいいます。社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合は、労働基準法の基準が理由になっていませんので、同条に抵触しません。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-112 12.17
<令和6年の問題を振り返って>労働基準法の適用単位
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労働基準法の択一式です。
労働者の定義を条文で読んでみましょう。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
労働基準法の「労働者」は、「事業」に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
「事業」のイメージです。
〇〇株式会社 | ||||
本社
|
|
工場 |
|
営業所 |
〇〇株式会社全体が事業となるのではなく、「本社」、「工場」、「営業所」それぞれが事業となります。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問2-ア】
労働基準法において一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定するが、例えば工場内の診療所、食堂等の如く同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合に、その部門が主たる部門との関連において従事労働者、労務管理等が明確に区別され、かつ、主たる部門と切り離して適用を定めることによって労働基準法がより適切に運用できる場合には、その部門を一の独立の事業とするとされている。

【解答】
【R6年問2-ア】 〇
|
|
|
| 工 場 |
|
|
| 診療所 |
<原則>
・一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定する
→ 同一場所にあるものは原則として1個の事業とする
→ 場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする
<例外>
・ 例えば工場内の診療所、食堂のように同一場所にあっても、著しく労働の態様を異にする部門が存する場合は?
→ その部門を一の独立の事業とする
・ 場所的に分散しているものであっても、出張所や支社等で、一の事業という程度の独立性がないものは?
→ 直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

①【H26年出題】 ×
労働基準法第9条にいう「事業」とは、場所的観念によって決定されるべきものです。支店、工場等それぞれが事業となりますので、それぞれで労働基準法が適用されます。
②【H29年出題】
何ら事業を営むことのない大学生が自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、その者に報酬を支払ったとしても、当該友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しないので、当該友人に労働基準法は適用されない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
労働基準法の労働者は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。
事業とは、「工場、鉱山、事務所、店舗等の如く一定の場所において相関連する組織のもとに業として継続的に行われる作業の一体をいう」とされています。
何ら事業を営むことのない大学生が、引っ越しの作業を手伝ってもらった友人は労働基準法第9条に定める労働者に該当しません。
(昭22.9.13発基17号など)
③【R4年出題】
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

【解答】
③【R4年出題】 〇
事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者は、労働基準法の労働者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-098 12.03
<令和6年の問題を振り返って>労働基準法上の賃金の解釈
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
【R6問1-E】
労働者に支給される物又は利益にして、所定の貨幣賃金の代わりに支給するもの、即ち、その支給により貨幣賃金の減額を伴うものは労働基準法第11条にいう「賃金」とみなさない。

【解答】
【R6問1-E】 ×
問題文の場合は、「賃金」とみなすとされています。
通達を確認しましょう。
① 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと。
(1) 所定貨幣賃金の代りに支給するもの、即ちその支給により貨幣賃金の減額を伴うもの。
(2) 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されているもの。
② 右に掲げるものであっても、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなさないこと。
(1)代金を徴収するもの、但しその代金が甚だしく低額なものはこの限りでない。
(2) 労働者の厚生福利施設とみなされるもの。
③ 退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し退職金、結婚手当等であって労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。
(昭22.9.13発基第17号)
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
退職手当で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、労働基準法上の「賃金」となり、「臨時に支払われる賃金」に当たります。
(昭22.9.13発基第17号)
②【R1年出題】
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は「実費弁償」に当たります。賃金ではありません。
(昭63.3.14基発150号)
③【H26年出題】
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

【解答】
③【H26年出題】 ×
賞与、家族手当、住宅手当は、労働基準法第11条の賃金に当たりますが、「解雇予告手当」は賃金ではありません。
(昭23.8.18基収2520号)
④【R3年出題】
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
労働者が法令により負担すべき所得税等を事業主が労働者に代わって負担することは、労働者が法律上当然生ずる義務を免れることとなりますので、事業主が労働者に代わって負担する部分は、福利厚生ではなく、「賃金」となります。
(昭63.3.14基発150号)
⑤【R2年出題】
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
食事の供与は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、次の要件を満たす場合は、原則として賃金ではなく「福利厚生」として取り扱われます。
①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと
②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと
③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものと認められるものであること
(昭30.10.10基発644号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-081 11.15
<令和6年の問題を振り返って>年次有給休暇の発生要件である出勤率
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
年次有給休暇の発生要件について条文を読んでみましょう。
第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
年次有給休暇の発生には
・6か月間継続勤務していること
・出勤率が8割以上あること
今回は、「出勤率」をみていきます。
出勤率は「全労働日(労働義務のある日)」に対する「出勤した日」の割合です。
出勤した日 |
全労働日 |
で算定します。
★出勤したとみなされる期間があります。
法第39条第10項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、これを出勤したものとみなす。 |
また、「年次有給休暇」を取得した日も、出勤したものとみなされます。
(H6.3.31基発181号)
★出勤率の基礎となる全労働日について
① 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。
② 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、③に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。
③ 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(1) 不可抗力による休業日
(2) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(3) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
(H25.7.10基発0710第3号)
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-E】
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、同法第39条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。

【解答】
【R6年問6-E】 ×
生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間」は、労働基準法上出勤したものとみなされませんが、「当事者の合意によって出勤したものとみなすことも差し支えない」とされています。
(H22.5.18基発0518第1号)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

【解答】
①【H28年出題】 〇
年次有給休暇を取得した日は、「出勤した」ものとして出勤率を計算します。
②【H28年出題】
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
「所定の休日に労働させた」場合におけるその日は、全労働日に「含まれません」。
(H25.7.10基発0710第3号)
③【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >というべきである。」
<選択肢>
① 影響を与えない ② 影響を与えるもの
③ 含まれない ④ 含まれるもの

【解答】
A ④ 含まれるもの
(平成25年6月6日 第一小法廷判決)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-081 11.14
<令和6年の問題を振り返って>高度プロフェッショナル制度の導入(決議の届出)
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「高度プロフェッショナル制度」の導入手順を確認しましょう。
①労使委員会を設置する
↓
②労使委員会で決議をする
※委員の5分の4以上の多数による決議がなされていることが条件です。
↓
③労使委員会の決議を所轄労働基準監督署長に届け出る
↓
④対象労働者の同意を書面で得る
↓
⑤対象労働者を対象業務に就かせる
条文を読んでみましょう。
第41条の2第1項 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により定められた事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における一定の業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第3号から第5号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。 (以下省略します) |
高度プロフェッショナル制度の対象になる労働者には、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-オ】
労働基準法第41条の2に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。

【解答】
【R6年問5-オ】 〇
高度プロフェッショナル制度の導入については、労使委員会の決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、効力が生じます。
単に労使委員会の決議が行われただけでは、導入できません。
過去問をどうぞ!
①【H17年出題】
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまでも取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。

【解答】
①【H17年出題】 ×
企画業務型裁量労働制を採用するための労使委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければなりません。届出を行わない場合は、企画業務型裁量労働制の効力は発生しません。
(法第38条の4、H12.1.1基発第1号)
②【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】
②【H24年出題】 〇
36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて、時間外労働等を行わせることが適法となります。単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れません。
(法第36条第1項)
条文で確認しましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
③【R3年出題】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】
③【R3年出題】 〇
36協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、時間外労働等は適法となります。
令和3年4月9日に所轄労働基準監督署長に届け出た場合は、効力が発生するのはその日以降ですので、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、労働基準法違反となります。
④【R4年出題】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。

【解答】
④【R4年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
ただし、届出は労使協定の効力の発生要件ではありません。届出をしていなくても、労使協定が締結されていれば1か月単位の変形労働時間制の効力が発生します。
なお、届出をしなくても効力は発生しますが、届出を怠ったことに対して罰則が適用されます。
(法第32条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-080 11.13
<令和6年の問題を振り返って>テレワークと事業場外みなし労働時間制
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラインより
★在宅勤務については、事業主が労働者の私生活にむやみに介入すべきではない自宅で勤務が行われ、労働者の勤務時間帯と日常生活時間帯が混在せざるを得ない働き方であることから、一定の場合には、労働時間を算定し難い働き方として、労働基準法第38条の2で規定する事業場外労働のみなし労働時間制(以下「みなし労働時間制」という。)を適用することができる。 在宅勤務についてみなし労働時間制が適用される場合は、在宅勤務を行う労働者が就業規則等で定められた所定労働時間により勤務したものとみなされることとなる。業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該必要とされる時間労働したものとみなされ、労使の書面による協定があるときには、協定で定める時間が通常必要とされる時間とし、当該労使協定を労働基準監督署長へ届け出ることが必要となる(労働基準法第38条の2)。 (H20.7.28基発第0728001号) |
では、事業場外みなし労働時間制の条文を読んでみましょう。
第38条の2 ① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ② ①のただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。 則第24条の2第3項 労使協定の届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該協定を届け出ることを要しない。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-ウ】
労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)においては、「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」さえ満たせば、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用することができる。

【解答】
【R6問5-ウ】 ×
「テレワーク」に、事業場外みなし労働時間制を適用できる条件を確認しましょう。
★次に掲げるいずれの要件をも満たす形態で行われる在宅勤務(労働者が自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)については、原則として、労働基準法第38条の2に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されます。
①当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと。
(H16.3.5基発第0305001号)
「情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと」のみでは、適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
上の令和6年の問題の解説のように、要件を満たした場合、情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)にも、労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制が適用されます。
②【H18年出題】
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。

【解答】
②【H18年出題】 〇
・労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いとき
↓
<原則>所定労働時間労働したものとみなされる
<業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合>
当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。
<労使協定があるとき>
労使協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる
③【R1年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

【解答】
③【R1年出題】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりませんが、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-062 10.26
<令和6年の問題を振り返って>専門業務型裁量労働制の適用手順【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
「専門業務型裁量労働制」の導入には、「労使協定」の締結が必要です。
労使協定で、対象業務やみなし労働時間を定めます。
条文を読んでみましょう。
第38条の3 ① 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を対象業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 (1) 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下「対象業務」という。) (2) 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 (3) 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 (4) 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 (5) 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 (6) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
★専門業務型裁量労働制の「対象業務」は、厚生労働省令・告示によって20業務が定められています。
★対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間は、「1日当たりの労働時間」を定めます。(みなし労働時間といいます)
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-エ】
使用者は、労働基準法第38条の3に定めるいわゆる専門業務型裁量労働制を適用するに当たっては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、専門業務型裁量労働制を適用することについて「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければならない。

【解答】
【R6年問5-エ】 〇
専門業務型裁量労働制を適用することについて、労使協定で、「当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。」を定めなければなりません。
また、「適用労働者の同意の撤回に関する手続き」も協定する必要があります。
(則第24条の2の2第3項)
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

【解答】
【H19年出題】 〇
ポイントを確認しましょう。
★労使協定に定めるべき時間は、「1日当たり」の労働時間です。
★休憩、深夜業及び休日に関する規定は適用されます。そのため、例えば、法定休日に労働させた場合には、割増賃金の支払いが必要です。
(H12.1.1基発第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-061 10.25
<令和6年の問題を振り返って>1か月単位の変形労働時間制の導入要件【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
1か月単位の変形労働時間制について条文を読んでみましょう。
第32条の2 ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(法定労働時間)を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の労使協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
★ 1か月単位の変形労働時間制を導入するには、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」が必要です。
なお、常時10人以上の労働者を使用する使用者は「就業規則」の作成と届出義務があります。
そのため、1か月単位の変形労働時間制を導入する手続きは以下のようになります。
常時使用する労働者数 | 導入要件 |
10人以上 | 労使協定 又は 就業規則 |
10人未満 | 労使協定 又は 就業規則その他これに準ずるもの |
労使協定で導入する場合は、届出が必要です。
★ 1か月以内の一定の期間(変形期間といいます)を平均して、1週間当たりの労働時間が1週間の法定労働時間(原則40時間・特例の事業場は44時間)を超えないようにしなければなりません。
変形期間の労働時間の総枠は次の式で計算します。
1週間の法定労働時間(40時間又は44時間)×変形期間の暦日数÷7
たとえば、法定労働時間が原則の40時間で、変形期間を1か月とした場合、
31日の月の労働時間の総枠は、40時間×31日÷7=177.1時間
30日の月の労働時間の総枠は、40時間×30日÷7=171.4時間
となります。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5-ア】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。

【解答】
【R6年問5-ア】 ×
常時10人未満の労働者を使用する使用者が1か月単位の変形労働時間制を適用するには、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらか必要です。
「必ず就業規則を作成」が誤りです。「労使協定」で導入することもできますし、「就業規則に準ずるもの」で導入することもできます。
なお、「1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定め」とありますが、特例の事業場の場合は「44時間」となります。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、労使の話合いによる制度の導入を促進するため、また、1か月単位の変形労働時間制以外の変形労働時間制の導入要件は労使協定により定めることとされていることも勘案し、就業規則その他これに準ずるものによる定め又は労使協定による定めのいずれによっても導入できるとされています。
就業規則その他これに準ずるものによる定めがある場合は、労使協定は不要です。
また、労使協定で採用する場合は、所轄労働基準監督署長への届出が必要ですが、届出によって効力が発生するわけではありません。そのため、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる」も誤りです。
(H11.1.29基発第45号)
②【R4年出題】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。

【解答】
②【R4年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を労使協定で採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。しかし、1か月単位の変形労働時間制の効力は労使協定の締結で発生しますので、「労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。」は誤りです。
③【H19年出題】
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

【解答】
③【H19年出題】 〇
変形期間の所定労働時間の総枠の計算式のポイントも確認しましょう。
「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」
・週法定労働時間は40時間が原則ですが、特例の事業場は44時間です。
・暦日数は、暦上の日数です。労働日数ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-045 10.9
<令和6年出題労基>就業規則等に関する問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R6年問7-A】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則は他の要件を具備していても無効とされている。

【解答】
①【R6年問7-A】 ×
絶対的必要記載事項の一部が記載されていない就業規則も、他の要件を具備している限り「有効」です。ただし、そのような就業規則を作成し届け出たとしても、使用者の法第89条違反の責任は免れません。
②【R6年問7-B】
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」及び「建設物及び設備の管理に関する事項」について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないが、これらはいわゆる必要的記載事項であるから、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されない。

【解答】
②【R6年問7-B】 〇
「起床、就寝、外出及び外泊に関する事項」、「行事に関する事項」、「食事に関する事項」、「安全及び衛生に関する事項」、「建設物及び設備の管理に関する事項」は、必要的記載事項ですので、そのいずれか一つを欠いても届出は受理されません。
(法第95条)
③【R6年問7-C】
同一事業場において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することは差し支えないが、別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となるのであって、それぞれ単独に同条の就業規則となるものではないとされている。

【解答】
③【R6年問7-C】 〇
同一事業場で、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することもできます。別個の就業規則を定めた場合には、当該2以上の就業規則を合したものが同法第89条の就業規則となります。それぞれが単独に同条の就業規則となるものではありません。
(H11.3.31基発168号)
④【R6年問7-D】
育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれるものであり、育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載する必要があるとされている。

【解答】
④【R6年問7-D】 〇
育児介護休業法による育児休業も、労働基準法第89条第1号の休暇に含まれます。育児休業の対象となる労働者の範囲等の付与要件、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、就業規則に記載しなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
⑤【R6年問7-E】
労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」は、同法の労働時間に関する規定が適用されないが、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければならないとされている。

【解答】
⑤【R6年問7-E】 〇
労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」にも法第89条は適用されます。そのため、就業規則には始業及び終業の時刻を定めなければなりません。
(S23.12.25基収4281号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-035 9.29
<令和6年度労基>第16条賠償予定の禁止からの問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
第16条の条文を読んでみましょう。
第16条 (賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |
ポイント!
「契約をしてはならない」となっていますので、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結しただけで16条違反になります。違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときではありません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-C】
使用者が労働者に対して損賠賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは、労働基準法第16条が禁止するところではないから、労働契約の締結に当たり、債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条に抵触するものではない。

【解答】
【R6年問3-C】 〇
第16条は、「金額を予定すること」を禁止しています。現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。
債務不履行によって使用者が損害を被った場合はその実損害額に応じて賠償を請求する旨の約定をしても、労働基準法第16条には抵触しません。
(昭22.9.13発基第17号)
過去問もどうぞ!
【R4年出題】
労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

【解答】
【R4年出題】 ×
違約金などを現実に徴収した時ではなく、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約を締結しただけで、違反が成立します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-034 9.28
<令和6年度労基>第3条「均等待遇」についての判例【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
まず、第3条を読んでみましょう。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
ポイント!
★第3条で禁止されている差別は、「国籍・信条・社会的身分」を理由とする差別に限定されています。「性別による差別」は第3条には含まれません。
★「有利」に取り扱うことも差別的取扱いに当たります。
では、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問1-B】
「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するものと解される。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R6年問1-B】 ×
判例のポイント!
・ 企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
・ 労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。
問題文の場合、「特定の信条を有することを、雇入れを拒む理由として定めること」も、当然に違法とすることはできません。
ちなみに、雇入れた後は、雇入れの場合のような広い範囲の自由はありません。
「労働基準法3条は、労働者の労働条件について信条による差別取扱を禁じているが、特定の信条を有することを解雇の理由として定めることも、右にいう労働条件に関する差別取扱として、右規定に違反するもの」とされています。
(大法廷判決 昭48.12.12三菱樹脂事件)
過去問もどうぞ!
【H28年出題】
労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H28年出題】 〇
労働基準法第3条は、「雇入れそのものを制限する規定ではない」とされています。
(大法廷判決 昭48.12.12三菱樹脂事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労働基準法)
R7-023 9.17
<令和6年度労基法>労働契約の問題を解いてみます
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の択一式です。
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問3】
使用者は、労働基準法第14条第2項に基づき厚生労働大臣が定めた基準により、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。

【解答】
①【R6年問3】〇
雇止めの予告の問題です。対象になる有期労働契約 (当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)に注意してください。
(有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準 H15.10.222厚生労働省告示第357号)
②【R6年出題】
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働契約の締結と有期労働契約(期間の定めのある労働契約)の更新のタイミングごとに、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」についても明示しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 〇
令和6年4月の改正で、労働条件の明示事項として、「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」が加わりました。
「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」に加え「就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲」を明示するタイミングは、「労働契約の締結時」と「有期労働契約の更新時」です。
また、原則として書面の交付による明示が必要です。
(則第4条第1項第1の3号、令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の択一式を振り返ります(労働基準法)
R7-012 9.6
令和6年度<労基法>年次有給休暇の問題を解くポイント【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法です。
令和6年の年次有給休暇の問題をどうぞ!
①【R6年問6】
月曜日から金曜日まで1日の所定労働時間が4時間の週5日労働で、1週間の所定労働時間が20時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、5労働日である。

【解答】
①【R6年問6】 ×
この問題のポイント!
比例付与の条件をおぼえましょう。(法第39条第3項、則第24条の3)
1週間の所定労働時間が30時間未満
かつ
1週間の所定労働日数が4日以下
※週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、
1年間の所定労働日数が216日以下
問題文は、1週間の所定労働時間は20時間ですが、1週間の所定労働日数が5日ですので、比例付与の対象になりません。
付与される年次有給休暇は、5労働日ではなく、通常の10労働日です。
②【R6年問6】
月曜日から木曜日まで1日の所定労働時間が8時間の週4日労働で、1週間の所定労働時間が32時間である労働者が、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に労働基準法第39条の規定により当該労働者に付与される年次有給休暇は、次の計算式により7労働日である。
〔計算式〕10日×4日/5.2日≒7.69日 端数を切り捨てて7日

【解答 】
②【R6年問6】 ×
①の問題と同様に、比例付与の条件がポイントです。
問題文は、1週間の所定労働日数は4日ですが、1週間の所定労働時間が32時間ですので、比例付与の対象になりません。
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に付与される年次有給休暇は、10労働日です。
③【R6年問6】
令和6年4月1日入社と同時に10労働日の年次有給休暇を労働者に付与した使用者は、このうち5日については、令和7年9月30日までに時季を定めることにより与えなければならない。

【解答】
③【R6年問6】 ×
この問題のポイント!
年次有給休暇の使用者の時季指定義務について
法定の基準日より前に、有給休暇を付与する場合の扱いについての問題です。
有給休暇の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないのが原則です。
しかし、基準日より前に10労働日以上の有給休暇を与えることとした場合は、「10労働日以上の有給休暇を与えることとした日から1年以内の期間に、その時季を定めることにより与えなければなりません。
令和6.4.1(入社) |
| 令和6.10.1 |
| 令和7.3.31 |
10日付与 |
| 法定の基準日 |
|
|
原則は、5日については、令和6年10月1日から1年以内(令和7年9月30日)までに、時季を定めることにより与えなければなりません。
ただし、前倒しで令和6年4月1日の入社日に付与した場合は、その日から1年以内(令和7年3月31日まで)に取得させることになります。
(法第37条第7項、則第24条の5第1項)
④【R6年問6】
使用者の時季指定による年5日以上の年次有給休暇の取得について、労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、労働基準法第39条第8項の「日数」に含まれ、当該日数分について使用者は時季指定を要しないが、労働者が時間単位で取得した分については、労働基準法第39条第8項の「日数」には含まれないとされている。

【解答】
④【R6年問6】 〇
この問題のポイント!
年次有給休暇の使用者の時季指定義務について
労働者自ら取得した半日年休・時間単位年休の取扱い
労働者が半日単位で年次有給休暇を取得した日数分については、0.5日として法第39条第8項の「日数」に含まれますので、当該日数分について使用者は時季指定を要しません。
また、労働者が時間単位で年次有給休暇を取得した日数分については、法第39条第8項の「日数」には含まれません。
(H30.12.28基発1228第15号)
⑤【R6年問6】
産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間及び生理日の就業が著しく困難な女性が同法第68条の規定によって就業しなかった期間は、労働基準法第39条第1項「使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」の適用においては、これを出勤したものとみなす。

【解答】
⑤【R6年問6】 ×
この問題のポイント!
出勤率の算定で、「出勤したものとみなす」期間
産前産後の女性が休業した期間は、「出勤したものとみなす」期間です。
一方、生理日の就業が著しく困難な女性が就業しなかった期間は、労働基準法上出勤したものとはみなされません。
(法第39条第10項、S23.7.31基収2675)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります
R7-003 8.28
<労働基準法>令和6年度選択式【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労働基準法の選択式です。
令和6年 選択問題1
年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、< A >、これを使用してはならない。」と定めている。

【解答】
<A> 児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
労基法第56条1項の「最低年齢」からの出題です。
中学校を卒業するまでは、原則として、労働者として使用できません。
令和6年 選択問題2
最高裁判所は、労働者が始業時刻及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の< B >に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の < B >に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の< B >に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。」

【解答】
<B> 指揮命令下
判例の問題です。(三菱重工長崎造船所事件)
何度も出題されていますので、過去問でもおなじみの問題です。
★ポイント!
「労働基準法上の労働時間の意義」
「労働基準法上の労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではありません。
「労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間」は、労働基準法上の労働時間に該当するとされました。
令和6年 選択問題3
最高裁判所は、賃金に当たる退職金債権放棄の効力が問題となった事件において、次のように判示した。
本件事実関係によれば、本件退職金の「支払については、同法〔労働基準法〕24条1項本文の定めるいわゆる全額払の原則が適用されるものと解するのが相当である。しかし、右全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もつて労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものというべきであるから、本件のように、労働者たる上告人が退職に際しみずから賃金に該当する本件退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合に、右全額払の原則が右意思表示の効力を否定する趣旨のものであるとまで解することはできない。もつとも、右全額払の原則の趣旨とするところなどに鑑みれば、右意思表示の効力を肯定するには、それが上告人の< C >ものであることが明確でなければならないものと解すべきである」。

【解答】
<C> 自由な意思に基づく
こちらも、過去問でおなじみの問題です。
ポイント!
賃金にあたる退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は「有効」とされています。
★令和6年度の労働基準法選択式 労働基準法選択式は、条文から1問、判例から2問でした。 過去問対策で、しっかり得点できる問題でした。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-341 8.2
労働基準法の賃金になるもの・ならないもの【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
労働基準法の賃金の定義を条文で読んでみましょう。
第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
労働基準法の賃金となるもの・ならないものを過去問でみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する場合、当該代わって負担する部分は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、労働基準法第11条の賃金とは認められない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
労働者が法令により負担すべき所得税等(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等を含む。)を事業主が労働者に代わって負担する部分は、労働者が法律上当然生ずる義務を免れるため、「賃金」となります。
※ちなみに、労働者が生命保険会社等と任意に保険契約を締結したときに、企業が保険料の補助を行う場合は、福利厚生のために使用者が負担するものとなり、賃金とは認められません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H30年出題】
いわゆるストック・オプション制度では、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法第11条の賃金には当たらない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
ストック・オプション制度から得られる利益は、労働の対償ではなく、賃金には当たりません。
(平9.6.1基発412号)
③【R1年出題】
私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たる。

【解答】
③【R1年出題】 ×
社用に用いた走行距離に応じて支給されるガソリン代は、実費弁償であり、「賃金」に当たりません。
(昭63.3.14基発150号)
④【H26年出題】
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働基準法第11条で定義する賃金に含まれる。

【解答】
④【H26年出題】 ×
解雇予告手当は賃金ではありません。
(昭23.8.18基収2520号)
⑤【H22年出題】
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

【解答】
⑤【H22年出題】 ×
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞等の恩恵的給付は、原則として賃金とはみなされません。
ただし、結婚手当等で、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確なものは、賃金となります。
(昭22.9.13発基17号)
⑥【H27年出題】
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、同法第24条第2項の「臨時に支払われる賃金」に当たる。

【解答】
⑥【H27年出題】 〇
労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である退職手当は、労働基準法第11条に定める賃金であり、「臨時の賃金等」に当たります。
(昭22.9.13発基17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-331 7.23
労基法で派遣労働者についてよく出るところ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「労働者派遣」について、「派遣労働者」・「派遣元事業主」・「派遣先事業主」の関係を確認しましょう。
下の図を見てください。
労働基準法上の義務は、労働契約関係にある派遣元事業主が負うのが原則ですが、一部、派遣先事業主が負う場合もあります。
過去問でチェックしましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
派遣先の事業に適用される規定もありますので、派遣先の指揮命令権者が使用者になることもあります。
(派遣法第44条動労基準法の適用に関する特例)
②【H30年出題】
派遣先の使用者が、派遣中の労働者に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる直接払の原則に違反しない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
派遣労働者に賃金を支払う義務があるのは、派遣元です。派遣元からの賃金を、派遣先が手渡すことだけであれば、直接払の原則に違反しません。
(昭61.6.6基発333号)
③【H18年出題】
労働者派遣中の労働者の休業手当について労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することになる。

【解答】
③【H18年出題】 〇
休業の際、休業手当を支払う義務は、派遣元にあります。
派遣労働者の休業手当について使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされます。派遣元の使用者について、派遣労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断します。
(昭61.6.6基発333号)
④【H29年出題】
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

【解答】
④【H29年出題】 ×
派遣労働者に対する労働条件(労働時間、休憩、休日等も含めて)の明示は、労働契約を締結する際に「派遣元」の使用者が行います。
なお、労働基準法上の労働時間、休憩、休日に関する規定は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により「派遣先の事業のみ」を派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされています。
(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)
⑤【H17年出題】
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

【解答】
⑤【H17年出題】 ×
派遣先の使用者が、派遣労働者に時間外・休日労働を行わせる場合は、「派遣元」の事業場で、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(昭61.6.6基発333号、労働者派遣法第44条)
⑥【H25年出題】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。

【解答】
⑥【H25年出題】 〇
派遣労働者については、「派遣元」で36協定を締結しますので、派遣元の労働者には派遣労働者が含まれます。
問題文は、「派遣先」ですので、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含みません。
(昭61.6.6基発333号)
⑦【H16年出題】
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。

【解答】
⑦【H16年出題】 〇
派遣労働者については、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、「派遣元」の事業についてなされます。
代替労働者の派遣の可能性も含めて、「派遣元」の事業の正常な運営を妨げるかどうかを判断することになります。
(昭61.6.6基発333号)
⑧【H25年出題】
派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

【解答】
⑧【H25年出題】 〇
派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、「派遣元」の使用者です。常時10人以上の人数には、派遣中の労働者も含みます。
(昭61.6.6基発333号)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
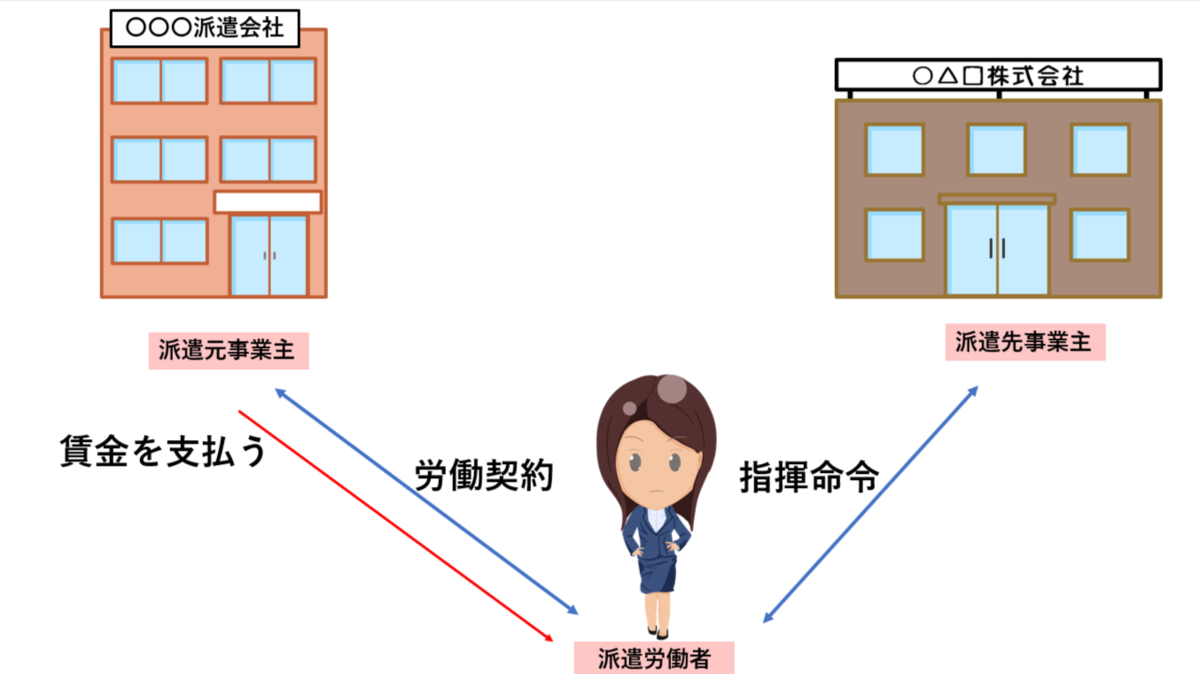
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-320 7.12
賃金の重要問題5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「賃金」の重要ポイントを過去問でみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
健康診断の結果に基づいて、医師の証明の範囲内で、使用者が休業を命じた場合には、使用者は労務の提供のなかった限度で賃金を支払わなくても差し支えないとされています。
問題文の休業を命じた日については「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当しません。
(昭63.3.14基発150号)
②【H23年出題】
労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労務の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労務を受領したものといえ、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
②【H23年出題】 ×
・労働者が、業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したこと
↓
債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえない
・使用者が、業務命令を事前に発したということは
↓
その指定した時間については出張・外勤以外の労務の受領をあらかじめ拒絶したものと解すべき
・労働者が提供した内勤業務については
↓
労務を受領したものとはいえない
・使用者は、労働者に対し内勤業務に従事した時間に対する賃金の支払義務は負わない
(昭和60年3月7日最高裁判所第1小法廷)
③【H23年出題】
労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
③【H23年出題】 ×
80%条項は、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を基礎として稼働率を算定する限りにおいては、有効です。
しかし、労働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎としている点は、公序に反し無効とされています。
労働基準法又は労働組合法上の権利を行使したことにより経済的利益を得られないこととすることによって権利の行使を抑制し、労働者に各権利を保障した趣旨を実質的に失わせることになるからです。
(平成元年12月14日最高裁判所第一小法廷)
④【H23年出題】
労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。

【解答】
④【H23年出題】 〇
5分の遅刻で、30分遅刻したものとして賃金カットをすることは、全額払違反となります。
ただし、第91条の減給制裁の制限内で行う場合は全額払い違反にはなりません。
(第91条 昭63.3.14基発150号)
⑤【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
家族手当は、割増賃金の基礎となる賃金に含めないことが原則です。
ただし、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎となる賃金に含めなければなりません。
(第37条 昭22.11.5基発231号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-319 7.11
おさえておきたい解雇のルール5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「解雇」のルールを過去問でチェックしていきます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができませんが、労働者が自由な判断で同意した場合は、取り消すことができるとされています。ただし、解雇予告の意思表示の取消しに対して労働者の同意がない場合は、取り消すことはできません。
問題文は、労働者は、解雇の取り消しの申出に同意せず、それに応じなかったため、予告どおりに解雇となります。任意退職にはなりません。
(昭33.2.13基発90号)
②【H24年出題】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

【解答】
②【H24年出題】 ×
即時解雇の効力が発生する日は、「即時解雇の意思表示をした日」or「解雇予告除外認定のあった日」どちらの日でしょうか?
解雇予告除外認定は、解雇の意思表示をする前に受けるのが原則です。
解雇予告除外認定は、除外事由に該当する事実があるか否かを確認する処分です。
認定されるべき事実がある場合は、使用者は有効に即時解雇することができます。
そのため、即時解雇の意思表示をした後に、解雇予告除外認定を受けた場合は、解雇の効力は、「使用者が即時解雇の意思表示をした日」に発生します。
(昭63.3.14基発150号)
③【H24年出題】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 〇
解雇予告について確認しましょう。
★30日前に予告する
例えば、8月31日に解雇する場合は、遅くとも8月1日には解雇予告をしなければなりません。
解雇の予告をした日は、予告期間に算入されないことがポイントです。
★即時解雇の場合は、解雇予告手当を支払う
即時解雇をする場合は、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払わなければなりません。
★予告期間と予告手当を組み合わせて30日にする
8月31日をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をした場合、予告期間は16日です。(解雇の予告をした日は算入しません。)そのため、解雇予告手当は、平均賃金の14日分以上が必要です。
(第20条第1項)
④【H24年出題】
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。

【解答】
④【H24年出題】 ×
解雇の予告期間中に、業務上の負傷をし療養のため休業した場合、たとえ休業期間が1日~2日の軽度のものでも労働基準法第19条が適用されますので、その後30日間は解雇できません。解雇の効力は、当初の予告どおりの日には発生しません。
(昭26.6.25基収2609号)
⑤【H24年出題】
労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等、労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
解雇も「退職」のひとつで、「退職」には、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等があります。
(第89条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-306 6.28
<選択式>最高裁判所の判例からの問題【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H21年選択式】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の< A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 経済生活の安定 ② 生活保障 ③ 最低賃金の保障
④ 不利益の補償

【解答】
①【H21年選択式】
A ① 経済生活の安定
★過払調整について
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労働基準法第24条第1項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではないと解するのが相当である。
この見地からすれば、許さるべき相殺は、過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならないものと解せられる。
(昭44.12.18最高裁判所第一小法廷)
②【H21年選択式】
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< B >という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の< B >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度で負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない。」としている。
<選択肢>
① 経済生活の安定 ② 生活保障 ③ 最低賃金の保障
④ 不利益の補償

【解答】
②【H21年選択式】
B ② 生活保障
★休業手当と民法536条第2項との関係について
「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条第2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。
(昭62.7.17最高裁判所第二小法廷)
③【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< C >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< C >というべきである。」
<選択肢>
① 影響を与えない ② 影響を与えるもの ③ 含まれない
④ 含まれるもの

【解答】
③【H26年選択式】
C ④ 含まれるもの
★労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日について
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
(平25.6.6最高裁判所第一小法廷)
④【H22年選択式】
賞与の対象期間の出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする就業規則の規定における出勤率の算定に当たり、労働基準法第65条の定める産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて、「労働基準法65条〔等〕の趣旨に照らすと、これにより上記権利〔産前産後休業の取得の権利〕等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、 < D >として無効となる」とするのが最高裁判所の判例である。
<選択肢>
① 権利の濫用 ② 公序に反するもの ③ 信義に反するもの
④ 不法行為

【解答】
D ② 公序に反するもの
★出勤率が90%以上であることを賞与の支給要件とする場合の出勤率の算定で、産前産後休業等を出勤日数に含めない取扱いについて
・ 従業員の年間総収入額に占める賞与の比重が高いため,90%条項で賞与が支給されない者の受ける経済的不利益が大きい
・従業員が産前産後休業等を取得した場合には,それだけで90%条項に該当して賞与の支給を受けられなくなる可能性が高い
・産前産後休業の取得の権利を保障した趣旨を実質的に失わせるというべきであるから、公序に反し無効である。
(平15.12.4最高裁判所第一小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-296 6.18
<選択式>監督又は管理の地位にある者の範囲【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
選択式の過去問をみていきます。
【H24年選択式】
労働基準法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について< A >の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方による。
(1) 原則
労働基準法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2) 適用除外の趣旨
〔略〕
(3) 実態に基づく判断
〔略〕
(4) 待遇に対する留意
管理監督者であるかの判定に当たっては、上記〔(1)から(3)〕のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、< B >待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。
(5) スタッフ職の取扱い
【略】
【選択肢】
① 課長相当職以上の ②経営者と一体的な立場にある者
③ 事業主のために行為をするすべての者
④ 使用者の利益を代表するすべての者
⑤ その地位にふさわしい ⑥ 取締役に近い
⑦ 部下の割増賃金を上回る ⑧ 複数の部下を持ち指揮命令を行っている者

【解答】
A ② 経営者と一体的な立場にある者
B ⑤ その地位にふさわしい
ポイント!
適用除外の趣旨を確認しましょう。
「職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。」とされています。
★「『監督若しくは管理の地位にある者』とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」とされています。
★「定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要がある」とされています。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-282 6.4
解雇の基本5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「解雇」の基本をみていきます。
なお、「解雇」とは、使用者が一方的に労働契約を終了させることです。
「労働契約法」では、「客観的に合理的な理由」がなく、社会通念上「相当と認められない」場合は、労働者を解雇することはできないことが定められています。
「労働基準法」では、解雇する際のルールとして、「解雇予告」、「解雇制限」が定められています。
過去問を解きながら基本を確認しましょう。
まず、第20条の条文を読んでみましょう。
第20条 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ② 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 第1項但書の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
労働者を解雇する場合は、少くとも30日前に予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
また、予告期間は、1日について平均賃金を支払った場合は、日数を短縮できます。例えば、10日分の平均賃金を支払った場合は、20日前に予告することになります。
また、次の場合は、解雇予告は要りません。
1天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
2労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合
ただし、1も2もその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受ける必要があります。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。

【解答】
①【H23年出題】 ×
労働者の一方的な労働契約の解約(任意退職)には、労働基準法第20条の規定は適用されません。
②【H23年出題】
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処せられる。

【解答】
②【H23年出題】 ×
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇」をしたとしても、労働基準法の罰則の対象にはなりません。
なお、解雇の民事的効力については、労働基準法ではなく、「労働契約法」に定められています。
労働契約法第16条 (解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 |
有効・無効の判断は、労働基準監督署ではなく、裁判所が行います。
③【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者に、適用されることがあります。
条文を読んでみましょう。
第21条 労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、(1)に該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、(2)若しくは(3)に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は(4)に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 (1) 日日雇い入れられる者 (2) 2か月以内の期間を定めて使用される者 (3) 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 (4) 試の使用期間中の者 |
試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、予告期間、予告手当が適用されます。
④【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。

【解答】
④【H23年出題】 ×
第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者にも適用されます。期間の途中で解雇する場合には、解雇の予告が必要です。
(第21条)
⑤【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。

【解答】
⑤【H23年出題】 〇
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能」となった場合は、予告手当を支払うことなく、即時に解雇することができますが、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要です。
(第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
休憩時間のすべてお話します
R6-281 6.3
休憩とは?条文読んでみましょう、過去問も!
・休憩時間とはどんな時間のことでしょう?
・労働時間がちょうど6時間の場合の休憩時間は?
・休憩付与の3つの原則は「途中付与」、「一斉付与」、「自由利用」です
・条文(第34条)を読んでみましょう
・過去問も解いてみましょう
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-269 5.22
絶対的必要記載事項の具体的な内容【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
就業規則には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
「絶対的必要記載事項」は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
今回は、絶対的必要記載事項の内容をみていきます。
まず、「絶対的必要記載事項」を確認しましょう。
絶対的必要記載事項は次の3つです。
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (2)賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (第89条第1号~3号) |
では、具体的な内容をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、絶対的必要記載事項です。
ちなみに、「臨時の賃金等」は、相対的必要記載事項です。
(第89条第1号)
②【H26年出題】
労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法第89条第1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
フレックスタイム制を採用する場合は、就業規則で、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定め」をすれば、「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務の要件を満たします。
また、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項も「始業及び終業の時刻」に関する事項ですので、就業規則に記載しなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
③【H28年出題】
労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」については、労働基準法の労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないから、就業規則に始業及び終業の時刻を定める必要はない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」にも第89条は適用されます。そのため、就業規則には、始業及び終業の時刻を定めなければなりません。
(S23.12.25基収4281号)
④【R1年出題】
同一事業場において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、例えば「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めることで差し支えない。

【解答】
④【R1年出題】 ×
労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則には、「勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻」を規定しなければなりません。
「労働時間は1日8時間とする」と労働時間だけ定めるだけでは足りません。
(H11.3.31基発168号)
⑤【H30年出題】
就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。

【解答】
⑤【H30年出題】 〇
絶対的必要記載事項の「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれます。
育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間を就業規則に記載する必要があります。
なお、対象者、申出手続、育児休業期間等は育児介護休業法に具体的に定められていますので、「育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定め」があれば記載義務は満たしている、とされています。
(H11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-268 5.21
労働基準法の労働者の具体例7問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
まず労働基準法の「労働者」の定義を条文で読んでみましょう。
第9条 (定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
①事業に「使用」される者で、②その対償に「賃金」が支払われる者は、労働基準法の労働者となります。
今回は、労働者に該当するか否かの具体例をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。

【解答】
①【R4年出題】 ×
法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではありません。
(H11.3.31基発168号)
②【H29年出題】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。

【解答】
②【H29年出題】 〇
株式会社の取締役でも、工場長、部長等職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働者として労働基準法の適用を受けます。
(S23.3.17基発461号)
③【R4年出題】
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

【解答】
③【R4年出題】 〇
事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者となります。そのような場合は、明確な契約関係がなくても労働基準法が適用されます。
④【H29年出題】
医科大学付属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

【解答】
④【H29年出題】 ×
研修医が、医療行為等に従事することは、「教育的な側面を強く有するもの」ではなく「病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなる」のであり、「病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価できる」限り、研修医は労働基準法第9条所定の「労働者に当たる」ものというべきである、とされています。
(H17.6.3最高裁判所第二小法廷)
⑤【H27年出題】
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
請負契約と労働契約は異なります。
「請負」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること」です。(民法632条)
請負は、業務を自己の業務として相手方から独立して処理するものです。(S23.1.9基発14号)
しかし、請負契約の形式をとっていても、使用従属関係の実体が認められるときは、その関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法の「労働者」に当たります。
⑥【H29年出題】
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多いです。しかし、請負契約によらず雇用契約によってその事業主と大工との間に使用従属関係が認められる場合は、労働者となり、労働基準法の適用を受けます。
大工が労働者に該当し、労働基準法が適用されることもあります。
(H11.3.31基発168号)
⑦【R1年出題】
いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。

【解答】
⑦【R1年出題】 〇
次の4つの全てに該当する芸能タレントは、労働基準法の労働者にはなりません。
①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている
②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない
③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない
④契約形態が雇用契約ではない
(S63.7.30基収355号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-255 5.8
第91条制裁規定の制限【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
今日は「制裁規定」をみていきます。
「制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」を就業規則に記載しなければなりません。(相対的必要記載事項です)
制裁の種類は、譴責、減給、出勤停止、懲戒解雇等がありますが、制裁の種類及び程度については、労働基準法上の制限はありません。
ただし、「減給の制裁」については、労働基準法上の制限が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
減給制裁の制限
・1回の事案について
→ 減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければなりません
※例えば、平均賃金が1万円なら、1回の事案で減給できるのは5千円までです
・一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額について
→当該賃金支払期における賃金総額の10分の1以内でなければなりません
※例えば、当該賃金支払期の賃金総額が25万円なら、減給の総額は2万5千円以内です。5件の事案が発生した場合は、5千円×5回=2万5千円まで減給できます。
※事案が6件になった場合は、2万5千円を超えた部分は次期賃金支払期に延ばさなければなりません。
(昭23.9.20基収1789号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
「一賃金支払期における賃金の総額」は、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいいます。
欠勤や遅刻等で賃金総額がカットされたときは、カットされた賃金総額を基礎として10分の1を計算します。
(昭25.9.8基収1338号)
②【R2年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。

【解答】
②【R2年出題】 ×
遅刻・早退・欠勤で労働の提供がなかった時間分の賃金を差し引くことは、減給制裁に当たりませんので、労働基準法第91条による制限は受けません。
※ただし、遅刻早退の時間分の賃金額を超える減給は制裁とみなされ、第91条の制限を受けます。
(昭63.3.14基発150号)
③【R3年出題】
就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第91条に違反する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めても、減給制裁に当たらないとされています。
(昭26.3.31基収938号)
④【H28年出題】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。

【解答】
④【H28年出題】 ×
出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、出勤停止の当然の結果となり、減給制裁に当たりません。
(昭23.7.3基収2177号)
⑤【H30年出題】
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。

【解答】
⑤【H30年出題】 ×
「制裁事由発生日(行為時)」ではなく、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
(昭30.7.19基収5875号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-254 5.7
必要記載事項の一部を記載しない就業規則の効力【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
就業規則の作成について条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 (1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (2)賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (4)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 (5) 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 (6) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 (7) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (8) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (9) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (10) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 (11) 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
(1)から(3)は必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」、(4)から(11)は定めをする場合は記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「退職手当」に関する事項は相対的必要記載事項です。退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項を、就業規則に規定しておかなければなりません。
不支給事由又は減額事由は、退職手当の決定、計算の方法に該当しますので、就業規則に記載する必要があります。
(H12.3.31基発168号)
②【H30年出題】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
「制裁の定め」は相対的必要記載事項です。制裁の定めをする場合は、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければなりません。制裁を定めをしない場合は、記載義務はありませんので、その旨を記載する義務もありません。
(第89条第9号)
③【H26年出題】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。

【解答】
③【H26年出題】 ×
絶対的必要記載事項の一部、又は、相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則も、その効力発生について他の要件を具備する限り有効とされています。「無効となる」は誤りです。
ただし、第89条違反の責を免れません。
(H11.3.31基発168号)
④【R3年出題】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることができるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効ですが、同条違反の責任は「免れない」とされています。
(H11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-252 5.5
休業手当の支払義務【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
「休業手当」の条文を読んでみましょう。
第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
使用者が本条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
「休日」については、休業手当を支給する義務はありません。
(S24.3.22基収4077号)
②【R3年出題】
就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、更に当該休職者に対しその休職期間中の賃金は月額の2分の1を支給する旨規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限りにおいては、使用者に本条の休業手当の支払義務は生じない。

【解答】
②【R3年出題】 ×
就業規則に、問題文のような規則を定めていても、定めていなくても、使用者の責に帰すべき事由による休業に対しては、平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
「会社の業務の都合」が使用者の責に帰すべき事由に該当する場合は、賃金規則に平均賃金の100分の60に満たない額の賃金を支給することを規定しても無効である、とされています。
(S23.7.12基発1031号)
③【R3年出題】
親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は本条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
問題文の事由は「使用者の責に帰すべき事由」に該当します。資材資金の不足による休業は、使用者の責任です。
(S12.6.11基収1998号)
④【R3年出題】
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。

【解答】
④【R3年出題】 〇
新規学卒者の採用内定については、一般的には、企業の例年の入社時期を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられます。
そのような場合に、企業の都合で就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間については、休業手当を支給すべきものと解されています。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-236 4.19
社労士受験のための
割増賃金②割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
例えば、時間外労働をさせた場合、「通常の労働時間」の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
通常の労働時間の賃金の計算式は、「月によって定められた賃金」については、「その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」と定められています。
詳しくはこちらの記事をどうぞ
なお、基本給と手当が支払われている場合は、手当も含めて計算します。
しかし、割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当が定められていますので、確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第37条第5項 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
則第21条 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 (1) 別居手当 (2) 子女教育手当 (3) 住宅手当 (4) 臨時に支払われた賃金 (5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
割増賃金の基礎に算入しなくてもよい手当は、頭文字をとって「か・つ・べ・し・ん・いち・の住宅」です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】
①【H26年出題】 〇
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づくものですので、割増賃金の基礎となる賃金から除外されます。
(則第21条)
②【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
家族手当も、通勤手当と同じく、労働とは直接関係のない個人的事情に基づくものですので、割増賃金の基礎となる賃金から除外されます。
しかし、「家族手当」といっても、扶養家族数に関係なく一律に支給される手当や、独身者に対しても一定額が支払われている場合は、「家族手当」とはみなされません。
そのため、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含めなければなりません。
(S23.11.5基発231号)
③【H19年出題】
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
「住宅手当」は、家族手当、通勤手当と同じく、労働とは直接関係のない個人的事情に基づくものですので、割増賃金の基礎となる賃金から除外されます。
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、「住宅に要する費用」に応じて算定される手当をいいます。
問題文のように、「住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当」や、「全員に一律に定額で支給される手当」は、除外される「住宅手当に該当しません」ので、割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しなければなりません。
(則第21条、H11.3.31基発170号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-235 4.18
社労士受験のための 割増賃金①通常の労働時間1時間当たりの賃金額
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第37条第1項、4項 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) ① 使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 |
割増賃金の率を確認しましょう。
・ 時間外に労働させた場合 →2割5分以上
1か月60時間を超えた場合 →超えた分は5割以上
・ 休日に労働させた場合 → 3割5分以上
・ 深夜に労働させた場合 → 2割5分以上
例えば、時間外労働を5時間させた場合は、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」×1.25×5時間で計算します。
「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」の計算についてみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数:240日
計算の基礎となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間
(A)300,000円÷(21×7)
(B)300,000円÷(21×8)
(C)300,000円÷(30÷7×40)
(D)300,000円÷(240×7÷12)
(E)300,000円÷(365÷7×40÷12)

【解答】
(D)300,000円÷(240×7÷12)
通常の労働時間の賃金の計算式は、「月給制(月によって定められた賃金)」の場合は、
「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」と定められています。 (則第19条第1項第4号)
原則は、「月給÷その月の所定労働時間数」ですが、月によって所定労働時間数が異なる場合には、「月給÷1年間における1月平均所定労働時間数」で計算します。
問題文は、月によって所定労働時間数が異なりますので、月給を、「1年間における 1月平均所定労働時間数」で除します。
「1年間における1月平均所定労働時間数」は、年間の所定労働時間数のトータル(年間所定労働日数×1日の所定労働時間数)を1年間の月数(12か月)で除して計算できます。
問題文では、年間所定労働日数は240日、1日の所定労働時間数は7時間です。(拘束時間8時間から休憩1時間を引いた時間です)
「1年間における1月平均所定労働時間数」の計算式は、240日×7時間÷12か月です。
通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式は、
300,000円÷(240×7÷12)となります。
(則第19条第1項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-219
R6.4.2 休業手当の重要ポイント
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
休業手当について条文を読んでみましょう。
第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
【H27年出題】
労働基準法第26条に定める休業手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
問題①
使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。

【解答】
問題① ×
★テーマ 休日に休業手当の支給義務はない
就業規則や労働協約で「休日」と定められている日には、休業手当を支給する義務がありません。問題文の場合は、土日が休日ですので、使用者は、5日分の休業手当を支払わなければなりません。
(昭24.3.22基収4077号)
問題②
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

【解答】
問題② 〇
★ テーマ 休業期間が一労働日に満たない場合の休業手当の額
現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
問題文は、所定労働時間が4時間に短縮され、現実に就労した時間に対して7,500円の支払がなされています。平均賃金10,000円の100分の60以上ですので、賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法となりません。
(昭27.8.7基収3445号)
問題③
就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。

【解答】
問題③ 〇
★ テーマ 休日に休業手当の支給義務はない
日曜日の休日をあらかじめ振り替えて水曜日とした場合、水曜日は休日になりますので、休業手当を支払う義務は生じません。
(昭24.3.22基収4077号)
問題④
休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。

【解答】
問題④ 〇
★テーマ 「休業」の定義
「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれます。
問題⑤
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
問題⑤ 〇
★テーマ 休電による休業には原則として休業手当の支払義務はない
休電による休業は、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないので、休業手当を支払わなくても第26条違反になりません。
(昭26.10.11基発696号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-208
R6.3.22 年次有給休暇⑥計画的付与
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
計画的に有給休暇の取得日を定めることを、計画的付与といいます。
条文を読んでみましょう。
第39条第6項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。 |
計画的付与の導入によって、気がねなく年次有給休暇を取得できるなどの効果が期待できます。
計画的付与の導入には、労使協定が必要です。
また、計画的付与の対象になるのは、有給休暇の日数のうち、5日を超える部分です。労働者が個人的な事由で有給休暇を取得できるよう、5日は残しておく必要があります。
例えば、有給休暇の日数が20日の場合、計画的付与の対象にできるのは、15日までです。
過去問をどうぞ!
①【H15年出題】
いわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法第39条第6項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が生じたときには、使用者は、相当程度の時間的余裕をもって行えば、当該労働者について、時季変更権を行使することができる。
②【H26年出題】
労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められていない。

【解答】
①【H15年出題】 ×
計画的付与については、労働者の時季指定権も使用者の時季変更権も行使できません。
(H22.5.18基発0518第1号)
②【H26年出題】 〇
有給休暇の計画的付与として、時間単位年休を与えることは認められていません。
(H21.5.29基発0529001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-207
R6.3.21 年次有給休暇⑤時季指定権と時季変更権
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第5項 使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 |
年次有給休暇は、「労働者の請求する時季」に与えることが原則です。(時季指定権)
しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」は、使用者は、時季を変更することができます。(時季変更権)
過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第30条第5項(当時は第3項)に定める使用者による時季変更権の行使の有効性が争われた事件において、次のように判示した。「労基法39条3項〔現行5項〕ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たって、< A >配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがって、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して< A >を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより< A >が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。そして、年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところである〔‥…〕から、勤務割を変更して< A >を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の目的いかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されないものであり、右時季変更権の行使は、結局、事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないものとして、無効といわなければならない。」
②【R5年出題】
労働基準法第30条第5項にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H27年選択式】
A 代替勤務者
(最高二小S62.7.10)
ポイント!
勤務割(シフト制)の事業場で、使用者が、通常の配慮をすれば、シフトを変更して代替勤務者を配置することが可能な状況であるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできない。
シフトを変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の目的によってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、許されない。
②【R5年出題】 〇
①の判例と同じです。
(最高二小S62.7.10)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-205
R6.3.19 年次有給休暇③出勤率の算定「出勤したものとみなす」
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
年次有給休暇の権利は、次の2つの要件を満たせば、法律上当然に発生します。
①雇入れの日から 6か月継続勤務 |
| ②全労働日の 8割以上出勤 |
出勤率は、「全労働日」に対する「出勤した日」の割合です。
実際は出勤していなくても、出勤したと「みなす」日があります。
条文を読んでみましょう。
第39条第10項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、出勤したものとみなす。 |
・業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
・育児休業又は介護休業をした期間
・産前産後の女性が休業した期間
は、出勤率については「出勤」として算定されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。
②【H28年出題】
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

【解答】
①【H18年出題】 ×
子の看護休暇を取得した期間は、出勤したものとみなす扱いにはなりません。
(法第39条第10項)
②【H28年出題】 〇
年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして取り扱います。
(H6.3.31基発181号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-204
R6.3.18 年次有給休暇②出勤率の算定「全労働日」
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
年次有給休暇の権利は、次の2つの要件を満たせば、法律上当然に発生します。
①雇入れの日から 6か月継続勤務 |
| ②全労働日の 8割以上出勤 |
年次有給休暇の権利の発生要件である「出勤率」は、「全労働日」に対する「出勤した日」の割合です。
「全労働日」とは、労働義務のある日のことで、暦日数から所定の休日を除いた日数のことです。
「全労働日」についての通達を確認しましょう。
1 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、2に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。 2 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。 (1) 不可抗力による休業日 (2) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 (3) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 (平25.7.10基発0710第3号) |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
②【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >というべきである。」

【解答】
①【H28年出題】 ×
年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいいます。
所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものとされています。
(平25.7.10基発0710第3号)
②【H26年選択式】
A 含まれるもの
★「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」の扱いについて
※不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等は、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれます。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日など、「労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日」は、出勤日数に算入すべきものとして「全労働日に含まれるもの」とされます。
解雇の日から解雇無効が確定するまでの期間について、その期間の労働日を全労働日に含めた上でその全部を出勤日として取り扱うことで、年次有給休暇の成立要件を満たしているものということができます。
(平25.6.6第一小法廷判決 平25.7.10基発0710第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-203
R6.3.17 年次有給休暇①権利の発生
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項・2項 (年次有給休暇) ① 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 ② 使用者は、1年6か月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6か月を超えて継続勤務する日(以下「6か月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、①の日数に、次の表の上欄に掲げる6か月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。 ただし、継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
|
年次有給休暇の付与日数を確認しましょう。
継続 勤務 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月以上 |
付与 日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
年次有給休暇の発生要件は、次の2つです。
①雇入れの日から 6か月継続勤務 |
| ②全労働日の 8割以上出勤 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働基準法第39条の趣旨は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりのある生活の実現にも資するという位置づけから、休日のほかに毎年一定日数以上の有給休暇を与えることにある。
②【H20年出題】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
③【R4年出題】
年次有給休暇の権利は、「労基法39条1項、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまって始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
④【H24年出題】
労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところであり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
「休日のほかに毎年一定日数以上の有給休暇を与える」の部分がポイントです。
「休日」は、「労働義務がない日」です。
年次有給休暇の「休暇」は「労働義務が免除される日」ですので、休暇は労働義務のある「労働日」に取得します。そのため、年次有給休暇は1労働日、2労働日と算定します。
②【H20年出題】 〇
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利です。
労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく、「請求」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないとされています。
(最高裁第二小法廷 昭和48年3月2日 白石営林署事件)
③【R4年出題】 ×
年次有給休暇の権利は、「労基法39条1項、2項の要件が充足されることによって「法律上当然に労働者に生ずる権利」であって、「労働者の請求をまって始めて生ずるものではなく」、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、「労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』」の観念を容れる余地はない」とされています。
ポイント!
・年次有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に労働者に生ずる権利で、労働者からの請求をまって生ずるものではありません。
(最高裁第二小法廷 昭和48年3月2日 白石営林署事件)
④【H24年出題】 〇
年次有給休暇をどのように利用するかは、労働者の自由です。
病気療養のために年次有給休暇を利用することもできます。
(昭24.12.28基発第1456号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-189
R6.3.3 平均賃金のポイント!
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第12条第1項・2項 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 (1) 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 (2) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と(1)の金額の合算額 ② 平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
★平均賃金の原則の計算式
3か月間に支払われた賃金の総額 |
その期間の総日数(暦日数) |
★平均賃金の最低保障額(賃金の全部が日給制、時間給制、出来高払制の場合)
賃金の総額 | × | 60 |
労働した日数 | 100 |
第12条第3項・4項 ③ 平均賃金の算定期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、算定期間及び賃金の総額から控除する。 (1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 (2) 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 (3) 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 (4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間 (5) 試みの使用期間 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 |
★③は「分子」(賃金総額)からも、「分母」(総日数)からも控除します
★④は、「分子」(賃金総額)からのみ控除します。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
②【H27年出題】
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
③【H27年出題】
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
④【H27年出題】
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
⑤【H27年出題】
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
賃金の総額に算入しない賃金は、
・臨時に支払われた賃金
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金(現物給与)で一定の範囲に属しないもの
です。
「通勤手当及び家族手当」は賃金総額に含みます。
(第12条第4項)
②【H27年出題】 ×
「公民権の行使により休業した期間」は、休業した期間の日数も賃金も平均賃金の計算に算入します。
賃金総額・その期間の日数の両方から控除されるのは以下の期間です。
(1) 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
(2) 産前産後の女性の休業期間
(3) 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
(4) 育児休業、介護休業期間
(5) 試用期間
(第12条第4項)
③【H27年出題】 ×
労働基準法施行規則第48条で、「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」と定められていますので、「死亡した日」は誤りです。
(則第48条)
④【H27年出題】 〇
「平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。」と規定されています。
賃金締切日が毎月月末で、7月31日に算定事由が発生した場合は、直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となります。
(第12条第2項)
⑤【H27年出題】 ×
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、それぞれの賃金ごとの賃金締切日から起算します。
6月25日に算定事由が発生した場合、
基本給(毎月月末締め)は、5月31日から遡った3か月
時間外手当(毎月20日締め)は、6月20日から遡った3か月
となります。
(S26.12.27基収5926号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-176
R6.2.19 1週間の労働時間を44時間とする特例
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について 8時間を超えて、労働させてはならない。
則第25条の2第1項 (法第40条) 使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。 第8号 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業) 第10号 映画・演劇業(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業) 第13号保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業) 第14号接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業) |
法定労働時間が1週間44時間となる特例が適用されるのは、以下の業種です。
常時10人未満の
・商業
・映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。)
・保健衛生業
・接客娯楽業
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)、第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。
②【H18年出題】
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
労働時間の特例は、1週間について「44時間」、1日について「8時間」までです。
(法第32条、40条、則第25条の2第1項)
②【H18年出題】 〇
物品の販売の事業は、法別表第1第8号の事業です。常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。
(法第32条、40条、則第25条の2第1項)
こちらもチェックしましょう。
・ 「1か月単位の変形労働時間制」と「フレックスタイム制」には、44時間の特例が適用されます。
例えば、1か月単位の変形労働時間制の変形期間の労働時間の総枠を計算する場合、特例対象の事業の場合は、44時間×変形期間の暦日数/7で計算します。
・ 「1年単位の変形労働時間制」と「1週間単位の非定型的変形労働時間制」には、44時間の特例は適用されません。
(H11.3.31基発170号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-166
R6.2.9 1か月単位の変形労働時間制の採用ルール
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
1か月単位の変形労働時間制について条文を読んでみましょう。
第32条の2 ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間・特例44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において40時間(特例44時間)又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
★ 1か月単位の変形労働時間制は、「1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間・特例44時間)を超えない」ことが条件です。
変形期間の所定労働時間の総枠は、次のように計算します。この範囲内なら平均すると1週間当たりの労働時間は、法定労働時間以内になります。
1週間の法定労働時間 (40時間・特例44時間) |
× | 変形期間の暦日数 |
7 |
例えば、法定労働時間が40時間の事業場で、変形期間を1か月とし暦日数が31日の場合の総枠は、40時間×31日/7=177.1時間となります。
1か月の総労働時間が177.1時間以内なら、特定された週に40時間又は特定された日に8時間を超えて労働させることができます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。
③【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
④【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。
⑤【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」又は「労使協定」のどちらかで採用できます。
ちなみに、10人以上の事業場は、就業規則の作成義務がありますので、「就業規則に準ずるもの」では採用できません。10人以上の事業場は、「就業規則」又は「労使協定」のどちらかになります。
「その他これに準ずるもの」は10人未満の事業場のみに適用されます。
また、10人以上でも10人未満でも、1か月単位の変形労働時間制を「労使協定」で採用する場合は、協定を所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。届出義務はありますが、届出をしなくても効力は発生します。そのため、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。」は誤りです。
(法第32条の2)
②【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、その期間の起算日を定める必要があります。
変形期間を1か月とする場合、毎月1日から月末までの暦月という要件はありません。
ちなみに、変形期間は1か月以内なら、例えば、2週間、4週間なども可能です。
(則第12条の2)
③【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、変形期間の所定労働時間の合計が40(又は44)×変形期間の暦日数/7の範囲内となることが条件です。
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度や1週間の労働時間の限度は定められていません。
(S63.1.1基発第1号)
④【R1年出題】 〇
★1か月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間です。
①1日について
→ 就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週間について
→ 就業規則その他これに準ずるものにより40時間(特例44時間)を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間(特例44時間)を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③ 変形期間について
→ 変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
問題文の場合、「1日6時間」の日ですので、①の「それ以外の日」に当たり、時間外労働となるのは、「8時間を超えて労働した時間」です。その日の労働時間は8時間ですので、延長した2時間は時間外労働にはなりません。
(S63.1.1基発第1号)
⑤【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者には適用されません。
(第60条)
「育児を行う者」については「適用しない」ではなく、「配慮をしなければならない」となっています。
条文を読んでみましょう。
則第12条の6 使用者は、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-156
R6.1.30 就業規則の作成・届出の義務
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 (1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 (2) 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (4) 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 (5) 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 (6) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 (7) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (8) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (9) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 (10) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 (11) 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 |
ポイント!
第89条の(1)、(2)、(3)は就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項です。
(4)から(11)は、定めをする場合は記載しなければならない相対的必要記載事項です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。
②【R2年出題】
1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。
③【R2年出題】
慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。
④【R3年出題】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。
⑤【H26年出題】
労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議することまで使用者に要求しているものではない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成・届け出義務があります。
派遣中の労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上使用する派遣元の使用者は、就業規則の作成・届出義務を負います。
派遣労働者の就業規則は、「派遣元使用者」が作成・届出義務を負うことに注意して下さい。
(S61.6.6基発333号)
②【R2年出題】 ×
労働基準法は、企業単位ではなく事業場単位で適用されます。
1つの企業が2つの工場をもっている場合は、それぞれの工場で労働基準法が適用されます。どちらの工場も使用している労働者が10人未満の場合は、就業規則の作成・届出義務はありません。
③【R2年出題】 ×
慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合、その旨を就業規則に記載するかどうかは、当事者の自由です。
(S23.10.30基発1575号)
④【R3年出題】 ×
同一事業場で、当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成することは可能です。
その場合、3割の労働者に適用される就業規則も当該事業場の就業規則の一部です。
そのため、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合等の意見を聴くだけでは、労働基準法第90条による意見聴取を行ったことにはなりません。
(S63.3.14基発150号)
⑤【H26年出題】 〇
労働基準法第90条に定める意見を聴取する義務は、労働者の団体的意見を求めるということで、協議までは要求していません。
就業規則についての意見を聴けば、労働基準法違反になりません。
(S25.3.15基収525号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働基準法
R6-146
R6.1.20 許されるべき相殺 最高裁判例より
過去問から学びましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第24条 ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
第24条では、賃金支払5原則が定められています。
賃金支払の5つの原則を確認しましょう。
・通貨払いの原則
・直接払いの原則
・全額払いの原則
・毎月一回以上払いの原則
・一定期日払いの原則
今日は「全額払」の原則に関する問題です。
賃金は労働した分を「全額」支払うのが原則です。ただし、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことができます。
今日は、賃金の過払があった場合などに相殺が許される要件をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。
②【H27年出題】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H29年出題】
賃金の過払を精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から控除することは、「その額が多額にわたるものではなく、しかもあらかじめ労働者にそのことを予告している限り、過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされていなくても労働基準法24条1項の規定に違反するものではない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
④【H21年選択式】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の < A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【R3年出題】 〇
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺」は、労働基準法第24条第1項但書によって除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、同項の禁止するところではない」とされています。
過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、かつ、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないなど、『労働者の経済生活の安定』をおびやかすおそれのない場合は、労働基準法第24条第1項に違反しません。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
②【H27年出題】 ×
金額が少額であるということだけで相殺が許されるものではありません。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
③【H29年出題】 ×
「過払のあった時期と合理的に接着した時期においてされる」ことも、相殺が許される条件の一つです。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
④【H21年選択式】
A 経済生活の安定
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷 福島県教組事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-132
R6.1.6 第19条解雇制限が適用される条件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
条文の「休業する期間」に注目してください。解雇制限が適用されるのは「休業する期間」です。
まず、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
②【R1年出題】
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
解雇制限を受けるのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために「休業する期間」及びその後30日間ですので、労働者が業務上の傷病により治療中だったとしても、休業しないで就労している場合は、解雇制限は受けません。
(第19条)
②【R1年出題】 〇
6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定だとしても、女性労働者が産前休業を請求しないで引き続き就労している場合は、解雇制限は受けません。
(S25.6.16基収1526号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされている。

【解答】
【R5年出題】 〇
6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、解雇制限は適用されません。しかし、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう行政指導を行うこととされています。
(第19条、S25.6.16基収1526号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-112
R5.12.17 退職時の証明
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第22条第1項 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 |
退職時の証明書の法定記載事項は、「使用期間」、「業務の種類」、「その事業における地位」、「賃金」、「退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)」です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
使用者は、労働者が自己の都合により退職した場合には、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について、労働者が証明書を請求したとしても、これを交付する義務はない。
②【R4年出題】
労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記載しなければならない。
③【H22年出題】
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「退職」の事由には、自己都合、会社の勧奨、定年、契約期間の満了、解雇などがあります。
退職時の証明書は、退職理由を問わず交付する義務がありますので、労働者が自己都合による退職をした場合でも、労働者が証明書を請求した場合は、交付する義務があります。
②【R4年出題】 ×
第22条第3項で、「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」と規定されています。
労働者が法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合は、請求があった事項だけを記載することになります。
③【H22年出題】 ×
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合は、解雇の事実のみを記載する義務があります。
第22条第3項で、「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」と規定されていますので、請求されていない解雇の理由を証明書に記載してはなりません。
(H11.1.29基発45号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者が、労働基準法第22条に基づく退職時の証明を求める回数について制限はない。

【解答】
【R5年出題】 〇
退職時の証明を求める回数について制限はありません。
(H11.3.31基発169号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-111
R5.12.16 年次有給休暇の時季変更権
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第39条第5項 使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。 ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 |
労働者には時季指定権があり、年次有給休暇を取得する時季は労働者が指定できます。
また、使用者には時季変更権があり、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、時季変更権を行使できます。
今日は、「時季変更権」についてみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年選択】
最高裁判所は、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合に対する、使用者の時季変更権の行使が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど< A >に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。[…(略)…]労働者が、右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…(略)…]使用者にある程度の < B >の余地を認めざるを得ない。もとより、使用者の時季変更権の行使に関する右< B >は、労働者の年次有給休暇の権利を保障している労働基準法39条の趣旨に沿う、合理的なものでなければならないのであって、右< B >が、同条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、同条3項[現5項]ただし書所定の時季変更権行使の要件を欠くものとして、その行使を違法と判断すべきである。」
②【H22年選択】
「労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、[…(略)…]事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との< A >を図る必要が生ずるのが通常」であり、労働者が、これを経ることなく、「その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、[…(略)…]使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるを得ない。」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H29年選択】
A 事業の正常な運営
B 裁量的判断
ポイント!
・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期のものであればあるほど、事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなる。
・ 労働者が、事前の調整を経ることなく、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、使用者の時季変更権の行使については、使用者にある程度の裁量的判断の余地が認められる。
・ 裁量的判断が、労働基準法39条の趣旨に反し、使用者が労働者に休暇を取得させるための状況に応じた配慮を欠くなど不合理であると認められるときは、その行使は違法となる。
(平成4.6.23最高裁判所第三小法廷)
②【H22年選択】
A 事前の調整
ポイント!
・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合には、それが長期のものであればあるほど、事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。
(平成4.6.23最高裁判所第三小法廷)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第39条第5項にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たり、勤務割による勤務体制がとられている事業場において、「使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【R5年出題】 〇
勤務割を変更して代替勤務者を配置することが可能な状況にあるにもかかわらず、休暇の利用目的のいかんによってそのための配慮をせずに時季変更権を行使することは、利用目的を考慮して年次休暇を与えないことに等しく、許されない、とされています。
(昭和62.7.10最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-110
R5.12.15 労基法第15項第1項の労働条件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ 就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
労働契約締結の際に、使用者は、労働者に対して「賃金、労働時間その他の労働条件」を明示する義務があります。
明示事項には、「必ず明示しなければならない事項」と「定めをしている場合は明示しなければならない事項」の2種類があります。
まず、過去問からどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
②【H24年出題】
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
③【H23年出題】
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
④【R4年出題】
労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。

【解答】
①【H16年出題】 〇
第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件は、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎などに関する条件を含む労働者の職場における一切の待遇のことです。
一方、第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、施行規則第5条で具体的に決められています。
第1条及び第2条の「労働条件」と第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、異なります。
②【H24年出題】 ×
「表彰に関する事項」は、それに関する定めをする場合は、労働契約の締結に際し、明示しなければならない事項です。
(則第5条)
③【H23年出題】 〇
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合は、労働者は、即時に労働契約を解除できます。
④【R4年出題】 ×
「契約解除の日から14日以内」は、民法の期間計算の原則によります。
9月1日に労働契約を解除した場合は、解除当日ではなく解除の翌日から数えて14日をいいます。契約解除の日から14日以内は、9月2日から数えて、9月15日までをいいます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

【解答】
【R5年出題】 〇
社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合は、社宅を供与する旨の条件は第15条第1項の「労働条件」に含まれません。そのため、社宅を供与しなかったときでも、労働者は即時に労働契約を解除することはできません。
ちなみに、社宅を利用する利益が、第11条にいう賃金である場合は、第15条第1項の「賃金、労働時間その他の労働条件」に該当しますので、社宅を供与しなかった場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
(S23.11.27基収3514号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-098
R5.12.3 第6条 中間搾取の排除
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
②【H26年出題】
労働基準法第6条は、業として他人の就業に介入して利益を得ることを禁止しており、その規制対象は、使用者であるか否かを問わないが、処罰対象は、業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員に限定される。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「何人も」とは、労働基準法の適用を受ける事業主に限定されません。その規制対象は、個人、団体又は公人、私人を問いません。そのため、公務員も規制対象となります。
(S23.3.2基発381号)
②【H26年出題】 ×
処罰対象は、個人、団体又は公人、私人を問いません。業として利益を得た法人又は当該法人のために実際の介入行為を行った行為者たる従業員だけではありません。
(S23.3.2基発381号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、労働基準法第6条違反が成立するのは利益を得た法人に限定され、法人の為に違反行為を計画し、かつ実行した従業員については、その者が現実に利益を得ていなければ同条違反は成立しない。

【解答】
【R5年出題】 ×
法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、法人の為に違反行為を計画し、かつ実行した従業員が現実に利益を得ていない場合でも、法人の従業員について第6条違反が成立します。
(S34.2.1633基収8770号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-097
R5.12.2 賃金直接払の原則
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
賃金支払五原則の条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金支払の原則は次の5つです。
1 通貨払い
2 直接払い
3 全額払い
4 毎月1回以上払い
5 一定期日払い
今日は「直接払いの原則」をみていきます。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
賃金は直接労働者に支払わなければならず、労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことは労働基準法第24条違反となる。
②【H28年出題】
労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合でも、使用者は当該賃金債権の譲受人に対してではなく、直接労働者に対し賃金を支払わなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H30年出題】
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
労働基準法第24条第1項は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止しています。そのため、労働者の親権者その他の法定代理人に賃金を支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは、第24条違反となります。
労働者の委任を受けた弁護士に賃金を支払うことはできません。
(S63.3.14基発150号)
②【H28年出題】 〇
労働者が賃金債権を他に譲渡した場合でも、労働基準法第24条の直接払いの原則は適用されますので、使用者は、直接労働者に対し賃金を支払わなければなりません。譲受人に対して賃金を支払うことはできません。
(最高三小43.3.12)
③【H30年出題】 〇
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、賃金直接払の原則には違反しません。
(S61.6.6基発333号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる直接払の原則は、労働者と無関係の第三者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の親権者その他法定代理人に支払うことは直接払の原則に違反しないが、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことは直接払の原則に違反する。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働者の親権者その他法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うこと、どちらも直接払の原則に違反します。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 労働基準法
R6-096
R5.12.1 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
今日は労働基準法です。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のポイントをみていきます。
まず、ガイドラインの趣旨を読んでみましょう。
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。 (労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインより) |
使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録しなければなりませんが、その原則的な方法をみていきます。
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
使用者は、労働時間の適正な把握を行うべき労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録することとされているが、その方法としては、原則として「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」のいずれかの方法によることとされている。

【解答】
【R5年出題】 〇
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいず
れかの方法によることとされています。
①使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
② タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎
として確認し、適正に記録すること。
なお、労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者
の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。
(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定))
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-095
R5.11.30 労働者の過半数を代表する者の要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
「労使協定」の労働者側の当事者は、
・事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
・労働者の過半数を代表する者
となります。
「労働者の過半数を代表する者」の条件を条文を読んでみましょう。
則第6条の2第1項、3項 ① 労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第41条第2項に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
②【H13年出題】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
③【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
労働者側の当事者である過半数を代表する者については、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」が条件です。
いわゆる管理監督者に当たる者は、過半数を代表する者になることはできません。
(則第6条の2第1項第1号)
②【H13年出題】 ×
監督又は管理の地位にある者は、「労働者の過半数を代表する者」になることはできません。
しかし、監督又は管理の地位にある者も「労働者」には該当します。そのため、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、監督又は管理の地位にある者も含みます。
(S46.1.1845基収6206号)
③【H22年出題】 ×
「協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」が条件ですので、「投票券等の書面を用いた労働者による投票」に限定されることはありません。
なお、「投票、挙手等」の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当事者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当する、とされています。
(H11.3.31基発169号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
いかなる事業場であれ、労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと、という要件さえ満たせば、労働基準法第24条第1項ただし書に規定する当該事業場の「労働者の過半数を代表する者」に該当する。

【解答】
【R5年出題】 ×
「労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと」という要件と、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと」という要件を満たす必要があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-089
R5.11.24 第5条 強制労働の禁止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
労働者の意思に反して「労働を強制すること」を禁止する規定です。労働者が現実に「労働」することは必要ではなく、労働することを「強要」したなら、第5条違反となります。
(S23.3.2基発381号)
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働基準法第5条に定める「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」の「不当」とは、本条の目的に照らし、かつ、個々の場合において、具体的にその諸条件をも考慮し、社会通念上是認し難い程度の手段をいい、必ずしも「不法」なもののみに限られず、たとえ合法的であっても、「不当」なものとなることがある。
②【R3年出題】
労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
③【H29年出題】
労働基準法第5条に定める強制労働の禁止に違反した使用者は、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」に処せられるが、これは労働基準法で最も重い刑罰を規定している。

【解答】
①【R2年出題】 〇
「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」を用いて「労働を強制」した場合は、第5条違反となります。その手段の正当であるか不当であるかによって第5条違反が決定されます。
(S63.3.14基発150号)
②【R3年出題】 〇
「脅迫」とは、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足ります。
(S63.3.14基発150号)
③【H29年出題】 〇
「強制労働の禁止」に違反した使用者には、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」という労働基準法で最も重い刑罰が科せられます。
(法第117条)
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第5条に定める「監禁」とは、物質的障害をもって一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことによって、労働者の身体を拘束することをいい、物質的障害がない場合には同条の「監禁」に該当することはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
「監禁」とは、一定の区画された場所から脱出できない状態に置くことにより、労働者の身体の自由を拘束することをいい、必ずしも物質的障害もってを手段とする必要はありません。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-082
R5.11.17 天災その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
第20条第1項、3項 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 |
★解雇が制限される期間は次の2つです。
① 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業する期間+その後30日間
② 産前産後の女性が休業する期間+その後30日間
(例外)
・打切補償を支払う場合
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
★解雇しようとする場合は、予告が必要です。
・少なくとも30日前に予告をする又は30日分以上の平均賃金を支払う(予告期間と平均賃金を併用することもできます)
(例外)
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要)
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
②【R2年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
③【H30年出題】
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
例外が認められる第19条、20条の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」、第20条の「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければなりません。使用者の一方的な判断で例外が適用されることを防ぐためです。
②【R2年出題】 ×
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由です。「事業場が火災により焼失した場合」はやむを得ない事由に該当しますが、事業主の故意又は過失に基づく場合は除かれます。
問題文の「使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合」はやむを得ない事由に含まれません。
(S63.3.14基発150号)
③【H30年出題】 ×
税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合は、「やむを得ない事由」に該当しません。その場合は、産前産後休業中の女性労働者は解雇できません。
(S63.3.14基発150号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、労働基準法第19条及び第20条にいう「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しない。

【解答】
【R5年出題】 〇
従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がないために事業が金融難に陥った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」に該当しません。
(S63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-076
R5.11.11 副業・兼業の休憩について
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第38条第1項 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 |
第38条第1項の規定により、複数の事業場における労働時間は通算されます。
また、事業主が異なっていても(会社が違っていても)、労働時間は通算されます。
(S23.5.14基発769)
まず、過去問をどうぞ
【H26年出題】
労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も通算される。

【解答】
【H26年出題】 〇
例えば、A株式会社の大阪支店と神戸営業所で労働した場合は、労働時間は通算されます。また、A株式会社の事業場とB株式会社の事業場で労働するような場合(事業主を異にする事業場において労働する場合)も労働時間は通算されます。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法に定められた労働時間規制が適用される労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、労働基準法第38条第1項により、当該労働者に係る同法第32条・第40条に定める法定労働時間及び同法第34条に定める休憩に関する規定の適用については、労働時間を通算することとされている。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働者が、事業主を異にする複数の事業場で労働する場合、第32条・第40条に定める法定労働時間は通算されます。
しかし、「休憩(法第 34 条)、休日(法第 35 条)、年次有給休暇(法第 39 条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されないこと。」とされています。
問題文の「第34条に定める休憩」の適用については、通算されません。
(R2.9.1基 発 0 901 第 3 号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-070
R5.11.5 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働の適用について
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
災害等による臨時の必要がある場合は、使用者は行政官庁の許可を受けて、時間外労働・休日労働をさせることができます。
条文を読んでみましょう。
第33条第1項 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働) 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 |
「年少者」の適用について条文を読んでみましょう。
第60条第1項 第32条の2から第32の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。 |
第32条の2から第32の5(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、 1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第36条(36協定による時間外・休日労働)、第40条(労働時間及び休日の特例)、第41条の2(高度プロフェッショナル制度)は、年少者には適用されません。
次に、「妊産婦」の適用について条文を読んでみましょう。
第66条第2項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 |
第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)、第36条第1項(36協定による場合)でも、 妊産婦は、時間外労働・休日労働をしないことを請求することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
②【H25年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
18歳未満の者には、第36条(36協定による時間外・休日労働)の規定は、適用されません。そのため、36協定があっても時間外労働を行わせることはできません。
第33条(災害等による臨時の必要がある場合)の規定は、18歳未満の者にも適用されます。災害等による臨時の必要がある場合は、満18歳未満の者でも時間外労働・休日労働をさせることができます。
②【H25年出題】 〇
妊産婦が請求した場合は、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合、36協定による場合でも、時間外労働・休日労働はさせられません。妊産婦全員ではなく、「妊産婦が請求した場合」に禁止されることに注意してください。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。

【解答】
【R5年出題】 〇
第33条第1項「災害等により臨時の必要がある場合の時間外労働等」の規定について
・年少者には適用されます。災害等により臨時の必要がある場合は年少者に時間外労働等をさせることができます。
・「妊産婦が請求」した場合は、災害等により臨時の必要がある場合でも、時間外労働等をさせることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-063
R5.10.29 産前産後休業
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第65条第1項、2項 (産前産後) ① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
ポイント!
①産前休業
・女性労働者からの「請求」が要件です。
・産前休業は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)です。
②産後休業
・産後休業は8週間です。請求は要件ではありません。
・6週間を経過した後は、女性労働者が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは可能です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
②【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
③【H25年出題】
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
④【R3年出題】
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
⑤【R3年出題】
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
「出産」の範囲は妊娠4か月以上で、1か月は28日として計算します。そのため、 4か月以上とは、85日以上となります。
(S23.12.23基発1885号)
②【R3年出題】 ×
「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩ですので、生産のみならず死産も含まれます。妊娠中絶も妊娠4か月以後に行った場合は、対象になります。
(S26.4.2婦発113号)
③【H25年出題】 ×
妊娠85日以上の場合は、労働基準法第65条が適用されます。妊娠100日目の女性が流産した場合は、産後休業を与えなければなりません。
(S23.12.23基発1885号)
④【R3年出題】 〇
出産当日は、産前6週間に含まれます。
(S25.3.31基収4057号)
⑤【R3年出題】 〇
6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、女性労働者からの請求が産前休業の条件です。女性労働者から請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
女性労働者が妊娠中絶を行った場合、産前6週間の休業の問題は発生しないが、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後行った場合には、産後の休業について定めた労働基準法第65条第2項の適用がある。

【解答】
【R5年出題】 〇
産前6週間は、自然の出産予定日を基準に計算し、産後8週間は、現実の出産日を基準に計算します。
妊娠中絶については、産前6週間の休業の問題は発生しません。
しかし、妊娠4か月(1か月28日として計算する。)以後に妊娠中絶を行った場合は、産後休業が適用されます。
(S26.4.2婦発113号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-058
R5.10.24 年少者、妊産婦等の坑内労働
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労働基準法です。
「坑内労働」について条文を読んでみましょう。
第63条 (坑内労働の禁止) 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
第64条の2(坑内業務の就業制限) 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 ① 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 ↓ 坑内で行われるすべての業務 ② ①に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 ↓ 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの |
★満18歳未満の者の坑内労働は禁止されています。
★妊産婦について
・妊娠中の女性は、坑内業務に就かせられません。
・産後1年を経過しない女性は、「本人が申し出た場合」のみ、坑内業務に就かせられません。
★上記の妊産婦以外の満18歳以上の女性について
・人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、就かせられません。
・女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事することができます。
では、過去問をどうぞ!
【H20年出題】
使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

【解答】
【H20年出題】 ×
「妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性」以外の女性については、坑内の管理、監督業務等に従事することができます。しかし、人力により行われる掘削の業務など女性に有害な業務には、従事できませんので、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることはできません。
(参照:H18.10.11基発第1011001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
年少者を坑内で労働させてはならないが、年少者でなくても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た女性については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
坑内で行われるすべての業務に就かせてはならないのは、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た「産後1年を経過しない」女性です。
問題文は、「産後1年を経過しない」が抜けているので誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-050
R5.10.16 労働者と使用者
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
「事業主」とは、その事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
②【R4年出題】
株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
③【H29年出題】
株式会社の取締役であっても業務執行権又は代表権を持たない者は、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者として労働基準法の適用を受ける。
④【R2年出題 】
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
使用者には、「事業主」、「事業の経営担当者」、「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」の3つがあります。
そのうち、「事業主」とは、その事業の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役ではなく「法人そのもの」をいいます。
②【R4年出題】 ×
法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者のような、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は、労働者になりません。
株式会社の代表取締役は、労働基準法の労働者ではありません。
(S23.1.9基発14号)
③【H29年出題】 〇
株式会社の取締役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合には、その限りにおいて労働基準法第9条に規定する労働者となります。
(S23.3.17基発461号)
④【R2年出題 】 ×
「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれません。各事業において、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限が与えられているか否かによります。
「係長」でも、与えられている責任と権限の有無によっては、係長が「使用者」になることもあります。
(S22.9.13発基第17号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第10条にいう「使用者」は、企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものであるから、同法第9条にいう「労働者」に該当する者が、同時に同法第10条にいう「使用者」に該当することはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
使用者となるか否かは、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限が与えられているか否かで判断します。企業内で比較的地位の高い者として一律に決まるものではありません。
例えば、課長は、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」という面では、労働基準法の労働者です。一方、その課長に、ある事項について権限と責任が与えられている場合は、その事項については、その課長は使用者となります。
「労働者」に該当する者が、同時に「使用者」に該当することは、あり得ます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労働基準法
R6-041
R5.10.7 賃金支払五原則の一つ 一定期日払いの原則
今日は、労働基準法です。
賃金支払5原則の条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金支払の原則は次の5つです。
1 通貨払い
2 直接払い
3 全額払い
4 毎月1回以上払い
5 一定期日払い
今日は、5つ目の「一定期日払い」の原則をみていきます。
賃金は、「毎月1回以上・一定期日を定めて」支払うのが原則です。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金は、毎月1回以上払いの原則・一定期日払いの原則について例外が認められています。
※「その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は、①1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、②1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、③1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給又は能率手当、です。(則第8条)
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
労働基準法第24条第2項にいう「一定の期日」の支払については、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではなく、「毎月第2土曜日」のような定めをすることも許される。

【解答】
【R1年出題】 ×
「一定の期日」の支払は、「毎月15日」等と暦日を指定することは必ずしも必要ではありません。例えば、「月の末日」、「土曜日」等とすることも可能です。
しかし、「毎月第2土曜日」のような定めは許されません。「第2土曜日」は例えば 9月なら9日、10月なら14日となり、月によって変動があるためです。
では、令和5年の問題をどうぞ
【R5年出題】
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることを定めるだけでなく、その支払日を繰下げることを定めることも労働基準法第24条第2項に定めるいわゆる一定期日払に違反しない。

【解答】
【R5年出題】 〇
賃金の所定支払日が休日に当たる場合に、その支払日を繰り上げることも、支払日を繰下げることもどちらも可能です。どちらでも一定期日払に違反しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-032
R5.9.28 労働基準法違反の労働契約
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働基準法です。
条文を読んでみましょう。
第13条 (労働基準法違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
労働基準法に違反する労働条件が含まれる労働契約は、契約全てが無効になるのではなく、「基準に達しない」部分だけが無効になることがポイントです。
例えば、「法定時間外労働に対する割増賃金は支払わない」という労働条件が定められていた場合は、その部分だけが無効になります。
そして、無効になった部分は、労働基準法の基準で埋められ、「法定時間外労働については割増賃金を支払う」となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H30年出題】
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

【解答】
①【H25年出題】 ○
労働基準法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効(空白)となり、空白となった部分は、労働基準法の基準で補充されます。
②【H30年出題】 ×
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、特例でその期間の上限が5年となっています。
その契約期間に違反した場合、労働基準法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年ではなく「5年」となります。
(平成15.10.22基発第1022001号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約は、期間の定めのない労働契約となる。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、法第13条により、法第14条第1項第1号(高度の専門的知識等を有する労働者)及び第2号(満60歳以上の労働者)については5年、その他のものについては3年となります。
「期間の定めのない労働契約となる」は誤りです。
(平成15.10.22基発第1022001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労働基準法
R6-023
R5.9.19 休憩時間のポイント!
今日は休憩時間のポイントを見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条 (休憩) ① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
休憩の3原則を確認しましょう。
①途中に与える
②一斉に与える
③自由に利用させる
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
休憩時間は、労働基準法第34条第2項により原則として一斉に与えなければならないとされているが、道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業には、この規定は適用されない。
②【R5年出題】
一昼夜交替制勤務は労働時間の延長ではなく二日間の所定労働時間を継続して勤務する場合であるから、労働基準法第34条の条文の解釈(一日の労働時間に対する休憩と解する)により一日の所定労働時間に対して1時間以上の休憩を与えるべきものと解して、2時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされている。
③【R5年出題】
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも労働基準法第34条第3項(休憩時間の自由利用)に違反しない。
④【R5年出題】
労働基準法第34条第1項に定める「6時間を超える場合においては少くとも45分」とは、一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味であり、休憩時間の置かれる位置は問わない。
⑤【R5年出題】
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
【解答】
①【R5年出題】 ×
休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません。ただし、労使協定がある場合は、一斉に与えなくてもよいことになります。
なお、以下の業種には一斉付与の原則が適用されませんので、労使協定は不要です。
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業 通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。) (施行規則第31条) |
「道路による貨物の運送の事業、倉庫における貨物の取扱いの事業」には、一斉付与の原則が適用されます。
②【R5年出題】 ×
一昼夜交替制勤務でも、労働基準法上は、労働時間の途中に法第34条第1項の休憩を与えればよい、とされています。
(S23.5.10基収1582号)
③【R5年出題】 ○
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、「事業場内で自由に休息し得る」場合には、必ずしも違法にはなりません。
(S23.10.30基発1575号)
④【R5年出題】 ○
一勤務の実労働時間の総計が6時間を超え8時間までの場合は、その労働時間の途中に少なくとも45分の休憩を与えなければならないという意味で、6時間を超えた時点で45分という意味ではありません。
(S35.5.10基収1582号)
⑤【R5年出題】 ○
休憩時間には、単に作業に従事しない手待ち時間は含まれません。休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。
昼食休憩時間に来客当番として待機させた時間は、手待ち時間になり、休憩時間ではなく労働時間となります。
(S32.9.13発基17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労働基準法
R6-013
R5.9.9 一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業の日の休業手当
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労働基準法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H27年出題】
当該労働者の労働条件は次のとおりである。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
(問題)
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
【解答】 〇
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日は平均賃金の100分の60に相当する金額を支払う義務があります。
現実の労働時間に対する賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合は、その差額を支払わなければなりません。
(S27.8.7基収3445号)
問題文の1日当たりの休業手当は、10,000円×100分の60=6,000円です。
使用者の責に帰すべき事由で労働時間が4時間になり、その労働時間に対し7,500円が支払われています。
現実の労働時間に対する賃金が平均賃金の100分の60以上ですので、賃金の支払に加えて休業手当を支払う必要はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
賃 金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円
A 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
7,000円-5,000円=2,000円
B 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
C 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
10,000円×0.6-5,000円=1,000円
D 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000円-5,000円)×0.6=1,200円
E 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。
【解答】 E
ポイント!
★1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、平均賃金の100分の60に相当する金額を支払う義務があります。
★現実の労働時間に対する賃金は5,000円で、平均賃金の100分の60(7,000円×100分の60)以上です。そのため、使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しません。
正しい記述はEです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和5年度選択式振り返り 労働基準法
令和5年度選択式振り返り 労働基準法
R6-003
R5.8.30 労働基準法選択式は時効と判例からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労働基準法です。
 Aは時効の問題です。
Aは時効の問題です。
条文を読んでみましょう。
第115条 (時効) この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。 附則第143条第3項 当分の間、「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。 |
★労働基準法の時効について確認しましょう。
・賃金(退職手当を除く) → 5年間(当分の間3年間)
・退職手当 → 5年間
・災害補償その他の請求権 → 2年間
Aは、災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)の時効ですので、「2年」となります。
 Bは、年次有給休暇の時季変更権の判例の問題です。
Bは、年次有給休暇の時季変更権の判例の問題です。
労働者が指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに、使用者が時季変更権を行使した場合の効力についてです。
判例では、「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権行使があったものとしてその効力を認めるのが相当である。」とされています。
(昭和57年3月18日最高裁判所第一小法廷)
Bは、「客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権行使があったものとしてその効力を認める」から、「遅滞なく」が入ります。
 Cは、「労働時間」についての問題です。
Cは、「労働時間」についての問題です。
同じ論点の問題が過去に出題されていますので確認しましょう。
【H22年出題】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
解答は「〇」です。
判例では、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労働基準法32条の労働時間に当たる。」とされています。
(平成14年2月28日最高裁判所第一小法廷)
今回のCの問題は、別の判例からの出題ですが、「不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず,労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。」とされています。
Cには、「労働からの解放」が入ります。
(平成19年10月19日最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 全額払の原則
労働基準法 全額払の原則
R5-357
R5.8.19 賃金債権放棄の意思表示の効力
賃金支払5原則の一つに、「全額払いの原則」があります。
今日は、全額払の原則と賃金債権放棄の意思表示についてみていきます。
賃金支払の原則は次の5つです。
(1) 通貨払い (2) 直接払い (3) 全額払い (4) 毎月1回以上払い (5) 一定期日払い |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
②【H25年出題】
退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H27年出題】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【R1年出題】 〇
・就業規則で支給条件が明確に定められている退職金は、労働基準法上の賃金に該当し、「全額払の原則」が適用されます。
・「全額払の原則」の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものです。
・賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である、とされています。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷 シンガー・ソーイング・メシーン事件)
②【H25年出題】 ×
労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をした場合、それが労働者の「自由な意思」に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「当該意思表示は有効」とするのが、最高裁判所の判例です。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷 シンガー・ソーイング・メシーン事件)
③【H27年出題】 ×
労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の「自由な意思」に基づくものである場合は、その意思表示は「有効」であるとするのが、最高裁判所の判例です。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷 シンガー・ソーイング・メシーン事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 36協定
労働基準法 36協定
R5-356
R5.8.18 労働者が時間外労働をする義務
三六協定の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 (時間外及び休日の労働) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
★労使協定の効力について
労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果です。
労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。
(昭和63年1月1日基発第1号)
では、過去問をどうぞ!
①【H20年選択式】
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。
②【H27年出題】
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めていたとしても、 36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H20年選択式】
A 合理的な
使用者が、三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た
↓
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めている
↓
就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなす
↓
労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う
(最高一小H3年11月28日 日立製作所武蔵工場事件)
②【H27年出題】 ×
36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、「当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り」、それが具体的な労働契約の内容をなし、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて「労働をする義務を負う」とするのが、最高裁判所の判例です。
(最高一小H3年11月28日 日立製作所武蔵工場事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 全額払いの原則
労働基準法 全額払いの原則
R5-333
R5.7.26 最高裁判例 適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺
「賃金支払五原則」を条文で読んでみましょう。
第24条 ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
今日は、全額払いの原則の判例をみてみましょう。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。
②【H27年出題】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H21年選択】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の < A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【R3年出題】 〇
賃金計算の過誤、違算等で、賃金の過払が生ずることがあります。これを精算・調整するため、後に支払われるべき賃金から控除できるとすることは、賃金支払の事務をする上で、合理的理由があるといえます。
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、第24条第1項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、禁止するところではない」と解されています。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷)
②【H27年出題】 ×
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、「過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」とされています。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷)
③【H21年選択】
A 経済生活の安定
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 前借金相殺の禁止
労働基準法 前借金相殺の禁止
R5-332
R5.7.25 前借金相殺の禁止は「労働することが条件となっている」がポイント
今日は、前借金相殺の禁止規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第17条 (前借金相殺の禁止) 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |
第17条の趣旨は、金銭貸借関係と労働関係を完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止することです。
(S22.9.13発基17号)
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。
②【R3年出題】
労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。
③【H28年出題】
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
第17条は、「労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること」を禁止しています。金銭を借り受けることだけでは、違反しません。
②【R3年出題】 ×
労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、「労働することを条件とする前貸の債権」には含まれません。
(S22.9.13発基17号)
③【H28年出題】 ×
「労働者」から意思表示があった場合の相殺は禁止されていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 労働条件の明示
労働基準法 労働条件の明示
R5-331
R5.7.24 派遣労働者に対する労働条件の明示
https://youtu.be/6yoxOsuFBoM まず、労働条件の明示義務について条文を読んでみましょう。
第15条第1項 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
労働契約締結の際、使用者は、賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務があります。
「派遣労働者」に対する労働条件の明示義務は、派遣先、派遣元どちらにあるでしょうか?
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

【解答】
①【H29年出題】 ×
派遣労働者への労働条件の明示については、派遣元が義務を負わない労働時間、休憩、休日等も含めて、労働契約関係にある派遣元に明示義務があります。
なお、労働者派遣法の労働基準法の適用に関する特例によって、労働時間、休憩、休日等は派遣先の事業が労働基準法に基づく義務を負います。
(S61.6.6基発333号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 休日
労働基準法 休日
R5-330
R5.7.23 休日の解釈
「休日」とは、労働義務のない日のことです。
今日は、「休日」の解釈をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
休日について
・毎週少なくとも1日の休日を与える(原則)
又は
・4週間を通じて4日以上の休日を与える(例外・変形休日制)
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
②【H24年出題】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
休日とは、「暦日」を指しますので、午前0時から午後12時までの24時間となります。
24時間連続していれば良いというものではなく、起算時点を問わない、というのは誤りです。
(S23.4.5基発535号)
②【H24年出題】 〇
一昼夜交代勤務の場合でも「暦日」の休日の原則が適用されます。
非番の継続24時間は、休日にはなりません。
(S23.11.9基収2968号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 解雇制限
労働基準法 解雇制限
R5-329
R5.7.22 解雇制限が適用される条件
今日は、解雇制限が適用される条件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。 |
今日は、「休業する期間」の部分に注目してください。解雇制限が適用されるのは「休業する期間」です。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
②【R1年出題】
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
労働基準法の解雇制限を受けるのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために「休業する期間」及びその後30日間ですので、労働者が業務上の傷病により治療中だったとしても、休業しないで就労している場合は、解雇制限は受けません。
②【R1年出題】 〇
女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内だったとしても、当該労働者が産前休業を請求しないで就労している場合は、解雇制限は受けません。
(S25.6.16基収1526号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 最高裁判例
労働基準法 最高裁判例
R5-328
R5.7.21 最高裁判例 研修医は労働者に該当する
今日は最高裁判例をみていきます。
まず、労働者の定義を条文で読んでみましょう。
第9条 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
医科大学付属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

【解答】
【H29年出題】 ×
この判例では、「研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たる」とされました。
臨床研修の目的は、医師の資質の向上を図ることで、教育的な側面を有しています。しかし、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定しています。
判例の要旨は、「研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」となっています。
(平成17年6月3日最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 休業手当
労働基準法 休業手当
R5-309
R5.7.2 休業手当支払いのルール
今日は休業手当の支払ルールです。
休業手当について条文を読んでみましょう。
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
【H27年出題】
当該労働者の労働条件は次のとおりである。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
① 使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。
② 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
③ 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
④ 休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。
⑤ 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
① ×
休業手当は、「休日」に支給する義務はありません。
問題文の場合は、休日を除いた5日分の休業手当を支払わなければなりません。
(S24.3.22基収4077号)
② 〇
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由が生じた場合も、その日は平均賃金の100分の60以上を支払わなければなりません。
実際に労働した時間分の賃金が、平均賃金の100分の60未満の場合は、その差額を支払わなければなりません。
問題文は、実際に労働した時間の賃金として7,500円が支払われています。平均賃金の100分の60以上が支払われていますので、その賃金の支払に加えて休業手当を支払う必要はありません。
(S27.8.7基収3445号)
③ 〇
振り替えによって休日となった水曜日に休業手当を支払う義務はありません。
④ 〇
使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も、休業手当の支払が必要です。
⑤ 〇
休電による休業については、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しませんので、休業手当を支払う義務はありません。
(S26.10.11基発696号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 平均賃金
労働基準法 平均賃金
R5-308
R5.7.1 平均賃金の計算方法
平均賃金の算定ルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条第1項~5項 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。 1 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ② 期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③ 期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。 1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間 5 試みの使用期間 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
平均賃金の計算式(原則)
3か月間の賃金の総額 |
3か月間の総日数 |
③について → 賃金総額(分子)、日数(分母)の両方から除外する
④について → 賃金総額(分子)から除外する
平均賃金の最低保障額
3か月間の賃金の総額 | × | 60 |
3か月間の労働した日数 | 100 |
※最低保障が適用されるのは、日給制、時間給制、出来高払制(請負制)の場合です。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
②【H27年出題】
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
③【H27年出題】
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
④【H27年出題】
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
⑤【H27年出題】
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
賃金の総額に算入しない賃金は、以下の賃金です。
・臨時の賃金
・3か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)
・現物給与で法令・労働協約に基づくもの以外のもの
★「通勤手当及び家族手当」は賃金総額に算入します。
②【H27年出題】 ×
平均賃金の計算の「期間」及び「賃金の総額」から除外するのは以下の期間です。
・ 業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間
・ 産前産後の休業期間
・ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・ 育児休業又は介護休業期間
・ 試用期間
★「公民権の行使により休業した期間」は、その日数とその期間中の賃金は、平均賃金の計算に算入します。
③【H27年出題】 ×
施行規則第48条で「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」と規定されています。
遺族補償を行う場合の平均賃金を算定すべき事由の発生日は、「死亡した日」ではありません。
(S25.10.19 基収2908号)
④【H27年出題】 〇
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日が起算日となります。
賃金締切日が毎月月末で、7月31日に算定事由が発生したときは、6月30日から遡った3か月で算定します。
⑤【H27年出題】 ×
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、直前の賃金締切日は、それぞれの賃金ごとの賃金締切日です。
問題文の場合は、基本給は5月31日、時間外手当は6月20日となります。
(S26.12.27基収5926号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 年次有給休暇の権利
労働基準法 年次有給休暇の権利
R5-292
R5.6.15 年次有給休暇請求権の行使
年次有給休暇の発生について、条文を読んでみましょう。
第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
「6か月間継続勤務」+「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たせば、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇の権利が発生します。
「10労働日」に注目してください。
年次有給休暇の権利を行使すると、その労働日の労働義務は消滅します。
10「労働日」となっているのは、年次有給休暇は労働義務のある日(=労働日)にしか取得できないからです。もともと就労義務のない休日に年次有給休暇を取得することはありえません。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。

【解答】
【H28年出題】 〇
「労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がない」がポイントです。会社に対して全く労働義務が免除されている場合は、年次有給休暇請求権の行使はできません。
(S48.3.6基発120号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 年次有給休暇の残余
労働基準法 年次有給休暇の残余
R5-291
R5.6.14 所定労働時間が変更になった場合の年次有給休暇の残余
年次有給休暇は時間単位で与えることができます。
条文を読んでみましょう。
法第39条第4項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 1 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 2 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) 3 その他厚生労働省令で定める事項 |
労使協定を締結することにより、年に5日を上限として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。

【解答】
【H28年出題】 〇
年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位年休の時間数はどのように変わるのでしょうか?又、時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるのでしょうか?
↓
時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されます。
問題文のように、
・所定労働時間が1日8時間から4時間に変更になった。
・変更前の年次有給休暇の残余が10日と5時間だった。
このような場合、変更前は10日と5/8日残っていると考えます。
1日の所定労働時間が8時間から4時間に変更され、1日の所定労働時間が2分の1になりました。残余の時間もそれに比例して2分の1となります。2.5/4となりますが、 1時間未満の端数を切り上げ、3時間となります。
★変更前の残余
10日(1日当たりの時間数は8時間)と5時間
★変更後の残余
10日(1日当たりの時間数は4時間)と3時間
(平成21年10月5日基発1005第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 年次有給休暇の発生要件
労働基準法 年次有給休暇の発生要件
R5-290
R5.6.13 年休発生には全労働日の8割以上の出勤が要件
①雇入れの日から起算して6か月間継続勤務、②全労働日の8割以上出勤、の要件を満たした場合、年次有給休暇の権利が発生します。
労働義務のある日は、「労働日」、労働義務のない日は「休日」です。「全労働日」とは、所定休日を除いた日のことをいいます。
「全労働日」に対する「出勤した日」の割合が8割以上あることが必要です。
今日は、「全労働日」から除外される日をみていきます。
通達のポイントを読んでみましょう。
<出勤率の基礎となる全労働日> ★年次有給休暇の請求権の発生について、全労働日の8割出勤を条件としているのは、労働者の勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低い者を除外する立法趣旨です。 1 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいいます。 所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれません。 2 「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます。 3 「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」でも、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれません。 ・ 不可抗力による休業日 ・ 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 ・ 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 (H25.7.10基発0710第3号) |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
②【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、第2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >というべきである。」
(選択肢)
① 含まれるもの ② 含まれない

【解答】
①【H28年出題】 ×
所定の休日に労働させた日は、全労働日に含まれません。
②【H26年選択式】
A ①含まれるもの
「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」は、例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日です。
「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」は、出勤率の算定に当たっては、請求の前年度における出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます。
(H25.7.10基発0710第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 均等待遇
労働基準法 均等待遇
R5-276
R5.5.30 第3条の労働条件と雇入れ
労働基準法第3条では、「国籍、信条、社会的身分」を理由として、労働者を差別することを禁止しています。
条文を読んでみましょう。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
★今日は、「賃金、労働時間その他の労働条件」に注目します。
労働条件の中に、賃金、労働時間は当然含まれますが、それ以外の条件は、どこまで含まれるでしょうか?
では、過去問をどうぞ
①【H30年出題】
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
②【H28年出題】
労働基準第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H21年出題】
労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いは、雇入れにおける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれます。
(S23.6.16基収1365号、S63.3.14基発150号)
「解雇の意思表示」そのものは労働条件とはいえません。しかし、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されている場合は、「労働条件」にあたります。
②【H28年出題】 〇
ポイント!
・企業者が、労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについては、原則として自由に決定できる。企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
・労働基準法3条は雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。
(S48.12.12最高裁判所大法廷 三菱樹脂事件)
③【H21年出題】 ×
労働基準法3条は雇入れ後における労働条件についての制限ですので、雇入れそのものを制約する規定ではありません。「雇入れにおける差別も含まれる」の部分が誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 1年単位の変形労働時間制
労働基準法 1年単位の変形労働時間制
R5-265
R5.5.19 1年単位の変形労働時間制の労働日について
1年単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定で、以下の事項を定めなければなりません。
① 1年単位の変形労働時間の対象になる労働者の範囲 ② 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限るものとする。) ③ 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。) ④ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間 ※対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合 ・最初の期間の労働日及び当該労働日ごとの労働時間 ・最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間 ⑤ 有効期間の定め |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制の対象期間は、 1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。
②【H22年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
③【H30年出題】
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
1年単位の変形労働時間制の「対象期間」は、「その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限る」とされています。
対象期間の最長は「1年」ですが、3か月や6か月とすることもできます。
②【H22年出題】 ×
労使協定で対象期間における「労働日」と「当該労働日ごとの労働時間」を特定する必要があります。
ただし、対象期間が長くなりますので、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合は、労使協定で、「最初の期間」の「労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を特定し、「最初の期間を除く各期間」については、「労働日数及び総労働時間」を定めることもできます。
1か月 (最初の期間) | 1か月 | 1か月 | 1か月 | ・・・ |
・労働日 ・労働日ごとの労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 |
・・・ |
なお、最初の期間を除く各期間については、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、書面で、各期間における労働日及び各期間における労働日ごとの労働時間を定めることとされています。
③【H30年出題】 〇
労働日と労働日ごとの労働時間はあらかじめ特定しなければなりません。
労働日を特定することは、反面、休日を特定することでもあります。
問題文のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合は、労働日が特定されたことにはなりません。
(H6.5.31基発330号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 解雇
労働基準法 解雇
R5-248
R5.5.2 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
まず、「解雇制限」の条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
<解雇制限期間>
・業務上の傷病のため療養中の期間とその後30日間
・産前産後休業期間とその後の30日間
は、解雇が禁止されています。
★例外
・打切補償を支払う場合
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要です。)
は、解雇制限が解除されます。
今日は、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」をみていきましょう。
ポイント!
「やむを得ない事由」とは
天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由です。
事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともなし難いような状況にある場合をいいます。
(昭63.3.14基発150号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
②【H30年出題】
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合」は含まれません。
事業場が火災により焼失した場合は、「その他やむを得ない事由」に該当しますが、事業主の故意又は重大な過失に基づく火災の場合は、除かれます。
(昭63.3.14基発150号)
※第19条と第20条の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は、同じ意味です。
②【H30年出題】 ×
税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には該当しません。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 労働時間
労働基準法 労働時間
R5-236
R5.4.20 「1日」とは?「1週間」とは?
まず、原則の法定労働時間の条文を読んでみましょう。
第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
★法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定しています。
労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限とする考え方です。
(昭63.1.1基発第1号)
「1週間」と「1日」の考え方をみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。
②【H30年出題】
労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。
日をまたがって継続勤務した場合は、暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とします。
例えば、4月20日(木)、21日(金)のどちらも労働日で、始業時刻が9時の場合で考えてみましょう
4月20日(木) | 4月21日(金) | |||
| 始 |
| 始 | |
20日の残業が21日の午前3時まで及んだ場合、21日の午前3時までの労働は、始業時刻の属する日(20日)の勤務における1日の労働となります。
(昭63.1.1基発第1号)
②【H30年出題】 〇
1週間とは、「就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週」をいいます。
何曜から始まる1週間とするかについて、就業規則等で別に定めることもできます。
(昭63.1.1基発第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 労働時間のカウント
労働基準法 労働時間のカウント
R5-222
R5.4.6 時間外労働、休日労働の割増賃金
まず、「法定労働時間」と「法定休日」の条文を読んでみましょう。
第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
※法定労働時間は、原則として「1日8時間以内、かつ、1 週40時間以内」です。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
※法定休日は、原則として、「週に1日以上」与えなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
A 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
B 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
C 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
D 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
E 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

【解答】
A ×
休日には時間外労働の概念がありませんので、8時間を超えても時間外労働の割増率は加算されません。問題文の場合は、10時間すべて休日労働に対する割増率で計算します。
ちなみに、休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜割増を加算する必要があります。
(H11.3.31基発第168号)
B ×
法定休日の割増賃金は暦日単位で適用されます。
休日割増で計算するのは日曜の24時までです。月曜の午前0時からは休日ではありませんので、休日割増の対象にはなりません。
C 〇
時間外労働が翌日の労働日に及んだ場合は、暦日で判断するのではなく、前日の労働時間の延長として扱われます。
火曜の午前3時までは、月曜日の労働時間の延長となり、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。
(S63.1.1基発第1号)
D ×
法定休日は「暦日」で適用されます。土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前0時以降は、土曜の勤務における時間外労働時間ではなく、休日労働として計算されます。
E ×
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
時間外 |
|
|
|
| 2 | 2 | 4 |
時間外労働となるのは、木曜の金曜の1日の法定労働時間を超えたそれぞれ「2時間」と、1週間の法定労働時間を超えた土曜の4時間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 平均賃金
労働基準法 平均賃金
R5-208
R5.3.23 平均賃金を計算しましょう。
今日は、平均賃金を計算します。
まず、条文を読んでみましょう。
第12条第1項~5項 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 1. 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2. 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ② ①の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③ ①、②に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。 1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2. 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間 5. 試みの使用期間 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
ポイント!
・ 平均賃金は、原則として次の計算式で算定します。
→算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額÷その期間の総日数
ただし、日給、時給、請負制による賃金の場合は、最低保障があります。
最低保障の計算式→賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60
※「総日数」と「労働日数」を区別しましょう。「総日数」は暦上の日数です。例えば、3月なら31日です。
・ 賃金締切日がある場合は、算定事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算した3か月で計算します。
・ 次の期間は、平均賃金の計算式の「日数」と「賃金の総額」の両方から控除します。
1.業務上の傷病により休業した期間
2.産前産後の女性の休業期間
3.使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
4.育児休業又は介護休業期間
5.試みの使用期間
・ 次の賃金は「賃金の総額」から除外されます。
臨時に支払われた賃金
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与など)
通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
では、過去問をどうぞ!
【R1年問1】
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
<条件>
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日
時間外手当については、毎月15日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
A 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
B 4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
C 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
D 通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
E 時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

【解答】
A 〇
平均賃金は、賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡る3か月で計算します。
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、それぞれの賃金の賃金締切日から遡ります。
問題文の場合、「基本給、通勤手当及び職務手当」の直前の賃金締切日は6月25日、「時間外手当」は7月15日です。
平均賃金は、((3月26日から6月25日までの基本給、通勤手当及び職務手当の総額)÷92日)+((4月16日から7月15日までの時間外手当の総額)÷91日)で計算します。
(S26.12.27 基収5926号)
B ×
賃金によって賃金締切日が異なりますので、Aの問題のように、それぞれの賃金締切日から遡って計算します。
C ×
「通勤手当」は平均賃金に算入しなければなりません。通勤手当が計算に入っていませんので誤りです。
D ×
E ×
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 みなし労働時間
労働基準法 みなし労働時間
R5-198
R5.3.13 事業場外労働のみなし労働時間制
例えば、外回りのセールスや出張のように、事業場の外で働く場合、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、また、使用者による労働時間の算定が困難な場合があります。
「事業場外労働」についてはみなし労働時間制の制度が設けられています。
では、条文を読んでみましょう。
第38条の2 ① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ② ①のただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
 みなし労働時間制とは
みなし労働時間制とは
→ 使用者には、労働者の労働時間を把握し、算定する義務があります。
しかし、事業場外の労働で、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合は、実際に労働した時間ではなく、特定された時間労働したとみなすことができる制度です。
ポイント!
事業場外の労働でも、「労働時間の算定」ができる場合は、みなし労働時間は適用されません。
事業場外労働のみなし労働時間の手順
★原則 「所定労働時間」労働したものとみなされます。
※当該業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなされます。
★労使協定で「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を定めた場合は、労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。
②【R1年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
③【H22年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。

【解答】
①【H18年出題】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合、原則は、「所定労働時間」労働したものとみなされます。例えば、所定労働時間が7時間の場合は、7時間労働したとみなされます。
しかし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます。例えば当該業務の遂行に通常必要とされる時間が8時間の場合は、8時間労働したとみなされます。
★当該業務に関し、労使協定で当該業務の遂行に通常必要とされる時間を定めた場合は、その時間労働したとみなされます。
②【R1年出題】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は、届出の必要はありません。
(則第24条の2第3項)
③【H22年出題】 ×
在宅勤務でも事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合があります。
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインについて」(令和3.3.25基発0325第2号/雇均発0325第3号/)を確認しましょう。
↓
事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難なときに適用される制度であり、使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用できる制度である。テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となる。
テレワークで、事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるのは、次の①と②の条件を満たす場合です。
① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと ② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと |
問題文では「どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため」となっていますが、情報通信機器を労働者が所持しているからといって制度が適用されないわけではありません。
ガイドラインでは、例えば、勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合は①の要件を満たすとされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 変形労働時間制
労働基準法 変形労働時間制
R5-197
R5.3.12 1か月単位の変形労働時間制採用のルール
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、1か月以内の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例事業場の場合は44時間)を超えなければ、特定の週、特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができます。
1か月単位の変形労働時間制の変形期間は1か月以内にすることが条件です。
1週間単位、10日単位、4週間単位なども可能です。
変形期間を1か月にした場合で考えてみましょう。
法定労働時間40時間の事業場で、31日の月なら、1か月の労働時間の総枠は次の式で計算できます。
40時間×31日÷7日 ≒ 177時間
1か月の所定労働時間のトータルが177時間以内なら、平均すると1週間当たりの労働時間が40時間以内となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
③【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。
④【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
⑤【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
変形期間を1か月とする場合に、毎月1日から月末までの暦月にするという規定はありません。
例えば、毎月16日を起算日として、16日~翌月15日という1か月でも可能です。
②【R1年出題】 ×
満18歳に満たない者には、原則として変形労働時間制は適用されませんので、その部分については正しいです。
育児を行う者については、適用除外を請求できる規定がありません。
なお、以下のような規定はあります。
則第12条の6 使用者は、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。 |
★変形労働時間制が適用されると、労働時間の長い週や日が出てきます。使用者は、育児を行う者等については、育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければなりません。
第66条第1項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間又は1日について法定労働時間を超えて労働させてはならない。 |
★妊産婦が対象の規定です。
例えば、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合でも、妊産婦から請求があった場合は、1週間または1日について法定労働時間を超えて労働させることはできません。
③【R1年出題】 〇
1か月単位の変形労働時間制で時間外労働になる部分を確認しましょう。
①1日の時間外労働
→1日8時間を超える時間を定めた日はその時間
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週の時間外労働
→1週40時間(特例事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、
それ以外の週は1週40時間(特例事業場は44時間)超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③変形期間時間外労働
→変形期間の法定労働時間総枠(40時間(44時間)×対象期間の暦日数÷7日)
を超えて労働した時間(①又は②で法定時間外労働となる時間を除く。)
問題文のように、所定労働時間が1日6時間(所定労働時間が1日8時間以内)の日で、時間外労働になるのは、8時間を超えて労働した時間です。
6時間の日に2時間延長しても労働時間は8時間ですので、1日あたりの時間外労働は発生しません。
週当たりでみても、2時間延長した日の代わりに同一週内の1日10時間の日の労働時間を2時間短縮しています。1週間当たりの労働時間は増えていませんので、1週間当たりでも時間外労働は発生しません。
④【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」又は「労使協定」で採用できます。「就業規則その他これに準ずるものによる定め」だけでも採用できます。
なお、労使協定で採用した場合は、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出る必要があります。しかし、三六協定とは異なり、労使協定の届出によって効力が発生するわけではありません。
⑤【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、1日の労働時間、1週間の労働時間の限度はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 就業規則
労働基準法 就業規則
R5-186
R5.3.1 絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
就業規則に定める事項には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
<絶対的必要記載事項> 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
<相対的必要記載事項> 4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 10表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 11 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |

「絶対的必要記載事項」は必ず就業規則に記載しなければならない事項です。
「相対的必要記載事項」は、定めをする場合は記載が義務づけられる事項です。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
②【H28年出題】
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。
③【R3年出題】
欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。
④【H25年出題】
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

【解答】
①【H25年出題】 〇
賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、絶対的必要記載事項ですので、就業規則に必ず記載しなければなりません。
ちなみに、臨時の賃金等は、「定めをする場合」は就業規則に記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。
②【H28年出題】 ×
退職手当は「退職手当の定めをする場合」は、適用される労働者の範囲などを就業規則に記載しなければならない相対的必要記載事項です。
退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合は、退職手当の決定及び計算の方法に該当しますので、就業規則に記載する必要があります。
(H11.3.31 基発168号)
③【R3年出題】 ×
欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替えることは違法ではありません。そのような取扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定する必要があります。
(S63.3.14基発150号)
④【H25年出題】 〇
従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用されるもの」である場合、11号の「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項については就業規則に規定しなければならない。」に当てはまります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 就業規則
労働基準法 就業規則
R5-185
R5.2.28 就業規則の意見聴取
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務があります。
また、就業規則の作成と変更の際には、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 10 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 11 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
 1から11のうち、1~3は就業規則への記載が義務づけられている「絶対的必要記載事項」、4~11は定めをする場合は記載が義務づけられる「相対的必要記載事項」です。
1から11のうち、1~3は就業規則への記載が義務づけられている「絶対的必要記載事項」、4~11は定めをする場合は記載が義務づけられる「相対的必要記載事項」です。
次に作成の手続について条文を読んでみましょう。
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。 |
今日は、作成と変更の際の手続である意見聴取をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
②【R3年出題】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。
③【H30年出題】
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。
④【R1年出題】
就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。
⑤【H27年出題】※行政手続における押印原則の見直しによる修正あり
労働基準法第90条第2項は、就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務づけているが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合又は意見書に氏名を記載しない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うものとされている。

【解答】
①【H21年出題】 〇
就業規則の作成だけでなく、その変更の際も意見聴取が必要です。
②【R3年出題】 ×
同一事業場で、事業場の一部の労働者のみ適用される就業規則を別に作成することもできます。
その場合でも、作成や変更に際しての意見聴取は、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
問題文のように、当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くだけでは、労働基準法第90条による意見聴取を行ったことにはなりません。
(S63.3.14基発150号)
③【H30年出題】 ×
同一事業場で、パートタイム労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することもできます。その場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則を合わせたものが「就業規則」となります。それぞれが単独に就業規則となるものではありません。
作成や変更に際しての意見聴取は、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
④【R1年出題】 ×
協議決定は要求されていません。意見を聴けば労働基準法違反になりません。
(S25.3.15基収525号)
なお、意見書の内容が反対意見でも、就業規則の効力には影響はありません。
(S24.3.28基発373号)
⑤【H27年出題】 〇 ※行政手続における押印原則の見直しによる修正あり
就業規則を行政官庁へ届け出る際は、意見書の添付が義務づけられていますが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合等は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うとされています。
(S23.10.30基発1575号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 産前産後
労働基準法 産前産後
R5-175
R5.2.18 産前産後休業のポイント!
今日は、「産前産後休業」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第65条 (産前産後) ① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
「出産」の範囲は妊娠4カ月以上の分娩をいいます。1か月は28日で計算しますので、4か月以上とは、85日以上のことです。生産だけでなく死産も含まれます。
(S23.12.23基発1885号)
産前6週間は、自然の出産予定日を基準に計算します。出産予定日よりも遅れて出産した場合は、予定日から出産当日までの期間は、産前休業に入ります。
(S25.3.31基収第4057号)
出産予定日 出産日
▼ ▼
予定日以前6週間 | 遅れた日数α日 | 出産日後8週間 |
産前休業(6週間+α日) | 産後休業 | |
出産日当日は、産前休業に含まれるのがポイントです。
(S25.3.31 基収第4057号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
②【R3年出題】
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
③【R3年出題】
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
妊娠4か月以後に行った妊娠中絶も「出産」の範囲に含まれます。
(S26.4.2 婦発113号)
②【R3年出題】 〇
産前休業(6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)は、女性労働者の請求が条件です。女性労働者から請求がなければ、就業させても労働基準法に違反しません。
③【R3年出題】 〇
産後8週間は、女性労働者からの請求の有無にかかわらず、就業させることはできません。産後6週間を経過している+女性労働者から請求があった+その者について医師が支障がないと認めた業務については、就かせることができます。
出産当日は、産前6週間に含まれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 妊産婦
労働基準法 妊産婦
R5-174
R5.2.17 妊産婦の労働時間・深夜労働
今日は、妊産婦の労働時間の規定をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第66条 ① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)及び第43条の5第1項(1週間単位の非定型的労働時間制)の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 ② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(36協定による場合)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
ポイントは、①②③すべて「妊産婦が請求した場合」が前提になっている点です。
妊産婦でも、体調や環境は一人一人違いますので、妊産婦からの請求があれば、保護が行われます。
① 変形労働時間制(1か月単位、1年単位、1週間単位)については、妊産婦から請求があれば、1週間又は1日の法定労働時間を超える時間は労働させられません。(変形労働時間制そのものを適用できないという意味ではありません。)
② 妊産婦から請求があれば、時間外又は休日に労働させられません。
③ 妊産婦から請求があれば、深夜労働はさせられません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
②【H25年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③【R3年出題】
労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。
④【H17年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
時間外労働、休日労働又は深夜業が制限されるのは、「妊産婦が請求した場合」です。すべての妊産婦ではありません。請求しない妊産婦については制限されません。
②【H25年出題】 〇
「妊産婦が請求した場合」がポイントです。
③【R3年出題】 ×
監督又は管理の地位にある者には労働時間の規定の適用がありません。そのため、監督又は管理の地位にある妊産婦には、第66条第1項、第2項は適用されませんので、「時間外労働・休日労働をしない」という請求はできません。
④【H17年出題】 ×
第41条に該当する者には、労働時間、休日、休憩の規定は適用されませんが、深夜業の規定は適用されます。
監督又は管理の地位にある妊産婦については、第66条第3項「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」の規定は適用されますので、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があれば、深夜業をさせることはできません。
(昭61.3.20基発第151号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 減給制裁
労働基準法 減給制裁
R5-165
R5.2.8 制裁規定の制限
就業規則の「制裁」の種類には、譴責、出勤停止、即時解雇等があります。
制裁の原因となる事案が公序良俗に反しない限りは、制裁自体は禁止されていません。
ただし、制裁のうち、「減給」については、労働した時間分をカットすることになりますので、労働基準法で制限が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
1回あたりの減給の額は、平均賃金の1日分の半額以内です。
また、複数回の減給事案があったとしても、減給の総額は、一賃金支払期の賃金の総額の10分の1以下にする必要があります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。
②【H16年出題】
就業規則で労働者に対して減給の定めをする場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。
③【H25年出題】
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

【解答】
①【R2年出題】 ×
遅刻・早退した時間分は、賃金が発生しません。例えば1時間遅刻して、1時間分の賃金をカットしても、減給制裁には当たりませんので、労働基準法第91条による制限を受けません。
ただし、遅刻、早退の時間分の賃金を超える減給は制裁に当たりますので、労働基準法第91条の制限を受けます。
(S63.3.14基発150号)
②【H16年出題】 ×
例えば、平均賃金が1万円の場合、減給の1回の額は5千円以内となります。また減給事案が5回発生した場合は、5千円×5回=2万5千円となります。しかし、総額は1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内となりますので、例えば1賃金支払期の賃金の総額が20万円の場合は、2万円が上限となります。残りの5千円は当該賃金支払期には減給できませんが、次期の賃金支払期に延ばすことは「可能」です。
(S23.9.20基収1789号)
③【H25年出題】 ×
平均賃金は、「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です。
減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」となります。
(S30.7.1929基収5875号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 使用者
労働基準法 使用者
R5-164
R5.2.7 使用者の定義
労働基準法の「使用者」の定義を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
労働基準法の「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者のことです。
次の3つが、労働基準法の「使用者」と定義されています。
・事業主
→ その事業の経営の主体
・事業の経営担当者
→ 法人の代表者、支配人など
・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
では、過去問をどうぞ!
①【R2問1-A】
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
②【R2問1-B】
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
③【R2問1-C】
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。

【解答】
①【R2問1-A】 ×
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体です。
個人企業の場合は企業主個人、株式会社など法人組織の場合は、「法人そのもの」をいいます。株式会社の代表取締役は、「事業主」には当たりません。
②【R2問1-B】 ×
「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいいます。
部長や課長等の形式にとらわれることなく、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによります。
そのため、「係長」でも、与えられている責任と権限によっては、「使用者」として労働基準法の義務についての履行の責任が問われます。
(S22.9.13発基第17号)
③【R2問1-C】 ×
「使用者」は、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによります。権限が与えられていなくて、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされません。
課長が、事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけの場合は、その伝達は課長が使用者として行ったことにはなりません。
(S22.9.13発基第17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 三六協定
労働基準法 三六協定
R5-156
R5.1.30 三六協定の限度時間
法定労働時間を超えて労働させる場合、法定休日に労働させる場合は、「36協定」を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
今日は、36協定の協定事項を確認しましょう。
第36条を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
次に、36協定に定める事項を確認しましょう。
第36条第2項 第36条第1項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 1年間に限るものとする。) 3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 4 対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 |
今日は第4号に注目します。
さらに条文を読んでみましょう。
第36条第3項、第4項 ③ 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。 ④ 限度時間は、1か月について45時間及び1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めた場合は、1か月について 42時間及び1年について320時間)とする。 |
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

【解答】
【R2年出題】 〇
36協定に定める時間外労働の限度時間は、1か月45時間、1年360時間です。1年単位の変形労働時間制で対象象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合は、1か月42時間、1年320時間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 第6条
労働基準法 第6条
R5-147
R5.1.21 中間搾取の排除
労働関係の開始や存続に関与して利益を得ることは、職業安定法などで認められている場合のほかは、禁止されています。
条文を読んでみましょう。
第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
②【H28年出題】
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
③【R2年出題】
労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
④【H15年出題】
ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
法律に基づいて許される場合は、手数料、報酬等を受けることができます。
職業安定法と船員職業安定法には、手数料や報酬等のルールが定められています。
(S23.3.2基発381号、S33.2.13基発90号)
②【H28年出題】 ×
違反行為の主体は、「他人の就業に介入して利益を得る」第三者です。規制対象は、「個人、団体又は公人たる私人たるとを問わない」とされています。そのため、公務員も規制対象となります。
(S23.3.2基発381号)
③【R2年出題】 〇
なお、使用者より利益を得る場合に限らず、労働者又は第三者より利益を得る場合も含みます。
(S23.3.2基発381号)
④【H15年出題】 〇
労働者派遣は、派遣元と労働者は「労働契約関係」、派遣先と労働者は「指揮命令関係」にあります。
派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働契約に介入するものではありませんので、中間搾取には該当しません。
問題文のように、派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであったとしても、労働基準法第6条の中間搾取には該当しません。※労働者派遣法に抵触する可能性はあります。
(S61.6.6基発333号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 危険有害業務
労働基準法 危険有害業務
R5-138
R5.1.12 危険有害業務の就業制限
妊産婦を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることは禁止されています。
また、妊産婦以外の女性についても、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせることが禁止されています。
条文を読んでみましょう。
第64条の3(危険有害業務の就業制限) ① 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、 哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ③ ①②に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
「危険有害業務の就業制限の範囲」は、女性労働基準規則第2条で定められています。
・「妊娠中の女性」の就業が制限される業務は、1号から24号まで24種類です。
・「産後1年を経過しない女性」については、24種類のうち、就業させてはならない業務が3種類、申し出た場合は就かせてはならない業務が19種類、就業させもいい業務が2種類です。
・「妊産婦以外の女性」については、24種類のうち就業させてはならない業務が2種類、就業させてもいい業務が22種類です。
※妊産婦以外の女性も就業させてはならない業務は、1号「重量物を取り扱う業務」と18号「有害物を発散する場所において行われる業務」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問3-A】
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
②【R2問3-B】
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具等を用いて行う業務に就かせてはならない。
③【R2問3-C】
使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
④【R2問3-D】
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
⑤【R2問3-E】
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。

【解答】
①【R2問3-A】 〇
「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦のみならず「妊産婦以外の女性」にも就かせてはならない業務です。
重量は、年齢別に定められています。満18歳以上は断続作業なら「30キログラム以上」、継続作業なら「20キログラム以上」です。30キログラム以上の重量物については、全女性に就業制限が適用されます。
②【R2問3-B】 ×
「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具等を用いて行う業務」については、妊産婦については「就かせてはならない業務」ですが、妊産婦以外の女性については、就かせても差し支えない業務です。
③【R2問3-C】 〇
「つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務」については、妊娠中の女性を就かせることはできません。
ちなみに、産後1年を経過しない女性については、「女性が申し出た場合は就かせてはならない業務」となり、妊産婦以外の女性については、就かせても差し支えない業務です。
④【R2問3-D】 〇
「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」が禁止されるのは、妊娠中の女性のみです。
「産後1年を経過しない女性」、「妊産婦以外の女性」を就かせても差し支えありません。
⑤【R2問3-E】 〇
「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」は、産後1年を経過しない女性が従事しない旨を使用者に申し出た場合は、就かせることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-128
R5.1.2 R4択一式より 賃金の非常時払い
災害などで出費を要することになった場合、労働者は、支払期日前でも、賃金の繰上払を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
第25条 (非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 則第9条 非常の場合は、次に掲げるものとする。 1 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 2 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 3 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
支払期日前でも繰上払の請求ができるのは以下の事由の場合です。
・出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合
★労働者のみならず、「労働者の収入によって生計を維持する者」も対象です。
★支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対する賃金です。使用者は、まだ労務の提供のない期間の賃金については支払う義務はありません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-ウ】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由の1つである「疾病」とは、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。

【解答】
【問6-ウ】 〇
「疾病」、「災害」は、業務上、業務外は問われません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。
②【H28年出題】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の事由も含まれるのがポイントです。
②【H28年出題】 ×
非常時払いの対象は、「既往の労働」に対する部分です。いまだ労務の提供のない期間は支払う義務はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-127
R5.1.1 R4択一式より 通貨以外のもので支払われる賃金
賃金は、「通貨払い」が原則ですが、例外もあります。
条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金の支払には、「通貨払い」、「直接払い」、「全額払い」、「毎月1回以上払い」、「一定期日払い」の5原則があります。
今日は「通貨払い」の例外に注目します。
賃金は「通貨」で支払うのが原則ですが、「法令」に別段の定めがある場合、「労働協約」に別段の定めがある場合は、通貨以外のもの(現物)で支払うことができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-ア】
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。

【解答】
【問6-ア】 〇
平均賃金を算定する際の「賃金の総額」には、「臨時」に支払われた賃金及び「3か月を超える期間ごと」に支払われる賃金並びに「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入しない、とされています。(法第12条第4項)
★「通貨以外のもので支払われた賃金」で一定の範囲に属するものは、平均賃金の算定基礎に含まれます。
賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもので、「評価額」は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない、とされています。(則第2条)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
②【H15年出題】
ある会社においては、労働協約により、通勤費として、労働者に対して、6か月定期券を購入して支給しているが、このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解される。

【解答】
①【R3年出題】 ×
労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。事業場の全ての労働者ではありません。
★労働協約は、「労働組合法でいう労働協約」のみを意味します。
労働組合がない場合の、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定は、労働協約ではありません。
昭和63.3.14基発150号)
②【H15年出題】 〇
通勤定期券は、「通貨以外もの(現物)」ですので、労働協約の定めが必要です。このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解され、平均賃金の算定の基礎にも含まれます。
(昭25.1.18基収130号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-109
R4.12.14 R4択一式より 割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合
今日は、判例からの問題です。
さっそく、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-C】
医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合、「本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはないから、上告人の当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないからといって不都合はなく、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということができる」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【問7-C】 ×
「平成29年7月7日付け最高裁判所第二小法廷判決」からの出題です。
『当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができない』場合は、当該年俸の支払により、「時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない。」とされています。
年俸のうち、時間外労働等の割増賃金に当たる部分が明らかにされていなかったことがポイントです。
この判決を踏まえて、平成29年7月31日付基発0731第27号「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」が発出されています。
ポイントは以下の通りです。
・時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含める方法で支払う場合には、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であること。
・このとき、割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法第37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、その差額を支払わなければならないこと。
では、過去問をどうぞ!
【H22年出題】
タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法第37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈することができるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
【H22年出題】 ×
時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができない場合、最高裁判所の判例では、「この歩合給の支給によって、時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきもの」とされています。
(高知県観光事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-108
R4.12.13 R4択一式より 契約解除の日から14日以内の起算日
「契約解除の日から14日以内」は、当日起算でしょうか?翌日起算でしょうか?
では、条文を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ ②の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
労働契約締結の際に、使用者は、労働条件を明示しなければなりません。
明示された労働条件が、実際の条件と異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除できます。その場合、労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。

【解答】
【問5-B】 ×
「解除当日から数える」の部分が誤りです。「契約解除の日から14日以内」は、民法の期間計算の原則によって初日は算入しません。
9月1日に労働契約を解除した場合は、翌日の9月2日から数えて14日以内ですので、9月15日までとなります。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
②【H28年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「即時に」がポイントです。例えば、2週間前に申し出るなどのような制限はありません。
②【H28年出題】 ×
「当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。」の部分が誤りです。第15条の「解除」は、過去に遡って、契約がなかったものと扱われるのではなく、労働契約関係を「将来に向かって」消滅させることをいいます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-107
R4.12.12 R4択一式より 労働契約の契約期間の上限
労働契約には、「期間の定めのある」契約と、「期間の定めのない」契約があります。
労働契約に契約期間を定める場合、最長は原則として3年です。長期労働契約はその間、労働者を拘束してしまうからです。
「期間の定めのない労働契約」については、いつでも労働者から契約解除ができますので、労働基準法上の制限はありません。
では、条文を読んでみましょう。
第14条 (契約期間等) 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 ① 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 ② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(①に掲げる労働契約を除く。) |
労働契約に契約期間を定める場合の上限は原則として3年です。
例外も確認しましょう。
<例外1>
一定の事業の完了に必要な期間を定める契約 → 3年を超える期間を定めることができます。例えば工事の完了に4年かかるような場合です。
<例外2>
専門的知識等で高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との契約 → 上限は5年となります。
※高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限られます。
<例外3>
満60歳以上の労働者との間の契約 → 上限は5年となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められていること等が必要である。

【解答】
【問5-A】 〇
「専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等」は、告示で限定列挙されていて、「社会保険労務士」はその一つです。
契約期間の上限を5年とするには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りません。社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められていること等が必要です。
(H15.10.22基発第1022001号)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
②【H27年出題】
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

【解答】
①【H28年出題】 〇
高度の専門的知識等を有しているだけでは、契約期間を5年とする労働契約は締結できません。高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていることが条件です。高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、上限は原則の3年です。
②【H27年出題】 〇
「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合で、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要です。例えば、6年で完了する工事現場では、労働者を6年間の契約で雇入れることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-088
R4.11.23 R4択一式より 三六協定の時間外労働の定義
時間外労働・休日労働をさせる場合は、「三六協定」の締結と届出が必要です。
今日のテーマは、三六協定が必要な「時間外労働」についてです。
では、三六協定の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は第35条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
★三六協定が必要な時間外労働・休日労働について
時間外労働 → 「労働基準法第32条から第32条の5まで若しくは第40条」で上限が決められている労働時間を延長する場合です。
休日労働 → 「第35条」の休日(原則週1回の休日)に労働させる場合です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-D】
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、労働基準法第36条第1項の協定をする必要はない。

【解答】
【問3-D】 〇
所定労働時間を超えて労働時間を延長した場合でも、1週の労働時間が法定労働時間以内で各日の労働時間が8時間以内・かつ休日労働を行わせない限りは、36協定をする必要はありません。
36協定が必要になるのは、法定労働時間を超えて労働させる場合、法定休日に労働させる場合です。
(H11.3.31基発168号)
過去問をどうぞ!
【H13年出題】
週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない事業場において、月曜日に10時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は休業としたときは、その週の総労働時間数は40時間であるので、この月曜から金曜までについては、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。

【解答】
【H13年出題】 ×
週の総労働時間数は40時間で法定労働時間以内ですが、1日8時間を超えている月曜日、火曜日、木曜日は時間外労働となります。三六協定の締結と、第37条に基づく割増賃金の支払が必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-087
R4.11.22 R4択一式より トラック運転手の労働時間
トラック運転手の労働時間の取扱いについて確認しましょう。
さっそく、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-B】
定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。

【解答】
【問2-B】 ×
いわゆる手待ち時間が大半を占めていても、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上は、労働時間と解されます。
(S33.10.11基収6286号)
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

【解答】
①【H30年出題】 ×
仮眠中であっても、トラックに乗り込む点で使用者の拘束を受けていること、また、万一の事故発生の場合には交替運転や故障修理を行うことから、一種の手待ち時間又は助手的な勤務として、労働時間と解されます。
(S33.10.11基収6286号)
こちらの過去問もどうぞ!
②【H22年出題】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
②【H22年出題】 〇
「仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる」とされています。
(最高裁第1小法廷H14.2.28大星ビル管理事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-086
R4.11.21 R4択一式より 年次有給休暇の権利の発生
年次有給休暇の権利の発生の要件を確認しましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
年次有給休暇の権利は、①6か月間継続勤務、②全労働日の8割以上出勤の2つの要件を満たした場合に発生します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-E】
年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまって始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【問7-E】 ×
年次有給休暇の権利について最高裁判所の判例では、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではない」とされています。年次有給休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』は不要です。
なお、第39条第5項では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と規定されています。
ここに出てくる「請求」は休暇の時季にかかる文言で、休暇の時季の指定という意味です。
(S48.3.2白石営林署事件)
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
②【H22年出題】
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。
③【H24年出題】
労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところであり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。

【解答】
①【H20年出題】 〇
年次有給休暇の権利は、所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利です。
(S48.3.2白石営林署事件)
②【H22年出題】 ×
年次有給休暇の成立について、労働者による休暇の請求やこれに対する使用者の承認は不要です。
労働者がその有する休暇の日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、使用者が時季変更権の行使をしない限り、労働者の時季指定によって年次有給休暇が成立します。
(S48.3.2白石営林署事件)
③【H24年出題】 〇
最高裁判例(S48.3.2白石営林署事件)では、「年次有給休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」とされています。
労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用する場合も、その請求時季が事業の正常な運営を妨げるものでない限り、使用者はこれを付与しなければならない、とされています。
(S24.12.28 基発第1456号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-085
R4.11.20 R4択一式より 労基法第22条「退職時等の証明」
労働者から退職時の証明書の交付を請求された場合、使用者には交付する義務があります。
条文を読んでみましょう。
第22条 (退職時等の証明) ① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ② 労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ③ 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 |
①は「退職時の証明」です。法定記載事項は、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)です。
②は「解雇理由証明書」です。解雇予告の期間中に、労働者から解雇理由について証明書を請求された場合に、交付しなければならないものです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-E】
労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記載しなければならない。

【解答】
【問5-E】 ×
第22条第3項で「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない」と規定されています。
例えば、解雇された労働者が解雇の事実のみが記入された証明書を請求した場合は、証明書に記載できるのは解雇の事実のみです。請求されていない解雇の理由を記載することはできません。
(H11.1.29基発45号)
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
②【H22年出題】
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
退職時の証明を請求する権利は、労働基準法第115条によって時効は2年となっています。そのため、退職から1年後に証明書の請求があった場合は、使用者には交付する義務があります。
(H11.3.31基発169号)
②【H22年出題】 ×
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合は、「解雇の理由」を証明書に記載することはできません。
証明書には労働者の請求しない事項を記載することはできないからです。
(H11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-084
R4.11.19 R4択一式より 労基法第5条「強制労働の禁止」
労働基準法第5条では、労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しています。
条文を読んでみましょう。
第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
第5条は、「強制してはならない」という規定ですので、労働することを強要した場合は労働者が現実に労働した事実がなくても、強要しただけで第5条に抵触します。
第5条に違反した場合は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。労働基準法上最も重い罰則です。
では令和4年の問題をどうぞ
【問4-D】
使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。

【解答】
【問4-D】 〇
第5条は、不当に拘束する手段で労働を強制することを禁止しています。問題文のように「労働の強制の目的がなく」、使用者の暴行が労働の強制につながっていない場合は、労働基準法第5条違反にはなりません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
②【H26年出題】
労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。

【解答】
①【R3年出題】 〇
脅迫によって使用者が労働者の意思に反して労働することを強制し得る程度であることが必要です。
(S22.9.13発基17号)
②【H26年出題】 〇
形式的な労働契約が成立していなくても、事実上労働関係が存在すると認められる場合は、強制労働違反が成立します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-083
R4.11.18 R4択一式より 労基法第3条「均等待遇」
今日のテーマは「均等待遇」です。
まず、条文を読んでみましょう。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
国籍、信条、社会的身分を理由として労働者を差別することを禁止している条文です。
なお、第3条で禁止している差別は、国籍・信条・社会的身分を理由する差別のみです。それ以外の理由による差別は第3条には抵触しません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-B】
労働基準法第3条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。

【解答】
【問4-B】 〇
「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいいます。
(S22.9.13 発基第17号)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法が第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。
②【H25年出題】
労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。
③【H30年出題】
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
有利に取り扱っても、不利に取り扱っても「差別的取扱」にあたります。
②【H25年出題】 〇
労働基準法第3条で禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分を理由とする」差別的取扱に限定されています。
③【H30年出題】 ×
「賃金、労働時間その他の労働条件」の「その他の労働条件」は、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等も含む趣旨とされています。
労働協約や就業規則等で解雇の基準や理由が規定されていれば、労働するための条件となりますので、第3条の「労働条件」になります。
(S23.6.16基収第1365号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-061
R4.10.27 R4択一式より 時間外労働は「実労働時間」で考える
まず、「36協定」の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は前条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
・36協定が必要な時間外労働・休日労働を確認しましょう
「法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)」を超えて労働させる場合
「法定休日(原則毎週少なくとも1回)」に労働させる場合
例えば、月曜日から金曜日までの所定労働時間が1日7時間、土日が休日の事業場で、金曜日の労働時間を1時間延長した場合を考えてみましょう。金曜日を1時間延長しても、1日8時間、1週間36時間です。法定労働時間内に収まっていますので、36協定は不要です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-C】
労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、1日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、労働基準法第36条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金の支払の必要はない。

【解答】
【問3-C】 〇
36協定や割増賃金が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。遅刻した分、終業時刻を繰り下げたとしても、1日の実労働時間が8時間以内なら36協定も割増賃金も不要です。
(H11.3.31基発168号)
過去問をどうぞ!
【H29年出題】
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

【解答】
【H29年出題】 〇
1日の所定労働時間が8時間で、1時間遅刻をした分、終業時刻を1時間繰り下げたとしても実働時間が8時間ですので、時間外労働にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-060
R4.10.26 R4択一式より 特別条項による時間外労働の上限
使用者は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、時間外労働をさせることができますが、労働時間の延長には上限が定められています。
・時間外労働の上限は、原則として、月45時間、年360時間です。
・臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)の場合は、月45時間、年360時間を超えて労働させることができます。
<特別条項の条件>
・時間外労働 →年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計 → 月100 時間未満
・時間外労働と休日労働の合計 → 「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80 時間以内
・月45時間の限度時間を超えることができるのは、年6か月まで
今日のテーマは特別条項による時間外労働の上限です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-B】
小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする労働基準法第36条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。

【解答】
【問3-B】 ×
特別条項の条件を満たしているかチェックしましょう
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 |
時間外労働 | 90時間 | 70時間 | 85時間 | 75時間 | 80時間 | 400時間 |
・時間外労働の上限は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月100 時間未満
・月45時間の限度時間を超えることができるのは、年6か月まで
・時間外労働と休日労働の合計が、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80 時間以内
→ 例えば、3月について、2~6か月の平均を出してみましょう。
2月~3月(2か月)の平均 → 77.5時間
1月~3月(3か月)の平均 → 81.66時間
※前年度の36協定の対象期間の時間数も入れて平均を出します。前年12月~3月(4か月)の平均、前年11月~3月(5か月)の平均、前年10月~3月(6か月)の平均もチェックが必要ですが、問題文では明らかにされていないので、今回は触れません。
チェックの結果、1月~3月の3か月の平均が80時間を超えています。そのため、特別条項の条件を満たしていません。
過去問をどうぞ!
【R2年出題】
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

【解答】
【R2年出題】 〇
時間外労働の上限は、原則として「1か月45時間、1年360時間」です。ただし、1年単位の変形労働時間制(対象期間が3か月を超える場合)により労働させる場合は、「1か月42時間、1年320時間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-059
R4.10.25 R4択一式より 教育訓練の時間は労働時間になる?ならない?
使用者が実施する「教育訓練」の時間は、労働基準法の労働時間となるのでしょうか?
まず令和4年の問題をどうぞ!
【問2-C】
労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働として取り扱うこととされている。

【解答】
【問2-C】 ×
「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば時間外労働にはならない」という考え方です。(S26.1.20基収2875号、H11.3.31基発168号)
「強制」なのか「自由参加」なのかがポイントです。問題文の場合は、「自由参加」ですので、労働時間ではなく、所定労働時間外に行われるときでも時間外労働にはなりません。
なお、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものです。そのため、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのが原則です。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となりますので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、割増賃金の支払が必要です。
(S47.9.18基発第602号)
過去問もどうぞ!
【H26年出題】
労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や、教育・研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである。

【解答】
【H26年出題】 〇
労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについて、ポイントは、「実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきもの」の部分です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-047
R4.10.13 R4択一式より 労使協定の効力の発生
「1か月単位の変形労働時間制」を導入する際は、「労使協定を締結する」、「就業規則その他これに準ずるものに定める」のどちらかが必要です。
労使協定の締結によって1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
今日のテーマは、「労使協定の効力の発生」です。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の2(1か月単位の変形労働時間制) ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間(法定労働時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。 |
第32条の2第2項により、1か月単位の変形労働時間制の労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
例えば、労使協定で1日10時間と定めた日には10時間まで労働させることができますし、1週52時間と定めた週には52時間まで労働させることができます。
この「労使協定」は、届出によって効力が発生するのでしょうか?それとも締結していれば効力が発生するのでしょうか?
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-B】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。

【解答】
【問7-B】 ×
1か月単位の変形労働時間制についての労使協定については、「届出」が効力の発生要件となっていません。労使協定が締結されていれば、効力が発生します。
労使協定を届出なくても効力は発生します。しかし、届け出なかった使用者については罰則が適用され、30万円以下の罰金に処せられます。
(参考)労使協定はどのような効力をもつのでしょうか?
労働基準法の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという「免罰効果」をもちます。
労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。
(S63.1.1基発1号)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
②【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」又は「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)の締結」のどちらかで採用することができます。
就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでも採用することができます。
また、労使協定の締結によって採用する場合は届出が必要ですが、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって」効力が発生するのではなく、締結することによって労使協定の効力が発生します。
②【H24年出題】 〇
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて発生します。単に同協定を締結したのみでは、効力は発生しませんので注意してください。
第36条の条文を確認しておきましょう。
| 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
「行政官庁に届け出た場合」に注目してください。36協定については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出て、初めて免罰効果が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-046
R4.10.12 R4択一式より 労働時間の特例
法定労働時間は、1週40時間、1日8時間が原則です。
ただし、一部の業種については、法定労働時間の特例措置が適用されます。
今日は、法定労働時間の特例をみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第40条 (労働時間及び休憩の特例) ① 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 ② ①の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 |
では、第40条の特例措置のうち、則第25条の2第1項の「法定労働時間の特例」を読んでみましょう。
則第25条の2 使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。 |
<法定労働時間の特例>
・1週間44時間、1日8時間
・対象の業種
常時10人未満の労働者を使用する
第8号 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
第10号 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 (映画の製作の事業を除く。)
第13号 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
第14号 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-A】
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。

【解答】
【問7-A】 ×
特例により、1週間については44時間まで、1日については8時間までです。
では、過去問もどうぞ!
【H18年出題】
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

【解答】
【H18年出題】 〇
「物品の販売の事業」は第8号に該当しますので、常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。
ちなみに、第8号は商業、第10条は映画演劇業、第13号は保健衛生業、第14号は接客娯楽業と略称で書かれることが多いです。
問題文の「物品の販売の事業」が第8号商業とつながるようにおさえておきましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-045
R4.10.11 R4択一式より 労基法第16条賠償予定の禁止
今日のテーマは、労働基準法第16条の賠償予定の禁止です。
では、第16条を読んでみましょう。
第16条 (賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |
使用者が労働契約の不履行について違約金を定める、又は損害賠償額を予定する契約をした場合は、第16条違反として、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-C】
労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

【解答】
【問5-C】 ×
第16条で禁止されているのは、「労働契約の不履行について違約金を定めること」、「損害賠償額を予定する契約をすること」です。違反が成立するのは、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときではなく、そのような契約をしたときです。
では、過去問もどうぞ!
①【H25年出題】
労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。
②【H30年出題】
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることは、労働の強制や労働者の自由意思を不当に拘束することにつながるため、禁止されています。
②【H30年出題】 ×
第16条で禁止しているのは「金額を予定すること」です。現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。
(S22.9.13発基第17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-030
R4.9.27 R4択一式より『健康診断の実施時間は労働時間になる?ならない?』
労働安全衛生法では、健康管理のため事業者に健康診断の実施が義務づけられています。
労働安全衛生法の健康診断は、一般的な健康の確保を図るための「一般健康診断」と、特定の有害業務に従事する労働者が対象になる「特殊健康診断」の2つに分けられます。
労働者が健康診断を受ける時間は労働時間になるのでしょうか?
令和4年の問題で確認しましょう。
では、過去問からどうぞ!労働安全衛生法の過去問です。
【H27年出題(安衛法)】
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものと解されている。

【解答】
【H27年出題(安衛法)】 〇
・一般健康診断の時間 → 労働時間にはなりません
・特殊健康診断の時間 → 労働時間となります(賃金の支払が必要です)
※健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについて
・労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものです。「業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではない」とされています。
・特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものですので、「所定労働時間内に行なわれるのを原則」とすること。また、「特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される」ので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであることとされています。
(S47.9.18基発第602号)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【R4問2-A】
労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。

【解答】
【R4問2-A】 ×
則第44条の定期健康診断、則第45条の特定業務従事者の健康診断は一般健康診断ですので、労働時間とはされません。
一定の有害業務に従事する労働者が対象の特殊健康診断は、労働時間と解されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(労働基準法)
令和4年基本問題(労働基準法)
R5-020
R4.9.17 R4択一式より『第4条 男女同一賃金の原則』
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、労働基準法第4条男女同一賃金の原則です。
では、条文を読んでみましょう。
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
過去問で、第4条のポイントを確認しましょう。
①【H25年出題】
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
②【H24年出題】
労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。
③【H30年出題】
労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
第4条で、女性であることを理由として差別的取扱いを禁止しているのは、「賃金」についてのみです。
②【H24年出題】 〇
なお、男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進、降格・教育訓練、一定の福利厚生の措置、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別的取扱いを禁止しています。
③【H30年出題】 〇
差別的取扱いとは、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる、とされています。
(H9.9.25基発第648号)
では、令和4年の問題をどうぞ!
④【R4年出題】
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4条違反となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
第4条に違反して、女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをした使用者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
第4条の違反が成立するのは、現実に差別的取扱いをした場合です。就業規則で賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、その規定は無効となるだけです。現実に男女差別待遇の事実が無い場合は、労働基準法第4条違反にはなりません。
(H9.9.25基発第648号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(労働基準法)
令和4年択一式を解いてみる(労働基準法)
R5-010
R4.9.7 R4「労基択一」は基本問題中心。問1労働者の定義について
令和4年の労働基準法の択一式は基本問題が中心でした。
今日は問1を見ていきましょう。
まず、第9条の「労働者」の定義を読んでみましょう。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
労働者は、「職業の種類」を問わず、事業又は事務所に「使用」され、「賃金」を支払われる者をいいます。
では、令和4年問1です。
A 労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。
B 労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。
C 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。
D 株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
E 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

 問題を解くときの考え方です
問題を解くときの考え方です
A ×
労働基準法の労働者は、事業に「使用」され、労働の対償に「賃金」を支払われる者です。求職活動中は条件に当てはまりません。
B ×
請負契約の形式を採っていても、その実体において使用従属関係が認められる場合は、「労働関係」となり、労働基準法の労働者となります。※「実体」で判断することがポイントです。
C ×
「同居の親族のみを使用する事業」は労働基準法の適用が除外されます。しかし、「親族以外の者」(他人)が使用されている場合は、労働基準法の適用を受けることになります。一時的に使用される親族以外の者は、労働基準法の労働者に該当します。
D ×
「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない。(H11.3.31基発168号)」とされています。
E 〇
『事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者』なら、労働基準法の労働者の定義に当てはまります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式①
復習しましょう/令和4年選択式①
R5-001
R4.8.29 令和4年選択式の復習~労基法
昨日は、本試験お疲れさまでした。
さっそく復習していきましょう。
今日は「労働基準法」です。
1 解雇予告期間の問題です。
<問題の主旨> 解雇予告手当を支払うことなく9月30日の終了をもって労働者を解雇しようとする場合、いつまでに解雇予告を行わなければならないでしょうか?
★ 解雇予告手当を支払うことなく、解雇しようとする場合は、「30日以上前」に解雇予告をしなければなりません。
★「解雇の予告を行った日」は、解雇予告期間の計算に算入されないのがポイントです。
平成26年に同じ問題が出題されています。解いてみましょう。
【H26年出題】
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

【解答】 ×
9月30日の終了をもって解雇するためには、8月31日には解雇の予告をしなければなりません。
民法の一般原則によって、解雇予告を行った日は、解雇予告期間に算入されないため、予告期間は予告を行った日の翌日から計算されます。
2 東亜ペイント事件(S61.7.14最二小判)からの出題です。
判例の内容を順を追って読んでみましょう。
・使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきである
↓
・ しかし、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制限に行使することができるものではなく、これを濫用することは許されない。
↓
・当該転勤命令について、業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合等、特段の事情がない場合には、当該転勤命令は権利の濫用に当たらないというべきである。
 ・業務上の必要性がない場合、・不当な動機・目的をもってなされた場合、・労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等特段の事情がある場合には、その転勤命令は権利の濫用に当たります。
・業務上の必要性がない場合、・不当な動機・目的をもってなされた場合、・労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等特段の事情がある場合には、その転勤命令は権利の濫用に当たります。
結論は、「本件転勤命令には業務上の必要性が優に存在し、労働者に与える不利益も通常甘受すべき程度であり、権利を濫用したとはいえない。」というものです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-358
R4.8.15 休業手当のポイント!
まず、休業手当の条文を読んでみましょう。
第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H21年選択式】
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< A >という観点から設けられたものであり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の < A >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない」としている。
②【H27年出題】
当該労働者の労働条件は次のとおりである。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
③【H27年出題】
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
①【H21年選択式】
A 生活保障
★休業手当は、労働者の「生活保障」のための制度です。
(昭62.7.17最高裁判所第二小法廷)
②【H27年出題】 〇
★1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合
↓
その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければなりません。
問題文は、平均賃金が10,000円で、その日の賃金として平均賃金の100分の60以上の7,500円の支払がなされていますので、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法となりません。
ちなみに、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
(昭27.8.7基収3445号)
③【H27年出題】 〇
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しませんので、休業手当を支払わなくても26条違反になりません。
(昭26.10.11基発696号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-348
R4.8.5 労働者の過半数を代表する者
労働者側の当事者は、「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合」、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、「労働者の過半数を代表する者」となります。
今日は、「労働者の過半数を代表する者」の要件を見てみましょう。
では、条文を読んでみましょう。
則第6条の2 ① 過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第41条第2項に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
②【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。
③【H25年出題】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
④【H19年出題】
使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「管理監督者」は、労働者の過半数を代表する者になることはできません。
なお、管理監督者は、労働基準法第9条の労働者に該当します。事業場の労働者の人数には管理監督者も含まれます。
(H11.3.31基発168号、H22.5.18基発0518第1号)
②【H22年出題】 ×
則第6条の2では、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続」と規定されています。
投票、挙手等の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当する、とされています。
「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」ということはありません。
(H11.3.31基発169号)
③【H25年出題】 〇
「派遣労働者について」
・労働者の人数の算定
→ 派遣労働者は、派遣元の事業場の労働者に含まれます。
派遣先の事業場の労働者には派遣労働者は含まれません。
(S61.6.6基発333号)
④【H19年出題】 〇
過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、「解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならない」こととしたものであること。
「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれる」ものであること、とされています。
(H11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-308
R4.6.26 労働者の定義
労働基準法の保護の対象になる「労働者」の定義を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第9条 (定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
「職業の種類を問わず」、「事業又は事務所に使用され」、「賃金を支払われる者」は労働者として、労働基準法の保護の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。
②【H29年出題】
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
形式上は請負契約でも、実態として「使用従属関係が認められる」ときは、労働基準法第9条の「労働者」に当たります。
(参考)
労働基準法上の労働者性は、次の1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する、とされています。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
(2)専属性の程度
(3)その他
★昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」より
②【H29年出題】 ×
請負契約によらず雇用契約によりその事業主と大工との間に使用従属関係が認められる場合は、労働基準法の労働者ですので、労働基準法の適用を受けます。
(平11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-307
R4.6.25 休憩時間の長さ
「休憩時間」は、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」です。(昭22.9.13発基17号)
休憩は、「途中付与」、「一斉付与」、「自由利用」が原則です。
今回は、休憩時間の長さがテーマです。
条文を読んでみましょう。
第34条 (休憩) ① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②【H23年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
③【H24年出題】
使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
労働時間が6時間を「超える」場合は45分以上、8時間を「超える」場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。
問題文の労働時間は6時間ちょうどですので、休憩を与える義務はありません。
②【H23年出題】 〇
36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合でも、使用者には、休憩時間を与える義務があります。
③【H24年出題】 ×
1日の労働時間が8時間を超える場合は、1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。1日の労働時間が16時間を超える場合でも、1時間以上の休憩を与えれば、労働基準法の条件は満たします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-306
R4.6.24 1週間単位の非定型的変形労働時間制
例えば、規模の小さい飲食店を思い浮かべてください。
★1週間単位の非定型的変形労働時間制の趣旨
日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に定まっていない場合に、1週間を単位として、一定の範囲内で、就業規則その他これに準ずるものによりあらかじめ特定することなく、1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、労働時間のより効率的な配分を可能とし、全体としての労働時間を短縮しようとするものであること。
(昭63.1.1基発第1号)
では、条文を読んでみましょう。
第32条の5 ① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。 ② 使用者は、①の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
則第12条の5 ① 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。 ② 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。 |
ポイント!
★1週間の非定型的変形労働時間制が導入できる事業は、規模30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店に限定されています。
★労使協定の締結が必要です。(所轄労働基準監督署長に届け出が必要です。)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。
②【H22年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、「かつ」、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場です。
事業と規模の両方に該当する必要があります。
②【H22年出題】 ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限は「10時間」と定められています。
また、1週間の所定労働時間は40時間以下で定めなければなりません。特例事業場でも44時間は適用されません。
 なお、事前通知については、則第12条の5第3項で以下のように定められています。
なお、事前通知については、則第12条の5第3項で以下のように定められています。
(原則) 1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。
(例外) 緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
原則として、1週間が始まる前に、1週間の各日の労働時間を書面で通知することにより、1日10時間まで労働させることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-305
R4.6.23 金品の返還
労働者が退職する場合に、賃金など労働者の権利に属する金品の返還が遅くなると、労働者の生活に支障をきたします。そのような不便を防ぐための規定です。
では、条文を読んでみましょう。
第23条 (金品の返還) ① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② 賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、①の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
|
「権利者」とは、労働者が退職の場合は労働者本人、労働者が死亡した場合は、その労働者の相続人です。(昭22.9.13発基第17号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
②【H30年出題】
労働基準法第20条第1項に定める解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
③【H12年出題】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
①【R2年出題】 〇
賃金又は金品について労使で争いがある場合は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還すればよいことになっています。
②【H30年出題】 〇
解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」とされています。
(昭23.3.17基発464号)
③【H12年出題】 ×
退職手当は、通常の賃金とは異なり、予め就業規則で定められた支払時期に支払えば足りるとされています。
(昭26.12.27基収5483号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-283
R4.6.1 労働条件を明示する方法
労働契約を締結する際に、使用者には労働条件を明示する義務があります。
明示すべき労働条件の範囲は厚生労働省令で定められていて、前回お話ししたように、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。
今回は、明示する方法を確認します。
もう一度、法第15条を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
施行規則第5条 ③ 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、絶対的明示事項(昇給に関す事項を除く。)とする。 ④ 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付とする。 ただし、当該労働者が次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。 1 ファクシミリを利用してする送信の方法 2 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
|
★絶対的明示事項のうち昇給以外は、書面の交付等による明示が義務付けられています。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。
②【R3年出題】
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」について、労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため、将来就業する可能性のある場所や、将来従事させる可能性のある業務を併せ、網羅的に明示しなければならない。
③【R2年出題】
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

【解答】
①【H24年出題】 ×
書面で明示しなければならない労働条件について、「当該労働者に適用する部分を明らかにして就業規則を交付すること」は差し支えないとされています。
(H11.1.29基発第45号)
②【R3年出題】 ×
「雇入れ直後の」就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りる、とされています。しかし、将来の就業場所や従事させる業務を併せ、網羅的に明示することは差し支えありません。
(H11.1.29基発第45号)
③【R2年出題】 〇
交付すべき書面の内容としては、就業規則と併せて賃金に関する事項がその労働者について確定できるものであればよい、とされています。
ですので、労働者の採用時に交付される辞令等で、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えありません。この場合、就業規則等が労働者に周知されていることが必須です。
(H11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-282
R4.5.31 労働契約締結時に明示すべき労働条件
前回の続きです。
労働契約を締結する際、使用者は労働者に労働条件を明示することが義務づけられています。
明示事項には、絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)と相対的明示事項(制度を設ける場合は明示しなければならない事項)があり、明示すべき労働条件の範囲は、厚生労働省令で定められています。
では、明示すべき労働条件の範囲を確認しましょう。
施行規則第5条 <絶対的明示事項> 1 労働契約の期間 2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 (期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る) 3 就業の場所、従事すべき業務 4 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換 5 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給 6 退職(解雇の事由を含む。)
<相対的明示事項> 7 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期 8 臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額 9 労働者に負担させるべき食費、作業用品等 10 安全及び衛生 11 職業訓練 12 災害補償及び業務外の傷病扶助 13 表彰及び制裁 14 休職 |
1から6の絶対的明示事項は、必ず明示する義務がありますが、7~14の相対的明示事項については、制度を設けていない場合は、明示義務はありません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。
②【H25年出題】
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
③【H18年出題】
使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。
④【H24年出題】
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
【解答】
①【R1年出題】 ×
「労働契約の期間」については、「期間の定めがある労働契約」の場合は「契約期間」を、「期間の定めのない労働契約」の場合は、「期間の定めのない旨」の明示が必要です。
(平11.1.29基発45号)
②【H25年出題】 〇
「期間の定めのある労働契約」で、更新する場合があるものの締結の場合は、更新する場合の基準を明示する義務があります。
契約更新の判断基準として、契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況等があります。
(平24.10.26基発1026第2号)
③【H18年出題】 ×
「所定労働時間を超える労働の有無」は絶対的明示事項ですが、「所定労働日以外の労働の有無」は明示すべき事項には入っていません。
④【H24年出題】 ×
「表彰に関する事項」は相対的明示事項です。表彰に関する制度を設けている場合は、労働契約を締結する際に明示する必要があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-281
R4.5.30 労働条件の明示
労働契約を締結する際、使用者は労働者に労働条件を明示することが義務づけられています。
労働条件がはっきりしないまま働くことによるトラブルを防止するためです。
では、条文を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
明示する事項と方法は、厚生労働省令で定められています。内容は次回お話します。
では、過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
②【H29年出題】
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

【解答】
①【H16年出題】 〇
労働基準法第1条と第2条の「労働条件」は、広く解釈され、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含んだ「労働者の職場における一切の待遇」をいう、とされています。
一方、第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、施行規則第5条で具体的に定められています。
問題文の通り、第1条・第2条の労働条件と第15条の労働条件は範囲が異なります。
②【H29年出題】 ×
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働契約関係にある「派遣元」の使用者が明示する義務を負っています。
労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、派遣元が労基法の義務を負わない労働時間、休憩、休日等も含めて、労働条件の明示をする必要があります。
(昭61.6.6基発333号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-280
R4.5.29 労働基準法違反の契約
労働基準法は、労働者を保護するために労働条件の最低ラインを定めるもので、強行法規としての効力をもちます。
労働基準法に違反する労働契約を締結した場合、その効力はどうなるのでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第13条 (この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
例えば、使用者と労働者が、「時間外労働をさせた場合でも、割増賃金を支給しない」と契約した場合で考えてみましょう。
労働基準法では、1日8時間を超えて労働させた場合は、使用者に2割5分増の割増賃金を支払う義務を課しています。
ですので、労働契約上の「割増賃金を支給しない」の部分は無効になります。無効になった部分は、労働基準法の規準により、「時間外労働をさせた場合は割増賃金を支給する」という内容に置き換わります。
なお、無効になるのは労働基準法の基準に達していない「割増賃金を支給しない」の部分のみです。それ以外の労働契約の部分は有効です。労働契約全体を無効にすると労働者の労働の機会そのものが無くなってしまうからです。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H27年出題】
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
「無効となった部分は、この法律で定める基準による。」の部分で、無効となった部分は、労働基準法の基準どおりに補充されることになります。
②【H27年出題】 〇
労働基準法第13条で無効になるのは、基準に「達しない」労働条件です。労働基準法の基準よりも有利な労働条件は有効です。
一方、労働組合法第16条は、『労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。』と規定されています。
労働協約で定める労働条件に「違反する」(→「達しない」ではありません。)労働契約の部分は、無効です。
★「労働条件の力関係」をおさえましょう。
労働基準法 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-265
R4.5.14 解雇予告の適用除外
今回のテーマは、解雇予告の適用が除外される労働者です。
条文を読んでみましょう。
第21条 前条の規定(解雇の予告)は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1 日日雇い入れられる者 2 2か月以内の期間を定めて使用される者 3 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 4 試の使用期間中の者 但し、第1号に該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 |
ポイント!
原則と例外をおさえてください。
「日日雇入れられる者」には、原則として解雇の予告の規定は適用されませんが、「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」は、解雇の予告の規定が適用されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が< A >を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
②【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。
③【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。
④【H26年出題】
試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

【解答】
①【H30年選択式】
A1か月
②【H23年出題】 ×
「6か月」の期間を定めて使用される者には、第20条(予告期間及び予告手当)が適用されますので、期間の途中で解雇される場合は予告が必要です。
③【H23年出題】 ×
「試みの使用期間」の長さに制限はありませんので、例えば3か月でも6か月でも差し支えありません。
ただし、「試みの使用期間中」であっても、「14日」を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告制度が適用されます。
(昭24.5.14基収1498号)
④【H26年出題】 〇
試みの使用期間中に、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告は不要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-264
R4.5.13 解雇の予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかった場合
例えば、5月1日に5月31日の終了をもって解雇する旨を予告していたが、その予告期間中に業務上の負傷をし、療養のため休業した場合、解雇予告の効力はどうなるのでしょうか?
第19条を確認しておきましょう。
第19条 (解雇制限) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(ただし・・・以下省略) |
※「業務上の負傷又は疾病の療養のため休業する期間とその後30日間」、「産前産後の休業期間中とその後30日間」は解雇できません。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
②【H30年出題】
労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。

【解答】
①【H24年出題】 ×
解雇予告期間 |
|
|
| ||||||
● 解雇 予告 |
| ● 業務上 負傷 |
|
|
| ● 解雇 予定日 |
|
|
|
|
| (解雇制限)業務上の傷病による療養のための休業期間+30日間 | |||||||
| |||||||||
解雇予告期間中に、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり休業を要する場合、それがたとえ1日か2日の軽度の負傷又は疾病であっても、第19条の解雇制限の適用があります。
問題文のように業務上の負傷をし療養のため2日間休業した場合は、休業期間中とその後30日間は解雇できません。
問題文の場合は、労働基準法第19条が適用され、当初の解雇予定日は解雇制限期間中となり、解雇できません。(解雇の効力は予告通りの日に発生しません。)
(昭和26.6.25基収2609号)
②【H30年出題】 ×
①の問題と同じです。解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合でも、第19条の解雇制限の対象になります。
なお、解雇制限期間が満了すると解雇できますが、改めて解雇予告が必要かどうかについては、行政通達では以下のようになっています。
「負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない」とされています。
(昭和26.6.25基収2609号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-263
R4.5.12 解雇の予告の除外
前回の続きです。
労働者を解雇する場合は、30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりませんが、予告などが除外される例外があります。
条文を読んでみましょう。
第20条 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。 ② ①の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 ※前条第2項 → その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
解雇予告等が除外される場合
① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
※①②ともに「所轄労働基準監督署長の認定」を受けなければなりません。
「天災事変その他やむを得ない事由」
→ 事業場が火災により焼失・震災に伴う事業場の倒壊など
「労働者の責に帰すべき事由」
→ 盗取、横領、傷害など
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
②【R2年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
③【H18年出題】
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇予告除外認定」という。)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。
④【H24年出題】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」でも、予告手当無しで即時解雇しようとする場合には、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受ける必要があります。
②【R2年出題】 ×
事業場が火災により焼失した場合は、「天災事変その他やむを得ない事由」に該当しますが、「使用者の重過失」に基づく場合は、除かれます。
(昭63.3.14基発第150号)
③【H18年出題】 〇
解雇予告除外認定は、解雇の意思表示をする前に受けることが原則です。
解雇予告除外認定は、ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分です。認定されるべき事実がある場合は、仮に認定を受けなかったとしても、使用者は有効に即時解雇ができる点がポイントです。
即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者が「即時解雇の意思表示をした日」に発生するとされています。「解雇予告除外認定を得た日」ではありませんので、注意してください。
(昭63.3.14基発150号)
④【H24年出題】 ×
解雇の意思表示の後に解雇予告除外認定を受けたとしても、認定されるべき事実がある場合は、有効に即時解雇ができるとされています。即時解雇の効力は、「当該認定のあった日」ではなく、「即時解雇の意思表示をした日」に発生します。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-262
R4.5.11 解雇の予告
労働者を解雇する場合は、「少なくとも30日前に予告する」、又は「30日分以上の平均賃金の支払い」が必要です。
条文を読んでみましょう。
第20条 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し・・・(以下今回は省略します。) ② 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 |
ポイント!
30日分以上の平均賃金を支払えば、即時解雇が可能です。
②について → 予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。
過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
②【R1年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。
③【H26年出題】
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。
④【H26年出題】
労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
⑤【H24年出題】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

【解答】
①【H16年出題】 〇
解雇予告手当を算定する場合の算定すべき事由の発生した日は、「労働者に解雇の通告をした日」です。
(昭39.6.12基収2316号)
②【R1年出題】 ×
30日間は、労働日ではなく暦日で計算されますので、休業日も含みます。
③【H26年出題】 ×
9月30日の終了をもって解雇するためには、8月31日には解雇の予告をしなければなりません。
民法の一般原則によって、解雇予告を行った日は、解雇予告期間に算入されないため、予告期間は予告を行った日の翌日から計算されます。
④【H26年出題】 〇
予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。
⑤【H24年出題】 〇
予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。
8月15日に解雇の予告をした場合、翌日の16日から31日までの16日間が予告期間となるので、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-261
R4.5.10 有期労働契約その2
前回の続きです。
有期労働契約は、労働者を長期に拘束することを避けるため、原則3年以内と定められています。
ただし、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」は、例外的に、3年を超える契約が認められています。
また、「専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合に限る。)」、「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約」は、最長5年までの契約期間が認められています。
今回は、「5年」が認められる要件をみていきましょう。
では、再度第14条を読んでみましょう。
第14条 (契約期間等) 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |
「高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準」の中には、「社会保険労務士の資格を有する者」も入っています。
ただし、社会保険労務士の国家資格を有しているだけでは足りず、「当該国家資格の名称を用いて当該国家資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等」が必要です。(H15.10.22基発第10220001号)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
②【H18年選択式】
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が< A >ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。
③【H25年出題】
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
④【H29年出題】
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。
⑤【H30年出題】
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
契約期間を5年とする労働契約を締結できる「専門的知識等であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者」は、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者」に限られます。
(法第14条第1項第1号)
②【H18年選択式】
A 1075万円を下回らない
一定の学歴と実務経験を有し、年収が1075万円以上である「システムエンジニアの業務に就こうとする者」との間に締結される労働契約は最長5年とすることができます。
(高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準 H15.10.22厚生労働省告示第356号)
③【H25年出題】 〇
満60歳以上の労働者との間の労働契約の契約期間は最長5年です。
(法第14条第1項第2号)
④【H29年出題】 ×
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の契約期間の上限は5年です。65歳に達するまでという規定はありません。
⑤【H30年出題】 ×
「満60歳以上」の労働者との間に締結される労働契約ですので、第14条に定める契約期間に違反し同法第13条の規定が適用された場合、当該労働契約の期間は3年ではなく「5年」となります。
労働基準法第13条も確認しておきましょう。
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」
第13条が適用されると、基準に達しない部分は「無効」、無効となった部分は、「この法律で定める基準」になります。
(平15.10.22第1022001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-260
R4.5.9 労働契約の期間(有期労働契約の上限その1)
労働契約には、「期間の定めのない労働契約」と「期間の定めのある労働契約」があります。
「期間の定めのない労働契約」は、労働者側からいつでも自由に解約できますので、労働基準法上の制限はありません。
一方、「期間の定めのある労働契約」は、契約期間中は原則として解約できません。例えば、契約期間を20年にすると、20年の間、労働者は退職できず、長期にわたり労働者を拘束することになってしまいます。そのため、労働基準法では、「期間の定めのある労働契約」は、原則として最長3年という制限を設けています。
では、条文で確認しましょう。
第14条 (契約期間等) 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |
<有期労働契約のポイント!>
★原則 → 3年を超えてはならない
☆例外その1・・・3年を超えて契約できるもの
・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
例えば、土木工事の事業で、その工事の終期までの期間を定める契約
・職業訓練のための訓練期間(第70条)
☆例外その2・・・5年まで契約できるもの
・専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約
(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合に限る。)
・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。
②【H23年出題】
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。

【解答】
①【H16年出題】 〇
労働基準法第13条で、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と規定されています。
第14条違反には第13条が適用され、基準に達しない部分は「無効」、無効となった部分は、「この法律で定める基準」になります。ですので、問題文の労働契約の期間は、「同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年」となります。
(法第13条、平15.10.22第1022001号)
②【H23年出題】 ×
有期労働契約の更新は可能です。更新による継続雇用期間については制限はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-244
R4.4.23 年俸制のこと
賃金を1年単位で決定している制度を、年俸制といいます。
労働者の成果や能力に対する評価で決定されます。
年俸制の労働者にも、労働基準法の賃金のルールは適用されますし、また、時間外労働等をさせた場合は、割増賃金の支払いも必要です。
今回は、年俸制のルールを確認します。
では、早速過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
年俸制にも賃金支払い五原則が適用されますので、「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払わなければなりません。
毎月、年俸額の12分の1を支払い、各月の支払いを一定額にする方法もありますが、年俸額の一部を賞与の時期に支払う方法(例えば、毎月、年俸額の16分の1を支払い、16分の4を2等分して賞与として支給する等)もとれます。各月の支払いを一定額とすることは求められていません。
では、もう一問どうぞ!
②【H17年出題】
年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。

【解答】
②【H17年出題】 〇
<この問題文の支払い方法>
毎月 → 年俸の16分の1+通勤手当
6月と12月 → 年俸の16分の2ずつを賞与として支給
時間外労働等を行った場合は、年俸制の労働者にも割増賃金を支払わなければなりません。
その際、「6月と12月に賞与として支払われている賃金」をどのように扱うのかがポイントです。
通達では、「施行規則第21条第4号の「臨時に支払われた賃金」及び第5号の「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」のいずれにも該当しないものであるから、割増賃金の算定基礎から除外できない」とされています。
ですので、賞与の部分も含めて計算しなければなりません。
なお、通勤手当は算定基礎に含めませんので、割増賃金の支払いは、問題文のように「月例給与に賞与部分を含めた年俸額」を基礎として計算します。
(H12.3.8基収78号)
★年俸制の平均賃金について
割増賃金と同じように扱います。賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1か月分の賃金として平均賃金を算定します。
(H12.3.8基収78号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-242
R4.4.21 割増賃金の計算の基礎に算入しない賃金
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者には割増賃金を支払う義務があります。
例えば、時間外労働の場合は、1時間当たりの賃金×1.25で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
今回のテーマは、割増賃金の計算の基礎になる1時間当たりの賃金の計算に算入しない賃金です。
条文を読んでみましょう。
第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) ⑤ 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 則第21条 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 1 別居手当 2 子女教育手当 3 住宅手当 4 臨時に支払われた賃金 5 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
1時間当たりの賃金は、手当も含めて計算します。しかし、「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」、「臨時に支払われた賃金」、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」の7つの手当などは計算に入れません。
家族手当は「家族の有無」、通勤手当は「交通機関の運賃」で決まり、労働とは関係ないからです。
また、賞与など(「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当する)も計算に入れません。
なお、覚え方は、「か つ べ し ん 一 住宅」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法の第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
②【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
③【H19年出題】
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
「通勤手当」は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。
②【H23年出題】 ×
「家族手当」は算定基礎賃金に含めないことが原則です。
しかし、例えば、家族がいない人にも支払われているとか、その家族数に関係なく一律に支給されている場合は、「家族手当」とはみなされず、割増賃金の計算に入れなければなりません。
(昭22.11.5基発231号)
③【H19年出題】 ×
問題文の住宅手当は、施行規則第21条でいう住宅手当に該当せず、割増賃金の計算の基礎となる賃金に「算入されます」。
住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、則第21条でいう住宅手当に当たりません。ですので、割増賃金の計算に入ります。
(H11.3.31基発170号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-231
R4.4.10 平均賃金の最低保障額
平均賃金は原則として、「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額」÷「3か月間の総日数」で計算します。
ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高給制(請負制)の場合は、最低保障額の定めがあります。
条文で確認しましょう。
第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下つてはならない。 ① 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 ② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 |
「月給制」の場合は、1か月の所定労働日数に関係なく賃金が支払われますので、平均賃金がそれほど変動することはありません。
しかし、例えば時間給制の場合は、出勤日数が非常に少ない月があると、平均賃金に響きます。
そのため、日給制、時間給制、出来高給制(請負制)の場合は、最低保障額が定められています。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

【解答】
【H19年出題】 〇
<最低保障額のポイント>
最低保障額は、分母が「総日数」ではなく、「その期間中に労働した日数」になること。また、「100分の60」は、労働日当たりの賃金の6割を保障するという考え方です。
 最低保障額の計算式
最低保障額の計算式
算定期間中の賃金総額÷算定期間中に労働した日数×100分の60
「原則の計算式」で算定した平均賃金が、最低保障額を下回る場合は、最低保障額が平均賃金となります。
★ちなみに・・・
「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合」の計算について
例えば、「月給制」と「時給制」が併給されている場合は、「月給制」の部分は「総日数」で除して算定し、「時給制」の部分は最低保障のルールで計算します。その2つの金額の合計額が最低保障額となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-230
R4.4.9 平均賃金から除外する賃金
前回は、「分母と分子の両方」から控除する期間を確認しました。
今回は、「分子の賃金総額」からのみ除外される賃金をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第12条第4項、5項 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
則第2条 ① 法第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。 |
 賃金の総額から除外される賃金は、①「臨時に支払われた賃金」、②「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、③「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」です。
賃金の総額から除外される賃金は、①「臨時に支払われた賃金」、②「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、③「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」です。
①「臨時に支払われた賃金」は、支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定で、かつ非常にまれに発生するものをいいます。例えば、結婚手当、私傷病手当、退職金などが該当します。
(昭22.9.13発基第17号、昭26.12.27基収第385号)
②「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は、年2回の賞与等をいいます。
(昭25.4.15基収392号)
③「通貨以外のもので支払われた賃金」は現物給与のことです。
賃金総額に算入される現物給与は、則第2条で定められている「法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもの」に限られます。それ以外の現物給与は賃金総額に算入されません。
過去問をどうぞ!
① 【H24年出題】
労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。
②【H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
③【H26年出題】
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

【解答】
① 【H24年出題】 ×
年に2回6か月ごとに支給される賞与は、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金の計算には算入しません。
②【H27年出題】 ×
「通勤手当及び家族手当」は、賃金総額に含まれます。
③【H26年出題】 〇
労働協約により支給される定期券は、労働基準法第11条に規定する賃金です。また、6か月定期乗車券は、各月の賃金の前払いとして認められます。
(昭33.2.13基発90)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-229
R4.4.8 平均賃金の計算から控除する期間及び賃金
平均賃金の計算式の、分母は「3か月間の総日数」、分子は「3か月間の賃金の総額」です。
ただし、3か月間のうちに、一定の期間がある場合は、その期間の日数と賃金総額は、分母からも分子からもそれぞれ控除して算定します。
計算に入れると、平均賃金が不当に低くなる可能性があるからです。
では、条文で読んでみましょう。
第12条第3項 平均賃金の算定期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。 ① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 ② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 ③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 ④ 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間 ⑤ 試みの使用期間 |
控除の対象になる期間は覚えましょう。
分母の「期間中の日数」からも、分子の「賃金総額」からも、どちらからも控除するのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
②【H13年出題】
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。
③【H19年出題】
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「公民権の行使により休業した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。
②【H13年出題】 ×
「通勤災害により療養のために休業した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。
③【H19年出題】 ×
「子の看護休暇を取得した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-228
R4.4.7 平均賃金 原則の計算式
平均賃金は、賃金の1日当たりの単価です。
解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の日の賃金、災害補償、減給制裁の制限額を算定するときに使います。
原則の計算式を条文で読んでみましょう。
第12条 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、・・・(以下例外。今回は省略します。) ② ①の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
平均賃金の原則の計算式は、
「算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額」÷「その期間の総日数」です。
「総日数」は「暦日数」のことです。例えば3月1日から5月31日までの3か月なら、92日です。
では、過去問をどうぞ
【R1年出題】
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
<条件>
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日
時間外手当については、毎月15日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
A 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
B 4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
C 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
D 通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
E 時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

【解答】
【R1年出題】
<この問題のポイント>
★賃金ごとに賃金締切日が異なる場合の平均賃金について
→ 各賃金ごとにその直前の締切日で算定します。
A 〇
「基本給、通勤手当、職務手当」は直前の賃金締切日である6月25日から遡り、「時間外手当」は直前の賃金締切日である7月15日から遡るのがポイントです。
B ×
C ×
「通勤手当」も平均賃金の計算に算入しなければなりません。問題文は通勤手当が入っていないので誤りです。
D ×
E ×
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-212
R4.3.22 法令等の周知義務
就業規則は職場のルールです。働く人はその内容を知っておかなければなりません。
使用者は、就業規則などを労働者に周知させる義務があります。
条文で確認しましょう。
第106条 (法令等の周知義務) 使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に規定する労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
則第52条の2 厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 2 書面を労働者に交付すること。 3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
②【R2年出題】
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に関する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「労働基準法、労働基準法に基づく命令」については、全文そのままではなく、要旨を周知させればよいことになっています。
しかし、就業規則は、要旨だけでなく全文の周知が必要です。
★周知義務が課せられているもの
・労働基準法、労働基準法に基づく命令の要旨
・就業規則(全文)
・労働基準法に規定する労使協定
①貯蓄金管理規定 ②賃金控除 ③1か月単位の変形労働時間制 ④フレックスタイム制 ⑤1年単位の変形労働時間制 ⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制 ⑦一斉休憩の適用除外 ⑧36協定 ⑨60時間超の時間外労働の場合の代替休暇 ⑩事業場外労働のみなし労働時間 ⑪専門業務型裁量労働制 ⑫時間単位の年次有給休暇 ⑬年次有給休暇の計画的付与 ⑭年次有給休暇の賃金を健康保険の標準標準日額で支払う制度 |
・労使委員会の決議
| ①企画業務型裁量労働制 ②高度プロフェッショナル制度 |
②【R2年出題】 ×
対象労働者に対してのみではなく、労働者全体への周知が義務付けられています。
(平11.3.31基発169号)
こちらもどうぞ!
③【H23年出題】
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。

【解答】
③【H23年出題】 〇
厚生労働省令で定められた3つの方法のいずれかの方法で周知しなければなりません。問題文の方法はそのうちの1つです。
パソコンなどで随時確認する方法です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法(就業規則)
労働基準法(就業規則)
R4-211
R4.3.21 制裁規定の制限
「制裁」には、譴責、戒告、出勤停止、減給、懲戒解雇などがあります。公序良俗に反しない限り、就業規則に定めることができます。
ただし、「減給」については、労働基準法で制限が設けられています。
減給は、労働した分の賃金をカットすることです。何も規制が無いと、例えば1回の遅刻に対する制裁として、1か月分の賃金を全てカットすることもできてしまうからです。
では、減給制裁の制限を条文で読んでみましょう。
第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
減給制裁は、「1回の額は平均賃金1日分の半額以内」、「一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額は、一賃金支払期の賃金の総額の10分の1以内」となっています。
(昭23.9.20基収1789号)
例えば、平均賃金が1万円、一賃金支払期の賃金総額が20万円なら、1回の額は5千円以内、一賃金支払期に減額できるのは2万円以内となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける
②【H28年出題】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。
③【R3年出題】
労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。
④【H16年出題】
就業規則で労働者に対して減給の定めをする場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
例えば、1時間遅刻した場合に、1時間分の賃金を差し引くことは、制裁による減給に該当しませんので、労働基準法第91条による制限は受けません。
ただし、1時間の遅刻に対して2時間分を減給することは制裁とみなされ、第91条による制限を受けることになります。
(昭63.3.14基発150号)
②【H28年出題】 ×
出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、「制裁としての出勤停止の当然の結果」で、減給制限に関する労働基準法第91条には関係ない、とされています。
(昭23.7.3基収2177号)
③【R3年出題】 〇
「一賃金支払期における賃金の総額」とは、当該賃金支払期に対し「現実に」支払われる賃金の総額をいいます。
(昭23.9.20基収1789号)
④【H16年出題】 ×
1賃金支払期の賃金総額が20万円の場合は、減給の総額は2万円以内です。もし、2万5千円の減給の制裁を行う必要がある場合は、5千円分は次期の賃金支払期に延ばすことができます。
「もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない」は誤りです。
(昭23.9.20基収1789号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法(就業規則)
労働基準法(就業規則)
R4-210
R4.3.20 就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
就業規則に記載する事項には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
いかなる場合でも絶対に記載しなければならない事項が「絶対的必要記載事項」、「定めをする場合」においては必ず記載しなければならない事項が「相対的必要記載事項」です。
では、条文で確認しましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
1から3が絶対的必要記載事項です。3の2以下は「定めをする場合においては」に注目してください。相対的必要記載事項です。
では過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
必要記載事項が記載されていない就業規則も、「他の要件を具備する限り有効」とされています。問題文の「労働基準法第13条に基づき、無効となる」の部分は誤りです。
しかし、定められた必要記載事項が記載されていないため、第89条違反の責任は免れません。
(平11.3.31基発168号)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。
③【H30年出題】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。
④【H25年出題】
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

【解答】
②【H23年出題】 〇
「休暇」は第1号の中に入っていますので、絶対的必要記載事項です。
年次有給休暇や産前産後休暇のように労働基準法で定められた休暇のみなならず、任意に設けている夏季休暇や慶弔休暇なども含まれます。
ボランティア休暇制度も「休暇」ですので、これに関する事項は就業規則に記載しなければなりません。
③【H30年出題】 ×
「制裁」は「定めをする場合」は記載しなければならない相対的必要記載事項です。制裁を定めない場合は、記載する義務はありません。
④【H25年出題】 〇
第10号は、「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」です。「従来の慣習」が当該事業場の労働者のすべてに適用されるのであれば、第10号に含まれますので、就業規則の記載が必要です。
(平11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法(就業規則)
労働基準法(就業規則)
R4-209
R4.3.19 就業規則の作成及び届出の義務
就業規則は、その事業場の「法的規範」としての性質を有します。
「就業規則」の作成手続きや、届出について条文で確認しましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 ※1~10まで記載事項がありますが、次回のテーマになりますので今回は省略します。
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、①の意見を記した書面を添付しなければならない。 |
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し届け出る義務があります。就業規則を変更した場合も同じです。
なお、「使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない」とされています。(則第49条)
また、作成、変更の場合は、過半数労働組合か、過半数労働組合がないときは労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
②【H25年出題】
派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者も0.5人ではなく1人で数えます。
労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」は労働者です。労働時間の長短は関係ありません。
なお、常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務はありません。
②【H25年出題】 〇
派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、「派遣元」の使用者です。派遣中の労働者は雇用関係のある派遣元の人数に入ります。
こちらもどうぞ!
③【H20年出題】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
④【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
⑤【H27年出題】
労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとすることにある。

【解答】
③【H20年出題】 ×
「同意を得なければならない」ではなく、「意見を聴かなければならない」です。
「同意を得るとか協議をするとかいうことまで要求しているものではない」とされていて、就業規則についての意見を聴けば労働基準法違反とならないという趣旨です。
(昭25.3.15基収第525号)
④【H21年出題】 〇
就業規則の作成のみならず、変更についても、意見聴取が必要です。
⑤【H27年出題】 〇
「労働協約」は労使の団体交渉で締結されますが、就業規則は、使用者が一方的に作成・変更することができます。
しかし、労働者が全く知らないままに就業規則の作成、変更が行われるのも問題です。
意見聴取を義務づけているのは、就業規則に労働者の団体的意見を反映させ、就業規則を合理的なものにするためです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-195
R4.3.5 1年変形/途中退職、途中入社の者の賃金清算
1年単位の変形労働時間制は、対象期間の途中に採用された人、途中で退職した人も対象になります。
実際に労働した期間が、対象期間よりも短い場合、賃金の清算が必要になることがあります。
条文を読んでみましょう。
第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条(災害等による臨時の場合)又は第36条第1項(三六協定)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 |
例えば、1年単位の変形労働時間制の対象期間を1月1日から12月31日までの1年間で設定している場合で考えてみましょう。
対象期間中の労働時間の総枠は、40時間×365日÷7≒2085.71時間です。
総枠の範囲内でこのように所定労働時間を設定したとします。
↓
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
170時間 | 147時間 | 180時間 | 166時間 | 180時間 | 166時間 | 180時間 | 180時間 | 166時間 | 180時間 | 180時間 | 190時間 |
この場合、年間の所定労働時間のトータルは2085時間で、1年間を平均すると1週間の労働時間が40時間以内になります。
☆条文に当てはめてみると
『対象期間より短い労働者』
例えば、Aさんが対象期間の途中の6月1日に入社したような場合です。Aさんが実際に労働した期間は6月1日~12月31日までで対象期間より短い期間です。
『労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた』
Aさんが所定労働時間分だけ労働した場合、6月1日から12月31日までの実際の労働時間のトータルは1,242時間となります。
次に、6月1日から12月31日までの期間を平均して1週間当たり40時間以内になる労働時間の総枠は、40時間×214日÷7≒1222.8時間で計算できます。
実労働時間の1,242時間から1222.8時間を引くと19.2時間になりますが、この19.2時間が『労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた』部分に当たります。
『第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない』
平均して1週間当たり40時間の枠を超えた19.2時間は、第37条の規定の例により割増賃金で清算することになります。
『(第33条(災害等による臨時の場合)又は第36条第1項(三六協定)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)』
例えば、36協定に基づいて時間外労働させた場合は、清算による割増賃金ではなく、本来の割増賃金の支払いが必要です。
過去問をどうぞ!
【H17年出題】
労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、同法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合には、同法第24条違反となる。

【解答】
【H17年出題】 〇
第37条違反ではなく、「第24条違反」になるのがポイントです。
最初に読んだ条文の「第37条の規定の例により」の部分に注目してください。
第37条は割増賃金の規定ですが、「第37条の規定の例により」とは、算定基礎賃金の範囲、割増率、計算方法等がすべて第37条と同じという意味です。
第37条の割増賃金ではないのがポイントです。そのため、清算のための割増賃金を支払わない場合は、第37条違反ではなく、第24条違反になります。
(平11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-194
R4.3.4 1年変形/連続して労働させる日数の限度
前回のテーマは、1年単位の変形労働時間制の対象期間の労働日数の限度、1日・1週間の労働時間の限度でした。
今回は連続して労働させる日数の限度についてお話します。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の4 1年単位の変形労働時間制 ③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 |
今回は、「連続して労働させる日数の限度」に注目します。
特定期間とそれ以外で設定が変わりますので注意してください。
☆ちなみに、「特定期間」とは?
特定期間とは、「対象期間中の特に業務が繁忙な期間」をいい、特定期間を設定する場合は、労使協定で定めます。
(特定期間 → 労基法第32条の4 第1項 第3号)
連続して労働させる日数の限度は、施行規則第12条の4で以下のように規定されています。
第12条の4 ⑤ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。 |
1年単位の変形労働時間の場合、連続労働日数は原則として最長6日です。
しかし、特に業務が繁忙な期間として「特定期間」を定めた場合は、その期間は「1週間に1日の休日が確保できる日数」=最長12日とすることができます。
(原則) 連続労働日数は最長6日まで
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆6日に1回は休日が必要です
(特定期間) 1週間に1日の休日が確保できる日数=連続労働日数は最長12日まで
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
1週目は日曜が休日、2週目は土曜が休日で、1週間に1日の休日が確保できています。特定期間は、連続労働日数は最長12日まで可能です。
では、穴埋め式でポイントを確認しましょう
則第12条の4
⑤ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は< A >日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は< B >が確保できる日数とする。

【解答】
A 6
B 1週間に1日の休日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-193
R4.3.3 1年変形/対象期間における労働日数の限度、1日及び1週間の労働時間の限度
1年単位の変形労働時間制の対象期間は、最長で1年間設定することができます。
対象期間が長いと、労働者の負担も増えますので、労働日数の限度、1日・1週間の労働時間の限度、連続して労働させる日数の限度が定められています。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の4 (1年単位の変形労働時間制) ③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 |
今回は、対象期間における「労働日数の限度」、「1日及び1週間の労働時間の限度」をお話しします。
まず、「労働日数の限度」については、則第12条の4第3項に、次のように定められています。
則第12条の4第3項 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、対象期間が3か月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。(以下省略) |
例えば対象期間を1年間とした場合は、1年間の労働日数の上限は280日です。
1年あたりの上限が280日ですので、例えば対象期間が6か月(暦日数は183日とする)だとすると、労働日数の上限は、280日×183日÷365日で計算します。答えは140.38日ですが、小数点以下は切り捨てますので労働日数の上限は140日になります。
では、穴埋め式でポイントを確認しましょう。
いわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合、対象期間における労働日数には限度が設けられている。労働日数の限度は、対象期間が < A >を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。

【解答】
A 3か月
労働日数の限度が適用されるのは、対象期間が3か月を超える場合に限られます。
対象期間が3か月以内の場合は、労働日数の制限はありません。
次は、「1日及び1週間の労働時間の限度」についてです。条文を読んでみましょう。
則第12条の4 ④ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。(以下省略) |
1年単位の変形労働時間制を採用する場合、1日、1週間の労働時間には上限が設けられています。1日は10時間以内、1週間は52時間以内です。
※対象期間が3か月を超える場合は、更に条件がありますが、今回はその説明は省略します。
※また、「積雪地域の建設業の屋外労働者等」、「隔日勤務のタクシー運転者」については、労働時間の上限に暫定措置が設けられていますが、今回はその説明は省略します。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

【解答】
【H30年出題】 ×
1日の労働時間の限度は10時間ですが、1週間の労働時間の限度は54時間ではなく「52時間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-192
R4.3.2 1年変形/対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間
1年単位の変形労働時間制を導入する際の「労使協定」には、対象期間の「労働日と労働日ごとの労働時間」を定めなければなりません。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の4 (1年単位の変形労働時間制) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。) 3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。) 4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 5 その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定め) |
今回は、第4号の「対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間」の部分に注目します。
1年単位の変形労働時間制は、対象期間を平均して1週間40時間を超えないことが条件です。前回は、そのための所定労働時間の総枠の計算についてお話ししました。
そして、その総枠の範囲内で、対象期間内の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を設定する必要があります。
例えば、対象期間を1年としたならば、1年間全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を労使協定締結時に特定しておかなければなりません。
しかし、全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」をあらかじめ特定できない場合の例外が()内の部分です。
( )内の内容
☆対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する
・「最初の期間(対象期間の初日の属する期間)」
→ 「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定する
・「最初の期間を除く各期間」
→ 「労働日数」と「総労働時間」を定める
例えば、対象期間が4月1日から1年間だとすると、対象期間を1か月ごとに区分することにより、労使協定締結時は以下のような定めが可能です。
①最初の期間 | ② | ③ | ④ | ・・・ |
4月1日~ 4月30日 | 5月1日~ 5月31日 | 6月1日~ 6月30日 | 7月1日~ 7月31日 | ・・・ |
・労働日 ・労働日ごとの 労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・・・
|
②以降の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」は後から特定しなければなりませんが、その際の手続きは以下の通りです。
条文を読んでみましょう。
第32条の4、則12条の4 ② 使用者は、労使協定で区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより(書面により)、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 |
☆最初の期間を除く各期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」の特定は、
・各期間の初日の少なくとも30日前
・過半数で組織する労働組合か労働者の過半数代表者の同意を得て
・書面により
行うことになります。
例えば、上の図でしたら、②の期間は「3月31日までに」、③の期間は「5月1日までに」、労働日と労働日ごとの労働時間を特定する必要があります。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
②【H18年出題】
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合おいて、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
1年単位の変形労働時間制については、原則として、対象期間中の労働日と各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定する必要があります。
②【H18年出題】 ×
「個々の対象労働者」ではなく、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」の同意を得て定めます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-191
R4.3.1 1年変形/労働時間の総枠について
1年単位の変形労働時間制を導入する場合の労働時間の総枠のルールについてお話しします。
条文を読んでみましょう。
第32条の4 (1年単位の変形労働時間制) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。) 3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。) 4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 5 その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定め) |
今回は、「対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内」の部分に注目します。
労働時間の総枠の考え方です。
対象期間を平均して1週間当たりの労働時間を40時間とするための規定です。
対象期間中の労働時間が、40時間×対象期間の暦日数÷7の範囲内に収まれば、平均すると1週間当たり40時間となります。
例えば、対象期間を1年(365日)とした場合は、
40時間×365÷7≒2085.71時間です。1年間の所定労働時間の総枠は2085.71時間となります。1年間の所定労働時間のトータルを2085.71時間以内に設定すれば、平均すると1週間当たりの労働時間が40時間以内になります。
なお、1か月単位の変形労働時間制は、第32条の2で「1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が32条第1項の労働時間(法定労働時間)を超えない」ことと規定されています。
「40時間」ではなく「法定労働時間」となっているのがポイント。総枠の計算式は、40時間(特例事業場は44時間)×変形期間の暦日数÷7となります。
1年単位には「44時間」の特例が適用されないので、対象期間の労働時間の総枠は「40時間」を使って計算します。一方、1か月単位には「44時間」の特例が適用されますので、労働時間の総枠は40時間又は44時間で計算します。違いに注意してください。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。

【解答】
【H28年出題】 〇
対象期間は、「その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限るものとする。」と定義されていますので、3か月や6か月でもよいです。
なお、労働時間の総枠は
6か月(例えば183日)の場合は、40時間×183日÷7≒1,045.71時間
3か月(例えば92日)の場合は、40時間×92日÷7≒525.71時間
となります。
次回も1年単位の変形労働時間制です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法
ここを乗り越えよう!労働基準法
R4-166
R4.2.4 休日の振替
「労働日」は労働する義務のある日、「休日」は労働する義務のない日です。
今日は「休日」がテーマです。
まず、「休日」のルールを条文で読んでみましょう。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 ② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
★休日は、「毎週1回」与えるのが原則です。例外的に4週間に4日も認められています。
さて、「休日の振替」についてお話します。
日曜が休日、月曜から土曜までが労働日。1日の労働時間が、月曜から金曜までは7時間、土曜が5時間の場合、カレンダーは以下のようになります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
業務の都合で日曜に7時間労働する必要が生じたので、あらかじめ同じ週の木曜の労働日と日曜の休日を入れ替えた場合、以下のようになります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7 | 7 | 7 | 7 | 休 | 7 | 5 |
結果、日曜は「労働日」、木曜は「休日」になります。このことを休日の振替といいます。日曜は「労働日」ですので、労働した7時間は休日労働ではありません。
ポイントは「あらかじめ」の部分です。事前に入れ替えることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保されている範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。

【解答】
①【H21年出題】 〇
一番のポイントは、『休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定する』の部分です。
また、「就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設けている」こと、「4週4日の休日が確保されている」こともポイントです。
(昭63.3.14基発150号)
次に、こちらもどうぞ!
②【H13年出題】
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。
③【H18年出題】
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。

【解答】
②【H13年出題】 〇
「就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定がある」、「4週4日の休日は確保されている」そして、「あらかじめ」、「振り替えるべき休日を特定して休日の振替を行った」場合は、当初の休日は労働日となります。その日は労働日となりますので、休日労働にはなりません。
(昭63.3.14基発150号)
③【H18年出題】 〇
以下のような勤務カレンダーで、あらかじめ1週目の日曜日と2週目の木曜日を振り替えた場合で考えてみましょう。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1週目 | 休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2週目 | 休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
1週目の日曜は「労働日」、2週目の木曜が「休日」になります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1週目 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2週目 | 休 | 7 | 7 | 7 | 木 | 7 | 5 |
1週目の日曜は労働日になりましたので、休日労働にはなりません。
ただし、休日を振り替えたことにより、1週目の労働時間が47時間となり法定労働時間を超えてしまいます。その場合、その超えた時間は時間外労働となりますので、時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。
(昭63.3.14基発150号)
 まとめ
まとめ
・休日の振替は、あらかじめ振替の休日を指定することが必要です。
なお、休日出勤させてから事後に他の勤務日を休ませるのは「代休」です。代休を与えても休日出勤の事実は無くなりませんので、休日労働の割増賃金の支払いが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法
ここを乗り越えよう!労働基準法
R4-156
R4.1.25 労働が2暦日にわたる場合の労働時間
労働基準法第32条では、1日の労働時間は8時間以内とされています。
「1日」とは、原則として「午前0時から午後12時まで」の暦日をさします。
(S63.1.1基発1号)
では、例えば、令和4年1月25日の労働が日をまたがって翌日の26日まで継続したように、勤務が2暦日にわたる場合は、どのようにカウントするのでしょうか?
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
例えば、1月25日の16時から26日の3時まで11時間勤務した場合は、「始業時刻の属する日」である25日の「1日」の労働とされます。
労働者は実際に25日から11時間連続で労働しているので、暦日が異なっていても1勤務とされます。
もし、原則どおりの暦日で考えると、26日0時でリセットされてしまい、26日の3時間は時間外労働にもならず、労働者に不利益になってしまうからです。
(昭和63.1.1基発1号)
では、こちらをどうぞ!
②【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間
A 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
B 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
C 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
D 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
E 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

【解答】
A ×
休日労働が8時間を超えても時間外の割増率を加算する必要はありません。問題文の法定休日の日曜の10時間労働は3割5分増で差し支えないとされています。ただし、深夜業に該当した場合は、深夜の2割5分増の加算が必要です。
(昭和22.11.21基発266号)
B ×
日曜の午後8時から月曜の午前3時までの勤務は、1勤務として扱われます。ただし、休日を含む2暦日にまたがった場合、休日の午前0時から午後12時までの時間帯は「休日労働」の割増率になります。
問題文の場合は、日曜の午後8時から午後12時までが、休日割増賃金対象の労働になります。
(平6.5.31基発331号)
C 〇
月曜日と火曜日は暦日が異なっていても1勤務として取り扱います。問題文の場合は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。
(昭和63.1.1基発1号)
D ×
Bと同じように考えます。
土曜から日曜の午前3時までの勤務は1勤務として扱われますが、法定休日の日曜の午前0時からは3時までは休日割増で計算します。
E ×
割増賃金の対象は、木曜と金曜が2時間ずつ、土曜は4時間です。
木曜と金曜は1日の法定労働時間である8時間を超えた時間が割増賃金の対象です。
月曜から金曜までで割増対象以外の通常の労働時間のトータルが34時間になります。1週間の法定労働時間は40時間以内ですので、土曜日は6時間までが通常の労働時間、4時間が割増賃金対象の労働時間となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
割増対象 |
|
|
|
| 2 | 2 | 4 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法編
ここを乗り越えよう!労働基準法編
R4-140
R4.1.9 1か月単位の変形労働時間制 その2(導入手続き)
前回に引き続き、1か月単位の変形労働時間制です。
今回は、1か月単位の変形労働時間制の導入の手続のお話です。
条文を読んでみましょう。
第32条の2 ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間・特例の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において法定労働時間(40時間・特例の場合は44時間)又は特定された日において法定労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」が必要です。
★ポイントその1
「又は」がポイント。「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらかという意味です。
なお、「労使協定」は所轄労働基準監督署長に届け出が必要です。
★ポイントその2
「就業規則に準ずるもの」がポイント。
「就業規則に準ずるもの」で導入できるのは労働者が10人未満の事業場です。労働者が10人以上の事業場は就業規則の作成義務がありますので、「就業規則に準ずるもの」では導入できません。
・10人以上の事業場 → 「労使協定」か「就業規則」(就業規則に準ずるものは不可)
・10人未満の事業場 → 「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」
★ポイントその3
「特定された週」「特定された日」がポイント。
労使協定や就業規則等に、各日、各週の所定労働時間を具体的に定めることが必要です。業務の都合があったとしても、使用者が途中で任意に変更することはできません。
では、過去問をどうぞ
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
③【H18年出題】
労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」だけでも採用することができます。
また、労使協定で採用することもでき、その場合は所轄労働基準監督署長に届け出が必要です。
しかし、問題文の「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。」の部分は誤りです。1か月単位の変形労働時間制の労使協定の効力は届け出によって発生するのではなく、労使協定の締結で発生します。
(H11.1.29基発45号)
②【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制では、1日、1週間の労働時間の限度は設けられていません。
(S63.1.1基発1号)
③【H18年出題】 ×
変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内であったとしても、途中で、任意に労働時間を変更することはできません。
(S63.1.1基発1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法編
ここを乗り越えよう!労働基準法編
R4-139
R4.1.8 1か月単位の変形労働時間制 その1
法定労働時間は、原則として1週40時間以内、1日8時間以内です。
例えば、月から金が所定労働日、土日が休日の場合で、1日の労働時間が8時間の場合、カレンダーは以下のようになります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 休 | 休 |
これで法定労働時間ピッタリです。
もし、月曜日に2時間残業したとすると、その2時間は法定時間外労働となりますので、2割5分以上の割増賃金が必要です。
さて、「1か月単位の変形労働時間制」は、1か月以内の一定の期間を平均して1週40時間(特例の事業場は44時間)以内であれば、長く労働する日や、長く労働する週があってよい、という制度です。
なお、1か月以内の一定の期間は、1週間でも2週間でも1か月でも任意に設定でき、その期間のことを変形期間といいます。
変形期間を平均して1週40時間(特例は44時間)とするには、まず、変形期間の労働時間の総枠を計算します。
計算式は次の通りです。
40時間(特例44時間)×変形期間の暦日数÷7
例えば変形期間を1か月と設定して計算してみましょう。
(前提)法定労働時間40時間、変形期間の暦日数31日
40時間×31日÷7 ≒ 177.1時間
1か月のトータルの労働時間が177.1時間以内なら、平均すると1週40時間以内になります。
例えば、月初が業務多忙な場合は、月初の労働時間を長くして全体のバランスをとることができます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9時間 | 9時間 | 9時間 | 9時間 | 9時間 | 9時間 | 休 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 休 | 休 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 休 | 休 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 休 | 休 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
6時間 | 6時間 | 6時間 |
|
|
|
|
変形労働時間制を採用すると、「特定された週」又は「特定された日」に法定労働時間を超えて労働させることができます。
上のカレンダーは1か月トータルの労働時間が177時間です。1週目の労働時間だけみると、1日9時間、1週54時間ですが、変形期間を平均すると1週40時間以内になりますので時間外労働にはなりません。
では、過去問をどうぞ
①【H19年出題】
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

【解答】
①【H19年出題】 〇
計算式「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」のポイント!
・その事業場の週法定労働時間
→ 原則40時間ですが、特例事業場は「44時間」です。
・変形期間の暦日数
→ 「労働日数」ではなく「暦日数」です。例えば、1週間なら7日、4週間なら28日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ① 労働基準法
どんな法律シリーズ① 労働基準法
R4-132
R4.1.1 労働基準法ってどんな法律?
労働基準法 ・・・ 昭和22年4月制定
まず、こちらの条文を読んでみましょう。
第13条 (労働基準法違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
例えば、使用者と労働者が、こんな内容の労働契約を締結した場合を考えてみましょう。
・ 始 業 8時
・ 終 業 21時
・ 休憩時間 12時~13時
・ 休 日 毎週日曜日
労働基準法の法定労働時間は、週40時間・1日8時間以内が原則ですが、その最低ラインよりも不利な労働契約の内容です。
この場合は、第13条にあるように、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」は、「その部分については無効」です。
労働基準法よりも不利な内容の部分は空欄になります。
そして、「無効となった部分は、この法律で定める基準による」となるので、空欄になった部分は労働基準法の基準に書き換えられます。
もう一つのポイントは、労働契約全体が白紙になるのではなく、労働基準法より不利な部分だけが空欄になることです。
労働契約全体が白紙になると、労働契約自体が無くなってしまい、それはそれで労働者保護に欠けてしまうからです。
では、過去問をどうぞ
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H21年出題】
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効になるだけでなく、無効になった部分は、労働基準法の基準で補充されます。
②【H21年出題】 ×
労働基準法の基準は最低ラインです。労働基準法の基準より有利なものはもちろん有効です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉛」条文の読み方(労働基準法)
「最初の一歩㉛」条文の読み方(労働基準法)
R4-131
R3.12.31 「総日数」と「労働日数」の違い
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、平均賃金の条文を読んでみましょう。
第12条 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 1 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 |
平均賃金の計算式の原則は、「3か月間の賃金総額÷その期間の総日数」です。
ポイント!総日数は「暦上の日数」
例えば、12月21日が算定事由発生日で、賃金締切日が15日の場合は、平均賃金は直前の賃金締切日の12月15日から遡った3か月で計算します。
9月16日~10月15日、10月16日~11月15日、11月16日~12月15日の賃金総額を91日(その期間の総日数)で除します。
また、日給、時給、出来高払制その他の請負制の場合は、最低保障が設けられています。
計算式は、「3か月間の賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60」です。
ポイント! 「労働日数」は、暦上の日数ではなく、実際に労働した日数
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

【解答】
①【H19年出題】 〇
この問題のチェックポイントは、
原則は、「その期間の総日数」で除すこと。
最低保障は、「その期間中に労働した日数」で除すこと、「100分の60」を忘れないようにしてください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉑」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉑」法律によって定義が異なる用語
R4-121
R3.12.21 「児童」の定義(労基法・児童手当法)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
労働基準法第56条 (最低年齢) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 |
労働基準法では、中学校を卒業するまでの年齢の児童を労働させることを、原則として禁止しています。
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日」が終了するまでが、保護の対象です。
児童手当法第3条 児童手当法において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 |
児童手当法の「児童」は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」にあって、「日本国内に住んでいる」又は「留学などのために海外に住んでいて一定の要件をみたす」者と定義されています。
そして、もう一つ、「支給要件児童」という用語もあります。
支給要件児童は、第4条で「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童」)又は「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童」と定義されています。
では、過去問を解いてみましょう
【労働基準法】
①【H29年出題】
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
②【H23年出題】
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
「満15歳に達するまで」ではなく、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。原則として労働させることができないのは、義務教育終了までです。
②【H23年出題】 〇
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者」でも、所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用することができる例外規定があります。
満13歳以上の場合は、「非工業的事業の職業」、満13歳未満の場合は、「映画の製作又は演劇の事業」(子役の俳優)で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものが許可の条件です。
といっても義務教育中のため学校優先です。「修学時間外に使用することができる」と規定されています。そのため、労働時間は「修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内」とされています。
(法第56条第2項、第60条第2項)
では、「児童手当法」の過去問を解いてみましょう。
【児童手当法】
③【H30年選択式】
11歳、8歳、5歳の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき< A >である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

【解答】
③【H30年選択式】
A35,000円
ポイント!
・支給の対象
児童手当は、父母、父母指定者、里親、施設の設置者などに支給されます。児童に支給するのではないので注意してください。
・児童手当の額(1人当たり月額)※施設入所等児童を除く
3歳未満 → 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 → 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 → 一律10,000円
問題文の場合は、10,000円+10,000円+15,000円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩②」過去問の活用(労働基準法)
「最初の一歩②」過去問の活用(労働基準法)
R4-102
R3.12.2 「労働時間」とは?(労基 過去問活用編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
今日は、「労働時間」の定義を確認しましょう。
労働基準法第32条で法定労働時間が定められています。
法第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
労働基準法では、労働時間の最長を「1週間40時間、1日8時間」と定めています。
この時間のことを「法定労働時間」といいます。(なお、1週44時間となる特例も設けられていますが、今日は詳しく触れません。)
使用者は、法定労働時間の範囲内で、事業場や労働者ごとに労働時間を定めますが、その時間のことを所定労働時間といいます。
例えば、就業規則で定めた所定労働時間が1日7時間で、ある日に9時間労働させた場合は、法定時間外労働は、1日8時間を超えた時間である1時間となります。
労働者に法定時間外労働をさせる場合は、36協定の締結と届出、割増賃金の支払が労働基準法で使用者に義務付けられています。

では、具体的に「労働時間」の意味を過去問で確認しましょう。
①【H21年出題】
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
②【R2年出題】
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「休憩時間」は、労働から解放されることが約束された時間のことです。
休憩時間の来客当番は、来客があった場合には、即、接客が義務づけられている状態ですので労働から解放されていません。その時間に実際に来客がなかった場合でも、「手待ち時間」であり、労働時間となります。
問題文の場合は、割増賃金を支払う義務があります。
(昭23.4.7基収1196号)
②【R2年出題】 〇
運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間でも、いつでも運転ができる状態にある時間は手待ち時間で、労働時間に当たります。
(昭33.10.11基収6286号)
★この過去問でおさえておくところ★
手待ち時間は労働時間

では、条文を穴埋めで確認しましょう。
第32条 (労働時間)
① 使用者は、労働者に、< A >を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、< A >を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

【解答】
A 休憩時間
例えば、
始業 8時
終業 17時
休憩12時~13時
の場合、拘束時間9時間、休憩1時間で、労働時間は8時間となります。
休憩時間は労働時間から除かれることに注意しましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩①」条文の読み方(労働基準法)
「最初の一歩①」条文の読み方(労働基準法)
R4-101
R3.12.1 専門用語に慣れましょう(労働基準法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
「勉強始めよう」と決意したものの、
専門用語が多すぎてくじけてしまう
過去問が活用できない(解くだけで終わってしまう)
条文の読み方が難しい
という方も多いと思います。
2022年まであと1か月。
新年から、社労士の受験勉強を本格化させようと決心している方も多いはず。
本格的なスタートの前に、
少しだけ条文や過去問に慣れてみましょう。
労働基準法から順番にお話していきます。

では早速、労働基準法第15条第1項を読んでみましょう。
第15条(労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
ポイント1 「その他の」
★「賃金、労働時間その他の労働条件」の「その他の」に注目してください。
「その他の」の前にある語句は、「その他の」の後ろにある語句の中に含まれます。
第15条の労働条件は、「賃金、労働時間」も含んだ「労働条件」となります。
★「その他の」ではなく、「の」のつかない「その他」という用語もあります。
例えば、第7条(公民権行使の保障)の条文は、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は・・・(以下略)」です。
「選挙権」と「公民としての権利」の間に「その他」が入っています。この場合は、「選挙権」と「公民としての権利」が並んでいるだけです。
ポイント2 「厚生労働省令で定める方法」
★「厚生労働省令」に注目してください。
後段に「厚生労働省令で定める方法」とありますが、この「厚生労働省令で定める方法」は、具体的には、「労働基準法施行規則第5条第4項」に規定されています。
「法令」には、法律、政令、省令があり、「法律」は国会、「政令」は内閣、「省令」は各大臣が制定します。
労働基準法の場合、国会が制定した法律として「労働基準法」、内閣が制定した政令として「時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」など、厚生労働大臣が制定した厚生労働省令として「労働基準法施行規則」があります。
労働契約時に明示する労働条件の明示の方法については、法律では「厚生労働省令で定める方法により明示」としか書いてありませんが、具体的な方法は「労働基準法施行規則」を見れば書いてある、という仕組みです。
ちなみに、労働基準法施行規則第5条第4項では、明示の方法は、「書面の交付とする」とされていますが、労働者が希望した場合には、「ファクシミリ」、「電子メール等」(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による明示も認められています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-075
R3.11.5 就業規則の意見聴取
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「就業規則の意見聴取」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7C】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

【解答】
①【R3年問7C】 ×
同一の事業場で、一部の労働者のみに適用される就業規則を別に作成することは可能です。ただし、意見聴取は、その事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は、全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
問題文は、当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合等になっているので誤りです。
(昭23.8.3基収2446号)
こちらもどうぞ!
②【H21年出題】
使用者は、パートタイム労働者など当該事業場の労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合には、当該一部の労働者のみ適用される別個の就業規則を作成することもできる。
③【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
④【H20年出題】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

【解答】
②【H21年出題】 〇
一部の労働者のみ適用される別個の就業規則を作成することもできます。その場合、労働基準法上の就業規則は、それぞれが単独でなるのではなく、その2つ以上の就業規則を合わせたものが労働基準法上の就業規則となります。
(平11.3.31基発168号)
③【H21年出題】 〇
就業規則の作成だけでなく、その変更についても、意見聴取が必要です。
(法第90条)
④【H20年出題】 ×
「同意を得なければならない」ではなく、「意見を聴かなければならない」です。
なお、意見書の内容が「反対」であったとしても、その就業規則の効力には影響しません。
(昭24.3.28基発373号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-074
R3.11.4 1か月単位の変形労働時間制導入手続き
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「1か月単位の変形労働時間制導入手続き」です。
では、どうぞ!
①【R3年問5B】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。

【解答】
①【R3年問5B】 ×
1か月単位の変形労働時間制を、労使協定で導入する場合は、所轄労働基準監督署長への届出が義務づけられています。
届出をしなかった場合は罰則が適用されます。しかし、届出は労使協定の効力の発生要件とはなっていません。締結することで効力が発生します。ですので、問題文の最後の「この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。」の部分が誤りです。
なお、36協定は、「所轄労働基準監督署長に届け出る」ことによって効力が発生しますので、違いに注意しましょう。
良かったら「36協定の免罰効果」の記事も参考にしてください。
(法第32条の2)
こちらもどうぞ!
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」によって導入することができます。
「就業規則その他これに準ずるものによる定め」だけでも導入が可能です。
また、①の問題で見たように、「労使協定」で導入する場合は届出が必要ですが、届出が効力の発生要件ではないので、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる」の部分も誤りです。
なお、常時10人以上の労働者を使用する事業は就業規則作成義務があるので、1か月単位の変形労働時間制を導入する場合は、「労使協定」又は「就業規則」のどちらかとなります。「就業規則に準ずるもの」では導入できません。
10人未満の事業場では、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」で導入できます。
こちらもどうぞ!
③【H19年出題】
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

【解答】
③【H19年出題】 〇
変形期間の所定労働時間の合計が、「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」で計算した時間内におさまるようにする必要があります。
例えば、変形期間を「1か月」とした場合、30日の月なら、「40時間×30日÷7=171.4時間」が1か月の総枠となります。1か月の所定労働時間の合計が171.4時間以内なら、変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となります。
ちなみに、特例事業場の場合は法定労働時間は44時間ですので、総枠は「44時間×30日÷7=188.5時間」となります。
最後に条文を穴埋めで確認しましょう!
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は< A >により、< B >以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の協定を行政官庁に届け出なければならない。

【解答】
A 就業規則その他これに準ずるもの
B 1か月
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-073
R3.11.3 前借金相殺の禁止
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「前借金相殺の禁止」です。
では、どうぞ!
①【R3年問2C】
労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

【解答】
①【R3年問2C】 ×
問題文のような「明らかに身分的拘束を伴わないもの」は、労働することを条件とする債権には「含まれない」とされています。
(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発第90号)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

【解答】
②【H27年出題】 〇
第17条は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することで、身分的拘束の発生を防止することを目的とした条文です。
(法第17条)
こちらもどうぞ!
③【H28年出題】
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
④【H25年出題】
労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

【解答】
③【H28年出題】 ×
「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること」は使用者側で行うことのみが禁止されます。労働者からの意思により相殺することは禁止されていません。
④【H25年出題】 ×
第17条で禁止しているのは、前借金自体ではなく、「労働者の賃金と相殺」することです。「当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず」の部分が誤りです。
最後に条文を穴埋めで確認しましょう!
第17条 (前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他< A >ことを条件とする前貸の債権と賃金を< B >してはならない。

【解答】
A 労働する
B 相殺
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-072
R3.11.2 36協定の免罰効果
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「36協定の免罰効果」です。
では、どうぞ!
①【R3年問5A】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】
①【R3年問5A】 〇
36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出をすることによって効力が発生します。締結しただけでは効力が発生しないのが36協定のポイントです。
問題文の36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出た令和3年4月9日に効力が発生します。ですので、届け出前の令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた時間外労働は、36協定の効果がないため、違法なものとなります。
(法第36条)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
③【H24年出題】
労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

【解答】
②【H24年出題】 〇
本来、時間外労働、休日労働は労働基準法違反です。
しかし、36協定を締結し、かつ所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になります。(免罰効果といいます。)
(法第36条)
③【H24年出題】 〇
36協定の直接効力は、時間外労働、休日労働の刑事上の免責です。
36協定の手続により免罰効果は生じますが、労働者に対して時間外又は休日労働命令をできる権利は生じません。時間外労働、休日労働命令に従わなければならない労働者の民事上の義務は、労働協約、就業規則などの根拠が必要です。
(法第36条、参照:昭63.1.1基発1)
次はこちらをどうぞ
④【H25年出題】
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

【解答】
④【H25年出題】 〇
36協定の効力は、その労働組合の組合員でない他の労働者にも及びます。
(昭23.4.5基発535号)
最後にこちらをどうぞ!
⑤【H20年選択】
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。

【解答】
A 合理的な
(最高一小H3.11.28)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-071
R3.11.1 時間単位の年次有給休暇
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「時間単位の年次有給休暇」です。
では、どうぞ!
①【R3年問2E】
労働基準法第39条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。

【解答】
①【R3年問2E】 ×
時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象になります。
しかし、日単位による取得の請求を時間単位に変更することや、時間単位による取得の請求を日単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められません。
(平21.5.29基発第0529001号)
★「時間単位年休」を導入する場合は、労使協定の締結が必要です。時間単位年休の制度により、労働者が時間単位で請求すれば、時間単位の年次有給休暇を取得することができることになります。
個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものではありませんし、時間単位で取得するか、日単位で取得するかは、労働者の意思によります。
(参照:平21.5.29基発第0529001号)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

【解答】
②【H25年出題】 〇
先ほどの①の解説にもありますが、時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象になります。
(平21.5.29基発第0529001号)
次はこちらをどうぞ
③【H26年出題】
労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められていない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
時間単位年休は、「労働者が時間単位による取得を請求した」場合に、時間単位により年次有給休暇を与えることができる制度です。そのため、計画的付与として時間単位年休を与えることは認められません。
(平21.5.29基発第0529001号)
では、条文を穴埋めで確認しましょう!
(時季指定権と時季変更権)
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが< A >場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

【解答】
A 事業の正常な運営を妨げる
(法第39条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-070
R3.10.31 賃金支払5原則「通貨払いの原則」
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「賃金支払5原則「通貨払いの原則」」です。
賃金の支払には5つの原則があります。
1 通貨払いの原則
2 直接払いの原則
3 全額払いの原則
4 毎月1回以上払いの原則
5 一定期日払いの原則
それぞれ原則の例外もおさえましょう。
では、どうぞ!
①【R3年問3イ】
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。

【解答】
①【R3年問3イ】 ×
「労働協約の適用を受けない労働者」には、通貨以外のもので支払うことはできません。
★ 賃金は、通貨で支払うのが原則ですが、「法令」又は「労働協約」に別段の定めがある場合は、通貨以外のもの(現物)で支払うこともできます。
労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことができるのは、「労働協約の適用を受ける労働者」に限定されます。
(法第24条、S63.3.14基発150号)
★ 労働協約は、労働組合法に規定されています。「労働組合」と使用者との間の協約ですので、労働組合のある事業場だけに存在するものです。
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
③【R1年出題】
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

【解答】
②【H29年出題】 〇
通貨以外のもの(現物)で賃金を支払うことができるのは、事業所のすべての労働者ではなく、「労働協約の適用を受ける労働者」に限られます。
(法第24条、S63.3.14基発150号)
③【R1年出題】 ×
労働協約と労使協定の違いに注意しましょう。
労働協約は、「労働組合」がある事業場だけのものです。
一方、労使協定は、労働組合がない事業場でも締結できます。労働組合がない事業場の場合は、「労働者の過半数を代表する者」と協定を締結します。
(法第24条)
では、こちらもどうぞ!
④【R3年問3ア】
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。

【解答】
④【R3年問3ア】 ×
問題文の場合は、「労働者の同意」が必要です。
退職手当は、通常の賃金よりも額が多いので、危険回避のため、振込み以外に小切手で支払うこともできますが、その場合も労働者の同意が必要です。
(則第7条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-060
R3.10.21 年少者の時間外、休日、深夜労働
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「年少者の時間外、休日、深夜労働」です。
では、どうぞ!
①【R3年問5C】
労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18歳に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。

【解答】
①【R3年問5C】 ×
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」の規定は、年少者にも適用されますので、そのような場合は年少者にも時間外労働、休日労働をさせることができます。
★年少者の時間外、休日、深夜労働の可否を確認しましょう。
| 時間外・休日労働 | |
| 三六協定 | × |
災害その他避けることのできない事由 | 〇 |
| 公務のため | 〇 |
| 深夜労働 | |
| × 原則禁止 | |
災害その他避けることのできない事由 | 〇 |
| 公務のため | × |
(法第33条、法第60条、第61条)
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
③【H13年出題】
36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
満18歳に満たない者には、36協定による時間外労働を行わせることはできませんが、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは可能です。
(法第60条)
③【H13年出題】 ×
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、満18歳未満の労働者にも、休日労働をさせることができます。
(法第60条)
では、「第33条」を穴埋めでチェックしましょう
第33条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
① 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< B >届け出なければならない。
② ①ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を< C >と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、 < D >(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

【解答】
A 許可
B 事後に遅滞なく
C 不適当
D 官公署の事業
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-052
R3.10.13 労基「減給制裁の制限」
令和3年の問題から「労働基準法」を学びましょう。
今日は減給制裁の制限です。
では、どうぞ!
①【R3年問7E】
労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。

【解答】
①【R3年問7E】 〇
「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」の10分の1を超えてはならないという趣旨です。
賃金の総額が欠勤や遅刻等により減額され少額となった場合でも、その少額となった賃金総額の10分の1を超えてはなりません。
(法第91条 S25.9.8基収1338号)
こちらもどうぞ!
②【H16年出題】
就業規則で労働者に対して減給の定めをする場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。

【解答】
②【H16年出題】 ×
一賃金支払期に、複数の減給事案が発生した場合、その減給の総額は、「その賃金支払期における賃金総額の10分の1以内」でなければなりません。
これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合は、次期の賃金支払期に延ばすことができます。
(S23.9.20基収1789号)
では条文を穴埋めで確認しましょう!
第91条 (制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の< A >を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の< B >を超えてはならない。

【解答】
A 半額
B 10分の1
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働基準法 応用問題
R4-042
R3.10.3 労基「管理監督者と妊産婦の労働時間」
和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労働基準法です。
では、どうぞ!
①【R3年問5D】
労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

【解答】
①【R3年問5D】 ×
解き方のポイント!
法第41条で、「監督又は管理の地位にある者」については「労働時間、休憩、休日の規定は適用されない」と規定されています。
また、第66条には、「妊産婦」について、「妊産婦が請求した場合は、災害等による臨時の必要がある場合や36協定の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならない」等の規定があります。
「監督又は管理の地位にある者」が「妊産婦」である場合、労働時間の規定は適用されるのか?というのがこの問題のテーマです。
「妊産婦のうち、第41条に該当する者については、労働時間に関する規定は適用されない」とされています。問題文のように、労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があったとしても、適用されません。
(法第66条、S61.3.20基発151号)
では、こちらもどうぞ!
②【H19年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。
③【H17年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【解答】
②【H19年出題】 ×
第66条第2項の規定は、監督又は管理の地位にある妊産婦には適用されません。
(S61.3.20基発第151号)
③【H17年出題】 ×
問題文の最後の「同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。」の部分が誤りです。深夜業をさせることはできません。
問題を解くポイント!
妊産婦が請求した場合は、「時間外労働、休日労働又は深夜業」をさせることはできません。
ただし、監督又は管理の地位にある者には、労働時間、休憩、休日は適用されませんので、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があったとしても、「時間外労働、休日労働」をさせることはできます。
しかし、第41条に規定する者については、「深夜業」の規定は適用されます。
ですので、「監督又は管理の地位にある妊産婦」から「深夜業をしない」請求があった場合は、深夜業をさせることはできません。
(S61.3.20基発151号)
第41条の条文を確認しましょう
第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第6号(< A >を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず< B >にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 < C >に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

【解答】
A 林業
B 監督若しくは管理の地位
C 監視又は断続的労働
※ちなみに、別表第一6号は農林の事業、第7号は畜産水産業の事業です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働基準法よく出るところ
R4-032
R3.9.23 労基法「差別的取り扱い」とは?
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は労働基準法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

【解答】
①【R3年問1B】 〇
「有利」に取り扱うこと、「不利」に取り扱うこと、どちらも「差別的取扱」となります。
(法第3条)
では、こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。

【解答】
②【H30年出題】 〇
第4条も差別的取扱いを禁止する条文ですが、こちらも、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も差別的取扱いに含まれます。
(法第4条、S22.9.13発基第17号)
では、条文を確認しましょう。
第3条
使用者は、労働者の< A >を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、< B >について、男性と差別的取扱をしてはならない。

【解答】
A 国籍、信条又は社会的身分
B 賃金
では、こちらの問題もどうぞ!
③【H29年出題】
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
④【H27年出題】
労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
第3条で差別禁止事由とされているのは、「国籍、信条、社会的身分」です。「性別」による差別は、第3条では禁止されていません。
(法第3条)
④【H27年出題】 〇
第4条で女性であることを理由として差別的取り扱いを禁止しているのは、「賃金」についてのみです。
賃金以外の労働条件についての差別的取扱いは第4条違反にはなりません。なお、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いは、男女雇用機会均等法に抵触する可能性があります。
(法第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働基準法の定番問題
R4-022
R3.9.13 「休日」に休業手当支払い義務はある?ない?
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は労働基準法です。
①【R3年問4B】
使用者が法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。

【解答】
①【問4B】 ×
休日は、「労働する義務のない日」ですので、休業手当を支給する義務はありません。ですので、休業手当を支払わなければならない日に「休日」は含みません。「労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日」(法定休日以外の休日)も休業手当の支払義務はありません。
(昭24.3.22基収4077号)
もう一問どうぞ!
②【H18問2C】
労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

【解答】
②【H18問2C】 〇
①の解説と同じです。
では、労働基準法第26条を穴埋めでチェックしましょう。
第26条 (休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その< A >の100分の< B >以上の手当を支払わなければならない。

【解答】
A 平均賃金
B 60
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労働基準法【択一】
R4-011
R3.9.2 第53回労基(択一)より~産前産後
第53回試験を振り返ってみましょう。
☆☆☆ 労働基準法は、過去問のポイントをしっかりおさえていれば、解きやすかったと思います。
【R3年問6】
A 労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
B 労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
C 使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
D 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
E 労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。

【解答】
問6A 〇
「出産」の範囲は、「妊娠4か月」以上の分娩のこと。
1か月は28日で計算するので、4か月以上とは85日以上のこととなります。
(S23.12.23基発1885)
問6B ×
妊娠中絶でも、妊娠4か月以後に行った場合は、産後休業の規定が適用されます。
(S26.4.2婦発113号)
問6C 〇
出産当日は「産前」に含まれます。
(S25.3.31基収4057号)
問6D 〇
産前休業は、女性の「請求」が条件ですので、請求がなければ就業禁止にはなりません。
一方、「産後休業」は、請求を条件にしていませんので、請求の有無にかかわらず、就業させることは禁止されています。(ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない、とされています。)
問6E 〇
第65条第3項では、『妊娠中の女性が「請求した場合」(この規定も請求が条件です。)においては、他の軽易な業務に転換させなければならない』と規定されています。女性が請求した業務に転換させることが原則ですが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まではありません。
(S61.3.20基発151号)
最後に条文をチェックしましょう
第65条(産前産後)
① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、< A >週間)以内に出産する予定の女性が休業を< B >場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後< C >週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、< D >の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

【解答】
A 14
B 請求した
C 8
D 妊娠中
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(労基法)
R4-002
R3.8.24 第53回選択労基~やや難しい★★☆
第54回試験に向けて、スタートします。
まずは、第53回試験を解いてみました。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、労働基準法です。
【問1】
労基法第16条(賠償予定の禁止)に出てくる「違約金」の性質について
「労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない」場合、違約金を支払う義務のある者は、「労働者本人」、「親権者」、そしてもう一つは?ということですが、解答は「身元保証人」です。
前後の文脈をみて、選択肢の中から、身元保証人を選べたと思います。
問1 A ☆☆☆(どうにか解ける)
【問2】
国際自動車事件(R2.3.30最1小判)からの出題です。
・使用者が労基法37条の「割増賃金を支払った」といえるか否かの判断について
ポイント
・前提 → 労働契約における賃金の定めにつき、「通常の労働時間の賃金」に当たる部分と「割増賃金に当たる部分」とを判別することができることが必要
・使用者が、「特定の手当」を支払うことにより、労基法第37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合
→労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべき
→その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない
Bについて
労基法第37条(割増賃金)で、「通常の労働時間」の賃金が割増賃金の基礎となると規定されているので、そこから「通常の労働時間の賃金」が選べたと思います。
問2 B ☆☆☆(どうにか解ける)
Cについて
「特定の手当」が「割増賃金」だと裁判で主張するには何が必要か?と考えてみる。
例えば、選択肢⑫のように、情報提供や説明の内容だけでは弱いような・・・。また、⑮のように我が国社会の一般的状況を持ち出してもなんとなく説得力に欠ける。
と考えてみると、ここは、⑭「当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け」が選べたのでは?と思います。
問2 C ★★★(でも難しいです)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法 選択対策
R3-352
R3.8.10 労基法選択問題~過去問より
今日は、労働基準法の選択対策です。過去問をどうぞ!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① H20年出題
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法[・・・・・]32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔・・・・・〕」というのが最高裁判所の判例である。
問題② H23年出題
「〔年次有給〕休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を< B >として発生するのであって、年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はないものといわなければならない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
問題③ H22年出題
「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間[当該期間]の満了により右雇用契約[当該雇用契約]が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間[当該期間]は契約の存続期間ではなく、< C >であると解するのが相当である。」とするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
問題①
A 合理的な
参照→最高一小H3.11.28
問題②
B 解除条件
参照→最高二小S48.3.2
問題③
C 試用期間
参照→最高三小H2.6.5
関連過去問もどうぞ!
④<H27年出題>
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。
⑤<H22年出題>
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
④<H27年出題> ×
当該就業規則の規定の内容が「合理的なもの」である限り、それが具体的労働契約の内容をなす。なので、その就業規則の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、「労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」ことになります。
参照→最高一小H3.11.28
⑤<H22年出題> ×
年次休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』の観念を容れる余地はない、とされています。
参照→最高二小S48.3.2
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【労基法】フレックスタイム制
R3-318
R3.7.7 清算期間が1か月を超える場合のフレックスタイム制
今日のテーマはフレックスタイム制です。
本題の前にフレックスタイム制を導入の要件を確認しておきましょう。
① 就業規則その他これに準ずるものに規定する
・「始業及び終業の時刻」をその労働者の決定に委ねること
② 労使協定で一定事項を定める
「清算期間」とは?
清算期間とは → その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(原則40時間、特例44時間)を超えない範囲内において労働させる期間をいい、< A >以内の期間に限るものとする。

【解答】
A 3か月
フレックスタイム制の清算期間の上限は3か月です。
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、一定のルールがあります。そのルールを次の問題で確認しましょう。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、清算期間が1か月を超える場合において、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するため、労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、清算期間の途中であっても、当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

【解答】
①<R1年出題> 〇
 フレックスタイム制の時間外労働は?
フレックスタイム制の時間外労働は?
フレックスタイム制の時間外労働は、清算期間の法定労働時間の総枠を超えた部分です。
例えば、清算期間が1か月の場合は1か月単位で労働時間を清算します。
1か月の法定労働時間の総枠は、暦日数が31日の月でしたら177.1時間です。もし、1か月でトータルした実際の労働時間が総枠を超えていれば、その枠を超えた時間が時間外労働となります。
 では、清算期間を3か月とした場合は?
では、清算期間を3か月とした場合は?
清算期間を3か月にした場合は、3か月単位で清算します。
暦日数が92日だとすると、法定労働時間の総枠は525.7時間(労働時間の週平均が40時間)となり、実際の労働時間のトータルが総枠を超えれば、超えた分が時間外労働となります。
ただし、清算期間が1か月を超える場合は、『1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えないこと』というルールがあります。
ですので、問題文のように、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当し、36協定の締結と届出、清算期間の途中でも割増賃金を支払う必要があります。
(法第32条の3)
★もう一つ注意★ 特例事業場の場合、清算期間が1か月以内なら「44時間」の特例が適用されますが、清算期間が1か月を超える場合は、特例は適用されませんので原則の40時間が適用されます。
こちらもどうぞ!
②<R2年出題>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

【解答】
②<R2年出題> ×
フレックスタイム制の労使協定
・清算期間が1か月以内 → 届出不要
・清算期間が1か月を超える → 届け出なければならない
(法第32条の3)
ついでに「労使協定の有効期間」もチェックしましょう。
清算期間が1か月を超える → 有効期間の定めをすること
(則第12条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働基準法 切り上げ切捨て
R3-289
R3.6.8 労基法・端数処理どこまで認められる?
今日は、労働基準法の端数処理はどこまで認めらるのか?がテーマです。
労働基準法には、「全額払いの原則」(労働した分は100%支払う)がありますが、計算の便宜上、一定のラインまでは端数処理が認められています。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。
②<H25年出題>
1日及び1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること、1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること並びに1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げることは、いずれも労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
①<H19年出題> ×
「1日」ごとに設問のような端数処理を行うのは、全額払いに原則に反します。
違反とならない端数処理は、
「1か月」の時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計の1時間未満の端数 → 30分未満切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
(昭63.3.14基発150号)
②<H25年出題> ×
問題文の最初の「1日」が誤りです。
時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは、「1日」単位は不可、「1か月」ならOKです。(①の問題と同じ)
問題の後半は〇です。
・ 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額の円未満の端数
→ 50銭未満切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
・ 1か月の時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端 数 → 50銭未満切り捨て、それ以上を1円に切り上げる
こちらも、どうぞ!
③<H29年出題>
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う事務処理方法は、労働基準法第24条違反として取り扱わないこととされている。
④<H24年出題>
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)に生じた千円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことは、労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】
③<H29年出題> 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額。)の100円未満の端数 → 50円未満切り捨て、それ以上を100円に切り上げる(OK)
④<H24年出題> 〇
1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、控除後の額)の千円未満の端数 → 翌月の賃金支払日に繰り越して支払う(OK)
③と④は、現金払いのときに封筒の中で小銭がジャラジャラたくさんにならないように、というイメージで覚えてください。
社労士受験のあれこれ
労働基準法 休業手当
R3-288
R3.6.7 休業手当の支払義務がある日・ない日
今日は、労働基準法「休業手当」です。
休業手当の支払義務が発生する日はどんな日なのでしょうか?
では、どうぞ!
<H27年出題>
■■問題文の労働者の労働条件■■
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
A 使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日間の休業手当を支払わなければならない。
B 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
C 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
D 休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労総契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。
E 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
A ×
ポイント!
「休日」=労働する義務のない日。もともと労働の予定のない日なので、休業手当を支払う義務はありません。
問題文の場合、所定休日の土曜日と日曜日には休業手当を支払う義務はありませんので、5日間の休業手当を支払うことになります。
(昭24.3.22基収4077号)
B 〇
ポイント!
一労働日の一部だけ休業した場合は、全体として平均賃金の100分の60まで支払わなければならない。
問題文の場合、労働基準法で義務付けられるのは、平均賃金(10,000円)×100分の60=6,000円以上です。
4時間の労働で7,500円の支払がなされているので、休業手当をプラスして支払う必要はありません。
しかし、例えば、使用者の責に帰すべき事由でその日の労働時間が1時間に短縮され、その日の賃金が1,875円の場合は、休業手当として6,000円との差額(4,125円)を支払わなければなりません。
(昭27.8.7 基収3445号)
C 〇
ポイント!
「休日」は休業手当の支払義務はありません。(Aと同じです。)
問題文の場合、振替によって、日曜日が「労働日」、水曜日が「休日」となっているので、水曜日に休ませても休業手当の支払義務はありません。
(昭24.3.22基収4077号)
D 〇
ポイント!
特定の労働者に対して、その意思に反して就業を拒否する場合も、「休業手当」の支払義務の対象です。
ちなみに、「休業」は丸一日とは限りません。Bの問題のように1日の一部だけ休業する場合も含まれます。
E 〇
ポイント!
休電による休業については、原則としての使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しません。
休業手当を支払わなくても、26条違反にはなりません。
(昭26.10.11基発696号)
社労士受験のあれこれ
出来高払い制の保障給
R3-287
R3.6.6 労基法・出来高払いの保障給は何に対する保障なの?
今日は、労働基準法第27条「出来高払い制の保障給」です。
では、どうぞ!
①<R1年選択>
労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、「使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定めている。

【解答】
A 労働時間
出来高払制の労働者の場合、本人は出勤していても、材料などが不足していると出来高が上がらず、そうすると賃金が支払われなくなります。
そのようなことのないよう、「労働時間」に応じ、一定額の保障をしなければならないことになっています。
ですので、労働者が労働者の責に帰すべき事由で「就業しなかった」(=労働時間が無い)場合は、保障給も支払う必要はありません。
(法第27条、昭23.11.11基発1639号)
では、こちらをどうぞ!
②<H26年出題>
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障することにある。
③<H28年出題>
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

【解答】
②<H26年出題> ×
「その出来高や成果」ではなく、「労働時間」に応じた賃金の支払を保障することが趣旨です。
③<H28年出題> 〇
「労働時間に応じた」一定額の賃金の保障が必要なので、原則は時間給となります。
「実労働時間の長短と関係なく」1か月について一定額を保障するものは、保障給とはいえません。
最後はこちらを
④<H13年出題>
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

【解答】
④<H13年出題> ×
出来高払制の保障給は「労働時間」に応じた保障を義務付けています。問題文のように休業している場合は、保障する必要はありません。
ただし、問題文のように「使用者の責に帰すべき事由によって休業」する場合は、「休業手当」を支払う義務があります。
社労士受験のあれこれ
労基法上の「休日」
R3-249
R3.4.29 労働基準法上「休日」とは?
今日のテーマは、労働基準法の「休日」です。
まず、労働基準法の「休日」の与え方について確認してみましょう。
<原則> 毎週少くとも1回
<例外> 4週間を通じ4日以上
では、どうぞ!
①<H29年出題>
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
②<H13年出題>
労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。
③<H24年出題>
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
①<H29年出題> ×
連続24時間、労働義務から解放しても「休日」を与えたことにはなりません。
原則として、労働基準法の「休日」は、午前零時から午後12時までの暦日を指します。起算時点は、午前零時です。
(昭23.4.5基発535号)
②<H13年出題> ×
休日は、原則として、午前零時から午後12時までの暦日ですが、例えば8時間3交替連続作業の場合などは、例外的に2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることも認められています。
(昭63.3.14基発150号)
③<H24年出題> 〇
一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、休日とは認められません。
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 〇 | 非番 | 〇 | 非番 | 〇 | 非番 | 休日 | 〇 |
8時 |  8時 8時 | 8時 |  8時 8時 | 8時 |  8時 8時 | 8時 |
※非番は休日とはならない。「休日」は原則どおり午前零時から午後12時までの暦日でなければなりません。
(昭23.11.9 基収2968号)
こちらの問題もどうぞ!
④<H23年出題>
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準じるものおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。
⑤<H13年出題>
4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場にあっては、年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。

【解答】
④<H23年出題> 〇
休日は「毎週1回」が原則。例外的に「4週間を通じ4日以上の休日」(変形休日制)が認められています。
変形休日制の場合、4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものおいて明らかにする必要があります。
(昭22.9.13発基17号、則第12条の2)
⑤<H13年出題> ×
変形休日制の場合、特定の4週間に4日の休日があればOKです。
どの4週間を区切っても、4日の休日がなければならないという意味ではありません。
④の問題で見たように、起算日を明らかにしなければならないのは、特定の4週間を明確にするためです。
(昭23.9.20基発1384号)
社労士受験のあれこれ
平均賃金
R3-248
R3.4.28 平均賃金~算定すべき事由の発生した日
労働基準法の「平均賃金」は、原則として『算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額』÷『その期間の総日数』で計算します。
今日のテーマは、「算定すべき事由の発生した日」についてです。
なお、「平均賃金」は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償、減給制裁の際に使われます。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
②<H25年出題>
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。
③<H30年出題>
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。
④<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

【解答】
①<H27年出題> ×
災害補償の場合、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」となります。
(施行規則第48条)
②<H25年出題> ×
③<H30年出題> ×
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
(昭30.7.19 29基収5875号)
④<H16年出題> 〇
解雇予告手当を算定する場合の「算定すべき事由の発生した日」は、労働者に解雇の通告をした日です。
(昭39.6.12 36基収2316号)
こちらの問題もどうぞ!
⑤<H27年出題>
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】 〇
ポイント!
①条文では、「算定すべき事由の発生した日以前3か月間」となっていますが、事由の発生した日の前日から遡ると解されています。
問題文の場合、7月31日に算定事由が発生していますので、前日の7月30日から遡ります。
②ただし、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算することになっています。問題文の場合、7月30日の直前の賃金締切日は6月30日となります。
(第12条)
社労士受験のあれこれ
労基法、安衛法、労働契約法の違い
R3-245
R3.4.25 使用者の定義(労基法・安衛法・労契法)
今日のテーマは、「使用者」の定義です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法の違いをチェックしましょう。
では労働基準法からからどうぞ!
①<労働基準法 H21年選択>
労働基準法において「使用者」とは、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする< A >をいう。
②<労働基準法 H26年出題>
労働基準法にいう「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいうと定義されている。

【解答】
①<労働基準法 H21年選択>
A すべての者
労働基準法の使用者
・事業主
・事業の経営担当者
・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
②<労働基準法 H26年出題> ×
労働基準法の使用者は、「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。
次は労働安全衛生法です!
③<安衛法 H28年出題>
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
④<安衛法 H26年出題>
労働安全衛生法では、「事業者」は、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主の為に行為をするすべての者をいう。」と定義されている。

【解答】
③<安衛法 H28年出題> 〇
労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念を異にしています。
「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。
労働基準法上の義務主体である「使用者」と違い、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしています。
(法第2条、昭47.9.18発基91号)
④<安衛法 H26年出題> ×
労働安全衛生法第2条で、「事業者」は、「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されています。
事業者の意味づけは③で解説している通りです。
最後は労働契約法をどうぞ!
⑤<労働契約法 H29年出題>
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。

【解答】
⑤<労働契約法 H29年出題> ×
「労働基準法第10条の「使用者」と同義である。」が誤りです。
労働契約法の「使用者」とは、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいいます。
したがって、個人企業の場合はその企業主個人を、会社その他の法人組織の場合はその法人そのものをいうものであり、これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当し、労働基準法の「使用者」より狭い概念であること、とされています。
(法第2条、H24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
労基法、安衛法、労働組合法、労働契約法の相違
R3-244
R3.4.24 労働者の定義(労基・安衛・労組・労契)
今日のテーマは、「労働者」の定義です。
労働基準法、労働安全衛生法、労働組合法、労働契約法の違いをチェックしましょう。
ではこちらからどうぞ!
①<労働基準法>
労基法第9条(定義)
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、< A >をいう。
第116条(適用除外)
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び< B >については、適用しない。
②<安衛法 H28年出題>
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
③<労働組合法 H23年出題>
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。
④<労働契約法 H24年出題>
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

【解答】
①<労働基準法>
A 賃金を支払われる者
B 家事使用人
②<安衛法 H28年出題> 〇
労働安全衛生法の労働者の定義は、「労働基準法第9条の労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)」をいうとされています。
(安衛法第2条)
③<労働組合法 H23年出題> 〇
労働組合法では、「「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。
(労組法第3条、昭和23年6月5日労発第262号)
④<労働契約法 H24年出題> 〇
労働契約法の「労働者」には、「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」のすべてが含まれます。そのため、その要件に該当すれば家事使用人にも労働契約法は適用されます。
なお、労働契約法第21条(適用除外)では、労働契約法の適用について、①国家公務員及び地方公務員については、適用しない。②使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
とされていて、家事使用人は適用除外に入っていません。
(法第2条、第21条、平24.8.10基発0810第2号)
社労士受験のあれこれ
割増賃金の算定
R3-213
R3.3.24 どこからどこまで?時間外労働・休日労働
今日は労働基準法です。
時間外労働は原則として2割5分以上、休日労働は3割5分以上の割増率で、賃金を計算しなければなりません。
今日は、日をまたがって残業したときなど、様々な事例の問題を解いてみましょう。
では、どうぞ!
<H30年出題>
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金についての問題。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
①<H30年出題>
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
②<H30年出題>
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
③<H30年出題>
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
④<H30年出題>
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
⑤<H30年出題>
日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払いの義務の対象労働になる。

【解答】
①<H30年出題> ×
★8時間を超えた2時間に対して時間外労働の割増率を加算する必要はありません。
法定休日には、時間外労働という概念がありませんので、法定休日の日曜に10時間労働した場合は、その10時間は休日労働の割増率だけで計算します。(深夜業に該当する場合は深夜割増を加算します。)
(労基法第37条、平11.3.31基発168号)
②<H30年出題> ×
★月曜の午前0時から3時までは休日ではありません。
法定休日は原則として暦日単位となり、問題文の場合は、日曜の午前0時から午後12時までの24時間が「休日」です。
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、休日割増賃金対象の労働は、日曜の午後8時から午後12時までです。
(平6.5.31基発331号)
③<H30年出題> 〇
問題文の場合、月曜の始業から火曜の午前3時までを1日の労働として扱うことになります。
通達(昭63.1.1基発1号)では、「継続勤務が二暦日にわたる場合はたとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする、とされています。
(昭63.1.1基発1号)
④<H30年出題> ×
★土曜の時間外労働は土曜の午後12時まで
②の問題と同じで、日曜の午前0時からは法定休日です。
問題文の場合、日曜の午前0時から3時までは休日労働で計算します。
(平6.5.31基発331号)
⑤<H30年出題> ×
★時間外労働は「1日単位」でも見なければならない
時間外労働となるのは、1日8時間を超えた部分ですので、まずは木曜2時間、そして金曜2時間です。
金曜日の時点で、法定労働時間内の労働が34時間、時間外労働が4時間です。
土曜日に10時間労働していますが、そのうち6時間までは週の法定労働時間以内の労働で、残りの4時間が時間外労働となります。
(労働基準法第32条)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 残業(法定時間内) | 2 | 2 | |||||
| 時間外労働 | 2 | 2 | 4 |
社労士受験のあれこれ
労働基準法第1条(労働条件の原則)
R3-182
R3.2.21 第1条チェック~労働基準法編
今日から、各法律の第1条をチェックしていきます。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
まずは、労働基準法です。
選択式からどうぞ!
<H19年選択>
労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

【解答】
A が人たるに値する生活を営む
「人たるに値する生活」とは、憲法第25条第1項の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」からきているものです。労働基準法で定める労働条件は「健康で文化的」な生活を送るための最低限の基準。そんな考えを意識しながら、労働基準法を読んでみてください。
では、過去問をどうぞ
①<H25年出題>
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。
②<H28年出題>
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】
①<H25年出題> 〇
労働基準法の定める労働条件は最低基準です。この最低基準を標準とするのではなく、労働関係の当事者は、さらに「向上」を図るように努めましょう、という感じで読んでみてください。
②<H28年出題> 〇
労働基準法が制定されたのは昭和22年ですが、その際の通達(昭和22年9月13日発基第17号)では、第1条について次のように記されています。
「本条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであって本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。」
労働基準法の各条文の基本観念です。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働者について
R3-179
R3.2.18 労働者性の判断(最高裁判例より)
今日は労働基準法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。
「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、< A >の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、< B >等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」

【解答】
A 時間的、場所的な拘束
B 報酬の支払方法、公租公課の負担
★ 「横浜南労基署長事件(平成8年11月28日最高裁)」からの出題です。判決では、労働者性は認められていません。
<キーワード>
・時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やか
・報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、 上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない
→ 「 報酬は、運賃表により出来高が支払われていた」
「所得税の源泉徴収並びに社会保険及び雇用保険の保険料の控除はされておらず、上告人は、報酬を事業所得として確定申告をした」
<参考>
『昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告 (労働基準法の「労働者」の判断基準について)』によると、
「実質的な使用従属性」を労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素をも勘案して総合的に判断する必要がある。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働に関する判断基準
イ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
ハ 拘束性の有無
ニ 代替性の有無
(2)報酬の労務対償性に関する判断基準
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
イ 機械、器具の負担関係
ロ 報酬の額
ハ その他
(2)専属性の程度
(3)その他
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第9条の労働者には該当しない。

【解答】 〇
芸能タレントの「労働者性」についての行政通達です。
人気の程度、就業の実態、収入の形態等からみて判断されます。
(昭63.7.30 基収355号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)請負関係と労働関係
R3-170
R3.2.9 「請負契約」と「労働契約」の違い
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-D>
下請負人が、その雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するとともに、当該業務を自己の業務として相手方(注文主)から独立して処理するものである限り、注文主と請負関係にあると認められるから、自然人である下請負人が、たとえ作業に従事することがあっても、労働基準法第9条の労働者ではなく、同法第10条にいう事業主である。

【解答】 〇
それぞれの関係を整理すると、下請負人と注文主は「請負関係」、下請負人とその雇用する労働者とは「雇用関係」にあります。
「請負」とは、 ① 請負事業主が、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること、② 請負事業主が、業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することの2つの要件を満たすことが必要です。
問題文はどちらも満たしているので、労働者ではなく事業主となります。
(参考:「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号))
こちらの問題もどうぞ!
①<H27年出題>
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。
②<H29年出題>
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

【解答】
①<H27年出題> 〇
労働契約の場合は、『使用者の指揮命令に従って労務を提供する→賃金が支払われる』という関係ですが、請負契約の場合は、『注文主から受けた仕事を完成させる→報酬が支払われる』という関係です。請負契約の場合は、注文主から指揮命令を受けないのがポイントです。
ですので、「その実体において使用従属関係が認められるとき」は、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たります。
②<H29年出題> ×
工場と大工が、請負契約ではなく雇用契約を結ぶことにより使用従属関係になることもあります。その場合は、大工は労働基準法第9条の労働者に該当します。
(昭23.12.25基収4281号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)金品の返還
R3-169
R3.2.8 労働者が退職した場合の金品の返還
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-オ>
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。

【解答】 〇
労基法第23条は、労働者の退職の際に、労働者の金品を迅速に返還すべきことを規定した条文です。足止め策に利用することなどを防止するためです。
例えば、退職した労働者から賃金支払いの請求があった場合は、所定の賃金支払い日前でも、請求日から7日以内に支払わなければなりません。
ちなみに、「権利者」とは、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は相続人です。
また、賃金又は金品に関して争いがある(賃金の額などについて労使で争いがある)場合は、異議のない部分を7日以内に支払うこととなっています。
(昭22.9.13基発17号)
こちらの問題もどうぞ!
①<H30年出題>
労働基準法第20条第1項に定める解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
②<H12年出題>
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
①<H30年出題> 〇
解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」とされています。
(昭23.3.17基発464号)
②<H12年出題> ×
退職手当は、通常の賃金とは扱いが異なり、「予め就業規則等で定められた支払時期」に支払えばよいとされています。
(昭26.12.27基収5483号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)就業規則の記載事項
R3-168
R3.2.7 就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-A>
慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。

【解答】 ×
就業規則へ記載するか否か、当事者の自由です。
(昭23.10.30基発1575号)
就業規則には、必ず記載しなければならない事項『絶対的必要記載事項』と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 『相対的必要記載事項』があり、以下のように定められています。
<絶対的必要記載事項>
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
<相対的必要記載事項>
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰及び制裁に関する事項
⑧ その他、当該事業場の労働者すべてに適用される定めに関する事項
問題文の「労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする」という事項は、絶対的必要記載事項でも相対的必要記載事項でも当てはまらないので、就業規則の記載は任意となります。
こちらの問題もどうぞ!
①<H25年出題>
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。
②<H14年出題>
休職に関する事項は、使用者がこれに関する定めをする場合には、労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条第1項の規定により、労働契約の締結に際し労働者に対して明示しなければならない労働条件とされており、また、それが当該事業場の労働者すべてに適用される定めであれば、同法第89条に規定する就業規則の必要記載事項でもある。

【解答】
①<H25年出題> 〇
「従来の慣習」を就業規則に規定しなければならないか?がテーマです。
問題文の、従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用される」の部分がポイントです。
相対的必要記載事項の最後の「そのほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に該当するので、就業規則に規定しなければなりません。
(昭23.10.30基発1575号)
②<H14年出題> 〇
「休職に関する事項」について
労働契約の際 → 「休職」については、労基法施行規則第5条で「定めをする場合は明示しなければならない」事項に掲げられているので、休職に関する事項の定めがあるる場合は明示しなければなりません。
就業規則 → 「休職」に関する事項が、「当該事業場の労働者すべてに適用される定め」であれば、就業規則の相対的必要記載事項として記載しなければなりません。
(労基法第15条第1項、第89条、同法施行規則第5条第1項)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働時間の定義
R3-167
R3.2.6 「労働時間」とはどんな時間のこと?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-A>
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。

【解答】 〇
運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間でも、万一の場合は運転を交替したり、故障個所を修理することもあり得ます。労働から解放されていないので、労働時間に当たります。
(昭33.10.11基発6286号)
こちらの問題もどうぞ!
①<H26年出題>
労働基準法第32条にいう「労働」とは、一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。したがって、例えば、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠をとっているときであってもそれは「労働」であり、その状態にある時間は労働基準法上の労働時間である。
②<H21年出題>
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。

【解答】
①<H26年出題> 〇
令和2年の問題と同じです。
「労働」の概念をつかみましょう。『一般的に、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、必ずしも現実に精神又は肉体を活動させていることを要件とはしない。」の部分がポイントです。
②<H21年出題> ×
来客当番として事務所に待機させた時間は、労働時間となります。問題文の場合は来客当番の時間を入れると法定労働時間を超えるので、割増賃金を支払う義務があります。
(昭23.4.7基収1196号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)解雇予告の意思表示
R3-166
R3.2.5 解雇予告の意思表示は取り消すことができるか?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-ウ>
使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。

【解答】 〇
いったん解雇を告げた後に、「やっぱり解雇は取り消したい」と言えるかどうかですが、解雇予告の意思表示を取り消すことは、一般的にはできません。
ただし、労働者が自らの判断で取消しに同意した場合は、取り消すことができるという解釈です。
(昭33.2.13基発90号)
こちらの問題もどうぞ!
①<H16年出題>
ある労働者を解雇しようと思い、労働基準法第20条の規定に従って、5月1日に、30日前の予告を行った。しかし、その後になって思い直し、同月10日、当該労働者に対し、「考え直した結果、やはり辞めてほしくないので、このままわが社にいてくれないか。」と申し出てみたが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。その場合、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は自己退職(任意退職)したこととなる。
②<H24年出題>
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

【解答】
①<H16年出題> ×
②<H24年出題> ×
どちらの問題も、解雇を予告した後、「やはり引き続きわが社にいてほしい」と解雇の取り消しを申し出ていますが、労働者は、解雇の取り消しに同意せずそれに応じていません。
その場合、「予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。」は誤りです。
行政解釈では、「解雇予告の意思表示の取り消しに対して、労働者の同意がない場合は、自己都合退職の問題は生じない」となっていて、このような場合は、自己都合退職ではなく、予告期間を経過した日に「解雇」ということになります。
(昭33.2.13基発90号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)解雇予告の除外
R3-165
R3.2.4 解雇予告除外認定の要件など
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-エ>
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。

【解答】 ×
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度に不可抗力かつ突発的な事由という意味です。
「事業場が火災により焼失した場合」は「やむを得ない事由」に該当しますが、「使用者の重過失による火災で事業場が焼失」した場合は除かれます。
(労基法第20条 昭63.3.14基発150号)
解雇予告の条文をチェック!
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。)
(解雇予告除外認定)
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。)
こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。

【解答】 〇
①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
②労働者の責に帰すべき事由
→所轄労働基準監督署長の認定を条件として、予告・予告手当なしで解雇することができます。
では、もう一問どうぞ!
<H18年出題>
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇予告除外認定」という。)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。

【解答】 〇
原則は、「解雇予告除外認定」は解雇の意思表示をなす前に受けるべきもの。
では、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、解雇の効力いつ発生するのでしょうか?
問題文にあるように、『解雇予告除外事由に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得る』とされます。
この問題のポイントは、そのような事実がある場合には、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する、の部分です。
平成24年には、即時解雇の効力は認定のあった日に発生するという出題がありましたが、それは誤りです。認定のあった日ではなく即時解雇の意思表示をした日に発生します。
(昭63.3.14基発150号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働条件の明示
R3-164
R3.2.3 書面の交付等による明示義務
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-イ>
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

【解答】 〇
労働者を雇い入れる際に、「賃金」に関する事項は、書面等による明示が必要です。
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
(昇給については書面でなくてもよい)
※基本給の額等を具体的に書面に記載するのが原則。
しかし、就業規則に規定されている賃金等級で労働者が賃金を確定できるのならば、等級を明確に示す方法でも可。
問題文のように、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。(ただし、就業規則が周知されていることが前提)
(労働基準法第15条、施行規則第5条、昭51.9.28基発第690号)
では、こちらの問題をどうぞ
①<H9年出題>
使用者は、労働契約の締結に際し、賃金に関する事項については、書面により明示しなければならないこととされているが、採用時に交付される辞令に就業規則に定める賃金等級が表示され、当該就業規則が労働者に周知されていれば、この書面による明示がなされていると解してよい。
②<H12年出題>
労働契約の締結に際し書面を交付して明示すべき労働条件のうち、退職に関する事項については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないが、明示事項の内容が膨大なものとなる場合は、労働者の利便性をも考慮し、適用される就業規則の関係条項名を網羅的に示すことで足りる。

【解答】
①<H9年出題> 〇
令和2年度の問題と同じです。
②<H12年出題> 〇
例えば、『定年、退職の手続き、解雇の事由及び手続「詳細は、就業規則第21条~25条」による』という記載でもよい。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)労働契約の契約期間
R3-163
R3.2.2 労働契約の契約期間の上限は?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-ア>
専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、当該労働者の有する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限って契約期間の上限を5年とする労働契約を締結することが可能となり、当該高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合の契約期間の上限は3年である。

【解答】 〇
高度の専門的知識等を有する労働者との間の労働契約 → 上限5年まで可能
※ただし高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限る。(高度の専門的知識を必要とする業務に就いていない場合は、上限3年まで)
労働契約は、次の2つに分けられます。
・期間の定めのない契約(労基法上規制なし)
・期間の定めのある契約(規制あり)
【期間の定めのある契約について)
原則 → 3年以内
例外その1(3年を超える期間が可能)
・建設工事などの有期事業(その事業の終わりまでの契約が可能)
・職業訓練(訓練期間が長期にわたる場合)
例外その2(上限5年まで)
・高度の専門的知識等を有する労働者をそのような高度の専門的知識等が必要な業務に就かせる場合
・満60歳以上の労働者との労働契約
(労働基準法第14条)
では、こちらの問題をどうぞ
①<H25年出題>
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
②<H27年出題>
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
③<H18年選択式出題>
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が < A >ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。

【解答】
①<H25年出題> 〇
満60歳以上の労働者との契約期間は上限5年です。
②<H27年出題> 〇
例えば、4年で完成する建設現場に、4年の契約期間で雇い入れるような場合です。
③<H18年選択式出題>
A 1,075万円を下回らない
高度の専門的な知識、技術又は経験については、告示で限定列挙されていて、そのうちの一つです。
(労働基準法第14条 H15.10.22厚労告356号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)派遣の仕組み
R3-162
R3.2.1 労基法の使用者は、派遣元?派遣先?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-E>
派遣労働者が派遣先の指揮命令を受けて労働する場合、その派遣中の労働に関する派遣労働者の使用者は、当該派遣労働者を送り出した派遣元の管理責任者であって、当該派遣先における指揮命令権者は使用者にはならない。

【解答】 ×
派遣労働者に関する労働基準法は、原則として、労働契約関係にある派遣元(派遣会社)が、使用者としての責任を負います。
ただし、 一部の規定については、派遣労働者の指揮命令権者である派遣先が、使用者としての責任を負うことになっています。
では、こちらの問題をどうぞ
①<H9年出題>
派遣先の使用者は、当該事業場において災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に法定時間外又は法定休日に労働させることができるが、この場合、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。
②<H17年出題>
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。

【解答】
①<H9年出題> 〇
第33条「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働・休日労働」について、事前に行政官庁の許可を受ける、又は事後に遅滞なく届出をする義務は「派遣先」が負います。
(昭61.6.6基発333号)
②<H17年出題> ×
36協定は「派遣元」で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ます。
(昭61.6.6基発333号)
ちなみに・・・
※派遣労働者については、派遣先の事業のみを当該労働者を使用する事業とみなして労働時間に係る規定を適用しています。
・労働時間の把握は?
派遣労働者に係る労働時間を適正に把握する義務は「派遣先」にある。
・36協定に基づく時間外労働等
派遣先が時間外労働等を行わせる場合は、36 協定の範囲内であること。もし、その範囲を超えて時間外労働等を行わせた場合には、派遣先は労基法違反となる。
(労働者派遣法第44条 労働基準法の適用に関する特例)
では、最後にこちらもどうぞ!
<H16年出題>
派遣中の派遣労働者については、派遣先が極端な繁忙状態になっており、当該派遣労働者が年次有給休暇を取得すれば派遣先の事業の正常な運営を妨げるような場合であっても、年次有給休暇の時季変更権の行使に係る事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。

【解答】 〇
事業の正常な運営を妨げるかどうかの判断は、「派遣元」の事業でなされます。
(昭61.6.6基発333号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労基法)36協定~時間外労働の限度時間
R3-158
R3.1.28 36協定で協定する事項は?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-C>
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

【解答】 〇
36協定には、対象期間の、「1日」「1か月」「1年」のそれぞれの期間の労働時間を延長して労働させることができる時間(時間外労働の時間)を協定することになっています。
その時間は、労基法に以下のように規定されています。
・1か月45時間、1年360時間
・1年単位の変形労働時間(対象期間が3か月を超える期間を定めている場合)は、1か月42時間、1年320時間
(労基法第36条)
では、第36条を穴埋めで確認しましょう!
第36条 時間外及び休日の労働
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は第35条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
【協定で定めること】
① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
② 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間。1年間に限るものとする。)
③ 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
④ 対象期間における< A >、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
※ ④の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
※ 限度時間は、1か月について< B >時間及び1年について< C >時間とする。
1年単位の変形労働時間制の対象期間として< D >を超える期間を定め労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とする。
それ以外に
・有効期間の定め、対象期間の起算日など
・通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合(特別条項)

【解答】
A 1日
B 45
C 360
D 3か月
(労基法第36条)
最後にもう一問どうぞ!
<H24年出題>
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】 〇
36協定は、「所轄労働基準監督署長に届出」をすることによって免罰効果が生まれることがポイントです。
単に「36協定を締結しました(届け出してません)」では、効果はありません。
(労基法第36条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(労基法)労基法上の「使用者」とは
R3-157
R3.1.27 労基法上使用者とはどのような立場の人?
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問1-B>
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。

【解答】 ×
労働基準法には様々な義務規定がありますが、使用者は、その履行の責任者となります。
部長や課長という名称ではなくて、労働基準法の義務について実質的に一定の権限を与えられている場合は、労働基準法の使用者として責任を問われることになります。
問題の場合、「係長」という名称でも、責任と権限があれば労働基準法の使用者になります。
参照:(昭和22.9.13発基第17号)
では、令和2年の問題からもう一問どうぞ!
<問1-C>
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。

【解答】 ×
一問目と同じです。
課長という役職であっても、権限がなく、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、労働基準法の使用者にはなりません。
参照:(昭和22.9.13発基第17号)
では、もう一問どうぞ!
<H24年出題>
労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう。

【解答】 ×
「事業主のために行為をするすべての者」です。管理監督者以上に限定されていません。
穴埋め式で条文check!
第10条 使用者の定義
この法律で使用者とは、< A >又は事業の< B >その他その事業の労働者に関する事項について、< C >をいう。

【解答】
A 事業主
B 経営担当者
C 事業主のために行為をするすべての者
(労基法第10条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(労基法)労基法の適用単位
R3-156
R3.1.26 労基法は場所単位で適用される
今日は労基法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-D>
1つの企業が2つの工場をもっており、いずれの工場も、使用している労働者は10人未満であるが、2つの工場を合わせて1つの企業としてみたときは10人以上となる場合、2つの工場がそれぞれ独立した事業場と考えられる場合でも、使用者は就業規則の作成義務を負う。

【解答】 ×
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成する義務があります。
「10人」は、企業単位で数えるのか、それとも事業場単位で数えるのか?というのがこの問題のテーマです。
労働基準法は、事業単位(「場所的観念」)で適用されます。
ですので、この問題の場合、工場単位で数えます。どちらも10人未満ですので、就業規則の作成義務はありません。
(労基法第89条)
★労働基準法は、企業単位ではなく、原則として場所的観念で適用されることを思い出してください。
では、こちらの問題もどうぞ!
<H26年出題>
労働基準法第9条にいう「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものであって、場所的観念によって決定されるべきものではない。

【解答】 ×
「事業」とは、経営上一体をなす支店、工場等を総合した全事業を指称するものではない。主として場所的観念によって決定すべきもの、とされています。
問題文の記述は逆になっています。
穴埋め式で条文check!
第9条 労働者の定義
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(「事業」という。)に使用される者で、< A >者をいう。

【解答】
A 賃金を支払われる
(労基法第9条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(労基)割増賃金の支払義務
R3-153
R3.1.23 違法な時間外労働に対する割増賃金
今日は労働基準法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問6-D>
労働基準法第37条は、「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合」における割増賃金の支払について定めているが、労働基準法第33条又は第36条所定の条件を充足していない違法な時間外労働ないしは休日労働に対しても、使用者は同法第37条第1項により割増賃金の支払義務があり、その義務を履行しないときは同法第119条第1号の罰則の適用を免れないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】 〇
<読み方>
・時間外労働、休日労働については、第33条、第36条の条件を満たすことが必要
↓
・第37条では、条件を満たした適法な時間外労働や休日労働について、割増賃金の支払を義務付けている
↓
・では、第33条、第36条の条件を満たしていない違法な時間外労働や休日労働の場合は、割増賃金は支払わなくてもいいのか?
↓
・一層強い理由でその支払義務があるものと解すべき
(参照:労働基準法第37条 昭35.7.14最高裁一小 小島撚糸事件)
では、こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。

【解答】 〇
令和2年度の問題と同じです。
穴埋めで条文もチェック!
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条
① 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、< B >のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< C >届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、< D >ことができる。
③ < E >のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

【解答】
A 許可
B 事態急迫
C 事後に遅滞なく
D 命ずる
E 公務
社労士受験のあれこれ
解説動画です。
(労基)就業規則の作成義務
R3-152
R3.1.22 就業規則~常時10人の数え方
今日は労働基準法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問7-C>
派遣元の使用者は、派遣中の労働者だけでは常時10人以上にならず、それ以外の労働者を合わせてはじめて常時10人以上になるときは、労働基準法第89条による就業規則の作成義務を負わない。

【解答】 ×
就業規則の作成・届出義務があるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です。
派遣元の使用者の場合、「派遣労働者とそれ以外の労働者を合わせて常時10人以上」になると、派遣労働者にも適用される就業規則を作成する義務があります。
参照:労働基準法第89条
基発第0331010号 平成21.3.31(派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について)
では、こちらの問題もどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
 <H26年出題>
<H26年出題>
労働基準法第89条に定める就業規則の作成義務等の要件である「常時10人以上の労働者を使用する」とは、10人以上の労働者を雇用する期間が1年のうち一定期間あるという意味であり、通常は8人であっても、繁忙期においてさらに2、3人雇い入れるという場合も、これに含まれる。

【解答】
 <R1年出題> ×
<R1年出題> ×
労働基準法第89条では、単に常時10人以上の「労働者」と規定されているだけです。ですので、短時間労働者かそうでないかには関係なく1人でカウントします。
(労働基準法第89条)
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
「常時10人以上」とは、たまに10人未満になることがあったとしても、通常、10人以上いる状態だと考えてください。
問題文は、通常8人、たまに10人以上になるということなので、労働基準法第89条でいう「常時10人以上」には当たりません。
(労働基準法第89条)
穴埋めで条文もチェック!
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、< A >並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
② 賃金(臨時の賃金等を除く。)決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに< B >に関する事項
③ 退職に関する事項(< C >を含む。)
④ 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑤ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
⑥ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
⑦ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑧ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
⑩ 表彰及び< D >の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
⑪ その他、当該事業場の< E >に適用される定めをする場合においては、これに関する事項

【解答】
A 休暇
B 昇給
C 解雇の事由
D 制裁
E 労働者のすべて
社労士受験のあれこれ
解説動画を作ってみました。よかったらどうぞ。
労基法「天災事変その他やむを得ない事由」とは?
R3-093
R2.11.24 「天災事変その他やむを得ない事由」に含まれる?
令和2年の問題をどうぞ!
<問5-エ>
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。

【解答】 ×
「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度の不可抗力そして突発的な事由。経営者として如何ともなし難い状況。
「事業場が火災により焼失した場合」は、通常は「やむを得ない」事由となりますが、「事業主の故意又は重大な過失」による場合は除かれます。
問題文は、「使用者の重過失による火災」なので、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には含まれません。
ちなみに、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は第19条(解雇制限)の条文にも登場しますが、同じ解釈です。
では、関連問題をどうぞ!
<H23年出題>
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。

【解答】〇
行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要です。使用者の勝手な判断による濫用を防止するためです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(労基)
R3-083
R2.11.14 <R2出題>覚える「危険有害業務の就業制限」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問3-A>
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。

【解答】 〇
★女性を「妊婦」「産婦」「その他の女性」の3つにグループ分けしています。
妊産婦については、母性保護のため、その妊娠・出産・哺育等に有害な業務に就かせてはならないとされています。
また、妊産婦以外のその他の女性も妊娠、出産機能に有害な業務の就業が制限されています。
★ 妊産婦等の就業制限の業務として24業務が規定されています。
妊婦 → 24のすべての業務に「就かせてはならない」
産婦 → 「就かせてはならない」業務が3、「申し出た場合就かせてはならない」業務が19、「就かせても差し支えない」業務が2
その他の女性 → 「重量物を取り扱う業務」、「有害物を発散する場所における業務」の2つについては「就かせてはならない」、それ以外の22の業務は「就かせても差し支えない」
★すべての女性の就業が禁止される「重量物を取り扱う業務」、「有害物を発散する場所における業務」の2つは覚えておきましょう。
では、こちらも
<問3-B>
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

【解答】 ×
「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」は、「妊婦」と「産婦」は就かせてはならない業務ですが、その他の女性は「就かせても差し支えない業務です。
では、選択練習問題をどうぞ!
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3
① 使用者は、< A >を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

【解答】
A 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(労基)
R3-072
R2.11.3 <R2出題>問題の意図「減給制裁」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問7-E>
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。

【解答】 ×
「ノーワークノーペイの法則」
例えば1時間遅刻した分として1時間分の賃金を控除することは減給制裁になりません。
しかし、1時間の遅刻に対して、例えば3時間分の賃金を控除してしまうと、働いた2時間分まで引かれてしまうことになり、そこは労基法第91条の制限を受けます。
この問題の意図は、「ノーワークノーペイ」(労働していない分は賃金は発生しない)と「減給制裁」(ペナルティとして労働した時間分まで控除してしまう)の違いです。
減給制裁の条文をどうぞ
第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の< A >を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の< B >を超えてはならない。

【解答】
A 半額
B 10分の1
<減給制限>
・1回の額 → 平均賃金の1日分の半額を超えてはならない
・総額 → 一賃金支払期の賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
※減給については労基法で制限がかかっています。ペナルティだとしても、賃金の大部分を減給されてしまうと、労働者の生活が成り立たないからです。
では、こちらの問題をどうぞ!
<H28年出題>
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。

【解答】 ×
出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、「制裁としての出勤停止」の当然の結果なので、91条違反にはなりません。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(労基)
R3-063
R2.10.25 R2出題・【選択練習】中間搾取の排除
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄< A >を埋めてください。
労働基準法第6条に定める「< A >も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
(参考:問4C)

【解答】 A 何人
労働基準法第6条(公民権行使の保障)の主体は「何人も」です。個人、団体、公人、私人たるとを問いません。
関連問題をどうぞ!
<H28出題>
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。

【解答】 ×
他人の就業に介入して利益を得る(中間搾取)行為は、団体・個人、公人・私人関係なく禁止されています。もちろん公務員であってもこのような行為は禁止されています。
最後にもう一問どうぞ
<H23年出題>
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

【解答】 ×
第6条は「法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」となっていますので、「法律によって許される場合」もあります。問題文は、「他の法律の定め如何にかかわらず」の部分が誤りです。
なお、法律に基づいて許される場合とは、職業安定法などの規定による場合です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(労基)
R3-053
R2.10.15 R2出題・年次有給休暇の時季指定義務
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
<R2問6より>
使用者は、労働基準法第39条第7項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。

【解答】 〇
労働基準法施行規則第24条の6からの出題です。
イメージはこのような感じです。
使用者 : 「年次有給休暇ですが、いつ取りたいですか?」(取得時季について当該労働者の意見を聴かなければならない)
労働者 : 「10月23日に取得したいです。」
使用者 : 「それでは、10月23日に休んでください。」(聴取した意見を尊重するよう努めなければならない)
 労働基準法第39条第7項では、年5日の有給休暇の付与が使用者に義務付けられています。
労働基準法第39条第7項では、年5日の有給休暇の付与が使用者に義務付けられています。
労働基準法第39条第7項を穴埋め式で確認しましょう。
【問題です】
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が< A >労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち< B >日については、< C >(継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間の初日をいう。)から< D >年以内の期間に、労働者ごとにその< E >を定めることにより与えなければならない。

【解答】
A 10
B 5
C 基準日
D 1
E 時季
なお、「労働者自身の時季指定」又は「計画的付与」によって有給休暇を与えた場合は、その日数分、使用者の時季指定義務の5日から控除することができます。
例えば、労働者が自ら時季指定して2日間有給休暇を取得した場合は、使用者が時季指定しなければならない日数は3日間となります。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(労基)
R3-043
R2.10.5 R2出題・難問解決策「食事の供与は賃金になる?」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2・問4より>
食事の供与(労働者が使用者の定める施設に住み込み1日に2食以上支給を受けるような特殊の場合のものを除く。)は、食事の支給のための代金を徴収すると否とを問わず、①食事の供与のために賃金の減額を伴わないこと、②食事の供与が就業規則、労働協約等に定められ、明確な労働条件の内容となっている場合でないこと、③食事の供与による利益の客観的評価額が、社会通念上、僅少なものとして認められるものであること、の3つの条件を満たす限り、原則として、これを賃金として取り扱わず、福利厚生として取り扱う。

【解答】 〇
令和2年労基法問4の問題です。
問4は「誤っているもの」を解く問題ですが、「公民権行使の保障」の肢が明らかに間違っていたので、問4そのものは解きやすい問題でした。
今回取り上げた問題は、一字一句覚える必要はありません。参考程度にとどめてください。
おさえておきたいポイントは「食事の供与」が「賃金」なのか、それとも「福利厚生」なのかという論点です。
「食事の供与」が「福利厚生」として取り扱われるポイントが3つあるというのが問題文から分かります。「賃金」=「労働の対償」であることが大前提。この3つに当てはまったら労働の対償とは言えないということです。
ちなみに、行政通達によると、現物給与について「賃金」となるか否かについて、「労働者から代金を徴収するものは原則として賃金ではない」となっていますが、「その徴収金額が実際費用の3分の1以下であるときは、徴収金額と実際費用の3分の1との差額部分」については賃金とみなされることになっています。
参考程度に。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~労働基準法
R3-033
R2.9.25 R2出題・労使協定届出いる?いらない?
労働基準法には、11の労使協定が規定されています。
大きく分けると、所轄労働基準監督署長に届出がいる労使協定、届出しなくていい労使協定の2つのパターンがあります。
令和2年度の問題で確認しましょう!
フレックスタイム制の労使協定
<R2年問6B>
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

【解答】 ×
フレックスタイム制の労使協定は
清算期間が
・1か月を超える場合 → 届け出がいる
・1か月以内の場合 → 届け出はいらない
問題文の「清算期間の長さにかかわらず」の部分が誤りです。
では、同じパターンの問題をどうぞ!
<R1出題>
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。

【解答】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制の労使協定は、
労使協定で定める時間が
・法定労働時間を超える → 労使協定の届出がいる
・法定労働時間以下 → 労使協定の届出はいらない
 労働基準法上の労使協定について、届出がいる・いらないは、おさえておきましょう。
労働基準法上の労使協定について、届出がいる・いらないは、おさえておきましょう。
 こちらもどうぞ「労使協定の効果って?」
こちらもどうぞ「労使協定の効果って?」
労働基準法上の労使協定の効力は、
その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつもの
(例えば、「36協定」を締結して、所轄労働基準監督署長に届け出をすれば、時間外労働、休日労働させても、労働基準法には違反しないという免罰効果が生まれる)
↓
しかし、労使協定からは、「労働者の民事上の義務」は、直接生じない。
↓
「労働者の民事上の義務」は労働協約、就業規則等の根拠が必要
(例えば、なぜ労働者には「時間外労働をしなければならない義務」があるのか?この義務は36協定から生まれているのではなく、就業規則などに「残業義務」についてルールがあるから。)
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(労基法)
R3-023
R2.9.15 過去の論点は繰り返す(R2労基・法令等の周知義務)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
労働基準法第106条 法令等の周知義務
問題<H16年出題>
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。

【解答】 ×
労働基準法及びこれに基づく命令 → 要旨を周知すれば足りる
就業規則 → 全文の周知が必要(要旨だけではダメ)
 条文を確認しましょう。
条文を確認しましょう。
第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項(貯蓄金の管理)、第24条第1項ただし書(賃金の一部控除)、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の3第1項(フレックスタイム制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)、第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(一斉休憩の適用除外)、第36条第1項(三六協定)、第37条第3項(代替休暇)、第38条の2第2項(事業場外労働のみなし労働時間制)、第38条の3第1項(専門業務型裁量労働制)並びに第39条第4項(時間単位年休)、第6項(有給休暇の計画的付与)及び第9項ただし書(有給休暇の賃金)に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(企画業務型裁量労働制)(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項(高度プロフェッショナル制度)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
なお、就業規則だけでなく、労使協定、労使委員会の決議も全文を周知する必要があります。
労使協定、労使委員会の決議で周知が義務付けられるのは、「労働基準法に規定する」労使協定、労使委員会の決議です。
では、令和2年度の問題から2問どうぞ!
 <R2年問2Aより>
<R2年問2Aより>
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
 <R2年問2Bより>
<R2年問2Bより>
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に規定する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

【解答】
 <R2年問2Aより> ×
<R2年問2Aより> ×
就業規則は、全文の周知が必要
 <R2年問2Bより> ×
<R2年問2Bより> ×
周知義務は、対象労働者に対してのみではなく、すべてが対象。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(労働基準法)
R3-013
R2.9.5 第52回試験・択一労働基準法の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 労基法 択一式
一肢ずつ見ると、「あまり見たことない・・・?」ような肢があって、それが答えになっている問題が多いように感じました。
でも、基本的な肢をつかって消去法で解いていくと、正解にたどりつく出題でした。
例えば、問1で考えると、
A 事業主の定義
株式会社の場合、事業主は「法人そのもの」のことで代表取締役ではない
B 使用者の定義
使用者に当たるか否かは、役職名ではなく、与えられた責任と権限の有無によるので、係長が使用者になることもあり得る
C 使用者の定義
Bと同様。役職が課長でも、権限外の事項を単に伝達しただけでは、使用者とはみなされない
E 労働者派遣の使用者
指揮命令関係にある派遣先も、労働基準法の使用者として責任を問われる部分がある。
消去法で、解答は「D」となります。
全体的に 労働基準法でかなりの部分を占める「労働時間」に関する問題が1問しかなかった。。。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(労基)
R3-004
R2.8.27 第52回試験・選択労基
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 労基選択式
1 第96条の2の寄宿舎についての「監督上の行政措置」からの出題でした。
ちょっと意外な個所からの出題です。
「計画」なので、前もって届け出が必要、と考えると、2つまでは絞れます。「14日前まで」と自信をもって選べたかどうかでしょうか?
なお、平成21年に同じ論点の問題が択一式で出題されています。「工事着手30日前までに届け出」で「誤」の問題でした。
ポイント! 択一式の論点は、数年後に選択式で出題されることが多い
2 労基法上の「労働者性」についての最高裁判例からの出題です。
労働基準法第9条で「労働者」の定義が規定されています。
しかし、現実は、働き方が多様化していて、「労働者」に当たるか否か、判断に迷う事例が多々あります。
ですので、古典的ではあるものの、非常に今日的な論点の問題だと思いました。
でも、「C」の選択肢は難しいです。
明日は安衛法です。
社労士受験のあれこれ
目的条文check 1 労働編
1 労働編
R2-260
R2.8.17 労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック
目的条文は要チェック!
本日は、「労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「労働基準法」
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、< D >において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< E >各々その義務を履行しなければならない。

【解答】
A 人たるに値する生活
B 基準
C 向上
D 対等の立場
E 誠実に
問2 「労働安全衛生法」
(目的)
第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< A >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。

【解答】
A 自主的活動
B 安全と健康
C 快適な職場環境
問3 「労災保険法」
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< A >に寄与することを目的とする。
第2条 労働者災害補償保険は、< B >が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、 < C >を行うことができる。
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び< D >(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

【解答】
A 福祉の増進
B 政府
C 社会復帰促進等事業
D 官公署の事業
問4 「雇用保険法」
 R2年4月1日改正 要チェックです!
R2年4月1日改正 要チェックです!
(目的)
第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。
(管掌)
第2条 雇用保険は、< C >が管掌する。
2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、< D >が行うこととすることができる。
(雇用保険事業)
第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< E >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

【解答】
A 子を養育するための休業
B 福祉の増進
C 政府
D 都道府県知事
E 育児休業給付
社労士受験のあれこれ
横断編(労基・労災・雇用の「船員」)
R2-243
R2.7.31 横断編/労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?」です。
では、どうぞ!
問 題
 <労働基準法>
<労働基準法>
船員法第1条第1項に規定する船員については、労働基準法は、全面的に適用されない。
 <労災保険法>
<労災保険法>
船員法上の船員については、労災保険法が適用される。
 <雇用保険法>
<雇用保険法>
船員法第1条に規定する船員を雇用する(政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては、雇用保険の強制適用事業となる。

【解答】
 <労働基準法> ×
<労働基準法> ×
船員法第1条第1項に規定する船員には、労働基準法が一部適用されます。
労働者全般に当てはまる基本原則の部分(第1条から第11条まで)、それに関する罰則規定は船員にも適用されますが、これ以外は労働基準法は適用されません。
船員の労働形態は特殊ですので、一般労働者向けの労働基準法は一部だけ適用され、他は船員法によって保護されます。
 <労災保険法> 〇
<労災保険法> 〇
船員法上の船員は、労災保険法適用です。
 <雇用保険法> 〇
<雇用保険法> 〇
船員法第1条に規定する船員を雇用する事業は、雇用保険の強制適用事業です。
ただし、
・政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員 → 適用除外
※漁船に乗り組むため雇用される者でも、1年を通じて船員として雇用される場合は適用されます。
こちらもどうぞ!
①<雇用保険法・H22年出題>
船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。
②<雇用保険法・H25年出題>
船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

【解答】
①<雇用保険法・H22年出題> ×
労働者を1人でも雇用すれば、雇用保険は適用です。
ですので、船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、人数関係なく強制適用となります。
②<雇用保険法・H25年出題> 〇
漁船に乗り組むため雇用される者であっても、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。
社労士受験のあれこれ
横断編(労基と安衛)
R2-242
R2.7.30 横断編/労基法は「使用者」、安衛は?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「労基法は「使用者」、安衛は?」です。
では、どうぞ!
問 題
<労働基準法>
労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の < A >に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
<労働安全衛生法>
労働安全衛生法において、< B >とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
【選択肢】
① 労務 ② 人事 ③ 労働者
④ 事業主 ⑤ 事業者 ⑥ 事業所

【解答】
A ③ 労働者
B ⑤ 事業者
★労働基準法の責任主体は使用者。使用者は次の3つに分けられます。
・事業主(その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの)
・事業の経営担当者
・労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
★労働安全衛生法では、使用者という用語は使っていません。労働安全衛生法の義務主体は、規定の多くが「事業者」。
・事業者とは、その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの
→ 労働基準法では、例えば、係長に労務管理についての権限があれば、その権限の範囲で係長は労働基準法の使用者(責任主体)となります。(使用者の概念が幅広い)
一方、労働安全衛生法は、「事業者(その事業の経営の主体)」と明確です。
こちらもどうぞ!
<労基法・H16年出題>
ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。

【解答】 ×
労働基準法の違反行為をした者(この問題では法人の代表者、違反行為をした本人)には、もちろん、罰則が科されます。
また、両罰規定により、事業主(法人そのもの)に対しても罰金刑が科されます。(法人は人間ではないので懲役刑はありません。)
安衛法から一問どうぞ!
【労働安全衛生法・事業者の責務】
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と< C >を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
【選択肢】
① 労働者の地位の向上 ② 作業環境の改善 ③ 労働条件の改善

【解答】
C ③ 労働条件の改善
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-232
R2.7.20 選択式の練習/労基法の時効
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労基法の時効」です。
令和2年4月の改正点の確認です。
では、どうぞ!
問 題
法第115条
この法律の規定による< A >の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
↓ アンダーライン部分は附則で以下のように読み替えます。
法附則第143条
この法律の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による< A >(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権 (< A >の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
【選択肢】
① 年次有給休暇 ② 労働条件通知書 ③ 賃金

【解答】
A ③ 賃金
労基法の時効
・賃金(退職手当除く。) → 5年間(当分の間3年間) 改正点です。
改正点です。
 令和2年4月の民法改正に合わせ、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間は5年間に延長されました。ただし、経過措置で当分の間は3年とされています。
令和2年4月の民法改正に合わせ、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間は5年間に延長されました。ただし、経過措置で当分の間は3年とされています。
 「賃金(退職手当除く。)」の内容は?
「賃金(退職手当除く。)」の内容は?
金品の返還(23条。賃金の請求に限る。)、賃金の支払 (24条)、非常時払(25条)、休業手当(26条)、出来高払制の保障給(27条)、時間外・休日労働に対する 割増賃金(37条1項)、有給休暇期間中の賃金(39条 9項)、未成年者の賃金請求権(59条)
・退職手当 → 5年間(変更なし)
・災害補償 → 2年間(変更なし)
・その他 → 2年間(変更なし)
 「その他」の内容は?
「その他」の内容は?
帰郷旅費(15条3項、64条)、退職時の証明(22条)、 金品の返還(23条。賃金を除く。)、年次有給休暇請求権 (39条)
こちらもどうぞ!
賃金等請求権の消滅時効の起算点は、現行の労働基準法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点である< B >を維持し、これを労働基準法上明記すること。
【選択肢】
① 雇い入れの日 ② 賃金支払日 ③ 退職の日

【解答】
B ② 賃金支払日
賃金消滅時効の起算点は、「賃金支払日」です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-222
R2.7.10 選択式の練習/高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲」です。
高度プロフェッショナル制度の導入の流れ
 労使委員会を設置
労使委員会を設置
 労使委員会で決議
労使委員会で決議
 労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出
労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出
 対象労働者の同意を得る(書面で)
対象労働者の同意を得る(書面で)
 対象労働者を対象業務に就かせる
対象労働者を対象業務に就かせる
POINT! 定期報告
 決議の有効期間満了
決議の有効期間満了
 の労使委員会で決議すべき事項は、「対象業務」、「対象労働者の範囲」などですが、今日は、「対象労働者」がテーマです。
の労使委員会で決議すべき事項は、「対象業務」、「対象労働者の範囲」などですが、今日は、「対象労働者」がテーマです。
ではどうぞ!
問 題
高度プロフェッショナル制度の対象労働者
次のいずれにも該当する労働者
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による< A >に基づき< B >が明確に定められていること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の< C >の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
【選択肢】
① 同意 ② 契約 ③ 合意
④ 職務 ⑤ 裁量 ⑥ 役割
⑦ 2倍 ⑧ 3倍 ⑨ 5倍

【解答】
A ③ 合意
B ④ 職務
C ⑧ 3倍
ロの要件をもう少し詳しく見てみましょう
基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額は、< D >円以上であること。
【選択肢】
① 850万 ② 1075万 ③ 1275万

【解答】
D ② 1075万
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-212
R2.6.30 選択式の練習/解雇予告制度が除外される労働者は?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「解雇予告制度が除外される労働者は?」です。
労働者を解雇しようとする場合は、原則として、解雇予告が必要です。
・ 少くとも30日前にその予告をする
・ 30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う
※ 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することも可能
しかし、予告制度が除外される場合もありますので、確認しましょう。
ではどうぞ!
問 題
解雇の予告の規定は、次の労働者については適用しない。
 日日雇い入れられる者
日日雇い入れられる者
 2か月以内の期間を定めて使用される者
2か月以内の期間を定めて使用される者
 < A >以内の期間を定めて使用される者
< A >以内の期間を定めて使用される者
 試の使用期間中の者
試の使用期間中の者
ただし、 に該当する者が< B >を超えて引き続き使用されるに至った場合、
に該当する者が< B >を超えて引き続き使用されるに至った場合、 若しくは
若しくは に該当する者が< C >を超えて引き続き使用されるに至った場合又は
に該当する者が< C >を超えて引き続き使用されるに至った場合又は に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇の予告の規定が適用される。
に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇の予告の規定が適用される。
【選択肢】
① 30日 ② 季節的業務に4か月 ③ 季節的業務に6か月
④ 1か月 ⑤ 31日 ⑥ 2週間 ⑦ 所定の期間
⑧ 4か月 ⑨ 6か月

【解答】
A ② 季節的業務に4か月
B ④ 1か月
C ⑦ 所定の期間
こちらもどうぞ!
①<H15年出題>
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
②<H23年出題>
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。

【解答】
①<H15年出題> ×
2か月の期間を定めて雇い入れた労働者には、解雇予告の規定は適用されませんので、期間の途中で解雇する場合でも解雇の予告はいりません。
なお、2か月の期間で雇い入れられた労働者を、所定の期間(この問題の場合なら2か月)を超えて引き続き使用した場合には、解雇予告の規定が適用されます。
②<H23年出題> ×
「6か月の期間を定めて使用される者」には解雇予告の規定が適用されますので、期間の途中で解雇する場合には、予告が必要です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-202
R2.6.20 選択式の練習/労働基準法の適用を除外されるのは?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労基法・適用除外」です。
労働基準法は、労働者を一人でも使用する事業に適用されます。
今日のテーマは労働基準法第116条の「適用除外」です。
ではどうぞ!
問題
第116条(適用除外)
① 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、< A >については、適用しない。
② この法律は、< B >及び家事使用人については、適用しない。
【選択肢】
① 船員法第1条第1項に規定する船員 ② 一般職の国家公務員
③ 一般職の地方公務員 ④ 行政執行法人の職員
⑤ 同居の親族を使用する事業 ⑥ 同居の親族のみを使用する事業

【解答】
A ① 船員法第1条第1項に規定する船員
船員法の船員には、労働基準法の総則(第1条~第11条)、適用除外、罰則は適用されますが、それ以外は適用除外です。
B ⑥ 同居の親族のみを使用する事業
同居の親族のみを使用する事業は労基法は適用除外ですが、同居の親族+他人を使用している事業は、労基法は適用です。
こちらもどうぞ!
①H20年出題
労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
②H16年出題
船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働基準法の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。

【解答】
①H20年出題 〇
②H16年出題 ×
船員法の船員には、労働基準法の総則(第1条~第11条)は適用されます。
船員については、労基法は全面除外ではなく、適用される部分も一部あります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-192
R2.6.10 選択式の練習/就業規則と「就業規則に準ずるもの」
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「就業規則と「就業規則に準ずるもの」」です。
 フレックスタイム制について、労基法第32条の3では、「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については・・・(以下略)」
フレックスタイム制について、労基法第32条の3では、「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については・・・(以下略)」
と定められています。
フレックスタイム制は労働者の自主的な時間管理が前提ですので、「始業と終業の時刻は労働者が決定する」ことを就業規則その他これに準ずるもので約束しておくことが必要です。
今日のテーマは、「就業規則その他これに準ずるもの」の意味です。
ではどうぞ!
問題
常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、< A >により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。
(平成30年択一式の問題を参考に作成)
【選択肢】
① 就業規則その他これに準ずるもの ② 就業規則
③ 就業規則に準ずるもの

【解答】
A ② 就業規則
フレックスタイム制については、「就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねること」とするのが要件です。
10人以上の場合は就業規則の作成義務がありますので、「就業規則に準ずるもの」は使えません。問題文は10人以上の事業場ですので、「就業規則」によることが必要です。
こちらもどうぞ!
労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定すべきものである。

【解答】 〇
コアタイムやフレキシブルタイムは、設ける・設けないは任意ですが、そのような時間帯を設けるときには就業規則に規定する必要があります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-182
R2.5.31 選択式の練習/災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働」です。
時間外労働・休日労働をさせることができるのは、
・ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合
・ 公務のために臨時の必要がある場合
・ 36協定を締結し行政官庁に届け出た場合
です。
ではどうぞ!
問題
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その< A >において第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、< B >のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
【選択肢】
① 許可の範囲 ② 労使協定の範囲 ③ 必要の限度
④ 事態急迫 ⑤ 非常事態 ⑥ 緊急事態

【解答】
A ③ 必要の限度
B ④ 事態急迫
 事後に遅滞なく届出があった場合 → 行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
事後に遅滞なく届出があった場合 → 行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
こちらもどうぞ!
<H22年出題>
労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度におい行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。

【解答】 〇
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-172
R2.5.21 選択式の練習/時間外、休日、深夜の割増賃金の率
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「時間外、休日、深夜の割増賃金の率」です。
ではどうぞ!
問 題
使用者が、法33条又は36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、
< A >又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ< B >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について< C >時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、< A >の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、 < A >の賃金の計算額の< D >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【選択肢】
① 通常の労働時間 ② 法定労働時間 ③ 平均的な労働時間
④ 厚生労働省令で定める率 ⑤ 就業規則その他これに準ずるもので定める率
⑥ 政令で定める率 ⑦ 45 ⑧ 60 ⑨ 80
⑩ 3割5分 ⑪ 2割5分 ⑫ 5割

【解答】
A ① 通常の労働時間
B⑥ 政令で定める率
C ⑧ 60
D ⑪ 2割5分
ポイント!
Bの「政令で定める率」について
→ 時間外及び休日の割増率は「政令」で具体的に定められています。
「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で
・時間外労働については2割5分
・休日労働については3割5分
と定められています。
 ちなみに
ちなみに
政令は「内閣」が、省令は「大臣」が制定します。
こちらの問題もどうぞ
<H29年出題>
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】 ×
休日は原則として暦日で考えます。休日には法定労働時間の概念がないので、8時間を超えたとしても休日割増の3割5分以上のみで計算します。
しかし、休日労働が深夜の時間帯になったときは、3割5分(休日割増)+2割5分(深夜割増)=6割以上で計算します。
体に負担のかかる深夜の時間帯の労働については、別枠で割増をプラスするという考え方です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-162
R2.5.11 選択式の練習/高プロ・健康福祉確保措置等
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、高度プロフェッショナル制度の健康福祉確保措置等です。
→ 高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されません。
頑張りすぎて健康を害することのないようするため、高プロを運用する過程で、健康・福祉確保措置等を講ずる必要があります。
ではどうぞ!
問 題
 健康管理時間の把握
健康管理時間の把握
対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間(=休憩時間その他対象労働者が労働していない時間)を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法※に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
※厚生労働省令で定める方法
タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、< A >によることができる。
【選択肢】
① 勤務間インターバル ② 自己申告 ③ 上司の確認

【解答】 A ② 自己申告
ポイント
対象労働者の健康管理時間を把握することと把握方法
 休日の確保
休日の確保
対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ< B >日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
【選択肢】
① 103 ② 104 ③ 105

【解答】 B ② 104
ポイント
対象労働者には、年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与える
 選択的措置
選択的措置
対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに< C >時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜の時刻の間において労働させる回数を1箇月について < D >以内とすること。
ロ 健康管理時間を1箇月又は3箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
※ 厚生労働省令で定める時間
1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、
・ 1箇月 100時間
・ 3箇月 240時間
ハ 1年に1回以上の継続した2週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。
ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。
【選択肢】
① 10 ② 11 ③ 12 ④13
⑤ 3回 ⑥ 4回 ⑦ 5回 ⑧ 6回

【解答】 C ② 11 D ⑥ 4回
ポイント
イ~ニのいずれかを決議で定めて実施する
イ → 勤務間インターバルの確保(11時間以上)、深夜業の回数の制限
ロ → 健康管理時間の上限
ハ → 1年間に継続2週間以上の休日を与える(本人が請求した場合は連続1週間を2回以上)
二 → 臨時の健康診断
 健康管理時間の状況に応じた健康・確保措置
健康管理時間の状況に応じた健康・確保措置
対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
※ 厚生労働省令で定める措置
①  に掲げるいずれかの措置(
に掲げるいずれかの措置( で使用者が講ずることとした措置以外のもの)
で使用者が講ずることとした措置以外のもの)
② 健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導を行う
③ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与する
④ 対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する
⑤ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をする
⑥ 産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせる
※①~⑥の措置の中から決議で定め、実施する必要があります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-152
R2.5.1 選択式の練習/高度プロフェッショナル制度の対象労働者
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「高度プロフェッショナル制度」です。
問 題
〔高度プロフェッショナル制度の対象労働者〕
 と
と のいずれにも該当すること
のいずれにも該当すること
 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき < A >が明確に定められていること。
使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき < A >が明確に定められていること。
 厚生労働省令で定める方法 → 次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
厚生労働省令で定める方法 → 次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
①業務の内容
②責任の程度
③< A >において求められる< B >その他の< A >を遂行するに当たって求められる水準
 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が< C >の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が< C >の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
 厚生労働省令で定める額 → < D >万円
厚生労働省令で定める額 → < D >万円
【選択肢】
①職務 ②職務遂行能力 ③結果 ④成果 ⑤能力 ⑥職制 ⑦評価 ⑧基準 ⑨平均給与額 ⑩基準年間平均賃金 ⑪基準給与 ⑫基準年間平均給与額 ⑬1,080 ⑭1,075 ⑮1,095 ⑯885

【解答】
A①職務 B ④成果 C ⑫基準年間平均給与額
D ⑭1,075
基準年間平均給与額=厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額のこと
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労基法)
R2-142
R2.4.21 労働基準法/選択式の練習
今日から、選択式の練習問題に入ります。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、どうぞ。
問題1
労働基準法第4条は、< A >について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、< A >以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
【選択肢】
①雇入れ ②定年 ③賃金 ④ 退職理由
問題2
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、< B >及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは含まれない。
【選択肢】
①通勤手当 ②家族手当 ③臨時に支払われた賃金 ④割増賃金
問題3
労基法24条1項本文は、いわゆる賃金全額払いの原則を定めており、賃金の控除を禁止しているが、右原則の趣旨とするところは、使用者により賃金が一方的に控除されることを禁止し、もって労働者に賃金の全額を受領させ、労働者の < C >をはかろうとするものであるから、その趣旨に鑑みると、使用者が労働者の同意を得て相殺により賃金を控除することは、それが< D >に基づくものである限り、右賃金全額払いの原則によって禁止されるものではないと解するのが相当である。
【選択肢】
①生活保障 ②経済生活の安定 ③雇用の安定 ④経済の発展
⑤労働者の完全な自由意思 ⑥労働協約 ⑦就業規則 ⑧労使協定

【解答】
A ③賃金
B ③臨時に支払われた賃金
C ②経済生活の安定
D ⑤労働者の完全な自由意思
問題3は「日新製鋼事件」より。
 択一式もどうぞ!
択一式もどうぞ!
①<H25年出題>
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
②<H27年出題>
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
③<H30年出題>
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
① ○
② ×
通勤手当及び家族手当は、平均賃金の計算の際の賃金総額に含まれます。
③ ○
日新製鋼事件です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-132
R2.4.10 割増賃金/1時間当たりの賃金額の出し方
「第52回(令和2年度)の社会保険労務士試験の詳細が公示されました。 試験日は、令和2年8月23日(日)です。
|
今日は、割増賃金/1時間当たりの賃金額の出し方です。
時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の2割5分以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
通常の労働時間1時間当たりの賃金はどのように計算するのでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働時間数:240日
計算の対象となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間
A 300,000円÷(21×7)
B 300,000円÷(21×8)
C 300,000円÷(30÷7×40)
D 300,000円÷(240×7÷12)
E 300,000円÷(365÷7×40÷12)

【解答】 D
労基法施行規則第19条の通常の労働時間1時間当たりの賃金額の計算式
 月によって定められた賃金の場合
月によって定められた賃金の場合
月給 ÷ 月の所定労働時間数
※月によって所定労働時間数が異なる場合は
月給 ÷ 1年間の一月平均所定労働時間数
問題文の場合、対象月の所定労働日数が21日、年間所定労働日数が240日なので、月によって所定労働時間数は異なります。ですので、月給÷1年間の一月平均所定労働時間数で計算します。
240日×7時間(拘束時間8時間-休憩1時間=1日の所定労働時間7時間)が年間の所定労働時間の合計です。それを12か月で割ると、1年間の一月平均所定労働時間数となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-122
R2.3.25 労働基準法第1条の趣旨は?
労働基準法第1条では、
① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
と規定されています。
労働基準法の最初に出てくる条文ですが、この条の趣旨は?
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】 ○
第1条第1項は、労働憲章的規定です。労働条件は、人間らしく生活するための必要を満たすべきものであること。
こちらもどうぞ。
<H18年出題>
労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。

【解答】 ○
第1条第2項に規定されています。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H19年出題>
労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

【解答】 が人たるに値する生活を営む
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-112
R2.3.11 年次有給休暇の残余の数え方
 年次有給休暇を時間単位で取得すると、有休の残余が「○日と○時間」となります。
年次有給休暇を時間単位で取得すると、有休の残余が「○日と○時間」となります。
年の途中で、所定労働時間が変わった場合、有休の残余の数え方はどうなるのでしょう?
 (H28年出題)
(H28年出題)
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。

【解答】 ○
日単位に満たない時間単位の部分は、所定労働時間の変更に比例して時間数が変わります。
変更前の1日の所定労働時間は8時間ですので、残余の10日と5時間の「5時間」の部分は所定労働時間の「8分の5」残っていると考えてください。
変更後の1日は所定労働時間は4時間です。時間単位の部分は「所定労働時間の4時間×8分の5=2.5」。1時間未満を切上げて「3時間」となります。ですので、残余は10日と3時間となります。
なお、1日当たりの時間数は、変更前は8時間ですが、変更後は4時間となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-102
R2.2.24 出来高払制の保障給
 今日は、出来高払制の保障給のルールを確認しましょう。
今日は、出来高払制の保障給のルールを確認しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

【解答】 ○
労基法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定されていて、「労働時間」に応じた一定額のものであることが必要です。
出来高払制その他の請負制の場合、出来高がゼロだったら賃金もゼロというのは許されず、労働者が働いた以上は、労働時間に応じた一定額の保障をしなければなりません。
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H13年出題>
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

【解答】 ×
出来高払制その他の請負制で労働した場合は、「労働時間」に応じた一定額の保障が必要ですが、問題文のように「休業する」(=労働していない)場合は、第27条の保障給は不要です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-92
R2.2.5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
★ 今日は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」です。この制度は、対象の事業・規模が限定されているのがポイントです。
 H28年出題
H28年出題
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。

【解答】 ×
一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、
「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつこれを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(=小売業、旅館、料理店、飲食店)」で常時使用する労働者数が「30人未満」であること。
事業の種類と規模、どちらにも該当していることが条件です。
 こちらもどうぞ。
こちらもどうぞ。
<H22年出題>
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

【解答】 ×
1日の労働時間の上限は10時間と定められています。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-82
R2.1.20 「通勤手当」と「家族手当」→含むor含まない?
「通勤手当」と「家族手当」
控除するのか、含めるのか、迷いませんか??
では、さっそく、次の問題を解いてみてください。
 H27年出題
H27年出題
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

【解答】 ×
「平均賃金」の問題です。
通勤手当及び家族手当は、控除の対象になっていません。平均賃金の計算に算入します。
 では、次の問題はどうでしょう?
では、次の問題はどうでしょう?
H26年出題
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】 ○
こちらは、「割増賃金」の問題です。
「労働とは直接関係のない個人的事情」の部分がポイントです。「通勤手当」は、個々人の通勤距離や通勤に要した費用によって決まるもので、労働の内容と全く関係ないからです。
ここもチェック!
なお、「通勤手当でも距離に関係なく支払われる部分がある場合は、その部分を算定基礎に算入する」という通達にも注意してください。
通勤に要した費用や距離に関係なく支給するものは、割増賃金の計算に算入しなければなりません。
 では、もう一問どうぞ
では、もう一問どうぞ
H23年出題
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】 ×
こちらも「割増賃金」の問題です。
扶養家族がいる労働者に対して、家族の人数に応じて支給されるものは、割増賃金の計算から除外します。扶養家族の人数などは個人的事情だからです。
しかし、家族数に関係なく一律に支給されているとなると、算定基礎賃金に含めなければなりません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-72
R2.1.2 時間外労働の端数処理(労働基準法)
あけましておめでとうございます!
今年も、「社会保険労務士合格研究室」どうぞよろしくお願いいたします。
さて、日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
今日から、過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H28 労基法(問3)より
H28 労基法(問3)より
1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】 ○
この問題のポイントは、冒頭の「1か月の」の部分です。
1か月の時間外労働等の時間数の「合計」についてなら、このような端数処理方法が許されますが、例えば、「1日」単位でこの端数処理をすると、第24条(全額払の原則)違反となってしまいます。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H19年出題】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】 ×
「1日における」、「1日ごとに」の部分で迷わず「×」にしてください。問題文は最後まで読まなくていいです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-62
R1.12.12 R1労基/休業手当の性質
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「休業手当の性質」についてです。
 R1労基(問5)より
R1労基(問5)より
労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

【解答】 ×
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき休業の場合は、休業手当の支払を使用者に義務付けています。
休業手当は「賃金」と解され、その支払いについては第24条が適用されます。
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H19年出題】
労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

【解答】 ○
ポイント!
休業手当は労働基準法第11条の「賃金」
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-52
R1.11.20 R1労基/労働契約締結時の労働条件の明示
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労基法「労働契約締結時の労働条件の明示」についてです。
 R1労基(問4)より
R1労基(問4)より
労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。

【解答】 ×
 「労働契約の期間」に関する事項は、労働契約を締結する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」で、書面の交付等による明示が必要です。
「労働契約の期間」に関する事項は、労働契約を締結する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」で、書面の交付等による明示が必要です。
期間の定めのある労働契約の場合は「その期間」を明示し、期間の定めをしない場合は「その旨」の明示が必要です。
 問題文の「期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい」の部分が誤りです。期間の定めがない場合は、「定めがない」と明示しなければならない。
問題文の「期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい」の部分が誤りです。期間の定めがない場合は、「定めがない」と明示しなければならない。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H25年出題>
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。

【解答】 ○
更新する場合がある有期雇用については、労働契約締結時に「更新の基準」を明示しなければならないのがポイントです。
更新の判断基準を明示することによって、労働者が自身の雇用の継続の可能性をある程度予見できるようになるからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-41
R1.10.30 R1労基/解雇予告期間
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労基「解雇予告期間」についてです。
 R1労基(問4)より
R1労基(問4)より
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。

【解答】 ×
予告期間は労働日ではなく「暦日」で計算されます。
 平成26年に具体的な日数計算の問題が出題されています。確認しましょう。
平成26年に具体的な日数計算の問題が出題されています。確認しましょう。
(H26年出題)
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

【解答】 ×
9月30日解雇しようとする場合は、8月31日までに予告しなければなりません。
予告した当日(8月31日)は予告期間の「30日」の計算には入りませんので注意しましょう。8月31日は、予告した時点で既に何時間か過ぎていて丸1日ないからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-31
R1.10.17 R1労基/1か月単位の変形労働時間制
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「1か月単位の変形労働時間制」についてです。
 R1労働基準法(問2)より
R1労働基準法(問2)より
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。

【解答】 ×
1か月単位の変形労働時間については、1日についても、1週間についても、労働時間の上限は設けられていません。
 1年単位の変形労働時間制については、1日、1週間の労働時間の上限が定められています。比較しましょう。平成30年に出題されています。
1年単位の変形労働時間制については、1日、1週間の労働時間の上限が定められています。比較しましょう。平成30年に出題されています。
<H30年出題>
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

【解答】 ×
1週間の労働時間の限度は54時間ではなく、52時間です。
1年単位の変形労働時間制の場合は、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間と、それぞれ上限が設定されているのがポイントです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-21
R1.9.30 R1労基法/解雇制限のルール
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「解雇制限」についてです。
 R1労基法(問4)より
R1労基法(問4)より
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】 ○
第19条の解雇制限は、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間に適用されます。「休業」する期間は解雇制限がかかりますが、産前休業を請求しないで「就労」している場合は、解雇制限はかかりません。
※産前休業は労働者からの請求が要件です。忘れないようにしてくださいね。
☆同様の問題が平成29年に出題されています。
コチラの記事もご覧ください。

社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労基法)
R2-11
R1.9.15 R1労基法より・1か月単位の変形労働時間制採用ルール
令和元年の問題を振り返っています。
今日は労基法の基本的な問題を解いてみます。
 R1労基法(問2)より
R1労基法(問2)より
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

【解答】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「労使協定」によるか又は「就業規則その他これに準ずるもの」に定めることによって、採用することができます。
☆「又は」がポイントです。「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらかでOK。
この問題の場合は、「就業規則その他これに準ずるもの」による定めだけでも足りるということです。
ちなみに、「就業規則に準ずるもの」で採用できるのは、就業規則の作成義務がない常時10人未満の事業場だけです。
・常時10人以上 → 「労使協定」か「就業規則」
・常時10人未満 → 「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(労基法)
R1.9.1 R1選択式(労基法)振り返ります!
第51回試験から1週間たちました。
今日から、令和元年の問題を振り返ります。
第1回目は、「労基法選択式」です。
【労働基準法】
A、Bは最高裁判例「あけぼのタクシー事件」、Cは出来高払いの保障給の条文の出題です。
 「あけぼのタクシー事件」はH23年選択式でも出題されています。
「あけぼのタクシー事件」はH23年選択式でも出題されています。
<参考 H23年選択>
「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇制限期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法第12条1項所定の< A >に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されていると解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
(解答)平均賃金の6割
★択一式でも出題されています。
<参考 H21年択一>
労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨を包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。
(解答) ×
「使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されない」の部分が×です。
最高裁判所の判例では、「解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許される」となっています。
 出来高払制の保障給はH28年に出題されています。
出来高払制の保障給はH28年に出題されています。
<参考 H28年択一>
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
(解答)○
「出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず」の部分がポイントです。
今後の勉強のポイント
択一式で出題された箇所は、「選択式」に姿を変えて出題されることが多いです。
択一式の過去問を解くときは、常に「選択式で出題されるかも」と意識して、キーワードをおさえてくださいね。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労働分野】目的条文
R1.8.16 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)
 夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。
【労働基準法】
(労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として< B >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
この法律は、労働基準法と相まつて、< C >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< D >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< E >を確保するとともに、< F >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して< G >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< H >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >等を図り、もつて労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< K >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< L >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。

【解答】
A 人たるに値する生活 B 労働条件を低下させてはならない
C 労働災害の防止 D 自主的活動の促進 E 安全と健康
F 快適な職場環境の形成 G 迅速かつ公正な H 社会復帰の促進
I 安全及び衛生の確保 J 福祉の増進 K 生活及び雇用の安定
L 職業の安定 M 福祉の増進
★ 注意 ★
Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」
Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保
社労士受験のあれこれ
三六協定その2
R1.8.10 穴埋めで確認・三六協定(特別条項など)
条文の空欄を埋めてください
<特別条項を設ける場合の上限>
・ 36協定においては、所定の事項のほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第2項第4号に関して協定した時間を含め< A >時間未満の範囲内に限る。)並びに1年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め< B >時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。
この場合において、36協定に、併せて第2項第2号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が1か月について45時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、1か月について42時間)を超えることができる月数(1年について< C >か月以内に限る。)を定めなければならない。
<36協定で労働させる場合の時間外・休日労働の上限>
・ 使用者は、36協定で定めるところによって労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であっても、次の要件を満たすものとしなければならない。
1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、1日について労働時間を延長して労働させた時間
→ < D >時間を超えないこと。
2 1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 → < E >時間未満であること。
3 対象期間の初日から1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の1か月当たりの平均時間
→ < F >時間を超えないこと。

【解答】
A 100 B 720 C 6 D 2 E 100 F 80
社労士受験のあれこれ
第41条の2高度プロフェッショナル制度(労基法)
R1.8.3 穴埋めで確認・高プロ
条文の空欄を埋めてください
長文ですが、頑張りましょう。
<労基法第41条の2>
労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の< A >以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、労働時間、休憩、休日及び < B >に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。
一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た < C >との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下「対象業務」という。)
二 対象労働者(次のいずれにも該当する労働者であって、対象業務に就かせようとするものの範囲)
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による< D >に 基づき職務が明確に定められていること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃 金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の< E >倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
三 対象業務に従事する対象労働者の< F >を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(「< F >時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
四 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ< G >日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
五 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した< H >時間を確保し、かつ、深夜の間において労働させる回数を1箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
ロ < F >時間を1箇月又は< I >箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
ハ 1年に1回以上の継続した< J >週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。
ニ < F >時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に< K >(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。
六 対象業務に従事する対象労働者の< F >時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、< K >の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
七 対象労働者の同意の撤回に関する手続
八 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
九 使用者は、同意をしなかった対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

【解答】
A 5分の4 B 深夜の割増賃金 C 成果 D 合意
E 3 F 健康管理 G 104 H 休息 I 3
J 2 K 健康診断
社労士受験のあれこれ
36協定(労働基準法)
R1.7.30 労基法第36条穴埋めの練習
条文の空欄を埋めてください
<労基法第36条>
36協定で定めること
1 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 < A >に限るものとする)
3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
4 対象期間における1日、< B >及び< C >のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
★ 4の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して< D >時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
★ 限度時間は、< B >について< E >時間及び< C >について< F >時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めたときは、< B >について42時間及び< C >について320時間)とする。

【解答】
A 1年間 B 1箇月 C 1年
D 通常予見される E 45 F 360
社労士受験のあれこれ
1年単位の変形労働時間制
R1.7.19 1年変形・労使協定で定めること
まずは過去問をどうぞ
<H18年出題>
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

【解答】 ×
「個々の対象労働者の同意を得て」が誤りです。
「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て」です。
 1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定に「対象期間の労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を協定しなければなりません。(対象期間全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定しなければならない)
1年単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定に「対象期間の労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を協定しなければなりません。(対象期間全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定しなければならない)
※ ただし、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合は、
「最初の期間」→ 労働日及び当該労働日ごとの労働時間を定める
「最初の期間を除く各期間」→ 労働日数及び総労働時間を定める
※ 各期間のうち最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間を定めたときの、「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を定め方
・ 当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、書面により当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
社労士受験のあれこれ
解雇予告
R1.6.20 解雇予告手当・よく出るところ
★★まずは過去問をどうぞ
<H26年出題>
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

【解答】 ×
解雇の予告期間には、解雇予告をした当日は入れません。(予告をした時点でその日は、すでに丸一日ないからです。)解雇予告をした翌日から計算します。
ですので、9月30日をもって解雇するには、遅くても8月31日には解雇予告をしなければなりません。
もう一問どうぞ
<H16年出題>
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

【解答】 ○
5月14日(解雇予告をした翌日)から5月31日まで予告期間が18日。12日分の解雇予告手当を支払うことにより、5月31日をもって解雇することができます。
さらにもう一問どうぞ
<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

【解答】 ○
「解雇の通告をした日」が○です。
解雇事由の発生した日という問題は×ですので、注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
36協定の効力の要件
R1.5.8 労働基準法36協定のポイントをおさえよう。
まずは条文を穴埋めで確認しましょう
<第36条>
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の < A >との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 三六協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲二 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 < B >に限るものとする。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における1日、< C >及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

【解答】 A 過半数を代表する者 B 1年間 C 1か月
では、過去問もどうぞ
<H24年出題>
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】 ○
時間外労働、休日労働を適法に行わせるためには、三六協定を締結するだけでは足りません。三六協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって「労働基準法違反にならない」免罰効果が生まれます。
社労士受験のあれこれ
休日の定義(労働基準法)
R1.5.6 労働基準法の「休日」とは?
まずは条文を穴埋めで確認しましょう
<第35条 休日>
① 使用者は、労働者に対して、< A >の休日を与えなければならない。
② ①の規定は、< B >を通じ< C >以上の休日を与える使用者については適用しない。

【解答】 A 毎週少くとも1回 B 4週間 C 4日
ポイント! 休日の原則は毎週少なくとも1回。例外的に4週間に4日もOK
なお、「法定休日」とは、第35条で定められた「休日」のことです。
では、過去問もどうぞ
<H29年出題>
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

【解答】 ×
第35条の休日は、原則として「暦日」単位となっているので、起算時点は午前0時となります。
※ 8時間3交替制の場合は継続24時間の休日が認められる例外もあります。
社労士受験のあれこれ
就業規則の記載事項
H31.4.12 絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
さっそく、過去問をどうぞ
<H28年出題>
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。

【解答】 ×
退職手当の「不支給事由又は減額事由」は、退職手当の決定、計算の方法に関する事項に該当するので、不支給事由や減額事由を設ける場合には、就業規則に記載する必要があります。
※退職手当については、就業規則の相対的必要記載事項です。退職手当制度は労働基準法で義務付けられているものではありません。しかし、退職手当制度を設ける場合は、争いを避けるためルールを明文化してくださいね、ということです。
社労士受験のあれこれ
年次有給休暇・出勤率のルール
H31.4.10 出勤したものと「みなす」期間
6か月継続勤務し、出勤率が8割以上の場合、年次有給休暇の権利が発生します。
要件の一つである「出勤率8割以上」とは、「全労働日(労働する義務のある日)」に対して「出勤した日」の割合が8割以上、ということです。
実際は出勤していなくても、「出勤したもの」とみなして出勤率を算定する期間が定められていますので、確認しましょう。
では、過去問をどうぞ
<H18年出題>
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業若しくは同条第2号に規定する介護休業をした期間又は同法第16条の2に規定する子の看護休暇を取得した期間並びに産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間は、同法第39条第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなされる。

【解答】 ×
「子の看護休暇を取得した期間」は、出勤したものとみなされる期間には入っていません。
※出勤したものとみなされる期間(第39条10項)
・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
・育児休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間
・産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
こちらもどうぞ
<H28年出題>
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。

【解答】 ○
年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなして、出勤率を計算思します。
社労士受験のあれこれ
労働基準法第19条 解雇制限
H31.2.20 解雇が制限される期間
 まずは過去問をどうぞ。
まずは過去問をどうぞ。
⓵<H27年出題>
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。

【解答】 ○
【原則】 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は解雇してはいけない。
【例外】 ①労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、②天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合は解雇できる。
 例外②については、「行政官庁の認定」が必要ですので注意してください。
例外②については、「行政官庁の認定」が必要ですので注意してください。
もう一問どうぞ!
②<H29年出題>
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】 ○
解雇制限がかかるのは、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間」とされています。対象は「休業中」ですので、休業しないで就労している場合は解雇制限はかかりません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法第37条割増賃金
H31.2.19 割増賃金の計算・端数処理はどこまで?
 まずは過去問をどうぞ。
まずは過去問をどうぞ。
<H19年出題>
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】 ×
問題文のように、日々の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数を四捨五入することはできません。
1日ごとではなく、「1か月間」の時間外労働、休日労働、深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるのは認められています。
 あくまでも「割増賃金の計算の便宜上」の扱いです。
あくまでも「割増賃金の計算の便宜上」の扱いです。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法)
H31.1.18 H30年出題/法令又は労働協約に抵触する就業規則
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」です。
※ 今日は、「法令又は労働協約に抵触する就業規則」です。
H30年 労働基準法(問7E)
都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

【解答】 ×
正しくは、「行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる」です。
なお、この就業規則の変更命令は、所轄労働基準監督署長が、文書で行うこととされています。
過去問もどうぞ
<H25年出題>
行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

【解答】 〇
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法)
H31.1.2 H30年出題/割増賃金のルールその4
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその4」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその3」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3B)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。

【解答】 ×
前回の「割増賃金のルールその3」と同じ考え方です。
割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっていますので、休日割増賃金対象の労働となるのは月曜日に日付が変わるまで(日曜の24時まで)です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法)
H30.12.13 H30年出題/割増賃金のルールその3
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルールその3」です。
「割増賃金のルールその1」はこちらをどうぞ。
「割増賃金のルールその2」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3D)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。

【解答】 ×
日曜の午前0時から午前3時までの労働は、土曜の勤務の時間外労働時間ではなく、「法定休日」の労働として計算します。
割増賃金率を計算する際の「法定休日」は暦日単位となっています。前日の勤務から継続していたとしても、日付が法定休日に変わったところ(休日の午前0時以降)からは、割増賃金率は休日労働の3割5分以上で計算します。
【過去問もどうぞ】
(H16年出題)
始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。

【解答】 ×
法定休日の午前0時から、法定休日の労働として割増賃金の計算を行わなければなりません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法)
H30.12.11 H30年出題/割増賃金のルール②
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルール②」です。
「割増賃金のルール①」はこちらをどうぞ。
H30年 労働基準法(問3C)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。

【解答】 ○
行政解釈では、「労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻までの分は前日の超過勤務時間として取り扱われる」となっています。
設問の場合ですと、月曜の時間外労働がそのまま火曜の午前3時まで継続していますので、日付が変わっても(火曜の始業時刻までは)、月曜の超過勤務時間として取り扱われます。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法)
H30.12.10 H30年出題/割増賃金のルール①
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「割増賃金のルール①」です。
H30年 労働基準法(問3A)
(前提条件)
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
(問題)
日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。

【解答】 ×
「8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになる」は間違い。休日については労働が8時間を超えても時間外労働にはなりません。
設問の場合は、10時間すべて休日労働に対する割増率(3割5分増)で計算することになります。
※なお、休日労働が深夜になった場合は、深夜労働の割増率を加算する必要があります。
【過去問もどうぞ】
<H29年出題>
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】 ×
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法)
H30.11.23 H30年出題/平均賃金の算定すべき事由の発生した日
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」を確認しましょう。
※ 今日は、「平均賃金の算定すべき事由の発生した日」です。
H30年 労働基準法(問7D)
労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。

【解答】 ×
「制裁事由発生日」ではなく、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」です。
【こちらの過去問もどうぞ】
<H16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

【解答】 ○
こちらも解雇事由発生日ではありません。注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法 基礎編)
H30.11.1 H30年出題/第16条 賠償予定の禁止
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労働基準法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労働基準法第16条です。
H30年 労働基準法(問5B)
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

【解答】 ×
★「現実に生じた損害」について賠償を請求することは禁止されていません。
労基法第16条を確認しましょう。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
→ 第16条で禁止されているのは、「金額を予定する」ことです。あらかじめ損害賠償額が決められていると、実際の損害額に関係なく、労働者が高額な損害賠償額を支払わなければならなくなるからです。
【過去問もチェックしましょう!】
<H20年出題>
使用者は労働契約の不履行について、労働者に損害賠償を請求してはならない。

【解答】 ×
現実に生じた損害を請求することは禁止されていないので、労働者に損害賠償を請求することは可能です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法 基礎編)
H30.10.16 H30年出題/年少者の時間外労働
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働基準法の「基礎」を確認しましょう。
H30年 労働基準法(問1エ)
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。

【解答】 ○
★ポイント
・ 年少者(満18歳に満たない者)については、第36条は適用されませんので、36協定による時間外、休日労働は禁止されています。
・ ただし、第33条は適用されますので、災害等により臨時の必要がある場合、公務のために臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができます。
 ついでに、「災害等」の年少者の深夜労働も。
ついでに、「災害等」の年少者の深夜労働も。
年少者の深夜業は原則として禁止されていますが・・・
・ 第33条の「災害等」により臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができますし、深夜業を行わせることもできます。
・ 「公務のため」に臨時の必要がある場合は、時間外労働、休日労働を行わせることができますが、深夜業は認められません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労働基準法 基礎編)
H30.9.24 H30年出題/労基法基礎問題
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労働基準法の「基礎」を確認しましょう。
H30年労基法問7E
都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
【解答】 ×
「こんな条文見たことない」で、「×」を付けられる問題です。
では、労働基準法では、「法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている」場合、どのような規定になっているのでしょう?
↓ 条文の空欄を埋めてください。
第92条
就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の< A >ことができる。
【解答】 A 変更を命ずる
なお、変更を命ずるのは、所轄労働基準監督署長です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労基選択編)
H30.9.1 H30年選択・労基法振り返ります
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労働基準法の選択式です。
A 解雇予告制度の適用除外より
問題なく解けたと思います。
★ポイント!
「解雇予告の規定が除外される」労働者については、「例外(予告が必要になる場合)」きっちり覚える。
★過去問もチェック
<H13年にこんな問題が出ています。>
日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
<解答> ×
1か月を超えて引き続き使用される至った場合は適用されるので「×」です。
B 育児時間より
これも問題なく解けたと思います。
★過去問をチェックすると・・・
<H15年出題>
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
<解答> ×
労働者× → 女性○
男性は育児時間を請求できないので。(労働者という表現だと男性も入ってしまう)
C 三晃社事件(最高裁判例)より
前後の文脈で判断できたでしょうか?
★過去問チェック
<平成9年に出題されています。>
就業規則において、退職後一定期間同業他社への就職を禁止することは、社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは必ずしもいえないが、同業他社への就職を理由として退職金を減額する旨の規定は著しく不合理であって、公序良俗に反し無効である。
<解答> ×
退職金には「功労報償」的な面があるため、同業他社へ転職したときに、退職金の額を自己都合退職の半額とする定めは、合理性のない措置とすることはできない。
もう一つ見てみましょう。「退職金」の性格については、「労働の一般常識」で平成13年に以下のような問題が出ています。
<H13年(労働一般常識)>
退職金の性格をめぐっては様々な説がある。様々な説の中には、在職中の功労に報いるものであるとする説、退職後の生活を保障するためのものであるとする説、賃金の後払いであるとする説などがある。
<解答> ○
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】基本の条文(労働編)
H30.8.20 【選択式対策】基本条文チェック!(労基、安衛、労災、雇用)
 涼しくなりましたね。風に秋を感じます。
涼しくなりましたね。風に秋を感じます。
あと1週間です!
迷いは捨てて、ご自分の直感で勉強を進めてくださいね。
■■
前回までは「目的条文」を確認してきました。
今回からは、おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【労働基準法】
(労働条件の決定)
① 労働条件は、労働者と使用者が、< A >において決定すべきものである。② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< B >各々その義務を履行しなければならない。
【労働安全衛生法】
(定義)
・ 労働災害
→ 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は< C >その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
・ 労働者
→ 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
・ < D >
→ 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
・ 化学物質
→ 元素及び化合物をいう。
・ < E >
→ 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
【労災保険法】
(通勤の定義)
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、< F >により行うことをいい、< G >を除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する< H >の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
【雇用保険法】
(失業等給付)
失業等給付は、< I >、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

【解答】
A 対等の立場 B 誠実に C 作業行動 D 事業者
E 作業環境測定 F 合理的な経路及び方法 G 業務の性質を有するもの
H 住居間 I 求職者給付
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労働分野】目的条文
H30.8.15 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)
 夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。
【労働基準法】
(労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として< B >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(目的)
この法律は、労働基準法と相まつて、< C >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< D >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< E >を確保するとともに、< F >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して< G >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< H >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >等を図り、もつて労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< K >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< L >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。

【解答】
A 人たるに値する生活 B 労働条件を低下させてはならない
C 労働災害の防止 D 自主的活動の促進 E 安全と健康
F 快適な職場環境の形成 G 迅速かつ公正な H 社会復帰の促進
I 安全及び衛生の確保 J 福祉の増進 K 生活及び雇用の安定
L 職業の安定 M 福祉の増進
★ 注意 ★
Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」
Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労働基準法】三六協定
H30.7.18 【選択式対策】 三六協定のルール
 問題の数をこなしていくと、問題を見たときに、「この問題は何を問うているのか?」が瞬時に分かるようになります。
問題の数をこなしていくと、問題を見たときに、「この問題は何を問うているのか?」が瞬時に分かるようになります。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働基準法」です。
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について< A >時間を超えてはならない。
② < B >は、労働時間の延長を適正なものとするため、①の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る< C >その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して < D >を定めることができる。
③ ①の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が②の< D >に < E >したものとなるようにしなければならない。
④ 行政官庁は、②の< D >に関し、①の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な< F >及び指導を行うことができる。

【解答】
A 2 B 厚生労働大臣 C 割増賃金の率 D 基準
E 適合 F 助言
過去問もどうぞ
<H14年選択式>
労働基準法施行規則第16条第1項においては、使用者は、労働基準法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに< G >及び< G >を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない、と規定されている。
また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長等に関する基準」第2条においては、労働基準法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働協定において< G >を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、< H >及び< J >としなければならない、と規定されている。

【解答】
G 1日 H 1日を超え3か月以内の期間 J 1年間
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労働基準法】労働者過半数代表者
H30.6.24 【選択式対策】労使協定・労働者の過半数を代表する者
 6月の最終の日曜日。いいお天気で暑かったですね。ランニングをしたら汗だくになりました。
6月の最終の日曜日。いいお天気で暑かったですね。ランニングをしたら汗だくになりました。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働基準法」です。
◆ 労使協定の「労働者の過半数を代表する者」は、次のいずれにも該当する者とする。
① 法第41条第2号に規定する< A >でないこと。
② 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される < B >等の方法による手続により選出された者であること。
◆ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として< C >をしないようにしなければならない。

A 監督又は管理の地位にある者 B 投票、挙手
C 不利益な取扱い
過去問もチェック!
<H13年出題>
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

<解答> ×
監督又は管理の地位にある者も「労働者」です。
ですので、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の数には監督又は管理の地位にある者も含みます。
ただし、「代表者」にはなれません。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労働基準法】就業規則
H30.5.26 【選択式対策】法令及び労働協約との関係
 なかなか解けない・納得できない問題が出てきたら、とりあえず飛ばして次に行ってみましょう。受験勉強は「割り切り」も必要です。
なかなか解けない・納得できない問題が出てきたら、とりあえず飛ばして次に行ってみましょう。受験勉強は「割り切り」も必要です。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働基準法」です。
第92条 (法令及び労働協約との関係)
① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に< A >。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則< B >。

【解答】
A 反してはならない B の変更を命ずることができる
★ 力関係は、①法令、②労働協約、③就業規則、④労働契約の順番です。
いっしょに、労働基準法違反の労働契約についてもチェックしておきましょう。
第13条 (この法律違反の契約)
この法律で定める基準に< C >労働条件を定める労働契約は、その部分については< D >とする。この場合において、< D >となつた部分は、この法律で定める基準による。

【解答】
C 達しない D 無効
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労基法】減給制裁のルール
H30.4.30 【選択式対策】減給制裁のルール
 ゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィークですね。
お仕事が休みの方も多いと思います。
自分のペースを守って、計画通りに勉強を進めてくださいね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労働基準法」です。
条文の空欄を埋めてください。
第91条 (制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が< A >を超え、総額が< B >の10分の1を超えてはならない。

【解答】
A 平均賃金の1日分の半額 B 一賃金支払期における賃金の総額
おさえるべきポイント★
択一式でよく問われるポイントをcheckしましょう。
①H20年出題
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。又、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
②H14年出題
就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用をうける。

【解答】
① ×
「表彰及び制裁」は、就業規則の「相対的必要記載事項」ですので、いかなる場合でも必ず記載する、という部分が誤りです。
② ×
例えば1時間遅刻をした場合は1時間働いていないのですから、その1時間分の賃金を引くことは減給制裁ではありません。
1時間の遅刻に対し、1時間分の賃金額を超える減給をするならば、減給制裁の規定が適用されます。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労基法】事業場外労働
H30.4.9 【選択式対策】事業場外労働
本試験まで、あと4か月と少し。
そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
今日から選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしていきます。
★ では、今日は労働基準法の「事業場外労働」の条文をチェックしましょう。
条文の空欄を埋めてください。
(事業場外労働)
第38条の2
① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、< A >ときは、< B >労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常< B >を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該< C >労働したものとみなす。
② ①項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を①項ただし書の当該< C >とする。
③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

【解答】 A 労働時間を算定し難い B 所定労働時間
C 業務の遂行に通常必要とされる時間
社労士受験のあれこれ
労働協約の適用範囲
H30.3.8 H29年問題より「労働協約の適用範囲」
H29年本試験【労働基準法問6A】を解いてみてください。
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

【解答】 ○
★ 賃金には「通貨払い」の原則がありますので、現物給与は禁止されています。
ただし、例外的に「労働協約」に別段の定めがある場合は、現物給与(例えば通勤定期券など)で支払うことも許されます。
★ 「労働協約」とは、「労働組合」と使用者との間で結ばれた労働条件に関する協定で、その協約を締結した組合の組合員に対してのみ適用されるのが原則です。
(労働組合法には、一般的拘束力(第17条)などの例外がありますが、それについては、ここでは触れません。)
★ ですので、労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者(=原則としてその協約を締結した組合の組合員)に限られる、ということになります。
★ 「労働協約」の定義を確認しておきましょう。以下は、労働組合法第14条です。空欄を埋めてください。
【労働組合法第14条 労働協約の効力の発生】
< A >と使用者又はその団体との間の< B >その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。

【解答】
A 労働組合 B 労働条件
社労士受験のあれこれ
妊産婦の時間外労働等について
H30.2.13 H29年問題より「妊産婦の時間外労働等」
H29年本試験【労働基準法問7D】を解いてみてください。
使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。

【解答】 ×
★ 「すべての妊産婦」の部分が誤りです。
労基法第66条第2項と3項を確認してみましょう。
「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害等による臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のために臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(三六協定)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。」
「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」
「妊産婦が請求した場合」の箇所をチェックしてください。
★ 妊産婦だから一律に時間外労働等を禁止するのではなく、「妊産婦からの請求」により時間外労働が制限されることがポイントです。
妊娠中や産後の体調などは個人によって違いますので、必要なら「請求してくださいね」という趣旨です。
社労士受験のあれこれ
休業手当について
H30.2.9 H29年問題より「休業手当の支給義務」
H29年本試験【労働基準法問6E】を解いてみてください。
労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。

【解答】 ○
★ 本来は労働しなければならない日に、使用者の都合で休業させる場合は、生活保障のため休業手当の支払いが必要です。
が、もともと労働する義務のない休日については、休業手当の支払義務はありません。
社労士受験のあれこれ
1か月単位の変形労働時間制の時間外労働
H30.1.23 H29年問題より「1か月単位の変形労働時間制の時間外労働」
H29年本試験【労基法問1A】を解いてみてください。
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。

【解答】 ○
★ 1か月単位の変形労働時間制で時間外労働となる時間
① 1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間を、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間を、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
★ 上の通達を問題文のパターンを当てはめてみましょう。
<所定労働日と所定労働時間>
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長、土曜日に6時間の労働をさせた場合
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9+α | 9+α | 9+α | 9+α | 6 |
① 1日については、9時間を超えて労働した時間が時間外労働になるので、+αの部分がすべて時間外労働になる
② 1週間については、40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間=+αの時間を除く。)が時間外労働になる。
+αの時間を除くと、この週の労働時間は、週所定労働時間36時間プラス土曜の6時間で42時間。土曜日の2時間が時間外労働となる。
社労士受験のあれこれ
時間外労働の考え方
H30.1.5 H29年問題より「時間外労働」の考え方/労働基準法
H29年本試験【労基法問4D】を解いてみてください。
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条(労働基準法第36条)に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

【解答】 ○
★ 例えば、始業8時~終業17時(休憩1時間)・所定労働時間8時間の事業場で、ある労働者が遅刻をしたので、始業・終業を1時間ずらし9時~18時(休憩1時間)にした場合でも、実働時間は8時間です。
★ 実働時間が8時間を超えていないので、36協定がなくても違反とはなりません。また割増賃金の支払いも要りません。
ポイント!
労働基準法第32条の労働時間(法定労働時間)は、「実労働時間」のことです。
社労士受験のあれこれ
基本の問題その1(労働基準法)
H29.12.14 H29年問題より「基本」を知ろう・労働基準法
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題。
そんな問題を取り上げていきます。
割増賃金の率
時間外労働+深夜、休日労働+深夜のときの割増率
★ 時間外労働、休日労働をさせた場合は、割増賃金の支払いが義務付けられています。また、深夜の時間帯に労働させた場合も割増賃金の支払いが必要です。
● 例えば、所定労働時間8時間(始業9時・終業18時・休憩1時間)で、18時以降に時間外労働をさせた場合を考えてみましょう。(月60時間超は超えていないものとして)
・ 18時以降は2割5分以上の割増率で計算します。
時間外労働が深夜(22時以降)に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして5割以上の割増率で計算します。
● 次に、法定休日に労働させた場合を考えてみましょう。
・ 法定休日の労働は3割5分以上の割増率で計算します。休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜の時間帯は深夜の割増率(2割5分以上)をプラスして6割以上の割増率で計算します。
では、平成29年【問1】Eを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問1】E)
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

<解答> ×
★ 休日には「8時間を超え」という概念がないので時間外の割増率は合算しません。休日労働が8時間を超えたとしても、深夜の時間帯にならなければ、3割5分で計算すればOKです。
社労士受験のあれこれ
定番問題その11(労働基準法)
H29.11.20 H29年問題より「定番」を知る・労働基準法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (業務上の傷病の治療中の解雇制限)
解雇制限期間は、業務上の傷病による療養のため「休業する期間」+30日間、産前産後の女性が「休業する期間」+30日間。
★ 労働基準法第19条では、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定されています。
★ 解雇制限がかかるのは、「休業する期間」及びその後30日間です。
業務上のケガや病気の治療中でも休まず就労している場合、又産前でも休まず就労している場合は、解雇制限はかかりません。
これを覚えると、平成29年【問3】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】D)
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
定番問題その1(労働基準法)
H29.10.25 H29年問題より「定番」を知る・労働基準法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (労基法第3条 均等待遇)
労基法第3条で禁止されている差別の理由は、「国籍、信条、社会的身分」のみ。
★ 労働基準法第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
※ 差別の理由が「国籍、信条、社会的身分」に限定されているのがポイント。
「国籍、信条、社会的身分」以外の理由で労働条件について差別的取り扱いをしたとしても労基法第3条には違反しません。
これを覚えると、平成29年【問5】アが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】ア
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。

<解答> ×
「性別」は入りません。性別を理由に労働条件について差別的取り扱いがあったとしても第3条違反ではありません。(性別による差別は男女雇用機会均等法に違反する可能性があります。)
社労士受験のあれこれ
覚えれば解ける問題その1(労働基準法)
H29.10.10 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・労基法
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける(児童の定義)
「中学校卒業」までは、労働させてはならない(原則)
労働基準法では、「児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」と規定されています。
中学校を卒業するまで(児童)は、原則として、労働させることはできません。
これを覚えると、平成29年【問7】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】A)
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。

<解答> ×
◆ 使用することが禁止されているのは中学校卒業までです。満15歳に達するまでではなく、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。
◆ なお、「年少者」の定義は満18歳に満たない者です。こちらは年度末ではありませんので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
まずは原則!(H29年労基法より)
H29.9.25 平成29年度・労基法の問題より
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じること、ありませんか?
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
肝心の「幹」の部分が置き去りになると、確かに面白くありません。
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則
休日は原則「暦日」単位で与える。
※ 暦日とは、「午前0時~午後12時まで」(暦の上の一日のこと)をさします。
この原則で、平成29年度【問1】Dが解けます。
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。

<解答> ×
「一暦日」が原則ですので、午前0時から起算するのが原則です。24時間解放すればよいというものではありません。
社労士受験のあれこれ
平成29年度選択式を解きました。(労基、安衛編)
H29.9.4 平成29年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。
<労働基準法>
【AとB】
最高裁判例(平成4年6月23日 第三小法廷判決ー時事通信社事件)からの出題です。
◆ 平成22年選択式でも同じ判例から出題されていますし、何度も目にした文章だと思います。
◆ 平成22年度と今回の平成29年度の選択式から、この判例のポイントを考えてみましょう。
◆ この判例のテーマは、労働者が長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合の「使用者の時季変更権」です。
●時季変更権とは・・・
年次有給休暇は、労働者の請求する時季に与えなければならないことになっていますが、労働者から請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者に時季変更権が認められています。
<平成22年と平成29年のキーワード>
・ 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合、それが長期になるほど、代替勤務者の確保などが難しくなり、「事業の正常な運営」に支障を来す蓋然性が高まる。
↓
・ 業務計画やほかの労働者の休暇予定などと「事前の調整」を図る必要が生ずるのが通常。(やはり事前の調整が必要)
↓
・ 労働者が、そのような調整を経ず、始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季を指定した場合、それに対する使用者の時季変更権の行使については、使用者にある程度の「裁量的判断」が認められる。(事前の調整がない場合は、休暇の時期をずらすなど、ある程度の裁量的判断が認められる)
★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。
【C】
労働基準法の「出産」の定義からの出題です。
この問題は解けた方が多かったのでは?と思います。
<労働安全衛生法>
【D】
労働安全衛生法第28条の2リスクアセスメントからの出題です。
平成19年の選択式でも出題された条文です。
【E】
労働安全衛生法第65条の3の「作業管理」からの出題です。
平成16年の選択式でも出題された条文です。

労働基準法A・B、労働安全衛生法D・Eは、過去の選択式で出題された判例や条文です。
ただし、全く同じ問題ではなく、穴あきの部分が変わっています。
今後の勉強のポイント!
★ 歴史は繰り返される
過去に「選択式」で出題されたものは再び表舞台に登場する。
★ ただし、穴あきの箇所は変わる
全体のポイントをつかむことが必要。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)
H29.7.31 目的条文のチェック(労働編)
いよいよ7月最終日です!
明日から8月。8月の頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(労働編)です。
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< A >を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< B >の確保等を図り、もつて労働者の < C >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が< A >場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< B >及び雇用の安定を図るとともに、< C >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< D >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< E >を図ることを目的とする。

<解答>
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が<A 人たるに値する生活>を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、<B この基準>を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<C 向上>を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、<A 労働基準法>と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B 安全と健康>を確保するとともに、<C 快適な職場環境>の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な<A 保険給付>を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の<B 安全及び衛生>の確保等を図り、もつて労働者の<C 福祉の増進>に寄与することを目的とする。
ここもポイント!
「労働安全衛生法」と「労災保険法」の目的条文の比較
安全と○○
→ こちらの記事をどうぞ! H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が<A 自ら職業に関する教育訓練を受けた>場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<B 生活>及び雇用の安定を図るとともに、<C 求職活動>を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<D 職業の安定>に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<E 福祉の増進>を図ることを目的とする。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ78
H29.6.7 第115条 時効
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「時効」です。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第115条 時効)
この法律の規定による賃金(< A >を除く。)、災害補償その他の請求権は< B >年間、この法律の規定による< A >の請求権は< C >年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

(解答) A 退職手当 B 2 C 5
★ この規定によって、例えば年次有給休暇の時効は2年間となり、その年度にとらなかった有給休暇は次の年度に繰り越しされます。
 では、過去問です。
では、過去問です。
<H13年出題>
退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。

<解答> ×
★ 退職手当以外の賃金の請求権は、「2年間」です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ77
H29.6.6 第114条 付加金の支払その2
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「付加金の支払 その2」です。
 労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。
労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。
「付加金の支払その1」では、付加金の支払い対象となる手当等を勉強しました。
今日は、付加金の支払いの請求のルールをみていきましょう。
 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第114条 付加金の支払)
< A >は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、< B >の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと< C >の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から < D >年以内にしなければならない。

(解答) A 裁判所 B 労働者 C 同一額 D 2
★ ポイント
・ 付加金の支払いを命ずることができるのは「裁判所」。「労働基準監督署」ではありません。
・ 付加金の額は、使用者が支払わなければならない未払金と「同一額」。
・ 付加金の支払を「命ずることができる」。「命じなければならない」ではありません。
 では、過去問です。
では、過去問です。
<H20年出題>
労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。

<解答> ×
★ 「命ずることができる」です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ76
H29.6.5 第114条 付加金の支払その1
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「付加金の支払 その1」です。
 労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。
労働者に特に重要な金銭が支払われない場合について、付加金の制度が設けられています。
付加金を請求できるのはどんなときか?、付加金の支払いを命ずるのはどこなのか?などがポイントです。
 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第114条 付加金の支払)
裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(< A >)若しくは第37条 (< B >)の規定に違反した使用者又は第39条第7項(年次有給休暇)の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。

(解答) A 休業手当 B 割増賃金
★ 付加金の請求ができるのは次の4つの場合です。
| 第20条違反 | 解雇予告手当を支払わない |
| 第26条違反 | 休業手当を支払わない |
| 第37条違反 | 割増賃金を支払わない |
| 第39条違反 | 年次有給休暇の賃金を支払わない |
※ 第○○条という条文番号までは覚えなくて構いませんが、対象になる4つの手当等は覚えてください。
 過去問です。
過去問です。
<H15年出題>
裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。

<解答> ×
★ 第24条(全額払い)違反は、付加金制度の対象になりません。
→ その2に続きます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ75
H29.6.2 第109条 記録の保存
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「記録の保存」です。
 トラブルになったときなどのために、労働関係の重要書類には保存義務が課せられています。
トラブルになったときなどのために、労働関係の重要書類には保存義務が課せられています。
 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第109条 記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を< A >保存しなければならない。

(解答) A 3年間
 過去問です。
過去問です。
<① H14年出題>
タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、これらの書類を3年間保存しなければならない。
<② H11年出題>
使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日である。

<解答>
① 〇
★ 「その他労働関係に関する重要な書類」に該当するものとして、出勤簿、タイムカード等の記録、労働基準法に基づく労使協定の協定書などがあります。
② 〇
★ 3年間の起算日(施行規則第56条)
① 労働者名簿 → 労働者の死亡、退職又は解雇の日
② 賃金台帳 → 最後の記入をした日
③ 雇入れ又は退職に関する書類 → 労働者の退職又は死亡の日
④ 災害補償に関する書類 → 災害補償を終わった日
⑤ 賃金その他労働関係に関する重要な書類 → その完結の日
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ74
H29.6.1 第108条 賃金台帳
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「賃金台帳」です。
 賃金台帳を見れば、労働日数や労働時間数と賃金がリンクしているかどうか、一目瞭然です。賃金台帳を調製することは、労務管理の改善にもなります。
賃金台帳を見れば、労働日数や労働時間数と賃金がリンクしているかどうか、一目瞭然です。賃金台帳を調製することは、労務管理の改善にもなります。
 では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第108条 賃金台帳)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を< A >記入しなければならない。
■ 「賃金計算の基礎となる事項」、「賃金の額」の他に賃金台帳に記入しなければならない事項
① 氏名、② 性別、③ 賃金計算期間、④ 労働日数、⑤ 労働時間数、⑥ 労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は深夜労働をさせた場合は、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数、⑦ 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額、⑧ 賃金の一部を控除した場合には、その額

(解答) A 賃金支払の都度遅滞なく
 過去問です。
過去問です。
<H13年出題>
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。

<解答> ×
「すべての労働者」の部分が誤りです。
賃金台帳に記入する事項は法令で定められていますが、日々雇入れられる者と第41条該当者については、記入しなくてもよい事項があります。
<記入しなくてもよい事項>
・ 日々雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用される者を除く) → 「③ 賃金計算期間」
・ 第41条該当者(労働時間や休日の規定が適用されないので) → 「⑤ 労働時間数」、「⑥ 労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は深夜労働をさせた場合は、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数」(ただし、行政解釈では、第41条該当者でも深夜労働時間数は記入すること、とされています。)
ここもポイント!
「日々雇入れられる者」について
■労働者名簿の調製は不要
■賃金台帳の調製は必要
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ73
H29.5.31 第107条 労働者名簿
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「労働者名簿」です。
 使用者には、労働者一人ずつの労働者名簿の調製が義務付けられています。
使用者には、労働者一人ずつの労働者名簿の調製が義務付けられています。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第107条 労働者名簿)
① 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(< A >を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
② ①の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

(解答) A 日日雇い入れられる者
 過去問です。
過去問です。
<H22年出題>
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(2か月以内の期間を定めて使用される者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴等の事項を記入しなければならない。

<解答> ×
労働者名簿の調製義務がないのは、日々雇入れられる労働者です。(頻繁に異動するため、名簿を作成する必要性がない)
※ 問題文の2か月以内の期間を定めて使用される者については、労働者名簿の調製が必要です。
★ ちなみに、労働者名簿に記入しなければならない事項は、労働者の氏名、生年月日、履歴のほか、次の事項です。
① 性別、② 住所、③ 従事する業務の種類(常時30人未満の労働者を使用する事業では、記入不要)、④ 雇入の年月日、⑤ 退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)、⑥ 死亡の年月日及びその原因
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ72
H29.5.30 第106条 法令等の周知義務その2
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令等の周知義務その2」です。
★ その1はコチラ → 「法令等の周知義務その1」
 今日は、法令等を労働者に周知させる「方法」を確認しましょう。
今日は、法令等を労働者に周知させる「方法」を確認しましょう。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(施行規則第52条の2 周知方法)
法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2 < A >を労働者に交付すること。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

(解答) A 書面
★ 1~3の3つの方法のうちどれかの方法で周知させなければなりません。
ちなみに3は、フロッピーディスク等に記録された就業規則等をパソコンなどで確認する方法です。
 過去問です。
過去問です。
<H24年出題>
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科されることはない。

<解答> ×
周知義務に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ71
H29.5.29 第106条 法令等の周知義務その1
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令等の周知義務その1」です。
 使用者には、法令等を労働者に周知させる義務があります。「周知」の方法も決まっていますので、チェックしてくださいね。
使用者には、法令等を労働者に周知させる義務があります。「周知」の方法も決まっていますので、チェックしてくださいね。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第106条 法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の< A >、< B >、第18条第2項(貯蓄金管理)、第24条第2項ただし書(賃金の一部控除)、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の3(フレックスタイム制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)、第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(休憩の一斉付与の除外)、第36条第1項(36協定)、第37条第3項(代替休暇)、第38条の2第2項(事業場外労働)、第38条の3第1項(専門業務型裁量労働制)並びに第39条第4項(時間単位の有給休暇)、第6項(有給休暇の計画的付与)及び第7項ただし書(有給休暇の賃金)に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項(企画業務型裁量労働制)に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

(解答) A 要旨 B 就業規則
★ 周知義務があるもの
| 労働基準法と同法に基づく命令の要旨 |
| 就業規則 |
| 労使協定(14種類) |
| 企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議 |
 過去問です。
過去問です。
<① H16年出題>
労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文の周知までは求められていない。
<② H11年出題>
使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。

<解答>
① ×
労働基準法とこれに基づく命令は「要旨」のみ周知すればOKですが、就業規則は「全文」を周知させることが求められます。
② ×
周知義務があるのは労働基準法に規定されている労使協定のみで、労働基準法に規定されている労使協定以外の労使協定には周知義務はありません。
※ 周知の方法については明日の記事で。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ70
H29.5.22 第92条 法令及び労働協約と就業規則との関係
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「法令及び労働協約と就業規則との関係」です。
 国会や行政が定めたルールが「法令」、労働組合と使用者が合意の上で定めたルールが「労働協約」、使用者が定めたルールが「就業規則」。この中で一番強い効力を持つのが「法令」で、次が「労働協約」、その次が「就業規則」です。
国会や行政が定めたルールが「法令」、労働組合と使用者が合意の上で定めたルールが「労働協約」、使用者が定めたルールが「就業規則」。この中で一番強い効力を持つのが「法令」で、次が「労働協約」、その次が「就業規則」です。
 就業規則は、より効力の強い法令や労働協約に反することができません。条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
就業規則は、より効力の強い法令や労働協約に反することができません。条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(第92条 法令及び労働協約との関係)
① 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される< A >に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は< A >に牴触する就業規則の< B >ことができる。

(解答) A 労働協約 B 変更を命ずる
 過去問です。
過去問です。
<H25年出題>
行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

<解答> 〇
★ なお、労働基準法施行規則第50条では、「法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第17号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。」と規定されています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ69
H29.5.19 第91条 制裁規定の制限
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日のテーマは「制裁規定の制限」です。
 就業規則の記載事項に「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」があり、「制裁」の定めをする場合は、種類及び程度を就業規則に記載しなければなりません。(相対的必要記載事項)
就業規則の記載事項に「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」があり、「制裁」の定めをする場合は、種類及び程度を就業規則に記載しなければなりません。(相対的必要記載事項)
(労働基準法第89条 → こちらをどうぞ)
 「制裁」の種類には、減給以外に、譴責、出勤停止、懲戒解雇などがありますが、その内容については、労働基準法による制限はありません。
「制裁」の種類には、減給以外に、譴責、出勤停止、懲戒解雇などがありますが、その内容については、労働基準法による制限はありません。
ただし、「減給」は、労働した分の賃金をカットする制裁ですので、制限がないと、今月の賃金ゼロという事態もあり得ます。故に、労働者を守るため、労働基準法では「減給」制裁については制限を設けています。
 では条文の確認です。空欄を埋めてください。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第91条 制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の< A >、総額が一賃金支払期における賃金の総額の < B >てはならない。

(解答) A 半額を超え B 10分の1を超え
★ 例えば、平均賃金10,000円、一賃金支払期の賃金30万円の場合であてはめてみましょう。
・ 1回の事案に対する減給額
→ 10,000円の半額=5,000円以内
・ 一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額
→ 300,000円×10分の1=30,000円以内
 過去問です。
過去問です。
<H14年出題>
就業規則で、労働者が遅刻をした場合にその時間に相当する賃金額を減額する制度を定める場合には、減給の制裁規定の制限に関する労働基準法第91条の規定の適用をうける。

<解答> ×
★ 例えば1時間遅刻したときに1時間分の賃金をカットすることは減給ではありません。(ノーワークノーペイです)
遅刻した時間を超える減給(労働した時間分まで減給してしまう)は、労基法第91条の適用を受けます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ68
H29.5.18 第90条 就業規則作成の手続
今日から、「労働基準法を学ぶ」シリーズ再開します。
本日のテーマは「就業規則の作成手続」です。
 労働基準法第90条では、就業規則の作成、変更の際は、労働者側の意見を聴くことが義務付けられています。
労働基準法第90条では、就業規則の作成、変更の際は、労働者側の意見を聴くことが義務付けられています。
 条文の確認です。空欄を埋めてください。
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第89条 就業規則の作成手続)
① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の< A >。
② 使用者は、第89条の規定により届出をなすについて、①の< B >を添付しなければならない。

(解答) A 意見を聴かなければならない B 意見を記した書面
 過去問です。
過去問です。
<H20年出題>
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

<解答> ×
★ 同意を得なければならないではなく、「意見を聴かなければならない」です。
求められているのは「意見を聴くこと」で、同意を得ることまでは求められていません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ67
H29.5.2 第89条 就業規則の作成及び届出の義務(その2)
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「就業規則の作成及び届出の義務(その2)」です。
※ その1はコチラ
 条文の確認です。空欄を埋めてください。
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第89条 就業規則の作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 < A >に関する事項(< B >の事由を含む。)
3の2 < C >の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、 < C >の決定、計算及び支払の方法並びに< C >の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(< C >を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(解答) A 退職 B 解雇 C 退職手当
 過去問です。
過去問です。
<H24年出題>
労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。

<解答> ×
退職手当に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項ではなく、定めをする場合は記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。
「退職手当」の制度を設ける、設けないは、自由です。(ですので、問題文にあるような「期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。」という決まりもありません。)
※ 「退職手当」の制度を設けた場合は、「適用される労働者の範囲(退職手当が支給されるのは誰なのか?)」、 「退職手当の決定、計算、支払の方法(勤続年数や退職理由等で決まるのが一般的)」、「退職手当の支払の時期(いつ支払われるのか?)」を就業規則に定めなければなりません。(これらの点をはっきりさせておかないと、トラブルになりやすいからです。)
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ66
H29.5.1 第89条 就業規則の作成及び届出の義務(その1)
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「就業規則の作成及び届出の義務(その1)」です。
 就業規則とは
就業規則とは
職場のルールや労働条件を定めたものです。
 条文の確認です。空欄を埋めてください。
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第89条 就業規則の作成及び届出の義務)
常時< A >人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(解答) A 10
 過去問です。
過去問です。
① <H26年出題>
労働基準法第89条に定める就業規則とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称である。
② <H20年出題>
1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を作成しなければならない。

<解答>
① 〇
② ×
就業規則を作成・届出義務は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に課せられています。
★ その2に続きます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ65
H29.4.28 第81条 打切補償
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「打切補償」です。

労働基準法第8章では「災害補償」について規定されています。
労働者が業務上負傷したり、疾病にかかったりした場合等の使用者の補償責任が規定されています。
・ 75条(療養補償)→ 業務上の傷病についての補償(治療を受けさせてその費用を使用者が支払う、又は、治療費を労働者に支払う)
・ 76条(休業補償)→ 療養中に賃金が受けられない場合の補償
・ 77条(障害補償)→ 傷病が治ったあと身体障害が残った場合の補償
・ 79条(遺族補償)→ 労働者が業務上死亡した場合の遺族への補償
・ 80条(葬祭料) → 労働者が業務上死亡した場合の葬祭を行うものへの補償

本日のテーマは、第81条 打切補償です。
療養開始後3年を経過しても治っていない場合、打切補償を行った場合は、その後は補償を行わなくてもよくなるという規定です。
 条文の確認です。空欄を埋めてください。
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第81条 打切補償)
第75条(療養補償)の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後< A >年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の < B >日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

(解答) A 3 B 1200
 過去問です。
過去問です。
<H19年出題>
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。

<解答> 〇
労働基準法第19条の規定により、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間とその後30日間は解雇することができません。(第19条の記事はこちら)使用者には、療養補償をする義務があるからです。
ただし、打切補償を行えば、以後は補償義務がなくなるため、解雇することも可能になります。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ64
H29.4.27 第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」です。

生理日に、腹痛などで就労が難しい女性は、休暇を請求することができます。
暦日単位だけでなく、半日単位や時間単位の請求も可能です。
 条文の確認です。空欄を埋めてください。
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第68条 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が< A >女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

(解答) A 著しく困難な
 過去問です。
過去問です。
<H20年出題>
労働基準法第68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、少なくとも月に1日は有給で休暇を与えなければならないとしている。

<解答> ×
有給にする義務はありません。
なお、生理期間などは人によって様々ですので、休暇の日数を限定することはできません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ63
H29.4.26 第67条 育児時間
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「育児時間」です。

生後1年未満の生児を育てる女性は、授乳等のための時間として、休憩時間以外に、1日2回少なくとも30分ずつの育児時間を請求することができます。
 条文の確認です。空欄を埋めてください。
条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第67条 育児時間)
① 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも< A >分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
② 使用者は、①の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

【解答】 A 30
 過去問です。
過去問です。
<H15年出題>
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

<解答> ×
育児時間を請求できるのは女性のみです。問題文では、「生児を育てる労働者」となっていますが、このような表現ですと男性も含まれてしまいます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ62
H29.4.25 第66条 妊産婦の労働時間等その2
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「妊産婦の労働時間等その2」です。
※ 「妊産婦の労働時間等その1」はコチラからどうぞ。

「妊産婦の労働時間等その2」では、妊産婦が、第41条該当者(管理監督者等)の場合をみていきます。
第41条に該当する労働者には、「労働時間」、「休憩」、「休日」に関するルールが適用されません。
第41条についてはこちらをどうぞ。
↓
では、41条に該当する労働者について、「妊産婦の労働時間等」のルールはどのようになるのでしょうか?
 過去問を解いてみましょう
過去問を解いてみましょう
①<H14年出題>
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この66条第2項の規定は、妊産婦であっても同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者に該当するものには適用されない。
②<H15年出題>
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。

<解答>
① 〇
第41条に該当する労働者には、労働時間・休日のルールは適用されません。ですので、第41条に該当する労働者は、「時間外や休日の労働をしない」という請求はできません。
② ×
第41条に該当する労働者でも「深夜業」のルールは適用されます。第41条に該当する妊産婦から請求があった場合は、深夜労働はさせられません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ61
H29.4.24 第66条 妊産婦の労働時間等その1
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「妊産婦の労働時間等その1」です。

妊産婦は、時間外や休日に労働しないこと等を請求することができます。
一律に時間外労働等に従事させることができない、のではなく、健康状態などは個人差があるため、妊産婦からの「請求があった」場合であることに注意してください。
 では条文の確認です。空欄を埋めてください。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第66条 妊産婦の労働時間等)
① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)及び第32条の5第1項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)の規定にかかわらず、法定労働時間を超えて労働させてはならない。
② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害等の事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(三六協定による場合)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、< A >をさせてはならない。

<解答>
A 深夜業
ポイント
① 変形労働時間制をとっている場合、1日又は1週間の法定労働時間を超える部分ができます。妊産婦は、1日又は1週間の法定労働時間を超える時間について、労働しないことを請求できます。(フレックスタイム制は、この規定の対象にはなりません。)
② 妊産婦は、時間外、休日に労働しないことを請求できます。
③ 妊産婦は、深夜労働をしないことを請求できます。
★ 制限がかかるのは、妊産婦からの「請求があった範囲内」です。
 過去問です。
過去問です。
<H13年出題>
使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。

<解答> ×
深夜業をさせることができないのは、「妊産婦から請求があった場合」です。(請求が無ければ深夜業も「可」です。)
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ60
H29.4.21 第65条 産前産後
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「産前産後」です。
 では条文の確認です。空欄を埋めてください。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第65条 産前産後)
① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、< A >週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後< B >週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、< C >が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

<解答>
A 14 B 8 C 妊娠中の女性
ポイント
①産前休業 → 産前休業は労働者からの請求が条件です。請求がなければ、休業させなくても構いません。
②産後休業 → 産後は、労働者からの請求があっても無くても関係なく、就業させることが禁止されています。ただし、産後6週間を経過し、「労働者が請求した場合」でその者について「医師が支障がないと認めた業務」であれば、就業させても差し支えない、とされています。
 過去問です。
過去問です。
①<H25年出題>
使用者は、妊娠100日目の女性が流産した場合については、労働基準法第65条に規定する産後休業を与える必要はない。
②<H19年出題>
使用者は、労働基準法第65条第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

<解答>
① ×
出産の範囲は、妊娠4か月以上(1か月28日で計算するので妊娠85日以上のこと)です。流産等でも妊娠4か月以上なら、産後休業の規定が適用されます。
② ×
軽易な業務への転換の規定は、「妊娠中の女性」だけに適用されます。産後1年を経過しない女性(産婦)には適用されません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ59
H29.4.20 第64条の3 危険有害業務の就業制限
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「危険有害業務の就業制限」です。
 では条文の確認です。空欄を埋めてください。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第64条の3 危険有害業務の就業制限)
① 使用者は、妊娠中の女性及び< A >を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、< B >に関して、準用することができる。
③ ①、②に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

<解答>
A 産後1年 B 妊産婦以外の女性
★ 妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務の範囲は、女性則第2条で1号から24号まで定められています。
1. 妊婦 → 24の業務すべてに就かせてはならない、と規定されています。
2. 産婦 → 就かせてはならない業務が3業務、申し出た場合就かせてはならない業務が19業務、就かせても差し支えない業務が2業務に分けられています。
3. 妊産婦以外の女性 → 24業務のうち、22業務は就業させることができますが、2業務については就かせてはならないと規定されています。
※ 3.について
具体的には、「重量物を取り扱う業務」、「鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」の2つの業務は妊産婦以外の女性も就業が禁止されています。
 過去問です。
過去問です。
①<H25年出題>
労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。
②<H15年出題>
使用者は、妊産婦以外の女性についても、妊産婦の就業が禁止される業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務として厚生労働省令で定めるものに就かせてはならない。

<解答>
① ×
産後6か月ではなく、産後1年を経過しない女性(産婦)です。
② 〇
「重量物取扱い業務」と「有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」は、全ての女性の就業が禁止されます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ58
H29.4.19 第64条の2 坑内業務の就業制限
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「坑内業務の就業制限」です。
★ 今日から「妊産婦等の保護規定」を勉強します。すべての「女性」を一般的に保護するというものではなく、「母性保護」の見地からの保護規定です。
 では条文の確認です。空欄を埋めてください。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第64条の2 坑内業務の就業制限)
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
1、 < A >の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た < B >を経過しない女性 → 坑内で行われるすべての業務
2、 1、に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 → 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

<解答>
A 妊娠中 B 産後1年
| ★坑内のすべての業務について就業させることが禁止されている |
① 妊娠中の女性 ② 産後1年を経過しない女性(②については本人が申し出た場合のみ) |
★人力による掘削の業務等に就業させることが禁止されている (坑内の管理・監督業務等には就業させることができる) |
| ①②以外の満18歳以上の女性 |
※ ちなみに、満18歳未満(男女問わず)の者は、年少者の規定により、坑内で労働させることが禁止されています。(第63条)
 過去問です。
過去問です。
<H20年出題>
使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。

<解答> ×
※ 満18歳以上の女性を3つにグループ分けして覚えましょう。
| ① | ② | ③ |
| 妊娠中の女性 | 産後1年を経過しない女性(産婦) | ①と②以外の女性 |
※ ↑ 上の表の①と②(②は坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合)以外の女性でも、男性と同じように坑内業務に就かせることはできません。人力による掘削の業務等に就業させることが禁止されています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ57
H29.4.18 第64条 帰郷旅費
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日のテーマは「帰郷旅費」。
★ 年少者が使用者から解雇され、親元に帰りたくても旅費がないため路頭に迷う。そんなことにならないよう、使用者は帰郷旅費を負担しなければならない、という規定です。
 では条文の確認です。空欄を埋めてください。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第64条 帰郷旅費)
< A >才に満たない者が解雇の日から< B >以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、< A >才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の< C >を受けたときは、この限りでない。

<解答>
A 満18 B 14日 C 認定
ポイント
★ 例外 ★
解雇の事由が満18歳に満たない者の責に帰すべき事由で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は、帰郷旅費を負担する必要はありません。
 過去問です。
過去問です。
<H19年出題>
使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18歳に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必ず必要な旅費を負担しなければならない。

<解答> ×
30日以内ではなく14日以内です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ56
H29.4.17 第61条 年少者の深夜業
4月14日に、平成29年度社会保険労務士試験の詳細が公示されました。
試験は、8月27日(日曜日)です。
受験勉強もこれからが本番です!

では、本日も「労働基準法を学ぶ」シリーズです。
本日のテーマは年少者の「深夜業」。
★ 「年少者は深夜に働かせてはいけない」というルールです。例外もありますが、まずは、原則だけをおさえましょう。
 では条文の確認です。空欄を埋めてください。※例外規定は省略しています。
では条文の確認です。空欄を埋めてください。※例外規定は省略しています。
(第61条 年少者の深夜業)
① 使用者は、満18才に満たない者を午後< A >時から午前< B >時までの間において使用してはならない。以下例外アリ(今回は省略)
② 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、①の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
③ 例外アリ(今回は省略)
④ 前3項の規定は、第33条第1項の規定(災害等の理由によって臨時の必要がある場合)によって労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第6号(農林)、第7号(畜産、養蚕、水産)若しくは第13号(保健衛生)に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
⑤ ①及び②の時刻は、行政官庁の許可を受けて使用する児童については、①の時刻は、午後< C >時及び午前< D >時とし、②の時刻は、午後< E >時及び午前< F >時とする。

<解答>
A 10 B 5 C 8 D 5 E 9 F 6
ポイント
★ 年少者の深夜業は原則禁止
<深夜の時間帯>
午後10時から午前5時まで (特例 午後11時から午前6時まで)
■児童の深夜の時間帯
午後8時から午前5時まで (特例 午後9時から午前6時)
※ 特例で午後9時まで就労が認められる児童は「演劇子役」(演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務)です。
<災害等や公務の場合>
★ 災害等の理由によって臨時の必要がある場合
年少者 → 時間外労働・休日労働、深夜労働が可能
★ 公務のため臨時の必要がある場合
年少者 → 時間外労働・休日労働は可能、深夜労働は不可
 過去問です。
過去問です。
<H23年出題>
満15歳に達した日以後の最初の3月31日までが終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合には、午後8時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合に地域又は期間を限って午後9時から午前6時までとする場合には午後9時から午前6時まで)の間は使用してはならない。

<解答> 〇
年少者の深夜業は禁止されています。児童の深夜時間は午後8時から午前5時まで(特例午後9時から午前6時まで)です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ55
H29.4.14 第60条 年少者の労働時間及び休日
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は年少者の「労働時間と休日」です。
★ 年少者を、一般の大人と同じルールで労働させるのは酷ですので、年少者を保護するためのルールが定められています。
 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第60条 労働時間及び休日)
① 第32条の2から第32条の5(1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)まで、第36条(三六協定による時間外・休日労働)及び第40条(法定労働時間・休憩時間の特例)の規定は、< A >については、これを適用しない。
② 行政官庁の許可を受けて使用する児童についての第32条(労働時間)の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは 「、< B >を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、< B >を通算して1日について< C >時間」とする。
※ 今回は第3項は省略します

<解答>
A 満18才に満たない者 B 修学時間 C 7
ポイント
児童の労働時間は、修学時間(授業時間のこと)を通算して、1週40時間、1日7時間です。1日に労働させ得る時間は、7時間から授業時間を引いた時間となります。
 過去問です。
過去問です。
<H13年出題>
36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。

<解答> ×
第60条で、「三六協定による時間外・休日労働」は年少者には適用しないと定められているので、36協定があったとしても、年少者には時間外・休日労働はさせられません。
一方、第33条は年少者にも適用されます。ですので、災害等による臨時の必要がある場合、公務のため臨時の必要がある場合は、年少者にも時間外・休日労働をさせることができます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ54
H29.4.13 第59条 未成年者の賃金請求権
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「未成年者の賃金請求権」です。
★ 未成年の子どもが働いて得た賃金を親が横取りしてはいけない、という規定です。
 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第59条 未成年者の賃金請求権)
未成年者は、< A >して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない

<解答>
A 独立
 過去問です。
過去問です。
<H20年出題>
賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。

<解答> ×
未成年者にも第24条の直接払いの原則が適用されます。親に支払うことは禁止されています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ53
H29.4.12 第58条 未成年者の労働契約
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「未成年者の労働契約」です。
★ 親が勝手に使用者と労働契約を結んで子どもに労働させることはできない、という規定です。
 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第58条 未成年者の労働契約)
① 親権者又は後見人は、< A >に代って労働契約を締結してはならない。
② 親権者若しくは後見人又は< B >は、労働契約が< A >に不利であると認める場合においては、< C >これを解除することができる。

<解答>
A 未成年者 B 行政官庁 C 将来に向って
※ 「行政官庁」→ 労働基準監督署長
※ 「将来に向かって」→ 遡及しないということ
ポイント
親権者若しくは後見人又は行政官庁→接続詞の読み方を確認しましょう。
「又は」と「若しくは」が使われているときは、「又は」で大きく分けて、その中で小さく分けるときに「並びに」を使います。
「又は」の前後で「親権者若しくは後見人」OR「行政官庁」と分けて、その中で小さく「親権者OR後見人」となります。
労働契約を解除できるのは、「親権者(父母)か後見人(親権者がいないときなど)」か、「行政官庁」です。
 過去問です。
過去問です。
<H11年出題>
労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができ、また満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの労働者について、当該労働者の通う学校の学校長も、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができる。

<解答> ×
学校長には、労働契約を解除する権限はありません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ52
H29.4.11 第57条 年少者の証明書
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「年少者の証明書」です。
★ 年少者は「満18歳未満」、児童は「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(義務教育が終わるまで)」の者のことです。
※児童は年少者に含まれます。念のため。
 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第57条 年少者の証明書)
① 使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
② 使用者は、行政官庁の許可を受けて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する< A >の証明書及び親権者又は後見人の< B >を事業場に備え付けなければならない。

<解答>
A 学校長 B 同意書
ポイント
「年少者」を使用する場合に事業場に備え付けるもの
・ 年齢を証明する戸籍証明書
「児童」の場合は、年齢を証明する戸籍証明書に加えて
・ 修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
・ 親権者又は後見人の同意書
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ51
H29.4.10 第56条 最低年齢
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「最低年齢」です。
 まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
まずは条文の確認です。空欄を埋めてください。
(第56条 最低年齢)
① 使用者は、児童が< A >まで、これを使用してはならない。
② ①の規定にかかわらず、別表第一第1号から第5号までに掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満< B >歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。< C >の事業については、満< B >歳に満たない児童についても、同様とする。

<解答>
A 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する B 13
C 映画の製作又は演劇
★簡単にまとめると
<原則>義務教育が終わるまでは労働者として使用できない。
<例外> 13歳以上の場合は非工業的業種、13歳未満の場合は映画の製作又は演劇の事業は使用できる。(ちなみに非工業的業種の中には、映画の製作又は演劇の事業も含まれます)
ただし、・児童の健康及び福祉に有害でない・労働が軽易・行政官庁の許可を受ける ・修学時間外に使用することが条件です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ50
H29.3.27 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その3
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」その3です。
その1はコチラ (農業・水産業)
その2はコチラ (管理監督者)
 前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」、その2では、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみました。
前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」、その2では、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみました。
今回は、「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」を勉強しましょう。
→ 労働密度が薄い業務に従事する労働者が対象です。ただ、監視断続的労働と言っても、危険なものもあれば緊張度の高い業務もあり、勤務態様はさまざまです。そのため、監視断続的労働については、「労働時間、休憩、休日」の適用除外については、行政官庁の許可がいることがポイントです。
 過去問です
過去問です
(平成20年出題)
労働基準法第41条第2号により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されているいわゆる管理監督者については、適用除外の要件として行政官庁の許可を得なければならない。

<解答> ×
管理監督者については、行政官庁の許可は不要です。
※ 行政官庁の許可が適用除外の要件になるのは、監視又は断続的労働に従事する者です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ49
H29.3.24 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その2
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」その2です。
その1はコチラ
 前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」をみましたので、今回は、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみていきます。
前回のその1では、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」をみましたので、今回は、「2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」をみていきます。
→ 第41条の「監督若しくは管理の地位にある者」とは?
・ 労働条件の決定その他労務管理について「経営者と一体的な立場」にあるもの。一般的には、部長、工場長等ですが、名称ではなく実態で判断すべきものとされています。
 過去問です
過去問です
①(平成18年出題)
労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
②(平成13年出題)
労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

<解答>
①(平成18年出題) ×
「休日」と「休暇」は別物であることに注意しましょう。第41条に該当する労働者には、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんが、年次有給休暇の規定は適用されます。
②(平成13年出題) ×
その1でも勉強しましたが、第41条に該当する者にも「深夜業」の規定は適用されますので、深夜業に対する割増賃金は支払う必要があります。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ48
H29.3.23 第41条 労働時間等に関する規定の適用除外その1
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「労働時間等に関する規定の適用除外」です。
 第41条では、「労働時間」、「休憩」、「休日」に関するルールが適用除外になる労働者が規定されています。
第41条では、「労働時間」、「休憩」、「休日」に関するルールが適用除外になる労働者が規定されています。
第41条に該当する労働者には、時間外労働・休日労働の割増賃金も適用されません。
 では、条文を確認しましょう。
では、条文を確認しましょう。
第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3. 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
 今日は、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」を勉強しましょう。
今日は、「1. 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者」を勉強しましょう。
* 農業・水産業の事業は天候に大きく左右されます。そのため法定労働時間や毎週1回の休日などを適用することが難しく、適用除外となっています。
* 別表第一第6号は「農林の事業」、第7号は「水産の事業」です。
* しかし、第41条では、「第6号(林業を除く。)」となっていて、林業は除かれている点に注意です。
* つまり、第41条に該当するのは、農業と水産業の事業に従事する労働者です。林業は41条には該当しません。
 過去問です。
過去問です。
<H16年出題>
農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。

<解答> ×
誤りが2個所あります。
1つ目の誤りは「農林漁業」の個所。林業が入っているので誤りです。林業に従事する労働者には、労働時間、休憩及び休日の規定が適用されます。
2つ目の誤りは深夜業の割増賃金の点。「労働時間」と「深夜業」は別ものです。第41条で除外される「労働時間」に深夜業は入っていません。
ですので、農業・水産業に従事する労働者でも、深夜労働した場合は、深夜の割増賃金の支払が必要です。
ポイント! 第41条に該当する労働者にも「深夜業」の規定は適用されます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ47
H29.3.22 第39条 年次有給休暇(比例付与)
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。
本日は「年次有給休暇(比例付与)」です。
★ 正社員と比べると、所定労働日数や所定労働時間が少ないパート労働者にも、年次有給休暇の権利は発生します。
ただし、付与日数は、所定労働日数に比例した日数となります。
 比例付与の対象になる労働者の要件を確認しましょう。
比例付与の対象になる労働者の要件を確認しましょう。
↓ 比例付与の対象になる労働者の要件です。空欄を埋めてください。
① 1週間の所定労働日数が< A >日以下
※ 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は、1年間の所定労働日数が< B >日以下
かつ
② 1週間の所定労働時間が< C >時間未満

<解答> A 4 B 216 C 30
注意するポイントです!
◆ 「未満」と「以下」を意識して
◆ ①かつ②の「かつ」に注意。①と②を両方満たす労働者が比例付与の対象
 ですので、週所定労働日数が「5日以上」又は週所定労働時間が「30時間以上」の場合は、比例付与ではなく通常の付与日数となります。
ですので、週所定労働日数が「5日以上」又は週所定労働時間が「30時間以上」の場合は、比例付与ではなく通常の付与日数となります。
 それでは過去問です。
それでは過去問です。
<H19年出題>
使用者は、その事業場に、同時に採用され、6カ月間継続勤務し、労働基準法第39条所定の要件を満たした週の所定労働時間20時間(勤務形態は1日4時間、週5日勤務)の労働者と週の所定労働時間30時間(勤務形態は1日10時間、週3日勤務)の労働者の二人の労働者がいる場合、両者には同じ日数の年次有給休暇を付与しなければならない。

<解答> 〇
付与日数はどちらも「10労働日」です。
前者は「週5日」勤務、後者は「週30時間(ちょうど)」なので、どちらも比例付与ではなく通常の付与日数となります。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ46
H29.3.21 第38条の4 企画業務型裁量労働制
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は「企画業務型裁量労働制」です。
★ 専門業務型裁量労働制よりも、導入手続きなどが複雑です。比べてみましょう。
↓
 導入手続
導入手続
「専門業務型裁量労働制」は、労使協定の締結で導入することができますが、同じ裁量労働制でも、「企画業務型」の場合は「労使委員会」の設置が必要です。
 定期報告
定期報告
決議が行われた日から起算して6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回(当分の間、6か月以内ごとに1回)、所轄労働基準監督署長へ定期報告が必要です。
(専門業務型裁量労働制には定期報告はありません)
★ 企画業務型裁量労働制に不可欠なのが「労使委員会」です。
労使委員会とは、第38条の4で「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」と定義されています。
→ 労使委員会は「労働者側委員」と「使用者側委員」で構成されます。労働者側委員が半数以上を占めていることが必要です。
★ 今日は、「労使委員会」の要件を確認しましょう。
第38条の4第2項(労使委員会の要件)
1. 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
→ 「労働者側委員」は、過半数組合か過半数代表者に、任期を定めて指名されていることが要件
2. 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。
3. 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
 過去問です。
過去問です。
<H22年出題>
労働基準法第38条の4第1項に定めるいわゆる労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の労働者の投票又は挙手によって選出されなければならない。

<解答> ×
要件は、過半数組合か過半数代表者に、任期を定めて指名されていることです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ45
H29.3.13 第38条の3 専門業務型裁量労働制
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は「専門業務型裁量労働制」です。
 導入に当たっては労使協定が必要(所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。)
導入に当たっては労使協定が必要(所轄労働基準監督署長への届け出が必要です。)
★ 労使協定で定めること
① 対象業務
② 労働時間として算定される時間(みなし労働時間)
③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等について、使用者が具体的な指示をしないこと
④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じたの健康及び福祉を確保するための措置の内容
⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置の内容
⑥ 有効期間の定め
⑦ ④と⑤についての労働者ごとの記録を労使協定の有効期間中及び満了後3年間保存すること
 ①の対象業務について
①の対象業務について
★ 対象業務とは「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」と定義されていて、19業務が定められています。

★ 簡単に言うとどんな制度?
仕事の進め方などは労働者の裁量に任せる。使用者は時間配分などについて具体的な指示はしない。労働時間は、労使協定で定めた労働時間で算定される。例えば、労使協定の②のみなし労働時間を9時間と定めたら、実際に何時間働いたか関係なく9時間で算定される。
働きすぎで健康を害すること等を防ぐために、健康福祉確保措置などが必要になる。
 過去問です。
過去問です。
<H12年出題>
専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。

<解答> ×
専門業務型裁量労働制は、就業規則に明記するだけでは導入できません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ44
H29.3.10 第38条の2 事業場外労働のみなし労働時間制
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「事業場外労働のみなし労働時間」です。
★ 出張や外回りのセールスなど、事業場外で労働する場合で労働時間の算定ができないときのルールを定めた規定です。
★ まずは条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
【第38条の2】
① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、< A >労働したものと< B >。
ただし、当該業務を遂行するためには通常< A >を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常< C >とされる時間労働したものと< B >。
② ①項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を①項ただし書の当該業務の遂行に通常< B >とされる時間とする。
③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

【解答】
A 所定労働時間 B みなす C 必要
※ 「みなす」とは → 実際の労働時間には関係なく、所定労働時間労働したことにする、という意味です。
ポイント!
事業場外労働のみなし労働時間制の対象になるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、労働時間を算定し難いときです。事業場外の業務でも、使用者が具体的に指揮監督している場合は労働時間の管理もできるので、みなし労働時間制は適用されません。
例えば
★ 直行直帰で1日中事業場外で労働した場合(所定労働時間7時間の場合)
(原則)
その日の労働時間は7時間(所定労働時間)で算定する
(通常所定労働時間を超えて労働することが必要となっている場合)
例えば、その事業場外労働が常態として8時間行われている場合は、8時間(当該業務の遂行に通常必要とされる時間)で算定する
(労使協定を締結した場合)
「通常必要とされる時間」を労使協定で締結した場合は、「労使協定で定めた時間」(=通常必要とされる時間)で算定する
 過去問です
過去問です
<H18年出題>
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。

<解答> 〇
条文そのままの問題です。
こういう長文の問題は、隅から隅まで読むのではなく、キーワードをチェックしてください。
「労働時間を算定しがたい」、「所定労働時間」、「通常必要」、「みなす」、「労使協定で定める」がキーワードです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ43
H29.3.7 第38条 時間計算
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「時間計算」です。
★ 例えば、午前中は大阪支店、午後からは神戸営業所で労働した場合、労働時間は通算されるのでしょうか?
これについては、労働基準法第38条に規定されています。
★第38条 時間計算
労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
↓
事業場が違っていても労働時間は通算します。
ですので、午前中の大阪支店の労働時間と午後からの神戸営業所の労働時間は通算されます。
 過去問です
過去問です
<H22年出題>
労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。

<解答> ×
同じA社の大阪支店と神戸営業所のように、同じ事業主で事業場が異なっていても労働時間は通算されます。
また、A社とB社のように、事業主が異なっていても労働時間は通算されます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ42
H29.3.3 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金③
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金③」です。
★「割増賃金①」の記事はコチラ →時間外、休日及び深夜の割増賃金①
「割増賃金②」の記事はコチラ →時間外、休日及び深夜の割増賃金②
今日も昨日に引き続き割増賃金の単価の計算のルールです。
■ 割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」に割増率をかけて計算します。通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算方法は以下のとおりです。
1. 時間によって定められた賃金 → 時給そのまま
2. 日によって定められた賃金 → 日給 ÷ 1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)
3. 週によって定められた賃金 → 週給 ÷ 週の所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異る場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)
4. 月によって定められた賃金 → 月給 ÷ 月の所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)
5. 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金 → 前各号に準じて算定した金額
6. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 → その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 ÷ 当該賃金算定期間における総労働時間数
 過去問です
過去問です
<H16年出題>
その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

<解答> ×
総所定労働時間数ではなく、「総労働時間数」(時間外労働の時間も含む)で除します。
★ちなみに
出来高払制その他の請負制の場合、「1.0」の部分は賃金総額に含まれているので、割増率は0.25(休日0.35)で計算します。(1.25(休日1.35)ではありません。)
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ41
H29.3.2 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金②
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金②」です。
★「割増賃金②」の記事はコチラをどうぞ→時間外、休日及び深夜の割増賃金①
今日は割増賃金の単価の計算のルールをおさえましょう。
■次の条文の空欄を埋めてください。
(第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)
⑤ 第1項(時間外、休日)及び第4項(深夜)の割増賃金の基礎となる賃金には、 < A >、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
※ その他厚生労働省令で定める賃金 → 別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、< B >を超える期間ごとに支払われる賃金

<解答>
A 家族手当 B 1か月
★ 家族手当や通勤手当も労働の対償ですので「賃金」です。
ただし、家族手当は「家族の数」に応じて支払われるもの、通勤手当は「通勤にかかる費用」に応じて支払われるもの。労働の対価ではあるけれど仕事内容には直接関係ありません。そのため、割増賃金の基礎には算入しなくてもよいことになっています。
★ 割増賃金の基礎に入れないものは、個人の事情に基づいて支給される(仕事内容に直接関係のない)「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」と、毎月支払われるものではない「臨時に支払われる賃金」、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば賞与など)」です。
 過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ。
<① H23年出題>
労働基準法第37条第に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

<解答> ×
家族数に関係なく一律で支給されている場合は、「家族手当」という名目であっても割増賃金の算定基礎賃金に含めなければなりません。
なぜなら、「家族数」に関係なく(=個人の事情に関係なく)使用者が額を決めているからです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ40
H29.2.27 第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金①
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「割増賃金①」です。
1週40時間(特例44時間)、1日8時間の労働時間と原則毎週1回の休日は、労働基準法の最低ラインですので、時間外労働や休日労働をさせた場合は、使用者に割増賃金の支払いが義務付けられています。
また、深夜労働についても割増賃金の支払が必要です。本来は寝る時間帯に労働する労働者への補償の意味があります。
■それでは、次の条文の空欄を埋めてください。
(第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金)
① 使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一か月について< A >時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
※政令で定める率 → 第33条又は第36条第1項の規定により延長した労働時間の労働については< B >とし、これらの規定により労働させた休日の労働については< C >とする。
④ 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の< D >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

<解答>
A 60 B 2割5分 C 3割5分 D 2割5分
※ 60時間を超える時間外労働の割増率は、中小事業主には当分の間、適用が猶予されています。
 時間外労働とは?
時間外労働とは?
午前9時始業・午後5時終業・休憩時間が1時間で、所定労働時間が7時間の会社で時間外労働をさせた場合の割増賃金率を確認しましょう。
もし、午後11時まで残業した場合、割増賃金の率はどうなるでしょう?(1か月60時間は超えていないものとします。)
午後5時~ 午後6時 | 1時間当たりの賃金×1.00×1時間 ※ 7時間の所定労働時間と足しても法定労働時間内(1日8時間以内)のため、割増賃金は不要 |
午後6時~ 午後10時 | 1時間当たりの賃金×1.25×4時間 ※ 時間外労働 |
午後10時~ 午後11時 | 1時間当たりの賃金×1.50×1時間 ※ 時間外労働(1.25)+深夜割増(0.25) |
 過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ。
<H13年出題>※月60時間を超える時間外労働ではないものとします。
変形労働時間制を採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、その午後5時から6時まで労働した時間については、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間は正午から1時間である。

<解答> ○
1時間始業時刻がずれたとしても、1日の実労働時間が8時間以内なので、割増賃金は不要です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ39
H29.2.24 第36条 時間外及び休日の労働②
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「三六協定②」です。
★ 三六協定①はコチラの記事をどうぞ
★ 第36条の手続き(三六協定の締結+届け出)をとることにより、法定労働時間を超える労働(時間外労働)や法定休日に労働させること(休日労働)が可能になります。
といいましても、無制限に時間外労働をさせてもいい、というわけではなく、厚生労働大臣が労働時間の延長の限度等の基準を定めることができることになっています。
その「基準」について、労使協定の当事者は協定の内容が「基準に適合したものとなるようにしなければならない」、行政官庁は「必要な助言、指導を行うことができる」と規定されています。
その部分の条文の空欄を埋めてください。
(第36条 時間外及び休日の労働)
② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、第1項の協定(三六協定)で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る< A >その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して < B >を定めることができる。
③ 第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は< C >は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が②の< B >に適合したものとなるようにしなければならない。
④ 行政官庁は、②の< B >に関し、第1項の協定(三六協定)をする使用者及び労働組合又は< C >に対し、必要な助言及び< D >を行うことができる。

<解答>
A 割増賃金の率 B 基準 C 労働者の過半数を代表する者
D 指導
 三六協定の延長時間等のポイント!
三六協定の延長時間等のポイント!
| 厚生労働大臣 | 基準を定める |
| 使用者と労働組合(又は労働者の過半数代表者) | 基準に適合したものとなるようにする |
| 行政官庁(所轄労働基準監督署長) | 助言及び指導ができる |
 過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ。
<H11年出題>
時間外・休日労働の協定を締結する使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、時間外・休日労働の協定で定める労働時間の延長の限度等について労働基準法第36条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた基準に適合したものとなるようにしなければならない。また、この基準に適合しない協定については、所轄労働基準監督署長は適合したものに変更することができる。

<解答> ×
所轄労働基準監督署長ができるのは「助言及び指導」です。適合したものに変更することはできません。
★ 例えば、延長時間の限度として、1か月45時間、1年間360時間(1年単位の変形労働時間制(対象期間3カ月超)の場合は、1か月42時間、1年間320時間)という基準が定められています。延長時間の限度としては、↑この数字をおさえておけばいいと思います。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ38
H29.2.23 第36条 時間外及び休日の労働①
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。本日は「三六協定①」です。
★ 法定労働時間、法定休日の例外規定として、第33条と第36条があります。
第33条についてはコチラの記事をどうぞ
→H29.2.21 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
★ 第33条では災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等のルールが定められていますが、一般的な時間外労働・休日労働については、第36条で手続きが定められています。具体的には、労使協定の締結と行政官庁へ届け出ですが、第36条にちなんで、この労使協定は「三六協定」とよばれています。
★ では法第36条の空欄を埋めてみましょう。
(第36条 時間外及び休日の労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に< A >場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は前条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
(施行規則第16条)
① 使用者は、法第36条第1項の協定(三六協定)をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに< B >及び < B >を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。
② ①の協定(労働協約による場合を除く。)には、< C >の定めをするものとする。

<解答>
A 届け出た B 1日 C 有効期間
 ポイント!
ポイント!
三六協定には、時間外労働時間の枠を協定しなければなりません。
具体的には、「1日及び1日を超える一定の期間」の時間外労働の上限を協定します。 → 「1日を超える一定期間」は、「1日を超え3カ月以内の期間及び1年間」と決められています。
ということで三六協定には
① 1日の時間外労働の上限
② 1日を超え3カ月以内の期間の時間外労働の上限
③ 1年間の時間外労働の上限
を協定することになります。
例えば、「延長することができる時間 → 1日5時間、1か月40時間、1年300時間」というように協定します。
この場合、時間外労働は協定した時間の枠内ならOKですが、それを超える時間外労働は違法となります。
 過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ。
<H24年出題>
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責を免れない。

<解答> ○
→ 「単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責を免れない。」がポイントです。
時間外労働・休日労働は、労使協定を届け出ることによって適法となります。協定を締結しただけではだめ。届出をしないと、時間外労働・休日労働をさせることはできません。
★ちなみに・・・
例えば、1年単位の変形労働時間制を採用するには労使協定を締結し、行政官庁へ届け出る義務があります。ただし、三六協定とは異なり、届け出をしなかった場合でも免罰効果は発生します。
 労使協定届出のポイント
労使協定届出のポイント
| ■ 届出をしないと免罰効果が発生しない(三六協定はこれに当たる) |
■ 届出義務がある(罰則もある)が、届出は免罰効果発生の要件ではない (例/1年単位の変形労働時間制はこれに当たる) |
■ そもそも届出義務がない (例/フレックスタイム制がこれに当たる) |
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ37
H29.2.21 第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
「労働基準法を学ぶ」シリーズです。
★ 1週40時間(特例44時間)以内、1日8時間以内の労働時間を守り、また、毎週1日(又は4週4日)の休日を必ず与えることが、労働基準法上の使用者の義務です。
そうは言っても、現実には、どうしても残業や休日労働が避けられないことがあります。
そこで、労働基準法には、時間外労働・休日労働ができる例外規定が設けられているのです。
★ 労働基準法第33条では、例外として、「災害等の事由で臨時の必要がある場合」、「公務のため臨時の必要がある場合」に、時間外労働、休日労働をさせることができる、と規定されています。今日は、この規定を勉強します。
(なお、ここで使っている「時間外労働」とは「法定労働時間を超える労働」のこと、「休日労働」は「法定休日に労働」させること、という意味です。)
★ ちなみに、時間外労働、休日労働については第36条の「三六協定」によることが一般的ですが、三六協定についてはまた別の日に書きますね。
 では法第33条の空欄を埋めてみましょう。
では法第33条の空欄を埋めてみましょう。
(第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
① 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< B >なければならない。
② ①項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ < C >のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

<解答>
A 許可 B 事後に遅滞なく届け出 C 公務
 ポイント!
ポイント!
【法定労働時間を延長すること、休日労働させることが適法になるのは次の3つ】
| 第33条① | 災害その他避けることのできない事由で臨時の必要がある場合 (原則として事前に行政官庁の許可が必要) |
| 第33条③ | 公務のために臨時の必要がある場合 |
| 第36条 | 労使協定を締結し行政官庁に届け出た場合(三六協定) |
 過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ。
<H11年出題>
使用者は、労使協定の締結がなくとも、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けることにより、法定労働時間を超えて労働させることができるが、事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合、当該年度の終了時までに行政官庁に報告すれば足りる。

<解答> ×
→ 事態急迫のために許可を受ける時間的余裕がない場合は、事後に遅滞なく届け出なければなりません。「 当該年度の終了時までに行政官庁に報告」は誤りです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ36
H29.2.17 第35条 休日
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「休日」です。
★ 1年365日のうち、労働義務のある日が「労働日」、それ以外は「休日」です。「休日」は労働義務のない日です。
★ 労働基準法で義務付けられた休日を「法定休日」といいます。
★ では法第35条の空欄を埋めてみましょう。
① 使用者は、労働者に対して、< A >少くとも1回の休日を与えなければならない。
② ①の規定は、< B >を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

<解答>
A 毎週 B 4週間
 ポイント!
ポイント!
「法定休日」の与え方
<原則> 毎週少なくとも1回
<例外> 4週4日(変形休日制)
 過去問をどうぞ。
過去問をどうぞ。
<H23年出題>
使用者が、労働者に対して、4週間を通じ4日以上の休日を与え、その4週間の起算日を就業規則その他これに準ずるものにおいて明らかにしているときには、当該労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与えなくても、労働基準法第35条違反とはならない。

<解答> ○
→ 毎週1回の休日を与えることが原則ですが、例外で4週4日変形休日制も認められています。
変形休日制の場合、就業規則その他これに準ずるもので4週間の起算日を明らかにする必要があります。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ35
H29.2.16 第34条 休憩
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「休憩」です。
★ 途切れなく労働し続けると、誰しも疲労がたまり能率が落ちてしまいます。労働基準法では、労働時間の途中に休憩時間を与える義務を使用者に課しています。
★ 次の空欄を埋めてみましょう。
① 使用者は、労働時間が< A >を超える場合においては少くとも45分、 < B >を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の< C >に与えなければならない。
② ①の休憩時間は、< D >に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、①の休憩時間を< E >に利用させなければならない。

<解答>
A 6時間 B 8時間 C 途中 D 一斉 E 自由
 ポイント!
ポイント!
休憩の与え方の3原則は「途中に」「一斉に」「自由に」です。
 テーマ別の過去問をどうぞ。
テーマ別の過去問をどうぞ。
★テーマ「一斉に」
①<H23年出題>
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、使用者は、その定めに基づき、労働基準法第34条第1項に定める休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
★テーマ「自由に」
②<H26年出題>
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。

<解答>
★テーマ「一斉に」①<H23年出題> ○
→ 労使協定を締結すれば、一斉付与の原則の適用が除外されます。
ちなみに、法別表第一第4号(運輸交通業)、第8号(商業)、第9号(金融・広告業)、第10号(映画・演劇業)、第11号(通信業)、第13号(保健衛生業)、第14号(接客娯楽業)、官公署の事業は、一斉付与の例外で、休憩を一斉に与えなくてもよいことになっています。
★テーマ「自由に」②<H26年出題> ○
→ 休憩時間とは、労働から100%解放される時間。自由に使える時間のことです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ34
H29.2.15 第32条の5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」です。
★ 1週間単位の非定型的変形労働時間制のポイントは、対象になる「事業の種類、規模」が限定されていることです。
★ ポイントを意識して、次の空欄を埋めてみましょう。
① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業(< A >、旅館、料理店及び < B >の事業)であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数< C >未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について< D >時間まで労働させることができる。
② 使用者は、①の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
事前の通知の方法 → 1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該 < E >する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の< F >までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。

<解答>
A 小売業 B 飲食店 C 30 D 10 E 1週間の開始 F 前日
少ない人数で業務の繁閑を乗り切るための制度です。就業規則で労働時間を特定することが難しいため、繁閑に応じて非定型的に労働時間を設定できます。当該1週間の開始する前(日曜日から1週間が始まる場合は前週の土曜日まで)に、1週間の各日の労働時間を書面で通知します。
 過去問です
過去問です
<H22年出題>
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

<解答> ×
1日の労働時間の上限は10時間と定められています。
1週間の各日の労働時間が特定されるのが前週末になるため、上限が設定されています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ33
H29.2.14 第32条の4 1年単位の変形労働時間制③
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制③」です。
1年単位の変形労働時間制シリーズも本日で終わります。
★ ①と②はこちらです → 「1年単位の変形労働時間制①」「1年単位の変形労働時間制②」
★ 1年単位の変形労働時間制は、対象期間の「労働日数の限度」「1日と1週間の労働時間の限度」、「連続して労働させる日数の限度」が決められているのがポイントです。1か月単位の変形労働時間制には、そのような決まりはありません。
1か月単位の変形労働時間制よりも1年単位の変形労働時間制の方が、労働者への負担が重いため、規制が厳しいと考えてください。
★ では、次の空欄を埋めてみましょう。(例外等は省略しています)
■ 労働日数の限度は、対象期間が< A >を超える場合は対象期間について1年当たり< B >とする。
■ 1日の労働時間の限度は< C >時間とし、1週間の労働時間の限度は < D >時間とする。
■ 対象期間における連続して労働させる日数の限度は< E >日とし、特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は< F >の休日が確保できる日数とする。

<解答>
A 3か月 B 280 C 10 D 52 E 6 F 1週間に1日
~~ポイント~~
1年単位の変形労働時間制は、原則は最低6日に1回は休日を入れなければなりません。ただし、特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)は、1週間に1日の休日でOKです。(1週間に1日でいいということは、労働日が12日連続することも可能だということ)
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ32
H29.2.13 第32条の4 1年単位の変形労働時間制②
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制②」です。
★ ①はこちらです → 「1年単位の変形労働時間制①」
★ 1年単位の変形労働時間制を導入する際の条件として、労使協定で対象期間中の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を定める必要があります。
(カレンダーで労働日と休日が特定できて、労働日ごとの労働時間が特定できるということ)
★ しかし、対象期間全体の労働日と労働日ごとの労働時間の特定が難しい場合は以下のような例外も認められています。
→ <対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合>
| 最初の期間 | 「労働日」と「労働日ごとの労働時間」 |
| 最初の期間を除く各期間 | 「労働日数」と「総労働時間」 |
例えば、対象期間が1年で、その1年を1か月ごとに区切った場合、最初の1か月だけは「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定する必要がありますが、2か月目以降は各1か月間の「労働日数」と「総労働時間」だけ決めておけばよい、というものです。
 それでは、最初の期間以外の期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」は、「いつまでに」特定すればよいのでしょうか?またその際の「手続き」はどうなっているのでしょうか?
それでは、最初の期間以外の期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」は、「いつまでに」特定すればよいのでしょうか?またその際の「手続き」はどうなっているのでしょうか?
この点については、第32条の4第2項に規定されています。以下の条文の空欄を埋めてみましょう。
<第32条の4第2項>
使用者は、労使協定により対象期間を1か月以上ごとの期間ごとに区分することとしたときは、当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも< A >前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の < B >を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

<解答>
A 30 B 同意
ポイント!
<最初の期間以外の各期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」の特定について>
・ いつまでに特定する?
→ 各期間の初日の少なくとも30日前まで
・ 手続きは?
→ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得る
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ31
H29.2.10 第32条の4 1年単位の変形労働時間制①
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1年単位の変形労働時間制①」です。
まずは、第32条の4の条文の空欄を埋めてください。
【第32条の4 (1年単位の変形労働時間制)】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が< A >時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が< A >時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限るものとする。)
3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。)
4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5 有効期間の定め

<解答>
A 40
→ 1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制は、期間を平均して1週間当たり40時間(特例の場合は44時間)になればOKという制度でしたが、1年単位の変形労働時間制は、44時間の特例は適用されませんので、平均して1週間当たり40時間になることが条件です。
 それでは過去問をどうぞ。
それでは過去問をどうぞ。
■■平成17年出題
使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができる。

<解答>
■■ ×
1年単位の変形労働時間制の場合は、対象期間を平均して1週40時間以内であることが条件です。(44時間は不可)
変形労働時間制で1週44時間の特例が適用されるのは、1か月単位の変形労働時間制とフレックスタイム制の2つです。
<所定労働時間の総枠の計算方法>
| 1か月単位の変形労働時間制 | その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7 ★週法定労働時間 → 原則40時間(特例措置対象事業場は44時間) |
| フレックスタイム制 | その事業場の週法定労働時間×清算期間の暦日数÷7 ★週法定労働時間 → 原則40時間(特例措置対象事業場は44時間) |
| 1年単位の変形労働時間制 | 40時間×対象期間の暦日数÷7 ★44時間の特例は適用されません |
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ30
H29.2.7 第32条の3 フレックスタイム制
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「フレックスタイム制」です。
まずは、第32条の3の条文の空欄を埋めてください。
【第32条の3 (フレックスタイム制)】
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る< A >をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間)超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月以内の期間に限るものとする。)
3 清算期間における< B >
4 標準となる< C >
5 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻(コアタイム)
6 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻(フレキシブルタイム)

<解答>
A 始業及び終業の時刻
→ 接続詞の「及び」がポイント。フレックスタイム制は始業時刻と終業時刻の両方を労働者が決める制度です。
終業時刻は労働者が決められるが始業時刻は固定されているというパターンではフレックスタイム制とは言えません。
B 総労働時間
→ 総労働時間は、「その事業場の週法定労働時間×清算期間の暦日数÷7」以内になるように定めます。1か月単位の変形労働時間制と同じ計算式です。
ちなみに、「その事業場の週法定労働時間」とは、原則40時間・特例措置対象事業場は44時間です。
C 1日の労働時間
→ 年次有給休暇を取得したときの計算に使います。
 それでは過去問をどうぞ。
それでは過去問をどうぞ。
■■平成13年出題
フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。

<解答>
■■ ×
フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)とコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)の設定は強制ではなく任意です。
条文の「労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には」、「労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には」を見て下さい。下線部の「場合には」がポイントです。コアタイム、フレキシブルタイムは設けなくても構いません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ29
H29.1.27 第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「1か月単位の変形労働時間制」です。
まずは、第32条の2の条文の空欄を埋めてください。
【第32条の2 (1か月単位の変形労働時間制)】
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は< A >により、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(40時間(特例措置対象事業場は44時間))又は特定された日において同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

<解答>
A 就業規則その他これに準ずるもの
 1か月単位の変形労働時間制とは?
1か月単位の変形労働時間制とは?
★ 1か月以内の一定の期間(例えば、2週間、4週間、1か月など)を設定して、その期間を平均して1週間当たり40時間(特例の場合は44時間)になればOK。
★ それによって、1週の労働時間が40時間(特例の場合は44時間)を超えることや、1日の労働時間が8時間を超えることが可能になります。
★ ただし、各日、各週の労働時間を特定しておくことが条件です。
 それでは過去問をどうぞ。
それでは過去問をどうぞ。
■■平成19年出題
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠は、次の計算式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

<解答>
■■ ○
例えば、変形期間を1か月で設定した場合、31日の月の所定労働時間の総枠は、
40時間 × 31日 ÷ 7 ≒ 177.1時間となります。
1か月の所定労働時間の総枠が177.1時間以内であれば、平均すると1週間当たりの労働時間は40時間以内となります。
※ 特例の事業場の場合は、「40時間」でなく「44時間」で計算します。
※ 計算式の「暦日数」に注意してください。「労働日数」ではありません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ28
H29.1.23 第32条 労働時間
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、法定労働時間です。
まずは、第32条と則第25条の2の条文の空欄を埋めてください。
【第32条 (労働時間)】
① 使用者は、労働者に、< A >を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、< A >を除き1日について < B >時間を超えて、労働させてはならない。
【則第25条の2 (労働時間の特例)】
使用者は、法別表第一第8号、第10号(< C >の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時< D >人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について< E >時間、1日について < B >時間まで労働させることができる。
・ 第8号 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
・ 第10号 映画・演劇業(映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業)
・ 第13号 保健衛生業(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)
・ 第14条 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)

<解答>
A 休憩時間 B 8 C 映画の製作 D 10 E 44
 法定労働時間
法定労働時間
労働基準法で定められた労働時間のことを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間は、1週40時間(特例は44時間)、1日8時間です。
★ 「労働時間」は拘束時間から休憩時間を除いた時間です。例えば、始業8時、終業17時、休憩時間12時~13時の場合、労働時間は、拘束時間(9時間)から休憩時間(1時間)を引いた8時間となります。
 それでは過去問をどうぞ。
それでは過去問をどうぞ。
■■問題① 平成20年出題
1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。
■■問題② 平成18年出題
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

<解答>
■■問題① 平成20年出題 ×
→ 労働基準法に反しません。
1日6時間×週6日=1週36時間。1週40時間以内・1日8時間以内で法定労働時間内に収まっています。
■■問題② 平成18年出題 ○
→ 特例で1週44時間まで認められます。
ちなみに、「物品の販売の事業」は、法別表第一第8号(商業)に該当します。
★法別表第一第8号 商業(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ27
H29.1.19 「労働協約」と「労使協定」
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、「労働協約」と「労使協定」です。
★労使協定の場合、労働者側の協定当事者は次のように「過半数組合」か「過半数代表者」となります。
① 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合
② ①のような労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
→ 過半数組合があればその労働組合と協定し、過半数組合がなければ、過半数代表者と協定することになるので、労働組合がない事業場でも労使協定を結ぶことが可能です。
★労働協約は、「労働組合法」で、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。」と規定されています。
→ 「労働協約」は、労働組合だけが対象です。「労働者の過半数を代表する者との協定」は労働協約にはなりません。

 次の二つの過去問を比べてみてください。
次の二つの過去問を比べてみてください。
■■問題① 平成25年出題
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。
■■問題② 平成12年出題
事業場の過半数の労働者を組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。

<解答>
■■問題① 平成25年出題 ○
→ 「労使協定」の場合
労働組合が労使協定を締結する場合、事業場のすべての労働者の代表という立場となるため、その組合の組合員でない他の労働者にも効力が及ぶことになります。
■■問題② 平成12年出題 ○
→ 「労働協約」の場合(現物給与は労使協定ではなく「労働協約」によることが条件でしたよね)
現物給与で支払うことができるのは、労働協約の適用を受ける労働者に限定されます。
※労働協約の適用範囲は、原則としてその労働組合の組合員のみです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ26
H29.1.18 第28条 最低賃金
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第28条・最低賃金です。
労働基準法第28条の条文の空欄を埋めてください。
<法第28条>
賃金の最低基準に関しては、< A >の定めるところによる。

【解答】
A 最低賃金法
 1時間当たりの賃金の最低ラインは、「最低賃金法」の定めるところによって決定されます。
1時間当たりの賃金の最低ラインは、「最低賃金法」の定めるところによって決定されます。
最低賃金法については、労働の一般常識で勉強します。
★最低賃金についてはこちらの記事をどうぞ。
↓
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ25
H29.1.17 第27条 出来高払制の保障給
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第27条・出来高払制の保障給です。
まずは、労働基準法第27条の条文の空欄を埋めてください。
<法第27条>
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、< A >に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

【解答】
A 労働時間
 出来高制(歩合制)をとる場合、出来高がゼロなら賃金もゼロというわけにはいきません。仮に出来高があがらなくても就業した以上は、その時間分の賃金を払わなければならない、という規定です。
出来高制(歩合制)をとる場合、出来高がゼロなら賃金もゼロというわけにはいきません。仮に出来高があがらなくても就業した以上は、その時間分の賃金を払わなければならない、という規定です。
では、過去問を解いてみましょう。
【H26年出題】
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用する労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払いを保障しようとすることにある。

<解答> ×
出来高や成果に応じた賃金ではなく、「労働時間」に応じた賃金を保障することが第27条の趣旨です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ24
H29.1.16 第26条 休業手当
「労働基準法を学ぶ」シリーズ。本日は、第26条・休業手当です。
まずは、労働基準法第26条の条文の空欄を埋めてください。
<法第26条>
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の< A >以上の手当を支払わなければならない。

【解答】
A 100分の60
 使用者の責に帰すべき事由で労働時間が短縮された日の休業手当
使用者の責に帰すべき事由で労働時間が短縮された日の休業手当
★ 現実に就労した時間に対して支払われた賃金 < 平均賃金の100分の60
↓
その差額を支払わなければならない
| ← ← ← ← ← ← ← ←平 均 賃 金→ → → → → → → → | ||
| 100分の60 | ||
| 就労した時間分の賃金 | 休業手当 | |
では、過去問を解いてみましょう。
【H27年出題】
<労働条件>
・ 所定労働時間 1日8時間
・ 賃金 15,000円
・ 計算された平均賃金 10,000円
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。

<解答> ○
現実に就労した時間に対して支払われた賃金の7,500円が、平均賃金(10,000円)の100分の60以上あるため、休業手当を加える必要はありません。
労災保険「休業(補償)給付」との違いはこちらから ↓
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ23
H29.1.11 第25条 非常時払い
「労働基準法を学ぶ」シリーズ続いています。
本日は、第25条・非常時払です。
まずは、労働基準法第25条の条文の空欄を埋めてください。
<法第25条>
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、< A >に対する賃金を支払わなければならない。

【解答】
A 既往の労働
 非常時払を請求できる事由
非常時払を請求できる事由
| 労働者本人 | 出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
| 労働者の収入によって生計を維持する者 |
★ 労働者本人の事由だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者も対象です。
 「既往の労働」とは?
「既往の労働」とは?
既に働いた分ということ。
(未だ労働していない分は入りません)
では、過去問を解いてみましょう。
【H26年出題】
労働基準法第24条第2項に従って賃金の支払期日が定められている場合、労働者が疾病等非常の場合の費用に充てるため、既に提供した労働に対する賃金を請求する場合であっても、使用者は、支払期日前には、当該賃金を支払う義務を負わない。

<解答>×
疾病等非常の場合は、支払期日前でも既に労働を提供した分の賃金を請求することができます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ22
H29.1.10 第24条 賃金の支払
本日も引き続き、「労働基準法を学ぶ」シリーズです。
本日は、第24条・賃金支払5原則です。
まずは、労働基準法第24条の条文の空欄を埋めてください。
<法第24条>
賃金は、< A >で、< B >労働者に、その< C >を支払わなければならない。ただし、法令若しくは< D >に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、< A >以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との< E >がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、< F >1回以上、< G >を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

【解答】
A 通貨 B 直接 C 全額 D 労働協約 E 書面による協定
F 毎月 G 一定の期日
 「例外」をおさえるのがポイント!
「例外」をおさえるのがポイント!
「賃金」の支払いは、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上払い、⑤一定期日払いの5つの原則を守って支払わなければなりません。
ただし、例外も認められています。
| 通貨払いの例外 | ・ 法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合 ・ 厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合 |
全額払いの例外 (一部控除が認められる) | ・ 法令に別段の定めがある場合 ・ 労使協定がある場合 |
毎月1回以上払い、一定期日払いの例外
| ・ 臨時に支払われる賃金 ・ 賞与 ・ その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金 |
それでは、第24条の最大のポイントを過去問を使って3つ覚えましょう。
【① H20年出題】
使用者は、賃金を、銀行に対する労働者の預金への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
【② H20年出題】
使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
【③ H18年出題】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。

<解答>
【① H20年出題】 ○
【② H20年出題】 ×
通貨払いの例外は労使協定では認められません。
【③ H18年出題】 ×
全額払いの例外が認められるのは、労働協約ではなく「労使協定がある場合」です。
★ポイントはこの3つ★
| 例 外 | 手続き |
| 口座振込み | 労働者の同意 |
| 通貨以外のもので支払う | 労働協約 |
| 賃金の一部控除 | 労使協定 |
「労働協約」と「労使協定」を混同しないよう注意しましょう。
★ 近日中に「労働協約」と「労使協定」の違いをアップしますね。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ21
H29.1.6 第23条 金品の返還
続きますが、本日も「労働基準法を学ぶ」シリーズです。
まず、労働基準法第23条について、空欄を埋めてください。
<法第23条>
① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、< A >の請求があつた場合においては、< B >に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
② ①の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、< C >部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

【解答】
A 権利者 B 7日以内 C 異議のない
 では、過去に出題された問題を解いてみましょう。
では、過去に出題された問題を解いてみましょう。
【平成12年出題】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは退職手当についても同様である。

【解答】 ×
★ 賃金は、使用者が定めた賃金支払日に支払うのが原則ですが、第23条はその特例です。労働者の退職又は死亡の場合、権利者から請求があれば使用者は7日以内に支払わなければならないことになっています。
★ ただし、「退職手当」は制度の有無などについては使用者の自由ですので、この特例は適用されません。あらかじめ決められた期日が来るまでは支払わなくてもよいという扱いになっています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ20
H29.1.5 第22条 退職時等の証明
本日は、「労働基準法を学ぶ20」です。
まず、労働基準法第22条について、次の空欄を埋めてください。
<法第22条>
① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が< A >の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
② 労働者が、第20条第1項の< A >の< B >がされた日から退職の日までの間において、当該< A >の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、< A >の< B >がされた日以後に労働者が当該< A >以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
③ 前2項の証明書には、< C >事項を記入してはならない。
④ 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、< D >ことを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは< E >に関する通信をし、又は①及び②の証明書に< F >を記入してはならない。

【解答】
A 解雇 B 予告 C 労働者の請求しない
D 労働者の就業を妨げる E 労働組合運動 F 秘密の記号
 第22条の証明書は「2種類」あります
第22条の証明書は「2種類」あります
★第1項の証明書「退職証明書」
・ 請求できるのは → 退職した労働者
・ 証明事項は次の5項目
① 使用期間 |
| ② 業務の種類 |
| ③ その事業における地位 |
| ④ 賃金 |
| ⑤ 退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む) |
★第2項の証明書「解雇理由証明書」
・ 請求できるのは → 解雇の予告を受けた労働者
解雇予告された日から退職(解雇)日までの間
・ 証明事項は → 「解雇の理由」
 よくでるポイント!
よくでるポイント!
では、過去に出題された問題を解いてみましょう。
【① 平成11年出題】
労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付する必要があるが、その証明書には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない。
【② 平成16年出題】
労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。

【解答】
【① 平成11年出題】 ×
証明書に記入できるのは、「労働者が請求した事項」のみです。
第3項で「 前2項の証明書には、労働者の請求しない 事項を記入してはならない。」と規定されていますよね。
例えば、労働者が「解雇の事実のみ」についての証明書を請求してきた場合は、記入できるのは「解雇の事実」のみです。使用者は請求されていない「解雇の理由」を勝手に記入することはできません。(この部分は平成22年に出題されています。)
【② 平成16年出題】 ○
第2項の「解雇理由証明書」を請求できるのは、解雇の予告がされた日から退職の日までの間=解雇予告期間中です。
即時解雇の場合は、予告期間がないので「解雇理由証明書」の請求はできません。
即時解雇の場合や、退職後に「解雇の理由」について証明を請求する場合は、「第1項(退職証明書)」の規定をつかいます。5つの項目の中の「解雇の理由」についての証明を請求することになります。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ19
H29.1.4 第21条 解雇の予告除外
今年もよろしくお願いします!
新年第1段は、「労働基準法を学ぶ19」です。
労働基準法第21条について、次の空欄を埋めてください。
<法第21条>
前条の規定(解雇の予告)は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が< A >を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が< B >を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が< C >を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 < D >以内の期間を定めて使用される者
三 < E >に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

【解答】
A 1箇月 B 所定の期間 C 14日 D 2箇月 E 季節的業務
 ここから下は去年の9月22日の記事からです。(少し変えている部分もあります。)
ここから下は去年の9月22日の記事からです。(少し変えている部分もあります。)
労働者を解雇するには、原則として解雇の予告が必要です。
ただし、契約期間が短い労働者や試用期間中の労働者は、解雇予告の規定が除外になることがあります。
★解雇予告の規定から除外されるのは次の4つのどれかに該当する労働者です。
<労働基準法第21条>
① 日日雇い入れられる者
② 2箇月以内の期間を定めて使用される者
③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④ 試の使用期間中の者
ただし、この4つに該当しても、例外的に解雇予告が必要になる場合もあります。
試験対策としては、例外を覚えることがポイントです。
では、過去問を解いてみましょう。
① 平成13年出題
日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
② 平成15年出題
使用者が、2か月の期間を定めて雇入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
③ 平成19年出題
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月を経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
④ 平成23年出題
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。

<解答>
① 平成13年出題 ×
日々雇入れられる者でも、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。
② 平成15年出題 ×
2か月以内の期間を定めて雇入れた労働者に対しては、解雇の予告に関する規定は適用されません。
ただし、2か月以内の契約でも、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。
例えば、当初1か月の契約で雇入れた労働者を、当初の約束である1か月を超えて引き続き使用している場合は、解雇予告の規定が適用されます。
この問題の場合は、当初の契約が2カ月かつ当初の契約期間を超えていませんので、予告は不要です。
③ 平成19年出題 ×
「季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間」ということは、季節的業務に4か月以内の契約なので、解雇の予告に関する規定は適用されません。
解雇予告の規定が適用されるのは、上記②のパターンと同様、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合です。
④ 平成23年出題 ×
試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。試みの使用期間中だから予告がいらない、というのは間違いですので注意してくださいね。
ちなみに試みの使用期間(試用期間)を設けるか、設けないか、設けた場合の期間などは会社の自由です。
社労士受験のあれこれ
【年末総集編】労働基準法を学ぶシリーズその1~18
H28.12.28 労働基準法を学ぶシリーズ(まとめ)
~年末特集~
今年の特集記事を振り返ります。
今日振り返る特集は、「労働基準法を学ぶ」その1~18までです。
 全体記事はこちらをどうぞ↓
全体記事はこちらをどうぞ↓
平成28年度の過去記事はコチラ → 社労士受験のあれこれH28年度
平成29年度の記事はコチラ → 社労士受験のあれこれH29年度
第21条以降の解説は、来年に続きます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ18
H28.12.9 第20条 解雇の予告
労働基準法第20条について、次の空欄を埋めてください。
<法第20条 解雇の予告>
① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、< A >事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は< B >事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
② 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

<解答>
A 天災事変その他やむを得ない B 労働者の責に帰すべき
★ 解雇予告のポイント!
| <例えば平成28年11月30日に解雇する場合> | |
| 少なくとも30日前に予告する | 10月31日に予告すれば予告期間は30日となる ★ 10月31日は予告日数に算入しない |
| 30日分以上の平均賃金を支払う | 11月30日に即時解雇する場合は、30日分以上の平均賃金を支払う |
| 1日について平均賃金を支払った場合→その日数を短縮できる。 | 例えば、11月10日に予告した場合、予告期間は20日になり、解雇予告手当として10日分以上の平均賃金を支払う ★ 11月10日は予告日数に算入しない |
| <例外・予告規定が除外される場合> | |
| ① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合 | 行政官庁の認定が必要 |
| ② 労働者の責めに帰すべき事由に基づく場合 | |

過去問も解いてみましょう。
<H16年出題>
使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。

【解答】 ○
この場合の予告期間は、18日間(予告した日(5月13日)は予告期間に算入しません)となりますので、必要な解雇予告手当は、平均賃金の12日分となります。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ17
H28.12.8 第19条 解雇制限
労働基準法第19条について、次の空欄を埋めてください。
<法第19条 解雇制限>
① 使用者は、労働者が< A >負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後< B >間並びに< C >の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後< B >間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて< D >を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために < E >となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の< F >を受けなければならない。

<解答>
A 業務上 B 30日 C 産前産後 D 打切補償
E 事業の継続が不可能 F 認定
解雇制限期間は2つ!
| 例外(解雇できる) | |
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間 | ・ 打切補償を支払う場合(認定不要) ・ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(認定要) |
② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間 | ・ 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(認定要) |

過去問も解いてみましょう。
<H19年出題>
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。

【解答】 ○
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は、行政官庁の認定を受けなければなりません。使用者側が一方的に「やむを得ない事由だ!」「事業の継続が不可能だ!」と言ってもダメなのです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ16
H28.12.7 第18条 強制貯金
労働基準法第18条第1項と第2項について、次の空欄を埋めてください。
<法第18条 強制貯金>
① 使用者は、労働契約に< A >して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
② 使用者は、労働者の貯蓄金をその< B >を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。

<解答>
A 附随 B 委託
貯蓄金管理のポイント!
①強制 (労働契約に附随) | 禁止 |
②任意 (委託を受けて管理) | 可能(労使協定の締結&届出が必要になるなど一定の規制あり |

過去問も解いてみましょう。
<H23年出題>
使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

【解答】 ×
問題文のキーワードは「労働契約に附随」という部分です。労働契約に附随する貯蓄契約や貯蓄金管理契約は、禁止されています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ15
H28.12.6 第17条 前借金相殺の禁止
労働基準法第17条について、次の空欄を埋めてください。
<法第17条 前借金相殺の禁止>
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を< A >してはならない。

<解答>
A 相殺
ポイント!
| 禁止 | 禁止されていない |
| 使用者側からの相殺 | 労働者側の自己の意思による相殺 |

過去問も解いてみましょう。
<H20年出題>
使用者は、前借金と賃金とを相殺してはならない。

【解答】 ○
使用者側が行う相殺は禁止されています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ14
H28.12.5 第16条 賠償予定の禁止
労働基準法第16条について、次の空欄を埋めてください。
<法第16条 賠償予定の禁止>
使用者は、労働契約の< A >について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

<解答>
A 不履行
ポイント!
★ 実際に損害を受けた場合に、使用者が損害賠償を請求することは可能です。

過去問も解いてみましょう。
<H12年出題>
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際の労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。

【解答】 ○
前もって損害賠償額を予定する契約をすることは禁止されていますが、実際に被った損害の賠償を請求することは可能です。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ13
H28.12.1 第15条 労働条件の明示
労働基準法第15条について、次の空欄を埋めてください。
<法第15条 労働条件の明示>
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
<施行規則第5条 労働条件>
使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第4号の2から第11号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
1 労働契約の期間に関する事項
1の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
2 始業及び終業の時刻、< A >の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
3 賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに< B >に関する事項
4 退職に関する事項(< C >を含む。)
4の2 < D >の定めが適用される労働者の範囲、< D >の決定、計算及び支払の方法並びに< D >の支払の時期に関する事項
5 臨時に支払われる賃金(< D >を除く。)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
6 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
7 安全及び衛生に関する事項
8 職業訓練に関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
10 表彰及び制裁に関する事項
11 < E >に関する事項
② 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに掲げる事項(< B >に関する事項を除く。)とする。
③ 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする

<解答>
A 所定労働時間を超える労働 B 昇給 C 解雇の事由
D 退職手当 E 休職
ポイント!
★ 使用者は労働契約締結時には労働条件を明示しなけれななりません。労働契約そのものは口約束でも成立しますが、労働条件の中でも労働時間や賃金など特に大事な部分は書面で明示する義務があります。
絶対的明示事項(必ず明示する) → 第1号から第4号まで(上の青字の部分)
相対的明示事項(定めがある場合は明示する) → 第4号の2号から第11号まで
★ 絶対的明示事項は、書面の交付が必要です(後から言った言わないというトラブルを避けるため)。ただし、絶対的明示事項の中の「昇給に関する事項」は口頭でもOKです。(昇給については未知数なので)

過去問も解いてみましょう。
<H11年出題>
労働契約の締結に際し、使用者は労働者に対して賃金、労働時間等の労働条件を明示する必要があるが、その際、就業場所や労働時間に関する事項はもとより、退職手当や賞与に関する事項も書面で明示する必要がある。

【解答】 ×
退職手当(第4の2号)や賞与(第5号)に関する事項は相対的明示事項ですので、口頭でもOKです。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ12
H28.11.30 第14条 契約期間
労働基準法第14条について、次の空欄を埋めてください。
<契約期間>
労働契約は、期間の定めのないものを除き、< A >を定めるもののほかは、 < B >年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、< C >年)を超える期間について締結してはならない。
1 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2 < D >歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

<解答>
A 一定の事業の完了に必要な期間 B 3 C 5 D 満60
| 期間の定めのない労働契約(無期雇用) | 労基法上の規制なし | |
| 期間の定めのある労働契約(有期雇用) | 原則 | 上限3年 |
例外その1 ① 専門的知識等を有する労働者 ② 満60歳以上の労働者 | 上限5年 | |
例外その2 一定の事業の完了に必要な期間を定める場合(工事現場など) | 労基法上の規制なし | |
少しだけ民法を・・・。
★ 民法では、「無期雇用(期間の定めがない契約)」の場合は、労使当事者はいつもで解約の申し出ができる、とされています。お互いいつでも解約することができるので、労働基準法で規制をかける必要はありません。
一方、「有期雇用(期間の定めがある契約)」の場合は、やむを得ない事由があるときは契約の解除ができる、と規定されています(やむを得ない事由がなければ解除できないということ)。例えば、20年の契約を結んだ場合、民法のルールだと20年間はやむを得ない事由がない限り、労働者には退職の自由がないことになります。
労働者が長期労働契約に拘束されることを防ぐために、労働基準法では、有期雇用の場合は原則として3年を上限と定めています。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ11
H28.11.17 第13条 労基法違反の契約
労働基準法第13条について、次の空欄を埋めてください。
<労基法違反の契約>
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となつた部分は、この法律で定める基準による。

<解答>
A 無効
労働基準法で定める労働条件は最低ラインです。例えば労働基準法では1日の労働時間の上限は8時間と決められています。(労働時間が長くなるとその分健康的な生活から遠ざかるから、という考えから)
★ では、もし「労働契約」の内容が「労働時間は12時間とする」となっていたら?労働基準法の最低ラインよりも条件が悪いですが、このような労働契約はどうなるのでしょう?
労働基準法の考え方は以下の通りです。
↓
↓
「その部分については無効」と定められていますので、1日の労働時間12時間の部分は空欄(無効)となります。
さらに「無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と定められているので空欄になった部分は、労働基準法の最低基準である「1日の労働時間は8時間」が入っていきます。
ポイント!
★ 労働契約全体が無効になると労働者の働く場がなくなるので、労働基準法よりも不利な部分だけが無効になるということも注意してください。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ10
H28.11.10 第12条 平均賃金
労働基準法第12条について、次の空欄を埋めてください。
<平均賃金の算定方法(原則)>
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前< A >間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の< B >で除した金額をいう。

<解答>
A 3か月 B 総日数
★ 例外で時給制・日給制等の場合は最低保障が設けられていますが、まずは原則の算定方法を押さえましょう。
<ポイント>
★ 算定事由発生日の「直前の賃金締切日」からさかのぼった3か月間で計算する
★ 「総日数」とは、労働日数ではなく暦上の日数のこと
例えば、11月10日に即時解雇をしたい場合、予告期間の代わりに30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
この場合の平均賃金は、賃金締切日が末日の場合、直近の賃金締切日の10月31日からさかのぼるので、10月1日~10月31日分、9月1日~9月30日分、8月1日~8月31日分、の3か月の賃金総額で計算することになります。
では、以下の要件で計算してみましょう。(月給制とします。)
8月1日~8月31日分 → 230,000円
9月1日~9月30日分 → 230,000円
10月1日~10月31日分→ 230,000円
↓
(230,000円+230,000円+230,000円)÷ 92日 = 7,500円
平均賃金は7,500円となり、解雇予告手当は、7,500円×30日分で計算します。
では、次の問題を解いてみましょう。
<平成16年出題>
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。

<解答> ○
解雇の事由が発生した日ではありませんので注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ9
H28.11.2 第11条 賃金の定義
労働基準法第11条について、次の空欄を埋めてください。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、 < A >として< B >が労働者に支払うすべてのものをいう。

<解答>
A 労働の対償 B 使用者
<第11条のポイント>
例えば、従業員の結婚のお祝いとして社長が渡す結婚祝金は賃金ではありません。「労働の対償」ではなく「おめでとう」という気持ちのものだからです。
しかし、例えば結婚手当として就業規則などで支給要件が決まっている場合は、「賃金」となります。就業規則で定めた場合は、使用者には支払う義務があり、また、労働者には受ける権利があるからです。
では、次の問題を解いてみましょう。
<平成22年出題>
結婚手当は、使用者が任意的、恩恵的に支給するという性格を持つため、就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が使用者に義務付けられている場合でも、労働基準法第11条に定める賃金には当たらない。

<解答> ×
就業規則によってあらかじめ支給条件が明確に定められている結婚手当は、賃金に当たります。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ8
H28.11.1 第10条 使用者の定義
今日から11月です。クリスマスケーキやお節料理の話題も。早いですね。
さて、労働基準法第10条について、次の空欄を埋めてください。
この法律で使用者とは、< A >又は事業の< B >その他その事業の労働者に関する事項について、< A >のために< C >者をいう。

<解答>
A 事業主 B 経営担当者 C 行為をするすべての
<第10条のポイント>
使用者として①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者、の3つが規定されています。
例えば、○○株式会社の場合だと、「①事業主」とは○○株式会社のこと、「②事業の経営担当者」とは代表者などのこと、「③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」は、労務管理などについて実質的に権限と責任がある人のことをいいます。
もし、労働基準法違反があった場合、使用者は責任を問われる立場になります。
それでは、平成11年に出題された問題を解いてみましょう。
<問題>
労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与えられておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、同法の使用者とはみなされない。

<解答> ○
部長という肩書がついていても、労務管理等で一定の権限がない場合は、労働基準法の「使用者」にはなりません。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ7
H28.10.31 第9条 労働者の定義
労働基準法第9条について、次の空欄を埋めてください。
この法律で「労働者」とは、< A >の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に< B >者で、< C >を支払われる者をいう。

<解答>
A 職業 B 使用される C 賃金
<第9条のポイント>
★ 「労働者」に該当するかどうかのポイント
・ 使用従属関係があるかどうか
例えば、業務内容や勤務時間等について使用者の指示通りに働いている(自分で決められない)場合は、労働者に該当する可能性が高いです。
・ 労働の対償として「賃金」が支払われている
例えば、欠勤や遅刻等の場合は報酬がマイナスされている場合は、時間で拘束され、その対価として報酬が支払われていることになり、労働者に該当する可能性が高いです。
★ 労働者かどうかの判断は「実態」による、というのがポイントです。
では、次の問題を解いてみましょう。
<H13年出題>
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。

<解答> ×
まず、「部長」や「工場長」という管理職であっても、「事業に使用」され、労働の対償として「賃金」を支払われる場合は「労働者」となることに注意してください。
そして例えば、取締役(企業の重役)で、かつ部長の職にあるような人の場合は、「部長」の部分では労働者となります。このように「取締役」でも労働者に該当することがあります。
使用者としての責任を問われる立場でもあり、反面、「事業に使用」され、労働の対償として「賃金」を支払われる面では「労働者」として保護される立場でもあります。
このように「使用者」の面と「労働者」の面、両方持つこともあり得ます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ6
H28.10.28 労働基準法別表第一
労働基準法別表第一では、事業が種類ごとに1号から15号まで分けられています。
労働基準法の規定の中には、事業の種類によって適用が決まるものがあるからです。
ちょっと横道にそれますが、例えば、労働基準法第41条は以下のように定められています。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
二 略
三 略
ちなみに別表第一では、
第6号 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
第7号 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
と規定されています。(簡単に言うと第6号は「農林業」、第7号は「水産業」です。)
別表第一第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業は、天気に左右される事業ですので、第41条により労働時間、休憩、休日の規定が除外されることになっています。
ただし、「第6号(林業を除く。)」とあるので、第6号のうち「林業」は第41条の規定から除かれています。
つまり、「農業・水産業」は第41条の規定により労働時間、休憩、休日の規定が除外されますが、「林業」は第41条から除かれるため、労働時間、休憩、休日の規定が適用されます。

話がそれましたが、別表第一で事業が15種類に区分されているのは、労働基準法の規定が事業の種類によって異なることがあるからです。
この15区分に当てはまらない事業でも、労働者を使用すれば、労働基準法は適用されます。
では、平成11年に出題された問題を解いてみましょう。
【問題】
労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者については、労働基準法は適用されない。

<解答> ×
15区分の事業に当てはまらなくても、労働基準法は適用されます。
例えば、「社会保険労務士の事業」は別表第一に掲げる事業には該当しませんが、労働者を使用すれば労働基準法は適用されます。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ5
H28.10.27 第7条 公民権行使の保障
労働基準法第7条について、次の空欄を埋めてください。
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は < A >を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は< A >の執行に妨げがない限り、< B >することができる。

<解答>
A 公の職務 B 請求された時刻を変更
<第7条のポイント>
★ 公民権行使のために就業しなかった時間は、有給でも無給でも、どちらでもかまいません。
労働基準法を学ぶ4
H28.10.25 第6条 中間搾取の排除
労働基準法第6条について、次の空欄を埋めてください。
何人も、< A >に基いて許される場合の外、業として< B >に介入して利益を得てはならない。

<解答>
A 法律 B 他人の就業
<第6条のポイント>
★ 法律に基づいて許される場合とは?
「職業安定法」の規定による有料職業紹介などはOKです。
★ 他人の就業に介入とは?
例えば、使用者と労働者が労働契約を開始するにあたって、職業紹介や募集などの形で第三者が入ってくるような場合です。
★ 「労働者派遣」は、中間搾取には該当しません。
労働者派遣の場合、労働者は、「派遣元」と「労働契約」を結び、「派遣先」からは「指揮命令」を受けます。「労働者」と「派遣元」と「派遣先」の関係を合わせてひとつの労働関係ととらえられています。
「派遣法」について、平成18年労働一般常識の選択式の問題を解いてみましょう。
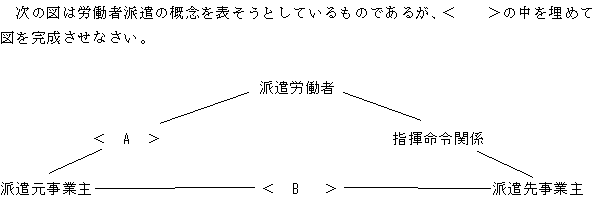

<解答>
A 雇用関係 B 労働者派遣契約
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ3
H28.10.24 第5条 強制労働の禁止
労働基準法第5条について、次の空欄を埋めてください。
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他< A >を不当に拘束する手段によつて、労働者の< B >に反して労働を強制してはならない。

<解答>
A 精神又は身体の自由 B 意思
<第5条のポイント>
★ 第5条違反は、労働基準法上、一番重い罰則が科せられます。
→ 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
★ 精神又は身体を不当に拘束する手段とは?
→ 長期労働契約、労働契約不履行に関する賠償額予定契約、強制貯金などがあります。例えば、使用者に強制貯金をするよう強要され、その貯金がおろせない労働者が退職できないような状況を想像していただければと思います。
★ 「強制してはならない」の意味
→ 実際に労働しなくても「労働を強要」すれば、第5条に抵触します。
★★ちなみに「その他」の読み方★★
「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体を不当に拘束する手段を不当に拘束する手段」
「その他」の前にある事項と「その他」の後ろにある事項が、対等に並んでいる関係です。
暴行、脅迫、監禁、とそれ以外の手段で精神又は身体を不当に拘束する手段という意味で読んでください。
なお、「その他の」というように「の」がつくとまた違う意味になります。このことはまた別の機会にお話しします。
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ2
H28.10.21 第4条 男女同一賃金の原則
労働基準法第4条について、次の空欄を埋めてください。
使用者は、労働者が女性であることを理由として、< A >について、男性と < B >取扱いをしてはならない。

<解答>
A 賃金 B 差別的
<第4条のポイント>
★ 第4条で禁じられているのは一般的な男女差別ではなく、「賃金」についてのみです。
「賃金以外の労働条件」について女性だからという理由で男性と差があっても、労基法第4条違反にはなりません。(男女雇用機会均等法などに触れる可能性があります。)
★ 女性を「有利」に扱うことも、「差別的取扱い」です。
~労働基準法には「差別的取扱い」と「不利益取扱い」という紛らわしい用語が出てきます。
第3条均等待遇、第4条男女同一賃金の原則では「差別的取扱い」が禁止されています。
しかし、例えば第104条(監督機関に対する申告)では、監督機関に申告したことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取扱をすることを禁止しています。(「不利益な取扱い」という用語は他の個所にも出てきます。)
社労士受験のあれこれ
労働基準法を学ぶ
H28.10.20 第3条 均等待遇
労働基準法第3条について、次の空欄を埋めてください。
使用者は、労働者の国籍、< A >又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、< B >をしてはならない。

<解答>
A 信条 B 差別的取扱
<第3条のポイント>
★「国籍、信条、社会的身分」は限定列挙で、第3条で禁止されている差別の理由はこの3つだけです。
例えば、「性別」を理由とする差別は、第3条違反とはなりません。
~~「性別」を理由とする差別は労基法第3条違反にはなりませんが、男女雇用機会均等法などに触れる可能性はあります。~~
社労士受験のあれこれ
家事使用人
H28.10.19 労働基準法と労働契約法の「家事使用人」
「労働基準法」と「労働契約法」の適用除外を比較してみましょう。
【労働基準法】
(適用除外)
第116条 略
② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。
【労働契約法】
(適用除外)
第22条 略
2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。
「同居の親族のみ」の場合は、労働基準法も労働契約法も適用除外ですが、「家事使用人」については、労働契約法では適用除外になっていないことがポイントです。
過去問で確認してみましょう。
<労働基準法 H20年出題>
労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
<労働契約法 H24年出題>
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

【解答】
<労働基準法 H20年出題> ○
★ 労働基準法では「家事使用人」は適用除外です。
<労働契約法 H24年出題> ○
★ 労働契約法の労働者は、第2条で「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」と定義されていて、これに当てはまれば、家事使用人も労働者となります。(家事使用人は適用除外とはされていません。)
社労士受験のあれこれ
ひっかけ問題(引っかかってはいけない)
H28.9.29 シリーズひっかけ(労基・育児時間)
いきなりですが、次の問題を解いてみてください。
<平成15年出題>
生後満1年に達しない生児を育てる労働者は、労働基準法第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

<解答> ×
育児時間を請求できるのは女性のみです。
「・・・を育てる労働者は・・・」という表現だと男性も含まれてしまいます。
社労士受験のあれこれ
プチ知識(労働基準法)
H28.9.28 平均賃金その3(日給制等の最低保障)
さて、本日は平均賃金その3です。
平均賃金は、原則として「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額」÷「算定事由発生日以前3か月間の総日数」で計算します。
※ 総日数とは暦日数のことですので、例えば、9月1日から11月30日の3カ月間で平均賃金を計算するなら分母は、「91日」となります。
しかし、賃金が日給や時給で計算される場合は、原則の計算式ですと不利になる可能性があります。
そのため、最低保障額が設定されています。
最低保障額は、「賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」で計算します。
※ 分母が総日数ではなく「労働日数」であること、100分の60をかけることに注意してくださいね。
★日給制、時給制、出来高払制その他の請負制の場合は、「原則」と「最低保障」のどちらか高い方が平均賃金となります。
では、過去問で確認しましょう!
<平成19年出題>
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

<解答> ○
最低保障の計算式は、
「賃金の総額」÷「その期間中に労働した日数」×100分の60です。
社労士受験のあれこれ
プチ知識(労働基準法)
H28.9.27 平均賃金その2(賃金総額と日数から控除するもの)
昨日のプチ知識では、「平均賃金の賃金総額に算入しないもの」を確認しましたが、①臨時の賃金(結婚手当など、めったに支給されないもの)、②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス等)、③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの、の3つは「賃金総額」(分子)から除外する賃金です。
昨日の記事はこちら→ H28.9.26 平均賃金その1(平均賃金に算入しないもの)
今日のプチ知識は、「賃金総額」(分子)からも「日数」(分母)からも除外する期間と賃金を確認しましょう!
↓
平均賃金の算定期間中に、次の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。
① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
② 産前産後の女性が65条の規定によつて休業した期間
③ 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
④ 育児休業又介護休業をした期間
⑤ 試みの使用期間
それでは、過去問で確認しましょう。
① 平成13年出題
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。
② 平成19年出題
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

<解答>
① 平成13年出題 ×
業務上の負傷又は疾病による療養のために休業期間は控除されますが、「通勤災害」の療養のための休業期間については控除できません。
※通勤災害については、使用者に補償義務はありません。「業務上」とは区別されますので、注意してくださいね。
② 平成19年出題 ×
子の看護休暇を取得した期間は、控除できません。
社労士受験のあれこれ
プチ知識(労働基準法)
H28.9.26 平均賃金その1(平均賃金に算入しないもの)
平均賃金は、「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額」÷「その期間の総日数」で算定します。
※賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日からさかのぼります。
※日給制等の場合は最低保障があります。
今日は、平均賃金の賃金総額に算入しないものを確認しましょう!
条文ではこうなっています。
↓
労働基準法第12条第4条
賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
↓
賃金総額に算入しないものは
① 臨時の賃金(結婚手当など、めったに支給されないもの)
② 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス等)
③ 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
★③がややこしいですよね。
まず、「通貨以外のもの」=現物給与のことです。
「通貨以外のもの」については、「法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる」場合は労働基準法上の賃金に当たるので、平均賃金の賃金総額に算入します。
逆に、「法令や労働協約に定められていない」通貨以外のものは、賃金とは言えないので平均賃金の賃金総額にも算入しない、ということです。
それでは、過去問で確認しましょう。
<平成24年出題>
ある会社で、労働協約により通勤費として6か月ごとに定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に定める賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。

<解答>
② 平成24年出題 ×
労働協約に基づいて支給されている通勤定期は、労働基準法上の「賃金」に当たります。また、6か月の定期券は各月分の前払いと考え、1か月ごとに支給されたと扱い、平均賃金の計算に算入します。
社労士受験のあれこれ
プチ知識(労働基準法)
H28.9.22 解雇予告が適用されない労働者
労働者を解雇するには、原則として解雇の予告が必要です。
ただし、解雇予告の規定が適用除外になる労働者もいます。
今日は、適用除外の規定から適用除外される要件を確認しましょう。
★解雇予告の規定から除外されるのは次の4つのどれかに該当する労働者です。
<労働基準法第21条>
① 日日雇い入れられる者
② 2箇月以内の期間を定めて使用される者
③ 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
④ 試の使用期間中の者
ただし、この4つに該当しても、例外的に解雇予告が必要になる場合もあります。
試験対策としては、例外を覚えることがポイントです。
では、過去問でチェックしてみましょう。
① 平成13年出題
日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
② 平成15年出題
使用者が、2か月の期間を定めて雇入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
③ 平成19年出題
季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定めて雇入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月を経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
④ 平成23年出題
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。

<解答>
① 平成13年出題 ×
日々雇入れられる者でも、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。
② 平成15年出題 ×
2か月以内の期間を定めて雇入れた労働者に対しては、解雇の予告に関する規定は適用されません。
ただし、2か月以内の契約でも、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告の規定が適用されます。
例えば、当初1か月の契約で雇入れた労働者を、当初の約束である1か月を超えて引き続き使用している場合は、解雇予告の規定が適用されます。
③ 平成19年出題 ×
「季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間」ということは、季節的業務に4か月以内の契約なので、解雇の予告に関する規定は適用されません。
季節的業務に解雇予告の規定が適用されるのは、上記②のパターンと同様、所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに至った場合です。
④ 平成23年出題 ×
試みの使用期間中でも、14日を超えて引き続き使用されている場合は、解雇予告の規定が適用されます。試みの使用期間中だから予告がいらない、というのは間違いですので注意してくださいね。
ちなみに試みの使用期間(試用期間)を設けるか、設けないか、設けた場合の期間などは会社の自由です。
社労士受験のあれこれ
初めての勉強のコツ
H28.9.9 「ポイント」のつかみ方(労働基準法第2条)
例えば、労働基準法第2条の条文をみてみましょう。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
条文を読むとだいたい雰囲気は分かりますが、合格するためには、ポイントをつかむことが必要です。
ポイントは、過去の出題をチェックすれば分かります!
① まずは、平成19年選択式から見ましょう。<A>を埋めてください。
労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、<A>決定すべきものである。」とされている。
①の答 「対等の立場において」
ポイントその1「労働条件」は労働者と使用者が対等の立場で決めるもの。どちらかが優位にたって決めるものではない。
では、次は択一式です。
② 平成21年出題
使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にその義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。
③ 平成15年出題
労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。
②平成21年出題の答 ×
③平成15年出題の答 ○
ポイントその2労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実の各々その義務を履行する義務は、使用者だけでなく労働者にも課せられている。
これでポイントがつかめました。下のアンダーラインの個所がポイントです。
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

では、次の問題も解いてください。
④ 平成13年出題
労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定違反には罰則は設けられていない。
④平成13年出題の答 ○
第2条は訓示的規定とされていて、罰則はありません。
(※ちなにに第1条も罰則はありません。)
ポイントその3 第2条には罰則がない。
最後の問題です。
⑤ 平成25年出題
労働基準法第2条第1項が、「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」との理念を明らかにした理由は、概念的には対等者である労働者と使用者との間にある現実の力関係の不平等を解決することが、労働基準法の重要な視点であることにある。
⑤平成25年出題の答 ○
労働基準法の考え方ということで、参考程度に読むくらいで大丈夫です。
社労士受験のあれこれ
平成28年度選択式を解きました。(労基、安衛編)
H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
平成28年度の選択式を解きました。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析しました。
よければお読みください。
本日は、労働基準法と労働安全衛生法です。
<労働基準法>
【AとB】
最高裁判例(平成27年6月8日 第二小法廷判決)からの出題です。
・ 療養補償給付を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない
↓
・ 使用者が、労働基準法81条の規定による打切補償の支払をすることにより
↓
・ 解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書適用を受けることができる
という結論になっています。
もし、この最高裁判例を読んだことがなくても、「解雇制限」の問題なので、打切補償、療養開始後3年という部分は引き出せるのではないかなーと思います。
★ちなみに、平成27年の選択式は「平成26年1月24日」判決からの出題、平成26年度の選択式は、「平成25年6月6日」判決からの出題でした。
3年連続最新の最高裁判例からの出題となっています。
★最高裁判例の勉強のポイントは、判例を読み込むことではなく「キーワード」を押さえることと言えます。
【C】
企画業務型裁量労働制の対象業務の定義からの出題です。
⑩と⑫は候補から外せたと思いますが、「⑪使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる」と迷った方もいらっしゃるのではないでしょうか?
⑪は「専門業務型裁量労働制」の対象業務の定義に出てくる用語です。
専門業務型の場合は、厚生労働省令で19の対象業務(研究開発など)が具体的に定められていることを思い出せれば、⑪も候補から外すことができるのでは?と思います。
<労働安全衛生法>
【D】
総括安全衛生管理者の資格からの出題です。
総括安全衛生管理者イコール「統括管理」する者という図式は、『平成12年選択式』、『平成24年択一式』でも出題されています。過去問などでしっかり勉強した方にとっては易しかったと思います。名称は「総括」だけど仕事は「統括」がポイントです!
ちなみに当研究室でも直前対策として取り上げています。
コチラです → H28.8.12 直前!「安衛法」の選択対策 第6回目
【E】
今年の改正事項である「ストレスチェック」からの出題です。
ストレスチェックの実施者の定義です。
当研究室でも平成28年2月3日に、H28.2.3 ストレスチェックその1 として取り上げていますが、精神保健福祉士を強調していませんね・・・。反省です。
社労士受験のあれこれ
【直前】「労働基準法」の選択対策
H28.8.15 直前!「労基法」の選択対策
本試験は、8月28日。まだ、時間はあります。
自信をもって答えられるよう、今まで勉強したところをひとつひとつしっかり復習していきましょう。
では、今日は労働基準法の選択問題です。
平成13年、14年の過去問からです。
<平成14年出題>
労働基準法施行規則第16条第1項においては、使用者は、労働基準法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに<A >及び<A >を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について協定しなければならない、と規定されている。また、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長等に関する基準」第2条においては、労働基準法第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下「時間外労働協定」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、時間外労働協定において<A >を超える一定の期間についての延長することができる時間を定めるに当たっては、当該一定の期間は、<B >及び<C >としなければならない、と規定されている。
<平成13年出題>
労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び< D >に対し、必要な< E >及び指導を行うことができる」旨定められている。

【解答】
A 1日 B 1日を超え3カ月以内の期間 C 1年間
D 労働組合又は労働者の過半数を代表する者 E 助言
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)
H28.8.1 目的条文のチェック(労働編)
いよいよ8月です!
8月の頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(労働編)です。
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< B >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< A >を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< B >の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の< C >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が< A >場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< B >及び雇用の安定を図るとともに、< C >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< D >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< E >を図ることを目的とする。

<解答>
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が<A 人たるに値する生活>を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、<B この基準>を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<C 向上>を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、<A 労働基準法>と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び<B 自主的活動>の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、<C 快適な職場環境>の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な<A 保険給付>を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の<B 社会復帰>の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の<C 福祉の増進>に寄与することを目的とする。
ここもポイント!
「労働安全衛生法」と「労災保険法」の目的条文の比較
安全と○○
→ こちらの記事をどうぞ! H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が<A 自ら職業に関する教育訓練を受けた>場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<B 生活>及び雇用の安定を図るとともに、<C 求職活動>を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<D 職業の安定>に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<E 福祉の増進>を図ることを目的とする。
社労士受験のあれこれ
横断・日雇労働者
H28.7.8 金曜日は横断 (日雇労働者/労基・雇用・健保)
金曜日は横断です。
「日雇労働者」について過去の出題ポイントを集めました。
<労働基準法>
問題①(H11年出題)
日々雇入れられる者については、労働者名簿の調製は必要なく、また、労働契約締結時に書面で労働条件を明示する必要もない。
問題②(H13年出題)
日々雇入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
<雇用保険法>
問題③(H25年選択式)
雇用保険法第42条は、同法第3章第4節において<A >とは、<B >又は<C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
問題④(H20年出題)
日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
問題⑤(H20年出題)
日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その事実のあった日から起算して10日以内に、日雇労働被保険者資格取得届を提出しなければならない。
問題⑥(H20年出題)
日雇労働被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所において、雇用保険被保険者証及び日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない。
<健康保険法>
問題⑦
健康保険法の「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1. 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、イに掲げる者にあっては< A >を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる< B >を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く。)を除く。)
イ 日々雇い入れられる者
ロ < C >以内の期間を定めて使用される者
2. 季節的業務に使用される者(継続して< D >を超えて使用されるべき場合を除く。)
3. 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して< E >を超えて使用されるべき場合を除く。)
問題⑧(H19年出題)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるときは、保険医療機関等に日雇特例被保険者手帳を提出しなければならない。

<解答>
<労働基準法>
問題①(H11年出題) ×
日々雇入れられる者でも労働契約締結時に絶対的明示事項(昇給に関する事項は除く)は書面の交付が必要です。
なお、日々雇入れられる者は、「労働者名簿の調製」は不要です。
問題②(H13年出題) ×
日々雇入れられる者については、解雇予告の規定は原則として除外されます。
ただし、日々雇入れられる者でも「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」は、解雇の予告が必要です。
<雇用保険法>
問題③(H25年選択式)
A 日雇労働者 B 日々雇用される者 C 30日 D 18日 E 31日
問題④(H20年出題) ○
次の①又は②に該当した場合は、日雇労働者でなくなります。
①前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 |
※ ただし、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、引き続き、日雇労働被保険者となることができます。
問題⑤(H20年出題) ×
10日以内ではなく「5日以内」です。ちなみに提出先は管轄公共職業安定所長です。
問題⑥(H20年出題) ×
日雇労働被保険者には、雇用保険被保険証は交付されません。
管轄公共職業安定所長は日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき、任意加入の認可をしたときは、「日雇労働被保険者手帳」を交付しなければならないと規定されています。
ここもポイント!
日雇労働被保険者には「確認」の制度は適用されません。
<健康保険法>
問題⑦
A 1月 B 所定の期間 C 2月 D 4月 E 6月
問題⑧(H19年出題) ×
保険医療機関等に提出するのは、「受給資格者票」です。
社労士受験のあれこれ
選択対策/(労働基準法)
H28.7.7 木曜日だけど選択式対策!(労働基準法)
今週は労働基準法です。
テーマは「罰則(両罰規定)」です。
では、問題です。
(1) この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の< A >を科する。
ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。(2)において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
(2) 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その< B >に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を< C >した場合においては、事業主も< D >として罰する。
【選択肢】
① 懲役刑又は罰金刑 ② 指示 ③ 更生 ④ 改善 ⑤ 拒否 ⑥ 是正 ⑦ 停止 ⑧ 教示 ⑨ 懲役刑 ⑩ 教唆 ⑪ 罰金刑 ⑫ 共犯者 ⑬ 過料 ⑭ 実行犯 ⑮ 責任者 ⑯ 行為者

解答に入る前に確認です。
「事業主」とは、法人の場合は「法人そのもの」、個人企業の場合は「企業主個人」のこと。

<解答>
A ⑪ 罰金刑 B ⑥ 是正 C ⑩ 教唆 D ⑯ 行為者
(1) この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主(事業主=法人の場合はその法人そのもの)に対しても各本条の罰金刑を科する。
(違反行為をした本人に対して罰則が適用されるのはもちろん、事業主にも罰金刑が科されます。法人に懲役刑は科せられないので罰金刑の対象になります。)
ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。(2)において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
(事業主(=ここでは法人の場合は代表者を事業主とする)が違反防止の措置をとった場合は、罰金刑は科せられません)
(2) 事業主(=ここでも法人の場合は代表者を事業主とする)が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
(事業主(法人の代表者)も行為者としての罰則が適用され、懲役刑を科せされることもありあます)

択一式の過去問もチェックしておきましょう。
(H20年出題)
労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。
(H10年出題)
労働基準法違反をした事業主(事業主が法人である場合においては、その代表者)が教唆した場合、当該事業主についても行為者として罰則が適用されるが、罰金刑にとどまり、懲役刑を科せられることはない。
<答>
(平成20年) ○
例えば、従業者が労働基準法に違反する行為をした場合、違反行為をした本人に対して罰則が適用されるのはもちろん、事業主にも罰金刑が科されます。(両罰規定といいます) ただし、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は、事業主に罰金刑は科さないとされています。
(平成10年) ×
行為者として懲役刑が科されることもあります。
社労士受験のあれこれ
【横断】時効(労働編)
H28.7.1 金曜日は横断 時効(労働編)
金曜日は「横断」です。
今週は、労働基準法、労災保険法、雇用保険法の「時効」を横断的に整理しましょう。
労災保険法は、時効の起算日や時効が関係ないものをおさえることもポイントです。
【労働基準法】
① この法律の規定による賃金(< A >を除く。)、災害補償その他の請求権は < B >年間、この法律の規定による< A >の請求権は< C >年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
【労災保険法】
② H13年出題
障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
② H16年出題
療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。
③ H18年出題
休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
④ H18年出題
障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
【雇用保険法】
⑤
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。

<解答>
【労働基準法】
① A 退職手当 B 2 C 5
【労災保険法】
② H13年出題 ×
障害補償一時金、遺族補償一時金の時効は5年です。
★覚え方のポイント
「障害」「遺族」と名の付く給付(年金、一時金、差額一時金)の時効は5年。
ただし、障害も遺族も「前払一時金」の時効は2年。
② H16年出題 ×
療養の給付は現物給付なので、時効は関係ないので×です。
療養の費用の支給を受ける権利の時効は、「療養の費用を支出した日の翌日」から起算して2年です。
③ H18年出題 ×
休業補償給付を受ける権利の時効は、「当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から」2年です。
④ H18年出題 ○
障害補償給付は、「治ゆ」したときに支給される給付なので、時効の起算日も、「当該傷病が治って障害が残った日の翌日」から起算します。
ここもチェック!
★傷病(補償)年金は、政府の「職権」で支給決定されるので、時効はありません。
傷病(補償)年金の時効についてはコチラの記事(4月3日UP)をどうぞ。
【雇用保険法】
⑤ ×
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利の時効は2年です。
社労士受験のあれこれ
書類の保存期間 2年3年4年5年
H28.6.10 金曜日は横断 書類の保存期間
書類の保存期間は2年、3年、4年、5年、それ以外と各法律さまざまです。
でも、覚えておけば得点できます。どんどん覚えましょう。
では、過去問をどうぞ。
① 労働基準法(H22年出題)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
② 労働安全衛生法(H22年出題)
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
③ 労働安全衛生法(H19年出題)
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。
④ 労働安全衛生法(H21年出題)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
⑤ 労災保険法
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管しなければならない。
⑦ 徴収法(H19年出題)
事業主もしくは事業主であった者又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。
⑧ 徴収法(H22年出題)
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は4年である。
⑨ 健康保険法(H22年出題)
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題)
事業主は、厚生年金保険法に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

【解答】
① 労働基準法(H22年出題) ○
ポイント
・ その他労働関係に関する重要な書類 → タイムカード等の記録、残業命令書等が該当する
・ 企画業務型裁量労働制の実施状況にかかる労働者ごとの記録 → 決議の有効期間中+その満了後3年間)
② 労働安全衛生法(H22年出題) ○
・ 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育のうち、保存義務があるのは特別教育のみ。
・ 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議事で重要なものに係る記録も保存期間は3年
③ 労働安全衛生法(H19年出題) ○
④ 労働安全衛生法(H21年出題) ○
・ 保存期間が5年のもの → 健康診断個人票、面接指導の結果の記録(長時間労働、ストレスチェック)
⑤ 労災保険法 ×
2年間ではなく、3年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題) ○
・ 雇用保険に関する書類(雇用保険二事業及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。) → 2年間
・ 被保険者に関する書類 → 4年間
⑦ 徴収法(H19年出題) ×
⑧ 徴収法(H22年出題) ○
・ 労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類 →その完結の日から3年間
・ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 → 4年間
ポイント
・ 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿もおさえておきましょう。
① 労働保険事務等処理委託事業主名簿
② 労働保険料等徴収及び納付簿
③ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
①と②は3年間、③は4年間保存
⑨ 健康保険法(H22年出題) ×
5年間ではなく「2年間」保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題) ×
厚生年金保険法に関する書類 → その完結の日から2年間保存
健康保険法と同じなのでおぼえやすいです。
年次有給休暇(計画的付与)
H28.5.25 5日を超える部分が計画的付与の対象
年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の取得率UPのためにも活用できる制度です。
例えば、今年のゴールデンウィークは、5月2日(月)と5月6日(金)が平日でした。この日に年次有給休暇を計画的付与すれば、4月29日(祝)から5月8日(日)まで、10連休の設定ができることになります。
計画的付与の本試験のポイント
★ 導入手続は「労使協定」
★ 5日を超える部分が対象。
計画的付与の対象になると時季指定権も時季変更権も使えなくなります。そのため、労働者が自由に使えるように5日は残しておいて、それ以外を計画的付与の対象にできます。例えば、年次有給休暇の権利が18日ある場合は、計画的付与の対象は13日までとなります。
★ 付与の方法は限定されていない
事業場全体で一斉付与する、班別に交替制で付与する、個人別に付与するなどの方法があります。

では、過去問を解いてみましょう。
①平成20年出題
労働基準法第39条第6項の規定に基づき、労使協定により年次有給休暇の計画的付与の定めがなされた場合には、使用者は、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、労働者の時季指定にかかわらず、当該労使協定の定めに従って年次有給休暇を付与することができる。
②平成17年出題
いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれないところから、前年度から年次有給休暇日数が3日繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者については、当年度に新たに発生した12日分の権利のうち5日を超える部分である7日に限り計画的付与の対象とすることができる。
③平成22年出題
労働基準法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与は、当該事業場の労使協定に基づいて年次有給休暇を計画的に付与しようとするものであり、個々の労働者ごとに付与時期を異なるものとすることなく、事業場全体で一斉に付与しなければならない。
【解答】
①平成20年出題 ○
ポイントは、「労働者の時季指定にかかわらず」の部分。計画的付与の対象になると、労働者の時季変更権は使えません。労使協定で定めた通りに年次有給休暇が付与されます。
ちなみに、平成15年には、「使用者の時季変更権も使えない」という論点が出題されています。
○計画的付与の場合は、時季指定権も時季変更権も使えなくなることがポイント。
②平成17年出題 ×
計画的付与の対象になる年次有給休暇の日数には、前年度から繰り越された日数も含まれます。問題の場合は、前年度から繰り越された3日と当年度に新たに発生した12日の合計の15日分のうち、5日を残した10日が計画的付与の対象となります。
③平成22年出題 ×
計画的付与の方法は、事業場全体で一斉に付与の方法に限られません。個々の労働者で付与時期が異なる方法もあり得ます。

ちなみに、ちょっと難しいですが、こんな問題も出題されています。
④平成17年出題
労働基準法第39条第6項の規定に基づくいわゆる労使協定による有給休暇を与える時季に関する定めは、免罰的効力を有するにすぎないので、同条第5項の規定に基づく個々の労働者のいわゆる時季指定権の行使を制約するには、さらに就業規則上の根拠を必要とする。
【解答】×
計画的付与の労使協定には免罰的効力だけでなく、時季指定権、時季変更権の行使を制約する効力があります。ですので、就業規則上の根拠はいりません。
例えば、三六協定の効力(免罰的効力しかない)とは違いますので、注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ
業務災害と解雇の関係
H28.5.8 業務上の傷病と解雇制限 その2 ~労基法編~
今日は、業務上の負傷と解雇制限その2です。
その1はこちら → 「業務上の傷病と解雇制限 その1 ~労基法編~」
もう一度労働基準法第19条を見てみましょう。
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
業務上の傷病で療養のために休業する期間+30日間は解雇が禁止されていますが、2つの例外が設けられています。
① 打切補償を支払う場合 (認定不要)
② 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合(行政官庁の認定が必要)
①か②の場合は、解雇が可能になります。
ここでチェック 打切補償とは?
第81条
第75条の規定(療養補償)によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
業務上の傷病については治るまで使用者が補償するのが原則ですが、療養開始後3年を経過しても治らない場合は、打切補償(平均賃金の1200日分)を行えば、その後は補償義務がなくなる、という規定です。
★★解雇制限との関係★★ 療養後3年経過して打切補償を行った → 補償義務がなくなる → 解雇も可能になる、という考え方です。

では、平成13年出題の問題を解いてみましょう。
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。

【解答】 ×
打切補償を支払った場合のみではなく、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも、解雇制限の規定の適用が除外されます。
ちなみに、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合は、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定が必要です。(打切補償の場合は認定不要です。)

さて、労働基準法の「災害補償」の義務は、実際は「労働者災害補償保険法」が代行しています。
労災保険法と解雇制限の関係については、次回お話ししますね。
社労士受験のあれこれはこちら
業務災害と解雇の関係
H28.5.7 業務上の傷病と解雇制限 その1 ~労基法編~
労働基準法には、「災害補償」という規定があり、労働者が業務上負傷した又は疾病にかかった場合は、使用者に補償責任が課せられています。
例えば、労働基準法第75条を読むと、
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」と規定されています。(例えば、使用者が費用を負担して労働者を入院させて治療を受けさせる等をする義務があるということ)
「業務上の傷病については使用者には補償責任がある」ため、労働基準法第19条では、業務上の傷病で療養中の労働者を解雇することが禁止されています。
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」
ここもチェック!
★ 解雇が禁止されるのは、「療養のために休業する期間」です。治療中でも休業しないで出勤している場合は、解雇は可能です。
★ 休業期間の長短は問われないので、例えば1日だけの休業でも、休業後30日間は解雇できません。

では、H15年に出題された問題を解いてみてください。
一定の期間を契約期間とする労働契約により雇入れられた労働者が、契約期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。

【解答】 ×
第19条で禁止されているのは、「解雇」です。
契約期間の満了による労働契約の終了は解雇ではありませんよね。
業務上の傷病による療養で休業中に契約期間が満了になった場合は、そこで終了しても問題ありません。
第19条には例外規定がありますが、そのお話はまた後日。→後日の記事はコチラ
社労士受験のあれこれはこちら
みなし労働時間のルール ~労基法~
H28.5.6 みなし労働時間制のときの休憩・休日・深夜など
労働働基準法には、「事業場外労働のみなし労働時間制」、「専門業務型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」の3つのみなし労働時間制があります。
この3つは対象者や導入手続はそれぞれ違いますが、実際に何時間労働したかではなく、「定められた労働時間」労働したものと「みなす」という点は共通です。
例えば専門業務型裁量労働制は、労使協定でみなし労働時間を10時間と定めれば、実際に7時間で帰ろうが、12時間労働しようが関係なく10時間労働したとみなされます。
今日は、この3つに共通のルールを確認しましょう。(昭和63.1.1基発1号)
★事業場外・専門業務型・企画業務型共通/みなしの適用範囲
「みなし労働時間制に関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女性の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。
また、みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないものであること。」
※年少者・女性の労働時間にはみなし労働時間は適用されないので、実際の労働時間でカウントします。
例えば、第66条では妊産婦から請求があった場合は時間外労働はさせられないことが規定されています。ここにはみなし労働時間は適用されないので、実際に労働させる時間が1日に8時間を超えることはできないということです。
※みなし労働時間制をとっていても、休憩、深夜業、休日は法定どおりに適用しなければなりません。休日や深夜に労働させた場合は割増賃金が必要です。

では問題を解いてみましょう!
① 平成17年出題
労働基準法第38条の3及び第38条の4の規定に基づく裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、同法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用されるとともに、同法第6章の2の女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても適用される。
② 平成19年出題
労働基準法第38条の3に規定するいわゆる専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、当該協定に定めるべき時間は、1日当たりの労働時間であり、休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されないので、法定休日に労働させた場合には、当該休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。

【解答】
① 平成17年出題 ×
労働時間のみなしに関する規定は、女性の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定についても「適用されない」です。
② 平成19年出題 ○
休憩、深夜業及び休日に関する規定は適用されるので、休日労働の場合には、割増賃金が必要です。
社労士受験のあれこれはこちら
割増賃金の単価
H28.4.29 割増賃金の単価に算入しなくてもいい賃金
家族手当や通勤手当も「労働の対償として支払われるもの」ですので、労働基準法上の賃金です。
ただし、家族手当は「家族の数」に応じて支払われるものですし、通勤手当は「通勤にかかる費用」に応じて支払われるもの。労働の対価ではあるけれど仕事内容には直接関係ありません。
そのため、割増賃金の基礎には算入しなくてもよいことになっています。
ちなみに受験生のときに教えてもらった、割増賃金の基礎に算入しなくてよい賃金の語呂合わせ「かつべしんいち」をずっと覚えています。(その後住宅手当が加わったので「かつべしんいちの住宅」にアレンジしました。)語呂合わせは苦手なので、覚えているのはこれだけですが。
か(家族手当)つ(通勤手当)べ(別居手当)し(子女教育手当)ん(臨時に支払われる賃金)一(1か月を超える期間ごとに支払われる賃金)、じゅうたく(住宅手当)
では、問題を解いてみましょう!
① H23年出題
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている賃金は、算定基礎賃金に含める必要はない。
② H26年出題
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
③ H19年出題
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】
① H23年出題 × 含める必要がある
② H26年出題 ○
③ H19年出題 × 割増賃金の基礎となる賃金に算入する
「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」という名称だからといって、すべてが割増賃金の基礎賃金に算入しなくてもいいというわけではありません。
家族数に関係なく一律で支給されている家族手当、通勤手当でも距離に関係なく支払われている部分、住宅の形態ごとに一律に定額で支給されている住宅手当等は、割増賃金の基礎賃金に算入することになります。
例えば、扶養家族が1人の労働者にも扶養家族が3人の労働者にも一律の家族手当を支給している場合、その家族手当の額は労働者の個人的事情(家族数)に応じて決められているわけではないからです。
割増賃金の基礎から除外できるのは、あくまでも「労働者の個人的事情」に基づくものです。

割増賃金の単価の計算方法もチェック!
例えば、月給制の場合、割増賃金の基礎となる賃金は、
「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異る場合には、1年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額」と規定されています。
※以下の要件で計算してみましょう。
・基本給20万円、皆勤手当1万円、職務手当3万円、通勤手当1万5千円
・1年間の1か月平均所定労働時間数169時間
割増賃金の基礎となる賃金の計算式は、
(20万円+1万円+3万円)÷169です。
社労士受験のあれこれはこちら
横断 最低保障額(労基・雇用保険)
H28.4.27 「平均賃金(労基)」と「賃金日額(雇保)」の最低保障を比較する
労働基準法の平均賃金は、原則として「3か月間の賃金の総額」÷「3か月間の総日数」で算定します。
ただし、日給制、時給制、出来高払い制等の場合は、原則の計算式で算定すると低くなる場合があるため、最低保障額が設けられています。
また、雇用保険法では基本手当の日額は「賃金日額×給付率」で算定しますが、賃金日額は原則として「6か月間の賃金総額」÷「180日」で算定します。
こちらも、日給制、時給制、出来高払い等の場合の最低保障額が設けられています。
■■では、最低保障額についての過去問をチェックしましょう。
① 労働基準法 (H19年出題)
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。
② 雇用保険法 (H18年選択(改))
賃金日額は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を A で除して得た額の100分の B に相当する額の方が高ければ、後者の額が賃金日額となる。
【解答】
① 労働基準法 (H19年出題) ○
② 雇用保険法 (H18年選択)
A 当該最後の6か月間に労働した日数 B 70
ポイント!
| 労働基準法 「平均賃金」 | 雇用保険法 「賃金日額」 |
| 3か月間の賃金総額 | 6か月間の賃金総額 |
原 則 → 総日数で除す 最低保障 → 労働した日数で除した金額の100分の60 | 原 則 → 180で除す 最低保障 → 労働した日数で除した額の100分の70 |
ちなみに、
・総日数とは暦上の日数(例えば4月は30日間、5月は31日間)のこと
総日数と労働した日数はイコールではありません。
社労士受験のあれこれはこちら
横断 所定労働時間の一部休業
H28.4.18 労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」の違い
所定労働時間の一部を休業した日について、労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」を比べてみましょう。
<労基 休業手当の場合>
・平均賃金 10,000円
・1日の所定労働時間 8時間
【問】使用者の責めに帰すべき事由で労働時間が4時間に短縮された。その日の賃金として実際に労働した4時間分に対する5,000円を支払えば問題ないか?
【答】×間違い
1日の所定労働時間の一部を使用者の責めに帰すべき事由で休業させた場合でも、その日の保障として、平均賃金の100分の60以上を支払う必要があります。問の場合は、平均賃金の100分の60(6000円)と労働分の賃金5000円との差額の1000円をプラスしなければなりません。
<労災 休業(補償)給付の場合>
・ 給付基礎日額 10,000円
・ 1日の所定労働時間 8時間
【問】所定労働時間のうち4時間労働して、4時間が労働不能だった。その日の4時間分の労働に対して5,000円支払われた場合、休業(補償)給付の額は?
【答】休業(補償)給付の額は3,000円
給付基礎日額(10,000円)と労働に対する賃金(5,000円)との差額の60%が支給されます。(10,000円-5,000円)×100分の60=3,000円。
★労働不能だった時間の60%が労災保険から支給されるという考え方です。
| 労基法 休業手当 | 労災保険法 休業(補償)給付 |
使用者は、労働した時間分の賃金+休業分の保障として、平均賃金の100分の60以上は支払わなけばならない。 | 休業(補償)給付として、労働不能分の給付基礎日額の100分の60が支給される |
社労士受験のあれこれはこちら
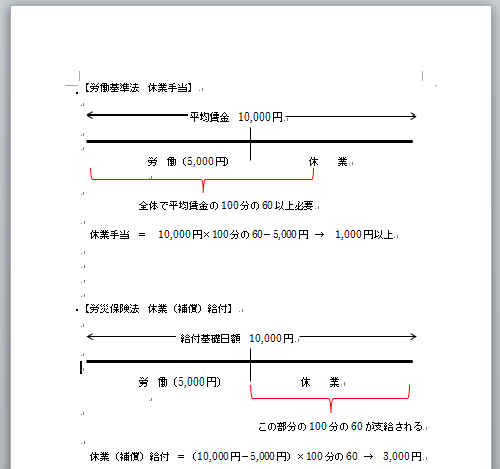
休業手当を解くコツ
H28.4.16 休業手当の4つのポイント
社労士試験では、重要論点は繰り返し出題されています。なので、過去問を解いていると、「どこかで見たような・・・?」と思うことがよくありますよね?
繰り返し出題されるのは重要だから。重要論点を知っておくと、問題文を隅々まで読まなくてもよくなるので、楽に早く勉強できます。
それでは、労働基準法の過去問を解きながら休業手当の重要論点をチェックしていきましょう!
<ポイントその1> そもそも休業手当は「何を保障」する制度?
H21年選択
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の A という観点から設けられたもの」であり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の A のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない」としている。
<ポイントその2> 民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」との違い
H17年出題
最高裁の判例によると、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」は、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法第536条第2項の「債権者の責めに帰すべき事由」より広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当であるとされている。
H26年出題
労働基準法第26条の定める休業手当の趣旨は、使用者の故意又は過失により労働者が休業を余儀なくされた場合に、労働者の困窮をもたらした使用者の過失責任を問う、取引における一般原則たる過失責任主義にあるとするのが、最高裁判所の判例である。
H22年出題
労働基準法第26条に定める休業手当は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払が義務付けられるものであり、例えば、親工場の経営難により、下請工場が資材、資金を獲得できず休業した場合、下請工場の使用者は休業手当の支払義務を負わない。
<ポイントその3> 休業手当は労働基準法の「賃金」に当たるか?
H13年出題
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき休業手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払う賃金には該当せず、必ずしも労働基準法第24条で定める方法により支払う必要はない。
<ポイントその4> 派遣労働者の適用は派遣元か派遣先か?
H13年出題
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当に関する規定の適用については、同条の「使用者の責に帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
H18年出題
労働者派遣中の労働者の休業手当について、労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。したがって、派遣先の事業場が天災事変等の不可抗力によって操業できないために、派遣されている労働者を当該派遣先の事業場で就業させることができない場合であっても、それが使用者の責に帰すべき事由に該当しないこととは必ずしもいえず、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断し、その責に帰すべき事由に該当しないかどうかを判断することとなる。

【解答】
<ポイントその1>
H21年選択式 A 生活保障
※使用者の責めに帰すべき事由で労働者を休業させる場合、使用者は労働者の「生活保障」のために休業手当を支給する義務がある。
休業手当は、労働者の「生活保障」のための制度。
<ポイントその2>
H17年出題 ○
民法第536条2項(債権者の責めに帰すべき事由)より労働基準法(使用者の責めに帰すべき事由)の方が、範囲が広い
*民法の考え方(債権者の責めに帰すべき事由)→ 故意・過失があること
*労働基準法の考え方(使用者の責めに帰すべき事由) → 使用者側に起因する経営・管理上の障害も含まれる。
この考え方を知っておけば、次の問題も解けます。
H26年出題 ×
民法の一般原則である過失責任主義(故意又は過失がある場合に責任を問われる)より広いのがポイント。使用者側に起因する経営・管理上の障害も含まれます。
H22年出題 ×
設問のような経営障害も「使用者の責めに帰すべき事由」に含まれます。(親工場の経営難について下請工場には故意も過失もありませんが、使用者は労働者の生活保障のために休業手当を支払う義務がある。)
<ポイントその3>
H13年出題 ×
休業手当は、労働基準法上の「賃金」です。
「賃金」なので、賃金支払いの原則どおり、毎月1回以上一定期日に支払わなければなりません。
また、休業手当は所定休日については支払う義務はありません。
<ポイントその4>
H13年出題 ○
H18年出題 ○
派遣労働者についての「使用者の責めに帰すべき事由」があるかどうかの判断は、「派遣元の使用者」に適用されます。
社労士受験のあれこれはこちら
年次有給休暇
H28.4.1 年次有給休暇の比例付与
パートやアルバイトのように、所定労働日数や所定労働時間数が少ない労働者にも、年次有給休暇の権利は発生します。
ただし、年次有給休暇の付与日数は、通常の労働者の所定労働日数との比率によって、決まります。(比例付与といいます。)
では、次の事例を考えてみましょう。
以下のAとBは同時に採用され、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤しています。AとBの付与日数はそれぞれ何日でしょう?
A (1日4時間・週5日勤務 → 週所定労働時間20時間)
B (1日10時間・週3日勤務 → 週所定労働時間30時間)
答は、A、Bともに付与日数は「10労働日」です。
A、Bともに比例付与の対象ではないのがポイントです。
比例付与の対象になるのは、
「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」の労働者です。(*週以外で労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」)
Aは週5日勤務、Bは週30時間勤務なので、どちらも比例付与の対象にはなりません。
★週所定労働日数が5日以上又は週所定労働時間が30時間以上の場合は、通常の付与日数となります。
この事例は平成19年に出題されていますが、比例付与の対象者の事例はよく出題されています。4日以下(又は年間216日以下)かつ30時間未満が「比例」付与の対象です。数字はもちろんですが、「かつ、以下、未満」もしっかりチェックしてくださいね。
なお、比例付与の日数は、通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(5.2日)との比率で決められています。
例えば、比例付与の対象者で、週所定労働日数4日の場合だと6か月経過日の付与日数は、
10日×4日/5.2日 ≒ 7労働日(1未満切り捨て)となります。
1か月単位の変形労働時間制
H28.3.30 1か月単位の変形労働時間制の導入手続
例えば、月末が忙しい事業場などでは1か月単位の変形労働時間制が効果的です。
変形期間1か月(暦日31日の月の場合)、1か月の法定労働時間の総枠は、以下の式で計算できます。
40時間×変形期間の暦日数(31日)÷7 ≒ 177.1時間
(※ポイント 特例措置対象事業場は40ではなく「44時間」で計算します)
実際に1か月単位の変形労働時間制を組んでみると下の例のようになります。
1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 休 | 休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 休 | 休 |
15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 休 | 休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 休 | 休 |
29 月 | 30 火 | 31 水 | |||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||
忙しい月末の4日間は1日11時間労働(11時間×4日=44時間)、それ以外は1日7時間労働を19日(7時間×19日=133時間)で、1か月の総労働時間は177時間。平均すると週の法定労働時間内におさまります。
月末に1日の法定労働時間(8時間)を超える日が設定されていますが、各日、各週の労働時間を具体的に特定していますし、総労働時間が法定労働時間の総枠(この場合は約177.1時間)内におさまっているので、OKです。
忙しい月末の労働時間が長いですが、1か月全体で平均をとるので、時間外労働ではありませんし割増賃金も不要です。

【導入手続】
1か月単位の変形労働時間制を導入するためには、
「労使協定または就業規則その他これに準ずるものによる定め」が必要です。
※「または」がポイント!
「労使協定」で定めるか、「就業規則その他これに準ずるもの」で定めるか、どちらの方法でも導入できます。
ただし、「就業規則その他これに準ずるもの」の場合、10人以上規模の事業場の場合は、就業規則の作成義務があるので、「就業規則」によることが必要です。(就業規則に準ずるものは不可)
10人未満の事業場の場合は、就業規則の作成義務がないので、「就業規則に準ずるもの」で定めることにより導入することができます。
10人以上の事業場 → 労使協定 又は 就業規則
10人未満の事業場 → 労使協定 又は 就業規則その他これに準ずるもの
用語の意味 ~労働契約法~
H28.3.14 労働契約法第15条
次の文章は、労働契約法第15条に関する行政通達です。(平成24.8.10基発0810第2号)
空欄○○に入る用語は何でしょう?

(1) 趣旨
○○は、使用者が企業秩序を維持し、企業の円滑な運営を図るために行われるものであるが、○○の権利濫用が争われた裁判例もみられ、また、○○は労働者に労働契約上の不利益を生じさせるものであることから、権利濫用に該当する○○による紛争を防止する必要がある。
このため、法第15条において、権利濫用に該当するものとして無効となる○○の効力について規定したものであること。
(2) 内容
ア 法第15条は、使用者が労働者を○○することができる場合であっても、その○○が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにするとともに、権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び態様その他の事情が考慮されることを規定したものであること。
イ 法第15条の「○○」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられているものであること。

【解答】 懲戒
労働基準法第89条の就業規則作成に出てくる「制裁」と同じ意味で、就業規則の「相対的必要記載事項」だということも注意してくださいね。懲戒をする場合は、「懲戒の種類と程度」を就業規則に定めておかなければなりません。
懲戒とは「労働者に労働契約上の不利益を生じさせる」ものです。そんな懲戒権を、何の根拠もなく使うことはできないんだと考えてください。
<参考>労働契約法第15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
選択式の練習 ~労働基準法~
H28.3.11 司法警察官の職務
次の空欄にはすべて同じ用語が入ります。何が入るでしょう?
第101条
① A は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
② ①の場合において、 A は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
第102条
A は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。
第104条
① 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は A に申告することができる。
② 使用者は、①の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

【解答】 労働基準監督官
過半数代表者の選び方 ~労働基準法~
H28.3.4 労使協定/管理監督者の位置づけ
労働基準法第41条の管理監督者(例えば、部長や支店長など)も、事業に使用されて賃金を受ける者なので、もちろん労働者です。ただし、「経営者と一体的な立場にある」という位置付けで、労働時間、休憩、休日の適用は除外されています。

さて、労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合があればその労働組合と協定しますが、そのような労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者と協定を結びます。

労働者だけど経営者と一体的な立場にある第41条の管理監督者は、労使協定の過半数代表者を選出する場合にどのように扱うのでしょうか?労働基準法施行規則で以下のように規定されています。
労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
過半数代表者は、「法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。」が条件になっていますよね?経営者と一体的な立場にある管理監督者は労働者代表として協定を結ぶにはふさわしくないということです。

では、平成13年に出題された問題を解いてみましょう。
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。

【解答】×
第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者も労働者です。労働者の過半数を代表する者の「労働者」の範囲には含まれます。
ポイント!
第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者の扱い
・ 労働者の数には含まれる。
・ 労働者の過半数を代表する者にはなれない
違いを意識する ~労働基準法~
H28.2.26 就業規則と労使協定
次の問題の正誤を考えてください。
◆ 年次有給休暇の時間単位での取得は、労働基準法第39条第1項所定の事項を記載した就業規則の定めをおくことを要件に、年5日の範囲内で認められている。

【解答】 ×
年次有給休暇の時間単位の取得は、就業規則の定めではなく「労使協定」を定めることが要件です。
→ 使用者が一方的に就業規則でルール化するのではなく、労使で協定を結んだうえで導入してください、という考え方です。

では、次の問題も解いてみてください。平成12年に出題された問題です。
◆ 専門業務型裁量労働制においては、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が、当該業務に従事する労働者に対し具体的指示をしないこと等を労使協定で定めることが要件とされているが、この要件は、就業規則にその旨を明記することにより労使協定の定めに代えることができる。

【解答】 ×
専門業務型裁量労働制の採用の要件は「労使協定」です。就業規則に明記するだけでは採用できません。
労働基準法 似た用語
H28.2.15 休業手当と休業補償
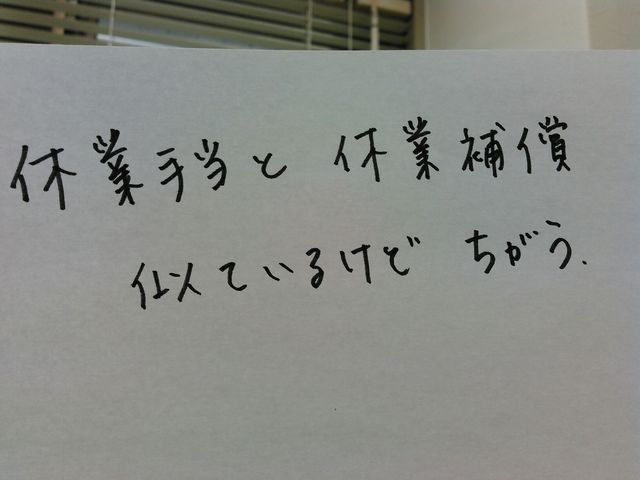
■休業手当とは(第26条)
<使用者の責めに帰すべき休業の場合>
休業期間中、平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
※会社都合で労働者を休業させる場合は休業手当を支払う義務がある
■休業補償とは(第76条)
<労働者が業務上の負傷、疾病による療養のため労働できないために賃金を受けない場合>
療養中、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
※業務上の負傷、疾病等については、使用者に補償責任がある(災害補償)
実際は、この使用者の補償責任は、「労働者災害補償保険法(労災保険法)」でカバーされている
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★ポイント
・「休業手当」は労働基準法上の「賃金」に当たる。所定の賃金支払日に支払うべき
・「休業補償」は労働基準法上の「賃金」ではない(労働の対償でないから)
労働基準法 三六協定
H28.2.14 三六協定・割増賃金が必要な時間外労働とは
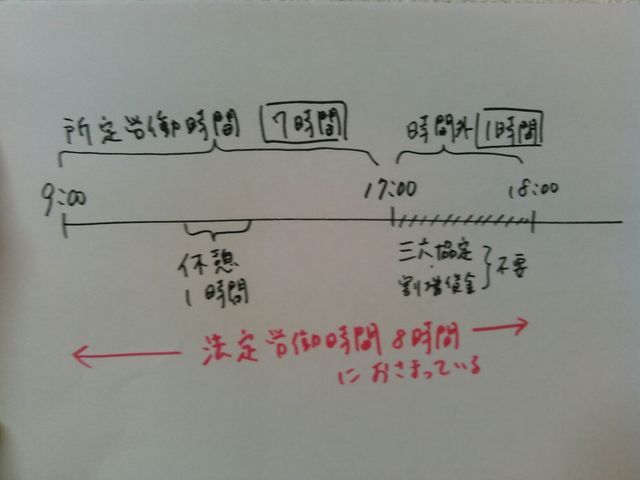
次の問題は〇×どちらでしょう?
【問題1】
1日7時間労働制の労働者に1時間以内の時間外労働をさせるには、三六協定が必要である。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問題1 答】×
三六協定は不要です。
「法定労働時間」を超えて労働させる場合、三六協定の締結・届出が必要です。
この問題のように、所定労働時間が1日7時間の場合、1時間時間外労働させたとしても実労働時間は8時間労働で法定労働時間内におさまります。故に三六協定は必要ありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問題2】
1日7時間労働制の労働者に1時間の時間外労働をさせた場合、その時間外労働の1時間については、原則として通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【問題2 答】○
7時間+1時間で実労働時間が法定労働時間(8時間)以内なので、1時間の時間外労働について割増賃金を支払う必要はありません。ただし、1時間分の通常の賃金(通常の1時間当たりの賃金×1.00)は必要です。
H28.1.27 賃金・報酬、賞与
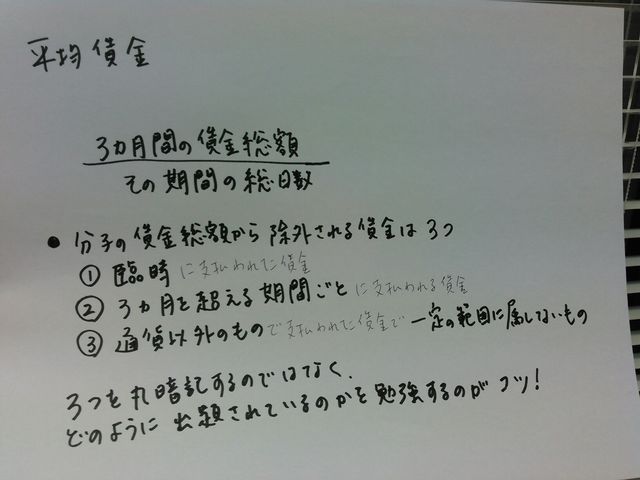
■労働の対償→賃金・報酬、賞与
「労働の対償として受けるもの」は一般的に言うと給料ですが、受験勉強では、まず法律ごとの呼び方を押さえることから始めます。
・労働基準法、雇用保険法、労働保険徴収法では、「賃金」といいます。
*例えば、雇用保険法の基本手当の日額や、徴収法の労働保険料は「賃金」を基に計算します。
・健康保険法、厚生年金保険法では、「報酬、賞与」といいます。
*例えば、厚生年金保険法では会社員として支払う厚生年金保険料や将来受けとる年金額は、「報酬、賞与」を基に計算します。
■ポイント
・「賃金」、「報酬、賞与」は「労働の対償」として支払われるもの
・しかし、保険料や給付額の計算に賃金の全てを算入するわけではない
*例えば、労働基準法の平均賃金は賃金をもとに計算しますが、賃金を全て算入するのではなく、夏・冬のボーナスなど平均賃金の計算から除外される賃金があります。
どの科目でも現物給与、臨時に支払われるものの扱いなどは頻出事項です。過去問で練習して慣れていきましょう。
H28.1.26 解雇予告
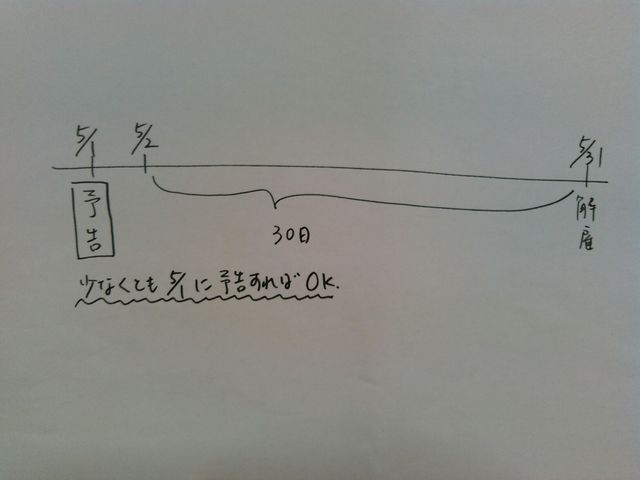
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成12年に、「5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。」という問題が出題されました。答えは〇です。
解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要ですが、予告をした日は30日の計算に入れないのがポイントです。仮に5月1日の午前11時に解雇予告した場合、5月1日という日は既に11時間過ぎていて残り13時間しかないですよね。ですので1日としてカウントされないと考えてみてください。
H28.1.22 就業規則作成義務
「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。」
常時10人以上の労働者を使用する場合、使用者は、就業規則を作成・届出する義務がありますが、「10人」以上という人数は、どういう単位で計算するのでしょうか?
例えば、大阪本社で8人、神戸工場で5人の労働者を使用する「○○株式会社」(企業全体では13人)は就業規則の作成・届出義務はありません。
労働基準法は「事業単位」で適用されます。「事業」とは「企業」ではなく、「事業場」(場所単位)を指すのでしたよね。
就業規則の作成・届出も事業場単位で考えてください。
○○株式会社は、事業場単位で見ると、大阪8人、神戸5人。それぞれ10人未満なので、就業規則を作成する義務も届出をする義務もないということです。
(ポイント)
労働基準法の適用単位は「事業」ごと。
事業とは、一企業全体ではなく、原則として本店、支店など場所ごとにとらえる。
H28.1.21 労働安全衛生法「労働時間」クイズ
労働安全衛生法に規定されている次のもののうち、当然に労働時間となるものはどれでしょう?(一つとは限りません。)
1 雇入れ時・作業内容変更時の教育
2 特別教育
3 職長教育
4 一般健康診断
5 特殊健康診断
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】
当然に労働時間となるのは、1・2・3・5です。
1・2・3の安全衛生教育や5の特殊健康診断が法定時間外に行われたとするなら、使用者は当然に割増賃金を支払わなければなりません。
4の一般健康診断は、労働者の一般的な健康管理のために行うもの。業務との関連がないので、当然に労働時間とはされません。
H28.1.20 労働基準法「船員の適用について」
「第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。」
◆船員法とは?◆
一定の船舶に乗り組む船員を保護するための法律です。
◆船員法に規定する船員についての労働基準法の適用は?◆
労働基準法は一部だけ適用されます。
(試験のポイント)
「労働基準法は、船員法第1条に規定する船員については、全面的に適用しない」は誤りです。適用される部分もあります。
◆船員法に規定する船員にも適用される労働基準法の規定は?◆
労働基準法の総則部分(第1条から第11条まで)とそれに関係する罰則規定は船員
法第1条に規定する船員にも適用されます。それ以外は適用除外です。
(船員に適用される部分)
第1条 労働条件の原則
第2条 労働条件の決定
第3条 均等待遇
第4条 男女同一賃金の原則
第5条 強制労働の禁止
第6条 中間搾取の排除
第7条 公民権行使の保障
第9条 労働者の定義
第10条 使用者の定義
第11条 賃金の定義
罰 則
H28.1.4 割増賃金の率
時間外労働をさせた場合は2割5分増し、休日労働をさせた場合は3割5分増しの割増賃金を支払わなければなりません。
2割5分、3割5分という割増賃金の率は、「法律」ではなく「政令」で定められています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
労働基準法第37条
「使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1カ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
法律と命令(政令や省令)をあわせて「法令」と呼ばれます。
法律は「国会」が定めるものですので、それなりの手続きや時間が必要で、制定にしろ改正にしろ、そう簡単にはいきません。
一方、政令は内閣が、省令は大臣が制定するもので、法律よりも軽い位置づけです。
時間外労働や休日労働の割増賃金の率は、経済情勢などによって率を変える必要も出てくるかもしれません。そんなときに、割増賃金の率が法律できっちり決まっていると、改正に時間がかかってしまいます。
その点、政令なら、内閣で決めることができるので、割増率を変えることも柔軟にできる、という考え方です。