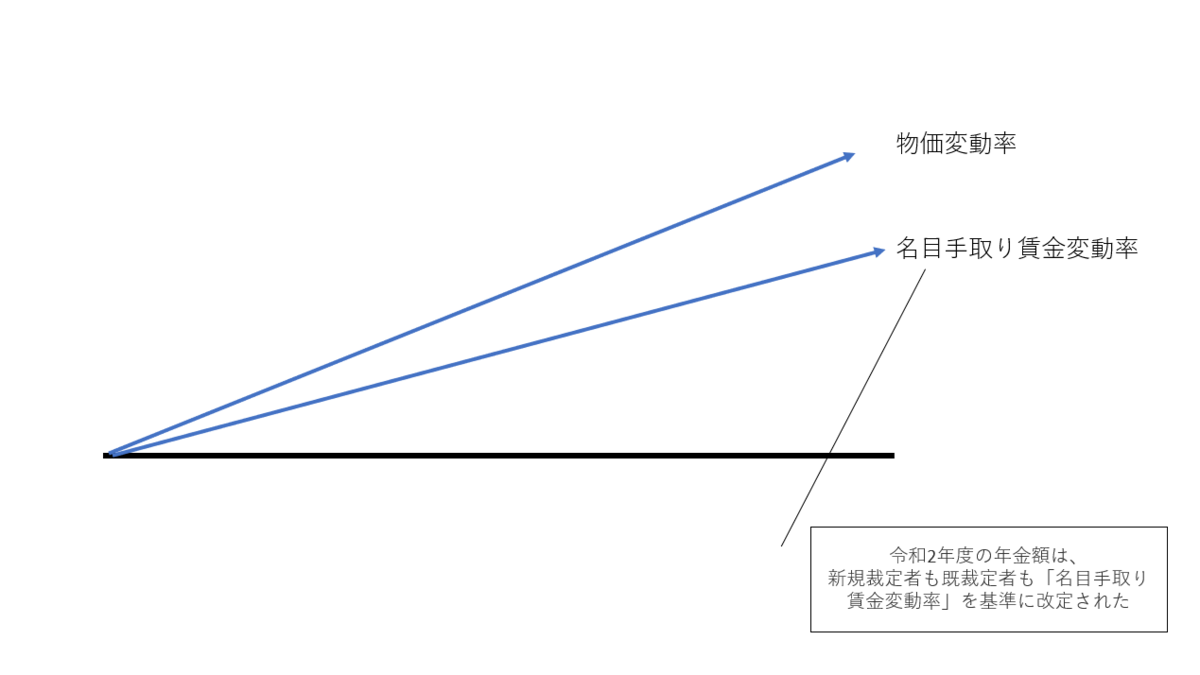合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
国民年金法「失権」
R8-116 12.18
付加年金と寡婦年金の失権事由
今回は付加年金と寡婦年金の失権事由をみていきましょう。
まずは、付加年金の失権事由を条文で読んでみましょう
法第48条 (失権) 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
★ 付加年金は、老齢基礎年金と同じ「終身年金」です。
次は寡婦年金の失権事由を条文で読んでみましょう
法第51条 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 →第40条第1項 ・ 死亡したとき。 ・ 婚姻をしたとき。 ・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 法附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
国民年金法において、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金には失権が規定されているが、付加年金及び寡婦年金には失権が規定されていない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
付加年金及び寡婦年金にも失権が規定されています。
②【H25年出題】
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
付加年金は老齢基礎年金にプラスして支給されますので、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。
また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。
条文を読んでみましょう。
法第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。 |
★ 「全額」がポイントです。「全部又は一部」ではありません。
➂【H24年出題】
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。

➂【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、寡婦が65歳に達したときに消滅します。寡婦が老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも同様です。
④【H24年出題】
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅します。ただし、直系血族又は直系姻族の養子となった場合は消滅しません。
⑤【H23年出題】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止されるのではなく、寡婦年金の受給権は「消滅」します。
⑥【H26年出題】
寡婦年金の受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】
⑥【H26年出題】 〇
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅します。
⑦【R4年出題】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

【解答】
⑦【R4年出題】 ×
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、受給権が消滅します。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R8-115 12.17
基準障害|はじめて2級による障害基礎年金
■■「はじめて2級による障害基礎年金」とは?
・既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にある(障害等級に該当しない障害)
↓
・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に
↓
・基準障害と他の障害とを併合して、初めて、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態に至った場合
↓
・障害基礎年金が支給されます。
簡単に言いますと
先にあった 障害 1・2級未満 |
+ | 新たに 発生した障害 (基準障害) |
→ | 初めて 1・2級に 該当 |
→ | 障害基礎年金が 支給される |
※基準障害について、初診日要件・保険料納付要件を満たしていること
※65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が1・2級に該当していること
では、条文を読んでみましょう。
法第30条の3 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者(初診日要件を満たしている)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 保険料納付要件は、「基準傷病」の初診日の前日で判断される。 ➂ ①の障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】
①【R7年出題】 〇
ポイントを確認しましょう
・基準傷病の初診日に、被保険者(被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるものを含む。)である。(初診日要件を満たしている)
・基準傷病以外の傷病により障害の状態にある
・基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に
・初めて、「基準障害」と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った
・基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以降であるときに限る
②【H18年出題】
既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。

【解答】
②【H18年出題】 〇
「赤字」の部分がポイントです。
既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
➂【H29年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

【解答】
➂【H29年出題】 ×
いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、その請求は、65歳に達した日以後でも行うことができます。
④【H20年出題】
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】
④【H20年出題】 ×
「支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始」が誤りです。
・ いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権が発生します。
・ 当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができます。
・ 支給は当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から開始されます。
⑤【R6年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
いわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となったときに受給権が発生します。65歳以降でも請求は可能です。また、請求によって受給権が発生するのではありませんが、支給は請求があった月の翌月からとなります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法(合算対象期間)
R8-114 12.16
昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した場合の合算対象期間
国民年金法がスタートしたのは昭和36年4月1日ですが、当初、外国人は適用が除外されていました。
外国人が、国民年金に強制加入となったのは、昭和57年1月1日以降です。
S36.4.1 | S57.1.1 |
国民年金適用除外 | 強制加入 |
今回は、昭和36年5月1日以降に日本国籍を取得した者に関する合算対象期間をみていきます。
日本国籍の取得以後は強制加入となりますが、日本国籍を取得する前の期間については、要件を満たせば合算対象期間になります。
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第8条第5項10号・11号 (10) 昭和36年5月1日以後国籍法の規定により日本の国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る。)その他政令で定める者の日本国内に住所を有していた期間であって、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律による改正前の国民年金法第7条第1項に該当しなかったため国民年金の被保険者とならなかった期間(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに第3項に規定する第2項各号に掲げる期間並びに第4号の2、第5号、第7号及び第7号の2に掲げる期間を除く。) (11) (10)に掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間(20歳未満であった期間及び60歳以上であった期間に係るものを除く。)のうち、昭和36年4月1日から当該日本の国籍を取得した日の前日までの期間に係るもの |
過去問を解いてみましょう
①【H25年出題】
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。以下同じ。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】
①【H25年出題】 ×
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していた
20歳以上60歳未満の期間のうち
国民年金の適用除外だった昭和36年4月1日から昭和57年1月1日前(昭和56年12月31日まで)の期間です。
昭和57年1月1日以後は、外国人でも強制加入になったため、合算対象期間にはなりません。
「昭和61年4月1日前の期間」が誤りです。
(昭60法附則第8条第5項第10号)
②【H25年出題】
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)
20歳以上60歳未満の期間のうち
昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。
(昭60法附則第8条第5項第11号)
➂【R7年出題】
昭和36年5月1日以後で、20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で、外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間にならない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
合算対象期間になります。
・昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した
(20歳に達した日の翌日~65歳に達した日の前日までの間)
↓
・合算対象期間になるのは
日本国内に住所を有していなかった(海外に在住していた)
20歳以上60歳未満の期間のうち
外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間です。
(昭60法附則第8条第5項第11号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法(障害基礎年金)
R8-113 12.15
障害基礎年金の額の改定ルール
障害基礎年金の等級には、「1級」と「2級」があります。
障害の程度は変わることもあり、障害の程度が増進又は軽減した場合は、障害基礎年金の額の改定が行われます。
条文を読んでみましょう。
法第34条 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ➂ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ④ 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したもの(初診日要件を満たしたもの)が、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ⑤ 第30条第1項ただし書の規定(保険料納付要件)は、④の場合に準用する。 ⑥ ①の規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする。 |
④その他障害との併合について
(例)2級の障害基礎年金の受給権者に
↓
「その他障害」が発生した。
※「その他障害」とは、1・2級に該当しないもの(3級以下)
初診日要件や保険料納付要件を満たしている
↓
2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合
↓
2級→1級に額の改定を請求できます
※ポイント!
65歳に達する日の前日までの間に請求することが条件です。
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができるが、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月から始められる。

【解答】
①【R7年出題】 ×
改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する「月」ではなく「翌月」から始められます。
②【R6年出題】
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して「1年6か月」ではなく、原則として、「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。
➂【R5年出題】
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】
➂【R5年出題】 〇
「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は除かれていることにも注意してください。
④【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」に当たります。
そのため、1年を経過した日後でなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができます。
(則第33条の2の2第1項第9号)
⑤【H29年出題】
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
1級から2級への改定、2級から1級への改定は、受給権者が65歳以上でも行われます。65歳未満の場合に限られません。
⑥【H26年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

【解答】
⑥【H26年出題】 ×
2級の障害基礎年金の受給権者に
↓
3級の障害(その他障害)が発生した。
※初診日に厚生年金保険の被保険者(=国年第2号被保険者)
↓
2級と「その他障害」を併合して、2級より増進した場合でも
↓
額の改定は請求できません。
※初診日に66歳ですので額の改定請求はできません。
その他障害との併合により額の改定請求ができるのは、「65歳に達する日の前日までの間」に増進し、かつその期間内に請求することが条件です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「任意加入被保険者」
R8-111 12.13
任意加入被保険者の資格取得日
第2号被保険者でもなく、第3号被保険者でもなく、第1号被保険者にも該当しない者は、国民年金に「任意加入」することができます。
任意加入する目的は、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たすため」、「老齢基礎年金の額を増やすため(満額にするため・満額に近づけるため)」です。
任意加入被保険者の条文を読んでみましょう
法附則第5条第1項~第3項 (任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①の(1)又は(2)に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 ➂ 任意加入の申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得するものとする。 |
特例による任意加入被保険者についても条文を読んでみましょう
令和7法附則第40条第1項 (任意加入被保険者の特例) 昭和50年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する場合は、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
★任意加入被保険者の特例は、「65歳以上70歳未満」の者が対象です。
ポイントは「昭和50年4月1日以前生まれであること」、「老齢年金の受給権を有しないことです。
老齢年金の受給権がある場合は、特例の任意加入被保険者になることはできません。そのため、老齢基礎年金の額を増やす目的の場合は、特例の任意加入はできません。
では、過去問を解いてみましょう
①【R2年出題】
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」は任意加入することができます。
問題文の場合は、日本国籍を有していますので、日本国内に住所を有していなくても、老齢基礎年金を満額にするために任意加入被保険者の申出をすることができます。
②【R2年出題】
20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
②【R2年出題】 〇
保険料半額免除期間は老齢基礎年金の額の計算上、4分の3で計算されますので、問題文の条件ですと老齢基礎年金は満額になりません。
そのため、老齢基礎年金の額を増やすために、任意加入被保険者となることができます。
➂【R6年出題】
甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

【解答】
➂【R6年出題】 ×
任意加入被保険者の特例(65歳以上70歳未満)は、「老齢年金の受給権を有しない者」が対象です。
甲は、受給資格期間を満たし老齢基礎年金の受給権がありますので、老齢基礎年金が満額でなくても、65歳以降は任意加入できません。
④【R7年出題】
国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者については、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得することになっているが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の場合は、最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得することができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
国民年金法附則第5条に基づく任意加入保険者は、厚生労働大臣に任意加入の申出をした日に資格を取得します。
最長60歳まで遡って任意加入被保険者の資格を取得するという規定はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金の繰下げ」
R8-110 12.12
老齢基礎年金|特例的な繰下げみなし増額
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得しても、65歳で請求をしないで、66歳以後に繰り下げて受けることができます。
老齢基礎年金の額は、繰り下げた期間に応じて増額されます。
・ 繰下げ受給するつもりで、65歳で老齢基礎年金の請求を行わなかった場合、例えば、「68歳で繰下げの申出をして増額された老齢基礎年金を受ける」こともできますし、「68歳で繰下げの申出をしないで、「65歳到達時点」の本来の老齢基礎年金をさかのぼって請求する」こともできます。
★今日のテーマは、「特例的な繰下げみなし増額制度」です。
・特例的な繰下げみなし増額制度の趣旨を確認しましょう
繰下げ上限年齢の引上げに伴い、70歳に達した日後も繰下げ待機を選択することが可能になる一方で、年金給付に係る支分権の消滅時効は5年間である。こうした中では、繰下げ上限年齢を引き上げたとしても、70歳に達した日後の繰下げ待機を選択しにくくなってしまう。このような阻害要因を緩和する観点から、70歳に達した日後に繰下げ待機していた者が、65歳時点からの本来受給を選択した場合に、増額された年金の支給が可能となるよう、改正を行う(令和5年4月1日施行)。
(令4.3.29年管管発0329第14号)
「特例的な繰下げみなし増額制度」とは?
「70歳」に達した日より後に、「65歳からの本来の老齢基礎年金」をさかのぼって受けることを請求し、かつ繰下げの申出をしない場合、請求した日の「5年前の日」に繰下げの申出があったものとみなされる制度です。その場合、「繰下げによって増額」された年金が一括で支払われます。
特例的な繰下げみなし増額制度について条文を読んでみましょう
法第28条第5項 老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、70歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に繰下げの申出をしないときは、当該請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 80歳に達した日以後にあるとき。 (2) 65歳に達した日から当該請求をした日の5年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき。 |
★「80歳以後」に請求する場合、「請求の日の5年前の日以前に障害年金や遺族年金の受給権者となった」場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。

【解答】
①【R6年出題】 〇
「70歳」に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時(=繰下げの申出をしない時)は、請求の5年前に繰下げの申し出があったものとみなされ、増額された老齢基礎年金が支給されます。
例えば、73歳で老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げの申出をしないときは、請求の5年前の68歳で繰下げの申出をしたものとみなされます。その場合、3年繰下げとなり、3年分増額された老齢基礎年金が支給されます。
なお、繰下げみなし増額制度は原則として「昭和27年4月2日以後生まれの者」が対象です。
②【R7年出題】
老齢基礎年金の支給を受ける権利は、受給資格期間が10年以上ある者が65歳に達した日から老齢基礎年金の請求をすることなく5年を経過したときに消滅する。そのため、72歳に達した時点で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受けることとなる。

②【R7年出題】 ×
「72歳に達した時点(=70歳に達した日より後)」で、老齢基礎年金を請求し、かつ、繰下げ申出をしないときは、請求の5年前(=67歳時点)に繰下げの申し出があったものとみなして、増額された老齢基礎年金が支給されます。
「繰下げ増額のない老齢基礎年金の支給を受ける」は誤りです。
➂【R7年出題】
繰下げ待機中の老齢基礎年金の受給権者が、年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡した場合に、遺族が未支給年金を請求する時は、特例的な繰下げみなし増額は適用されず、年金の支給を受ける権利が時効消滅していない過去5年分に限って支給されることになる。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
「繰下げ待機中の受給権者が年金を請求せずに70歳に達した日後に死亡し、遺族が未支給年金を請求するときは、特例増額を適用せず、支分権が時効消滅していない過去5年分に限り支給することとする。
なお、特例増額が適用される本来請求をした日以後に受給権者が死亡した場合には、未支給年金にも特例増額が適用される。」とされています。
(令4.3.29年管管発0329第14号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金」
R8-109 12.11
老齢基礎年金を繰下げ受給するための条件
老齢基礎年金の受給権は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上有する者が、65歳に達したときに、発生します。
条文を読んでみましょう
法第26条 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 ※10年の計算には合算対象期間も合算されます。 |
老齢基礎年金は繰り下げて受給することもできます。
条文を読んでみましょう
法第28条第1項 (支給の繰下げ) 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 ※他の年金たる給付とは ・国民年金の他の年金給付(付加年金を除く) ・厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。) |
過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」、繰下げの申出はできません。
他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。
障害基礎年金は国民年金の他の年金給付に該当します。
そのため、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。
②【R6年出題】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

【解答】
②【R6年出題】 ×
「遺族厚生年金」は、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」に該当します。
「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に遺族厚生年金の受給権者となった」場合は、実際には遺族厚生年金は受給しなくても、支給繰下げの申出はできません。
➂【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

【解答】
➂【R1年出題】 〇
「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」となっていますので、「老齢厚生年金」の受給権者でも老齢基礎年金の繰下げの申出をすることは可能です。
④【R7年出題】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって、かつ、他の年金給付(加給年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者でない者による当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、65歳に達する前に行わなければならない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは」繰下げの申出はできません。
他の年金たる給付とは、「国民年金の他の年金給付(付加年金を除く)」、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」です。
問題文は、「他の年金給付(加給年金を除く。)」となっていますが、加給年金ではなく付加年金です。
又、支給繰下げの申出は、「65歳に達する前」にはできません。繰下げの申出ができるのは、「66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの」です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R8-108 12.10
遺族基礎年金|失権と支給停止を整理しましょう
遺族基礎年金の「失権」事由と「支給停止」について整理しましょう。
「失権」について条文を読んでみましょう
第40条 ① 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 ② 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、①の規定によつて消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、遺族基礎年金の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ➂ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、①によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (2) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (3) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (4) 20歳に達したとき。 |
②について
配偶者が遺族基礎年金を受けるには、「子」と生計を同じくしていることが要件で、配偶者が受ける遺族基礎年金には必ず「子」の加算が加算されています。
「子」の数が減ると、子の数に応じて加算額も減額されます。
ただし、「子」のすべてが減額事由に該当すると、「子」がいなくなるため、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
次に「支給停止」について条文を読んでみましょう
第41条 ① 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 ② 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 (第41条の2、第42条は今回は省略します) |
では、過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【R4年出題】 〇
夫の受給する遺族基礎年金の額は、1人分の子の加算額が加算された780,900円×改定率+224,700円×改定率です。
加算の対象になっている子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の要件を満たさなくなります。
夫は「子と生計を同じくする」という要件を満たさなくなるため、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅します。
②【H30年出題】
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
(子は18歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】
②【H30年出題】 ×
・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、「子の遺族基礎年金は支給停止」となります。
→ 法第41条第2項の「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。配偶者と子に受給権が発生した場合は、配偶者が優先するためです。
・妻が再婚した場合、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
→ 法第40条第1項第2号の「婚姻をしたとき」に該当し、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
・当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、「支給停止が解除される」は誤りで、子の遺族基礎年金は「支給が停止」されます。
→ 法第41条第2項の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」に該当します。
子の遺族基礎年金は、母(問題文では妻)と引き続き生計を同じくしている場合は、その間、その支給が停止されます。
➂【H30年出題】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。
(子は 18 歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

【解答】
➂【H30年出題】 ×
第2号被保険者である40歳の妻が死亡し、40歳の夫と子がいる場合、以下の年金の受給権が発生します。
40歳の夫 → 遺族基礎年金のみ
(年齢要件を満たさないため、遺族厚生年金は受けられません。)
子 → 遺族基礎年金と遺族厚生年金
「遺族基礎年金」については、配偶者が優先されますので、「夫」に遺族基礎年金が支給され、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
子には、遺族厚生年金のみ支給されます。
④【R5年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
・配偶者の遺族基礎年金について
配偶者の遺族基礎年金は、子が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。」は、子の加算額が減額されます。(法第39法第3項第3号)
問題文のように、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子(=配偶者以外の者の養子)となった場合は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
・子の遺族基礎年金について
「養子となったとき」は遺族基礎年金の受給権は消滅しますが、「直系血族又は直系姻族の養子」となったときは失権しません。問題文の子は、直系血族又は直系姻族の養子となっていますので、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
⑤【R7年出題】
夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が、直系姻族と養子縁組したときは、妻の受給権は消滅するが、子に対する遺族基礎年金の支給停止は解除される。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
遺族基礎年金の受給権を有する妻が、「直系姻族と養子縁組」しても、妻の受給権は消滅しません。
子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「裁定」
R8-073 11.05
給付を受ける権利の裁定
例えば、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある人が65歳に達すると、老齢基礎年金の受給権が発生します。
ただし、給付を受ける権利を取得したとしても、自動的には支払われません。
給付を受けるためには、裁定請求の手続きが必要です。
給付を受ける権利を制度の運営者(国民年金の場合は厚生労働大臣)が確認することを「裁定」といい、裁定は受給権者からの請求によって行われます。
条文を読んでみましょう
法第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。 |
ちなみに、国民年金の「給付」は、次のように規定されています。
法第15条 (給付の種類) この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 (1) 老齢基礎年金 (2) 障害基礎年金 (3) 遺族基礎年金 (4) 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。

【解答】
①【R7年出題】 〇
法第16条は、脱退一時金に準用されます。脱退一時金を受ける権利は、厚生労働大臣が裁定します。
(法附則第9条の3の2第7項)
また、脱退一時金の裁定請求は、「日本年金機構」に請求書を提出することによって行われます。
(則第63条)
※「法第16条(裁定)の規定による請求の受理についての厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせる」とされています。(脱退一時金についても同様です。)
(法第109条の4第1項第6号)
②【R7年出題】
市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。

【解答】
②【R7年出題】 〇
「国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。」と規定されています。(法第3条第3項)
市町村長が処理する事務は、国民年金法施行令第1条の2に定められています。
例えば、年金の加入歴が第1号被保険者のみの場合の老齢基礎年金の請求書は市町村に提出します。
問題文の「裁定の請求の受理・送付等」について条文を読んでみましょう。
則第64条第1項 市町村長は、令第1条の2第3号から第6号までの規定によって、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。 |
➂【R7年出題】
厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
「厚生労働大臣は、法第16条(裁定・脱退一時金に準用する場合を含む。)の規定による受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならない。」とされています。
(則第65条第1項)
また、「厚生労働大臣は、法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、所定の事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを①の通知書に添えて、当該受給権者に交付しなければならない。」とされています。
(則第65条第2項)
④【R5年出題】
老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。

【解答】
④【R5年出題】 〇
年金の受給権の裁定をしたときは、厚生労働大臣は年金証書を交付します。
ただし、例外もあります。
「老齢基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているとき、障害基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の年金証書の交付を受けているとき及び遺族基礎年金の受給権を裁定した場合においてその受給権者が当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の年金証書の交付を受けているときは、この限りでない。」
上記の場合は、「当該老齢厚生年金の年金証書は当該老齢基礎年金の年金証書と、当該障害厚生年金の年金証書は当該障害基礎年金の年金証書と、当該遺族厚生年金の年金証書は当該遺族基礎年金の年金証書とみなす」とされています。
(則第65条第2項、第3項)
⑤【H29年出題】
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
「国民年金基金」が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「国民年金基金」が裁定します。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(法第133条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「被保険者の届出」
R8-072 11.04
第1号被保険者・第3号被保険者の届出
第1号被保険者と第3号被保険者の「届出」についてみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第12条 (届出) ・第1号被保険者について ① 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。 ② 世帯主は、被保険者に代って、届出をすることができる。 ➂ 住民基本台帳法の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく届出があったものとみなす。 ④ 市町村長は、届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であって厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。 ・第3号被保険者 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
・第1号被保険者 → 市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出なければならない
・第3号被保険者 → 厚生労働大臣に届け出なければならない
第1号被保険者と第3号被保険者の違いがポイントです。
②【R7年出題】
被保険者(第3号被保険者を除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
第1号被保険者は、厚生労働大臣ではなく「市町村長」に届け出なければなりません。
➂【R4年出題】
第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。

【解答】
➂【R4年出題】 ×
第1号被保険者は、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければなりません。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、氏名及び住所の変更の届出は要りません。
(則第7条第、則第8条)
④【H20年出題】
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
④【H20年出題】 ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届ではなく「種別変更届」を市町村長に提出しなければなりません。
(則第6条の2)
⑤【H27年出題】
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
第2号被保険者については、国民年金法の届出の規定は適用されません。
そのため、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合は、国民年金法の届出は不要です。
(法附則第7条の4)
⑥【R7年出題】
第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
第3号被保険者については、「厚生労働大臣」に届け出なければならない点がポイントです。
⑦【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を「日本年金機構」に提出しなければなりません。
(則第1条の4第2項)
⑧【R2年出題】
20歳に達したことにより、第3号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、資格取得届の届出を要しないものとされている。

【解答】
⑧【R2年出題】 ×
20歳に達したことにより第3号被保険者の資格を取得した場合は、当該第3号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるとしても、資格取得届の届出は必要です。
※第1号被保険者については、20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときは、届出は要しません。
(則第1条の4第1項)
⑨【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
⑨【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者の届出に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができます。
ちなみに、健康保険組合に委託できるのは、事務の「一部」です。「全部又は一部」ではありませんので注意しましょう。
なお、全国健康保険協会には委託できません。
⑩【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

【解答】
⑩【R1年出題】 〇
第3号被保険者の届出については、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「被保険者」
R8-071 11.03
国民年金の被保険者の資格取得の時期
国民年金の被保険者の資格取得の時期をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第7条 (被保険者の資格) 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 (1)第1号被保険者 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2)第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者 (3)第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの |
法第8条 (資格取得の時期) 前条の規定による被保険者は、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至った日に、その他の者については同号又は第5号のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 (1) 20歳に達したとき。 (2) 日本国内に住所を有するに至ったとき。 (3) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。 (4) 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 (5) 被扶養配偶者となったとき。 |
過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
第1号被保険者は、「20歳に達した日」に資格を取得します。
「20歳に達した日」は、20歳の誕生日の前日ですので、問題文の場合は、平成31年3月31日が20歳に達した日で、その日に第1号被保険者の資格を取得します。
「被保険者期間」は「被保険者の資格を取得した日の属する月」から算入されます。問題文は、「平成31年3月」から被保険者期間に算入されます。
②【H29年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

【解答】
②【H29年出題】 〇
第1号被保険者と第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはその年齢要件はありません。
そのため、厚生年金保険の被保険者であれば、20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者となります。
➂【R5年出題】
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

【解答】
➂【R5年出題】 ×
特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であったとしても、65歳未満の場合は、第2号被保険者となります。
※65歳以上で、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有している場合は、厚生年金保険の被保険者でも、第2号被保険者にはなりません。(法附則第3条)
④【R7年出題】
20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

【解答】
④【R7年出題】 ×
20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った「日」に、国民年金第2号被保険者の資格を取得します。翌日ではありません。
⑤【H27年出題】
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
被扶養配偶者が20歳に達した場合、第3号被保険者に該当しますので、20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得します。
⑥【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
被扶養配偶者が18歳である場合は、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは、その「被扶養配偶者」が20歳に達したときです。厚生年金保険の被保険者が20歳に達したときではありません。
⑦【H29年出題】
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)が任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたときは、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
「日本国内に住所を有しない」場合は、第1号被保険者にはなりません。
そのため、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)」は、国民年金に任意加入することができます。
厚生労働大臣に申し出て任意加入被保険者となることができ、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得します。
(法附則第5条第1項、第3項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R8-069 11.01
配偶者に対する遺族基礎年金の減額改定
遺族基礎年金は、「配偶者」に支給される場合と「子」に支給される場合がありますが、今回は、「配偶者」に対する遺族基礎年金をみていきます。
遺族基礎年金が支給される配偶者は、「子」と生計を同じくしていることが条件です。
そのため、配偶者に対する遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算額が加算されています。
条文を読んでみましょう
法第38条 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 法第39条 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、法第38条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |
★配偶者に支給される遺族基礎年金
子が1人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率 |
子が2人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率+224,700円×改定率 |
子が3人 | 780,900円×改定率 +224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率 |
例えば、子が3人いる場合は、基本の額に(224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率)が加算されます。
3人の子のうち、1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、子の加算額が3人→2人に減額改定されます。
減額改定について条文を読んでみましょう
法第39条第3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (5) 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |
子が(1)~(8)に該当したときは、その子の分、加算額が減額されます。
ただし、「1人を除いた」の部分がポイントです。
配偶者は子があることが要件です。子が全員(1)~(8)に該当した場合は、減額ではなく、遺族基礎年金は失権します。
そのため、「減額」されて支給されるのは、1人でも子がある場合です。
では、問題を解いてみましょう
①【R2年出題】
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

【解答】
①【R2年出題】 〇
配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算額が加算されます。
②【R7年出題】
配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。

【解答】
②【R7年出題】 ×
「配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にあるときを除いて、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに年金額が減額改定される。また、障害等級(1級・2級)に該当する障害の状態にある子の場合は、20歳に達したときに年金額が減額改定される。」となります。
「20歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」は誤りです。
➂【R4年出題】
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
➂【R4年出題】 〇
子が1人で、その子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、子がいなくなるため、夫の遺族基礎年金は減額改定ではなく、失権します。
条文を読んでみましょう
法第40条第2項 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金」
R8-068 10.31
老齢基礎年金の額の計算
老齢基礎年金の満額は「780,900円×改定率」です。
ただし、満額の老齢基礎年金が支給されるのは、保険料納付済期間だけで「480月」ある場合です。
480月の中に、保険料免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金額が減額されます。この方式を「フルペンション減額方式」といいます。
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「学生納付特例の期間」及び「納付猶予の期間」は、老齢基礎年金の額には反映しません。なお、追納すると「保険料納付済期間」として老齢基礎年金の額に算入されます。
(法第27条第8号、平24法附則第14条)
②【R4年出題】
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

【解答】
②【R4年出題】 ×
老齢基礎年金の年金額に反映されるのは、「4分の1」ではなく「4分の3」に相当する月数です。
具体的に計算してみましょう
(その1)保険料納付済期間が480月の場合
・780,900円×改定率×480月/480月(満額)
(その2)保険料納付済期間400月、保険料半額免除期間が80月の場合
・780,900円×改定率×(400月+80月×4分の3(60月))/480月
<老齢基礎年金の額に反映する半額免除期間について>
480月 |
| ||
保険料納付済期間 | 4分の1免除期間 | 半額免除期間 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ポイント!
国庫負担は、480月が限度です。(赤色の部分)
例えば、保険料納付済期間は、老齢基礎年金の額の計算では「1」で反映します。
ただし、「1」のうち、8分の4(2分の1)は国庫負担で、本人が負担した保険料は8分の4(2分の1)です。
半額免除期間は、国庫負担8分の4(2分の1)+保険料負担(8分の2)で、4分の3(8分の6)が反映します。
480月を超えた部分は国庫負担が入りませんので、保険料負担分の8分の2(4分の1)のみが反映します。
問題文は、正しくは、「保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の 4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。」となります。
➂【R5年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】
➂【R5年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳に達した日の属する月前」の期間及び「60歳に達した日の属する月以後の期間」は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
(昭60年法附則第8条第4項)
④【R4年出題】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
④【R4年出題】 ×
老齢基礎年金の額は満額となりません。
問題文の場合、23歳から65歳までの42年間、第1号厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)です。
ただし、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間は「合算対象期間」で老齢基礎年金の年金額には反映しません。
そのため、老齢基礎年金の額に保険料納付済期間として反映するのは、23歳~60歳までの37年間です。60歳以後の5年間は合算対象期間で、老齢基礎年金の額には算入されません。
(昭60年法附則第8条第4項)
⑤【R7年出題】
昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が下記のとおりであるとき、この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は444月となる。
第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月、保険料未納月数24月)
第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間)
第3号被保険者期間 336月

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「456月」となります。
・第1号被保険者期間のうち、保険料を納付した期間が「保険料納付済期間」となりますので、108月です。
・第2号被保険者期間は、20歳以上60歳未満の期間ですので、12月はすべて保険料納付済期間です。
・第3号被保険者期間の336月はすべて保険料納付済期間です。
老齢基礎年金の年金額に反映するのは、108月+12月+336月=456月です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「失踪宣告・死亡の推定」
R8-067 10.30
「失踪宣告」と「死亡の推定」
「失踪宣告」と「死亡の推定」の違いを意識しましょう
■「失踪宣告」について
民法に規定されています。
・「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。」とされていて、失踪の宣告を受けた者は7年の期間が満了した時に、死亡したものとみなす。」とされています。
(民法第30条第1項、第31条)
生死が明らかでない者を、法律上死亡したものとみなす制度です。
■「死亡の推定」について
失踪期間の満了を待っているうちに、子が高校を卒業してしまい遺族基礎年金が受けられなくなる可能性もあります。
そのため、国民年金法では、特例を設けています。
国民年金法の条文を読んでみましょう
法第18条の3 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった者の生死が3か月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。 |
ポイント!
死亡の推定が適用されるのは、「船舶」の沈没等、「航空機」の墜落等の場合です。
過去問を解いてみましょう
①【H18年出題】
失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。

【解答】
①【H18年出題】 ×
失踪宣告があったときは、行方不明になってから「7年」を経過した日に死亡したものとみなされます。
②【H26年出題】
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。

②【H26年出題】 〇
失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、「生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件」については、行方不明になった日を死亡日として取り扱うことになっています。
条文を読んでみましょう
第18条の4 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金について「死亡日」とあるのは「行方不明となった日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となった当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。 |
行方不明となった日=死亡日 | 生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件 |
7年を経過した日 | 身分関係、年齢、障害の状態 |
➂【R2年出題】
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

【解答】
➂【R2年出題】 ×
遺族基礎年金の支給に関する保険料納付要件は、「死亡日の前日」で判断されます。そのため失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の保険料納付要件は、「行方不明となった日の前日」で判断されます。
④【R7年出題】
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者の子に対する遺族基礎年金は、失踪の宣告を受けた日において子の年齢が18歳に達する日以後の最初の3月31日に達している場合であっても、失踪の宣告を受けた者の所在が明らかでなくなった日が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であれば、その日まで遡って受給できる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態は、行方不明となった日ではなく、死亡したとみなされた日で判断されます。
なお、遺族基礎年金の受給権は、行方不明となった日ではなく、死亡したとみなされた日に発生します。
⑤【H26年出題】
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
「1か月間」ではなく「3か月間」です。
⑥【H22年出題】
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。

【解答】
⑥【H22年出題】 ×
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、「その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日」ではなく、「その船舶が行方不明になった日」にその者は死亡したものと推定されます。
なお、遺族基礎年金の受給権は、「船舶が沈没等をした日・航空機が墜落等をした日」に発生します。
⑦【H29年出題】
冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。

【解答】
⑦【H29年出題】 ×
冬山の登山中に行方不明になっても、死亡の推定は適用されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「合算対象期間」
R8-043 10.06
合算対象期間の基本3つ
老齢基礎年金の支給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることです。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年未満でも、合算対象期間を合算して10年以上あれば、要件を満たします。
「合算対象期間」は、「カラ期間」ともいわれ、10年の計算には入りますが、老齢基礎年金の年金額の計算には入りません。
今回は、合算対象期間の基本を3つみていきます
 任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間
任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間
 海外在住邦人について
海外在住邦人について
 厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
では、合算対象期間の過去問を解いてみましょう
 <任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間>
<任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間>
①【H23年出題】
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。

【解答】
①【H23年出題】 ×
昭和60年改正前の国民年金法(旧法)で、任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間は合算対象期間となります。ただし、「20歳以上65歳未満」ではなく合算対象期間となるのは「20歳以上60歳未満」の期間です。
(昭60法附則第8条第5項第1号)
②【R5年出題】
昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】
②【R5年出題】 ×
学生が国民年金に強制加入することになったのは、「平成3年4月1日」以降で、それまでは「任意加入」することができました。
そのため、合算対象期間になるのは、昭和36年4月1日から平成3年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生で任意加入しなかった期間となります。
(昭60法附則第8条第5項第1号)
★学生について
旧 法 | 新 法 | |
S36.4.1 | S61.4.1 | H3.4.1 |
任意加入 | 強制加入 | |
 <海外在住邦人について>
<海外在住邦人について>
➂【R7年出題】
日本国籍を有する人が、20歳から60歳までの間に、日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は、国民年金の任意加入被保険者でなくても、老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
旧法の国民年金法では、日本国籍を有する人が海外に在住している間は国民年金の適用が除外され、任意加入もできませんでした。
そのため、日本国籍を有する人が日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間(旧法の期間)は、合算対象期間となります。20歳から60歳までの間に限られていることにも注意してください。
(昭60法附則第8条第5項第9号)
旧 法 | 新 法 |
適用除外(任意加入もできない) | 任意加入できる |
 厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
厚生年金保険の被保険者期間の20歳未満・60歳以後
④【R7年出題】
昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間及び60歳以上の期間は合算対象期間となる。

【解答】
④【R7年出題】 〇
昭和61年4月1日以後の第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は合算対象期間です。
(昭60法附則第8条第4項)
★第2号被保険者期間について
第2号被保険者 | ||
| 20歳 | 60歳 |
合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |
なお、「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで」の間の、被用者年金(厚生年金保険・共済年金)の被保険者期間についても、20歳未満・60歳以上の期間は合算対象期間となります。
(昭60法附則第8条第6項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「保険料納付済期間」
R8-025 9.18
保険料納付済期間に含む期間・含まない期間
国民年金法には、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」があります。
年金の受給資格の有無や、受給額の計算に影響します。
今回は、「保険料納付済期間」の定義をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第5条第1項 国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定(滞納処分)により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び第88条の2の規定(産前産後期間の保険料免除)により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
<保険料納付済期間>
①第1号被保険者としての被保険者期間のうち
・納付された保険料に係るもの
・産前産後期間の保険料免除により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの
・滞納処分により徴収された保険料は保険料納付済期間に含む
・一部免除により納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものは除く
②第2号被保険者としての被保険者期間
③第3号被保険者としての被保険者期間
①+②+③の期間を保険料納付済期間といいます。
では、過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間も、「滞納処分により徴収」された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間」も、保険料納付済期間となります。
②【R3年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

【解答】
②【R3年出題】 〇
例えば半額免除の規定が適用され、免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく「保険料半額免除期間」です。
(法第5条第5項)
保険料半額免除期間
半額 納 付 |
半額 免 除 |
③【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】
③【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用されている者について、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。
(法第5条第6項)
保険料4分の1免除期間
4分の3 納 付
|
4分の1 免 除 |
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
④【H24年出題】 〇
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間ではなく「保険料納付済期間」となります。
法第94条第4項に規定されています。読んでみましょう。
| 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 |
⑤【R5年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては、保険料納付済期間には算入されず、「合算対象期間」に算入されます。
(昭60法附則第8条第4項)
20歳 |
| 60歳 |
合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |
⑥【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
⑥【H24年出題】 ×
「障害基礎年金と遺族基礎年金」については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、「保険料納付済期間」となります。老齢基礎年金との違いに注意しましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第30条の4の障害基礎年金」
R8-024 9.17
第30条の4の障害基礎年金の支給停止事由
第30条の4の障害基礎年金は、20歳前傷病による障害基礎年金ともいわれます。
国民年金に加入する前(=国民年金保険料の負担をしていない)に初診日がある傷病が対象ですので、通常の障害基礎年金にはない支給停止事由が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項、第2項 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 (1) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 (2) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 (3) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 (4) 日本国内に住所を有しないとき。 ② ①(1)に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が第36条第1項又は第41条第1項に規定する給付が行われることによるものであるときは、この限りでない。
第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問を解きながら覚えるポイントをつかみましょう
①【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、支給が停止されます。
②【H25年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】
②【H25年出題】 〇
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。
③【R7年出題】
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が、恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。

【解答】
③【R7年出題】 〇
■国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の支給が停止される事由
・恩給法に基づく年金たる給付、労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
・少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
・日本国内に住所を有しないとき
なお、「受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えるとき」も支給が停止されます。 次の問題で確認しましょう。
④【R7年出題】
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止される。

【解答】
④【R7年出題】 〇
国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に、その全部又は2分の1に相当する部分が支給停止されます。
なお、扶養親族等がいない場合は、
・前年の所得が472万1千円を超える場合 → 年金の全額が支給停止
・前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下の場合→ 2分の1が支給停止
となります。
⑤【R5年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1ではなく、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されます。
⑥【H27年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

【解答】
⑥【H27年出題】 ×
「受給権者の前年の所得」で判断されます。
扶養親族の所得は合算しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「不服申立て」
R8-023 9.16
国民年金法の不服申立て・審査請求と訴訟との関係
「不服申立て」について、問題を解きながらポイントをおさえましょう。
まず、「不服申立て」について条文を読んでみましょう。
第101条 ① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ただし、第14の4第1項又は第2項の規定による決定(国民年金原簿の訂正請求についての厚生労働大臣の訂正する旨又は訂正しない旨の決定)については、この限りでない。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 ⑤ ①の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法第2章(第22条を除く。)及び第4章の規定は、適用しない。 ⑥ 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法をいう。)の定めるところにより、当該共済各法に定める審査機関に審査請求をすることができる。 ⑦ 共済組合等が行った障害の程度の診査に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく障害基礎年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
(審査請求と訴訟との関係) 第101条の2 前条①に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
過去問を解きながらポイントをおさえましょう
<社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる>
①【H30年出題】
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
「2か月以内」がポイントです。
<国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨の厚生労働大臣の決定>
②【H28年出題】
厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正の請求について、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが、その決定を受けた者が、その決定に不服があるときは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
厚生労働大臣が行った国民年金原簿の訂正請求に係る訂正をする旨又は訂正をしない旨の決定については、社会保険審査官に対する審査請求の対象になりません。
<審査請求と訴訟との関係>
③【H29年出題】
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審官の決定」を経た後でなければ、提起することができない、とされています。
④【R7年出題】
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
①被保険者の資格に関する処分
②給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
③保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分
ポイント!
①又は②について
①又は②の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。となります。
③について
③の処分について
・社会保険審査官に審査請求をする
又は
・社会保険審査官に審査請求をせずに、処分の取消しの訴えを提起する
→ ③の処分については、「審査請求する」か「処分の取消しの訴えを提起する」を選択することが可能です。
⑤【R6年出題】
国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ提起することができない。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ、提起することができない、となります。
<共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分>
⑥【R3年出題】
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)の定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることができない。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分については、社会保険審査官に対する審査請求の対象になりません。
共済組合等に係る共済各法の定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(国民年金法)から学ぶ
R8-012 9.05
R7年選択式は国民年金の保険料額・学生納付特例の所得要件
令和7年の国民年金の選択式は、
①国民年金の保険料額
②学生納付特例の所得要件
からの出題でした。
どちらも数字の暗記が必要でした。
 国民年金の保険料額について
国民年金の保険料額について
過去問からどうぞ!
【R5年出題】
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

【解答】
【R5年出題】 ×
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)」ではなく、「17,000円」に保険料改定率を乗じて得た額となります。
なお、保険料改定率は、毎年度、名目賃金変動率に応じて改定されます。
(法第87条)
平成16年の改正で、国民年金の保険料は、毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度に引上げが完了しました。
産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことにより、令和元年度以降は、保険料額は100円引き上げられ17,000円となっています。
令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
国民年金の保険料は、< A >の年金制度改正により、< A >度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の< B >に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、< C >の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。
<選択肢>
⑨ 13,300円 ⑩ 16,800円 ⑪ 16,900円 ⑫ 17,000円
⑬ 遺族基礎年金の父子家庭への支給
⑭ 産前産後期間の保険料免除制度
⑮ 年金額の特例水準の解消
⑯ 年金生活者支援給付金
⑰ 平成6年 ⑱ 平成12年 ⑲ 平成16年 ⑳ 平成24年

【解答】
<A> ⑲ 平成16年
<B> ⑪ 16,900円
<C> ⑭ 産前産後期間の保険料免除制度
 学生納付特例に係る所得要件
学生納付特例に係る所得要件
まず過去問をどうぞ!
【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
【H28年出題】 〇
学生納付特例については、「世帯主又は配偶者」の所得要件は問われないのがポイントです。
本人の所得のみで判断されます。
(法第90条の3)
令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは< D >万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき < E >万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。
<選択肢>
① 32 ② 35 ③ 36 ④ 38
⑤ 103 ⑥ 106 ⑦ 128 ⑧ 168

【解答】
<D> ⑦ 128
<E> ④ 38
(令第6条の9)
・学生納付特例に係る所得要件は、扶養親族等がないときは128万円です。
・学生納付特例に係る所得要件の額と半額免除の所得要件の額は同じです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R7-327 07.21
遺族基礎年金の事例問題を解いてみましょう
今回は、遺族基礎年金の事例問題を解いています。
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡した場合に、一定の遺族に支給されます。
次の(1)から(4)のいずれかに該当することが要件ですが、
(1)と(2)は保険料納付要件が問われます。
(1) 被保険者が、死亡したとき。
(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
(3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
(4) 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
事例問題を解きながら、4つの要件を具体的にイメージしましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R7-320 07.14
障害基礎年金の事例問題を解いてみましょう
障害基礎年金の受給権は、次の3つの要件を満たした場合、障害認定日に発生します。 ・初診日要件
・保険料納付要件
・障害認定日要件
事例の過去問を解きながら、障害基礎年金のルールを身につけましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「配偶者の遺族基礎年金の額」
R7-317 07.11
配偶者の遺族基礎年金の減額改定と失権
配偶者の遺族基礎年金には、必ず子の加算額が加算されます。
子の加算額は、子の数に応じて算定されます。
子の数が減少すると、それに応じて、子の加算額が減額されます。
条文を読んでみましょう。
法第39条第3項 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 (5) 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |
■ 配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が2人の場合)
2人の子のうち1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態ではない)は、子の加算額が「2人分」から「1人分」に減額改定されます。
■配偶者に支給される遺族基礎年金について(子が1人の場合)
1人しかいない子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態ではない)は、子がいなくなるため配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。「減額改定」ではありませんので、注意して下さい。
「配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、法第40条第1項の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、法第39条第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。」
(法第40条第2項)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H25年出題】 〇
生計を同じくしている子が1人の妻が遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
②【R4年出題】
被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合で、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、生計を同じくする子がいなくなるので、夫の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
③【H19年出題】※改正による修正あり
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が「配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき」は失権します。
そのため、加算事由に該当するすべての子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、配偶者の遺族基礎年金は失権します。
ちなみに、子が直系血族又は直系姻族の養子となったときでも、子自身の遺族基礎年金は失権しません。
(法第40条第1項第3号)
④【R5年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】
④【R5年出題】 〇
・配偶者の遺族基礎年金について
→ 「すべての子が配偶者以外の者の養子となった場合」は配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。問題文のように「すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合」は、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅します。
・子の遺族基礎年金について
→ 養子となった場合でも、「直系血族又は直系姻族の養子になった」場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金の額」
R7-316 07.10
<遺族基礎年金>配偶者に支給する額と子に支給する額の違い
遺族基礎年金の額についてみていきます。
「配偶者」に支給する額と「子」に支給する額は、それぞれ計算式が異なりますので注意しましょう。
・遺族基礎年金の額(基本の額)について条文を読んでみましょう。
法第38条 (年金額) 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
・配偶者に支給する額について条文を読んでみましょう。
法第39条第1項 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち 2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |
★配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず「子の加算」が加算されます。
子が1人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率) |
子が2人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (224,700円×改定率) |
子が3人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (224,700円×改定率)+(74,900円×改定率) |
・子に支給する額について条文を読んでみましょう。
法第39条の2第1項 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、780,900円×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 |
★子に支給される遺族基礎年金の額
子が1人の場合 | (780,900円×改定率) ※加算はありません |
子が2人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率) |
子が3人の場合 | (780,900円×改定率)+(224,700円×改定率)+ (74,900円×改定率) |
それぞれの子に支給される額は、「子の人数で除して得た額」です。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。

【解答】
①【R2年出題】 〇
配偶者が遺族基礎年金を受ける要件は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、子と生計を同じくすること」です。
配偶者は必ず子と生計を同じくしていますので、配偶者に支給される遺族基礎年金には、必ず、子の加算額が加算されます。
②【R3年出題】
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
(※令和3年度の給付額です)

【解答】
②【R3年出題】 ×
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として「224,700円、74,900円、74,900円」を合計した金額です。
子それぞれが受給する額は、子の数で除した金額となります。
③【H22年出題】
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

【解答】
③【H22年出題】 ×
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に「224,700円に改定率を乗じて得た額」を加算した額を2(子の人数)で除して得た額となります。
④【H28年出題】
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

【解答】
④【H28年出題】 ×
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、「224,700円に改定率を乗じて得た額」と「74,900円に改定率を乗じて得た額」を加算し、その合計額を3で除した額が3人の子それぞれに支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「併給調整」
R7-313 07.07
国民年金法の併給調整についてお話しします
一人の人に複数の年金の受給権が発生することがあります が、原則は「一人一年金」です。
ただし、併給できる組合せもあります。
よく出題されますので、問題を解けるようにしましょう。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「学生納付特例」
R7-306 06.30
学生納付特例制度についてお話しします
学生が国民年金に強制加入となったのは、平成3年4月からです。
平成3年3月までは、学生は任意加入でした。
学生も第1号被保険者として国民年金の保険料を納付しなければなりませんが、学生については、保険料の納付が猶予される制度があります。
「学生納付特例制度」といいます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「納付猶予」
R7-301 06.25
保険料納付猶予制度について
・保険料納付猶予制度は、50歳未満(50歳に達する日の属する月の前月まで)の第1号被保険者が対象です。
・所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
★保険料納付猶予のポイント!
・所得は本人のみならず、配偶者の所得も一定以下であることが条件です
・老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

【解答】
①【R5年出題】 ×
・学生納付特例制度 → 国民年金法本則(法第90条の3)に規定されています
・納付猶予制度 → 本則ではなく、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されています。
②【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

【解答】
②【R3年出題】 ×
納付猶予制度は、令和12年6月までの時限措置です。ちなみに、3月までではなく6月までですので注意しましょう。
学生納付特例制度は時限措置ではなく、恒久的な制度ですので問題文は誤りです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「国民年金原簿」
R7-300 06.24
国民年金原簿と訂正の請求
国民年金原簿には、保険料の納付状況などが記録されています。
また、年金記録が事実と異なると思う人は、年金記録の訂正を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
法第14条 (国民年金原簿) 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
法第14条の2第1項 (訂正の請求) ① 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。
法第14条の3 (訂正に関する方針) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。 ② 厚生労働大臣は、方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
法第14条の4 (訂正請求に対する措置) ① 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。 ② 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。 ③ 厚生労働大臣は、決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
当分の間、第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録・訂正の請求の対象から除かれています。
第2号被保険者については、「第1号厚生年金被保険者」のみが対象となります。
(法附則第7条の5第1項)
②【R4年出題】
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

【解答】
②【R4年出題】 〇
第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)、地方公務員共済組合の組合員(第3号厚生年金被保険者)又は私立学校教職員共済制度の加入者(第4号厚生年金被保険者)であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されません。
(法附則第7条の5第1項)
③【R1年出題】
国民年金原簿には、所定の事項を記録するものとされており、その中には、保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
保険料4分の3免除、保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項は、国民年金原簿の記載事項です。
(則第15条)
④【H30年出題】
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

【解答】
④【H30年出題 〇
寡婦年金を受けることができる妻は、死亡した夫に関する国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。
(法第14条の2第2項)
⑤【R2年出題】
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
厚生労働大臣は、「社会保険審査会」ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければなりません。
⑥【H27年選択式】
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は< A >に委任されており、 < A >が決定しようとするときは、あらかじめ< B >に諮問しなければならない。

【解答】
⑥【H27年選択式】
<A> 地方厚生局長又は地方厚生支局長
<B> 地方年金記録訂正審議会
条文を読んでみましょう。
法第109条の9 ① この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第109条の5第1項及び第2項並びに第10章に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ② 地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ③ 第14条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。 ※厚生労働省組織令第153条の2 ① 地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。 ② 地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
事例問題(国民年金法)
R7-299 06.23
国民年金法の事例問題を解いてみましょう
厚生年金保険に7年間、第1号被保険者として保険料を27年間納付した男性が54歳で死亡した場合の「事例問題」を解いていきます。
<問題のテーマ>
①遺族が80歳の母の場合
②遺族が50歳の妻の場合
③遺族が12歳と15歳の子の場合
④遺族が50歳の弟と60歳の兄の場合
⑤事実婚関係の45歳の妻と13歳の妻の連れ子の場合
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R7-297 06.21
障害基礎年金の失権
障害基礎年金の受給権の消滅時期を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (3) 厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
図でイメージしましょう。
少なくとも、65歳までは失権しないことがポイントです。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第31条 (併給の調整) ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
②【H20年出題】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
②【H20年出題】 ×
★ポイント!
厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態 → 3級のことです。
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、その時点では当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金が失権する時期は、「3級に該当しなくなった日から3年を経過」か「65歳」のどちらか遅い方です。
3級に該当しなくなった日から3年を経過しても、65歳未満の場合は、失権しません。
③【H30年出題】
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
「3級に該当する程度の状態」の場合は、障害基礎年金は失権しませんので注意してください。
図でイメージしましょう。
63歳の時に障害状態が3級程度に軽減した場合、障害基礎年金の支給が停止されますが、3級に該当する程度の状態にある間は失権はしません。
そのため、3級に該当する状態のまま、5年経過後に再び障害状態が悪化し2級に該当した場合は、支給停止が解除されます。
④【R3年出題】
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
④【R3年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときは、当該障害基礎年金の受給権は消滅しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
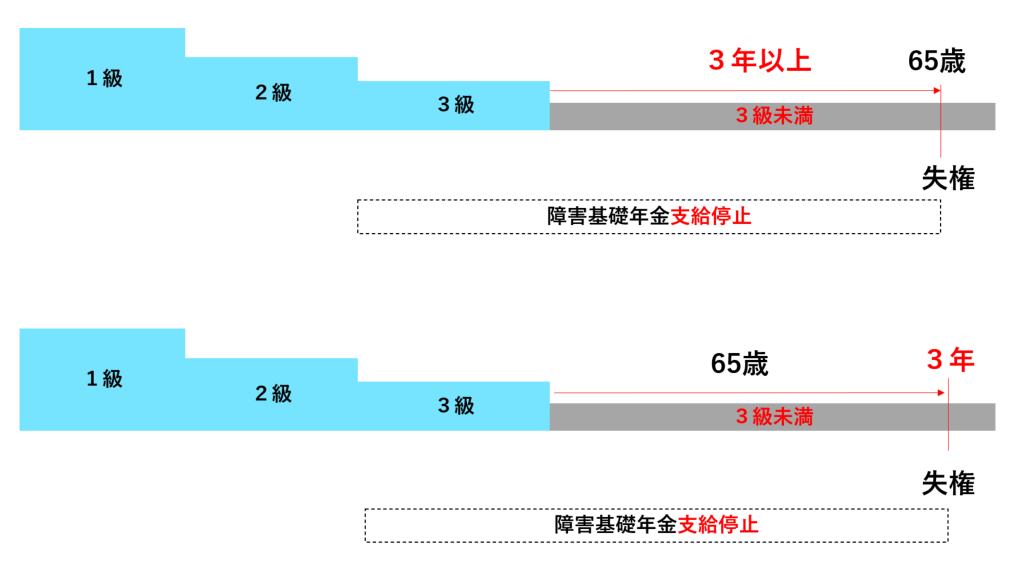
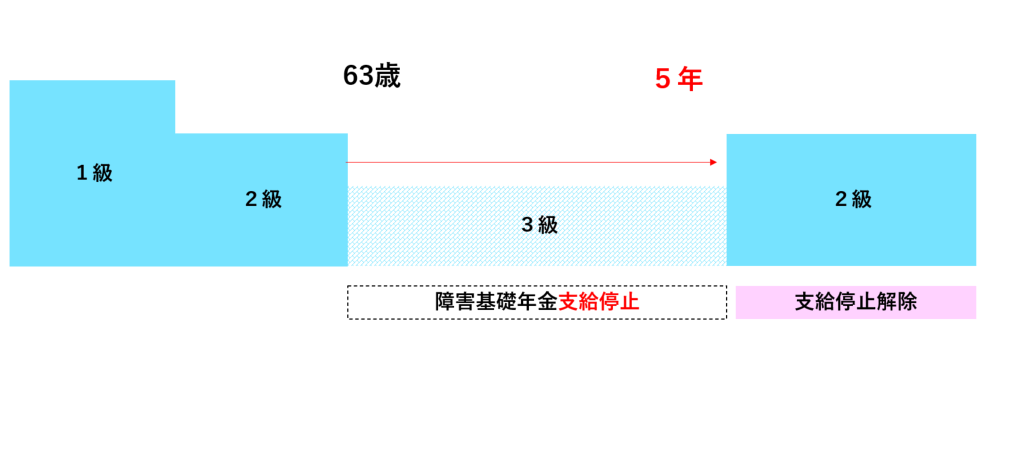
国民年金法「障害基礎年金」
R7-296 06.20
その他障害との併合による障害基礎年金の額の改定
例えば、2級の障害基礎年金の受給権者に、その他障害(1級・2級未満の障害)が発生し、前後の障害を併合すると障害の程度が1級に増進した場合は、障害基礎年金の額の改定を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
法第34条第4項 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。)に係る当該初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 |
図でイメージしましょう。
<その他障害のポイント!>
・1級、2級に該当しないこと(3級以下)
・初診日要件、保険料納付要件を満たしていること
<額の改定の要件>
・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したこと
+
・その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に額の改定を請求すること
過去問をどうぞ!
【H26年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。

【解答】
【H26年出題】 ×
その他障害による額の改定の要件は、「その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に、従前の障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害とを併合した障害の程度が従前の障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。」です。
問題文のように、その他障害の初診日の段階で、66歳の場合は、要件を満たしませんので、障害基礎年金の額の改定請求はできません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
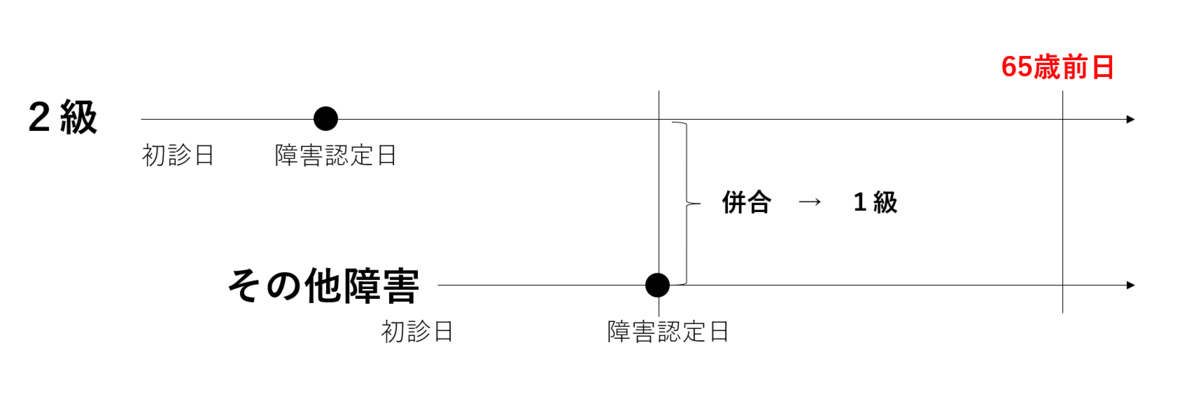
国民年金法「障害基礎年金」
R7-295 06.19
障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定
例えば、障害等級が2級から1級に変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。
今回は、
・厚生労働大臣の職権による改定
・受給権者からの請求による改定
をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第34条第1項~第3項 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ③ 請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
★障害の程度が増進(重くなった)ときは、受給権者は、額の改定を請求できます。
<請求の要件>
・障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日後
又は
・厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても請求できます。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
受給権者が65歳以上でも、障害基礎年金の額の改定の対象となります。
②【R5年出題】
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
③【R6年出題】
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】
③【R6年出題】 ×
「1年6か月」ではなく、「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
④【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

④【R2年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年経過しなくても、額の改定請求を行うことができます。
「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合」は、「障害の程度が増進したことが明らかな場合として厚生労働省令で定める場合」に該当しますので、1年経過しなくても、年金額の改定の請求をすることができます。
(則第32条の2の2第1項第9号)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「用語の定義」
R7-294 06.18
「保険料納付済期間」の定義
「用語の定義」を正確におさえておくと、条文も読みやすくなります。
今回は「保険料納付済期間」の定義をみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第5条第1項 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中の納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
<保険料納付済期間とは>
★第1号被保険者としての被保険者期間
・保険料を納付した期間
※督促・滞納処分により徴収された保険料を含む
※一部免除によりその残余の額が納付又は徴収されたものは除く。
・産前産後期間中の免除を受けた期間
★第2号被保険者としての被保険者期間
★第3号被保険者としての被保険者期間
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

【解答】
①【H24年出題】 〇
督促及び滞納処分により保険料が納付された期間も、保険料納付済期間に含まれます。
②【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
②【H24年出題】 〇
保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
(法第94条)
③【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】
③【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用されている者で、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合は、保険料納付済期間ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。
(法第5条第1項、第6項)
④【R2年出題】
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「産前産後期間の保険料免除」により保険料を免除された期間は、「保険料納付済期間」となります。
ちなみに、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間です。
(法第5条第1項、第3項)
⑤【H28年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
第2号被保険者としての被保険者期間は「保険料納付済期間」に含まれます。
ただし、「老齢基礎年金」については、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。
条文を読んでみましょう。
昭60年法附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
⑥【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
⑥【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、合算対象期間となります。
「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」には、そのような扱いはありません。第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、原則とおり、「保険料納付済期間」となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金・厚生年金保険「時効」
R7-279 06.03
<国年・厚年比較>時効について
国民年金法と厚生年金保険法の「時効」を比較してみましょう。
まず、国民年金の条文を読んでみましょう。
国民年金法第102条 (時効) ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ② 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
ポイント!
「年金給付」→ 年金のみです。死亡一時金は入りません。
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
第92条 (時効) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ③ 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 |
ポイント!
「保険給付」 → 障害手当金も入ります。年金のみではありません。
過去問をどうぞ!
国民年金法
①国年【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①国年【H27年出題】 ×
「年金給付」を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
「死亡一時金」を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
②国年【R2年出題】
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
②国年【R2年出題】 〇
「年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うもの」を「支分権」といいます。
支分権の時効についての問題です。
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は「支払期月の翌月の初日」から起算して5年を経過したときに時効によって消滅します。
厚生年金保険法
①厚年【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①厚年【H29年出題】 ×
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から「5年」を経過したときは、時効によって消滅します。
国民年金の「死亡一時金」は「2年」ですので違いに注意しましょう。
②厚年【H30年出題】
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間であっても進行する。

【解答】
②厚年【H30年出題】 ×
年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、「進行しない」。
③厚年【R4年出題】
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】
③厚年【R4年出題】 〇
支分権の時効の問題です。
時効の起算点の「支払期月の翌月の初日」がポイントです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「振替加算の練習その4」
R7-275 05.30
<振替加算第4回目>老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・第4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
今回は第4回目です。
老齢基礎年金は、請求によって繰上げて受けることができ、また、申出によって繰り下げて受けることもできます。
<老齢基礎年金の繰上げについて>
・繰上げ請求のあった日の属する月の翌月から支給される
・繰り上げた月数によって減額される
<老齢基礎年金の繰下げについて>
・申出のあった日の属する月の翌月から支給される
・繰り下げた月数によって増額される
老齢基礎年金を繰り上げて、又は繰り下げて受ける場合の振替加算の扱いをみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 振替加算は、「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「65歳に達した日の属する月の翌月」から加算されます。振替加算は、繰上げされません。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 問題文のとおり「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます
(昭60法附則第14条)
②【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
②【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算されません。
③【R3年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】
③【R3年出題】 〇
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後に加算されます。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 振替加算も繰下げて支給されます。ただし、振替加算額には、繰下げによる増額はありません。
④【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】
④【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「振替加算の練習その3」
R7-274 05.29
<振替加算第3回目>振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・第4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
今回は第3回目です。
<振替加算が行われないとき>
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、要件に該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。
※政令で定めるものは、老齢厚生年金又は退職共済年金で、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上のものです。 (昭61年経過措置令第25条) |
<振替加算が支給停止されるとき>
昭60年法附則第16条 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
単なる老齢厚生年金ではなく、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金であることに注意して下さい。
②【H27年出題】
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
②【H27年出題】 〇
合意分割の結果、離婚時みなし被保険者期間を含めて厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となる老齢厚生年金を受けることになった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。
③【R3年出題】
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

【解答】
③【R3年出題】 ×
「中高齢の期間短縮特例」により、昭和26年4月2日生まれの女性は、35歳以後の厚生年保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が19年ある場合は、「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」あるとみなされます。
問題文の妻は、中高齢の期間短縮特例を満たしているため、妻の老齢基礎年金に振替加算は行われません。
④【H30年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】
④【H30年出題】 〇
障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算は支給が停止されます。
⑤【H21年出題】
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。

【解答】
⑤【H21年出題】 〇
障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間振替加算が支給停止されます。
⑥【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

【解答】
⑥【H21年出題】 ×
障害基礎年金の受給権を有していても、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。
⑦【R3年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
⑦【R3年出題】 ×
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときでも、振替加算の支給は停止されません。
⑧【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

【解答】
⑧【H21年出題】 〇
配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚しても、離婚したことを理由とする振替加算の支給停止はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「振替加算の練習その2」
R7-273 05.28
<振替加算第2回目>振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第2回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・第4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
今回は第2回目です。
<振替加算の額>
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であるもの)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)=1級・2級 |
★振替加算の額は
224,700円×改定率×「その者の生年月日に応じて政令で定める率」です。
政令で定める率は、以下の通りです。
受給権者の生年月日 | 政令で定める率 |
大正15年4月2日~昭和2年4月1日まで | 1.000 |
↓ | ↓ |
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日まで | 0.067 |
生年月日が若いほど、政令で定める率が小さくなる(振替加算の額が少なくなる)のがポイントです。
<振替加算のみの老齢基礎年金>
老齢基礎年金の額がゼロでも、要件に該当する場合は、振替加算のみの老齢基礎年金が支給されることがあります。
・保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間を除く。)を有しない場合は、老齢基礎年金の額はゼロです。
↓
・合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例期間に限る。)を合算した期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。ただし、老齢基礎年金の額はゼロです。
↓
・そのような者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給されます。
(昭60法附則第15条第2項)
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれたものであるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

【解答】
①【R4年出題】 ×
振替加算の額は、「受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額です。
②【H18年出題】
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。

【解答】
②【H18年出題】 ×
振替加算の金額は、「224,700円に改定率を乗じて得た額」に、「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者の生年月日」に応じて定められた率を乗じた額です。
③【H27年出題】
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】
③【H27年出題】 〇
・甲(妻)は、合算対象期間のみ40年有していて、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしている。
・甲(妻)は乙(夫)の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていて、65歳時点で夫に生計を維持されている
・甲には、65歳になると「振替加算額に相当する額の老齢基礎年金」が支給されます
④【H21年出題】
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

【解答】
④【H21年出題】 ×
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月でもあれば、その期間で計算された老齢基礎年金が支給されます。
「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」ではなく、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)の月数に応じて計算された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「振替加算の練習その1」
R7-272 05.27
<振替加算第1回目>振替加算が支給される要件
振替加算の基本はこちらの動画<音声が出ますのでご注意ください>をご覧ください。
今回から4回に分けて振替加算の問題をみていきます。
・第1回目 振替加算が加算される要件
・第2回目 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
・第3回目 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
・第4回目 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたとき
今回は第1回目です。
振替加算が加算される要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
昭60法附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、224,700円に改定率を乗じて得た額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則240以上であるもの)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)=1級・2級 |
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。

【解答】
①【H22年出題】 〇
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に振替加算を加算する特例が設けられています。
②【H21年出題】
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
遺族基礎年金には振替加算は加算されません。
③【R2年出題】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

【解答】
③【R2年出題】 〇
「振替加算の対象となる者」に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る「振替加算の加算開始事由に該当した日」における生計維持関係により行われます。
④【H30年出題】
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
④【H30年出題】 〇
老齢厚生年金の額に加給年金額が加算される要件は、原則として厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることです。
ただし、中高齢の期間短縮特例が適用される場合もあります。問題文の昭和25年4月2日生まれの男性の場合は、40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る)が19年以上あれば要件を満たします。
問題文の夫の老齢厚生年金には加給年金額が加算されていますので、妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
⑤【H27年出題】
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
65歳より後に要件に該当した場合でも、振替加算は加算されます。
問題文の妻には、老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
⑥【H27年出題】
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
⑥【H27年出題】 〇
妻が65歳になった後で振替加算の要件に該当した場合の問題です。
夫は67歳のときに、退職時改定で、老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間(20年以上)の要件を満たした
・夫に生計を維持されている老齢基礎年金を受給している66歳の妻に、その時点から振替加算が加算されます。
(図でイメージしましょう)
なお、その際、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
(昭60法附則第14条第2項、則第17条の3第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
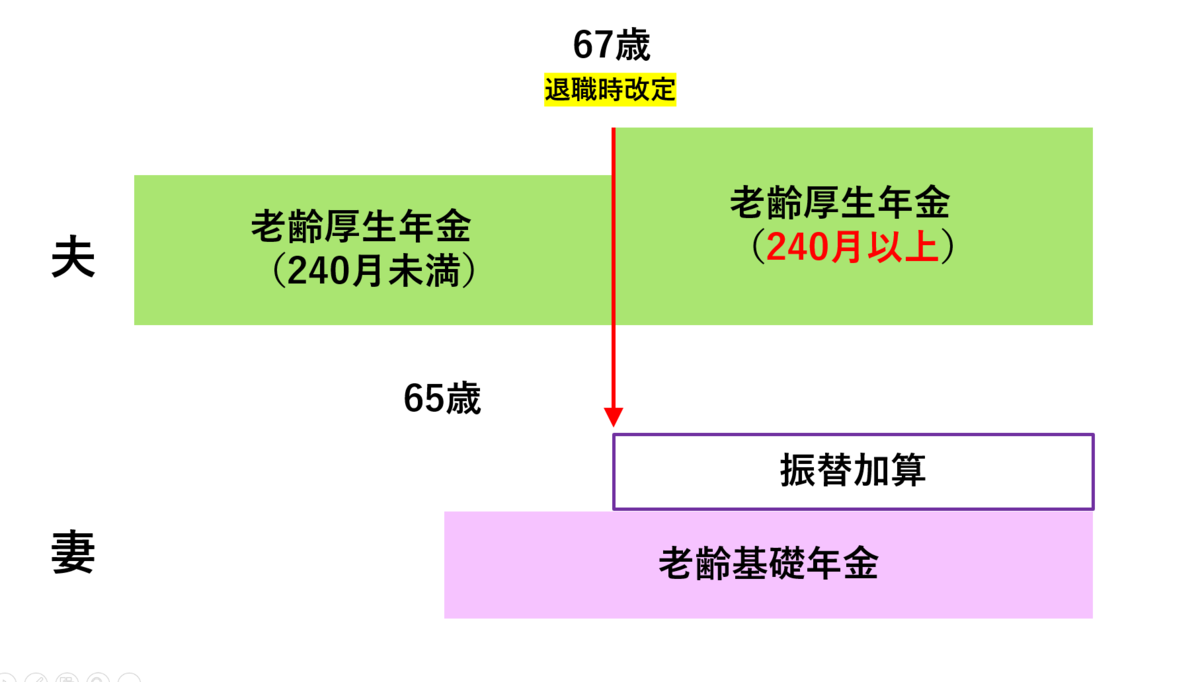
国民年金法「振替加算」
R7-271 05.26
「振替加算」の基本をお話しします
「振替加算」の基本をお話しします。
振替加算は、昭和61年4月1日前の「旧法」の制度や、厚生年金保険法の加給年金額の仕組みを知ると、分かりやすいです。
「なぜ、振替加算の制度ができたのか?」
「なぜ、振替加算の額は生年月日によって変わるのか?」 等お話ししています。
また、5月27日以降、4回に分けて振替加算問題も解いていきます。
【今後のスケジュール】
5月27日<1回目> 振替加算が加算される要件
5月28日<2回目> 振替加算の額・振替加算のみの老齢基礎年金
5月29日<3回目> 振替加算が行われないとき、振替加算の支給が停止されるとき
5月30日<4回目> 老齢基礎年金を繰上げたとき、繰り下げたときの振替加算
また、5月31日は、老齢厚生年金と障害厚生年金に加算される「配偶者加給年金額」もみていきます。
YouTubeはこちらから
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<比較>遺族基礎年金と遺族厚生年金
R7-257 05.12
【国年と厚年を比較】遺族年金の子の支給停止の違いをお話しします
遺族基礎年金と遺族厚生年金の「子」の支給停止の扱いについてお話しします。
<共通事項>
・配偶者が遺族基礎(厚生)年金の受給権を有する場合、子の年金はどうなる?
<例外>
・配偶者の年金が申し出により支給停止になった場合
・生計を同じくするその子の父・母がある場合
<応用>
・配偶者に遺族基礎年金の受給権がない場合
などお話しします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第3号被保険者届出その3」
R7-255 05.10
第3号被保険者「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」
第3号被保険者に関する届出のうち「種別確認届」と「被扶養配偶者でなくなったことの届出」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
則第6条の3 (種別確認届) 第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。 |
※配偶者である第2号被保険者が転職等により加入する年金制度が変わったときに必要な届出です。
(届出が必要な例)
・民間企業の会社員が転職で国家公務員になった
(第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得した)
・地方公務員が民間企業に転職した
(第3号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した)
など
※届出が要らない場合
・第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき
・実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあっては私学教職員共済制度の加入者をいう。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したとき
第12条の2 (被扶養配偶者でなくなったことの届出) 第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
則第6条の2の2 (被扶養配偶者でなくなったことの届出) 法第12条の2第1項の規定による届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行わなければならない。 |
※届出が必要なとき
・第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた
・離婚した
※届出が要らない場合
・第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった
・第3号被保険者が「厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき」
・死亡した
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、種別確認の届出が必要です。
②【R4年出題】
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

【解答】
②【R4年出題】 ×
「種別変更」ではなく「種別確認」の届出を日本年金機構に対して行わなければなりません。
③【R2年出題】
第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、被扶養配偶者でなくなった旨の届書の提出は不要です。
④【H27年出題】
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

【解答】
④【H27年出題】 〇
・第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者から第1号被保険者の種別の変更の届出が必要です。
・さらに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければなりません。
※なお、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者が、その被扶養配偶者であった者について健康保険の被扶養者でなくなったことの届出を事業主を経由して日本年金機構に提出したときは、「被扶養配偶者非該当届」の提出があったものとみなし、被扶養配偶者非該当届の提出は不要とされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第3号被保険者届出その2」
R7-254 05.09
第3号被保険者の届出が遅れた場合の特例
「第3号被保険者」の制度は、昭和61年4月の新法施行時に創設されました。
当初は、第3号被保険者に該当したときは、本人が市町村に直接届出をしなければならなかったので、届出もれが多くみられました。
平成14年4月からは、第2号被保険者が雇用される会社等を通じて、届出を行うようになっています。
今回は、届け出漏れがあった人を救済するための特例をみていきます。
「平成17年4月1日前」と「平成17年4月1日以後」の違いに注意してください。
条文を読んでみましょう。
★平成17年4月1日前 平成16年法附則第21条 ① 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されない期間について、厚生労働大臣に届出をすることができる。 ② 届出が行われたときは、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 |
・「第3号被保険者」に該当していたが、届出をしていなかった場合、2年前以前の期間は、「未納期間」と同じ扱いになります。
↓
・厚生労働大臣に届出をすると、届出を行った日以後、その期間は「保険料納付済期間」として算入されます。
ポイント!
「届出」が遅滞したことの理由は問われません。
★平成17年4月1日以後 法附則第7条の3 第3号被保険者となったことに関する届出又は第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者となったことに関する届出が行われた日の属する月前の当該届出に係る第3号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除く。)は、保険料納付済期間に算入しない。 ② 第3号被保険者又は第3号被保険者であつた者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、①の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。 ③ ②の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。 |
・第3号被保険者に該当したことの届出が遅れた
↓
・届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間は保険料納付済期間に算入される
・それ以外は、保険料納付済期間に算入されない
↓
・保険料納付済期間に算入されない期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由がある
↓
・厚生労働大臣にその旨を届け出る
↓
・届出が行われた日以後、保険料納付済期間に算入される
ポイント!
届出の遅滞につき「やむを得ない」事由があること
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

【解答】
①【R4年出題】〇
ポイントを箇条書きで確認します。
・第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったとき
・第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得する
・ただし、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間
・保険料納付済期間に算入されない期間について、届出の遅滞につきやむを得ない事由がある
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
・その場合、届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入される
②【H29年出題】
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

【解答】
②【H29年出題】 〇
・平成26年4月1日に第3号被保険者に該当した
↓
・資格取得の届出が遅れた(平成29年4月13日)
↓
・保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のみ(平成27年3月以降の各月のみ保険料納付済期間に算入される)
↓
・算入されなかった期間について、届出の遅滞につきやむを得ない事由がある
↓
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
↓
・届出が行われた日以後、当該届出に係る期間(保険料納付済期間に算入されなかった平成26年4月から平成27年2月までの期間)が保険料納付済期間に算入される
③【H19年出題】
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。

【解答】
③【H19年出題】 〇
厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、保険料納付済期間に算入されます。
④【H22年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。

【解答】
④【H22年出題】 〇
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)については、保険料納付済期間に算入されるのは、原則として、「届出をした日の属する月の前々月までの2年間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「第3号被保険者届出その1」
R7-253 05.08
第3号被保険者の取得・喪失・種別変更の届出
「第3号被保険者」の制度は、昭和61年4月の新法施行時に創設されました。
当初は、第3号被保険者に該当したときは、本人が市町村に直接届出をしなければならなかったので、届出もれが多くみられました。
平成14年4月からは、第2号被保険者が雇用される会社等を通じて、届出を行うようになっています。
条文を読んでみましょう。
第12条 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
★届け出について
第1号被保険者 | 市町村長(特別区の区長を含む。) |
第3号被保険者 | 厚生労働大臣 |
(法第12条第1項、第5項)
②【R2年出題】
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
第3号被保険者は、市町村長ではなく「厚生労働大臣」に提出します。
なお、提出先は、「日本年金機構」です。
条文を読んでみましょう。
則第1条の4第2項 第3号被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによつて行わなければならない。 |
③【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければなりません。
(則第1条の4第2項)
④【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

【解答】
④【R1年出題】 〇
第3号被保険者
|
→ |
事業主等 |
→ |
厚生労働大臣 |
事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
⑤【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
⑤【H29年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、第3号被保険者に係る届出に係る事務の一部を「事業主が設立する健康保険組合」に委託することができます。
なお、全国健康保険協会には委託できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法(申請免除)
R7-250 05.05
申請免除についてお話しします
申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)についてみていきます。
・対象になる人 (ポイントは所得要件など)
・対象になる期間
→ 最大で2年2月前までさかのぼります。(通常は2年1月前です)
・前年の所得で判断されますが、1月から6月分は前々年の所得で判断されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「脱退一時金」
R7-236 04.21
脱退一時金についてお話しします(国年)
脱退一時金は外国人に対して支給される給付で、平成7年4月に創設されました。
日本国籍を有しない人が、公的年金制度の被保険者資格を喪失し、
日本国内に住所を有しなくなった場合に支給されるものです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「令和7年度の年金額」
R7-229 04.14
令和7年度の年金額の改定についてお話しします
年金額は、780,900円×改定率で計算します。
令和7年度の年金額は、831,700円です。
(昭和31年4月1日以前生まれは、829,300円です。)
・改定率の基準
新規裁定者→名目手取り賃金変動率
既裁定者→物価変動率
・物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っている場合
・マクロ経済スライド についてお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「保険料の額」
R7-222 04.07
令和7年度国民年金保険料についてお話しします
令和7年度の国民年金保険料は17510円です。
17510円は、「17,000円×1.030」で計算します。
17000円、1.030の根拠についてお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「寡婦年金」
R7-215 03.31
寡婦年金のすべてお話しします
寡婦年金は、夫が死亡した場合、妻に支給される年金です。
死亡した夫の要件と
受給できる妻の要件をおさえましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害基礎年金と障害厚生年金
R7-212 03.28
障害基礎年金と障害厚生年金の額の計算
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級、2級、3級があります。
国民年金法の条文を読んでみましょう。
国民年金法第33条 ① 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 |
(障害基礎年金の額)
1級 → 2級の額×100分の125
2級 → 78万900円×改定率
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第50条 ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 ③ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
第50条③について
・障害基礎年金が支給されない障害厚生年金には最低保障額が設けられています。
最低保障額は、障害基礎年金の額(2級)×4分の3です。
※最低保障額が適用されるのは
・障害等級3級の場合(障害基礎年金が支給されないので)
・老齢年金の受給権を有する65歳以上の者が、厚生年金保険加入中に障害になった場合
(老齢年金の受給権を有する65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者にならないので、1・2級でも障害基礎年金が支給されないからです。)
では、過去問をどうぞ!
<国民年金法>
①【国年R3年出題】
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円に端数処理を行った、976,100円となる。
(注)令和3年度の給付額です。

【解答】
①【国年R3年出題】 ×
・ 障害等級2級の額は、780,900円×改定率で、端数処理は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げます。
・ 障害等級1級の障害基礎年金の額は、2級の障害基礎年金×1.25となりますが、端数処理は、原則の方法となり50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
そのため、1級の額は780,900円×1.25=976,125円となります。(ちなみに令和3年度は1円未満の端数が出ませんでした)
<厚生年金保険法>
①【厚年R4年出題】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

【解答】
①【厚年R4年出題】 ×
2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金と同じように計算します。
・被保険者期間は、障害認定日の属する月の「前月」ではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間を基礎とします。
例えば、令和7年3月1日が障害認定日だとすると、計算に入るのは令和7年3月までの被保険者期間です。
・計算の基礎となる月数が300に満たないときは、300で計算します。
②【厚年R1年出題】
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。

【解答】
②【厚年R1年出題】 〇
障害等級1級の場合は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(被保険者期間の月数が300未満のときは、300とする。)の100分の125です。
③【厚年R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。

【解答】
③【厚年R2年出題】 ×
最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の「4分の3」に相当する額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「遺族基礎年金」
R7-208 03.24
遺族基礎年金の額についてお話しします
遺族基礎年金の額のポイントをお話しします。
■「配偶者」に支給する場合
→ 必ず、「子」の数に応じた加算額が加算されます。
子がいない場合は、配偶者に遺族基礎年金は支給されません。
■「子」に支給する場合
→ 「子」が1人のみの場合は、加算額はありません。
「子」が2人以上の場合は、加算額が加算されます。
なお、子が2人以上の場合、それぞれの子に支給される額は、「子の数」で除した額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「法定免除」
R7-201 03.17
法定免除についてお話しします
国民年金法の「法定免除」についてお話しします 。
<内容です>
・法定免除の要件
・法定免除の対象になる被保険者
・免除される期間(いつからいつまで)
・既に納付された保険料はどうなる?
・前納した保険料は還付される?
・法定免除に該当しても保険料を納付できる?
・届出が必要
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「老齢基礎年金」
R7-195 03.11
老齢基礎年金の計算式(フルペンション減額方式)
満額の老齢基礎年金は、780,900円×改定率で計算します。
満額の老齢基礎年金は、「保険料納付済期間」が480月ある場合に支給されます。
免除期間、合算対象期間、未納期間などがある場合は、その分、年金が減額されます。
条文を読んでみましょう。
第27条 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。 (1) 保険料納付済期間の月数 (2) 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数 (3) 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数 (4) 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数 (5) 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数 (6) 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数 (7) 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数 (8) 保険料全額免除期間(学生納付特例期間・50歳未満の納付猶予期間に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の2分の1に相当する月数 |
老齢基礎年金の額の計算は、「国庫負担」と関連します。
国庫負担については、こちらをどうぞ
→http://www.syarogo-itonao.jp/17370185749152
★老齢基礎年金の計算式については下の図をどうぞ
★例えば、
・保険料納付済期間400月
・4分の3免除期間の月数40月
・全額免除期間の月数40月
の場合の計算式は以下のようになります。
780,900円 ×改定率 | × | 400月+40月×8分の5(25月)+40月×2分の1(20月) |
480 |
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映されます。
(法第27条第4号)
②【R4年出題】
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
②【R4年出題】 ×
「納付猶予の期間」及び「学生納付特例の期間」は、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されません。
(法第27条第8号、H16法附則第19条第4項、H26法附則第14条第3項)
③【R4年出題】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
③【R4年出題】 ×
老齢基礎年金では、第2号被保険者の20歳未満と60歳以降の期間は「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の額には反映しません。
問題文では、60歳から65歳までの5年間は合算対象期間ですので、老齢基礎年金を計算するための保険料納付済期間は、37年間です。
そのため、老齢基礎年金の額は満額にはなりません。
(S60法附則第8条第4項)
④【R5年出題】
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の負担割合も免除の種類に応じて異なっている。

【解答】
④【R5年出題】 ×
国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたのは、平成15年4月1日以降ではなく、「平成21年4月1日」以降です。
ちなみに、「保険料の全額免除期間」については、その後追納しない場合、
・平成21年4月1日前の分 → 3分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます
・平成21年4月1日以降の分 → 2分の1が老齢基礎年金の年金額に反映されます
(H16法附則第9条、第10条)
⑤【R3年出題】
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、 60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円※令和3年度の給付額)となる。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
問題文は、満額にはなりません。
ポイント!
・保険料納付済期間「1」が反映する期間
→ 30歳から60歳までの30年間+60歳から65歳までの5年間=35年間
・全額免除期間(20歳から30歳までの10年間)のうち、国庫負担が行われる期間
■ 全額免除期間について、国庫負担が行われるのは、「480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数」が限度です。
■ 問題の場合は、480から保険料納付済期間の月数(35年×12=420月)を控除して得た月数である「60月(5年間)」について、3分の1の国庫負担が行われます。※平成21年4月前の期間なので、「3分の1」となります。
■ 全額免除期間のうち残りの5年は国庫負担が行われないので、年金額に反映しません。
■ 老齢基礎年金の額に反映するのは、420月+60月×3分の1となり、満額にはなりません。
(法第27条、H16法附則第10条第15項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
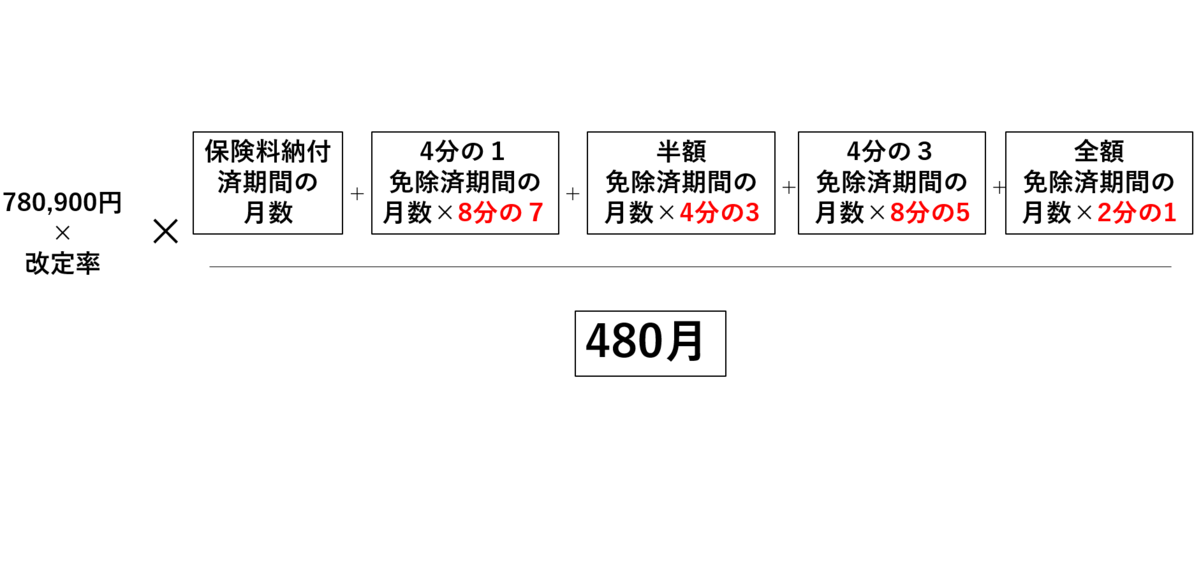
<国民年金法>遺族基礎年金
R7-187 03.03
遺族基礎年金の失権事由についてお話しします<国年>
「遺族基礎年金」を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の「配偶者又は子」です。
・配偶者と子の共通の失権事由 ・配偶者特有の失権事由
・子特有の失権事由をみていきましょう。
★特によく出題されるのは、「配偶者の遺族基礎年金が失権する事由」です。
(例)遺族が配偶者と子1人の場合で、その子が18歳の年度末を終了したときは、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「付加年金」
R7-183 02.27
付加年金は老齢基礎年金とワンセット(支給要件と年金額)
付加保険料(月400円)を納付した場合、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
条文を読んでみましょう。
第43条 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
第47条 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
第48条 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。
第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は対象となりません。
②【R4年出題】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

【解答】
②【R4年出題】 ×
付加保険料に係る納付済期間が60月ある場合の付加年金の額は、400円ではなく、「200円」に60月を乗じて得た額です。
付加保険料の月額が400円ですので、60月納付した場合、納付した付加保険料の総額は24,000円、支給される付加年金は1年あたり12,000円です。2年受給すると納付した付加保険料と同額になります。
③【H29年出題】
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

【解答】
③【H29年出題】 ×
付加年金の額は、改定率による改定はありません。200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で計算します。
④【R5年出題】
老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。

【解答】
④【R5年出題】 ×
老齢基礎年金と付加年金はワンセットです。老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合は、付加年金も繰上げて支給され、老齢基礎年金と同じ率で減額されます。
(法附則第9条の2第6項)
⑤【H29年出題】
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金も支給が繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
(法第46条)
⑥【H20年出題】
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。

【解答】
⑥【H20年出題】 ×
付加年金が支給停止されるのは、「老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているとき」です。「全部又は一部」ではありません。
⑦【R4年出題】
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。

【解答】
⑦【R4年出題】 〇
老齢基礎年金と老齢厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も老齢基礎年金とセットで支給されます。
(法第20条)
⑧【R4年出題】
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

【解答】
⑧【R4年出題】 〇
障害基礎年金を受給することを選択したときは、老齢基礎年金の支給は停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると、付加年金もセットで支給が停止されます。
(法第20条、第47条)
⑨【H26年出題】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。

【解答】
⑨【H26年出題】 ×
65歳以上については、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。その際は、付加年金も支給されます。
(法第20条)
⑩【H21年出題】
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

【解答】
⑩【H21年出題】 ×
遺族基礎年金と老齢基礎年金の受給権を取得し、遺族基礎年金を選択した場合は老齢基礎年金の支給が停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されると付加年金の支給も停止されます。
(法第20条、第47条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>遺族基礎年金
R7-174 02.18
子に対する遺族基礎年金の支給停止事由を整理しましょう
遺族基礎年金には「支給停止」規定があります。
今回は、「子」独自の支給停止事由を見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第41条第2項 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項(受給権者の申出による年金の支給停止)又は次条第1項の規定(配偶者の所在が1年以上明らかでないときに、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請による支給停止)によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
第42条第1項、第2項 ① 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② 遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる |
では、過去問をどうぞ!
①【R6年出題】
第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。

【解答】
①【R6年出題】 ×
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、原則として「支給停止」されます。
問題文の場合は、「夫」が遺族基礎年金を受給し、その間は、「子」に対する遺族基礎年金が支給停止されます。
★第2号被保険者である妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫と16歳の子がいる場合
→ 夫には「遺族基礎年金」の受給権が発生しますが、年齢要件を満たさないので遺族厚生年金の受給権は発生しません。16歳の子には「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の受給権が発生します。
この場合、夫が遺族基礎年金を受給し、子は遺族厚生年金のみ受給します。
②【H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるのが原則です。
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、例外で、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
③【H30年出題】
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
(本問における子は 18 歳に達した日以後の最初の3 月31日に達していないものとする。)

③【H30年出題】 ×
・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合
→子の遺族基礎年金は支給停止となります。
・妻が再婚した場合
→妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
→子の遺族基礎年金は、当該妻(子からみると母)と生計を同じくしている場合は、支給停止となります。
④【H30年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。

【解答】
④【H30年出題】 ×
「その申請のあった日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給が停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
「国民年金法」事後重症の障害基礎年金
R7-173 02.17
事後重症の障害基礎年金についてお話しします
今回の内容は以下の通りです。
★「通常の障害基礎年金」と「事後重症の障害基礎年金」との大きな違い
・通常の障害基礎年金→障害認定日に受給権が発生します
・事後重症の障害基礎年金→請求によって受給権が発生します
★「事後重症の障害基礎年金」の大切なキーワード
・65歳に達する日の前日までに
・請求する
★請求をしなくても事後重症の障害基礎年金が支給される例外の仕組みもおさえましょう
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>障害基礎年金
R7-171 02.15
(国年)障害基礎年金に加算される子の加算
障害基礎年金には、1級と2級があり、生計を維持する子がいる場合は、加算額がプラスされます。
障害基礎年金の額は、以下の通りです。
第1級 780,900円×改定率×100分の125
第2級 780,900円×改定率
※50円未満の端数は切り捨て、50円以上100円未満の端数は100円に切り上げます。
「子」の加算について条文を読んでみましょう。
法第33条の2 ① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 ③ 子の加算額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 (1) 死亡したとき。 (2) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 (3) 婚姻をしたとき。 (4) 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 (5) 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 (6) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 (7) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 (8) 20歳に達したとき。 |
★子の加算額について
1人目・2人目 | 224,700円×改定率 |
3人目以降 | 74,900円×改定率 |
では過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

【解答】
①【R4年出題】 ×
障害基礎年金には、配偶者に係る加算額は加算されません。
★配偶者については、「1級・2級の障害厚生年金」に加給年金額が加算されます。
②【H25年出題】
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。

【解答】
②【H25年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に子を有することとなった場合でも、加算額の対象となります。
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至った場合は、子を有するに至った日の属する月の翌月から加算額が加算されます。
③【H22年出題】
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は減額される。

【解答】
③【H22年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときでも、加算額は減額されません。
「受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき」は減額されます。受給権者の配偶者の養子になっても、減額されません。
④【H19年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されているその者の子がある場合の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき、その子の障害の状態に関わらず、減額される。

【解答】
④【H19年出題】 ×
子の加算は、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したときに終了しますが、その子が障害等級に該当する障害の状態にあるときは終了しません。
「その子の障害の状態に関わらず、減額される。」が誤りです。
18歳年度末・障害なし
▼
|
18歳年度末・障害状態 20歳
▼ ▼
|
|
18歳年度末 障害状態でなくなった 20歳
(障害状態)
▼ ▼ ▼
|
|
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>追納
R7-166 02.10
保険料の追納についてお話しします
国民年金には、「保険料免除」の制度があります。
「免除」を受けた期間がある場合は、その分、老齢基礎年金の年金額が減額されます。
また、学生納付特例・納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映しません。
そのため、免除を受けた期間については後から「追納」することができます。
追納すると、その期間は「保険料納付済期間」となります。
・追納の要件(追納できる人)
・追納できる期間
・追納する額(加算が行われる場合があります)
などをお話しします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
R7-159 02.03
遺族基礎年金と遺族厚生年金を比較しましょう
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」を比較しましょう!
・死亡した人の要件
・遺族の範囲 を
比較してみましょう。
<今日の内容>
・ 遺族基礎年金の支給要件
・ 遺族厚生年金の支給要件
・ 遺族基礎年金の遺族の範囲
・ 遺族厚生年金の遺族の範囲
・ 遺族基礎年金の過去問
・ 遺族厚生年金の過去問
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法「障害基礎年金」
R7-156 01.30
障害基礎年金の受給権の消滅
障害基礎年金の受給権の消滅をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定(障害基礎年金の併合によって従前の障害基礎年金の受給権の消滅)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (1) 死亡したとき。 (2) 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、65歳に達した日において、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 (3) 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
ポイント!
「国民年金法」の障害等級は「1級、2級」ですが、「厚生年金保険法」の障害等級は「1級、2級、3級」です。
厚生年金保険法の障害等級は3級まであることに注意してください。
では、図①と図②でイメージしましょう。
ポイント!
少なくとも「65歳」までは失権しません。
それでは過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
①【H20年出題】 ×
※厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害=障害等級3級です。
63歳時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたとしても、65歳までは障害基礎年金の受給権は消滅しません。問題文の場合、63歳時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。
②【R3年出題】
障害基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において、65歳に達していないときでも、当該障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級(=3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとしても、65歳に達していないときは障害基礎年金の受給権は消滅しません。
③【H30年出題】
63歳の時に障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
63歳の時に障害状態が3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当した場合は、「支給停止が解除されます」。
「3級」に該当している間は、失権することはありません。
図③でイメージしましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
図①
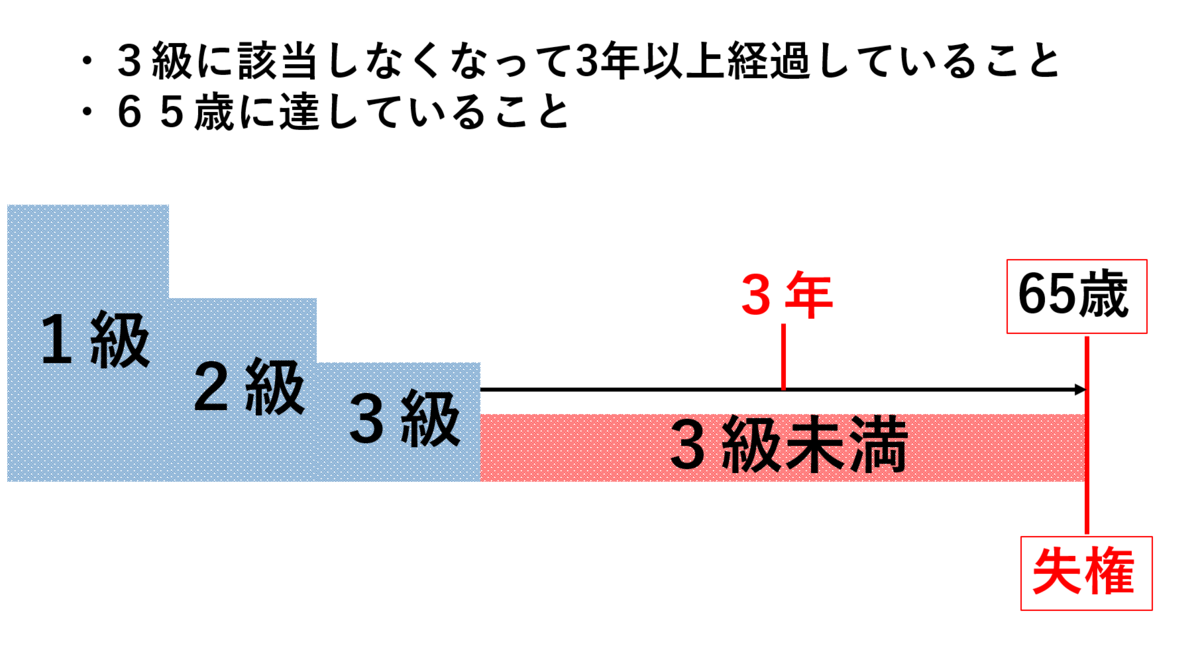
図②
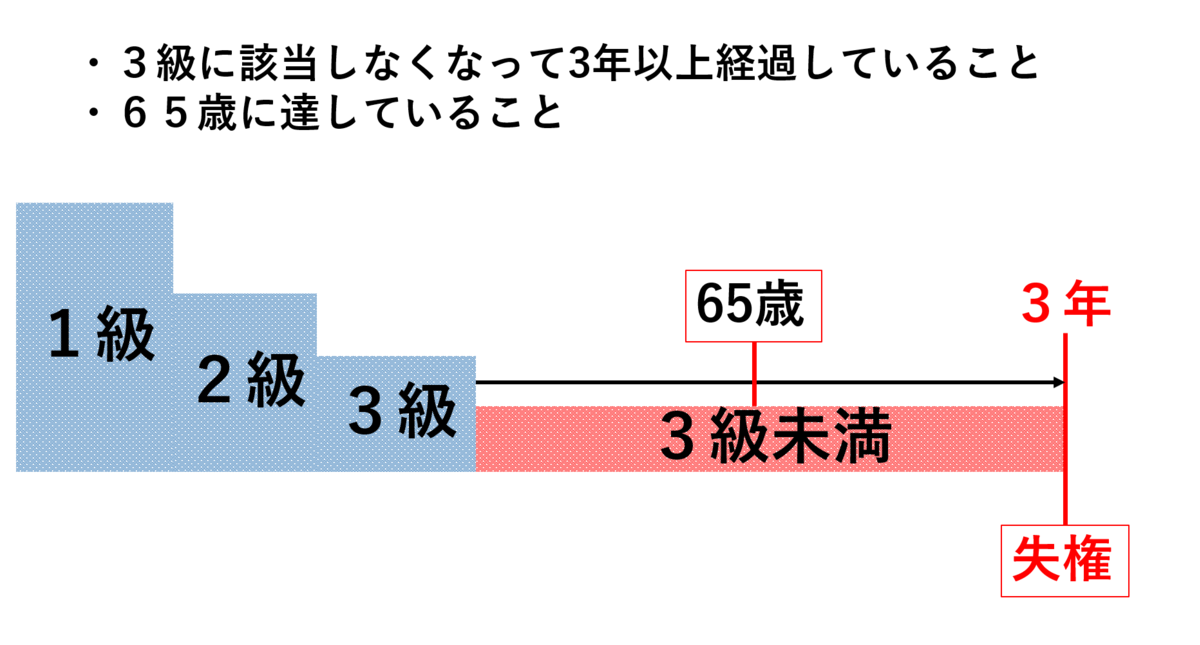
図③
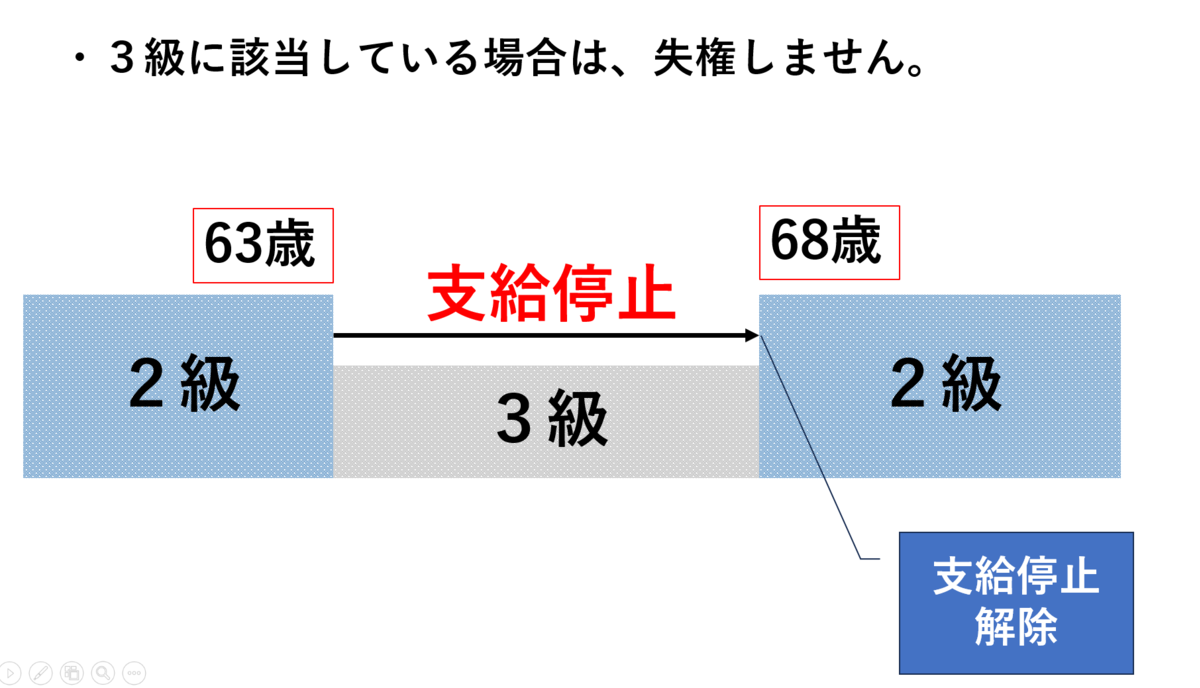
国民年金法「資格喪失」
R7-155 01.29
第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の資格喪失の時期
国民年金の強制被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種別があります。
それぞれの資格喪失の時期をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第9条 (資格喪失の時期) 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日((2)に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は(3)から(5)までのいずれかに該当するに至ったとき((4)については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 (1) 死亡したとき→(翌日喪失・共通) (2) 日本国内に住所を有しなくなったとき→(翌日喪失・第1号被保険者) (3) 60歳に達したとき(当日喪失・第1号被保険者、第3号被保険者) (4) 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(翌日喪失・厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったとき当日喪失・第1号被保険者) (5) 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(当日喪失・第2号被保険者) (6) 被扶養配偶者でなくなったとき(翌日喪失・第3号被保険者) |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【H30年出題】 〇
「第1号被保険者」、「第3号被保険者」は、「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますので、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。「当日」喪失がポイントです。
なお、60歳に達した日とは、60歳の誕生日の前の日です。例えば、令和7年1月29日が60歳の誕生日だとすると、第1号被保険者・第3号被保険者は、令和7年1月28日に資格を喪失します。
②【R4年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。

【解答】
②【R4年出題】 〇
第1号被保険者又は第3号被保険者は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失します。また、死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失します。
③【H25年出題】 ※改正による修正あり
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【H25年出題】 ×
第2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、60歳に達したことによる資格の喪失はありません。
④【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
④【R4年出題】 〇
「厚生年金保険の被保険者」は原則として、「国民年金の第2号被保険者」です。
ただし、65歳以上で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権者は、第2号被保険者となりません。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
⑤【R3年出題】
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
⑤【R3年出題】 〇
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点で、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、国民年金の被保険者資格を喪失するのではなく、第3号被保険者から第1号被保険者又は、第3号被保険者から第2号被保険者への「種別変更」となります。
例えば、日本国内に居住する40歳の者が、離婚し被扶養配偶者でなくなった時点で無職の場合は、第1号被保険者に「種別変更」となります。
20歳 40歳
第3号被保険者 | 第1号被保険者 |
→ | 種別変更 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法の国庫負担
R7-143 01.17
国民年金の給付費に対する国庫負担
通常、基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の給付に要する費用の総額の「2分の1」は国庫負担で賄われています。
また、免除期間等については、特別国庫負担があります。
下の図①でイメージしてください。
問題を解いてみましょう。
①【H26年出題】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
<ポイントその1>
・4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に対する国庫負担
→ 「480」から保険料納付済期間の月数を乗じて得た月数が限度となります。
★例えば、60歳以降に任意加入した場合、480月を超える場合がありますが、国庫負担が行われるのは、「480月」が限度です。
図②でイメージしましょう。
<ポイントその2>
・保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、その7分の4を国庫が負担します。
「7分の4」とは?図③でイメージしましょう。
(法第85条)
②【R3年出題】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

【解答】
②【R3年出題】 〇
「学生納付特例」及び「納付猶予」の期間は国庫負担の対象となりません。そのため、老齢基礎年金の額は、ゼロで計算されます。
(法第85条)
③【R3年出題】
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の「4分の1」ではなく、「2分の1」に相当する額を合計した、当該費用の「100分の40」ではなく「100分の60」に相当する額を負担することになっています。
図④でイメージしましょう。
(法第85条)
④【R4年出題】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

【解答】
④【R4年出題】 〇
「付加年金」の給付に要する費用及び「死亡一時金の加算額(8500円)」の給付に要する費用の総額の「4分の1」に相当する額に、国庫負担が行われています。
(昭60法附則第34条第1項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
図①
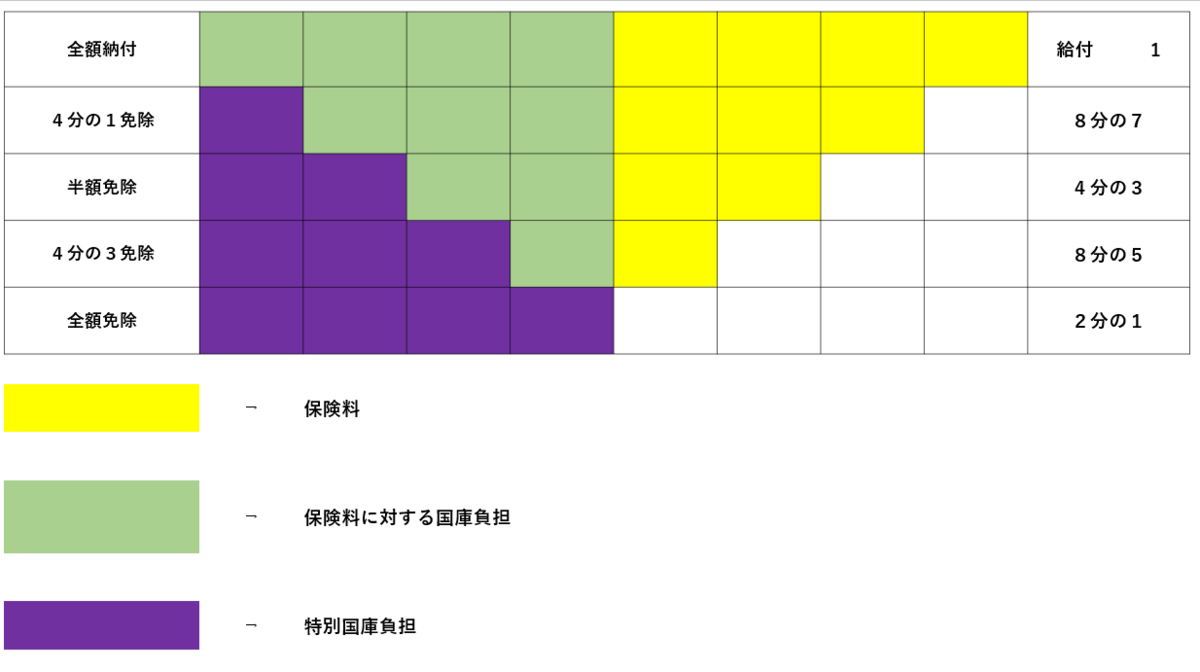
図②
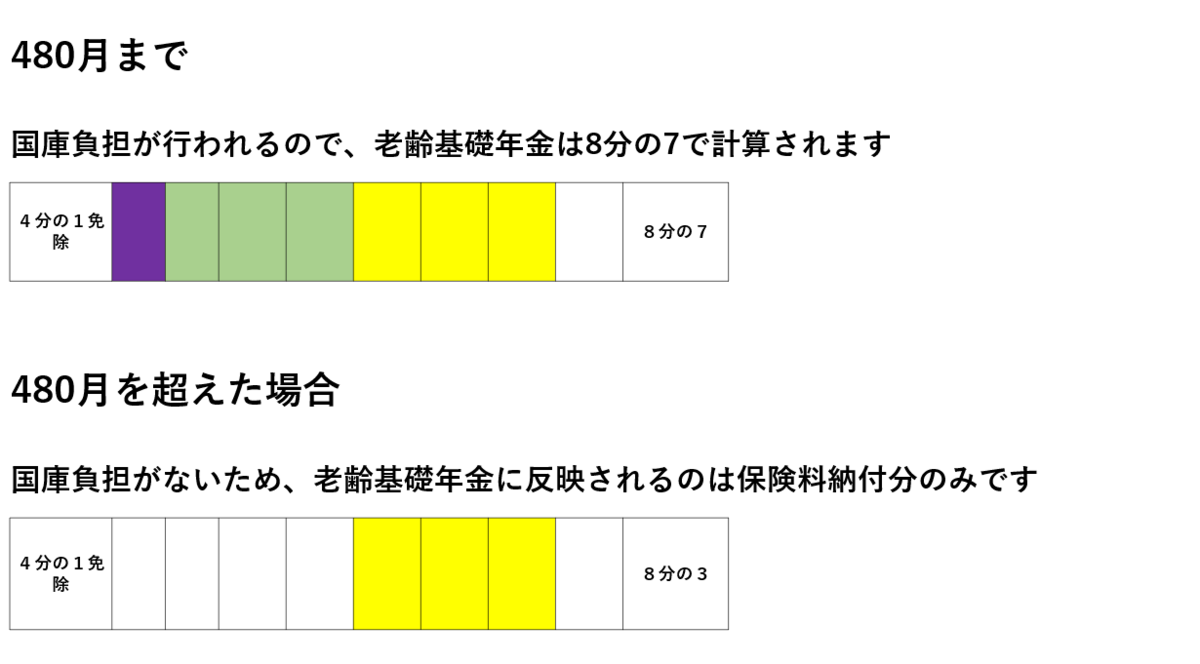
図③
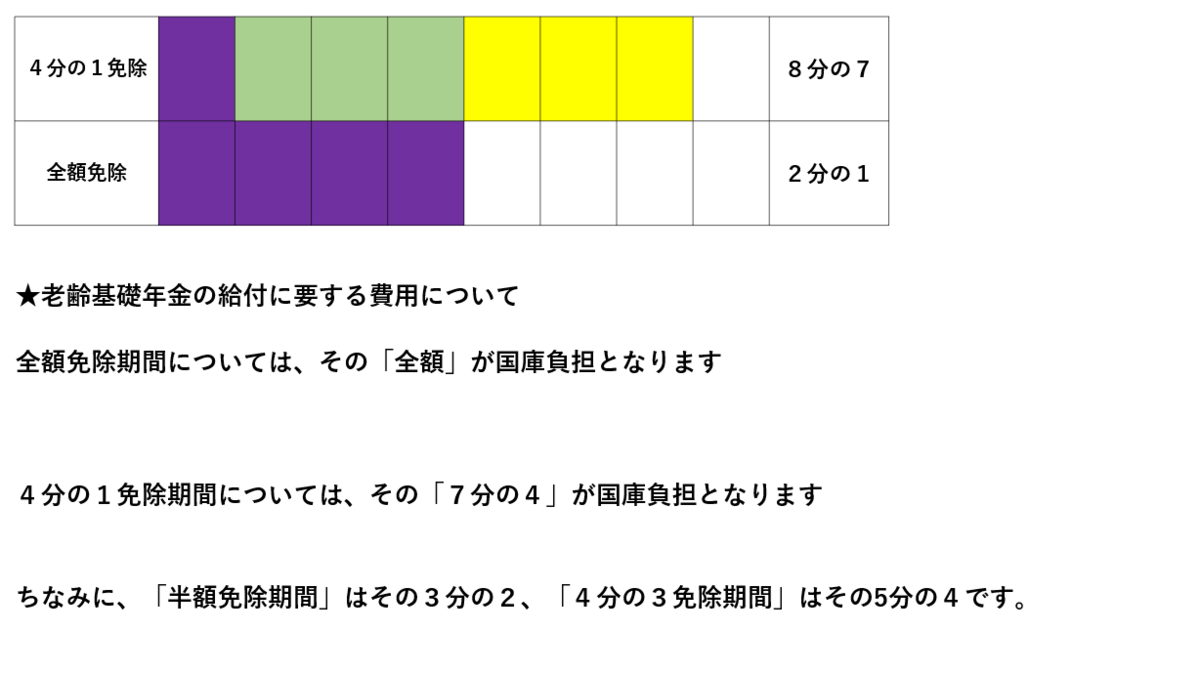
図④
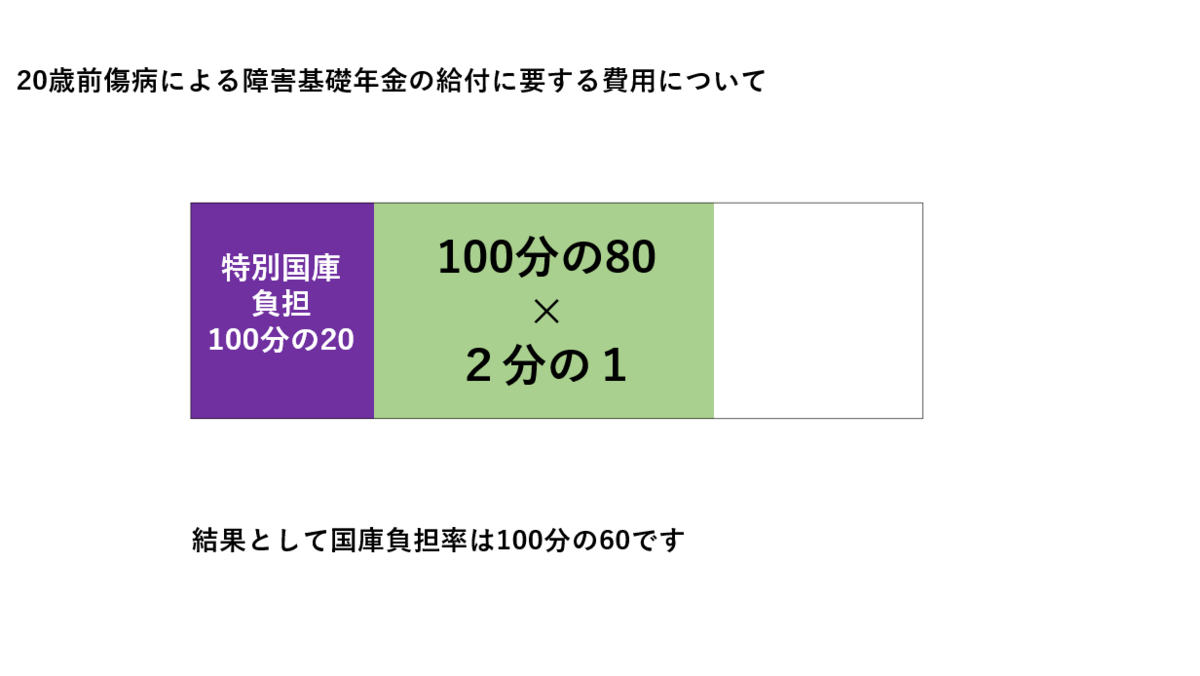
国民年金法の併給調整
R7-139 01.13
国民年金の「併給調整」の覚え方をお話しします
同一人に複数の年金の受給権が発生することがあります。
★原則は一人一年金です
★例外もあります
<例外の重要ポイント!>
・老齢基礎年金と付加年金はセットで支給されます
・支給事由が同じ「国民年金の年金」と「厚生年金保険の年金」は2階建てで併給されます
・支給事由が異なっていても「65歳以上限定」で併給される組合せがあります
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法・厚生年金保険法の違い
R7-135 01.09
国民年金法・厚生年金保険法の目的の異なる点
国民年金法と厚生年金保険法の違いを条文で確認しましょう。
国民年金法の第1条と第2条です。
第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 |
(参考)
日本国憲法第25条
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づいています。
厚生年金保険法第1条です。
第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
過去問をどうぞ!
①【国年H28年選択式】
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】
<A> 安定
<B> 共同連帯
②【国年R5年選択式】
国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して< A >を行うものとする。」と規定されている。
<選択肢>
① 年金支給
② 年金の給付
③ 必要な給付
④ 保険給付

【解答】
<A> ③ 必要な給付
③【国年H26年出題】
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

【解答】
③【国年H26年出題】 ×
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して「必要な保険給付」ではなく、「必要な給付」を行うものとされています。
「保険原理」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる仕組みのことですが、国民年金法の給付には、保険原理によらないものもあります。例えば、20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料の負担なく給付されるものです。
国民年金法に基づくすべての給付が保険原理により行われるものではないので、国民年金法では「保険給付」ではなく、「必要な給付」という用語を使います。
なお、厚生年金保険法では「保険給付」という用語を使います。
ちなみに法律の名称も「国民年金法」には「保険」が入っていません。「厚生年金保険法」は「保険」が入っています。
④【厚年H30年出題】
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

【解答】
④【厚年H30年出題】 ×
問題文は国民年金制度の目的条文です。国民年金はすべての国民が対象ですので、「国民」という言葉が使われています。
厚生年金保険制度は「労働者」が対象ですので、「労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的」としています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法・厚生年金保険法について
R7-134 01.08
国民年金法・厚生年金保険法で最低限おさえたい歴史
国民年金法、厚生年金保険法の歴史で重要な年号をまとめました。
昭和14年 | 船員保険法制定 | ・社会保険方式による日本で最初の公的年金 ・昭和15年施行 |
昭和16年 | 労働者年金保険法制定 | ・昭和17年施行 ・昭和19年に「厚生年金保険法」に改称 |
昭和34年 | 国民年金法制定 | ・昭和34年11月福祉年金(無拠出制)開始 |
昭和36年 4月 | 国民皆年金の実施 | ・国民年金(拠出制)開始 |
昭和61年 4月 | 基礎年金の導入 | ・「基礎年金」と「報酬比例」の2階建て ・基礎年金は全国民が対象 第1号被保険者(自営業等) 第2号被保険者(会社員、公務員等) 第3号被保険者(専業主婦等) |
平成27年 10月 | 被用者年金一元化 | ・被用者の年金制度が厚生年金に統一された |
年金の歴史を図でイメージしましょう。(下の図を参照してください)
ポイント!
・昭和36年4月「国民皆年金」
・昭和61年4月「基礎年金の導入」
★昭和61年4月前の制度を「旧法」、昭和61年4月以降の制度を「新法」といいます。
過去問をどうぞ!
①【H19年出題(社一)】
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。

【解答】
①【H19年出題(社一)】 〇
国民年金法は昭和34年に制定、昭和36年4月から全面施行され、国民皆年金が実現しました。
②【H19年出題(国年)】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
②【H19年出題(国年)】 ×
国民年金法は昭和34年に制定され、同年10月ではなく「同年11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始されました。また、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立しました。
③【H15年選択式(国年)】
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
<選択肢>
① 大正15年4月1日
② 大正15年4月2日
③ 昭和2年4月1日
④ 昭和2年4月2日
⑤ 裁定日
⑥ 初診日
⑦ 障害認定日
⑧ 裁定請求日

【解答】
<A> ② 大正15年4月2日
<B> ⑦ 障害認定日
ポイント!
・ 「大正15年4月2日」以降生まれの人は、老齢基礎年金(新法の年金)の対象となります。ただし、施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった人を除きます。
・ 「障害認定日」が昭和61年4月1日以降の人は、障害基礎年金(新法の年金)の対象となります。
④【R6年出題(社一)】
日本の公的年金制度は、予測することが難しい将来のリスクに対して、社会全体であらかじめ備えるための制度であり、現役世代の保険料負担により、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養である賦課方式を基本とした仕組みで運営されている。賃金や物価の変化を年金額に反映させながら、生涯にわたって年金が支給される制度として設計されており、必要なときに給付を受けることができる保険として機能している。

【解答】
④【R6年出題(社一)】 〇
日本の公的年金制度は、「賦課方式」を基本とした仕組みで運営されていることがポイントです。
賦課方式とは、現役世代の保険料負担で、その時々の高齢世代の年金給付をまかなう世代間扶養の仕組みです。
(令和5年版厚生労働白書P256)
【R1年出題(社一)】※問題文修正あり
被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得したのは、平成27年10月1日である。

【解答】
【R1年出題(社一)】 〇
被用者年金一元化が行われたのは、平成27年10月1日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
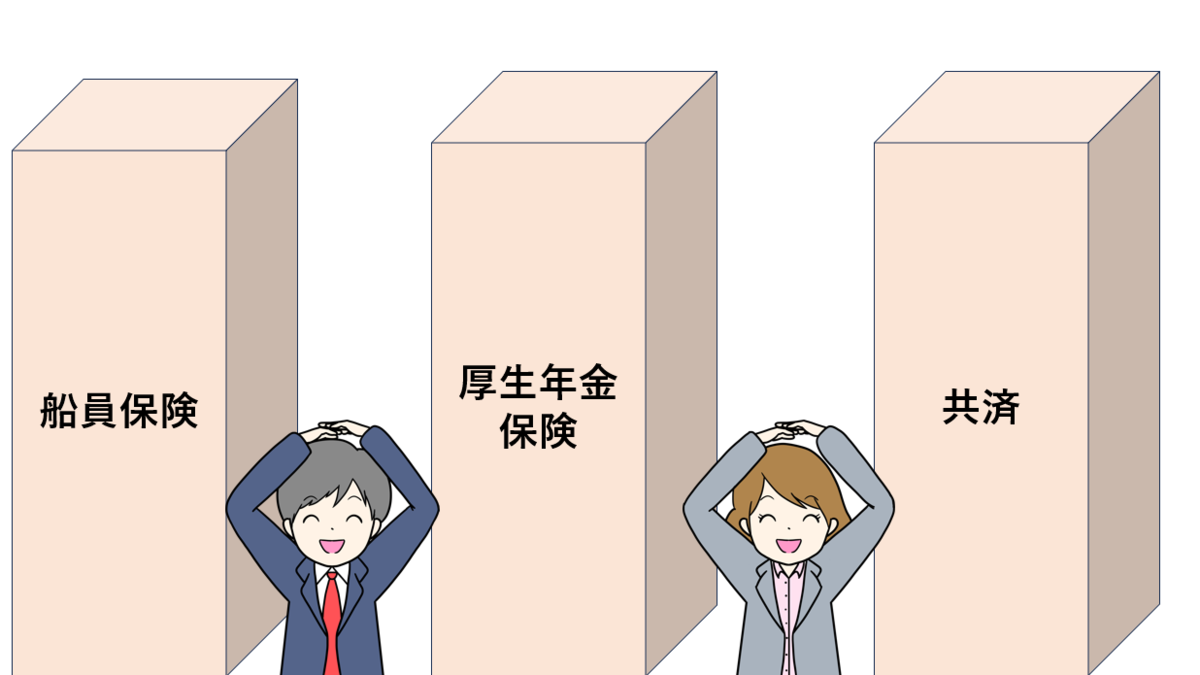
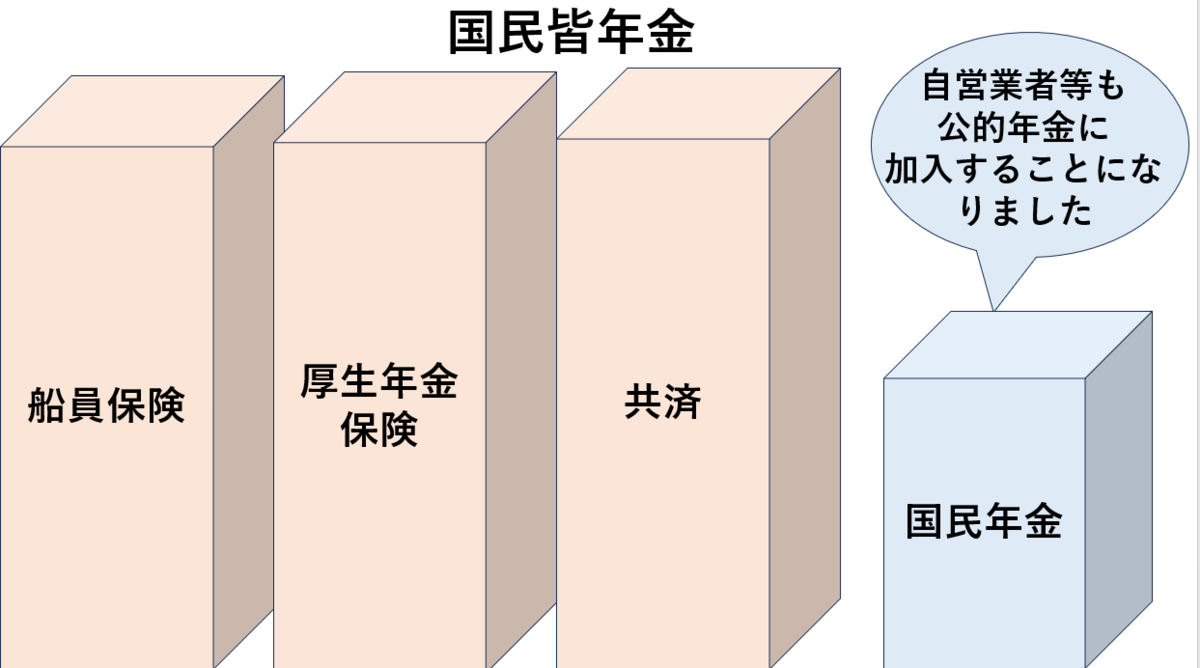
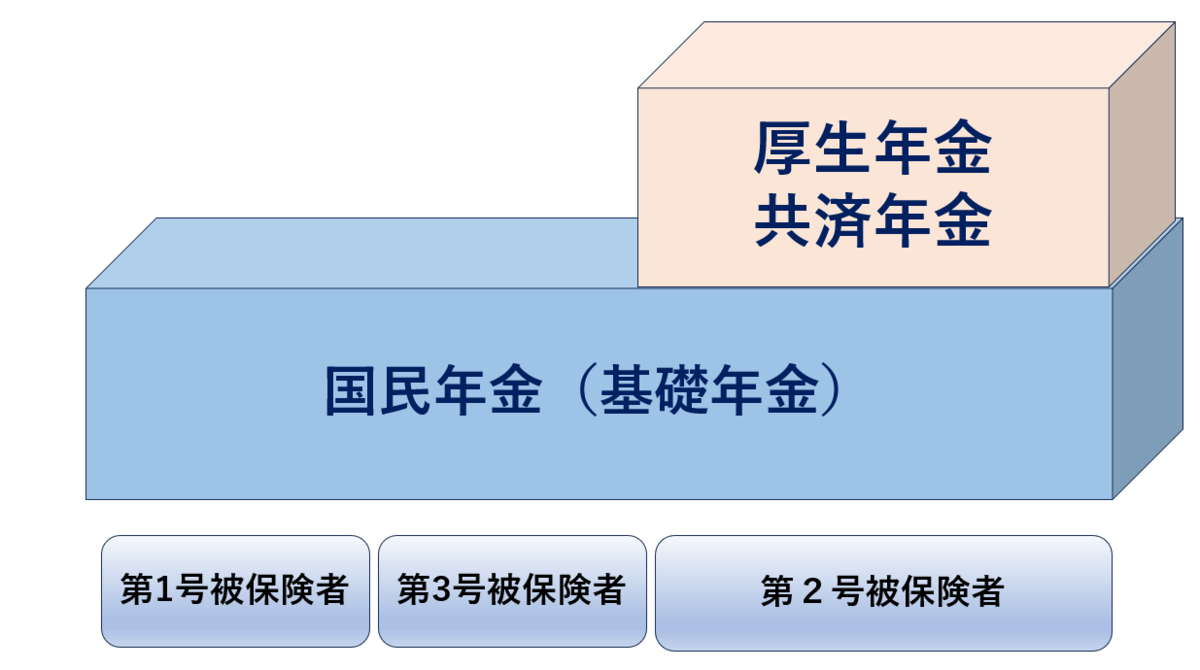
繰上げ支給の老齢基礎年金
R7-132 01.06
繰り上げ支給の老齢基礎年金についてお話しします
繰上げ支給の老齢基礎年金のポイントは、
・請求によって受給権が発生すること
・繰り上げた月数に応じて減額されること
です。
その他さまざまな注意点があり、本試験でも頻出される箇所です。
繰り上げ支給の老齢基礎年金の注意点をYouTubeでお話ししています。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法<死亡一時金>
R7-118 12.23
国民年金「死亡一時金」についてお話しします
YouTubeで「死亡一時金」についてお話ししました。
今日の内容です。
・死亡一時金の支給要件 → キーワードは36月
・死亡一時金が支給されないのは、どんなとき? → (ヒントは掛け捨てにならない)
・死亡一時金の遺族となるのは? → 生計維持と生計同一の違いもポイントです
・死亡一時金の額(最低と最高は覚えましょう)
・付加保険料を納付していた場合の加算
・死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たしたとき
・死亡一時金と遺族厚生年金は併給できる?
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法<寡婦年金>
R7-111 12.16
寡婦年金についてお話しします<国民年金法>
今日は寡婦年金についてお話ししています。
寡婦年金は「第1号被保険者」独自の給付です。
・死亡した夫の要件
・妻の要件
・寡婦年金の額の計算方法
・寡婦年金の失権 などがポイントです。
特に、「繰上げ支給の老齢基礎年金」との関係、「死亡一時金」との関係もよく出題されますので注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-105 12.10
<令和6年の問題を振り返って>障害・遺族基礎年金と労働基準法の災害補償との調整
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
条文を読んでみましょう。
第36条第1項 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
第41条第1項 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
第52条 寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問3-B】
労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。

【解答】
【R6年問3-B】 〇
・ 労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金は、6年間、支給が停止されます。
・ 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、支給が停止されます。
「労働基準法の障害補償(遺族補償)」との調整規定です。「労働者災害補償保険法の障害(補償)年金、遺族(補償)年金」ではありませんので注意しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。

【解答】
①【H20年出題】 ×
同一の支給事由で、労働者災害補償保険法による遺族補償年金と遺族基礎年金が支給されるときは、遺族補償年金が減額され、遺族基礎年金は全額支給されます。
(労災保険法別表第1)
同一事由で労災保険法から年金が支給されても、国民年金・厚生年金は、本人が保険料を負担していますので、減額されません。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですので、同一事由で、労災保険の年金と国民年金・厚生年金が支給される場合は、労災保険の年金が減額されます。
②【H26年出題】
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、労災保険法の遺族補償年金が減額され、遺族基礎年金は支給停止されません。
③【H20年出題】
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

【解答】
③【H20年出題】 〇
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときは、障害補償年金が減額され、障害基礎年金は全額支給されます。
(労災保険法別表第1)
こちらの問題もどうぞ!
①【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「20歳前傷病による障害基礎年金」独自の支給停止事由です。
労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項、第2項 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金(=20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する期間、その支給を停止する。 (1) 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 (2)以下省略します ② (1)に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、支給停止されない。 |
②【H25年出題】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。

【解答】
②【H25年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときは、その該当する期間、その支給が停止されます。
ただし、労働者災害補償保険法による年金たる給付の全額が支給停止されているときは、原則として、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>合算対象期間
R7-104 12.09
国民年金の合算対象期間の<基本>についてお話しします
合算対象期間の「基本」についてお話しします。
合算対象期間は「カラ期間」ともいわれます。
老齢基礎年金の受給資格期間の10年の計算には入りますが、 老齢基礎年金の「年金額」の計算には入らないからです。
合算対象期間の代表例で、よく出題される期間をみていきます。
・厚生年金保険等の加入期間のうち、合算対象期間になる期間
・日本国籍を有する者が海外に在住している期間のうち合算対象期間になる期間
・会社員、公務員の被扶養配偶者だった期間のうち合算対象期間になる期間
などです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-102 12.07
<令和6年の問題を振り返って>国民年金基金の加入員
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金基金には、「地域型国民年金基金」(地域型基金)と「職能型国民年金基金」職能型基金)があります。
国民年金基金の加入について条文を読んでみましょう。
第127条 (加入員) ① 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 ② 申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。 ③ 加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日((1)又は(4)に該当するに至ったときは、その日とし、(3)に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする。)に、加入員の資格を喪失する。 (1) 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。 (2) 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。 (3) 保険料を納付することを要しないものとされたとき(一部免除・学生納付特例・納付猶予を含む。) (4) 農業者年金の被保険者となったとき。 (5) 当該基金が解散したとき。 ④ 加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。 |
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問2-エ】
国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。

【解答】
①【R6問2-エ】 〇
「申出をした日」(当日)に、加入員の資格を取得します。
②【R6問2-オ】
国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【R6問2-オ】 ×
第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を「喪失した日」に、加入員の資格を喪失します。翌日喪失ではなく当日喪失です。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
国民年金基金の加入は任意ですが、加入後に任意に資格を喪失することはできません。
②【H29年出題】
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【H29年出題】 〇
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。
③【H29年出題】
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。

【解答】
③【H29年出題】 〇
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失します。当日喪失がポイントです。
④【H27年出題】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
④【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員が、保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失します。
⑤【R2年出題】
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
任意加入被保険者のうち、次の者は、国民年金基金の加入員となることができます。
■ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
■ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
(法附則第5条第11項)
⑥【H29年出題】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
地域型国民年金基金の加入員となることができます。
「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者」は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができます。
⑦【H24年出題】
第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。

【解答】
⑦【H24年出題】×
「第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。」となっていますので、地域型か職能型のどちらかを選択できます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-101 12.06
<令和6年の問題を振り返って>基礎年金拠出金の算定
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金保険料を負担しませんが、第2号被保険者と第3号被保険者にも、基礎年金が支給されます。
第2号被保険者と第3号被保険者に支給される基礎年金の費用に充てるため、厚生年金保険の保険者は、基礎年金拠出金を負担します。
「基礎年金拠出金」について条文を読んでみましょう。
第91条の2 (基礎年金拠出金) ① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 ③ 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
第94条の3 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 ② 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。 ③ 実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。 |
<基礎年金拠出金の計算式>
|
| 政府及び実施機関に係る被保険者の総数 (第2号被保険者+第3号被保険者) |
保険料・拠出金算定対象額
| × |
国民年金の被保険者の総数 |
★政府及び実施機関に係る被保険者の総数
■厚生年金保険の実施者たる政府 → 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者+その被扶養配偶者である第3号被保険者
■実施機関たる共済組合等
・国家公務員共済組合連合会 → 第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
・地方公務員共済組合連合会 → 第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
・日本私立学校振興・共済事業団 → 第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問1-D】
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

【解答】
【R6問1-D】 〇
基礎年金拠出金の額は、「国民年金(1号、2号、3号)の被保険者数」と「第2号+第3号の被保険者数」の人数比で按分されます。
過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。

【解答】
①【R2年選択式】
<A> 実施機関たる共済組合等
★実施機関たる共済組合等の定義も確認しましょう。
「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(法第5条第9項)
②【R4年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

【解答】
②【R4年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者」とされています。
納付者が対象ですので、「保険料全額免除」を受けている者や滞納している者は算入されません。
(令第11条の3)
③【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

【解答】
③【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について
・第1号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者数 → 20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者数 → すべての者
となります。
第2号被保険者数は、すべての者ではなく、第1号被保険者の年齢の範囲に合わせて、「20歳以上60歳未満の者」です。
(令第11条の3)
④【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
国民年金保険料を納付しなければならないのは、第1号被保険者のみです。
第2号被保険者・第3号被保険者は、国民年金保険料を納付する必要はありません。
条文を読んでみましょう。
法第94条の6 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<国民年金法>任意加入被保険者
R7-097 12.02
国民年金の「任意加入被保険者」についてお話しします
国民年金の強制被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)に該当しない場合は、任意加入することができます。
任意加入する目的は次の2つです。
①老齢基礎年金の額を増やすため
(満額にするor満額に近づける)
②老齢基礎年金等の受給資格期間を満たすため
任意加入被保険者には、「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の2種類あります。
★「任意加入被保険者」は①と②のどちらの目的でも加入できます。
★「特例による任意加入被保険者」は、②の目的のみです。老齢基礎年金等の受給権がある場合は、任意加入できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-095 11.30
<令和6年の問題を振り返って>付加保険料の納付
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
付加保険料の納付について条文を読んでみましょう。
第87条の2 ① 第1号被保険者(保険料の免除を受けている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、400円の付加保険料を納付する者となることができる。 ② 付加保険料の納付は、国民年金の保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 ③ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 ④ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、③の申出をしたものとみなす。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問8-ウ】
付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。

【解答】
【R6年問8-ウ】 ×
産前産後期間で保険料を納付することを要しないものとされた各月についても、付加保険料を納付することができます。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
保険料の免除を受けている者(法定免除、申請全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除)は、付加保険料を納付できません。
②【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
追納を行った月については、付加保険料を納付できません。
③【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
付加保険料の納付は、申出によってやめることができます。「その申し出をした日の属する月以後」ではなく、「その申出をした日の属する月の前月以後」の各月の付加保険料を納付する者でなくなることができます。
④【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料を納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

【解答】
④【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付することができません。国民年金基金の加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
⑤【R4年出題】
厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
付加保険料の納期限は、翌月末日です。
納期限までに納付しなかったときでも、納付期限から2年間は付加保険料を納付できます。
問題文のような扱いはありません。
⑥【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
⑥【R2年出題】 〇
「任意加入被保険者」も、付加保険料を納付できます。
(法附則第5条第9条)
ちなみに「特例による任意加入被保険者」は、付加保険料を納付できません。
(H6法附則第11条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-094 11.29
<令和6年の問題を振り返って>遺族基礎年金の支給要件
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
遺族基礎年金の支給要件について条文を読んでみましょう。
法第37条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 (1) 被保険者が、死亡したとき。 (2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。 (3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 (4) 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
(1)と(2)を「短期要件」、(3)と(4)を長期要件といいます。
ポイント!
★(1)と(2)は保険料納付要件が問われます。
★(3)と(4)の25年の計算には、合算対象期間も含みます。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問6-D】
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

【解答】
①【R6年問6-D】 ×
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上あることが必要です。
老齢基礎年金は、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が10年以上あれば受給権が発生しますが、長期要件の遺族基礎年金の場合は25年以上必要です。
②【R6年問6-E】
国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

【解答】
②【R6年問6-E】 〇
国民年金の被保険者である者が死亡した時(=短期要件)の場合は、保険料納付要件が問われます。「死亡日の前日」に、死亡日の属する月の「前々月」までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の「3分の2以上」ある場合は、保険料納付要件を満たします。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

【解答】
①【H30年出題】 〇
保険料納付要件の特例を満たしています。
「死亡日」が令和8年4月1日前にあり、死亡した者が65歳未満であれば、保険料納付要件の特例が適用されます。特例の要件は、「死亡日の前日」に、「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」ことです。
問題文の場合は、平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡(60歳未満)、死亡日の前日(平成30年4月1日)に、死亡日の属する月の前々月までの1年間(平成29年3月から平成30年2月までの期間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(=未納がない)ので、特例の要件を満たします。
(S60法附則第20条第2項)
②【R4年出題】
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。

【解答】
②【R4年出題】 〇
長期要件の「25年以上」の計算には、合算対象期間も含みます。
(法附則第9条)
③【H30年出題】
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
※本問における子は18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする。)

【解答】
③【H30年出題】 ×
老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した場合、短期要件には該当しないので、「長期要件」で要件をみます。
長期要件の場合、「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」が25年以上必要です。
問題文の者は、保険料納付済期間を15年有するのみですので、遺族基礎年金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-093 11.28
<令和6年の問題を振り返って>学生納付特例制度
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
「学生納付特例制度」について条文を読んでみましょう。
法第90条の3第1項 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。 (1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 (2) 第90条第1項第2号及び第3号に該当するとき。 ・ 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ・ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が135万円以下であるとき。 (3) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 |
(1)の前年の所得について
扶養親族等がないときは、「128万円」となります。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問5-B】
学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。

【解答】
【R6問5-B】 ×
定時制及び通信制課程の生徒も、学生納付特例制度を利用することができます。
(令第6条の6)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
学生納付特例の所得要件は、学生本人のみの所得で判断します。
「世帯主又は配偶者」の所得は問われないのがポイントです。
②【H28年選択式】
国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
<選択肢>
① 1年2か月
② 1年6か月
③ 2年2か月
④ 2年6か月

【解答】
<A> ③ 2年2か月
(平成26年3月31日年管発0331第9号)
免除の申請は、保険料の納期限から2年を経過していない期間について行うことができます。
例えば、令和4年9月分の納期限は、令和4年10月31日です。免除の申請期限は、令和6年10月31日までとなります。申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等を申請できます。
しかし、休日等の関係で納期限が翌々月になることがあります。その場合は2年2か月前までが対象となります。
厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の2年2か月前の月から申請のあった日の属する年の翌年3月までが対象です。
④【H28年出題】
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

④【H28年出題】 〇
申請全額免除の対象から、学生は除外されています。
(法第90条第1項)
⑤【R5年出題】
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
保険料の法定免除の要件に該当した場合は、学生も法定免除の適用を受けることができます。
(法第89条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-079 11.12
<令和6年の問題を振り返って>基準障害による障害基礎年金について
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
基準障害による障害基礎年金とは?
・複数の障害があるが、単独では障害等級1・2級に該当しない
↓
・併合して初めて障害等級1・2級に該当すると、障害基礎年金が支給される仕組み
↓
・併合のきっかけになる傷病が「基準傷病」、基準傷病にかかる障害が「基準障害」
↓
・基準障害の障害認定日が基準障害による障害基礎年金の障害認定日になる
↓
・初診日、保険料納付要件は、「基準障害」について問われる
第1の傷病 | ● ● 初診日 障害認定日 | |||||
|
|
|
|
| 併合 初めて2級以上に該当 | |
|
|
|
|
| ||
基準傷病 |
| ● ● 初診日 障害認定日 | ||||
基準障害による障害基礎年金の条文を読んでみましょう。
第30条の3 ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において第30条第1項各号のいずれかに該当した者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)の初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ③ 基準障害による障害基礎年金の支給は、当該障害基礎年金の請求があった月の翌月から始めるものとする。 |
★保険料納付要件は、「基準傷病」に係る初診日の前日で判断されます。
(法第30条の3第2項)
令和6年の問題をどうぞ!
【R6問10-D】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】
【R6問10-D】 ×
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、1・2級に該当した日に受給権が発生します。ただし、支給は請求のあった「月の翌月」からです。請求のあった月からではありません。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
初診日要件は、「基準傷病に係る初診日」で判断されます。基準傷病以外の傷病については、初診日要件は問われません。
②【H29年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
基準障害による障害基礎年金は、「65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当」することが条件ですが、請求は、65歳に達した日以後でも行うことができます。
③【H20年出題】
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】
③【H20年出題】 ×
基準障害の規定による障害基礎年金について
・所定の要件に該当すれば受給権は発生します
・障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができます
・支給は「請求のあった月の翌月から」開始されます。「当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から」ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金の強制被保険者について
R7-078 11.11
【社労士受験】国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者についてお話しします
今日の内容です。
・第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の定義をおさえましょう
・「国内居住要件」の有無、「年齢要件」の有無がポイントです。
・第1号被保険者と第3号被保険者から除外されるものをおぼえましょう。
・第3号被保険者は、国内に住所を有することが原則ですが、海外特例に該当すると、国内に住所を有しなくても第3号被保険者となります。
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-076 11.09
<令和6年の問題を振り返って>国民年金の適用(技能実習、海外に居住する場合など)
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金の強制被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種類があります。
国民年金の強制被保険者の要件について条文を読んでみましょう。
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「第1号被保険者」という。) (2) 厚生年金保険の被保険者(「第2号被保険者」という。) (3) 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(「第3号被保険者」という。)
則第1条の2 (第1号被保険者、第3号被保険者の適用を除外される者) (1) 日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(=在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」の場合) (2) 日本の国籍を有しない者であって、入管法に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの (=在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」の場合)
則第1条の3 (国内居住要件の特例) 第3号被保険者の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 (1) 外国において留学をする学生 (2) 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (4) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの (5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
令和6年の問題を解いてみましょう
①【R6年問4-A】
技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。

【解答】
①【R6年問4-A】 ×
技能実習の在留資格で日本に在留する外国人も公的年金に加入しなければなりません。実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合
・講習期間中 → 「国民年金」に加入します
・実習期間中 → 「厚生年金保険」に加入します ※厚生年金保険の適用事業所でない場合は、引き続き国民年金に加入します
「講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要はない。」ではなく、「講習期間は国民年金、実習期間は厚生年金保険の対象となる」となります。
(参照:厚生労働省HPhttps://www.mhlw.go.jp/content/000721075.pdf)
②【R6年問4-B】
日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。

【解答】
②【R6年問4-B】 〇
第1号被保険者は、「国内居住要件」がありますので、海外に居住する場合は、資格を喪失します。ただし、「20歳以上65歳未満」の「日本国籍を有する者」は、国民年金の任意加入被保険者になることができます。
③【R6年問4-D】
第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【R6年問4-D】 ×
第3号被保険者は、日本国内に住所を有することが原則です。
ただし、「外国において留学をする学生」は、国内居住要件の例外が認められますので第3号被保険者の資格は喪失しません。
(則第1条の3第1号)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
外国人も国民年金の対象となります。
ただし、「本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの」は、除外されます。
(則第1条の2第2号)
②【R3年出題】
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
第3号被保険者は「国内居住要件」を満たすことが原則ですが、「外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったとき」は、海外特例で第3号被保険者の資格は喪失しません。
(則第1条の3)
③【R3年出題】
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

【解答】
③【R3年出題】 〇
第3号被保険者は、国内居住要件を満たすことが原則ですが、「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する」場合は、海外特例で、第3号被保険者となることができます。
(則第1条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-075 11.08
<令和6年の問題を振り返って>国民年金保険料の前納
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
国民年金の保険料の納付期限は、翌月末日が原則ですが、前払い(前納)することもできます。
保険料の前納について条文を読んでみましょう。
第93条 ① 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問1-C】
国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。

【解答】
【R6年問1-C】 ×
条文で確認しましょう。
令第7条 (保険料の前納期間) 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。 |
★前納は「6か月」又は「年」を単位とするのが原則ですが、それ以外の期間も可能です。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
昭和34年8月2日生まれの者は、60歳に達した日(令和元年8月1日)に資格を喪失し、被保険者期間は令和元年7月までとなります。
平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することができます。
②【R2年出題】
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

【解答】
②【R2年出題】 ×
一部免除の保険料も、前納することができます。
③【H30年出題】
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】
③【H30年出題】 ×
前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「各月が経過した際に」、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
④【H29年出題】
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。

【解答】
④【H29年出題】 〇
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に「被保険者の資格を喪失した場合」、「第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合」は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付されます。
(令第9条)
⑤【H24年出題】
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
国民年金保険料を前納する方法で、最も割引率が高くなるのは、「口座振替による支払」です。
(令第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-074 11.07
<令和6年の問題を振り返って>障害基礎年金の支給要件についての基本問題
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の受給権発生要件は、次の3つです。
①初診日
②保険料納付要件
③障害認定日
条文を読んでみましょう。
第30条 ① 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 (1) 被保険者であること。 (2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 昭60法附則第20条第1項 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件を満たすものとする。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。 |
★3つの要件を満たした場合は、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問2-ア】
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。

【解答】
①【R6年問2-ア】 〇
「初診日」要件についての問題です。
初診日に①か②のどちらかに該当していることです。
① 国民年金の被保険者であること
② 国民年金の被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
②【R6年問2-ウ】
障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。

【解答】
②【R6年問2-ウ】 〇
「保険料納付要件」についての問題です。
「保険料納付要件」の原則
・ 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である
「保険料納付要件」の特例
・ 初診日が令和8年4月1日前にある
・ 初診日に65歳未満
・ 初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない(=保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと)
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

【解答】
①【H29年出題】 〇
初診日に、「被保険者であった者(かつて被保険者だったが、初診日には被保険者ではない)」の場合、初診日に「日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。」が条件です。
問題文の場合は、「日本国内に住所を有しない」となっているので、障害基礎年金は支給されません。
②【H27年出題】
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

【解答】
②【H27年出題】 〇
障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」です。
ただし、初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となります。なお、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われます。
③【H29年出題】
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
(令第4条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<社労士国民年金>法定免除について
R7-057 10.21
国民年金の法定免除についてお話しします【社労士受験対策】
法定免除についてお話しします。
今日の内容です。
★法定免除の対象から除外される人
→ 産前産後の保険料の免除を受ける人、一部免除を受ける人
★法定免除される期間(いつからいつまで免除される?)
→ 法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間
★法定免除される事由
→ 障害基礎年金等の受給権者、生活保護法の生活扶助を受ける人、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき
★法定免除事由に該当しても保険料の納付は可能
→ 被保険者等から、保険料を納付する旨の申出があったとき
★法定免除事由に該当したときの届出
→ 14日以内
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
YouTubeでお話ししています。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-055 10.19
<令和6年度国年>障害の程度が変わった場合の障害基礎年金の額の改定【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害の状態が変わった場合、障害基礎年金の額が改定されます。
今日は、職権で改定される場合と、受給権者からの請求によって改定される場合をみていきます。
障害の程度が変わった場合の額の改定について条文を読んでみましょう。
法第34条第1項~3項 (障害の程度が変わった場合の年金額の改定) ① 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は①の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
①は厚生労働大臣の職権による改定です。
②は、障害の程度が増進した場合(重くなった場合)の受給権者からの改定請求です。「障害基礎年金の受給権を取得した日」又は「厚生労働大臣の診査を受けた日」から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができません。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を経過しなくても行うことができます。
では令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-B】
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

【解答】
【R6年問6-B】 ×
「1年6か月」ではなく「1年」を経過した日より後でなければ行うことができません。
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

【解答】
①【R5年出題】 〇
障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して 「1年」を経過した日後でなければ行うことができません。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年を経過しなくても行うことができます。
②【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日のいずれか遅い日以後、「心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した」状態に至った場合は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として法第34条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合」に該当し、1年を経過しなくても額の改定請求を行うことができます。
(法第34条第3項、則第33条の2の2第1項第9号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-054 10.18
<令和6年度国年>老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせ【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
★ 年金は1人1年金が原則です。
例えば、「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」の受給権がある場合は、両方を一緒に受けることはできません。どちらかを選択して受給します。
その際、遺族基礎年金を受給することを選択した場合は、障害基礎年金は支給停止となります。
逆に、障害基礎年金を受給することを選択した場合は、遺族基礎年金は支給停止となります。
★ 同じ理由で支給される基礎年金と厚生年金は併給できます。
老齢厚生年金
|
|
障害厚生年金 |
|
遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
|
|
障害基礎年金 |
|
遺族基礎年金 |
★ 65歳以上の場合は、以下の組み合わせを選択することができます。
遺族厚生年金
|
|
老齢厚生年金 |
|
遺族厚生年金 |
|
老齢基礎年金
|
|
障害基礎年金 |
|
障害基礎年金 |
|
さっそく、令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問7-ア】
65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。

【解答】
【R6年問7-ア】 〇
65歳以上の場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できますが、65歳未満は併給できません。
そのため、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金は65歳まで支給停止されます。65歳以降は、繰り上げて減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。
60歳 65歳
遺族厚生年金 | 支給停止 | 遺族厚生年金 |
| 老齢基礎年金繰り上げ | |
(法第20条、法附則第9条の2の4)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、「他方の年金の受給権は消滅する」ではなく、「他方の年金は支給停止」されます。
例えば、障害基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金は支給停止となります。老齢基礎年金の受給権は消滅するのではなく、「支給停止」ですので、いつでも老齢基礎年金に選択替えをすることができます。
(法第20条)
②【H30年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

【解答】
②【H30年出題】 〇
65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給されませんが、65歳以降は併給できます。
(法第20条、法附則第9条の2の4)
③【R5年出題】
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
65歳以上の場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。
(法第20条、法附則第9条の2の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-053 10.17
<令和6年度国年>老齢基礎年金の繰下げの申し出ができない者【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
老齢基礎年金の繰下げの条件について条文を読んでみましょう。
第28条第1項(支給の繰下げ) ① 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 |
★老齢基礎年金の繰下げの申し出の条件は、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していないことです。
ただし、①「65歳」に達したときに、「他の年金たる給付」の受給権者であった、②65歳に達した日から66歳に達した日までの間に「他の年金たる給付」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。
「他の年金たる給付」とは、「他の年金給付(付加年金を除く。)」又は「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」のことをいいます。
「他の年金給付(付加年金を除く。)」とは、国民年金の障害基礎年金と遺族基礎年金のこと、「厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)」とは、障害厚生年金と遺族厚生年金です。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問9-B】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

【解答】
【R6年問9-B】 ×
問題文の場合は、支給繰下げの申し出はできません。
「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき」は繰下げの申し出はできません。
実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合でも、遺族厚生年金の受給権者です。そのため、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。
(法第28条第1項)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権を有していても、老齢基礎年金の支給繰下げをすることは可能です。
また、老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げる必要はありませんので、問題文のように、老齢基礎年金のみ繰り下げることもできます。
(法第28条第1項)
②【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
②【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者となったときは、支給繰下げの申出はできません。
(法第28条第1項)
③【H24年出題】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

【解答】
③【H24年出題】 ×
「寡婦年金」は他の年金たる給付の中には入りませんので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<社労士国民年金>老齢基礎年金の繰下げ
R7-050 10.14
老齢基礎年金の繰下げについてお話しします【社労士受験対策】
老齢基礎年金の繰下げについてYouTubeでお話ししています。
内容は以下の通りです。
・老齢基礎年金の繰下げの申し出ができる人の要件
・66歳後に他の年金給付の受給権を取得した場合
・繰下げ加算率
・特例的な繰下げみなし増額制度
YouTubeでご覧ください。
YouTubeでお話ししています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-042 10.6
<令和6年度国年>障害基礎年金の受給権者がさらに障害基礎年金の受給権を取得した場合【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
障害基礎年金の併合について条文を読んでみましょう。
第31条 ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
年金は「一人一年金」が原則ですが、障害基礎年金の受給権が複数発生した場合の特別規定です。
障害基礎年金の受給権が複数発生した場合は、一年金を選択するのではなく、前後の障害を併合した程度の障害基礎年金が支給されます。
第32条 ① 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるためにその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。 |
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問6-A】
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得するが、後発の障害に基づく障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために支給停止される場合は、当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される。

【解答】
【R6年問6-A】 ×
障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得します。
ただし、後発の障害基礎年金が、労働基準法の障害補償を受けることができるために6年間支給停止される場合は、「その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。」となります。
(法第32条第2項)
過去問もどうぞ!
【R4年出題】
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】
【R4年出題】 ×
新たに取得した障害基礎年金が障害補償による支給停止の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し「同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金」ではなく、「従前の障害基礎年金を支給する。」です。
(法第32条第2項)
こちらの過去問もどうぞ!
【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する

【解答】
【R1年出題】 〇
前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、「従前の障害基礎年金の受給権は消滅」するのがポイントです。支給停止ではありません。
(法第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-029 9.23
<令和6年度国年>国民年金保険料の産前産後期間の免除制度【社労士受験対策】
産前産後期間の国民年金保険料の免除制度について
令和6年に4肢出題されました。
①免除される期間
②保険料免除に関する届出
③付加保険料の納付
④保険料納付済期間
問題を解きながら要点をチェックしましょう!
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民年金法)
R7-028 9.22
<令和6年度国年>事例問題・特例による任意加入被保険者【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の択一式です。
さっそく令和6年の問題をどうぞ!
【R6年出題問9】
甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

【解答】
【R6年出題問9】 ×
甲の年金加入歴を図で確認しましょう。
20歳 | 23歳 | 30歳 | 45歳 60歳 | 65歳 |
3年間 | 7年間 | 15年間 | 20年間 | |
未加入 | 厚年被保険者 | 第3号被保険者 | 厚年被保険者(第2号) | |
カラ期間 | 保険料納付済期間 | カラ期間 | ||
★老齢基礎年金の額は以下のよう計算します。
・ 保険料納付済期間=7年+15年+15年(45歳~59歳)=37年
・ 合算対象期間=3年間(任意加入しなかった期間)+5年間(60歳~64歳)
=8年
老齢基礎年金の額 → 780,900円×改定率×444月/480月
★甲は「65歳」ですので、任意加入するとすれば、特例による任意加入となります。
特例による任意加入の条件を確認しましょう。
H16法附則第23条第1項 昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するも(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。 (1) 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
特例による任意加入は、65歳になっても、老齢基礎年金の受給権がない者が対象です。
甲は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有しますので、特例による任意加入はできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(国民年金法)
R7-020 9.14
<令和6年度>国民年金法は幅広い内容の出題でした。解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年の問題を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金の択一式です。
令和6年問10の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。

【解答】
①【R6年出題】 ×
遺族基礎年金を受ける要件に、「日本国内に住所を有している」はありません。
(法第37条の2)
②【R6年出題】
第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
夫と子に発生する年金を図で確認しましょう。
夫(50歳) |
| 子(16歳) |
|
| 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金
|
| 遺族基礎年金 (支給停止) |
※夫には遺族厚生年金の受給権は発生しません。
(55歳未満のため)
夫と子の両方に遺族基礎年金の受給権が発生した場合について、条文を読んでみましょう。
第41条第2項 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 |
夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
問題文の場合は、子の遺族基礎年金は支給停止、子は遺族厚生年金のみ受給します。夫は遺族基礎年金を受給します。
(第41条第2項)
③【R6年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】
③【R6年出題】 ×
保険料半額免除期間の月数は「2分の1」、保険料4分の1免除期間は「4分の3」で計算します。
問題文にあてはめると、48月×2分の1+12月×4分の3=33月です。死亡一時金の支給要件は「36月以上あること」ですので、遺族に死亡一時金は支給されません。
(法第52条の2)
④【R6年出題】
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
基準障害による障害基礎年金は、請求によって受給権が発生するのではなく、「所定の要件に該当」したときに受給権が発生します。ただし、支給は「請求のあった月の翌月」からとなります。請求のあった月からではありません。
(法第30条の3)
⑤【R6年出題】
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
条文で確認しましょう。
第96条第1項~3項 ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(国民年金法)
R7-010 9.4
<令和6年度国年選択式>保険料の納付事務を行うことができる者・遺族基礎年金が支給される子・死亡一時金の遺族【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、国民年金法の選択式です。
令和6年 選択問題1
国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした< A >、納付事務を< B >ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを< C >という。
<選択肢>
「完全かつ効率的に行う」、「申請に基づき実施する」、「適正かつ円滑に行う」
「適正かつ確実に実施する」
「市町村(特別区を含む。)」、「実施機関」、「都道府県」、「保険者」
「指定納付受託者」、「指定代理納付者」、「納付受託者」、「保険料納付確認団体」

【解答】
<A> 市町村(特別区を含む。)
<B> 適正かつ確実に実施する
<C> 納付受託者
(法第92条の3、第92条の4)
紛らわしい用語に注意しましょう
「指定代理納付者」(第92条の2の2)
厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であって、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(←クレジットカード)
「保険料納付確認団体」(法第109条の3)
同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであって、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの
・ 当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務
納付受託者のポイント!
「納付受託者」は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができます。
・国民年金基金又は国民年金基金連合会
・納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの(コンビニエンスストア等)
・厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
納付受託者について過去問を解いてみましょう。
①【R1年出題】
国民年金基金は、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務を行うことができるとされており、国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であっても行うことができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
国民年金基金又は国民年金基金連合会は、国民年金基金の加入員に限って、保険料の納付に関する事務を行うことができます。
(第92条の3第1項)
②【H22年出題】
厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものの委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。

【解答】
②【H22年出題】 〇
市町村が保険料の納付事務を行うことができるのは、保険料を滞納している者で市町村から特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限られます。
(第92条の3第1項)
③【H30年出題】
保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
国民年金保険料納付受託記録簿は、その完結の日から「3年間」保存しなければなりません。
(法第92条の5、則第72条の7)
令和6年 選択問題2
遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に< D >こと」と規定されている。
<選択肢>
「婚姻をしていない」
「日本国内に住所を有している」
「離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない」
「養子縁組をしていない」

【解答】
<D> 婚姻をしていない
過去問を解いてみましょう
【R4年出題】
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

【解答】
【R4年出題】 〇
図でイメージしましょう。
受給権発生 ▼ |
|
|
| 18歳年度末 ▼ |
| 20歳 ▼ |
遺族基礎年金 | ||||||
|
| ▲ 障害等級に該当し、20歳まで障害の状態にある | ||||
(法第40条第3項)
令和6年 選択問題3
遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の < E >であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
<選択肢>
「配偶者又は子」、「配偶者、子又は父母」、「配偶者、子、父母又は孫」
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」

【解答】
<E> 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

【解答】
【R1年出題】 〇
祖父母と孫では、死亡一時金を受ける順位は孫が優先します。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の順番はおぼえましょう。
(法第52条の3)
令和6年の選択式 1つめは、似たような用語が多くて、覚えにくいところです。 2つめの子の要件は、択一式でもよく出ますので、対策ができていたと思います。 3つめは、遺族の範囲と順位がポイントです。死亡一時金のみならず、死亡に関する給付についての暗記必須箇所です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<超基本>20歳前傷病による障害基礎年金
R6-358 8.19
<超基本>20歳前傷病による障害基礎年金についてお話します【社労士受験対策】
20歳前傷病による障害基礎年金の超基本をお話します。
今日の内容です
・20歳前傷病による障害基礎年金とは?
・20歳前傷病による障害基礎年金の受給権発生日2つ
・20歳前傷病による障害基礎年金独自の支給停止の規定
・20歳前傷病による障害基礎年金に対する国庫負担
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
未支給年金のこと
R6-351 8.12
国民年金の未支給年金についてお話します【社労士受験対策】
未支給年金についてお話します
★年金の受給権者が死亡した場合、必ず未支給年金があります。
年金は後払いだからです。
★未支給年金は自己の名で請求します。
★未支給年金が請求できる遺族の範囲と順位
★未支給年金を請求できる同順位者が2人以上あるとき
★遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合、受給権者の子ではないけれど、子とみなして未支給年金が請求する場合
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法と厚生年金保険法の違い
R6-350 8.11
支給停止の違い(遺族基礎年金と遺族厚生年金)【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法と厚生年金保険法です。
受給権者本人の判断で、年金の支給停止の申出をすることができます。
まず国民年金法の条文を読んでみましょう。
国民年金法第20条の2第1項 年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
厚生年金保険にも同じ規定があります。条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第38条の2第1項 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。 |
では、国民年金の過去問をどうぞ!
【国民年金法H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
【国民年金法H28年出題】 〇
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されます。
ただし、配偶者に対する遺族基礎年金が受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
(法第41条第2項)
次は厚生年金保険法の過去問をどうぞ!
【厚生年金保険法H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。

【解答】
【厚生年金保険法H30年出題】 ×
子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されます。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
国民年金法との違いに注意しましょう。
(法第66条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-349 8.10
令和6年度の国民年金保険料など【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H30年出題】※令和6年度に合わせて問題修正しています。
令和6年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,980円である。

【解答】
【H30年出題】 〇
令和6年度の国民年金保険料の月額は、
17,000円×保険料改定率(0.999)≒16,980円です。
(法第87条第3項)
★令和元年度以後の保険料は、17,000円×保険料改定率で計算します。
端数は、5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。
★保険料改定率について
保険料改定率は、前年度の保険料改定率×名目賃金変動率です。
保険料について過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
★3月31日に死亡した場合、被保険者の資格は、死亡した日の翌日(4月1日)に喪失します。
★被保険者期間は、資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までですので、3月までです。
・保険料は2月分までではなく「3月分」まで納付しなければなりません。
(第11条第1項、第87条第2項)
②【H28年出題】
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
市町村長ではなく、「厚生労働大臣」から、通知が行われます。
(法第92条第1項)
③【H26年出題】
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】
③【H26年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第88条第2項、3項 ② 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
④【R5年出題】
厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

【解答】
④【R5年出題】 ×
「その納付が確実と認められるときに限り」ではありません。
条文を読んでみましょう。
第92条の2 厚生労働大臣は、被保険者から、保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-348 8.9
国民年金基金の基本10問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
国民年金基金の基本問題10問です。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」は、第1号被保険者とみなされ、国民年金基金の加入員となることができます。
(法附則第5条第11項)
②【R5年出題】
国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【R5年出題】 ×
国民年金保険料を納付することを要しないものとされたとき及びその一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、国民年金基金の加入員の資格を喪失します。「該当するに至った日の翌日」ではなく、「当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」に加入員の資格を喪失します。
(第127条第3項第3号)
③【H29年出題】
国民年金基金が徴収する掛金の額は、額の上限の特例に該当する場合を除き、1か月につき68,000円を超えることはできない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
国民年金基金の掛金の上限は、額の上限の特例に該当する場合を除き1か月につき68,000円です。
(基金令第34条)
④【R3年出題】
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。

【解答】
④【R3年出題】 ×
国民年金基金には障害に関する一時金はありません。
条文を読んでみましょう。
第128条第1項 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 |
⑤【R4年出題】
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
「老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。」が誤りです。
条文を読んでみましょう。
第129条第1項 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。 |
⑥【H22年出題】
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

【解答】
⑥【H22年出題】 ×
国民年金基金の支給する一時金の額にも下限が決められています。
国民年金基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない、とされています。
(法第130条第3項)
⑦【R1年出題】
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。

【解答】
⑦【R1年出題】 ×
400円ではなく「200円」です。
条文を読んでみましょう。
第131条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。(←支給を停止することができる。) |
⑧【H27年出題】
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

【解答】
⑧【H27年出題】 〇
遺族基礎年金と間違えないようにしましょう。「死亡一時金」がポイントです。
(法第129条第3項)
⑨【H29年出題】
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】
⑨【H29年出題】 〇
「国民年金基金」が裁定するがポイントです。
(法第133条)
⑩【H30年出題】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

【解答】
⑩【H30年出題】 ×
「基金の加入員期間の年数にかかわらず」が誤りです。
中途脱退者とは、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が15年に満たないものをいいます。
(法第137条の17、基金令第45条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-338 7.30
<10問で分かる>繰上げ支給の老齢基礎年金【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
老齢基礎年金の繰上げのよく出る問題をみていきましょう。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の繰上げ請求はできません。
(法附則第9条の2)
②【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されませんし、任意加入被保険者になることもできません。
(法附則第9条の2の3)
③【H23年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。

【解答】
③【H23年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった「日」に発生します。(翌日ではありません。)そして、受給権発生日の属する月の翌月から支給されます。
(法附則第9条の2第3項)
④【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】
④【H26年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
(法附則第9条の2第2項)
⑤【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
⑤【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。振替加算額は、65歳に達した日以後でなければ加算されません。
(S60法附則第14条)
⑥【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算額は繰上げされません。老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は、65歳に達した日の属する月の翌月から加算されます。
なお、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げられますが、振替加算には繰下げによる増額はありません。
(S60法附則第14条)
⑦【H24年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。

【解答】
⑦【H24年出題】 〇
事後重症の障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までの間、請求できます。
ただし、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前でも、事後重症による障害基礎年金の請求はできません。
(法附則第9条の2の3)
⑧【H26年出題】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】
⑧【H26年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅します。
⑨【H19年出題】
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。

【解答】
⑨【H19年出題】 ×
付加年金は、老齢基礎年金に連動していますので、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合は、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されます。また、その際、減額率、増額率も同じように適用されます。
(法附則第9条の2第6項)
⑩【H27年出題】
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
⑩【H27年出題】 〇
ポイントその1
振替加算は、妻自身の老齢基礎年金に加算される年金です。夫の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止されていた場合でも、要件を満たせば、加算が行われます。
ポイントその2
老齢基礎年金の支給を繰り上げていても、振替加算は繰り上げられませんので、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算されます。
(S60法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
「事後重症」について国年・厚年両方の視点でお話します
R6-337 7.29
問題が解ける!事後重症【社労士受験対策】
「事後重症」について国民年金・厚生年金保険、それぞれの視点でお話します。
<今日の内容>
・事後重症の条件
キーワードは、
障害認定日後65歳に達する日の前日までに障害等級に該当すること
請求で受給権が発生すること
・事後重症の障害基礎年金でも請求が不要な場合
障害厚生年金が3級から2級に改定になった場合
★65歳に達した日の前日までの条件を忘れないようにすることがポイントです。
・「障害厚生年金」の受給権者でも、障害基礎年金の受給権は無いことがあります。
★1度も1・2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者
→ 障害基礎年金の受給権はありません
★2級だったが障害状態が軽減して現在3級の場合
→ 3級の間は障害基礎年金の支給は停止されますが、障害基礎年金の受給権はあります
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-327 7.19
10問で分かる!死亡一時金【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
支給要件の条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項、2項 (支給要件) ① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 ② 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 (1) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 (2) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。「第2号被保険者、第3号被保険者」としての被保険者期間は対象とされません。
(第43条、第49条、第52条の2)
②【H23年出題】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。

【解答】
②【H23年出題】 ×
65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、「死亡一時金、脱退一時金」については、第1号被保険者とみなされます。しかし、寡婦年金については、第1号被保険者とみなされません。
(H6法附則第11条第9項、H16法附則第23条第9項)
★ちなみに、65歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金について第1号被保険者とみなされます。
(法附則第5条第9項)
★「付加保険料」については、65歳未満の任意加入被保険者は、第1号被保険者とみなされ付加保険料を納付できます。65歳以上70歳未満の特例の任意加入被保険者は、付加保険料は納付できません。
| 寡婦年金 | 死亡一時金 | 脱退一時金 | 付加保険料 | |
| 任意加入被保険者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特例の任意加入被保険者 | × | 〇 | 〇 | × |
③【R1年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】
③【R1年出題】 〇
保険料4分の1免除期間は、「4分の3」相当ですので、48月×4分の3=36月となります。要件を満たしますので、死亡一時金が支給されます。
(第52条の2第1項)
④【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

【解答】
④【H24年出題】 ×
「保険料全額免除期間」は、保険料を全く納付していませんので、計算に入りません。
(第52条の2第1項)
⑤【R2年出題】
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
(原則)
死亡した者の死亡日に、その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません。
(例外)
ただし、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金は支給されます。
例えば、18歳に達した日以後の最初の3月に遺族基礎年金の受給権が発生しても、同じ月に受給権が消滅し、結局遺族基礎年金は支給されません。その場合は、死亡一時金が支給されます。
次に遺族の範囲について条文を読んでみましょう。
第52条の3 (遺族の範囲及び順位等) ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
⑥【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

【解答】
⑥【R1年出題】 〇
遺族の順位は決まっていて、祖父母と孫では、孫が優先します。
(第52条の3)
死亡一時金の額についての過去問をどうぞ!
⑦【H26年出題】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。

【解答】
⑦【H26年出題】 ×
死亡一時金の額は、6段階で設定されていて、32万円が最高です。32万円支給されるのは、420月以上の場合です。
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
月数は、以下の月数を合算します。
死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における
保険料納付済期間の月数
+
保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
+
保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
+
保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
(第52条の4第1項)
⑧【H29年出題】
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。

【解答】
⑧【H29年出題】 〇
付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族の死亡一時金の額には、8,500円が加算されます。
(第52条の4第2項)
支給の調整について条文を読んでみましょう。
第52条の6(支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
過去問をどうぞ!
⑨【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
⑨【H24年出題】×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、その者の選択によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。
例えば、死亡一時金を選択した場合は、死亡一時金が支給され、寡婦年金は支給されません。
(第52条の6)
⑩【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
⑩【R3年出題】 〇
・1人1年金の原則
遺族厚生年金と寡婦年金はどちらか選択です。
・寡婦年金を選択した場合
死亡一時金は支給されません
・遺族厚生年金を選択した場合
死亡一時金も支給されます。
(第20条、第52条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-315 7.7
国民年金の被保険者期間の計算【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
被保険者期間の計算について条文を読んでみましょう。
第11条 (被保険者期間の計算) ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 |
被保険者期間は月単位で計算します。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
平成11年4月1日生まれの者は平成31年3月31日に20歳に達し、その日に資格を取得します。被保険者期間に算入されるのは、資格を取得した日の属する月からですので、平成31年3月からです。
(第11条)
②【H26年出題】
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

【解答】
②【H26年出題】 ×
昭和29年4月1日生まれの場合、60歳に達するのは、平成26年3月31日です。被保険者期間に算入されるのは、「資格を喪失した日の属する月の前月」までですので、平成26年2月までです。
(第11条)
③【H29年出題】
平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

【解答】
③【H29年出題】 〇
同じ月に取得と喪失がある場合は、その月は1か月として、被保険者期間に算入されます。
(第11条)
④【H26年出題】
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
④【H26年出題】〇
・ 4月1日に資格取得・4月30日に資格喪失の場合は1か月が被保険者期間に算入されます。
・ 4月1日に資格取得・同年5月31日に資格喪失の場合、資格を喪失した日の属する月の前月が4月ですので、1か月が被保険者期間に算入されます。
(第11条)
⑤【R5年出題】
被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間を2か月として被保険者期間に算入する。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
同じ月に、資格取得と資格喪失があるときは、その月は1か月として被保険者期間に算入されますが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、「後の被保険者期間」で1か月として被保険者期間に算入されます。「前後を合算」は誤りです。
(第11条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-314 7.6
<選択式>学生納付特例のチェックポイント【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。
<選択肢>
① 1年2か月 ② 1年6か月 ③ 2年2か月 ④ 2年6か月

【解答】
A ③ 2年2か月
免除される期間は、「厚生労働大臣の指定する期間」です。
具体的にみてみましょう。
1.申請免除及び納付猶予の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間
2.学生納付特例の対象となる厚生労働大臣が指定する期間
申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間
(平成26年厚生労働省告示第191号)
国民年金保険料の免除がさかのぼって申請できるのは、保険料の納期限から2年を経過していない期間です。
例えば、令和4年8月分の保険料の納付期限は令和4年9月30日です。令和6年9月30日までに免除の申請をすれば、2年1か月前の分まで遡って免除されます。
※「2年2か月」遡及できる場合
なお、保険料の納期限は翌月末日ですが、その日が土日等の場合は、翌々月の第1営業日が納付期限になります。
例えば、令和4年6月の保険料は、7月31日が日曜日だったため、8月1日が納期限となります。そのため、令和4年6月分の免除申請の期限は令和6年8月1日となります。この場合は2年2月前の分まで遡って免除されます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
学生納付特例の適用を受けるには所得要件がありますが、世帯主又は配偶者の所得は問われず、本人の所得要件のみが問われるのがポイントです。
(第90条の3第1項)
所得要件を確認しましょう
| 本人 | 世帯主 | 配偶者 |
申請免除(全額・一部) | 〇 | 〇 | 〇 |
学生納付特例 | 〇 | ― | ― |
納付猶予 | 〇 | ― | 〇 |
②【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

【解答】
②【R3年出題】 ×
納付猶予制度は法附則に規定される時限措置で、有効期間は令和12年6月までです。
(H26年法附則第14条の3)
学生納付特例制度は、国民年金法本則に規定される恒久的な制度で、時限措置ではありません。
(第90条の3)
③【H28年出題】
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

【解答】
③【H28年出題】 〇
学生等は、申請全額免除・一部免除・納付猶予の対象から除外されています。
ただし、法定免除は学生等にも適用されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-313 7.5
<選択式>国民年金の給付制限【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、選択式からどうぞ!
【H26年選択式】
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< A >ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< B >ことができる。
<選択肢>
① 医師の診療を拒んだ ② 全額の支給を停止する
③ 全部を一時差し止める ④ 全部又は一部を一時差し止める
⑤ 全部又は一部を行わない ⑥ 当該職員の指導に従わない
⑦ 当該職員の診断を拒んだ ⑧ 療養に関する指示に従わない

【解答】
A ⑧ 療養に関する指示に従わない
B ⑤ 全部又は一部を行わない
「全部又は一部を行わないことができる」の条文を読んでみましょう。
第70条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。 |
では、択一式の過去問もどうぞ!
①【R5年出題】
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「障害基礎年金は支給しない」です。
「支給しない」の条文を読んでみましょう。
第69条 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 |
「故意」の場合は、「全部又は一部を行わないことができる」ではなく「支給しない」です。
②【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。

【解答】
②【R1年出題】 〇
遺族基礎年金の受給権が「消滅する」条文を読んでみましょう。
第71条第2項 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 |
③【R1年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべきものを故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。

【解答】
③【R1年出題】 〇
「支給しない」条文を読んでみましょう。
第71条第1項 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 |
④【R2年出題】
遺族基礎年金の受給権者である配偶者が、正当な理由がなくて、指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないときは、当該遺族基礎年金は支給を停止するとされている。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「支給を停止する」ではなく、「年金給付の支払を一時差し止めることができる」です。
差止めの場合、届出を提出すれば、差止められていた年金がさかのぼって支払われます。
「一時差し止めることができる」の条文を読んでみましょう。
第73条 受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 |
⑤【R1年出題】
受給権者が、正当な理由がなくて、国民年金法第107条第1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず、又は当該調査における職員の質問に応じなかったときは、年金給付の額の全部又は一部につき、その支給を一時差し止めることができる。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
差し止めと違い、支給停止の場合は、停止された年金は支払われません。
条文を読んでみましょう。
第72条 年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 (1) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。 (2) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。 |
⑥【R4年出題】
国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

【解答】
⑥【R4年出題】 ×
受診命令に従わず、職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を「一時差し止めることができる」ではなく、「その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる」です。
(第72条第2号)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金のことお話します
R6-309 7.1
遺族基礎年金の額についてもう少し詳しくお話します【社労士受験対策】
先日は、遺族基礎年金の3つの基本をお話しました。
↓
https://youtu.be/4cv6AR25kZk?si=ziNHPLdWhmSHUjQC
今回は、遺族基礎年金の額についてもう少し詳しくお話します。
★遺族基礎年金の額
・配偶者が受給する場合
・子が受給する場合
★死亡当時胎児だった子が生まれた場合
★子の数が減った場合
★配偶者の遺族基礎年金が失権するとき
★応用編
・ すべての子が直系血族又は直系姻族の養子になった場合の遺族基礎年金の受給権
YouTubeでお話しています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-303 6.25
<選択式>年金額の改定・財政の現況及び見通しの作成【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
<選択肢>
① 国民生活の現況 ② 国民生活の状況 ③ 国民の生活水準
④ 国民生活の安定 ⑤ 改定 ⑥ 所要 ⑦ 是正 ⑧ 訂正

【解答】
A ③ 国民の生活水準
B ⑤ 改定
(法第4条)
年金額の改定の規定です。
②【H26年選択式】
政府は、少なくとも< A >年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び< B >期間における見通しを作成しなければならない。
この< B >期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね < C >年間とする。
<選択肢>
① 3 ② 5 ③ 7 ④ 10 ⑤ 25 ⑥ 30
⑦ 50 ⑧ 100 ⑨ 財政均衡 ⑩ 財政計画
⑪ 収支均衡 ⑫ 将来推計

【解答】
A ② 5
B ⑨ 財政均衡
C ⑧ 100
(第4条の3第1項)
年金の財政は、有限均衡方式がとられています。長期的な財政の均衡が義務づけられています。
条文を読んでみましょう。
第4条の2 (財政の均衡) 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 |
財政均衡期間は約100年で、この期間で給付と負担のバランスを図ることになっています。
政府は、給付と負担のバランスを確認するため、少なくとも5年ごとに財政検証を行っています。
③【R3年選択式】
国民年金法第16条の2第1項の規定によると、政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に< A >ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下本問において「給付額」という。)を< B >するものとし、政令で、給付額を< B >する期間の < C >を定めるものとする。
<選択肢>
① 給付額に不足が生じない ② 給付の支給に支障が生じない
③ 財政窮迫化をもたらさない ④ 財政収支が保たれる
⑤ 改定 ⑥ 減額 ⑦ 調整 ⑧ 変更
⑨ 開始年度 ⑩ 終了年度 ⑪ 開始年度及び終了年度 ⑫ 年限

【解答】
A ② 給付の支給に支障が生じない
B ⑦ 調整
C ⑨ 開始年度
(第16条の2第1項)
調整期間とは、マクロ経済スライドが適用される期間のことです。
政均衡期間に均衡を保つことができないと見込まれる場合には、給付額を調整するため、マクロ経済スライドを行い、給付水準を調整します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
遺族基礎年金の基本について
R6-302 6.24
遺族基礎年金の3つの基本をお話します。【社労士受験対策】
遺族基礎年金の3つの基本をお話しします。
①死亡した人の要件
・短期要件と長期要件があります。
・保険料納付要件が必要な場合と、不要な場合があります。
②遺族基礎年金を受けることができる遺族
死亡した者に生計を維持されていた「配偶者又は子」です。
ただし、配偶者は、「子と生計を同じくすること」が条件です。
③遺族基礎年金の額
「配偶者」に支給される場合と、「子」に支給される場合で分けて、おさえましょう。
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害基礎年金の受給権発生要件の基本
R6-295 6.17
障害基礎年金の受給権3つのポイントについてお話をします【社労士受験対策】
障害基礎年金発生の3つの要件を確認しましょう。
①初診日
・初診日とは?
・初診日の要件
②保険料納付要件
・初診日の前日
・初診日の属する月の前々月
・特例が適用される条件
③障害認定日
・1年6か月と治った日
YouTubeで解説しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-294 6.16
<選択式>老齢基礎年金の繰上げと繰下げ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
今日は選択式の過去問です。
では、過去問をどうぞ!
【H21年選択式】※改正による修正あり
① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

【解答】
<A> 60歳以上65歳未満
<B> 任意加入被保険者
<C> 65歳
(法附則第9条の2第1項)
繰上げのポイント!
★繰上げ請求ができるのは、60歳から65歳になるまでの間です
★任意加入被保険者は繰上げ請求できません
② 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】
<D> 付加年金
<E> 老齢
(第28条第1項)
繰下げのポイント!
★66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない
★65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない
★65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない
「他の年金たる給付」とは
↓
(国民年金法の)他の年金給付(付加年金を除く。)
又は
厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
こちらの問題もどうぞ!
①【R1年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

【解答】
①【R1年出題】 ×
老齢基礎年金の支給の繰上げは、国民年金法附則で当分の間の措置として規定されています。
老齢基礎年金の支給繰下げは、国民年金法第28条で規定されています。
(第28条、附則第9条の2)
②【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
②【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者となったときは、繰下げの申出はできません。
※他の年金たる給付は、簡単に書きますと、障害や遺族の年金です。
問題文のように、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、「障害基礎年金」の受給権者となったときは、支給繰下げの申出をすることができません。
(第28条第1項)
③【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。

③【R1年出題】 〇
「66歳前に老齢基礎年金を請求していない」、「65歳に達したときに他の年金たる給付の受給権者でない」、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていない」場合は、老齢基礎年金の繰下げの申出ができます。
「他の年金たる給付」から、老齢厚生年金は除かれますので、問題文の場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることができます。
(第28条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-290 6.12
保険料納付済期間や保険料免除期間のことなど【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。

【解答】
①【H24年出題】 〇
第91条で、「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。」とされています。
ただし、翌月末日が、日曜日、休日、土曜日等の場合は、その翌日が期限となります。
例えば、令和6年5月分の国民年金の保険料の納期限は、翌月末日(令和6年6月30日)が日曜日ですので、その翌日(令和6年7月1日)となります。
(第91条、国税通則法第10条第2項)
②【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
②【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、障害基礎年金の要件では、「保険料納付済期間」となります。
<第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間>
★老齢基礎年金★
「合算対象期間」となります。
受給資格期間の計算には入りますが、年金額には反映しません。
★障害基礎年金・遺族基礎年金★
「保険料納付済期間」となります。
(第5条第1項)
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

【解答】
③【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
「督促及び滞納処分により保険料が納付された期間」も保険料納付済期間に含まれます。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
④【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第3項 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※「納付猶予」の期間も保険料全額免除期間に含まれます。(H16法附則第19条) |
保険料を追納した期間は、保険料全額免除期間から除かれ、保険料納付済期間とされます。
⑤【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まれない。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
例えば、保険料4分の1免除をうけた場合、残りの4分の3は納付する義務があります。
残りの4分の3を納付した期間は、「保険料納付済期間」ではなく、「保険料4分の1免除期間」となります。
条文を読んでみましょう。
第5条第6項 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-289 6.11
障害基礎年金重要5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
では過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「事後重症」の問題です。
「その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。」が誤りです。
条文を読んでみましょう。
第30条の2第1項 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 |
事後重症の障害基礎年金は、「65歳に達する日の前日までの間」に、請求することができます。
★事後重症のポイント!
・初診日の要件を満たしていること
・初診日の前日に保険料納付要件を満たしていること
・障害認定日に障害等級に不該当であること(=障害基礎年金の受給権は発生しない)
・障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当したこと
・65歳に達する日の前日までの間に請求すること
↓
事後重症の障害基礎年金は、「請求」によって受給権が発生します。
②【H21年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
「子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。」が誤りです。
障害基礎年金に加算される額は、以下の額です。
1人目、2人目の子は、1人につき224,700円×改定率
3人目以降は、1人につき74,900円×改定率
(第33条の2第1項)
③【H23年出題】
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
受給権を取得した日の翌日以後に子を有するに至った場合でも、加算が行われます。
条文を読んでみましょう。
第33条の2第2項 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |
④【H21年出題】
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。

【解答】
④【H21年出題】 ×
初診日の要件、障害認定日の要件、保険料納付要件を満たしていれば、障害認定日に65歳を超えていても、障害基礎年金の受給権は発生します。
ちなみに「初診日」の要件は、初診日に次のどちらかに該当していることです。
(1) 被保険者であること。
(2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
問題文は初診日に(2)の要件を満たしていますので、障害認定日が65歳を超えていても、障害基礎年金が支給されます。
(第30条)
⑤【H21年出題】
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。

【解答】
⑤【H21年出題】 〇
旧国民年金法の「障害福祉年金」とは、拠出制の障害年金の要件に該当しない場合などに支給された年金で、費用は全額国庫負担でした。
昭和61年3月31日に、障害福祉年金の受給権を有していた者が、昭和61年4月1日に障害等級1、2級に該当する場合は、障害福祉年金ではなく「障害基礎年金」として支給されます。
なお、支給される障害基礎年金は、「第30条の4の障害基礎年金=20歳前に初診日がある障害基礎年金」です。
(昭60法附則第25条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
老齢基礎年金の計算式のすべて
R6-288 6.10
老齢基礎年金の額の計算について原則のお話をします【社労士受験対策】
老齢基礎年金の額の計算の原則のお話をします。
・老齢基礎年金の満額の額は?
・満額支給されるのはどのような場合?
→20歳から60歳までの480月すべてが保険料納付済期間であること
・保険料納付済期間とは?
第1号被保険者期間+第2号被保険者期間+第3号被保険者期間
→第1号被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されるのは?
→第2号被保険者期間のうち、保険料納付済期間に算入されるのは?
・老齢基礎年金が減額される例
→未納期間がある場合
・保険料免除期間がある場合
→免除の種類によって老齢基礎年金の額に反映される割合が決まります
・過去問を解いてみましょう
→学生納付特例期間と納付猶予期間の扱い
→第2号被保険者期間のうち老齢基礎年金の額に反映される期間
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-278 5.31
寡婦年金よく出る5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、寡婦年金の条文を読んでみましょう。
第49条第1項、3項(支給要件) ① 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 ③ 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
ポイント!
第1号被保険者だけでなく「任意加入被保険者」の期間も含みます。特例任意加入被保険者は含まれません。
夫の死亡時に60歳未満の妻については、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。寡婦年金が支給されるのは、60歳から65歳になるまでです。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H24年出題】 〇
65歳に達したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
寡婦年金の失権について条文を読んでみましょう。
第51条(失権) 寡婦年金の受給権は、受給権者が65歳に達したとき、又は第40条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 (第40条第1項) (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻をしたとき。 (3) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときも、寡婦年金の受給権は消滅します。 附則第9条の2第5項 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。 |
②【H24年出題】
寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。

【解答】
②【H24年出題】 〇
寡婦年金の受給権は、養子となったときは消滅しますが、直系血族又は直系姻族の養子となったときは除かれます。そのため、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはありません。
(第51条)
③【H24年出題】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。

【解答】
③【H24年出題】 ×
寡婦年金の額には、付加保険料の納付分は反映しません。
寡婦年金の額は、夫の第1号被保険者(任意加入被保険者も含みます)の期間で計算した老齢基礎年金の4分の3です。
条文を読んでみましょう。
第50条 (年金額) 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
④【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
寡婦年金の額の算定には、第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は反映しません。
(第50条)
⑤【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、寡婦年金が優先されるのではありません。寡婦年金と死亡一時金のどちらか選択となります。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 (支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金を選択した場合は、寡婦年金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-277 5.30
振替加算の基本5問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、振替加算の条件を確認しましょう。
下のイメージ図をご覧ください。
なお、振替加算が支給されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
の人に限られることにも注意しましょう。
過去問を解きながら重要ポイントをチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】
①【H21年出題】 ×
遺族基礎年金には振替加算額は加算されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第14条第1項 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金の額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない。 (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が原則として240以上であるもの (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(1級又は2級) |
振替加算は「老齢基礎年金の額」に加算されます。
遺族基礎年金を選択した場合は、振替加算相当額は加算されません。
②【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
障害基礎年金の全額が支給停止されている場合は、振替加算に相当する部分は支給停止されません。
条文を読んでみましょう。
昭60年附則第16条第1項 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間振替加算に相当する部分の支給を停止する。 |
障害基礎年金等の給付を受けることができる場合は、振替加算は支給停止されます。
障害基礎年金が全額支給停止されている(=受けることができない)場合は、支給停止されません。
③【H21年出題】
振替加算の受給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と納付猶予の期間は除く。)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、65歳に達した月において振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

【解答】
③【H21年出題】 ×
合算対象期間と学生納付特例期間のみで10年以上の場合でも、老齢基礎年金の受給資格期間は満たします。しかし、どちらも老齢基礎年金の額には反映しませんので、老齢基礎年金の額はゼロになります。
老齢基礎年金の額自体はゼロでも、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給されます。
問題文の場合は、老齢基礎年金の額に反映する期間が1月以上1年未満ありますので、振替加算相当額のみではなく、1月以上1年未満の分が反映された老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
(昭60年附則第15条第1項)
④【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

【解答】
④【H21年出題】 〇
配偶者と離婚しても、振替加算は支給停止されません。
⑤【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】
⑤【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されます。しかし、増額はされません。
(昭60年附則第14条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
年金制度の歴史をお話します
R6-274 5.27
年金制度のポイントは昭和36年と昭和61年【社労士受験対策】
年金制度の歴史をお話します。
<厚生年金保険と国民年金の誕生>
①船員保険制度
昭和14年制定、昭和15年施行
社会保険方式による日本初の公的年金制度
など
②厚生年金保険法
労働者年金保険法としてスタート
など
③国民年金法
昭和36年4月より拠出制がスタートしたことによって
国民皆年金の実現!
<旧法から新法へ>
④基礎年金の登場 昭和61年4月
・昭和61年4月1日前を「旧法」、昭和61年4月1日以後を「新法」といいます
・年金制度が2階建てになりました
・国民年金の被保険者が第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者に区分されました
⑤新法と旧法の違い
1 旧法は「縦割り」、新法は「2階建て」
2 専業主婦は旧法では任意加入、新法では第3号被保険者として強制加入です
3 船員保険は旧法では独立していましたが、新法では厚生年金に統合されました
詳しくは、YouTubeでお話ししています。
YouTubeをご覧ください
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
https://youtu.be/UMR4m6jvQr4?si=Be9bRoLQwbXNt3vy
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-264 5.17
第2号・第3号被保険者は保険料の納付義務なし【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
第1号被保険者は、国民年金の保険料を納付しなければなりませんが、第2号被保険者と第3号被保険者には保険料の納付義務はありません。
条文を読んでみましょう。
第94条の6 (第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例) 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
第2号被保険者、第3号被保険者にも、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されますが、給付に必要な費用は、「基礎年金拠出金」を通して行われます。
そのため、第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付する必要はありません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
第1号被保険者と任意加入被保険者には国民年金保険料の納付義務があります。
第2号被保険者及び第3号被保険者には国民年金保険料の納付義務はありません。
(第88条第1項、第94条の6)
②【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
国民年金保険料の納付義務があるのは「第1号被保険者」です。第2号被保険者と第3号被保険者は国民年金保険料を納付することを要しません。
(第88条第1項、第94条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
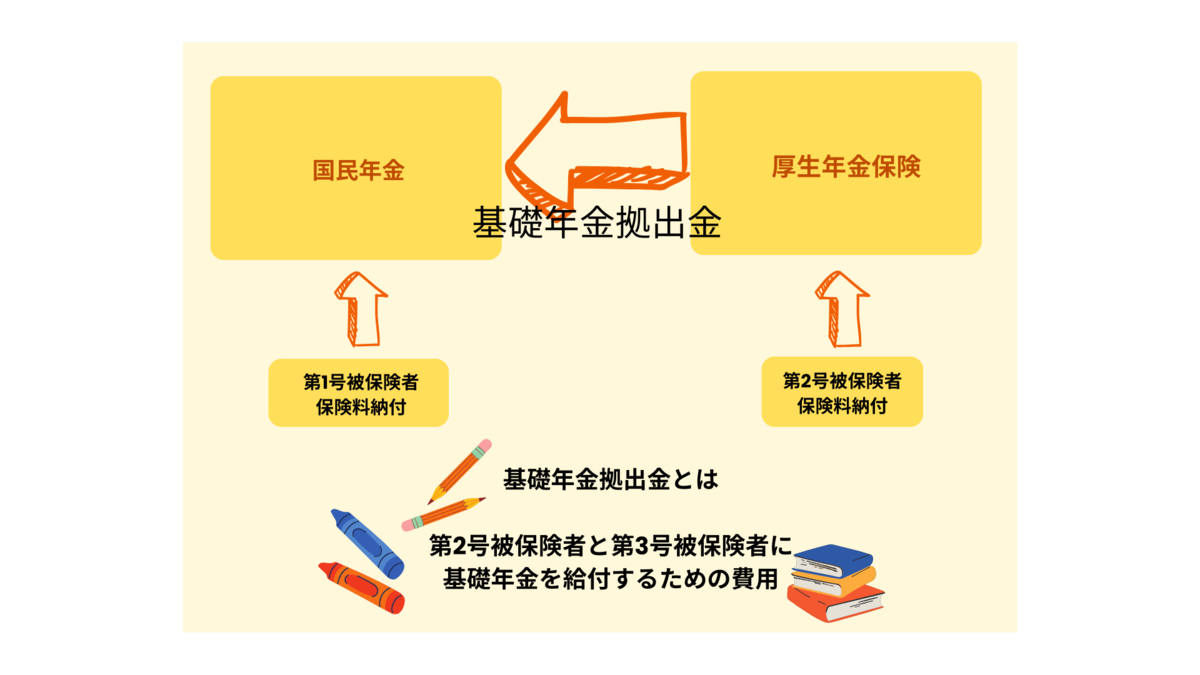
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-263 5.16
付加年金と死亡一時金の加算額に対する国庫負担【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
第1号被保険者は、付加保険料(月額400円)を納付することができます。以下の給付には、付加保険料の納付が反映されます。
★付加年金
老齢基礎年金に上乗せして「付加年金」が支給されます。
付加年金は200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数で計算します。
★死亡一時金の加算額
死亡した者の付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある場合、死亡一時金に8500円が加算されます。
今回は、付加年金と死亡一時金の加算額の費用に対する国庫負担をみていきます。
条文を読んでみましょう。
S60年法附則第34条第1項第1号 (国民年金事業に要する費用の負担の特例) 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。 |
★付加年金の給付に要する費用、死亡一時金の加算額に要する費用の「4分の1」を国庫が負担します。
※第52条の4第1項に定める額とは、12万円から32万円まで6段階で設定されている死亡一時金の額のことです。
その額は「除く」としていますので、4分の1の国庫負担が行われるのは、死亡一時金に加算される額(=8500円)に対してです。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

【解答】
①【R4年出題】 〇
「付加年金の給付に要する費用」と「死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)=死亡一時金に加算される額(8500円)のこと」の総額の4分の1に相当する額を国庫が負担します。
(S60年法附則第34条第1項第1号)
②【H26年出題】
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の額の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。

【解答】
②【H26年出題】 〇
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に死亡一時金に加算される額(8,500円)の給付に要する費用については、4分の1を国庫が負担します。
(S60年法附則第34条第1項第1号)
③【H26年出題】
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。

【解答】
③【H26年出題】 ×
付加年金の給付に要する費用の国庫負担は、3分の1ではなく「4分の1」です。
(S60年法附則第34条第1項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-248 5.1
第3号被保険者となる要件【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「第3号被保険者」について条文を読んでみましょう。
第7条第1項第3号 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
則第1条の3 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 (1) 外国において留学をする学生 (2) 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者 (3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 (4) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの (5) 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
第3号被保険者のポイントは?
■第2号被保険者に扶養される配偶者
■20歳以上60歳未満
■日本国内に住所を有する(原則)
※外国において留学する学生、外国に赴任する第2号被保険者に同行する者などは、国内居住要件の例外が認められます
なお、日本国籍を有しない者で、「医療滞在」や「観光等を目的とするロングステイ」の場合は、第1号被保険者・第3号被保険者から除外されます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
★国籍要件について
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、全て、「国籍要件」はありません。
★年齢要件(20歳以上60歳未満)について
第1号被保険者、第3号被保険者は年齢要件があります。
第2号被保険者は年齢要件はありません。
★国内居住要件について
第1号被保険者は、「国内居住要件」があります。
第2号被保険者は、「国内居住要件」はありません。
第3号被保険者は、原則は「国内居住要件」がありますが、例外もあります。
(第7条第1項)
②【H17年出題】※改正による修正あり
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。

【解答】
②【H17年出題】 ×
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でも、要件を満たせば第3号被保険者となります。
なお、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は第1号被保険者からは除外されます。
(第7条第1項)
③【R3年出題】
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
第3号被保険者は、国内居住が原則ですが、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、海外特例により第3号被保険者として認定されます。第3号被保険者の資格は喪失しません。
(第7条第1項、則第1条の3)
④【R3年出題】
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

【解答】
④【R3年出題】 〇
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する場合は、海外特例により、第3号被保険者となることができます。
(第7条第1項、則第1条の3第3号)
⑤【H27年出題】
第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
「日本年金機構」が行うの部分がポイントです。
(令第4条)
⑥【R3年出題】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
 「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者ではないことがポイントです!
「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者ではないことがポイントです!
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者です。
ただし、「65歳以上」で「老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権」を有する場合は、第2号被保険者となりません。
問題の「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は第2号被保険者ではありません。
 第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。問題の配偶者は第2号被保険者の配偶者ではないので、第3号被保険者になりません。
第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。問題の配偶者は第2号被保険者の配偶者ではないので、第3号被保険者になりません。
(第7条、附則第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
ご質問に答えます 国民年金法
R6-247 4.30
1号から除外される厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者とは?【社労士受験対策】
国民年金の第1号被保険者から除外される「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」についてご質問がありました。
まず、第1号被保険者の定義を条文で読んでみましょう。
第7条第1項第1号 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。) |
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、第1号被保険者から除外されます。
 20歳以上60歳未満で、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とは、どんな人でしょう?
20歳以上60歳未満で、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」とは、どんな人でしょう?
例えば、昭和15年4月1日以前生まれで一定の要件を満たした女性の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、「55歳から59歳まで」の間でした。
早ければ55歳から特別支給の老齢厚生年金を受けることができました。その場合、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる」者になりますので、第1号被保険者から除外されます。
他に、坑内員、船員も一定要件を満たせば、早ければ55歳から老齢厚生年金を受けることができました。
注意しましょう
「受給資格期間を満たしている者」ではありませんので、注意してください。
例えば、現在、55歳の人で保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上ある場合は、受給資格期間を満たしています。しかし、実際に老齢厚生年金を「受けることはできない」ので、第1号被保険者からは除外されません。
 「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は国民年金に「任意加入」できます。
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は国民年金に「任意加入」できます。
条文を読んでみましょう。
附則第5条第1項 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
第1号被保険者から除外される「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、(1)の規定で国民年金に任意加入できます。
先ほどの例の昭和15年4月1日以前生まれの女性で、「55歳から59歳まで」の間に特別支給の老齢厚生年金を受けることができたとしても、65歳からの老齢基礎年金は満額支給されるとは限りません。
老齢基礎年金を満額にしたい又は満額に近づけたい場合は、国民年金に任意加入して保険料を納付することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-229 4.12
申請のあった日以後保険料全額免除期間に算入することができる
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「申請全額免除」の条文を読んでみましょう。
第90条第1項 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の3免除、半額免除期、4分の1免除期間の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 (1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。 (2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 (3) 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。 (4) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。 |
保険料の全額免除の申請をした場合は、「申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる」という部分に注目してください。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H28年出題】 ×
障害基礎年金の受給権は発生しません。初診日の前日の「保険料納付要件」を満たしていないからです。
★保険料が免除される期間は、「厚生労働大臣が指定する期間」です。
厚生労働大臣が指定する期間は、申請免除の場合、「申請のあった日の属する月の2年2月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間」となります。
→遡って保険料の免除を申請することができるのは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間です。
★ただし、保険料全額免除期間に算入されるのは、「申請のあった日以後」です。
★障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」で判断されます。
22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請をして、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となったとしても、「保険料全額免除期間」に算入されるのは、申請のあった日以後です。
初診日の前日の時点では、すべての期間が「滞納」で保険料納付要件を満たしませんので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
(法第30条第1項、第90条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-228 4.11
社労士受験のための 任意加入被保険者と口座振替納付
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
国民年金の任意加入被保険者は、原則として、口座振替で保険料を納付しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
附則第5条第1項、2項(任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 (1) 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (2) 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) (3) 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①(1)又は(2)に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 |
★ (3)日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは、口座振替の申出をする必要はありません。
★ 特例による任意加入被保険者も、原則として口座振替で保険料を納付しなければなりません。(H6附則第11条第2項)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】※改正による修正あり
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
日本国内に住所を有する者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合は、「口座振替納付を希望する旨の申出」または「口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出」が必要です。
(附則第5条第2項)
②【H28年出題】
日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
日本国内に住所を有する任意加入被保険者は口座振替納付が原則ですが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができます。
(則第2条の2第2号)
③【H21年出題】
国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない

【解答】
③【H21年出題】 ×
日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない者(海外に在住している場合)は、口座振替納付を希望する旨の申出は不要です。
(附則第5条第2項)
④【R2年出題】
60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

【解答】
④【R2年出題】 ×
特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付できないので、誤りです。
なお、任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る)が、65歳に達した日に、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合は、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされます。
(H16附則第23条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-214
R6.3.28 付加保険料の7つのポイント
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「付加保険料」の納付について条文を読んでみましょう。
第87条の2 ① 第1号被保険者(法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除を受けている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。 ② 付加保険料の納付は、国民年金保険料の納付が行われた月(追納により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後期間の免除により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 ③ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 ④ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、③の申出をしたものとみなす。 |
第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付することができます。付加保険料を納付した場合、老齢基礎年金に付加年金がプラスされます。
過去問をどうぞ!
これまで過去問①②の次に解答①②としてきましたが、リクエストを頂きましたので、今回から過去問①解答①→過去問②解答②の順番にします。 |
①【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
「任意加入被保険者」は付加保険料の納付については第1号被保険者とみなされ、付加保険料を納付できます。
なお、特例任意加入被保険者は付加保険料を納付できません。
(法附則第5条第9項)
②【R1年出題】
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
産前産後期間の保険料免除の期間は、付加保険料を納付することができます。
(第87条の2第2項)
③【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
③【H29年出題】 ×
保険料の免除(法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予、一部免除)を受けている者は、付加保険料は納付できません。
(第87条の2第1項)
④【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

【解答】
④【H26年出題】 ×
追納によって保険料が納付されたものとみなされた月は、付加保険料は納付できません。
(法第87条の2第1項)
⑤【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
そのため、付加保険料を納付する者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
(法第87条の2第4項)
⑥【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
付加保険料の納付は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、納付をやめることができます。
やめることができるのは、その申し出をした日の属する月以後の各月ではなく、申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)です。
(法第87条の2第3項)
ちなみに、付加保険料の納付を始めるときは、「その申出をした日の属する月以後の各月」からとなります。
⑦【H26年出題】
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

【解答】
⑦【H26年出題】 ×
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合でも、納付を辞退したものとはみなされません。
付加保険料を納期限までに納付しなかった場合でも、国民年金の保険料と同様、納期限から2年以内は納付することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-198
R6.3.12 基礎年金拠出金の算定基礎となる被保険者数
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
今日のテーマは「基礎年金拠出金」の算定です。
・厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
・実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
(第94条の2第1項、2項)
条文を読んでみましょう。
第94条の3第1項、2項 ① 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 ※政府及び実施機関に係る被保険者の総数とは ・ 厚生年金保険の実施者たる政府 →第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ・ 実施機関たる共済組合等 → 当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者 ■国家公務員共済組合連合会 →当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ■地方公務員共済組合連合会 →当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ■日本私立学校振興・共済事業団 →第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者 ② 被保険者の総数並びに政府及び実施機関に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする。
令第11条の3 法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする |
基礎年金拠出金の額の出し方
基礎年金の給付に 要する費用 | × | 第2号被保険者+第3号被保険者 |
国民年金の被保険者の総数 |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。
②【R4年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。
③【H30年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

【解答】
①【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について
・第1号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者 → 20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者 → すべての者
「第2号被保険者にあってはすべての者」は誤りです。
(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)
②【R4年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者」の総数です。
保険料の負担がない保険料全額免除期間は入りません。
(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)
③【H30年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者」の総数です。
保険料全額免除期間、保険料未納期間は入りません。
(第94条の3第1項、2項、令11条の4第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-197
R6.3.11 死亡一時金と寡婦年金の調整
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
「死亡一時金」と「寡婦年金」の両方の受給権を取得した場合の調整のルールをみていきます。
条文を読んでみましょう。
第52条の6(支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
死亡一時金と寡婦年金の両方を受けることはできません。「その者の選択」により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、どちらか一つが支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
③【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
①【H18年出題】 〇
同一人の死亡で、死亡一時金と寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つを受給します。
(第52条の6)
②【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、「その者の選択」により、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つが支給されます。
寡婦年金が優先されるわけではありません。
(第52条の6)
③【R3年出題】 〇
遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった場合の調整についての問題です。
★ポイント1 「一人一年金の原則」
2つ以上の年金の受給権が発生した場合は、原則として、一つの年金を選択し受給します。
遺族厚生年金と寡婦年金は併給できませんので、どちらか一つを選択します。
(第20条)
★ポイント2 「寡婦年金と死亡一時金は選択」
寡婦年金と死亡一時金はどちらかを選択します。寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。死亡一時金を選択した場合は、寡婦年金は支給されません。
(第52条の6)
・寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
・遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されます。(遺族厚生年金と死亡一時金には調整規定がないからです。)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-196
R6.3.10 死亡一時金と遺族基礎年金の関係
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2 第2項 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 (1) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 (2) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |
同一の死亡で遺族基礎年金が支給される場合は、死亡一時金は原則として支給されません。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】
【R2年出題】 ×
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません。
ただし、例外的に、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金が支給されます。
例えば、子が18歳に達した日の属する年度の年度末(3月)に被保険者が死亡した場合、遺族基礎年金の受給権は発生しますが、同一月に受給権が消滅するため、結局遺族基礎年金は支給されません。
そのため、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金を支給する例外が設けられています。
(第52条の2第2項第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-183
R6.2.26 振替加算その2 振替加算が支給停止されるとき
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
昨日は、「振替加算が行われないとき」をみましたが、今日は振替加算の支給停止をみていきます。
★ 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止されます。 (第16条第1項) |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
②【R1年出題】
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで第2号被保険者期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。
③【R3年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算された額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H30年出題】 〇
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金等を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給が停止されます。
ただし、障害基礎年金、障害厚生年金等が全額支給停止になっている場合は、振替加算は支給停止されません。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第28条)
②【R1年出題】 〇
障害基礎年金を受給している間は、振替加算は支給停止されます。
ただし、障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合は、障害基礎年金は全額支給停止になりますので、老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第28条)
③【R3年出題】 ×
振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の支給を受けることができるときでも、振替加算は支給停止されません。
(昭60年法附則第14条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-182
R6.2.25 振替加算その1 振替加算が行われないとき
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
振替加算が行われる者の条件を確認しましょう。
・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者 ・配偶者の年金の加給年金額の対象になっていたこと (配偶者が次の年金の受給権者であること(加給年金額が加算されるもの)) (1) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間の月数が原則として240以上であるものに限る。)の受給権者 (2) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。=1・2級) ・振替加算の額 224,700円×改定率×その者の生年月日に応じて政令で定める率 |
今日は、「振替加算が行われないとき」のルールをみていきます。
★ 老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は加算されません。
(昭60年法附則第14条第1項)
加給年金額と振替加算のイメージ図
(例)夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算され、妻に振替加算が加算される場合
(63歳) (65歳)
夫 | 報酬比例部分 | 老齢厚生年金(240月以上) | |
|
| 老齢基礎年金 | |
|
| 加給年金額 |
|
|
|
| 65歳 |
妻 |
|
| 老齢厚生年金 |
|
|
| 老齢基礎年金 |
|
|
| 振替加算 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題 】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
②【H27年出題】
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
①【H30年出題 】 〇
老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、振替加算は加算されません。
政令で定められている老齢厚生年金は、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上(20年以上)あるものです。
なお、中高齢の期間短縮特例を満たす場合は、15~19年となります。
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第25条)
②【H27年出題】 〇
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
この期間には、「離婚時みなし被保険者期間」も算入します。
離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなります。
(昭60年法附則第14条第1項、経過措置令第25条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-172
R6.2.15 遺族基礎年金の保険料納付要件
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第37条 (支給要件) 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、(1)又は(2)に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 (1) 被保険者が、死亡したとき。 (2) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。 (3) 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 (4) 保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
★遺族基礎年金の保険料納付要件
(1)か(2)に該当する場合は、保険料納付要件が問われます。
(原則)
死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
(特例) S60法附則第20条第2項
・死亡日が令和8年4月1日前にあること
・死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと
・死亡日において65歳未満であること
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
②【R4年出題】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
問題文は、保険料納付要件の特例を満たします。
■死亡日が令和8年4月1日前にあること
↓
死亡日は平成30年4月2日
■死亡日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がないこと
↓
平成30年4月1日(死亡日の前日)に、平成29年3月から平成30年2月までの期間(死亡日の属する月の前々月までの1年間)に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない(保険料の未納期間がない)
H30年4月 | H30年3月 | H30年2月 | ~~~~~~ | H29年3月 |
死亡 |
| 死亡日の属する月の前々月までの1年間 | ||
■死亡日において65歳未満であること
↓
第1号被保険者が死亡(死亡日に20歳以上60歳未満)
(S60法附則第20条第2項)
②【R4年出題】 ×
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者の場合は、第37条の(4)の条件を満たします。
(3)、(4)に該当する場合は、保険料納付要件は問われませんので、死亡日の前日に、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合でも、遺族基礎年金は支給されます。
(第37条第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-162
R6.2.5 国民年金基金の給付について
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
まず、国民年金基金の業務について条文を読んでみましょう。
第128条第1項 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 |
★基金の年金について
・基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない、とされています。
(法第129条第1項)
★基金の一時金について
・基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない、とされています。
(法第129条第3項)
給付の支給のルールについて条文を読んでみましょう。
第130条 ① 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。 ② 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、200円に納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間(第87条の規定による保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る。以下「加入員期間」という。)の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。 ③ 基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない。
第131条 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金の額のうち、200円に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の障害に関し、一時金の支給を行うものとされている。
②【R4年出題】
国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。
③【H22年出題】
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。
④【R1年出題】
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。
⑤【R3年出題】
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の「死亡」に関し、一時金の支給を行うものとされています。
「障害」に関する支給はありません。
(第128条第1項)
②【R4年出題】 ×
国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、「老齢基礎年金の受給権を取得したとき」には、支給されるものでなければならない、と規定されています。老齢基礎年金の受給権を取得した時点には限られません。
(法第129条第1項)
③【H22年出題】 ×
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければなりません。
また、国民年金基金の支給する一時金の額にも下限が定められています。
基金が支給する一時金の額は、「8,500円」を超えるものでなければなりません。
(法第130条第3項)
④【R1年出題】 ×
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されている場合を除いては、その支給を停止することはできません。
ただし、当該年金の額のうち、「200円」に当該基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、支給を停止することができます。
(法第131条)
⑤【R3年出題】 〇
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金額は、200円に増額率を乗じて得た額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければなりません。
(法第130条第2項、基金令第24条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 国民年金法
R6-152
R6.1.26 年金の内払調整
過去問から学びましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第21条 ① 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
② 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
③ 同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。 |
①について
例えば、寡婦年金の受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したため、寡婦年金の受給権が消滅しました。しかし、寡婦年金の受給権が消滅した日の属する月の翌月以降の分として、寡婦年金の支払が行われました。その場合、支払われた寡婦年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金の内払とみなされます。
消滅
寡婦年金(乙年金) | 内払 |
↓
繰上支給の老齢基礎年金(甲年金) |
寡婦年金を返還して、改めて老齢基礎年金を支給するのではなく、内払調整によって支払われた寡婦年金は、繰上げ支給の老齢基礎年金の内払とみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
②【R2年出題】
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の遺族基礎年金が支払われた場合における当該遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができる。
③【R3年出題】
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

【解答】
①【H20年出題】 〇
年金の支給を停止すべき事由が生じました。
↓
にもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われました。
↓
支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができます。
(法第21条第2項)
②【R2年出題】 〇
遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じました。
↓
にもかかわらず、翌月以降も減額しない額の遺族基礎年金が支払われました
↓
減額すべきであった部分は、その後に支払うべき遺族基礎年金の内払とみなすことができます。
(法第21条第2項)
③【R3年出題】 〇
障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を受けていた者が、その後、老齢基礎年金を受けることを選択した場合、障害厚生年金は支給停止されます。
しかし、翌月以降も障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は老齢基礎年金の内払とみなすことができます。
(法第21条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-144
R6.1.18 過誤払いの年金の返還金債権への充当
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第21条の2 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
則第86条の2 年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 (1) 年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者が、当該年金たる給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。 (2) 遺族基礎年金の受給権者が同一の支給事由に基づく他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族基礎年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき |
(1)の例をみてみましょう。
例えば、老齢基礎年金を受給している夫が令和6年1月18日に死亡しました。老齢基礎年金は受給権が消滅した月(令和6年1月)まで支給されますが、死亡の翌月以後も、老齢基礎年金が過誤払されました。この場合、過誤払いされた年金は、本来なら妻が返還しなければなりません。しかし、夫の死亡により妻に遺族基礎年金が支給される場合は、妻に支払う遺族基礎年金の金額を過誤払による返還金債権の金額に充当することができます。
死亡
夫 | 老齢基礎年金 | 過誤払 |
↑返還金債権の金額に充当できる
妻 |
| 遺族基礎年金 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡しその受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分として老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
②【H29年出題】
遺族である子が2人で受給している遺族基礎年金において、1人が婚姻したことにより受給権が消滅したにもかかわらず、引き続き婚姻前と同額の遺族基礎年金が支払われた場合、国民年金法第21条の2の規定により、過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
妻に支払う「老齢基礎年金」の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することはできません。
充当することができるのは、「年金たる給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族基礎年金の受給権者」です。夫の死亡に伴う遺族基礎年金が妻に支払われる場合は、充当の対象になります。
(則第86条の2第1号)
②【H29年出題】 ×
過誤払として、もう1人の遺族である子が受給する遺族基礎年金の支払金の金額を返還すべき年金額に充当することができるのは、「他の遺族基礎年金の受給権者の死亡に伴う」場合です。
婚姻で受給権が消滅した場合は、充当の対象になりません。
(則第86条の2第2号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
「その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。」が誤りです。
「当該年金給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。」となります。
「死亡」によって受給権が消滅したにもかかわらず、翌月以降も年金が過誤払された場合に、過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付で調整する場合は、内払ではなく「充当」という用語を使います。
「充当」は死亡した人と残された人の年金との調整ですが、「内払」は1人の年金間での調整です。
(法第21条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-131
R6.1.5 第2号被保険者期間の合算対象期間
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
S60年附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条(老齢基礎年金の支給要件)及び第27条(老齢基礎年金の年金額)並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
例えば、18歳から63歳まで厚生年金保険の被保険者だった場合、その間はすべて国民年金第2号被保険者となります。ただし、老齢基礎年金の適用については、20歳前の期間と60歳以後の期間は、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」に算入されます。
18歳 20歳 60歳 63歳
厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者) | ||
合算対象期間 | 保険料納付済期間 | 合算対象期間 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
②【R4年出題】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。
③【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間・60歳以後の期間は、合算対象期間(カラ期間)となり、老齢基礎年金の支給要件の「10年以上」の期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額の計算には算入されません。
(S60年附則第8条第4項)
②【R4年出題】 ×
60歳から65歳までの期間が「合算対象期間」になるため、老齢基礎年金は満額になりません。
20歳 23歳 60歳 65歳
未加入 | 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者) | |
保険料納付済期間(37年間) | 合算対象期間 | |
老齢基礎年金の額に反映するのは、23歳から60歳までの期間です。
(S60附則第8条第4項)
③【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間が「合算対象期間」になるのは、「老齢基礎年金」のみです。
障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、「保険料納付済期間」となります。ちなみに、遺族基礎年金も同様に保険料納付済期間となります。
(S60附則第8条第4項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。

【解答】
【R5年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては「合算対象期間」に算入され、保険料納付済期間には算入されません。
(S60附則第8条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-130
R6.1.4 老齢基礎年金の支給要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第26条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
老齢基礎年金の受給権は、「保険料納付済期間+保険料免除期間」を10年以上有する者が65歳に達したときに発生します。
条文では、「保険料免除期間」が2か所出てきます。
1つめの「保険料免除期間」からは、「学生納付特例及び納付猶予」の期間が除かれています。学生納付特例期間と納付猶予期間は、老齢基礎年金の年金額に反映しないからです。
2つめの「保険料免除期間」では、学生納付特例期間と納付猶予期間は除外されていません。そのため、10年以上の計算には、学生納付特例期間と納付猶予期間が含まれます。
また、附則第9条第1項で、老齢基礎年金の支給要件の特例が規定されています。
特例により、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年未満でも、「合算対象期間」を合算した期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の要件を満たします。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。
②【R4年出題】
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)を合算した期間を7年、合算対象期間を5年有している場合は、65歳に達したときに、老齢基礎年金の受給権が発生します。
(法第26条、附則第9条)
②【R4年出題】 ×
納付猶予期間も学生納付特例期間も、保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されません。
(第27条、H16附則第19条第4項、H26附則第14条第3項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。

【解答】
【R5年出題】 〇
老齢基礎年金の支給を受けるには、保険料納付済期間と保険料免除期間と、合算対象期間を合算した期間が10年以上必要です。
(法第26条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-129
R6.1.3 国民年金の年金と厚生年金保険の年金の組み合わせ
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第20条第1項、附則第9条の2の4 年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65歳に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。 |
ポイント!
年金は、「一人一年金」が原則です!
例外的に「併給できる」パターンをおさえましょう。
過去問でみていきましょう。
①【H21年出題】
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。
②【R4年出題】
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。
③【R4年出題】
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
④【H26年出題】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
⑤【H30年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
国民年金の年金には、「老齢基礎年金」、「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「付加年金」があります。
★同時に2つ以上の年金の受給権を取得することもあります。
その場合は、「一人一年金の原則」が適用され、一つの年金を選択して受給します。その際、選択しなかった年金は、「支給停止」となります。「失権」ではありませんので、注意しましょう。
★例外で、「付加年金」は、「老齢基礎年金」と併給できます。
→問題文は、「遺族基礎年金」、「老齢基礎年金」、「付加年金」の受給権を取得しています。一人一年金の原則で、「遺族基礎年金」か「老齢基礎年金」のいずれか一方を選択して受給します。
老齢基礎年金を選択した場合は「付加年金」も支給されます。
遺族基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金が支給停止になりますので、付加年金も支給停止となります。
②【R4年出題】 〇
老齢基礎年金、障害基礎年金、付加年金の受給権を取得した場合で、「障害基礎年金」の受給を選択したときは、「老齢基礎年金と付加年金」は、障害基礎年金を受給する間、支給が停止されます。
③【R4年出題】 〇
「基礎年金」と「厚生年金」は同一の支給事由の場合は併給されます。
老齢厚生年金
|
| 障害厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
| 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
付加年金は老齢基礎年金と併給できます。そのため、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給されます。
④【H26年出題】 ×
「基礎年金」と「厚生年金」の支給事由が異なっていても、65歳以上の場合は、併給できる場合があります。
65歳以上の「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」
65歳以上の「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」
65歳以上の「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」
★65歳以上に限って併給できるパターン
遺族厚生年金
|
| 老齢厚生年金 |
| 遺族厚生年金 |
老齢基礎年金
| 障害基礎年金 | 障害基礎年金 |
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給することができます。老齢基礎年金を受給する場合は、付加年金も併給できます。
⑤【H30年出題】 〇
65歳以降は、「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」を併給することができます。
ただし、65歳前は併給できません。そのため、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択して受給することになります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

【解答】
【R5年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、併給できます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-128
R6.1.2 学生納付特例と保険料の納付猶予
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
まず、過去問からどうぞ!
【R3年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、令和12年6月までの時限措置である。

【解答】
【R3年出題】 ×
「学生納付特例制度」は、法第90条の3に規定されていて、時限的な措置ではなく恒久的な措置です。
一方、「保険料の納付猶予制度」は、平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条に規定されている「令和12年6月まで」の時限的な措置です。
なお、保険料の納付猶予制度は、50歳に達する日の属する月の前月までが対象です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

【解答】
【R5年出題】 ×
学生納付特例制度は、本則(第90条の3)に規定されています。
保険料の納付猶予制度は、本則ではなく、法附則(平成16年法附則第19条、平成26年法附則第14条)に規定されている時限措置です。「令和12年6月まで」にも注意しましょう。年度末の3月まではなく、6月までがポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 国民年金法
R6-127
R6.1.1 老齢基礎年金の額と国庫負担
今日は国民年金法です。
国庫負担と老齢基礎年金の額との関係をみていきます。
さっそく、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。

【解答】
【R5年出題】 ×
・保険料納付済期間の月数は、老齢基礎年金の年金額には「1」で反映されますが、そのうち「2分の1」は国庫負担です。
保険料 |
国庫負担 |
・保険料全額免除期間は、老齢基礎年金の年金額には原則「2分の1」で反映されます。
免除 |
国庫負担 |
→ 問題文の、「保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているから」の部分です。
※ちなみに、学生納付特例・50歳未満の納付猶予期間には国庫負担がありませんので、年金額には反映しません。
なお、「国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられた」のは、「平成21年4月1日」以降です。「平成15年4月1日以降」の部分が誤りです。
全額免除期間は、平成21年4月以降は、年金額には「2分の1」が反映しますが、平成21年3月までは「3分の1」が反映します。
(第27条、H16法附則第9条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 国民年金法
R6-126
R5.12.31 国民年金保険料の額の改定
今日は国民年金法です。
保険料の額の改定についてみていきます。
★「令和元年度以後」の年度に属する月の保険料は、
「17,000円」に保険料改定率を乗じて得た額となります。
(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げます。)
(第87条第3項)
★保険料改定率は、「前年度の保険料改定率」×「名目賃金変動率」で計算します。
なお、「名目賃金変動率」の内訳は、「物価変動率」×「実質賃金変動率」です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

【解答】
【R5年出題】 ×
令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「令和元年度以後」の年度に属する月の月分の保険料として定められている「17,000円」に「保険料改定率」を乗じて得た額となります
保険料改定率は、「前年度の保険料改定率」×「名目賃金変動率」で計算します。
令和5年度の保険料改定率は、以下の計算式で計算します。
・前年度の保険料改定率 → 0.976
・物価変動率 → 0.998
・実質賃金変動率 → 0.998
保険料改定率は、0.976×名目賃金変動率(0.998×0.998)=0.972です。
令和5年度の保険料額は、17,000円×保険料改定率(0.972) ≒ 16,520円です。
★ 計算の基礎となる保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成29年度まで毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降は月額16,900円で固定されることになっていました。
しかし、産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴って、令和元年度以降の計算の基礎となる保険料の額は100円引き上げられ、月額17,000円となっています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-125
R5.12.30 20歳前傷病による障害基礎年金の「所得」による支給停止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第36条の3第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
第36条の4第1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。 |
「第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)」は、「受給権者の所得」による支給停止があります。
「20歳前傷病による障害基礎年金」には、所得による支給停止以外に、以下の事由による支給停止があります。
① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。
② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
④ 日本国内に住所を有しないとき。
通常の障害基礎年金にはない支給停止事由ですので、注意しましょう。
今日は「所得による支給停止」をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
②【H30年出題】※改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が472万1千円を超えるときは全額が、その年の10月から翌年の9月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない。
③【H25年出題】
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
所得は、「受給権者の前年の所得」で判断します。「所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出」の部分が誤りです。
(第36条の3第1項)
②【H30年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止のポイント
★前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下のとき(扶養親族等がいないとき)
→ 2分の1が支給停止される
★前年の所得が472万1千円を超えるとき(扶養親族等がいないとき)
→ 全額が支給停止される
★支給停止期間は「その年の10月から翌年の9月まで」
全額支給
|
|
全額支給停止 |
2分の1支給停止
|
(370万4千円) (472万1千円)
(令第5条の4)
③【H25年出題】 ×
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災等の災害で、住宅、家財等の財産について被害金額がその価格のおおむね「2分の1」以上の損害を受けた場合は、所得を理由とする支給停止は行われません。
3分の1ではなく「2分の1」です。
(第36条の4第1項)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。
②【R5年出題】
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「全部又は3分の1」ではなく、「全部又は2分の1」です。
(第36条の3第1項)
②【R5年出題】 〇
チェックポイントは、「2分の1以上」、その損害を受けた月から「翌年の9月まで」です。
(第36条の4第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-101
R5.12.6 受給権の保護と公課の禁止
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
「受給権の保護」について条文を読んでみましょう。
第24条 (受給権の保護) 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。 |
★国民年金の給付を受ける権利は、保護されていて、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。
例外的に、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができます。
次は、「公課の禁止」について条文を読んでみましょう。
第25条 (公課の禁止) 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。 |
★国民年金の給付は、原則として課税されません。
例外的に、老齢基礎年金及び付加年金は課税対象となります。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には、公課を課することができる。
②【R3年選択式】
国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、< A >として、課することができない。ただし、< B >については、この限りでない。」と規定している。

【解答】
①【H25年出題】 〇
老齢基礎年金及び付加年金は、課税対象となります。
②【R3年選択式】
A 給付として支給を受けた金銭を標準
B 老齢基礎年金及び付加年金
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

【解答】
【R5年出題】 ×
国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。
例外的に、「老齢基礎年金又は付加年金」を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることはできますが、「担保に供する」ことはできません。
また、遺族基礎年金については、例外なく、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-093
R5.11.28 厚生年金保険の被保険者は(原則)国民年金第2号被保険者
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金第2号被保険者です。
条文を読んでみましょう。
第7条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者は国民年金の被保険者とする。(「第2号被保険者」という。) 法附則第3条 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。 |
厚生年金保険の被保険者は、国民年金第2号被保険者となります。
ただし、当分の間は、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。
★65歳以上の厚生年金保険の被保険者でも、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者は、第2号被保険者となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。
③【R3年出題】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者です。20歳未満でも厚生年金保険の被保険者であれば国民年金の第2号被保険者です。
第1号被保険者と第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」という年齢枠がありますが、第2号被保険者には「20歳以上60歳未満」の年齢枠がないのがポイントです。
②【R4年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者は、第2号被保険者にはなりません。
そのため、厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者であったとしても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
③【R3年出題】 〇
「第3号被保険者」になるには、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。
「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は、厚生年金保険の被保険者であっても、国民年金の第2号被保険者ではありません。
問題文の55歳の配偶者は、第2号被保険者の配偶者ではありませんので、第3号被保険者になりません。
(法第7条第1項第3号)
では令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者でも、65歳未満の場合は、第2号被保険者になります。問題文は、「62歳」の特別支給の老齢厚生年金の受給権者ですので、第2号被保険者です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-087
R5.11.22 付加保険料納付済期間を有していた場合
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の4 (死亡一時金の額) ① 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次に定める額とする。
② 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。 |
・死亡一時金の額は、「保険料納付済期間の月数」+「保険料4分の1免除期間の月数の4分の3」+「保険料半額免除期間の月数の2分の1」+「保険料4分の3免除期間の月数の4分の1」を合算した月数に応じて12万円から32万円まで6段階設定されています。
・付加保険料納付済期間が3年以上ある者の場合は、死亡一時金の額に8,500円が加算されます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
②【H29年出題】
死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算される。
③【R2年出題】
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
④【H21年出題】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

【解答】
①【H24年出題】 ×
死亡一時金の支給要件と死亡一時金の額の計算には、「保険料全額免除期間」は入りません。
死亡一時金は保険料が掛け捨てになることを防ぐための給付です。そのため、一部免除の期間は計算に入りますが、全額免除の期間は計算に入りません。
(法第52条の2)
②【H29年出題】 〇
付加保険料納付済期間が3年以上ある者の遺族に支給される死亡一時金の額には、8,500円が加算されます。
③【R2年出題】 〇
保険料納付済期間が36月間で、併せて付加保険料を36月間(3年間)納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円+8,500円で128,500円となります。
④【H21年出題】 ×
夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していたとしても、寡婦年金の額には加算はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。

【解答】
【R5年出題】 ×
夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合でも、寡婦年金の額には加算はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-080
R5.11.15 付加年金の支給要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第87条の2第1項 第1号被保険者(法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、保険料一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金の保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。
第43条 (付加年金の支給要件) 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 (付加年金の年金額) 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
|
・付加保険料(月400円)を納付することができるのは、第1号被保険者のみです。なお、65歳未満の任意加入被保険者も付加保険料を納付できます。
・保険料の免除を受けている者は付加保険料を納付できません。
・国民年金基金の加入員も付加保険料を納付できません。
・付加年金は、付加保険料の保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金の上乗せで支給されます。
・付加年金の年金額は、「200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。
②【R4年出題】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

【解答】
①【H19年出題】 ×
付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、「第1号被保険者」としての被保険者期間を対象とした給付です。
第2号被保険者、第3号被保険者としての被保険者期間は対象になりません。
②【R4年出題】 ×
付加保険料に係る納付済期間を60月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される付加年金の額は、年額で、「200円」に60月を乗じて得た額です。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。

【解答】
【R5年出題】 ×
付加保険料の額は月400円で、付加年金の額は「200円」×付加保険料に係る納付済期間の月数で計算します。付加年金は、月400円の付加保険料を納付していることが前提です。
そのため、付加年金は、「付加保険料」の保険料納付済期間を有する者(=付加保険料を納付した者)が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加保険料の納付済期間の月数に応じて支給されます。
なお、第2号被保険者、第3号被保険者は付加保険料を納付することはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-074
R5.11.9 死亡一時金の遺族の範囲
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第52条の2第1項 (死亡一時金の支給要件) 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
第52条の3(遺族の範囲及び順位等) ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金(①ただし書に規定するものを除く。)を受けるべき者の順位は、①に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と「生計を同じくしていた」ものです。
また、受ける順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
②【R1年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族が、死亡した者の祖父母と孫のみであったときは、当該死亡一時金を受ける順位は孫が優先する。なお、当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これらの者以外の三親等内の親族は、死亡一時金の遺族になりません。
②【R1年出題】 〇
祖父母と孫では、死亡一時金を受ける順位は孫が優先します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金をうけることができる遺族はいないものとする。

【解答】
【R5年出題】 ×
死亡した甲の妹は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていた場合は、生計を維持していなくても死亡一時金の支給を受けることができます。
「生計維持」の要件には「収入要件」がありますが、「生計同一」には収入要件はありません。
死亡一時金の対象になる遺族は、「生計を同じくしていること」ですので、生計維持要件は問われません。
(参照:H23.3.23年発0323第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-067
R5.11.2 法定免除の対象になる月
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第89条第1項 被保険者(産前産後の保険料免除及び保険料一部免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 1 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に同法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 2 生活保護法による生活扶助を受けるとき。 3 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所など)に入所しているとき。 |
★法定免除から除外される被保険者
・産前産後免除の要件を満たしている場合は、法定免除の対象から除外されます。産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるからです。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除を受けている間は、法定免除の対象から除外されます。
★法定免除が適用される期間
法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月
~
該当しなくなる日の属する月まで
・例えば、11月2日に法定免除の要件に該当した場合は、前月(10月)から免除されます。10月の保険料納期限は11月末で、まだ期限が到来していないからです。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
②【R2年出題】
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
法定免除事由に該当すれば、当然に保険料を納付する義務がなくなります。法定免除には所得要件はありません。
②【R2年出題】 〇
保険料の法定免除事由に該当した場合、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から当然に保険料が免除になります。ただし、「届出」が必要です。法定免除事由に該当した日から14日以内に届書を市町村に提出しなければなりません。なお、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は要りません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の対象となる。

【解答】
【R5年出題】 〇
学生納付特例の適用を受けている第1号被保険者が、法定免除の要件に該当した場合は、法定免除の対象になります。法定免除の期間は、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-061
R5.10.27 保険料免除期間の定義
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
法第5条第2項~6項 ② 「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。 ③ 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ④ 「保険料4分の3免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑤ 「保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑥ 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
ポイント!
・保険料免除期間は、「第1号被保険者」のみに適用されます。
・保険料免除期間には、以下の期間があります。
保険料全額免除期間
保険料4分の3免除期間
保険料半額免除期間
保険料4分の1免除期間
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
②【R3年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)を含みます。
②【R3年出題】 〇
例えば半額免除については、保険料の半額は免除されますが、残りの部分(半額)は納付義務があります。残りの部分(半額)を納付すると、「保険料半額免除期間」となります。
保険料の一部免除については、免除されていない残りの部分が納付されることにより、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間となります。
③【H24年出題】 〇
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間となります。
保険料納付済期間にはなりません。
④【H24年出題】 〇
保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間は、保険料を追納することができます。
追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされ、「保険料納付済期間」となります。
問題文のように、保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
(第94条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】
【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用され、免除されないその残余の4分の3の部分が納付又は徴収された場合は、その期間は、「保険料4分の1免除期間」となります。保険料納付済期間ではありません。
なお、免除された4分の1を追納により納付した場合は、保険料納付済期間となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-056
R5.10.22 国民年金保険料の追納の要件
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第94条第1項 (保険料の追納) 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
★ポイントを確認しましょう。
・老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
・承認を受けた月の前10年以内の期間内に限って追納することができます。
・「一部免除」の期間については、免除の部分以外が納付されていなければ、追納できません。例えば、半額免除の場合は、免除されていない残りの半額が納付されていることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前 10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
②【H29年出題】
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有する者、遺族基礎年金の受給権を有する者でも、追納は可能です。障害基礎年金、遺族基礎年金は、支給停止や失権する可能性があるためです。
なお、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
②【H29年出題】 〇
例えば、4分の3免除は、残りの4分の1を納付することにより、保険料4分の3免除期間となります。4分の1を納付しない場合は、保険料4分の3免除期間には算入されません。
追納についても、一部免除の保険料については、その残余の額が納付されていないときは、追納はできません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。

【解答】
【R5年出題】 ×
老齢基礎年金の受給権者は、保険料の追納はできません。
老齢基礎年金を請求していなくても、老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-047
R5.10.13 寡婦年金 死亡した夫の要件
過去問で解ける問題をみていきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第49条第1項 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 |
★死亡した夫の要件を確認しましょう。
・夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上あること
※学生納付特例・納付猶予の期間は年金額には反映しません
・夫が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けたことがあるときは、寡婦年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間を5年有する夫が死亡した場合、所定の要件を満たす妻に寡婦年金が支給される。なお、当該夫は上記期間以外に第1号被保険者としての被保険者期間を有しないものとする。
②【H28年出題】
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
③【R2年出題】
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。
④【H28年出題】
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
⑤【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
死亡した夫は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あることが条件です。ただし、その期間に、合算対象期間は算入できません。
問題文は、第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が5年あるだけですので、寡婦年金は支給されません。
②【H28年出題】 〇
★任意加入被保険者は付加保険料が納付できます。また、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金については第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
(法附則第5条第9項)
★なお、特例による任意加入被保険者は、付加保険料は納付できません。また、寡婦年金については、第1号被保険者としての被保険者期間とはみなされません。
死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされます。
(H16法附則第23条第9項)
③【R2年出題】 ×
年金の支給は、受給権を取得した月の翌月から始まります。
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合は、その夫は、老齢基礎年金を「受けていません」。そのため、要件を満たした妻に寡婦年金が支給されます。
④【H28年出題】 ×
寡婦年金の額について条文を読んでみましょう。
第50条 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の老齢基礎年金の額の規定例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
問題文は、「4分の3」が抜けているので誤りです。
なお、「第1号被保険者としての被保険者期間」だけで計算することがポイントです。
⑤【H24年出題】 〇
寡婦年金の額の算定には、「第1号被保険者」としての被保険者期間のみが反映します。第2号被保険者・第3号被保険者としての被保険者期間は反映されません。
(法第50条)
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。

【解答】
【R5年出題】 〇
寡婦年金の支給要件は「第1号被保険者期間」のみで判断されます。第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年のみの場合は、寡婦年金の支給要件を満たしません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-038
R5.10.4 20歳前傷病による障害基礎年金の受給権発生日
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 |
20歳前に初診日がある場合(=国民年金加入前の傷病という意味です。)の障害基礎年金の受給権の発生日を確認しましょう。
★①★障害認定日が20歳前にある場合
初診日 | 障害認定日 |
| 20歳 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「20歳に達した日」に障害基礎年金の受給権が発生します
★②★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H26年出題】 ×
まず、「障害認定日」の定義を確認しましょう。
障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」となるので、障害認定日が1年6か月より早くなる可能性もあります。
しかし、問題文は、25歳時点で「継続して治療中(治っていない)」です。そのため、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」が障害認定日です。
初診日が19歳の時なので、障害認定日は、20歳に達した日後になります。
先ほどの図の②に該当します。
★②★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
受給権は、20歳に達した日ではなく、「障害認定日」に障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に発生します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。

【解答】
【R5年出題】 ○
初診日が19歳で継続して治療中ですので、障害認定日は、20歳に達した日後となります。障害認定日に障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、障害認定日に受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-029
R5.9.25 老齢基礎年金繰上げの注意点
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
条文を読んでみましょう。
法附則第9条の2第5項 (老齢基礎年金の支給の繰上げ) 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
法附則第9条の2の3 第30条第1項(第2号に限る。)、第30条の2、第30条の3、第30条の4第2項、第34条第4項、第36条第2項ただし書及び第49条並びに附則第5条(任意加入被保険者)の規定は、当分の間、繰上げ支給の老齢齢基礎年金の受給権者については、適用しない。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。
②【H23年出題】
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止される。
③【H19年出題】
国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。

【解答】
①【R4年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
②【H23年出題】 ×
繰上げ支給による老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は「支給停止される」のではなく「受給権が消滅」します。
③【H19年出題】 ○
<国民年金の任意加入と老齢基礎年金の繰上げとの関係>
・国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求はできません。 (法附則第9条の2第1項)
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができません。
令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。

【解答 】
【R5年出題】 ○
老齢基礎年金の支給の繰上げをした場合は、寡婦年金の受給権は消滅しますので、寡婦年金は支給されません。
また、老齢基礎年金の支給繰上げをした場合は、国民年金の任意加入被保険者になることもできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 国民年金法
R6-019
R5.9.15 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、国民年金法です。
まず、過去問からどうぞ!
★今日の過去問は「厚生年金保険法」です。
①【H28年出題(厚生年金保険)】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
②【H19年出題(厚生年金保険法)】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

【解答】
①【H28年出題(厚生年金保険)】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなくても構いません。別々に繰下げの申出をすることができます。
(厚生年金保険法第44条の3)
②【H19年出題(厚生年金保険法)】 ×
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。
では、令和5年の問題をどうぞ!
★国民年金法です。
【R5年出題】
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。

【解答】
【R5年出題】 ×
老齢基礎年金の支給繰下げの申出と、老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、同時に行う必要はありません。
(法第28条)
比較しましょう こちらの過去問もどうぞ!
【H26年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】
【H26年出題】 〇
支給繰上げの請求は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
(附則第9条の2第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 国民年金法
R6-008
R5.9.4 国年選択式は国民年金事業の円滑な実施・国民年金の給付・被保険者の要件からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は国民年金法です。
 AからCは、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置からの問題です。
AからCは、国民年金事業の円滑な実施を図るための措置からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第74条第1項 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1) 教育及び広報を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。 (3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。 |
令和5年度は、A 教育及び広報、B 相談その他の援助、C 利便の向上が入ります。
なお、平成23年に同じ問題が出題されています。
【H23年選択式】
政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) <A 教育及び広報>を行うこと。
(2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という。)に対し、 <B 相談その他の援助>を行うこと。
(3) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する<C 情報>その他の被保険者等の利便の向上に資する<C 情報>を提供すること。
★★選択式も過去問対策が大切です。
 Dは、国民年金の給付からの問題です。
Dは、国民年金の給付からの問題です。
条文を読んでみましょう。
第2条 (国民年金の給付) 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 |
Dは「必要な給付」が入ります。保険給付ではありませんので注意しましょう。
過去問を確認しましょう。
【H26年出題】
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。
【解答】 ×
必要な保険給付ではなく、「必要な給付」です。
保険原理とは、負担した保険料に応じた保険給付が行われるというものです。国民年金法の給付には、例えば、保険料の負担が求められない20歳前の障害基礎年金など、保険原理によらないものもあります。
そのため、国民年金は「保険給付」ではなく、「必要な給付」とされています。
なお、厚生年金保険法は、「保険給付」となります。
 Eは被保険者の要件の問題です。
Eは被保険者の要件の問題です。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の共通点は、「国籍要件」が問われない点です。
Eには、国籍が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国年・厚年 時効
国年・厚年 時効
R5-352
R5.8.14 <比較>国年「死亡一時金」と厚年「障害手当金」の時効
国民年金の「死亡一時金」と厚生年金保険法の「障害手当金」は年金ではなく一時金で支給されます。
それぞれの時効を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
【国民年金法】 第102条第1項、第4項 ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
時効のポイント!
・年金給付を受ける権利 → 5年
・死亡一時金を受ける権利 → 2年
・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2年
【厚生年金保険法】 第92条第1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 |
時効のポイント!
・保険給付を受ける権利 → 5年
・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2年
では、過去問をどうぞ!
①国民年金法【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
②厚生年金保険法【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①国民年金法【H27年出題】 ×
年金給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
死亡一時金を受ける権利→これを行使することができる時から2年を経過したとき
に、時効によって消滅します。
「年金給付(5年)」と「死亡一時金(2年)」の時効の違いに注意してください。
②厚生年金保険法【H29年出題】 ×
保険給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
に時効によって消滅します。
「保険給付」には年金だけでなく一時金(障害手当金)も含まれます。
障害手当金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
ポイント!
同じ「一時金」でも、国民年金の「死亡一時金」の時効は2年、厚生年金保険の「障害手当金」の時効は5年です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 第2号被保険者・第3号被保険者
国民年金法 第2号被保険者・第3号被保険者
R5-348
R5.8.10 国民年金の保険料の負担義務
国民年金の保険料の納付義務について、条文を読んでみましょう。
第87条第1項、第2項 (保険料) ① 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 ② 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
第94条の6 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
第1号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務があります。
第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務はありません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
②【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料は負担しません。
第2号被保険者は、厚生年金保険に保険料を納付しています。その保険料の一部が基礎年金拠出金となっています。
基礎年金拠出金は、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用に充てられます。
②【H30年出題】 ×
「第2号被保険者」と「第3号被保険者」としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 第2号被保険者・第3号被保険者
国民年金法 第2号被保険者・第3号被保険者
R5-348
R5.8.10 国民年金の保険料の負担義務
国民年金の保険料の納付義務について、条文を読んでみましょう。
第87条第1項、第2項 (保険料) ① 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 ② 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
第94条の6 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
第1号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務があります。
第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務はありません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
②【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料は負担しません。
第2号被保険者は、厚生年金保険に保険料を納付しています。その保険料の一部が基礎年金拠出金となっています。
基礎年金拠出金は、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用に充てられます。
②【H30年出題】 ×
「第2号被保険者」と「第3号被保険者」としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 法定免除
国民年金法 法定免除
R5-347
R5.8.9 法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出
法定免除の期間については、申出により保険料を納付することもできます。
条文を読んでみましょう。
第89条 ① 被保険者(産前産後の免除及び保険料の一部免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 1 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 2 生活保護法による生活扶助を受けるとき。 3 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。 厚生労働省令で定める施設→国立ハンセン病療養所等、国立保養所、厚生労働大臣が指定するもの ② 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
②【R2年出題】
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
③【H29年出題】
国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
法定免除の要件に該当していても、被保険者又は被保険者であった者から保険料を納付する旨の申出があったときは、申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができます。
②【R2年出題】 〇
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、保険料を納付する旨の申出により、申出のあった期間に係る保険料を納付することができます。
③【H29年出題】 〇
法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、「障害基礎年金の受給権者」も「生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者」のどちらも行うことができます。
★保険料を納付する申出ができる理由
法定免除を受けている期間は、老齢基礎年金の額の計算上は、2分の1となります。
法定免除に該当していても、将来の老齢基礎年金を増額するために、保険料納付の申出をすることができます。
障害基礎年金の受給権者でも、障害の程度が軽くなり障害基礎年金が支給停止になり、老齢基礎年金を選択する可能性があります。
また、法定免除を受けていた期間は、追納することもできますが、追納は10年以内でないとできませんし、当時の保険料額に加算が行われることもあるためです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 未支給年金
国民年金法 未支給年金
R5-319
R5.7.12 年金の支給期間と未支給年金
年金の受給権者が死亡した場合の未支給年金をみていきましょう。
まず、年金の支給期間と支払期月を見ていきましょう。
第18条 (年金の支給期間及び支払期月) ① 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 ② 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 ③ 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 |
★年金は、年6回に分けて偶数月に支給されます。
年金は「後払い」です。例えば、8月に支給されるのは、6月分と7月分です。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。

【解答】
【H29年出題】 ×
年金は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から「権利が消滅した日の属する月」まで月単位で支給されます。
受給権者が死亡した場合は、「死亡日の属する月」まで支給されます。
平成29年2月27日に死亡した場合は、老齢基礎年金は「2月分」まで支給されます。
平成29年2月に、12月分と1月分が支給されていますので、未支給年金請求者が請求できるのは、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない「2月分」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 配偶者に対する遺族基礎年金の額
国民年金法 配偶者に対する遺族基礎年金の額
R5-318
R5.7.11 配偶者に対する遺族基礎年金の増額改定
遺族基礎年金は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子に支給されます。
配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者に生計を維持していたことが条件です。
遺族基礎年金は、配偶者に支給されるパターンと、子に支給されるパターンがありますが、今日は配偶者に支給されるパターンをみていきます。
では、配偶者の条件を条文で読んでみましょう。
(遺族の範囲) 第37条の2 ① 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 1 配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 2 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 ② 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。 |
★配偶者は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた子と生計を同じくすること」が条件です。
配偶者は子と生計を同じくすることが条件ですので、配偶者に支給する遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算が行われるのがポイントです。
配偶者に対する遺族基礎年金について、条文を読んでみましょう。
第39条第1項、2項 ① 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
|
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
②【R3年出題】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月までさかのぼって改定される。
③【H29年出題】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が死亡当時被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生するのは、「子が生まれたとき」です。
受給権の発生日は夫の死亡当時には遡りません。
②【R3年出題】 ×
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、遺族基礎年金の加算の対象になります。
胎児であった子が生まれたときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなすとされていますので、遺族基礎年金の額は、「その生まれた日の属する月の翌月から」改定されます。
③【H29年出題】 ×
「死亡当時被保険者によって生計を維持されていなかった子」は遺族基礎年金の対象になりません。問題文のように養子縁組をしても、年金額が改定されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 死亡一時金
国民年金法 死亡一時金
R5-317
R5.7.10 死亡一時金と寡婦年金の調整
今日は、死亡一時金と寡婦年金の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
死亡一時金と寡婦年金は、併給できません。
本人の「選択」で、どちらか一方を受けることになります。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
②【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
①【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、妻本人の選択によって、死亡一時金と寡婦年金のどちらかが支給されます。死亡一時金を選択した場合は寡婦年金は支給されない、寡婦年金を選択した場合は死亡一時金は支給されない、となります。
②【R3年出題】 〇
・一人一年金の原則
複数の年金の受給権が発生した場合は、原則として、選択した一の年金を受けることになります。
遺族厚生年金と寡婦年金の受給権が発生した場合は、どちらかを選択します。
・死亡一時金と寡婦年金
死亡一時金と寡婦年金は、どちらかを選択します。
問題文のように、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。一人一年金の原則により遺族厚生年金は支給停止となります。
また、遺族厚生年金と死亡一時金は支給調整されませんので、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 障害基礎年金
国民年金法 障害基礎年金
R5-316
R5.7.9 障害基礎年金 申請免除と初診日について
今日は、申請免除と初診日の関係をみていきます。
まず、「申請免除」で、保険料が免除される期間を確認しましょう。
<申請免除の対象となる厚生労働大臣が指定する期間> 申請のあった日の属する月の2年2か月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間 |
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H28年出題】 ×
障害基礎年金の受給権は発生しません。
・保険料免除期間に算入されるのは「申請のあった日以後」です。過去に遡って、未納が保険料免除期間になるわけではありません。
・保険料納付要件は「初診日の前日」でみます。
初診日の前日の時点では、20歳からの期間がすべて滞納期間です。
・保険料納付要件を満たしていませんので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 障害基礎年金
国民年金法 障害基礎年金
R5-315
R5.7.8 障害基礎年金の受給権発生
障害基礎年金の受給権の発生要件をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第30条(支給要件) 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者であること。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 |
★障害基礎年金の受給権の発生要件は
①初診日
②障害認定日
③保険料納付要件
の3つです。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態になった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H28年出題】 〇
受給権の発生要件を確認しましょう。
①初診日要件について
初診日に、国民年金第1号被保険者です。
初診日に「被保険者であること。」の要件を満たしています。
②保険料納付要件について
初診日は、平成26年4月8日です。
20歳に達した月(平成22年4月)から初診日の属する月の前々月(平成26年2月)までの納付状況をみることになります。
47か月のうち、平成22年4月から平成25年3月までの36か月が学生納付特例期間、平成25年4月から平成26年2月までの11か月が滞納期間です。
47カ月のうち、3分の2以上が保険料免除期間(学生納付特例期間)ですので、保険料納付要件を満たします。
③障害認定日について
障害認定日において障害等級2級の状態になった場合は、障害認定日に受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金④
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金④
R5-303
R5.6.26 20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止④日本国内に住所を有しないとき
引き続き、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止をみていきます。
初診日が国民年金に加入する前の障害に対する年金で、保険料を負担していないことが特徴です。そのため、通常の障害基礎年金とは違う支給停止事由が設定されています。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4日本国内に住所を有しないとき。 |
今日は、4日本国内に住所を有しないときをみていきます。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
②【R4年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
③【H28年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

【解答】
①【H25年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。
②【R4年出題】 ×
受給権者が日本国内に住所を有しないときに支給が停止されるのは、20歳前傷病による障害基礎年金です。
しかし、通常の障害基礎年金(事後重症による障害基礎年金も)は、日本国内に住所を有しないときでも、支給停止されません。
③【H28年出題】 ×
20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由に、「日本国籍を有しなくなったとき」はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金③
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金③
R5-302
R5.6.25 20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止③労災保険の年金を受けることができるとき
引き続き、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止をみていきます。
初診日が国民年金に加入する前の障害に対する年金で、保険料を負担していないことが特徴です。そのため、通常の障害基礎年金とは違う支給停止事由が設定されています。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項、2項 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4 日本国内に住所を有しないとき。 ② 1に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第1項(労働基準法の規定による障害補償)又は第41条第1項に規定する給付(労働基準法の規定による遺族補償)が行われることによるものであるときは、この限りでない。 |
今日は、1をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
②【H25年出題】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
③【H20年出題】
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときは、支給が停止されます。
②【H25年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときは、支給が停止されます。
ただし、「労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。」となっていますので、労働者災害補償保険法による年金たる給付の全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されません。
③【H20年出題】 〇
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときに支給が停止されるのは、20歳前の障害に基づく障害基礎年金です。
通常の障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金②
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金②
R5-301
R5.6.24 20歳前傷病による障害基礎年金②刑事施設等に拘禁されているときの支給停止
前回は、20歳前傷病による障害基礎年金の「所得による支給停止」をみました。
今日は、刑事施設等に拘禁されているときの支給停止をみていきます。
では、条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(2及び3に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4 日本国内に住所を有しないとき。 |
今日は、2と3をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
②【H28年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給停止されますが、厚生労働省令で定める場合に限られています。
厚生労働省令では、「少年法24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合」と規定されています。
(則第34条の4)
②【H28年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」は支給停止されていますが、こちらも厚生労働省令で定める場合に限られています。
刑事施設等に拘禁されている場合であっても、有罪が確定するまでは、その支給は停止されません。
(則第34条の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金①
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金①
R5-300
R5.6.23 20歳前傷病による障害基礎年金①所得による支給停止
20歳前傷病による障害基礎年金は、国民年金加入前に初診日があるため、保険料を拠出せずに支給される年金です。
そのため、通常の障害基礎年金と異なる理由で支給停止が行われます。
今日は、「所得」による支給停止をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第36条の3第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
第36条の4第1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。 |
★扶養親族等がいない場合は、前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下の場合は2分の1が支給停止、472万1千円を超える場合は全額停止となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】※改正による修正あり
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
②【H25年出題】※問題文修正あり
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年9月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
③【H27年出題】※問題文修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
④【H25年出題】※問題文修正あり
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
①【H20年出題】※改正による修正あり 〇
前年の所得に基づいて支給停止される期間は、その年の10月から翌年の9月までです。
②【H25年出題】※問題文修正あり ×
支給停止されるのは、年金額の全部又は2分の1(子の加算額が加算されている場合は、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)です。
③【H27年出題】※問題文修正あり ×
所得は「受給権者」のみの所得です。扶養親族の所得を合算しません。
④【H25年出題】※問題文修正あり ×
被害金額がその価格のおおむね「2分の1以上」である損害を受けた者がある場合です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金
国民年金法 老齢基礎年金
R5-283
R5.6.6 老齢基礎年金の額と国庫負担の関係
老齢基礎年金の満額は780,900円×改定率です。
保険料納付済期間の月数が480の場合は満額支給されますが、480未満の場合は、その分、年金額が減額されます。
保険料納付済期間の月数は1で計算しますが、免除期間は以下のように計算します。
保険料4分の1免除期間 → 8分の7
保険料半額免除期間 → 4分の3
保険料4分の3免除期間 → 8分の5
保険料全額免除期間 → 2分の1
この割合は、国庫負担との関係で決まります。
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8分の7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4分の3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8分の5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2分の1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国庫負担 | 保険料 | ||||||
※ 保険料納付済期間の月数は1で計算しますが、2分の1は国庫負担です。
※ 保険料全額免除期間については保険料はゼロですが、特別国庫負担が入り、老齢基礎年金の額には2分の1が反映します。ちなみに、学生納付特例、納付猶予期間には国庫負担が入りませんので、老齢基礎年金の額の計算ではゼロになります。
※ 国庫負担は平成21年3月までは3分の1でした。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】 ※問題文を修正しています
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額の計算式として、正しいものはどれか。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)
(A)780,900円×改定率×(360月+120月×1/2)÷480月
(B)780,900円×改定率×(360月+120月×1/3)÷480月
(C)780,900円×改定率×(360月+108月×1/2+12月×1/3)÷480月
(D)780,900円×改定率×(360月+108月×1/3+12月×2/3)÷480月
(E)780,900円×改定率×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月

【解答】
(E)780,900円×改定率×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月
全額免除期間の計算は、国庫負担の割合で変わります。国庫負担は平成21年3月までは3分の1でした。
|
| 国庫負担 |
H12年4月~H21年3月 | 108か月 | 3分の1 |
H21年4月~H22年3月 | 12か月 | 2分の1 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 任意加入被保険者
国民年金法 任意加入被保険者
R5-282
R5.6.5 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合
国民年金の任意加入被保険者は、第1号被保険者と同様に、国民年金保険料を負担します。
ただし、任意加入被保険者については、保険料を滞納した場合、被保険者資格を喪失することがあるのがポイントです。
まず、任意加入被保険者を確認しましょう。次の3種類です。(法附則第5条)
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
③日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の扱いについて、条文を読んでみましょう。
附則第5条第6項第4号 上記①、②の被保険者は、次に該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。 ・ 保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
附則第6条第8項第4号 上記③の被保険者は、次に該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。 ・ 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。 |
①、②の被保険者は「日本国内に住所を有する」、③の被保険者は「日本国内に住所を有しない」がポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
②【H29年出題】
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
③【H22年出題】
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年が経過した日に被保険者資格を喪失する。
④【H27年出題】
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の資格喪失日は、「督促状で指定した期限の日の翌日」です。
②【H29年出題】 ×
「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、「その指定した期限の日の翌日」に被保険者の資格を喪失します。
特例による任意加入被保険者も同じ扱いです。
③【H22年出題】 ×
「日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した日の「翌日」に、被保険者資格を喪失します。
日本国内に住所を有しない場合は、保険料の徴収の時効が過ぎると、任意加入被保険者資格を喪失します。
④【H27年出題】 ×
海外に居住する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく「2年間が経過した日の翌日」に、被保険者資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金の繰上げ
国民年金法 老齢基礎年金の繰上げ
R5-271
R5.5.25 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権の発生
「繰上げ支給」の受給権の発生について、ご質問がありました。
今回のテーマは、繰上げ支給の条文の読み方です。
老齢基礎年金の受給権は、要件を満たせば65歳に達した日に発生します。
しかし、請求することにより、60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受給することもできます。
条文を読んでみましょう。
附則第9条の2第1項~4項 (老齢基礎年金の支給の繰上げ) ① 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。 ② 繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。 ③ 繰上げの請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。 ④ 繰上げにより支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。 |
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は請求することによって発生します。
★「③ 繰上げの請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」について
・第26条では、老齢基礎年金は、「65歳に達したとき」に支給する、と規定されています。繰上げ請求をした場合は、第26条の規定にかかわらず、「請求があった日」に老齢基礎年金の受給権が発生するという意味です。
こちらの条文も読んでみましょう。
第18条第1項 (年金の支給期間) 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 |
・年金の支給については、第18条第1項で、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から」始める、とありますので、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給は、請求があった日の属する月の翌月から始まります。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
②【H29年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の「翌日」ではなく、「繰上げ請求のあった日」に発生します。
年金の支給は、「受給権発生日(繰上げ請求のあった日)の属する月の翌月」からです。
②【H29年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給は、その請求があった日の属する月の「翌月」分からです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算の支給停止
国民年金法 振替加算の支給停止
R5-259
R5.5.13 障害年金を受けることができるときの振替加算
障害基礎年金などの支給を受けることができるときは、その間、振替加算は支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
S60年法附則第16条第1項 振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。 |
★ 「障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」は、障害基礎年金、障害厚生年金などで、その全額につき支給を停止されている給付は除かれます。
(S61年経過措置政令第28条)
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
②【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
③【R1年出題】
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険者期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

【解答】
①【H30年出題】 〇
障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額の支給は停止されます。
②【H21年出題】 ×
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額の支給は停止されます。
しかし、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合は、振替加算の支給は停止されません。
③【R1年出題】 〇
障害基礎年金を受給している間は、振替加算の支給は停止されます。
しかし、障害基礎年金の全額が支給停止されている場合は、振替加算の支給は停止されません。
問題文のように、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、障害基礎年金は全額支給停止となりますので、老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算に相当する額の老齢基礎年金
国民年金法 振替加算に相当する額の老齢基礎年金
R5-258
R5.5.12 振替加算に相当する額のみの老齢基礎年金が支給されるとき
合算対象期間、学生納付特例期間は老齢基礎年金の額には反映しません。
例えば、20歳から60歳まですべて合算対象期間の場合は、老齢基礎年金の支給期間は満たしているものの、年金額はゼロです。しかし、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算に相当する額の老齢基礎年金」が支給されます。
条文を読んでみましょう。
(S60年法附則第15条第1項) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において加給年金額が加算される老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。 1. 合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間が、10年以上であること。 2. 附則第12条第1項第2号から第7号まで及び第18号から第20号までのいずれかに該当すること。 |
「振替加算に相当する額の老齢基礎年金」が支給される要件のポイント!
・「保険料納付済期間」及び「保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)」を有しない。
・「合算対象期間」と「保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)」とを合算した期間が、10年以上あること
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】
【H27年出題】 〇
甲は、40年間全て合算対象期間ですので老齢基礎年金の額はゼロです。
しかし振替加算の支給要件には該当しますので、老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額のみの老齢基礎年金が支給されます。
★注意しましょう★
例えば、20歳から60歳までの間に、保険料納付済期間を1か月有し、他は全て合算対象期間の人が、老齢基礎年金の受給権を有した場合は、480分の1で計算された老齢基礎年金が支給されます。
そのような人が、振替加算の支給要件に該当している場合は、480分の1の老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
振替加算額に相当する額のみの老齢基礎年金が支給されるのは、老齢基礎年金の額に反映しない合算対象期間と学生納付特例の期間のみを有する人です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算の加算要件
国民年金法 振替加算の加算要件
R5-257
R5.5.11 240月以上の老齢厚生年金を受けることができる場合の振替加算
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるもの又は中高齢の期間短縮特例を満たしているものに限る。)を受けることができる場合は、振替加算は加算されません。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条)
さっそく、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
②【R3年出題】
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
老齢基礎年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金又は中高齢の期間短縮特例を満たした老齢厚生年金を受けることができるときは、老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
★老齢厚生年金を受けていても、被保険者期間の月数が240月未満の場合又は中高齢の期間短縮特例を満たしていない場合は、振替加算が加算されます。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条)
②【R3年出題】 ×
昭和26年3月2日生まれの女性の場合、35歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が19年あれば、中高齢の期間短縮特例を満たします。
問題文の妻は、41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有し、中高齢の期間短縮特例に該当しますので振替加算は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算を受けるための手続
国民年金法 振替加算を受けるための手続
R5-256
R5.5.10 振替加算「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
振替加算を受けるための手続をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
則第17条の3 老齢基礎年金の受給権者は、昭和60年改正法附則第14条第2項又は第18条第3項の規定に該当するに至ったときは、一定の事項を記載した届書に一定の書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。 |
「昭和60年改正法附則第14条第2項」では、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した後に、配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢の期間短縮特例の場合も含みます)を満たした老齢厚生年金を受けられるようになった場合は、老齢基礎年金に振替加算が加算されると規定されています。
夫
65歳 退職時改定
(240月未満) (240月)
|
|
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
妻(老齢基礎年金の受給権者)
65歳
| 振替加算 |
老齢基礎年金 | |
このような場合は、振替加算の支給を受けるために、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
【H27年出題】 〇
妻が65歳に達した後に、夫が退職時改定により、加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たしたことがポイントです。
この場合、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することによって、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算と繰上げ繰下げ
国民年金法 振替加算と繰上げ繰下げ
R5-255
R5.5.9 老齢基礎年金を繰上げ・繰下げた場合の振替加算
老齢基礎年金は要件を満たせば、65歳に達したときに受給権が発生しますが、繰り上げて受給することもできますし、繰下げて受給することもできます。
老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合、振替加算はどのようになるのでしょうか?
振替加算はいつから加算されるのか、条文を読んでみましょう。
S60年法附則第14条第4項 振替加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
②【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
③【R3年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は繰上げされません。振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ行われません。
夫
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | |
| 加給年金額 |
|
妻
60歳 65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
例えば、老齢基礎年金の受給権者である妻が60歳で老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合でも、振替加算が加算されるのは65歳からです。
なお、夫の老齢厚生年金に加算されている加給年金額は、妻が老齢基礎年金を繰上げした場合でも、65歳になるまで支給されます。
②【H30年出題】 ×
振替加算について
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合 → 65歳に達した日の属する月の翌月から加算されます。(問題文の「請求のあった日の属する月の翌月から加算」は誤りです。)
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合 → 振替加算も繰下げて支給されますので、問題文の通り、申出のあった日の属する月の翌月から加算されます。
③【R3年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されます。ただし、振替加算額は繰下げによる増額はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算
国民年金法 振替加算
R5-254
R5.5.8 振替加算が加算される要件
老齢基礎年金に振替加算が加算され得るのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人です。
「生年月日」のポイント!
大正15年4月2日以降生まれ→ 新法の対象者です。
昭和41年4月1日以前生まれ → 新法施行日の昭和61年4月1日に20歳以上です。
まず、過去問からどうぞ!
【H30年出題】
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
【H30年出題】 〇
まず、問題文の夫婦の年金を図でイメージしましょう。
(注)妻は、厚生年金保険の被保険者期間を有しないと仮定しています。
夫(昭和25年4月2日生まれ)
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | |
| 加給年金額 |
|
妻(昭和28年4月2日生まれ)
65歳
振替加算 |
老齢基礎年金 |
★夫について(昭和25年4月2日生まれ)
・60歳から64歳まで → 報酬比例部分のみ支給されます
・65歳から → 老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
また生計維持関係のある妻がいるため、加給年金額が加算されます。
加給年金額が加算される要件を確認しましょう。
原則として、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上あることが条件です。
問題文の夫の被保険者期間は20年未満ですが、「45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間が19年」で中高齢の期間短縮特例を満たします。240月以上とみなされて加給年金額が加算されます。
★妻について(昭和28年4月2日生まれ)
夫に加算されている加給年金額は、妻が65歳に達したときに終了します。
加給年金額の対象になっていた妻が65歳になり、老齢基礎年金を受けるようになると、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
振替加算が加算される要件を確認しましょう
<老齢基礎年金の受給権者(問題文では「妻」)の要件>
・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であること
・65歳に達した日に、配偶者によって生計を維持していた(65歳に達した日の前日に配偶者が受給権を有する年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと)
・ただし、妻自身が被保険者期間が原則240月以上で計算される老齢厚生年金、退職共済年金を受けることができるときは、振替加算は加算されません。
<配偶者(問題では「夫」)の要件>
・老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる月数が原則として240以上であるもの)の受給権者
・障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
※加給年金額が加算される年金の受給権者であることが条件です。
振替加算の額を確認しましょう
振替加算の額は、224,700円×改定率×政令で定める率で計算します。
政令で定める率は、大正15年4月2日生まれ~昭和2年4月1日以前生まれが1.000で、年齢が若くなるほど小さくなります。昭和36年4月2日~昭和41年4月1日生まれは、0.067です。
なお、問題文の昭和28年4月2日生まれの妻の振替加算の額は、224,700円×改定率×0.280です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前に初診日がある場合
国民年金法 20歳前に初診日がある場合
R5-244
R5.4.28 20歳前傷病による障害基礎年金の支給要件
20歳前に初診日がある場合(=国民年金加入前に初診日がある場合)は、第30条の4の20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を拠出しないで支給される年金ですので、通常の障害基礎年金とは異なる支給停止事由が設定されているのが特徴です。
では、条文を読んでみましょう。
第30条の4第1項 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 |
★障害認定日が20歳前にある場合
初診日 | 障害認定日 |
| 20歳 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「20歳に達した日」に障害基礎年金の受給権が発生します
★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
②【H26年出題】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
③【H22年出題】
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

【解答】
①【H30年出題】 ×
傷病の初診日に19歳の者に支給されるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」です。「20歳前傷病による障害基礎年金」は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないので、保険料納付要件は問われません。
20歳で第1号被保険者の資格を取得した後の未納期間は、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給要件には関係ありません。
問題文の場合は、初診日から1年6か月経過後の障害認定日に障害等級1級又は2級に該当していた場合は、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。
②【H26年出題】 ×
障害認定日は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」又は、「1年6か月以内に傷病が治った場合その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)」です。
問題文の場合、初診日から継続して治療しています(治っていない)ので、障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」となります。
初診日が19歳ですので、障害認定日は20歳に達した後になります。
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「20歳に達した日」ではなく、「障害認定日」に障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。
③【H22年出題】 ×
初診日に20歳未満でも、厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)である場合は、障害基礎年金の初診日要件(初診日に国民年金の被保険者であること)を満たしています。
そのため、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。
障害認定日が20歳未満でも「障害認定日」に、「障害基礎年金と障害厚生年金」の受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金
国民年金法 老齢基礎年金
R5-229
R5.4.13 任意加入被保険者と第2号被保険者の違い
まず、「保険料納付済期間」の定義を条文で確認しましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
■任意加入被保険者について
第2号被保険者でもなく、第3号被保険者でもなく、しかし第1号被保険者にも該当しない人は、国民年金に任意加入することができます。
条文を読んでみましょう。
附則第5条第1項 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
★任意加入被保険者は、第1号被保険者と同じように保険料を納付します。(ただし、免除は受けられません。)
また、任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、第1号被保険者とみなされ、「保険料納付済期間」に算入されます。
■第2号被保険者について
厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者となります。
第2号被保険者は、第1号被保険者・第3号被保険者とは異なり、20歳以上60歳未満の年齢枠がないのがポイントです。
第2号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入されます。
しかし、「老齢基礎年金」については、保険料納付済期間に算入されるのは、「20歳以上60歳未満」の期間だけで、20歳未満、60歳以後の期間は「合算対象期間」となります。
条文を読んでみましょう。
昭60年法附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の支給要件及び老齢基礎年金の年金額については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
※なお、「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」については、第2号被保険者の20歳前、60歳以後も保険料納付済期間として扱われます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

【解答】
【H30年出題】 〇
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、第1号被保険者とみなされ、老齢基礎年金の年金額には、保険料納付済期間として反映します。
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)であった期間は、老齢基礎年金の規定では、「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の支給要件期間の10年には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 保険料
国民年金法 保険料
R5-228
R5.4.12 令和5年度の国民年金保険料
国民年金の保険料についてみていきましょう。
国民年金の保険料の額は、令和5年度に属する月の月分については、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)となります。
(第87条第3項)
保険料改定率は、前年度保険料改定率×名目賃金変動率で算定します。
※名目賃金変動率=前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率です。
令和5年度の指標は以下の通りです。
前年度保険料改定率 | 0.976 |
前々年の物価変動率 | 0.998 (-0.20%) |
4年前の年度の実質賃金変動率 | 0.998 (-0.20%) |
令和5年度の保険料改定率は、0.976×(0.998×0.998)=0.972となります。
では、問題を解いてみましょう。
(平成30年の過去問を参考にしています。)
【問題】
令和5年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,520円である。

【解答】 〇
令和5年度の国民年金保険料の月額は、
17,000円×保険料改定率(0.972)=16,524円の5円未満を切り捨てた16,520円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 遺族基礎年金
国民年金法 遺族基礎年金
R5-217
R5.4.1 遺族基礎年金を受けることができる配偶者の条件
遺族基礎年金の遺族の範囲を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第37条の2第1項 (遺族の範囲) 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 ① 配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、②に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 ② 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
配偶者のポイント!
・「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれます。
・被保険者又は被保険者であった者(=死亡した人のことです)の死亡の当時その者によって生計を維持していること、かつ、子と生計を同じくすることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
平成31年4月に死亡した第1号被保険者の女性には、15年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の男性との間に14歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。

【解答】
【R1年出題】 ×
配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。
問題文の男性は、女性の死亡時に生計を維持し、かつ、14歳の子と生計を同じくしていますので、遺族基礎年金の受給権者となります。
女性の死亡により遺族基礎年金の受給権者になるのは、当該男性と子です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 特例による任意加入
国民年金法 特例による任意加入
R5-216
R5.3.31 特例による任意加入のポイント
国民年金には「任意加入」の制度があります。
任意加入の対象は、「老齢基礎年金の受給資格がない(受給資格期間を満たしていない)人」や、「保険納付済期間が40年ないため、満額の老齢基礎年金が受給できない(老齢基礎年金を増やしたい)人」です。
今日は、「特例による任意加入被保険者」の制度をみていきます。
「特例の任意加入」は、65歳以上70歳未満の人で、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人」のみが対象です。受給資格期間を満たしていて、老齢基礎年金を増やしたい人は、特例の任意加入はできません。
では、条文を読んでみましょう。
H6法附則第11条、H16法附則第23条 (任意加入被保険者の特例) 昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。 ただし、その者が老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。 ① 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) ② 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
任意加入被保険者の特例のポイント!
★生年月日の条件があります。
昭和40年4月1日以前に生まれた者
★老齢基礎年金等、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合は、任意加入できません。
★年齢は、65歳以上70歳未満です。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
②【R1年出題】
67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
特例による任意加入被保険者が、厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したときは「その日」に、被保険者の資格を喪失します。
老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、「その日の翌日」に被保険者の資格を喪失します。
ポイント!
特例による任意加入は、「老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権」を有しないことです。
老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するのが目的です。そのため、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、その翌日に資格を喪失します。
(H6法附則第11条)
②【R1年出題】 ×
第2号被保険者期間が8年間ありますので、あと2年間保険料納付済期間があれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得できます。
特例による任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得すると、その日の翌日に資格を喪失します。
そのため、問題文の男性が、任意加入し、保険料を納付することができるのは、67歳から2年間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金
国民年金法 老齢基礎年金
R5-215
R5.3.30 合算対象期間は老齢基礎年金の年金額に反映しない
老齢基礎年金の受給資格は、原則として「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」が10年以上あることです。
保険料納付済期間+保険料免除期間が10年未満の場合は、「合算対象期間」も入れて10年以上になれば、受給資格を満たします。
条文を読んでみましょう。
第28条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
第28条は老齢基礎年金の原則の受給資格についての規定です。
「保険料免除期間」が2回出てきます。
学生納付特例及び納付猶予の期間は、ただし書(2回目の保険料免除期間)では除外されていませんので、10年の受給資格期間には算入されます。
しかし、1回目の保険料免除期間からは除かれています。老齢基礎年金の年金額の計算に入らないからです。
「合算対象期間」については、附則第9条で、「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」に「合算対象期間」も合算して10年以上あれば受給資格期間を満たすと規定されています。ただし、合算対象期間は「カラ期間」といい、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
今回は合算対象期間をみていきます。
今回、出てくる合算対象期間は
・第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以降のもの
・日本国籍を有している人が海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
です。
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
【R1年出題】 〇
18歳~19歳 | 20歳 60歳 | 60歳~65歳 |
厚年 | 海外居住(日本国籍有)で任意加入しなかった | 厚年 |
カラ期間 | カラ期間 | カラ期間 |
・18歳から19歳までの厚生年金保険の加入期間、20歳から60歳まで国民年金には任意加入しなかった期間、60歳から65歳までの厚生年金保険の加入期間、すべて「合算対象期間」です。
合算対象期間のみで10年以上でも、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしますが、老齢基礎年金の額には反映しません。結果として65歳から老齢基礎年金が支給されることはありません
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 第3号被保険者
国民年金法 第3号被保険者
R5-204
R5.3.19 第3号被保険者の届出
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。
資格取得届などの提出先や提出期限などを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条第5項~9項 5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 6 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 7 第2号被保険者を使用する事業主とは、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主をいう。 8 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 9 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
ポイント!
・ 第3号被保険者の届出先は「厚生労働大臣」です。
・ 届出は、事業主、共済組合等を経由します。
「第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者」の場合 →第2号被保険者を使用する事業主を経由します。
「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者」の場合 → 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由します。
・ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の「一部」を「健康保険組合」に委託できます。→委託できるのは事務の「一部」です。「全部」は委託できませんので注意して下さい。
・ 届出が事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
②【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
③【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
④【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
★被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する届出について
・第1号被保険者は → 市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出ます。
・第3号被保険者は → 厚生労働大臣に届け出ます。
②【H29年出題】 〇
資格取得の届出は、14日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。
※日本年金機構は、厚生労働大臣から権限を委任されて、取得の手続を行います。
(則第1条の4)
以下の届出の提出期限は、第1号被保険者・第3号被保険者ともに「14日以内」です。
・資格取得の届出
・資格喪失の届出
・種別変更の届出
・住所変更の届出
・氏名変更の届出
③【R1年出題】 〇
第3号被保険者の届出のイメージ
第3号被保険者 |
→ → | 事業主 共済組合等 経由 |
→ → → | 厚生労働大臣 (日本年金機構) |
|
| ※受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。 |
|
|
④【H29年出題】 ×
届出に係る事務の一部を「健康保険組合」に委託することがきます。全国健康保険協会には委託できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金の繰下げ
国民年金法 老齢基礎年金の繰下げ
R5-193
R5.3.8 老齢基礎年金繰下げの条件
老齢基礎年金の繰下げの要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第28条第1項 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 |
繰下げ申出ができる要件のポイント!
・66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していないこと
・65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者でないこと
・65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていないこと
※「他の年金たる給付」とは
他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいいます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
②【H24年出題】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
③【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
④【H30年出題】
65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったときは、繰下げの申出はできません。
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において「障害基礎年金」の受給権者となった(=他の年金たる給付の受給権者となったということです)ときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。
②【H24年出題】 ×
寡婦年金の受給権は65歳に達したときに消滅します。
寡婦年金の受給権者であった者も、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けられます。
③【R1年出題】 〇
ポイントその1 「他の年金たる給付」から、「老齢厚生年金」は除かれます。
そのため、「65歳に達したとき」に老齢厚生年金の受給権者でも、また、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に老齢厚生年金の受給権者となっても、老齢基礎年金を繰下げることができます。
ポイントその2 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできます。
老齢厚生年金を65歳から受給し、老齢基礎年金を67歳から繰下げて受けることも可能です。
④【H30年出題】 ×
65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも、老齢基礎年金の支給繰下げの申出ができます。
条件は次の通りです。
・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢基礎年金を請求していないこと
・老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ
当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないこと
(S60 法附則第18条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 種別変更
国民年金法 種別変更
R5-182
R5.2.25 国民年金の種別変更
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種別があります。
例えば、日本国内に居住する23歳の大学生は第1号被保険者です。卒業し民間企業に就職すると厚生年金保険の被保険者となり、国民年金は第2号被保険者となります。
この場合、第1号被保険者の資格を喪失→第2号被保険者の資格を取得ではなく、第1号被保険者から第2号被保険者に「種別変更」となります。
条文を読んでみましょう。
第11条の2 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。 |
例えば、ある月に、第1号被保険者から第3号被保険者に種別が変更した場合は、その月は、変更後の第3号被保険者であった月とみなされます。
また、ある月に、第2号被保険者→第3号被保険者→第1号被保険者と、2回以上種別に変更があったときは、その月は最後の種別の第1号被保険者であった月とみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
②【H30年出題】
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
③【H24年出題】
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者になった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

【解答】
①【R3年出題】 〇
例えば、第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点で、第1号被保険者に該当するときは、第1号被保険者に種別の変更となります。国民年金の被保険者資格は喪失しません。
その後、第1号被保険者のまま60歳に達したときは、60歳に達した日に国民年金の資格を喪失します。
②【H30年出題】 ×
同一の月に、2回以上、被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされます。問題文の場合は、「第3号被保険者」であった月とみなされます。
③【H24年出題】 ×
第1号被保険者から第3号被保険者になった月は、「第3号被保険者」であった月とみなされます。すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合でも、第1号被保険者とはみなされません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 障害基礎年金
国民年金法 障害基礎年金
R5-170
R5.2.13 障害基礎年金 額の改定請求
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合は、年金額の改定請求ができます。
条文を読んでみましょう。
第34条第2項、3項 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
③ 請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求は、「受給権を取得した日」又は「障害の程度の診査を受けた日」から1年を経過した日を過ぎていることが条件です。
ただし、厚生労働省令で定める障害の程度が増進したことが明らかな場合は、1年たたなくても額の改定を請求することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。
②【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年たたずに額の改定請求が可能です。
②【R2年出題】 〇
「心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着したもの」は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」に当たります。受給権を取得した日から起算して6か月しか経過していなくても、年金額の改定の請求をすることができます。
(則第33条の2の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 国民年金基金
国民年金法 国民年金基金
R5-162
R5.2.5 国民年金基金の加入員
今日のテーマは国民年金基金です。
国民年金基金は、「加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする」とされています。
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行ないます。
また、国民年金基金には、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の2種類があります。
今日は、国民年金基金の加入員をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第127条 ① 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 ② 申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。 附則第5条第11項 「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは、第116条第1項及び第2項(国民年金基金の組織)並びに第127条第1項の規定(国民年金基金の加入員)の適用については、第1号被保険者とみなす。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。
②【H29年出題】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
③【H24年出題】
第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
国民年金基金の加入者になることができるのは、第1号被保険者です。
任意加入被保険者のうち、「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」と「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」も、国民年基金の加入者となることができます。
(法附則第5条)
②【H29年出題】 ×
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入できます。
ちなみに、任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」は、国民年金基金の加入員から除外されています。
(法附則第5条)
③【H24年出題】 ×
第127条第1項で、「第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。」と規定されていますので、同時に2つの基金には加入できません。
しかし、問題文のように、職能型国民年金基金の方が優先するということはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 令和5年度の年金額
国民年金法 令和5年度の年金額
R5-154
R5.1.28 令和5年度の年金額の改定
 「改定率」は毎年度見直されます。
「改定率」は毎年度見直されます。
老齢基礎年金の満額は、780,900円×改定率で計算します。
「改定率」は、毎年度見直しが行われます。
 名目手取り賃金変動率と物価変動率
名目手取り賃金変動率と物価変動率
★改定率の改定に使われる指標は、
新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」
既裁定者は「物価変動率」
です。
★令和5年度の改定については、
「物価変動率」=+2.5%、「名目手取り賃金変動率」=+2.8%
を用います。
 マクロ経済スライドについて
マクロ経済スライドについて
マクロ経済スライドとは?
→ 公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定されます。その率を、賃金と物価の変動がプラスとなる場合は、改定率から控除する仕組みです。
令和5年度の「マクロ経済スライドによるスライド調整率」は-0.3%です。
 マクロ経済スライドのキャリーオーバー(未調整分)
マクロ経済スライドのキャリーオーバー(未調整分)
マクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額を下げないという措置は維持した上で、調整できなかった分を翌年度以降に繰り越す制度のことです。
前年度までのマクロ経済スライドの未調整分は、-0.3%です。
 令和5年度の改定率
令和5年度の改定率
<新規裁定者>
・名目手取り賃金変動率(+2.8%)を用いて改定されます。
さらに、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(-0.3%)と、マクロ経済スライドの未調整分の調整(-0.3%)が行われます。
イメージ
名目手取り 賃金変動率 +2.8
| マクロ経済スライド -0.3 |
マクロ経済スライド未調整分 -0.3 | |
+2.2
|
新規裁定者の改定率=0.996(令和4年度の改定率)×1.022=1.018です。
令和5年度の年金額は780,900円×1.018=795,000円となります。
※100円未満四捨五入しています。
<既裁定者>
・物価変動率(+2.5%)を用いて改定されます。
さらに、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(-0.3%)と、マクロ経済スライドの未調整分の調整(-0.3%)が行われます。
イメージ
物価変動率 +2.5
| マクロ経済スライド -0.3 |
マクロ経済スライド未調整分 -0.3 | |
+1.9
|
既裁定者の改定率=0.996(令和4年度の改定率)×1.019=1.015です。
令和5年度の年金額は780,900円×1.015=792,600円となります。
※100円未満四捨五入しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 追納
国民年金法 追納
R5-153
R5.1.27 追納が可能な期間
第1号被保険者は、毎月、国民年金の保険料を納付する義務がありますが、収入が少ないなどの場合は、保険料の免除を受けることができます。
免除を受けた期間は保険料免除期間となり、老齢基礎年金の額ではカットされて計算されます。
しかし、保険料を「追納」することにより、保険料免除期間を保険料納付済期間にすることもできます。
今日のテーマは、「追納」です。
条文を読んでみましょう。
第94条第1項 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。 ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
・老齢基礎年金の受給権者は、追納できません。
・追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限ります。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

【解答】
【R2年出題】 〇
問題文の場合、承認の日の属する月が令和2年4月です。
追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内ですので、令和2年3月から10年以内にあるものです。
問題文の場合は、平成22年4月から平成28年3月分までが、追納できる期間です。
H18年7月 H22年4月 H28年3月
10年以内にないので、追納できない
| 追納できる |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 任意加入被保険者
国民年金法 任意加入被保険者
R5-144
R5.1.18 任意加入被保険者と480月の関係
国民年金の任意加入には、「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」があります。
「任意加入被保険者」の目的は2つです。
1つ目は、老齢基礎年金の受給資格を得られない人が、「老齢基礎年金の受給資格要件を満たすため」、2つ目は老齢基礎年金の受給資格はあるけれど満額ではない人が、「老齢基礎年金を増やすため」です。
なお、「特例による任意加入被保険者」の目的は、1つ目の「老齢基礎年金の受給資格要件を満たすため」だけです。
任意加入の条件を条文で読んでみましょう。
附則第5条 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
過去問をどうぞ!
【R2問9-C】
20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
【R2問9-C】 〇
保険料半額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算上、4分の3(平成21年4月以降の場合)となります。
問題文の場合、老齢基礎年金の額に反映するのは、保険料納付済期間の月数(360)+保険料半額免除の月数(120月×4分の3)=450月となります。
65歳から受け取ることができる老齢基礎年金は満額ではありませんので、老齢基礎年金を増やすために、60歳から65歳までの間、任意加入することができます。
なお、月数が480に達したとき(=老齢基礎年金が満額になったとき)は、その日に任意加入被保険者の資格を喪失します。
こちらもどうぞ!
【H24問3-C】
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【H24問3-C】 〇
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間と多段階免除期間を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失します。
本人から資格喪失の申出がなくても、自動的に資格喪失になるのがポイントです。
(法附則第5条第5項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 寡婦年金
国民年金法 寡婦年金
R5-135
R5.1.9 寡婦年金 死亡した夫の条件
寡婦年金の支給要件のうち、死亡した夫の要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第49条 (支給要件) 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
「夫」の条件を確認しましょう。
・ 死亡日の前日に、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、10年以上あること
※保険料免除期間は、「学生納付特例期間及び納付猶予期間」以外となっていますので、「学生納付特例期間及び納付猶予期間」しか有しない場合は、寡婦年金は支給されません。
・老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けていないこと
では、過去問をどうぞ!
①【R2問9-A 】
68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。
②【R2年問4-E】
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。

【解答】
①【R2問9-A 】 ×
死亡した夫は、「第1号被保険者」としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることが条件です。
特例による任意加入被保険者は、寡婦年金については、「第1号被保険者」とみなされないのがポイントです。
特例による任意加入被保険者として保険料を納付した期間は計算に入りませんので、10年以上という要件を満たせません。そのため、妻に寡婦年金は支給されません。
★「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」が第1号被保険者とみなされるか否かはポイントですので、おさえておきましょう。
<第1号被保険者とみなされるもの、みなされないもの>
| 付加保険料納付 | 寡婦年金 | 死亡一時金 | 脱退一時金 |
任意加入被保険者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特例による 任意加入被保険者 | × | × | 〇 | 〇 |
(附則第5条第9項、H16法附則第23条第9項)
②【R2年問4-E】 ×
老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を「受けたことがある夫」が死亡したときは、寡婦年金は支給されません。
しかし、問題文のように、夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合は、夫は老齢基礎年金を「受けたことがない」ため、他の要件を満たせば、妻に寡婦年金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金「任意加入被保険者」の目的と条件
国民年金「任意加入被保険者」の目的と条件
R5-129
R5.1.3 任意加入被保険者になる目的と条件を確認しましょう
平成25年の国民年金の過去問についてご質問がありました。
「任意加入」がテーマの問題です。今日はご質問にお答えします。
まず、任意加入の条件を条文で読んでみましょう。
附則第5条 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
 任意加入する目的は2つです。
任意加入する目的は2つです。
1つ目は、老齢基礎年金の受給資格がない人が、「老齢基礎年金の受給資格要件を満たすため」、2つ目は老齢基礎年金の受給資格はあるけれど満額ではない人が、「老齢基礎年金を増やすため」です。
では、過去問をどうぞ!
【H25年問8-C】
大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった、その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となった。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。
※設問の女性は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする。

【解答】
【H25年問8-C】 ×
設問の場合、国民年金の任意加入の申出をすれば、任意加入被保険者になることができます。
まず、設問の女性の年金履歴を確認しましょう。
・22歳から26歳まで → 厚生年金保険の被保険者
・26歳から昭和61年3月まで → 未加入(会社員の被扶養配偶者)
・昭和61年4月から平成26年3月まで → 第3号被保険者
なお、26歳から昭和61年3月までの未加入期間は「合算対象期間」となります。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、かつ、第1号厚生年金被保険者の期間が1年以上ありますので、60歳から「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」が支給されます。
ポイント!
・受給資格は満たしていますので、65歳から老齢基礎年金を受給できます。しかし、20歳から22歳までが空白になっているのと、26歳からの合算対象期間がありますので、老齢基礎年金は満額ではありません。
任意加入の目的の2つ目の「老齢基礎年金の受給資格はあるけれど満額ではない人」に該当しますので、保険料納付済期間を増やすため、60歳から65歳まで任意加入することができます。(法附則第5条第1項第2号に該当します)
・「特別支給の老齢厚生年金」の支給が開始されても、任意加入して老齢基礎年金を増やすことは可能です。
では、こちらの過去問をどうぞ!
【R2年問9-B】
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】
【R2年問9-B】 ×
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中でも、任意加入することは可能です。
日本国内に住所を有していなくても日本国籍を有している場合は、法附則第5条第1項第3号「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」に該当しますので、任意加入被保険者の申出をすることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-123
R4.12.28 R4択一式より 法定免除される期間
法定免除事由に該当した場合、保険料が免除されるのはいつからいつまででしょうか?
では、条文を読んでみましょう。
第89条 1 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 ② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ③ 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
2 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない。 |
法定免除の要件に該当した場合は、当然に保険料が免除されますので、免除の申請をする必要はありません。
※法定免除事由に該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に届書を提出する必要があります。(則第75条)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-D】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【解答】
【問9-D】 〇
法定免除の要件に該当するに至ったときは、保険料は当然に免除されます。
例えば、令和4年12月に要件に該当した場合は、令和4年11月(該当するに至った日の属する月の前月)から免除されます。国民年金の保険料の納期限は翌月末日ですので、免除事由に該当した12月に期限がくる11月分から免除となります。
「免除事由に該当しなくなる日の属する月」まで免除されます。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
法定免除される期間は、その該当するに至った日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する「月」までの期間です。
なお、生活保護法には8種類の扶助がありますが、法定免除の事由に該当するのは「生活扶助」のみです。
こちらの過去問もどうぞ!
②【H26年出題】
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
③【R2年出題】
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
④【R2年出題】
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
法定免除事由に該当すると当然に保険料は免除されますが、希望すれば、保険料を納付することができます。
③【R2年出題】 〇
②の問題と同じです。
保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができます。
④【R2年出題】 〇
法定免除事由に該当した場合、14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければなりません。法定免除事由に該当していることを、知ってもらうためです。
そのため、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は不要です。
(則第75条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-122
R4.12.27 R4択一式より 国民年金の被保険者の資格喪失日
国民年金の強制加入被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者がありますが、それぞれの資格喪失事由と喪失日を確認しましょう。
条分を読んでみましょう。
第9条 (資格喪失の時期) 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(②に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は③から⑤までのいずれかに該当するに至ったとき(④については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したとき。 ② 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ③60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)。 ④ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ⑤厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く。)。 ⑥ 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)。 |
ポイント!
・例えば、40歳で会社を退職し自営業を始めた場合、国民年金の種別は第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。その場合、「第2号被保険者資格を喪失→第1号被保険者資格を取得」という流れではなく、第1号被保険者から第2号被保険者に「種別変更」となります。
その後、第1号被保険者のまま60歳に達したときは、そこで国民年金の被保険者の資格を喪失します。
「資格喪失」とは国民年金の被保険者資格を喪失するという意味です。「種別変更」とは違いますので注意しましょう。
・第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の定義をおさえましょう。それぞれ、その条件に当てはまらなくなったときに資格を喪失します。
・「翌日喪失」か「当日喪失」かを覚えましょう。死亡による喪失の場合は「翌日」、年齢による喪失の場合は「当日」が覚えやすいです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-E】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。

【解答】
【問8-E】 〇
第1号被保険者と第3号被保険者は「20歳以上60歳未満」という年齢要件がありますので、「60歳」で資格を喪失します。
年齢で資格を喪失する場合は「当日喪失」です。また「60歳に達した日」=「60歳の誕生日の前日」です。例えば、令和4年12月28日が60歳の誕生日なら、令和4年12月27日に資格を喪失します。
なお、第2号被保険者には20歳以上60歳未満の年齢要件がありませんので、60歳に達しても資格は喪失しません。
また、死亡の場合は「翌日喪失」です。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通です。
過去問をどうぞ!
【H25年出題】 ※改正による修正あり
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【H25年出題】 ×
厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)は、60歳に達しても国民年金の被保険者の資格を喪失しません。
厚生年金保険の被保険者が国民年金の第2号被保険者の資格を喪失するのは、原則として、「65歳に達した日」となります。
※老齢基礎年金等の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者は、65歳以降も国民年金の第2号被保険者です。
(法附則第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-121
R4.12.26 R4択一式より 第2号被保険者期間の合算対象期間
老齢基礎年金の受給資格は、「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」が10年以上あることですが、10年未満の場合は、附則第9条の特例により「合算対象期間」も合算して10年以上あれば受給資格を満たします。
「合算対象期間」は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額には反映しませんので、カラ期間ともいわれます。
今日のテーマは、「第2号被保険者」としての被保険者期間のうちの合算対象期間です。
では、条文を読んでみましょう。
(昭60年法附則第8条第4項) 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条(老齢基礎年金の支給要件)及び第27条(老齢基礎年金の年金額)の適用については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
老齢基礎年金の年金額は、第1号被保険者の年齢(20歳以上60歳未満)の基準に合わせています。20歳から60歳までの40年間すべて保険料納付済期間なら満額が支給される仕組みです。
しかし、第2号被保険者については、厚生年金保険の被保険者なら20歳前でも60歳以上でも原則第2号被保険者となります。
そのため、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、老齢基礎年金の受給資格や年金額について「保険料納付済期間」として扱われるのは、「20歳以上60歳未満」の期間です。20歳未満、60歳以後の期間は「合算対象期間」となります。
※例えば、18歳から63歳まで厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)だった場合
18歳 20歳 60歳 63歳
厚生年金保険の被保険者(=第2号被保険者) | ||
カラ期間 | 保険料納付済期間 | カラ期間 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-D】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
【問8-D】 ×
問題文の場合、厚生年金保険の被保険者期間のうち、60歳~65歳までの5年間は、合算対象期間です。42年間のうちその5年間は、老齢基礎年金の額の計算には算入されませんので、老齢基礎年金は満額になりません。
20歳 23歳 60歳 65歳
未加入 | 厚生年金保険の被保険者(=第2号被保険者) | |
保険料納付済期間 (37年) | 合算対象期間 (5年) | |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
②【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間と60歳以後の期間は、「合算対象期間」です。老齢基礎年金の年金額を計算する場合は、保険料納付済期間には算入されません。
②【H24年出題】 ×
障害基礎年金には、合算対象期間という扱いがありません。そのため、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、受給資格期間・年金額の計算ともに「保険料納付済期間」とされます。
なお、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-120
 R4.12.25 R4択一式より 付加年金の計算式
R4.12.25 R4択一式より 付加年金の計算式
付加年金の計算式を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第87条の2第1項 第1号被保険者(保険料の免除を受けている者、国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金の保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。
第43条 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 |
付加保険料は月400円で、申出をした月から納付できます。
付加年金は200円×付加保険料の納付月数で計算され、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
付加保険料を40年(480月)納付した場合は、付加年金の計算式は200円×480月で、年間96,000円となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

【解答】
【問9-B】 ×
付加保険料の納付済期間が60月の場合、付加年金の額は年額で、「200円」に60月を乗じて得た額となります。
付加保険料は月400円ですが、付加年金の計算は「200円」で計算するのがポイントです。
付加保険料を60月間納付した場合、納付した付加保険料はトータルで、400円×60月=24,000円です。
一方、65歳から支給される付加年金は、200円×60月で、年額12,000円です。
付加年金を2年受給すれば、納付した付加保険料とイコールになる計算です。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。
②【H29年出題】
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
付加年金の額は、200円×300か月=年額60,000円です。
②【H29年出題】 ×
付加年金の額には、改定率による改定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-100
R4.12.5 R4択一式より 65歳以上の厚生年金保険の被保険者
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。
第1号被保険者と第3号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢要件がありますが、第2号被保険者には、年齢要件がないのがポイントです。
ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の受給権の有無で扱いが変わりますので、注意しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第7条第1項第2号・法附則第3条 厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者とする。 65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。 |
ポイント!
厚生年金保険の被保険者で65歳以上の者については、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給権を有している場合は、第2号被保険者となりません。
★65歳の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権がある場合
65歳 70歳
厚生年金保険の被保険者 | |
国民年金第2号被保険者 |
|
▲国民年金の資格喪失
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-A】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【問7-A】 〇
65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している場合は、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、65歳に達したときに、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
②【H26年出題】※改正による修正あり
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者ではありませんので、55歳の配偶者は第3号被保険者となりません。
②【H26年出題】 × ※改正による修正あり
老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していない65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者となります。
障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、老齢又は退職の年金の受給権がなければ第2号被保険者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-099
R4.12.4 R4択一式より 寡婦年金が受給できる妻の年齢
今日は、寡婦年金が受給できる妻の年齢について確認しましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第49条 (寡婦年金の支給要件) ① 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 ③ 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
 寡婦年金の受給権が発生するのは、「夫との婚姻関係が10年以上継続した『65歳未満』の妻」です。
寡婦年金の受給権が発生するのは、「夫との婚姻関係が10年以上継続した『65歳未満』の妻」です。
年金の支給は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から始まります。しかし、寡婦年金の場合、60歳未満の妻については、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から始まるのがポイントです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-B】
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。

【解答】
【問3-B】 〇
寡婦年金の受給要件は「65歳未満の妻」です。「妻が60歳未満」であるときは、寡婦年金の受給権が発生します。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
②【H20年出題】
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。

【解答】
①【H20年出題】 ×
寡婦年金の受給権が発生するのは、「65歳未満の妻」です。「60歳以上65歳未満」の妻に限りの部分が誤りです。
②【H20年出題】 〇
夫の死亡の当時に60歳未満の妻にも寡婦年金の受給権は発生しますが、支給は妻が「60歳に達した日の属する月の翌月」から開始されます。
なお、寡婦年金は老齢基礎年金が受給できるまでの有期年金ですので、65歳に達したときに失権します。支給されるのは、「65歳に達した日の属する月」までです。
(法第51条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-098
R4.12.3 R4択一式より 学生納付特例事務法人の行う事務
学生納付特例事務法人制度は、学生が、学生納付特例の申請手続きをしやすくするために、学生の委託を受けた大学が、学生納付特例申請の代行を行う制度です。
学生納付特例事務法人の行う事務について条文で確認しましょう。
第109条の2の2第1項(学生納付特例の事務手続に関する特例) 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、学生納付特例申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において学生等被保険者の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。 |
★大学等の教育施設では、学生等被保険者に係る学生納付特例申請の代行ができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問1-A】
国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

【解答】
【問1-A】 ×
学生納付特例事務法人は、学生等被保険者の委託を受けて、学生納付特例申請の事務を行います。「保険料の納付」に関する事務は行うことができません。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

【解答】
【H27年出題】 〇
法第109条の2の2第2項で、「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなす。」と規定されています。
なお、第3項では、「学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。」とされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-078
R4.11.13 R4択一式より 基礎年金拠出金の額の算定基礎
厚生年金保険の実施者たる政府、実施機関たる共済組合等は、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担します。
条文を読んでみましょう。
第94条の2(基礎年金拠出金) ① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 |
次に「基礎年金拠出金」の額について条文を読んでみましょう。
第94条の3 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあっては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあっては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 |
 基礎年金拠出金の額は、「保険料・拠出金算定対象額」に「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を乗じて得た額となります。
基礎年金拠出金の額は、「保険料・拠出金算定対象額」に「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を乗じて得た額となります。
令和4年の問題をどうぞ!
【問8-C】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

【解答】
【問8-C】 ×
基礎年金拠出金の額は、「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を使って計算します。「被保険者の総数」には、第1号被保険者数も入りますが、その数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数」です。
「保険料全額免除期間」は入りません。保険料を全額又は一部納付している人が対象です。
(施行令第11条の3)
では、過去問もどうぞ!
①【R2年選択】
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
②【H23年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。
③【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

【解答】
①【R2年選択】
A 実施機関たる共済組合等
②【H23年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間と保険料一部免除期間を有する者が算入されます。除外されるのは、保険料を納付していない「保険料全額免除」及び「保険料未納者」です。
(施行令第11条の3)
③【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について
・第1号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者 → 20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者 → すべての者
となります。
第2号被保険者はすべての者ではなく年齢要件がありますので注意してください。
(施行令第11条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-077
R4.11.12 R4択一式より 老齢基礎年金の額に反映されない期間
老齢基礎年金の支給については、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上あることが条件です。
「学生の納付特例」の期間は、老齢基礎年金の額に反映されるでしょうか?それとも反映されないでしょうか?
まず、条文読んでみましょう。
第26条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
 「保険料免除期間」が2か所出てきます。
「保険料免除期間」が2か所出てきます。
1つめの保険料免除期間はかっこ書きで学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものが除かれています。
学生納付特例によって猶予された保険料については、老齢基礎年金の年金額の計算には反映しません。65歳で老齢基礎年金が支給されるのは、「保険料納付済期間」と「学生納付特例期間以外の保険料免除期間」を有する者だけですので注意してください。
しかし、2つ目の保険料免除期間についてはかっこ書きがありません。受給資格期間の10年には、学生納付特例期間も算入されるからです。
※「納付猶予」の期間も学生納付特例期間と同じように扱われます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-B】
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
【問8-B】 ×
学生納付特例の期間、納付猶予の期間のどちらも、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映しません。
(第26条、H26法附則第14条)
過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
②【R1年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

【解答】
①【H29年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料を追納すれば老齢基礎年金の額には反映しますが、追納しなければ老齢基礎年金の計算には入りません。
②【R1年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間だけで10年以上有している場合、どちらも老齢基礎年金の額には反映しませんので、65歳になっても老齢基礎年金は支給されません。
※なお、婚姻していて振替加算の要件に該当する場合は、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給される可能性があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-076
R4.11.11 R4択一式より 障害基礎年金の併合
障害基礎年金の受給権者に、さらに障害基礎年金の受給権が発生した場合は、前後の障害が併合されます。
条文を読んでみましょう。
第31条 (併給の調整) ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
★前後の障害が併合された場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅するのがポイントです。
では、併合の際、障害基礎年金のどちらかが支給停止されている場合の条文も読んでみましょう。
第32条 ① 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定(労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。)によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。 |
★①は前の障害基礎年金が支給停止されている場合、②は後の障害基礎年金が支給停止されている場合です。
片方が支給停止されている間は、併合しない障害基礎年金が支給されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】
【問5-A】 ×
「併合認定の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」の部分が誤りです。
新たに取得した障害基礎年金が障害補償による支給停止の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間は、併合した障害基礎年金ではなく、「従前の障害基礎年金」が支給されます。
過去問もどうぞ!
①【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する
②【H26年出題】
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。

【解答】
①【R1年出題】 〇
第31条の「併合の調整」の条文からの出題です。前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅するのがポイントです。
②【H26年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じていますので、第31条の併合の対象となります。精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択ではなく、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得します。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-075
R4.11.10 R4択一式より 「国年」脱退一時金の請求要件
日本国籍を有しない人が、国民年金の資格を喪失し日本国内に住所を有しなくなった場合、脱退一時金の請求ができます。
今日は脱退一時金の請求要件を確認しましょう。
まず条文を読んでみましょう。
法附則第9条の3の2第1項 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 日本国内に住所を有するとき。 2 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。 3 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 |
 脱退一時金の請求要件
脱退一時金の請求要件
・ 請求日の前日に、第1号被保険者としての被保険者期間に係る次の期間が6月以上あること(※任意加入被保険者・特例任意加入被保険者も含みます)
「保険料納付済期間の月数」+「保険料4分の1免除期間の月数×4分の3」+「保険料半額免除期間の月数×2分の1」+「保険料4分の3免除期間の月数×4分の1」
・ 国民年金の被保険者でないこと
・ 第26条ただし書に該当するもの(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと)
・ 日本国内に住所を有していないこと
・ 障害基礎年金などの受給権を有したことがないこと
・ 最後に公的年金の被保険者の資格を喪失した日から2年経過していないこと
(資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年経過していないこと)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-C】
脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。

【解答】
【問3-C】 〇
日本国内に住所を有する場合は、脱退一時金の請求はできません。
最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、請求することが条件です。
過去問もどうぞ!
①【R2年出題】
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金を受けることはできない。
②【H23年出題】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。
③【H30年出題】
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
日本国内に住所を有する場合は、脱退一時金は受けられません。
②【H23年出題】 ×
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「2年を経過」している場合は、脱退一時金は請求できません。
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「2年以内」に請求することが条件です。
③【H30年出題】 ×
「障害基礎年金の受給権を有したことがあるとき」は、脱退一時金は請求できません。障害基礎年金の受給権を有した場合は、たとえ障害基礎年金の支給を停止されていても、脱退一時金は請求できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-058
R4.10.24 R4択一式より 振替加算の額の計算
振替加算が行われるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日までの間に生まれた者です。
大正15年4月1日以前生まれの者は「旧法」の対象者で老齢基礎年金が支給されませんので、振替加算も行われません。
また、昭和41年4月2日以降生まれの者にも振替加算は行われません。昭和41年4月2日以降生まれの者は、新法施行日(昭和61年4月1日)に20歳未満です。
20歳から60歳まで会社員の被扶養配偶者だったとしても、すべて第3号被保険者となり満額の老齢基礎年金が支給されるからです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-A】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

【解答】
【問9-A】 ×
振替加算の額は、「受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となります。
なお、224,700円×改定率は、加給年金額と同じ額です。
「受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率」は、1.000から0.067までです。
生年月日が最も古い大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの率は、1.000ですので、振替加算の額は224,700円×改定率×1.000で加給年金額と同じです。
昭和36年4月2日から昭和41年4月1日以前生まれの率は、0.067です。
生年月日が若くなるほど、率が小さくなることがポイントです。20歳から60歳まで会社員に扶養される配偶者だった場合、若い人ほどカラ期間が短く、第3号被保険者期間が長くなるからです。
(S60年附則第14条)
過去問もどうぞ!
【H28年出題】
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

【解答】
【H28年出題】 ×
振替加算の額は、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-057
R4.10.23 R4択一式より 付加年金と死亡一時金の加算額の国庫負担
今日は、付加年金と死亡一時金の加算額の国庫負担の割合を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
S60年法附則第34条第1項第1号(国民年金事業に要する費用の負担の特例) 国庫は、当分の間、毎年度、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。 |
死亡一時金の額は、保険料納付済期間と保険料免除期間の月数に応じて、12万円から32万円で、付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である場合は、8500円が加算されます。
条文の「死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)」のかっこ書きは、「同法第52条の4第1項に定める額(12万円から32万円)の給付に要する費用を除く」となります。
この部分は、「死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用)」と読んでください。
令和4年の問題をどうぞ!
【問6-D】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

【解答】
【問6-D】 〇
「付加年金の給付に要する費用」と「付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用」の給付に要する費用については、4分の1を国庫が負担します。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。
②【H26年出題】
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。
③【H26年出題】
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の額の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
「付加年金」と「死亡一時金の加算額」に要する費用は、4分の1が国庫負担で賄われます。
②【H26年出題】 ×
付加年金の給付に要する費用については、その「4分の1」を国庫が負担します。
③【H26年出題】 〇
死亡一時金の額の加算額(付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合の加算額)の給付に要する費用については、その「4分の1」を国庫が負担します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-056
R4.10.22 R4択一式より 老齢基礎年金と付加年金
付加保険料は月額400円です。
付加保険料を納付した人には、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加年金も支給されます。
付加年金は、200円×付加保険料納付済期間の月数で計算します。
条文を読んでみましょう。
第43条 (支給要件) 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 (年金額) 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
第47条 (支給停止) 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
第48条 (失権) 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問3-A】
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
②【問3-E】
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

【解答】
①【問3-A】 〇
付加年金は老齢基礎年金とセットになる年金です。老齢基礎年金と老齢厚生年金を併給する場合は、付加年金も支給されます。
②【問3-E】 〇
障害基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金は支給停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されている間は付加年金も支給停止されます。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
②【H26年出題】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
③【H21年出題】
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

【解答】
①【H25年出題】 〇
付加年金は老齢基礎年金とセットです。付加年金の受給権は、老齢基礎年金と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。
②【H26年出題】 ×
老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給する場合も、老齢基礎年金が支給されているなら、付加年金も支給されます。
③【H21年出題】 ×
遺族基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金が支給停止されます。老齢基礎年金がその全額につき支給停止されているときは、その間、付加年金も支給停止になります。「遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。」の部分が誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-055
R4.10.21 R4択一式より 国民年金原簿の訂正の請求
もし、国の年金記録が事実と異なっているなら、正確な年金額が算定できません。年金記録が事実と異なると思われる場合は、国に年金記録の訂正を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
第14条(国民年金原簿) 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 |
第14条の2(訂正の請求) 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 |
附則第7条の5 (国民年金原簿の特例等) 第14条及び第14条の2の規定の適用については、当分の間、被保険者とあるのは、「第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものを除く。」とする。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問1-B】
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

【解答】
【問1-B】 〇
第14条の2の厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求については、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者であった期間は、除かれます。
過去問をどうぞ!
【R2年出題】
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

【解答】
【R2年出題】 〇
第2号被保険者のうち、国民年金原簿の記録の対象となる被保険者は、当分の間、第1号厚生年金被保険者のみです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-042
R4.10.8 R4択一式より 障害認定日の定義
障害基礎年金は、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件の3つの要件を満たした場合、障害認定日に受給権が発生します。
今日のテーマは障害認定日の定義です。
では、条文を読んでみましょう。
第30条 (支給要件) ① 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者であること。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
★障害基礎年金は、障害認定日に障害等級(1級及び2級)に該当する場合に支給されます。
障害認定日は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)」となります。
※ちなみに「初診日」は、「傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-C】
障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。

【解答】
【問10-C】 〇
障害認定日は、
・傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
・傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)
のどちらか早い方です。
障害認定日は遅くても「初診日から起算して1年6か月を経過した日」となります。
では、過去問もどうぞ!
①【H24年出題】
初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
②【H27年出題】
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
「その期間後に傷病が治った」の部分が誤りです。
「初診日から起算して、1年6か月を経過した日」又はその「期間内」に傷病が治った場合は、その治った日が障害認定日となります。
②【H27年出題】 〇
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日」も傷病が治った日として取り扱われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-041
R4.10.7 R4択一式より 第2号被保険者の20歳未満と60歳以上の取扱い
厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者として位置づけられています。
第1号被保険者と第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはその要件が無いのがポイントです。
今日のテーマは第2号被保険者の20歳未満と60歳以上の部分の扱いです。
では、条文で第2号被保険者の定義を読んでみましょう。
第7条・附則第3条 厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)は国民年金の第2号被保険者とする。 |
 第2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、厚生年金保険の被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の第2号被保険者となります。
第2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、厚生年金保険の被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の第2号被保険者となります。
ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金・老齢厚生年金など「老齢又は退職を支給事由とする年金」の受給権がある場合は、第2号被保険者から除かれます。
では、次に「老齢基礎年金」の保険料納付済期間の定義を条文で読んでみましょう。
昭和60年改正法附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。
|
 老齢基礎年金の年金額の計算は、第1号被保険者の年齢に合わせて20歳以上60歳未満の40年間が基本になります。
老齢基礎年金の年金額の計算は、第1号被保険者の年齢に合わせて20歳以上60歳未満の40年間が基本になります。
そのため厚生年金保険の被保険者の20歳未満60歳以上の期間は合算対象期間として取り扱われ、保険料納付済期間には算入されません。
※ただし、老齢厚生年金の計算には算入されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間とされ、老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
【問8-A】 ×
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者ですが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」とされますので、老齢基礎年金の額には反映されません。
では、こちらもどうぞ!
【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
【H24年出題】 ×
障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も保険料納付済期間となります。
フルペンション減額方式をとっている老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年が基本になっていますが、障害基礎年金は、フルペンション減額方式をとっていないためです。
なお、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-040
R4.10.6 R4択一式より 遺族基礎年金18歳年度末までに障害状態になったとき
遺族基礎年金の対象になる子の要件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」です。
遺族基礎年金の受給権を取得した当時は障害状態になかった子が、18歳年度末までに障害状態になった場合、その子の遺族基礎年金の受給権は18歳年度末で消滅するのでしょうか?それとも20歳まで受給できるのでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第40条第3項 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 2 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 3 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 4 20歳に達したとき。 |
今日は「2」の「ただし以下」に注目してください。
子の遺族基礎年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。ただし、「障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。」とありますので、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態」にあるときは、その時点では失権しません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-A】
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

【解答】
【問6-A】 〇
遺族基礎年金の受給権取得時には障害の状態になかった子が、その後18歳年度末までの間に障害の状態となり引き続き障害の状態にある場合は、18歳年度末時点では失権しません。
先ほど読んだ条文では、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態」あるときは失権しない、となっていました。受給権取得当時に障害状態になくても、18歳年度末に障害状態にある場合は、引き続き遺族基礎年金を受給できます。
問題文のように、「子が20歳に達するまでの間障害の状態にあった」ときは、20歳になったときに失権します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-038
R4.10.5 R4択一式より『障害基礎年金に加算される加算額』
障害基礎年金の受給権者に子がいる場合は、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。
今日のテーマは、障害基礎年金に加算される加算額です。
では、条文を読んでみましょう。
第33条の2 ① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ 224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、その額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |

障害基礎年金の加算の対象は「子」です。
配偶者については、1・2級の障害厚生年金の加給年金額の対象になります。

受給権を取得した当時に生計維持している子はもちろん加算額の対象ですが、受給権を取得した日後に有するに至った子も加算額の対象になります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

【解答】
【問5-B】 ×
配偶者は、障害基礎年金の加算額の対象ではありません。
それでは過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
②【H21年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。

【解答】
①【H25年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が受給権を取得した後に一定の要件に該当する子を有することとなった場合でも、その子を対象とした加算額が加算されます。その場合、子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。
②【H21年出題】 ×
障害基礎年金に加算される子の加算額は、1人目2人目はそれぞれ224,700円×改定率、3人目以降はそれぞれ74,900円×改定率となります。
例えば、子が1人なら224,700円×改定率、子が2人なら224,700円×改定率×2、子が3人なら224,700円×改定率×2+74,900円×改定率となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(国民年金法)
令和4年基本問題(国民年金法)
R5-028
R4.9.25 R4択一式より『寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金』
今日のテーマは、寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金の関係です。
寡婦年金は、60歳から65歳までの有期年金です。
受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した場合、寡婦年金の受給権はどうなるでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第51条・附則第9条の2 寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ・ 65歳に達したとき ・ 死亡したとき。 ・ 婚姻をしたとき。 ・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 ・ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき。 |
寡婦年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金を繰上げ受給したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。「選択」や「支給停止」ではないことがポイントです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【R4問7-E】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

【解答】
【R4問7-E】 ×
受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
過去問もどうぞ!
①【H23年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止される。
②【H29年出題】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金のどちらかを受給することができる。

【解答】
①【H23年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止されるではなく「受給権が消滅」します。
②【H29年出題】 ×
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者には、寡婦年金は支給されません。
(法附則第9条の2の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(国民年金法)
令和4年択一式を解いてみる(国民年金法)
R5-019
R4.9.16 R4「国年択一」は基本問題中心。今日は『遺族基礎年金の支給要件』
令和4年の国民年金法の択一式は、基本問題が中心でした。
厚生年金保険法の択一式と同様、テキストと過去問学習が役立ったと思います。
テキストと過去問の繰り返しが大切です。
今日は「遺族基礎年金の支給要件」の問題を見てみましょう。
まずは、条文を読んでみましょう。
第37条 (支給要件) 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ※令和8年4月1日前に死亡した者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは保険料納付要件を満たす。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。(S60年改正法附則第20条第2項) 1被保険者が、死亡したとき。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。 3老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 4保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
ポイント!保険料納付要件
★1と2(短期要件)は、保険料納付要件が問われます。
被保険者期間中の滞納期間が3分の1未満であることが原則です。しかし、死亡日に65歳以上である場合を除き、令和8年4月1日前の死亡については、死亡日の直近1年間のうちに滞納期間がなければ、要件を満たします。
★3と4(長期要件)は死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問5-C】
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。
②【問10-B】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。

【解答】
①【問5-C】 〇
長期要件は、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」です。
この場合、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年に満たない場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と「合算対象期間」を合算して25年以上あれば、要件を満たします。「合算対象期間」も合算できることがポイントです。
(S60年改正法附則第12条)
②【問10-B】 ×
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が25年以上ある第1号被保険者が死亡した場合は、4の長期要件を満たしますので、死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合でも影響はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑨
復習しましょう/令和4年選択式⑨
R5-009
R4.9.6 令和4年「国年選択」は条文の穴埋めでした
令和4年の国民年金の選択式は、条文の穴埋め問題でした。
 障害基礎年金の支給停止について
障害基礎年金の支給停止について
第36条第2項からの出題です。
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 |
障害の状態が軽快し障害等級(1・2級)に該当しなくなったときは、「その障害の状態に該当しない間」は、障害基礎年金の支給が停止になります。
 寡婦年金の額について
寡婦年金の額について
第50条からの出題です。
| 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
寡婦年金の額は、「第1号被保険者」の期間を基礎として計算した「老齢基礎年金」の額の4分の3です。
 国民年金基金の業務について
国民年金基金の業務について
第128条からの出題です。
1 基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 2 基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。 |
基金は、①年金の支給を行う、②死亡一時金の支給を行う、③福祉施設をすることができるとされています。
「福祉を増進する」が問われました。
 被保険者に対する情報の提供について
被保険者に対する情報の提供について
第14条の5からの出題です。
| 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。 |
択一式で何度か出題されています。通知は、受給権者に対しではなく「被保険者に対し」ての部分がポイントです。
「ねんきん定期便」の根拠になっている条文です。
「理解を増進させ、及びその信頼を向上させる」、「分かりやすい形で通知」が問われました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-364
R4.8.21 選択対策・付加保険料
第1号被保険者は、毎月の保険料にプラスして付加保険料を納付することができます。
穴埋め式で、条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
第87条の2 1 第1号被保険者(法定免除、申請全額免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の< A >以後の各月につき、毎月の保険料のほか、< B >円の付加保険料を納付する者となることができる。 2 付加保険料の納付は、毎月の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 3 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の< C >以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 4 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その< D >日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなす。 |

【解答】
A 属する月
B 400
C 属する月の前月
D 加入員となった
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
②【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
③【R1年出題】
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
④【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
⑤【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
⑥【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
半額免除を受けている期間は、付加保険料は納付できません。
※ 法定免除、申請全額免除、一部免除、学生納付特例・納付猶予の規定で保険料を納付することを要しないものとされている者は、付加保険料は納付できません。
②【H26年出題】 ×
追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月は、付加保険料は納付できません。
③【R1年出題】 ×
「産前産後期間の保険料免除」を受けた月については、付加保険料を納付することができます。
④【H30年出題】 ×
付加保険料を納付する者でなくなるのは、その申し出をした日の属する月の「前月」以後の各月です。
⑤【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は、付加保険料を納めることができないからです。
⑥【R2年出題】 〇
任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができます。
※ちなみに、特例の任意加入被保険者は、付加保険料を納付できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-354
R4.8.11 国民年金の保険料前納
令和4年度の国民年金の保険料は16,590円です。
国民年金の保険料には、前納制度があり、割引があるのがポイントです。
条文を読んでみましょう。
第93条 (保険料の前納) 1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
令第7条 (保険料の前納期間) 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。 令第8条 (前納の際の控除額) 政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)を控除した額とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。
②【H26年出題】
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。
③【H27年出題】
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる
④【H28年出題】
国民年金保険料を1年分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。
⑤【H21年出題】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
⑥【H30年出題】
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
一部免除の保険料も前納することができます。
②【H26年出題】 〇
前納の期間の原則は、「6か月」単位又は「年」単位ですが、「6か月」又は「年」以外の単位の前納も可能です。
③【H27年出題】 〇
2年間の前納は、口座振替でも可能ですが、納付書による現金納付、クレジットカードでも可能です。
④【H28年出題】 ×
1年分前納する場合、割引率が高いのは、口座振替による支払の方です。
⑤【H21年出題】 〇
「年4分の利率による複利現価法」を覚えておきましょう。
⑥【H30年出題】 ×
前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
健康保険の任意継続被保険者の前納との違いをおさえてください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年度の年金額改定
令和4年度の年金額改定
R4-346
R4.8.3 令和4年度年金額・物価変動率と名目手取り賃金変動率
まず、問題からどうぞ!
令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、< A >に従い改定されました。
< A >がマイナス0.4%となり、かつ< B >(マイナス0.2%)を下回るため、< A >を用いて改定されます。
また、< A >がマイナスのため、< C >(マイナス0.3%)による調整は行われませんが、翌年度以降の年金額改定時に繰り越されます。
【選択肢】
① 物価変動率
② マクロ経済スライド調整率
③ 名目手取り賃金変動率

【解答】
A ③ 名目手取り賃金変動率
B ① 物価変動率
C ② マクロ経済スライド調整率
 既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額は、原則として「物価変動率」に応じて改定されます。
既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額は、原則として「物価変動率」に応じて改定されます。
しかし、例外的に次の3つのパターンのどれかに当てはまる場合は、「名目手取り賃金変動率」を用いて改定します。
物価 | 賃金 |
| 物価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| 賃金 |
| 物価 | 賃金 |
① ② ③
物価も賃金もプラス 物価がプラス 物価も賃金もマイナス
物価の方が伸びが大きい 賃金がマイナス 賃金の方が落込みが大きい
 令和4年度は、名目手取り賃金変動率も物価変動率もマイナスで、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っています。(上の図の③に当てはまります。)
令和4年度は、名目手取り賃金変動率も物価変動率もマイナスで、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っています。(上の図の③に当てはまります。)
そのため、新規裁定年金、既裁定年金ともに「名目手取り賃金変動率(▲0.4%)」を用いて改定されました。
また、賃金や物価による改定率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
 老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率で計算します。
老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率で計算します。
令和3年度の改定率が1.000でしたので、
令和4年度の改定率は、1.000×0.996=0.996となります。
令和4年度の老齢基礎年金の額は、
780,900円×0.996 ≒ 77万7,800円となります。
※端数処理は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-331
R4.7.19 寡婦年金と死亡一時金の調整
寡婦年金と死亡一時金の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 (支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
★ 死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、「その者の選択」によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
①【H18年出題】 〇
「死亡一時金」と「寡婦年金」はその者の選択によりどちらか一つを受給できます。
★ 寡婦年金は、60歳から65歳までの有期年金ですので、妻の年齢によっては数か月しか受給できないこともあり得ます。その場合は、死亡一時金の方が受給額が多い可能性もあります。そのような理由から選択制になっています。
★寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に取得した者が、法52条の6により寡婦年金を選択した場合には、死亡一時金の受給権は消滅します。(S50.4.26庁文発1249)
②【H24年出題】 ×
死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、その者の選択により、どちらか一つが支給されます。
もう一問どうぞ!
③【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
③【R3年出題】 〇
同時に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった場合の調整の問題です。
ポイント!
「一人一年金の原則」により → 遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択
「寡婦年金と死亡一時金」 → 受給権者の選択によりどちらか一つを選択
寡婦年金を選択した場合 → 死亡一時金は支給されません。
遺族厚生年金を選択した場合 → 遺族厚生年金と死亡一時金の両方が受給できます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-330
R4.7.18 死亡一時金の額
死亡一時金の額は、保険料を納付した月数によって決まります。
条文を読んでみましょう。
第52条の4 (死亡一時金の額) ① 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。
② 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。
②【R2年出題】
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
①【H26年出題】 ×
死亡一時金の額が32万円になるのは、420か月以上ある場合です。
②【R2年出題】 〇
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月の場合の死亡一時金は120,000円です。また、付加保険料を納付した期間が36月(3年)あるので、8,500円が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-329
R4.7.17 死亡一時金の遺族の範囲と順位
死亡一時金の遺族の範囲を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第52条の3 ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、第52条の2第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第52条の2 第3項 死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
|
死亡一時金を受けることができる遺族の順序は、①配偶者、②子、③父母、④孫、 ⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
②【H27年出題】
死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
三親等内の親族は、死亡一時金を受けることができる遺族に入りません。
②【H27年出題】 〇
下の図も参考にしてください。
夫が死亡した後、子が遺族基礎年金の受給権を取得したものの、その子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、遺族基礎年金が支給停止されている場合の死亡一時金の支給についての問題で、第52条の2第3項に該当します。
第52条の3第1項ただし書きで、「第52条の2第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」となっています。
上記の場合は、死亡した者の配偶者であってその者と生計を同じくしていた者(後妻)が死亡一時金を受けることになります。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
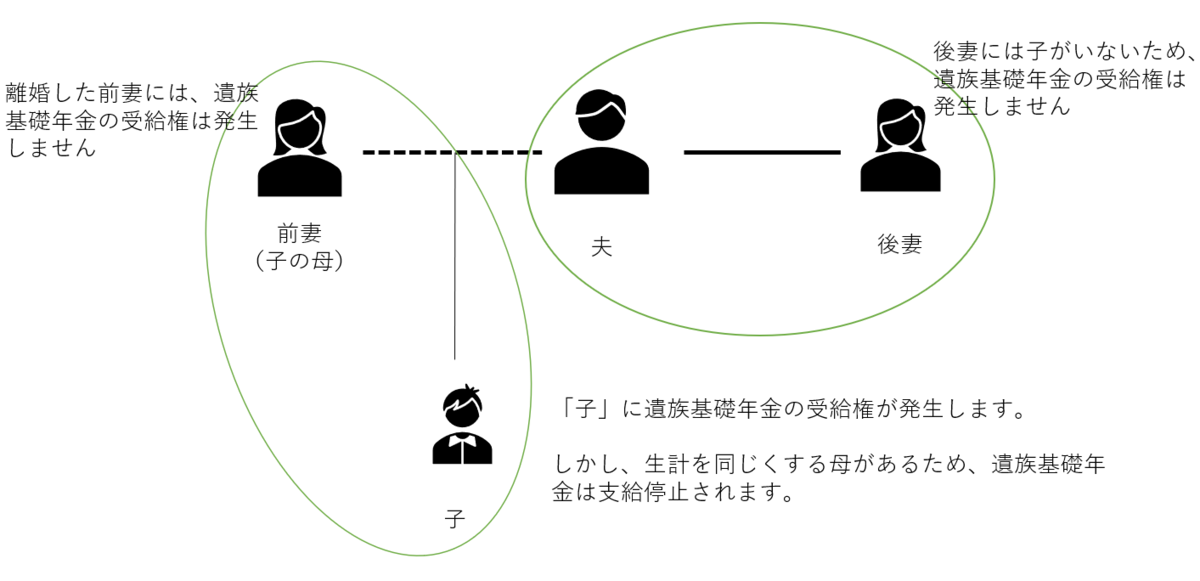
 国民年金法
国民年金法
R4-328
R4.7.16 死亡一時金が支給されないとき
死亡一時金が支給されない場合を見ていきましょう。
さっそく条文を読んでみましょう。
第52条の2 ① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 ② ①項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 2 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |
ポイント! 「受けたことがある者」
老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を「受けたことがある者」が死亡したときは、死亡一時金は支給されません。
例えば、老齢基礎年金を受ける権利があったとしても、老齢基礎年金を受けないまま死亡した場合は、死亡一時金の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも支給される。
②【H28年出題】
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
③【R2年出題】
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
死亡一時金は、「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者」が死亡した場合は支給されません。
また、遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として死亡一時金は支給されません。
ちなみに、同一人物の死亡によって寡婦年金と遺族基礎年金の両方の受給権が発生することはあり得ます。しかし両方とも受給できるわけではなく、一人一年金の原則が適用されますので、どちらかの年金を選択して受給することになります。
②【H28年出題】 ×
死亡した人が遺族基礎年金の支給を受けたことがあったとしても、死亡一時金の支給要件には影響しません。
③【R2年出題】 ×
同一の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給しないこととなっています。
ただし、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給されます。
例えば、子が18歳に達した日の属する年度の年度末(3月)に父が死亡した場合、遺族基礎年金の受給権はその3月に発生しますが、実際、遺族基礎年金は支給されません。
このように死亡と同じ月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-327
R4.7.15 死亡一時金の支給要件
国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納付した人が死亡した場合、一定の遺族に対して死亡一時金が支給されます。
老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがない人が死亡したことが条件で、保険料の掛け捨てを防止することを趣旨としています。
条文を読んでみましょう。
第52条の2 (支給要件) 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 |
ポイント!
★36月の数え方
「保険料納付済期間の月数」、「4分の1免除期間の月数の4分の3」、「半額免除期間の月数の2分の1」、「4分の3免除期間の月数の4分の1」を合算します。
「保険料全額免除期間」は計算に入りません。保険料の負担が全くないからです。
死亡日の属する月の前月まで
前々月ではなく「前月」までの月数で計算します。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
②【H27年出題】
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】
①【H24年出題】 ×
「保険料全額免除期間」は36月の計算に入りません。
②【H27年出題】 〇
65歳以上の特例による任意加入被保険者も、死亡一時金の対象になります。
★「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。
しかし、「付加保険料の納付」と「寡婦年金」は「特例による任意加入被保険者」には適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-326
R4.7.14 老齢基礎年金の繰上げ繰下げと振替加算
老齢基礎年金は、繰上げて受給することもできますし、繰下げて受給することもできます。
その際、振替加算はどうなるのか確認しましょう。
今日は過去問からどうぞ!
①【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
②【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
③【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
④【R3年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
ポイント! 老齢基礎年金の繰上げの請求をしても、振替加算は繰上げされません。振替加算は65歳から支給されます。
60歳 65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
例えば、60歳から老齢基礎年金を繰上げ請求しても、振替加算は65歳からです。
②【H30年出題】 ×
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても振替加算は繰上げされませんので、振替加算は「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「65歳に達した日の属する月の翌月」から加算されます。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、問題文の通り、「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます。
65歳 68歳
| 振替加算 |
| 繰下げ支給の老齢基礎年金 |
③【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額には繰下げ増額はありません。
④【R3年出題】 〇
振替加算のポイント
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合 → 振替加算は繰上げされず65歳から
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合 → 振替加算も繰下げて支給される。ただし、振替加算額には繰下げによる増額はありません。
厚生年金保険の「加給年金額」もチェックしましょう。
例えば、加給年金額の加算の対象になっている配偶者が、老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は、加給年金額はどうなるのでしょう?
⑤【厚生年金保険法H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
⑤【厚生年金保険法H28年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は配偶者が65歳に達するまで支給されます。
★例えば、妻が夫の受給する老齢厚生年金の加給年金額の対象になっている場合で、妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合
・妻が65歳に達するまで、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます
・妻が65歳に達すると、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-325
R4.7.13 法定免除の期間など
昨日の続きで、法定免除を見ていきます。
もう一度、条文を読んでみましょう。
第89条 1 被保険者(産前産後免除及び保険料の一部免除の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 ② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ③ 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定するもの)に入所しているとき。 2 1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、1項の規定は適用しない。 |
★免除される期間
「要件に該当するに至った日の属する月の前月」から「これに該当しなくなる日の属する月」までの期間です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※法改正による修正あり
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
②【H26年出題】
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
③【R2年出題】
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
免除される期間は、その該当するに至った日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する「月」までの期間です。
例えば、令和4年7月13日に免除事由に該当した場合は、6月から免除されます。
6月分の保険料の納期限は7月末日です。免除事由に該当している7月末に納期限がくる6月分から免除される仕組みです。
②【H26年出題】 〇
法第89条第2項では、法定免除事由に該当していても、本人から保険料を納付する旨の申出があったときは、申出のあった期間に係る保険料に限って納付することができることを規定しています。
<法定免除に該当していても申出によって保険料が納付できる理由は?>
・法定免除の期間は、老齢基礎年金の計算の際に減額されるので。
・追納することもできますが、10年以内という期限があることと、10年以内でも一定期間を過ぎると加算が行われるので。
③【R2年出題】 〇
法定免除事由に該当した場合は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出する必要があります。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、提出は不要です。
(則第75条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-298
R4.6.16 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の資格喪失
任意加入被保険者は、強制ではなく本人の申出により「任意」で加入している関係上、保険料を滞納した場合は、その資格を喪失します。
では、「保険料を滞納した場合の喪失」について、条文で確認しましょう。
任意加入被保険者の種類(法附則第5条第1項) ① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) ② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) ③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
法附則第5条第5項 ①と②について 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その指定期限の翌日に資格を喪失する。 ③について 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、2年間が経過した日の翌日に資格を喪失する。 |
 ポイント!
ポイント!
①と②は「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者、③は「日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者です。滞納した場合の喪失日の違いに注意しましょう。
滞納した場合の扱いは、特例による任意加入被保険者も同じです。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
②【H29年出題】
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
③【H22年出題】
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「日本国内に住所を有する」の部分がポイントです。
督促状で指定した期限の「翌日」の部分もポイントです。当日ではありませんので、注意してください。
②【H29年出題】 ×
「日本国内に住所を有する」ので、資格の喪失は、「督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その指定期限の翌日」です。
③【H22年出題】 ×
「日本国内に住所を有しない」の部分がポイントです。
「2年経過した日」ではなく、2年間が経過した日の「翌日」に被保険者資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-297
R4.6.15 任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違い
任意加入被保険者も特例による任意加入被保険者も、第1号被保険者と同じように保険料を納付します。
しかし、付加保険料、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金については注意が必要です。
 「任意加入被保険者」は、「付加保険料の納付」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「脱退一時金」については、第1号被保険者と同じように扱われます。
「任意加入被保険者」は、「付加保険料の納付」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「脱退一時金」については、第1号被保険者と同じように扱われます。
(法附則第5条第9項)
 「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。
「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。
しかし、「付加保険料の納付」と「寡婦年金」は「特例による任意加入被保険者」には適用されません。
特例による任意加入の目的は増やすことではなく受給権を得るためです。老齢基礎年金の上乗せになる付加保険料の納付ができないのは、そのためです。
保険料の掛け捨てを防止する趣旨である死亡一時金と脱退一時金は、特例による任意加入被保険者にも適用されます。
(H16法附則第23条第10項)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
②【H23年出題】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
③【H27年出題】
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
④【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
⑤【R2年出題】
60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができ、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者として扱われます。
②【H23年出題】 ×
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、「死亡一時金」と「脱退一時金」の給付については、第1号被保険者として扱われますが、「寡婦年金」については適用されません。
③【H27年出題】 〇
死亡一時金については、特例による任意加入被保険者は第1号被保険者として扱われますので、支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給されます。
④【R2年出題】 〇
任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができます。ただし、特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することはできません。
⑤【R2年出題】 ×
付加保険料の部分が誤りです。特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付できません。
なお、任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、65歳に達した日に、老齢基礎年金の受給権を有していない場合は、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-296
R4.6.14 任意加入被保険者と口座振替
任意加入被保険者は、年金の受給権確保等のため、月々の保険料を確実に納付する必要があります。そのため、口座振替による保険料納付が原則となっています。
よく出題されていますので、確認していきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
法附則第5条 (任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①の第1号又は第2号に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 |
ポイント!
第1号又は第2号(日本国内に住所を有する者)が、任意加入の申出を行う場合は、「口座振替納付を希望する」旨の申出又は「口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨」の申出が必要です。
★特例による任意加入被保険者も同じです。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
②【H28年出題】
日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。
③【H21年出題】
国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者の保険料の納付は、口座振替納付が原則となります。任意加入の申出を行おうとする者は、「口座振替納付を希望する旨」又は「口座振替納付によらない正当な事由に該当する旨」の申出をしなければなりません。
なお、この規定が適用されるのは、「日本国内に住所を有する」ものです。
②【H28年出題】 〇
「口座振替納付によらない正当な事由がある場合」は、則第2条の2で以下のように定められています。
①申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
②資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
③その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
問題文は②に該当しますので、口座振替によらないことができます。
(則第2条の2)
③【H21年出題】 ×
「日本国内に住所を有しない」ものは、口座振替納付を希望する旨の申出は要りません。(法附則第5条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-295
R4.6.13 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
前回は、「任意加入被保険者」のお話をしましたが、今回のテーマは「特例による任意加入被保険者」です。
任意加入被保険者との違いをおさえましょう。
まず、「特例による任意加入被保険者」の条文を読んでみましょう。
H6法附則第11条、H16法附則第23条 (任意加入被保険者の特例) 昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。 ただし、その者が老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。 1 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
 特例による任意加入被保険者のポイント!
特例による任意加入被保険者のポイント!
要件に該当すれば65歳から70歳まで特例で任意加入が認められます。ただし、「昭和40年4月1日以前生まれ」に限定されています。また、老齢基礎年金等の受給権を有する者は特例の任意加入はできません。目的は老齢基礎年金の受給権を得ること。増やす目的では、特例の任意加入はできません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
②【H27年出題】
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
③【R3年出題】
昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

【解答】
①【H21年出題】 ×
日本国内に住所を有しなくても、日本国籍を有する65歳以上70歳未満のものは、特例の任意加入が認められています。ただし、昭和40年4月1日以前生まれに限られます。
②【H27年出題】 ×
特例による任意加入被保険者になることができるのは、昭和40年4月1日以前生まれの場合に限られます。ちなみに、昭和30年4月1日以前生まれの場合でも、もちろん、特例の任意加入被保険者になることはできます。
③【R3年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有する場合でも、特例による任意加入被保険者となることができます。障害基礎年金は、障害の状態によっては、支給停止や失権の可能性があるからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-294
R4.6.12 任意加入被保険者の加入要件
国民年金法には、「任意加入被保険者」、「特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)」として、任意に国民年金に加入できる制度があります。
任意加入の目的は2つです。
 1つめ 老齢基礎年金を増やす
1つめ 老齢基礎年金を増やす
65歳からの老齢基礎年金を満額受給するためには、20歳から60歳までの40年間(480月)すべて保険料納付済期間であることが必要です。
免除や滞納などで満額に満たない人は、任意加入して、老齢基礎年金を増やすことができます。
 2つめ 老齢基礎年金の受給権を得る
2つめ 老齢基礎年金の受給権を得る
また、老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上必要です。その期間に足りない場合は、受給権を得るために任意加入することができます。
「任意加入被保険者」は、1つ目、2つ目どちらの目的でも任意加入できます。
一方、「特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)」は、2つ目の「老齢基礎年金の受給権を得る」目的に限定されます。1つめの「老齢基礎年金を増やす」目的では加入できませんので注意しましょう。
今回のテーマは「任意加入被保険者」の加入要件です。
まず、条文を読んでみましょう。
第5条 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
 1~3の人は第1号被保険者の要件に当てはまりません。しかし、厚生労働大臣に申し出て任意加入することができます。ただし、第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できません。(任意加入する必要もないためです)
1~3の人は第1号被保険者の要件に当てはまりません。しかし、厚生労働大臣に申し出て任意加入することができます。ただし、第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できません。(任意加入する必要もないためです)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
②【H29年出題】
60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。
③【R2年出題】
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
「日本国内に住所を有する」60歳以上65歳未満の者は、国籍を問わず任意加入することができます。
なお、「日本国内に住所を有しない」20歳以上65歳未満の者が任意加入する場合は、「日本国籍を有する者」に限られます。
②【H29年出題】 〇
「老齢基礎年金の繰上げ請求」を行った者は、国民年金の任意加入被保険者になることはできません。既に繰り上げて受給している老齢基礎年金を増やすことができないからです。
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、国民年金の任意加入被保険者となって、65歳以降の老齢基礎年金を増やすことができます。
(法附則第9条の2の3)
③【R2年出題】 ×
日本国籍を有していれば、日本国内に住所を有していなくても、任意加入被保険者の申出をすることができます。
なお、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中でも任意加入被保険者になることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-274
R4.5.23 国年の第2号被保険者
国民年金の強制加入被保険者として、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つがあります。
今回は、第2号被保険者がテーマです。
条文を読んでみましょう。
第7条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者とする。 法附則第3条 (被保険者の資格の特例) 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。 |
ポイント!
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。
年齢要件や国内居住要件がないのがポイントです。
ただし、厚生年金保険の被保険者で65歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権がある者は、第2号被保険者となりません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②【H26年出題】(改正による修正あり)
65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
③【H27年出題】
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
第1号被保険者と第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」という年齢要件がありますが、第2号被保険者には年齢要件はありません。
厚生年金保険の被保険者であれば20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者となります。
②【H26年出題】(改正による修正あり) ×
65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権」を有していなければ、第2号被保険者となります。
「障害」を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、「老齢又は退職」を支給事由とする年金給付の受給権を有していなければ、第2号被保険者となります。
③【H27年出題】 〇
第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが条件です。
問題文の場合、厚生年金保険の被保険者ではありますが、65歳以上でかつ「厚生年金保険の在職老齢年金を受給中=(老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有する)」ですので、第2号被保険者にはなりません。
そのため、その者の配偶者は第3号被保険者とはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-256
R4.5.5 保険料納付済期間の定義
国民年金の給付の要件の1つに保険料納付要件があります。保険料納付要件をみるときに登場するのは「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」ですが、今回は「保険料納付済期間」の定義です。
条文を読んでみましょう。
第5条 国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
<国民年金法の保険料納付済期間>
以下の期間を合算した期間です。
↓
・第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定(督促及び滞納処分)により徴収された保険料を含む、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは除く)に係るもの及び産前産後期間中の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの
+
・第2号被保険者としての被保険者期間
+
・第3号被保険者としての被保険者期間
※国民年金に保険料を納付する義務があるのは、第1号被保険者です。第2号被保険者と第3号被保険者は、個別に国民年金に保険料を納付する義務はありません。
そのため、国民年金の保険料の滞納があり得るのは第1号被保険者のみです。第2号被保険者と第3号被保険者には「滞納」があり得ないので、被保険者期間がそのまま「保険料納付済期間」となりますが、第1号被保険者は保険料を納付した期間が保険料納付済期間となります。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
②【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
③【H24年出題】
保険料全額免除期間を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
④【R2年出題】
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

【解答】
①【H24年出題】 〇
保険料を滞納し、督促及び滞納処分を受け、それによって保険料を納付した場合は、「保険料納付済期間」となります。
②【H24年出題】 〇
例えば、4分の3免除を受けた場合は、保険料の4分の3は免除されますが、残りの4分の1は納付する義務があります。4分の3免除の規定により、その4分の1が納付された期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料4分の3免除期間」です。
③【H24年出題】 〇
保険料を追納した期間は、「保険料納付済期間」です。
④【R2年出題】 ×
産前産後期間の保険料免除期間は、全額免除期間ではなく「保険料納付済期間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-237
R4.4.16 免除の所得要件
申請全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例、納付猶予を受けるには、所得要件があります。
今回は、免除の所得要件を確認します。
保険料免除の所得基準は以下の通りです。
申請全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
学生納付特例 | 128万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人のみ |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 本人・配偶者 |
・ 「88万円」だけ覚えてください。40ずつ増えます。+40で「128万円」、+40で「168万円」です。
・ 学生納付特例は半額免除の基準と同額、納付猶予は全額免除の基準と同額です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が168万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。
②【H26年出題】 ※改正による修正あり
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
③【H29年選択】※改正による修正あり
国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が< A >に扶養親族等1人につき< B >を加算した額以下のときとされている。
なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
④【H24年出題】
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
⑤【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇 ※改正による修正あり
扶養親族等がいない場合は、4分の1免除の所得基準は、168万円以下です。
(令第6条の9の2)
②【H26年出題】 〇 ※改正による修正あり
全額免除の所得基準は、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円です。当てはめて計算すると、(4+1)×35万円+32万円=207万円です。207万円以下であれば、全額免除の対象です。
(令6条の7)
③【H29年選択】※改正による修正あり
半額免除の所得基準の問題です。
A128万円
B38万円
※扶養親族1人当たりの加算額は38万円が原則です。同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等の場合は、加算額が変わります。
④【H24年出題】 ×
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、本人・世帯主・配偶者がそれぞれ免除事由に該当することが必要です。
⑤【H28年出題】 〇
学生納付特例は、本人の所得のみで判断します。世帯主、配偶者の所得は関係ありません。
なお、納付猶予は、本人と配偶者がそれぞれ免除事由に該当することが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-220
R4.3.30 障害基礎年金の支給要件「保険料納付要件」
障害基礎年金の3要件は「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」です。
今日は、「保険料納付要件」を確認しましょう。
条文を読んでみましょう
第30条 (障害基礎年金の保険料納付要件) 当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
昭和60年附則第20条 (障害基礎年金の支給要件の特例) 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは保険料納付要件を満たす。 ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。 |
 ポイント!
ポイント!
・ 保険料納付要件を見るのは「初診日の前日」
→ 初めて病院に行った日(初診日)に保険料を納付しても間に合わない
・ 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が全体の3分の2以上あること
・ 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないものは、滞納には当たらな い(加入直後の障害の場合)
・ 初診日が令和8年4月1日前にある場合の特例
→ 直近の1年間に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」=「1年間のすべてが保険料納付済期間と保険料免除期間(滞納がない)」場合は納付要件を満たす。(ただし、初診日に65歳以上の場合は、特例は適用しない)
例えば、令和3年1月に国民年金の資格を取得し、初診日が令和4年3月30日の場合は、保険料納付要件は令和4年1月までを見ます。
令和3年1月 |
|
|
|
|
| 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
資格取得月 |
|
|
|
|
| 保険料 納期限 2月末 | 保険料 納期限 3月末 | 初診日の 属する月 |
保険料の納期限がきている1月分までの納付状況で判断します。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。
②【H22年出題】
初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。
③【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
保険料納付要件の特例のポイント!
・初診日が令和8年4月1日前にある
・直近の1年間に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない」こと。=直近の1年間に滞納期間がないこと
・初診日に65歳未満であること
②【H22年出題】 ×
保険料納付要件は「初診日の属する月の前々月までの1年間」でみますので、初診日が平成22年8月30日の場合は、平成22年「6」月分までの1年間のうちに保険料の滞納がないことが条件です。また、初診日に65歳未満であることも必要です。
③【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳前の期間及び60歳以降の期間」は、老齢基礎年金では、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、年金額の計算には入りません。
しかし、「障害基礎年金」については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳前の期間及び60歳以降の期間」も保険料納付済期間に入ります。
また、老齢基礎年金はフルペンション減額方式ですので、40年間すべて保険料納付済期間の場合は満額受給できますが、免除、合算対象期間、滞納があるとその分、減額されます。
一方、障害基礎年金の額は、加入期間などに関係なく定額で支給されます。
ちなみに、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-219
R4.3.29 障害基礎年金の支給要件「障害認定日」
「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」が障害基礎年金支給の3要件です。
要件を満たした場合は、障害認定日に受給権が発生します。
今日は「障害認定日」を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第30条 (障害基礎年金の支給要件) 1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
障害認定日に1級、2級に該当する程度の障害状態にあると判定された場合は、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。
「障害認定日」は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日となります。なお、治った日には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も含まれます。
なお、障害認定日に障害の状態に該当しない場合は、障害基礎年金の受給権は発生しません。
しかし、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害状態に該当した場合は、「事後重症の障害基礎年金」を請求することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
②【H27年出題】
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
③【R1年出題】
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。
④【H29年出題】
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
『その期間後に傷病が治った場合』ではなく、『その期間「内」にその傷病が治った場合』です。障害認定日は、最長で「初診日から起算して、1年6か月を経過した日」で、その前に治った場合はその治った日が障害認定日になります。
②【H27年出題】 〇
初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となりますが、治っていない場合でも症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も障害認定日として取り扱われます。
③【R1年出題】 〇
・通常の障害基礎年金(第30条第1項)
→ 障害認定日に受給権が発生します
・事後重症による障害基礎年金(第30条の2第1項)
→ 支給の請求をした日に受給権が発生します
④【H29年出題】 ×
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」と規定されています。
施行令4条の6及び別表で障害等級表が定められていて、その中に精神の障害も載っています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-218
R4.3.28 障害基礎年金の支給要件「初診日」
障害基礎年金には、「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」の3つの支給要件があります。
今日は「初診日」要件を確認しましょう。
まず条文を読んでみましょう。
第30条 (障害基礎年金の支給要件) 1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
|
★「初診日」とは、『傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日』のことです。
「初診日」に「被保険者であること」又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」が要件です。
60歳以上65歳未満の被保険者でないときに初診日がある場合は、「国内居住要件」があることに注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。
②【H29年出題】
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 ×
初診日に「被保険者」で、「障害認定日」に障害等級の1級又は2級で、「保険料納付要件」を満たしているので、障害基礎年金の支給要件は満たしています。
初診日に保険料の納付猶予の適用を受けていることは関係ありません。
②【H29年出題】 〇
「被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日」がある場合は、初診日に日本国内に住所を有することが必要です。問題文のように、初診日に日本国内に住所を有しない場合は、初診日の要件を満たさないので障害基礎年金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-205
R4.3.15 追納その4 追納の保険料の額
追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算がつきます。
では、条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ③ 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。 |
追納する場合は、当時の保険料額に政令で定める額が加算されます。
例えば、全額免除された保険料を令和3年度中に追納する場合、以下の額になります。
数字を覚える必要はありません。古くなるほど率が高いことと、直近のR1年度とR2年度分には加算がないことがポイントです。
①政令で定める率(施行令第10条)
②当時の保険料額
③令和3年度中に追納する場合の額
| H23年度 | H24 年度 | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | R1 年度 | R2 年度 |
① | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | ― |
② | 15,020 | 14,980 | 15,040 | 15,250 | 15,590 | 16,260 | 16,490 | 16,340 | 16,410 | 16,540 |
③ | 15,350 | 15,200 | 15,180 | 15,330 | 15,650 | 16,310 | 16,520 | 16,360 | 16,410 | 16,540 |
なお、免除月が平成31年3月で、令和3年4月に追納する場合は、加算はありません。
平成31年3月は平成30年度ですので、令和3年度に追納する場合は、加算額がつくのが原則です。ただし、平成31年3月の保険料の納期限は平成30年4月末です。令和3年4月中なら納期限から2年以内ですので、加算はつきません。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
②【H18年出題】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
③【H28年出題】
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
保険料に加算額が加算されるのは、免除月の属する年度の4月1日から起算して「3年以上経過後」の年度に追納する場合です。「3年以上経過後」がポイントです。
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
例えば、平成30年度に免除月がある場合、免除月の属する年度の4月1日(平成30年4月1日)から3年以上経過後(令和3年4月1日)の年度(令和3年度)に追納する場合は、追納加算率を乗じた額が保険料に加算されます。
②【H18年出題】 〇
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
・免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内なら加算されません
→ 例えば、平成30年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(令和2年度以内)なら、加算されません。
・免除の月が3月のときは、翌々年の4月中ならば加算されません。
→ 例えば、平成31年3月に免除を受けた場合は、翌々年の4月(令和3年4月)中なら加算されません。
③【H28年出題】 ×
免除を受けた月が平成25年3月の場合は、翌々年の4月(平成27年4月)以内なら、加算は行われません。平成28年4月が誤りです。
H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 |
H24年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(H26年度以内)に追納するなら加算されません。H27年度以降に追納する場合は、経過年数に応じて加算されます。
例外的に、平成25年3月が免除月の場合は、平成27年4月に追納する場合は、加算は行われません。平成25年3月の保険料の納期限(平成25年4月)から2年以内だからです。
※平成25年3月は「平成24年度」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-204
R4.3.14 追納その3 追納と保険料納付済期間
追納を行うと、保険料免除期間は「保険料納付済期間」になります。
条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ④ 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 |
追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされるのは、「追納が行われた日」です。
追納した場合、保険料免除期間は、追納が行われた日に「保険料納付済期間」になります。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料全額免除期間を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-203
R4.3.13 追納その2 追納の順序
「学生納付特例」、「納付猶予」の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、額の計算には入りません。
そのため、追納の順序では、原則として「学生納付特例」、「納付猶予」が優先されます。
では、追納の順序を条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ② その一部につき追納をするときは、追納は、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。 ただし、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条第1項若しくは第90第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。 |
追納の順序
・「先に経過した月の分から(古い方から)」、順次行うのが原則です
・「学生納付特例(納付猶予)」期間がある場合
学生納付特例期間、納付猶予期間は老齢基礎年金の額の計算に入らないので、「学生納付特例期間」「納付猶予期間」を優先して追納を行います。
それ以外の期間は、先に経過した月の分から順次行います。
例えば、次のような場合は、①学生納付特例 → ②半額免除 → ③全額免除の順番で追納を行います。
古 → → → → → → → → → → →新 | ||
半額免除 | 全額免除 | 学生納付特例 |
ただし、学生納付特例より古い他の免除期間を優先できる例外も設けられています。
学生納付特例を先に追納しなければならないがために、他の免除期間が10年の追納期間に間に合わないことが出てくるためです。
そのため、学生納付特例期間より古い他の免除期間がある場合は、どちらを優先するか本人が選択することもできるようになっています。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
納付することを要しないものとされた保険料の一部について納付する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
②【R1年出題】
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
原則として、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間が優先で、次いで、全額免除期間又は一部免除期間のそれぞれ古い分から順次行うこととされています。
②【R1年出題】 ×
平成27年6月分から 平成28年3月分 | 平成28年4月分から 平成29年3月分 | 平成29年4月分から 令和元年6月分 |
保険料全額免除期間 | 学生納付特例の期間 | 保険料全額免除期間 |
学生納付特例の期間の保険料から優先的に追納するのが原則です。
しかし、学生納付特例より古い保険料全額免除期間を先に追納する選択も可能です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-202
R4.3.12 国年・追納その1 追納の要件
国民年金の保険料の免除を受けた場合、後から保険料を追納することができます。
追納の要件を条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ① 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。 ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
 ポイント!
ポイント!
・老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
・追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内です
・一部免除を受けた場合は、残りの納付すべき保険料が納付されていること
→ 例えば、4分の3 免除については、残りの4分の1が納付されていないと追納できません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
②【H29年出題】
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
③【R2年出題】
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有していても、追納はできます。
障害基礎年金は受給権があっても、障害の程度が軽くなると支給停止になる可能性があるからです。追納によって将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。
なお、遺族基礎年金の受給権者も追納が可能です。遺族基礎年金も失権することがあるからです。
②【H29年出題】 〇
4分の3免除を受けても残りの4分の1を納付していなければ、未納期間になるので、追納はできません。
③【R2年出題】 〇
H18年7月 | ・・・ | H22年 4月 | ・・・ | H28年 3月 | ・・・ | R2年 3月 | R2年 4月 |
全 額 免 除 期 間 |
| ||||||
| 追納可能 |
| 追納 承認 | ||||
平成18年7月から平成28年3月 → 全額免除期間
追納の承認の日の属する月 → 令和2年4月
追納ができるのは「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るもの」に限られますので、平成22年4月から平成28年3月までとなります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-179
R4.2.17 遺族基礎年金の支給停止(その3 子に対する支給停止)
今回は、子に対する遺族基礎年金の支給停止です。
では、条文です。
第41条 ② 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 |
 子に支給する遺族基礎年金について
子に支給する遺族基礎年金について
◇配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止
→遺族基礎年金が配偶者に支給される間は、子の遺族基礎年金は支給が停止されます。
(例外)
・配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項により支給停止されているとき
第20条の2は「受給権者の申出による支給停止」です。
配偶者が申し出ることによって、配偶者の遺族基礎年金が支給停止になっている場合は、子の遺族基礎年金は支給されます。
・第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているとき
第41条の2第1項は、「配偶者が所在不明の場合の支給停止」です。
子の申し出によって配偶者の遺族基礎年金の支給が停止されますが、その間は、子が遺族基礎年金を受給します。
◇生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、支給停止
例えば、夫婦が離婚し、元妻が子と生計を同じくしていた場合で、元夫が死亡した場合。
元夫から定期的に養育費が送金されるなどして生計維持関係が認められた場合、子は遺族基礎年金の受給権を取得します。元妻には遺族基礎年金の受給権は発生しません。
しかし、子が母(元妻)と生計を同じくしている場合は、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
②【H30年出題】
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
③【H30年出題】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
★原則 → 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止。
★例外 → 配偶者の遺族基礎年金が「受給権者の申出により支給停止」されたとき → 子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
②【H30年出題】 ×
夫の死亡で妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、第41条第2項の「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する」に該当するので、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
その後、妻が再婚した場合は、第40条第1項第2号「婚姻をしたとき」に該当するので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。なお、子の受給権は消滅しません。
そして、その子がその妻(母)と引き続き生計を同じくしている場合は、第41条第2項の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」に該当するので、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
③【H30年出題】 ×
第2号被保険者である40歳の妻が死亡して、生計維持されていた40歳の夫と子がある場合、40歳の夫には「遺族基礎年金」、子には「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の受給権が発生します。
遺族基礎年金については、第42条第2項「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。」に当てはまるので、夫に遺族基礎年金が支給され、子の遺族基礎年金が支給停止になります。
★なお、夫の遺族厚生年金については、受給要件は55歳以上です。妻の死亡当時40歳の夫には遺族厚生年金の受給権は発生しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-178
R4.2.16 遺族基礎年金の支給停止(その2 所在不明の場合)
今回は、所在不明の場合の支給停止です。
では、条文です。
第41条の2 ① 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。 ② 配偶者は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第42条 ① 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② ①の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 |
◇ 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有している間は、子の遺族基礎年金は支給停止となります。(このことは次回お話しします。)
しかし、配偶者が1年以上所在不明の場合は、子の申請によって配偶者の遺族基礎年金が支給停止されます。
(第41条の2)
◇ 例えば、2人の子が遺族基礎年金を受けていて、1人の子が1年以上所在不明になったときは、他の子が申請を行うと、所在不明になったときにさかのぼって、所在不明の子の年金が支給停止されます。
(第42条)
では、過去問をどうぞ
①【H26年出題】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
②【H22年出題 】(改正による修正あり)
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
③【H30年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
④【H15年出題】(改正による修正あり)
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された配偶者又は子は、それぞれ支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
6か月以上ではなく、「1年以上」明らかでないときです。
②【H22年出題 】(改正による修正あり) ×
「申請した日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時に遡って」、支給が停止されます。
③【H30年出題】 ×
②の問題と同じく、いつから支給停止されるかがポイントの問題です。
「申請のあった日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時に遡って」、支給が停止されます。
④【H15年出題】(改正による修正あり) 〇
所在不明になった人は、いつでも支給停止の解除の申請ができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-177
R4.2.15 遺族基礎年金の支給停止(その1 労基法との調整)
前回までは遺族基礎年金の「失権」についてお話ししました。
今回からは「支給停止」のお話です。
「失権」とは、受給権が消滅することです。例えば、婚姻した場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後離婚したとしても、受給権は復活しません。
「支給停止」とは、何かの事由で年金がストップすることです。支給停止事由がなくなれば、年金は再開されます。
今回は「支給停止」の1回目です。
では条文をどうぞ。
第41条 (支給停止) 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 |
業務上の事由で死亡し、労働基準法の遺族補償が行われる場合は、遺族基礎年金は6年間支給が停止されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H12年出題】
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
②【H20年出題】
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
③【H26年出題】
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
①【H12年出題】 ×
「労働者災害補償保険法の規定による遺族補償」ではなく、「労働基準法の規定による遺族補償」が行われるべきであるときは、遺族基礎年金は、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
 ポイント!
ポイント!
「労働基準法」と「労働者災害補償保険法」の違い
・労働基準法には、「災害補償」の規定があり、労働者の業務上の傷病等については、使用者に補償責任を負わせています。
「労働基準法の規定による遺族補償」は、労働者が業務上死亡した場合に、使用者が補償すべきものです。
・しかし、実際に、使用者が全ての補償を行うのは難しいため、労働基準法の災害補償義務を代行する保険が「労働者災害補償保険法」です。
保険料は、事業主が全額負担し、労働者の業務上の傷病等については、労災保険法から保険給付が行われます。
②【H20年出題】 ×
「労働者災害補償保険法」から「遺族補償年金」が支給されるときは、遺族基礎年金の支給は停止されません。労災保険法の遺族補償年金が減額されます。
 ポイント!
ポイント!
国民年金・厚生年金保険の年金は、業務上外関係なく支給されます。例えば、業務上の死亡の場合は、労災保険の年金も支給されますし、国民年金・厚生年金保険からも年金が支給されます。
「同一の事由」で労災保険の年金と国民年金・厚生年金保険から年金が支給される場合は、調整のため労災保険の年金が減額されます。国民年金・厚生年金保険の年金は支給停止されません。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、国民年金・厚生年金保険は、被保険者本人が保険料を負担しているためです。
(労災保険法別表第1)
③【H26年出題】 〇
②の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-176
R4.2.14 遺族基礎年金の失権(その2 それぞれ特有の事由)
前回は、配偶者、子共通の失権事由がテーマでしたが、今回は、配偶者、子それぞれ特有の失権事由です。
では、条文を見てみましょう。
第40条 ② 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、配偶者、子共通の失権事由の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、加算額の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ③ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、配偶者、子共通の失権事由の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 2 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 3 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 4 20歳に達したとき。 |
②は配偶者特有の失権事由です。
配偶者の遺族基礎年金は子があることが条件で、必ず子の加算額がつきます。
加算事由に該当する子がいなくなった場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
③は子特有の失権事由です。
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了
→失権します。
ただし、障害状態にある場合は失権しません。
・障害状態でなくなったとき
→失権します。
ただし、障害状態でなくなっても18歳に達した日以後の最初の3月31日までは、失権しません。
・20歳に達したとき
→失権します。
では、過去問をどうぞ
①【H27年出題】
子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
18歳の年度末に障害の状態にあった場合で、その後、20歳になる前に障害の状態に該当しなくなった場合は、そこで遺族基礎年金の受給権は消滅します。
なお、18歳の年度末に障害の状態にあって、障害の状態のまま20歳になった場合は、20歳に達したときに遺族基礎年金の受給権は消滅します。
では、次の過去問をどうぞ!
②【H19年出題】(改正による修正あり)
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が、直系血族又は直系姻族の養子になったときはこの限りではない。
③【H28年出題】
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【H19年出題】(改正による修正あり) ×
「直系血族又は直系姻族以外の」養子になった場合、遺族基礎年金の受給権は消滅します。しかし、「直系血族又は直系姻族の養子」になった場合は失権しません。
例えば、被保険者である夫が死亡し、妻と子(1人)に遺族基礎年金の受給権が発生し、その子が「直系血族又は直系姻族の養子になった」場合を考えてみます。
子が「直系血族又は直系姻族の養子」になったとしても、子の受給権は消滅しません。
では、妻の受給権はどうでしょうか?
前々回に、「配偶者の遺族基礎年金の減額改定」の条文を読みました。
減額事由の中に、「子が配偶者以外の者の養子となったとき」という規定があったのを思い出してください。「配偶者以外の者」の部分がポイントです。
子から見ると「直系血族又は直系姻族の養子」になっても失権事由にはなりませんが、配偶者から見ると、子が「配偶者以外の者の養子」となるので、減額事由に該当します。
1人だけの子が減額事由である「配偶者以外の者の養子」となった場合は、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
問題文の「加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅する」の部分は正しいですが、「その子が、直系血族又は直系姻族の養子になったときはこの限りではない」の部分が誤りです。子の養子縁組が、直系血族又は直系姻族とだったとしても、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
③【H28年出題】 〇
②の解説と同じケースの問題です。
・ 配偶者と1人の子に遺族基礎年金の受給権が発生
↓
・ その子が直系血族又は直系姻族の養子となった
↓
・ 子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない
↓
・ しかし、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-175
R4.2.13 遺族基礎年金の失権(その1 配偶者、子共通の事由)
遺族基礎年金の失権事由を確認しましょう。
まず、「配偶者」と「子」の共通の失権事由からです。
では、条文を見てみましょう。
第40条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 2について・・・届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。 3について・・・届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。 |
配偶者が受給する場合、子が受給する場合の共通の失権事由です。
1、2、3のいずれかに該当すれば、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】(改正による修正あり)
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
②【H30年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
③【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
④【H16年出題】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】
①【H20年出題】(改正による修正あり) 〇
配偶者と子に共通する失権事由は、「死亡」、「婚姻」、「直系血族又は直系姻族以外の養子」の3つです。
②【H30年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
③【R1年出題】 ×
受給権者である子から見ると、「死亡した被保険者の兄」は叔父にあたり、直系ではなく傍系血族です。「直系血族又は直系姻族以外」の養子になった場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅しますので、叔父(傍系血族)の養子になった場合は、遺族基礎年金は失権します。
④【H16年出題】 〇
「夫の父」は直系姻族です。直系姻族との養子縁組ですので、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
 次回、配偶者、子それぞれ特有の失権事由に続きます。
次回、配偶者、子それぞれ特有の失権事由に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-174
R4.2.12 配偶者に支給する遺族基礎年金の増額と減額
前回の続きです。
配偶者に支給する遺族基礎年金には、子の加算額がつきます。
子の数が増減すると遺族基礎年金の額も改定されます。
では、条文を読んでみましょう。
法第39条 ② 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 |
遺族基礎年金が増額されるパターンです。
第37条の2第2項で、『被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。』となっています。「将来に向かって」ですので、生まれたときから遺族の範囲に入ります。
『生まれた日の属する月の翌月』から、遺族基礎年金の額が増額改定されます。
では、次も読んでみましょう。
法第39条 ③ 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 1 死亡したとき。 2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 4 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 5 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 6 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 7 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 8 20歳に達したとき。 |
配偶者に対する遺族基礎年金が減額改定されるパターンです。
配偶者の遺族基礎年金には子の数に応じた加算額がつきます。
例えば、子が3人ある場合は、3人分の加算額として「224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率」が加算されています。その後、子のうちの1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了し加算の要件に該当しなくなると、加算額は2人分の「224,700円×改定率+224,700円×改定率」に減額改定されます。
条文の「子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が・・・」の部分がポイントです。
配偶者の遺族基礎年金は子があることが条件です。例えば、子が1人のみで、その子が加算の要件に該当しなくなった場合は子がいなくなるので、遺族基礎年金は減額改定ではなく、失権します。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
②【H25年出題】
妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H29年出題】 ×
遺族基礎年金の対象になる遺族は、被保険者の死亡の当時、被保険者によって生計を維持していたことが条件です。
問題文のように、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった子と養子縁組をしても、遺族の範囲に入る「子」の要件に当てはまらないので、増額改定は行われません。
②【H25年出題】 〇
1人の子と生計を同じくしている妻の遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率+224,700円×改定率です。その子が加算事由に該当しなくなると、生計を同じくしている子がいなくなるので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-173
R4.2.11 遺族基礎年金の額(配偶者と子の違い)
遺族基礎年金は「配偶者」に支給されるパターンと、「子」に支給されるパターンがあります。それぞれの遺族基礎年金の額を確認しましょう。
まず、遺族基礎年金の額を条文で見てみましょう。
第38条 (遺族基礎年金の額) 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
★遺族基礎年金の基本額は、「780,900円×改定率」です。
では、「配偶者」に支給されるパターンを見てみましょう。
第39条 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |
ポイント! 配偶者と子の両方が遺族基礎年金の受給権を取得した場合、遺族基礎年金は配偶者が受けます。
遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、「子」と生計を同じくすることが条件です。配偶者が遺族基礎年金を受ける場合は、必ず子の数に応じた加算額がつきます。
第1子、第2子はそれぞれ224,700円×改定率、第3子以降は1人増えるごとに74,900円×改定率が加算されます。
配偶者が受ける遺族基礎年金は、基本額の780,900円×改定率のみということはあり得ず、必ず子の加算額がつくことがポイントです。
次に「子」に支給されるパターンを見てみましょう。
第39条の2 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、780,900円×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 |
ポイント! 条文の「子が2人以上あるとき」の部分に注目してください。子に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上の場合は加算額がつきますが、子が1人の場合は加算額がつかないのがポイントです。
子が1人の場合は780,900円×改定率
子が2人の場合は780,900円×改定率+224,700円×改定率
子が3人の場合は780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率
となります。
個々の受給権者に支給される額は、子の数で除した額になります。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。
②【H22年出題】
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
③【H28年出題】
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
④【R3年出題】
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
配偶者の遺族基礎年金には必ず子の加算額が加算されます。
②【H22年出題】 ×
受給権者が子2人のときの子に支給する遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率」に「224,700円×改定率」を加算した額です。合計額を2で除して得た額を2人の子それぞれに支給します。
③【H28年出題】 ×
受給権者が子3人のときの子に支給する遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率」+「224,700円×改定率」+「74,900円×改定率」です。その合計額を3で除した額が3人の子それぞれに支給されます。
④【R3年出題】 ×
受給権者が子4人のときの子に支給する遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率」に子の加算として「224,700円×改定率、74,900円×改定率、74,900円×改定率」を合計した金額を子の数の4で除した額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-162
R4.1.31 障害基礎年金の子の加算・要件をみるタイミング
障害基礎年金の受給権者に子がいるときは、子の加算が行われます。
要件をどの時点でみるかが今日のテーマです。
★では、条文で確認しましょう。
第33条の2 ① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |
子の加算額は、「生計維持関係」があることが前提です。
障害基礎年金の受給権発生時に生計維持関係がある場合はもちろん加算されますが、受給権を取得した翌日以後に生計維持関係のある子を有することに至った場合も、子の加算が行われるのがポイントです。
ちなみに、遺族基礎年金の場合の生計維持関係は「死亡の当時」で判断されます。
第37条の2で、「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、一定の要件に該当したものとする。」となっています。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
②【H25年出題】
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
③【H23年出題】
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。

【解答】
①【H19年出題】 〇
障害基礎年金の加算額の対象は、子だけです。配偶者については、1・2級の障害厚生年金の加給年金額の対象になります。
②【H25年出題】 ×
障害基礎年金の受給権を取得した後でも、要件を満たす子を有することになった場合は、子の加算額が加算されます。その場合は、子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額に子の加算額が加算されます。
③【H23年出題】 ×
②の問題と同じです。受給権を取得した時点で要件を満たす子がいなくても、後日、有することになった場合は、加算の対象になります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-152
R4.1.21 障害厚生年金 額の改定その2 3級から2級への改定①
3級の障害が重くなり2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に額の改定が行われます。
その場合、「障害基礎年金」は、「事後重症」になることがポイントです。
初診日に厚生年金保険の被保険者(国民年金は第2号被保険者)で、障害認定日に3級に該当した場合、「3級の障害厚生年金」の受給権が発生しますが、障害基礎年金の受給権はありません。
その後、障害の程度が増進し2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に額の改定が行われます。一方、障害基礎年金は「障害認定日」に障害等級(1・2級)に該当しなかったものが、その後障害等級(1・2級)に該当することになり、「事後重症」となります。(下の図でご確認ください)
障害厚生年金の3級から2級への額の改定は、障害基礎年金の事後重症の要件を満たす必要があるのがポイントです。
 ここで、「国民年金法」の条文を読んでみましょう。
ここで、「国民年金法」の条文を読んでみましょう。
国民年金法第30条の2 (事後重症の障害基礎年金) ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 ④ 第①項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに①項の請求があったものとみなす。 |
★ 最後の「そのときに①項の請求があったものとみなす。」に注目してください。
事後重症の障害基礎年金は「請求」によって受給権が発生します。しかし、障害厚生年金の障害等級が3級から2級に改定された場合は、改めて請求しなくても、障害厚生年金の改定に伴い、請求が行われたとみなされます。
 では、国民年金の過去問をどうぞ!
では、国民年金の過去問をどうぞ!
①【国民年金H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
②【国民年金H22年出題】
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
①【国民年金H30年出題】 ×
障害厚生年金が3級から2級に改定された場合は、障害基礎年金は、事後重症の「請求があったものとみなす。」ことになっています。請求しなくても、事後重症の障害基礎年金の受給権が発生します。
②【国民年金H22年出題】 ×
①の問題と同じです。障害基礎年金に係る事後重症の請求をしなくても、受給権が発生します。
次回に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
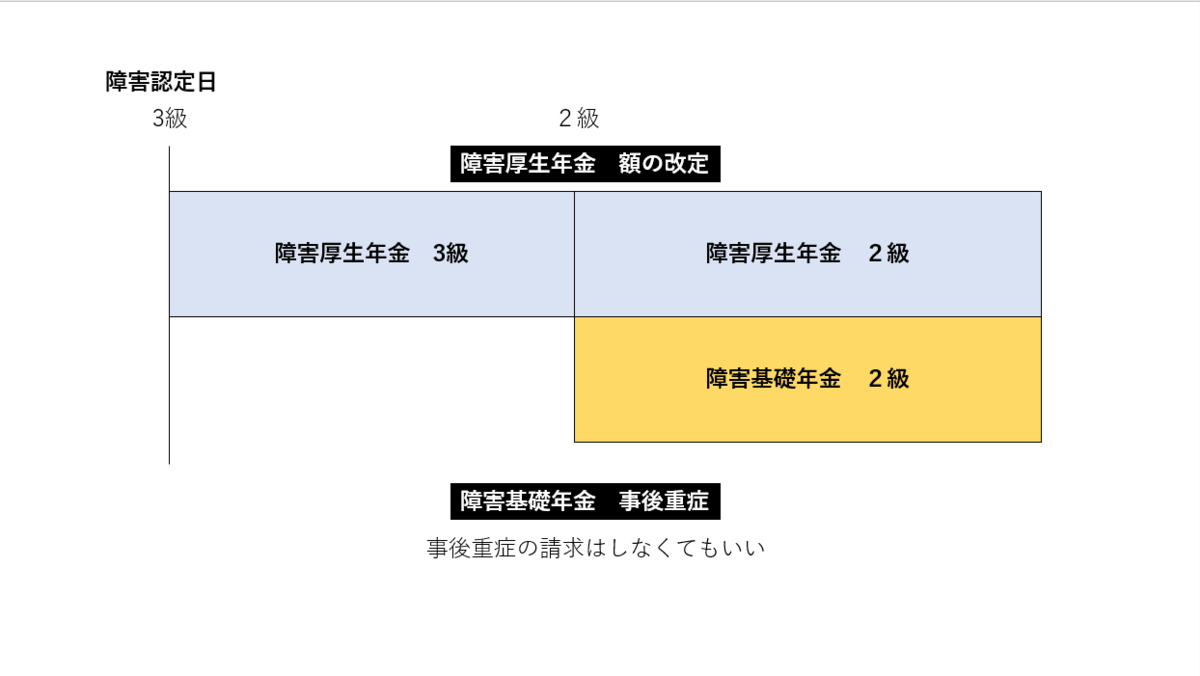
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-150
R4.1.19 20歳前傷病による障害基礎年金 その3 支給停止されるとき②
前回に引き続き、第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)の支給停止です。
第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)には、受給権者の所得による支給停止があります。
条文を見てみましょう。
第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定により子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。 |
★チェックポイント!
・ 第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)には、所得による支給停止がある。
・ 所得は「受給権者」の前年の所得で判断される
・ 停止期間は「その年の10月から翌年の9月」まで(令和3年8月改正)
・ 停止されるのは、「全部又は2分の1」
全額支給
|
2分の1支給停止
|
全額支給停止 |
2分の1支給 |
▲ ▲ ▲
0 370万4千円 472万1千円
※扶養親族等がいない場合、前年の所得が472万1千円を超えるときは、全額が支給停止、370万4千円を超え、472万1千円以下のときは、2分の1が支給停止されます。
(施行令第5条の4)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】※R3年8月改正による修正あり
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年9月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
②【H27年出題】※R3年8月改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
③【H17年出題】※R3年8月改正による修正あり
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の10月から翌年9月までその支給を停止される。
④【H20年出題】※R3年8月改正による修正あり
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H25年出題】※R3年8月改正による修正あり ×
支給停止されるのは、年金額の「全部又は2分の1」に相当する部分です。
②【H27年出題】※R3年8月改正による修正あり ×
「受給権者本人」の所得で判断されます。扶養親族の所得は合算しません。
③【H17年出題】※R3年8月改正による修正あり ×
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、第30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)ではなく、第30条の通常の障害基礎年金です。所得による支給停止はありません。
④【H20年出題】※R3年8月改正による修正あり 〇
子の加算額が加算されている20歳前傷病による障害基礎年金が、所得によって2分の1が支給停止される場合、子の加算額を控除した額の2分の1に相当する部分の支給が停止されます。
もう一問どうぞ!
⑤【H25年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
⑤【H25年出題】 ×
被害金額がその価額のおおむね「3分の1」ではなく「2分の1」以上である損害を受けた者が対象です。
その損害を受けた月から翌年の9月までは、所得を理由とする支給停止は行われません。
(法第36条の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-149
R4.1.18 20歳前傷病による障害基礎年金 その2 支給停止されるとき①
前回の続きです。
20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を負担していない人に対して支給する福祉的な意味のある年金です。
そのため、通常の障害基礎年金とは違う理由で支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
第36条の2 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4 日本国内に住所を有しないとき。 |
ポイント!
「第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)」限定の支給停止事由です。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。
②【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
③【H25年出題】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
④【R3年出題】
国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。
⑤【H30年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
⑥【H25年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】
①【H20年出題】 〇
労災保険法の障害補償年金を受けることができるときに支給停止されるのは、20歳前の障害に基づく障害基礎年金だけです。
問題文は「いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く」となっています。通常の障害基礎年金について問われているので、「その支給は停止されない」で〇です。
②【R1年出題】 〇
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、労災保険法の年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合は、その期間、支給停止されます。
なお、条文の「労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付」に注目してください。調整の対象は「年金」で、「障害」の年金に限られません。
③【H25年出題】 〇
②の問題のように20歳前傷病による障害基礎年金は、「労災保険法の年金たる給付を受給できる場合」は、その期間、支給停止されます。
ただし、労災保険法による年金たる給付の「全額が支給停止されているとき」は、20歳前傷病による障害基礎年金は原則として支給停止されません。
(法第36条の2第2項)
④【R3年出題】 ×
刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているときに、支給が停止されるのは、第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)です。
問題文は、法第30条第1項の規定による障害基礎年金(通常の障害基礎年金)について問われているので、刑事施設、労役場等の施設に拘禁されている間も、支給停止にはなりません。
⑤【H30年出題】 〇
問題文の施設に収容されている間は、20歳前傷病による障害基礎年金は、支給停止されます。
(則第34条の4)
⑥【H25年出題】 〇
「30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金」について問われているので、「日本国内に住所を有しない」ときは支給停止される、で正解です。
次回に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-148
R4.1.17 20歳前傷病による障害基礎年金 その1受給権の発生
通常の障害基礎年金は、初診日に「国民年金の被保険者」であることが条件です。
(又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である場合でも要件を満たします。)
20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金です。
20歳前に初診日があるというのは、国民年金に加入する前に初診日があるということです。
旧法では、20歳前に障害になった場合は、全額国庫負担の障害福祉年金が支給されていましたが、新法では、障害基礎年金が支給されることになりました。
ただし、国民年金加入前に初診日があるので国民年金の保険料は納付していません。 そのため、通常の障害基礎年金とは違うルールがありますので区別しましょう。
では、まず、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権の発生日を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 |
・初診日が20歳未満で、
①障害認定日以後に20歳に達したとき → 20歳に達した日
②障害認定日が20歳に達した日後であるとき → 障害認定日
①は20歳に達した日、②は障害認定日に、障害等級にあれば、受給権が発生します。
★下の図も参考にしてください。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
②【H22年出題】
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

【解答】
①【H26年出題】 ×
初診日が19歳の時なので、障害認定日は、20歳に達した日後になります。
下の図では②に該当します。
受給権は、20歳に達した日ではなく、「障害認定日」に障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に発生します。
ちなみに、障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」となるので、障害認定日が1年6か月より早くなる可能性もあります。
しかし、問題文は、25歳時点で「継続して治療中」です。(治っていない)そのため、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」が障害認定日です。
②【H22年出題】 ×
初診日に20歳未満でも、「厚生年金保険の被保険者」である場合は、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。
問題文の場合は、「障害認定日」に障害厚生年金と障害基礎年金の受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
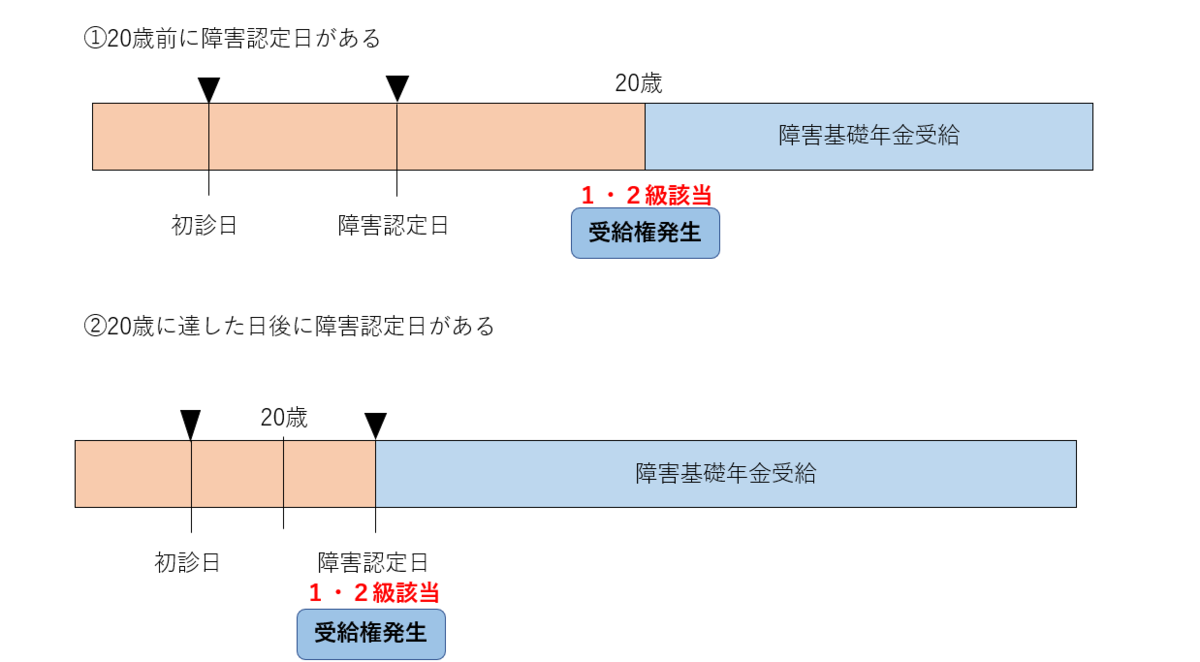
 どんな法律シリーズ⑦ 国年・厚年(旧法から新法へ)
どんな法律シリーズ⑦ 国年・厚年(旧法から新法へ)
R4-138
R4.1.7 国年・厚年その2(旧法から新法へ)
前回は、年金制度の創成期のお話をしました。
その後の経済の高度成長の中で、年金制度も充実期を迎えます。
そして、加速する高齢化、経済成長の安定化から、公的年金も大きな見直しが行われました。
昭和60年改正の大きな柱は次の3つです。
① 基礎年金の導入
② 厚生年金の給付水準の適正化
③ 女性の年金権の確立
「昭和61年4月1日」前後で年金制度が大きく変わります。昭和61年4月1日前の制度を「旧法」、それ以後を「新法」といいます。
① 基礎年金の導入について
それまでの公的年金は、自営業者等が加入する「国民年金」、民間の会社員が加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済年金」の大きく3つに分かれていました。
それぞれが独自に運営されていたので、給付面でも負担面でも制度間に格差があったこと、また、産業構造の変化に伴い財政基盤が不安定になる問題も起こっていました。
このため、登場したのが「全国民共通の基礎年金」です。
国民年金は「基礎年金」として、全国民共通の年金を担当することになりました。また、厚生年金等の被用者年金は基礎年金に上乗せされる報酬比例年金として位置づけられました。
「基礎年金」の導入によって、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金や共済年金」となる「2階建ての年金」の方式になりました。
② 厚生年金の給付水準の適正化について
加入期間が延びてもこれ以上給付水準が高くならないよう、給付乗率や定額単価も見直しが行われました。
具体的には、大正15年4月2日から昭和21年4月1日以前生まれの人の給付乗率や定額単価は、生年月日が若くなっていくほど逓減していきます。
新法施行時に40歳未満だった昭和21年4月2日以後生まれの人には新法の給付乗率や定額単価を適用しますが、40歳を過ぎていた昭和21年4月1日以前生まれの人は、旧法の水準から徐々に新法の水準に近づけていくイメージです。昭和61年4月1日を境に、給付乗率や定額単価をいきなり減らすことができないからです。
③ 女性の年金権の確立について
旧法では民間サラリーマン等の妻(専業主婦)は、国民年金には「任意で加入できる」位置づけでした。任意加入しなかった場合は、老後は、サラリーマンの夫の年金に加算される配偶者加給年金額で保障されることになっていました。
ただし、妻が任意加入していない場合は、離婚すると老齢年金が受給できない、障害になっても障害年金が受給できない問題もありました。
そのため、新法では、サラリーマン等の妻(専業主婦)も国民年金に第3号被保険者として加入することになりました。ただし、保険料は、第3号被保険者が個別に負担するのではなく、夫の加入する被用者年金制度全体で負担しています。
※妻と夫が逆の場合も同じです。
過去問をどうぞ!
【H15年選択式】
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【解答】
A 大正15年4月2日
★「基礎年金」という名称が登場するのは新法からです。
新法の「老齢基礎年金」が支給されるのは、昭和61年4月1日に60歳未満だった大正15年4月2日以降生まれの人です。ただし、大正15年4月2日以降生まれでも、昭和61年3月31日に旧法の老齢・退職給付の受給権があった場合は、そのまま旧法が適用されます。
B 障害認定日
★障害基礎年金は障害認定日に受給権が発生します。障害認定日(受給権の発生日)が昭和61年4月1日以降なら、新法の障害基礎年金が支給されます。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
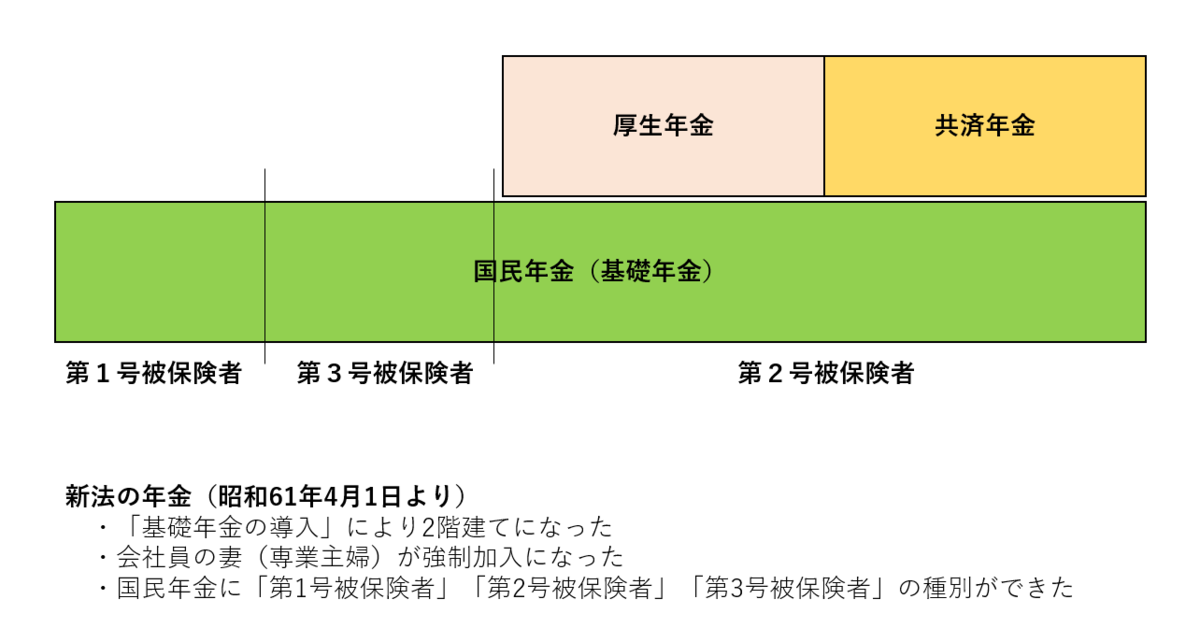
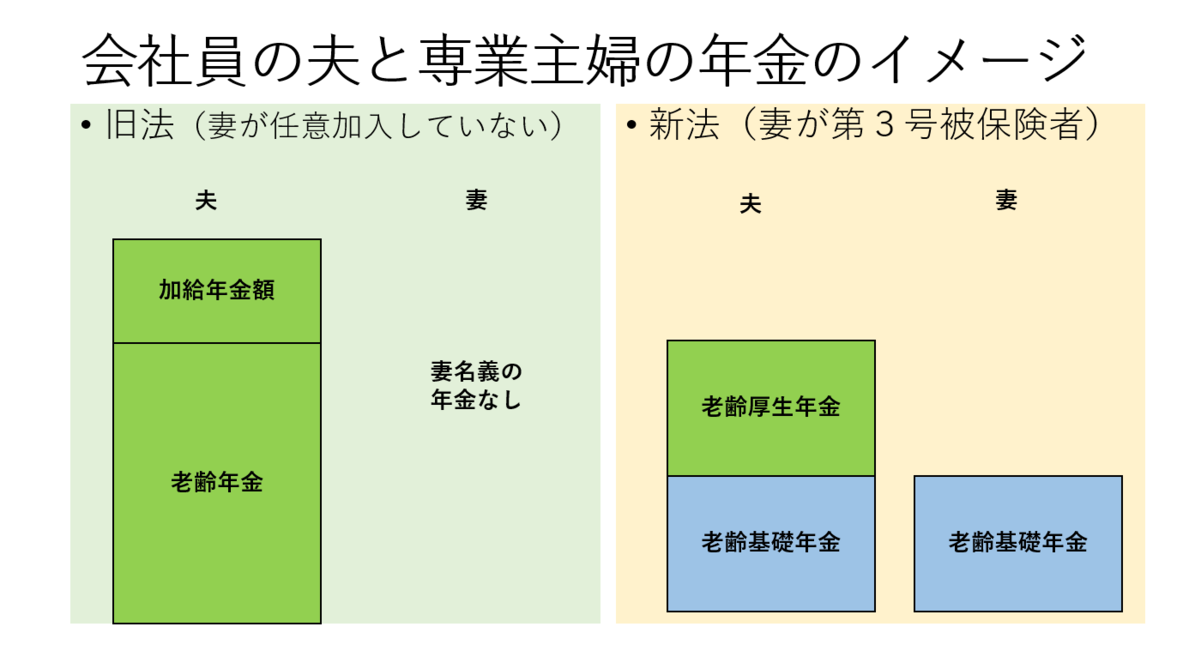
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
 どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法
どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法
R4-137
R4.1.6 国民年金法・厚生年金保険法ってどんな法律?その1
今日は、厚生年金保険法・国民年金法の創成期のお話です。
・昭和17年 労働者年金保険法発足
(昭和19年厚生年金保険法に改称)
・昭和29年 厚生年金保険法全面改正
(「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての給付方式を採用)
・昭和36年 国民年金法全面施行
(国民皆年金の実現)
★昭和17年にスタートした労働者年金は、工場等で働く男子労働者を被保険者としていました。労働力の保全強化を図ることなどが背景にありました。
昭和19年に名称が厚生年金保険法に改められ、被保険者の範囲は、事務職員や女性にも広がりました。
報酬比例部分のみだった養老年金が、「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建ての老齢年金になったのが、昭和29年の改正です。
★民間の会社員や公務員には公的な年金制度があり、老後の所得が保障されていましたが、自営業者等には、そのような制度が無いことが問題になっていました。
しかし、自営業者等にも老後の保障が必要だということで、国民年金法が制定されたのが昭和34年です。拠出制の国民年金制度が昭和36年に施行され、国民皆年金が実現しました。
「国民皆年金」とは、民間の会社員、公務員だけでなく、それ以外の自営業者等もすべての人が職業に関係なく公的年金の保護の対象になるという意味です。
なお、拠出制は昭和36年からですが、無拠出制の福祉年金制度は昭和34年からスタートしていました。
既に高齢になっている人、障害のある人等には、全額国庫負担の老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金等が支給されました。
★老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)の全てが保険料納付済期間なら満額の年金が支給されます。
しかし、大正15年4月2日から昭和16年4月1日以前生まれの人は、480月ではなく、加入可能年数×12で計算します。
なぜなら、国民年金制度が発足した昭和36年4月1日に既に20歳になっているからです。その年代の人は、昭和36年4月1日から60歳までの間の全てが保険料納付済期間なら、満額の老齢基礎年金が支給されます。
例えば大正15年4月2日~昭和2年4月1日の間に生まれた人は「25年」、昭和15年4月2日~昭和16年4月1日の間に生まれた人は39年が加入可能年数です。
20歳から60歳まで40年間加入できるのは、昭和16年4月2日以後生まれの人です。
★創成期の年金のポイントは以下の通りです。
(創成期の年金の特徴)
・「縦割り」の運営でした
制度ごとに支給要件や給付水準が設定されていて、統一されていませんでした。
・加入が「任意」な人もいました
例えば、会社員の妻などは任意加入でした。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
【H19年出題】 ×
無拠出制の福祉年金の給付の開始は、昭和34年11月からです。10月ではありません。
(法附則第1条)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
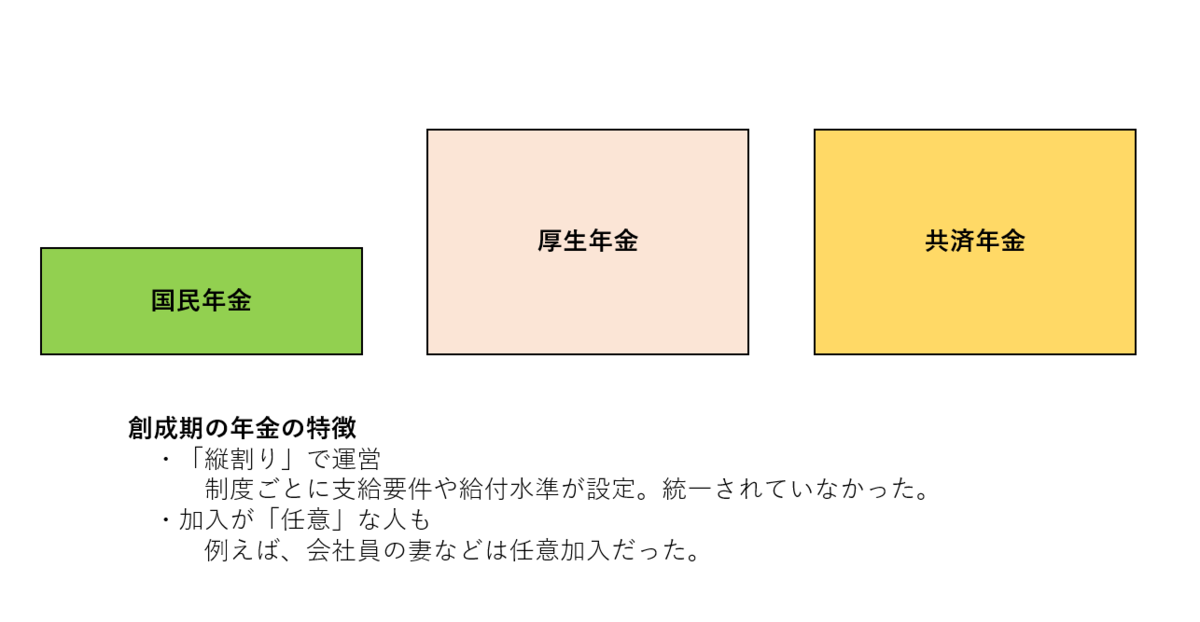
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
 「最初の一歩㉖」条文の読み方(国民年金法)
「最初の一歩㉖」条文の読み方(国民年金法)
R4-126
R3.12.26 専門用語に慣れましょう「前月」と「前々月」の違い(その2)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
「寡婦年金」の条文を読んでみましょう。
第49条(寡婦年金の支給要件) 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 |
1行目の「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての」に注目してください。
「死亡日の属する月の前月まで」で前々月ではありません。
例えば、令和3年12月25日に死亡したとすると、「10年」は令和3年11月まででみることになります。
死亡が12月25日なら資格喪失は12月26日で、「被保険者期間」は11月までです。
寡婦年金の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間に応じて年金額が計算されるので、最後の11月分まで計算に入れる方が、有利になるからです。
では、過去問をどうぞ
①【H28年出題】
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
②【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
寡婦年金の額は、「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額」ではなく、「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3」です。
②【H24年出題】 〇
寡婦年金の額に反映するのは、「第1号被保険者」としての期間だけです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉕」条文の読み方(国民年金法)
「最初の一歩㉕」条文の読み方(国民年金法)
R4-125
R3.12.25 専門用語に慣れましょう「前月」と「前々月」の違い(その1)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
「障害基礎年金」の条文を読んでみましょう。
第30条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者であること。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 |
保険料納付要件の「初診日の属する月の前々月までに」に注目してください。
例えば、初診日が令和3年12月24日だとすると、保険料納付要件は、令和3年10月までの被保険者期間でみます。
国民年金の保険料の納期限は、以下のようになります。
令和3年10月分の保険料 → 納期限は令和3年11月末日
令和3年11月分の保険料 → 納期限は令和3年12月末日
令和3年12月23日の時点で、保険料の納期限がきているのは10月分までです。「納付しなければならない保険料」を納付しているかどうかをみるので、「前々月」となっています。
11月分はまだ納期限がきていませんので、保険料納付要件には入れません。
では、過去問をどうぞ
①【H28年出題】
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
①【H28年出題】 〇
ポイント
・平成26年4月8日が初診日
・保険料納付要件をみる期間
平成22年4月(資格取得日の属する月)から平成26年2月(初診日の属する月の前々月)まで(3年11か月)
・保険料納付済期間+保険料免除期間が、そのうちの3分の2以上あればよい
3年11か月のうち、保険料免除期間が3年間。
3分の2以上の要件を満たしているので、障害基礎年金の受給権が発生します。
★遺族基礎年金で保険料納付要件をみるときも、「前々月」までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉓」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉓」法律によって定義が異なる用語
R4-123
R3.12.23 「障害等級」の定義(国民年金法・厚生年金保険法)その2
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、こちらの条文を読んでみましょう。
国民年金法第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」という表現に注意してください。
国民年金法の条文で単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級」のことです。
一方、国民年金法の条文で「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」と書いてある場合は、「1級・2級・3級」のことです。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H20年出題―国民年金法】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
①【H20年出題―国民年金法】 ×
「厚生年金保険法に規定する障害等級」は「3級」も入ることに注意してください。
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していても、その時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金の受給権が消滅するのは、次のどちらか遅い方です。
・3級程度の障害の状態に該当しなくなって3年経過
・65歳
少なくとも65歳までは失権しません。
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第53条(失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
|
こちらは厚生年金保険法の条文ですので、「障害等級」は、1級、2級、3級です。
消滅する時期は国民年金法と同じです。
では、厚生年金保険法の過去問も解いてみましょう。
②【H15年出題―厚生年金保険法】
障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

【解答】
②【H15年出題―厚生年金保険法】 〇
こちらは、「厚生年金保険法」ですので、単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級・3級」のことです。
消滅の時期は、国民年金の障害基礎年金と同じです。
・3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳以上のとき → その日に消滅
・3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳未満のとき → その後65歳に達した日に消滅
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉒」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉒」法律によって定義が異なる用語
R4-122
R3.12.22 「障害等級」の定義(国民年金法・厚生年金保険法)その1
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
国民年金法第30条 1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
厚生年金保険法第47条 1 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
★ 「障害基礎年金」も「障害厚生年金」も、「初診日」「保険料納付要件」「障害認定日」の3つの要件を満たすことが必要です。
★ 国民年金法の「障害等級」は、1級・2級、厚生年金保険法の「障害等級」は、1級・2級・3級です。
同じ「障害等級」という用語でも、範囲が違うことに注意しましょう。
(例1) 例えば、「初診日」に40歳・厚生年金保険の被保険者だった場合、同時に「国民年金の第2号被保険者」でもあります。
そして、障害認定日に、「1級」に該当した場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給されます。
障害厚生年金 1級 |
障害基礎年金 1級 |
(例2) 例えば、例1と同じく「初診日」に40歳・厚生年金保険の被保険者(同時に「国民年金の第2号被保険者」)だった場合。
障害認定日に「3級」に該当した場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。障害基礎年金には3級がないので、障害基礎年金は支給されません。
障害厚生年金 3級 |
では、「厚生年金保険法」の過去問を解いてみましょう。
①【H22年出題ー厚生年金保険法】
障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
①【H22年出題―厚生年金保険法】 ×
「軽度のものから」ではなく、「重度のものから1級、2級及び3級」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑭」過去問の活用(国民年金法)
「最初の一歩⑭」過去問の活用(国民年金法)
R4-114
R3.12.14 老齢基礎年金の支給要件(国年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
早速、条文を読んでみましょう
第26条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
★老齢基礎年金の支給要件のポイントは次の2つです。
① 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上あること
② 65歳に達したこと
★注意するポイントは次の2つです。
① 合算対象期間
保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年に満たない場合でも、「合算対象期間」を合算して10年以上あれば支給要件を満たします。 (附則第9条第1項)
②学生納付特例期間
1行目の「保険料免除期間(第90条の3第1項(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」に注目してください。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に入りません。年金の計算上はゼロになるので、例えば40年間ずっと学生納付特例期間だった場合は、老齢基礎年金は支給されません。年金額の計算に入らないので、1行目の保険料免除期間から学生納付特例期間は除かれています。
しかし、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年」の部分の保険料免除期間から学生納付特例期間は除かれていません。
学生納付特例期間は受給資格をみるときの10年には算入されるからです。
※なお、「納付猶予期間」も学生納付特例期間と同じ扱いです。
では、過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。
②【H29年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
③【H30年出題】
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間は老齢基礎年金の額には反映しません。ですので、当該期間以外に被保険者期間を有していない場合は、老齢基礎年金の額はゼロ、老齢基礎年金は支給されません。
②【H29年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額には反映されません。しかし、10年以上の受給資格期間には算入されます。
③【H30年出題】 ×
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給権が発生します。
では、年金の支給期間の条文を穴埋めで確認しましょう。
第18条 (年金の支給期間及び支払期月)
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の< A >から始め、権利が消滅した日の< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の < A >からその事由が消滅した日の< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

【解答】
A 属する月の翌月
B 属する月
C 前月
例えば、昭和31年12月11日生まれの人は、令和3年12月10日に65歳に達し、要件を満たせば、令和3年12月10日に老齢基礎年金の受給権が発生します。
年金の支給は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」からですので、令和4年1月から支給が始まります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑬」条文の読み方(国民年金法)
「最初の一歩⑬」条文の読み方(国民年金法)
R4-113
R3.12.13 専門用語に慣れましょう 〇〇歳に達した日(国年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第8条 (資格取得の時期) 第7条の規定による被保険者は、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については①から③までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については④に該当するに至った日に、その他の者については④又は⑤のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 ① 20歳に達したとき。 ② 日本国内に住所を有するに至ったとき。 ③ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。 ④ 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 ⑤ 被扶養配偶者となったとき。 |
第9条 (資格喪失の時期) 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(②に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は③から⑤までのいずれかに該当するに至ったとき(④については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したとき。 ② 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ③ 60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)。 ④ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ⑤ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
⑥ 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)。 |
★〇〇歳に達するのはいつでしょう?
「年齢に関する法律」では、「年齢は出生の日より之を起算す」と規定されています。
年齢の計算は、初日を算入することがポイントです。
例えば、令和3年4月1日午後1時に生まれた場合は、令和3年4月1日0時から起算し、令和4年3月31日24時をもって満1年となります。令和4年3月31日24時を暦日で考えて、1歳に達するのは令和4年3月31日となります。
では、過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
②【R1年出題】
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
③【H26年出題】
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

【解答】
①【H30年出題】 〇
第1号被保険者・第3号被保険者は、「60歳に達したとき」に資格を喪失します。
「60歳に達したときに該当するに至った日(当日)」に資格を喪失しますが、「60歳に達した日」は60歳の誕生日の前日です。
②【R1年出題】 ×
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達するのは、平成31年3月31日です。
被保険者期間は、「資格を取得した日の属する月」からスタートしますので、被保険者期間に算入されるのは、平成31年3月からです。
(法第11条)
③【H26年出題】 ×
昭和29年4月1日生まれの者が60歳に達するのは、平成26年3月31日です。
被保険者期間は、「資格を喪失した日の属する月の前月まで」ですので、被保険者期間に算入されるのは、平成26年2月までです。
(法第11条)
では、「被保険者期間」の条文を穴埋めで確認しましょう。
第11条 (被保険者期間の計算)
1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の< A >からその資格を喪失した日の< B >までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を< C >として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

【解答】
A 属する月
B 属する月の前月
C 1か月
例えば、「昭和36年4月1日生まれ」の第1号被保険者の場合、資格取得は20歳に達する日(昭和56年3月31日)、資格喪失は60歳に達する日(令和3年3月31日)です。
被保険者期間に算入されるのは、昭和56年3月から令和3年2月までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-100
R3.11.30 障害基礎年金の併合認定
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「障害基礎年金の併合認定」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9A】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【R3年問9A】 〇
障害基礎年金の受給権者に更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。
「障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中」でも、障害基礎年金の受給権者であることに注意してください。
(法第31条)
もう一問どうぞ!
②【H26年出題】
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。

【解答】
②【H26年出題】 ×
どちらかを選択するのではなく、前後の障害が併合されます。
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金の受給権者に、更に足の障害による障害等級1級の障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。
前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した場合は、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。
(法第31条)
条文を穴埋めで確認しましょう
第31条 (併給の調整)
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、< A >した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
障害基礎年金の受給権者が< A >した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、< B >する。

【解答】
A 前後の障害を併合
B 消滅
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-099
R3.11.29 時効消滅不整合期間
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「時効消滅不整合期間」です。
では、どうぞ!
①【R3年問3E】
被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。

【解答】
①【R3年問3E】 ×
「法定免除期間」ではなく、「学生納付特例期間」とみなされます。年金の受給資格期間には算入されますが、年金の額には反映しません。
★「時効消滅不整合期間」とは?
例えば、夫が会社員(第2号被保険者)、妻が専業主婦(第3号被保険者)の夫婦で、夫が退職し自営業になった場合の国民年金の種別を考えてみましょう。
夫は第2号被保険者から第1号被保険者に、妻は第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更になります。
その際、妻が第3号から第1号への種別変更の届出をしていなかったとすると、実態は国民年金の第1号被保険者であったにもかかわらず、記録上は第3号被保険者のままになってしまいます。その期間のことを「不整合期間」といいます。
3号不整合記録を1号に切り替えると保険料を納付しなければなりませんが、2年の時効が経過した期間は保険料を納められません。その期間を「時効消滅不整合期間」といいます。
救済措置として「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」があります。この届出によって、「時効消滅不整合期間」は「特定期間」となります。
特定期間は「学生納付特例期間」とみなされ、年金の受給資格期間に算入されることになります。
なお、「特定期間」の対象は、昭和61年4月から平成25年6月までの間です。
(法附則第9条の4の2)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
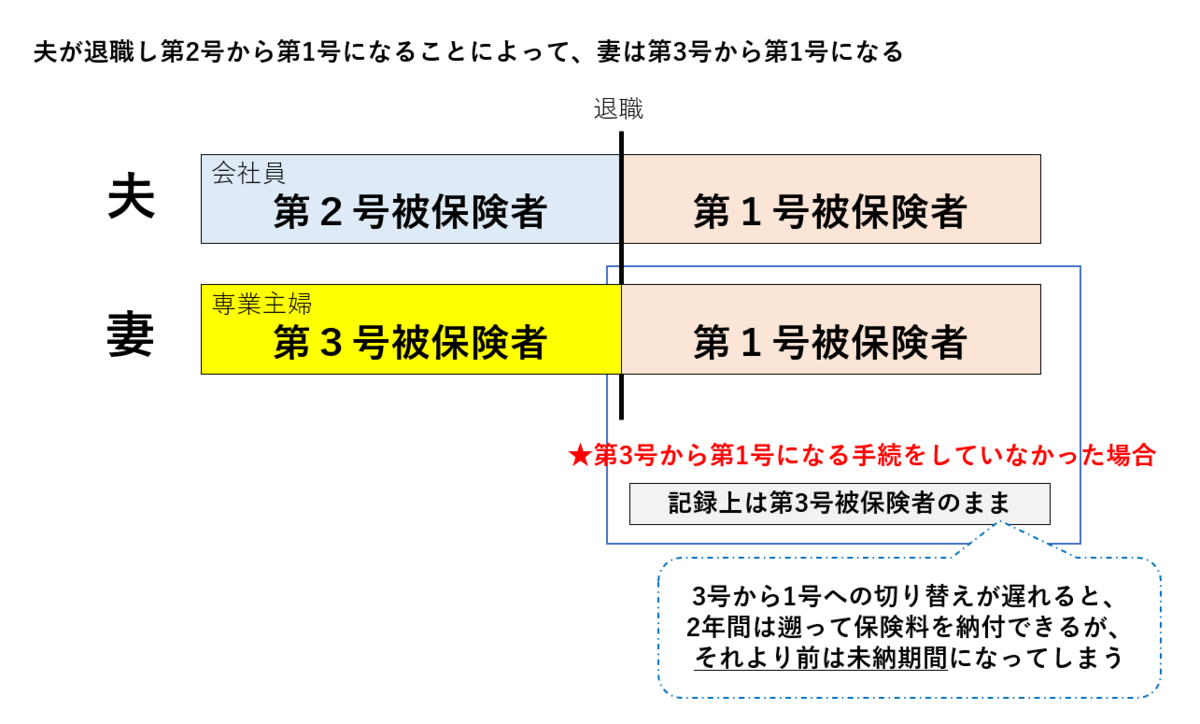
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-085
R3.11.15 国民年金基金加入員資格の喪失
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金基金加入員資格の喪失」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4エ】
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。
(注)基金=国民年金基金のことです。

【解答】
①【R3年問4エ】 ×
国民年金基金には、申し出による資格喪失の規定はありません。
(法第127条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。
③【H29年出題】
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。
④【H27年出題】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得する」の部分は正しいです。しかし①の問題で見たように、申出による資格喪失はできませんので、「喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失」の部分が誤りです。
(法第127条)
③【H29年出題】 〇
第2号被保険者は国民年金基金に加入できませんので、第2号被保険者となったときは、加入員の資格を喪失します。資格を喪失するのは「その日」がポイントです。
(法第127条)
④【H27年出題】 〇
国民年金保険料の全部又は一部について免除された時は、加入員の資格を喪失します。「その月の初日」に加入員の資格を喪失するのがポイントです。
(法第127条)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第127条第3項
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至ったときは、その日とし、第三号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた< A >とする。)に、加入員の資格を喪失する。
一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。
二 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。
三 保険料免除の規定によりその全部又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四 < B >の被保険者となったとき。
五 当該基金が< C >したとき。

【解答】
A 月の初日
B 農業者年金
C 解散
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-084
R3.11.14 国民年金と厚生年金の調整
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金と厚生年金の調整」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9D】
父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

【解答】
①【R3年問9D】 〇
基礎年金と厚生年金は支給事由が同じなら、2階建てで併給できます。
父が死亡したことによる「遺族基礎年金」と、祖父が死亡したことによる「遺族厚生年金」は、支給事由が異なります。そのため、問題文の遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給されず、どちらかを選択することになります。
(法第20条)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】※改正による修正あり
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について厚生年金保険法から同一の支給事由による年金たる保険給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。

【解答】
②【H24年出題】 ×
遺族基礎年金は、同一の支給事由による遺族厚生年金と併給されます。その場合、 遺族基礎年金も遺族厚生年金も、全額が支給されます。
(法第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-083
R3.11.13 寡婦年金と死亡一時金
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「寡婦年金と死亡一時金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
①【R3年問9E】 〇
同一人に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権が発生した場合の問題です。
ポイントその1
「一人一年金の原則」がありますので、「遺族厚生年金」と「寡婦年金」はどちらかを選択します。
ポイントその2
死亡一時金と寡婦年金については、「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」となっていますので、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
なお、遺族厚生年金と死亡一時金は調整されませんので、両方とも支給されます。
(法第20条、第52条の6)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
②【H24年出題】 ×
「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」です。
(法第20条、第52条の6)
こちらもどうぞ!
③【H25年出題】
『ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。』
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。

【解答】
③【H25年出題】 〇
寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみの選択になります。
死亡一時金と遺族厚生年金はどちらも受給できます。
(法第20条、第52条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-082
R3.11.12 受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき」です。
では、どうぞ!
①【R3年問6B】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

【解答】
①【R3年問6B】 ×
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、『将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす』と規定されています。
生まれたときから遺族になりますので、遺族基礎年金の額の改定は、「生まれた日の属する月の翌月から」となります。被保険者又は被保険者であった者の死亡した日までさかのぼりません。
(法第37条の2、第39条)
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
③【H13年出題】
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する。

【解答】
②【H30年出題】 ×
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、生まれたときに受給権が発生します。そして、「生まれた日の属する月の翌月から」遺族基礎年金の額が改定されます。
(法第37条の2、第39条)
③【H13年出題】 〇
「その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する」の部分がポイントです。
(法第37条の2、第39条)
条文を穴埋めで確認しましょう
第37条の2 (遺族の範囲)
1 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって< A >し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって< A >し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と< B >すること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、1の規定の適用については、< C >、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって< A >していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と< B >していたものとみなす。

【解答】
A 生計を維持
B 生計を同じく
C 将来に向かって
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-081
R3.11.11 一人一年金の原則(併給の調整)
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「一人一年金の原則(併給の調整)」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10B】
併給の調整に関し、国民年金法第20条第1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。

【解答】
①【R3年問10B】 〇
一人に対して、複数の年金の受給権が発生することがあります。年金は、「一人一年金」の原則があります。例えば、障害基礎年金と老齢基礎年金が支給されるときは、まず、両方の年金の支給が停止されます。障害基礎年金の受給を選択した場合は、障害基礎年金の支給停止が解除され、老齢基礎年金はそのまま支給停止となります。
その後、老齢基礎年金に選択替えをすることもできます。その場合、問題文のように、「支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。」となります。
(法第20条)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題】
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。
③【H25年出題】
併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

【解答】
②【H23年出題】 ×
「他方の年金の受給権は消滅」が誤りです。選択しなかった他方の年金は「支給停止」になります。
(法第20条)
③【H25年出題】 ×
いわゆる選択替えは、「いつでも、将来に向かって撤回することができる」と規定されています。「毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる」は誤りです。
(法第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-080
R3.11.10 国民年金基金の中途脱退者
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金基金の中途脱退者」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4ア】
国民年金基金(以下「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者をいう。

【解答】
①【R3年問4ア】 〇
国民年金基金における中途脱退者の要件は、
・基金の加入員資格を中途で喪失している
・資格を喪失した日に、当該基金が支給する年金の受給権を有しない
・当該基金の加入員期間が15年に満たない
の3つです。
(法第137条の17、基金令第45条)
★なお、国民年金基金連合会は、基金から年金の現価相当の移換を受け、中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行います。
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。
③【H23年出題】
A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。

【解答】
②【H30年出題】 ×
中途脱退者とは、「当該基金の加入員期間の年数にかかわらず」ではなく、「15年に満たない者」をいいます。
(基金令第45条)
③【H23年出題】 〇
基金の加入員期間は通算して20年になるので、中途脱退者ではありません。そのため、年金又は一時金の支給は、国民年金基金連合会からではなく、A県の地域型国民年金基金から受けることになります。
(法第137条の17)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-079
R3.11.9 国民年金~年金の支払調整(内払)
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金~年金の支払調整(内払)」です。
では、どうぞ!
①【R3年問2A】
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

【解答】
①【R3年問2A】 〇
「内払」は「同一人」に対する年金間の調整です。
国民年金と厚生年金保険は制度が違いますが、内払調整の対象となります。
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降も障害厚生年金が支払われたときは、障害厚生年金を返還し、改めて老齢基礎年金を支給するのではなく、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる、という規定です。
(法第21条)
こちらもどうぞ!
②【H22年出題 改正による修正あり】
障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。

【解答】
②【H22年出題 改正による修正あり】 ×
障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)と老齢基礎年金は、異なる制度の年金ですが、利便性に資するため、内払調整の対象となります。①の問題と同じです。
条文を穴埋めで確認しましょう!
第21条 第3項
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(< A >が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する< B >以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の< C >とみなすことができる。

【解答】
A 厚生労働大臣
B 月の翌月
C 内払
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-078
R3.11.8 国民年金種別の変更
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金種別の変更」です。
★ 被保険者の種別とは、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区分を言います。
では、どうぞ!
①【R3年問2C】
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
①【R3年問2C】 〇
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、翌日に被保険者の資格を喪失します。しかし、その時点で、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、資格喪失ではなく、「種別の変更」となります。
(法第9条)
こちらもどうぞ!
②【H20年出題】
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
②【H20年出題】 ×
第2号被保険者から第1号被保険者になるのは「種別変更」です。資格取得届ではなく「種別変更届」を、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に提出しなければなりません。
(法第12条、則第6条の2)
こちらもどうぞ!
③【H30年出題】
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者の種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

【解答】
③【H30年出題】 ×
同一月に、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があり、更に第3号被保険者への種別の変更があった場合は、その月は第2号被保険者ではなく、最後の種別の「第3号被保険者」であった月とみなされます。
(法第11条の2)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、< A >の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は< B >の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
A 変更後
B 最後
(法第11条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-077
R3.11.7 用語の定義~保険料免除期間
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「用語の定義~保険料免除期間」です。
では、どうぞ!
①【R3年問6E】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

【解答】
①【R3年問6E】 〇
「保険料免除期間」には、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間の4種類があります。
そのうち、保険料の一部が免除されるのは、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間の3種類です。
例えば、「保険料半額免除期間」とは、その半額につき納付することを要しないものとされた保険料に係るものをいいますが、「納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。」とされています。
例えば、令和3年度の国民年金の保険料は、16610円です。半額免除の場合、8,300円が免除され、残りの8,310円を納付した期間は、「保険料半額免除期間」となります。「保険料納付済期間」ではありませんので、注意しましょう。
なお、残りの8,310円を納付しない場合は未納期間となります。
(法第5条)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
その一部の額が免除された保険料については、その残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間ではなく、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間のどれかとなります。
(法第5条)
③【H24年出題】 〇
②の問題と同じです。保険料納付済期間ではなく保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間のどれかとなります。
(法第5条)
④【H24年出題】 〇
法第94条第4項で「追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす」と規定されています。保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
条文を穴埋めで確認しましょう!
第5条 (用語の定義)
国民年金法において、「< A >」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。
「保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定(< B >)により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

【解答】
A 保険料免除期間
B 追納
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-076
R3.11.6 第1号被保険者の条件
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「第1号被保険者の条件」です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

【解答】
①【R3年問3C】 〇
「日本の国籍を有しない者」で、次の①又は②に該当する場合は、国民年金の第1号被保険者から除外されます。
①在留資格が特定活動(医療滞在又は医療滞在者の付添人) (ア)本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの (イ)(ア)の活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの |
②在留資格が特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在又は長期滞在者の配偶者) 本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの |
問題文は②に該当するので、第1号被保険者からは除外されます。
※なお、①又は②に該当する場合は、第3号被保険者からも除外されます。
(則第1条の2)
こちらもどうぞ!
②【R1年出題】
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
国籍、年齢、国内居住要件は整理しておきましょう。
| 国籍 | 年齢 | 国内居住 | |
第1号被保険者 | 問わない | 20歳~60歳 | あり |
| 第2号被保険者 | 問わない | なし | |
| 第3号被保険者 | 20歳~60歳 | あり (例外あり) |
条文を穴埋めで確認しましょう!
第7条(被保険者の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 < A >を有する< B >の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2 < C >の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
3 第2号被保険者の配偶者(< A >を有する者又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち< B >のもの(以下「第3号被保険者」という。)

【解答】
A 日本国内に住所
B 20歳以上60歳未満
C 厚生年金保険
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-068
R3.10.29 第3号被保険者の国内居住要件
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「第3号被保険者の国内居住要件」です。
では、どうぞ!
①【R3年問3A】
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【R3年問3A】 ×
外国に赴任する第2号被保険者に同行するため海外に行く場合は、第3号被保険者の資格は喪失しません。
★第3号被保険者には、健康保険法の被扶養者の認定要件と同様、国内居住要件があります。
ただし、日本国内に住所がなくても、「外国に留学をする学生」、「外国に赴任する被保険者に同行する者」、「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者」など、日本国内に生活の基礎があると認められる者は、国内居住要件の例外として認められます。
(法第7条、則第1条の3、R元.11.13保保発1113第1号)
こちらもどうぞ!
②【R3年問3B】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
②【R3年問3B】 〇
「第3号被保険者」は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。
厚生年金保険法の被保険者は第2号被保険者となります。ただし、厚生年金保険の被保険者でも、「65歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者」は第2号被保険者になりません。
問題文の「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は第2号被保険者ではないので、その収入によって生計を維持していても、55歳の配偶者は、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となります。
(法第7条、法附則第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-065
R3.10.26 障害基礎年金事後重症の事例問題より
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「事後重症の障害基礎年金の事例問題」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10C】
22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】
①【R3年問10C】 ×
事後重症の障害基礎年金の受給権は発生します。
※事後重症の条件は、「65歳に達する日の前日まで」の間に障害等級(1級又は2級)に該当すること+「65歳に達する日の前日まで」に請求することです。
ちなみに、この女性の年金についてもう少し見てみましょう
・特別支給の老齢厚生年金について(第1号厚生年金被保険者の女性の場合)
昭和33年4月2日生まれの場合、61歳から、「報酬比例部分」のみの老齢厚生年金が支給されます。
ただし、「障害者の特例」が適用され、「障害等級3級以上の障害の状態にある」+「被保険者でない」+「請求する」ことによって、「定額部分」も支給されます。
・障害基礎年金について
初診日 → 国民年金の被保険者である(問題文の場合は第3号被保険者)
保険料納付要件 → 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間だけで3分の2以上ある
※第2号被保険者と第3号被保険者には「保険料免除期間」も「未納」もありません。
障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当しなくても、要件を満たせば、事後重症の障害基礎年金の請求が可能です。
こちらもどうぞ!
②【H21年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
③【H24年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。

【解答】
②【H21年出題】 ×
事後重症の障害基礎年金を請求できるのは、65歳に達する日の前日までの間です。
(法第30条の2)
③【H24年出題】 〇
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、事後重症の障害基礎年金は請求できません。
(法附則第9条の2の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-057
R3.10.18 国年「併給できる年金、できない年金」
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は併給できる年金、できない年金です。
では、どうぞ!
①【R3年問9C】
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

【解答】
①【R3年問9C】 ×
★ポイント①
65歳未満でも65歳以上でも年齢に関係なく、「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」は併給できませんので、この問題は誤りです。
★ポイント②
(2級なのに障害基礎年金の受給権が発生しない理由)
65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、かつ老齢の年金の受給権がある場合は、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
初診日に厚生年金保険の被保険者であるものの、65歳以上で老齢年金の受給権がある場合は、国民年金の被保険者ではありません。そのため、障害等級2級に該当しても、「障害厚生年金」の受給権は発生しますが、「障害基礎年金」の受給権は発生しません。
★ポイント③
問題文の場合、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」と「2級の障害厚生年金」のどちらかを選択することになります。
(法第7条、法第20条、法附則第3条)
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
③【H26年出題(改正による修正あり)】
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
65歳以上でも65歳未満でも、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」は併給できません。
(法第20条)
③【H26年出題】 ×
原則として、厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者です。
ただし、65歳以上で「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有している」場合は、第2号被保険者から除外されます。
問題文のように、65歳以上で、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権なし、障害の年金給付の受給権あり」の場合は、第2号被保険者となります。
(法第7条、法附則第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)国民年金法 応用問題
R4-048
R3.10.9 国年「20歳前傷病による障害基礎年金の国庫負担」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は国民年金法です。
では、どうぞ!
①【R3年問5E】
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。

【解答】
①【R3年問5E】 ×
20歳前の傷病による障害基礎年金は、他の年金と比較して国庫負担率を高くすることになっています。
まず、給付費の100分の20を特別に国庫負担することになっています。
残りの部分(100分の80)については、原則どおりの「2分の1」の国庫負担が行われます。
合計して、国庫負担率は100分の60となります。
(法第85条)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、100分の20(特別国庫負担)+(100分の80×2分の1)で、6割が国庫負担となります。
(法第85条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)国民年金法よく出るところ
R4-038
R3.9.29 国年「任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は国民年金法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1C】
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

【解答】
①【R3年問1C】 ×
老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失するのは、「特例よる任意加入被保険者」です。任意加入被保険者は、その事由では資格喪失しません。
ポイント!「任意加入する目的」をおさえましょう。
「任意加入被保険者」は、「老齢年金の受給権を得るため」、「老齢基礎年金の額を増やすため」に任意加入することができます。ですので、老齢年金の受給権ができても資格は喪失しません。
一方、「特例による任意加入被保険者」の目的は「老齢年金の受給権を得るため」だけです。そのため、目的が達成すると(老齢年金の受給権を取得すると)その翌日に資格を喪失します。「老齢基礎年金の額を増やす」目的では特例による任意加入はできませんので、注意しましょう。
(法附則第5条、H6法附則第11条)
では、こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

【解答】
②【H27年出題】 ×
「特例による任意加入被保険者」となることができるのは、「昭和40年4月1日以前生まれ」に限られます。
ポイント!
「特例による任意加入被保険者」は「昭和40年4月1日以前生まれ」という生年月日の要件がつきますが、「任意加入被保険者」には生年月日の要件はありません。
(H16法附則第23条)
次はこちらをどうぞ!
③【H28年出題】
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

【解答】
③【H28年出題】 〇
任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違いをチェックしておきましょう。
| 任意加入被保険者 | 特例による任意加入被保険者 | |
| 付加保険料 | 〇 納付できる | × 納付できない |
| 寡婦年金 | 〇 支給される | × 支給されない |
| 死亡一時金 | 〇 支給される | 〇 支給される |
| 脱退一時金 | 〇 支給される | 〇 支給される |
(法附則第5条、H6法附則第11条)
★ワンポイントアドバイス 覚え方★
死亡一時金と脱退一時金は、生活保障というよりも掛捨て防止の意味合いが大きいです。掛捨て防止の給付は、特例による任意加入被保険者も対象になる、と覚えましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)国民年金法の定番問題
R4-028
R3.9.19 老齢基礎年金の計算と国庫負担
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は国民年金法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

【解答】
①【R3年問1B】 〇
老齢基礎年金の国庫負担のポイント!
・保険料4分の1免除期間 → (480-保険料納付済期間の月数)を限度として国庫負担の対象となる
・学生納付特例及び納付猶予の期間 → 国庫負担の対象とならない
(法第85条)
では、こちらもどうぞ!
②【H19問7D】
保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。
③【H29問7B】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【解答】
②【H19問7D】 ×
保険料4分の1免除期間については、8分の7が老齢基礎年金の額に反映されます。
(480-保険料納付済期間の月数が限度)
なお、60歳以降に国民年金に任意加入して、保険料納付済期間+保険料免除期間の月数が480月を超えることがあります。
4分の1免除期間について国庫負担が入るのは(480-保険料納付済期間の月数)が限度です。それを超える4分の1免除期間は、国庫負担がないため「8分の3」で計算されます。(下図参照)
(法第27条)
③【H29問7B】 〇
学生納付特例の期間と納付猶予の期間については国庫負担がないので、老齢基礎年金は、「ゼロ」で計算されます。
保険料が追納されていれば、保険料納付済期間としてフルで計算されます。
(法第27条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
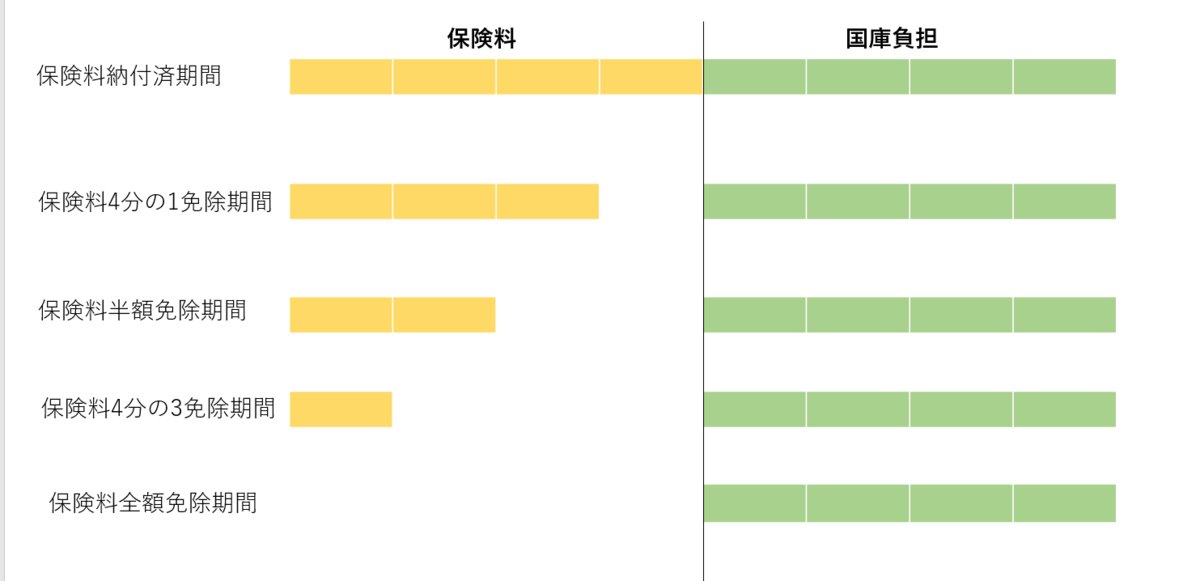
第53回試験・国民年金法【択一】
R4-021
R3.9.12 第53回国年(択一)より~令和3年度の給付額
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 問題文が長いのが特徴です。(国民年金法に限りませんが・・・)「ポイント」を早く見つけないと、問題を解くのに時間がかかってしまいます。日々、勉強をする際に、「納得」することが必要なのでは?と思います。「これはこういうことなんだ」と納得すると、頭に入りやすいし、本試験でもポイントが見つけやすく、そして応用も効くと思います。
【R3年問8】令和3年度の給付額について
(問8-A)
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円)となる。
(問8-B)
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円に端数処理を行った、976,100円となる。
(問8-C)
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
(問8-D)
国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12万円に(1-0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
(問8-E)
第1号被保険者として令和3年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和3年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額とする。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

【解答】
(問8-A) ×
昭和31年4月2日生まれの者が、満額の老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間が480月あることが条件です。
問題文の場合、保険料納付済期間が、360月(30年)+60月(5年)=420月、保険料全額免除期間が120月(10年)です。
全額免除期間の計算を考えてみましょう。
問題文の場合、
・保険料全額免除期間は平成21年3月以前の期間なので、3分の1で計算される
・3分の1で計算されるのは、480月から保険料納付済期間(420月)を控除した月数(60月)が限度となる
そのため、老齢基礎年金の額は満額になりません。
(法第27条、H16附則第9条)
(問8-B) ×
障害等級1級の障害基礎年金の額は、976,125円です。問題文のような端数処理は行いません。
条文を確認しましょう。
法第33条 ① 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、①の規定にかかわらず、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 |
2級の障害基礎年金は、780,900円×改定率ですが、100円単位になるよう端数処理を行います。
1級の障害基礎年金は2級の額×1.25ですが、100円単位の端数処理の規定がついていないので、原則のルールである1円単位で計算します。
(法第33条、法第17条)
(問8-C) ×
遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合、1人目には加算がつかないのがポイントです。
例えば、子が1人の場合は、遺族基礎年金の額は780,900円です。
2人目から加算がつき、問題文の場合は、2人目224,700円+3人目74,900円+4人目74,900円が加算されます。
(法第39条の2)
(問8-D) ×
死亡一時金の額には、改定率は適用されません。
(法第52条の4)
(問8-E) 〇
脱退一時金は、「基準月の属する年度の保険料額×2分の1×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数」で計算します。
この問題は、「50か月」保険料を納付しているので、「48」を掛ける点がポイントです。
詳細はこちらの記事をどうぞ→ 国年【令和3年4月改正】脱退一時金の改正 (R3.6.27【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(国民年金法)
R4-010
R3.9.1 第53回選択国年~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「国民年金法」の選択式です。
問題1 調整期間(第16条の2)
調整期間の条文は、15年前の平成18年にも選択式で出題されています。選択式も過去問のチェックは欠かせません。
とはいいましても、Aの選択肢は、文脈で考えてしまって、結果として迷った方も多かったのではないでしょうか?
財政均衡期間に財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合は、給付額を調整するため、マクロ経済スライドを適用しますが、給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度は政令で定めることとなっています。
なお、調整期間の開始年度は、政令(施行令第4条の2の2)で、「平成17年度」とされています。
問題1 ★☆☆ 暗記が肝心
問題2 公課の禁止(第25条)
こちらも見慣れた条文ですが、「基準」か「標準」かで迷いませんでしたか?
一字一句覚えていれば迷わないのですが、なかなかそこまで覚えるのは難しいので。
「老齢基礎年金と付加年金」は例外的に課税対象になるという点は、解けたと思います。
問題2 ★☆☆ 暗記が肝心
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金法 選択対策
R3-357
R3.8.15 国民年金法 選択問題(老齢基礎年金の繰上げと繰下げ)
今日は国民年金の選択対策。テーマは「老齢基礎年金の繰上げと繰下げ」です!
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
<H21年選択式 出題> ※改正による修正あり
1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「納付猶予」の期間を除く。)を有する者であって、< A >であるもの(< B >でないものに限るものとし、法附則第9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、< C >に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。
2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が、< C >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< D >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< E >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< C >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】
A 60歳以上65歳未満
B 任意加入被保険者
C 65歳
D 付加年金
E 老齢
(法附則第9条の2、法第28条)
では、過去問もどうぞ!
①<H23年出題>
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
②<H26年出題>
任意加入被保険者である者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることはできない。
③<H23年出題>
繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】
①<H23年出題> ×
繰上げ支給は、「国民年金法の附則において当分の間の措置」として規定されています。一方、繰下げ支給は、附則ではなく本則で規定されています。
繰上げ → 法附則9条の2
繰下げ → 法第28条
②<H26年出題> 〇
任意加入被保険者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求はできません。
(法附則第9条の2)
③<H23年出題> ×
「支給停止」が誤り。寡婦年金の受給権は「消滅」します。
寡婦年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の繰上げの請求をして、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。
(法附則第9条の2第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金基金のこと
R3-339
R3.7.28 国民年金基金の給付について
今日のテーマは「国民年金基金の給付」です。
では条文をチェックしましょう!
空欄を埋めてください。
第115条 (基金の給付)
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第1条の目的を達成するため、加入員の< A >に関して必要な給付を行なうものとする。
第128条 (基金の業務)
基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の< B >に関し、一時金の支給を行なうものとする。

【解答】
A 老齢
B 死亡
(法第115条、第128条)
では、こちらをどうぞ!
①<H15年出題>
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。
②<H29年出題>
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】
①<H15年出題> 〇
国民年金基金は、老齢に関して「年金」、死亡に関して「一時金」の給付を行います。障害や脱退に関する給付は行いません。
②<H29年出題> 〇
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、「国民年金基金」が裁定するのがポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
(法第133条)
では、こちらもどうぞ
③<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときから3年を限度に、その者に支給されるものでなければならない。
④<H16年出題>
基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
⑤<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金額は、200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

【解答】
③<H22年出題> 〇
基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が『老齢基礎年金の受給権を取得したとき』には、その者に支給されるものでなければならない、とされています。
また、老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該『老齢基礎年金の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない』とされています。
老齢基礎年金の上乗せのイメージです。
(法第129条)
④<H16年出題> ×
「死亡一時金又は遺族基礎年金」ではなく、『その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない』とされています。
(法第129条)
⑤<H22年出題> ×
一時金の額については下限が定められていて、『基金が支給する一時金の額は、8,500円を超えるものでなければならない』とされています。
(法第130条)
最後にポイントを穴埋めでチェックしましょう
第129条 (基金の給付の基準)
1 基金が支給する年金は、少なくとも、当該基金の加入員であった者が< A >の受給権を取得したときには、その者に支給されるものでなければならない。
2 < A >の受給権者に対し基金が支給する年金は、当該< A >の受給権の消滅事由以外の事由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
3 基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が< B >を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
第130条
1 基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
2 老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、< C >円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
3 基金が支給する一時金の額は、< D >円を超えるものでなければならない。

【解答】
A 老齢基礎年金
B 死亡一時金
C 200
D 8,500
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
20歳前傷病による障害基礎年金その3
R3-338
R3.7.27 20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止ルール②
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。
昨日の続きです。
ではこちらからどうぞ!
①<H25年出題>
国民年金法第34条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
②<H27年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

【解答】
①<H25年出題> ×
支給停止されるのは、「全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1」ではなく、「全部又は2分の1」に相当する部分です。
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★所得による支給制限がある
前年の所得額(扶養親族等がいない場合)
4,621,000円を超える → 年金の全額が支給停止
3,604,000円を超え4,621,000円以下 → 2分の1の年金額が支給停止
3,604,000円以下 → 全額支給される(支給停止なし)
(法第36条の3)
②<H27年出題> ×
「受給権者」の前年の所得で判断されます。扶養親族の所得は合算しません。
では、こちらもどうぞ
③<H25年出題>
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
③<H25年出題> ×
3分の1以上ではなく「2分の1」以上です。
20歳前傷病による障害基礎年金は、所得による支給制限がありますが、被災し、住宅、家財又はその他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた場合は、当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わないことになっています。
(法第36条の4)
最後にこちらをどうぞ
④<H17年出題>
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までその支給を停止される。

【解答】
④<H17年出題> ×
20歳前に初診日があっても、初診日に第2号被保険である場合は、20歳前の傷病による障害基礎年金ではなく、一般の障害基礎年金が支給されます。ですので、所得による支給停止はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
20歳前傷病による障害基礎年金その2
R3-337
R3.7.26 20歳前傷病の障害基礎年金の支給停止ルール①
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、保険料の負担なく受給できる年金です。そのため、一般の障害基礎年金には無い、独自の支給停止ルールがあります。
ではこちらからどうぞ!
①<H25年出題>
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】
①<H25年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★日本国内に住所を有しないときは支給停止
(一般の障害基礎年金は、日本国内に住所を有しなくても支給停止にはなりません。)
(法第36条の2)
次はこちらをどうぞ
②<H30年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。

【解答】
②<H30年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」、「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給停止
(一般の障害基礎年金は、このような施設に収容されていても支給停止になりません。)
(法第36条の2、則第34条の4)
次はこちらを!
③<R1年出題>
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
④<H25年出題>
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
⑤<H20年出題>
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

【解答】
③<R1年出題> 〇
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント
★「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは支給停止
(一般の障害基礎年金はこの理由では支給停止になりません)
④<H25年出題> 〇
③の問題でみたように、「労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる」ときは20歳前の傷病による障害基礎年金は支給停止になります。しかし、労災保険法の年金たる給付が全額支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は原則として支給停止されません。
⑤<H20年出題> 〇
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、労災保険法の障害補償年金を受けることができるときでも、その支給は停止されません。
明日も続きます!
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
20歳前傷病による障害基礎年金その1
R3-336
R3.7.25 20歳前傷病の障害基礎年金の受給要件
今日のテーマは、「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給要件です。
では条文チェックからどうぞ!
空欄を埋めてください。
第32条の4第1項(20歳前傷病による障害基礎年金)
疾病にかかり、又は負傷し、その< A >において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは< B >において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその< C >において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。

【解答】
A 初診日
B 20歳に達した日
C 障害認定日
20歳前傷病による障害基礎年金のポイント!
●初診日に20歳未満である=国民年金の被保険者でない
●受給権の発生
・ 障害認定日以後に20歳に達した
→ 20歳に達した日に1級または2級の障害状態にあれば20歳に達した日
・ 障害認定日が20歳に達した日後
→ 障害認定日に1級または2級の障害状態にあれば障害認定日
では、こちらをどうぞ!
①<H26年出題>
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
②<H30年出題>
傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
③<H22年出題>
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

【解答】
①<H26年出題> ×
問題文の場合、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」です。
「20歳に達した日」、「障害認定日」どちらが後に来るかがポイントです。
「障害認定日」は初診日から1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は治った日)です。
問題文の場合、25歳現在、「継続して治療している」状況なので、障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日となります。
そして、初診日に19歳なので、障害認定日は20歳に達した日よりも後になります。
ですので、「20歳に達した日」ではなく「障害認定日」の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に「20歳前傷病による障害基礎年金」の受給権が発生します。
②<H30年出題> ×
「初診日」に19歳であったこと(国民年金の被保険者ではない)がポイントです。
「初診日に国民年金の被保険者でない」、「障害認定日に障害等級1級、2級に該当している」ので、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。
第1号被保険者の資格を取得した後、全て未納期間であったことは関係ありません。
③<H22年出題> ×
「障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降」の部分が誤りです。
初診日が20歳未満でも、その初診日において「厚生年金保険の被保険者」だったことがポイントです。
初診日に厚生年金保険の被保険者(=国民年金の第2号被保険者)ですので、障害認定日に障害等級に該当していれば、「障害認定日」に障害基礎年金と障害厚生年金の受給権が発生します。
初診日に国民年金の被保険者ですので、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。
★明日は、「通常の障害基礎年金」と「20歳前の傷病による障害基礎年金」の違いをお話しします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民年金第2号被保険者のこと
R3-335
R3.7.24 厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者(原則)
厚生年金保険の被保険者は、国民年金法の第2号被保険者です。
第2号被保険者のポイントは以下の3つです。
・国籍要件なし
・国内居住要件なし
・年齢要件(20歳以上60歳未満)なし
ではどうぞ!
①<H29年出題>
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②<H20年出題>
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①<H29年出題> 〇
第1号被保険者と第3号被保険者は年齢要件(20歳以上60歳未満)がありますが、第2号被保険者にはそれがないので、20歳未満でも厚生年金保険の被保険者なら国民年金の第2号被保険者です。
(法第7条)
②<H20年出題> ×
第2号被保険者は60歳に達しても資格は喪失しません。
★第1号被保険者と第3号被保険者は、60歳に達した日に資格を喪失します。
では、こちらをどうぞ!
③<H25年出題>改正による修正あり
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住所を有する配偶者(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。
④<H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
★厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される「70歳未満」の者です。
といっても、厚生年金保険の被保険者すべてが国民年金の第2号被保険者となるわけではありません。
厚生年金保険の被保険者が第2号被保険者になる要件として、「65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない被保険者に限る。」という規定が法附則第3条にありますので注意してください。
③<H25年出題> 〇
ポイントその1
★厚生年金保険の高齢任意加入被保険者(70歳以上)は国民年金の第2号被保険者。
なぜなら、「老齢基礎年金、老齢厚生年金等」の受給権がないから。
ポイントその2
第3号被保険者は「第2号被保険者」の配偶者。
問題文の場合、第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満ですので、第3号被保険者となります。
④<H27年出題> 〇
問題文の場合、年齢が「65歳以上」で「厚生年金保険の在職老齢年金を受給する」(老齢の年金の受給権がある)ため、第2号被保険者ではありません。
ですので、生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者でも、「第2号被保険者」の被扶養配偶者ではないので、第3号被保険者とはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国年 令和3年度の年金額
R3-312
R3.7.1 令和3年度の年金額の改定について
老齢基礎年金の満額は、780,900円×改定率です。
令和3年度の改定率は「1.000」ですので、令和3年度の年金額は、780,900円×1.000=780,900円となります。
今日のテーマは、改定率が「1.000」になった根拠です。
まずは、こちらからどうぞ!
<R2年出題>
年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また68歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。

【解答】 ×
改定の基準が逆です。正しくは次の通りです。
・68歳に到達する年度前(新規裁定者)→ 名目手取り賃金変動率
・68歳に到達した年度以後(既裁定者) → 物価変動率
(法第27条の2)

今回の指標は、
・ 物価変動率 → 0.0%
・ 名目手取り賃金変動率 → ▲0.1%
となりました。賃金がマイナスになっていることに注目してください。
ポイント!
既裁定者は原則として「物価変動率」が基準ですが、令和3年4月より、『物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、「名目手取り賃金変動率」を基準とする。』と改正されています。(法第27条の3)
今回は、「名目手取り賃金変動率がマイナス0.1%、物価変動率は0.0%」です。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回っていますので上の条件に当てはまり、既裁定者も「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されています。
つまり、令和3年度は、新規裁定者・既裁定者とも、『名目手取り賃金変動率(▲0.1%)』を基準に改定されています。
令和2年度の改定率が「1.001」でしたので、そこからマイナス0.1%して、今年度の改定率は「1.000」です。
ちなみに、名目手取り賃金変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドは行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和3年度の国民年金保険料
R3-309
R3.6.28 【国年】令和3年度の保険料の計算根拠
令和3年度の国民年金保険料の計算根拠が今日のテーマです。
まずはこちらをどうぞ!
令和元年度以後の年度に属する月の月分の保険料の額は、< A >に保険料改定率を乗じて得た額(その額に< B >円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< B >円以上< C >円未満の端数が生じたときは、これを< C >円に切り上げるものとする。)とする。

【解答】
A 17,000
B 5
C 10
令和元年度以後の保険料は、「17,000円×保険料改定率」で計算します。
端数は、5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切り上げます。(保険料額は10円単位まで)
さて、令和3年度の保険料改定率は「0.977」ですので、
令和3年度の国民年金の保険料は、17,000円×0.977
10円未満を四捨五入で端数処理して、「16,610円」です。
★「保険料改定率」の改定基準は?
保険料改定率は、「前年度保険料改定率 × 名目賃金変動率」となります。
名目賃金変動率は、簡単に言うと「物価変動率 × 実質賃金変動率」です。
 保険料の改定は「保険料改定率」。保険料改定率は、名目賃金変動率を基準にしています。
保険料の改定は「保険料改定率」。保険料改定率は、名目賃金変動率を基準にしています。
一方、年金額の改定は「改定率」。改定率は、原則として、新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」、既裁定者は「物価変動率」が基準になります。
名目手取り賃金変動率は、簡単に言うと、「物価変動率 × 実質賃金変動率×可処分所得割合変化率」です。
「名目賃金変動率」と「名目手取り賃金変動率」は違うので注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国年 【令和3年4月改正】脱退一時金の改正
R3-308
R3.6.27 【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ
令和3年4月の脱退一時金の改正が今日のテーマです。
脱退一時金の支給額の計算に使う月数の上限が36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
特定技能1号の創設で期限付きの在留期間の最長期間が5年となったこと、短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等による見直しです。
まずは条文の穴埋めをどうぞ!
附則第9条の3の2 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第3項 脱退一時金の額は、基準月(請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。)の属する年度における保険料の額に< A >を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とする。

【解答】
A 2分の1
◇脱退一時金の額の計算式
基準月の保険料額×2分の1×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数
政令で定める数は施行令14条の3の2に次のように規定されています。
| 6月以上12月未満 | 6 |
| 12月以上18月未満 | 12 |
| 18月以上24月未満 | 18 |
| 24月以上30月未満 | 24 |
| 30月以上36月未満 | 30 |
| 36月以上42月未満 | 36 |
| 42月以上48月未満 | 42 |
| 48月以上54月未満 | 48 |
| 54月以上60月未満 | 54 |
| 60月以上 | 60 |
 6の倍数なので覚えやすいです。
6の倍数なので覚えやすいです。
★例えば、基準月が令和3年度にあり、保険料納付済期間等の月数が60月の場合の脱退一時金の額は、
16,610円(令和3年度の保険料額)×2分の1×60=498,300円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国年 【令和3年4月改正】寡婦年金
R3-307
R3.6.26 寡婦年金の改正されたところをチェック
今日は、「寡婦年金」の改正点をチェックしましょう。
まずは条文の穴埋めをどうぞ!
第49条 寡婦年金の支給要件
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が < A >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< A >年以上継続した< B >の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、老齢基礎年金又は< C >の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。

【解答】
A 10
B 65歳未満
C 障害基礎年金
令和3年4月の改正点は?
・改正前
死亡した夫が、「障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は寡婦年金は支給されない
↓
・改正後
「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したとき」は寡婦年金は支給されない
◇改正で、死亡した夫の障害基礎年金の受給状況の条件が、老齢基礎年金と同じになりました。
◇改正前は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、実際に障害基礎年金を受けていなくても、寡婦年金は支給されませんでした。(夫が障害基礎年金の受給権者であったというだけで寡婦年金は支給されなかった)
改正後は、夫に障害基礎年金の受給権があったとしても、実際に障害基礎年金を受けていない場合は、寡婦年金は支給されることになりました。
ちなみに、「障害基礎年金の受給権があるが、実際に障害基礎年金を受けていない」ってどんなとき? → 『障害基礎年金の受給権発生日と死亡日が同じ月』のときです。
こちらもどうぞ!
①<H20年出題>
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
②<H20年出題>
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。

【解答】
①<H20年出題> ×
「60歳以上65歳未満の妻」ではなく「65歳未満の妻」が対象です。
妻が60歳未満の場合は、60歳から寡婦年金が支給されます。(②の問題)
(法第49条)
②<H20年出題> 〇
寡婦年金は60歳から65歳まで支給される有期年金です。
年金は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から、「権利が消滅した日の属する月」まで支給されます。
寡婦年金は夫の死亡によって支給されるので、60歳以上の妻の場合は、「夫の死亡した日の属する月の翌月」から支給されます。夫の死亡当時に妻が60歳未満の場合は、「妻が60歳に達した日の属する月の翌月」から支給を始める、と規定されています。
そして寡婦年金は65歳で失権しますので、最大で「65歳に達した日の属する月」まで支給されます。
(法第18条、第49条3項、51条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害 3級から2級への額の改定 その3
R3-280
R3.5.30 事後重症のポイント(国民年金)その2
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、国民年金の視点に戻ります。
事後重症は「65歳に達する日の前日まで」に障害等級に該当、その期間内に請求するという条件がポイントでした。
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H22年出題>
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。
②<H30年出題>
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】
①<H22年出題> ×
問題文の場合、障害基礎年金に係る事後重症の請求は要りません。
障害の程度が増進し障害厚生年金の額が改定されたときは、そのときに事後重症の請求があったものとみなすことになっているからです。ですので、事後重症の請求をしなくても障害基礎年金が支給されます。(図1参照)
(法第30条の2)
②<H30年出題> ×
①の問題と同じく「障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない」の部分が誤りです。
障害厚生年金が3級から2級に改定されたときに、事後重症の請求をしたものとみなされます。
(法第30条の2)
社労士受験のあれこれ
図1
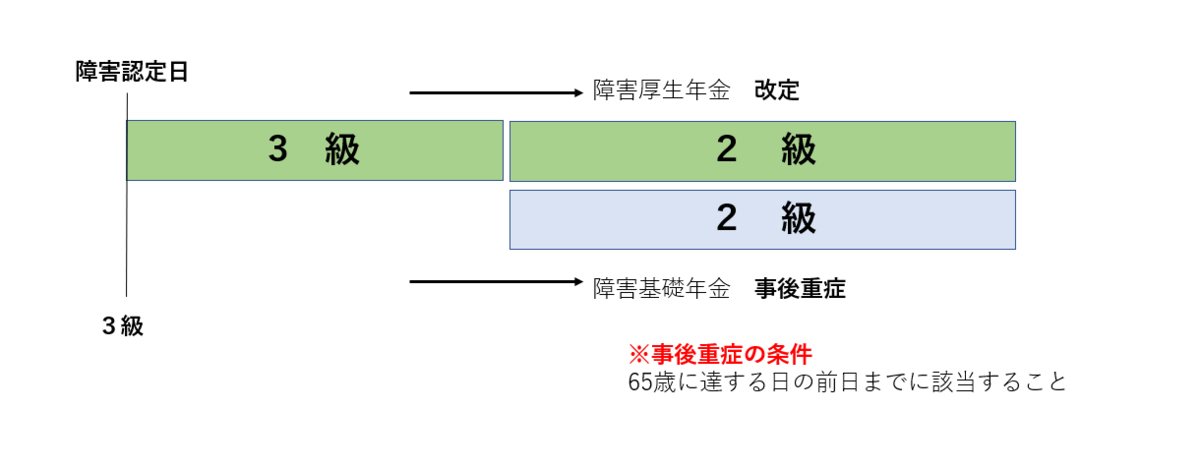
障害 3級から2級への額の改定 その1
R3-278
R3.5.28 事後重症のポイント(国民年金)その1
障害認定日に障害等級3級だった人がその後2級になった場合、「国民年金」「厚生年金保険」でそれぞれ視点が違います。
今日は、国民年金の視点で見ていきましょう。
国民年金の場合、「障害認定日に障害等級に該当していない」その後「障害等級に該当した」ということで「事後重症」になります。
※ 国民年金の「障害等級」は1級、2級です。(厚生年金保険の「障害等級」は1級、2級、3級です。)
では、どうぞ!
①<H18年出題>
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日おいて障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
②<H21年出題>
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
③<R1年出題>
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。

【解答】
①<H18年出題> 〇
 この問題の事後重症のポイント!
この問題の事後重症のポイント!
■65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の前々日)までに
・障害の程度が2級以上の状態に該当すること
・請求すること
(法第30条の2)
②<H21年出題> ×
「その者の年齢に関わりなく」が誤りです。
事後重症の障害基礎年金は、障害認定日後『65歳に達する日の前日まで』の間に請求することが条件です。
③<R1年出題> 〇
受給権が発生する日をおさえましょう。
(通常の障害基礎年金)障害認定日に障害等級に該当 → 障害認定日に受給権発生
事後重症の障害基礎年金 → 支給請求日に受給権発生
※事後重症の障害基礎年金は、請求日に受給権が発生し、請求日が属する月の翌月分から支給されます。請求が遅れると、支給開始時期も遅くなります。
(法第30条の2)
社労士受験のあれこれ
国年 受給権者の届出(住基ネットとの関係)
R3-277
R3.5.27 受給権者の届出と機構保存本人確認情報
今日のテーマは国民年金「受給権者の届出と機構保存本人確認情報の関係」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H24年出題>
厚生労働大臣は、法第18条第3項に規定する年金の支払期月の前月において、住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

【解答】 ×
「年金の支払期月の前月」ではなく「毎月」行います。
住所や氏名の異動情報の取得を、月に1回行っています。
(則第18条)
次はこちらを
②<H25年出題>
老齢基礎年金の受給権者は、住所又は氏名を変更したときは、日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者については、当該届書を提出する必要はない。

【解答】
②<H25年出題> 〇
年金の受給権者は、氏名又は住所を変更したときは、14日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければなりません。
しかし、氏名変更届、住所変更届については、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はありません。
(則第19条、20条)
こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は要しない。
④<H27年出題>
老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方の機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。

【解答】
③<H24年出題> 〇
受給権者が死亡した場合は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければなりません。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができ、受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合は、国民年金法の規定による死亡の届出は不要です。
(法第105条、則第24条)
④<H27年出題> ×
「年金受給権者死亡届」の提出は省略できますが、「未支給年金請求書」の提出は省略できません。
(則第24条、25条)
社労士受験のあれこれ
国年 年金の支給期間
R3-275
R3.5.25 国年 年金の支給期間は、いつからいつまで?
今日のテーマは「年金の支給期間」です。
まず条文の確認からどうぞ!
法第18条 (年金の支給期間及び支払期月)
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の< A >から始め、権利が消滅した日の< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の < A >からその事由が消滅した日の< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

【解答】
A 属する月の翌月
B 属する月
C 前月
※年金は、月単位で支給されます。
ではこちらをどうぞ!
①<H27年出題>
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。
②<H23年出題>
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。

【解答】
①<H27年出題> ×
婚姻した日の属する月の前月分までの部分が誤りです。
年金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで支給されます。
婚姻で遺族基礎年金が失権した場合は、『婚姻した日の属する月』分までの遺族基礎年金が支給されます。
(法第18条)
②<H23年出題> ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は、『繰上げ請求のあった日』に発生します。翌日に発生の部分が誤りです。
なお、支給は「受給権発生日の属する月の翌月から」で合ってます。
(法第18条)
こちらもどうぞ!
③<H29年出題>
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
④<H29年出題>
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが、裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合、生計を同じくしていた65歳の妻は、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を未支給年金として受給することができる。この場合、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は、妻自身の名で請求し、夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる。

【解答】
③<H29年出題> ×
1月分と2月分の年金の部分が誤りです。
平成29年2月27日に死亡した場合、年金は「権利が消滅した日の属する月」までですので、2月分まで支給されます。
また年金は、「年6期、偶数月、後払い」と覚えましょう。問題文の場合、平成29年2月に12月分と1月分が支払われています。
未支給年金請求者が請求できるのは、2月分のみとなります。
(法第18条、第19条)
④<H29年出題> 〇
未支給年金として請求できるのは、夫が受けるはずだった『65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分』までとなります。
未支給年金のポイントを穴埋め式で確認しましょう
第19条 (未支給年金)
1 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の< A >であって、その者の死亡の当時その者と< B >ものは、< C >で、その未支給の年金の支給を請求することができる。
2 1の場合において死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、1に規定する者は、< C >で、その年金を請求することができる。

【解答】
A 三親等内の親族
B 生計を同じくしていた
C 自己の名
社労士受験のあれこれ
国年 前納について②
R3-272
R3.5.22 保険料「前納」でよく出るところ その2
引き続き、国民年金保険料の前納のルールを見ていきましょう。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。

【解答】
①<H27年出題> 〇
保険料が前納された後、前納期間の経過前に保険料の額の引上げがあった場合は、前納保険料のうち未経過分については、引上げ後に納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当されます。
(令第8条の2)
こちらもどうぞ!
②<H21年出題>
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
③<H25年出題>
保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

【解答】
②<H21年出題> 〇
前納期間の途中で、資格を喪失した場合や第2号被保険者、第3号被保険者になった場合は、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、未経過期間分が還付されます。
(令第9条)
③<H25年出題> 〇
保険料を前納した後、途中で保険料の免除を受けた場合も、未経過期間分が還付の対象となります。
(令第9条)
社労士受験のあれこれ
国年 前納について①
R3-271
R3.5.21 保険料「前納」でよく出るところ その1
国民年金保険料の前納のルールを見ていきましょう。
前納とは、まとめて前払いをする制度です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。
②<H27年出題>
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。

【解答】
①<R1年出題> ×
平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月間をまとめて前納することは可能です。
保険料の前納は、「6月」単位又は「年」単位で行うのが原則です。
ただし、例外もあり、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合は、6月又は年以外の単位も可能です。
6月又は年以外の単位の場合は、任意の月分から当年度末または翌年度末までの期間となりますが、問題文の昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者は、60歳に達する令和元年8月1日に資格を喪失するので、平成31年4月から令和元年7月分までの4か月間をまとめることができます。
(令7条)
②<H27年出題> 〇
2年前納は口座振替でできます。また、口座振替のみならず、現金・クレジットカード納付でも2年前納ができます。
(令7条)
では、こちらもどうぞ
③<H21年出題>
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
④<H24年出題>
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。

【解答】
③<H21年出題> 〇
割引があるのが前納のメリットです。割引額は年利4%の複利現価法で計算します。4分という利率を覚えておきましょう。
(令8条)
④<H24年出題> ×
国民年金保険料を1年間分前納する場合、現金よりも口座振替による支払の方が割引率は高くなります。
(参考) 令和3年度の国民年金保険料は月16,610円ですが、1年分前納した場合、「現金」、「クレジットカード」だと195,780円(3,540円割引)、「口座振替」だと195,140円(4,180円割引)となります。
(令8条)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H30年出題>
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】
⑤<H30年出題> ×
「前納に係る期間の各月の初日が到来したとき」が誤りです。
『「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす』です。
(法第93条)
社労士受験のあれこれ
学生納付特例 その2
R3-270
R3.5.20 学生納付特例のポイントその2
引き続き、テーマは「学生納付特例」です。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【解答】
①<H29年出題> 〇
学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間の10年以上の計算には入りますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されないのがポイントです。納付猶予の期間も同じです。
(法第26条、第27条)
こちらもどうぞ!
②<H30年出題>
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。
③<R1年出題>
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

【解答】
②<H30年出題> 〇
学生納付特例期間は老齢基礎年金の額の計算には反映されませんが、追納すれば保険料納付済期間となり年金の額が増えます。
なお、追納できるのは、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に限れられることにも注意してください。
(法第94条)
③<R1年出題> ×
「学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない」が誤りです。
学生納付特例期間(納付猶予も含む)は、老齢基礎年金の額に反映されませんので、一部につき追納する場合は、まず学生納付特例期間(納付猶予)を優先し、それ以外の免除を古い順番に行うのが原則です。
ただし、問題文のように学生納付特例より前に納付義務が生じた保険料があるときは、古い保険料から追納することができます。
問題文の場合
・ 平成27年6月分から平成28年3月分 保険料全額免除期間
・ 平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間
・ 平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間
となっていますので、学生納付特例の期間よりも古い平成27年6月分から平成28年3月分の保険料全額免除期間の保険料を先に追納することができます。
(法第94条)
最後にこちらもどうぞ!
国民年金制度創設当初は、学生は任意加入だったが、< A >4月1日から強制加入に改められた。

【解答】
A 平成3年
社労士受験のあれこれ
学生納付特例 その1
R3-269
R3.5.19 学生納付特例のポイントその1
テーマは「学生納付特例」です。
では、どうぞ!
①<H28年出題>
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
②<H28年出題>
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①<H28年出題> 〇
申請全額免除は、学生には適用されません。
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除も学生には適用されません。
・「法定免除」は、学生にも適用されます。
(法第90条)
②<H28年出題> 〇
学生納付特例は、学生本人の前年の所得のみで判断されます。世帯主や配偶者の前年の所得は関係ありません。
(法第90条の3)
こちらもどうぞ!
③<H24年出題>
学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が、承認期間中に学校を退学した場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければならない。
④<H23年出題>
学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。
⑤<H27年出題>
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

【解答】
③<H24年出題> 〇
退学等の理由で学生でなくなった場合は、学生納付特例不該当届を提出しなければなりません。なお、卒業の場合は提出不要です。
(則第77条の9)
④<H23年出題> ×
学生納付特例事務法人は、保険料の納付に関する事務はできません。
学生納付特例事務法人とは、学生が学生納付特例の手続きをしやすくするために、大学等が学生の委託を受けて、申請の代行を行う制度のことです。
(法第109条の2の2)
⑤<H27年出題> 〇
「学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をした日」がポイントです。
学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない、とされています。
(法第109条の2の2)
社労士受験のあれこれ
国年 国民年金原簿
R3-268
R3.5.18 国民年金原簿 よく出るところ
まず、国民年金法第14条を確認しておきましょう。
第14条 (国民年金原簿)
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう。)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
では、どうぞ!
①<H28年出題>
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。

【解答】
①<H28年出題> 〇
当分の間、第2号被保険者のうち、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者は、国民年金原簿の記録管理は行われていません。
(法第14条、附則第7条の5)
次はこちらをどうぞ!
②<H30年出題>
寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

【解答】
②<H30年出題> 〇
「年金記録が事実と異なる」と思う場合は、厚生労働大臣に年金記録の訂正請求ができます。例えば、国民年金の保険料を納付していたのに記録がない、とか、会社で働いていた期間の厚生年金保険の記録がない、などの場合です。
訂正請求ができるのは、本人(被保険者又は被保険者であった者)で、自己の特定国民年金原簿記録についてですが、本人が死亡している場合は、遺族が請求できます。
※ただし、本人の死亡に伴う未支給年金または遺族年金等を受けることができる人に限定されています。
寡婦年金の場合は、「妻」が「死亡した夫」に係る特定国民年金原簿記録について、国民年金原簿の訂正請求をすることができます。
ちなみに、特定国民年金原簿記録とは、「被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容」です。
(法第14条の2)
では、こちらをどうぞ!
③<R2年出題>
国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。

【解答】
③<R2年出題> ×
社会保険審査会ではなく、「社会保障審議会」に諮問しなければならない、です。
なお、「社会保険審査会」は行政不服審査を行う機関で、「社会保障審議会」は厚生労働大臣の諮問機関です。
(法第14条の2)
最後はこちらを
④<H27年選択式>
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。
これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は< A >に委任されており、 < A >が決定しようとするときは、あらかじめ< B >に諮問しなければならない。

【解答】
A 地方厚生局長又は地方厚生支局長
B 地方年金記録訂正審議会
(法第14条の4、第109条の9、令11条の12の2)
※地方厚生(支)局長が、年金記録の訂正請求に対して、その訂正(不訂正)の決定を行うときは、あらかじめ地方年金記録訂正審議会に諮問しなければなりません。
社労士受験のあれこれ
国年 種別変更
R3-267
R3.5.17 第1号、第2号、第3号被保険者~種別変更
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの
種別があります。
例えば、40歳の会社員が退職して自営業を始めた場合、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者に種別が変わります。
この場合のポイントは、第2号被保険者の資格を喪失して第1号被保険者の資格を取得するのではなく、第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」となる点です。
では、どうぞ!
①<H22年出題>
被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなし、同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
②<H30年出題>
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
③<H24年出題>
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者になった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

【解答】
①<H22年出題> 〇
★被保険者の種別に変更があった月★
・変更後の種別の被保険者であった月とみなす。
・同月中に2回以上の種別変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。
(法第11条の2)
②<H30年出題> ×
同一月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者への種別の変更があった場合、その月は「最後の種別の被保険者であった月」とみなすので、当該月は第3号被保険者であった月とみなします。
(法第11条の2)
③<H24年出題> ×
第1号被保険者から第3号被保険者になった月は、第3号被保険者であった月とみなします。すでに第1号被保険者としての保険料が納付されていても、関係ありません。
(法第11条の2)
では、こちらもどうぞ
④<H20年出題>
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
④<H20年出題> ×
「資格取得届」が誤りです。
第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」ですので、「種別変更の届出」を、当該事実があった日から14日以内に市町村長に提出しなければなりません。
(則第6条の2)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H27年出題>
第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出をしなければならない。

【解答】
⑤<H27年出題> ×
第2号被保険者には、国民年金法の届出の規定は適用されません。
ですので、第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更した場合の種別変更の届出は不要です。
(法附則第7条の4)
社労士受験のあれこれ
国年 第3号被保険者届出いろいろ その2
R3-266
R3.5.16 第3号被保険者の届出
引き続き、第3号被保険者の届出いろいろです。
では、どうぞ!
①<H29年出題>
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①<H29年出題> 〇
ポイント! 第3号被保険者の資格取得の届出 → 提出期限(14日以内)と提出先(日本年金機構)がポイントです。
次はこちらをどうぞ
②<H27年出題>
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。以下本問において同じ。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

【解答】
②<H27年出題> 〇
第2号被保険者の夫と第3号被保険者の妻が離婚した場合
・「第1号被保険者の種別の変更の届出」を市町村長(特別区の区長を含む。)に提出
・「被扶養配偶者非該当届」を離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へを提出
★「被扶養配偶者非該当届」のポイント
・「全国健康保険協会管掌」の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった者については、被扶養配偶者非該当届の提出は不要。
・ 配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなった場合、第3号被保険者が被用者年金制度に加入した又は死亡したことにより第3号被保険者でなくなった場合は、被扶養配偶者非該当届の提出は不要
・ 被扶養配偶者非該当届の提出が必要なのは、(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合、(2)離婚した場合です。
(H26年11月1日 年管管発1101第1号)
社労士受験のあれこれ
国年 第3号被保険者届出いろいろ
R3-265
R3.5.15 第3号被保険者(平成17年4月1日前と以後)
今日は、第3号被保険者の届出色々です。
現在は、会社員や公務員の被扶養配偶者(第3号被保険者)に該当した場合は、第2号被保険者の事業主等を経由して届け出を行うので、届出もれは基本的にありません。
しかし、事業主経由で第3号被保険者の届出を行うようになったのは平成14年4月からです。
第3号被保険者制度ができた昭和61年4月から平成14年3月までは、自分自身で市町村に届出を提出しなければならず、その届出をしなかった人が多数存在しました。
届出をしなかった期間は、未納期間となり、年金の受給資格ができない、あるいは受給額が減るという不利益が生じてしまいます。
今日は、このような人たちを救済するための特例がテーマです。
では、どうぞ!
①<H19年出題>
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間について、その届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。
②<H22年出題>
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後の期間に限る。)は、原則として、届出をした日の属する月の前々月までの2年間を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
③<H29年出題>
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

【解答】
この問題のポイント!
<第3号被保険者の取得の届出が遅れた場合の取扱い>
★平成17年4月1日前
第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)
↓
届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる
※届出の遅滞の理由の有無は問わない
★平成17年4月1日以後
第3号被保険者に該当したが届け出をしていなかった(未納期間)
↓
届出の遅滞がやむを得ないと認められるとき
↓
届出を行うことによって「保険料納付済期間」となる
①<H19年出題> 〇
「平成17年4月1日以後の期間」がポイントです。
第3号被保険者期間のうち、届出の遅滞によって保険料納付済期間に算入されない平成17年4月1日以後の期間については、届出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、その旨の届出をすることができます。
届出が行われた日以後、届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されます。
(法附則第7条の2)
②<H22年出題> 〇
平成17年4月1日以後については、第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間は、原則として保険料納付済期間に算入されません。(届け出の遅滞がやむを得ないと認められるときは、届出をすることができます。)
ちなみに、「届出をした日の属する月の前々月までの2年間」は保険料納付済期間に算入されます。
(疑問その1 届け出をした日の属する月の前月はどうなるのか?)
例えば、2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合、2021年4月は保険料納付済期間となります。
国民年金の保険料の納期限は翌月末日です。2021年4月分は5月末までに納付すればいいので、3号の取得も5月14日に届け出れば、2021年4月は保険料納付済期間に算入できるという理屈です。
(疑問その2 なぜ2年間なのか?)
保険料の納付の時効の期間に合わせた扱いです。
2019年4月1日に第3号被保険者の資格を取得したものの届出が遅れて、2021年5月14日に届出を行った場合は、2021年3月までの2年間も保険料納付済期間となります。
(法附則第7条の2)
③<H29年出題> 〇
資格取得日 → 平成26年4月1日
資格取得の届出 → 平成29年4月13日
・ 届け出をした日の属する月の前々月までの2年間は「保険料納付済期間」となる。(平成27年3月~平成29年2月まで、平成29年3月も)
・ 平成26年4月から平成27年2月までの期間は、届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるとき → その旨を届け出れば → 届出日以後、保険料納付済期間に算入される。
(法附則第7条の2)
社労士受験のあれこれ
国年・付加年金
R3-226
R3.4.6 付加年金でよく出るところ
今日のテーマは、付加年金のよく出るところです。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第43条(支給要件)
付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が< A >の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条(年金額)
付加年金の額は、< B >円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
A 老齢基礎年金
B 200
では、こちらをどうぞ
①<H19年出題>
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

【解答】 ×
「付加年金、寡婦年金、死亡一時金」は、「第1号被保険者」としての被保険者期間が対象です。第2号被保険者、第3号被保険者としての被保険者期間は対象になりません。
こちらもどうぞ!
②<H27年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

【解答】 〇
付加年金の額は、200円×300か月=年額60,000円で計算します。
なお、この場合納付した付加保険料は400円×300か月=120,000円です。付加年金を2年間受給したら、納付した付加保険料と同額となります。
(第44条(年金額))
では、こちらをどうぞ
③<H19年出題>
政府は、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を含む。)の額を調整するものとする。
④<H29年出題>
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

【解答】
③<H19年出題> ×
(付加年金を含む。)が誤り。付加年金は除かれます。
④<H29年出題> ×
付加年金の額には、改定率による改定はありません。
(第16条の2)
最後にこちらをどうぞ!
⑤<H19年出題>
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。
⑥<H25年出題>
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

【解答】
⑤<H19年出題> ×
減額率、増額率は、付加年金も老齢基礎年金と同じように適用されます。
※老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる場合
→ 付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給され、減額率、増額率も同じように適用されます。
(第46条、附則第9条の2)
⑥<H25年出題> 〇
第47条で「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」と定められています。
「全額」に注意してください。「全部又は一部」と出題されたら誤りです。
第48条で「付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。」と定められていて、老齢基礎年金同様付加年金も終身年金です。
社労士受験のあれこれ
国年・付加保険料のこと②
R3-225
R3.4.5 付加保険料の納付の辞退
引き続き、付加保険料のことです。
今日のテーマは、付加保険料の納付の辞退です。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第87条の2
第3項
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する< A >以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び第93条第1項の規定により< B >されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】
A 月の前月
B 前納
では、こちらをどうぞ
①<H30年出題>
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】 ×
「申出をした日の属する月以後」ではなく、「申出をした日の属する月の前月以後」です。
例えば、4月5日に申出をした場合は、納付の辞退は、3月分からです。
3月分の納期限は4月末日。申出時点ではまだ期限が来ていないからです。
また、既に納付されたもの、前納されたものは除かれます。
こちらもどうぞ!
②<H26年出題>
付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

【解答】 ×
「辞退したものとみなされる。」が誤りです。
平成26年3月までは、納期限までに付加保険料を納付しなかった場合は、付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされ、以後納付できなくなっていました。
しかし、平成26年4月以降は、『辞退の申出をしたものとみなさない』ことになっていて、現在は、納期限を経過しても、2年間は付加保険料を納付することができます。
では、最後にこちらをどうぞ
③<H27年出題>
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
④<R1年出題>
平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される

【解答】
③<H27年出題> 〇
国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できないので、国民年金基金の加入員になったときは、加入員になった日に付加保険料納付の辞退の申出をしたものとみなされます。
(第87条の2第4項)
④<R1年出題> ×
「令和元年7月分以後」が誤りです。
令和元年8月に国民年金基金の加入員になった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされます。
しかし、問題文の「平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納」していた点に注目してください。
第87条の2第3項では、付加保険料の辞退の対象から、『既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。』とされています。
令和元年7月分は前納されているので、辞退できません。
国民年金基金の加入員となった日の属する月以後(令和元年8月以後)は付加保険料を納付できないので、辞退の対象となります。
社労士受験のあれこれ
国年・付加保険料のこと①
R3-224
R3.4.4 付加保険料を納付できる場合、できない場合
今日は国民年金法です。
今日のテーマは、付加保険料を納付できる場合とできない場合です。
★付加年金
付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされて支給されます。
では、どうぞ!
まずは穴埋め式からどうぞ!
第87条の2
第1号被保険者(第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び< A >を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、保険料のほか、< B >円の保険料を納付する者となることができる。

【解答】
A 国民年金基金の加入員
→(付加保険料と国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せという目的が同じなので、国民年金基金の加入員は付加保険料は納付できません)
B 400
★ 保険料の免除を受けている者、国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できません。
では、こちらをどうぞ
①<R1年出題>
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
②<H29年出題>
保険料の半額を納付することを要しないものとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
③<H26年出題>
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
④<H23年出題>
独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となったときに、付加保険料を納付する者となる。

【解答】
①<R1年出題> ×
産前産後期間の保険料免除の期間の各月については、付加保険料を納付することができます。
★付加保険料を納付できる月
・国民年金の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)
・産前産後の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月
(第87条の2第2項)
②<H29年出題> ×
半額免除期間は付加保険料の納付はできません。
★以下の保険料免除期間は付加保険料の納付はできません。
・法定免除
・申請全額免除
・学生納付特例、納付猶予期間
・4分の3免除、半額免除、4分の1免除
(第87条の2第1項)
③<H26年出題> ×
保険料の追納を行った月は、付加保険料を納付することはできません。
(第87条の2第2項)
④<H23年出題> 〇
独立行政法人農業者年金基金法第17条で以下のように定められています。
「農業者年金の被保険者のうち国民年金法第87条の2第1項の規定による保険料(付加保険料)を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、付加保険料を納付する者となる。」
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-212
R3.3.23 夫・妻の年金「振替加算⑧加算のタイミング(応用編)」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算がつくタイミング「応用編」です。
では、どうぞ!
①<H27年出題>
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生まれ)は、60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳の時に婚姻し、婚姻以後は継続して、厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で、夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合であっても、妻が65歳に達する日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に振替加算が加算される。
②<H27年出題>
特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生まれ)は、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生まれ)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は、67歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】
①<H27年出題> 〇
(この問題のポイント)
・妻が60歳で老齢基礎年金の支給を繰上げても、振替加算は繰上げされないので、振替加算の加算は65歳以後。
・在職老齢年金の仕組みで老齢厚生年金が全額支給停止になると、配偶者加給年金額も支給停止となる。
・配偶者加給年金額が支給停止されていた場合でも、妻が65歳になると振替加算が加算される
・振替加算は、65歳に達する日の属する月の翌月分から加算。翌月分からの部分がポイントです。
②<H27年出題> ×
妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されないではなく「加算されます」。
(問題文の妻の現状)
・65歳時点で、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていなかった
・65歳以後、特例による任意加入被保険者として保険料を納付した
・67歳で老齢基礎年金の受給権を取得した
この妻は振替加算の要件を満たしているので、67歳から受給する老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(昭和60年国民年金法附則第18条)
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-211
R3.3.22 夫・妻の年金「振替加算⑦加算のタイミング(基礎編)」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算がつくタイミング(基礎編)です。
まずこちらからどうぞ!
①<H18年出題>
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。

【解答】 ×
例えば、夫が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)の受給権を取得した当時、妻が65歳未満なら、夫の老齢厚生年金に妻が65歳になるまで加給年金額が加算され、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
問題文のように、夫が老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)の受給権を取得した当時、妻が65歳以上で振替加算の要件を満たしている場合は、夫の老齢厚生年金には加給年金額は加算されず、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(昭和60年国民年金法附則第14条第2項)
では、こちらをどうぞ!
②<H27年出題>
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】 〇
退職時改定で、夫が初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、妻が65歳未満なら夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されますが、問題文のように妻が66歳の場合は、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
なお、問題文のように、妻が65歳になった後に、夫が240月(原則)の要件を満たした場合は、振替加算の要件を満たしているか確認を受けるために、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。
(昭和60年国民年金法附則第14条第2項)
社労士受験のあれこれ
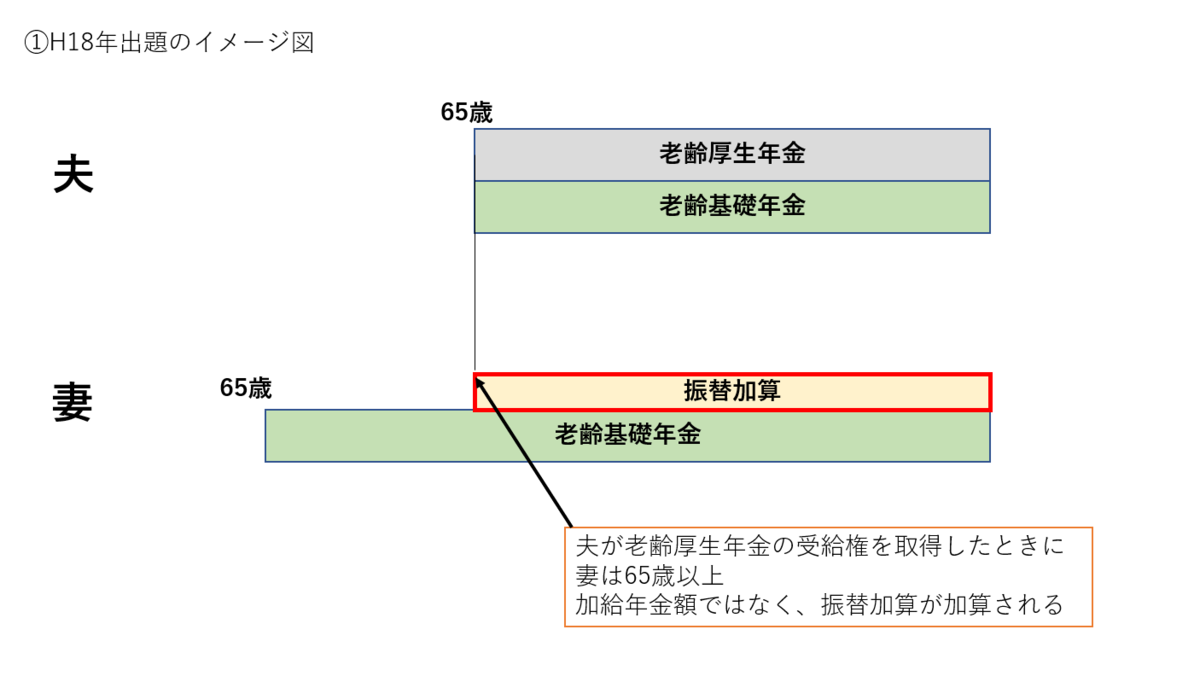
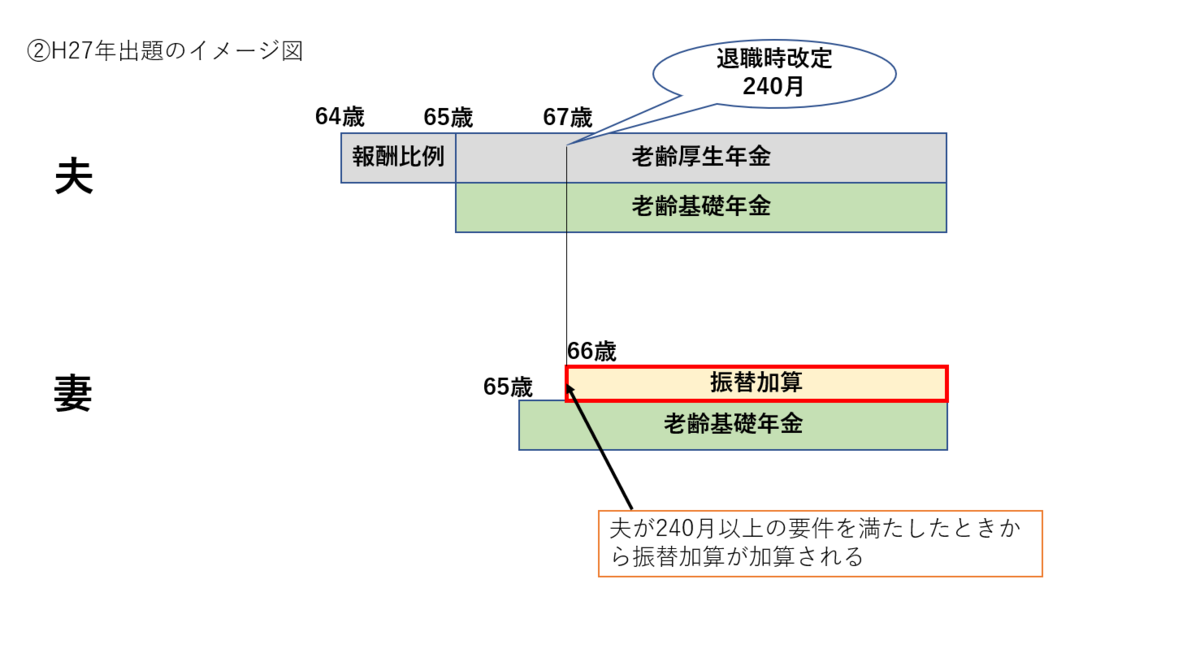
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-210
R3.3.21 夫・妻の年金「振替加算⑥振替加算のみの老齢基礎年金」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算だけの老齢基礎年金です。
まずこちらからどうぞ!
①<R1年出題>
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

【解答】 〇
老齢基礎年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上あれば受給資格ができます。
ただし、保険料全額免除期間のうち、「学生納付特例期間」と「納付猶予期間」は注意が必要です。
「学生納付特例期間」と「納付猶予期間」は受給資格の10年以上の計算には入りますが、老齢基礎年金の額の計算は「ゼロ」となります。(合算対象期間と同じ扱いです。)
問題文のように、「学生納付特例の期間及び納付猶予の期間だけで10年以上」の場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金の計算はゼロとなりますので支給されません。
(国民年金法第26条)
先ほどの問題をおさえたら、こちらをどうぞ!
②<H20年出題(修正)>
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が10年あり、かつ、それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】 〇
「合算対象期間+学生納付特例」のみで10年の場合、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金はゼロとなります。
しかし、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算相当額の老齢基礎年金」(=振替加算のみの老齢基礎年金)が支給されます。
(昭和60年国民年金法附則第15条)
なお、良く出題される典型的な問題として、例えば『「保険料納付済期間が1か月+合算対象期間で10年以上ある場合」は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給される』というパターンがあります。これは「×」です。
このような場合は、保険料納付済期間1か月で計算した老齢基礎年金に振替加算が加算されることになりますので、注意しましょう。
ではこちらも!
③<H27年出題>
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】 〇
問題文の場合、甲は40年間すべて合算対象期間ですので、老齢基礎年金の受給資格はありますが、老齢基礎年金の額はゼロです。
しかし、振替加算の要件に該当していますので、65歳から「振替加算相当額の老齢基礎年金」が支給されます。
最後にもう一問どうぞ!
④<R1年出題>
合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって、所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金については、支給の繰下げはできない。

【解答】 〇
振替加算のみの老齢基礎年金は繰下げできません。
(昭和60年国民年金法附則第15条第4項)
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-209
R3.3.20 夫・妻の年金「振替加算⑤障害年金との関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、障害年金との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
②<H30年出題>
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】
①<H21年出題> 〇
②<H30年出題> 〇
どちらの問題も同じです。
振替加算は、『障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの』の支給を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分は支給停止となります。
(昭和60年国民年金法附則第16条)
では、もう一問どうぞ!
③<H21年出題>
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。

【解答】 ×
最後が誤りで、「振替加算に相当する部分の支給は停止されない」です。
先ほどの問題で、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等障害を支給事由とする年金を受けることができる場合は、その間、振替加算に相当する部分は支給停止になることを勉強しました。
では、その障害基礎年金等が支給停止になっている場合は、振替加算はどうなるのか?というのがこの問題のテーマです。
障害基礎年金等が全額支給停止されている場合は、振替加算に相当する部分の支給は停止されません。
(昭和60年国民年金法附則第16条)
最後にもう一問どうぞ!
④<R1年出題>
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで第2号被保険者期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

【解答】 〇
66歳の女性の現状
・障害基礎年金を受給中
・配偶者に生計維持されている。65歳に達するまで配偶者の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されていた。
・障害等級が3級程度に軽減し、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した
この女性が、障害基礎年金を受給している間は、振替加算は支給停止です。しかし、障害の程度が3級程度に軽減すると、障害基礎年金は全額支給停止となり、振替加算は支給停止ではなくなります。
この女性は、老齢基礎年金を受給することに変更するのですが、その場合、65歳時点で配偶者に生計維持されており、他の振替加算の要件も満たしているので、老齢基礎年金に振替加算が加算されることになります。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-208
R3.3.19 夫・妻の年金「振替加算④振替加算の額」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、振替加算の額です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H18年出題>
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。
②<H28年出題>
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

【解答】
①<H18年出題> ×
振替加算の額は、「224,700円×改定率」×「生年月日に応じて定められた率」で計算しますが、「生年月日」は「老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日」ではなく、「老齢基礎年金の受給権者」の生年月日です。
②<H28年出題> ×
振替加算の額は、「老齢基礎年金の額」ではなく「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額となります。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
★もう少し詳しくみましょう。
振替加算の額は「224,700円×改定率」×「老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて定められた率」で計算します。
「224,700円×改定率」は「加給年金額」と同じですが、その額がそのまま振替加算になるのではなく、その額に「生年月日に応じて定められた率」を乗じるのがポイントです。
「生年月日に応じて定められた率」が一番大きい「1.000」になるのは「大正15年4月2日~昭和2年4月1日まで」生まれで、生年月日が若くなるほど率は小さくなり、一番小さくなるのが「昭和40年4月2日~昭和41年4月1日まで」生まれの「0.067」となります。
振替加算は、旧法時代に任意加入だった「カラ期間」をカバーするための制度です。
第3号被保険者制度ができた「昭和61年4月1日」に、20歳に近いほど第3号被保険者期間が長い(カラ期間が少ない)ので、振替加算が少なくなり、「昭和61年4月1日」に60歳に近いほどカラ期間は多い(第3号被保険者期間が短い)ので振替加算が多くなります。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-207
R3.3.18 夫・妻の年金「振替加算③繰上げ・繰下げとの関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、老齢基礎年金の繰上げ・繰下げとの関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
②<H22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。

【解答】
①<H21年出題> ×
老齢基礎年金を繰下げた場合は振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算については増額されません。
②<H22年出題> 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算については繰上げされません。振替加算の加算は、受給権者が65歳に達した日以後となります。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
もう一問どうぞ
③<H30年出題>
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】 ×
「老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算」の部分が誤りです。
(振替加算が加算される時期)
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合
→ 振替加算は申出のあった日の属する月の翌月から加算
(振替加算も繰下げて支給される)
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合
→ 65歳に達した日の属する月の翌月から加算
(振替加算は繰上げされない)
社労士受験のあれこれ
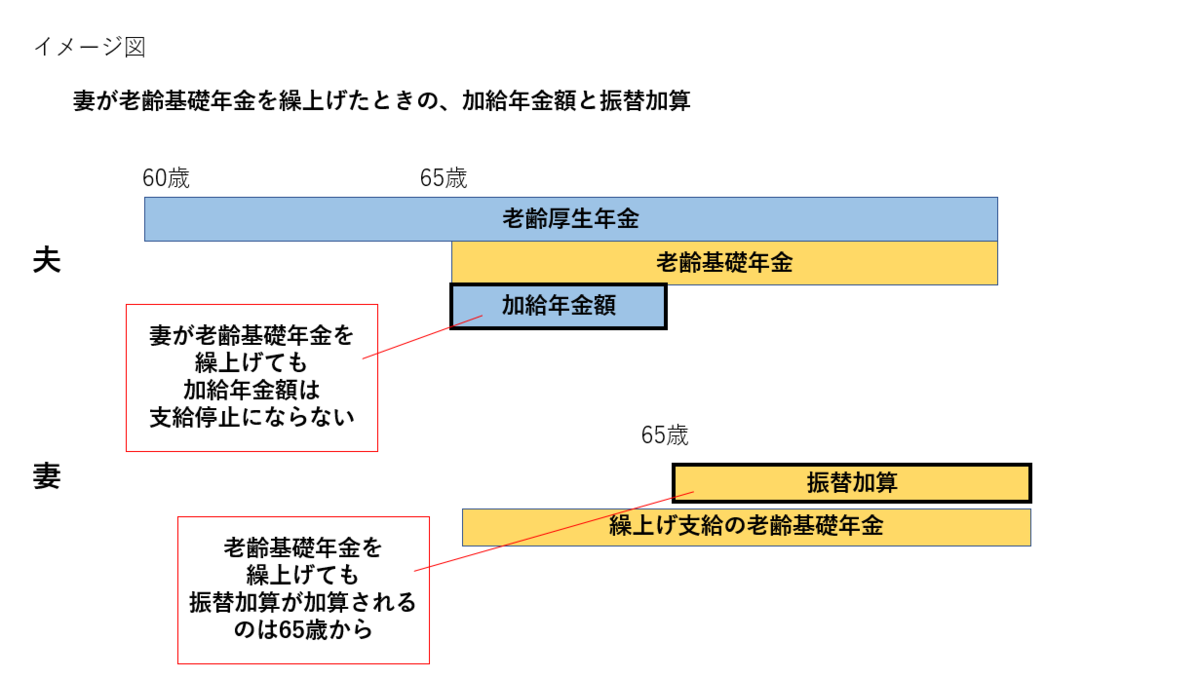
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-206
R3.3.17 夫・妻の年金「振替加算②老齢厚生年金との関係」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、老齢厚生年金との関係です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H30年出題>
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

【解答】 〇
この問題のテーマは、「老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることができるときに、振替加算は加算されるのか?」です。
問題文のポイントは、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の「月数が240以上」であることです。
振替加算が加算されないのは、被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金を受けることができるときです。
単に老齢厚生年金を受けることができる、ではなく、240月以上(中高齢期間短縮特例の場合は15~19年)で計算される老齢厚生年金であることに注意してください。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
もう一問どうぞ
②<厚生年金保険 H24年出題>
(離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について)
振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間が含まれる。
③<H27年出題>
67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)と66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)が離婚をし、妻が、厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより、離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合、妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる。

【解答】
②<厚生年金保険 H24年出題> 〇
「みなし被保険者期間」も含んで算定した厚生年金保険の被保険者期間が240月以上の場合、振替加算は行われません。「みなし被保険者期間」も含まれるのがポイントです。
(厚生年金保険法平成24年の出題です。)
③<H27年出題> 〇
上の②と同じです。「みなし被保険者期間」も含んで算定した厚生年金保険の被保険者期間が240月以上になった場合は、振替加算は行われなくなります。
では、こちらもどうぞ!
④<H21年出題>
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】 ×
遺族基礎年金と老齢基礎年金の両方の受給権が発生したときは、どちらかを選択することになり、遺族基礎年金を選択した場合は、振替加算は加算されません。振替加算は老齢基礎年金に加算されるものだからです。
最後にこちらもどうぞ!
⑤<H21年出題>
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として、振替加算は支給停止とはならない。

【解答】 〇
振替加算は老齢基礎年金と同様、受給権者本人の権利に基づいているので、離婚したとしても支給停止にはなりません。
明日も振替加算です。
社労士受験のあれこれ
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-205
R3.3.16 夫・妻の年金「振替加算①対象になる生年月日」
年金の仕組みを勉強しましょう。
テーマは「振替加算」です。
今日は、「振替加算の対象となる生年月日」です。
こちらの問題をどうぞ!
①<H22年出題>
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例が設けられている。

【解答】 〇
「老齢基礎年金の額に加算額を加算する特例」とは振替加算のことです。
老齢厚生年金、障害厚生年金に加算される配偶者加給年金額は、配偶者が65歳に達したときに加算されなくなります。
65歳に達したときに、配偶者自身が老齢基礎年金の受給権を取得し、今まで相手の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額が振り替わって、自身の老齢基礎年金に加算される仕組みになっています。
ポイント! 振替加算の対象は「大正15年4月2日~昭和41年4月1日以前生まれ」
振替加算の対象は、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれです。
◆なぜ大正15年4月2日生まれ以降?
振替加算は「老齢基礎年金(新法)」に加算されるものだからです。新法の対象者が大正15年4月2日~生まれだからです。
大正15年4月1日以前生まれの場合は旧法の対象となるので、65歳以降も、相手の老齢年金に加給年金額が加算され続けます。
◆なぜ昭和41年4月1日以前まで?
昭和41年4月2日以降生まれには振替加算はつきません。なぜなら「第3号被保険者」の制度ができた「昭和61年4月1日」に20歳未満だったからです。
仮に20歳から60歳までの40年間被扶養配偶者だった場合、その間ずっと第3号被保険者で、65歳から満額の老齢基礎年金が受給できるので、振替加算でカバーする必要がないからです。
昭和41年4月1日以前生まれの場合は、「昭和61年4月1日」に20歳を過ぎています。同じように40年間被扶養配偶者だった場合、「任意加入」だった旧法時代にカラ期間ができてしまい、満額の老齢基礎年金が受給できない場合があります。
振替加算はそのようなカラ期間をカバーするための制度です。
(昭和60年国民年金法附則第14条)
では、もう一問どうぞ
②<H30年出題>
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】 〇
この問題のチェックポイント!
<夫(老齢厚生年金の受給権者)の要件>
◆夫の生年月日
大正15年4月2日以降生まれであること(新法の対象者であること)
→旧法の対象者だと旧法のルールが適用され、配偶者が65歳になっても加給年金額が加算されるからです。
◆夫の老齢厚生年金が加給年金額が加算される要件を満たしていること
原則として被保険者期間が240月以上あることが条件ですが、昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれの場合は、40歳以降の第1号厚生年金被保険者期間が19年以上あればOKです。
<妻(振替加算の対象)の要件>
◆妻の生年月日
大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれであること
◆65歳に達した日に夫に生計を維持されていること
→65歳に達した日の前日に、夫の年金の加給年金額の対象になっていたこと
(対象になる夫の年金)
・老齢厚生年金又は退職共済年金(被保険者期間の月数が原則として240月以上)
・障害厚生年金又は障害共済年金(1級又は2級)
「振替加算」は、夫婦とも新法の対象であるときに行われます。片方が旧法の場合は、旧法のルール(配偶者が65歳になっても引き続き加給年金額が加算される)が適用されるので、振替加算は行われません。
明日も振替加算です。
社労士受験のあれこれ
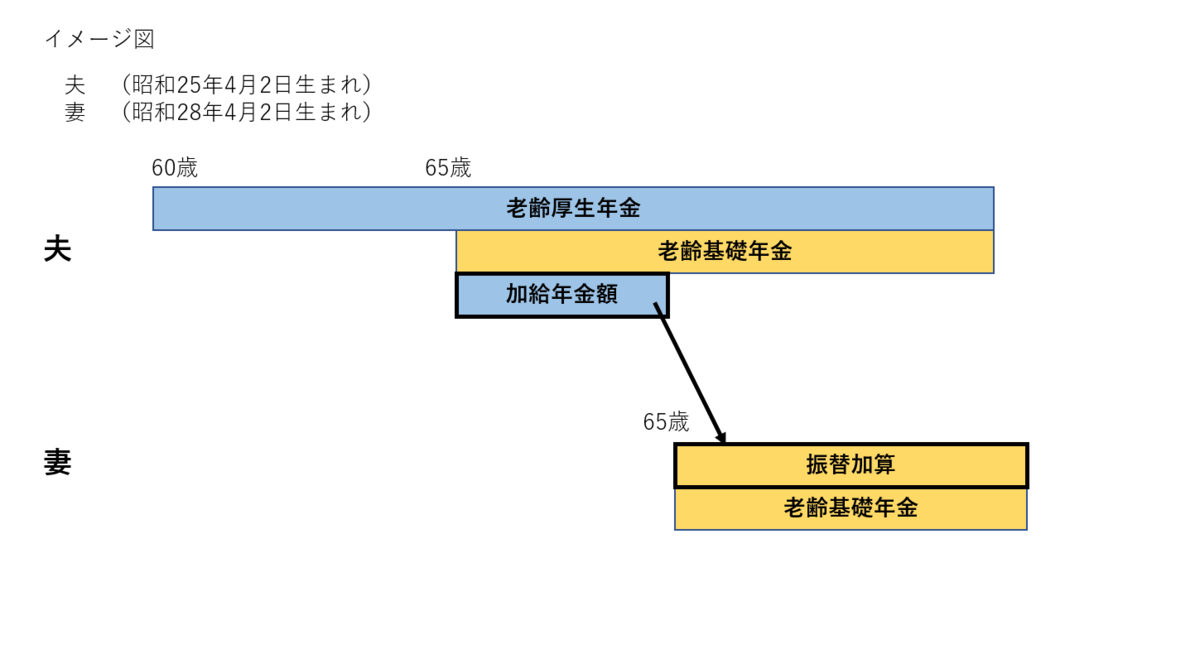
年金のしくみ(夫婦単位)
R3-204
R3.3.15 夫・妻の年金「加給年金額⑨届出について」
年金の仕組みを勉強しましょう。
引き続き、テーマは「加給年金額」です。
今日は、「届出」についてです。
こちらの問題をどうぞ!
①<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する子を除く。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
問題文の場合、不該当の届出は要りません。
ポイント! 加給年金額対象者の不該当の理由が「年齢」の場合は届出不要
配偶者又は子が、加給年金額の対象から外れるのは次のいずれかに該当した場合です。
1 死亡したとき。
2 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
4 配偶者が、65歳に達したとき。
5 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。
6 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
7 子が、婚姻をしたとき。
8 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
9 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
10 子が、20歳に達したとき。
★ 加給年金額対象者が不該当になった場合は、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければなりませんが、不該当の事由が「年齢」の場合(上記4、8、10の場合)は、届出は要りません。
例えば、配偶者が離婚した場合は届け出が必要です。(届け出がないと、日本年金機構は、誰がいつ離婚したかを把握できないからです)
(厚生年金保険法第44条第4項、施行規則第32条)
では、こちらの問題をどうぞ
②<H18年出題>
老齢厚生年金の受給権者であって、大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者については、その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が加算されなくなり、振替加算も行われない。

【解答】 ×
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が65歳に達したときは、加給年金額が加算されなくなるという部分は正しいです。
しかし、その配偶者が大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの場合は、その配偶者の老齢基礎年金に振替加算が行われます。
今日で加給年金額のお話は終わります。明日からのテーマは「振替加算」です。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その6(旧法のしくみ)
R3-195
R3.3.6 旧法の老齢年金の支給開始年齢は何歳だった?
年金の歴史についてお話しています。
今日は、旧法の「老齢年金」です。
既にお話していますように、昭和61年3月までの旧制度では、「国民年金」「厚生年金保険」「共済年金」がそれぞれ独立して運営されていました。
例えば、「老齢年金」の支給要件や支給開始年齢は、旧国民年金法と旧厚生年金保険法では以下のように異なっていました。
・旧国民年金法の場合
→支給要件(保険料納付済期間+免除期間が原則として25年以上ある)を満たした者に、65歳から「老齢年金」を支給
・旧厚生年金保険法の場合
→支給要件(原則として被保険者期間が20年以上ある)を満たした者に、60歳から「老齢年金」を支給(ただし、女性と坑内員は55歳から支給)
では一旦ここで旧法の話は終わりまして、国民年金法(新法)の「第1号被保険者」の定義をみてみましょう。
第1号被保険者とは ① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者 ② 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない ③ 厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等)を受けることができる者は除く。 ④ 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。 |
③に注目してください。「(厚生年金保険法に基づく老齢給付等)を受けることができる者」は第1号被保険者から除外されます。
20歳以上60歳未満でそのような人がいるんですか?とよく聞かれますが、旧法では、女性や坑内員などのように55歳から老齢年金を受けることができる人がいて、新法になってからも経過措置として残っていました。
60歳前から老齢給付等を受けられる場合は、もう第1号被保険者として保険料を納付する必要はないので除外とされています。
※「受給資格期間を満たした」と「受けることができる」は違いますので注意してください。
※ちなみに・・・
日本国内に住所を有し20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、第1号被保険者からは除外されますが、「任意加入」することはできます。
こちらの問題をどうぞ!
<H17年出題>
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。

【解答】 ×
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でも、被扶養配偶者の場合は第3号被保険者となります。
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」が除外されるのは、第1号被保険者の場合です。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その5(第3号被保険者)
R3-194
R3.3.5 旧法から新法へ(会社員等の被扶養配偶者)
年金の歴史についてお話しています。
旧法では、「会社員の夫と専業主婦の妻」が年金モデルになっていて、老後は夫が老齢年金を受給し、夫の年金に妻の加給年金額が加算されるという仕組みでした。そして、妻は国民年金への加入は任意でした。
旧法のポイント会社員等に扶養される配偶者は、国民年金の加入は任意だった
しかし、妻が任意加入しなかった場合、老後に妻名義の年金が支給されない点などが問題になっていました。
そのため、昭和61年4月1日からは「第3号被保険者」として、会社員等の被扶養配偶者も国民年金に強制加入することになりました。ただし、個別に保険料を負担するのではなく、会社員等が加入する厚生年金保険や共済組合で負担することになりました。
例えば、昭和29年4月2日生まれの女性で、20歳から60歳まで会社員の夫に扶養されていた場合
■昭和49年4月(20歳)~昭和61年3月まで
・国民年金は任意加入
国民年金に任意加入していなかった場合 → 合算対象期間
■昭和61年4月~平成26年3月まで
・国民年金は強制加入(第3号被保険者) → 保険料納付済期間
こちらの問題をどうぞ!
①<H23年出題>
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
②<H26年出題>
昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。

【解答】
①<H23年出題> ×
20歳以上「65歳未満」ではなく、20歳以上「60歳未満」です。
先ほど書きました会社員等の被扶養配偶者がこの規定に該当します。任意加入できるけれど任意加入しなかった期間は合算対象期間となりますが、「20歳以上60歳未満」という枠がありますので注意してください。
また「昭和60年改正前の国民年金法」の期間は、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間です。
(昭和60年法附則第8条第5項)
②<H26年出題> 〇
国民年金の任意加入被保険者になっていたが、保険料を滞納していた期間については、合算対象期間となります。(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その4(基礎年金の導入)
R3-193
R3.3.4 旧法から新法へ(基礎年金の誕生)
年金の歴史についてお話しています。
旧法の年金には大きく分けて3つのグループがありました。
①厚生年金保険・船員保険(民間企業の従業員等)
②共済組合(公務員等)
③国民年金(自営業者等)
この3つの制度が、縦割りでばらばらに運営されていたのが旧法の特徴です。
<旧法のイメージ図>
厚生年金 船員保険 | 共済年金 | ||||
| 国民年金 | |||||
昭和36年4月1日に国民皆年金が実現しましたが、その後、第一次産業が衰退するなど産業構造の変化もあり国民年金の財政は不安定になり、また各制度間の格差も問題になっていました。
そこで、昭和60年に国民年金法が大改正されました。旧法では自営業者等だけを対象にしていた国民年金は、昭和61年4月1日以降、基礎年金として全国民共通の年金制度に生まれ変わりました。
厚生年金保険と共済年金は、基礎年金の上乗せという形式になりました。(このときに船員保険は厚生年金保険に統合されました。)
<新法のイメージ図>
| 厚生年金 | 共済年金 | ||||
国民年金(基礎年金) | |||||
国民年金の被保険者が、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類になったのも新法からです。
こちらの問題をどうぞ!
<H15年選択>
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【解答】
A 大正15年4月2日
B 障害認定日
★「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」。基礎年金という名称は新法から使われています。
★「老齢基礎年金」の対象は、新法施行時に60歳未満だった「大正15年4月2日以降生まれ」の者です。
ただし、問題文に「施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。」とあるように、新法施行日に旧法の老齢・退職給付の受給権のあった者は、引き続き旧法の対象となるので、そのまま旧制度の年金を受けます。
★障害基礎年金は「障害認定日」に受給権が発生します。昭和61年4月1日以降に障害認定日があれば、新法の障害基礎年金の対象になります。
例えば、初診日が昭和61年4月1日前にあっても、障害認定日がそれ以降の場合は新法の対象です。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その3(創成期)
R3-192
R3.3.3 国民年金の誕生(国民皆年金の実現)
年金の歴史についてお話しています。
民間企業の会社員や公務員の老齢については、厚生年金保険、共済年金でカバーできていましてが、自営業者や農林水産業に従事する人たちの年金制度はありませんでした。
しかし、老齢人口が増える。核家族化が進み子が親を扶養する力も弱まっていく。老齢者の生活は国が保障するべきではないかという機運が高まる。そんな時代背景の中、自営業者等を対象とする国民年金が誕生しました。
国民年金の創設により、すべての国民が、「国民年金」「厚生年金保険」「共済」のどれかの制度に加入することになりました。このことを「国民皆年金」といいます。
こちらの問題をどうぞ!
①<H19年出題(社一)>
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。

【解答】 〇
国民年金法は、昭和34年制定、昭和36年4月施行です。
もともと被用者のための年金制度(厚生年金保険、共済年金)は存在していて、国民年金ができたことによって、「国民皆年金」が実現したことがポイントです。
では、こちらもどうぞ!
②<H19年出題(社一)>
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。
③<H19年出題(国年)>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
②<H19年出題(社一)> 〇
国民皆保険と国民皆年金。どちらも「昭和36年4月」に実現しました。
③<H19年出題(国年)> ×
無拠出制の福祉年金の給付が開始されたのは昭和34年11月からです。(10月が間違い)
「福祉年金」とは、保険料の負担なしで支給される年金で、「老齢福祉年金」「障害福祉年金」「母子(準母子)福祉年金」があります。例えば、「老齢福祉年金」は国民年金が成立したときに既に高齢になっていた人が対象です。
「福祉年金」の今
老齢福祉年金はそのまま支給されていますが、障害福祉年金と母子(準母子)福祉年金は、新法施行日(昭和61年4月1日)以降、それぞれ障害基礎年金、遺族基礎年金に裁定替えされています。
(昭60年法附則第25条、第28条)
社労士受験のあれこれ
年金の歴史その2(創成期)
R3-191
R3.3.2 厚生年金保険法の誕生
年金の歴史についてお話しています。
現在の公的年金には、「国民年金法」と「厚生年金保険法」がありますが、先にできたのは厚生年金保険法です。
社労士試験の科目の順番が、厚生年金保険法→国民年金法と厚生年金保険法の方が先なのはそのためです。
昭和16年に「労働者年金保険法」が制定されました(昭和17年施行)。対象は、工場で働く男性労働者でした。労働力を保全し強化することによって生産力を上げるという社会的な要請があったそうです。
その労働者年金保険法が「厚生年金保険法」という名称に改められたのが昭和19年。その際、事務系の労働者や女性も対象になりました。
そして、昭和29年に厚生年金保険法が全面改正されました。実際に養老年金の受給者が生ずることへの対応です。このときの改正で、老齢年金は定額部分と報酬比例部分の2階建てになりました。また、男子の支給開始年齢が55歳だったものが段階的に60歳に引き上げられることになりました。
(参考:平成18年版、平成23年版厚生労働白書など)
★旧法と新法
昭和61年4月1日より前の年金制度を旧法、それ以降を新法といいます。
新法の厚生年金保険は国民年金(基礎年金)の2階部分という位置づけです。
例えば、65歳からの年金は、1階に老齢基礎年金があって、2階に老齢厚生年金という形です。
しかし、60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」は定額部分(1階)と報酬比例部分(2階)で、厚生年金だけで2階建てになっています。これは国民年金と厚生年金保険が別個に運営されていた旧法の形を引き継いでいます。
旧法の厚生年金保険の老齢年金の支給開始年齢は60歳で定額部分と報酬比例部分の2階建てになっていました。新法になったときに国民年金の支給開始年齢に合わせて65歳開始になりましたが、いきなり60歳から65歳に引き上げることはできません。
ですので、まずは定額部分の開始年齢を1歳ずつ引き上げ、その次に報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げることで、段階的に60歳代前半の老齢厚生年金をなくしていく方法をとっています。旧法の形を徐々になくしていくイメージで考えてみてください。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史(創成期)
R3-190
R3.3.1 社会保険方式の年金制度はいつ始まった?
今日から年金の歴史を勉強しましょう。
20歳で国民年金に加入 → 40年保険料を納付 → 65歳から老齢年金を受給 → 人生100年と考えると年金を受ける期間は約40年近くなる。
考えてみたら、年金との付き合いは「被保険者」+「受給権者」で約80年という期間なのですね。
その間、社会や経済はどんどん変化していくので、それに合わせて年金も法改正が行われます。
年金の勉強に必要なのは、そんな変化の歴史です。
本日は、年金の創成期のお話です。
まずはこちらをどうぞ!
<社一 H22年出題>
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

【解答】 ×
船員保険法の制定は大正14年ではなく、昭和14年です。(昭和15年から施行)
また、年金等給付を含む総合保険で、「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。
★船員保険は、日本で最初の社会保険方式による「公的年金」★
創成期の船員保険は、船員を対象とする「年金」、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」、「健康保険に相当する疾病給付」を総合的に行う保険でした。
戦時体制下で、物資の海上輸送を担う船員の確保が急務だった頃です。
その後の船員保険は?
船員保険の「年金」は、昭和61年4月1日に、厚生年金保険法に統合されました。被保険者の減少や著しい高齢化で年金財政が悪化し、船員保険のみでは存続が厳しくなったからです。
また、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」は、平成22年からそれぞれ労災保険法、雇用保険法に統合されました。
現在の船員保険は、「職務外の疾病等に関する給付(健康保険に相当する部分)」と労災についての船員独自の上乗せの給付を行っています。
(参考:厚生労働白書平成23年版)
社労士受験のあれこれ
国民年金法第1条(目的)
R3-188
R3.2.27 第1条チェック~国民年金法編
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は国民年金法です。
条文をチェックしましょう!
<H28年選択>
(第1条 目的)
国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の< A >がそこなわれることを国民の < B >によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】
A 安定
B 共同連帯
★国民年金は「日本国憲法第25条第2項に規定する理念」に基づいています。
(参考)憲法第25条
① すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
国民年金は第2項の「国の社会保障的義務」の理念に基づきます。(第1項ではないので注意してください。)
では、こちらもどうぞ
<H26年出題>
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

【解答】×
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な「保険給付」ではなく「給付」を行います。
厚生年金保険法では「保険給付」といいますが、国民年金は「給付」といいます。
法律の名称も、「厚生年金保険法」と「国民年金法」。
国民年金には「保険」という用語が入っていません。
国民年金も保険方式で運営されるものの、例えば、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金や、保険料の全額免除期間のように、保険料の負担と給付が結び付かない給付があるからです。
ですので、「すべての給付は保険原理により行われる」の部分も誤り。保険原理でない給付も存在します。
(参考)国民年金法第2条
国民年金は、第1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(保険給付ではなく「必要な給付」となっています。)
社労士受験のあれこれ
(年金)第三種被保険者(船員・坑内員)の被保険者期間(その1国年編)
R3-180
R3.2.19 第三種被保険者の被保険者期間(3分の4・5分の6)が反映するか否か?(その1国年編)
今日は年金です!
令和2年度の出題振り返りは、いったん、終了します。
今日は、質問を頂きましたので、そちらのお返事です。
<質問の内容> 『平成24年の国民年金問題1で、厚生年金保険の第三種被保険者の納付済期間と老齢基礎年金の計算が違う点について』 |
厚生年金保険には「第三種被保険者」という種別があり、「坑内員・船員」が該当します。
労働が過酷だったため、厚生年金保険の被保険者期間は、昭和61年3月以前は「第3種被保険者であった期間×3分の4」、昭和61年4月から平成3年3月までは「第3種被保険者であった期間×5分の6」でカウントします。
3分の4倍又は5分の6倍した被保険者期間が、反映するものと反映しないものがあります。今日はそのお話です。
では、(国年)平成24年出題の問題をどうぞ!
<国年H24年出題>
国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については、その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。

【解答】 ×
国民年金の「保険料納付済期間」には、旧法の厚生年金保険の被保険者期間も含まれます。その際、第三種被保険者期間は3分の4倍でカウントされます。
ただし、「老齢基礎年金」の額の計算をする際の「保険料納付済期間」については、第三種被保険者期間は、3分の4倍又は5分の6倍しない「実期間」となります。
なぜなら、老齢基礎年金は「780,900円×改定率」が満額なので、3分の4倍(又は5分の5倍)して計算してもそれほどメリットが無いからではないか?と私は思っています。
ですので、平成24年の問題は、「その期間に3分の4を乗じて得た期間を保険料納付済期間として、老齢基礎年金の額が計算される。」の部分が誤りで、老齢基礎年金の額は、3分の4を乗じない「実期間」を保険料納付済期間として計算することになります。
<第三種被保険者であった期間のポイント>
・老齢基礎年金の受給資格を見る場合の保険料納付済期間
→ 3分の4倍又は5分の6倍した期間が適用
・老齢基礎年金の額を計算する場合の保険料納付済期間
→ 実期間で計算(3分の4倍、5分の6倍しない)
(参照:国民年金 昭和60年改正法附則第8条第2項、第3項)
★第三種被保険者のテーマは、明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
年金額の改定(国年と厚年)
R3-176
R3.2.15 国年と厚年を比較・年金額改定
まずは国民年金法です!
令和2年度の問題をどうぞ!(国年)
<問2-選択・国年>
国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに< B >の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。

【解答】
A 国民の生活水準
B 改定
国民年金は、老齢、障害、死亡を保障するための制度です。
「国民の生活水準」に著しい変動があれば、速やかに年金額の改定が行われます。
(国民年金法第4条)
こちらの問題もどうぞ!
<厚生年金保険法 年金額の改定>
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、< C >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】
C 賃金
厚生年金保険法の場合は、「賃金」という用語が入るのが特徴です。厚生年金保険は被用者のための年金制度だからです。
(厚生年金保険法第2条の2)
・国民年金 → 国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合
・厚生年金保険 → 国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合
こちらの問題もどうぞ!(厚生年金保険)
<H30年出題・厚年>
厚生年金保険法に基づく保険料率は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】 ×
冒頭の「厚生年金保険法に基づく保険料率」が誤りです。この条文は、保険料率ではなく、「年金たる保険給付」の改定のルールです。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(年金)被保険者期間のカウント
R3-133
R3.1.3 第1号被保険者の資格取得・喪失と保険料
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-B>
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

【解答】 〇
■ 平成12年1月1日生まれの場合、令和元年12月31日に20歳に達するので、その日に第1号被保険者の資格を取得します。なお、その後ずっと第1号被保険者だった場合、60歳に達した日(令和41年12月31日)に資格を喪失します。
■ 被保険者期間は月単位で計算します。被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までですので、問題文の場合、令和元年12月から令和41年11月までとなります。
■ 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収されます。
こちらの問題もどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
 <H26年出題>
<H26年出題>
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。
 <H29年出題>
<H29年出題>
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

【解答】
 <R1年出題> ×
<R1年出題> ×
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達するのは平成31年3月31日です。被保険者期間に算入されるのは、平成31年3月からです。
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
昭和29年4月1日生まれの者が60歳に達して資格を喪失するのは平成26年3月31日です。被保険者期間は、資格を喪失した日の属する月の前月ですので、被保険者期間に算入されるのは平成26年2月までです。
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
第1号被保険者が平成29年3月31日に死亡した場合、翌日の平成29年4月1日に資格を喪失します。被保険者期間は同年3月までで、保険料の納付義務も3月分までです。
社労士受験のあれこれ
(年金)老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした
R3-132
R3.1.2 支給繰下げの申出があったものとみなされるのはいつ?
令和2年度の問題をどうぞ!
<問5-D>
老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70歳達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。

【解答】 〇
この問題のポイントは
・ 66歳~70歳までの間に遺族厚生年金の受給権を取得した
・ 支給繰下げの申出をしたのが70歳
この場合、『遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日』に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
・66歳に達した日後に次の①又は②に掲げる者が支給繰下げの申出をしたときは、次の①又は②に定める日において、支給繰下げの申出があったものとみなす。
① 70に達する日前に他の年金たる給付(※)の受給権者となった者
→ 他の年金たる給付(※)を支給すべき事由が生じた日
(※)他の年金たる給付とは? → 他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)
② 70歳に達した日後にある者(①該当する者を除く。)
→ 70歳に達した日
問題文の場合①に該当します。70歳に達する前に他の年金たる給付(問題文の場合、遺族厚生年金)の受給権者となっているので、「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」に繰下げの申出があったものとみなされます。
 ちなみに、このような場合
ちなみに、このような場合
<繰下げの増額率の計算は?>
①の場合は、「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」、②の場合は、「70歳に達した日」の時点で、増額率が計算されます。
<繰下げた老齢基礎年金はいつから支給される?>
①の場合は、「他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日」の属する月の翌月から、②の場合は、「70歳に達した日」の属する月の翌月から、支給されます。
問題文の場合は、増額率は「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」の時点で計算し、支給は「遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日」の属する月の翌月からとなります。
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】 〇
以下の場合は、繰下げの申出はできません。
・65歳に達したときに、他の年金たる給付(※)の受給権者であったとき
・65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付(※)の受給権者となったとき
※他の年金たる給付 → 他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。
問題文では、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となった」とあるので、繰下げの申出はできません。
社労士受験のあれこれ
(年金)追納できる期間
R3-131
R3.1.1 追納できるのはいつからいつまで?
あけましておめでとうございます! 今年も「社会保険労務士合格研究室」をよろしくお願いします。 合言葉の「毎日コツコツ」頑張りましょう! |
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-エ>
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

【解答】 〇
追納できるのは、「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るもの」に限られています。
アンダーライン部分「以前10年」ではなく「前10年」なのがポイント。承認を受けた月は入りません。
問題文の場合、追納の承認を受けたのが令和2年4月なので、その前月から10年以内が対象です。
令和2年3月からさかのぼって10年以内にあるのは平成22年4月ですので、追納の対象は平成22年4月から平成28年3月までとなります。
こちらの問題もどうぞ!
<H30年出題>
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

【解答】 〇
老齢基礎年金の受給権者は追納できないことにも注意してください。
ちなみに、「障害基礎年金の受給権者は追納できるか否か」という問題が過去に出題されていますが、「障害基礎年金の受給権者は追納できます」。
障害基礎年金は、障害の状態によっては支給停止になる可能性もありますよね?追納して老齢基礎年金の受給額を増やす選択もできるのです。
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

【解答】 〇
一部免除の期間も追納できます。
例えば、4分の1免除は、「4分の1」は免除されますが、残りの4分の3は納付しなければなりません。
4分の3を納付してこその「4分の1免除期間」であり、その免除された4分の1を追納することは可能です。
一方、4分の3を納付していなければ未納期間です。問題文にあるように4分の3を納付していないときは、追納もできません。
社労士受験のあれこれ
(年金)脱退一時金(日本から出国する外国人が対象)
R3-130
R2.12.31 脱退一時金を受けた後のこと
今年も1年ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
良いお年を。
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-ウ>
日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、平成7年4月から平成9年3月までの2年間、国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成23年4月から日本に居住することになり、60歳までの8年間、第1号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】 ×
「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている」が間違いで、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしません。
脱退一時金には、「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。」という規定があります。
問題文でいうと、脱退一時金の計算の基礎となった「平成7年4月から平成9年3月までの2年間」は、被保険者でなかったことになります。(合算対象期間にもならない)
再び日本国内に居住し8年間保険料を納付しても、受給資格期間の10年に満たないので老齢基礎年金の受給資格はできません。
こちらの問題もどうぞ!
<H20年出題>
脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。

【解答】 〇
令和2年度の出題と同じ趣旨です。
ちなみに。。。
日本と「年金通算の社会保障協定」を締結している国の場合、一定の要件を満たすと、年金の加入期間を通算することができます。
ただし、脱退一時金を受けた場合は、その計算の基礎となった期間は通算されなくなります。
社労士受験のあれこれ
(年金)法定免除と保険料納付
R3-129
R2.12.30 法定免除に該当していても保険料は納付できる?
令和2年度の問題をどうぞ!
<問10-イ>
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。

【解答】 〇
法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。
将来の老齢基礎年金を増やしたい場合は、本人の申出によって、法定免除の期間の保険料を納付することもできます。
こちらの問題もどうぞ!
<H29年出題>
国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

【解答】 〇
もう一問どうぞ!
<H16年出題>
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。

【解答】 ×
法定免除の対象になるのは、障害基礎年金、障害厚生年金等(1・2級)の受給権者です。
障害厚生年金の受給権者でも3級(一度も2級以上に該当していない)は、法定免除の対象になりません。
ちなみに、過去に1・2級の障害年金を受けていたが、障害の程度が軽くなり、現在3級に該当している場合は、法定免除の対象となります。
※ なお、3級に該当しなくなった日から起算して、障害状態に該当することなく3年を経過した場合は、法定免除の対象から除かれます。(保険料の納付義務が発生する)
社労士受験のあれこれ
(年金)法定免除について
R3-127
R2.12.28 法定免除→いつから免除になる?手続きは?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問10-オ >
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】 〇
この問題のチェックポイントはこちら!
 「法定免除」の事由に該当している?
「法定免除」の事由に該当している?
「生活保護法による生活扶助を受けるようになった」→ 法定免除事由に該当する
生活保護には、「生活扶助」「住宅扶助」「教育扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8つの扶助がありますが、保険料の法定免除の対象になるのは、そのうちの「生活扶助」です。
 いつから免除される?
いつから免除される?
■法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になる。
例えば、12月に該当した場合は、11月から免除になります。(11月分の納期限が12月末なので)
■既に納付された保険料は免除にならない。
 手続きは?
手続きは?
法定免除事由に該当した日から14日以内に届書を市町村に提出しなければならない。(厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、提出不要)
★法定免除の効果は要件に該当すれば当然に発生します。届出の有無は効果に関係ありませんが、該当した事実を確認するために必要です。
こちらもどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
 <H27年出題>
<H27年出題>
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
 <H26年出題>
<H26年出題>
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

【解答】
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
法定免除は、要件に該当すれば当然に免除の対象になるため、当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得は関係ありません。
また、法定免除の期間(その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで)もしっかりおさえてください。
 <H27年出題> ×
<H27年出題> ×
法定免除の対象は「生活扶助」のみです。生活扶助以外の扶助は、申請免除の対象になり得ます。
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
老齢基礎年金の額を増やすために、法定免除期間中、本人から保険料を納付する旨の申出があった場合、その期間の保険料を納付することができます。
社労士受験のあれこれ
(年金)死亡一時金の額+α
R3-126
R2.12.27 死亡一時金の算定と付加保険料
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問2-A >
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】 〇
この問題のポイント!
 死亡一時金の額は「定額」・保険料を納付した月数によって、6段階
死亡一時金の額は「定額」・保険料を納付した月数によって、6段階
<死亡一時金の額>
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における次の月数を合算した月数に応じて定められています。
・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
・保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
・保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
| 月数 | 金額 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 | |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 | +25,000 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 | +25,000 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 | +50,000 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 | +50,000 |
| 420月以上 | 320,000円 | +50,000 |
 付加保険料の納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円加算される
付加保険料の納付済期間が3年以上ある場合は、8,500円加算される
こちらもどうぞ!
 <R1年出題>
<R1年出題>
死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者期間としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく、当該被保険者に死亡一時金の支給対象となる遺族があるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。
 <H24年出題>
<H24年出題>
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
 <H24年出題>
<H24年出題>
死亡一時金の額は、毎年度、所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である。
 <H24年出題>
<H24年出題>
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算される。

【解答】
 <R1年出題> 〇
<R1年出題> 〇
保険料4分の1免除期間は「4分の3」で計算しますので、問題文の場合、48月×4分の3=36月です。
死亡一時金は合算した月数(令和2年度の解説をご確認ください。)が36月以上あることが条件ですので、要件を満たします。
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
保険料全額免除期間は36月の計算に入れません。(保険料を全く納めていないので)
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
死亡一時金の額は、6段階の定額です。
 <H24年出題> ×
<H24年出題> ×
付加保険料の納付は、寡婦年金の額には反映しません。付加保険料が反映するのは死亡一時金のみです。
社労士受験のあれこれ
(年金)基礎年金拠出金
R3-121
R2.12.22 基礎年金拠出金は第2号と第3号の基礎年金の費用
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 選択式>
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。

【解答】
A 実施機関たる共済組合等
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に保険料を納付していませんが、基礎年金を受けることができます。
第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用のため、厚生年金保険から国民年金に「基礎年金拠出金」を支払っています。
こちらもどうぞ!
 <H28年出題>
<H28年出題>
実施機関たる共済組合等は、毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の基礎年金拠出金を、厚生労働省令の定めるところにより、日本年金機構に納付しなければならない。
 <H24年出題>
<H24年出題>
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。

【解答】
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
日本年金機構ではなく、「国民年金の管掌者たる政府」に納付します。
 <H24年出題> 〇
<H24年出題> 〇
第2号被保険者と第3号被保険者からは国民年金の保険料は徴収しません。第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付の費用は、基礎年金拠出金が使われます。
社労士受験のあれこれ
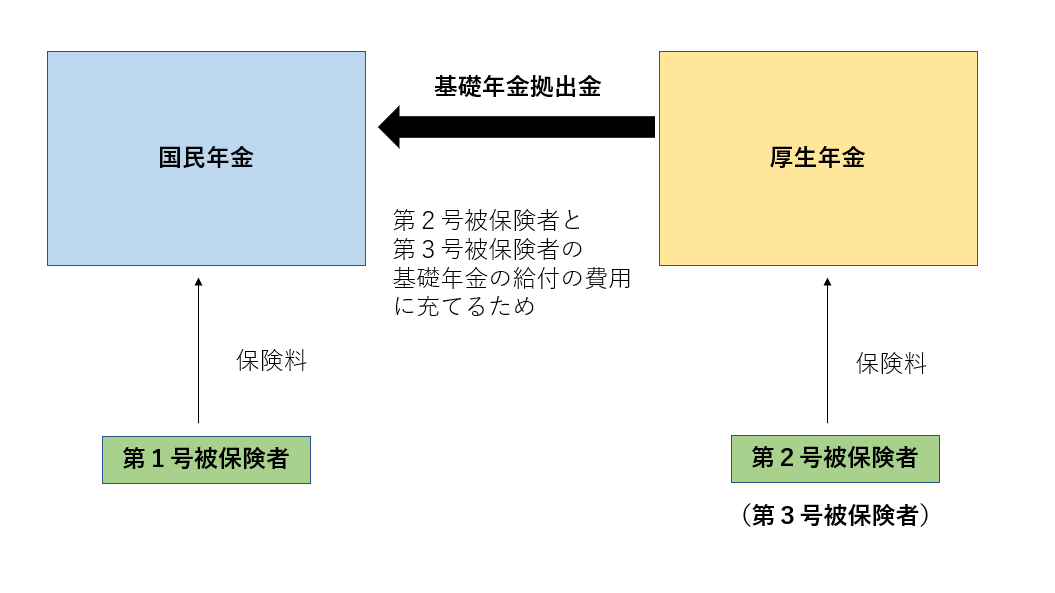
(年金)基準障害(前後の障害を併合して初めて障害等級に該当)
R3-120
R2.12.21 基準障害~初診日・保険料納付要件はどこでみる?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問3‐A>
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。

【解答】 ×
「基準傷病による障害基礎年金」は、「はじめて2級以上に該当したことによる障害基礎年金」とも言われます。
既に先発の傷病による障害(単独では2級に満たない)があったところに、新たに傷病(基準傷病)が発生し、先発障害と基準障害を併合して初めて1・2級に該当した場合の規定です。
基準傷病(基準障害)は、後から新しく発生した傷病で、1・2級に該当するきっかけになる傷病のことです。
「初診日要件」と「保険料納付要件」は、「基準傷病」で判断するのがポイントです。
問題文の場合、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合でも、基準傷病に係る初診日に被保険者であれば初診日要件を満たします。
こちらもどうぞ!
 <H18年出題>
<H18年出題>
既に障害の状態にある者が、新たに発生した傷病(「基準傷病」という)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当した場合には、基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として、障害基礎年金が支給される。
 <H29年出題>
<H29年出題>
国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとしても、その請求を65歳に達した日以後に行うことはできない。
 <H20年出題>
<H20年出題>
いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

【解答】
 <H18年出題> 〇
<H18年出題> 〇
令和2年の出題と同じ趣旨です。
「初診日要件」と「保険料納付要件」は、「基準傷病」で判断するのがポイントです。
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
請求は、65歳に達した日以後でもできます。
 <H20年出題> ×
<H20年出題> ×
基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件(基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して、初めて障害の程度が2級以上に該当)に該当すれば受給権が発生します。
65歳に達した日以後でも請求できますが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月からではなく、「請求があった月の翌月」から開始されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)老齢基礎年金の受給資格
R3-119
R2.12.20 厚年第3種被保険者の被保険者期間の特例
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問9‐D>
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】 ×
老齢基礎年金の受給資格を満たしているので、65歳以上の特例の任意加入被保険者になることはできません。
★ 厚生年金保険の第3種被保険者とは、「坑内員・船員」である被保険者のことです。過酷な労働だったため、受給資格期間を計算する際の特例が設けられています。
| 昭和61年3月まで | 平成3年3月まで | 平成3年4月以降 |
| 3分の4倍 | 5分の6倍 | 実期間 |
問題文の場合、平成3年3月までの実期間が72月、平成3年4月以降が36月。72月は5分の6倍で計算しますので、老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たします。
そのため、65歳以上の特例による任意加入はできません。
こちらもどうぞ!
<厚年 H25年選択>
厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、昭和61年4月1日から< A >4月1日前までの被保険者期間について、当該第3種被保険者であった期間に< B >を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。

【解答】
A 平成3年
B 5分の6
社労士受験のあれこれ
(年金)国年保険料の前納
R3-116
R2.12.17 一部免除の保険料は前納できる?できない?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問2‐D>
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

【解答】 ×
一部免除の保険料も、前納は適用されます。
こちらもどうぞ!
<H30年出題>
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】 ×
「各月の初日が到来」が×です。
前納に係る期間の「各月が経過した」際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
もともと、国民年金の保険料は、翌月末日が納期限(後払い)であることを思えば、納得だと思います。
では、こちらで横断の練習をどうぞ!
【国民年金】 保険料の前納
前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の< A >した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【健康保険】 任意継続被保険者の保険料の前納
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
前納された保険料については、前納に係る期間の< B >が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
A 各月が経過
B 各月の初日
※健康保険の任意継続被保険者の保険料は、通常は「当月10日」が納期限です。それをヒントに考えるといいと思います。
社労士受験のあれこれ
(年金)振替加算の生計維持の認定
R3-115
R2.12.16 振替加算の加算事由と生計維持の認定
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問7‐B>
老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。

【解答】 〇
例えば、妻(振替加算の対象)が65歳になった後に、夫が240月(原則)以上で計算された老齢厚生年金を受けられるようになった場合は、そこで、生計維持関係を確認することになります。
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】 〇
問題文の場合、退職時改定によって加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たすことになりますが、妻が既に66歳になっていますので加給年金額は加算されません。
夫の厚生年金保険の資格喪失日から妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
その際、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することが必要です。(身分関係や生計維持関係の確認のためです)
社労士受験のあれこれ
(年金)保険料全額免除期間の定義
R3-114
R2.12.15 保険料全額免除期間に入るもの、入らないもの
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問5‐B>
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

【解答】 ×
「産前産後期間の保険料免除」は全額免除期間には入りません。
※ 「産前産後期間の保険料免除」は保険料納付済期間に入ります。
こちらもどうぞ!
 <H24年出題>
<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
 <令和元年出題>
<令和元年出題>
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。

【解答】
 <H24年出題> 〇
<H24年出題> 〇
保険料の全額免除を受けたとしても、「追納」で保険料を納付した場合は、保険料納付済期間となります。
ちなみに、「追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたもの」とみなされます。追納した日に、その月分が保険料免除期間から保険料納付済期間に変わるイメージで。
 <令和元年出題> ×
<令和元年出題> ×
産前産後期間の免除の期間
| 免除の届出をした後に出産した場合 | 出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで ※多胎妊娠の場合 出産予定月の3か月前~出産予定月の翌々月まで |
| 免除の届出を行う前に出産した場合 | 出産月の前月~出産月の翌々月まで ※多胎妊娠の場合 出産月の3か月前~出産月の翌々月まで |
問題文の場合、保険料免除の届出をした後の出産ですので、「出産予定日」を基準にします。免除期間は、出産予定月の前月~出産予定月の翌々月まで。令和元年9月分から令和元年12月分となります。
なお、免除期間は4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)です。
届け出後の出産は「出産予定日」、届け出前の出産は「出産日」が基準です。
社労士受験のあれこれ
(年金)任意加入被保険者と国民年金基金
R3-113
R2.12.14 任意加入被保険者は国民年金基金に加入できる?できない?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問2‐C>
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。

【解答】 〇
任意加入被保険者のうち、国民年金基金に加入できるのは、
・ 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
・ 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
の2つです。
→ ちなみに、
「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」、65歳以上70歳未満の「特例による任意加入被保険者」は基金に加入できませんので注意しましょう。
こちらもどうぞ!
 <H29年出題>
<H29年出題>
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
 <H29年出題>
<H29年出題>
国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、加入員の資格を喪失する。
 <H27年出題>
<H27年出題>
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
 <H29年出題> ×
<H29年出題> ×
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員になることができます。(令和2年の問題と同じ)
 <H29年出題> 〇
<H29年出題> 〇
農業者年金の被保険者は基金に加入できません。翌日ではなく「その日」に、加入員の資格を喪失することにも注意してください。
 <H27年出題> 〇
<H27年出題> 〇
喪失日の「その月の初日」にも気を付けてください。
社労士受験のあれこれ
(年金)国民年金の時効
R3-111
R2.12.12 国年時効の起算日は?
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問7‐D>
年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。

【解答】 〇
※年金の支分権の時効についての問題です。
■年金には、
・基本権 → 年金を受ける権利
・支分権 → 支払い期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利
の2つがあり、支分権の時効の起算日は、年金の支払期月の翌月の初日です。
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】 ×
★ 「年金」と「保険料、死亡一時金」の時効の違いに注意しましょう。
| 年金給付を受ける権利 | その支給すべき事由が生じた日から5年 |
・保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 ・死亡一時金を受ける権利 | これらを行使することができる時から2年 |
穴埋めで練習しましょう!
年金給付を受ける権利は、< A >から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する< B >から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び< C >を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
A その支給すべき事由が生じた日
B 支払期月の翌月の初日
C 死亡一時金
社労士受験のあれこれ
(年金)失踪宣告と生計維持
R3-108
R2.12.9 失踪宣告を受けた場合の生計維持関係はどの時点でみる?
令和2年の問題をどうぞ!
<厚年 問1‐C>
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある者とする。)が行方不明になり、その後失踪の宣告を受けた場合、失踪者の遺族が遺族厚生年金を受給するに当たっての生計維持に係る要件については、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われる。

【解答】 〇
★ 行方不明となった人の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所は失踪宣告をすることができ、行方不明から7年間が満了したときに死亡したものとみなされます。
遺族厚生年金等については、「行方不明となった日」を「死亡日」として取り扱い、生計維持関係や保険料納付要件等をみることになります。
ただし、遺族厚生年金等の受給権は、失踪宣告が確定した日に発生し、受給権者の身分関係、年齢、障害状態は、失踪宣告による死亡日(7年後)で判断します。
この問題は、「生計維持に係る要件」についてですので、行方不明となった当時の失踪者との生計維持関係が問われます。
では、こちらもどうぞ!
 国年 H18年出題
国年 H18年出題
失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。
 国年 H26年出題
国年 H26年出題
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
 国年 R2出題
国年 R2出題
失踪の宣告を受けたことにより死亡とみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。

【解答】
 国年 H18年出題 ×
国年 H18年出題 ×
「5年」ではなく、7年を経過した日に死亡したものとみなされます。
 国年 H26年出題 〇
国年 H26年出題 〇
・ 生計維持関係、被保険者資格、保険料納付要件 → 行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
・ 受給権者の身分関係、年齢、障害状態 → 失踪宣告による死亡日(7年後)で判断
 国年 R2出題 ×
国年 R2出題 ×
保険料納付要件は、「死亡日の前日」で判断します。失踪宣告の場合は、「行方不明となった日」を「死亡日」としますので、保険料納付要件は「行方不明となった日の前日」で判断することになります。
社労士受験のあれこれ
(年金)老齢基礎年金繰下げの増額率
R3-106
R2.12.7 繰下げ増額率の計算式
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問10‐ア>
第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生まれ)が、令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、付加年金額に25.9%を乗じて得た額が付加年金額に加算され、申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される。

【解答】 ×
増額率は、25.2%(1,000分の7×36月)です。
■ 老齢基礎年金の繰下げについては、繰下げた月数分、老齢基礎年金が増額されます。月数は、「受給権取得月~繰下げの申出をした日の属する月の前月まで」です。
■ 問題文の場合、65歳に到達した平成29年4月に受給権を取得し、令和2年4月に繰下げの申出を行っていますので、平成29年4月から令和2年3月までの月数である36月で増額率を出します。
■ 付加年金は老齢基礎年金と一心同体なので、増額率、支給開始月ともに老齢基礎年金と同じです。
では、こちらもどうぞ!
 空欄を埋めてください
空欄を埋めてください
昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は< A >に当該年金の受給権を取得した日の< B >から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の< C >までの月数(当該月数が< D >を超えるときは、< D >)を乗じて得た率をいう。
 <H22年出題>
<H22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。
 <H29年出題>
<H29年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

【解答】 〇

A 1,000分の7
B 属する月
C 属する月の前月
D 60
 <H22年出題> ×
<H22年出題> ×
申出を行った日の属する月ではなく、申出を行った日の属する月の前月までの月数です。
 <H29年出題> 〇
<H29年出題> 〇
ポイント!
老齢基礎年金を繰下げた場合、付加年金についても繰り下げられ、老齢基礎年金と同じ率で増額されます。
もう一つ。繰上げの場合も同様です。老齢基礎年金を繰り上げた場合、付加年金も繰り上げられ老齢基礎年金と同じ率で減額されます。
社労士受験のあれこれ
(年金)障害の程度が変わった場合の年金額の改定
R3-105
R2.12.6 障害が増進したことによる改定請求
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問1‐エ>
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】 〇
障害基礎年金については、障害の程度(障害等級)に変更があった場合、額の改定が行われます。
厚生労働大臣の職権による改定と、障害の程度が増進したことによる受給権者からの改定請求による方法がありますが、今回の出題は、受給権者からの改定請求についてです。
短期間のうちに、何回も「障害の程度が変わった」という請求を避けるため、原則として、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年待たなければ、額の改定請求はできません。
ただし、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」は、1年経過しなくても請求することができます。
「障害の程度が増進したことが明らかである場合」については、厚生労働省令で具体的に定められていて、問題文の「人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着」するに至ったこともその一つです。
つまり、人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合は、受給権取日から1年経過していなくても、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求ができます。
では、こちらもどうぞ!
★空欄を埋めてください。
【障害の程度が変わった場合の年金額の改定】
1 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が< A >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 2の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が< A >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して < B >でなければ行うことができない。

【解答】 〇
A 増進
B 1年を経過した日後
社労士受験のあれこれ
(年金)障害の程度の審査のための診断書
R3-104
R2.12.5 障害基礎年金・障害の現状に関する届出
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問6‐C>
障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前1か月以内に作成されたその障害の状況に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
障害状態確認届(診断書)の作成期間は、指定日前1か月以内から、令和元年8月から「指定日前3か月以内」に拡大されています。
★「障害状態確認届」とは → 厚生労働大臣が指定した年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するためのもの
では、こちらもどうぞ!
<厚生年金保険 障害の現状に関する届出 (参考)H21年出題>
障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の額の全部につき支給停止されている者を除く。)であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 〇
国民年金同様、厚生年金保険も「3か月」です。
また、全部につき支給停止されている場合は、診断書の提出は不要です。(国年も同様)
社労士受験のあれこれ
(年金)「生計維持」の認定
R3-103
R2.12.4 生計維持要件850万円について
令和2年の問題をどうぞ!
<国年 問1‐ウ>
遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。

【解答】 ×
定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)の収入が年額850万円未満(又は所得が年額655.5万円未満)となると認められるときは、収入の認定要件に該当します。
★『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕』より
■生計維持認定対象者は?
| 国民年金法 | 厚生年金保険法 |
|---|---|
| 老齢基礎年金の振替加算等の対象者 | 老齢厚生年金の加給年金額の対象の配偶者及び子 |
| 障害基礎年金の加算額の対象の子 | 障害厚生年金の加給年金額の対象の配偶者 |
| 遺族基礎年金の受給権者 | 遺族厚生年金の受給権者 |
| 寡婦年金の受給権者 |
■収入に関する認定要件は、「厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外」とされています。
■具体的には、
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。
※障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者の場合は、「エ」が「ア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。」となります。
では、こちらもどうぞ!
 <厚生年金 H18年出題>
<厚生年金 H18年出題>
老齢厚生年金の加給年金額に係る生計維持関係は、受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり、かつ厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者であって、近い将来に年収が850万円(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については、維持関係があるとは認定されない。
 <厚生年金 H27年出題>
<厚生年金 H27年出題>
老齢厚生年金(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)の加給年金額に係る生計維持関係の認定要件について、受給権者がその権利を取得した当時、その前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外の者でなければならず、この要件に該当しないが、定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合であっても、生計維持関係が認定されることはない。

【解答】
 <厚生年金 H18年出題> ×
<厚生年金 H18年出題> ×
 <厚生年金 H27年出題> ×
<厚生年金 H27年出題> ×
生計維持の要件は、「厚生労働大臣が定める年収850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められない者」とされています。
前年の収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が年額850万円未満(前年の所得(前年の所得が確定しない場合は前々年の所得)が年額655.5万円未満)でなかったとしても、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められれば、認定要件に該当します。
社労士受験のあれこれ
(国年)任意加入被保険者の申出
R3-099
R2.11.30 国年/任意加入被保険者の要件
令和2年の問題をどうぞ!
<問9‐B>
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】 ×
日本国籍を有していれば、日本国内に住所を有していなくても任意加入できます。
任意加入被保険者の申出ができる要件は次の通りです。
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
※ただし、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当する場合は、任意加入できません。
問題文の場合は、③に当てはめて考えてみてください。
なお、老齢基礎年金を増やすことは「任意加入」の目的の一つです。
問題文のように特別支給の老齢厚生年金を受給していても、老齢基礎年金を満額にするために65歳まで任意加入することは可能です。
ちなみに、65歳以上70歳未満の「特例」の任意加入被保険者の場合は、老齢基礎年金を増やす目的では任意加入できません。受給資格期間を満たせない人だけを対象にしています。
こちらもどうぞ!
 <H25年出題>
<H25年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
 <H27年出題>
<H27年出題>
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

【解答】
 <H25年出題> ×
<H25年出題> ×
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、国籍問わず、任意加入できます。
 <H27年出題> ×
<H27年出題> ×
65歳以上70歳未満を対象とする特例による任意加入被保険者の条件のポイントは、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない」ことと、「昭和40年4月1日以前生まれ」であることです。
問題文の「昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り」が間違いです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(国年)
R3-089
R2.11.20 <R2出題>覚える「第3号被保険者の届出」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問6-B>
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。

【解答】 ×
第3号被保険者は「厚生労働大臣」に届出なければなりません。
なお、第1号被保険者は「市町村長」に届出します。
では、関連問題をどうぞ!
 H20年出題
H20年出題
第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとされている。
 R1年出題
R1年出題
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
 H23年出題
H23年出題
健康保険組合を設立する事業主は、その使用する第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の経由に係る事務の全部又は一部を当該健康保険組合に委託することができる。

【解答】
 H20年出題 〇
H20年出題 〇
第3号被保険者の届出は、第2号被保険者を使用する事業主や共済組合等を経由して行います。
平成14年3月までは、第3号被保険者が自ら市町村長に届出をすることになっていましたが届け出漏れが多かったため、平成14年4月から事業主等を経由することになりました。
 R1年出題 〇
R1年出題 〇
第2号被保険者を使用する事業主(共済組合等)が届出を受理した=そのときに厚生労働大臣に届出があったとみなされます。
 H23年出題 ×
H23年出題 ×
健康保険組合に委託できるのは「一部」です。「全部」委託することはできません。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(国年)
R3-079
R2.11.10 <R2出題>問題の意図「被保険者期間がない者の障害基礎年金」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問2-イ>
初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。

【解答】 ×
問題の意図は、「初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者に障害基礎年金は支給されるか?」です。
国民年金に加入してすぐ初診日があるような場合です。
例えば、令和2年11月8日に20歳に達して第1号被保険者の資格を取得して、同年11月20日に初診日がある人の場合、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がありません。
障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある」場合に適用されます。
前々月までに被保険者期間がない場合は、滞納が無いということで、保険料納付要件は問わず、障害基礎年金が支給されます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(国年)
R3-068
R2.10.30 R2出題【選択練習】年金額改定の基準
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>を埋めてください。
年金額の改定は、受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では、< A >を基準として、また68歳に到達した年度以後は< B >を基準として行われる。
【選択肢】 ①物価変動率 ②名目手取り賃金変動率 ③名目賃金変動率
(参考:問6A)

【解答】
A ②名目手取り賃金変動率
B ①物価変動率
 年金の額は、毎年度、賃金や物価の動向に合わせて改定されています。
年金の額は、毎年度、賃金や物価の動向に合わせて改定されています。
 新規裁定者(68歳到達年度前)は、まだ現役に近いので働く人の生活水準(名目手取り賃金変動率)に合わせる、既裁定者(68歳到達年度以後)は、引退世代の生活水準(物価変動率)に合わせる、と考えてみてください。
新規裁定者(68歳到達年度前)は、まだ現役に近いので働く人の生活水準(名目手取り賃金変動率)に合わせる、既裁定者(68歳到達年度以後)は、引退世代の生活水準(物価変動率)に合わせる、と考えてみてください。
ちなみに・・・
令和2年度は、
・物価変動率 → +0.5%
・名目手取り賃金変動率 → +0.3%
でした。
「物価」「名目手取り賃金」が両方とも「+」で「物価」の方が上回っています。このような場合は、既裁定者は「物価」ではなく「名目手取り賃金変動率」を基準とします。
なぜなら「年金」は世代間扶養だから。年金は現役世代の保険料で支えられています。既裁定者の方が新規裁定者よりも年金額の伸びが大きくなるのは、理屈に合わないからです。
令和2年度の年金額は、新規裁定者も既裁定者も「名目手取り賃金変動率」を基準に改定が行われました。
(名目手取り賃金変動率「+0.3%」にスライド調整率「̠̠0.1%」がかかりました。)
R2年問題から~定番問題(国年)
R3-059
R2.10.21 R2出題・死亡一時金と年金との関係
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問1より
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】 ×
死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金は支給されます。
★遺族基礎年金と死亡一時金の関係
(原則)
死亡した者の死亡日にその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。 → 死亡一時金は支給されない。
(例外)
死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき → 死亡一時金は支給される。
例えば、被保険者の死亡時に、子が18歳の年度末(3月)だった場合、遺族基礎年金の受給権は発生しますが、同月中に受給権は消滅してしまいます。 そのため、結局、受給権はできても遺族基礎年金は受給できません。 この場合は、例外規定の「死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき」に該当しますので、死亡一時金が支給されます。 |
では、類似問題をどうぞ!
<H24年出題>
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】 ×
死亡一時金の支給を受ける者が、夫の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、どちらか一方を支給し、他方は支給しない、とされています。寡婦年金が優先されるわけではありません。
ポイント! 死亡一時金と寡婦年金のどちらを受けるかは、受給権者が選択する
問題文は、寡婦年金を優先しているので間違いです。
寡婦年金と死亡一時金では、寡婦年金の方が額が多いと考えがちですが、そうとも限りません。
例えば、65歳近くなって寡婦年金の受給権ができたとしたら、死亡一時金の方が額が多くなる可能性がありますので。
では、穴埋め問題をどうぞ!
1 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が< B >月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。ただし、老齢基礎年金又は< C >の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
2 1の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
① 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により< D >を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該< D >の受給権が消滅したときを除く。
② 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により < D >を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該< D >の受給権が消滅したときを除く。

【解答】
A 前月
B 36
C 障害基礎年金
D 遺族基礎年金
最後にもう一問どうぞ!
<H28年出題>
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。

【解答】 ×
上記の穴埋め問題でも出てきましたように、死亡した者が、「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある」ときは、死亡一時金は支給されません。
一方、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときでも、要件を満たせば遺族に死亡一時金が支給されます。
「死亡一時金」は掛け捨て防止が目的です。
老齢基礎年金や障害基礎年金をうけたことがあるなら国民年金の保険料は掛け捨てにはなりませんよね。だから、老齢基礎年金や障害基礎年金をうけたことがある者が死亡した場合は、死亡一時金は支給されません。
一方、遺族基礎年金を受けたことがある者が死亡したときは、要件を満たせば死亡一時金は支給されます。遺族基礎年金の場合、受ける本人の保険料納付要件ではなく、死亡した人の保険料納付要件が反映されるからです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(国年)
R3-049
R2.10.11 R2出題・難問解決策「寡婦年金の支給要件」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問4より>
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。

【解答】 ×
寡婦年金の条文を読んでみると、死亡した夫の要件として、
「夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は、寡婦年金は支給しないとあります。
老齢基礎年金の「支給を受けていた」ときは寡婦年金は支給されませんが、受給権があったとしても「支給を受けていない」場合なら、寡婦年金は支給されます。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H14年出題>
寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。

【解答】 〇
死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていたときは、寡婦年金は支給されません。
ではこちらもどうぞ!
<H18年出題>
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給をうけたことがなければ寡婦年金は支給される。

【解答】 ×
死亡した夫が、「障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は、寡婦年金は支給されません。
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、実際に支給をうけていなくても寡婦年金は支給されません。
老齢基礎年金との違いに注意してください。
ちなみに、行政解釈では、夫が障害基礎年金の受給権者であった場合とは、現実の年金の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさす、とされています。
では、選択の練習をどうぞ!
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が < A >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< B >年以上継続した < C >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が< D >の受給権者であったことがあるとき、又は < E >の支給を受けていたときは、この限りでない。

【解答】
A 10
B 10
C 65
D 障害基礎年金
E 老齢基礎年金
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~国民年金法
R3-039
R2.10.1 R2・任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違い
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金の強制被保険者ですが、それに当てはまらない人でも、任意で加入できる制度があります。
任意加入には次の2つパターンがあります。
1.任意加入被保険者
2.特例による任意加入被保険者
今日のテーマは、1.と2.の違いです。
 付加保険料
付加保険料
<R2年問3E>
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】 〇
「任意加入被保険者」も第1号被保険者と同じように付加保険料を納付できます。
では、「特例による任意加入被保険者」は付加保険料を納付できるでしょうか?
こちらの問題をどうぞ
<H15年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を納付する者となることができるが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付する者となることはできない。

【解答】 〇
特例による任意加入被保険者の目的は、「老齢基礎年金の受給資格を得るため」で、増やすためではありません。
一方、「付加保険料」の目的は増やすため。
目的が合致しないため、特例による任意加入被保険者は付加保険料の納付はできません。
 「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違い
「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違い
| 任意加入被保険者 | 特例による 任意加入被保険者 | |
|---|---|---|
| 付加保険料 | 〇 納付できる | × 納付できない |
| 寡婦年金 | 〇 算入される | × 算入されない |
| 死亡一時金 | 〇 算入される | 〇 算入される |
| 脱退一時金 | 〇 算入される | 〇 算入される |
 寡婦年金
寡婦年金
<R2年問9A>
68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した当該夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。

【解答】 ×
寡婦年金は支給されません。
特例による任意加入被保険者としての期間は、寡婦年金の期間には算入されないからです。(上の表を参照)
では、こちらをどうぞ!
<H28年出題>
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

【解答】 〇
上の表を参照してください。「特例による任意加入被保険者」と比較しておさえてください。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(国民年金法)
R3-029
R2.9.21 過去の論点は繰り返す(R2・国年「死亡一時金の要件」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
死亡一時金の要件
問題<H24年出題>
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。

【解答】 ×
全額免除期間は、36月の月数の計算には入りません。
全額免除期間は、保険料の負担が「ゼロ」だった期間。
死亡一時金は、保険料の掛け捨て防止のためのものなので、保険料の負担のなかった期間(=全額免除期間)は計算に入りません。
<死亡一時金の支給要件>
・死亡日の前日の保険料納付要件
・死亡日の前月まででみる(前々月ではない)
| 保険料納付済期間の月数 | 1 |
| 保険料4分の1免除期間の月数 | 4分の3 |
| 保険料半額免除期間の月数 | 2分の1 |
| 保険料4分の3免除期間の月数 | 4分の1 |
・合算して36月以上あること
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2問3D>
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月、保険料全額免除期間の月数が6か月、保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】 ×
死亡一時金の保険料納付要件は、36月。
問題文の場合、18か月+24か月×2分の1=30月となります。(全額免除期間は計算に入れません)
要件を満たさないので、死亡一時金は支給されません。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(国民年金法)
R3-022
R2.9.14 第52回試験・択一国年の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 国年 択一式
厚生年金保険と同様に、テキストと過去問で対応できる問題で、これなら勉強の成果が出せると思いました。
ただ、テキストや過去問の記載そのままではありませんので、丸暗記ではちょっと厳しい。
テキストのアンダーライン部分、過去問で「誤り」とされた部分の言わんとする意味を知っておく必要があります。
背景や理由を知っておくと勉強が格段に楽になります。
 遺族基礎年金は「子」のための年金
遺族基礎年金は「子」のための年金
問2 E
「遺族基礎年金」を受給できる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者又は子
↓
「配偶者」については、「子と生計を同じくすること」が要件
↓
言い方を変えると、遺族基礎年金を受給できる「配偶者」には必ず子がいる
↓
ということは、配偶者の受給する遺族基礎年金には、子の数に応じた加算額が必ず加算されている
ですので、問2E「被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。」は「〇」です。
遺族基礎年金は「子」のための年金だということを意識してください。
 付加保険料は、老齢基礎年金の上乗せを目的に納付する保険料
付加保険料は、老齢基礎年金の上乗せを目的に納付する保険料
問3 E
「付加保険料」は老齢基礎年金の上乗せを目的として、国民年金保険料に付加して支払うもの
↓
対象は第1号被保険者のみ
(第2号、第3号被保険者はそもそも国民年金保険料を負担していないので不可)
↓
では、任意加入被保険者は、付加保険料を支払うことができるか??
↓
(一般の)任意加入被保険者は、「老齢基礎年金」を増やす目的でも加入できるので、付加保険料も納付できる
↓
しかし、特例の任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)は、老齢基礎年金を増やす目的ではなく、「受給資格」を得るための加入なので、付加保険料は納付できない
ですので、問3E「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。」は「〇」です。
(特例ではない一般の任意加入被保険者なので、付加保険料の納付OK)
全体的に 何にでも「理由」がある。「理由」を意識すると丸暗記はいらない。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(国民年金法)
R3-012
R2.9.4 第52回試験・選択(国年)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 国年 選択式
1 年金額の改定からの出題
年金額の改定のルールで、よく注意して見ていた条文だったと思います。
2 遺族基礎年金についての出題
遺族基礎年金には、「短期要件」と「長期要件」がありますが、保険料納付要件が問われる短期要件からの出題でした。
3 基礎年金拠出金についての出題
「実施機関たる共済組合等」。いつも思いますが、覚えにくい用語ですね。。。
ただ、選択肢の中からは選びやすかったと思います。
ポイント! 基本を大切に
社労士受験のあれこれ
令和2年度の国民年金の数字
R2-265
R2.8.22 令和2年度の国民年金の数字check
 本試験の前日・当日にチェックしてほしいこと
本試験の前日・当日にチェックしてほしいこと
「数字」
覚えていたら解けるけど、覚えてなければ手も足も出ません。
当日、ぎりぎりまで数字を頭に叩き込んでください。
では、どうぞ!
令和2年度 老齢基礎年金の満額
780,900円 × 改定率< A > ≒ < B >円
<老齢基礎年金の額 40年間すべて保険料納付済期間の場合>
老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)とする。
令和2年度 国民年金保険料
17,000円 × 保険料改定率< E > ≒ < F >円

【解答】
A 1.001
B 781,700
C 50円
D 100円
780,900円×1.001=781,680.9円 → 781,700円(100円未満で四捨五入)
E 0.973
F 16,540円
17,000円(法定額)×0.973(保険料改定率)=16,541円 → 16,540円
(10円未満で四捨五入)
社労士受験のあれこれ
目的条文check 2 社保編
2 社保編
R2-261
R2.8.18 健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック
目的条文は要チェック!
本日は、「健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「健康保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(基本的理念)
第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< C >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< D >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< E >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

【解答】
A 業務災害
B 福祉の向上
C 高齢化
D 後期高齢者医療制度
E 常に
問2 「国民年金法」
(国民年金制度の目的)
第1条 国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(管掌)
第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、 < C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた< D >(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< E >が行うこととすることができる。

【解答】
A 日本国憲法第25条第2項
B 健全な国民生活
C 全国市町村職員共済組合連合会
D 日本私立学校振興・共済事業団
E 市町村長(特別区の区長を含む。)
問3 「厚生年金保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の< A >の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(管掌)
第2条 厚生年金保険は、< C >が、管掌する。

【解答】
A 生活
B 福祉の向上
C 政府
社労士受験のあれこれ
横断編(不服申立て)
R2-259
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「審査請求を棄却したものとみなすことができる」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
A 3か月
問2 「雇用保険法」
① 資格取得・喪失の確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して < B >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
B 3か月
問3 「健康保険法」
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
審査請求をした日から< C >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
C 2月
D 社会保険審査会
問4 「国民年金法」
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は< E >その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
審査請求をした日から< F >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
E 保険料
F 2月
問5 「厚生年金保険法」
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
② ①の審査請求をした日から< G >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< H >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
G 2月
H 社会保険審査会
| 棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
では、こちらをどうぞ!
①<国民年金 H30年出題>
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
②<厚生年金保険法 H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】
①<国民年金 H30年出題> 〇
「2か月」がポイントです!
②<厚生年金保険法 H29年出題> ×
・第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行います。
・脱退一時金については、「社会保険審査会」で〇です。
(国民年金も「脱退一時金」は、「社会保険審査会」に対して審査請求ができます。
社労士受験のあれこれ
横断編(公課の禁止)
R2-258
R2.8.15 横断編/課税されるもの、されないもの
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「課税されるもの、されないもの」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
<H24年出題>
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

【解答】 〇
労災保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」と規定されています。
※ 労災保険の保険給付には、「現金給付」と「現金給付」があるので「金品」
問2 「雇用保険法」
<H28年出題>
租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

【解答】 ×
雇用保険法では「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とされています。
常用就職支度手当は失業等給付の中に入っていますので、課税できません。
※雇用保険法には現物給付がないので「金銭」となっています。
なお、雇用保険二事業の助成金等は失業等給付ではありませんので、公課を課することができます。
問3 「健康保険法」
<H18年出題>
出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

【解答】 〇
健康保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされています。
保険給付(もちろん出産手当金出産育児一時金も含まれます。)は、課税されません。
問4 「国民年金法」
<H25年出題>
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

【解答】 〇
国民年金法のルールは、以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、公課を課することができる。
問5 「厚生年金保険法」
障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。

【解答】 〇
厚生年金保険法のルールは以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、公課を課することができる。
※ 「老齢厚生年金」は課税されますが、障害厚生年金は課税されません。
社労士受験のあれこれ
横断編(療養に関する指示に従わないとき)
R2-257
R2.8.14 横断編/療養に関する指示に従わないときの制限
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「療養に関する指示に従わないときの制限」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が故意の犯罪行為若しくは< A >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの< B >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の< C >。

【解答】
A 重大な過失
B 原因
C 全部又は一部を行わないことができる
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< D >。

【解答】
D 一部を行わないことができる
 「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその< F >となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< G >。
自己の故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその< F >となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

【解答】
E 重大な過失
F 原因
G 全部又は一部を行わないことができる
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは< H >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの< I >となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の< J >。
障害厚生年金の受給権者が、< K >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
H 重大な過失
I 原因
J 全部又は一部を行わないことができる
K 故意
こちらもどうぞ!
 問1労災保険法
問1労災保険法
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
 問2 健康保険法
問2 健康保険法
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
 問3 国民年金法(R元年出題)
問3 国民年金法(R元年出題)
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題)
問4 厚生年金保険法(R元年出題)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
 問1労災保険法 ×
問1労災保険法 ×
キーワードは、「故意に」「直接の原因」。
全部又は一部を行わないことができるではなく、「保険給付を行わない」です。
 問2 健康保険法 ×
問2 健康保険法 ×
キーワードは、「闘争、泥酔又は著しい不行跡」。
行わないではなく、「全部又は一部を行わないことができる」です。
 問3 国民年金法(R元年出題) 〇
問3 国民年金法(R元年出題) 〇
キーワードは、「故意に」。
故意に死亡させた者には支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
故意に障害 → 障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
重大な過失 → 保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士受験のあれこれ
横断編(支給制限~全部制限)
R2-256
R2.8.13 横断編/支給制限「行わない」のはどんなとき?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「支給制限「行わない」のはどんなとき?」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】
A 故意に
B 直接の原因
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< C >により、又は< D >給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

【解答】
C 自己の故意の犯罪行為
D 故意に
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
< E >障害又はその< F >となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < E >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によっ遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を< E >死亡させた者についても、同様とする。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< E >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
E 故意に
F 直接の原因
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< G >、障害又はその< H >となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< G >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< G >死亡させた者についても、同様とする。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< G >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
G 故意に
H 直接の原因
社労士受験のあれこれ
横断編(受給権の保護)
R2-255
R2.8.12 横断編/受給権の保護
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「受給権の保護」です。
では、どうぞ!
「労災保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外あり)
年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・国年、厚年も同様)
「雇用保険法」
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外なし)
「健康保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外なし)
「国民年金法」
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、厚年も同様)
・ 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢基礎年金、付加年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
「厚生年金保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、国年も同様)
・ 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢厚生年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
 では、問題をどうぞ!
では、問題をどうぞ!
 労災保険法<H24年出題>
労災保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
 雇用保険法<H23年出題>
雇用保険法<H23年出題>
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
 健康保険法<H24年出題>
健康保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。
 国民年金法<H28年出題>
国民年金法<H28年出題>
給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H26年出題>
厚生年金保険法<H26年出題>
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、< A >に行わせるものとされている。

【解答】
 労災保険法<H24年出題> 〇
労災保険法<H24年出題> 〇
 雇用保険法<H23年出題> 〇
雇用保険法<H23年出題> 〇
 健康保険法<H24年出題> ×
健康保険法<H24年出題> ×
保険給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押さえ、すべてできません。
 国民年金法<H28年出題> 〇
国民年金法<H28年出題> 〇
脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
※厚生年金保険でも、脱退一時金は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
 厚生年金保険法<H26年出題> ×
厚生年金保険法<H26年出題> ×
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押えの対象にはなりません。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
A 独立行政法人福祉医療機構
社労士受験のあれこれ
横断編(60・65・70・75歳)その1
R2-253
R2.8.10 横断編/年齢再確認!60・65・70・75歳その1
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「年齢再確認!60・65・70・75歳 その1」です。
では、どうぞ!
 国民年金法
国民年金法
空欄を埋めてください。
<任意加入被保険者>
次の1から3のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
2 日本国内に住所を有する< A >の者
3 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >のもの
<特例による任意加入被保険者>
昭和< C >年4月1日以前に生まれた者であって、次の1,2のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
ただし、その者が国民年金法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
1 日本国内に住所を有する< D >の者
2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< D >のもの

【解答】

A 60歳以上65歳未満
B 20歳以上65歳
C 40
D 65歳以上70歳未満
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 昭和40年4月1日以前に生まれた者
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
空欄を埋めてください。
<任意単独被保険者>
適用事業所以外の事業所に使用される< E >の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< F >を得なければならない。
<高齢任意加入被保険者>
適用事業所に使用される< G >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に< H >て、被保険者となることができる。
適用事業所以外の事業所に使用される< I >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、< J >を受けて、被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< K >を得なければならない。

【解答】
E 70歳未満
F 事業主の同意
G 70歳以上
H 申し出
I 70歳以上
J 厚生労働大臣の認可
K 事業主の同意
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 国民年金の「特例による任意加入被保険者」と違い、生年月日の要件がない
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと
・ 「適用事業所」と「適用事業所以外」で要件が違うので、注意。
こちらもどうぞ!
<国民年金 H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】 〇
原則 → 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者
ただし、厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合は、第2号被保険者にはならない。
問題文の場合、「在職老齢年金を受給する」「65歳以上70歳未満の被保険者」ということで、「老齢年金の受給権がある+65歳以上」ですので、厚生年金保険の被保険者なのですが、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
一方、第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが条件です。
問題文の場合は、第2号被保険者の配偶者に当たりませんので、第3号被保険者にはなりません。
なお、厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」は、「国民年金の第2号被保険者」です。なぜなら、「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない」からです。
社労士受験のあれこれ
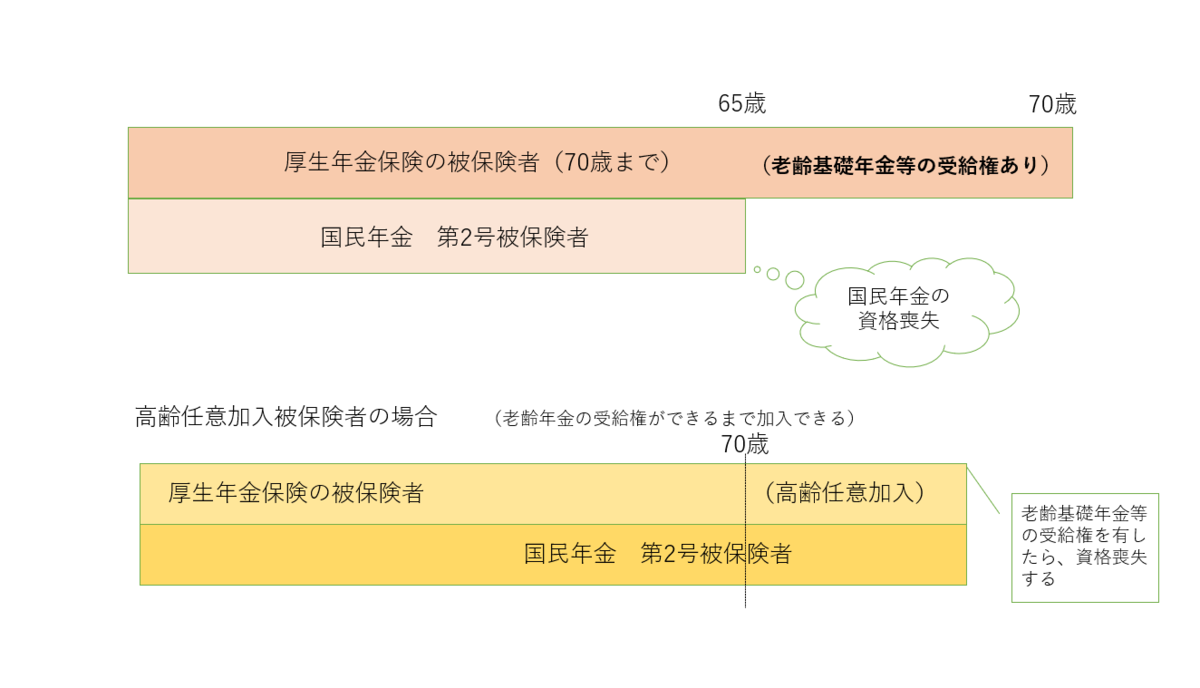
横断編(未支給の保険給付・給付)
R2-249
R2.8.6 横断編/未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?」です。
では、どうぞ!
問 題
 雇用保険<H29年出題>
雇用保険<H29年出題>
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。

【解答】
 〇
〇
ポイント!
★未支給の失業等給付を受けることができる範囲と順序を覚えましょう。
・死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」(順序もこのとおり)
★「失業」の認定を受けなければならない
受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当の支給を請求する者 → 当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
★請求期間がある
未支給給付請求者は、死亡した受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、請求しなければならない。
次は労災、どうぞ!
 労災保険<H22年出題>
労災保険<H22年出題>
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

【解答】
 C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
ポイント!
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順序を覚えましょう。
労災保険からもう一問!
 労災保険法<H30年出題>
労災保険法<H30年出題>
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
未支給の遺族(補償)年金の支給を請求できるのは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」です。
では、国民年金法です!
 国民年金法<R元年出題>
国民年金法<R元年出題>
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。

【解答】 〇
ポイント!
国民年金の未支給年金を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
最後は厚生年金保険です!
 厚生年金保険<H30年出題>
厚生年金保険<H30年出題>
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
厚生年金保険の未支給の保険給付を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
→ 国民年金と同じです。
なお、国民年金の未支給の対象は「年金給付」、厚生年金保険は「保険給付」です。
社労士受験のあれこれ
横断編(障害等級・労災、国年、厚年)
R2-248
R2.8.5 横断編/それぞれの障害等級~労災、国年、厚年
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「障害等級・労災、国年、厚年」です。
では、どうぞ!
問 題
 傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
 ×
×
「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。
ポイント!
ちなみに、傷病補償年金の支給要件として、「当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」があります。
厚生労働省令で定める傷病等級は「第1級~第3級」です。
第1級 → 常時介護を要する状態
第2級 → 随時介護を要する状態
第3級 → 常態として労働不能
★ 傷病等級は、「治っていない傷病」です。
次どうぞ!
 障害(補償)給付
障害(補償)給付
空欄に埋めてください。
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は < A >とする。

【解答】
 A 障害補償一時金
A 障害補償一時金
ポイント!
障害等級第1級~第7級 → 障害補償年金
障害等級第8級~第14級 → 障害補償一時金
★ 障害等級は、「負傷し又は疾病にかかり治った」ときです。
 傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
第1級 → 給付基礎日額の313日分
第2級 → 給付基礎日額の277日分
第3級 → 給付基礎日額の245日分
 障害基礎年金(国民年金法)
障害基礎年金(国民年金法)
空欄を埋めてください。
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の①、②のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して< B >を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、< C >であること。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから< D >とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
B 1年6月
C 60歳以上65歳未満
D 1級及び2級
ポイント!
障害基礎年金の障害等級は、重いほうから1級、2級
1級の年金額は、2級の年金額×100分の125
 障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金・障害手当金
(障害手当金の受給権者)
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して< E >を経過する日までの間におけるその< F >日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

【解答】
E 5年
F 傷病の治った(障害手当金は「治っている」ことが要件です。)
ポイント!
厚生年金には、「障害厚生年金」と「障害手当金」があります。
障害厚生年金 → 障害等級1級~3級
障害手当金 → 3級よりも軽い状態
社労士受験のあれこれ
横断編(遺族の範囲その2「国年」)
R2-246
R2.8.3 横断編/「国年」遺族の範囲を整理する
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「遺族の範囲その2「国年」」です。
「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。
整理しておきましょう。
今日は、国年編です。
では、どうぞ!
問 題
 遺族基礎年金<R元年出題>
遺族基礎年金<R元年出題>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】
 〇
〇
遺族には国内居住要件はありません。
遺族基礎年金を受けることができる遺族のポイント!
・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者又は子
・配偶者の要件 → 子があること(子と生計を同じくすること)
・子の要件 → ①18歳の年度末までの間にある
②20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある
婚姻していない
次は寡婦年金です!
 寡婦年金<H20年出題>
寡婦年金<H20年出題>
寡婦年金は、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。

【解答】
 ×
×
「65歳未満」の妻であることが条件です。
夫の死亡当時、妻が60歳未満でも受給権は発生しますが、支給は60歳以降(60歳にに達した日の属する月の翌月から)になります。
寡婦年金を受けることができる妻のポイント!
・寡婦年金を受けることができるのは妻のみ。(夫はダメ)
・夫の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた妻
・夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻
 穴埋め式で寡婦年金をチェックしましょう。
穴埋め式で寡婦年金をチェックしましょう。
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< B >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、
夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< C >年以上継続した< D >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は < E >の支給を受けていたときは、この限りでない。

【解答】
A 前月
B 10
C 10
D 65
E 老齢基礎年金
最後は死亡一時金!
 死亡一時金<H28年選択>
死亡一時金<H28年選択>
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

【解答】 ×
死亡一時金の対象になる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これらの者以外の三親等内の親族は遺族に入りません。
死亡一時金を受けることができる遺族のポイント!
・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-238
R2.7.26 選択式の練習/おぼえておきたい合算対象期間
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「合算対象期間」です。
「合算対象期間」(カラ期間)
保険料納付済期間と保険料免除期間では10年に足りない場合に、合算対象期間を入れて10年以上になれば、老齢基礎年金の受給資格ができます。ただし、年金額には反映されません。
では、どうぞ!
問 題
① 第2号被保険者としての被保険者期間のうち< A >の期間は、合算対象期間である。
② 国会議員であった期間(60歳前の期間に限る。)のうち、昭和36年4月1日から < B >までの期間は合算対象期間となる。
③ 厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間のうち、< C >(昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る。)は、合算対象期間となる。
【選択肢】
① 20歳以上60歳未満 ② 20歳未満及び60歳以上
③ 20歳未満及び65歳以上 ④ 昭和55年3月31日
⑤ 昭和61年3月31日 ⑥ 昭和56年12月31日
⑦ 昭和36年4月1日前 ⑧ 昭和36年4月1日以後
⑨ 昭和61年4月1日以後

【解答】
A ② 20歳未満及び60歳以上
 第2号被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」(老齢基礎年金の額に反映する期間)は20歳以上60歳未満の期間です。(第1号被保険者の年齢に合わせている)
第2号被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」(老齢基礎年金の額に反映する期間)は20歳以上60歳未満の期間です。(第1号被保険者の年齢に合わせている)
ですので、20歳未満と60歳以上の期間は、年金額に反映しない合算対象期間となります。
B ④ 昭和55年3月31日
 国会議員は、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用を除外されており、国民年金に加入することができなかったので合算対象期間とされています。(ただし、60歳未満に限りますので注意してください。)
国会議員は、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用を除外されており、国民年金に加入することができなかったので合算対象期間とされています。(ただし、60歳未満に限りますので注意してください。)
昭和55年4月1日からは、国会議員は「任意加入」できることになりました。任意加入しなかった場合は合算対象期間です。
なお、新法になってから(昭和61年4月1日から)は、強制加入です。
C ⑧ 昭和36年4月1日以後
こちらもどうぞ!
①<H25年出題>
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とされる。
②<H25年出題>
60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は合算対象期間に算入される。
③<H25年出題>
20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。
(女性は昭和29年4月2日生まれ、「現在」は平成25年4月12日とする)

【解答】
①<H25年出題> ×
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間のうち、保険料納付済期間になるのは20歳以上60歳未満の期間です。20歳前、60歳以後の期間は合算対象期間となります。
②<H25年出題> ×
昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの間で国会議員だった期間のうち、合算対象期間になるのは60歳未満に限ります。60歳以上65歳未満の期間は合算対象期間には入りません。
③<H25年出題> ×
厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間が合算対象期間となるには、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限られます。
問題文は、保険料納付済期間又は保険料免除期間がないので、合算対象期間には入りません。
社労士受験のあれこれ
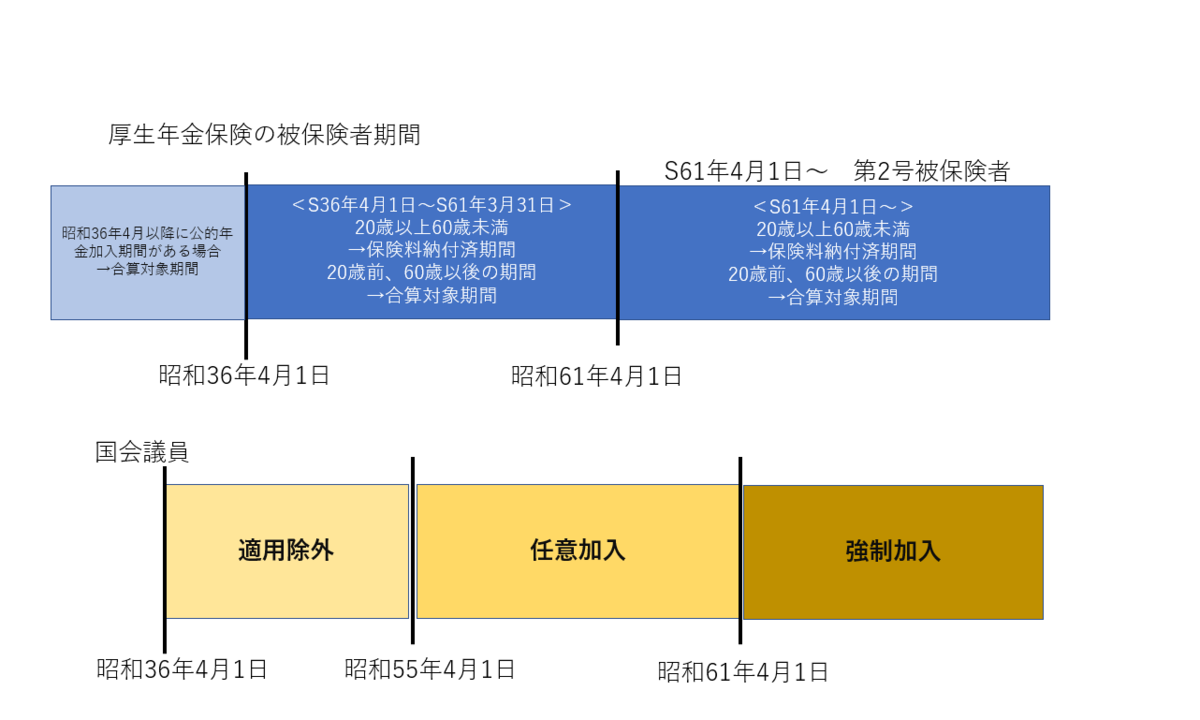
選択式対策(国民年金法)
R2-228
R2.7.16 選択式の練習/繰下げ支給の老齢基礎年金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。
では、どうぞ!
問 題
老齢基礎年金の受給権を有する者であって< A >に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が< B >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< C >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< D >を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は< B >歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【選択肢】
① 65歳に達する前 ② 66歳に達する前 ③ 60歳に達する前
④ 65 ⑤ 60 ⑥ 70
⑤ 付加年金 ⑥ 遺族基礎年金 ⑥ 障害基礎年金
⑦ 障害 ⑧ 遺族 ⑨ 老齢

【解答】
A ② 66歳に達する前
B ④ 65
C ⑤ 付加年金
D ⑨ 老齢
 繰下げの要件
繰下げの要件
・ 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない
・ 65歳に達したとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないこと
※付加年金の受給権者は繰下げの申し出OK
厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者でないこと
※特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は繰下げOK
ポイント!
繰下げ支給は、老齢基礎年金の受給権発生から1年以上待つことが条件です。
こちらもどうぞ!
 R1年出題
R1年出題
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
 H24年出題
H24年出題
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

【解答】
 R1年出題 〇
R1年出題 〇
65歳に達したとき、又は「65歳に達した日から66歳に達した日まで」の間に、他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないことが、繰下げの要件です。
問題文は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者になっていますので、繰下げの申し出はできません。
 H24年出題 ×
H24年出題 ×
寡婦年金は65歳に達したときに失権するので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けられます。
ちなみに・・・66歳に達した日後に障害基礎年金の受給権を取得したら繰下げは?
例えば、67歳で障害基礎年金の受給権取得後に、繰下げの申し出をした場合、繰下げの増額率はどうなる?
↓
実際に繰下げの申し出をした時点ではなく、障害基礎年金の受給権が発生したときに繰下げの申し出をしたものとみなされます。
・ 増額率は、「障害基礎年金の受給権が発生」した時点で計算されます
・ 繰下げの老齢基礎年金は、「繰下げの申出をした日の属する月の翌月から」ではなく、障害基礎年金を受ける権利が発生した月の翌月から支給されます。
繰下げでよく出る問題
<H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】 ×
老齢基礎年金の繰下げを申し出た場合、振替加算も繰下げされますが、振替加算は増額されません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-218
R2.7.6 選択式の練習/年金・旧法と新法
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「旧法と新法」です。
年金制度は「昭和61年4月1日」がポイントです。
昭和61年4月1日前の制度を旧法、昭和61年4月1日以後の制度を新法といいます。
昭和61年4月1日に、「基礎年金」が導入され、すべての職業の人が国民年金に加入することになり、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の区分ができました。
また、それまで任意加入だった会社員に扶養される妻(夫)が第3号被保険者として強制加入となりました。
1階に「基礎年金」、2階にサラリーマンや公務員が加入する厚生年金が乗っかる2階建ての年金制度になったのもこのときでした。
今日のテーマは旧法から新法への切り替えがテーマです。
ではどうぞ!
問 題
<H15年選択式>
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
【選択肢】
① 大正15年4月1日 ② 大正15年4月2日 ③ 昭和40年4月2日
④ 初診日 ⑤ 20歳に達した日 ⑥ 障害認定日

【解答】
A ② 大正15年4月2日
新法の「老齢基礎年金」の対象は、原則として大正15年4月2日以降生まれの者
B ⑥ 障害認定日
障害認定日(受給権が発生する日)が昭和61年4月1日以降なら新法の障害基礎年金の対象になります。
引き続きこちらも!
①<H16年出題>
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。
②<H16年出題>
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

【解答】
①<H16年出題> ×
旧法の国民年金の母子年金及び準母子年金は、今の遺族基礎年金にあたる年金です。新法施行日の前日(昭和61年3月31日)に、旧国民年金法の母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には、昭和61年4月1日以後も、そのまま母子年金、準母子年金として支給されます。遺族基礎年金への裁定替えはしません。
②<H16年出題> 〇
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、母子年金、準母子年金の保険料納付要件などを満たさなかった場合の年金です。(「福祉」年金という名称に着目してください。)
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、遺族基礎年金に裁定替えされ、遺族基礎年金として支給されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-208
R2.6.26 選択式の練習/繰上げ支給の老齢基礎年金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「繰上げ支給の老齢基礎年金」です。
★ 法律は、「本則」と「附則」で構成されています。老齢基礎年金の繰上げは「附則」に規定されていて、「当分の間」の措置とされているのがポイントです。
一方、「老齢基礎年金の繰下げ」は、「本則」で規定されています。
ではどうぞ!
問題
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上< A >歳未満であるもの(< B >でないものに限る。)は、当分の間、< A >歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その請求があった日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期を合算して10年以上あることが要件となる。
請求があったときは、その< C >から、その者に老齢基礎年金を支給する。
< D >の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
【選択肢】
① 70 ② 65 ③ 75
④ 任意加入被保険者 ⑤ 第1号被保険者
⑥ 確定拠出年金の加入者
④ 請求があった日の翌日 ⑤ 請求があった日
⑥ 厚生労働大臣の確認があった日
⑦ 寡婦年金 ⑧ 障害基礎年金 ⑨ 遺族厚生年金

【解答】
A ② 65
繰上げ請求ができるのは、60歳以上65歳未満
B ④ 任意加入被保険者
任意加入被保険者は繰上げの請求はできない。
C ⑤ 請求があった日
老齢基礎年金は、通常は「65歳に達した日」に受給権が発生しますが、繰上げ請求を行った場合は、「請求があった日」に受給権が発生します。
なお、年金の支給は、「支給すべき事由が発生した日の属する月の翌月から」となりますので、繰上げ支給の老齢基礎年金は、請求のあった日の翌月から支給されます。
D ⑦ 寡婦年金
繰上げ支給の老齢基礎年金を請求した場合、「寡婦年金は支給停止」、「寡婦年金とどちらか選択」はどちらも間違いです。寡婦年金の受給権は消滅しますので注意しましょう。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。

【解答】 ×
65歳まで
繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は、どちらかを選択となります。
65歳以降
繰上げて減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-198
R2.6.16 選択式の練習/申請全額免除の要件
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「申請全額免除の要件」です。
ではどうぞ!
問題
<保険料の全額申請免除の要件>
被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
<要件>
1. 保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から< A >月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額(扶養親族等の数に1を加えた数を< B >円に乗じて得た額に< C >円を加算した額)以下であるとき。
2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。
3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額(< D >円)以下であるとき。
4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが、要件に該当しないときは、免除されない。
【選択肢】
① 22万 ② 25万 ③ 32万 ④ 35万 ⑤ 42万 ⑥ 50万 ⑦ 3 ⑧ 6 ⑨ 12
⑩ 65万 ⑪ 103万 ⑫ 125万

【解答】
A ⑧ 6
B ④ 35万
C ① 22万
全額免除の所得要件 → (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
所得要件は前年の所得で。(1月から6月までの間は、前々年の所得)
D ⑫ 125万
こちらもどうぞ!
①H24年出題
法第9条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
②H26年出題
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。

【解答】
①H24年出題 ×
本人、世帯主、配偶者が免除の要件に該当することが必要です。
②H26年出題 〇
全額免除の所得要件をあてはめてみると、
(4人+1)×35万円+22万円=197万円
夫の所得は197万円、妻の所得は0円なので全額免除の対象になります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-188
R2.6.6 選択式の練習/障害基礎年金の額の改定請求
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害基礎年金の額の改定請求」です。
ではどうぞ!
問題
(障害の程度が変わった場合の年金額の改定)
1 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が< A >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 2の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が< A >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して < B >を経過した日後でなければ行うことができない。
(改定の請求)
障害基礎年金の額の改定の請求は、一定事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
改定の請求の請求書には、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにする書類、当該請求書を提出する日前< C >以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書等を添えなければならない。
加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前< D >以内に作成された「加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本」、「加算額対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類」を添えなければならない。
【選択肢】
① 変化 ② 増進 ③ 軽減
④ 1年 ⑤ 1年6か月 ⑥ 3年 ⑦ 1月 ⑧ 2月
⑨ 3月 ⑩ 6月

【解答】
A ② 増進
B ④ 1年
C ⑨ 3月
D ⑦ 1月
★ 障害給付額改定請求書には、提出する日前1月以内の障害の状態を記入した診断書を添えることになっていましたが、令和元年8月より、提出する日前「3月」以内の障害の状態を記入した診断書を添えることに改正されました。
加算額対象者があるときの身分関係を明らかにすることができる証明書等は、提出する日前1月以内に作成されたものとなります。(変更なし)
こちらの問題もどうぞ!
<H26年出題>
障害基礎年金の額の改定請求は、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。

【解答】 〇
障害基礎年金の額の改定請求ができるのは、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後です。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年たつ前でも改定請求ができます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-178
R2.5.27 選択式の練習/令和2年度の年金額
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「令和2年度の年金額」です。
ではどうぞ!
問題
老齢基礎年金の額は、780,900円に< A >を乗じて得た額(その額に < B >ものとする。)とする。
ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
1. 保険料納付済期間の月数
2. 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
3.保険料4分の1免除期間の月数から2.に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
4.保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
5.保険料半額免除期間の月数から4.に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
6.保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
7.保険料4分の3免除期間の月数から6.に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
8.保険料全額免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の < C >に相当する月数
【選択肢】
① 物価変動率 ② 名目手取り賃金変動率 ③ 改定率
④ 5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる
⑤ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
⑥ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる
⑦ 2分の1 ⑧ 3分の1 ⑨ 4分の1

【解答】
A ③ 改定率
B ⑤ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
C ⑦ 2分の1
ポイント!
老齢基礎年金を計算する際、「全額免除期間」の月数は2分の1で計算します。
ただし、全額免除期間のうち、「学生納付特例の期間」と「50歳未満の納付猶予期間」は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入しますが、老齢基礎年金の額の計算には算入しませんので、注意してください。
ちなみに、令和2年度の年金額は??
基礎年金は、「780,900円×改定率」で計算します。
令和2年度の年金額は、780,900円×< D > = < E >円です。
【選択肢】
① 1.001 ② 0.999 ③ 1.003
④ 781,700 ⑤ 780,100 ⑥ 783,200

【解答】
C ① 1.001 令和2年度の改定率は「1.001」です。
D ④ 781,700
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-168
R2.5.17 選択式の練習/(改正)国年・強制加入被保険者
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「強制加入被保険者」です。
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの区分があります。
令和2年4月1日より、第1号被保険者と第3号被保険者の要件が改正されました。
ではどうぞ!
問 題
■第1号被保険者■
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満
 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない
第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない
 第1号被保険者から除外される者
第1号被保険者から除外される者
・ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
・ この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
■第2号被保険者■
 厚生年金保険の被保険者
厚生年金保険の被保険者
■第3号被保険者■
 第2号被保険者の配偶者
第2号被保険者の配偶者
 主として第2号被保険者の収入により生計を維持する(被扶養配偶者)
主として第2号被保険者の収入により生計を維持する(被扶養配偶者)
 20歳以上60歳未満
20歳以上60歳未満
 < A >を有する者
< A >を有する者
又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る
 第3号被保険者から除外される者
第3号被保険者から除外される者
・ 第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
【選択肢】
① 日本国内に所得 ② 日本国内に住所 ③ 日本国内で職業

【解答】
A ② 日本国内に住所
ポイント
令和2年4月1日より、第3号被保険者については「国内居住要件」が付くことになりました。
<例外> 海外に居住していても渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、特例で第3号被保険者となります。
 「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、第1号被保険者、第3号被保険者から適用除外されます。
「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、第1号被保険者、第3号被保険者から適用除外されます。
適用除外として厚生労働省令で定める者は
↓
① 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの → 在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)
② 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの → 在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」
こちらの問題もどうぞ!
<R元年出題>
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

【解答】 ×
| 国籍要件 | 国内居住要件 | 年齢要件 (20歳以上60歳未満) | |
| 第1号被保険者 | なし | あり | あり |
| 第2号被保険者 | なし | なし(原則65歳未満) | |
| 第3号被保険者 | あり(例外あり) | あり |
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-158
R2.5.7 選択式の練習/令和2年度の国民年金保険料
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「令和2年度の国民年金の保険料」です。
ではどうぞ!
問 題
令和2年度の保険料の額
→ 17,000円 × < A >
【選択肢】
①名目賃金変動率 ②名目手取り賃金変動率 ③物価変動率 ④改定率 ⑤保険料改定率

【解答】
A ⑤保険料改定率
こちらの問題もどうぞ
保険料改定率の計算式は、
前年度の保険料改定率 × < B >です。
【選択肢】
①名目賃金変動率 ②名目手取り賃金変動率 ③物価変動率 ④改定率

【解答】 ①名目賃金変動率
名目賃金変動率 → 前々年の物価変動率 ×4年前の年度の実質賃金変動率
もう一問どうぞ!
令和2年度の保険料の計算式
17,000円 × < C > ≒ < D >円
【選択肢】
①0.967 ②0.965 ③0.973 ④16,340 ⑤16,410 ⑥16,540

【解答】
C ③0.973 D ⑥16,540
※ 5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-148
R2.4.27 選択式の練習/老齢基礎年金の計算
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、問題です。
※平成28年択一式を選択式にアレンジしています。
問 題
昭和30年4月8日生まれの男性の年金加入歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給できる年金額及び計算式の空欄を埋めてください。
※振替加算は考慮しなくていい
※年金額は令和2年度価額で計算
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月
■計算式
781,700円 × < A >/480月 + < B >
■年金額
< C >円
<選択肢>
①456月 ②180月 ③420月
④8500円 ⑤200円×36月 ⑥400円×36月
⑦691,188 ⑧691,200 ⑨691,088

【解答】
A ③420月 B ⑤200円×36月 C ⑦691,188
年金給付の額は、50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

【解答】 ○
200円×300月で計算します。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-138
R2.4.17 障害基礎年金の保険料納付要件
障害基礎年金の受給要件は次の3つです。
 初診日
初診日
①初診日に被保険者である。
②被保険者であった者で、日本国内に住所有、60歳以上65歳未満
 保険料納付要件
保険料納付要件
初診日の前日に初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上ある
 障害認定日
障害認定日
初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日)に障害等級に該当する程度の障害の状態にある
障害等級 → 1級又は2級
 (H28年出題)
(H28年出題)
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】 ×
障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」でみます。問題文の場合、22歳の誕生月に全額免除の申請をし、さかのぼって保険料全額免除期間となりましたが、初診日の前日の時点では、被保険者期間のすべてが滞納期間です。
ですので、保険料納付要件を満たしていないので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
こちらの問題もどうぞ!
<H22年出題>
初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。

【解答】 ×
平成22年7月分までの1年間ではなく、平成22年6月分までの1年間です。
★初診日が令和8年4月1日前にある場合の特例(初診日に65歳未満であること)
→ 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、保険料納付要件を満たす。
初診日の属する月の前々月までの1年間ですので、平成22年6月までの1年間となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-128
R2.4.4 寡婦年金の額の算出
国民年金法の「寡婦年金」は、ポイントがたくさんで、高頻度で出題されています。
ポイントを一つ一つおさえましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額とされている。

【解答】 ×
老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額の4分の3です。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H24年出題>
寡婦年金の額の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】○
寡婦年金の額には、死亡した夫の第1号被保険者としての被保険者期間だけが反映されます。
先ほどの問題でチェック してほしい箇所
してほしい箇所
↓
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額の4分の3に相当する額とされている。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-118
R2.3.21 子に支給する遺族基礎年金の額
 遺族基礎年金を受給できるのは、
遺族基礎年金を受給できるのは、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時生計を維持していた配偶者又は子です。
支給のパターンとしては、①子のある配偶者に支給する、②子に支給する、の2つがあります。
ポイントは、「子」の加算額の出し方です。①と②で異なりますので注意しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

【解答】 ×
受給権者が子3人のときの遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率」です。
それぞれの子がそれぞれ受給権者です。それぞれの子に支給されるのは、合計額を子の人数である3で割った額となります。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H22年出題>
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

【解答】 ×
受給権者が子2人の場合の遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率+224,700円×改定率」です。それぞれの子に支給されるのは、その額を2で割った額です。
 受給権者が「子のある配偶者」か「子」であるかで、年金の額の計算方法が変わります。
受給権者が「子のある配偶者」か「子」であるかで、年金の額の計算方法が変わります。
| 子のある配偶者 | 子 | |
| 子1人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率 | 780,900円×改定率 (加算無し) |
| 子2人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 224,700円×改定率 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率 |
| 子3人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 224,700円×改定率+ 74,900円×改定率 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 74,900円×改定率 |
ポイント
配偶者が遺族基礎年金を受けるには、子と生計を同じくすること(子のあること)が条件です。
・子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されない
・配偶者の遺族基礎年金には、子の数に応じた加算額が必ず加算される
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-108
R2.3.6 追納するときの加算
 追納とは
追納とは
免除された保険料を、後から納付できる制度のことです。
追納すると、保険料免除期間から保険料納付済期間に変わります。
 (H18年出題)
(H18年出題)
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。

【解答】 ○
追納する場合は、一定額の加算がついた保険料を納付することになります。
ただし、免除を受けた年度の翌々年度までに追納する場合は、加算額はつきません。(保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額で納付することができることが考慮されています)
例えば、免除を受けたのが平成29年度の場合は、令和元年度中に追納する場合は、加算がつかない本来の額で納付できます。
★ポイント★ と言っても免除月が3月の場合は注意!
平成30年3月の保険料の納付期日は平成30年4月。保険料の徴収権の時効が消滅するのは、そこから2年後の令和2年4月。
平成30年3月に免除を受けた場合、令和2年4月中に追納するときは加算はつきません。→ 問題文のカッコ書きの部分(免除の月が3月のときは、翌々年の4月までなら加算されない)です。
※平成30年3月は「平成29年度」、令和2年4月は「令和2年度」です。平成30年3月から見て令和2年4月は、翌々年度ではなく、翌々年4月ですので注意してくださいね。
 もう一問どうぞ
もう一問どうぞ
<H19年出題>
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

【解答】○
・免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後の年度から加算が行われる。
例えば、免除月が平成28年10月なら、翌々年度(平成29年度、30年度)中なら加算は行われませんが、令和元年度(平成28年4月1日から起算して3年を経過した日以後の年度)から加算が行われます。
※免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合は除かれていることにも注意。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-98
R2.2.16 保険料全額免除期間に含まれるもの
 国民年金法第5条では、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」などの用語の定義が規定されています。
国民年金法第5条では、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」などの用語の定義が規定されています。
また、「保険料免除期間」とは、「保険料全額免除期間」「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」を合算した期間とされています。
今日の問題は、第5条からです。
 H28年出題
H28年出題
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。

【解答】 ×
「学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間」も保険料全額免除期間に含まれます。
国民年金法第5条第3項では、「保険料全額免除期間」は次のように定義されています。
「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、全額申請免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※ ちなみに50歳未満の納付猶予期間も保険料全額免除期間に含まれます。(法附則)
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H21年出題>
国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

【解答】 ×
学生納付特例も含まれます。また、附則により、50歳未満の納付猶予も保険料全額免除期間に含まれます。
 では、こちらの問題もどうぞ
では、こちらの問題もどうぞ
<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】 ○
保険料全額免除を受けた期間でも、保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。(保険料全額免除期間からは追納した期間は除かれます。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-88
R2.1.28 第2号被保険者の20歳前、60歳以後の期間
★ 国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者は「20歳以上60歳未満」という年齢制限がありますが、第2号被保険者にはそのような年齢制限がありません。
国民年金の年金額の計算上、第2号被保険者の20歳未満、60歳以後の期間の扱いはどうだったでしょう?というのが今日のテーマです。
 H28年出題
H28年出題
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】 ○
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間が全て保険料納付済期間であれば満額支給される仕組みです。
ですので、第2号被保険者としての被保険者期間も、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映されるのは「20歳から60歳まで」となり、20歳前、60歳以後の期間は合算対象期間となります。
<老齢基礎年金の計算額のルール>
「第2号被保険者としての被保険者期間」は、
・ 保険料納付済期間 → 20歳から60歳まで
・ 合算対象期間 → 20歳前、60歳以後
 「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のルールも確認しましょう。
「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のルールも確認しましょう。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H24年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】 ×
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間の保険料の納付状況で年金額を計算しますが、障害基礎年金はそうではありません。
ですので、障害基礎年金については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も「保険料納付済期間」となります。
(遺族基礎年金も障害基礎年金と同様の考え方です。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国年法)
R2-78
R2.1.13 年金の支給期間(国年)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H27 国年法(問5)より
H27 国年法(問5)より
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

【解答】 ×
年金は、権利が消滅した日の属する月まで支給されます。
問題文の場合、遺族基礎年金は、婚姻した日の属する月の前月分までではなく、婚姻した日の属する月まで支給されます。
【穴埋め式で確認しましょう】
<年金の支給期間>
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する< A >から始め、権利が消滅した日の属する< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する< C >からその事由が消滅した日の属する< D >までの分の支給を停止する。
ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止< E >。

【解答】
A 月の翌月 B 月 C 月の翌月 D 月 E しない
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-68
R1.12.26 R1国年/遺族基礎年金の受給権消滅
和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「遺族基礎年金の受給権消滅」についてです。
 R1国年法(問2)より
R1国年法(問2)より
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の受給権は消滅しない。

【解答】 ×
死亡した被保険者の兄の養子(ということは、叔父の養子)となったときは、子の受給権は消滅します。
ポイント★
養子になったときは遺族基礎年金の受給権は消滅。
※ただし、養子でも、直系血族又は直系姻族の養子になった場合は受給権は消滅しません。「叔父」は直系ではなく傍系なので、叔父の養子になった場合は受給権は消滅します。
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H16年出題>
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】 ○
夫の父(ということは直系姻族)の養子になった場合、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-58
R1.12.5 R1国年/老齢基礎年金の繰上げと繰下げの違い
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げの違い」についてです。
 R1国年法(問5)より
R1国年法(問5)より
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

【解答】 ×
繰上げと繰下げが逆です。
・繰上げ → 国民年金法附則9条の2で当分の間の措置として規定されている
・繰下げ → 国民年金法第28条で規定されている
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H23年出題】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。

【解答】 ×
国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されているのは、繰上げ支給です。繰下げ支給の規定は附則ではなく本則です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-48
R1.11.12 R1国年/老齢基礎年金の繰上げ減額率
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「老齢基礎年金の繰上げ減額率」についてです。
 R1国年法(問4)より
R1国年法(問4)より
昭和31年4月20日生まれの者が、平成31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12%である。

【解答】 ○
 昭和31年4月20日生まれの人は、令和3(2021)年4月に65歳になります。
昭和31年4月20日生まれの人は、令和3(2021)年4月に65歳になります。
老齢基礎年金の繰上げ減額率は、「1,000分の5×繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数」です。
問題の場合ですと、繰上げ請求月の平成31(2019)年4月から、65歳に達する月の前月である令和3(2021)年3月まで、24か月です。
繰上げ減額率は1,000分の5×24=12%となります。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H29年出題>
64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。

【解答】 ×
繰上げ減額率=1,000分の5×12か月で6%となります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-37
R1.10.26 R1国年/老齢基礎年金繰下げのルール
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「老齢基礎年金繰下げのルール」についてです。
 R1国年法(問4)より
R1国年法(問4)より
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】 ○
 老齢基礎年金の繰下げの申出の条件を整理しておきましょう。
老齢基礎年金の繰下げの申出の条件を整理しておきましょう。
 又は
又は の場合は、繰下げの申出はできない。
の場合は、繰下げの申出はできない。
 65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき
65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき
 65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき
問題文では、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となった」とあるので、 に当てはまり、老齢基礎年金の繰下げの申出はできません。
に当てはまり、老齢基礎年金の繰下げの申出はできません。
 平成21年には選択式で出題されています。
平成21年には選択式で出題されています。
【H21年選択式】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が< A >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付 (< B >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(< C >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< A >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】
A 65歳 B 付加年金 C 老齢
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-27
R1.10.9 R1国年法/障害基礎年金・初診日の要件
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「障害基礎年金・初診日の要件」についてです。
 R1国年法(問2)より
R1国年法(問2)より
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。

【解答】 ×
障害基礎年金は、以下の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。
①初診日要件を満たしていること
初診日に
1.被保険者であること。
2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
②障害認定日要件を満たしていること
障害認定日に障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
③保険料納付要件を満たしていること
 問題文は、初診日に保険料の納付猶予の適用を受けているという前提ですが、納付猶予の適用を受けていても被保険者ですので初診日要件は満たしています。
問題文は、初診日に保険料の納付猶予の適用を受けているという前提ですが、納付猶予の適用を受けていても被保険者ですので初診日要件は満たしています。
さらに、障害認定日に1級又は2級に該当し、保険料納付要件を満たしているということなので、障害基礎年金の支給要件は満たしています。
「障害基礎年金が支給されることはない。」は誤りです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-17
R1.9.23 R1国年/被保険者期間のカウント
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「被保険者期間」についてです。
 R1国年(問3)より
R1国年(問3)より
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

【解答】 ×
平成11年4月1日生まれの者は、誕生日の前日の平成31年3月31日に20歳に達し、その日に第1号被保険者の資格を取得します。
被保険者期間は、「月単位」で、資格を取得した日の属する月から算入されますので、問題文の場合は、平成31年3月から被保険者期間に算入されます。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(国民年金法)
R2-10
R1.9.11 R1選択式(国民年金法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第9回目は、「国民年金法 選択式」です。
 AとBは「積立金の運用の目的」からの出題です。
AとBは「積立金の運用の目的」からの出題です。
★「積立金の運用の目的」は、H20年にも選択式で出題されています。
<参考 H20年選択>
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の < A >のために、< B >から、< C >に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(解答)
A 被保険者の利益 B 長期的な観点 C 安全かつ効率的
 Cは、「指定代理納付者による納付」についての出題です。
Cは、「指定代理納付者による納付」についての出題です。
★クレジットカードの納付に関する規定です。
「保険料の徴収上有利と認められるときに限り」という文言は、「口座振替による納付」でも出てきますので、覚えやすいと思います。
 DとEは「延滞金」からの出題です。
DとEは「延滞金」からの出題です。
どの科目でもよく出題される部分なので、解きやすい問題だったと思います。
といっても、科目ごとに少しずつルールが異なるので、横断的な勉強が効果的です。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】国民年金の沿革
R1.8.23 【選択式対策】国民年金法の始まりを確認
本日のcheckは国民年金法です。
(H19年択一式のアレンジ問題です)
国民年金は、昭和< A >年に制定された国民年金法に基づき、 同年< B >月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金体制が成立した。

【解答】
A 34 B 11
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社会保険分野】目的条文
R1.8.17 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックです。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
遺族基礎年金の額(国民年金)
R1.7.23 子に支給する遺族基礎年金
まずは過去問をどうぞ
<H28年出題>
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

【解答】 ×
受給権者が子3人のときの遺族基礎年金の額は、
780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率
です。
加算額は2人目が224,700円×改定率、3人目以降は74,900円×改定率です。
もう一問どうぞ
<H22年出題>
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

【解答】 ×
子に支給する遺族基礎年金は、子が2人のときは、780,900円×改定率+224,700円×改定率です。
それぞれの子に支給される額は、(780,900円×改定率+224,700円×改定率)÷2です。
社労士受験のあれこれ
保険料の追納(国民年金法)
R1.7.15 追納のルールよく出るところ
過去問をどうぞ
<H20年出題>
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。

【解答】 ○
この問題のポイントは、追納できないのは「老齢基礎年金」の受給権者である点です。
障害基礎年金の受給権者は追納できます。障害基礎年金は支給停止になったり失権する可能性があるからです。(給付が一生保障されているわけではない)
なお、遺族基礎年金の受給権者も同じ考え方で、追納可能です。
もう一問どうぞ
<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】○
追納が行われたら → 追納が行われた日に追納に係る月の保険料が納付されたとみなす。 → 保険料免除期間から保険料納付済期間に変わる。
社労士受験のあれこれ
国民年金保険料の免除
R1.7.6 学生納付特例のルールなど
過去問をどうぞ
<H28年出題>
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】 ○
「学生納付特例」については、「学生本人」の所得のみで要件を判断されます。
世帯主や配偶者の所得は問わないのがポイントです。学生の場合、一般的に親に扶養されていることが多いからです。
もう一問どうぞ
<H24年出題>
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。

【解答】×
申請免除は、本人のみならず、世帯主、配偶者も免除事由に該当することが要件です。
世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときは、免除の対象にはなりません。
※全額免除だけでなく、4分の3、半額、4分の1も同じです。
 ちなみに、50歳未満の「納付猶予」については、本人と配偶者が免除事由に該当することが要件です。
ちなみに、50歳未満の「納付猶予」については、本人と配偶者が免除事由に該当することが要件です。
社労士受験のあれこれ
H31年度の国民年金保険料
R1.7.2 H31年度の国民年金保険料は16,410円
空欄を埋めてください
平成31年度の国民年金保険料の月額
平成31年度の国民年金保険料の月額は、< A >円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,410円である。

【解答】 A 17,000
国民年金保険料の法定額は、平成31年度以降月額17,000円になりました。
※ 平成31年度の保険料改定率は0.965です。
平成31年度国民年金保険料額 → 17,000円 × 0.965 ≒ 16,410円
(5円未満切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げ)
社労士受験のあれこれ
国民年金基金の行う業務
R1.7.1 「国民年金基金」からの支給をチェック
過去問をどうぞ
<H15年出題>
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者の老齢、死亡に関して必要な給付を行うが、障害に関する給付は行わない。

【解答】 ○
国民年金基金は、老齢については「年金」、死亡については「一時金」の支給を行います。
国民年金基金には障害についての給付はありません。(付け加えると、脱退についての給付もありません。)
では、もう一問どうぞ
<H17年出題>
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。

【解答】 × 遺族基礎年金が誤り。
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に、その遺族が死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない、です。
さらにもう一問どうぞ
<H22年出題>
国民年金基金が支給する年金額は200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが、国民年金基金の支給する一時金の額については下限は定められていない。

【解答】 ×
国民年金基金が支給する年金額 → 200円×加入員の加入月数を超えるものでなければならない。(この部分は正しい)
国民年金基金が支給する一時金の額 → 8,500円を超えるものでなければならない。(一時金の額も下限が定められている。)
社労士受験のあれこれ
国民年金・事例問題
R1.6.22 遺族基礎年金/事実上の親子関係
★★まずは過去問をどうぞ
<H25年出題>
(前提条件) ある男性が学校を卒業後20歳で就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。
(問題) 男性が死亡した当時、生計を維持していた者が5年間同居していた事実婚関係の45歳の妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合、妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し、すべて受給することができるが、当該遺族には遺族基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】 ○
◆問題のポイント
・「配偶者」「夫」「妻」には事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係)が含まれる。
・要件を満たせば、設問の事実婚の妻は「死亡一時金」「遺族厚生年金」を受けることができる。
・遺族基礎年金、遺族厚生年金の遺族となる「子」については、事実上の親子関係は含まれない。養子縁組をしていることが条件。
・設問の「子」は死亡した者と養子縁組をしていないので死亡した者の「子」ではない。そのため、死亡した者と生計維持関係があったとしても遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権は発生しない。
・遺族基礎年金の場合、遺族となる「配偶者」は、死亡した者の子と生計を同じくしていることが条件。設問の妻は、「死亡した者の子」と生計を同じくしていないので、遺族基礎年金の受給権は発生しない。
・国民年金の「死亡一時金」と厚生年金保険の「遺族厚生年金」は併給できる。
社労士受験のあれこれ
老齢基礎年金の繰下げ
R1.6.7 老齢基礎年金の繰下げのルール
条文の空欄を埋めてください
老齢基礎年金の受給権を有する者であって< A >歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が< B >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付( < C >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(< D >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ)の受給権者であったとき、又は < B >歳に達した日から< A >歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】 A 66 B 65 C 付加年金 D 老齢
社労士受験のあれこれ
国民年金原簿
R1.5.20 【国年】国民年金原簿に記録されないもの
 今日のテーマは国民年金原簿
今日のテーマは国民年金原簿
「国民年金原簿」については第14条で以下のように規定されています。

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号、その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。
では、過去問をどうぞ
<H28年出題>
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが、当分の間、第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている。

【解答】○
厚生年金保険法に規定する第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者は国民年金原簿の記録の対象から除かれています。
社労士受験のあれこれ
【前納】国民年金と健康保険の違い
R1.5.16 国民年金と健康保険の前納、どこが違う??
 条文の空欄を埋めてください。
条文の空欄を埋めてください。
【健康保険法】 (任意継続被保険者の保険料の前納)
1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料については、前納に係る期間の< A >ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【国民年金法】 (保険料の前納)
1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の< B >際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
【健康保険法】 A 各月の初日が到来した
【国民年金法】 B 各月が経過した
社労士受験のあれこれ
被保険者の届出(国民年金法)
H31.4.23 いつまでに?どこに?届出(国年第1号被保険者)
さっそく、過去問をどうぞ
<H20年出題>
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】 ×
第2号被保険者から第1号被保険者への「種別変更」ですので、資格取得届ではなく「種別変更届」を提出します。期限は14日以内、届出先は市町村長でOKです。
もう一問どうぞ
<H15年出題>
第3号被保険者である被扶養配偶者が、就職により第2号被保険者になったときは、本人の届出の必要はない。

【解答】 ○
第2号被保険者は国民年金での手続きは不要です。厚生年金保険法の手続きがそのまま国民年金に反映されるからです。
社労士受験のあれこれ
障害基礎年金の加算(国民年金法)
H31.4.22 障害基礎年金につく加算の対象は?
さっそく、過去問をどうぞ
<H19年出題>
障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。

【解答】 ○
障害基礎年金の加算の対象になるのは「子」。配偶者は対象になりません。
ちなみに、配偶者加給年金額は、厚生年金険法の「障害厚生年金」に加算されます。(ただし、障害等級1級又は2級の障害厚生年金のみです。3級には配偶者加給年金額は加算されません。)
もう一問どうぞ
<H25年出題>
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。

【解答】 ×
受給権を取得した後に生計維持関係にある子を有するに至った場合でもOKです。「権利を取得した日の翌日以後」に生計維持関係にある子を有する至った場合は、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から加算額が加算されます。
社労士受験のあれこれ
20歳前傷病による障害基礎年金
H31.4.6 20歳前に初診日がある障害基礎年金の受給権発生日は?
さっそく過去問をどうぞ
<H26年出題>
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】 ×
 初診日が、「被保険者でなかった19歳の時」なので、第30条の4の「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になる。
初診日が、「被保険者でなかった19歳の時」なので、第30条の4の「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象になる。
 受給権の発生は?
受給権の発生は?
「障害認定日」と「20歳」どちらが前かで変わります。

・障害認定日以後に20歳に達したとき(障害認定日が20歳と同時か20歳より前)
→20歳に達した日に障害等級1級・2級に該当している場合は、20歳に達した日に発生
・障害認定日が20歳に達した日後であるとき(障害認定日が20歳より後)
→その障害認定日に障害等級1級・2級に該当している場合は、障害認定日に発生
 この問題については、初診日が19歳ですので、障害認定日(初診日から起算して1年6か月)が20歳より後になります。
この問題については、初診日が19歳ですので、障害認定日(初診日から起算して1年6か月)が20歳より後になります。
ですので、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権は、「障害認定日」に発生します。
社労士受験のあれこれ
寡婦年金の支給要件
H31.4.4 「障害基礎年金の受給権者」であったことがある、とは?
寡婦年金は、
「その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき」は支給されません。
「障害基礎年金の受給権者であったことがある」とはどういう意味でしょう?
「支給を受けていたとき」とどこが違うのかが、今日のテーマです。
では過去問をどうぞ
<H18年出題>
死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。

【解答】 ×
「夫が障害基礎年金の受給権者であった場合」とは、現実の年金の受給の有無にかかわらず裁定を受けた場合をさします。
死亡した夫が実際に障害基礎年金を受けたことがなくても、夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあれば、寡婦年金は支給されません。
社労士受験のあれこれ
国民年金第2号被保険者のこと
H31.3.30 厚生年金の被保険者=国民年金第2号被保険者だけど
 厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者です。
厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者です。
国民年金の第2号被保険者のポイントは、「国内居住要件」「年齢要件」が無いことです。
 ただし、厚生年金保険の被保険者で65歳以上の場合は注意が必要です。
ただし、厚生年金保険の被保険者で65歳以上の場合は注意が必要です。
・ 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者
ただし、65歳以上の者で、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、第2号被保険者とされない。
では過去問をどうぞ
<H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】 ○
 在職中の場合、70歳までは厚生年金保険の被保険者となります。ただし、①在職老齢年金を受給している(老齢・退職を支給事由とする年金の受給権があるということ)、②65歳以上、なので、この場合、厚生年金保険の被保険者ではあるけれど、国民年金の第2号被保険者とはなりません。
在職中の場合、70歳までは厚生年金保険の被保険者となります。ただし、①在職老齢年金を受給している(老齢・退職を支給事由とする年金の受給権があるということ)、②65歳以上、なので、この場合、厚生年金保険の被保険者ではあるけれど、国民年金の第2号被保険者とはなりません。
 第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが要件です。問題文の配偶者は、「第2号被保険者」の配偶者ではありません。そのため第3号被保険者にはなりません。
第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが要件です。問題文の配偶者は、「第2号被保険者」の配偶者ではありません。そのため第3号被保険者にはなりません。
社労士受験のあれこれ
法定免除の事由に該当したとき/国民年金法
H31.3.27 法定免除・保険料を納付する旨の申出があったとき
まずは過去問からどうぞ
<H26年出題>
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。

【解答】 ○
法定免除の事由に該当した場合、保険料は当然に免除されます。
※免除される期間
事由に該当するに至った日の属するの前月から該当しなくなる日の属する月まで
※例外
被保険者等から、「保険料を納付する」という申し出があった場合は、申出のあった期間に限っては、保険料を納付することができます。
社労士受験のあれこれ
国民年金法/不服申立て
H31.3.14 審査請求と訴訟との関係
★★まずは過去問をどうぞ
<H29年出題>
厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】 ×
「再審査請求に対する社会保険審査会の裁決」ではなく、「審査請求に対する社会保険審査官の決定」を経た後でなければ提起できない、です。
★ 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」、「③保険料その他の徴収金」に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して審査請求ができ、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求ができます。
【訴訟との関係について】
 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ処分取消しの訴えは提起できませんが、「③保険料その他の徴収金」はルールが違うので注意しましょう。
「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」は、審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ処分取消しの訴えは提起できませんが、「③保険料その他の徴収金」はルールが違うので注意しましょう。
★ 「⓵被保険者の資格」、「②給付(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)」の処分については、社会保険審査官の決定の後、処分取消しの訴えを提起することができます。(社会保険審査官の決定の後、社会保険審査会に再審査請求をする方を選んでも良い)
★ 「③保険料その他の徴収金」の処分については、社会保険審査官に審査請求することができますが、審査請求を経ずに処分取消しの訴えを提起することもできます。
社労士受験のあれこれ
社会保障制度の沿革を知ろう
H31.3.13 最低限おさえておきたい年金制度の沿革②
 昨日は、年金制度の沿革のポイントを選択式で学びました。
昨日は、年金制度の沿革のポイントを選択式で学びました。
今日は、年金だけでなく健康保険の沿革もまとめて確認しましょう。
過去問をどうぞ
<⓵ 国年H19年出題>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。
<② 健保H21年出題>
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。

【解答】
⓵ ×
無拠出制の福祉年金の給付が始まったのは、昭和34年10月からではなく昭和34年11月からです。
福祉年金とは、制度の発足時点で既に70歳以上の人等が対象でした。保険料の納付が前提になっていない点が特徴の年金です。
老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金があります。
 ついでに厚生年金保険の沿革も。
ついでに厚生年金保険の沿革も。
昭和16年に工場の男子労働者を対象に「労働者年金保険法」が公布(昭和17年施行)されました。その後昭和19年に女子労働者や事務職員などにも適用されるようになり、名称が「厚生年金保険法」に改定されました。
② ×
健康保険法の制定は大正11年ですが、翌年に関東大震災が発生したので、大正15年(ただし、保険給付及び費用に関する規定は昭和2年)から施行されました。
社労士受験のあれこれ
国民年金法/年金制度の沿革
H31.3.12 最低限おさえておきたい年金制度の沿革⓵
 年金の勉強が難しく感じるのは、時代に合わせて年金制度が変わっていくから。
年金の勉強が難しく感じるのは、時代に合わせて年金制度が変わっていくから。
年金の勉強を始める前に、まず、年金の始まりを知っておきましょう。
過去問をどうぞ
<H15年出題>
1 国民年金法は、昭和< A >年に制定され、国民皆年金体制が整った。その後、高度経済成長期には給付改善が行われた。特に昭和< B >年には、年金額の大幅な引き上げとともに< C >スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。
昭和50年代に入ると、世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果、昭和60年改正が行われ、公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた。
2 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< D >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)、障害基礎年金については< E >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【解答】
A 34 B 48 C 物価 D 大正15年4月2日 E 障害認定日
★ポイント
A 国民年金法の制定は昭和34年。拠出制(保険料が徴収される)が開始されたのが昭和36年4月。
B・C 昭和48年は「福祉元年」といわれている。この年に導入されたのが物価の変動に合わせて年金の額を改定する物価スライド制。このときは物価変動率が5%を超えて変動することが条件だったので、完全自動物価スライド制ではなかった。
なお、5%枠をなくし、完全自動物価スライド制が導入されたのは、平成元年。
D 「基礎年金」という名前が付くのは新法の年金。新法の老齢基礎年金の対象は、大正15年4月2日以降生まれの人。
E 障害基礎年金も遺族基礎年金も昭和61年4月1日以降に受給権が発生した人が対象。障害基礎年金は「障害認定日」、遺族基礎年金は「死亡日」。
社労士受験のあれこれ
国民年金法/寡婦年金と老基礎繰上げ
H31.3.8 老齢基礎年金を繰上げたら寡婦年金はどうなる?
 老齢基礎年金の受給権は原則65歳で発生しますが、要件を満たせば60歳以上65歳未満の間に繰上げ請求をすることができます。
老齢基礎年金の受給権は原則65歳で発生しますが、要件を満たせば60歳以上65歳未満の間に繰上げ請求をすることができます。
 一方、寡婦年金は60歳以上65歳未満の間に支給される有期年金です。
一方、寡婦年金は60歳以上65歳未満の間に支給される有期年金です。
 寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、寡婦年金はどうなるのか?が今日のテーマです。
寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、寡婦年金はどうなるのか?が今日のテーマです。
過去問です。
<H23年出題>
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。

【解答】 ×
支給停止ではなく、寡婦年金の受給権は「消滅」(=権利そのものがなくなる)します。
社労士受験のあれこれ
国民年金法/遺族基礎年金
H31.3.7 「養子」になったとき・遺族基礎年金
 遺族基礎年金の対象は、「子のある配偶者」と「子」です。
遺族基礎年金の対象は、「子のある配偶者」と「子」です。
 今日のテーマは、配偶者や子が「養子」になったとき、遺族基礎年金はどうなる?です。
今日のテーマは、配偶者や子が「養子」になったとき、遺族基礎年金はどうなる?です。
 配偶者、子に共通のルール「直系血族又は直系姻族以外の養子」になったときは失権する
配偶者、子に共通のルール「直系血族又は直系姻族以外の養子」になったときは失権する
過去問です。
<H16年出題>
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】 ○
遺族基礎年金の失権事由は、「直系血族又は直系姻族以外の養子」になったとき。ですので、遺族基礎年金の受給権者が直系血族又は直系姻族の養子になったとしても失権しません。(※このルールは受給権者が配偶者でも子でも同じです。)
「夫の父」は直系姻族ですので、「夫の父」の養子になっても遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
 「子」が配偶者以外の者の養子になったときの配偶者の年金額
「子」が配偶者以外の者の養子になったときの配偶者の年金額
※ 配偶者の遺族基礎年金の額は、子の数によって変わります。
 例えば「子」が3人いて、そのうちの1人が配偶者以外の者の養子になった場合、配偶者の遺族基礎年金に加算される子が3人から2人になり、結果として配偶者の遺族基礎年金は減額改定となります。
例えば「子」が3人いて、そのうちの1人が配偶者以外の者の養子になった場合、配偶者の遺族基礎年金に加算される子が3人から2人になり、結果として配偶者の遺族基礎年金は減額改定となります。
 配偶者の遺族基礎年金の加算対象になっていた「子」が1人で、その子が配偶者以外の養子になったときは、加算対象になる子がゼロになり、配偶者の遺族基礎年金は失権します。子がいないと配偶者には遺族基礎年金は支給されませんので。
配偶者の遺族基礎年金の加算対象になっていた「子」が1人で、その子が配偶者以外の養子になったときは、加算対象になる子がゼロになり、配偶者の遺族基礎年金は失権します。子がいないと配偶者には遺族基礎年金は支給されませんので。
では過去問です。
<H19年出題>
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときはこの限りでない。

【解答】 ×
・ 配偶者に支給する遺族基礎年金 → 加算事由に該当する子が1人でその子が配偶者以外の者の養子となったときは、子がいなくなるので受給権は消滅。
その子が直系血族又は直系姻族の養子になったとしても、「配偶者以外の者の養子」なので、配偶者の受給権は消滅します。
なお、直系血族又は直系姻族の養子になった子本人の遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
もう一問どうぞ
<H28年出題>
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】 ○
・ 子が直系血族又は直系姻族の養子となった → 子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない
・ 配偶者の有する遺族基礎年金 → 加算対象になっていた子が1人でその子が「配偶者以外の者の養子」となったので、配偶者の受給権は消滅
社労士受験のあれこれ
国民年金法/保険料納付済期間
H31.3.3 第2号被保険者期間のうちの20歳未満と60歳以上の期間
 「厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者です。
「厚生年金保険の被保険者」は国民年金の第2号被保険者です。
 第2号被保険者のポイントは、第1号や第3号と違って20歳以上60歳未満という年齢要件がない点です。
第2号被保険者のポイントは、第1号や第3号と違って20歳以上60歳未満という年齢要件がない点です。
 ですので、「厚生年金保険の被保険者」であれば、20歳未満の期間も60歳以後の期間も国民年金の第2号被保険者となります。(※65歳以上で老齢又は退職の年金の受給権がある場合は、第2号被保険者ではなくなります。)
ですので、「厚生年金保険の被保険者」であれば、20歳未満の期間も60歳以後の期間も国民年金の第2号被保険者となります。(※65歳以上で老齢又は退職の年金の受給権がある場合は、第2号被保険者ではなくなります。)
 第2号被保険者期間のうちの「20歳未満」と「60歳以後」の期間は、「保険料納付済期間」になるのかどうか?が今日のテーマです。
第2号被保険者期間のうちの「20歳未満」と「60歳以後」の期間は、「保険料納付済期間」になるのかどうか?が今日のテーマです。
 老齢基礎年金について
老齢基礎年金について
過去問をどうぞ。
<H28年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】 ○
第2号被保険者期間のうち、老齢基礎年金の額の計算に入れるのは、第1号被保険者の年齢に合わせて「20歳以上60歳未満」の部分だけです。老齢基礎年金は20歳から60歳未満の40年で満額という考え方だからです。
20歳前の期間と60歳以後の期間は、老齢基礎年金では「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映しません。
 では、次は障害基礎年金と遺族基礎年金について
では、次は障害基礎年金と遺族基礎年金について
過去問をどうぞ。
<H24年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】 ×
「保険料納付済期間とする」が正解です。
障害基礎年金の場合は40年で満額というフルペンション減額方式でないからです。※遺族基礎年金も同じ考え方です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H31.2.2 H30年出題/老齢基礎年金の受給権の消滅
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「老齢基礎年金の受給権の消滅」です。
H30年 国民年金法(問2B)
老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。

【解答】 〇
老齢基礎年金は、生きている限り支給される終身年金です。消滅事由は死亡のみです。
過去問もどうぞ
<H13年出題>
老齢基礎年金は、65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される。

【解答】〇
年金は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、権利が消滅した日の属する月まで「月単位」で支給されます。
老齢基礎年金の場合は、支給すべき事由が生じた日=65歳に達した日、権利が消滅した日=死亡した日となります。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H31.1.31 H30年出題/保険料を前納したときのルール
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「保険料を前納したときのルール」です。
H30年 国民年金法(問3D)
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】 ×
前納に係る期間の各月の「初日が到来したとき」が誤りで、前納に係る期間の「各月が経過した際」にそれぞれその月の保険料が納付されたとみなされます。
健康保険と比較してみましょう
健康保険の任意継続被保険者も保険料を前納することができます。この場合は、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
国民年金の保険料の前納とごちゃまぜにならないようにご注意を。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H31.1.17 H30年出題/老齢基礎年金の額の計算のルール
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「老齢基礎年金の額の計算のルール」です。
H30年 国民年金法(問9C)
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

【解答】 〇
★国民年金の「任意加入被保険者」としての被保険者期間について
国民年金の「任意加入被保険者」だった期間は、「第1号被保険者期間」とみなされます。
任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、第1号被保険者として保険料を納付したことと同じ扱いですので、老齢基礎年金の額を計算する際には、保険料納付済期間として扱われます。
★「第2号被保険者」期間について
第2号被保険者と第1号被保険者の違いとして、第2号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢要件がありません。
例えば、18歳から64歳までずっと民間企業に勤務していた場合、その間は厚生年金保険の被保険者であり、かつ国民年金の第2号被保険者でもあります。
ただし、第2号被保険者期間のうち、老齢基礎年金の額に反映されるのは「20歳以上60歳未満」の40年間の部分だけです。
老齢基礎年金は、第1号被保険者の基準に合わせている、と考えてみてください。
第2号被保険者期間(厚生年金保険の被保険者期間)のうち、20歳未満の部分、60歳以上の部分は、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
過去問もどうぞ
<H28年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】 〇
第2号被保険者の20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間となり、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H31.1.16 H30年出題/60歳に達したとき
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「60歳に達したとき」です。
H30年 国民年金法(問7D)
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】 〇
ポイントは2つです。
 60歳で資格を喪失するのは、第1号と第3号
60歳で資格を喪失するのは、第1号と第3号
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のうち、「20歳から60歳」という年齢要件があるのは、第1号と第3号です。
そのため、第1号と第3号は60歳に達した日に国民年金の資格を喪失します。
第2号には20歳から60歳という縛りがありませんので、60歳喪失から除外されています。
 年齢で喪失の場合は「その日」に喪失
年齢で喪失の場合は「その日」に喪失
年齢で資格を喪失する場合は、「翌日喪失」ではなく、「当日喪失」です。
60歳に達したときに該当するに至った「日」に喪失します。
ちなみに、60歳に達した日は60歳の誕生日の前日です。
過去問もどうぞ
<H20年出題>
すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

【解答】 ×
「すべての強制被保険者」が×です。
第2号被保険者は、60歳に達したことを理由に資格は喪失しません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H31.1.15 H30年出題/被保険者期間の計算
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「被保険者期間の計算」です。
H30年 国民年金法(問6A)
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

【解答】 ×
同一月に2回以上種別変更があった場合、その月は「最後の種別の被保険者であった月」とみなされます。
問題文のように、同一月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者と種別変更した場合は、第3号被保険者であった月とみなされます。
過去問もどうぞ
<H13年出題>
被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。

【解答】 ×
翌月からではなく、その月から最期の種別の被保険者であった月とみなされます。
★ついでに、「被保険者期間」の計算の方法も確認しておきましょう。
(被保険者期間の計算)
被保険者期間を計算する場合には、< A >によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する< B >までをこれに算入する。

【解答】
A 月 B 月の前月
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H31.1.9 H30年出題/基礎年金拠出金の額の算定基礎
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「基礎年金拠出金の額の算定基礎」です。
H30年 国民年金法(問1D)
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

【解答】 ×
「保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者」の総数です。
保険料免除期間には「全額免除期間」は入りません。また、保険料未納期間も入りません。
過去問もどうぞ
<H23年出題 その1>
政府及び実施機関に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は、20歳以上65歳未満の者に限られる。
<H23年出題 その2>
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。

【解答】
<H23年出題 その1> ×
20歳以上65歳未満ではなく、「20歳以上60歳未満」の者です。老齢基礎年金の支給要件の保険料納付済期間の考え方と同じですよね。
なお、第3号被保険者は、すべての者が基礎年金拠出金の算定基礎となります。
<H23年出題 その2> ×
保険料免除期間のうち、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間は、算入されます。
除かれるのは、全く保険料を払っていない全額免除期間です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H30.12.25 H30年出題/振替加算と老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」です。
※ 今日は、「振替加算と老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ」です。
H30年 国民年金法(問5オ)
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。

【解答】 ×
「老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され」の部分が誤りです。
正しくは、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても → 振替加算は繰上げされない。振替加算は65歳から加算される、です。
【では過去問をどうぞ】
<①H17年出題>
振替加算は、老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は繰上げ受給したときから加算され、繰下げ受給した場合は繰下げ受給したときから加算される。
<②H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】
① ×
前半が×です。老齢基礎年金を繰上げ受給した場合でも、振替加算は65歳からしか加算されません。老齢基礎年金を繰下げ受給した場合は振替加算も繰下げされますので後半は○です。
② ×
「振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され」までは○ですが、繰下げをしても当該振替加算額は増額はされません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H30.12.6 H30年出題/中途脱退者の定義(国民年金基金)
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」を確認しましょう。
※ 今日は、「中途脱退者の定義(国民年金基金)」です。
H30年 国民年金法(問1B)
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。

【解答】 ×
「基金の加入員期間の年数にかかわらず」の部分が×です。
中途脱退者は、国民年金基金令で、加入員期間が15年未満のものと定められています。
【過去問もどうぞ】
<H20年出題>
国民年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、国民年金基金連合会を設立することができるが、中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、当該基金加入員期間が20年に満たない者をいう。

【解答】 ×
20年未満ではなく15年未満です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法)
H30.11.18 H30年出題/付加保険料の納付について
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「国民年金法」を確認しましょう。
※ 今日は、「付加保険料の納付について」です。
H30年 国民年金法(問6E)
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

【解答】 ×
申出をした日の属する月以後の各月ではなく「申出をした日の属する月の前月以後の各月」に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる、です。(※既に納付されたもの及び前納されたものを除く。)
付加保険料の納付期日は翌月末日。納付の辞退は、まだ期日が到来していない前月分から、となります。
★ちなみに、納付が始められるのは、その申出をした日の属する月以後の各月(申し込んだ月分)からとなります。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法 基礎編)
H30.10.28 H30年出題/遺族基礎年金の保険料納付要件
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
国民年金法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「遺族基礎年金の保険料納付要件」です。
H30年 国民年金法(問3A)
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。

【解答】 ○
★ 保険料納付要件の経過措置の問題です。
原則の保険料納付要件は、「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あること」ですが、それを満たしていない場合、経過措置で納付要件を見ることができます。
では、保険料納付要件の経過措置のポイントを確認しましょう。
① 死亡日が平成38年4月1日前にあること
② 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がない(=直近1年間に保険料の未納期間がない)こと
③ 死亡日に65歳以上の者には適用されない
3つの要件を問題文に当てはめてみると
① 死亡日は平成30年4月2日。
② 死亡日の前日である平成30年4月1日に、死亡日の属する月の前々月(平成30年2月)までの1年間が保険料納付済期間と保険料免除期間のみで未納期間がない。
③ 死亡したのは第1号被保険者なので、60歳未満までの者の死亡。
保険料納付要件の経過措置の要件を満たしていることになります。
★ なぜ、保険料納付要件は、死亡日の属する月の前々月までで見るのでしょう?
平成30年2月分の保険料の納期限は平成30年3月末、平成30年3月分の保険料の納付期限は平成30年4月末です。
例えば、平成30年4月30日に死亡した場合、前日の4月29日の段階で納付期限が来ているのは平成30年2月分までで、平成30年3月分はまだ納付期限が来ていません。
納付期限が来ている月までで保険料納付要件を確認することになっているからです。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法 基礎編)
H30.10.8 H30年出題/遺族基礎年金の支給要件
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
国民年金法の「基礎」を確認しましょう。
※ 遺族基礎年金の支給要件を確認しましょう。
H30年国民年金法(問8A)
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。

【解答】 ×
ポイント!
まずは死亡した者の要件をおさらいしましょう。
① 被保険者が、死亡したとき。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
③ 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
★ 問題文の場合、③の老齢基礎年金の受給権者が死亡した、に当てはまりますが、この場合、保険料納付済期間+保険料免除期間=25年以上あることが条件です。
問題文では、15年しかありませんので、子に遺族基礎年金は支給されません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(国民年金法 選択編)
H30.9.20 <H30年選択>国民年金法振り返ります
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、国民年金法の選択式です。
A・B 機構保存本人確認情報の提供より
■ 被保険者、年金受給権者について、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができる(基礎年金番号と個人番号が結びついている)場合は、「氏名変更届」と「住所変更届」の提出を省略することができます。
Aについて
厚生労働大臣は、毎月、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、保有情報を更新することになっています。
Bについて
厚生労働大臣は、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要な場合(基礎年金番号と個人番号が結びついていない場合)は、受給権者に対し、個人番号の報告を求めることができます。
C 指定全額免除申請事務取扱者より
要件に該当する被保険者等は、全額免除申請又は納付猶予申請を、指定全額免除申請事務取扱者に委託することできる制度からの出題でした。
D・E 老齢基礎年金の繰下げの増額率より
<同じ論点の過去問・平成22年出題>
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。
【解答】 ×
申出を行った日の属する月までではなく「申出を行った日の属する月の前月」までの月を単位とする期間です。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】基本の条文(社会保険編)
H30.8.21 【選択式対策】基本条文チェック!(健保、国年、厚年)
 テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。
テキストを読み返すときは、「映像を脳裏に焼き付ける」イメージを持つのがいいのではないかと思います。
本試験の最中、「ここ、テキストのあのページの右上に書いてあった!」となったときに、目を閉じれば、そのページの映像が頭の中に浮かび上がるように。
■■
おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【健康保険法】
(基本的理念)
健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< A >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< B >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< C >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける< D >を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
【国民年金法】
(用語の定義)
・ 「政府及び実施機関」とは、< E >及び実施機関たる共済組合等をいう。
・ この法律において、「実施機関たる共済組合等」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< F >をいう。
【厚生年金保険法】
(障害厚生年金の受給権者)
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して < G >(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに< H >があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の< I >に満たないときは、この限りでない。

【解答】
A 高齢化 B 後期高齢者医療 C 常に D 医療の質の向上
E 厚生年金保険の実施者たる政府 F 日本私立学校振興・共済事業団
G 1年6月を経過した日 H 国民年金の被保険者期間 I 3分の2
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社会保険分野】目的条文
H30.8.16 【選択式対策】目的条文チェック!(健保、国年、厚年)
 ご質問いただきました。
ご質問いただきました。
★「一般常識の勉強方法」
・ 労働分野 → 労働経済の数字(例えば、完全失業率やら労働力率etc)を、小数点以下まで覚える必要はありませんが、「用語の意味」はおさえてください。例えば、「完全失業率」=「労働力人口に占める完全失業者の割合」というように。
・ 社会保険分野 → 得点しやすい分野です。今年は、国民健康保険法の改正個所、確定拠出年金法の「数字」あたりに力を入れてほしいです。(まだ10日もあります!間に合います)
★「予備校の選び方」
これは相性などもあり、人によって全く違うと思うので、「○○が良い」とは言えなくて、申し訳ないです。
まずは、各学校の無料体験講座などを受けてみて、比較してみるのもいいのでは?と思います。
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第4回目「社会保険分野・目的条文」です。
【健康保険法】
この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
国民年金制度は、< C >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを< D >によつて防止し、もつて健全な < E >に寄与することを目的とする。
【厚生年金保険法】
この法律は、< F >の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、 < F >及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務災害 B 福祉の向上 C 日本国憲法第25条第2項
D 国民の共同連帯 E 国民生活の維持及び向上 F 労働者 G 福祉の向上
★Cのポイント
日本国憲法第25条第2項(1項ではなく2項)
「 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・国民年金法】死亡一時金
H30.8.3 【選択式対策】死亡一時金の条文チェック
8月に入りました。勉強の遅れは、まだまだ取り戻せます!(でも焦りは禁物)
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
【死亡一時金】
 <支給要件>
<支給要件>
・ 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の< B >に相当する月数を合算した月数が< C >以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
・ ただし、老齢基礎年金又は< D >の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。
・ 死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により< E >を受けることができる者があるとき。(ただし、当該死亡日の属する月に当該< E >の受給権が消滅したときを除く。)
二 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により< E >を受けることができるに至ったとき。(ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該< E >の受給権が消滅したときを除く。)

【解答】
A 前月 B 4分の1 C 36月 D 障害基礎年金 E 遺族基礎年金
※ Aについて・・・「前々月」ではありません。
 <死亡一時金の遺族の範囲>
<死亡一時金の遺族の範囲>
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と< F >ものとする。

【解答】
F 生計を同じくしていた
※ 「生計を維持」ではありません。
 <死亡一時金の金額>
<死亡一時金の金額>
・ 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、次の額とする。
月数
36月以上180月未満 → < H >円
180月以上240月未満 → 145,000円
240月以上300月未満 → 170,000円
300月以上360月未満 → 220,000円
360月以上< G >月未満 → 270,000円
< G >月以上 → < I >円
・ 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、< J >円を加算した額とする。

【解答】
G 420 H 120,000 I 320,000 J 8,500
※ Gについて・・・「480」ではありません。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・国民年金法】基礎年金拠出金
H30.7.10 【選択式対策】国民年金/基礎年金拠出金
 朝からセミが大合唱。暑いです!
朝からセミが大合唱。暑いです!
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
<基礎年金拠出金>
1 < A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 < B >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、< C >は、< A >が負担し、又は< B >が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

【解答】
A 厚生年金保険の実施者たる政府 B 実施機関たる共済組合等
C 厚生労働大臣
過去問もどうぞ
(H25年出題)
基礎年金拠出金の算定基礎となる「政府及び実施機関に係る被保険者」とは、厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者をいい、その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない。

【解答】 × 第3号被保険者も含みます。
 「基礎年金拠出金」って?
「基礎年金拠出金」って?
基礎年金の給付の費用に充てるために、厚生年金保険の実施者たる政府と実施機関たる共済組合等が、国民年金に拠出しているものです。
 「基礎年金拠出金の額」はどうやって算出するの?
「基礎年金拠出金の額」はどうやって算出するの?
「国民年金の被保険者総数」に対する「第2号被保険者総数+第3号被保険者の総数」の比率を使って算出します。基礎年金拠出金は、第2号被保険者の数だけでなく、第3号被保険者の数も含めて算出してますよー、というのがこの問題の論点です。
 そもそも「基礎年金拠出金」のお金はどこから出てるの?
そもそも「基礎年金拠出金」のお金はどこから出てるの?
厚生年金保険の保険料が使われています。そして、その中には第3号被保険者の基礎年金の費用分も含まれている、と考えてください。
 第2号被保険者、第3号被保険者は国民年金に保険料を払わなくてもいい?
第2号被保険者、第3号被保険者は国民年金に保険料を払わなくてもいい?
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に対して保険料を個別で納付する必要はありません。第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金は、基礎年金拠出金でまかなうからです。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・国民年金法】年金額の改定など
H30.6.12 【選択式対策】国民年金第4条、4条の2、4条の3
 難しく考えすぎると、なかなか勉強がはかどりません。問題文は単純に読んでみましょう。
難しく考えすぎると、なかなか勉強がはかどりません。問題文は単純に読んでみましょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
第4条 (年金額の改定)
この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
第4条の2 (財政の均衡)
国民年金事業の財政は、< B >にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
第4条の3 (財政の現況及び見通しの作成)
1 政府は、少なくとも< C >ごとに、保険料及び< D >の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 1の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね < E >間とする。

【解答】
A 国民の生活水準 B 長期的 C 5年 D 国庫負担
E 100年
★★ついでに厚生年金保険もチェック
厚生年金保険法第2条の2 (年金額の改定)
この法律による年金たる保険給付の額は、< F >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

【解答】 F 国民の生活水準、賃金
※ 厚生年金保険は「賃金」が入ります。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・国民年金法】寡婦年金
H30.5.16 【選択式対策】寡婦年金の要件チェック
 今日の神戸の最高気温は27.1℃ですって。暑かったはずです。
今日の神戸の最高気温は27.1℃ですって。暑かったはずです。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民年金法」です。
第49条 (寡婦年金の支給要件)
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの < B >としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した < D >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が< E >の受給権者であつたことがあるとき、又は < F >の支給を受けていたときは、この限りでない。

【解答】
A 前月
※ 前々月ではありません。
B 第1号被保険者
※ 第1号被保険者としての被保険者期間のみが対象です
ポイント! 寡婦年金については、任意加入被保険者も第1号被保険者とみなされます。(ただし、特例の任意加入被保険者は含みませんので注意)
C 10
※ 平成29年8月1日改正です。その前は25年でした。
D 65
E 障害基礎年金
※ 障害基礎年金の受給権者であった場合、とは、死亡した夫が障害基礎年金の裁定を受けた場合、現実に受給が有った、無かったにかかわらず、寡婦年金は支給されない、という意味です。
F 老齢基礎年金
※ 老齢基礎年金の支給を受けていたとき → Eとの違いに注意してください。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・国民年金】脱退一時金
H30.4.19 【選択式対策】脱退一時金
平成30年度の試験は、8月26日(日)。いよいよです!
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は国民年金法です。
条文の空欄を埋めてください。
法附則第9条の3の2(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの< A >としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が < B >以上である日本国籍を有しない者(< C >でない者に限る。)であつて、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、請求できない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 < D >その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して < E >を経過しているとき。
2 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。

【解答】
A 第1号被保険者 B 6月 C 被保険者 D 障害基礎年金
E 2年
おさえるポイント★
A → 「任意加入被保険者」、「特例の任意加入被保険者」も「第1号被保険者」とみなされます。
B → 「保険料全額免除期間」は6月の計算には入りません。(保険料を全く納付していないので)
C → 「国民年金の被保険者」である者は脱退一時金の請求はできません
D → 「障害基礎年金」の受給権を有したことがあるときは脱退一時金は支給されません。なお、平成21年に「遺族基礎年金」の受給権を有したことがある者の脱退一時金の請求について出題されました。遺族基礎年金の受給権を有したことがある者でも、要件を満たせば、脱退一時金は請求できます。
ついでにもう一問どうぞ★
★ 次の条文の空欄を埋めてください。
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、< F >に対して審査請求をすることができる。

【解答】 F 社会保険審査会
※ 社会保険審査官ではないので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
裁定(国民年金基金)
H30.3.27 H29年問題より「裁定請求(国民年金基金)」
H29年本試験【国民年金法問5C】を解いてみてください。
国民年金基金が支給する年金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、国民年金基金が裁定する。

【解答】 ○
★ 年金を受ける資格ができても、年金の支給は自動的には始まりません。年金を受けるためには、請求の手続きが必要です。
国民年金基金の年金を受ける権利ができた場合は、受給権者の請求に基づいて、「国民年金基金」が裁定(受給要件を満たしているかどうかのチェック)します。

■■ついでに、国民年金・厚生年金保険の「裁定」の条文をチェックしましょう!
・ 国民年金法第16条(裁定)
給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、< A >が裁定する。
・ 厚生年金保険法第33条(裁定)
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。

【解答】 A 厚生労働大臣 B 実施機関
社労士受験のあれこれ
国年・任意加入
H30.2.28 H29年問題より「国民年金・任意加入」
H29年本試験【国民年金法問10A】を解いてみてください。
60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者となることができる。

【解答】 ○
★ 問題文の場合、任意加入できる者の要件の中の「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」に該当します(「特別支給の老齢厚生年金の受給権者」とあるので、65歳未満だと判断できる)ので、任意加入することができます。
任意加入には、①老齢基礎年金の受給権を得るため、②老齢基礎年金を増やす(満額に近づける)ため、という2つの目的があります。
問題文の場合でしたら、被保険者期間は第2号被保険者としての30年のみ。ですので、老齢基礎年金の受給権はある、しかし、老齢基礎年金は満額ではない。任意加入の目的としては②となります。
★ なお、「任意加入被保険者の特例」(昭和40年4月1日以前生まれ・65歳以上70歳未満の特例)については、老齢基礎年金等の受給権がある場合は、任意加入は認められません。
★ 「任意加入被保険者」の条件を確認しておきましょう。条文の空欄を埋めてください。
<任意加入被保険者>
次の各号のいずれかに該当する者(< A >及び< B >を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する< C >歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
二 日本国内に住所を有する60歳以上< D >歳未満の者
三 < E >を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない< F >歳以上< G >歳未満のもの

【解答】
A 第2号被保険者 B 第3号被保険者 C 20
D 65 E 日本国籍 F 20 G 65
社労士受験のあれこれ
遺族基礎年金の要件
H30.1.14 H29年問題より「遺族基礎年金の要件」
H29年本試験【国民年金法問2ア】を解いてみてください。
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

【解答】 ×
★ 遺族基礎年金の対象になる「配偶者又は子」は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持」していたことが要件です。
問題文の場合、「死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった」とありますので、遺族基礎年金の対象となる子には該当しません。ですので、年金が増額されることもありません。
★ ちなみに、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持されていたものとみなされ、生まれた日の属する月の翌月から年金額が改定されます。
社労士受験のあれこれ
基本の問題その6(国民年金法)
H29.12.25 H29年問題より「基本」を知ろう・国民年金法
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
国民年金第3号被保険者「種別確認の届出」
「種別確認」の届出と「種別変更」の届出を間違えないように。
★ 国民年金の第3号被保険者の場合、例えば、夫が国家公務員から引き続き(1日も空けずに)民間企業の会社員に変わった場合でも、妻は第3号被保険者のままです。
ただし、上の例のように、夫が転職によって、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者(民間企業の会社員)の資格を取得したとき等は、第3号被保険者は「種別確認の届出」の提出が必要となります。
★ポイント! 第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後、引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得した場合(民間企業間の転職)は、「種別確認の届出」は不要です。
同じく、公務員等の場合、資格喪失後引き続き同一の共済組合等の資格を取得した場合は、種別確認の届出は不要です。
では、平成29年【問1】Cを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問1】C)
第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

<解答> ○
社労士受験のあれこれ
定番問題その17(国民年金法)
H29.12.6 H29年問題より「定番」を知る・国民年金法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (未支給年金)
年金は「支給事由が生じた日の属する月の翌月」から「権利が消滅した日の属する月」まで支給される。死亡の場合は「死亡した月」まで支給される。
★ 例えば、年金を受けている者が11月7日に死亡した場合、権利が消滅した11月分まで年金が支給されます。
年金は、2カ月分ずつ後払いされるので、10月分と11月分の2カ月分は、本来は12月に支給されます。しかし、死亡のため、10月分と11月分が支給されないまま残ってしまっています。これが「未支給年金」です。
| 2月支払 | 4月支払 | 6月支払 | 8月支払 | 10月支払 | 12月支払 |
| 12月、1月分 | 2月、3月分 | 4月、5月分 | 6月、7月分 | 8月、9月分 | 10月、11月分 |
これを覚えると、平成29年【問9】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問9】A)
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。

<解答> ×
未支給年金として請求できるのは、2月分です。1月分は既に支払済みです。
社労士受験のあれこれ
定番問題その7(国民年金法)
H29.11.6 H29年問題より「定番」を知る・国民年金法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (老齢基礎年金と付加年金の繰上げ・繰下げ)
老齢基礎年金と付加年金は一心同体
★ 老齢基礎年金を繰上げ、繰下げした場合、付加年金も同じように繰上げ・繰下げて支給されます。
★ そして、老齢基礎年金と同様に、繰上げの場合は繰上げ月数に応じて減額、繰下げの場合も繰下げ月数に応じて増額されます。
これを覚えると、平成29年【問6】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問6】D)
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

<解答> 〇
 ポイント 老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行った → 付加年金も支給が繰下げられる → 付加年金の額も、老齢基礎年金と同じ率で増額される。
ポイント 老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行った → 付加年金も支給が繰下げられる → 付加年金の額も、老齢基礎年金と同じ率で増額される。
社労士受験のあれこれ
覚えれば解ける問題その7(国民年金法)
H29.10.18 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・国民年金法
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (喪失日と被保険者期間)
「死亡」の場合、国民年金の被保険者資格は「翌日」に喪失
「被保険者期間」の計算は、「資格取得月」から「資格喪失日の前月」まで
★ 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者全て、死亡した場合は、「死亡した日の翌日」に資格を喪失します。(任意加入被保険者についても同様です。)
★ 「被保険者期間」は「月単位」で計算します。「資格を取得した日の属する月」から「資格を喪失した日の属する月の前月」までを算入します。
これを覚えると、平成29年【問10】Bが解けます。
★問題です。(平成29年【問10】B)
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

<解答> ×
平成29年3月31日に死亡した場合、翌日の4月1日に資格を喪失します。
第1号被保険者としての被保険者期間は同年3月(資格喪失日の属する月(4月)の前月)までとなり、3月分までの保険料を納付する義務があります。
社労士受験のあれこれ
まずは原則!その9(国民年金法)
H29.10.5 H29年問題より原則を学ぶ・障害基礎年金
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(障害基礎年金・初診日の要件)
障害基礎年金「初診日」に「国内居住要件」があるのは?
障害基礎年金は、①初診日、②障害認定日、③保険料納付要件の3つを条件に当てはまれば、受給権が発生します。
今日は、1つめの要件である「初診日」の要件を確認しましょう。
◆◆初診日とは → 傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のこと
◆◆障害基礎年金を受けるには、「初診日」に、次のどちらかに当てはまることが条件です。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
 初診日の国内居住要件をチェック
初診日の国内居住要件をチェック
① 初診日に国民年金の被保険者(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者、任意加入被保険者、特例任意加入被保険者)なら国内居住要件は問われません。
② 初診日に「被保険者であった者=現在は被保険者ではない者」の場合は、初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に住所があることが要件です。
この原則で、平成29年【問2】オが解けます。
★問題です。(平成29年【問2】オ)
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

<解答> 〇
◆ 問題文の「被保険者であった者が60歳以上65歳未満」の部分がポイントです。この場合は、初診日に日本国内に住所がない場合は、初診日の要件を満たさないので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
社労士受験のあれこれ
平成29年度選択式を解きました。(国民年金編)
H29.9.16 平成29年度選択式(国民年金編)~次につなげるために~
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「国民年金法」です。
【A、B】
保険料半額免除の所得要件からの出題です。
4分の3免除、半額免除、4分の1免除で、それぞれ所得要件が78万円、118万円、158万円と40万円ずつ増えていくのが特徴です。
免除の所得要件は、よく出る、かつ覚えていないと解けない箇所です。暗記必須です。
【C、D】
「寡婦年金」からの出題です。
■Cについて
H14年、H18年、H20年に択一式で出題された箇所です。
H18年の問題は、「死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあっても、実際に支給を受けたことがなければ寡婦年金は支給される。」でしたが、答は「×」です。
夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある場合は、「支給を受けたことがあっても無くても」寡婦年金は支給されません。
また、夫が老齢基礎年金の「支給を受けていたとき」は寡婦年金は支給されません。
障害基礎年金と老齢基礎年金の違いを意識しながら読んでみてください。
■Dについて
夫の死亡時に妻が60歳未満か60歳以上かで、支給開始の時期が変わります。
【E】
「受給権者に関する調査」からの出題です。
問題文の「受給権者に対して」の部分がヒントです。
「受給権」や「支給停止」などに関係することは何か?と考えてみると解けそうです。
今後の勉強のポイント!
★ 過去の択一式の論点はおさえる。
免除の要件や寡婦年金は、択一式の頻出箇所です。落とすわけにはいきません。過去に何度も出題されている箇所は、選択式でも要注意。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】選択式の練習(国民年金法)
H29.8.23 選択式の練習(用語の定義)
選択式の練習問題です。
本日は、国民年金法の「用語の定義」です。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
法第5条 (用語の定義)
8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。
9 この法律において、「< A >」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。

<解答>
8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び<A 実施機関たる共済組合等>をいう。
9 この法律において、「<A 実施機関たる共済組合等>」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は<B 日本私立学校振興・共済事業団>をいう。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】選択式の練習(国民年金法)
H29.8.14 選択式の練習(国民年金法・平成29年度保険料)
選択式の練習問題です。
本日は、国民年金法の保険料からです。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
(平成19年選択式より ※平成29年度向けに改めています)
1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成29年度に属する月の月分は< A >円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の < B >年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成29年度の保険料改定率は< C >である。

<解答>
A 16,900 B 2 C 0.976
平成29年度の保険料は
16,900円 × 0.976 ≒ 16,490円
<端数処理> 5円未満切り捨て、5円以上10円未満10円に切り上げ
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)
H29.8.1 目的条文のチェック(社会保険編)
8月になりました!
ここからの頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。
目的条文のチェック(労働編)はコチラです。
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

<解答>
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
※ 業務災害→ 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。
ココもポイント!
第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。
コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
★★憲法第25条第2項も見ておきましょう。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その35
H29.7.28 国民年金・公課の禁止
「国民年金を学ぶ」シリーズその35です。
今日のテーマは「公課の禁止」です。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第25条(公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、< A >については、この限りでない。

<解答> A 老齢基礎年金及び付加年金
★ 老齢基礎年金及び付加年金は、課税対象となります。
 過去問です。
過去問です。
<H17年出題>
老齢基礎年金及び付加年金については、租税その他の公課を課すことができ、またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる。

<解答> 〇
★ 老齢基礎年金及び付加年金については、課税対象であり、また、国税滞納処分により差し押さえることができます。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その34
H29.7.27 国民年金・受給権の保護
「国民年金を学ぶ」シリーズその34です。
今日のテーマは「受給権の保護」です。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第24条(受給権の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、< A >を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び < B >を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

<解答> A 年金給付 B 老齢基礎年金及び付加年金
★ 原則 → ■「給付」を受ける権利
「譲り渡す」「担保に供す」「差し押さえる」禁止
★ 例外 → ■「年金給付」を受ける権利
別に法律で定めるところにより担保に供することができる
■「老齢基礎年金及び付加年金」
国税滞納処分により差し押さえることができる
 過去問です。
過去問です。
<H19年出題>
給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き、担保に供することはできない。また、給付を受ける権利は、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き、譲り渡すことはできない。

<解答> ×
★「年金給付を受ける権利」を別に法律で定めるところにより「担保に供する」ことはできますが、後段の「譲渡する」ことについての例外はありません。
ちなみに、「年金給付を受ける権利は「別に法律で定めるところにより」担保に供することができますが、具体的には「独立行政法人福祉医療機構法」の定めるところによります。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その33
H29.7.26 国民年金・損害賠償請求権
「国民年金を学ぶ」シリーズその33です。
今日のテーマは「損害賠償請求権」です。
★ 「障害」や「死亡」が第三者の行為で生じた場合、第三者からの損害賠償と年金給付が重ならないように調整が行われます。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第22条(損害賠償請求権)
1 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その< A >で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 1の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その< B >で、給付を行う責を免かれる。

<解答> A 給付の価額の限度 B 価額の限度
 過去問です。
過去問です。
<H22年出題>
死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、その損害賠償額との調整は行われない。

<解答> 〇
★ 「死亡一時金」については、損害賠償との調整は行われません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その32
H29.7.25 国民年金・受給権者の申出による支給停止
「国民年金を学ぶ」シリーズその32です。
今日のテーマは「受給権者の申出による支給停止」です。
★ 年金の受給を希望しない場合、申出によって、年金の支給を停止することができる制度です。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第20条の2(受給権者の申出による支給停止)
年金給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その< A >の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。

<解答> A 全額
※ 全部又は一部ではありませんので、注意しましょう。
 過去問です。
過去問です。
<H24年出題>
受給権者の申出による年金給付の支給停止は、いつでも撤回することができ、過去に遡って給付を受けることができる。

<解答> ×
★ 受給権者が年金の支給停止の申出をした場合、「申出の日の属する月の翌月」から支給停止となります。
また、支給停止の申出は、「いつでも、将来に向かって」撤回できます。この場合も撤回の申出の日の属する月の翌月から支給停止が解除されます。過去にさかのぼって給付を受けることはできません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その31
H29.7.24 国民年金・併給の調整その2(国民年金と厚生年金の調整編)
「国民年金を学ぶ」シリーズその31です。
今日のテーマは「併給の調整その2(国民年金と厚生年金の調整編)」です。
■■その1はコチラ→「併給の調整その1(国民年金の年金編)」です。
★ 国民年金と厚生年金が「同一支給事由」の場合は、2階立ての年金が支給されます。
・ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
・ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
・ 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
★ 例外的に、支給事由が異なっていても併給されるパターンがあります。覚えましょう。
・ 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金
※ 遺族厚生年金は老後の所得保障としての役割があるので老後は老齢基礎年金と併給できる。
・ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
※ 障害基礎年金を受けながら働いた(厚生年金に加入した)場合、老後は障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できる。
・ 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
■■例外の組み合わせは、「65歳」に達していることが要件です。
 過去問です。
過去問です。
<① H20年出題>
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生年金は、いずれも併給することができる。
<② H19年出題>
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げにより減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。

<解答>
<① H20年出題> ×
老齢基礎年金と障害厚生年金は、併給されません。
<② H19年出題> ×
老齢基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは、65歳以上の場合に限ります。
65歳前は併給できませんので、繰上げた老齢基礎年金と遺族厚生年金のうち、どちらかを選択することになります。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その30
H29.7.21 国民年金・併給の調整その1(国民年金の年金編)※訂正あり
※ 7月24日に条文削除しました
「国民年金を学ぶ」シリーズその30です。
今日のテーマは「併給の調整その1(国民年金の年金編)」です。
★ 併給調整には、「国民年金の年金どうしの調整」と「国民年金と厚生年金の調整」がありますが、今日は「国民年金の年金どうしの調整」です。
★ 「複数の年金の受給権」
国民年金の年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金があります。
では、1人に対して複数の年金の受給権が発生した場合、どのように調整するのでしょうか?
★ 「一人に対して一つの年金が原則」
例えば、「障害基礎年金」の受給権者に、「遺族基礎年金」の受給権ができた場合、「選択」によって一つの年金が支給され、他の年金は支給停止になります。
【選択の流れ】
① 「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」は両方ともいったん支給停止
↓
② 「遺族基礎年金」の支給を希望する場合は、「遺族基礎年金」の支給停止の解除を申請する。→ 遺族基礎年金が支給される
↓
③ 「障害基礎年金」は支給停止。(失権ではないので、選択替えをすることは可能)
ポイント! 老齢基礎年金と付加年金は同時に支給(併給)されます。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その29
H29.7.20 国民年金・未支給年金
「国民年金を学ぶ」シリーズその29です。
今日のテーマは「未支給年金」です。
★ 例えば、年金の受給権者が死亡した場合、必ず未支給年金が残ります。
理由は2つです。
・ 年金は、死亡した月まで支給されるから。(年金の支給期間は権利が消滅した月まで)
・ 年金は後払いだから。
例えば、7月に死亡した場合、7月分まで年金が支給されますが、6月の支払期月に支払われた年金は、4月分と5月分です。6月分と7月分は未支給年金となります。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第19条(未支給年金)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の< A >であつて、その者の死亡の当時その者と< B >していたものは、< C >で、その未支給の年金の支給を請求することができる。

<解答> A 三親等内の親族 B 生計を同じく C 自己の名
 過去問です。
過去問です。
<H28年出題>
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。

<解答> ×
★ 未支給の年金を相続人に相続する、という規定はありません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その28
H29.7.19 国民年金・端数処理その2
「国民年金を学ぶ」シリーズその28です。
今日のテーマは「端数処理その2」です。
★ 年金は、「年6期」に分けて、「偶数月」に、「前月分」までが支払われます。
今日は、支払期月ごとの金額の端数処理について勉強します。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
① 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
② ①の規定による支払額に< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
③ 毎年< B >月から翌年< C >月までの間において②の規定により切り捨てた金額の合計額(< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該< C >月の支払期月の年金額に加算するものとする。

<解答> A 1円 B 3 C 2
★ 年金は、6期に分けて支払われます。支払期月ごとの金額に1円未満の端数が出たときは、1円未満は切り捨てて支払われます。
支払期月ごとに切り捨てられた端数の合計額は2月の支払期月の年金額に加算されます。
 過去問です。
過去問です。
<H28年出題>
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

<解答> ×
★ 「毎年3月から翌年2月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。」です。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その27
H29.7.18 国民年金・年金の支給期間と支払期月
「国民年金を学ぶ」シリーズその27です。
今日のテーマは「年金の支給期間及び支払期月」です。
★ 年金は「月」単位で支給されます。日割り計算などはありません。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(年金の支給期間及び支払期月)
第18条 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する< A >から始め、権利が消滅した日の属する< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する< A >からその事由が消滅した日の属する< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

<解答> A 月の翌月 B 月 C 前月
★ 年金の支払は、「偶数月」「年6期」「後払い」です。
例えば、老齢基礎年金の受給権は、原則として65歳に達したときに発生しますが、年金は「65歳に達した日の属する月の翌月」から支給されます。
また、老齢基礎年金は受給権者の死亡により受給権が消滅します。その場合、年金は、「死亡した日の属する月」まで支給されます。(死亡した月分まで支給される)
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その26
H29.7.14 国民年金・端数処理
「国民年金を学ぶ」シリーズその26です。
今日のテーマは「端数処理」です。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(端数処理)
第17条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< A >以上< B >未満の端数が生じたときは、これを< B >に切り上げるものとする。
令第4条の3 年金たる給付の額を計算する過程において、< A >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< A >以上< B >未満の端数が生じたときは、これを< B >に切り上げることができる。

<解答> A 50銭 B 1円
 ちなみに、老齢基礎年金の満額は780,900円×改定率で計算しますが、このときの端数処理も押さえておきましょう。
ちなみに、老齢基礎年金の満額は780,900円×改定率で計算しますが、このときの端数処理も押さえておきましょう。
第27条
老齢基礎年金の額は、78,900円に改定率を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)とする。

<解答> C 50円 D 100円
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その25
H29.7.13 国民年金・裁定
「国民年金を学ぶ」シリーズその25です。
今日のテーマは「裁定」です。
★ 例えば、老齢基礎年金は、受給資格期間を満たした人が65歳に達すれば、そのときに受給権が発生します。
ただし、受給権が発生したからと言って、自動的に年金が支払われるわけではありません。
年金請求書を提出し受給権の発生を確認してもらわなけれなばなりません。このことを「裁定」と言います。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(裁定)
第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基いて、< A >が裁定する。

<解答> A 厚生労働大臣
裁定は、厚生労働大臣が行います。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その24
H29.7.12 国民年金・給付の種類
「国民年金を学ぶ」シリーズその24です。
今日のテーマは「給付の種類」です。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
(給付の種類)
第15条 この法律による給付は、次のとおりとする。
一 老齢基礎年金
二 障害基礎年金
三 遺族基礎年金
四 付加年金、寡婦年金及び< A >

<解答> A 死亡一時金
※ 付加年金、寡婦年金、死亡一時金は、第1号被保険者独自の給付です。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その23
H29.7.11 国民年金・届出(第1号被保険者)
「国民年金を学ぶ」シリーズその23です。
今日のテーマは「届出(第1号被保険者)」です。
★ 日本国内に住んでいる人が20歳になれば、(第2号被保険者、第3号被保険者に該当しなければ)「国民年金第1号被保険者」となります。
その場合は、「国民年金被保険者資格取得届書」を提出しなければなりません。
★ 今日は、「第1号被保険者」の「届出」が必要な場面、提出期限、提出先を勉強します。
 「第1号被保険者」の届出について条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
「第1号被保険者」の届出について条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第12条(届出)
1 被保険者(第3号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を< A >に届け出なければならない。
2 被保険者の属する世帯の< B >は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる。
3 住民基本台帳法第22条から第24条まで(転入届、転居届、転出届)、第30条の46又は第30条の47の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第29条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項の規定による届出があつたものとみなす。
4 < A >は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したとき(氏名及び住所の変更に関する事項の届出であつて厚生労働省令で定めるものを受理したときを除く。)は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない。

<解答>
A 市町村長 B 世帯主
★ 「第1号被保険者」は、「資格取得届」、「資格喪失届」、「種別変更届」、「氏名変更届」、「住所変更届」を「14日以内」に「市町村長」に提出しなければなりません。
(※ 第2号被保険者は、厚生年金保険法で規定されていますので、国民年金の届出をする義務はありません。)
★ 届出は、第1号被保険者本人が行いますが、被保険者の代わりに「世帯主」が届け出することができます。
 過去問を解いてみましょう。
過去問を解いてみましょう。
<① H20年出題>
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
<② H14年出題>
第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したときは、国民年金手帳を添えて、当該事実のあった日から14日以内に市町村長に届け出なければならない。

<解答>
<① H20年出題> ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になるのは「種別変更」ですので、「資格取得届」ではなく「種別変更届」を14日以内に提出しなければなりません。
<③ H14年出題> ×
60歳に達したことによる資格喪失の場合は、資格喪失届の提出は不要です。
※ なお、死亡したことによる資格喪失の場合も資格喪失届は不要です。被保険者が死亡した場合は、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、死亡の届出を行います。
次回は、第3号被保険者の届出です。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その22
H29.7.10 国民年金・種別の変更
「国民年金を学ぶ」シリーズその22です。
今日のテーマは「種別の変更」です。
★ ポイント 「種別」とは?
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区分のこと
例えば、会社員が退職して自営業者になった場合は、国民年金は第2号被保険者から第1号被保険者へ、被保険者の種別が変更されます。
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
第11条の2
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があつた月は、< A >の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は< B >の被保険者であつた月とみなす。

<解答>
A 変更後 B 最後の種別
 過去問を解いてみましょう。
過去問を解いてみましょう。
<H13年出題>
被保険者が同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別を変更したときは、最後の種別の被保険者期間の計算は、その翌月からとする。

<解答> ×
その翌月からではなく、「その月」から最後の種別の被保険者期間として計算されます。
(例) H29年7月に、第1号被保険者→第2号被保険者→第3号被保険者と種別が変更した場合は、H29年7月は最後の種別の「第3号被保険者」であった月とみなされます。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その21
H29.7.7 国民年金・被保険者期間
「国民年金を学ぶ」シリーズその21です。
今日のテーマは「被保険者期間」です。
★ ポイント 被保険者期間は「月」単位です!
 条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文を確認しましょう。空欄を埋めてください。
1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する< A >からその資格を喪失した日の属する< B >までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を< C >として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を< D >する。

<解答>
A 月 B 月の前月 C 1箇月 D 合算
 過去問を解いてみましょう。
過去問を解いてみましょう。
<① H26年出題>
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。
<② H22年出題>
被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間として算入するが、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後の被保険者期間のみをとって1か月として算入する。

<解答>
<① H26年出題> 〇
★ 4月1日資格取得、同年4月30日資格喪失の場合
「資格を取得した日の属する月にその資格を喪失(=同月得喪)」で1か月として被保険者期間に算入されます。
★ 4月1日資格取得、同年5月31日資格喪失の場合
被保険者期間は「資格を喪失した日の属する月の前月」まで(=5月31日喪失なので4月まで)となるので、1か月として被保険者期間に算入されます。
<② H22年出題> 〇
同一の月に、資格取得と喪失があり、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、「後の被保険者期間のみをとって1か月」で算入されます。
例えば、7月3日に資格取得、同月16日に喪失、さらに同月25日に資格取得した場合、25日~の資格で1か月の被保険者期間に算入されます。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その20
H29.7.6 任意加入被保険者の資格の喪失②
「国民年金を学ぶ」シリーズその20です。
前回に引き続き、任意加入被保険者の資格の喪失です。
 今日のポイント
今日のポイント
★「国内に住所を有する」任意加入被保険者が、国内に住所を有しなくなったとき
→ 「翌日」に資格を喪失します。
★「日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったとき
→ 「翌日」に資格を喪失します。
 過去問を解いてみましょう。
過去問を解いてみましょう。
<H17年出題>
日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

<解答> ×
★ 日本国内に住所を有するに至った日の「翌日」に資格を喪失します。
※ ただし、その日に更に強制被保険者の資格を取得したときは、翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その19
H29.7.5 任意加入被保険者の資格の喪失①
「国民年金を学ぶ」シリーズその19です。
前回は、任意加入被保険者は、申出をすることにより任意加入することができ、任意加入の「申出をした日」に資格を取得することを勉強しました。
今回は、任意加入被保険者の資格の喪失です。
 今日のポイント
今日のポイント
任意加入保険者の資格喪失理由の1つに、「保険料の滞納」があります。
「国内に居住」している者と「海外に居住」している者で、喪失時期が違いますので注意しましょう。
 条文の確認です。空欄Aを埋めてください。
条文の確認です。空欄Aを埋めてください。
<保険料を滞納した場合の資格喪失>
★ 日本国内に住所がある場合 ★
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
↓
保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その日の翌日に資格を喪失する。
★ 日本国内に住所を有しない場合(海外に住んでいる場合) ★
③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
↓
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく< A >が経過したとき。
→ その日の翌日に資格を喪失する。

<解答> A 2年間
 過去問です。
過去問です。
<① H12年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
<② H22年出題>
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

<解答>
<① H12年出題> ×
その日ではなくその日の「翌日」に資格を喪失します。
<② H22年出題> ×
2年を経過した日ではなく2年間が経過した日の「翌日」に資格を喪失します。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その18
H29.7.4 任意加入被保険者の資格の取得
「国民年金を学ぶ」シリーズその18です。
前回と前々回で、「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」について勉強しました。
今回は、「任意加入被保険者」、「特例による任意加入被保険者」の資格の取得です。
★★ 任意加入被保険者は、厚生労働大臣に「申出」をすることによって資格を取得するのがポイントです。
 過去問です。
過去問です。
<① H22年出題>
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人は、申出をした日に任意加入被保険者の資格を取得する。
<② H21年出題>
国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

<解答>
<① H22年出題> 〇
「申出をした日」に資格を取得するのがポイントです。
<② H21年出題> ×
任意加入被保険者のうち、保険料の納付方法が原則として口座振替になるのは「日本国内に住所」を有する者です。日本国籍を有し日本国内に住所を有しない任意加入被保険者は、口座振替納付希望の申出をする必要はありません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その17
H29.7.3 国民年金・特例による任意加入被保険者
「国民年金を学ぶ」シリーズその17です。
前回は、「任意加入被保険者」ですしたが、今日は、「特例による任意加入被保険者」です。
※ 「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」の違いをおさえるのがポイントです。
 違いその1
違いその1
特例による任意加入被保険者は、「老齢基礎年金の受給資格(原則25年必要)がない人が、それを得るため」の制度です。
「老齢基礎年金の金額を増額(老齢基礎年金の満額には保険料納付済期間が40年必要)する」目的では任意加入できません。→ 老齢基礎年金等の受給権がある人は対象外。
 違いその2
違いその2
特例による任意加入被保険者には、生年月日の要件があります。
 では、特例による任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、特例による任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
(任意加入被保険者の特例)
昭和< A >以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する< B >歳以上< C >歳未満の者
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >歳以上 < C >歳未満のもの

<解答>
A 昭和40年4月1日 B 65 C 70
ポイント!
・ 昭和40年4月1日以前生まれであること
・ 老齢基礎年金、老齢厚生年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと
 過去問です。
過去問です。
<H21年出題>
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。

<解答> ×
昭和40年4月1日以前生まれ、日本国籍を有する、65歳以上70歳未満、日本国内に住所を有しない場合は特例による任意加入被保険者となり得ます。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その16
H29.6.30 国民年金・任意加入被保険者
「国民年金を学ぶ」シリーズその16です。
今日は、「任意加入被保険者」です。
※ 任意加入被保険者には、「特例の任意加入被保険者」もありますが、特例については後日。今日は、特例ではない任意加入被保険者についてです。
 なぜ任意加入するのか?
なぜ任意加入するのか?
「老齢基礎年金の受給資格(原則25年必要)がない人が、それを得るため」、「老齢基礎年金の金額を増額(老齢基礎年金の満額には保険料納付済期間が40年必要)するため」です。
 では、任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、任意加入の要件を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
附則第5条 (任意加入被保険者)
次の各号のいずれかに該当する者(< A >及び< B >を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上< C >歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
二 日本国内に住所を有する< D >歳以上< E >歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない < F >歳以上< G >歳未満のもの

<解答>
A 第2号被保険者 B 第3号被保険者 C 60 D 60 E 65
F 20 G 65
ポイント!
・ 第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できない。(その必要がない)
・ 任意加入できるのは、第1号被保険者から除外されている人
① 20歳以上60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる人
② 60歳以上65歳未満の人(国内居住)
③ 20歳以上65歳未満で外国に住んでいる人(日本国籍を有することが要件)
 過去問です。
過去問です。
<① H25年出題>
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
<② H13年出題>
日本国籍を有する者で、外国に居住している20歳以上65歳未満の者は、申し出により、被保険者となることがきる。

<解答>
<① H25年出題> ×
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であれば、「日本国籍を有していなくても」任意加入できます。
<② H13年出題> 〇
20歳以上「65歳未満」ですので注意してください。60歳未満ではありません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その15
H29.6.29 国民年金・資格喪失の時期(その3)
「国民年金を学ぶ」シリーズその15です。
今日は、「資格の喪失の時期」その3です。
 今日は、第2号被保険者の資格喪失のポイントです。
今日は、第2号被保険者の資格喪失のポイントです。
第2号被保険者は、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」に資格を喪失します。
・ ただし、例えば、会社を退職した後に第1号被保険者になる場合、引き続き別の会社に就職し厚生年金保険に加入する(第2号被保険者のまま)場合、退職後に被扶養配偶者として第3号被保険者になる場合は、国民年金の資格は喪失しません。
・ では、「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」に国民年金の資格を喪失するのはどんなときでしょう?
例えば、18歳で就職した人が19歳で退職し、そのまま就職しなかった場合や、63歳で退職しそのまま就職しなかった場合などを考えてもらえばいいと思います。
・ ポイント!
「厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき」は、「その日」に国民年金の資格を喪失します。
例えば、平成29年6月29日に退職した場合、翌日の6月30日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失します。そしてその日(6月30日)に国民年金の資格も喪失します。
 過去問です。
過去問です。
<H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日(同日において、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

<解答> ×
翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その14
H29.6.28 国民年金・資格喪失の時期(その2)
「国民年金を学ぶ」シリーズその14です。
昨日は、「資格喪失日」の2つのポイント「「死亡」のときは「翌日」、「年齢」のときは「その日」が資格喪失日」を勉強しました。今日は、その続きです。
 今日は、第1号被保険者の資格喪失のポイントです。
今日は、第1号被保険者の資格喪失のポイントです。
第1号被保険者の要件は、次の4つでした。
| ① 日本国内に住所がある |
| ② 20歳以上60歳未満 |
| ③ 第2号被保険者、第3号被保険者どちらにも該当しない |
| ④ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は適用除外 |
・ 第1号被保険者は20歳以上60歳未満という年齢要件があるので、60歳に達したときはその日に資格を喪失することは、昨日勉強しました。
・ さらに、第1号被保険者の場合、「日本国内に住所を有しなくなった」とき、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった」ときは、資格を喪失します。
・ 資格喪失日は、「日本国内に住所を有しなくなった」ときは「翌日」、「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった」ときは「その日」となります。
 過去問です。
過去問です。
<① H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日
<② H19年出題> 強制加入被保険者の資格喪失の時期について
日本国内に住所を有しなくなった日(同日において、第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)の翌日

<解答>
<① H19年出題> ×
翌日ではなく「その日」に資格を喪失します。
なお、第2号被保険者、第3号被保険者には、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除外するルールがありませんので、この事由による資格喪失はありません。
<② H19年出題> 〇
なお、第2号被保険者、第3号被保険者には、国内居住要件がありませんので、国内に住所を有しなくなっても資格喪失しません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その13
H29.6.27 国民年金・資格喪失の時期(その1)
「国民年金を学ぶ」シリーズその13です。
昨日は、国民年金の資格取得の時期でしたが、今日は「資格喪失」の時期を勉強します。
 「種別変更」とは違うので注意
「種別変更」とは違うので注意
例えば、20歳のときは学生で第1号被保険者として資格を取得し、その後就職し厚生年金保険に加入し第2号被保険者になった場合、第1号被保険者の資格喪失→第2号被保険者の資格取得ではありません。
この場合は、国民年金の区分が第1号被保険者から第2号被保険者へと変わる「種別変更」となります。
今日勉強する「資格喪失」は国民年金の資格を喪失することです。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかの区分が変更となるのは「種別変更」ですので注意してください。
 今日は、資格喪失時期の代表的なものを2つ覚えましょう。「翌日」か「当日」かに注目してください。
今日は、資格喪失時期の代表的なものを2つ覚えましょう。「翌日」か「当日」かに注目してください。
① 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通
死亡したとき → 死亡した日の「翌日」に資格喪失
② 第1号被保険者、第3号被保険者
60歳に達したとき → 60歳に達した「日」に資格喪失
(第2号被保険者は、20歳~60歳という年齢要件がないため、60歳に達したことによる資格喪失はありません。)
★ 今日のポイント ★
「死亡」のときは「翌日」、「年齢」のときは「その日」が資格喪失日。
 過去問です。
過去問です。
<① H14年出題>
第1号被保険者が60歳に達したときは、その日に被保険者資格を喪失し、被保険者が死亡したときは、その翌日に被保険者資格を喪失する。
<② H25年出題>
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

<解答>
<① H14年出題> 〇
<② H25年出題> ×
厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)は、60歳に達したことによる資格喪失はありません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その12
H29.6.26 国民年金・資格取得の時期
「国民年金を学ぶ」シリーズその12です。
国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の定義を勉強しました。
今日は、国民年金の強制被保険者の資格取得日を確認します。
第1号、第2号、第3号のどれで国民年金の資格がスタートするかは、人によって違います。
一定の要件に当てはまった「当日」から当然に国民年金の資格がスタートする、というイメージです。
 「資格取得日」を具体例で確認しましょう。
「資格取得日」を具体例で確認しましょう。
① 平成29年4月1日に20歳の誕生日をむかえる学生の国民年金の資格取得日は?
※ 日本国内に居住しており、会社員や被扶養配偶者ではない
② 平成29年4月1日に就職し厚生年金保険の被保険者の資格を取得した18歳の会社員の国民年金の資格取得日は?
③ 厚生年金保険の被保険者である夫(25歳)に扶養される妻が、平成29年4月1日に20歳の誕生日をむかえた。妻の国民年金の資格の取得日は?

<解答>
① 20歳に達した日(誕生日の前日)である平成29年3月31日に「第1号被保険者」として資格取得
② 厚生年金保険の資格を取得した日である平成29年4月1日に「第2号被保険者」として資格取得
※ 第2号被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の被保険者となる
③ 20歳に達した日(誕生日の前日)である平成29年3月31日に「第3号被保険者」として資格取得
 過去問です。
過去問です。
<H27年出題>
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

<解答> 〇
ポイント!
・ 厚生年金保険の被保険者は18歳でも国民年金の「第2号被保険者」となる。
・ 第2号被保険者の被扶養配偶者は「第3号被保険者」となる。ただし、第3号被保険者の要件は20歳以上60歳未満であることなので、「20歳に達した日」に第3号被保険者として資格を取得する。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その11
H29.6.23 国民年金・第3号被保険者
「国民年金を学ぶ」シリーズその11です。
国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者のチェックポイントをみてきました。今日は、第3号被保険者です。
 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第7条 (被保険者の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
二 厚生年金保険の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
三 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち < A >未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)
施行令第4条(被扶養配偶者の認定)
法第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して< B >が行う。

<解答> A 20歳以上60歳未満 B 日本年金機構
★ 第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者の被扶養配偶者です。
★ 第1号被保険者、第2号被保険者との比較 ★
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
| 日本国内に住所がある | 国内居住要件なし | 国内居住要件なし |
| 20歳以上60歳未満 | 年齢要件なし(65歳以上の場合例外あり) | 20歳以上60歳未満 |
 過去問です。
過去問です。
<① H21年出題>
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。
<② H15年出題>
第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。

<解答>
<① H21年出題> ×
国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみです。
<② H15年出題> 〇
国籍要件が問われないのは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通です。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その10
H29.6.22 国民年金・第2号被保険者
「国民年金を学ぶ」シリーズその10です。
昨日は、国民年金の第1号被保険者のチェックポイントを勉強しました。
今日は、第2号被保険者です。
 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第7条 (被保険者の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
二 < A >の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
三 第2号被保険者の配偶者であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの(以下「第3号被保険者」という。)

<解答> A 厚生年金保険
★ 厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。
★ 第1号被保険者との比較 ★
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
| 日本国内に住所があること | 国内居住要件なし |
| 20歳以上60歳未満であること | 年齢要件なし(65歳以上の場合例外あり※) |
 過去問です。
過去問です。
<H17年出題>
厚生年金保険の被保険者は、すべて国民年金の第2号被保険者となる。

<解答> ×
厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上の場合は国民年金第2号被保険者にならないことがあります。厚生年金保険の被保険者が「すべて」国民年金第2号被保険者となるわけではないので誤りです。
↓解説しますと
★ 第2号被保険者には原則として年齢要件はありません。
ただし、例外があり、厚生年金保険の被保険者で、「65歳以上」で、「老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付の受給権」を「有する」場合は、国民年金第2号被保険者には「ならない」ことになっています。
 会社員等は、原則として70歳まで厚生年金保険に加入しますが、国民年金第2号被保険者となるか否かは、65歳以上の場合、老齢基礎年金等の受給権の有無がポイントです。
会社員等は、原則として70歳まで厚生年金保険に加入しますが、国民年金第2号被保険者となるか否かは、65歳以上の場合、老齢基礎年金等の受給権の有無がポイントです。
・ 65歳以上で老齢基礎年金等の受給権がある人の場合は、厚生年金保険の被保険者ではあっても、65歳以降は国民年金第2号被保険者ではなくなります。
・ 逆に、65歳以上でも老齢基礎年金等の受給権がない人の場合は、厚生年金保険の被保険者=国民年金第2号被保険者となります。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その9
H29.6.21 国民年金・第1号被保険者
「国民年金を学ぶ」シリーズその9です。
国民年金の強制被保険者として、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類が規定されています。
それぞれの要件をおさえましょう。
今日は「第1号被保険者」のチェックポイントです。
 では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第7条 (被保険者の資格)
< A >を有する< B >歳以上< C >歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第1号被保険者」という。)

<解答>
A 日本国内に住所 B 20 C 60
★ 第1号被保険者の問題でチェックするポイント ★
| ① 日本国内に住所がある |
| ② 20歳以上60歳未満 |
| ③ 第2号被保険者、第3号被保険者どちらにも該当しない |
| ④ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は適用除外 |
 チェックポイントをおさえたところで、過去問をどうぞ。
チェックポイントをおさえたところで、過去問をどうぞ。
<H22年出題>
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。

<解答> 〇
上の表の4つのチェックポイントに該当しているので、第1号被保険者となります。国籍要件は問われないので、外国人でも、第1号被保険者となります。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その8
H29.6.20 国民年金・用語の定義(政府及び実施機関)
「国民年金を学ぶ」シリーズその8です。
「用語の定義」シリーズ第3弾。は、「政府及び実施機関」の定義です。
 では、を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第5条 (用語の定義)
・ この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。
・ この法律において、「< A >」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。

<解答>
A 実施機関たる共済組合等 B 日本私立学校振興・共済事業団
 参考
参考
「厚生年金保険の実施者たる政府」と「実施機関たる共済組合等」は「基礎年金拠出金」を負担・納付する主体となります。
■第94条の2
・ 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
・ 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その7
H29.6.19 国民年金・用語の定義(保険料免除期間)
「国民年金を学ぶ」シリーズその7です。
「用語の定義」シリーズ第2弾です。
6月16日は、「保険料納付済期間」のお話しでしたが、今日は「保険料免除期間」です。
なお、「保険料免除期間」は、国民年金に個別に保険料納付義務がある「第1号被保険者」が対象です。
(第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金に個別に保険料を納付する義務がないので、保険料免除期間は関係ありません。)
 では、「保険料免除期間」を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、「保険料免除期間」を条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第5条 (用語の定義)
この法律において、「保険料免除期間」とは、< A >、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。

<解答>
A 保険料全額免除期間
「保険料免除期間」は、「保険料全額免除期間」+「保険料4分の3免除期間」+「保険料半額免除期間」+「保険料4分の1免除期間」です。
 過去問です!
過去問です!
<H21年出題>
国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

<解答> ×
「保険料全額免除期間」には、法定免除、申請全額免除のみではなく、「学生納付特例」も入ります。
また、法附則の特例で、納付猶予の期間(①30歳未満、②30歳以上50歳未満)も「保険料全額免除期間」に算入されます。
※ ちなみに、免除されていた保険料を「追納」すれば、保険料納付済期間となります。
ここもチェック!
一部免除(保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」)は、免除された部分以外の部分を納付することによって、「保険料免除期間」に算入されます。(例えば4分の3免除の場合は、残りの4分の1を納付することによって「4分の3免除期間」となります。残りの4分の1を納付しない場合は「未納」扱いとなります。)
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その6
H29.6.16 国民年金・用語の定義(保険料納付済期間)
「国民年金を学ぶ」シリーズその6です。
今日から、「用語の定義」シリーズが続きます。
本日は、「保険料納付済期間」です。
 例えば、「老齢基礎年金」の受給要件は原則として「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」が合わせて25年以上あることです。
例えば、「老齢基礎年金」の受給要件は原則として「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」が合わせて25年以上あることです。
では、「保険料納付済期間」とは?
 条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
条文で確認しましょう。空欄を埋めてください。
第5条 (用語の定義)
この法律において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち< A >(第96条の規定〔督促及び滞納処分〕により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定〔保険料の一部免除〕によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び < B >としての被保険者期間を合算した期間をいう。

<解答>
A 納付された保険料 B 第3号被保険者
【保険料納付済期間】
| 第1号被保険者としての被保険者期間 | 保険料を全額納付した期間だけが保険料納付済期間 ※ 未納期間や免除期間は保険料納付済期間には入りません。 |
| 第2号被保険者としての被保険者期間 | 第2号被保険者期間全体が保険料納付済期間 ※ 「老齢基礎年金」の場合は全体ではないので要注意です。(詳しくは後日) |
| 第3号被保険者としての被保険者期間 | 第3号被保険者期間全体が保険料納付済期間 |
★ 第2号被保険者と第3号被保険者には「未納」があり得ないので、原則すべてが保険料納付済期間となります。
 過去問です!
過去問です!
<① H24年出題>
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
<② H24年出題>
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

<解答>
<① H24年出題> 〇
督促及び滞納処分で保険料が納付された期間も「保険料納付済期間」に入ります。
<② H24年出題> 〇
例えば、保険料4分の3免除を受ける場合、4分の3は免除されますが残りの4分の1は納付義務があります。
免除された4分の3以外の「4分の1」を納付した期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料免除期間」の保険料4分の3免除期間となります。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その5
H29.6.15 国民年金第4条の3・財政の現況及び見通しの作成
今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその5です。
 政府は、5年ごとに「財政検証」を行うことになっています。
政府は、5年ごとに「財政検証」を行うことになっています。
※ 財政の仕組み
年金の財政は、負担(保険料)の上限を固定し、その負担(保険料)の収入の範囲内で、給付水準を調整する仕組みがとられています。(保険料水準固定方式)←保険料を払う側(現役世代)の負担が重くなりすぎることを回避できる方法。
政府は、定期的に、長期的な収支の見通しをたてて、給付水準の調整が必要かどうかなどを検証することになっています。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
第4条の3 (財政の現況及び見通しの作成)
1 政府は、少なくとも< A >年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 第1項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね < B >年間とする。
3 政府は、第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない

<解答>
A 5 B 100
★ 財政検証は少なくとも5年ごとに行う。財政均衡を図る期間はおおむね100年間。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その4
H29.6.14 国民年金第4条の2・財政の均衡
今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその4です。
 年金財政は、「有限均衡方式」がとられています。有限均衡方式は、平成16年改正で採用された方式で、約100年間の期間で給付と負担の均衡を図るという考え方です。
年金財政は、「有限均衡方式」がとられています。有限均衡方式は、平成16年改正で採用された方式で、約100年間の期間で給付と負担の均衡を図るという考え方です。
※平成16年改正前は、「永久均衡方式」がとられていて、こちらは、永久に給付と負担を均衡させるという考え方でした。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
第4条の2 (財政の均衡)
国民年金事業の財政は、< A >的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。

<解答>
A 長期
★ 財政は、「長期的」に均衡を保つことが義務付けられています。「永久的に」ではありません。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その3
H29.6.13 国民年金第4条・年金額の改定
今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその3です。
国民年金法による年金の額は、諸事情に応じて改定されます。第4条は、年金額の改定についての規定です。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
第4条 (年金額の改定)
この法律による年金の額は、< A >その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

<解答>
A 国民の生活水準
★ 国民年金は、国民の老齢、障害、死亡について、年金を支給することによって生活を安定させます。「国民の生活水準」が著しく変動した場合は、それに応じて年金額の改定が行われます。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その2
H29.6.12 国民年金第3条・保険者
今日は、「国民年金を学ぶ」シリーズその2です。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
第3条 (管掌)
1 国民年金事業は、< A >が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)、< B >、< C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< D >(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

<解答>
A 政府 B 国家公務員共済組合連合会 C 全国市町村職員共済組合連合会
D 市町村長
★ 国民年金事業を運営しているのは政府です。(「保険者」といいます。)
★ 「共済組合等」には、国民年金事業の事務の一部が委任されています。例えば、第2号厚生年金被保険者期間のみの人、第3号厚生年金被保険者期間のみの人、第4号厚生年金被保険者期間のみを有する人の老齢基礎年金の裁定請求の受理・審査に関する事務などがあてはまります。
★ 国民年金の事務の一部(第1号被保険者資格の取得・喪失の届出等の受理・審査する等)は、「市町村長」が処理することになっています。
(ここでは詳細の説明は省きます。ざっくりとイメージしてください)
★ ちなみに、 「日本年金機構」は、平成22年1月1日に設立された特殊法人。国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など) を担います。(日本年金機構ホームページより)
 過去問です。
過去問です。
<H19年出題>
国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団にのみ行わせることができる。

<解答> ×
★ 「全国市町村職員共済組合連合会」にも行わせることができます。
社労士受験のあれこれ
国民年金を学ぶ その1
H29.6.9 国民年金制度の目的
今日から「国民年金を学ぶ」シリーズを始めます。不定期になりますが、条文を順番に見ていきましょう。
 さっそく第1条から参ります。空欄を埋めてください。
さっそく第1条から参ります。空欄を埋めてください。
第1条 (国民年金制度の目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< A >の安定がそこなわれることを国民の< B >によつて防止し、もつて健全な< A >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の< C >、< D >又は < E >に関して必要な給付を行うものとする。

<解答> A 国民生活 B 共同連帯 C 老齢 D 障害 E 死亡
★ 国民年金の目的は、「健全な国民生活の維持向上」に寄与すること。老齢、障害、死亡で生活の安定が損なわれることを、国民の共同連帯で防止します。(→国民全員が強制加入し保険料を出し合います。)
国民の「老齢」、「障害」、「死亡」に対して、必要な給付が行われます。
★ 「保険」とは、「保険料を納める」→「イザというときに保険がおりる」というもので、国民年金も基本的には「保険」の方式をとっています。
が、「国民年金保険」ではなく「国民年金」、「保険給付」ではなく「必要な給付」という名称がついています。なぜならば、国民の生活を維持するために、保険料を納付していなくても受けられる給付(保険の方式をとっていない給付)があるからです。
 過去問です。
過去問です。
<H26年出題>
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理により行われる。

<解答> ×
★ 「保険給付」ではなく必要な「給付」を行う、です。
国民年金の給付には、保険原理に基づかないものもあります。例えば、20歳前に初診日がある障害基礎年金(第30条の4)などがその一例です。
社労士受験のあれこれ
H29年度 国民年金の年金額
H29.2.22 H29年度の年金額は0.1%引き下げ
平成29年1月27日に、平成29年度の年金額が発表されました。
 まずは老齢基礎年金の満額の計算式を確認しましょう。
まずは老齢基礎年金の満額の計算式を確認しましょう。
満額の年金額 → 780,900円 × 改定率
 年金額は、毎年度「改定率」を改定することによって改定されます。
年金額は、毎年度「改定率」を改定することによって改定されます。
改定率の改定は
★ 新規裁定者の場合 → 名目手取り賃金変動率を基準に改定される
★ 既裁定者の場合 → 物価変動率を基準に改定される
 指標を確認すると
指標を確認すると
★ 物価変動率 → マイナス0.1%
★ 名目手取り賃金変動率 → マイナス1.1%
ポイント どちらもマイナスで、名目手取り賃金変動率の方が、物価変動率より、下落率が大きいことに注目してください。
・ 年金額の改定は、名目手取り賃金変動率よりも物価変動率が下回ることを前提としています。
・ が、今年度は、逆になっていますよね。
・ そのため、今年度は、例外で、新規裁定者も物価変動率によって改定されることになります。
 マクロ経済スライドはどうなる?
マクロ経済スライドはどうなる?
今年度は、物価変動率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整率はかかりません。(マイナスをさらにマイナスにはしません。)
★ マクロ経済スライドは、賃金や物価がプラスになった場合の調整です。
 今年度の年金額の計算式
今年度の年金額の計算式
★ 新規裁定者も既裁定者も「物価変動率」によって改定されます。
★ 改定率 = H28年度の改定率(0.999)× 物価変動率(0.999)= 0.998
★ 今年度の年金額
780,900円 × 0.998 = 779,338.2円
50円未満を切り捨て、50円以上100円未満を100円に切り上げて、
平成29年度の老齢基礎年金の満額は、779,300円となります。
社労士受験のあれこれ
2016よく読んでいただいた記事
H28.12.30 今年よく読んでいただいた「振替加算」
~年末特集~
いつも「社会保険労務士合格研究室」をお読みいただきありがとうございます!
日本全国、色々なところからアクセスいただいています。
検索でこのサイトに来ていただく方が大半です。なかでも、「振替加算」という検索ワードが目立ちます。
ということで、今年最後の「社労士受験のあれこれ」は 「振替加算」の記事で締めくくりたいと思います。
「振替加算」の記事で締めくくりたいと思います。
来年もよろしくお願いいたします。
 シリーズ振替加算 その1
シリーズ振替加算 その1
【H28.4.25 振替加算が加算される人の生年月日】
年金を勉強するときは、「40年間サラリーマンだった夫」と「40年間専業主婦だった妻」をイメージしてみてください。年金制度はそのような夫婦をモデルにして設計されています。
さて、40年間厚生年金保険に加入していた夫には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されます。生計維持関係のある妻がいる場合は「加給年金額」もプラスされます。
ところが、あるときに、加給年金額は加算されなくなります。なぜなら、妻が65歳になって老齢基礎年金を受けるようになると、加給年金額が妻の老齢基礎年金に振り替わるからです。
夫に支給されていた加給年金額が姿を変えて妻の老齢基礎年金に加算されることを「振替加算」といいます。(といっても加給年金額と振替加算の額はイコールではありませんので注意)
※ なお、「夫」と「妻」が逆になるパターンでもOKですが、ここでは、サラリーマンの夫と専業主婦の妻で話を進めていきます。
まず、一つ目のポイントは、振替加算が加算される妻の生年月日です。
老齢基礎年金に振替加算が加算されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日までの間に生まれた者です。
■■大正15年4月1日以前生まれの妻には振替加算は加算されない■■
大正15年4月1日以前生まれの者は、新法の老齢基礎年金ではなく、旧法の対象です。
旧法の考え方は、「専業主婦には年金は支給しない。その代わり夫の老齢年金に加給年金額を加算する」というものです。
加給年金額は通常は65歳未満の配偶者が対象ですが、大正15年4月1日以前生まれの配偶者のについては65歳以上でも加給年金額の対象になるのはそのためです。
ポイント 大正15年4月1日以前生まれの妻の場合は、65歳以降も夫の加給年金額の対象。老齢基礎年金も振替加算も対象外。
■■昭和41年4月2日以降生まれの妻には振替加算は支給されない■■
年金のモデルは「40年間専業主婦だった妻」です。
第3号被保険者制度ができたのは昭和61年4月1日の新法以降です。その前の旧法時代は、専業主婦は任意加入でした。
(第3号被保険者制度のお話はこちらから → 旧法と新法(第3号被保険者))
昭和41年4月2日以降生まれの妻は、20歳以降の期間がすべて新法です。20歳から60歳まで専業主婦なら、40年間第3号被保険者です。それで満額の老齢基礎年金が支給されます。振替加算でカバーする必要はありません。
一方、昭和41年4月1日以前生まれの妻は、昭和61年4月1日に20歳を過ぎているので、旧法時代を経験しています。専業主婦は旧法時代は任意加入でした。20歳から60歳までの間の旧法時代に任意加入しなかった場合は、その分老齢基礎年金がカットされます。振替加算はその部分をカバーするためのものです。
ポイント 昭和41年4月2日以降生まれの妻の場合は、40年間ずっと第3号被保険者の可能性あり。それで満額の老齢基礎年金が保障される。
 シリーズ振替加算 その2
シリーズ振替加算 その2
【H28.5.9 振替加算はいつから加算される?】
シリーズ振替加算その2です。
振替加算は老齢基礎年金に加算されるので、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から行われます。(原則)
ただし、振替加算の開始時期は条件によって変わります。よく出るところを押さえましょう。
① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合)
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合)
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合)
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】
① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合) ×
夫の老齢厚生年金の受給権が発生した当時に妻が65歳を超えている場合は、夫の老齢厚生年金が支給されるときから、妻の年金に振替加算が加算されます。(夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算される代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されるイメージ)
② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合) ×
老齢基礎年金を繰上げたとしても、振替加算は65歳からです。
③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合) ×
老齢基礎年金を繰り下げた場合は振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。
 シリーズ振替加算 その3
シリーズ振替加算 その3
【H28.5.16 生年月日で変わる振替加算の額】
振替加算は夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額が、妻の老齢基礎年金に振り替わるというイメージですが、加給年金額イコール振替加算の額ではありません。
加給年金額は、224,700円×改定率ですが、振替加算は224,700円×改定率に生年月日に応じて定められた乗率(1.000~0.067)をかけて計算します。
ちなみに、生年月日に応じて定められた乗率が1.000になるのは、大正15年4月2日~昭和2年4月1日までに生まれた妻で0.067になるのは昭和36年4月2日~昭和40年4月1日までに生まれた妻です。
ポイントは、生年月日の若い妻(昭和41年生まれに近づく)ほど、乗率が小さくなることです。
シリーズ振替加算のその1でもお話ししたように、振替加算のモデルは20歳から60歳までずっとサラリーマンの妻(専業主婦)だった人です。
例えば、新法の対象者は大正15年4月2日生まれからですが、大正15年4月2日生まれに近い人ほど、旧法の期間が長い(その当時任意加入していなければカラ期間になる)ため、老齢基礎年金の額が小さくなります。そこをカバーするため、大正15年4月2日に近づくほど振替加算の乗率は乗率は1.000に近づきます。
では、昭和41年4月1日生まれの妻はどうでしょう?昭和41年4月1日生まれの人は昭和61年3月に20歳に達するので、旧法期間は1か月だけです。仮に任意加入しなかったとしても、昭和61年4月からは第3号被保険者ですので、満額に近い老齢基礎年金が支給されます。
とすると、振替加算は少なくてもいいですよね。ですので、乗率は0.067と小さくなります。
大正15年4月生まれに近づくほど旧法が長く(カラ期間が長い)、昭和41年4月1日に近づくほど旧法が短い(第3号被保険者期間が長い)ことをしっかり押さえてください。カラ期間が長い生年月日ほど、振替加算の額も高く設定されています。

では、最後に問題を解いてみましょう。
H18年出題
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。

【解答】 ×
乗率は、老齢厚生年金等の受給権者(夫)の生年月日ではなく、老齢基礎年金の受給権者(妻)の生年月日に応じて定められています。
 シリーズ振替加算 その4
シリーズ振替加算 その4
【H28.5.20 振替加算が行われなくなるとき】
シリーズ振替加算その4です。
これまで勉強してきたように、専業主婦の年金は旧法と新法で異なります。そもそも振替加算とは、旧法・任意加入→新法・第3号被保険者強制加入という制度の移り変わりで老齢基礎年金が満額にならない人をカバーするためのものです。
ですので、年金が十分に支給される人には、振替加算がつかない場合もあります。
~~ちなみに、旧法で任意加入して保険料を納付した+新法は全て第3号被保険者だった人の場合、老齢基礎年金が満額になりますが、その場合でも要件に合えば振替加算は加算されます。~~
★振替加算が行われないパターン → 妻も厚生年金保険に加入していたことがあり、老齢厚生年金を受けることができるとき
ただし、これは厚生年金保険の被保険者期間が240月以上(中高齢の特例含む)で計算される老齢厚生年金が対象です。
逆に、老齢厚生年金を受けることができる妻でも、厚生年金保険の被保険者期間が原則として240月未満(20年未満)の場合は、振替加算が加算されます。
★振替加算が支給停止されるパターン → 妻が障害基礎年金、障害厚生年金等の給付を受けることができるとき
障害基礎年金等なら保険料納付済期間の月数に関わらず満額支給されますよね。振替加算でカバーする必要がないからです。

では、問題を解いてみましょう!!
① H20年出題(改)
老齢基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
② H21年出題
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
③ H21年出題
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】
① H20年出題(改) ○
「被保険者期間の月数が240以上」が最大のポイントです。
② H21年出題 ×
障害基礎年金が全額支給停止されている場合は、振替加算は支給停止されません。
昭60法附則第16条では次のように規定されています。
「振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める額を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止する」
障害を支給事由とする年金を「受けることができるとき」はその間振替加算に相当する部分が停止されますが、障害基礎年金が全額支給停止(受けることができない)の場合は、振替加算は支給停止されません。
◇◇ちなみに、平成21年には次のような問題も出ています。
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
障害基礎年金等を受給できる(支給停止されていない)とあるので、その間、振替加算は支給停止されます。答えは○です。
③ H21年出題 ×
振替加算は老齢基礎年金に加算されるものです。遺族基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。
 シリーズ振替加算 その5(最終回)
シリーズ振替加算 その5(最終回)
【H28.5.24 振替加算相当額の老齢基礎年金】
シリーズ振替加算その5です。
最終回は、「振替加算相当額の老齢基礎年金」です!
さて、老齢基礎年金の受給資格は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あることです。ただし、25年の計算には入るけど、老齢基礎年金の額の計算には入らない期間がありますよね。
学生納付特例期間、30歳未満の納付猶予期間、合算対象期間は、受給資格の有無の25年を見るときには入りますが、老齢基礎年金の額には反映しません。
例えば、合算対象期間と学生納付特例期間のみで25年を満たした人の場合は、老齢基礎年金の受給資格はあるけれど、老齢基礎年金の額としてはゼロになります。
そして、そのような人が、「振替加算」の要件に該当している場合は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給されるのです。

では、代表的な問題を2つ解いてみましょう。
① H20年出題
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
② H17年出題
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。

【解答】
① H20年出題 ○
合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年で、「それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間」というのがポイント。この場合の老齢基礎年金はゼロになってしまいますが、振替加算の要件に該当している場合は振替加算と同額の老齢基礎年金が支給されます。
② H17年出題 ×
例えば、保険料納付済期間が1月でそれ以外はすべて合算対象期間で受給資格を満たした場合は、1月で計算した老齢基礎年金とそれに振替加算が加算されます。振替加算の額のみの老齢基礎年金ではありません。
社労士受験のあれこれ
【年末総集編】年金教室 第1回目~第17回目
H28.12.29 年金教室まとめ(第1回目~第17回目)
~年末特集~
今年の特集記事を振り返ります。
今日振り返る特集は、「年金教室」第1回目~第17回目までです。
 全体記事はこちらをどうぞ↓
全体記事はこちらをどうぞ↓
平成28年度の過去記事はコチラ → 社労士受験のあれこれH28年度
平成29年度の記事はコチラ → 社労士受験のあれこれH29年度
まだまだ続く予定です。
社労士受験のあれこれ
年金教室第17回目
H28.12.20 年金教室17 合算対象期間2
久しぶりの年金教室です。第17回目です。
前回(第16回目はコチラ)に引き続き、合算対象期間のお話です。
平成28年度の本試験で「第2号被保険者の合算対象期間」が出題されていました。
大事なところですので、ここも押さえておきましょう。

<H28年国民年金法問7Cより>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【答】○
★ 老齢基礎年金は、国民年金の第1号被保険者の基準に合わせて考えてください。
国民年金の第1号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢制限がありましたよね?
満額の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間フルで保険料を払った結果です。
★ 一方、第2号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢制限がないため、20歳未満でも、60歳以上でも原則として国民年金の被保険者です。(第1号被保険者よりも第2号被保険者の方が幅が広い。)
そのため、第2号被験者の場合、「保険料納付済期間」として「老齢基礎年金」の年金額に反映するのは、第1号被保険者と重なる20歳以上60歳未満の部分のみとされています。20歳未満と60歳以上の部分は、老齢基礎年金の額には反映しない合算対象期間と扱われます。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.16 必ず出る改正点(国年編)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度国民年金法問2のEです。端数処理の改正からの問題です。
<問題文>
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。

【答え】 ×
ポイント!
★ 年金は、偶数月(2,4,6,8,10,12月)に2カ月分ずつ後払いされます。
そのときの端数処理
・ 1円未満の端数 → 切り捨て
・ 毎年3月から翌年2月までの間に切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数は切り捨て) → 当該2月の支払期月の年金額に加算する
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.11.28 国民年金の事例問題その4
本日は平成28年度国民年金問9のAです。
<問題文>
昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。

| 20歳~23歳 | 厚生年金保険 | 3年 | 保険料納付済期間 |
23歳~40歳 | 国民年金第1号被保険者 | 17年 | 未納 |
| 40歳~55歳 | 厚生年金保険 | 15年 | 保険料納付済期間 |
| 55歳~60歳 | 国民年金第1号被保険者 | 5年 | 未納 |
★ 老齢基礎年金の受給資格は「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」で25年以上あることが条件です。この人の場合は、保険料納付済期間が18年しかありませんので、受給資格はできません。
★ では、中高齢の期間短縮特例はどうでしょう?
男性の場合は40歳以後の第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が15年~19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格ができる特例がありますが、この人は昭和25年4月2日生まれですので、40歳以後19年必要です。これにも当てはまりません。
★ 昭和27年4月1日以前生まれの場合、第1号厚生年金被保険者(民間企業)、第2号厚生被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)、第4号厚生被保険者(私学共済)の期間を合算して(単独でも可)、20年以上あれば受給資格ができるという特例もありますが、これでも足りません。
ということで、「受給資格期間は満たしていない」ので、答は「×」です。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.11.22 国民年金の事例問題その3
本日は平成28年度国民年金問8のAです。
<問題文>
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その障害認定日に障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。
★ 初診日以後に免除申請をしていることがこの問題のポイント
| 20歳 | 21歳6か月 | 22歳 |
| 初診日 | 免除申請 |
この人は、22歳の誕生月に全額免除の申請を行ったことにより、資格取得月までさかのぼって全額免除期間となりました。
しかし、初診日の前日当時は、20歳から初診日の属する月の前々月までの期間はすべて「滞納」でした。つまり保険料納付要件は満たしていません。そのため障害基礎年金の受給権は発生しません。
【答え】 ×
保険料納付要件は「初診日の前日」でみることがポイント。
初診日以後に未納分の保険料を納付しても、免除申請をしても、障害基礎年金の保険料納付要件には入れてもらえない。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.11.21 国民年金の事例問題その2
今日は、平成28年度国民年金問8のCについて考えてみましょう。
<問題文>
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

・ 平成22年4月~平成25年3月まで → 学生納付特例
・ 平成25年4月~ → 滞納
・ 初診日 → 平成26年4月8日
★ 保険料納付要件を満たしているか否かがこの問題のポイント!
保険料納付要件は、「初診日の属する月の前々月」までで判断されますよね。
この人の場合は、国民年金に初めて加入した平成22年4月から初診日の属する月の前々月(平成26年4月の前々月=「平成26年2月」)までの、47か月の保険料の納付状況が対象です。
47か月のうち、「保険料免除期間」が36か月、「未納期間」が11か月です。
全体の3分の2以上が保険料免除期間ですので、保険料納付要件を満たします。
ですので、障害認定日に2級に該当している場合は2級の障害基礎年金の受給権が発生し、障害認定日の属する月の翌月から年金の支給が開始されます。
答えは「○」です。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.11.16 国民年金の事例問題その1
今日は、平成28年度国民年金問9のDについて考えてみましょう。
<問題文>
昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。

図にしてみると↓このようになります。
| 20歳から27歳 | 35歳から50歳 | 60歳 | |
| 第1号被保険者 | 第1号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者 | 第1号被保険者 |
| 保険料納付済期間 | 未納 | 保険料納付済期間 | 未納 |
★ 既に勉強しているように、老齢基礎年金の受給資格は「保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間」で25年以上あることが条件です。
この人の場合は、保険料納付済期間が22年しかありませんので、受給資格はできません。
★ では、中高齢の期間短縮特例はどうでしょう?
女性の場合は35歳以後の第1号厚生年金被保険者の被保険者期間が15年~19年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格ができる特例がありますが・・・。
しかし、この特例も昭和26年4月1日以前生まれの人までが対象なので、これにも当てはまりません。
★ 第1号厚生年金被保険者(民間企業)、第2号厚生被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)、第4号厚生被保険者(私学共済)の期間を合算して(単独でも可)20年~24年以上あれば受給資格ができるという特例もありますが、これにも当てはまりません。
ということで、問題の条件では老齢基礎年金の受給資格はできません。答えは「×」となります。
社労士受験のあれこれ
年金教室第16回目
H28.11.15 年金教室16 合算対象期間
年金教室第16回目です。
今日は、合算対象期間のお話です。
難しいから嫌いという人が多い難所です。
この難所を勉強しすぎると年金が苦痛になるばかり。今の時期は、分かりやすいところだけ見ておけばOKです。
ということで、今日は、合算対象期間の中でも分かりやすい「会社員の妻(又は夫)」が当てはまる合算対象期間を押さえましょう。

◆ 例えば、会社員(又は公務員)の夫に扶養される妻で、新法が施行された昭和61年4月に38歳だった場合、60歳になるまでの22年は「第3号被保険者」で、老齢基礎年金の算定では「保険料納付済期間」となります。
一方、旧法時代は、会社員の夫に扶養される妻は「任意加入」だったことは既に勉強しました。
旧法時代に、この妻が任意加入できるのに「任意加入していなかった」場合、20歳から昭和61年3月までの18年間は、「合算対象期間」となります。
◆ 老齢基礎年金は、保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上あることが条件ですが、この妻の保険料納付済期間は、第3号被保険者期間としての22年しかありません。
◆ こんなときに登場するのが「合算対象期間」です。保険料納付済期間+保険料免除期間だけで足りない場合は、合算対象期間も合算して25年以上あれば、受給資格ができます。
この妻の場合は保険料納付済期間(22年)+合算対象期間(18年)=40年で受給資格ができるという仕組みです。
◆ ただし、合算対象期間は別名「カラ期間」と言われ、老齢基礎年金の額には計算には入りません。ですので、この妻の老齢基礎年金は40年ではなく、保険料納付済期間の22年分で計算されます。
社労士受験のあれこれ
年金教室第15回目
H28.11.9 年金教室15 老齢基礎年金の受給資格その2
年金教室第15回目です。
復習しますと、老齢基礎年金の受給要件は次の3つでしたよね。
① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)があること
② 65歳に達したこと
③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年あること
★ 保険料納付済期間や保険料免除期間には、「旧法」時代の期間も含まれます。
例えば、昭和30年4月2日生で、20歳から60歳まで全て「国内居住」・「自営業者」・「保険料は全て納付」の人の場合、
・昭和50年4月1日(20歳到達) (旧法)国民年金加入
・昭和61年4月1日(ここから新法) 制度改正 国民年金第1号被保険者
・平成27年4月1日(60歳到達) 国民年金資格喪失
老齢基礎年金の受給要件は旧法も通算されますので、この人の場合、旧法の加入期間11年、新法(第1号被保険者)の加入期間29年で、合計40年です。
受給資格はもちろん満たしますし、老齢基礎年金も満額受給できます。
★今日のポイント★
旧法の加入期間も通算されます。
では、問題も解いてみましょう。
<平成16年出題>
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち、保険料の免除を受けた期間は、保険料納付済期間とみなされる。

<解答> ×
旧国民年金の時代に「免除」を受けていた期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料免除期間」として受給資格や年金額に算入されます。
社労士受験のあれこれ
年金教室第14回目
H28.11.8 年金教室14 老齢基礎年金の受給資格
金教室第14回目です。
では、老齢基礎年金の受給資格を確認しましょう。
以下条文です。↓
(国民年金法第26条)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
条件は3つです。
① 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)があること
★ 老齢基礎年金の額は、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」で計算されるということです。例えば、未納期間や合算対象期間は、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
★ ただし、( )の部分、保険料免除期間から、(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の部分に注意して下さい。
保険料免除期間のうち、学生納付特例と納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額には反映されないという意味です。
② 65歳に達したこと
★ 老齢基礎年金の受給権が発生するのは65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)です。
③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して25年あること
★ この部分の「保険料免除期間」には、先ほどの( )の部分(学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)がありません。
ということは、学生納付特例・納付猶予の期間も受給資格期間の25年には算入されるということです。
★★まずは、老齢基礎年金の受給権は、原則として「保険料納付済期間と保険料免除期間を足して25年以上ある人が65歳に達したとき」に発生するということを押さえましょう。
保険料納付済期間の定義はコチラ → 年金教室11 保険料納付済期間
保険料免除期間の定義はコチラ → 年金教室12 保険料免除期間
では、問題も解いてみましょう。
<平成15年出題>
老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は、年金の受給資格期間としては算入されるが、年金額の算出にあたっては算入されない。

<解答> ○
★ちなみに「納付猶予」の期間も同じ扱いです。
~~納付猶予制度の対象者~~
平成28年6月まで → 30歳未満
平成28年7月から → 50歳未満
(平成37年6月までの時限措置)
社労士受験のあれこれ
年金教室第13回目
H28.11.7 年金教室13 老齢基礎年金の対象者
年金教室の第13回目です。
さて、いよいよ老齢基礎年金の受給資格に入ります。
全国民共通の「基礎年金」の制度が始まったのは、昭和61年4月1日でしたよね。
「老齢基礎年金」は、もちろん新法の年金です。
老齢基礎年金の対象になるか否かは以下のとおりです。
| 大正15年4月1日以前生まれ(昭和61年4月1日前に60歳到達) | 旧法の老齢年金 |
| 大正15年4月2日以後生まれ | 新法の老齢基礎年金 |
老齢基礎年金の対象者は「大正15年4月2日以後」に生まれた人です。
★★それでは、国民年金の過去問(H15年選択式)の一部を解いてみましょう。
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)、障害基礎年金については障害認定日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【解答】 大正15年4月2日
<ポイント>
新法の「老齢基礎年金」は大正15年4月2日以降生まれの人が対象です。
ただし、アンダーラインの部分に注意してください。
↓
「老齢基礎年金については<A 大正15年4月2日>以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権があった者を除く。)」
↓
★大正15年4月2日以降に生まれた者でも、施行日(昭和61年4月1日)に旧法の老齢給付の受給権があった人は、そのまま旧法の年金を受けることになります。
社労士受験のあれこれ
年金教室第12回目
H28.11.4 年金教室12 保険料免除期間
年金教室の第12回目です。
昨日は、「保険料納付済期間」の定義でしたが、今日は「保険料免除期間」について勉強しましょう。昨日の記事→<保険料納付済期間とは?>
再度確認しますと、例えば、国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給されますが、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算して25年以上あることという条件があります。
まずは、保険料免除期間は、「第1号被保険者のみ」に当てはまることがポイントです。国民年金に保険料を納付する義務があるのは第1号被保険者のみでしたよね。ということは納付を免除されるのも第1号被保険者のみという理屈です。
■「保険料免除済期間」の定義を確認してみると
① 保険料全額免除期間
② 保険料4分の3免除期間
③ 保険料半額免除期間
④ 保険料4分の1免除期間
①~④を合算した期間のことを「保険料免除期間」といいます。
★ ①の「全額免除期間」には次の種類があります。
・ 法定免除
・ 申請全額免除
・ 学生納付特例
・ 50歳未満の納付猶予
★ ちなみに、②~④を一部免除といいますが、免除された部分以外は納付義務があることに注意してください。
例えば、「4分の3免除期間」の場合、免除された4分の3以外の「4分の1」を納付することによってその期間が「4分の3免除期間」となります。
(もし、その4分の1を納付しない場合は未納期間となります。)

ーーー年金教室の過去の記事はこちらからどうぞ。ーーー
H28年11月3日 「年金教室第11回目」 保険料納付済期間
H28年10月26日 「年金教室第10回目」 保険料と基礎年金拠出金
H28年10月12日 「年金教室第9回目」 旧法と新法の違い
H28年10月11日 「年金教室第8回目」 旧法時代の公的年金は「分立」していた
H28年 9月30日 「年金教室第7回目」 国民皆年金といっても・・・
H28年 9月23日 「年金教室第6回目」 国民皆年金
H28年 9月20日 「年金教室第5回目」 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」
H28年 9月19日 「年金教室第4回目」 国民年金の誕生その2「福祉年金」
H28年 9月16日 「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1
H28年 9月12日 「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生
社労士受験のあれこれ
年金教室第11回目
H28.11.3 年金教室11 保険料納付済期間
年金教室の第11回目です。
今日は、「保険料納付済期間」の定義について勉強しましょう。
例えば、国民年金の老齢基礎年金は65歳から支給されますが、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合算して25年以上あることという条件があります。
■「保険料納付済期間」の定義を確認してみると
① 第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るもの
② 第2号被保険者としての被保険者期間
③ 第3号被保険者としての被保険者期間
①と②と③を合算した期間が「保険料納付済期間」とされています。
★ 第1号被保険者だけ、「納付された保険料に係るもの」という条件がついていることに注意してください。
年金教室第10回目で、国民年金に個々に保険料を納付する義務があるのは第1号被保険者のみだということをお話ししました。(→ 年金教室第10回目はこちら)
ですので、第1号被保険者の場合は、全額保険料を納めた月だけが「保険料納付済期間」としてカウントされます。(全額免除や一部免除を受けていた期間や未納期間は、当然保険料納付済期間には算入されません。)
★ 第2号被保険者と第3号被保険者は、個別に国民年金に保険料を納付する義務がないので、滞納などもあり得ません。ですので、第2号被保険者だった月や第3号被保険者だった月はそのまま保険料納付済期間としてカウントされることになります。

ーーー年金教室の過去の記事はこちらからどうぞ。ーーー
H28年10月26日 「年金教室第10回目」 保険料と基礎年金拠出金
H28年10月12日 「年金教室第9回目」 旧法と新法の違い
H28年10月11日 「年金教室第8回目」 旧法時代の公的年金は「分立」していた
H28年 9月30日 「年金教室第7回目」 国民皆年金といっても・・・
H28年 9月23日 「年金教室第6回目」 国民皆年金
H28年 9月20日 「年金教室第5回目」 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」
H28年 9月19日 「年金教室第4回目」 国民年金の誕生その2「福祉年金」
H28年 9月16日 「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1
H28年 9月12日 「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生
社労士受験のあれこれ
年金教室第10回目
H28.10.26 年金教室10 保険料と基礎年金拠出金
久しぶりの年金教室です。今日は第10回目です。
過去の記事はこちらからどうぞ。
H28年10月12日 「年金教室第9回目」 旧法と新法の違い
H28年10月11日 「年金教室第8回目」 旧法時代の公的年金は「分立」していた
H28年 9月30日 「年金教室第7回目」 国民皆年金といっても・・・
H28年 9月23日 「年金教室第6回目」 国民皆年金
H28年 9月20日 「年金教室第5回目」 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」
H28年 9月19日 「年金教室第4回目」 国民年金の誕生その2「福祉年金」
H28年 9月16日 「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1
H28年 9月12日 「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生
H28年 9月 7日 「年金教室第1回目」 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?
今日のテーマは、国民年金の「保険料」と「基礎年金拠出金」です。
■ 昭和61年4月に今の年金制度になってから、国民年金には全国民が加入し、第1号被保険者も第2号被保険者も第3号被保険者も基礎年金を受給します。
ただし、国民年金に「保険料」を支払う義務があるのは、「第1号被保険者」のみです。第2号被保険者と第3号被保険者には国民年金に保険料を納付する必要はありません。
| 保険料納付義務 | |
| 第1号被保険者 | 有 |
| 第2号被保険者 | 無 |
| 第3号被保険者 | 無 |
■ しかし、第2号被保険者も第3号被保険者も、65歳になれば国民年金から老齢基礎年金を受給します。
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金に対して保険料は納付しません。ですので、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用は「基礎年金拠出金」で賄われています。
■ 基礎年金拠出金の負担(納付)は?
第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の費用に充てるため、厚生年金保険の実施者たる政府と実施機関たる共済組合等は「基礎年金拠出金」を負担(実施機関たる共済組合等は納付)することになっています。
ちなみに第3号被保険者分の費用は、配偶者が負担しているのではなく、第2号被保険者全体の保険料で賄われています。(被扶養配偶者がいてもいなくても厚生年金保険料に差はありません。)
社労士受験のあれこれ
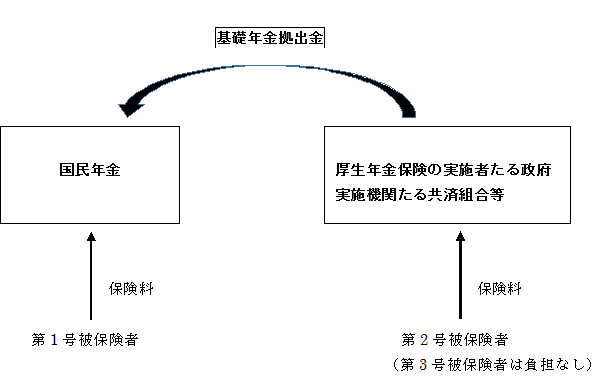
年金教室第9回目
H28.10.12 年金教室9 旧法と新法の違い
昨日の年金教室8回目では、「旧法時代の年金の特徴」についてお話ししました。
記事はこちらからどうぞ。
今日は、「新法」(現在の制度)と「旧法」の違いを押さえましょう。
ちなみに、旧法から新法に変わったのは、「昭和61年4月1日」です。
国民皆年金が実現した「昭和36年4月1日」と並ぶ年金の最重要年号です。しっかりおぼえましょう。
| 旧 法 | 新 法 | |
| 国民年金の位置づけ | 自営業者等が対象 | 全国民が対象となり、「基礎年金」が開始された。 ・ 新法になって、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者という種別ができた |
| 会社員の妻 | 国民年金には任意加入 | 「第3号被保険者」として国民年金に強制加入になった ・ 個別の保険料の負担はない |
| 厚生年金・共済年金 | 各制度が分立していた | 1階部分が「国民年金(基礎年金)」で「厚生年金」、「共済年金」は2階部分に乗る形になった ・ 会社員や公務員等は、「厚生年金(共済年金)」に加入すると同時に「国民年金(基礎年金)」にも加入することになった (加入も、給付も2階建てとなった) |
| 船員保険 | 独立していた | 厚生年金保険に統合され、船員保険から年金部門がなくなった |
社労士受験のあれこれ
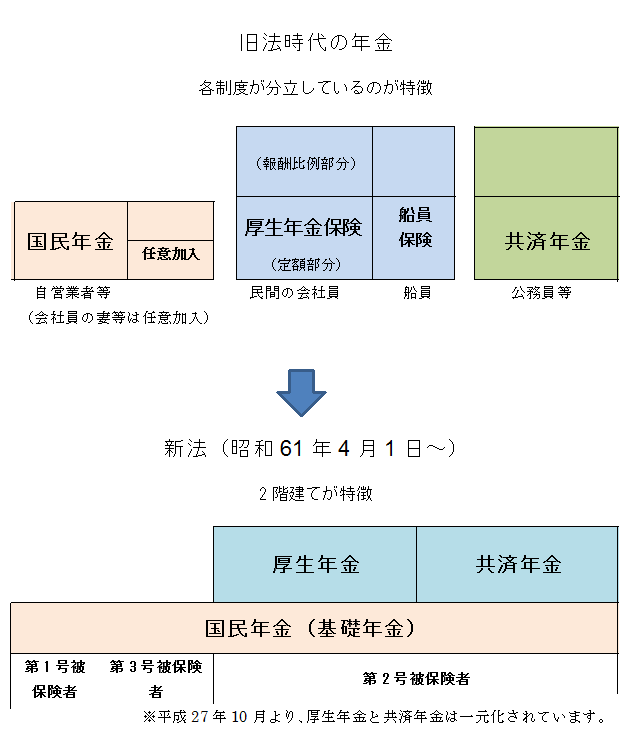
年金教室第8回目
H28.10.11 年金教室8 旧法時代の公的年金は「分立」していた
久しぶりの年金教室です。
過去の年金教室はこちらからどうぞ。
H28年9月30日 「年金教室第7回目」 国民皆年金といっても・・・
H28年9月23日 「年金教室第6回目」 国民皆年金
H28年9月20日 「年金教室第5回目」 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」
H28年9月19日 「年金教室第4回目」 国民年金の誕生その2「福祉年金」
H28年9月16日 「年金教室第3回目」 国民年金の誕生その1
H28年9月12日 「年金教室第2回目」 「厚生年金保険」の誕生
H28年9月7日 「年金教室第1回目」 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?
今日は、年金教室第8回目です。
昭和61年4月に基礎年金制度が導入されますが、その前(昭和61年3月まで)の制度は、旧法と呼ばれます。
新法は、国民年金(基礎年金)は全国民が対象で、国民年金の上に厚生年金保険が乗っかるという2階建ての制度ですが、旧法は違います。
旧法では、公的年金はそれぞれの制度が「分立」していました。2階建てではなく縦割りだったことが特徴です。
① 自営業者等 → 国民年金
② 民間企業の会社員 → 厚生年金保険
船員 → 船員保険
③ 公務員等 → 共済年金
社労士受験のあれこれ
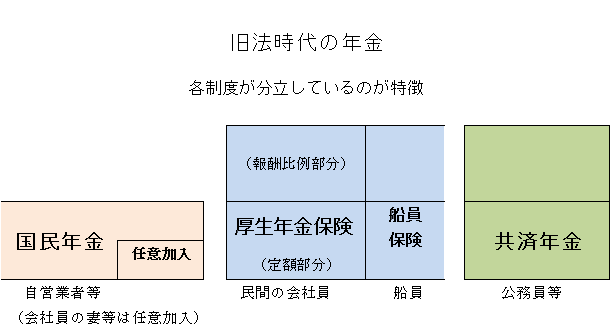
ひっかけ問題(引っかかってはいけない)
H28.10.7 シリーズひっかけ(国年・強制被保険者)
次の問題を解いてみてください。
<平成21年出題>
国民年金の被保険者のうち、国内居住用件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。

<解答> ×
第3号被保険者は国内居住用件は問われません。
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」のみです。
第2号被保険者は、国内の事業主と雇用関係があるため、第2号被保険者自身が海外に居住していても問題ないからです。また、夫(妻)の海外勤務に伴い妻(夫)も海外に居住することがあり得るので、第3号被保険者にも国内居住要件はありません。
社労士受験のあれこれ
年金教室第7回目
H28.9.30 年金教室7 国民皆年金といっても・・・
昭和36年4月に拠出制の国民年金がスタートし、「国民皆年金」が実現しました。
ただし、国民皆年金とは言っても、「任意加入」とされる人たちがいました。
その代表が、「専業主婦(サラリーマン)の奥さん」です。
老後はサラリーマンの夫の老齢年金(妻がいれば加給年金もつくし、夫の死後は遺族年金が支給される)で暮らせるので、あえて妻が自分で保険料を払って老後に備える必要はないでしょう、というのが当時の考え方です。
また、「学生」も任意加入とされていました。
★ただし、任意加入しなければ、もし、離婚することになっても妻自身の老後の備えがない、又、もし、事故などにあっても障害年金は支給されない、というリスクがある、ということも意識しておいてくださいね。
ということで、当時は、サラリーマンの妻や学生は、国民年金に強制加入ではなく、「任意加入」だった、というのが今日のポイントです。
それでは、過去問です。
① 平成16年選択
国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、<A>福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、<B>年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。
当初は任意加入であった被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成<C>年4月から強制加入と改められた。
(注)問題文の「被用者年金」とは、厚生年金保険(民間企業のサラリーマン等)や共済年金(公務員等)のことです。
ーーーーーーーーーー【選択肢】ーーーーーーーーーー
① 遺児 ② 4 ③ 寡婦 ④ 大正5 ⑤ 昭和5 ⑥ 2
⑦ 3 ⑧ 遺族 ⑨ 昭和2 ⑩ 母子 ⑪ 7 ⑫ 大正15
② 平成16年出題
被用者年金制度加入者の配偶者が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金に加入しなかった期間は、合算対象期間とされる。
(注)問題文の「被用者年金」とは、厚生年金保険(民間企業のサラリーマン等)や共済年金(公務員等)のことです。

【解答】
① 平成16年選択
<A> ⑩母子 <B> ⑤昭和5 <C> ⑦3
ポイント! 昭和36年当時は、被用者年金加入者(サラリーマンや公務員)の配偶者と学生は任意加入だった。強制加入になったのは、前者は昭和61年4月から、後者は平成3年4月から。
② 平成16年択一 ○
サラリーマン等の妻が任意加入できるのにしなかった期間は、「合算対象期間」とされます。(老齢基礎年金の受給資格期間には入るが、老齢基礎年金の額には反映されない)
社労士受験のあれこれ
年金教室第6回目
H28.9.23 年金教室6 国民皆年金
昭和36年4月に拠出制の国民年金がスタートし、「国民皆年金」が実現しました。
サラリーマンの「厚生年金」、公務員の「共済年金」、船員の「船員保険」は既に存在していました。(被用者年金と言われる年金です。)
昭和36年4月にスタートした国民年金で、自営業者や農林水産業に従事している人も年金に加入できるようになりました。
サラリーマンや公務員だけでなく自営業者等も年金に加入できるようになったので「国民皆年金」と言われます。

★まだ先の話になりますが、昭和61年4月に「基礎年金」制度が始まり、そのときに1階が基礎年金、2階が厚生年金(共済年金)という2階建ての年金制度に生まれ変わります。
が、昭和36年4月に国民皆年金がスタートしたころの年金制度は2階建てではなく、それぞれの年金制度が縦割りで個別に運営されていたことに注意しておいてくださいね。
ですので、昭和36年4月当時の国民年金は、現在のように「全国民」が加入するものではなく、被用者以外の「自営業者」等のためのものだったということがポイントです。
ちなみに、基礎年金が導入された昭和61年4月以降の年金制度を「新法」、昭和61年3月までの年金制度を「旧法」と言います。

さて、旧法の国民年金には、「老齢年金」、「障害年金」、「母子(準母子)年金」などの年金がありました。(新法の年金では「基礎年金」と言いますが、旧法時代は基礎年金という用語はありません。)
そして、これら旧法時代の年金は現在でもそのままの名称で支給されています。
こちらの問題で確認しましょう。
<平成16年出題>
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金又は準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。

<解答> ×
母子年金、準母子年金は新法以降もそのまま支給されています。遺族基礎年金へは裁定替えされません。
★母子福祉年金・準母子福祉年金との違いに注意しましょう。
こちらをどうぞ → H28.9.20 年金教室5 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」
社労士受験のあれこれ
年金教室第5回目
H28.9.20 年金教室5 国民年金の誕生その3「福祉年金のその後」
さて、昭和34年11月に給付が開始された無拠出制の福祉年金ですが、福祉年金は現在どうなっているのでしょうか?
「老齢福祉年金」は、現在も「老齢福祉年金」として支給されています。
「障害福祉年金」と「母子(準母子)福祉年金」については、昭和61年4月1日以降、「障害福祉年金」→「障害基礎年金」に、「母子(準母子)福祉年金」→「遺族基礎年金」にそれぞれ裁定替えされています。
過去問もチェックしておきましょう!
①平成21年出題
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。
②平成16年出題
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

<解答>
①平成21年出題 ○
障害福祉年金は、昭和61年4月1日に障害基礎年金に裁定替えされました。
②平成16年出題 ○
母子福祉年金・準母子福祉年金は、昭和61年4月1日に遺族基礎年金に裁定替えされました。
社労士受験のあれこれ
年金教室第4回目
H28.9.19 年金教室4 国民年金の誕生その2「福祉年金」
さて、拠出制の国民年金がスタートしたのは昭和36年4月ですが、その前に無拠出制の福祉年金がスタートしました。
福祉年金には、既に高齢だった人に対する「老齢福祉年金」、既に障害を有する人に対する「障害福祉年金」、既に遺族だった人に対する「母子福祉年金」等がありました。
「福祉年金」とは無拠出制であることがポイント。費用は全額国庫負担で賄われていたことをしっかりおさえておけばOKです。
ついでに過去問も解いてみましょう。
<平成19年出題>
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【答】×
無拠出制の福祉年金の給付は昭和34年10月ではなく、昭和34年11月に給付が開始されました。
社労士受験のあれこれ
年金教室第3回目
H28.9.16 年金教室3 国民年金の誕生その1
拠出制の国民年金法がスタートしたのは「昭和36年4月1日」です。
この年号は重要なのでしっかり覚えましょう。(ちなみに昭和36年の流行語に、「巨人大鵬卵焼き」というのがあるそうです。)
★厚生年金や共済年金は既に存在していた★
会社員には「厚生年金」、公務員には「共済年金」があり、会社員や公務員には既に年金制度がありましたが、農林水産業に従事している人や自営業者のための年金制度はありませんでした。
★自営業者などには年金がなかった★
厚生年金や共済年金でカバーできない農林水産業従事者や個人商店の店主等のために作られた年金制度が「国民年金」です。
★国民皆年金★
拠出制の国民年金が開始されたのが「昭和36年4月」です。これで、会社員や公務員以外の全国民が年金制度に加入することになりました。このことを「国民皆年金」といいます。
★保険料と給付★
ちなみに、昭和36年当時の保険料は月100円(35歳以降150円)で、40年加入した場合の年金額は3500円だったそうです。(平成23年厚生労働白書より)
社労士受験のあれこれ
年金教室第2回目
H28.9.12 年金教室② 「厚生年金保険」の誕生
年金教室第1回目では、船員のための年金(船員保険)が昭和14年に創設されたことを勉強しました。
第1回目はコチラからどうぞ→年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?
今日は、厚生年金保険法の始まりをお話しします。

★「労働者年金保険法」
現在の厚生年金保険は「労働者年金保険法」という名称で、昭和16年に制定されました。対象は工場で働く男子労働者でした。(平成23年版の厚生労働白書によると制定当時は「産業戦士の恩給制度」とも呼ばれていたそうです。)
★「厚生年金保険」へ
厚生年金保険と名称が改められたのは昭和19年です。その際に、事務職員や女子労働者にも適用されるようになりました。

厚生年金保険(労働者年金保険法)が制定されたのは、75年も前なのです。
社会も激変しました。
戦後 → 高度経済成長 → 安定成長 → 少子高齢化社会と、社会情勢の変化に伴って年金制度も改正が繰り返されています。
社労士受験のあれこれ
年金教室 第1回目
H28.9.7 年金教室① 「社会保険方式」の一番古い公的年金は?
今日から年金教室を始めます。
年金制度は生活や経済に密着しているものなので、社会の変動に合わせて、改正が繰り返されています。そして改正のたびにどんどん複雑に難しくなってしまい、勉強しないといけないことが増える一方です。
そんな年金ですが、少しでも勉強が楽になるよう、今日から「年金教室」と題しまして、基本事項からちょっと難しいところまで、解説していきます。年金はわかると面白いです!
「年金教室」は不定期に書いていきます。どうぞよろしくお願いします!
今日のタイトルは、「「社会保険方式」の一番古い公的年金は?」です。

まず、「保険」とは、保険料を負担することによって給付が受けられる制度で、社会保険というのは、国が責任をもって運営している保険という意味です。
★★「保険」とは、保険料を負担すればいざというときそれに応じた給付が受けられるもの。もし保険料を払わなかった場合は、給付が受けられなくなる可能性もある、ということ。
健康保険などの医療保険、年金、介護保険、雇用保険などは「社会保険」方式で運営されています。
例えば、「年金保険」の場合は、老齢、障害、死亡というリスクに備えて保険料を払う(強制加入)。そして実際に老齢(65歳)になると、保険料を払った期間等に応じた年金が支払われるという仕組み。
さて、日本で一番古い「社会保険方式」による公的年金は「船員保険」です。
船員保険の創設は昭和14年です。
戦時体制下で船員の確保が必要だったからだそうです。(平成23年版厚生労働白書より)
当時の船員保険は、年金だけでなく、「健康保険相当部分(職務外の疾病部門)」「労災相当部分(職務上疾病・年金部門)」「雇用保険相当部分(失業部門)」の分野もカバーする総合保険でした。
しかし、被保険者数の減少や高齢化等のため財政が悪化し、基礎年金制度が始まった昭和61年4月に船員保険の年金部門は、厚生年金保険に統合され、船員保険から年金部門はなくなりました。
★ちなみに、「労災相当部分」、「雇用保険相当部分」は、平成22年1月に、「労災保険法」、「雇用保険法」に統合されました。
★現在の船員保険は、「健康保険相当部分」と「船員独自の上乗給付」を行っています。
過去問もチェック!
① H16年出題
船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。
② H22年出題
船員保険法は大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。
【解答】
① H16年出題 ○
② H22年出題 ×
大正14年ではなく昭和14年制定。
「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。
社労士受験のあれこれ
H28年度選択式を解きました。その5(年金編)
H28.9.6 平成28年度選択式(年金編)~次につなげるために~
平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。
★労基・安衛編はコチラから。
→ H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
★労災・雇用編はコチラから。
→ H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~
★一般常識編はコチラから。
→ H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~
★健康保険編はコチラから
→ H28.9.5 平成28年度選択式(健康保険編)~次につなげるために~
ラストは、厚生年金保険法・国民年金法です。
<厚生年金保険法>
【A】、【B】、【C】
60歳台後半の在職老齢年金の問題です。
最初は数字を入れる問題?と思いましたが、用語を入れる問題でした。
選択肢に似たような用語が並んでいるので、きっちり覚えていないと選ぶのが大変なところです。
在老の問題は、毎年のように出題されますが、今年のように「用語」に焦点を当てるパターンは珍しいです。この問題を見て、条文を読んで重要用語をおさえていくことも必要だと思いました。
【D】、【E】
「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置」からの出題です。
【D】については、平成23年の国民年金法の選択式で同じ個所が出題されています。(やはり繰り返されています。)
【E】も頻出事項です。まぎらわしい選択肢もなかったので、できた方が多かったと思います。
<国民年金法>
【A】、【B】
目的条文からの出題です。
「社労士受験のあれこれ」でも取り上げました。
こちらからどうぞ。 → H28.8.2 目的条文のチェック(社会保険編)
【C】
保険料の免除期間の問題です。
例えば、平成26年10月分の保険料の納付期限は平成26年12月1日(月)です。(平成26年11月30日が日曜日のため)。
平成26年10月分の保険料の免除を受けるには、平成26年12月1日から2年後の平成28年12月1日までの免除申請をすることになります。
★通常は翌月末日が納付期限ですが、曜日の関係で納付期限が翌月になる場合もあります。そのようなときは、2年2カ月前までが免除の対象になります。
【D】、【E】
財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任についての問題です。
難しいです・・・。
ここまでチェックしていた方はすごい!と思います。
平成28年度の選択肢の検証はこれで終わります。
択一式についても、ボチボチ検証していきたいと思っています。
社労士受験のあれこれ
「国民年金法」の選択対策
H28.8.25 「国民年金」の選択対策
あと2日。
もうゴールが見えてきました。
今日は、国民年金法の選択問題です。
(用語の定義)
この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び< A >をいう。
この法律において、<「 A 」>とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は< B >をいう。
(基礎年金拠出金)
1 厚生年金保険の< C >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 < D >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 < E >が作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の< C >が負担し、又は< D >が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

(用語の定義)
A 実施機関たる共済組合等 B 日本私立学校振興・共済事業団
(基礎年金拠出金)
C 実施者たる政府 D 実施機関たる共済組合等 E 財政の現況及び見通し
社労士受験のあれこれ
【直前】「国民年金法」の選択対策
H28.8.19 直前!「国民年金法」の選択対策
まだまだ、巻き返しできます!
がんばりましょう。
今日は国民年金法の選択問題です。
<平成28年度・保険料額と保険料率>
◆ 平成28年度の保険料の額は、法律に規定された額(< A >円)に保険料改定率を乗じて得た額(その額に< B >円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< B >円以上< C >円未満の端数が生じたときは、これを< C >円に切り上げるものとする。)とする。
◆ 平成28年度の保険料改定率は< D >となったため、平成28年度の保険料額は< E >円となっている。
◆ なお、平成28年度の保険料改定率は、前年度(平成27年度)の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の2年前の< F >変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の< G >変動率(3年前から5年前のものの3年平均)で算出されている。

【解答】
A 16,660 B 5 C 10
D 0.976 E 16,260
※平成28年度の保険料額 → 16,660円×0.976≒16,260円
F 物価 G 実質賃金
※ 保険料改定率は前年度の保険料改定率×「名目賃金変動率」で改定されます。(「名目手取り賃金変動率」ではないので注意してくださいね。)
■■名目賃金変動率 = 2年前の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(健保・国年・厚年)
H28.8.2 目的条文のチェック(社会保険編)
いよいよ8月です!
8月の頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(社会保険編)です。
目的条文のチェック(労働編)はコチラです。
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその< A >の< B >以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< C >に寄与することを目的とする。
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第< A >項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて< B >の安定がそこなわれることを国民の< C >によつて防止し、もつて健全な< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその< A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。

<解答>
【健康保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者又はその<A 被扶養者>の<B 業務災害>以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と<C 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
ココもポイント!
第2条(基本的理念)のキーワードもチェックしておきましょう。
コチラをどうぞ → H28.3.12 健康保険基本的理念のキーワード
【国民年金法】
(第1条 目的)
国民年金制度は、日本国憲法第25条第<A 2>項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて<B 国民生活>の安定がそこなわれることを国民の<C 共同連帯>によつて防止し、もつて健全な<B 国民生活>の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(第2条 国民年金の給付)
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
★ 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項の理念に基づいています。第25条第1項ではありませんので注意してくださいね。
★★憲法も見ておきましょう。
第25条(国民の生存権、国の社会保障的義務)
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
【厚生年金保険法】
(第1条 目的)
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその<A 遺族>の生活の安定と<B 福祉の向上>に寄与することを目的とする。
★厚生年金保険は「保険給付」といいますが、国民年金は「給付」で保険給付とはいいません。
この違いについてはコチラ → H28.1.28 国民年金と厚生年金保険の違い
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その2
H28.7.29 金曜日は横断 (不服申し立て その2)
金曜日は「横断」です。
今週は、「不服申し立ての横断整理その2」で、テーマは「処分の取消しの訴え」です。
その1はこちら → 「審査請求」と「再審査請求」の期限
厚年一元化に伴う改正点はこちら → H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
※雇用保険の解答を修正しました。(H28.8.1)
では問題です。空欄を埋めてください。
【労災保険法】
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【健康保険法】
ⅰ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
ⅱ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
Ⅲ < A >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<A>に入るのは次のどちらでしょう?
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分
【国民年金法】
ⅰ 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ ⅰに規定する処分(< B >(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<B>に入るのは次のどちらでしょう。
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分
【厚生年金保険法】
ⅰ 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
ⅲ < C >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<C>に入るのはどちらでしょう?
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分

【解答】
【労災保険法】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<労働者災害補償保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、労働者災害補償保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<雇用保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「①確認、②失業等給付に関する処分、③不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴え」をするには、雇用保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
※審査請求と雇用保険審査官が入れ替わっていましたので訂正しました。(H28.8.1)
【健康保険法】
<A>には、「① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることが可能です。
【国民年金法】
<B>には、「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分」が入ります。
★「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)」について処分取消しの訴えをするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」については、社会保険審査官に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
【厚生年金保険法】
<C>には、「① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その1
H28.7.22 金曜日は横断 (不服申し立て その1)
金曜日は「横断」です。
今週から、「不服申し立て」の横断整理に入ります。(何回かに分けてUPします。)
今週は、「審査請求」と「再審査請求」の期限を整理しましょう。
以下の問題の空欄を埋めてください。
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して < >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
<参考>
次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
| 1 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合審査会 |
| 2 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合審査会 |
| 3 第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 |

<解答>
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から <3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して<3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、脱退一時金に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
ポイント!
★労災保険・雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険 <共通>
審査請求 → 3カ月
再審査請求 → 2カ月
★労災保険・雇用保険
棄却したものとみなす → 3カ月
★健康保険・国民年金・厚生年金保険
棄却したものとみなす → 2カ月
社労士受験のあれこれ
選択対策/国民年金法(障害基礎年金)
H28.7.20 水曜日は選択式対策!(国民年金法)
今週は国民年金法です。
テーマは障害基礎年金の額の改定です。
それでは問題です。下の選択肢から選んでください。
1 < A >は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、< A >に対し、障害の程度が< B >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 第2項の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が< B >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は第1項の規定による< A >の診査を受けた日から起算して< C >でなければ行うことができない。
『選択肢』
① 6か月を経過した日以後 ② 変更 ③ 固定 ④ 1年を経過した日後⑤ 変化 ⑥ 市町村長 ⑦ 増進 ⑧ 保険者 ⑨ 1年6か月を経過した日後 ⑩ 1年を経過した日以後 ⑪ 厚生労働大臣 ⑫ 実施機関

【解答】
A ⑪ 厚生労働大臣 B ⑦ 増進 C ④ 1年を経過した日後
障害の程度が重くなったり軽くなったりした場合は、年金額が改定されます。
★第1項は厚生労働大臣の職権による年金額の改定です。
★第2項は障害の程度が増進した場合、受給権者から改定請求ができるという規定です。 (増進したということは年金額が増えるということ)
◆増進による改定請求のポイント
① 1年を経過した日「以後」ではなく 、1年を経過した日「後」
② 障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は1年以内でも請求できる。
ついでに、次の問題も解いてみましょう。
【問題】
障害基礎年金の受給権者が行う改定請求は、受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して1年を経過した日から行うことができる。(障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)

【解答】×
受給権者から改定請求ができるのは、原則として1年を経過した「日後」からです。1年を経過した日からではありません。
社労士受験のあれこれ
【横断】資格取得届
H28.7.15 金曜日は横断 (資格取得届)
金曜日は「横断」です。
(2日遅れの更新で申し訳ないです。)
今週は、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法の「資格取得届」でよく出るところを横断的に整理しましょう。
※ ちなみに、労災保険法には「資格取得届」はありません。
では、問題です。
【雇用保険法】
① 事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日から10日以内に、雇用保険被保険者資格取得届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
【健康保険法】
②(平成22年出題) 事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。
【国民年金法】
③(平成20年出題) 第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。
④ 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。
【厚生年金保険法】
⑤ 法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から10日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届又は当該届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとする。

【解答】
【雇用保険法】
① ×
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、「当該事実のあった日の属する月の翌月10日まで」です。
【健康保険法】
②(平成22年出題) ×
①新規適用事業所の届出と②被保険者の資格取得の届出は5日以内ですが、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出は、「速やかに」です。
★健康保険法の事業主の行う届出の提出期限は原則として「5日以内」です。
「5日以内」ではないものを覚えていくのがポイントです。
★提出期限が「速やかに」の届出
「報酬月額の変更の届出(随時改定)」、「育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出」、「産前産後休業を終了した際の報酬月額の変更の届出」
【国民年金法】
③(平成20年出題) ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、資格取得届ではなく「種別変更届」を提出しなければなりません。(期限は14日以内、提出先は市町村長です。)
④ ○
第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出の経由先について
・ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者の場合 → その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由(経由の事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる)
・ 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者の場合 → その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由
【厚生年金保険法】
⑤ ×
当該事実があった日から10日以内ではなく「5日以内」です。(船員被保険者は10日以内)
※ 法第27条は第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者については、適用されません。
社労士受験のあれこれ
国民年金法<保険料納付済期間の定義>
H28.7.14 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(国民年金)
今週は、「保険料納付済期間」の定義を確認しましょう。
国民年金法第5条
「保険料納付済期間」とは、次の3つを合算したもの
① 第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料に係るもの ⅰ 督促及び滞納処分の規定により徴収された保険料を含む ⅱ 保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く |
| ② 第2号被保険者としての被保険者期間 |
| ③ 第3号被保険者としての被保険者期間 |
第1号被保険者のポイント!
第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者の中で、国民年金の保険料を負担する義務があるのは第1号被保険者のみです。
そのため、第1号被保険者は、全額きっちり納付した部分が「保険料納付済期間」となります。
<一部免除の部分> 例えば半額免除については、免除された半額以外の半額を納付した場合は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間に入ります。(表のⅱの部分)
<追納した場合> 保険料の免除を受けていた期間でも、追納した場合は、保険料納付済期間になります。
第2号被保険者・第3号被保険者のポイント!
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料を負担する義務がないので、(ということは滞納もあり得ないので)、第2号被保険者期間、第3号被保険者期間は、原則として、その期間がまるごと保険料納付済期間となります。
ここもチェック・基礎年金の給付の費用
・第1号被保険者 → 自分で直接国民年金に保険料を納付する
・第2号被保険者、第3号被保険者 → 第2号被保険者、第3号被保険者の基礎年金の給付に充てる費用として「基礎年金拠出金」という名前でまとめて厚生年金保険から国民年金にお金が送られている
問題を解いてみましょう!
問題①H24出題
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
問題②H24年出題
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
問題③H23年出題 (老齢基礎年金の合算対象期間について)
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間は、合算対象期間とされる。
問題④H24出題
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

問題①H24出題 ○
督促及び滞納処分により保険料が納付された期間も保険料納付済期間になります。
問題②H24年出題 ○
例えば、次のように用語をあてはめて考えてみてください。
保険料納付済期間には、保険料の一部免除(4分の3免除)の規定により、その一部の額(4分の3)につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額(4分の1)が納付又は徴収されたものは含まない。 → 保険料納付済期間ではなく「保険料免除期間」(4分の3免除期間)です。
問題③H23年出題 (老齢基礎年金の合算対象期間について) ○
老齢基礎年金の保険料納付済期間には、第2号被保険者としての20歳未満・60歳以上の期間は、入りません。
なぜなら、老齢基礎年金は第1号被保険者の基準(20歳以上60歳未満)に合わせて作られていて、20~60歳の40年で満額となるからです。
そのため、第2号被保険者の20歳未満・60歳以上の期間は、合算対象期間(カラ期間)として扱われます。(受給資格期間の25年には入る・老齢基礎年金の年金額の計算には入らない)
問題④H24出題 ×
障害基礎年金は、老齢基礎年金とは違いフルペンション方式ではないので、第2号被保険者の20歳前の期間及び60歳以降の期間も保険料納付済期間となります。(遺族基礎年金も同じ)
社労士受験のあれこれ
国民年金法/平成28年度保険料と年金額
H28.6.22 水曜日は選択式対策/国民年金法
今週は国民年金法です。
① 保険料 (平成19年出題(改))
国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成28年度に属する月の月分は< A >円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の< B >年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)とされている。平成28年度の保険料改定率は< C >である。
② 平成28年度の年金額
老齢基礎年金の額(満額)は、780,900円に改定率を乗じて計算する。
改定率は、毎年度改定され、新規裁定者(68歳到達年度前)は< D >に調整率を乗じて得た率を基準として改定し、既裁定者(68歳到達年度以後)は< E >に調整率を乗じて得た率を基準として改定される。
平成28年度年金額改定に係る< D >がマイナス0.2%、< E >がプラス0.8%、マクロ経済スライド調整によるスライド調整率はマイナス0.7%となり、 < D >がマイナス、< E >がプラスとなっているため、改定率は、新規裁定者及び既裁定者ともに「1」を基準として改定される。そのためマクロ経済スライド調整も行われない。
平成28年度の年金額の改定率は、平成27年度と同じ< F >となった。

<解答>
① 保険料 (平成19年出題(改))
A 16,660 B 2 C 0.976
★ 平成28年度保険料改定率=前年度の保険料改定率×名目賃金変動率
平成28年度の保険料= 16,660円×0.976 ≒ 16,260円
(端数処理 → 5円未満は切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ)
② 平成28年度の年金額
D 名目手取り賃金変動率 E 物価変動率 F 0.999
★ 平成28年度年金額改定の仕組みはこちらの記事をどうぞ → H28年度年金額
★ 平成28年度の老齢基礎年金の満額は、780,900円×0.999 ≒ 780,100円
(端数処理 → 50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

ここもポイント!
保険料改定率は「名目賃金変動率」、新規裁定者の改定率は「名目手取り賃金変動率」が基準となります。名称が似ているので間違えないようにしましょう。
「名目賃金変動率」
= ①2年前の物価変動率×②4年前の年度の実質賃金変動率
「名目手取り賃金変動率」
=①前年の物価変動率×②3年前の年度の実質賃金変動率×③3年前の年度の可処分所得割合変化率
社労士受験のあれこれ
条文を読むと分かることもある/国民年金
H28.6.9 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(国民年金)
◆◆なんとなくモヤ~っとしていることも、条文を読むとパーッとすっきりすることがあります。
分からないと思ったら、基本に戻って条文を読んでみるのも効果があるかもしれません。
◆◆まず、「基本権」と「支分権」の違いを確認しましょう。
基本権は「年金を受ける権利」、支分権は「年金の支給を受ける権利(2カ月に1回年金を受け取る権利)」です。
◆◆老齢基礎年金の「基本権」は、以下の要件を満たすと自動的に発生します。(法第26条)
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
★老齢基礎年金の受給権は、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が25年以上ある(原則)、65歳に達した、という条件が揃えば自動的に発生します。(基本権)
ただし、実際に2カ月に1回の年金を受ける(支分権)ためには、要件が満たされているという確認を受けるために、「裁定請求」が必要です。
◆◆「繰上げ支給の老齢基礎年金」の場合は、自動的ではなく「請求」によって基本権が発生することがポイントです。(附則第9条の2)
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
原則として、保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて25年以上ある場合は、65歳に達すれば自動的に受給権が発生しますが、「早く受けたい」という人は60歳~64歳の間に老齢基礎年金の繰上げ請求をすることができます。繰上げの場合、「請求すること」によって基本権が発生します。
◆◆65歳に達したときは「支給する」(第26条)となっていますが、繰上げの場合は「請求することができる」(附則第9条の2)となっていますよね。
60~64歳の間に自動的に老齢基礎年金の基本権が発生することはなく、繰上げの「請求」によって受給権が発生するということです。
老齢基礎年金の繰上げを請求した場合は、「請求があった日」に受給権が発生(基本権)し、その翌月から実際に年金が支払われます。
◆◆ついでに
障害基礎年金も同じように読んでください。
第30条の通常の障害基礎年金は、初診日、保険料納付要件、障害認定日の3つの要件を満たせば、当然に受給権が発生します。
一方、事後重症の場合は、「請求できる」と規定されていて、請求することにより受給権が発生します。
では、次の問題を解いてみましょう。(H18年出題)
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
【解答】○
「請求することによって」の部分がポイント。事後重症は請求によって受給権が発生します。
ただし、請求しなくても「請求があったものとみなして」支給される例外もあります。この話はまた後日。
社労士受験のあれこれ
横断 国民年金と厚生年金保険の時効
H28.6.3 金曜日は横断 /国年と厚年
国民年金法、厚生年金保険法の時効として「2年」と「5年」があります。
国民年金と厚生年金保険の違う点を意識してください。
では、まず国民年金法から。
(国民年金法)
(時効)
年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
<問題 H18年出題>
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
【解答】 ×
「給付」を受ける権利ではなく「年金給付」を受ける権利の時効は5年です。
★★注意しましょう★★
国民年金の「給付」は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金。「給付」の内容には「年金」と「一時金」があります。
「給付」と「年金給付」では範囲が違うことに注意してください。
給付のうち、「年金給付」の時効は5年、「死亡一時金」の時効は2年です。
次は厚生年金保険です。
(厚生年金保険法)
(時効)
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む。)は、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
<問題 H23年出題>
保険給付を受ける権利は、5年を経過したとき、時効により消滅する。
【解答】 ○
★★ポイント★★
「保険給付」を受ける権利の時効は5年です。「保険給付」ですので、年金も一時金も両方とも時効は5年です。
<国年と厚年の時効の比較>
| 2年 | 5年 | |
| 国民年金法 | 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利 死亡一時金を受ける権利 | 年金給付を受ける権利 |
| 厚生年金法 | 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利 | 保険給付を受ける権利 |
科目別 国民年金法
科目別 厚生年金保険法
社労士受験のあれこれ
シリーズ振替加算 その5(最終回)
H28.5.24 振替加算相当額の老齢基礎年金
シリーズ振替加算その5です。
最終回は、「振替加算相当額の老齢基礎年金」です!
さて、老齢基礎年金の受給資格は、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あることです。ただし、25年の計算には入るけど、老齢基礎年金の額の計算には入らない期間がありますよね。
学生納付特例期間、30歳未満の納付猶予期間、合算対象期間は、受給資格の有無の25年を見るときには入りますが、老齢基礎年金の額には反映しません。
例えば、合算対象期間と学生納付特例期間のみで25年を満たした人の場合は、老齢基礎年金の受給資格はあるけれど、老齢基礎年金の額としてはゼロになります。
そして、そのような人が、「振替加算」の要件に該当している場合は、「振替加算相当額のみの老齢基礎年金」が支給されるのです。

では、代表的な問題を2つ解いてみましょう。
① H20年出題
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。
② H17年出題
振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間が1年未満であり、合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には、振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される。

【解答】
① H20年出題 ○
合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年で、「それ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間」というのがポイント。この場合の老齢基礎年金はゼロになってしまいますが、振替加算の要件に該当している場合は振替加算と同額の老齢基礎年金が支給されます。
② H17年出題 ×
例えば、保険料納付済期間が1月でそれ以外はすべて合算対象期間で受給資格を満たした場合は、1月で計算した老齢基礎年金とそれに振替加算が加算されます。振替加算の額のみの老齢基礎年金ではありません。
社労士受験のあれこれはこちら
【改正】国民年金法/選択対策
H28.5.22 基礎年金拠出金の負担と納付
被用者年金一元化に伴って、国民年金法の用語も改正されています。
次の空欄を埋めてみましょう。
国民年金法第5条(用語の定義)
8 この法律において、「政府及び実施機関」とは、厚生年金保険の A 及び B をいう。
9 この法律において、「 B 」とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、 C 又は D をいう。
国民年金法第94条の2 (基礎年金拠出金)
1 厚生年金保険の A は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
2 B は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。
3 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の A が負担し、又は B が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

【解答】
A 実施者たる政府 B 実施機関たる共済組合等
C 地方公務員共済組合連合会 D 日本私立学校振興・共済事業団
■■ちなみに「基礎年金拠出金」とは?
第2号被保険者・第3号被保険者の「基礎年金」の費用のために、実施者たる政府と実施機関たる共済組合等が負担(納付)するもの。
★国民年金第2号被保険者(厚生年金被保険者)と第3号被保険者は、国民年金に保険料を納付する義務はありませんが、第2号被保険者・第3号被保険者にも老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金は支給されますよね?基礎年金拠出金はその費用に充てるためのものです。
社労士受験のあれこれ
国年と労災保険 併給調整その2
H28.5.21 第30条の4の障害基礎年金と労災保険の調整
併給調整その1はこちら → ★
今日は併給調整その2。労災保険法の年金と国民年金の30条の4の障害基礎年金との調整です。
30条の4の障害基礎年金(20歳前に初診日がある障害基礎年金)は、国民年金に加入前の傷病によって支給されるもので、国庫負担の率が高いので、通常の障害基礎年金とは異なる支給停止事由がありましたよね。
確認してみましょう。
国民年金法第36条の2
第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4 日本国内に住所を有しないとき。
★<原則>上記1号に注目して下さい。
労災保険法の規定による年金を受けることができるときは、労災保険法の年金は全額支給され、「第30条の4の障害基礎年金」は支給停止されます。(同一事由であるかどうかは問われません。)
★<例外>ただし、以下のような例外規定があります。
2 前項第1号に規定する給付(労災保険法の年金)が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 → 労災保険法の年金が全額支給停止されているときは、第30条の4の障害基礎年金は支給停止にならず、支給されます。

では過去問を解いてみましょう。
H25年出題(国年)
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
【解答】 ○
労災保険法の年金が全額支給停止のときは、第30条の4の障害基礎年金は支給されます。

【参考】労災保険法附則第59条、第60条のお話
労災保険法の、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」には「前払一時金」の制度があります。
前払一時金を受けると、一定額までは障害(補償)年金、遺族(補償)年金の支給が停止されます。でも、その場合でも月々の年金をまとめて前払いしているだけで、実際は年金が支給されているのと同じです。
ですので、前払一時金を受けて労災保険の年金が支給停止されている場合は、第30条の4の障害基礎年金は原則どおり支給停止となります。
| 労災保険の年金 | 第30条の4 障害基礎年金 |
| 支給 | 支給停止 |
全額支給停止
| 支給 |
| ※前払一時金を受けたことにより年金が停止される場合 | 支給停止 |
併給調整その3に続きます。
社労士受験のあれこれはこちら
シリーズ振替加算 その4
H28.5.20 振替加算が行われなくなるとき
シリーズ振替加算その4です。
これまで勉強してきたように、専業主婦の年金は旧法と新法で異なります。そもそも振替加算とは、旧法・任意加入→新法・第3号被保険者強制加入という制度の移り変わりで老齢基礎年金が満額にならない人をカバーするためのものです。
ですので、年金が十分に支給される人には、振替加算がつかない場合もあります。
~~ちなみに、旧法で任意加入して保険料を納付した+新法は全て第3号被保険者だった人の場合、老齢基礎年金が満額になりますが、その場合でも要件に合えば振替加算は加算されます。~~
★振替加算が行われないパターン → 妻も厚生年金保険に加入していたことがあり、老齢厚生年金を受けることができるとき
ただし、これは厚生年金保険の被保険者期間が240月以上(中高齢の特例含む)で計算される老齢厚生年金が対象です。
逆に、老齢厚生年金を受けることができる妻でも、厚生年金保険の被保険者期間が原則として240月未満(20年未満)の場合は、振替加算が加算されます。
★振替加算が支給停止されるパターン → 妻が障害基礎年金、障害厚生年金等の給付を受けることができるとき
障害基礎年金等なら保険料納付済期間の月数に関わらず満額支給されますよね。振替加算でカバーする必要がないからです。

では、問題を解いてみましょう!!
① H20年出題(改)
老齢基礎年金の受給権者が、厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受給できる場合は、振替加算は行われない。
② H21年出題
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
③ H21年出題
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、遺族基礎年金を選択した場合であっても、振替加算の加算要件を満たす場合には、当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が加算される。

【解答】
① H20年出題(改) ○
「被保険者期間の月数が240以上」が最大のポイントです。
② H21年出題 ×
障害基礎年金が全額支給停止されている場合は、振替加算は支給停止されません。
昭60法附則第16条では次のように規定されています。
「振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める額を受けることができるときは、その間、振替加算に相当する部分の支給を停止する」
障害を支給事由とする年金を「受けることができるとき」はその間振替加算に相当する部分が停止されますが、障害基礎年金が全額支給停止(受けることができない)の場合は、振替加算は支給停止されません。
◇◇ちなみに、平成21年には次のような問題も出ています。
振替加算が加算された老齢基礎年金を受給している者であって、その者が障害基礎年金等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき(当該障害基礎年金は支給停止されていない。)は、その間当該加算に相当する額が支給停止される。
障害基礎年金等を受給できる(支給停止されていない)とあるので、その間、振替加算は支給停止されます。答えは○です。
③ H21年出題 ×
振替加算は老齢基礎年金に加算されるものです。遺族基礎年金に振替加算額が加算されることはありません。
社労士受験のあれこれはこちら
国年・厚年と労災保険 併給調整その1
H28 .5.18 同一事由で国年・厚年と労災保険から給付を受けられるとき
まず、労災保険、国民年金、厚生年金保険の目的を確認してみるとこんな感じになります。
| 労災保険 | 国民年金 | 厚生年金保険 |
業務上・通勤による 負傷、疾病、障害、死亡等 | 老齢、障害、死亡 (業務上外は問わない) | 老齢、障害、死亡 (業務上外は問わない)
|
例えば、民間企業のサラリーマンが業務上や通勤により死亡した場合は、労災保険と国民年金と厚生年金保険から、遺族に対して遺族年金が支給されることになります。が、すべて100%ずつ支給されるわけではありません。
ポイント!
「同一の事由」で労災保険の年金給付と社会保険(国民年金・厚生年金保険)が支給される場合は、労災保険の年金給付が減額されます。
※社会保険は本人が保険料を負担しているので減額するのは問題ありです。一方、労災保険の保険料は全額事業主負担(本人負担なし)なので労災保険の方を減額しましょうという考え方です。
ということでポイントは
| 「同一事由」による労災保険の年金給付と社会保険(国年・厚年)の調整 |
| 労災保険の年金給付 → 減額支給 |
| 社会保険(国年・厚年) → 全額支給 |

では、問題を解いてみましょう!
① H14年出題(労災)
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金又は遺族年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
② H12年出題(労災)
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることになる。
③ H12年出題(労災)
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。
④ H26出題(国年)
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
⑤ H12年出題(国年)
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

【解答】
① H14年出題(労災) ○
「同一の事由」で社会保険(国年・厚年)の年金と労災保険の年金給付が支給される場合は、労災の年金給付が減額調整されるので○です。
なお、国民年金法の寡婦年金も「死亡」によって支給される年金ですので忘れないでくださいね。
② H12年出題(労災) ○
休業補償給付(休業給付)と厚生年金保険法の障害厚生年金又は国民年金法の障害基礎年金が同一事由で支給されることもあり得ます。その場合は、休業補償給付(休業給付)が減額調整されます。
労災保険は年金給付だけでなく、休業補償給付(休業給付)も減額調整の対象ですので押さえてくださいね。
③ H12年出題(労災) ○
労災保険の年金給付が減額調整されるのは「同一事由」の社会保険(国年・厚年)の年金です。老齢厚生年金・老齢基礎年金と同一事由の労災保険の年金給付はありませんので、同時に受ける労災の年金給付も減額調整されません。
④ H26出題(国年) ○
同一事由で、遺族基礎年金と労災保険法の遺族補償年金を受けることができる場合は、労災保険法の遺族補償年金が減額調整され、遺族基礎年金は全額支給されます。
⑤ H12年出題(国年) ○
労災保険の年金給付との調整と間違えないようにしてくださいね。
併給調整その2に続きます!
社労士受験のあれこれはこちら
シリーズ振替加算 その3
H28.5.16 生年月日で変わる振替加算の額
振替加算は夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額が、妻の老齢基礎年金に振り替わるというイメージですが、加給年金額イコール振替加算の額ではありません。
加給年金額は、224,700円×改定率ですが、振替加算は224,700円×改定率に生年月日に応じて定められた乗率(1.000~0.067)をかけて計算します。
ちなみに、生年月日に応じて定められた乗率が1.000になるのは、大正15年4月2日~昭和2年4月1日までに生まれた妻で0.067になるのは昭和36年4月2日~昭和40年4月1日までに生まれた妻です。
ポイントは、生年月日の若い妻(昭和41年生まれに近づく)ほど、乗率が小さくなることです。
シリーズ振替加算のその1でもお話ししたように、振替加算のモデルは20歳から60歳までずっとサラリーマンの妻(専業主婦)だった人です。
例えば、新法の対象者は大正15年4月2日生まれからですが、大正15年4月2日生まれに近い人ほど、旧法の期間が長い(その当時任意加入していなければカラ期間になる)ため、老齢基礎年金の額が小さくなります。そこをカバーするため、大正15年4月2日に近づくほど振替加算の乗率は乗率は1.000に近づきます。
では、昭和41年4月1日生まれの妻はどうでしょう?昭和41年4月1日生まれの人は昭和61年3月に20歳に達するので、旧法期間は1か月だけです。仮に任意加入しなかったとしても、昭和61年4月からは第3号被保険者ですので、満額に近い老齢基礎年金が支給されます。
とすると、振替加算は少なくてもいいですよね。ですので、乗率は0.067と小さくなります。
大正15年4月生まれに近づくほど旧法が長く(カラ期間が長い)、昭和41年4月1日に近づくほど旧法が短い(第3号被保険者期間が長い)ことをしっかり押さえてください。カラ期間が長い生年月日ほど、振替加算の額も高く設定されています。

では、最後に問題を解いてみましょう。
H18年出題
振替加算の金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額に、老齢厚生年金等の受給権者である配偶者の生年月日に応じて定められた率を乗じた額である。

【解答】 ×
乗率は、老齢厚生年金等の受給権者(夫)の生年月日ではなく、老齢基礎年金の受給権者(妻)の生年月日に応じて定められています。
社労士受験のあれこれはこちら
改正 不服申立 ~国民年金編~
H28.5.14 平成28年4月不服申立改正(国年)
条文を読みながら、改正点をチェックしましょう!
<審査請求>
■国民年金法第101条
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
◆社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条 (審査請求期間)
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
ポイント! 審査請求は3月以内
審査請求できる期間が、60日から3か月に延長され、使いやすくなりました。

<再審査請求>
◆社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条 (再審査請求期間等)
再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。
ポイント! 再審査請求する、しないは「任意」
改正前は、審査請求→再審査請求という流れでしたが、改正後は、再審査請求する、しないは任意となりました。ただし、再審査請求をする場合は、「審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月以内」となっています。
■国民年金法第101条第2項
審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
ポイント!
改正前は、「審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をしすることができる」となっていました。
改正後は、2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができ、そのあとは再審査請求を選択することもできますが、再審査請求をせずに処分取消しの訴えをすることも可能です。

<審査請求と訴訟との関係>
■国民年金法第101条の2
前条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
ポイント! 社会保険審査会の裁決を経なくても処分取消しの訴えができる
改正前は、「処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の採決を経た後でなければ、提起することができない」となっていましたが、改正で、「審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」となり、審査請求に対する社会保険審査官の決定があれば(社会保険審査会へ再審査請求をしなくても)処分取消しの訴えができるようになりました。
ただし、「保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」は、この規定から除外されていて、審査請求しなくても処分取消しの訴えができます。
社労士受験のあれこれはこちら
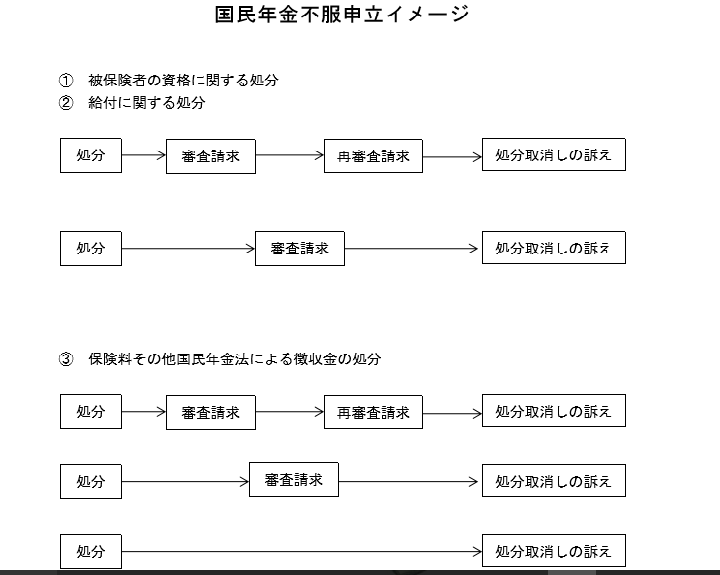
シリーズ振替加算 その2
H28.5.9 振替加算はいつから加算される?
シリーズ振替加算その2です。
その1(振替加算が加算される人の生年月日)はこちら → 振替加算その1
振替加算は老齢基礎年金に加算されるので、妻が65歳に達した日の属する月の翌月から行われます。(原則)
ただし、振替加算の開始時期は条件によって変わります。よく出るところを押さえましょう。
① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合)
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が、当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時、65歳を超えている場合は振替加算の対象とされない。
② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合)
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた場合、振替加算も同時に繰り上げて支給される。
③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合)
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】
① H18年出題(夫よりも妻が年上の場合) ×
夫の老齢厚生年金の受給権が発生した当時に妻が65歳を超えている場合は、夫の老齢厚生年金が支給されるときから、妻の年金に振替加算が加算されます。(夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算される代わりに妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されるイメージ)
② H13年出題(老齢基礎年金を繰上げた場合) ×
老齢基礎年金を繰上げたとしても、振替加算は65歳からです。
③ H21年出題(老齢基礎年金を繰り下げた場合) ×
老齢基礎年金を繰り下げた場合は振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額は増額されません。
社労士受験のあれこれはこちらから
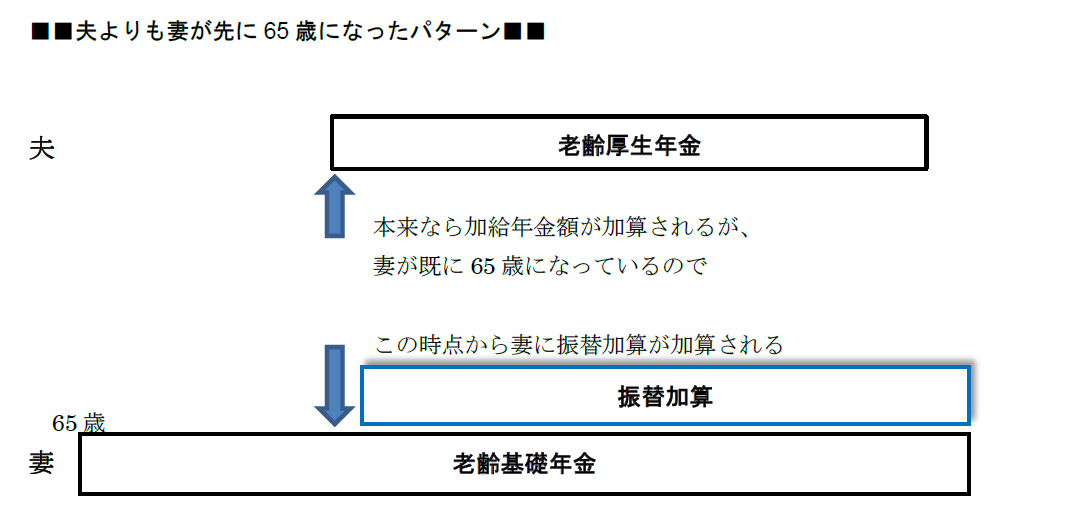
遺族の失権 ~国年・厚年~
H28.5.4 子(孫)の失権の時期■国年・厚年
遺族基礎年金(国年)、遺族厚生年金(厚年)の子、孫(孫は厚年のみ)の失権の時期をチェックしましょう。
ちなみに労災保険の遺族(補償)年金の子、孫、兄弟姉妹の失権時期はこちらから → ★
では、遺族基礎年金の子、遺族厚生年金の子、孫の要件から確認してみることにしましょう。
<国民年金>
子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
<厚生年金保険>
子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
※ ちなみに国民年金法では「障害等級」と表現されますが、厚生年金保険法では「障害等級の1級又は2級」と表現されます。厚生年金保険法の場合、「障害等級」は「1級から3級」までですよね。3級は含まない「1級又は2級」限定という意味です。
子(又は孫)の要件に該当しなくなったときに遺族基礎(厚生)年金の受給権が消滅します。
<国民年金>
① 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
→ 原則は高校卒業の年度末で失権。ただし、そのときに障害状態にある場合は失権しない。
② 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。
→ 障害状態に該当しなくなっても高校卒業の年度末までは失権しない。
③ 20歳に達したとき。
→ 遺族基礎年金は20歳で失権(20歳以降は、本人に30条の4(20歳前にあ初診日がある)の障害基礎年金が支給される)
※厚生年金保険は「子、孫」、「障害等級の1級又は2級」に読み替えてください。

では、問題を解いてみましょう。
①国年H16年出題
遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。
②厚年H22年出題
老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより当該死亡者の子または孫が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、当該子または孫が障害等級の3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①国年H16年出題 ○
被保険者等の死亡当時に障害状態になく、その後障害状態になった場合でも18歳年度末に障害状態にあれば20歳まで遺族基礎年金を受給できます。
比較してみましょう!
労災保険は、死亡当時に障害状態にあれば障害状態にある限り受給できます。違いに注意してくださいね。労災保険はこちら→ ★
②厚年H22年出題 ○
18歳年度末に障害状態(1級又は2級)にあれば20歳まで受給できますが、3級の場合は原則どおり18歳年度末で失権です。
社労士受験のあれこれはこちら
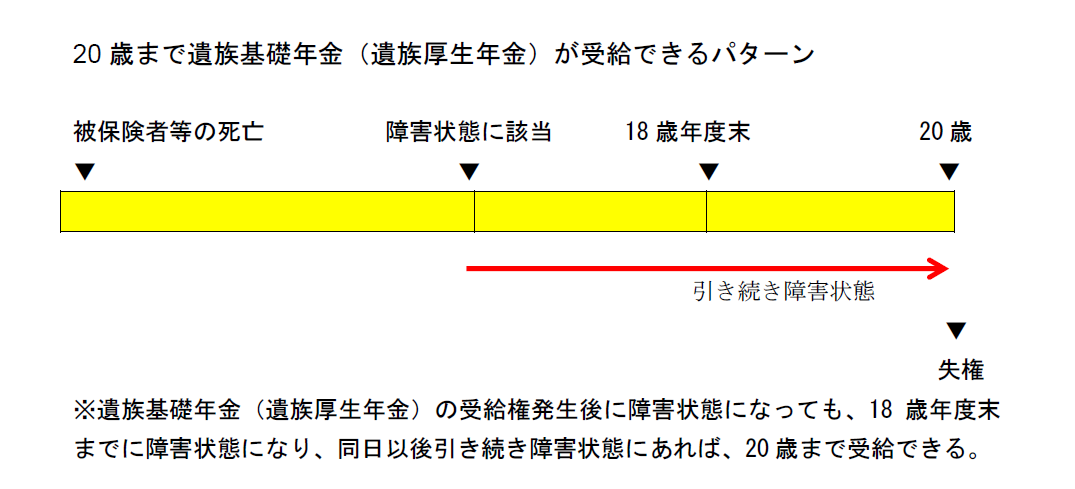
障害基礎年金の支給停止と失権
H28.4.28 2級に該当しなくなったら障害基礎年金はどうなる?
障害基礎年金は、障害等級(1・2級)に該当する程度の障害の状態に該当するときに支給されます。
では、障害が軽くなって1・2級に該当しない程度になった場合、障害基礎年金の受給権はどうなるのでしょうか?
ここでは、「支給停止」と「失権」という用語の違いを意識してください。
支給停止とは → 受給権はあるが事情によって支給が止まっている状態。支給停止事由がなくなれば再開される。
失権とは → 受給権が消滅すること。再開されることはない。
具体的に過去問でチェックしてみましょう。
「2級以上に該当しなくなった場合」
①H18年出題
障害基礎年金は、受給権者が2級以上の状態に該当しない程度の障害に軽快したときは、その間、支給が停止される。
「受給権が消滅する時期について」
②H20年出題
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
ポイント! 2級以上に該当しなくなってもいきなり失権はしない。
①H18年出題 ○
2級以上の状態に該当しない程度の障害に軽快したときは、その間、支給が停止されます。「失権(受給権が消滅)する」ではありません。「支給停止」されているだけですので、また2級以上の状態に該当すれば障害基礎年金の支給が再開します。
ポイント! 受給権は少なくとも65歳までは失権しない。
②H20年出題 ×
※問題文の中の「厚生年金保険法に規定する障害等級」とは1級・2級・3級のことです。国民年金の障害等級は1・2級、厚生年金保険の障害等級は1・2・3級ですので注意してくださいね。
障害基礎年金の受給権は、①3級に該当しない状態のまま3年経過した又は②3級に該当しない状態のまま65歳になった、①か②のどちらか遅い方で失権します。少なくとも65歳までは失権しません。
問題文では、「63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過」となっています。3級に該当しなくなってから3年経過していますが、65歳前ですので、この時点では受給権は消滅しません。
社労士受験のあれこれはこちら
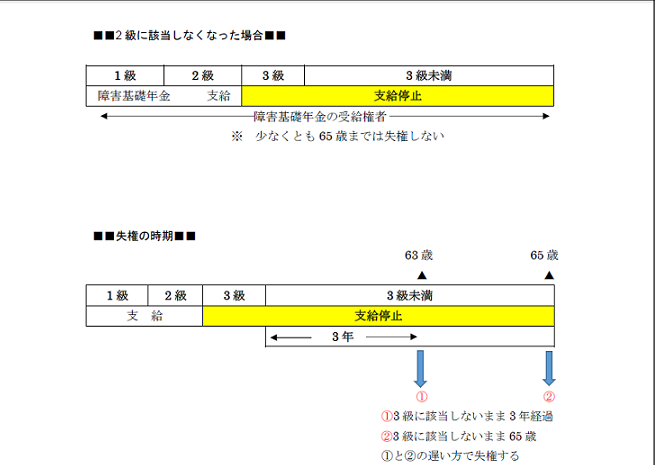
横断 前納(健保・国年)
H28.4.26 健保(任継)・国年の前納比較
健康保険法の任意継続被保険者と国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者含む)には前納制度があります。
比較してみましょう。空欄を埋めてください。
<健康保険法 ・ 任意継続被保険者の保険料の前納>
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
前納された保険料については、前納に係る期間の A ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の B までに払い込まなければならない。
<国民年金法 ・ 前納>
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の C 際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

【解答】
A 各月の初日が到来した B 初月の前月末日 C 各月が経過した

ここもチェック!
→ 割引額は年利4%の複利原価法によって計算される(共通)
→ 前納期間の原則
<健保> 4月~9月まで若しくは10月~翌年3月までの6か月間
4月~翌年3月までの12か月間
<国年> 6月又は年単位
・・・・ただし例外あり。過去問でチェック!・・・・・
(健保 H26年出題)
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
<解答> ○
6月又は12月の間に、
・任意継続被保険者の資格を取得した → 6月間又は12月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間の保険料を前納できる
(例)4月に資格を取得した場合、5月~9月又は5月~翌年3月までの期間で前納可
・資格を喪失することが明らか → 6月間又は12月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料を前納できる
(例)9月に資格を喪失することが明らかな場合、4月~8月までの期間で前納可
(国年 H26年出題)
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(すでに前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。
<解答> ○
社労士受験のあれこれはこちら
シリーズ振替加算 その1
H28.4.25 振替加算が加算される人の生年月日
年金を勉強するときは、「40年間サラリーマンだった夫」と「40年間専業主婦だった妻」をイメージしてみてください。年金制度はそのような夫婦をモデルにして設計されています。
さて、40年間厚生年金保険に加入していた夫には、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」が支給されます。生計維持関係のある妻がいる場合は「加給年金額」もプラスされます。
ところが、あるときに、加給年金額は加算されなくなります。なぜなら、妻が65歳になって老齢基礎年金を受けるようになると、加給年金額が妻の老齢基礎年金に振り替わるからです。
夫に支給されていた加給年金額が姿を変えて妻の老齢基礎年金に加算されることを「振替加算」といいます。(といっても加給年金額と振替加算の額はイコールではありませんので注意)
※ なお、「夫」と「妻」が逆になるパターンでもOKですが、ここでは、サラリーマンの夫と専業主婦の妻で話を進めていきます。
まず、一つ目のポイントは、振替加算が加算される妻の生年月日です。
老齢基礎年金に振替加算が加算されるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日までの間に生まれた者です。
■■大正15年4月1日以前生まれの妻には振替加算は加算されない■■
大正15年4月1日以前生まれの者は、新法の老齢基礎年金ではなく、旧法の対象です。
旧法の考え方は、「専業主婦には年金は支給しない。その代わり夫の老齢年金に加給年金額を加算する」というものです。
加給年金額は通常は65歳未満の配偶者が対象ですが、大正15年4月1日以前生まれの配偶者のについては65歳以上でも加給年金額の対象になるのはそのためです。
ポイント 大正15年4月1日以前生まれの妻の場合は、65歳以降も夫の加給年金額の対象。老齢基礎年金も振替加算も対象外。
■■昭和41年4月2日以降生まれの妻には振替加算は支給されない■■
年金のモデルは「40年間専業主婦だった妻」です。
第3号被保険者制度ができたのは昭和61年4月1日の新法以降です。その前の旧法時代は、専業主婦は任意加入でした。
(第3号被保険者制度のお話はこちらから → 旧法と新法(第3号被保険者))
昭和41年4月2日以降生まれの妻は、20歳以降の期間がすべて新法です。20歳から60歳まで専業主婦なら、40年間第3号被保険者です。それで満額の老齢基礎年金が支給されます。振替加算でカバーする必要はありません。
一方、昭和41年4月1日以前生まれの妻は、昭和61年4月1日に20歳を過ぎているので、旧法時代を経験しています。専業主婦は旧法時代は任意加入でした。20歳から60歳までの間の旧法時代に任意加入しなかった場合は、その分老齢基礎年金がカットされます。振替加算はその部分をカバーするためのものです。
ポイント 昭和41年4月2日以降生まれの妻の場合は、40年間ずっと第3号被保険者の可能性あり。それで満額の老齢基礎年金が保障される。
社労士受験のあれこれはこちら
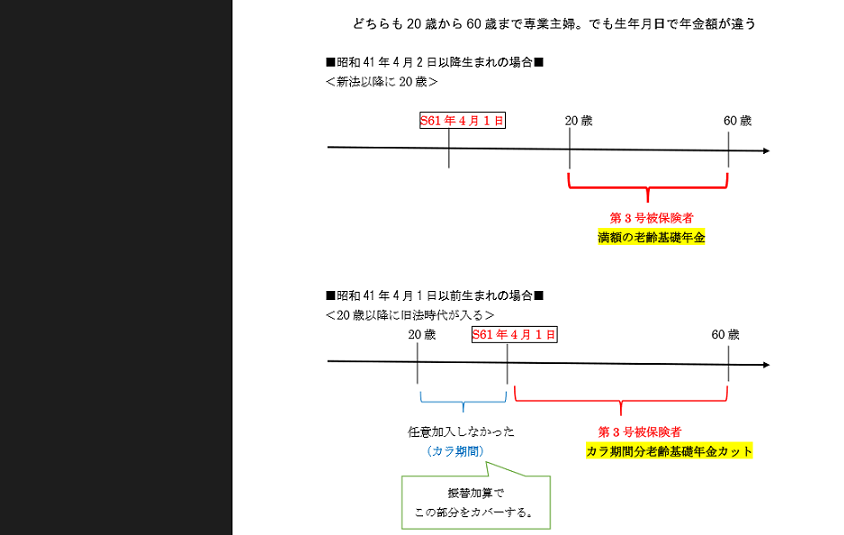
第2号被保険者のポイント
H28.4.23 国民年金第2号被保険者のよく出るところ
厚生年金保険の被保険者のことを国民年金では「第2号被保険者」といいます。
国民年金法第7条第1項第2号で以下のように定義されています。
「厚生年金保険の被保険者を「第2号被保険者」という。」
■■国民年金第2号被保険者は、国民年金(基礎年金・1階部分)と厚生年金保険(2階部分)の2階建てで年金に加入し、年金給付も国民年金(基礎年金)と厚生年金保険の2階建てです。加入も給付も2階建てになることをしっかりイメージしてくださいね。
では、過去問をチェックしてみましょう。
第1号被保険者、第3号被保険者と比較しながら解いてください。
①H15年出題
第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者ともに国籍要件を問わない。
②H15年出題
第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。
③H14年出題
厚生年金保険法の被保険者は、60歳に達した日に、国民年金の被保険者資格を喪失する。

①H15年出題 ○
第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者ともに国籍要件はありません。
②H15年出題 ○
第1号被保険者は「国内に居住していること」が要件ですが、第2号被保険者と第3号被保険者には、国内居住要件はありません。海外転勤になっても第2号被保険者、第3号被保険者のままです。
③H14年出題 ×
第1号被保険者と第3号被保険者は20歳以上60歳未満という年齢要件があるので、60歳に達したときに資格を喪失します。
第2号被保険者には20歳以上60歳未満という年齢要件がないので、60歳になっても国民年金の被保険者資格は喪失しません。
■■60歳以上でも20歳未満でも、厚生年金保険の被保険者なら国民年金第2号被保険者となります。
※なお、65歳以上の被保険者で老齢又は退職を支給事由とする年金給付であって政令で定める給付の受給権がある場合は、65歳以上は国民年金第2号被保険者でなくなります。
比較してみましょう!
社労士受験のあれこれはこちら
第3号被保険者のポイント
H28.4.19 国民年金第3号被保険者のよく出るところ
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
国民年金法では以下のように定義されています。
国民年金法第7条第1項第3号(第3号被保険者の定義)
第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの
ポイント
① 第2号被保険者の配偶者であること
※自営業の夫(第1号被保険者)に扶養される妻は第3号ではなく第1号被保険者
② 20歳以上60歳未満
③ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定について
※健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。(令第4条 )

では、過去問をチェックしてみましょう。
①H27年出題
日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
②H27年出題
18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。
③H17年出題
60歳未満で厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者は、被扶養配偶者であっても、第3号被保険者とならない。
④H27年出題
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
⑤H25年出題
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。

【解答】
①H27年出題 ×
第3号被保険者には、「国内居住」、「国籍」要件は問われません。
設問のように、「日本国内に住所を有しない外国籍の者」でも、20歳以上60歳未満で、第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合は、第3号被保険者になり得ます。
②H27年出題 ○
第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」という年齢要件があります。第2号被保険者に扶養される19歳の配偶者は第3号被保険者にはなりません。その被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者になります。
③H17年出題 ×
「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は、第1号被保険者からは除外されています。が、第3号被保険者の場合は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができても、第3号被保険者となり得ます。
★★第1号被保険者と比較してみてください。★★
④H27年出題 ○
厚生年金保険の被保険者でも「65歳以上」で、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付であって政令で定める給付」の受給権がある場合は、国民年金の第2号被保険者になりません。
設問の場合、仮に「在職老齢年金を受給」している方を夫とすると、老齢年金の受給権がある・年齢が「65歳以上70歳未満」なので、夫は国民年金の第2号被保険者ではありません。
第3号被保険者とは「第2号被保険者の被扶養配偶者」です。設問の妻は、夫が第2号被保険者ではないので、妻は第3号被保険者ではなく、要件に合えば第1号被保険者となります。
⑤H25年出題 ○
「厚生年金保険の高齢任意加入被保険者」だということは老齢年金の受給権がないということ。ですので、70歳以上でも国民年金の第2号被保険者となります。
高齢任意加入被保険者(=国民年金第2号被保険者)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となります。
社労士受験のあれこれはこちら
遺族の範囲
H28.4.17 国民年金の遺族の範囲
国民年金で「死亡」についての給付は、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金です。それぞれ遺族の範囲が違います。チェックしましょう。
【遺族基礎年金】
<遺族の範囲> 被保険者(又は被保険者であった者)の配偶者又は子
| 被保険者(又は被保険者であった者)の死亡当時、死亡した者に生計維持されていた |
配偶者の要件 子と生計を同じくしている |
子の要件(現に婚姻をしていないこと) ①18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(高校卒業の年度末まで) ② 20歳未満で障害等級(1・2級)に該当する障害の状態にある |
【寡婦年金】
<遺族の範囲> 妻(夫に寡婦年金が支給されることはありません)
妻の要件 ①夫の死亡の当時夫に生計維持されていた ②夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続していた ③夫の死亡当時65歳未満 |
【死亡一時金】
<遺族の範囲> 死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
死亡当時、死亡した者と生計を同じくしていた *生計維持ではない |

それでは、過去問で練習してみましょう。
①H16年出題
遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる。
②H23年出題
配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。
③H14年出題
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持され、事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され、子に対する遺族基礎年金は、養子縁組をしていなくても事実上の親子関係にあれば支給される。
④H20年出題
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
⑤H22年出題
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

【解答】
①H16年出題 ○
被保険者の死亡当時に障害等級に該当していなくても、18歳年度末までに障害等級に該当すれば、20歳まで「子」として遺族基礎年金を受給できます。
*遺族厚生年金の「子、孫」も同じ扱いです。
*労災保険法の遺族(補償)年金の子、孫、兄弟姉妹は、国年、厚年とは違う扱いです。(また後日、書きます。)
②H23年出題 ×
配偶者が遺族基礎年金を受けるには、被保険者(又は被保険者であった者)の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、かつ、子と生計を同じくしていたことが要件です。
被保険者の死亡当時に生計を同じくしていなかった子は、年金額の計算には入りません。
(※死亡当時に胎児であった子が出生したときは、死亡当時に生計を同じくしていたとみなされます。)
こちらの問題、誤って〇にしていましたが、解答は「×」です。 令和4年2月28日に訂正しました。 |
③H14年出題 ×
「養子縁組をしていない事実上の親子関係」の場合は、「被保険者又は被保険者であった者の子」には含まれず、遺族基礎年金は支給されません。
ちなみに、
※養子縁組をしている場合は遺族基礎年金が支給されます。
※例えば内縁の妻の連れ子には、遺族基礎年金は支給されません。
④H20年出題 ×
60歳以上65歳未満ではなく、「65歳未満」の妻が対象です。
夫の死亡当時妻が60歳未満でも受給権は発生します。その場合、寡婦年金は、60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。
⑤H22年出題 ×
孫が抜けています。正しくは、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」は他の科目でも出てきますので、順番通りに覚えておきましょう。
社労士受験のあれこれはこちら
国民年金 第1号被保険者のポイント
H28.4.13 国民年金第1号被保険者のよく出るところ
自営業者、学生等は国民年金の第1号被保険者です。
第1号被保険者の定義は以下のとおりです。
(国民年金法第7条第1項1号)
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。)
ポイント
・ 日本国内に住所があること
・ 20歳以上60歳未満
・ 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないこと
・ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者でないこと
では、過去問をチェックしてみましょう!
H22年出題
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができない場合、原則として第1号被保険者となる。
H21年出題
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び第3号被保険者である。

【解答】
<H22年出題> ○
国籍要件はありませんので、外国人でも要件にあえば、原則として第1号被保険者になります。
<H21年出題> ×
国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみで、第2号被保険者とび第3号被保険者は国内居住要件はありません。
例えば会社員が海外転勤などで国内にいなくても、第2号被保険者のまま、また、夫(又は妻)に伴って海外に住む妻(又は夫)も第3号被保険者のままです。

ここもチェック
厚生年金保険法に基づく老齢給付等を「受けることができる」者とは?
例えば、坑内員や船員について早くて55歳から老齢厚生年金を支給する特例がありますよね。
そのように60歳前でも老齢給付等を「受けることができる」場合があります。その場合、もう保険料は納めなくてもよいという意味で、第1号被保険者から除外されます。(強制加入からは除外されますが、任意加入することはできます。)
★★例えば20歳から45歳まできっちり保険料を納めていると、保険料納付済期間が25年になり老齢基礎年金の受給資格は満たしますが、まだ実際に老齢年金は「受けられません」。この場合は、第1号被保険者から除外されず、強制加入です。
横断 国民年金と厚生年金保険の任意加入
H28.4.12 老齢年金の受給権を有しない者の任意加入
国民年金、厚生年金には、老齢年金の受給権のない者の任意加入の制度があります。
国民年金と厚生年金の主な違いは次の点です。
<老齢年金の受給権がない者の任意加入>
| 国民年金(特例任意加入被保険者) | 厚生年金(高齢任意加入被保険者) | |
| 生年月日 | 昭和40年4月1日以前生まれ | 要件なし |
| 年齢 | 65歳以上70歳未満 | 70歳以上 |

過去問でチェックしてみましょう。
<国民年金>H27年出題
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
<厚生年金>H20年出題
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。
<厚生年金>H26年出題
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

<国民年金>H27年出題 ×
昭和30年4月1日以前ではなく「昭和40年4月1日以前」生まれが対象
<厚生年金>H20年出題 ○
<厚生年金>H26年出題 ×
「適用事業所以外」の場合は、厚生労働大臣に申し出ではなく厚生労働大臣の「認可」を受け、「認可があった日」に資格を取得する。
ポイント!
厚生年金・高齢任意加入被保険者は、「適用事業所」か「適用事業所以外」かで違う。どちらの問題なのか確認してから解答しましょう!
| 適用事業所の高齢任意加入被保険者 | 適用事業所以外の高齢任意加入被保険者 |
実施機関に申し出る *事業主の同意はなくてもよい | 厚生労働大臣の認可を受ける 事業主の同意を得る |
| 申出が受理された日に資格を取得 | 認可があった日に資格を取得 |
横断 保険料の納付期限
H28.4.10 健・国年・厚年の保険料納付期限
健康保険・国民年金・厚生年金の保険料の納付期限を整理しましょう。
表は、左から「納付義務者」「納付期限」「負担義務」です。
健康保険
| 事業主 | 翌月末日 | (原則)事業主と被保険者が 2分の1ずつ負担 |
任意継続被保険者 | 当月10日 (初回分は保険者が指定する日) *前納制度あり (前納に係る期間の初月の前月末日) | 全額任意継続被保険者が負担 |
国民年金
第1号被保険者 任意加入被保険者 特例任意加入被保険者 | 翌月末日 *前納制度あり | 世帯主・配偶者の一方は 被保険者の保険料を連帯して納付する義務あり |
厚生年金保険
事業主 当然被保険者 任意単独被保険者 高齢任意加入被保険者 (適用事業書・事業主の同意あり) 高齢任意加入被保険者 (適用事業所以外) | 翌月末日 | 事業主と被保険者が2分の1ずつ負担 |
高齢任意加入被保険者 (適用事業所・事業主の同意なし) | 翌月末日 *前納制度 なし | 全額被保険者が負担 |

過去問で練習してみましょう
<健保H13年出題>
任意継続被保険者は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として保険料を前納することができるが、保険料を前納しようとする場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の1日までに払い込まなければならない。
<健保H15年出題>
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
<国年H18年出題>
毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。
<厚年H21年出題>
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。

【解答】
<健保H13年出題> ×
前納の場合は、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。
<健保H15年出題> ○
任意継続被保険者は、保険料の納付は本人の義務。保険料も本人が全額負担する。
<国年H18年出題> ×
任意加入被保険者も保険料の納付期限は翌月末日。
<厚年H21年出題> ×
適用事業所の高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者も、保険料の納付期限は翌月末日。
国民年金 「法定免除」
H28.4.8 法定免除の要件
国民年金制度には、「法定免除」と「申請免除」があります。
「申請免除」は、被保険者等から「申請」があったとき、「厚生労働大臣の指定する期間」、保険料の全額(又は一部)が免除される制度です。
では、「法定免除」の要件はどうでしょう?
今日は法定免除についてお話しします。
★★法定免除の事由★★
① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
ポイント!
・ 障害等級1・2級の受給権者が対象→1回も1・2級に該当したことがない3級の受給権者は対象外
・ 3級にも該当しないまま3年経過すると法定免除の対象から除外される
| 1級 | 2級 | 3級 | 3級未満 | |
| 障害基礎年金 支給停止 | ||||
| 3年 | 法定免除されなくなくなる | |||
| 法定免除 | ||||
■1・2級の受給権者が3級になっても3級未満になっても、少なくとも65歳までは失権しません。(失権するまでは1・2級の受給権はある)
ただし、3級に該当しなくなってそのまま3年経過した場合は、法定免除の対象から除外され、保険料の免除は行われなくなります。
② 生活保護法による生活扶助等を受けるとき。
ポイント!
・ 生活保護法の「生活扶助以外の扶助」は、「申請免除」の対象
③ 国立ハンセン病療養所、国立保養所等に入所しているとき。
★★法定免除の期間★★
「該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間」
・ 例えば、生活保護法の生活扶助を受けることになった場合は、受け始めた日の属する月の前月から免除されます。
4月に受け始めた場合は3月から免除。(3月の保険料の納付期限が4月末なので。4月はもう生活扶助を受け始めている)
★★手続き★★
法定免除事由に該当するに至ったときは、所定の届書を14日以内に、日本年金機構に提出する。(厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない)
・ 「申請」ではないので注意してください。

ここもチェック!
「納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。」
・ 法定免除される期間でも、本人が「納付します」という申し出をすれば、申出のあった期間の保険料を納付することができます。
「確認」
H28.3.22 健・厚・雇にはあるが、国、労災にはない
厚生年金保険法では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる」と規定されています。(ただし例外有)
健康保険法、雇用保険法にも「確認」について規定があります。
厚生年金保険法・健康保険法・雇用保険法の共通点は、資格の取得や喪失について、事業主に「届出」が義務づけられている点です。
何月何日に誰が入社して、何月何日に誰が退職したのかをチェックするのが確認です。
一方、「国民年金法」、「労災保険法」には確認の規定はありません。
国民年金法、労災保険法には、資格の得喪について事業主からの届出義務はありませんよね。労災保険は、労働者なら誰でも保護が受けられるので、個人ごとに得喪を届け出る必要はありません。
【改正】厚生年金保険法
H28.3.2 保険給付の端数処理
厚生年金保険法第35条です。空欄を埋めてください。
保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に A 未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、 A 以上 B 未満の端数が生じたときは、これを B に切り上げるものとする。

【解答】
A 50銭 B 1円
改正前は50円と100円でしたよね。改正前は100円単位でしたが、改正後は1円単位で裁定、改定されます。
※ 改正後の端数処理は、平成27年10月以後に裁定・改定された保険給付に適用されます。
※ 国民年金法も同様に端数処理方法が改正されています。
※ ただし、老齢基礎年金の満額(780,900円×改定率)などは、50円未満切り捨て50円以上100円未満は100円に切り上げる端数処理(100円単位)です。気をつけてくださいね。
年金制度の歴史
H28.2.29 厚生年金、共済年金、いつからスタートしたの?
平成27年10月より、被用者年金が一元化されています。
一元化された厚生年金、共済年金など、これまでの年金の歴史をおさえておきましょう。
被用者(会社員、船員など)
| 昭和14年 | 船員保険法制定 ・昭和15年6月施行 ・昭和61年4月 厚生年金保険法に統合 |
| 昭和16年 | 労働者年金保険法制定 ・昭和17年6月施行 ・昭和19年 厚生年金保険法に改称 |
被用者(公務員など)
| 昭和23年 | 国家公務員共済組合法制定 ・昭和23年7月施行 |
| 昭和28年 | 私立学校教職員共済法制定(当時の名称は私立学校教職員共済組合法) ・昭和29年1月施行 |
| 昭和37年 | 地方公務員等共済組合法制定 ・昭和37年12月施行 |
自営業者など
| 昭和34年 | 国民年金法制定 ・昭和34年11月 無拠出制スタート ・昭和36年 4月 拠出制スタート |
今日のポイント!
被用者年金(厚生年金、共済年金)のほうが、国民年金よりも歴史が古い。
選択式の練習 ~国民年金法~
H28.2.21 国民年金 財政の現況及び見通しの作成
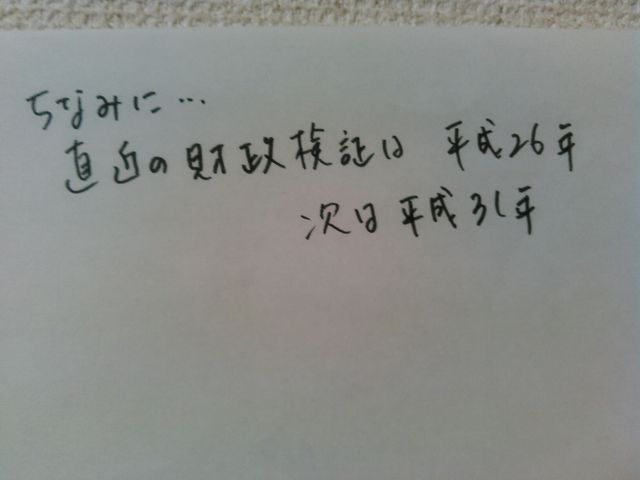
次の空欄を埋めてください。
1 政府は、少なくとも A ごとに、保険料及び B の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
2 1項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね C 間とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】
A 5年 B 国庫負担 C 100年
H28.2.1 平成28年度国民年金保険料
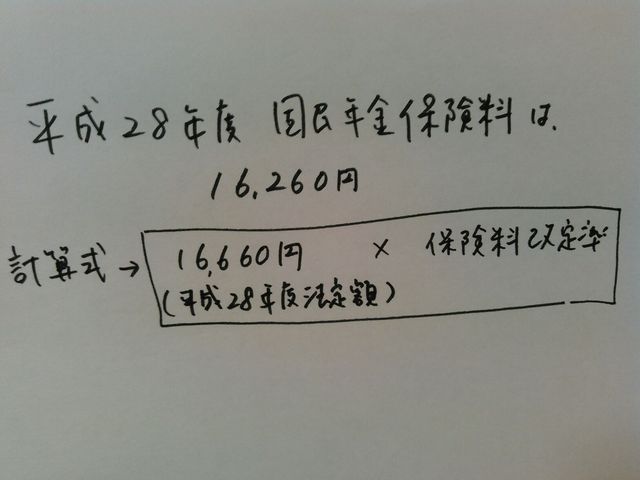
平成28年度の国民年金保険料は16260円です。
まだ2月。数字を暗記する時期ではありません。
平成28年度の国民年金保険料の計算式だけチェックしておきましょう。
平成28年度の国民年金保険料は、
「平成28年度の法定の保険料額(16660円)」×「保険料改定率」で算出されます。
H28.1.31 平成28年度年金額
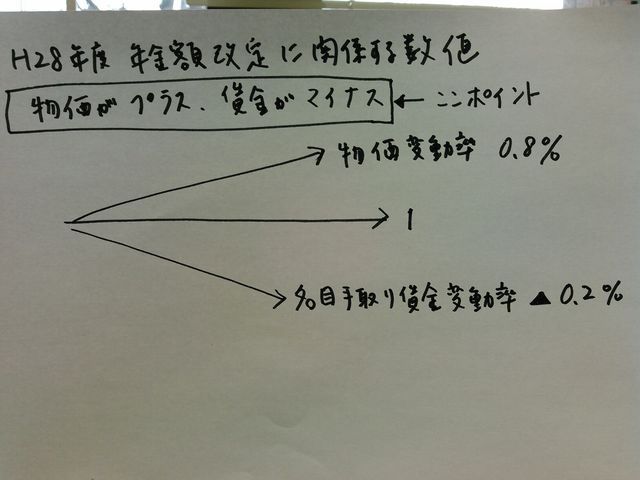
平成28年1月29日、厚生労働省より平成28年度の年金額が発表されました。
平成28年度の年金額は平成27年度と同額になるということです。
物価スライドも賃金スライドも行われません。
スライドの仕組みについては、またお話ししますね。
H28.1.30 「給付」と「年金給付」
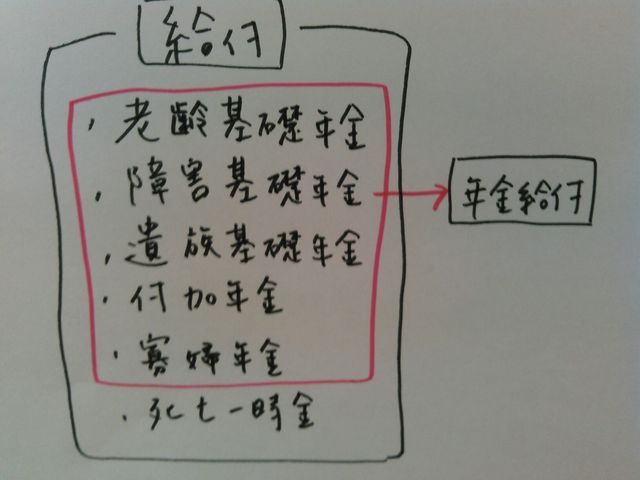
「給付①を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金給付②を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アンダーライン「①給付」と「②年金給付」は範囲が異なります。「死亡一時金」が入るかどうかがポイントです。
まず、国民年金法の「給付」は、
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金、死亡一時金と規定されています。(この中で「年金」ではなく「一時金」で支給されるのは死亡一時金だけですよね。)
ということは「①給付」のように単に「給付」と表現されている場合は、死亡一時金も入っています。
一方、「②年金給付」という表現は年金として給付されるものだけを指しますので、死亡一時金は入りません。
H28.1.28 国民年金と厚生年金保険の違い
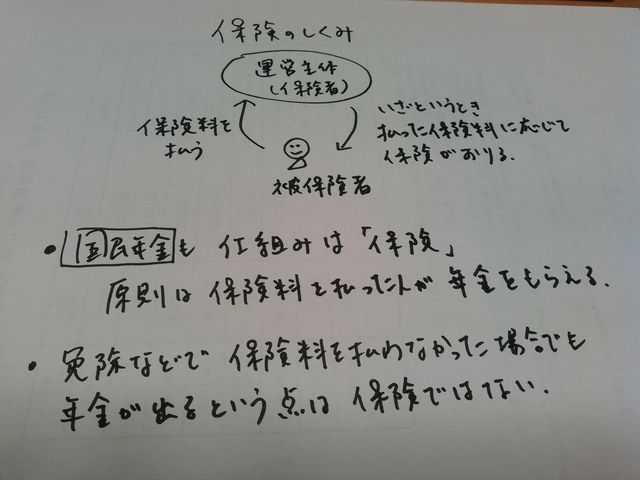
国民年金法と厚生年金保険法という法律の名称。厚生年金保険は「保険」という用語が入っていますが、国民年金は国民年金保険とは言いません。
また、厚生年金は、「保険給付」と言いますが、国民年金は「給付」でやはり保険給付とは言いません。
国民年金法も、原則は、保険料を払った人だけが払った分に応じて年金を受け取る、一方保険料を払わなかった人には年金は出ないという「保険」の仕組みをとっています。
でも、国民年金には、免除などで保険料を払わなかった人に対しても年金が支払われるという面があり、保険ではない部分もあります。
ですので、国民年金保険、保険給付とは言わず「国民年金法」「給付」という用語が使われています。
※とはいっても、国民年金も「被保険者」、「保険料」という用語は使います。国民年金も基本は「保険」です。
H28.1.17 年金額の改定
年金は、日々の生活を保障するために支給されるもの。
国民の生活水準は、上がったり下がったりと変動があります。年金の額も、生活水準が上がればアップ、下がればダウンさせる必要があります。
国民年金法、厚生年金保険法、それぞれに年金額の改定についての規定がありますが、国民年金法と厚生年金保険法で違う点、分かりますか?
<国民年金法>
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
<厚生年金保険法>
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金は「国民の生活水準」ですが、厚生年金保険は「国民の生活水準、賃金」となっていますよね。
厚生年金保険法は「労働者」が対象の年金制度なので、賃金の変動も、年金額の改定に影響します。
また、国民年金は「年金」、厚生年金保険法は「年金たる保険給付」となっています。この違いはまた別の日にお話しします。
H28.1.16 国民年金法と厚生年金保険法の目的条文
国民年金法と厚生年金保険法の目的条文の空欄を埋めてください。
<国民年金法第1条>
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって A 生活の安定がそこなわれることを A の共同連帯によって防止し、もって健全な A 生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
<厚生年金保険法第1条>
この法律は、 B の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、
B 及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国民年金は全国民が対象の年金制度なので、空欄Aには「国民」が入ります。
厚生年金保険は、会社員や公務員など雇われて働く人が対象なので、空欄Bには「労働者」が入ります。
H28.1.10 旧法と新法(第3号被保険者)
■旧法と新法
昭和61年4月1日に全国民共通の基礎年金制度がスタートしました。
基礎年金が導入される前の年金制度を「旧法」、基礎年金が導入された後の現在の年金制度を「新法」といいます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■第3号被保険者は昭和61年4月1日からできた制度
第3号被保険者制度は新法の制度です。
サラリーマンに扶養される妻(妻と夫が逆でも可です)は、昭和61年4月1日以降は第3号被保険者として国民年金に強制加入し、第3号被保険者期間についても保険料納付済期間として扱われるので、要件を満たせば老齢基礎年金も支給されます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■旧法時代のサラリーマンに扶養される妻の年金
では、第3号被保険者制度がなかった旧法時代は、サラリーマンに扶養される妻の年金はどうだったのでしょう?
旧法時代は、サラリーマンに扶養される妻の国民年金への加入は、「任意」でした。老後は夫の老齢年金、夫の死後は遺族年金が支給されるので、あえて妻は強制加入しなくてもいいでしょう、という考え方です。
夫婦が一生連れ添っていればそれでも構いませんが、離婚したり、あるいは事故で障害を負ってしまった場合でも、国民年金に加入していない妻には全く年金が支給されませんでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■制度が変わると年金も少々複雑に
このことは、老齢基礎年金の「合算対象期間」、「振替加算」などを勉強するうえでも大切なポイントになります。
合算対象期間も振替加算も難しくて・・・という声を聞きます。でも、制度の背景が分かるととても面白く分かりやすい箇所なんです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■ポイント
サラリーマンに扶養される妻(20歳~60歳)は、旧法では「任意加入」、新法では第3号被保険者として強制加入