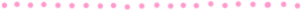合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和5年度版
毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ
(過去記事)
このページは令和5年度版です。
こちらのページは令和5年度試験向けに書いた記事です。
法改正は反映されていませんので、ご注意ください。
令和7年度試験向けの「社労士受験のあれこれ」はこちらからどうぞ。
社労士受験のあれこれ(令和7年度版)
 8月27日(日) 当日です!
8月27日(日) 当日です!
 毎日コツコツ頑張ってきた皆様の合格を祈ります!
毎日コツコツ頑張ってきた皆様の合格を祈ります!
 社会保険 第1条
社会保険 第1条
R5-365
R5.8.27 健保・年金など社会保険 第1条チェック✅
今日は、社会保険の第1条をチェックします。
条文を読んでみましょう。
<健康保険法> 第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
<国民年金法> 第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 |
<厚生年金保険法> 第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
<国民健康保険法> 第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 |
<児童手当法> 第1条 この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。 |
<高齢者の医療の確保に関する法律> 第1条 この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
<介護保険法> 第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 |
<確定給付企業年金法> 第1条 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
<確定拠出年金法> 第1条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
穴埋めでチェックしましょう
★健康保険法
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。
★国民年金法
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを< A >によって防止し、もって < B >に寄与することを目的とする。
★厚生年金保険法
この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及び < A >の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
★国民健康保険法
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって< A >に寄与することを目的とする。
★児童手当法
この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、< A >が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、< B >に資することを目的とする。
★高齢者の医療の確保に関する法律
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< A >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び< B >を図ることを目的とする。
★介護保険法
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< A >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< B >を図ることを目的とする。
★確定給付企業年金法
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< A >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
★確定拠出年金法
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が< A >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
【解答】
★健康保険法
A 福祉の向上
★国民年金法
A 国民の共同連帯
B 健全な国民生活の維持及び向上
★厚生年金保険法
A その遺族
B 福祉の向上
★国民健康保険法
A 社会保障及び国民保健の向上
★児童手当法
A 父母その他の保護者
B 次代の社会を担う児童の健やかな成長
★高齢者の医療の確保に関する法律
A 国民の共同連帯
B 高齢者の福祉の増進
★介護保険法
A 国民の共同連帯
B 福祉の増進
★確定給付企業年金法
A 給付の内容
B 福祉の向上
★確定拠出年金法
A 自己の責任
B 福祉の向上
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働の一般常識 第1条
労働の一般常識 第1条
R5-364
R5.8.26 一般常識(労働編) 第1条チェック✅
今日は、労働の一般常識の第1条をチェックしましょう。
<障害者の雇用の促進等に関する法律> 第1条 この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする。 |
<労働契約法> 第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 |
<男女雇用機会均等法> 第1条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
第2条第1項 (基本的理念) この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 |
<短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律> 第1条 この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
<労働組合法> 第1条 この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |
<社会保険労務士法> 第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2(社会保険労務士の職責) 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。 |
穴埋めでチェックしましょう
★障害者の雇用の促進等に関する法律
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、< A >の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の< B >を図ることを目的とする。
★労働契約法
この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が< A >により成立し、又は変更されるという< A >の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、< B >労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、< C >に資することを目的とする。
★男女雇用機会均等法
この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して < A >の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
★短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて< A >に寄与することを目的とする。
★労働組合法
この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより< A >を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< B >を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。
★社会保険労務士法
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。
【解答】
★障害者の雇用の促進等に関する法律
A 職業リハビリテーション
B 職業の安定
★労働契約法
A 合意
B 合理的な
C 個別の労働関係の安定
★男女雇用機会均等法
A 妊娠中及び出産後の健康
★短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
A 経済及び社会の発展
★労働組合法
A 労働者の地位
B 労働協約
★社会保険労務士法
A 健全な発達
B 福祉の向上
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労基・安衛・労災・雇用 第1条
労基・安衛・労災・雇用 第1条
R5-363
R5.8.25 労基・安衛・労災・雇用 第1条チェック✅
労基法、安衛法、労災保険法、雇用保険法の第1条をチェックします。
条文を読んでみましょう。
労働基準法 第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |
労働安全衛生法 第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 |
労働者災害補償保険法 第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 |
雇用保険法 第1条 (目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (管掌) ① 雇用保険は、政府が管掌する。 ② 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第3条 (雇用保険事業) 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 |
では、穴埋めで確認しましょう
★労働基準法
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
★労働安全衛生法
この法律は、< A >と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >を促進することを目的とする。
★労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の < A >の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< B >の確保等を図り、もって労働者の< C >に寄与することを目的とする。
★雇用保険法
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< B >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< C >を図ることを目的とする。
【解答】
★労働基準法
A 人たるに値する生活
B 基準
★労働安全衛生法
A 労働基準法
B 安全と健康
C 快適な職場環境の形成
★労働者災害補償保険法
A 社会復帰
B 安全及び衛生
C 福祉の増進
★雇用保険法
A 子を養育するための休業
B 職業の安定
C 福祉の増進
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 給付制限
健康保険法 給付制限
R5-362
R5.8.24 健康保険給付制限 最終チェック!
健康保険の給付制限をチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
第121条 保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
③【H22年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部または一部を行わないことができる。
④【H28年出題】
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
【解答】
①【R3年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、『自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき』は、当該給付事由に係る保険給付は、行わない、です。
「重過失」は入りません。
②【H23年出題】 ×
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、『その全部又は一部を行わないことができる』です。
「給付の全部について行わないものとする。」は誤りです。
③【H22年出題】 ×
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、『保険給付の一部』を行わないことができる、です。
「保険給付の全部または一部」は誤りです。
④【H28年出題】 〇
正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の『全部又は一部』を行わないことができる、です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 賃金
労働保険徴収法 賃金
R5-361
R5.8.23 徴収法上の賃金となるもの・ならないもの
徴収法の「賃金」の定義を条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
徴収法上の賃金には、通貨だけでなく、一定の範囲の現物給付も入ります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(労災)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
②【H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
③【H26年出題】(労災)
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金と解することとされており、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含める。
④【H29年出題】(労災)
労働者の退職後の生活保障や在職中の死亡保障を行うことを目的として事業主が労働者を被保険者として保険会社と生命保険等厚生保険の契約をし、会社が当該保険の保険料を全額負担した場合の当該保険料は、賃金とは認められない。
⑤【H29年出題】(労災)
住居の利益は、住居施設等を無償で供与される場合において、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金とならない。
【解答】
①【H29年出題】 〇(労災)
前払退職金は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されます。
※なお、退職を事由として支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等で退職前に一時金として支払われるものは、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しません。
(平成15.10.1基徴発1001001号)
②【H26年出題】 〇(労災)
祝金、見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等で事業主に支給義務があったとしても、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含まれません。
(昭和25.2.16基発127号)
③【H26年出題】 〇(労災)
雇用保険料その他社会保険料の労働者負担分を、事業主が、労働協約等の定めによって義務づけられて負担した場合、その負担額は賃金となり、労働保険料等の算定基礎となる賃金総額に含めます。
(昭和51.3.31労徴発12号)
④【H29年出題】 〇(労災)
会社が全額負担する生命保険の掛金は、賃金になりません。
(昭30.3.31基災1239号)
⑤【H29年出題】 〇(労災)
則第3条で「賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」と規定されていますので、住居の利益は賃金になります。
ただし、問題文のように、住居施設等を無償で供与される場合で、住居施設が供与されない者に対して、住居の利益を受ける者との均衡を失しない定額の均衡手当が一律に支給されない場合は、当該住居の利益は賃金となりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 日雇労働被保険者
雇用保険法 日雇労働被保険者
R5-360
R5.8.22 日雇労働被保険者のポイント!
日雇労働被保険者のポイントをチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第42条 (日雇労働者) 日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された者(引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう。 1 日々雇用される者 2 30日以内の期間を定めて雇用される者
第43条第1項 (日雇労働被保険者) ① 被保険者である日雇労働者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、日雇労働求職者給付金を支給する。 1 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者 2 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 3 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であって、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者 4 1~3に掲げる者のほか、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けた者 |
過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
雇用保険法第42条は、同法第3章4節において< A >とは、< B >又は < C >以内の期間を定めて雇用される者のいずれかに該当する労働者(前2月の各月において< D >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< E >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)を除く。)をいう旨を規定している。
②【H29年選択式】
雇用保険法第43条第2項は、「日雇労働被保険者が前< A >の各月において < B >以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。」と規定している。
③【H29年出題】
日雇労働被保険者に関しては、被保険者資格の確認の制度が適用されない。
【解答】
①【H25年選択式】
A 日雇労働者
B 日々雇用される者
C30日
D18日
E31日
日雇労働者とは次のどちらかに該当する者です。
・日々雇用される者
・30日以内の期間を定めて雇用される者
ちなみに、この日雇労働者が、連続する前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたとき及び同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されたときは、日雇労働者とされません。
ただし、雇用保険法第43条第2項の認可(引き続き日雇労働被保険者として取り扱われる旨の認可)を受けたときは、引き続いて日雇労働被保険者として取り扱われます。
②【H29年選択式】
A2月
B18日
③【H29年出題】 〇
日雇労働被保険者には、「確認」の制度は適用されません。
(法第43条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 適用
労災保険法 適用
R5-359
R5.8.21 労災保険が適用される労働者
労災保険の保護の対象になる労働者を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第3条 ① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 ② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】 ※改正による修正あり
労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、< A >法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び< B >給付の4種類である。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び< C >年金である。
②【H26年出題】
2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。
③【H26年出題】
ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。
④【H26年出題】
船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
⑤【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

【解答】
①【R1年選択式】
A 労働基準
B 二次健康診断等
C 傷病
★労災保険法の労働者とは、労働基準法上の労働者です。
②【H26年出題】 〇
労働者は、労働時間に関係なく労災保険が適用されます。また、2以上の適用事業所に使用される場合は、それぞれの事業で、労災保険法が適用されます。
③【H26年出題】 〇
出向労働者の保険関係の所在については、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定されます。
(昭和35.11.2基発第932号)
④【H26年出題】 ×
船員法上の船員には、労災保険法が適用されます。
⑤【R1年出題】 ×
労働者派遣事業の労災保険の適用は、派遣元事業主の事業が適用事業となります。
派遣労働者の保険給付の請求に当たり、保険給付請求書の事業主の証明は「派遣元事業主」が行います。
(昭和61.6.30発労徴41・基発383号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 選択式
労働安全衛生法 選択式
R5-358
R5.8.20 <選択式>作業の管理・作業時間の制限
選択式の過去問をチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第65条の3 (作業の管理) 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。 |
第65条の4(作業時間の制限) 事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの(高圧室内業務)に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年選択式】
労働安全衛生法第65条の3は、いわゆる労働衛生の3管理の一つである作業管理について、「事業者は、労働者の< A >に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。」と定めている。
②【H16年選択式】
いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して、労働者< B >を適切に< C >するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。」と述べられている。
③【H23選択式】
労働安全衛生法第65条の4においては、「事業者は、< D >その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。」と規定されている。
(選択肢)
① 深夜業 ② 潜水業務 ③ 粉じん作業に係る業務
【解答】
①【H29年選択式】
A 健康
ちなみに、労働衛生の3管理とは、「作業環境管理」、「作業管理」、「健康管理」です。
②【H16年選択式】
B の従事する作業
C 管理
(H12.3.24最高裁判所第二小法廷)
③【H23選択式】
D ② 潜水業務
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 全額払の原則
労働基準法 全額払の原則
R5-357
R5.8.19 賃金債権放棄の意思表示の効力
賃金支払5原則の一つに、「全額払いの原則」があります。
今日は、全額払の原則と賃金債権放棄の意思表示についてみていきます。
賃金支払の原則は次の5つです。
(1) 通貨払い (2) 直接払い (3) 全額払い (4) 毎月1回以上払い (5) 一定期日払い |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
②【H25年出題】
退職金は労働者にとって重要な労働条件であり、いわゆる全額払の原則は強行的な規制であるため、労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をしたとしても、同原則の趣旨により、当該意思表示の効力は否定されるとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H27年出題】
退職金は労働者の老後の生活のための大切な資金であり、労働者が見返りなくこれを放棄することは通常考えられないことであるから、労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、これが労働者の自由な意思に基づくものであるか否かにかかわらず、労働基準法第24条第1項の賃金全額払の原則の趣旨に反し無効であるとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【R1年出題】 〇
・就業規則で支給条件が明確に定められている退職金は、労働基準法上の賃金に該当し、「全額払の原則」が適用されます。
・「全額払の原則」の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活をおびやかすことのないようにしてその保護をはかろうとするものです。
・賃金にあたる退職金債権放棄の効力について、労働者が賃金にあたる退職金債権を放棄する旨の意思表示をした場合、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、当該意思表示は有効である、とされています。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷 シンガー・ソーイング・メシーン事件)
②【H25年出題】 ×
労働者が退職に際し退職金債権を放棄する意思表示をした場合、それが労働者の「自由な意思」に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、「当該意思表示は有効」とするのが、最高裁判所の判例です。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷 シンガー・ソーイング・メシーン事件)
③【H27年出題】 ×
労働者が退職金債権を放棄する旨の意思表示は、それが労働者の「自由な意思」に基づくものである場合は、その意思表示は「有効」であるとするのが、最高裁判所の判例です。
(昭和48.1.19最高裁判所第二小法廷 シンガー・ソーイング・メシーン事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 36協定
労働基準法 36協定
R5-356
R5.8.18 労働者が時間外労働をする義務
三六協定の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 (時間外及び休日の労働) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は第35条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
★労使協定の効力について
労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果です。
労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。
(昭和63年1月1日基発第1号)
では、過去問をどうぞ!
①【H20年選択式】
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。
②【H27年出題】
労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めていたとしても、 36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H20年選択式】
A 合理的な
使用者が、三六協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た
↓
使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めている
↓
就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなす
↓
労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う
(最高一小H3年11月28日 日立製作所武蔵工場事件)
②【H27年出題】 ×
36協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、「当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り」、それが具体的な労働契約の内容をなし、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて「労働をする義務を負う」とするのが、最高裁判所の判例です。
(最高一小H3年11月28日 日立製作所武蔵工場事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険に関する一般常識 介護保険法
社会保険に関する一般常識 介護保険法
R5-355
R5.8.17 介護保険最終チェック!
今日は介護保険法をチェックしましょう!
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
市町村又は特別区(以下「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
②【H27年出題】
市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
③【H27年出題】
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
④【H27年出題】
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。
⑤【H27年出題】
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。

【解答】
①【H27年出題】 ×
法第5条第1項で、「国」は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない、と規定されています。
市町村ではなく「国」の責務です。
あわせて、法第5条第2項も読んでみましょう。
| 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 |
→必要な助言及び適切な援助は、都道府県の責務です。
②【H27年出題】 ×
第14条で、「介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く」と規定されています。
また、介護認定審査会は、共同で設置することができます。
(地方自治法第252条の7第1項)
③【H27年出題】 ×
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の「100分の12.5」に相当する額を負担します。
(第124条第1項)
④【H27年出題】 〇
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担します。
(法第124条第3項)
⑤【H27年出題】 ×
法第27条第1項で、「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。」とされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働に関する一般常識 労働経済
労働に関する一般常識 労働経済
R5-354
R5.8.16 令和4年就労条件総合調査より
今日は、令和4年就労条件総合調査の結果をみてみましょう。
過去問をどうぞ!
※令和4年就労条件総合調査を参照して解説していきます。
①【H28年出題】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
②【H28年出題】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
③【H28年出題】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
④【R4年出題】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。

【解答】
①【H28年出題】 ×
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えています。
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では47.1%となっています。「3割にとどまっている。」は誤りです。
(参照 令和4年就労条件総合調査)
②【H28年出題】 〇
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、7.9%で10パーセントに達していません。みなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 6.5%、「専門業務型裁量労働制」が 1.2%、「企画業務型裁量労働制」が 0.2%となっています。
ちなみに、みなし労働時間制を採用している企業割合は14.1%です。
(参照 令和4年就労条件総合調査)
③【H28年出題】 ×
フレックスタイム制を採用している企業割合は、8.2%です。「3割を超えている。」は誤りです。
ちなみに、変形労働時間制を採用している企業割合は 64.0%です。変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が34.3%、「1か月単位の変形労働時間制」が26.6%、「フレックスタイム制」が 8.2%となっています。
(参照 令和4年就労条件総合調査)
④【R4年出題】 〇
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなります。
なお、令和3年の1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1 人平均は17.6 日、このうち労働者が取得した日数は10.3日で、取得率は 58.3%となっており、昭和 59 年以降過去最高となっています。
(参照 令和4年就労条件総合調査)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-353
R5.8.15 配偶者に係る加給年金額の支給停止
配偶者に係る加給年金額が支給停止されるのはどんなときでしょう?
条文を読んでみましょう。
第46条第6項 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、配偶者について加算する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
②【R3年出題】
老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、障害等級1級若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。
③【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されますが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が「240か月」以上の場合に限られます。
②【R3年出題】 ×
老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されます。
障害厚生年金には3級の障害厚生年金も含まれますので、配偶者が3級の障害厚生年金を受給している間は、加給年金額は支給停止されます。
しかし、「障害手当金」を受給していても加給年金額の支給は停止されません。
(令3条の7)
③【H28年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は支給停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国年・厚年 時効
国年・厚年 時効
R5-352
R5.8.14 <比較>国年「死亡一時金」と厚年「障害手当金」の時効
国民年金の「死亡一時金」と厚生年金保険法の「障害手当金」は年金ではなく一時金で支給されます。
それぞれの時効を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
【国民年金法】 第102条第1項、第4項 ① 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 ④ 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 |
時効のポイント!
・年金給付を受ける権利 → 5年
・死亡一時金を受ける権利 → 2年
・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2年
【厚生年金保険法】 第92条第1項 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から5年を経過したとき、保険給付の返還を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。 |
時効のポイント!
・保険給付を受ける権利 → 5年
・保険料等を徴収・還付を受ける権利 → 2年
では、過去問をどうぞ!
①国民年金法【H27年出題】※改正による修正あり
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
②厚生年金保険法【H29年出題】※改正による修正あり
障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
①国民年金法【H27年出題】 ×
年金給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
死亡一時金を受ける権利→これを行使することができる時から2年を経過したとき
に、時効によって消滅します。
「年金給付(5年)」と「死亡一時金(2年)」の時効の違いに注意してください。
②厚生年金保険法【H29年出題】 ×
保険給付を受ける権利→その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき
に時効によって消滅します。
「保険給付」には年金だけでなく一時金(障害手当金)も含まれます。
障害手当金を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。
ポイント!
同じ「一時金」でも、国民年金の「死亡一時金」の時効は2年、厚生年金保険の「障害手当金」の時効は5年です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 被保険者期間
厚生年金保険法 被保険者期間
R5-351
R5.8.13 厚生年金保険の被保険者期間
被保険者期間は、月単位で算定します。
条文を読んでみましょう。
第19条第1項、2項 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
③【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算されるのは、「被保険者であった期間」です。
②【H30年出題】 〇
平成29年10月1日に資格取得、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、資格を取得した月(平成29年10月)から資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの5か月間です。
平成30年3月は被保険者期間には算入されません。
③【H28年出題】 〇
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するのが原則です。
ただし、問題文のように、同じ月に資格取得と資格喪失があり、その月にさらに国民年金の第1号被保険者となった場合は、その月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害手当金
厚生年金保険法 障害手当金
R5-350
R5.8.12 障害手当金が支給されない場合
「障害手当金」が支給されない場合を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第56条 障害手当金の障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) 2 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) 3 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第77条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者 |
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。
②【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
③【H18年出題】
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く。)には支給しない。
④【H28年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
障害手当金の障害の程度を定めるべき日に、「年金たる保険給付の受給権者」である場合は、障害手当金は支給されません。
遺族厚生年金=年金たる保険給付です。
②【H30年出題】 ×
老齢厚生年金=年金たる保険給付です。
障害の程度を定めるべき日に、老齢厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
③【H18年出題】 〇
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者には支給されません。
しかし、障害厚生年金の受給権者については「最後に障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した者(現に障害状態に該当しない者に限る。)」には障害手当金が支給されます。
④【H28年出題】 〇
当該傷病について「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付」を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 基礎年金拠出金
国民年金法 基礎年金拠出金
R5-349
R5.8.11 基礎年金拠出金の内訳
基礎年金拠出金は、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用に充てられます。
基礎年金拠出金について条文を読んでみましょう。
第94条の2第1項、2項 ① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 |
基礎年金拠出金の額は、基礎年金の給付に要する費用に「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を乗じて得た額となります。
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。
②【H30年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。
③【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

【解答】
①【R4年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間」を有する者の総数です。
「保険料全額免除期間」は入りません。
(令第11条の3)
②【H30年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数には、「保険料免除期間のうち保険料全額免除期間、保険料未納期間」は入りません。
(令第11条の3)
③【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者
・第1号被保険者→保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者→20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者→すべての者
第2号被保険者はすべての者ではありませんので、注意してください。
(令第11条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 第2号被保険者・第3号被保険者
国民年金法 第2号被保険者・第3号被保険者
R5-348
R5.8.10 国民年金の保険料の負担義務
国民年金の保険料の納付義務について、条文を読んでみましょう。
第87条第1項、第2項 (保険料) ① 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 ② 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
第94条の6 第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。 |
第1号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務があります。
第2号被保険者、第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付する義務はありません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
②【H30年出題】
被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料は負担しません。
第2号被保険者は、厚生年金保険に保険料を納付しています。その保険料の一部が基礎年金拠出金となっています。
基礎年金拠出金は、第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金の給付に要する費用に充てられます。
②【H30年出題】 ×
「第2号被保険者」と「第3号被保険者」としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 法定免除
国民年金法 法定免除
R5-347
R5.8.9 法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出
法定免除の期間については、申出により保険料を納付することもできます。
条文を読んでみましょう。
第89条 ① 被保険者(産前産後の免除及び保険料の一部免除の規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 1 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 2 生活保護法による生活扶助を受けるとき。 3 前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。 厚生労働省令で定める施設→国立ハンセン病療養所等、国立保養所、厚生労働大臣が指定するもの ② 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
②【R2年出題】
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
③【H29年出題】
国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
法定免除の要件に該当していても、被保険者又は被保険者であった者から保険料を納付する旨の申出があったときは、申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができます。
②【R2年出題】 〇
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、保険料を納付する旨の申出により、申出のあった期間に係る保険料を納付することができます。
③【H29年出題】 〇
法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、「障害基礎年金の受給権者」も「生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者」のどちらも行うことができます。
★保険料を納付する申出ができる理由
法定免除を受けている期間は、老齢基礎年金の額の計算上は、2分の1となります。
法定免除に該当していても、将来の老齢基礎年金を増額するために、保険料納付の申出をすることができます。
障害基礎年金の受給権者でも、障害の程度が軽くなり障害基礎年金が支給停止になり、老齢基礎年金を選択する可能性があります。
また、法定免除を受けていた期間は、追納することもできますが、追納は10年以内でないとできませんし、当時の保険料額に加算が行われることもあるためです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 国庫負担
健康保険法 国庫負担
R5-346
R5.8.8 健康保険事業の事務の執行
健康保険の事務費についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第151条 (国庫負担) 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第152条 ① 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 ② ①の国庫負担金については、概算払をすることができる。 |
健康保険の事務費については、国が負担しています。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。
②【H23年選択式】
1 国庫は、毎年度、< A >の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに< B >の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における< C >を基準として、厚生労働大臣が算定する。
3 上記2の国庫負担金については、< D >をすることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、全国健康保険協会だけでなく、健康保険組合に対しても、国庫が負担しています。
②【H23年選択式】
A 予算
B 介護納付金
C 被保険者数
D 概算払い
★介護納付金とは?
介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料は、医療保険料と一体的に各医療保険者が徴収します。
↓
徴収した介護保険料は、「介護納付金」として社会保険診療報酬支払基金に納付します。
↓
社会保険診療報酬支払基金から、各市町村に交付されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 保険医療機関・保険薬局
健康保険法 保険医療機関・保険薬局
R5-345
R5.8.7 保険医療機関・保険薬局の指定
今日は、保険医療機関・保険薬局の指定をみていきます。
★厚生労働大臣の指定を受けた病院又は診療所 → 保険医療機関
★厚生労働大臣の指定を受けた薬局 → 保険薬局
条文を読んでみましょう。
第65条第1項 保険医療機関又は保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行い、指定の日から起算して6年を経過したときは、その効力を失う。
②【H28年出題】
保険医個人が開設する診療所は、病床の有無に関わらず、保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。
③【H22年出題】
保険医療機関または保険薬局は、3か月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、またその登録の抹消を求めることができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
・保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により、厚生労働大臣が行います。
※「厚生労働大臣の指定」の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されています。(第205条、則第159条第1項)
・指定の効力は6年間です。
(法第68条)
②【H28年出題】 ×
「病床の有無に関わらず」が誤りです。
「保険医療機関の指定を受けた日から、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされる。」のは、保険医個人が開設する診療所です。「病院又は病床を有する診療所」は除かれます。
(法第68条第2項)
③【H22年出題】 ×
保険医療機関又は保険薬局は、「1月以上の予告期間」を設けて、その指定を辞退することができます。
(法第79条第1項)
ちなみに、保険医又は保険薬剤師は、「1月以上の予告期間」を設けて、その登録の抹消を求めることができます。
(法第79条第2項)
保険医療機関・保険薬局は、「指定」、「辞退」
保険医・保険薬剤師は、「登録」、「抹消」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 報酬支払基礎日数
健康保険法 報酬支払基礎日数
R5-344
R5.8.6 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数
定時決定の条文を読んでみましょう。
第41条第1項 (定時決定) 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 |
今日は、報酬支払の基礎となった日数をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

【解答】
【H28年出題】 ×
4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によることとされています。
① 月給者については、各月の暦日数による。
② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数による。
③ 日給者については、各月の出勤日数による。
問題文の場合は、その月における暦日の数から欠勤日数を控除した日数ではなく、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から欠勤日数を控除した日数が、支払基礎日数となります。
(H18.5.12庁保険発第0512001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 埋葬料と埋葬費
健康保険法 埋葬料と埋葬費
R5-343
R5.8.5 埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合
今日は、埋葬料と埋葬費をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第100条 ① 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。 ② 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、①の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 |
①埋葬料のポイント!
→被保険者により生計を維持していた者に支給されます。
実際に埋葬を行うことが条件ではありません。
②埋葬費のポイント!
→被保険者により生計を維持していた者がいないとき(=埋葬料の支給を受けるべき者がいないとき)は、実際に「埋葬を行った者」に、5万円の範囲内で埋葬に要した費用(実費)が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
埋葬料の支給要件にある「その者により生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部若しくは大部分を維持していた者に限られず、生計の一部を維持していた者も含まれる。
②【H25年出題】
埋葬を行う者とは、埋葬を行った者をいうのであるから、被保険者が死亡し社葬を行った場合には、たとえその被保険者に配偶者がいたとしても、配偶者には埋葬料は支給されない。
③【H28年出題】
被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

【解答】
①【H24年出題】 〇
埋葬料の支給要件の「その者により生計を維持していた者」には、生計の一部を維持していた者も含まれます。
(S8.8.7保発502)
②【H25年出題】 ×
埋葬料は、埋葬を行った事実により支給されるのではなく、被保険者の死亡により支給されるものです。
埋葬を行う者とは、実際に埋葬を行った者ではありません。埋葬を行うべき者のことですので、被保険者が死亡し社葬を行った場合で、その被保険者に配偶者がいた場合は、配偶者に埋葬料が支給されます。
③【H28年出題】 〇
被保険者が死亡し、埋葬料の支給を受けるべき者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に実費が支給されます。
別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合は、実際に埋葬を行った弟に、埋葬料の金額の範囲内でその埋葬に要した費用(実費)が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 延滞金
健康保険法 延滞金
R5-342
R5.8.4 健康保険 延滞金の計算
今日は、延滞金の計算についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第181条 ① 督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 1 徴収金額が1000円未満であるとき。 2 納期を繰り上げて徴収するとき。 3 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。 ② 徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。 ③ 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は延滞金の金額が100円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 ⑤ 延滞金の金額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。
②【H27年選択】※改正による修正あり
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。令和5年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.4%とされたため、令和5年における延滞税特例基準割合は年1.4%となった。このため、令和5年における延滞金の割合の特例は、< A >までの期間については年< B >%とされ、< A >の翌日以後については年< C >%とされた。

【解答】
①【H28年出題】 〇
延滞金は、「納期限の翌日」から「徴収金完納又は財産差押えの日の前日」までの期間の日数に応じて算定されます。
問題文の場合は、「納期限の翌日=6月1日」から「完納の日の前日=7月30日」までの日数によって計算します。
②【H27年選択】※改正による修正あり
A 納期限の翌日から3か月を経過する日
B2.4
C8.7
※延滞金の割合の特例の条文を読んでみましょう。
附則第9条 (延滞金の割合の特例)
第181条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
令和5年における延滞税特例基準割合は年1.4%です。
令和5年の延滞金の割合の特例は、
3か月を経過する日までの期間→1.4%+1%=2.4%
3か月を経過する日の翌日以後の期間→1.4%+7.3%=8.7%
となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 有期事業の一括
徴収法 有期事業の一括
R5-341
R5.8.3 有期事業の一括のポイント!
今日は、「有期事業の一括」のポイントをみていきます。
条文を読んでみましょう。
法第7条、則第6条 2以上の事業が次の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を一の事業とみなす。 1 事業主が同一人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)であること。 3 それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。 ・ 概算保険料に相当する額が160万円未満 かつ ・ 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満 ・ 建設の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満 4 それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行なわれること。 5 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。 ・ それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 ・ それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。)を同じくすること。 ・ それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。 |
2以上の有期事業が要件に該当する場合は、徴収法上、その全部が一の事業とみなされます。
労働保険料の申告・納付については、継続事業と同じように、年度更新の手続を行います。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
②【H28年出題】
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
③【H28年出題】
労働保険徴収法第7条に定める有期事業の一括の要件を満たす事業は、事業主が一括有期事業開始届を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより有期事業の一括が行われ、その届出は、それぞれの事業が開始された日の属する月の翌月10日までにしなければならないとされている。
④【H28年出題】
当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至った場合は、その時点から有期事業の一括の対象事業とされる。
⑤【H28年出題】
有期事業の一括が行われると、その対象とされた事業はその全部が一つの事業とみなされ、みなされた事業に係る労働保険徴収法施行規則による事務については、労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」であり、又は「立木の伐採の事業」であることとされています。
②【H28年出題】 ×
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件は、それぞれの事業の規模が、
「概算保険料の額が160万円未満」であることです。
かつ
・立木の伐採の事業は、素材の見込生産量が1000立方メートル未満
・建設の事業は請負金額が1億8000万円未満
であることが要件です。
「労働者数」は一括の要件に入っていません。
③【H28年出題】 ×
要件を満たす事業は、自動的に有期事業の一括が行われます。届出によって行われるのではありません。
④【H28年出題】 ×
・ 当初、独立の有期事業として保険関係が成立した事業が、その後、事業の規模が変動し有期事業の一括のための要件を満たすに至っても、有期事業の一括の対象にはなりません。
・ また、当初は一括の対象になっていた事業が、その後、事業の規模が増加し要件の規模以上になったとしても、一括の対象からは除外されません。
⑤【H28年出題】 〇
有期事業の一括が行われると、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われます。
労働保険料の納付の事務を行うこととなる一つの事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長が、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 印紙保険料
徴収法 印紙保険料
R5-340
R5.8.2 徴収法 印紙保険料のポイント!
今日は印紙保険料の出題ポイントをみていきましょう。
過去問からどうぞ!
①【H28年出題】
請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。
②【H28年出題】
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。
③【H28年出題】
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
④【H28年出題】
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
⑤【H28年出題】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
建設の事業が数次の請負で行われる場合は、請負事業の一括により元請負人のみが事業主とされます。
一括の対象になるのは、「労災保険に係る保険関係」です。
「雇用保険に係る保険関係」は、元請負人に一括されませんので、それぞれの事業ごとに適用されます。
そのため、下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料については、元請負人ではなく、その日雇労働被保険者を使用する「下請負人」が納付しなければなりません。
(法第23条)
②【H28年出題】 ×
日雇労働被保険者についても「一般保険料」の対象となります。
日雇労働被保険者を使用する事業主は、一般保険料+印紙保険料を負担することになります。
(法第31条)
③【H28年出題】 〇
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主の義務
→毎月の雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに報告しなければなりません。
→日雇労働被保険者を一人も使用せず、雇用保険印紙の受払いのない月も、報告義務があります。
(則第54条)
④【H28年出題】 ×
認定決定された印紙保険料の追徴金の割合は、納付すべき印紙保険料額の「100分の25」です。
確定保険料の額が認定決定された場合の追徴金よりも高いことに注意してください。
(法第25条)
⑤【H28年出題】 ×
認定決定に係る印紙保険料と追徴金は、印紙ではなく現金で納付します。
所轄都道府県労働局収入官吏だけでなく、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することもできます。
(則第38条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 給付制限
雇用保険法 給付制限
R5-339
R5.8.1 基本手当の給付制限
今日は基本手当の給付制限をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第32条第1項、2項、附則第5条第4項 ① 受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。以下この条において同じ。)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。 2 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。 3 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 4 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 5 その他正当な理由があるとき。 ② 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
第33条第1項 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
では、過去問をどうぞ!
(注意)問題文の「受給資格者」には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付を受けている者は除かれるものとします。
①【H28年出題】
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
②【H28年出題】
就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
③【H28年出題】
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
④【H28年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
⑤【H28年出題】
管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
自己の責に帰すべき重大な理由によって解雇された場合、又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されません。
この間は、「失業の認定を行う必要はない」とされています。
(行政手引52205)
②【H28年出題】 〇
受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は基本手当は支給されません。ただし、就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、給付制限は受けません。
(法第32項第1項第3号)
③【H28年出題】 ×
技能習得手当は、基本手当にプラスして支給されるものです。
受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間は、技能習得手当も支給されません。
(法第36条第3項)
④【H28年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されません。
ただし、職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときは、給付制限は受けません。
(法第32条第1項第1号)
⑤【H28年出題】 ×
「管轄公共職業安定所の長は、法第33条第1項の規定により基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対し、職業紹介又は職業指導を行うものとする。」と定められています。
正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対しては、職業紹介及び職業指導が行われます。
(則第48条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 傷病手当
雇用保険法 傷病手当
R5-338
R5.7.31 雇用保険 傷病手当いろいろ
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした「後」において、疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合は、基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働の意思又は能力がないと認められる者が傷病となった場合には、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められないから、傷病手当は支給されない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H28年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合は、傷病手当が支給される。
④【H28年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
⑤【H28年出題】
傷病の認定は、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して10日以内に受けなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「労働の意思又は能力がないと認められる者」が傷病となった場合は、疾病又は負傷のため職業に就くことができないとは認められません。そのため、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002)
②【H28年出題】 〇
基本手当の支給を受けることができる日は、傷病手当は支給されません。
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、「証明書」による失業の認定の対象となり、基本手当の支給を受けることができます。そのため、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
③【H28年出題】 ×
延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者には、傷病手当は支給されません。傷病手当を支給しうる日数は、受給資格者の所定給付日数から、既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数だからです。
(行政手引53004)
④【H28年出題】 ×
傷病手当の日額は、法第16条の規定による「基本手当の日額」に相当する額です。基本手当の日額と同じです。
(法第37条第3項)
⑤【H28年出題】 ×
傷病の認定は、原則として、天災その他認定を受けなかったことについてやむを得ない理由がない限り、職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日までに受けなければなりません。
(則第63条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 被保険者
雇用保険法 被保険者
R5-337
R5.7.30 雇用保険の被保険者となるもの・ならないもの
雇用保険の適用事業所に雇用される労働者は、「被保険者」となります。
※ただし、第6条で適用除外とされているものは、被保険者にはなりません。
被保険者は、「一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4つの種類に分けられます。
今日は、被保険者となるもの、ならないものをみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者とならない。
②【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。
③【H27年出題】
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、休学中の者は、他の要件を満たす限り雇用保険法の被保険者となる。
④【H27年出題】
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
⑤【H27年出題】
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等からみて雇用関係が明確でないので被保険者となることはない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
農業協同組合、漁業協同組合の役員は、雇用関係が明らかでない限り雇用保険の被保険者となりません。
(行政手引20351)
②【H27年出題】 〇
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用が見込まれない者は、被保険者となりません。(法第6条第2号)
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
③【H27年出題】 〇
学生又は生徒で、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外の者(昼間学生)は被保険者になりません。(法第6条第4号)
ただし、昼間学生でも、休学中の者は、雇用保険の被保険者となります。
(行政手引20303)
④【H27年出題】 〇
「国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの」は、被保険者になりません。(法第6条第6号)
④は、「国の事業」に雇用される者についての問題です。
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者となりません。
※都道府県等の事業、市町村等の事業は、適用除外について承認が必要ですが、国等の事業の場合は、承認は要りません。
(則第4条、行政手引23002)
⑤【H27年出題】 ×
生命保険会社の外務員、損害保険会社の外務員、証券会社の外務員は、その職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態から判断して「雇用関係が明確である場合」は、被保険者となります。
(行政手引20351)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 遺族補償給付
労災保険法 遺族補償給付
R5-336
R5.7.29 遺族補償給付(遺族補償年金・遺族補償一時金)のポイント
今日は「遺族補償給付」をみていきます。
「遺族補償給付」には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
③【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
④【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
⑤【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
①【H28年出題】 〇
遺族補償給付は、労働者が業務上死亡した場合に支給されます。
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合は、業務上の死亡に該当します。また、妻は遺族補償年金を受けるに当たり、年齢・障害要件は問われませんので、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた場合は、遺族補償年金を受けることができます。
ポイント!
「年金」を受けるには、死亡当時「生計を維持」していたことが条件です。
「一時金」の場合は、「生計維持」していなくても、受けられる場合があります。
②【H28年出題】 ×
相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態があれば「生計を維持していた」ものにあたります。共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになります。
(S41.1.31基発73号)
③【H28年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき」は消滅します。
自分の伯父は直系血族・直系姻族ではありませんで、伯父の養子となったときは、遺族補償年金を受ける権利は消滅します。
(法第16条の4第1項第3号)
④【H28年出題】 ×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることがあります。
遺族補償一時金が支給される要件は、次の2つです。
① 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき。
② 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合に、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、支給された遺族補償年金の額及び前払一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
例えば、遺族補償年金を受けていた妻が再婚し、遺族補償年金の受給権が消滅しました。他に遺族補償年金の受給資格者がなく、支給された年金と前払一時金の額が給付基礎日額の1000日未満の場合は、1000日分と既に支給された年金等の合計額との差額が、妻に支給されます。
このように、遺族補償年金の受給権を失権した者が、遺族補償一時金の受給権者になることもあります。
(法第16条の6)
⑤【H28年出題】 〇
遺族補償一時金の受給資格者は以下の通りです。
① 配偶者
② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
③生計を維持していない子・父母・孫・祖父母
④兄弟姉妹
労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった兄弟姉妹でも、遺族補償一時金の受給者となることがあります。
(法第16条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 療養の給付
労災保険法 療養の給付
R5-335
R5.7.28 療養の給付の請求書の記載事項
今日は、療養の給付の請求書に記載する事項をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 |
療養補償給付は、原則として「療養の給付」(現物給付)です。
「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、例外で「療養の費用の支給」(現金給付)が行われます。
なお、療養補償給付は「治る」まで行われます。
では、過去問をどうぞ!
【H25年出題】
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。
(A) 災害の発生の時刻及び場所
(B) 通常の通勤の経路及び方法
(C) 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
(D) 加害者がいる場合、その氏名及び住所
(E) 労働者の氏名、生年月日及び住所

【解答】 (D)
「療養給付」とありますので、通勤災害に関する問題です。
現物給付の「療養の給付」の請求書は、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。
その請求書に記載しなければならない事項の中に、「加害者がいる場合、その氏名及び住所」はありません。
(則第18条の5)
<参考>第三者行為について
第三者行為については、以下のように規定されています。
則第22条
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 深夜業
労働安全衛生法 深夜業
R5-334
R5.7.27 深夜業を含む業務の出題ポイント
「深夜業を含む業務」の出題ポイントをみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
使用者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
②【H17年出題】
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
③【H29年出題】
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループの計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売している。
Z1店舗 常時使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 常時使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)
<問題1> Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
<問題2> Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
「特定業務従事者」の健康診断の問題です。深夜業を含む業務はその対象です。
対象になる有害業務として、「多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務」、「多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務」などが定められていて、「深夜業を含む業務」もその中の一つです。
通常の定期健康診断は、1年以内ごとに1回実施しなければなりませんが、特定業務従事者の健康診断は、「当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回」、実施する義務があります。
(則第45条、則第13条第1項第3号)
②【H17年出題】 〇
常時1000人以上の労働者を使用する事業場と、有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任する義務があります。
「有害業務」の範囲は、①の問題の特定業務従事者の健康診断の対象になる有害業務と範囲が同じです。そのため、「深夜業を含む業務」も対象です。
「深夜業を含む業務」に常時500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
(則第13条第1項第3号)
③【H29年出題】
<問題1> 〇
Y市にある工場では、常時600人の労働者が、深夜業を含む業務に従事しています。そのため、専属の産業医を選任しなければなりません。
<問題2> ×
Y市にある工場では、衛生管理者を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要はありません。
<衛生管理者のポイント>
・「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
↓
衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任とする必要があります。
★「健康上特に有害な業務」は、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる業務です。この中に「深夜業を含む業務」は入りません。
・常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務のうち一定の業務を行う事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理免許を受けた者から選任する必要があります。
★「健康上特に有害な業務のうち一定の業務」は、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から5号、9号に掲げる業務です。深夜業を含む業務は入りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 全額払いの原則
労働基準法 全額払いの原則
R5-333
R5.7.26 最高裁判例 適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺
「賃金支払五原則」を条文で読んでみましょう。
第24条 ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 |
今日は、全額払いの原則の判例をみてみましょう。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第24条第1項の禁止するところではないと解するのが相当と解される「許さるべき相殺は、過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合でなければならない」とするのが最高裁判所の判例である。
②【H27年出題】
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H21年選択】
賃金の過払が生じたときに、使用者がこれを精算ないし調整するため、後に支払われるべき賃金から過払分を控除することについて、「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、[・・・(略)・・・]その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の < A >との関係上不当と認められないものであれば、同項[労働基準法第24条第1項]の禁止するところではないと解するのが相当である」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【R3年出題】 〇
賃金計算の過誤、違算等で、賃金の過払が生ずることがあります。これを精算・調整するため、後に支払われるべき賃金から控除できるとすることは、賃金支払の事務をする上で、合理的理由があるといえます。
「適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、第24条第1項但書によつて除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、禁止するところではない」と解されています。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷)
②【H27年出題】 ×
過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金から控除することは、「過払のあつた時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、また、あらかじめ労働者にそのことが予告されるとか、その額が多額にわたらないとか、要は労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのない場合」とされています。
(S44.12.18最高裁判所第一小法廷)
③【H21年選択】
A 経済生活の安定
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 前借金相殺の禁止
労働基準法 前借金相殺の禁止
R5-332
R5.7.25 前借金相殺の禁止は「労働することが条件となっている」がポイント
今日は、前借金相殺の禁止規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第17条 (前借金相殺の禁止) 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 |
第17条の趣旨は、金銭貸借関係と労働関係を完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止することです。
(S22.9.13発基17号)
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。
②【R3年出題】
労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。
③【H28年出題】
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
第17条は、「労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること」を禁止しています。金銭を借り受けることだけでは、違反しません。
②【R3年出題】 ×
労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、「労働することを条件とする前貸の債権」には含まれません。
(S22.9.13発基17号)
③【H28年出題】 ×
「労働者」から意思表示があった場合の相殺は禁止されていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 労働条件の明示
労働基準法 労働条件の明示
R5-331
R5.7.24 派遣労働者に対する労働条件の明示
https://youtu.be/6yoxOsuFBoM まず、労働条件の明示義務について条文を読んでみましょう。
第15条第1項 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
労働契約締結の際、使用者は、賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務があります。
「派遣労働者」に対する労働条件の明示義務は、派遣先、派遣元どちらにあるでしょうか?
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

【解答】
①【H29年出題】 ×
派遣労働者への労働条件の明示については、派遣元が義務を負わない労働時間、休憩、休日等も含めて、労働契約関係にある派遣元に明示義務があります。
なお、労働者派遣法の労働基準法の適用に関する特例によって、労働時間、休憩、休日等は派遣先の事業が労働基準法に基づく義務を負います。
(S61.6.6基発333号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 休日
労働基準法 休日
R5-330
R5.7.23 休日の解釈
「休日」とは、労働義務のない日のことです。
今日は、「休日」の解釈をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
休日について
・毎週少なくとも1日の休日を与える(原則)
又は
・4週間を通じて4日以上の休日を与える(例外・変形休日制)
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
②【H24年出題】
労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
休日とは、「暦日」を指しますので、午前0時から午後12時までの24時間となります。
24時間連続していれば良いというものではなく、起算時点を問わない、というのは誤りです。
(S23.4.5基発535号)
②【H24年出題】 〇
一昼夜交代勤務の場合でも「暦日」の休日の原則が適用されます。
非番の継続24時間は、休日にはなりません。
(S23.11.9基収2968号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 解雇制限
労働基準法 解雇制限
R5-329
R5.7.22 解雇制限が適用される条件
今日は、解雇制限が適用される条件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、その事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けなければならない。 |
今日は、「休業する期間」の部分に注目してください。解雇制限が適用されるのは「休業する期間」です。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。
②【R1年出題】
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
労働基準法の解雇制限を受けるのは、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために「休業する期間」及びその後30日間ですので、労働者が業務上の傷病により治療中だったとしても、休業しないで就労している場合は、解雇制限は受けません。
②【R1年出題】 〇
女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内だったとしても、当該労働者が産前休業を請求しないで就労している場合は、解雇制限は受けません。
(S25.6.16基収1526号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 最高裁判例
労働基準法 最高裁判例
R5-328
R5.7.21 最高裁判例 研修医は労働者に該当する
今日は最高裁判例をみていきます。
まず、労働者の定義を条文で読んでみましょう。
第9条 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
医科大学付属病院に勤務する研修医が、医師の資質の向上を図ることを目的とする臨床研修のプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に医療行為等に従事することは、教育的な側面を強く有するものであるため、研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たることはないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

【解答】
【H29年出題】 ×
この判例では、「研修医は労働基準法第9条所定の労働者に当たる」とされました。
臨床研修の目的は、医師の資質の向上を図ることで、教育的な側面を有しています。しかし、そのプログラムに従い、臨床研修指導医の指導の下に、研修医が医療行為等に従事することを予定しています。
判例の要旨は、「研修医がこのようにして医療行為等に従事する場合には、これらの行為等は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可避的に有することとなるのであり、病院の開設者の指揮監督の下にこれを行ったと評価することができる限り、上記研修医は労働基準法9条所定の労働者に当たるものというべきである。」となっています。
(平成17年6月3日最高裁判所第二小法廷)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社保一般常識 介護保険法
社保一般常識 介護保険法
R5-327
R5.7.20 介護保険法 過去問でみる要介護認定など
今日は、介護保険法の過去問をみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
②【H29年出題】
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
③【H29年出題】
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。
④【H29年出題】
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
⑤【H29年出題】
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「介護認定審査会」とは
・審査判定業務を行わせるため、市町村に置かれています。
・介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命します。
(第14条、第15条、第27条第5項)
②【H29年出題】 〇
要介護認定は、申請のあった日から30日以内に行われるのが原則です。
(第27条第11項)
③【H29年出題】 〇
要介護認定は、有効期間内に限って、その効力を有します。
有効期間が満了した後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができます。
(第28条)
④【H29年出題】 〇
介護保険法による保険給付は次の3つです。
①「介護給付」・・・要介護状態に関する保険給付
②「予防給付」・・・要支援状態に関する保険給付
③「市町村特別給付」・・・要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの
(第18条)
⑤【H29年出題】 ×
第2号被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」と定義されています。
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失します。
(第9条、第11条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働一般常識 社会保険労務士法
労働一般常識 社会保険労務士法
R5-326
R5.7.19 社労士 信用失墜行為の禁止
社会保険労務士は、信用失墜行為を行うことが禁止されています。
条文を穴埋めで読んでみましょう。
法第16条 (信用失墜行為の禁止) 社会保険労務士は、社会保険労務士の< A >又は< B >を害するような行為をしてはならない。 |

【解答】
A 信用
B 品位
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。

【解答】
【H29年出題】 ×
信用失墜行為の禁止違反には、罰則規定がありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 併合認定
厚生年金保険法 併合認定
R5-325
R5.7.18 併合認定の対象になる障害厚生年金の条件
今日は併合認定をみていみます。
条文を読んでみましょう。
第48条 (障害厚生年金の併給の調整) ① 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級の1級又は2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。 ② 障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |
障害厚生年金の受給権者に、更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度の障害厚生年金が支給されます。
この併合認定の対象になる先発の障害厚生年金は、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものは除かれます。
少しの間でも、1・2級の状態にあったことがある障害厚生年金が対象です。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
②【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H29年出題】 〇
現在は3級でも、1回でも1・2級に該当したことがある障害厚生年金の受給権者に対して、新たに1・2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、併合認定の対象となります。
前後の障害を併合した障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
②【H27年出題】 ×
受給権を取得した当時から1回も障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金は、併合認定の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金の加給年金額
厚生年金保険法 障害厚生年金の加給年金額
R5-324
R5.7.17 障害厚生年金に加算される加給年金額のポイント!
1級・2級の障害厚生年金を受けることができる者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、加給年金額が加算されます。
※3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。
※子については、障害基礎年金の加算対象になります。
(イメージ図)
障害等級1級・2級の場合
障害厚生年金
| (加算対象) → 配偶者 |
障害基礎年金
| (加算対象) → 子 |
条文を読んでみましょう。
第50条の2第1項~3項 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを 100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
障害厚生年金の受給権を取得した時点で生計を維持している配偶者は加給年金額の対象となります。それだけでなく、受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持している配偶者を有するに至った場合も加給年金額の対象となるのが、障害厚生年金のポイントです。
※国民年金の障害基礎年金の子の加算も同じです。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
②【H24年出題】
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
1級・2級の障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、配偶者加給年金額が加算されます。
配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加算されます。
②【H24年出題】 ×
その受給権を取得した日の翌日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときも、配偶者加給年金額の加算対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害手当金の額
厚生年金保険法 障害手当金の額
R5-323
R5.7.16 障害手当金の額の計算式と最低保障額
今日は障害手当金の額の計算式を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第57条 (障害手当金の額) 障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が同条第3項に定める額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。 |
※障害手当金の額は、第50条第1項の規定の例により計算した額(報酬比例の年金額)×100分の200です。
※最低保障額は、(障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額)×2です。
※第50条第1項と第3項を読んでみましょう。
第50条第1項 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定(老齢厚生年金)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 第50条第3項 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が2級の障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額を障害厚生年金の額とする。 |
※第3項は障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年選択式】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額とする。ただし、その額が障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額に< A >を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。
②【H29年出題】
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。

【解答】
①【H26年選択式】
A 2
障害手当金の額は報酬比例の年金額×2です。
最低保障額は、3級の障害厚生年金の最低保障額×2です。
※ちなみに、3級の障害厚生年金(=障害基礎年金を受けることができない)の最低保障額は、780,900円×改定率(2級の障害基礎年金)×4分の3です。
②【H29年出題】 ×
最低保障額は、障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額に「4分の3を乗じて得た額」の2倍に相当する額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金の額の計算
厚生年金保険法 障害厚生年金の額の計算
R5-322
R5.7.15 障害厚生年金の額の計算に算入される被保険者期間
障害厚生年金は、①初診日、②保険料納付要件、③障害認定日の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。
今日は、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第50条第1項、2項 ① 障害厚生年金の額は、第43条第1項の規定(老齢厚生年金の額)の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①に定める額の100分の125に相当する額とする。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
障害厚生年金は、老齢厚生年金と同じように計算します。
・1級の場合は、1.25倍します。
・被保険者期間が300月未満の場合は、300月の最低保障があります。
・障害厚生年金の計算には、障害認定日の属する月後は算入されません。=障害認定日の属する月まで算入されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
②【H29年出題】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
③【R4年出題】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

【解答】
①【H22年出題】 ×
計算の基礎となるのは、障害認定日の属する「月」までです。
②【H29年出題】 〇
障害認定日の属する月(平成29年3月)までが計算の基礎となります。平成29年4月以後の被保険者期間は計算に入りません。
③【R4年出題】 ×
「障害認定日の属する月」までが計算の基礎となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 老齢厚生年金の加給年金額
厚生年金保険法 老齢厚生年金の加給年金額
R5-321
R5.7.14 老齢厚生年金と障害基礎年金の子の加算
今日は、65歳以上で「障害基礎年金」と「老齢厚生年金」を併給している場合を見ていきます。
まず、老齢厚生年金の加給年金額の条文を読んでみましょう。
第44条第1項 (加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 ただし、国民年金法第33条の2第1項(障害基礎年金の子の加算)の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
老齢厚生年金の加給年金額の対象になるのは、65歳未満の配偶者と子です。
65歳以上の場合、障害基礎年金と老齢厚生年金を併給することができます。
障害基礎年金にも老齢厚生年金にも子の加算がありますが、障害基礎年金に子の加算額が行われる場合は、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止されます。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
【H29年出題】 〇
障害基礎年金に子の加算が行われ、老齢厚生年金の子の加給年金額は支給が停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金と老齢厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金と老齢厚生年金
R5-320
R5.7.13 遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整
遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある場合の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権がある場合
★遺族厚生年金が老齢厚生年金より高い場合
→老齢厚生年金との差額分の遺族厚生年金を受けることができます。
遺族厚生年金 | →受給 |
|
老齢厚生年金相当額 支給停止 |
受給→ | 老齢厚生年金
|
★遺族厚生年金が老齢厚生年金より低い場合
→遺族厚生年金は全額支給停止されます。
|
|
老齢厚生年金
|
遺族厚生年金 全額支給停止 |
受給→ |
※自身の老齢厚生年金が優先されます。
※65歳未満の場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金はどちらか選択です。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
【H29年出題】 〇
65歳以上の場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方の受給権がある場合は、老齢厚生年金が優先されます。遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、加給年金額は除きます。)に相当する部分の支給が停止されます。
老齢厚生年金より遺族厚生年金の方が高い場合は、老齢厚生年金との差額が支給されます。
(法第64条の2、第60条第1項第2号ロ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 未支給年金
国民年金法 未支給年金
R5-319
R5.7.12 年金の支給期間と未支給年金
年金の受給権者が死亡した場合の未支給年金をみていきましょう。
まず、年金の支給期間と支払期月を見ていきましょう。
第18条 (年金の支給期間及び支払期月) ① 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 ② 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。 ③ 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 |
★年金は、年6回に分けて偶数月に支給されます。
年金は「後払い」です。例えば、8月に支給されるのは、6月分と7月分です。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
老齢基礎年金の支給を受けている者が平成29年2月27日に死亡した場合、未支給年金請求者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年1月分と2月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。

【解答】
【H29年出題】 ×
年金は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から「権利が消滅した日の属する月」まで月単位で支給されます。
受給権者が死亡した場合は、「死亡日の属する月」まで支給されます。
平成29年2月27日に死亡した場合は、老齢基礎年金は「2月分」まで支給されます。
平成29年2月に、12月分と1月分が支給されていますので、未支給年金請求者が請求できるのは、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない「2月分」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 配偶者に対する遺族基礎年金の額
国民年金法 配偶者に対する遺族基礎年金の額
R5-318
R5.7.11 配偶者に対する遺族基礎年金の増額改定
遺族基礎年金は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子に支給されます。
配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者に生計を維持していたことが条件です。
遺族基礎年金は、配偶者に支給されるパターンと、子に支給されるパターンがありますが、今日は配偶者に支給されるパターンをみていきます。
では、配偶者の条件を条文で読んでみましょう。
(遺族の範囲) 第37条の2 ① 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 1 配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 2 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 ② 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。 |
★配偶者は、「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた子と生計を同じくすること」が条件です。
配偶者は子と生計を同じくすることが条件ですので、配偶者に支給する遺族基礎年金には、必ず子の数に応じた加算が行われるのがポイントです。
配偶者に対する遺族基礎年金について、条文を読んでみましょう。
第39条第1項、2項 ① 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
|
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
②【R3年出題】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月までさかのぼって改定される。
③【H29年出題】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が死亡当時被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

【解答】
①【H30年出題】 ×
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生するのは、「子が生まれたとき」です。
受給権の発生日は夫の死亡当時には遡りません。
②【R3年出題】 ×
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、遺族基礎年金の加算の対象になります。
胎児であった子が生まれたときは、「将来に向かって」、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなすとされていますので、遺族基礎年金の額は、「その生まれた日の属する月の翌月から」改定されます。
③【H29年出題】 ×
「死亡当時被保険者によって生計を維持されていなかった子」は遺族基礎年金の対象になりません。問題文のように養子縁組をしても、年金額が改定されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 死亡一時金
国民年金法 死亡一時金
R5-317
R5.7.10 死亡一時金と寡婦年金の調整
今日は、死亡一時金と寡婦年金の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
死亡一時金と寡婦年金は、併給できません。
本人の「選択」で、どちらか一方を受けることになります。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。
②【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
①【H24年出題】 ×
寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした場合は、妻本人の選択によって、死亡一時金と寡婦年金のどちらかが支給されます。死亡一時金を選択した場合は寡婦年金は支給されない、寡婦年金を選択した場合は死亡一時金は支給されない、となります。
②【R3年出題】 〇
・一人一年金の原則
複数の年金の受給権が発生した場合は、原則として、選択した一の年金を受けることになります。
遺族厚生年金と寡婦年金の受給権が発生した場合は、どちらかを選択します。
・死亡一時金と寡婦年金
死亡一時金と寡婦年金は、どちらかを選択します。
問題文のように、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。一人一年金の原則により遺族厚生年金は支給停止となります。
また、遺族厚生年金と死亡一時金は支給調整されませんので、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 障害基礎年金
国民年金法 障害基礎年金
R5-316
R5.7.9 障害基礎年金 申請免除と初診日について
今日は、申請免除と初診日の関係をみていきます。
まず、「申請免除」で、保険料が免除される期間を確認しましょう。
<申請免除の対象となる厚生労働大臣が指定する期間> 申請のあった日の属する月の2年2か月前(納期限から2年を経過した期間を除く。)の月から当該申請のあった日の属する年の翌年6月(申請のあった日の属する月が1月から6月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の6月)までの期間のうち必要と認める期間 |
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H28年出題】 ×
障害基礎年金の受給権は発生しません。
・保険料免除期間に算入されるのは「申請のあった日以後」です。過去に遡って、未納が保険料免除期間になるわけではありません。
・保険料納付要件は「初診日の前日」でみます。
初診日の前日の時点では、20歳からの期間がすべて滞納期間です。
・保険料納付要件を満たしていませんので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 障害基礎年金
国民年金法 障害基礎年金
R5-315
R5.7.8 障害基礎年金の受給権発生
障害基礎年金の受給権の発生要件をみていきましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第30条(支給要件) 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者であること。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 |
★障害基礎年金の受給権の発生要件は
①初診日
②障害認定日
③保険料納付要件
の3つです。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態になった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
【H28年出題】 〇
受給権の発生要件を確認しましょう。
①初診日要件について
初診日に、国民年金第1号被保険者です。
初診日に「被保険者であること。」の要件を満たしています。
②保険料納付要件について
初診日は、平成26年4月8日です。
20歳に達した月(平成22年4月)から初診日の属する月の前々月(平成26年2月)までの納付状況をみることになります。
47か月のうち、平成22年4月から平成25年3月までの36か月が学生納付特例期間、平成25年4月から平成26年2月までの11か月が滞納期間です。
47カ月のうち、3分の2以上が保険料免除期間(学生納付特例期間)ですので、保険料納付要件を満たします。
③障害認定日について
障害認定日において障害等級2級の状態になった場合は、障害認定日に受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 標準賞与額
健康保険法 標準賞与額
R5-314
R5.7.7 健保 標準賞与額のポイント
今日は、健康保険の「標準賞与額」をみていきましょう。
なお、賞与とは、「3か月を超える期間ごとに受けるもの」です。
条文を読んでみましょう。
第45条 (標準賞与額の決定) 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。 |
則第27条 (賞与額の届出) 被保険者の賞与額に関する届出は、賞与を支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 |
第167条第2項 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
②【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
③【R4年出題】
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
540万円ではなく、「573万円」です。
ポイント!
・標準賞与額は、賞与額から1000円未満を切り捨てた額です。
・年度の累計は、573万円です。累計が573万円に達した後も賞与が支給された場合は、それ以降の標準賞与額は0円となります。
②【H29年出題】 〇
前月から引き続き被保険者だった者が資格を喪失した場合、資格を喪失した月に支給された賞与については、保険料は徴収されません。
※保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月でも、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額の573万円には算入されます。
(H19.5.1庁保険発第0501001号)
③【R4年出題】 〇
資格を取得した月に支給された賞与は、保険料の徴収の対象となります。
6月25日に介護保険の第2号被保険者となった場合は、6月に支給された賞与から、一般保険料額と介護保険料額を控除することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 不服申立て
労働保険徴収法 不服申立て
R5-313
R5.7.6 徴収法 行政不服審査法による審査請求
労働保険徴収法の徴収金に関する処分に不服がある者は、行政不服審査法に基づき、厚生労働大臣に審査請求を行います。
では、さっそく過去問をどうぞ!
★平成28年度の概算保険料に係る認定決定に不服がある事業主が行うことができる措置についての問題です。
①【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、その処分庁である都道府県労働局歳入徴収官に対し、異議申立てを行うことができる。
②【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、その処分に係る都道府県労働局に置かれる労働者災害補償保険審査官に対し、審査請求を行うことができる。
③【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、厚生労働大臣に対し、再審査請求を行うことができる。
④【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、直ちにその取消しの訴えを提起することができる。
⑤【H28年出題】(労災)
事業主は、当該認定決定について、取消しの訴えを提起する場合を除いて、代理人によらず自ら不服の申立てを行わなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「厚生労働大臣」に対し、「審査請求」行うことができる、です。
(行政不服審査法第4条)
②【H28年出題】 ×
①と同じく、「厚生労働大臣」に対し、「審査請求」行うことができる、です。
(行政不服審査法第4条)
③【H28年出題】 ×
①と同じく、厚生労働大臣に対し、「審査請求」行うことができる、です。
(行政不服審査法第4条)
④【H28年出題】 〇
行政事件訴訟法第8条で、「処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。」と規定されています。
問題文の認定決定については、厚生労働大臣の裁決を経なくても、直ちにその取消しの訴えを提起することができます。
⑤【H28年出題】 ×
行政不服審査法第12条で、「審査請求は、代理人によってすることができる。」と定められています。事業主は当該認定決定について、代理人によって審査請求を行うことができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 失業の認定
雇用保険法 失業の認定
R5-312
R5.7.5 基本手当は失業していることについて認定を受けた日に支給される
今日は、「失業の認定」のルールをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条第1項~2項 (失業の認定) ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
②【H28年出題】
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。
③【H28年出題】
公共職業安定所の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
④【H28年出題】
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
失業の認定は受給資格者に労働の意思と能力があって、しかも就職し得ないことについての認定です。そのため、受給資格者が自ら認定日に出頭して、失業の認定を受けなければなりません。
しかし、以下の場合は、代理人による失業の認定が認められています。
・ 未支給失業等給付にかかるもの
・ 公共職業能力開発施設に入校中の場合
(則第17条の2第4項、則第27条、行政手引51401)
②【H28年出題】 〇
失業の認定は、あらかじめ定められた認定日に行うことが原則です。
しかし、受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の認定日に出頭できない場合は、受給資格者の申出により、認定日の変更の取扱いを受けることができます。
「子弟の入学式又は卒業式等への出席」はやむを得ない理由に該当しますので、認定日の変更が可能です。
(行政手引51351)
③【H28年出題】 ×
公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、「1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
(則第24条)
④【H28年出題】 〇
受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となります。
(行政手引51256)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働者災害補償保険法 通勤災害
労働者災害補償保険法 通勤災害
R5-311
R5.7.4 逸脱・中断(日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの)
通勤経路を逸脱・中断した場合について条文を読んでみましょう。
第7条第3項 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 |
中断は「寄り道」、逸脱は「回り道」のイメージです。
通勤経路を逸脱・中断した場合、逸脱・中断の間とその後の移動は通勤になりません。
例外的に、逸脱、中断が、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱の間・中断の間は通勤となりませんが、その後の移動は通勤となります。
では、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを条文で読んでみましょう。
則第8条 (日常生活上必要な行為) 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3 選挙権の行使その他これに準ずる行為 4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤となる。
②【H27年出題】
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
③【H28年出題】
会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。
④【R3年出題】
腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は、通勤災害と認められない。
⑤【H25年出題】
女性労働者が1週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所から帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合であったとしても、逸脱の間、中断の間は、通勤となりません。
②【H27年出題】 ×
出退勤の途中に、理髪店や美容院にたちよる行為は、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当します。
退勤の途中で美容院に立ち寄り、髪のセットをしている間は通勤になりませんが、その後直ちに合理的な経路に復した後は、通勤に該当します。
(S58.8.2基発420)
③【H28年出題】 〇
通常の医療行為だけでなく、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」に該当します。
(S48.11.22 基発644)
④【R3年出題】 〇
自宅と反対方向にある病院から駅に向かう途中の路上は、逸脱の間(合理的経路に復する前)ですので、通勤災害となりません。
⑤【H25年出題】 〇
要介護状態にある夫の父の介護の場合は、介護終了後に合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 元方事業者
労働安全衛生法 元方事業者
R5-310
R5.7.3 元方事業者の講ずべき措置
今日は、元方事業者の講ずべき措置についてみていきます。
まず、元方事業者の定義が、平成19年の選択式で出題されていますので、確認しましょう。
過去問をどうぞ!
【H19年選択式】
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

【解答】
A 一の場所
では、元方事業者の講ずべき措置について条文を読んでみましょう。
第29条 (元方事業者の講ずべき措置等) ① 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。 ② 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。 ③ ②の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
②【H22年出題】
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
③【H26年出題】
労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。

【解答】
①【H18年出題】 〇
あらゆる業種に適用されることがポイントです。
「構内下請企業は、親企業内の設備の修理、製品の運搬、梱包等危険、有害性の高い作業を分担することが多く、さらにその作業場所が親企業の構内であることから、その自主的な努力のみでは十分な災害防止の実をあげられない面があるので、当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人およびその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、指示義務を負わせることとしたものであること」とされています。
(S47.9.18発基第91号)
②【H22年出題】 ×
第29条第1項、第2項とも、「関係請負人又は関係請負人の労働者が・・・」となっていますので、関係請負人の労働者も、指導及び指示の対象です。
③【H26年出題】 ×
労働安全衛生法第29条には、罰則は付いていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 休業手当
労働基準法 休業手当
R5-309
R5.7.2 休業手当支払いのルール
今日は休業手当の支払ルールです。
休業手当について条文を読んでみましょう。
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
【H27年出題】
当該労働者の労働条件は次のとおりである。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
① 使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。
② 使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
③ 就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。
④ 休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかかわらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいうから、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も含まれる。
⑤ 休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
① ×
休業手当は、「休日」に支給する義務はありません。
問題文の場合は、休日を除いた5日分の休業手当を支払わなければなりません。
(S24.3.22基収4077号)
② 〇
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由が生じた場合も、その日は平均賃金の100分の60以上を支払わなければなりません。
実際に労働した時間分の賃金が、平均賃金の100分の60未満の場合は、その差額を支払わなければなりません。
問題文は、実際に労働した時間の賃金として7,500円が支払われています。平均賃金の100分の60以上が支払われていますので、その賃金の支払に加えて休業手当を支払う必要はありません。
(S27.8.7基収3445号)
③ 〇
振り替えによって休日となった水曜日に休業手当を支払う義務はありません。
④ 〇
使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を拒否する場合も、休業手当の支払が必要です。
⑤ 〇
休電による休業については、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しませんので、休業手当を支払う義務はありません。
(S26.10.11基発696号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 平均賃金
労働基準法 平均賃金
R5-308
R5.7.1 平均賃金の計算方法
平均賃金の算定ルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条第1項~5項 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の1によって計算した金額を下ってはならない。 1 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ② 期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③ 期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。 1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 3 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 4 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間 5 試みの使用期間 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
平均賃金の計算式(原則)
3か月間の賃金の総額 |
3か月間の総日数 |
③について → 賃金総額(分子)、日数(分母)の両方から除外する
④について → 賃金総額(分子)から除外する
平均賃金の最低保障額
3か月間の賃金の総額 | × | 60 |
3か月間の労働した日数 | 100 |
※最低保障が適用されるのは、日給制、時間給制、出来高払制(請負制)の場合です。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
②【H27年出題】
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から除外する。
③【H27年出題】
労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
④【H27年出題】
賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
⑤【H27年出題】
賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
賃金の総額に算入しない賃金は、以下の賃金です。
・臨時の賃金
・3か月を超える期間ごとの賃金(賞与など)
・現物給与で法令・労働協約に基づくもの以外のもの
★「通勤手当及び家族手当」は賃金総額に算入します。
②【H27年出題】 ×
平均賃金の計算の「期間」及び「賃金の総額」から除外するのは以下の期間です。
・ 業務上の負傷、疾病による療養のための休業期間
・ 産前産後の休業期間
・ 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・ 育児休業又は介護休業期間
・ 試用期間
★「公民権の行使により休業した期間」は、その日数とその期間中の賃金は、平均賃金の計算に算入します。
③【H27年出題】 ×
施行規則第48条で「災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。」と規定されています。
遺族補償を行う場合の平均賃金を算定すべき事由の発生日は、「死亡した日」ではありません。
(S25.10.19 基収2908号)
④【H27年出題】 〇
賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日が起算日となります。
賃金締切日が毎月月末で、7月31日に算定事由が発生したときは、6月30日から遡った3か月で算定します。
⑤【H27年出題】 ×
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、直前の賃金締切日は、それぞれの賃金ごとの賃金締切日です。
問題文の場合は、基本給は5月31日、時間外手当は6月20日となります。
(S26.12.27基収5926号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 介護保険法 選択式
介護保険法 選択式
R5-307
R5.6.30 毎年のように選択式で出題されている介護保険法
過去10年間で、介護保険法は選択式で6回出題されています。
まとめてチェックしましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、< A >並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< B >に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
②【R4年選択式】
介護保険法における「要介護状態」とは、< A >があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、< B >の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である< A >が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が< B >に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
③【H29年選択式】
介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して< A >とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。
④【R1年選択式】
介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、< A >を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
⑤【R2年選択式】
介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から< A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。
⑥【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
①【H27年選択式】
A 機能訓練
B 国民の共同連帯の理念
②【R4年選択式】
A 身体上又は精神上の障害
B 6か月
(則第2条)
③【H29年選択式】
A 常に健康の保持増進に努める
④【R1年選択式】
A その保健医療の向上及び福祉の増進
⑤【R2年選択式】
A 1年6か月
⑥【H30年選択式】
A3年
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
障害者雇用促進法 障害者雇用率
R5-306
R5.6.29 雇用率未達成企業からの障害者雇用納付金の徴収
従業員を常時43.5人以上雇用する民間企業には、障害者を1人以上雇用する義務があります。
条文を読んでみましょう。
第43条第1項 (一般事業主の雇用義務等) 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。 |
民間企業の障害者雇用率は、「100分の2.3」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R4年選択式】
全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率は< A >パーセントである。
障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常時雇用労働者< B >の事業主に限る。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。
(選択肢)
①2.0 ②2.3 ③2.5 ④2.6
⑤50人超 ⑥100人超 ⑦200人超 ⑧300人超
②【H27年出題】※改正による修正あり
障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.3パーセント)以上の対象障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。

【解答】
①【R4年選択式】
A ②2.3
B ⑥100人超
法定雇用率を満たしていない事業主から、障害者雇用納付金が徴収されます。
障害者雇用納付金の対象になるのは、常時雇用労働者100人超の事業主です。
②【H27年出題】 ×
障害者雇用納付金は、未達成1人につき月5万円です。
(法第54条、施行令第17条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金
厚生年金保険法 障害厚生年金
R5-305
R5.6.28 障害基礎年金の併合による障害厚年金の額の改定
障害基礎年金の併合によって、障害厚生年金の額が改定されることがあります。
条文を読んでみましょう。
第52条2の第2項 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第34条第4項(その他障害による額の改定)及び第36条第2項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。 |
図でイメージしましょう。
①会社員(厚生年金保険の被保険者)のときに初診日がある傷病で2級の障害厚生年金と障害基礎年金を受給しています。
障害厚生年金 2級 |
障害基礎年金 2級 |
②会社を退職後、自営業者になりました。(国民年金第1号被保険者となりました)
国民年金第1号被保険者のときに初診日がある傷病で「その他障害」が発生しました。
障害厚生年金 2級 |
+ |
| → | 障害厚生年金 1級 |
障害基礎年金 2級 | その他障害 | → | 障害基礎年金 1級 |
■障害基礎年金について
2級の障害基礎年金の受給権者にさらに「その他障害」が発生しました。
国民年金法第34条4項の規定により、前後の障害を併合した障害の程度が増進した場合は、額の改定を請求することができます。
その結果、障害基礎年金は1級に額が改定されます。
■障害厚生年金について
障害基礎年金が2級から1級に改定されたことに合わせて、障害厚生年金も1級に改定されます。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
障害等級2級の障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が、国民年金の第1号被保険者になり、その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法第34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われ、当該障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された場合には、障害厚生年金についても障害等級1級の額に改定される。

【解答】
【H27年出題】 〇
時系列で確認しましょう。
・2級の障害厚生年金と障害基礎年金の受給権者が
↓
・国民年金の第1号被保険者になった
↓
・第1号被保険者期間中に初診日がある傷病によって、国民年金法34条第4項の規定による障害基礎年金とその他障害との併合が行われた
↓
・併合の結果、障害基礎年金が障害等級1級の額に改定された
↓
・障害厚生年金も障害等級1級の額に改定される
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 在職老齢年金
厚生年金保険法 在職老齢年金
R5-304
R5.6.27 在職老齢年金の用語の定義
在職老齢年金の用語をチェックしましょう。
過去問からどうぞ!
【H28年選択式】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。

【解答】
A 総報酬月額相当額
B 支給停止調整額
C 支給停止基準額
用語を確認しましょう。
・総報酬月額相当額とは
→ (その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
・基本月額とは
→ 老齢厚生年金の額÷12 (老齢厚生年金の月額)
※加給年金額・繰下げ加算額は除きます。
・「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額以下の場合
→ 全額支給されます。
・「基本月額+総報酬月額相当額」が支給停止調整額を超える場合
→ (基本月額+総報酬月相当額-支給停止調整額)×2分の1が支給停止されます。(月額)
・支給停止基準額とは
(基本月額+総報酬月相当額-支給停止調整額)×2分の1に12をかけた額です。(支給停止される額の年額です。)
★「支給停止調整額」は毎年度見直されます。
条文を読んでみましょう。
第46条第3項 支給停止調整額は、48万円とする。ただし、48万円に平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率をそれぞれ乗じて得た額(その額に5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとする。)が48万円(支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至った場合においては、当該年度の4月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。 |
支給停止調整額は令和4年度の47万円から、令和5年度は「48万円」になりました。
過去問をどうぞ!
【H25年出題】※問題文修正あり
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(480,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である20,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。

【解答】
【H25年出題】 ×
問題文は、基本月額に「老齢基礎年金」を含んでいるので、誤りです。
在職老齢年金は厚生年金保険の制度ですので、老齢基礎年金は関係ありません。
在職中でも老齢基礎年金は全額支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金④
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金④
R5-303
R5.6.26 20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止④日本国内に住所を有しないとき
引き続き、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止をみていきます。
初診日が国民年金に加入する前の障害に対する年金で、保険料を負担していないことが特徴です。そのため、通常の障害基礎年金とは違う支給停止事由が設定されています。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4日本国内に住所を有しないとき。 |
今日は、4日本国内に住所を有しないときをみていきます。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。
②【R4年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。
③【H28年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。

【解答】
①【H25年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給が停止されます。
②【R4年出題】 ×
受給権者が日本国内に住所を有しないときに支給が停止されるのは、20歳前傷病による障害基礎年金です。
しかし、通常の障害基礎年金(事後重症による障害基礎年金も)は、日本国内に住所を有しないときでも、支給停止されません。
③【H28年出題】 ×
20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由に、「日本国籍を有しなくなったとき」はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金③
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金③
R5-302
R5.6.25 20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止③労災保険の年金を受けることができるとき
引き続き、20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止をみていきます。
初診日が国民年金に加入する前の障害に対する年金で、保険料を負担していないことが特徴です。そのため、通常の障害基礎年金とは違う支給停止事由が設定されています。
条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項、2項 ① 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4 日本国内に住所を有しないとき。 ② 1に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。ただし、その支給の停止が前条第1項(労働基準法の規定による障害補償)又は第41条第1項に規定する給付(労働基準法の規定による遺族補償)が行われることによるものであるときは、この限りでない。 |
今日は、1をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
②【H25年出題】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
③【H20年出題】
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときは、支給が停止されます。
②【H25年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付を受けることができるときは、支給が停止されます。
ただし、「労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。」となっていますので、労働者災害補償保険法による年金たる給付の全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されません。
③【H20年出題】 〇
労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときに支給が停止されるのは、20歳前の障害に基づく障害基礎年金です。
通常の障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金②
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金②
R5-301
R5.6.24 20歳前傷病による障害基礎年金②刑事施設等に拘禁されているときの支給停止
前回は、20歳前傷病による障害基礎年金の「所得による支給停止」をみました。
今日は、刑事施設等に拘禁されているときの支給停止をみていきます。
では、条文を読んでみましょう。
第36条の2第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(2及び3に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。 1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4 日本国内に住所を有しないとき。 |
今日は、2と3をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
②【H28年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合であっても、未決勾留中の者については、その支給は停止されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が「少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき」は支給停止されますが、厚生労働省令で定める場合に限られています。
厚生労働省令では、「少年法24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合」と規定されています。
(則第34条の4)
②【H28年出題】 〇
20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」は支給停止されていますが、こちらも厚生労働省令で定める場合に限られています。
刑事施設等に拘禁されている場合であっても、有罪が確定するまでは、その支給は停止されません。
(則第34条の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金①
国民年金法 20歳前傷病による障害基礎年金①
R5-300
R5.6.23 20歳前傷病による障害基礎年金①所得による支給停止
20歳前傷病による障害基礎年金は、国民年金加入前に初診日があるため、保険料を拠出せずに支給される年金です。
そのため、通常の障害基礎年金と異なる理由で支給停止が行われます。
今日は、「所得」による支給停止をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第36条の3第1項 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
第36条の4第1項 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の9月までの第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は、行わない。 |
★扶養親族等がいない場合は、前年の所得が370万4千円を超え472万1千円以下の場合は2分の1が支給停止、472万1千円を超える場合は全額停止となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】※改正による修正あり
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。
②【H25年出題】※問題文修正あり
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年9月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
③【H27年出題】※問題文修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
④【H25年出題】※問題文修正あり
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金については、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
①【H20年出題】※改正による修正あり 〇
前年の所得に基づいて支給停止される期間は、その年の10月から翌年の9月までです。
②【H25年出題】※問題文修正あり ×
支給停止されるのは、年金額の全部又は2分の1(子の加算額が加算されている場合は、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)です。
③【H27年出題】※問題文修正あり ×
所得は「受給権者」のみの所得です。扶養親族の所得を合算しません。
④【H25年出題】※問題文修正あり ×
被害金額がその価格のおおむね「2分の1以上」である損害を受けた者がある場合です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 保険料免除
健康保険法 保険料免除
R5-299
R5.6.22 保険料免除(少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された場合)
少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された期間は、健康保険料は免除されます。
条文を読んでみましょう。
第158条 (保険料の徴収の特例) 前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。)である者が第118条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号のいずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号のいずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。 ただし、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至った月に同項各号のいずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。
※第118条第1項 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 |
少年院に収容された場合等は、公費で医療が行われますので、健康保険の疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われず、また、保険料は徴収されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。
②【H29年出題】
前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
・ 前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合等
→ 免除される期間は、「該当した月」から該当しなくなった月の「前月」まで
※問題文は、「その翌月以後、拘禁されなくなった月まで」となっているので誤りです。
・ 資格を取得した月に刑事施設に拘禁された場合等
→ 免除される期間は、該当した月の「翌月」から該当しなくなった月の「前月」まで
・ 拘禁された、拘禁されなくなったのが同じ月にある場合
→ 保険料は免除されません。
②【H29年出題】 ×
任意継続被保険者は、刑事施設に拘禁されたとき等でも、保険料の免除はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 給付制限
健康保険法 給付制限
R5-298
R5.6.21 少年院、刑事施設、労役場等に収容・拘禁された場合の給付制限
さっそく条文を読んでみましょう。
第118条 ① 被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、行わない。 1 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。 ② 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。 |
ポイントその1
少年院に収容された場合等は、公費で医療が行われますので、健康保険の疾病、負傷、出産に係る保険給付は行われません。
「死亡」については、健康保険の保険給付が行われます。
ポイントその2
被保険者が少年院、刑事施設、労役場に収容・拘禁されたとき等でも、被扶養者がそれに該当しない場合は、被扶養者に対する保険給付は行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
保険者は、被保険者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)を行わないが、被扶養者に係る保険給付を行うことは妨げられない。
②【H29年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合には、被扶養者に対する保険給付を行うことができない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
被保険者が少年院等に収容されたときには、疾病、負傷又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は行われません。
被扶養者については、被扶養者がそのような状態にない場合は、被扶養者に係る保険給付は行われます。
②【H29年出題】 ×
被保険者又は被保険者であった者が、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合でも、被扶養者に対する保険給付は行われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金の支給
健康保険法 傷病手当金の支給
R5-297
R5.6.20 傷病手当金と老齢年金の調整
傷病手当金と老齢基礎年金・老齢厚生年金は同時に受けられるでしょうか?
条文を読んでみましょう。
法第108条第5項 傷病手当金の支給を受けるべき者(資格喪失後の継続給付により傷病手当金を受けるべき者に限る。)が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
則第89条第2項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
ポイントその1!
老齢退職年金給付と調整されるのは、「資格喪失後の継続給付により傷病手当金を受ける者」に限られます。
老齢退職年金給付を受けることができる者には、資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、原則として支給されません。退職後に、老齢年金と傷病手当金の両方が支給されると、所得保障が重複してしまうからです。
ポイントその2!
ただし、「老齢退職年金給付の額÷360」が、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるとき、「老齢退職年金給付は支給されない」ではなく、「傷病手当金は支給されない」です。
ただし、「老齢退職年金給付の額÷360」が、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
②【H27年出題】 〇
「適用事業所に使用される被保険者」=在職中に傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 印紙保険料
労働保険徴収法 印紙保険料
R5-296
R5.6.19 印紙保険料の認定決定と追徴金
日雇労働被保険者を使用する事業主は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することによって、印紙保険料を納付します。
事業主が印紙保険料の納付を怠ったときについて条文を読んでみましょう。
第25条第1項、2項 (印紙保険料の決定及び追徴金) ① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の 100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行います。納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用保険)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H28年出題】(雇用保険)
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
③【H28年出題】(雇用)
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
①【H25年出題】(雇用保険) 〇
印紙保険料の認定決定の通知は、納入告知書によって行われます。
(則第38条第5項)
②【H28年出題】(雇用保険) ×
徴収される追徴金は、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の「100分の25」です。
③【H28年出題】(雇用) ×
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、「日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)」又は、「所轄都道府県労働局収入官吏」に納付しなければなりません。
雇用保険印紙ではなく、現金で納付するのがポイントです。
(則第38条第3項第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 賃金
雇用保険法 賃金
R5-295
R5.6.18 賃金日額の算定
基本手当の日額の算定の基礎となるのが賃金日額です。
賃金日額の算定方法や、算入される賃金についてみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第17条第1項、2項 ① 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 ② ①の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、①の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 1 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額 2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額 |
★賃金日額は、離職前6か月間の1日当たりの平均の賃金額です。
原則は①で計算します。
②は最低保障です。最低保障が適用されるのは、日給制、時間給制、出来高払制その他の請負制の場合です。
★基本手当の日額は、賃金日額×給付率で計算します。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
月当たり一定の時間外労働があったものとみなして支給される定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に含まれない。
②【H25年出題】
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
③【H25年出題】
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金を除く)の総額を90で除して得た額とされている。
④【H25年出題】
支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれる。
⑤【H25年出題】
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
定額残業手当が、実際に行われた時間外労働に基づいて算出された額を上回るとき、その差額は賃金に「含まれます」。
雇用保険法の賃金とは、名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。
「労働の対償として支払われるもの」とは、労働した時間に対して支払われるものだけでなく、契約等で支給が事業主に義務づけられているものも含まれます。
(行政手引50402)
②【H25年出題】 〇
賃金日額には、最高限度額と最低限度額があります。
最高限度額は年齢階層別に設定されていますが、最低限度額は年齢に関係なく一律で設定されています。
例えば、令和4年8月1日から1年間の45歳以上60歳未満の賃金日額の上限は、16,710円です。この場合の基本手当の日額は、16,710円×給付率(50%)=8,355円となります。
給付率は、原則50%~80%で、賃金日額が高いほど給付率は低くなり、賃金日額が低いほど給付率は高くなります。
なお、60歳以上65歳未満の給付率は45%~80%です。
③【H25年出題】 ×
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、被保険者期間として計算された最後の「6」か月間に支払われた賃金の総額を「180」で除して得た額です。なお、賃金の総額から除外されるのは、臨時に支払われる賃金及び「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」です。
④【H25年出題】 〇
賃金日額の計算にあたり算入される賃金は、「被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金」です。支払義務が確定した賃金であって所定の支払日を過ぎてもなお支払われていない賃金は、賃金日額の算定対象に含まれます。
(行政手引50451)
⑤【H25年出題】 ×
住居の利益は、原則として賃金となりますので、賃金日額の算定対象に含まれます。
(行政手引50501)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 通勤災害
労災保険法 通勤災害
R5-294
R5.6.17 通勤の定義「就業に関し」
https://youtu.be/QpSV5kMZ5lM 「通勤」の定義を条文で読んでみましょう。
法第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
今日は、「就業に関し」に注目しましょう。
「就業に関し」とは、往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示しています。通勤と認められるには、往復行為が業務と密接な関連をもって行われることを要します。
(H18.3.31基発第0331042号)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。
②【H24年出題】
運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。
③【H24年出題】
業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。
④【H24年出題】
昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
所定の就業日に所定の就業開始時刻に合わせて住居を出て就業の場所へ向う場合は、「寝すごしによる遅刻」、「ラッシュを避けるための早出」等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があるとされます。
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合でも、要件を満たせば通勤に該当します。
(H18.3.31基発第0331042号)
②【H24年出題】 ×
午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合は、業務以外の目的のために行われるものと考えられ、就業との関連性はないと認められます。
問題文の場合は、運動部の練習に参加する目的で行われるものと考えられるので、通勤には該当しません。
(H18.3.31基発第0331042号)
③【H24年出題】 ×
業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えない、とされています。
(H18.3.31基発第0331042号)
④【H24年出題】 ×
通勤は1日について1回のみしか認められないものではありません。昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、昼休みについていえば、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるので、その往復行為は就業との関連性を認められます。
問題文は、通勤に該当します。
(H18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 安全委員会・衛生委員会
労働安全衛生法 安全委員会・衛生委員会
R5-293
R5.6.16 安全委員会・衛生委員会の構成
安全委員会、衛生委員会の構成員について条文を読んでみましょう。
法第17条第2項~4項(安全委員会) ② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の委員は、1人とする。 1総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2安全管理者のうちから事業者が指名した者 3 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。 ④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 ⑤ 前2項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第18条第2項~4項(衛生委員会) ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 1総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2衛生管理者のうちから事業者が指名した者 3産業医のうちから事業者が指名した者 4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 ※ 安全委員会の③~⑤の規定は、衛生委員会に準用します。 |
★安全委員会・衛生委員会の議長となるのは、第1号の委員です。 <第1号の委員について> 「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」とは、総括安全衛生管理者の選任を必要としない事業場について規定されたものです。 「これに準ずる者」とは、当該事業場において事業の実施を統括管理する者以外の者で、その者に準じた地位にある者(たとえば副所長、副工場長など)をさします。 (S47.9.18基発第602号)
では、過去問をどうぞ! 【H26年出題】 事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
【解答】 【H26年出題】 × 労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないのは、「第1号の委員(議長)以外」の委員の半数です。 ※事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除きます。
|
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 年次有給休暇の権利
労働基準法 年次有給休暇の権利
R5-292
R5.6.15 年次有給休暇請求権の行使
年次有給休暇の発生について、条文を読んでみましょう。
第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
「6か月間継続勤務」+「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たせば、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇の権利が発生します。
「10労働日」に注目してください。
年次有給休暇の権利を行使すると、その労働日の労働義務は消滅します。
10「労働日」となっているのは、年次有給休暇は労働義務のある日(=労働日)にしか取得できないからです。もともと就労義務のない休日に年次有給休暇を取得することはありえません。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対して全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は年次有給休暇請求権の行使ができないと解されている。

【解答】
【H28年出題】 〇
「労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がない」がポイントです。会社に対して全く労働義務が免除されている場合は、年次有給休暇請求権の行使はできません。
(S48.3.6基発120号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 年次有給休暇の残余
労働基準法 年次有給休暇の残余
R5-291
R5.6.14 所定労働時間が変更になった場合の年次有給休暇の残余
年次有給休暇は時間単位で与えることができます。
条文を読んでみましょう。
法第39条第4項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 1 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 2 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。) 3 その他厚生労働省令で定める事項 |
労使協定を締結することにより、年に5日を上限として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。

【解答】
【H28年出題】 〇
年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位年休の時間数はどのように変わるのでしょうか?又、時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるのでしょうか?
↓
時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されます。
問題文のように、
・所定労働時間が1日8時間から4時間に変更になった。
・変更前の年次有給休暇の残余が10日と5時間だった。
このような場合、変更前は10日と5/8日残っていると考えます。
1日の所定労働時間が8時間から4時間に変更され、1日の所定労働時間が2分の1になりました。残余の時間もそれに比例して2分の1となります。2.5/4となりますが、 1時間未満の端数を切り上げ、3時間となります。
★変更前の残余
10日(1日当たりの時間数は8時間)と5時間
★変更後の残余
10日(1日当たりの時間数は4時間)と3時間
(平成21年10月5日基発1005第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 年次有給休暇の発生要件
労働基準法 年次有給休暇の発生要件
R5-290
R5.6.13 年休発生には全労働日の8割以上の出勤が要件
①雇入れの日から起算して6か月間継続勤務、②全労働日の8割以上出勤、の要件を満たした場合、年次有給休暇の権利が発生します。
労働義務のある日は、「労働日」、労働義務のない日は「休日」です。「全労働日」とは、所定休日を除いた日のことをいいます。
「全労働日」に対する「出勤した日」の割合が8割以上あることが必要です。
今日は、「全労働日」から除外される日をみていきます。
通達のポイントを読んでみましょう。
<出勤率の基礎となる全労働日> ★年次有給休暇の請求権の発生について、全労働日の8割出勤を条件としているのは、労働者の勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低い者を除外する立法趣旨です。 1 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいいます。 所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれません。 2 「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます。 3 「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」でも、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれません。 ・ 不可抗力による休業日 ・ 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日 ・ 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 (H25.7.10基発0710第3号) |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
②【H26年選択式】
最高裁判所は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の成立要件に係る「全労働日」(同条第1項、第2項)について、次のように判示した。
「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上であることという年次有給休暇権の成立要件は,法の制定時の状況等を踏まえ,労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと,前年度の総暦日の中で,就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないものは,不可抗力や使用者側に起因する経営,管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として,上記出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >と解するのが相当である。
無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり,このような日は使用者の責めに帰すべき事由による不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから,法39条1項及び2項における出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に< A >というべきである。」
(選択肢)
① 含まれるもの ② 含まれない

【解答】
①【H28年出題】 ×
所定の休日に労働させた日は、全労働日に含まれません。
②【H26年選択式】
A ①含まれるもの
「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」は、例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日です。
「労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日」は、出勤率の算定に当たっては、請求の前年度における出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれます。
(H25.7.10基発0710第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法 保険給付
国民健康保険法 保険給付
R5-289
R5.6.12 国民健康保険の法定給付と任意給付
まず、国民健康保険法の第1条と第2条を読んでみましょう。
第1条 (目的) 国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民健康保険) 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 |
■国民健康保険の保険給付は、3つに分けられます。
法定給付 |
任意給付 | |
絶対的必要給付 | 相対的必要給付 | |
療養の給付 入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 療養費 訪問看護療養費 特別療養費 移送費 高額療養費 高額介護合算療養費 | 出産育児一時金 葬祭費、葬祭の給付 | 傷病手当金 出産手当金 |
相対的必要給付と任意給付の条文を読んでみましょう。
第58条 ① 市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
② 市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、①の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。 |
①は相対的必要給付です。
「給付を行うものとする」となっていますが、「特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」のがポイントです。
②は任意給付です。
傷病手当金その他の保険給付(出産手当金)は、「行うことができる」となっています。給付を行うか行わないか、また、内容についても保険者が決定します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
②【R1年出題】
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
③【H26年出題】※改正による修正あり
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる

【解答】
①【H26年出題】 ×
「移送費」は絶対的必要給付です。
条文では、「市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。」となっています。
問題文の「条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」では相対的必要給付になりますので間違いです。
②【R1年出題】 〇
出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は、相対的必要給付です。
③【H26年出題】 〇
「傷病手当金の支給」は任意給付です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法 就業規則
労働契約法 就業規則
R5-288
R5.6.11 就業規則違反の労働契約
就業規則は、労働条件を統一的に設定するものです。
今日は、「就業規則」の内容を下回る労働契約の効力を確認しましょう。
条文を読んでみましょう!
労働契約法第12条 (就業規則違反の労働契約) 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。 |
ポイント!
★ 就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定める基準まで引き上げられます。
★「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」とは、例えば、就業規則に定められた賃金より低い賃金等就業規則に定められた基準を下回る労働条件を内容とする労働契約をいいます。
★就業規則で定める基準以上の労働条件を定める労働契約は、有効とする趣旨です。
★「その部分については、無効とする」とは、就業規則で定める基準に達しない部分のみを無効とする趣旨で、労働契約中のその他の部分は有効です。
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
就業規則で定める基準と異なる労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となり、無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。

【解答】
【H26年出題】 ×
就業規則で定める基準と「異なる」労働条件を定める労働契約の「異なる」が誤りです。
就業規則で定める基準に「達しない」労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となりますが、「達しない」とは、就業規則に定める基準を下回る、という意味です。
就業規則で定める基準以上の労働条件を定める労働契約は、有効です。
(H24.8.10基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法 労働契約の内容の変更
労働契約法 労働契約の内容の変更
R5-287
R5.6.10 労働契約の変更についての基本原則
労働契約の内容を変更する際の基本原則を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
労働契約法第8条 (労働契約の内容の変更) 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 |
労働契約の変更については、「合意」が原則です。
では、過去問をどうぞ!
【H24年出題】
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるとされている。

【解答】
【H24年出題】 〇
「合意により」と規定されているとおり、労働契約の内容である労働条件は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより変更されるものです。
そのため、労働契約の変更の要件として、変更内容について書面を交付することまでは求められていません。
(H24.8.10基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 3号分割(応用編)
厚生年金保険法 3号分割(応用編)
R5-286
R5.6.9 特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるとき
3号分割は、国民年金の第3号被保険者(特定被保険者の被扶養配偶者)からの請求によって行われます。
特定期間の標準報酬月額と標準賞与額を2分の1ずつ分割します。
条文を読んでみましょう。
第78条の14第1項 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法の第3号被保険者に該当していたものをいう。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。 ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 |
今回は、「当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。」の部分に注目します。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
②【H28年出題】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下「特定被保険者」という。)が、障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。
③【R1年出題】
障害厚生年金の受給権者である特定被保険者(厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者をいう。)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から除くものとする。

【解答】
①【R3年出題】 ×
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者で、その障害厚生年金の計算に特定期間が入っている場合は、その期間は3号分割の対象になりません。
なぜなら、3号分割は第3号被保険者からの請求によって行われるからです。特定被保険者の合意がなくても行われるからです。
障害厚生年金は老齢厚生年金などと比べると保護が必要な年金です。3号分割請求により、特定被保険者が受給している障害厚生年金が合意なく減額されることを防ぐためです。
問題文のように、特定被保険者が、特定期間の「全部」をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者である場合は、3号分割標準報酬改定請求はできません。
②【H28年出題】 〇
「障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする。」と規定されています。
特定被保険者が、障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれます。
(令第3条の12の11)
③【R1年出題】 〇
②の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 3号分割(基本編)
厚生年金保険法 3号分割(基本編)
R5-285
R5.6.8 離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度
今日は、3号分割の基本をチェックしましょう。
条文を読んでみましょう。
第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) ① 被保険者(被保険者であった者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であった期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法の第3号被保険者に該当していたものをいう。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。)に係る被保険者期間の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 ② 実施機関は、①の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 ③ 実施機関は、①の請求があった場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 ④ 特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす。 ⑤ 改定され、及び決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。 |
まず、用語をおさえましょう。
・特定被保険者 → 厚生年金保険の被保険者(被保険者であった者を含む)
・特定期間 → 特定被保険者が厚生年金保険の被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が第3号被保険者であった期間
では、過去問をどうぞ!
※「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関する問題です。
①【H26年出題】
いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。
②【H26年出題】
分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。
③【H26年出題】※問題文を修正しています
実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
④【H26年出題】
老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。
⑤【H26年出題】
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
3号分割の請求ができるのは、「特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるとき」です。
「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった特定被保険者及び被扶養配偶者について、当該被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる場合」も、3号分割の対象となります。
(則第78条の14第1号)
②【H26年出題】 〇
平成20年4月1日前の期間は、特定期間に含まれません。
3号分割の対象になるのは、平成20年4月1日以降の期間です。
(H16年法附則第46条)
③【H26年出題】 ×
特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を『特定被保険者の標準報酬月額に「2分の1」』を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定されます。
※標準賞与額についても、「2分の1」を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定されます。
3号分割は「2分の1」がポイントです。「合意した按分割合に基づいて算出した割合」ではありません。
④【H26年出題】 〇
改定され、及び決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有します。
老齢厚生年金の受給権者の年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われます。
(法第78条の18)
⑤【H26年出題】 〇
原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、3号分割の請求はできません。
(則第78条の17)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金
R5-284
R5.6.7 遺族厚生年金の短期要件と長期要件
遺族厚生年金には、「短期要件」と「長期要件」があります。
条文を読んでみましょう。
第58条 ① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、1又は2に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 2被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 3 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 4老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
② 死亡した被保険者又は被保険者であった者が1から3までのいずれかに該当し、かつ、4にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、1から3までのいずれかのみに該当し、4には該当しないものとみなす。 |
短期要件と長期要件を確認しましょう
|
| *1 |
短期要件 | 1厚生年金保険加入中に死亡 | あり |
2厚生年金保険加入中に初診日がある傷病により資格喪失後に死亡(初診日から5年以内) | あり | |
31、2級の障害厚生年金の受給権者が死亡 | なし | |
長期 | 4老齢厚生年金の受給権者(25年以上*2)が死亡 25年以上*2ある者が死亡 | なし |
*1 保険料納付要件
*2 保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上
★「長期要件」は、厚生年金保険の被保険者期間が25年以上ではなく、「保険料納付済期間+保険料免除期間」が25年以上です。25年以上は、国民年金全体(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)で計算します。
★「長期要件」の25年以上の計算には合算対象期間も算入します。「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る」となります。
(附則第14条)
★例えば、保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある人が、厚生年金保険の被保険者であるとき(在職中)に死亡した場合、短期要件と長期要件の両方に当てはまります。
その場合は、「その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、短期要件のいずれかのみに該当し、長期要件には該当しないもの」とみなされます。
申出がなければ、短期要件の扱いになります。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。
②【H17年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者に限る)の死亡により支給される遺族厚生年金の額の計算において、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障は適用されないが、給付乗率については生年月日に応じた乗率が適用される。
③【H26年出題】
障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
④【R3年出題】
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
<報酬比例部分の「給付乗率について>
遺族厚生年金の原則の計算式は、報酬比例部分×4分の3です。
報酬比例部分の計算式は、平成15年4月以降の期間分については、「平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」です。
「長期要件」の場合は、死亡した者が昭和21年4月1日以前生まれの場合、給付乗率は生年月日に応じた読み替えが行われます。
なお、「短期要件」の場合は、定率(1000分の5.481(H15年4月以降)か1000分の7.125(H15年3月以前))です。
(S60年附則第59条)
②【H17年出題】 〇
「長期要件」の場合の給付乗率には、生年月日に応じた乗率が適用されます。
一方、被保険者期間の月数は「300月の最低保障」は適用されず、実際の被保険者期間で計算されます。
なお、「短期要件」の場合は、計算の基礎となる被保険者期間の月数に300月の最低保障が適用されます。
③【H26年出題】 〇
「障害等級2級の障害厚生年金を受給する者」の死亡で支給される遺族厚生年金は、「短期要件」です。被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、300か月として計算されます。
(法第60条第1項)
| 短期要件 | 長期要件 |
給付乗率 | 定率 | 生年月日に応じた読み替えあり |
被保険者期間が300月未満 | 最低保障あり | 最低保障なし |
④【R3年出題】 ×
・ 第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡 → 短期要件
・ 保険料納付済期間が40年ある → 長期要件
申出がなければ、「短期要件」のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出され
ます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金
国民年金法 老齢基礎年金
R5-283
R5.6.6 老齢基礎年金の額と国庫負担の関係
老齢基礎年金の満額は780,900円×改定率です。
保険料納付済期間の月数が480の場合は満額支給されますが、480未満の場合は、その分、年金額が減額されます。
保険料納付済期間の月数は1で計算しますが、免除期間は以下のように計算します。
保険料4分の1免除期間 → 8分の7
保険料半額免除期間 → 4分の3
保険料4分の3免除期間 → 8分の5
保険料全額免除期間 → 2分の1
この割合は、国庫負担との関係で決まります。
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8分の7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4分の3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8分の5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2分の1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 国庫負担 | 保険料 | ||||||
※ 保険料納付済期間の月数は1で計算しますが、2分の1は国庫負担です。
※ 保険料全額免除期間については保険料はゼロですが、特別国庫負担が入り、老齢基礎年金の額には2分の1が反映します。ちなみに、学生納付特例、納付猶予期間には国庫負担が入りませんので、老齢基礎年金の額の計算ではゼロになります。
※ 国庫負担は平成21年3月までは3分の1でした。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】 ※問題文を修正しています
国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額の計算式として、正しいものはどれか。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)
(A)780,900円×改定率×(360月+120月×1/2)÷480月
(B)780,900円×改定率×(360月+120月×1/3)÷480月
(C)780,900円×改定率×(360月+108月×1/2+12月×1/3)÷480月
(D)780,900円×改定率×(360月+108月×1/3+12月×2/3)÷480月
(E)780,900円×改定率×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月

【解答】
(E)780,900円×改定率×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月
全額免除期間の計算は、国庫負担の割合で変わります。国庫負担は平成21年3月までは3分の1でした。
|
| 国庫負担 |
H12年4月~H21年3月 | 108か月 | 3分の1 |
H21年4月~H22年3月 | 12か月 | 2分の1 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 任意加入被保険者
国民年金法 任意加入被保険者
R5-282
R5.6.5 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合
国民年金の任意加入被保険者は、第1号被保険者と同様に、国民年金保険料を負担します。
ただし、任意加入被保険者については、保険料を滞納した場合、被保険者資格を喪失することがあるのがポイントです。
まず、任意加入被保険者を確認しましょう。次の3種類です。(法附則第5条)
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
②日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
③日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の扱いについて、条文を読んでみましょう。
附則第5条第6項第4号 上記①、②の被保険者は、次に該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。 ・ 保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
附則第6条第8項第4号 上記③の被保険者は、次に該当するに至った日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。 ・ 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したとき。 |
①、②の被保険者は「日本国内に住所を有する」、③の被保険者は「日本国内に住所を有しない」がポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
②【H29年出題】
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
③【H22年出題】
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年が経過した日に被保険者資格を喪失する。
④【H27年出題】
海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の翌日に、被保険者資格を喪失する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の資格喪失日は、「督促状で指定した期限の日の翌日」です。
②【H29年出題】 ×
「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者が保険料を滞納し、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、「その指定した期限の日の翌日」に被保険者の資格を喪失します。
特例による任意加入被保険者も同じ扱いです。
③【H22年出題】 ×
「日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者が保険料を滞納したときは、その後、保険料を納付することなく2年間が経過した日の「翌日」に、被保険者資格を喪失します。
日本国内に住所を有しない場合は、保険料の徴収の時効が過ぎると、任意加入被保険者資格を喪失します。
④【H27年出題】 ×
海外に居住する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく「2年間が経過した日の翌日」に、被保険者資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 被保険者の届出
健康保険法 被保険者の届出
R5-281
R5.6.4 同時に2以上の事業所に使用される場合
被保険者が、同時に2以上の事業所に使用される場合の届出をみていきます。
条文を読んでみましょう。
則第1条の2 (選択) ① 被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。 ② 当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、①の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
則第2条第1項 (選択の届出) 選択は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、一定の事項を記載した届書を全国健康保険協会を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 |
同時に2か所以上の適用事業に使用される場合、被保険者は、10日以内に選択の届出が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。
②【R4年選択式】
被保険者(日雇特例被保険者を除く。)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から < A >日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を全国健康保険協会を選択しようとするときは< B >に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。
(選択肢)
① 5 ② 7 ③ 10 ④ 14
⑤ 厚生労働大臣 ⑥ 全国健康保険協会の都道府県支部
⑦ 全国健康保険協会の本部 ⑧ 地方厚生局長

【解答】
①【H27年出題】 ×
被保険者が同時に2つの事業所に使用される場合で、それぞれの適用事業所の保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して保険者を選択する届出を提出します。
その場合、2つの事業所の保険者がどちらも全国健康保険協会であっても、管轄する年金事務所が異なる場合は、当該被保険者に関する事務を行う年金事務所を選択することになります。
②【R4年選択式】
A ③ 10
B ⑤ 厚生労働大臣
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 有期事業
労働保険徴収法 有期事業
R5-280
R5.6.3 有期事業の成立と消滅
労働保険徴収法には、「継続事業」と「有期事業」という分け方があります。
徴収法の有期事業は、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」で、労災保険のみの取扱いです。雇用保険には「有期事業」の扱いはありません。
また、有期事業以外は、「継続事業」となります。
では、「有期事業」の成立と消滅について条文を読んでみましょう。
第3条 (保険関係の成立) 労災保険法の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
第4条の2 (保険関係の成立の届出等) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
第5条 (保険関係の消滅) 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
③【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が消滅した場合であって、納付した概算保険料の額が確定保険料の額として申告した額に足りないときは、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内にその不足額を、確定保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。
④【H27年出題】(労災)
複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
保険関係成立届は、成立の日の翌日から起算して10日以内に提出します。「翌日起算」がポイントです。
保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長ですが、「一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しないもの(雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業を除く。)」と「労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業」は、「所轄労働基準監督署長」に提出します。
(則第1条、4条)
②【H27年出題】 〇
有期事業の概算保険料の申告・納付の期限は、「成立した日の翌日から起算して20日以内」です。「翌日起算」と「20日以内」がポイントです。
(法第15条の2)
③【H27年出題】 〇
有期事業の確定保険料の申告・納付の期限は、「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。ここは、「当日起算」となります。保険関係が消滅するのは、事業が廃止又は終了した日の翌日です。
(法第19条第2項、3項)
④【H27年出題】 〇
有期事業の賃金総額は、当該保険関係に係る「全期間」で算定します。保険年度単位ではありません。
(法第15条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 被保険者
雇用保険法 被保険者
R5-279
R5.6.2 雇入れ時に31日以上の雇用が見込まれない場合
以下の場合は、雇用保険の被保険者から除外されます。
条文を読んでみましょう。
第6条 次に掲げる者については、雇用保険法は、適用しない。 1. 1週間の所定労働時間が20時間未満である者(特例高年齢被保険者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 2. 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) (3.~6.は省略) |
★1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、雇用保険は適用除外です。
※日雇労働被保険者に該当する者は、被保険者となります。
★同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、雇用保険は適用除外です。
※日雇労働被保険者に該当する者は被保険者となります。
※日雇労働者で前2月の各月に18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となります。
過去問をどうぞ!
①【R2年選択】
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。
②【H27年出題】
当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

【解答】
①【R2年選択】
A20時間以上
B31日以上
①と②の要件を両方満たす場合は、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上である
②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれる
②【H27年出題】 〇
当初は31日以上雇用されることが見込まれない場合でも、雇入れ後に、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合は、その時点から一般被保険者となります。
(行政手引20303)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 事業主からの費用徴収
労災保険法 事業主からの費用徴収
R5-278
R5.6.1 保険関係成立届を提出しない事業主に対する費用徴収
保険関係成立届を提出していない期間中に事故が発生した場合、事業主は、保険給付に要した費用を徴収されることがあります。
条文を読んでみましょう。
第31条第1項 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 1. 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出が行われていない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 2. 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故 3. 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |
★今日は、1.の故意又は重大な過失により、事業主が保険関係成立届の提出を行っていない期間中に生じた事故についての費用徴収をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
②【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
③【R1年選択式】
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後< A >以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから< B >を経過してもなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
「故意」と認定された場合は、費用徴収率が100%となります。
★故意の認定について
① 事業主が、当該事故に係る事業に関し、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう指導を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合
② 事業主が、当該事故に係る事業に関し、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう勧奨(「加入勧奨」という。)を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合
(H17.9.22基発第0922001号)
「指導」や「加入勧奨」を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合は「故意」と認定されます。
②【H27年出題】 〇
「重大な過失」と認定された場合は、費用徴収率が40%となります。
★重大な過失の認定について
事業主が、当該事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、かつ、保険関係成立日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないとき
(H17.9.22基発第0922001号)
③【R1年選択式】
A 10日
B 1年
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 派遣労働者
労働安全衛生法 派遣労働者
R5-277
R5.5.31 派遣労働者の健康診断の実施義務
労働安全衛生法では、事業者に、健康診断の実施義務が課せられています。
派遣労働者に対する健康診断は、派遣元、派遣先どちらに実施義務が課せられているかが今日のテーマです。
★なお、健康診断は、「一般健康診断(雇入れ時の健康診断、定期健康診断等)」と、有害な業務に常時従事する労働者を対象とする「特殊健康診断」の大きく2つに分けられます。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
②【H30年出題】
派遣労働者に関する労働安全衛生法第66条第2項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
一般健康診断は、一般的な健康管理が目的ですので、雇用主である「派遣元」の事業者に実施義務が課せられています。
しかし、有害な業務に従事する労働者に対して実施する「特殊健康診断」は、業務に関する健康管理ですので、指揮命令を行う「派遣先」の事業者にその実施義務が課せられています。
(派遣法第45条第3項)
②【H30年出題】 〇
・ 派遣労働者に関する特殊健康診断の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければなりません。
(派遣法第45条第3項)
・ 派遣先の事業者は、派遣労働者の特殊健康診断を行ったときは、健康診断の結果を記録した書面を作成し、派遣元の事業者に送付しなければなりません。
(派遣法第45条第10条)
★特殊健康診断の結果の保存及び通知について
派遣労働者については、派遣先が変更になった場合にも、当該派遣労働者の健康管理が継続的に行われるよう、労働者派遣法第45条第11項の規定に基づき、派遣元事業者は、派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければなりません。
また、派遣元事業者は、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければなりません。
(平成27年9月30日基発0930第5号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 均等待遇
労働基準法 均等待遇
R5-276
R5.5.30 第3条の労働条件と雇入れ
労働基準法第3条では、「国籍、信条、社会的身分」を理由として、労働者を差別することを禁止しています。
条文を読んでみましょう。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
★今日は、「賃金、労働時間その他の労働条件」に注目します。
労働条件の中に、賃金、労働時間は当然含まれますが、それ以外の条件は、どこまで含まれるでしょうか?
では、過去問をどうぞ
①【H30年出題】
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。
②【H28年出題】
労働基準第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
③【H21年出題】
労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いは、雇入れにおける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「その他の労働条件」には、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件も含まれます。
(S23.6.16基収1365号、S63.3.14基発150号)
「解雇の意思表示」そのものは労働条件とはいえません。しかし、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されている場合は、「労働条件」にあたります。
②【H28年出題】 〇
ポイント!
・企業者が、労働者を雇用するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件で雇うかについては、原則として自由に決定できる。企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。
・労働基準法3条は雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。
(S48.12.12最高裁判所大法廷 三菱樹脂事件)
③【H21年出題】 ×
労働基準法3条は雇入れ後における労働条件についての制限ですので、雇入れそのものを制約する規定ではありません。「雇入れにおける差別も含まれる」の部分が誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者医療確保法 費用
高齢者医療確保法 費用
R5-275
R5.5.29 後期高齢者支援金
75歳以上の後期高齢者は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
後期高齢者医療の財源は、「公費・後期高齢者支援金・後期高齢者の保険料」です。
今日は、後期高齢者支援金を中心にみていきます。
後期高齢者支援金は、現役世代からの支援金のことです。
では、条文を読んでみましょう。
第100条第1項、4項 (後期高齢者交付金) ① 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。 ④ 後期高齢者交付金は、第118条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもって充てる。 |
★後期高齢者負担率とは
・後期高齢者の保険料で負担する割合で、2年ごとに政令で定められます。令和4年度・5年度は、11.72%です。
★100分の50とは
・公費で負担する割合です
第118条 (後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。 ② 保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。 |
★保険者とは
・医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団です。
後期高齢者医療広域連合 |
↑ 後期高齢者交付金 |
社会保険診療報酬支払基金 |
↑ 後期高齢者支援金等 |
保険者 |
↑ 保険料 |
医療保険の被保険者(現役世代) |
★高齢者医療の財政のうち、後期高齢者支援金(現役世代からの支援)の占める割合は約4割です。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】(※改正による修正あり)
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
②【H22年出題】
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。

【解答】
①【H28年出題】(※改正による修正あり) ×
保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは、都道府県ではなく、「社会保険診療報酬支払基金」です。
②【H22年出題】 ×
国が交付する調整交付金は、3分の1ではなく「12分の1」です。
(法第95条)
★公費について
(国の負担)
・負担対象額の12分の3+調整交付金(負担対象額の12分の1)
(都道府県の負担)
・負担対象額の12分の1
(市町村の一般会計における負担)
・負担対象額の12分の1
(法第93条、95条、96条、98条)
12分の3+12分の1+12分の1+12分の1=「12分の6」です。公費が占める割合は約50%となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働一般常識 判例より
労働一般常識 判例より
R5-274
R5.5.28 在籍出向を命ずる場合の同意について
在籍出向を命ずる際に、労働者の個別の同意は必要でしょうか?
★在籍出向とは?
・出向元の企業と出向先の企業は出向契約、労働者は、出向元の企業と出向先の企業のそれぞれと雇用契約を結びます。
さっそく過去問をどうぞ!
【H28年出題】
いわゆる在籍出向においては、就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は、当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【H28年出題】 ×
「新日本製鐵事件(H15.04.18最二小判)」からの出題です。
就業規則にも労働協約にも、出向に関する詳細な規定が設けられていることがポイントです。
・就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定がある
・労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられている
↓
使用者は、労働者の「個別的同意なし」に、在籍出向を命ずることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 滞納処分
厚生年金保険法 滞納処分
R5-273
R5.5.27 厚年 滞納処分
保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときの滞納処分についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第86条第5項、6項 ⑤ 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、指定都市にあっては、区又は総合区とする。)に対して、その処分を請求することができる。 1 督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。 2 繰上徴収の要件のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
⑥ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
厚生年金保険法第86条の規定によると、厚生労働大臣は、保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができ、当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならないとされている。
②【H25年出題】
厚生労働大臣は、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないとき、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
厚生労働大臣は、期限を指定して督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないときは、納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができます。
市町村が市町村税の例によって処分したときは、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければなりません。
②【H25年出題】 〇
納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が、その指定の期限までに保険料を納付しないときも滞納処分の対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 督促
厚生年金保険法 督促
R5-272
R5.5.26 厚生年金保険料等の督促
厚生年金保険の保険料等を滞納した者に対する督促の手続をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項~4項 (保険料等の督促) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状は、納付義務者が、健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 ④ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、繰上徴収の要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
②【H25年出題】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
③【H25年出題】
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
④【R1年選択】
保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合には、厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを督促しなければならないが、この期限は、督促状を< A >以上を経過した日でなければならない。
(選択肢)
① 受領した日から起算して10日
② 受領した日から起算して20日
③ 発する日から起算して10日
④ 発する日から起算して20日

【解答】
①【H25年出題】 〇
保険料の繰上徴収の規定により保険料を徴収するときは、督促状は発しません。
ちなみに、繰上徴収とは?
条文をチェックしましょう。
第85条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。 1 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 イ 国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。 ロ 強制執行を受けるとき。 ハ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ニ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ホ 競売の開始があったとき。 2 法人たる納付義務者が、解散をした場合 3 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 4 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至った場合 |
②【H25年出題】 ×
保険料等の督促状は、納付義務者が健康保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、「同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。」です。「代えることができる」ではありません。
③【H25年出題】 〇
督促状により指定する期限の、「督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日」は覚えましょう。
④【R1年選択】
A ③ 発する日から起算して10日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金の繰上げ
国民年金法 老齢基礎年金の繰上げ
R5-271
R5.5.25 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権の発生
「繰上げ支給」の受給権の発生について、ご質問がありました。
今回のテーマは、繰上げ支給の条文の読み方です。
老齢基礎年金の受給権は、要件を満たせば65歳に達した日に発生します。
しかし、請求することにより、60歳から65歳になるまでの間に、繰り上げて受給することもできます。
条文を読んでみましょう。
附則第9条の2第1項~4項 (老齢基礎年金の支給の繰上げ) ① 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る。)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、第26条ただし書に該当したときは、この限りでない。 ② 繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。 ③ 繰上げの請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。 ④ 繰上げにより支給する老齢基礎年金の額は、第27条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。 |
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権は請求することによって発生します。
★「③ 繰上げの請求があったときは、第26条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。」について
・第26条では、老齢基礎年金は、「65歳に達したとき」に支給する、と規定されています。繰上げ請求をした場合は、第26条の規定にかかわらず、「請求があった日」に老齢基礎年金の受給権が発生するという意味です。
こちらの条文も読んでみましょう。
第18条第1項 (年金の支給期間) 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 |
・年金の支給については、第18条第1項で、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から」始める、とありますので、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給は、請求があった日の属する月の翌月から始まります。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
②【H29年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の「翌日」ではなく、「繰上げ請求のあった日」に発生します。
年金の支給は、「受給権発生日(繰上げ請求のあった日)の属する月の翌月」からです。
②【H29年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給は、その請求があった日の属する月の「翌月」分からです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 指定健康保険組合
健康保険法 指定健康保険組合
R5-270
R5.5.24 指定健康保険組合による健全化計画の作成
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第28条 (指定健康保険組合による健全化計画の作成) ① 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ② 承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。 ③ 厚生労働大臣は、承認を受けた指定健康保険組合の事業及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は当該健康保険組合と地域型健康保険組合との合併を命ずることができる。
②【H25年選択式】
健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下、「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする< A >の計画とする。
(選択肢)
① 2年間 ② 3年間 ③ 4年間 ④ 5年間

【解答】
①【H30年出題】 ×
「健康保険組合が準用する第7条の39第1項(監督)の規定による命令に違反したとき、又は前条第2項の規定(健全化計画に従い事業を行わなければならない)に違反した指定健康保険組合、同条第3項の求め(健全化計画の変更の求め)に応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。」と規定されています。(第29条第2項)
健全化計画に従わない場合は、厚生労働大臣は「当該健康保険組合の解散を命ずることができる」です。
②【H25年選択式】
A ② 3年間
健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3年間」の計画とされています。
(令第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 保険関係の消滅
徴収法 保険関係の消滅
R5-269
R5.5.23 事業が廃止又は終了したときは保険関係は翌日に消滅
今日は、保険関係の消滅についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第5条 (保険関係の消滅) 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
「廃止」は継続事業、「終了」は有期事業です。
廃止・終了の日の翌日に、当然に保険関係は消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
②【H27年出題】(労災)
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
③【H23年出題】(労災)
労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業を廃止した場合に、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で、納付すべき確定保険料がないときは、確定保険料申告書を提出する必要はないが、保険関係消滅申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
事業を廃止したときは、保険関係はその翌日に自動的に消滅します。
保険関係廃止届は存在しません。
なお、継続事業の場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出して労働保険料の精算を行わなければなりません。ちなみに、50日以内は「当日起算」です。
(法第19条)
②【H27年出題】 ×
暫定任意適用事業も、事業を廃止した場合には、保険関係はその翌日に自動的に消滅します。保険関係の消滅の申請は不要です。
ちなみに、労災保険も雇用保険も暫定任意適用事業の場合は、加入は事業主の任意ですので、脱退も任意です。
暫定任意適用事業が脱退する場合は、厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限が委任されています。)が必要で、保険関係は、認可があった日の翌日に消滅します。
③【H23年出題】 ×
暫定任意適用事業がその事業を廃止した場合は、自動的に保険関係が消滅しますので、保険関係消滅申請書の提出は不要です。
また、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一でも、確定保険料申告書は提出しなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 特定受給資格者
雇用保険法 特定受給資格者
R5-268
R5.5.22 特定受給資格者に該当する要件
「基本手当」の受給資格や所定給付日数の決定の際に、「特定理由離職者」と「特定受給資格者」が出てきます。
条文を読んでみましょう。
・「特定理由離職者」とは
法第13条第3項 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。 則第19条の2(法第13条第3項の厚生労働省令で定める者) 法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。 1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) 2 正当な理由のある自己都合退職 |
・「特定受給資格者」とは
法第23条第2項 特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者を除く。)をいう。 1 基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの 2 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 |
特定受給資格者は、「倒産等による離職」と「解雇等による離職」の2つに分けられます。
今日は「特定受給資格者」についてみていきます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】(※修正あり)
① 出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
② 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。
③ 事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当する。
④ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、当該労働契約が更新されないこととなったことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当する。

【解答】
① 〇
「事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたこと。」を理由として離職した場合は、特定受給資格者に該当します。(則第36条第5号ホ)
出産後に事業主の法令違反により就業させられたことを理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
② 〇
「事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないこと」を理由として離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第6号)
③ 〇
「事業所において、労働施策総合法第27条第1項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者」は特定受給資格者に該当します。(則第35条第2号)
④ 〇
「期間の定めのある労働契約」について
・ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
・ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと。
上記を理由に離職した者は特定受給資格者に該当します。
(則第36条第7号、7号の2)
★ちなみに・・・
「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)」を理由に離職した者は、「特定理由離職者」となりますが、これは、労働契約の更新又は延長する旨が明示されていない場合です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 受給権の保護
労災保険法 受給権の保護
R5-267
R5.5.21 労災保険給付の受給権の保護
労災保険の保険給付を受ける権利は保護されています。
条文を読んでみましょう。
第12条の5 ① 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 ② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
②【H24年出題】
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
③【R1年出題】
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労働者が退職したとしても、労災保険給付を受ける権利は変わりません。
②【H24年出題】 〇
保険給付を受ける権利は、譲渡、担保に供すること、差押えは禁止されています。
③【R1年出題】 ×
「保険給付」と「社会復帰促進等事業の一環として行われる特別支給金」との違いに注意しましょう。
譲渡、差押えの規定は特別支給金には準用されませんので、特別支給金については譲渡、差押えは禁止されていません。
(特別金支給規則第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 衛生管理者
労働安全衛生法 衛生管理者
R5-266
R5.5.20 衛生管理者の選任要件
業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければなりません。
衛生管理者は、衛生に関する技術的事項を管理します。
今日は、衛生管理者の選任要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第12条第1項 (衛生管理者) 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(総括安全衛生管理者が統括管理する業務)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
則第10条 (厚生労働省令で定める資格) 1 医師 2 歯科医師 3 労働衛生コンサルタント 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
則第7条第3号 (衛生管理者の選任) 衛生管理者は、次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。 ・ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業 ↓ 第1種衛生管理者免許を有する者 衛生工学衛生管理者免許を有する者 則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等)
・ その他の業種 ↓ 第1種衛生管理者免許を有する者 第2種衛生管理者免許を有する者 衛生工学衛生管理者免許を有する者 則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等) |
・衛生管理者は、「都道府県労働局長の免許を受けた者」、「厚生労働省令で定める資格を有する者」のうちから選任しなければなりません。
過去問をどうぞ!
①【令和元年選択式】
衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか< A >などが定められている。
(選択肢)
①衛生管理士 ②看護師 ③作業環境測定士 ④労働衛生コンサルタント
②【H25年選択式】
労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、 砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を< B >のうちから選任」しなければならない旨規定している。
(選択肢)
①衛生工学衛生管理者免許を受けた者 ②第一種衛生管理者免許を受けた者
③第二種衛生管理者免許を受けた者 ④保健師免許を受けた者
③【H24年出題】
常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。

【解答】
①【令和元年選択式】
A ④労働衛生コンサルタント
②【H25年選択式】
B ①衛生工学衛生管理者免許を受けた者
(則第7条第1項第6号)
③【H24年出題】 ×
製造業の事業場の事業者は、「第1種衛生管理者免許を有する者」、「衛生工学衛生管理者免許を有する者」、「則第10条各号に掲げる者(医師、歯科医師等)」から衛生管理者を選任しなければなりません。
製造業の場合は、第2種衛生管理者免許を有するだけでは衛生管理者として選任できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 1年単位の変形労働時間制
労働基準法 1年単位の変形労働時間制
R5-265
R5.5.19 1年単位の変形労働時間制の労働日について
1年単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定で、以下の事項を定めなければなりません。
① 1年単位の変形労働時間の対象になる労働者の範囲 ② 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限るものとする。) ③ 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。) ④ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間 ※対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する場合 ・最初の期間の労働日及び当該労働日ごとの労働時間 ・最初の期間を除く各期間の労働日数及び総労働時間 ⑤ 有効期間の定め |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制の対象期間は、 1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。
②【H22年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
③【H30年出題】
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
1年単位の変形労働時間制の「対象期間」は、「その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限る」とされています。
対象期間の最長は「1年」ですが、3か月や6か月とすることもできます。
②【H22年出題】 ×
労使協定で対象期間における「労働日」と「当該労働日ごとの労働時間」を特定する必要があります。
ただし、対象期間が長くなりますので、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとした場合は、労使協定で、「最初の期間」の「労働日及び当該労働日ごとの労働時間」を特定し、「最初の期間を除く各期間」については、「労働日数及び総労働時間」を定めることもできます。
1か月 (最初の期間) | 1か月 | 1か月 | 1か月 | ・・・ |
・労働日 ・労働日ごとの労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 |
・・・ |
なお、最初の期間を除く各期間については、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、書面で、各期間における労働日及び各期間における労働日ごとの労働時間を定めることとされています。
③【H30年出題】 〇
労働日と労働日ごとの労働時間はあらかじめ特定しなければなりません。
労働日を特定することは、反面、休日を特定することでもあります。
問題文のように、変形期間開始後にしか休日が特定できない場合は、労働日が特定されたことにはなりません。
(H6.5.31基発330号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者医療確保法 特定健康診査
高齢者医療確保法 特定健康診査
R5-264
R5.5.18 高齢者医療確保法 40歳以上の加入者に対する特定健康診査
特定健康診査は、40歳から74歳の人を対象に、生活習慣病を予防するために行われます。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
第19条第1項 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
第20条(特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 |
高齢者医療確保法で「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。(法第7条第2項)
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
・ 厚生労働大臣は、< A >(糖尿病その他の政令で定める< B >に関する健康診査をいう。)及び< C >の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「< A >等基本指針」という。)を定めるものとする。
・ 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、< A >等基本指針に即して、< D >年ごとに、< D >年を1期として、< A >等実施計画を定めるものとする。
・ 保険者は、< A >等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< E >歳以上の加入者に対し、< A >を行うものとする。

【解答】
A 特定健康診査
B 生活習慣病
C 特定保健指導
D 6
E 40
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(改正による修正あり)
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。
②【H29年出題】(改正による修正あり)
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定めます。
↓
保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めます。
↓
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行います。
②【H29年出題】 〇
高齢者医療確保法における保険者は、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法 労働契約の成立
労働契約法 労働契約の成立
R5-263
R5.5.17 労働契約法 労働契約の成立要件
労働契約法の「労働契約が成立する要件」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
労働契約法第6条 (労働契約の成立) 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 |
労働契約の成立は、労働者と使用者の合意によります。
合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働」すること、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」です。
(参照 H24.8.10 基発0810第2号)
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。

【解答】
【H28年出題】 ×
労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみで成立します。
契約内容について書面を交付することまでは求められません。
(参照 H24.8.10 基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 厚生年金保険原簿
厚生年金保険法 厚生年金保険原簿
R5-262
R5.5.16 厚生年金保険原簿の訂正の請求
例えば、「ある会社で働いたことがあるのに、厚生年金保険の記録がない」、「標準報酬月額が違う」など、年金記録が事実と異なっていると思うときは、厚生労働大臣に年金記録の訂正を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
第28条 (記録) 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)、基礎年金番号その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
第28条の2第1項 (訂正の請求) 第1号厚生年金被保険者であり、又はあった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。 |
★「実施機関」は、被保険者に関する原簿を備え、一定事項を記録します。
★「厚生労働大臣」に、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるのは、第1号厚生年金被保険者である者、又は第1号厚生年金被保険者であった者です。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(以下本問において「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
②【H30年出題】
第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
③【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
④【H30年出題】
厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
この問題のチェックポイントは、訂正請求ができるのは、「第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者」であることです。
②【H30年出題】 〇
訂正請求の対象になるのは、第1号厚生年金被保険者に係る記録です。
第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合)、第4号厚生年金被保険者(日本私立学校振興・共済事業団)に係る期間は、訂正請求の対象外です。
③【H30年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者であった者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族はその死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができます。
また、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者も、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができます。
④【H30年出題】 〇
条文を確認しましょう。
法第28条の3
① 厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
② 厚生労働大臣は、①の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 老齢厚生年金の繰上げ
厚生年金保険法 老齢厚生年金の繰上げ
R5-261
R5.5.15 繰上げ支給の老齢厚生年金の額の改定
厚生年金保険の被保険者期間を1か月でも有し、かつ、国民年金の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上ある場合は、65歳に達したときに老齢厚生年金の受給権が発生します。
老齢厚生年金は繰り上げて支給を受けることもできます。
老齢厚生年金の繰上げ受給を受けながら在職している場合の老齢厚生年金の額の改定についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
法附則第7条の3第1項~5項 ① 当分の間、次の各号に掲げる者であって、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金法の規定による任意加入被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、65歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があった日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が10年以上でないときは、この限りでない。 1. 男子又は女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和36年4月2日以後に生まれた者 2. 女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和41年4月2日以後に生まれた者 (3.、4.は省略します) ② 繰上げの請求は、国民年金法に規定する老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、これらの請求と同時に行わなければならない。 ③ 繰上げの請求があったときは、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 ④ 繰上げ支給の老齢厚生年金の額は、老齢厚生年金の額から政令で定める額を減じた額とする。 ⑤ 繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者であって、繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有するものが65歳に達したときは、65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
・①について
1.(男子・女子(2号、3号、4号)と2.(女子(1号))は、特別支給の老齢厚生年金が支給されない人です。老齢厚生年金は65歳から支給されます。
・②について
老齢厚生年金の繰上げ請求は、老齢基礎年金と同時に行います。
・⑤について
繰上げ請求後65歳になる前に、厚生年金保険の被保険者期間を有した場合、その期間は65歳時点で、年金額に反映します。
例えば、60歳で老齢厚生年金を繰上げ受給し、その後、62歳から64歳まで厚生年金保険の被保険者だった場合は、その期間分は、65歳到達時の改定で年金額に反映します。
過去問をどうぞ!
【H30年出題】
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65歳に達したときは、その者が65歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

【解答】
【H30年出題】 〇
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者で、繰上げの請求があった日以後に被保険者期間を有する場合は、65歳に達したときに、65歳に達した日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算に算入します。
年金額の改定は、65歳に達した日の属する月の翌月からとなります。
(法附則第7条の3第5項)
※繰上げ支給の老齢厚生年金の受給者については、65歳以降は、在職定時改定、退職改定が適用されます。
(法附則第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-260
R5.5.14 年金額の改定と加給年金額
65歳で老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、生計を維持されている配偶者又は子がいる場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
ただし、その老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上で計算されていることが条件です。(中高齢の期間短縮特例を満たしている場合は15年~19年となります)
今日は、65歳時点では20年未満だった人が、その後、在職し厚生年金保険の被保険者期間が20年になった場合の加給年金額についてみていきます。
では、条文を読んでみましょう。
第44条第1項 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職時改定又は退職改定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、老齢厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
★ 被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の権利を取得した当時、受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
★ 老齢厚生年金の権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満だったとき
↓
その後在職し、「在職時改定」又は「退職改定」により240月以上となるに至った当時、その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、加給年金額が加算されます。
※在職により被保険者期間が増え、増えた期間分が老齢厚生年金に反映されるのは、在職時改定又は退職改定のタイミングです。その際に、240月以上となり、生計維持されている配偶者又は子がいるときは、加給年金額が加算されます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。

【解答】
【H30年出題】 ×
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、被保険者期間の月数が240未満であったとしても、その後在職(=厚生年金保険の被保険者として保険料を負担すること)し、被保険者資格を喪失した際の退職改定で、被保険者期間の月数が240以上になった場合は、加給年金額の加算の対象となります。
240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいて生計維持関係が認められた場合は、加給年金額が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算の支給停止
国民年金法 振替加算の支給停止
R5-259
R5.5.13 障害年金を受けることができるときの振替加算
障害基礎年金などの支給を受けることができるときは、その間、振替加算は支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
S60年法附則第16条第1項 振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給を停止する。 |
★ 「障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの」は、障害基礎年金、障害厚生年金などで、その全額につき支給を停止されている給付は除かれます。
(S61年経過措置政令第28条)
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
②【H21年出題】
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合においても、振替加算に相当する部分の支給は停止される。
③【R1年出題】
障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険者期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。

【解答】
①【H30年出題】 〇
障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていないものとする。)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額の支給は停止されます。
②【H21年出題】 ×
振替加算が行われている老齢基礎年金の受給権者が、障害基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、振替加算額の支給は停止されます。
しかし、当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合は、振替加算の支給は停止されません。
③【R1年出題】 〇
障害基礎年金を受給している間は、振替加算の支給は停止されます。
しかし、障害基礎年金の全額が支給停止されている場合は、振替加算の支給は停止されません。
問題文のように、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、障害基礎年金は全額支給停止となりますので、老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算に相当する額の老齢基礎年金
国民年金法 振替加算に相当する額の老齢基礎年金
R5-258
R5.5.12 振替加算に相当する額のみの老齢基礎年金が支給されるとき
合算対象期間、学生納付特例期間は老齢基礎年金の額には反映しません。
例えば、20歳から60歳まですべて合算対象期間の場合は、老齢基礎年金の支給期間は満たしているものの、年金額はゼロです。しかし、振替加算の要件に該当する場合は、「振替加算に相当する額の老齢基礎年金」が支給されます。
条文を読んでみましょう。
(S60年法附則第15条第1項) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有さず、かつ、次の各号のいずれかに該当するものが、同日において加給年金額が加算される老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、この限りでない。 1. 合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間が、10年以上であること。 2. 附則第12条第1項第2号から第7号まで及び第18号から第20号までのいずれかに該当すること。 |
「振替加算に相当する額の老齢基礎年金」が支給される要件のポイント!
・「保険料納付済期間」及び「保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)」を有しない。
・「合算対象期間」と「保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)」とを合算した期間が、10年以上あること
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は、20歳から60歳まで海外に居住し、その期間はすべて合算対象期間であった。また、60歳以降も国民年金に加入していなかった。その後、甲が61歳の時に、厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し、65歳まで継続して乙に生計を維持され、乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合、甲が65歳になると老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額の老齢基礎年金が支給される。

【解答】
【H27年出題】 〇
甲は、40年間全て合算対象期間ですので老齢基礎年金の額はゼロです。
しかし振替加算の支給要件には該当しますので、老齢基礎年金の受給要件に該当するものとみなされ、振替加算額に相当する額のみの老齢基礎年金が支給されます。
★注意しましょう★
例えば、20歳から60歳までの間に、保険料納付済期間を1か月有し、他は全て合算対象期間の人が、老齢基礎年金の受給権を有した場合は、480分の1で計算された老齢基礎年金が支給されます。
そのような人が、振替加算の支給要件に該当している場合は、480分の1の老齢基礎年金と振替加算が支給されます。
振替加算額に相当する額のみの老齢基礎年金が支給されるのは、老齢基礎年金の額に反映しない合算対象期間と学生納付特例の期間のみを有する人です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算の加算要件
国民年金法 振替加算の加算要件
R5-257
R5.5.11 240月以上の老齢厚生年金を受けることができる場合の振替加算
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金、退職共済年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるもの又は中高齢の期間短縮特例を満たしているものに限る。)を受けることができる場合は、振替加算は加算されません。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条)
さっそく、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする。)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない。
②【R3年出題】
41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生まれ)は、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である。妻には、22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生まれ)がいる。当該夫が65歳になり、老齢厚生年金の受給権が発生した時点において、妻の年間収入が850万円未満であり、かつ、夫と生計を同じくしていた場合は、当該妻に振替加算が行われる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
老齢基礎年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金又は中高齢の期間短縮特例を満たした老齢厚生年金を受けることができるときは、老齢基礎年金に振替加算は加算されません。
★老齢厚生年金を受けていても、被保険者期間の月数が240月未満の場合又は中高齢の期間短縮特例を満たしていない場合は、振替加算が加算されます。
(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第25条)
②【R3年出題】 ×
昭和26年3月2日生まれの女性の場合、35歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が19年あれば、中高齢の期間短縮特例を満たします。
問題文の妻は、41歳から60歳までの19年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有し、中高齢の期間短縮特例に該当しますので振替加算は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算を受けるための手続
国民年金法 振替加算を受けるための手続
R5-256
R5.5.10 振替加算「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」
振替加算を受けるための手続をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
則第17条の3 老齢基礎年金の受給権者は、昭和60年改正法附則第14条第2項又は第18条第3項の規定に該当するに至ったときは、一定の事項を記載した届書に一定の書類を添えて、速やかに、これを機構に提出しなければならない。 |
「昭和60年改正法附則第14条第2項」では、老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した後に、配偶者が厚生年金保険の被保険者期間が240月(中高齢の期間短縮特例の場合も含みます)を満たした老齢厚生年金を受けられるようになった場合は、老齢基礎年金に振替加算が加算されると規定されています。
夫
65歳 退職時改定
(240月未満) (240月)
|
|
老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | |
妻(老齢基礎年金の受給権者)
65歳
| 振替加算 |
老齢基礎年金 | |
このような場合は、振替加算の支給を受けるために、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生まれ)が、厚生年金保険法第43条第3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合、夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生まれ)は、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することにより、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
【H27年出題】 〇
妻が65歳に達した後に、夫が退職時改定により、加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たしたことがポイントです。
この場合、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出することによって、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算と繰上げ繰下げ
国民年金法 振替加算と繰上げ繰下げ
R5-255
R5.5.9 老齢基礎年金を繰上げ・繰下げた場合の振替加算
老齢基礎年金は要件を満たせば、65歳に達したときに受給権が発生しますが、繰り上げて受給することもできますし、繰下げて受給することもできます。
老齢基礎年金を繰上げ・繰下げした場合、振替加算はどのようになるのでしょうか?
振替加算はいつから加算されるのか、条文を読んでみましょう。
S60年法附則第14条第4項 振替加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
②【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
③【R3年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも、振替加算額は繰上げされません。振替加算は、受給権者が65歳に達した日以後でなければ行われません。
夫
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | |
| 加給年金額 |
|
妻
60歳 65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
例えば、老齢基礎年金の受給権者である妻が60歳で老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合でも、振替加算が加算されるのは65歳からです。
なお、夫の老齢厚生年金に加算されている加給年金額は、妻が老齢基礎年金を繰上げした場合でも、65歳になるまで支給されます。
②【H30年出題】 ×
振替加算について
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合 → 65歳に達した日の属する月の翌月から加算されます。(問題文の「請求のあった日の属する月の翌月から加算」は誤りです。)
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合 → 振替加算も繰下げて支給されますので、問題文の通り、申出のあった日の属する月の翌月から加算されます。
③【R3年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されます。ただし、振替加算額は繰下げによる増額はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 振替加算
国民年金法 振替加算
R5-254
R5.5.8 振替加算が加算される要件
老齢基礎年金に振替加算が加算され得るのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人です。
「生年月日」のポイント!
大正15年4月2日以降生まれ→ 新法の対象者です。
昭和41年4月1日以前生まれ → 新法施行日の昭和61年4月1日に20歳以上です。
まず、過去問からどうぞ!
【H30年出題】
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月2日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

【解答】
【H30年出題】 〇
まず、問題文の夫婦の年金を図でイメージしましょう。
(注)妻は、厚生年金保険の被保険者期間を有しないと仮定しています。
夫(昭和25年4月2日生まれ)
60歳 65歳
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | |
| 老齢基礎年金 | |
| 加給年金額 |
|
妻(昭和28年4月2日生まれ)
65歳
振替加算 |
老齢基礎年金 |
★夫について(昭和25年4月2日生まれ)
・60歳から64歳まで → 報酬比例部分のみ支給されます
・65歳から → 老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。
また生計維持関係のある妻がいるため、加給年金額が加算されます。
加給年金額が加算される要件を確認しましょう。
原則として、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上あることが条件です。
問題文の夫の被保険者期間は20年未満ですが、「45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間が19年」で中高齢の期間短縮特例を満たします。240月以上とみなされて加給年金額が加算されます。
★妻について(昭和28年4月2日生まれ)
夫に加算されている加給年金額は、妻が65歳に達したときに終了します。
加給年金額の対象になっていた妻が65歳になり、老齢基礎年金を受けるようになると、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
振替加算が加算される要件を確認しましょう
<老齢基礎年金の受給権者(問題文では「妻」)の要件>
・大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であること
・65歳に達した日に、配偶者によって生計を維持していた(65歳に達した日の前日に配偶者が受給権を有する年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと)
・ただし、妻自身が被保険者期間が原則240月以上で計算される老齢厚生年金、退職共済年金を受けることができるときは、振替加算は加算されません。
<配偶者(問題では「夫」)の要件>
・老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる月数が原則として240以上であるもの)の受給権者
・障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る。)
※加給年金額が加算される年金の受給権者であることが条件です。
振替加算の額を確認しましょう
振替加算の額は、224,700円×改定率×政令で定める率で計算します。
政令で定める率は、大正15年4月2日生まれ~昭和2年4月1日以前生まれが1.000で、年齢が若くなるほど小さくなります。昭和36年4月2日~昭和41年4月1日生まれは、0.067です。
なお、問題文の昭和28年4月2日生まれの妻の振替加算の額は、224,700円×改定率×0.280です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 全国健康保険協会
健康保険法 全国健康保険協会
R5-253
R5.5.7 全国健康保険協会の事業計画や業績評価など
今日は、全国健康保険協会の事業計画や業績評価などをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第7条の27(事業計画等の認可) 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第7条の28(財務諸表等) ① 協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。 ② 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第7条の30(各事業年度に係る業績評価) ① 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。 ② 厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結し、作成した財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
②【H30年出題】
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
③【H23年出題】
全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
毎事業年度の決算は、翌事業年度の5月31日までに完結します。
財務諸表に、事業報告書等を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければなりません。
②【H30年出題】 〇
厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行います。評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければなりません。
③【H23年出題】 ×
全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、評価の結果を通知し、公表しなければならないのは、「全国健康保険協会の理事長」ではなく「厚生労働大臣」です。
また、評価の結果を通知するのは、全国健康保険協会に対してです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法 労働保険事務組合
徴収法 労働保険事務組合
R5-252
R5.5.6 労働保険事務組合 報奨金の支給要件
事業主から委託を受け、労働保険料を正しく納付することが、労働保険事務組合の重要な役割です。
労働保険料の納付状況が著しく良好な労働保険事務組合には、報奨金が支給されます。
今日は、報奨金の支給要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令)第1条第1項 労働保険事務組合が委託を受けてする労働保険料の納付の状況が次の各号に該当するときは、当該労働保険事務組合に対して労働保険料に係る報奨金を交付する。 1. 7月10日において、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。以下「前年度の労働保険料等」という。)であって、常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託に係るものにつき、その確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合にあっては、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。ただし、同日において当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていないことが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、同日後の日で厚生労働大臣が定める日までに当該確定保険料の額の合計額の100分の95以上の額が納付されていること。 2. 前年度の労働保険料等について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないこと。 3. 偽りその他不正の行為により、前年度の労働保険料等の徴収を免れ、又はその還付を受けたことがないこと。 |
さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(雇用)
労働保険事務組合が、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金を含み延滞金を除く。)について国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件とされている。
②【H30年出題】(雇用)
納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、政府から、労働保険料に係る報奨金の交付を受けることができる。
③【H30年出題】(雇用)
労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
④【H30年出題】(雇用)
労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下の額とされている。

【解答】
①【H30年出題】(雇用) ×
労働保険事務組合が報奨金の交付を受ける要件として、前年度の労働保険料について国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがあります。
前年度の労働保険料については、当該労働保険料に係る「追徴金及び延滞金」が含まれます。
②【H30年出題】(雇用) ×
確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべき場合は、確定保険料の額と当該追徴金又は延滞金の額との合計額)の合計額の100分の95以上の額が納付されていることが条件です。
納付すべき労働保険料を完納していた場合に限り、は誤りです。
③【H30年出題】(雇用) ×
労働保険料に係る報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、労働保険事務組合報奨金交付申請書を、「所轄都道府県労働局長」に提出しなければなりません。
なお、申請書は10月15日までに提出しなければなりません。
(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令第2条)
④【H30年出題】(雇用) ×
労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、次のいずれか低い額以内とされています。
・1,000万円
・常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額
労働保険料に係る報奨金の額は、現在、労働保険事務組合ごとに、2千万円以下ではなく、「1千万円以下の額」とされています。
(労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 就職が困難な者
雇用保険法 就職が困難な者
R5-251
R5.5.5 就職困難者のポイント
就職困難者のポイントをおさえましょう。
「就職が困難な者」について条文を読んでみましょう。
則第32条 (法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者) 法第22条第2項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。 ① 障害者雇用促進法に規定する身体障害者 ② 障害者雇用促進法に規定する知的障害者 ③ 障害者雇用促進法に規定する精神障害者 ④ 売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第48条各号又は第85条第1項各号に掲げる者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの ⑤ 社会的事情により就職が著しく阻害されている者 |
就職困難者の所定給付日数は、法第22条第2項で以下のように定められています。
算定基礎期間 離職日の年齢 | 1年未満 | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
雇用保険法施行規則によると、就職が困難な者には障害者の雇用の促進等に関する法律にいう身体障害者、知的障害者が含まれるが、精神障害者は含まれない。
②【H30年出題】
算定基礎期間が1年未満の就職が困難な者に係る基本手当の所定給付日数は150日である。
③【H30年出題】
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者であって、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたる。
④【H30年出題】
就職が困難な者であるかどうかの確認は受給資格決定時になされ、受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれない。
⑤【H30年出題】
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
就職が困難な者には、精神障害者も含まれます。
②【H30年出題】 〇
算定基礎期間が1年未満の就職が困難なものの所定給付日数は、45歳未満でも、45歳以上65歳未満でも150日です。
③【H30年出題】 〇
売春防止法第26条第1項の規定により保護観察に付された者で、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったものは、就職が困難な者にあたります。
④【H30年出題】 〇
就職が困難な者であるかどうかの確認は、受給資格決定時になされます。受給資格決定後に就職が困難なものであると認められる状態が生じた者は、就職が困難な者には含まれません。
(行政手引50304)
⑤【H30年出題】 〇
身体障害者の確認は、求職登録票又は身体障害者手帳のほか、医師の証明書によって行うことができます。
(行政手引50304)
なお、「管轄公共職業安定所の長は、基本手当の支給を受けようとする者が就職が困難な者に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が就職が困難な者に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。」とされています。(則第19条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 傷病補償年金
労災保険法 傷病補償年金
R5-250
R5.5.4 傷病補償年金のポイント
傷病補償年金のポイントをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条の8第3項 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 1. 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級~3級)に該当すること。 |
★療養開始後1年6か月を経過した日に要件に該当するとき
療養開始 1年6か月 治ゆ
療養補償給付 |
| |
休業補償給付 | 傷病補償年金 |
|
| ▲(1~3級) | ||
★療養開始後1年6か月を経過した日後に要件に該当することとなったとき
療養開始 1年6か月 治ゆ
療養補償給付 |
| |
休業補償給付 | 傷病補償年金 |
|
| ▲(1~3級) | ||
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。
②【H29年出題】
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
③【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
④【H29年出題】
傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
労災保険の保険給付は、「請求」によって支給されます。
しかし、傷病補償年金は例外で、請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定されるのがポイントです。
被災した労働者が療養開始後1年6か月を経過した日に要件に該当したときは、所轄労働基準監督署長は、傷病補償年金の支給の決定をしなければなりません。
そのため、労働者は、療養開始後1年6か月経過した日に治っていないときは、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければなりません。
(則第18条の2)
②【H29年出題】 〇
傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態で認定されます。
(則18条第2項)
③【H29年出題】 〇
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級(1から3級)に該当しなくなった場合、傷病補償年金の受給権は消滅します。
その後も療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。休業補償給付は請求が必要ですので注意してください。
療養開始 1年6か月
療養補償給付 | ||
休業補償給付 | 傷病補償年金 | 休業補償給付 |
▲(1~3級) ▲不該当
ちなみに年金は、受給権が消滅した月まで支給されます。
傷病補償年金は傷病等級に該当しなくなった月まで支給され、翌月から休業補償給付が支給されます。
④【H29年出題】 ×
法第18条の2で、「傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。」と規定されていて、傷病等級の変更も所轄労働基準監督署長の職権で行われます。
則第18条の3で、「所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。」となっています。「裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 安全衛生教育
労働安全衛生法 安全衛生教育
R5-249
R5.5.3 派遣労働者に対する安全衛生教育の実施義務
労働安全衛生法には、労働者を新たに雇い入れた場合、又は作業内容を変更した場合の「雇入れ時等の安全衛生教育」、一定の危険又は有害な業務に労働者を就かせる場合の「特別教育」、一定の業種で新たに職務に就くことになった職長等に対する「職長等の教育」の規定があります。
派遣労働者に対する安全衛生教育を実施する義務は、「派遣元」、「派遣先」どちらの事業者にあるのでしょうか?
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
②【H19年出題】
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
③【H27年出題】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

【解答】
①【H27年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育の実施義務は、「派遣元」の事業者に課せられています。派遣労働者と労働契約関係にあるのは派遣元です。派遣元の事業者は、派遣労働者を雇い入れたときに、雇入れ時の安全衛生教育を実施します。
(法第59条第1項、労働者派遣法第45条)
②【H19年出題】 ×
作業内容変更時の安全衛生教育の実施の義務は、「派遣元」事業者と「派遣先」事業者の両方に課せられています。
(法第59条第2項、労働者派遣法第45条)
③【H27年出題】 ×
危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務は、派遣先の事業者のみに課せられています。派遣先で、危険・有害業務に派遣労働者を就かせる場合に、派遣先事業者が実施します。
(法第59条第3項、労働者派遣法第45条)
※ちなみに「職長等教育」については「派遣先事業者」のみに実施が義務づけられています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 解雇
労働基準法 解雇
R5-248
R5.5.2 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
まず、「解雇制限」の条文を読んでみましょう。
第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
<解雇制限期間>
・業務上の傷病のため療養中の期間とその後30日間
・産前産後休業期間とその後の30日間
は、解雇が禁止されています。
★例外
・打切補償を支払う場合
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(→所轄労働基準監督署長の認定が必要です。)
は、解雇制限が解除されます。
今日は、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」をみていきましょう。
ポイント!
「やむを得ない事由」とは
天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由です。
事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともなし難いような状況にある場合をいいます。
(昭63.3.14基発150号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
②【H30年出題】
使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合」は含まれません。
事業場が火災により焼失した場合は、「その他やむを得ない事由」に該当しますが、事業主の故意又は重大な過失に基づく火災の場合は、除かれます。
(昭63.3.14基発150号)
※第19条と第20条の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は、同じ意味です。
②【H30年出題】 ×
税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には該当しません。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 確定拠出年金法 脱退一時金
確定拠出年金法 脱退一時金
R5-247
R5.5.1 確定拠出年金法 脱退一時金の支給要件
確定拠出年金法の給付は、「老齢給付金、障害給付金、死亡一時金」ですが、「当分の間、脱退一時金の支給を請求することができる」とされています。
今日は、脱退一時金の要件をみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
「企業型年金」と「個人型年金」がありますが、今回は「個人型」です。
附則第3条第1項、施行令第60条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 1. 60歳未満であること。 2. 企業型年金加入者でないこと。 3. 個人型年金に加入できない者であること。 4. 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。 5. 障害給付金の受給権者でないこと。 6. その者の通算拠出期間が1月以上5年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること。 7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。 |
ポイント!
3.について
個人型年金に加入できない者とは
・国民年金第1号被保険者で、保険料の申請免除の対象者、生活保護法による生活扶助を受ける法定免除の対象者
・日本国籍を有しない海外居住者
4.について
国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者とは
・国民年金の任意加入被保険者のうち「日本国籍を有する海外居住者」です。
★ 令和4年5月から、外国籍の人が海外に居住し、国民年金の被保険者になることができなくなった場合に、要件を満たせば、脱退一時金を請求することができるようになりました。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては < A >に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
1. < B >歳未満であること。
2. 企業型年金加入者でないこと。
3. 個人型年金に加入できない者であること。
4. 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。
5. 障害給付金の受給権者でないこと。
6. その者の通算拠出期間が< C >以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が< D >円以下であること。
7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < E >年を経過していないこと。

【解答】
A 個人型記録関連運営管理機関
B60
C1月以上5年
D25万
E 2
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】
【H29年出題】 ×
通算拠出期間については「1月以上5年以下」であること、又は個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については「25万円以下」であることです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法 契約期間中の解雇
労働契約法 契約期間中の解雇
R5-246
R5.4.30 契約期間中はやむを得ない事由があるときに該当しない場合は解雇できない
有期労働契約期間中の解雇のルールをみていきます。
有期労働契約中の解雇について、民法では以下のように定められています。
民法第628条 (やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 |
民法では、「やむを得ない事由があるとき」について規定されていますが、「やむを得ない事由があるときに該当しない」場合の取扱いは明らかになっていません。
「やむを得ない事由があるときに該当しない」場合は、解雇できないことを明らかにしているのが、労働契約法第17条です。
条文を読んでみましょう。
第17条第1項 (契約期間中の解雇等) 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 |
使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中は有期契約労働者を解雇することができないことを規定しています。
参照 H24.8.10基発0810第2号
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
使用者は、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合であっても、その契約が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない。
②【H28年出題】
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。
③【R1年出題】
有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合、当該事由に該当することをもって労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される。

【解答】
①【H22年出題】 ×
有期労働契約の期間中でも、「やむを得ない事由がある」場合は、労働者を解雇することができます。
②【H28年出題】 〇
契約期間は労働者と使用者が合意により決定したもので、遵守されるべきものです。
そのため、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されます。
(H24.8.10基発0810第2号)
③【R1年出題】 〇
契約期間中でも一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合であっても、当該事由に該当することをもって法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではありません。
実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断されます。
(H24.8.10基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金の支給停止
厚生年金保険法 遺族厚生年金の支給停止
R5-245
R5.4.29 子に対する遺族厚生年金の支給停止
遺族厚生年金には、いくつかの支給停止事由が設けられています。
今日は、第66条第1項の「子」に関しての支給停止の規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第66条第1項 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文(60歳までの支給停止)、次項本文(配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合)又は次条(所在不明の場合)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
例えば、厚生年金保険の被保険者が死亡し、死亡の当時、その者によって生計を維持していた配偶者と子がいる場合は、「配偶者と子」に遺族厚生年金の受給権が発生します。
配偶者と子に受給権が発生したときの調整規定です。
★「子」に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する間、支給停止されます。 → 「配偶者」が遺族厚生年金を受給します。
★次に当てはまる場合は、「子」の支給停止が解除され、子に遺族厚生年金が支給されます。
・遺族基礎年金の受給権がない夫の遺族厚生年金が60歳まで支給停止されているとき
・配偶者が遺族基礎年金の受給権を有せず、子が遺族基礎年金の受給権を有する場合で配偶者の遺族厚生年金が支給停止されているとき
・配偶者の所在が1年以上明らかでなく、配偶者の遺族厚生年金が支給停止されているとき
過去問では、「配偶者の遺族厚生年金が支給停止」されていても、子の支給停止は解除されないパターンがよく出ていますので注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
②【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
③【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。
【解答】
①【H26年出題】 〇
被保険者の死亡で、妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間は、子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。
★妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているとき
→ 子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。(引き続き支給停止されます。)
②【H30年出題】 ×
①の問題と同じです。
★妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたとき
→ 子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。(引き続き支給停止されます。)
③【R3年出題】 ×
★妻が、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金が全額支給停止となったとき
→ 子の遺族厚生年金の支給停止は解除されません。(引き続き支給停止されます。)
→ ちなみに、子の「遺族基礎年金」についても、引き続き支給停止されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 20歳前に初診日がある場合
国民年金法 20歳前に初診日がある場合
R5-244
R5.4.28 20歳前傷病による障害基礎年金の支給要件
20歳前に初診日がある場合(=国民年金加入前に初診日がある場合)は、第30条の4の20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を拠出しないで支給される年金ですので、通常の障害基礎年金とは異なる支給停止事由が設定されているのが特徴です。
では、条文を読んでみましょう。
第30条の4第1項 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 |
★障害認定日が20歳前にある場合
初診日 | 障害認定日 |
| 20歳 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「20歳に達した日」に障害基礎年金の受給権が発生します
★障害認定日が20歳後にある場合
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「障害認定日」に障害基礎年金の受給権が発生します
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。
②【H26年出題】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
③【H22年出題】
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

【解答】
①【H30年出題】 ×
傷病の初診日に19歳の者に支給されるのは「20歳前傷病による障害基礎年金」です。「20歳前傷病による障害基礎年金」は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないので、保険料納付要件は問われません。
20歳で第1号被保険者の資格を取得した後の未納期間は、20歳前の傷病による障害基礎年金の受給要件には関係ありません。
問題文の場合は、初診日から1年6か月経過後の障害認定日に障害等級1級又は2級に該当していた場合は、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。
②【H26年出題】 ×
障害認定日は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」又は、「1年6か月以内に傷病が治った場合その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)」です。
問題文の場合、初診日から継続して治療しています(治っていない)ので、障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」となります。
初診日が19歳ですので、障害認定日は20歳に達した後になります。
初診日 |
| 20歳 | 障害認定日 |
|
|
| 障害基礎年金 |
「20歳に達した日」ではなく、「障害認定日」に障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生します。
③【H22年出題】 ×
初診日に20歳未満でも、厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)である場合は、障害基礎年金の初診日要件(初診日に国民年金の被保険者であること)を満たしています。
そのため、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。
障害認定日が20歳未満でも「障害認定日」に、「障害基礎年金と障害厚生年金」の受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 国や地方公共団体の負担との調整
健康保険法 国や地方公共団体の負担との調整
R5-243
R5.4.27 国や地方公共団体が医療費を負担する場合の調整
例えば、災害時などに、国や地方公共団体が医療費を負担する場合があります。
そのような場合の健康保険の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第55条第4項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。 |
まず、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
公害健康被害の補償等に関する法律(以下本問において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。
②【H30年出題】
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
③【H16年出題】
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。

【解答】
①【R3年出題】 〇
例えば水質汚濁等の公害で病気になった場合は、公害補償法の制度で療養の給付などの補償が行われます。
公害補償法で、補償給付の支給がされた場合は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、健康保険による保険給付は行わない、とされています。
(公害補償法第14条、昭50.12.8保険発第110号・庁保険発第20号)
②【H30年出題】 〇
災害救助法の目的は、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ること」です。
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われません。
③【H16年出題】 〇
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類の保護があります。
生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付では、健康保険による保険給付が優先されます。
費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分は、医療扶助の対象となります。
健康保険からの保険給付 | 自己負担分 (医療扶助の給付対象) |
(生活保護法第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 介護保険との関係
健康保険法 介護保険との関係
R5-242
R5.4.26 健康保険と介護保険の給付との調整
介護保険には、医療を提供するサービスもあります。
健康保険と介護保険の医療の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第55条第3項 (他の法令による保険給付との調整) 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
同一の病気やけがについて、介護保険から給付を受けることができる場合は、健康保険の給付は行われません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
②【H22年出題】
被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
③【R4年出題】
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る療養については、医療保険から行うものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
同一の傷病で、介護保険の給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われません。
②【H22年出題】 ×
同一の「疾病、負傷または死亡」の「死亡」の部分が誤りです。介護保険には死亡に関する給付がありませんので、死亡については介護保険との調整は行われません。
③【R4年出題】 〇
介護保険適用病床に入院している要介護者である患者が、急性憎悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合は、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則です。
しかし、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のある場合は、当該病床で療養の給付又は医療が行われることは可能です。
この場合の緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされています。
(H12.3.31保険発第55号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 労災との関係
健康保険法 労災との関係
R5-241
R5.4.25 健康保険と労災保険の調整について
健康保険では、被保険者と被扶養者の「疾病、負傷、死亡、出産」について保険給付を行います。
ただし、労災保険法に規定する「業務災害」にあたるものは、健康保険の対象から除外されます。
「通勤災害」については、健康保険からは除外されていませんが、労災保険から給付を受けることができる場合は、調整が行われます。
では、条文を読んでみましょう。
第55条 第1項(他の法令による保険給付との調整) 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
例えば、通勤途上で事故にあい、労災保険の通勤災害に関する保険給付の受給権を得た場合は、健康保険法からの給付は行われません。
労災保険と健康保険の調整が行われるのは、労災保険法に基づく給付を「受けることができる」ときです。「受けたとき」ではありませんので、労災保険の給付の受給権があれば調整の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。
②【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
③【R1年出題】
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険により給付する。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われない。
④【R3年出題】
被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「同一の疾病、負傷又は死亡」について、労働者災害補償保険法の規定により給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われません。
被保険者が通勤途上の事故で死亡し、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合は、健康保険の埋葬料は支給されません。
②【H28年出題】 〇
請負で働く場合は労働契約関係にないので、労災保険の対象にはなりません。そのため、請負業務中に負傷しても労災保険から保険給付が行われません。そのような場合は、健康保険の給付が行われます。
(平成25.8.14事務連絡)
③【R1年出題】 〇
・事業所について、労災保険が適用されるべきであるにもかかわらず、その適用が行われていない場合、その間に発生した通勤災害については、遡って労災保険から給付されます。
・労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害については、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものは、健康保険から給付が行われます。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われません。
(S48.12.1保険発第105号・庁保険発第24号)
④【R3年出題】 〇
労災保険法における業務災害は、健康保険の給付の対象外です。
また、労災保険法における通勤災害は、労災保険からの給付が優先されます。
そのため、保険者は、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができます。
(平成25.8.14事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 口座振替
労働保険徴収法 口座振替
R5-240
R5.4.24 労働保険料の口座振替について
事業主が、労働保険料を口座振替で納付することを希望した場合のポイントを見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第21条の2第1項 (口座振替による納付等) 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下単に「労働保険料」という。)の納付(厚生労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
則第38条の2 口座振替による納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない。 則第38条の4 口座振替による納付の対象は、納付書によって行われる概算保険料及び延納する場合における概算保険料並びに確定保険料の不足額とする。 |
では、過去問をどうぞ!
なお、問題文の「労働保険料」から印紙保険料は除きます。
①【H30年出題】(労災)
口座振替により納付することができる労働保険料は、納付書により行われる概算保険料(延納する場合を除く。)と確定保険料である。
②【H30年出題】(労災)
口座振替による労働保険料の納付が承認された事業主は、概算保険料申告書及び確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するが、この場合には労働基準監督署を経由して提出することはできない。
③【H30年出題】(労災)
労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。
④【H30年出題】(労災)
労働保険料の口座振替の承認は、労働保険料の納付が確実と認められれば、法律上、必ず行われることとなっている。
⑤【H30年出題】(労災)
労働保険料の追徴金の納付については、口座振替による納付の対象とならない。

【解答】
①【H30年出題】(労災) ×
延納される概算保険料も口座振替による納付の対象です。
②【H30年出題】(労災) ×
口座振替による労働保険料の納付が承認されたからといって、労働基準監督署を経由できなくなることはありません。
一定の場合は、労働基準監督署を経由することもできます。
③【H30年出題】(労災) ×
増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となりません。
④【H30年出題】(労災) ×
その納付が確実と認められ、「かつ」、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限って、事業主からの申出を承認することができます。承認することができる、ですので、法律上、必ず行われるものではありません。
⑤【H30年出題】(労災) 〇
追徴金の納付については、口座振替による納付の対象となりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 賃金
雇用保険法 賃金
R5-239
R5.4.23 賃金日額の基になる賃金
一般被保険者が失業した場合は、「基本手当」が支給されます。
基本手当の額は、在職中の「賃金」に基づいて算定されます。
今日は、「賃金」の定義と範囲を確認しましょう。
では、「賃金」の定義を条文で読んでみましょう。
第4条第4項、5項 ④ 雇用保険法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ⑤ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
則第2条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) ① 賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。 ② 通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。 |
★労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものを「賃金」と定義します。
★「通貨以外のもので支払われるもの(現物給与)」で当然に賃金に算入されるのは、「食事、被服及び住居の利益」です。その他の現物給与は、公共職業安定所長が具体的に定めた場合に算入されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、賃金と認められる。
②【H30年出題】
接客係等が客からもらうチップは、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金と認められる。
③【H30年出題】
月給者が1月分の給与を全額支払われて当該月の中途で退職する場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入される。
④【H30年出題】
支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われない未払賃金のある月については、未払額を除いて賃金額を算定する。

【解答】
①【H30年出題】 ×
健康保険法に基づく傷病手当金は健康保険の給付金ですので、賃金ではありません。また、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付となりますので賃金ではありません。
(行政手引50502(2))
②【H30年出題】 〇
チップは、接客係等が「客からもらう」場合は賃金にはなりませんが、一度事業主の手を経て再分配されるものであれば賃金となります。
(行政手引50502(2))
③【H30年出題】 ×
月給者が月の途中で退職する場合で、その月分の給与が全額支払われている場合、退職日の翌日以後の分に相当する金額は賃金日額の算定の基礎に算入されません。
(行政手引50503(3))
④【H30年出題】 ×
未払賃金のある月は、未払額を含めて賃金額を算定します。
なお、未払額の認定に当たっては、当該労働者の稼働実績、過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみが認定されます。
(行政手引50609(9))
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 二次健康診断等給付
労災保険法 二次健康診断等給付
R5-238
R5.4.22 二次健康診断等給付のポイント
二次健康診断等給付は、脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するために行われます。
事業場で行われる定期健康診断など(一次健康診断)で異常の所見が認められた人が対象です。
二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があります。
二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握する検査で、特定保健指導は、脳・心臓疾患の発症の予防のための面接による保健指導です。
条文を読んでみましょう。
第26条 ① 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断(一般健康診断)又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 ② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 1. 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(①に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。「二次健康診断」という。) 2. 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。) ③ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
②【H30年出題】
特定保健指導は、医師又は歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
③【H30年出題】
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。
④【H30年出題】
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。
⑤【H30年出題】
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
二次健康診断等給付の目的は発症の予防ですので、一次健康診断で既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には行われません。症状を有する場合は、健康保険の保険給付や、労災保険の療養補償給付等の対象になります。
②【H30年出題】 ×
特定保健指導は、医師又は「保健師」による面接によって行われます。
具体的には、「栄養指導」、「運動指導」、「生活指導」が行われます。
③【H30年出題】 〇
既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、特定保健指導は行われません。
④【H30年出題】 〇
二次健康診断の実施の日から「3か月以内」に結果を証明する書面の提出を受けた場合は、事業者は、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければなりません。
(法第27条)
⑤【H30年出題】 〇
二次健康診断等給付は、労働者の請求に基づいて行われます。
現物給付ですので、請求書は健診給付病院等を経由して提出します。所轄労働基準監督署長ではなく、「所轄都道府県労働局長」に提出することがポイントです。
(則第18条の19)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 安全衛生管理体制
労働安全衛生法 安全衛生管理体制
R5-237
R5.4.21 派遣労働者の安全衛生管理体制
事業者には、総括安全衛生管理者等の選任や、安全委員会等の設置などが義務づけられています。
必要な安全衛生管理体制は労働者の人数などによって決まりますが、派遣労働者については、派遣元、派遣先のどちらの事業者が義務を負うのでしょうか?
派遣労働者は、「派遣元」とは労働契約関係、「派遣先」とは指揮命令関係にあります。
事業者としての労働安全衛生法の責任は、原則として労働契約関係にある派遣元にあります。しかし、例えば、現場作業に関することなどは、特例で「派遣先」の事業者に適用されます。また、派遣元、派遣先の両方に適用されるものもあります。
なお、派遣労働者についての労働安全衛生法の適用に関する特例は、労働者派遣法第45条に規定されています。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。
②【H27年出題】
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。
③【H30年出題】
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。
④【H19年出題】
派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

【解答】
①【H19年出題】 ×
★「安全管理者」と「安全委員会」について
現場で安全確保のための措置をとる必要があるため、安全管理者の選任の義務、安全委員会の設置義務ともに、「派遣先事業者」のみに課せられています。
人数は、派遣中の労働者も含めて派遣先で算出します。
ポイント!
安全管理者の選任と、安全委員会の設置の義務は、「派遣先」のみに課せられます。
②【H27年出題】 〇
★「衛生管理者」について
衛生管理者は、派遣元事業者、派遣先事業者のどちらにも選任義務が課せられています。
派遣中の労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」双方の労働者の数に含まれます。
③【H30年出題】 〇
★「総括安全衛生管理者」、「衛生管理者」、「産業医」、「衛生委員会」について
派遣元事業者、派遣先事業者のどちらにも、選任・設置義務が課せられています。
派遣中の労働者については、「派遣元事業場」及び「派遣先事業場」双方の労働者の数に含まれます。
問題文のように、派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて選任・設置しなければなりません。
④【H19年出題】 ×
派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、「派遣先事業者のみ」ではなく、「派遣元事業者」と「派遣先事業者」の双方に課せられています。
ポイント!
「総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医」の選任・「衛生委員会」の設置の義務は、「派遣元」「派遣先」の双方に課せられます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 労働時間
労働基準法 労働時間
R5-236
R5.4.20 「1日」とは?「1週間」とは?
まず、原則の法定労働時間の条文を読んでみましょう。
第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
★法第32条第1項で1週間の法定労働時間を規定し、同条第2項で1日の法定労働時間を規定しています。
労働時間の規制は1週間単位の規制を基本として1週間の労働時間を短縮し、1日の労働時間は1週間の労働時間を各日に割り振る場合の上限とする考え方です。
(昭63.1.1基発第1号)
「1週間」と「1日」の考え方をみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。
②【H30年出題】
労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。
日をまたがって継続勤務した場合は、暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われます。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とします。
例えば、4月20日(木)、21日(金)のどちらも労働日で、始業時刻が9時の場合で考えてみましょう
4月20日(木) | 4月21日(金) | |||
| 始 |
| 始 | |
20日の残業が21日の午前3時まで及んだ場合、21日の午前3時までの労働は、始業時刻の属する日(20日)の勤務における1日の労働となります。
(昭63.1.1基発第1号)
②【H30年出題】 〇
1週間とは、「就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週」をいいます。
何曜から始まる1週間とするかについて、就業規則等で別に定めることもできます。
(昭63.1.1基発第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律
R5-235
R5.4.19 後期高齢者医療制度の基本
後期高齢者医療は、原則として75歳以上の人を被保険者としています。
後期高齢者医療は、「後期高齢者支援金(現役世代からの支援金)」と「公費」と「被保険者の保険料」で賄われています。高齢者も被保険者として保険料を負担していることがポイントです。
条文を読んでみましょう。
第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1. 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 2.1.に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
②【H29年出題】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入して設けられる。
③【H22年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
④【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】
①【H29年出題】 ×
後期高齢者医療は、高齢者の「疾病、負傷又は死亡」に関して必要な給付を行います。死亡に関しても給付を行います。
②【H29年出題】 〇
後期高齢者医療制度を運営するのは、後期高齢者医療広域連合です。後期高齢者医療広域連合は都道府県単位の広域連合で、当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入しています。
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務を処理しますが、「保険料の徴収の事務」は除かれていることに注意してください。
保険料の徴収は、市町村が行います。
③【H22年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「75」歳以上の者、または65歳以上「75」歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者です。
④【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療の被保険者になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法
労働契約法
R5-234
R5.4.18 使用者の安全配慮義務
労働契約法には、使用者の「安全配慮義務」の規定があります。
条文を読んでみましょう。
第5条 (労働者の安全への配慮) 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 |
第5条の趣旨を確認しましょう。
通常、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具等を用いて労働に従事します。判例では、労働契約の内容として具体的に定めなくても、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を負っているものとされています。
しかし、このことは、民法等の規定からは明らかになっていませんので、労働契約法第5条で、使用者は当然に安全配慮義務を負うことが規定されています。
(参照:H24.8.10基発0810第2号)
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
使用者は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に、安全配慮義務を負う。
②【H24年出題】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされている。
③【H28年出題】
労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を求めているが、その内容は一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
第5条の内容をみてみましょう。
・ 使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほか、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮義務を負うことを規定しています。
・ 法第5条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくても、労働契約上の付随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものです。
(参照:H24.8.10基発0810第2号)
②【H24年出題】 〇
なお、法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれます。
(参照:H24.8.10基発0810第2号)
③【H28年出題】 〇
「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではありませんが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められます。
(参照:H24.8.10基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法
労働契約法
R5-233
R5.4.17 使用者が労働者を懲戒する場合
労働契約法の懲戒の規定を読んでみましょう。
第15条 (懲戒) 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 |
「懲戒」についての考え方をみてみましょう。
★第15条の趣旨
「懲戒」は、使用者が、企業秩序を維持し、企業の円滑な運営を図るために行われるものです。
しかし、懲戒の権利濫用が争われた裁判例もあり、また、懲戒は労働者に労働契約上の不利益を生じさせるものです。
「権利濫用に該当する懲戒」による紛争を防止するために、「権利濫用に該当」するものとして無効となる懲戒の効力について規定しています。
★内容
① 使用者が労働者を懲戒することができる場合でも、その懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにしています。
権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び態様その他の事情が考慮されます。
② 法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義です。労働基準法第89条では、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられています。
(参照:H24.8.10基発0810第2号)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、その権利を濫用したものとして、無効とされることがある。
②【R1年出題】
労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。
③【H26年出題】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
④【H30年出題】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H24年出題】 〇
使用者が労働者を懲戒することができる場合でも、当該懲戒が、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされます。
②【R1年出題】 〇
労働契約法第15条の「懲戒」は、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同じ意味です。
労働基準法では、制裁は、就業規則の相対的必要記載事項として位置づけられています。事業場に懲戒の「定めがある場合」は、その種類及び程度について就業規則に記載しなければなりません。
③【H26年出題】 〇
最高裁判所の判例のポイントは、次の2点です。
① 使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておかなければならない
② 就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることが必要。
(平成15年10月10日最高裁判所第二小法廷 フジ興産事件)
④【H30年出題】 ×
就業規則に懲戒の種別及び事由を定めておくだけでは足りません。
その内容を、事業場の労働者に周知させる手続が採られていることが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 被保険者期間
厚生年金保険法 被保険者期間
R5-232
R5.4.16 厚年被保険者期間の計算
「被保険者期間」は月単位で計算します。
条文を読んでみましょう。
第19条第1項・2項 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 |
ポイント!
★被保険者期間の計算は「月」単位です。
資格を取得した「月」から資格を喪失した月の「前月」までで計算します。
★同じ月に取得と喪失がある場合は、その月は1か月で計算します。
ただし、その月に、更に「厚生年金保険の被保険者の資格」を取得したとき、「国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者の資格」を取得したときは、先の分は被保険者期間には算入しません。
・資格を取得した月に資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格を取得したとき
1日 末日
取得 A社 喪失 | 取得 B社 |
被保険者期間は、あとのB社の期間だけで1か月となります。
A社では厚生年金保険料は徴収されません。
・資格を取得した月に資格を喪失し、さらにその月に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したとき
1日 末日
取得 A社 喪失 | 第1号被保険者 |
A社の期間は被保険者期間に算入しません。この月は、国民年金の第1号被保険者であった月となります。
A社では厚生年金保険料は徴収されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
②【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
被保険者期間は月単位で計算します。
問題文の被保険者期間は、資格を取得した月(平成29年10月)から、資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの5か月間です。
資格を喪失した月(平成30年3月)は被保険者期間には算入されません。
②【H28年出題】 〇
平成28年3月に、厚生年金保険の被保険者の資格の取得と喪失があり、同じ月に更に国民年金の第1号被保険者となった場合、平成28年3月は、国民年金の第1号被保険者であった月となります。厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-231
R5.4.15 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金額
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金額のポイントをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
法第78条の27(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例) 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして加給年金額の規定を適用する。この場合において、加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。
令第3条の13第2項 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について加給年金額が加算される場合は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金のうち最も早い日において受給権を取得したものについて加給年金額を加算するものとする。 この場合において、当該最も早い日において受給権を取得した老齢厚生年金が2以上あるときは、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間(当該一の期間が2以上ある場合は、次に掲げる順序による。)に基づく老齢厚生年金について加給年金額を加算するものとする。 1.第1号厚生年金被保険者期間 2.第2号厚生年金被保険者期間 3.第3号厚生年金被保険者期間 4.第4号厚生年金被保険者期間 |
ポイント!
★加給年金額が加算される老齢厚生年金は、原則として被保険者期間が240月以上あることが条件です。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その期間を合算します。
★加給年金額が加算される年金は?
「最も早い日」に受給権を取得した老齢厚生年金に加算されます。
↓
「最も早い日」に受給権を取得した年金が2以上あるときは、「厚生年金被保険者期間が最も長い」老齢厚生年金に加算されます。
↓
「最も長い」期間が2以上あるときは、1.第1号→ 2.第2号 →3.第3号 → 4.第4号の順番となります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。
②【H30年出題】
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に、一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり、加給年金額の加算を受けることができる場合は、遅い日において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の加算を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第1号の170か月と第2号の130か月を合算して、被保険者期間が240月以上ありますので、加給年金額が加算されます。
第1号の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権と第2号に基づく老齢厚生年金の受給権を、同じ日に取得した場合は、加給年金額は、被保険者期間が長い方の第1号の被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加算されます。
②【H30年出題】 ×
2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なる場合は、加給年金額は、「早い日」に受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金にのみ加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 特別加算
厚生年金保険法 特別加算
R5-230
R5.4.14 老齢厚生年金の配偶者加給年金額に加算される特別加算
老齢厚生年金(被保険者期間が原則として240月以上)の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される「特別加算」をみていきましょう。
【加給年金額が加算される要件(原則)】
老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あること)の額には、65歳時点(又は定額部分の支給開始時点)で、生計を維持している65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算されます。
(加給年金額の額)
・ 配偶者 → 224,700円×改定率
・ 子 → 1人目、2人目 各224,700円×改定率
3人目以降 各74,900円×改定率
(法第44条第1項、2項)
では、配偶者の加給年金額に加算される「特別加算」について条文を読んでみましょう。
昭60年法附則第60条第2項 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、加給年金額の額(224,700円×改定率)に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
|
ポイント!
・「生年月日」は配偶者ではなく、老齢厚生年金の受給権者の生年月日です
・特別加算が加算されるのは、昭和9年4月2日以降生まれの受給権者です
・特別加算は、生年月日が若い方が額が多いことが特徴です
・昭和18年4月2日以後生まれの人は、一律同じ額です
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
②【H30年出題】
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。
③【H25年出題】
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者加給年金額に加算される特別加算は、「受給権者」の生年月日に応じて行われます。
配偶者の生年月日ではありません。
②【H30年出題】 ×
特別加算の額は、「受給権者の生年月日」に応じて33,200円×改定率から165,800円×改定率の範囲内で決められています。受給権者の生年月日が「遅い」ほど特別加算の額は大きくなります。
③【H25年出題】 〇
配偶者加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権者は99,500円×改定率で、昭和18年4月2日生まれの受給権者は165,800円×改定率です。昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金
国民年金法 老齢基礎年金
R5-229
R5.4.13 任意加入被保険者と第2号被保険者の違い
まず、「保険料納付済期間」の定義を条文で確認しましょう。
第5条第1項 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
■任意加入被保険者について
第2号被保険者でもなく、第3号被保険者でもなく、しかし第1号被保険者にも該当しない人は、国民年金に任意加入することができます。
条文を読んでみましょう。
附則第5条第1項 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3. 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
★任意加入被保険者は、第1号被保険者と同じように保険料を納付します。(ただし、免除は受けられません。)
また、任意加入被保険者として保険料を納付した期間は、第1号被保険者とみなされ、「保険料納付済期間」に算入されます。
■第2号被保険者について
厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者となります。
第2号被保険者は、第1号被保険者・第3号被保険者とは異なり、20歳以上60歳未満の年齢枠がないのがポイントです。
第2号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入されます。
しかし、「老齢基礎年金」については、保険料納付済期間に算入されるのは、「20歳以上60歳未満」の期間だけで、20歳未満、60歳以後の期間は「合算対象期間」となります。
条文を読んでみましょう。
昭60年法附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の支給要件及び老齢基礎年金の年金額については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
※なお、「障害基礎年金」と「遺族基礎年金」については、第2号被保険者の20歳前、60歳以後も保険料納付済期間として扱われます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。

【解答】
【H30年出題】 〇
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、第1号被保険者とみなされ、老齢基礎年金の年金額には、保険料納付済期間として反映します。
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者(=国民年金第2号被保険者)であった期間は、老齢基礎年金の規定では、「合算対象期間」となり、老齢基礎年金の支給要件期間の10年には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 保険料
国民年金法 保険料
R5-228
R5.4.12 令和5年度の国民年金保険料
国民年金の保険料についてみていきましょう。
国民年金の保険料の額は、令和5年度に属する月の月分については、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)となります。
(第87条第3項)
保険料改定率は、前年度保険料改定率×名目賃金変動率で算定します。
※名目賃金変動率=前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率です。
令和5年度の指標は以下の通りです。
前年度保険料改定率 | 0.976 |
前々年の物価変動率 | 0.998 (-0.20%) |
4年前の年度の実質賃金変動率 | 0.998 (-0.20%) |
令和5年度の保険料改定率は、0.976×(0.998×0.998)=0.972となります。
では、問題を解いてみましょう。
(平成30年の過去問を参考にしています。)
【問題】
令和5年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,520円である。

【解答】 〇
令和5年度の国民年金保険料の月額は、
17,000円×保険料改定率(0.972)=16,524円の5円未満を切り捨てた16,520円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 健康保険組合
健康保険法 健康保険組合
R5-227
R5.4.11 健康保険組合の合併・分割・設立事業所の増減・解散の手続
健康保険組合の合併、分割、設立事業所の増減、解散に関しての手続をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第23条第1項 (合併) 健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第24条第1項~2項 (分割) ① 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ② 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。
第25条第1項 (設立事業所の増減) 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
第26条 (解散) ① 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 1.組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 2.健康保険組合の事業の継続の不能 3.厚生労働大臣による解散の命令 ② 健康保険組合は、前項1.又は2.に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ③ 健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。 ④ 協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②【H30年出題】
健康保険組合は、分割しようとするときは、当該健康保険組合に係る適用事業所に使用される被保険者の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
③【R3年出題】
健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。
④【H23年出題】
健康保険組合は、①組合会議員の定数の2分の1以上の組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、のいずれかの理由により解散する。
⑤【H29年出題】
健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
⑥【R3年出題】
健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

【解答】
①【H25年出題】 ×
合併の場合は、組合会において組合会議員の定数の「4分の3」以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
②【H30年出題】 ×
分割の場合は、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
③【R3年出題】 〇
健康保険組合に新しく適用事業所が加入する、又は、健康保険組合に加入している設立事業所が分離するときの手続です。
そのような場合は、その増加又は減少に係る適用事業所の「事業主の全部」及びその適用事業所に使用される「被保険者の2分の1以上の同意」を得なければなりません。
④【H23年出題】 ×
健康保険組合の解散の理由は、①組合会議員の定数の「4分の3」以上の多数による組合会の議決、②健康保険組合の事業の継続の不能、③厚生労働大臣による解散の命令、の3つです。
なお、①と②は「厚生労働大臣の認可」が必要です。③は厚生労働大臣の命令による強制解散ですので、認可は要りません。
⑤【H29年出題】 〇
解散により消滅した健康保険組合の権利義務は、「全国健康保険協会」が承継します。
⑥【R3年出題】 〇
健康保険組合が解散する場合に、健康保険組合の財産をもって債務を完済できないときは、「設立事業所の事業主」に対し、債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができます。
健康保険組合と事業主との連帯責任の規定ですので、「被保険者」に対しては負担を求めることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 継続事業の一括
労働保険徴収法 継続事業の一括
R5-226
R5.4.10 継続事業の一括の効果
継続事業の一括について条文を読んでみましょう。
法第9条 (継続事業の一括) 事業主が同一人である2以上の事業(有期事業以外の事業に限る。)であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、この法律の規定の適用については、当該認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業に使用される労働者とみなす。この場合においては、厚生労働大臣が指定する一の事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。 |
ポイント!
・継続事業(=有期事業以外の事業)に限られます。
・継続事業の一括には厚生労働大臣の認可が必要です。なお、認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。
・通常、保険関係は、それぞれの事業ごとに成立しています。厚生労働大臣の認可を受けることによって、それぞれの保険関係を一つにまとめて事務処理を行うことになります。
・保険関係は、指定事業に一括され、指定事業以外の事業の保険関係は消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、都道府県労働局長が指定する一の事業(「指定事業」という。)以外の事業にかかる保険関係は、消滅する。
②【H30年出題】(労災)
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、その労働者の所属する被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長がそれぞれの事務所掌に応じて行う。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括について都道府県労働局長の認可があったときは、指定事業に保険関係が一括されますので、指定事業以外の事業にかかる保険関係は、消滅します。
この場合、「指定事業以外の事業」は保険関係の消滅について、労働保険料の確定精算を行うことになります。
「指定事業」は、増加概算保険料の納付の手続が必要になることがあります。
②【H30年出題】(労災) 〇
継続事業の一括が行われても、労災保険や雇用保険の給付に関する事務や、雇用保険の被保険者に関する事務は一括されません。
被一括事業の労働者に係る労災保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の事務や雇用保険の被保険者資格の確認の事務等は、被一括事業のぞれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 介護休業給付金
雇用保険法 介護休業給付金
R5-225
R5.4.9 介護休業給付金の支給要件
今日は介護休業給付金の支給要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第64条の4第1項 (介護休業給付金) 介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業をした場合において、当該介護休業(当該対象家族を介護するための2回以上の介護休業をした場合にあっては、初回の介護休業とする。)を開始した日前2年間(当該介護休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。 |
介護休業とは
→ 対象家族を介護するための休業のこと
対象家族とは
→ 被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹及び孫並びに配偶者の父母
では、過去問をどうぞ!
【H30年問6】
本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
A 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
B 介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
C 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が60日に達した日後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
E 介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給付金を受給することができる。

【解答】
【H30年問6】
A ×
第61条の4第6項で次のように定められています。
被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。 1 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業 2 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業 |
同一の対象家族について3回まで介護休業給付金の対象になります。4回目以後は、介護休業給付金は支給されません。
B ×
父母、配偶者の父母には養父母が含まれます。
また、子には養子が含まれます。
(行政手引59802)
C ×
介護休業給付金が支給されないのは、『同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業』です。
(第61条の4第6項)
E 〇
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合でも、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となります。
(行政手引59861)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 療養補償給付
労災保険法 療養補償給付
R5-224
R5.4.8 療養補償給付「療養の給付」について
療養補償給付は、現物給付の「療養の給付」が原則で、例外として、現金給付の「療養の費用の支給」があります。
今日は「療養の給付」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 |
では、さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。
②【R1年出題】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
③【H27年出題】
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
④【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、「居宅における療養に伴う世話その他の看護」も含まれます。
②【R1年出題】 〇
療養の給付は、「指定病院等」で行われます。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等でも、「指定病院等」に該当しないときは、療養の給付は行われません。
療養補償給付としての療養の給付が行われる「指定病院等」とは、問題文のとおり、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者です。
(則第11条)
③【H27年出題】 ×
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、請求書を、直接ではなく、「指定病院等を経由」して、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(則第12条)
④【H27年出題】 ×
療養の給付が行われるのは、治ゆするまでです。
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になると、療養の給付は行われません。
問題文のように、神経症状のような症状や障害が残ったとしても、治療の余地がなくなれば、療養の給付は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 罰則の適用
労働安全衛生法 罰則の適用
R5-223
R5.4.7 労働安全衛生法 両罰規定
労働安全衛生法では、「事業者」には、労働者の安全と健康を守るため、様々な義務が課せられています。
違反した「事業者」は、罰則の対象になります。
ところで、「事業者」とは、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」をいいます。個人企業の場合は事業主個人、法人の場合は法人そのものをさします。
法人の場合、法人自体は人間ではありませんので、法人自体が違反行為をすることはあり得ません。
そのため第122条には、両罰規定が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第122条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 |
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、違反行為をしたときは、行為者は処罰の対象となります。
また、事業主である「法人又は人」にも罰則が適用されます。労働安全衛生法の罰則には懲役もありますが、法人そのものに懲役刑は科せられません。「法人又は人」に対しては罰金刑が科せられます。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
②【R2年出題】
労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
従業者が労働安全衛生法の措置義務に違反する行為に及んだ場合は、行為者である従業者は処罰の対象となります。
両罰規定で事業者にも罰金刑が科せられます。
②【R2年出題】 ×
法人の従業者が違反行為をしたときは、当該従業者は罰則の対象となります。
また、事業者にも罰金刑が科せられます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 労働時間のカウント
労働基準法 労働時間のカウント
R5-222
R5.4.6 時間外労働、休日労働の割増賃金
まず、「法定労働時間」と「法定休日」の条文を読んでみましょう。
第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
※法定労働時間は、原則として「1日8時間以内、かつ、1 週40時間以内」です。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 ② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
※法定休日は、原則として、「週に1日以上」与えなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間
A 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
B 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
C 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
D 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
E 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

【解答】
A ×
休日には時間外労働の概念がありませんので、8時間を超えても時間外労働の割増率は加算されません。問題文の場合は、10時間すべて休日労働に対する割増率で計算します。
ちなみに、休日労働が深夜に及んだ場合は、深夜割増を加算する必要があります。
(H11.3.31基発第168号)
B ×
法定休日の割増賃金は暦日単位で適用されます。
休日割増で計算するのは日曜の24時までです。月曜の午前0時からは休日ではありませんので、休日割増の対象にはなりません。
C 〇
時間外労働が翌日の労働日に及んだ場合は、暦日で判断するのではなく、前日の労働時間の延長として扱われます。
火曜の午前3時までは、月曜日の労働時間の延長となり、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。
(S63.1.1基発第1号)
D ×
法定休日は「暦日」で適用されます。土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前0時以降は、土曜の勤務における時間外労働時間ではなく、休日労働として計算されます。
E ×
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
時間外 |
|
|
|
| 2 | 2 | 4 |
時間外労働となるのは、木曜の金曜の1日の法定労働時間を超えたそれぞれ「2時間」と、1週間の法定労働時間を超えた土曜の4時間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 最低賃金法
最低賃金法
R5-221
R5.4.5 派遣中の労働者の最低賃金
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は、都道府県ごとに決められていて、その都道府県内のすべての労働者に適用されます。
また、特定最低賃金は、特定の産業又は職業ごとに決められています。その産業の基幹的労働者に適用されます。
今日は、派遣労働者に対する最低賃金をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第13条 (派遣中の労働者の地域別最低賃金) 労働者派遣法に規定する派遣中の労働者については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用する。
第18条 (派遣中の労働者の特定最低賃金) 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあっては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額を適用する。 |
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。

【解答】
【R1年出題】 〇
「派遣中の労働者」に対する賃金は、雇用契約関係にある「派遣元」に支払義務があります。
派遣中の労働者の地域別最低賃金については、「派遣先の事業場の所在地」を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険労務士法
社会保険労務士法
R5-220
R5.4.4 社会保険労務士に対する懲戒処分
社会保険労務士に対する懲戒処分をみていきましょう。
社会保険労務士に対する懲戒処分は次の3種類です。(法第25条)
① 戒告
② 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③ 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
懲戒処分の条文を読んでみましょう。
第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒) 1 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等の禁止の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、1に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
第25条の3(一般の懲戒) 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分をすることができる。
|
社会保険労務士に対して懲戒処分をする権限があるのは、「厚生労働大臣」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
②【H26年出題】
社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。
③【R1年出題】
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】
①【H20年出題】 ×
懲戒処分をする権限は、全国社会保険労務士会連合会には委任されていません。
②【H26年出題】 〇
社会保険労務士法第25条の30で、「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。」と規定されています。
そのため、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえます。
③【R1年出題】 ×
社会保険労務士会は、「所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき」は、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、『注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。』と規定されています。(第25条の33)
社会保険労務士会による注意勧告の対象になります。
社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分の対象ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 加給年金額
厚生年金保険法 加給年金額
R5-219
R5.4.3 加給年金額の対象の配偶者が65歳に達したとき
所定の要件を満たした老齢厚生年金と障害厚生年金には加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第44条第1項 (老齢厚生年金の加給年金額) 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、在職定時改定又は退職時改定の規定により当該月数が240以上となるに至った当時。)その者によって生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
加給年金額が加算される老齢厚生年金は、被保険者期間が240月以上あることが原則です。ただし、中高齢の期間短縮特例に該当する場合は、その期間以上あれば対象となります。
老齢厚生年金の加給年金額の対象は、「65歳未満の配偶者」と「子」です。
第50条の2第1項 (障害厚生年金の加給年金額) 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。 |
加給年金額が加算されるのは1級・2級の障害厚生年金です。3級の場合は加給年金額は加算されません。また、加給年金額の対象は、「65歳未満の配偶者」です。「子」は障害基礎年金で加算の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
②【R1年出題】
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
加給年金額の対象になっている配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額が支給されなくなります。
なお、配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合は、65歳以降も加給年金額が加算されます。
(法第50条の2第4項)
ちなみに、老齢厚生年金も同じです。加給年金額の対象になっている配偶者が65歳に達したときは、その月の翌月から加給年金額の加算がなくなります。
②【R1年出題】 ×
加給年金額の対象になっている配偶者が、①死亡したとき、②受給権者による生計維持の状態がやんだとき、③配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき、④配偶者が、65歳に達したときに該当したときは、その翌月から加給年金額が加算されません。
①から③に該当したときは「加給年金額対象者の不該当の届出」を10日以内に提出しなければなりません。
④については、届出は不要です。
(則第46条)
※老齢厚生年金の配偶者の加給年金額も同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 標準報酬月額
厚生年金保険法 標準報酬月額
R5-218
R5.4.2 育児休業等終了時改定
育児休業等終了時改定は、育児休業等が終了した日に3歳未満の子を養育している被保険者が対象です。
随時改定の要件に該当しなくても、標準報酬月額の改定が行われます。

※まず、随時改定の要件を確認してみましょう。
① 昇給又は降給等により固定的賃金が変動したこと
② 変動月から3カ月間の報酬の平均月額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと
③ 報酬支払基礎日数が3か月すべて17日(短時間労働者は11日)以上であること
★育児休業等終了時改定は、
育児休業等終了時に報酬に変動があり、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3カ月間の報酬の平均額による標準報酬月額と従前の標準報酬月額に、1等級以上の差が生じた場合に行われます。また、報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)の月は除いて算定します。
では、条文を読んでみましょう。
第23条の2第1項 (育児休業等を終了した際の改定) 実施機関は、育児休業等を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という。)において子であって、当該育児休業等に係る3歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。 |
※育児休業等終了日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始している場合は、育児休業等終了時改定による標準報酬月額の改定は行われません。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、被保険者が現に使用される事業所において、育児休業等終了日又は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。
②【R1年出題】
月給制である給与を毎月末日に締め切り、翌月10日に支払っている場合、4月20日に育児休業から職場復帰した被保険者の育児休業等終了時改定は、5月10日に支払った給与、6月10日に支払った給与及び7月10日に支払った給与の平均により判断する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合は、その月は除いて平均を出します。
随時改定とは違い、3か月すべてが17日以上である必要はありません。
②【R1年出題】 ×
育児休業等終了時改定は、「育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間」の給与の平均で判断します。問題文は、4月20日に職場復帰していますので、4月、5月、6月に支払った給与で判断されます。
4月10日払い | 給与なし(育児休業中のため) | |
5月10日払い | 17日未満 | (4月19日育休終了、20日職場復帰のため) |
6月10日払い | 17日以上 | |
17日未満の月は除いて平均を出します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 遺族基礎年金
国民年金法 遺族基礎年金
R5-217
R5.4.1 遺族基礎年金を受けることができる配偶者の条件
遺族基礎年金の遺族の範囲を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第37条の2第1項 (遺族の範囲) 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 ① 配偶者については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、②に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 ② 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
配偶者のポイント!
・「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれます。
・被保険者又は被保険者であった者(=死亡した人のことです)の死亡の当時その者によって生計を維持していること、かつ、子と生計を同じくすることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
平成31年4月に死亡した第1号被保険者の女性には、15年間婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の男性との間に14歳の子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し、かつ所定の要件が満たされている場合であっても、遺族基礎年金の受給権者は子のみであり、当該男性は、当該子と生計を同じくしていたとしても遺族基礎年金の受給権者になることはない。

【解答】
【R1年出題】 ×
配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含まれます。
問題文の男性は、女性の死亡時に生計を維持し、かつ、14歳の子と生計を同じくしていますので、遺族基礎年金の受給権者となります。
女性の死亡により遺族基礎年金の受給権者になるのは、当該男性と子です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 特例による任意加入
国民年金法 特例による任意加入
R5-216
R5.3.31 特例による任意加入のポイント
国民年金には「任意加入」の制度があります。
任意加入の対象は、「老齢基礎年金の受給資格がない(受給資格期間を満たしていない)人」や、「保険納付済期間が40年ないため、満額の老齢基礎年金が受給できない(老齢基礎年金を増やしたい)人」です。
今日は、「特例による任意加入被保険者」の制度をみていきます。
「特例の任意加入」は、65歳以上70歳未満の人で、「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人」のみが対象です。受給資格期間を満たしていて、老齢基礎年金を増やしたい人は、特例の任意加入はできません。
では、条文を読んでみましょう。
H6法附則第11条、H16法附則第23条 (任意加入被保険者の特例) 昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。 ただし、その者が老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。 ① 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) ② 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
任意加入被保険者の特例のポイント!
★生年月日の条件があります。
昭和40年4月1日以前に生まれた者
★老齢基礎年金等、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合は、任意加入できません。
★年齢は、65歳以上70歳未満です。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したとき、又は老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、それぞれその日に被保険者の資格を喪失する。
②【R1年出題】
67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
特例による任意加入被保険者が、厚生年金保険法の被保険者の資格を取得したときは「その日」に、被保険者の資格を喪失します。
老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、「その日の翌日」に被保険者の資格を喪失します。
ポイント!
特例による任意加入は、「老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権」を有しないことです。
老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するのが目的です。そのため、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したときは、その翌日に資格を喪失します。
(H6法附則第11条)
②【R1年出題】 ×
第2号被保険者期間が8年間ありますので、あと2年間保険料納付済期間があれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得できます。
特例による任意加入被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得すると、その日の翌日に資格を喪失します。
そのため、問題文の男性が、任意加入し、保険料を納付することができるのは、67歳から2年間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金
国民年金法 老齢基礎年金
R5-215
R5.3.30 合算対象期間は老齢基礎年金の年金額に反映しない
老齢基礎年金の受給資格は、原則として「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」が10年以上あることです。
保険料納付済期間+保険料免除期間が10年未満の場合は、「合算対象期間」も入れて10年以上になれば、受給資格を満たします。
条文を読んでみましょう。
第28条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
第28条は老齢基礎年金の原則の受給資格についての規定です。
「保険料免除期間」が2回出てきます。
学生納付特例及び納付猶予の期間は、ただし書(2回目の保険料免除期間)では除外されていませんので、10年の受給資格期間には算入されます。
しかし、1回目の保険料免除期間からは除かれています。老齢基礎年金の年金額の計算に入らないからです。
「合算対象期間」については、附則第9条で、「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」に「合算対象期間」も合算して10年以上あれば受給資格期間を満たすと規定されています。ただし、合算対象期間は「カラ期間」といい、老齢基礎年金の年金額には反映しません。
今回は合算対象期間をみていきます。
今回、出てくる合算対象期間は
・第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以降のもの
・日本国籍を有している人が海外に居住していた期間のうち、国民年金に任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
です。
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
日本国籍を有している者が、18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し、20歳から60歳まで国民年金には加入せず、国外に居住していた。この者が60歳で帰国し、再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合、65歳から老齢基礎年金が支給されることはない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがなく、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
【R1年出題】 〇
18歳~19歳 | 20歳 60歳 | 60歳~65歳 |
厚年 | 海外居住(日本国籍有)で任意加入しなかった | 厚年 |
カラ期間 | カラ期間 | カラ期間 |
・18歳から19歳までの厚生年金保険の加入期間、20歳から60歳まで国民年金には任意加入しなかった期間、60歳から65歳までの厚生年金保険の加入期間、すべて「合算対象期間」です。
合算対象期間のみで10年以上でも、老齢基礎年金の受給資格期間は満たしますが、老齢基礎年金の額には反映しません。結果として65歳から老齢基礎年金が支給されることはありません
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 60歳以上の被保険者
健康保険法 60歳以上の被保険者
R5-214
R5.3.29 60歳以上の被保険者が退職・再雇用される場合
60歳以上の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合の手続をみていきます。
60歳以上の人が退職し再雇用された場合、例えば、正社員から嘱託社員に変わったり、退職金の支払いがあったとしても、1日の空白も無ければ、健康保険の被保険者の資格は継続します。
再雇用後に嘱託社員に変わった場合、報酬が下がることがあります。
通常は、報酬が下がった場合は、随時改定によって標準報酬月額が見直されます。随時改定の場合、標準報酬月額の改定は、固定的賃金の変動(報酬が下がった月)から 4か月目からになります。
そこで、60歳以上の被保険者については、退職し1日の空白も無く再雇用された場合は、被保険者資格喪失届と被保険者資格取得届を同時に提出することができます。
それによって、再雇用された月から、再雇用後の報酬に応じた標準報酬月額に決定されます。
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。

【解答】
【R1年出題】 〇
この取扱いは、「60歳」以降に退職後継続して再雇用されるものに対して適用されます。高齢者の継続雇用の支援が目的です。
(H25.1.25保保発0125第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金
健康保険法 傷病手当金
R5-213
R5.3.28 傷病手当金の待期期間
傷病手当金の待期期間をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項 (傷病手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して「3日を経過した日」から支給されます。言い換えると、第4日目から支給されます。
傷病手当金が出るまでの3日間のことを待期といいます。
待期は、休業が連続3日で完成します。
例えば、
休 | 休 | 休 | 休 | 出 | 休 |
3日連続して休んでいますので、傷病手当金は4日目から支給されます。
休 | 休 | 休 | 出 | 休 |
3日連続して休んでいるので待期は完成しています。傷病手当金は5日目から支給されます。
休 | 出 | 休 | 休 |
休みが3日連続していないので待期は完成していません。
(参照:S32.1.31保発2号の2)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
②【H28年出題】
傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。
③【R1年選択】
4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、 < A >起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬をうけなくなった< B >又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった< B >から起算されることになる。
<選択肢>
① 4月1日から ② 4月3日から ③ 4月4日から ④ 4月5日から
⑤ 日 ⑥ 日の2日後 ⑦ 日の3日後 ⑧ 日の翌日

【解答】
①【H28年出題】 ×
待期は「労務に服することができなくなった日」から起算します。
ただし、労務に服することができなくなったのが『業務終了後』の場合は「翌日」から起算します。
問題文は、労務に服することができなくなったのが就業中ですので、翌日ではなく「その日」が傷病手当金の待期期間の起算日となります。
(S5.10.13保発52号)
②【H28年出題】 〇
金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 |
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 |
待期は、労務不能の日が連続3日で完成します。所定休日も待期に算入されます。
そのため、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成します。
③【R1年選択】
A ④4月5日から
B ⑤日
★支給期間の起算日
4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 |
休 | 休 | 休 | 出 | 休 |
1日から3日まで連続3日間休業していますので、待期期間が完成しています。傷病手当金は、再び休業した5日から支給されます。
傷病手当金の支給期間は、「同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間」です。問題文の傷病手当金の支給期間は、4月5日から起算します。
★報酬があったため傷病手当金が支給停止されていた場合
報酬を受けることができる場合は、その間は傷病手当金は支給されません。
報酬を受けなくなれば傷病手当金が支給されますので、その場合の傷病手当金の支給期間は、「報酬をうけなくなった日又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった日」から起算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 確定保険料
労働保険徴収法 確定保険料
R5-212
R5.3.27 納付した概算保険料が確定保険料より多い場合
継続事業と一括有期事業は、保険年度単位で保険料を申告納付します。
保険年度の初めに概算保険料を申告・納付し、年度終了後に確定保険料で精算する仕組みです。
今日は、納付した概算保険料が確定保険料より多かった場合の手続です。
条文を読んでみましょう。
法第19条第6項 事業主が納付した概算保険料の額が、確定保険料の額をこえる場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他この法律の規定による徴収金に充当し、又は還付する。
則第36条第1項 (労働保険料の還付) 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付するものとする。
則第37条 (労働保険料の充当) 1 還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額又は法第 20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金をいう。)等に充当するものとする。 2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、1の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金等に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。 |
ポイント!
★納付した概算保険料の額が、確定保険料の額をこえる場合
→政府は、そのこえる額を次の保険年度の労働保険料等に「充当」、又は「還付」します。
・還付について
→ 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、超過額の還付を請求したときは、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏は、その超過額を還付します。
・充当について
→ 還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料等に充当します。
→ 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、充当したときは、その旨を事業主に通知しなければなりません。
※充当が行われるのは、還付請求がない場合です。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(労災)
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【R4年出題】(労災)
概算保険料を納付した事業主が、所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は当該事業主が申告すべき正しい確定保険料の額を決定し、これを事業主に通知することとされているが、既に納付した概算保険料の額が所轄都道府県労働局歳入徴収官によって決定された確定保険料の額を超えるとき、当該事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができる。
③【H24年出題】(雇用)
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
④【H29年出題】(雇用)
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
労働保険料還付請求書は、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出します。
②【R4年出題】 〇
既に納付した概算保険料の額が、認定決定された確定保険料の額を超えるときは、事業主はその通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に労働保険料還付請求書を提出することによって、その超える額の還付を請求することができます。
③【H24年出題】 〇
所轄都道府県労働局歳入徴収官が、超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当するのは、還付請求が行われないときです。
④【H29年出題】 ×
所轄都道府県労働局歳入徴収官が超過額を充当した場合、「当該事業主による充当についての承認」は不要です。しかし、「当該事業主への充当後の通知」は必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 被保険者であった期間
雇用保険法 被保険者であった期間
R5-211
R5.3.26 2年を超えて遡って雇用保険に加入できる場合
基本手当の所定給付日数は、年齢、被保険者であった期間(算定基礎期間)、離職理由などで決まります。
しかし、事業主が、雇用保険の加入の手続を怠っていた場合、「被保険者であった期間(算定基礎期間)」が短くなってしまい、結果として所定給付日数が少なくなる可能性があります。
遡って雇用保険に加入できるのは、最大で2年です。雇用保険に加入すると保険料を負担することになりますが、雇用保険料の時効が2年だからです。
しかし、雇用保険料が給料から天引きされていたことが明らかな場合は、2年を超えて遡って、雇用保険に加入することができます。
では、条文を読んでみましょう。
第22条第4項、第5項 4 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるときは、当該確認のあった日の2年前の日に当該被保険者となったものとみなして、算定基礎期間の算定を行うものとする。 5 次に掲げる要件のいずれにも該当する者(①に規定する事実を知っていた者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項第②に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日」とする。 ① その者に係る資格取得の届出がされていなかったこと。 ② 厚生労働省令で定める書類に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に雇用保険料の被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。 |
被保険者の資格取得と喪失については、厚生労働大臣の確認によって効力が発生します。確認は、通常は、事業主からの届出によって行われることが原則です。
しかし、何かの理由で資格取得の届出が遅れた場合は、相当期間遡って、資格取得の事実が確認されることになります。
ただし、雇用保険料の時効が2年ですので、遡ることができるのは最大で2年です。本当は2年前の日より前に資格を取得していたとしても、2年前の日より前の期間は、被保険者であった期間に算入されません。確認が行われた日の2年前の日が、資格取得日となります。
資格取得日 2年前の日 確認
▼ ▼ ▼
|
|
算入されない | 被保険者であった期間 |
|
|
▲資格取得日
<特例> 2年を超える遡及適用について
給与明細等の確認書類により、資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、雇用保険料の被保険者負担分が、給料から天引きされていたことが明らかである時期がある場合
↓
給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日が、資格取得日とみなされます。
資格取得日 給料天引き 2年前の日 確認
▼ ▼ ▼ ▼
|
|
算入されない | 被保険者であった期間 |
|
|
▲資格取得日
(行政手引23501)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
②【R1年出題】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。

【解答】
①【R3年出題】 〇
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前は、原則として、被保険者であった期間に算入されません。資格取得日は、確認が行われた日の2年前の日となります。
②【R1年出題】 〇
被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に、『被保険者の負担すべき額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期』がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含まれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 障害補償給付
労災保険法 障害補償給付
R5-210
R5.3.25 障害の程度が自然的経過により増進・軽減したとき
障害補償給付には、「障害補償年金」と「障害補償一時金」があります。
条文を読んでみましょう。
法第15条第1項 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 |
 「障害補償給付」には「年金」と「一時金」があることに注意してください。
「障害補償給付」には「年金」と「一時金」があることに注意してください。
障害等級第1級~7級は「年金」、障害等級第8級~14級は「一時金」が支給されます。
今日は、障害補償年金を受ける労働者の障害の程度が、自然的な経過により増進し、又は軽減した場合の改定についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
・ 条文の最初に注目してください。「障害補償給付」ではなく「障害補償年金」です。対象は、「障害補償年金」を受ける労働者に限られます。「障害補償一時金」には適用されません。
・「当該障害の程度に変更があった」とは、障害の程度が自然的な経過により増進又は軽減したことをいいます。
・新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するとは、例えば・・・
その1 障害等級3級の人の障害の程度が増進し2級になった場合は、2級の障害補償年金が支給され、従前の3級の障害補償年金は支給されません。
その2 障害等級5級の人の障害の程度が軽減し7級になった場合は、7級の障害補償年金が支給され、従前の5級の障害補償年金は支給されません。
その3 障害等級7級の人の障害の程度が軽減し10級になった場合は、10級の障害補償一時金が支給され、従前の7級の障害補償年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
自然的経過による変更で障害補償給付の変更が行われるのは、障害補償「年金」を受けている場合のみです。
②【H30年出題】 〇
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進又は軽減したとしても、障害補償給付の変更は適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 健康診断
労働安全衛生法 健康診断
R5-209
R5.3.24 健康診断の結果(記録・通知)
事業者には、労働者に対し健康診断を行う義務があります。
今日は、「健康診断の結果の記録」、「健康診断の結果の通知」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第66条の3 (健康診断の結果の記録) 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに第66条の2の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。 則第51条 (健康診断結果の記録の作成) 事業者は、第43条等の健康診断又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。
第66条の6(健康診断の結果の通知) 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 則第51条の4(健康診断の結果の通知) 事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 |
ちなみに、上の条文に出てくる健康診断は以下の健康診断です。
法第66条第1項 → 一般健康診断
第2項 → 有害業務に従事する労働者の特別の項目についての健康診断
第3項 → 有害業務に従事する労働者の歯科医師による健康診断
第4項 → 都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断
第5項ただし書 → 労働者が他の医師又は歯科医師により受けた健康診断
法第66条の2 → 深夜業従事者の自発的健康診断
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。
②【R1年出題】
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。

【解答】
①【H27年出題】 ×
健康診断個人票は、5年間保存義務があります。
②【R1年出題】 ×
事業者は、健康診断を受けた労働者に対して、遅滞なく、健康診断の結果を通知する義務があります。異常所見が認められた労働者に限りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 平均賃金
労働基準法 平均賃金
R5-208
R5.3.23 平均賃金を計算しましょう。
今日は、平均賃金を計算します。
まず、条文を読んでみましょう。
第12条第1項~5項 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 1. 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2. 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ② ①の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ③ ①、②に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。 1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2. 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又は介護休業をした期間 5. 試みの使用期間 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
ポイント!
・ 平均賃金は、原則として次の計算式で算定します。
→算定すべき事由の発生した日以前3か月間の賃金の総額÷その期間の総日数
ただし、日給、時給、請負制による賃金の場合は、最低保障があります。
最低保障の計算式→賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60
※「総日数」と「労働日数」を区別しましょう。「総日数」は暦上の日数です。例えば、3月なら31日です。
・ 賃金締切日がある場合は、算定事由の発生した日の直前の賃金締切日から起算した3か月で計算します。
・ 次の期間は、平均賃金の計算式の「日数」と「賃金の総額」の両方から控除します。
1.業務上の傷病により休業した期間
2.産前産後の女性の休業期間
3.使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間
4.育児休業又は介護休業期間
5.試みの使用期間
・ 次の賃金は「賃金の総額」から除外されます。
臨時に支払われた賃金
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年2回の賞与など)
通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
では、過去問をどうぞ!
【R1年問1】
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
<条件>
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日
時間外手当については、毎月15日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
A 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
B 4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
C 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
D 通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
E 時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

【解答】
A 〇
平均賃金は、賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡る3か月で計算します。
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合は、それぞれの賃金の賃金締切日から遡ります。
問題文の場合、「基本給、通勤手当及び職務手当」の直前の賃金締切日は6月25日、「時間外手当」は7月15日です。
平均賃金は、((3月26日から6月25日までの基本給、通勤手当及び職務手当の総額)÷92日)+((4月16日から7月15日までの時間外手当の総額)÷91日)で計算します。
(S26.12.27 基収5926号)
B ×
賃金によって賃金締切日が異なりますので、Aの問題のように、それぞれの賃金締切日から遡って計算します。
C ×
「通勤手当」は平均賃金に算入しなければなりません。通勤手当が計算に入っていませんので誤りです。
D ×
E ×
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険一般常識
社会保険一般常識
R5-207
R5.3.22 社会保険制度改正の施行日
社会保険制度の改正の施行日を確認しましょう。
さっそく、令和元年の過去問をどうぞ!
【R1年問10】
社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、後記AからEまでのうちどれか。
① 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
② 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。
③ 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。
④ 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。
⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。
⑥ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。
A①→②→③→⑤→④→⑥
B③→①→②→⑤→⑥→④
C②→①→④→⑤→③→⑥
D③→②→①→⑤→⑥→④
E②→③→①→⑤→⑥→④

【解答】
A①→②→③→⑤→④→⑥
① 被用者年金一元化の施行は、平成27年10月1日です。
70歳未満の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者が、厚生年金保険法の被保険者になったのは、平成27年10月1日からです。
その際、厚生年金保険の被保険者が4つの種別に区分されるようになりました。
1 第1号厚生年金被保険者 → 2から4までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(民間企業の会社員)
2 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
3 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
4 第4号厚生年金被保険者 → 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
② 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額は、平成28年4月1日に改正されました。
端数処理もチェックしておきましょう。
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額(→ 5円未満切捨て、5円以上10円未満10円に切り上げ)に3分の2を乗じた額(→ 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満1円に切り上げ)です。
③ 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになったのは、平成29年1月1日です。
④ 老齢基礎年金の年金請求について、マイナンバーでも行えるようになったのは、平成30年3月5日です。
⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が「10年以上」に短縮されたのは、平成29年8月1日です。
⑥ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになったのは平成31年4月1日です。
ちなみに、国民年金法の「保険料納付済期間」は国民年金法第5条第1項で、「第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。」と定義されています。
「産前産後の国民年金保険料免除期間」は保険料免除期間ではなく、保険料納付済期間に入りますので注意しましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働一般常識
労働一般常識
R5-206
R5.3.21 令和2年労使間の交渉等に関する実態調査
我が国の労使間の交渉に関する「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」からの問題が、令和元年に出題されました。
今日は令和元年の過去問をみていきます。
※ 解説は、最新の「令和2年労使間の交渉等に関する実態調査」を参照します。
では、過去問をどうぞ!
※出題当時は、「平成29年」労使間の交渉等に関する実態調査からの出題でしたが、今回は「令和2年」版に修正しています。
①【R1年出題】
労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」労働組合は9割を超えている。
②【R1年出題】
過去3年間(平成29年7月1日から令和2年6月30日の期間)において、労働組合と使用者との間で発生した労働争議の状況をみると、「労働争議があった」労働組合は5%未満になっている。
③【R1年出題】
使用者側との労使関係の維持について労働組合の認識をみると、安定的(「安定的に維持されている」と「おおむね安定的に維持されている」の合計)だとする割合が約4分の3になっている。

【解答】
①【R1年出題】 〇
労働協約を「締結している」93.1%、「締結していない」6.8%となっています。
★「労働協約」とは
労使間で結ばれる労働条件その他に関する取決めを書面により両当事者が署名又は記名押印して作成したもの
②【R1年出題】 〇
「労働争議があった」2.7%、「労働争議がなかった」97.2%となっています。
ちなみに、労働争議がなかった理由(複数回答 主なもの3つまで)は、「対立した案件がなかったため」が最も高くて、次が「対立した案件があったが話合いで解決したため」、「対立した案件があったが労働争議に持ち込むほど重要性がなかったため」となっています。
★労働争議とは
労働組合と使用者側との間で労働関係に関する主張が一致しないで、争議行為が発生若しくは第三者機関が関与したもの(労働委員会によるあっせん、調停、仲裁や都道府県労政主管課及び労政主管事務所の職員による助言等)をいいます。
③【R1年出題】 ×
「安定的に維持されている」51.1%、「おおむね安定的に維持されている」38.8%で、「安定的」と認識している労働組合は89.9%です。約4分の3より多いので、誤りです。
参照:令和2年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-r02gaiyou.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 6年間支給停止
厚生年金保険法 6年間支給停止
R5-205
R5.3.20 厚生年金保険の年金と労働基準法の災害補償との調整
厚生年金保険法の保険給付は業務上・業務外を問いませんので、障害厚生年金と遺族厚生年金は、業務上の障害や死亡でも支給されます。
その障害や死亡について、労働基準法の災害補償を受ける権利がある場合の調整についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第54条第1項 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給を停止する。
第64条 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。 |
ポイント!
労災保険法との調整ではなく、「労働基準法」の障害補償・遺族補償との調整です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法第79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
②【H28年出題】
障害厚生年金は、その受給権者が当該障害厚生年金に係る傷病と同一の傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を取得したときは、6年間その支給を停止する。

【解答】
①【R1年出題】 〇
障害厚生年金にも同じ趣旨の規定があります。
②【H28年出題】 ×
「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付」ではなく、同一の傷病について「労働基準法第77条の規定による障害補償」を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されます。
★ちなみに、社会保険(国民年金と厚生年金)と労災保険の年金との調整については労災保険法に規定があります。
「同一の事由」で社会保険と労災保険の年金給付が支給される場合は、労災保険の年金が減額され、社会保険の年金は全額支給されます。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、社会保険は被保険者本人が保険料を負担しているからです。
例えば、業務上の傷病で障害等級に該当する障害の状態にある場合に、同一の傷病によって、労働基準法第77条の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、支給が停止されます。
一方、労働者災害補償保険法による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならず全額支給されます。労災保険の障害補償年金は減額されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 第3号被保険者
国民年金法 第3号被保険者
R5-204
R5.3.19 第3号被保険者の届出
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。
資格取得届などの提出先や提出期限などを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条第5項~9項 5 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 6 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 7 第2号被保険者を使用する事業主とは、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業所の事業主をいう。 8 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 9 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。 |
ポイント!
・ 第3号被保険者の届出先は「厚生労働大臣」です。
・ 届出は、事業主、共済組合等を経由します。
「第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者」の場合 →第2号被保険者を使用する事業主を経由します。
「第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者」の場合 → 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由します。
・ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の「一部」を「健康保険組合」に委託できます。→委託できるのは事務の「一部」です。「全部」は委託できませんので注意して下さい。
・ 届出が事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。
②【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。
③【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。
④【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
★被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する届出について
・第1号被保険者は → 市町村長(特別区の区長を含む。)に届け出ます。
・第3号被保険者は → 厚生労働大臣に届け出ます。
②【H29年出題】 〇
資格取得の届出は、14日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。
※日本年金機構は、厚生労働大臣から権限を委任されて、取得の手続を行います。
(則第1条の4)
以下の届出の提出期限は、第1号被保険者・第3号被保険者ともに「14日以内」です。
・資格取得の届出
・資格喪失の届出
・種別変更の届出
・住所変更の届出
・氏名変更の届出
③【R1年出題】 〇
第3号被保険者の届出のイメージ
第3号被保険者 |
→ → | 事業主 共済組合等 経由 |
→ → → | 厚生労働大臣 (日本年金機構) |
|
| ※受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。 |
|
|
④【H29年出題】 ×
届出に係る事務の一部を「健康保険組合」に委託することがきます。全国健康保険協会には委託できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 共済組合の組合員
健康保険法 共済組合の組合員
R5-203
R5.3.18 共済組合の組合員と健康保険の関係
健康保険の強制適用事業所は、以下の通りです。
・常時5人以上の従業員を使用する個人経営の法定17業種の事業の事業所 ・国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの |
★ 国、地方公共団体の事業所も、健康保険の強制適用事業所になることがポイントです。
強制適用事業所に使用される従業員は、当然、健康保険の被保険者となります。そのため、国、地方公共団体に使用される人も健康保険の被保険者となります。
国や地方公共団体に使用される人は、健康保険の被保険者ですが、同時に共済組合の組合員でもあります。
両方から保険給付が行われることのないように、健康保険法では共済組合に関する特例が規定されています。
条文を読んでみましょう。
第200条 (共済組合に関する特例) 1 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法による保険給付は、行わない。 2 共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。 |
共済組合の組合員に対しては、健康保険の保険給付は行われません。
※特例の対象になるのは、国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済の加入者です。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
②【R1年出題】
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】
①【H20年出題】 ×
共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者と「なります」。
しかし、健康保険法からの保険給付は行われません。
②【R1年出題】 〇
「共済組合の給付の種類及び程度は、健康保険法の給付の種類及び程度以上であることを要する。」と規定されています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 概算保険料
労働保険徴収法 概算保険料
R5-202
R5.3.17 概算保険料の計算式
継続事業と一括有期事業は、保険年度単位で労働保険料を申告・納付します。
概算保険料は、保険年度の6月1日から40日以内に、申告・納付します。
今日は、概算保険料の計算式を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条、則第24条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。 ・その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の見込額(当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合にあっては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)に当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 ※特別加入者がいない場合の条文です。 |
ポイント!
・ 概算保険料(原則)=その保険年度の賃金総額の見込額×一般保険料率です。
・ 概算保険料は、その保険年度の賃金総額の「見込額」を使って計算するのが原則です。
ただし、当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の「100分の50以上100分の200以下」の場合は、「直前の保険年度の賃金総額」を使います。
・ 保険年度の中途に保険関係が成立した場合は、成立日から保険年度の末日までの賃金総額の見込額で計算します。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】(労災)
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料にかかる保険料率を乗じて算定する。
②【R3年出題】(雇用)
(前提条件)
保険関係成立年月日:令和元年7月10日
事業の種類:食料品製造業
令和2年度及び3年度の労災保険率:1000分の6
令和2年度及び3年度の雇用保険率:1000分の9
令和元年度の確定賃金総額:4,000万円
令和2年度に支払いが見込まれていた賃金総額:7,400万円
令和2年度の確定賃金総額:7,600万円
令和3年度に支払いが見込まれる賃金総額:3,600万円
(問題)
令和2年度における賃金総額はその年度当初には7,400万円が見込まれていたので、当該年度の概算保険料については、下記の算式により算定し、111万円とされた。
7,400万円×1000分の15=111万円

【解答】
①【R1年出題】 〇
概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度の賃金総額に一般保険料料率を乗じて算定します。
また、賃金総額については、1,000円未満切捨てです。
②【R3年出題】 ×
令和2年度の賃金総額の見込額は7,400万円で、直前の保険年度(令和元年度)の確定賃金総額4,000万円の100分の50以上100分の200以下の範囲内です。
そのため、令和2年度の概算保険料は、その保険年度の賃金総額の見込額ではなく、直前の保険年度の賃金総額で算定します。
算式は、4,000万円×1000分の15=60万円となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 被保険者期間
雇用保険法 被保険者期間
R5-201
R5.3.16 最後に被保険者となった日前に受給資格を取得したことがある場合
基本手当は、被保険者が失業した場合に、原則として離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給されます。
※特定受給資格者・特定理由離職者については、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格ができます。
★今日のテーマ★ 例えば、今回離職したB社の前に、A社で被保険者であった期間がある場合、A社の被保険者であった期間をB社の被保険者であった期間に通算できるか否かが今日のテーマです。
条文を読んでみましょう。
法第14条第2項 被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、被保険者であった期間に含めない。 1 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間 2 (今日は省略します) |
★ 今回の離職前に、受給資格等を取得したことがある場合は、今回の被保険者であった期間に含まれません。
| 2年 | ||
A社 13か月 |
| B社 5か月 | |
B社の離職の日以前2年間に、A社の被保険者であった期間があります。
しかし、A社の離職で受給資格の決定を受けている場合は、B社の離職で被保険者期間を算定する際の被保険者であった期間には、通算できません。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が高年齢受給資格を取得したことがある場合には、当該高年齢受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれない。
②【R1年出題】
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格の決定を受けた事がある場合における当該受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、今回の被保険者期間には含まれません。
ポイント!
★当該受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に基づいて基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金を受給したか否かは問いません。
(行政手引50103(3))
②【R1年出題】 ×
最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合は、当該特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれません。特例一時金を受給したか否かは問われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 特別支給金
労災保険法 特別支給金
R5-200
R5.3.15 労災 特別支給金のポイント
★「特別支給金」とは
労災保険の保険給付の上乗せとして支給される給付です。
「社会復帰促進等事業」の中の「被災労働者等援護事業」の事業の一つとして行われています。
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類があります。
ボーナス特別支給金 |
一般の特別支給金 |
保険給付 |
例えば、「傷病補償年金」(保険給付)には、特別支給金として「傷病特別支給金」(一般の特別支給金)と「傷病特別年金」(ボーナス特別支給金)が上乗せされます。
傷病特別年金 |
傷病特別支給金 |
傷病補償年金 |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。
②【R2年出題】
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
③【R1年出題】
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「傷病特別支給金」は傷病補償年金に上乗せされる一般の特別支給金です。
傷病特別支給金は、傷病等級に応じた定額です。第1級114万円、第2級107万円、第3級100万円です。
②【R2年出題】 〇
例えば、傷病補償年金の上乗せとして、「傷病特別支給金」と「傷病特別年金」があります。
「傷病特別支給金」は、①の問題でみましたように定額です。
「傷病特別年金」は、「算定基礎日額」を使って算定します。算定基礎日額は、算定基礎年額÷365日で計算します。
算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与額の総額(直近1年間のボーナスの総額です)とするのが原則です。
(例外)
「給付基礎年額(給付基礎日額×365日)の20%に相当する額」と「特別給与の総額」を比較して、少ない方が算定基礎年額となります。
ただし、150万円を超える場合は、算定基礎年額は150万円となります。
そのため、問題文にもありますように、算定基礎年額が150万円を超えることはありません。
(特別支給金支給規則第6条第1項)
ちなみに、傷病特別年金の額は
1級 算定基礎日額×313日分
2級 算定基礎日額×277日分
3級 算定基礎日額×245日分
です。
③【R1年出題】 ×
特別加入者には、ボーナス特別支給金は支給されませんので、傷病特別支給金は支給されますが、傷病特別年金は支給されません。
特別加入者には、賃金やボーナスの概念がないためです。
(特別支給金支給規則第19条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 雇入れ時の健康診断
労働安全衛生法 雇入れ時の健康診断
R5-199
R5.3.14 雇入れ時の健康診断の対象者など
労働者を雇い入れた際は、事業者には健康診断の実施が義務づけられています。
条文を読んでみましょう。
則第43条 (雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 |
 雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。
雇入れ時の健康診断の対象は、「常時使用する労働者」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
②【R1年出題】
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。
③【R1年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。
④【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

【解答】
①【H27年出題】 ×
有期雇用で1年限りの契約でも、「常時使用する労働者」に該当し、雇入れ時の健康診断の対象になります。
(H19.10.1基発第1001016号他)
②【R1年出題】 〇
短時間労働者の場合、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に、雇入れ時の健康診断の実施義務が課せられます。
なお、1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、実施することが「望ましい」とされています。
(H19.10.1基発第1001016号他)
(参考)
★事業主が一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の①及び②のいずれの要件をも満たす者とされています。
①期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって当該契約の契約期間が1年以上(一定の有害業務に従事する短時間労働者にあっては6か月)である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行についてより)
③【R1年出題】 ×
6か月ではなく「3か月」です。
医師による健康診断を受けた後3か月以内の者を雇い入れる場合で、その者が結果を証明する書面を提出したときは、その項目については省略できます。
④【H17年出題】 ×
雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、「すべての労働者」です。
(法第59条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 みなし労働時間
労働基準法 みなし労働時間
R5-198
R5.3.13 事業場外労働のみなし労働時間制
例えば、外回りのセールスや出張のように、事業場の外で働く場合、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、また、使用者による労働時間の算定が困難な場合があります。
「事業場外労働」についてはみなし労働時間制の制度が設けられています。
では、条文を読んでみましょう。
第38条の2 ① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ② ①のただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、②の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
 みなし労働時間制とは
みなし労働時間制とは
→ 使用者には、労働者の労働時間を把握し、算定する義務があります。
しかし、事業場外の労働で、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合は、実際に労働した時間ではなく、特定された時間労働したとみなすことができる制度です。
ポイント!
事業場外の労働でも、「労働時間の算定」ができる場合は、みなし労働時間は適用されません。
事業場外労働のみなし労働時間の手順
★原則 「所定労働時間」労働したものとみなされます。
※当該業務を遂行するためには所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」労働したものとみなされます。
★労使協定で「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を定めた場合は、労使協定で定めた時間労働したものとみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
労働基準法第38条の2の規定によれば、労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、原則として所定労働時間労働したものとみなされるが、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされる。この場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間が、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とされる。
②【R1年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定で定める時間が法定労働時間以下である場合には、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
③【H22年出題】
労働基準法第38条の2に定めるいわゆる事業場外労働のみなし労働時間制は、情報通信機器を用いて行う在宅勤務の場合、どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため、適用されない。

【解答】
①【H18年出題】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合、原則は、「所定労働時間」労働したものとみなされます。例えば、所定労働時間が7時間の場合は、7時間労働したとみなされます。
しかし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます。例えば当該業務の遂行に通常必要とされる時間が8時間の場合は、8時間労働したとみなされます。
★当該業務に関し、労使協定で当該業務の遂行に通常必要とされる時間を定めた場合は、その時間労働したとみなされます。
②【R1年出題】 〇
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合は、届出の必要はありません。
(則第24条の2第3項)
③【H22年出題】 ×
在宅勤務でも事業場外労働のみなし労働時間制が適用される場合があります。
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインについて」(令和3.3.25基発0325第2号/雇均発0325第3号/)を確認しましょう。
↓
事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難なときに適用される制度であり、使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用できる制度である。テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となる。
テレワークで、事業場外労働のみなし労働時間制が適用されるのは、次の①と②の条件を満たす場合です。
① 情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと ② 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと |
問題文では「どのような要件の下でも、結局は当該通信機器を通じて使用者の管理を受けることとなるため」となっていますが、情報通信機器を労働者が所持しているからといって制度が適用されないわけではありません。
ガイドラインでは、例えば、勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合は①の要件を満たすとされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 変形労働時間制
労働基準法 変形労働時間制
R5-197
R5.3.12 1か月単位の変形労働時間制採用のルール
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、1か月以内の期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例事業場の場合は44時間)を超えなければ、特定の週、特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができます。
1か月単位の変形労働時間制の変形期間は1か月以内にすることが条件です。
1週間単位、10日単位、4週間単位なども可能です。
変形期間を1か月にした場合で考えてみましょう。
法定労働時間40時間の事業場で、31日の月なら、1か月の労働時間の総枠は次の式で計算できます。
40時間×31日÷7日 ≒ 177時間
1か月の所定労働時間のトータルが177時間以内なら、平均すると1週間当たりの労働時間が40時間以内となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、満18歳に満たない者及びその適用除外を請求した育児を行う者については適用しない。
③【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制により所定労働時間が、1日6時間とされていた日の労働時間を当日の業務の都合により8時間まで延長したが、その同一週内の1日10時間とされていた日の労働を8時間に短縮した。この場合、1日6時間とされていた日に延長した2時間の労働は時間外労働にはならない。
④【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
⑤【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
変形期間を1か月とする場合に、毎月1日から月末までの暦月にするという規定はありません。
例えば、毎月16日を起算日として、16日~翌月15日という1か月でも可能です。
②【R1年出題】 ×
満18歳に満たない者には、原則として変形労働時間制は適用されませんので、その部分については正しいです。
育児を行う者については、適用除外を請求できる規定がありません。
なお、以下のような規定はあります。
則第12条の6 使用者は、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制又は1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。 |
★変形労働時間制が適用されると、労働時間の長い週や日が出てきます。使用者は、育児を行う者等については、育児等に必要な時間を確保できるよう配慮しなければなりません。
第66条第1項 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制及び1週間単位の非定型的変形労働時間制の規定にかかわらず、1週間又は1日について法定労働時間を超えて労働させてはならない。 |
★妊産婦が対象の規定です。
例えば、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合でも、妊産婦から請求があった場合は、1週間または1日について法定労働時間を超えて労働させることはできません。
③【R1年出題】 〇
1か月単位の変形労働時間制で時間外労働になる部分を確認しましょう。
①1日の時間外労働
→1日8時間を超える時間を定めた日はその時間
それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週の時間外労働
→1週40時間(特例事業場は44時間)を超える時間を定めた週はその時間、
それ以外の週は1週40時間(特例事業場は44時間)超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)
③変形期間時間外労働
→変形期間の法定労働時間総枠(40時間(44時間)×対象期間の暦日数÷7日)
を超えて労働した時間(①又は②で法定時間外労働となる時間を除く。)
問題文のように、所定労働時間が1日6時間(所定労働時間が1日8時間以内)の日で、時間外労働になるのは、8時間を超えて労働した時間です。
6時間の日に2時間延長しても労働時間は8時間ですので、1日あたりの時間外労働は発生しません。
週当たりでみても、2時間延長した日の代わりに同一週内の1日10時間の日の労働時間を2時間短縮しています。1週間当たりの労働時間は増えていませんので、1週間当たりでも時間外労働は発生しません。
④【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」又は「労使協定」で採用できます。「就業規則その他これに準ずるものによる定め」だけでも採用できます。
なお、労使協定で採用した場合は、所轄労働基準監督署長に労使協定を届け出る必要があります。しかし、三六協定とは異なり、労使協定の届出によって効力が発生するわけではありません。
⑤【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、1日の労働時間、1週間の労働時間の限度はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働一般常識
労働一般常識
R5-196
R5.3.11 就労条件総合調査(労働費用)
今日は令和3年就労条件総合調査の結果をみていきましょう。
令和元年の過去問を解いていきます。
※令和元年当時の問題は「平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照していますが、今日は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照します。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は約7割、「現金給与以外の労働費用」の割合は約3割となっている。
②【R1年出題】
「現金給与以外の労働費用」に占める割合を企業規模計でみると、「法定福利費」が最も多くなっている。
③【R1年出題】
「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。
④【R1年出題】
「法定外福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「住居に関する費用」が最も多く、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」がそれに続いている。
⑤【R1年出題】
「法定外福利費」に占める「住居に関する費用」の割合は、企業規模が大きくなるほど高くなっている。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「労働費用」とは
→使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)のことです。「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与の費用」、「退職給付等の費用」、「教育訓練費」等があります。
令和2年(平成 31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は常用労働者1人1か月平均408,140円です。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は82.0%で、「現金給与以外の労働費用」の割合は18.0%です。
参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」
②【R1年出題】 〇
「法定福利費」とは
→法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)のこと。
「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等があります。
「法定外福利費」とは
→法律で義務付けられていない福利厚生関係の費用のこと。
「住居に関する費用」、「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」等があります。
「現金給与以外の労働費用」に占める割合は「法定福利費」が68.6%で最も多くなっています。
参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」
③【R1年出題】 〇
「法定福利費」に占める割合は、「厚生年金保険料」が55.5%、「健康保険料・介護保険料」が34.8%、「労働保険料」が7.3%となっています。
参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」
④【R1年出題】 〇
「法定外福利費」に占める割合は、「住居に関する費用」が51.4%、「医療保健に関する費用」が14.9%、「食事に関する費用」が10.1%となっています。
参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」
⑤【R1年出題】 〇
「法定外福利費」に占める「住居に関する費用」の割合は、1000人以上規模は70.5%ですが、30~99人規模ですと21.8%です。
参照「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 事後重症
厚生年金保険法 事後重症
R5-195
R5.3.10 障害厚生年金の事後重症のチェックポイント
障害厚生年金の受給権発生要件は、次の3つです。
①初診日要件
→ 初診日に厚生年金保険の被保険者であること
②障害認定日要件
→ 障害認定日に障害等級1級~3級に該当していること
③保険料納付要件
→ 初診日の前日の保険料納付状況で判断されます
初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付要件が問われます
①、②、③の要件を満たした場合は、障害認定日に障害厚生年金の受給権が発生します。
★「障害認定日」に障害等級1~3級に該当しない場合は、受給権は発生しません。
ただし、後日、1~3級に該当した場合は、「事後重症」として障害厚生年金を請求することができます。
今日は事後重症のチェックポイントをみていきましょう。
事後重症の条文を読んでみましょう。
第47条の2第1項(事後重症の障害厚生年金) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であった者であって、障害認定日において障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級(1~3級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害厚生年金の支給を請求することができる。 |
★保険料納付要件を満たしていることが前提です。
チェックポイント!
・障害認定日に1~3級に該当しなかった
↓
・障害認定日後65歳に達する日の前日までに、1~3級に該当した
↓
・その期間内(障害認定日後65歳に達する日の前日まで)に、障害厚生年金を請求すること
↓
・「請求」することによって事後重症の障害厚生年金の受給権が発生します。
※請求した日に受給権が発生します。
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始まりますので、事後重症の障害厚生年金は、請求した月の翌月から支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者であって、かつ、当該初診日の属する月の前々月までに、国民年金の被保険者期間を有しない者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、障害認定日後から65歳に達する日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その期間内に、障害厚生年金の支給を請求することができる。
②【H26年出題】
いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。
③【R1年出題】
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後64歳のときにその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った場合、その者が支給繰上げの老齢厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の支給を請求することはできない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
事後重症の請求の条件は、「障害認定日後から65歳に達する日の「前日」までの間に、障害等級に該当すること」+「その期間内に請求すること」です。
問題文は「前日」が抜けているので誤りです。
②【H26年出題】 ×
事後重症の障害厚生年金は、「障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき」に請求することができます。
厚生年金保険法の「障害等級」は1級、2級、3級です。障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合でも請求することができます。
③【R1年出題】 〇
65歳に達する日の前日までの間にある場合でも、繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者や繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者には、事後重症の障害厚生年金の規定は適用されません。
(法附則第16条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 老齢厚生年金
厚生年金保険法 老齢厚生年金
R5-194
R5.3.9 65歳未満の老齢厚生年金と65歳以上の老齢厚生年金
 「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、65歳から支給されます。
「老齢厚生年金」は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば、65歳から支給されます。
 「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から64歳までの間、特別に支給される老齢厚生年金です。60歳台前半の老齢厚生年金と呼ばれることもあります。
「特別支給の老齢厚生年金」は、60歳から64歳までの間、特別に支給される老齢厚生年金です。60歳台前半の老齢厚生年金と呼ばれることもあります。
特別支給の老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが支給要件です。
条文を読み比べてみましょう。
まず、通常の「老齢厚生年金」の条文です。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
「被保険者期間を有する者」の部分に注目してください。
厚生年金保険の被保険者期間は「月」単位で算定しますので、1か月でもあれば「被保険者期間を有する者」となります。
次に特別支給の老齢厚生年金の条文です。
法附則第8条 (老齢厚生年金の特例) 当分の間、65歳未満の者(附則第7条の3第1項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者に老齢厚生年金を支給する。 1 60歳以上であること。 2 1年以上の被保険者期間を有すること。 3 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
特別支給の老齢厚生年金は、「1年以上」の厚生年金保険の被保険者期間が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
②【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
③【H28年出題】
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
④【H30年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があることが条件です。
②【H24年出題】 〇
65歳以上の老齢厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あること、60歳以上65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。
③【H28年出題】 ×
2以上の種別の被保険者期間を有する場合、「1年以上の被保険者期間」については、2以上の種別の被保険者期間を合算することになっています。
問題文の場合、「第1号厚生年金被保険者期間・8か月」+「第4号厚生年金被保険者期間・10か月」=18か月で厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ありますので、特別支給の老齢厚生年金を受給できます。
(法附則第20条)
60歳 62歳 65歳
特別支給の老齢厚生年金(1号分) |
| |
| (4号分) |
|
| 老齢基礎年金 | |
昭和31年4月2日生まれの女性の場合、第1号厚生年金被保険者期間に係る特別支給の老齢厚生年金は60歳から、第4号厚生年金被保険者期間に係る分は62歳から支給されます。
④【H30年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金は有期年金ですので、65歳に達したときに受給権が消滅します。65歳に達すると、新たに終身年金の老齢厚生年金の受給権が発生します。
そのため、特別支給の老齢厚生年金を受給していた人も、65歳で改めて老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出する必要があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 老齢基礎年金の繰下げ
国民年金法 老齢基礎年金の繰下げ
R5-193
R5.3.8 老齢基礎年金繰下げの条件
老齢基礎年金の繰下げの要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第28条第1項 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。 |
繰下げ申出ができる要件のポイント!
・66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していないこと
・65歳に達したときに、他の年金たる給付の受給権者でないこと
・65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となっていないこと
※「他の年金たる給付」とは
他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいいます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
②【H24年出題】
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
③【R1年出題】
老齢厚生年金を受給中である67歳の者が、20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが、老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合は、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる。なお、この者は老齢基礎年金及び老齢厚生年金以外の年金の受給権を有していたことがないものとする。
④【H30年出題】
65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする。)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
65歳に達した日から66歳に達した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったときは、繰下げの申出はできません。
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において「障害基礎年金」の受給権者となった(=他の年金たる給付の受給権者となったということです)ときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出はできません。
②【H24年出題】 ×
寡婦年金の受給権は65歳に達したときに消滅します。
寡婦年金の受給権者であった者も、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けられます。
③【R1年出題】 〇
ポイントその1 「他の年金たる給付」から、「老齢厚生年金」は除かれます。
そのため、「65歳に達したとき」に老齢厚生年金の受給権者でも、また、65歳に達した日から66歳に達した日までの間に老齢厚生年金の受給権者となっても、老齢基礎年金を繰下げることができます。
ポイントその2 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできます。
老齢厚生年金を65歳から受給し、老齢基礎年金を67歳から繰下げて受けることも可能です。
④【H30年出題】 ×
65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも、老齢基礎年金の支給繰下げの申出ができます。
条件は次の通りです。
・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に老齢基礎年金を請求していないこと
・老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ
当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないこと
(S60 法附則第18条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 保険料免除
健康保険法 保険料免除
R5-192
R5.3.7 産前産後休業中の保険料免除
産前産後の休業期間中は、健康保険の保険料が免除されます。
条文を読んでみましょう。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。 |
ポイント!
・免除の要件
→ 事業主が保険者等に申出をすること
・免除される期間
→休業を開始した日の属する月から休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
②【R1年出題】
産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く。)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は 3月分から免除対象となる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
免除されるのは、産前産後休業を開始した日の「属する月」からその産前産後休業が終了する日の「翌日が属する月の前月」までです。
「属する月」と「前月」がチェックポイントです。
ちなみに、事業主負担分、被保険者負担分ともに免除されます。
②【R1年出題】 〇
産前産後休業は、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産日後56日です。
・5月16日が出産予定日で3月25日から休業していました。
5月16日が出産予定日の場合、出産日以前42日は4月5日~ですので、産前産後休業を開始した日の属する月の「4月」から保険料が免除されます。
・しかし、実際は、予定日より前の5月10日に出産しました。
その場合は、実際の出産日以前42日は、3月30日からとなります。
3月25日から休業していますので、保険料免除の開始は、産前産後休業を開始した日の属する月の「3月」に変更されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 賃金総額の特例
労働保険徴収法 賃金総額の特例
R5-191
R5.3.6 賃金総額の特例が認められる請負による建設の事業
労働保険料には、
・一般保険料
・第1種特別加入保険料
・第2種特別加入保険料
・第3種特別加入保険料
・印紙保険料
・特例納付保険料
があります。
通常の労働者の労働保険料が「一般保険料」です。
一般保険料の額について、条文を読んでみましょう。
第11条 (一般保険料の額) 1 一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 2 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 3 厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
|
「一般保険料」の額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額です。
ただし、「賃金総額」には特例があります。(第3項)
条文を読んでみましょう。
則第12条 (賃金総額の特例) 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2 立木の伐採の事業 3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。) 4 水産動植物の採捕又は養殖の事業 |
ポイント!
特例が認められるのは、
・労災保険料
・賃金総額を正確に算定することが困難なもの
ですので注意してください。
今日は、「請負による建設の事業」の特例をみていきます。
請負による建設の事業の労災保険料は、下請負人の労働者も含めて賃金総額を算定しなければなりません。
しかし、元請負人が、下請負人の労働者も含めた賃金総額を正確に算定することが困難な場合があるので、特例が認められています。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題(雇用)】
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
②【R1年出題(労災)】
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
③【R4年出題(労災)】
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

【解答】
①【H30年出題(雇用)】 ×
賃金総額の特例が認められるのは、賃金総額を正確に算定することが困難なものです。
請負による建設の事業だから認められるものではありません。
②【R1年出題(労災)】 ×
賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業は、「請負金額×労務費率」が賃金総額となります。
請負金額とは、
①事業主が注文者からその事業に使用する工事用の資材の支給を受けたり、又は機械器具等の貸与を受けた場合
→ 支給された物の価格(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額に加算します。
②機械装置の組み立て又は据付けの事業の場合
→機械装置の価額(消費税等相当額を除く。)は請負代金に加算しません。
請負代金に機械装置の価額(消費税等相当額を除く。)が含まれている場合は、その価額を控除します。
問題文の場合は、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等を請負代金に加算します。
(則第13条)
③【R4年出題(労災)】 〇
消費税を含まない請負金額を用いて計算します。
(則第13条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 基本手当
雇用保険法 基本手当
R5-190
R5.3.5 証明書による失業の認定
基本手当を受けるには、受給資格者が失業認定日に出頭して失業の認定を受けなければなりません。
しかし、一定の理由で出頭できない場合は、「証明書」で失業の認定を受けることができます。
今日は、証明書による失業の認定をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第15条第4項 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 |
 証明書によって失業の認定が受けられるのは、上記の4つの理由に限られます。
証明書によって失業の認定が受けられるのは、上記の4つの理由に限られます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
④【R1年出題】
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

【解答】
①【H21年出題】 〇
病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合で、証明書によって失業の認定を受け、基本手当が支給されるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。
20日の場合は、証明書による失業の認定を受けることはできません。
②【H28年出題】 〇
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。基本手当の支給を受けることができる日は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53003(3))
③【H25年出題】 ×
面接のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合で、証明書によって失業の認定が受けられるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合です。
民間の職業紹介事業者の紹介の場合は、証明書による失業の認定は受けられません。
④【R1年出題】 〇
天災その他やむを得ない理由で公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった「最初の失業認定日」に証明書を提出した場合は、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も「含めて」、失業の認定を行うことができます。
(則第28条、行政手引51401)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 基本手当の減額
雇用保険法 基本手当の減額
R5-189
R5.3.4 自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額
失業の認定に係る期間中に、自己の労働による収入があった場合、基本手当の額が調整されます。
条文を読んでみましょう。
第19条 (基本手当の減額) 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(以下「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 ① 収入の1日分に相当する額から1,310円(控除額)を控除した額と基本手当の日額との合計額(=「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき → 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 ② 合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき → 当該超える額(=「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 ③ 超過額が基本手当の日額以上であるとき → 基礎日数分の基本手当を支給しない。 |
★「合計額」とは、「(収入の1日分に相当する額-1,310円(控除額))+基本手当の日額」です。
①全額支給
合計額 ≤ 賃金日額×100分の80
→ 基本手当は減額されず、全額支給されます。
②減額支給
合計額 > 賃金日額×100分の80
→ 基本手当は減額されます。基本手当日額から超過額を控除します。
③不支給
超過額 ≧ 基本手当の日額
→ 基本手当は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
失業の認定に係る期間中に得た収入によって基本手当が減額される自己の労働は、原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)をいう。
②【H26年出題】
受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、その収入の1日分に相当する額に雇用保険法第19条第2項に定める額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないときは、基本手当の日額に100分の80を乗じ、基礎日数を乗じて得た額を支給する。
③【H26年出題】
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所長にその収入の額を届け出なければならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
自己の労働による収入とは短時間就労による収入です。原則として1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合を除く。)で、就職とはいえない程度のものをいいます。
(行政手引51652)
②【H26年出題】 ×
「(収入の1日分に相当する額-控除額)+基本手当の日額」(合計額)が賃金日額の100分の80以下の場合は、基本手当は減額されません。「基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額」が支給されます。
③【H26年出題】 〇
「受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出」なければなりません。
(法第19条第3項)
届出については、「その者が自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない」とされています。
(則第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 特別加入者
労災保険法 特別加入者
R5-188
R5.3.3 特別加入者の通勤災害
特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等・特定作業従事者」、「海外派遣者」の3つの種類があります。
労災保険法は、「労働者」の業務災害や通勤災害などを保護するための保険です。しかし、労働者と同じような業務に従事することの多い中小事業主や一人親方等は、労災保険に特別加入することによって、労働者に準じて保護が受けられます。
また、労災保険は「属地主義」をとっていますので、例えば海外支店に転勤になった海外派遣者は、日本の労災保険の保護は受けられなくなります。しかし、労災保険に特別加入することによって、海外派遣者も労災保険の保護の対象となります。
特別加入者は、原則として労働者と同じ保護が受けられます。
しかし、「一人親方等・特定作業従事者」の一部は、通勤の実態がないなどの理由で通勤災害の保護の対象から除外されます。
今日は、通勤災害の保護の対象から除外される特別加入者を確認しましょう。
通勤災害の保護の対象から除外される特別加入者は以下の一人親方等、特定作業従事者です。(則第46条の22の2)
・自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業に従事する者 → 個人タクシー業者、個人貨物運送業者など ・漁船による水産動植物の採捕の事業(船員法第1条に規定する船員が行う事業を除く。)に従事する者 → 漁船による自営の漁業者 ・特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者 ・家内労働者 |
 ポイント!
ポイント!
・中小事業主等、海外派遣者は、すべて通勤災害の保護の対象です。
・通勤災害の保護から除外されるのは、「一人親方等、特定作業従事者」の「一部」です。全てではありませんので注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< A >はその一例に該当する。
選択肢
①医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者
②介護作業従事者
③個人タクシー事業者
④船員法第1条に規定する船員
②【H26年出題】
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
③【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
④【H22年出題】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
⑤【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
①【H30年選択式】
③ 個人タクシー事業者
②【H26年出題】 〇
個人貨物運送業者には通勤災害に関する保険給付は支給されません。
③【H26年出題】 〇
家内労働者には通勤災害に関する保険給付は支給されません。
④【H22年出題】 ×
漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、住居と就業の場所との往復の実態が明確でないので、通勤災害に関する保険給付は支給されません。
⑤【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者は、住居と就業の場所との往復の実態が明確でないので、通勤災害に関する保険給付は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 報告
労働安全衛生法 報告
R5-187
R5.3.2 労働者死傷病報告の提出
今日は、労働者死傷病報告をみていきます。
休業日数が4日以上か4日未満かで、様式が異なります。
条文を読んでみましょう。
則第97条 (労働者死傷病報告) ① 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ② 休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から 6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
・死亡、4日以上の休業の場合 → 「遅滞なく」報告しなければなりません。
・4日未満の休業の場合 → 期間ごとにまとめて報告しなければなりません。
1~3月分 →4月末日まで
4~6月分 →7月末日まで
7~9月分 →10月末日まで
10~12月分 →1月末日まで
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
②【H25年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③【R3年出題】
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

【解答】
①【H29年出題】 〇
死傷病報告が必要になるのは、以下の場合です。
・労働災害により死亡又は休業した場合
・就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき
・事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡又は休業したとき
事業場内で負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合でも労働者死傷病報告書の提出が必要です。
②【H25年出題】 ×
休業の日数が2日の場合は、 1~3月分は4月末日まで、4~6月分は7月末日まで、 7~9月分は10月末日まで、10~12月分は1月末日が提出期限となります。
なお、死亡又は4日以上の休業の場合は、「遅滞なく」提出しなければなりません。
③【R3年出題】 ×
労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞なく、死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働者への周知義務はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 就業規則
労働基準法 就業規則
R5-186
R5.3.1 絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
就業規則に定める事項には、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」があります。
条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
<絶対的必要記載事項> 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
<相対的必要記載事項> 4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 10表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 11 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |

「絶対的必要記載事項」は必ず就業規則に記載しなければならない事項です。
「相対的必要記載事項」は、定めをする場合は記載が義務づけられる事項です。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
②【H28年出題】
退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。
③【R3年出題】
欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。
④【H25年出題】
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

【解答】
①【H25年出題】 〇
賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、絶対的必要記載事項ですので、就業規則に必ず記載しなければなりません。
ちなみに、臨時の賃金等は、「定めをする場合」は就業規則に記載しなければならない「相対的必要記載事項」です。
②【H28年出題】 ×
退職手当は「退職手当の定めをする場合」は、適用される労働者の範囲などを就業規則に記載しなければならない相対的必要記載事項です。
退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合は、退職手当の決定及び計算の方法に該当しますので、就業規則に記載する必要があります。
(H11.3.31 基発168号)
③【R3年出題】 ×
欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替えることは違法ではありません。そのような取扱いが制度として確立している場合には、就業規則に規定する必要があります。
(S63.3.14基発150号)
④【H25年出題】 〇
従来の慣習が「当該事業場の労働者のすべてに適用されるもの」である場合、11号の「当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項については就業規則に規定しなければならない。」に当てはまります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 就業規則
労働基準法 就業規則
R5-185
R5.2.28 就業規則の意見聴取
常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務があります。
また、就業規則の作成と変更の際には、過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 10 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 11 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
 1から11のうち、1~3は就業規則への記載が義務づけられている「絶対的必要記載事項」、4~11は定めをする場合は記載が義務づけられる「相対的必要記載事項」です。
1から11のうち、1~3は就業規則への記載が義務づけられている「絶対的必要記載事項」、4~11は定めをする場合は記載が義務づけられる「相対的必要記載事項」です。
次に作成の手続について条文を読んでみましょう。
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、意見を記した書面を添付しなければならない。 |
今日は、作成と変更の際の手続である意見聴取をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
②【R3年出題】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。
③【H30年出題】
同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。
④【R1年出題】
就業規則の作成又は変更について、使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者と協議決定することが要求されている。
⑤【H27年出題】※行政手続における押印原則の見直しによる修正あり
労働基準法第90条第2項は、就業規則の行政官庁への届出の際に、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付することを使用者に義務づけているが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合又は意見書に氏名を記載しない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うものとされている。

【解答】
①【H21年出題】 〇
就業規則の作成だけでなく、その変更の際も意見聴取が必要です。
②【R3年出題】 ×
同一事業場で、事業場の一部の労働者のみ適用される就業規則を別に作成することもできます。
その場合でも、作成や変更に際しての意見聴取は、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
問題文のように、当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くだけでは、労働基準法第90条による意見聴取を行ったことにはなりません。
(S63.3.14基発150号)
③【H30年出題】 ×
同一事業場で、パートタイム労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成することもできます。その場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則を合わせたものが「就業規則」となります。それぞれが単独に就業規則となるものではありません。
作成や変更に際しての意見聴取は、当該事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
(H11.3.31基発168号)
④【R1年出題】 ×
協議決定は要求されていません。意見を聴けば労働基準法違反になりません。
(S25.3.15基収525号)
なお、意見書の内容が反対意見でも、就業規則の効力には影響はありません。
(S24.3.28基発373号)
⑤【H27年出題】 〇 ※行政手続における押印原則の見直しによる修正あり
就業規則を行政官庁へ届け出る際は、意見書の添付が義務づけられていますが、過半数労働組合もしくは過半数代表者が故意に意見を表明しない場合等は、意見を聴いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するよう取り扱うとされています。
(S23.10.30基発1575号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法 被保険者
国民健康保険法 被保険者
R5-184
R5.2.27 国民健康保険の適用除外
国民健康保険の対象になるのは、被用者保険(健康保険など)に加入していない人です。
また、国民健康保険の保険者には「都道府県等」と「国民健康保険組合」があります。
今日は、国民健康保険の適用除外を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 1 健康保険法の規定による被保険者。ただし、日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 4 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 7 健康保険法の日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。 8 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10国民健康保険組合の被保険者 11 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
国民健康保険から除外されるのは、以下の通りです。
・健康保険などの被用者保険の被保険者とその被扶養者
・後期高齢者医療の被保険者
・生活保護を受けている人
などです。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。
②【H20年出題】
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
③【H20年出題】
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となりません。
②【H20年出題】 〇
後期高齢者医療の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
※なお、後期高齢者医療の被保険者になるのは、次の人です。
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
③【H20年出題】 〇
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金
R5-183
R5.2.26 養子になったときの遺族厚生年金の受給権
遺族厚生年金の受給権者が「養子」になった場合の受給権が今日のテーマです。
まず、遺族厚生年金の受給権の消滅事由を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第63条第1項 (遺族厚生年金の失権) 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 4 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。 |
2について
・婚姻した場合は遺族厚生年金の受給権は消滅します。事実婚でも同様です。
3について
・直系血族及び直系姻族以外の者の養子(事実上の養子も含む)となった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅します。直系血族・直系姻族の養子になっても失権しないのがポイントです。
4について
・離縁で、死亡した人との親族関係が終了した場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅します。離縁とは養子縁組の解消です。
※他に、「30歳未満の妻」の失権、「子、孫」の失権、「父母、孫、祖父母」の失権の規定もありますが、今回は省略します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
②【H29年出題】
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。
③【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
直系姻族の養子となった場合は、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
②【H29年出題】 ×
母と再婚した夫は直系姻族となります。子が母と再婚した夫の養子になっても遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
③【R3年出題】 ×
乙は丙の父の妻ですので、丙からみると乙は直系姻族です。丙が乙の養子になっても丙の遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 種別変更
国民年金法 種別変更
R5-182
R5.2.25 国民年金の種別変更
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの種別があります。
例えば、日本国内に居住する23歳の大学生は第1号被保険者です。卒業し民間企業に就職すると厚生年金保険の被保険者となり、国民年金は第2号被保険者となります。
この場合、第1号被保険者の資格を喪失→第2号被保険者の資格を取得ではなく、第1号被保険者から第2号被保険者に「種別変更」となります。
条文を読んでみましょう。
第11条の2 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。 |
例えば、ある月に、第1号被保険者から第3号被保険者に種別が変更した場合は、その月は、変更後の第3号被保険者であった月とみなされます。
また、ある月に、第2号被保険者→第3号被保険者→第1号被保険者と、2回以上種別に変更があったときは、その月は最後の種別の第1号被保険者であった月とみなされます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
②【H30年出題】
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。
③【H24年出題】
被保険者期間の計算において、同一の月に種別変更が1回あり、第1号被保険者から第3号被保険者になった月につき、すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合は、当該月は第1号被保険者とみなす。

【解答】
①【R3年出題】 〇
例えば、第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点で、第1号被保険者に該当するときは、第1号被保険者に種別の変更となります。国民年金の被保険者資格は喪失しません。
その後、第1号被保険者のまま60歳に達したときは、60歳に達した日に国民年金の資格を喪失します。
②【H30年出題】 ×
同一の月に、2回以上、被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなされます。問題文の場合は、「第3号被保険者」であった月とみなされます。
③【H24年出題】 ×
第1号被保険者から第3号被保険者になった月は、「第3号被保険者」であった月とみなされます。すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合でも、第1号被保険者とはみなされません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 短時間労働者
健康保険法 短時間労働者
R5-181
R5.2.24 短時間労働者の報酬支払基礎日数
健康保険の被保険者となる「短時間労働者」の範囲を確認しましょう。
同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間又は1月の所定労働日数が4分の3未満で、次の要件に当てはまる人です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金の月額が8.8万円以上
③学生でない
④特定適用事業所又は任意特定適用事業所に使用されている
では、定時決定の条文を読んでみましょう。
第41条第1項 (定時決定) 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 |
定時決定は、4月、5月、6月の報酬の平均をとるのが原則です。ただし、その中に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、その月は除かれます。
短時間労働者の場合は、17日が「11日」となります。短時間労働者の定時決定は、「11日未満の月」を除いて平均を出します。
※随時改定、育児休業等を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定についても、短時間労働者は「11日」となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
※本問における短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のことをいう。
②【R3年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
①【H29年出題】 〇
・短時間労働者の定時決定
→ 報酬支払いの基礎となった日数が11日未満の月は、除きます。
・短時間労働者の随時改定
→ 継続した3か月間の各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、随時改定は行われません。
②【R3年出題】 ×
短時間労働者の定時決定では、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満の月は除いて行われます。
問題文の場合、4月は11日、5月は15日、6月は16日で、すべて11日以上ですので、4月・5月・6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 認定決定
労働保険徴収法 認定決定
R5-180
R5.2.23 概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定
今日は、概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定をみていきます。
それぞれの違いに注意しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条第3項(概算保険料の認定決定) 政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
法第19条第4項(確定保険料の認定決定) 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 |
 認定決定は、申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに行われます。
認定決定は、申告書を提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときに行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題(労災)】
概算保険料の納付は事業主による申告納付方式がとられているが、事業主が所定の期限までに概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
②【H25年出題(雇用)】
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
③【H25年出題(雇用)】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
④【R3年出題(労災)】
事業主の納付した概算保険料の額が、労働保険徴収法第15条第3項の規定により政府の決定した概算保険料の額に足りないとき、事業主はその不足額を同項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
⑤【H26年出題(雇用)】
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
①【R3年出題(労災)】 〇
概算保険料の認定決定についての問題です。
認定決定を行うのは都道府県労働局歳入徴収官です。
②【H25年出題(雇用)】 ×
概算保険料の認定決定の通知は、納入告知書ではなく「納付書」によって行われます。
(則第38条第4項)
③【H25年出題(雇用)】 〇
確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条第5項)
★「納付書」と「納入告知書」について
則第38条第4項で以下のように定められています。
「労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならない。」
★原則は「納付書」です。例外の「納入告知書」によって行われるものをおぼえましょう。
「納入告知書」で行われるものは次の4つです。
①有期事業のメリット制の差額徴収、②認定決定された確定保険料とその追徴金、③印紙保険料の認定決定とその追徴金、④特例納付保険料
上記以外は「納付書」で行われます。
④【R3年出題(労災)】 〇
認定決定された概算保険料の不足額の納期限は、通知を受けた日から15日以内です。翌日から起算するのがポイントです。
(法第15条第4項)
ちなみに、認定決定された確定保険料の不足額の納期限も同じです。
(法第19条第5項)
⑤【H26年出題(雇用)】 ×
概算保険料の認定決定の場合は、追徴金は徴収されません。
「確定保険料」の認定決定については、追徴金が徴収されます。
(法第21条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 短期雇用特例被保険者
雇用保険法 短期雇用特例被保険者
R5-179
R5.2.22 短期雇用特例被保険者の失業には特例一時金
短期雇用特例被保険者が失業した場合、「特例一時金」が支給されます。
今日は、「特例一時金」の要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第39条第1項 (特例受給資格) 特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上であったときに、支給する。 |
★特例一時金を受けることができる資格のことを「特例受給資格」といいます。
★特例一時金の額は、基本手当日額に相当する額の30日分(当分の間40日分)です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3問5-A】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
②【R3問5-B】
特例一時金の支給を受けることができる期間内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して3か月を上限として受給期限が延長される。
③【R3問5-C】
特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。
④【R3問5-D】
短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が11日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある場合、被保険者期間は1か月として計算される。
⑤【R3問5-E】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

【解答】
①【R3問5-A】 〇
特例一時金を受けることができる期限(受給期限)は、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日です。
(行政手引55151)
②【R3問5-B】 ×
6か月間の受給期限内に、疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合でも、受給期限の延長はありません。
(行政手引55151)
③【R3問5-C】 〇
待期の取扱いは、一般の受給資格者と同じです。
(行政手引55755)
④【R3問5-D】 〇
特例受給資格の被保険者期間は、暦月単位で計算するのがポイントです。各月に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるときに、その月は被保険者期間の1か月となります。※11日以上の月が6か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるときは、その月を1か月で計算します。
同一暦月に、A事業所で11日以上、B事業所で11日以上ある場合でも、被保険者期間は2か月ではなく、1か月で計算されます。
(行政手引55104)
⑤【R3問5-E】 〇
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合には、特例一時金は支給されません。
一般の受給資格者とみなして、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り一般の受給資格者に対する求職者給付が支給されます。
一般の受給資格者とみなして支給される求職者給付は基本手当、技能習得手当、寄宿手当に限られます。「公共職業訓練等」を受けることに対して支給されますので、傷病手当は入りません。
(行政手引56401)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 通勤災害
労災保険法 通勤災害
R5-178
R5.2.21 単身赴任者の住居間の移動
まず、通勤の定義を条文で確認しましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
|
 、
、 、
、 の移動が、通勤として労災保険の保護の対象になります。
の移動が、通勤として労災保険の保護の対象になります。
 は、複数で就業する労働者の事業場間の移動、
は、複数で就業する労働者の事業場間の移動、 は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動です。
は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動です。
今日は 「単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動」をみていきます。
「単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動」をみていきます。
例えば、大阪に家族を残し、東京に単身赴任している労働者が、大阪の帰省先住居から東京の赴任先住居に移動中に事故にあい負傷した場合、要件を満たせば通勤災害として労災保険の保険給付の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
【R3年出題】
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1~2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関等の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害と認められない。

【解答】
【R3年出題】 〇
赴任先住居と帰省先住居の移動が通勤と認められるか否かのポイントをチェックしましょう。
・移動に反復・継続性が認められること
→ おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に、「反復・継続性」が認められます。
(H18.3.31基労管発第0331001号・基労補発第0331003号)
・帰省先住居から赴任先住居への移動の場合
→ 業務に就く当日又は前日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。
※前々日以前に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。
・赴任先住居から帰省先住居への移動の場合
→ 業務に従事した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて 差し支えない。
※翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。
(H18.3.31基発第0331042号)
問題文は、交通機関等の状況等に問題はなかったが、夏季休暇の2日目(業務に従事した日の翌々日)に移動しています。そのため就業との関連性が認められませんので、通勤には該当しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 安全衛生管理体制
労働安全衛生法 安全衛生管理体制
R5-177
R5.2.20 安全衛生管理体制・業種や人数がポイント
安全衛生管理体制の全体像をみていきましょう。
今日の過去問には、X市の本社、Y市の食料品製造工場、Z市の2店舗が出てきます。
業種や規模は、企業単位ではなく、事業場ごとで判断します。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
次に示す業態をとる株式会社についての安全衛生管理に関する記述のうち、正しいものはどれか。なお、衛生管理者及び産業医については、選任の特例(労働安全衛生規則第8条及び同規則第13条第3項)を考えないものとする。
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。
工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループの計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2店舗を置き、自社製品を小売している。
Z1店舗 使用する労働者数 常時15人
Z2店舗 使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち 12人は1日4時間労働の短時間労働者)
A X市にある本社には、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。
B Y市にある工場には、安全委員会及び衛生委員会を設置しなければならず、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、産業医については、その工場に専属の者を選任しなければならない。
C Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
D X市にある本社に衛生管理者が選任されていれば、Z市にあるZ1店舗には衛生推進者を選任しなくてもよい。
E Z市にあるZ2店舗には衛生推進者の選任義務はない。

【解答】
A ×
X市にある本社は、施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)第3号の「その他の業種」に該当します。「その他の業種」の場合、総括安全衛生管理者の選任は常時千人以上の労働者を使用する事業場が対象です。
また、衛生管理者及び産業医の選任義務があるのは、常時50人以上を使用する事業場です。
X市にある本社では、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医の選任義務はありません。
(令第2条、第4条、第5条)
B 〇
Y市の工場は、常時600人の労働者を使用しています。食料品の製造業の場合、安全委員会は常時100人以上規模、衛生委員会は(業種関係なく)50人以上規模の事業場で設置義務がありますので、安全委員会と衛生委員会の両方の設置が必要です。また、それぞれの委員会に代えて安全衛生委員会を設置することもできます。
産業医については、常時50人以上規模の事業場で選任義務があります。
また、「常時千人以上」の労働者を使用する事業場又は「一定の有害業務に常時500人以上」の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の者を選任する義務があります。
Y市の工場では、600人の労働者が深夜業に従事していることがポイントです。一定の有害業務には、「深夜業を含む業務」が入っています。深夜業を含む業務に常時600人の労働者を従事させていますので、専属の産業医が必要です。
(法第17条、第18条、第19条、則第13条)
C ×
Y市の工場では衛生管理者を3人選任しなければなりません。
また、「常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任」する必要があります。
上記の業務には、「深夜業を含む業務」が入っていないのがポイントです。衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する必要はありません。
(則第7条)
D ×
安全衛生管理体制は、「事業場ごと」に適用されますので、本社と店舗は別となります。
Z市にあるZ1店舗では、衛生推進者を選任する義務があります。
ちなみに、本社も10人以上50人未満の規模ですので、衛生管理者ではなく衛生推進者の選任が必要です。
(則第12条の2)
E ×
事業場の人数には、パートタイマー等の数も含まれます。Z市にあるZ2店舗にも衛生推進者の選任義務があります。
(S47.9.18 基発第602号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 総括安全衛生管理者
労働安全衛生法 総括安全衛生管理者
R5-176
R5.2.19 総括安全衛生管理者の選任要件
総括安全衛生管理者は、その事業場のトップというイメージです。例えば、支店長や工場長などが該当します。
今日は、総括安全衛生管理者の選任要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第10条 ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は救護に関する措置の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの ② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 |
ポイント!
総括安全衛生管理者は、「事業場ごと」に選任します。
総括安全衛生管理者の仕事は「統括管理」です。総括管理ではないので注意しましょう。
なお、「業務を統括管理する」とは、「1号~5号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもって取りまとめること」をいいます。
(S47.9.18基発第602号)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、< A >をもって充てなければならない。」とされている。
②【R2年出題】
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
③【H24年出題】
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。

【解説】
①【H28年選択式】
A 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
「統括管理」がポイントです。
「事業の実施を統括管理する者」とは、「工場長、作業所長等名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者」をいいます。
(S47.9.18基発第602号)
②【R2年出題】 〇
総括安全衛生管理者の条件は、「事業の実施について実質的に統括管理する権限および責任を有する者」ですので、資格の有無は問われません。
③【H24年出題】 〇
「常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場」には、総括安全衛生管理者の選任義務があります。人数は、企業全体の人数ではなく「事業場」の人数です。
当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等は要りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 産前産後
労働基準法 産前産後
R5-175
R5.2.18 産前産後休業のポイント!
今日は、「産前産後休業」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第65条 (産前産後) ① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ② 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 |
「出産」の範囲は妊娠4カ月以上の分娩をいいます。1か月は28日で計算しますので、4か月以上とは、85日以上のことです。生産だけでなく死産も含まれます。
(S23.12.23基発1885号)
産前6週間は、自然の出産予定日を基準に計算します。出産予定日よりも遅れて出産した場合は、予定日から出産当日までの期間は、産前休業に入ります。
(S25.3.31基収第4057号)
出産予定日 出産日
▼ ▼
予定日以前6週間 | 遅れた日数α日 | 出産日後8週間 |
産前休業(6週間+α日) | 産後休業 | |
出産日当日は、産前休業に含まれるのがポイントです。
(S25.3.31 基収第4057号)
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
②【R3年出題】
6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
③【R3年出題】
使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
妊娠4か月以後に行った妊娠中絶も「出産」の範囲に含まれます。
(S26.4.2 婦発113号)
②【R3年出題】 〇
産前休業(6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)は、女性労働者の請求が条件です。女性労働者から請求がなければ、就業させても労働基準法に違反しません。
③【R3年出題】 〇
産後8週間は、女性労働者からの請求の有無にかかわらず、就業させることはできません。産後6週間を経過している+女性労働者から請求があった+その者について医師が支障がないと認めた業務については、就かせることができます。
出産当日は、産前6週間に含まれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 妊産婦
労働基準法 妊産婦
R5-174
R5.2.17 妊産婦の労働時間・深夜労働
今日は、妊産婦の労働時間の規定をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第66条 ① 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項(1か月単位の変形労働時間制)、第32条の4第1項(1年単位の変形労働時間制)及び第43条の5第1項(1週間単位の非定型的労働時間制)の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。 ② 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合)及び第3項(公務のため臨時の必要がある場合)並びに第36条第1項(36協定による場合)の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 ③ 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 |
ポイントは、①②③すべて「妊産婦が請求した場合」が前提になっている点です。
妊産婦でも、体調や環境は一人一人違いますので、妊産婦からの請求があれば、保護が行われます。
① 変形労働時間制(1か月単位、1年単位、1週間単位)については、妊産婦から請求があれば、1週間又は1日の法定労働時間を超える時間は労働させられません。(変形労働時間制そのものを適用できないという意味ではありません。)
② 妊産婦から請求があれば、時間外又は休日に労働させられません。
③ 妊産婦から請求があれば、深夜労働はさせられません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、すべての妊産婦について、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならない。
②【H25年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定に基づき、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
③【R3年出題】
労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。
④【H17年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
時間外労働、休日労働又は深夜業が制限されるのは、「妊産婦が請求した場合」です。すべての妊産婦ではありません。請求しない妊産婦については制限されません。
②【H25年出題】 〇
「妊産婦が請求した場合」がポイントです。
③【R3年出題】 ×
監督又は管理の地位にある者には労働時間の規定の適用がありません。そのため、監督又は管理の地位にある妊産婦には、第66条第1項、第2項は適用されませんので、「時間外労働・休日労働をしない」という請求はできません。
④【H17年出題】 ×
第41条に該当する者には、労働時間、休日、休憩の規定は適用されませんが、深夜業の規定は適用されます。
監督又は管理の地位にある妊産婦については、第66条第3項「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。」の規定は適用されますので、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があれば、深夜業をさせることはできません。
(昭61.3.20基発第151号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険一般常識 確定拠出年金法
社会保険一般常識 確定拠出年金法
R5-173
R5.2.16 確定拠出年金のポイント!
過去問を解きながら、確定拠出年金のポイントをみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R3問6-A】
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。
②【R3問6-B】
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。
③【R3問6-C】
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
④【R3問6-D】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
⑤【R3問6-E】
個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

【解答】
①【R3問6-A】 ×
法第12条で、企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。」と規定されています。
(法第12条)
②【R3問6-B】 〇
法第19条第1項で、企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、「年1回以上」、定期的に掛金を拠出すると規定されています。「年1回以上」がポイントです。
なお、第19条第3項で、「企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。」と規定されていて、企業型年金加入者も自ら掛金を拠出することができます。
語尾にも注目してください。事業主は「掛金を拠出する」ですが、企業型年金加入者の方は「掛金を拠出することができる」で任意になっていることにも注意してください。
③【R3問6-C】 〇
企業型年金加入者掛金は、自ら掛金を拠出することができますが、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、「企業型年金加入者が決定し、又は変更する。」とされています。(法第19条第3項)
なお、事業主掛金の額は、「企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。」とされています。(法第19条第2項)
④【R3問6-D】 〇
国民年金第3号被保険者も、個人型年金加入者となることができます。
(法第62条)
⑤【R3問6-E】 〇
個人型年金加入者期間については、条文を読んでみましょう。
第63条第1項、第2項
① 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
② 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 遺族厚生年金
厚生年金保険法 遺族厚生年金
R5-172
R5.2.15 遺族厚生年金・死亡した者の要件
遺族厚生年金の「死亡した者」の要件をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第58条第1項 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。
(保険料納付要件) ・ ・(特例)令和8年4月1日前に死亡した者の死亡については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない場合でも保険料納付要件を満たす。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳未満である場合に限る。 |
<保険料納付要件について>
・死亡日の前日の保険料納付要件が問われるのは、 (被保険者の死亡=在職中の死亡)と
(被保険者の死亡=在職中の死亡)と (在職中に初診日がある傷病により初診日から5年以内の死亡)の場合です。
(在職中に初診日がある傷病により初診日から5年以内の死亡)の場合です。
 は障害厚生年金の裁定時に保険料納付要件を満たしているため、
は障害厚生年金の裁定時に保険料納付要件を満たしているため、 は保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)で25年以上あるため、死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。
は保険料納付済期間+保険料免除期間(+合算対象期間)で25年以上あるため、死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。
<短期要件と長期要件>
 から
から を「短期要件」、
を「短期要件」、 を「長期要件」といいます。今日は触れませんが、年金額の計算のルールが異なります。
を「長期要件」といいます。今日は触れませんが、年金額の計算のルールが異なります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者が遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしていれば、死亡の当時、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
②【R1年出題】
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。
③【H23年出題】
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
③【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
④【R3年出題】
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。

【解答】
①【R2年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者の資格を喪失後、被保険者であった間に初診日がある傷病で初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときは、死亡した者について、「保険料納付要件を満たしていること」が条件です。
②【R1年出題】 〇
1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、保険料納付要件は問われません。
③【H23年出題】 ×
1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、保険料納付要件は問われません。しかし、3級の障害厚生年金の受給権者の死亡については、保険料納付要件を満たすことが必要です。
③【R3年出題】 〇
保険料納付要件の特例は、「令和8年4月1日前に死亡していること」、「死亡日に65歳未満」であること、「死亡日の前日に死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない(=滞納期間がない)こと」です。
甲の場合、令和和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していますが、在職中の令和3年3月15日に初診日がある傷病で初診日から5年以内の令和3年8月1日に死亡しています。
甲は、原則の保険料納付要件は満たしていませんが、保険料納付要件の特例を満たしていますので、遺族厚生年金の支給対象となります。
R2 7 月 | R2 8 月 | R2 9 月 | R2 10 月 | R2 11 月 | R2 12 月 | R3 1 月 | R3 2 月 | R3 3 月 | R3 4 月 | R3 5 月 | R3 6 月 | R3 7 月 | R3 8 月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前 々月 |
| 死亡 |
死亡日の属する月の前々月までの1年間(R2年7月~R3年6月) 保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない=滞納期間がない |
|
| |||||||||||
④【R3年出題】 〇
長期要件については、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上ある事が必要ですが、「合算対象期間」も合算できます。合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合は、要件を満たします。
(法附則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 届出
厚生年金保険法 届出
R5-171
R5.2.14 70歳以上の使用される者の届出
厚生年金保険の被保険者資格は70歳に達した日に喪失します。
そのため、70歳以上の者は、在職中でも厚生年金保険の保険料の負担はありません。しかし、在職老齢年金の仕組みは適用されますので、事業主は70歳以上の使用される者についても届出が必要です。
条文を読んでみましょう。
第27条、則第10条の4 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(70歳以上の使用される者を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、厚生労働省令で定める要件(適用事業所に使用される者であって、かつ適用除外に該当するものでないこと)に該当するに至った日及び当該要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう。)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。
②【H29年出題】※改正による修正あり-
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の届出をしなければならない(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、この限りでない)。
一方、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。

【解答】
①【R2年出題】 〇
被保険者が70歳に到達し、引き続き使用されることにより「70歳以上の使用される者」の要件に該当する場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出が必要です。
ただし、その者の標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額の場合は、70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届の提出は省略できます。
(則第15条の2、第22条)
②【H29年出題】 ×
・70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合
(標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と同額の場合)
→ 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届は省略できます。
(標準報酬月額に相当する額が70歳到達日の前日の標準報酬月額と異なる場合)
→ 70歳以上被用者該当届及び70歳到達時の被保険者資格喪失届は70歳到達日から5日以内に提出しなければなりません。
・70歳以上の者を新たに雇い入れたとき
→ 70歳以上の使用される者の該当の届出が必要です。
ポイント!70歳以上の者(適用除外に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出が必要です。在職老齢年金の仕組みが適用されるからです。
(則第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 障害基礎年金
国民年金法 障害基礎年金
R5-170
R5.2.13 障害基礎年金 額の改定請求
障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合は、年金額の改定請求ができます。
条文を読んでみましょう。
第34条第2項、3項 ② 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
③ 請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求は、「受給権を取得した日」又は「障害の程度の診査を受けた日」から1年を経過した日を過ぎていることが条件です。
ただし、厚生労働省令で定める障害の程度が増進したことが明らかな場合は、1年たたなくても額の改定を請求することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
障害基礎年金の額の改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。
②【R2年出題】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年たたずに額の改定請求が可能です。
②【R2年出題】 〇
「心臓を移植したもの又は人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着したもの」は、「障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」に当たります。受給権を取得した日から起算して6か月しか経過していなくても、年金額の改定の請求をすることができます。
(則第33条の2の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 高額介護合算療養費
健康保険法 高額介護合算療養費
R5-169
R5.2.12 高額介護合算療養費のポイント!
高額介護合算療養費制度とは?
→ 健康保険と介護保険の自己負担の合算額が、限度額を超えた場合に、限度額を超えた額が支給される制度です。
・毎年8月1日から翌年7月31日の1年間が計算期間です。
まず、高額介護合算療養費の条文を読んでみましょう。
第115条の2第1項 (高額介護合算療養費) 一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。
②【H30年出題】
高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
③【R2年出題】
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
④【H25年選択】
高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超えた場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は< A >円である。
70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は < B >円である。

【解答】
①【H25年出題】 ×
高額介護合算療養費は、健康保険の被保険者とその被扶養者で個別にするのではなく、健康保険上の世帯単位(被保険者とその被扶養者)で算定します。
(令43条の2)
②【H30年出題】 ×
高額介護合算療養費は、健康保険法の高額療養費が支給されていることは条件ではありません。なお、高額療養費が支給されている場合は、一部負担金等の額から高額療養費は控除されます。
(令43条の2)
③【R2年出題】 〇
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前と変更後の自己負担額は合算されます。
(令43条の2)
④【H25年選択】
<A>500
<B>670,000
★高額介護合算療養費が支給されるのは、
「介護合算一部負担金等世帯合算額」が「介護合算算定基準額+支給基準額(500円)を超えた場合です。
「支給基準額」とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額です。
高額介護合算療養費が支給されるのは、「介護合算一部負担金等世帯合算額」から「介護合算算定基準額」を控除した額が500円を超える場合に限ります。
(H20年厚生労働省告示225号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 延納
労働保険徴収法 延納
R5-168
R5.2.11 継続事業(一括有期事業)の概算保険料の延納
今日は、概算保険料の延納の制度をみていきましょう。
継続事業と一括有期事業の労働保険料は、保険年度ごとに算定します。概算保険料は、7月10日が納期限ですが、事業主が申請することにより、延納することができます。
今日のテーマは、継続事業と一括有期事業の延納です。単独の有期事業の延納は別のルールがあります。
条文を読んでみましょう。
第18条 (概算保険料の延納) 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が 第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。 |
 延納のポイント!
延納のポイント!
■事業主の申請が必要です。
■延納できる概算保険料
・年度の概算保険料、保険関係成立当初の概算保険料
・認定決定による概算保険料
・増加概算保険料
・追加徴収による概算保険料
※確定保険料は延納できません。
■概算保険料の額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円以上)
又は
労働保険事務組合に労働保険事務を委託している
■10月1日以降に成立した事業は、延納できません。
<延納回数をみてみましょう>
■保険関係が前年度以前に成立している場合
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
期間 | 4月1日~7月31日 | 8月1日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
納期限 | 7月10日 | 10月31日 ※11月14日 | 1月31日 ※2月14日 |
※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、第2期と第3期の納期限が14日延長されます。
■年度の中途に保険関係が成立した場合
・4月1日~5月31日に成立した場合→3回の延納が可能です。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 |
期間 | 成立日~7月31日 | 8月1日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
納期限 | 成立した日の 翌日から50日以内 | 10月31日 ※11月14日 | 1月31日 ※2月14日 |
・6月1日~9月30日に成立した場合→2回の延納が可能です。
| 第1期 | 第2期 |
期間 | 成立日~11月30日 | 12月1日~3月31日 |
納期限 | 成立した日の翌日から 50日以内 | 1月31日 ※2月14日 |
・10月1日以降に成立した場合 → 延納できません。一括して納付します。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問8-A(雇用)】
概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。
②【R2問8-C(雇用)】
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。

【解答】
①【R2問8-A(雇用)】 〇
7月1日に保険関係が成立した場合、2回に分けて納付することができます。最初の期分の納付期限は、7月1日の翌日から起算して50日以内ですので、8月20日となります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|
|
| 成立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第1期 納付期限 8月20日 | 第2期 納付期限 1月31日 ※2月14日 | |||||||
②【R2問8-C(雇用)】 〇
概算保険料の延納が認められている事業主は、申請することにより、増加概算保険料も延納することができます。
増加概算保険料の延納は、見込額が増加した日以後、「4月1日から7月31日まで」、「8月1日から11月30日まで」、「12月1日から翌年3月31日」までの各期に分けて納付できます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
第1期 | 第2期 | 第3期 | |||||||||
問題文では第1期に属する7月1日に増加が見込まれていますので、3等分にして延納することができます。
最初の期分の納付期限は、7月1日の翌日から起算して30日以内ですので7月31日となります。
8月1日から11月30日までの分は10月31日(11月14日)、12月1日から翌年3月31日までの分は1月31日(2月14日)までに納付します。
(則第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 失業の認定
雇用保険法 失業の認定
R5-167
R5.2.10 失業の認定要領
基本手当の支給を受けるためには、公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした上で、失業の認定を受けることが必要です。
なお、「失業」とは、第4条で、「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」と定義されています。
失業の認定とは、受給資格者が失業状態(労働の意思も能力が有るけれど、就職できない状態)にあることを確認することです。
条文を読んでみましょう。
第15条 ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 |
なお、失業の認定は、原則として、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年問2-A】
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
②【R2年問2-B】
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
③【R2年問2-C】
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。
④【R2年問2-D】
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。
⑤【R2年問2-E】
認定対象期間において一の求人に係る筆記試験と採用面接が別日程で行われた場合、求人への応募が2回あったものと認められる。

【解答】
①【R2年問2-A】 〇
失業の認定は、失業の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間に、求職活動実績が原則として2回以上あることを確認して行われます。
求職活動実績として認められる求職活動は、就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動や求人への応募等が該当します。
公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等は求職活動実績として認められます。問題文のように、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことも、求職活動実績として認められます。
(参照:行政手引51254)
②【R2年問2-B】 ×
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われます。そのため代理人による失業の認定はできません。
(行政手引51252)
なお、未支給失業等給付に係る失業の認定は、公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、遺族の代理人が失業の認定を受けることができます。
(行政手引53104)
③【R2年問2-C】 ×
内職、自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者は、労働の意思を有するものとしては「取り扱われません」。
(行政手引51254)
④【R2年問2-D】 ×
求職条件として短時間労働を希望する者の場合、雇用保険の被保険者と「なり得る」求職条件を希望する者に限り、労働の意思を有すると推定されます。
(行政手引51254)
⑤【R2年問2-E】 ×
書類選考、筆記試験、採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合は、そのいずれまでを受けたかにかかわらず、「一の応募」として取り扱われます。
(行政手引51254)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 障害補償給付の額
労災保険法 障害補償給付の額
R5-166
R5.2.9 障害補償給付「加重障害」
既に身体障害のあった人が、新たな業務上の傷病によって同一の部位の障害の程度を加重したときは、その加重した程度で障害補償給付が行われます。「加重障害」といいます。
加重障害で給付される額は、加重された身体障害の等級の給付額と、既にあった身体障害の等級の給付額との差額となります。
条文を読んでみましょう。
則第14条第5項 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額)を差し引いた額による。 |
例えば
・既存の障害が5級(184日分)で、加重した障害が3級(245日分)の場合
新たに支給される年金は、61日分(245日分-184日分)で計算します。
ちなみに、既存の障害は、労災でも私傷病でも原因は問われませんが、既存の障害で労災保険から年金を受けている場合は、その年金は引き続き支給されます。
・既存の障害が14級(56日分)で、加重した障害が10級(302日分)の場合
246日分(302日分-56日分)の一時金が支給されます。
・既存の障害が8級(503日分の一時金)で、加重した障害が7級(131日分の年金)の場合
新たに支給される年金は、131日分-(503日分÷25)で計算します。
一時金は、年金の25年分です。一時金の日数を25で割った1年あたりの額との差額を出すのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
【R2年問5】
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 給付基礎日額の67日分
B 給付基礎日額の156日分
C 給付基礎日額の189日分
D 給付基礎日額の223日分
E 給付基礎日額の379日分

【解答】
「A 給付基礎日額の67日分」の障害補償一時金が支給されます。
既にあった障害は第11級、加重した障害は第12級で、どちらも「一時金」の等級です。
加重によって支給される一時金は、「223日分-156日分」=67日分で計算します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 減給制裁
労働基準法 減給制裁
R5-165
R5.2.8 制裁規定の制限
就業規則の「制裁」の種類には、譴責、出勤停止、即時解雇等があります。
制裁の原因となる事案が公序良俗に反しない限りは、制裁自体は禁止されていません。
ただし、制裁のうち、「減給」については、労働した時間分をカットすることになりますので、労働基準法で制限が設けられています。
条文を読んでみましょう。
第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
1回あたりの減給の額は、平均賃金の1日分の半額以内です。
また、複数回の減給事案があったとしても、減給の総額は、一賃金支払期の賃金の総額の10分の1以下にする必要があります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける。
②【H16年出題】
就業規則で労働者に対して減給の定めをする場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。
③【H25年出題】
労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

【解答】
①【R2年出題】 ×
遅刻・早退した時間分は、賃金が発生しません。例えば1時間遅刻して、1時間分の賃金をカットしても、減給制裁には当たりませんので、労働基準法第91条による制限を受けません。
ただし、遅刻、早退の時間分の賃金を超える減給は制裁に当たりますので、労働基準法第91条の制限を受けます。
(S63.3.14基発150号)
②【H16年出題】 ×
例えば、平均賃金が1万円の場合、減給の1回の額は5千円以内となります。また減給事案が5回発生した場合は、5千円×5回=2万5千円となります。しかし、総額は1賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内となりますので、例えば1賃金支払期の賃金の総額が20万円の場合は、2万円が上限となります。残りの5千円は当該賃金支払期には減給できませんが、次期の賃金支払期に延ばすことは「可能」です。
(S23.9.20基収1789号)
③【H25年出題】 ×
平均賃金は、「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」です。
減給の制裁に関し、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日」となります。
(S30.7.1929基収5875号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 使用者
労働基準法 使用者
R5-164
R5.2.7 使用者の定義
労働基準法の「使用者」の定義を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 |
労働基準法の「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者のことです。
次の3つが、労働基準法の「使用者」と定義されています。
・事業主
→ その事業の経営の主体
・事業の経営担当者
→ 法人の代表者、支配人など
・その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
では、過去問をどうぞ!
①【R2問1-A】
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体をいい、個人企業にあってはその企業主個人、株式会社の場合は、その代表取締役をいう。
②【R2問1-B】
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
③【R2問1-C】
事業における業務を行うための体制としていくつかの課が設置され、課が所掌する日常業務の大半が課長権限で行われていれば、課長がたまたま事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけであっても、その伝達は課長が使用者として行ったこととされる。

【解答】
①【R2問1-A】 ×
「事業主」とは、その事業の経営の経営主体です。
個人企業の場合は企業主個人、株式会社など法人組織の場合は、「法人そのもの」をいいます。株式会社の代表取締役は、「事業主」には当たりません。
②【R2問1-B】 ×
「使用者」とは労働基準法各条の義務についての履行の責任者をいいます。
部長や課長等の形式にとらわれることなく、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによります。
そのため、「係長」でも、与えられている責任と権限によっては、「使用者」として労働基準法の義務についての履行の責任が問われます。
(S22.9.13発基第17号)
③【R2問1-C】 ×
「使用者」は、労働基準法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによります。権限が与えられていなくて、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は使用者とはみなされません。
課長が、事業主等の上位者から権限外の事項について命令を受けて単にその命令を部下に伝達しただけの場合は、その伝達は課長が使用者として行ったことにはなりません。
(S22.9.13発基第17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金
厚生年金保険法 障害厚生年金
R5-163
R5.2.6 障害厚生年金の失権のタイミング
障害厚生年金の失権時期を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第53条 (失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 第48条第2項 前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |
今日は2号と3号に注目しましょう。
障害厚生年金の障害等級は1級から3級まであります。
障害厚生年金の受給権の消滅は、3級に該当しなくなって3年経過したとき、又は、65歳に達したときのどちらか遅い方です。
少なくとも65歳までは失権しないのがポイントです。
★障害厚生年金の失権のタイミング
・65歳で失権(3級に該当しなくなって3年を経過している)
3級未満 ▼3年経過 ▼65歳
支給停止 |
|
▲失権
・3級に該当しなくなって3年を経過した日に失権(65歳以上)
3級未満 ▼65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその者が65歳に達した日に消滅する。
②【H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったため支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
③【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
63歳の時に障害の程度が軽減し支給停止になった場合、65歳時点ではまだ3年経過していませんので65歳に達した日には消滅しません。
3級に該当しないまま3年経過した時点で失権します。
63歳 66歳
3級未満 65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
②【H30年出題】 〇
64歳の時点で障害等級に該当しなくなって支給停止になり、その状態のまま65歳に達したとしても、3年経過していませんので、65歳時点では障害厚生年金の受給権は消滅しません。
64歳 67歳
3級未満 65歳 ▼3年経過
支給停止 |
|
▲失権
③【R2年出題】 ×
3級に該当しなくなると障害厚生年金の支給は停止されます。その状態のまま3年が経過しても65歳までは失権しません。65歳に達する日の前日までに障害等級3級に該当した場合は、支給停止が解除され、障害厚生年金が支給されます。
<65歳に達していない場合>
3級 3級未満 3年経過 3級該当
▼ ▼ ▼ ▼
3級 支給 | 支給停止 | 3級 支給再開 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 国民年金基金
国民年金法 国民年金基金
R5-162
R5.2.5 国民年金基金の加入員
今日のテーマは国民年金基金です。
国民年金基金は、「加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする」とされています。
国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行ないます。
また、国民年金基金には、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の2種類があります。
今日は、国民年金基金の加入員をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第127条 ① 第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。 ② 申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする。 附則第5条第11項 「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」、「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは、第116条第1項及び第2項(国民年金基金の組織)並びに第127条第1項の規定(国民年金基金の加入員)の適用については、第1号被保険者とみなす。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。
②【H29年出題】
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、地域型国民年金基金の加入員となることができない。
③【H24年出題】
第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合、当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することとなり、地域型国民年金基金には加入できない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
国民年金基金の加入者になることができるのは、第1号被保険者です。
任意加入被保険者のうち、「日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者」と「日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」も、国民年基金の加入者となることができます。
(法附則第5条)
②【H29年出題】 ×
日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入できます。
ちなみに、任意加入被保険者のうち、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」は、国民年金基金の加入員から除外されています。
(法附則第5条)
③【H24年出題】 ×
第127条第1項で、「第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。」と規定されていますので、同時に2つの基金には加入できません。
しかし、問題文のように、職能型国民年金基金の方が優先するということはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金
健康保険法 傷病手当金
R5-161
R5.2.4 労務に服することができないとき
傷病手当金の支給要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第99条第1項 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
 傷病手当金の支給要件は次の3つです。
傷病手当金の支給要件は次の3つです。
・療養中であること
・労務に服することができないこと
・連続3日間の待期期間を満たしていること
今日は、要件の1つ「労務に服することができない」をみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない。
②【R2年出題】
伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。
③【H25年出題】
傷病手当金は、傷病が休業を要する程度でなくとも、遠隔地であり、通院のため事実上働けない場合には支給される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたい」とされています。
・被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能でも、職場転換などで就労可能な他の比較的軽微な労務に服して相当額の報酬を得ている場合
→ 労務不能には該当しません。
・本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業や内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することで賃金を得る場合等
→ 労務不能に「該当します」。
問題文の後半が誤りです。
(H15.2.25保保発第0225007号/庁保険発第4号)
②【R2年出題】 〇
自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって保険事故としての疾病と解されます。病原体保有者が隔離収容等のため労務に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となります。
(S29.10.25保険発第261号)
③【H25年出題】 〇
傷病が休業を要する程度でなくても、病院が遠隔地で、通院のため事実上働けない場合には、傷病手金が支給されます。
(S2.5.10保理2211)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 特別加入者の保険料
労働保険徴収法 特別加入者の保険料
R5-160
R5.2.3 特別加入保険料の月割計算
特別加入者の保険料の額は、保険料算定基礎額に、特別加入保険料率を乗じて計算します。
例えば中小事業主等の特別加入者で給付基礎日額が10,000円の場合、保険料算定基礎額は、3,650,000円(10,000円×365)で、その額に第1種特別加入保険料率を乗じて計算します。
今日は、保険料算定基礎額の月割計算の方法をみていきましょう。
・保険年度の中途に新たに特別加入者となった者又は特別加入者でなくなった者
→ 保険料算定基礎額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該保険年度中に特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
・有期事業について
→ 保険料算定基礎額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該特別加入に係る期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額を12で除して得た額に、その者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数を乗じて得た額とする。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数を切り捨てる。
②【H24年出題】(労災) ※改正による修正あり
個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。
なお、事業の種類等は次のとおりである。
・事業の種類 飲食店
・当該事業に係る労災保険率 1000分の3
・中小事業主等の特別加入に係る承認日 令和4年12月15日
・給付基礎日額 8千円
・特別加入保険料算定基礎額 292万円
(A)8千円×107日×1000分の3
(B)8千円×108日×1000分の3
(C)292万円×12分の1×3か月×1000分の3
(D)292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3
(E)292万円×12分の1×4か月×1000分の3

【解答】
①【R2年出題】(労災)×
継続事業の場合で、保険年度の中途に第1種特別加入者でなくなった場合の保険料算定基礎額は、特別加入保険料算定基礎額÷12×当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数となります。当該月数に1月未満の端数があるときはその月数は1月に切り上げます。
★「月割計算」するのがポイントです。例えば、令和5年2月3日に特別加入した場合は、特別加入とされた期間の月数は、2月と3月の「2か月」となります。
②【H24年出題】(労災) E
E 「292万円×12分の1×4か月×1000分の3」で算定します。
292万円は8千×365です。
月割計算の際、1月未満の端数は1月に切り上げるのがポイントですので、12月から3月までの4か月となります。
保険年度の中途に新しく特別加入者となった場合は、特別加入申請の承認日の属する月を1月に切り上げ、また、保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった者は、特別加入者たる地位の消滅日の前日の属する月を、1月に切り上げます。
例えば、以下のような場合は、6月と1月をそれぞれ1月に切り上げます。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|
| 加入 |
|
|
|
|
|
| 脱退 |
|
|
※有期事業の場合
有期事業についての特別加期間のすべてにおいての端数処理となります。
例えば、有期事業全体で6か月と10日の場合は、10日の端数を1か月に切り上げ、 7か月となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 訓練延長給付
雇用保険法 訓練延長給付
R5-159
R5.2.2 訓練延長給付の延長期間
訓練延長給付は、公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象です。
延長期間には、待期中、受講中、終了後の3つがあります。
・所定給付日数分の基本手当を支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間(90日が限度) ・受講している期間(2年が限度) ・受講終了日における支給残日数が30日未満で公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者 |
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
受給資格者が公共職業安定所の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるための雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。
②【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

【解答】
①【H25年出題】 ×
所定給付日数分の基本手当を支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している者については、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く 「90日」の期間内の失業している日について、支給されます。
②【R2年出題】 〇
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合のその日額は、本来の基本手当の日額と同じ額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 遺族補償年金
労災保険法 遺族補償年金
R5-158
R5.2.1 遺族補償年金の受給資格者と受給権者
遺族補償年金を受ける資格のある遺族のことを「受給資格者」といいます。受給資格者には順位が定められていて、そのうち最先順位者が年金を受ける「受給権者」になります。
「受給資格者」は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。
ただし、「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者については、労働者の死亡の当時、一定の年齢要件か一定の障害状態に該当した場合に限られます。
では受給資格者の範囲と順位を条文で読んでみましょう。
第16条の2 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4 前3号の年齢要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 ③ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。 |
※労働者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳上60歳未満であったものは遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。(S40年改正法附則第43条)
順位を確認しましょう。
 妻・60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
妻・60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
 18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある子
18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある子
 60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
 18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある孫
18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある孫
 60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
 18歳年度末までの間にある又は60歳以上又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
18歳年度末までの間にある又は60歳以上又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
 55歳以上60歳未満の夫
55歳以上60歳未満の夫
 55歳以上60歳未満の父母
55歳以上60歳未満の父母
 55歳以上60歳未満の祖父母
55歳以上60歳未満の祖父母
 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
遺族補償年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
②【R2年出題】
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

【解答】
①【H19年出題】 〇
障害等級第5級以上と、労働が高度の制限を受ける、がキーワードです。
(則第15条)
②【R2年出題】 ×
Yの死亡の当時19歳の子は、遺族の条件に当てはまりませんので、受給資格者にも受給権者にもなりません。
Yの死亡の当時17歳の子については、Yから定期的に養育費を送金されていて生計維持関係があるため、受給資格者となります。
遺族補償年金の受給資格者は17歳の子のみとなり、その子が受給権者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 面接指導
労働安全衛生法 面接指導
R5-157
R5.1.31 面接指導の条件
今日は、面接指導をみていきましょう。
面接指導には、
①長時間労働者、②研究開発業務従事者、③高度プロフェッショナル制度対象者の3つのパターンがあります。
 以下の点がポイントです。
以下の点がポイントです。
①長時間労働者 | 月80時間を超える 時間外労働・休日労働を行った + 疲労の蓄積がある | 労働者からの 申出が必要 |
②研究開発業務従事者 | 月100時間を超える 時間外労働・休日労働を行った | 申出不要 |
③高度プロフェッショナル制度対象者 | 1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた時間について月100時間を超えた | 申出不要 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
②【R2年出題】
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
③【R2年出題】
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者に対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
④【R2年出題】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよい。

【解答】
①【R2年出題】 ×
事業者が面接指導を行う義務があるのは、『1月当たり「80時間」を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合』です。
(法第66条の8、則第52条の2、第52条の3)
②【R2年出題】 ×
研究開発に係る業務に従事する労働者については、『1月当たり「100時間」を超えた場合』は、労働者からの申出の有無にかかわらず、事業者は面接指導を行う義務があります。
(法第66条の8の2、則第52条の7の2)
③【R2年出題】 〇
高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超える者に対して、事業者は面接指導を行う義務があります。労働者からの申出の有無は問いません。
(法第66条の8の4、則第52条の7の4)
④【R2年出題】 ×
労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者については、労働時間を把握する義務があります。
高度プロフェッショナル制度により労働する労働者については、労働時間を把握する義務の対象から除外されています。
(法第66条の8の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 三六協定
労働基準法 三六協定
R5-156
R5.1.30 三六協定の限度時間
法定労働時間を超えて労働させる場合、法定休日に労働させる場合は、「36協定」を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
今日は、36協定の協定事項を確認しましょう。
第36条を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
次に、36協定に定める事項を確認しましょう。
第36条第2項 第36条第1項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間(労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、 1年間に限るものとする。) 3 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 4 対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 5 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 |
今日は第4号に注目します。
さらに条文を読んでみましょう。
第36条第3項、第4項 ③ 前項第4号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。 ④ 限度時間は、1か月について45時間及び1年について360時間(1年単位の変形労働時間制の対象期間として3か月を超える期間を定めた場合は、1か月について 42時間及び1年について320時間)とする。 |
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

【解答】
【R2年出題】 〇
36協定に定める時間外労働の限度時間は、1か月45時間、1年360時間です。1年単位の変形労働時間制で対象象期間として3か月を超える期間を定めて労働させる場合は、1か月42時間、1年320時間です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 2種類以上の被保険者であった期間
厚生年金保険法 2種類以上の被保険者であった期間
R5-155
R5.1.29 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の年金額
厚生年金保険の被保険者には第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の4つの種別があります。
例えば、民間企業の会社員と、国家公務員の経験がある人の場合は、第1号厚生年金被保険者としての期間と、第2号厚生年金被保険者としての期間の2つの種別の被保険者であった期間を有することとなります。
今日は、2つ以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の年金額の計算について確認しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の額の計算においては、その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を合算して1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を算出する。
②【H29年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
③【H28年出題】
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日おいて2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
④【H30年出題】
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。
⑤【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。

【解答】
①【H29年出題】 ×
例えば、第1号厚生年金被保険者期間が10年、第4号厚生年金被保険者期間が19年ある場合、合算して計算するのではなく、第1号厚生年金被保険者期間分と、第4号厚生年金被保険者期間分をそれぞれで計算します。
また、年金の支給は、10年分は厚生労働大臣から、19年分は日本私立学校振興・共済事業団から、それぞれ支給されます。
★2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金について
年金額の計算 | それぞれの種別ごとに計算 |
年金の支給事務 | それぞれの実施機関が行う |
(法第78条の26第2項)
②【H29年出題】 ×
「2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するもの」とみなして額を計算します。
(法第78条の30)
③【H28年出題】 ×
障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
(法第78条の33)
★2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金について
年金額の計算 | 2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算 |
年金の支給事務 | 初診日に加入していた実施機関が行う |
④【H30年出題】 〇
短期要件の遺族厚生年金の額は、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をします。
(法第78条の32第1項)
⑤【H28年出題】 〇
長期要件の遺族厚生年金は、各号の被保険者期間に係る被保険者期間ごとにそれぞれの実施機関から支給されます。
(法第78条の32第2項)
★2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金について
年金額の計算 | <短期要件> 2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算 <長期要件> 各被保険者期間ごとに支給される |
年金の支給事務 | <短期要件> 死亡日(又は初診日)に加入していた実施機関が行う <長期要件> それぞれの実施機関が行う |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 令和5年度の年金額
国民年金法 令和5年度の年金額
R5-154
R5.1.28 令和5年度の年金額の改定
 「改定率」は毎年度見直されます。
「改定率」は毎年度見直されます。
老齢基礎年金の満額は、780,900円×改定率で計算します。
「改定率」は、毎年度見直しが行われます。
 名目手取り賃金変動率と物価変動率
名目手取り賃金変動率と物価変動率
★改定率の改定に使われる指標は、
新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」
既裁定者は「物価変動率」
です。
★令和5年度の改定については、
「物価変動率」=+2.5%、「名目手取り賃金変動率」=+2.8%
を用います。
 マクロ経済スライドについて
マクロ経済スライドについて
マクロ経済スライドとは?
→ 公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定されます。その率を、賃金と物価の変動がプラスとなる場合は、改定率から控除する仕組みです。
令和5年度の「マクロ経済スライドによるスライド調整率」は-0.3%です。
 マクロ経済スライドのキャリーオーバー(未調整分)
マクロ経済スライドのキャリーオーバー(未調整分)
マクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額を下げないという措置は維持した上で、調整できなかった分を翌年度以降に繰り越す制度のことです。
前年度までのマクロ経済スライドの未調整分は、-0.3%です。
 令和5年度の改定率
令和5年度の改定率
<新規裁定者>
・名目手取り賃金変動率(+2.8%)を用いて改定されます。
さらに、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(-0.3%)と、マクロ経済スライドの未調整分の調整(-0.3%)が行われます。
イメージ
名目手取り 賃金変動率 +2.8
| マクロ経済スライド -0.3 |
マクロ経済スライド未調整分 -0.3 | |
+2.2
|
新規裁定者の改定率=0.996(令和4年度の改定率)×1.022=1.018です。
令和5年度の年金額は780,900円×1.018=795,000円となります。
※100円未満四捨五入しています。
<既裁定者>
・物価変動率(+2.5%)を用いて改定されます。
さらに、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(-0.3%)と、マクロ経済スライドの未調整分の調整(-0.3%)が行われます。
イメージ
物価変動率 +2.5
| マクロ経済スライド -0.3 |
マクロ経済スライド未調整分 -0.3 | |
+1.9
|
既裁定者の改定率=0.996(令和4年度の改定率)×1.019=1.015です。
令和5年度の年金額は780,900円×1.015=792,600円となります。
※100円未満四捨五入しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 追納
国民年金法 追納
R5-153
R5.1.27 追納が可能な期間
第1号被保険者は、毎月、国民年金の保険料を納付する義務がありますが、収入が少ないなどの場合は、保険料の免除を受けることができます。
免除を受けた期間は保険料免除期間となり、老齢基礎年金の額ではカットされて計算されます。
しかし、保険料を「追納」することにより、保険料免除期間を保険料納付済期間にすることもできます。
今日のテーマは、「追納」です。
条文を読んでみましょう。
第94条第1項 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。 ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
・老齢基礎年金の受給権者は、追納できません。
・追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限ります。
では、過去問をどうぞ!
【R2年出題】
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

【解答】
【R2年出題】 〇
問題文の場合、承認の日の属する月が令和2年4月です。
追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内ですので、令和2年3月から10年以内にあるものです。
問題文の場合は、平成22年4月から平成28年3月分までが、追納できる期間です。
H18年7月 H22年4月 H28年3月
10年以内にないので、追納できない
| 追納できる |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 適用除外
健康保険法 適用除外
R5-152
R5.1.26 健保・季節的業務に使用される者
健康保険の適用事業所に使用される者は、被保険者となります。
しかし、一定の者は、健康保険の適用が除外されています。
除外されるものの一つに「季節的業務に使用される者」があります。
「季節的業務に使用される者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。」とされています。季節的業務に使用される者は、健康保険の一般の被保険者からは除外されます。
しかし、「継続して4か月を超えて使用されるべき場合を除く。」という例外があります。季節的業務でも当初から継続して4か月を超える予定で使用される場合は、当初から一般の被保険者となります。
(法第3条第1項第4号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
季節的業務に使用される者について、当初4か月以内の期間において使用される予定であったが業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。
②【H25年出題】
季節的業務に使用される者が、当初4か月未満使用される予定であったが、業務の都合により、継続して4か月以上使用されることになった場合には、そのときから被保険者となる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
季節的業務に当初4か月以内の予定で使用された場合は、一般の被保険者から除外されます。業務の都合等で継続して4か月を超えたとしても一般の被保険者にはなりません。
(S9.4.17保発191)
②【H25年出題】 ×
季節的業務に当初4か月未満の予定で使用された場合は、業務の都合で、継続して4か月以上使用されることになった場合でも被保険者にはなりません。
(S9.4.17保発191)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 雇用保険印紙購入通帳
労働保険徴収法 雇用保険印紙購入通帳
R5-151
R5.1.25 雇用保険印紙購入通帳の交付と印紙の購入
日雇労働被保険者を使用した場合、事業主は、「その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の日雇労働被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。」とされています。(則第40条)
雇用保険印紙は、第1級、第2級、第3級の3種類で、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)で販売されています。(則第41条)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、「雇用保険印紙購入通帳の交付」を受けなければなりません。(則第42条第1項)
雇用保険印紙購入通帳によって、日本郵便株式会社の営業所から必要な枚数を購入することになります。
「雇用保険印紙購入通帳」には有効期間があります。条文を読んでみましょう。
則第42条 ② 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。 ③ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。 ④ 雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。 ⑧ 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。 |
有効期間があるのは、「雇用保険印紙購入通帳」です。印紙そのものには有効期間はありませんので注意してください。
雇用保険印紙購入通帳の更新手続きは、「有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間」です。具体的には、3月1日から3月31日までの間です。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(雇用保険)
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙の購入申込書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
②【18年出題】(雇用保険)
事業主は、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けることにより、公共職業安定所にて雇用保険印紙を購入することができる。
③【H20年出題】(雇用保険)
雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日から1年間に限り、その効力を有する。
④【R2年出題】(雇用保険)
雇用保険印紙購入通帳の有効期間満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて雇用保険印紙購入通帳更新申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、有効期間の更新を受けなければならない。

【解答】
①【H23年出題】(雇用保険) ×
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けるために提出するのは、雇用保険印紙の購入申込書ではなく、「雇用保険印紙購入通帳交付申請書」です。
(様式第9号、則第42条)
②【18年出題】(雇用保険) ×
雇用保険印紙は、①「あらかじめ雇用保険印紙購入通帳交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳の交付を受ける」→②「総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)にて雇用保険印紙を購入する」という流れで購入します。
印紙は、公共職業安定所ではなく、総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)で販売されます。
(則第41条、42条、43条)
③【H20年出題】(雇用保険) ×
雇用保険印紙購入通帳は、「その交付の日の属する保険年度」に限り、その効力を有する、です。
(則第42条)
④【R2年出題】(雇用保険) 〇
雇用保険印紙購入通帳の更新手続きは、有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、行います。
(則第42条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 延長給付
雇用保険法 延長給付
R5-150
R5.1.24 広域延長給付と全国延長給付
基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間、年齢、離職理由、就職が困難な者であるかどうかで決まります。
しかし、その時の雇用失業情勢や、地域の状況などにより、所定給付日数の延長が行われることもあります。
延長給付には、訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付があります。
今日は、広域延長給付と全国延長給付をみていきます。
<広域延長給付>
厚生労働大臣が失業者が多数発生した地域について広域職業紹介活動を行わせた場合において必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り当該地域に係る広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当と認められる受給資格者について、所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置(広域延長措置)を決定することができる。
(行政手引52401)
※広域延長給付は、90日を限度として行われます。
<全国延長給付>
厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、すべての受給資格者を対象として一定日数の給付日数を延長するための措置(全国延長措置)を決定することができる。
また、厚生労働大臣は、全国延長措置を決定した後において必要があると認めるときは、上記により指定した期間を延長することができることとなっている。
(行政手引52451)
※全国延長給付は、「すべての受給資格者」が対象です。
※全国延長給付は、90日を限度として行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
②【H25年出題】
全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。
③【R2年出題】
厚生労働大臣は、雇用保険法第27条第1項に規定する全国延長給付を支給する指定期間を超えて失業の状況について政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、当該指定期間を延長することができる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
1.5倍ではなく、「100分の200」以上となるに至り、かつその状態が継続すると認められる場合に行われます。
(法第25条、令第6条)
②【H25年出題】 ×
全国延長給付が行われる基準は、「連続する4月間(基準期間)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められること」とされています。
1 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。
2 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
「100分の4」が基準ですので、100分の3の場合は、全国延長給付は行われません。
(法第27条、令第7条)
③【R2年出題】 〇
厚生労働大臣は、全国延長措置を決定した後で必要があると認めるときは、指定した期間を延長することができます。
(法第27条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 未支給の保険給付
労災保険法 未支給の保険給付
R5-149
R5.1.23 労災・未支給の保険給付を請求できる範囲
今日は、労災保険の未支給の保険給付をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第11条第1項 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 |
未支給の保険給付を請求できるのは、
・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
★ただし、遺族(補償)等年金の場合は範囲が違います。未支給の保険給付を請求できるのは、遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族となります。遺族(補償)等年金には転給があるからです。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】 ※改正による修正あり
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
②【H22年出題】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
③【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
未支給の保険給付は、死亡した者の名ではなく、遺族が「自己の名」で請求することがポイントです。
②【H22年出題】 C
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順序は覚えましょう。
③【H30年出題】 〇
死亡した者と同順位の受給権者があるときは、未支給の保険給付の受給権者は、その者が第1位となります。死亡した者と同順位の受給権者がなく後順位の受給資格者があるときは次順位の受給資格者が、未支給の保険給付の受給権者の第1位となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 事業場とは
労働安全衛生法 事業場とは
R5-148
R5.1.22 労働安全衛生法の適用は事業場単位
例えば、総括安全衛生管理者の選任は、法第10条で、「事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し・・・」と定められています。
「事業場ごと」がポイントです。事業場単位で選任することになります。
今日は、労働安全衛生法の適用単位を確認しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同じである。
②【H28年出題】
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
③【R3年出題】
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。

【解答】
①【R2年出題】 〇
労働安全衛生法は、労働基準法と同じように、事業場を単位として適用されます。
安全衛生管理体制等は、事業場ごとの業種、規模等に応じて、適用されます。
適用は、「企業単位」ではありませんので注意して下さい。
「事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行なわれる作業の一体をいう。」とされています。同じ企業でも、工場、事務所、店舗のそれぞれで適用されることになります。
一の事業場であるか否かは主として場所的観念によって決定されます。
(S47.9.18発基第91号)
②【H28年出題】 〇
例えば、「〇〇製鉄」という企業の場合、製鉄所と本社はそれぞれ別の事業場です。
事業場の業種の区分は、その業態によって個別に決まりますので、製鉄所の業種の区分は「製造業」、当該製鉄所を管理する本社は労働安全衛生法施行令第2条第3号の「その他の業種」となります。
(S47.9.18発基第91号)
③【R3年出題】 ×
安全衛生管理体制は、事業場ごとに適用されます。総括安全衛生管理者は、企業全体ではなく、その事業場の業種や労働者数が基準となります。そして、総括安全衛生管理者は、企業全体の安全衛生管理を統括管理するのではなく、「その事業場」の安全衛生に関する業務の統括管理を行います。
(S47.9.18発基第91号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 第6条
労働基準法 第6条
R5-147
R5.1.21 中間搾取の排除
労働関係の開始や存続に関与して利益を得ることは、職業安定法などで認められている場合のほかは、禁止されています。
条文を読んでみましょう。
第6条 (中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
何人も、他の法律の定め如何にかかわらず、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
②【H28年出題】
労働基準法第6条は、法律によって許されている場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないとしているが、その規制対象は、私人たる個人又は団体に限られ、公務員は規制対象とならない。
③【R2年出題】
労働基準法第6条に定める「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」の「利益」とは、手数料、報償金、金銭以外の財物等いかなる名称たるかを問わず、また有形無形かも問わない。
④【H15年出題】
ある労働者派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであっても、当該労働者派遣事業の事業主が業として労働者派遣を行う行為は、「何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。」と規定する労働基準法第6条の中間搾取には該当しない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
法律に基づいて許される場合は、手数料、報酬等を受けることができます。
職業安定法と船員職業安定法には、手数料や報酬等のルールが定められています。
(S23.3.2基発381号、S33.2.13基発90号)
②【H28年出題】 ×
違反行為の主体は、「他人の就業に介入して利益を得る」第三者です。規制対象は、「個人、団体又は公人たる私人たるとを問わない」とされています。そのため、公務員も規制対象となります。
(S23.3.2基発381号)
③【R2年出題】 〇
なお、使用者より利益を得る場合に限らず、労働者又は第三者より利益を得る場合も含みます。
(S23.3.2基発381号)
④【H15年出題】 〇
労働者派遣は、派遣元と労働者は「労働契約関係」、派遣先と労働者は「指揮命令関係」にあります。
派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働契約に介入するものではありませんので、中間搾取には該当しません。
問題文のように、派遣事業が、所定の手続を踏まないで行われている違法なものであったとしても、労働基準法第6条の中間搾取には該当しません。※労働者派遣法に抵触する可能性はあります。
(S61.6.6基発333号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 児童手当法 児童手当いろいろ
児童手当法 児童手当いろいろ
R5-146
R5.1.20 児童手当の支給ルール
児童手当法はよく出題されます。ポイントをしっかりおさえましょう。
では、さっそく令和2年の過去問をどうぞ!
①【R2問8-A】
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
②【R2問8-B】
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
③【R2問8-C】
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
④【R2問8-D】
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
⑤【R2問8-E】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

【解答】
①【R2問8-A】 〇
「児童」の定義です。「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」ですので、高校卒業までが児童となります。
児童は、「日本国内に住所を有すること」が条件ですが、留学などの理由で海外に住んでいる場合も対象となります。
なお、「支給要件児童」は、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。「中学校修了前の児童」という。)と「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)」ですので、年齢の違いに注意してください。
(法第3条第1項、第4条第1項第1号)
②【R2問8-B】 ×
児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払います。例えば、10月に支給されるのは、6月~9月分です。
前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払われます。
(法第8条第4項)
③【R2問8-C】 〇
児童手当の増額は、額の改定の認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。手続きが遅れた場合は、原則として遅れた分が受けられなくなります。
(法第9条)
④【R2問8-D】 〇
児童手当を受けるのは、支給要件児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父又は母等です。児童本人が受けるのではありませんので注意してください。
一般受給資格者が死亡した場合で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、支給の対象になっていた児童に、その未支払の児童手当が支払われます。
(法第12条)
⑤【R2問8-E】 〇
児童手当を不正受給した場合は、罰則があります。
(法第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害手当金
厚生年金保険法 障害手当金
R5-145
R5.1.19 障害手当金は症状が固定していることが条件
今日は、障害手当金の支給要件を確認しましょう。
障害手当金は、障害の状態が、障害厚生年金を受けることができる状態よりも軽いときに支給されます。
では、条文を読んでみましょう。
第55条第1項 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。 |
障害の状態は、「初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日」でみることになります。
「初診日から5年以内に治っていること」が条件です。治っているということは症状が固定していることです。
では、過去問をどうぞ!
【R2問10-エ】
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過するまでの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。

【解答】
【R2問10-エ】 〇
障害厚生年金の障害状態は「障害認定日」で定められます。
障害認定日は、「初診日から1年6か月を経過した日」又は、「1年6か月以内に傷病が治った場合はその日」となります。傷病が治らなくても、初診日から1年6か月を経過した日に障害等級に該当する程度の状態であれば、要件を満たします。
一方、障害手当金は、初診日から起算して5年以内に、その傷病が「治っている」ことが条件ですので、治っていなければ支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 任意加入被保険者
国民年金法 任意加入被保険者
R5-144
R5.1.18 任意加入被保険者と480月の関係
国民年金の任意加入には、「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」があります。
「任意加入被保険者」の目的は2つです。
1つ目は、老齢基礎年金の受給資格を得られない人が、「老齢基礎年金の受給資格要件を満たすため」、2つ目は老齢基礎年金の受給資格はあるけれど満額ではない人が、「老齢基礎年金を増やすため」です。
なお、「特例による任意加入被保険者」の目的は、1つ目の「老齢基礎年金の受給資格要件を満たすため」だけです。
任意加入の条件を条文で読んでみましょう。
附則第5条 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
過去問をどうぞ!
【R2問9-C】
20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、保険料納付済期間を30年間、保険料半額免除期間を10年間有しており、これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は、任意加入被保険者となることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

【解答】
【R2問9-C】 〇
保険料半額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算上、4分の3(平成21年4月以降の場合)となります。
問題文の場合、老齢基礎年金の額に反映するのは、保険料納付済期間の月数(360)+保険料半額免除の月数(120月×4分の3)=450月となります。
65歳から受け取ることができる老齢基礎年金は満額ではありませんので、老齢基礎年金を増やすために、60歳から65歳までの間、任意加入することができます。
なお、月数が480に達したとき(=老齢基礎年金が満額になったとき)は、その日に任意加入被保険者の資格を喪失します。
こちらもどうぞ!
【H24問3-C】
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間や、いわゆる保険料の多段階免除期間(その段階に応じて規定されている月数)を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【H24問3-C】 〇
65歳未満の任意加入被保険者は、保険料納付済期間と多段階免除期間を合算し、満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失します。
本人から資格喪失の申出がなくても、自動的に資格喪失になるのがポイントです。
(法附則第5条第5項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 被扶養者
健康保険法 被扶養者
R5-143
R5.1.17 被扶養者は原則国内に居住していることが条件
健康保険の被扶養者として認定されるには、原則として、国内に居住していることが条件です。
条文を読んでみましょう。
第3条第7項 「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。 1 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2 被保険者の3親等内の親族で1に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4 3の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの |
被扶養者の認定基準として、原則として「日本国内に住所を有すること」という条件があります。例外として、日本国内に住所がない場合でも、「外国に一時的に留学する学生など、日本国内に生活の基礎があると認められる者」があります。
過去問をどうぞ!
①【R2問9-A】
被扶養者の認定において、被保険者が海外赴任することになり、被保険者の両親が同行する場合、「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とし、渡航先国で「家族帯同ビザ」の発行がない場合には、発行されたビザが就労目的でないか、渡航が海外赴任に付随するものであるかを踏まえ、個別に判断する。
②【R2問3-オ】
被保険者(海外に赴任したことがない被保険者とする。)の被扶養者である配偶者に日本国外に居住し日本国籍を有しない父がいる場合、当該被保険者により生計を維持している事実があると認められるときは、当該父は被扶養者として認定される。

【解答】
①【R2問9-A】 〇
まず、「外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」を確認しましょう。
施行規則第37条の2で次のように定められています。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②に掲げる者と同等と認められるもの
⑤ そのほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
問題文は、②外国に赴任する被保険者に同行する者に該当します。
「家族帯同ビザ」の確認により当該両親が被扶養者に該当するか判断することを基本とします。
(令元11.13保保発1113 第 1 号)
②【R2問3-オ】 ×
配偶者の父母が被扶養者となるには、生計維持関係があることと、同一世帯に属することが条件です。
問題文の場合、被保険者は国内に居住していて、配偶者の父は国外に居住しているので、同一世帯要件を満たしていません。また問題文の父は、日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものにも該当していません。
(則第37条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 日雇労働被保険者
労働保険徴収法 日雇労働被保険者
R5-142
R5.1.16 日雇労働被保険者の労働保険料の負担
雇用保険の日雇労働被保険者が失業した場合は、日雇労働求職者給付金が支給されます。
日雇労働求職者給付金には、印紙保険料の納付要件があります。
事業主は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど印紙保険料を納付しなければなりません。印紙保険料は、事業主が、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印して行われます。
雇用保険印紙には、第1級(176円)、第2級(146円)、第3級(96円)があり、事業主と日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担します。
労働保険料の被保険者負担分を確認しましょう。
労働保険には、「労災保険」と「雇用保険」があります。
「労災保険」の保険料は、事業主が全額負担します。
「雇用保険」の保険料は、賃金総額×雇用保険率で計算します。そのうち、被保険者が負担するのは、賃金総額×「雇用保険率-二事業率」×2分の1で計算します。
さらに、日雇労働被保険者については、「印紙保険料の額の2分の1の額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)」を負担します。
(第31条第1項、第2項)
過去問をどうぞ!
①【R2問10-C(雇用)】
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。
②【R2問10-D(雇用)】
日雇労働被保険者は、労働保険徴収法第31条第1項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額が176円のときは88円を負担するものとする。

【解答】
①【R2問10-C(雇用)】 ×
労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業の一般保険料率は、「労災保険率+雇用保険率」です。
「労災保険率」の部分は全額事業主が負担します。
雇用保険の被保険者の負担分は、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から、「一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額となります。
被保険者負担分=(雇用保険率-二事業率)×2分の1です。
②【R2問10-D(雇用)】 〇
日雇労働被保険者は、①の問題文の被保険者負担分「(雇用保険率-二事業率)×2分の1」のほかに、印紙保険料の額の2分の1を負担します。
日雇労働被保険者は、一般被保険者と同じ雇用保険料額を負担し、さらに、印紙保険料の2分の1を負担します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 支給制限
雇用保険法 支給制限
R5-141
R5.1.15 不正行為による給付制限
不正な行為により給付を受けた場合の支給停止処分をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条 ① 偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、基本手当の全部又は一部を支給することができる。 ② 新たに受給資格を取得した場合には、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当を支給する。 |
不正に「求職者給付又は就職促進給付」の支給を受け、又は受けようとした場合は、以後、「基本手当」は支給されません。
例えば、基本手当を不正受給した場合は、以後、基本手当は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問5-B】
不正な行為により基本手当の支給を受けようとしたことを理由として基本手当の支給停止処分を受けた場合であっても、その後再就職し新たに受給資格を取得したときには、当該新たに取得した受給資格に基づく基本手当を受けることができる。

【解答】
①【R2問5-B】 〇
不正行為で基本手当の支給停止処分を受けた場合でも、その後の再就職で取得した新たな受給資格に基づく基本手当は支給されます。
では、次の条文です。
第61条の3 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
|
1について
高年齢雇用継続基本給付金を不正に受けた場合に給付制限の対象になるのは、「高年齢雇用継続基本給付金」です。
2について
例えば、基本手当を不正受給した場合、その受給資格に関係する高年齢再就職給付金は支給されません。
過去問をどうぞ!
②【R2問5-E】
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。
③【H22問6-D】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

【解答】
②【R2問5-E】 〇
高年齢雇用継続基本給付金の不正受給で給付制限の対象になるのは、「高年齢雇用継続基本給付金」です。その後の離職による基本手当は、給付制限されません。
③【H22問6-D】 〇
不正な行為により基本手当の支給を受けた場合、高年齢再就職給付金は給付制限の対象になります。支給要件を満たしたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできません。
次の条文を読んでみましょう。
第61条の9 ① 偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。 ② 育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となった場合には、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する。 |
では、過去問をどうぞ!
④【R2問5-D】
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。

【解答 】
④【R2問5-D】 ×
新たに育児休業給付金の支給要件を満たした場合、新たな受給資格に係る育児休業給付金は支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 傷病補償年金
労災保険法 傷病補償年金
R5-140
R5.1.14 傷病補償年金と打切補償
労働者が「業務上」負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間とその後30日間は解雇が禁止されています。
ただし、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治ゆしない場合は、使用者が打切補償(平均賃金の1200日分)を行えば、解雇が可能になります。打切補償を行うことによって補償義務がなくなるからです。
(労働基準法第19条)
しかし、業務上の傷病について、労災保険から保険給付が行われると、使用者の労働基準法の補償義務はなくなります。そうなると、使用者は打切補償をすることもなくなりますので、解雇制限が解除されなくなってしまいます。
そのため、労災保険法では、打切補償を支払ったと「みなす」という規定があり、それによって解雇することが可能になります。確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |
・療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合
→ 3年を経過した日に打切補償を支払ったものとみなす → 解雇できる
・療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
→ 傷病補償年金を受けることとなった日に打切補償を支払ったものとみなす → 解雇できる
では、過去問をどうぞ!
【R2問6-B】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

【解答 】
【R2問6-B】 ×
療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けていない場合は、その時点では、打切補償を支払ったものとはみなされません。しかし、その後に、傷病補償年金を受けることとなった場合は、その時点で打切補償を支払ったとみなされ、解雇制限が解除されます。
打切補償を支払ったとみなされるのは、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法 安全衛生教育
労働安全衛生法 安全衛生教育
R5-139
R5.1.13 安全衛生教育の対象者をおぼえましょう
労働安全衛生法の3つの安全衛生教育を確認しましょう。
・「雇入時・作業内容変更時の安全衛生教育」
労働者を雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したときの、その従事する業務に関する教育
・「特別教育」
危険又は有害な業務に労働者をつかせるときの、当該業務に関する特別の教育
・「職長教育」
新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対する教育
では、過去問をどうぞ!
①【R2問10-A】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
②【R2問10-B 】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。
③【R2問10-D】
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
④【R2問10-E】
事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

【解答】
①【R2問10-A】 ×
雇入れ時等の安全衛生教育は、「労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したとき」に行わなければなりません。「労働者」となっていますので全労働者が対象です。常時使用する労働者だけでなく、「臨時に雇用する労働者」に対しても義務となります。
(則第35条)
なお、「雇入れ時の健康診断」の対象者は、「常時使用する労働者」ですので、違いに注意してください。
(則第43条)
②【R2問10-B 】 〇
作業内容変更時の教育も、雇入れ時と同様に、全労働者が対象です。
③【R2問10-D】 〇
特別教育を必要とする業務は、厚生労働省令で定められていて、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務もその対象です。
(則第36条)
なお、最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は「就業制限業務」となり、業務に就かせる場合は、フォークリフト運転技能講習の修了などの条件がつきます。
(則別表3)
規模が小さいものは特別教育、大きいものは就業制限というイメージです。
④【R2問10-E】 〇
職長教育は新任の職長に対する教育です。
対象になる業種はおさえておきましょう。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
たばこ製造業、繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業
※令和5年4月1日から「食料品製造業(除く:うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業)」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに対象業種に追加されます。
※うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業は従前から職長教育の対象です
問題文の「金属製品製造業」は職長教育の対象です。
(令第19条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法 危険有害業務
労働基準法 危険有害業務
R5-138
R5.1.12 危険有害業務の就業制限
妊産婦を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることは禁止されています。
また、妊産婦以外の女性についても、女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務に就かせることが禁止されています。
条文を読んでみましょう。
第64条の3(危険有害業務の就業制限) ① 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、 哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ② ①の規定は、①に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ③ ①②に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 |
「危険有害業務の就業制限の範囲」は、女性労働基準規則第2条で定められています。
・「妊娠中の女性」の就業が制限される業務は、1号から24号まで24種類です。
・「産後1年を経過しない女性」については、24種類のうち、就業させてはならない業務が3種類、申し出た場合は就かせてはならない業務が19種類、就業させもいい業務が2種類です。
・「妊産婦以外の女性」については、24種類のうち就業させてはならない業務が2種類、就業させてもいい業務が22種類です。
※妊産婦以外の女性も就業させてはならない業務は、1号「重量物を取り扱う業務」と18号「有害物を発散する場所において行われる業務」です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問3-A】
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
②【R2問3-B】
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具等を用いて行う業務に就かせてはならない。
③【R2問3-C】
使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
④【R2問3-D】
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
⑤【R2問3-E】
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。

【解答】
①【R2問3-A】 〇
「重量物を取り扱う業務」は、妊産婦のみならず「妊産婦以外の女性」にも就かせてはならない業務です。
重量は、年齢別に定められています。満18歳以上は断続作業なら「30キログラム以上」、継続作業なら「20キログラム以上」です。30キログラム以上の重量物については、全女性に就業制限が適用されます。
②【R2問3-B】 ×
「さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具等を用いて行う業務」については、妊産婦については「就かせてはならない業務」ですが、妊産婦以外の女性については、就かせても差し支えない業務です。
③【R2問3-C】 〇
「つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務」については、妊娠中の女性を就かせることはできません。
ちなみに、産後1年を経過しない女性については、「女性が申し出た場合は就かせてはならない業務」となり、妊産婦以外の女性については、就かせても差し支えない業務です。
④【R2問3-D】 〇
「高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務」が禁止されるのは、妊娠中の女性のみです。
「産後1年を経過しない女性」、「妊産婦以外の女性」を就かせても差し支えありません。
⑤【R2問3-E】 〇
「動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務」は、産後1年を経過しない女性が従事しない旨を使用者に申し出た場合は、就かせることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 確定給付企業年金法
確定給付企業年金法
R5-137
R5.1.11 確定給付企業年金の掛金・支給のルール
今日のテーマは確定給付企業年金です。
確定給付企業年金の給付には、「老齢給付金」と「脱退一時金」があります。
また、規約で定めるところにより、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付も行うことができます。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2問6-A】
加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
②【R2問6-B】
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
③【R2問6-C】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
④【R2問6-D】
老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
⑤【R2問6-E】
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】
①【R2問6-A】 ×
★加入者期間の計算について
加入者期間の計算は月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の「前月」までが算入されます。
(法第28条)
②【R2問6-B】 ×
★掛金について
・事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
・加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。
(法第55条)
加入者が負担できるのは、掛金の一部です。加入者が掛金の全部を負担することはできません。
③【R2問6-C】 ×
★年金給付の支給期間について
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
(法第33条)
年金給付の支給期間は、終身又は10年以上ではなく、「終身又は5年以上」です。
④【R2問6-D】 〇
老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができます。
(法第39条)
⑤【R2問6-E】 ×
★老齢給付金の失権について
老齢給付金の受給権は、1~3のいずれかに該当することとなったときは、消滅します。
1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
(法第40条)
老齢給付金の受給権は、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」にも、消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法 障害厚生年金
厚生年金保険法 障害厚生年金
R5-136
R5.1.10 障害厚生年金の初診日要件
障害厚生年金は、「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」の条件を満たせば、受給権が発生します。
今日は、「初診日」の要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第47条 (障害厚生年金の受給権者) 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 |
ポイント!
「初診日」とは、傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。
「初診日」に厚生年金保険の被保険者であったことが条件です。
過去問をどうぞ!
①【R2問4-E】
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。
②【R2問4-B】
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①【R2問4-E】 ×
障害厚生年金は、初診日に「厚生年金保険の被保険者」であることが条件です。
問題文の場合、初診日は国民年金の第1号被保険者ですので、障害厚生年金の初診日要件を満たしません。そのため、障害厚生年金を受給することはできません。
②【R2問4-B】 ×
障害厚生年金は、初診日に「厚生年金保険の被保険者」であることが条件で、初診日に高齢任意加入被保険者だった場合は、初診日要件を満たします。
初診日に高齢任意加入被保険者で、初診日の前日に保険料の納付要件を満たしている場合は、障害厚生年金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法 寡婦年金
国民年金法 寡婦年金
R5-135
R5.1.9 寡婦年金 死亡した夫の条件
寡婦年金の支給要件のうち、死亡した夫の要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第49条 (支給要件) 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が 10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。
60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
「夫」の条件を確認しましょう。
・ 死亡日の前日に、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、10年以上あること
※保険料免除期間は、「学生納付特例期間及び納付猶予期間」以外となっていますので、「学生納付特例期間及び納付猶予期間」しか有しない場合は、寡婦年金は支給されません。
・老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けていないこと
では、過去問をどうぞ!
①【R2問9-A 】
68歳の夫(昭和27年4月2日生まれ)は、65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し、令和2年4月に老齢基礎年金の受給資格を満たしたが、裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時、当該夫により生計を維持し、当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合、この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなければ、妻には65歳まで寡婦年金が支給される。なお、死亡した夫は、障害基礎年金の受給権者にはなったことがなく、学生納付特例の期間、納付猶予の期間、第2号被保険者期間及び第3号被保険者期間を有していないものとする。
②【R2年問4-E】
夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合には、他の要件を満たしていても、その者の妻に寡婦年金は支給されない。

【解答】
①【R2問9-A 】 ×
死亡した夫は、「第1号被保険者」としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あることが条件です。
特例による任意加入被保険者は、寡婦年金については、「第1号被保険者」とみなされないのがポイントです。
特例による任意加入被保険者として保険料を納付した期間は計算に入りませんので、10年以上という要件を満たせません。そのため、妻に寡婦年金は支給されません。
★「任意加入被保険者」と「特例による任意加入被保険者」が第1号被保険者とみなされるか否かはポイントですので、おさえておきましょう。
<第1号被保険者とみなされるもの、みなされないもの>
| 付加保険料納付 | 寡婦年金 | 死亡一時金 | 脱退一時金 |
任意加入被保険者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特例による 任意加入被保険者 | × | × | 〇 | 〇 |
(附則第5条第9項、H16法附則第23条第9項)
②【R2年問4-E】 ×
老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を「受けたことがある夫」が死亡したときは、寡婦年金は支給されません。
しかし、問題文のように、夫が老齢基礎年金の受給権を取得した月に死亡した場合は、夫は老齢基礎年金を「受けたことがない」ため、他の要件を満たせば、妻に寡婦年金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法 傷病手当金
健康保険法 傷病手当金
R5-134
R5.1.8 傷病手当金と休業補償給付の調整
労働者災害補償保険法の休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、業務外の傷病を併発し、その傷病についても労務不能の場合、労災の休業補償給付と、健康保険の傷病手当金は併給できるでしょうか?
では、過去問をどうぞ
【R2問10-A】
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

【解答】
【R2問10-A】 ×
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によっても労務不能の状態になった場合は、原則として、傷病手当金は支給されません。休業補償給付も傷病手当金も生活保障が目的で、両方併せて受けると、就労して受ける収入よりも多くなってしまうからです。
ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額分は支給されます。差額分の傷病手当金が支給されることがあるので、「休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。」が誤りです。
(昭和33年7月8日保険発第95号の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働保険徴収法 請負事業の一括
労働保険徴収法 請負事業の一括
R5-133
R5.1.7 請負事業の一括の出題ポイント
「請負事業の一括」の出題ポイントを確認しましょう。
例えば、ビルの工事現場では、元請A社の労働者、下請B社の労働者、孫請C社の労働者がいっしょに仕事をしています。労災保険は、A社、B社、C社それぞれで成立するのではなく、その工事現場で成立します。その際、労災保険の保険関係は、元請負人A社に一括されるのがポイントです。
条文を読んでみましょう。
第8条第1項 (請負事業の一括) 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 |
 下請負事業が元請負事業に法律上当然に一括され、徴収法上の事業主は、元請負人のみとなります。
下請負事業が元請負事業に法律上当然に一括され、徴収法上の事業主は、元請負人のみとなります。
第8条第2項(下請負事業の分離) 元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して事業主として適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして適用する。 |
 下請負事業を元請負事業から分離させ、独立させることもできます。その場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。※認可の権限は都道府県労働局長に委任されています。
下請負事業を元請負事業から分離させ、独立させることもできます。その場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。※認可の権限は都道府県労働局長に委任されています。
★認可申請の手続き
・元請負人と下請負人が共同で、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、申請書を所轄都道府県労働局長に提出する
・下請負事業の事業の規模が、「概算保険料が160万円以上」又は「請負金額が1億8千万円以上」であることが必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問8-A労災】
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
②【R2問8-B労災 】
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
③【R2問8-C労災】
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、請負事業の一括が行われるのは、「労災保険に係る保険関係が成立している事業」についてであり、「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については行われない。
④【R2問8-D労災】
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。
⑤【R2問8-E労災】
請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。

【解答】
①【R2問8-A労災】 ×
請負事業の一括の対象は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」です。「立木の伐採の事業」には適用されません。
②【R2問8-B労災 】 ×
請負事業の一括は、法律上当然に行われます。届出や申請など手続きは不要です。
③【R2問8-C労災】 〇
一の事業とみなして元請負人のみが事業主とされるのは、「労災保険に係る保険関係」のみです。「雇用保険に係る保険関係が成立している事業」については一括されませんので、雇用保険については、原則通り、元請、下請それぞれの事業ごとに適用されます。
④【R2問8-D労災】 ×
請負事業の一括が行われると、元請負人が、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、事業主として保険料の納付の義務を負います。
しかし、だからといって、労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となることはありません。
⑤【R2問8-E労災】 ×
元請負人が保険料を納付しないときに下請負人に対して保険料の請求ができる、という規定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法 傷病手当
雇用保険法 傷病手当
R5-132
R5.1.6 雇用保険の傷病手当のポイントをつかみましょう
一般被保険者の「求職者給付」は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当で構成されています。
今日は、傷病手当のポイントを確認しましょう。
傷病手当が支給される要件をみてみましょう。
1.受給資格者であること
2.離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
3.疾病又は負傷のため職業に就くことができない場合であること
4.3.の状態が2.の後において生じたものであること
(行政手引53002)
今日のポイントは4.です。
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、求職の申込みをした後に生じたことが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2問4-A】
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
②【R2問4-B】
有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行い、その後において疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
③【R2問4-C】
つわり又は切迫流産(医学的に疾病と認められるものに限る。)のため職業に就くことはできない場合には、その原因となる妊娠(受胎)の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには傷病手当が支給されない。
④【R2問4-D】
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
⑤【R2問4-E】
求職の申込みの時点においては疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあった者が、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合は、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。

【解答】
①【R2問4-A】 ×
傷病手当は支給されません。傷病手当は、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、求職の申込みをした後に生じたことが条件だからです。
そのため、以下の場合、傷病手当は支給されません。
・疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合
・かかる状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合でも、公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続している場合
(行政手引53002)
②【R2問4-B】 ×
・有効な求職の申込みを行った後において当該求職の申込みの取消し又は撤回を行った場合
→その後、疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態となった場合は、傷病手当は支給できない、とされています。
(行政手引53002)
③【R2問4-C】 ×
・つわり又は切迫流産のため職業に就くことができない場合
→ その原因となる妊娠の日が求職申込みの日前であっても、当該つわり又は切迫流産が求職申込後に生じたときには傷病手当は支給し得る、とされています。
(行政手引53002)
④【R2問4-D】 ×
・訓練延長給付に係る基本手当を受給中に疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合
→ 延長給付(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、地域延長給付)に係る基本手当を受給中の受給資格者には、傷病手当は支給されません。
傷病手当が支給される日数は、所定給付日数から既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数だからです。
(行政手引53004)
⑤【R2問4-E】 〇
・ 求職の申込みの時点では疾病又は負傷にもかかわらず職業に就くことができる状態にあったが、その後疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態になった場合
→ 傷病手当の支給要件に該当します。
(行政手引53002)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法の給付制限
労災保険法の給付制限
R5-131
R5.1.5 労災の給付制限「故意の犯罪行為、重大な過失」
労災保険法の支給制限を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
①は「行わない」となっているのがポイントです。労働者の「故意」による傷病は、業務や通勤との因果関係がないので、保険給付は行われません。
②は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」ですので、絶対ではなく裁量になることがポイントです。
過去問をどうぞ!
①【R2問1-A】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
②【R2問1-B】
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
③【R2問1-C】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
④【R2問1-D】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
⑤【R2問1-E】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
①【R2問1-A】 〇
政府が保険給付の全部又は一部を行わないことができるのは、「重大な過失」による場合です。「過失」の場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
②【R2問1-B】 ×
労働者の「故意の犯罪行為」による場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
③【R2問1-C】 〇
重大ではない「過失」の場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
④【R2問1-D】 〇
療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。しかし、「正当な理由」がある場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
⑤【R2問1-E】 〇
療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。しかし、「正当な理由」がある場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法の「労働者」の定義
労働安全衛生法の「労働者」の定義
R5-130
R5.1.4 労働安全衛生法と労働基準法の「労働者」
労働安全衛生法は、労働基準法とは一体としての関係にあります。
保護の対象になる「労働者」の定義は、労働基準法の労働者と同じです。
条文を読んでみましょう。
労働基準法 第9条 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第116条第2項 労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 |
労働安全衛生法 第2条 労働者とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 |
労働基準法も労働安全衛生法も「同居の親族のみを使用する事業」及び「家事使用人」は適用除外です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。
②【H28年出題】
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
③【R3年出題】
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。

【解答】
①【R2年出題】 〇
労働基準法と労働安全衛生法ともに、「同居の親族のみを使用する事業又は事務所」、「家事使用人」については適用されません。
②【H28年出題】 〇
労働基準法第10条の「使用者」は、①事業主、②事業の経営担当者、③その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。
労働安全衛生法の事業者は、「事業を行う者で、労働者を使用するもの」と定義されています。
労働安全衛生法の主たる義務者である「事業者」は、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。
(昭和47年9月18日発基91号)
労働基準法上の「使用者」には、例えば部長や課長なども該当することがありますので、労働安全衛生法とは概念が異なります。
③【R3年出題】 ×
労働安全衛生法の「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者です。一人親方は、元方事業者とは使用従属関係はなく労働者ではありませんので、労働法上の保護の対象にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金「任意加入被保険者」の目的と条件
国民年金「任意加入被保険者」の目的と条件
R5-129
R5.1.3 任意加入被保険者になる目的と条件を確認しましょう
平成25年の国民年金の過去問についてご質問がありました。
「任意加入」がテーマの問題です。今日はご質問にお答えします。
まず、任意加入の条件を条文で読んでみましょう。
附則第5条 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
 任意加入する目的は2つです。
任意加入する目的は2つです。
1つ目は、老齢基礎年金の受給資格がない人が、「老齢基礎年金の受給資格要件を満たすため」、2つ目は老齢基礎年金の受給資格はあるけれど満額ではない人が、「老齢基礎年金を増やすため」です。
では、過去問をどうぞ!
【H25年問8-C】
大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった、その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となった。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。
※設問の女性は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする。

【解答】
【H25年問8-C】 ×
設問の場合、国民年金の任意加入の申出をすれば、任意加入被保険者になることができます。
まず、設問の女性の年金履歴を確認しましょう。
・22歳から26歳まで → 厚生年金保険の被保険者
・26歳から昭和61年3月まで → 未加入(会社員の被扶養配偶者)
・昭和61年4月から平成26年3月まで → 第3号被保険者
なお、26歳から昭和61年3月までの未加入期間は「合算対象期間」となります。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、かつ、第1号厚生年金被保険者の期間が1年以上ありますので、60歳から「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」が支給されます。
ポイント!
・受給資格は満たしていますので、65歳から老齢基礎年金を受給できます。しかし、20歳から22歳までが空白になっているのと、26歳からの合算対象期間がありますので、老齢基礎年金は満額ではありません。
任意加入の目的の2つ目の「老齢基礎年金の受給資格はあるけれど満額ではない人」に該当しますので、保険料納付済期間を増やすため、60歳から65歳まで任意加入することができます。(法附則第5条第1項第2号に該当します)
・「特別支給の老齢厚生年金」の支給が開始されても、任意加入して老齢基礎年金を増やすことは可能です。
では、こちらの過去問をどうぞ!
【R2年問9-B】
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】
【R2年問9-B】 ×
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中でも、任意加入することは可能です。
日本国内に住所を有していなくても日本国籍を有している場合は、法附則第5条第1項第3号「日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの」に該当しますので、任意加入被保険者の申出をすることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-128
R5.1.2 R4択一式より 賃金の非常時払い
災害などで出費を要することになった場合、労働者は、支払期日前でも、賃金の繰上払を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
第25条 (非常時払) 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 則第9条 非常の場合は、次に掲げるものとする。 1 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 2 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 3 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合 |
支払期日前でも繰上払の請求ができるのは以下の事由の場合です。
・出産、疾病、災害、結婚、死亡、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合
★労働者のみならず、「労働者の収入によって生計を維持する者」も対象です。
★支払期日前に請求できるのは「既往の労働」に対する賃金です。使用者は、まだ労務の提供のない期間の賃金については支払う義務はありません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-ウ】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由の1つである「疾病」とは、業務上の疾病、負傷であると業務外のいわゆる私傷病であるとを問わない。

【解答】
【問6-ウ】 〇
「疾病」、「災害」は、業務上、業務外は問われません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。
②【H28年出題】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて支払期日前に賃金を支払わなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
労働者本人だけでなく、労働者の収入によって生計を維持する者の事由も含まれるのがポイントです。
②【H28年出題】 ×
非常時払いの対象は、「既往の労働」に対する部分です。いまだ労務の提供のない期間は支払う義務はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-127
R5.1.1 R4択一式より 通貨以外のもので支払われる賃金
賃金は、「通貨払い」が原則ですが、例外もあります。
条文を読んでみましょう。
第24条 (賃金の支払) ① 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。 |
賃金の支払には、「通貨払い」、「直接払い」、「全額払い」、「毎月1回以上払い」、「一定期日払い」の5原則があります。
今日は「通貨払い」の例外に注目します。
賃金は「通貨」で支払うのが原則ですが、「法令」に別段の定めがある場合、「労働協約」に別段の定めがある場合は、通貨以外のもの(現物)で支払うことができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-ア】
通貨以外のもので支払われる賃金も、原則として労働基準法第12条に定める平均賃金等の算定基礎に含まれるため、法令に別段の定めがある場合のほかは、労働協約で評価額を定めておかなければならない。

【解答】
【問6-ア】 〇
平均賃金を算定する際の「賃金の総額」には、「臨時」に支払われた賃金及び「3か月を超える期間ごと」に支払われる賃金並びに「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入しない、とされています。(法第12条第4項)
★「通貨以外のもので支払われた賃金」で一定の範囲に属するものは、平均賃金の算定基礎に含まれます。
賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもので、「評価額」は、法令に別段の定がある場合の外、労働協約に定めなければならない、とされています。(則第2条)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。
②【H15年出題】
ある会社においては、労働協約により、通勤費として、労働者に対して、6か月定期券を購入して支給しているが、このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解される。

【解答】
①【R3年出題】 ×
労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られます。事業場の全ての労働者ではありません。
★労働協約は、「労働組合法でいう労働協約」のみを意味します。
労働組合がない場合の、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定は、労働協約ではありません。
昭和63.3.14基発150号)
②【H15年出題】 〇
通勤定期券は、「通貨以外もの(現物)」ですので、労働協約の定めが必要です。このような通勤定期券は、労働基準法第11条の「賃金」と解され、平均賃金の算定の基礎にも含まれます。
(昭25.1.18基収130号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-126
R4.12.31 R4択一式より 障害厚生年金の加給年金額
障害厚生年金の額には、加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第50条の2 1 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 2 加給年金額は、22万4,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
ポイント!
・加給年金額が加算されるのは1級と2級の障害厚生年金です。3級の障害厚生年金には加算されません。
・対象は65歳未満の配偶者です。子については障害基礎年金で加算が行われます。
・加給年金額は22万4,700円×改定率です。
障害等級1級又は2級 |
| 障害等級3級 |
障害厚生年金
+加給年金額(配偶者) |
|
障害厚生年金 |
障害基礎年金
+加算額(子) |
|
|
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問6-A】
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。
②【問6-B】
昭和9年4月2日以後に生まれた障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】
①【問6-A】 ×
障害厚生年金の加給年金額の対象は、65歳未満の配偶者のみです。子は障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。
②【問6-B】 ×
障害厚生年金の額に加算される配偶者に係る加給年金額には、特別加算は行われません。
過去問をどうぞ!
【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
【H29年出題】 〇
障害厚生年金の受給権を取得した時点では、生計を維持している配偶者がなくても、受給権を取得した日の翌日以後に有するに至った場合は、加給年金額の対象になります。その場合は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
(法第50条の2第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-125
R4.12.30 R4択一式より 高年齢雇用継続給付と60歳台前半の老齢厚生年金
60歳台前半で在職中(=厚生年金保険の被保険者ということです。)の場合、60歳台前半の老齢厚生年金には、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
また、雇用保険からは、高年齢雇用継続給付が支給される場合があります。
高年齢雇用継続給付は、60歳時点の賃金と比べて、60歳以後の賃金が60歳時の75%未満となった場合に、支給される給付です。
60歳以降の賃金が、60歳時点と比べて61%未満になった場合は、支給対象月の賃金の15%が高年齢雇用継続給付として支給されます。61%以上75%未満の場合は、15%から逓減する率となります。
雇用保険から高年齢雇用継続給付が支給される場合、在職老齢年金の支給停止基準額に加えて、60歳台前半の老齢厚生年金がカットされる仕組みになっています。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-D】
60歳以降も在職している被保険者が、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その間、60歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止となる。

【解答】
【問8-D】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる間、60歳代前半の老齢厚生年金は最大で標準報酬月額の6%が支給停止されますが、「全額支給停止」とは限りません。
★60歳以降の支給対象月の賃金が60歳時点と比べて61%未満になった場合、高年齢雇用継続基本給付金は「支給対象月の賃金の15%」が支給されます。
その場合、60歳台前半の老齢厚生年金は、「標準報酬月額の6%」が支給停止されます。
雇用保険から「15」支給されると、年金が「6」停止されるイメージです。
支給対象月の賃金が61%以上75%未満の場合は、高年齢雇用継続基本給付金は15%から逓減する率になりますが、その場合は老齢厚生年金の支給停止の率も6%から逓減する率となります。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している63歳の者が、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金を受給した場合、当該高年齢雇用継続基本給付金の受給期間中は、当該特別支給の老齢厚生年金には、在職による支給停止基準額に加えて、最大で当該受給権者に係る標準報酬月額の10%相当額が支給停止される。
②【H24年出題】
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合に、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者は、その者の老齢厚生年金について、標準報酬月額に法で定める率を乗じて得た額に相当する部分等が支給停止され、高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の受給による特別支給の老齢厚生年金の支給停止額は、最大で「標準報酬月額の6%」です。
②【H24年出題】 〇
高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる場合、60歳代前半の老齢厚生年金は、最大で標準報酬月額の6%に相当する部分が支給停止されます。一方、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は支給停止されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-124
R4.12.29 R4択一式より 加給年金額の減額改定
加給年金額が加算された老齢厚生年金は、対象の配偶者や子が一定の要件に該当した場合は、加給年金額が加算されなくなります。
条文を読んでみましょう。
第44条第4項 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。 1死亡したとき。 2 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 3 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。 4 配偶者が、65歳に達したとき。 5 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 6 養子縁組による子が、離縁をしたとき。 7 子が、婚姻をしたとき。 8 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 9 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。 10 子が、20歳に達したとき。 |
例えば、加給年金額の対象になる配偶者は65歳未満という年齢要件があります。そのため、配偶者が65歳に達すると加給年金額が加算されなくなり、その翌月から減額改定されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問6-E】
老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。
②【問3-B】
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。

【解答】
①【問6-E】 ×
加給年金額の対象となる配偶者は受給権者によって「生計を維持」していたことが条件です。
そのため、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合は、加給年金額は加算されなくなり、翌月から加給年金額は減額されます。
(法第44条第4項第2号)
②【問3-B】 〇
子が婚姻したときは加給年金額は加算されなくなります。18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に婚姻したときでも、婚姻した月の翌月から加給年金額は減額されます。
(法第44条第4項第7号)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。
②【H26年出題】
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

【解答】
①【R3年出題】 ×
障害等級2級に該当しなくなっても、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合は、加給年金額は減額されません。
問題文の場合は、17歳ですので、障害等級2級でなくなっても、その時点では加給年金額の加算の対象からは外れません。
(法第44条第4項第9号)
②【H26年出題】 ×
配偶者が、65歳に達したときは、加給年金額の対象から外れます。受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できなかったとしても加給年金額は減額されます。
※配偶者が大正15年4月1日以前生まれ(旧法対象者)の場合は、65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算されます。
(法第44条第4項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-123
R4.12.28 R4択一式より 法定免除される期間
法定免除事由に該当した場合、保険料が免除されるのはいつからいつまででしょうか?
では、条文を読んでみましょう。
第89条 1 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 ② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ③ 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
2 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定は適用しない。 |
法定免除の要件に該当した場合は、当然に保険料が免除されますので、免除の申請をする必要はありません。
※法定免除事由に該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に届書を提出する必要があります。(則第75条)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-D】
被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【解答】
【問9-D】 〇
法定免除の要件に該当するに至ったときは、保険料は当然に免除されます。
例えば、令和4年12月に要件に該当した場合は、令和4年11月(該当するに至った日の属する月の前月)から免除されます。国民年金の保険料の納期限は翌月末日ですので、免除事由に該当した12月に期限がくる11月分から免除となります。
「免除事由に該当しなくなる日の属する月」まで免除されます。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
法定免除される期間は、その該当するに至った日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する「月」までの期間です。
なお、生活保護法には8種類の扶助がありますが、法定免除の事由に該当するのは「生活扶助」のみです。
こちらの過去問もどうぞ!
②【H26年出題】
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
③【R2年出題】
障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。
④【R2年出題】
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
法定免除事由に該当すると当然に保険料は免除されますが、希望すれば、保険料を納付することができます。
③【R2年出題】 〇
②の問題と同じです。
保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができます。
④【R2年出題】 〇
法定免除事由に該当した場合、14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければなりません。法定免除事由に該当していることを、知ってもらうためです。
そのため、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出は不要です。
(則第75条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-122
R4.12.27 R4択一式より 国民年金の被保険者の資格喪失日
国民年金の強制加入被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者がありますが、それぞれの資格喪失事由と喪失日を確認しましょう。
条分を読んでみましょう。
第9条 (資格喪失の時期) 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(②に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は③から⑤までのいずれかに該当するに至ったとき(④については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したとき。 ② 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ③60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)。 ④ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ⑤厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれかに該当するときを除く。)。 ⑥ 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)。 |
ポイント!
・例えば、40歳で会社を退職し自営業を始めた場合、国民年金の種別は第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。その場合、「第2号被保険者資格を喪失→第1号被保険者資格を取得」という流れではなく、第1号被保険者から第2号被保険者に「種別変更」となります。
その後、第1号被保険者のまま60歳に達したときは、そこで国民年金の被保険者の資格を喪失します。
「資格喪失」とは国民年金の被保険者資格を喪失するという意味です。「種別変更」とは違いますので注意しましょう。
・第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の定義をおさえましょう。それぞれ、その条件に当てはまらなくなったときに資格を喪失します。
・「翌日喪失」か「当日喪失」かを覚えましょう。死亡による喪失の場合は「翌日」、年齢による喪失の場合は「当日」が覚えやすいです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-E】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。

【解答】
【問8-E】 〇
第1号被保険者と第3号被保険者は「20歳以上60歳未満」という年齢要件がありますので、「60歳」で資格を喪失します。
年齢で資格を喪失する場合は「当日喪失」です。また「60歳に達した日」=「60歳の誕生日の前日」です。例えば、令和4年12月28日が60歳の誕生日なら、令和4年12月27日に資格を喪失します。
なお、第2号被保険者には20歳以上60歳未満の年齢要件がありませんので、60歳に達しても資格は喪失しません。
また、死亡の場合は「翌日喪失」です。第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者共通です。
過去問をどうぞ!
【H25年出題】 ※改正による修正あり
厚生年金保険の被保険者は、60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【H25年出題】 ×
厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)は、60歳に達しても国民年金の被保険者の資格を喪失しません。
厚生年金保険の被保険者が国民年金の第2号被保険者の資格を喪失するのは、原則として、「65歳に達した日」となります。
※老齢基礎年金等の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者は、65歳以降も国民年金の第2号被保険者です。
(法附則第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-121
R4.12.26 R4択一式より 第2号被保険者期間の合算対象期間
老齢基礎年金の受給資格は、「保険料納付済期間」+「保険料免除期間」が10年以上あることですが、10年未満の場合は、附則第9条の特例により「合算対象期間」も合算して10年以上あれば受給資格を満たします。
「合算対象期間」は、受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額には反映しませんので、カラ期間ともいわれます。
今日のテーマは、「第2号被保険者」としての被保険者期間のうちの合算対象期間です。
では、条文を読んでみましょう。
(昭60年法附則第8条第4項) 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条(老齢基礎年金の支給要件)及び第27条(老齢基礎年金の年金額)の適用については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。 |
老齢基礎年金の年金額は、第1号被保険者の年齢(20歳以上60歳未満)の基準に合わせています。20歳から60歳までの40年間すべて保険料納付済期間なら満額が支給される仕組みです。
しかし、第2号被保険者については、厚生年金保険の被保険者なら20歳前でも60歳以上でも原則第2号被保険者となります。
そのため、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、老齢基礎年金の受給資格や年金額について「保険料納付済期間」として扱われるのは、「20歳以上60歳未満」の期間です。20歳未満、60歳以後の期間は「合算対象期間」となります。
※例えば、18歳から63歳まで厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)だった場合
18歳 20歳 60歳 63歳
厚生年金保険の被保険者(=第2号被保険者) | ||
カラ期間 | 保険料納付済期間 | カラ期間 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-D】
大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
【問8-D】 ×
問題文の場合、厚生年金保険の被保険者期間のうち、60歳~65歳までの5年間は、合算対象期間です。42年間のうちその5年間は、老齢基礎年金の額の計算には算入されませんので、老齢基礎年金は満額になりません。
20歳 23歳 60歳 65歳
未加入 | 厚生年金保険の被保険者(=第2号被保険者) | |
保険料納付済期間 (37年) | 合算対象期間 (5年) | |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。
②【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間と60歳以後の期間は、「合算対象期間」です。老齢基礎年金の年金額を計算する場合は、保険料納付済期間には算入されません。
②【H24年出題】 ×
障害基礎年金には、合算対象期間という扱いがありません。そのため、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も、受給資格期間・年金額の計算ともに「保険料納付済期間」とされます。
なお、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-120
 R4.12.25 R4択一式より 付加年金の計算式
R4.12.25 R4択一式より 付加年金の計算式
付加年金の計算式を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第87条の2第1項 第1号被保険者(保険料の免除を受けている者、国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、国民年金の保険料のほか、400円の付加保険料を納付する者となることができる。
第43条 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。 |
付加保険料は月400円で、申出をした月から納付できます。
付加年金は200円×付加保険料の納付月数で計算され、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。
付加保険料を40年(480月)納付した場合は、付加年金の計算式は200円×480月で、年間96,000円となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】
第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。

【解答】
【問9-B】 ×
付加保険料の納付済期間が60月の場合、付加年金の額は年額で、「200円」に60月を乗じて得た額となります。
付加保険料は月400円ですが、付加年金の計算は「200円」で計算するのがポイントです。
付加保険料を60月間納付した場合、納付した付加保険料はトータルで、400円×60月=24,000円です。
一方、65歳から支給される付加年金は、200円×60月で、年額12,000円です。
付加年金を2年受給すれば、納付した付加保険料とイコールになる計算です。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。
②【H29年出題】
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
付加年金の額は、200円×300か月=年額60,000円です。
②【H29年出題】 ×
付加年金の額には、改定率による改定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-119
 R4.12.24
R4.12.24 R4択一式より 減給制裁と随時改定の関係
R4択一式より 減給制裁と随時改定の関係
減給制裁が行われた場合、随時改定の対象になるでしょうか?
まず、随時改定の条文を読んでみましょう。
第43条 (随時改定) 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 |
随時改定の要件は次の3つです。
①昇給や降給等で固定的賃金に変動があったこと。
②変動月からの3カ月間の報酬(残業手当等の非固定的賃金を含みます)の平均に該当する標準報酬月額と従前の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと。
③3カ月とも報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であること。
※要件を満たした場合、報酬が変動した月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
被保険者Aは、労働基準法第91条の規定により減給の制裁が6か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

【解答】
【問8-A】 ×
減給制裁は固定的賃金の変動に当たりませんので、随時改定の対象とはなりません。随時改定の手続はできません。
(厚生労働省「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-118
R4.12.23 R4択一式より 夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定
令和元年に成立した「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に対する附帯決議として、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」が付されました。
今日は、上記の附帯決議を踏まえた令和3年の通知で、「夫婦共同扶養の場合の被扶養者の認定」をみていきましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-C】
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。

【解答】
【問4-C】 ×
「健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方」ではなく、「被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする、とされています。
(令和3年4月30日保保発 0430 第 2 号)
改正前は昭和60年通知が基準になっていましたが、現在は令和3年通知に基づきます。
昭和60年通知と令和3年通知を比較してみましょう。
令和3年通知 | 昭和60年通知(廃止) |
被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする。
夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。 | 年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。
夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること |
※昭和60年通知は廃止されました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-117
R4.12.22 R4択一式より 保険外併用療養費の額
まず、「保険外併用療養費」の制度を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 (保険外併用療養費) 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
第63条第2項3号~5号 ・「評価療養」とは → 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの (例 先進医療など) ・「患者申出療養」とは → 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの ・「選定療養」とは → 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養 (例 差額ベッドなど) |
例えば、自己負担割合3割の被保険者が先進医療を受け、トータルの医療費が80万円でそのうち先進医療に係る費用が30万円だった場合で考えてみましょう。
保険診療 50万円 | 先進医療 30万円 |
・保険給付される部分(保険外併用療養費) 35万円 ・一部負担金に当たる額 15万円 |
全額自己負担 |
通常の治療なら「療養の給付」として支給される部分が、「保険外併用療養費」として支給されます。
本人は、15万円+30万円=45万円を負担します。
ちなみに、保険診療の一部負担金に当たる部分は、高額療養費の対象となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-D】
患者自己負担割合が3割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30万円、選定療養が10万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12万円を当該保険医療機関に支払う。

【解答】
【問4-D】 ×
保険診療と選定療養を併せて受けた場合は保険外併用療養費の対象となります。
保険診療30万円のうち自己負担額は3割の9万円で、21万円が保険外併用療養費として支給されます。また、選定療養の10万円は全額自己負担です。
被保険者が保険医療機関に支払う額は、9万円+10万円=19万円です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。
②【H28年出題】
患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用については保険外併用療養費が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
予約診療は選定療養の対象となります。
特別料金は全額自己負担です。通常の治療の部分は、一部負担金に相当する部分は本人が負担しますが、残りは保険外併用療養費として保険給付が行われます。
②【H28年出題】 〇
患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象にはなりません。療養の給付と同じ範囲の部分は、保険外併用療養費として支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-116
R4.12.21 R4択一式より 都道府県単位保険料率の変更の手続
全国健康保険協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000分の130の範囲で支部被保険者を単位として協会が決定します。
※ 支部被保険者とは → 各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいいます。
※ 支部被保険者を単位として決定する一般保険料率のことを「都道府県単位保険料率」といいます。
今日は、都道府県単位保険料率の変更の手続を見ていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第160条第6項、7項、8項 6 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 7 支部長は、意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。 8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
支部長 | 意見を求められた場合 都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合 | 予め評議会の意見を聴く |
↓ | 理事長に対し意見の申出を行う | |
理事長 | 支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経る | |
↓ | 保険料率の変更について認可を申請する | |
厚生労働大臣 | 保険料率の変更について認可する | |
★運営委員会 → 事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に置かれます。
★評議会 → 都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに設けられます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-ウ】
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

【解答】
【問3-ウ】 〇
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときのプロセスです。
①あらかじめ、理事長が支部長の意見を聴く
↓
②運営委員会の議を経る
↓
③理事長は、変更について厚生労働大臣の認可を受ける
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
②【H23年出題】
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。
③【R1年出題】
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

【解答】
①【H26年出題】※改正による修正あり 〇
協会が管掌する健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲で、都道府県ごとに設定されます。
②【H23年出題】 ×
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、「×運営委員会 → 〇理事長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いたうえで、「×理事長に対しその変更について意見の申出を行う →〇運営委員会の議を経なければならない」となります。
③【R1年出題】 ×
「厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。」が誤りです。
法第160条第10項と11項で以下のように定められています。
第10項 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
第11条 厚生労働大臣は、協会が10項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-115
R4.12.20 R4択一式より 使用されるに至った日から自宅待機とされた場合
入社することになったものの、入社日から自宅待機となった場合、健康保険の被保険者の資格はどのように扱われるのでしょうか?
資格取得日について条文を読んでみましょう。
第35条 (資格取得の時期) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は適用除外に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。 |
 「適用事業所に使用されるに至った日」、「事業所が適用事業所となった日」、「適用除外に該当しなくなった日」に被保険者の資格を取得します。
「適用事業所に使用されるに至った日」、「事業所が適用事業所となった日」、「適用除外に該当しなくなった日」に被保険者の資格を取得します。
適用事業所に入社した場合は、その日に健康保険の被保険者の資格を取得します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-B】
適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

【解答】
【問2-B】 〇
当初から自宅待機でも健康保険の被保険者の資格は取得します。
・休業手当は報酬ですので、休業手当の支払いの対象となった日の初日に資格を取得します。
・資格取得時の標準報酬月額は、現に支払われる休業手当等に基づき決定されます。
・休業手当で標準報酬月額が決定した後に、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象となります。
(S50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
過去問をどうぞ!
【R3年出題 】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
【R3年出題 】 〇
★一時帰休に伴って低額な休業手当等が支払われることになった場合
→ 固定的賃金の変動とみなして、随時改定の対象となります。※ただし、報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限ります。
★休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消し、通常の報酬が支払われるようになったとき
→ 随時改定の対象となります。
(S50.3.29保険発第25号・庁保険発第8号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-114
R4.12.19 R4択一式より 健康保険組合の設立要件
健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立の2種類ありますが、本日は任意設立を見ていきます。
条文を読んでみましょう。
第11条 1 一又は二以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該一又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。 2 適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時3000人以上でなければならない。
第12条 1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、同意は、各適用事業所について得なければならない。 |
 健康保険組合は、1社単独で設立する単一組合と、2社以上が共同で設立する総合組合があります。人数要件があり、単独で設立する場合は常時700人以上、共同で設立する場合は常時3000人以上の被保険者が必要です。
健康保険組合は、1社単独で設立する単一組合と、2社以上が共同で設立する総合組合があります。人数要件があり、単独で設立する場合は常時700人以上、共同で設立する場合は常時3000人以上の被保険者が必要です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

【解答】
【問5-B】 〇
健康保険組合を設立するときは、「被保険者の2分の1以上の同意」が必要です。また、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
2以上の適用事業所で健康保険組合を設立する場合、それぞれの適用事業所ごとに被保険者の2分の1以上の同意を得なければなりません。
なお、健康保険組合は、「設立の認可を受けた時に成立」します。(法第15条)
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任されている。
②【R3年出題】
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
第205条で、「健康保険法に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。」と規定されています。しかし、健康保険組合の設立の認可に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長には委任されていません。
ちなみに、健康保険組合の設立の認可の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して行います。(則第3条第2項)
②【R3年出題】 ×
第8条で、「健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。」と規定されています。特例退職被保険者ではなく、任意継続被保険者です。
ちなみに、「日雇特例被保険者」は入りませんので注意してください。日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会のみだからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-113
R4.12.18 R4択一式より 概算保険料の追加徴収
保険年度の中途から保険料率の引き上げを実施した場合、政府は、引き上げによって増加した労働保険料を追加徴収します。
条文を読んでみましょう。
第17条 (概算保険料の追加徴収) 政府は、一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、労働保険料を追加徴収する。
則第26条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項 2 納期限 |
増加概算保険料は、一定の基準以上の増加があった場合に適用されますが、追加徴収は額の多少を問わず徴収されるのがポイントです。
令和4年の問題をどうぞ!
【問9-E】(雇用)
事業主は、政府が保険年度の中途に一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率、第三種特別加入保険料率の引上げを行ったことにより、概算保険料の増加額を納付するに至ったとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収すべき概算保険料の増加額等を通知した納付書によって納付することとなり、追加徴収される概算保険料に係る申告書を提出する必要はない。

【解答】
【問9-E】(雇用) 〇
ポイントは以下の2点です。
・納入告知書ではなく、「納付書」で納付することになります。
・所轄都道府県労働局歳入徴収官が追加徴収する概算保険料の増加額を通知します。事業主は、申告書を提出する必要はありません。
(則第38条第4項、5項)
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行ったときは、増加した保険料の額の多少にかかわらず、法律上、当該保険料の額について追加徴収が行われることとなっている。
②【H30年出題】(労災)
追加徴収される概算保険料については、所轄都道府県労働局歳入徴収官が当該概算保険料の額の通知を行うが、その納付は納付書により行われる。
③【H22年出題】(労災)
政府が、保険年度の中途に、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行った場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に対して、保険料率の引上げによる労働保険料の増加額等を通知して、追加徴収を行うこととなるが、当該事業主は当該通知を発せられた日から起算して50日以内に増加額を納付しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収のポイントは、「増加した保険料の額の多少にかかわらず」行われることです。
②【H30年出題】(労災) 〇
追加徴収される概算保険料は、納入告知書ではなく、「納付書」により行われます。
③【H22年出題】(労災) ×
納期限は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-112
R4.12.17 R4択一式より 増加概算保険料の納期限
増加概算保険料の納付要件を確認しましょう。
①事業規模の拡大等により賃金総額の見込額が増加した場合
要件 → 増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の見込額に基づく概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上
(法第16条、則第25条)
②「労災保険に係る保険関係のみ」が成立している事業又は「雇用保険に係る保険関係のみ」が成立している事業が「労災保険及び雇用保険に係る保険関係」が成立している事業に該当するに至ったため一般保険料率が変更した場合
要件 → 変更後の一般保険料率に基づく概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上
(法附則第5条、則附則第4条)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】(雇用)
事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなければならない。

【解答】
【問9-B】(雇用) 〇
労災保険のみが成立している事業の一般保険料率は労災保険率のみですが、労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業に該当するに至った場合は、一般保険料率は「労災保険率+雇用保険率」に上がります。
その際、変更後の一般保険料率に基づく概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上になった場合は、差額を納付しなければなりません。
納期限は、「一般保険料率が変更された日から30日以内」ですが、翌日起算ですので、「一般保険料率が変更された日の翌日から起算して30日以内」となります。
(法附則第5条)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】(労災)
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
②【H23年出題】(労災)
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。

【解答】
①【H23年出題】(労災) 〇
継続事業も有期事業も、増加概算保険料の納期限は、当該賃金総額の「増加が見込まれた日」から30日以内です。「実際に支払った賃金総額が既に納付した賃金総額の見込額の2倍を超えるに至った日」ではなく、「増加が見込まれた日」からであることがポイントです。なお、起算日は、翌日起算です。
(法第16条)
②【H23年出題】(労災) 〇
納期限は、一般保険料率が変更された日から30日以内です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
R5-111
R4.12.16 R4択一式より 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件として、「算定基礎期間に相当する期間が5年以上」という要件があります。
5年以上の算定のルールを確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金の対象者は、60歳以上65歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)で、被保険者であった期間が通算して5年以上であるものです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
60歳に達した被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、57歳から59歳まで連続して20か月基本手当等を受けずに被保険者でなかったものが、当該期間を含まない過去の被保険者期間が通算して5年以上であるときは、他の要件を満たす限り、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

【解答】
【問5-A】 ×
高年齢雇用継続基本給付金の被保険者であった期間は、基本手当の被保険者であった期間の取扱いと同じです。
例えば、A社で被保険者の資格を喪失した後、B社で被保険者資格を取得した場合、A社とB社の間が1年以内で基本手当等を受けていない場合は、被保険者であった期間は通算されます。
問題文の場合は、57歳から59歳まで被保険者でなかった期間が1年を超えていますので、その間基本手当等を受けていなかったとしても前後の被保険者であった期間は通算されません。
そのため、60歳に達した日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。
(行政手引59011)
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

【解答】
【R1年出題】 〇
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない場合は高年齢雇用継続基本給付金の受給資格はありません。
しかし、その後5年に達した場合は、受給資格ができ、5年に達する日の属する月から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。「60歳に達した日の属する月」に遡っては支給されませんので、注意しましょう。
また、高年齢雇用継続基本給付金は、最長で65歳に達する日の属する月までとなります。
(行政手引59011)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
R5-110
R4.12.15 R4択一式より 雇用保険被保険者転勤届
労働者が1人でも雇用される事業は、原則として雇用保険の適用事業となります。
「事業」とは、企業全体ではなく、本店、支店、事務所の単位をいいます。
また、雇用保険法施行規則第3条では、届出等の事務は、事業所ごとに処理すること、となっています。
今日は雇用保険被保険者転勤届を見てみましょう。
条文を読んでみましょう。
則第13条 (被保険者の転勤の届出) 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 |
★転勤届は、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-A】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

【解答】
【問3-A】 〇
転勤は、被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されるに至ったことをいいます。
転勤の場合は、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内でも、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければなりません。
(行政手引21752)
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときには、当該届出は不要である。

【解答】
①【H24年出題】 ×
両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、雇用保険被保険者転勤届の提出が必要です。
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
「雇用保険被保険者資格取得届」、「雇用保険被保険者資格喪失届」、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付支給申請書」には、マイナンバーの記載が必要です。
被保険者(日雇労働被保険者を除く。)のマイナンバーが変更されたときは、事業主は、速やかに、個人番号変更届を提出しなければなりません。
(則第14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-109
R4.12.14 R4択一式より 割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払う場合
今日は、判例からの問題です。
さっそく、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-C】
医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合、「本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはないから、上告人の当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないからといって不都合はなく、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということができる」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【問7-C】 ×
「平成29年7月7日付け最高裁判所第二小法廷判決」からの出題です。
『当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができない』場合は、当該年俸の支払により、「時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということはできない。」とされています。
年俸のうち、時間外労働等の割増賃金に当たる部分が明らかにされていなかったことがポイントです。
この判決を踏まえて、平成29年7月31日付基発0731第27号「時間外労働等に対する割増賃金の解釈について」が発出されています。
ポイントは以下の通りです。
・時間外労働等に対する割増賃金を基本給や諸手当にあらかじめ含める方法で支払う場合には、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができることが必要であること。
・このとき、割増賃金に当たる部分の金額が労働基準法第37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、その差額を支払わなければならないこと。
では、過去問をどうぞ!
【H22年出題】
タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法第37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈することができるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
【H22年出題】 ×
時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができない場合、最高裁判所の判例では、「この歩合給の支給によって、時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきもの」とされています。
(高知県観光事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-108
R4.12.13 R4択一式より 契約解除の日から14日以内の起算日
「契約解除の日から14日以内」は、当日起算でしょうか?翌日起算でしょうか?
では、条文を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) ① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ② 明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ③ ②の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
労働契約締結の際に、使用者は、労働条件を明示しなければなりません。
明示された労働条件が、実際の条件と異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除できます。その場合、労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。

【解答】
【問5-B】 ×
「解除当日から数える」の部分が誤りです。「契約解除の日から14日以内」は、民法の期間計算の原則によって初日は算入しません。
9月1日に労働契約を解除した場合は、翌日の9月2日から数えて14日以内ですので、9月15日までとなります。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労働基準法第15条第1項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
②【H28年出題】
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「即時に」がポイントです。例えば、2週間前に申し出るなどのような制限はありません。
②【H28年出題】 ×
「当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。」の部分が誤りです。第15条の「解除」は、過去に遡って、契約がなかったものと扱われるのではなく、労働契約関係を「将来に向かって」消滅させることをいいます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-107
R4.12.12 R4択一式より 労働契約の契約期間の上限
労働契約には、「期間の定めのある」契約と、「期間の定めのない」契約があります。
労働契約に契約期間を定める場合、最長は原則として3年です。長期労働契約はその間、労働者を拘束してしまうからです。
「期間の定めのない労働契約」については、いつでも労働者から契約解除ができますので、労働基準法上の制限はありません。
では、条文を読んでみましょう。
第14条 (契約期間等) 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 ① 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 ② 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(①に掲げる労働契約を除く。) |
労働契約に契約期間を定める場合の上限は原則として3年です。
例外も確認しましょう。
<例外1>
一定の事業の完了に必要な期間を定める契約 → 3年を超える期間を定めることができます。例えば工事の完了に4年かかるような場合です。
<例外2>
専門的知識等で高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者との契約 → 上限は5年となります。
※高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限られます。
<例外3>
満60歳以上の労働者との間の契約 → 上限は5年となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められていること等が必要である。

【解答】
【問5-A】 〇
「専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等」は、告示で限定列挙されていて、「社会保険労務士」はその一つです。
契約期間の上限を5年とするには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りません。社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められていること等が必要です。
(H15.10.22基発第1022001号)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
②【H27年出題】
契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。

【解答】
①【H28年出題】 〇
高度の専門的知識等を有しているだけでは、契約期間を5年とする労働契約は締結できません。高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていることが条件です。高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、上限は原則の3年です。
②【H27年出題】 〇
「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合で、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要です。例えば、6年で完了する工事現場では、労働者を6年間の契約で雇入れることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
R5-106
R4.12.11 R4択一式より 住所地特例の適用(介護保険)
介護保険法の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります。
条文を読んでみましょう。
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
 介護保険の保険者は「市町村及び特別区」です。第1号被保険者も第2号被保険者も、住所地の市町村の介護保険の被保険者となるのが原則です。
介護保険の保険者は「市町村及び特別区」です。第1号被保険者も第2号被保険者も、住所地の市町村の介護保険の被保険者となるのが原則です。
しかし、介護保険法には「住所地特例」があります。住所地特例とは、一定の施設に入所し住民票を移しても、引き続き、移す前の市町村の被保険者となる仕組みです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-E】
介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。

【解答】
【問10-E】 〇
問題文の場合は、住所地特例によって、特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となります。
住所地特例対象施設は、「介護保険施設」、「特定施設」、「老人福祉法に規定する養護老人ホーム」です。
(法第13条)
用語の定義も確認しましょう。
・「介護保険施設」は、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいいます。
(法第8条第25項)
・「特定施設」は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいいます。
(法第8条第11項)
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。

【解答】
【R1年出題】 ×
介護保険法に規定する介護保険施設は、住所地特例対象施設です。
問題文の場合は、住所地特例の適用を受けますので、介護保険の保険者はA県A市のままです。
(法第13条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(障害者の雇用の促進等に関する法律)
令和4年の問題を復習しましょう(障害者の雇用の促進等に関する法律)
R5-105
R4.12.10 R4択一式より 障害者に対する差別の禁止
まず、条文を読んでみましょう。
第34条 (障害者に対する差別の禁止) 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
第35条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。
第36条第1項 (障害者に対する差別の禁止に関する指針) 厚生労働大臣は、前2条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。 |
★「差別の禁止に関する指針」のポイントを確認しましょう★
基本的な考え方は以下の通りです。
・全ての事業主が対象です
・禁止される差別は、「障害者であることを理由とする差別」です
→ ここでいう差別は、直接差別のことです。車いす、補助犬その他の支援器具等の利用、介助者の付添い等の社会的不利を補う手段の利用等を理由とする不当な不利益取扱いを含みます。
・事業主や同じ職場で働く者が障害の特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要です
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-C】
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

【解答】
【問4-C】 〇
「差別の禁止に関する指針」では、募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの各項目で、障害者であることを理由に障害者を排除すること、障害者に対してのみ不利な条件とすること等が、差別に該当するとして整理されています。
また、次の3つの措置を講ずることは、障害者であることを理由にする差別に該当しないとされています。
・ 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うこと。
・ 合理的配慮を提供し、労働能力等を適正に評価した結果として障害者でない者と異なる取扱いをすること。
・ 合理的配慮に係る措置を講ずること(その結果として、障害者でない者と異なる取扱いとなること)。
参照:障害者差別禁止指針(平成27年厚生労働省告示第116号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-104
R4.12.9 R4択一式より 加給年金額の支給停止
厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上ある人に、生計維持関係のある配偶者や子がいる場合は、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
ただし、その加給年金額は、支給停止されることもあります。
条文を読んでみましょう。
第46条第6項 加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。 |
今日は、「老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)」の部分を見ていきます。
加給年金額の加算対象の配偶者が、被保険者期間の月数が240以上で計算される老齢厚生年金の支給を受けることができる場合は、加給年金額は支給停止されます。
※原則は240月(20年)以上が対象ですが、中高齢の期間短縮特例に該当する場合は、15~19年となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-E】
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

【解答】
【問9-E】 〇
加給年金額の加算の対象となっている妻が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合は、夫の老齢厚生年金に加算されていた加給年金額は支給停止となります。
★令和4年4月の改正点を確認しましょう。
<改正前>
配偶者の240月以上の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額支給停止されている場合 → 本人の老齢厚生年金に加算される加給年金額は支給されることになっていました。
<改正後>
配偶者の240月以上の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額支給停止されている場合 → 本人の老齢厚生年金に加算される加給年金額は支給停止されることになりました。(施行令第3条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-103
R4.12.8 R4択一式より 厚生年金保険の未支給保険給付
年金の受給権者が死亡した場合、必ず、未支給年金が発生します。
年金は権利が消滅した月まで支払われますので、例えば、12月20日に死亡した場合、年金は12月分まで支払われます。
年金は2か月分ずつ後払いされます。10月分と11月分が12月に支給されていますが、12月分は未支給となります。
まず、未支給保険給付の条文を読んでみましょう。
第37条 (未支給の保険給付) ① 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ③ 死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 ④ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。 ⑤ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
★ 未支給保険給付(=「保険給付」ですので、年金のみならず一時金も含まれます)が発生するのは、以下の場合です。
・ 保険給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき
・ 死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかったとき
★ 未支給の保険給付を請求することができるのは、以下の遺族です。
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-E】
保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされる。

【解答】
【問10-E】 〇
未支給の保険給付を受けることができる順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦①から⑥以外の3親等内の親族です。
同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表して請求することになります。その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとなり、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとなります。
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
②【H23年出題】
保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。

【解答】
①【H30年出題】 〇
未支給の保険給付は、「死亡した受給権者の名」ではなく、請求する遺族の「自己の名」で請求することがポイントです。
②【H23年出題】 ×
同順位者が2人以上あるときは、そのうち1人が代表して請求することになり、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなされ、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされますので、「同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-102
R4.12.7 R4択一式より 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の繰下げ
老齢厚生年金の受給権を有する者で、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
今日は、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の、繰下げの申出についてみていきましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-D】
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。

【解答】
【問9-D】 〇
第78条の28で、「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る老齢厚生年金について、一の期間に基づく老齢厚生年金についての支給繰下げの申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない」と規定されています。
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合は、繰下げの申出は同時に行わなければなりません。
(法第78条の28)
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
問題文の場合、支給繰下げの申出は、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金を同時に行わなければなりません。
2つ以上の種別の老齢厚生年金を受けることができる場合は、全て同時に繰下げの申出をしなければなりません。
こちらの過去問もどうぞ!
②【H28年出題】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。
③【H27年出題】
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行う必要はありません。
老齢厚生年金のみ繰下げる又は老齢基礎年金のみ繰下げることも可能です。
(法第44条の3)
③【H27年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行う必要があります。老齢基礎年金のみ繰上げる、又は老齢厚生年金のみ繰上げることはできません。
(法附則第7条の3第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-101
R4.12.6 R4択一式より 短時間労働者の社会保険適用要件
短時間労働者の社会保険の適用条件を確認しましょう。
短時間労働者に対する適用について
◎「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」といいます。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
◎ 4分の3基準を満たさない場合でも、以下の①から④までの4つの要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
② 月額賃金が8.8万円以上であること。
③ 学生でないこと。
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(i) 特定適用事業所
(ii) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(iii) 国又は地方公共団体の適用事業所
※「特定適用事業所」の企業規模要件は、令和4年10月の改正で、500人超える企業から、「100人」を超える企業に引き下げられました。
参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-A】
常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働き、継続して1年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

【解答】
【問7-A】 ×
Xは、短時間労働者の社会保険適用の4つの条件に当てはまりますので、厚生年金保険の被保険者となります。
① 1週の所定労働時間が25時間 → 20時間以上
② 月額賃金が15万円 → 8.8万円以上
③ 学生でない
④ 地方公共団体に使用されている
※地方公共団体は、平成29年4月から被保険者数に関わらず、適用されます。
★なお、令和4年10月の改正で、「継続して1年以上使用されることが見込まれる」という雇用期間の要件はなくなりました。雇用期間は、通常の被保険者と同様に「2か月を超えて見込まれること」となります。
過去問をどうぞ!
【R2年出題】
特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
【R2年出題】 〇
問題文の場合、4分の3基準を満たさない短時間労働者ですので、厚生年金保険の被保険者となるには、報酬の月額が88,000円以上あることが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-100
R4.12.5 R4択一式より 65歳以上の厚生年金保険の被保険者
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。
第1号被保険者と第3号被保険者は、20歳以上60歳未満という年齢要件がありますが、第2号被保険者には、年齢要件がないのがポイントです。
ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、老齢基礎年金・老齢厚生年金等の受給権の有無で扱いが変わりますので、注意しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第7条第1項第2号・法附則第3条 厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者とする。 65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。 |
ポイント!
厚生年金保険の被保険者で65歳以上の者については、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の受給権を有している場合は、第2号被保険者となりません。
★65歳の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権がある場合
65歳 70歳
厚生年金保険の被保険者 | |
国民年金第2号被保険者 |
|
▲国民年金の資格喪失
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-A】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
【問7-A】 〇
65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有している場合は、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、65歳に達したときに、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。
(法附則第4条)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。
②【H26年出題】※改正による修正あり
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者」であることが条件です。
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者ではありませんので、55歳の配偶者は第3号被保険者となりません。
②【H26年出題】 × ※改正による修正あり
老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していない65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者となります。
障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、老齢又は退職の年金の受給権がなければ第2号被保険者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-099
R4.12.4 R4択一式より 寡婦年金が受給できる妻の年齢
今日は、寡婦年金が受給できる妻の年齢について確認しましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第49条 (寡婦年金の支給要件) ① 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 ③ 60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。 |
 寡婦年金の受給権が発生するのは、「夫との婚姻関係が10年以上継続した『65歳未満』の妻」です。
寡婦年金の受給権が発生するのは、「夫との婚姻関係が10年以上継続した『65歳未満』の妻」です。
年金の支給は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」から始まります。しかし、寡婦年金の場合、60歳未満の妻については、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から始まるのがポイントです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-B】
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。

【解答】
【問3-B】 〇
寡婦年金の受給要件は「65歳未満の妻」です。「妻が60歳未満」であるときは、寡婦年金の受給権が発生します。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
寡婦年金は、夫の死亡当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。
②【H20年出題】
夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで支給される。

【解答】
①【H20年出題】 ×
寡婦年金の受給権が発生するのは、「65歳未満の妻」です。「60歳以上65歳未満」の妻に限りの部分が誤りです。
②【H20年出題】 〇
夫の死亡の当時に60歳未満の妻にも寡婦年金の受給権は発生しますが、支給は妻が「60歳に達した日の属する月の翌月」から開始されます。
なお、寡婦年金は老齢基礎年金が受給できるまでの有期年金ですので、65歳に達したときに失権します。支給されるのは、「65歳に達した日の属する月」までです。
(法第51条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-098
R4.12.3 R4択一式より 学生納付特例事務法人の行う事務
学生納付特例事務法人制度は、学生が、学生納付特例の申請手続きをしやすくするために、学生の委託を受けた大学が、学生納付特例申請の代行を行う制度です。
学生納付特例事務法人の行う事務について条文で確認しましょう。
第109条の2の2第1項(学生納付特例の事務手続に関する特例) 国及び地方公共団体並びに国立大学法人法に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法に規定する公立大学法人及び私立学校法に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、学生納付特例申請に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において学生等被保険者の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。 |
★大学等の教育施設では、学生等被保険者に係る学生納付特例申請の代行ができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問1-A】
国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。

【解答】
【問1-A】 ×
学生納付特例事務法人は、学生等被保険者の委託を受けて、学生納付特例申請の事務を行います。「保険料の納付」に関する事務は行うことができません。
では、過去問をどうぞ!
【H27年出題】
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。

【解答】
【H27年出題】 〇
法第109条の2の2第2項で、「学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなす。」と規定されています。
なお、第3項では、「学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない。」とされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-097
R4.12.2 R4択一式より 資格喪失後の継続給付の条件
資格喪失後に、継続して傷病手当金・出産手当金を受けることができます。その条件として、「資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった」ことがあります。
今日は、1年の算定ルールを確認しましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 法附則第3条第6項 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
 資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが条件です。ただし、この「1年以上被保険者であった」の被保険者には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが条件です。ただし、この「1年以上被保険者であった」の被保険者には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
では、令和4年の問題をどうぞ
【問9-C】
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

【解答】
【問9-C】 ×
資格喪失後の傷病手当金を受けるには、資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが必要です。ただし、この期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者は除かれます。
問題文の場合は、資格喪失の日の前日までの被保険者であった期間は、共済組合の組合員の期間を除くと、10か月しかありません。そのため、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする。
②【H23年出題】
継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。
③【H27年出題】
継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
保険者が異なっていても、資格喪失日の前日まで1日の空白も無く1年以上被保険者であった場合は、資格喪失後も継続して傷病手当金を受けることができます。
②【H23年出題】 ×
資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、要件を満たせば、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができます。
③【H27年出題】 〇
資格喪失後に任意継続被保険者となった場合は、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができます。
一方、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできません。
(法附則第3条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-096
R4.12.1 R4択一式より 介護休業期間中の出産手当金
介護休業期間中でも、出産手当金は支給されるでしょうか?
まず、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】
被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

【解答】
【問9-B】 〇
出産手当金の支給要件に該当すると認められる者には、介護休業期間中でも、出産手当金が支給されます。
※ちなみに、「傷病手当金」も同じです。支給要件に該当すれば、介護休業期間中でも、傷病手当金が支給されます。
(H11.3.31保険発46・庁保険発9)
では、次の条文を読んでみましょう。
第108条 (傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整) ① 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないとき(第103条第1項又は第3項若しくは第4項に該当するときを除く。)は、その差額を支給する。 ② 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合は、その期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
報酬の全部又は一部を受けることができる場合は、その期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。
出産手当金も同じ扱いです。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。
②【H23年出題】
介護休業期間中に病気にかかり、その病気の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合には、傷病手当金が支給される。この場合、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について調整を行うこととされている。

【解答】
①【H27年出題】 〇
要件に該当すれば、介護休業期間中でも出産手当金が支給されます。また、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額について報酬(介護休業手当)との調整が行われます。
(H11.3.31保険発46・庁保険発9)
②【H23年出題】 〇
要件に該当すれば、介護休業期間中でも傷病手当金が支給されます。また、その期間に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金の支給額について報酬(介護休業手当等)との調整が行われます。
(H11.3.31保険発46・庁保険発9)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-095
R4.11.30 R4択一式より 健保「報酬」の定義
保険料の額や傷病手当金・出産手当金は「標準報酬月額」を使って計算します。
「標準報酬月額」は、「報酬月額」に基づいて決まります。報酬月額は1月当たりの報酬の額のことです。
今日のテーマは、「報酬」の定義です。
では、条文を読んでみましょう。
第3条 5 健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 6 健康保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
「報酬」とは → 労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの
※「臨時」に受けるもの、「3月を超える期間ごと」に受けるものは、報酬から除かれます。
「3月を超える期間ごとに受けるもの」とは、年3回以下の賞与などのことです。
「賞与」とは → 「3月を超える期間ごと」に受けるもの
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-B】
健康保険法第3条第5項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

【解答】
【問7-B】 〇
3か月を超える期間ごとに受けるものは報酬から除外されます。
3か月を超える期間ごとに受ける報酬に該当するものは、年間を通じ4回以上支給される報酬以外の報酬となります。ですので、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、『年間を通じ4回以上』支給される場合は、報酬に該当します。
(S36.1.26保発第5号)
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
②【R1年出題】
保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
通勤手当は、「報酬」に含まれます。
②【R1年出題】 〇
通勤手当は6か月ごとに支給されても、実態は毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に当てられるものですので、報酬となります。
(昭和27.12.4保文発7241)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-094
R4.11.29 R4択一式より 健康保険組合の役員
今日のテーマは、健康保険組合の役員です。
まず、「組合会」について条文を読んでみましょう。
第18条 (組合会) 1 健康保険組合に、組合会を置く。 2 組合会は、組合会議員をもって組織する。 3 組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。
|
組合会は、健康保険組合の議決機関で、組合会議員で組織されています。
組合会議員の定数は偶数で、事業主が選定する選定議員と被保険者である組合員が互選する互選議員がそれぞれ半数ずつです。
次に「役員」について条文を読んでみましょう。
第21条 (役員) 1 健康保険組合に、役員として理事及び監事を置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。 4 監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。 5 監事は、理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。 |
 健康保険組合には、役員として理事及び監事を置くことになっています。
健康保険組合には、役員として理事及び監事を置くことになっています。
理事は組合の執行機関、監事は監査機関です。
理事の定数は、偶数で、事業主の選定した選定議員が半数、被保険者である組合員の互選した互選議員が半数です。
理事長は健康保険組合の代表者です。事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事の選挙で決められます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-C】
健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙で選出する。なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

【解答】
【問5-C】 〇
健康保険組合の監事の任務は、「健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査」することです(第22条第4項)
事業主の選定した選定議員と被保険者である組合員の互選した互選議員のうちから、それぞれ1人が選出されます。
監事には中立が求められるため、理事又は健康保険組合の職員と兼務できません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定する。
②【H22年出題】
健康保険組合の監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1人を選挙することになっており、監事のうち一人は理事または健康保険組合の職員を兼ねることができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
健康保険組合の理事は、事業主の選定した組合会議員と被保険者である組合員の互選した組合会議員が半々で構成されています。代表者である理事長は、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、「理事が選挙」します。「事業主が選定」は誤りです。
②【H22年出題】 ×
中立的な立場が求められる監事については、理事または健康保険組合の職員を兼ねることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-093
R4.11.28 R4択一式より 徴収法上の賃金
「賃金」は「労働の対償」として、「事業主が労働者」に支払うものをいいます。
賃金は、徴収法では、労働保険料の計算に使われます。
では、賃金の定義を条文で確認しましょう。
第2条 2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 |
★賃金には、一定の現物給付も含まれます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問10-E(労災)】
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。
②【問10-D(労災)】
健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

【解答】
①【問10-E(労災)】 〇
労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、賃金と認められます。ただし、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は、賃金とは認められません。
(S24.6.14基災収3850号)
②【問10-D(労災)】 〇
健康保険法の傷病手当金は、賃金ではありません。
標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合で、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額について → 恩恵的給付と認められる場合には、賃金とは認められず、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含みません。
(S27.5.10基収2244号)
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題(労災)】
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
②【H24年出題(労災)】
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定めるいわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

【解答】
①【H26年出題(労災)】 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金などの個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約などで支払いが事業主に義務付けられていても、賃金としては取り扱われません。
(S25.2.16基発127号)
②【H24年出題(労災)】 〇
労働基準法の「休業手当」は賃金です。(S25.4.10基収950号)解雇予告手当は賃金ではありません。(S23.8.18基収2520号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-092
R4.11.27 R4択一式より 法人の取締役の労災保険料
一般保険料の額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
今日のテーマは、法人の取締役の賃金が賃金総額に含まれるか否かについてです。
では、条文を読んでみましょう。
第11条 (一般保険料の額) ① 一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 ② 「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
第12条 (一般保険料に係る保険料率) 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、労災保険率 3 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、雇用保険率 |
一般保険料額は、賃金総額×一般保険料率で計算します。
一般保険料率は、以下の通りです。
① 労災保険と雇用保険に係る保険関係が成立している事業
→ 労災保険率+雇用保険率
② 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業
→ 労災保険率
③ 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業
→ 雇用保険率
また、計算に使う「賃金総額」は、「すべての『労働者』に支払う賃金の総額」です。
では、令和4年の問題をどうぞ。
【問10-A(労災)】
法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

【解答】
【問10-A(労災)】 〇
法人の取締役でも、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合は、「労働者」として労災保険が適用されます。
そのため、労災保険料を計算する場合は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)は、賃金総額に含まれます。
(S61.3.14基発141号)
なお、雇用保険については、「株式会社の取締役は、原則として、被保険者としない。取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものに限り被保険者となる。」とされています。(行政手引20351)
過去問もどうぞ!
【H24年出題(雇用)】
労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。

【解答】
【H24年出題(雇用)】 〇
一元適用事業は、「賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)」のように、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係をまとめて、一般保険料を計算します。
二元適用事業は、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定することになっていますので、「賃金総額×労災保険率+賃金総額×雇用保険率」で計算します。
ただし、一元適用事業でも、労災保険が適用される労働者の範囲と雇用保険が適用される労働者の範囲が異なることがあります。そのような場合は、それぞれの保険で賃金総額が変わりますので、二元適用事業と同じように、「労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして」一般保険料の額を算定することになります。
(法第39条、整備令第17条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
R5-091
R4.11.26 R4択一式より 高年齢再就職給付金の支給要件
今日は、「高年齢再就職給付金」がテーマです。
まず、条文を読んでみましょう。
第61条の2 (高年齢再就職給付金) ① 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。 2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 ② 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。 |
★高年齢再就職給付金の対象者の条件
・受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後→60歳到達時以後に安定した職業に就き被保険者となったこと
・基本手当の受給資格については、算定基礎期間が5年以上あること
・基本手当の受給期間内に再就職し、就職日の前日の支給残日数が100日以上あること
★高年齢再就職給付金の支給対象期間
・基本手当の支給残日数が200日以上
→ 就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
・基本手当の支給残日数が100日以上200日未満
→ 就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
※ただし、2年又は1年を経過する日の前に65歳に達する日がある場合は、65歳に達する日の属する月まで
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-E】
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。

【解答】
【問5-E】 〇
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けた場合は、新たな基本手当の受給資格に基づいては高年齢再就職給付金の受給資格は生じません。そのため、被保険者資格の再取得があったとしても、高年齢再就職給付金の支給対象にはなりません。
※ただし、被保険者資格喪失後、当該高年齢再就職給付金に係る基本手当の受給資格に基づいて、再度基本手当を受給した後、被保険者資格の再取得があった場合は、当該再度の基本手当の支給分を差し引いても支給残日数が、100日以上又は200日以上である場合は、再度高年齢再就職給付金の対象となります。
(行政手引59314)
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
高年齢再就職給付金は、基本手当の支給残日数のいかんにかかわらず、当該被保険者が65歳に達する日の属する月よりも後の月について支給されることはない。
②【H30選択式】
雇用保険法第61条の2第1項は、「高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第22条第3項の規定による算定基礎期間が< A >以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1 当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、< B >未満であるとき。
2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。」と規定している。

【解答】
①【H22年出題】 〇
高年齢再就職給付金は、例えば、支給残日数が200日以上の場合は、就職日の翌日から2年を経過した日の属する月までが支給対象ですが、2年経過前に65歳に到達する場合は、65歳に達する日の属する月までとなります。
②【H30選択式】
A5年
B100日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-090
R4.11.25 R4択一式より 脳・心臓疾患の労災認定基準
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が、令和3年に改正されました。
働き方の多様化や職場環境の変化に応じて、最新の医学的知見を踏まえて、検証が行われたことによります。
新たに認定基準に追加されたポイントは以下の通りです。
■長期間の過重業務について
・労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されました。
・労働時間以外の負荷要因が見直されました。勤務間インターバルが短い勤務、身体的負荷を伴う業務などが評価対象として追加されました。
■短期間の過重業務・異常な出来事について
・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合が明確化されました。
では、令和4年の問題をどうぞ!
※「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)」より
①【問1-A】
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、 1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。
②【問1-C】
短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。

【解答】
①【問1-A】 ×
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと判断できます。
しかし、その水準には至らないが、これに近い時間外労働が認められる場合は、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる、とされています。
「労働時間」と「労働時間以外の負荷要因」を総合的に考慮して判断するのがポイントです。
労働時間以外の負荷要因として、「拘束時間の長い勤務」、「休日のない連続勤務」、「出張の多い業務」、「心理的負荷を伴う業務」などがあります。
②【問1-C】 〇
「発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合」、「発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等は、業務と発症との関連性が強いと評価できる、とされています。
★短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して判断されます。
① 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であるか否か
② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否か
※厚生労働省パンフレット「脳・心臓疾患の労災認定」を参照しました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-089
R4.11.24 R4択一式より 合理的な経路及び方法(通勤)
通勤の定義の一つである「合理的な経路及び方法」について確認しましょう。
まず条文を読んでみましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
★「合理的な経路及び方法」とは、一般的に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいいます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問6-D】
マイカー通勤の労働者が、経路上の道路工事のためにやむを得ず通常の経路を迂回して取った経路は、ふだんの通勤経路を外れた部分についても、通勤災害における合理的な経路と認められる。
②【問6-E】
他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が、いつもどおり親戚に子供を預けるために、自宅から徒歩10分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100メートルのところにある親戚の家まで、子供とともに歩き、子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち、勤務先会社と親戚の家との間の往復は、通勤災害における合理的な経路とは認められない。

【解答】
①【問6-D】 〇
経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる、とされています。
(H18.3.31基発第 0331042 号)
②【問6-E】 ×
他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば 当然就業のためにとらざるを得ない経路です。そのため、合理的な経路と認められます。
(H18.3.31基発第 0331042 号)
過去問をどうぞ!
【R3年出題】
自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中、他の自動車との接触事故で負傷したが、労働者Xは所持している自動車運転免許の更新を失念していたため、当該免許が当該事故の1週間前に失効しており、当該事故の際、労働者Xは、無免許運転の状態であった。この場合は、諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの、通勤災害と認められる可能性はある。

【解答】
【R3年出題】 〇
例えば、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法と認められません。
「飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要はないが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることがあることは当然である。」とされています。
(H18.3.31基発第 0331042 号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-088
R4.11.23 R4択一式より 三六協定の時間外労働の定義
時間外労働・休日労働をさせる場合は、「三六協定」の締結と届出が必要です。
今日のテーマは、三六協定が必要な「時間外労働」についてです。
では、三六協定の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は第35条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
★三六協定が必要な時間外労働・休日労働について
時間外労働 → 「労働基準法第32条から第32条の5まで若しくは第40条」で上限が決められている労働時間を延長する場合です。
休日労働 → 「第35条」の休日(原則週1回の休日)に労働させる場合です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-D】
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、労働基準法第36条第1項の協定をする必要はない。

【解答】
【問3-D】 〇
所定労働時間を超えて労働時間を延長した場合でも、1週の労働時間が法定労働時間以内で各日の労働時間が8時間以内・かつ休日労働を行わせない限りは、36協定をする必要はありません。
36協定が必要になるのは、法定労働時間を超えて労働させる場合、法定休日に労働させる場合です。
(H11.3.31基発168号)
過去問をどうぞ!
【H13年出題】
週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない事業場において、月曜日に10時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は休業としたときは、その週の総労働時間数は40時間であるので、この月曜から金曜までについては、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。

【解答】
【H13年出題】 ×
週の総労働時間数は40時間で法定労働時間以内ですが、1日8時間を超えている月曜日、火曜日、木曜日は時間外労働となります。三六協定の締結と、第37条に基づく割増賃金の支払が必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-087
R4.11.22 R4択一式より トラック運転手の労働時間
トラック運転手の労働時間の取扱いについて確認しましょう。
さっそく、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-B】
定期路線トラック業者の運転手が、路線運転業務の他、貨物の積込を行うため、小口の貨物が逐次持ち込まれるのを待機する意味でトラック出発時刻の数時間前に出勤を命ぜられている場合、現実に貨物の積込を行う以外の全く労働の提供がない時間は、労働時間と解されていない。

【解答】
【問2-B】 ×
いわゆる手待ち時間が大半を占めていても、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上は、労働時間と解されます。
(S33.10.11基収6286号)
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

【解答】
①【H30年出題】 ×
仮眠中であっても、トラックに乗り込む点で使用者の拘束を受けていること、また、万一の事故発生の場合には交替運転や故障修理を行うことから、一種の手待ち時間又は助手的な勤務として、労働時間と解されます。
(S33.10.11基収6286号)
こちらの過去問もどうぞ!
②【H22年出題】
ビルの巡回監視等の業務に従事する労働者の実作業に従事していない仮眠時間についても、労働からの解放が保障されていない場合には労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。

【解答】
②【H22年出題】 〇
「仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる」とされています。
(最高裁第1小法廷H14.2.28大星ビル管理事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-086
R4.11.21 R4択一式より 年次有給休暇の権利の発生
年次有給休暇の権利の発生の要件を確認しましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
第39条第1項 使用者は、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
年次有給休暇の権利は、①6か月間継続勤務、②全労働日の8割以上出勤の2つの要件を満たした場合に発生します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-E】
年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまって始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
【問7-E】 ×
年次有給休暇の権利について最高裁判所の判例では、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではない」とされています。年次有給休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』は不要です。
なお、第39条第5項では、「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と規定されています。
ここに出てくる「請求」は休暇の時季にかかる文言で、休暇の時季の指定という意味です。
(S48.3.2白石営林署事件)
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまって始めて生ずるものではないとするのが最高裁判所の判例である。
②【H22年出題】
労働者の時季指定による年次有給休暇は、労働者が法律上認められた休暇日数の範囲内で具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をし、使用者がこれを承認して初めて成立するとするのが最高裁判所の判例である。
③【H24年出題】
労働基準法第39条に定める年次有給休暇の利用目的は同法の関知しないところであり、労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用することもできる。

【解答】
①【H20年出題】 〇
年次有給休暇の権利は、所定の要件を満たすことによって法律上当然に労働者に生ずる権利です。
(S48.3.2白石営林署事件)
②【H22年出題】 ×
年次有給休暇の成立について、労働者による休暇の請求やこれに対する使用者の承認は不要です。
労働者がその有する休暇の日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、使用者が時季変更権の行使をしない限り、労働者の時季指定によって年次有給休暇が成立します。
(S48.3.2白石営林署事件)
③【H24年出題】 〇
最高裁判例(S48.3.2白石営林署事件)では、「年次有給休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」とされています。
労働者が病気療養のために年次有給休暇を利用する場合も、その請求時季が事業の正常な運営を妨げるものでない限り、使用者はこれを付与しなければならない、とされています。
(S24.12.28 基発第1456号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-085
R4.11.20 R4択一式より 労基法第22条「退職時等の証明」
労働者から退職時の証明書の交付を請求された場合、使用者には交付する義務があります。
条文を読んでみましょう。
第22条 (退職時等の証明) ① 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ② 労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ③ 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 |
①は「退職時の証明」です。法定記載事項は、①使用期間、②業務の種類、③その事業における地位、④賃金、⑤退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)です。
②は「解雇理由証明書」です。解雇予告の期間中に、労働者から解雇理由について証明書を請求された場合に、交付しなければならないものです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-E】
労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記載しなければならない。

【解答】
【問5-E】 ×
第22条第3項で「証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない」と規定されています。
例えば、解雇された労働者が解雇の事実のみが記入された証明書を請求した場合は、証明書に記載できるのは解雇の事実のみです。請求されていない解雇の理由を記載することはできません。
(H11.1.29基発45号)
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
使用者は、労働者が退職から1年後に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由について証明書を請求した場合は、これを交付する義務はない。
②【H22年出題】
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
退職時の証明を請求する権利は、労働基準法第115条によって時効は2年となっています。そのため、退職から1年後に証明書の請求があった場合は、使用者には交付する義務があります。
(H11.3.31基発169号)
②【H22年出題】 ×
解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合は、「解雇の理由」を証明書に記載することはできません。
証明書には労働者の請求しない事項を記載することはできないからです。
(H11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-084
R4.11.19 R4択一式より 労基法第5条「強制労働の禁止」
労働基準法第5条では、労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しています。
条文を読んでみましょう。
第5条 (強制労働の禁止) 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 |
第5条は、「強制してはならない」という規定ですので、労働することを強要した場合は労働者が現実に労働した事実がなくても、強要しただけで第5条に抵触します。
第5条に違反した場合は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。労働基準法上最も重い罰則です。
では令和4年の問題をどうぞ
【問4-D】
使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。

【解答】
【問4-D】 〇
第5条は、不当に拘束する手段で労働を強制することを禁止しています。問題文のように「労働の強制の目的がなく」、使用者の暴行が労働の強制につながっていない場合は、労働基準法第5条違反にはなりません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法第5条に定める「脅迫」とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。
②【H26年出題】
労働基準法第5条は、使用者が労働者に強制労働をさせることを禁止しているが、必ずしも形式的な労働契約により労働関係が成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りるとされている。

【解答】
①【R3年出題】 〇
脅迫によって使用者が労働者の意思に反して労働することを強制し得る程度であることが必要です。
(S22.9.13発基17号)
②【H26年出題】 〇
形式的な労働契約が成立していなくても、事実上労働関係が存在すると認められる場合は、強制労働違反が成立します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-083
R4.11.18 R4択一式より 労基法第3条「均等待遇」
今日のテーマは「均等待遇」です。
まず、条文を読んでみましょう。
第3条 (均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 |
国籍、信条、社会的身分を理由として労働者を差別することを禁止している条文です。
なお、第3条で禁止している差別は、国籍・信条・社会的身分を理由する差別のみです。それ以外の理由による差別は第3条には抵触しません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-B】
労働基準法第3条にいう「信条」には、特定の宗教的信念のみならず、特定の政治的信念も含まれる。

【解答】
【問4-B】 〇
「信条」とは、特定の宗教的又は政治的信念をいいます。
(S22.9.13 発基第17号)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働基準法が第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。
②【H25年出題】
労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。
③【H30年出題】
労働基準法第3条にいう「賃金、労働時間その他の労働条件」について、解雇の意思表示そのものは労働条件とはいえないため、労働協約や就業規則等で解雇の理由が規定されていても、「労働条件」にはあたらない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
有利に取り扱っても、不利に取り扱っても「差別的取扱」にあたります。
②【H25年出題】 〇
労働基準法第3条で禁止しているのは、「国籍、信条又は社会的身分を理由とする」差別的取扱に限定されています。
③【H30年出題】 ×
「賃金、労働時間その他の労働条件」の「その他の労働条件」は、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等も含む趣旨とされています。
労働協約や就業規則等で解雇の基準や理由が規定されていれば、労働するための条件となりますので、第3条の「労働条件」になります。
(S23.6.16基収第1365号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-082
R4.11.17 R4択一式より 適用事業所の高齢任意加入被保険者
70歳以上の者で、老齢基礎年金、老齢厚生年金など老齢又は退職を支給事由とする年金受給権を有しないものは、任意に厚生年金保険に加入することができます。
高齢任意加入被保険者には、「適用事業所に使用される者」と「適用事業所以外の事業所に使用される者」の2種類あります。
それぞれの違いが、出題ポイントです。
今日は、高齢任意加入被保険者の保険料の負担について確認しましょう。
| 保険料 |
適用事業所の 高齢任意加入被保険者 | 原則 全額自己負担 ※事業主の同意がある場合は折半で負担することもできる |
適用事業以外の事業所の 高齢任意加入被保険者 | 事業主と折半で負担 ※加入について、保険料の負担について事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣の認可を受ける |
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問2-A】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下「当該被保険者」という。)を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。
②【問2-C】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下「当該被保険者」という。)が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
①【問2-A】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、かつ、保険料の納付義務も本人が負います。
なお、事業主の同意がある場合は、事業主が保険料の半額を負担し、かつ、保険料の納付義務も事業主が負います。
(附則第4条の3第7項)
②【問2-C】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までに納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の「前月の末日」に資格を喪失します。
なお、初めて納付すべき保険料を滞納し、指定の期限までに納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなされます。
また、事業主の同意がある場合は、事業主が保険料の納付義務を負いますので、保険料滞納による資格喪失はありません。
(附則第4条の3第6項)
※ちなみに、「適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上」の者は、保険料の納付義務について事業主の同意を得ることが前提ですので、滞納による資格喪失はありません。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

【解答】
【H29年出題】 ×
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、保険料を納付する義務を負うことにつき同意することができます。又、その同意を将来に向かって撤回することもできます。ただし、「第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者」に係る事業主には適用されません。
(法附則第4条の3第7項、8項、10項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-081
R4.11.16 R4択一式より 在職定時改定
令和4年4月に在職定時改定が導入されました。
65歳以降も働いている場合は、負担した保険料が、毎年、年金額に反映する仕組みです。
条文を読んでみましょう。
第43条第2項 受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1月以内である場合は、基準日の属する月前の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 |
★在職定時改定は、65歳以上70歳未満の受給権者が対象です。60歳台前半の老齢厚生年金には適用されません。
★毎年9月1日(基準日)に基準日の属する月前の被保険者であった期間を、老齢厚生年金の額に反映させ、基準日の属する月の翌月(10月)から年金の額を改定する仕組みです。
厚生年金保険の被保険者(在職中) | ||
| ②の期間分→令和6年10月から増額 | |
| ①の期間分→令和5年10月から増額 | |
老齢厚生年金
| ||
老齢基礎年金 | ||
65歳 ①基準日 ②基準日
(令和5年9月1日) (令和6年9月1日)
①の期間 → 65歳到達月から令和5年8月まで
②の期間 → 前年9月から令和6年8月まで
令和4年の問題をどうぞ!
【問9-B】
65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。

【解答】
【問9-B】 ×
基準日は7月1日ではなく「9月1日」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-080
R4.11.15 R4択一式より 在職老齢年金と経過的加算額
「経過的加算額」は在職老齢年金の支給停止の対象となるか?ならないかが今日のテーマです。
まず、在職老齢年金の条文を読んでみましょう。
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
★経過的加算額については法附則で規定されています。確認しましょう。
・基本月額の計算では、繰下げ加算額と同じように除外されます。
・支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときでも、繰下げ加算額は支給停止されず全額支給されますが、経過的加算額も同じように全額支給されます。
(S60年法附則第26条第1項)
令和4年の問題をどうぞ!
【問8-C】
在職中の被保険者が65歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。

【解答】
【問8-C】 ×
経過的加算額は在職老齢年金の支給停止の対象にはなりません。
なお、老齢基礎年金も在職老齢年金の支給停止の対象となりません。
過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。
②【H26年出題】
66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。
③【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
経過的加算額も繰下げ加算額も、基本月額の計算から除かれます。
②【H26年出題】 〇
老齢厚生年金の繰下げ加算額は、在職老齢年金の支給停止の対象になりません。老齢厚生年金が全額支給停止されても、繰下げ加算額は全額支給されます。
③【H24年出題】 ×
60歳台後半の在職老齢年金で、経過的加算額と繰下げ加算額は支給停止の対象になりませんので、全額支給されます。
なお、老齢基礎年金も支給停止の対象にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-079
R4.11.14 R4択一式より 在職老齢年金の支給停止調整額
在職老齢年金のルールを確認しましょう。
・「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円以下の場合
→ 老齢厚生年金は全額支給されます
・「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超える場合
→ 老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止されます。
→ 支給停止額は、「(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」で計算します。
条文を読んでみましょう。
第46条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)の支給を停止するものとする。 |
用語の定義をおさえましょう。
総報酬月額相当額 →標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
基本月額 →老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げ加算額を除く。)÷12
支給停止基準額 →(総報酬月額相当額+基本月額-支給停止調整額)×2分の1×12
★「支給停止調整額」は、令和4年度は47万円です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-E】
在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。

【解答】
【問8-E】 〇
支給停止調整額は、名目賃金変動率に応じて改定されます。令和4年度は47万円ですが、年度によっては改定されることもあります。
なお、支給停止調整額を計算する際の端数処理は、5千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5千円以上1万円未満の端数が生じたときは、これを1万円に切り上げるものとされています。
(法第46条第3項)
では、過去問をどうぞ!
【H28年選択】
厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「< A >」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が< B >を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、< A >と基本月額との合計額から< B >を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「< C >」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、< C >が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同法第44条の3条第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。

【解答】
A 総報酬月額相当額
B 支給停止調整額
C 支給停止基準額
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-078
R4.11.13 R4択一式より 基礎年金拠出金の額の算定基礎
厚生年金保険の実施者たる政府、実施機関たる共済組合等は、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担します。
条文を読んでみましょう。
第94条の2(基礎年金拠出金) ① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 |
次に「基礎年金拠出金」の額について条文を読んでみましょう。
第94条の3 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあっては、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあっては、当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(国家公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあっては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者及びその被扶養配偶者である第3号被保険者とする。)とする。)の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。 |
 基礎年金拠出金の額は、「保険料・拠出金算定対象額」に「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を乗じて得た額となります。
基礎年金拠出金の額は、「保険料・拠出金算定対象額」に「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を乗じて得た額となります。
令和4年の問題をどうぞ!
【問8-C】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

【解答】
【問8-C】 ×
基礎年金拠出金の額は、「被保険者の総数」に対する「第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)と第3号被保険者の総数」の比率を使って計算します。「被保険者の総数」には、第1号被保険者数も入りますが、その数は、「保険料納付済期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数」です。
「保険料全額免除期間」は入りません。保険料を全額又は一部納付している人が対象です。
(施行令第11条の3)
では、過去問もどうぞ!
①【R2年選択】
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
②【H23年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間に限られ、保険料免除期間を有する者及び保険料未納者は除かれる。
③【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者数にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

【解答】
①【R2年選択】
A 実施機関たる共済組合等
②【H23年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間と保険料一部免除期間を有する者が算入されます。除外されるのは、保険料を納付していない「保険料全額免除」及び「保険料未納者」です。
(施行令第11条の3)
③【R1年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者について
・第1号被保険者数 → 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者
・第2号被保険者 → 20歳以上60歳未満の者
・第3号被保険者 → すべての者
となります。
第2号被保険者はすべての者ではなく年齢要件がありますので注意してください。
(施行令第11条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-077
R4.11.12 R4択一式より 老齢基礎年金の額に反映されない期間
老齢基礎年金の支給については、原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上あることが条件です。
「学生の納付特例」の期間は、老齢基礎年金の額に反映されるでしょうか?それとも反映されないでしょうか?
まず、条文読んでみましょう。
第26条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
 「保険料免除期間」が2か所出てきます。
「保険料免除期間」が2か所出てきます。
1つめの保険料免除期間はかっこ書きで学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものが除かれています。
学生納付特例によって猶予された保険料については、老齢基礎年金の年金額の計算には反映しません。65歳で老齢基礎年金が支給されるのは、「保険料納付済期間」と「学生納付特例期間以外の保険料免除期間」を有する者だけですので注意してください。
しかし、2つ目の保険料免除期間についてはかっこ書きがありません。受給資格期間の10年には、学生納付特例期間も算入されるからです。
※「納付猶予」の期間も学生納付特例期間と同じように扱われます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-B】
国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
【問8-B】 ×
学生納付特例の期間、納付猶予の期間のどちらも、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映しません。
(第26条、H26法附則第14条)
過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
②【R1年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。

【解答】
①【H29年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料を追納すれば老齢基礎年金の額には反映しますが、追納しなければ老齢基礎年金の計算には入りません。
②【R1年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間だけで10年以上有している場合、どちらも老齢基礎年金の額には反映しませんので、65歳になっても老齢基礎年金は支給されません。
※なお、婚姻していて振替加算の要件に該当する場合は、振替加算に相当する額の老齢基礎年金が支給される可能性があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-076
R4.11.11 R4択一式より 障害基礎年金の併合
障害基礎年金の受給権者に、さらに障害基礎年金の受給権が発生した場合は、前後の障害が併合されます。
条文を読んでみましょう。
第31条 (併給の調整) ① 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。 |
★前後の障害が併合された場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅するのがポイントです。
では、併合の際、障害基礎年金のどちらかが支給停止されている場合の条文も読んでみましょう。
第32条 ① 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。 ② 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定(労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。)によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。 |
★①は前の障害基礎年金が支給停止されている場合、②は後の障害基礎年金が支給停止されている場合です。
片方が支給停止されている間は、併合しない障害基礎年金が支給されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。

【解答】
【問5-A】 ×
「併合認定の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。」の部分が誤りです。
新たに取得した障害基礎年金が障害補償による支給停止の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間は、併合した障害基礎年金ではなく、「従前の障害基礎年金」が支給されます。
過去問もどうぞ!
①【R1年出題】
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されるが、当該前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する
②【H26年出題】
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。

【解答】
①【R1年出題】 〇
第31条の「併合の調整」の条文からの出題です。前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は消滅するのがポイントです。
②【H26年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じていますので、第31条の併合の対象となります。精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択ではなく、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得します。この場合、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-075
R4.11.10 R4択一式より 「国年」脱退一時金の請求要件
日本国籍を有しない人が、国民年金の資格を喪失し日本国内に住所を有しなくなった場合、脱退一時金の請求ができます。
今日は脱退一時金の請求要件を確認しましょう。
まず条文を読んでみましょう。
法附則第9条の3の2第1項 (日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であって、第26条ただし書に該当するものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 日本国内に住所を有するとき。 2 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。 3 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。 |
 脱退一時金の請求要件
脱退一時金の請求要件
・ 請求日の前日に、第1号被保険者としての被保険者期間に係る次の期間が6月以上あること(※任意加入被保険者・特例任意加入被保険者も含みます)
「保険料納付済期間の月数」+「保険料4分の1免除期間の月数×4分の3」+「保険料半額免除期間の月数×2分の1」+「保険料4分の3免除期間の月数×4分の1」
・ 国民年金の被保険者でないこと
・ 第26条ただし書に該当するもの(老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと)
・ 日本国内に住所を有していないこと
・ 障害基礎年金などの受給権を有したことがないこと
・ 最後に公的年金の被保険者の資格を喪失した日から2年経過していないこと
(資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年経過していないこと)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-C】
脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。

【解答】
【問3-C】 〇
日本国内に住所を有する場合は、脱退一時金の請求はできません。
最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、請求することが条件です。
過去問もどうぞ!
①【R2年出題】
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)が、日本国内に住所を有する場合、脱退一時金を受けることはできない。
②【H23年出題】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。
③【H30年出題】
障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
日本国内に住所を有する場合は、脱退一時金は受けられません。
②【H23年出題】 ×
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「2年を経過」している場合は、脱退一時金は請求できません。
最後に被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して「2年以内」に請求することが条件です。
③【H30年出題】 ×
「障害基礎年金の受給権を有したことがあるとき」は、脱退一時金は請求できません。障害基礎年金の受給権を有した場合は、たとえ障害基礎年金の支給を停止されていても、脱退一時金は請求できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
R5-074
R4.11.9 R4択一式より 介護保険法の保険給付
今日は介護保険の保険給付を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第18条 (保険給付の種類) 介護保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 ① 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。) ② 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。) ③ ①、②に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(「市町村特別給付」という。) |
第62条 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-C】
介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。

【解答】
【問9-C】 ×
市町村特別給付は、「行わなければならない」ではなく、「行うことができる」です。
では、過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
②【H24年出題】
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
介護保険法の保険給付は、「介護給付」、「予防給付」、「市町村特別給付」の3つです。
②【H24年出題】 ×
厚生労働大臣ではなく「市町村又は特別区」の認定を受けなければなりません。
条文をチェックしましょう。
第19条 (市町村の認定)
1 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(高齢者医療確保法)
令和4年の問題を復習しましょう(高齢者医療確保法)
R5-073
R4.11.8 R4択一式より 後期高齢者医療・保険料の徴収
後期高齢者医療の費用は、「公費」、「後期高齢者交付金(医療保険各法の保険者からの支援金)」、「後期高齢者が負担する保険料」で構成されています。
今日のテーマは後期高齢者の保険料の徴収です。
まず、後期高齢者の保険料のポイントを確認しましょう。
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。(第104条)
ポイント!保険料を徴収するのは「市町村」です。
では、保険料の徴収の方法を条文で読んでみましょう。
第107条第1項 (保険料の徴収の方法) 市町村による保険料の徴収については、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。 |
 保険料の徴収には「特別徴収」と「普通徴収」がありますが、「特別徴収」が原則です。
保険料の徴収には「特別徴収」と「普通徴収」がありますが、「特別徴収」が原則です。
特別徴収とは、「市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること」をいいます。→ 年金保険者が年金から保険料を天引きし、それを年金保険者が納入する方法です。
特別徴収以外は、普通徴収となります。
普通徴収とは、「市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収すること」をいいます。 → 個別に保険料を納付する方法です。
「普通徴収」の条文を読んでみましょう。
第108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) 1 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-D】
後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】
【問9-D】 〇
世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負っています。
では、過去問もどうぞ!
①【H23年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
②【H23年出題】
保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、②は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。
③【H27年出題】
高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村(特別区を含む。)が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。
④【H23年出題】
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。

【解答】
①【H23年出題】 ×
保険料を徴収するのは、市町村(特別区を含む。)です。都道府県は徴収しません。なお、保険料は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために徴収します。
②【H23年出題】 ×
保険料徴収の方法は、①特別徴収、②普通徴収の2つです。③その他はありませんので誤りです。
①特別徴収と②普通徴収の定義は問題文の通りです。
③【H27年出題】 〇
配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
④【H23年出題】 ×
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令ではなく「市町村の条例」で定めます。(第109条)
ちなみに、「政令」は内閣が制定するものです。条例は自治体の法令です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民健康保険法)
R5-072
R4.11.7 R4択一式より 国民健康保険組合の設立
まず、国民健康保険の「保険者」を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第3条 (保険者) 1 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 |
・都道府県と市町村がともに、保険者として国民健康保険を運営します。
・国民健康保険組合は、業種ごとに組織されています。
今日のテーマの「国民健康保険組合の設立」について条文を読んでみましょう。
第13条(組織) 1 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
第17条 (設立) 1 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 5 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
国民健康保険組合(以下「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】
【問8-A】 ×
認可の申請は、「15人以上」の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者 「300人以上」の同意を得て行うものとされています。
では、過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
②【R2年選択】
国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、< A >の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「都道府県知事」の認可がポイントです。厚生労働大臣の認可ではありませんので注意してください。
②【R2年選択】
A 1又は2以上の市町村
1又は2以上の「都道府県」ではありませんので、注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働一般常識)
令和4年の問題を復習しましょう(労働一般常識)
R5-071
R4.11.6 R4択一式より 年次有給休暇の取得率
「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」から、「年次有給休暇の取得率」を確認しましょう。
まず、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-E】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が大きくなるほど取得率が高くなっている。

【解答】
【問2-E】 〇
年次有給休暇の取得率は 企業規模計で56.6%です。
企業規模別にみると、1000人以上規模は60.8%、300~999人は56.3%、100~299人は55.2%、30~99人は51.2%で、規模が大きくなるほど取得率は高くなります。
過去問もどうぞ!
【H24年出題】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模でみると、1000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。

【解答】
【H24年出題】 ×
令和3年就労条件総合調査によると、企業規模計の年次有給休暇取得率は56.6%で、昭和59年以降過去最高となっています。「50%を下回っており」の部分が誤りです。
企業規模でみると、1000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高いです。
<参考>ちなみに、平成24年当時の問題は、「平成23年就労条件総合調査」からの出題で、そのときの取得率は48.1%で50%を下回っていました。
(参照:「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働一般常識)
令和4年の問題を復習しましょう(労働一般常識)
R5-070
R4.11.5 R4択一式より 特別休暇制度の有無
「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」から、「特別休暇制度の有無」を確認しましょう。
まず、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-A】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」が最も多くなっている。

【解答】
【問2-A】 〇
特別休暇制度がある企業割合は 59.9%です。
特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、「夏季休暇」42.0%、「病気休暇」23.8%、「リフレッシュ休暇」13.9%(以下省略します。)となっています。
(参照:「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」)
では、令和3年就労条件総合調査をもとに、「みなし労働時間制」の過去問も解いてみましょう。
①【H28年出題】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
②【H24年出題】(※問題文を修正しています)
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では13.1%だが、企業規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、8.2%です。10パーセントに達していません。
なお、みなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が6.7%、「専門業務型裁量労働制」が1.2%、「企画業務型裁量労働制」が0.3%です。
②【H24年出題】(※問題文を修正しています) 〇
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では13.1%です。企業規模別にみると、1000人以上規模は25.6%、300~999人は16.5%、100~299人は12.8%、30~99人は12.4%です。規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向です。
(参照:「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働一般常識)
令和4年の問題を復習しましょう(労働一般常識)
R5-069
R4.11.4 R4択一式より 変形労働時間制の採用割合
「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」から、変形労働時間制の採用割合を確認しましょう。
まず、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-B】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制を採用している企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」よりも多くなっている。

【解答】
【問2-B】 〇
変形労働時間制を採用している企業割合は 59.6%で約6割です。変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が 25.0%、「フレックスタイム制」が 6.5%となっています。「1年単位」が「1か月単位」よりも多くなっています。
(参照:「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」)
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【解答】
【H28年出題】 ×
フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.5%です。
(参照:「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-068
R4.11.3 R4択一式より 資格喪失後の出産手当金の継続給付
出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までの間、労務に服さなかった期間について支給されます。
資格喪失時に、出産手当金を受けている(又は受ける条件を満たしている)場合は、要件を満たせば退職後も継続して出産手当金を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
第104条 (傷病手当金又は出産手当金の継続給付) 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
※被保険者の資格を喪失した日まで1年以上被保険者であった者で、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けているもの(又は支給要件を満たしているもの)は、退職後も、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金の給付を受けることができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-D】
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。

【解答】
【問5-D】 ×
出産手当金の支給を受けることはできません。「その資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」という要件を満たしていないからです。
過去問をどうぞ!
【H24年出題】
被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

【解答】
【H24年出題】 ×
資格喪失後の出産手当金の継続給付は、「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」ことが条件です。問題文のような「資格喪失後6か月以内に出産」だけでは要件は満たしません。
★なお、資格喪失後6月以内に出産した場合は、要件を満たせば、『出産育児一時金』の支給が受けられます。
条文を読んでみましょう。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付) 1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。 |
最後の保険者から受けることができるのは、出産手当金ではなく、「出産育児一時金」ですので注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-067
R4.11.2 R4択一式より 介護保険料率の定め方
まず、健康保険の被保険者に関する保険料額を確認しましょう
・介護保険第2号被保険者である被保険者 → 一般保険料額と介護保険料額との合算額
・介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者 → 一般保険料額
※「一般保険料額」は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率+特定保険料率)を乗じて得た額です。
※「介護保険料額」は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額です。
(法第156条)
今日のテーマは「介護保険料率」の定め方です。
条文を読んでみましょう。
第160条第16条 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 |
介護保険第2号被保険者は、介護保険法で、40歳以上65歳未満の医療保険加入者と定義されています。介護保険第2号被保険者である健康保険の被保険者は、健康保険料といっしょに介護保険料を徴収されます。
そのため、介護保険料率は、「介護保険第2号被保険者」である被保険者の総報酬額の総額をもとに定められます。
では令和4年の問題をどうぞ!
【問4-C】
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

【解答】
【問4-C】 ×
介護保険料率は、「介護納付金」÷「当該年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額」で得た率を基準として、保険者が定めます。
分子は、前年度の実績ではなく、「当該年度」における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の「見込額」となります。
なお、「総報酬額」とは、「標準報酬月額及び標準賞与額の合計額」です。
※介護保険第2号被保険者の介護保険料の流れを確認しましょう。
介護保険第2号被保険者 |
↓介護保険料 |
健康保険 |
↓介護納付金 |
社会保険診療報酬支払基金 |
↓介護給付費交付金 |
市町村 |
介護保険第2号被保険者の介護保険料は、医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基金を通して、市町村に交付されます。
なお、介護保険第1号被保険者の保険料は、介護保険法のルールによって、市町村が徴収します。
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】※改正による修正あり
介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。

【解答】
【H29年出題】※改正による修正あり 〇
介護保険料率は、毎年度、決定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-066
R4.11.1 R4択一式より 出産手当金と傷病手当金の調整
「出産手当金」と「傷病手当金」の両方の支給要件を満たした場合、どちらの支給が優先されるでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) 1 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第2項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第99条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 2 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く。)は、出産手当金の内払とみなす。 |
出産手当金と傷病手当金の両方を受給できる期間は、出産手当金を優先し、出産手当金が支給され、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金と出産手当金は、支給を始める日が違いますので、1日あたりの支給額が異なる場合があります。その場合、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-C】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

【解答】
【問2-C】 〇
出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件を満たした期間は、出産手当金の支給が優先されます。
・出産手当金の額 > 傷病手当金の額 → その期間中の傷病手当金は支給されません
・出産手当金の額 < 傷病手当金の額 → 差額が支給されます
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。
②【H30年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
傷病手当金と出産手当金が逆です。
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、「出産手当金」の支給が優先され、その期間中は「傷病手当金」の支給は停止されます。
②【H30年出題】 ×
出産手当金と傷病手当金の両方の支給要件を満たした期間は出産手当金が優先されます。選択制ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-065
R4.10.31 R4択一式より 法人の役員に係る保険給付の特例
健康保険の保険給付は「労災保険法の規定による業務災害」以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して行われます。労災保険からの給付が受けられない場合は、健康保険の給付が受けられます。
なお、労災保険は労働者を保護するための保険ですので、法人の役員としての業務に起因する傷病等については、労災保険からは保険給付が行われません。
しかし、被保険者等が法人の役員である場合は、法人の役員としての業務に起因する負傷等は、健康保険の保険給付でも対象外となっています。
法人の役員の業務上の負傷は、使用者側の責に帰すべきものなので、労使折半の健康保険から保険給付を行うことが適当でないと考えられるからです。
(参考:H25.8.14事務連絡 全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
では、条文を読んでみましょう。
第53条の2(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例) 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。 |
 被保険者等(被扶養者も含みます)が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外となります。
被保険者等(被扶養者も含みます)が法人の役員である場合に、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については、原則として保険給付の対象外となります。
ただし例外に注意してください。「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務で厚生労働省令で定めるもの」は保険給付の対象になります。
ちなみに、厚生労働省令で定めるものは、『厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。』とされています。(則第52条の2)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-A】
被保険者の数が5人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

【解答】
【問2-A】 ×
法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して健康保険から保険給付が行われるのは、被保険者の数が「5人未満」である適用事業所に使用される場合です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
②【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
①【H26年出題】 〇
傷病手当金も保険給付の対象になるのがポイントです。
②【H30年出題】 〇
役員の業務内容が、当該法人の従業員が従事する業務と同一であると認められない場合は、健康保険の給付対象にはなりません。
(H25.8.14事務連絡 全国健康保険協会あて厚生労働省保険局保険課通知)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-064
R4.10.30 R4択一式より 徴収法「名称・所在地等変更届」
今日のテーマは、「名称・所在地等変更届」です。
保険関係が成立した場合は、保険関係が成立した日から10日以内に「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
また、事業の名称や所在地等に変更があった場合は届け出が必要です。
条文を読んでみましょう。
第4条の2第2項 保険関係が成立している事業の事業主は、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
則第5条 (変更事項の届出) 1 法第4条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 ① 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ② 事業の名称 ③ 事業の行われる場所 ④ 事業の種類 ⑤ 有期事業にあっては、事業の予定される期間 2 法第4条の2第2項の規定による届出は、1の各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。 ① 労働保険番号 ② 変更を生じた事項とその変更内容 ③ 変更の理由 ④ 変更年月日 |
★ 名称・所在地等変更届は、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-C(雇用)】
事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定される期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届け出なければならない。

【問10-C(雇用)】 〇
有期事業は、「事業の予定される期間」に変更があったときは、名称・所在地等変更届の提出が必要です。
過去問をどうぞ!
【H25年出題(労災)】
名称、所在地等変更届は、労働保険の保険関係が成立している事業の事業主が、その氏名又は名称及び住所等の事項に変更があった場合に、その変更を生じた日の当日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

【解答】
【H25年出題(労災)】 ×
名称、所在地等変更届の提出期限は、変更を生じた日の「当日」からではなく「翌日」から起算して10日以内です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-063
R4.10.29 R4択一式より 有期事業のメリット制の適用条件
労災保険率は、事業の種類ごとに定められています。しかし、事業の種類が同じでも、事業主の災害防止に対する努力によって、企業ごとの災害発生率には差が生じます。
メリット制とは、業務災害の発生が多ければ労災保険率(又は労災保険料)を引き上げる、逆に発生が少なければ労災保険率(又は労災保険料)を引き下げる制度です。
今日は、「有期事業」のメリット制の適用要件を確認します。
徴収法で、有期事業とは、「建設の事業」と「立木の伐採の事業」です。
有期事業でメリット制の適用を受ける事業の規模は以下の通りです。
有期事業のメリット制の対象になる事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が40万円以上であること。 2 建設の事業にあっては請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1,000立方メートル以上であること。 |
★1か2のいずれかに該当することが条件です。
「いずれか」がポイントです。
1 確定保険料の額が40万円以上
又は
2 建設の事業 → 請負金額が1億1千万円以上
立木の伐採の事業 → 素材の生産量が1,000立方メートル以上
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-C(労災)】
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業であって、その事業の素材の見込生産量が1000立方メートル以上のとき、労災保険のいわゆるメリット制の適用対象となるものとされている。

【解答】
【問9-C(労災)】 ×
メリット制の適用を受けるのは、「見込生産量」ではなく「生産量」が1000立方メートル以上のときです。見込ではなく確定した生産量です。
有期事業の一括の適用を受けていない立木の伐採の有期事業で、その事業の素材の生産量が1000立方メートル以上のときは、労災保険のメリット制の適用対象となります。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題(労災)】
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
②【H22年出題(労災)】
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。

【解答】
①【H28年出題(労災)】 ×
「有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度」の部分が誤りです。
継続事業と一括有期事業のメリット制は、問題文の通り、一定の範囲内で労災保険率を上げ下げする制度です。
「有期事業」の場合は、労災保険率を上下させるのではなく、「確定保険料の額」を一定の範囲で上げ下げする制度です。
②【H22年出題(労災)】 〇
有期事業のメリット制が適用されると、確定保険料の額は上げ下げされます。確定保険料の額が引き上げられた場合は、差額が徴収されます。
引き上げられた場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、引き上げられた確定保険料の額と既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収します。その場合、「納入告知書」によって、通知されるのがポイントです。
(則第35条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
R5-062
R4.10.28 R4択一式より 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
https://youtu.be/WSLec7UEQy8 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件のひとつに、「被保険者であった期間が通算して5年以上あること」があります。
この「被保険者であった期間」は、基本手当の「被保険者であった期間」と同じ取扱いです。
例えば、A社の被保険者資格喪失後に、B社に再就職し被保険者資格を取得した場合、A社とB社の被保険者であった期間を通算できるか否かは以下のように考えます。
↓
・被保険者であった期間に係る被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格を喪失した日が当該被保険者資格取得日前1年の期間内にあり、この期間内に、基本手当(基本手当の支給を受けたものとみなされる傷病手当等を含みます)又は特例一時金を受けていない場合は通算されます。
(参照:行政手引59011)
↓
A社とB社の間が1年以内で、かつ基本手当を受給しない場合は、通算されます。
・1年を超えている場合は通算できません。
・1年以内でも基本手当を受給した場合は通算できません。
令和4年の問題をどうぞ!
【問5-D】
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。

【解答】
【問5-D】 ×
基本手当の支給を受けずに1年以内(8か月)で被保険者資格を再取得していますので、被保険者であった期間は通算されます。
問題文のように、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格を喪失した後、基本手当の支給を受けずに、1年以内に被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格でも高年齢雇用継続基本給付金を受けることができます。
(行政手引59311)
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

【解答】
【R1年出題】 〇
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある場合は、60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までが対象です。
問題文のように、60歳に達した日に5年未満であったとしても、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合は、その時点で資格を満たします。その場合は、「5年に達する日の属する月」から65歳に達する日の属する月までが対象となります。「60歳に達した日の属する月」まで遡ることはありませんので、注意してください。
(行政手引59011)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-061
R4.10.27 R4択一式より 時間外労働は「実労働時間」で考える
まず、「36協定」の条文を読んでみましょう。
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下「労働時間」という。)又は前条の休日(以下「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
・36協定が必要な時間外労働・休日労働を確認しましょう
「法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)」を超えて労働させる場合
「法定休日(原則毎週少なくとも1回)」に労働させる場合
例えば、月曜日から金曜日までの所定労働時間が1日7時間、土日が休日の事業場で、金曜日の労働時間を1時間延長した場合を考えてみましょう。金曜日を1時間延長しても、1日8時間、1週間36時間です。法定労働時間内に収まっていますので、36協定は不要です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-C】
労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、1日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、労働基準法第36条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金の支払の必要はない。

【解答】
【問3-C】 〇
36協定や割増賃金が必要なのは、実労働時間が8時間を超えた場合です。遅刻した分、終業時刻を繰り下げたとしても、1日の実労働時間が8時間以内なら36協定も割増賃金も不要です。
(H11.3.31基発168号)
過去問をどうぞ!
【H29年出題】
1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、労働基準法第36条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

【解答】
【H29年出題】 〇
1日の所定労働時間が8時間で、1時間遅刻をした分、終業時刻を1時間繰り下げたとしても実働時間が8時間ですので、時間外労働にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-060
R4.10.26 R4択一式より 特別条項による時間外労働の上限
使用者は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって、時間外労働をさせることができますが、労働時間の延長には上限が定められています。
・時間外労働の上限は、原則として、月45時間、年360時間です。
・臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)の場合は、月45時間、年360時間を超えて労働させることができます。
<特別条項の条件>
・時間外労働 →年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計 → 月100 時間未満
・時間外労働と休日労働の合計 → 「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80 時間以内
・月45時間の限度時間を超えることができるのは、年6か月まで
今日のテーマは特別条項による時間外労働の上限です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-B】
小売業の事業場で経理業務のみに従事する労働者について、対象期間を令和4年1月1日から同年12月31日までの1年間とする労働基準法第36条第1項の協定をし、いわゆる特別条項により、1か月について95時間、1年について700時間の時間外労働を可能としている事業場においては、同年の1月に90時間、2月に70時間、3月に85時間、4月に75時間、5月に80時間の時間外労働をさせることができる。

【解答】
【問3-B】 ×
特別条項の条件を満たしているかチェックしましょう
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 |
時間外労働 | 90時間 | 70時間 | 85時間 | 75時間 | 80時間 | 400時間 |
・時間外労働の上限は年720時間以内
・時間外労働と休日労働の合計は月100 時間未満
・月45時間の限度時間を超えることができるのは、年6か月まで
・時間外労働と休日労働の合計が、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80 時間以内
→ 例えば、3月について、2~6か月の平均を出してみましょう。
2月~3月(2か月)の平均 → 77.5時間
1月~3月(3か月)の平均 → 81.66時間
※前年度の36協定の対象期間の時間数も入れて平均を出します。前年12月~3月(4か月)の平均、前年11月~3月(5か月)の平均、前年10月~3月(6か月)の平均もチェックが必要ですが、問題文では明らかにされていないので、今回は触れません。
チェックの結果、1月~3月の3か月の平均が80時間を超えています。そのため、特別条項の条件を満たしていません。
過去問をどうぞ!
【R2年出題】
労働基準法第36条第3項に定める「労働時間を延長して労働させることができる時間」に関する「限度時間」は、1か月について45時間及び1年について360時間(労働基準法第32条の4第1項第2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間及び1年について320時間)とされている。

【解答】
【R2年出題】 〇
時間外労働の上限は、原則として「1か月45時間、1年360時間」です。ただし、1年単位の変形労働時間制(対象期間が3か月を超える場合)により労働させる場合は、「1か月42時間、1年320時間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-059
R4.10.25 R4択一式より 教育訓練の時間は労働時間になる?ならない?
使用者が実施する「教育訓練」の時間は、労働基準法の労働時間となるのでしょうか?
まず令和4年の問題をどうぞ!
【問2-C】
労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働として取り扱うこととされている。

【解答】
【問2-C】 ×
「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば時間外労働にはならない」という考え方です。(S26.1.20基収2875号、H11.3.31基発168号)
「強制」なのか「自由参加」なのかがポイントです。問題文の場合は、「自由参加」ですので、労働時間ではなく、所定労働時間外に行われるときでも時間外労働にはなりません。
なお、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものです。そのため、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのが原則です。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間となりますので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、割増賃金の支払が必要です。
(S47.9.18基発第602号)
過去問もどうぞ!
【H26年出題】
労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについては、就業規則上の制裁等の不利益な取扱いの有無や、教育・研修の内容と業務との関連性が強く、それに参加しないことにより本人の業務に具体的な支障が生ずるか否か等の観点から、実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきものである。

【解答】
【H26年出題】 〇
労働者が使用者の実施する教育、研修に参加する時間を労働基準法上の労働時間とみるべきか否かについて、ポイントは、「実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断すべきもの」の部分です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-058
R4.10.24 R4択一式より 振替加算の額の計算
振替加算が行われるのは、大正15年4月2日~昭和41年4月1日までの間に生まれた者です。
大正15年4月1日以前生まれの者は「旧法」の対象者で老齢基礎年金が支給されませんので、振替加算も行われません。
また、昭和41年4月2日以降生まれの者にも振替加算は行われません。昭和41年4月2日以降生まれの者は、新法施行日(昭和61年4月1日)に20歳未満です。
20歳から60歳まで会社員の被扶養配偶者だったとしても、すべて第3号被保険者となり満額の老齢基礎年金が支給されるからです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-A】
老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。

【解答】
【問9-A】 ×
振替加算の額は、「受給権者の老齢基礎年金の額」ではなく、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となります。
なお、224,700円×改定率は、加給年金額と同じ額です。
「受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率」は、1.000から0.067までです。
生年月日が最も古い大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの率は、1.000ですので、振替加算の額は224,700円×改定率×1.000で加給年金額と同じです。
昭和36年4月2日から昭和41年4月1日以前生まれの率は、0.067です。
生年月日が若くなるほど、率が小さくなることがポイントです。20歳から60歳まで会社員に扶養される配偶者だった場合、若い人ほどカラ期間が短く、第3号被保険者期間が長くなるからです。
(S60年附則第14条)
過去問もどうぞ!
【H28年出題】
振替加算の額は、その受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される。

【解答】
【H28年出題】 ×
振替加算の額は、「224,700円×改定率」に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-057
R4.10.23 R4択一式より 付加年金と死亡一時金の加算額の国庫負担
今日は、付加年金と死亡一時金の加算額の国庫負担の割合を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
S60年法附則第34条第1項第1号(国民年金事業に要する費用の負担の特例) 国庫は、当分の間、毎年度、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。 |
死亡一時金の額は、保険料納付済期間と保険料免除期間の月数に応じて、12万円から32万円で、付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である場合は、8500円が加算されます。
条文の「死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)」のかっこ書きは、「同法第52条の4第1項に定める額(12万円から32万円)の給付に要する費用を除く」となります。
この部分は、「死亡一時金の給付に要する費用(付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用)」と読んでください。
令和4年の問題をどうぞ!
【問6-D】
国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

【解答】
【問6-D】 〇
「付加年金の給付に要する費用」と「付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用」の給付に要する費用については、4分の1を国庫が負担します。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は、その全額が第1号被保険者の保険料によって賄われる。
②【H26年出題】
付加年金の給付に要する費用については、その3分の1を国庫が負担する。
③【H26年出題】
付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の額の加算額の給付に要する費用については、その4分の1を国庫が負担する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
「付加年金」と「死亡一時金の加算額」に要する費用は、4分の1が国庫負担で賄われます。
②【H26年出題】 ×
付加年金の給付に要する費用については、その「4分の1」を国庫が負担します。
③【H26年出題】 〇
死亡一時金の額の加算額(付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合の加算額)の給付に要する費用については、その「4分の1」を国庫が負担します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-056
R4.10.22 R4択一式より 老齢基礎年金と付加年金
付加保険料は月額400円です。
付加保険料を納付した人には、老齢基礎年金の受給権を取得したときに、付加年金も支給されます。
付加年金は、200円×付加保険料納付済期間の月数で計算します。
条文を読んでみましょう。
第43条 (支給要件) 付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
第44条 (年金額) 付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
第47条 (支給停止) 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
第48条 (失権) 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問3-A】
付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。
②【問3-E】
老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

【解答】
①【問3-A】 〇
付加年金は老齢基礎年金とセットになる年金です。老齢基礎年金と老齢厚生年金を併給する場合は、付加年金も支給されます。
②【問3-E】 〇
障害基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金は支給停止されます。老齢基礎年金が全額支給停止されている間は付加年金も支給停止されます。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
②【H26年出題】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を併給するときには、付加年金は支給停止される。
③【H21年出題】
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

【解答】
①【H25年出題】 〇
付加年金は老齢基礎年金とセットです。付加年金の受給権は、老齢基礎年金と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅します。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止されます。
②【H26年出題】 ×
老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給する場合も、老齢基礎年金が支給されているなら、付加年金も支給されます。
③【H21年出題】 ×
遺族基礎年金を選択した場合は、老齢基礎年金が支給停止されます。老齢基礎年金がその全額につき支給停止されているときは、その間、付加年金も支給停止になります。「遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。」の部分が誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-055
R4.10.21 R4択一式より 国民年金原簿の訂正の請求
もし、国の年金記録が事実と異なっているなら、正確な年金額が算定できません。年金記録が事実と異なると思われる場合は、国に年金記録の訂正を請求することができます。
条文を読んでみましょう。
第14条(国民年金原簿) 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。 |
第14条の2(訂正の請求) 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 |
附則第7条の5 (国民年金原簿の特例等) 第14条及び第14条の2の規定の適用については、当分の間、被保険者とあるのは、「第2号被保険者のうち第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるものを除く。」とする。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問1-B】
厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。

【解答】
【問1-B】 〇
第14条の2の厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求については、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者であった期間は、除かれます。
過去問をどうぞ!
【R2年出題】
国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

【解答】
【R2年出題】 〇
第2号被保険者のうち、国民年金原簿の記録の対象となる被保険者は、当分の間、第1号厚生年金被保険者のみです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-054
R4.10.20 R4択一式より 70歳以上の使用される者の老齢厚生年金の調整
厚生年金保険の当然被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の者です。
厚生年金保険の被保険者資格は70歳に達したときに喪失します。そのため、70歳以上の者は、在職中でも厚生年金保険の保険料は徴収されません。
しかし、在職老齢年金の仕組みは、70歳以上の者にも適用されます。
厚生年金保険の被保険者の場合は、総報酬月額相当額は、「標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」となります。一方、70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではありませんので、総報酬月額相当額は、「その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の1年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額」となります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-B】
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。

【解答】
【問8-B】 ×
適用事業所に使用される70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者ではなく、保険料も徴収されませんが、在職老齢年金の仕組みは適用されます。
(法第46条)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】※改正による修正あり
老齢厚生年金を受給している被保険者であって適用事業所に使用される者が70歳に到達したときは、その日に被保険者の資格を喪失し、当該喪失日が属する月以後の保険料を納めることはないが、一定の要件に該当する場合は、老齢厚生年金の一部又は全部が支給停止される。
②【H28年出題】
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

【解答】
①【H23年出題】 〇 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳以上の者には、在職老齢年金の仕組みが適用されます。
②【H28年出題】 ×
当初は、70歳以上の者のうち昭和12年4月1日以前生まれの者には、在職老齢年金の仕組みは適用されていませんでした。
しかし、平成27年10月1日の改正により、昭和12年4月1日以前生まれの70歳以上の者にも、在職老齢年金の仕組みが適用されることになりました。
昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることがあります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-053
R4.10.19 R4択一式より 厚生年金保険・擬制的任意適用事業所
強制適用事業所が、従業員の減少などで強制適用事業所の要件を欠いた場合は、任意適用事業所の認可を受けたものとみなされます。このことを擬制適用といいます。
擬制適用によって、その事業所で働く従業員は引き続き社会保険の適用を受けることができます。
条文を読んでみましょう。
第7条 強制適用事業所が、強制適用の要件に該当しなくなったときは、その事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなす。 |
例えば、個人の事業所の従業員の数が5人未満になった、法人の事業所が個人の事業所になった場合など、強制適用事業所の要件に該当しなくなる場合があります。
その場合は、「認可があったものとみなす」扱いとなります。改めて適用事業所となるための認可の申請手続きをとらなくても、引き続き厚生年金保険の適用事業所のままです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-D】
厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。

【解答】
【問7-D】 ×
認可があったものとみなされますので、任意適用の申請をしなくても、引き続き適用事業所となります。
過去問をどうぞ!
【R1年出題】
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

【解答】
【R1年出題】 ×
任意適用事業所の認可申請を行わなくても、適用事業所として継続します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-052
R4.10.18 R4択一式より 遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の年齢要件
今日は、遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の年齢要件を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第59条 (遺族厚生年金の遺族) 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 |
第62条 (中高齢寡婦加算) 遺族厚生年金(長期要件に該当することにより支給されるものであって、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であるものを除く。)の受給権者である妻であってその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったもの又は40歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であった者の子で遺族基礎年金の遺族の要件に該当するものと生計を同じくしていたものが65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算する。 |
ポイント!
★遺族厚生年金の遺族の要件
妻には年齢要件・障害要件はありません。
夫、父母、祖父母には年齢要件、子、孫には年齢要件・障害要件があります。
★中高齢寡婦加算の妻の要件
対象は妻のみです。
・遺族厚生年金の受給権取得当時、生計を同じくする子がいない場合(遺族基礎年金が支給されない場合) → 夫の死亡当時、妻の年齢が40歳以上65歳未満であること
・遺族厚生年金の受給権取得当時、生計を同じくする子がいる場合(遺族基礎年金が支給される場合) → 妻が40歳に達した当時遺族基礎年金を受けていること
※中高齢寡婦加算が加算されるのは、65歳に達するまでです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-C】
被保険者であった45歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

【解答】
【問10-C】 ×
・夫の死亡当時、子のいない38歳の妻
→ 「遺族厚生年金」は受けることができます。中高齢寡婦加算は、子がいない場合は夫の死亡当時40歳以上であることが要件ですので、中高齢寡婦加算は支給されません。
・妻の死亡した当時、子のいない38歳の夫
→ 夫は妻の死亡当時55歳以上であることが要件ですので、遺族厚生年金を受けることはできません。なお、子の有無は関係ありません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
②【H27年出題】
子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
21歳の子も54歳の夫も年齢要件を満たしませんので、遺族厚生年金を受けることはできません。
②【H27年出題】 〇
子のない妻は、夫の死亡当時に40歳以上65歳未満であることが条件です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-051
R4.10.17 R4択一式より 任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者は健康保険の保険料を納付する義務があります。
今日は、任意継続被保険者の保険料をみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第157条 (任意継続被保険者の保険料) 任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
第161条 (保険料の負担及び納付義務) 1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第164条 (保険料の納付) 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
|
例えば、健康保険の被保険者が10月17日に退職した場合、その翌日に資格を喪失します。資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であって、資格を喪失した日から20日以内に保険者に申出をした場合、10月18日に任意継続被保険者の資格を取得します。
その場合、任意継続被保険者の保険料は、10月から算定されます。初めて納付すべき保険料(10月分)の納期限は、保険者が指定する日です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問2-D】
任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

【解答】
【問2-D】 〇
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定されます。
例えば10月17日に退職した場合は、在職中の保険料は資格喪失月の前月の9月分まで徴収され、任意継続被保険者としての保険料は10月分からとなります。
過去問をどうぞ!
【H30年出題】
一般の被保険者に関する保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

【解答】
【H30年出題】 ×
任意継続被保険者に関する保険料について、初めて納付すべき保険料については、「保険者が指定した日」までに納付しなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-050
R4.10.16 R4択一式より 確定保険料の認定決定と追徴金
「確定保険料申告書」を提出しなかったとき、申告書の記載に誤りがあるときは、政府が職権で確定保険料の額を決定(認定決定)し、事業主に通知することになっています。その際、追徴金が課されます。
では、条文を読んでみましょう。
第19条第4項、第5項 4 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 5 認定決定の通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の認定決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の認定決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
第21条 (追徴金) 1 政府は、事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。 2 認定決定された確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。 |
ポイント!
確定保険料の認定決定は、「事業主が確定保険料申告書を提出しないとき」、又は「その申告書の記載に誤りがあると認めるとき」に行われます。
なお、政府が認定決定した確定保険料の額について事業主に通知する場合は、「納入告知書」によって行います。
では、令和4年の問題をどうぞ
【問8-D(労災)】
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。

【解答】
【問8-D(労災)】 〇
「天災その他やむを得ない理由により、認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合」には、追徴金は徴収されません。
「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、火災、洪水、暴風雨等不可抗力的なできごと及びこれに類する真にやむを得ない客観的な事故をいい、法令の不知、営業の不振、資金難等は含まれない」(昭56.9.25労徴発68号)とされています。
問題文は、法令の不知によるものですので、追徴金が徴収されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題(労災)】
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。
②【H26年出題(雇用)】
事業主が、提出した確定保険料申告書に記載の誤りがあり、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、納付した概算保険料の額が、当該通知を受けた額に足りないときは、その不足額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。ただし、法令の不知、営業の不振等やむを得ない理由による場合は、追徴金を徴収しないこととされている。

【解答】
①【R1年出題(労災)】 ×
認定決定された確定保険料は、「通知を受けた日から15日以内」に納付しなければなりません。なお、起算日は翌日です。「通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」に納付しなければなりません。
②【H26年出題(雇用)】 ×
「天災その他やむを得ない理由」の場合は追徴金は徴収されませんが、「法令の不知、営業の不振等」はそれに含まれません。そのため、「法令の不知、営業の不振等」の理由の場合は、追徴金が徴収されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
R5-049
R4.10.15 R4択一式より 高年齢再就職給付金と再就職手当の調整
まず、「高年齢再就職給付金」の要件を条文で読んでみましょう。
第61条の2第1項 (高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となった場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至ったときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 当該職業に就いた日の前日における支給残日数が、100日未満であるとき。 2 当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。 |
高年齢再就職給付金の要件のポイント!
・受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること
・60歳到達時以後に安定した職業に就くことにより被保険者となったこと
・就職日の前日の支給残日数が100日以上あること
では、「高年齢再就職給付金」が支給される具体例を確認しましょう。
① 60歳到達時に離職した者が基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった
② 60歳到達時に一般被保険者であった者がその後に離職し、基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった
③ 60歳到達時に被保険者でなかった者であっても、その直前の被保険者資格に基づき基本手当の支給を受け、かつ、60歳到達時以後、当該基本手当の受給期間内に支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者となった
(行政手引59021(1))
★高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、再就職手当の支給を受けることができる場合の調整を、条文で読んでみましょう。
第61条の2第4項 (高年齢再就職給付金) 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。 |
「再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない。」となっていますので、どちらの給付を受けるかは本人の選択となります。
(行政手引59051(1))
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-C】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

【解答】
【問5-C】 ×
「その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され」の部分が誤りです。どちらを受けるかは本人の選択です。本人の選択で、高年齢再就職給付金を受けたときは、再就職手当は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。

【解答】
【R1年出題】 〇
「雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当」とは、再就職手当のことです。本人の選択で再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-048
R4.10.14 R4択一式より 労災保険「再発」とは
労災保険法の保険給付は、「治っていない」か「治った」がポイントです。
例えば、仕事中にケガをし、療養を受けている間は、「療養補償給付」が支給されます。ケガが治ったとき(治ゆしたとき)は療養補償給付は終了します。治った後に一定の障害が残った場合は、障害補償給付が支給されます。
そして、その後再発した場合は、療養補償給付が再度受けられるようになります。
今日のテーマは「再発」の認定要件です。
まず、「治った」とはどういう状態なのでしょうか?
・労災保険で傷病が「治った」ときとは、身体の諸器官・組織が完全に回復した状態のみをいうものではありません。傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
この状態を「治ゆ」(症状固定)といいます。
では、次に「再発」の要件を令和4年の問題でみてみましょう。
【問-7】
業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次のアからエの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること
イ 当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3年以内であること
ウ 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること
エ 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること
A (アとイ)
B (アとエ)
C (アとイとエ)
D (アとウとエ)
E (アとイとウとエ)

【解答】
【問-7】 D (アとウとエ)
再発として再び療養(補償)等給付を受けることができる要件は次の3つを満たした場合です。
①その症状の悪化が、当初の業務又は通勤による傷病と相当因果関係があると認められること
②症状固定の時からみて、明らかに症状が悪化していること
③療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること
問題文では、アとウとエの3つの要件を満たすことが条件となります。
(参考:厚生労働省パンフレット「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
それでは、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
②【H28年出題】
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態は「治ゆ」(症状固定)となります。「医療効果が期待できなくなった状態」とは、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態です。
治ゆ後は、療養の給付は行われません。
(参考:厚生労働省パンフレット「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
②【H28年出題】 ×
傷病が一旦症状固定と認められた後に再び発症し、「再発」の要件を満たした場合は、再び療養補償給付が支給されます。
(参考:厚生労働省パンフレット「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-047
R4.10.13 R4択一式より 労使協定の効力の発生
「1か月単位の変形労働時間制」を導入する際は、「労使協定を締結する」、「就業規則その他これに準ずるものに定める」のどちらかが必要です。
労使協定の締結によって1か月単位の変形労働時間制を採用する場合は、労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
今日のテーマは、「労使協定の効力の発生」です。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の2(1か月単位の変形労働時間制) ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法第32条第1項の労働時間(法定労働時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。 |
第32条の2第2項により、1か月単位の変形労働時間制の労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
例えば、労使協定で1日10時間と定めた日には10時間まで労働させることができますし、1週52時間と定めた週には52時間まで労働させることができます。
この「労使協定」は、届出によって効力が発生するのでしょうか?それとも締結していれば効力が発生するのでしょうか?
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-B】
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。

【解答】
【問7-B】 ×
1か月単位の変形労働時間制についての労使協定については、「届出」が効力の発生要件となっていません。労使協定が締結されていれば、効力が発生します。
労使協定を届出なくても効力は発生します。しかし、届け出なかった使用者については罰則が適用され、30万円以下の罰金に処せられます。
(参考)労使協定はどのような効力をもつのでしょうか?
労働基準法の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという「免罰効果」をもちます。
労働者の民事上の義務は、当該協定から直接生じるものではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要です。
(S63.1.1基発1号)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
②【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」又は「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)の締結」のどちらかで採用することができます。
就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでも採用することができます。
また、労使協定の締結によって採用する場合は届出が必要ですが、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって」効力が発生するのではなく、締結することによって労使協定の効力が発生します。
②【H24年出題】 〇
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて発生します。単に同協定を締結したのみでは、効力は発生しませんので注意してください。
第36条の条文を確認しておきましょう。
| 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、労働時間又は休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 |
「行政官庁に届け出た場合」に注目してください。36協定については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出て、初めて免罰効果が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-046
R4.10.12 R4択一式より 労働時間の特例
法定労働時間は、1週40時間、1日8時間が原則です。
ただし、一部の業種については、法定労働時間の特例措置が適用されます。
今日は、法定労働時間の特例をみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第40条 (労働時間及び休憩の特例) ① 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 ② ①の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 |
では、第40条の特例措置のうち、則第25条の2第1項の「法定労働時間の特例」を読んでみましょう。
則第25条の2 使用者は、法別表第1第8号、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。 |
<法定労働時間の特例>
・1週間44時間、1日8時間
・対象の業種
常時10人未満の労働者を使用する
第8号 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
第10号 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 (映画の製作の事業を除く。)
第13号 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
第14号 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-A】
使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。

【解答】
【問7-A】 ×
特例により、1週間については44時間まで、1日については8時間までです。
では、過去問もどうぞ!
【H18年出題】
使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。

【解答】
【H18年出題】 〇
「物品の販売の事業」は第8号に該当しますので、常時10人未満の労働者を使用するものは、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。
ちなみに、第8号は商業、第10条は映画演劇業、第13号は保健衛生業、第14号は接客娯楽業と略称で書かれることが多いです。
問題文の「物品の販売の事業」が第8号商業とつながるようにおさえておきましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-045
R4.10.11 R4択一式より 労基法第16条賠償予定の禁止
今日のテーマは、労働基準法第16条の賠償予定の禁止です。
では、第16条を読んでみましょう。
第16条 (賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 |
使用者が労働契約の不履行について違約金を定める、又は損害賠償額を予定する契約をした場合は、第16条違反として、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-C】
労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。

【解答】
【問5-C】 ×
第16条で禁止されているのは、「労働契約の不履行について違約金を定めること」、「損害賠償額を予定する契約をすること」です。違反が成立するのは、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときではなく、そのような契約をしたときです。
では、過去問もどうぞ!
①【H25年出題】
労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。
②【H30年出題】
債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることは、労働の強制や労働者の自由意思を不当に拘束することにつながるため、禁止されています。
②【H30年出題】 ×
第16条で禁止しているのは「金額を予定すること」です。現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではありません。
(S22.9.13発基第17号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-044
R4.10.10 R4択一式より 在職老齢年金「総報酬月額相当額」
在職老齢年金の計算には、「基本月額」と「総報酬月額相当額」が使われます。
今日は、「総報酬月額相当額」の計算方法がテーマです。
では、総報酬月額相当額の定義を確認しましょう。
「総報酬月額相当額」とは → 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額 です。
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。

【解答】
【問8-A】 ×
総報酬月額相当額には「その月の標準報酬月額」と「その月以前1年間の標準賞与額の合計」を使いますので、標準報酬月額や標準賞与額が変われば、総報酬月額相当額も変わります。
では、過去問もどうぞ!
【H27年出題】
在職老齢年金を受給する者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月の翌月から、新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、年金額が改定される。

【解答】
【H27年出題】 ×
「改定が行われた月の翌月から」が誤りです。
総報酬月額相当額が変わった月から支給停止額が再計算されます。
総報酬月額相当額が改定された場合は、「改定が行われた月」から、新たな総報酬月額相当額に基づいて年金額が改定されます。
(法第46条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(厚生年金保険法)
R5-043
R4.10.9 R4択一式より 障害手当金が支給されない場合
障害手当金は「一時金」として支給される保険給付です。
今日のテーマは、支給要件に該当しても、障害手当金が支給されない場合です。
では、条文を読んでみましょう。
第56条 障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、障害手当金を支給しない。 1 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。) 2 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。) 3 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者 |

厚生年金保険・国民年金の「年金」の受給権者には障害手当金は支給されません。
年金は、「障害」に限定されず、「老齢」、「障害」、「遺族」が対象です。
<例外> 障害厚生年金(障害基礎年金)の受給権者でも、3級に該当しなくなった日から起算して3年を経過した受給権者(現に障害状態に該当しない場合)には、障害手当金が支給されます。

同じ傷病で労災保険から障害補償給付、複数事業労働者障害給付、障害給付を受ける権利を有する者には障害手当金は支給されません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問3-D】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。

【解答】
【問3-D】 〇
「年金たる保険給付の受給権者(国民年金の場合は「年金たる給付」)」には、原則として障害手当金は支給されません。
「年金たる保険給付」には遺族厚生年金も含まれます。障害手当金の障害の程度を定めるべき日に遺族厚生年金の受給権者である場合は、障害手当金は支給されません。
では、過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合には、その者には障害手当金が支給されない。
②【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「同一の傷病」により労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されません。「同一の傷病」がポイントです。
②【R3年出題】 ×
同一の傷病により、障害手当金の受給権と労災保険法の障害補償給付の受給権を取得した場合、両方の保険給付が支給されるのではなく、障害手当金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-042
R4.10.8 R4択一式より 障害認定日の定義
障害基礎年金は、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件の3つの要件を満たした場合、障害認定日に受給権が発生します。
今日のテーマは障害認定日の定義です。
では、条文を読んでみましょう。
第30条 (支給要件) ① 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者であること。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 ② 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
★障害基礎年金は、障害認定日に障害等級(1級及び2級)に該当する場合に支給されます。
障害認定日は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)」となります。
※ちなみに「初診日」は、「傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」です。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-C】
障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。

【解答】
【問10-C】 〇
障害認定日は、
・傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
・傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)
のどちらか早い方です。
障害認定日は遅くても「初診日から起算して1年6か月を経過した日」となります。
では、過去問もどうぞ!
①【H24年出題】
初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
②【H27年出題】
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

【解答】
①【H24年出題】 ×
「その期間後に傷病が治った」の部分が誤りです。
「初診日から起算して、1年6か月を経過した日」又はその「期間内」に傷病が治った場合は、その治った日が障害認定日となります。
②【H27年出題】 〇
「症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日」も傷病が治った日として取り扱われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-041
R4.10.7 R4択一式より 第2号被保険者の20歳未満と60歳以上の取扱い
厚生年金保険の被保険者は、国民年金では第2号被保険者として位置づけられています。
第1号被保険者と第3号被保険者には「20歳以上60歳未満」の年齢要件がありますが、第2号被保険者にはその要件が無いのがポイントです。
今日のテーマは第2号被保険者の20歳未満と60歳以上の部分の扱いです。
では、条文で第2号被保険者の定義を読んでみましょう。
第7条・附則第3条 厚生年金保険の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)は国民年金の第2号被保険者とする。 |
 第2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、厚生年金保険の被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の第2号被保険者となります。
第2号被保険者には、20歳以上60歳未満の年齢要件がありません。そのため、厚生年金保険の被保険者は20歳未満でも60歳以上でも国民年金の第2号被保険者となります。
ただし、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢基礎年金・老齢厚生年金など「老齢又は退職を支給事由とする年金」の受給権がある場合は、第2号被保険者から除かれます。
では、次に「老齢基礎年金」の保険料納付済期間の定義を条文で読んでみましょう。
昭和60年改正法附則第8条第4項 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間に算入せず、合算対象期間に算入する。
|
 老齢基礎年金の年金額の計算は、第1号被保険者の年齢に合わせて20歳以上60歳未満の40年間が基本になります。
老齢基礎年金の年金額の計算は、第1号被保険者の年齢に合わせて20歳以上60歳未満の40年間が基本になります。
そのため厚生年金保険の被保険者の20歳未満60歳以上の期間は合算対象期間として取り扱われ、保険料納付済期間には算入されません。
※ただし、老齢厚生年金の計算には算入されます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間とされ、老齢基礎年金の額に反映される。

【解答】
【問8-A】 ×
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者ですが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」とされますので、老齢基礎年金の額には反映されません。
では、こちらもどうぞ!
【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
【H24年出題】 ×
障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も保険料納付済期間となります。
フルペンション減額方式をとっている老齢基礎年金は20歳から60歳までの40年が基本になっていますが、障害基礎年金は、フルペンション減額方式をとっていないためです。
なお、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-040
R4.10.6 R4択一式より 遺族基礎年金18歳年度末までに障害状態になったとき
遺族基礎年金の対象になる子の要件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと」です。
遺族基礎年金の受給権を取得した当時は障害状態になかった子が、18歳年度末までに障害状態になった場合、その子の遺族基礎年金の受給権は18歳年度末で消滅するのでしょうか?それとも20歳まで受給できるのでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第40条第3項 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 2 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 3 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 4 20歳に達したとき。 |
今日は「2」の「ただし以下」に注目してください。
子の遺族基礎年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。ただし、「障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。」とありますので、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態」にあるときは、その時点では失権しません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-A】
子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。

【解答】
【問6-A】 〇
遺族基礎年金の受給権取得時には障害の状態になかった子が、その後18歳年度末までの間に障害の状態となり引き続き障害の状態にある場合は、18歳年度末時点では失権しません。
先ほど読んだ条文では、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態」あるときは失権しない、となっていました。受給権取得当時に障害状態になくても、18歳年度末に障害状態にある場合は、引き続き遺族基礎年金を受給できます。
問題文のように、「子が20歳に達するまでの間障害の状態にあった」ときは、20歳になったときに失権します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 第54回社会保険労務士試験合格発表の日に
第54回社会保険労務士試験合格発表の日に
R5-039
R4.10.5 合格発表の日に皆様へ
今日は、第54回社会保険労務士試験の合格発表でした。
まず、合格された方。
 おめでとうございます!
おめでとうございます!
コロナ禍で何かと変化が大きい時期に、コツコツ勉強を重ねて、
晴れて合格通知を手にされたこと。本当に素晴らしいです。
私のホームページもYouTubeもkindleも「毎日コツコツ」がテーマです。
「毎日コツコツで合格しました」というメッセージも頂きました。
本当にありがとうございました。
今回は残念だった方。
「継続は力なり」です。
毎日コツコツ勉強を重ねて、毎日合格に近づいていきましょう。
皆さまが合格するまで私も毎日コツコツ更新していきます。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民年金法)
R5-038
R4.10.5 R4択一式より『障害基礎年金に加算される加算額』
障害基礎年金の受給権者に子がいる場合は、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。
今日のテーマは、障害基礎年金に加算される加算額です。
では、条文を読んでみましょう。
第33条の2 ① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ 224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、その額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |

障害基礎年金の加算の対象は「子」です。
配偶者については、1・2級の障害厚生年金の加給年金額の対象になります。

受給権を取得した当時に生計維持している子はもちろん加算額の対象ですが、受給権を取得した日後に有するに至った子も加算額の対象になります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。

【解答】
【問5-B】 ×
配偶者は、障害基礎年金の加算額の対象ではありません。
それでは過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
②【H21年出題】
障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の要件に該当する子があるときは、子の数が何人であっても、1人につき同額の加算額が加算される。

【解答】
①【H25年出題】 ×
障害基礎年金の受給権者が受給権を取得した後に一定の要件に該当する子を有することとなった場合でも、その子を対象とした加算額が加算されます。その場合、子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金に子の加算額が加算されます。
②【H21年出題】 ×
障害基礎年金に加算される子の加算額は、1人目2人目はそれぞれ224,700円×改定率、3人目以降はそれぞれ74,900円×改定率となります。
例えば、子が1人なら224,700円×改定率、子が2人なら224,700円×改定率×2、子が3人なら224,700円×改定率×2+74,900円×改定率となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-037
R4.10.4 R4択一式より『健康保険法・審査請求と訴訟との関係』
今日のテーマは、健康保険法・審査請求と訴訟との関係です。
では、条文を読んでみましょう。
第189条 (審査請求及び再審査請求) ① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ④ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第192条 (審査請求と訴訟との関係) 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
第190条 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
 今日は、「審査請求と訴訟との関係」に注目します。
今日は、「審査請求と訴訟との関係」に注目します。
・第189条について
「被保険者の資格」、「標準報酬」、「保険給付」に関する処分に不服がある場合は→社会保険審査官に審査請求→社会保険審査会に再審査請求という流れになっています。
・第192条について
「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」となっていて、審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合は、再審査請求をしないで、「処分の取り消しの訴え」を提起することができます。
・ちなみに第190条について
「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。」とされています。こちらは、社会保険審査会に審査請求をしないで、直接、処分の取り消しの訴えを提起することができます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問7-C】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

【解答】
【問7-C】 ×
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての「審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後」でなければ、提起することができません。
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定の後は、「社会保険審査会に再審査請求」をすることもできますが、再審査請求せずに、処分の取消しの訴えを提起することもできます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(健康保険法)
R5-036
R4.10.3 R4択一式より『健康保険と介護保険の関係』
同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定による給付を受けることができるときは、健康保険の給付は行われません。
今日は、健康保険と介護保険の調整を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第55条第3項 被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 |
「介護保険法」の給付が優先されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
②【H22年出題】
被保険者に係る療養の給付または入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費もしくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病、負傷または死亡について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
同一の傷病について、介護保険法の給付を受けることができる場合には、介護保険が優先し、健康保険の療養の給付は行われません。
②【H22年出題】 ×
問題文の「同一の疾病、負傷または死亡」に注目してください。介護保険法には、「死亡」に関する給付がありませんので、死亡については健康保険との調整は行われません。
では令和4年の問題をどうぞ!
【問1-D】
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る療養については、医療保険から行うものとされている。

【解答】
【問1-D】 〇
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合については、当該患者を医療保険適用病床に転床させて療養を行うことが原則です。
しかし、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により,患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為を行う必要のあることが想定され、このような場合については,当該病床において療養の給付又は医療が行われることは可能であり、この場合の当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものであること、とされています。
(平成18年4月28日 老老発第0428001号・保医発第0428001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(社会保険労務士法)
令和4年の問題を復習しましょう(社会保険労務士法)
R5-035
R4.10.2 R4択一式より『補佐人制度』
社会保険労務士は、労働や社会保険に関する事項について、裁判所で、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができます。
令和4年の問題から、補佐人制度を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第2条の2 ① 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 ② 陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第25条の9の2 社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。 |
では、過去問からどうぞ!
①【R1年出題】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
②【H28年出題】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
③【H30年出題】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちからその補佐人を選任しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく、「弁護士である訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができます。
②【H28年出題】 ×
補佐人として、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができるのは、特定社会保険労務士に限られません。
③【H30年出題】 ×
社会保険労務士法人は、裁判所において補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述する事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができます。
この場合、当該社会保険労務士法人は、「委託者に」、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければなりません。
『「当該社会保険労務士法人」がその社員のうちからその補佐人を選任しなければならない。』が誤りです。
令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

【解答】
【問5-A】 〇
社会保険労務士が補佐人として行った陳述は、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取リ消し、又は更生しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
令和4年の問題を復習しましょう(徴収法)
R5-034
R4.10.1 R4択一式より『一括有期事業報告書の提出』
一括有期事業については、確定保険料申告書を提出する際に、「一括有期事業報告書」を提出しなければなりません。
一括有期事業報告書は、請負金額から賃金総額を算定するためのもので、前年4月から当年3月31日までに終了した事業の具体的実施内容を記載します。
今日のテーマは一括有期事業報告書です。
条文を読んでみましょう。
則第34条 (一括有期事業についての報告) 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1 日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、所定の事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 |
★ 確定保険料申告書と同時に提出します。提出期限・提出先は確定保険料申告書と同じです。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題(労災)】
2以上の有期事業が労働保険徴収法による有期事業の一括の対象になると、それらの事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法が適用され、原則としてその全体が継続事業として取り扱われることになる。
②【H23年出題(雇用)】
一括有期事業報告書は、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの一括された事業の明細を報告するものであり、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①【H30年出題(労災)】 〇
労働保険料の申告、納付については一般の継続事業と同じように年度更新の手続きがとられます。
(昭40.7.31基発901号)
②【H23年出題(雇用)】 〇
一括有期事業報告書は、確定保険料申告書の提出に加え、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するものです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-C(労災)】
二以上の有期事業が一括されて一の事業として労働保険徴収法の規定が適用される事業の事業主は、確定保険料申告書を提出する際に、前年度中又は保険関係が消滅した日までに終了又は廃止したそれぞれの事業の明細を記した一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
【問8-C(労災)】 〇
なお、提出期限は、「次の保険年度の6月1 日から起算して40日以内」又は「保険関係が消滅した日から起算して50日以内」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(雇用保険法)
R5-033
R4.9.30 R4択一式より『高年齢雇用継続給付の支給対象月の定義』
今日は、高年齢雇用継続給付の「支給対象月」の定義を確認しましょう。
高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金は、支給対象期間の暦月単位で計算されます。支給対象月とは支給対象期間の暦月のことです。
では、支給対象月の要件を読んでみましょう。
第61条第2項 (高年齢雇用継続基本給付金) 「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。
第61条の2第2項 (高年齢再就職給付金) 「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して2年(当該就職日の前日における支給残日数が200日未満である被保険者については、1年)を経過する日の属する月(その月が被保険者が65歳に達する日の属する月後であるときは、65歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。 |
高年齢雇用継続基本給付金の「支給対象月」を図でイメージしましょう。
60歳に 達した日 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65歳に達した日 |
支給対象月は、60歳に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月までの期間内にある月です。なお、65歳に達した日の属する月は、一般被保険者から高年齢被保険者に切り替わります。
★今日のポイント★
「支給対象月」の要件は、「初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること」、「初日から末日までの全期間にわたって育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となっていないこと」です。
他にも要件がありますが、今日は省略します。
では、過去問からどうぞ!
①【R1年出題】
再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。
②【H27年出題】
高年齢雇用継続給付を受けていた者が、暦月の途中で、離職により被保険者資格を喪失し、1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象とならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
支給対象月は、「その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者である」ことが条件です。月の途中で再就職した場合は、要件を満たしませんので、その月の高年齢再就職給付金は支給されません。
②【H27年出題】 〇
①の問題と同じです。月の途中で、離職し1日以上の被保険者期間の空白が生じた場合は、その月は高年齢雇用継続給付の支給対象となりません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問5-B】
支給対象期間の暦月の初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した場合、他の要件を満たす限り当該月に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができる。

【解答】
【問5-B】 ×
初日から末日までの間に引き続いて介護休業給付の支給対象となる休業を取得した月は、高年齢雇用継続基本給付金を受けることはできません。
なお、月の一部が介護休業給付の支給対象となる場合は、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。
(行政手引59013)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-032
R4.9.29 R4択一式より『業務の性質を有するものは通勤から除かれる』
今日のテーマは、「業務の性質を有するもの」です。「業務の性質を有するもの」は「通勤」の定義から除かれます。
では、通勤の定義を条文で読んでみましょう。
法第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
「業務の性質を有するものを除く」の部分に注目してください。
「業務の性質を有するもの」は通勤ではなく、業務災害となります。
会社の通勤専用バスの利用に起因する事故、突発的事故等による緊急用務のため、休日に呼び出しを受け、緊急に出勤する途上の事故などは通勤ではなく、業務上となります。
今日は、「出張中」の災害の扱いを確認しましょう。
では、過去問からどうぞ!
①【H25年出題】
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。
②【H26年出題】
明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指揮監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
「出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱うこと。」とされています。
(H18.3.31基労管発第0331001号/基労補発第0331003号/)
②【H26年出題】 ×
出張については、一般的に、その過程全般が業務行為と認められます。
問題文のように、出張のため、自宅から自転車で駅に向かう途中の事故は、通勤ではなく、業務上とされます。
(S34.7.15基収第2980号)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-A】
労働者が上司から直ちに2泊3日の出張を命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。

【解答】
【問6-A】 ×
通勤災害ではなく業務災害となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働安全衛生法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働安全衛生法)
R5-031
R4.9.28 R4択一式より『重層的な請負関係の事業場の安全衛生管理体制』
今日のテーマは重層的な請負関係の事業場の安全衛生管理体制です。
さっそく令和4年の問題をどうぞ!
【問8】
下記に示す事業者が一の場所において行う建設業の事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この場所では甲社の労働者及び下記乙①社から丙②社までの4社の労働者が作業を行っており、作業が同一の場所において行われることによって生じる労働災害を防止する必要がある。
甲社 鉄骨造のビル建設工事の仕事を行う元方事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時5人
乙①社 甲社から鉄骨組立工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時10人
乙②社 甲社から壁面工事一式を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時10人
丙①社 乙①社から鉄骨組立作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時14人
丙②社 乙②社から壁材取付作業を請け負っている事業者
当該場所において作業を行う労働者数 常時14人
A 甲社は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
B 甲社は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
C 甲社は、当該建設工事の請負契約を締結している事業場に、当該建設工事における安全衛生の技術的事項に関する管理を行わせるため店社安全衛生管理者を選任しなければならない。
D 甲社は、労働災害を防止するために協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には自社が請負契約を交わした乙①社及び乙②社のみならず丙①社及び丙②社も参加する組織としなければならない。
E 甲社は、丙②社の労働者のみが使用するために丙②社が設置している足場であっても、その設置について労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

【解答】
| 甲社 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
乙①社 | 乙②社 | ||
|
|
|
|
丙①社 | 丙②社 | ||
甲社は元方事業者で、かつ、建設業ですので特定元方事業者となります。
A 〇
一の場所で作業を行う労働者数が、元方事業者の労働者5人+関係請負人の労働者48人の合計53人です。
原則として、労働者数が常時50人以上の場合は、特定元方事業者は統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
(法第15条、施行令第7条)
B 〇
統括安全衛生責任者を選任した事業場で建設業の場合は、元方安全衛生管理者を選任しなければなりません。
※元方安全衛生管理者の選任が必要なのは建設業のみです。造船業の場合は選任義務はありませんので注意してください。
(法第15条の2)
C ×
統括安全衛生責任者の選任が義務づけられている規模の事業場ですので、店社安全衛生管理者の選任義務はありません。
(法第15条の3)
D 〇
特定元方事業者の甲社には、協議組織の設置及び運営を行うことが義務づけられています。
「特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織」であることが条件となっていますので、自社が請負契約を交わした乙①社及び乙②社のみならず丙①社及び丙②社も参加する組織でなければなりません。
(則第635条)
E 〇
法第29条第1項で「元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。」と規定されています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
令和4年の問題を復習しましょう(労働基準法)
R5-030
R4.9.27 R4択一式より『健康診断の実施時間は労働時間になる?ならない?』
労働安全衛生法では、健康管理のため事業者に健康診断の実施が義務づけられています。
労働安全衛生法の健康診断は、一般的な健康の確保を図るための「一般健康診断」と、特定の有害業務に従事する労働者が対象になる「特殊健康診断」の2つに分けられます。
労働者が健康診断を受ける時間は労働時間になるのでしょうか?
令和4年の問題で確認しましょう。
では、過去問からどうぞ!労働安全衛生法の過去問です。
【H27年出題(安衛法)】
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものと解されている。

【解答】
【H27年出題(安衛法)】 〇
・一般健康診断の時間 → 労働時間にはなりません
・特殊健康診断の時間 → 労働時間となります(賃金の支払が必要です)
※健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについて
・労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものです。「業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではない」とされています。
・特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものですので、「所定労働時間内に行なわれるのを原則」とすること。また、「特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解される」ので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであることとされています。
(S47.9.18基発第602号)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【R4問2-A】
労働安全衛生法により事業者に義務付けられている健康診断の実施に要する時間は、労働安全衛生規則第44条の定めによる定期健康診断、同規則第45条の定めによる特定業務従事者の健康診断等その種類にかかわらず、すべて労働時間として取り扱うものとされている。

【解答】
【R4問2-A】 ×
則第44条の定期健康診断、則第45条の特定業務従事者の健康診断は一般健康診断ですので、労働時間とはされません。
一定の有害業務に従事する労働者が対象の特殊健康診断は、労働時間と解されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(厚生年金保険法)
令和4年基本問題(厚生年金保険法)
R5-029
R4.9.26 R4択一式より『障害厚生年金の額の計算』
今日のテーマは障害厚生年金の額の計算です。
条文を読んでみましょう。
第50条 (障害厚生年金の額) ① 障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、①の規定にかかわらず、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例で計算します。
ただし、老齢厚生年金は、実際の厚生年金保険の被保険者期間で計算しますが、障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合は300月で計算します。
また1級の場合は、100分の125の額となります。
障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、障害認定日の属する月までとなります。障害認定日を初診日にする問題、属する月を「属する月の前月」とする問題に注意しましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【R4問10-D】
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。

【解答】
【R4問10-D】 ×
障害厚生年金の額の計算には、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間が算入されます。「障害認定日の属する月の前月まで」の部分が誤りです。
では過去問もどうぞ!
①【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
②【H29年出題】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
③【H22年出題】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

【解答】
①【H22年出題】 ×
計算の基礎になるのは、「障害認定日の属する月」までの期間です。
②【H29年出題】 〇
計算の基礎になるのは、障害認定日の属する月(平成29年3月)までの期間です。障害認定日の属する月後(平成29年4月以後)の被保険者期間はその計算の基礎となりません。
③【H22年出題】 ×
240か月ではなく、「300か月に満たないときは、これを300か月とする」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(国民年金法)
令和4年基本問題(国民年金法)
R5-028
R4.9.25 R4択一式より『寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金』
今日のテーマは、寡婦年金と繰上げ支給の老齢基礎年金の関係です。
寡婦年金は、60歳から65歳までの有期年金です。
受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得した場合、寡婦年金の受給権はどうなるでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第51条・附則第9条の2 寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ・ 65歳に達したとき ・ 死亡したとき。 ・ 婚姻をしたとき。 ・ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 ・ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき。 |
寡婦年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金を繰上げ受給したときは、寡婦年金の受給権は消滅します。「選択」や「支給停止」ではないことがポイントです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【R4問7-E】
寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。

【解答】
【R4問7-E】 ×
受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合は、寡婦年金の受給権は消滅します。
過去問もどうぞ!
①【H23年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止される。
②【H29年出題】
妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中に、一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡した場合、妻には寡婦年金を受給する権利が発生し、繰上げ支給の老齢基礎年金か寡婦年金のどちらかを受給することができる。

【解答】
①【H23年出題】 ×
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、寡婦年金は支給停止されるではなく「受給権が消滅」します。
②【H29年出題】 ×
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けた者には、寡婦年金は支給されません。
(法附則第9条の2の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(健康保険法)
令和4年基本問題(健康保険法)
R5-027
R4.9.24 R4択一式より『移送費として支給される額』
今日のテーマは「移送費」です。
さっそく条文を読んでみましょう。
第97条 ① 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 ② 移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
則第80条 (移送費の額) 法第97条第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
則第81条 (移送費の支給が必要と認める場合) 保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 1 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 2 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 3 緊急その他やむを得なかったこと。 |
★移送費とは?
負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、その経済的な出費について補填を行い、必要な医療が受けられることを可能にするとの考え方から、現金により支給されます。
なお、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはなりません。
参照:H6.9.9保険発第119号・庁保険発第9号
令和4年の問題をどうぞ!
【R4問3-イ】
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を超えることができない。

【解答】
【R4問3-イ】 ×
移送費には一部負担金はありませんので、「3割の患者自己負担分を差し引いた」の部分が誤りです。
なお、移送費は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用に基づいて算定した額の範囲での実費が支給されます。
では、過去問もどうぞ!
【H24年出題】
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

【解答】
【H24年出題】 〇
移送費の金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用で算定した額の範囲内での実費です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(社会保険一般常識)
令和4年基本問題(社会保険一般常識)
R5-026
R4.9.23 R4択一式より『高齢者医療確保法 審査請求』
国民健康保険法、介護保険法、高齢者医療確保法の「審査請求」は、横断学習が効果的です。
令和4年は、高齢者医療確保法から審査請求の問題が出題されました。
では、3つまとめて条文を読んでみましょう。
(国民健康保険法) 第91条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 第92条 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。
(介護保険法) 第183条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 第184条 介護保険審査会は、各都道府県に置く。
(高齢者の医療の確保に関する法律) 第128条 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 第129条 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 |
★ 審査請求先は「社会保険審査会」ではありませんので注意しましょう。
「国民健康保険審査会」「介護保険審査会」「後期高齢者医療審査会」は各都道府県に置かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【国民健康保険法・H18年出題】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
②【国民健康保険法・R1年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
③【介護保険法・R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
④【高齢者医療確保法・H25年出題】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
令和4年の問題です!
⑤【高齢者医療確保法・R4問7-E】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
①【国民健康保険法・H18年出題】 ×
社会保険審査会ではなく、「国民健康保険審査会」です。
②【国民健康保険法・R1年出題】 〇
ポイントは、「国民健康保険審査会」です。
なお、「徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)」のカッコの部分は、国民健康保険法第78条に規定されています。
③【介護保険法・R3年出題】 〇
介護保険審査会は、各都道府県に置かれます。
④【高齢者医療確保法・H25年出題】 ×
社会保険審査会ではなく、「後期高齢者医療審査会」です。
⑤【高齢者医療確保法・R4問7-E】 〇
後期高齢者医療審査会がポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(労働一般常識)
令和4年基本問題(労働一般常識)
R5-025
R4.9.22 R4択一式より『同一労働同一賃金ガイドライン』
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者との間に待遇の相違が存在する場合に、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものであり、いかなる待遇の相違が不合理と認められるものでないのか等の原則となる考え方及び具体例を示したものです。
令和4年にガイドラインからの問題が出ましたので、確認しましょう。
では、まず、条文を読んでみましょう。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第8条 (不合理な待遇の禁止) 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。 |
 同一企業内で、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇で不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
同一企業内で、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇で不合理な待遇差を設けることが禁止されています。
「職務内容」、「職務内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止しています。このことを「均衡」待遇規定といいます。
第9条 (通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止) 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 |
 「職務内容」、「職務内容及び配置の変更の範囲」が同じ場合は、「差別的取扱い」が禁止されています。このことを「均等」待遇規定といいます。
「職務内容」、「職務内容及び配置の変更の範囲」が同じ場合は、「差別的取扱い」が禁止されています。このことを「均等」待遇規定といいます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問4-E】
賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。

【解答】
【問4-E】 〇
なお、ガイドラインでは、問題とならない例として、「賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社において、通常の労働者であるXと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるYに対し、Xと同一の賞与を支給している。」が示されています。
また、問題となる例として、「賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給しているA社において、通常の労働者であるXと同一の会社の業績等への貢献がある有期雇用労働者であるYに対し、Xと同一の賞与を支給していない。」が示されています。
参照:「同一労働同一賃金ガイドライン」(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(徴収法)
令和4年基本問題(徴収法)
R5-024
R4.9.21 R4択一式より『雇用保険暫定任意適用事業』
労働者を1人でも雇用する事業は、当然に雇用保険の適用事業です。
しかし、一部の農林水産業は、当分の間、雇用保険の適用は任意となります。
今日は、令和4年の択一式から、雇用保険暫定任意適用事業を見ていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
<雇用保険法> 第5条 (適用事業) 雇用保険法においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。 附則第2条 (暫定任意適用事業) 次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であって、政令で定めるものは、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。 1 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 2 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。) 施行令第2条 法附則第2条第1項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。 |
★雇用保険の暫定任意適用事業は、民間の個人経営の農林水産の事業で5人未満の労働者を雇用するものです。
なお、船員を雇用する事業は、原則として強制適用事業となります。
<徴収法> 附則第2条 (雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置) ① 雇用保険暫定任意適用事業の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 ② 任意加入の申請は、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ行うことができない。 ③ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければならない。 ④ 雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなす。 |
① 雇用保険暫定任意適用事業の場合、雇用保険に係る保険関係が成立するのは、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日です。※厚生労働大臣の認可の権限は、都道府県労働局長に委任されています。
② 労働者の2分の1以上の同意が必要なのは、労働者にも保険料の負担があるためです。なお、認可があれば、同意しなかった者も含めてその事業に雇用される者全員に雇用保険が適用されます。★「その事業に使用される労働者の2分の1」とは、労働者総数の2分の1以上ではなく、適用除外となる労働者を除いた労働者の2分の1以上の者をいう、とされています。 (行政手引20154)
③ 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければなりません。
④ 例えば、5人未満の農業の法人が個人経営になったなどのように、強制適用事業から暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に任意加入の認可があったものとみなされます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問10-A(雇用)】
雇用保険法第6条に該当する者を含まない4人の労働者を雇用する民間の個人経営による農林水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)において、当該事業の労働者のうち2人が雇用保険の加入を希望した場合、事業主は任意加入の申請をし、認可があったときに、当該事業に雇用される者全員につき雇用保険に加入することとなっている。
②【問10-B(雇用)】
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされ、事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に改めて提出することとされている。

【解答】
①【問10-A(雇用)】 〇
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、任意加入の申請をしなければなりません。雇用される労働者4人の場合は、2人以上が加入を希望した場合となります。
なお、労災保険の暫定任意の場合は、「過半数」が希望したとき、となります。労働者が4人の場合、過半数は3人以上です。
②【問10-B(雇用)】 ×
雇用保険の適用事業に該当する事業が、事業内容の変更、使用労働者の減少、経営組織の変更等により、雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、自動的に雇用保険の任意加入の認可があったものとみなされます。法律上当然に認可を受けたとみなされますので、任意加入の認可の手続きを行う必要はありません。後半部分の「事業主は雇用保険の任意加入に係る申請書を・・・」の部分が誤りです。
(行政手引20157)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(雇用保険法)
令和4年基本問題(雇用保険法)
R5-023
R4.9.20 R4択一式より『特例高年齢被保険者』
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、『特例高年齢被保険者』です。
特例高年齢被保険者は、2以上の事業所で勤務する65歳以上の者に関する制度で、令和4年1月1日の改正で設けられた制度です。
さっそく、令和4年に出題されましたので、確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第37条の5(高年齢被保険者の特例) ① 次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行った日から高年齢被保険者となることができる。 1 二以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること。 2 一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること。 3 二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること。 ② ①の規定により特例高年齢被保険者となった者は、①の1~3の要件を満たさなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出なければならない。 ③ ①②の規定による申出を行った労働者については、第9条第1項の規定による確認が行われたものとみなす。 |
★特例高年齢被保険者の資格取得について
要件に該当する場合は、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長に申し出ることによって、申出を行った日から特例高年齢被保険者となることができます。
★特例高年齢被保険者の資格喪失について
二の事業主の適用事業の両方又はいずれか一方を離職した日の翌日又は死亡した日の翌日に資格を喪失します。
また、一の適用事業の週所定労働時間が5時間未満又は20時間以上となった場合、二の適用事業の週所定労働時間の合計が20時間未満となった場合は、当該事実のあった日に資格を喪失します。
資格喪失手続は、本人からの申出によることとなります。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問1-A】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合に支給される高年齢求職者給付金の賃金日額は、当該離職した適用事業において支払われた賃金のみにより算定された賃金日額である。
②【問1-B】
特例高年齢被保険者が同じ日に1の事業所を正当な理由なく自己の都合で退職し、他方の事業所を倒産により離職した場合、雇用保険法第21条の規定による待期期間の満了後1か月以上3か月以内の期間、高年齢求職者給付金を支給しない。
③【問1-C】
特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職したことにより、1週間の所定労働時間の合計が20時間未満となったときは、特例高年齢被保険者であった者がその旨申し出なければならない。
④【問1-D】
特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。
⑤【問1-E】
2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。

【解答】
①【問1-A】 〇
1の適用事業を離職した場合の賃金日額は、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする」となっています。
問題文の通り、特例高年齢被保険者が1の適用事業を離職した場合の高年齢求職者給付金の賃金日額は、「当該離職した適用事業において支払われた賃金のみ」により算定されます。
(第37条の6第2項)
②【問1-B】 ×
離職理由による給付制限については、同日付で2の事業所を離職した場合又は同日付で2の事業所の所定労働時間が減少した場合で、その離職理由が異なっている場合には、給付制限の取扱いが離職者にとって不利益とならない方の離職理由に一本化して給付する、とされています。
問題文の場合は、不利益とならない方の離職理由である「倒産による離職」に一本化して給付されます。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領2279第9)
③【問1-C】 〇
特例高年齢被保険者は、二の事業主に雇用されなくなった場合や、二の事業主における合計した1週間の所定労働時間が20時間未満になる等、特例高年齢被保険者の要件を満たさなくなったときは、被保険者資格を喪失しますので、その旨管轄公共職業安定所の長に申し出なければなりません。
資格喪失手続は、必ず、特例高年齢被保険者本人からの申出によることになります。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領1160)
④【問1-D】 〇
特例高年齢被保険者には、賃金日額の下限の規定は適用されません。
(法第37条の6第2項)
⑤【問1-E】 〇
特例高年齢被保険者に係る適用事業は、二の事業主は異なる事業主であることが必要です。事業所が別であっても同一の事業主である場合は、特例高年齢被保険者となることができません。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領1070)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(労働者災害補償保険法)
令和4年基本問題(労働者災害補償保険法)
R5-022
R4.9.19 R4択一式より『(通勤災害)住居と就業の場所』
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、『(通勤災害)住居と就業の場所』です。
通勤となる移動は3種類ありますが、代表的な移動は、「住居と就業の場所との間の往復」です。
条文を読んでみましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
「住居」とは労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをさします。
「就業の場所」は、業務を開始し又は終了する場所をいいます。
(S48.12.1保険発第105号・庁保険発第24号)
令和4年の問題で、「住居」・「就業の場所」になる例、ならない例を確認しましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問5-A】
同一市内に住む長女が出産するため、15日間、幼児2人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
②【問5-B】
アパートの2階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。
③【問5-C】
一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。
④【問5-D】
外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。
⑤【問5-E】
労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に1か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。

【解答】
①【問5-A】 〇
長女が出産するため、長女宅に泊まり込んだ労働者にとって長女宅は、住居と認められ、長女宅から勤務先に向かう途中の事故は通勤災害と認められています。
(S52.12.23基収1027号)
②【問5-B】 ×
アパートについては、部屋の外戸が住居と通勤経路の境界となります。
自室のドアから出て1階に降りようとした時の階段は通勤経路となりますので、足が滑り転倒して負傷した場合は、通勤災害に当たります。
(S49.4.9基収314)
③【問5-C】 〇
一戸建て屋敷構えの住居の玄関先は住居内となり、住居と就業の場所との間とはいえません。自宅の門をくぐって玄関先の石段での負傷は、通勤災害に当たりません。
(S52.12.23基収981)
④【問5-D】 〇
得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先は就業の場所に当たります。
(S48.11.22基発644)
⑤【問5-E】 〇
長期入院中の夫の看護のために病院に寝泊まりしている病院は住居に当たり、その病院から出勤する途中の事故は、通勤災害と認められます。
(S52.12.23基収981)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(労働安全衛生法)
令和4年基本問題(労働安全衛生法)
R5-021
R4.9.18 R4択一式より『作業主任者の選任』
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、『作業主任者の選任』です。
まず、条文を読んでみましょう。
第14条 (作業主任者) 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
則第18条 (作業主任者の氏名等の周知) 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。 |
作業主任者の選任が必要な作業は、「高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるもの」です。
施行令第6条で、高圧室内作業、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業などが規定されています。
また、作業主任者の資格は、①「都道府県労働局長の免許を受けた者」又は②「都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」の2種類です。
例えば、高圧室内作業については「高圧室内作業主任者免許を受けた者」から選任しなければなりません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問9-E】
労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。
②【問9-D】
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知するよう努めなければならないとされている。

【解答】
①【問9-E】 ×
「経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから」が誤りです。作業主任者は、『都道府県労働局長の免許を受けた者』又は『都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者』のうちから、作業の区分に応じて、選任しなければなりません。
②【問9-D】 ×
関係労働者に周知するよう「努めなければならない」ではなく、「周知させなければならない。」です。努力義務ではなく、義務規定です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(労働基準法)
令和4年基本問題(労働基準法)
R5-020
R4.9.17 R4択一式より『第4条 男女同一賃金の原則』
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、労働基準法第4条男女同一賃金の原則です。
では、条文を読んでみましょう。
第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |
過去問で、第4条のポイントを確認しましょう。
①【H25年出題】
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
②【H24年出題】
労働基準法第4条は、賃金についてのみ女性であることを理由とする男性との差別的取扱いを禁止したものであり、その他の労働条件についての差別的取扱いについては同条違反の問題は生じない。
③【H30年出題】
労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
第4条で、女性であることを理由として差別的取扱いを禁止しているのは、「賃金」についてのみです。
②【H24年出題】 〇
なお、男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進、降格・教育訓練、一定の福利厚生の措置、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別的取扱いを禁止しています。
③【H30年出題】 〇
差別的取扱いとは、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる、とされています。
(H9.9.25基発第648号)
では、令和4年の問題をどうぞ!
④【R4年出題】
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4条違反となる。

【解答】
④【R4年出題】 ×
第4条に違反して、女性であることを理由として賃金について男性と差別的取扱いをした使用者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
第4条の違反が成立するのは、現実に差別的取扱いをした場合です。就業規則で賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、その規定は無効となるだけです。現実に男女差別待遇の事実が無い場合は、労働基準法第4条違反にはなりません。
(H9.9.25基発第648号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(国民年金法)
令和4年択一式を解いてみる(国民年金法)
R5-019
R4.9.16 R4「国年択一」は基本問題中心。今日は『遺族基礎年金の支給要件』
令和4年の国民年金法の択一式は、基本問題が中心でした。
厚生年金保険法の択一式と同様、テキストと過去問学習が役立ったと思います。
テキストと過去問の繰り返しが大切です。
今日は「遺族基礎年金の支給要件」の問題を見てみましょう。
まずは、条文を読んでみましょう。
第37条 (支給要件) 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ※令和8年4月1日前に死亡した者については、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは保険料納付要件を満たす。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、この限りでない。(S60年改正法附則第20条第2項) 1被保険者が、死亡したとき。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。 3老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 4保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。 |
ポイント!保険料納付要件
★1と2(短期要件)は、保険料納付要件が問われます。
被保険者期間中の滞納期間が3分の1未満であることが原則です。しかし、死亡日に65歳以上である場合を除き、令和8年4月1日前の死亡については、死亡日の直近1年間のうちに滞納期間がなければ、要件を満たします。
★3と4(長期要件)は死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問5-C】
保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。
②【問10-B】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。

【解答】
①【問5-C】 〇
長期要件は、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」です。
この場合、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年に満たない場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と「合算対象期間」を合算して25年以上あれば、要件を満たします。「合算対象期間」も合算できることがポイントです。
(S60年改正法附則第12条)
②【問10-B】 ×
「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間」が25年以上ある第1号被保険者が死亡した場合は、4の長期要件を満たしますので、死亡日の前日の保険料納付要件は問われません。死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合でも影響はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(厚生年金保険法)
令和4年択一式を解いてみる(厚生年金保険法)
R5-018
R4.9.15 R4「厚年択一」は解きやすい問題が多かったです。今日は『老齢厚生年金の支給繰下げ』
令和4年の厚生年金保険法の択一式は、全体的に解きやすかったです。
テキストの読み込みと過去問対策の大切さが分かる出題でした。
今日は、「老齢厚生年金の支給繰下げ」の問題をみていきます。
まず、老齢厚生年金の支給繰下げの条件を令和2年の選択式の問題で確認しましょう。
(復習)では令和2年選択式からどうぞ!
厚生年金保険法第44条の3第1項の規定によると、老齢厚生年金の受給権を有する者であってその< A >前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができるとされている。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(< B >を除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は当該老齢厚生年金の< A >までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでないとされている。

【解答】
A 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日
B 老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金
老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、受給権を取得してから1年待たなければなりません。
また、「老齢厚生年金の受給権を取得したときに他の年金たる給付の受給権者であったとき」、又は「老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間に他の年金たる給付の受給権者となったとき」は、支給繰下げの申出はできません。
他の年金たる給付とは、「他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)」をいいます。
「老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金」は例外になっているのがポイントです。
例えば、老齢厚生年金の受給権取得日から1年経過した日までの間に、「老齢基礎年金+付加年金」の受給権があったとしても老齢厚生年金の支給繰下げの申出は可能です。同じく、老齢厚生年金の受給権取得日から1年経過した日までの間に、「障害基礎年金」の受給権があったとしても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
では令和4年の問題をどうぞ!
①【問5-C】
68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。
②【問5-D】
老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。
③【問5-E】
令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる上限が70歳から75歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3月31日時点で、70歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者に限られる。

【解答】
①【問5-C】 〇
第44条の3第3項で、「支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第36条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあった月の翌月から始めるものとする。」と規定されています。
68歳0か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対しては、当該申出を行った月の翌月から開始されます。
②【問5-D】 ×
「経過的加算」は、支給繰下げの申出に応じた増額の対象となります。
繰下げ加算額は、(繰下げ対象額+経過的加算額)×増額率で計算します。
(令3条の5の2第1項)
③【問5-E】 〇
令和4年4月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる上限が75歳に引き上げられています。
繰下げ受給の受給率は、「繰り下げた月数×0.7%」で計算します。10年繰下げた場合、120月×0.7%=84%増額されます。
ただし、対象になるのは、①「令和4年3月31日時点で70歳未満の者(昭和27年4月2日以降生まれ)」あるいは②「老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の者(老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない)」に限られます。
①、②に該当しない場合は、繰下げの申出の上限は70歳です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(健康保険法)
令和4年択一式を解いてみる(健康保険法)
R5-017
R4.9.14 R4「健保択一」は長文が多く12ページのボリューム。今日は『被保険者証』
令和4年の健康保険の択一式は、長文問題が多く12ページのボリュームでした。
問題文を読むときは、まず「キーワード」を見つけ出すことが大切です。
では、今日は、「被保険者証」の問題を解いてみましょう。
まず、条文を読んでみましょう。
則第47条(被保険者証の交付) 1 協会は、厚生労働大臣から、被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。 2 健康保険組合は被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。 3 保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。 4 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。 5 保険者は、任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。 |
被保険者の資格取得の確認を行ったときは、協会(又は健康保険組合)は、被保険者証を被保険者に交付します。
被保険者証は「保険者から事業主に送付」→「事業主から被保険者に送付」の流れが原則です。
ただし、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から直接、被保険者に送付することもできます。(テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能とするため、令和3年に改正されました。)
また、任意継続被保険者については、保険者から直接任意継続被保険者に送付されます。
則第51条 (被保険者証の返納) 事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 2 前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、5日以内に、これを保険者に返納しなければならない。 4 被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。 |
資格喪失の場合は、事業主は遅滞なく被保険者証を回収し、保険者に返納します。この場合、被保険者は5日以内に被保険者証を事業主に提出しなければなりません。
任意継続被保険者の場合は、本人が、5日以内に保険者に返納します。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【R4年問1-C】
事業主は、被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。
②【R4年問2-E】
保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

【解答】
①【R4年問1-C】 ×
(被保険者証の返納の問題)
資格喪失の場合は、事業主が遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければなりません。返納の場合は、後半部分の「被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。」という例外規定はありません。
②【R4年問2-E】 〇
(被保険者証の交付の問題)
被保険者証の交付については、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続きを可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(社保一般常識)
令和4年択一式を解いてみる(社保一般常識)
R5-016
R4.9.13 R4「社一択一」は全て法令からの出題。今日は『確定給付企業年金法』について
令和4年の社会保険一般常識の択一式は、全問、法令からの出題でした。
細かい箇所からの出題も多かったので、難しく感じた方も多かったのではないでしょうか。
今日は、「確定給付企業年金法」の問題をみていきましょう。
では、令和4年問6「確定給付企業年金法」の問題をどうぞ!
A
確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。
B
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
C
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
D
企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。
E
連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

【解答】
A × 基金は、規約の変更については、厚生労働大臣の同意ではなく、厚生労働大臣の「認可」を受けなければならないとされています。
(法第16条)
B × 障害給付金は、「給付を行わなければならない」ではなく「給付を行うことができる」です。
(法第29条第2項)
C ×
少なくとも6年ごとではなく、少なくとも「5年」ごとに掛金の額を再計算しなければならないとされています。
(法第57条、第58条)
D ×
10以上ではなく、その会員となろうとする「20以上」の事業主等が発起人とならなければならない、です。
(法第91条の5)
E 〇
「6か月以内」がポイントです。
(法第100条の2)
選択式の練習もどうぞ!
| 第16条 基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の< A >を受けなければならない。 |
(給付の種類) ① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 < B > ② 事業主等は、規約で定めるところにより、①各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 1 障害給付金 2 < C > |
第57条 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 第58条 事業主等は、少なくとも< D >ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。 |
事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。 連合会は、全国を通じて1個とする。 連合会を設立するには、その会員となろうとする< E >以上の事業主等が発起人とならなければならない。 |
連合会は、毎事業年度終了後< F >以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |

選択練習の解答
A 認可
B 脱退一時金
C 遺族給付金
D 5年
E 20
F6か月
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(労働一般常識)
令和4年択一式を解いてみる(労働一般常識)
R5-015
R4.9.12 R4「労一択一」は統計から3問。今日は『労働力調査』
令和4年労働一般常識は、問1「労働力調査2021年平均結果」、問2「令和3年就労条件総合調査」、問3「令和2年転職者実態調査」で、3問が統計からの出題でした。
問4は労働関係法規、問5は社会保険労務士法令でした。
今日は、問1労働力調査の問題を見てみましょう。
「労働力調査(基本集計)2021年平均結果(総務省統計局)」からの出題です。
A
2021年の就業者数を産業別にみると、2020年に比べ最も減少したのは「宿泊業、飲食サービス業」であった。
B
2021年の年齢階級別完全失業率をみると、15~24歳層が他の年齢層に比べて、最も高くなっている。
C
2021年の労働力人口に占める65歳以上の割合は、10パーセントを超えている。
D
就業上の地位別就業者数の推移をみると、「自営業主・家族従事者」の数は2011年以来、減少傾向にある。
E
役員を除く雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は、2015年以来、一貫して減少傾向にある。

【解答】
A 〇 2021年の就業者数を産業別にみると、2020年に比べ最も減少したのは「宿泊業、飲食サービス業」で、22万人減少しました。
B 〇 完全失業率は2021年平均で2.8%です。15~24歳層は、4.6%となっています。
ちなみに、「完全失業率」は、「労働力人口に占める完全失業者の割合」です。
C 〇 2021年の労働力人口の総数は6860万人で、うち65歳以上は929万人です。
ちなみに「労働力人口」は、「15 歳以上人口のうち,就業者と完全失業者を合わせた人口」です。
D 〇 なお、自営業主・家族従事者の数は660万人です。
E × 「2015年以来、一貫して減少傾向」が誤りです。雇用者全体に占める「正規の職員・従業員」の割合は2015年は62.6%で、2021年は63.3%です。
※総務省統計局「労働力調査(基本集計) 2021年(令和3年)平均結果」を参照しています。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(徴収法)
令和4年択一式を解いてみる(徴収法)
R5-014
R4.9.11 R4「徴収択一」は長文問題が多かったです。今日は『賃金総額の特例』
令和4年の徴収法の択一は長文問題が多くみられました。
今日は、「賃金総額の特例」の問題を見てみましょう。
一般保険料の額は、「賃金総額」×一般保険料に係る保険料率で計算します。
「賃金総額」は、原則として、「事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額」ですが、「厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。」(法第11条第3項)という特例があります。
令和4年は、この「賃金総額の特例」が出題されました。
まず、「厚生労働省令で定める事業」を読んでみましょう。
則第12条(賃金総額の特例) 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2 立木の伐採の事業 3 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。) 4 水産動植物の採捕又は養殖の事業 |
賃金総額の特例が認められる条件は1~4に当てはまる事業で、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」ですので、注意してください。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【R4年問10-B】労災
労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
②【R4年問10-C】労災
労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

【解答】
①【R4年問10-B】労災 ×
『造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)』、『水産動植物の採捕又は養殖の事業』については、『その事業の労働者につき労働基準法の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。』とされています。
★賃金総額=(平均賃金に相当する額×それぞれの労働者の使用期間の総日数)の合算額
なお、『立木の伐採の事業』については、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。』とされています。
★賃金総額
=素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額×生産するすべての素材の材積
(則第14条、第15条)
②【R4年問10-C】労災 〇
『請負による建設の事業』については、『その事業の種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする』とされています。
また、請負金額に、「消費税等相当額を含まない」のがポイントです。
では、過去問もどうぞ!
③【H26年出題】労災
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、業態の特殊性等の理由により賃金総額を原則どおり正確に算定することが困難な事業については、特例による賃金総額の算出が認められているが、その対象となる事業には、「請負による建設の事業」や「水産動植物の採捕又は養殖の事業」が含まれる。
④【H30年出題】雇用
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。

【解答】
③【H26年出題】労災 〇
特例による賃金総額の算出が認められているのは、「請負による建設の事業」、「立木の伐採の事業」、「造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)」、「水産動植物の採捕又は養殖の事業」です。
④【H30年出題】雇用 ×
請負による建設の事業だから、常に、特例が認められるのではなく、「賃金総額を正確に算定することが困難なもの」に限られています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(雇用保険法)
令和4年択一式を解いてみる(雇用保険法)
R5-013
R4.9.10 R4「雇用択一」は適用から給付まで網羅した内容でした。問4所定給付日数
令和4年の雇用保険の択一式は、適用から給付内容まで網羅した出題でした。
今日は、問4所定給付日数の問題を見ていきます。
では、令和4年問4の問題をどうぞ。
【R4年問4】
次の①から④の過程を経た者の④の離職時における基本手当の所定給付日数として正しいものはどれか。
① 29歳0月で適用事業所に雇用され、初めて一般被保険者となった。
② 31歳から32歳まで育児休業給付金の支給に係る休業を11か月間取得した。
③ 33歳から34歳まで再び育児休業給付金の支給に係る休業を12か月間取得した。
④ 当該事業所が破産手続を開始し、それに伴い35歳1月で離職した。
一般の受給資格者の所定給付日数
算定基礎期間 区分 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
一般の受給資格者 | 90日 | 120日 | 150日 |
特定受給資格者の所定給付日数
算定基礎期間 年齢 | 1年 未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
A90日
B120日
C150日
D180日
E210日

【解答】 C
 「育児休業給付金」の支給を受けていることがポイントです。
「育児休業給付金」の支給を受けていることがポイントです。
→ 算定基礎期間の算定については、「被保険者であった期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。」とされています。 (法第22条第3項、第61条の7第8項)
★問題文を整理してみます。
・29歳0月で資格取得~35歳1月で離職なので、被保険者であった期間は74か月(6年2か月)です。
・育児休業給付金の支給に係る休業の期間23か月(1年11か月)は、算定基礎期間から除外します。
・事業所が破産手続を開始したために離職していますので、特定受給資格者に該当します。
・離職の日の年齢は35歳です。
「特定受給資格者」、「算定基礎期間」1年以上5年未満、「離職時の年齢」35歳以上45歳未満で、所定給付日数は「150日」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(労災保険法)
令和4年択一式を解いてみる(労災保険法)
R5-012
R4.9.9 R4「労災択一」は保険給付の出題ゼロでした。問3中小事業主の要件
令和4年の労災保険の択一式は、「保険給付」(例えば、療養補償給付とか休業補償給付とか・・・)の内容についての出題がありませんでした。
今日は、問3の「特別加入できる中小事業主」の問題を見ていきましょう。
まず、中小事業主と認められる企業の規模を確認しましょう。
業 種 | 常時使用する労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
中小事業主が特別加入する条件として、「労働者について保険関係が成立している」、「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している」ことが必要です。
労働保険事務組合に委託できるのは、上記の規模の中小事業主です。
では、令和4年問3の問題をどうぞ
【R4年問3】
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
B 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
C 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
D サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
E 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

【解答】
A × 金融業 → 常時50人以下
B × 不動産業 → 常時50人以下
C × 小売業 → 常時50人以下
D 〇 サービス業 → 常時100人以下
E × 保険業 → 常時50人以下
では、過去問もどうぞ!
【R3年出題】
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。

【解答】
【R3年出題】 ×
就業実態のない事業主を特別加入者としない扱いは、認められています。
中小事業主等の特別加入については、事業主が事業主と当該事業に徒事するその他の者を包括して加入申請を行い、政府の承認を受けることにより労災保険が適用されるものとなっていて、事業主自身が加入することが前提となっています。
しかし、実態として事業場で就業していないものまで包括して加入させることは適当ではないので、就業実態のない事業主が自ら包括加入の対象から除外することを申し出た場合には、特別加入者としない扱いになっています。
なお、任意包括の対象から除外できるのは、次のいずれかに該当する者です。
①病気療養中、高齢その他の事情のため、実際に就業しない事業主、②事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主
(平成15年5月20日基発第0520002号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(安衛法)
令和4年択一式を解いてみる(安衛法)
R5-011
R4.9.8 R4「安衛択一」は2点でOK。問10安全委員会等
令和4年の択一安衛法は、(問9)作業主任者がやや難しいです。(問8)建設業の安全衛生管理体制と(問10)安全委員会等は、テキストに載っていることを思い出しながら、解ける問題です。
今日は(問10)安全委員会、衛生委員会及び安全衛生委員会を見てみましょう。
では、令和4年問10の問題をどうぞ!
A 衛生委員会は、企業全体で常時50人以上の労働者を使用する企業において、当該企業全体を統括管理する事業場に設置しなければならないとされている。
B 安全委員会は、政令で定める業種に限定してその設置が義務付けられているが、製造業、建設業、運送業、電気業、ガス業、通信業、各種商品小売業及び旅館業はこれに含まれる。
C 安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないとされている場合において、事業者はそれぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができるが、これは、企業規模が300人以下の場合に限られている。
D 安全委員会及び衛生委員会の委員には、労働基準法第41条第2号に定める監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならないとされている。
E 事業者は、安全衛生委員会を構成する委員には、安全管理者及び衛生管理者のうちから指名する者を加える必要があるが、産業医を委員とすることについては努力義務とされている。

【解答】
A ×
衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する「事業場」で設置が義務づけられています。常時50人以上は、企業全体の人数ではなく、事業場単位の人数です。なお、衛生委員会は「全業種」が対象です。
(法第18条、令第9条)
B 〇
安全委員会の設置は、政令で定める業種に限定されていて、「常時100人以上・300人以上で総括安全衛生管理者の選任が必要な業種」と同じです。
なお、安全委員会は、業種の区分ごとに「50人以上」、又は「100人以上」規模の事業場で選任が必要です。総括安全衛生管理者の業種の分け方とは異なります。
(法第17条、令第8条)
C ×
安全委員会を設置しなければならない事業場は、衛生委員会も設けなければなりません。その場合は、委員会をそれぞれ別個に設けずに、合わせて安全衛生委員会を設置することができます。
「企業規模が300人以下」という条件はありませんので、誤りです。
(法第19条)
D ×
安全委員会及び衛生委員会の委員に、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者を選任してはならない、という規定はありません。
E ×
構成員として、「産業医のうちから事業者が指名した者」が規定されていて、産業医は必ず加えなければなりません。努力義務ではありません。
(法第19条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(労働基準法)
令和4年択一式を解いてみる(労働基準法)
R5-010
R4.9.7 R4「労基択一」は基本問題中心。問1労働者の定義について
令和4年の労働基準法の択一式は基本問題が中心でした。
今日は問1を見ていきましょう。
まず、第9条の「労働者」の定義を読んでみましょう。
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
労働者は、「職業の種類」を問わず、事業又は事務所に「使用」され、「賃金」を支払われる者をいいます。
では、令和4年問1です。
A 労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者である。
B 労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。
C 同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の労働者に該当しないこととされている。
D 株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされている。
E 明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。

 問題を解くときの考え方です
問題を解くときの考え方です
A ×
労働基準法の労働者は、事業に「使用」され、労働の対償に「賃金」を支払われる者です。求職活動中は条件に当てはまりません。
B ×
請負契約の形式を採っていても、その実体において使用従属関係が認められる場合は、「労働関係」となり、労働基準法の労働者となります。※「実体」で判断することがポイントです。
C ×
「同居の親族のみを使用する事業」は労働基準法の適用が除外されます。しかし、「親族以外の者」(他人)が使用されている場合は、労働基準法の適用を受けることになります。一時的に使用される親族以外の者は、労働基準法の労働者に該当します。
D ×
「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない。(H11.3.31基発168号)」とされています。
E 〇
『事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者』なら、労働基準法の労働者の定義に当てはまります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑨
復習しましょう/令和4年選択式⑨
R5-009
R4.9.6 令和4年「国年選択」は条文の穴埋めでした
令和4年の国民年金の選択式は、条文の穴埋め問題でした。
 障害基礎年金の支給停止について
障害基礎年金の支給停止について
第36条第2項からの出題です。
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。 |
障害の状態が軽快し障害等級(1・2級)に該当しなくなったときは、「その障害の状態に該当しない間」は、障害基礎年金の支給が停止になります。
 寡婦年金の額について
寡婦年金の額について
第50条からの出題です。
| 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。 |
寡婦年金の額は、「第1号被保険者」の期間を基礎として計算した「老齢基礎年金」の額の4分の3です。
 国民年金基金の業務について
国民年金基金の業務について
第128条からの出題です。
1 基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行ない、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする。 2 基金は、加入員及び加入員であった者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。 |
基金は、①年金の支給を行う、②死亡一時金の支給を行う、③福祉施設をすることができるとされています。
「福祉を増進する」が問われました。
 被保険者に対する情報の提供について
被保険者に対する情報の提供について
第14条の5からの出題です。
| 厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。 |
択一式で何度か出題されています。通知は、受給権者に対しではなく「被保険者に対し」ての部分がポイントです。
「ねんきん定期便」の根拠になっている条文です。
「理解を増進させ、及びその信頼を向上させる」、「分かりやすい形で通知」が問われました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑧
復習しましょう/令和4年選択式⑧
R5-008
R4.9.5 令和4年「厚年選択」は択一式のような問題でした
令和4年の選択式は、「択一式」対策がそのまま「選択式」対策になるような出題でした。
 産前産後休業期間中の保険料の免除期間について
産前産後休業期間中の保険料の免除期間について
条文からの出題でした。
第81条の2の2 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 |
★「開始した日の属する月」と「終了する日の翌日が属する月の前月」が問われました。
 遺族厚生年金が最初に支給されるのは誰でしょう?
遺族厚生年金が最初に支給されるのは誰でしょう?
・ 被保険者X(50歳)と生活を共にしているのは、妻Y(45歳)とYとYの先夫との子Z(10歳)
※XとZは養子縁組をしていない。事実上の親子関係であることがポイントです。
・ Xは、Xの先妻V(50歳)とXとVの子W(15歳)に養育費を送っている
Xが死亡した場合、遺族厚生年金が最初に支給されるのは誰でしょう?
①まず、遺族基礎年金の受給権が発生するのは誰でしょう?
遺族基礎年金の受給権が発生するのは、先妻との子Wです。
Z、Y、Vには遺族基礎年金の受給権は発生しません。
なぜなら、
・ZはXと養子縁組をしていないため、「事実上の親子関係」です。「事実上の親子関係の子」は、遺族基礎年金の対象になる「子」にはならないからです。
・妻Yは、死亡したXの子と生計を同じくしていないからです。
・先妻Vは、死亡したときはXの妻ではないからです。
②遺族厚生年金の受給権が発生するのは誰でしょう?
死亡した当時の妻Yと先妻との子Wです。
③妻Yと子Wは遺族厚生年金の支給順位は同順位です。どちらが優先するでしょう?
第66条第2項によります。
第66条第2項 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が所在不明による支給停止の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
配偶者Yは遺族基礎年金の受給権がなく、子Wが遺族基礎年金の受給権を有するため、配偶者Yの遺族厚生年金は、支給停止されます。
遺族厚生年金が最初に支給されるのは、「W」となります。
 65歳未満の在職老齢年金の計算
65歳未満の在職老齢年金の計算
今年の改正点からの出題です。
計算式は、(総報酬月額相当額41万円+基本月額10万円-47万円)×2分の1
=2万円です。
支給停止額は、月額2万円です。
 事後重症の障害厚生年金
事後重症の障害厚生年金
事後重症のポイントは、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至った+その期間内に請求することです。
★「65歳に達する日の前日」が問われました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑦
復習しましょう/令和4年選択式⑦
R5-007
R4.9.4 令和4年「健保選択」は、数字の暗記が決め手
令和4年の健康保険の選択式は、4つが数字でした。
 短時間労働者に対する適用について
短時間労働者に対する適用について
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が平成28年10月1日より実施されています。
◎「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」といいます。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
◎ 4分の3基準を満たさない場合でも、以下の①から⑤までの5つの要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
① 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
② 雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
③ 月額賃金が8.8万円以上であること。
④ 学生でないこと。
⑤ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(i) 特定適用事業所
(ii) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(iii) 国又は地方公共団体の適用事業所
 令和4年10月以降の改正について
令和4年10月以降の改正について
※②の雇用期間要件が廃止されます。
※「特定適用事業所」の企業規模要件が、500人超える企業から、「100人」を超える企業に引き下げられます。
参照:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)
★令和4年は、「88,000円以上」が問われました。
 保険外併用療養費について
保険外併用療養費について
保険外併用療養費は、評価療養、患者申出療養、選定療養を受けたときが対象です。
令和4年の選択式では、厚生労働省告示に掲げられている第1号から第11号までの選定療養のうち、4号と7号からの出題でした。
4号は「病床数が200以上の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。)」、7号は、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く。)」です。
★「200以上」と「180日」が問われました。
 同時に2以上の事業所に使用される場合の手続きについて
同時に2以上の事業所に使用される場合の手続きについて
被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合の手続の問題です。
保険者が2以上ある場合は、被保険者は、被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければなりません。
その場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・2以上事業所勤務届」を、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に提出します。提出先は、全国健康保険協会を選択しようとするときは「厚生労働大臣」に、健康保険組合を選択しようとするときは、「健康保険組合」です。
全国健康保険協会の適用と徴収の業務は、厚生年金保険とセットになりますので、「厚生労働大臣」が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑥
復習しましょう/令和4年選択式⑥
R5-006
R4.9.3 令和4年「社一選択」は統計から1問、法令から4問
令和4年の社会保険の一般常識の選択は、統計から1問、法令から4問出題されました。
 「令和元年度国民医療費の概況」から
「令和元年度国民医療費の概況」から
~令和元年度の国民医療費の状況~
・令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円です。
前年度の43兆3,949億円に比べ9,946億円、2.3%の増加となっています。
~年齢階級別国民医療費~
・年齢階級別にみると、0~14歳は 2兆 4,987億円(構成割合5.6%)、15~44 歳は 5兆2,232億円(同11.8%)、45~64 歳は9兆6,047億円(同 21.6%)、65歳以上は 27兆629億円(同61.0%)となっています。
★65歳以上の構成割合が問われました。
参照:厚生労働省 令和元(2019)年度 国民医療費の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/19/index.html
 確定拠出年金の「死亡一時金」を受ける遺族の順位
確定拠出年金の「死亡一時金」を受ける遺族の順位
確定拠出年金法第41条からの出題です。
第41条 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。 ① 配偶者 ② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの ③ 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ④ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しないもの |
遺族の順位は、条文に並んでいる順位です。
配偶者は「生計維持」の条件が無いことに注目してください。
「生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹」がいた場合、第一順位は「配偶者」です。
★「死亡一時金」の遺族の順位まで覚えていた人は少ないと思います。優先されるのが「配偶者」なのか、それとも「生計維持」なのかで、迷った方が多かったのではないでしょうか?
 児童手当法の費用の負担について
児童手当法の費用の負担について
児童手当法で「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。」と定義されています。
また、「支給要件児童」は、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)、中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(どちらも施設入所等児童を除く。)」をいいます。
★被用者に対する児童手当の支給に要する費用の問題ですが、費用が発生するのは、中学校修了前の児童と考えると、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」が選べると思います。
 介護保険法の「要介護状態」の定義について
介護保険法の「要介護状態」の定義について
介護保険法第7条で、「「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。」と定義されています。
★重要用語の定義は、きちんと覚えておくことがポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑤
復習しましょう/令和4年選択式⑤
R5-005
R4.9.2 令和4年選択式の復習~労働一般常識
令和4年の選択式は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」と「日立メディコ事件の判例」からの出題でした。
どちらも見た事がある方が多かったと思います。
では、問題の解き方です。
 障害者雇用率制度など
障害者雇用率制度など
・「障害者雇用率制度」について
現在の民間企業に対する法定雇用率は2.3パーセントです。
※常時43.5人以上の労働者を使用する民間企業は、障害者を1人以上雇用する義務があります。
・「障害者雇用納付金制度」について
「障害者雇用納付金」が徴収されるのは、法定雇用率が未達成の企業です。常用労働者が100人超の企業が対象です。不足1人当たり月額5万円です。
また、法定雇用率を達成している企業に対しては、障害者雇用調整金が支給されます。こちらも常用労働者が100人超の企業が対象で、超過1人当たり月額2万7千円です。
・「ジョブコーチ」について
ジョブコーチ(職場適応援助者)は、障害者の職場適応に課題がある場合に、職場に出向き、専門的な支援を行うことによって、障害者の職場適応を図ります。
配置型ジョブコーチ、訪問型ジョブコーチ、企業在籍型ジョブコーチの3つの種類があります。
 日立メディコ事件(S61.12.04最一小判)
日立メディコ事件(S61.12.04最一小判)
労働契約法第19条は、「有期労働契約の更新等」のルールを定めています。
・有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合(同条第1号)
・労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合(同条第2号)
↓
使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められません。
そのため、使用者は、従前の有期労働契約と同一の労働条件で労働者による有期労働契約の更新又は締結の申込みを承諾したものとみなされ、有期労働契約が同一の労働条件(契約期間を含む。)で成立することとしたものであること。」とされています。
第19条2号には、「日立メディコ事件」の内容が反映されています。
「有期労働契約の期間満了後も雇用関係が継続されるものと期待することに合理性が認められる場合には、解雇に関する法理が類推されるものと解せられる」と判示した日立メディコ事件最高裁判決の要件が規定されています。
(参照:平成24年8月10日基発0810第2号)
過去問をどうぞ!
【H29年出題】
有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。

【解答】 ×
「この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。」が誤りです。
「労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合」であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、「従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。」です。
★ 使用者は、従前の有期労働契約と同一の労働条件で労働者による有期労働契約の更新又は締結の申込みを承諾したものとみなされ、有期労働契約が同一の労働条件(契約期間を含む。)で成立します。
(労働契約法第19条 平成24年8月10日基発0810第2号)
 労働契約法は、条文のもとになった判例のポイントも押さえておきましょう。
労働契約法は、条文のもとになった判例のポイントも押さえておきましょう。
なお、本試験のキーワードになったのは、「継続が期待されていた」と「従前の労働契約が更新された」でした。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式④
復習しましょう/令和4年選択式④
R5-004
R4.9.1 令和4年選択式の復習~雇用保険法
令和4年の雇用保険の選択式は、「暗記」が勝負でした。
 賃金日額と基本手当の日額について
賃金日額と基本手当の日額について
・「賃金日額」は原則として、「算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額」です。
完全な賃金月が12あるときは、「最後の完全な6賃金月」で計算することになります。
・賃金日額の算定は「雇用保険被保険者離職票」に基づいて行われます。離職票には、離職の日以前の賃金支払い状況を記入する欄があります。
・令和3年8月から令和4年7月までの賃金日額の最低限度額は2,577円です。算定した賃金日額が2500円の場合、最低限度額が適用されます。その場合、基本手当の日額は2,577円×100分の80=2,061円となります。
 教育訓練給付の支給要件について
教育訓練給付の支給要件について
支給要件を確認しましょう。
※「基準日」とは対象教育訓練を開始した日です。
①基準日に一般被保険者等の場合
・支給要件期間が3年以上あること
※当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金
を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること
②基準日に一般被保険者等でない場合
・基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内(原則)にあり、支給要件期間が3年以上あること
※ 当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受けようとする者は、支給要件期間が1年以上あること
問題文にあてはめてみましょう。
(前提)
・平成25年中に教育訓練給付金を受給している
・離職期間中に教育訓練を開始する場合、最も早く支給要件を満たす離職の日は?
A社 → 平成26年6月1日就職、平成28年7月31日離職・基本手当受給
B社 → 平成29年9月1日就職、平成30年9月30日離職・基本手当受給
B社 → 令和1年6月1日再就職、令和3年8月31日離職・基本手当受給なし
B社 → 令和4年6月1日再就職、令和5年7月31日離職・基本手当受給なし
(ポイント)
・過去に教育訓練給付金を受けたことがあるため、支給要件期間は3年必要です
・基本手当を受給しても支給要件期間は通算されます。
・A社とB社の間は1年を超えていますので、支給要件期間としては通算できません。
B社の平成29年9月1日~平成30年9月30日の1年1か月と令和1年6月1日~令和3年8月31日の2年3か月が通算できます。そのため、最も早く3年以上の支給要件を満たすのは、令和3年8月31日の離職となります。
また、教育訓練給付金の額として算定された額が「4千円」を超えない場合は、教育訓練給付金は支給されません。
 基本的な数字は暗記必須です。
基本的な数字は暗記必須です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式③
復習しましょう/令和4年選択式③
R5-003
R4.8.31 令和4年選択式の復習~労働者災害補償保険法
今まであまり取り上げられなかった視点からの問題でした。
解き方を考えてみましょう。
 同一の部位に加重障害が生ずるとともに、他の部位にも新たな身体障害が残った場合の障害等級
同一の部位に加重障害が生ずるとともに、他の部位にも新たな身体障害が残った場合の障害等級
(問題の主旨)
・ 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)
・ 新たな業務災害で、同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)
↓
この場合の障害等級と新たに給付される障害補償の額が問われました。
(考え方)
① まず、同一部位の加重された後の身体障害の等級を定めます。
② 次に他の部位の身体障害の等級を定め、両者を併合して現在の身体障害の該当する等級を認定します。
③ 現在の等級の額から既にあった障害の等級の額を控除して得た額が、給付額となります。
(問題文にあてはめます)
① 同一部位(1下肢)の等級は加重された後、10級の7となります。
② 新たな部位の身体障害の等級は12級の8の2です。両者を併合して繰り上げた結果、現在の等級は「9級」となります。
※「併合」は重い方の障害等級が全体の障害等級となりますが、13級以上の障害が2つありますので、重い方の10級を1級繰り上げた結果「9級」となります。
③ 新たな障害につき給付される障害補償の額は、現在の等級(9級・391日分)から、既にあった障害の等級(13級・101日分)を控除した額=「290日」分となります。
 中小事業主が特別加入する際の保険関係について
中小事業主が特別加入する際の保険関係について
中小事業主の特別加入は、労働者に関して成立している保険関係に、中小事業主が組み込まれる形で行われます。
保険関係上、中小事業主は、「労働者」とみなされることによって、労災保険の保護の対象となります。
また、保険関係は、場所ごとに成立します。建設の事業の場合は、建設工事の現場、営業活動を行う本店等はそれぞれ別個に保険関係が成立します。
保険関係は、「労働者を使用するものがあること」によって成立します。
問題文の場合、建設現場は労働者がいるため保険関係が成立しますが、営業の事業を行う本店等は、労働者が従事していないため保険関係が成立していません。
中小事業主の特別加入は、労働者の保険関係が成立していることが前提です。保険関係が成立していない営業等の事業については、事業主は特別加入することはできません。そのため、「営業等の事業に係る業務」に起因する事業主の死亡に関しては、保険給付の対象になりません。
 覚えて解くという問題ではなく、前後の文章をじっくり読んで、今まで学んだ知識と照らし合わせて、正解を引き出す問題でした。
覚えて解くという問題ではなく、前後の文章をじっくり読んで、今まで学んだ知識と照らし合わせて、正解を引き出す問題でした。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式②
復習しましょう/令和4年選択式②
R5-002
R4.8.30 令和4年選択式の復習~労働安全衛生法
今日は労働安全衛生法です。
例年に比べると、解きやすい問題でした。
3 労働安全衛生法 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育について
令和2年に択一式で同じ問題が出ています。解いてみましょう。
【R2年出題】
事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならない。

【解答】 〇
ポイント!
雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育は、常時使用する労働者のみでなく「全労働者」が対象です。
4 事業者の責務について
第3条「事業者の責務」は、H18年の選択式にも出題されています。
【H18年選択式】
労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて< A >なければならない。」と規定されている。

【解答】
A 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
令和4年は、「快適な職場環境の実現」が問われました。
令和4年度の労基・安衛選択式は、「過去問」の対策をしていれば得点できました。
★重要な条文は、繰り返し出題されます
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式①
復習しましょう/令和4年選択式①
R5-001
R4.8.29 令和4年選択式の復習~労基法
昨日は、本試験お疲れさまでした。
さっそく復習していきましょう。
今日は「労働基準法」です。
1 解雇予告期間の問題です。
<問題の主旨> 解雇予告手当を支払うことなく9月30日の終了をもって労働者を解雇しようとする場合、いつまでに解雇予告を行わなければならないでしょうか?
★ 解雇予告手当を支払うことなく、解雇しようとする場合は、「30日以上前」に解雇予告をしなければなりません。
★「解雇の予告を行った日」は、解雇予告期間の計算に算入されないのがポイントです。
平成26年に同じ問題が出題されています。解いてみましょう。
【H26年出題】
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

【解答】 ×
9月30日の終了をもって解雇するためには、8月31日には解雇の予告をしなければなりません。
民法の一般原則によって、解雇予告を行った日は、解雇予告期間に算入されないため、予告期間は予告を行った日の翌日から計算されます。
2 東亜ペイント事件(S61.7.14最二小判)からの出題です。
判例の内容を順を追って読んでみましょう。
・使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきである
↓
・ しかし、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制限に行使することができるものではなく、これを濫用することは許されない。
↓
・当該転勤命令について、業務上の必要性が存しない場合又は業務上の必要性が存する場合であっても当該転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合等、特段の事情がない場合には、当該転勤命令は権利の濫用に当たらないというべきである。
 ・業務上の必要性がない場合、・不当な動機・目的をもってなされた場合、・労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等特段の事情がある場合には、その転勤命令は権利の濫用に当たります。
・業務上の必要性がない場合、・不当な動機・目的をもってなされた場合、・労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合等特段の事情がある場合には、その転勤命令は権利の濫用に当たります。
結論は、「本件転勤命令には業務上の必要性が優に存在し、労働者に与える不利益も通常甘受すべき程度であり、権利を濫用したとはいえない。」というものです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします