合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和4年度版
毎日コツコツ。 社労士受験のあれこれ
(過去記事)
このページは令和4年度版です。
 穴埋め式で確認・第1条
穴埋め式で確認・第1条
R4-371
R4.8.28 第1条をチェック(一般常識編)
空欄を埋めてみましょう。
★男女雇用機会均等法
第1条 (目的) この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
第2条 (基本的理念) 1 この法律においては、労働者が< A >により差別されることなく、また、女性労働者にあっては< B >を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。 2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。 |

【解答】
★男女雇用機会均等法
A 性別
B 母性
★労働組合法
第1条 (目的) この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の< C >させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の< D >を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する< E >を締結するための< F >をすること及びその手続を助成することを目的とする。 |

【解答】
★労働組合法
C 地位を向上
D 団体行動
E 労働協約
F 団体交渉
★国民健康保険法
第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって< G >に寄与することを目的とする。 |

【解答】
★国民健康保険法
G 社会保障及び国民保健の向上
★介護保険法
第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< I >し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< J >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び< K >を図ることを目的とする。 |

【解答】
★介護保険法
Ⅰ 尊厳を保持
J 国民の共同連帯
K 福祉の増進
★高齢者の医療の確保に関する法律
第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< L >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< M >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の< N >を図ることを目的とする。 |

【解答】
★高齢者の医療の確保に関する法律
L 国民の共同連帯
M 費用負担
N 福祉の増進
★社会保険労務士法
第1条 (目的) この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< O >と労働者等の< P >に資することを目的とする。 |

【解答】
★社会保険労務士法
O 健全な発達
P 福祉の向上
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 穴埋め式で確認・第1条
穴埋め式で確認・第1条
R4-370
R4.8.27 第1条をチェック(社会保険編)
空欄を埋めてみましょう。
★健康保険法
第1条 (目的) この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< A >に寄与することを目的とする。
第2条 (基本的理念) 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< B >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< C >制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける< D >の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。 |

【解答】
★健康保険法
A 福祉の向上
B 高齢化
C 後期高齢者医療
D 医療の質
★国民年金法
第1条 (国民年金制度の目的) 国民年金制度は、< E >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< F >に寄与することを目的とする。 |

【解答】
★国民年金法
E 日本国憲法第25条第2項
F 健全な国民生活の維持及び向上
★厚生年金保険法
第1条 (この法律の目的) この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と< G >に寄与することを目的とする。 |

【解答】
★厚生年金保険法
G 福祉の向上
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 穴埋め式で確認・第1条
穴埋め式で確認・第1条
R4-369
R4.8.26 第1条をチェック(労働編)
空欄を埋めてみましょう。
★労働基準法
第1条 (労働条件の原則) ① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 |

【解答】
★労働基準法
A 人たるに値する生活
B 基準
★労働安全衛生法
第1条 (目的) この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< C >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< D >を確保するとともに、< E >を促進することを目的とする。 |

【解答】
★労働安全衛生法
C 自主的活動
D 安全と健康
E 快適な職場環境の形成
★労働者災害補償保険法
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< F >の確保等を図り、もって労働者の < G >に寄与することを目的とする。 |

【解答】
★労働者災害補償保険法
F 安全及び衛生
G 福祉の増進
★雇用保険法
第1条 (目的) 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< H >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< I >を図ることを目的とする。 |

【解答】
★雇用保険法
H 子を養育するための休業
Ⅰ 福祉の増進
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-368
R4.8.25 過去問から選択対策・安衛法
過去問から選択問題をチェックしましょう。
では、どうぞ!
①【H19年選択式】
労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、< A >において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という。)」と定義されている。

【解答】
①【H19年選択式】
A 一の場所
②【H20年選択式】
労働者の健康の保持増進のための措置として、労働安全衛生法第69条第1項では、「事業者は、労働者に対する< B >その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない」とされている。
また、事業者の講ずるこれらの措置は、危険有害要因の除去のための措置とは異なり、その性質上、労働者の努力なくしては予期した効果を期待できないものであることから、同条第2項では、「労働者は、前項の事業者が講ずる措置を< C >して、その健康の保持増進に努めるものとする」とされている。

【解答】
②【H20年選択式】
B 健康教育及び健康相談
C 利用
③【H22年選択式】
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、作動部分上の< D >又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で < E >してはならない。」と規定されている。

【解答】
③【H22年選択式】
D 突起物
E 展示
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険・国民年金事業の概況
厚生年金保険・国民年金事業の概況
R4-367
R4.8.24 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をチェックしましょう。
★適用状況 ・ 公的年金被保険者数は、令和2年度末現在で6,756万人となっており、前年度末に比べて6万人(0.1%)減少している。 ・ 国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、令和2年度末現在で1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)減少している。 ・ 厚生年金被保険者数(第1~4号)は、令和2年度末現在で4,513万人(うち第1号4,047万人、第2~4号466万人)となっており、前年度末に比べて25万人 (0.6%)増加している。 ・ 国民年金の第3号被保険者数は、令和2年度末現在で793万人となっており、前年度末に比べて27万人(3.3%)減少している。
★厚生年金保険 適用状況 ※ この統計では基本的に、被用者年金一元化により新たに厚生年金保険の適用対象となった、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団の情報を含まない。 ・ 令和2年度末現在の適用事業所数は、250万9千か所であり、前年度末に比べて7.4万か所(3.0%)増加している。 ・ 被保険者数は、令和2年度末現在で4,047万人となっており、前年度末に比べて 10万人(0.2%)増加している。男女別にみると、男子は2,479万人(対前年度末比9万人、0.4%減)、女子は1,569万人(対前年度末比19万人、1.2%増)となっている。 ・ 短時間労働者数は、令和2年度末現在で53万人となっており、前年度末に比べて6万人(12.3%)増加している。男女別にみると、男子は14万人(対前年度末比1万人、6.6%増)、女子は39万人(対前年度末比5万人、14.4%増)となっている。 ・ 育児休業等期間中(産前産後休業期間を含む)の保険料免除者数は、令和2年度末現在で45万人であり、前年度末に比べて2万人(5.0%)増加している。男女別にみると、男子は1万人(対前年度末比3千人、35.2%増)、女子は44万人(対前年度末比2万人、4.5%増)となっている。
★国民年金 適用状況(第1号被保険者及び第3号被保険者) ・ 令和2年度末現在の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)減少している。男女別にみると、男子は758万人(対前年度末比1万人、0.2%増)、女子は691万人(対前年度末比5万人、0.7%減)となっている。 ・ 令和2年度末現在の第3号被保険者数は、793万人となっており、前年度末に比べて27万人(3.3%)減少している。男女別にみると、男子は12万人(対前年度末比3千人、2.9%増)、女子は781万人(対前年度末比28万人、3.4%減)となっている。 ・ 令和2年度末現在の全額免除・猶予者数は609万人、全額免除・猶予割合は 42.6%となっている。 ・ 令和2年度末現在の一部免除者数は36万人、一部免除割合は2.5%となっている。 ・ また、令和元年度から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が施行されている。令和2年度末現在の産前産後免除者数は、1万人となっている。 |
問題を解いてみましょう。
【問題1】
国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、令和2年度末現在で1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)< A >している。
(選択肢)
① 増加
② 減少
【問題2】
短時間労働者数は、令和2年度末現在で53万人となっており、前年度末に比べて 6万人(12.3%)増加している。男女別にみると、男子は< B >万人(対前年度末比1万人、6.6%増)、女子は< C >万人(対前年度末比5万人、14.4%増)となっている。
(選択肢)
① 14
② 30
③ 39
④ 23
【問題3】
令和元年度から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が施行されている。令和2年度末現在の産前産後免除者数は、< D >万人となっている。
(選択肢)
① 1
② 10
③ 100

【解答】
【問題1】
A ② 減少
【問題2】
B ① 14
C ③ 39
【問題3】
D ① 1
参照:厚生労働省『令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 能力開発基本調査
能力開発基本調査
R4-366
R4.8.23 令和3年度「能力開発基本調査」の結果
令和3年度能力開発基本調査の結果を読んでみましょう。
★労働者に求める能力・スキルについて 企業の発展にとって最も重要と考える労働者の能力・スキルについて、管理職を除く正社員では、50歳未満では、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」 ( 55.7%)、「職種に特有の実践的スキル」(41.4%)の順で、50歳以上では、「マネジメント能力・リーダーシップ」(55.6%)、「課題解決スキル(分析・思考・創造力等)」(39.3%)の順で、それぞれ多くなっている。正社員以外では、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」(56.2%)、「職種に特有の実践的スキル」(34.1%)の順で多くなっている。
★ 能力開発や人材育成に関する問題点 能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所は、76.4%となり、4分の3以上の事業所で、能力開発や人材育成に関する問題があることがうかがえる。 能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所のうち、問題点の内訳は、「指導する人材が不足している」(60.5%)が最も高く、「人材育成を行う時間がない」(48.2%)、「人材を育成しても辞めてしまう」(44.0%)と続いている。
★ 自信のある能力・スキル 仕事をする上で自信のある能力・スキルがあると回答した割合は、労働者全体で87.6%であり、正社員では90.3%、正社員以外では82.7%となっている。 自信のある能力・スキルの内容については、「チームワーク、協調性・周囲との協働力」が最も多く、正社員で51.5%、正社員以外で57.1%となっている。次いで、「定型的な事務・業務を効率的にこなすスキル」(正社員 41.2%、正社員以外 40.7%)が多くなっている。 また、最も少ない回答は、正社員では「語学(外国語)力」(2.4%)、正社員以外では「専門的なITの知識・能力(システム開発・運用、プログラミング等)」 (1.5%)となっている。 |
では、問題を解いてみましょう。
【問題1】
企業の発展にとって最も重要と考える労働者の能力・スキルについて、管理職を除く正社員では、50歳未満では、「< A >」( 55.7%)、「職種に特有の実践的スキル」(41.4%)の順で、50歳以上では、「マネジメント能力・リーダーシップ」(55.6%)、「課題解決スキル(分析・思考・創造力等)」(39.3%)の順で、それぞれ多くなっている。正社員以外では、「< A >」(56.2%)、「職種に特有の実践的スキル」(34.1%)の順で多くなっている。
(選択肢)
① 営業力・接客スキル
② コミュニケーション能力・説得力
③ チームワーク、協調性・周囲との協働力
【問題2】
能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所は、76.4%となり、4分の3以上の事業所で、能力開発や人材育成に関する問題があることがうかがえる。
能力開発や人材育成に関して何らかの問題があるとする事業所のうち、問題点の内訳は、「< B >」(60.5%)が最も高く、「人材育成を行う時間がない」(48.2%)、「人材を育成しても辞めてしまう」(44.0%)と続いている。
(選択肢)
① 適切な教育訓練機関がない
② 指導する人材が不足している
③ 育成を行うための金銭的余裕がない
【問題3】
仕事をする上で自信のある能力・スキルがあると回答した割合は、労働者全体で87.6%であり、正社員では90.3%、正社員以外では82.7%となっている。
自信のある能力・スキルの内容については、「< C >」が最も多く、正社員で51.5%、正社員以外で57.1%となっている。次いで、「定型的な事務・業務を効率的にこなすスキル」(正社員 41.2%、正社員以外40.7%)が多くなっている。
(選択肢)
① チームワーク、協調性・周囲との協働力
② コミュニケーション能力・説得力
③ 課題解決スキル(分析・思考・創造力等)

【解答】
【問題1】
A ③ チームワーク、協調性・周囲との協働力
【問題2】
B ② 指導する人材が不足している
【問題3】
C ① チームワーク、協調性・周囲との協働力
※厚生労働省『令和3年度「能力開発基本調査」の結果』を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00105.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-365
R4.8.22 選択対策・在職時改定と退職時改定
令和4年4月から、在職時改定が導入されています。
65歳以上の者は、「在職中」であっても、毎年1回、定時に年金額の改定を行うことになりました。
資格喪失時(退職時・70歳到達時)の老齢厚生年金の額の改定(退職時改定)は、もともとありましたが、今回の改正で、退職を待たずに、就労した分が早期に年金額に反映されることになりました。
穴埋め式で条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
第43条 (年金額) 1 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額 (被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、< A >を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2 受給権者が毎年< B > (以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する< C >の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する< D >から、年金の額を改定する。 ただし、基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し、かつ、当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が< E >以内である場合は、基準日の属する< C >の被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、基準日の属する< D >から、年金の額を改定する。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して< E >を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して< F >から、年金の額を改定する。 |

【解答】
A 再評価率
B 9月1日
C 月前
D 月の翌月
E 1月
F 1月を経過した日の属する月
 在職時改定について
在職時改定について
→ 第43条第2項が改正で導入された「在職時改定」です。
★在職時改定で、年金額が改定されるのは、基準日の属する月の翌月(10月分)からです。
★在職時改定が適用されるのは、「65歳以上」の老齢厚生年金の受給権者です。
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金の受給権者には在職時改定は適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
在職老齢年金の受給権者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合、当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、平成28年3月から年金額が改定される。
②【R2年出題】
被保険者である老齢厚生年金の受給権者(昭和25年7月1日生まれ)が70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における老齢厚生年金は、当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の計算の基礎となり、令和2年8月分から年金の額が改定される。

【解答】
①【H28年出題】 ×
従来からある「退職時改定」の問題です。
退職時改定による老齢厚生年金の額は、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から改定されます。
ただし、第14条第2号(その事業所又は船舶に使用されなくなったとき)、第3号(適用事業所でなくする認可があったとき、任意単独被保険者の資格喪失の認可があったとき)、第4号(適用除外に該当するに至ったとき)までのいずれかに該当するに至った場合は、「その日」から起算して1月を経過した日の属する月から改定されます。
問題文の場合は、1月31日に退職(事業所に使用されなくなった)ですので、1月31日から起算して1月を経過した日(2月末日)の属する月=平成28年2月から老齢厚生年金の額が改定されます。
②【R2年出題】 ×
同じく「退職時改定」の問題です。
7月1日生まれの者が70歳になり資格を喪失するのは、70歳に達した日=6月30日です。
資格を喪失した日(6月30日)から起算して1月を経過した日(7月31日)の属する月=7月分から老齢厚生年金の額が改定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-364
R4.8.21 選択対策・付加保険料
第1号被保険者は、毎月の保険料にプラスして付加保険料を納付することができます。
穴埋め式で、条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
第87条の2 1 第1号被保険者(法定免除、申請全額免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の< A >以後の各月につき、毎月の保険料のほか、< B >円の付加保険料を納付する者となることができる。 2 付加保険料の納付は、毎月の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く。)又は産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。 3 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の< C >以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 4 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その< D >日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなす。 |

【解答】
A 属する月
B 400
C 属する月の前月
D 加入員となった
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。
②【H26年出題】
保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。
③【R1年出題】
付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。
④【H30年出題】
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
⑤【H27年出題】
付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
⑥【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

【解答】
①【H29年出題】 ×
半額免除を受けている期間は、付加保険料は納付できません。
※ 法定免除、申請全額免除、一部免除、学生納付特例・納付猶予の規定で保険料を納付することを要しないものとされている者は、付加保険料は納付できません。
②【H26年出題】 ×
追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月は、付加保険料は納付できません。
③【R1年出題】 ×
「産前産後期間の保険料免除」を受けた月については、付加保険料を納付することができます。
④【H30年出題】 ×
付加保険料を納付する者でなくなるのは、その申し出をした日の属する月の「前月」以後の各月です。
⑤【H27年出題】 〇
国民年金基金の加入員は、付加保険料を納めることができないからです。
⑥【R2年出題】 〇
任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができます。
※ちなみに、特例の任意加入被保険者は、付加保険料を納付できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-363
R4.8.20 任意継続被保険者の資格喪失
任意継続被保険者の資格喪失を確認しましょう。
条文の空欄を埋めてみましょう。
第38条 (任意継続被保険者の資格喪失) 任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 1 任意継続被保険者となった日から起算して< A >を経過したとき。 2 死亡したとき。 3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 4 被保険者となったとき。 5 < B >の被保険者となったとき。 6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 7 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、< C >が到来したとき。 |

【解答】
A 2年
B 船員保険
C その申出が受理された日の属する月の末日
ポイント!
※第7号は改正で追加されました。
任意継続被保険者本人の申出により、資格を喪失することが可能になりました。
保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したときの「翌日」(=受理された日の翌月1日)に資格を喪失します。
例えば、8月20日に資格喪失の申出が受理された場合は、9月1日が資格喪失日となります。
※「翌日」喪失が原則ですが、第4号から第6号に該当した場合は、「当日」に資格を喪失します。
・ 被保険者となったとき。→ 当日喪失
・ 船員保険の被保険者となったとき。 → 当日喪失
・ 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 → 当日喪失
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
任意継続被保険者は、後期高齢者医療の被保険者となった日の翌日からその資格を喪失する。
②【H30年出題】
任意継続被保険者が75歳に達し、後期高齢者医療の被保険者になる要件を満たしたとしても、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過していない場合は、任意継続被保険者の資格が継続するため、後期高齢者医療の被保険者になることはできない。
③【H29年出題】
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いてはその月の10日とされている。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。
④【H27年出題】
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、督促状により指定する期限の翌日にその資格を喪失する。

【解答】
①【H26年出題】 ×
後期高齢者医療の被保険者となったときは、「その日」に任意継続被保険者の資格を喪失します。
②【H30年出題】 ×
任意継続被保険者が75歳に達し後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に任意継続被保険者の資格を喪失します。2年を経過していなくても、任意継続被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療の被保険者となります。
③【H29年出題】 〇
任意継続被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失します。
なお、任意継続被保険者の保険料の納付期日は、その月の10日です。
※初めて納付すべき保険料について
「初めて納付すべき保険料」の納付期日は、「保険者が指定する日」です。
「初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。」とされています。
④【H27年出題】 ×
「督促状により指定する期限の翌日」ではなく、納付期日(その月の10日)の翌日に資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-362
R4.8.19 「追徴金」の注意点
今日は、「追徴金」の注意点を確認しましょう。
「追徴金」が徴収されるのは、
・「政府が確定保険料の額を認定決定したとき」と
・「政府が印紙保険料額を認定決定したとき」です。
次に、「滞納処分」と「延滞金」の条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) 1労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 3 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
第28条 (延滞金) 政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、労働保険料の額が1000円未満であるときは、延滞金を徴収しない。 ※令和4年の延滞金の割合は、年14.6%→年8.7%、年7.3%→年2.4%です。 |
 第27条の「督促と滞納処分」は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」が対象、第28条の「延滞金」は「労働保険料」のみが対象になっていることに注目してください。
第27条の「督促と滞納処分」は「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」が対象、第28条の「延滞金」は「労働保険料」のみが対象になっていることに注目してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題(雇用保険)】
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
②【H22年出題(雇用保険)】
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。
③【H26年出題(雇用保険)】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】
①【R1年出題(雇用保険)】 〇
「追徴金」が入っている点がポイントです。
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」とは、「労働保険料」と「その他この法律の規定による徴収金」です。
「追徴金」は労働保険料ではありませんが、「その他この法律の規定による徴収金」として、督促、滞納処分の対象になります。
(昭55.6.5発労徴40号)
②【H22年出題(雇用保険)】 ×
追徴金を納付しないときは、「国税滞納処分の例によって処分」されることはありますが、延滞金が徴収されることはありません。
第28条の延滞金が徴収されるのは、「労働保険料の納付を督促したとき」に限られます。追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しなかったとしても延滞金は徴収されません。
③【H26年出題(雇用保険)】 ×
追徴金は労働保険料ではありませんので、納付しない場合でも延滞金は徴収されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-361
R4.8.18 選択対策・高年齢被保険者の特例
改正された「高年齢被保険者の特例」を確認しましょう。
65歳以上のマルチジョブホルダーが雇用保険の被保険者になることができるようになりました。
「マルチジョブホルダー」とは、2以上の事業主の適用事業に雇用され、いずれの事業主においても1週間の所定労働時間が20時間未満であるが、そのうち2の事業主における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である労働者をいう、と定義されています。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1010より)
では、空欄を埋めてみましょう。
第37条の5 (高年齢被保険者の特例)
次の①から③に掲げる要件のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該< A >から高年齢被保険者となることができる。
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される< B >歳以上の者であること。
② 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< C >未満であること。
③ 2の事業主の適用事業(申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が< D >以上であるものに限る。)における1週間の所定労働時間の合計が< E >以上であること。
則第65条の6 (厚生労働省令で定める申出)
法第37条の5第1項の申出は、所定の事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届と併せて< F >公共職業安定所の長に提出することによって行うものとする。

【解答】
A 申出を行った日
B 65
C 20時間
D 5時間
E 20時間
F 管轄
「高年齢被保険者の特例」のポイントです!
※ここから「マルチ高年齢被保険者」といいます。
・マルチ高年齢被保険者に関する資格取得手続きは、必ず本人からの申出によることとなります。(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1090)
・マルチ高年齢被保険者となる日は「申出を行った日」です。遡及による資格確認は行いません。
(マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)
・「管轄公共職業安定所の長(当該者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長)」に申し出ます。
・2の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれないものは、マルチ高年齢被保険者となりません。 (マルチジョブホルダー業務取扱要領 1070)
まとめ
マルチ高年齢被保険者は以下の要件をすべて満たすことが必要です。
⓵ 2以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者
⓶ 2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
⓷ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
※ 雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。
※ 2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
(参照:厚生労働省ホームページ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-360
R4.8.17 選択対策・疾病の範囲
今日は選択式の練習です。
空欄を埋めてみましょう。
過去問をどうぞ!
①【H18年選択式】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。

【解答】
A 労働基準法施行規則
B 労働者災害補償保険法施行規則
C 業務に起因することの明らかな疾病
D 通勤による負傷
E 通勤に起因することの明らかな疾病
こちらもどうぞ!
空欄を埋めてみましょう。
法第20条の3
複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する2以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6 (複数業務要因災害による疾病の範囲)
法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、< F > 別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他< G >とする。

【解答】
F 労働基準法施行規則
G 2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病
★Fについて
労働基準法施行規則別表第1の2の第8号は「過重負荷による脳・心臓疾患」、第9号は「心理的負荷による精神障害」です。
<複数業務要因災害の範囲>
複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災則第 18 条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている、とされています。
(令和2年8月 21 日 基発 0821 第1号より)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-359
R4.8.16 安衛法の選択対策
今日は選択式の練習です。
空欄を埋めてみましょう。
第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、< A >及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
第29条 (元方事業者の講ずべき措置等)
1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な< B >を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な < C >を行なわなければならない。
3 2の< C >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該< C >に従わなければならない。
第31条の4
注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その< D >に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる< D >をしてはならない。
第35条 (重量表示)
一の貨物で、重量が< E >以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
第66条第4項 健康診断
< F >は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、< G >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を< H >することができる。

【解答】
A 風紀
B 指導
C 指示
D 指示
E 1トン
F 都道府県労働局長
G 労働衛生指導医
H 指示
★F、G、Hについて
・労働衛生指導医について
第95条第1項で、「都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く。」と規定されています。
また、第95条第2項で、「労働衛生指導医は、第65条第5項(都道府県労働局長の指示する作業環境測定の実施)又は第66条第4項(都道府県労働局長の指示する臨時の健康診断)の規定による指示に関する事務その他労働者の衛生に関する事務に参画する。」と規定されています。
・第65条第5項も確認しておきましょう。
「都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-358
R4.8.15 休業手当のポイント!
まず、休業手当の条文を読んでみましょう。
第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H21年選択式】
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< A >という観点から設けられたものであり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の < A >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度での負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とするといわなければならない」としている。
②【H27年出題】
当該労働者の労働条件は次のとおりである。
所定労働日:毎週月曜日から金曜日
所定休日:毎週土曜日及び日曜日
所定労働時間:1日8時間
賃金:日給15,000円
計算された平均賃金:10,000円
使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。
③【H27年出題】
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しない。

【解答】
①【H21年選択式】
A 生活保障
★休業手当は、労働者の「生活保障」のための制度です。
(昭62.7.17最高裁判所第二小法廷)
②【H27年出題】 〇
★1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合
↓
その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければなりません。
問題文は、平均賃金が10,000円で、その日の賃金として平均賃金の100分の60以上の7,500円の支払がなされていますので、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法となりません。
ちなみに、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければなりません。
(昭27.8.7基収3445号)
③【H27年出題】 〇
休電による休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しませんので、休業手当を支払わなくても26条違反になりません。
(昭26.10.11基発696号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保障統計
社会保障統計
R4-357
R4.8.14 介護保険・後期高齢者医療の統計
出題実績のある統計をチェックしましょう。
<令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査> ■被保険者の年齢構成 令和3年9月30日現在の被保険者数は18,145千人となっており、うち75歳以上の被保険者数は17,852千人で、被保険者の98.4%を占めている。一定の障害の状態にあるとして認定を受けた65歳から74歳の被保険者数は293千人となっている。また、被保険者の平均年齢は82.9歳となっている。 |
<令和元年度 介護保険事業状況報告> ■要介護(要支援)認定者数 要介護(要支援)認定者(以下「認定者」という。)数は、令和元年度末現在で 669万人となっている。うち、第1号被保険者は656万人(男性204万人、女性452万人)、第2号被保険者は13万人(男性7万人、女性6万人)となっている。
認定を受けた第1号被保険者のうち、前期高齢者(65歳~75歳未満)は73万人、後期高齢者(75歳以上)は583万人で、第1号被保険者の認定者に占める割合は、それぞれ11.1%、88.9%となっている。
認定者を要介護(要支援)状態区分別にみると、要支援1:93万人、要支援2: 94万人、要介護1:135万人、要介護2:116万人、要介護3:88万人、要介護4:82万人、要介護5:60万人となっており、軽度(要支援1~要介護2)の認定者が 約65.6%を占めている。 |
では、問題をどうぞ!
【問1】 (平成27年に出題された問題を修正しています。)
「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省)」によると、令和3年9月30日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数は、5,547千人となっており、うち75歳以上の被保険者数は被保険者の79.6%を占めている。
【問2】 (平成27年に出題された問題を修正しています。)
「令和元年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」によると、要介護(要支援)認定者数は、令和元年度末現在で1,561万人となっており、そのうち軽度(要支援1から要介護2)の認定者が、全体の約83.5%を占めている。

【解答】
【問1】 ×
「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省)」によると、令和3年9月30日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数は、「18,145千人」で、うち75歳以上の被保険者数は被保険者の「98.4%」を占めています。
【問2】 ×
「令和元年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」によると、要介護(要支援)認定者数は、令和元年度末現在で「669万人」で、そのうち軽度(要支援1から要介護2)の認定者が、全体の約「65.6%」を占めています。
※厚生労働省「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai.html
※厚生労働省「令和元年度 介護保険事業状況報告」を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/19/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 就労条件総合調査
就労条件総合調査
R4-356
R4.8.13 令和3年就労条件総合調査「労働時間制度」
令和3年就労条件総合調査「労働時間制度」のポイントを読んでみましょう。
■ 週休制 主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 83.5%(令和2年調査 82.5%)となっており、このうち「完全週休2日制」を採用している企業割合は 48.4%(同 44.9%)となっている。 「完全週休2日制」を採用している企業を企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 66.7%、「300~999 人」が 60.0%、「100~299 人」が 53.7%、 「30~99 人」が 45.0%となっている。
■ 変形労働時間制 変形労働時間制を採用している企業割合は 59.6%(令和2年調査 59.6%)となっている。これを企業規模別にみると、「1,000 人以上」が 76.4%、「300~999 人」が 69.5%、「100~299 人」が 63.1%、「30~99 人」が 56.9%となっており、また、変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、「1年単位の変形労働時間制」が 31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が 25.0%、「フレックスタイム制」が 6.5%となっている。
■みなし労働時間制 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は 8.2%(令和2年調査 8.9%)となっており、これをみなし労働時間制の種類別にみると、「事業場外みなし労働時間制」が 6.7%、「専門業務型裁量労働制」が 1.2%、「企画業務型裁量労働制」が 0.3%となっている。 |
では、問題を解いてみましょう。
(H28年の過去問を参考にしています。)
問1から問3は、「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
【問1】 何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
【問2】 フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。
【問3】 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

【解答】
【問1】 ×
30~99人規模の企業で、完全週休2日制を採用している割合は、45.0%です。「3割にとどまっている」は誤りです。
【問2】 ×
フレックスタイム制を採用している企業割合は、6.5%です。「3割を超えている」は誤りです。
【問3】 〇
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、8.2%です。10パーセントに達していません。
厚生労働省「令和3年就労条件総合調査」の概況を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaikyou.pdf
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-355
R4.8.12 「厚年」被保険者期間
今回のテーマは「被保険者期間」です。
条文を読んでみましょう。
第19条 1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 |
 「被保険者期間」は「月」単位でカウントします。
「被保険者期間」は「月」単位でカウントします。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。
②【H30年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
③【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「被保険者であった期間」と「被保険者期間」は違いますので、注意しましょう。
資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの「日単位」で計算される期間は「被保険者であった期間」です。
「被保険者期間」は、資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までの「月単位」で計算される期間です。
②【H30年出題】 〇
H29年 10月 | 11月 | 12月 | H30年 1月 | 2月 | 3月 |
資格取得 |
|
|
|
| 資格喪失 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間です。
資格を取得した月(平成29年10月)からその資格を喪失した月の前月(平成30年2月)までの「月単位」で計算されます。資格を喪失した月(平成30年3月)は被保険者期間には算入されません。
③【H28年出題】 〇
平成28年3月 | |
3/1・・・・・・・・・・・3/20 | 3/21・・・・・・・・・・・・・・・・ |
厚生年金保険 被保険者 | 国民年金 第1号被保険者 |
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪といいます)は、その月は、「1箇月」として被保険者期間に算入されます。
ただし、問題文のように、その月に更に国民年金の第1号被保険者の資格を取得したときは、被保険者期間には算入されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-354
R4.8.11 国民年金の保険料前納
令和4年度の国民年金の保険料は16,590円です。
国民年金の保険料には、前納制度があり、割引があるのがポイントです。
条文を読んでみましょう。
第93条 (保険料の前納) 1 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
令第7条 (保険料の前納期間) 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。 令第8条 (前納の際の控除額) 政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に10円未満の端数がある場合において、その端数金額が5円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときは、これを10円として計算する。)を控除した額とする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。
②【H26年出題】
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。
③【H27年出題】
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる
④【H28年出題】
国民年金保険料を1年分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。
⑤【H21年出題】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
⑥【H30年出題】
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
一部免除の保険料も前納することができます。
②【H26年出題】 〇
前納の期間の原則は、「6か月」単位又は「年」単位ですが、「6か月」又は「年」以外の単位の前納も可能です。
③【H27年出題】 〇
2年間の前納は、口座振替でも可能ですが、納付書による現金納付、クレジットカードでも可能です。
④【H28年出題】 ×
1年分前納する場合、割引率が高いのは、口座振替による支払の方です。
⑤【H21年出題】 〇
「年4分の利率による複利現価法」を覚えておきましょう。
⑥【H30年出題】 ×
前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「前納に係る期間の各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
健康保険の任意継続被保険者の前納との違いをおさえてください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-353
R4.8.10 任意継続被保険者の保険料前納
任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負います。
任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、その月の10日(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)です。
今回は、任意継続被保険者の保険料の「前納」を確認しましょう。
第165条 (任意継続被保険者の保険料の前納) 1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 2 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 3 前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
令48条 (保険料の前納期間) 任意継続被保険者の保険料の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を取得した日の属する月の翌月以降の期間又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
令第49条 (前納の際の控除額) 法第65条第2項の政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。
②【H26年出題】
任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。
③【H22年選択式】 ※修正あり
1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の< A >が到来したときに、それぞれの月の保険料が納付されたものとみなす。
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< B >までに払い込まなければならない。
前納すべき保険料額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< C >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、< D >である。

【解答】
①【R2年出題】 ×
前納の場合、保険料の割引があります。
②【H26年出題】 〇
前納の期間の単位は、「4月から9月まで」、「10月から翌年3月まで」の6か月間又は「4月から翌年3月まで」の12か月間です。
しかし、例外もあります。
・途中で任意継続被保険者の資格を取得した者
→ 資格を取得した日の属する月の翌月分からの期間
・資格を喪失することが明らかである者
→ 資格を喪失する日の属する月の前月分までの期間
③【H22年選択式】 ※修正あり
A 各月の初日
B 初月の前月末日 (則第139条第1項)
C 年4分の利率
D 5月
Aについて
前納された保険料は、前納期間の「各月の初日」にその月分の保険料が納付されたとみなされます。
※国民年金の場合は、「各月が経過した際」に、その月分の保険料が納付されたとみなされます。
Bについて
「4月から9月までの6か月間」、「4月から翌年3月までの12か月間」の期限は、3月末日、「10月から翌年3月までの6か月間」の期限は、9月末日です。
Dについて
途中で資格取得した場合は、前納できるのは、資格を取得した日の属する月の翌月分からの期間となりますので、初月は5月となります。期間は、「5月から9月まで」又は、「5月から翌年3月まで」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-352
R4.8.9 納付書と納入告知書
徴収法では、「納付書」と「納入告知書」の区別が問われます。
「納入告知書」によるものを覚えておきましょう。
・有期事業に係るメリット制の差額の徴収 ・認定決定に係る確定保険料と追徴金 ・認定決定に係る印紙保険料と追徴金 ・特例納付保険料 |
納入告知書に係るもの以外は、「納付書」によります。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H22年出題】(労災)
労働保険徴収法第20条に規定する有期事業のメリット制の適用により、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該引き上げられた確定保険料の額と当該事業主が既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収するものとし、通知を発する日から起算して30日を経過した日を納期限と定め、当該納期限、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項を事業主に通知しなければならない。
③【H27年出題】(雇用)
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。
④【H25年出題】(雇用)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
「認定決定された概算保険料」の額の通知は、納入告知書ではなく、「納付書」で行われます。
なお、「認定決定された確定保険料」の額の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(則第38条)
②【H22年出題】(労災) 〇
有期事業のメリット制が適用され、確定保険料の額を引き上げた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、引き上げられた確定保険料の額と既に申告・納付した確定保険料の額との差額を徴収します。
問題文では触れられていませんが、この通知は、「納入告知書」によって行われます。
(法第20条、則第38条)
③【H27年出題】(雇用) 〇
特例納付保険料の額と納期限の通知は、「納入告知書」によって行われます。
(法第26条、則第38条、59条)
④【H25年出題】(雇用) 〇
認定決定による印紙保険料と追徴金の通知は「納入告知書」によって行われます。
この場合は、事業主は、雇用保険印紙ではなく、現金で納付することになります。
(法第25条、則第38条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-351
R4.8.8 高年齢雇用継続基本給付金の支給額
https://youtu.be/o4yVW49E-1A 高年齢雇用継続基本給付金(以下、「基本給付金」とします。)の額は、原則は、支給対象月に支払われた賃金額の15%です。
・支給対象月に支払われた賃金額が、「みなし賃金日額×30」の61%以上75%未満の場合 → 15%から一定の割合で逓減させた率で計算します。
・支給対象月に支払われた賃金+基本給付金の額が、支給限度額(360,584円)を超えるとき → 基本給付金の額は、「360,584円-支給対象月の賃金」となります。
・基本給付金の額が賃金日額の最低限度額の8割(2577円×0.8)を超えないとき → 基本給付金は支給されません。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。
②【H22年出題】
高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額。)となる。

【解答】
①【R1年出題】 〇
②【H22年出題】 〇
①と②ともに、「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満であることがポイントです。
「支給対象月に支払われた賃金の額」が、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の100分の61未満の場合
→ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給対象月の賃金額に100分の15を乗じて得た額」となります。
ただし、その額に支給対象月の賃金額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、「支給限度額から支給対象月の賃金額を減じて得た額」となります。
例えば、「みなし賃金日額に30を乗じて得た額(60 歳到達時の賃金月額)」が 30 万円で、「支給対象月に支払われた賃金」が 18 万円の場合、60歳時点の60%ですので、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、18万円×15%=2万7千円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-350
R4.8.7 遺族補償年金の失権
今日は、遺族補償年金の失権事由を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第16条の4 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 4 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 6 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 |
労災保険の遺族補償年金には、転給があるのがポイントです。
受給権者が失権したときに、後順位者があるときは、次順位者が受給権者になります。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。
②【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
③【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。
④【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
⑤【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 〇
事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、遺族補償年金の受給権は消滅します。
②【H28年出題】 〇
直系血族又は直系姻族以外の養子になったときは失権します。伯父は直系ではなく傍系となりますので、伯父の養子になった場合は失権事由に該当します。
③【H23年出題】 ×
労働者の死亡の時から「引き続き障害の状態にある」ときは、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても失権しません。
「労働者の死亡のときから引き続き」がポイントです。
労働者の死亡時に、障害要件を満たしていて引き続き障害の状態にある場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても失権しません。
④【H23年出題】 ×
労働者の死亡の当時年齢要件を満たしている場合は、障害の状態がなくなっても受給権には影響しません。
労働者の死亡の当時60歳以上であった祖父母は、年齢要件を満たしていますので、障害の状態がなくなっても、受給権は消滅しません。
⑤【H23年出題】 ×
孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは年齢要件を満たしていますので、障害の状態の有無は関係ありません。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にその障害の状態がなくなったとしても、受給権は消滅しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-349
R4.8.6 特定元方事業者の講ずべき措置
「特定元方事業者」とは、建設業・造船業に属する事業の元方事業者です。
特定元方事業者は、同一の場所でいくつかの会社が混在して作業を行うにあたり、労働災害を防止するための措置を講じなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第30条 (特定元方事業者等の講ずべき措置) 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調整を行うこと。 3 作業場所を巡視すること。 4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。 5と6は省略します。 |
特定元方事業者の講ずべき措置として、
「協議組織の設置及び運営」
「作業間の連絡及び調整」
「作業場所の巡視」
「教育に対する指導及び援助」
等があります。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
②【H27年出題】
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。
③【H20年出題】
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。

【解答】
①【H18年出題】 ×
「協議組織の設置及び運営」を行うことに関する措置を講じなければならないのは、「特定元方事業者」です。
「製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」は、「協議組織の設置及び運営」を行うことに関する措置を講じる義務はありませんので、この問題は「誤」となります。
ちなみに、「製造業に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者」については、「作業間の連絡及び調整を行う」ことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない、という規定はあります。(法第30条の2)
②【H27年出題】 ×
特定元方事業者の作業場所の巡視は、「毎作業日に少なくとも1回」、行わなければなりません。
(則第637条)
③【H20年出題】 ×
特定元方事業者が講ずるのは、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する「指導及び援助」を行うことです。安全衛生教育を行うことではありません。
安全衛生教育は、それぞれの事業者が行うべきものですので、関係請負人である事業者は、その労働者に対して、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-348
R4.8.5 労働者の過半数を代表する者
労働者側の当事者は、「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合」、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、「労働者の過半数を代表する者」となります。
今日は、「労働者の過半数を代表する者」の要件を見てみましょう。
では、条文を読んでみましょう。
則第6条の2 ① 過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 2 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であって、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
③ 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
④ 使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第41条第2項に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。
②【H22年出題】
労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者とされており、労働者の過半数を代表する者の選出は、必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない。
③【H25年出題】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働いているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
④【H19年出題】
使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「管理監督者」は、労働者の過半数を代表する者になることはできません。
なお、管理監督者は、労働基準法第9条の労働者に該当します。事業場の労働者の人数には管理監督者も含まれます。
(H11.3.31基発168号、H22.5.18基発0518第1号)
②【H22年出題】 ×
則第6条の2では、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続」と規定されています。
投票、挙手等の「等」には、労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが該当する、とされています。
「必ず投票券等の書面を用いた労働者による投票によって行わなければならない」ということはありません。
(H11.3.31基発169号)
③【H25年出題】 〇
「派遣労働者について」
・労働者の人数の算定
→ 派遣労働者は、派遣元の事業場の労働者に含まれます。
派遣先の事業場の労働者には派遣労働者は含まれません。
(S61.6.6基発333号)
④【H19年出題】 〇
過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、「解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならない」こととしたものであること。
「過半数代表者として正当な行為」には、法に基づく労使協定の締結の拒否、1年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれる」ものであること、とされています。
(H11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保障費用統計
社会保障費用統計
R4-347
R4.8.4 令和元(2019)年度社会保障費用統計
令和元(2019)年度社会保障費用統計のポイントを確認しましょう。
・ 2019 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は 123 兆 9,241 億円であり、対前年度増加額は 2 兆 5,254 億円、伸び率は 2.1%、対 GDP 比は 22.14%であり対前年度比で 0.34%ポイント増加した。
<社会保障給付費(ILO 基準)> (1)社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して部門別にみると、「医療」が 40 兆 7,226 億円で総額に占める割合は 32.9%、 「年金」が 55 兆 4,520 億円で44.7%、「福祉その他」が 27 兆 7,494 億円で 22.4%である。 (2)部門別給付費の対前年度伸び率は、「医療」が 2.5%、「年金」が 0.4%、「福祉その他」が 5.1%である。 (3)子どものための教育・保育給付費交付金が増加したことなどにより、「福祉その他」の伸び率が高かった。 |
では、問題をどうぞ!
<問題>
「令和元年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、令和元年度の社会保障給付費の総額は123 兆 9,241 億円であり、部門別にみると、「医療」が55 兆 4,520 億円で全体の44.7%を占めている。次いで「年金」が40 兆 7,226 億円で全体の32.9%、「福祉その他」は 27 兆 7,494 億円で 22.4%となっている。

【解答】 ×
「年金」が 55 兆 4,520 億円で全体の44.7%を占めていて、「医療」は 40 兆 7,226 億円で全体の32.9%です。
国立社会保障・人口問題研究所ホームページ(https://www.ipss.go.jp/)を参照しています
令和元年度社会保障費用統計(概要)
https://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-R01/R01-houdougaiyou.pdf
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年度の年金額改定
令和4年度の年金額改定
R4-346
R4.8.3 令和4年度年金額・物価変動率と名目手取り賃金変動率
まず、問題からどうぞ!
令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、< A >に従い改定されました。
< A >がマイナス0.4%となり、かつ< B >(マイナス0.2%)を下回るため、< A >を用いて改定されます。
また、< A >がマイナスのため、< C >(マイナス0.3%)による調整は行われませんが、翌年度以降の年金額改定時に繰り越されます。
【選択肢】
① 物価変動率
② マクロ経済スライド調整率
③ 名目手取り賃金変動率

【解答】
A ③ 名目手取り賃金変動率
B ① 物価変動率
C ② マクロ経済スライド調整率
 既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額は、原則として「物価変動率」に応じて改定されます。
既裁定者(68歳到達年度以後の受給権者)の年金額は、原則として「物価変動率」に応じて改定されます。
しかし、例外的に次の3つのパターンのどれかに当てはまる場合は、「名目手取り賃金変動率」を用いて改定します。
物価 | 賃金 |
| 物価 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| 賃金 |
| 物価 | 賃金 |
① ② ③
物価も賃金もプラス 物価がプラス 物価も賃金もマイナス
物価の方が伸びが大きい 賃金がマイナス 賃金の方が落込みが大きい
 令和4年度は、名目手取り賃金変動率も物価変動率もマイナスで、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っています。(上の図の③に当てはまります。)
令和4年度は、名目手取り賃金変動率も物価変動率もマイナスで、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)が物価変動率(▲0.2%)を下回っています。(上の図の③に当てはまります。)
そのため、新規裁定年金、既裁定年金ともに「名目手取り賃金変動率(▲0.4%)」を用いて改定されました。
また、賃金や物価による改定率がマイナスですので、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
 老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率で計算します。
老齢基礎年金の額は、780,900円×改定率で計算します。
令和3年度の改定率が1.000でしたので、
令和4年度の改定率は、1.000×0.996=0.996となります。
令和4年度の老齢基礎年金の額は、
780,900円×0.996 ≒ 77万7,800円となります。
※端数処理は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律
R4-345
R4.8.2 後期高齢者医療
条文を読んでみましょう。
第47条 (後期高齢者医療) 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第50条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 2 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
②【H22年出題】
市町村(特別区を含む。以下同じ)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
③【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
④【H23年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
後期高齢者医療は、高齢者の「疾病、負傷又は死亡」に関して必要な給付を行います。死亡についても給付の対象です。
②【H22年出題】 〇
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の運営主体です。
都道府県ごとにすべての市町村が加入して設けられています。
③【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、適用除外となっています。
④【H23年出題】 ×
保険料を徴収するのは、市町村(特別区を含む。)です。都道府県は徴収しません。
保険料を徴収するのは、後期高齢者医療広域連合ではないことにも注意してください。
後期高齢者医療広域連合の行う事務から、保険料の徴収の事務は除かれています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 就労条件総合調査
就労条件総合調査
R4-344
R4.8.1 令和3年就労条件総合調査「労働費用」
「労働費用」のポイントをみてみましょう。
★労働費用総額
令和2年(平成 31(令和元)会計年度)の「労働費用総額」は常用労働者 1 人 1 か月平均 408,140円となっています。
「労働費用総額」に占める「現金給与額」の割合は 82.0%、「現金給与以外の労働費用」の割合は 18.0%となっています。
★ 現金給与以外の労働費用
「現金給与以外の労働費用」73,296 円の内訳は、「法定福利費」50,283 円(構成割合68.6%)、「退職給付等の費用」15,955 円(同 21.8%)、「法定外福利費」4,882 円(同 6.7%)などとなっています。
★ 法定福利費
「法定福利費」50,283 円の内訳は、「厚生年金保険料」27,905 円(構成割合 55.5%)、「健康保険料・介護保険料」17,496 円(同 34.8%)、「労働保険料」3,695 円(同 7.3%)などとなっています。
★ 法定外福利費
「法定外福利費」4,882 円の内訳は、「住居に関する費用」2,509 円(構成割合 51.4%)、「医療保健に関する費用」729 円(同 14.9%)、「食事に関する費用」493 円(同 10.1%)などとなっています。
問題を解いてみましょう。
問題1
「令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)」によると、現金給与額が労働費用総額に占める割合は、< A >%である。
〈選択肢〉 ① 18.0 ② 42.0 ③ 53.0 ④ 82.0
問題2
現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合は、< B >%となっている。法定福利費の中で最も大きな割合を占めているのが< C >である。
〈選択肢〉
① 38.6 ② 68.6 ③ 78.6 ④ 98.6
⑤ 健康保険料・介護保険料 ⑥ 厚生年金保険料
⑦ 児童手当拠出金 ⑧ 労働保険料

【解答】
問題1
A ④ 82.0
問題2
B ② 68.6
C ⑥ 厚生年金保険料
※令和3年就労条件総合調査(厚生労働省)を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 障害者雇用状況
障害者雇用状況
R4-343
R4.7.31 令和3年障害者雇用状況の集計結果
ポイントを確認しましょう。
★民間企業における雇用状況
(雇用されている障害者の数)
・ 民間企業(43.5人以上規模の企業:法定雇用率2.3%)に雇用されている障害者
の数は597,786.0人で、前年より19,494.0人増加(対前年比3.4%増)し、18年連
続で過去最高となった。
(実雇用率、法定雇用率達成企業の割合)
・ 実雇用率は、10年連続で過去最高の2.20%(前年は2.15%)、法定雇用率達成
企業の割合は47.0%(同48.6%)であった。
(法定雇用率未達成企業の状況)
・ 令和3年の法定雇用率未達成企業は56,618社。そのうち、不足数が0.5人また
は1人である企業(1人不足企業)が、63.9%と過半数を占めている。
・ また、障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は32,644社であり、
未達成企業に占める割合は、57.7%となっている。
問題を解いてみましょう。
問題1
「令和3年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、法定雇用率を達成している民間企業の割合は、< A >%であった。
【選択肢】
① 27.0 ② 47.0 ③ 87.0 ④ 97.0
問題2
「令和3年障害者雇用状況の集計結果(厚生労働省)」によると、法定雇用率未達成企業のうち障害者を1人も雇用していない企業(0人雇用企業)は、未達成企業全体の< B >%であった。
【選択肢】
① 27.7 ② 57.7 ③ 87.7 ④ 97.7

【解答】
問題1
A ② 47.0
問題2
B ② 57.7
※厚生労働省「令和3年障害者雇用状況の集計結果」を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23014.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働組合基礎調査
労働組合基礎調査
R4-342
R4.7.30 令和3年「労働組合基礎調査」
今日は、令和3年労働組合基礎調査の結果を見てみましょう。
ポイントは3つです。
① 労働組合数、労働組合員数及び推定組織率
・労働組合数 → 23,392 組合 (前年より 369 組合(1.6%)減少しています)
・労働組合員数 → 1,007 万8千人(前年より3万8千人(0.4%)減少しています)
・推定組織率 → 16.9% (前年(17.1%)より 0.2 ポイント低下しています)
② 女性の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 → 347 万人(前年より3万4千人(1.0%)増加しています)
・推定組織率 → 12.8% (前年(12.8%)と同水準です)
③ パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 → 136 万3千人 (前年より1万2千人(0.8%)減少しています)
・全労働組合員数に占める割合は 13.6%
(前年(13.7%)より 0.1 ポイント低下しています)
・推定組織率 → 8.4% (前年(8.7%)より 0.3 ポイント低下しています)
では、問題を解いてみましょう。
問題1
「令和3年労働組合基礎調査(厚生労働省)」によると、労働組合の推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は約5割となっている。
問題2
「令和3年労働組合基礎調査(厚生労働省)」によると、女性の推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は12.8%で、前年と同水準となっている。
過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
政府は、毎年6月30日現在における労働組合数と労働組合員数を調査し、労働組合組織率を発表している。この組織率は、通常、推定組織率と言われるが、その理由は、組織率算定の分母となる雇用労働者数として「< A >」の結果を用いているからである。

【解答】
問題1 ×
労働組合の推定組織率は、16.9%です。
問題2 〇
女性の推定組織率は12.8%で、前年と同水準です。
【H28年選択式】
A 労働力調査
※厚生労働省「令和3年労働組合基礎調査の概況」を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/21/dl/gaikyou.pdf
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 最低賃金法
最低賃金法
R4-341
R4.7.29 最低賃金額と最低賃金の効力
使用者は、労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
賃金の最低限度は、最低賃金法に基づいて定められます。
条文を読んでみましょう。
第3条 (最低賃金額) 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によって定めるものとする。
第4条 (最低賃金の効力) 1 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。 2 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
②【H20年選択】
最低賃金法においては、「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については< A >とする。この場合において、< A >となった部分は、最低賃金< B >定をしたものとみなす。
③【H26年出題】
最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
最低賃金額は、時間又は日ではなく、「時間」によって定められます。
②【H20年選択】
A 無効
B と同様の
③【H26年出題】 ×
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。
最低賃金法第40条で、「第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
★「地域別最低賃金」額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法第40条で、50万円以下の罰金に処せられます。
★「特定最低賃金額」以上の賃金を支払わなかった場合は、労働基準法の全額払違反として、労働基準法第120条で、30万円以下の罰金に処せられます。→ 具体的には、特定最低賃金が適用される労働者に対して支払った賃金が、地域別最低賃金額以上特定最低賃金額未満の場合です。
※船員に適用される特定最低賃金について
船員に適用される特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法第40条の罰則が適用されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-340
R4.7.28 遺族厚生年金 子・孫の失権事由
遺族厚生年金の遺族となる子、孫は、被保険者等の死亡当時、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。(法第59条第1項第2号)
子・孫は一定の年齢になった、障害状態でなくなった場合は、遺族厚生年金の受給権が消滅します。
子・孫特有の失権事由を条文で確認しましょう。
法第63条第2項 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ① 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。 ② 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 ③ 子又は孫が、20歳に達したとき。 |
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、遺族厚生年金の受給権者である場合に、その事情が止んだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)又は20歳に達したとき、遺族厚生年金の受給権は消滅する。
②【H27年出題】 ※法改正による修正あり
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)が死亡したことにより、子が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その子が障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、子の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③【R1年出題】
障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、16歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに当該受給権は消滅する。一方、障害等級2級に該当する障害の状態にある子に遺族厚生年金の受給権が発生し、19歳のときに障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、20歳に達したときに当該受給権は消滅する。

【解答】
①【H19年出題】 〇
「18歳に達する日以後の最初の3月31日」までは、障害状態の有無は問われません。
1級又は2級の障害の状態にある子又は孫について、その事情が止んだときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは失権しません。
又、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫が、その状態のまま20歳に達したときは、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
②【H27年出題】 〇 ※法改正による修正あり
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態でなければ、子・孫の遺族厚生年金の受給権は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。
問題文のように、障害等級3級に該当する障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、消滅します。
③【R1年出題】 ×
・問題文の前半について
被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、16歳で障害等級3級に該当する障害の状態になりました。18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに3級の場合は、そこで受給権は消滅します。問題文の前半は「〇」です。
・問題文の後半について
被保険者等の死亡当時、障害等級2級の障害の状態だった子が、19歳のときに障害等級3級の障害の状態になりました。その場合は、「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。」に該当しますので、その時点で受給権は消滅します。「20歳に達したときに当該受給権は消滅する。」の部分が「×」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-339
R4.7.27 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
遺族厚生年金の失権事由の一つに「直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき」があります。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次に該当するに至ったときは、消滅する。 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき (法第63条第1項第3号) |
・養子となった場合でも、「直系血族、直系姻族の養子」であれば、失権しないのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権は、受給権発生後に直系姻族の養子となった場合であっても、消滅しない。
②【H23年出題】
被保険者であった者の死亡により、死亡した者の子(障害等級1級又は2級に該当する者を除く。)が遺族厚生年金の受給権者となった場合において、その後当該子が10歳で父方の祖父の養子となった場合でも、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了するまでは受給権は消滅しない。
③【H29年出題】
子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権は、「直系姻族の養子」となった場合は、消滅しません。
②【H23年出題】 〇
祖父は「直系血族」です。祖父の養子になっても失権しません。
③【H29年出題】 ×
被保険者等が死亡したことにより、生計を維持していた妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生しました。
その後、妻(子の母)が再婚し、子が妻(子の母)の夫の養子になりました。
子からみると、母と再婚した夫は直系姻族です。母と再婚した夫の養子になっても失権しません。
ちなみに、母(死亡した者の妻)の遺族厚生年金は、「婚姻した」ことにより、失権します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-338
R4.7.26 30歳未満の妻の遺族厚生年金
夫の死亡当時、夫によって生計を維持していた妻には、子の有無や年齢に関係なく遺族厚生年金の受給権が発生します。
今回は、夫の死亡当時30歳未満だった妻の遺族厚生年金の失権について確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
1 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに消滅する。 2 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに消滅する。 (法第63条第1項5項) |
ポイント! 夫の死亡当時30歳未満の妻について
1について
夫の死亡当時30歳未満で子がいない場合は、遺族基礎年金の受給権は取得できませんので、遺族厚生年金の受給権のみ取得します。
その場合は、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに失権します。
夫死亡
(妻27歳・子なし) 30歳
遺族厚生年金 |
← ← ← ← ← 5年 → → → → 失権
2について
夫の死亡当時子がある場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得します。
しかし、妻が30歳に到達する前に子の死亡等により、遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに失権します。
夫死亡
(妻27歳・子あり) 妻28歳
遺族厚生年金 | |
遺族基礎年金 | ← ← ← 5年 → → → 失権 |
子死亡
(遺族基礎年金失権)
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。
②【H29年出題】
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。
③【H26年出題】
遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しない場合、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに、その受給権は消滅する。

【解答】
①【R3年出題】 ×
夫の死亡の当時27歳で子のいない妻の遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときではなく、「遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき」に消滅します。
②【H29年出題】 ×
妻が30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日」から起算して5年を経過したときに遺族厚生年金の受給権が消滅します。
③【H26年出題】 〇
夫の死亡当時30歳未満で、遺族基礎年金の受給権を取得しない妻の遺族厚生年金の受給権は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したときに消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-337
R4.7.25 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金
今回は2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の遺族厚生年金です。
「短期要件」と「長期要件」で異なりますので、注意しましょう。
ポイントを確認しましょう。
(短期要件の場合)
・ 被保険者が、死亡したとき。
・ 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
・ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
死亡日▼
第3号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者 |
★被保険者が死亡した場合は、死亡日に加入していた実施機関が、裁定・支給事務を行います。
(長期要件の場合)
・ 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
※25年の計算には合算対象期間も入ります。
★それぞれの実施機関が、それぞれの加入期間ごとに裁定・支給事務を行います。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
②【H30年出題】
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

【解答】
①【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)の死亡は長期要件に該当します。
長期要件の遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給されます。
問題文の場合、「第1号厚生年金被保険者期間」分は、第1号の実施機関から、「第3号厚生年金被保険者期間」分は、第3号の実施機関から支給されます。
(第78条の32第2項)
②【H30年出題】 〇
障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合は、「短期要件」の遺族厚生年金が支給されます。
2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算して、遺族厚生年金の額の計算をします。
なお、1級・2級の障害厚生年金の受給権者の死亡による遺族厚生年金の裁定・支給の事務は、初診日に加入していた実施機関が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-336
R4.7.24 夫の遺族厚生年金
今日は、夫に支給される遺族厚生年金を見ていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
遺族厚生年金の支給対象になる「夫、父母、祖父母」については、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件です。
ただし、60歳に達するまでは支給停止され、遺族厚生年金は60歳から支給されます。
しかし、「夫」の場合は、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、60歳未満でも遺族厚生年金は支給停止されません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。
②【H29年出題】
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 ×
夫に対する当該遺族厚生年金は、夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳までの間でも、支給停止されません。遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。
②【H29年出題】 〇
妻の死亡当時の夫の状況
・夫の年齢は55歳 → 遺族厚生年金の受給権が発生します
・15歳の子と生計を同じくしている → 遺族基礎年金の受給権が発生します。
夫の遺族厚生年金は、原則は60歳までは支給停止されますが、遺族基礎年金の受給権を有しているので、60歳前でも支給停止にならず、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができます。
しかし、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金の受給権が消滅します。その際、夫はまだ60歳に達していませんので、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は、原則どおり遺族厚生年金は支給停止となります。
(妻死亡)
夫55歳
子15歳 子18歳年度末 夫60歳
遺族厚生年金 | 支給停止 | 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金 |
|
|
遺族基礎年金失権
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-335
R4.7.23 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金のポイントを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第78条の30 (障害厚生年金の額の特例) 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。
第78条の31 (障害手当金の額の特例) 障害手当金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定(障害厚生年金の額の特例)を準用する。
第78条の33 (障害厚生年金等に関する事務の特例) 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、それぞれの被保険者の種別ごとに定められた事務の実施機関が行う。 |
ポイント!
例えば、第3号厚生年金被保険者であった期間と第1号厚生年金被保険者であった期間を有し、初診日に第1号厚生年金被保険者であった場合
初診日▼
第3号厚生年金被保険者 | 第1号厚生年金被保険者 |
・初診日に加入していた実施機関が、年金額の計算・裁定・支給事務を行います。
・年金額の計算は、他の実施機関の加入期間分も合算して計算します。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
②【H29年出題】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の支給に関する事務は、障害認定日ではなく「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
②【H29年出題】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を「合算」し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-334
R4.7.22 2以上の障害が生じた場合の障害厚生年金の併合認定
障害厚生年金の受給権者に更に障害厚生年金の受給権が生じた場合は、併合認定が行われます。
条文を読んでみましょう。
第48条 (障害厚生年金の併給の調整) 1 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く)の受給権者に対して更に障害厚生年金(障害等級1級又は2級)を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。 2 障害厚生年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。 |
併合認定のイメージ
・併合認定の対象になるのは、「1級又は2級に該当したことがある障害厚生年金」です。
・先発の年金が3級でも、障害基礎年金が支給停止になっている場合(短期間でも1級又は2級の障害状態にあったことがある場合)は、併合認定の対象になります。
・なお、障害基礎年金の受給権がない3級は対象外です。
2級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |
2級 | 2級 | 1級 |
3級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |
支給停止 | 2級 | 1級 |
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
②【H29年出題】
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
③【R3年出題】
厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。

【解答】
①【H27年出題】 ×
受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の場合、障害基礎年金の受給権がありません。
先発の障害が3級の障害厚生年金(受給権を取得した当時から引き続き1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)の場合は、第48条の併合認定の対象になりません。
②【H29年出題】 〇
受給権を取得した当時は2級に該当したが、現在は3級である障害厚生年金の場合は、障害基礎年金の受給権があります。
障害厚生年金の受給権を取得した当時は2級に該当したが、現在は3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、併合認定の対象になります。
第48条により、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。
3級 | + | 2級 | → 併合 | 1級 |
支給停止 | 2級 | 1級 |
③【R3年出題】 ×
2級の障害厚生年金の受給権者が、更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、「従前の障害厚生年金の受給権は消滅」します。支給停止ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-333
R4.7.21 障害厚生年金の失権
障害厚生年金の受給権の消滅について確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第53条(失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定(二以上の障害が生じた場合の併合認定)によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。 ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。 ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
障害厚生年金が失権するとき
・二以上の障害が生じ、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅します。
・受給権者が死亡したときは、受給権は消滅します。
・障害等級に該当しなくなったときは、65歳までは支給停止されます。
障害等級に該当しないまま65歳に達したときは、そこで失権します。※65歳時点で障害等級に該当しなくなった日から3年未満の場合は失権しません。
・障害等級に該当しないまま3年を経過したときはそこで失権します。※3年を経過した時点で、65歳未満の場合は失権しません。
★「障害等級に該当しなくなってから3年経過したとき」か「65歳に達したとき」のどちらか遅い方に失権します。
例えば、63歳のときに障害等級に該当しなくなったときは、65歳時点では、3年経過していないので、失権しません。障害等級に該当しなくなってから3年経過した日に失権します。
★厚生年金保険法の「障害等級」は1級から3級です。「障害等級に該当する程度の障害の状態にない」ということは、3級未満ということです。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。
②【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者の障害の状態が障害等級に該当しなくなったため、当該障害厚生年金の支給が停止され、その状態のまま3年が経過した。その後、65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金に係る傷病により障害等級3級に該当する程度の障害の状態になったとしても、当該障害厚生年金は支給されない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとしても、障害等級に該当しなくなってから3年未満の場合は失権しません。
問題文は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったのが64歳時点です。65歳の時点では3年未満ですので失権しません。
②【R2年出題】 ×
障害等級に該当しなくなった場合でも、少なくとも65歳までは支給停止で、受給権は消滅しません。
支給が停止されたまま3年経過したとしても、65歳に達する日の前日までに3級に該当した場合は、支給停止が解除され、3級の障害厚生年金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-332
R4.7.20 障害厚生年金の配偶者加給年金額
1級・2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
条文を読んでみましょう。
第50条の2 1 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金の額に加給年金額を加算した額とする。 2 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 3 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
ポイント!
★配偶者加給年金額が加算されるのは、1級・2級の障害厚生年金です。3級の障害厚生年金には配偶者加給年金額は加算されません。
★65歳未満の配偶者が対象です。子については障害基礎年金の方で加算が行われます。
★受給権を取得した後に、生計を維持する配偶者を有するに至った場合も、配偶者加給年金額の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
障害等級1級又は2級の障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持している子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、当該子に係る加給年金額が加算された額とする。
②【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
③【H24年出題】
障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
子は、障害厚生年金の加給年金額の対象になりません。
子は、障害基礎年金の方で加算の対象になります。
②【H29年出題】 〇
受給権が発生した時点では、生計を維持している配偶者がいなかったとしても、その後、例えば結婚をして対象になる配偶者を有するに至ったときは、加給年金額が加算されます。
その場合は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額が加算されます。
③【H24年出題】 ×
障害厚生年金の受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときでも、1級・2級の障害厚生年金には、配偶者加給年金額が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-331
R4.7.19 寡婦年金と死亡一時金の調整
寡婦年金と死亡一時金の調整をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第52条の6 (支給の調整) 死亡一時金の支給を受ける者が、寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。 |
★ 死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、「その者の選択」によりどちらか一つが支給され、他は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
死亡一時金の支給を受けることができる者が、同一人の死亡により寡婦年金を受けとることができるときは、死亡一時金か寡婦年金のどちらか一つをその者の選択により受給できる。
②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
①【H18年出題】 〇
「死亡一時金」と「寡婦年金」はその者の選択によりどちらか一つを受給できます。
★ 寡婦年金は、60歳から65歳までの有期年金ですので、妻の年齢によっては数か月しか受給できないこともあり得ます。その場合は、死亡一時金の方が受給額が多い可能性もあります。そのような理由から選択制になっています。
★寡婦年金と死亡一時金の受給権を同時に取得した者が、法52条の6により寡婦年金を選択した場合には、死亡一時金の受給権は消滅します。(S50.4.26庁文発1249)
②【H24年出題】 ×
死亡一時金と寡婦年金の受給権を同時に取得した場合は、その者の選択により、どちらか一つが支給されます。
もう一問どうぞ!
③【R3年出題】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
③【R3年出題】 〇
同時に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった場合の調整の問題です。
ポイント!
「一人一年金の原則」により → 遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択
「寡婦年金と死亡一時金」 → 受給権者の選択によりどちらか一つを選択
寡婦年金を選択した場合 → 死亡一時金は支給されません。
遺族厚生年金を選択した場合 → 遺族厚生年金と死亡一時金の両方が受給できます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-330
R4.7.18 死亡一時金の額
死亡一時金の額は、保険料を納付した月数によって決まります。
条文を読んでみましょう。
第52条の4 (死亡一時金の額) ① 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。
② 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、8,500円を加算した額とする。 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が300か月以上ある場合については、一律に32万円である。
②【R2年出題】
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり、同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する死亡一時金の額は、120,000円に8,500円を加算した128,500円である。なお、当該死亡した者は上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。

【解答】
①【H26年出題】 ×
死亡一時金の額が32万円になるのは、420か月以上ある場合です。
②【R2年出題】 〇
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月の場合の死亡一時金は120,000円です。また、付加保険料を納付した期間が36月(3年)あるので、8,500円が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-329
R4.7.17 死亡一時金の遺族の範囲と順位
死亡一時金の遺族の範囲を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第52条の3 ① 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。ただし、第52条の2第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。 ② 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による。 ③ 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第52条の2 第3項 死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く。)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより第41条第2項の規定によって当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、前項の規定は適用しない。
|
死亡一時金を受けることができる遺族の順序は、①配偶者、②子、③父母、④孫、 ⑤祖父母、⑥兄弟姉妹です。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。
②【H27年出題】
死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
三親等内の親族は、死亡一時金を受けることができる遺族に入りません。
②【H27年出題】 〇
下の図も参考にしてください。
夫が死亡した後、子が遺族基礎年金の受給権を取得したものの、その子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、遺族基礎年金が支給停止されている場合の死亡一時金の支給についての問題で、第52条の2第3項に該当します。
第52条の3第1項ただし書きで、「第52条の2第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」となっています。
上記の場合は、死亡した者の配偶者であってその者と生計を同じくしていた者(後妻)が死亡一時金を受けることになります。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
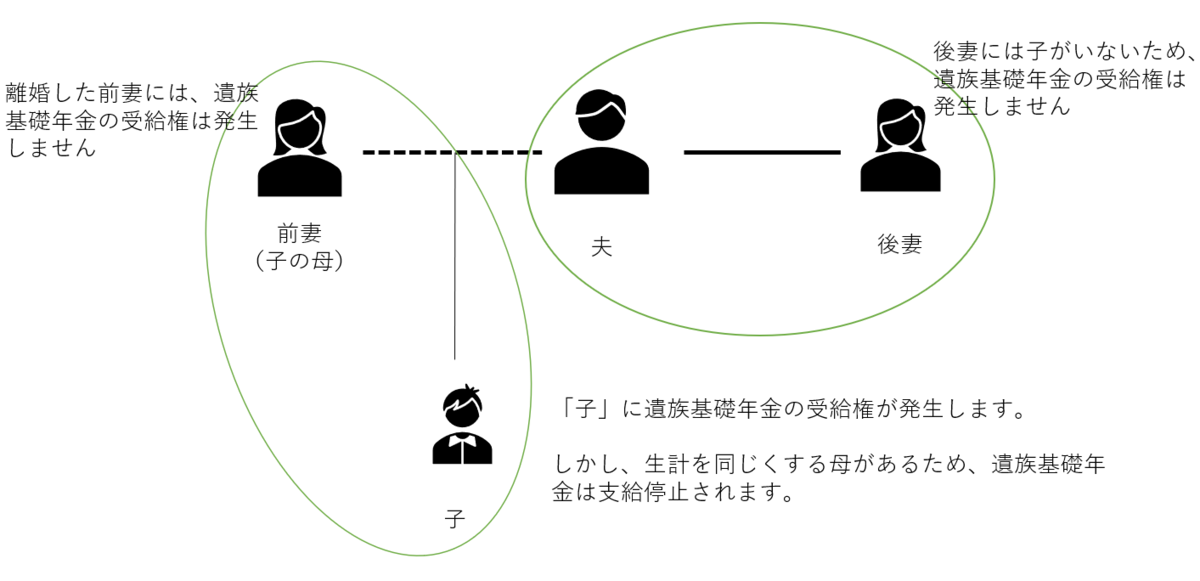
 国民年金法
国民年金法
R4-328
R4.7.16 死亡一時金が支給されないとき
死亡一時金が支給されない場合を見ていきましょう。
さっそく条文を読んでみましょう。
第52条の2 ① 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 ② ①項の規定にかかわらず、死亡一時金は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。 1 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき。ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 2 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の配偶者が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき。ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。 |
ポイント! 「受けたことがある者」
老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を「受けたことがある者」が死亡したときは、死亡一時金は支給されません。
例えば、老齢基礎年金を受ける権利があったとしても、老齢基礎年金を受けないまま死亡した場合は、死亡一時金の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
死亡一時金は、寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合にも支給される。
②【H28年出題】
死亡一時金は、遺族基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、その遺族に支給されない。なお、本問において死亡した者は、遺族基礎年金以外の年金の支給を受けたことはないものとする。
③【R2年出題】
死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であっても、死亡一時金は支給されない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
死亡一時金は、「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者」が死亡した場合は支給されません。
また、遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、原則として死亡一時金は支給されません。
ちなみに、同一人物の死亡によって寡婦年金と遺族基礎年金の両方の受給権が発生することはあり得ます。しかし両方とも受給できるわけではなく、一人一年金の原則が適用されますので、どちらかの年金を選択して受給することになります。
②【H28年出題】 ×
死亡した人が遺族基礎年金の支給を受けたことがあったとしても、死亡一時金の支給要件には影響しません。
③【R2年出題】 ×
同一の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給しないこととなっています。
ただし、死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、死亡一時金が支給されます。
例えば、子が18歳に達した日の属する年度の年度末(3月)に父が死亡した場合、遺族基礎年金の受給権はその3月に発生しますが、実際、遺族基礎年金は支給されません。
このように死亡と同じ月に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、死亡一時金が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-327
R4.7.15 死亡一時金の支給要件
国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納付した人が死亡した場合、一定の遺族に対して死亡一時金が支給されます。
老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがない人が死亡したことが条件で、保険料の掛け捨てを防止することを趣旨としています。
条文を読んでみましょう。
第52条の2 (支給要件) 死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が 36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。 ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、この限りでない。 |
ポイント!
★36月の数え方
「保険料納付済期間の月数」、「4分の1免除期間の月数の4分の3」、「半額免除期間の月数の2分の1」、「4分の3免除期間の月数の4分の1」を合算します。
「保険料全額免除期間」は計算に入りません。保険料の負担が全くないからです。
死亡日の属する月の前月まで
前々月ではなく「前月」までの月数で計算します。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して 36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。
②【H27年出題】
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

【解答】
①【H24年出題】 ×
「保険料全額免除期間」は36月の計算に入りません。
②【H27年出題】 〇
65歳以上の特例による任意加入被保険者も、死亡一時金の対象になります。
★「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。
しかし、「付加保険料の納付」と「寡婦年金」は「特例による任意加入被保険者」には適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-326
R4.7.14 老齢基礎年金の繰上げ繰下げと振替加算
老齢基礎年金は、繰上げて受給することもできますし、繰下げて受給することもできます。
その際、振替加算はどうなるのか確認しましょう。
今日は過去問からどうぞ!
①【H22年出題】
老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合であっても、振替加算額については、受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない。
②【H30年出題】
振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。
③【H21年出題】
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。
④【R3年出題】
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の振替加算については、受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、振替加算も繰下げて支給されるが、振替加算額が繰下げにより増額されることはない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
ポイント! 老齢基礎年金の繰上げの請求をしても、振替加算は繰上げされません。振替加算は65歳から支給されます。
60歳 65歳
| 振替加算 |
繰上げ支給の老齢基礎年金 | |
例えば、60歳から老齢基礎年金を繰上げ請求しても、振替加算は65歳からです。
②【H30年出題】 ×
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても振替加算は繰上げされませんので、振替加算は「請求のあった日の属する月の翌月」からではなく、「65歳に達した日の属する月の翌月」から加算されます。
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、問題文の通り、「申出のあった日の属する月の翌月」から加算されます。
65歳 68歳
| 振替加算 |
| 繰下げ支給の老齢基礎年金 |
③【H21年出題】 ×
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給されますが、振替加算額には繰下げ増額はありません。
④【R3年出題】 〇
振替加算のポイント
・老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合 → 振替加算は繰上げされず65歳から
・老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合 → 振替加算も繰下げて支給される。ただし、振替加算額には繰下げによる増額はありません。
厚生年金保険の「加給年金額」もチェックしましょう。
例えば、加給年金額の加算の対象になっている配偶者が、老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は、加給年金額はどうなるのでしょう?
⑤【厚生年金保険法H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
⑤【厚生年金保険法H28年出題】 ×
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は配偶者が65歳に達するまで支給されます。
★例えば、妻が夫の受給する老齢厚生年金の加給年金額の対象になっている場合で、妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をした場合
・妻が65歳に達するまで、夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます
・妻が65歳に達すると、妻の老齢基礎年金に振替加算が加算されます
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-325
R4.7.13 法定免除の期間など
昨日の続きで、法定免除を見ていきます。
もう一度、条文を読んでみましょう。
第89条 1 被保険者(産前産後免除及び保険料の一部免除の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 ② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ③ 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定するもの)に入所しているとき。 2 1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、1項の規定は適用しない。 |
★免除される期間
「要件に該当するに至った日の属する月の前月」から「これに該当しなくなる日の属する月」までの期間です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※法改正による修正あり
第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く。)が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
②【H26年出題】
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
③【R2年出題】
第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
免除される期間は、その該当するに至った日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の属する「月」までの期間です。
例えば、令和4年7月13日に免除事由に該当した場合は、6月から免除されます。
6月分の保険料の納期限は7月末日です。免除事由に該当している7月末に納期限がくる6月分から免除される仕組みです。
②【H26年出題】 〇
法第89条第2項では、法定免除事由に該当していても、本人から保険料を納付する旨の申出があったときは、申出のあった期間に係る保険料に限って納付することができることを規定しています。
<法定免除に該当していても申出によって保険料が納付できる理由は?>
・法定免除の期間は、老齢基礎年金の計算の際に減額されるので。
・追納することもできますが、10年以内という期限があることと、10年以内でも一定期間を過ぎると加算が行われるので。
③【R2年出題】 〇
法定免除事由に該当した場合は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出する必要があります。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、提出は不要です。
(則第75条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-324
R4.7.12 法定免除の要件
今回のテーマは「法定免除」です。
対象者を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第89条 被保険者(産前産後免除及び保険料の一部免除の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。 ① 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者(最後に厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。 ② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。 ③ 厚生労働省令で定める施設(国立ハンセン病療養所等、国立保養所、その他厚生労働大臣が指定するもの)に入所しているとき。 |
ポイント!
★法定免除の対象は、
・障害基礎年金、1級・2級の障害厚生年金等の受給権者
→ただし、厚生年金保険法の障害等級(3級)に該当しなくなってから3年を経過した者は、法定免除の対象外になります。
・生活保護法の生活扶助を受ける人
・国立ハンセン病療養所等に入所している人
過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。
②【H27年出題】
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。

【解答】
①【H16年出題】 ×
法定免除は、障害基礎年金の受給権があることが条件です。1・2級に該当したことがない3級の障害厚生年金の受給権者には、法定免除は適用されません。
②【H27年出題】 ×
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの種類の扶助があります。
法定免除の対象になるのは、そのうちの「生活扶助」を受ける場合です。
医療扶助のみを受ける場合は法定免除の対象になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-323
R4.7.11 収入がある者についての被扶養者の認定
被扶養者の認定には、次のような基準があります。
★「認定対象者」(被扶養者としての届出に係る者)が被保険者と同一世帯に属している場合
① 認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当する。
② ①の条件に該当しない場合でも、認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入を上廻らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えない。
①について
被扶養者の収入 |
|
|
被保険者の年間収入 |
| |
▲2分の1
②について
被扶養者の収入 |
| |
被保険者の年間収入 |
| |
▲2分の1
★認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合には180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当する。
被扶養者の収入 |
|
被保険者からの援助 | |
(昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】 ※改正による修正あり
認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が 130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。
(なお、認定対象者は、日本国内に住所を有している)
②【H27年出題】 ※改正による修正あり
年収250万円の被保険者と同居している母(58歳であり障害者ではない。)は、年額100万円の遺族厚生年金を受給しながらパート労働しているが健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパート労働による給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができる。(なお、母は日本国内に住所を有している。)
③【H22年出題】 ※改正による修正あり
被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年間100万円であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。(なお、父は日本国内に住所を有している。)

【解答】
①【R1年出題】 〇
認定対象者と被保険者が同一世帯に属している場合、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが、被扶養者となる条件です。
しかし、被保険者の年間収入の2分の1以上でも、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合で、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する者として差し支えないとされています。
※ちなみに、令和2年4月から被扶養者については「日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」という要件が追加されています。
②【H27年出題】 ×
認定要件の年収には、年金や給与も含まれます。
問題文の58歳の母の年間収入は、100万円の遺族厚生年金+120万円のパート労働による給与=220万円です。年間収入130万円以上ですので、被扶養者となりません。
③【H22年出題】 ×
被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が、130万円未満(認定対象者が60歳以上又は障害者の場合には180万円未満)で、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ないことが条件です。
問題文の父の年間収入は、被保険者からの援助額より多いので、被扶養者に該当しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-322
R4.7.10 短時間労働者の社会保険の適用
★1週間の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の「4分の3以上」の場合は、健康保険、厚生年金保険の被保険者として取り扱われます。
★「4分の3未満の場合」
・平成28年10月から
特定適用事業所(被保険者数が常時501人以上の企業)に、厚生年金保険・健康保険が適用されました。
・平成29年4月から
任意特定適用事業所(被保険者数が常時500人以下の企業の事業所で、短時間労働者が社会保険に加入することについて労使合意を行った事業所)にも、厚生年金保険・健康保険が適用されるようになりました。
「4分の3未満」でも適用される要件を確認しましょう。
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間または1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である者で、次の①から④の全てに該当するもの ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 ② 継続して1年以上使用されることが見込まれること。 ③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が 8万8千円以上であること。 ④ 学生でないこと |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
②【H30年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
③【R3年出題】
短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定している者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
特定適用事業所とは、「常時501人以上」の企業の各適用事業所です。
(H24年法附則第46条第12項)
②【H30年出題】 ×
短時間労働者の適用条件の1つである「報酬」は、法第3条第1項9号で「報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額」とされています。
除外される報酬は以下の通りです。
・ 臨時に支払われる賃金 (結婚手当等)
・ 1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
・ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 (割増賃金等)
・ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
・ 深夜労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
・ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
(則第23条の4、R4.3.18保保発0318第1号)
問題文の「家族手当」と「通勤手当」はともに報酬に含まないで算定します。
③【R3年出題】 ×
「事業主との雇用関係の有無にかかわらず」の部分が誤りです。
「「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院等に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)」とされています。
(R4.3.18保保発0318第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-321
R4.7.9 印紙保険料の追徴金
日雇労働被保険者を使用する事業主は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付することにより、印紙保険料を納付します。
事業主が印紙保険料の貼付を怠った場合は、政府は、認定決定を行います。
では、条文を読んでみましょう。
第25条 (印紙保険料の決定及び追徴金) ① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
★ 追徴金は、納付すべき印紙保険料額の100分の25です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題(雇用)】
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H28年出題(雇用)】
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
③【H24年出題(雇用)】
事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった場合、当該事業主は追徴金を徴収されることはないが、罰則規定を適用されることがある。
④【H28年出題(雇用)】
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
①【H25年出題(雇用)】 〇
印紙保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」により行われます。
(則第38条第5項)
②【H28年出題(雇用)】 ×
100分の10ではなく、「100分の25」です。
印紙保険料以外の労働保険料の追徴金の「100分の10」よりも高いことがポイントです。
③【H24年出題(雇用)】 ×
「事業主が日雇労働被保険者に対し日雇労働被保険者手帳の提出を求めないために、日雇労働被保険者がこれを提出せず、雇用保険印紙の貼付がなされなかった」ときは、正当な理由に当たりません。
そのため、追徴金の対象になります。
なお、「雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった」場合は、罰則規定が適用され、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
(法第46条第1号)
④【H28年出題(雇用)】 ×
認定決定に係る印紙保険料と追徴金は、日本銀行又は所轄都道府県労働局収入官吏に納付します。
雇用保険印紙ではなく、現金で納付します。
問題文の「日本銀行に納付することはできず」が誤りです。
(則第38条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-320
R4.7.8 雇用保険料率と被保険者負担分
雇用保険料は、賃金総額×雇用保険料率で計算します。
令和4年度は、年度途中で雇用保険料率が変わります。
例えば、「一般の事業」の場合、
令和4年4月1日から9月30日まで → 1000分の9.5
令和4年10月1日から令和5年3月31日まで → 1000分の13.5
となります。
内訳は、
前半の1000分の9.5については
→ 被保険者負担が1000分の3、事業主負担が1000分の6.5
後半の1000分の13.5については
→ 被保険者負担が1000分の5、事業主負担が1000分の8.5
となります。
過去問をどうぞ!
【R2年出題(雇用)】
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業に係る被保険者は、「当該事業に係る一般保険料の額」から、「当該事業に係る一般保険料の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1の額を負担するものとする。

【解答】
【R2年出題(雇用)】 ×
労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業の場合、「労災保険」に係る保険料は全額事業主負担となります。
問題文のように「当該事業に係る一般保険料の額」と書くと、労災保険と雇用保険が成立している事業の場合は、労災保険料も含まれてしまうので注意してください。
被保険者が負担するのは、「当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額」から「当該事業に係る雇用保険率に応ずる部分の額に相当する額に二事業率を乗じて得た額」を減じた額の2分の1となります。
例えば、令和4年度前半の「一般の事業」の雇用保険率は1000分の9.5で、そのうち1000分の3.5が二事業率です。二事業率の部分は、全額事業主負担です。
「1000分の9.5」から「二事業の1000分の3.5」を減じた額の2分の1が被保険者が負担する部分です。被保険者負担分は1000分の3となります。
(法第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-319
R4.7.7 日雇労働求職者給付金の給付制限
日雇労働求職者給付金も必ずチェックしておきましょう。
今日は給付制限です。
条文を読んでみましょう。
第52条 (給付制限) ① 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 紹介された業務が、その者の能力からみて不適当であると認められるとき。 2 紹介された業務に対する賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。 3 職業安定法第20条(第2項ただし書を除く。)の規定に該当する事業所に紹介されたとき。 4 その他正当な理由があるとき。 ③ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間は、日雇労働求職者給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、日雇労働求職者給付金の全部又は一部を支給することができる。 |
ポイント!
・日雇労働被保険者が、公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合で、その拒否の理由が、法第 52 条第 1 項ただし書各号の一に該当しない場合は、その拒否した日から起算して 7 日間は、失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給は行われません。
★基本手当の支給の給付制限と異なり、「離職理由に基づく給付制限」は設けられていません。
(参照:行政手引90701)
・不正受給の場合の給付制限は、「支給を受け、又は受けようとした月及びその月の翌月から3か月間」です。「支給を受け、又は受けようとした日から3か月間」ではないので注意してください。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。
②【R2年出題】
日雇労働被保険者が公共職業安定所の紹介した業務に就くことを拒否した場合において、当該業務に係る事業所が同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所である場合、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けない。
③【H25年出題】
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
給付制限は、その拒んだ日から起算して「7日間」です。
②【R2年出題】 〇
職業安定法第20条(同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所)に該当する事業所の場合は、日雇労働求職者給付金の給付制限を受けません。
(法第52条第1項第3号)
③【H25年出題】 ×
その支給を受けた月及びその月の翌月から「3か月間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-318
R4.7.6 雇用保険 代理人が登場するところ
雇用保険法の手続きで「代理人」が登場する問題をチェックしましょう。
今日は、過去問からスタートします。どうぞ!
①【R2年出題】
基本手当の受給資格者が求職活動等やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができない場合、失業の認定を代理人に委任することができる。
②【H25年出題】
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。
③【H28年出題】
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

【解答】
①【R2年出題】 ×
ポイント! 代理人による失業の認定は不可
失業の認定は、受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものです。そのため、代理人による失業の認定はできません。
(行政手引51252)
②【H25年出題】 〇
失業等給付の支給は、口座振込が原則です。ただし、受給資格者の申出により、やむを得ないと認められる事由がある場合に限り、現金で支払うことができます。
(則第44条、第45条)
そして、則第46条で、「受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。」と規定されています。
③【H28年出題】 〇
ポイント! 未支給失業等給付は代理人の認定が認められています。
則第17条の2第4項で、「未支給給付請求者は、この条の規定による請求(未支給失業等給付の請求)を、代理人に行わせることができる。」と規定されています。
例えば、遺族が幼児の可能性もあるからです。
また、公共職業能力開発施設に入校中の場合は、受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けることができます。
その場合は、先ほどの則第17条の2第4項が準用され、代理人による失業の認定が認められています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-317
R4.7.5 失業の認定について
基本手当は、失業している日(失業していることについて認定を受けた日に限る。)について、支給されます。
今日は、「失業の認定」を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第15条 ⑤ 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。 |
「求職活動実績」として認められる求職活動は、就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し、受給資格者と再就職の援助者との間に、就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当します。
単なる職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しません。
(行政手引51254)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績として認められる。
②【H27年出題】
失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたことは、求職活動実績として認められます。
(行政手引51254)
②【H27年出題】 ×
求職活動実績には、公共職業安定所、許可・届出のある民間需給調整機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいう。)が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等が含まれます。 また、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことも、該当します。
(行政手引51254)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-316
R4.7.4 海外派遣者の特別加入
労災保険法は、属地主義がとられていて、国内の労働者の災害だけが保護の対象です。
海外で業務に従事する場合は、通常は労災保険の保護の対象外となります。しかし、労災保険に特別加入することにより、労災保険の保護を受けることができます。
海外派遣者として特別加入できるのは、次の3つです。
① 開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く。)を行う団体から派遣され、開発途上にある地域で行われる事業に従事する者 ② 日本国内の事業(有期事業を除く。)から派遣され、海外において行われる事業(海外支店や工場など)で行われる事業に従事する労働者 ③ 日本国内の事業(有期事業を除く。)から派遣され、特定事業に該当する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の者 |
★③について
「特定事業」は中小企業に該当する規模の事業のことです。
海外の事業が特定事業(中小企業の規模)の場合は、現地法人の社長として派遣される者も特別加入することができます。
★日本国内の事業が有期事業の場合は、海外派遣者の特別加入は認められません。
★日本国内の事業が継続事業なら、派遣先の海外の事業が有期事業の場合でも、特別加入させることができます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
②【H26年出題】
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

【解答】
①【H24年出題】 ×
派遣先の海外の事業が中小企業(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業)に該当する場合は、その事業の代表者も、労災保険の特別加入の対象となります。
②【H26年出題】 ×
海外支店で現地採用された者は、国内の事業からの派遣ではないので、特別加入の対象外です。
海外派遣者のポイント!
・ 新たに派遣される者に限らず、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることもできます。
・ 単なる留学の目的で海外に派遣される者は、特別加入の対象となりません。
・ 海外出張者は、特別加入しなくても通常の労災保険の保護の対象となります。
(昭52.3.30基発第192号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-315
R4.7.3 遺族補償一時金
「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今回のテーマは「遺族補償一時金」です。
条文を読んでみましょう。
法第16条の6、16条の8 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 ① 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 → 給付基礎日額の1,000日分 ② 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額(給付基礎日額の1,000日分)に満たないとき。 → 「給付基礎日額の1,000日分」から「支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額」を控除した額
法第16条の7 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者 2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 |
① 例えば、労働者の死亡の当時、遺族が障害状態にない50歳の夫のみだった場合、夫は、遺族補償年金を受けることはできませんが、遺族補償一時金(給付基礎日額の1,000日分)を受けられます。
② 例えば、労働者の死亡当時生計を維持されていた遺族が妻のみだった場合、妻は遺族補償年金を受けることができます。しかし、その後妻の受給権が消滅し、既に支給されていた年金が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、支給された年金の額の合計額との差額が支給されます。
遺族補償一時金を受ける遺族の順位
①配偶者(生計維持の有無は関係なし)
②生計維持していた子
③生計を維持していた父母
④生計を維持していた孫
⑤生計を維持していた祖父母
⑥生計を維持していなかった子
⑦生計を維持していなかった父母
⑧生計を維持していなかった孫
⑨生計を維持していなかった祖父母
⑩兄弟姉妹(生計維持の有無は関係なし)
過去問をどうぞ!
①【H10年出題】
遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。
②【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
③【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
④【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
①【H10年出題】 〇
遺族補償年金を受けている妻が再婚をした場合、遺族補償年金の受給権は失権します。その場合、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日未満の場合は、差額が遺族補償一時金として支給されます。
労働者との身分関係は「労働者の死亡の当時」でみることがポイントです。再婚により遺族補償年金の受給権が失権した場合でも、労働者の死亡の当時は妻だったので、遺族補償一時金の請求ができます。
②【H28年出題】 ×
①の問題のように、遺族補償年金の受給権を失権したものでも、遺族補償一時金の受給権を得ることがあります。
③【H25年出題】 〇
「遺族補償年金」は、労働者の死亡の当時その収入により生計を維持していたことが条件ですが、「遺族補償一時金」は、労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
④【H28年出題】 〇
③の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-314
R4.7.2 労災 保険給付の一時差し止め
保険給付を受ける者が行政庁の命令に従わないときは、政府は保険給付の支払いを一時差し止めることができます。
条文を読んでみましょう。
法第47条の3 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前2条の規定による命令(報告、出頭等の命令、受診命令)に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 |
一時差し止められた保険給付は、差止め事由がなくなれば、差し止められていた給付の支払が行われます。
支給停止とは違いますので注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
②【H25年出題】
政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
③【H24年出題】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な書類その他の物件を政府に提出しないときは、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができます。
②【H25年出題】 〇
受診命令に従わないときは、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができます。
※参考 第47条の2(受診命令) 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 |
③【H24年出題】 ×
行政の出頭命令に従わないときは、政府は、「保険給付の支払を一時差し止めること」ができます。「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。」は誤りです。
※参考 第47条(労働者及び受給者の報告、出頭等) 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、報告等を命ずることができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-313
R4.7.1 障害補償給付・障害等級の変更
障害等級は、1級から14級まであり、1級から7級の障害が残った場合は「障害補償年金」、8級から14級の障害が残った場合は「障害補償一時金」が支給されます。
障害補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があった場合は、変更後の障害等級に応じた障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。
条文を読んでみましょう。
法第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
★「変更があった」とは?
障害の程度が自然的経過により増進し、又は軽減したことをいいます。
※「変更」に含まれないもの→「新たな傷病で障害の程度が加重した」、「傷病が再発した後治ゆし、その後に残った障害の程度が増進又は軽度になった」場合は変更に含まれません。
★対象は「障害補償年金」のみ
主語に注目してください。変更の対象は、「障害補償年金」を受ける労働者に限定されています。
「障害補償一時金」の場合は、後から障害の程度が増進又は軽減した場合でも、変更の対象にはなりません。
★具体例
・障害等級3級が自然的経過により増進し、障害等級1級に該当するに至った場合
→ 新たに該当した「1級」の障害補償年金を支給し、その後は3級の障害補償年金は支給されません。
・障害等級5級が自然的経過により軽減し、障害等級8級に該当するに至った場合
→ 新たに該当した「8級」の障害補償一時金を支給し、その後は5級の障害補償年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「障害補償年金を受ける者」と「自然的経過により変更」がチェックポイントです。
また、「新たに該当することとなった障害等級に応ずる「障害補償給付」が支給され」の「障害補償給付」にも注目してください。「障害補償給付」には「年金」も「一時金」も含まれます。1級から7級の範囲内の変更なら年金が支給されますが、8級以下になった場合は一時金が支給されます。
②【H30年出題】 〇
「障害補償一時金」の場合は、障害の程度が自然的経過により変更しても、障害補償給付の変更が行われることはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
R4-312
R4.6.30 障害補償給付・併合と併合繰上げ
同一のケガや病気で障害が2つ以上残ったときは、原則として、重い方の障害等級が全体の障害等級となります。(併合といいます)
しかし、13級以上の障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級を1級ないし3級繰り上げます。(併合繰上げといいます。)
条文を読んでみましょう。
則第14条 ② 別表第一に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 ③ 次の各号に掲げる場合には、重い方の障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。 1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級繰り上げ 2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級繰り上げ 3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級繰り上げ |
(併合について)
例えば、同一事由で、14級と9級の2つの障害が残った場合は、全体として重い方の9級の障害等級となります。
重い方の障害等級が全体の障害等級となるのは、一方が14級の場合に限られます。
(併合繰上げについて)
併合繰上げが行われるのは、13級以上の障害が2つ以上残った場合です。
例えば、同一の事由で、5級と4級が残った場合は、重い方の4級が3級繰り上がって、全体として障害等級は1級となります。
しかし、例外もあります。
13級と9級が残った場合は、重い方の9級が1級繰り上がって8級となります。
8級の一時金は「503日分」、13級(101日分)と9級(391日分)を合算すると492日分です。繰り上がった結果の方が大きくなるのは、13級と9級が残った場合だけです。このため、13級と9級が残った場合は、繰り上がった8級の一時金ではなく、13級と9級を合算した492日分の一時金が支給されます。(則第14条第3項但し書き)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で、一方の障害が第14級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
②【H30年出題】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級

【解答】
①【R2年出題】 〇
同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で、一方の障害が第14級に該当するときは、全体として重い方の障害等級になります。例えば、14級と10級が残った場合は、全体として10級となります。
②【H30年出題】 ×
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合は、「8級以上」が、5級と7級の2つあるので、重い方の5級が2級繰り上がって「第3級」となります。
② 第4級、第5級の2障害がある場合は、「5級以上」が、4級と5級の2つあるので、重い方の4級が3級繰り上がって「第1級」となります。
③ 第8級、第9級の2障害がある場合は、「13級以上」が8級と9級の2つあるので、重い方の8級が1級繰り上がって「第7級」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-311
R4.6.29 ストレスチェック
ストレスチェックとは?
・労働者が、ストレスに関する質問票に記入して
↓
・それを集計、分析して
↓
・自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。
労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するため、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく医師による面接指導等を内容とする制度(以下「ストレスチェック制度」という。)で、平成27年12月から始まりました。なお、この制度は、メンタルヘルス不調の労働者を把握することを目的とした制度ではありません。
(参照:平成27.5.1基発0501第3号)
条文を読んでみましょう。
第66条の10 (心理的な負担の程度を把握するための検査等) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】 ※改正による修正あり
労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、< A >又は公認心理師とされている。
②【H30年出題】
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。
③【H30年出題】
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。
④【H30年出題】
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。
⑤【H30年出題】
ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。
⑥【H30年出題】
ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。

【解答】
①【H28年選択式】 ※改正による修正あり
A 精神保健福祉士
(則第52条の10)
②【H30年出題】 〇
則第52条の9で「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回」、ストレスチェックを行わなければならない旨規定されています。
産業医の選任が義務づけられている常時50人以上の労働者を使用する事業者が対象です。常時50人未満の事業場は、当分の間「行うように努めなければならない(努力義務)」となっています。
(法第66条の10、則第52条の9、法附則第4条)
③【H30年出題】 〇
④【H30年出題】 〇
⑤【H30年出題】 〇
検査の項目については、次の3つが定められています。
1 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
(則第52条の9)
⑥【H30年出題】 ×
則第52条の10第2項で、「検査を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。」と規定されています。
人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者が従事することができない事務は、ストレスチェックの実施に直接従事すること及び実施に関連してストレスチェックの実施者の指示のもと行われる労働者の健康情報を取り扱う事務をいいます。
「ストレスチェックを受けていない労働者に対する受検の勧奨」は、健康情報を取り扱う事務に含まれないので、人事に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者が従事して差し支えないとされています。
(平成27.5.1基発0501第3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-310
R4.6.28 特定業務従事者の健康診断
一定の有害な業務に従事する労働者については、その業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回定期に健康診断を実施しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
則第45条 (特定業務従事者の健康診断) 事業者は、第13条第1項第3号に掲げる業務(一定の有害業務)に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目(定期健康診断の診断項目)について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目(胸部エックス線及び喀痰検査)については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。 |
★ 定期健康診断は1年以内ごとに1回行わなければなりませんが、特定業務従事者については、当該業務への配置換えの際及び6か月以内ごとに1回の実施が義務づけられています。
診断項目は定期健康診断の診断項目です。
では、過去問をどうぞ!
①【H17年出題】
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
②【H27年出題】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

【解答】
①【H17年出題】 〇
強烈な騒音を発する場所における業務は、特定業務従事者の健康診断の対象です。
(則第45条第1項)
②【H27年出題】 〇
深夜業を含む業務は、特定業務従事者の健康診断の対象です。
(則第45条第1項)
ポイント!「有害な業務の範囲」について
一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。
特定業務従事者の業務の範囲は、専属の産業医が必要な「一定の有害な業務」の範囲と同じです。
その中に、「深夜業を含む業務」が入っているのがポイントです。
過去問で確認しましょう。
③【H17年出題】
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

【解答】
③【H17年出題】 〇
「深夜業を含む業務」に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医を選任しなければなりません。
ポイント! 衛生管理者の選任要件にも注意しましょう。
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない事業場は、1 常時千人を超える労働者を使用する事業場
2 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務(一定の有害業務)に常時30人以上の労働者を従事させるもの
※2の一定の有害業務に、「深夜業」が含まれないことがポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-309
R4.6.27 定期健康診断
事業者は、常時使用する労働者に対して、定期的に健康診断を行わなければなりません。
定期健康診断のポイントをおさえましょう。
条文を読んでみましょう。
則第44条 (定期健康診断) ① 事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 ② 一定の項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 |
★ 定期健康診断と雇入れ時の健康診断の項目の違い
定期健康診断は「胸部エックス線検査及び喀痰検査」ですが、雇入れ時の健康診断は「胸部エックス線検査」です。「喀痰検査」以外は雇入れ時の健康診断の項目と同じです。
★ 省略できる項目は、厚生労働大臣が定める基準に具体的に定められています。省略できるのは、「医師が必要でないと認めるとき」ですので、注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題 】
事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。
②【H27年出題】
常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。
③【R1年出題】
期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。

【解答】
①【R1年出題 】 ×
「定期健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること」とされています。
(S47.9.18基発第602号)
②【H27年出題】 ×
定期健康診断は、「常時使用する労働者」が対象です。
常時使用する短時間労働者とは次の①と②のどちらの要件も満たす者です。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(特定業務従事者の健康診断は6か月)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
問題文の場合は、「通常の労働者と同じ所定労働時間」で「1年ちょうど」の契約で雇い入れていますので、対象となります。
(H26.7.24基発0724第2号)
③【R1年出題】 〇
1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件(契約期間が原則1年以上)に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましい、とされています。
(H26.7.24基発0724第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-308
R4.6.26 労働者の定義
労働基準法の保護の対象になる「労働者」の定義を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第9条 (定義) この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |
「職業の種類を問わず」、「事業又は事務所に使用され」、「賃金を支払われる者」は労働者として、労働基準法の保護の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる。
②【H29年出題】
工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
形式上は請負契約でも、実態として「使用従属関係が認められる」ときは、労働基準法第9条の「労働者」に当たります。
(参考)
労働基準法上の労働者性は、次の1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する、とされています。
1 使用従属性に関する判断基準
(1)指揮監督下の労働
①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
②業務遂行上の指揮監督の有無
③拘束性の有無
④代替性の有無
(2)報酬の労務対償性
2 労働者性の判断を補強する要素
(1)事業者性の有無
(2)専属性の程度
(3)その他
★昭和60年厚生労働省「労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」より
②【H29年出題】 ×
請負契約によらず雇用契約によりその事業主と大工との間に使用従属関係が認められる場合は、労働基準法の労働者ですので、労働基準法の適用を受けます。
(平11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-307
R4.6.25 休憩時間の長さ
「休憩時間」は、「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」です。(昭22.9.13発基17号)
休憩は、「途中付与」、「一斉付与」、「自由利用」が原則です。
今回は、休憩時間の長さがテーマです。
条文を読んでみましょう。
第34条 (休憩) ① 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ② 休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ③ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
使用者は、所定労働時間が5時間である労働者に1時間の所定時間外労働を行わせたときは、少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②【H23年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合においても、使用者は、1日の労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
③【H24年出題】
使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
労働時間が6時間を「超える」場合は45分以上、8時間を「超える」場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。
問題文の労働時間は6時間ちょうどですので、休憩を与える義務はありません。
②【H23年出題】 〇
36協定を締結し、行政官庁に届け出た場合でも、使用者には、休憩時間を与える義務があります。
③【H24年出題】 ×
1日の労働時間が8時間を超える場合は、1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。1日の労働時間が16時間を超える場合でも、1時間以上の休憩を与えれば、労働基準法の条件は満たします。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-306
R4.6.24 1週間単位の非定型的変形労働時間制
例えば、規模の小さい飲食店を思い浮かべてください。
★1週間単位の非定型的変形労働時間制の趣旨
日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に定まっていない場合に、1週間を単位として、一定の範囲内で、就業規則その他これに準ずるものによりあらかじめ特定することなく、1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、労働時間のより効率的な配分を可能とし、全体としての労働時間を短縮しようとするものであること。
(昭63.1.1基発第1号)
では、条文を読んでみましょう。
第32条の5 ① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。 ② 使用者は、①の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
則第12条の5 ① 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。 ② 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。 |
ポイント!
★1週間の非定型的変形労働時間制が導入できる事業は、規模30人未満の小売業、旅館、料理店及び飲食店に限定されています。
★労使協定の締結が必要です。(所轄労働基準監督署長に届け出が必要です。)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。
②【H22年出題】
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、「かつ」、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場です。
事業と規模の両方に該当する必要があります。
②【H22年出題】 ×
1週間単位の非定型的変形労働時間制については、1日の労働時間の上限は「10時間」と定められています。
また、1週間の所定労働時間は40時間以下で定めなければなりません。特例事業場でも44時間は適用されません。
 なお、事前通知については、則第12条の5第3項で以下のように定められています。
なお、事前通知については、則第12条の5第3項で以下のように定められています。
(原則) 1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。
(例外) 緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
原則として、1週間が始まる前に、1週間の各日の労働時間を書面で通知することにより、1日10時間まで労働させることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-305
R4.6.23 金品の返還
労働者が退職する場合に、賃金など労働者の権利に属する金品の返還が遅くなると、労働者の生活に支障をきたします。そのような不便を防ぐための規定です。
では、条文を読んでみましょう。
第23条 (金品の返還) ① 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ② 賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、①の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
|
「権利者」とは、労働者が退職の場合は労働者本人、労働者が死亡した場合は、その労働者の相続人です。(昭22.9.13発基第17号)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないが、この賃金又は金品に関して争いがある場合においては、使用者は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還しなければならない。
②【H30年出題】
労働基準法第20条第1項に定める解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
③【H12年出題】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合においては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。このことは、退職手当についても同様である。

【解答】
①【R2年出題】 〇
賃金又は金品について労使で争いがある場合は、異議のない部分を、7日以内に支払い、又は返還すればよいことになっています。
②【H30年出題】 〇
解雇予告手当は、「解雇の申し渡しと同時に支払うべきもの」とされています。
(昭23.3.17基発464号)
③【H12年出題】 ×
退職手当は、通常の賃金とは異なり、予め就業規則で定められた支払時期に支払えば足りるとされています。
(昭26.12.27基収5483号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険に関する一般常識
社会保険に関する一般常識
R4-304
R4.6.22 介護保険法「介護支援専門員」
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、訪問介護、デイサービスなどのサービスを受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。 (参考:厚生労働省ホームページ)
条文を読んでみましょう。
第69条の2 (介護支援専門員の登録) 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、介護支援専門員実務研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、一定の事由に該当する者については、この限りでない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りでない。
②【H26年出題】
介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。

【解答】
①【H22年出題】 〇
(参考)介護保険法第69条の2第1項各号に掲げられているのは、「心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」等です。
②【H26年出題】 〇
登録を受けている者は、都道府県知事に対し、「介護支援専門員証」の交付を申請することができます。介護支援専門員証の有効期間は、5年です。ただし、法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い交付されたものは除かれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働に関する一般常識
労働に関する一般常識
R4-303
R4.6.21 令和2年度雇用均等基本調査から「育児休業取得者の割合」
「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施しています。
参照:厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査:調査の概要」
今回は、「育児休業制度の利用状況」から、「 育児休業者の割合」を読んでみましょう。
① 女性 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、令和2年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は 81.6%と、前回調査(令和元年度 83.0%)より 1.4 ポイント低下した。 ② 男性 平成30年10月1日から令和元年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和2年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は 12.65%と、前回調査(令和元年度 7.48%)より 5.17 ポイント上昇した。この内、育休期間が5日未満の取得者の割合は 28.33%だった。 参照:厚生労働省「令和2年度雇用均等基本調査:調査の概要」 |
では、問題を解いてみましょう。
【問題①】
平成30年10月1日から令和元年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和2年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は81.6%だった。
【問題②】
平成30年10月1日から令和元年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和2年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申出をしている者を含む。)の割合は 12.65%で、この内、育休期間が5日未満の取得者の割合は28.33%だった。

【解答】
【問題①】 ×
「12.65」%です。81.6%は女性の取得率です。
細かい数字まで覚える必要はありません。ざっくりで結構です。
【問題②】 〇
育休期間が5日未満の取得者の割合は 28.33%です。
参照:厚生労働省「「令和2年度雇用均等基本調査」の結果概要https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r02/07.pdf
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働に関する一般常識
労働に関する一般常識
R4-302
R4.6.20 令和3年就労条件総合調査の概況から「年次有給休暇の取得率」
就労条件総合調査は、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施されています。
今回は、令和3年就労条件総合調査の概況から、「労働者1人平均年次有給休暇の取得状況」をみてみましょう。
令和2年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1 人平均は 17.9 日(令和2年調査 18.0 日)、このうち労働者が取得した日数は 10.1 日(同 10.1日)で、取得率は 56.6%(同 56.3%)となっており、昭和 59 年以降過去最高となっている。 取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 73.3%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 45.0%と最も低くなっている。 参照:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」 |
では、問題を解いてみましょう。
【問題①】
令和2年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者1 人平均は 17.9 日、このうち労働者が取得した日数は 10.1 日で、取得率は 56.6%となっており、昭和 59 年以降過去最低となっている。
【問題②】
年次有給休暇の取得率を産業別にみると、「宿泊業,飲食サービス業」が 73.3%と最も高く、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 45.0%と最も低くなっている。

【解答】
【問題①】 ×
昭和 59 年以降過去最低ではなく、昭和 59 年以降過去最高となっています。
【問題②】 ×
「宿泊業,飲食サービス業」と「電気・ガス・熱供給・水道業」が逆です。「電気・ガス・熱供給・水道業」が 73.3%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が 45.0%と最も低くなっています。
参照:厚生労働省「令和3年就労条件総合調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/21/dl/gaikyou.pdf
では、過去問もどうぞ!
【R2年選択式】
我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには< A >、年次有給休暇の取得率を知るには< B >、男性の育児休業取得率を知るには< C >が使われている。

【解答】
A 雇用動向調査
B 就労条件総合調査
C 雇用均等基本調査
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-301
R4.6.19 60歳台前半の在職老齢年金
令和4年4月から、60歳台前半の在職老齢年金の計算式が改正されました。確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法附則第11条 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。 |
用語の定義を確認しましょう。
★総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額) + (その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
★基本月額
老齢厚生年金の額(加給年金額を除く) ÷ 12
★支給停止調整額
令和4年度は47万円
① 「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円以下の場合は、全額支給されます。
② 「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超える場合は、
(「基本月額+総報酬月額相当額」-47万円)の2分の1が支給停止されます。
③ 支給停止基準額「(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×2分の1」が、老齢厚生年金の額以上の場合は、全額支給停止されます。
※上記の計算式は月額です。支給停止基準額は、正確には12を乗じた額となります。
例えば、基本月額が20万円、総報酬月額相当額が32万円の場合は、20万円+32万円=52万円で47万円を超えますので、一部が支給停止になります。
(20万円+32万円-47万円)×2分の1=2万5千円が支給停止されます。
過去問をどうぞ!
【H25年出題】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。

【解答】
【H25年出題】 ×
「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と「その月以前」の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-300
R4.6.18 65歳以上の老齢厚生年金と遺族厚生年金の調整
今日のテーマは、65歳以上の人が「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」の受給権を得た場合の調整です。
条文を読んでみましょう。
第64条の2 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。 |
ポイント!
 65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合
→ 本人の老齢厚生年金が支給されます。(老齢厚生年金が優先です)本人が納付した保険料を年金額に反映させるためです。
→ 遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より高い場合は、差額が受けられます。
→ 老齢厚生年金が遺族厚生年金より高い場合は、遺族厚生年金は全額支給停止されます。
例えば、老齢厚生年金が30万円、遺族厚生年金が40万円の場合、遺族厚生年金のうち30万円は支給停止され、差額の10万円が遺族厚生年金として支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】※改正による修正あり
遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
②【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H22年出題】 〇 ※改正による修正あり
65歳以上で、老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権があるときは、老齢厚生年金を支給し、遺族厚生年金は、「当該老齢厚生年金の額に相当する部分」の支給が停止されます。
遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ、その差額が支給されます。
また、遺族厚生年金が老齢厚生年金より低ければ、遺族厚生年金は全額支給停止となります。
②【H29年出題】 〇
老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合は、加給年金の額は除かれることに注意してください。
(法第60条第1項第2号ロ、法第64条の2)
★ポイント!
「65歳に達している」がポイントです。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」はどちらかを選択します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-299
R4.6.17 65歳以上の配偶者の遺族厚生年金
遺族厚生年金は、報酬比例部分×4分の3で計算します。※報酬比例部分は、死亡した人の被保険者期間や報酬をベースに計算します。
ただし、老齢厚生年金の受給権がある65歳以上の配偶者が受給する遺族厚生年金については、注意が必要です。
では、条文を読んでみましょう。
第60条、法附則第17条の2 (年金額) 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①に定める額とする。 ① 第59条第1項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → 死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定(老齢厚生年金の年金額)の例により計算した額の4分の3に相当する額。 ただし、短期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算した額とする。 ② 遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき → ①に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額 イ ①に定める額に3分の2を乗じて得た額 ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(加給年金額が加算された老齢厚生年金にあっては、加給年金額は除く。)に2分の1を乗じて得た額
|
ポイント!
遺族厚生年金の額は、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3」で計算するのが原則です。
ただし、65歳以上で、老齢厚生年金の受給権を有する人が、配偶者の死亡により遺族厚生年金の受給権を有する場合の年金額は、
次の①と②の額を比較し、高い方になります。
① 死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分×4分の3
② 「①の計算式の額×3分の2」と「自身の老齢厚生年金(子の加給年金額は除く)の額×2分の1」を合計した額
例えば、夫(老齢厚生年金(報酬比例部分)の額が80万円)、妻(65歳以上・老齢厚生年金の額が70万円)の場合であてはめると、夫が死亡した場合の妻の遺族厚生年金の額は、以下のようになります。
① 80万円×4分の3=60万円
② 「60万円×3分の2」+「70万円×2分の1」=75万円
①と②の高い方になりますので、妻の遺族厚生年金は②の75万円となります。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
②【R3年出題】
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

【解答】
①【H28年出題】 ×
遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として計算した「老齢厚生年金の額の4分の3」に相当する額です。しかし、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額を最低保障とする規定はありません。
②【R3年出題】 ×
配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)の遺族厚生年金の額は①と②のどちらか多い方です。
①死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3
②①の額の3分の2+配偶者本人の老齢厚生年金の額の2分の1
 ワンポイント!
ワンポイント!
第60条第1項に、「ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、①に定める額とする。」と規定されています。
65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する配偶者でも、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の支給を受けるときは、遺族厚生年金の額は①で計算します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-298
R4.6.16 任意加入被保険者が保険料を滞納した場合の資格喪失
任意加入被保険者は、強制ではなく本人の申出により「任意」で加入している関係上、保険料を滞納した場合は、その資格を喪失します。
では、「保険料を滞納した場合の喪失」について、条文で確認しましょう。
任意加入被保険者の種類(法附則第5条第1項) ① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) ② 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) ③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
法附則第5条第5項 ①と②について 保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その指定期限の翌日に資格を喪失する。 ③について 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、2年間が経過した日の翌日に資格を喪失する。 |
 ポイント!
ポイント!
①と②は「日本国内に住所を有する」任意加入被保険者、③は「日本国内に住所を有しない」任意加入被保険者です。滞納した場合の喪失日の違いに注意しましょう。
滞納した場合の扱いは、特例による任意加入被保険者も同じです。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
②【H29年出題】
日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく2年間が経過したときは、その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する。
③【H22年出題】
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者資格を喪失する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「日本国内に住所を有する」の部分がポイントです。
督促状で指定した期限の「翌日」の部分もポイントです。当日ではありませんので、注意してください。
②【H29年出題】 ×
「日本国内に住所を有する」ので、資格の喪失は、「督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その指定期限の翌日」です。
③【H22年出題】 ×
「日本国内に住所を有しない」の部分がポイントです。
「2年経過した日」ではなく、2年間が経過した日の「翌日」に被保険者資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-297
R4.6.15 任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違い
任意加入被保険者も特例による任意加入被保険者も、第1号被保険者と同じように保険料を納付します。
しかし、付加保険料、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金については注意が必要です。
 「任意加入被保険者」は、「付加保険料の納付」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「脱退一時金」については、第1号被保険者と同じように扱われます。
「任意加入被保険者」は、「付加保険料の納付」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「脱退一時金」については、第1号被保険者と同じように扱われます。
(法附則第5条第9項)
 「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。
「特例による任意加入被保険者」は、「死亡一時金」と「脱退一時金」は、第1号被保険者と同じ扱いです。
しかし、「付加保険料の納付」と「寡婦年金」は「特例による任意加入被保険者」には適用されません。
特例による任意加入の目的は増やすことではなく受給権を得るためです。老齢基礎年金の上乗せになる付加保険料の納付ができないのは、そのためです。
保険料の掛け捨てを防止する趣旨である死亡一時金と脱退一時金は、特例による任意加入被保険者にも適用されます。
(H16法附則第23条第10項)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。
②【H23年出題】
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者は、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金等の給付に関する規定の適用については、第1号被保険者とみなされる。
③【H27年出題】
65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。
④【R2年出題】
日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
⑤【R2年出題】
60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができ、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金については、第1号被保険者として扱われます。
②【H23年出題】 ×
65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は、「死亡一時金」と「脱退一時金」の給付については、第1号被保険者として扱われますが、「寡婦年金」については適用されません。
③【H27年出題】 〇
死亡一時金については、特例による任意加入被保険者は第1号被保険者として扱われますので、支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給されます。
④【R2年出題】 〇
任意加入被保険者は、付加保険料を納付することができます。ただし、特例による任意加入被保険者は付加保険料を納付することはできません。
⑤【R2年出題】 ×
付加保険料の部分が誤りです。特例による任意加入被保険者は、付加保険料を納付できません。
なお、任意加入被保険者(昭和40年4月1日以前に生まれた者に限る。)が、65歳に達した日に、老齢基礎年金の受給権を有していない場合は、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-296
R4.6.14 任意加入被保険者と口座振替
任意加入被保険者は、年金の受給権確保等のため、月々の保険料を確実に納付する必要があります。そのため、口座振替による保険料納付が原則となっています。
よく出題されていますので、確認していきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
法附則第5条 (任意加入被保険者) ① 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの ② ①の第1号又は第2号に該当する者が任意加入の申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。 |
ポイント!
第1号又は第2号(日本国内に住所を有する者)が、任意加入の申出を行う場合は、「口座振替納付を希望する」旨の申出又は「口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨」の申出が必要です。
★特例による任意加入被保険者も同じです。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出または口座振替によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を、厚生労働大臣に対して行わなければならない。
②【H28年出題】
日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合は、原則として、保険料は口座振替納付により納付しなければならないが、任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合には、口座振替納付によらないことができる。
③【H21年出題】
国民年金法の規定によると、日本国籍を有する者であって日本国内に住所を有しない60歳以上65歳未満のものが任意加入の申出をする場合には、正当な事由がある場合を除き、口座振替納付を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者の保険料の納付は、口座振替納付が原則となります。任意加入の申出を行おうとする者は、「口座振替納付を希望する旨」又は「口座振替納付によらない正当な事由に該当する旨」の申出をしなければなりません。
なお、この規定が適用されるのは、「日本国内に住所を有する」ものです。
②【H28年出題】 〇
「口座振替納付によらない正当な事由がある場合」は、則第2条の2で以下のように定められています。
①申出を行う時点において、預金口座又は貯金口座を有していない場合
②資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合
③その他前2号に掲げる事由に準ずる事由により口座振替納付によらない正当な事由があると認められる場合
問題文は②に該当しますので、口座振替によらないことができます。
(則第2条の2)
③【H21年出題】 ×
「日本国内に住所を有しない」ものは、口座振替納付を希望する旨の申出は要りません。(法附則第5条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-295
R4.6.13 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者
前回は、「任意加入被保険者」のお話をしましたが、今回のテーマは「特例による任意加入被保険者」です。
任意加入被保険者との違いをおさえましょう。
まず、「特例による任意加入被保険者」の条文を読んでみましょう。
H6法附則第11条、H16法附則第23条 (任意加入被保険者の特例) 昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。 ただし、その者が老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。 1 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの |
 特例による任意加入被保険者のポイント!
特例による任意加入被保険者のポイント!
要件に該当すれば65歳から70歳まで特例で任意加入が認められます。ただし、「昭和40年4月1日以前生まれ」に限定されています。また、老齢基礎年金等の受給権を有する者は特例の任意加入はできません。目的は老齢基礎年金の受給権を得ること。増やす目的では、特例の任意加入はできません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
任意加入被保険者の特例については、日本国籍を有する65歳以上70歳未満の者が、日本国内に住所を有しない場合は認められていない。
②【H27年出題】
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。
③【R3年出題】
昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。

【解答】
①【H21年出題】 ×
日本国内に住所を有しなくても、日本国籍を有する65歳以上70歳未満のものは、特例の任意加入が認められています。ただし、昭和40年4月1日以前生まれに限られます。
②【H27年出題】 ×
特例による任意加入被保険者になることができるのは、昭和40年4月1日以前生まれの場合に限られます。ちなみに、昭和30年4月1日以前生まれの場合でも、もちろん、特例の任意加入被保険者になることはできます。
③【R3年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有する場合でも、特例による任意加入被保険者となることができます。障害基礎年金は、障害の状態によっては、支給停止や失権の可能性があるからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-294
R4.6.12 任意加入被保険者の加入要件
国民年金法には、「任意加入被保険者」、「特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)」として、任意に国民年金に加入できる制度があります。
任意加入の目的は2つです。
 1つめ 老齢基礎年金を増やす
1つめ 老齢基礎年金を増やす
65歳からの老齢基礎年金を満額受給するためには、20歳から60歳までの40年間(480月)すべて保険料納付済期間であることが必要です。
免除や滞納などで満額に満たない人は、任意加入して、老齢基礎年金を増やすことができます。
 2つめ 老齢基礎年金の受給権を得る
2つめ 老齢基礎年金の受給権を得る
また、老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上必要です。その期間に足りない場合は、受給権を得るために任意加入することができます。
「任意加入被保険者」は、1つ目、2つ目どちらの目的でも任意加入できます。
一方、「特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)」は、2つ目の「老齢基礎年金の受給権を得る」目的に限定されます。1つめの「老齢基礎年金を増やす」目的では加入できませんので注意しましょう。
今回のテーマは「任意加入被保険者」の加入要件です。
まず、条文を読んでみましょう。
第5条 (任意加入被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 2 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。) 3 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの |
 1~3の人は第1号被保険者の要件に当てはまりません。しかし、厚生労働大臣に申し出て任意加入することができます。ただし、第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できません。(任意加入する必要もないためです)
1~3の人は第1号被保険者の要件に当てはまりません。しかし、厚生労働大臣に申し出て任意加入することができます。ただし、第2号被保険者、第3号被保険者は任意加入できません。(任意加入する必要もないためです)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
②【H29年出題】
60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。
③【R2年出題】
60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生まれ)は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり、あと1年間、国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は、日本国籍を有していても、日本国内に住所を有していなければ、任意加入被保険者の申出をすることができない。

【解答】
①【H25年出題】 ×
「日本国内に住所を有する」60歳以上65歳未満の者は、国籍を問わず任意加入することができます。
なお、「日本国内に住所を有しない」20歳以上65歳未満の者が任意加入する場合は、「日本国籍を有する者」に限られます。
②【H29年出題】 〇
「老齢基礎年金の繰上げ請求」を行った者は、国民年金の任意加入被保険者になることはできません。既に繰り上げて受給している老齢基礎年金を増やすことができないからです。
なお、特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、国民年金の任意加入被保険者となって、65歳以降の老齢基礎年金を増やすことができます。
(法附則第9条の2の3)
③【R2年出題】 ×
日本国籍を有していれば、日本国内に住所を有していなくても、任意加入被保険者の申出をすることができます。
なお、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中でも任意加入被保険者になることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-293
R4.6.11 毎年7月1日の定時決定
「標準報酬月額」は、保険料の計算、傷病手当金などの計算に使われます。
標準報酬月額は、毎年7月1日に見直しをします。「定時決定」といいます。
★「報酬」、「報酬月額」、「標準報酬月額」と似たような用語が登場します。
「報酬」は、労働の対償として受けるもののことで、時給制の人もいれば、月給制の人もいて様々です。
報酬を月ベースになおしたものを「報酬月額」といいます。
報酬月額を1等級から50等級まで50段階に区分したものを「標準報酬月額」といいます。
では、条文を読んでみましょう。
第41条 (定時決定) ① 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ② ①の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ③ ①の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 |
定時決定のポイント!
★毎年7月1日現在で行います
★「4月+5月+6月の報酬の総額÷その期間の月数」で計算した額が「報酬月額」です。
・ ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者の場合は11日)未満の月は除いて計算します。分母の「その期間の月数」は「3」と限りません。「2」になることも「1」になることもありますので注意しましょう。
・ 例えば、4月、5月、6月の報酬(報酬支払基礎日数は17日以上)が、それぞれ、188,500円、196,200円、182,300円だったとすると、(188,500円+196,200円+182,300円)÷3で、「報酬月額」は189,000円です。この額を標準報酬月額等級表にあてはめ、「標準報酬月額」は190,000円となります。
★決定された標準報酬月額の有効期間は、その年の9月から翌年の8月までです。
★定時決定を行わない者
・ 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
・ 7月から9月までのいずれかの月に随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定が行われる者
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)
②【H29年出題】
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。
③【R3年出題】
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

【解答】
①【H19年出題】 〇
定時決定は、4月・5月・6月に支払われた報酬で算定します。
問題文のように、毎月末日締め、翌月15日支払いの場合は、4月15日払い(3月分)、5月15日払い(4月分)、6月15日払い(5月分)で算定します。
②【H29年出題】 ×
6月1日から7月1日に資格を取得したものは、その年の定時決定の対象から除外されます。問題文の6月1日に被保険者資格を取得した者は、その年の定時決定は行いません。
③【R3年出題】 ×
定時決定の届出の提出期限は、7月10日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-292
R4.6.10 下請負事業の分離
建設の事業が数次の請負で行われている場合は、下請負事業が元請負事業に一括され、徴収法上、元請負人のみが事業主として取り扱われます。
しかし、一定規模以上の下請負事業は、元請負人の請負に係る事業から分離し、保険関係を独立させることができます。
条文を読んでみましょう。
第8条 (請負事業の一括) ① 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。
② ①に規定する場合において、元請負人及び下請負人が、当該下請負人の請負に係る事業に関して①の規定の適用を受けることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可があったときは、当該請負に係る事業については、当該下請負人を元請負人とみなして①の規定を適用する。
則第8条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請) 法第8条第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
則第9条 (下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準) 法第8条第2項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号(有期事業の一括の要件)に該当する事業以外の事業でなければならない。 |
下請負事業の分離のポイント!
・請負事業の一括は法律上当然に行われますが、下請負人を分離させる場合は、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限が委任されています)の認可が必要です。
・有期事業の一括の要件に該当しない規模のものが分離の対象です。
分離の要件=概算保険料が160万円以上、又は請負金額が1億8千万円以上であること
過去問をどうぞ!
①【H27年出題(労災)】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8千万円未満でなければならない。
②【H27年出題(労災)】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。
③【H27年出題(労災)】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書については、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に当該申請書を提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【H27年出題(労災)】 ×
「厚生労働省令で定める事業」とは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」のことです。
下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の事業の規模が、概算保険料が160万円以上、又は、請負金額が1億8千万円以上でなければなりません。
②【H27年出題(労災)】 ×
下請負事業の分離の認可は、いずれかが単独で行うことはできません。元請負人と下請負人が共同で、「下請負人を事業主とする認可申請書」を所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
③【H27年出題(労災)】 〇
「下請負人を事業主とする認可申請書」は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
しかし、例外で、「やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。」と定められています。
やむを得ない理由とは、「天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等」とされています。
(昭47.11.24労徴発41号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-291
R4.6.9 請負事業の一括
建設の事業が数次の請負で行われている場合は、下請負事業が元請負事業に一括され、徴収法上、元請負人のみが事業主として取り扱われます。
条文を読んでみましょう。
第8条 (請負事業の一括) 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行なわれる場合には、この法律の規定の適用については、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみを当該事業の事業主とする。 則第7条 法第8条第1項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする |
請負事業の一括のポイント!
一括の対象になるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「建設の事業」です。
法律上当然に一括されます。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題(労災)】
請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。
②【R2年出題(労災)】
請負事業の一括は、元請負人が、請負事業の一括を受けることにつき所轄労働基準監督署長に届け出ることによって行われる。
③【H26年出題(労災)】
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
④【R2年出題(労災)】
請負事業の一括が行われ、その事業を一の事業とみなして元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付の義務を負い、更に労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となる。

【解答】
①【R2年出題(労災)】 ×
請負事業の一括が適用されるのは、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「建設の事業」が数次の請負によって行われるものです。「立木の伐採」の事業には適用されません。
(則第7条)
②【R2年出題(労災)】 ×
請負事業の一括は、法律上当然に行われます。「届け出」や「認可」などの手続きは要りません。
(法第8条)
③【H26年出題(労災)】 〇
「雇用保険」に係る保険関係は一括されません。それぞれの「事業単位」で、労働保険徴収法が適用されます。
④【R2年出題(労災)】 ×
請負事業の一括が行われた場合、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含めて、事業主として保険料の納付の義務を負います。
しかし、労働関係の当事者として下請負人やその使用する労働者に対して使用者となることはありません。
 次回は、下請負事業の分離の要件です。
次回は、下請負事業の分離の要件です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-290
R4.6.8 傷病手当と基本手当の関係
受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業安定所に出頭することができない場合で、その期間が継続して15日未満の場合は、「証明書」で失業の認定を受け、「基本手当」を受けることができます。
継続して15日以上の場合は、基本手当の代わりに、傷病手当を受けることができます。
今回は、疾病又は負傷の理由で、引き続き30日以上職業に就くことができない場合の「受給期間の延長」がテーマです。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から1年(所定給付日数が330日の場合は1年+30日、360日の場合は1年+60日)が原則です。
しかし、この受給期間内に、妊娠、出産等の理由で引き続き30日以上職業に就くことができない場合は、申し出により、受給期間を離職日の翌日から最長4年まで延長することができます。
「疾病又は負傷」により引き続き30日以上職業に就くことができない場合も、受給期間の延長の対象になります。
★その際のポイントは以下の通りです★
・当該傷病を理由として傷病手当の支給を受ける場合は、当該傷病に係る期間については、受給期間の延長の措置の対象とされません。
そのため、受給期間の延長を申請した後に、同一の傷病を理由として傷病手当の支給を申請した場合には、受給期間の延長の措置が取り消されます。
(行政手引50271)
★「傷病手当」と「受給期間の延長」の関係の注意点です★
・公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う以前に疾病又は負傷により職業に就くことができない状態にある場合は、傷病手当の対象にはなりません。しかし、受給期間の延長の申出をすることはできます。
・疾病又は負傷を理由として受給期間を延長した場合でも、その後受給資格者が当該疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を申請したときは、受給期間の延長が当初からなかったものとみなされ、傷病手当の支給が行われます。
なお、その場合の傷病手当の支給日数は、当該疾病又は負傷を理由とする受給期間の延長が無いものとした場合の支給できる日数が限度です。
(行政手引53002)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
離職前から引き続き傷病のため職業に就くことができない状態にある者について、一定の要件を満たす場合には、その者の申出により当該離職に係る受給期間を延長することは可能であるが、当該離職の日までの傷病期間に相当する日数は受給期間の延長の対象とはならない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H22年出題】
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
例えば、離職前から引き続き240日間、傷病のために職業につくことができない場合は、申し出により受給期間を延長することができます。
240日間について、離職日までが150日、離職日の翌日以後が90日の場合は、離職の日までの150日間は、受給期間の延長の対象にはなりません。原則の受給期間に加えることができるのは離職の翌日以後の90日間となります。
(行政手引50272)
②【H28年出題】 〇
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができます。
傷病手当は支給されません。
(行政手引53003)
③【H22年出題】 ×
傷病手当の条件は疾病又は負傷のために職業に就くことができない状態が「求職の申込み後」において生じたものであることです。
問題文のように「求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合」は、傷病手当は支給されません。
(行政手引53002)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-289
R4.6.7 傷病手当の支給要件
疾病又は負傷により職業に就くことができない場合、その期間が継続して15日未満なら、「証明書」による失業の認定で基本手当を受けることができます。
その期間が継続して15日以上の場合は、基本手当の代わりに「傷病手当」を受けることができます。
今回のテーマは「傷病手当」です。
では、条文を読んでみましょう。
第37条 ① 傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間内の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日(疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができないことについての認定を受けた日に限る。)について、第4項の規定による日数に相当する日数分を限度として支給する。 ② ①の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。 ③ 傷病手当の日額は、基本手当の日額に相当する額とする。 ④ 傷病手当を支給する日数は、①の認定を受けた受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数とする。 ⑤ 給付制限の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、傷病手当を支給しない。 ⑥ 傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。 ⑧ ①の認定を受けた受給資格者が、当該認定を受けた日について、健康保険法の規定による傷病手当金、労働基準法の規定による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付その他これらに相当する給付であって法令により行われるもののうち政令で定めるものの支給を受けることができる場合には、傷病手当は、支給しない。 ⑨ 自己の労働による収入を得た場合の減額、待期、未支給の請求手続き、並びに不正受給による給付制限の規定は、傷病手当について準用する。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が当該受給資格に係る離職前から継続している場合には、他の要件を満たす限り傷病手当が支給される。
②【H28年出題】
傷病手当の日額は、雇用保険法第16条の規定による基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額である。
③【R2年出題】
訓練延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者が疾病又は負傷のため公共職業訓練等を受けることができなくなった場合、傷病手当が支給される。
④【H24年出題】
広域延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「離職前から継続」している場合は、傷病手当は支給されません。
傷病手当は、次の要件に該当した場合に支給されます。
1 受給資格者であること
2 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしていること
3 疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であること
4 疾病又は負傷のために職業に就くことができない状態が「求職の申込み後」において生じたものであること
★4がポイントです。
疾病又は負傷のため職業に就くことができない状態が、当該受給資格に係る離職前から継続している場合、又は係る状態が当該受給資格に係る離職後に生じた場合であっても、公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行う前に生じその後も継続している場合は、傷病手当の対象となりません。
(行政手引53302)
②【H28年出題】 ×
傷病手当の日額は基本手当の日額に相当する額(基本手当の日額と同じ額)です。
なお、傷病手当を支給する日数は、受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
また、傷病手当の支給があったときは、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当の支給があったものとみなされます。
(法第37条第3項、第4項、第6項)
③【R2年出題】 ×
②の解説でお話ししましたように、傷病手当を支給する日数は、受給資格者の所定給付日数から当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数です。
「所定給付日数-既に基本手当を支給した日数」が傷病手当を支給する日数ですので、延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当は支給されません。
(行政手引53004)
④【H24年出題】 〇
③と同じです。延長給付に係る基本手当を受給中の受給資格者については、傷病手当が支給されることはありません。
(行政手引53004)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-288
R4.6.6 失業の認定日の変更
基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。
失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われるのが原則です。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
今日のテーマは、失業の認定日の変更です。
法第15条第3項で、厚生労働省令で定める受給資格者については別段の定めをすることができる、と規定されています。
厚生労働省令を読んでみましょう。
則第23条 法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。 ① 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの ② 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者 |
受給資格者が職業に就くためその他やむを得ない理由のため、所定の失業の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合は、受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。
★「職業に就くためその他やむを得ない理由」については、行政手引51351でいくつか掲げられています。
・「就職」する場合(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない。)
・ 法第15条第4項各号(証明書による失業の認定)に該当する場合
・公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合
・各種国家試験、検定等の資格試験を受験する場合
等々 (以下省略します。)
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
②【H28年出題】
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。
③【H27年出題】
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
受給資格者の申出により、公共職業安定所長が失業の認定日を変更することができます。
②【H28年出題】 〇
「子弟の入学式又は卒業式等への出席」の場合は、申し出ることによって失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
失業の認定日変更の申出は、原則として、事前に行うこととされています。
ただし、変更事由が突然生じた場合、失業の認定日前に就職した場合等であって、事前に変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
(行政手引51351)
③【H27年出題】 ×
親族の傷病についての介護、危篤、死亡、葬儀の場合は、申し出ることによって失業の認定日の変更の取扱いを受けることができます。
申出を受けた日が失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日について、失業の認定が行われます。
(則第24条第2項第2号、行政手引51351)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-287
R4.6.5 失業の認定日
基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給されます。
失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければなりません。
今回のテーマは「失業の認定日」です。
条文を読んでみましょう。
第15条 (失業の認定) ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 ③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 |
 失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の 28日の各日について行うのが原則ですが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行います。 (則第24条)
失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の 28日の各日について行うのが原則ですが、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行います。 (則第24条)
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
②【R1年出題】
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

【解答】
①【H27年出題】 〇
失業の認定は、前回の認定日以後、当該認定日の前日までの期間について行われます。
②【R1年出題】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-286
R4.6.4 証明書による失業の認定
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて提出しなければなりません。
しかし、一定の理由の場合は、「証明書」で失業の認定を行うことができます。
今回のテーマは「証明書による失業の認定」です。
条文を読んでみましょう。
第15条 (失業の認定) ④ 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。 1 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。 2 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 3 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。 4 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
|
証明書による失業の認定が受けられるのは、上の1から4の場合に限られます。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。
②【H28年出題】
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。
③【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定日に、民間の職業紹介事業者の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由を記載した証明書を提出することによって、公共職業安定所に出頭しなくても、失業の認定を受けることができる。
④【R1年出題】
受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

【解答】
①【H21年出題】 〇
疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合で証明書による失業の認定を受けることができるのは、その期間が継続して15日未満の場合です。
②【H28年出題】 〇
なお、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合でその期間が継続して15日以上の場合は、傷病手当の対象になります。ただし、その状態が「求職の申込み後」に生じたことが条件です。
③【H25年出題】 ×
証明書による失業の認定が受けられるのは、「公共職業安定所の紹介」に応じて求人者に面接する場合です。民間の職業紹介事業者の紹介の場合は対象外です。
ちなみに、「公共職業安定所の紹介によらないで」求人者に面接する場合は、「失業の認定日の変更」の申出ができます。
(行政手引51351)
④【R1年出題】 〇
例えば、地震などで受給資格者が出頭できない場合は、官公署の証明書などを受け、事故がやんだ後における最初の失業の認定日に公共職業安定所に出頭して証明書を提出したときは、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間も含めて、失業の認定を受けることができます。
(行政手引51401)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-285
R4.6.3 療養給付(通勤災害)の一部負担金
通勤災害で療養給付を受けた場合、労働者は一部負担金を納付しなければなりません。
一部負担金は、200円(健康保険法の日雇特例被保険者は100円)で、休業給付から控除されます。
なお、業務災害の療養補償給付の場合は、一部負担金は徴収されません。業務災害は、使用者に補償義務があるからです。
では、条文を読んでみましょう。
第31条 ② 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、 200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ③ 政府は、労働者から徴収する一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
則第44条の2 (一部負担金) ① 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者(一部負担金が徴収されない者)は、次の各号に掲げる者とする。 1 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 3 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ② 一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。 ③ 法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
②【H24年出題】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
③【H24年出題】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。
④【H25年出題】
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
⑤【H25年出題】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
⑥【H24年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
一部負担金は、通勤災害の「療養給付」が対象です。
②【H24年出題】 〇
一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)です。
③【H24年出題】 ×
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金は徴収しません。
④【H25年出題】 ×
療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金は徴収しません。
⑤【H25年出題】 〇
休業給付の初回の給付額から、一部負担金が控除されます。
⑥【H24年出題】 〇
休業給付で最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から、一部負担金の額に相当する額が控除されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-284
R4.6.2 総括安全衛生管理者を選任する事業場
今回のテーマは総括安全衛生管理者を選任する事業場です。
まず、条文を読んでみましょう。
第10条 (総括安全衛生管理者) ① 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項(救護に関する措置)の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。 1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの ② 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない |
 総括安全衛生管理者は「事業場ごと」に選任します。
総括安全衛生管理者は「事業場ごと」に選任します。
第10条第2項で、「総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。」と規定されています。イメージとしては、工場長や作業所長などです。
ちなみに、労働安全衛生法は、労働基準法と同様に「事業場単位」で適用されます。一の事業場であるか否かは、「場所的観念」で決定されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務をもっぱら行っている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
②【R3年出題】
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
③【R2年出題】
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
④【H24年出題】
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
総括安全衛生管理者は、政令で定める規模の「事業場ごとに」選任します。
事業場の業種の区分は、例えば、〇〇製鉄株式会社の場合、「製鉄所」は製造業ですが、別の場所にある管理事務部門の本社や支店は「その他の業種」となります。
ちなみに、総括安全衛生管理者の選任義務があるのは、「製造業」では労働者数が常時300人以上の事業場、「その他の業種」では、労働者数が常時1,000人以上の事業場です。
(S47.9.18発基第91号)
②【R3年出題】 ×
企業全体における労働者数ではなく、事業場の労働者数が基準になり、企業全体ではなくその事業場の安全衛生管理を統括管理します。
(令第2条)
③【R2年出題】 〇
総括安全衛生管理者の選任の要件は、「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」です。安全管理者の資格や衛生管理者の資格は問われません。
④【H24年出題】 〇
常時100人以上の労働者を使用する清掃業の事業場は、総括安全衛生管理者を選任する義務があります。
総括安全衛生管理者のキーワードは「統括管理」です。名前は総括安全衛生管理者だけど、仕事は総括管理ではなく統括管理です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-283
R4.6.1 労働条件を明示する方法
労働契約を締結する際に、使用者には労働条件を明示する義務があります。
明示すべき労働条件の範囲は厚生労働省令で定められていて、前回お話ししたように、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。
今回は、明示する方法を確認します。
もう一度、法第15条を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
施行規則第5条 ③ 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、絶対的明示事項(昇給に関す事項を除く。)とする。 ④ 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付とする。 ただし、当該労働者が次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。 1 ファクシミリを利用してする送信の方法 2 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
|
★絶対的明示事項のうち昇給以外は、書面の交付等による明示が義務付けられています。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。
②【R3年出題】
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」について、労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため、将来就業する可能性のある場所や、将来従事させる可能性のある業務を併せ、網羅的に明示しなければならない。
③【R2年出題】
労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき賃金に関する事項及び書面について、交付すべき書面の内容としては、労働者の採用時に交付される辞令等であって、就業規則等(労働者への周知措置を講じたもの)に規定されている賃金等級が表示されたものでもよい。

【解答】
①【H24年出題】 ×
書面で明示しなければならない労働条件について、「当該労働者に適用する部分を明らかにして就業規則を交付すること」は差し支えないとされています。
(H11.1.29基発第45号)
②【R3年出題】 ×
「雇入れ直後の」就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りる、とされています。しかし、将来の就業場所や従事させる業務を併せ、網羅的に明示することは差し支えありません。
(H11.1.29基発第45号)
③【R2年出題】 〇
交付すべき書面の内容としては、就業規則と併せて賃金に関する事項がその労働者について確定できるものであればよい、とされています。
ですので、労働者の採用時に交付される辞令等で、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えありません。この場合、就業規則等が労働者に周知されていることが必須です。
(H11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-282
R4.5.31 労働契約締結時に明示すべき労働条件
前回の続きです。
労働契約を締結する際、使用者は労働者に労働条件を明示することが義務づけられています。
明示事項には、絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)と相対的明示事項(制度を設ける場合は明示しなければならない事項)があり、明示すべき労働条件の範囲は、厚生労働省令で定められています。
では、明示すべき労働条件の範囲を確認しましょう。
施行規則第5条 <絶対的明示事項> 1 労働契約の期間 2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準 (期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限る) 3 就業の場所、従事すべき業務 4 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換 5 賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給 6 退職(解雇の事由を含む。)
<相対的明示事項> 7 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、退職手当の支払の時期 8 臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額 9 労働者に負担させるべき食費、作業用品等 10 安全及び衛生 11 職業訓練 12 災害補償及び業務外の傷病扶助 13 表彰及び制裁 14 休職 |
1から6の絶対的明示事項は、必ず明示する義務がありますが、7~14の相対的明示事項については、制度を設けていない場合は、明示義務はありません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。
②【H25年出題】
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
③【H18年出題】
使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。
④【H24年出題】
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。
【解答】
①【R1年出題】 ×
「労働契約の期間」については、「期間の定めがある労働契約」の場合は「契約期間」を、「期間の定めのない労働契約」の場合は、「期間の定めのない旨」の明示が必要です。
(平11.1.29基発45号)
②【H25年出題】 〇
「期間の定めのある労働契約」で、更新する場合があるものの締結の場合は、更新する場合の基準を明示する義務があります。
契約更新の判断基準として、契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況等があります。
(平24.10.26基発1026第2号)
③【H18年出題】 ×
「所定労働時間を超える労働の有無」は絶対的明示事項ですが、「所定労働日以外の労働の有無」は明示すべき事項には入っていません。
④【H24年出題】 ×
「表彰に関する事項」は相対的明示事項です。表彰に関する制度を設けている場合は、労働契約を締結する際に明示する必要があります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-281
R4.5.30 労働条件の明示
労働契約を締結する際、使用者は労働者に労働条件を明示することが義務づけられています。
労働条件がはっきりしないまま働くことによるトラブルを防止するためです。
では、条文を読んでみましょう。
第15条 (労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
明示する事項と方法は、厚生労働省令で定められています。内容は次回お話します。
では、過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、同法第1条「労働条件の原則」及び第2条「労働条件の決定」でいう労働条件の範囲とは異なる。
②【H29年出題】
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により派遣先の事業のみを派遣中の労働者を使用する事業とみなして適用することとされている労働時間、休憩、休日等については、派遣先の使用者がその義務を負う。

【解答】
①【H16年出題】 〇
労働基準法第1条と第2条の「労働条件」は、広く解釈され、賃金、労働時間、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含んだ「労働者の職場における一切の待遇」をいう、とされています。
一方、第15条に基づいて明示すべき労働条件の範囲は、施行規則第5条で具体的に定められています。
問題文の通り、第1条・第2条の労働条件と第15条の労働条件は範囲が異なります。
②【H29年出題】 ×
派遣労働者に対する労働条件の明示は、労働契約関係にある「派遣元」の使用者が明示する義務を負っています。
労働者派遣法における労働基準法の適用に関する特例により、派遣元が労基法の義務を負わない労働時間、休憩、休日等も含めて、労働条件の明示をする必要があります。
(昭61.6.6基発333号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-280
R4.5.29 労働基準法違反の契約
労働基準法は、労働者を保護するために労働条件の最低ラインを定めるもので、強行法規としての効力をもちます。
労働基準法に違反する労働契約を締結した場合、その効力はどうなるのでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第13条 (この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
例えば、使用者と労働者が、「時間外労働をさせた場合でも、割増賃金を支給しない」と契約した場合で考えてみましょう。
労働基準法では、1日8時間を超えて労働させた場合は、使用者に2割5分増の割増賃金を支払う義務を課しています。
ですので、労働契約上の「割増賃金を支給しない」の部分は無効になります。無効になった部分は、労働基準法の規準により、「時間外労働をさせた場合は割増賃金を支給する」という内容に置き換わります。
なお、無効になるのは労働基準法の基準に達していない「割増賃金を支給しない」の部分のみです。それ以外の労働契約の部分は有効です。労働契約全体を無効にすると労働者の労働の機会そのものが無くなってしまうからです。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H27年出題】
労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とすると定めている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
「無効となった部分は、この法律で定める基準による。」の部分で、無効となった部分は、労働基準法の基準どおりに補充されることになります。
②【H27年出題】 〇
労働基準法第13条で無効になるのは、基準に「達しない」労働条件です。労働基準法の基準よりも有利な労働条件は有効です。
一方、労働組合法第16条は、『労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。』と規定されています。
労働協約で定める労働条件に「違反する」(→「達しない」ではありません。)労働契約の部分は、無効です。
★「労働条件の力関係」をおさえましょう。
労働基準法 > 労働協約 > 就業規則 > 労働契約
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「要介護状態」の比較
「要介護状態」の比較
R4-279
R4.5.28 「要介護状態」比較/介護保険法と育児・介護休業法と労災保険法
■介護保険の保険給付には、「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」があります。
「介護給付」は要介護状態にある者に対しての保険給付です。
■育児・介護休業法の「介護休業」は、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
それぞれの「要介護状態」の定義を比較しましょう。
まず、介護保険法の条文を読んでみましょう。
第7条 (定義) 介護保険法において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 施行規則第2条 厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 |
次に、育児・介護休業法の条文を読んでみましょう。
第2条 (定義) 要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
施行規則第2条 厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。 |
介護保険法の要介護状態は、「6月間」にわたり継続して、常時介護を要する状態、育児介護休業法の要介護状態は、「2週間以上の期間」にわたり常時介護を必要とする状態です。
法律によって違いますので、注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
「労災保険法」の問題です。
労災【H25年出題】
女性労働者が1週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所から帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

【解答】
労災【H25年出題】 〇
合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合は、逸脱・中断の間とその後の移動は通勤になりません。
しかし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、合理的な経路に戻ってからの移動は通勤となります。(この場合でも、逸脱・中断の間は通勤になりません。)
問題文は、日常生活上必要な行為に該当しますので、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当します。
■ ここでも「要介護状態」という用語が出てきます。定義は「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」をいいます。
(則第7条、第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法
労働契約法
R4-278
R4.5.27 契約期間についての配慮
短期間の有期労働契約を反復更新することは、雇止めに関するトラブルにつながりやすくなります。
最初からその有期契約労働者を使用しようとする期間を契約期間とする等によって、全体として契約期間を長期化し、契約更新の回数そのものを減少させる配慮が必要です。
条文を読んでみましょう。
第17条第2項 (契約期間についての配慮) 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 |
法第17条第2項では、その有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定するよう、使用者は配慮しなければならないことを規定しています。
(平24.8.10基発0810第2号)
過去問をどうぞ!
【H23年出題】 ※法改正による修正あり
使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないとされている。

【解答】
【H23年出題】 〇 ※法改正による修正あり
ポイントを穴埋めでチェックしましょう。
・契約期間についての配慮(法第17条第2項関係)
有期労働契約については、短期間の契約が< A >された後に雇止めされることによる紛争がみられるところであるが、短期間の有期労働契約を< A >するのではなく、当初からその有期契約労働者を使用しようとする期間を契約期間とする等により全体として契約期間が< B >することは、雇止めに関する紛争の端緒となる契約更新の回数そのものを減少させ、紛争の防止に資するものである。
このため、法第17条第2項において、その有期労働契約により労働者を使用する目的に応じて適切に契約期間を設定するよう、使用者は配慮しなければならないことを規定したものであること。
(平24.8.10基発0810第2号)

【解答】
A 反復更新
B 長期化
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法
労働契約法
R4-277
R4.5.26 契約期間中の解雇
民法第628条では、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる」と規定されています。
民法で明らかにされていない「やむを得ない事由があるときに該当しない場合」の取扱いを定めているのが、労働契約法第17条です。
条文を読んでみましょう。
第17条 (契約期間中の解雇) 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 |
ポイント!
■ 労働契約法第17条第1項は、使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中は有期契約労働者を解雇することができないことを規定しています。
■ 「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されています。
(平24.8.10基発0810第2号)
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
使用者は、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合であっても、その契約が満了するまでの間においては、労働者を解雇することができない。
②【H28年出題】
使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。
③【R1年出題】
有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合、当該事由に該当することをもって労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される。

【解答】
①【H22年出題】 ×
「やむを得ない事由がある」場合は、契約が満了するまでの間でも、労働者を解雇することができます。
(民法第628条)
②【H28年出題】 〇
労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
「やむを得ない事由」があると認められる場合は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されています。
③【R1年出題】 〇
実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断されます。
(平24.8.10基発0810第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-276
R4.5.25 障害厚生年金の計算の基礎になる期間
障害厚生年金の計算式は以下の通りです。
1級 → 報酬比例の年金額×1.25(+配偶者の加給年金額)
2級 → 報酬比例の年金額(+配偶者の加給年金額)
3級 → 報酬比例の年金額(最低保障額あり)
障害厚生年金の受給権の発生以降も厚生年金保険の被保険者期間がある場合、障害厚生年金の額の計算に算入されるのはどこまででしょう?
条文を読んでみましょう。
第51条 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない。 |
障害認定日の属する月「後」の被保険者であった期間は、計算に入りません。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。
②【H29年出題】
傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
③【H28年出題】
被保険者である障害厚生年金の受給権者が被保険者資格を喪失した後、被保険者となることなく1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から障害厚生年金の額が改定される。

【解答】
①【H22年出題】 ×
障害認定日の属する「月の前月」までではなく、「障害認定日の属する月」までが、その計算の基礎とされます。
|
| 障害認定日 |
|
|
条文の「障害認定日の属する月後」の「後」に注目してください。計算に入れるのは障害認定日の属する月までです。
②【H29年出題】 〇
障害認定日が平成29年3月1日ですので、障害厚生年金の額の計算に入れるのは平成29年3月までです。平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎とされません。
③【H28年出題】 ×
障害厚生年金には退職時改定の仕組みはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-275
R4.5.24 障害厚生年金の最低保障額
初診日に厚生年金保険の被保険者(=国民年金第2号被保険者)だった場合、障害等級1・2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金の2階建てで支給されますが、3級の場合は、障害厚生年金のみ支給されます。
障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金には最低保障額があります。
条文を読んでみましょう。
第50条 (障害厚生年金の額) 1 障害厚生年金の額は、第43条第1項(老齢厚生年金の額)の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。 2 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、1項の規定にかかわらず、1項に定める額の100分の125に相当する額とする。 3 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを 100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。 |
★ 国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額は、777,800円(令和4年度)×4分の3=583,350円を端数処理(50円未満切り捨て、50円以上100円未満を100円に切り上げ)して、58万3400円です。
★ポイント1・2級でも障害基礎年金が支給されない場合があります。
「厚生年金保険の被保険者」でも、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合は、国民年金の第2号被保険者となりません。
(詳細は前回の記事をどうぞ→R4.5.23 国年の第2号被保険者)
そのため、初診日に厚生年金保険の被保険者でも国民年金の第2号被保険者でない場合は、障害等級1・2級でも、障害厚生年金のみの支給となります。
その場合でも、障害厚生年金の最低保障額が適用されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額が、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは、障害等級2級の障害基礎年金の額に3分の2を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する。
②【R2年出題】
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
③【H29年出題】
障害の程度が障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)に満たないときは、当該額とする。

【解答】
①【H25年出題】 ×
最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の額に「4分の3」を乗じて得た額です。
②【R2年出題】 ×
①と同じです。最低保障額は、障害等級2級の障害基礎年金の年金額の4分の3に相当する額です。
③【H29年出題】 〇
障害厚生年金の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額×4分の3に端数処理(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)をした額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-274
R4.5.23 国年の第2号被保険者
国民年金の強制加入被保険者として、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つがあります。
今回は、第2号被保険者がテーマです。
条文を読んでみましょう。
第7条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者とする。 法附則第3条 (被保険者の資格の特例) 第7条第1項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「の被保険者」とあるのは、「の被保険者(65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。)」とする。 |
ポイント!
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となります。
年齢要件や国内居住要件がないのがポイントです。
ただし、厚生年金保険の被保険者で65歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権がある者は、第2号被保険者となりません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
②【H26年出題】(改正による修正あり)
65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
③【H27年出題】
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
第1号被保険者と第3号被保険者には、「20歳以上60歳未満」という年齢要件がありますが、第2号被保険者には年齢要件はありません。
厚生年金保険の被保険者であれば20歳未満でも、国民年金の第2号被保険者となります。
②【H26年出題】(改正による修正あり) ×
65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権」を有していなければ、第2号被保険者となります。
「障害」を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、「老齢又は退職」を支給事由とする年金給付の受給権を有していなければ、第2号被保険者となります。
③【H27年出題】 〇
第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが条件です。
問題文の場合、厚生年金保険の被保険者ではありますが、65歳以上でかつ「厚生年金保険の在職老齢年金を受給中=(老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有する)」ですので、第2号被保険者にはなりません。
そのため、その者の配偶者は第3号被保険者とはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-273
R4.5.22 健保・保険料の源泉控除
事業主は被保険者負担分の保険料を、報酬から控除できます。
控除のルールを条文で読んでみましょう。
第167条 (保険料の源泉控除) 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 |
ポイント!
被保険者の当月分の給料から控除できるのは、前月分の被保険者負担分の保険料です。
ただし、被保険者が月末に退職し、当月分の保険料が徴収される場合は、前月分と当月分を控除することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。
②【R1年出題】
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。
③【H26年出題】
勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間にかかるもの)で4月分及び5月分の健康保険料を控除することができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
保険料は、資格を取得した月から徴収されますので、5月23日に被保険者資格を取得した場合は5月分から徴収されます。
給与から控除できるのは、前月分です。
月給制で、毎月20日締め、当月末日払いの場合、6月に支給される最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で前月分の5月分の保険料を控除できます。
しかし、毎月末日締め、当月25日払いの場合、当月の5月に支給される最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では保険料を控除できません。翌月の6月に支給される給与から控除します。
②【R1年出題】 ×
7月30日退職の場合は、翌日の7月31日に資格を喪失します。
第156条で、「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない」と規定されていますので、資格喪失月は保険料が生じないのがポイントです。
7月30日に退職した場合、保険料が生じるのは6月分までです。7月25日支払いの給与(6月16日から7月15日までの期間に係るもの)で、6月分の保険料を控除します。
③【H26年出題】 〇
5月31日退職の場合は、資格喪失日が6月1日で、保険料は5月分まで生じます。
末日退職の場合の健康保険料の源泉控除は、前月分と当月分を控除できますので、毎月末日締め、当月25日払いの場合、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間にかかるもの)で前月の4月分と当月の5月分の保険料を控除することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-272
R4.5.21 資格喪失月の賞与の保険料は?
賞与の保険料額の計算式は、以下の通りです。
・介護保険第2号被保険者
→ 「標準賞与額×一般保険料率」+「標準賞与額×介護保険料率」
・介護保険第2号被保険者以外
→ 「標準賞与額×一般保険料率」
★ 事業主と被保険者が2分の1ずつ負担します。事業主は、被保険者の負担分を賞与から控除できます。条文を読んでみましょう。
第167条 (保険料の源泉控除) ② 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を賞与から控除することができる。
②【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
③【R3年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
事業主は、賞与から、被保険者の負担する標準賞与額に係る保険料を控除することができます。
②【H29年出題】 〇
資格を喪失した月の保険料については、第156条第3項で次のように定められています。
「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」
問題文のように、前月から引き続き被保険者である者が、7月25日に退職し26日に資格を喪失した場合は、7月分の保険料は算定されませんので、事業主は納付する義務はありません。
資格喪失月に支給された賞与についても、保険料は算定されませんので、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。
(法第156条第3項)
③【R3年出題】 〇
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与が支給され、同月20日に退職した場合、当該賞与に係る保険料は徴収されません。
しかし、「保険料徴収の必要がない被保険者資格の喪失月であっても、被保険者期間中に支払われる賞与に基づき決定される標準賞与額は、年度の累計額に算入する。被保険者資格の喪失月であり資格喪失日の前日までに支払われる賞与額についても被保険者賞与支払届の提出を徹底すること。標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。」とされています。
(H19.5.1庁保険発第0501001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-271
R4.5.20 健康保険/保険料の負担
健康保険の保険料は、原則として被保険者と事業主がそれぞれ2分の1を負担します。
また、保険料の納付義務を負うのは、事業主です。
条文を読んでみましょう。
第161条 (保険料の負担及び納付義務) 1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 3 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
第162条 (健康保険組合の保険料の負担割合の特例) 健康保険組合は、前条第1項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。 |
ポイント!
任意継続被保険者は、本人が保険料の全額を負担し、保険料の納付義務も本人が負います。
では、過去問をどうぞ!
①【H15年出題】
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うが、任意継続被保険者の負担する保険料を納付する義務を負わない。
②【H30年出題】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。
③【H19年出題】
健康保険組合は、規約で定めるところにより、一般保険料額だけではなく、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができる。

【解答】
①【H15年出題】 〇
任意継続被保険者の保険料は、本人が納付義務を負います。
②【H30年出題】 〇
保険料額は、事業主と被保険者が2分の1ずつ負担するのが原則ですが、健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担割合を増加することができます。
ポイント!
・健康保険組合だけの特例です。全国健康保険協会には適用されません。
・負担割合を増加できるのは「事業主の負担分」です。被保険者の負担割合は増加できません。
③【H19年出題】 〇
「健康保険組合」は、規約で定めるところにより、介護保険料額についても事業主の負担割合を被保険者よりも高くすることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-270
R4.5.19 増加概算保険料
労働保険の保険料は、保険年度当初に概算で申告・納付し、保険年度が終了してから確定精算する仕組みになっています。(継続事業の場合)
しかし、年度の途中で、事業規模が拡大したなどの理由で、賃金総額の見込額が増加し、一定の要件に当てはまった場合は、「増加概算保険料」を申告・納付することになっています。
今回のテーマは「増加概算保険料」です。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H23年出題(労災)】
労災保険に係る保険関係のみ成立していた事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため、一般保険料に係る保険料率が変更した場合において、当該変更後の保険料率に基づいて算定した概算保険料の額が、既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であるときは、増加概算保険料を申告・納付しなければならない。
②【H23年出題(労災)】
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当するに至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである。
③【H22年出題(労災)】
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料を延納していないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。

【解答】
①【H23年出題(労災)】 〇
増加概算保険料の申告・納付の要件は、以下の2つです。
1 労働者数の増加等によって、概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が増加した
→ 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である
2 労災保険に係る保険関係のみ成立している事業又は雇用保険に係る保険関係のみ成立している事業が労災保険及び雇用保険の両保険に係る保険関係が成立する事業に該当するに至ったため一般保険料率が変更した
→ 変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であることとする。
問題文は2に該当しますので、増加概算保険料の申告・納付が必要です。
(法第16条、則第25条、法附則第5条、則附則第4条)
②【H23年出題(労災)】 〇
増加概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業も有期事業も同じです。賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内です。
(法第16条)
③【H22年出題(労災)】 ×
増加概算保険料も延納できますが、もともとの概算保険料を延納していることが条件です。問題文のように、増加前の概算保険料を延納していないときは、増加概算保険料の延納はできません。
(則第30条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-269
R4.5.18 雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険の被保険者は、「離職した日の翌日」又は「死亡した日の翌日」から被保険者資格を喪失します。
また、被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合、又、 被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合は、それぞれ当該事実のあった日に被保険者資格を喪失します。
(行政手引20601)
今日のテーマは被保険者の資格を喪失したときの手続きです。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
②【R2年出題】
公共職業安定所長は、雇用保険被保険者資格喪失届の提出があった場合において、被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨につき当該届出をした事業主に通知しなければならないが、被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。
③【R2年出題】
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、雇用保険法第7条に規定する届出の義務に違反する行為をしたときは、その法人又は人に対して罰金刑を科すが、行為者を罰することはない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
「事実のあった日」は、被保険者資格を喪失した日のことで、離職の場合は「離職した日の翌日」です。例えば、5月31日に離職した場合は、資格喪失日は6月1日です。資格喪失届は「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に提出しなければなりませんので、期限は、6月2日から起算して10日以内です。
②【R2年出題】 ×
「被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者に対しては通知しないことができる。」の部分が誤りです。
則第11条(被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がない場合の通知)には、次のように定められています。
公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者にも通知しなければなりません。
(則第11条)
③【R2年出題】 ×
「行為者を罰することはない」の部分が誤りで、行為者は罰則の対象です。
条文で確認しましょう。
第86条
法人(法人でない労働保険事務組合を含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
※行為者は罰せられ、法人又は人に対しても罰金刑が科されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-268
R4.5.17 「一定の障害状態」遺族補償年金
労働者が業務上死亡した場合、一定の遺族に「遺族補償年金」が支給されます。
前回は、遺族補償年金の対象になる遺族の第一の条件である「生計維持」についてお話しました。
さらに、「妻以外」の者は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。今回のテーマは「障害要件」です。
条文を読んでみましょう。
第16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること 4 前3号の要件(年齢要件)に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
遺族補償年金を受ける遺族の条件として、「妻」以外の者は、労働者の死亡の当時 1号から3号の「年齢要件」又は4号の「障害要件」に該当しなければなりません。
今回は、「厚生労働省令で定める障害の状態」がテーマです。
「厚生労働省令で定める障害の状態」については、次のように定められています。
則第15条 (遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態) 法第16条の2第1項第4号(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。 |
ポイントは、「5級以上」の部分と「労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上」の部分です。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】 ※改正による修正あり
遺族補償年金(複数事業労働者遺族年金において準用する場合を含む。)又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】
①【H19年出題】 〇
労働の高度の制限とは、「完全な労働不能で長期間にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を要するものよりも軽いが、労働の著しい制限よりは重く、長期間にわたり中等度の安静を要すること」をいうとされています。
(昭41.1.31基発73号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-267
R4.5.16 遺族補償年金~「生計を維持していた」
労働者が業務上死亡した場合、一定の遺族に「遺族補償年金」が支給されます。
条文を読んでみましょう。
第16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること 4 前3号の要件(年齢要件)に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
今日のポイント!
遺族補償年金を受けることができる遺族の第1条件は、労働者の死亡当時その収入によって「生計を維持していた」ものです。
今回のテーマは「生計維持」です。
「生計維持」の認定については、則第14条の4で次のように定められています。
則第14条の4 (遺族補償給付等に係る生計維持の認定) 遺族補償年金及び遺族補償一時金(複数事業労働者遺族給付及び遺族給付において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
②【H17年出題】
遺族補償年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。
③【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
④【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「妻」以外の者は、労働者の死亡の当時、「年齢要件」又は「障害要件」に該当する必要がありますが、妻は年齢、障害の要件は問われません。妻は「生計を維持していた」場合は、遺族補償年金を受けることができます。
②【H17年出題】 ×
「労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要」の部分が誤りです。「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。」とされています。
(昭41.1.31基発第73号)
③【H28年出題】 ×
②と同じ考え方です。
「労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる」、「いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。」という解釈ですので、労働者と同程度の収入があり、生活費を分担していた妻も、遺族補償年金を受けることができます。
④【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
「遺族補償年金」は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ものでなければなりませんが、「遺族補償一時金」は、「生計を維持していない」ものでも対象になり得ます。
(法第16条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-266
R4.5.15 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育
労働者を新しく雇い入れたとき、労働者の作業内容を変更したときは、安全衛生教育を行わなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第59条 (安全衛生教育) 1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 1項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 |
過去問をどうぞ!
①【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
②【H22年出題】
事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、雇入れた労働者すべてを対象として、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することができる。
③【H22年出題】
事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。

【解答】
①【H17年出題】 ×
雇入れ時の健康診断の対象は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者だけでなく臨時に使用する労働者も含む「全労働者」が対象です。
※「雇入れ時の健康診断」については、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目(項目は省略します。)について医師による健康診断を行わなければならない」と規定されています。(則第43条)
※一方、「雇入れ時の安全衛生教育」については、「事業者は、労働者を雇い入れたときは・・・」となっていますので、全ての労働者が対象です。
②【H22年出題】 ×
労働者を雇い入れたときは、則第35条で、①から⑧の事項について安全衛生教育を行うことが義務付けられています。
①から⑧のうち、①から④の事項については、「その他の業種」(総括安全衛生管理者の選任要件である労働者数が常時1,000人以上の事業場)の場合は、省略することができます。その他の業種では機械などを扱う事がほとんど無いからです。
問題文の「燃料小売業」は、その他の業種ではありませんので、①から④の事項を省略することはできません。
③【H22年出題】 ×
「事業者は、教育する事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」と規定されていますので、問題文のように当該事項の「全部」に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、「全部」の事項についての安全衛生教育を省略することができます。
ちなみに、特別教育、職長教育にも同じ規定があります。
(則第35条第2項、則第37条、則第40条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-265
R4.5.14 解雇予告の適用除外
今回のテーマは、解雇予告の適用が除外される労働者です。
条文を読んでみましょう。
第21条 前条の規定(解雇の予告)は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 1 日日雇い入れられる者 2 2か月以内の期間を定めて使用される者 3 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 4 試の使用期間中の者 但し、第1号に該当する者が1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。 |
ポイント!
原則と例外をおさえてください。
「日日雇入れられる者」には、原則として解雇の予告の規定は適用されませんが、「1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合」は、解雇の予告の規定が適用されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
日日雇い入れられる者には労働基準法第20条の解雇の予告の規定は適用されないが、その者が< A >を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
②【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。
③【H23年出題】
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試みの使用をされている者には適用されることはない。
④【H26年出題】
試みの使用期間中の労働者を、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告について定める労働基準法第20条の規定は適用されない。

【解答】
①【H30年選択式】
A1か月
②【H23年出題】 ×
「6か月」の期間を定めて使用される者には、第20条(予告期間及び予告手当)が適用されますので、期間の途中で解雇される場合は予告が必要です。
③【H23年出題】 ×
「試みの使用期間」の長さに制限はありませんので、例えば3か月でも6か月でも差し支えありません。
ただし、「試みの使用期間中」であっても、「14日」を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告制度が適用されます。
(昭24.5.14基収1498号)
④【H26年出題】 〇
試みの使用期間中に、雇入れの日から起算して14日以内に解雇する場合は、解雇の予告は不要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-264
R4.5.13 解雇の予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかった場合
例えば、5月1日に5月31日の終了をもって解雇する旨を予告していたが、その予告期間中に業務上の負傷をし、療養のため休業した場合、解雇予告の効力はどうなるのでしょうか?
第19条を確認しておきましょう。
第19条 (解雇制限) 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(ただし・・・以下省略) |
※「業務上の負傷又は疾病の療養のため休業する期間とその後30日間」、「産前産後の休業期間中とその後30日間」は解雇できません。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。
②【H30年出題】
労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。

【解答】
①【H24年出題】 ×
解雇予告期間 |
|
|
| ||||||
● 解雇 予告 |
| ● 業務上 負傷 |
|
|
| ● 解雇 予定日 |
|
|
|
|
| (解雇制限)業務上の傷病による療養のための休業期間+30日間 | |||||||
| |||||||||
解雇予告期間中に、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり休業を要する場合、それがたとえ1日か2日の軽度の負傷又は疾病であっても、第19条の解雇制限の適用があります。
問題文のように業務上の負傷をし療養のため2日間休業した場合は、休業期間中とその後30日間は解雇できません。
問題文の場合は、労働基準法第19条が適用され、当初の解雇予定日は解雇制限期間中となり、解雇できません。(解雇の効力は予告通りの日に発生しません。)
(昭和26.6.25基収2609号)
②【H30年出題】 ×
①の問題と同じです。解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合でも、第19条の解雇制限の対象になります。
なお、解雇制限期間が満了すると解雇できますが、改めて解雇予告が必要かどうかについては、行政通達では以下のようになっています。
「負傷し又は疾病にかかり休業したことによって、前の解雇予告の効力の発生自体は中止されるだけであるから、その休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない」とされています。
(昭和26.6.25基収2609号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-263
R4.5.12 解雇の予告の除外
前回の続きです。
労働者を解雇する場合は、30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりませんが、予告などが除外される例外があります。
条文を読んでみましょう。
第20条 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。 ② ①の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。 ※前条第2項 → その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
解雇予告等が除外される場合
① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
※①②ともに「所轄労働基準監督署長の認定」を受けなければなりません。
「天災事変その他やむを得ない事由」
→ 事業場が火災により焼失・震災に伴う事業場の倒壊など
「労働者の責に帰すべき事由」
→ 盗取、横領、傷害など
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても、使用者は、労働基準法第20条所定の予告手当を支払うことなく、労働者を即時に解雇しようとする場合には、行政官庁の認定を受けなければならない。
②【R2年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。
③【H18年出題】
労働基準法第20条第1項ただし書の事由に係る行政官庁の認定(以下「解雇予告除外認定」という。)は、原則として解雇の意思表示をなす前に受けるべきものではあるが、それは、同項ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分であって、認定されるべき事実がある場合には使用者は有効に即時解雇をなし得るものと解されるので、そのような事実がある場合には、即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生すると解されている。
④【H24年出題】
労働者によるある行為が労働基準法第20条第1項ただし書の「労働者の責に帰すべき事由」に該当する場合において、使用者が即時解雇の意思表示をし、当日同条第3項の規定に基づいて所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は、当該認定のあった日に発生すると解されている。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」でも、予告手当無しで即時解雇しようとする場合には、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受ける必要があります。
②【R2年出題】 ×
事業場が火災により焼失した場合は、「天災事変その他やむを得ない事由」に該当しますが、「使用者の重過失」に基づく場合は、除かれます。
(昭63.3.14基発第150号)
③【H18年出題】 〇
解雇予告除外認定は、解雇の意思表示をする前に受けることが原則です。
解雇予告除外認定は、ただし書に該当する事実があるか否かを確認する処分です。認定されるべき事実がある場合は、仮に認定を受けなかったとしても、使用者は有効に即時解雇ができる点がポイントです。
即時解雇の意思表示をした後、解雇予告除外認定を得たときは、その解雇の効力は使用者が「即時解雇の意思表示をした日」に発生するとされています。「解雇予告除外認定を得た日」ではありませんので、注意してください。
(昭63.3.14基発150号)
④【H24年出題】 ×
解雇の意思表示の後に解雇予告除外認定を受けたとしても、認定されるべき事実がある場合は、有効に即時解雇ができるとされています。即時解雇の効力は、「当該認定のあった日」ではなく、「即時解雇の意思表示をした日」に発生します。
(昭63.3.14基発150号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-262
R4.5.11 解雇の予告
労働者を解雇する場合は、「少なくとも30日前に予告する」、又は「30日分以上の平均賃金の支払い」が必要です。
条文を読んでみましょう。
第20条 (解雇の予告) ① 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し・・・(以下今回は省略します。) ② 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。 |
ポイント!
30日分以上の平均賃金を支払えば、即時解雇が可能です。
②について → 予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。
過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
②【R1年出題】
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。
③【H26年出題】
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。
④【H26年出題】
労働基準法第20条に定める解雇の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
⑤【H24年出題】
使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

【解答】
①【H16年出題】 〇
解雇予告手当を算定する場合の算定すべき事由の発生した日は、「労働者に解雇の通告をした日」です。
(昭39.6.12基収2316号)
②【R1年出題】 ×
30日間は、労働日ではなく暦日で計算されますので、休業日も含みます。
③【H26年出題】 ×
9月30日の終了をもって解雇するためには、8月31日には解雇の予告をしなければなりません。
民法の一般原則によって、解雇予告を行った日は、解雇予告期間に算入されないため、予告期間は予告を行った日の翌日から計算されます。
④【H26年出題】 〇
予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。
⑤【H24年出題】 〇
予告の一部を平均賃金で支払い、その分予告期間を短縮する方法(予告手当と予告期間の併用)も可能です。
8月15日に解雇の予告をした場合、翌日の16日から31日までの16日間が予告期間となるので、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-261
R4.5.10 有期労働契約その2
前回の続きです。
有期労働契約は、労働者を長期に拘束することを避けるため、原則3年以内と定められています。
ただし、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」は、例外的に、3年を超える契約が認められています。
また、「専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合に限る。)」、「満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約」は、最長5年までの契約期間が認められています。
今回は、「5年」が認められる要件をみていきましょう。
では、再度第14条を読んでみましょう。
第14条 (契約期間等) 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |
「高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準」の中には、「社会保険労務士の資格を有する者」も入っています。
ただし、社会保険労務士の国家資格を有しているだけでは足りず、「当該国家資格の名称を用いて当該国家資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等」が必要です。(H15.10.22基発第10220001号)
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
②【H18年選択式】
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が< A >ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。
③【H25年出題】
使用者は、満60歳以上の労働者との間に、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。
④【H29年出題】
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約について、労働契約期間の上限は当該労働者が65歳に達するまでとされている。
⑤【H30年出題】
労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
契約期間を5年とする労働契約を締結できる「専門的知識等であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者」は、「当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者」に限られます。
(法第14条第1項第1号)
②【H18年選択式】
A 1075万円を下回らない
一定の学歴と実務経験を有し、年収が1075万円以上である「システムエンジニアの業務に就こうとする者」との間に締結される労働契約は最長5年とすることができます。
(高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準 H15.10.22厚生労働省告示第356号)
③【H25年出題】 〇
満60歳以上の労働者との間の労働契約の契約期間は最長5年です。
(法第14条第1項第2号)
④【H29年出題】 ×
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約の契約期間の上限は5年です。65歳に達するまでという規定はありません。
⑤【H30年出題】 ×
「満60歳以上」の労働者との間に締結される労働契約ですので、第14条に定める契約期間に違反し同法第13条の規定が適用された場合、当該労働契約の期間は3年ではなく「5年」となります。
労働基準法第13条も確認しておきましょう。
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」
第13条が適用されると、基準に達しない部分は「無効」、無効となった部分は、「この法律で定める基準」になります。
(平15.10.22第1022001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-260
R4.5.9 労働契約の期間(有期労働契約の上限その1)
労働契約には、「期間の定めのない労働契約」と「期間の定めのある労働契約」があります。
「期間の定めのない労働契約」は、労働者側からいつでも自由に解約できますので、労働基準法上の制限はありません。
一方、「期間の定めのある労働契約」は、契約期間中は原則として解約できません。例えば、契約期間を20年にすると、20年の間、労働者は退職できず、長期にわたり労働者を拘束することになってしまいます。そのため、労働基準法では、「期間の定めのある労働契約」は、原則として最長3年という制限を設けています。
では、条文で確認しましょう。
第14条 (契約期間等) 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。 1 専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 2 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) |
<有期労働契約のポイント!>
★原則 → 3年を超えてはならない
☆例外その1・・・3年を超えて契約できるもの
・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
例えば、土木工事の事業で、その工事の終期までの期間を定める契約
・職業訓練のための訓練期間(第70条)
☆例外その2・・・5年まで契約できるもの
・専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約
(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就かせる場合に限る。)
・満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
過去問をどうぞ!
①【H16年出題】
労働基準法第14条第1項では、労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(弁護士、社会保険労務士等に係る労働契約で同項第1号に該当するもの、又は同項第2号に該当するものについては5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。この労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条違反となり、当該労働契約の期間は、同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年となる。
②【H23年出題】
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(労働基準法第14条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならず、また、期間を定める労働契約の更新によって継続雇用期間が10年を超えることがあってはならない。

【解答】
①【H16年出題】 〇
労働基準法第13条で、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」と規定されています。
第14条違反には第13条が適用され、基準に達しない部分は「無効」、無効となった部分は、「この法律で定める基準」になります。ですので、問題文の労働契約の期間は、「同項第1号又は第2号に該当するものについては5年、その他のものについては3年」となります。
(法第13条、平15.10.22第1022001号)
②【H23年出題】 ×
有期労働契約の更新は可能です。更新による継続雇用期間については制限はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法
国民健康保険法
R4-259
R4.5.8 国民健康保険の審査請求
今回は、国民健康保険の審査請求です。
条文を読んでみましょう。
第91条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(附則第10条第1項に規定する拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第92条 (審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 |
ポイント!
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
②【H18年出題】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
③【H29年出題】
国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
審査請求先は、「国民健康保険審査会」です。
②【H18年出題】 ×
審査請求先は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」です。
③【H29年出題】 〇
第103条で、『第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。』と規定されています。
訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働組合法
労働組合法
R4-258
R4.5.7 労働協約の一般的拘束力
労働協約の適用範囲は、原則として、労働協約を締結した労働組合とその構成員です。しかし、労働組合法第17条では、要件を満たす場合は、その労働組合に加入していない労働者にも拡張することが規定されています。
条文を読んでみましょう。
第17条 (一般的拘束力) 一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H13年出題】
ある工場において、常時使用される同種の労働者の3分の2以上の労働者が、同一の労働協約の適用を受けるに至ったときには、同じ工場で使用される非組合員である同種の労働者にも、当該労働協約が適用されることとなる。
②【H30年出題】
ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場において、その労働協約の適用を受ける者の数が当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
③【H23年出題】
労働協約は、それを締結した労働組合の組合員の労働契約を規律するものであり、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつことはあり得ない。

【解答】
①【H13年出題】 ×
労働協約が拡張適用される条件は、常時使用される同種の労働者の「4分の3以上」の労働者が、同一の労働協約の適用を受けるに至ったときです。
②【H30年出題】 〇
第17条は、「一の工場事業場」ごとに適用されることがポイントです。
「一の工場事業場」とは、個々の工場事業場のことです。一つの企業が複数の工場事業場を有する場合は、その企業内の個々の工場事業場の各々が「一の工場事業場」となります。
ある企業に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数のものが一の労働協約の適用を受けているとしても、その企業のある工場事業場で、その労働協約の適用を受ける者の数がその工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合は、その工場事業場においては、一般的拘束力は適用されません。
(昭29.4.7労発第111号)
③【H23年出題】 ×
第17条の一般的拘束力が適用され、当該労働組合に加入していない労働者の労働契約を規律する効力をもつこともあります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-257
R4.5.6 年金の支給開始について
年金は、その事由が生じた月の翌月から権利が消滅した月まで、月単位で支給されます。
条文を読んでみましょう。
第36条(年金の支給期間) 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。 |
5月 | 6月 | ・・・・・ | 10月 | 11月 |
支給事由 発生 |
| ・・・・・
| 権利消滅 |
|
年金の支給期間は、事由が生じた月の翌月(6月)から、権利が消滅した月(10月)までです。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
②【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

【解答】
①【H28年出題】 ×
「初診日要件」、「保険料納付要件」を満たし、障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合は、障害認定日に受給権が発生し、障害厚生年金は、障害認定日の属する月の翌月分から支給されます。障害認定日が月の初日であっても同じです。
「ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。」が誤りです。
②【H30年出題】 〇
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合は、死亡した日の翌日に資格を喪失します。
また、遺族厚生年金の受給権は、被保険者等が死亡した日に発生し、死亡した日の属する月の「翌月」から支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-256
R4.5.5 保険料納付済期間の定義
国民年金の給付の要件の1つに保険料納付要件があります。保険料納付要件をみるときに登場するのは「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」ですが、今回は「保険料納付済期間」の定義です。
条文を読んでみましょう。
第5条 国民年金法において、「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び第88条の2の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
<国民年金法の保険料納付済期間>
以下の期間を合算した期間です。
↓
・第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定(督促及び滞納処分)により徴収された保険料を含む、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは除く)に係るもの及び産前産後期間中の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの
+
・第2号被保険者としての被保険者期間
+
・第3号被保険者としての被保険者期間
※国民年金に保険料を納付する義務があるのは、第1号被保険者です。第2号被保険者と第3号被保険者は、個別に国民年金に保険料を納付する義務はありません。
そのため、国民年金の保険料の滞納があり得るのは第1号被保険者のみです。第2号被保険者と第3号被保険者には「滞納」があり得ないので、被保険者期間がそのまま「保険料納付済期間」となりますが、第1号被保険者は保険料を納付した期間が保険料納付済期間となります。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。
②【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
③【H24年出題】
保険料全額免除期間を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
④【R2年出題】
保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。

【解答】
①【H24年出題】 〇
保険料を滞納し、督促及び滞納処分を受け、それによって保険料を納付した場合は、「保険料納付済期間」となります。
②【H24年出題】 〇
例えば、4分の3免除を受けた場合は、保険料の4分の3は免除されますが、残りの4分の1は納付する義務があります。4分の3免除の規定により、その4分の1が納付された期間は、保険料納付済期間ではなく、「保険料4分の3免除期間」です。
③【H24年出題】 〇
保険料を追納した期間は、「保険料納付済期間」です。
④【R2年出題】 ×
産前産後期間の保険料免除期間は、全額免除期間ではなく「保険料納付済期間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-255
R4.5.4 高額介護合算療養費
高額介護合算療養費とは??
「健康保険」の一部負担金と「介護保険」の利用者負担額を合算して、「介護合算算定基準額+支給基準額」を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。超えた金額は、健康保険と介護保険の自己負担額の比率で按分して支給されます。
計算期間は、1年間(8月1日から翌年7月31日)です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】
高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は< A >円である。
70歳未満で標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は < B >円である。
②【H25年出題】
高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。
③【H28年出題】
70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
④【H30年出題】
高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

【解答】
①【H25年選択式】
A 500
B 670,000
(平成20年厚生労働省告示第225号、令43条の3)
高額介護合算療養費は、「介護合算一部負担金等世帯合算額-介護合算算定基準額」が、500円を超える場合に限り、支給されます。
②【H25年出題】 ×
「個別に」算定ではなく、「世帯」単位で算定します。
(H21.4.30保保発0430001)
③【H28年出題】 ×
高額介護合算療養費を算定する場合も、70歳未満の21,000円未満のものは算定対象から除かれます。
(H21.4.30保保発0430001)
④【H30年出題】 ×
「健康保険法に基づく高額療養費が支給されていること」は要件ではありません。
なお、合算する場合は、健康保険の一部負担金等の額から高額療養費は除かれ、また、介護保険の利用者負担額から高額介護サービス費は除かれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-254
R4.5.3 月の途中で後期高齢者医療の被保険者になった場合の高額療養費
75歳になり後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した場合、健康保険の資格は喪失します。
今日のテーマは、月の途中で後期高齢者医療の被保険者になった場合の高額療養費の自己負担限度額についてです。
月の途中(2日~末日)に、後期高齢者医療の被保険者になった月は、その月に受けた療養は、「健康保険」、「後期高齢者医療」の自己負担限度額をそれぞれ「2分の1」にして、支給要件を見ることになります。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。
②【R1年出題】
標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400円である者が、月の初日以外の日において75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円とされている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
★月の初日以外の日に75歳に達した場合のポイント!
・健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用される
・個人単位で両制度のいずれも通常の基準額の2分の1の額を設定する
②【R1年出題】 〇
健康保険と後期高齢者医療でそれぞれ2分の1の高額療養費算定基準額が適用されるので、問題文の場合は、外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-253
R4.5.2 (高額療養費)長期高額疾病の特例
長期間にわたり高額な医療費がかかる特定疾病については、自己負担限度額の特例が設けられています。負担軽減のためです。
特定疾病については施行令第41条第9項で以下の要件が定められています。
1 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
2 1の治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
要件に基づき、指定されているのが次の3つです。
① 人工腎臓を実施する慢性腎不全 (人工透析)
② 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害及び先天性血液凝固第Ⅸ因子障害 (血友病)
③ 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(血液製剤に起因するHIV感染症)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は10,000円とされている。
②【H28年出題】
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。

【解答】
①【R2年出題】 ×
★長期高額疾病(特定疾病)に係る自己負担限度額の特例
・自己負担限度額は月額1万円です。※限度額を超える分は高額療養費が現物給付で支給されます。
・ただし、「慢性腎不全」のうち「70歳未満」の「上位所得者(標準報酬月額53万円以上)」については自己負担限度額は2万円です。
問題文の高額療養費算定基準額は1万円ではなく「2万円」です。
(昭59.9.28厚告156)
②【H28年出題】 ×
2万円ではなく「1万円」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-252
R4.5.1 多数回該当・高額療養費
高額療養費に該当する月以前12か月間に、高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。自己負担を軽減するためです。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が2か月以上ある場合をいい、3か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。
②【H28年選択式】
55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円- < A >)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は < B >となる。また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、< C >となる。
③【H18年出題】
転職により、健康保険組合の被保険者から全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に変更した場合であっても、高額療養費の算定にあたっての支給回数は通算される。

【解答】
①【H26年出題】 ×
多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の12か月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいいます。4か月目からは高額療養費算定基準額が「多数回該当」の上限額になります。
②【H28年選択式】
A 842,000円
B 45,820円
C 140,100円
■70歳未満の被保険者(標準報酬月額83万円)の場合
(高額療養費算定基準額)
・252,600円+(医療費-842,000円)×1%
・多数回該当の場合 140,100円
ポイント!
842,000円について → 842,000円の30%が252,600円です。
計算式!
・高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
252,600円+(100万円-84万2千円)×1% = 25万4,180円
・高額療養費
30万円 - 25万4,180円 = 4万5,820円
③【H18年出題】 ×
健康保険組合の被保険者から協会健保の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合は、支給回数は通算されないことになっています。
(昭59.9.29保険発第74号・庁保険発第18号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-251
R4.4.30 高額療養費/世帯合算
高額療養費は、「1人単位」で計算するのが原則ですが、同一世帯で、複数人が医療機関にかかった場合は、一部負担金等を合算して計算することができます。
また、同一人物でも、高額療養費は医療機関ごとに計算するのが原則ですが、同一人物が同一月に複数の医療機関にかかった場合も、世帯合算が適用されます。
合算の対象になるのは、「70歳未満」の場合は21,000円以上の自己負担額です。「70歳以上」の場合は、合算の対象に制限はありませんので、すべての自己負担額を合算できます。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。

【解答】
【H30年出題】 ×
夫婦がともに被保険者の場合は、70歳未満、70歳以上関係なく、世帯合算の対象になりません。
世帯合算の単位は、「被保険者+その被扶養者」のまとまりです。
<計算事例>
・70歳未満の被保険者A(標準報酬月額32万円)
→ 医療費20万円(一部負担金 6万円)
・70歳未満の被扶養者B
→ 医療費3万円(窓口負担 9千円)
・70歳未満の被扶養者C
→ 医療費100万円(窓口負担 30万円)
世帯合算の対象になるのは「2万1千円以上」の被保険者Aと被扶養者Cの負担分です。被扶養者Bは2万1千円未満なので、世帯合算されません。
①高額療養費算定基準額(自己負担限度額)
8万100円+(120万円-26万7千円)×1% = 8万9430円
②高額療養費
36万円 - 8万9430円 = 27万570円
となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-250
R4.4.29 高額療養費の要件
例えば、病気で入院し、1か月間で医療費が100万円かかった場合、一部負担金は3割の30万円となります。
このうちの自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として払い戻されます。(限度額適用認定証を提示し、払い戻しではなく現物給付として受ける方法もあります。)
 70歳未満の被保険者(標準報酬月額28万円)、医療費100万円の場合の高額療養費
70歳未満の被保険者(標準報酬月額28万円)、医療費100万円の場合の高額療養費
①自己負担限度額(高額療養費算定基準額)
8万100円+(100万円-26万7千円)×1% = 8万7430円
②高額療養費
30万円-8万7430円 = 21万2570円
→ 21万2570円が高額療養費として払い戻されます。
医療費総額 100万円 | ||
療養の給付
70万円 | 一部負担金 30万円 | |
自己負担限度額 8万7430円 | 高額療養費 21万2570円 | |
条文を読んでみましょう
第115条 (高額療養費) ① 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 ② 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。 |
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は高額療養費の算定対象とならない。
②【H23年出題】
高額療養費の支給要件の取扱いでは、同一の医療機関であっても入院診療分と通院診療分はそれぞれ区別される。
③【H27年出題】
同一の月に同一の保険医療機関において内科及び歯科をそれぞれ通院で受診したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、高額療養費の計算には入りません。
★高額療養費の算定対象とならない負担
・食事療養標準負担額
・生活療養標準負担額
・保険外のもの
保険外併用療養費に係る自費負担分など
②【H23年出題】 〇
★高額療養費の支給要件の取扱いポイント
・暦月単位で計算
例えば、3月15日から4月10日まで入院療養を受けた場合は、「3月15日から3月31日まで」と「4月1日から4月10日まで」に区別します。
・1人ずつ計算
・医療機関ごとに計算
・医科、歯科別で計算
・入院と通院はそれぞれで計算
問題文のように、同一の医療機関でも入院診療分と通院診療分は、それぞれ区別します。
③【H27年出題】 ×
内科と歯科は、それぞれ区別して算定します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-249
R4.4.28 離職理由による給付制限
・ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとき
・ 正当な理由がないと認められるにもかかわらず自己の都合によって退職したとき
→ 待期満了後1か月以上3か月以内の間 、基本手当は支給されません。
では、条文を読んでみましょう。
第33条 (離職理由による給付制限) 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、待期期間の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 |
「離職理由の判定については、客観的資料、関係者の証言、離職者の申立等を基に慎重に判断する」とされています。 (行政手引52201)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。
②【H28年出題】
自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
③【H26年出題】
上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより退職した場合は、自己の都合によって退職した場合であっても、正当な理由があるためこれを理由とする給付制限は行われない。
④【H29年出題】
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。
⑤【H26年出題】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合であっても、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、他の要件を満たす限り基本手当が支給される。

【解答】
①【H23年出題】 ×
給付制限期間の起算日が誤っています。
「離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後」ではなく、「待期期間の満了後」1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間です。
②【H28年出題】 ×
行政手引によると、「失業の認定を行う必要はない」となっています 。
なお、給付制限は、所定給付日数が短縮されるものではありません。
(行政手引52205)
③【H26年出題】 〇
問題文の場合は、「正当な理由あり」に該当するので、給付制限は行われません。
ちなみに、「正当な理由」とは、被保険者の状況(健康状態、家庭の事情等)、事業所の状況 (労働条件、雇用管理の状況、経営状況等)その他からみて、その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合をいいます。被保険者の主観的判断は考慮されません。
(行政手引52203)
④【H29年出題】 ×
問題文の場合は、「正当な理由あり」に該当しますので、給付制限は受けません。
(行政手引52203)
⑤【H26年出題】 〇
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練の受講開始日以後は、給付制限が解除されますので、要件を満たせば、基本手当が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-248
R4.4.27 療養補償給付と休業補償給付と傷病補償年金
労災保険の保険給付には、「治ゆ前」に支給されるものと「治ゆ後」に支給されるものがあます。
今日のテーマは、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金ですが、この3つは「治ゆ前」に支給されるものです。
それぞれが、併給されるか否かが良く問われます。
 まずは図でイメージしましょう。
まずは図でイメージしましょう。
・病気やけがの治療
→ 治ゆするまで「療養補償給付」が受けられます。
・所得補償
→休業4日目から「休業補償給付」が受けられます。
→療養開始後1年6か月が経過した日(又は同日後)に、傷病が治っておらず、傷病等級1~3級に該当した場合は、「傷病補償年金」に切り替わります。
療養補償給付 | 治 ゆ | |
休業補償給付 | 傷病補償年金 | |
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
②【H24年出題】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
③【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
④【H27年出題】
傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
⑤【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「症状が安定して疾病が固定した状態」、「医療効果が期待しえない状態」の場合は、症状が残っていても、療養の必要はなくなったものとされ、療養の給付は行われません。
(昭23.1.13基災発第3号)
②【H24年出題】 〇
治療としての「療養補償給付」と労働することができない期間の所得補償である「休業補償給付」は併給されます。
③【H24年出題】 〇
治療としての「療養補償給付」と、治ゆ前の所得補償である「傷病補償年金」は併給されます。
④【H27年出題】 〇
⑤【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも所得補償ですので、併給されることはありません。
ポイント!
「年金」は「支給事由が生じた月の翌月」から、「権利が消滅した月」まで「月単位」で支給されます。
傷病補償年金の受給権が生じた月は、「休業補償給付」が支給され、その翌月から傷病補償年金の支給が始まります。
また、傷病等級に該当しなくなり傷病補償年金の受給権が消滅した場合は、消滅した月まで傷病補償年金が支給され、要件に合えば、その翌月から休業補償給付が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 傷病補償年金 受給権発生 |
|
|
|
| 傷病補償年金 受給権消滅 |
|
休 | 休 | 傷 | 傷 | 傷 | 傷 | 傷 | 休 |
休 → 休業補償給付
傷 → 傷病補償年金
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-247
R4.4.26 面接指導「研究開発業務」、「高度プロフェッショナル制度」編
前回までは、長時間労働者に対する面接指導をみてきました。
今回は、「研究開発業務に従事する労働者」、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」に対する面接指導です。
条文を読んでみましょう。
第66条の8の2 「新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する者」 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第36条第11項に規定する業務(新技術・新商品等の研究開発の業務)に従事する者(同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
則第52条の7の2 法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり 100時間とする。 |
ポイント!
対象は、労働基準法第36条第11項(新技術・新商品等の研究開発の業務)に従事する者に限られます。
では、こちらの条文も読んでみましょう
第66条の8の4「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者」 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定(高度プロフェッショナル制度)により労働する労働者であって、その健康管理時間が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。 則第52条の7の4 法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で定める時間は、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。
|
ポイント!
労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)が対象です。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
②【R2年出題】
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
・新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する労働者について
時間外・休日労働が1月当たり「100時間」を超えた場合は、「労働者からの申出の有無にかかわらず」面接指導を行わなければなりません。
なお、時間外・休日労働が1月当たり「80時間」を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合は、「長時間労働者に対する面接指導」の対象となりますが、この場合は「労働者の申出」が必要です。
②【R2年出題】 〇
・高度プロフェッショナル制度により労働する労働者について
1週間当たり40時間を超える健康管理時間が、1月当たり100時間を超える場合は、「労働者からの申出の有無にかかわらず」、面接指導を行わなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-246
R4.4.25 長時間労働者の面接指導その2
前回の続きです。
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、事業者は、面接指導を行わなければなりません。
今回は事後措置などを確認します。
では、条文を読んでみましょう。
第66条の8 (面接指導等) ③ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、面接指導の結果を記録しておかなければならない。 則第52条の6 (面接指導結果の記録の作成) 事業者は、面接指導の結果に基づき、面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない |
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。

【解答】
①【H25年出題】 〇
面接指導の結果の記録の保存期間は、5年間です。
では、条文の続きをどうぞ
第66条の8 (面接指導等) ④ 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
⑤ 事業者は、④の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
則第52条の7 (面接指導の結果についての医師からの意見聴取) 面接指導の結果に基づく医師からの意見聴取は、当該面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。 |
では、過去問をどうぞ!
②【H21年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
③【H25年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
④【H25年出題】
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

【解答】
②【H21年出題】 〇
面接指導の結果について、医師から意見を聴取しなければなりません。
③【H25年出題】 〇
医師からの意見聴取は、厚生労働省令(則第52条の7)で、「面接指導が行われた後、遅滞なく」、と規定されています。
④【H25年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
事業者は、面接指導の結果に基づく医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 < A >の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の< B >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

【解答】
A 深夜業
B 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-245
R4.4.24 長時間労働者の面接指導その1
長時間労働による「脳・心臓疾患」の発症を予防するため、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対して、面接指導を行わなければなりません。
今回は「面接指導その1」です。
条文を読んでみましょう。
第66条の8 (面接指導等) ① 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。
則第52条の2 (面接指導の対象となる労働者の要件等) ① 法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 ② ①の超えた時間の算定は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。 ③ 事業者は、①の超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
則第52条の3 (面接指導の実施方法等) ① 面接指導は、要件に該当する労働者の申出により行うものとする。 ② ①の申出は、超えた時間の算定の期日後、遅滞なく、行うものとする。 ③ 事業者は、労働者から申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。 ④ 産業医は、要件に該当する労働者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
②【H21年出題】 ※改正による修正あり
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。
③【H18年選択式】 ※改正による修正あり
労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう < A >することができる旨規定されている。

【解答】
①【R2年出題】 ×
長時間労働者の面接指導は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間」を超えていることが要件です。
★長時間労働者の面接指導のポイント!
・休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「80時間」を超えている
かつ
・疲労の蓄積が認められる
・労働者の「申出」が必要
②【H21年出題】 ×
長時間労働者の面接指導は、「本人の申出の有無にかかわらず」ではなく、「本人の申出により」、実施しなければならない、です。
③【H18年選択式】
A 勧奨
長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-244
R4.4.23 年俸制のこと
賃金を1年単位で決定している制度を、年俸制といいます。
労働者の成果や能力に対する評価で決定されます。
年俸制の労働者にも、労働基準法の賃金のルールは適用されますし、また、時間外労働等をさせた場合は、割増賃金の支払いも必要です。
今回は、年俸制のルールを確認します。
では、早速過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
労働基準法では、年俸制をとる労働者についても、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないが、各月の支払いを一定額とする(各月で等分して支払う)ことは求められていない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
年俸制にも賃金支払い五原則が適用されますので、「毎月1回以上、一定の期日を定めて」支払わなければなりません。
毎月、年俸額の12分の1を支払い、各月の支払いを一定額にする方法もありますが、年俸額の一部を賞与の時期に支払う方法(例えば、毎月、年俸額の16分の1を支払い、16分の4を2等分して賞与として支給する等)もとれます。各月の支払いを一定額とすることは求められていません。
では、もう一問どうぞ!
②【H17年出題】
年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。

【解答】
②【H17年出題】 〇
<この問題文の支払い方法>
毎月 → 年俸の16分の1+通勤手当
6月と12月 → 年俸の16分の2ずつを賞与として支給
時間外労働等を行った場合は、年俸制の労働者にも割増賃金を支払わなければなりません。
その際、「6月と12月に賞与として支払われている賃金」をどのように扱うのかがポイントです。
通達では、「施行規則第21条第4号の「臨時に支払われた賃金」及び第5号の「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」のいずれにも該当しないものであるから、割増賃金の算定基礎から除外できない」とされています。
ですので、賞与の部分も含めて計算しなければなりません。
なお、通勤手当は算定基礎に含めませんので、割増賃金の支払いは、問題文のように「月例給与に賞与部分を含めた年俸額」を基礎として計算します。
(H12.3.8基収78号)
★年俸制の平均賃金について
割増賃金と同じように扱います。賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1か月分の賃金として平均賃金を算定します。
(H12.3.8基収78号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-243
R4.4.22 割増賃金の算定方式
割増賃金は、1時間当たりの単価×割増率で計算します。
今回は、1時間当たりの単価の出し方がテーマです。
計算のルールを条文で読んでみましょう。
則第19条 法第37条第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの労働時間数を乗じた金額とする。 1 時間によって定められた賃金については、その金額 2 日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額 3 週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額 4 月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額 5 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 6 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額 7 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額 |
例えば、月給制の場合は、通常の労働時間1時間当たりの賃金額は、『月ぎめの賃金÷月の所定労働時間数』で計算します。
では、過去問をどうぞ!
①【H15年出題】
労働基準法第37条は、使用者が第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長した場合においては、その時間の労働については、一定の方法により計算した割増賃金を支払わなければならない旨規定しているが、これは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給制により賃金が支払われる場合であっても、当該時間外労働については、その労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならない。
②【H28年出題】
労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働日数:240日
計算の基礎となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間
A 300,000円÷(21×7)
B 300,000円÷(21×8)
C 300,000円÷(30÷7×40)
D 300,000円÷(240×7÷12)
E 300,000円÷(365÷7×40÷12)

【解答】
①【H15年出題】 〇
月給制で賃金が支払われる場合でも、時間外労働は、その労働時間に対する通常の賃金1.00が必要ですので、割増賃金は「通常の労働時間1時間当たりの賃金額×1.25」で計算します。
②【H28年出題】 D
月給制の場合は、その金額を原則として月の所定労働時間数で除します。しかし、「月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数」で除します。
問題文の場合は、月によって所定労働時間数が異なりますので、年間平均1か月の所定労働時間数で除します。
年間平均1か月の所定労働時間数は、年間所定労働日数×1日の所定労働時間数÷12か月で計算します。問題文の場合は、240日×7時間÷12か月ですので、計算式は300,000円÷(240×7÷12)です。
こちらもどうぞ!
③【H16年出題】
その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。
④【H18年出題】 ※改正による修正あり
賃金が出来高払制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項又は第33条の規定によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働をした時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働をした時間数を乗じた金額の2割5分(1か月60時間を超える時間外労働については、その超えた時間については5割)を支払えば足りる。

【解答】
③【H16年出題】 ×
出来高払制の場合は、賃金の総額を、当該期間における「総労働時間数」で除した金額を基礎とします。「総所定労働時間数」ではありませんので注意してください。
④【H18年出題】 〇 ※改正による修正あり
出来高払制の場合の割増賃金の計算式は、
「当該期間の出来高払制の賃金の総額」÷「当該期間の総労働時間数」×0.25(又は0.5)、0.35です。
1.25(又は1.5)、1.35ではなく、0.25(又は0.5)、0.35で差し支えないとされています。
(H11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-242
R4.4.21 割増賃金の計算の基礎に算入しない賃金
時間外労働、休日労働、深夜労働をさせた場合、使用者には割増賃金を支払う義務があります。
例えば、時間外労働の場合は、1時間当たりの賃金×1.25で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
今回のテーマは、割増賃金の計算の基礎になる1時間当たりの賃金の計算に算入しない賃金です。
条文を読んでみましょう。
第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) ⑤ 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 則第21条 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 1 別居手当 2 子女教育手当 3 住宅手当 4 臨時に支払われた賃金 5 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
1時間当たりの賃金は、手当も含めて計算します。しかし、「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」、「臨時に支払われた賃金」、「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」の7つの手当などは計算に入れません。
家族手当は「家族の有無」、通勤手当は「交通機関の運賃」で決まり、労働とは関係ないからです。
また、賞与など(「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当する)も計算に入れません。
なお、覚え方は、「か つ べ し ん 一 住宅」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法の第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
②【H23年出題】
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。
③【H19年出題】
労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の計算の基礎となる賃金には算入しない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
「通勤手当」は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しません。
②【H23年出題】 ×
「家族手当」は算定基礎賃金に含めないことが原則です。
しかし、例えば、家族がいない人にも支払われているとか、その家族数に関係なく一律に支給されている場合は、「家族手当」とはみなされず、割増賃金の計算に入れなければなりません。
(昭22.11.5基発231号)
③【H19年出題】 ×
問題文の住宅手当は、施行規則第21条でいう住宅手当に該当せず、割増賃金の計算の基礎となる賃金に「算入されます」。
住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は、則第21条でいう住宅手当に当たりません。ですので、割増賃金の計算に入ります。
(H11.3.31基発170号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 介護保険法
介護保険法
R4-241
R4.4.20 要介護認定
要介護状態や要支援状態になった場合、介護保険から介護サービスが受けられます。
介護サービスを受けるには、市町村の認定が必要です。
では、条文を読んでみましょう。
第19条 (市町村の認定) ① 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(「要介護認定」という。)を受けなければならない。 ② 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(「要支援認定」という。)を受けなければならない。 |
<要介護認定の流れ>
一次判定
市町村の認定調査員による心身の状況調査+主治医の意見書に基づくコンピュータ判定
↓
二次判定
介護認定審査会で審査判定
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
②【R1年出題】
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
処分とは要介護認定申請の結果のことです。要介護認定は、原則として、申請のあった日から30日以内に行われます。
(法第27条第11項)
②【R1年出題】 〇
要介護認定は、その『申請のあった日にさかのぼって』効力が生じます。
(法第27条第8項)
次に、「介護認定審査会」の条文を読んでみましょう。
第14条 (介護認定審査会) 審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く。
第15条 (委員) ① 介護認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。
|
「介護認定審査会」は、「審査判定業務」を行うため、「市町村」に置かれるのがポイントです。
※なお、要介護認定に関する処分に不服がある場合は、「介護保険審査会」に審査請求ができます。名前が似ているので注意しましょう。「介護保険審査会」は、都道府県に置かれます。
では、過去問をどうぞ!
③【R3年出題】
介護認定審査会は、市町村(特別区を含む。)におかれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
④【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

【解答】
③【R3年出題】 ×
委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者」のうちから、市町村長が任命します。
④【H29年出題】 〇
介護認定審査会は、厚生労働大臣が定める基準に従い「審査及び判定」を行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-240
R4.4.19 高齢任意加入被保険者 保険料の負担編
高齢任意加入被保険者には、「適用事業所に使用される者」と「適用事業所以外の事業所に使用される者」の2種類があります。
「適用事業所以外の事業所に使用される者」は、事業主が保険料の半額を負担することと納付の義務を負うことについて同意を得ることを条件に、資格を取得します。
一方、「適用事業所に使用される者」は、事業主の同意がなくても資格を取得できます。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料負担と納付については、原則として本人の責任になりますので、滞納したときの扱いがポイントになります。
では、条文を読んでみましょう。
附則第4条の3 (適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者) ⑦ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定(保険料の源泉控除)は、適用しない。 ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
⑧ 事業主は、被保険者の同意を得て、将来に向かって同意を撤回することができる。 |
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその1
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその1
・保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う
・事業主が同意をしたとき → 事業主が保険料の半額を負担し、かつ、事業主が保険料を納付する義務を負う
・事業主は将来に向かってその同意を撤回できる(被保険者の同意が必要)
では、続きです。
附則第4条の3 ③ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、被保険者とならなかったものとみなす。ただし、事業主の同意がある場合は、この限りでない。
⑥ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき(ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
|
 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその2
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者のポイントその2
・初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、納付しないとき
→ 被保険者とならなかったものとみなす
※事業主の同意がある場合は、この規定は適用されません
・保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないとき
→ 保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
※事業主の同意がある場合は、この規定は適用されません。
ポイント
・「適用事業所以外の事業所に使用される」高齢任意加入被保険者は、保険料の半額負担と納付義務は事業主が負いますので、滞納の問題は生じません。
しかし、「適用事業所に使用される」高齢任意加入被保険者は、保険料負担と納付義務は本人が負いますので、滞納の場合は資格喪失のペナルティがあります。しかし、事業主の同意がある場合は、責任は事業主にあるため、滞納の問題は生じなくなります。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。ただし、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主ではないものとする)が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときはこの限りではない。
②【H29年出題】
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
③【H27年出題】 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主ではないものとする)は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
①【H24年出題】 〇 ※改正による修正あり
まず、「適用事業所に使用される」の部分をチェックしましょう。「適用事業所以外の事業所」の高齢任意加入被保険者には、この規定は適用されません。
また、後半の、「事業主の同意」の部分は、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主には適用されません。
(附則第4条の3第10項)
②【H29年出題】 ×
この規定が適用されないのは、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主です。
(附則第4条の3第10項)
③【H27年出題】 ×※改正による修正あり
保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、「保険料の納期限の属する月の前月の末日」に資格を喪失します。
例えば、4月分の保険料を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、保険料の納期限(5月末日)の前月の末日(4月30日)に資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-239
R4.4.18 高齢任意加入被保険者 資格取得編
厚生年金保険の被保険者の資格は70歳に達したときに喪失します。
しかし、70歳に達しても老齢年金の受給権がない場合は、70歳以上でも受給権を取得するまで厚生年金保険に任意で加入できます。
高齢任意加入被保険者には、「適用事業所に使用される者」と「適用事業所以外の事業所に使用される者」の2種類があります。
問題文を解くときは、どちらの高齢任意加入被保険者のことなのかを意識しましょう。
条文を読んでみましょう
附則第4条の3 (適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者) ① 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。 ② 申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
附則第4条の5 (適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者) 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。 認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。 |
適用事業所に使用される場合、適用事業所以外の事業所に使用される場合の共通点は、「老齢厚生年金、老齢基礎年金等老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権がないこと」です。
また、「適用事業所に使用される」場合は「実施機関に申出」、「適用事業所以外の事業所に使用される」場合は「事業主の同意+厚生労働大臣の認可」が必要です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。
②【H20年出題】 ※改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「適用事業所以外の事業所」に使用される場合は、事業主の同意を得たうえで、「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりません。この点は任意単独被保険者と同じです。「申出」ではありませんので注意しましょう。
また、「認可を受けた日」に資格を取得します。
②【H20年出題】 〇※改正による修正あり
「適用事業所」に使用される場合は、実施機関に申し出る必要があります。事業主の同意は要りません。
次はこちらをどうぞ!
③【H21年出題】
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。

【解答】
③【H21年出題】 ×
障害給付や遺族給付の受給権者でも、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の年金の受給権を有しない場合は、高齢任意加入被保険者になることができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-238
R4.4.17 任意単独被保険者
適用事業所に使用される70歳未満の者は、当然に厚生年金保険の被保険者となります。
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳未満の者は、任意に厚生年金保険に加入でき、「任意単独被保険者」といいます。
では、条文を読んでみましょう。
(任意単独被保険者) 第10条 ① 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。 ② ①の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第11条 任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。 |
適用事業以外の事業所の従業員でも、単独で厚生年金保険の被保険者になることができます。任意単独被保険者といいます。
加入の場合は、その事業所の事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。事業主の同意は、保険料の半額負担と納付義務を負うことの同意です。
また、厚生労働大臣の認可を受けて、資格を喪失することもできます。喪失の際は、事業主の保険料の負担等の義務が無くなるため、事業主の同意は要りません。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには、保険料を全額負担し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
②【H27年出題】
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
③【H19年出題】
任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。

【解答】
①【H24年出題】 ×
任意単独被保険者の保険料は、事業主と被保険者がそれぞれ半額負担します。そのため、任意単独被保険者になるには、事業主の同意が必要です。
②【H27年出題】 ×
任意単独被保険者の資格の喪失には、事業主の同意は要りません。
③【H19年出題】 〇
任意単独被保険者は、「厚生労働大臣の認可があった日」に、資格を取得します。
なお、任意単独被保険者が、厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失する場合は、厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」に資格を喪失します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-237
R4.4.16 免除の所得要件
申請全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例、納付猶予を受けるには、所得要件があります。
今回は、免除の所得要件を確認します。
保険料免除の所得基準は以下の通りです。
申請全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人・世帯主・配偶者 |
学生納付特例 | 128万円+扶養親族等の数×38万円 | 本人のみ |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 | 本人・配偶者 |
・ 「88万円」だけ覚えてください。40ずつ増えます。+40で「128万円」、+40で「168万円」です。
・ 学生納付特例は半額免除の基準と同額、納付猶予は全額免除の基準と同額です。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が168万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。
②【H26年出題】 ※改正による修正あり
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が207万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
③【H29年選択】※改正による修正あり
国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が< A >に扶養親族等1人につき< B >を加算した額以下のときとされている。
なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。
④【H24年出題】
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
⑤【H28年出題】
前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。以下本問において同じ。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

【解答】
①【H26年出題】 〇 ※改正による修正あり
扶養親族等がいない場合は、4分の1免除の所得基準は、168万円以下です。
(令第6条の9の2)
②【H26年出題】 〇 ※改正による修正あり
全額免除の所得基準は、(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円です。当てはめて計算すると、(4+1)×35万円+32万円=207万円です。207万円以下であれば、全額免除の対象です。
(令6条の7)
③【H29年選択】※改正による修正あり
半額免除の所得基準の問題です。
A128万円
B38万円
※扶養親族1人当たりの加算額は38万円が原則です。同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等の場合は、加算額が変わります。
④【H24年出題】 ×
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、本人・世帯主・配偶者がそれぞれ免除事由に該当することが必要です。
⑤【H28年出題】 〇
学生納付特例は、本人の所得のみで判断します。世帯主、配偶者の所得は関係ありません。
なお、納付猶予は、本人と配偶者がそれぞれ免除事由に該当することが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-236
R4.4.15 療養の給付 一部負担金
保険医療機関や保険薬局で治療などを受けた場合、70歳未満の場合は、かかった医療費の3割を一部負担金として支払います。
今回のテーマは一部負担金です。
条文を読んでみましょう。
第74条 (一部負担金) 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、療養の給付に要する費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 1 70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30 2 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(3に掲げる場合を除く。) 100分の20 3 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30 |
一部負担金の割合は以下の通りです。
①70歳未満 → 100分の30 (←誤っていたので修正しました)
②70歳以上(③を除く) → 100分の20
③70歳以上の現役並所得者 → 100分の30
では、過去問をどうぞ!
①【R2年選択式】
保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の< A >以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。
<選択肢>
① 前月の標準報酬月額が28万円
② 前月の標準報酬月額が34万円
③ 標準報酬月額が28万円
④ 標準報酬月額が34万円

【解答】
A ③ 標準報酬月額が28万円
70歳以上の現役並み所得者の一部負担金の割合は100分の30です。
現役並み所得については、施行令第34条で、「療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上」と規定されています。
(令第34条)
つぎはこちらをどうぞ!
②【H27年選択式】
平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、< B >から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。
例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について< C >であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。
本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。
<選択肢>
① 70歳に達する日 ②70歳に達する日の属する月
③ 70歳に達する日の属する月の翌月 ④ 70歳に達する日の翌日
⑤ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が383万円未満
⑥ 被保険者と被扶養者の収入を合わせて算定し、その額が520万円未満
⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
⑧ 被保険者のみの収入により算定し、その額が520万円未満

【解答】
②【H27年選択式】
B ③ 70歳に達する日の属する月の翌月
C ⑦ 被保険者のみの収入により算定し、その額が383万円未満
★Bについて
一部負担金の割合が2割か3割になる「70歳以上」とは、「70歳に達する日の属する月の翌月」からとなります。
★Cについて
70歳以上で、標準報酬月額が28万円以上の場合は、原則として一部負担金の割合は3割です。
ただし、標準報酬月額が28万円以上でも、
・「被保険者」と「その被扶養者(70歳以上の場合に限る。)」の収入が合わせて520万円未満
・当該被扶養者がいない場合は、「被保険者」の収入が383万円未満
の場合は、申請により一部負担金の割合が2割になります。
問題文の場合は、被扶養者である妻が70歳未満ですので、被扶養者の収入は合算しません。「被保険者のみ」の収入が383万円未満の場合は、申請により一部負担金の額が2割となります。
(施行令第34条)
最後にもう一問どうぞ!
③【H24年出題】※改正による修正あり
70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。

【解答】
③【H24年出題】 〇 ※改正による修正あり
70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上でも、被保険者と70歳以上の被扶養者の収入を合わせて520万円未満の場合、申請により2割負担となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-235
R4.4.14 徴収法で「賃金」と解されるもの、解されないもの
労災保険の保険料、雇用保険の保険料は、事業主が労働者に支払う「賃金」の総額を基礎に計算されます。
今回は、保険料の基になる「賃金」の定義を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第2条 (定義) ② 労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 ③ 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
則第3条 (通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価) 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 |
通貨以外のもので支払われるのもの(現物給与)も賃金に含まれます。
現物給与として賃金に算入されるものは、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものです。
通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めます。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】(雇用)
労働保険徴収法における「賃金」は、通貨で支払われるもののみに限られず、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるものも含むものとされている。
②【H26年出題】(労災)
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
③【H24年出題】(労災)
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。
④【H29年出題】(労災)
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。

【解答】
①【H19年出題】(雇用) 〇
なお、通貨以外のもので支払われるものの「評価」に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定めます。
②【H26年出題】(労災) 〇
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金など個人的、臨時的な吉凶禍福に対して支給されるものは、労働協約等によって事業主に支給が義務付けられていても賃金としては取り扱いません。
問題文のような就業規則で定められた慶弔見舞金であっても、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含まれません。
(昭25.2.16基発127号)
③【H24年出題】(労災) 〇
退職を事由として支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額には算入されません。
(平15.10.1基徴発1001001号)
④【H29年出題】(労災) 〇
「前払い退職金」について
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確で、労働者の通常の生計に充てられる経常的な収入としての意義があるため、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されます。
(平15.10.1基徴発1001001号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-234
R4.4.13 「算定対象期間」について
基本手当は、算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給されます。
また、特定受給資格者又は特定理由離職者の場合は、離職の日以前 2 年間に被保険者期間が12か月以上なくても、離職の日以前 1 年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、基本手当の受給資格を満たします。
今回は、「算定対象期間」がテーマです。
条文を読んでみましょう。
第13条 (基本手当の受給資格) 1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。「算定対象期間」という。)に、被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給する。 2 特定理由離職者及び特定受給資格者(1の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、受給資格を満たす。
則第18条 (法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由) 法第13条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。 1 事業所の休業 2 出産 3 事業主の命による外国における勤務 4 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用 5 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの |
離職の日以前 2 年間(特定理由離職者又は特定受給資格者の場合は2年間又は1年間)が原則の算定対象期間です。
しかし、疾病、負傷その他一定の理由により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、賃金の支払を受けることができなかった日数が原則の算定対象期間に加算されます。ただし、算定対象期間は最大で 4 年間です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者であった者が、離職の日まで業務外の事由による傷病のため欠勤し引き続き6か月間賃金を受けていなかった場合、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその6か月間を加算した期間となる。
②【H23年出題】
被保険者であった者が、離職の日の6か月前まで4年間、海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった場合、受給資格を判断する際に用いる、雇用保険法第13条第1項にいう「離職の日以前2年間」は、2年間にその4年間を加算した期間となる。
③【H29年出題】
離職の日以前2年間に、疾病により賃金を受けずに15日欠勤し、復職後20日で再び同一の理由で賃金を受けずに80日欠勤した後に離職した場合、受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に係るものに該当しないとき、算定対象期間は2年間に95日を加えた期間となる。

【解答】
①【H26年出題】 〇
疾病、負傷により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、その日数が2年に加算されます。
「疾病又は負傷」は、業務上、業務外の別を問わない、とされていますので、問題文の場合は加算の対象になります。
(行政手引50152)
②【H23年出題】 ×
「海外の子会社に勤務していたため日本で賃金の支払を受けていなかった」場合は加算の対象になります。
しかし、算定対象期間は最長で4年間ですので、「離職の日以前2年間」に加算できるのは2年間が限度、「離職の日以前1年間」に加算できるのは3年間が限度です。
問題文の場合は加算できるのは4年間ではなく、最大で2年間です。
(行政手引50153)
③【H29年出題】 〇
賃金の支払を受けることができなかった日数は、30 日以上「継続」していることが条件です。
しかし、例外もあります。
途中で中断した場合でも、次の①~③のすべてに該当する場合は、これらの期間の日数をすべて加算することができます。
① 離職の日以前 2 年間又は 1 年間に、受給要件の緩和が認められる理由により賃金の支払を受けることができなかった期間があること。
② 同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の中断した期間との間が 30 日未満であること
なお、①の期間以外である当該期間についても、30 日以上であることを必要とせず、30日未満であってもその対象となり得る。
③ ②の各期間の賃金の支払を受けることができなかった理由は、同一のものが途中で中断したものであると判断できる
問題文は、15日と80日の欠勤が「同一の理由」であることと、中断が「20日間」であることがポイントです。
80日+15日=95日を原則の算定対象期間に加算できます。
(行政手引50153)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-233
R4.4.12 逸脱・中断と「日常生活上必要な行為」
合理的な通勤経路を、逸脱・中断した場合は、「逸脱・中断の間」と「合理的な通勤経路に戻った後の移動」は通勤となりません。
しかし、日常生活上必要な行為によって合理的な通勤経路を「逸脱・中断」した場合は、合理的な通勤経路に戻った後の移動は通勤として認められます。
今回は、「日常生活上必要な行為」を確認します。
条文を読んでみましょう。
第7条 ② 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) ③ 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
則第8条 (日常生活上必要な行為) 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3 選挙権の行使その他これに準ずる行為 4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
②【H27年出題】
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
③【H28年出題】
会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。
④【H25年出題】
女性労働者が1週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」であったとしても、逸脱・中断の間は通勤になりません。
②【H27年出題】 ×
理美容院に立ち寄ることは、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当します。合理的な経路に復した後は、通勤になります。
(昭48.11.22基発第644号)
③【H28年出題】 〇
「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」には、通常の医療を受ける行為に限らず、人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも含んでいる、とされています。
(昭48.11.22基発第644号)
④【H25年出題】 〇
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護は、「継続的に又は反復して行われるもの」に限られます。
問題文のように1週間に数回介護を行う場合は、「継続的に又は反復して」に該当します。
(昭48.11.22基発第644号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-232
R4.4.11 安全衛生法と法定労働時間
安全衛生法では、一定の事業場で、安全委員会・衛生委員会の設置が義務付けられています。委員会は、毎月1回以上開催しなければなりません。
また、第59条では、「雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育」、「特別教育」、第60条では、「職長教育」が規定されています。
そして、第66条では「健康診断」が規定されています。
委員会の時間、安全衛生教育の時間や健康診断の時間が「労働時間」となるか否かが今回のテーマです。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。
②【H27年出題】
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払いについて、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
③【H21年出題】※労働基準法
労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
第59条、第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるために、事業者の責任で実施されなければならないものです。そのため、安全衛生教育は、「所定労働時間内に行なうことを原則とする」とされています。
また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されます。教育が法定時間外に行なわれた場合は、割増賃金の支払いが必要です。
★ ちなみに、特別教育、職長教育を企業外で行なう場合の講習会費、講習旅費等についても、安全衛生法に基づいて行なうものについては、事業者が負担すべきものである、とされています。
(昭47.9.18基発第602号)
②【H27年出題】 〇
・一般健康診断について → 労働時間と解されない
一般的な健康の確保をはかることが目的で、業務遂行との関連において行なわれるものではないため。
・特殊健康診断について → 労働時間と解される
事業の遂行にからんで当然実施されなければならないもので、所定労働時間内に行なわれることが原則。特殊健康診断の実施に要する時間は「労働時間」と解されます。当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、割増賃金の支払いが必要です。
★ ちなみに、第66条第1項から第4項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべき、とされています。
(昭47.9.18基発第602号)
③【H21年出題】※労働基準法 〇
安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されます。そのため、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、参加した労働者に対して、割増賃金を支払う義務があります。
(昭47.9.18基発第602号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-231
R4.4.10 平均賃金の最低保障額
平均賃金は原則として、「算定事由発生日以前3か月間の賃金総額」÷「3か月間の総日数」で計算します。
ただし、賃金が日給制、時間給制、出来高給制(請負制)の場合は、最低保障額の定めがあります。
条文で確認しましょう。
第12条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下つてはならない。 ① 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 ② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 |
「月給制」の場合は、1か月の所定労働日数に関係なく賃金が支払われますので、平均賃金がそれほど変動することはありません。
しかし、例えば時間給制の場合は、出勤日数が非常に少ない月があると、平均賃金に響きます。
そのため、日給制、時間給制、出来高給制(請負制)の場合は、最低保障額が定められています。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

【解答】
【H19年出題】 〇
<最低保障額のポイント>
最低保障額は、分母が「総日数」ではなく、「その期間中に労働した日数」になること。また、「100分の60」は、労働日当たりの賃金の6割を保障するという考え方です。
 最低保障額の計算式
最低保障額の計算式
算定期間中の賃金総額÷算定期間中に労働した日数×100分の60
「原則の計算式」で算定した平均賃金が、最低保障額を下回る場合は、最低保障額が平均賃金となります。
★ちなみに・・・
「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合」の計算について
例えば、「月給制」と「時給制」が併給されている場合は、「月給制」の部分は「総日数」で除して算定し、「時給制」の部分は最低保障のルールで計算します。その2つの金額の合計額が最低保障額となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-230
R4.4.9 平均賃金から除外する賃金
前回は、「分母と分子の両方」から控除する期間を確認しました。
今回は、「分子の賃金総額」からのみ除外される賃金をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第12条第4項、5項 ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
則第2条 ① 法第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。 |
 賃金の総額から除外される賃金は、①「臨時に支払われた賃金」、②「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、③「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」です。
賃金の総額から除外される賃金は、①「臨時に支払われた賃金」、②「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、③「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」です。
①「臨時に支払われた賃金」は、支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定で、かつ非常にまれに発生するものをいいます。例えば、結婚手当、私傷病手当、退職金などが該当します。
(昭22.9.13発基第17号、昭26.12.27基収第385号)
②「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は、年2回の賞与等をいいます。
(昭25.4.15基収392号)
③「通貨以外のもので支払われた賃金」は現物給与のことです。
賃金総額に算入される現物給与は、則第2条で定められている「法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のもの」に限られます。それ以外の現物給与は賃金総額に算入されません。
過去問をどうぞ!
① 【H24年出題】
労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。
②【H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
③【H26年出題】
ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定の基礎に加えなければならない。

【解答】
① 【H24年出題】 ×
年に2回6か月ごとに支給される賞与は、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金の計算には算入しません。
②【H27年出題】 ×
「通勤手当及び家族手当」は、賃金総額に含まれます。
③【H26年出題】 〇
労働協約により支給される定期券は、労働基準法第11条に規定する賃金です。また、6か月定期乗車券は、各月の賃金の前払いとして認められます。
(昭33.2.13基発90)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-229
R4.4.8 平均賃金の計算から控除する期間及び賃金
平均賃金の計算式の、分母は「3か月間の総日数」、分子は「3か月間の賃金の総額」です。
ただし、3か月間のうちに、一定の期間がある場合は、その期間の日数と賃金総額は、分母からも分子からもそれぞれ控除して算定します。
計算に入れると、平均賃金が不当に低くなる可能性があるからです。
では、条文で読んでみましょう。
第12条第3項 平均賃金の算定期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、期間及び賃金の総額から控除する。 ① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 ② 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間 ③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 ④ 育児介護休業法に規定する育児休業又は介護休業をした期間 ⑤ 試みの使用期間 |
控除の対象になる期間は覚えましょう。
分母の「期間中の日数」からも、分子の「賃金総額」からも、どちらからも控除するのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
平均賃金の計算において、労働者が労働基準法第7条に基づく公民権の行使により休業した期間は、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
②【H13年出題】
平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。
③【H19年出題】
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「公民権の行使により休業した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。
②【H13年出題】 ×
「通勤災害により療養のために休業した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。
③【H19年出題】 ×
「子の看護休暇を取得した期間」は、平均賃金の計算上、控除の対象になっていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-228
R4.4.7 平均賃金 原則の計算式
平均賃金は、賃金の1日当たりの単価です。
解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の日の賃金、災害補償、減給制裁の制限額を算定するときに使います。
原則の計算式を条文で読んでみましょう。
第12条 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、・・・(以下例外。今回は省略します。) ② ①の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 |
平均賃金の原則の計算式は、
「算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額」÷「その期間の総日数」です。
「総日数」は「暦日数」のことです。例えば3月1日から5月31日までの3か月なら、92日です。
では、過去問をどうぞ
【R1年出題】
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどれか。
<条件>
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日
時間外手当については、毎月15日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
A 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
B 4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
C 3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。
D 通勤手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。
E 時間外手当を除いて、4月、5月及び6月に支払われた賃金の総額をその計算期間の暦日数92で除した金額が平均賃金になる。

【解答】
【R1年出題】
<この問題のポイント>
★賃金ごとに賃金締切日が異なる場合の平均賃金について
→ 各賃金ごとにその直前の締切日で算定します。
A 〇
「基本給、通勤手当、職務手当」は直前の賃金締切日である6月25日から遡り、「時間外手当」は直前の賃金締切日である7月15日から遡るのがポイントです。
B ×
C ×
「通勤手当」も平均賃金の計算に算入しなければなりません。問題文は通勤手当が入っていないので誤りです。
D ×
E ×
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
R4-227
R4.4.6 後期高齢者医療・費用の負担
後期高齢者医療の財源は、「後期高齢者の保険料」「後期高齢者交付金」「公費」で構成されています。
構成比のイメージです。
後期高齢者の保険料
約10% | 後期高齢者交付金 (現役世代からの支援)
約40% | 公費
50% |
※現役並み所得者(3割負担の人)の費用には公費負担はありません。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。
②【H29年出題】
市町村(特別区を含む。)は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。

【解答】
①【H22年出題】 ×
調整交付金は、負担対象額の見込額の総額の「12分の1」です。
「公費」は「国」「都道府県」「市町村」が負担しています。
負担割合は以下の通りです。
・国の負担
→ 負担対象額の12分の3+調整交付金12分の1
・都道府県の負担
→ 負担対象額の12分の1
・市町村の一般会計における負担
→ 負担対象額の12分の1
★国+都道府県+市町村=12分の6です。公費が50%を占めます。
(第93条、95条、96条、98条)
②【H29年出題】 〇
市町村(特別区を含む。)は、その一般会計において、負担対象額の12分の1を負担しています。
次に、「保険料」の過去問をどうぞ!
③【H23年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
後期高齢者医療の被保険者は保険料を負担します。
保険料を徴収するのは、「市町村(特別区を含む。)」で、「都道府県」は保険料の徴収は行いません。
(法第104条)
最後に「後期高齢者交付金」の過去問をどうぞ!
④【H28年出題】
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。

【解答】
④【H28年出題】 ×
「都道府県」ではなく、「社会保険診療報酬支払基金」が徴収します。
(法第118条)
「後期高齢者支援金」は現役世代から後期高齢者世代への支援です。
保険者
↓
↓
社会保険診療報酬支払基金
保険者から「後期高齢者支援金等」を徴収
後期高齢者医療広域連合に「後期高齢者交付金」を交付
↓
↓
後期高齢者医療広域連合
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険労務士法
社会保険労務士法
R4-226
R4.4.5 不正行為の指示等に関する懲戒
社会保険労務士に対する懲戒処分は3種類あります。
条文を読んでみましょう。
第25条 (懲戒の種類) 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。) |
次に、不正行為の指示等を行ったときの懲戒規定を読んでみましょう。
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒) ① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等を行ったときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 ② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、①項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 |
①は「故意に」、②は「相当の注意を怠り」の部分に注目してください。
「故意」の方が処分が重いのがポイントです。
また、主語が「厚生労働大臣」であるのもポイントです。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
②【H28年出題】
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。
③【H20年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
「故意に」真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、「1年以内の業務停止又は失格処分の処分をすることができる」とされているので、失格処分を受けることもあります。
②【H28年出題】 ×
「相当の注意を怠り」、不正行為の指示等を行ったときは、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる」です。失格処分までは規定されていません。
③【H20年出題】 ×
懲戒処分は厚生労働大臣が行い、全国社会保険労務士会連合会への委任はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-225
R4.4.4 厚生年金保険・国庫負担
厚生年金保険の財源は主に保険料ですが、国庫負担もあります。
今日は国庫負担がテーマです。
条文を読んでみましょう。
第80条 (国庫負担等) ① 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。 ② 国庫は、①に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。 ③ 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。 |
★「国庫負担」とは、年金給付の財源として、税負担をもとに国が支出するものです。(参照:厚生労働省ホームページ)
 先に「実施機関」を確認しましょう。
先に「実施機関」を確認しましょう。
・第1号厚生年金被保険者
→ 厚生労働大臣
・第2号厚生年金被保険者
→ 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
・第3号厚生年金被保険者
→ 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
・第4号厚生年金被保険者
→ 日本私立学校振興・共済事業団
 では、第80条を確認しましょう。
では、第80条を確認しましょう。
①について
厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)にも、その被扶養配偶者(第3号被保険者)にも「基礎年金」が支給されます。そのための費用として、厚生年金保険の実施者たる政府は「基礎年金拠出金」を負担しています。その基礎年金拠出金の額の2分の1を国庫が負担しています。
②について
厚生年金保険事業の事務の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用は国庫が負担する。 → 事務費は、予算の範囲内で国庫が負担しています。
③について
実施機関(厚生労働大臣を除く)が納付する「基礎年金拠出金」と実施機関(厚生労働大臣を除く。)による「事務の執行に要する費用の負担」については、厚生年金保険法に定めるもののほか、共済各法の定めるところによります。
過去問をどうぞ!
【H29年選択式】
厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する< A >に相当する額を負担する。

【解答】
A 基礎年金拠出金の額の2分の1
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-224
R4.4.3 厚生年金保険の保険料の源泉控除
事業主は、保険料の被保険者負担分を報酬から控除することができます。
条文を読んでみましょう。
第84条 (保険料の源泉控除) ① 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。 ② 事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 ③ 事業主は、保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。 |
<原則>
事業主が報酬から控除できるのは、前月分の被保険者負担分の保険料です。
<月末退職の場合>
前月分と当月分を控除できます。
例えば、4月30日退職・5月1日喪失の場合、保険料は4月分まで徴収されます。
4月の報酬から、3月分と4月分の保険料を控除できます。
<賞与の保険料>
賞与の被保険者負担分の保険料は、賞与から控除できます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所または船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
②【H30年出題】
第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合において、事業主が被保険者の負担すべき保険料を報酬から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
控除できるのは、原則として「前月分の保険料」のみです。ただし、月末退職のように当月分の保険料が徴収される場合は、「前月分と当月分の保険料」を控除することができます。
②【H30年出題】 〇
被保険者負担分の保険料を控除したときは、控除の計算書を作成し、控除額を被保険者に通知しなければなりません。
 ちなみに、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、法第84条の2(保険料の徴収等の特例)で、「共済各法の定めるところによる」と規定されています。
ちなみに、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、法第84条の2(保険料の徴収等の特例)で、「共済各法の定めるところによる」と規定されています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-223
R4.4.2 厚生年金保険の保険料の納付
事業主には、被保険者負担分と事業主負担分の保険料を納付する義務があります。
今回は、保険料の納付のルールを確認します。
条文を読んでみましょう。
第83条 (保険料の納付) ① 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。 ② 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 ③ ②の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。 |
事業主は、厚生年金保険の保険料を翌月末日までに納付しなければなりません。例えば、4月分の保険料は5月末日までに納付することになります。
翌月下旬ごろに、保険料の「納入告知書」が事業所に届きますので、それに保険料を添えて納付します。
②は「納入告知書の額が本来納付すべき保険料額より多かった」、「納付した保険料額が本来納付すべき保険料額より多かった」場合の事務簡素化のための規定です。
6か月間の保険料を繰り上げて先に納付したものとみなすことができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
厚生年金保険の毎月の保険料は、当月末日までに、納付しなければならない。
②【H30年選択式】
厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その< A >以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができるとされている。
<選択肢>
①納入の告知又は納付の日から1年
②納入の告知又は納付の日から6か月
③納入の告知又は納付の日の翌日から1年
④納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
③【H25年出題】
厚生労働大臣は、厚生年金保険法第83条第2項の規定によって、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
納付期日は、当月末日ではなく、「翌月末日」までです。
②【H30年選択式】
A ④納入の告知又は納付の日の翌日から6か月
③【H25年出題】 ×
第83条第3項に、納期を繰り上げて納付をしたものとみなすときは、「厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。」と規定されています。「事前にその旨を当該納付義務者に通知し同意を得なければならない。」ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-222
R4.4.1 厚生年金保険の保険料の負担及び納付義務
厚生年金保険の保険料は「標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額」です。
被保険者と事業主が半額ずつ負担し、事業主が納付義務を負います。
では、条文を読んでみましょう。
第82条 (保険料の負担及び納付義務) ① 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 ② 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 ③ 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。 ④ 第2号厚生年金被保険者についての①の規定の適用については、①の「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 ⑤ 第3号厚生年金被保険者についての①の規定の適用については、①の「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。 |
例えば、標準報酬月額が41万円の場合、厚生年金保険料は7万5,030円(41万円×1000分の183)で、被保険者と事業主がそれぞれ3万7515円ずつ負担します。
事業主は、被保険者負担分と事業主負担分を合わせた7万5030円を納付する義務を負います。
 さて、今日の過去問は、「2か所以上の事業所に使用される被保険者の保険料」です。
さて、今日の過去問は、「2か所以上の事業所に使用される被保険者の保険料」です。
先に、2か所で厚生年金保険に加入している被保険者の標準報酬月額の決定のルールを確認しておきましょう。
法第24条第2項で、「同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定、資格取得時の決定、随時改定、育児休業を終了した際の改定若しくは産前産後休業を終了した際の改定又は保険者算定の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。」とされています。
例えば、A社とB社で厚生年金保険の被保険者となっている場合、A社の「報酬月額」とB社の「報酬月額」の合算額がその者の報酬月額となります。その合算した報酬月額で標準報酬月額が決定されます。
A社とB社の標準報酬月額を合算ではありませんので、注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。
②【H30年出題】
被保険者が厚生年金保険法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとされている。

【解答】
①【H28年出題】 〇
被保険者が2以上の適用事業所に使用される場合、それぞれの事業主が負担する保険料についての問題です。
それぞれの事業所の「報酬月額」で按分します。「標準報酬月額」ではないのでご注意ください。
按分割合は「各事業所について算定した報酬月額」÷「当該被保険者の報酬月額」です。
各事業主が負担する保険料は「当該被保険者の保険料の半額」×按分割合です。
なお、各事業主が納付する保険料は、「各事業主が負担すべき保険料+これに応ずる被保険者が負担すべき保険料」となります。
(令第4条第1項)
例えば、被保険者がA事業所とB事業所で被保険者になっている場合の報酬月額は下の図のようなイメージです。
被保険者の報酬月額(A+B) | |
A事業所の報酬月額 | B事業所の報酬月額 |
A事業主の負担割合は、A÷(A+B)です。
②【H30年出題】 〇
被保険者が船舶と同時に船舶以外の事業所に使用される場合の保険料の負担と納付について
・当該被保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは「船舶所有者」で、「船舶所有者以外の事業主」は保険料を負担、保険料を納付する義務は負いません。
(令第4条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-221
R4.3.31 厚生年金保険の保険料
厚生年金保険は、国庫負担と保険料によって賄われています。
今回は「保険料」の勉強です。
条文を読んでみましょう。
第81条 (保険料) 1 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 4 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。(表は省略します) |
用語について
・政府等 → 政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く)
・被保険者期間
→ 「被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」
・保険料額
→ 標準報酬月額×保険料率、標準賞与額×保険料率
・保険料率
→ 平成29年9月以後の月分・・・1,000分の183.00
ポイントを穴埋めでチェックしましょう
問題1
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(< A >を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

【解答】
A 基礎年金拠出金
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000分の183.00に固定(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の保険料率は平成29年9月に、第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが、第4号厚生年金被保険者の保険料率は平成31年4月12日時点において上限に達していない。
②【H24年出題】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
(第1号厚生年金被保険者の保険料率について)
平成16年の年金改正で保険料水準固定方式がとられるようになりました。厚生年金保険の保険料率は、平成16年10月から毎年引き上げられ(平成17年度からは9月に引き上げられています。)、平成29年9月に1000分の183になり、そこで固定されました。
(第2号及び第3号厚生年金被保険者の保険料率について)
被用者年金一元化によって、保険料率が毎年度引き上げられ、平成30年9月にそれぞれ1,000分の183に達し、固定されています。
(第4号厚生年金被保険者の保険料率について)
保険料率は毎年度引き上げられ、令和9年4月に1,000分の183に達します。
(H24年法律第63号附則第83、84、85条)
②【H24年出題】 ×
例えば、令和4年3月31日に資格取得、令和4年9月30日に退職・10月1日に資格喪失した場合で考えてみましょう。
被保険者期間は、「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月」までとなりますので、3月から9月までとなります。
3/31 取得 |
|
|
|
|
| 9/30 退職 | 10/1 喪失 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
厚生年金保険の保険料は「被保険者期間の計算の基礎となる各月」に徴収されますので、退職した日(9月30日)が属する月(9月分)の保険料は徴収されます。
ポイント!
・月末に被保険者の資格を取得した月 → 保険料が徴収される
・月の末日付けで退職したとき → 退職した日が属する月分の保険料は徴収される
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-220
R4.3.30 障害基礎年金の支給要件「保険料納付要件」
障害基礎年金の3要件は「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」です。
今日は、「保険料納付要件」を確認しましょう。
条文を読んでみましょう
第30条 (障害基礎年金の保険料納付要件) 当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
昭和60年附則第20条 (障害基礎年金の支給要件の特例) 初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは保険料納付要件を満たす。 ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、この限りでない。 |
 ポイント!
ポイント!
・ 保険料納付要件を見るのは「初診日の前日」
→ 初めて病院に行った日(初診日)に保険料を納付しても間に合わない
・ 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間が全体の3分の2以上あること
・ 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がないものは、滞納には当たらな い(加入直後の障害の場合)
・ 初診日が令和8年4月1日前にある場合の特例
→ 直近の1年間に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」=「1年間のすべてが保険料納付済期間と保険料免除期間(滞納がない)」場合は納付要件を満たす。(ただし、初診日に65歳以上の場合は、特例は適用しない)
例えば、令和3年1月に国民年金の資格を取得し、初診日が令和4年3月30日の場合は、保険料納付要件は令和4年1月までを見ます。
令和3年1月 |
|
|
|
|
| 令和4年1月 | 令和4年2月 | 令和4年3月 |
資格取得月 |
|
|
|
|
| 保険料 納期限 2月末 | 保険料 納期限 3月末 | 初診日の 属する月 |
保険料の納期限がきている1月分までの納付状況で判断します。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
障害基礎年金について、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし、当該初診日において65歳未満であるときに限られる。
②【H22年出題】
初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。
③【H24年出題】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
保険料納付要件の特例のポイント!
・初診日が令和8年4月1日前にある
・直近の1年間に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がない」こと。=直近の1年間に滞納期間がないこと
・初診日に65歳未満であること
②【H22年出題】 ×
保険料納付要件は「初診日の属する月の前々月までの1年間」でみますので、初診日が平成22年8月30日の場合は、平成22年「6」月分までの1年間のうちに保険料の滞納がないことが条件です。また、初診日に65歳未満であることも必要です。
③【H24年出題】 ×
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳前の期間及び60歳以降の期間」は、老齢基礎年金では、保険料納付済期間ではなく「合算対象期間」となります。老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、年金額の計算には入りません。
しかし、「障害基礎年金」については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、「20歳前の期間及び60歳以降の期間」も保険料納付済期間に入ります。
また、老齢基礎年金はフルペンション減額方式ですので、40年間すべて保険料納付済期間の場合は満額受給できますが、免除、合算対象期間、滞納があるとその分、減額されます。
一方、障害基礎年金の額は、加入期間などに関係なく定額で支給されます。
ちなみに、遺族基礎年金も障害基礎年金と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-219
R4.3.29 障害基礎年金の支給要件「障害認定日」
「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」が障害基礎年金支給の3要件です。
要件を満たした場合は、障害認定日に受給権が発生します。
今日は「障害認定日」を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第30条 (障害基礎年金の支給要件) 1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
障害認定日に1級、2級に該当する程度の障害状態にあると判定された場合は、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生します。
「障害認定日」は、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日となります。なお、治った日には、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も含まれます。
なお、障害認定日に障害の状態に該当しない場合は、障害基礎年金の受給権は発生しません。
しかし、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害状態に該当した場合は、「事後重症の障害基礎年金」を請求することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。
②【H27年出題】
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
③【R1年出題】
国民年金法第30条第1項の規定により、障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが、同法第30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による障害基礎年金の受給権の発生日はその支給の請求日である。
④【H29年出題】
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
『その期間後に傷病が治った場合』ではなく、『その期間「内」にその傷病が治った場合』です。障害認定日は、最長で「初診日から起算して、1年6か月を経過した日」で、その前に治った場合はその治った日が障害認定日になります。
②【H27年出題】 〇
初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となりますが、治っていない場合でも症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も障害認定日として取り扱われます。
③【R1年出題】 〇
・通常の障害基礎年金(第30条第1項)
→ 障害認定日に受給権が発生します
・事後重症による障害基礎年金(第30条の2第1項)
→ 支給の請求をした日に受給権が発生します
④【H29年出題】 ×
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当します。
「障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。」と規定されています。
施行令4条の6及び別表で障害等級表が定められていて、その中に精神の障害も載っています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-218
R4.3.28 障害基礎年金の支給要件「初診日」
障害基礎年金には、「初診日」、「保険料納付要件」、「障害認定日」の3つの支給要件があります。
今日は「初診日」要件を確認しましょう。
まず条文を読んでみましょう。
第30条 (障害基礎年金の支給要件) 1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
|
★「初診日」とは、『傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日』のことです。
「初診日」に「被保険者であること」又は「被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」が要件です。
60歳以上65歳未満の被保険者でないときに初診日がある場合は、「国内居住要件」があることに注意してください。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。
②【H29年出題】
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

【解答】
①【R1年出題】 ×
初診日に「被保険者」で、「障害認定日」に障害等級の1級又は2級で、「保険料納付要件」を満たしているので、障害基礎年金の支給要件は満たしています。
初診日に保険料の納付猶予の適用を受けていることは関係ありません。
②【H29年出題】 〇
「被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日」がある場合は、初診日に日本国内に住所を有することが必要です。問題文のように、初診日に日本国内に住所を有しない場合は、初診日の要件を満たさないので障害基礎年金は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-217
R4.3.27 資格喪失後の傷病手当金と老齢退職年金給付
資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができる場合は、どちらが優先されるでしょう?
では、条文を読んでみましょう。
第108条第5項 傷病手当金の支給を受けるべき者(資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者に限る。)が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
則第89条第2項 法第108条第5項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。 |
資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けることができる者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。老齢退職年金給付が優先されます。
ただし、老齢退職年金給付の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
なお、傷病手当金の額は「日単位」ですが、年金の額は「年単位」です。老齢退職年金給付は360で割った日額で傷病手当金と比較します。365ではありませんので注意してください。
老齢退職年金給付÷360が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。
②【H27年出題】
適用事業所に使用される被保険者が傷病手当金を受けるときには、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われない。
③【H17年出題】
適用事業所に使用される常勤職員であって傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合算額を360で除して得た額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給される。

【解答】
①【H23年出題】 ×
老齢退職年金給付が優先されますので、「傷病手当金は支給されない」となります。
②【H27年出題】 〇
傷病手当金と老齢退職年金給付が調整されるのは、「資格喪失後の継続給付の傷病手当金」の場合です。退職していることが前提です。
問題文は、「適用事業所に使用される被保険者」です。在職中の傷病手当金は、老齢基礎年金及び老齢厚生年金との調整は行われません。
③【H17年出題】 ×
②と同様に、③も「適用事業所に使用される常勤職員」ですので、「傷病手当金」と「老齢基礎年金・老齢厚生年金」の調整は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-216
R4.3.26 督促及び滞納処分
納期限を過ぎても労働保険料が納付されない場合、督促状が送付されます。
また、滞納した保険料を納付しない場合は、滞納処分が行われます。
条文を読んでみましょう。
第27条 (督促及び滞納処分) ① 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 ② 督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ③ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。 |
滞納処分とは、滞納金を強制的に徴収するためのもので、滞納者の財産を差し押さえ、それを換価した代金を滞納金に充てる行政処分です。
過去問をどうぞ!
①【H22年出題】(雇用)
事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。
②【R1年出題】(雇用)
労働保険徴収法第27条第3項に定める「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、法定納期限までに納付すべき概算保険料、法定納期限までに納付すべき確定保険料及びその確定不足額等のほか、追徴金や認定決定に係る確定保険料及び確定不足額も含まれる。
③【H22年出題】(雇用)
事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわらず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例によって処分されることはない。

【解答】
①【H22年出題】(雇用) 〇
概算保険料・確定保険料を、所定の納期限までに申告しなかった場合は、政府は認定決定を行います。認定決定の納期限までに納付しない場合は、督促が行われます。
②【R1年出題】(雇用) 〇
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」には、「追徴金」が含まれているのがポイントです。
③【H22年出題】(雇用) ×
「追徴金」は、国税滞納処分の例によって処分されることはありますが、延滞金の対象にはなりません。問題文は逆になっています。
第27条(督促及び滞納処分)は、「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」を納付しない場合が対象ですが、第28条(延滞金)は、「労働保険料の納付」を督促したときが対象です。
第28条(延滞金)は「労働保険料」だけが対象になっているのがポイントです。
「追徴金」は労働保険料ではありませんので、延滞金の対象にはなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-215
R4.3.25 受給期間内に再就職・再離職し、新しく受給資格を得た場合
「受給期間」は有効期間のようなイメージで、基本手当を受けることができる期間です。原則として、基準日の翌日から1年です。(所定給付日数が330日の場合は1年+30日、所定給付日数が360日の場合は1年+60日です)
例えばA社を離職して基本手当の受給資格を得た場合、A社の離職の日の翌日から1年間が受給期間です。A社の離職による基本手当は1年間有効です。もし、その1年の間にB社に再就職し、B社を離職しそこで新しく受給資格を得た場合、A社の離職による基本手当はどうなるのでしょうか?
条文を読んでみましょう。
第20条第3項 前の受給資格を有する者が、受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。 |
★ 受給資格者が、受給期間内に再び就職し、新たに受給資格を得た後に離職したときは、前の受給期間は消滅し、原則としてその離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となります。この場合、前の受給資格に基づく基本手当は支給されません。
(行政手引50251)
A社を離職して基本手当の受給資格を得た場合、A社の離職の日の翌日から1年間が受給期間です。その間にB社に再就職し、B社を離職しそこで受給資格を得た場合、A社の受給期間は消滅し、B社の離職の日の翌日から1年間が新たな受給期間となります。A社の受給資格に基づく基本手当は支給されなくなります。
ちなみに、再就職先のB社を離職したときに、B社の離職で受給資格を得られなかった場合は、A社の受給期間内で、A社の受給資格による基本手当の残日数分を受給することができます。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
②【H21年出題】
受給資格者がその受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって高年齢受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であっても、その受給資格に係る基本手当の残日数分を受給することはできない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
再離職で新たな受給資格を得たときは、前の受給資格に係る受給期間内だったとしても、基本手当の残りがあったとしても、前の受給資格に基づく基本手当は受給できません。
②【H21年出題】 〇
再離職で受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内だったとしても、その受給資格に係る基本手当は受給できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-214
R4.3.24 労災保険の適用事業と適用除外
労働者を1人でも使用する事業は、労災保険の適用事業となります。
ただし、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法の保護を受けられる事業は、労災保険法の適用は除外されます。
条文を読んでみましょう。
第3条 (適用事業及び適用除外) ① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 ② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
・ 国の直営事業には労災保険法は適用されません。
(なお、国の直営事業に該当する事業は現在ありません。)
・ 官公署の事業とは、非現業の官公署のことです。国家公務員災害補償法や地方公務 員災害補償法の適用があるので、労災保険法は適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
②【H29年出題】
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
③【H29年出題】
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
④【H29年出題】
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
⑤【H29年出題】
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

【解答】
①【H29年出題】 ×
・ 都道府県、市町村の「非現業」の官公署
→ 地方公務員災害補償法が適用されるので、労災保険の適用は除外
※ただし、「非常勤職員」には、地方公務員災害補償法で定める災害補償の条例 が適用される
・ 都道府県、市町村の「現業部門」
→ 労災保険法では、労災保険の適用は除外されていない
→ ただし、「常勤職員」は、地方公務員災害補償法第67条第2項で労災保険の適用が除外されている
→「都道府県、市町村の現業部門」の非常勤職員には、労災保険法が適用される。
問題文の「市の経営する水道事業の非常勤職員」には労災保険法が適用されます。
②【H29年出題】 ×
行政執行法人の職員には国家公務員災害補償法が適用されますので、労災保険法の適用は除外されます。
③【H29年出題】 ×
非現業の一般職の国家公務員には、労災保険法は適用されません。
④【H29年出題】 〇
国の直営事業には労災保険は適用されません。
⑤【H29年出題】 ×
常勤の地方公務員には労災保険は適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-213
R4.3.23 定期自主検査
ボイラーなどの機械については、一定期間ごとに検査を行うことが義務づけられています。「定期自主検査」といいます。
定期自主検査の対象機械等は、政令で38種類定められています。
では、条文を読んでみましょう。
第45条 (定期自主検査) ① 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 ② 事業者は、①の機械等で政令で定めるものについて①の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない。 |
① 定期自主検査が義務づけられている機械は、施行令第15条で38種類定められています。
なお、38種類の中には、特定機械等も含まれています。
② 定期自主検査の対象になる機械等のうち、特に検査が技術的に難しい機械等については、「一定の資格を有する労働者」か「検査業者」に検査を実施させなければなりません。「特定自主検査」といいます。
★特定自主検査の対象機械等
動力により駆動されるプレス機械、フォークリフト、車両系建設機械、
不整地運搬車、高所作業車
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。
②【H30年出題】
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 ×
作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、特定自主検査の対象です。
特定自主検査は、「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は「検査業者」に実施させなければならない、とされています。
その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有する者にも実施させることができます。検査業者だけではありません。
②【H30年出題】 ×
定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません。
(則第135条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-212
R4.3.22 法令等の周知義務
就業規則は職場のルールです。働く人はその内容を知っておかなければなりません。
使用者は、就業規則などを労働者に周知させる義務があります。
条文で確認しましょう。
第106条 (法令等の周知義務) 使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、労働基準法に規定する労使協定並びに労使委員会の決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
則第52条の2 厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。 2 書面を労働者に交付すること。 3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 |
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働基準法第106条により使用者に課せられている法令等の周知義務は、労働基準法、労働基準法に基づく命令及び就業規則については、その要旨を労働者に周知させればよい。
②【R2年出題】
使用者は、労働基準法第36条第1項(時間外及び休日の労働)に関する協定及び同法第41条の2第1項(いわゆる高度プロフェッショナル制度に係る労使委員会)に規定する決議を労働者に周知させなければならないが、その周知は、対象労働者に対してのみ義務付けられている。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「労働基準法、労働基準法に基づく命令」については、全文そのままではなく、要旨を周知させればよいことになっています。
しかし、就業規則は、要旨だけでなく全文の周知が必要です。
★周知義務が課せられているもの
・労働基準法、労働基準法に基づく命令の要旨
・就業規則(全文)
・労働基準法に規定する労使協定
①貯蓄金管理規定 ②賃金控除 ③1か月単位の変形労働時間制 ④フレックスタイム制 ⑤1年単位の変形労働時間制 ⑥1週間単位の非定型的変形労働時間制 ⑦一斉休憩の適用除外 ⑧36協定 ⑨60時間超の時間外労働の場合の代替休暇 ⑩事業場外労働のみなし労働時間 ⑪専門業務型裁量労働制 ⑫時間単位の年次有給休暇 ⑬年次有給休暇の計画的付与 ⑭年次有給休暇の賃金を健康保険の標準標準日額で支払う制度 |
・労使委員会の決議
| ①企画業務型裁量労働制 ②高度プロフェッショナル制度 |
②【R2年出題】 ×
対象労働者に対してのみではなく、労働者全体への周知が義務付けられています。
(平11.3.31基発169号)
こちらもどうぞ!
③【H23年出題】
労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務は、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置することによっても果たされ得る。

【解答】
③【H23年出題】 〇
厚生労働省令で定められた3つの方法のいずれかの方法で周知しなければなりません。問題文の方法はそのうちの1つです。
パソコンなどで随時確認する方法です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法(就業規則)
労働基準法(就業規則)
R4-211
R4.3.21 制裁規定の制限
「制裁」には、譴責、戒告、出勤停止、減給、懲戒解雇などがあります。公序良俗に反しない限り、就業規則に定めることができます。
ただし、「減給」については、労働基準法で制限が設けられています。
減給は、労働した分の賃金をカットすることです。何も規制が無いと、例えば1回の遅刻に対する制裁として、1か月分の賃金を全てカットすることもできてしまうからです。
では、減給制裁の制限を条文で読んでみましょう。
第91条 (制裁規定の制限) 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 |
減給制裁は、「1回の額は平均賃金1日分の半額以内」、「一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額は、一賃金支払期の賃金の総額の10分の1以内」となっています。
(昭23.9.20基収1789号)
例えば、平均賃金が1万円、一賃金支払期の賃金総額が20万円なら、1回の額は5千円以内、一賃金支払期に減額できるのは2万円以内となります。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
労働者が、遅刻・早退をした場合、その時間に対する賃金額を減給する際も労働基準法第91条による制限を受ける
②【H28年出題】
服務規律違反に対する制裁として一定期間出勤を停止する場合、当該出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、減給制限に関する労働基準法第91条違反となる。
③【R3年出題】
労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。
④【H16年出題】
就業規則で労働者に対して減給の定めをする場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
例えば、1時間遅刻した場合に、1時間分の賃金を差し引くことは、制裁による減給に該当しませんので、労働基準法第91条による制限は受けません。
ただし、1時間の遅刻に対して2時間分を減給することは制裁とみなされ、第91条による制限を受けることになります。
(昭63.3.14基発150号)
②【H28年出題】 ×
出勤停止期間中の賃金を支給しないことは、「制裁としての出勤停止の当然の結果」で、減給制限に関する労働基準法第91条には関係ない、とされています。
(昭23.7.3基収2177号)
③【R3年出題】 〇
「一賃金支払期における賃金の総額」とは、当該賃金支払期に対し「現実に」支払われる賃金の総額をいいます。
(昭23.9.20基収1789号)
④【H16年出題】 ×
1賃金支払期の賃金総額が20万円の場合は、減給の総額は2万円以内です。もし、2万5千円の減給の制裁を行う必要がある場合は、5千円分は次期の賃金支払期に延ばすことができます。
「もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない」は誤りです。
(昭23.9.20基収1789号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法(就業規則)
労働基準法(就業規則)
R4-210
R4.3.20 就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
就業規則に記載する事項には、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項があります。
いかなる場合でも絶対に記載しなければならない事項が「絶対的必要記載事項」、「定めをする場合」においては必ず記載しなければならない事項が「相対的必要記載事項」です。
では、条文で確認しましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |
1から3が絶対的必要記載事項です。3の2以下は「定めをする場合においては」に注目してください。相対的必要記載事項です。
では過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
必要記載事項が記載されていない就業規則も、「他の要件を具備する限り有効」とされています。問題文の「労働基準法第13条に基づき、無効となる」の部分は誤りです。
しかし、定められた必要記載事項が記載されていないため、第89条違反の責任は免れません。
(平11.3.31基発168号)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。
③【H30年出題】
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。
④【H25年出題】
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

【解答】
②【H23年出題】 〇
「休暇」は第1号の中に入っていますので、絶対的必要記載事項です。
年次有給休暇や産前産後休暇のように労働基準法で定められた休暇のみなならず、任意に設けている夏季休暇や慶弔休暇なども含まれます。
ボランティア休暇制度も「休暇」ですので、これに関する事項は就業規則に記載しなければなりません。
③【H30年出題】 ×
「制裁」は「定めをする場合」は記載しなければならない相対的必要記載事項です。制裁を定めない場合は、記載する義務はありません。
④【H25年出題】 〇
第10号は、「当該事業場の労働者のすべてに適用される定め」です。「従来の慣習」が当該事業場の労働者のすべてに適用されるのであれば、第10号に含まれますので、就業規則の記載が必要です。
(平11.3.31基発168号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法(就業規則)
労働基準法(就業規則)
R4-209
R4.3.19 就業規則の作成及び届出の義務
就業規則は、その事業場の「法的規範」としての性質を有します。
「就業規則」の作成手続きや、届出について条文で確認しましょう。
第89条 (作成及び届出の義務) 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 ※1~10まで記載事項がありますが、次回のテーマになりますので今回は省略します。
第90条 (作成の手続) ① 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、届出をなすについて、①の意見を記した書面を添付しなければならない。 |
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し届け出る義務があります。就業規則を変更した場合も同じです。
なお、「使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合においては、遅滞なく、就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない」とされています。(則第49条)
また、作成、変更の場合は、過半数労働組合か、過半数労働組合がないときは労働者の過半数代表者の意見を聴かなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。
②【H25年出題】
派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者も0.5人ではなく1人で数えます。
労働基準法では、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」は労働者です。労働時間の長短は関係ありません。
なお、常時10人未満の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務はありません。
②【H25年出題】 〇
派遣労働者に関して、就業規則の作成義務を負うのは、「派遣元」の使用者です。派遣中の労働者は雇用関係のある派遣元の人数に入ります。
こちらもどうぞ!
③【H20年出題】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
④【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
⑤【H27年出題】
労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとすることにある。

【解答】
③【H20年出題】 ×
「同意を得なければならない」ではなく、「意見を聴かなければならない」です。
「同意を得るとか協議をするとかいうことまで要求しているものではない」とされていて、就業規則についての意見を聴けば労働基準法違反とならないという趣旨です。
(昭25.3.15基収第525号)
④【H21年出題】 〇
就業規則の作成のみならず、変更についても、意見聴取が必要です。
⑤【H27年出題】 〇
「労働協約」は労使の団体交渉で締結されますが、就業規則は、使用者が一方的に作成・変更することができます。
しかし、労働者が全く知らないままに就業規則の作成、変更が行われるのも問題です。
意見聴取を義務づけているのは、就業規則に労働者の団体的意見を反映させ、就業規則を合理的なものにするためです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働契約法
労働契約法
R4-208
R4.3.18 「懲戒」について
労働者に対して懲戒を行う際のルールを確認します。
労働契約法の条文を読んでみましょう。
第15条 (懲戒) 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 |
この規定の趣旨、内容を確認しましょう。
■趣旨
懲戒は、使用者が企業秩序を維持し、企業の円滑な運営を図るために行われるものです。
しかし、「懲戒の権利濫用が争われた裁判例もみられる」、「懲戒は労働者に労働契約上の不利益を生じさせるものである」ことから、権利濫用に該当する懲戒による紛争を防止するために、労働契約法第15条で、権利濫用に該当するものとして無効となる懲戒の効力を規定しています。
■内容
・ 法第15条は、使用者が労働者を懲戒することができる場合でも、その懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には権利濫用に該当するものとして無効となることを明らかにしています。
また、権利濫用であるか否かを判断するに当たっては、労働者の行為の性質及び態様その他の事情が考慮されることを規定しています。
・ 法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義です。同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられています。
→ 労働基準法第89条第9号は、就業規則の「相対的必要記載事項」です。
(参照:平成24年8月10日 基発0810第2号)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、その権利を濫用したものとして、無効とされることがある。
②【R1年出題】
労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。
③【H30年出題】
「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことをもって足り、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも、労働基準法に定める罰則の対象となるのは格別、就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずることに変わりはない。」とするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
①【H24年出題】 〇
使用者が労働者を懲戒することができる場合でも、懲戒が、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その権利を濫用したものとして、無効とされることがあります。
②【R1年出題】 〇
労働基準法第89条第9号は、「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項」となっていて、就業規則の相対的必要記載事項です。
懲戒(制裁)の定めをする場合は、その種類及び程度について就業規則に記載しなければなりません。
③【H30年出題】 ×
「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていない場合でも」が誤りです。就業規則が法的規範としての性質を有するものとして拘束力を生ずるには、「適用をうける事業場の労働者への周知手続」が必要です。
(参照:フジ興産事件)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-207
R4.3.17 離婚時みなし被保険者期間と遺族厚生年金
引き続き、離婚時みなし被保険者期間のよく出るところを見ていきます。
自身が厚生年金保険の被保険者になったことがなく、離婚時みなし被保険者期間のみを有する者が死亡した場合、遺族厚生年金は支給されるでしょうか?
まず、「遺族厚生年金」の死亡した人の条件を確認しましょう。
第58条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。 2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。 3 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。 4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
第78条の11 第4号に該当する場合にあっては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。 |
第4号には、「離婚時みなし被保険者期間を有する者」が含まれることがポイントです。
また、「25年以上」には、合算対象期間も合算されます。(附則第14条)
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】 ※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上あるものとする)を取得した後に死亡した場合は、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
②【H19年出題】
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。

【解答】
①【H28年出題】 〇 ※改正による修正あり
国民年金の第1号被保険者期間しか有していなくても、離婚時みなし被保険者期間を有した場合は、老齢厚生年金の受給権を取得します。
そのような場合で、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡した場合は、一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
老齢厚生年金 (離婚時みなし被保険者期間のみ) |
老齢基礎年金 (第1号被保険者期間のみ(25年以上)) |
②【H19年出題】 〇
自身は厚生年金保険の被保険者になったことがなく離婚時みなし被保険者期間のみの者が死亡した場合でも、遺族に遺族厚生年金が支給されることがあります。
ただし、死亡した者の保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が原則として25年以上あることが条件です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
R4-206
R4.3.16 離婚時みなし被保険者期間の扱いその1
「離婚時みなし被保険者期間」とは?
例えば、厚生年金保険の被保険者の夫から第3号被保険者の妻に厚生年金の分割が行われた場合、妻は厚生年金保険の被保険者ではありませんが、分割を受けたことにより、その期間は(厚生年金保険の)被保険者期間であったとみなされます。これを「みなし被保険者期間」といいます。
■合意分割
・ 対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間
→ 第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす。(離婚時みなし被保険者期間)
(第78条の7)
■3号分割
・ 特定期間に係る被保険者期間
→ 被扶養配偶者の被保険者期間であったものとみなす。(被扶養配偶者みなし被保険者期間)
(第78条の15)
今日のテーマは「みなし被保険者期間」です。
「みなし被保険者期間」を算入するか算入しないかが問われるポイントです。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。
②【H29年出題】
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
③【R3年出題】
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金は、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間があることが条件です。みなし被保険者期間は、「1年以上」には算入されません。そのため、自身で厚生年金保険に加入したことがなく、みなし被保険者期間しか有しない場合は、特別支給の老齢厚生年金は受給できません。
(法附則第17条の10)
②【H29年出題】 〇
特別支給の老齢厚生年金の定額部分は、「1,628円×改定率×厚生年金保険の被保険者期間の月数」で計算しますが、みなし被保険者期間は、この計算には算入されません。
(法附則第17条の10)
③【R3年出題】 〇
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算される要件である「被保険者期間の月数が240以上」の被保険者期間には、みなし被保険者期間は算入されません。
加給年金額が加算されるには、自身の厚生年金保険の被保険者期間が原則として240以上あることが条件です。
(法附則第17条の10)
※「被扶養配偶者みなし被保険者期間」も「離婚時みなし被保険者期間」と同じ扱いです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-205
R4.3.15 追納その4 追納の保険料の額
追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算がつきます。
では、条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ③ 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。 |
追納する場合は、当時の保険料額に政令で定める額が加算されます。
例えば、全額免除された保険料を令和3年度中に追納する場合、以下の額になります。
数字を覚える必要はありません。古くなるほど率が高いことと、直近のR1年度とR2年度分には加算がないことがポイントです。
①政令で定める率(施行令第10条)
②当時の保険料額
③令和3年度中に追納する場合の額
| H23年度 | H24 年度 | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | R1 年度 | R2 年度 |
① | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | ― |
② | 15,020 | 14,980 | 15,040 | 15,250 | 15,590 | 16,260 | 16,490 | 16,340 | 16,410 | 16,540 |
③ | 15,350 | 15,200 | 15,180 | 15,330 | 15,650 | 16,310 | 16,520 | 16,360 | 16,410 | 16,540 |
なお、免除月が平成31年3月で、令和3年4月に追納する場合は、加算はありません。
平成31年3月は平成30年度ですので、令和3年度に追納する場合は、加算額がつくのが原則です。ただし、平成31年3月の保険料の納期限は平成30年4月末です。令和3年4月中なら納期限から2年以内ですので、加算はつきません。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
②【H18年出題】
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
③【H28年出題】
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
保険料に加算額が加算されるのは、免除月の属する年度の4月1日から起算して「3年以上経過後」の年度に追納する場合です。「3年以上経過後」がポイントです。
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
例えば、平成30年度に免除月がある場合、免除月の属する年度の4月1日(平成30年4月1日)から3年以上経過後(令和3年4月1日)の年度(令和3年度)に追納する場合は、追納加算率を乗じた額が保険料に加算されます。
②【H18年出題】 〇
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 |
・免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内なら加算されません
→ 例えば、平成30年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(令和2年度以内)なら、加算されません。
・免除の月が3月のときは、翌々年の4月中ならば加算されません。
→ 例えば、平成31年3月に免除を受けた場合は、翌々年の4月(令和3年4月)中なら加算されません。
③【H28年出題】 ×
免除を受けた月が平成25年3月の場合は、翌々年の4月(平成27年4月)以内なら、加算は行われません。平成28年4月が誤りです。
H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 |
H24年度に免除月がある場合は、翌々年度以内(H26年度以内)に追納するなら加算されません。H27年度以降に追納する場合は、経過年数に応じて加算されます。
例外的に、平成25年3月が免除月の場合は、平成27年4月に追納する場合は、加算は行われません。平成25年3月の保険料の納期限(平成25年4月)から2年以内だからです。
※平成25年3月は「平成24年度」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-204
R4.3.14 追納その3 追納と保険料納付済期間
追納を行うと、保険料免除期間は「保険料納付済期間」になります。
条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ④ 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 |
追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされるのは、「追納が行われた日」です。
追納した場合、保険料免除期間は、追納が行われた日に「保険料納付済期間」になります。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料全額免除期間を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-203
R4.3.13 追納その2 追納の順序
「学生納付特例」、「納付猶予」の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には入りますが、額の計算には入りません。
そのため、追納の順序では、原則として「学生納付特例」、「納付猶予」が優先されます。
では、追納の順序を条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ② その一部につき追納をするときは、追納は、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第89条第1項若しくは第90条第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。 ただし、学生納付特例又は納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第89条第1項若しくは第90第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。 |
追納の順序
・「先に経過した月の分から(古い方から)」、順次行うのが原則です
・「学生納付特例(納付猶予)」期間がある場合
学生納付特例期間、納付猶予期間は老齢基礎年金の額の計算に入らないので、「学生納付特例期間」「納付猶予期間」を優先して追納を行います。
それ以外の期間は、先に経過した月の分から順次行います。
例えば、次のような場合は、①学生納付特例 → ②半額免除 → ③全額免除の順番で追納を行います。
古 → → → → → → → → → → →新 | ||
半額免除 | 全額免除 | 学生納付特例 |
ただし、学生納付特例より古い他の免除期間を優先できる例外も設けられています。
学生納付特例を先に追納しなければならないがために、他の免除期間が10年の追納期間に間に合わないことが出てくるためです。
そのため、学生納付特例期間より古い他の免除期間がある場合は、どちらを優先するか本人が選択することもできるようになっています。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】 ※改正による修正あり
納付することを要しないものとされた保険料の一部について納付する場合は、原則として、全額免除期間又は一部免除期間、次いで学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の順に、それぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている。
②【R1年出題】
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
原則として、学生等の納付特例期間又は納付猶予期間が優先で、次いで、全額免除期間又は一部免除期間のそれぞれ古い分から順次行うこととされています。
②【R1年出題】 ×
平成27年6月分から 平成28年3月分 | 平成28年4月分から 平成29年3月分 | 平成29年4月分から 令和元年6月分 |
保険料全額免除期間 | 学生納付特例の期間 | 保険料全額免除期間 |
学生納付特例の期間の保険料から優先的に追納するのが原則です。
しかし、学生納付特例より古い保険料全額免除期間を先に追納する選択も可能です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民年金法
国民年金法
R4-202
R4.3.12 国年・追納その1 追納の要件
国民年金の保険料の免除を受けた場合、後から保険料を追納することができます。
追納の要件を条文で確認しましょう。
第94条 (保険料の追納) ① 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。 ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 |
 ポイント!
ポイント!
・老齢基礎年金の受給権者は追納できません。
・追納できるのは、承認の日の属する月前10年以内です
・一部免除を受けた場合は、残りの納付すべき保険料が納付されていること
→ 例えば、4分の3 免除については、残りの4分の1が納付されていないと追納できません。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
②【H29年出題】
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
③【R2年出題】
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
障害基礎年金の受給権を有していても、追納はできます。
障害基礎年金は受給権があっても、障害の程度が軽くなると支給停止になる可能性があるからです。追納によって将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。
なお、遺族基礎年金の受給権者も追納が可能です。遺族基礎年金も失権することがあるからです。
②【H29年出題】 〇
4分の3免除を受けても残りの4分の1を納付していなければ、未納期間になるので、追納はできません。
③【R2年出題】 〇
H18年7月 | ・・・ | H22年 4月 | ・・・ | H28年 3月 | ・・・ | R2年 3月 | R2年 4月 |
全 額 免 除 期 間 |
| ||||||
| 追納可能 |
| 追納 承認 | ||||
平成18年7月から平成28年3月 → 全額免除期間
追納の承認の日の属する月 → 令和2年4月
追納ができるのは「承認の日の属する月前10年以内の期間に係るもの」に限られますので、平成22年4月から平成28年3月までとなります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-201
R4.3.11 出産手当金その2 報酬との調整・傷病手当金との調整
報酬と出産手当金との調整のルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第108条 (出産手当金と報酬との調整) ② 出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
報酬を受けることができる場合 → 出産手当金は支給されません
ただし、報酬の額が、出産手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
出産手当金について、出産した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
②【H27年出題】
被保険者が介護休業期間中に出産手当金の支給を受ける場合、その期間内に事業主から介護休業手当で報酬と認められるものが支給されているときは、その額が本来の報酬と出産手当金との差額より少なくとも、出産手当金の支給額について介護休業手当との調整が行われる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
報酬が出産手当金より少ないときは、差額が支給されます。
②【H27年出題】 〇
介護休業期間中でも、要件に該当する場合は、傷病手当金又は出産手当金が支給されます。
傷病手当金又は出産手当金が支給される場合で、同じ期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、傷病手当金又は出産手当金の支給額について調整が図られます。
(平成11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)
次に、出産手当金と傷病手当金の支給調整を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第103条 (出産手当金と傷病手当金との調整) ① 出産手当金を支給する場合(第108条第3項又は第4項に該当するときを除く。)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。 ただし、その受けることができる出産手当金の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 ② 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。 |
出産手当金と傷病手当金の両方が支給される場合は、出産手当金が優先され、その期間は傷病手当金は支給されません。
ただし、出産手当金の額が、傷病手当金より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
では、過去問をどうぞ!
③【H24年出題】
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、傷病手当金の支給が優先され、その期間中は出産手当金の支給は停止される。
④【H30年出題】
出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合、いずれかを選択して受給することができる。

【解答】
③【H24年出題】 ×
出産手当金が優先されます。
傷病手当金の受給中に出産手当金が支払われるときは、出産手当金の支給が優先され、その期間中は傷病手当金の支給は停止されます。
④【H30年出題】 ×
③の問題と同じです。選択制ではなく、出産手当金が優先されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 健康保険法
健康保険法
R4-200
R4.3.10 出産手当金その1 支給要件
被保険者が出産した場合、産前産後の休業中は健康保険から出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給要件を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第102条 (出産手当金) 被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 |
出産手当金が支給されるのは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日です。
 「出産日当日」は産前?産後?
「出産日当日」は産前?産後?
条文の「出産の日以前42日」と「出産の日後56日」に注目してください。42日には「出産の日」を含み、56日は出産の日の翌日からとなります。出産当日は「産前」に入ります。
 「出産予定日」より出産が遅れた場合は?
「出産予定日」より出産が遅れた場合は?
産前休業は、出産予定日6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得できます。
条文の『出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日』の部分に注目してください。
出産が予定日よりも遅れた場合は、出産予定日以前42日から出産日後56日が支給期間となるので、遅れた日数分も出産手当金が支給されます。
予定日以前42日 | 遅れた日数分 | 出産の日後56日間 | |||||||
|
| 予定日 |
|
| 出産日 |
|
|
|
|
 「任意継続被保険者」には支給される?
「任意継続被保険者」には支給される?
任意継続被保険者には出産手当金は支給されません。
なお、同様に、特例退職被保険者にも出産手当金は支給されません。(附則第3条)
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)< A >(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日< B >までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。」と規定している。
②【R2年出題】
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、その差額が出産手当金として支給される。
③【H18年出題】
被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。

【解答】
①【H30年選択式】
A 以前42日
B 後56日
「前」ではなく「以前」、「以後」ではなく「後」なのがポイントです。
出産日当日は、「産前」に含まれることに注意してください。
②【R2年出題】 ×
出産手当金が支給されるのは、「労務に服さなかった期間」です。
問題文の「通常の労務に服している期間」があった場合は、その間は出産手当金は支給されません。
③【H18年出題】 〇
予定日より遅れた日数分も支給されます。
問題文のように予定日より5日遅れて出産した場合、支給期間は、産前は42日+5日、産後は出産の翌日から56日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 徴収法
徴収法
R4-199
R4.3.9 概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定
労働保険料の申告書を納期限までに提出しないとき、申告書の記載に誤りがあるときは、認定決定が行われます。
「概算」で申告納付する概算保険料と「実績」で申告納付する確定保険料では、同じ認定決定でもルールに違いがあります。
条文を読んでみましょう。
第15条第3項(概算保険料) 政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。
第19条第4項(確定保険料) 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 |
政府が職権で、事業主が納付しなければならない労働保険料の額を決定し、通知することを認定決定といいます。
「申告書を提出しないとき」、「申告書の記載に誤りがあるとき」に行われます。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。
②【H25年出題】(雇用保険)
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用保険) ×
概算保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」ではなく「納付書」によって行われます。
②【H25年出題】(雇用保険) 〇
確定保険料の認定決定の通知は、「納入告知書」によって行われます。
★ 労働保険料の納付は、「納入告知書」に係るものを除き「納付書」によって行わなければならないとされていますので、原則は「納付書」によって行われます。
「納入告知書」によるものは限られていますので、納入告知書によるものの方を覚えておきましょう。
■■納入告知書によるもの■■
「確定保険料の認定決定と追徴金」、「有期事業のメリット制の差額徴収」、「印紙保険料の認定決定と追徴金」、「特例納付保険料」
(則第38条第5項)
また、確定保険料の認定決定が行われた場合は、「追徴金」が徴収されます。
条文を読んでみましょう。
第21条 (追徴金) ① 政府は、事業主が認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。 ② 納付すべき確定保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。 |
追徴金は懲罰的な金銭です。認定決定に係る確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、追徴金が徴収されます。また、追徴金は「納入告知書」で納付します。
一方、概算保険料は概算的に前払いする保険料ですので、認定決定に係る概算保険料には、追徴金は賦課されません。
では、過去問をどうぞ!
③【H26年出題】(雇用保険)
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
③【H26年出題】(雇用保険) ×
概算保険料の認定決定には、追徴金は徴収されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 雇用保険法
雇用保険法
R4-198
R4.3.8 【雇用】不正受給に対する返還命令
例えば、不正な行為で基本手当の支給を受けた場合は、その金額は全て返還しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
第10条の4 (返還命令等) ① 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
② ①の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策総合推進法に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者(厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、①の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。 |
①は不正受給を行った者に対する処分です。
不正受給した金額は返還しなければならず、また、不正に受給した額の最大2倍の額の納付が命じられます。
例えば20万円を不正に受給し、2倍の40万円の納付が命ぜられた場合は、60万円を納付することになります。三倍返しとなります。
②は、例えば、事業主が虚偽の申請書等を提出したことによって、不正受給が行われた場合は、事業主も連帯して返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ぜられることがあります。
過去問をどうぞ!
①【H26年選択】
雇用保険法第10条の4第1項は、「偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の< A >以下の金額を納付することを命ずることができる。」と規定している。
②【H27年出題】
指定教育訓練実施者が偽りの届出をしたために、教育訓練給付が不当に支給された場合、政府は、当該教育訓練実施者に対し、当該教育訓練給付の支給を受けた者と連帯して同給付の返還をするよう命ずることができる。

【解答】
①【H26年選択】
A 額の2倍に相当する額
②【H27年出題】 〇
指定教育訓練実施者が不正受給に加担している場合は、教育訓練実施者も連帯して、返還をするよう命ぜられることがあります。
※指定教育訓練実施者とは、教育訓練給付制度の対象になる厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいいます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-197
R4.3.7 【労災】不正受給者からの費用徴収
不正行為で労災の保険給付を受けた場合、保険給付に要した費用の全部又は一部が回収されます。
条文を読んでみましょう。
第12条の3 (不正受給者からの費用徴収) ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 ② ①の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
政府は、不正受給者から、保険給付に要した費用の全部又は一部を回収することができます。
また、不正受給に事業主が加担している場合は、政府は、事業主にも連帯して、保険給付に要した費用の全部または一部の納付を命ずることができます。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
②【R2年出題】
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③【H22年出題】
偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
回収の対象になるのは、「不当利得」した部分に限られるのがポイントです。
「保険給付」に要した費用に相当する金額の全部又は一部に注目してください。「不当利得分」の全部又は一部ではありません。
保険給付の全部を不正受給した場合は全部が徴収の対象になりますし、保険給付の一部を不正受給した場合はその不当利得部分は全て徴収の対象になります。
(昭40.7.31基発906号)
②【R2年出題】 〇
事業主にも連帯して責任を負わせるための規定です。
③【H22年出題】 ×
政府は、不正受給者から、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができ、また、事業主が虚偽の報告又は証明をし、不正受給に加担している場合は、事業主に対して不正受給者と連帯して納付を命ずることができます。
「保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働安全衛生法
労働安全衛生法
R4-196
R4.3.6 安全管理者・衛生管理者の専属要件
安全管理者、衛生管理者は、事業場に専属の者から選任しなければなりません。
しかし、例外もあります。
条文を読んでみましょう。
則第4条 (安全管理者の選任) その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、その労働安全コンサルタントのうち1人については、この限りでない。
則第7条 (衛生管理者の選任) その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、その労働衛生コンサルタントのうち1人については、この限りでない。 |
安全管理者はその事業場に専属の者から選任するのが原則です。
ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントがいる場合は、労働安全コンサルタントのうちの1人は、専属でなくてもいいことになっています。
※衛生管理者も同じです。
ちなみに、「労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント」は、労働安全・労働衛生のスペシャリストです。事業場の診断・指導を行い、安全衛生水準を向上させるための国家資格です。
では、過去問をどうぞ
①【H12年出題】
複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。
②【H15年出題】
事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの1人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。
【解答】
①【H12年出題】 〇
例えば、3人の衛生管理者を選任し、3人の衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントが1人います。労働衛生コンサルタントのうち1人は、専属でなくても差し支えないので、問題文の労働衛生コンサルタントは専属でなくてもよいことになります。
| 衛生管理者 1 | 衛生管理者 2 | 衛生管理者 3 |
 |  |
(コンサルタント) |
| 専属 | 専属 | 外部 可 |
②【H15年出題】 ×
外部の労働安全コンサルタントを選任できるのは、2人以上の安全管理者を選任する場合で、その中に労働安全コンサルタントがいる場合です。労働安全コンサルタントのうち1人は、外部の労働安全コンサルタントから選任することができます。
| 安全管理者 1 | 安全管理者 2 | 安全管理者 3 | 安全管理者 4 |
 |  |
(コンサルタント) |
(コンサルタント) |
| 専属 | 専属 | 専属 | 外部 可 |
問題文の場合、「1人を除いて」ではなく、「そのうち1人については」、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない、となります。外部の労働安全コンサルタントで差し支えないのは1人です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-195
R4.3.5 1年変形/途中退職、途中入社の者の賃金清算
1年単位の変形労働時間制は、対象期間の途中に採用された人、途中で退職した人も対象になります。
実際に労働した期間が、対象期間よりも短い場合、賃金の清算が必要になることがあります。
条文を読んでみましょう。
第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条(災害等による臨時の場合)又は第36条第1項(三六協定)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 |
例えば、1年単位の変形労働時間制の対象期間を1月1日から12月31日までの1年間で設定している場合で考えてみましょう。
対象期間中の労働時間の総枠は、40時間×365日÷7≒2085.71時間です。
総枠の範囲内でこのように所定労働時間を設定したとします。
↓
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
170時間 | 147時間 | 180時間 | 166時間 | 180時間 | 166時間 | 180時間 | 180時間 | 166時間 | 180時間 | 180時間 | 190時間 |
この場合、年間の所定労働時間のトータルは2085時間で、1年間を平均すると1週間の労働時間が40時間以内になります。
☆条文に当てはめてみると
『対象期間より短い労働者』
例えば、Aさんが対象期間の途中の6月1日に入社したような場合です。Aさんが実際に労働した期間は6月1日~12月31日までで対象期間より短い期間です。
『労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた』
Aさんが所定労働時間分だけ労働した場合、6月1日から12月31日までの実際の労働時間のトータルは1,242時間となります。
次に、6月1日から12月31日までの期間を平均して1週間当たり40時間以内になる労働時間の総枠は、40時間×214日÷7≒1222.8時間で計算できます。
実労働時間の1,242時間から1222.8時間を引くと19.2時間になりますが、この19.2時間が『労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた』部分に当たります。
『第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない』
平均して1週間当たり40時間の枠を超えた19.2時間は、第37条の規定の例により割増賃金で清算することになります。
『(第33条(災害等による臨時の場合)又は第36条第1項(三六協定)の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)』
例えば、36協定に基づいて時間外労働させた場合は、清算による割増賃金ではなく、本来の割増賃金の支払いが必要です。
過去問をどうぞ!
【H17年出題】
労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、同法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合には、同法第24条違反となる。

【解答】
【H17年出題】 〇
第37条違反ではなく、「第24条違反」になるのがポイントです。
最初に読んだ条文の「第37条の規定の例により」の部分に注目してください。
第37条は割増賃金の規定ですが、「第37条の規定の例により」とは、算定基礎賃金の範囲、割増率、計算方法等がすべて第37条と同じという意味です。
第37条の割増賃金ではないのがポイントです。そのため、清算のための割増賃金を支払わない場合は、第37条違反ではなく、第24条違反になります。
(平11.1.29基発45号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-194
R4.3.4 1年変形/連続して労働させる日数の限度
前回のテーマは、1年単位の変形労働時間制の対象期間の労働日数の限度、1日・1週間の労働時間の限度でした。
今回は連続して労働させる日数の限度についてお話します。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の4 1年単位の変形労働時間制 ③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 |
今回は、「連続して労働させる日数の限度」に注目します。
特定期間とそれ以外で設定が変わりますので注意してください。
☆ちなみに、「特定期間」とは?
特定期間とは、「対象期間中の特に業務が繁忙な期間」をいい、特定期間を設定する場合は、労使協定で定めます。
(特定期間 → 労基法第32条の4 第1項 第3号)
連続して労働させる日数の限度は、施行規則第12条の4で以下のように規定されています。
第12条の4 ⑤ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は6日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は1週間に1日の休日が確保できる日数とする。 |
1年単位の変形労働時間の場合、連続労働日数は原則として最長6日です。
しかし、特に業務が繁忙な期間として「特定期間」を定めた場合は、その期間は「1週間に1日の休日が確保できる日数」=最長12日とすることができます。
(原則) 連続労働日数は最長6日まで
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
☆6日に1回は休日が必要です
(特定期間) 1週間に1日の休日が確保できる日数=連続労働日数は最長12日まで
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 |
1週目は日曜が休日、2週目は土曜が休日で、1週間に1日の休日が確保できています。特定期間は、連続労働日数は最長12日まで可能です。
では、穴埋め式でポイントを確認しましょう
則第12条の4
⑤ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は< A >日とし、同条第1項の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は< B >が確保できる日数とする。

【解答】
A 6
B 1週間に1日の休日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-193
R4.3.3 1年変形/対象期間における労働日数の限度、1日及び1週間の労働時間の限度
1年単位の変形労働時間制の対象期間は、最長で1年間設定することができます。
対象期間が長いと、労働者の負担も増えますので、労働日数の限度、1日・1週間の労働時間の限度、連続して労働させる日数の限度が定められています。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の4 (1年単位の変形労働時間制) ③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 |
今回は、対象期間における「労働日数の限度」、「1日及び1週間の労働時間の限度」をお話しします。
まず、「労働日数の限度」については、則第12条の4第3項に、次のように定められています。
則第12条の4第3項 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、対象期間が3か月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。(以下省略) |
例えば対象期間を1年間とした場合は、1年間の労働日数の上限は280日です。
1年あたりの上限が280日ですので、例えば対象期間が6か月(暦日数は183日とする)だとすると、労働日数の上限は、280日×183日÷365日で計算します。答えは140.38日ですが、小数点以下は切り捨てますので労働日数の上限は140日になります。
では、穴埋め式でポイントを確認しましょう。
いわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合、対象期間における労働日数には限度が設けられている。労働日数の限度は、対象期間が < A >を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。

【解答】
A 3か月
労働日数の限度が適用されるのは、対象期間が3か月を超える場合に限られます。
対象期間が3か月以内の場合は、労働日数の制限はありません。
次は、「1日及び1週間の労働時間の限度」についてです。条文を読んでみましょう。
則第12条の4 ④ 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。(以下省略) |
1年単位の変形労働時間制を採用する場合、1日、1週間の労働時間には上限が設けられています。1日は10時間以内、1週間は52時間以内です。
※対象期間が3か月を超える場合は、更に条件がありますが、今回はその説明は省略します。
※また、「積雪地域の建設業の屋外労働者等」、「隔日勤務のタクシー運転者」については、労働時間の上限に暫定措置が設けられていますが、今回はその説明は省略します。
では、過去問をどうぞ!
【H30年出題】
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

【解答】
【H30年出題】 ×
1日の労働時間の限度は10時間ですが、1週間の労働時間の限度は54時間ではなく「52時間」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-192
R4.3.2 1年変形/対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間
1年単位の変形労働時間制を導入する際の「労使協定」には、対象期間の「労働日と労働日ごとの労働時間」を定めなければなりません。
では、条文を読んでみましょう。
第32条の4 (1年単位の変形労働時間制) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。) 3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。) 4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 5 その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定め) |
今回は、第4号の「対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間」の部分に注目します。
1年単位の変形労働時間制は、対象期間を平均して1週間40時間を超えないことが条件です。前回は、そのための所定労働時間の総枠の計算についてお話ししました。
そして、その総枠の範囲内で、対象期間内の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を設定する必要があります。
例えば、対象期間を1年としたならば、1年間全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を労使協定締結時に特定しておかなければなりません。
しかし、全体の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」をあらかじめ特定できない場合の例外が()内の部分です。
( )内の内容
☆対象期間を1か月以上の期間ごとに区分する
・「最初の期間(対象期間の初日の属する期間)」
→ 「労働日」と「労働日ごとの労働時間」を特定する
・「最初の期間を除く各期間」
→ 「労働日数」と「総労働時間」を定める
例えば、対象期間が4月1日から1年間だとすると、対象期間を1か月ごとに区分することにより、労使協定締結時は以下のような定めが可能です。
①最初の期間 | ② | ③ | ④ | ・・・ |
4月1日~ 4月30日 | 5月1日~ 5月31日 | 6月1日~ 6月30日 | 7月1日~ 7月31日 | ・・・ |
・労働日 ・労働日ごとの 労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・労働日数 ・総労働時間 | ・・・
|
②以降の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」は後から特定しなければなりませんが、その際の手続きは以下の通りです。
条文を読んでみましょう。
第32条の4、則12条の4 ② 使用者は、労使協定で区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより(書面により)、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 |
☆最初の期間を除く各期間の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」の特定は、
・各期間の初日の少なくとも30日前
・過半数で組織する労働組合か労働者の過半数代表者の同意を得て
・書面により
行うことになります。
例えば、上の図でしたら、②の期間は「3月31日までに」、③の期間は「5月1日までに」、労働日と労働日ごとの労働時間を特定する必要があります。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制においては、1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定められているため、この範囲において労働する限り、どのような場合においても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要はない。
②【H18年出題】
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合おいて、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

【解答】
①【H22年出題】 ×
1年単位の変形労働時間制については、原則として、対象期間中の労働日と各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定する必要があります。
②【H18年出題】 ×
「個々の対象労働者」ではなく、「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者」の同意を得て定めます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働基準法
労働基準法
R4-191
R4.3.1 1年変形/労働時間の総枠について
1年単位の変形労働時間制を導入する場合の労働時間の総枠のルールについてお話しします。
条文を読んでみましょう。
第32条の4 (1年単位の変形労働時間制) 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。 1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。) 3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。) 4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 5 その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定め) |
今回は、「対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内」の部分に注目します。
労働時間の総枠の考え方です。
対象期間を平均して1週間当たりの労働時間を40時間とするための規定です。
対象期間中の労働時間が、40時間×対象期間の暦日数÷7の範囲内に収まれば、平均すると1週間当たり40時間となります。
例えば、対象期間を1年(365日)とした場合は、
40時間×365÷7≒2085.71時間です。1年間の所定労働時間の総枠は2085.71時間となります。1年間の所定労働時間のトータルを2085.71時間以内に設定すれば、平均すると1週間当たりの労働時間が40時間以内になります。
なお、1か月単位の変形労働時間制は、第32条の2で「1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が32条第1項の労働時間(法定労働時間)を超えない」ことと規定されています。
「40時間」ではなく「法定労働時間」となっているのがポイント。総枠の計算式は、40時間(特例事業場は44時間)×変形期間の暦日数÷7となります。
1年単位には「44時間」の特例が適用されないので、対象期間の労働時間の総枠は「40時間」を使って計算します。一方、1か月単位には「44時間」の特例が適用されますので、労働時間の総枠は40時間又は44時間で計算します。違いに注意してください。
では、過去問をどうぞ!
【H28年出題】
労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。

【解答】
【H28年出題】 〇
対象期間は、「その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限るものとする。」と定義されていますので、3か月や6か月でもよいです。
なお、労働時間の総枠は
6か月(例えば183日)の場合は、40時間×183日÷7≒1,045.71時間
3か月(例えば92日)の場合は、40時間×92日÷7≒525.71時間
となります。
次回も1年単位の変形労働時間制です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法
国民健康保険法
R4-190
R4.2.28 被保険者資格証明書と特別療養費
前回からの続きです。
国民健康保険料を1年間滞納すると、被保険者証の返還が求められ代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
その場合、医療機関の窓口では医療費を全額支払い、後から自己負担以外の分が現金で返ってきます。これを「特別療養費」といいます。
では、条文を読んでみましょう。
第9条 ⑥ 世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。 |
滞納により被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書」が交付されます。
ただし、18歳の年度末までの者(高校生以下)には、有効期間6か月の短期被保険者証が交付されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯の属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」にある者には、有効期間を6か月とする被保険者証が交付されます。
被保険者資格証明書が交付されているときは、療養の給付等の現物給付は受けられません。しかし、高校生以下には6か月間有効の被保険者証が交付され、現物給付が受けられます。
次は「特別療養費」の条文を読んでみましょう。
第54条の3 (特別療養費) ① 市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。 |
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、「特別療養費」が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
②【R1年出題】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、「特別療養費」が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法
国民健康保険法
R4-189
R4.2.27 国民健康保険料を滞納した場合
国民健康保険の保険料の滞納については、滞納の期間で扱いが変わります。
条文を読んでみましょう。
第9条 ③ 市町村は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 ※ 国民健康保険組合にも準用されます。
第63条2 ① 市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6か月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 ③ 市町村及び組合は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。 |
★ 滞納が「1年間」になると被保険者証の返還が求められ、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。(被保険者資格証明書については次回お話します。)
また、滞納が1年6カ月になると、保険給付の全部又は一部が差し止められます。
保険給付を差し止められていても、さらに滞納している場合は、差し止め中の保険給付から滞納保険料に充当されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。
②【R2年出題】
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

【解答】
①【H28年選択式】
A 1年間
B 被保険者資格証明書
「被保険者資格証明書」が交付されると、現物給付が受けられなくなるので、医療機関では医療費を一旦全額支払うことになります。
(法第9条第3項、6項)
②【R2年出題】 〇
滞納が1年6カ月になると保険給付の全部又は一部が差し止められ、さらに滞納すると、差し止められている保険給付から、滞納保険料に充当されます。
(法第63条の2)
★次回に続きます
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働施策総合推進法
労働施策総合推進法
R4-188
R4.2.26 募集・採用の年齢制限の禁止
募集、採用時の年齢制限は、原則として禁止されています。
条文を読んでみましょう。
第9条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。 |
厚生労働省令(則第1条の3)では、年齢制限が認められる例外が規定されています。
例えば、定年制の定めをしている会社で、定年の年齢を下回ることを条件として、募集、採用を行うことは認められています。ただし、「期間の定めのない労働契約」を締結することを目的とする場合に限られます。
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。

【解答】
【H26年出題】 ×
労働施策総合推進法で年齢制限が原則として禁止されているのは、「募集、採用」です。昇進または職種の変更については、特に規制されていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-187
R4.2.25 遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額が加算されるとき
例えば、海外に居住している1級の障害厚生年金を受給中の夫(35歳)、妻(35歳)、子(10歳)の家族で、夫が死亡した場合を考えてみます。
夫は国内では第1号被保険者でしたが、日本国内に住所を有しなくなったため、国民年金の被保険者の資格を喪失しています。なお、任意加入もしていません。
夫の死亡により、遺族厚生年金と遺族基礎年金は支給されるでしょうか?
・遺族厚生年金は?
→ 「障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき」に該当しますので、要件を満たせば妻と子に受給権が発生します。
・では、遺族基礎年金は?
→ 遺族基礎年金は次の4つのどれかに該当することが条件です。
(国民年金法第37条)
① 被保険者が、死亡したとき。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。
③ 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
④ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
死亡した夫は4つのどれにも該当しませんので、遺族基礎年金は支給されません。
このように、遺族厚生年金は支給されても、妻と子が生計を同じくしているのに、遺族基礎年金が支給されないケースがあります。
そこで、遺族厚生年金に遺族基礎年金相当額が加算される規定があります。
条文で確認しましょう。
昭和60年附則第74条 ① 配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第59条第1項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であって、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第60条第1項第1号及び第62条第1項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条第1項(子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。 |
★ この規定により、先ほどのケースの妻の遺族厚生年金には、遺族基礎年金の額と子の加算額に相当する額が加算されます。
では、過去問をどうぞ
①【H29年出題】(改正による修正あり)
国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が25年未満であった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。
②【H18年出題】
遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。

【解答】
①【H29年出題】(改正による修正あり) 〇
最初に説明したのは、妻と子の例でしたが、この問題のように遺族が「子」のみの場合でも、遺族厚生年金に遺族基礎年金の額に相当する額が加算されます。
昭和60年附則第74条第2項に次のように規定されています。
| 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第60条第1項第1号及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条の2第1項(子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。 |
(昭和60年附則第74条第2項)
②【H18年出題】 〇
①の問題と同じです。
(昭和60年附則第74条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-186
R4.2.24 子が出生したときの父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の失権
例えば、被保険者等の死亡の当時、配偶者も子もなくて、父がいる場合は、父が遺族厚生年金の受給権者になります。
しかし、死亡当時胎児であった子が出生した場合は、子が先順位になりますので父の受給権は消滅します。
では、条文を読んでみましょう。
第63条 ③ 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。 |
★ 胎児であった子の出生で受給権が消滅するのは、子より後順位の父母、孫、祖父母です。
では、過去問です!
①【H24年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。
②【R2年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は消滅する。一方、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときでも、妻の有する遺族厚生年金の受給権は消滅しない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
配偶者と子は、同じ順位ですので、胎児であった子が出生しても、妻の受給権は消滅しません。
②【R2年出題】 〇
①の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-185
R4.2.23 遺族厚生年金・所在不明の場合の支給停止
今回は、1年以上所在不明の場合の支給停止です。
ポイントは、支給停止のスタートと解除のタイミングです。
では、条文を読んでみましょう。
第67条 ① 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② 配偶者又は子は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。 |
★ 支給停止は、所在が明らかでなくなったときにさかのぼるのがポイントです。申請したときからではありません。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
配偶者に対する遺族厚生年金は、その配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子の申請によって、申請の日からその支給を停止する。
②【R2年出題】
死亡した被保険者の2人の子が遺族厚生年金の受給権者である場合に、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでないときは、他の受給権者の申請によってその所在が明らかでなくなった時にさかのぼってその支給が停止されるが、支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「申請の日から」ではなく、「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給を停止されます。
配偶者と子が受給権者になった場合、配偶者に遺族厚生年金を支給し、子の遺族厚生年金は支給停止になるのが原則です。しかし、配偶者が所在不明で配偶者の遺族厚生年金の支給が停止されると、子の支給停止が解除されます。
(法第66条第1項、第67条)
②【R2年出題】 〇
所在が1年以上明らかでないとき
☆「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」支給が停止されます。
所在不明になった日が属する月の翌月から支給停止されます。
☆支給停止された者はいつでもその支給停止の解除を申請することができます。
支給停止が解除されるのは、「支給停止の解除の申請をした日」が属する月の翌月からです。所在が明らかになった日ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-184
R4.2.22 遺族厚生年金・配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しないとき
遺族厚生年金の受給権は配偶者と子の両方に発生、しかし遺族基礎年金の受給権は子のみに発生する場合があります。
その場合の調整が今日のテーマです。
では、条文を読んでみましょう。
第66条 ② 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条(1年以上の所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
☆この条文のシチュエーション
夫Aと妻Bの夫婦に子Cがいた。 しかし夫婦は離婚し、子Cは妻Bと生計を同じくし、夫Aは、Cの養育費を送金している。 その後、夫Aは、Dと再婚し、現在は、夫Aと妻Dが夫婦となっている。 |
そして厚生年金保険の被保険者である夫Aが死亡した場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権はどうなるでしょうか?
・ 子Cについて → 死亡した被保険者(A)と生計維持関係が認められると、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給権が発生する
・ 元妻Bについて → 死亡したAとは夫婦ではないので、遺族年金の受給権は発生しない
・ 妻Dについて → 「遺族厚生年金」の受給権が発生する。しかし、死亡したA
の子(C)と生計を同じくしていないので遺族基礎年金の受給権は発生しない
条文に当てはめると、『配偶者(妻D)に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者(夫A)の死亡について、配偶者(妻D)が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子(C)が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する』となります。
配偶者(妻D)の遺族厚生年金は支給停止されます。
では、過去問をどうぞ!
【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、妻の遺族厚生年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって、子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止される。
※遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権者の所在が明らかでない場合を考慮する必要はない。

【解答】
【H26年出題】 〇
冒頭のシチュエーションに当てはめて問題文を読んでみてください。
妻の遺族厚生年金は支給停止され、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
(法第66条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-183
R4.2.21 遺族厚生年金・配偶者と子の支給調整
遺族厚生年金の支給順位では、配偶者と子は同順位です。配偶者と子が両方受給権者になったときの調整方法が今日のテーマです。
では、条文を見てみましょう。
第66条 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 |
配偶者と子が受給権者になった場合、配偶者に遺族厚生年金を支給し、子の遺族厚生年金は支給停止になるのが原則です。
例外的に、配偶者の遺族厚生年金が第65条の2(夫、父母、祖父母の支給停止)、第66条第2項(配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しないとき)、第67条(所在不明のときの支給停止)の規定で支給停止されている場合は、子に支給されます。
※「第66条第2項(配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しないとき)」は次回お話しします。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
遺族厚生年金の遺族の順位において、配偶者と子は同順位であるが、配偶者が妻(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、妻に遺族厚生年金を支給する間、子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く。以下同じ。)の支給が停止され、配偶者が夫(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る。以下同じ。)の場合には、子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。
②【H26年出題】
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
③【H30年出題】
被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。
④【R3年出題】
遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が、障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。妻は、障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額支給停止となった。妻には生計を同じくする子がいるが、子の遺族基礎年金については、引き続き支給停止となるが、妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから、子の遺族厚生年金は支給停止が解除される。

【解答】
①【H22年出題】 ×
最後の「子に遺族厚生年金を支給する間、夫の支給が停止される。」の部分が誤りです。
妻(遺族基礎年金の受給権を有する)に遺族族厚生年金を支給する間は、子の支給は停止されます。
夫の場合も同じで、夫(遺族基礎年金の受給権を有する)に遺族厚生年金を支給する間は、子の支給が停止されます。
(法第66条)
②【H26年出題】 〇
受給権者はその意思によって、年金の支給停止を申し出ることができます。
問題文のように、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
国民年金法の「遺族基礎年金」との違いに注意してください。遺族基礎年金の場合は、配偶者が申し出ることによって、配偶者の遺族基礎年金が支給停止になっている場合は、子の遺族基礎年金は支給されます。
参考 → R4.2.17 遺族基礎年金の支給停止(その3 子に対する支給停止)
(法第66条)
③【H30年出題】 ×
「子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。」が誤りです。
妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときでも、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されません。
(法第66条)
④【R3年出題】 ×
妻が、「障害基礎年金と障害厚生年金」を選択し、「遺族基礎年金と遺族厚生年金」が全額支給停止になった場合でも、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給停止は解除されず、支給停止のままです。
(法第66条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-182
R4.2.20 遺族厚生年金・夫、父母、祖父母の支給停止
遺族厚生年金の遺族となる「夫、父母、祖父母」は、被保険者等の死亡の当時55歳以上であることが条件です。
しかし、遺族厚生年金の支給が始まるのは60歳からです。
条文を読んでみましょう。
第65条の2 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。 |
「夫、父母、祖父母」は、被保険者等の死亡当時55歳以上であることが条件ですが、60歳までは支給停止されます。
ただし、遺族基礎年金の受給権がある「子のある夫」については、60歳までの間も支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
夫(障害の状態にない)に対する遺族厚生年金は、当該夫が60歳に達するまでの期間、支給停止されるが、夫が妻の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは、支給停止されない。
②【R1年出題】
平成26年4月1日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60歳に到達するまでの間、その支給を停止する。
③【H29年出題】
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】
①【H27年出題】 〇
☆夫のポイント
・妻の死亡当時55歳以上であること
・夫が60歳に達するまでは支給停止
・夫が遺族基礎年金の受給権を有するとき(子があるとき)は、支給停止されません
②【R1年出題】 ×
夫に対する当該遺族厚生年金 → 原則は60歳に達するまでは支給停止ですが、遺族基礎年金の受給権を有する場合は、60歳前でも支給されます。
③【H29年出題】 〇
妻死亡
(夫55歳、子15歳) (子18歳年度末) (夫60歳)
▼ ▼ ▼
遺族厚生年金 | 支給停止 | 支給再開 |
遺族基礎年金 |
| |
▲遺族基礎年金失権
(夫について)
・ 子が18歳の年度末までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できる
・ 子が18歳の年度末が終了したときに遺族基礎年金は失権する
・ その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-181
R4.2.19 遺族厚生年金の遺族の優先順位
前回は、遺族の要件をみましたが、今回はその優先順位です。
では、条文を読んでみましょう。
第59条 ② 父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
③ 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。 |
 最も優先順位が高いのは、「配偶者又は子」です。配偶者と子は同順位です。
最も優先順位が高いのは、「配偶者又は子」です。配偶者と子は同順位です。
そして、「配偶者又は子」がいない場合は「父母」、「配偶者、子又は父母」がいない場合は「孫」、「配偶者、子、父母又は孫」がいない場合は「祖父母」の順番になります。
順位が高い遺族がいる場合は、それ以下の人は遺族厚生年金を受けることができる遺族になりません。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持していた。妻及び子が当該被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得したが、その1年後に妻が死亡した。この場合、母が当該被保険者の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得することはない。
②【H23年出題】
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。
③【R2年出題】
被保険者の死亡当時10歳であった遺族厚生年金の受給権者である被保険者の子が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したことによりその受給権を失った場合において、その被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していたその被保険者の父がいる場合でも、当該父が遺族厚生年金の受給権者となることはない。
④【H27年出題】
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲の適用については、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。

【解答】
①【H29年出題】 〇
生計維持されていたのが「妻、子、母」の場合、最も優先順位の高い「妻と子」に受給権が発生します。
『「父母」は、配偶者又は子が、遺族厚生年金の受給権を取得したときは、遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。』とされていますので、問題文の場合、母は遺族厚生年金の対象の遺族にはなりません。
転給の制度もありませんので、妻が失権しても、母が遺族厚生年金の受給権を取得することはありません。
②【H23年出題】 ×
①の問題と同じです。
妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、母は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。
③【R2年出題】 〇
①、②と同じです。
子が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、父は遺族厚生年金を受けることはできません。子が失権したとしても、転給されることもありません。
④【H27年出題】 〇
「将来に向かって」がポイントです。死亡当時胎児だった子は、出生以降、遺族厚生年金の対象になります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-180
R4.2.18 遺族厚生年金の遺族「配偶者、子、父母、孫、祖父母」の要件
遺族基礎年金の遺族となる「子のある配偶者」又は「子」以外に、遺族厚生年金の遺族には、子のない配偶者、父母、孫、祖父母が入ります。
では、条文を読んでみましょう。
第59条 (遺族) 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
昭和60年法附則第72条第2項 平成8年4月1日前に死亡した「夫、父母、祖父母」については、障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあること。 |
遺族の条件は以下の通りです。
★被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持していたこと
・妻 → 年齢要件、障害要件は問わない
・夫、父母、祖父母
→ 55歳以上であること
(平成8年4月1日前に死亡した場合は、障害等級1級、2級であれば年齢は問わない)
・子、孫
→ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある、又は20歳未満で障害等級1級、2級、かつ、現に婚姻をしていない
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
②【R1年出題】
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
③【R3年出題】
85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。

【解答】
①【R2年出題】 ×
遺族基礎年金の遺族になる配偶者は子があることが条件ですが、遺族厚生年金の遺族の配偶者は、子の有無は問われません。
55歳以上の夫は、子がいない場合でも受給権者になり得ます。
②【R1年出題】 ×
54歳の夫と21歳の子は年齢要件に合いませんので、両方とも遺族にはなりません。
③【R3年出題】 〇
60歳の子は年齢要件に合わないので、遺族になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-179
R4.2.17 遺族基礎年金の支給停止(その3 子に対する支給停止)
今回は、子に対する遺族基礎年金の支給停止です。
では、条文です。
第41条 ② 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 |
 子に支給する遺族基礎年金について
子に支給する遺族基礎年金について
◇配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは支給停止
→遺族基礎年金が配偶者に支給される間は、子の遺族基礎年金は支給が停止されます。
(例外)
・配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項により支給停止されているとき
第20条の2は「受給権者の申出による支給停止」です。
配偶者が申し出ることによって、配偶者の遺族基礎年金が支給停止になっている場合は、子の遺族基礎年金は支給されます。
・第41条の2第1項の規定によりその支給を停止されているとき
第41条の2第1項は、「配偶者が所在不明の場合の支給停止」です。
子の申し出によって配偶者の遺族基礎年金の支給が停止されますが、その間は、子が遺族基礎年金を受給します。
◇生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、支給停止
例えば、夫婦が離婚し、元妻が子と生計を同じくしていた場合で、元夫が死亡した場合。
元夫から定期的に養育費が送金されるなどして生計維持関係が認められた場合、子は遺族基礎年金の受給権を取得します。元妻には遺族基礎年金の受給権は発生しません。
しかし、子が母(元妻)と生計を同じくしている場合は、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
②【H30年出題】
夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。
③【H30年出題】
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される。

【解答】
①【H28年出題】 〇
★原則 → 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、支給停止。
★例外 → 配偶者の遺族基礎年金が「受給権者の申出により支給停止」されたとき → 子に対する遺族基礎年金は支給停止されません。
②【H30年出題】 ×
夫の死亡で妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、第41条第2項の「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する」に該当するので、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
その後、妻が再婚した場合は、第40条第1項第2号「婚姻をしたとき」に該当するので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。なお、子の受給権は消滅しません。
そして、その子がその妻(母)と引き続き生計を同じくしている場合は、第41条第2項の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。」に該当するので、子の遺族基礎年金は支給停止されます。
③【H30年出題】 ×
第2号被保険者である40歳の妻が死亡して、生計維持されていた40歳の夫と子がある場合、40歳の夫には「遺族基礎年金」、子には「遺族基礎年金と遺族厚生年金」の受給権が発生します。
遺族基礎年金については、第42条第2項「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。」に当てはまるので、夫に遺族基礎年金が支給され、子の遺族基礎年金が支給停止になります。
★なお、夫の遺族厚生年金については、受給要件は55歳以上です。妻の死亡当時40歳の夫には遺族厚生年金の受給権は発生しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-178
R4.2.16 遺族基礎年金の支給停止(その2 所在不明の場合)
今回は、所在不明の場合の支給停止です。
では、条文です。
第41条の2 ① 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。 ② 配偶者は、いつでも、①の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第42条 ① 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。 ② ①の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 |
◇ 配偶者が遺族基礎年金の受給権を有している間は、子の遺族基礎年金は支給停止となります。(このことは次回お話しします。)
しかし、配偶者が1年以上所在不明の場合は、子の申請によって配偶者の遺族基礎年金が支給停止されます。
(第41条の2)
◇ 例えば、2人の子が遺族基礎年金を受けていて、1人の子が1年以上所在不明になったときは、他の子が申請を行うと、所在不明になったときにさかのぼって、所在不明の子の年金が支給停止されます。
(第42条)
では、過去問をどうぞ
①【H26年出題】
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
②【H22年出題 】(改正による修正あり)
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
③【H30年出題】
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
④【H15年出題】(改正による修正あり)
1年以上の所在不明によって遺族基礎年金の支給を停止された配偶者又は子は、それぞれ支給停止につき、いつでもその解除の申請をすることができる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
6か月以上ではなく、「1年以上」明らかでないときです。
②【H22年出題 】(改正による修正あり) ×
「申請した日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時に遡って」、支給が停止されます。
③【H30年出題】 ×
②の問題と同じく、いつから支給停止されるかがポイントの問題です。
「申請のあった日の属する月の翌月から」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時に遡って」、支給が停止されます。
④【H15年出題】(改正による修正あり) 〇
所在不明になった人は、いつでも支給停止の解除の申請ができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-177
R4.2.15 遺族基礎年金の支給停止(その1 労基法との調整)
前回までは遺族基礎年金の「失権」についてお話ししました。
今回からは「支給停止」のお話です。
「失権」とは、受給権が消滅することです。例えば、婚姻した場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅します。その後離婚したとしても、受給権は復活しません。
「支給停止」とは、何かの事由で年金がストップすることです。支給停止事由がなくなれば、年金は再開されます。
今回は「支給停止」の1回目です。
では条文をどうぞ。
第41条 (支給停止) 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 |
業務上の事由で死亡し、労働基準法の遺族補償が行われる場合は、遺族基礎年金は6年間支給が停止されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H12年出題】
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働者災害補償保険法の規定による遺族補償が行われるべきであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
②【H20年出題】
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
③【H26年出題】
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。

【解答】
①【H12年出題】 ×
「労働者災害補償保険法の規定による遺族補償」ではなく、「労働基準法の規定による遺族補償」が行われるべきであるときは、遺族基礎年金は、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
 ポイント!
ポイント!
「労働基準法」と「労働者災害補償保険法」の違い
・労働基準法には、「災害補償」の規定があり、労働者の業務上の傷病等については、使用者に補償責任を負わせています。
「労働基準法の規定による遺族補償」は、労働者が業務上死亡した場合に、使用者が補償すべきものです。
・しかし、実際に、使用者が全ての補償を行うのは難しいため、労働基準法の災害補償義務を代行する保険が「労働者災害補償保険法」です。
保険料は、事業主が全額負担し、労働者の業務上の傷病等については、労災保険法から保険給付が行われます。
②【H20年出題】 ×
「労働者災害補償保険法」から「遺族補償年金」が支給されるときは、遺族基礎年金の支給は停止されません。労災保険法の遺族補償年金が減額されます。
 ポイント!
ポイント!
国民年金・厚生年金保険の年金は、業務上外関係なく支給されます。例えば、業務上の死亡の場合は、労災保険の年金も支給されますし、国民年金・厚生年金保険からも年金が支給されます。
「同一の事由」で労災保険の年金と国民年金・厚生年金保険から年金が支給される場合は、調整のため労災保険の年金が減額されます。国民年金・厚生年金保険の年金は支給停止されません。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、国民年金・厚生年金保険は、被保険者本人が保険料を負担しているためです。
(労災保険法別表第1)
③【H26年出題】 〇
②の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-176
R4.2.14 遺族基礎年金の失権(その2 それぞれ特有の事由)
前回は、配偶者、子共通の失権事由がテーマでしたが、今回は、配偶者、子それぞれ特有の失権事由です。
では、条文を見てみましょう。
第40条 ② 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、配偶者、子共通の失権事由の規定によって消滅するほか、子が1人であるときはその子が、子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、加算額の減額改定事由のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ③ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、配偶者、子共通の失権事由の規定によって消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 2 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 3 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 4 20歳に達したとき。 |
②は配偶者特有の失権事由です。
配偶者の遺族基礎年金は子があることが条件で、必ず子の加算額がつきます。
加算事由に該当する子がいなくなった場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
③は子特有の失権事由です。
・18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了
→失権します。
ただし、障害状態にある場合は失権しません。
・障害状態でなくなったとき
→失権します。
ただし、障害状態でなくなっても18歳に達した日以後の最初の3月31日までは、失権しません。
・20歳に達したとき
→失権します。
では、過去問をどうぞ
①【H27年出題】
子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
18歳の年度末に障害の状態にあった場合で、その後、20歳になる前に障害の状態に該当しなくなった場合は、そこで遺族基礎年金の受給権は消滅します。
なお、18歳の年度末に障害の状態にあって、障害の状態のまま20歳になった場合は、20歳に達したときに遺族基礎年金の受給権は消滅します。
では、次の過去問をどうぞ!
②【H19年出題】(改正による修正あり)
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が、直系血族又は直系姻族の養子になったときはこの限りではない。
③【H28年出題】
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【H19年出題】(改正による修正あり) ×
「直系血族又は直系姻族以外の」養子になった場合、遺族基礎年金の受給権は消滅します。しかし、「直系血族又は直系姻族の養子」になった場合は失権しません。
例えば、被保険者である夫が死亡し、妻と子(1人)に遺族基礎年金の受給権が発生し、その子が「直系血族又は直系姻族の養子になった」場合を考えてみます。
子が「直系血族又は直系姻族の養子」になったとしても、子の受給権は消滅しません。
では、妻の受給権はどうでしょうか?
前々回に、「配偶者の遺族基礎年金の減額改定」の条文を読みました。
減額事由の中に、「子が配偶者以外の者の養子となったとき」という規定があったのを思い出してください。「配偶者以外の者」の部分がポイントです。
子から見ると「直系血族又は直系姻族の養子」になっても失権事由にはなりませんが、配偶者から見ると、子が「配偶者以外の者の養子」となるので、減額事由に該当します。
1人だけの子が減額事由である「配偶者以外の者の養子」となった場合は、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
問題文の「加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅する」の部分は正しいですが、「その子が、直系血族又は直系姻族の養子になったときはこの限りではない」の部分が誤りです。子の養子縁組が、直系血族又は直系姻族とだったとしても、配偶者の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
③【H28年出題】 〇
②の解説と同じケースの問題です。
・ 配偶者と1人の子に遺族基礎年金の受給権が発生
↓
・ その子が直系血族又は直系姻族の養子となった
↓
・ 子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない
↓
・ しかし、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-175
R4.2.13 遺族基礎年金の失権(その1 配偶者、子共通の事由)
遺族基礎年金の失権事由を確認しましょう。
まず、「配偶者」と「子」の共通の失権事由からです。
では、条文を見てみましょう。
第40条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき。 3 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)。 2について・・・届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。 3について・・・届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。 |
配偶者が受給する場合、子が受給する場合の共通の失権事由です。
1、2、3のいずれかに該当すれば、遺族基礎年金の受給権は消滅します。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】(改正による修正あり)
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
②【H30年出題】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
③【R1年出題】
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
④【H16年出題】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】
①【H20年出題】(改正による修正あり) 〇
配偶者と子に共通する失権事由は、「死亡」、「婚姻」、「直系血族又は直系姻族以外の養子」の3つです。
②【H30年出題】 〇
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
③【R1年出題】 ×
受給権者である子から見ると、「死亡した被保険者の兄」は叔父にあたり、直系ではなく傍系血族です。「直系血族又は直系姻族以外」の養子になった場合は、遺族基礎年金の受給権は消滅しますので、叔父(傍系血族)の養子になった場合は、遺族基礎年金は失権します。
④【H16年出題】 〇
「夫の父」は直系姻族です。直系姻族との養子縁組ですので、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
 次回、配偶者、子それぞれ特有の失権事由に続きます。
次回、配偶者、子それぞれ特有の失権事由に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-174
R4.2.12 配偶者に支給する遺族基礎年金の増額と減額
前回の続きです。
配偶者に支給する遺族基礎年金には、子の加算額がつきます。
子の数が増減すると遺族基礎年金の額も改定されます。
では、条文を読んでみましょう。
法第39条 ② 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 |
遺族基礎年金が増額されるパターンです。
第37条の2第2項で、『被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。』となっています。「将来に向かって」ですので、生まれたときから遺族の範囲に入ります。
『生まれた日の属する月の翌月』から、遺族基礎年金の額が増額改定されます。
では、次も読んでみましょう。
法第39条 ③ 配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。 1 死亡したとき。 2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 4 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 5 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 6 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 7 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 8 20歳に達したとき。 |
配偶者に対する遺族基礎年金が減額改定されるパターンです。
配偶者の遺族基礎年金には子の数に応じた加算額がつきます。
例えば、子が3人ある場合は、3人分の加算額として「224,700円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率」が加算されています。その後、子のうちの1人が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了し加算の要件に該当しなくなると、加算額は2人分の「224,700円×改定率+224,700円×改定率」に減額改定されます。
条文の「子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が・・・」の部分がポイントです。
配偶者の遺族基礎年金は子があることが条件です。例えば、子が1人のみで、その子が加算の要件に該当しなくなった場合は子がいなくなるので、遺族基礎年金は減額改定ではなく、失権します。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
②【H25年出題】
妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【H29年出題】 ×
遺族基礎年金の対象になる遺族は、被保険者の死亡の当時、被保険者によって生計を維持していたことが条件です。
問題文のように、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった子と養子縁組をしても、遺族の範囲に入る「子」の要件に当てはまらないので、増額改定は行われません。
②【H25年出題】 〇
1人の子と生計を同じくしている妻の遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率+224,700円×改定率です。その子が加算事由に該当しなくなると、生計を同じくしている子がいなくなるので、妻の遺族基礎年金の受給権は消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-173
R4.2.11 遺族基礎年金の額(配偶者と子の違い)
遺族基礎年金は「配偶者」に支給されるパターンと、「子」に支給されるパターンがあります。それぞれの遺族基礎年金の額を確認しましょう。
まず、遺族基礎年金の額を条文で見てみましょう。
第38条 (遺族基礎年金の額) 遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
★遺族基礎年金の基本額は、「780,900円×改定率」です。
では、「配偶者」に支給されるパターンを見てみましょう。
第39条 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円×改定率に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 |
ポイント! 配偶者と子の両方が遺族基礎年金の受給権を取得した場合、遺族基礎年金は配偶者が受けます。
遺族基礎年金を受けることができる配偶者は、「子」と生計を同じくすることが条件です。配偶者が遺族基礎年金を受ける場合は、必ず子の数に応じた加算額がつきます。
第1子、第2子はそれぞれ224,700円×改定率、第3子以降は1人増えるごとに74,900円×改定率が加算されます。
配偶者が受ける遺族基礎年金は、基本額の780,900円×改定率のみということはあり得ず、必ず子の加算額がつくことがポイントです。
次に「子」に支給されるパターンを見てみましょう。
第39条の2 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、780,900円×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち1人については、224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 |
ポイント! 条文の「子が2人以上あるとき」の部分に注目してください。子に支給される遺族基礎年金は、子が2人以上の場合は加算額がつきますが、子が1人の場合は加算額がつかないのがポイントです。
子が1人の場合は780,900円×改定率
子が2人の場合は780,900円×改定率+224,700円×改定率
子が3人の場合は780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率
となります。
個々の受給権者に支給される額は、子の数で除した額になります。
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者である夫が死亡し、その妻に遺族基礎年金が支給される場合、遺族基礎年金には、子の加算額が加算される。
②【H22年出題】
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
③【H28年出題】
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
④【R3年出題】
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
配偶者の遺族基礎年金には必ず子の加算額が加算されます。
②【H22年出題】 ×
受給権者が子2人のときの子に支給する遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率」に「224,700円×改定率」を加算した額です。合計額を2で除して得た額を2人の子それぞれに支給します。
③【H28年出題】 ×
受給権者が子3人のときの子に支給する遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率」+「224,700円×改定率」+「74,900円×改定率」です。その合計額を3で除した額が3人の子それぞれに支給されます。
④【R3年出題】 ×
受給権者が子4人のときの子に支給する遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率」に子の加算として「224,700円×改定率、74,900円×改定率、74,900円×改定率」を合計した金額を子の数の4で除した額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!健康保険法
ここを乗り越えよう!健康保険法
R4-172
R4.2.10 入院時食事療養費
入院の場合、診察や手術などは「療養の給付」として現物給付が行われます。そして入院時の食事についても現物給付が行われます。
今日は、入院時の食事がテーマです。
診察や手術については、療養に要した費用の原則100分の30を一部負担金として本人が負担し、残りが療養の給付として健康保険から現物給付されます。
一部負担金 | 療養の給付 |
食事については、食費の一部を「食事療養標準負担額」として本人が負担し、残りが「入院時食事療養費」として健康保険から現物給付されます。
食事療養標準負担額 | 入院時食事療養費 |
では、「入院時食事療養費」を条文で確認しましょう。
第85条 (入院時食事療養費) 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等である病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。 |
「療養の給付」と併せて受けた食事療養に要した費用の部分がポイントです。入院時食事療養費は療養の給付とセットになります。
また、「特定長期入院被保険者」は、入院時の食事は「入院時生活療養費」として給付が行われますので、入院時食事療養費の対象から除かれています。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ。)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
本当なら、被保険者本人が食事療養に要した費用を病院に支払い、そして入院時食事療養費は、保険者から被保険者に支給すべきものです。
しかし、実際は、入院時食療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度で、被保険者に代わって保険者から病院等に支払う方式をとっています。そして、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされ、結果として現物給付になる、という仕組みです。
(法第85条第5項、第6項)
次に、入院時食事療養費の額を確認しましょう。
第85条 ② 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 ③ 厚生労働大臣は、②の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 |
★入院時食事療養費の計算式は以下の通りです。
入院時食事療養費の額 =
厚生労働大臣が定める食事療養の費用の額* - 食事療養標準負担額
*厚生労働大臣が定める額より実費の方が少ない場合は実費
では、過去問をどうぞ!
②【H23年出題】
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
③【H27年出題】(改正による修正あり)
入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円とされているが、被保険者及び全ての被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき100円とされている。

【解答】
②【H23年出題】 ×
中央社会保険医療協議会が定める基準ではなく、「厚生労働大臣」が定める基準です。
③【H27年出題】(改正による修正あり) 〇
食事療養標準負担額は、平均的な家計の食費の状況、特定介護保険施設等の食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定めることになっています。
食事療養標準負担額は、原則として、1食につき460円です。内容は、食材費相当額プラス調理費相当額です。
しかし、「所得の状況」その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に額が定められていて、問題文のような「住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者」は、1食につき100円となっています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-171
R4.2.9 継続事業・一括有期事業の確定保険料(その2精算)
前回の続きです。
年度終了後に、確定した賃金総額で保険料を算定し、概算で納付した保険料とのプラスマイナスを調整することになります。
今回は、その精算の手続きがテーマです。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R1年出題(労災)】
事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。

【解答】
①【R1年出題(労災)】×
既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一で過不足がないとき=納付すべき労働保険料がない場合の確定保険料申告書は、日本銀行は経由できません。
※納付すべき労働保険料がある場合の確定保険料申告書は、日本銀行を経由することができます。
 次は、納付した概算保険料よりも確定保険料のほうが少ない場合の手続きを条文で確認しましょう。
次は、納付した概算保険料よりも確定保険料のほうが少ない場合の手続きを条文で確認しましょう。
則第36条 (労働保険料の還付) 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料の認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。
則第37条 (労働保険料の充当) 第36条の還付請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、超過額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律の規定により労災保険適用事業主から徴収する一般拠出金をいう。)等に充当するものとする。 |
ポイント!
★既に納付した概算保険料が確定保険料よりも多い場合の超過額について
「還付」か「充当」です。
還付 → 還付請求が必要
充当 → 還付請求がない場合は充当される
では、過去問をどうぞ!
②【R1年出題(労災)】
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
③【H24年出題(雇用)】
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
④【H29年出題(雇用)】
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

【解答】
②【R1年出題(労災)】 ×
提出先が誤りです。
事業主は、超過額の還付を請求できますが、労働保険料還付請求書は、「官署支出官」又は「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出しなければなりません。
(則第36条)
③【H24年出題(雇用)】 〇
超過額の還付請求が行われないときは、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」は、超過額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当します。
(則第37条)
④【H29年出題(雇用)】 ×
超過額を概算保険料等に充当した場合は、「その旨を事業主に通知しなければならない」とされています。(則第37条第2項)「事業主による充当についての承認」は要しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-170
R4.2.8 継続事業・一括有期事業の確定保険料(その1期限)
継続事業・一括有期事業の労働保険料は年度単位(4月1日から翌年3月31日まで)で計算します。
保険料は保険年度の最初に、概算で申告・納付し、保険年度が終了し賃金総額が確定した後でプラスマイナスを精算することになります。
毎年度6月1日から40日以内に、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と今年度の概算保険料の申告・納付を行います。この手続きを「年度更新」といいます。
今日は、年度終了後の確定保険料がテーマです。
では、条文で確認しましょう。
第19条 (確定保険料) ① 事業主は、保険年度ごとに、確定保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に提出しなければならない。 ③ 事業主は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは確定保険料を、申告書に添えて、次の保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から50日以内)に、納付しなければならない。 |
確定保険料申告書は、次の保険年度の6月1日から40日以内に提出しなければなりません。なお、6月1日当日から起算します。納付している概算保険料が確定保険料の額に足りないときは不足額も納付します。
また、保険年度の中途で保険関係が消滅した場合も、労働保険料の精算のため確定保険料の申告・納付が必要です。期限は、保険関係が消滅した日から50日以内です。こちらも保険関係が消滅した日、当日から起算します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題(雇用)】
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
②【R1年出題(労災)】
継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
③【H23年出題(労災)】
有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。
④【H30年出題(雇用)】
確定保険料申告書は、納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①【H26年出題(雇用)】 〇
平成26年6月30日に事業が廃止された場合、その翌日(7月1日)に保険関係が消滅します。
年度の中途に保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。起算日は当日ですので、7月1日から起算して50日の8月19日が期限となります。
②【R1年出題(労災)】 〇
第1種特別加入保険料についても年度の中途で承認が取り消された場合は、保険料の精算が必要です。
保険年度の中途に承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料、第3種特別加入保険料については、それぞれ当該承認が取り消された日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければなりません。
(法第19条)
③【H23年出題(労災)】 〇
一括有期事業の労働保険料も継続事業と同じように年度更新を行います。保険年度の中途で保険関係が消滅した場合も同じです。
(法第19条)
④【H30年出題(雇用)】 〇
納付した概算保険料の額が確定保険料の額以上の場合でも、確定保険料申告書の提出は必要です。
(則第38条)
次回、過不足の具体的な精算手続きに続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!雇用保険法
ここを乗り越えよう!雇用保険法
R4-169
R4.2.7 雇用保険「訓練延長給付」
雇用失業情勢やその地域の特殊な状況などで、所定給付日数分の基本手当では、保護が不十分な場合があります。
そのため、給付日数の延長の制度が設けられていて、現在(令和4年2月7日)、以下の5種類があります。
①訓練延長給付(公共職業訓練等を受講する場合)
②個別延長給付(災害の場合等)
③広域延長給付(失業者が多数発生した地域で厚生労働大臣が広域職業紹介活動を行わせた場合)
④全国延長給付(全国的に失業の状況が著しく悪化した場合)
⑤地域延長給付(雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者)
※地域延長給付は離職の日が令和4年3月31日までの者が対象です。
今日は、「訓練延長給付」がテーマです。
条文を見てみましょう。
第24条(訓練延長給付)、施行令第4条、第5条) ① 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間(2年)を超えるものを除く。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間(公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間に限る。)を含む)内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。 ② 公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が政令で定める日数(30日)に満たないものに限る。)で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、期間内の失業している日について、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。この場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、政令で定める日数(30日)から支給残日数を差し引いた日数を限度とするものとする。 |
★訓練延長給付とは?
公共職業安定所長の指示によって公共職業訓練等を受ける受給資格者が対象で、次の3つがあります。
・ 公共職業訓練等を受講するために待期している期間
・ 受講している期間
・ 受講終了後
(参照:行政手引52351)
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
②【H22年出題】
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。
③【H14年出題】
公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。
④【R2年出題】
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「1年以内」ではなく「2年以内」のものに限られています。
②【H22年出題】 ×
公共職業訓練等を受けるために待期している期間も、訓練延長給付の対象になります。
所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間が対象です。
公共職業訓練等を受けるために待期している期間のうち、公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く「90日間」の期間内の失業している日について、その所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。
(行政手引52353)
③【H14年出題】 〇
公共職訓練等の受講終了後の延長給付のポイントは以下の通りです。
・ 公共職業訓練等を受け終わる日の支給残日数(受講終了日の翌日から受給期間の最後の日までの間の基本手当を受けることができる日数のこと)が30日未満
・ 公共職業安定所長が政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めた
・ 支給限度日数は、30 日から支給残日数を差し引いた日数
(行政手引52355)
④【R2年出題】 〇
訓練延長給付によって支給される基本手当の日額は、本来支給される基本手当の日額と同じ額です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-168
R4.2.6 労災「受給権の保護」
例えば、業務災害によって休業補償給付を受けている場合、退職後も引き続き受けられるのでしょうか?
労災保険の保険給付の受給権は保護されています。条文で確認しましょう。
第12条の5 ① 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 ② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 |
「保険給付を受ける権利」は、労働者の「退職によって変更されることはない」となっています。保険給付を受ける権利は、雇用関係の存続とは関係なく、退職後も変わらず継続します。在職中に受けていた休業補償給付は退職後も支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
②【H21年出題】
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労災保険給付を受ける権利は、退職した後も継続します。
②【H21年出題】 ×
労働関係が解消された後も、引き続いて休業補償給付を受けることができます。
通常は、退職後も次の仕事に就いて賃金を得ることができます。しかし、業務上の傷病による療養中は仕事に就くことができません。「労働することができないために賃金を受けない」状態にあるといえるからです。
こちらもどうぞ!
③【H24年出題】
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
④【R1年出題】
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差し押さえは禁止されている。

【解答】
③【H24年出題】 〇
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることはできません。
④【R1年出題】 ×
保険給付ではなく、社会復帰促進等事業の「特別支給金」の問題ですので注意してください。
特別支給金については、譲渡、差し押さえは禁止されていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働安全衛生法
ここを乗り越えよう!労働安全衛生法
R4-167
R4.2.5 「特別教育」の対象業務と「就業制限」の対象業務
まず、「特別教育」の条文を読んでみましょう。
第59条第3項 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
 一定の危険又は有害な業務に就かせるときは特別教育が必要です。特別教育が必要な業務は、施行規則第36条に定められています。
一定の危険又は有害な業務に就かせるときは特別教育が必要です。特別教育が必要な業務は、施行規則第36条に定められています。
次に、「就業制限業務」の条文を読んでみましょう。
第61条 事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。 |
 例えば、ボイラーやクレーン等は操作を誤ると、周囲を巻き込む大きな災害につながります。そのため、危険な作業を伴う業務は「就業制限業務」とされていて、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければその業務に就かせられません。就業制限に係る業務は施行令第20条に定められています。
例えば、ボイラーやクレーン等は操作を誤ると、周囲を巻き込む大きな災害につながります。そのため、危険な作業を伴う業務は「就業制限業務」とされていて、免許や技能講習など必要な資格を有する者でなければその業務に就かせられません。就業制限に係る業務は施行令第20条に定められています。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
事業者は、 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

【解答】
①【R2年出題】 〇
1トン未満のフォークリフトの運転の業務は、「特別教育」の対象業務です。
(則第36条)
 ポイント!
ポイント!
「フォークリフトの運転の業務」について
・1トン未満 → 特別教育
・1トン以上 → 就業制限業務
小さいのは特別教育、大きいのは就業制限業務というイメージです。
他にイメージしやすいものを覚えておきましょう。
「ボイラー」について
・小型ボイラー → 特別教育
・ボイラー(小型ボイラー除く) → 就業制限業務
「クレーンの運転」について
・5トン未満 → 特別教育
・5トン以上 → 就業制限業務
「移動式クレーンの運転」について
・1トン未満 → 特別教育
・1トン以上 → 就業制限業務
「高所作業車の運転」について
・10メートル未満 → 特別教育
・10メートル以上 → 就業制限業務
では、こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。
③【H22年出題】
事業者は、作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については一定の資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないが、当該業務に就くことができる者は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う高所作業車運転技能講習を修了した者でなければならない。

【解答】
②【H28年出題】 ×
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転は、就業制限業務ではなく特別教育の対象になる業務です。
③【H22年出題】 〇
作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転は就業制限業務で、就かせることができるのは「高所作業車運転技能講習を修了した者」です。
なお、別表第3では、「高所作業車運転技能講習を修了した者」、「その他厚生労働大臣が定める者」と規定されていますが、「その他厚生労働大臣が定める者」は現在該当なしです。
(則第41条、則別表第3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法
ここを乗り越えよう!労働基準法
R4-166
R4.2.4 休日の振替
「労働日」は労働する義務のある日、「休日」は労働する義務のない日です。
今日は「休日」がテーマです。
まず、「休日」のルールを条文で読んでみましょう。
第35条 (休日) ① 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 ② ①の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 |
★休日は、「毎週1回」与えるのが原則です。例外的に4週間に4日も認められています。
さて、「休日の振替」についてお話します。
日曜が休日、月曜から土曜までが労働日。1日の労働時間が、月曜から金曜までは7時間、土曜が5時間の場合、カレンダーは以下のようになります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
業務の都合で日曜に7時間労働する必要が生じたので、あらかじめ同じ週の木曜の労働日と日曜の休日を入れ替えた場合、以下のようになります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
7 | 7 | 7 | 7 | 休 | 7 | 5 |
結果、日曜は「労働日」、木曜は「休日」になります。このことを休日の振替といいます。日曜は「労働日」ですので、労働した7時間は休日労働ではありません。
ポイントは「あらかじめ」の部分です。事前に入れ替えることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
就業規則に休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設けている事業場においては、当該規定に基づき休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定することによって、4週4日の休日が確保されている範囲内において、所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができる。

【解答】
①【H21年出題】 〇
一番のポイントは、『休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定する』の部分です。
また、「就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設けている」こと、「4週4日の休日が確保されている」こともポイントです。
(昭63.3.14基発150号)
次に、こちらもどうぞ!
②【H13年出題】
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。
③【H18年出題】
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。

【解答】
②【H13年出題】 〇
「就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定がある」、「4週4日の休日は確保されている」そして、「あらかじめ」、「振り替えるべき休日を特定して休日の振替を行った」場合は、当初の休日は労働日となります。その日は労働日となりますので、休日労働にはなりません。
(昭63.3.14基発150号)
③【H18年出題】 〇
以下のような勤務カレンダーで、あらかじめ1週目の日曜日と2週目の木曜日を振り替えた場合で考えてみましょう。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1週目 | 休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2週目 | 休 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
1週目の日曜は「労働日」、2週目の木曜が「休日」になります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1週目 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2週目 | 休 | 7 | 7 | 7 | 木 | 7 | 5 |
1週目の日曜は労働日になりましたので、休日労働にはなりません。
ただし、休日を振り替えたことにより、1週目の労働時間が47時間となり法定労働時間を超えてしまいます。その場合、その超えた時間は時間外労働となりますので、時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。
(昭63.3.14基発150号)
 まとめ
まとめ
・休日の振替は、あらかじめ振替の休日を指定することが必要です。
なお、休日出勤させてから事後に他の勤務日を休ませるのは「代休」です。代休を与えても休日出勤の事実は無くなりませんので、休日労働の割増賃金の支払いが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!確定給付企業年金法
ここを乗り越えよう!確定給付企業年金法
R4-165
R4.2.3 確定給付企業年金法の老齢給付金
確定給付企業年金法の給付の種類を条文で確認しましょう。
第29条 (給付の種類) ① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退一時金 ② 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 1 障害給付金 2 遺族給付金 |
確定給付企業年金の給付には、「老齢給付金」と「脱退一時金」があります。「障害給付金」と「遺族給付金」は任意です。
過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < A >

【解答】
①【H30年選択式】
A 脱退一時金
 今日は老齢給付金のお話です。
今日は老齢給付金のお話です。
老齢給付金の支給要件を条文で読んでみましょう。
第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② ①に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で定める年齢以上1の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ ②の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
施行令第28条 (老齢給付金の支給を開始できる年齢) 法第36条第2項第2号の政令で定める年齢は、50歳とする。 |
 ポイント!
ポイント!
老齢給付金の支給開始時期は、60歳から70歳の間で、規約で設定することができます。
また、規約で定めることにより、50歳以上の規約で定める年齢で労働者が退職した場合に支給することもできます。
老齢給付金を支給するための加入者期間は20年以下であることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
②【H30年選択式】 ※改正による修正あり
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達 した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】
②【H30年選択式】 ※改正による修正あり
A 60歳以上70歳以下
B 50歳未満
こちらもどうぞ!
③【H26年出題】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
④【H26年出題】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
老齢給付金は、年金として支給することとされていますが、規約でその全部又は一部を一時金として支給することを定めた場合は、一時金で支給することができます。
(法第38条)
④【H26年出題】 〇
年金給付は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給することが条件です。
(法第33条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!障害者雇用促進法
ここを乗り越えよう!障害者雇用促進法
R4-164
R4.2.2 障害者雇用率制度
事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇用することが義務づけられています。
★条文を確認しましょう。
第37条 (対象障害者の雇用に関する事業主の責務) ① 全て事業主は、対象障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。 ② 「対象障害者」とは、身体障害者、知的障害者又は精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る。)をいう。 |
※ 第38条で「雇用に関する国及び地方公共団体の義務」、第43条で「一般事業主の雇用義務等」が定められています。
★第43条を読んでみましょう。
第43条 (一般事業主の雇用義務等) 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。 |
事業主は、「雇用する労働者数×障害者雇用率」以上の対象障害者を雇用する義務があります。
障害者雇用率は以下の通りです。
| 法定雇用率 |
民間企業 | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.5% |
民間企業の場合、労働者を43.5人以上雇用する事業主は、障害者の雇用義務が生じます。
過去問をどうぞ!
①【H25年選択式】 ※法改正による修正あり
障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める対象障害者の割合が一定以上になるよう義務づけられている。この法定雇用率は令和3年3月1日から改定され、それにともなって、毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所の長に報告する必要のある民間企業は、< A >人以上に拡大された。
< A >人以上の企業には、< B >を選任するよう努力することが求められている。

【解答】
①【H25年選択式】 ※法改正による修正あり
A 43.5
B 障害者雇用推進者
(法第43条、第78条第2項、則第7条)
 43.5人以上の民間企業のポイント!
43.5人以上の民間企業のポイント!
・障害者雇用状況報告書の提出
毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況を7月15日までに報告する(義務)
・障害者雇用推進者
障害者雇用推進者の選任(努力義務)
もう一問どうぞ!
②【R2年出題】
障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。

【解答】
②【R2年出題】 ×
「1週間の所定労働時間にかかわりなく」が誤りです。
対象障害者である短時間労働者は、その1人をもって、0.5人に相当するものとみなされます。
※「重度身体障害者又は重度知的障害者」の場合
重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その1人をもって、2人に相当するものとみなされます。
重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもって、1人に相当するものとみなされます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-163
R4.2.1 障害厚生年金の加給年金額
前回お話したように、障害基礎年金には「子」の加算額が加算されます。
「配偶者」は「障害厚生年金」の加給年金額の対象になります。
今回は、障害厚生年金の加給年金額がテーマです。
★では、条文を確認しましょう。
第52条の2 ① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金に加給年金額を加算した額とする。 ② 加給年金額は、224,700円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ③ 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。 |
 ポイント!
ポイント!
・ 加給年金額が加算されるのは、1級又は2級の障害厚生年金です。
3級の障害厚生年金には加給年金額は加算されません。
・ 対象は65歳未満の配偶者です
・ 加給年金額は「224,700円×改定率」です。老齢厚生年金の配偶者加給年金額に は、特別加算がプラスされますが、障害厚生年金の加給年金額には特別加算はつきません。
・ 受給権を取得した日の翌日以後に、対象になる配偶者を有することに至った場合でも加給年金額は加算されます
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。
②【H29年出題】
障害等級1級に該当する障害厚生年金の受給権者が、その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。

【解答】
①【H22年出題】 〇
加給年金額が加算される障害厚生年金は、「障害等級1級又は2級」です。対象は、「65歳未満」の配偶者です。年齢にも注意してください。
②【H29年出題】 〇
受給権を取得した日の翌日以後に対象の配偶者を有するに至った場合でも加給年金額は加算されます。その場合は、配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、加給年金額が加算されます。
(障害基礎年金の子の加算と同じです。→ (参考)前回の記事をどうぞ)
次はこちらをどうぞ!
③【R1年出題】
加給年金額が加算された障害厚生年金の額について、当該加給年金額の対象になっている配偶者(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。)が65歳に達した場合は、当該加給年金額を加算しないものとし、その該当するに至った月の翌月から当該障害厚生年金の額を改定する。
④【H20年出題】
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
加給年金額は、次のどれかに該当するに至ったときは、加算がなくなります。
1 死亡したとき。
2 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
3 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
4 配偶者が、65歳に達したとき。
問題文の場合は4に当てはまります。その該当するに至った月の翌月から加給年金額が加算されなくなります。
なお、「大正15年4月1日以前に生まれた者を除く。」の部分もポイントです。「大正15年4月1日以前に生まれた者」は旧法の対象者で、新法の老齢基礎年金が支給されません。ですので、振替加算も行われません。
「大正15年4月1日以前に生まれた者」は、65歳以降も加給年金額の対象となります。
(法第50条の2第4項)
④【H20年出題】 ×
「配偶者の生年月日にかかわらず」が誤りです。
配偶者が「大正15年4月1日以前生まれ」の場合は、配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月からも加給年金額が加算されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-162
R4.1.31 障害基礎年金の子の加算・要件をみるタイミング
障害基礎年金の受給権者に子がいるときは、子の加算が行われます。
要件をどの時点でみるかが今日のテーマです。
★では、条文で確認しましょう。
第33条の2 ① 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、障害基礎年金にその子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じて得た額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 ② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)を有するに至ったことにより、子の加算額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する。 |
子の加算額は、「生計維持関係」があることが前提です。
障害基礎年金の受給権発生時に生計維持関係がある場合はもちろん加算されますが、受給権を取得した翌日以後に生計維持関係のある子を有することに至った場合も、子の加算が行われるのがポイントです。
ちなみに、遺族基礎年金の場合の生計維持関係は「死亡の当時」で判断されます。
第37条の2で、「遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、一定の要件に該当したものとする。」となっています。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
障害基礎年金の加算額は、受給権者によって生計を維持されている一定の要件に該当する子があるときに加算され、配偶者に対する加算はない。
②【H25年出題】
障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有することとなった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、その子を対象として加算額が加算されることはない。
③【H23年出題】
障害基礎年金に係る子の加算は、受給権者が当該受給権を取得した時点において、その者によって生計を維持する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子がなければ、行われない。

【解答】
①【H19年出題】 〇
障害基礎年金の加算額の対象は、子だけです。配偶者については、1・2級の障害厚生年金の加給年金額の対象になります。
②【H25年出題】 ×
障害基礎年金の受給権を取得した後でも、要件を満たす子を有することになった場合は、子の加算額が加算されます。その場合は、子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額に子の加算額が加算されます。
③【H23年出題】 ×
②の問題と同じです。受給権を取得した時点で要件を満たす子がいなくても、後日、有することになった場合は、加算の対象になります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!健康保険法
ここを乗り越えよう!健康保険法
R4-161
R4.1.30 法人の役員である被保険者又はその被扶養者の保険給付の特例
健康保険法の保険給付は、「業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産」に関して行われます。
「業務災害以外の」がポイントです。
例えば、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合、労働者でないため労災保険法の業務災害にはなりません。そのような労災保険の給付の対象にならない負傷は、原則として健康保険の給付が受けられます。
では、例えば社長が業務中に負傷した場合はどうでしょう?
社長の場合、特別加入していなければ労災保険の給付は受けられません。健康保険の目的条文をそのまま適用すると、「労災保険法の業務災害以外の負傷」ということで健康保険の保険給付の対象になってしまいます。
しかし、社長は業務災害については補償責任を負う立場です。また、健康保険の保険料は労使折半です。そのため、社長の業務上の負傷等について健康保険から保険給付を行うのは適当でないということから、健康保険の給付は行わないことになっています。
★条文を読んでみましょう。
第52条の2 (法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例) 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
則第52条の2(法第53条の2の厚生労働省令で定める業務) 法第53条の2の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。 |
法人の役人については、原則として、その法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡については健康保険の保険給付は行われません。
なお、法人の役員としての業務とは、法人の役員がその法人のために行う業務全般を指します。
ただし、「法人の役員の業務」から「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるもの」は除かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
②【H26年出題】
被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
③【H30年出題】
被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。

【解答】
①【H28年出題】 〇
労災保険の業務災害にならない請負業務中の負傷等については、原則として健康保険の給付が行われます。
(法第1条、平成25.8.14事務連絡)
②【H26年出題】 〇
法人の役人については、原則として、その法人の役員としての業務に起因する負傷等については健康保険の保険給付は行われません。
しかし、例外で、被保険者が5人未満の適用事業所の法人の役員については、業務遂行の過程で業務に起因して生じた傷病についても健康保険の保険給付の対象になります。
傷病手当金も支給されます。
(平成25.8.14事務連絡)
③【H30年出題】 〇
健康保険の給付対象となる業務は、「当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるもの」と定められています。(則第52条の2)
役員の業務内容が当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められない場合には健康保険の給付対象になりません。
(平成25.8.14事務連絡)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-160
R4.1.29 特別加入保険料率
労災保険法の特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つの種類があります。
特別加入者の保険料は、原則として、『「保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)」×特別加入保険料率』で計算します。
なお、保険年度の中途で加入・脱退した場合は月割計算、有期事業の場合は全期間で計算します。
今日は、保険料の算定に使う特別加入保険料率を確認します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題(労災)】
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
②【R2年出題(労災)】
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類にかかわらず、労働保険徴収法施行規則によって同一の率に定められている。
③【H26年出題(労災)】
第3種特別加入保険料率は、海外派遣者が海外において従事している事業と同種又は類似の日本国内で行われている事業についての業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定めるとされ、令和4年度の厚生労働大臣の定める率は、事業の種類にかかわらず一律に1000分の5とされている。

【解答】
①【H26年出題(労災)】 ×
第1種特別加入保険料率は、「中小事業主等」の保険料率です。
考慮されるのは、「通勤災害に係る災害率」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。特別加入者は二次健康診断等給付の対象外だからです。
なお、「厚生労働大臣の定める率」は、零ですので、結果として、第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率と同じです。
(法第13条、則第21条の2)
★穴埋めで確認しましょう★
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去 < A >年間の< B >に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。
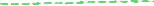
<解答>
A 3
B 二次健康診断等給付
②【R2年出題(労災)】 ×
第2種特別加入保険料率は、「一人親方等」の保険料率です。
第2種特別加入保険料率は、事業又は作業の種類によって違います。範囲は、最低1000分の3から最高1000分の52まであります。
(則第23条、別表第5)
③【H26年出題(労災)】 ×
第3種特別加入保険料率は、「海外派遣者」の保険料率です。
第3種特別加入保険料率は、事業の種類にかかわらず一律に「1000分の3」です。
(則第23条の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!雇用保険法
ここを乗り越えよう!雇用保険法
R4-159
R4.1.28 「待期」について
さっそく、条文を読んでみましょう。
第21条 (待期) 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して7日に満たない間は、支給しない。 |
待期の期間中は、基本手当は支給されません。
待期は、受給資格者が離職後最初に求職の申込みをした日から進行します。求職の申込みをした日以後通算7日の失業の認定が行われることによって待期は満了します。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】
雇用保険法第21条は、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日 (< A >のため職業に就くことができない日を含む。)が< B >に満たない間は、支給しない。

【解答】
A 疾病又は負傷
B 通算して7日
「通算」がポイントです。連続して又は断続して7日に達することが条件です。
次はこちらをどうぞ!
②【H23年出題】
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。
③【H26年出題】
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
④【H29年出題】
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

【解答】
②【H23年出題】 〇
待期日数は、現実に失業し、失業の認定を受けた日数が連続又は断続して7日になることが条件です。
5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合は、待期が満了していませんので、その5日について基本手当は支給されません。
③【H26年出題】 ×
待期の日数には、「傷病」のため職業に就くことができない日も含まれるのがポイントです。
問題文のように、疾病で職業に就くことができなくなった3日間も「待期」に通算されます。
11日目からではなく、8日目から基本手当が支給されます。
④【H29年出題】 ×
待期の期間も失業の認定は行われます。
失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定があって初めて「失業の日」又は「疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日」として認められます。
そのため、失業( 傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われなければならない、とされています。
(行政手引51102(2))
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-158
R4.1.27 傷病補償年金の変更
傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があり、傷病等級が変わった場合のルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 |
例えば、2級の傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに3級に該当した場合は、それ以後は3級の傷病補償年金が支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
②【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
③【H21年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けられない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

【解答】
①【H20年出題】 ×
傷病補償年金(傷病年金)の障害の程度に変更があったときも、所轄労働基準監督署長の職権で変更に関する決定が行われます。労働者からの請求ではありません。
(則第18条の3)
②【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合は、傷病補償年金の受給権は消滅します。そして、要件に該当すれば、労働者は休業補償給付を請求することができます。
なお、年金は、支給を受ける「権利が消滅した月」まで支給されます。(法第9条)休業補償給付はその翌月から支給されます。
③【H21年出題】 ×
休業補償給付の支給は、労働者の請求が必要です。
(法第12条の8)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働安全衛生法
ここを乗り越えよう!労働安全衛生法
R4-157
R4.1.26 安全委員会・衛生委員会の構成メンバー
一定の業種で、常時50人以上又は100人以上の労働者を使用する事業場では、安全委員会を、また、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場では衛生委員会を設けなければなりません。
安全委員会を設けなければならない事業場では、衛生委員会も設けなければなりませんが、その場合は、それぞれを合わせた安全衛生委員会を設置することもできます。
今回は、安全委員会・衛生委員会の構成メンバーを確認します。
★条文をどうぞ
第17条(安全委員会) ② 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2 安全管理者のうちから事業者が指名した者 3 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 安全委員会の議長は、第1号の委員がなるものとする。 ④ 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。 |
安全委員会の構成メンバーの規定です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
事業者が労働安全衛生法第17条の規定により安全委員会を設置しなければならない場合、事業者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときを除き、その委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「その委員の半数については」が誤りです。
過半数労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名しなければならないのは、「第1号の委員(議長となる委員)以外の委員の半数については」です。
★安全委員会の議長について
第1号の委員(総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者)が議長となります。
なお、第1号の「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの」は、総括安全衛生管理者の選任義務がない事業についての規定です。
「これに準ずるもの」は事業の実施を統括管理する者以外でその者に準じた地位にある者(副所長や副工場長など)をさします。
(昭和47年9月18日 基発第602号)
★次は衛生委員会の構成メンバーです。条文をどうぞ
第18条 (衛生委員会) ② 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。 1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者 2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者 3 産業医のうちから事業者が指名した者 4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者 ③ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。 |
★「議長」や「過半数組合等の推薦に基づく指名」は、安全委員会と同じです。
では、過去問をどうぞ!
②【H12年出題】
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
③【H16年出題】
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

【解答】
②【H12年出題】 〇
作業環境測定士については、語尾の「指名することができる」がポイントです。委員のメンバーにするか否かは任意です。
③【H16年出題】 ×
産業医は、衛生委員会の構成員となります。
産業医は、専属の産業医に限られませんので、嘱託の場合でも指名しなければなりません。
(昭和63年9月16日基発第601号の1)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法
ここを乗り越えよう!労働基準法
R4-156
R4.1.25 労働が2暦日にわたる場合の労働時間
労働基準法第32条では、1日の労働時間は8時間以内とされています。
「1日」とは、原則として「午前0時から午後12時まで」の暦日をさします。
(S63.1.1基発1号)
では、例えば、令和4年1月25日の労働が日をまたがって翌日の26日まで継続したように、勤務が2暦日にわたる場合は、どのようにカウントするのでしょうか?
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
労働基準法第32条第2項にいう「1日」とは午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいい、継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とする。

【解答】
①【R1年出題】 〇
例えば、1月25日の16時から26日の3時まで11時間勤務した場合は、「始業時刻の属する日」である25日の「1日」の労働とされます。
労働者は実際に25日から11時間連続で労働しているので、暦日が異なっていても1勤務とされます。
もし、原則どおりの暦日で考えると、26日0時でリセットされてしまい、26日の3時間は時間外労働にもならず、労働者に不利益になってしまうからです。
(昭和63.1.1基発1号)
では、こちらをどうぞ!
②【H30年出題】
労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働時間に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述のうち、正しいものはどれか。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩;午後1時から1時間
A 日曜に10時間の労働があると、休日割増賃金の対象になるのは8時間で、8時間を超えた2時間は休日労働に加えて時間外労働も行われたことになるので、割増賃金は、休日労働に対する割増率に時間外労働に対する割増率を加算する必要がある。
B 日曜の午後8時から月曜の午前3時まで勤務した場合、その間の労働は全てが休日割増賃金対象の労働になる。
C 月曜の時間外労働が火曜の午前3時まで及んだ場合、火曜の午前3時までの労働は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われる。
D 土曜の時間外労働が日曜の午前3時まで及んだ場合、日曜の午前3時までの労働に対する割増賃金は、土曜の勤務における時間外労働時間として計算される。
E 日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

【解答】
A ×
休日労働が8時間を超えても時間外の割増率を加算する必要はありません。問題文の法定休日の日曜の10時間労働は3割5分増で差し支えないとされています。ただし、深夜業に該当した場合は、深夜の2割5分増の加算が必要です。
(昭和22.11.21基発266号)
B ×
日曜の午後8時から月曜の午前3時までの勤務は、1勤務として扱われます。ただし、休日を含む2暦日にまたがった場合、休日の午前0時から午後12時までの時間帯は「休日労働」の割増率になります。
問題文の場合は、日曜の午後8時から午後12時までが、休日割増賃金対象の労働になります。
(平6.5.31基発331号)
C 〇
月曜日と火曜日は暦日が異なっていても1勤務として取り扱います。問題文の場合は、月曜の勤務における1日の労働として取り扱われます。
(昭和63.1.1基発1号)
D ×
Bと同じように考えます。
土曜から日曜の午前3時までの勤務は1勤務として扱われますが、法定休日の日曜の午前0時からは3時までは休日割増で計算します。
E ×
割増賃金の対象は、木曜と金曜が2時間ずつ、土曜は4時間です。
木曜と金曜は1日の法定労働時間である8時間を超えた時間が割増賃金の対象です。
月曜から金曜までで割増対象以外の通常の労働時間のトータルが34時間になります。1週間の法定労働時間は40時間以内ですので、土曜日は6時間までが通常の労働時間、4時間が割増賃金対象の労働時間となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
割増対象 |
|
|
|
| 2 | 2 | 4 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!介護保険法
ここを乗り越えよう!介護保険法
R4-155
R4.1.24 介護保険法・保険料のしくみ
介護保険法の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類です。
それぞれ介護保険料を負担していますが、徴収の方法が違います。
では、条文を読んでみましょう。
第129条 (保険料) ① 市町村(市町村又は特別区)は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② ①の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、①の規定にかかわらず、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
ポイント!
・ 市町村が徴収するのは「第1号被保険者」に対する保険料
・ 「保険料率」は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
・ 市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない
★第1号被保険者からの徴収方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
①特別徴収
老齢等年金給付(老齢・退職、障害、遺族)が年額18万円以上の者が対象
(年金から徴収される)
②普通徴収
納付書などで徴収する
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
②【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
①【H21年出題】 〇
市町村又は特別区が徴収する保険料は、第1号被保険者に対するものです。
②【H30年選択式】
A 3年
では、もう一問どうぞ!
③【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
市町村は、第2号被保険者から保険料は徴収しません。
(第2号被保険者の流れ)
第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料といっしょに徴収します。
そして、各医療保険者から、社会保険診療報酬支払基金を通して、市町村に交付されます。
各医療保険者
↓ 『介護給付費・地域支援事業支援納付金』として納付
↓
社会保険診療報酬支払基金
↓ 『介護給付費交付金』、『地域支援事業支援交付金』として交付
↓
市町村
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!高年齢者雇用安定法
ここを乗り越えよう!高年齢者雇用安定法
R4-154
R4.1.23 定年と高年齢者雇用確保措置
まず、「定年」の条文を読んでみましょう。
第8条 (定年を定める場合の年齢) 事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。 ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
施行規則第4条の2 法第8条の厚生労働省令で定める業務は、鉱業法に規定する事業における坑内作業の業務とする。 |
「定年」の定めをする場合は、「60歳以上」にする必要があります。なお、「定めをする場合は」ですので、定年を定めないのもOKです。
なお、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(坑内作業の業務)の場合は、60歳を下回る年齢が認められます。
※「高年齢者」の定義は?
高年齢者雇用安定法で「高年齢者」とは、「55歳以上」の者をいいます。
(法第2条、則第1条)
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「65歳以上とすることを義務づけ」が誤りです。原則として「60歳を下回ることができない」です。
では、次に高年齢者雇用確保措置を読んでみましょう。
第9条 (高年齢者雇用確保措置) 定年(65歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、「高年齢者雇用確保措置」のいずれかを講じなければならない。 1 当該定年の引上げ 2 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)の導入 3 当該定年の定めの廃止 |
定年を65歳未満にしている事業主は、高年齢者雇用確保措置として1~3のいずれかの措置の実施が義務づけられています。
1 65歳まで定年の引き上げ
2 65歳までの継続雇用制度の導入
3 定年制の廃止
では、過去問をどうぞ!
②【R1年出題】
65歳未満の定年の定めをしている事業主が、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、新たに継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。)を導入する場合、事業主は、継続雇用を希望する労働者について労使協定に定める基準に基づき、継続雇用をしないことができる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
平成25年3月31日までは、経過措置として、労使協定で継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができました。しかし、現在は、その経過措置は廃止されています。
継続雇用制度は、定年後も引き続き働きたいと希望する人全員を対象にする必要があります。
 なお、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」(第10条の2)が設けられています。
なお、令和3年4月から「高年齢者就業確保措置」(第10条の2)が設けられています。
こちらは、「70歳」までの就業機会を確保するためのものです。
(対象)
・ 定年年齢を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・ 継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
以下の1~5のいずれかの措置を講ずるよう「努めなければならない」とされています。(努力義務です。)
1 70歳まで定年年齢の引き上げ
2 70歳までの継続雇用制度の導入
3 定年制の廃止
4 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
①事業主が自ら実施する社会貢献事業
②事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※4、5を創業支援等措置といいます。
※「雇用」だけでなく、業務委託契約などが入っているのが特徴です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-153
R4.1.22 障害厚生年金 額の改定その3 3級から2級へ②65歳以上の場合
障害認定日に3級だったものが、その後2級に増進した場合、障害厚生年金は3級から2級に改定、障害基礎年金は事後重症になることを、前回お話しました。
しかし、3級から2級に増進したときに65歳以上だった場合は注意が必要です。今回は、65歳以上で障害の程度が増進した場合がテーマです。
では、第52条の条文を見てみましょう。
第52条 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は①の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ④から⑥は省略
⑦ ①から③まで及び前項の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。 |
★⑦に注目してください。
「当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないもの」とは、「受給権を取得した当時から1度も障害等級1級又は2級に該当したことがない」という意味です。
65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないもの)には、1・2級への等級改定は行われません。
「障害基礎年金の事後重症」の適用は、65歳に達する日の前日までに限られています。そのため、65歳以上の3級の障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進しても、事後重症の障害基礎年金の受給権は発生しません。
ですので、65歳以降は3級から1・2級への改定は行わないことになっています。1・2級の障害厚生年金だけ支給されることがないようにするためです。
では、過去問をどうぞ
①【H23年出題】
老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者であって、かつ障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額の改定請求をすることができない。
②【H27年出題】
63歳の障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)が、老齢基礎年金を繰上げ請求した場合において、その後、当該障害厚生年金に係る障害の程度が増進したときは、65歳に達するまでの間であれば実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
65歳以上の者だけでなく、老齢基礎年金を繰り上げて受給している者も、事後重症の障害基礎年金は請求できません。
また、「障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む。)の受給権を有しないものに限る。)」とは、受給権を取得した当時から3級で、1度も1級・2級に該当したことがないという意味です。
問題文の「老齢基礎年金(繰上げ支給を含む。)の受給権者又は65歳以上の者」は、事後重症の障害基礎年金の請求ができません。ですので、障害の程度が3級から増進しても、障害厚生年金の額の改定請求はできません。
(法第52条第7項、法附則第16条の3)
②【H27年出題】 ×
「老齢基礎年金を繰上げ請求している」かつ「3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)」は、障害の程度が増進しても、障害厚生年金の額の改定は請求できません。
(法第52条第7項、法附則第16条の3)
もう一問どうぞ!
③【R2年出題】
障害等級2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級2級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
この問題は、2級の障害状態に該当していたことがあり、障害基礎年金の受給権があることがポイントです。
2級だったものが、症状が軽減して3級の程度になった場合、障害厚生年金は3級、障害基礎年金は支給停止となります。
その後、再び2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に改定、障害基礎年金は支給停止が解除され、2級の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。
この場合は、65歳に達した日以後でも、3級から2級に額の改定が行われます。
(下の図も参考にしてください。)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
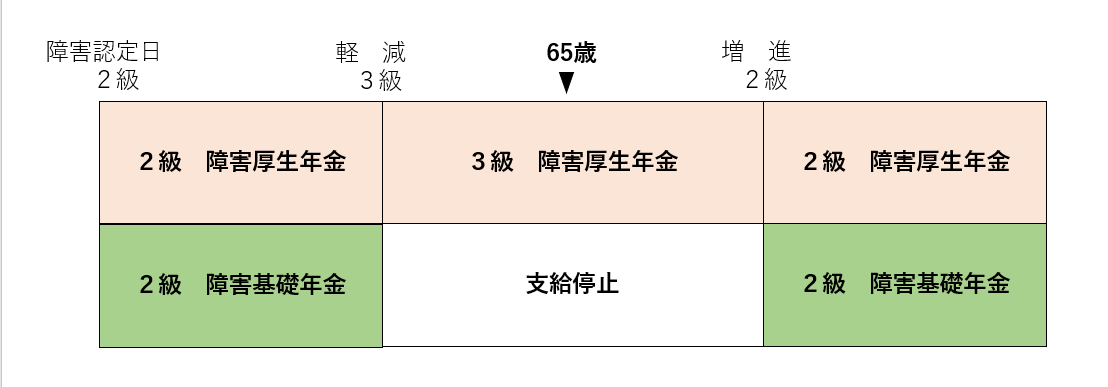
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-152
R4.1.21 障害厚生年金 額の改定その2 3級から2級への改定①
3級の障害が重くなり2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に額の改定が行われます。
その場合、「障害基礎年金」は、「事後重症」になることがポイントです。
初診日に厚生年金保険の被保険者(国民年金は第2号被保険者)で、障害認定日に3級に該当した場合、「3級の障害厚生年金」の受給権が発生しますが、障害基礎年金の受給権はありません。
その後、障害の程度が増進し2級に該当した場合、障害厚生年金は3級から2級に額の改定が行われます。一方、障害基礎年金は「障害認定日」に障害等級(1・2級)に該当しなかったものが、その後障害等級(1・2級)に該当することになり、「事後重症」となります。(下の図でご確認ください)
障害厚生年金の3級から2級への額の改定は、障害基礎年金の事後重症の要件を満たす必要があるのがポイントです。
 ここで、「国民年金法」の条文を読んでみましょう。
ここで、「国民年金法」の条文を読んでみましょう。
国民年金法第30条の2 (事後重症の障害基礎年金) ① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項各号のいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 ④ 第①項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法の規定による障害厚生年金について、同法第52条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに①項の請求があったものとみなす。 |
★ 最後の「そのときに①項の請求があったものとみなす。」に注目してください。
事後重症の障害基礎年金は「請求」によって受給権が発生します。しかし、障害厚生年金の障害等級が3級から2級に改定された場合は、改めて請求しなくても、障害厚生年金の改定に伴い、請求が行われたとみなされます。
 では、国民年金の過去問をどうぞ!
では、国民年金の過去問をどうぞ!
①【国民年金H30年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない。
②【国民年金H22年出題】
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
①【国民年金H30年出題】 ×
障害厚生年金が3級から2級に改定された場合は、障害基礎年金は、事後重症の「請求があったものとみなす。」ことになっています。請求しなくても、事後重症の障害基礎年金の受給権が発生します。
②【国民年金H22年出題】 ×
①の問題と同じです。障害基礎年金に係る事後重症の請求をしなくても、受給権が発生します。
次回に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
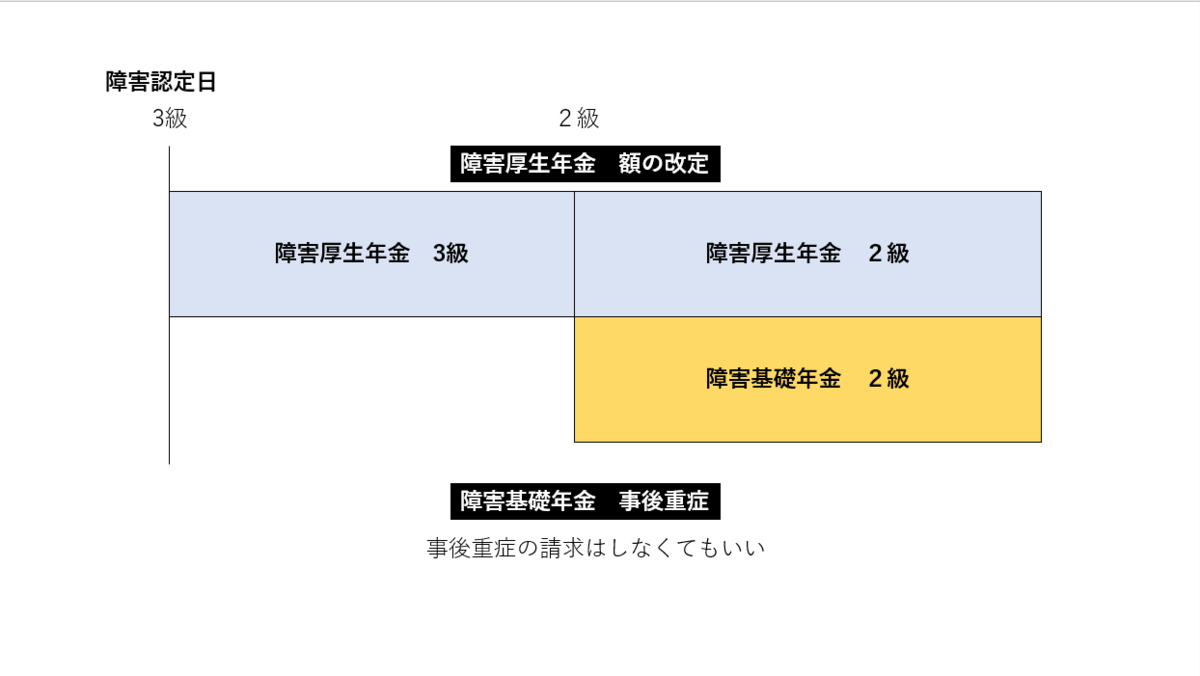
 ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
ここを乗り越えよう!厚生年金保険法
R4-151
R4.1.20 障害厚生年金 額の改定 その1
障害の程度は、重くなったり軽くなったりすることがあります。その場合は、年金額が増額改定されたり、減額改定されます。又、障害等級に該当しなくなった場合は支給停止されます。
改定の方法として、「実施機関の職権による改定」、「障害の程度が増進したことによる改定請求」、「その他障害による併合改定」があります。
まず、「実施機関の職権による改定」を条文で読んでみましょう。
第52条 ① 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 |
実施機関が障害の程度を診査して、職権で障害厚生年金の額を改定することができます。
改定が行われた場合は、改定が行われた月の翌月から、改定後の額による障害厚生年金の支給が始まります。
さて、今回は、「障害の程度が増進したことによる改定請求」をメインにお話します。
第52条の条文の続きを読んでみましょう。
第52条 ② 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。 ③ ②の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は①の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。 |
障害の程度が増進した場合は、障害厚生年金の額の改定請求ができます。
改定請求は、原則として1年待たなければなりません。
「障害厚生年金の受給権を取得した日」
又は
「実施機関の診査を受けた日」
から起算して1年を経過した日後でなければ、行うことができません。
しかし、「障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合」は、例外的に1年を経過しなくても額の改定請求をすることができます。
「障害厚生年金の受給権を取得した日」又は「実施機関の診査を受けた日」のどちらか遅い日以降に、例えば、「両眼の視力の和が0.04以下のもの」に該当した場合等は、1年を経過していなくても、改定請求ができます。(施行規則第47条の2の2)
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
障害厚生年金の受給権者が障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合、当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ再び改定の請求を行うことはできない。
②【H27年出題】
40歳の障害厚生年金の受給権者が実施機関に対し障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求を行ったが、実施機関による診査の結果、額の改定は行われなかった。このとき、その後、障害の程度が増進しても当該受給権者が再度、額の改定請求を行うことはできないが、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合については、実施機関による診査を受けた日から起算して1年を経過した日後であれば、再度、額の改定請求を行うことができる。

【解答】
①【R2年出題】 ×
1年6か月ではなく「1年」です。
実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後なら、再び改定の請求を行うことができます。
②【H27年出題】 ×
・その後、障害の程度が増進した場合
→ 実施機関の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後なら、再度、額の改定請求を行うことができます。(「再度、額の改定請求を行うことはできない」の部分が誤りです。)
・障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合
→ 実施機関による診査を受けた日から起算して1年を経過しなくても、額の改定請求ができます。
次回に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-150
R4.1.19 20歳前傷病による障害基礎年金 その3 支給停止されるとき②
前回に引き続き、第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)の支給停止です。
第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)には、受給権者の所得による支給停止があります。
条文を見てみましょう。
第36条の3 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(第33条の2第1項の規定により子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。 |
★チェックポイント!
・ 第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)には、所得による支給停止がある。
・ 所得は「受給権者」の前年の所得で判断される
・ 停止期間は「その年の10月から翌年の9月」まで(令和3年8月改正)
・ 停止されるのは、「全部又は2分の1」
全額支給
|
2分の1支給停止
|
全額支給停止 |
2分の1支給 |
▲ ▲ ▲
0 370万4千円 472万1千円
※扶養親族等がいない場合、前年の所得が472万1千円を超えるときは、全額が支給停止、370万4千円を超え、472万1千円以下のときは、2分の1が支給停止されます。
(施行令第5条の4)
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】※R3年8月改正による修正あり
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるときは、その年の10月から翌年9月までの間、年金額の全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される。
②【H27年出題】※R3年8月改正による修正あり
20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。
③【H17年出題】※R3年8月改正による修正あり
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の10月から翌年9月までその支給を停止される。
④【H20年出題】※R3年8月改正による修正あり
いわゆる20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定の額を超えるときは、原則として、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【H25年出題】※R3年8月改正による修正あり ×
支給停止されるのは、年金額の「全部又は2分の1」に相当する部分です。
②【H27年出題】※R3年8月改正による修正あり ×
「受給権者本人」の所得で判断されます。扶養親族の所得は合算しません。
③【H17年出題】※R3年8月改正による修正あり ×
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある障害基礎年金は、第30条の4(20歳前傷病による障害基礎年金)ではなく、第30条の通常の障害基礎年金です。所得による支給停止はありません。
④【H20年出題】※R3年8月改正による修正あり 〇
子の加算額が加算されている20歳前傷病による障害基礎年金が、所得によって2分の1が支給停止される場合、子の加算額を控除した額の2分の1に相当する部分の支給が停止されます。
もう一問どうぞ!
⑤【H25年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた者がある場合は、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。

【解答】
⑤【H25年出題】 ×
被害金額がその価額のおおむね「3分の1」ではなく「2分の1」以上である損害を受けた者が対象です。
その損害を受けた月から翌年の9月までは、所得を理由とする支給停止は行われません。
(法第36条の4)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-149
R4.1.18 20歳前傷病による障害基礎年金 その2 支給停止されるとき①
前回の続きです。
20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を負担していない人に対して支給する福祉的な意味のある年金です。
そのため、通常の障害基礎年金とは違う理由で支給停止されます。
条文を読んでみましょう。
第36条の2 第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。 2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 4 日本国内に住所を有しないとき。 |
ポイント!
「第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)」限定の支給停止事由です。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。
②【R1年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金を受給中である者が、労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合、その該当する期間、当該20歳前傷病による障害基礎年金は支給を停止する。
③【H25年出題】
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
④【R3年出題】
国民年金法第30条第1項の規定による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、その該当する期間、その支給が停止される。
⑤【H30年出題】
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する。
⑥【H25年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは支給停止される。

【解答】
①【H20年出題】 〇
労災保険法の障害補償年金を受けることができるときに支給停止されるのは、20歳前の障害に基づく障害基礎年金だけです。
問題文は「いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く」となっています。通常の障害基礎年金について問われているので、「その支給は停止されない」で〇です。
②【R1年出題】 〇
「20歳前傷病による障害基礎年金」は、労災保険法の年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていないものとする。)場合は、その期間、支給停止されます。
なお、条文の「労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付」に注目してください。調整の対象は「年金」で、「障害」の年金に限られません。
③【H25年出題】 〇
②の問題のように20歳前傷病による障害基礎年金は、「労災保険法の年金たる給付を受給できる場合」は、その期間、支給停止されます。
ただし、労災保険法による年金たる給付の「全額が支給停止されているとき」は、20歳前傷病による障害基礎年金は原則として支給停止されません。
(法第36条の2第2項)
④【R3年出題】 ×
刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているときに、支給が停止されるのは、第30条の4の障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)です。
問題文は、法第30条第1項の規定による障害基礎年金(通常の障害基礎年金)について問われているので、刑事施設、労役場等の施設に拘禁されている間も、支給停止にはなりません。
⑤【H30年出題】 〇
問題文の施設に収容されている間は、20歳前傷病による障害基礎年金は、支給停止されます。
(則第34条の4)
⑥【H25年出題】 〇
「30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金」について問われているので、「日本国内に住所を有しない」ときは支給停止される、で正解です。
次回に続きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!国民年金法
ここを乗り越えよう!国民年金法
R4-148
R4.1.17 20歳前傷病による障害基礎年金 その1受給権の発生
通常の障害基礎年金は、初診日に「国民年金の被保険者」であることが条件です。
(又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である場合でも要件を満たします。)
20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金です。
20歳前に初診日があるというのは、国民年金に加入する前に初診日があるということです。
旧法では、20歳前に障害になった場合は、全額国庫負担の障害福祉年金が支給されていましたが、新法では、障害基礎年金が支給されることになりました。
ただし、国民年金加入前に初診日があるので国民年金の保険料は納付していません。 そのため、通常の障害基礎年金とは違うルールがありますので区別しましょう。
では、まず、20歳前傷病による障害基礎年金の受給権の発生日を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第30条の4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。 |
・初診日が20歳未満で、
①障害認定日以後に20歳に達したとき → 20歳に達した日
②障害認定日が20歳に達した日後であるとき → 障害認定日
①は20歳に達した日、②は障害認定日に、障害等級にあれば、受給権が発生します。
★下の図も参考にしてください。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
②【H22年出題】
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

【解答】
①【H26年出題】 ×
初診日が19歳の時なので、障害認定日は、20歳に達した日後になります。
下の図では②に該当します。
受給権は、20歳に達した日ではなく、「障害認定日」に障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、「障害認定日」に発生します。
ちなみに、障害認定日は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、「その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日」となるので、障害認定日が1年6か月より早くなる可能性もあります。
しかし、問題文は、25歳時点で「継続して治療中」です。(治っていない)そのため、「初診日から起算して1年6か月を経過した日」が障害認定日です。
②【H22年出題】 ×
初診日に20歳未満でも、「厚生年金保険の被保険者」である場合は、20歳前傷病による障害基礎年金ではなく、通常の障害基礎年金の受給権が発生します。
問題文の場合は、「障害認定日」に障害厚生年金と障害基礎年金の受給権が発生します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
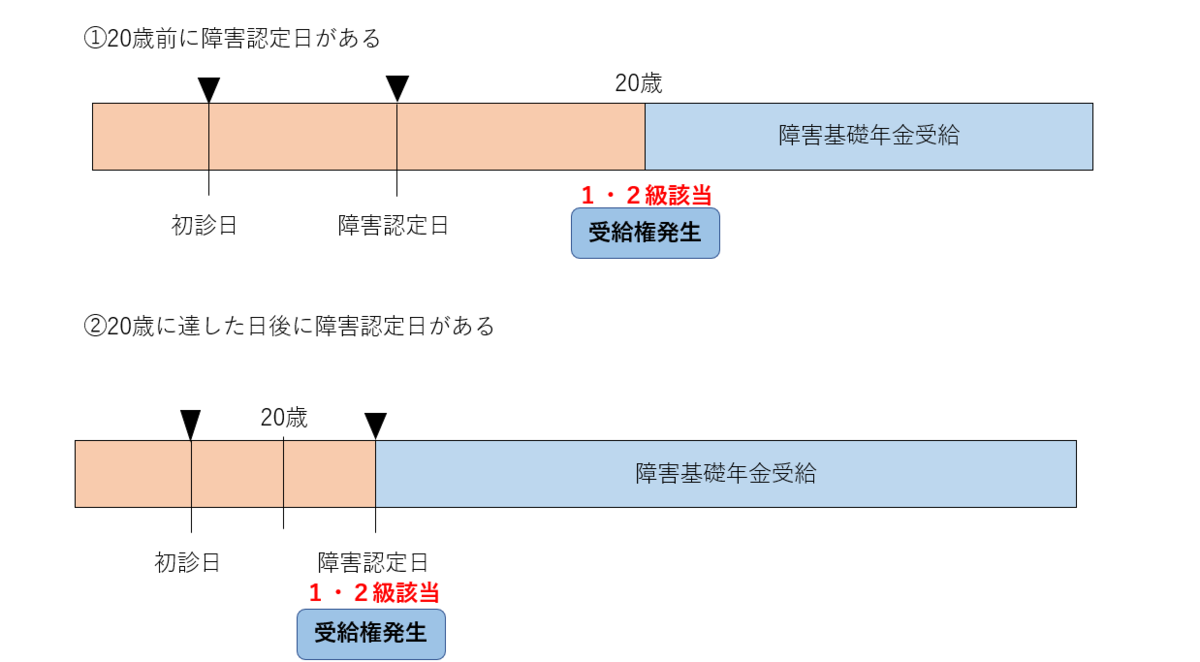
 ここを乗り越えよう!健康保険法
ここを乗り越えよう!健康保険法
R4-147
R4.1.16 健康保険の強制適用事業所
健康保険は、個人ごとに加入するのではなく、「事業所単位」で適用を受けます。
健康保険の適用を受ける事業所を「適用事業所」といい、強制的に適用される「強制適用事業所」と、厚生労働大臣の認可を受けて任意に適用を受ける「任意適用事業所」があります。
強制でも任意でも「適用事業所」に使用される者は、健康保険の被保険者となります。
今日は、「強制適用事業所」の要件をみていきます。
強制適用事業所は、法第3条で以下のように規定されています。
① 法定16業種の事業を行っている事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの (個人経営の事業所) ② 国、地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用するもの |
問題を解くときに最初にチェックするポイントは「個人経営」?それとも「法人」?です。
「法人」なら、業種関係なく、常時1人でも従業員がいれば強制適用事業所です。
「個人経営」なら、法定16業種か否か、5人以上か5人未満で、適用が変わります。
| 個人経営 | 法人 | ||
従業員数 | 5人以上 | 5人未満 | 1人以上 | |
業種 | 法定16業種 | 〇 | × | 〇 |
法定16業種以外 | × | × | 〇 | |
〇の事業所が強制適用事業所です。
×の事業所は強制適用ではありませんが、任意で加入することができます。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。
②【R1年出題】
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならない。
③【H24年出題】
健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は除かれる。

【解答】
①【H23年出題】 〇
・常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所
→飲食業は法定16業種以外の業種ですので、個人経営の場合は人数に関係なく、強制適用事業所になりません。
・常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所
→法人の場合は、業種に関係なく、常時従業員が1人でもいれば、強制適用事業所です。
(法第3条)
②【R1年出題】 ×
法人の代表者は、法人に使用される者として、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。
法人の場合は、常時1人以上の従業員がいれば強制適用です。代表者1人の法人でも強制適用事業所になります。
(昭24.7.28保発第74号)
③【H24年出題】 ×
適用除外の規定で被保険者になることができない者でも、常時雇用されている者なら、「常時5人以上」の人数に算入されます。
(昭18.4.5保発905号)
もう1問どうぞ!
④【R1年出題】
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】
④【R1年出題】 〇
健康保険法第3条では、「国、地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用するもの」は強制適用事業所です。
国、地方公共団体も健康保険の強制適用事業所になることに注意してください。
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。(適用除外されていません。)
ただし、法第200条で、「国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。」と規定されています。
共済組合と健康保険の両方から二重に保険給付を受けるのではなく、共済組合の組合員には健康保険の保険給付を行わないことになっています。なお、保険料も徴収されません。
(法第200条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-146
R4.1.15 メリット制の収支率の考え方 (過去問編)
前回からの続きです。
今回は、「収支率」のよく出るところを過去問で確認します。
さて、メリット収支率は、保険料に対する保険給付の割合です。
もう少し詳しく書くと、
(分母)「連続する3保険年度中の確定保険料×第1種調整率」
に対する
(分子)「保険給付等(業務災害に係る保険給付及び特別支給金)」
の割合です。
ポイント!
「分母」も「分子」も、「業務災害」に関するものだけ
収支率の計算に入るもの、入らないものを過去問で確認しましょう。
ではどうぞ!
①【R2年出題】(労災)
メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
②【H22年出題】(労災)
メリット収支率の算定に当たっては、特別加入の承認を受けた海外派遣者に係る保険給付及び特別支給金の額は、その算定基礎となる保険給付等の額には含まれない。
③【H18年出題】(労災)
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって、厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は含まれない。

【解答】
①【R2年出題】(労災) 〇
「特別支給金」も収支率の計算に入ります。
分子は、「業務災害として支給した保険給付+特別支給金」です。
(則18条の2)
②【H22年出題】(労災) 〇
「海外派遣者」は国内の使用者の指揮命令下にないので、海外派遣者の保険料、保険給付等の額ともに、収支率の計算に入りません。
★特別加入している「中小事業主」については、分母(保険料)、分子(保険給付)ともに収支率の計算に含まれます。
(則18条の2)
③【H18年出題】(労災) 〇
業務災害に対する保険給付のうち、以下のものは収支率の計算に入れません。
・ 遺族補償一時金(年金が失権した場合に支給される遺族補償一時金との差額)
・ 障害補償年金差額一時金
・ 特定の業務に長期間従事することにより発生する疾病であって厚生労働省令で定めるものにかかった者に係る保険給付の額
・ 海外派遣者に対する保険給付の額
※なお、特別支給金も同じ扱いです。
★「分母」もみておきましょう。
・ 収支率の「分母」は保険料。「一般保険料の額」+「第1種特別加入保険料の額」です。
あくまでも「業務災害」に関する保険料ですので、「非業務災害率」の部分は除外されることに注意してください。
「非業務災害率」は、一律1,000分の0.6です。
例えば、労災保険率が1,000分の3なら、業務災害の部分が「1,000分の2.4」、非業務災害の部分が「1,000分の0.6」です。
収支率の計算に入れるのは1,000分の2.4の部分です。
・ 分子と調整するために、分母の保険料の額には「第1種調整率」を乗じます。第1種調整率は、一般の事業は100分の67です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!徴収法
ここを乗り越えよう!徴収法
R4-145
R4.1.14 メリット制の収支率の考え方(制度の仕組み編)
労災保険率は、事業の種類ごとに決められています。
事業の種類によって労働災害が発生するリスクが異なるからです。
しかし、同じ種類の事業でも、作業環境の改善を行うなど個々の事業主の企業努力で災害発生率は変わります。
メリット制は、企業努力で労働災害を抑えた場合はその企業の労災保険率を引き下げる、逆に労働災害が多い場合はその企業の労災保険率を引き上げて、労働災害の防止のための努力を促す制度です。
継続事業、一括有期事業、単独有期事業のそれぞれでメリット制が設けられていますが、今日は、「継続事業」のメリット制のお話です。
メリット制適用の条件として、次の3点があります。
① 事業の継続性
連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)に労災保険に係る保険関係成立後3年以上経過していること
② 事業の規模
連続する3保険年度中の各保険年度に次の A か B のどちらかを満たしていること
A100 人以上の労働者を使用した事業
B20 人以上 100 人未満の労働者を使用した事業で、災害度係数が 0.4 以上
③収支率
収支率が100分の85を超え又は100分の75以下になることが必要です。
「収支率」が今日のテーマです。
★収支率とは?
「収支率」は、労災保険料に対する保険給付の割合です。政府から見ると労災保険料が収入、保険給付が支出です。労働災害が多いと、割合が高くなります。
★メリット制が適用される収支率の範囲は?
メリット収支率が低い(具体的には75パーセント以下)の場合は、労災保険率が低くなります。(最大で、40%割り引かれます)
逆にメリット収支率が高い(具体的には85%を超える)場合は、労災保険率が高くなります。(最大で40%割増されます。)
なお、75%を超え85%以下の時は、メリット制は適用されませんので、労災保険率の増減はありません。
ポイントは、メリット制に関係するのは「業務災害」だけという点です。
非業務災害(通勤災害や二次健康診断等給付)は、企業の努力でどうにかなるものではないからです。
次回に続きます。
次回は、メリット収支率の問題を解きます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!雇用保険法
ここを乗り越えよう!雇用保険法
R4-144
R4.1.13 就職促進給付の対象者
失業等給付には、次の4つがあります。
・ 求職者給付
・ 就職促進給付
・ 教育訓練給付
・ 雇用継続給付
今日は、失業等給付の中の一つ「就職促進給付」のお話です。
就職促進給付の中身は次の3つです。
1 就業促進手当
「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」
2 移転費
3 求職活動支援費
さて、一般被保険者が失業して、基本手当の受給資格を得ると「受給資格者」になります。
高年齢被保険者は「高年齢受給資格者」、短期雇用特例被保険者は「特例受給資格者」、日雇労働被保険者は「日雇受給資格者」になります。
「就職促進給付」の対象を一覧にまとめました。
「就業手当」、「再就職手当」、「就業促進定着手当」は「受給資格者」だけが対象です。
「常用就職支度手当」、「移転費」、「求職活動支援費」は受給資格者等が対象です。「等」がポイントです。
↓
就業促進手当 | 就業手当 | 受給資格者 |
再就職手当 | 受給資格者 | |
就業促進定着手当 | 受給資格者 (再就職手当の受給者で、要件を満たした人) | |
常用就職支度手当 | 受給資格者等 (受給資格者、高年齢受給資格者、 特例受給資格者、日雇受給資格者) | |
移転費 |
| 受給資格者等 |
求職活動支援費 |
| 受給資格者等 |
では、過去問です
①【H23年出題】
特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。
②【H21年出題】
特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。

【解答】
①【H23年出題】 〇
常用就職支度手当は以下の「受給資格者等」が対象です。
・受給資格者
→ 職業に就いた日の前日の基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 未満であること
・高年齢受給資格者
→ 高年齢求職者給付金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して 1 年を経過していない者を含む。
・特例受給資格者
→ 特例一時金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過していないものを含む
・日雇受給資格者
→ 日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者
常用就職支度手当のポイント
★「安定した職業に就いた受給資格者等」が対象です。
→ 1 年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等で常用就職支度手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるもの
★身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定める者
(法第56条の3第1項第2号、則第82条の3)
②【H21年出題】 ×
移転費は、受給資格者等が、
・公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介した職業に就くため
又は
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため
↓
↓
その住所又は居所を変更する場合で、公共職業安定所長が必要があると認めたときに支給されます。(法第 58 条第 1 項)
受給資格者等(受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が対象です。
問題文のように、特例受給資格者及び日雇受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就くために住所を変更する場合は、要件を満たせば、移転費を受給することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-143
R4.1.12 打切補償と傷病補償年金の関係 その2(問題編)
前回は、打切補償と傷病補償年金の関係を条文で読みました。
前回の記事 → R4.1.11 打切補償と傷病補償年金の関係 その1(条文編)
今回は実践編です。問題を解いてみましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。
②【H24年選択式】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により< A >を支払ったものとみなす。

【解答】
①【H29年出題】 〇
3年を経過した日に打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
下の図を参照してください。①のパターンです。
②【H24年選択式】
A 打切補償
次はこちらをどうぞ!
③【R2年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

【解答】
③【R2年出題】 ×
「3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り」の部分が誤りです。
打切補償を支払ったとみなされ解雇制限が解除されるのは、
①療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合
②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
です。
3年を経過した日に傷病補償年金を受けていなくても、その後受けることになった場合は、その傷病補償年金を受けることとなった日に、打切補償を支払ったものとみなされます。下の図の②のパターンです。
最後にこちらをどうぞ!
④【オリジナル】
通勤により負傷した労働者が、当該負傷に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。

【解答】
④【オリジナル】 ×
「通勤」による災害には使用者の補償責任はありません。労働基準法の解雇制限も適用されません。
ですので、傷病年金を受けていて打切補償を支払ったものとみなす規定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
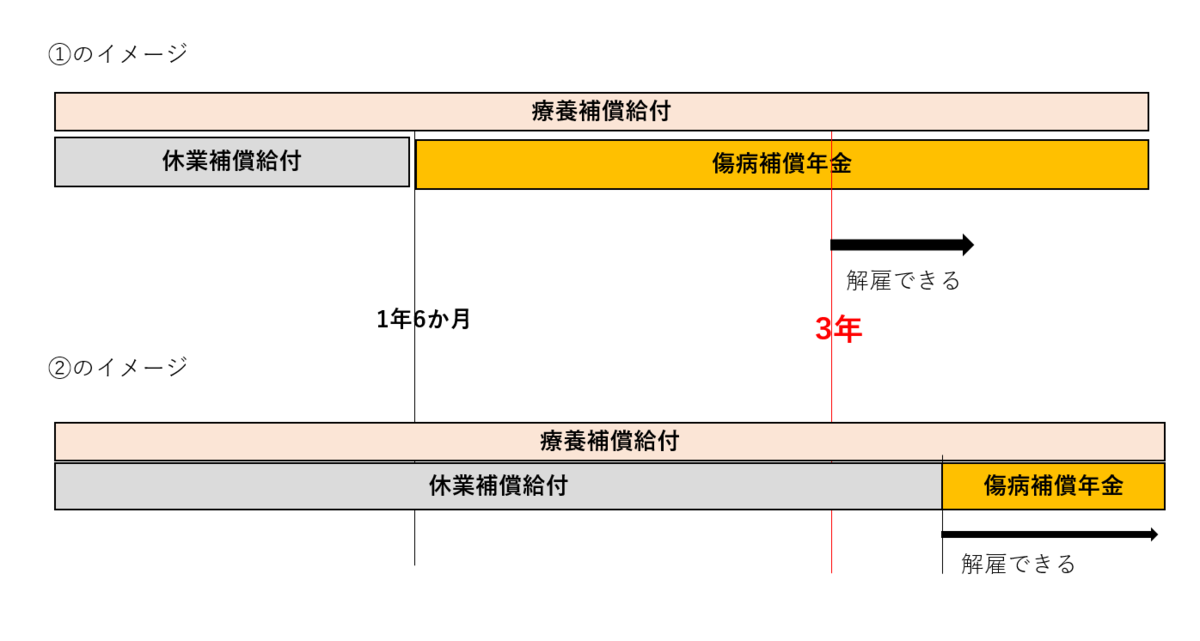
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-142
R4.1.11 打切補償と傷病補償年金の関係 その1(条文編)
まず、労働基準法の「解雇制限」の条文を読んでみましょう
労働基準法第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② ①の但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
労働基準法では、労働者が「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇禁止としています。
ただし、「使用者が打切補償を支払う場合」は解雇できる例外が設けられています。
では、次に打切補償の条文を読んでみましょう。
第81条 (打切補償) 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。 |
労働基準法では、労働者が「業務上」負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者に「療養補償」をする義務を課しています。
療養補償はなおるまで行わなければなりません。しかし、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合は、「打切補償」を行うことによって、以後補償する義務はなくなります。
「療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇が禁止されているのは、使用者に補償義務があるからです。「打切補償」を支払うと補償義務もなくなるので、解雇もできることになります。
しかし、業務上の負傷、疾病については、実際には労災保険法で補償が行われます。
ですので、使用者が労働基準法の療養補償を行うことはありません。そして、打切補償を行うこともありません。
労災保険法では、「傷病補償年金」を受けていることによって「打切補償」を行ったとみなす規定が設けられています。
「傷病補償年金」を受けているということは、「なおっていない」ことなので、解雇はできないことを頭において条文を読んでみてください。
労災保険法第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |
労働基準法の「打切補償」が療養開始後3年を経過してもなおらない場合なので、この条文も「3年」がキーワードです。
①療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合
②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
①は「3年を経過した日」、②は「傷病補償年金を受けることとなった日」に「打切補償」を支払ったものとみなされ、解雇することができるようになります。
(下の図も参考にしてください)
次回は、「問題編」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
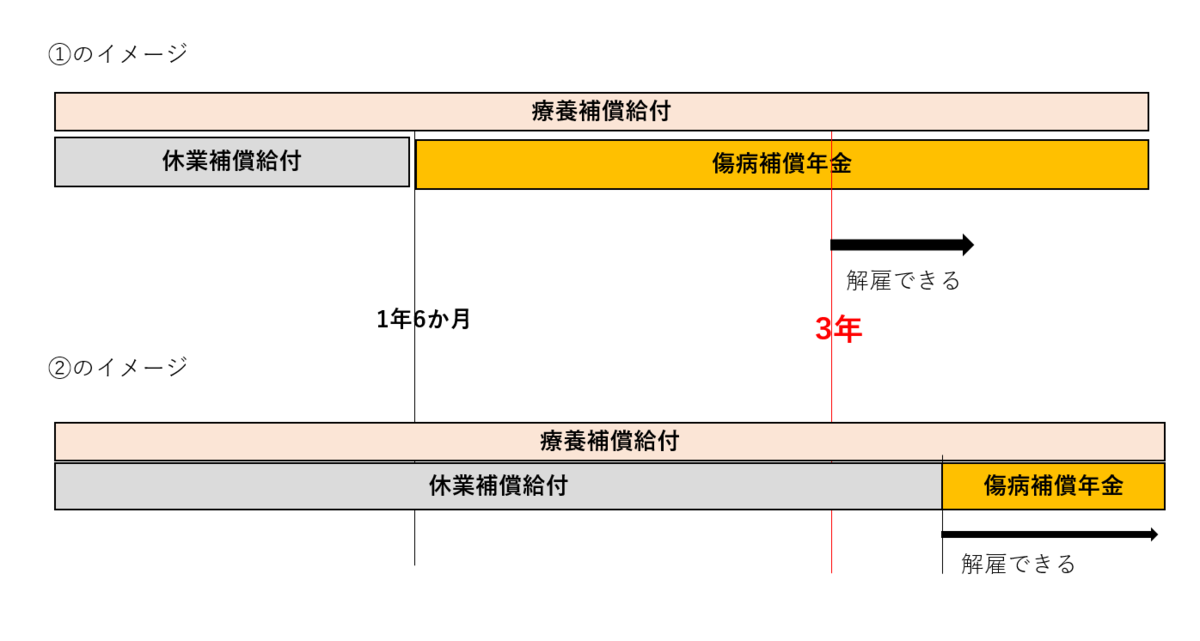
 ここを乗り越えよう!労働安全衛生法
ここを乗り越えよう!労働安全衛生法
R4-141
R4.1.10 健康診断の種類
条文を読んでみましょう。
第66条 (健康診断) ① 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。 ② 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 ③ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 ④ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 |
①から④の内容は以下の通りです。
①は「一般健康診断」です。
■ 雇入れ時の健康診断
■ 定期健康診断
・1年以内ごとに1回
■ 特定業務従事者の健康診断
・「配置替えの際」と「6か月以内ごとに1回」
■ 海外派遣労働者の健康診断
・海外に6か月以上派遣される労働者
・6か月以上の海外派遣から国内勤務になったとき
■ 給食従業員の検便
・雇入れの際
・当該業務への配置換えの際
②は一定の有害業務に従事する労働者に対する「特別の項目」についての健康診断です。
有害因子が健康に及ぼす影響を把握するために行います。
・有害業務に従事する労働者
・有害業務に従事した後他の業務に配置転換した労働者(後から表面化することがあるため)
③は、「歯科医師」による健康診断です。
一定の有害な業務に従事する労働者が対象です。
・雇入れの際
・当該業務への配置換えの際
・当該業務に就いた後6か月以内ごとに1回
④は、都道府県労働局長が指示する「臨時の健康診断」です。
では、過去問をどうぞ
①【H23年選択式】
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。
②【H17年出題】
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
③【H27年出題】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。
④【R2年選択式】
事業者は、労働者を本邦外の地域に< A >以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
⑤【H15年出題】
事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際及び1年以内ごとに1回、定期に、検便による健康診断を行なわなければならない。
⑥【条文穴埋め問題】
都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、 < A >の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。

【解答】
①【H23年選択式】
A 常時使用する
「雇入れ時の健康診断」、「定期健康診断」は、「常時使用する労働者」が対象です。
(則第43条、第44条)
②【H17年出題】 〇
③【H27年出題】 〇
②の「強烈な騒音を発する場所における業務」と③の「深夜業を含む業務」は「特定業務従事者の健康診断」の対象となる業務です。「当該業務への配置替えの際」と「6か月以内ごとに1回」の健康診断が必要です。
対象になる業務は、則第13条に定められています。
則第13条は、専属の産業医の選任が必要な事業場(その業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場)の有害業務を定めていて、500人以上で専属の産業医が必要な有害業務と、特定業務従事者に当たる有害業務は範囲が同じなのがポイントです。
特に「深夜業を含む業務」はよく出ますので注意してください。
(則第13条、第45条)
④【R2年選択式】
A 6月
(則第45条の2)
⑤【H15年出題】 ×
給食従事者の検便が義務づけられるのは、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際です。「1年以内ごとに1回などの定期」の義務はありません。
(則第48条)
⑥【条文穴埋め問題】
A 労働衛生指導医
労働衛生指導医は、都道府県労働局に置かれます。
労働衛生指導医は、「臨時の健康診断の指示」と「作業環境測定の実施の指示」で「都道府県労働局長」とセットで出てきます。
(法第65条、第66条、第95条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法編
ここを乗り越えよう!労働基準法編
R4-140
R4.1.9 1か月単位の変形労働時間制 その2(導入手続き)
前回に引き続き、1か月単位の変形労働時間制です。
今回は、1か月単位の変形労働時間制の導入の手続のお話です。
条文を読んでみましょう。
第32条の2 ① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間・特例の場合は44時間)を超えない定めをしたときは、その定めにより、特定された週において法定労働時間(40時間・特例の場合は44時間)又は特定された日において法定労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の協定を行政官庁に届け出なければならない。 |
1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」が必要です。
★ポイントその1
「又は」がポイント。「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらかという意味です。
なお、「労使協定」は所轄労働基準監督署長に届け出が必要です。
★ポイントその2
「就業規則に準ずるもの」がポイント。
「就業規則に準ずるもの」で導入できるのは労働者が10人未満の事業場です。労働者が10人以上の事業場は就業規則の作成義務がありますので、「就業規則に準ずるもの」では導入できません。
・10人以上の事業場 → 「労使協定」か「就業規則」(就業規則に準ずるものは不可)
・10人未満の事業場 → 「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」
★ポイントその3
「特定された週」「特定された日」がポイント。
労使協定や就業規則等に、各日、各週の所定労働時間を具体的に定めることが必要です。業務の都合があったとしても、使用者が途中で任意に変更することはできません。
では、過去問をどうぞ
①【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。
③【H18年出題】
労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「就業規則その他これに準ずるものによる定め」だけでも採用することができます。
また、労使協定で採用することもでき、その場合は所轄労働基準監督署長に届け出が必要です。
しかし、問題文の「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。」の部分は誤りです。1か月単位の変形労働時間制の労使協定の効力は届け出によって発生するのではなく、労使協定の締結で発生します。
(H11.1.29基発45号)
②【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制では、1日、1週間の労働時間の限度は設けられていません。
(S63.1.1基発1号)
③【H18年出題】 ×
変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内であったとしても、途中で、任意に労働時間を変更することはできません。
(S63.1.1基発1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労働基準法編
ここを乗り越えよう!労働基準法編
R4-139
R4.1.8 1か月単位の変形労働時間制 その1
法定労働時間は、原則として1週40時間以内、1日8時間以内です。
例えば、月から金が所定労働日、土日が休日の場合で、1日の労働時間が8時間の場合、カレンダーは以下のようになります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 休 | 休 |
これで法定労働時間ピッタリです。
もし、月曜日に2時間残業したとすると、その2時間は法定時間外労働となりますので、2割5分以上の割増賃金が必要です。
さて、「1か月単位の変形労働時間制」は、1か月以内の一定の期間を平均して1週40時間(特例の事業場は44時間)以内であれば、長く労働する日や、長く労働する週があってよい、という制度です。
なお、1か月以内の一定の期間は、1週間でも2週間でも1か月でも任意に設定でき、その期間のことを変形期間といいます。
変形期間を平均して1週40時間(特例は44時間)とするには、まず、変形期間の労働時間の総枠を計算します。
計算式は次の通りです。
40時間(特例44時間)×変形期間の暦日数÷7
例えば変形期間を1か月と設定して計算してみましょう。
(前提)法定労働時間40時間、変形期間の暦日数31日
40時間×31日÷7 ≒ 177.1時間
1か月のトータルの労働時間が177.1時間以内なら、平均すると1週40時間以内になります。
例えば、月初が業務多忙な場合は、月初の労働時間を長くして全体のバランスをとることができます。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9時間 | 9時間 | 9時間 | 9時間 | 9時間 | 9時間 | 休 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 休 | 休 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 休 | 休 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 休 | 休 |
29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
6時間 | 6時間 | 6時間 |
|
|
|
|
変形労働時間制を採用すると、「特定された週」又は「特定された日」に法定労働時間を超えて労働させることができます。
上のカレンダーは1か月トータルの労働時間が177時間です。1週目の労働時間だけみると、1日9時間、1週54時間ですが、変形期間を平均すると1週40時間以内になりますので時間外労働にはなりません。
では、過去問をどうぞ
①【H19年出題】
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

【解答】
①【H19年出題】 〇
計算式「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」のポイント!
・その事業場の週法定労働時間
→ 原則40時間ですが、特例事業場は「44時間」です。
・変形期間の暦日数
→ 「労働日数」ではなく「暦日数」です。例えば、1週間なら7日、4週間なら28日です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ⑦ 国年・厚年(旧法から新法へ)
どんな法律シリーズ⑦ 国年・厚年(旧法から新法へ)
R4-138
R4.1.7 国年・厚年その2(旧法から新法へ)
前回は、年金制度の創成期のお話をしました。
その後の経済の高度成長の中で、年金制度も充実期を迎えます。
そして、加速する高齢化、経済成長の安定化から、公的年金も大きな見直しが行われました。
昭和60年改正の大きな柱は次の3つです。
① 基礎年金の導入
② 厚生年金の給付水準の適正化
③ 女性の年金権の確立
「昭和61年4月1日」前後で年金制度が大きく変わります。昭和61年4月1日前の制度を「旧法」、それ以後を「新法」といいます。
① 基礎年金の導入について
それまでの公的年金は、自営業者等が加入する「国民年金」、民間の会社員が加入する「厚生年金」、公務員等が加入する「共済年金」の大きく3つに分かれていました。
それぞれが独自に運営されていたので、給付面でも負担面でも制度間に格差があったこと、また、産業構造の変化に伴い財政基盤が不安定になる問題も起こっていました。
このため、登場したのが「全国民共通の基礎年金」です。
国民年金は「基礎年金」として、全国民共通の年金を担当することになりました。また、厚生年金等の被用者年金は基礎年金に上乗せされる報酬比例年金として位置づけられました。
「基礎年金」の導入によって、1階部分が「基礎年金」、2階部分が「厚生年金や共済年金」となる「2階建ての年金」の方式になりました。
② 厚生年金の給付水準の適正化について
加入期間が延びてもこれ以上給付水準が高くならないよう、給付乗率や定額単価も見直しが行われました。
具体的には、大正15年4月2日から昭和21年4月1日以前生まれの人の給付乗率や定額単価は、生年月日が若くなっていくほど逓減していきます。
新法施行時に40歳未満だった昭和21年4月2日以後生まれの人には新法の給付乗率や定額単価を適用しますが、40歳を過ぎていた昭和21年4月1日以前生まれの人は、旧法の水準から徐々に新法の水準に近づけていくイメージです。昭和61年4月1日を境に、給付乗率や定額単価をいきなり減らすことができないからです。
③ 女性の年金権の確立について
旧法では民間サラリーマン等の妻(専業主婦)は、国民年金には「任意で加入できる」位置づけでした。任意加入しなかった場合は、老後は、サラリーマンの夫の年金に加算される配偶者加給年金額で保障されることになっていました。
ただし、妻が任意加入していない場合は、離婚すると老齢年金が受給できない、障害になっても障害年金が受給できない問題もありました。
そのため、新法では、サラリーマン等の妻(専業主婦)も国民年金に第3号被保険者として加入することになりました。ただし、保険料は、第3号被保険者が個別に負担するのではなく、夫の加入する被用者年金制度全体で負担しています。
※妻と夫が逆の場合も同じです。
過去問をどうぞ!
【H15年選択式】
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。

【解答】
A 大正15年4月2日
★「基礎年金」という名称が登場するのは新法からです。
新法の「老齢基礎年金」が支給されるのは、昭和61年4月1日に60歳未満だった大正15年4月2日以降生まれの人です。ただし、大正15年4月2日以降生まれでも、昭和61年3月31日に旧法の老齢・退職給付の受給権があった場合は、そのまま旧法が適用されます。
B 障害認定日
★障害基礎年金は障害認定日に受給権が発生します。障害認定日(受給権の発生日)が昭和61年4月1日以降なら、新法の障害基礎年金が支給されます。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
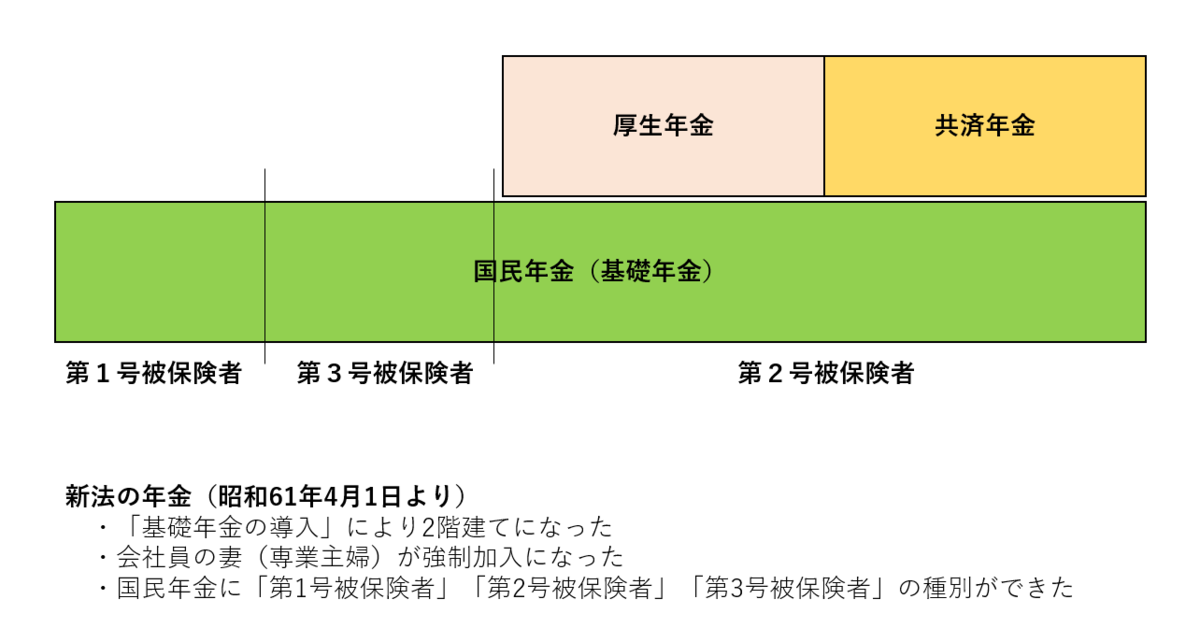
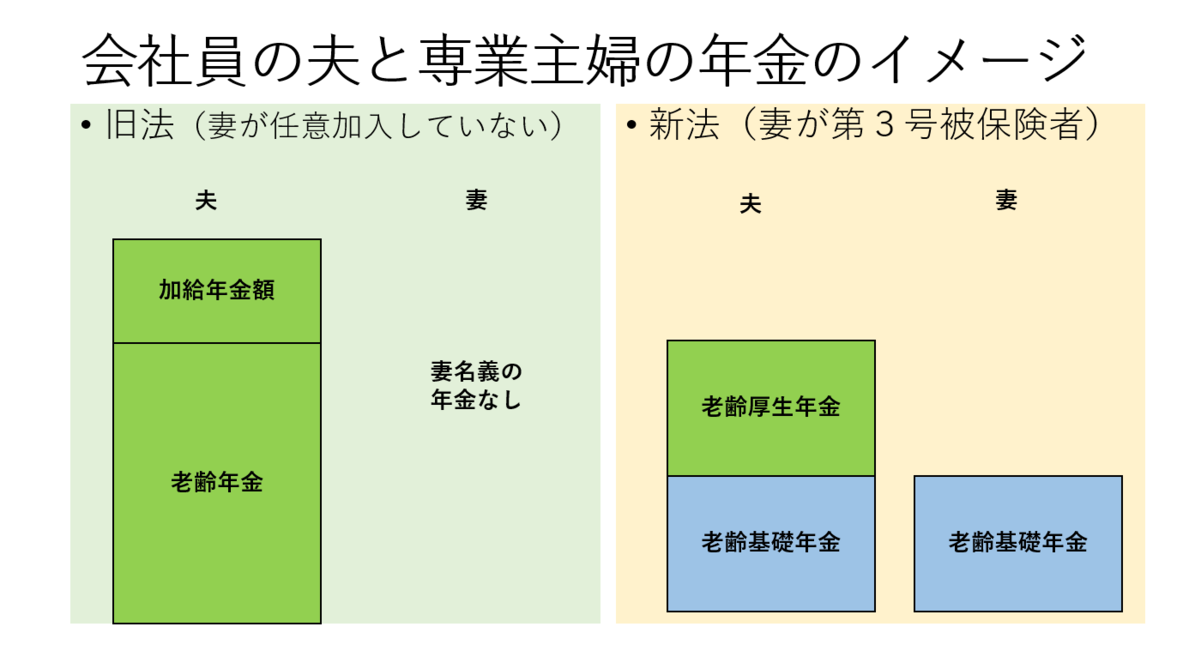
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
 どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法
どんな法律シリーズ⑥ 国民年金法・厚生年金保険法
R4-137
R4.1.6 国民年金法・厚生年金保険法ってどんな法律?その1
今日は、厚生年金保険法・国民年金法の創成期のお話です。
・昭和17年 労働者年金保険法発足
(昭和19年厚生年金保険法に改称)
・昭和29年 厚生年金保険法全面改正
(「定額部分+報酬比例部分」という2階建ての給付方式を採用)
・昭和36年 国民年金法全面施行
(国民皆年金の実現)
★昭和17年にスタートした労働者年金は、工場等で働く男子労働者を被保険者としていました。労働力の保全強化を図ることなどが背景にありました。
昭和19年に名称が厚生年金保険法に改められ、被保険者の範囲は、事務職員や女性にも広がりました。
報酬比例部分のみだった養老年金が、「定額部分」と「報酬比例部分」の2階建ての老齢年金になったのが、昭和29年の改正です。
★民間の会社員や公務員には公的な年金制度があり、老後の所得が保障されていましたが、自営業者等には、そのような制度が無いことが問題になっていました。
しかし、自営業者等にも老後の保障が必要だということで、国民年金法が制定されたのが昭和34年です。拠出制の国民年金制度が昭和36年に施行され、国民皆年金が実現しました。
「国民皆年金」とは、民間の会社員、公務員だけでなく、それ以外の自営業者等もすべての人が職業に関係なく公的年金の保護の対象になるという意味です。
なお、拠出制は昭和36年からですが、無拠出制の福祉年金制度は昭和34年からスタートしていました。
既に高齢になっている人、障害のある人等には、全額国庫負担の老齢福祉年金、障害福祉年金、母子福祉年金等が支給されました。
★老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480月)の全てが保険料納付済期間なら満額の年金が支給されます。
しかし、大正15年4月2日から昭和16年4月1日以前生まれの人は、480月ではなく、加入可能年数×12で計算します。
なぜなら、国民年金制度が発足した昭和36年4月1日に既に20歳になっているからです。その年代の人は、昭和36年4月1日から60歳までの間の全てが保険料納付済期間なら、満額の老齢基礎年金が支給されます。
例えば大正15年4月2日~昭和2年4月1日の間に生まれた人は「25年」、昭和15年4月2日~昭和16年4月1日の間に生まれた人は39年が加入可能年数です。
20歳から60歳まで40年間加入できるのは、昭和16年4月2日以後生まれの人です。
★創成期の年金のポイントは以下の通りです。
(創成期の年金の特徴)
・「縦割り」の運営でした
制度ごとに支給要件や給付水準が設定されていて、統一されていませんでした。
・加入が「任意」な人もいました
例えば、会社員の妻などは任意加入でした。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
【H19年出題】 ×
無拠出制の福祉年金の給付の開始は、昭和34年11月からです。10月ではありません。
(法附則第1条)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
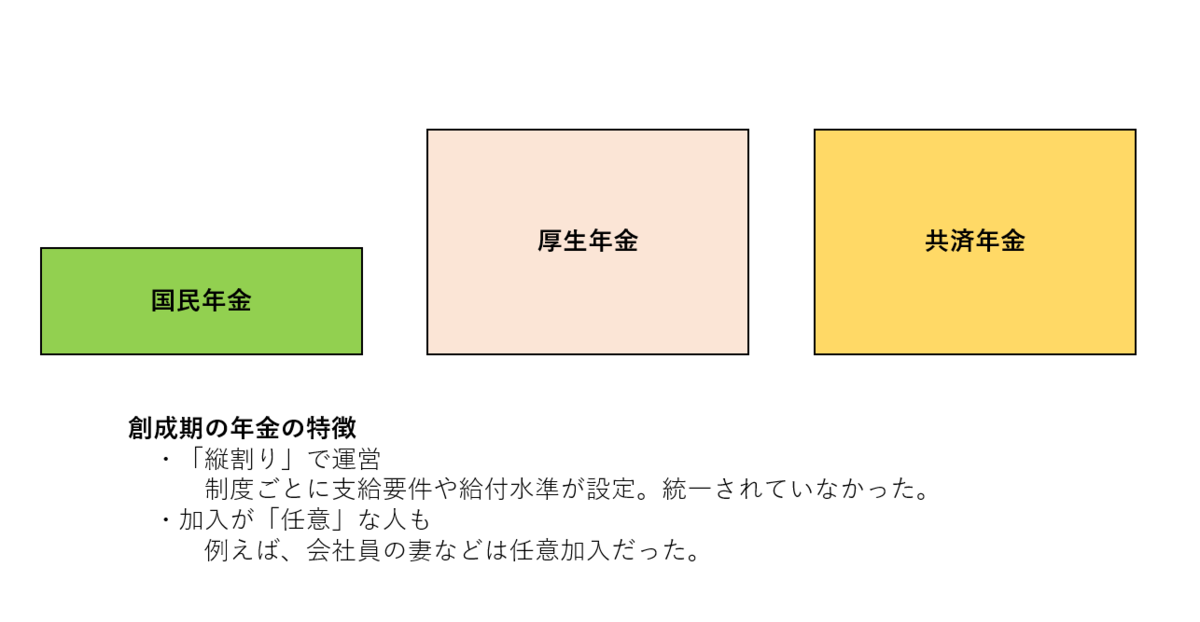
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
 どんな法律シリーズ⑤ 健康保険法
どんな法律シリーズ⑤ 健康保険法
R4-136
R4.1.5 健康保険法ってどんな法律?
健康保険法・・・大正11年制定、大正15年7月施行、昭和2年1月全面施行
(制定から全面施行までの期間が長いのがポイントです)
「保険料を負担」することによって「保険給付を受けられる」ことが保険の仕組みです。
「保険者」とは、保険の運営主体のことで、健康保険法の場合は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」です。
「被保険者」とは保険料を負担する義務と保険給付を受ける権利がある人のことです。
被保険者は「保険料」を納付することによって、保険事故(業務災害以外の負傷、疾病若しくは死亡又は出産)の際は、保険給付を受けることができます。
ケガや病気の場合は、保険医療機関で診察や薬を受けたり、場合によっては入院や手術のこともありますが、それも保険給付の1つで「療養の給付」といいます。
さて、健康保険は、個人で加入するのではなく、「事業所」単位で加入するのがポイントです。
法律上当然に健康保険の適用を受ける事業所を「強制適用事業所」、厚生労働大臣の認可を受けて任意に加入した事業所を「任意適用事業所」といいます。
強制でも任意でも健康保険の「適用事業所」で使用される者は、健康保険の被保険者となります。(ただし、被保険者になるには、一定の条件があります。)
よく出るポイントを過去問で確認しましょう。
①【H18年出題】
船員保険の被保険者及び疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができない。
②【H20年出題】
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。

【解答】
①【H18年出題】 ×
「船員保険」は船員を対象とした医療保険ですので、「船員保険の被保険者」は健康保険の被保険者から除外されます。しかし、疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者になることができます。
(法第3条)
②【H20年出題】 ×
後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被保険者から除外されますので、健康保険の資格は喪失します。
(法第3条)
★日本は「国民皆保険制度」をとっていますので、すべての人が公的な医療保険で治療を受けることができます。
医療保険には、「健康保険」、「船員保険」、「共済組合(国家公務員、地方公務員)」、「私立学校教職員共済」、「国民健康保険」があり、健康保険がその中心になっています。
また、原則として75歳以上の人は「後期高齢者医療」の被保険者となりますので、各医療保険からは除外されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ④ 雇用保険法
どんな法律シリーズ④ 雇用保険法
R4-135
R4.1.4 雇用保険法ってどんな法律?
雇用保険法・・・昭和49年制定、昭和50年施行
(「失業保険法」は昭和22年施行、雇用保険制定により廃止)
まず、目的条文を読んでみましょう。空欄を埋めてください。
第1条
雇用保険は、労働者が< A >した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< B >するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< C >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の< D >及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【解答】
A 失業
B 子を養育
C 職業の安定
D 能力の開発
雇用保険は「失業」のみならず、雇用に関する総合的な機能を有する制度です。
体系的にイメージしましょう。
第3条では次のように定められています。
第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 |
・ 労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に「失業等給付」、子を養育するための休業をした場合に「育児休業給付」を支給します。
・ 失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るために「雇用保険二事業」として雇用安定事業と能力開発事業を行っています。
| 雇用保険 | 失業等給付 | 求職者給付 |
| 就職促進給付 | ||
| 教育訓練給付 | ||
| 雇用継続給付 | ||
| 育児休業給付 | ||
| 雇用保険二事業 | 雇用安定事業 | |
| 能力開発事業 |
「育児休業給付」は、令和2年4月に「失業等給付」から分離され、「子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付」として位置づけられています。
「雇用保険二事業」では主に企業に対する助成金の事業を行っています。「雇用調整助成金」もその一つです。
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた。しかし、従業員を解雇するのではなく、休業させ従業員の雇用の維持を図った。休業させる場合は休業手当を支払わなければなりませんが、その休業手当を助成しているのが雇用調整助成金です。
「雇用の安定」を図ったことに対する助成ですので、「雇用保険二事業」のうちの「雇用安定事業」で行われます。
なお、雇用保険料は賃金総額×雇用保険率で計算します。(詳しくは徴収法で勉強します。)
雇用保険率は、一般の事業の場合、令和3年度は1,000分の9です。
1000分の9のうち、「1000分の6」は、失業等給付と育児休業給付に、1000分の3は雇用保険二事業に充てられます。
1000分の6の部分は事業主と労働者が折半します。
1000分の3は事業主が全額負担します。主に企業に対する助成金を行っているからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ③ 労働者災害補償保険法
どんな法律シリーズ③ 労働者災害補償保険法
R4-134
R4.1.3 労災保険法ってどんな法律?
労働者災害補償保険法・・・昭和22年施行
労働基準法と時を同じくして公布・施行されました。
労働基準法の第8章は「災害補償」です。
労働者の業務上の負傷等について、使用者に対して、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料を行うことが定められていて、また打切補償についても規定されています。
ただ、実際に、大きな業務災害が起こった時などに、使用者が災害補償を完全に履行できるかが問題です。
その問題を解決するのが労災保険です。
「保険」の仕組みをとり、すべての事業主が保険料を負担し、いざ、災害が発生したときは迅速に労働者に対して補償が行われる制度です。
使用者の「災害補償」の責任を代行するのが労災保険です。
労災保険は、保険料は全額事業主負担、保険給付の対象は全ての労働者であることがポイントです。被保険者という概念もありません。
他の公的保険、例えば健康保険には「被保険者」の範囲が位置付けられていて、被保険者は事業主と折半で保険料を負担し、負傷等の場合は被保険者に対して保険給付が行われます。
さて、労災保険は当初は「業務災害」だけが保護の対象でしたが、交通事情等の変化に伴い通勤途上の災害も保護する必要がでてきました。
「通勤災害」が労災保険の保護の対象に加わったのは、昭和48年の改正です。
そして、過労死等の原因になる脳血管疾患及び心臓疾患の発症を予防するための「二次健康診断等給付」が加わったのは、平成13年4月です。
さらに、令和2年9月からは、「複数事業労働者」への保険給付(複数業務要因災害に関する保険給付)も加わりました。
★では、目的条文を読んでみましょう。空欄を埋めて下さい。
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は< A >による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は< A >により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< B >に寄与することを目的とする。
解答は、A 「通勤」、B 「福祉の増進」です。
なお、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等の「等」は、二次健康診断等給付をさしています。
★では、次は第2条の2です。
| 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 |
労災保険法のメインの目的は「保険給付」を行うことです。
そして保険給付に付帯する事業が「社会復帰促進等事業」です。
■保険給付は、次の4つです。
① 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
② 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(①に掲げるものを除く。)
③ 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付
④ 二次健康診断等給付
■「社会復帰促進等事業」は次の3つです。
① 被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 (社会復帰促進事業)
② 被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 (被災労働者等援護事業)
③ 労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 (安全衛生確保等事業)
例えば、業務上の負傷が治癒し、障害等級第1級の障害が残った場合は、保険給付として、「障害補償年金」が支給されます。
それに上乗せして、社会復帰促進等事業の「被災労働者等援護事業」から「特別支給金」として、障害特別支給金と障害特別年金が支給されます。
(例)障害等級1級の場合
(社会復帰促進等事業) 特別支給金 | 障害特別年金 (算定基礎日額×313日分)/年 |
障害特別支給金 342万円(一時金) | |
(保険給付) | 障害補償年金 (給付基礎日額×313日分)/年 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ② 労働安全衛生法
どんな法律シリーズ② 労働安全衛生法
R4-133
R4.1.2 労働安全衛生法ってどんな法律?
労働安全衛生法・・・昭和47年制定
労働基準法が制定されたのは昭和22年です。そのときの労働基準法の第5章には、「安全及び衛生」の規定が設けられていました。
その後、日本の経済、産業は高度成長に入っていきます。
昭和47年の労働安全衛生法制定時の通達では、「近年のわが国の産業経済の発展は、世界にも類のない目ざましいものがあり、それに伴い、技術革新、生産設備の高度化等が急激に進展したが、この著しい経済興隆のかげに、今なお多くの労働者が労働災害を被っているという状況にある」とあります。
そこで、「最低基準の遵守確保」だけでなく、「労働災害の防止に関する総合的、計画的な対策を推進」することにより「職場における労働者の安全と健康を確保」し、「快適な職場環境の形成を促進すること」が目的になっているのが労働安全衛生法です。
労働基準法で規制できるのは、使用者と労働者の雇用関係のみですが、労働安全衛生法は、機械や原材料、重層的下請関係なども規制しているのが特徴です。
労働安全衛生法は、労働基準法の一部だった「安全及び衛生」が労働基準法から分離し、昭和47年に独立した法律です。
(参考)昭和47.9.18 基発第91号
では、過去問を解いてみましょう
①【H15年選択式】
労働安全衛生法と労働基準法との関係については、労働安全衛生法制定時の労働事務次官通達で明らかにされており、それによると、労働安全衛生法は形式的には労働基準法から分離独立したものとなっているが、安全衛生に関する事項は労働者の< A >の重要な一端を占めるものであり、労働安全衛生法第1条、労働基準法第42条等の規定により、労働安全衛生法と< A >についての一般法である労働基準法とは < B >関係に立つものである、とされている。
②【H29年出題】
労働安全衛生法は、労働基準法と一体的な関係にあるので、例えば「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、」に始まる労働基準法第1条第2項に定めるような労働憲章的部分は、労働安全衛生法の施行においても基本となる。

【解答】
①【H15年選択式】
A 労働条件
B 一体としての
★ポイント! 労働安全衛生法と労働基準法は『一体としての関係』に立つ
(参考)昭和47.9.18 基発第91号
なお、上記の記述には、「賃金、労働時間、休日などの一般的労働条件の状態は、労働災害の発生に密接な関連を有することにかんがみ、かつ、この法律の第1条の目的の中で「労働基準法と相まって、……労働者の安全と健康を確保する……ことを目的とする。」と謳っている趣旨に則り、この法律と労働基準法とは、一体的な運用が図られなければならないものである。」と続きます。
②【H29年出題】 〇
労働基準法の労働憲章的部分(具体的には第1条から第3条まで)は、労働安全衛生法の施行にあたっても当然その基本とされなければならない、とされています。
(参考)昭和47.9.18 基発第91号
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 どんな法律シリーズ① 労働基準法
どんな法律シリーズ① 労働基準法
R4-132
R4.1.1 労働基準法ってどんな法律?
労働基準法 ・・・ 昭和22年4月制定
まず、こちらの条文を読んでみましょう。
第13条 (労働基準法違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 |
例えば、使用者と労働者が、こんな内容の労働契約を締結した場合を考えてみましょう。
・ 始 業 8時
・ 終 業 21時
・ 休憩時間 12時~13時
・ 休 日 毎週日曜日
労働基準法の法定労働時間は、週40時間・1日8時間以内が原則ですが、その最低ラインよりも不利な労働契約の内容です。
この場合は、第13条にあるように、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約」は、「その部分については無効」です。
労働基準法よりも不利な内容の部分は空欄になります。
そして、「無効となった部分は、この法律で定める基準による」となるので、空欄になった部分は労働基準法の基準に書き換えられます。
もう一つのポイントは、労働契約全体が白紙になるのではなく、労働基準法より不利な部分だけが空欄になることです。
労働契約全体が白紙になると、労働契約自体が無くなってしまい、それはそれで労働者保護に欠けてしまうからです。
では、過去問をどうぞ
①【H25年出題】
労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
②【H21年出題】
労働基準法で定める基準に違反する労働条件を定める労働契約の部分は、労働基準法で定める基準より労働者に有利なものも含めて、無効となる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効になるだけでなく、無効になった部分は、労働基準法の基準で補充されます。
②【H21年出題】 ×
労働基準法の基準は最低ラインです。労働基準法の基準より有利なものはもちろん有効です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉛」条文の読み方(労働基準法)
「最初の一歩㉛」条文の読み方(労働基準法)
R4-131
R3.12.31 「総日数」と「労働日数」の違い
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、平均賃金の条文を読んでみましょう。
第12条 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。 1 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60 2 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 |
平均賃金の計算式の原則は、「3か月間の賃金総額÷その期間の総日数」です。
ポイント!総日数は「暦上の日数」
例えば、12月21日が算定事由発生日で、賃金締切日が15日の場合は、平均賃金は直前の賃金締切日の12月15日から遡った3か月で計算します。
9月16日~10月15日、10月16日~11月15日、11月16日~12月15日の賃金総額を91日(その期間の総日数)で除します。
また、日給、時給、出来高払制その他の請負制の場合は、最低保障が設けられています。
計算式は、「3か月間の賃金の総額÷その期間中に労働した日数×100分の60」です。
ポイント! 「労働日数」は、暦上の日数ではなく、実際に労働した日数
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。

【解答】
①【H19年出題】 〇
この問題のチェックポイントは、
原則は、「その期間の総日数」で除すこと。
最低保障は、「その期間中に労働した日数」で除すこと、「100分の60」を忘れないようにしてください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉚」条文の読み方(厚生年金保険法)
「最初の一歩㉚」条文の読み方(厚生年金保険法)
R4-130
R3.12.30 「被保険者であった期間」と「被保険者期間」
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
条文を読んでみましょう。
第19条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 |
『被保険者期間』は月単位で算定されます。
例えば、12月31日に資格取得、1月31日に退職した(資格喪失は2月1日)場合は、被保険者期間は2か月です。
「被保険者期間」は、年金額の計算(平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数)や、保険料の徴収(被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収される)に使われます。
では、こちらの過去問をどうぞ
①【H21年出題】
厚生年金保険法で定める「被保険者期間」とは、被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの日単位で計算される期間である。

【解答】
①【H21年出題】 ×
被保険者の資格を取得した日から被保険者の資格を喪失した日の前日までの『日単位』で計算される期間は「被保険者であった期間」のことです。12月31日資格取得、1月31日退職・2月1日資格喪失なら、被保険者であった期間は、12月31日から1月31日までの32日間です。
「被保険者期間」は、最初に書きましたように「月単位」で算定します。
次にこちらの条文を読んでみましょう。
第47条 (障害厚生年金の受給権者) 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(「初診日」)において被保険者であった者が、・・・(以下略)
附則第9条の3 (長期加入者の特例) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるときは、報酬比例部分と定額部分を合わせた年金が支給される。 |
★第47条
「被保険者であった者」に注目してください。障害厚生年金は、初診日に「被保険者」であったことが要件です。
厚生年金保険法で「被保険者であった」ということは、在職中だったという意味です。ですので、障害厚生年金は在職中に初診日があることが条件です。
★附則第9条の3
「被保険者でなく」に注目してください。
長期加入者(44年以上)に対して、報酬比例部分に定額部分が加算される特例の条件は、「被保険者でない」ことイコール退職していることです。
定額部分が加算されるには退職していることが必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉙」条文の読み方(労働安全衛生法)
「最初の一歩㉙」条文の読み方(労働安全衛生法)
R4-129
R3.12.29 「努める」(努力義務)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第3条 ① 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 |
第3条と第4条の語尾を比べてください。第4条の主語は「労働者」で、語尾は「努めなければならない」で、努力義務です。
労働者は労働安全衛生法では保護される立場です。しかし労働災害を防止するためには、労働者の協力も不可欠です。ただし、厳格に義務づけるのではなく、もう少し軟らかめに努力を促しています。
では、過去問をどうぞ
①【H12出題】
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

【解答】
①【H12出題】 〇
努力義務がポイントです。
では、こちらの条文を穴埋めで確認しましょう。
第3条
② 機械、器具その他の設備を< A >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< A >する者は、これらの物の< A >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に< B >。

【解答】
A 設計
B に資するように努めなければならない
「努力義務」がポイントです。
機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者についても、それぞれの立場で労働災害の防止の措置を講ずる努力が求められています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉘」条文の読み方(健康保険法)
「最初の一歩㉘」条文の読み方(健康保険法)
R4-128
R3.12.28 「行わない」と「行わないことができる」の違い
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第116条 被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
第117条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第119条 保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。 |
第116条の「行わない」は絶対的給付制限で、「絶対に支給しない」という意味です。保険者の裁量で、「行う」、「行わない」を決めることはできません。
第117条は、「その全部又は一部を行わないことができる」で保険者が適用するか否かを決めます。「行う」、「行わない」又は「全部」なのか「一部」なのかは保険者が判断します。
第119条は、「行わないことができる」ですが、「全部又は一部」ではなく「一部」になっているのがポイントです。「全部を停止する」ことはできません。
では、過去問をどうぞ
①【R3年出題】
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
②【H23年出題】
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その給付の全部について行わないものとする。
③【H22年出題】
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
絶対的給付制限が適用されるのは、「自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたとき」です。「重過失」は含まれません。
②【H23年出題】 ×
「闘争、泥酔、著しい不行跡」の場合は、「全部について行わない」ではなく、「その全部又は一部を行わないことができる」です。
③【H22年出題】 ×
「正当な理由なしに療養に関する指示に従わない」ときは、「全部または一部」ではなく、保険給付の「一部」を行わないことができる、です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉗」条文の読み方(労災保険法)
「最初の一歩㉗」条文の読み方(労災保険法)
R4-127
R3.12.27 「推定する」と「みなす」の違い
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
労災保険法の条文を読んでみましょう。
第10条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。 |
「推定する」とは、「一応そのようにしておく」というイメージです。
船舶や航空機の事故で3か月間生死が分からない場合は、一応、事故のあった日に死亡したと推測します。遺族に対して迅速に保険給付を行うためです。
「推定する」の場合、反証があれば覆ります。もし、後日、労働者が生きていることが分かれば、受給していた遺族補償給付等を返還しなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「行方不明となって3か月経過した日」ではなく、「労働者が行方不明となった日」に、当該労働者は、死亡したものと推定する、です。
遺族補償年金の支給は、労働者が行方不明となった日の属する月の翌月に遡って、開始します。
★ポイント! 「死亡の推定」は、船舶と航空機の事故に限定されています。
次はこちらの条文を読んでみましょう。
第16条の2 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4 1~3の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 |
②に注目してください。「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生した」ときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子と「みなす」。こちらは、みなすという用語を使っています。
「みなす」は、推定ではなく確定です。反証で覆ることはありません。
労働者の死亡当時に胎児だった子が出生したときは、必ず「生計維持」されていたとみなされますので、生まれた時点から受給資格者になります。
★ 妻以外は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
★ なお、55歳以上60歳未満で障害状態ではない夫、父母、祖父母、兄弟姉妹も暫定的に受給資格者になります。ただし、受給権者になっても60歳までは遺族補償年金は支給停止されます。(昭和40年改正法附則第43条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉖」条文の読み方(国民年金法)
「最初の一歩㉖」条文の読み方(国民年金法)
R4-126
R3.12.26 専門用語に慣れましょう「前月」と「前々月」の違い(その2)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
「寡婦年金」の条文を読んでみましょう。
第49条(寡婦年金の支給要件) 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、この限りでない。 |
1行目の「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての」に注目してください。
「死亡日の属する月の前月まで」で前々月ではありません。
例えば、令和3年12月25日に死亡したとすると、「10年」は令和3年11月まででみることになります。
死亡が12月25日なら資格喪失は12月26日で、「被保険者期間」は11月までです。
寡婦年金の場合、保険料納付済期間、保険料免除期間に応じて年金額が計算されるので、最後の11月分まで計算に入れる方が、有利になるからです。
では、過去問をどうぞ
①【H28年出題】
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額とされている。
②【H24年出題】
寡婦年金の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】
①【H28年出題】 ×
寡婦年金の額は、「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額」ではなく、「老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の4分の3」です。
②【H24年出題】 〇
寡婦年金の額に反映するのは、「第1号被保険者」としての期間だけです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉕」条文の読み方(国民年金法)
「最初の一歩㉕」条文の読み方(国民年金法)
R4-125
R3.12.25 専門用語に慣れましょう「前月」と「前々月」の違い(その1)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
「障害基礎年金」の条文を読んでみましょう。
第30条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 1 被保険者であること。 2 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 |
保険料納付要件の「初診日の属する月の前々月までに」に注目してください。
例えば、初診日が令和3年12月24日だとすると、保険料納付要件は、令和3年10月までの被保険者期間でみます。
国民年金の保険料の納期限は、以下のようになります。
令和3年10月分の保険料 → 納期限は令和3年11月末日
令和3年11月分の保険料 → 納期限は令和3年12月末日
令和3年12月23日の時点で、保険料の納期限がきているのは10月分までです。「納付しなければならない保険料」を納付しているかどうかをみるので、「前々月」となっています。
11月分はまだ納期限がきていませんので、保険料納付要件には入れません。
では、過去問をどうぞ
①【H28年出題】
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】
①【H28年出題】 〇
ポイント
・平成26年4月8日が初診日
・保険料納付要件をみる期間
平成22年4月(資格取得日の属する月)から平成26年2月(初診日の属する月の前々月)まで(3年11か月)
・保険料納付済期間+保険料免除期間が、そのうちの3分の2以上あればよい
3年11か月のうち、保険料免除期間が3年間。
3分の2以上の要件を満たしているので、障害基礎年金の受給権が発生します。
★遺族基礎年金で保険料納付要件をみるときも、「前々月」までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉔」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉔」法律によって定義が異なる用語
R4-124
R3.12.24 「障害等級」と「傷病等級」の定義(労災保険法)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
前回は、国民年金法と厚生年金保険法の「障害等級」の定義をお話しました。
今回は、「労災保険法の障害等級」です。
では、条文を読んでみましょう。
第15条 ① 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 ② 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。 |
(別表第一)
障害補償年金 | 第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 同 277日分 | |
第3級 | 同 245日分 | |
第4級 | 同 213日分 | |
第5級 | 同 184日分 | |
第6級 | 同 156日分 | |
第7級 | 同 131日分 | |
障害補償一時金 | 第8級 | 同 503日分 |
第9級 | 同 391日分 | |
第10級 | 同 302日分 | |
第11級 | 同 223日分 | |
第12級 | 同 156日分 | |
第13級 | 同 101日分 | |
第14級 | 同 56日分 |
障害補償給付の障害等級は1級から14級までありますが、1級から7級の場合は「障害補償年金」、8級から14級の場合は「障害補償一時金」が支給されます。
例えば、1級の場合は、「給付基礎日額×313日分」が1年あたりの額です。14級の場合は、「給付基礎日額×56日分」が一括で支払われます。
過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。

【解答】
①【H30年出題】 〇
障害等級は障害等級表によって定められますが、障害等級表に載っていない障害もあります。そのような障害は、障害等級表に定められた障害等級を準用します。
では、次に「傷病等級」の条文を読んでみましょう
第12条の8 ③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 1 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 |
(別表第二)
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 同 277日分 |
第3級 | 同 245日分 |
・傷病補償年金の「傷病等級」は1級から3級までです。年金の額は、障害補償年金の1級から3級と同じです。
・傷病補償年金は「治っていない事(治癒前)」の給付です。
・障害補償給付は「治った(治癒している)」後の給付です。
では、過去問を解いてみましょう
②【H30年出題】
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
②【H30年出題】 ×
療養の開始後1年を経過した日ではなく、療養の開始後「1年6か月を経過した日」です。
なお、「② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」の「厚生労働省令で定める傷病等級」は、第1級から第3級です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉓」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉓」法律によって定義が異なる用語
R4-123
R3.12.23 「障害等級」の定義(国民年金法・厚生年金保険法)その2
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、こちらの条文を読んでみましょう。
国民年金法第35条 (失権) 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 |
「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」という表現に注意してください。
国民年金法の条文で単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級」のことです。
一方、国民年金法の条文で「厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級」と書いてある場合は、「1級・2級・3級」のことです。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H20年出題―国民年金法】
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。

【解答】
①【H20年出題―国民年金法】 ×
「厚生年金保険法に規定する障害等級」は「3級」も入ることに注意してください。
障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、3級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過していても、その時点では障害基礎年金の受給権は消滅しません。
障害基礎年金の受給権が消滅するのは、次のどちらか遅い方です。
・3級程度の障害の状態に該当しなくなって3年経過
・65歳
少なくとも65歳までは失権しません。
次に厚生年金保険法の条文を読んでみましょう。
厚生年金保険法第53条(失権) 障害厚生年金の受給権は、第48条第2項の規定によって消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。 3 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
|
こちらは厚生年金保険法の条文ですので、「障害等級」は、1級、2級、3級です。
消滅する時期は国民年金法と同じです。
では、厚生年金保険法の過去問も解いてみましょう。
②【H15年出題―厚生年金保険法】
障害厚生年金の受給権は、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日において、その者が65歳以上であるときはその日に、その者が65歳未満のときはその後65歳に達した日に消滅する。

【解答】
②【H15年出題―厚生年金保険法】 〇
こちらは、「厚生年金保険法」ですので、単に「障害等級」と書いてあれば、「1級・2級・3級」のことです。
消滅の時期は、国民年金の障害基礎年金と同じです。
・3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳以上のとき → その日に消滅
・3級に該当しなくなった日からそのまま該当することなく3年を経過した日に65歳未満のとき → その後65歳に達した日に消滅
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉒」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉒」法律によって定義が異なる用語
R4-122
R3.12.22 「障害等級」の定義(国民年金法・厚生年金保険法)その1
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
国民年金法第30条 1 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
厚生年金保険法第47条 1 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。 ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。 2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 |
★ 「障害基礎年金」も「障害厚生年金」も、「初診日」「保険料納付要件」「障害認定日」の3つの要件を満たすことが必要です。
★ 国民年金法の「障害等級」は、1級・2級、厚生年金保険法の「障害等級」は、1級・2級・3級です。
同じ「障害等級」という用語でも、範囲が違うことに注意しましょう。
(例1) 例えば、「初診日」に40歳・厚生年金保険の被保険者だった場合、同時に「国民年金の第2号被保険者」でもあります。
そして、障害認定日に、「1級」に該当した場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の2階建ての年金が支給されます。
障害厚生年金 1級 |
障害基礎年金 1級 |
(例2) 例えば、例1と同じく「初診日」に40歳・厚生年金保険の被保険者(同時に「国民年金の第2号被保険者」)だった場合。
障害認定日に「3級」に該当した場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。障害基礎年金には3級がないので、障害基礎年金は支給されません。
障害厚生年金 3級 |
では、「厚生年金保険法」の過去問を解いてみましょう。
①【H22年出題ー厚生年金保険法】
障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
①【H22年出題―厚生年金保険法】 ×
「軽度のものから」ではなく、「重度のものから1級、2級及び3級」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉑」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉑」法律によって定義が異なる用語
R4-121
R3.12.21 「児童」の定義(労基法・児童手当法)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
労働基準法第56条 (最低年齢) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 |
労働基準法では、中学校を卒業するまでの年齢の児童を労働させることを、原則として禁止しています。
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日」が終了するまでが、保護の対象です。
児童手当法第3条 児童手当法において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 |
児童手当法の「児童」は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」にあって、「日本国内に住んでいる」又は「留学などのために海外に住んでいて一定の要件をみたす」者と定義されています。
そして、もう一つ、「支給要件児童」という用語もあります。
支給要件児童は、第4条で「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童」)又は「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童」と定義されています。
では、過去問を解いてみましょう
【労働基準法】
①【H29年出題】
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
②【H23年出題】
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
「満15歳に達するまで」ではなく、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。原則として労働させることができないのは、義務教育終了までです。
②【H23年出題】 〇
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者」でも、所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用することができる例外規定があります。
満13歳以上の場合は、「非工業的事業の職業」、満13歳未満の場合は、「映画の製作又は演劇の事業」(子役の俳優)で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものが許可の条件です。
といっても義務教育中のため学校優先です。「修学時間外に使用することができる」と規定されています。そのため、労働時間は「修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内」とされています。
(法第56条第2項、第60条第2項)
では、「児童手当法」の過去問を解いてみましょう。
【児童手当法】
③【H30年選択式】
11歳、8歳、5歳の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき< A >である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

【解答】
③【H30年選択式】
A35,000円
ポイント!
・支給の対象
児童手当は、父母、父母指定者、里親、施設の設置者などに支給されます。児童に支給するのではないので注意してください。
・児童手当の額(1人当たり月額)※施設入所等児童を除く
3歳未満 → 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 → 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 → 一律10,000円
問題文の場合は、10,000円+10,000円+15,000円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑳」過去問の活用(社保一般常識)
「最初の一歩⑳」過去問の活用(社保一般常識)
R4-120
R3.12.20 医療保険や年金等の歴史(社一編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
医療保険、年金等の法律の施行日をおさえましょう。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H28年選択式】
世界初の社会保険は、< A >で誕生した。当時の< A >では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、 < A >に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、< B >に「健康保険法」を制定した。
②【H21年出題(健保)】
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
③【H19年出題】
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。
④【H19年出題】
高齢化や核家族化等の進行に従い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された。

【解答】
①【H28年選択式】
A ドイツ
B 大正11年
ポイント!
世界初の社会保険はドイツで誕生しました
②【H21年出題(健保)】 ×
「同時に施行」が間違いです。
健康保険法の制定は「大正11年」ですが、施行は大正15年、ただし保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年施行です。
関東大震災の影響で、全面施行は昭和2年まで延期されました。
健康保険は、日本で最初の医療保険です。
(法附則第1条)
③【H19年出題】 〇
ポイント!
国民皆保険体制の実現は昭和36年4月です。
④【H19年出題】 〇
ポイント!
介護保険法は平成12年4月から施行されました。
では、引き続き過去問を解いてみましょう
⑤【H22年出題】
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。
⑥【H19年出題】
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。
⑦【H24年出題】
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
⑧【H19年出題】
確定給付企業年金法は、平成13年に制定・施行された

【解答】
⑤【H22年出題】 ×
船員保険法の制定は、「昭和」14年です。
船員保険制度は船員のみを対象とした年金等給付を含む総合保険で、健康保険に相当する疾病給付も対象でした。
ポイント!
船員保険制度の養老年金等は、「社会保険方式」による「日本最初の公的年金」制度です。(参照:平成23年版厚生労働白書)
⑥【H19年出題】 〇
国民年金法が昭和36年4月に全面施行されたことによって、国民皆年金が実現しました。
ポイント!
国民皆保険も国民皆年金も「昭和36年4月」です。
⑦【H24年出題】 〇
ポイント!
確定拠出年金法は、平成13年6月制定・同年10月施行です。
⑧【H19年出題】 ×
確定給付企業年金法は、平成13年制定ですが、施行は平成14年4月です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑲」条文の読み方(高齢者医療確保法)
「最初の一歩⑲」条文の読み方(高齢者医療確保法)
R4-119
R3.12.19 専門用語に慣れましょう「後期高齢者医療の被保険者」(社一編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第50条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |
第51条 (適用除外) 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 2 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
★国民の全てが何らかの医療保険に加入していることを、「国民皆保険」といいます。
医療保険は、職業によって以下の種類があります。
・健康保険 → 民間企業の会社員とその被扶養者
・船員保険 → 船員とその被扶養者
・共済組合 → 国家公務員又は地方公務員とその被扶養者
・私立学校教職員共済 → 私立学校教職員とその被扶養者
・国民健康保険 → 上記以外の人とその家族
そして、75歳(障害の認定を受けた場合は65歳以上75歳未満)になると、各医療保険の被保険者や被扶養者の資格を喪失し、「後期高齢者医療」の被保険者となります。
「後期高齢者医療」は、各医療保険から独立していることがポイントです。
では、過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
②【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】
①【H22年出題】 ×
年齢が間違っています。
70歳以上ではなく「75歳以上」、65歳以上70歳未満ではなく、「65歳以上75歳未満です。
②【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)は、後期高齢者医療の被保険者になりません。
★後期高齢者医療に必要な費用について
費用のうち、5割を公費(税金)で負担しています。
残りの約4割が、現役(各医療保険の保険者)からの支援金です。
そして、約1割が、後期高齢者が負担している保険料となります。
公費(税金) 5割 | |
各医療保険からの支援金 約4割 | 保険料 約1割 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑱」過去問の活用(労働一般常識)
「最初の一歩⑱」過去問の活用(労働一般常識)
R4-118
R3.12.18 統計調査の問題(労一編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
労働の実態を知るために活用できるのが統計調査です。
統計調査の名称や役割を過去問から学びます。
では、過去問を解いてみてください。
①【H26年選択式】
労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている < A >である。この調査は、統計法に基づいて行われる< B >であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。
< A >は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、< C >についても調べている。
②【R2年選択式】
1 我が国の労働の実態を知る上で、政府が発表している統計が有用である。年齢階級別の離職率を知るには< A >、年次有給休暇の取得率を知るには< B >、男性の育児休業取得率を知るには< C >が使われている。
2 労働時間の実態を知るには、< D >や< E >、毎月勤労統計調査がある。< D >と< E >は世帯及びその世帯員を対象として実施される調査であり、毎月勤労統計調査は事業所を対象として実施される調査である。
3 < D >は毎月実施されており、就業状態については、15歳以上人口について、毎月の末日に終わる1週間(ただし12月は20日から26日までの1週間)の状態を調査している。< E >は、国民の就業の状態を調べるために、昭和57年以降は5年ごとに実施されており、有業者については、1週間当たりの就業時間が調査項目に含まれている。

【解答】
①【H26年選択式】
A 毎月勤労統計調査
B 基幹統計調査
C 出勤日数
★「毎月勤労統計調査」のポイント
・厚生労働省が実施している
・基幹統計調査(国の行政機関が作成する統計のうち総務大臣が指定する特に重要な統計)
★厚生労働省で行っている「賃金」に関する基幹調査には、「毎月勤労統計調査」と「賃金構造基本統計調査」があります。
・毎月勤労統計調査 → 賃金、労働時間、雇用の毎月の変動を把握する
(労働者全体の賃金の水準や増減の状況をみる)
・賃金構造基本統計調査 → 賃金構造の実態を詳細に把握する
(男女、年齢勤続年数や学歴などの属性別にみるとき)
②【R2年選択式】
A 雇用動向調査
B 就労条件総合調査
C 雇用均等基本調査
D 労働力調査
E 就業構造基本調査
「就労条件総合調査」と「労働力調査」の2つをおさえましょう。
★就労条件総合調査のポイント
・厚生労働省が実施している
・一般統計
・調査事項 → 企業の属性、労働時間制度、賃金制度、労働費用に関する事項
・我が国の民間企業の就労条件の現状を明らかにすることが目的
★労働力調査のポイント
・総務省が実施している
・基幹統計調査
・目的 → 我が国の就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得る事
参考にしました。
総務省統計局ホームページ「労働力調査結果」 https://www.stat.go.jp/data/roudou/index.html
厚生労働省ホームページ 「厚生労働統計」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑰」条文の読み方(労働組合法)
「最初の一歩⑰」条文の読み方(労働組合法)
R4-117
R3.12.17 専門用語に慣れましょう 「労働者の定義」(労働組合法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
労働組合法第3条を読んでみましょう。
第3条 (労働者) 労働組合法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 |
労働組合法上の「労働者」については、「本条にいう「労働者」とは他人との間に使用従属の関係に立って労務に服し、報酬を受けて生活する者をいうのであって、現に就業していると否とを問わないから、失業者をも含む。」とされています。(S23.6.5 労発第262号)
一方、労働基準法の「労働者」の定義は、「事業に使用される者」「賃金を支払われる者」となっています。現在働いていることが前提となっていますので、失業者は含まれません。
では、過去問をどうぞ
①【H23年出題】
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう

【解答】
①【H23年出題】 〇
労働基準法の「労働者」の定義との違いに注意しましょう。
参考に、労働基準法の「労働者」の定義はこちらです。
↓
「労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」(労働基準法第9条)
では、次に「労働協約」の条文を読んでみましょう。
第14条 (労働協約の効力の発生) 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。 |
「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる」点がポイントです。
過去問を解いてみましょう
②【H23年出題】
労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。

【解答】
②【H23年出題】 ×
書面に作成されていない場合は、効力は生じません。
労働協約は、「書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印すること」によってその効力を生じます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑯」過去問の活用(厚生年金保険法)
「最初の一歩⑯」過去問の活用(厚生年金保険法)
R4-116
R3.12.16 老齢厚生年金の計算(厚年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
さて、第43条の条文を読んでみましょう。
第43条 (年金額) 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。 |
第43条は、老齢厚生年金の年金額の計算方法を規定しています。
老齢厚生年金の計算式は次の通りです。
平均標準報酬額 × 1,000分の5.481 × 被保険者期間の月数
では、過去問を解いてみましょう
①【H23年選択式】
老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「< A >」という。)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)の1,000分の< B >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。

【解答】
A 再評価率
B 5.481
ポイント!「平均標準報酬額」の出し方
老齢厚生年金の計算には、厚生年金保険に加入していた全期間の「標準報酬月額と標準賞与額」を使いますが、それを平均したものが「平均標準報酬額」です。
「平均標準報酬額」の計算式は、「標準報酬月額と標準賞与額の総額」÷「被保険者期間の月数」で、平均標準報酬額の計算の際、標準報酬月額と標準賞与額に「再評価率」を乗じます。
再評価率を乗じるのは、過去の標準報酬を現在の水準に読み替えるためです。
そして、再評価率は、毎年度改定されます。
例えば、昭和29年度以降生まれの人の昭和57年度の報酬は、再評価率1.472(令和3年度)を乗じることによって現在の水準に読み替えられます。
在職中の標準報酬月額や標準賞与額が高い人ほど、平均標準報酬額は高くなりますし、在職期間が長い人ほど被保険者期間が長くなるので、年金額が多くなります。
厚生年金が報酬比例といわれる理由です。
ポイント!「給付乗率」について
★平成15年4月1日に注意しましょう
なお、「平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数」は、平成15年4月以降の期間の計算式です。
平成15年4月から、「総報酬制」が導入され、「賞与」からも月々の報酬(標準報酬月額)と同じ率の保険料が徴収されるようになりました。
そのため、年金額に賞与の額も反映されるようになりました。
平成15年3月までは、「賞与」から「特別保険料」が徴収されていましたが、年金額には反映されません。
平成15年3月までの被保険者期間の計算式は、「平均標準報酬月額×1,000分の7.125×被保険者期間の月数」です。
平均標準報酬月額は「標準報酬月額」だけで計算します。
なお、「1,000分の5.481」は「1,000分の7.125÷1.3」です。
年間の賞与は月々の給料の3割という考え方からです。
★昭和21年4月1日以前生まれにも注意しましょう
「給付乗率」は昭和21年4月1日以前生まれの場合は、生年月日によって読み替えがあります。
旧法から新法になった際に給付乗率が下がりました。その際、いきなり下げるのではなく、段階的に給付乗率を下げる必要があったためです。そのため、旧法に近い人(生年月日の古い人)ほど給付乗率が旧法に近いのが特徴です。
(平成15年3月までの期間)
大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の9.5
・
・
・
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の7.23
(平成15年4月以降の期間)
大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の7.308
・
・
・
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれの給付乗率 1,000分の5.562
最後に過去問をどうぞ
②【H18年選択式】
平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の標準報酬月額及び標準賞与額に係る< C >(生年度別)を改定することによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

【解答】
C 再評価率
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑮」条文の読み方(厚生年金保険法)
「最初の一歩⑮」条文の読み方(厚生年金保険法)
R4-114
R3.12.15 専門用語に慣れましょう「被保険者期間を有する」(厚年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、第42条を読んでみましょう。
第42条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 |
第42条では、老齢厚生年金の支給要件を3つ定めています。
1 被保険者期間を有すること
2 65歳以上
3 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あること
1について
「被保険者」とは「厚生年金保険の被保険者」のこと、そして「被保険者期間」とは厚生年金保険の被保険者期間です。
被保険者期間は月単位で算定され、最短で1か月です。「被保険者期間を有する」とは、1か月でも厚生年金保険の被保険者期間を有する、という意味です。
2について
老齢厚生年金の受給権は、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)に受給権が発生します。
3について
老齢基礎年金の受給資格を満たしていることという意味です。(合算対象期間も合算できます。)老齢厚生年金は、老齢基礎年金の上乗せですので、まず、老齢基礎年金の受給要件を満たしていることが前提です。
例えば、保険料納付済期間が10年(第1号被保険者としての期間が9年11か月、厚生年金保険の被保険者期間が1か月)の場合、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が受給できます。
老齢基礎年金の計算式は、「780,900円×改定率×480分の120」で、老齢厚生年金は1か月の被保険者期間をベースに計算されます。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。
②【H30年出題】
特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
65歳以上から支給される本来の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月でもあれば支給されますが、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが要件です。
(法第42条、法附則第8条)
②【H30年出題】 〇
65歳からの老齢厚生年金と、特別支給の老齢厚生年金は「別物」です。
特別支給の老齢厚生年金を受けていた場合でも、65歳から支給される老齢厚生年金を受けようとする場合は、改めて、老齢厚生年金に係る裁定の請求書を提出しなければなりません。
(施行規則第30条の2)
こちらの問題もどうぞ!
③【H30年出題】
老齢基礎年金を受給している66歳の者が、平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した(同月に更に被保険者の資格を取得していないものとする。)。当該期間以外に被保険者期間を有しない場合、老齢厚生年金は支給されない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
問題文の場合、老齢厚生年金が支給されます。
65歳時点で厚生年金保険の被保険者期間を有していなくても、その後に被保険者期間を1か月でも有した場合は、老齢厚生年金の受給要件を満たしますので、老齢厚生年金が支給されます。
ポイント
「平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し、同月20日に喪失した」場合、厚生年金保険の被保険期間は1か月となります。(同月得喪といいます。)
法第19条で、「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。」と規定されている部分です。
ただし、「その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法の第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。」という例外があります。
問題文の場合は、「同月に更に被保険者の資格を取得していない」とありますので、1か月の被保険者期間として算定されます。
しかし、例えば、
■令和3年12月1日入社(厚生年金保険の資格取得)
↓
■同年12月20日退職
↓
■同年12月21日 厚生年金保険資格喪失・国民年金の第1号被保険者になった
このような場合、12月は厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
そしてもう一つのパターンとして、令和3年12月1日に資格取得、同年12月20日付で退職し、12月中に別の会社に就職し厚生年金保険の被保険者となった場合は、後の会社の資格で厚生年金保険の被保険者期間が算定されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑭」過去問の活用(国民年金法)
「最初の一歩⑭」過去問の活用(国民年金法)
R4-114
R3.12.14 老齢基礎年金の支給要件(国年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
早速、条文を読んでみましょう
第26条 (支給要件) 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第90条の3第1項(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。 ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。 |
★老齢基礎年金の支給要件のポイントは次の2つです。
① 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上あること
② 65歳に達したこと
★注意するポイントは次の2つです。
① 合算対象期間
保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年に満たない場合でも、「合算対象期間」を合算して10年以上あれば支給要件を満たします。 (附則第9条第1項)
②学生納付特例期間
1行目の「保険料免除期間(第90条の3第1項(学生納付特例)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」に注目してください。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に入りません。年金の計算上はゼロになるので、例えば40年間ずっと学生納付特例期間だった場合は、老齢基礎年金は支給されません。年金額の計算に入らないので、1行目の保険料免除期間から学生納付特例期間は除かれています。
しかし、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年」の部分の保険料免除期間から学生納付特例期間は除かれていません。
学生納付特例期間は受給資格をみるときの10年には算入されるからです。
※なお、「納付猶予期間」も学生納付特例期間と同じ扱いです。
では、過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。
②【H29年出題】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。
③【H30年出題】
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間は老齢基礎年金の額には反映しません。ですので、当該期間以外に被保険者期間を有していない場合は、老齢基礎年金の額はゼロ、老齢基礎年金は支給されません。
②【H29年出題】 〇
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間は、老齢基礎年金の額には反映されません。しかし、10年以上の受給資格期間には算入されます。
③【H30年出題】 ×
65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて10年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給権が発生します。
では、年金の支給期間の条文を穴埋めで確認しましょう。
第18条 (年金の支給期間及び支払期月)
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の< A >から始め、権利が消滅した日の< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の < A >からその事由が消滅した日の< B >までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの< C >までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

【解答】
A 属する月の翌月
B 属する月
C 前月
例えば、昭和31年12月11日生まれの人は、令和3年12月10日に65歳に達し、要件を満たせば、令和3年12月10日に老齢基礎年金の受給権が発生します。
年金の支給は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」からですので、令和4年1月から支給が始まります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑬」条文の読み方(国民年金法)
「最初の一歩⑬」条文の読み方(国民年金法)
R4-113
R3.12.13 専門用語に慣れましょう 〇〇歳に達した日(国年編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第8条 (資格取得の時期) 第7条の規定による被保険者は、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者については①から③までのいずれかに該当するに至った日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については④に該当するに至った日に、その他の者については④又は⑤のいずれかに該当するに至った日に、それぞれ被保険者の資格を取得する。 ① 20歳に達したとき。 ② 日本国内に住所を有するに至ったとき。 ③ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者でなくなったとき。 ④ 厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき。 ⑤ 被扶養配偶者となったとき。 |
第9条 (資格喪失の時期) 第7条の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(②に該当するに至った日に更に第2号被保険者若しくは第3号被保険者に該当するに至ったとき又は③から⑤までのいずれかに該当するに至ったとき(④については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となったときに限る。)は、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したとき。 ② 日本国内に住所を有しなくなったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ③ 60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)。 ④ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者となったとき(第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く。)。 ⑤ 厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき(第7条第1項各号のいずれかに該当するときを除く。)。
⑥ 被扶養配偶者でなくなったとき(第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときを除く。)。 |
★〇〇歳に達するのはいつでしょう?
「年齢に関する法律」では、「年齢は出生の日より之を起算す」と規定されています。
年齢の計算は、初日を算入することがポイントです。
例えば、令和3年4月1日午後1時に生まれた場合は、令和3年4月1日0時から起算し、令和4年3月31日24時をもって満1年となります。令和4年3月31日24時を暦日で考えて、1歳に達するのは令和4年3月31日となります。
では、過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】
第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。
②【R1年出題】
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。
③【H26年出題】
昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

【解答】
①【H30年出題】 〇
第1号被保険者・第3号被保険者は、「60歳に達したとき」に資格を喪失します。
「60歳に達したときに該当するに至った日(当日)」に資格を喪失しますが、「60歳に達した日」は60歳の誕生日の前日です。
②【R1年出題】 ×
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達するのは、平成31年3月31日です。
被保険者期間は、「資格を取得した日の属する月」からスタートしますので、被保険者期間に算入されるのは、平成31年3月からです。
(法第11条)
③【H26年出題】 ×
昭和29年4月1日生まれの者が60歳に達するのは、平成26年3月31日です。
被保険者期間は、「資格を喪失した日の属する月の前月まで」ですので、被保険者期間に算入されるのは、平成26年2月までです。
(法第11条)
では、「被保険者期間」の条文を穴埋めで確認しましょう。
第11条 (被保険者期間の計算)
1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の< A >からその資格を喪失した日の< B >までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を< C >として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

【解答】
A 属する月
B 属する月の前月
C 1か月
例えば、「昭和36年4月1日生まれ」の第1号被保険者の場合、資格取得は20歳に達する日(昭和56年3月31日)、資格喪失は60歳に達する日(令和3年3月31日)です。
被保険者期間に算入されるのは、昭和56年3月から令和3年2月までです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑫」過去問の活用(健康保険法)
「最初の一歩⑫」過去問の活用(健康保険法)
R4-112
R3.12.12 報酬の範囲(健保編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、昨日の復習から始めましょう。
次の「報酬」の定義について、条文の空欄を埋めてください。
第3条第5項(報酬の定義)
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、< A >として受けるすべてのものをいう。ただし、< B >に受けるもの及び< C >を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

【解答】
A 労働の対償
B 臨時
C 3か月
今日は、報酬に含まれるもの、含まれないものを過去問から具体的に学びましょう
①【H24年出題】
この法律において報酬とは、臨時に受けるもの等を除き、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるものであり、通勤手当は、自宅と勤務場所との往復にかかる交通費の実費弁償的な手当のため報酬には含まれない。
②【H26年出題】
労働基準法に基づく解雇予告手当又は退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの若しくは事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものは報酬又は賞与には含まれない。
③【R1年出題】
退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。

【解答】
①【H24年出題】 ×
「通勤手当」は報酬に当たります。
なお、通勤手当が3か月ごとや6か月ごとに支給されているとしても、実態は、毎月の通勤に対し支給されるもので、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているものなので、報酬となります。
(昭27.12.4保文発2741)
②【H26年出題】 〇
「労働基準法に基づく解雇予告手当」、「退職を事由に支払われる退職金で、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるもの」は、報酬又は賞与には含まれません。
(昭24.6.24保文発1175号、平15.10.1保保発第1001002号/庁保険発第1001001号)
③【R1年出題】 〇
今日のポイント(退職金)
・退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの
→報酬又は賞与には該当しません
・在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合
→報酬又は賞与に該当します。(労働の対償としての性格が明確で、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有するから)
(平15.10.1保保発第1001002号/庁保険発第1001001号)
次に、「現物給与」の過去問を解いてみましょう
④【H28年出題】
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額は、その地方の時価によって都道府県知事が定めることになっている(健康保険組合が規約で別段の定めをした場合を除く。)。

【解答】
④【H28年出題】 ×
都道府県知事ではなく、「厚生労働大臣」が定めます。
「通貨以外のもの」(現物給与)も報酬又は賞与に含まれます。
現物給与の価額は、その地方の時価によって「厚生労働大臣」が定めることになっていますが、健康保険組合は、規約で別の定めをすることができます。
(法第46条)
最後に「現物給与の価額」の条文を穴埋めで確認しましょう。
第46条 (現物給与の価額)
① 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、< A >が定める。
② < B >は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

【解答】
A 厚生労働大臣
B 健康保険組合
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑪」条文の読み方(健康保険法)
「最初の一歩⑪」条文の読み方(健康保険法)
R4-111
R3.12.11 報酬の定義(健保編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文で用語の定義を読んでみましょう。
第3条 ⑤ この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
⑥ この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 |
報酬は、保険料の計算や傷病手当金、出産手当金の基になり、また、賞与も保険料の計算の基になります。
「報酬」は、「労働の対償として受けるすべてのもの」と定義されていて、通勤手当、住宅手当なども報酬となります。
しかし、「臨時に受けるもの」と「3月を超える期間ごとに受けるもの」は報酬から除外されます。
「臨時に受けるもの」は、大入り袋など常態として受ける報酬以外のもの、「3月を超える期間ごとに受けるもの」は、年3回以下の回数で支給される賞与のことです。
なお、「報酬」、「報酬月額」、「標準報酬月額」の違いにも注意しましょう。
「報酬」は労働の対償として受けるすべてのもの、「報酬月額」はそれを月ベースに換算したもの、「標準報酬月額」は、報酬月額を標準報酬月額等級(健康保険の場合1級から50級)にあてはめて簡単な数字にしたものです。
次に「賞与」は、「3月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されていて、年3回以下の賞与のことです。もし、賞与が年間を通して4回以上支給されている場合は「報酬」に入ります。
「標準賞与額」は、「賞与額」の1,000円未満を切り捨てた額です。
ただし、年度の賞与額の累計額は573万円が上限です。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H23年出題】
健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいうが、臨時に受けるもの及び3か月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
②【H22年出題】 ※改正による修正あり
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。
③【H28年出題】
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】
①【H23年出題】 〇
「臨時に受けるもの」及び「3か月を超える期間ごとに受けるもの」は、報酬に含まれないのがポイントです。
②【H22年出題】 〇
標準報酬月額は、50等級に区分されていて、最低は第1級の58,000円、最高は第50級の1,390,000円です。
(法第42条)
③【H28年出題】 ×
年度の上限は、540万円ではなく、「573万円」です。
標準賞与額のポイント
・賞与額の1,000円未満の端数は切り捨てて、その月の標準賞与額を決定します
・その年度(毎年4月1日~翌年3月31日まで)の標準賞与額の累計額の上限は573万円です
・573万円を超えることとなる場合は、累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度はその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額はゼロ円になります。
 ちょっと話は変わりますが・・・
ちょっと話は変わりますが・・・
「労働基準法」「労災保険法」「雇用保険法」「徴収法」では、「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」は「賃金」といいます。
労働基準法を例にとりますと、 「臨時の賃金」、「3か月を超える期間ごとの賃金」も「賃金」に含まれます。
しかし、平均賃金を算定するときは、 「臨時の賃金」、「3か月を超える期間ごとの賃金(年3回以下の賞与)」は、賃金の総額から控除します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑩」過去問の活用(徴収法)
「最初の一歩⑩」過去問の活用(徴収法)
R4-110
R3.12.10 保険関係の成立と消滅(徴収法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
保険関係の成立の条文を読んでみましょう。
第3条 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。 |
なお、労災保険法第3条第1項は、「労働者を使用する事業を適用事業とする」、雇用保険法第5条第1項は、「労働者が雇用される事業を適用事業とする」としています。
労働者を使用(雇用)するようになった日に労働保険の保険関係が成立します。
例えば、令和3年12月10日に初めて労働者を雇い入れたが、その日にその労働者が業務上の負傷をしてしまった。そのような場合でも、令和3年12月10日に労災保険の保険関係が成立しているので、労災保険の保険給付の対象となります。
同時に労働保険料を納付する義務も発生します。
では、過去問をどうぞ。
①【H25年出題(労災)】
労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

【解答】
①【H25年出題(労災)】 ×
「保険関係成立届を提出することによって成立する」の部分が誤りです。
保険関係は、仮に保険関係成立届を提出しなかったとしても、「事業が開始された日」に自動的に成立します。
次は、保険関係の消滅の条文を読んでみましょう。
第5条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
継続事業の場合は「廃止」、有期事業の場合は「終了」という用語を使いますが、いずれにしても、保険関係はその翌日に消滅します。
では、過去問を解いてみましょう。
②【H29年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。
③【H26年出題(雇用)】
平成26年6月30日に事業を廃止すれば、その年の8月19日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
②【H29年出題(労災)】 ×
ポイントその1
「保険関係廃止届」なるものは存在しません。
ポイントその2
届出によって消滅するのではなく、廃止又は終了したときは、自動的にその翌日に保険関係関係が消滅します。
③【H26年出題(雇用)】 〇
事業を廃止した場合は、労働保険料を精算するために、確定保険料申告書を提出しなければなりません。
確定保険料申告書の提出期限は、保険関係が消滅した日から50日以内です。消滅した日は午前零時から始まりますので、当日から起算するのがポイントです。
平成26年6月30日に事業を廃止した場合は、その翌日の7月1日に保険関係が消滅します。7月1日から起算して50日以内ですので、その年の8月19日が期限となります。
(法第19条)
最後に確定保険料申告書の納期限を条文で確認しましょう。
第19条 (確定保険料)
事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から< A >日以内(保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日から< B >日以内)に提出しなければならない。
有期事業については、その事業主は、次に掲げる労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、保険関係が消滅した日から< B >日以内に提出しなければならない。

【解答】
A 40
B 50
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑨」条文の読み方(徴収法)
「最初の一歩⑨」条文の読み方(徴収法)
R4-109
R3.12.9 専門用語に慣れましょう(当日起算・翌日起算)(徴収法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第4条の2 (保険関係の成立の届出) 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 |
「10日以内」の起算日が、「当日起算」か「翌日起算」かがポイントです。
初日の扱いについては、民法第140条で、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」と規定されています。
「期間の初日は、算入しない」ので原則は翌日起算です。しかし、例外的に「その期間が午前零時から始まるとき」は、初日から起算することになります。
保険関係成立届は、「成立した日から10日以内」に提出しますが、起算日は、原則どおり翌日となります。
保険関係が成立した日とは、初めて労働者を雇い入れた日です。始業が9時だとするとその日は既に9時間過ぎていて丸一日ありません。そのため、初日は算入せず、翌日起算となります。
では、過去問を解いてみましょう。
①【R1年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
②【H27年出題(労災)】
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題(労災)】 〇
「その成立した日から10日以内」で正しいです。
起算日は翌日です。
②【H27年出題(労災)】 〇
「成立した日の翌日から起算して10日以内」で正しいです。
★ ①の問題の「その成立した日から10日以内」は「翌日起算」ですので、②の問題の「成立した日の翌日から起算して10日以内」と同じ意味です
では、次の条文を読んでみましょう。
第15条 (概算保険料の納付) 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。 (途中省略あり) |
その保険年度の6月1日から40日以内の起算日は、「初日の6月1日」です。その保険年度の6月1日は午前零時から始まり丸一日ありますので、当日起算です。
納期限は6月1日から40日で、7月10日です。
一方、保険年度の中途に保険関係が成立したものは、「保険関係が成立した日から50日以内」ですが、こちらは翌日起算です。保険関係が成立した日は、丸一日ないからです。
過去問を解いてみましょう
③【H30年出題(雇用)】
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

【解答】
③【H30年出題(雇用)】 〇
・継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料の納期限
→ 保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日まで
(午前零時から始まる。当日起算)
・保険年度の中途で保険関係が成立した事業
→保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
(午前零時に始まらないので、翌日起算)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑧」過去問の活用(雇用保険法)
「最初の一歩⑧」過去問の活用(雇用保険法)
R4-108
R3.12.8 「賃金」の定義と「賃金日額」(雇用保険編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、法第4条第4項を読んでみましょう。
第4条 (定義) ④ この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 |
一般の被保険者が失業した場合、基本手当が受給できます。そして、その基本手当の額は、在職中の「賃金」をベースにして算定されます。
「賃金」の定義を定めているのが法第4条第4項で、「労働の対償として事業主が労働者に対して支払うすべてのもの」を賃金としています。
次に、第17条第1項を読んでみましょう。
第17条 (賃金日額) 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 |
「基本手当の日額」は、「賃金日額×厚生労働省令で定める率」で計算します。
賃金日額の算定の基礎になる賃金は、「被保険者として雇用された期間に対するものとして同期間中に事業主の支払義務が確定した賃金」であり、「原則として最後の完全な6賃金月の労働の対価として支払われるべき賃金」となります。
(参照:行政手引50451)
なお、賃金のうち、「臨時に支払われる賃金」及び 「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は賃金日額の算定の基礎から除外されます。
例えば「大入り袋」のような臨時的に不確定に支払われるものは「臨時の賃金」、支払回数が年間3回以内の賞与は、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当し、賃金日額の計算に入りません。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H21年出題】
雇用保険法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいうが、通貨で支払われるものに限られる。
②【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われたものに限られる。
③【H22年出題】
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「通貨で支払われるものに限られる」の部分が誤りです。
「現物給与」も賃金です。
ただし、賃金に含まれる範囲は厚生労働省令で定められていますので、現物給与については、法第4条第4項で「通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令(則第2条)で定める範囲外のものを除く」となっています。
通貨以外のもの(現物給与)については、施行規則第2条で範囲が定められている「食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるもの」は賃金に算入されます。
②【H22年出題】 〇
賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金で算定します。
③【H22年出題】 ×
家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額に算入されます。それらの多寡は、基本手当の日額に影響します。
最後に条文を穴埋めで確認しましょう。
第17条 (賃金日額)
① 賃金日額は、算定対象期間において第14条(第1項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の< A >間に支払われた賃金(< B >に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を < C >で除して得た額とする。

【解答】
A 6か月
B 臨時
C 180
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑦」条文の読み方(雇用保険法)
「最初の一歩⑦」条文の読み方(雇用保険法)
R4-107
R3.12.7 専門用語に慣れましょう「以上・以下」と「超える・未満」(雇用保険編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、第22条の条文を読んでみましょう。
第22条 (所定給付日数) ① 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 1 算定基礎期間が20年以上である受給資格者 150日 2 算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者 120日 3 算定基礎期間が10年未満である受給資格者 90日
② 前項の受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、その算定基礎期間が1年以上の受給資格者にあっては次の各号に掲げる当該受給資格者の区分に応じ当該各号に定める日数とし、その算定基礎期間が1年未満の受給資格者にあっては150日とする。 1 基準日において45歳以上65歳未満である受給資格者 360日 2 基準日において45歳未満である受給資格者 300日 |
「以上」と「未満」に注目してください。
「20年以上」は20年を含みます。「10年未満」は10年を含みません。
「以上」と「以下」は基準の数値を含み、「超える」と「未満」は基準の数値を含みません。
例えば、「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」で算定基礎期間が1年、基準日の年齢が45歳の場合、所定給付日数は、360日です。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H27年出題】
特定受給資格者以外の受給資格者(雇用保険法第13条第3項に規定する特定理由離職者を除く。)の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は150日である。
②【H30年出題】
算定基礎期間が1年未満の就職が困難なものに係る基本手当の所定給付日数は150日である。
③【H26年選択】
雇用保険法第22条第2項において、受給資格者で厚生労働省令で定める理由により就職が困難なものに係る所定給付日数は、同条が規定する算定基礎期間が1年であり、当該基本手当の受給資格に係る離職の日において45歳である受給資格者にあっては < A >とされている。

【解答】
①【H27年出題】 〇
一般の受給資格者(就職が困難なもの、特定受給資格者・特定理由離職者以外)の所定給付日数は、「基準日の年齢」に関係ないことがポイントです。
算定基礎期間が20年以上の場合は、基準日の年齢にかかわらず、所定給付日数は150日です。
※「基準日」とは、「基本手当の受給資格に係る離職の日」のことです。
②【H30年出題】 〇
「就職が困難なもの」の所定給付日数の1つ目のポイントは、算定基礎期間が1年未満か1年以上か?です。
1年未満の場合は、基準日の年齢に関係なく所定給付日数は150日です。
2つ目のポイントは、「1年以上」の場合は、基準日に「45歳未満」か「45歳以上65歳未満」で所定給付日数が変わる点です。45歳未満なら300日、45歳以上65歳未満なら360日です。
③【H26年選択】
A 360日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑥」過去問の活用(労災保険法)
「最初の一歩⑥」過去問の活用(労災保険法)
R4-106
R3.12.6 「療養の給付」と「療養の費用の支給」の区別(労災保険編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
業務上の負傷、疾病の治療については、療養補償給付が行われます。
第13条を見てみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 移送 ③ 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
|
療養補償給付は、「療養の給付」が原則で、例外的に「療養の費用の支給」が行われます。
「療養の給付」は現物給付です。負傷、疾病について診察などの治療が行われます。
「療養の費用の支給」は現金給付で、「療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合」に例外的に行われます。
では、過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等という。」)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
②【H27年出題】
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
療養の給付は、指定病院等で行われます。
指定病院等とは、
・社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所(労災病院のことです)
・都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者
のことです。
問題文のように、厚生労働大臣が健康保険法に基づいて指定する病院等でも、労災保険の指定病院等に該当しないときは療養の給付は行われません。
ちなみに、例外的に「療養の費用の支給」が行われるのは、
・療養の給付をすることが困難な場合
・療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合(施行規則第11条の2)
です。近くに指定病院等がないなどの理由が想定されています。
②【H27年出題】 ×
「療養の給付」の請求書は、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出します。
「療養の費用の支給」の請求書は、「直接」、所轄労働基準監督署長に提出し、その後労働者本人に現金が支払われます。
今日の過去問のポイント!
「療養補償給付」には、
「療養の給付(現物給付)」と「療養の費用の支給(例外)」がある
療養の給付の請求書は「指定病院等を経由」
療養の費用の請求書は「直接」所轄労働基準監督署長に提出
最後に穴埋め問題をどうぞ。
③【H28年選択式】
労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。

【解答】
A 療養の費用
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑤」条文の読み方(労働者災害補償保険法)
「最初の一歩⑤」条文の読み方(労働者災害補償保険法)
R4-105
R3.12.5 専門用語に慣れましょう「及び・並びに」(労災保険編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
早速、法第16条の7を読んでみましょう。
法第16条の7 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者 2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 |
2の「及び」に注目してください。
及びは「and」ですので、「A及びB」なら「AとB」と読めます。「AとBとC」なら、「A、B及びC」となります。
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母」は、「子と父母と孫と祖父母」と並べているだけです。
3は「及び」と「並びに」が出てきますが、どちらもandの意味です
「及び」で小さくまとめて、大きく分けるときに「並びに」が使われます。
「A、B、C及びD並びにE」なら、『「AとBとCとD」と「E」』となり、「ABCD」と「E」が分けられます。
「子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹」ですと、『「子と父母と孫と祖父母」と「兄弟姉妹」』となります。
「子と父母と孫と祖父母」は生計を維持あり・なしで、2のグループか3のグループに入るか変わりますが、「兄弟姉妹」は生計維持あり・なし関係なく3のグループとなりますので、「子と父母と孫と祖父母」と分けて並べられています。
では、令和3年の問題を解いてみましょう。
【R3年出題(問6)】
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
B 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
C 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
D 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
E 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

【解答】 A
第16条の7では、遺族補償一時金を受けることができる遺族を、次の各号に掲げる者としています。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
そして、第2項で、「遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。」と規定しています。
順序は、第1号→第2号→第3号で、第2号と第3号に掲げる者は並んでいる順序です。
まとめますと
①配偶者(生計維持あるなし関係なく)
生計維持していた②子、③父母、④孫、⑤祖父母
生計維持していなかった⑥子、⑦父母、⑧孫、⑨祖父母
⑩兄弟姉妹(生計維持あるなし関係なく)
配偶者は生計維持あるなし関係なく1番ですので、Aが誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩④」過去問の活用(労働安全衛生法)
「最初の一歩④」過去問の活用(労働安全衛生法)
R4-104
R3.12.4 「健康診断」と「安全衛生教育」の違い(労働安全衛生法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
★ 労働者を雇い入れたとき、事業者には、「健康診断」、「安全衛生教育」を行う義務があります。
条文を確認しましょう。
施行規則第43条 (雇入時の健康診断) 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。 (項目 略)
法第59条 (安全衛生教育) ① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ② ①の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 |
対象になる労働者に注目してください。
健康診断は「常時使用する労働者」、安全衛生教育は「労働者」です。
この違いが勉強のポイントです。
過去問で確認しましょう。
①【H23年 選択】
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。
②【R2年出題】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない。
③【H17年出題】
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

【解答】
①【H23年 選択】
A 常時使用する
②【R2年出題】 ×
雇入れ時の安全衛生教育は、常時使用する労働者のみならず、臨時に雇用する労働者にも行う義務があります。
条文では「労働者」となっていますので、雇入れ時の安全衛生教育は、雇用形態を問わずすべての労働者が対象です。
(法第59条)
③【H17年出題】 ×
雇入れ時の健康診断の対象は「常時使用する労働者」ですが、雇入れ時の安全衛生教育の対象は、「すべての労働者」です。
今日の過去問のポイント!
雇入れ時の「健康診断」と「安全衛生教育」は対象になる労働者の範囲が異なります。
健康診断は「常時使用」、安全衛生教育は「すべて」です。
最後に条文で復習しましょう。
施行規則第43条 (雇入時の健康診断)
事業者は、< B >労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、< C >を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
(項目 略)
法第59条 (安全衛生教育)
① 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
② 1の規定は、労働者の< D >したときについて準用する。

【解答】
B 常時使用する
C 3月
D 作業内容を変更
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩③」条文の読み方(労働安全衛生法)
「最初の一歩③」条文の読み方(労働安全衛生法)
R4-103
R3.12.3 専門用語に慣れましょう(労働安全衛生法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、法第3条第2項を読んでみましょう。
第3条 (事業者等の責務) 第2項 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 |
接続詞の「若しくは」と「又は」に注目してください。どちらも「or」です。
例えば、「A又はB」なら、「AかB」です。
3つ以上なら、「A、B、又はC」(AかBかC)となります。
「A若しくはB又はC」というように、「若しくは」と「又は」の両方使われることもあります。
この場合は、「若しくは」で小さくつなげて、「又は」で大きくつなげています。
「A若しくはB」又は「C」とつながります。
第3条第2項の場合は、
A 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者
B 原材料を製造し、若しくは輸入する者
C 建設物を建設し、若しくは設計する者
とすると、「A、B又はC」と大きくつなげて、その中のまとまりは「若しくは」でつなげています。
例えば、Aなら輸入の前に「若しくは」が入っていますので、「設計か製造か輸入」となります。
では、第3条第2項からの過去問もチェックしておきましょう。
【R2年出題】
労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている。

【解答】
【R2年出題】 〇
例えば、「原材料の製造者又は輸入者」については、原材料が原因になる労働災害を防止するために、製造や輸入の段階で労働災害防止のための措置をとる努力が求められています。
(法第3条第2項、第3項)
最後に条文で復習しましょう。
法第3条 第2項
機械、器具その他の設備を< A >し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは< A >する者は、これらの物の< A >、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に< B >なければならない。

【解答】
A 設計
B 資するように努め
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩②」過去問の活用(労働基準法)
「最初の一歩②」過去問の活用(労働基準法)
R4-102
R3.12.2 「労働時間」とは?(労基 過去問活用編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
今日は、「労働時間」の定義を確認しましょう。
労働基準法第32条で法定労働時間が定められています。
法第32条 (労働時間) ① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 |
労働基準法では、労働時間の最長を「1週間40時間、1日8時間」と定めています。
この時間のことを「法定労働時間」といいます。(なお、1週44時間となる特例も設けられていますが、今日は詳しく触れません。)
使用者は、法定労働時間の範囲内で、事業場や労働者ごとに労働時間を定めますが、その時間のことを所定労働時間といいます。
例えば、就業規則で定めた所定労働時間が1日7時間で、ある日に9時間労働させた場合は、法定時間外労働は、1日8時間を超えた時間である1時間となります。
労働者に法定時間外労働をさせる場合は、36協定の締結と届出、割増賃金の支払が労働基準法で使用者に義務付けられています。

では、具体的に「労働時間」の意味を過去問で確認しましょう。
①【H21年出題】
労働者を就業規則に定める休憩時間に来客当番として事務所に待機させたが、その時間に実際に来客がなかった場合には、休憩時間以外の労働時間が法定労働時間どおりであれば、使用者は、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
②【R2年出題】
運転手が2名乗り込んで、1名が往路を全部運転し、もう1名が復路を全部運転することとする場合に、運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間は労働時間に当たる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
「休憩時間」は、労働から解放されることが約束された時間のことです。
休憩時間の来客当番は、来客があった場合には、即、接客が義務づけられている状態ですので労働から解放されていません。その時間に実際に来客がなかった場合でも、「手待ち時間」であり、労働時間となります。
問題文の場合は、割増賃金を支払う義務があります。
(昭23.4.7基収1196号)
②【R2年出題】 〇
運転しない者が助手席で休息し又は仮眠している時間でも、いつでも運転ができる状態にある時間は手待ち時間で、労働時間に当たります。
(昭33.10.11基収6286号)
★この過去問でおさえておくところ★
手待ち時間は労働時間

では、条文を穴埋めで確認しましょう。
第32条 (労働時間)
① 使用者は、労働者に、< A >を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、< A >を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

【解答】
A 休憩時間
例えば、
始業 8時
終業 17時
休憩12時~13時
の場合、拘束時間9時間、休憩1時間で、労働時間は8時間となります。
休憩時間は労働時間から除かれることに注意しましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩①」条文の読み方(労働基準法)
「最初の一歩①」条文の読み方(労働基準法)
R4-101
R3.12.1 専門用語に慣れましょう(労働基準法編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
「勉強始めよう」と決意したものの、
専門用語が多すぎてくじけてしまう
過去問が活用できない(解くだけで終わってしまう)
条文の読み方が難しい
という方も多いと思います。
2022年まであと1か月。
新年から、社労士の受験勉強を本格化させようと決心している方も多いはず。
本格的なスタートの前に、
少しだけ条文や過去問に慣れてみましょう。
労働基準法から順番にお話していきます。

では早速、労働基準法第15条第1項を読んでみましょう。
第15条(労働条件の明示) 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 |
ポイント1 「その他の」
★「賃金、労働時間その他の労働条件」の「その他の」に注目してください。
「その他の」の前にある語句は、「その他の」の後ろにある語句の中に含まれます。
第15条の労働条件は、「賃金、労働時間」も含んだ「労働条件」となります。
★「その他の」ではなく、「の」のつかない「その他」という用語もあります。
例えば、第7条(公民権行使の保障)の条文は、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は・・・(以下略)」です。
「選挙権」と「公民としての権利」の間に「その他」が入っています。この場合は、「選挙権」と「公民としての権利」が並んでいるだけです。
ポイント2 「厚生労働省令で定める方法」
★「厚生労働省令」に注目してください。
後段に「厚生労働省令で定める方法」とありますが、この「厚生労働省令で定める方法」は、具体的には、「労働基準法施行規則第5条第4項」に規定されています。
「法令」には、法律、政令、省令があり、「法律」は国会、「政令」は内閣、「省令」は各大臣が制定します。
労働基準法の場合、国会が制定した法律として「労働基準法」、内閣が制定した政令として「時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」など、厚生労働大臣が制定した厚生労働省令として「労働基準法施行規則」があります。
労働契約時に明示する労働条件の明示の方法については、法律では「厚生労働省令で定める方法により明示」としか書いてありませんが、具体的な方法は「労働基準法施行規則」を見れば書いてある、という仕組みです。
ちなみに、労働基準法施行規則第5条第4項では、明示の方法は、「書面の交付とする」とされていますが、労働者が希望した場合には、「ファクシミリ」、「電子メール等」(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)による明示も認められています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-100
R3.11.30 障害基礎年金の併合認定
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「障害基礎年金の併合認定」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9A】
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。

【解答】
①【R3年問9A】 〇
障害基礎年金の受給権者に更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。
「障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中」でも、障害基礎年金の受給権者であることに注意してください。
(法第31条)
もう一問どうぞ!
②【H26年出題】
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のときに、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金が支給される。

【解答】
②【H26年出題】 ×
どちらかを選択するのではなく、前後の障害が併合されます。
精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金の受給権者に、更に足の障害による障害等級1級の障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。
前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得した場合は、従前の障害基礎年金の受給権は消滅します。
(法第31条)
条文を穴埋めで確認しましょう
第31条 (併給の調整)
障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、< A >した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
障害基礎年金の受給権者が< A >した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、< B >する。

【解答】
A 前後の障害を併合
B 消滅
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-099
R3.11.29 時効消滅不整合期間
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「時効消滅不整合期間」です。
では、どうぞ!
①【R3年問3E】
被保険者又は被保険者であった者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間は、当該届出の行われた日以後、国民年金法第89条第1項に規定する法定免除期間とみなされる。

【解答】
①【R3年問3E】 ×
「法定免除期間」ではなく、「学生納付特例期間」とみなされます。年金の受給資格期間には算入されますが、年金の額には反映しません。
★「時効消滅不整合期間」とは?
例えば、夫が会社員(第2号被保険者)、妻が専業主婦(第3号被保険者)の夫婦で、夫が退職し自営業になった場合の国民年金の種別を考えてみましょう。
夫は第2号被保険者から第1号被保険者に、妻は第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更になります。
その際、妻が第3号から第1号への種別変更の届出をしていなかったとすると、実態は国民年金の第1号被保険者であったにもかかわらず、記録上は第3号被保険者のままになってしまいます。その期間のことを「不整合期間」といいます。
3号不整合記録を1号に切り替えると保険料を納付しなければなりませんが、2年の時効が経過した期間は保険料を納められません。その期間を「時効消滅不整合期間」といいます。
救済措置として「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」があります。この届出によって、「時効消滅不整合期間」は「特定期間」となります。
特定期間は「学生納付特例期間」とみなされ、年金の受給資格期間に算入されることになります。
なお、「特定期間」の対象は、昭和61年4月から平成25年6月までの間です。
(法附則第9条の4の2)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
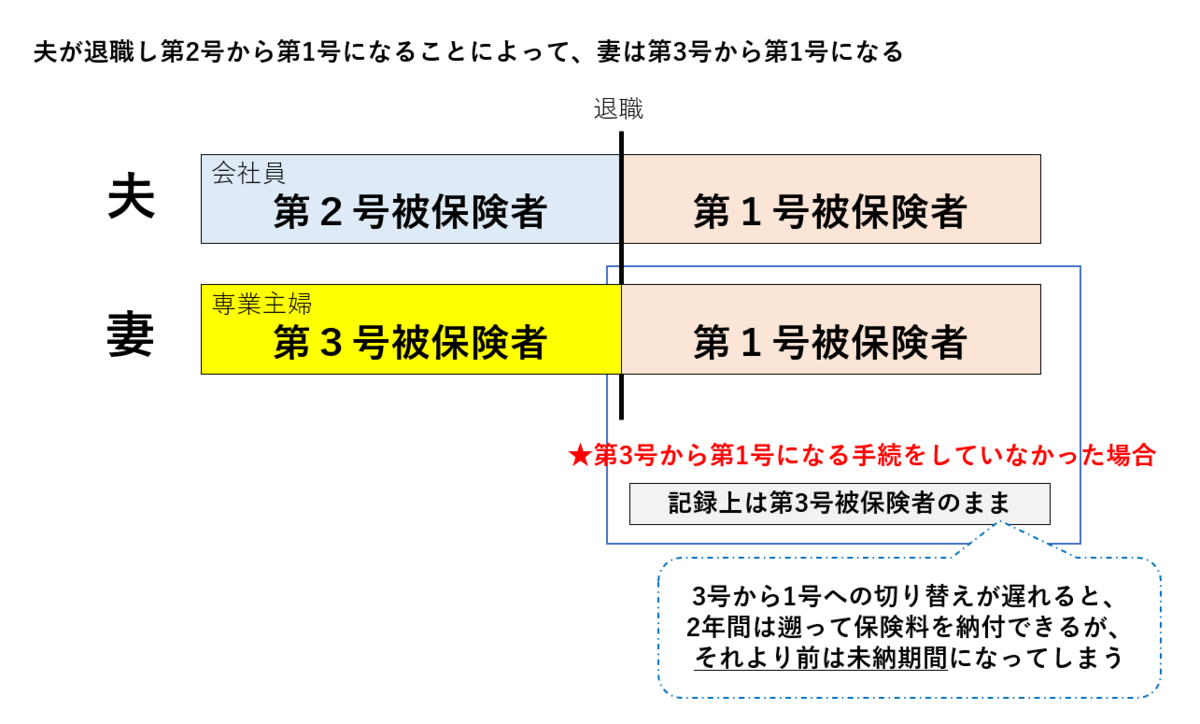
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-098
R3.11.28 2以上の種別の被保険者であった期間がある場合の中高齢寡婦加算
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「2以上の種別の被保険者であった期間がある場合の中高齢寡婦加算」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7E】
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金(中高齢の寡婦加算額が加算されるものとする。)は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を加算し、それぞれ1の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて按分した額とする。

【解答】
①【R3年問7E】 ×
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上あること)が死亡した場合、遺族厚生年金は長期要件となります。
中高齢寡婦加算額は按分して支払われるのではなく、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間に基づく遺族厚生年金に加算されます。また、最も長い一の期間が2以上ある場合は、①第1号②第2号③第3号④第4号の順序で加算されます。
なお、長期要件の場合の中高齢寡婦加算は、死亡した夫の被保険者期間が240月以上あることが条件です。240月以上の計算は、2以上の種別の被保険者であった期間を合算します。
(施行令第3条の13の7)
ここもチェック!
| 2以上の種別の被保険者であった期間を有する場合の遺族厚生年金について | |
| 年金の決定、支払 | |
| 短期要件 | 死亡日(又は初診日)に加入していた実施機関が行う |
| 長期要件 | それぞれの加入期間ごとに各実施機関が行う |
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間が15年、第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。
③【H30年出題】
障害等級1級の障害厚生年金の受給権者(厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件には該当しないものとする。)が死亡し、その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合、遺族厚生年金の額については、その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお、それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は、300か月として計算する。

【解答】
②【H28年出題】 〇
第1号(15年)+第3号(18年)ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される遺族厚生年金は長期要件です。長期要件の場合は、それぞれの被保険者期間に応じた遺族厚生年金が、それぞれの実施機関から支給されます。
(法第78条の32)
③【H30年出題】 〇
問題文は障害等級1級の障害厚生年金の受給権者の死亡ですので、短期要件の遺族厚生年金です。
2以上の種別に係る被保険者であった期間を合算して、1つにまとめて計算した遺族厚生年金が、初診日における被保険者の種別に応じた実施機関から支給されます。
(法78条の第32)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-097
R3.11.27 異なる被保険者の種別に係る資格の得喪
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「異なる被保険者の種別に係る資格の得喪」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7D】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【R3年問7D】 〇
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有したときは、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。
第1号厚生年金被保険者と第2号厚生年金被保険者が両方適用されるのではなく、第1号厚生年金被保険者の「資格を喪失」することに注意しましょう。
(法第18条の2)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
昭和20年10月2日以後に生まれた者であり、かつ、平成27年10月1日の前日から引き続いて国、地方公共団体に使用される者で共済組合の組合員であった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
③【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
平成27年10月1日に、被用者年金が一元化され、国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員も厚生年金保険の被保険者となりました。
昭和20年10月2日以後に生まれた者(施行時に70歳未満)で、かつ、施行日の前日(平成27年9月30日)に共済組合の組合員や私立学校教職員共済の加入者だった者は、平成27年10月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得しました。
(H24法附則第5条)
③【H28年出題】 ×
第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に第1号厚生年金被保険者の資格を喪失しますので、「2以上事業所選択届」を届け出ることはありません。
このような場合は、資格取得届・資格喪失届を提出することになります。
(法第18条の2)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第18条の2(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、第13条の規定にかかわらず、同時に、< A >の資格を取得しない。
< A >が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、< B >に、当該< A >の資格を喪失する。

【解答】
A 第1号厚生年金被保険者
B その日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-096
R3.11.26 基準障害による障害厚生年金
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「基準障害による障害厚生年金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4ア】
厚生年金保険法第47条の3第1項に規定する基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金の支給は、当該障害厚生年金の請求があった月の翌月から始まる。

【解答】
①【R3年問4ア】 〇
「基準障害による障害厚生年金」は、基準障害と他の障害とを併合して初めて1級又は2級に該当したときに、併合した障害の程度による障害厚生年金が支給されるものです。
初めて1級又は2級に該当したときではなく、当該障害厚生年金の「請求があった月の翌月」から始まるのがポイントです。
(法第47条の3)
ポイント!
「その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない障害厚生年金」は法第48条の併合認定の対象になる障害厚生年金からは除かれることを、ひとつ前の記事で書きました。
こちら → R3.11.25 2以上の障害が生じた場合の併合認定
受給権を取得した当時から3級の障害厚生年金は、法第48条の併合認定の対象にはなりませんが、例えば、先発の障害厚生年金が3級で、後発の障害(基準障害)と併合して初めて1級または2級に該当した場合は、第47条の3の基準障害による障害厚生年金の対象となります。
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
「基準傷病の初診日」は、基準傷病以外の傷病の初診日より後であることが条件です。併合のきっかけになるのが基準傷病ですので、一番後ろにくることになります。
(法第47条の3)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第47条の3(基準障害による障害厚生年金)
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後< A >までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の < B >に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。

【解答】
A 65歳に達する日の前日
B 1級又は2級
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-095
R3.11.25 2以上の障害が生じた場合の併合認定
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「2以上の障害が生じた場合の併合認定」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4イ】
厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたことにより、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止するものとされている。

【解答】
①【R3年問4イ】 ×
併合認定した場合、従前の障害厚生年金は、支給停止ではなく、「失権」します。
例えば、2級の障害厚生年金の受給権者に対して更に2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害が併合されます。併合の結果1級に該当した場合は、1級の障害厚生年金が支給されます。
併合の結果、1級の障害厚生年金受給権を取得した場合は、従前の障害厚生年金の受給権は消滅します。支給停止ではありませんので注意しましょう。
(法第48条)
ポイント!
法第48条の併合認定の対象になる障害厚生年金からは、「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るもの」は除かれます。
一度でも1級か2級の状態にあったものが併合の対象となります。
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
③【H27年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】
②【H29年出題】 〇
①の問題と同じです。
「障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は障害等級3級」ということは、障害基礎年金が支給停止中ということです。
先発の障害厚生年金が、1度でも1級又は2級に該当したことがある場合は、現在3級でも法第48条の規定による併合の対象となります。
③【H27年出題】 ×
受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことがない3級の障害厚生年金は、併合の対象になりません。
(法第48条)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第48条(障害厚生年金の併給の調整)
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の< A >に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を< B >した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
障害厚生年金の受給権者が前後の障害を< B >した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、< C >する。

【解答】
A 1級又は2級
B 併合
C 消滅
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-094
R3.11.24 3号分割/特定被保険者が障害厚生年金の受給権者のとき
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「3号分割/特定被保険者が障害厚生年金の受給権者のとき」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1E】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。

【解答】
①【R3年問1E】 ×
3号分割制度は、当事者の合意は不要です。
そのため、特定被保険者(分割される側)が障害厚生年金の受給権者で、問題文のように特定期間の全てが障害厚生年金の計算の基礎となっている場合は、特定被保険者の被扶養配偶者(分割を受ける側)は、3号分割標準報酬改定請求はできません。
(法第78条の14)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者(以下「特定被保険者」という。)が、障害厚生年金の受給権者である場合、当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は、3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から除かれる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
①と同じです。
特定被保険者が障害厚生年金の受給権者である場合、障害厚生年金の計算の基礎になっている被保険者期間は3号分割標準報酬改定請求の対象になりません。そのため、障害厚生年金の計算の基礎になっている被保険者期間は、改定される期間から除かれます。
(法第78条の14)
用語の定義を穴埋めで確認しましょう!
【H26年出題】※穴埋めにアレンジ
いわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」について、分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として< A >であった期間をいい、< B >前の期間を含まない。

【解答】
A 国民年金の第3号被保険者
B 平成20年4月1日
(法第78条の14)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-093
R3.11.23 加給年金額が支給停止されるとき
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「加給年金額が支給停止されるとき」です。
では、どうぞ!
①【R3年問8D】
老齢厚生年金における加給年金額の対象となる配偶者が、障害等級1級又は2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。

【解答】
①【R3年問8D】 ×
加給年金額の対象の配偶者が、障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合も、加給年金額は支給停止されます。
★加給年金額の対象になる配偶者が、以下の給付を受けることができるときは、加給年金額が支給停止されます。
・ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る。)
・ 障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの支給を受けることができるとき
→ 障害厚生年金は、1級、2級に限定されていませんので、配偶者が3級の障害厚生年金の支給を受けるときでも、加給年金額の支給が停止されます。
→ なお、「障害手当金」については、受給していても、加給年金額は支給停止されません。
(法第46条、施行令第3条の7)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
③【H22年出題】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
④【H28年出題】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
①の問題と同じです。配偶者が3級の障害厚生年金を受給している場合は、加給年金額は支給停止されます。
(法第46条)
③【H22年出題】 〇
加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給が停止されます。
ポイント!
・ 支給停止の対象になるのは、240月以上で計算される老齢厚生年金に限られます。(中高齢期間短縮特例該当者は240月未満でも240月とみなされます。)
・ 対象になる配偶者の老齢厚生年金が「全額支給停止されている」場合は、加給年金額は支給停止されず、加算されます。
④【H28年出題】 ×
対象になる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときでも、加給年金額は、配偶者が65歳になるまで加算されます。
(法第46条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-092
R3.11.22 脱退一時金の額の計算
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「脱退一時金の額の計算」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9D】
脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。

【解答】
①【R3年問9D】 〇
脱退一時金は、「被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率」で計算します。この場合の平均標準報酬額の算出に当たって、各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率は乗じません。
(法附則第29条)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。

【解答】
②【H27年出題】 ×
前年9月ではなく、前年10月です。
支給率は、資格喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率です。
被保険者であった期間に応じた数は、「6」から「60」まで設定されています。(最終月が2021年(令和3年)4月以降の場合)
例えば、被保険者であった期間が60月以上の場合の支給率は、「資格喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率×2分の1×60」ですので、1000分の183×2分の1×60で「5.5」となります。(小数点以下1位未満の端数は四捨五入)(法附則第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-091
R3.11.21 脱退一時金の支給要件のチェックポイント
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「脱退一時金の支給要件のチェックポイント」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9C】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【解答】
①【R3年問9C】 〇
この問題のチェックポイント!
■「ある日本国籍を有しない者」
→脱退一時金は「日本国籍を有しない者」が対象です。
■「最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過」している。
→脱退一時金は、「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき」は支給されません。
問題文の時点では、「1年が経過」したところです。脱退一時金の請求は可能です。
■「厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上」有している
→脱退一時金は、被保険者期間が6か月以上あることが要件です。
■「障害厚生年金等の受給権を有したことがない」
→障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるときは、脱退一時金は支給されません。
(法附則第29条)
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
③【H26年出題】修正あり
日本国籍を有しない者について、障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。
④【R1年出題】
被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
③【H26年出題】 ×
「障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したこと」がある場合は、脱退一時金は請求できません。障害手当金は、「その他政令で定める保険給付」に入っています。
(法附則第29条、施行令第12条)
④【R1年出題】 ×
脱退一時金の請求に回数は設けられていませんので、所定の要件を満たせば、再度、脱退一時金の支給を請求することもできます。
(法附則第29条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-090
R3.11.20 老齢厚生年金の繰下げと遡及の選択
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「老齢厚生年金の繰下げと遡及の選択」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E】
昭和28年4月10日生まれの女性は、65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する予定でいたが、配偶者が死亡したことにより、女性が68歳の時に遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、68歳で老齢厚生年金の繰下げの申出をせずに、65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給することができる。また、遺族厚生年金の受給権を取得してからは、その老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給することができる。

【解答】
①【R3年問9E】 〇
 老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げはそれぞれ選択できます(同時に繰下げなくてもいい)
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げはそれぞれ選択できます(同時に繰下げなくてもいい)
問題文のように、「65歳から老齢基礎年金を受給」し、「老齢厚生年金は繰下げし70歳から受給する」選択も可能です。
 66歳に達した日後に他の年金を受ける権利ができた場合の選択肢は2つ
66歳に達した日後に他の年金を受ける権利ができた場合の選択肢は2つ
①他の年金が発生した時点の繰下げ増額率で、繰下げの老齢厚生年金を受給する
②65歳からの本来の老齢厚生年金を遡って請求する
問題文のように、68歳で遺族厚生年金の受給権を取得した場合、②を選択し、「65歳に老齢厚生年金を請求したものとして遡って老齢厚生年金を受給すること」ができます。この場合は、繰下げによる増額はありません。
 遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整
遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より多い場合は、差額の遺族厚生年金が支給されます。
問題文のように、「老齢厚生年金の年金額と遺族厚生年金の年金額を比較して遺族厚生年金の年金額が高ければ、その差額分を遺族厚生年金として受給すること」ができます。
遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整は、こちらの記事で解説しています。
こちら→ R3.11.18 遺族厚生年金の額の計算
(法第44条の3)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。
③【H28年出題】
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。

【解答】
②【H26年出題】 ×
67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となっても、老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができます。
その場合、繰下げ増額率は、遺族厚生年金の受給権ができた時点で計算されます。
なお、65歳の時点に遡って老齢厚生年金を請求することもできます。
(法第44条の3)
③【H28年出題】 〇
老齢厚生年金の支給繰下げの申出と、老齢基礎年金の支給繰下げの申出は、それぞれ別にすることができます。
(法第44条の3)
なお、支給繰上げについては、老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-089
R3.11.19 障害手当金と労災保険の関係
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「障害手当金と労災保険の関係」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10B】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
①【R3年問10B】 ×
「両方の保険給付が支給される」が誤りです。
障害の程度を定めるべき日において当該傷病について、「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付」を受ける権利を有する者には、障害手当金を支給しない、と規定されています。
問題文の場合は、「障害手当金」は支給されません。
(法第56条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

【解答】
②【H25年出題】 ×
当該障害の原因となった傷病について「労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されない」の部分は正しいですが、「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される」の部分が誤りです。「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者」にも「障害手当金」は支給されません。
(法第56条)
条文を穴埋めで確認しましょう
第55条 第1項 (障害手当金の受給権者)
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して< A >を経過する日までの間におけるその傷病の< B >日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

【解答】
A 5年
B 治った
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-088
R3.11.18 遺族厚生年金の額の計算
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「遺族厚生年金の額の計算」です。
では、どうぞ!
①【R3年問8C】
63歳の被保険者の死亡により、その配偶者(老齢厚生年金の受給権を有し、65歳に達している者とする。)が遺族厚生年金を受給したときの遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額と、当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額のうちいずれか多い額とする。

【解答】
①【R3年問8C】 ×
問題文の遺族厚生年金の基本の額と比較する「当該遺族厚生年金の受給権者の有する老齢厚生年金の額に3分の2を乗じて計算した額」の部分が誤りです。
遺族厚生年金の基本の計算式は、「死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額×4分の3」です。
ただし、遺族のうち「65歳以上で老齢厚生年金の受給権を有する配偶者」の遺族厚生年金は、次の2つのうち、どちらか多い額となります。
ⓐ 「死亡した被保険者の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の額×4分の3」(上記の基本の計算式)
ⓑ ⓐの額×3分の2 + 配偶者自身の老齢厚生年金の額×2分の1
(法第60条)
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
②【H29年出題】 〇
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上の場合の規定で、遺族自身の老齢厚生年金を優先して受給できるようにするための調整です。
遺族厚生年金の受給権者が65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金は全額支給、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます。
遺族厚生年金の額が、老齢厚生年金より多い場合は、差額の遺族厚生年金が支給されます。
(法第64条の2)
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
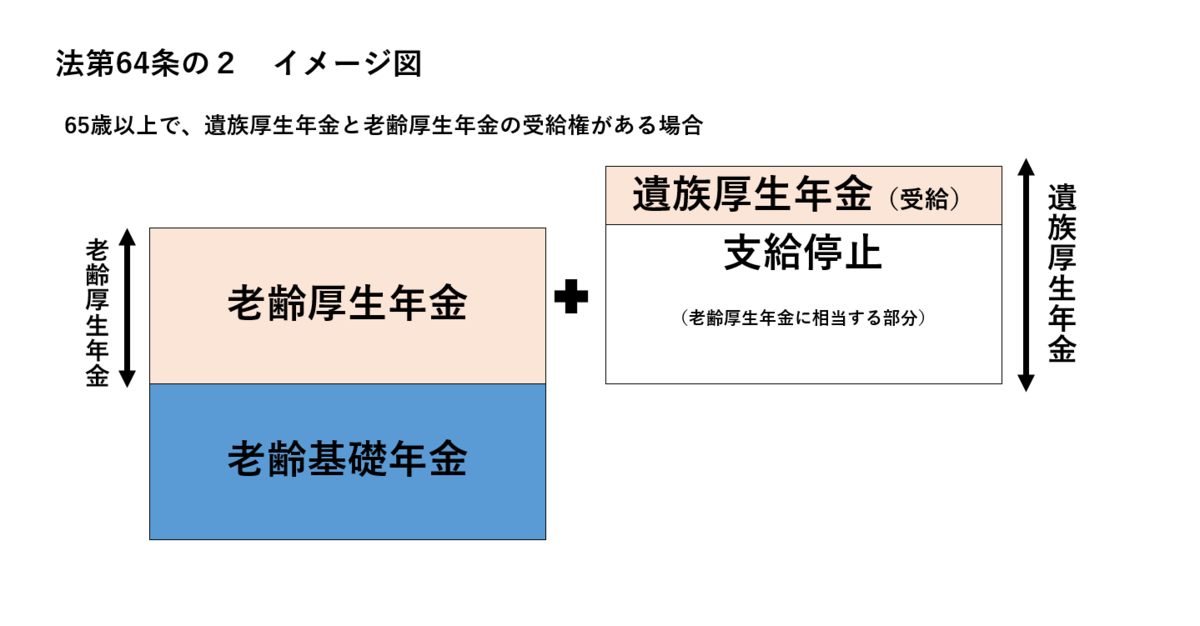
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-087
R3.11.17 遺族厚生年金の失権事由
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「遺族厚生年金の失権事由」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10E】
第1号厚生年金被保険者が死亡したことにより、当該被保険者の母が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、当該母に事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた場合でも、当該母は、自身の老齢基礎年金と当該遺族厚生年金の両方を受給することができる。

【解答】
①【R3年問10E】 ×
婚姻をしたときは、遺族厚生年金の受給権は消滅します。
婚姻には、「届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合」も含まれます。
問題文の母の遺族厚生年金の受給権は、「事実上の婚姻関係にある配偶者が生じた」ことによって消滅します。ですので、母が受給できるのは、自身の老齢基礎年金のみとなります。
(法第63条)
★なお、「直系血族及び直系姻族以外の者の養子」となったときも、遺族厚生年金の受給権は消滅します。ここに出てくる「養子」についても、「届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者」を含みます。
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
遺族厚生年金の受給権者である妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻した場合であっても、遺族厚生年金の失権事由である離縁による親族関係の終了には該当しないため、その受給権は消滅しない。

【解答】
②【H27年出題】 〇
妻が実家に復籍して姓も婚姻前に戻しても、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
(昭32.2.9保文発9485)
なお、遺族厚生年金の失権事由である「離縁による親族関係の終了」について、「離縁」とは養子縁組関係の終了のみをいいます。
(昭30.4.11保文発3441)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-086
R3.11.16 経過的寡婦加算のこと
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「経過的寡婦加算のこと」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
昭和32年4月1日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。

【解答】
①【R3年問1B】 ×
昭和32年4月1日生まれの妻には、経過的寡婦加算は加算されません。
経過的寡婦加算が加算されるのは、「昭和31年4月1日以前」に生まれた妻です。新法が施行された昭和61年4月1日に30歳以上だった人が対象です。
第3号被保険者の制度が始まったのは昭和61年4月。昭和61年4月から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金と経過的寡婦加算を合わせて 中高齢寡婦加算の額(遺族基礎年金の4分の3)と同じ額になるよう設定されています。
昭和31年4月2日以降生まれの場合、昭和61年4月から60歳に達するまですべて国民年金に加入すると「遺族基礎年金の4分の3」の額は支給されるので、経過的寡婦加算は加算されません。
(昭和60年法附則第73条)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】※改正による修正あり
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある老齢厚生年金の受給権者(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上。)が死亡したことによりその妻(昭和25年4月2日生まれ)に支給される遺族厚生年金は、その権利を取得した当時、妻が65歳以上であっても、経過的寡婦加算が加算される。なお、当該妻は障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給権を有しないものとする。

【解答】
②【H27年出題】 〇
ポイント!
・遺族厚生年金の受給権が発生したときに、既に妻が65歳以上でも、経過的寡婦加算が加算されます
・長期要件(保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上)の場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間の月数が原則240か月以上あることが条件です。
(昭和60年法附則第73条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-085
R3.11.15 国民年金基金加入員資格の喪失
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金基金加入員資格の喪失」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4エ】
基金の加入員は、いつでも基金に申し出て、加入員の資格を喪失することができる。
(注)基金=国民年金基金のことです。

【解答】
①【R3年問4エ】 ×
国民年金基金には、申し出による資格喪失の規定はありません。
(法第127条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
第1号被保険者は、国民年金基金に対し加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得し、加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失する。
③【H29年出題】
国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。
④【H27年出題】
国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「加入員となる申出をした日に当該加入員の資格を取得する」の部分は正しいです。しかし①の問題で見たように、申出による資格喪失はできませんので、「喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を喪失」の部分が誤りです。
(法第127条)
③【H29年出題】 〇
第2号被保険者は国民年金基金に加入できませんので、第2号被保険者となったときは、加入員の資格を喪失します。資格を喪失するのは「その日」がポイントです。
(法第127条)
④【H27年出題】 〇
国民年金保険料の全部又は一部について免除された時は、加入員の資格を喪失します。「その月の初日」に加入員の資格を喪失するのがポイントです。
(法第127条)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第127条第3項
加入員は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号又は第四号に該当するに至ったときは、その日とし、第三号に該当するに至ったときは、当該保険料を納付することを要しないものとされた< A >とする。)に、加入員の資格を喪失する。
一 被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第3号被保険者となったとき。
二 地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき。
三 保険料免除の規定によりその全部又は一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき。
四 < B >の被保険者となったとき。
五 当該基金が< C >したとき。

【解答】
A 月の初日
B 農業者年金
C 解散
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-084
R3.11.14 国民年金と厚生年金の調整
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金と厚生年金の調整」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9D】
父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。

【解答】
①【R3年問9D】 〇
基礎年金と厚生年金は支給事由が同じなら、2階建てで併給できます。
父が死亡したことによる「遺族基礎年金」と、祖父が死亡したことによる「遺族厚生年金」は、支給事由が異なります。そのため、問題文の遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給されず、どちらかを選択することになります。
(法第20条)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】※改正による修正あり
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡について厚生年金保険法から同一の支給事由による年金たる保険給付を受けるときは、その間、その額の5分の2に相当する額が支給される。

【解答】
②【H24年出題】 ×
遺族基礎年金は、同一の支給事由による遺族厚生年金と併給されます。その場合、 遺族基礎年金も遺族厚生年金も、全額が支給されます。
(法第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-083
R3.11.13 寡婦年金と死亡一時金
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「寡婦年金と死亡一時金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E】
第1号被保険者として30年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

【解答】
①【R3年問9E】 〇
同一人に、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権が発生した場合の問題です。
ポイントその1
「一人一年金の原則」がありますので、「遺族厚生年金」と「寡婦年金」はどちらかを選択します。
ポイントその2
死亡一時金と寡婦年金については、「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」となっていますので、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されません。
なお、遺族厚生年金と死亡一時金は調整されませんので、両方とも支給されます。
(法第20条、第52条の6)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】
夫の死亡により、寡婦年金と死亡一時金の受給要件を同時に満たした妻に対しては、寡婦年金が支給される。ただし、夫の死亡日の属する月に寡婦年金の受給権が消滅したときは、この限りでない。

【解答】
②【H24年出題】 ×
「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」です。
(法第20条、第52条の6)
こちらもどうぞ!
③【H25年出題】
『ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない。』
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が結婚して以後25年間同居していた50歳の妻だけである場合、妻は遺族として、寡婦年金と死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得するが、寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみを選択することとなり、死亡一時金を選択した場合、遺族厚生年金も受給できる。

【解答】
③【H25年出題】 〇
寡婦年金と死亡一時金はどちらか一方のみの選択になります。
死亡一時金と遺族厚生年金はどちらも受給できます。
(法第20条、第52条の6)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-082
R3.11.12 受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたとき」です。
では、どうぞ!
①【R3年問6B】
配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。

【解答】
①【R3年問6B】 ×
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、『将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす』と規定されています。
生まれたときから遺族になりますので、遺族基礎年金の額の改定は、「生まれた日の属する月の翌月から」となります。被保険者又は被保険者であった者の死亡した日までさかのぼりません。
(法第37条の2、第39条)
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される。なお、当該子以外に子はいないものとする。
③【H13年出題】
妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する。

【解答】
②【H30年出題】 ×
夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、生まれたときに受給権が発生します。そして、「生まれた日の属する月の翌月から」遺族基礎年金の額が改定されます。
(法第37条の2、第39条)
③【H13年出題】 〇
「その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の額を改定する」の部分がポイントです。
(法第37条の2、第39条)
条文を穴埋めで確認しましょう
第37条の2 (遺族の範囲)
1 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって< A >し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって< A >し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と< B >すること。
二 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、1の規定の適用については、< C >、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって< A >していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と< B >していたものとみなす。

【解答】
A 生計を維持
B 生計を同じく
C 将来に向かって
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-081
R3.11.11 一人一年金の原則(併給の調整)
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「一人一年金の原則(併給の調整)」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10B】
併給の調整に関し、国民年金法第20条第1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。

【解答】
①【R3年問10B】 〇
一人に対して、複数の年金の受給権が発生することがあります。年金は、「一人一年金」の原則があります。例えば、障害基礎年金と老齢基礎年金が支給されるときは、まず、両方の年金の支給が停止されます。障害基礎年金の受給を選択した場合は、障害基礎年金の支給停止が解除され、老齢基礎年金はそのまま支給停止となります。
その後、老齢基礎年金に選択替えをすることもできます。その場合、問題文のように、「支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。」となります。
(法第20条)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題】
障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。
③【H25年出題】
併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

【解答】
②【H23年出題】 ×
「他方の年金の受給権は消滅」が誤りです。選択しなかった他方の年金は「支給停止」になります。
(法第20条)
③【H25年出題】 ×
いわゆる選択替えは、「いつでも、将来に向かって撤回することができる」と規定されています。「毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる」は誤りです。
(法第20条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-080
R3.11.10 国民年金基金の中途脱退者
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金基金の中途脱退者」です。
では、どうぞ!
①【R3年問4ア】
国民年金基金(以下「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15年に満たない者をいう。

【解答】
①【R3年問4ア】 〇
国民年金基金における中途脱退者の要件は、
・基金の加入員資格を中途で喪失している
・資格を喪失した日に、当該基金が支給する年金の受給権を有しない
・当該基金の加入員期間が15年に満たない
の3つです。
(法第137条の17、基金令第45条)
★なお、国民年金基金連合会は、基金から年金の現価相当の移換を受け、中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行います。
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。
③【H23年出題】
A県の地域型国民年金基金に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し、再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが、50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合、加入員期間は通算して20年になるため、年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける。

【解答】
②【H30年出題】 ×
中途脱退者とは、「当該基金の加入員期間の年数にかかわらず」ではなく、「15年に満たない者」をいいます。
(基金令第45条)
③【H23年出題】 〇
基金の加入員期間は通算して20年になるので、中途脱退者ではありません。そのため、年金又は一時金の支給は、国民年金基金連合会からではなく、A県の地域型国民年金基金から受けることになります。
(法第137条の17)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-079
R3.11.9 国民年金~年金の支払調整(内払)
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金~年金の支払調整(内払)」です。
では、どうぞ!
①【R3年問2A】
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。

【解答】
①【R3年問2A】 〇
「内払」は「同一人」に対する年金間の調整です。
国民年金と厚生年金保険は制度が違いますが、内払調整の対象となります。
同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降も障害厚生年金が支払われたときは、障害厚生年金を返還し、改めて老齢基礎年金を支給するのではなく、その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる、という規定です。
(法第21条)
こちらもどうぞ!
②【H22年出題 改正による修正あり】
障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の支給を停止し、老齢基礎年金を支給すべき場合に、支給を停止すべき月の翌月以降の分として障害厚生年金が支払われた場合であっても、両年金は、異なる制度の年金であるので、障害厚生年金を老齢基礎年金の内払とみなすことはできない。

【解答】
②【H22年出題 改正による修正あり】 ×
障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)と老齢基礎年金は、異なる制度の年金ですが、利便性に資するため、内払調整の対象となります。①の問題と同じです。
条文を穴埋めで確認しましょう!
第21条 第3項
同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(< A >が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する< B >以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の< C >とみなすことができる。

【解答】
A 厚生労働大臣
B 月の翌月
C 内払
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-078
R3.11.8 国民年金種別の変更
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「国民年金種別の変更」です。
★ 被保険者の種別とは、第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区分を言います。
では、どうぞ!
①【R3年問2C】
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。

【解答】
①【R3年問2C】 〇
第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったときは、翌日に被保険者の資格を喪失します。しかし、その時点で、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、資格喪失ではなく、「種別の変更」となります。
(法第9条)
こちらもどうぞ!
②【H20年出題】
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
②【H20年出題】 ×
第2号被保険者から第1号被保険者になるのは「種別変更」です。資格取得届ではなく「種別変更届」を、当該事実があった日から14日以内に、市町村長に提出しなければなりません。
(法第12条、則第6条の2)
こちらもどうぞ!
③【H30年出題】
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者の種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

【解答】
③【H30年出題】 ×
同一月に、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があり、更に第3号被保険者への種別の変更があった場合は、その月は第2号被保険者ではなく、最後の種別の「第3号被保険者」であった月とみなされます。
(法第11条の2)
条文を穴埋めで確認しましょう!
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、< A >の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は< B >の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
A 変更後
B 最後
(法第11条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-077
R3.11.7 用語の定義~保険料免除期間
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「用語の定義~保険料免除期間」です。
では、どうぞ!
①【R3年問6E】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

【解答】
①【R3年問6E】 〇
「保険料免除期間」には、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間の4種類があります。
そのうち、保険料の一部が免除されるのは、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間の3種類です。
例えば、「保険料半額免除期間」とは、その半額につき納付することを要しないものとされた保険料に係るものをいいますが、「納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。」とされています。
例えば、令和3年度の国民年金の保険料は、16610円です。半額免除の場合、8,300円が免除され、残りの8,310円を納付した期間は、「保険料半額免除期間」となります。「保険料納付済期間」ではありませんので、注意しましょう。
なお、残りの8,310円を納付しない場合は未納期間となります。
(法第5条)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。
③【H24年出題】
保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
④【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
②【H28年出題】 〇
その一部の額が免除された保険料については、その残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間ではなく、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間のどれかとなります。
(法第5条)
③【H24年出題】 〇
②の問題と同じです。保険料納付済期間ではなく保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間、保険料4分の1免除期間のどれかとなります。
(法第5条)
④【H24年出題】 〇
法第94条第4項で「追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす」と規定されています。保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。
条文を穴埋めで確認しましょう!
第5条 (用語の定義)
国民年金法において、「< A >」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。
「保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって第90条の2第2項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第94条第4項の規定(< B >)により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

【解答】
A 保険料免除期間
B 追納
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-076
R3.11.6 第1号被保険者の条件
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「第1号被保険者の条件」です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

【解答】
①【R3年問3C】 〇
「日本の国籍を有しない者」で、次の①又は②に該当する場合は、国民年金の第1号被保険者から除外されます。
①在留資格が特定活動(医療滞在又は医療滞在者の付添人) (ア)本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの (イ)(ア)の活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの |
②在留資格が特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在又は長期滞在者の配偶者) 本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの |
問題文は②に該当するので、第1号被保険者からは除外されます。
※なお、①又は②に該当する場合は、第3号被保険者からも除外されます。
(則第1条の2)
こちらもどうぞ!
②【R1年出題】
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
国籍、年齢、国内居住要件は整理しておきましょう。
| 国籍 | 年齢 | 国内居住 | |
第1号被保険者 | 問わない | 20歳~60歳 | あり |
| 第2号被保険者 | 問わない | なし | |
| 第3号被保険者 | 20歳~60歳 | あり (例外あり) |
条文を穴埋めで確認しましょう!
第7条(被保険者の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1 < A >を有する< B >の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「第1号被保険者」という。)
2 < C >の被保険者(以下「第2号被保険者」という。)
3 第2号被保険者の配偶者(< A >を有する者又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち< B >のもの(以下「第3号被保険者」という。)

【解答】
A 日本国内に住所
B 20歳以上60歳未満
C 厚生年金保険
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-075
R3.11.5 就業規則の意見聴取
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「就業規則の意見聴取」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7C】
同一事業場において当該事業場の全労働者の3割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90条による意見聴取を行ったこととされる。

【解答】
①【R3年問7C】 ×
同一の事業場で、一部の労働者のみに適用される就業規則を別に作成することは可能です。ただし、意見聴取は、その事業場の全労働者の過半数で組織する労働組合又は、全労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
問題文は、当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合等になっているので誤りです。
(昭23.8.3基収2446号)
こちらもどうぞ!
②【H21年出題】
使用者は、パートタイム労働者など当該事業場の労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合には、当該一部の労働者のみ適用される別個の就業規則を作成することもできる。
③【H21年出題】
使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
④【H20年出題】
就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

【解答】
②【H21年出題】 〇
一部の労働者のみ適用される別個の就業規則を作成することもできます。その場合、労働基準法上の就業規則は、それぞれが単独でなるのではなく、その2つ以上の就業規則を合わせたものが労働基準法上の就業規則となります。
(平11.3.31基発168号)
③【H21年出題】 〇
就業規則の作成だけでなく、その変更についても、意見聴取が必要です。
(法第90条)
④【H20年出題】 ×
「同意を得なければならない」ではなく、「意見を聴かなければならない」です。
なお、意見書の内容が「反対」であったとしても、その就業規則の効力には影響しません。
(昭24.3.28基発373号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-074
R3.11.4 1か月単位の変形労働時間制導入手続き
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「1か月単位の変形労働時間制導入手続き」です。
では、どうぞ!
①【R3年問5B】
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。

【解答】
①【R3年問5B】 ×
1か月単位の変形労働時間制を、労使協定で導入する場合は、所轄労働基準監督署長への届出が義務づけられています。
届出をしなかった場合は罰則が適用されます。しかし、届出は労使協定の効力の発生要件とはなっていません。締結することで効力が発生します。ですので、問題文の最後の「この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。」の部分が誤りです。
なお、36協定は、「所轄労働基準監督署長に届け出る」ことによって効力が発生しますので、違いに注意しましょう。
良かったら「36協定の免罰効果」の記事も参考にしてください。
(法第32条の2)
こちらもどうぞ!
②【R1年出題】
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

【解答】
②【R1年出題】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」によって導入することができます。
「就業規則その他これに準ずるものによる定め」だけでも導入が可能です。
また、①の問題で見たように、「労使協定」で導入する場合は届出が必要ですが、届出が効力の発生要件ではないので、「当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる」の部分も誤りです。
なお、常時10人以上の労働者を使用する事業は就業規則作成義務があるので、1か月単位の変形労働時間制を導入する場合は、「労使協定」又は「就業規則」のどちらかとなります。「就業規則に準ずるもの」では導入できません。
10人未満の事業場では、「労使協定」又は「就業規則その他これに準ずるもの」で導入できます。
こちらもどうぞ!
③【H19年出題】
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7

【解答】
③【H19年出題】 〇
変形期間の所定労働時間の合計が、「その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7」で計算した時間内におさまるようにする必要があります。
例えば、変形期間を「1か月」とした場合、30日の月なら、「40時間×30日÷7=171.4時間」が1か月の総枠となります。1か月の所定労働時間の合計が171.4時間以内なら、変形期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となります。
ちなみに、特例事業場の場合は法定労働時間は44時間ですので、総枠は「44時間×30日÷7=188.5時間」となります。
最後に条文を穴埋めで確認しましょう!
第32条の2 1か月単位の変形労働時間制
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は< A >により、< B >以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、①の協定を行政官庁に届け出なければならない。

【解答】
A 就業規則その他これに準ずるもの
B 1か月
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-073
R3.11.3 前借金相殺の禁止
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「前借金相殺の禁止」です。
では、どうぞ!
①【R3年問2C】
労働基準法第17条にいう「労働することを条件とする前貸の債権」には、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融や賃金の前払いのような弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものも含まれる。

【解答】
①【R3年問2C】 ×
問題文のような「明らかに身分的拘束を伴わないもの」は、労働することを条件とする債権には「含まれない」とされています。
(昭22.9.13発基17号、昭33.2.13基発第90号)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
労働基準法第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸しの債権と賃金とを相殺することを禁止し、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することにより金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的としたものである。

【解答】
②【H27年出題】 〇
第17条は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離することで、身分的拘束の発生を防止することを目的とした条文です。
(法第17条)
こちらもどうぞ!
③【H28年出題】
労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
④【H25年出題】
労働契約を締結する際に、労働者の親権者が使用者から多額の金銭を借り受けることは、人身売買や労働者の不当な足留めにつながるおそれがあるため、当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず、労働基準法第17条に違反する。

【解答】
③【H28年出題】 ×
「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺すること」は使用者側で行うことのみが禁止されます。労働者からの意思により相殺することは禁止されていません。
④【H25年出題】 ×
第17条で禁止しているのは、前借金自体ではなく、「労働者の賃金と相殺」することです。「当該労働者の賃金と相殺されるか否かを問わず」の部分が誤りです。
最後に条文を穴埋めで確認しましょう!
第17条 (前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他< A >ことを条件とする前貸の債権と賃金を< B >してはならない。

【解答】
A 労働する
B 相殺
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-072
R3.11.2 36協定の免罰効果
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「36協定の免罰効果」です。
では、どうぞ!
①【R3年問5A】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

【解答】
①【R3年問5A】 〇
36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出をすることによって効力が発生します。締結しただけでは効力が発生しないのが36協定のポイントです。
問題文の36協定は、所轄労働基準監督署長に届け出た令和3年4月9日に効力が発生します。ですので、届け出前の令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた時間外労働は、36協定の効果がないため、違法なものとなります。
(法第36条)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】
労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを所轄労働基準監督署長に届け出てはじめて使用者が労働者に適法に時間外労働又は休日労働を行わせることを可能とするのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結したのみでは、労働基準法違反の責めを免れない。
③【H24年出題】
労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を適法に行わせるための手続を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者の民事上の義務は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものではない。

【解答】
②【H24年出題】 〇
本来、時間外労働、休日労働は労働基準法違反です。
しかし、36協定を締結し、かつ所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、適法に時間外労働又は休日労働を行わせることが可能になります。(免罰効果といいます。)
(法第36条)
③【H24年出題】 〇
36協定の直接効力は、時間外労働、休日労働の刑事上の免責です。
36協定の手続により免罰効果は生じますが、労働者に対して時間外又は休日労働命令をできる権利は生じません。時間外労働、休日労働命令に従わなければならない労働者の民事上の義務は、労働協約、就業規則などの根拠が必要です。
(法第36条、参照:昭63.1.1基発1)
次はこちらをどうぞ
④【H25年出題】
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。

【解答】
④【H25年出題】 〇
36協定の効力は、その労働組合の組合員でない他の労働者にも及びます。
(昭23.4.5基発535号)
最後にこちらをどうぞ!
⑤【H20年選択】
使用者が労働者に対し時間外労働を命じる場合について、「労働基準法〔…〕32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる三六協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が< A >ものである限り、それが具体的な労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする〔…〕」というのが最高裁判所の判例である。

【解答】
A 合理的な
(最高一小H3.11.28)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-071
R3.11.1 時間単位の年次有給休暇
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「時間単位の年次有給休暇」です。
では、どうぞ!
①【R3年問2E】
労働基準法第39条に従って、労働者が日を単位とする有給休暇を請求したとき、使用者は時季変更権を行使して、日単位による取得の請求を時間単位に変更することができる。

【解答】
①【R3年問2E】 ×
時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象になります。
しかし、日単位による取得の請求を時間単位に変更することや、時間単位による取得の請求を日単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められません。
(平21.5.29基発第0529001号)
★「時間単位年休」を導入する場合は、労使協定の締結が必要です。時間単位年休の制度により、労働者が時間単位で請求すれば、時間単位の年次有給休暇を取得することができることになります。
個々の労働者に対して時間単位による取得を義務付けるものではありませんし、時間単位で取得するか、日単位で取得するかは、労働者の意思によります。
(参照:平21.5.29基発第0529001号)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
労働基準法第39条第4項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時から午前10時までの1時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5項のいわゆる時季変更権を行使することができる。

【解答】
②【H25年出題】 〇
先ほどの①の解説にもありますが、時間単位年休も、使用者の時季変更権の対象になります。
(平21.5.29基発第0529001号)
次はこちらをどうぞ
③【H26年出題】
労働基準法第39条第6項に定めるいわゆる労使協定による有給休暇の計画的付与については、時間単位でこれを与えることは認められていない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
時間単位年休は、「労働者が時間単位による取得を請求した」場合に、時間単位により年次有給休暇を与えることができる制度です。そのため、計画的付与として時間単位年休を与えることは認められません。
(平21.5.29基発第0529001号)
では、条文を穴埋めで確認しましょう!
(時季指定権と時季変更権)
使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが< A >場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

【解答】
A 事業の正常な運営を妨げる
(法第39条第5項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-070
R3.10.31 賃金支払5原則「通貨払いの原則」
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「賃金支払5原則「通貨払いの原則」」です。
賃金の支払には5つの原則があります。
1 通貨払いの原則
2 直接払いの原則
3 全額払いの原則
4 毎月1回以上払いの原則
5 一定期日払いの原則
それぞれ原則の例外もおさえましょう。
では、どうぞ!
①【R3年問3イ】
賃金を通貨以外のもので支払うことができる旨の労働協約の定めがある場合には、当該労働協約の適用を受けない労働者を含め当該事業場のすべての労働者について、賃金を通貨以外のもので支払うことができる。

【解答】
①【R3年問3イ】 ×
「労働協約の適用を受けない労働者」には、通貨以外のもので支払うことはできません。
★ 賃金は、通貨で支払うのが原則ですが、「法令」又は「労働協約」に別段の定めがある場合は、通貨以外のもの(現物)で支払うこともできます。
労働協約の定めによって通貨以外のもので支払うことができるのは、「労働協約の適用を受ける労働者」に限定されます。
(法第24条、S63.3.14基発150号)
★ 労働協約は、労働組合法に規定されています。「労働組合」と使用者との間の協約ですので、労働組合のある事業場だけに存在するものです。
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
③【R1年出題】
労働基準法第24条第1項は、賃金は、「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。」と定めている。

【解答】
②【H29年出題】 〇
通貨以外のもの(現物)で賃金を支払うことができるのは、事業所のすべての労働者ではなく、「労働協約の適用を受ける労働者」に限られます。
(法第24条、S63.3.14基発150号)
③【R1年出題】 ×
労働協約と労使協定の違いに注意しましょう。
労働協約は、「労働組合」がある事業場だけのものです。
一方、労使協定は、労働組合がない事業場でも締結できます。労働組合がない事業場の場合は、「労働者の過半数を代表する者」と協定を締結します。
(法第24条)
では、こちらもどうぞ!
④【R3年問3ア】
使用者は、退職手当の支払については、現金の保管、持ち運び等に伴う危険を回避するため、労働者の同意を得なくても、当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができるほか、銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付することによることができる。

【解答】
④【R3年問3ア】 ×
問題文の場合は、「労働者の同意」が必要です。
退職手当は、通常の賃金よりも額が多いので、危険回避のため、振込み以外に小切手で支払うこともできますが、その場合も労働者の同意が必要です。
(則第7条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-069
R3.10.30 中高齢寡婦加算の額
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「中高齢寡婦加算の額」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1A】
夫の死亡により、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する遺族厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上あるものとする。)の受給権者となった妻が、その権利を取得した当時60歳であった場合は、中高齢寡婦加算として遺族厚生年金の額に満額の遺族基礎年金の額が加算されるが、その妻が、当該夫の死亡により遺族基礎年金も受給できるときは、その間、当該加算される額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
①【R3年問1A】 ×
中高齢寡婦加算として加算される額は、満額の遺族基礎年金ではなく、「遺族基礎年金の額×4分の3」です。
中高齢寡婦加算のポイント!
・死亡した夫について
「短期要件」でも「長期要件」でも中高齢寡婦加算は加算されますが、「長期要件」の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上あることが条件です。
・妻について
①夫の死亡当時40歳以上65歳未満
②夫の死亡当時40歳未満だった場合は、40歳当時に子と生計を同じくしていて遺族基礎年金を受給していること
・中高齢寡婦加算が加算されるのは妻が65歳に達するまで
・遺族基礎年金を受けることができる間は、中高齢寡婦加算は支給停止される
(法第62条、第65条)
こちらもどうぞ!
②【H15年出題】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の年金額の3分の2に相当する額になっている。
③【H17年出題】
遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。

【解答】
②【H15年出題】 ×
老齢基礎年金の年金額の3分の2ではなく、「遺族基礎年金」の額の「4分の3」に相当する額です。
(法第62条)
③【H17年出題】 ×
「中高齢の寡婦加算の額」は、「老齢基礎年金」ではなく「遺族基礎年金」の額の4分の3相当額です。
・中高齢寡婦加算の額は、生年月日にかかわらず一定の額
中高齢寡婦加算の額の計算式
=遺族基礎年金の額×4分の3
・経過的寡婦加算の額は、妻の生年月日に応じた率を使って計算する
経過的寡婦加算の額の計算式
=「中高齢寡婦加算の額」-「老齢基礎年金の満額」×「妻の生年月日に応じた率」
では、こちらもどうぞ!
④【H28年出題】
被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

【解答】
④【H28年出題】 〇
妻に遺族基礎年金が支給されている間は、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給は停止されます。
(法第65条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-068
R3.10.29 第3号被保険者の国内居住要件
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「第3号被保険者の国内居住要件」です。
では、どうぞ!
①【R3年問3A】
第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
①【R3年問3A】 ×
外国に赴任する第2号被保険者に同行するため海外に行く場合は、第3号被保険者の資格は喪失しません。
★第3号被保険者には、健康保険法の被扶養者の認定要件と同様、国内居住要件があります。
ただし、日本国内に住所がなくても、「外国に留学をする学生」、「外国に赴任する被保険者に同行する者」、「観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者」など、日本国内に生活の基礎があると認められる者は、国内居住要件の例外として認められます。
(法第7条、則第1条の3、R元.11.13保保発1113第1号)
こちらもどうぞ!
②【R3年問3B】
老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
②【R3年問3B】 〇
「第3号被保険者」は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。
厚生年金保険法の被保険者は第2号被保険者となります。ただし、厚生年金保険の被保険者でも、「65歳以上で、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者」は第2号被保険者になりません。
問題文の「老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者」は第2号被保険者ではないので、その収入によって生計を維持していても、55歳の配偶者は、第3号被保険者ではなく、第1号被保険者となります。
(法第7条、法附則第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法
R4-067
R3.10.28 訪問看護療養費のこと
令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。
今日は「訪問看護療養費のこと」です。
では、どうぞ!
①【R3年問1E】
訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

【解答】
①【R3年問1E】 〇
「訪問看護事業」の定義についての問題です。
この問題文のポイントを、穴埋めで見てみましょう。空欄を埋めてください。
『訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、< A >において継続して療養を受ける状態にある者(< B >がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の< A >において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(< C >等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。

【解答】
A 居宅
B 主治の医師
C 保険医療機関
(法第88条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。
③【H24年出題】
訪問看護は、医師、歯科医師又は看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う。
④【H28年選択式】改正による修正あり
訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< A >が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、< B >の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「保険医療機関」の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費ではなく、「療養の給付」の対象となります。
法第88条で、「保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるもの」は、訪問看護事業から除かれています。
保険医療機関等によるものは「療養の給付」の対象、介護保険法の介護老人保健施設、介護医療院によるものは介護保険の対象です。
(法第88条)
③【H24年出題】 ×
訪問看護は、「療養上の世話又は必要な診療の補助」ですので、医師、歯科医師は入りません。
(法第88条、則第68条)
④【H28年選択式】改正による修正あり
A 保険者
B 自己
(法第88条)
最後に穴埋め問題をどうぞ!
訪問看護は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び< D >が行う。

【解答】
D 言語聴覚士
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-066
R3.10.27 在老~基本月額と総報酬月額相当額
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「在老~基本月額と総報酬月額相当額」です。
では、どうぞ!
①【R3年問7B】
在職中の老齢厚生年金の支給停止の際に用いる総報酬月額相当額とは、被保険者である日の属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額のことをいい、また基本月額とは、老齢厚生年金の額(その者に加給年金額が加算されていればそれを加算した額)を12で除して得た額のことをいう。

【解答】
①【R3年問7B】 ×
基本月額は、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)÷12で計算します。「加給年金額」は基本月額の計算に入りません。
(法第46条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
在職老齢年金の支給停止額を計算する際の「総報酬月額相当額」とは、その者の標準報酬月額と直前の7月1日以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額である。
③【H29年出題】
60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

【解答】
②【H25年出題】 ×
「総報酬月額相当額」は、被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額です。
★総報酬月額相当額の計算式
(その月の標準報酬月額) + (その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
(法第46条)
③【H29年出題】 ×
「経過的加算額」及び「繰下げ加算額」は、基本月額の計算に入りません。
★基本月額の計算式
老齢厚生年金の額 ÷ 12
※「加給年金額」、「繰下げ加算額」、「経過的加算額」は基本月額の計算から除かれます。
(法第46条、昭和60年法附則第62条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-065
R3.10.26 障害基礎年金事後重症の事例問題より
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は「事後重症の障害基礎年金の事例問題」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10C】
22歳から30歳まで第2号被保険者、30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生まれ)は、59歳の時に初診日がある傷病により、障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が、当該障害の状態のまま、61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが、その後当該障害の状態が悪化し、障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため、63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行ったとしても障害基礎年金の受給権は発生しない。

【解答】
①【R3年問10C】 ×
事後重症の障害基礎年金の受給権は発生します。
※事後重症の条件は、「65歳に達する日の前日まで」の間に障害等級(1級又は2級)に該当すること+「65歳に達する日の前日まで」に請求することです。
ちなみに、この女性の年金についてもう少し見てみましょう
・特別支給の老齢厚生年金について(第1号厚生年金被保険者の女性の場合)
昭和33年4月2日生まれの場合、61歳から、「報酬比例部分」のみの老齢厚生年金が支給されます。
ただし、「障害者の特例」が適用され、「障害等級3級以上の障害の状態にある」+「被保険者でない」+「請求する」ことによって、「定額部分」も支給されます。
・障害基礎年金について
初診日 → 国民年金の被保険者である(問題文の場合は第3号被保険者)
保険料納付要件 → 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間だけで3分の2以上ある
※第2号被保険者と第3号被保険者には「保険料免除期間」も「未納」もありません。
障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当しなくても、要件を満たせば、事後重症の障害基礎年金の請求が可能です。
こちらもどうぞ!
②【H21年出題】
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。
③【H24年出題】
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。

【解答】
②【H21年出題】 ×
事後重症の障害基礎年金を請求できるのは、65歳に達する日の前日までの間です。
(法第30条の2)
③【H24年出題】 〇
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、事後重症の障害基礎年金は請求できません。
(法附則第9条の2の3)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法
R4-064
R3.10.25 傷病手当金「療養」の意味
令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。
今日は「傷病手当金「療養」の意味」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9D】
傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。

【解答】
①【R3年問9D】 ×
傷病手当金は、「療養のため」労務に服することができないときに支給されます。
この「療養」とは、保険医から療養の給付を受けることだけでなく、自費診療による療養も含まれます。
(S2.2.26保発345)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題】
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。

【解答】
②【H23年出題】 〇
「自費診療で受けた療養」、「自宅での療養」、「病後の静養」についても、傷病手当金の要件である「療養」に該当するので、傷病手当金の支給対象となります。
※美容整形手術による療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲には入りませんので、傷病手当金も支給されません。
(S2.2.26保発345)
比較しましょう/日雇特例被保険者の傷病手当金
③【H23年出題】
日雇特例被保険者に対する傷病手当金の支給に当たっては、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていることで足り、労務不能期間のすべてにおいて当該傷病につき療養の給付を受けていることを要しない。

【解答】
③【H23年出題】 〇
一般の被保険者の傷病手当金は、療養の給付を受けていることが要件ではなく自費療でも対象になりますが、日雇特例被保険者の傷病手当金の場合は、「療養の給付を受けていること」が要件で、自費診療等の場合は傷病手当金は支給されません。
ただし、労務不能となった際にその原因となった傷病について療養の給付を受けていればよく、労務不能期間のすべてに療養の給付を受けていることを要しない、とされています。
(H15.2.25庁保発1)
条文を穴埋めで確認しましょう
第99条 (傷病手当金)
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため< A >ができないときは、その< A >ができなくなった日から起算して< B >を経過した日から < A >ができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】
A 労務に服すること
B 3日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ徴収法
R4-063
R3.10.24 有期事業の概算保険料の延納
令和3年の問題から徴収法を学びましょう。
今日は「有期事業の概算保険料の延納」です。
では、どうぞ!
①【R3年問9B(労災保険)】
有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日から起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。

【解答】
①【R3年問9B(労災保険)】 〇
(有期事業(一括有期事業を除く。)の延納の条件)
■概算保険料の額が75万円以上
又は
労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している
■事業の全期間が6か月を超える
問題文は、事業の全期間が200日、概算保険料の額が80万円ですので、申請により分割納付をすることができます。
(則第28条)
こちらもどうぞ!
②【H22年出題(労災)】
保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
③【H29年出題(労災)】
延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。
④【H27年出題(雇用)】
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

【解答】
②【H22年出題(労災)】 〇
ポイント!有期事業の延納は、全期間を通じ、「4月1日~7月31日」「8月1日~11月30日」「12月1日~翌年3月31日」の各期に分けられます。
★有期事業の延納の「最初の期」のとり方と納期限をおさえましょう。
保険関係成立日からその日の属する期の末日までの期間が
・2月を超えるとき
→ 保険関係成立日からその日の属する期の末日までが「最初の期」
・2月以内のとき
→ 保険関係成立日からその日の属する期の次の期の末日までが「最初の期」
保険関係成立日が7月1日の場合、保険関係成立日の属する期は「4月1日~7月31日」の期です。
保険関係成立日からその期の末日(7月31日)までは2月以内ですので、最初の期は、保険関係成立日(7月1日)からその日の属する期の次の期の末日(11月30日)までとなります。
また最初の期の納期限は、成立日の翌日から20日以内ですので、7月21日となります。
(則28条)
③【H29年出題(労災)】 〇
| 4月~7月 | 8月~11月 | 12月~3月 | 4月~7月 |
| 6月15日成立 | 6月5日終了 | ||
第1期 (6月15日~11月30日) | 第2期 (12月1日~3月31日) | 第3期 (4月1日~6月5日) | |
ポイント!
★第1期は6月15日~11月30日まで
※6月15日から6月15日の属する期の末日(7月31日)まで2月以内なので、次の期とつながります。
★最初の期の納期限は、保険関係成立日の翌日から20日以内
(則第28条)
④【H27年出題(雇用)】 〇
★有期事業の延納の納期限について
・最初の期 → 保険関係成立日の翌日から20日以内
・第2期以降
4月1日~7月31日 → 3月31日
8月1日~11月30日 → 10月31日
12月1日~3月31日 → 翌年1月31日
ポイント!
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していても納期限は延長されません
・4月1日~7月31日の期の納期限は「3月31日」です。
(則第28条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ雇用保険法
R4-062
R3.10.23 雇用保険・所定労働時間の算定について
令和3年の問題から雇用保険法を学びましょう。
今日は「所定労働時間の算定について」です。
では、どうぞ!
★被保険者資格の有無の判断に係る所定労働時間の算定に関する問題です。
①【R3年問1A】
雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合、勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定する。
②【R3年問1E】
雇用契約書等における1週間の所定労働時間と実際の勤務時間に常態的に乖離がある場合であって、当該乖離に合理的な理由がない場合は、原則として実際の勤務時間により1週間の所定労働時間を算定する。

【解答】
①【R3年問1A】 〇
「1週間の所定労働時間が20時間未満の者」は、雇用保険の被保険者となりません。(ただし日雇労働被保険者に該当する場合は被保険者となります)
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。
問題文のように、「雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合」や「シフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合」は、勤務実績に基いて平均の所定労働時間を算定することとなっています。
(行政手引20303)
②【R3年問1E】 〇
例えば、事業所に入職してから離職までの全期間を平均して1週間当たりの通常の勤務時間が概ね20時間以上に満たず、そのことについて合理的な理由がない場合は、原則として1週間の所定労働時間は20時間未満であると判断し、被保険者とはならない、とされています。
(参照:行政手引20303)
もう一問どうぞ!
③【R3年問1B】
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定する。

【解答】
③【R3年問1B】 〇
所定労働時間が1か月の単位で定められている場合は、当該時間を12分の52で除して得た時間を1週間の所定労働時間として算定します。
なお、所定労働時間が1年間の単位でしか定められていない場合は、当該時間を52で除して得た時間を1週間の所定労働時間とします。
(行政手引20303)
では、こちらもどうぞ!
④【R2年選択式】
雇用保険法の適用について、1週間の所定労働時間が< A >であり、同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれる場合には、同法第6条第3号に規定する季節的に雇用される者、同条第4号に規定する学生又は生徒、同条第5号に規定する船員、同条第6号に規定する国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者を除き、パートタイマー、アルバイト、嘱託、契約社員、派遣労働者等の呼称や雇用形態の如何にかかわらず被保険者となる。

【解答】
④【R2年選択式】
A 20時間以上
B 31日以上
(法第6条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労災保険法
R4-061
R3.10.22 心理的負荷による精神障害の認定基準
令和3年の問題から労災保険法を学びましょう。
今日は「心理的負荷による精神障害の認定基準」です。
では、どうぞ!
★ 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関する問題です。
①【R3年問4A】
人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

【解答】
①【R3年問4A】 〇
人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われ、行為が「反復・継続していない場合」は「中」になります。
また、上記のような「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃を受けて、「会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった場合」は「強」となります。
(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))
もう一問どうぞ!
②【R3年問4D】
治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。

【解答】
②【R3年問4D】 ×
治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が「反復・継続していない」場合は、「中」となります。
上記のような場合で、「会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった」場合は、「強」となります。
(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))
では、こちらもどうぞ!
③【R3年問4E】
「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。

【解答】
③【R3年問4E】 〇
「上司等」には、職務上の地位が上位の者のみならず、「同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合」、「同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合」も含まれます。
(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-060
R3.10.21 年少者の時間外、休日、深夜労働
令和3年の問題から労働基準法を学びましょう。
今日は「年少者の時間外、休日、深夜労働」です。
では、どうぞ!
①【R3年問5C】
労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18歳に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。

【解答】
①【R3年問5C】 ×
「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」の規定は、年少者にも適用されますので、そのような場合は年少者にも時間外労働、休日労働をさせることができます。
★年少者の時間外、休日、深夜労働の可否を確認しましょう。
| 時間外・休日労働 | |
| 三六協定 | × |
災害その他避けることのできない事由 | 〇 |
| 公務のため | 〇 |
| 深夜労働 | |
| × 原則禁止 | |
災害その他避けることのできない事由 | 〇 |
| 公務のため | × |
(法第33条、法第60条、第61条)
こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。
③【H13年出題】
36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
満18歳に満たない者には、36協定による時間外労働を行わせることはできませんが、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは可能です。
(法第60条)
③【H13年出題】 ×
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合は、満18歳未満の労働者にも、休日労働をさせることができます。
(法第60条)
では、「第33条」を穴埋めでチェックしましょう
第33条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
① 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の< A >を受けて、その必要の限度において第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の< A >を受ける暇がない場合においては、< B >届け出なければならない。
② ①ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を< C >と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、①の規定にかかわらず、 < D >(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

【解答】
A 許可
B 事後に遅滞なく
C 不適当
D 官公署の事業
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ社保一般常識
R4-059
R3.10.20 確定拠出年金法(企業型と個人型)
令和3年の問題から社保一般常識を学びましょう。
今日は「確定拠出年金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問6D】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
①【R3年問6D】 〇
国民年金第3号被保険者は、「個人型年金加入者」となることができます。
確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」の2種類ありますが、それぞれの対象者をおさえましょう。
| 企業型年金 | 個人型年金 | |
| 実施 | 厚生年金適用事業所の事業主 | 国民年金基金連合会 |
| 加入者 | ・第1号等厚生年金被保険者 (第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者) (原則は60歳未満→規約に定めがある場合、65歳までの規約で定める年齢まで加入できる。ただし、60歳前と同一の実施事業所で引き続き使用されること等が必要。) | ・国民年金第1号被保険者 ・60歳未満の厚生年金保険の被保険者 ・国民年金第3号被保険者 |
(法第2条、第9条、第62条)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
②【H30年出題】
第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書参照)
③【H29年出題】
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

【解答】
②【H24年出題】 〇
確定拠出年金法は、「平成13年6月制定、10月施行」は、おさえておきましょう。
②【H30年出題】 〇
平成29年版厚生労働白書「第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」に記載されています。「私的年金の普及・拡大」を図る、「高齢期に向けた個人の継続的な自助努力の支援」に取り組むことなどが載っています。
③【H29年出題】 〇
60歳未満の第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員)は、個人型年金加入者になることができます。
なお、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)も個人型年金の加入者になることができます。
※第2号(国家公務員)、第3号(地方公務員)は、企業型年金には加入できません。
(法第9条、第62条)
では、「定義」を穴埋めでチェックしましょう
第2条 (定義)
確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
確定拠出年金法において「企業型年金」とは、< A >が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。
確定拠出年金法において「個人型年金」とは、< B >が、実施する年金制度をいう。

【解答】
A 厚生年金適用事業所の事業主
B 国民年金基金連合会
(法第2条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-058
R3.10.19 厚年「遺族厚生年金・長期要件と短期要件」
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「遺族厚生年金・長期要件と短期要件」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10A】
20歳から30歳まで国民年金の第1号被保険者、30歳から60歳まで第2号厚生年金被保険者であった者が、60歳で第1号厚生年金被保険者となり、第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡した。当該被保険者の遺族が当該被保険者の死亡当時生計を維持されていた60歳の妻のみである場合、当該妻に支給される遺族厚生年金は、妻が別段の申出をしたときを除き、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件のみに該当する遺族厚生年金として年金額が算出される。

【解答】
①【R3年問10A】 ×
遺族厚生年金には、「短期要件」と「長期要件」がありますが、両方に該当する場合は、「その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときを除き、『短期要件』のいずれかのみに該当し、『長期要件』には該当しないものとみなす」とされています。 問題文は、逆になっているので×です。
問題文の場合、
・第1号厚生年金被保険者期間中に64歳で死亡 → 短期要件(在職中の死亡)
・保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上 → 長期要件
となります。別段の申出をしたときを除き、短期要件に該当する遺族厚生年金として年金額が算出されます。
(法第58条)
こちらもどうぞ!
②【H23年出題(改正による修正あり)】
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である被保険者(障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者を除く。)が死亡したときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、厚生年金保険法第58条第1項第1号(短期要件)に該当し、同条第1項第4号(長期要件)には該当しないものとみなされる。

【解答】
②【H23年出題】 〇
長期要件(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上)と短期要件(被保険者が死亡)の両方に当てはまる場合は、別段の申出をした場合を除き、短期要件に該当し、長期要件には該当しないものとみなされます。
(法第58条)
こちらもどうぞ!
③【H27年出題(改正による修正あり)】
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額の計算における給付乗率については、死亡した者が昭和21年4月1日以前に生まれた者であるときは、生年月日に応じた読み替えを行った乗率が適用される。

【解答】
③【H27年出題】 〇
問題文は「長期要件」です。長期要件の場合は、給付乗率について生年月日に応じた読み替えがあります。
遺族厚生年金の原則の計算式は、老齢厚生年金と同じで「平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数」です。
ただし、短期要件と長期要件でルールが違うのがポイントです。
| 短期要件 | 長期要件 | |
| 給付乗率 | 定率 | 昭和21年4月1日以前生まれ →生年月日に応じて読み替え |
| 被保険者期間の月数 | 300月の 最低保障あり | 実期間で計算 |
(法第60条)
では、長期要件と短期要件を穴埋めでチェックしましょう
1 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
2 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して< A >年を経過する日前に死亡したとき。
3 < B >に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
4 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< C >年以上である者が、死亡したとき。

【解答】
A 5
B 障害等級の1級又は2級
C 25
★1、2、3が「短期要件」、4が「長期要件」です。
また、1と2は障害厚生年金と同じく保険料納付要件が問われます。
(法第58条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ国民年金法
R4-057
R3.10.18 国年「併給できる年金、できない年金」
令和3年の問題から国民年金法を学びましょう。
今日は併給できる年金、できない年金です。
では、どうぞ!
①【R3年問9C】
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。

【解答】
①【R3年問9C】 ×
★ポイント①
65歳未満でも65歳以上でも年齢に関係なく、「老齢基礎年金」と「障害厚生年金」は併給できませんので、この問題は誤りです。
★ポイント②
(2級なのに障害基礎年金の受給権が発生しない理由)
65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、かつ老齢の年金の受給権がある場合は、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
初診日に厚生年金保険の被保険者であるものの、65歳以上で老齢年金の受給権がある場合は、国民年金の被保険者ではありません。そのため、障害等級2級に該当しても、「障害厚生年金」の受給権は発生しますが、「障害基礎年金」の受給権は発生しません。
★ポイント③
問題文の場合、「老齢基礎年金+老齢厚生年金」と「2級の障害厚生年金」のどちらかを選択することになります。
(法第7条、法第20条、法附則第3条)
こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。
③【H26年出題(改正による修正あり)】
65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。

【解答】
②【H29年出題】 ×
65歳以上でも65歳未満でも、「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」は併給できません。
(法第20条)
③【H26年出題】 ×
原則として、厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者です。
ただし、65歳以上で「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有している」場合は、第2号被保険者から除外されます。
問題文のように、65歳以上で、「老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権なし、障害の年金給付の受給権あり」の場合は、第2号被保険者となります。
(法第7条、法附則第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ健康保険法
R4-056
R3.10.17 健保「資格喪失後の出産手当金の継続給付」
令和3年の問題から健康保険法を学びましょう。
今日は資格喪失後の出産手当金の継続給付です。
では、どうぞ!
①【R3年問9B】
1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職日の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。

【解答】
①【R3年問9B】 ×
「退職日において通常勤務していた」の部分がポイントです。 退職日に勤務したときは、資格喪失後の出産手当金は支給されません。
「資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けている」ことが、出産手当金の継続給付の要件です。なお、実際に支給を受けていなくても「受ける条件」を満たしている場合は、「支給を受けている」こととなります。
出産手当金は「労務に服さなかった」ことが条件です。退職日に勤務していたということは、その条件を満たしていません。
そのため、資格喪失後の出産手当金は支給されません。
(法第104条)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
5月25日が出産予定日(多胎妊娠ではない。)である被保険者が、同年3月20日に勤務していた適用事業所を退職し、被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失日の前日において引き続き1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者期間、特例退職被保険者期間又は共済組合の組合員である期間を除く。)があれば、資格喪失後に出産手当金の継続給付を受けることができる。
③【H24年出題】
被保険者資格が喪失日(任意継続被保険者の資格を取得した者にあっては、その資格を取得した日)の前日までの間引き続き1年以上であった者が、被保険者の資格喪失後6か月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から出産手当金を受けることができる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
出産手当金(多胎妊娠ではない。)は、出産予定日以前42日からが対象です。
5月25日が出産予定日の場合は4月14日~となり、3月20日に退職した場合は、資格喪失時に出産手当金を受ける条件を満たしていないので、資格喪失後に出産手当金の継続給付は受けられません。
(法第104条)
③【H24年出題】 ×
資格喪失後6月以内の出産の規定は、資格喪失後の「出産育児一時金」が当てはまります。
★確認しましょう。(資格喪失後の出産育児一時金)
「1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。」
(法第106条)
条文を穴埋めでチェックしましょう!
第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して< A >からその給付を受けることができる。
第106条 (資格喪失後の出産育児一時金の給付)
1年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後< B >以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を< C >から受けることができる。

【解答】
A 同一の保険者
B 6月
C 最後の保険者
★第106条の「1年以上被保険者であった者」は、第104条の条件と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ徴収法
R4-055
R3.10.16 徴収「労働保険事務組合の届出」
令和3年の問題から徴収法を学びましょう。
今日は労働保険事務組合の届出です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E(雇用)】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、委託を受けた日の翌日から起算して14日以内に、労働保険徴収法施行規則第64条に定める事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【R3年問9E(雇用)】 ×
「14日以内」が誤りです。
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、「遅滞なく」、労働保険事務等処理委託届を提出しなければなりません。
なお、委託の解除の時も同じく、「遅滞なく」、労働保険事務等処理委託解除届を提出しなければなりません。
ポイント!
「労働保険事務等処理委託届」「労働保険事務等処理委託解除届」の提出は、「遅滞なく」
(則第64条)
こちらもどうぞ!
②【H20年出題(雇用)】
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託解除届をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
③【R1出題(雇用)】
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
④【H23年出題(労災)】
労働保険事務組合が、労働保険事務の処理に係る業務を廃止しようとするときは、60日前までに、労働保険事務等処理委託解除届を当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
②【H20年出題(雇用)】 〇
「労働保険事務等処理委託解除届」のチェックポイントは、「遅滞なく」と「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。
(則第64条)
③【R1出題(雇用)】 ×
提出先は、「厚生労働大臣」ではなく、「その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。
ポイント!
「変更の届出」のチェックポイントは、「14日以内」と「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長」です。
★ 労働保険事務組合の認可を受けるときは、「申請書」に「①定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)、②労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類、③最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類」を添付します。
↓
申請書又は添付書類の①若しくは②に記載された事項に変更を生じた場合に、「変更の届出」が必要です。③に変更があっても届出は要りません。
(則第65条)
④【H23年出題(労災)】 ×
業務の廃止の場合は、労働保険事務等処理委託解除届ではなく、「労働保険事務組合業務廃止届」を提出します。
「労働保険事務組合業務廃止届」は、「60日前までに」がチェックポイントです。
(則第66条)
もう一問どうぞ!
⑤【R1年出題(雇用)】
労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
⑤【R1年出題(雇用)】 ×
「労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業」がポイントで、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由」が誤りです。
原則として、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由しますが、第64条の規定により行う届書(労働保険事務等処理委託届)のうち労災二元適用事業等に係るものは、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して行います。
(則第78条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ雇用保険法
R4-054
R3.10.15 雇用「教育訓練給付」
令和3年の問題から雇用保険法を学びましょう。
今日は教育訓練給付です。
では、どうぞ!
①【R3年問6B】
一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。

【解答】
①【R3年問6B】 〇
一般教育訓練給付金は、一時金として支給されます。
なお、「特定一般教育訓練給付金」も一時金として支給されます。
(行政手引58014、行政手引58114)
こちらもどうぞ!
②【R3年問6E】
一般被保険者でなくなって1年を経過しない者が負傷により30日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。

【解答】
②【R3年問6E】 ×
疾病又は負傷を理由として傷病手当の支給を受ける場合でも、その疾病又は負傷に係 る期間は、適用対象期間の延長の対象に含まれます。
(行政手引58022)
★基準日に一般被保険者等でない者が、教育訓練給付の支給対象者となるには、基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日が基準日以前1年以内にあることが必要です。
しかし、当該基準日の直前の一般被保険者等でなくなった日から1年以内に妊娠 、 出産 、育児等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することがで きない日がある場合には、適用対象期間の延長が認められます。
★基準日とは、「教育訓練を開始した日」です。
では穴埋めで確認しましょう!
(適用対象期間の延長申請の手続)
延長の措置を受けようとする一般被保険者等であった者は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始することができなくなるに至った日の翌日から直前の一般被保険者等でなくなった日から起算して< A >年を経過する日までの間(延長後の適用対象期間が< A >年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間) に、延長申請書に、医師の証明書その他の適用対象期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類を添えて、住居所管轄安定所に提出しなければならない。

【解答】
A 20
(則101条の2の5 行政手引58024)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労災保険法
R4-053
R3.10.14 労災「特別加入者の支給制限」
令和3年の問題から労災保険法を学びましょう。
今日は特別加入者の支給制限です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
①【R3年問3C】 ×
「保険給付を全額支給・費用の全部又は一部を事業主から徴収」の部分が誤りです。
特別加入している中小事業主等の事故が、
・保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
・事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき
政府は、当該事故に係る保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」と規定されています。
労働者の事故の場合は、「事業主からの費用徴収」になりますが、特別加入者については、「支給制限」になることがポイントです。
(法第34条)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
問題文の中に「一般保険料」とあるので、労働者に関する問題です。労働者の場合、「事業主が、故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」については、事業主からの費用徴収の対象となります。労働者に対して支給制限は行われないので注意しましょう。
(法第31条)
では条文を穴埋めで確認しましょう!
・ 中小事業主等の事故が第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。
・一人親方等及び特定作業従事者の事故が、第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。
・海外派遣者の事故が、第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。

【解答】
A 全部又は一部を行わないことができる
(法第34条、35条、36条)
★保険給付の支給制限が行われるのは、
中小事業主等 → 第一種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
事業主の故意又は重大な過失によって生じた事故
一人親方等 → 第二種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
海外派遣者 → 第三種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労働基準法
R4-052
R3.10.13 労基「減給制裁の制限」
令和3年の問題から「労働基準法」を学びましょう。
今日は減給制裁の制限です。
では、どうぞ!
①【R3年問7E】
労働基準法第91条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として10分の1を計算しなければならない。

【解答】
①【R3年問7E】 〇
「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」の10分の1を超えてはならないという趣旨です。
賃金の総額が欠勤や遅刻等により減額され少額となった場合でも、その少額となった賃金総額の10分の1を超えてはなりません。
(法第91条 S25.9.8基収1338号)
こちらもどうぞ!
②【H16年出題】
就業規則で労働者に対して減給の定めをする場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。

【解答】
②【H16年出題】 ×
一賃金支払期に、複数の減給事案が発生した場合、その減給の総額は、「その賃金支払期における賃金総額の10分の1以内」でなければなりません。
これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合は、次期の賃金支払期に延ばすことができます。
(S23.9.20基収1789号)
では条文を穴埋めで確認しましょう!
第91条 (制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の< A >を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の< B >を超えてはならない。

【解答】
A 半額
B 10分の1
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)社保一般常識 応用問題
R4-051
R3.10.12 国民健康保険法「国民健康保険の適用除外」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は国民健康保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問7B】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】
①【R3年問7B】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第9号)
こちらもどうぞ!
②【H20年出題】(改正による修正あり)
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
③【H20年出題】(改正による修正あり)
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
④【H20年出題】(改正による修正あり)
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
②【H20年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く))に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第9号)
③【H20年出題】 〇
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第8号)
④【H20年出題】 〇
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第10号)
では、こちらもどうぞ!
⑤【R3年出題】
都道府県が当該都道府県の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。
⑥【H25年出題】(改正による修正あり)
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有する至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
「翌日」が誤りです。資格取得は「その日」です。
・都道府県の区域内に住所を有するに至った日
・国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日
から、その資格を取得します。
(法第7条)
⑥【H25年出題】 ×
資格喪失は原則として「翌日」です。
・都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日
・国民健康保険法第6条の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日の翌日
から、その資格を喪失します。
ただし、例外もあります。
・都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有する至ったときは、その日から資格を喪失します。
・適用除外事由の中の第9号(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者)及び第10号(国民健康保険組合の被保険者)については、該当するに至った日から、その資格を喪失します。
(法第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働一般常識 応用問題
R4-050
R3.10.11 労働契約法「就業規則の変更による労働契約の内容の変更」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労働契約法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3B】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合について定めた労働契約法第10条本文にいう「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情」のうち、「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者だけでなく、少数労働組合が含まれるが、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体は含まれない。

【解答】
①【R3年問3B】 ×
「労働者で構成されその意思を代表する親睦団体」も含まれます。
★ 「労働組合等との交渉の状況」は、労働組合等事業場の労働者の意思を代表するものとの交渉の経緯、結果等をいいます。
「労働組合等」には、労働者の過半数で組織する労働組合その他の多数労働組合や事業場の過半数を代表する労働者のほか、少数労働組合や、労働者で構成されその意思を代表する親睦団体等労働者の意思を代表するものが広く含まれるものであること、とされています。
(法第10条、H24.8.10基発0810第2号)
こちらもどうぞ!
②【H22年出題】
使用者は、労働者との合意がなければ労働者の不利益に労働条件を変更することはできないが、事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる。
③【H23年出題】
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、労働契約法第10条ただし書に該当する場合を除き、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとされている。

【解答】
②【H22年出題】 ×
★ポイント! 労働契約の変更の基本原則は、「合意」です。
法第8条では、労働者と使用者が「合意」した場合に、「労働契約の内容である労働条件」が「変更」されるという法的効果が生じることを規定しています。
また、法第9条では、使用者が労働者と合意することなく就業規則の変更により労働契約の内容である労働条件を労働者の不利益に変更することはできない、と規定しています。
そして、第10条に例外規定が設けられています。
「就業規則の変更」という方法で労働条件を変更する場合、使用者が変更後の就業規則を「労働者に周知させ」たこと、就業規則の変更が「合理的なもの」であることという要件を満たした場合に、「合意の原則」の例外として、「労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによる」という法的効果が生じることを規定しています。
この法第10条は、就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となる場合に適用されます。
問題文のように、「事業場の労働者の過半数を代表する労働組合の意見を聴いて就業規則を変更する場合には、労働条件を労働者の不利益に変更することができる」という規定はありません。
(法第10条、H24.8.10基発0810第2号)
③【H23年出題】 〇
「合理性判断の考慮要素」
法第10条の「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況」は、就業規則の変更が合理的なものであるか否かを判断するに当たっての考慮要素として例示されたものです。
個別具体的な事案に応じて、これらの考慮要素に該当する事実を含め就業規則の変更に係る諸事情が総合的に考慮され、合理性判断が行われます。
(法第10条、H24.8.10基発0810第2号)
では、条文を穴埋めで確認しましょう
第8条
労働者及び使用者は、その< A >により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
第9条
使用者は、労働者と< A >することなく、就業規則を変更することにより、労働者の< B >に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第10条
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に< C >させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける< B >の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして< D >なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として< A >していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

【解答】
A 合意
B 不利益
C 周知
D 合理的
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)厚生年金保険法 応用問題
R4-049
R3.10.10 厚年「特別支給の老齢厚生年金・長期加入者の特例」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は厚生年金保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問9B】
昭和33年4月10日生まれの男性は、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該男性は、厚生年金保険の被保険者でなければ、63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給される。

【解答】
①【R3年問9B】 ×
「長期加入者の特例」の問題です。
昭和16年4月2日生まれ(第1号の女子は昭和21年4月2日生まれ)以降から、特別支給の老齢厚生年金が報酬比例部分のみになる部分があります。(図を参照してください。)
長期加入者の特例とは、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上であるときは、定額部分(場合によっては加給年金額も)が支給される特例です。
昭和33年4月10日生まれの男性は、63歳から報酬比例分の支給が開始されますが、厚生年金保険の被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上であるときは、定額部分も合わせて支給されます。
しかし、問題文の場合は、被保険者期間は、第1号が4年、第2号が40年となっています。「44年」をみるときは、2種以上の被保険者であった期間は、合算しないこととなっているので、問題文の場合は、要件をみたさないので、63歳から支給されるのは原則どおり報酬比例部分のみとなります。
(法附則第9条の3)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

【解答】
②【H28年出題】 ×
上の問題と同じで、「44年以上」をみるときは、2種以上の期間は合算できませんので、問題文の場合は、定額部分は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
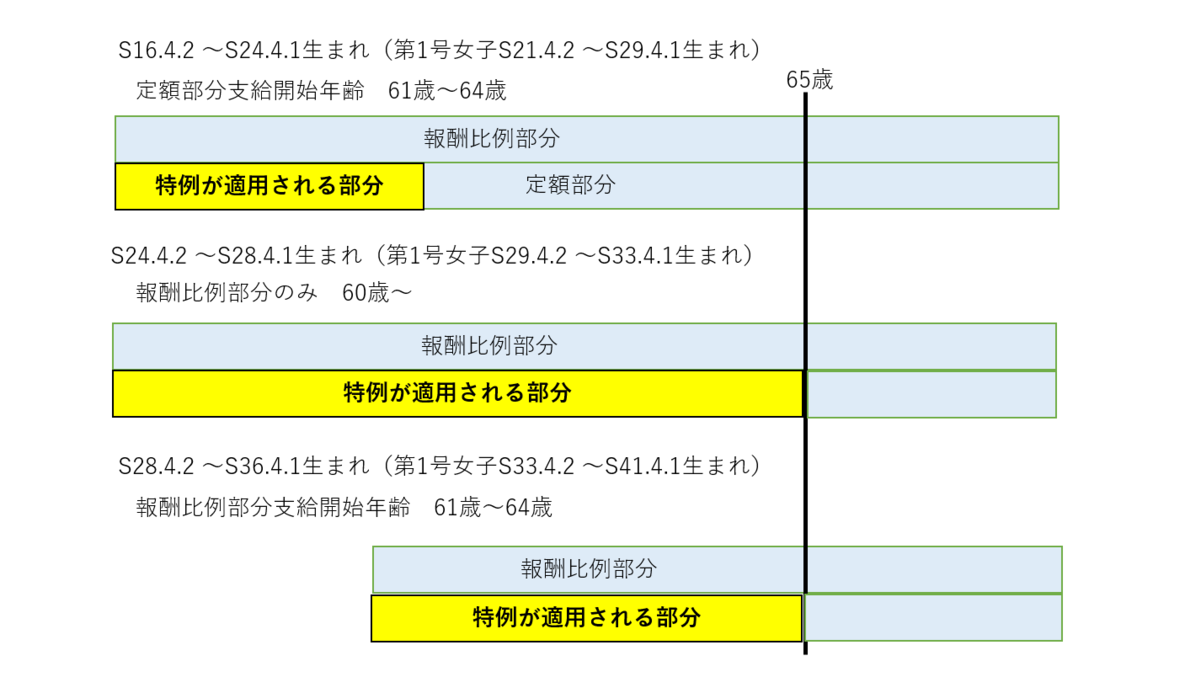
(令和3年出題より)国民年金法 応用問題
R4-048
R3.10.9 国年「20歳前傷病による障害基礎年金の国庫負担」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は国民年金法です。
では、どうぞ!
①【R3年問5E】
国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。

【解答】
①【R3年問5E】 ×
20歳前の傷病による障害基礎年金は、他の年金と比較して国庫負担率を高くすることになっています。
まず、給付費の100分の20を特別に国庫負担することになっています。
残りの部分(100分の80)については、原則どおりの「2分の1」の国庫負担が行われます。
合計して、国庫負担率は100分の60となります。
(法第85条)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、その7割を国庫が負担することとなる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については、100分の20(特別国庫負担)+(100分の80×2分の1)で、6割が国庫負担となります。
(法第85条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)健保法 応用問題
R4-047
R3.10.8 健保「健康保険と労災保険の関係」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は健康保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問9E】
被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

【解答】
①【R3年問9E】 〇
被保険者が副業として行う請負業務中の負傷や、被扶養者の請負業務やインターンシップ中の負傷などのように、労災保険の給付が受けられない場合は、原則として健康保険の給付が行われます。
問題文のテーマは、「業務災害・通勤災害と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、健康保険の保険者は、まずは労災保険への請求を促し、健康保険の給付を留保することができるか?」というものです。
回答は、
・ 労災保険法の業務災害については健康保険の給付の対象外であり、また、労災保険法における通勤災害については労災保険からの給付が優先される。そのため、まずは労災保険の請求を促し、健康保険の給付を留保することができる。
・ ただし、保険者において、健康保険の給付を留保するに当たっては、関係する医療機関等に連絡を行うなど、十分な配慮を行うこと。
とされています。
(法第1条 平成25.8.1事務連絡)
こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。
③【H30年出題】
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

【解答】
②【H28年出題】 〇
請負業務中に負傷した場合、「業務」ではあっても労働者ではないので労災保険の給付の対象にはなりません。このような労災保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われます。
(法第1条 平成25.8.1事務連絡)
③【H30年出題】 ×
「通勤災害」は健康保険の対象ですが、労災保険からの給付が優先されます。労災保険の給付を受けることができる場合には、健康保険の保険給付は行われませんので、問題文の場合は、埋葬料は支給されません。
(法第55条)
穴埋めで条文を確認しましょう!
第1条 (目的)
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(< A >第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
第55条 (他の法令による保険給付との調整)
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の< B >について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

【解答】
A 労働者災害補償保険法
B 疾病、負傷又は死亡
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)徴収法 応用問題
R4-046
R3.10.7 徴収「特例納付保険料」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8D(雇用)】
労働保険徴収法第26条第2項の規定により厚生労働大臣から特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主が、特例納付保険料を納付する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対して書面により申し出た場合、同法第27条の督促及び滞納処分の規定並びに同法第28条の延滞金の規定の適用を受ける。

【解答】
①【R3年問8D(雇用)】 〇
「特例納付保険料」は労働保険料の1つです。
「督促及び滞納処分」は労働保険料その他徴収金を納付しないとき、「延滞金」は、労働保険料を納付しない場合の規定で、労働保険料である特例納付保険料もその対象となります。
★ 「特例納付保険料」とは、2年を超えて遡って雇用保険の加入手続きを行った労働者について、本来納付すべきであった労働保険料を納付することができる制度です。
事業主は、厚生労働大臣の納付勧奨を受けて、納付の申出を行い、本来納付すべきであった雇用保険料に相当する額に10%をプラスした額を、特例納付保険料として納付することができます。
(法第26条)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
特例納付保険料は、その基本額のほか、その額に100分の10を乗じて得た額を加算したものとされている。
③【H27年出題】
厚生労働大臣による特例納付保険料の納付の勧奨を受けた事業主から当該保険料を納付する旨の申出があった場合には、都道府県労働局歳入徴収官が、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限とする納入告知書により、当該事業主に対し、決定された特例納付保険料の額を通知する。

【解答】
②【H27年出題】 〇
特例納付保険料は、「基本額」+「加算額(基本額×100分の10)」で計算します。
(法第26条)
③【H27年出題】 〇
特例納付保険料の納付は、「通知を発する日から起算して30日を経過した日」を納期限とすること、「納入告知書」によることがポイントです。
(法第26条、則第38条、則第59条)
穴埋めで確認しましょう!
則第59条 (特例納付保険料に係る通知)
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して< A >日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特例納付保険料の額
二 納期限

【解答】
A 30
では、こちらの条文も確認しましょう!
第10条 (労働保険料)
1 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
2 1の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
① 一般保険料
② 第一種特別加入保険料
③ 第二種特別加入保険料
④ 第三種特別加入保険料
⑤ 印紙保険料
⑥ < B >

【解答】
B 特例納付保険料
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)雇用保険法 応用問題
R4-045
R3.10.6 雇用「特定理由離職者」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は雇用保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問4B】
いわゆる登録型派遣労働者については、派遣就業に係る雇用契約が終了し、雇用契約の更新・延長についての合意形成がないが、派遣労働者が引き続き当該派遣元事業主のもとでの派遣就業を希望していたにもかかわらず、派遣元事業主から当該雇用契約期間の満了日までに派遣就業を指示されなかったことにより離職した者は、特定理由離職者に該当する。

【解答】
①【R3年問4B】 〇
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) により離職した者は「特定理由離職者」となります。
★ただし、特定受給資格者のいずれかに該当する者(特に3年以上の雇止めに該当する者)は、特定理由離職者に該当しませんので注意しましょう。
問題文の場合は、上記の要件に該当し、特定理由離職者となります。
(法第13条 行政手引50305-2)
こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
期間の定めのない労働契約を締結している者が雇用保険法第33条第1項に規定する正当な理由なく離職した場合、当該離職者は特定理由離職者とはならない。
③【H22年出題】
結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったことにより離職した者は、特定理由離職者に当たる。

【解答】
②【H27年出題】 〇
法第33条の「正当な理由のある」自己都合退職者は特定理由離職者になります。
問題文は、「正当な理由なく」となっていますので、特定理由離職者になりません。
(法第13条 行政手引50305-2)
③【H22年出題】 〇
「結婚に伴う住所の変更のため通勤が不可能になったこと」は、「法第33条の正当な理由」に該当するので、特定理由離職者となります。
(法第13条 行政手引50305-2)
こちらもどうぞ!
④【H29年出題】
配偶者と別居生活を続けることが家庭生活の上からも、経済的事情からも困難となり、配偶者と同居するために住所を移転したことにより事業所への通勤が不可能となったことで退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

【解答】
④【H29年出題】 ×
配偶者と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合は、法第33条の「正当な理由」に当たり、離職理由による給付制限は受けません。
また、特定理由離職者にも該当します。
(行政手引52203、行政手引50305-2)
では、条文を確認しましょう!
(法第13条第3項)
< A >とは、離職した者のうち、第23条第2項各号(特定受給資格者)のいずれかに該当する者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。
(則第19条の2)
法第13条第3項の厚生労働省令で定める者は、次のいずれかの理由により離職した者とする。
1 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)
2 法第33条第1項の< B >

【解答】
A 特定理由離職者
B 正当な理由
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労災保険法 応用問題
R4-044
R3.10.5 労災「単身赴任者等の通勤災害」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労災保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問2D】
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1~2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害とは認められない。

【解答】
①【R3年問2D】 〇
休暇の「1日目」は「交通機関の状況等は特段の問題はなかった」、「2日目」に「家族の住む自宅へ帰る」の部分がポイントです。
通達では以下のようになっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『「赴任先住居」から「帰省先住居」への移動について』
・「業務に従事した当日又はその翌日」に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。
・翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的事由があるときに限り、就業との関連性が認められる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問題文の場合、単身赴任者が家族の住む自宅に帰るのは、休暇の2日目(業務に従事した日の翌々日)です。そして「交通機関の状況等の合理的事由」はありません。
そのため、就業との関連性は認められず、通勤災害とは認められません。
(法第7条 H18.3.31基発0331042)
通勤の定義を条文で確認しましょう
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、< A >経路及び方法により行うことをいい、< B >を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

【解答】
A 合理的な
B 業務の性質
2は、複数就業者の事業場間の移動のこと
3は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動のこと
(法第7条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働安全衛生法 応用問題
R4-043
R3.10.4 安衛「安衛法上の労働者の定義」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労働安全衛生法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8A】
労働安全衛生法では、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者だけをいうものではなく、建設業におけるいわゆる一人親方(労災保険法第35条の規定により保険給付を受けることができることとされた者)も下請負人として建設工事の業務に従事する場合は、元方事業者との関係において労働者としている。

【解答】
①【R3年問8A】 ×
労働安全衛生法第2条で、「労働者」は、「労働基準法第9条に規定する労働者をいう」と規定されていますので、労働安全衛生法の労働者と労働基準法の労働者は同一です。
一人親方は、労働基準法でも労働安全衛生法でも労働者とはなりません。
(法第2条)
では、こちらもどうぞ!
②【H28年出題】
労働安全衛生法における「事業者」は、労働基準法第10条に規定する「使用者」とはその概念を異にするが、「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
③【R2年出題】
労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されない。また、家事使用人についても適用されない。

【解答】
②【H28年出題】 〇
労働基準法の「使用者」は、「事業主、事業の経営担当者、その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」です。
一方、労働安全衛生法の主たる義務者は「事業者」で、労働基準法第10条の「使用者」とはその概念が異なります。
「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではありません。)、個人企業であれば事業経営主を指しています。
労働安全衛生法ではその安全衛生上の責任を明確にするため、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえています。
なお、労働安全衛生法上の「労働者」は、労働基準法第9条に規定する労働者と同じです。
(法第2条、昭47.9.18発基91号)
③【R2年出題】 〇
労働安全衛生法は、労働基準法と同じく、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されず、また、家事使用人についても適用されません。
(法第2条)
第2条の条文を確認しましょう
第2条(定義)
労働安全衛生法において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 < A >
労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者
労働基準法第9条に規定する労働者(< B >を使用する事業又は事務所に使用される者及び< C >を除く。)をいう。
三 事業者
事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質
元素及び化合物をいう。
四 < D >
作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

【解答】
A 労働災害
B 同居の親族のみ
C 家事使用人
D 作業環境測定
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働基準法 応用問題
R4-042
R3.10.3 労基「管理監督者と妊産婦の労働時間」
和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労働基準法です。
では、どうぞ!
①【R3年問5D】
労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず、監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

【解答】
①【R3年問5D】 ×
解き方のポイント!
法第41条で、「監督又は管理の地位にある者」については「労働時間、休憩、休日の規定は適用されない」と規定されています。
また、第66条には、「妊産婦」について、「妊産婦が請求した場合は、災害等による臨時の必要がある場合や36協定の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならない」等の規定があります。
「監督又は管理の地位にある者」が「妊産婦」である場合、労働時間の規定は適用されるのか?というのがこの問題のテーマです。
「妊産婦のうち、第41条に該当する者については、労働時間に関する規定は適用されない」とされています。問題文のように、労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があったとしても、適用されません。
(法第66条、S61.3.20基発151号)
では、こちらもどうぞ!
②【H19年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項の規定により、妊産婦が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働又は休日労働をさせてはならないが、この第66条第2項の規定は、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦にも適用される。
③【H17年出題】
使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)が請求した場合においては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。

【解答】
②【H19年出題】 ×
第66条第2項の規定は、監督又は管理の地位にある妊産婦には適用されません。
(S61.3.20基発第151号)
③【H17年出題】 ×
問題文の最後の「同法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、休日労働及び深夜業をさせることができる。」の部分が誤りです。深夜業をさせることはできません。
問題を解くポイント!
妊産婦が請求した場合は、「時間外労働、休日労働又は深夜業」をさせることはできません。
ただし、監督又は管理の地位にある者には、労働時間、休憩、休日は適用されませんので、監督又は管理の地位にある妊産婦から請求があったとしても、「時間外労働、休日労働」をさせることはできます。
しかし、第41条に規定する者については、「深夜業」の規定は適用されます。
ですので、「監督又は管理の地位にある妊産婦」から「深夜業をしない」請求があった場合は、深夜業をさせることはできません。
(S61.3.20基発151号)
第41条の条文を確認しましょう
第41条 (労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第6号(< A >を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず< B >にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 < C >に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

【解答】
A 林業
B 監督若しくは管理の地位
C 監視又は断続的労働
※ちなみに、別表第一6号は農林の事業、第7号は畜産水産業の事業です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)社保一般常識よく出るところ
R4-041
R3.10.2 社一「令和2年版厚生労働白書」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は社会保険一般常識です。
では、どうぞ!
①【R3年問10D】
社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が49.5%、介護、福祉その他が39.4%を占めていたが、医療は1990年代半ばから、介護、福祉その他は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成29)年度には、年金が21.6%と、1989年度の約2倍となっている。

【解答】
①【R3年問10D】 ×
ヒント!
法律の制定の順番を思い出しましょう。
・健康保険法制定(大正11年) 日本最初の医療保険
・船員保険法制定(昭和14年) 社会保険方式による日本最初の公的年金制度
・介護保険法施行(平成12年)
この順番を意識して問題文を読んでみると、1989(平成元)年度に、介護、福祉その他が39.4%を占めてる、という部分に違和感を覚えると思います。
令和2年版厚生労働白書によると、
(社会保障給付費の部門別構成割合の推移)
・1989(平成元)年度においては年金が49.5%、医療が39.4%を占めていた
・医療は1990年代半ばから、年金は2004 (平成16)年度からその割合が減少に転じ、介護、福祉その他の割合が増加してきている。
・2017年度には、介護と福祉その他を合わせて21.6%と、1989年度の約2倍となっている
(参照:令和2年版厚生労働白書 P120)
では、もう一問どうぞ!
②【R3問10A】
公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第1号被保険者は、対前年比 70万人増で近年増加傾向にある一方、第2号被保険者(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第 3号被保険者は、それぞれ対前年比 34万人減、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。

【解答】
②【R3問10A】 ×
(公的年金制度の被保険者数の増減について)
・ 第 2号被保険者は対前年比 70万人増 で、近年増加傾向にある
・ 第 1号被保険者や第 3号被保険者はそれぞれ対前年比 34 万人、23万人減で、近年減少傾向にある
・ (要因)被用者保険の適用拡大や厚生年金の加入促進策の実施、高齢者等の就労促進などが考えられる。
(参照:令和2年版厚生労働白書)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働一般常識よく出るところ
R4-040
R3.10.1 労一「令和元年版労働経済白書」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は労働一般常識です。
令和3年度は問1と問2が労働経済の問題でした。
問1は、「令和元年版労働経済白書」(令和元年9月28日閣議配布)から
問2は、「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」(令和3年2月12日公表)からの問題でした。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
正社員について、働きやすさの向上のために、労働者が重要と考えている企業側の雇用管理を男女別・年齢階級別にみると、男性は「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」、女性は「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」がいずれの年齢層でも最も多くなっている。

【解答】
①【R3年問1B】 ×
男女ともにいずれの年齢階級においても「職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化」が最も多い。次いで「有給休暇の取得促進」、「労働時間の短縮や働き方の柔軟化」が高くなっています。
(参照:令和元年版労働経済白書P126)
※令和元年版労働経済白書のメインテーマは、「人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について」です。
では、こちらもどうぞ!
②【R3問1C】
正社員について、男女計における1か月当たりの労働時間と働きやすさとの関係をみると、労働時間が短くなるほど働きやすいと感じる者の割合が増加し、逆に労働時間が長くなるほど働きにくいと感じる者の割合が増加する。
③【R3問1D】
正社員について、テレワークの導入状況と働きやすさ・働きにくさとの関係をみると、テレワークが導入されていない場合の方が、導入されている場合に比べて、働きにくいと感じている者の割合が高くなっている。
④【R3問1E】
勤務間インターバル制度に該当する正社員と該当しない正社員の働きやすさを比較すると、該当する正社員の方が働きやすさを感じている。

【解答】
②【R3問1C】 〇
労働時間が
・短くなるほど → 働きやすいと感じる者の割合が増加
・長くなるほど → 働きにくいと感じる者の割合が増加
③【R3問1D】 〇
・テレワークが導入されていない場合の方が、働きにくいと感じている者の割合が高い
④【R3問1E】 〇
・勤務間インターバル制度に該当する方が働きやすさを感じている
※この3問については、理屈というよりも、「そうだろうなー」と納得できるので、解きやすいと思います。
参照:令和元年版労働経済白書
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)厚生年金保険法よく出るところ
R4-039
R3.9.30 厚年「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は厚生年金保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が異なる。なお、いずれの場合も、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
②【R3年問3D】
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると、昭和35年8月22日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子と、同日生まれの第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子とでは、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は同じである。

【解答】
①【R3年問3C】 〇
(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢)
★どちらも昭和35年8月22日生まれ、報酬比例部分のみ
・第1号厚生年金被保険者期間のみを有する女子 → 62歳開始
・第1号厚生年金被保険者期間のみを有する男子 → 64歳開始
②【R3年問3D】 〇
(特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢)
★どちらも昭和35年8月22日生まれ、報酬比例部分のみ
・第4号厚生年金被保険者期間のみを有する女子 → 64歳
・第4号厚生年金被保険者期間のみを有する男子 → 64歳
ポイント!
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、
①「第1号~第4号の男子」、「第2号~第4号の女子」
②「第1号の女子」
の2つのパターンがあります。女子は、「第2号~第4号」と「第1号」で支給開始年齢が異なりますので注意してください。
★①の生年月日をおぼえましょう。節目の「昭和16年」、「昭和24年」、「昭和28年」、「昭和36年」をおさえてください。
②の節目は、プラス5年で、「昭和21年」、「昭和29年」、「昭和33年」、「昭和41年」です。
では、こちらもどうぞ!
③【H29年出題】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
④【H24年出題】(改正による修正あり)
厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の支給開始年齢の読み替えに関する記述のうち、誤っているものはどれか。
A 男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
B 男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。
C 女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。
D 女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。
E 女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。

【解答】
③【H29年出題】 〇
報酬比例部分→60歳から、定額部分→64歳から
④【H24年出題】(改正による修正あり)
A ×
B 〇
C 〇
D 〇
E 〇
A 男子 昭和27年4月2日生まれ → 60歳から報酬比例部分が支給
B 男子 昭和36年4月1日生まれ → 64歳から報酬比例部分が支給
C 女子(第1号)昭和33年4月2日生まれ → 61歳から報酬比例部分が支給
D 女子(第1号)昭和36年4月2日生まれ → 62歳から報酬比例部分が支給
E 女子(第1号)昭和41年4月1日生まれ → 64歳から報酬比例部分が支給
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)国民年金法よく出るところ
R4-038
R3.9.29 国年「任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は国民年金法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1C】
任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は、老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失する。

【解答】
①【R3年問1C】 ×
老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日に資格を喪失するのは、「特例よる任意加入被保険者」です。任意加入被保険者は、その事由では資格喪失しません。
ポイント!「任意加入する目的」をおさえましょう。
「任意加入被保険者」は、「老齢年金の受給権を得るため」、「老齢基礎年金の額を増やすため」に任意加入することができます。ですので、老齢年金の受給権ができても資格は喪失しません。
一方、「特例による任意加入被保険者」の目的は「老齢年金の受給権を得るため」だけです。そのため、目的が達成すると(老齢年金の受給権を取得すると)その翌日に資格を喪失します。「老齢基礎年金の額を増やす」目的では特例による任意加入はできませんので、注意しましょう。
(法附則第5条、H6法附則第11条)
では、こちらもどうぞ!
②【H27年出題】
日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないときは、昭和30年4月1日以前生まれの場合に限り、厚生労働大臣に申し出て特例による任意加入被保険者となることができる。

【解答】
②【H27年出題】 ×
「特例による任意加入被保険者」となることができるのは、「昭和40年4月1日以前生まれ」に限られます。
ポイント!
「特例による任意加入被保険者」は「昭和40年4月1日以前生まれ」という生年月日の要件がつきますが、「任意加入被保険者」には生年月日の要件はありません。
(H16法附則第23条)
次はこちらをどうぞ!
③【H28年出題】
任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。以下本問において同じ。)は、付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ、任意加入被保険者としての被保険者期間は、寡婦年金、死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる。

【解答】
③【H28年出題】 〇
任意加入被保険者と特例による任意加入被保険者の違いをチェックしておきましょう。
| 任意加入被保険者 | 特例による任意加入被保険者 | |
| 付加保険料 | 〇 納付できる | × 納付できない |
| 寡婦年金 | 〇 支給される | × 支給されない |
| 死亡一時金 | 〇 支給される | 〇 支給される |
| 脱退一時金 | 〇 支給される | 〇 支給される |
(法附則第5条、H6法附則第11条)
★ワンポイントアドバイス 覚え方★
死亡一時金と脱退一時金は、生活保障というよりも掛捨て防止の意味合いが大きいです。掛捨て防止の給付は、特例による任意加入被保険者も対象になる、と覚えましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)健康保険法よく出るところ
R4-037
R3.9.28 健保「資格喪失月の賞与」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は健康保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1D】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

【解答】
①【R3年問1D】 〇
ポイント!
(資格喪失月に支払われた賞与について)
・原則として保険料は徴収されません
・標準賞与額として決定され、その年度の標準賞与額の累計額に算入されます
法第156条、(H19.5.1 庁保険発第0501001号)
では、こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
③【H25年出題】
前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
③【H25年出題】 〇
資格喪失月に支給された賞与について、原則として保険料を納付する義務はありません。
※年度の標準賞与額の累計額には算入されます。
では、最後にこちらをどうぞ!
第45条 (標準賞与額の決定)
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >万円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】
A 1,000
B 573
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)徴収法よく出るところ
R4-036
R3.9.27 徴収法「暫定任意適用事業の保険関係の消滅」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問8E(労災)】
労災保険暫定任意適用事業の事業主がなした保険関係の消滅申請に対して厚生労働大臣の認可があったとき、当該保険関係の消滅に同意しなかった者については労災保険に係る保険関係は消滅しない。

【解答】
①【R3年問8E(労災)】 ×
厚生労働大臣の認可があった日の翌日に、その事業についての保険関係が消滅するので、当該保険関係の消滅に同意しなかった者も含めて、全労働者の保険関係が消滅します。
(整備省令第3条)
★暫定任意適用事業は、保険関係の成立が「任意」ですので、保険関係を任意に消滅させることもできます。
★その場合、暫定任意適用事業の成立は「厚生労働大臣の認可があった日」、消滅は「厚生労働大臣の認可があった日の翌日」です。
では、こちらもどうぞ!
②【H29年出題(労災)】
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
③【H23年出題(労災)】
雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、保険関係の消滅の申請をして所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。

【解答】
②【H29年出題(労災)】 ×
労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で違いがあります。
| 暫定任意適用事業の保険関係の消滅の申請要件 | |
労災保険 暫定任意適用事業 | ・労働者の過半数の同意を得る ・保険関係成立後1年以上経過している ・特例給付が行われる事業の場合は特別保険料を徴収する一定期間を経過している |
雇用保険 暫定任意適用事業 | ・労働者の4分の3以上の同意を得る |
③【H23年出題(労災)】 ×
雇用保険暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる要件は、4分の3以上の同意です。また、1年経過の要件はありません。
では、最後にこちらをどうぞ!
④【H27年出題(労災)】
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

【解答】
④【H27年出題(労災)】 ×
適用事業でも暫定任意適用事業でも、事業の廃止又は終了の日の翌日に、法律上当然に保険関係が消滅します。
問題文の場合、事業の廃止によってその翌日に保険関係が消滅するので、保険関係の消滅の申請は要りません。
(法第5条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)雇用保険法よく出るところ
R4-035
R3.9.26 雇用保険「男性の育児休業給付金」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は雇用保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問7D】
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

【解答】
①【R3年問7D】 ×
男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日から対象育児休業となります。
なお、出産予定日から育児休業を取得する場合もあり得ます。
(行政手引59503)
では、こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。

【解答】
②【H26年出題】 ×
男性が取得する育児休業は、配偶者の出産日から対象となります。
(行政手引59503)
では、最後にこちらをどうぞ!
【R1選択】
雇用保険法第61条の7第1項は、育児休業給付金について定めており、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより子を養育するための休業をした場合、「当該< A >前2年間(当該< A >前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により< B >以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が< C >以上であったときに、支給単位期間について支給する。」と規定している。

【解答】
A 休業を開始した日
B 引き続き30日
C 通算して12箇月
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労災保険法よく出るところ
R4-034
R3.9.25 労災「特別加入者と通勤災害」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は労災保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3B】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
①【R3年問3B】 ×
特別加入者も、通常の労働者と同様に通勤災害の保護の対象となります。
ただし、一人親方等の一部は、住居と就業の場所との間の往復の状況を考慮して、通勤災害は適用除外となっています。
問題文の「個人貨物運送業者」は、通勤災害の適用は行われません。
(法第35条、則第46条の22の2)
では、こちらもどうぞ!
②【H30年選択】
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< A >はその一例に該当する。
~選択肢~
①医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者
②介護作業従事者
③個人タクシー事業者
④船員法第1条に規定する船員
③【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
④【H22年出題】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

【解答】
②【H30年選択】 ③個人タクシー事業者
個人タクシー事業者は、通勤災害は適用されません。
③【H26年出題】 〇
家内労働者は通勤災害は適用されません。
④【H22年出題】 ×
漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者は、通勤災害は適用されません。
ポイント! 一人親方等で、通勤災害が適用されない者は覚えましょう。
・ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
(個人タクシー業者、個人貨物運送業者)
・ 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員法第1条の船員が行う事業除く。)
(漁船による自営漁業者)
・ 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者
・ 家内労働者又はその補助者
★通勤災害が適用されないのは、すべての一人親方等ではなく、上記の者のみですので注意してください。
では、最後にこちらの条文をチェックしましょう。
則第46条の26(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、< B >が定める基準によって行う。

【解答】
B 厚生労働省労働基準局長
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)安衛法よく出るところ
R4-033
R3.9.24 安衛法「労働者死傷病報告」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は労働安全衛生法です。
では、どうぞ!
①【R3年問10E】
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、その発生状況及び原因その他の厚生労働省令で定める事項を各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

【解答】
①【R3年問10E】 ×
事業者は、労働者が労働災害により死亡し、又は4日以上休業したときは、労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
労働者に周知する義務はありません。
(則第97条)
では、こちらもどうぞ!
②【H29年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③【H25年出題】
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
労働者死傷病報告書は、労働災害だけでなく、就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内での負傷、窒息又は急性中毒による死亡、休業も対象となっています。
(則第97条)
③【H25年出題】 ×
労働者死傷病報告書の提出時期は2種類あります。
・死亡又は休業4日以上 → 「遅滞なく」提出(様式23号)
・休業4日未満 → 「四半期」ごとに提出(様式24号)
問題文の提出時期は、遅滞なくではなく、四半期単位となります。
では、条文を確認しましょう。
則第97条(労働者死傷病報告)
1 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 1の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における< A >までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
A 最後の月の翌月末日
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働基準法よく出るところ
R4-032
R3.9.23 労基法「差別的取り扱い」とは?
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は労働基準法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
労働基準法第3条が禁止する「差別的取扱」をするとは、当該労働者を有利又は不利に取り扱うことをいう。

【解答】
①【R3年問1B】 〇
「有利」に取り扱うこと、「不利」に取り扱うこと、どちらも「差別的取扱」となります。
(法第3条)
では、こちらもどうぞ!
②【H30年出題】
労働基準法第4条の禁止する賃金についての差別的取扱いとは、女性労働者の賃金を男性労働者と比較して不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も含まれる。

【解答】
②【H30年出題】 〇
第4条も差別的取扱いを禁止する条文ですが、こちらも、不利に取り扱う場合だけでなく、有利に取り扱う場合も差別的取扱いに含まれます。
(法第4条、S22.9.13発基第17号)
では、条文を確認しましょう。
第3条
使用者は、労働者の< A >を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条
使用者は、労働者が女性であることを理由として、< B >について、男性と差別的取扱をしてはならない。

【解答】
A 国籍、信条又は社会的身分
B 賃金
では、こちらの問題もどうぞ!
③【H29年出題】
労働基準法第3条は、使用者は、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として、労働条件について差別的取扱をすることを禁じている。
④【H27年出題】
労働基準法第4条は、賃金について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、賃金以外の労働条件についてはこれを禁止していない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
第3条で差別禁止事由とされているのは、「国籍、信条、社会的身分」です。「性別」による差別は、第3条では禁止されていません。
(法第3条)
④【H27年出題】 〇
第4条で女性であることを理由として差別的取り扱いを禁止しているのは、「賃金」についてのみです。
賃金以外の労働条件についての差別的取扱いは第4条違反にはなりません。なお、賃金以外の労働条件についての差別的取扱いは、男女雇用機会均等法に抵触する可能性があります。
(法第4条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)社会保険労務士法の定番問題
R4-031
R3.9.22 社会保険労務士法/補佐人
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は社会保険労務士法です。
では、どうぞ!
①【R3年問5B】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。

【解答】
①【R3年問5B】 ×
社会保険労務士は補佐人として、弁護士とともに裁判所に出頭し、「陳述」をすることができます。「尋問」は入りません。
複雑化する労働保険や社会保険に関する行政訴訟や、個別労働紛争に関する民事訴訟に、対応するためです。
(法第2条の2)
では、こちらもどうぞ!
②【R1年出題】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
③【H28年出題】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
④【H30年出題】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちからその補佐人を選任しなければならない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく、「弁護士である訴訟代理人とともに」です。
(法第2条の2)
③【H28年出題】 ×
弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができるのは、特定社会保険労務士に限りません。
(法第2条の2)
④【H30年出題】 ×
補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述する事務について、社会保険労務士法人がその社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができます。その場合、「委託者」に選任させなければならない、とされています。
「当該社会保険労務士法人」が選任しなければならない、は誤りです。
(法第25条の9の2)
最後に条文を確認しましょう。
(第2条の2)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、< A >として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、< B >をすることができる。
(第25条の9の2)
社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。
この場合において、当該社会保険労務士法人は、< C >に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。

【解答】
A 補佐人
B 陳述
C 委託者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働契約法の定番問題
R4-030
R3.9.21 労働契約の成立場面における就業規則と労働契約の法的関係
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は労働契約法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3A】
労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めているが、同条は、労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。

【解答】
①【R3年問3A】 〇
労働契約法第7条は、
・労働契約で労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合
↓
・「合理的な労働条件が定められている就業規則」である、+「就業規則を労働者に周知させていた」という要件を満たしている場合
↓
・就業規則で定める労働条件が労働契約の内容を補充し、「労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による」という法的効果が生じる
ことを規定したものです。
そして、第7条本文に「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において」と規定されていますので、第7条は「労働契約の成立場面について適用される」ものです。
既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場で新たに就業規則を制定した場合は適用されません。
(H24年.8.10 基発0810第2号)
では、こちらもどうぞ!
②【R1問3B】
就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、労働契約法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない。
③【H27問1E】
労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。

【解答】
②【R1問3B】 〇
就業規則に定められている事項でも、労働条件でないものは、労働契約法第7条本文によっても労働契約の内容とはなりません。
(H24年.8.10 基発0810第2号)
③【H27問1E】 〇
労働基準法の「周知」とは、①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、② 書面を労働者に交付すること、③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること、のいずれかの方法によることとされています。
労働契約法第7条の「周知」は、①から③の方法に限定されず、実質的に判断されます。周知させていた場合には、労働者が実際に就業規則の存在や内容を知っているか否かにかかわらず、法第7条の「周知させていた」に該当します。
(H24年.8.10 基発0810第2号)
最後に労働契約法第6条と第7条の条文を確認しましょう。
(労働契約の成立)
第6条
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して< A >ことについて、労働者及び使用者が< B >することによって成立する。
第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が< C >が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その < D >によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

【解答】
A 賃金を支払う
B 合意
C 合理的な労働条件
D 就業規則で定める労働条件
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)厚生年金保険法の定番問題
R4-029
R3.9.20 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる子の要件
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は厚生年金保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3A】
障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。

【解答】
①【R3年問3A】 ×
17歳の時に障害の状態でなくなった場合でも、18歳に達した日以後の最初の3月31日までは、加給年金額の加算の対象のままです。
老齢厚生年金の加給年金額の対象になる子の条件を確認しましょう。
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
・20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子
18歳の年度末までは、障害の状態の有無は問われないのがポイントです。
(法第44条)
では、こちらもどうぞ!
②【H21問4B】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。

【解答】
②【H21問4B】 ×
障害等級1級又は2級でない場合は、18歳に達する日以後の最初の3月31日で加給年金額の対象から外れます。その後、19歳で障害状態になったとしても、加給年金額の対象にはなりません。
(法第44条)
それでは、加給年金額の減額改定の事由を条文で確認しましょう。
加給年金額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至った月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
四 配偶者が、65歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によって受給権者の< A >の者の養子となったとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、< B >が終了したとき。
九 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(< B >までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
十 子が、< C >歳に達したとき。

【解答】
A 配偶者以外
B 18歳に達した日以後の最初の3月31日
C 20
(法第44条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)国民年金法の定番問題
R4-028
R3.9.19 老齢基礎年金の計算と国庫負担
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は国民年金法です。
では、どうぞ!
①【R3年問1B】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

【解答】
①【R3年問1B】 〇
老齢基礎年金の国庫負担のポイント!
・保険料4分の1免除期間 → (480-保険料納付済期間の月数)を限度として国庫負担の対象となる
・学生納付特例及び納付猶予の期間 → 国庫負担の対象とならない
(法第85条)
では、こちらもどうぞ!
②【H19問7D】
保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。
③【H29問7B】
学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については、保険料が追納されていなければ、老齢基礎年金の額には反映されない。

【解答】
②【H19問7D】 ×
保険料4分の1免除期間については、8分の7が老齢基礎年金の額に反映されます。
(480-保険料納付済期間の月数が限度)
なお、60歳以降に国民年金に任意加入して、保険料納付済期間+保険料免除期間の月数が480月を超えることがあります。
4分の1免除期間について国庫負担が入るのは(480-保険料納付済期間の月数)が限度です。それを超える4分の1免除期間は、国庫負担がないため「8分の3」で計算されます。(下図参照)
(法第27条)
③【H29問7B】 〇
学生納付特例の期間と納付猶予の期間については国庫負担がないので、老齢基礎年金は、「ゼロ」で計算されます。
保険料が追納されていれば、保険料納付済期間としてフルで計算されます。
(法第27条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
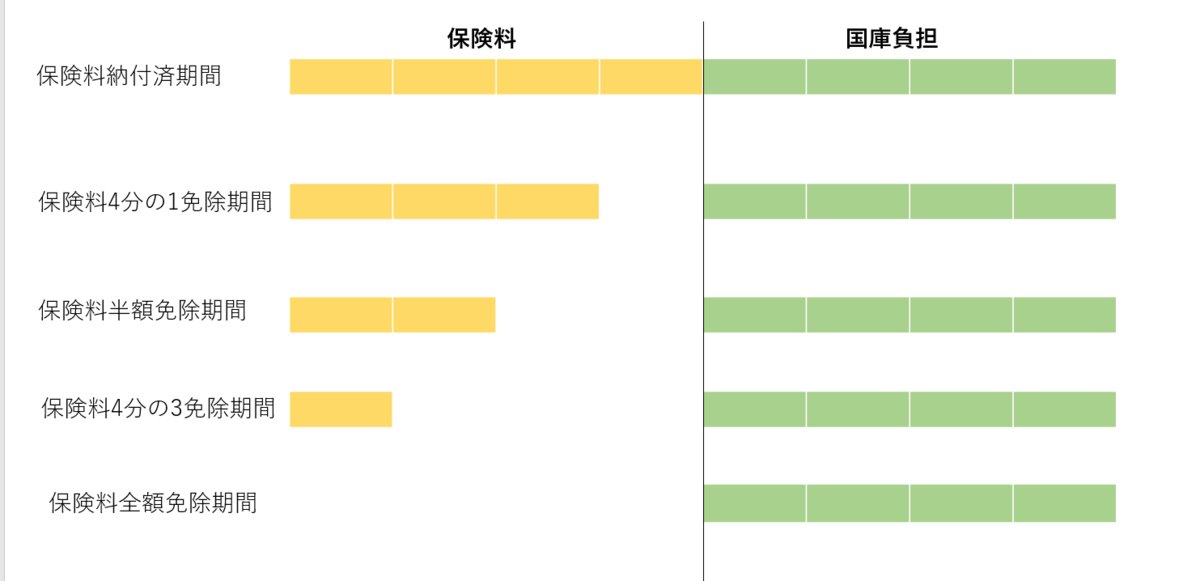
(令和3年出題より)健康保険法の定番問題
R4-027
R3.9.18 休業手当と随時改定
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は健康保険です。
では、どうぞ!
①【R3年問1A】
一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。

【解答】
①【R3年問1A】 〇
低額な休業手当が支払われることとなった場合は、随時改定の対象となります。ただし、固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限られます。
ちなみに、休業手当等をもって標準報酬月額の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象となります。
(S50.3.29保険発25・H15.2.25庁保険発3)
では、こちらもどうぞ!
②【R3問1B】
賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰休で低額な休業手当等の支払が行われ、5月1日に一時帰休の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。

【解答】
②【R3問1B】 ×
①の問題の解説にも書きましたように、一時帰休に伴う随時改定は、低額な休業手当等の支払が継続して『3か月を超える』場合に行われます。
この『3か月』は「暦日単位」ではなく「月単位」で計算します。
問題文の場合は、一時帰休の開始が2月19日ですので、2、3、4月で3か月です。5月1日が「3か月を超える場合」に該当し、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行います。
しかし、問題文では、「5月1日に一時帰休の状態が解消している」ということですので、3か月を超えません。そのため随時改定は行いません。
(参照:H29.6.2付け厚生労働省年金局事業管理課長 事務連絡)
では、随時改定の条文を確認しましょう。
① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、< A >日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を< B >で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった < C >に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を< C >として、その著しく高低を生じた月の< D >から、標準報酬月額を改定することができる。
② ①の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(< E >までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

【解答】
A 17
B 3
C 報酬月額
D 翌月
E 7月から12月
(法第43条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)徴収法の定番問題
R4-026
R3.9.17 労働保険事務組合が処理できない事務
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は徴収法です。
では、どうぞ!
①【R3年問9C(雇用)】
保険給付に関する請求書等の事務手続及びその代行、雇用保険二事業に係る事務手続及びその代行、印紙保険料に関する事項などは、事業主が労働保険事務組合に処理を委託できる労働保険事務の範囲に含まれない。

【解答】
①【R3年問9C(雇用)】 〇
労働保険事務組合は、中小事業主から委託を受けて、労働保険事務の処理を行います。
しかし、労働保険事務組合に委託できない事務処理もあります。
(労働保険事務組合に委託できない事務)
・印紙保険料に関する事項(法第33条で除外されている)
・保険給付に関する請求書等の事務手続
・雇用保険二事業に係る事務手続
(法第33条)
では、こちらもどうぞ!
②【R1問9D(雇用)】
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
③【H18問10C(雇用)】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険料に関する事項も含まれる。
④【H19問8E(雇用)】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く。)の納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務を処理することはできない。

【解答】
②【R1問9D(雇用)】 ×
労働保険事務組合は、労災保険の保険給付に関する請求の事務は、処理できません。
③【H18問10C(雇用)】 ×
印紙保険料に関する事項は除かれています。
④【H19問8E(雇用)】 ×
雇用保険の被保険者の資格取得及び喪失の届出に関する事務は、処理できます。
最後に、労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主の規模を確認しましょう。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、その使用する労働者数が常時< A >人(金融業若しくは保険業、< B >又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又は< C >を主たる事業とする事業主については100人)以下の事業主である。

【解答】
A 300
B 不動産業
C サービス業
(則第62条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)雇用保険法の定番問題
R4-025
R3.9.16 特定受給資格者の範囲
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は雇用保険法です。
今日のテーマは「特定受給資格者」です。
まず、特定受給資格者の定義を確認しましょう。
特定受給資格者には、「倒産等による離職」と「解雇等による離職」の2種類があります。
「特定受給資格者」とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者に該当する受給資格者を除く)をいう。 一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの (倒産等による離職) 二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者 (解雇等による離職) (法第23条) |
では、どうぞ!
①【R3年問4A】
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。

【解答】
①【R3年問4A】 ×
特定受給資格者に該当しません。
「事業所の廃止」に伴い離職した者は、特定受給資格者(倒産等による離職)に該当します。しかし、「事業の廃止」から「事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものは除く」と規定されているので、問題文の場合は特定受給資格者に該当しません。
(則第35条)
★ 「特定受給資格者」の「倒産等による離職」の範囲は、施行規則第35条で以下のように定められています。
1 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者 2 事業所において、労働施策総合推進法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者 3 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者 4 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 |
では、特定受給資格者の問題をもう少しどうぞ
②【H30問5D】
事業所において、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇い労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は特定受給資格者に該当する。
③【H29問4A】
事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した場合、退職に正当な理由がないものとして給付制限を受ける。

【解答】
②【H30問5D】 〇
「労働施策総合推進法による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者」は、特定受給資格者に該当します。
★ 「大量雇用変動届」は、1か月以内の期間に30人以上の離職者の発生が見込まれるときに、提出するものです。
★ 「3で除して得た数を超える」とは、「3分の1を超える」ということです。
(則第34条)
③【H29問4A】 ×
「事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者」は特定受給資格者に該当します。
問題文の「事業所に係る事業活動が停止し、再開される見込みがないために当該事業所から退職した」場合は特定受給資格者に該当しますので、離職理由による給付制限は受けません。
(法第33条、則第34条)
 (参考)特定受給資格者の「解雇等による離職」の範囲はこちらの記事をどうぞ。 → R3.8.13 雇用保険法 選択問題(特定受給資格者の定義)
(参考)特定受給資格者の「解雇等による離職」の範囲はこちらの記事をどうぞ。 → R3.8.13 雇用保険法 選択問題(特定受給資格者の定義)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労災保険法の定番問題
R4-024
R3.9.15 遺族補償一時金の受給資格者の順位
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は労災保険法です。
①【R3年問6】
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
B 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
C 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
D 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
E 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

【解答】
A ×
B 〇
C 〇
D 〇
E 〇
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次のとおりです。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 その他の子、父母、孫及び祖父母
4 兄弟姉妹
★「配偶者」は「生計維持していた」、「生計維持していない」、どちらでも第1順位です。
★子、父母、孫、祖父母は、「生計維持していた」方が優先です。
★兄弟姉妹は、「生計維持していた」、「生計維持していない」、どちらでも一番最後です。
(法第16条の7)
「遺族補償一時金」と「遺族補償年金」と比較してみましょう。
②【H18問5A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
②【H18問5A】 ×
遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
「遺族補償年金」を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られます。一方、「遺族補償一時金」は、生計を維持していなかった者も、受給資格者の範囲に入ります。
こちらは、「遺族補償給付」(年金も一時金も含む)についての問題ですので、生計を維持していたものに限られません。
(法第16条の2、第16条の7)
では、「障害補償年金差額一時金」とも比較してみましょう。
③【H26選択】
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、< A >の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、< A >の順序である。

【解答】
A 祖父母及び兄弟姉妹
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順序は、「生計を同じくしていた」①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、「生計を同じくしていなかった」⑦配偶者、⑧子、⑨父母、⑩孫、⑪祖父母、⑫兄弟姉妹、です。
「生計維持」ではなく、「生計を同じくしていた」が基準となります。
また、遺族の順序は、「生計を同じくしていた」方が優先されます。
(法附則第58条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働安全衛生法の定番問題
R4-023
R3.9.14 「周知義務」あるもの、ないもの(安衛)
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は労働安全衛生法です。
①【R3年問10D】
安全管理者又は衛生管理者を選任した事業者は、その事業場における安全管理者又は衛生管理者の業務の内容その他の安全管理者又は衛生管理者の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させる義務がある。

【解答】
①【R3問10D】 ×
「安全管理者、衛生管理者」の選任について、労働者への周知義務はありません。
※選任後は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務があります。
(則第4条、第7条)
ちなみに、
・安全衛生推進者、衛生推進者を選任したとき
→安全衛生推進者等の「氏名」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない (則第12条の4)
・作業主任者を選任したとき
→作業主任者の「氏名及びその者に行わせる事項」を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない (則第18条)
もう一問どうぞ!
②【H20問9D】
事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
②【H20問9D】 ×
安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会は、毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知させる義務があります。
しかし、報告書を所轄労働基準監督署長に提出する義務はありません。
(則第23条)
では、労働安全衛生規則第23条を穴埋めでチェックしましょう。
(委員会の会議)
・ 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を< A >以上開催するようにしなければならない。
・ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に< B >させなければならない。
1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2 書面を労働者に交付すること。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
・ 事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを< C >間保存しなければならない。
1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
2 委員会における議事で重要なもの

【解答】
A 毎月1回
B 周知
C 3年
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労働基準法の定番問題
R4-022
R3.9.13 「休日」に休業手当支払い義務はある?ない?
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は労働基準法です。
①【R3年問4B】
使用者が法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。

【解答】
①【問4B】 ×
休日は、「労働する義務のない日」ですので、休業手当を支給する義務はありません。ですので、休業手当を支払わなければならない日に「休日」は含みません。「労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日」(法定休日以外の休日)も休業手当の支払義務はありません。
(昭24.3.22基収4077号)
もう一問どうぞ!
②【H18問2C】
労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。

【解答】
②【H18問2C】 〇
①の解説と同じです。
では、労働基準法第26条を穴埋めでチェックしましょう。
第26条 (休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その< A >の100分の< B >以上の手当を支払わなければならない。

【解答】
A 平均賃金
B 60
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・国民年金法【択一】
R4-021
R3.9.12 第53回国年(択一)より~令和3年度の給付額
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 問題文が長いのが特徴です。(国民年金法に限りませんが・・・)「ポイント」を早く見つけないと、問題を解くのに時間がかかってしまいます。日々、勉強をする際に、「納得」することが必要なのでは?と思います。「これはこういうことなんだ」と納得すると、頭に入りやすいし、本試験でもポイントが見つけやすく、そして応用も効くと思います。
【R3年問8】令和3年度の給付額について
(問8-A)
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900円)となる。
(問8-B)
障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円に端数処理を行った、976,100円となる。
(問8-C)
遺族基礎年金の受給権者が4人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900円に子の加算として224,700円、224,700円、74,900円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
(問8-D)
国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1%)によって改定されるため、3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12万円に(1-0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
(問8-E)
第1号被保険者として令和3年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が、令和3年8月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額とする。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

【解答】
(問8-A) ×
昭和31年4月2日生まれの者が、満額の老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付済期間が480月あることが条件です。
問題文の場合、保険料納付済期間が、360月(30年)+60月(5年)=420月、保険料全額免除期間が120月(10年)です。
全額免除期間の計算を考えてみましょう。
問題文の場合、
・保険料全額免除期間は平成21年3月以前の期間なので、3分の1で計算される
・3分の1で計算されるのは、480月から保険料納付済期間(420月)を控除した月数(60月)が限度となる
そのため、老齢基礎年金の額は満額になりません。
(法第27条、H16附則第9条)
(問8-B) ×
障害等級1級の障害基礎年金の額は、976,125円です。問題文のような端数処理は行いません。
条文を確認しましょう。
法第33条 ① 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 ② 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、①の規定にかかわらず、①に定める額の100分の125に相当する額とする。 |
2級の障害基礎年金は、780,900円×改定率ですが、100円単位になるよう端数処理を行います。
1級の障害基礎年金は2級の額×1.25ですが、100円単位の端数処理の規定がついていないので、原則のルールである1円単位で計算します。
(法第33条、法第17条)
(問8-C) ×
遺族基礎年金の受給権者が子のみの場合、1人目には加算がつかないのがポイントです。
例えば、子が1人の場合は、遺族基礎年金の額は780,900円です。
2人目から加算がつき、問題文の場合は、2人目224,700円+3人目74,900円+4人目74,900円が加算されます。
(法第39条の2)
(問8-D) ×
死亡一時金の額には、改定率は適用されません。
(法第52条の4)
(問8-E) 〇
脱退一時金は、「基準月の属する年度の保険料額×2分の1×保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数」で計算します。
この問題は、「50か月」保険料を納付しているので、「48」を掛ける点がポイントです。
詳細はこちらの記事をどうぞ→ 国年【令和3年4月改正】脱退一時金の改正 (R3.6.27【国年】脱退一時金の支給上限年数の引上げ)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・厚生年金保険法【択一】
R4-020
R3.9.11 第53回厚年(択一)より~遺族厚生年金
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 一筋縄ではいかない、ひねりの効いた問題が多かったように思います。暗記したことを組み立てたり、図を書いてみたり、今年の厚生年金保険の問題は解くのに工夫が必要です。
【R3年問5】
(問5-ア)
老齢厚生年金の受給権者(被保険者ではないものとする。)が死亡した場合、国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年であったとしても、その期間と同法に規定する合算対象期間を合算した期間が25年以上である場合には、厚生年金保険法第58条第1項第4号に規定するいわゆる長期要件に該当する。
(問5-イ)
厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。
(問5-ウ)
85歳の老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者により生計を維持していた未婚で障害等級2級に該当する程度の障害にある60歳の当該受給権者の子は、遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
(問5-エ)
厚生年金保険の被保険者であった甲には妻の乙と、甲の前妻との間の子である15歳の丙がいたが、甲が死亡したことにより、乙と丙が遺族厚生年金の受給権者となった。その後、丙が乙の養子となった場合、丙の遺族厚生年金の受給権は消滅する。
(問5-オ)
厚生年金保険の被保険者の死亡により、被保険者の死亡の当時27歳で子のいない妻が遺族厚生年金の受給権者となった。当該遺族厚生年金の受給権は、当該妻が30歳になったときに消滅する。

【解答】
(問5-ア) 〇
「老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき」は長期要件に該当します。
この「25年」に合算対象期間が含まれることがこの問題のポイントです。
問題文の通り、「保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間」とを合算した期間が25年以上の場合は、長期要件に該当します。
(法第58条、附則第14条)
(問5-イ) 〇
保険料納付要件の特例の条件は、
・死亡日が令和8年4月1日前にある
・死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納期間がない
・死亡日に65歳未満
です。
問題文の場合、
死亡日=令和3年8月1日
死亡日の属する月(令和3年8月)の前々月までの1年間(令和2年7月から令和3年6月まで)に「保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がない」(滞納期間がない)
・死亡時に50歳
ということで、要件を満たしているので、保険料納付要件の特例が適用され遺族厚生年金の支給対象となります。
(法第58条、S60年法附則第64条)
(問5-ウ) 〇
遺族となる「子」の要件は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。」です。
問題文の場合は、年齢要件に該当しないので、遺族となりません。
(法第59条)
(問5-エ) ×
直系血族及び直系姻族以外の養子となったときは遺族厚生年金の受給権は消滅しますが、問題文の場合は、直系姻族の養子ですので、遺族厚生年金の受給権は消滅しません。
(法第63条)
(問5-オ) ×
30歳未満の子のいない妻の遺族厚生年金は、「遺族厚生年金の受給権を取得した日」から5年を経過したときに消滅します。問題文の場合、妻が30歳になったときは、まだ5年経過していませんので、消滅しません。
(法第63条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・健康保険法【択一】
R4-019
R3.9.10 第53回健保(択一)より~複合問題
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 細かい知識を問われる問題が目立ちました。しかし、テキストや過去問で強調されているところをおさえていれば、問題は解けます。難問に引きずられることがないよう、基本で勝負できるようにしましょう。
【R3年問10】
(問10-A)
賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。
(問10-B)
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。
(問10-C)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
(問10-D)
倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。
(問10-E)
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【解答】
(問10-A) 〇
時間給の単価に変動はない、しかし、勤務体系に変更(1日の所定労働時間が8時間から6時間になった)があった場合、「固定的賃金の変動に該当」し、随時改定の対象となります。
(参照:「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について〔健康保険法〕 R3.4.1事務連絡)
(問10-B) ×
7月から9月までのいずれかの月から、「随時改定」、「育児休業を終了した際の改定」、「産前産後休業を終了した際の改定」が行われた場合は、その年の定時決定は行われません。
(法第41条)
(問10-C) 〇
保険料控除のポイント
①「前月分」の保険料を報酬から控除することができる
②被保険者がその事業所に使用されなくなった場合(退職の場合)
→前月分と当月分の保険料を報酬から控除することができる
※月の途中で退職した場合 → 前月分のみ控除することができる
※月末に退職した場合 → 前月分と今月分の2か月分を控除することができる
(法第167条)
(問10-D) 〇
・国民健康保険には、倒産・解雇などにより離職した者(雇用保険の特定受給資格者)及び雇止めなどにより離職された者(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険料(税)を軽減する制度があります。
・そのため、失業後に、任意継続被保険者となった場合よりも、国民健康保険の保険料が低くなる場合もあります。
・しかし、任意継続被保険者が保険料を前納した場合、前納に係る期間の経過前には、その資格を喪失したとき(他の健康保険の被保険者となったとき、死亡したとき等)以外は、前納された保険料を還付する取扱いはありません。
・このため、特定受給資格者等である任意継続被保険者が、保険料を前納した後に国民健康保険の軽減制度について知った場合は、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることによって、前納を初めからなかったものとすることができるようになっています。
(参照:H22.3.24 保保発0324第2号)
(問10-E) 〇
療養費として支給される額は、「健康保険の療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)」に基づいて計算した額」から、「一部負担金の割合を乗じて得た額」を差し引いた額となります。「実際に支払った額」が基準になるわけではないので注意してください。また、食事療養や生活療養を受けた場合も同じように計算します。
(法第87条)
■この問題のポイントを穴埋めでチェックしておきましょう。
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を< A >。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、< B >が定める。

【解答】
A 除く
B 保険者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・社会保険一般常識【択一】
R4-018
R3.9.9 第53回社一(択一)より~介護保険法
第53回試験を振り返ってみましょう。
★☆☆ 法令4問、白書1問で構成されていました。白書は「令和2年版」からの出題です。前年度の白書はチェックしておきましょう。法令はそれほど難しくなく、一般常識の法令は広く浅く勉強することが肝要です。
【R3年問8】
(問8-A)
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
(問8-B)
介護認定審査会は、市町村におかれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
(問8-C)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
(問8-D)
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
(問8-E)
介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。

【解答】
(問8-A) ×
介護保険の保険料は市町村が徴収しますが、対象は第1号被保険者で、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
第2号被保険者の介護保険料は市町村が徴収するのではなく、以下の流れになります。
・各医療保険者が医療保険の保険料といっしょに介護保険料を徴収する
↓
・社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から納付金を徴収する
↓
・社会保険診療報酬支払基金から各市町村に交付する
(法第125条、第131条、第150条)
(問8-B) ×
<介護認定審査会のポイント>
・市町村におかれる
・審査判定業務を行う
・介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する
問題文の「介護支援専門員から任命される」の部分が誤りです。
(法第14条)
(問8-C) ×
世帯主、配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負っています。
(法第132条)
(問8-D) 〇
<介護保険審査会のポイント>
・各都道府県に置かれる(Bの介護認定審査会と比較してください)
・保険給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる
(法第183条)
(問8-E) ×
「14日以内」が誤りです。
<ポイント>
・要介護認定は、有効期間内に限り、その効力を有する。
・有効期間の満了後も要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができる。(※要介護更新認定の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行う)
・災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
(法第28条、則第39条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労働の一般常識その2【択一】
R4-017
R3.9.8 第53回労一(択一)より~関連法規その2
第43回試験を振り返ってみましょう。
昨日に引き続き労働一般常識(択一)です。
【R3年問4】
(問4-エ)
A社において、定期的に職務の内容及び勤務地の変更がある通常の労働者の総合職であるXは、管理職となるためのキャリアコースの一環として、新卒採用後の数年間、店舗等において、職務の内容及び配置に変更のない短時間労働者であるYの助言を受けながら、Yと同様の定型的な業務に従事している場合に、A社がXに対し、キャリアコースの一環として従事させている定型的な業務における能力又は経験に応じることなく、Yに比べ基本給を高く支給していることは、パートタイム・有期雇用労働法に照らして許されない。
(問4-オ)
女性労働者につき労働基準法第65条第3項に基づく妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として男女雇用機会均等法第9条第3項の禁止する取扱いに当たるが、当該労働者につき自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき、又は事業主において当該労働者につき降格の措置を執ることなく軽易な業務への転換をさせることに円滑な業務運営や人員の適正配置の確保などの業務上の必要性から支障がある場合であって、上記措置につき男女雇用機会均等法第9条第3項の趣旨及び目的に実質的に反しないものと認められる特段の事情が存在するときは、同項の禁止する取扱いに当たらないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
(問4-エ) ×
「同一労働同一賃金ガイドライン」からの出題です。
「同一労働同一賃金ガイドライン」では、通常の労働者(正社員)とパートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者との間に、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例が示されています。
問題文は、『同一労働同一賃金ガイドライン』の中で、「問題とならない例」として示されています。
ポイント!
正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合
賃金の決定基準・ルールの相違は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるものであってはならない。
(参照:同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)
(問4-オ) 〇
ポイント!
妊娠中の軽易な業務への転換を契機として降格させる事業主の措置について
<最高裁の判決> 軽易な業務への転換を契機として降格させる措置は、例外に該当する場合を除き、原則として男女雇用機会均等法第9条第3項の禁止する「不利益取扱い」に当たる。
(参照 平成26.10.23最一小判)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労働の一般常識その1【択一】
R4-016
R3.9.7 第53回労一(択一)より~関連法規その1
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 労働経済から2問、法令から3問でした。内容は難しい。じっくり落ち着いて取り組まなければならない問題でした。
【R3年問4】
(問4-ア)
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。
(問4-イ)
定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保しなければならない
(問4-ウ)
労働施策総合推進法第30条の2第1項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。

【解答】
(問4-ア) 〇
「合理的配慮指針」の、合理的配慮に関する基本的な考え方の一つです。
「事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、合理的配慮の提供義務違反を問われない。」
(障害者の雇用の促進等に関する法律 合理的配慮指針 第2基本的な考え方)
(問4-イ) ×
「定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主」、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)」を導入している事業主は、
「高年齢者就業確保措置」を講ずるよう努めなければならない、とされています。→ポイント1 努力義務
「高年齢者就業確保措置」とは、
①70歳までの定年の引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入
③定年の定めの廃止
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
・事業主が実施する社会貢献事業
・事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業
→ ポイント2 ④と⑤は「創業支援等措置」で、「雇用」によらない措置です。※導入には過半数組合等の同意が必要です。
「高年齢者就業確保措置」の「就業」に注目してください。「雇用」と言っていない点がポイントです。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2)
(問4-ウ) 〇
「パワハラ防止対策義務化」についての問題です。
大企業は、令和2年6月1日~職場におけるパワーハラスメント対策が義務化されていますが、中小事業主が義務化になるのは令和4年4月1日からです。それまでは努力義務です。
(労働施策総合推進法第30条の2、附則第3条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労働保険徴収法【択一】
R4-015
R3.9.6 第53回徴収(択一)より~有期事業の一括
第53回試験を振り返ってみましょう。
★☆☆ 数字を中心に過去問の基本事項をしっかり押さえていれば、しっかり対応できたと思います。
【R3年問10(労災)】
(問10-A)
有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額(労働保険徴収法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額)に相当する額が160万円未満でなければならない。
(問10-B)
有期事業の一括が行われる要件の一つとして、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業であり、かつ建設の事業又は立木の伐採の事業であることが定められている。
(問10-C)
建設の事業に有期事業の一括が適用されるには、それぞれの事業の種類を同じくすることを要件としているが、事業の種類が異なっていたとしても、労災保険率が同じ事業は、事業の種類を同じくするものとみなして有期事業の一括が適用される。
(問10-D)
同一人がX株式会社とY株式会社の代表取締役に就任している場合、代表取締役が同一人であることは、有期事業の一括が行われる要件の一つである「事業主が同一人であること」に該当せず、有期事業の一括は行われない。
(問10-E)
X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、その事業の規模及び事業の種類が有期事業の一括の要件を満たすものであっても、X会社が元請として施工する有期事業とは一括されない。

【解答】
(問10-A) 〇
有期事業の一括には、規模の要件があります。
①概算保険料の額が160万円未満
かつ
②建設の事業 → 請負金額が1億8千万円未満
立木の伐採の事業 → 素材の見込生産量が1000立方メートル未満
■建設の事業でも、立木の伐採の事業でも、概算保険料が160万円未満であることが要件です。
(法第7条、則第6条)
(問10-B) 〇
それぞれの事業が、建設の事業に該当するか、又は立木の伐採の事業に該当することが要件です。また、一括されるのは「労災保険」のみであることにも注意しましょう。雇用保険は一括されません。
(法第7条、則第6条)
(問10-C) ×
一括の要件として、「それぞれの事業が事業の種類(労災保険率表に掲げる事業の種類をいう)を同じくすること」があります。「労災保険率表」に掲げる事業の種類を同じくすることが要件なので、『事業の種類が異なって』いる場合は、労災保険率が同じでも一括されません。
(則第6条)
(問10-D) 〇
「事業主が同一人であること」とは、その事業が同じ企業に属していることをいいます。
(問10-E) 〇
建設の請負事業の場合は、徴収法上、「元請負人」のみが事業主となります。ですので、X会社がY会社の下請として施工する建設の事業は、元請のY会社の工事に一括されます。X会社が元請として施工する有期事業とは一括されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・雇用保険法【択一】
R4-014
R3.9.5 第53回雇用保険(択一)より~算定基礎期間
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 丸暗記ではない、じっくり丁寧な勉強が求められていると思いました。
【R3年問3】
(問3-A)
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
(問3-B)
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
(問3-C)
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
(問3-D)
かつて被保険者であった者が、離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、当該離職に係る被保険者であった期間は算定基礎期間に含まれない。
(問3-E)
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。

【解答】
■算定基礎期間とは?
離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間
※当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)
「算定基礎期間」から除かれる期間についての問題です。
(問3-A) 〇
雇用された期間又は被保険者であった期間に育児休業給付金の支給を受けた期間が ある場合は、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
(問3-B) 〇
事業主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、遡って加入手続きができるのは、2年以内です。
ただし、雇用保険料が賃金から控除されていたことが明らかな場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きをすることができます。
問題文のように、「被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前」については、「被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間」は、算定基礎期間に含まれません。
(問3-C) 〇
労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず被保険者となり、算定基礎期間にも含まれます。
(行政手引20352)
(問3-D) 〇
例えば、A社を離職後、B社に就職した場合、A社の資格を喪失した日後1年以内にB社で資格を再取得しなかった場合には、その期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていなかったとしても、A社で被保険者であった期間は、B社を離職した際の算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
(問3-E) ×
算定基礎期間に含まれません。
以前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある場合は、その受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、今回の離職の算定基礎期間に含まれません。
(行政手引50302)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労災保険法【択一】
R4-013
R3.9.4 第53回労災(択一)より~加重障害
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 条文を丸暗記しても解けない問題とテキスト・過去問で対応できる問題が半々でした。
【R3年問5】
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。
A163.88日分
B166.64日分
C184日分
D182.35日分
E182.53日分

【解答】 A
ポイント!
「加重障害」の問題です。
『既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合』の障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付となります。
給付額は、現在の障害等級の障害補償給付の額から、既にあった障害等級に応ずる障害補償給付の額を差し引いた額となります。
問題文の場合、現在は5級(年金)、既存の障害は8級(一時金)であることがポイントです。
この場合は、既存の一時金は25で割って差額を出します。(一時金は25年分の年金をまとめて支払っている計算です。)
計算式は、5級の年金(184日分/年間)- 8級の一時金の25分の1(503日分÷25)です。
答えは、「163.88日分」となります。
(法第15条、則14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
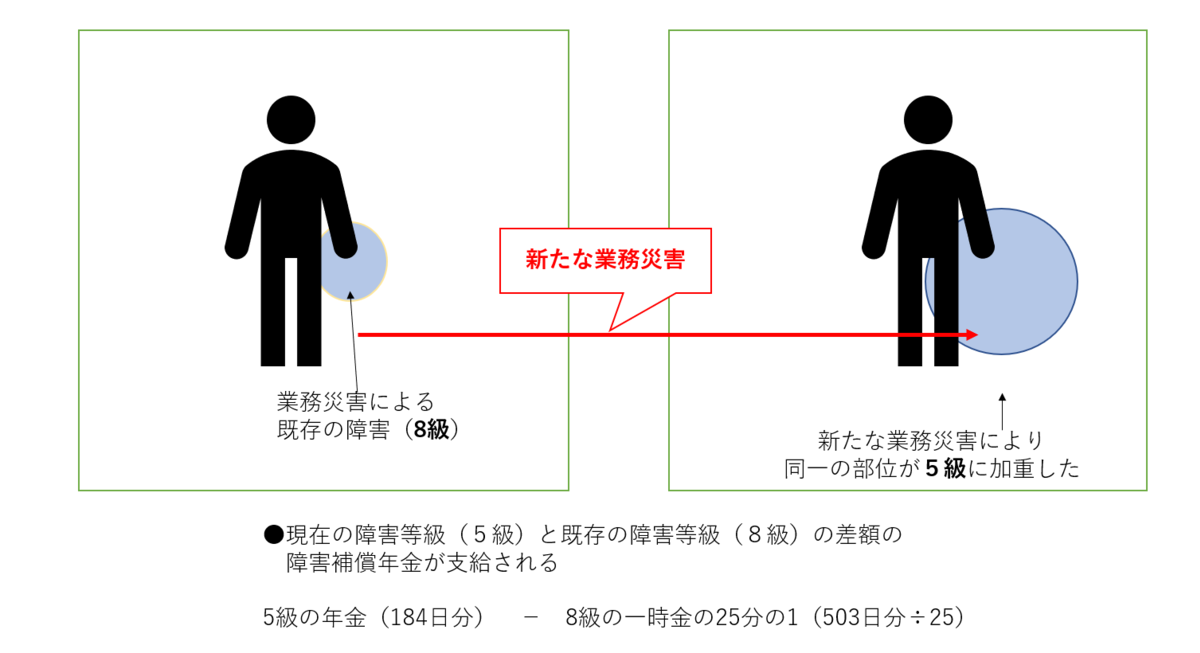
第53回試験・労働安全衛生法【択一】
R4-012
R3.9.3 第53回安衛(択一)より~総括安全衛生管理者
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 引っかけてくる設問にも、「もしかしたらこんな規定があるのかな?」と、悩んでしまいます。でも、勉強した範囲で、覚えている範囲で、知っている範囲で、設問に〇、×(場合によっては△も)をつけながら、なんとか正解にたどりつきたい、今年の労働安全衛生法は、そんな問題でした。
【R3年問9】
問9ア
総括安全衛生管理者は、労働安全衛生法施行令で定める業種の事業場の企業全体における労働者数を基準として、企業全体の安全衛生管理を統括管理するために、その選任が義務づけられている。
問9イ
総括安全衛生管理者は、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することを統括管理する。
問9ウ
総括安全衛生管理者は、労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関することを統括管理する。
問9エ
総括安全衛生管理者は、健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関することを統括管理する。
問9オ
総括安全衛生管理者は、労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関することを統括管理する。

【解答】
問9ア ×
「企業全体」という部分が誤りです。労働安全衛生法は労働基準法と同じで、「事業場単位」で適用されます。
企業全体ではなく、事業場ごとの業種、事業場ごとの労働者数が基準になります。
なお、総括安全衛生管理者は、「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」をもって充てなければならない、と規定されていて、工場長や支店長などがイメージです。企業全体ではなく、工場や支店の責任者です。
(法第10条、施行令第2条)
問9イ 〇
問9ウ 〇
問9エ 〇
問9オ 〇
総括安全衛生管理者に統括管理させる業務として、
① 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
② 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
⑤ 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
の5つを第10条で定めています。
赤い字の部分がポイントですが、労働安全衛生法の中に出てくる用語ばかりですので、総括安全衛生管理者が統括管理する業務として問われたら、×ではなく〇をつけられるのではないかと思います。暗記で解く問題ではなく、勉強したすべてを引っ張ってきて解く問題だと思いました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労働基準法【択一】
R4-011
R3.9.2 第53回労基(択一)より~産前産後
第53回試験を振り返ってみましょう。
☆☆☆ 労働基準法は、過去問のポイントをしっかりおさえていれば、解きやすかったと思います。
【R3年問6】
A 労働基準法第65条の「出産」の範囲は、妊娠4か月以上の分娩をいうが、1か月は28日として計算するので、4か月以上というのは、85日以上ということになる。
B 労働基準法第65条の「出産」の範囲に妊娠中絶が含まれることはない。
C 使用者は、産後8週間(女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせる場合は6週間)を経過しない女性を就業させてはならないが、出産当日は、産前6週間に含まれる。
D 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性労働者については、当該女性労働者の請求が産前の休業の条件となっているので、当該女性労働者の請求がなければ、労働基準法第65条第1項による就業禁止に該当しない。
E 労働基準法第65条第3項は原則として妊娠中の女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない。

【解答】
問6A 〇
「出産」の範囲は、「妊娠4か月」以上の分娩のこと。
1か月は28日で計算するので、4か月以上とは85日以上のこととなります。
(S23.12.23基発1885)
問6B ×
妊娠中絶でも、妊娠4か月以後に行った場合は、産後休業の規定が適用されます。
(S26.4.2婦発113号)
問6C 〇
出産当日は「産前」に含まれます。
(S25.3.31基収4057号)
問6D 〇
産前休業は、女性の「請求」が条件ですので、請求がなければ就業禁止にはなりません。
一方、「産後休業」は、請求を条件にしていませんので、請求の有無にかかわらず、就業させることは禁止されています。(ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない、とされています。)
問6E 〇
第65条第3項では、『妊娠中の女性が「請求した場合」(この規定も請求が条件です。)においては、他の軽易な業務に転換させなければならない』と規定されています。女性が請求した業務に転換させることが原則ですが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まではありません。
(S61.3.20基発151号)
最後に条文をチェックしましょう
第65条(産前産後)
① 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、< A >週間)以内に出産する予定の女性が休業を< B >場合においては、その者を就業させてはならない。
② 使用者は、産後< C >週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
③ 使用者は、< D >の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

【解答】
A 14
B 請求した
C 8
D 妊娠中
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(国民年金法)
R4-010
R3.9.1 第53回選択国年~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「国民年金法」の選択式です。
問題1 調整期間(第16条の2)
調整期間の条文は、15年前の平成18年にも選択式で出題されています。選択式も過去問のチェックは欠かせません。
とはいいましても、Aの選択肢は、文脈で考えてしまって、結果として迷った方も多かったのではないでしょうか?
財政均衡期間に財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合は、給付額を調整するため、マクロ経済スライドを適用しますが、給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度は政令で定めることとなっています。
なお、調整期間の開始年度は、政令(施行令第4条の2の2)で、「平成17年度」とされています。
問題1 ★☆☆ 暗記が肝心
問題2 公課の禁止(第25条)
こちらも見慣れた条文ですが、「基準」か「標準」かで迷いませんでしたか?
一字一句覚えていれば迷わないのですが、なかなかそこまで覚えるのは難しいので。
「老齢基礎年金と付加年金」は例外的に課税対象になるという点は、解けたと思います。
問題2 ★☆☆ 暗記が肝心
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(厚生年金保険法)
R4-009
R3.8.31 第53回選択厚年~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「厚生年金保険法」の選択式です。
問題1 賞与の定義(第3条)
迷うようなひっかけ選択肢も無いですし、ばっちり解けたと思います。
問題1 ☆☆☆ どうにか解ける
問題2 交付金(第84条の3)
■まずは「実施機関」の確認をしましょう。
第1号厚生年金被保険者 → 厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団
■「共済組合等」のキャッシュフローは、以下のようなイメージです。
・実施機関(厚生労働大臣を除く。)は、厚生年金勘定に拠出金を納付する。(厚生年金の給付に必要な費用を分担するため)
↓
・実施機関(厚生労働大臣を除く。)に係る保険給付に必要な費用(「厚生年金保険給付費等」)は、厚生年金勘定から、共済組合等に交付金として交付される。
■「厚生年金保険給付費等」とは、「実施機関(厚生労働大臣を除く。)に係る厚生年金保険法の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用」をいいます。
問題2 ★★☆ やや難しい
問題3 適用事業所の一括(第8条の2)
択一式でもよく出題されるところなので、解けたと思います。
問題3 ☆☆☆ どうにか解ける
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(健康保険法)
R4-008
R3.8.30 第53回選択健保~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「健康保険法」の選択式です。
問題1 一般保険料率(第156条、第160条)
第156条では、保険料額について、介護保険第2号被保険者は、「一般保険料額+介護保険料額」、介護保険第2号被保険者以外は「一般保険料額」とされています。
「一般保険料額」は、標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ「一般保険料率」を乗じて計算します。
「一般保険料率」の内訳は、「基本保険料率+特定保険料率」となります。
特定保険料率は、後期高齢者医療制度への支援金等に充てるための保険料率で、特定保険料率の計算式は、
「(前期高齢者納付金等の額、後期高齢者支援金等の額)÷総報酬額の総額の見込額」で得た率を基準として、保険者が定めることになっています。
協会けんぽの場合、分子は(前期高齢者納付金等の額、後期高齢者支援金等の額-国庫補助額)となります。
ちなみに、
国庫補助額を「控除」か「加算」かで迷いませんでしたか?保険者は国庫補助額の分、負担が減ると考えると「控除」が選べます。
「総報酬額」か「総報酬額の総額」かで迷いませんでしたか?「総報酬額」は個別の標準報酬月額と標準賞与額の合計です。保険者全体の総額を使うので、「総報酬額の総額」となります。
問題1 ★☆☆ 暗記が肝心
問題2 標準報酬月額(第40条)
この問題は、ばっちり解けると思います。
問題2 ☆☆☆ どうにか解ける
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(社会保険一般常識)
R4-007
R3.8.29 第53回選択社一~やや難しい★★☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「社会保険に関する一般常識」の選択式です。
問題1 国民健康保険法(第76条)
市町村は被保険者の属する世帯の世帯主から国民健康保険の「保険料」を徴収します。その「保険料」についての問題です。
「Aを解く手順」→選択肢の中の「納付」か「交付」のどちらになるかをまず検討する → 後に続くかっこ書きの前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金の納付に要する費用を含む、という点に注目する → 「納める」(納付)を選ぶ → かっこ書きのような納付金なども含んだ名称として「国民健康保険事業費納付金の納付」を選ぶ。
Bは、直前の「その他の」がヒントです。Bには、「その他の」の前に出てくる国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用も含まれます。そのような費用も含めた全体の費用と考えると、「国民健康保険事業に要する費用」が出てくると思います。
問題1 ★★☆ やや難しい
問題2 船員保険法(第93条)
船員保険独自の給付「行方不明手当金」からの問題です。
問題2 ★☆☆ 暗記が肝心
問題3 児童手当法(第8条)
児童手当の支給はよく出題されるところですが、ちょっと難しいです。
問題3 ★★★ 難しい
問題4 確定給付企業年金法(第41条)
脱退一時金を受けるための要件についての問題です。5年と迷うかもしれませんが、10年、15年は長すぎると感じるのではないでしょうか?
問題4 ★☆☆ 暗記が肝心
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(労働一般常識)
R4-006
R3.8.28 第53回選択労一~難しい★★★
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の選択式です。
問題1 労働施策総合推進法(法第9条、則第1条の3、則附則第10条)
「労働者の募集・採用の際の年齢制限禁止」からの出題です。
労働施策総合推進法では、労働者の募集・採用の際に、原則として年齢制限を禁止しています。
ただし、例外事由に該当する場合は、年齢制限を行うこともできます。
その例外規定の1つとして、新しく「就職氷河期世代」の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用が可能になっています。(令和5年3月31日までの措置です)
その就職氷河期世代の年齢層の問題でした。施行規則附則第10条で「35歳以上55歳未満」と規定されています。
問題1 ★★★ 難しい
問題2 「生涯現役社会の実現に向けた環境整備」、「高年齢求職者の再就職支援」、「中高年齢者等の起業」がテーマです。
(令和2年版厚生労働白書 第3節「生涯現役社会」の実現より)
助成金の名称と内容を暗記するのは難しいです。しかし、文脈からなんとか当てはめることができると思います。
Bのヒントは、問題文の中の「65歳以降の定年延長、66歳以降の継続雇用延長」という部分です。「キャリアアップ」「処遇改善」「雇用安定」というワードは合わないので、「65歳超雇用推進」という用語になるのではないかと考えてみる。
Dのヒントは、問題文の中の「ハローワーク等の紹介により60歳以上の高年齢者等を雇い入れた」の部分です。「雇用継続」「人材開発」「人材確保」というワードは合わないので、「特定求職者雇用開発助成金」ではないかと考えてみる。
問題2 ★★★ 難しい
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(雇用保険法)
R4-005
R3.8.27 第53回選択雇用保険~どうにか解ける☆☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、雇用保険法の選択式です。
問題1 (法第13条)
「算定対象期間」についての出題です。
A、Bともに問題なく解けたと思います。
問題1 ☆☆☆ どうにか解ける
問題2
「失業の認定の対象となる求職活動実績の基準」(行政手引51254)からの出題です。
「失業の認定」は求職活動の実績に基づいて行われます。受給資格者について「労働の意思及び能力がある」ことを確認されなければなりません。
失業の認定は、認定対象期間に、求職活動を行った実績が原則2回以上あることを 確認できた場合に行われます。
今回は、「求職活動実績が1回以上」あれば失業の認定が行われる例外についての問題でした。
行政手引51254によると、例外が当てはまるのは、
「法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合」
「初回支給認定日における認定対象期間(待期期間を除く。)である場合」
「認定対象期間の日数が14日未満となる場合」
「求人への応募を行った場合(当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする。)」
「巡回職業相談所における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合」
に該当する場合です。
■「認定対象期間の日数が14日未満」という箇所がヒントです。期間が短いので、求職活動の実績は例外的に「1回」で足りる、というように。
■求職活動は、「就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認しうる活動」であることが必要で、「単に、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない 。」とされています。
雇用保険法の「失業」の定義の条文に出てくる「労働の意思及び能力を有する」という用語を思い出しながら解いてみると、「D」については消去法で答えが出せると思います。
■「巡回職業相談所」はテキストにも出てこない用語なので、選びにくかったのではないでしょうか?しかし、選択肢の中の「年金事務所」や「労働基準監督署」で失業の認定を行うなんて聞いたことが無いし、「都道府県労働局」も各都道府県に1つずつしかないので、「失業の認定」を行うにはちょっと不便そうです。そう考えると、「巡回職業相談所」になると思います。
問題2 ★☆☆ 消去法で解く
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(労災保険法)
R4-004
R3.8.26 第53回選択労災~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、労災保険法の選択式です。
問題1
令和2年改正の「複数業務要因災害」からの出題です。
A 複数事業労働者の定義(法第7条第1項第2号、則第5条)
複数事業労働者には、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」も含むと定められています。
なぜなら、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症の時期が必ずしも一致しないことがあるからです。傷病等が発症した時点で複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあるがゆえの規定です。
(参照: R2.8.21基発0821第1号)
B 複数業務要因災害に係る事務の所轄(則第1条)
複数業務要因災害に係る事務の所轄は、「生計を維持する程度の最も高い事業」の主たる事務所を管轄する局又は署となります。
なお、「生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所」とは? → 原則として複数就業先のうち給付基礎日額の算定期間における賃金総額が最も高い事業場を指します。
(参照: R2.8.21基発0821第1号)
問題1 ★★☆ やや難しい
問題2
年金の「支給停止期間」からの出題です。(法第9条)
この問題は大丈夫だったと思います。
問題2 ☆☆☆ どうにか解ける
問題3
遺族補償年金を受けることができる遺族(法第16条の2、S40法130附則第43条)
D 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の年齢
法16条の3では、「60歳以上」、しかし、附則では暫定措置として55歳以上とされています。ですので、私は「55歳以上」だと考えています。でも、本則上の年齢を問われているとしたら、60歳以上です。
E 子、孫、兄弟姉妹の年齢
この問題は迷わず解けたと思います。
問題3 ☆☆☆ どうにか解ける
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(安衛法)
R4-003
R3.8.25 第53回選択安衛~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、労働安全衛生法の選択式です。
問題3
労働安全衛生法第62条(中高年齢者等についての配慮)からの出題です。
暗記していれば、「心身の条件」を選べます。しかし、暗記していなかった場合は、選択肢を一つずつ当てはめて考えてみる。候補は、「希望する仕事」「就業経験」「労働時間」あたりですが、条文中の「特に配慮を必要」「適正な配置」というキーワードをヒントにすれば、「心身の条件」が選べたのではないでしょうか。
問題3D ☆☆☆(どうにか解ける)
問題4
『高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合、墜落の危険防止のため、作業床を設置しなければならない』という施行規則第518条からの出題です。
ここまで暗記するのは難しいです。『何メートル???」と焦った方も多かったと思います。
問題4E ★★★ 難しい
 ちなみに、平成27年(問8A)に施行規則第519条から似たような問題が出題されていました。その過去問で「2メートル」という数字をインプットしていた方もいらっしゃるのでは?
ちなみに、平成27年(問8A)に施行規則第519条から似たような問題が出題されていました。その過去問で「2メートル」という数字をインプットしていた方もいらっしゃるのでは?
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(労基法)
R4-002
R3.8.24 第53回選択労基~やや難しい★★☆
第54回試験に向けて、スタートします。
まずは、第53回試験を解いてみました。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、労働基準法です。
【問1】
労基法第16条(賠償予定の禁止)に出てくる「違約金」の性質について
「労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない」場合、違約金を支払う義務のある者は、「労働者本人」、「親権者」、そしてもう一つは?ということですが、解答は「身元保証人」です。
前後の文脈をみて、選択肢の中から、身元保証人を選べたと思います。
問1 A ☆☆☆(どうにか解ける)
【問2】
国際自動車事件(R2.3.30最1小判)からの出題です。
・使用者が労基法37条の「割増賃金を支払った」といえるか否かの判断について
ポイント
・前提 → 労働契約における賃金の定めにつき、「通常の労働時間の賃金」に当たる部分と「割増賃金に当たる部分」とを判別することができることが必要
・使用者が、「特定の手当」を支払うことにより、労基法第37条の定める割増賃金を支払ったと主張している場合
→労働契約に係る契約書等の記載内容のほか諸般の事情を考慮して判断すべき
→その判断に際しては、当該手当の名称や算定方法だけでなく、当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない
Bについて
労基法第37条(割増賃金)で、「通常の労働時間」の賃金が割増賃金の基礎となると規定されているので、そこから「通常の労働時間の賃金」が選べたと思います。
問2 B ☆☆☆(どうにか解ける)
Cについて
「特定の手当」が「割増賃金」だと裁判で主張するには何が必要か?と考えてみる。
例えば、選択肢⑫のように、情報提供や説明の内容だけでは弱いような・・・。また、⑮のように我が国社会の一般的状況を持ち出してもなんとなく説得力に欠ける。
と考えてみると、ここは、⑭「当該労働契約の定める賃金体系全体における当該手当の位置付け」が選べたのでは?と思います。
問2 C ★★★(でも難しいです)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
お疲れさまでした。頭を休ませてくださいね
R4-001
R3.8.23 頑張りました!
試験から一夜明けました。
本当に頑張りましたね!
私も去年の試験から1日も休まず、毎日コツコツ記事をアップできました。
いつも読んでくださっている皆様のおかげです。ありがとうございます。
今年の試験の振り返りも書いていきますので、落ち着いたら読みに来てくださいね。
まずは頭を休めて、気分転換してください。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします

