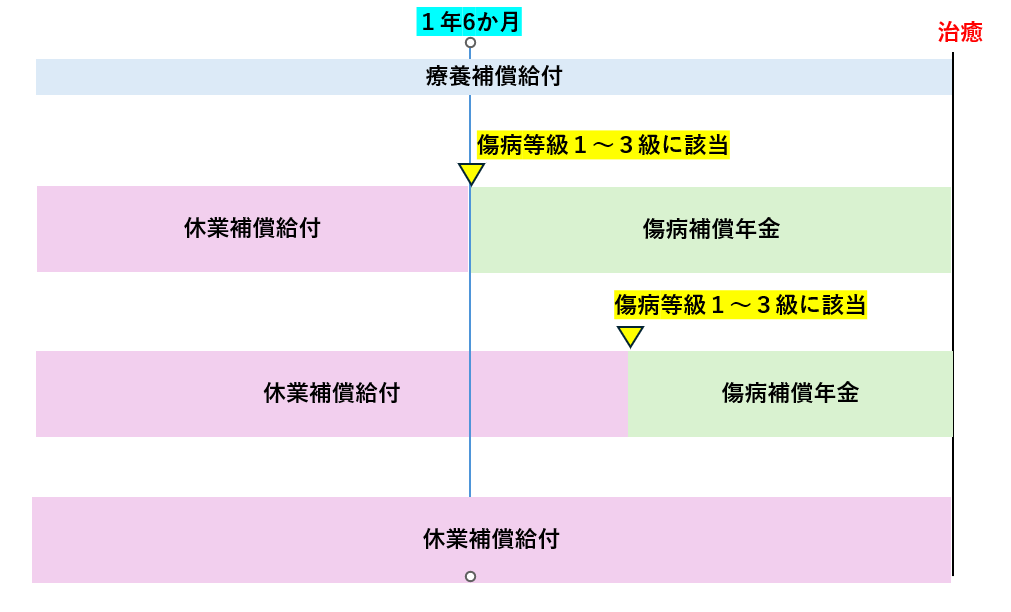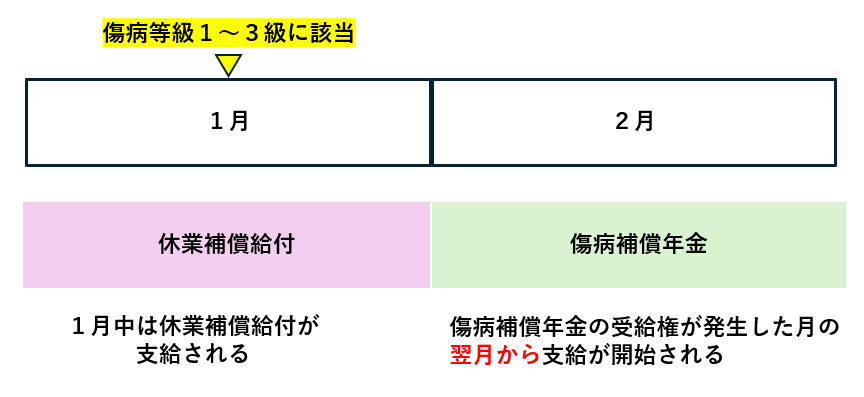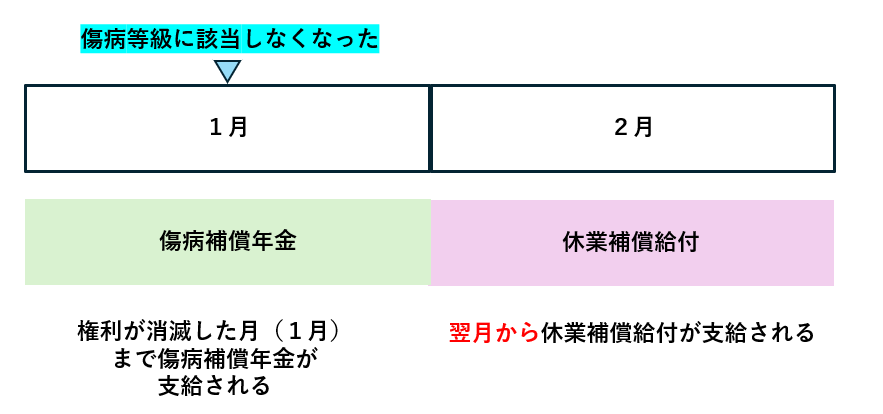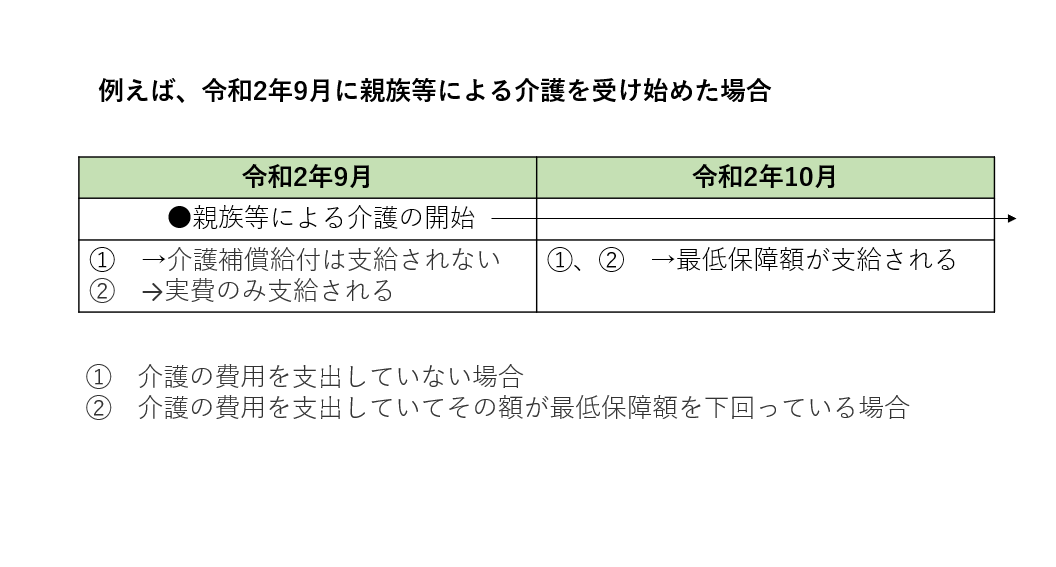合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
労災保険法「傷病補償年金」
R8-142 01.13
ポイントをお話しします|傷病補償年金
最初に、傷病補償年金について下の図①でイメージしましょう。
では、条文を読んでみましょう
法第12条の8第3項 ③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級~3級)に該当すること。
法第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。 |
★傷病補償年金の額
1級 | 給付基礎日額の313日分 |
2級 | 277日分 |
3級 | 245日分 |
★傷病補償年金の支給についてポイント
傷病補償年金は、他の保険給付と違い、支給の請求は不要です。
支給の決定は、請求によってではなく、政府の職権で行われます。支給事由に該当したときは、所轄労働基準監督署長が支給決定を行います。
では、過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
①【H24年出題】 〇
どちらも「治る前」の給付で、療養補償給付は治療のため、傷病補償年金は所得補償のためのものですので、併給される場合があります。
②【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
②【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも所得補償ですので、併給されません。
休業補償給付から傷病補償年金への切り替えについて下の図②でイメージしましょう
➂【H29年出題】
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】
➂【H29年出題】 〇
傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定されます。
(則第18条第2項)
④【H29年出題】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

【解答】
④【H29年出題】 〇
療養開始後1年6か月を経過した日に治っていない労働者は、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければなりません。所轄労働基準監督署長が支給事由に該当するか否か認定するためです。
(則第18条の2第1項)
※療養の開始後1年6か月を経過しても治っておらず、傷病補償年金の支給決定を受けるに至っていない場合
→ 毎年1月1日から同月末日までの間に休業補償給付を請求する際に、合わせて、「傷病の状態に関する報告書」も所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(則第19条の2)
⑤【H20年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

【解答】
⑤【H20年出題】 ×
障害の程度が重くなったときは、「変更についての請求書を提出する必要がある」の部分が誤りです。
障害の程度が、軽くなったり重くなったりして、傷病等級に変更があったときは、「請求」ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で変更に関する決定が行われます。
条文を読んでみましょう
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 則第18条の3 (傷病補償年金の変更) 所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。 |
⑥【H29年出題】
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、「傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない」です。
⑦【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅します。
ただし、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。
傷病補償年金から休業補償給付の切り替えについて、下の図③でイメージしましょう。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「休業補償給付の支給要件」
R8-141 01.12
基本をお話しします|休業補償給付が支給される要件
今回のテーマは「休業補償給付」の支給要件です。
業務上の傷病により、仕事に就けないときに支給されます。
条文を読んでみましょう
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
※部分算定日について ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、最高限度額の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |
<部分算定日の算定式>
(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×100分の60
下の図①でイメージしましょう
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】
①【R7年出題】 ×
休業給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用される時期についての問題です。
療養を開始した日から起算して「3年」ではなく「1年6か月」を経過した日以後の日から年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。
年齢については、「四半期の初日」で適用されるのもポイントです。
下の図②でイメージしましょう
②【R5年選択式】
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。
<選択肢>
① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑭ 賃金 ⑮ 通院
⑯ 能力喪失 ⑲ 療養

【解答】
<A> ⑲ 療養
<B> ⑦ 4
<C> ②100分の60
➂【H30年出題】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

【解答】
➂【H30年出題】 〇
休業の初日から第3日目までの期間は、休業補償給付は支給されません。
そのため、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主は、労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。
なお、複数業務要因災害と通勤災害については、労働基準法の補償責任が規定されていませんので、事業主による休業補償は義務付けられていません。
④【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
「休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付は支給される」とされています。
(昭58.10.13最高裁判所第一小法廷)
⑤【R7年出題】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
④の問題と同じです。
出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合でも、休業補償給付は支給されます。
⑥【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
休業補償給付は、「賃金を受けない日」について支給されます。
「賃金を受けない日」には、「全部を受けない日」と「一部を受けない日」があります。
「一部を受けない日(=一部を受ける日)」は、「全部労働不能」の場合は、「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」とされています。
問題文のように、「所定労働時間の全部労働不能」の労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合は、「賃金を受けない日」に当たりませんので、休業補償給付は支給されません。
⑦【H30年出題】※改正による修正あり
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

【解答】
⑦【H30年出題】 〇
問題文に「療養開始後1年6か月未満」とありますので、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がない前提です。
「部分算定日」の休業補償給付の額は、(「休業給付基礎日額」-「部分算定日に対して支払われる賃金の額」)×100分の60で計算します。
⑧【R2年出題】
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

【解答】
⑧【R2年出題】 ×
・休業補償給付の額は、(100%-20%)×100分の60=48%
・休業特別支給金の額は、(100%-20%)×100分の20=16%
となります。
すべて合わせても100%になりません。
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
図①
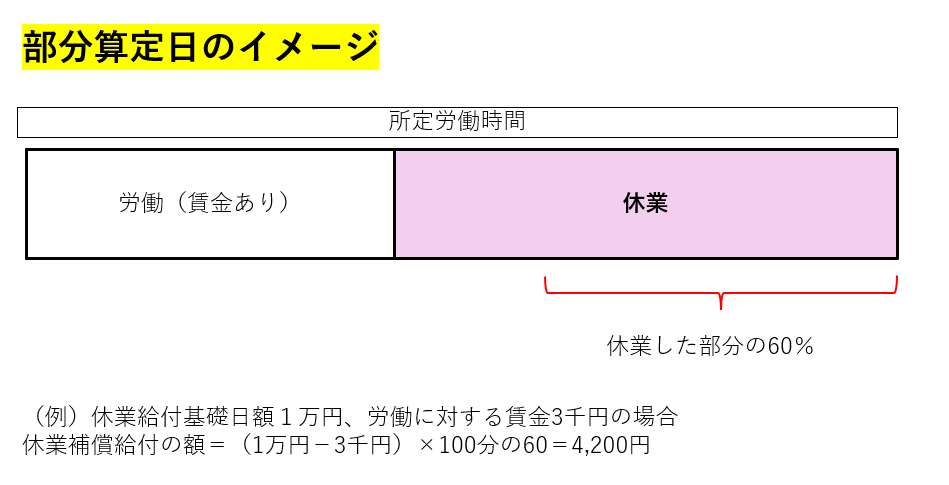
図②
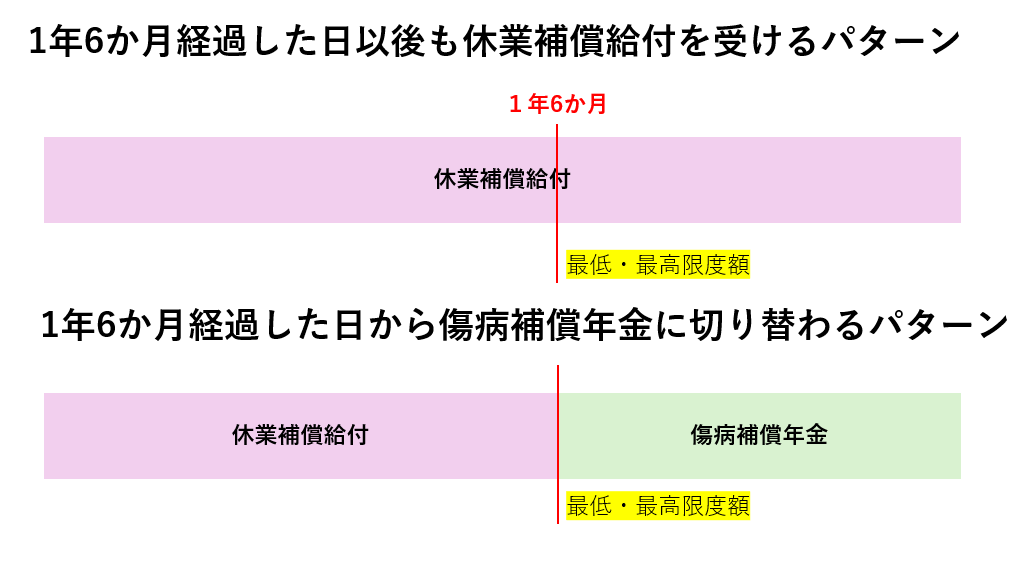
YouTubeはこちらからどうぞ!
労災保険法「介護補償給付」
R8-080 11.12
介護補償給付の基本問題
介護補償給付が支給される要件を確認しましょう。
① 一定の障害の状態に該当していること
② 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること
➂ 病院または診療所に入院していないこと・障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限る)等に入所していないこと
条文を読んでみましょう
法第12条の8第4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (1) 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) (2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 ※厚生労働大臣が定める施設(則第18条の3の3) 1 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又 は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの 3 親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であって当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの (3) 病院又は診療所に入院している間 |
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。

①【R7年出題】 ×
介護補償給付の対象になる「常時介護」、「随時介護」を要する障害の状態は、厚生労働省令で定められています。
常時介護 | ① 精神神経の障害で常時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で常時介護を要するもの ➂ ①、②と同程度の介護を要する状態にあるもの |
随時介護 | ① 精神神経の障害で随時介護を要するもの ② 胸腹部臓器の障害で随時介護を要するもの ➂ 障害等級1級又は傷病等級1級に該当し、常時介護を要する障害の状態に該当しないもの |
両眼を失明するととともに、障害または傷病等級第1級・第2級の障害を有する場合は、常時介護の③に該当し、常時介護を要する状態となります。
問題文は、「他に障害を負っているか否かにかかわらず」の部分が誤りです。
(則別表第3)
②【R7年出題】
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
介護補償給付は、「障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する」労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって「厚生労働省令で定める程度のもの」により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに支給されます。
「障害補償一時金」の支給を受けた労働者が、「加齢」で介護を要する状態となっても、介護補償給付は受けられません。
➂【R7年出題】
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
病院又は診療所に入院し、介護を受けている間は、介護補償給付は支給されません。また療養補償給付を受ける権利は、介護補償給付の支給要件ではありません。
④【R7年出題】
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
障害者支援施設に入所し、生活介護を受けている間は、介護補償給付を受けることはできません。
⑤【H24年出題】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

【解答】
⑤【H24年出題】 〇
特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。
⑥【R7年出題】
介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
介護補償給付は、介護の費用として支出した額(実費)が支給されます。
ただし、上限と最低保障があります。
「最低保障」が適用される要件は、「親族等による介護を受けた」ことです。
問題文のように、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合(=介護の費用を支出していない場合)であって、親族による介護を受けた日があるときは、最低保障額が支給されます。
最低保障額は、障害の程度に応じて定額とされていて、常時介護の場合は一律85,490円、随時介護の場合は42,700円です。
(則第18条の3の4)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「休業補償給付」
R8-051 10.14
休業補償給付の基本問題
今回は、休業補償給付についてみていきます。
休業補償給付について条文を読んでみましょう。
法第14条 ① 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、 1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、(以下、今回は省略します) ② 休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、①の額に別表第1第1号から第3号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第1号から第3号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。 |
②について
国民年金・厚生年金保険の年金は、業務上、業務外問わず支給されます。
そのため、同一の事由で、労災保険の年金と「国民年金・厚生年金の年金」が支給されることがあります。
その場合は、どちらも100%支給されるのではなく、労災保険の年金が減額されます。どちらからも100%支給されると、被災前の賃金よりも高額になるためです。
「休業補償給付」を受ける労働者が、同一事由で障害基礎年金、障害厚生年金を受ける際も、休業補償給付が減額されます。その際、休業補償給付は、「障害厚生年金又は障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率」を乗じて減額された額となります。
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「3年」ではなく「1年6か月」です。
休業補償給付は、休業給付基礎日額を用いて算定します。
療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後、休業給付基礎日額には年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。
療養開始後1年6か月を経過した日から傷病補償年金に切り替わる場合がありますが、その場合は当初から年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されます。それに合わせて、引き続き休業補償給付を受ける場合にも、1年6か月経過した日以後は、年齢階層別の最低限度額と最高限度額が適用されることになります。
②【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】
②【H30年出題】×
「休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、休日、出勤停止の懲戒処分等のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても、支給される。」とされています。
(最高裁判所第一小法廷 昭和58.10.13)
➂【R7年出題】
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
②の問題と同じです。出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない日でも休業補償給付は支給されます。
④【R7年出題】
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。

【解答】
④【R7年出題】 〇
休業補償給付の額は減額されますが、その際、「障害厚生年金又は障害基礎年金」と傷病補償年金との調整について定める率を用います。
なお、この減額に当たっては、調整された休業補償給付の額と厚生年金等の額の合計が、調整前の休業補償給付の額より低くならないように調整限度額が設けられています。
(令第1条第1項)
ちなみに、厚生年金、国民年金は減額されず、全額支給されます。
⑤【R7年出題】
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
休業特別支給金の支給の申請は、「休業補償給付の請求後」ではなく、「休業補償給付の請求と同時に」行わなければなりません。
(特別支給金則第3条第5項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「適用」
R8-033 9.26
労災保険の適用について
労災保険は、労働者を使用する事業に適用されます。
条文を読んでみましょう。
第3条 ① 労災保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 ② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
今回は、「出向の場合」、「労働者派遣の場合」、「就労継続支援を行う事業場の場合」、「インターンシップの実習」、「公立小学校教諭に臨時的任用された場合」の労災保険の適用をみていきます。
問題を解いてみましょう
①【R7年出題】
出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「常に出向先事業に係る保険関係による」が誤りです。
出向労働者に係る保険関係が、出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行なった契約ならびに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定することとされています。
(昭和35.11.2基発第932号)
②【R7年出題】
派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
労災保険は、労働者を使用する事業(=「労働契約関係」にある事業)を適用事業とします。そのため、派遣労働者については、労働契約関係にある「派遣元事業主」が労災保険の適用事業となります。
(昭61.6.30基発383号)
➂【R7年出題】
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者で、「雇用契約が有る」場合は労働基準法上の労働者ですので、労災保険が適用されます。しかし、「雇用契約が無い」場合は労災保険法は適用されません。
(平18.10.2障障発第1002003号)
④【R7年出題】
インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。

【解答】
④【R7年出題】 ×
インターンシップの実態によっては、労災保険が適用されることがあります。
一般に、インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条の労働者に該当しません。
しかし、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられますので、労災保険が適用されます。
(平9.9.18基発第636号)
⑤【R7年出題】
育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

⑤【R7年出題】 ×
非現業部分の地方公務員には「地方公務員災害補償法」、非常勤職員には、原則として、地方公務員災害補償法に基づいて定められる災害補償の条例が適用されます。
(法第3条第2項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労働者災害補償保険法「二次健康診断等給付」
R8-017 9.10
二次健康診断等給付の基本10問
・労働安全衛生法に基づく定期健康診断等のうち、直近のものを「一次健康診断」といいます。
・一次健康診断で、脳血管疾患・心臓疾患の発生にかかわる一定の項目のいずれにも異常の所見が認められる労働者が対象です。
・二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があります。
・二次健康診断等給付は、労働者の請求に基づいて行われます。
では、条文を読んでみましょう。
法第26条 ① 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 ② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 (1) 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(前項に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。以下「二次健康診断」という。) (2) 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。) ③ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。 |
過去問をどうぞ!
①【R7年出題】
二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。

【解答】
①【R7年出題】 〇
二次健康診断等給付は、「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院)又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所」において行うとされています。
(則第11条の3、第18条の19)
②【R7年出題】
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
当該検査項目の「いずれかに」ではなく、「いずれの項目にも」異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われます。
③【H30年出題】
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
「既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する」と認められる場合は、二次健康診断等給付は行われません。
④【H30年出題】
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
④【H30年出題】 〇
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければなりません。
健診給付病院等を「経由」することと、「所轄都道府県労働局長」に提出することがポイントです。所轄労働基準監督署長ではありませんので、注意しましょう。
(則第18条の19)
⑤【R7年出題】
二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者一人につき、1年度内1回に限り支給される。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
二次健康診断が受けられるのは、1年度内1回限りです。
⑥【R7年出題】
二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
特定保健指導は、医師又は保健師による面接によって行われます。内容は、「栄養指導、運動指導、生活指導」です。
⑦【H30年出題】
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

【解答】
⑦【H30年出題】 ×
特定保健指導は、「医師または歯科医師」ではなく、「医師又は保健師」による面接によって行われます。
⑧【H30年出題】
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。

【解答】
⑧【H30年出題】 〇
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われません。
⑨【H30年出題】
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。

【解答】
⑨【H30年出題】 〇
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、「医師の意見をきかなければならない。」とされています。
(法第27条、則第18条の17)
⑩【R7年出題】
特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。

【解答】
⑩【R7年出題】 〇
特別加入者は、労働安全衛生法の健康診断(一次健康診断)の対象にならないため、二次健康診断等給付の対象にもなりません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(労災保険法)から学ぶ
R8-005 8.29
遺族補償年金の遺族の障害要件と社会復帰促進等事業
令和7年の選択式で出題された 「遺族補償年金の遺族の障害要件」と
「遺族補償年金の遺族の障害要件」と 「社会復帰促進等事業」をみていきましょう。
「社会復帰促進等事業」をみていきましょう。
 遺族補償年金の遺族の障害要件について
遺族補償年金の遺族の障害要件について
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」で、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。
ただし、「妻」以外は、労働者の死亡の当時、「年齢要件」か「障害要件」を満たしていることが必要です。
「障害要件」は、過去に出題されています。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】
【H19年出題】 〇
遺族の要件の一つである「厚生労働省令で定める障害の状態」のポイントは、「第5級以上」、「労働が高度の制限を受ける」の部分です。
なお、この規定は、複数事業労働者遺族年金にも準用されます。
(則第15条)
では、令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の < A >に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、< B >が高度の制限を受けるか、若しくは< B >に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
<選択肢>
① 第1級 ② 第5級以上 ③ 第8級以上 ④ 第12級以上
⑤ 日常生活 ⑥ 日常生活又は社会生活 ⑦ 労働 ⑧ 労働又は社会生活

【解答】
【R7年選択式】
<A> ② 第5級以上
<B> ⑦ 労働
 「社会復帰促進等事業」について
「社会復帰促進等事業」について
「長期家族介護者援護金」と「判例」からの出題です。
ヒントになる過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われるものであるが、その事務は所轄労働基準監督署長が行う。

【解答】
①【H22年出題】 〇
特別支給金の支給の事務は所轄労働基準監督署長が行います。
条文を読んでみましょう。
則第1条第3項 労働者災害補償保険等関係事務のうち、保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が行う。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める者を所轄労働基準監督署長とする。 (1) 事業場が2以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合 その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 (2) 当該労働者災害補償保険等関係事務が複数業務要因災害に関するものである場合 生計維持事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長 |
②【H29年出題】
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

【解答】
②【H29年出題】 ×
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨です。
(平15.9.4最高裁判所第一小法廷 中央労基署長(労災就学援護費)事件)
では、令和7年の問題をどうぞ!
【R7年選択式】
労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が< A >以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
<選択肢>
① 3年 ② 5年 ③ 7年 ④ 10年

【解答】
<A> ④ 10年
★「長期家族介護者援護金」の内容まで暗記するのは大変です。
過去問でもカバーできません。
「長期」をヒントに考えると、「10年かな?」と考えられると思いますが、難しいです。
【R7年選択式】
最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は,労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を< A >するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが,具体的に支給を受けるためには,< B >に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、< B >の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、< B >の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
<選択肢>
① 確保 ② 代替 ③ 補完 ④ 付加
⑤ 厚生労働大臣 ⑥ 都道府県労働局長 ⑦ 労働基準監督署長
⑧ 労働者災害補償保険審査官

【解答】
<A> ③ 補完
<B> ⑦ 労働基準監督署長
(平15.9.4最高裁判所第一小法廷 中央労基署長(労災就学援護費)事件)
判例を一字一句覚える必要はありませんが、文脈でヒントを探してみましょう
<A>について
法第2条の2で、「労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。」と定められています。
主たる事業は「保険給付」で、「社会復帰促進等事業」は附帯する事業として行うことができるという位置づけです。
試しに、選択肢を入れてみると、「保険給付を確保するため」、「保険給付を代替するため」、「保険給付を付加するため」、どれも社会復帰促進等事業の説明としてはしっくりきません。「補完」を入れると、「保険給付を補完するため」となり、ぴったりします。
<B>について
先ほどの条文で読みましたように、所轄労働基準監督署長は、「保険給付(二次健康診断等給付を除く。)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務」を行います。
その条文から、「労働基準監督署長」を選ぶことができますが、問題文の中に「保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定している」もヒントになります。「保険給付と同様の手続」という部分で、「労働基準監督署長」を選ぶことができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「特別支給金」
R7-329 07.23
休業特別支給金の額と支給申請
「特別支給金」は、「社会復帰促進等事業」の中の、「被災労働者等援護事業」として行われていて、「保険給付」の上乗せとして支給されます。
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」があります。
下の図で特別支給金をイメージしましょう。
今回のテーマは「休業特別支給金」です。
「休業特別支給金」について条文を読んでみましょう。
特別支給金規則第3条 (休業特別支給金) ① 休業特別支給金は、労働者が業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額とする。(以下省略) ② 省略 ③ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ④ 省略 ⑤ 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。 ⑥ 休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。 |
★特別支給金の申請期限について
・休業特別支給金 → 2年以内
・それ以外 → 5年以内
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】※改正による修正あり
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
特別支給金の申請は、原則として関連する保険給付の請求と同時に行わなければなりません。
②【R2年出題】
休業特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業として行われているものであることから、その申請は支給の対象となる日の翌日から起算して5年以内に行うこととされている。

【解答】
②【R2年出題】 ×
休業特別支給金の申請は支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行うこととされています。
③【H28年出題】
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

【解答】
③【H28年出題】 ×
休業特別支給金の額は、1日につき「算定基礎日額」ではなく、「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額です。
★「給付基礎日額」と「算定基礎日額」の違いに注意しましょう。
・「給付基礎日額」について
→ 保険給付の計算のもとになります。
給付基礎日額は、原則として「労働基準法の平均賃金」に相当する額です。
「臨時に支払われた賃金」、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」、「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入されません。
・「算定基礎日額」について
→ 「ボーナス特別支給金」の計算のもとになります。
「算定基礎年額」は、「負傷又は発病の日以前1年間に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額です。
ただし、「特別給与の総額」が、給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額が算定基礎年額となります。
また、「150万円」を超える場合には、「150万円」となりますので、算定基礎年額の上限は150万円です。
※「臨時に支払われた賃金」は、給付基礎日額にも算定基礎年額の計算にも入りません。
なお、「算定基礎日額」は、算定基礎年額÷365です。
④【H28年出題】
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
④【H28年出題】 〇
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならないとされています。
また、特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければなりません。
(特別支給金規則第12条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「介護補償給付」
R7-322 07.16
介護(補償)等給付の支給額
★介護補償給付の支給要件を確認しましょう。
・ 障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有すること
・ 厚生労働省令で定める程度の障害であること
→第1級は「すべて」、第2級は「精神神経・胸腹部臓器の障害」のみ
・ 常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること
なお、以下の施設に入所している間は、介護補償給付は支給されません。
・ 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
・ 病院又は診療所に入院している間
など
(法第12条の8第4項、則第18条の3の2)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。 |
★「常時介護」の場合の支給額をみていきましょう。(則第18条の3の4)
「介護の費用として支出した額」(実費)が支給されるのが原則です。
ただし、上限と最低保障額が設定されています。
| ①介護の費用を支出した | 実費 (上限177,950円) |
親族等の介護を受けている | ②介護の費用を支出していない | 最低保障額 85,490円 |
③介護の費用を支出したが、 85,490円を下回る |
※「最低保障額」が適用されるのは、親族等(親族、友人、知人)の介護を受けている場合です。
※「随時介護」の場合は、上限88,980円、最低保障額42,700円です。
★介護補償給付は「月単位」で支給されます。
「支給すべき事由が生じた月」から「支給すべき事由が消滅した月」の各月について支給されます。
ただし、「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されません。
・上の表の②の場合
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(その翌月から支給されます)
・上の表の③の場合
「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額が適用されないので、「実費」が支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、 < A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行われる。

【解答】
①【H19年選択式】
<A> 常時又は随時
<B> 当該労働者
②【H23年出題】
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】
②【H23年出題】 〇
条文を穴埋めでチェックしましょう
第19条の2
介護補償給付は、< A >を単位として支給するものとし、その月額は、 < B >介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して< C >が定める額とする。
・・・・・・・・・・・
<A> 月
<B> 常時又は随時
<C> 厚生労働大臣
③【H25年出題】
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】
③【H25年出題】 〇
「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません。
そのため、親族等による介護を受けたとしても、介護に要する費用として支出された額が労災保険法施行規則に定める額に満たない場合は、当該介護に要する費用として支出された額(実費)が支給されます。
④【R2年出題】
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】
④【R2年出題】 ×
「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」は誤りです。
「その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき」は、最低保障額が支給されます。(支給すべき事由が生じた月は支給されません。)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「派遣労働者」
R7-288 06.12
派遣労働者の労災についての出題
「派遣労働者」は、「派遣元事業主」とは「労働契約関係」にあり、「派遣先事業主」とは「指揮命令関係」にあります。
「派遣労働者」の労災保険は、労働契約関係にある派遣元事業主が労災保険の適用事業となります。
「労働者災害補償保険法に関しては、同法第3条第1項は「労働者を使用する事業を適用事業とする」と規定しており、この「使用する」は労働基準法等における「使用する」と同様労働契約関係にあるという意味に解されており、また、労働基準法上の災害補償責任が派遣元事業主に課される以上、労災保険法と労働基準法との関係を考慮すれば、労災保険法の適用についても同様に取り扱い、派遣元事業主を労災保険の適用事業とすることが適当である。」とされています。
(昭61.6.30基発第383号)
さっそく過去問をどうぞ!
①【H22年選択式】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が< A >との間の労働契約に基づき< A >の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき< B >の支配下にある場合には、一般に< C >があるものとして取り扱われる。
(選択肢)
① 業務起因性 ② 業務遂行性 ③ 条件関係 ④ 相当因果関係
⑤ 派遣先事業主 ⑥ 派遣先責任者 ⑦ 派遣元事業主
⑧ 派遣元事業主及び派遣先事業主
⑨ 派遣元事業主又は派遣先事業主
⑩ 派遣元責任者

【解答】
①【H22年選択式】
<A> ⑦ 派遣元事業主
<B> ⑤ 派遣先事業主
<C> ② 業務遂行性
(昭61.6.30基発第383号)
②【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。

【解答】
②【R1年出題】 〇
①の選択式と同じ問題です。
(昭61.6.30基発第383号)
③【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。

【解答】
③【R1年出題】 〇
派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるとされています。
(昭61.6.30基発第383号)
④【R1年出題】
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。

【解答】
④【R1年出題】 〇
<派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たって>
・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となる
・したがって、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となる
とされています。
(昭61.6.30基発第383号)
⑤【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
・保険給付請求書の事業主の証明は派遣元事業主が行います。
・派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写を当該保険給付請求書に添付させることとされています。
(昭61.6.30基発第383号)
⑥【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

【解答】
⑥【R1年出題】 ×
派遣労働者の保険給付の請求に当たり、保険給付請求書の事業主の証明は「派遣先」ではなく「派遣元事業主」が行うこととされています。
(昭61.6.30基発第383号)
⑦【H30年出題】
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

【解答】
⑦【H30年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第46条 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第35条第1項に規定する団体、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主又は船員職業安定法に規定する船員派遣の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「遺族補償年金」
R7-267 05.22
労災「遺族補償年金」の失権事由
遺族補償年金の失権事由をみていきましょう。
ちなみに、遺族補償年金には、「転給」の制度があります。
例えば、労働者が死亡し、要件を満たす妻と子がいる場合は、妻と子が受給資格者となります。受給資格者内の順位は①妻、②子で、遺族補償年金を受ける受給権者は、最先順位者の妻となります。
その後、妻が失権した場合、次順位者の子が受給権者となります。
では、失権について条文を読んでみましょう。
法第16条の4 ① 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。(=養子縁組の解消) (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 ② 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。 |
「妻」以外は、労働者の死亡当時、「年齢」要件か「障害」要件を満たしている必要があります。
例えば、年齢要件のみで受給資格者となった子の場合は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。
また、子が労働者の死亡の当時から引き続き障害状態にあり、「障害」要件を満たしている場合は、年齢は関係ありません。
障害状態でなくなった場合は失権しますが、障害状態でなくなっても年齢要件を満たしている場合(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき)は失権しません。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利は、婚姻したときは消滅します。婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、消滅します。
②【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、直系血族又は直系姻族である者の養子となったときは、消滅する。

【解答】
②【H23年出題】 ×
遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族である者の養子」となったときは、消滅しません。
③【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】
③【H28年出題】 〇
自分の伯父は傍系血族です。遺族補償年金を受ける権利は、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子」となったときは消滅しますので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
④【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

【解答】
④【H23年出題】 ×
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。
⑤【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

【解答】
⑤【H23年出題】 ×
障害の状態にあった祖父母がその障害の状態がなくなったときでも、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合(年齢要件を満たしている場合)は、消滅しません。
⑥【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】
⑥【H23年出題】 ×
障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときでも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき(年齢要件を満たしているとき)は、消滅しません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「休業補償給付」
R7-248 05.03
休業補償給付の支給額
さっそく「休業補償給付」について条文を読んでみましょう。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |
<部分算定日の例をみてみましょう>
午 前 | 午 後 |
通院のため休業 | 勤 務 |
給付基礎日額 → 12,000円
午後の労働に対する賃金 → 5,000円
休業補償給付の額
=(給付基礎日額-部分算定日に対して支払われる賃金の額)×100分の60
=(12,000円-5,000円)×100分の60
=4,200円
※複数事業労働者が、一方の事業場で休業し、他方の事業場で年次有給休暇を取得した場合なども部分算定日に該当します。
<部分算定日の休業補償給付のポイント!>
・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)×100分の60
★「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合
→ (最高限度額を適用しない給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)×100分の60
★控除して得た額が最高限度額を超える場合
→ 最高限度額×100分の60
過去問をどうぞ!
①【R5年選択式】
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。
(選択肢)
① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失
⑪ 療養

【解答】
①【R5年選択式】
<A> ⑪ 療養
<B> ⑦ 4
<C> ② 100分の60
②【H30年出題】※改正による修正あり
業務上の傷病により、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

②【H30年出題】 〇
「療養開始後1年6か月」とは
→ 療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後は、「年齢階層別の最高限度額」が適用されます。
療養開始後1年6か月未満の場合は、「年齢階層別の最高限度額」は適用されませんので、「休業給付基礎日額から当該部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60」に相当する額となります。
③【R2年出題】
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。

【解答】
③【R2年出題】 ×
例えば、給付基礎日額が10,000円、所定労働時間の労働した時間に対して支払われる賃金が給付基礎日額の20%(2,000円)の場合で考えてみましょう。
休業補償給付=(10,000円−2,000円)×100分の60=4,800円
休業特別支給金=(10,000円−2,000円)×100分の20=1,600円
休業補償給付と休業特別支給金とを合わせても、給付基礎日額の100%にはなりません。
④【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
④【H30年出題】 〇
休業補償給付は、「賃金を受けない日」について支給されます。
「賃金を受けない日」は、以下のような日をいいます。
全部労働不能の場合 | 平均賃金の60%未満の金額しか受けない日 |
一部労働不能の場合 | ・労働不能の時間について全く賃金を受けない日 ・「平均賃金と実労働時間に対する賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日 |
問題文は、「全部労働不能」で休業中に「平均賃金の6割以上」の金額が支払われているので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため、休業補償給付は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「支給制限と費用徴収の違い」
R7-239 04.24
特別加入者に対する支給制限
労災保険の特別加入者は次の3種類です。
■中小事業主等
■一人親方その他の自営業者・特定作業従事者
■海外派遣者
特別加入者の「支給制限」について条文を読んでみましょう。
法第34条第1項第4号 中小事業主及びその事業に従事する者の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が中小事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。
法第35条第1項第7号 一人親方その他の自営業者・特定作業従事者の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
法第36条第1項第3号 海外派遣者の事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
ポイント!
「労働者」との違いに注意しましょう。
★労働者の場合
事業主が一般保険料(=労働者の保険料)を納付しない期間中に生じた事故については、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を「事業主から徴収することができる。」とされています。労働者の保険給付の支給を制限するのではなく、事業主から費用徴収します。
★特別加入者の場合
特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、費用徴収ではなく、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」と支給制限が行われます。
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】(※問題文修正しています)
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。
ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。
②【H26年出題】(※問題文修正しています)
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではなく、支給制限が行われます。
ちなみに、支給制限の対象になるのは、「督促状の指定期限の翌日以後に生じた事故」です。
③【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
③【R3年出題】 ×
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定され、その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
事業主からの費用徴収ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「特別加入者」
R7-238 04.23
特別加入者「一人親方等」について
労災保険には「特別加入」の制度があります。
特別加入には大きく3つの種類があります。
・中小事業主等
・一人親方等、特定作業従事者
・海外派遣者
今回は、「一人親方等、特定作業従事者」についてみていきます。
★一人親方等が労災保険に特別加入する場合は、一人親方等の団体が手続きを行います。
一人親方等 |
↓ |
一人親方等の団体 |
↓ |
所轄都道府県労働局長(所轄労働基準監督署長経由) |
・一人親方等その他の自営業者とは、「厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者」と「その者が行う事業に従事する者」です。
厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりです。(則第46条の17)
(1) 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など) (2) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(大工、左官、とび職人など) (3) 漁船による水産動植物の採捕の事業((7)に掲げる事業を除く。) (4) 林業の事業 (5) 医薬品の配置販売の事業 (6) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業(廃品回収業) (7) 船員法第1条に規定する船員が行う事業 (8) 柔道整復師が行う事業 (9) 高年齢者の雇用の安定等に関する法律に規定する創業支援等措置に基づき、高年齢者が行う事業 (10) あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 (11) 歯科技工士が行う事業 (12) 特定受託事業者が「業務委託事業者」から業務委託を受けて行う事業又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの(特定フリーランス事業) |
ポイント!
「特定フリーランス事業」の特別加入について
・令和6年11月1日から対象となっています。
・企業等から業務委託を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)が対象で、業種や職種は問われません。
・「特定作業従事者」とは、厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者です。厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりです。(則第46条の18)
・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業 ・ 特定の農業機械を用いる一定範囲の農作業 ・ 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの 職場適応訓練 事業主団体等委託訓練として行われる作業 ・ 家内労働者又は補助者が行う作業のうちプレス機械を使う加工作業等の特定のもの ・ 労働組合等の常勤役員が行う集会の運営、団体交渉等の労働組合等の活動に係る作業 ・ 介護関係業務に係る作業及び家事支援作業 ・ 芸能の提供の作業または演出・企画の作業 ・ アニメーションの制作の作業 ・ 情報処理システムの設計、開発、管理、監査その他の情報処理に係る作業 |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることはない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
介護作業に加え、「家事支援作業」が新たに特別加入の対象となったのは、平成30年4月です。「家事支援作業」は、家事(炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為)を代行し、又は補助する業務です。
介護作業従事者として特別加入している者は、「介護作業及び家事支援作業」のいずれの作業にも従事するものとして取り扱われます。
そのため、平成29年から介護作業従事者として特別加入している者が、訪問先の家庭で介護者以外の家族の家事支援作業をしているときに火傷し負傷した場合は、業務災害と認められることがあります。
(則第46条の5、平30.2.8基発0208第1号)
②【H30年選択式】
労災保険法第33条第3号及び第4号により、厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者とその者が行う事業に従事する者は特別加入の対象となる。この事業の例としては、< A >の事業が該当する。また、同条第5号により厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者についても特別加入の対象となる。特別加入はこれらの者(一人親方等及び特定作業従事者)の団体が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< B >はその一例に該当する。
(選択肢)
A | ① 介護事業 ② 畜産業 ③ 養蚕業 ④ 林業 |
B | ① 医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者 ② 介護作業従事者 ③ 個人タクシー事業者 ④ 船員法第1条に規定する船員 |

【解答】
②【H30年選択式】
<A> ④ 林業
<B> ③ 個人タクシー事業者
★<B>について
一人親方等・特定作業従事者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者については、「通勤災害」に関する保険給付が適用されません。
<通勤災害が適用されない者>
・ 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー・個人貨物運送業者など)
・ 漁船による自営漁業者
・ 危険有害な農作業(特定農作業・指定農業機械作業)に従事する者
・ 一定規模の農業の事業場において行う危険有害な農作業に従事する者
・ 家内労働に従事する者
(則第46条の22の2)
③【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
③【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態が明確に区別できないため、通勤災害に関する労災保険は適用されません。
②【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されません。
③【H22年出題】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

【解答】
③【H22年出題】 ×
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、通勤災害は適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「治ゆする前の保険給付」
R7-233 04.18
【労災】治ゆ前の保険給付(療養補償給付・休業補償給付・傷病補償年金)
治ゆ前の保険給付の関係を図でイメージしましょう。
ポイント!
「療養補償給付」と「休業補償給付」は併給されます。
「療養補償給付」と「傷病補償年金」は併給されます。
「休業補償給付」と「傷病補償年金」は併給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付は行われない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
療養補償給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで(治ゆするまで)行われます。
傷病の状況が残った場合でも、その症状が安定し、症状が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとされます。
治ゆすると療養補償給付は行われません。ただし、再発した場合は、再び療養補償給付が行われます。
(昭23.1.13基災発第3号)
②【H30年出題】
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
②【H30年出題】 ×
1年ではなく「1年6か月」です。
「傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後「1年6か月」を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級から3級)に該当すること。
(法第12条の8第3項)
③【H24年出題】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。

【解答】
③【H24年出題】 〇
療養補償給付も、休業補償給付も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、休業補償給付は「所得補償」のためのものです。
療養補償給付と休業補償給付は併給される場合があります。
(法第13条、第14条)
④【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
④【H24年出題】 〇
療養補償給付も、傷病補償年金も「治ゆ」する前に支給される給付ですが、療養補償給付は「治療」、傷病補償年金は「所得補償」のためのものです。
療養補償給付と傷病補償年金は併給される場合があります。
(法第12条の8第3項、法第13条)
⑤【H24年出題】
休業補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
法第18条第2項で、「傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。」と規定されています。
休業補償給付は、傷病補償年金と併給されることはありません。
なお、「年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。」とされています。
傷病補償年金の支給事由が生じた場合は、その支給すべき事由が生じた月の末日までは、休業補償給付が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 |
| 傷病補償年金の 支給事由が発生 |
|
休業補償給付 | 休業補償給付 | 傷病補償年金 |
⑥【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはありません。⑤の問題と同じです。
⑦【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合には、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。
8月 | 9月 | 10月 |
| 傷病補償年金の受給権 消滅 |
|
傷病補償年金 | 傷病補償年金 | 休業補償給付 |
⑧【H21年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けられない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

【解答】
⑧【H21年出題】 ×
「政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する」が誤りです。
休業補償給付が支給されるには、労働者の請求が必要です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
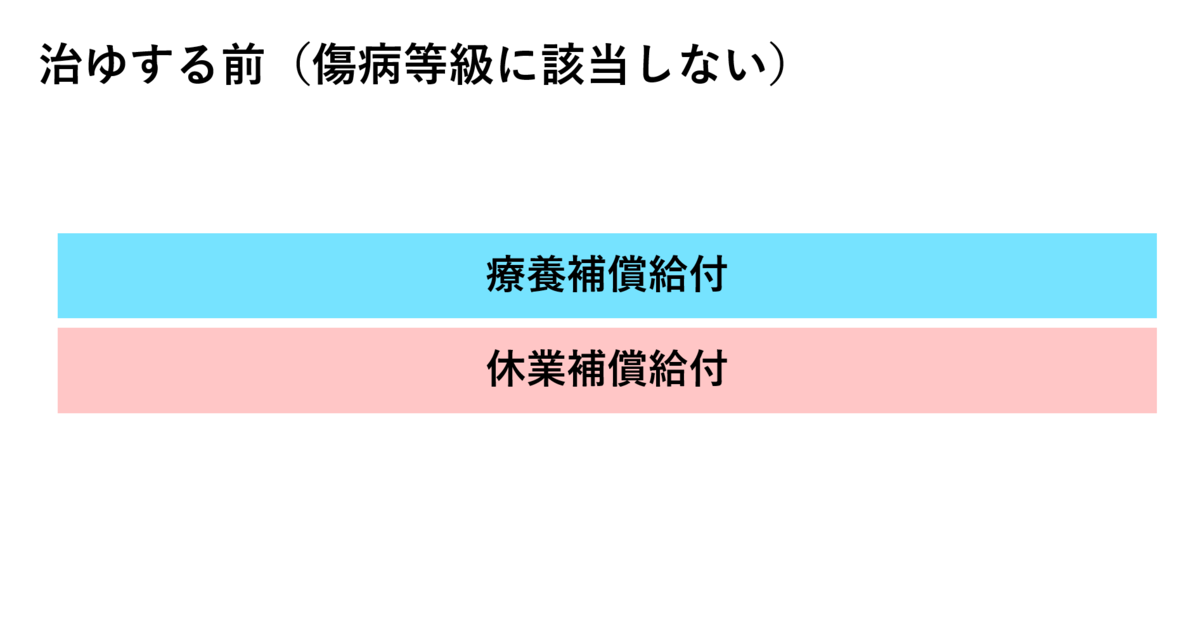
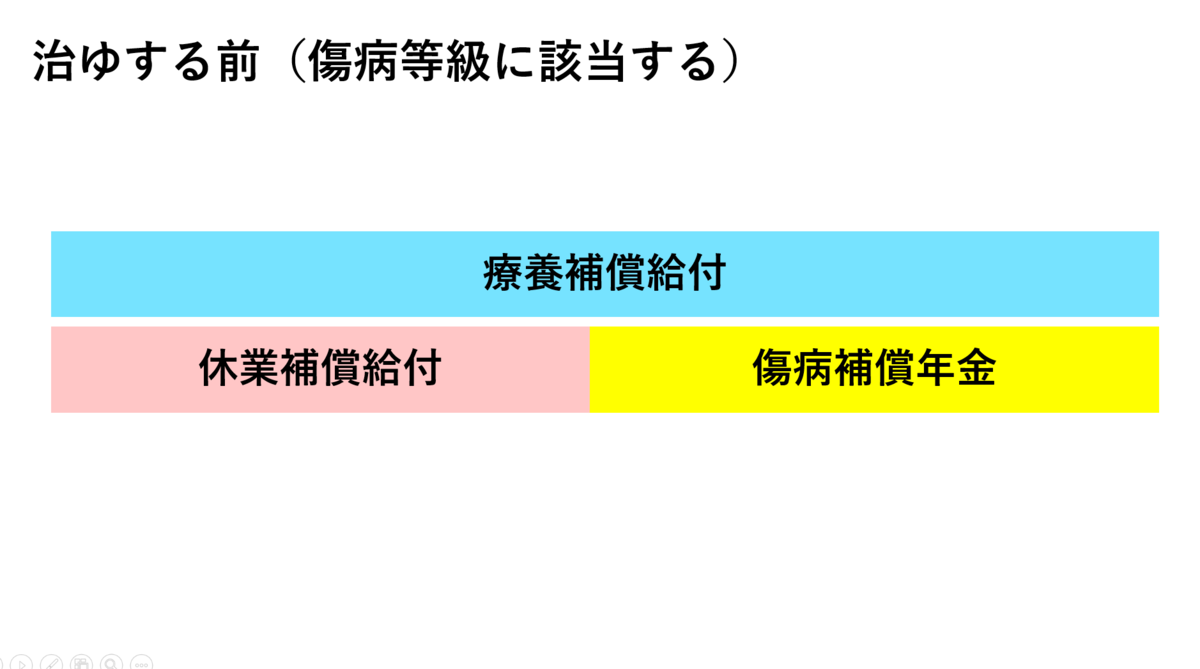
労災保険法「事業主からの費用徴収」
R7-226 04.11
事業主からの特別の費用徴収「故意・重大な過失」の認定
一定の要件に該当する事故については、事業主の注意を促すために、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。
条文を読んでみましょう。
第31条第1項 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 (1) 事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間(政府が認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 (2) 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故 (3) 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故として、正しいものはどれか。
<A> 事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故
<B> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
<C> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
<D> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故
<E> 事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故

【解答】
①【H26年出題】
<A> ×
保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故でも、「重大でない過失」の場合は、費用徴収されません。
<B> ×
一般保険料を納付しない期間中に生じた事故について費用徴収が行われるのは、「督促状に指定する期限後の期間」に限られます。政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故については、費用徴収されません。
<C> 〇
事業主が重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故については、費用徴収が行われます。
<D> ×
「第一種特別加入保険料」を納付しない期間中に生じた事故は、費用徴収の対象になりません。特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第34条)
<E> ×
<D>と同じく、特別加入者の場合は、「支給制限」の対象になります。(法第35条
②【R1年選択式】
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後< A >以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから< B >を経過してもなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。
<選択肢>
<A> ① 3日 ② 5日 ③ 7日 ④ 10日
<B> ① 3か月 ② 6か月 ③ 9か月 ④ 1年

【解答】
<A> ④10日
<B> ④ 1年
ポイント!
① 事業主の故意の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがある事業主であって、その提出を行っていないものについては、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
② 事業主の重大な過失の認定
保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない事業主であって、保険関係成立日以降1年を経過してなおその提出を行っていないものについて、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収の対象とする。費用徴収率は40%とする。
(令5.7.20基発第0720第1号)
③【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】
③【H27年出題】 〇
保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、原則、費用徴収率は100%となります。
(令5.7.20基発第0720第1号)
④【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】
④【H27年出題】 〇
加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定され、原則、費用徴収率は100%となります。
(令5.7.20基発第0720第1号)
⑤【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定され、費用徴収率は40%となります。
(令5.7.20基発第0720第1号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「社会保険との調整」
R7-199 03.15
同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合
同一の事由で労災の年金と国民年金・厚生年金保険の年金が支給される場合のポイントを確認しましょう。
同一の事由により、障害補償年金・傷病補償年金・休業補償給付と 厚生年金保険法の障害厚生年金及び国民年金法の障害基礎年金 が支給される場合
同一の事由により、遺族補償年金と 厚生年金保険法の遺族厚生年金及び国民年金法の遺族基礎年金若しくは寡婦年金 が支給される場合
労災保険の年金給付は「政令で定める率」を乗じて得た額(減額された額)となります。 ※厚生年金保険・国民年金の年金は、全額支給され、減額されません。(労働者が自ら保険料を負担しているからです。)
※通勤災害、複数業務要因災害に関する保険給付も同様に減額されます。 (法別表第1、法第14条第2項) |
過去問をどうぞ!
①【H18年出題】
労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。

【解答】
①【H18年出題】 ×
労災年金と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合は、労災年金は、減額された額が支給されます。
②【H12年出題】
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。

【解答】
②【H12年出題】 〇
年金だけでなく、休業補償給付も、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されます。
(法第14条第2項)
③【H12年出題】
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。

【解答】
③【H12年出題】 〇
労災保険の各種年金給付の額は、「同一の事由」により、厚生年金保険法又は国民年金法の年金を受けることができる場合は、減額されます。
老齢厚生年金、老齢基礎年金を受けることができても、支給事由が異なりますので、労災保険の各種年金給付は減額されません。
④【R5年出題】
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額とする。

【解答】
④【R5年出題】 〇
同一の事由により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となります。
(令第2条)
⑤【R5年出題】
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
障害基礎年金のみを既に受給している者が「新たに」障害補償年金を受け取る場合は、支給事由が異なりますので、障害補償年金の額は、減額されません。
⑥【R5年出題】
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額とする。

【解答】
⑥【R5年出題】 ×
障害基礎年金と遺族補償年金は、支給事由が異なりますので、遺族補償年金は減額されません。
⑦【R5年出題】
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、「0.80」の調整率を乗じて得た額となります。
(令第2条)
⑧【R5年出題】
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
⑧【R5年出題】 ×
遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は減額されません。
⑨【H14年出題】
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。

【解答】
⑨【H14年出題】 ×
厚生年金保険法で、「当該傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付を受ける権利を有する者には、障害手当金を支給しない。」と定められています。(厚生年金保険法第56条第3号)
同一事由による障害手当金は不支給となり、障害補償一時金又は障害一時金は全額支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労災保険法>遺族補償一時金
R7-189 03.05
<労災>遺族補償一時金を受けることができる遺族
今回は、遺族補償一時金を受けることができる遺族についてみていきます。
条文を読んでみましょう。
第16条の7 ① 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 (1) 配偶者 (2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 (3) 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 ② 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。 |
遺族補償一時金を受けることができる遺族の順位を確認しましょう。
① | 配偶者(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく) |
② | 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた 子、父母、孫、祖父母 |
③ | 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった 子、父母、孫、祖父母 |
④ | 兄弟姉妹(生計維持していた・生計維持していなかった関係なく) |
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
<A> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
<B> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
<C> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
<D> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
<E> 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

【解答】
①【R3年出題】
<A> ×
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より「後順位」となります。
配偶者は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、第1順位です。
<B> 〇
生計を維持していた祖父母は、生計を維持していなかった父母より先順位です。
<C> 〇
生計を維持していた孫は、生計を維持していなかった子より先順位です。
<D> 〇
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった子より後順位です。
兄弟姉妹は、「生計維持していた」・「生計維持していなかった」に関係なく、順位は最後です。
<E> 〇
生計を維持していた兄弟姉妹は、生計を維持していなかった父母より後順位です。
②【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
②【H25年出題】 〇
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
③【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることもあります。
<例>
・遺族補償年金を受けていた死亡労働者の妻が再婚し、遺族補償年金が失権。他に遺族補償年金の受給権者がいない場合で
↓
・妻に支給された遺族補償年金の額の合計が1000日未満の場合
↓
・1000日分との差額が遺族補償一時金として妻に支給されます
※身分は、労働者の死亡当時の身分関係で判断されます。再婚したとしても、労働者の死亡当時は労働者の妻だったので、一時金を受ける資格があります。
④【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
④【H18年出題】 ×
遺族補償給付には、「年金」と「一時金」があります。
「年金」は「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」が絶対条件です。
しかし「一時金」は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなくても、対象となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<労災保険法>遺族補償年金
R7-177 02.21
<労災>遺族補償年金の受給資格者と受給権者
労災保険法の「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今回は「遺族補償年金」の対象になる遺族についてみていきます。
遺族補償年金には「受給資格者」と「受給権者」があります。
遺族補償年金を受ける資格のある遺族が「受給資格者」です。受給資格者には、順位があり、その中の最先順位の遺族が実際に年金を受給する「受給権者」となります。
受 給 資 格 者 | ① | 受給権者 |
② |
| |
③ |
| |
④ |
| |
⑤ |
|
なお、遺族補償年金には「転給」の制度があります。
①の遺族が失権した場合は、②の遺族に受給権が移ります。
では、条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項~第3項 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 (3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 (4) 前3号の要件(年齢要件)に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
③ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。 |
ポイント!
・労働者の死亡当時、労働者の収入によって生計を維持していたものが対象です。
・妻以外は、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たしていることが必要です。
★昭40法附則第43条について
・夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹で、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものも遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。
・ただし、その者が60歳に達する月までの間は、遺族補償年金は支給停止されます。(若年停止)といいます。
★受給資格者の順位は次のようになります。
① | 「妻」又は「60歳以上又は障害状態の夫」 |
② | 18歳の年度末までの間にある又は障害状態の子 |
③ | 60歳以上又は障害状態の父母 |
④ | 18歳の年度末までの間にある又は障害状態の孫 |
⑤ | 60歳以上又は障害状態の祖父母 |
⑥ | 18歳の年度末までの間にある又は60歳以上又は障害状態の兄弟姉妹 |
⑦ | 55歳以上60歳未満の夫 |
⑧ | 55歳以上60歳未満の父母 |
⑨ | 55歳以上60歳未満の祖父母 |
⑩ | 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
遺族補償年金は、業務上の即死又は業務上の負傷若しくは疾病に起因する死亡の場合に支給されます。
傷病補償年金の受給者がその傷病が原因で死亡した場合は、業務上の死亡となり、遺族補償年金が支給されます。
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

【解答】
②【H28年出題】 ×
「生計を維持していた」とは、「専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態があれば足りる。共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになる」とされています。
問題文の「労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻」は、「生計を維持していた」に当たりますので、遺族補償年金を受けることができます。
(昭41.1.31基発73号)
③【H19年出題】
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】
③【H19年出題】〇
遺族の要件の一つである「厚生労働省令で定める障害の状態」のキーワードは、「第5級以上」、「労働が高度の制限を受ける」の部分です。
なお、この規定は、複数事業労働者遺族年金にも準用されます。
(則第15条)
④【R5年出題】
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。

【解答】
④【R5年出題】 ×
夫については、労働者の死亡当時、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
「障害の状態にない50歳の夫」は、両方とも満たしていませんので、遺族補償年金は受けられません。
⑤【R2年出題】
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
「子」については、労働者の死亡当時、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
・19歳の大学生について
→「年齢要件」を満たしていませんので、受給資格者になりません。なお、「障害要件」を満たしていれば受給資格者となります。
・17歳の高校生について
→「年齢要件」を満たしていて、かつ、「定期的に養育費を送金されていた=生計を維持されていた」ので、受給資格者となります。
⑥【R5年出題】
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

【解答】
⑥【R5年出題】 ×
「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす」とされています。生まれたときから、受給資格者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法(介護補償給付その2)
R7-162 02.06
介護補償給付の支給額(原則実費・上限、最低保障額あり)
前回は、介護補償給付の支給要件についてお話ししました。
今回は、介護補償給付として支給される額をみていきます。
★原則は介護費用として支払った額(実費)が支給されますが、上限と最低保障額があることがポイントです。
では、条文を読んでみましょう。
第19条の2 介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
則第18条の3の4 (介護補償給付の額) (1) その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合 → その月において介護に要する費用として支出された費用の額(実費) ※その額が177,950円を超えるときは、177,950円とする。(上限) (2) 親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合(最低保障額が適用される) ・ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある・親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある・介護に要する費用として支出された費用の額が81,290円に満たないとき → 81,290円(最低保障額) ・ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない・親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある(介護費用を支出せず、親族等による介護のみ) → 81,290円(最低保障額) |
★「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額が適用されません
「支給すべき事由が生じた月」において、介護に要する費用として支出された額が81,290円に満たない → 介護に要する費用として支出された額(実費・最低保障なし)
そのため、「支給事由が生じた月」に親族等による介護を受けた場合でも、介護に要する費用として支出された費用がゼロの場合は、介護補償給付の額もゼロとなります。
★ 「随時介護を要する状態」の場合は、上限が「88,980円」、最低保障額が「40,600円」となります。常時介護の2分の1です。(端数処理があります)
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】
①【H23年出題】 〇
介護補償給付は、「月」単位で支給されます。
②【H25年出題】
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】
②【H25年出題】 〇
★最低保障額のポイント!
・ 「支給すべき事由が生じた月」は、最低保障額は適用されません。
・ 最低保障額が適用される要件は、「親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある」ことです。
※ 例えば、「支給すべき事由が生じた月」が1月で、介護に要する費用として支出された額が81,290円未満で、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合
→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付の額は「介護に要する費用として支出された額=実費」です。
2月以降は最低保障額の81,290円が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
実 費 | 最低保障額 | 最低保障額 | 最低保障額 |
③【R2年出題】
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】
③【R2年出題】 ×
介護費用を支払わなくても、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合は、介護補償給付は支給されます。
※ ただし、「支給すべき事由が生じた月」は最低保障はありません。
例えば「支給すべき事由が生じた月」が1月で、介護に要する費用を支出しないで、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある場合
→ 1月は最低保障額が適用されませんので、介護補償給付は支給されません。
2月以降は最低保障額の81,290円が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
支給なし | 最低保障額 | 最低保障額 | 最低保障額 |
なお、「介護に要した費用の額の証明書」は、「介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合」に、添付しなければなりません。介護費用を支払っていない場合は、添付する必要はありません。
(則第18条の3の5)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法(介護補償給付その1)
R7-161 02.05
介護補償給付の支給要件
介護補償給付が支給される要件と、支給されない場合をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条の8第4項 介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) (2) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間 (3) 病院又は診療所に入院している間 |
★厚生労働省令で定める程度とは?
→「第1級(すべて)」と「第2級の精神神経の障害、胸腹部臓器の障害」です。
★障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものとは?
(1) 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に規定する施設であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
など
過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、 < A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行われる。

【解答】
①【H19年選択式】
<A> 常時又は随時
<B> 当該労働者
②【H21年出題】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

【解答】
②【H21年出題】 ×
介護補償給付は、「常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき」に支給されます。
「その障害の程度にかかわらず」ではなく、「障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のもの」であることが要件です。
③【H24年出題】
労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間については、介護補償給付は支給されない。

【解答】
③【H24年出題】 〇
老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は、介護補償給付は支給されません。
(則第18条の3の3)
④【H30年出題】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。

【解答】
④【H30年出題】 ×
病院又は診療所に入院している間は、介護補償給付は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法「支給制限」
R7-149 01.23
<労災>支給制限(労働者に対するペナルティ)
例えば、労働者が故意にケガの原因となった事故を生じさせた場合は、労災保険の保険給付は行われません。
事故の発生について労働者に非がある場合は、保険給付の支給制限を行うことによってペナルティが課されます。
支給制限の条文を読んでみましょう。
第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「故意に」のときは、政府は、「保険給付を行わない」=絶対的給付制限となります。
②【H26年出題】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
「故意に」のときは、絶対的給付制限です。
③【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】
③【H26年出題】 〇
「故意に」のときは、絶対的給付制限です。
④【H26年出題】
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
④【H26年出題】 〇
「正当な理由なく療養に関する指示に従わない」場合は、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」となります。
⑤【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
⑤【R2年出題】 〇
「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」のは、「重大な過失」の場合です。単なる「過失」の場合は、支給制限は行われません。
⑥【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
⑥【R2年出題】 ×
「故意の犯罪行為」の場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」です。
⑦【R6年出題】
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
⑦【R6年出題】 〇
「重大な過失」の場合は、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」となります。
⑧【R2年出題】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
⑧【R2年出題】 〇
「正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」ときは、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができるとなります。指示に従わないことに正当な理由があれば、支給制限は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険の特別加入制度
R7-137 01.11
労災特別加入者のうち「中小事業主等」について
労災保険には「特別加入制度」があります。
・労災保険法は「労働者」を保護するための制度ですが、労働者に準じて保護するにふさわしい者は、特別加入することができます。
・また、労災保険は日本国内に限って適用されますが、日本から海外の事業場に派遣された労働者についても、特別加入することができます。
特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」の3つの種別があります。
今回は、「中小事業主等」についてお話しします。
「中小事業主等」として特別加入できる者の要件を確認しましょう。
① 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で「労働保険事務組合」に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)
② ①の事業主が行う事業に従事する者(→家族労働者や法人企業の場合の代表権をもたない重役など)
※厚生労働省令で定める数について
金融業、保険業、不動産業、小売業 | 50人以下 |
卸売業、サービス業 | 100人以下 |
上記以外 | 300人以下 |
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
労災保険は、労働者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害に対して保険給付を行う制度であるが、業務の実態、災害の発生状況等に照らし、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨から、中小事業主等に特別加入の制度を設けている。

【解答】
①【H26年出題】 〇
特別加入の制度は、実質的に労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとする趣旨で設けられています。
(昭40.11.1基発第1454号)
②【H30年選択式】
労災保険法においては、労働基準法適用労働者には当たらないが、業務の実態、災害の発生状況等からみて、労働基準法適用労働者に準じて保護するにふさわしい一定の者に対して特別加入の制度を設けている。まず、中小事業主等の特別加入については、主たる事業の種類に応じ、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で< A >に労働保険事務の処理を委託している者及びその事業に従事する者である。この事業の事業主としては、卸売業又は< B >を主たる事業とする事業主の場合は、常時100人以下の労働者を使用する者が該当する。この特別加入に際しては、中小事業主が申請をし、政府の承認を受ける必要がある。給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< C >である。
<選択肢>
A | ① 社会保険事務所 ② 商工会議所 ③ 特定社会保険労務士 ④ 労働保険事務組合 |
B | ① 小売業 ② サービス業 ③ 不動産業 ④ 保険業 |
C | ① 20,000円 ② 22,000円 ③ 24,000円 ④ 25,000円 |

【解答】
<A> ④ 労働保険事務組合
<B> ② サービス業
<C> ④ 25,000円
(法第33条第1号、第34条、則第46条の16、則第46条の20)
③【R4年出題】
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
<A> 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<B> 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<C> 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
<E> 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

【解答】
③【R4年出題】
<D> サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法の歴史
R7-129 01.03
労災保険法の沿革をお話しします~労災保険の歴史
★ 労働者災害補償保険法は、昭和22年4月7日公布、同年9月1日から施行されました。
★ 労働条件の最低基準を定めた労働基準法は昭和22年9月に施行、同時に、業務上の災害を保護するため、労働者災害補償保険法が施行されました。
<その後の主な改正>
■昭和48年
「通勤災害」について、業務災害に準じた保護が加えられることになりました
■平成13年
「二次健康診断等給付」が施行されました。「二次健康診断」とその結果に基づく「特定保健指導」を労災保険の保険給付として行うことになりました。
■令和2年
「複数業務要因災害」に関する保険給付が加わりました。
条文を読んでみましょう。
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
労災保険の第1の目的は「保険給付」を行うことです。
第2の目的が、「社会復帰促進等事業」です。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 (1) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 (2) 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。) (3) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 (4) 二次健康診断等給付
第29条 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 (1) 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 (2) 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 (3) 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 |
過去問をどうぞ!
【令和元年選択式】 ※改正による修正あり
労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、< A >法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び< B >給付の4種類である。通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び< C >年金である。
<選択肢>
<A> ① 労働関係調整 ② 労働基準 ③ 労働組合 ④ 労働契約
<B> ① 求職者 ② 教育訓練 ③ 失業等 ④ 二次健康診断等
<C> ① 厚生 ② 国民 ③ 傷病 ④ 老齢

【解答】
<A> ② 労働基準
<B> ④ 二次健康診断等
<C> ③ 傷病
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-113 12.18
<令和6年の問題を振り返って>複数事業労働者の休業(補償)等給付について
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう
今日は、労災保険法の択一式です。
■複数事業労働者の給付基礎日額の算定方法を確認しましょう。
法第8条第3項 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。 |
複数事業労働者の給付基礎日額は、複数の就業先ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。
■「部分算定日」定義を確認しましょう。
★療養のために所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
★賃金が支払われる休暇(有給休暇、通勤手当・住宅手当等が支給される休業日)
例えば、給付基礎日額が10,000円、午前中の労働に対する賃金が4,000円の場合、休業(補償)等給付の額は以下の式で計算します。
(10,000円-4,000円)×60%=3,600円
・(給付基礎日額-部分算定日に対して実際に支払われた賃金)×60%です。
「複数事業労働者」についての通達を確認しましょう。
<複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件について>
(1) 休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業(補償)等給付」という。)の給付事由
①「療養のため」
②「労働することができない」ために
③「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の
第4日目から支給されます。
(2) 「労働することができない」とは
必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいいます。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはなりません。 |
★複数事業労働者について
複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要があります。
→ 例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合には、原則、「労働することができない」とは認められないことから、「賃金を受けない日」に該当するかの検討を行う必要はなく、休業(補償)等給付に係る保険給付については不支給決定となります。
→ ただし、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがあります。
(3) 「賃金を受けない日」について
「賃金を受けない日」には、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日があります。 →賃金の一部を受けない日とは ① 所定労働時間の全部について「労働することができない」場合で、平均賃金の 60%未満の金額しか受けない日 ② 通院等のため所定労働時間の一部について「労働することができない」場合で、当該一部休業した時間について全く賃金を受けないか、又は「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額」しか受けない日 |
★複数事業労働者については
複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより賃金を受けない日に該当しない状態でありながら、他の事業場において、傷病等により無給での休業をしているため、賃金を受けない日に該当する状態があり得ます。
したがって、複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る「賃金を受けない日」の判断については、まず複数就業先における事業場ごとに行うこととされています。
その結果、一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は「賃金を受けない日」に該当するものとして取り扱うこととなっています。
一方、全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わないこととなっています。
(令和3年3月18日/基管発0318第1号/基補発0318第6号/基保発0318第1号/)
では、令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問4-A】
休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して、業務災害に被災した複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。

【解答】
①【R6年問4-A】 〇
A社では労働者として就労している。しかし、B社では業務災害に係る通院のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない。
→「労働することができない」に該当すると認められることがある。
②【R6年問4-B】
休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して、被災した複数事業労働者については、複数の就業先のうち、一部の事業場において、年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう。)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら、他の事業場において、当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため、「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。

【解答】
②【R6年問4-B】 〇
A社では、年次有給休暇等により平均賃金相当額の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態である。しかし、B社では無給での休業をしている
→ 「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-082 11.16
<令和6年の問題を振り返って>労災特別加入(海外派遣者)について
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
特別加入には、次の3つの種類があります。
中小事業主及びその事業に従事する労働者以外の者(役員等) |
一人親方その他の自営業者及びその者が行う事業に従事する労働者以外の者(家族従事者等) 特定作業従事者 |
海外派遣者 |
今日は、「海外派遣者」についてみていきます。
海外派遣者として特別加入できるものの範囲を確認しましょう。(労災保険法第33条)
■独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者
■日本国内の事業主(有期事業を除く)から、海外で行われる事業に労働者として派遣される者
※「労働者として派遣される者」と「海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される者」があります。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6問6-A】
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、海外派遣者を特別加入させることについて政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

【解答】
①【R6問6-A】 〇
海外派遣者は、派遣元の団体又は事業主が、政府の承認を申請し、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
(法第36条)
②【R6問6-B】
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係が、転勤、在籍出向、移籍出向等のいずれの形態で処理されていても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではない。

【解答】
②【R6問6-B】 〇
海外派遣者と派遣元の事業との雇用関係は、転勤、在籍出向、移籍出向など様々な形態で処理されていたとしても、派遣元の事業主の命令で海外の事業に従事し、その事業との間に現実の労働関係をもつ限りは、特別加入の資格に影響を及ぼすものではありません。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
ちなみに、「海外出張」については、特別加入しなくても、国内の所属の事業場の労災保険から保険給付が行われます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
派遣先の海外の事業が中小規模の場合は、その事業の代表者は、労災保険の海外派遣者として特別加入の対象となります。
中小規模の事業(特定事業といいます)は以下の通りです。
業 種 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
上記以外の業種 | 300人以下 |
なお、特定事業に該当しない場合は、代表者などは特別加入できません。労働者のみが対象となります。
②【H26年出題】
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

【解答】
②【H26年出題】 ×
現地採用者は、海外派遣者特別加入制度の趣旨及びその加入の要件からみて、特別加入の資格がない、とされています。
問題文の海外支店に直接採用された者は、特別加入できません。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
③【R3年出題】
日本国内で行われている有期事業でない事業を行う事業主から、海外(業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く。)の現地法人で行われている事業に従事するため派遣された労働者について、急な赴任のため特別加入の手続きがなされていなかった。この場合、海外派遣されてからでも派遣元の事業主(日本国内で実施している事業について労災保険の保険関係が既に成立している事業主)が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができる。

【解答】
③【R3年出題】 〇
海外派遣者として特別加入できるのは、新たに派遣される者に限りません。既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることも可能である、とされています。
海外派遣されてからでも派遣元の事業主が申請すれば、政府の承認があった場合に特別加入することができます。
(S52.330労働省発労徴第21号・基発第192号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-065 10.29
<令和6年の問題を振り返って>通勤災害と認められた事例、認められなかった事例【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
通勤災害と認められた事例と認められなかった事例をみていきます。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問2-A】
マイカー通勤をしている労働者が、勤務先会社から市道を挟んだところにある同社の駐車場に車を停車し、徒歩で職場に到着しタイムカードを打刻した後、フォグライトの消し忘れに気づき、徒歩で駐車場へ引き返すべく市道を横断する途中、市道を走ってきた軽自動車にはねられ負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】
①【R6年問2-A】 ×
通勤災害と認められます。
・ マイカー通勤者が車のライトの消し忘れなどに気づき、駐車場に引き返すことは一般にあること。
・ いったん事業場に入った後でも、まだ時間の経過もほとんどないことから通勤に通常随伴する行為と認められる。
(昭和49.6.19基収第1739号)
②【R6年問2-B】
マイカー通勤をしている労働者が、同一方向にある配偶者の勤務先を経由するため、通常通り自分の勤務先を通り越して通常の通勤経路を450メートル走行し、配偶者の勤務先で配偶者を下車させて自分の勤務先に向かって走行中、踏切で鉄道車両と衝突して負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】
②【R6年問2-B】 ×
通勤災害と認められます
・ 妻の勤務先が同一方向にあり、かつ、夫の通勤経路からそれほど離れていない
・ 通勤をマイカーで行い、妻の勤務先を経由することは通常おこなわれるもの
・ 当該経路は合理的な経路として取り扱うのが妥当
(昭和49.3.4基収第289号)
③【R6年問2-C】
頸椎を手術した配偶者の看護のため、手術後1か月ほど姑と交替で1日おきに病院に寝泊まりしていた労働者が、当該病院から徒歩で出勤する途中、横断歩道で軽自動車にはねられ負傷したした場合、当該病院から勤務先に向かうとすれば合理的である経路・方法をとり逸脱・中断することなく出勤していたとしても、通勤災害とは認められない。

【解答】
③【R6年問2-C】 ×
通勤災害と認められます。
・入院中の夫の看護のため、妻が病院に寝泊まりすることは社会慣習上、通常行われること
・手術当日から長期間継続して寝泊まりしていた事実がある
・被災当日の当該病院は、被災労働者にとって就業のための拠点としての「住居」と認められる
(昭和52.12.23基収第981号)
④【R6年問2-D】
労働者が、退勤時にタイムカードを打刻し、更衣室で着替えをして事業場施設内の階段を降りる途中、ズボンの裾が靴に絡んだために足を滑らせ、階段を5段ほど落ちて腰部を強打し負傷した場合、通勤災害とは認められない。

【解答】
④【R6年問2-D】 〇
通勤災害とは認められません。
・事業主の支配下にある事業場施設の状況により生じた災害である
(昭和49.4.9基収第314号)
⑤【R6年問2-E】
長年営業に従事している労働者が、通常通りの時刻に通常通りの経路を徒歩で勤務先に向かっている途中に突然倒れ、急性心不全で死亡した場合、通勤災害と認められる。

【解答】
⑤【R6年問2-E】 ×
通勤災害とは認められません。
・ 発病の原因となるような通勤による負傷又は通勤に関連する突発的なできごとなどが認められないため「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められない
・ 通勤を単なるきっかけとして偶然に生じたものに過ぎない
(昭和50.6.9基収第4039号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
<社労士労災保険>通勤について
R7-064 10.28
労災「通勤」の定義についてお話しします
「通勤」の定義は、選択式でも択一式でも、よく出題されます。
用語の意義など、一つずつ解説します。
「通勤」とは、 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 住居と就業の場所との間の往復
(2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(3) 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
YouTubeでお話ししています
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-047 10.11
<令和6年出題労災>遺族補償年金の受給権の消滅【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
遺族補償年金の受給権の消滅について条文を読んでみましょう。
第16条の4第1項 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 (1) 死亡したとき。 (2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 (4) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 (5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 (6) 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 |
★(6)について
夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、労働者の死亡当時、「年齢」か「障害」のどちらかの要件を満たす必要があります。
「障害要件」に該当しなくなった場合は、受給権は消滅します。
ただし、障害要件に該当しなくなっても、年齢要件を満たしていれば、受給権は消滅しません。
令和6年の問題をどうぞ!
【R6年問5】
遺族補償年金の受給権に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という。
ア 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が死亡したときには消滅する。
イ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしたときには消滅する。
ウ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
エ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
オ 遺族補償年金の受給権は、当該遺族である兄弟姉妹が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。

【解答】
ア 〇
遺族補償年金の受給権者が死亡したときには受給権は消滅します。
イ 〇
遺族補償年金の受給権者が婚姻をしたときには受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合でも消滅します。
ウ 〇
遺族補償年金の受給権者が直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときには、受給権は消滅します。届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合でも消滅します。
エ ×
遺族補償年金の受給権者である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには、受給権は原則として消滅します。
ただし、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは、18歳の年度末になっても消滅しません。
「労働者の死亡時から引き続き障害の状態にあるときは消滅しない」という要件が抜けているので誤りです。
オ ×
「エ」の問題と同じです。
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅します。
②【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】
②【H28年出題】 〇
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が「直系血族又は直系姻族以外の者」の養子になったときには消滅します。自分の伯父は、直系血族でも直系姻族でもありませんので、自分の伯父の養子となったときは、消滅します。
③【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。

【解答】
③【H23年出題】 ×
兄弟姉妹が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、原則として遺族補償年金の受給権は消滅します。
ただし、労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときは消滅しません。
④【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。

【解答】
④【H23年出題】 ×
労働者の死亡の当時60歳以上であった祖父母は、労働者の死亡時に年齢要件を満たしていますので、障害の状態がなくなっても遺族補償年金の受給権は消滅しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(労災保険法)
R7-024 9.18
<令和6年度労災>支給制限、受給権の保護、不正受給者からの費用徴収など【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の択一式です。
では、令和6年問7の問題をどうぞ!
① 【R6年出題】
労働者が、重大な過失により、負傷、疾病、障害若しくは死亡又はこれらの原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
① 【R6年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
法第12条の2の2第2項 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
「故意」の場合の条文と比較しましょう。
法第12条の2の2第1項 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 |
「全部又は一部を行わないことができる」と「行わない」の違いを意識してください。
②【R6年出題】
労働者を重大な過失により死亡させた遺族補償給付の受給資格者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第16条の9第1項 労働者を故意に死亡させた者は、遺族補償給付を受けることができる遺族としない。 |
「重大な過失」により死亡させた場合の給付制限はありません。
③【R6年出題】
労働者が、懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合には、休業補償給付は行わない。

【解答】
③【R6年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第14条の2 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。 (1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 (2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
(休業補償給付を行わない場合) 則第12条の4 法第14条の2の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 (1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 (2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合 |
④【R6年出題】
労働者が退職したときは、保険給付を受ける権利は消滅する。

【解答】
④【R6年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 |
労働者が退職しても、保険給付を受ける権利は消滅しません。
⑤【R6年出題】
偽りその他不正の手段により労働者が保険給付を受けたときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該労働者を使用する事業主から徴収することができる。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第12条の3 ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 |
※事業主からではなく、「偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者」から徴収します。
条文の続きです。
| ② 事業主(徴収法第8条第2項又は第3項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の択一式を振り返ります(労災保険法)
R7-014 9.8
令和6年度<労災法>通勤途上の日常生活上必要な行為【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法です。
R6年労災問1の問題をどうぞ!
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱・中断した場合でも、当該逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、同条の通勤と認められることとされている。
この日常生活上必要な行為として、同法施行規則第8条が定めるものに含まれない行為はどれか。
A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為
B 帰途で総菜等を購入する行為
C はり師による施術を受ける行為
D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為
E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為

【解答】
「A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、日常生活上必要な行為として、労災保険法施行規則第8条に定めるものに含まれません。
「日常生活上必要な行為」として定められている行為を確認しましょう。
則第8条(日常生活上必要な行為) 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 (1) 日用品の購入その他これに準ずる行為 (2) 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為 (4) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 (5) 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |
問題文の「B 帰途で総菜等を購入する行為」は(1)に、「C はり師による施術を受ける行為」は(4)に、「D 職業能力開発校で職業訓練を受ける行為」は(2)に、「E 要介護状態にある兄弟姉妹の介護を継続的に又は反復して行う行為」は(5)に該当します。
(S48.11.22基発644)
通勤途上で、逸脱・中断をしたとしても、逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合」には、当該逸脱・中断の後、合理的な経路に復した後は、通勤と認められます。
ポイント!
ただし、逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合でも、「逸脱・中断」の間は通勤となりません。
ちなみに、「A 経路の近くにある公衆トイレを使用する行為」は、「ささいな行為」となります。通常経路の途中のささいな行為は、逸脱、中断に該当しません。
他にささいな行為として、帰途に経路の近くにある公園で短時間休息する場合、経路上の店でタバコ、雑誌等を購入する場合、駅構内でジュースの立飲みをする場合などがあります。
(S48.11.22基発644)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります
R7-005 8.30
<労災保険法>令和6年度選択式は併合繰上げ・未支給・遺族補償年金【社労士受験対策】
https://youtu.be/iIsF_FkpP7U?si=FoW2wuM5IfuX32Er令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、労災保険法の選択式です。
令和6年 選択問題1
労災保険法施行規則第14条第1項は、「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1に定めるところによる。」と規定し、同条第2項は、「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。」と規定するが、同条第3項柱書きは、「第< A >級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「2級」繰り上げた等級(同項第2号)、「第< B >級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする。
<選択肢>
「3」、「5」、「6」、「7」、「8」、「10」、「12」、「13」

【解答】
<A> 8
<B> 5
おぼえるポイント!
★障害等級は、障害等級表(労災保険法施行規則別表第1)にあてはめて、決定されます。
↓
★同じ事由による身体障害が2つ以上ある場合は、「重い方」の障害等級が全体の障害等級になります。
↓
★ただし、13級以上の身体障害が2つ以上ある場合は、重い方の等級が繰り上げられます。
・13級以上の障害が2つ以上ある場合 → 1級繰り上げ
・8級以上の障害が2つ以上ある場合 → 2級繰り上げ
・5級以上の障害が2つ以上ある場合 → 3級繰り上げ
令和6年 選択問題2
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた< C >から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。また、保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、< D >の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
<選択肢>
「月」、「月の翌月」、「日」、「日の翌日」
「事業主」、「自己」、「死亡した者」、「世帯主」

【解答】
<C> 月の翌月
<D> 自己
(法第9条第1項、法第11条第1項)
おぼえるポイント!
★年金は「月」単位で支給されます。
支給すべき事由が生じた「月の翌月」から支給を受ける権利が「消滅した月」まで
★未支給の保険給付は、「自己の名」で請求します。死亡した者の名ではありません。
ちなみに、未支給の保険給付を請求できるのは、死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
ただし、遺族(補償)等年金の場合は、遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族となります。
令和6年 選択問題3
最高裁判所は、遺族補償年金に関して次のように判示した。
「労災保険法に基づく保険給付は,その制度の趣旨目的に従い,特定の損害について必要額を塡補するために支給されるものであり,遺族補償年金は,労働者の死亡による遺族の< E >を塡補することを目的とするものであって(労災保険法1条,16条の2から16条の4まで),その塡補の対象とする損害は,被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり,かつ,相互補完性があるものと解される。〔…(略)…〕
したがって,被害者が不法行為によって死亡した場合において,その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受け,又は支給を受けることが確定したときは,損害賠償額を算定するに当たり,上記の遺族補償年金につき,その塡補の対象となる< E >による損害と同性質であり,かつ,相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で,損益相殺的な調整を行うべきものと解するのが相当である。」
<選択肢>
「生活基盤の喪失」、「精神的損害」、「相続財産の喪失」「被扶養利益の喪失」

【解答】
<E> 被扶養利益の喪失
(平27.3.4最高裁判所大法廷判決)
私の考えるポイント!
「生活基盤の喪失」と「被扶養利益の喪失」で迷われませんでしたか?私は迷いました。
遺族補償年金の遺族の要件は、労働者の死亡当時その収入によって「生計を維持」していたものです。
そこから、労働者の死亡によって、「被扶養利益」が喪失すると考えました。
令和6年の選択式について <A>から<D>は、択一式でよく出るところですので、過去問対策で解けます。 判例からの問題の<E>は、覚えて解く問題というより、じっくり考える問題です。 遺族補償年金の目的は?遺族補償年金の対象になる遺族は?など、様々な角度で考える問題でした。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-360 8.21
傷病補償年金と特別支給金の重要10問【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
傷病補償年金の条文を読んでみましょう。
第12条の8第3項 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 (1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 (2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 則第18条 (傷病等級) ① 法第12条の8第3項第2号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。 ② 障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする。 別表2
第18条第2項 ② 傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |
過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
①【H30年出題】 ×
「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。
下の図でイメージしてください。
②【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
②【H24年出題】 〇
「療養補償給付」も「傷病補償年金」も治ゆするまでの給付です。
療養補償給付は治療についての給付ですので、傷病補償年金と併給されます。
③【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されません。
④【H29年出題】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月を経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。

【解答】
④【H29年出題】 〇
傷病補償年金は、労働者の請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で支給決定されることがポイントです。
そのため、療養開始後1年6か月を経過した日に治っていないときは、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出させることになっています。
(則第18条の2第2項、第3項)
⑤【H29年出題】
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
「6か月以上」がポイントです。
⑥【H29年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。

【解答】
⑥【H29年出題】 〇
「打切補償を支払ったものとみなされる」=解雇することができます。
下の図でイメージしてください。
⑦【H20年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。

【解答】
⑦【H20年出題】 ×
傷病補償年金は、所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行いますが、傷病補償年金の傷病等級の変更も、所轄労働基準監督署長の職権で行われます。
(則第18条の3)
⑧【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

⑧【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合は、傷病補償年金の受給権は消滅しますが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。自動的に休業補償給付が支給されるのではなく、休業補償給付は「請求」が必要です。
⑨【H28年出題】
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

【解答】
⑨【H28年出題】 〇
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されます。
ただし、当分の間、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされています。
(特別支給金規則第5条の2、昭56.6.27基発第393号)
★保険給付と特別支給金のイメージ図です
傷病特別年金 | →ボーナス特別支給金 |
傷病特別支給金 | →一般の特別支給金 |
傷病補償年金 | 保険給付 |
⑩【R1年出題】
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

【解答】
⑩【R1年出題】 〇
「傷病特別支給金」は、傷病等級に応じて「定額」であることがポイントです。
(特別支給金規則第5条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
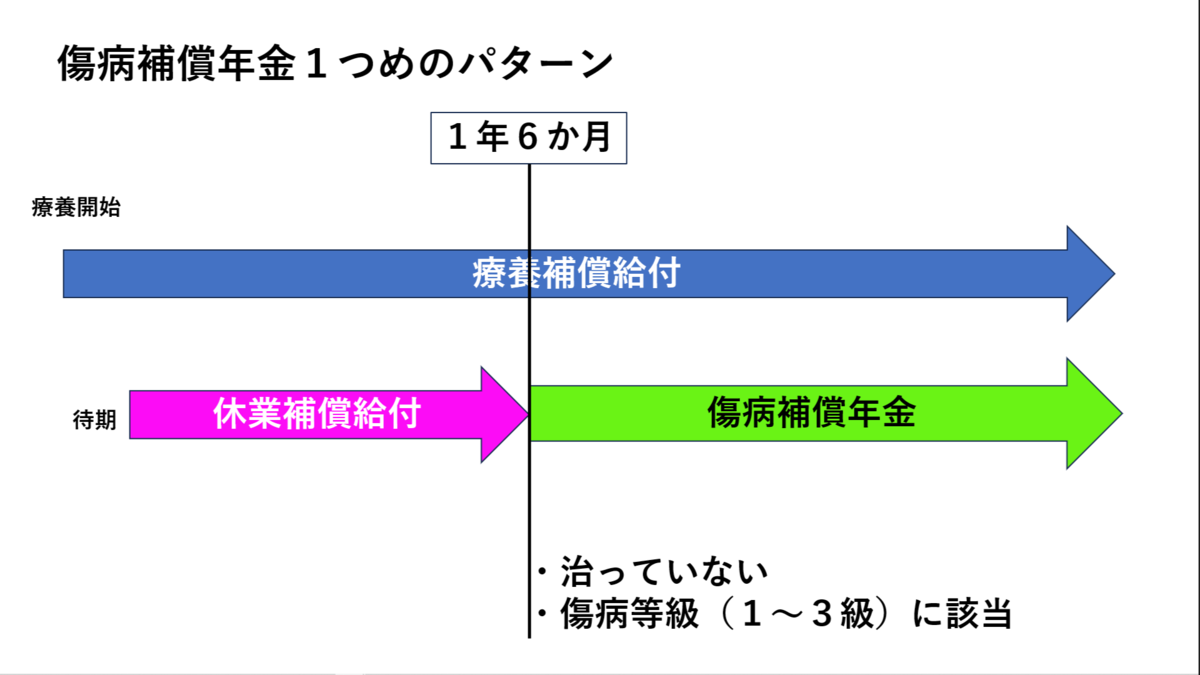
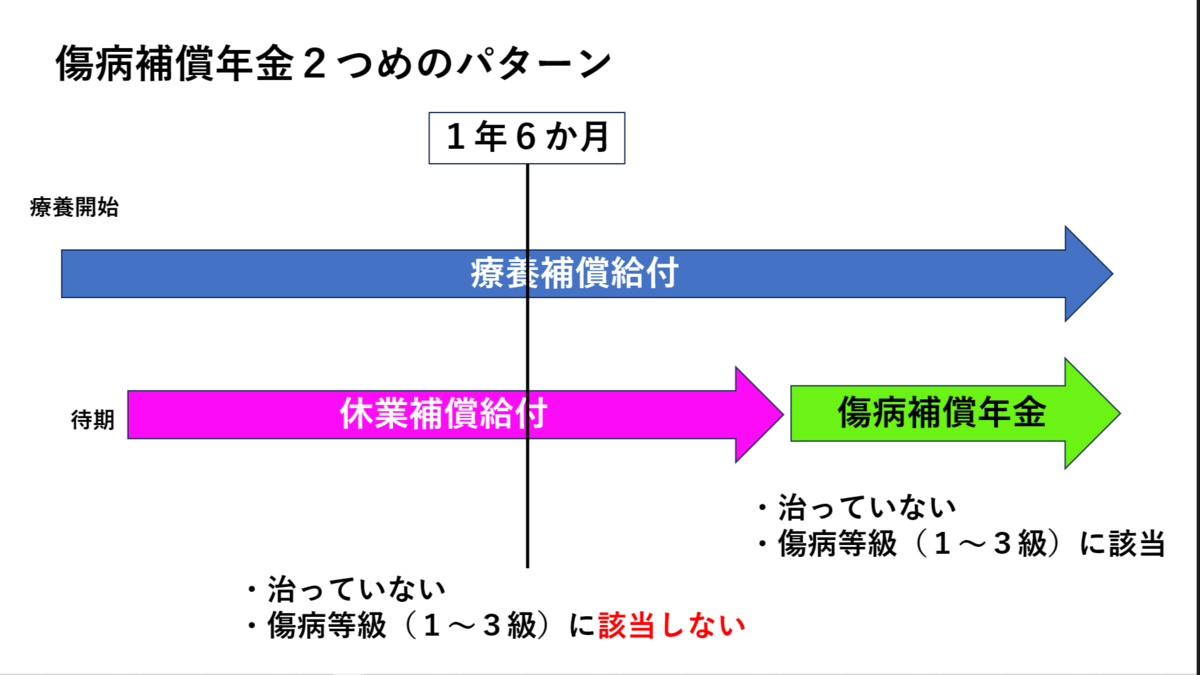
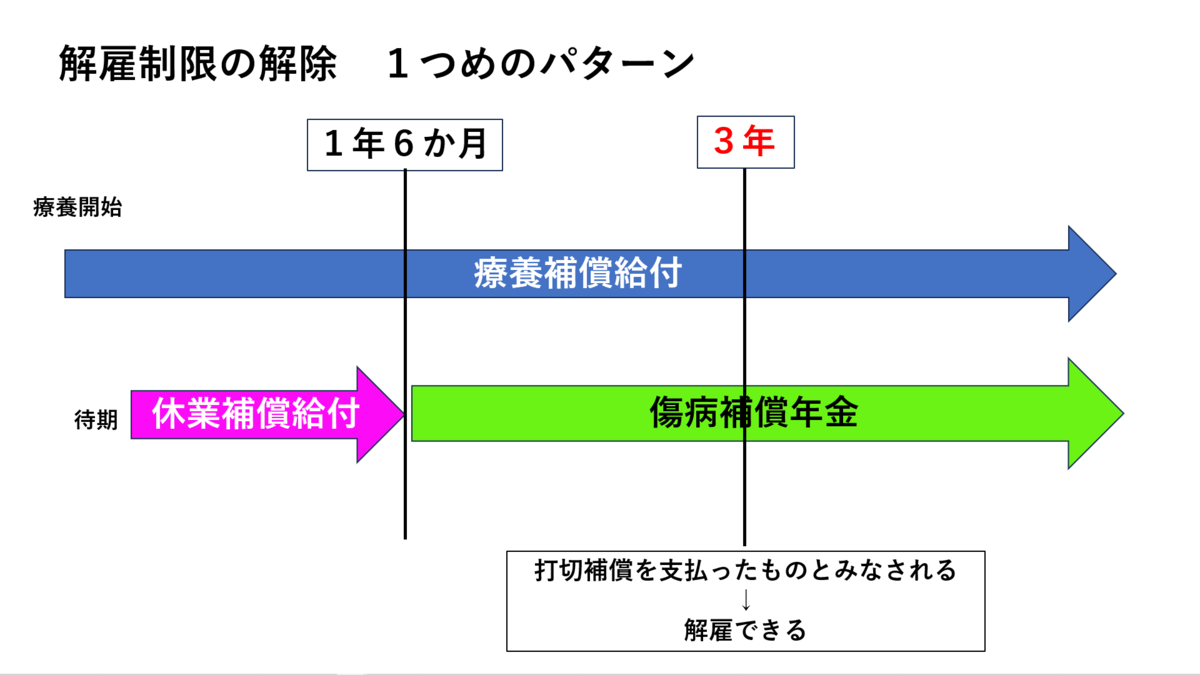
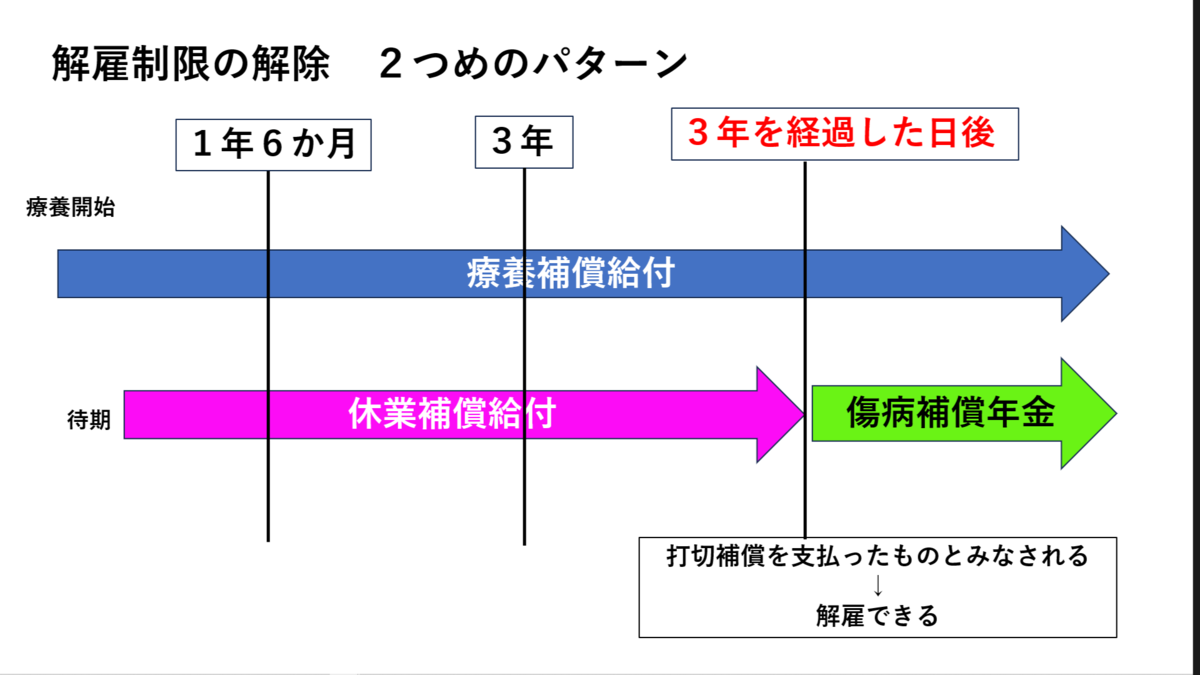
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-355 8.16
特別加入者と労働者の異なる点でよく出るところ【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者は労災保険法に特別加入することによって、労働者と同じ保護が受けられます。
ただし、労働者と特別加入者で違う点もありますので、ポイントを確認しましょう。
①二次健康診断等給付について
特別加入者は、二次健康診断等給付は対象になりません。労働者と違い、健康診断が義務づけられていないからです。
②社会復帰促進等事業について
特別加入者は、労働者と同じように社会復帰促進等事業が適用されます。
ただし、「特別支給金」の中の「ボーナス特別支給金」は、特別加入者には支給されません。
例えば、労働者については、傷病補償年金に特別支給金として、傷病特別支給金と傷病特別年金がプラスされます。しかし、特別加入者には、ボーナス特別支給金の傷病特別年金は支給されません。
傷病特別年金 | → ボーナス特別支給金 |
傷病特別支給金 | → 一般の特別支給金 |
傷病補償年金 | 保険給付 |
過去問をどうぞ!
【H28年出題】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

【解答】
【H28年出題】 〇
特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は、支給されません。なお、一般の特別支給金は支給されます。
(特別支給金規則第19条)
③通勤災害について
特別加入者にも通勤災害は適用されます。ただし、一人親方等の一部については、住居と就業の場所との間の往復が明確でないため、通勤災害が適用されません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
②【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
特別加入者である家内労働者については、通勤災害は適用されません。
(則第46条の22の2)
④給付基礎日額について
特別加入者には賃金がないため、給付基礎日額は、厚生労働大臣の定めた額から、申請に基づき決定した額となります。
過去問をどうぞ!
【H30年選択式】
(特別加入者の)給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は< A >である。

【解答】
A 25,000円
(則第46条の20第1項)
⑤特別加入者の支給制限
次の場合は、特別加入者の保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」とされています。
<中小事業主等について>
・ 事故が、第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
・ 業務災害の原因である事故が中小の事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき
<一人親方等について>
・ 事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
<海外派遣者について>
・ 事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
過去問をどうぞ!
【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
【R3年出題】 ×
「保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。」の部分が誤りです。
事業主から費用徴収するのではなく、保険給付が支給制限されます。
「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」となります。
(法第34条第1項第4号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-343 8.4
障害補償給付「準用」「加重」「併合繰上げ」「変更」【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
障害補償給付の重要ポイントを過去問でチェックしましょう。
過去問をどうぞ!
①【H21年問6】
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。

【解答】
①【H21年問6】 〇
<障害等級の準用>
障害等級表には、類型的な身体障害が掲げられています。障害等級表に掲げられていない障害は、その障害の程度に応じ、障害等級表に掲げる障害に準じて障害等級が認定されます。
(則第14条第1項、第4項)
②【H21年問6】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】
②【H21年問6】 ×
<加重障害>
既に身体障害のあった者が、新たな業務災害により、同一の部位について障害の程度が加重した場合は、加重した障害等級に応ずる障害補償給付となります。
加重する前も加重した後も年金の等級の場合、その額は、現在の障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既にあった障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額となります。
なお、既存の障害に係る従前の障害補償年金は、引き続き支給されます。
(則第14条第5項)
※下のイメージ図もご覧ください。
③【H21年問6】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば、次のとおりである。
①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合 第7級
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
③第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級

【解答】
③【H21年問6】 〇
<併合・併合繰上げ>
障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級によるのが原則です。
ただし、一定の場合は等級が繰り上げられます。
問題文を例にしてみましょう。
①第8級、第11条及び第13級の3障害がある場合
↓
第13級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を1級繰り上げ7級となります。
②第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合
↓
第5級以上に該当する障害が2以上あるので、重い方を3級繰り上げて1級となります。
③第6級及び第8級の2障害がある場合
↓
第8級以上に該当する障害が2以上あるので重い方を2級繰り上げて4級となります。
(則第14条第3項)
④【H21年問6】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

【解答】
④【H21年問6】 〇
<加重障害>
②と同じです。
ただし、加重前が一時金で加重後が年金の場合の給付額は、新たな等級の年金額から既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額となります。
(則第14条第5項)
⑤【H21年問6】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。

【解答】
⑤【H21年問6】 〇
<変更>
障害の程度が自然的な経過により増進し、又は軽減した場合の規定です。
例えば、3級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が、自然的経過により5級に軽減した場合は、新たに該当することとなった5級の障害補償年金が支給され、その後は、従前の3級の障害補償年金は支給されません。
この規定は、障害補償年金から障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)への変更です。
もともとが障害補償一時金の場合は、適用されません。
(第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-333 7.25
<選択式>休業補償給付の支給額について【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
まず、選択式の過去問をどうぞ!
【R5年選択式】
労災保険法第14条第1項は、「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による< A >のため労働することができないために賃金を受けない日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の< C >に相当する額とする。」と規定している。
<選択肢>
① 100分の50②100分の60③100分の70④100分の80
⑤ 2 ⑥ 3 ⑦ 4 ⑧ 7 ⑨ 通院 ⑩ 能力喪失
⑪ 療養

【解答】
A ⑪ 療養
B ⑦ 4
C ② 100分の60
★部分算定日とは
・療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日
・一部について賃金が支払われる休暇(例えば、時間単位の年次有給休暇を取得した場合など)
<部分算定日の休業補償給付の額の出し方を確認しましょう>
午前中は労働し、午後は通院のため休業した場合
※給付基礎日額は10,000円、午前中の労働に対する賃金が3000円の場合
休業補償給付の額
↓
給付基礎日額(10,000円)から部分算定日に対して支払われる賃金の額(3,000円)を控除して得た額の100分の60=4,200円
午前 | 午後 |
労働(3,000円)) | 通院のため休業 |
| (10,000円-3,000円)×60%=4,200円 |
給付基礎日額10,000円 | |
択一式の過去問もどうぞ!
①【H30年出題】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
休業の初日から第3日目までは待期期間となり、休業補償給付は支給されません。その間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。
なお、複数業務要因災害、通勤災害には、事業主の労働基準法の休業補償を行う義務はありません。
(第14条第1項、労基法第76条)
②【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】
②【H30年出題】 ×
会社の所定休日も、休業補償給付は支給されます。
③【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
③【H30年出題】 〇
所定労働時間の全部労働不能で、平均賃金の60%未満の金額しか受けない日は、「賃金を受けない日」として休業補償給付が支給されます。
問題文の場合は、休業中に平均賃金の6割以上の金額を受けていますので、「賃金を受けない日」に該当しません。そのため休業補償給付は支給されません。
(昭40.9.15基災発第14号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-322 7.14
<選択式>療養補償給付のポイント【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
過去問で療養補償給付のポイントをみていきます。
では、選択式の過去問をどうぞ!
【H28年選択式】
労災保険法第13条第2項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。
<選択肢>
① 治療材料 ② 薬剤 ③ リハビリ用品 ④ 療養の費用

【解答】
A ④ 療養の費用
第13条の条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 (1) 診察 (2) 薬剤又は治療材料の支給 (3) 処置、手術その他の治療 (4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 (5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 (6) 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
則第11条の2 (療養の費用を支給する場合) 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。 |
★療養補償給付の原則は「療養の給付(=現物給付)」です。
★ただし、「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、療養の費用の支給(=現金給付)が行われます。
択一式の過去問もどうぞ!
①【H21年出題】
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

【解答】
①【H21年出題】 ×
療養の給付は、指定病院等で行われます。
指定病院等とは、
・社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(=労災病院のこと)
又は
・都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
です。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院でも、労災保険の指定病院等でない場合は、療養の給付は行われません。
(則第11条第1項)
②【H21年出題】
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

【解答】
②【H21年出題】 ×
療養の給付に代えて療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合」のほか、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」です。
「労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合」では、療養の費用は支給されません。
(則第11条の2)
③【H21年出題】
療養の給付の範囲は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。

【解答】
③【H21年出題】 ×
療養の給付の範囲は、①~⑥の「ほか」政府が療養上相当と認めるものではありません。①~⑥の「なか」で政府が必要と認めるものに限られます。
(第13条第2項)
④【H21年出題】
療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

【解答】
④【H21年出題】 ×
指定病院等を変更しようとするときは、届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を「経由」して「所轄労働基準監督署長」に提出しなければなりません。
提出先は、都道府県労働局長ではなく「所轄労働基準監督署長」です。また、承認を受ける必要はありません。
指定病院等を「経由」することにも注意してください。
(則第12条第3項)
⑤【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

【解答】
⑤【H27年出題】 ×
症状が残っていてもそれが安定して、医療効果が期待しえない状態になった場合は、療養の必要がなくなったものとされ、療養の給付は行われなくなります。
(昭23.1.13基災3号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-308 6.30
遺族補償一時金の重要ポイント【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
「遺族補償給付」には「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今日は「遺族補償一時金」のお話です。
遺族補償一時金は、次の場合に支給されます。
①遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合
又は
②遺族補償年金の受給権者がすべて失権した場合に、支給された年金と前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
では、条文を読んでみましょう。
第16条の6第1項 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 (1) 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 (2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において給付基礎日額の 1000日分に満たないとき |
(1)例えば、労働者の死亡の当時、障害状態にない50歳の夫のみだった場合
↓
遺族補償一時金の額は給付基礎日額の1000日分
(2)給付基礎日額の1000日分は、年金の最低保障額のイメージです。
↓
遺族補償一時金の額は、支給された(年金+前払一時金)と給付基礎日額の1000日分との差額
遺族補償一時金を受けることができる遺族と順位は、次の通りです。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子→父母→孫→祖父母
3 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していない子→父母→孫→祖父母
4 兄弟姉妹
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
①【H25年出題】 〇
遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、生計を維持していた場合でも、生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
②【H28年出題】 〇
兄弟姉妹は、労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがあります。
(第16条の7第1項)
③【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
③【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
★遺族補償年金の受給資格者になるには、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたもの」でなければなりません。
★遺族補償一時金は、労働者の死亡当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
(第16条の2、第16条の7)
④【H10年出題】
遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。

【解答】
④【H10年出題】 〇
死亡労働者の妻が再婚をした場合、遺族補償年金の受給権は消滅します。支払われた遺族補償年金+前払一時金が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合は、差額が遺族補償一時金として支給されます。
「死亡した労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」の身分は、労働者の死亡の当時の身分によります。
再婚したとしても、労働者の死亡当時の妻は、遺族補償一時金の請求権を有することがあります。
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
⑤【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

【解答】
⑤【H28年出題】×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることはあり得ます。(④の問題のような場合です。)
(第16条の8第1項 昭和41.1.31基発第73号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-298 6.20
<選択式>業務上の疾病の範囲・通勤による疾病の範囲【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
選択式の過去問をみていきます。
過去問をどうぞ!
【H18年選択式】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、< B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。
<選択肢>
① 業務上の事故による疾病 ② 業務上の負傷に起因する疾病
③ 業務と因果関係のある疾病 ④ 業務に起因することの明らかな疾病
⑤ 業務に起因する疾病 ⑥ 通勤 ⑦ 通勤上の事由
⑧ 通勤上の事由による疾病 ⑨ 通勤と因果関係のある疾病
⑩ 通勤途上の事故 ⑪ 通勤途上の負傷
⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病 ⑬ 通勤による疾病
⑭ 通勤による負傷 ⑮ 通勤による負傷に起因する疾病
⑯ 労働安全衛生規則 ⑰ 労働基準法施行規則
⑱ 労働基準法施行令 ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則
⑳ 労働者災害補償保険法施行令

【解答】
A ⑰ 労働基準法施行規則
B ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則
C ④ 業務に起因することの明らかな疾病
D ⑭ 通勤による負傷
E ⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病
こちらの過去問もどうぞ!
①【H19年出題】
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

【解答】
①【H19年出題】 ×
「業務上の負傷に起因する疾病」は、別表第1の2第1号で定められていて、業務上の疾病に含まれます。
ちなみに、別表第1の2は職業病リストとよばれていて、業務上の疾病の範囲を明確にしています。
(労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2)
②【H19年出題】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

【解答】
②【H19年出題】 〇
業務上の疾病と認められるには、労働基準法施行規則別表第1の2(職業病リスト)で定められている疾病に該当しなければなりません。
なお、第1号から第10号までのリストには、業務と疾病の間に因果関係が確立している疾病が示されています。
示されていない疾病については、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」として業務と疾病の因果関係が認められた場合は、業務上の疾病として認められます。
③【H19年出題】
通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

【解答】
③【H19年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第22条第1項 療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
則第18条の4(通勤による疾病の範囲) 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。 |
通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。
④【H21年出題】
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

【解答】
④【H21年出題】 ×
通勤による疾病は、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」とされています。業務上の疾病と異なり、具体的な疾病の種類は挙げられていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-272 5.25
業務災害・通勤災害の範囲【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
業務災害、通勤災害の範囲をみていきます。
まず、業務災害、通勤災害の定義を条文で読んでみましょう。
第7条第1項 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 (1) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付 (2) 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。) (3) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付 (4) 二次健康診断等給付 |
業務災害とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」、通勤災害とは、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

【解答】
①【H25年出題】 ×
「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところを指します。
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないとされています。
「反復・継続性」とは、おおむね「1か月に1回以上」の往復行為又は移動がある場合に認められます。
(平18.3.31基発第0331042号、平18.3.31/基労管発第0331001号/基労補発第0331003号/)
②【H25年出題】
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。

【解答】
②【H25年出題】 〇
出張の機会を利用して出張期間内に、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われます。
(平18.3.31/基労管発第0331001号/基労補発第0331003号/)
③【H25年出題】
通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した場合、通勤による災害と認められない。

【解答】
③【H25年出題】 ×
「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいいます。
通勤の途中で、自動車にひかれた、電車が急停車したため転倒して受傷した、駅の階段から転落した、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷した、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった等、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められます。
問題文は、通勤による災害と認められます。
(平18.3.31基発第0331042号)
④【H25年出題】
通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認められる。

【解答】
④【H25年出題】 ×
被災者の故意によって生じた災害、通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合などは、通勤をしていることが原因となって災害が発生したものではありませんので、通勤災害とは認められません。
(平18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-271 5.24
通勤に該当する例・該当しない例【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
まず、「通勤」の定義を条文で読んでみましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 (1) 住居と就業の場所との間の往復 (2) 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 (3) (1)に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
★「就業に関し」について
「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示しています。つまり、通勤と認められるには、移動行為が業務と密接な関連をもって行われることを要します。
★「合理的な経路及び方法」について
「合理的な経路及び方法」とは、移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいいます。
★「業務の性質を有するもの」について
「業務の性質を有するもの」とは、移動による災害が業務災害と解されるものをいいます。
(平18.3.31基発第0331042号)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
所定の就業日に所定の就業開始時刻を目途に住居を出て就業の場所へ向う場合は、寝すごしによる遅刻、あるいはラッシュを避けるための早出等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があるとされています。
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合でも、通勤に該当することはあります。
(平18.3.31基発第0331042号)
②【H24年出題】
運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。

【解答】
②【H24年出題】 ×
運動部の練習に参加する等の目的で、例えば、
① 午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合
② 第2の就業場所にその所定の就業開始時刻と著しくかけ離れた時刻に出勤する場合
には、当該行為は、むしろ当該業務以外の目的のために行われるものと考えられるので、就業との関連性はないと認められます。そのため、通勤に該当しません。
(平18.3.31基発第0331042号)
③【H24年出題】
日々雇用される労働者が公共職業安定所等でその日の職業紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、通勤に該当しない。

【解答】
③【H24年出題】 〇
日々雇用される労働者について、公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は、未だ就職できるかどうか確実でない段階であり、職業紹介を受けるための行為であって、就業のための出勤行為であるとはいえないとされています。
ちなみに、日々雇用される労働者について
・継続して同一の事業に就業している場合は、就業することが確実であり、その際の出勤は、就業との関連性が認められます。
・公共職業安定所等でその日の紹介を受けた後に、紹介先へ向う場合で、その事業で就業することが見込まれるときも、就業との関連性を認めることができます。
(平18.3.31基発第0331042号)
④【H24年出題】
昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。

【解答】
④【H24年出題】 ×
通勤は1日について1回のみしか認められないものではありませんので、昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、昼休みについていえば、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられますので、その往復行為は就業との関連性を認められ、通勤に該当します。
(平18.3.31基発第0331042号)
⑤【H24年出題】
業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。

【解答】
⑤【H24年出題】 ×
業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えないとされています。
問題文の場合は通勤に該当することもあります。
(平18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-257 5.10
特別加入者に対する支給制限【社労士受験対策】
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
中小事業主等、一人親方等、海外派遣者は、労災保険に特別加入できます。
特別加入すると、労働者とみなされ、労働者と同じ補償が受けられます。
ただし、労働者とは異なる規定もありますので、注意しましょう。
今回は、労働者と異なる規定のひとつ「支給制限」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第34条第1項第4号 中小事業主等の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。
第35条第1項第7号 一人親方等及び特定作業従事者の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
第36条第1項第3号 海外派遣者の事故が、第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
★特別加入者の支給制限について
・中小事業主等のみに規定されているもの
中小事業主等の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・中小事業主等、一人親方等、海外派遣者共通で規定されているもの
事故が特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
★★「労働者」の場合と比較してみましょう。
① 事業主が故意又は重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故
② 事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故
③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
(第31条第1項)
①②③については、事業主に非があるため、「事業主からの費用徴収」の対象になります。労働者に対する保険給付は全額支給され、支給制限は行われません。
過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
①【R3年出題】 ×
特別加入している中小事業主等の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、「政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」です。
事業主から費用を徴収するのではなく、「支給制限」が行われます。
(第34条第1項第4号)
②【H26年出題】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第一種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
②【H26年出題】 ×
第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、「保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる(=費用徴収)。」ではなく、「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(=支給制限)」となります。
(第34条第1項第4号)
③【H26年出題】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき第二種特別加入保険料を納付せず、その後、政府から督促を受けるまでの期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
③【H26年出題】 ×
②の問題と同じです。第二種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故については、費用徴収ではなく、支給制限となります。
(第35条第1項第7号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-238 4.21
社労士受験のための 業務災害の認定の具体例
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
「業務災害」とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」のことです。
業務上と認められるには、
①業務遂行性が認められること(労働者が労働関係にあること)
↓
②業務起因性が成立していること(業務と傷病との間に因果関係があること)
が必要です。
「業務上」と認められるか否かの具体例をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
道路清掃工事の日雇い労働者が、正午からの休憩時間中に同僚と作業場内の道路に面した柵にもたれて休憩していたところ、道路を走っていた乗用車が運転操作を誤って柵に激突した時に逃げ遅れ、柵と自動車に挟まれて胸骨を骨折した場合、業務上の負傷と認められる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
★ポイント! 休憩時間中の災害について
休憩時間中の災害が、私的行為によって発生した場合は、業務起因性は認められませんので、業務災害になりません。
しかし、就業中なら業務行為に含まれてるような行為(例えば、トイレなどの生理的行為など)は、事業主の支配下で「業務に付随する行為」として取り扱われます。
問題文の場合は、道路が作業場で、しかも、常に自動車などによる交通危険にさらされている場所で休憩せざるを得なかった事情にありました。このような事情のため生じた負傷は、業務上の負傷となります。
(昭25.6.8基災収1252号)
②【H26年出題】
明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指導監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

【解答】
②【H26年出題】 ×
★ポイント! 出張中の災害について
出張中は、全般的に業務遂行性があり、その間の災害には業務起因性が認められ、一般的に業務上と認められます。ただし、積極的な私的行為や恣意的行為で自ら災害を発生させた場合などは業務上と認められません。
出張については、自宅を出てから自宅に帰るまでが出張途上にあると考えられます。問題文のように、出張の順路の一部が、通常の通勤経路と重複していたとしても、出張業務遂行中とみられます。
「通勤災害」ではなく、「業務災害」となります。
(昭34.7.15基収第2980号)
③【H27年出題】
会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。

【解答】
③【H27年出題】 〇
★ポイント! 運動会、宴会などの行事に参加中の災害について
全職員について参加が命じられ、これに参加すると出勤扱いとされるような会社主催の行事に参加する場合等は業務となります。
参加が推奨されているが任意である社内の親睦野球大会での負傷は、業務上の負傷に該当しません。
(平成18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-221 4.4
社労士受験のための 労災 未支給の保険給付の請求
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
未支給の保険給付について条文を読んでみましょう。
第11条 ① 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 ② 死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、①に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 ③ 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、①に規定する順序(遺族補償年金については第16条の2第3項に、複数事業労働者遺族年金については第20条の6第3項において準用する第16条の2第3項に、遺族年金については第22条の4第3項において準用する第16条の2第3項に規定する順序)による。 ④ 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 |
★ 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金、遺族年金については、転給があるため、未支給の保険給付を請求できる遺族の範囲が違います。
★ 保険給付の請求をしていない者が死亡した場合は、①に規定する者が、自己の名で保険給付を請求できます。
★ 「年金」の受給権者が死亡した場合は、必ず未支給年金が発生します。年金は死亡した月まで支給され、「後払い」だからです。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】※改正による修正あり
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
★ 未支給の保険給付を請求することができるのは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものです。
★ 遺族補償年金については、未支給の遺族補償年金を請求できるのは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族です(複数事業労働者遺族年金、遺族年金も同じです。)。
(第11条第1項)
②【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】
②【H30年出題】 〇
例えば、遺族補償年金を受ける権利を有する者が4月20日に死亡した場合、4月分が未支給になります。未支給の遺族補償年金は、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」が、自己の名で、請求できます。
(第11条第1項)
③【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかったときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができる。

【解答】
③【H30年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合で、「その死亡した者が死亡前にその遺族補償年金を請求していなかった」ときは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」が、自己の名で、その遺族補償年金を請求することができます。
(第11条第2項)
④【H30年出題】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡し、その者が死亡前にその保険給付を請求していなかった場合、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

【解答】
④【H30年出題】 〇
手続を簡素化するための規定です。未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人(代表者)がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人(代表者)に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます。
(第11条第4項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-210
R6.3.24 障害補償年金の自然的経過による変更
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
障害の程度が自然的経過により変更した場合の規定をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
障害補償年金を受ける労働者が対象です。(障害補償一時金は対象になりません。)
障害の程度が、自然的経過により変更(増進・軽減)した場合、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。
(例)
・5級の障害補償年金を受けていた労働者の障害の程度が、自然的経過により3級に増進した場合
↓
3級の障害補償年金が支給され、その後は5級の障害補償年金は支給されません。
・7級の障害補償年金を受けていた労働者の障害の程度が、自然的経過により9級に軽減した場合
↓
9級の障害補償一時金が支給され、その後は7級の障害補償年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「障害補償年金」を受ける者の障害の程度が、自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付(障害補償年金又は障害補償一時金)が支給されます。その後は、従前の障害補償年金は支給されません。
(第15条の2)
②【H30年出題】 〇
「障害補償一時金」を受けた者については、障害の程度が自然的経過により変更しても、障害補償給付の変更は行われません。
(第15条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-191
R6.3.5 遺族補償年金の受給資格者と受給権者
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
★遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。
ただし、「妻」以外の者は、労働者の死亡の当時、「年齢要件」か「障害条件」に該当した場合に限られます。
要件に該当する者が「受給資格者」となります。
受給資格者には順位があり、年金を受けることができるのは受給資格者の中の最先順位者です。年金を受ける者を「受給権者」といいます。
順位は以下の通りです。
① | 妻(年齢要件、障害要件はありません) 夫(60歳以上又は一定の障害) |
② | 子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は一定の障害) |
③ | 父母(60歳以上又は一定の障害) |
④ | 孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は一定の障害) |
⑤ | 祖父母(60歳以上又は一定の障害) |
⑥ | 兄弟姉妹(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある又は60歳以上又は一定の障害) |
⑦ | 夫(55歳以上60歳未満) |
⑧ | 父母(55歳以上60歳未満) |
⑨ | 祖父母(55歳以上60歳未満) |
⑩ | 兄弟姉妹(55歳以上60歳未満) |
(第16条の2第1項、3項、昭40年法附則43条)
★転給とは?
最先順位者が失権した場合に、次の順位の者が受給権者になることです。
では、過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。
②【R2年出題】
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。
③【H19年出題】
遺族補償年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
④【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「夫」は、「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
「障害の状態にない50歳の夫」は、どちらにも当てはまりませんので、遺族補償年金の受給資格者になりません。
(第16条の2第1項)
②【R2年出題】 ×
「子」は「年齢要件」か「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
19歳の大学生は、年齢要件を満たしませんので、一定の障害状態にない場合は、受給資格者になりません。
17歳の高校生は、年齢要件を満たしますので、一定の障害状態になくても、受給資格者になります。
(第16条の2第1項)
③【H19年出題】 〇
「第5級以上」、「労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度」がキーワードです。
(則第15条)
④【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
「遺族補償年金」は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければなりません。
一方、「遺族補償一時金」は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなくても、受けられる可能性があります。
(第16条の2第1項、第16条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労働者災害補償保険法
R6-178
R6.2.21 心理的負荷による精神障害の認定基準について
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
仕事が原因のストレス(業務による心理的負荷)で発病した精神障害については、労災認定の基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が定められています。
要件を満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
ちなみに、労働基準法施行規則別表第1の2第9号は、「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
②【H30年出題】
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。
③【H30年出題】
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。
④【H30年出題】
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
⑤【H30年出題】※改正による修正あり
認定基準においては、「ハラスメントやいじめのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

【解答】
①【H30年出題】 〇
★精神障害の認定要件について
精神障害の認定の要件は①、②、③のいずれも満たすことです。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
②【H30年出題】 ×
★業務による強い心理的負荷の有無の判断について
精神障害を発病した労働者が、その出来事及び出来事後の状況を主観的にどう受け止めたかによって評価するのではなく、同じ事態に遭遇した場合、同種の労働者が一般的にその出来事及び出来事後の状況をどう受け止めるかという観点から評価するとされています。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
③【H30年出題】 ×
★業務による心理的負荷評価表について
「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「中」、「弱」の三段階に区分されます。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
④【H30年出題】 ×
★長時間労働等の心理的負荷の評価について
発病直前の1か月におおむね「160」時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とするとされています。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
⑤【H30年出題】 ×
★業務による心理的負荷の評価期間について
業務による心理的負荷の評価期間は発病前おおむね6か月です。
しかし、心理的負荷を的確に評価するため、ハラスメントやいじめのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前おおむね6か月の期間にも継続しているときは、「開始時からのすべての行為」を評価の対象とするとされています。
(令5.9.1基 発 0901 第2 号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-168
R6.2.11 休業補償給付の基本問題
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
休業補償給付の条文を読んでみましょう。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。・・・(※以下省略します。) |
休業補償給付は、以下の要件を満たした場合に支給されます。
・「業務上」の傷病による療養のため
↓
・労働することができないため
↓
・賃金を受けない
休業補償給付の額は、1日当たり給付基礎日額の100分の60で、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
②【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。
③【H30年出題】
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
④【H30年出題】
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。
⑤【H30年出題】
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】
①【H24年出題】 〇
療養補償給付は、療養中に受けられる治療等のことです。休業補償給付は療養中に受けられる所得補償です。目的が違いますので同時に受けることができます。
(法第13条、第14条)
②【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも療養中に受けられる所得補償ですので、同時に支給されることはありません。
(法第18条第2項)
※ 年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わります。
例えば、1月に傷病補償年金を支給すべき事由が生じた場合は、傷病補償年金は2月から支給され、1月中は「休業補償給付」が支給されます。
③【H30年出題】 〇
労働基準法では、業務災害について補償を行うことを使用者に義務付けています。(災害補償といいます)
労働基準法第76条第1項では、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。」と規定されています。
なお、労働基準法の災害補償の事由について、労働者災害補償保険法から労働基準法の災害補償に相当する給付が行なわれる場合は、使用者は災害補償を行う責を免れます。(労働基準法第84条)
そのため、労災保険から休業補償給付が行われるときは、事業主は、労働基準法の休業補償を行う義務はなくなります。
ただし、休業の初日から第3日目までの期間は、労災保険の休業補償給付が行われませんので、事業主は労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければなりません。
(労基法第76条、第84条)
ちなみに、通勤災害、複数業務要因災害には、労働基準法の災害補償責任はありません。
④【H30年出題】 ×
休業補償給付は、会社の所定休日にも支給されます。
⑤【H30年出題】 〇
「平均賃金の100分の60以上の金額」が支払われている場合は、「休業する日」に該当しません。
所定労働時間の全部労働不能の労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、「休業する日」に該当しないので、休業補償給付は支給されません。
(昭40.9.15基災発第14号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-158
R6.2.1 派遣労働者に係る労災保険給付
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
★労働者派遣の「派遣元」「派遣先」「派遣労働者」の三者間の関係を確認しましょう。
① 派遣元と派遣労働者との間 → 労働契約関係にあります。
② 派遣元と派遣先との間 → 労働者派遣契約を締結し、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣します。
③ 派遣先 → 派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令します。
★労働者派遣事業に対する労働者災害補償保険は、派遣元事業主の事業が適用事業となります。
(参考 S61.6.30発労徴41号、基発第383号)
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある場合には、一般に業務遂行性があるものとして取り扱うこととされている。
②【R1年出題】
派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。
③【R1年出題】
派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。
④【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。
⑤【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

【解答】
①【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る業務災害の認定について
・派遣労働者が派遣元事業主との間の労働契約に基づき派遣元事業主の支配下にある
・派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき派遣先事業主の支配下にある
↓
業務遂行性があります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
②【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る業務災害の認定について
・派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為は、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば
↓
業務遂行性があります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
③【R1年出題】 〇
★派遣労働者に係る通勤災害の認定について
・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となります。そのため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となります。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
④【R1年出題】 〇
★派遣労働者の保険給付の請求について
・当該派遣労働者の「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することになっ ています。
(S61.6.30発労徴41号、基発第383号
⑤【R1年出題】 ×
★派遣労働者の保険給付の請求について
・保険給付請求書の事業主の証明は「派遣元事業主」が行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 労災保険法
R6-148
R6.1.22 支給制限(労働者へのペナルティ)
過去問から学びましょう。
今日は労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。 ② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
労働者に非がある場合は、労災の保険給付の支給制限が行われます。
①「故意に」は「行わない(絶対)」、②「故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない」は「全部又は一部を行わないことができる(裁量)」です。違いに注意しましょう。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
②【H26年出題】
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
③【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意に自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
④【H26年出題】
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
⑤【R2年出題】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
⑥【H26年出題】
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
⑦【H28年選択式】
労災保険法第13条第2項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。労災保険法第12条の2の2第2項によれば、「労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて< B >に従わないことにより」、負傷の回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「故意」とは、自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容することをいいます。
(労災保険法第12条の2の2第1項、S40.7.31基発901号)
②【H26年出題】 〇
労働者が「故意に」自らの負傷を生じさせたときは、「政府は保険給付を行わない。」
(労災保険法第12条の2の2第1項)
③【H26年出題】 〇
労働者が「故意に」自らの死亡の直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は「保険給付を行わない。」
(労災保険法第12条の2の2第1項)
④【H26年出題】 〇
「故意の犯罪行為」により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意によるものです。
(労災保険法第12条の2の2第2項、S40.7.31基発901号)
⑤【R2年出題】 〇
労働者が「重大な過失」により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
「重大でない過失」の場合は、保険給付の全部又は一部を行わないことはできません。
(労災保険法第12条の2の2第2項)
⑥【H26年出題】 〇
労働者が「正当な理由なく療養に関する指示に従わない」ことにより負傷の回復を妨げた場合は、政府は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」
(労災保険法第12条の2の2第2項)
⑦【H28年選択式】
A 療養の費用
B 療養に関する指示
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年の問題より 労災保険法
R6-133
R6.1.7 複数業務要因災害に係る労災保険給付額
まず、用語の定義を確認しましょう。
★複数事業労働者とは
事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者のことです。(法第1条)
★複数業務要因災害とは
複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のことです。(法第7条)
複数業務要因災害の対象になる傷病は、脳・心臓疾患、精神障害などです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
新卒で甲会社に正社員として入社した労働者Pは、入社1年目の終了時に、脳血管疾患を発症しその日のうちに死亡した。Pは死亡前の1年間、毎週月曜から金曜に1日8時間甲会社で働くと同時に、学生時代からパートタイム労働者として勤務していた乙会社との労働契約も継続し、日曜に乙会社で働いていた。また、死亡6か月前から4か月前は丙会社において、死亡3か月前から死亡時までは丁会社において、それぞれ3か月間の期間の定めのある労働契約でパートタイム労働者として、毎週月曜から金曜まで甲会社の勤務を終えた後に働いていた。Pの遺族は、Pの死亡は業務災害又は複数業務要因災害によるものであるとして所轄労働基準監督署長に対し遺族補償給付又は複数事業労働者遺族給付の支給を求めた。当該署長は、甲会社の労働時間のみでは業務上の過重負荷があったとはいえず、Pの死亡は業務災害によるものとは認められず、また甲会社と乙会社の労働時間を合計しても業務上の過重負荷があったとはいえないが、甲会社と丙会社・丁会社の労働時間を合計した場合には業務上の過重負荷があったと評価でき、個体側要因や業務以外の過重負荷により発症したとはいえないことから、Pの死亡は複数業務要因災害によるものと認められると判断した。Pの遺族への複数事業労働者遺族給付を行う場合における給付基礎日額の算定に当たって基礎とする額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(A) 甲会社につき算定した給付基礎日額である。
(B) 甲会社・乙会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
(C) 甲会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
(D) 甲会社・丙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。
(E) 甲会社・乙会社・丁会社それぞれにつき算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額である。

【解答】 E
■ 複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、「当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額とする。ただし、第9条第1項第5号の規定は、適用しない。」と」規定されています。(則第9条の2の2第1号)
■ 複数事業労働者の平均賃金相当額の算定期間と算定方法の「原則」を確認しましょう。
複数事業労働者に係る平均賃金相当額の原則的な算定期間は、傷病等の発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)以前3か月間であり、平均賃金相当額を算定すべき各事業場において賃金締切日がある場合は事業場ごとに算定事由発生日から直近の賃金締切日より起算すること。 (令和2年8月21日基発0821第2号) |
次に「複数業務要因災害」の場合を確認しましょう。
複数業務要因災害は原則として脳・心臓疾患及び精神障害を想定しています。
複数業務要因災害として認定される場合、どの事業場においても業務と疾病等との間に相当因果関係は認められません。
・遅発性疾病等の診断が確定した日にいずれかの事業場に使用されている場合は、当該事業場について当該診断確定日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月に支払われた賃金により平均賃金相当額を算定します。
・遅発性疾病等の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、遅発性疾病等の診断が確定した日までの間に他の事業場から賃金を受けている場合は、当該事業場の平均賃金相当額について、直前の賃金締切日以前3か月間において支払われた賃金により算定します
(令和2年8月21日基発0821第2号)
|
| 4か月前 ▼ |
| 3か月前 ▼ | 死亡 ▼ |
甲会社 |
|
| |||
乙会社 |
|
| |||
丙会社 |
|
|
| ||
丁会社 |
|
|
| ||
遅発性疾病等の診断が確定した日に使用されている「甲会社」、「乙会社」、「丁会社」で診断確定日以前3か月間(賃金締切日がある場合は、直近の賃金締切日以前3か月間)に支払われた賃金で平均賃金相当額を算定します。
丙会社は、「3か月前の日を始期として、遅発性疾病等の診断が確定した日までの間」に賃金を受けていませんので、計算に入りません。
(令和2年8月21日基発0821第2号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-083
R5.11.18 労災保険と「厚生年金保険・国民年金」との調整
過去問で解ける問題をみていきましょう。
今日は労災保険法です。
労災保険の保険給付と、「国民年金・厚生年金保険」の年金は、併給できます。
ただし、「同一の事由」で支給される場合は、「労災保険」の年金たる保険給付が減額されます。同一事由による補償が二重になることを防ぐためです。労災年金は減額されますが、「国民年金・厚生年金」は全額支給されます。「国民年金・厚生年金」は、本人が保険料を負担することにより、支給されるものだからです。
では、過去問をどうぞ!
①【H18年出題】(修正あり)
労災保険の年金たる保険給付(以下「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額が全額支給される。
②【H12年出題】
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。
③【H12年出題】
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。

【解答】
①【H18年出題】 ×
労災年金と「同一の事由」により厚生年金保険の年金又は国民年金の年金が支給される場合は、労災年金は、「減額」して支給されます。
(法別表第1)
②【H12年出題】 〇
休業補償給付を受ける労働者が「同一の事由」について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、休業補償給付の額が減額されます。
(法第14条第2項)
同一の事由で厚生年金・国民年金が支給される場合に調整される労災保険の保険給付は、年金だけでなく休業補償給付も対象になります。
③【H12年出題】 〇
同時に厚生年金保険法の老齢厚生年金又は国民年金法の老齢基礎年金を受けることができる場合でも、労災年金は、全額支給されます。給付事由が異なるためです。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
(ア)
同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額とする。
(イ)
障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
(ウ)
障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
(エ)
同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
(オ)
遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。

【解答】
(ア) 〇
「同一の事由」により障害補償年金と「障害厚生年金及び障害基礎年金」を受給する場合、障害補償年金は減額され、障害補償年金の額は、調整率を乗じて得た額となります。問題文の場合、調整率は「0.73」です。
(別表第1)
政令で定める率の一覧表(施行令第2条~第7条)
| 厚生年金 + 国民年金 |
厚生年金のみ |
国民年金のみ |
障害補償年金 複数事業労働者障害年金 障害年金 | 障害厚生年金 +障害基礎年金 0.73 | 障害厚生年金
0.83 | 障害基礎年金
0.88 |
傷病補償年金 複数事業労働者傷病年金 傷病年金 | 障害厚生年金 +障害基礎年金 0.73 | 障害厚生年金
0.88 | 障害基礎年金
0.88 |
遺族補償年金 複数事業労働者遺族年金 遺族年金 | 遺族厚生年金 +遺族基礎年金 又は寡婦年金 0.80 | 遺族厚生年金
0.84 | 遺族基礎年金 又は寡婦年金
0.88 |
※休業補償給付の額を調整する場合は、傷病補償年金と同じ調整率を使います。
(イ) ×
既に受給している障害基礎年金と、新たに受け取る障害補償年金は、支給事由が異なります。そのため、障害補償年金の額は調整されず、全額が支給されます。
(ウ) ×
障害基礎年金と遺族補償年金は支給事由が異なりますので、遺族補償年金は全額支給されます。
(エ) 〇
同一の事由により遺族補償年金と「遺族厚生年金及び遺族基礎年金」を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80を乗じて得た額となります。
(オ) ×
遺族基礎年金と障害補償年金は支給事由が異なりますので、障害補償年金は、全額支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労災保険法
R6-052
R5.10.18 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
今日は、労災保険法です。
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」の基本的な考え方を確認しましょう。
・業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があります。そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り扱われます。
・脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積が考慮されます。
・業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表される業務量や、業務内容、作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断する必要があります。
次に、「認定要件」を確認しましょう。
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱われます。
(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(「短期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
※(1)「発症前の長期間」とは、発症前おおむね6か月間をいいます
(2)「発症に近接した時期」とは、発症前おおむね1週間をいいます。
(参照:令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
では、過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。
②【R4年出題】
心理的負荷を伴う業務については、精神障害の業務起因性の判断に際して、負荷の程度を評価する視点により検討、評価がなされるが、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しては、同視点による検討、評価の対象外とされている。
③【R4年出題】
急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から1週間前までの間が評価期間とされている。

【解答】
①【R4年出題】 〇
「短期間の過重業務と発症との関連性」を時間的にみた場合、業務による過重な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられます。次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか否かを判断することとされています。
① 発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否かを判断すること。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
②【R4年出題】 ×
心理的負荷を伴う業務については、別表1及び別表2に掲げられている日常的に心理的負荷を伴う業務又は心理的負荷を伴う具体的出来事等について、負荷の程度を評価する視点により検討し、評価することとされています。
心理的負荷を伴う業務については、脳・心臓疾患の業務起因性の判断に際しても、負荷の程度を評価する視点による検討、評価の対象になります。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
③【R4年出題】 ×
異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされていますので、評価期間は、「発症直前から前日までの間」とされています。
(令和3年9月1 4日付 基発 0 9 1 4 第 1 号)
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914 第1 号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。
ア 狭心症
イ 心停止(心臓性突然死を含む。)
ウ 重篤な心不全
エ くも膜下出血
オ 大動脈解離

【解答】
【R5年出題】 5つ
なお、認定基準で対象疾病として取り扱われる脳・心臓疾患は以下の通りです。
< 脳血管疾患>
(1) 脳内出血(脳出血)
(2) くも膜下出血
(3) 脳梗塞
(4) 高血圧性脳症
< 虚血性心疾患等>
(1) 心筋梗塞
(2) 狭心症
(3) 心停止(心臓性突然死を含む。)
(4) 重篤な心不全
(5) 大動脈解離
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 労災保険法
R6-043
R5.10.9 労災不服申立てのポイント!
今日は、労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第38条 ① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 ② 審査請求をしている者は、審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 ③ 審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第40条 第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 |
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、都道府県労働局長に対して審査請求を行うことができる。
②【R5年出題】
審査請求をした日から起算して1か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
③【R5年出題】
処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
労災保険給付に関する決定に不服のある者は、「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を行うことができます。都道府県労働局長ではありません。
②【R5年出題】 ×
審査請求をした日から起算して「3か月」を経過しても審査請求についての決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる、です。1か月ではありません。
③【R5年出題】 ×
「処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する『労働者災害補償保険審査官の決定』を経た後でなければ、提起することができない。」です。
労働者災害補償保険審査官の決定に不服がある場合は、
①「労働保険審査会に再審査請求」→「処分の取消しの訴えを提起する」
②労働保険審査会に再審査請求をしないで、「処分の取消しの訴えを提起する」
のどちらでも選択することができます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-034
R5.9.30 労働者の死亡当時胎児であった子が出生したとき
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項、第2項 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 |
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが条件です。
また、妻以外の者は、労働者の死亡当時、「年齢要件」か、「障害要件」のどちらかを満たす必要があります。
過去問をどうぞ!
【H19年出題】
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族について、労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、その子は、将来に向かって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされ、また、その子が厚生労働省令で定める障害の状態で出生した場合についても、将来に向かって、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとみなされる。

【解答】
【H19年出題】 ×
労働者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、生まれたときから遺族補償年金の受給資格者となります。
労働者の死亡の当時胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたとみなされます。
しかし、労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態にあったものとはみなされません。そのため、そのような子の遺族補償年金の受給権は、「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」に失権します。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。

【解答】
【R5年出題】 ×
労働者の死亡当時、胎児であった子は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子」とみなされます。出生以後は遺族補償年金の受給資格者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-025
R5.9.21 遺族補償年金の受給資格者になる夫の要件
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
まず、条文を読んでみましょう。
第16条の2第1項 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 (1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 (2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 (3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 (4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたことが条件です。
また、妻以外の者は、年齢要件か障害要件を満たすことが条件です。
なお、昭和40年法附則第43条の遺族補償年金に関する特例により、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であったものは、遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。
では、過去問をどうぞ!
【R3年選択式】
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。
ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)、父母又は祖父母については、< A >歳以上であること。
2 子又は孫については、< B >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
3 兄弟姉妹については、< B >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は< A >歳以上であること。
4 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

【解答】
A60
B18
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。

【解答】
【R5年出題】 ×
夫は、年齢要件か障害要件のどちらかを満たす必要がありますので、妻の死亡当時、障害の状態にない50歳の夫は、遺族補償年金の受給資格者になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 労災保険法
R6-015
R5.9.11 障害補償給付 併合と併合繰上げ
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、労災保険法です。
まず、過去問からどうぞ!
【H30年出題】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級

【解答】
【H30年出題】 ×
①第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 → 「8級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の5級が2級繰り上がって「3級」となります。
②第4級、第5級の2障害がある場合 → 「5級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の4級が3級繰り上がって「1級」となります。
※問題文の2級は誤りです。
③第8級、第9級の2障害がある場合 → 「13級以上の身体障害が2以上あるとき」に該当しますので、重い方の8級が1級繰り上がって「7級」となります。
・ 障害等級は、別表第一に定めるところによります。
・ 障害が2以上あるときは、重い方の障害等級に該当する障害等級になるのが原則です。
・ 13級以上の障害が2つ以上あるときは、重い方の身体障害の該当する障害等級を 1級から3級繰り上げます。
①第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を1級繰り上げ
②第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を2級繰り上げ
③第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 重い方を3級繰り上げ
(例外)9級と13級の障害の場合は、障害補償一時金の額は、繰り上げられた8級(503日分)ではなく、9級(391日分)と13級(101日分)の合算額(492日分)となります。
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
業務上の災害により、ひじ関節の機能に障害を残し(第12条の6)、かつ四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の、障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級として正しいものはどれか。
A 併合第10級
B 併合第11級
C 併合第12級
D 併合第13級
E 併合第14級

【解答】 C
12級と14級の障害があるときは、併合して、重い方の障害等級12級が全体の障害等級となります。
なお、「13級以上の障害が2以上ある」には該当しないので、繰上げはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 労災保険法
R6-005
R5.9.1 労災選択式は休業補償給付と社会復帰促進等事業からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は労災保険法です。
 A~Cは休業補償給付の問題です。
A~Cは休業補償給付の問題です。
条文を読んでみましょう。
第14条第1項 休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、一日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下この項において「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(第8条の2第2項第2号に定める額(以下この項において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあつては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。 |
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による「(A)療養」のため労働することができないために賃金を受けない日の第「(B)4」日目から支給されます。
休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の「(C)100分の60」に相当する額です。
※部分算定日(労働者が所定労働時間のうちその一部分のみ労働する日など)の休業補償給付の額について確認しましょう。
・休業補償給付の額は、(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)の100分の60です。
・年齢階層別の最高限度額が適用されている場合は、最高限度額の適用がないものとした給付基礎日額で算定します。
・(給付基礎日額-部分算定日に支払われる賃金の額)が最高限度額を超える場合は、最高限度額の100分の60となります。
 D・Eは、社会復帰促進等事業の問題です。
D・Eは、社会復帰促進等事業の問題です。
条文を読んでみましょう。
第29条第1項 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 3 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 |
今回は、(D)健康診断と(E)賃金が問われました。
<賃金の支払の確保を図るために必要な事業とは?>
賃金の支払の確保等に関する法律で、「未払賃金立替払制度」が設けられています。
この制度により、企業が倒産したことで賃金が支払われずに退職した労働者に対して、未払賃金の立替払が行われます。
未払賃金の立替払事業は、社会復帰促進等事業の一環で行われています。
労災保険は、業務災害に対する使用者責任を国が代行する目的で作られた保険です。
未払賃金の立替払制度は、賃金支払に対する使用者責任を国が代行するもので、労災保険の目的と共通するからです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 適用
労災保険法 適用
R5-359
R5.8.21 労災保険が適用される労働者
労災保険の保護の対象になる労働者を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第3条 ① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 ② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R1年選択式】 ※改正による修正あり
労災保険法第1条によれば、労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的とする。同法の労働者とは、< A >法上の労働者であるとされている。そして同法の保険給付とは、業務災害に関する保険給付、複数業務要因災害に関する保険給付、通勤災害に関する保険給付及び< B >給付の4種類である。保険給付の中には一時金ではなく年金として支払われるものもあり、通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるのは、障害年金、遺族年金及び< C >年金である。
②【H26年出題】
2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。
③【H26年出題】
ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。
④【H26年出題】
船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
⑤【R1年出題】
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

【解答】
①【R1年選択式】
A 労働基準
B 二次健康診断等
C 傷病
★労災保険法の労働者とは、労働基準法上の労働者です。
②【H26年出題】 〇
労働者は、労働時間に関係なく労災保険が適用されます。また、2以上の適用事業所に使用される場合は、それぞれの事業で、労災保険法が適用されます。
③【H26年出題】 〇
出向労働者の保険関係の所在については、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定されます。
(昭和35.11.2基発第932号)
④【H26年出題】 ×
船員法上の船員には、労災保険法が適用されます。
⑤【R1年出題】 ×
労働者派遣事業の労災保険の適用は、派遣元事業主の事業が適用事業となります。
派遣労働者の保険給付の請求に当たり、保険給付請求書の事業主の証明は「派遣元事業主」が行います。
(昭和61.6.30発労徴41・基発383号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 遺族補償給付
労災保険法 遺族補償給付
R5-336
R5.7.29 遺族補償給付(遺族補償年金・遺族補償一時金)のポイント
今日は「遺族補償給付」をみていきます。
「遺族補償給付」には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
②【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
③【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
④【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
⑤【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
①【H28年出題】 〇
遺族補償給付は、労働者が業務上死亡した場合に支給されます。
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合は、業務上の死亡に該当します。また、妻は遺族補償年金を受けるに当たり、年齢・障害要件は問われませんので、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた場合は、遺族補償年金を受けることができます。
ポイント!
「年金」を受けるには、死亡当時「生計を維持」していたことが条件です。
「一時金」の場合は、「生計維持」していなくても、受けられる場合があります。
②【H28年出題】 ×
相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態があれば「生計を維持していた」ものにあたります。共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになります。
(S41.1.31基発73号)
③【H28年出題】 〇
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、「直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき」は消滅します。
自分の伯父は直系血族・直系姻族ではありませんで、伯父の養子となったときは、遺族補償年金を受ける権利は消滅します。
(法第16条の4第1項第3号)
④【H28年出題】 ×
遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることがあります。
遺族補償一時金が支給される要件は、次の2つです。
① 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき。
② 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合に、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、支給された遺族補償年金の額及び前払一時金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合
例えば、遺族補償年金を受けていた妻が再婚し、遺族補償年金の受給権が消滅しました。他に遺族補償年金の受給資格者がなく、支給された年金と前払一時金の額が給付基礎日額の1000日未満の場合は、1000日分と既に支給された年金等の合計額との差額が、妻に支給されます。
このように、遺族補償年金の受給権を失権した者が、遺族補償一時金の受給権者になることもあります。
(法第16条の6)
⑤【H28年出題】 〇
遺族補償一時金の受給資格者は以下の通りです。
① 配偶者
② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
③生計を維持していない子・父母・孫・祖父母
④兄弟姉妹
労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった兄弟姉妹でも、遺族補償一時金の受給者となることがあります。
(法第16条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 療養の給付
労災保険法 療養の給付
R5-335
R5.7.28 療養の給付の請求書の記載事項
今日は、療養の給付の請求書に記載する事項をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 |
療養補償給付は、原則として「療養の給付」(現物給付)です。
「療養の給付をすることが困難な場合」、「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」は、例外で「療養の費用の支給」(現金給付)が行われます。
なお、療養補償給付は「治る」まで行われます。
では、過去問をどうぞ!
【H25年出題】
療養給付たる療養の給付を受けようとする者が、療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない請求書に記載しなければならない事項として、労災保険法施行規則に掲げられていないものはどれか。
(A) 災害の発生の時刻及び場所
(B) 通常の通勤の経路及び方法
(C) 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地
(D) 加害者がいる場合、その氏名及び住所
(E) 労働者の氏名、生年月日及び住所

【解答】 (D)
「療養給付」とありますので、通勤災害に関する問題です。
現物給付の「療養の給付」の請求書は、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出します。
その請求書に記載しなければならない事項の中に、「加害者がいる場合、その氏名及び住所」はありません。
(則第18条の5)
<参考>第三者行為について
第三者行為については、以下のように規定されています。
則第22条
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働者災害補償保険法 通勤災害
労働者災害補償保険法 通勤災害
R5-311
R5.7.4 逸脱・中断(日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの)
通勤経路を逸脱・中断した場合について条文を読んでみましょう。
第7条第3項 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 |
中断は「寄り道」、逸脱は「回り道」のイメージです。
通勤経路を逸脱・中断した場合、逸脱・中断の間とその後の移動は通勤になりません。
例外的に、逸脱、中断が、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合は、逸脱の間・中断の間は通勤となりませんが、その後の移動は通勤となります。
では、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを条文で読んでみましょう。
則第8条 (日常生活上必要な行為) 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3 選挙権の行使その他これに準ずる行為 4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤となる。
②【H27年出題】
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
③【H28年出題】
会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。
④【R3年出題】
腰痛の治療のため、帰宅途中に病院に寄った労働者が転倒して負傷した。病院はいつも利用している駅から自宅とは反対方向にあり、負傷した場所はその病院から駅に向かう途中の路上であった。この場合は、通勤災害と認められない。
⑤【H25年出題】
女性労働者が1週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所から帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
逸脱・中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合であったとしても、逸脱の間、中断の間は、通勤となりません。
②【H27年出題】 ×
出退勤の途中に、理髪店や美容院にたちよる行為は、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当します。
退勤の途中で美容院に立ち寄り、髪のセットをしている間は通勤になりませんが、その後直ちに合理的な経路に復した後は、通勤に該当します。
(S58.8.2基発420)
③【H28年出題】 〇
通常の医療行為だけでなく、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」に該当します。
(S48.11.22 基発644)
④【R3年出題】 〇
自宅と反対方向にある病院から駅に向かう途中の路上は、逸脱の間(合理的経路に復する前)ですので、通勤災害となりません。
⑤【H25年出題】 〇
要介護状態にある夫の父の介護の場合は、介護終了後に合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 通勤災害
労災保険法 通勤災害
R5-294
R5.6.17 通勤の定義「就業に関し」
https://youtu.be/QpSV5kMZ5lM 「通勤」の定義を条文で読んでみましょう。
法第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
今日は、「就業に関し」に注目しましょう。
「就業に関し」とは、往復行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを必要とする趣旨を示しています。通勤と認められるには、往復行為が業務と密接な関連をもって行われることを要します。
(H18.3.31基発第0331042号)
では、過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合は、通勤に該当することはない。
②【H24年出題】
運動部の練習に参加する目的で、午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合も、通勤に該当する。
③【H24年出題】
業務の終了後、事業場施設内で、サークル活動をした後に帰宅する場合は、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除いても、通勤に該当することはない。
④【H24年出題】
昼休みに自宅まで時間的に十分余裕をもって往復できる労働者が、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤する往復行為は、通勤に該当しない。

【解答】
①【H24年出題】 ×
所定の就業日に所定の就業開始時刻に合わせて住居を出て就業の場所へ向う場合は、「寝すごしによる遅刻」、「ラッシュを避けるための早出」等、時刻的に若干の前後があっても就業との関連性があるとされます。
寝過ごしにより就業場所に遅刻した場合でも、要件を満たせば通勤に該当します。
(H18.3.31基発第0331042号)
②【H24年出題】 ×
午後の遅番の出勤者であるにもかかわらず、朝から住居を出る等、所定の就業開始時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合は、業務以外の目的のために行われるものと考えられ、就業との関連性はないと認められます。
問題文の場合は、運動部の練習に参加する目的で行われるものと考えられるので、通勤には該当しません。
(H18.3.31基発第0331042号)
③【H24年出題】 ×
業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えない、とされています。
(H18.3.31基発第0331042号)
④【H24年出題】 ×
通勤は1日について1回のみしか認められないものではありません。昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があって帰宅するような場合には、昼休みについていえば、午前中の業務を終了して帰り、午後の業務に就くために出勤するものと考えられるので、その往復行為は就業との関連性を認められます。
問題文は、通勤に該当します。
(H18.3.31基発第0331042号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 事業主からの費用徴収
労災保険法 事業主からの費用徴収
R5-278
R5.6.1 保険関係成立届を提出しない事業主に対する費用徴収
保険関係成立届を提出していない期間中に事故が発生した場合、事業主は、保険給付に要した費用を徴収されることがあります。
条文を読んでみましょう。
第31条第1項 政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあっては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 1. 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出が行われていない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 2. 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故 3. 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |
★今日は、1.の故意又は重大な過失により、事業主が保険関係成立届の提出を行っていない期間中に生じた事故についての費用徴収をみていきます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
②【H27年出題】
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
③【R1年選択式】
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後< A >以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから< B >を経過してもなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。

【解答】
①【H27年出題】 〇
「故意」と認定された場合は、費用徴収率が100%となります。
★故意の認定について
① 事業主が、当該事故に係る事業に関し、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署又は所轄公共職業安定所から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう指導を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合
② 事業主が、当該事故に係る事業に関し、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう勧奨(「加入勧奨」という。)を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合
(H17.9.22基発第0922001号)
「指導」や「加入勧奨」を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合は「故意」と認定されます。
②【H27年出題】 〇
「重大な過失」と認定された場合は、費用徴収率が40%となります。
★重大な過失の認定について
事業主が、当該事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、かつ、保険関係成立日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していないとき
(H17.9.22基発第0922001号)
③【R1年選択式】
A 10日
B 1年
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 傷病補償年金
労災保険法 傷病補償年金
R5-250
R5.5.4 傷病補償年金のポイント
傷病補償年金のポイントをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条の8第3項 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 1. 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級(1級~3級)に該当すること。 |
★療養開始後1年6か月を経過した日に要件に該当するとき
療養開始 1年6か月 治ゆ
療養補償給付 |
| |
休業補償給付 | 傷病補償年金 |
|
| ▲(1~3級) | ||
★療養開始後1年6か月を経過した日後に要件に該当することとなったとき
療養開始 1年6か月 治ゆ
療養補償給付 |
| |
休業補償給付 | 傷病補償年金 |
|
| ▲(1~3級) | ||
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。
②【H29年出題】
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。
③【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
④【H29年出題】
傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、所轄労働基準監督署長は、裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
労災保険の保険給付は、「請求」によって支給されます。
しかし、傷病補償年金は例外で、請求ではなく、所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定されるのがポイントです。
被災した労働者が療養開始後1年6か月を経過した日に要件に該当したときは、所轄労働基準監督署長は、傷病補償年金の支給の決定をしなければなりません。
そのため、労働者は、療養開始後1年6か月経過した日に治っていないときは、同日以降1か月以内に、「傷病の状態等に関する届」を提出しなければなりません。
(則第18条の2)
②【H29年出題】 〇
傷病補償年金の障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態で認定されます。
(則18条第2項)
③【H29年出題】 〇
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級(1から3級)に該当しなくなった場合、傷病補償年金の受給権は消滅します。
その後も療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができます。休業補償給付は請求が必要ですので注意してください。
療養開始 1年6か月
療養補償給付 | ||
休業補償給付 | 傷病補償年金 | 休業補償給付 |
▲(1~3級) ▲不該当
ちなみに年金は、受給権が消滅した月まで支給されます。
傷病補償年金は傷病等級に該当しなくなった月まで支給され、翌月から休業補償給付が支給されます。
④【H29年出題】 ×
法第18条の2で、「傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。」と規定されていて、傷病等級の変更も所轄労働基準監督署長の職権で行われます。
則第18条の3で、「所轄労働基準監督署長は、法第18条の2に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。」となっています。「裁量により、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 二次健康診断等給付
労災保険法 二次健康診断等給付
R5-238
R5.4.22 二次健康診断等給付のポイント
二次健康診断等給付は、脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するために行われます。
事業場で行われる定期健康診断など(一次健康診断)で異常の所見が認められた人が対象です。
二次健康診断等給付には、「二次健康診断」と「特定保健指導」があります。
二次健康診断は、脳血管と心臓の状態を把握する検査で、特定保健指導は、脳・心臓疾患の発症の予防のための面接による保健指導です。
条文を読んでみましょう。
第26条 ① 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断(一般健康診断)又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。 ② 二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。 1. 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査(①に規定する検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う医師による健康診断(1年度につき1回に限る。「二次健康診断」という。) 2. 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。) ③ 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
②【H30年出題】
特定保健指導は、医師又は歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
③【H30年出題】
二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われない。
④【H30年出題】
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。
⑤【H30年出題】
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】 〇
二次健康診断等給付の目的は発症の予防ですので、一次健康診断で既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者には行われません。症状を有する場合は、健康保険の保険給付や、労災保険の療養補償給付等の対象になります。
②【H30年出題】 ×
特定保健指導は、医師又は「保健師」による面接によって行われます。
具体的には、「栄養指導」、「運動指導」、「生活指導」が行われます。
③【H30年出題】 〇
既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、特定保健指導は行われません。
④【H30年出題】 〇
二次健康診断の実施の日から「3か月以内」に結果を証明する書面の提出を受けた場合は、事業者は、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければなりません。
(法第27条)
⑤【H30年出題】 〇
二次健康診断等給付は、労働者の請求に基づいて行われます。
現物給付ですので、請求書は健診給付病院等を経由して提出します。所轄労働基準監督署長ではなく、「所轄都道府県労働局長」に提出することがポイントです。
(則第18条の19)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 療養補償給付
労災保険法 療養補償給付
R5-224
R5.4.8 療養補償給付「療養の給付」について
療養補償給付は、現物給付の「療養の給付」が原則で、例外として、現金給付の「療養の費用の支給」があります。
今日は「療養の給付」をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 移送 ③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 |
では、さっそく過去問をどうぞ!
①【H30年出題】
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、病院又は診療所における療養に伴う世話その他の看護のうち、政府が必要と認めるものは含まれるが、居宅における療養に伴う世話その他の看護が含まれることはない。
②【R1年出題】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
③【H27年出題】
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
④【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

【解答】
①【H30年出題】 ×
療養補償給付としての療養の給付の範囲には、「居宅における療養に伴う世話その他の看護」も含まれます。
②【R1年出題】 〇
療養の給付は、「指定病院等」で行われます。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等でも、「指定病院等」に該当しないときは、療養の給付は行われません。
療養補償給付としての療養の給付が行われる「指定病院等」とは、問題文のとおり、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者です。
(則第11条)
③【H27年出題】 ×
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、請求書を、直接ではなく、「指定病院等を経由」して、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(則第12条)
④【H27年出題】 ×
療養の給付が行われるのは、治ゆするまでです。
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になると、療養の給付は行われません。
問題文のように、神経症状のような症状や障害が残ったとしても、治療の余地がなくなれば、療養の給付は行われません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 障害補償給付
労災保険法 障害補償給付
R5-210
R5.3.25 障害の程度が自然的経過により増進・軽減したとき
障害補償給付には、「障害補償年金」と「障害補償一時金」があります。
条文を読んでみましょう。
法第15条第1項 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 |
 「障害補償給付」には「年金」と「一時金」があることに注意してください。
「障害補償給付」には「年金」と「一時金」があることに注意してください。
障害等級第1級~7級は「年金」、障害等級第8級~14級は「一時金」が支給されます。
今日は、障害補償年金を受ける労働者の障害の程度が、自然的な経過により増進し、又は軽減した場合の改定についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
・ 条文の最初に注目してください。「障害補償給付」ではなく「障害補償年金」です。対象は、「障害補償年金」を受ける労働者に限られます。「障害補償一時金」には適用されません。
・「当該障害の程度に変更があった」とは、障害の程度が自然的な経過により増進又は軽減したことをいいます。
・新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するとは、例えば・・・
その1 障害等級3級の人の障害の程度が増進し2級になった場合は、2級の障害補償年金が支給され、従前の3級の障害補償年金は支給されません。
その2 障害等級5級の人の障害の程度が軽減し7級になった場合は、7級の障害補償年金が支給され、従前の5級の障害補償年金は支給されません。
その3 障害等級7級の人の障害の程度が軽減し10級になった場合は、10級の障害補償一時金が支給され、従前の7級の障害補償年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
自然的経過による変更で障害補償給付の変更が行われるのは、障害補償「年金」を受けている場合のみです。
②【H30年出題】 〇
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進又は軽減したとしても、障害補償給付の変更は適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 特別支給金
労災保険法 特別支給金
R5-200
R5.3.15 労災 特別支給金のポイント
★「特別支給金」とは
労災保険の保険給付の上乗せとして支給される給付です。
「社会復帰促進等事業」の中の「被災労働者等援護事業」の事業の一つとして行われています。
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類があります。
ボーナス特別支給金 |
一般の特別支給金 |
保険給付 |
例えば、「傷病補償年金」(保険給付)には、特別支給金として「傷病特別支給金」(一般の特別支給金)と「傷病特別年金」(ボーナス特別支給金)が上乗せされます。
傷病特別年金 |
傷病特別支給金 |
傷病補償年金 |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。
②【R2年出題】
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が150万円を超えることはない。
③【R1年出題】
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

【解答】
①【R1年出題】 〇
「傷病特別支給金」は傷病補償年金に上乗せされる一般の特別支給金です。
傷病特別支給金は、傷病等級に応じた定額です。第1級114万円、第2級107万円、第3級100万円です。
②【R2年出題】 〇
例えば、傷病補償年金の上乗せとして、「傷病特別支給金」と「傷病特別年金」があります。
「傷病特別支給金」は、①の問題でみましたように定額です。
「傷病特別年金」は、「算定基礎日額」を使って算定します。算定基礎日額は、算定基礎年額÷365日で計算します。
算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間の特別給与額の総額(直近1年間のボーナスの総額です)とするのが原則です。
(例外)
「給付基礎年額(給付基礎日額×365日)の20%に相当する額」と「特別給与の総額」を比較して、少ない方が算定基礎年額となります。
ただし、150万円を超える場合は、算定基礎年額は150万円となります。
そのため、問題文にもありますように、算定基礎年額が150万円を超えることはありません。
(特別支給金支給規則第6条第1項)
ちなみに、傷病特別年金の額は
1級 算定基礎日額×313日分
2級 算定基礎日額×277日分
3級 算定基礎日額×245日分
です。
③【R1年出題】 ×
特別加入者には、ボーナス特別支給金は支給されませんので、傷病特別支給金は支給されますが、傷病特別年金は支給されません。
特別加入者には、賃金やボーナスの概念がないためです。
(特別支給金支給規則第19条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 特別加入者
労災保険法 特別加入者
R5-188
R5.3.3 特別加入者の通勤災害
特別加入者には、「中小事業主等」、「一人親方等・特定作業従事者」、「海外派遣者」の3つの種類があります。
労災保険法は、「労働者」の業務災害や通勤災害などを保護するための保険です。しかし、労働者と同じような業務に従事することの多い中小事業主や一人親方等は、労災保険に特別加入することによって、労働者に準じて保護が受けられます。
また、労災保険は「属地主義」をとっていますので、例えば海外支店に転勤になった海外派遣者は、日本の労災保険の保護は受けられなくなります。しかし、労災保険に特別加入することによって、海外派遣者も労災保険の保護の対象となります。
特別加入者は、原則として労働者と同じ保護が受けられます。
しかし、「一人親方等・特定作業従事者」の一部は、通勤の実態がないなどの理由で通勤災害の保護の対象から除外されます。
今日は、通勤災害の保護の対象から除外される特別加入者を確認しましょう。
通勤災害の保護の対象から除外される特別加入者は以下の一人親方等、特定作業従事者です。(則第46条の22の2)
・自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業に従事する者 → 個人タクシー業者、個人貨物運送業者など ・漁船による水産動植物の採捕の事業(船員法第1条に規定する船員が行う事業を除く。)に従事する者 → 漁船による自営の漁業者 ・特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者 ・家内労働者 |
 ポイント!
ポイント!
・中小事業主等、海外派遣者は、すべて通勤災害の保護の対象です。
・通勤災害の保護から除外されるのは、「一人親方等、特定作業従事者」の「一部」です。全てではありませんので注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< A >はその一例に該当する。
選択肢
①医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者
②介護作業従事者
③個人タクシー事業者
④船員法第1条に規定する船員
②【H26年出題】
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
③【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
④【H22年出題】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。
⑤【R3年出題】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居と就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
①【H30年選択式】
③ 個人タクシー事業者
②【H26年出題】 〇
個人貨物運送業者には通勤災害に関する保険給付は支給されません。
③【H26年出題】 〇
家内労働者には通勤災害に関する保険給付は支給されません。
④【H22年出題】 ×
漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、住居と就業の場所との往復の実態が明確でないので、通勤災害に関する保険給付は支給されません。
⑤【R3年出題】 ×
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者は、住居と就業の場所との往復の実態が明確でないので、通勤災害に関する保険給付は支給されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 通勤災害
労災保険法 通勤災害
R5-178
R5.2.21 単身赴任者の住居間の移動
まず、通勤の定義を条文で確認しましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
|
 、
、 、
、 の移動が、通勤として労災保険の保護の対象になります。
の移動が、通勤として労災保険の保護の対象になります。
 は、複数で就業する労働者の事業場間の移動、
は、複数で就業する労働者の事業場間の移動、 は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動です。
は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動です。
今日は 「単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動」をみていきます。
「単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動」をみていきます。
例えば、大阪に家族を残し、東京に単身赴任している労働者が、大阪の帰省先住居から東京の赴任先住居に移動中に事故にあい負傷した場合、要件を満たせば通勤災害として労災保険の保険給付の対象となります。
では、過去問をどうぞ!
【R3年出題】
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1~2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関等の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害と認められない。

【解答】
【R3年出題】 〇
赴任先住居と帰省先住居の移動が通勤と認められるか否かのポイントをチェックしましょう。
・移動に反復・継続性が認められること
→ おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に、「反復・継続性」が認められます。
(H18.3.31基労管発第0331001号・基労補発第0331003号)
・帰省先住居から赴任先住居への移動の場合
→ 業務に就く当日又は前日に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。
※前々日以前に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。
・赴任先住居から帰省先住居への移動の場合
→ 業務に従事した当日又はその翌日に行われた場合は、就業との関連性を認めて 差し支えない。
※翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的理由があるときに限り、就業との関連性が認められる。
(H18.3.31基発第0331042号)
問題文は、交通機関等の状況等に問題はなかったが、夏季休暇の2日目(業務に従事した日の翌々日)に移動しています。そのため就業との関連性が認められませんので、通勤には該当しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 障害補償給付の額
労災保険法 障害補償給付の額
R5-166
R5.2.9 障害補償給付「加重障害」
既に身体障害のあった人が、新たな業務上の傷病によって同一の部位の障害の程度を加重したときは、その加重した程度で障害補償給付が行われます。「加重障害」といいます。
加重障害で給付される額は、加重された身体障害の等級の給付額と、既にあった身体障害の等級の給付額との差額となります。
条文を読んでみましょう。
則第14条第5項 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額)を差し引いた額による。 |
例えば
・既存の障害が5級(184日分)で、加重した障害が3級(245日分)の場合
新たに支給される年金は、61日分(245日分-184日分)で計算します。
ちなみに、既存の障害は、労災でも私傷病でも原因は問われませんが、既存の障害で労災保険から年金を受けている場合は、その年金は引き続き支給されます。
・既存の障害が14級(56日分)で、加重した障害が10級(302日分)の場合
246日分(302日分-56日分)の一時金が支給されます。
・既存の障害が8級(503日分の一時金)で、加重した障害が7級(131日分の年金)の場合
新たに支給される年金は、131日分-(503日分÷25)で計算します。
一時金は、年金の25年分です。一時金の日数を25で割った1年あたりの額との差額を出すのがポイントです。
では、過去問をどうぞ!
【R2年問5】
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11級の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 給付基礎日額の67日分
B 給付基礎日額の156日分
C 給付基礎日額の189日分
D 給付基礎日額の223日分
E 給付基礎日額の379日分

【解答】
「A 給付基礎日額の67日分」の障害補償一時金が支給されます。
既にあった障害は第11級、加重した障害は第12級で、どちらも「一時金」の等級です。
加重によって支給される一時金は、「223日分-156日分」=67日分で計算します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 遺族補償年金
労災保険法 遺族補償年金
R5-158
R5.2.1 遺族補償年金の受給資格者と受給権者
遺族補償年金を受ける資格のある遺族のことを「受給資格者」といいます。受給資格者には順位が定められていて、そのうち最先順位者が年金を受ける「受給権者」になります。
「受給資格者」は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。
ただし、「妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者については、労働者の死亡の当時、一定の年齢要件か一定の障害状態に該当した場合に限られます。
では受給資格者の範囲と順位を条文で読んでみましょう。
第16条の2 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4 前3号の年齢要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 ③ 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。 |
※労働者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、55歳上60歳未満であったものは遺族補償年金を受けることができる遺族とされます。(S40年改正法附則第43条)
順位を確認しましょう。
 妻・60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
妻・60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
 18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある子
18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある子
 60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
 18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある孫
18歳年度末までの間にある又は一定の障害の状態にある孫
 60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
 18歳年度末までの間にある又は60歳以上又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
18歳年度末までの間にある又は60歳以上又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
 55歳以上60歳未満の夫
55歳以上60歳未満の夫
 55歳以上60歳未満の父母
55歳以上60歳未満の父母
 55歳以上60歳未満の祖父母
55歳以上60歳未満の祖父母
 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
過去問をどうぞ!
①【H19年出題】
遺族補償年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。
②【R2年出題】
業務上の災害により死亡した労働者Yには2人の子がいる。1人はYの死亡の当時19歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう1人は、Yの死亡の当時17歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。2人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。

【解答】
①【H19年出題】 〇
障害等級第5級以上と、労働が高度の制限を受ける、がキーワードです。
(則第15条)
②【R2年出題】 ×
Yの死亡の当時19歳の子は、遺族の条件に当てはまりませんので、受給資格者にも受給権者にもなりません。
Yの死亡の当時17歳の子については、Yから定期的に養育費を送金されていて生計維持関係があるため、受給資格者となります。
遺族補償年金の受給資格者は17歳の子のみとなり、その子が受給権者となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 未支給の保険給付
労災保険法 未支給の保険給付
R5-149
R5.1.23 労災・未支給の保険給付を請求できる範囲
今日は、労災保険の未支給の保険給付をみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第11条第1項 労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。 |
未支給の保険給付を請求できるのは、
・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの
★ただし、遺族(補償)等年金の場合は範囲が違います。未支給の保険給付を請求できるのは、遺族(補償)等年金を受けることができる他の遺族となります。遺族(補償)等年金には転給があるからです。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】 ※改正による修正あり
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
②【H22年出題】
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
③【H30年出題】
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】
①【R2年出題】 〇
未支給の保険給付は、死亡した者の名ではなく、遺族が「自己の名」で請求することがポイントです。
②【H22年出題】 C
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順序は覚えましょう。
③【H30年出題】 〇
死亡した者と同順位の受給権者があるときは、未支給の保険給付の受給権者は、その者が第1位となります。死亡した者と同順位の受給権者がなく後順位の受給資格者があるときは次順位の受給資格者が、未支給の保険給付の受給権者の第1位となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法 傷病補償年金
労災保険法 傷病補償年金
R5-140
R5.1.14 傷病補償年金と打切補償
労働者が「業務上」負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間とその後30日間は解雇が禁止されています。
ただし、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治ゆしない場合は、使用者が打切補償(平均賃金の1200日分)を行えば、解雇が可能になります。打切補償を行うことによって補償義務がなくなるからです。
(労働基準法第19条)
しかし、業務上の傷病について、労災保険から保険給付が行われると、使用者の労働基準法の補償義務はなくなります。そうなると、使用者は打切補償をすることもなくなりますので、解雇制限が解除されなくなってしまいます。
そのため、労災保険法では、打切補償を支払ったと「みなす」という規定があり、それによって解雇することが可能になります。確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
法第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |
・療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合
→ 3年を経過した日に打切補償を支払ったものとみなす → 解雇できる
・療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
→ 傷病補償年金を受けることとなった日に打切補償を支払ったものとみなす → 解雇できる
では、過去問をどうぞ!
【R2問6-B】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

【解答 】
【R2問6-B】 ×
療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けていない場合は、その時点では、打切補償を支払ったものとはみなされません。しかし、その後に、傷病補償年金を受けることとなった場合は、その時点で打切補償を支払ったとみなされ、解雇制限が解除されます。
打切補償を支払ったとみなされるのは、療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限りません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法の給付制限
労災保険法の給付制限
R5-131
R5.1.5 労災の給付制限「故意の犯罪行為、重大な過失」
労災保険法の支給制限を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第12条の2の2 ① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 |
①は「行わない」となっているのがポイントです。労働者の「故意」による傷病は、業務や通勤との因果関係がないので、保険給付は行われません。
②は「保険給付の全部又は一部を行わないことができる」ですので、絶対ではなく裁量になることがポイントです。
過去問をどうぞ!
①【R2問1-A】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷の原因となった事故を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
②【R2問1-B】
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
③【R2問1-C】
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
④【R2問1-D】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
⑤【R2問1-E】
業務起因性の認められる疾病に罹患した労働者が、療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合であっても、指示に従わないことに正当な理由があれば、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
①【R2問1-A】 〇
政府が保険給付の全部又は一部を行わないことができるのは、「重大な過失」による場合です。「過失」の場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
②【R2問1-B】 ×
労働者の「故意の犯罪行為」による場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。
③【R2問1-C】 〇
重大ではない「過失」の場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
④【R2問1-D】 〇
療養に関する指示に従わないことにより疾病の程度を増進させた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。しかし、「正当な理由」がある場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
⑤【R2問1-E】 〇
療養に関する指示に従わないことにより疾病の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができます。しかし、「正当な理由」がある場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-090
R4.11.25 R4択一式より 脳・心臓疾患の労災認定基準
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が、令和3年に改正されました。
働き方の多様化や職場環境の変化に応じて、最新の医学的知見を踏まえて、検証が行われたことによります。
新たに認定基準に追加されたポイントは以下の通りです。
■長期間の過重業務について
・労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されました。
・労働時間以外の負荷要因が見直されました。勤務間インターバルが短い勤務、身体的負荷を伴う業務などが評価対象として追加されました。
■短期間の過重業務・異常な出来事について
・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合が明確化されました。
では、令和4年の問題をどうぞ!
※「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日付け基発0914第1号)」より
①【問1-A】
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、 1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められない場合には、これに近い労働時間が認められたとしても、業務と発症との関連性が強いと評価することはできない。
②【問1-C】
短期間の過重業務については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。

【解答】
①【問1-A】 ×
発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと判断できます。
しかし、その水準には至らないが、これに近い時間外労働が認められる場合は、特に他の負荷要因の状況を十分に考慮し、そのような時間外労働に加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できる、とされています。
「労働時間」と「労働時間以外の負荷要因」を総合的に考慮して判断するのがポイントです。
労働時間以外の負荷要因として、「拘束時間の長い勤務」、「休日のない連続勤務」、「出張の多い業務」、「心理的負荷を伴う業務」などがあります。
②【問1-C】 〇
「発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合」、「発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等は、業務と発症との関連性が強いと評価できる、とされています。
★短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に示す業務と発症との時間的関連を考慮して判断されます。
① 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であるか否か
② 発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合には、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が特に過重であるか否か
※厚生労働省パンフレット「脳・心臓疾患の労災認定」を参照しました。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-089
R4.11.24 R4択一式より 合理的な経路及び方法(通勤)
通勤の定義の一つである「合理的な経路及び方法」について確認しましょう。
まず条文を読んでみましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
★「合理的な経路及び方法」とは、一般的に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいいます。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問6-D】
マイカー通勤の労働者が、経路上の道路工事のためにやむを得ず通常の経路を迂回して取った経路は、ふだんの通勤経路を外れた部分についても、通勤災害における合理的な経路と認められる。
②【問6-E】
他に子供を監護する者がいない共稼ぎ労働者が、いつもどおり親戚に子供を預けるために、自宅から徒歩10分ほどの勤務先会社の前を通り過ぎて100メートルのところにある親戚の家まで、子供とともに歩き、子供を預けた後に勤務先会社まで歩いて戻る経路のうち、勤務先会社と親戚の家との間の往復は、通勤災害における合理的な経路とは認められない。

【解答】
①【問6-D】 〇
経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる、とされています。
(H18.3.31基発第 0331042 号)
②【問6-E】 ×
他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等にあずけるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば 当然就業のためにとらざるを得ない経路です。そのため、合理的な経路と認められます。
(H18.3.31基発第 0331042 号)
過去問をどうぞ!
【R3年出題】
自家用車で通勤していた労働者Xが通勤途中、他の自動車との接触事故で負傷したが、労働者Xは所持している自動車運転免許の更新を失念していたため、当該免許が当該事故の1週間前に失効しており、当該事故の際、労働者Xは、無免許運転の状態であった。この場合は、諸般の事情を勘案して給付の支給制限が行われることはあるものの、通勤災害と認められる可能性はある。

【解答】
【R3年出題】 〇
例えば、免許を一度も取得したことのないような者が自動車を運転する場合、自動車、自転車等を泥酔して運転するような場合には、合理的な方法と認められません。
「飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも、合理性を欠くものとして取り扱う必要はないが、この場合において、諸般の事情を勘案し、給付の支給制限が行われることがあることは当然である。」とされています。
(H18.3.31基発第 0331042 号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-048
R4.10.14 R4択一式より 労災保険「再発」とは
労災保険法の保険給付は、「治っていない」か「治った」がポイントです。
例えば、仕事中にケガをし、療養を受けている間は、「療養補償給付」が支給されます。ケガが治ったとき(治ゆしたとき)は療養補償給付は終了します。治った後に一定の障害が残った場合は、障害補償給付が支給されます。
そして、その後再発した場合は、療養補償給付が再度受けられるようになります。
今日のテーマは「再発」の認定要件です。
まず、「治った」とはどういう状態なのでしょうか?
・労災保険で傷病が「治った」ときとは、身体の諸器官・組織が完全に回復した状態のみをいうものではありません。傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。
この状態を「治ゆ」(症状固定)といいます。
では、次に「再発」の要件を令和4年の問題でみてみましょう。
【問-7】
業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次のアからエの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること
イ 当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3年以内であること
ウ 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること
エ 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること
A (アとイ)
B (アとエ)
C (アとイとエ)
D (アとウとエ)
E (アとイとウとエ)

【解答】
【問-7】 D (アとウとエ)
再発として再び療養(補償)等給付を受けることができる要件は次の3つを満たした場合です。
①その症状の悪化が、当初の業務又は通勤による傷病と相当因果関係があると認められること
②症状固定の時からみて、明らかに症状が悪化していること
③療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること
問題文では、アとウとエの3つの要件を満たすことが条件となります。
(参考:厚生労働省パンフレット「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
それでは、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
②【H28年出題】
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態は「治ゆ」(症状固定)となります。「医療効果が期待できなくなった状態」とは、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態です。
治ゆ後は、療養の給付は行われません。
(参考:厚生労働省パンフレット「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
②【H28年出題】 ×
傷病が一旦症状固定と認められた後に再び発症し、「再発」の要件を満たした場合は、再び療養補償給付が支給されます。
(参考:厚生労働省パンフレット「労災保険における傷病が「治ったとき」とは・・・」
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(労災保険法)
R5-032
R4.9.29 R4択一式より『業務の性質を有するものは通勤から除かれる』
今日のテーマは、「業務の性質を有するもの」です。「業務の性質を有するもの」は「通勤」の定義から除かれます。
では、通勤の定義を条文で読んでみましょう。
法第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
「業務の性質を有するものを除く」の部分に注目してください。
「業務の性質を有するもの」は通勤ではなく、業務災害となります。
会社の通勤専用バスの利用に起因する事故、突発的事故等による緊急用務のため、休日に呼び出しを受け、緊急に出勤する途上の事故などは通勤ではなく、業務上となります。
今日は、「出張中」の災害の扱いを確認しましょう。
では、過去問からどうぞ!
①【H25年出題】
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。
②【H26年出題】
明日午前8時から午後1時までの間に、下請業者の実施する隣町での作業を指揮監督するよう出張命令を受け、翌日、午前7時すぎ、自転車で自宅を出発し、列車に乗車すべく進行中、踏切で列車に衝突し死亡したが、同人が乗車しようとしていた列車が通常の通勤の場合にも利用していたものである場合は、通勤災害とされている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
「出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱うこと。」とされています。
(H18.3.31基労管発第0331001号/基労補発第0331003号/)
②【H26年出題】 ×
出張については、一般的に、その過程全般が業務行為と認められます。
問題文のように、出張のため、自宅から自転車で駅に向かう途中の事故は、通勤ではなく、業務上とされます。
(S34.7.15基収第2980号)
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問6-A】
労働者が上司から直ちに2泊3日の出張を命じられ、勤務先を出てすぐに着替えを取りに自宅に立ち寄り、そこから出張先に向かう列車に乗車すべく駅に向かって自転車で進行中に、踏切で列車に衝突し死亡した場合、その路線が通常の通勤に使っていたものであれば、通勤災害と認められる。

【解答】
【問6-A】 ×
通勤災害ではなく業務災害となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(労働者災害補償保険法)
令和4年基本問題(労働者災害補償保険法)
R5-022
R4.9.19 R4択一式より『(通勤災害)住居と就業の場所』
令和4年の択一式から、基本問題を取り上げていきます。
今日は、『(通勤災害)住居と就業の場所』です。
通勤となる移動は3種類ありますが、代表的な移動は、「住居と就業の場所との間の往復」です。
条文を読んでみましょう。
第7条第2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) |
「住居」とは労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをさします。
「就業の場所」は、業務を開始し又は終了する場所をいいます。
(S48.12.1保険発第105号・庁保険発第24号)
令和4年の問題で、「住居」・「就業の場所」になる例、ならない例を確認しましょう。
では、令和4年の問題をどうぞ!
①【問5-A】
同一市内に住む長女が出産するため、15日間、幼児2人を含む家族の世話をするために長女宅に泊まり込んだ労働者にとって、長女宅は、就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。
②【問5-B】
アパートの2階の一部屋に居住する労働者が、いつも会社に向かって自宅を出発する時刻に、出勤するべく靴を履いて自室のドアから出て1階に降りようとした時に、足が滑り転倒して負傷した場合、通勤災害に当たらない。
③【問5-C】
一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。
④【問5-D】
外回りの営業担当の労働者が、夕方、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先が就業の場所に当たる。
⑤【問5-E】
労働者が、長期入院中の夫の看護のために病院に1か月間継続して宿泊した場合、当該病院は就業のための拠点としての性格を有する住居と認められる。

【解答】
①【問5-A】 〇
長女が出産するため、長女宅に泊まり込んだ労働者にとって長女宅は、住居と認められ、長女宅から勤務先に向かう途中の事故は通勤災害と認められています。
(S52.12.23基収1027号)
②【問5-B】 ×
アパートについては、部屋の外戸が住居と通勤経路の境界となります。
自室のドアから出て1階に降りようとした時の階段は通勤経路となりますので、足が滑り転倒して負傷した場合は、通勤災害に当たります。
(S49.4.9基収314)
③【問5-C】 〇
一戸建て屋敷構えの住居の玄関先は住居内となり、住居と就業の場所との間とはいえません。自宅の門をくぐって玄関先の石段での負傷は、通勤災害に当たりません。
(S52.12.23基収981)
④【問5-D】 〇
得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、その得意先は就業の場所に当たります。
(S48.11.22基発644)
⑤【問5-E】 〇
長期入院中の夫の看護のために病院に寝泊まりしている病院は住居に当たり、その病院から出勤する途中の事故は、通勤災害と認められます。
(S52.12.23基収981)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(労災保険法)
令和4年択一式を解いてみる(労災保険法)
R5-012
R4.9.9 R4「労災択一」は保険給付の出題ゼロでした。問3中小事業主の要件
令和4年の労災保険の択一式は、「保険給付」(例えば、療養補償給付とか休業補償給付とか・・・)の内容についての出題がありませんでした。
今日は、問3の「特別加入できる中小事業主」の問題を見ていきましょう。
まず、中小事業主と認められる企業の規模を確認しましょう。
業 種 | 常時使用する労働者数 |
金融業 保険業 不動産業 小売業 |
50人以下 |
卸売業 サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |
中小事業主が特別加入する条件として、「労働者について保険関係が成立している」、「労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している」ことが必要です。
労働保険事務組合に委託できるのは、上記の規模の中小事業主です。
では、令和4年問3の問題をどうぞ
【R4年問3】
厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
B 不動産業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
C 小売業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
D サービス業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
E 保険業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主

【解答】
A × 金融業 → 常時50人以下
B × 不動産業 → 常時50人以下
C × 小売業 → 常時50人以下
D 〇 サービス業 → 常時100人以下
E × 保険業 → 常時50人以下
では、過去問もどうぞ!
【R3年出題】
特別加入者である中小事業主が高齢のため実際には就業せず、専ら同業者の事業主団体の会合等にのみ出席するようになった場合であっても、中小企業の特別加入は事業主自身が加入する前提であることから、事業主と当該事業に従事する他の者を包括して加入しなければならず、就業実態のない事業主として特別加入者としないことは認められない。

【解答】
【R3年出題】 ×
就業実態のない事業主を特別加入者としない扱いは、認められています。
中小事業主等の特別加入については、事業主が事業主と当該事業に徒事するその他の者を包括して加入申請を行い、政府の承認を受けることにより労災保険が適用されるものとなっていて、事業主自身が加入することが前提となっています。
しかし、実態として事業場で就業していないものまで包括して加入させることは適当ではないので、就業実態のない事業主が自ら包括加入の対象から除外することを申し出た場合には、特別加入者としない扱いになっています。
なお、任意包括の対象から除外できるのは、次のいずれかに該当する者です。
①病気療養中、高齢その他の事情のため、実際に就業しない事業主、②事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主
(平成15年5月20日基発第0520002号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式③
復習しましょう/令和4年選択式③
R5-003
R4.8.31 令和4年選択式の復習~労働者災害補償保険法
今まであまり取り上げられなかった視点からの問題でした。
解き方を考えてみましょう。
 同一の部位に加重障害が生ずるとともに、他の部位にも新たな身体障害が残った場合の障害等級
同一の部位に加重障害が生ずるとともに、他の部位にも新たな身体障害が残った場合の障害等級
(問題の主旨)
・ 業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)
・ 新たな業務災害で、同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し、かつ1手の小指を失った(12級の8の2)
↓
この場合の障害等級と新たに給付される障害補償の額が問われました。
(考え方)
① まず、同一部位の加重された後の身体障害の等級を定めます。
② 次に他の部位の身体障害の等級を定め、両者を併合して現在の身体障害の該当する等級を認定します。
③ 現在の等級の額から既にあった障害の等級の額を控除して得た額が、給付額となります。
(問題文にあてはめます)
① 同一部位(1下肢)の等級は加重された後、10級の7となります。
② 新たな部位の身体障害の等級は12級の8の2です。両者を併合して繰り上げた結果、現在の等級は「9級」となります。
※「併合」は重い方の障害等級が全体の障害等級となりますが、13級以上の障害が2つありますので、重い方の10級を1級繰り上げた結果「9級」となります。
③ 新たな障害につき給付される障害補償の額は、現在の等級(9級・391日分)から、既にあった障害の等級(13級・101日分)を控除した額=「290日」分となります。
 中小事業主が特別加入する際の保険関係について
中小事業主が特別加入する際の保険関係について
中小事業主の特別加入は、労働者に関して成立している保険関係に、中小事業主が組み込まれる形で行われます。
保険関係上、中小事業主は、「労働者」とみなされることによって、労災保険の保護の対象となります。
また、保険関係は、場所ごとに成立します。建設の事業の場合は、建設工事の現場、営業活動を行う本店等はそれぞれ別個に保険関係が成立します。
保険関係は、「労働者を使用するものがあること」によって成立します。
問題文の場合、建設現場は労働者がいるため保険関係が成立しますが、営業の事業を行う本店等は、労働者が従事していないため保険関係が成立していません。
中小事業主の特別加入は、労働者の保険関係が成立していることが前提です。保険関係が成立していない営業等の事業については、事業主は特別加入することはできません。そのため、「営業等の事業に係る業務」に起因する事業主の死亡に関しては、保険給付の対象になりません。
 覚えて解くという問題ではなく、前後の文章をじっくり読んで、今まで学んだ知識と照らし合わせて、正解を引き出す問題でした。
覚えて解くという問題ではなく、前後の文章をじっくり読んで、今まで学んだ知識と照らし合わせて、正解を引き出す問題でした。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-360
R4.8.17 選択対策・疾病の範囲
今日は選択式の練習です。
空欄を埋めてみましょう。
過去問をどうぞ!
①【H18年選択式】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。

【解答】
A 労働基準法施行規則
B 労働者災害補償保険法施行規則
C 業務に起因することの明らかな疾病
D 通勤による負傷
E 通勤に起因することの明らかな疾病
こちらもどうぞ!
空欄を埋めてみましょう。
法第20条の3
複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する2以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6 (複数業務要因災害による疾病の範囲)
法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、< F > 別表第1の2第8号及び第9号に掲げる疾病その他< G >とする。

【解答】
F 労働基準法施行規則
G 2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病
★Fについて
労働基準法施行規則別表第1の2の第8号は「過重負荷による脳・心臓疾患」、第9号は「心理的負荷による精神障害」です。
<複数業務要因災害の範囲>
複数業務要因災害による疾病の範囲は、労災則第 18 条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている、とされています。
(令和2年8月 21 日 基発 0821 第1号より)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-350
R4.8.7 遺族補償年金の失権
今日は、遺族補償年金の失権事由を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第16条の4 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 3 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。 4 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。 5 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。 6 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。 |
労災保険の遺族補償年金には、転給があるのがポイントです。
受給権者が失権したときに、後順位者があるときは、次順位者が受給権者になります。
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、婚姻の届出はしていないものの事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときは、消滅する。
②【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。
③【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときであっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、消滅する。
④【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった祖父母が、その障害の状態がなくなったときは、労働者の死亡の当時60歳以上であった場合であっても、消滅する。
⑤【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】
①【H23年出題】 〇
事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に至ったときでも、遺族補償年金の受給権は消滅します。
②【H28年出題】 〇
直系血族又は直系姻族以外の養子になったときは失権します。伯父は直系ではなく傍系となりますので、伯父の養子になった場合は失権事由に該当します。
③【H23年出題】 ×
労働者の死亡の時から「引き続き障害の状態にある」ときは、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても失権しません。
「労働者の死亡のときから引き続き」がポイントです。
労働者の死亡時に、障害要件を満たしていて引き続き障害の状態にある場合は、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了しても失権しません。
④【H23年出題】 ×
労働者の死亡の当時年齢要件を満たしている場合は、障害の状態がなくなっても受給権には影響しません。
労働者の死亡の当時60歳以上であった祖父母は、年齢要件を満たしていますので、障害の状態がなくなっても、受給権は消滅しません。
⑤【H23年出題】 ×
孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときは年齢要件を満たしていますので、障害の状態の有無は関係ありません。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にその障害の状態がなくなったとしても、受給権は消滅しません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-316
R4.7.4 海外派遣者の特別加入
労災保険法は、属地主義がとられていて、国内の労働者の災害だけが保護の対象です。
海外で業務に従事する場合は、通常は労災保険の保護の対象外となります。しかし、労災保険に特別加入することにより、労災保険の保護を受けることができます。
海外派遣者として特別加入できるのは、次の3つです。
① 開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く。)を行う団体から派遣され、開発途上にある地域で行われる事業に従事する者 ② 日本国内の事業(有期事業を除く。)から派遣され、海外において行われる事業(海外支店や工場など)で行われる事業に従事する労働者 ③ 日本国内の事業(有期事業を除く。)から派遣され、特定事業に該当する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の者 |
★③について
「特定事業」は中小企業に該当する規模の事業のことです。
海外の事業が特定事業(中小企業の規模)の場合は、現地法人の社長として派遣される者も特別加入することができます。
★日本国内の事業が有期事業の場合は、海外派遣者の特別加入は認められません。
★日本国内の事業が継続事業なら、派遣先の海外の事業が有期事業の場合でも、特別加入させることができます。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
海外派遣者について、派遣先の海外の事業が厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当する場合であっても、その事業の代表者は、労災保険の特別加入の対象とならない。
②【H26年出題】
日本に本社を有する企業であれば、その海外支店に直接採用された者についても、所轄都道府県労働局長に特別加入の申請をして承認を受けることによって、労災保険法が適用される。

【解答】
①【H24年出題】 ×
派遣先の海外の事業が中小企業(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業)に該当する場合は、その事業の代表者も、労災保険の特別加入の対象となります。
②【H26年出題】 ×
海外支店で現地採用された者は、国内の事業からの派遣ではないので、特別加入の対象外です。
海外派遣者のポイント!
・ 新たに派遣される者に限らず、既に海外の事業に派遣されている者を特別加入させることもできます。
・ 単なる留学の目的で海外に派遣される者は、特別加入の対象となりません。
・ 海外出張者は、特別加入しなくても通常の労災保険の保護の対象となります。
(昭52.3.30基発第192号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-315
R4.7.3 遺族補償一時金
「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
今回のテーマは「遺族補償一時金」です。
条文を読んでみましょう。
法第16条の6、16条の8 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 ① 労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 → 給付基礎日額の1,000日分 ② 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額(給付基礎日額の1,000日分)に満たないとき。 → 「給付基礎日額の1,000日分」から「支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額」を控除した額
法第16条の7 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者 2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 |
① 例えば、労働者の死亡の当時、遺族が障害状態にない50歳の夫のみだった場合、夫は、遺族補償年金を受けることはできませんが、遺族補償一時金(給付基礎日額の1,000日分)を受けられます。
② 例えば、労働者の死亡当時生計を維持されていた遺族が妻のみだった場合、妻は遺族補償年金を受けることができます。しかし、その後妻の受給権が消滅し、既に支給されていた年金が給付基礎日額の1,000日分に満たないときは、支給された年金の額の合計額との差額が支給されます。
遺族補償一時金を受ける遺族の順位
①配偶者(生計維持の有無は関係なし)
②生計維持していた子
③生計を維持していた父母
④生計を維持していた孫
⑤生計を維持していた祖父母
⑥生計を維持していなかった子
⑦生計を維持していなかった父母
⑧生計を維持していなかった孫
⑨生計を維持していなかった祖父母
⑩兄弟姉妹(生計維持の有無は関係なし)
過去問をどうぞ!
①【H10年出題】
遺族補償年金を受ける権利を有する死亡労働者の妻が再婚をした場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときには、当該再婚をした妻は遺族補償一時金の請求権を有することがある。
②【H28年出題】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
③【H25年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
④【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
①【H10年出題】 〇
遺族補償年金を受けている妻が再婚をした場合、遺族補償年金の受給権は失権します。その場合、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1,000日未満の場合は、差額が遺族補償一時金として支給されます。
労働者との身分関係は「労働者の死亡の当時」でみることがポイントです。再婚により遺族補償年金の受給権が失権した場合でも、労働者の死亡の当時は妻だったので、遺族補償一時金の請求ができます。
②【H28年出題】 ×
①の問題のように、遺族補償年金の受給権を失権したものでも、遺族補償一時金の受給権を得ることがあります。
③【H25年出題】 〇
「遺族補償年金」は、労働者の死亡の当時その収入により生計を維持していたことが条件ですが、「遺族補償一時金」は、労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、受給者となることがあります。
④【H28年出題】 〇
③の問題と同じです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-314
R4.7.2 労災 保険給付の一時差し止め
保険給付を受ける者が行政庁の命令に従わないときは、政府は保険給付の支払いを一時差し止めることができます。
条文を読んでみましょう。
法第47条の3 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前2条の規定による命令(報告、出頭等の命令、受診命令)に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 |
一時差し止められた保険給付は、差止め事由がなくなれば、差し止められていた給付の支払が行われます。
支給停止とは違いますので注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
②【H25年出題】
政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
③【H24年出題】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

【解答】
①【H25年出題】 〇
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な書類その他の物件を政府に提出しないときは、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができます。
②【H25年出題】 〇
受診命令に従わないときは、政府は、保険給付の支払を一時差し止めることができます。
※参考 第47条の2(受診命令) 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。 |
③【H24年出題】 ×
行政の出頭命令に従わないときは、政府は、「保険給付の支払を一時差し止めること」ができます。「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。」は誤りです。
※参考 第47条(労働者及び受給者の報告、出頭等) 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、報告等を命ずることができる。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-313
R4.7.1 障害補償給付・障害等級の変更
障害等級は、1級から14級まであり、1級から7級の障害が残った場合は「障害補償年金」、8級から14級の障害が残った場合は「障害補償一時金」が支給されます。
障害補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があった場合は、変更後の障害等級に応じた障害補償年金又は障害補償一時金が支給されます。
条文を読んでみましょう。
法第15条の2 障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 |
ポイント!
★「変更があった」とは?
障害の程度が自然的経過により増進し、又は軽減したことをいいます。
※「変更」に含まれないもの→「新たな傷病で障害の程度が加重した」、「傷病が再発した後治ゆし、その後に残った障害の程度が増進又は軽度になった」場合は変更に含まれません。
★対象は「障害補償年金」のみ
主語に注目してください。変更の対象は、「障害補償年金」を受ける労働者に限定されています。
「障害補償一時金」の場合は、後から障害の程度が増進又は軽減した場合でも、変更の対象にはなりません。
★具体例
・障害等級3級が自然的経過により増進し、障害等級1級に該当するに至った場合
→ 新たに該当した「1級」の障害補償年金を支給し、その後は3級の障害補償年金は支給されません。
・障害等級5級が自然的経過により軽減し、障害等級8級に該当するに至った場合
→ 新たに該当した「8級」の障害補償一時金を支給し、その後は5級の障害補償年金は支給されません。
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
②【H30年出題】
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。

【解答】
①【H21年出題】 〇
「障害補償年金を受ける者」と「自然的経過により変更」がチェックポイントです。
また、「新たに該当することとなった障害等級に応ずる「障害補償給付」が支給され」の「障害補償給付」にも注目してください。「障害補償給付」には「年金」も「一時金」も含まれます。1級から7級の範囲内の変更なら年金が支給されますが、8級以下になった場合は一時金が支給されます。
②【H30年出題】 〇
「障害補償一時金」の場合は、障害の程度が自然的経過により変更しても、障害補償給付の変更が行われることはありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
R4-312
R4.6.30 障害補償給付・併合と併合繰上げ
同一のケガや病気で障害が2つ以上残ったときは、原則として、重い方の障害等級が全体の障害等級となります。(併合といいます)
しかし、13級以上の障害が2つ以上あるときは、重い方の障害等級を1級ないし3級繰り上げます。(併合繰上げといいます。)
条文を読んでみましょう。
則第14条 ② 別表第一に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 ③ 次の各号に掲げる場合には、重い方の障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。 1 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 1級繰り上げ 2 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 2級繰り上げ 3 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき 3級繰り上げ |
(併合について)
例えば、同一事由で、14級と9級の2つの障害が残った場合は、全体として重い方の9級の障害等級となります。
重い方の障害等級が全体の障害等級となるのは、一方が14級の場合に限られます。
(併合繰上げについて)
併合繰上げが行われるのは、13級以上の障害が2つ以上残った場合です。
例えば、同一の事由で、5級と4級が残った場合は、重い方の4級が3級繰り上がって、全体として障害等級は1級となります。
しかし、例外もあります。
13級と9級が残った場合は、重い方の9級が1級繰り上がって8級となります。
8級の一時金は「503日分」、13級(101日分)と9級(391日分)を合算すると492日分です。繰り上がった結果の方が大きくなるのは、13級と9級が残った場合だけです。このため、13級と9級が残った場合は、繰り上がった8級の一時金ではなく、13級と9級を合算した492日分の一時金が支給されます。(則第14条第3項但し書き)
過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で、一方の障害が第14級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
②【H30年出題】
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は次の通りである。
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合 第3級
② 第4級、第5級の2障害がある場合 第2級
③ 第8級、第9級の2障害がある場合 第7級

【解答】
①【R2年出題】 〇
同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で、一方の障害が第14級に該当するときは、全体として重い方の障害等級になります。例えば、14級と10級が残った場合は、全体として10級となります。
②【H30年出題】 ×
① 第5級、第7級、第9級の3障害がある場合は、「8級以上」が、5級と7級の2つあるので、重い方の5級が2級繰り上がって「第3級」となります。
② 第4級、第5級の2障害がある場合は、「5級以上」が、4級と5級の2つあるので、重い方の4級が3級繰り上がって「第1級」となります。
③ 第8級、第9級の2障害がある場合は、「13級以上」が8級と9級の2つあるので、重い方の8級が1級繰り上がって「第7級」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-285
R4.6.3 療養給付(通勤災害)の一部負担金
通勤災害で療養給付を受けた場合、労働者は一部負担金を納付しなければなりません。
一部負担金は、200円(健康保険法の日雇特例被保険者は100円)で、休業給付から控除されます。
なお、業務災害の療養補償給付の場合は、一部負担金は徴収されません。業務災害は、使用者に補償義務があるからです。
では、条文を読んでみましょう。
第31条 ② 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、 200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。 ③ 政府は、労働者から徴収する一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。
則第44条の2 (一部負担金) ① 法第31条第2項の厚生労働省令で定める者(一部負担金が徴収されない者)は、次の各号に掲げる者とする。 1 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 2 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 3 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ② 一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については、100円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。 ③ 法第31条第3項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。
②【H24年出題】
政府は、療養給付を受ける労働者(法令で定める者を除く。)から、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)を一部負担金として徴収する。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額を徴収する。
③【H24年出題】
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者についても、一部負担金は徴収される。
④【H25年出題】
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
⑤【H25年出題】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
⑥【H24年出題】
療養給付を受ける労働者から一部負担金を徴収する場合には、労働者に支給すべき休業給付の額から、一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
一部負担金は、通勤災害の「療養給付」が対象です。
②【H24年出題】 〇
一部負担金の額は、200円(健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者については100円)です。
③【H24年出題】 ×
第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者からは、一部負担金は徴収しません。
④【H25年出題】 ×
療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金は徴収しません。
⑤【H25年出題】 〇
休業給付の初回の給付額から、一部負担金が控除されます。
⑥【H24年出題】 〇
休業給付で最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から、一部負担金の額に相当する額が控除されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「要介護状態」の比較
「要介護状態」の比較
R4-279
R4.5.28 「要介護状態」比較/介護保険法と育児・介護休業法と労災保険法
■介護保険の保険給付には、「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」があります。
「介護給付」は要介護状態にある者に対しての保険給付です。
■育児・介護休業法の「介護休業」は、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
それぞれの「要介護状態」の定義を比較しましょう。
まず、介護保険法の条文を読んでみましょう。
第7条 (定義) 介護保険法において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 施行規則第3条 厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 |
次に、育児・介護休業法の条文を読んでみましょう。
第2条 (定義) 要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
施行規則第2条 厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。 |
介護保険法の要介護状態は、「6月間」にわたり継続して、常時介護を要する状態、育児介護休業法の要介護状態は、「2週間以上の期間」にわたり常時介護を必要とする状態です。
法律によって違いますので、注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
「労災保険法」の問題です。
労災【H25年出題】
女性労働者が1週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所から帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

【解答】
労災【H25年出題】 〇
合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合は、逸脱・中断の間とその後の移動は通勤になりません。
しかし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、合理的な経路に戻ってからの移動は通勤となります。(この場合でも、逸脱・中断の間は通勤になりません。)
問題文は、日常生活上必要な行為に該当しますので、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当します。
■ ここでも「要介護状態」という用語が出てきます。定義は「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」をいいます。
(則第7条、第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-268
R4.5.17 「一定の障害状態」遺族補償年金
労働者が業務上死亡した場合、一定の遺族に「遺族補償年金」が支給されます。
前回は、遺族補償年金の対象になる遺族の第一の条件である「生計維持」についてお話しました。
さらに、「妻以外」の者は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。今回のテーマは「障害要件」です。
条文を読んでみましょう。
第16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること 4 前3号の要件(年齢要件)に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
遺族補償年金を受ける遺族の条件として、「妻」以外の者は、労働者の死亡の当時 1号から3号の「年齢要件」又は4号の「障害要件」に該当しなければなりません。
今回は、「厚生労働省令で定める障害の状態」がテーマです。
「厚生労働省令で定める障害の状態」については、次のように定められています。
則第15条 (遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態) 法第16条の2第1項第4号(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)及び法別表第一(法第20条の6第3項において準用する場合を含む。)遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に別表第一の障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。 |
ポイントは、「5級以上」の部分と「労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上」の部分です。
では、過去問をどうぞ!
①【H19年出題】 ※改正による修正あり
遺族補償年金(複数事業労働者遺族年金において準用する場合を含む。)又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】
①【H19年出題】 〇
労働の高度の制限とは、「完全な労働不能で長期間にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を要するものよりも軽いが、労働の著しい制限よりは重く、長期間にわたり中等度の安静を要すること」をいうとされています。
(昭41.1.31基発73号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-267
R4.5.16 遺族補償年金~「生計を維持していた」
労働者が業務上死亡した場合、一定の遺族に「遺族補償年金」が支給されます。
条文を読んでみましょう。
第16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること 4 前3号の要件(年齢要件)に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 |
今日のポイント!
遺族補償年金を受けることができる遺族の第1条件は、労働者の死亡当時その収入によって「生計を維持していた」ものです。
今回のテーマは「生計維持」です。
「生計維持」の認定については、則第14条の4で次のように定められています。
則第14条の4 (遺族補償給付等に係る生計維持の認定) 遺族補償年金及び遺族補償一時金(複数事業労働者遺族給付及び遺族給付において準用する場合を含む。)に規定する労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償年金を受けることができる。
②【H17年出題】
遺族補償年金を受けることができる遺族の要件としての「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ことが認められるためには、単に労働者と生計を一にしていただけでは足りず、労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要である。
③【H28年出題】
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
④【H18年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「妻」以外の者は、労働者の死亡の当時、「年齢要件」又は「障害要件」に該当する必要がありますが、妻は年齢、障害の要件は問われません。妻は「生計を維持していた」場合は、遺族補償年金を受けることができます。
②【H17年出題】 ×
「労働者の収入によって消費生活の大部分を営んでいたことが必要」の部分が誤りです。「もっぱら又は主として労働者の収入によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる。したがって、いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。」とされています。
(昭41.1.31基発第73号)
③【H28年出題】 ×
②と同じ考え方です。
「労働者の収入によって生計の一部を維持されていれば足りる」、「いわゆる共稼ぎもこれに含まれる。」という解釈ですので、労働者と同程度の収入があり、生活費を分担していた妻も、遺族補償年金を受けることができます。
④【H18年出題】 ×
「遺族補償給付」には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
「遺族補償年金」は、「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ものでなければなりませんが、「遺族補償一時金」は、「生計を維持していない」ものでも対象になり得ます。
(法第16条の7)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-248
R4.4.27 療養補償給付と休業補償給付と傷病補償年金
労災保険の保険給付には、「治ゆ前」に支給されるものと「治ゆ後」に支給されるものがあます。
今日のテーマは、療養補償給付、休業補償給付、傷病補償年金ですが、この3つは「治ゆ前」に支給されるものです。
それぞれが、併給されるか否かが良く問われます。
 まずは図でイメージしましょう。
まずは図でイメージしましょう。
・病気やけがの治療
→ 治ゆするまで「療養補償給付」が受けられます。
・所得補償
→休業4日目から「休業補償給付」が受けられます。
→療養開始後1年6か月が経過した日(又は同日後)に、傷病が治っておらず、傷病等級1~3級に該当した場合は、「傷病補償年金」に切り替わります。
療養補償給付 | 治 ゆ | |
休業補償給付 | 傷病補償年金 | |
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。
②【H24年出題】
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
③【H24年出題】
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。
④【H27年出題】
傷病補償年金は、休業補償給付と併給されることはない。
⑤【H30年出題】
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「症状が安定して疾病が固定した状態」、「医療効果が期待しえない状態」の場合は、症状が残っていても、療養の必要はなくなったものとされ、療養の給付は行われません。
(昭23.1.13基災発第3号)
②【H24年出題】 〇
治療としての「療養補償給付」と労働することができない期間の所得補償である「休業補償給付」は併給されます。
③【H24年出題】 〇
治療としての「療養補償給付」と、治ゆ前の所得補償である「傷病補償年金」は併給されます。
④【H27年出題】 〇
⑤【H30年出題】 〇
休業補償給付と傷病補償年金は、どちらも所得補償ですので、併給されることはありません。
ポイント!
「年金」は「支給事由が生じた月の翌月」から、「権利が消滅した月」まで「月単位」で支給されます。
傷病補償年金の受給権が生じた月は、「休業補償給付」が支給され、その翌月から傷病補償年金の支給が始まります。
また、傷病等級に該当しなくなり傷病補償年金の受給権が消滅した場合は、消滅した月まで傷病補償年金が支給され、要件に合えば、その翌月から休業補償給付が支給されます。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 傷病補償年金 受給権発生 |
|
|
|
| 傷病補償年金 受給権消滅 |
|
休 | 休 | 傷 | 傷 | 傷 | 傷 | 傷 | 休 |
休 → 休業補償給付
傷 → 傷病補償年金
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-233
R4.4.12 逸脱・中断と「日常生活上必要な行為」
合理的な通勤経路を、逸脱・中断した場合は、「逸脱・中断の間」と「合理的な通勤経路に戻った後の移動」は通勤となりません。
しかし、日常生活上必要な行為によって合理的な通勤経路を「逸脱・中断」した場合は、合理的な通勤経路に戻った後の移動は通勤として認められます。
今回は、「日常生活上必要な行為」を確認します。
条文を読んでみましょう。
第7条 ② 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と就業の場所との間の往復 2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 3 1に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。) ③ 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
則第8条 (日常生活上必要な行為) 法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 1 日用品の購入その他これに準ずる行為 2 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 3 選挙権の行使その他これに準ずる行為 4 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 5 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。) |
では、過去問をどうぞ!
①【H23年出題】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。
②【H27年出題】
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。
③【H28年出題】
会社からの退勤の途中に、定期的に病院で、比較的長時間の人工透析を受ける場合も、終了して直ちに合理的経路に復した後については、通勤に該当する。
④【H25年出題】
女性労働者が1週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

【解答】
①【H23年出題】 ×
逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」であったとしても、逸脱・中断の間は通勤になりません。
②【H27年出題】 ×
理美容院に立ち寄ることは、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当します。合理的な経路に復した後は、通勤になります。
(昭48.11.22基発第644号)
③【H28年出題】 〇
「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」には、通常の医療を受ける行為に限らず、人工透析など比較的長時間を要する医療を受けることも含んでいる、とされています。
(昭48.11.22基発第644号)
④【H25年出題】 〇
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護は、「継続的に又は反復して行われるもの」に限られます。
問題文のように1週間に数回介護を行う場合は、「継続的に又は反復して」に該当します。
(昭48.11.22基発第644号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-214
R4.3.24 労災保険の適用事業と適用除外
労働者を1人でも使用する事業は、労災保険の適用事業となります。
ただし、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法の保護を受けられる事業は、労災保険法の適用は除外されます。
条文を読んでみましょう。
第3条 (適用事業及び適用除外) ① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 ② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。 |
・ 国の直営事業には労災保険法は適用されません。
(なお、国の直営事業に該当する事業は現在ありません。)
・ 官公署の事業とは、非現業の官公署のことです。国家公務員災害補償法や地方公務 員災害補償法の適用があるので、労災保険法は適用されません。
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
②【H29年出題】
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
③【H29年出題】
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
④【H29年出題】
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
⑤【H29年出題】
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

【解答】
①【H29年出題】 ×
・ 都道府県、市町村の「非現業」の官公署
→ 地方公務員災害補償法が適用されるので、労災保険の適用は除外
※ただし、「非常勤職員」には、地方公務員災害補償法で定める災害補償の条例 が適用される
・ 都道府県、市町村の「現業部門」
→ 労災保険法では、労災保険の適用は除外されていない
→ ただし、「常勤職員」は、地方公務員災害補償法第67条第2項で労災保険の適用が除外されている
→「都道府県、市町村の現業部門」の非常勤職員には、労災保険法が適用される。
問題文の「市の経営する水道事業の非常勤職員」には労災保険法が適用されます。
②【H29年出題】 ×
行政執行法人の職員には国家公務員災害補償法が適用されますので、労災保険法の適用は除外されます。
③【H29年出題】 ×
非現業の一般職の国家公務員には、労災保険法は適用されません。
④【H29年出題】 〇
国の直営事業には労災保険は適用されません。
⑤【H29年出題】 ×
常勤の地方公務員には労災保険は適用されません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 労災保険法
労災保険法
R4-197
R4.3.7 【労災】不正受給者からの費用徴収
不正行為で労災の保険給付を受けた場合、保険給付に要した費用の全部又は一部が回収されます。
条文を読んでみましょう。
第12条の3 (不正受給者からの費用徴収) ① 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 ② ①の場合において、事業主(徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
政府は、不正受給者から、保険給付に要した費用の全部又は一部を回収することができます。
また、不正受給に事業主が加担している場合は、政府は、事業主にも連帯して、保険給付に要した費用の全部または一部の納付を命ずることができます。
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
②【R2年出題】
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
③【H22年出題】
偽りその他不正の手段により労災保険の保険給付を受けた者がある場合において、その保険給付が事業主の虚偽の報告又は証明をしたために行われたものであるときは、保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
回収の対象になるのは、「不当利得」した部分に限られるのがポイントです。
「保険給付」に要した費用に相当する金額の全部又は一部に注目してください。「不当利得分」の全部又は一部ではありません。
保険給付の全部を不正受給した場合は全部が徴収の対象になりますし、保険給付の一部を不正受給した場合はその不当利得部分は全て徴収の対象になります。
(昭40.7.31基発906号)
②【R2年出題】 〇
事業主にも連帯して責任を負わせるための規定です。
③【H22年出題】 ×
政府は、不正受給者から、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができ、また、事業主が虚偽の報告又は証明をし、不正受給に加担している場合は、事業主に対して不正受給者と連帯して納付を命ずることができます。
「保険給付を受けた者ではなく事業主が、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部を政府に返還しなければならない。」は誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-168
R4.2.6 労災「受給権の保護」
例えば、業務災害によって休業補償給付を受けている場合、退職後も引き続き受けられるのでしょうか?
労災保険の保険給付の受給権は保護されています。条文で確認しましょう。
第12条の5 ① 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。 ② 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 |
「保険給付を受ける権利」は、労働者の「退職によって変更されることはない」となっています。保険給付を受ける権利は、雇用関係の存続とは関係なく、退職後も変わらず継続します。在職中に受けていた休業補償給付は退職後も支給されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
労災保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
②【H21年出題】
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。

【解答】
①【H27年出題】 〇
労災保険給付を受ける権利は、退職した後も継続します。
②【H21年出題】 ×
労働関係が解消された後も、引き続いて休業補償給付を受けることができます。
通常は、退職後も次の仕事に就いて賃金を得ることができます。しかし、業務上の傷病による療養中は仕事に就くことができません。「労働することができないために賃金を受けない」状態にあるといえるからです。
こちらもどうぞ!
③【H24年出題】
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
④【R1年出題】
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差し押さえは禁止されている。

【解答】
③【H24年出題】 〇
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることはできません。
④【R1年出題】 ×
保険給付ではなく、社会復帰促進等事業の「特別支給金」の問題ですので注意してください。
特別支給金については、譲渡、差し押さえは禁止されていません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-158
R4.1.27 傷病補償年金の変更
傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更があり、傷病等級が変わった場合のルールを確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第18条の2 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。 |
例えば、2級の傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、新たに3級に該当した場合は、それ以後は3級の傷病補償年金が支給されます。
過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金又は傷病年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
②【H29年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。
③【H21年出題】
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の支給は打ち切られるが、なお療養のため労働することができないため賃金を受けられない状態にある場合には、政府が労働者の請求を待たず職権で休業補償給付の支給を決定する。

【解答】
①【H20年出題】 ×
傷病補償年金(傷病年金)の障害の程度に変更があったときも、所轄労働基準監督署長の職権で変更に関する決定が行われます。労働者からの請求ではありません。
(則第18条の3)
②【H29年出題】 〇
傷病等級に該当しなくなった場合は、傷病補償年金の受給権は消滅します。そして、要件に該当すれば、労働者は休業補償給付を請求することができます。
なお、年金は、支給を受ける「権利が消滅した月」まで支給されます。(法第9条)休業補償給付はその翌月から支給されます。
③【H21年出題】 ×
休業補償給付の支給は、労働者の請求が必要です。
(法第12条の8)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-143
R4.1.12 打切補償と傷病補償年金の関係 その2(問題編)
前回は、打切補償と傷病補償年金の関係を条文で読みました。
前回の記事 → R4.1.11 打切補償と傷病補償年金の関係 その1(条文編)
今回は実践編です。問題を解いてみましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。
②【H24年選択式】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において、同法第81条の規定により< A >を支払ったものとみなす。

【解答】
①【H29年出題】 〇
3年を経過した日に打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除されます。
下の図を参照してください。①のパターンです。
②【H24年選択式】
A 打切補償
次はこちらをどうぞ!
③【R2年出題】
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

【解答】
③【R2年出題】 ×
「3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り」の部分が誤りです。
打切補償を支払ったとみなされ解雇制限が解除されるのは、
①療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合
②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
です。
3年を経過した日に傷病補償年金を受けていなくても、その後受けることになった場合は、その傷病補償年金を受けることとなった日に、打切補償を支払ったものとみなされます。下の図の②のパターンです。
最後にこちらをどうぞ!
④【オリジナル】
通勤により負傷した労働者が、当該負傷に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。

【解答】
④【オリジナル】 ×
「通勤」による災害には使用者の補償責任はありません。労働基準法の解雇制限も適用されません。
ですので、傷病年金を受けていて打切補償を支払ったものとみなす規定はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
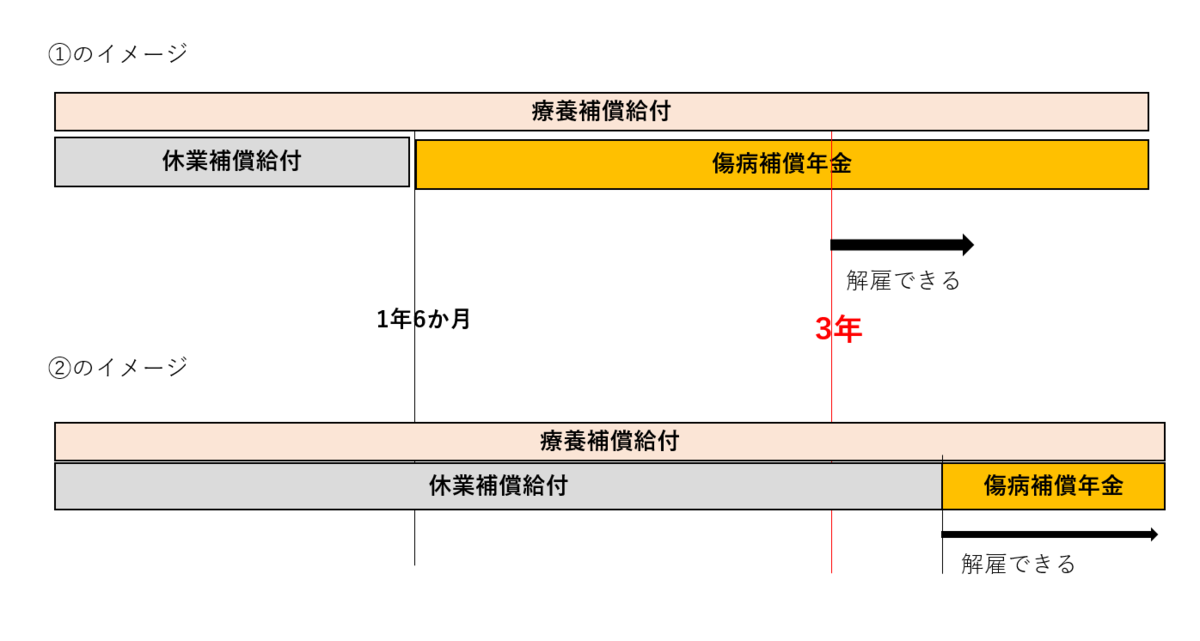
 ここを乗り越えよう!労災保険法
ここを乗り越えよう!労災保険法
R4-142
R4.1.11 打切補償と傷病補償年金の関係 その1(条文編)
まず、労働基準法の「解雇制限」の条文を読んでみましょう
労働基準法第19条 (解雇制限) ① 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。 ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。 ② ①の但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 |
労働基準法では、労働者が「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇禁止としています。
ただし、「使用者が打切補償を支払う場合」は解雇できる例外が設けられています。
では、次に打切補償の条文を読んでみましょう。
第81条 (打切補償) 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。 |
労働基準法では、労働者が「業務上」負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者に「療養補償」をする義務を課しています。
療養補償はなおるまで行わなければなりません。しかし、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合は、「打切補償」を行うことによって、以後補償する義務はなくなります。
「療養のために休業する期間及びその後30日間」は解雇が禁止されているのは、使用者に補償義務があるからです。「打切補償」を支払うと補償義務もなくなるので、解雇もできることになります。
しかし、業務上の負傷、疾病については、実際には労災保険法で補償が行われます。
ですので、使用者が労働基準法の療養補償を行うことはありません。そして、打切補償を行うこともありません。
労災保険法では、「傷病補償年金」を受けていることによって「打切補償」を行ったとみなす規定が設けられています。
「傷病補償年金」を受けているということは、「なおっていない」ことなので、解雇はできないことを頭において条文を読んでみてください。
労災保険法第19条 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。 |
労働基準法の「打切補償」が療養開始後3年を経過してもなおらない場合なので、この条文も「3年」がキーワードです。
①療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合
②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合
①は「3年を経過した日」、②は「傷病補償年金を受けることとなった日」に「打切補償」を支払ったものとみなされ、解雇することができるようになります。
(下の図も参考にしてください)
次回は、「問題編」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
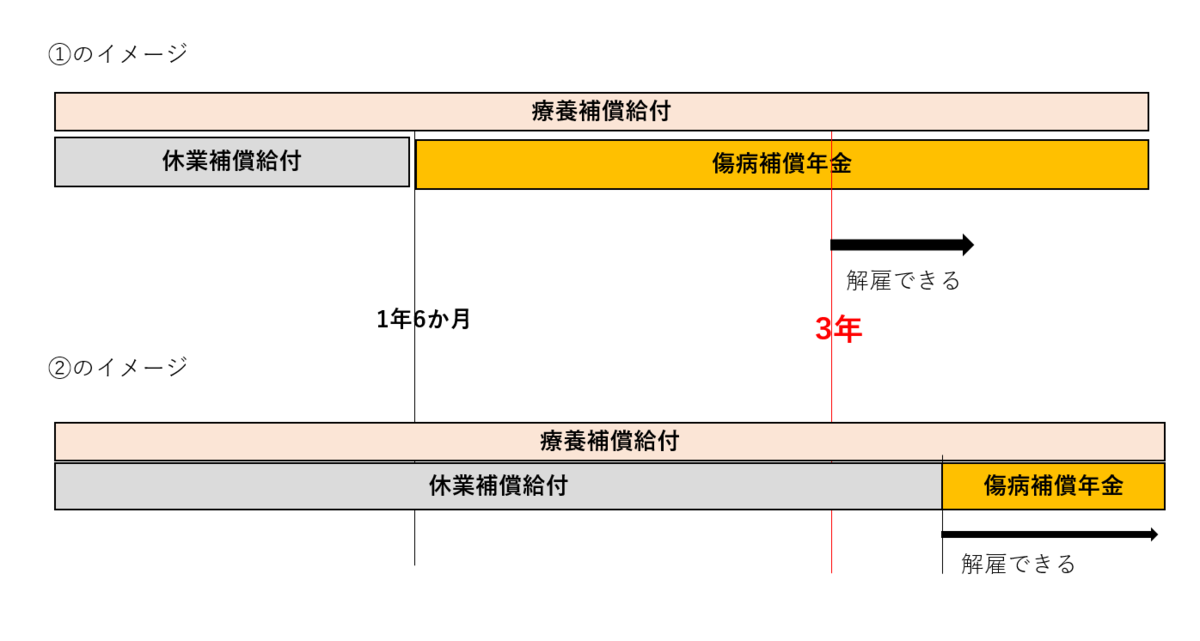
 どんな法律シリーズ③ 労働者災害補償保険法
どんな法律シリーズ③ 労働者災害補償保険法
R4-134
R4.1.3 労災保険法ってどんな法律?
労働者災害補償保険法・・・昭和22年施行
労働基準法と時を同じくして公布・施行されました。
労働基準法の第8章は「災害補償」です。
労働者の業務上の負傷等について、使用者に対して、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料を行うことが定められていて、また打切補償についても規定されています。
ただ、実際に、大きな業務災害が起こった時などに、使用者が災害補償を完全に履行できるかが問題です。
その問題を解決するのが労災保険です。
「保険」の仕組みをとり、すべての事業主が保険料を負担し、いざ、災害が発生したときは迅速に労働者に対して補償が行われる制度です。
使用者の「災害補償」の責任を代行するのが労災保険です。
労災保険は、保険料は全額事業主負担、保険給付の対象は全ての労働者であることがポイントです。被保険者という概念もありません。
他の公的保険、例えば健康保険には「被保険者」の範囲が位置付けられていて、被保険者は事業主と折半で保険料を負担し、負傷等の場合は被保険者に対して保険給付が行われます。
さて、労災保険は当初は「業務災害」だけが保護の対象でしたが、交通事情等の変化に伴い通勤途上の災害も保護する必要がでてきました。
「通勤災害」が労災保険の保護の対象に加わったのは、昭和48年の改正です。
そして、過労死等の原因になる脳血管疾患及び心臓疾患の発症を予防するための「二次健康診断等給付」が加わったのは、平成13年4月です。
さらに、令和2年9月からは、「複数事業労働者」への保険給付(複数業務要因災害に関する保険給付)も加わりました。
★では、目的条文を読んでみましょう。空欄を埋めて下さい。
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は< A >による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は< A >により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< B >に寄与することを目的とする。
解答は、A 「通勤」、B 「福祉の増進」です。
なお、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等の「等」は、二次健康診断等給付をさしています。
★では、次は第2条の2です。
| 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 |
労災保険法のメインの目的は「保険給付」を行うことです。
そして保険給付に付帯する事業が「社会復帰促進等事業」です。
■保険給付は、次の4つです。
① 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
② 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(①に掲げるものを除く。)
③ 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付
④ 二次健康診断等給付
■「社会復帰促進等事業」は次の3つです。
① 被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 (社会復帰促進事業)
② 被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 (被災労働者等援護事業)
③ 労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 (安全衛生確保等事業)
例えば、業務上の負傷が治癒し、障害等級第1級の障害が残った場合は、保険給付として、「障害補償年金」が支給されます。
それに上乗せして、社会復帰促進等事業の「被災労働者等援護事業」から「特別支給金」として、障害特別支給金と障害特別年金が支給されます。
(例)障害等級1級の場合
(社会復帰促進等事業) 特別支給金 | 障害特別年金 (算定基礎日額×313日分)/年 |
障害特別支給金 342万円(一時金) | |
(保険給付) | 障害補償年金 (給付基礎日額×313日分)/年 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉗」条文の読み方(労災保険法)
「最初の一歩㉗」条文の読み方(労災保険法)
R4-127
R3.12.27 「推定する」と「みなす」の違い
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
労災保険法の条文を読んでみましょう。
第10条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた労働者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。 |
「推定する」とは、「一応そのようにしておく」というイメージです。
船舶や航空機の事故で3か月間生死が分からない場合は、一応、事故のあった日に死亡したと推測します。遺族に対して迅速に保険給付を行うためです。
「推定する」の場合、反証があれば覆ります。もし、後日、労働者が生きていることが分かれば、受給していた遺族補償給付等を返還しなければなりません。
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。

【解答】
①【R2年出題】 ×
「行方不明となって3か月経過した日」ではなく、「労働者が行方不明となった日」に、当該労働者は、死亡したものと推定する、です。
遺族補償年金の支給は、労働者が行方不明となった日の属する月の翌月に遡って、開始します。
★ポイント! 「死亡の推定」は、船舶と航空機の事故に限定されています。
次はこちらの条文を読んでみましょう。
第16条の2 ① 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 1 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。 2 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 3 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。 4 1~3の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 ② 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 |
②に注目してください。「労働者の死亡の当時胎児であった子が出生した」ときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子と「みなす」。こちらは、みなすという用語を使っています。
「みなす」は、推定ではなく確定です。反証で覆ることはありません。
労働者の死亡当時に胎児だった子が出生したときは、必ず「生計維持」されていたとみなされますので、生まれた時点から受給資格者になります。
★ 妻以外は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
★ なお、55歳以上60歳未満で障害状態ではない夫、父母、祖父母、兄弟姉妹も暫定的に受給資格者になります。ただし、受給権者になっても60歳までは遺族補償年金は支給停止されます。(昭和40年改正法附則第43条第3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉔」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉔」法律によって定義が異なる用語
R4-124
R3.12.24 「障害等級」と「傷病等級」の定義(労災保険法)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
前回は、国民年金法と厚生年金保険法の「障害等級」の定義をお話しました。
今回は、「労災保険法の障害等級」です。
では、条文を読んでみましょう。
第15条 ① 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。 ② 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。 |
(別表第一)
障害補償年金 | 第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 同 277日分 | |
第3級 | 同 245日分 | |
第4級 | 同 213日分 | |
第5級 | 同 184日分 | |
第6級 | 同 156日分 | |
第7級 | 同 131日分 | |
障害補償一時金 | 第8級 | 同 503日分 |
第9級 | 同 391日分 | |
第10級 | 同 302日分 | |
第11級 | 同 223日分 | |
第12級 | 同 156日分 | |
第13級 | 同 101日分 | |
第14級 | 同 56日分 |
障害補償給付の障害等級は1級から14級までありますが、1級から7級の場合は「障害補償年金」、8級から14級の場合は「障害補償一時金」が支給されます。
例えば、1級の場合は、「給付基礎日額×313日分」が1年あたりの額です。14級の場合は、「給付基礎日額×56日分」が一括で支払われます。
過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。

【解答】
①【H30年出題】 〇
障害等級は障害等級表によって定められますが、障害等級表に載っていない障害もあります。そのような障害は、障害等級表に定められた障害等級を準用します。
では、次に「傷病等級」の条文を読んでみましょう
第12条の8 ③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。 1 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 |
(別表第二)
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 同 277日分 |
第3級 | 同 245日分 |
・傷病補償年金の「傷病等級」は1級から3級までです。年金の額は、障害補償年金の1級から3級と同じです。
・傷病補償年金は「治っていない事(治癒前)」の給付です。
・障害補償給付は「治った(治癒している)」後の給付です。
では、過去問を解いてみましょう
②【H30年出題】
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
②【H30年出題】 ×
療養の開始後1年を経過した日ではなく、療養の開始後「1年6か月を経過した日」です。
なお、「② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」の「厚生労働省令で定める傷病等級」は、第1級から第3級です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑥」過去問の活用(労災保険法)
「最初の一歩⑥」過去問の活用(労災保険法)
R4-106
R3.12.6 「療養の給付」と「療養の費用の支給」の区別(労災保険編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
業務上の負傷、疾病の治療については、療養補償給付が行われます。
第13条を見てみましょう。
第13条 ① 療養補償給付は、療養の給付とする。 ② 前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)による。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 6 移送 ③ 政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
|
療養補償給付は、「療養の給付」が原則で、例外的に「療養の費用の支給」が行われます。
「療養の給付」は現物給付です。負傷、疾病について診察などの治療が行われます。
「療養の費用の支給」は現金給付で、「療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合」に例外的に行われます。
では、過去問を解いてみましょう
①【R1年出題】
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等という。」)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
②【H27年出題】
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
療養の給付は、指定病院等で行われます。
指定病院等とは、
・社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所(労災病院のことです)
・都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者
のことです。
問題文のように、厚生労働大臣が健康保険法に基づいて指定する病院等でも、労災保険の指定病院等に該当しないときは療養の給付は行われません。
ちなみに、例外的に「療養の費用の支給」が行われるのは、
・療養の給付をすることが困難な場合
・療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合(施行規則第11条の2)
です。近くに指定病院等がないなどの理由が想定されています。
②【H27年出題】 ×
「療養の給付」の請求書は、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出します。
「療養の費用の支給」の請求書は、「直接」、所轄労働基準監督署長に提出し、その後労働者本人に現金が支払われます。
今日の過去問のポイント!
「療養補償給付」には、
「療養の給付(現物給付)」と「療養の費用の支給(例外)」がある
療養の給付の請求書は「指定病院等を経由」
療養の費用の請求書は「直接」所轄労働基準監督署長に提出
最後に穴埋め問題をどうぞ。
③【H28年選択式】
労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。

【解答】
A 療養の費用
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑤」条文の読み方(労働者災害補償保険法)
「最初の一歩⑤」条文の読み方(労働者災害補償保険法)
R4-105
R3.12.5 専門用語に慣れましょう「及び・並びに」(労災保険編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
早速、法第16条の7を読んでみましょう。
法第16条の7 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者 2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹 |
2の「及び」に注目してください。
及びは「and」ですので、「A及びB」なら「AとB」と読めます。「AとBとC」なら、「A、B及びC」となります。
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母」は、「子と父母と孫と祖父母」と並べているだけです。
3は「及び」と「並びに」が出てきますが、どちらもandの意味です
「及び」で小さくまとめて、大きく分けるときに「並びに」が使われます。
「A、B、C及びD並びにE」なら、『「AとBとCとD」と「E」』となり、「ABCD」と「E」が分けられます。
「子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹」ですと、『「子と父母と孫と祖父母」と「兄弟姉妹」』となります。
「子と父母と孫と祖父母」は生計を維持あり・なしで、2のグループか3のグループに入るか変わりますが、「兄弟姉妹」は生計維持あり・なし関係なく3のグループとなりますので、「子と父母と孫と祖父母」と分けて並べられています。
では、令和3年の問題を解いてみましょう。
【R3年出題(問6)】
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
B 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
C 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
D 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
E 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

【解答】 A
第16条の7では、遺族補償一時金を受けることができる遺族を、次の各号に掲げる者としています。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 前号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
そして、第2項で、「遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該各号に掲げる順序による。」と規定しています。
順序は、第1号→第2号→第3号で、第2号と第3号に掲げる者は並んでいる順序です。
まとめますと
①配偶者(生計維持あるなし関係なく)
生計維持していた②子、③父母、④孫、⑤祖父母
生計維持していなかった⑥子、⑦父母、⑧孫、⑨祖父母
⑩兄弟姉妹(生計維持あるなし関係なく)
配偶者は生計維持あるなし関係なく1番ですので、Aが誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ厚生年金保険法
R4-089
R3.11.19 障害手当金と労災保険の関係
令和3年の問題から厚生年金保険法を学びましょう。
今日は「障害手当金と労災保険の関係」です。
では、どうぞ!
①【R3年問10B】
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し、初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し、治療の効果が期待できない状態(治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ、また、労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合、両方の保険給付が支給される。

【解答】
①【R3年問10B】 ×
「両方の保険給付が支給される」が誤りです。
障害の程度を定めるべき日において当該傷病について、「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付」を受ける権利を有する者には、障害手当金を支給しない、と規定されています。
問題文の場合は、「障害手当金」は支給されません。
(法第56条)
こちらもどうぞ!
②【H25年出題】
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

【解答】
②【H25年出題】 ×
当該障害の原因となった傷病について「労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されない」の部分は正しいですが、「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される」の部分が誤りです。「労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者」にも「障害手当金」は支給されません。
(法第56条)
条文を穴埋めで確認しましょう
第55条 第1項 (障害手当金の受給権者)
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して< A >を経過する日までの間におけるその傷病の< B >日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

【解答】
A 5年
B 治った
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労災保険法
R4-061
R3.10.22 心理的負荷による精神障害の認定基準
令和3年の問題から労災保険法を学びましょう。
今日は「心理的負荷による精神障害の認定基準」です。
では、どうぞ!
★ 心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号)の業務による心理的負荷評価表の「平均的な心理的負荷の強度」の「具体的出来事」の1つである「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」の、「心理的負荷の強度を『弱』『中』『強』と判断する具体例」に関する問題です。
①【R3年問4A】
人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われたが、その行為が反復・継続していない場合、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなければ、心理的負荷の程度は「中」になるとされている。

【解答】
①【R3年問4A】 〇
人格や人間性を否定するような、業務上明らかに必要性がない精神的攻撃が行われ、行為が「反復・継続していない場合」は「中」になります。
また、上記のような「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃を受けて、「会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった場合」は「強」となります。
(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))
もう一問どうぞ!
②【R3年問4D】
治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が反復・継続していなくても、また、他に会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった等の事情がなくても、心理的負荷の程度は「強」になるとされている。

【解答】
②【R3年問4D】 ×
治療等を要さない程度の暴行による身体的攻撃が行われた場合、その行為が「反復・継続していない」場合は、「中」となります。
上記のような場合で、「会社に相談しても適切な対応がなく改善されなかった」場合は、「強」となります。
(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))
では、こちらもどうぞ!
③【R3年問4E】
「上司等」には、同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合、同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合も含む。

【解答】
③【R3年問4E】 〇
「上司等」には、職務上の地位が上位の者のみならず、「同僚又は部下であっても業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力が得られなければ業務の円滑な遂行を行うことが困難な場合」、「同僚又は部下からの集団による行為でこれに抵抗又は拒絶することが困難である場合」も含まれます。
(心理的負荷による精神障害の認定基準(令和2年5月29日付け基発0529第1号))
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ労災保険法
R4-053
R3.10.14 労災「特別加入者の支給制限」
令和3年の問題から労災保険法を学びましょう。
今日は特別加入者の支給制限です。
では、どうぞ!
①【R3年問3C】
特別加入している中小事業主が行う事業に従事する者(労働者である者を除く。)が業務災害と認定された。その業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失により生じさせたものである場合は、政府は、その業務災害と認定された者に対して保険給付を全額支給し、厚生労働省令で定めるところにより、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
①【R3年問3C】 ×
「保険給付を全額支給・費用の全部又は一部を事業主から徴収」の部分が誤りです。
特別加入している中小事業主等の事故が、
・保険料が滞納されている期間中に生じたものであるとき
・事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるとき
政府は、当該事故に係る保険給付の「全部又は一部を行わないことができる」と規定されています。
労働者の事故の場合は、「事業主からの費用徴収」になりますが、特別加入者については、「支給制限」になることがポイントです。
(法第34条)
こちらもどうぞ!
②【H26年出題】
事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付し、その後、重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
問題文の中に「一般保険料」とあるので、労働者に関する問題です。労働者の場合、「事業主が、故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」については、事業主からの費用徴収の対象となります。労働者に対して支給制限は行われないので注意しましょう。
(法第31条)
では条文を穴埋めで確認しましょう!
・ 中小事業主等の事故が第一種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。
・一人親方等及び特定作業従事者の事故が、第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。
・海外派遣者の事故が、第三種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の< A >。

【解答】
A 全部又は一部を行わないことができる
(法第34条、35条、36条)
★保険給付の支給制限が行われるのは、
中小事業主等 → 第一種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
事業主の故意又は重大な過失によって生じた事故
一人親方等 → 第二種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
海外派遣者 → 第三種特別加入保険料が滞納されている期間中の事故
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労災保険法 応用問題
R4-044
R3.10.5 労災「単身赴任者等の通勤災害」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は労災保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問2D】
配偶者と小学生の子と別居して単身赴任し、月に1~2回、家族の住む自宅に帰っている労働者が、1週間の夏季休暇の1日目は交通機関の状況等は特段の問題はなかったが単身赴任先で洗濯や買い物等の家事をし、2日目に家族の住む自宅へ帰る途中に交通事故に遭い負傷した。この場合は、通勤災害とは認められない。

【解答】
①【R3年問2D】 〇
休暇の「1日目」は「交通機関の状況等は特段の問題はなかった」、「2日目」に「家族の住む自宅へ帰る」の部分がポイントです。
通達では以下のようになっています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『「赴任先住居」から「帰省先住居」への移動について』
・「業務に従事した当日又はその翌日」に行われた場合は、就業との関連性を認めて差し支えない。
・翌々日以後に行われた場合は、交通機関の状況等の合理的事由があるときに限り、就業との関連性が認められる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問題文の場合、単身赴任者が家族の住む自宅に帰るのは、休暇の2日目(業務に従事した日の翌々日)です。そして「交通機関の状況等の合理的事由」はありません。
そのため、就業との関連性は認められず、通勤災害とは認められません。
(法第7条 H18.3.31基発0331042)
通勤の定義を条文で確認しましょう
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、< A >経路及び方法により行うことをいい、< B >を有するものを除くものとする。
1 住居と就業の場所との間の往復
2 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

【解答】
A 合理的な
B 業務の性質
2は、複数就業者の事業場間の移動のこと
3は、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居の間の移動のこと
(法第7条第2項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労災保険法よく出るところ
R4-034
R3.9.25 労災「特別加入者と通勤災害」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は労災保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問3B】
労働者を使用しないで行うことを常態とする特別加入者である個人貨物運送業者については、その住居とその就業の場所との間の往復の実態を明確に区別できることにかんがみ、通勤災害に関する労災保険の適用を行うものとされている。

【解答】
①【R3年問3B】 ×
特別加入者も、通常の労働者と同様に通勤災害の保護の対象となります。
ただし、一人親方等の一部は、住居と就業の場所との間の往復の状況を考慮して、通勤災害は適用除外となっています。
問題文の「個人貨物運送業者」は、通勤災害の適用は行われません。
(法第35条、則第46条の22の2)
では、こちらもどうぞ!
②【H30年選択】
通勤災害に関する保険給付は、一人親方等及び特定作業従事者の特別加入者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者には支給されない。< A >はその一例に該当する。
~選択肢~
①医薬品の配置販売の事業を行う個人事業者
②介護作業従事者
③個人タクシー事業者
④船員法第1条に規定する船員
③【H26年出題】
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
④【H22年出題】
一人親方等の特別加入者のうち、漁船による水産動植物の採捕の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は、自宅から漁港までの移動が通勤とみなされ、通勤災害に関しても労災保険の適用を受けることができる。

【解答】
②【H30年選択】 ③個人タクシー事業者
個人タクシー事業者は、通勤災害は適用されません。
③【H26年出題】 〇
家内労働者は通勤災害は適用されません。
④【H22年出題】 ×
漁船による水産動植物の採捕の事業を行う者は、通勤災害は適用されません。
ポイント! 一人親方等で、通勤災害が適用されない者は覚えましょう。
・ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
(個人タクシー業者、個人貨物運送業者)
・ 漁船による水産動植物の採捕の事業(船員法第1条の船員が行う事業除く。)
(漁船による自営漁業者)
・ 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者
・ 家内労働者又はその補助者
★通勤災害が適用されないのは、すべての一人親方等ではなく、上記の者のみですので注意してください。
では、最後にこちらの条文をチェックしましょう。
則第46条の26(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、< B >が定める基準によって行う。

【解答】
B 厚生労働省労働基準局長
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)労災保険法の定番問題
R4-024
R3.9.15 遺族補償一時金の受給資格者の順位
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は労災保険法です。
①【R3年問6】
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
B 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
C 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた孫は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より先順位となる。
D 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった子より後順位となる。
E 労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた兄弟姉妹は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より後順位となる。

【解答】
A ×
B 〇
C 〇
D 〇
E 〇
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次のとおりです。
1 配偶者
2 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
3 その他の子、父母、孫及び祖父母
4 兄弟姉妹
★「配偶者」は「生計維持していた」、「生計維持していない」、どちらでも第1順位です。
★子、父母、孫、祖父母は、「生計維持していた」方が優先です。
★兄弟姉妹は、「生計維持していた」、「生計維持していない」、どちらでも一番最後です。
(法第16条の7)
「遺族補償一時金」と「遺族補償年金」と比較してみましょう。
②【H18問5A】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】
②【H18問5A】 ×
遺族補償給付には、「遺族補償年金」と「遺族補償一時金」があります。
「遺族補償年金」を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られます。一方、「遺族補償一時金」は、生計を維持していなかった者も、受給資格者の範囲に入ります。
こちらは、「遺族補償給付」(年金も一時金も含む)についての問題ですので、生計を維持していたものに限られません。
(法第16条の2、第16条の7)
では、「障害補償年金差額一時金」とも比較してみましょう。
③【H26選択】
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、< A >の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、< A >の順序である。

【解答】
A 祖父母及び兄弟姉妹
障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順序は、「生計を同じくしていた」①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、「生計を同じくしていなかった」⑦配偶者、⑧子、⑨父母、⑩孫、⑪祖父母、⑫兄弟姉妹、です。
「生計維持」ではなく、「生計を同じくしていた」が基準となります。
また、遺族の順序は、「生計を同じくしていた」方が優先されます。
(法附則第58条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・労災保険法【択一】
R4-013
R3.9.4 第53回労災(択一)より~加重障害
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★☆ 条文を丸暗記しても解けない問題とテキスト・過去問で対応できる問題が半々でした。
【R3年問5】
業務上の災害により既に1上肢の手関節の用を廃し第8級の6(給付基礎日額の503日分)と障害等級を認定されていた者が、復帰直後の新たな業務上の災害により同一の上肢の手関節を亡失した場合、現存する障害は第5級の2(当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の184日分)となるが、この場合の障害補償の額は、当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の何日分となるかについての次の記述のうち、正しいものはどれか。
A163.88日分
B166.64日分
C184日分
D182.35日分
E182.53日分

【解答】 A
ポイント!
「加重障害」の問題です。
『既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合』の障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付となります。
給付額は、現在の障害等級の障害補償給付の額から、既にあった障害等級に応ずる障害補償給付の額を差し引いた額となります。
問題文の場合、現在は5級(年金)、既存の障害は8級(一時金)であることがポイントです。
この場合は、既存の一時金は25で割って差額を出します。(一時金は25年分の年金をまとめて支払っている計算です。)
計算式は、5級の年金(184日分/年間)- 8級の一時金の25分の1(503日分÷25)です。
答えは、「163.88日分」となります。
(法第15条、則14条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
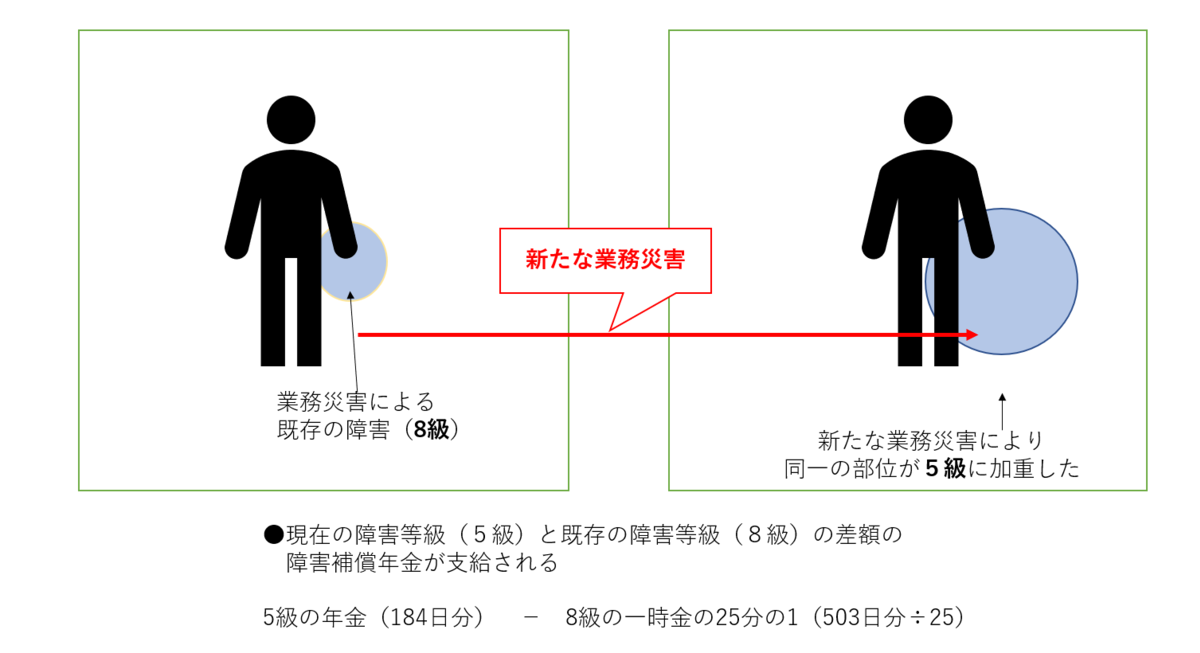
第53回選択式(労災保険法)
R4-004
R3.8.26 第53回選択労災~暗記が肝心★☆☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、労災保険法の選択式です。
問題1
令和2年改正の「複数業務要因災害」からの出題です。
A 複数事業労働者の定義(法第7条第1項第2号、則第5条)
複数事業労働者には、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」も含むと定められています。
なぜなら、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症の時期が必ずしも一致しないことがあるからです。傷病等が発症した時点で複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあるがゆえの規定です。
(参照: R2.8.21基発0821第1号)
B 複数業務要因災害に係る事務の所轄(則第1条)
複数業務要因災害に係る事務の所轄は、「生計を維持する程度の最も高い事業」の主たる事務所を管轄する局又は署となります。
なお、「生計を維持する程度の最も高い事業の主たる事務所」とは? → 原則として複数就業先のうち給付基礎日額の算定期間における賃金総額が最も高い事業場を指します。
(参照: R2.8.21基発0821第1号)
問題1 ★★☆ やや難しい
問題2
年金の「支給停止期間」からの出題です。(法第9条)
この問題は大丈夫だったと思います。
問題2 ☆☆☆ どうにか解ける
問題3
遺族補償年金を受けることができる遺族(法第16条の2、S40法130附則第43条)
D 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の年齢
法16条の3では、「60歳以上」、しかし、附則では暫定措置として55歳以上とされています。ですので、私は「55歳以上」だと考えています。でも、本則上の年齢を問われているとしたら、60歳以上です。
E 子、孫、兄弟姉妹の年齢
この問題は迷わず解けたと思います。
問題3 ☆☆☆ どうにか解ける
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法 選択対策
R3-354
R3.8.12 労災保険法 選択問題~改正点など
今日は、労災保険法の選択対策です。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
問題① 総則
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< B >に寄与することを目的とする。
第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、 < A >の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、< C >を行うことができる。
問題②
第7条
この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< D >」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。)
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付
問題③
法第20条の3
複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。)にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
労災保険法施行規則第18条の3の6(複数業務要因災害による疾病の範囲)
法第20条の3第1項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他< E >ことの明らかな疾病とする。

【解答】
問題①
A 複数事業労働者
B 福祉の増進
C 社会復帰促進等事業
(法第1条、第2条の2)
問題②
D 複数業務要因災害
(法第7条)
★ポイント!労災保険の目的の改正
・今般の改正により、労災保険の目的として、「複数事業労働者」の二以上の事業の業 務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)につ いても保険給付を行うことが加えられた。
・労災法第2条の2において、第1条の目的を達成するため、保険給付を行う場合について複数業務要因災害が加えられた。
・複数業務要因災害に関する保険給付は、それぞれの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない。そのため、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負わない。
参照 → R2.8.21 基発0821第1号
問題③
E 二以上の事業の業務を要因とする
(則第18条の3の6)
★ポイント!複数業務要因災害の範囲
複数業務要因災害による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の3の6により、労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(以下「脳・心臓疾患、精神障害」という。)及びその他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病としており、現時点においては、脳・心臓疾患、精神障害が想定されている。
参照 → R2.8.21 基発0821第1号
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【改正労災】複数事業労働者(特別加入者編)
R3-324
R3.7.13 複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)
今日のテーマは、「複数事業労働者の給付基礎日額(特別加入者編)」です。
以下のような場合も「複数事業労働者」となります。
・ある会社では「労働者」として働く一方、他の仕事で「特別加入」している
・複数の仕事で「特別加入」している
このような場合の給付基礎日額の算定についてみていきましょう。
では特別加入者の給付基礎日額のポイントからどうぞ!
穴埋めで確認しましょう。
(平成30年選択式より)
・中小事業主等の特別加入の給付基礎日額 → 当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とされており、最高額は、
< A >である。

【解答】
A 25,000円
特別加入者の給付基礎日額は、3,500円から最高25,000円まで、16段階の設定があります。また、家内労働者については、それにプラスして「2,000円、2,500円、3,000円」の設定もあります。
 特別加入者の給付基礎日額のポイント
特別加入者の給付基礎日額のポイント
| 自動変更対象額 | 適用なし |
| 年齢階層別の最高・最低限度額 | |
| スライド制 | 適用される |
では、複数事業労働者の場合の給付基礎日額は?
①労働者であって、かつ、特別加入者である場合
労働者としての給付基礎日額 + 特別加入者としての給付基礎日額
※労働者としての給付基礎日額 → 合算前に自動変更対象額、スライド制、年齢階層別最高・最低限度額を適用し算定
※特別加入者としての給付基礎日額 → 合算前に、スライド制のみ適用し算定
②複数の特別加入を行っている場合
特別加入者としての各給付基礎日額を合算 → 合算した額にスライド制のみ適用し算定
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【労災】特別加入者の範囲
R3-323
R3.7.12 令和3年4月改正 特別加入者の範囲その2
今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その2です!
特別加入者は、3つに分かれています。
第1種特別加入者 → 中小事業主等
第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者
第3種特別加入者 → 海外派遣者
今日は、「特定作業従事者」の範囲を確認しましょう。
では穴埋めでどうぞ!
【特定作業従事者の範囲】
1 農業における一定の作業
2 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる一定の作業
3 家内労働者及びその補助者が行う一定の作業
4 労働組合等の常勤の役員が行う一定の作業
5 介護関係業務に係る一定の作業及び家事支援に係る一定の作業
令和3年4月より追加された作業
↓
6 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における< A >の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
7 < B >の制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

【解答】
A 音楽、演芸その他の芸能
B アニメーシヨン
(則第46条の18)
★令和3年4月から追加されたのは次の2つです。
■芸能従事者
・芸能実演家(俳優、舞踊家、音楽家、演芸家、スタント等)
・芸能製作作業従事者(監督、撮影、衣装、メイク等)
■アニメーション制作作業従事者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【労災】特別加入者の範囲
R3-322
R3.7.11 令和3年4月改正 特別加入者の範囲その1
今日のテーマは、令和3年4月に改正された「特別加入者の範囲」その1です!
特別加入者は、3つに分かれています。
第1種特別加入者 → 中小事業主等
第2種特別加入者 → 一人親方等、特定作業従事者
第3種特別加入者 → 海外派遣者
令和3年4月より改正された「一人親方等」の範囲を確認しましょう。
では穴埋めでどうぞ!
【一人親方等の範囲】
1 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業
(例)個人タクシー業者や個人貨物運送業者など
2 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
(例)大工、左官、とび職人
3 漁船による水産動植物の採捕の事業(7に掲げる事業を除く。)
4 林業の事業
5 医薬品の配置販売の事業
6 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
7 船員法第1条に規定する船員が行う事業
8 < A >法第2条に規定する< A >が行う事業
9 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する< B >その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する< C >に係る< B >その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

【解答】
A 柔道整復師
B 委託契約
C 社会貢献事業
(則第46条の17)
★8と9が令和3年4月から追加された事業です。
9は、先日書きました「【改正】70歳までの就業確保措置」によって「創業支援等措置」に基づく事業を行う人が対象です。
★ 明日は特定作業従事者です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
労災保険法 令和2年9月改正その4
R3-298
R3.6.17 複数事業労働者の給付基礎日額~具体例
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
複数事業労働者とは → R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
複数業務要因災害とは → R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
複数事業労働者の給付基礎日額 → R3.6.16 複数事業労働者の給付基礎日額の算定について
今日のテーマは、複数事業労働者の給付基礎日額の具体例です。
まずは、労働基準法の平均賃金の出し方を確認しましょう。
労働基準法第12条
1.労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前< A >か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の< B >で除した金額をいう。
ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下ってはならない。
① 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に< C >で除した金額の< D >
② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と①の金額の合算額
2. 1.の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

【解答】
A 3
B 総日数
C 労働した日数
D 100分の60
<原則>
算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(※就労日数ではなく、暦日数です)
<最低保障額> 時間額や日額、出来高給の場合
算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ 労働日数 × 100分の60
※注意点
・算定事由発生日の前日から遡ります。
・賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から遡ります。
複数事業労働者の給付基礎日額の注意点
<労働基準法の平均賃金の最低保障について>
・複数事業労働者の給付基礎日額相当額
→ 時給や日給制等の場合、労基法の規定では、平均賃金の算定について最低保障の適用があります。しかし、労災保険法では、特例により、労基法の規定による最低保障は適用しない金額を給付基礎日額相当額とする、とされています。
(具体例)
A社とB社の2社で就業している場合
A社 → 月給15万円
B社 → 日給1万円で月9日勤務
直近3カ月の総日数は90日
■計算式■
A社 → 15万円×3か月÷90日 = 5,000円
B社 → 1万円×9日×3か月÷90日 = 3,000円※
給付基礎日額は、A社(5,000円)+B社(3,000円)=8,000円となります。
※B社は日給制なので、労働基準法では平均賃金の最低保障額が適用されます。
最低保障は、(10,000円×9日)×3か月÷(9日×3か月)×100分の60 = 6,000円となります。しかし、労災則第9条第1項第4号に基づく給付基礎日額相当額の特例として、労基法第12 条第1項ただし書の規定(最低保障)の適用を受けないものとした場合の金額を、給付基礎日額相当額とすることになります。
ちなみに・・・
各事業場の「平均賃金の最低保障額」が「合算後の額」より高い場合
→各事業の平均賃金の最低保障額のうち、最も高い額が給付基礎日額となります。
参照:労災保険法第8条、則9条の2の2、令和2.8.21基発0821第2号
社労士受験のあれこれ
労災保険法 令和2年9月改正その3
R3-297
R3.6.16 複数事業労働者の給付基礎日額の算定について
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
今日のテーマは、複数事業労働者の給付基礎日額です。
複数事業労働者とは → R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
複数業務要因災害とは → R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
条文を確認しましょう。
第8条
① 給付基礎日額は、労働基準法第12条の< A >に相当する額とする。この場合において、< A >を算定すべき事由の発生した日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって< B >が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
② 労働基準法第12条の< A >に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、①の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。
③ ①、②の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者(葬祭を行う者)に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、①、②に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を< C >した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額とする。

【解答】
A 平均賃金
B 疾病の発生
C 合算
ポイント!
給付基礎日額 = 労働基準法の平均賃金に相当する額
算定事由発生日 = ・負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日
・診断によって疾病の発生が確定した日
※複数事業労働者の給付基礎日額(原則)のポイント
複数事業労働者の業務上の事由による傷病等 (業務災害) | 複数事業労働者を使用する全事業における賃金をもとに給付基礎日額を算定する |
複数事業労働者(複数事業労働者に類する者を含む。)の2以上の事業の業務を要因とする事由による傷病等(複数業務要因災害) | |
| 複数事業労働者の通勤による傷病等(通勤災害) |
※複数事業労働者は複数の事業で働くことによって生計を立てているため、労災保険の保険給付もすべての事業の賃金を合算して算定するという考え方です。
※ 複数事業労働者に関する保険給付を行う場合における給付基礎日額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額(以下「給付基礎日額相当額」という。)を合算した額を基礎として算定します。
(令和2.8.21基発0821第2号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
労災保険法 令和2年9月改正その2
R3-296
R3.6.15 労災(改正)複数業務要因災害とは?
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
労災保険法の主たる事業は「保険給付」で、それに付随するものとして「社会復帰促進等事業」があります。
労災保険法の改正によって、「保険給付」は4つに分かれることになりました。
<保険給付の種類>
| 業務災害に関する保険給付 |
| 複数業務要因災害に関する保険給付 |
| 通勤災害に関する保険給付 |
| 二次健康診断等給付 |
今日は、新しく加わった「複数業務要因災害」がテーマです。
では、どうぞ!
空欄を埋めてください。
第7条
労災保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 < A >(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< B >」という。)に関する保険給付(1の業務災害を除く。)
3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
4 二次健康診断等給付

【解答】
A 複数事業労働者
B 複数業務要因災害
ポイント! 複数業務要因災害とは?
複数業務要因災害 → 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のこと。ただし、「業務災害」の場合は除かれます。
★さらにポイント
・複数業務要因災害の範囲 → 対象の傷病は「脳・心臓疾患、精神障害」
複数業務要因災害による疾病の範囲は、則第18条の3の6で、『労働基準法施行規則別表1の2第8号及び第9号に掲げる疾病(「脳・心臓疾患、精神障害」)及びその他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病』と規定されています。現時点で想定されているのは、脳・心臓疾患、精神障害です。
★複数業務要因災害のポイント色々
・複数業務要因災害に関する保険給付
「業務災害」は、1つの事業の業務上の負荷(労働時間やストレス)だけで労災認定をします。
このたび新しく加わった「複数業務要因災害」は、単独の事業場の負荷だけでは労災認定されなくても、複数の事業の業務上の負荷を総合的に評価することによって、労災認定されるものです。
「2以上の事業の業務を要因とする」とは、複数の事業での業務上の負荷を総合的に評価して当該業務と負傷、疾病、障害又は死亡の間に因果関係が認められることをいいます。
・労働基準法の災害補償責任
1つの就業先の業務上の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められないので、いずれの就業先も労働基準法上の災害補償責任は負いません。
(令和2.8.21基発0821第1号)
★複数業務要因災害に関する保険給付の種類
1 複数事業労働者療養給付
2 複数事業労働者休業給付
3 複数事業労働者障害給付
4 複数事業労働者遺族給付
5 複数事業労働者葬祭給付
6 複数事業労働者傷病年金
7 複数事業労働者介護給付
(法第20条の2)
 ちなみに、これまでは、業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、療養(補償)給付のように略称していました。今後は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するそうです。
ちなみに、これまでは、業務災害及び通勤災害に関する保険給付については、療養(補償)給付のように略称していました。今後は、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付をまとめて療養(補償)等給付のように略称するそうです。
(令和2.8.21基発0821第1号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
労災保険法 令和2年9月改正その1
R3-295
R3.6.14 労災(改正)複数事業労働者とは?
令和2年9月1日から、複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定及び複数業務要因災害に係る労災保険制度が施行されています。
<改正のポイント>
・複数事業労働者に関する保険給付について
→ すべての事業場の賃金を合算した額を基礎として給付基礎日額を決定する
・1つの事業における業務上の負荷(労働時間やストレス等)のみでは業務と疾病等の間に因果関係が認められない場合
→ すべての事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断する
では、どうぞ!
第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「< A >」という。)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
第2条の2
労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、< A >の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

【解答】
A 複数事業労働者
ポイント! 複数事業労働者とは?
複数事業労働者 → 事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のこと
簡単に言うと、算定事由発生日にA社とB社というように、複数の事業場で働いている労働者のことです。
★さらにポイント
労災法第7条第1項第2号で、複数事業労働者には「これに類する者も含む」とされています。
「これに類する者」の範囲は、則第5条で「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者」と定められています。
注目ポイントは、傷病等の発生時ではなく、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点」に2以上の事業に同時に使用されていたという点です。
複数業務要因災害の対象である複数事業労働者について、傷病等が発症した時点で、複数事業労働者に該当しない場合でも、当該傷病等の要因となる出来事と傷病等の因果関係が認められる期間の範囲内で複数事業労働者に当たるか否かを判断すべきときがあるからです。これは、傷病等の要因となる出来事と傷病等の発症時期がずれることがあるためです。
例えば、傷病等が発症した時点では、「A社」だけで働いていたが、「傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時期」に、「A社」と「B社」で就業していたような場合も複数事業労働者になるということです。
★もう一つポイント
『「労働者」であってかつ他の事業場で「特別加入をしている者」』及び『複数の事業場において特別加入をしている者』も複数事業労働者として保護の対象となります。
(令和2.8.21基発0821 第1号)
明日に続きます。
社労士受験のあれこれ
労災 療養補償給付その2
R3-294
R3.6.13 療養補償給付よく出るところ その2
昨日に引き続き、労災保険の「療養補償給付」です。
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<R1年出題>
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等という。」において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われない。
②<H21年出題>
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

【解答】
①<R1年出題> 〇
ポイント! 療養の給付(現物給付)は、指定病院等で
療養の給付が受けられるのは「指定病院等」です。
指定病院等とは
・ 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所(労災病院のこと)
・ 都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者 (労災保険指定医療機関・薬局等)
です。
指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等であっても、療養の給付は行われません。
(則第11条)
②<H21年出題> ×
ポイント! 療養の給付が原則、療養の費用の支給は例外
療養の費用が支給されるのは、「療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とされていて、例えば、近くに指定病院等がないような場合です。
問題文のように、指定病院等でない病院等での療養を望んだとしても、それだけでは療養の費用の支給の対象にはなりません。
(則11条の2、昭41.1.31基発第73号)
こちらもどうぞ!
③<H27年出題>
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
④<H22年出題>(改正あり)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由、⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
A ①~⑧
B ②~⑧
C ③~⑧
D ③、④
E ③、④、⑦

【解答】
③<H27年出題> ×
請求書の提出について
療養の給付 → 指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に提出
療養の費用の支給 → 直接、所轄労働基準監督署長に提出
(則第12条)
④<H22年出題>(改正あり) D
事業主の証明を受けなければならないものは、「③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況」です。
※令和2年9月の改正により
・証明を受ける事業主から「非災害発生事業場の事業主」は除かれます。
・「⑧労働者が複数事業労働者である場合は、その旨」が加わりました。
(則第12条の2)
社労士受験のあれこれ
労災 療養補償給付その1
R3-293
R3.6.12 療養補償給付よく出るところ その1
労災保険の「療養補償給付」には
・療養の給付(現物給付)
・療養の費用の支給(現金給付)
の2種類があります。
無料で治療などを受けられる療養の給付(現物給付)が原則で、療養の費用の支給(現金給付)は、例外です。
では、どうぞ!
①<H21年出題>
傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復していなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は行われない。
②<H28年出題>
業務上の疾病が治って療養の必要がなくなった場合には、その後にその疾病が再発しても、新たな業務上の事由による発病でない限り、業務上の疾病とは認められない。
③<H27年出題>
療養の給付は、その傷病が療養を必要としなくなるまで行われるので、症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になっても、神経症状のような傷病の症状が残っていれば、療養の給付が行われる。

【解答】
①<H21年出題> 〇
ポイント!
療養補償給付、療養給付は「治ゆ」するまで
療養補償給付(療養給付)は、治療の必要がなくなるまで行われます。
例えばケガの場合は、傷口が治った状態をイメージしてください。治ゆとは、「症状固定」の状態をいいます。「傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態になって治療の必要がなくなった場合」です。
(昭23.1.13基災発第3号)
②<H28年出題> ×
いったん、症状固定(治ゆ)が認められれば療養補償給付(療養給付)は終了しますが、再び発症し一定の要件を満たせば、「再発」となり、療養補償給付(療養給付)が再開されます。
③<H27年出題> ×
症状が安定して疾病が固定した状態になり、医療効果が期待しえない状態になれば、療養の給付は終了します。
では、こちらもどうぞ!
④<H24年出題>
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
⑤<H24年出題>
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】
④<H24年出題> 〇
療養補償給付も休業補償給付も「治ゆする前」の給付です。治療で休んでいる間は、療養補償給付と休業補償給付の両方を受けることができます。
⑤<H24年出題> 〇
傷病補償年金も「治ゆする前」の給付ですので、治療を受けながら(療養補償給付を受けながら)、受給することができます。
最後に条文を確認しましょう。
空欄を埋めてください。
第13条
① 療養補償給付は、療養の給付とする。
② ①の療養の給付の範囲は、次の各号(< A >が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 < B >
③ 政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて< C >することができる。

【解答】
A 政府
B 移送
C 療養の費用を支給
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-255
R3.5.5 「心理的負荷による精神障害の認定基準」その2
引き続き、今日も「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。
(認定基準について)
1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
1 対象疾病を発病している。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
ではどうぞ!
①<H24年出題>
認定基準における対象疾病の発病に至る原因の考え方は、環境由来の心理的負荷(ストレス)と、個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こるし、逆に脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする「ストレス-脆弱性理論」に依拠している。
②<H30年出題>
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかという観点から評価されるものであるとされている。

【解答】
①<H24年出題> 〇
・ 心理的負荷(ストレス)が非常に強い → 個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こる
・ 脆弱性が大きい → 心理的負荷(ストレス)が小さくても破綻が生ずる
※心理的負荷による精神障害の業務起因性を判断する要件 → 対象疾病の発病の有無、発病の時期及び疾患名について明確な医学的判断があること + 当該対象疾病の発病の前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負荷が認められること
(H23.12.26 基発1226 第1号)
②<H30年出題> ×
「主観的にどう受け止めたかという観点」が誤りです。
強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるものである、とされています。( 「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する者のこと。)
(H23.12.26 基発1226 第1号)
こちらもどうぞ!
③<H30年出題>
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね6か月の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として「強」、「弱」の二段階に区分することとされている。

【解答】
③<H30年出題> ×
「強」、「弱」の二段階ではなく、「強」、「中」、「弱」の三段階に区分されています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
最後にこちらをどうぞ
④<H30年出題>
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
⑤<H24年出題>
認定基準においては、例えば対象疾病の発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行っていたときには、手待時間が多いなど労働密度が特に低い場合を除き、心理的負荷の総合評価を「強」と判断するとしている。

【解答】
④<H30年出題> ×
120時間ではなく「160時間」を超える時間外労働を行った場合等です。
⑤<H24年出題> 〇
発病前おおむね6か月の間に、「特別な出来事」に該当する業務による出来事が認められた場合には、心理的負荷の総合評価が「強」と判断されます。
特別な出来事には、「心理的負荷が極度のもの」と 「極度の長時間労働」の2つ類型があります。
そのうち、「極度の長時間労働」とは、 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)とされています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-254
R3.5.4 「心理的負荷による精神障害の認定基準」その1
今日のテーマは「心理的負荷による精神障害の認定基準 」です。
(認定基準について)
1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱われます。
1 対象疾病を発病している。
2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる。
3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められない。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
ではどうぞ!
①<H30年出題>
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

【解答】
①<H30年出題> 〇
穴埋め式でポイントをおさえましょう!
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、< B >が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

【解答】
A 6か月
B 業務による強い心理的負荷
(H23.12.26 基発1226 第1号)
では、こちらもどうぞ
②<H30年出題>
認定基準においては、「いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする。」とされている。

【解答】
②<H30年出題> ×
問題文の最後の「発病前6か月以内の行為のみを評価の対象とする」が誤りです。
いじめやセクシュアルハラスメントのように、出来事が繰り返されるものについては、発病の6か月よりも前にそれが開始されている場合でも、発病前6か月以内の期間にも継続しているときは、開始時からのすべての行為を評価の対象とすることとされています。
(H23.12.26 基発1226 第1号)
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-253
R3.5.3 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 その2
引き続き、テーマは「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 」です。
(認定基準について)
次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した 脳・心臓疾患は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り 扱う。
(1) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る 異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。
(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(以下「短期間の過重業務」とい う。)に就労したこと。
(3) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下 「長期間の過重業務」という。)に就労したこと。
(H13.12.12 基発第1063号)
ではどうぞ!
①<H28年選択>
厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。
業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。
「発症前の長期間とは、発症前おおむね< A >をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前< B >におおむね100時間又は発症前< C >にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。

【解答】
①<H28年選択>
A 6か月間
B 1か月間
C 2か月間ないし6か月間
ポイント!
★ 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間
★ 労働時間(疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる)に着目
→ その時間が長いほど、業務の過重性が増す
→ 発症日を起点とした1か月単位の連続した期間をみて、
① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合 → 業務と発症との関連性が弱い
おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど → 業務と発症との関 連性が徐々に強まると評価できる
② 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる → 業務と発症との関連性が強いと評価できる
(H13.12.12 基発第1063号)
こちらもどうぞ
②<H22年出題>
厚生労働省労働基準局長通知(「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」平成13年12月12日付け基発第1063号)では、業務による明らかな過重負荷を「異常な出来事」、「短期間の過重業務」及び「長期間の過重業務」に区分し、認定要件としているが、これらの三種類の過重負荷の評価期間について、「異常な出来事」については発症直前から前日までの間を、「短期間の過重業務」については発症前おおむね1か月間を、「長期間の過重業務」については発症前おおむね3か月間としている。

【解答】 ×
■過重負荷の評価期間■
「異常な出来事」 → 発症直前から前日までの間
「短期間の過重業務」 → 発症前おおむね1週間
「長期間の過重業務」 → 発症前おおむね6か月間
社労士受験のあれこれ
業務上の疾病(労働基準法施行規則別表1の2)
R3-252
R3.5.2 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 その1
今日のテーマは、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準 」です。
まずこちらからどうぞ!
①<H18年選択>
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、 < B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

【解答】
①<H18年選択>
A 労働基準法施行規則
B 労働者災害補償保険法施行規則
C 業務に起因することの明らかな疾病
ポイント!
業務上の疾病の範囲 → 労働基準法施行規則
通勤による疾病の範囲 → 労働者災害補償保険法施行規則
で定められている。
労働基準法施行規則別表第1の2を見てみましょう
★空欄を埋めてください。
別表第一の二
一 業務上の< D >に起因する疾病
二 物理的因子による次に掲げる疾病
(省略)
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病
(省略)
四 化学物質等による次に掲げる疾病
(省略)
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病
(省略)
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次に掲げる疾病
(省略)
八 < E >にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)若しくは解離性大動脈瘤りゆう又はこれらの疾病に付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
十一 その他< F >ことの明らかな疾病

【解答】
D 負傷
E 長期間
F 業務に起因する
労働基準法施行規則別表第一の二(「職業病リスト」)の1号から10号で、一定の疾病が例示列挙されています。
また、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」は、例示列挙されている疾病以外に業務に起因したと認められる疾病が発生した場合に、当てはめるためのものです。
★ なお、「業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患」は、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に該当する疾病として取り扱われます。
要件は、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」によります。明日から、こちらの通達をみていきます。
こちらの問題もどうぞ!
②<H28年出題>
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

【解答】
②<H28年出題> 〇
「業務上の疾病」と認められるには、労働基準法施行規則別表第一の二の1号から11号のどれかに該当することが要件です。
社労士受験のあれこれ
労災~休業補償給付
R3-216
R3.3.27 休業補償給付 一部のみ労働する日②
昨日に引き続き、テーマは「休業補償給付」です。
今日は「一部のみ労働する日」の休業補償給付(その2)です。
では、どうぞ!
<H16年出題>
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。

【解答】 〇
所定労働時間の一部分だけ労働した日の休業補償給付は、「(給付基礎日額-実際に労働した部分の賃金額)×60%」で計算することは、前回お話しました。
今回の問題は、労働しなかった時間について、事業主が金額を支払った場合の取り扱いです。
休業補償給付は賃金を受けない日に支給されますが、一部労働不能の場合は、①「その労働不能の時間について全く賃金を受けない日」、②「平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか受けない日」が「賃金を受けない日」に該当します。
問題文は②に当たりますので、「賃金を受けない日」となり、休業補償給付が支給されます。
例えば、給付基礎日額が10,000円、実際に労働した部分の賃金が4,000円の場合で、労働しなかった時間に対して事業主から2,000円支払われた場合を考えてみましょう。
平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額が6,000円で、事業主からの2,000円はその60%未満です。
ですので、「賃金を受けない日」として、休業補償給付が3,600円((10,000円-4,000円)×60%)が支給されます。
(労災保険法第14条 昭40.7.31基発901号)
社労士受験のあれこれ
労災~休業補償給付
R3-215
R3.3.26 休業補償給付 一部のみ労働する日①
昨日に引き続き、テーマは「休業補償給付」です。
今日は「一部のみ労働する日」の休業補償給付(その1)です。
では、どうぞ!
①<H16年出題>
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。

【解答】 〇
所定労働時間の一部分だけ労働した日(=一部分だけ休業した日)も休業(補償)給付の対象になります。
そのような一部休業日の休業補償給付は、「(給付基礎日額 - 実際に労働した部分の賃金額)×60%」で計算します。
例えば、給付基礎日額(通常通り労働した場合の1日あたりの賃金額)が10,000円、実際に労働した部分の賃金が4,000円の場合、その日の休業(補償)給付は、(10,000円-4,000円)×60%=3,600円となります。
(労災保険法第14条)
こちらもどうぞ!
②<H13年出題>
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。
③<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額の100分の60に相当する額である。

【解答】
②<H13年出題> 〇
③<H30年出題> 〇
①の問題と同じです。
一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、「給付基礎日額」と「実際に労働した部分の賃金額」の差額の100分の60です。
なお、療養開始後1年6か月経過すると、給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。
②の問題のかっこ書き(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の部分は最高限度額が適用されたときのルールで、③の問題は「療養開始後1年6か月未満」なので最高限度額は適用されていないという前提です。
年齢別の最高限度額が適用されている場合のルールは第14条に規定されていますが、過去にそこが論点になったことがないので、今回は触れないでおきます。
(参考:労災保険法第14条)
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(以下「部分算定日」という。)又は複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(「最高限度額」を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、適用がないものとした場合における給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
社労士受験のあれこれ
労災~休業補償給付
R3-214
R3.3.25 休業補償給付 全部労働不能の場合
今日は労災保険法です。
テーマは「休業補償給付」です。
今日は「全部労働不能」の場合の休業補償給付です。
では、どうぞ!
<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】 〇
休業補償給付は、『労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給する』と規定されています。
この問題のポイントは、「賃金を受けない日」の定義です。
通達では、全部労働不能であって「平均賃金の60%未満の金額しか受けない日」を賃金を受けない日と定義づけています。(例えば、事業主から平均賃金の50%の金額を受けた場合は、「賃金を受けない日」に該当するため、休業補償給付は全額支給される。)
問題文のように、休業中に、事業主が「平均賃金の6割以上」を支払っている場合は、賃金を受けない日に該当しないので、休業補償給付は支給されません。
(労災保険法第14条、昭40.7.31基発第901号)
もう一問どうぞ!
<H16年出題>
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。

【解答】 〇
上の問題と同じです。平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、「賃金を受けない日」に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は支給されません。
穴埋め式で条文を確認しましょう
第14条
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために< A >日の第< B >日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の< C >に相当する額とする。

【解答】
A 賃金を受けない
B 4
C 100分の60
★明日は、一部のみ労働する日についてです。
社労士受験のあれこれ
労災保険法第1条(目的)~令和2年9月1日改正
R3-184
R3.2.23 第1条チェック~労災保険法編(改正)
各法律の第1条をチェックしています。
各法律の第1条を読むと、その法律の目的(目指すところ)や理念が見えてきます。
今日は労災保険法です。
労災保険法の第1条は、令和2年9月1日に改正されています。
条文をチェックしましょう!
<第1条>
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の2以上の事業の< A >を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の< A >を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

【解答】
A 業務
今回の改正で、『複数事業労働者』という用語が加わりました。
『複数事業労働者』とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者のことです。労働災害が起こった時に、複数の会社と労働契約関係にあった労働者などが該当します。
複数事業労働者についてのポイントは以下の通りです。
①給付基礎日額 → 全ての会社の賃金を合算した額をもとに算定する
②脳・心臓疾患、精神障害 → 全ての会社での負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価する
<労災保険法の体系>
労災保険法のメインは「保険給付」で、それに付帯する事業として「社会復帰促進等事業」があります。
「保険給付」の種類は、改正前は「業務災害に関する保険給付」「通勤災害に関する保険給付」「二次健康診断等給付」の3つでしたが、このたびの改正で、「複数業務要因災害に関する保険給付」が入り4種類になりました。
では、こちらの条文もどうぞ
第7条
労働者災害補償保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2 < B >(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「< C >」という。)に関する保険給付(前号(業務災害)に掲げるものを除く。)
3 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
4 二次健康診断等給付

【解答】
B 複数事業労働者
C 複数業務要因災害
<労働者災害補償保険法の成り立ち>
労災保険法は、労働基準法とともに昭和22年に施行されました。
労働基準法では、労働者の業務災害に対して、使用者に災害補償の義務を課しています。ただ、使用者だけで災害補償を完全に履行するのはハードルが高いのが現実です。
そこで、業務災害にあった労働者を保護し、使用者の負担を軽減するために、相互扶助の精神によってできたのが労災保険法です。保険料は全額使用者が負担し、保険給付は直接労働者に支払う形式です。労災保険は、使用者が行うべき災害補償を代行する役目をもつ保険です。
その後、昭和48年の法改正で、「通勤災害」が保険給付の対象に加わりました。
「二次健康診断等給付」が施行されたのは、平成13年です。
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労災)通勤の定義
R3-177
R3.2.16 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
今日は労災保険法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
通勤災害における通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、< A >な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされるが、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動も、厚生労働省令で定める要件に該当するものに限り、通勤に当たるとされている。
厚生労働省令で定める要件の中には、< B >に伴い、当該< B >の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により、当該< B >の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものによる移動が挙げられている。
イ 配偶者が、< C >にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を< D >すること。
ロ 配偶者が、学校等に在学し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園に通い、又は公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けている同居の子(< E >歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る。)を養育すること。
ハ 配偶者が、引き続き就業すること。
ニ 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
ホ その他配偶者が労働者と同居できないと認められるイからニまでに類する事情

【解答】
A 合理的
B 転任
C 要介護状態
D 介護
E 18
★ 通勤には次の3つの移動があります。
①住居と就業の場所との間の往復
(通常の家と職場の往復)
②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
(終業後に副業先に向かうための移動など)
③住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
(単身赴任者の赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動)
令和2年の選択式は、③に該当するための要件からの出題です。
やむを得ない事情により ⅰ「配偶者と別居した」、ⅱ「配偶者がない労働者が子と別居した」、Ⅲ「配偶者も子もない労働者が同居介護していた要介護状態にある父母又は親族と別居することになった」場合等が対象です。
令和2年度は、「配偶者」と別居することになったやむを得ない事情(介護、子の養育、配偶者の就業など)からの出題です。
(労災保険法第7条、施行規則第7条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H29年出題>
労働者が転任する際に配偶者が引き続き就業するため別居することになった場合の、配偶者が住む居宅は、「住居」と認められることはない。
②<H25年出題>
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

【解答】
①<H29年出題> ×
「住居」と認められます。配偶者と別居することになったやむを得ない事情の中に、「配偶者が、引き続き就業すること」という要件があります。
(労災保険法施行規則第7条)
②<H25年出題> ×
「反復・継続性」とは、おおむね毎月1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められます。
なお、「家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋は、当該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えない」の部分は〇です。
(H18.3.31基発第 0331042号、基労管発第0331001号、基労補発第0331003号)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(労災保険法)労災保険の罰則規定
R3-171
R3.2.10 労災保険~事業主等に関する罰則
今日は労災保険です!
令和2年度の問題をどうぞ!
①問4-ア
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
②問4-イ
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられたにもかかわらず、提出をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
③問4-ウ
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な文書の提出を命じられた際に、虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
④問4-エ
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り質問をさせたにもかかわらず、事業主が当該職員の質問に虚偽の陳述をした場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
⑤問4-オ
行政庁が労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に身分を示す証明書を提示しつつ事業場に立ち入り帳簿書類の検査をさせようとしたにもかかわらず、事業主が検査を拒んだ場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

【解答】
①問4-ア 〇 報告をしなかった場合
②問4-イ 〇 文書の提出をしなかった場合
③問4-ウ 〇 虚偽の記載をした文書を提出した場合
④問4-エ 〇 虚偽の陳述をした場合
⑤問4-オ 〇 検査を拒んだ場合
<労災保険法の罰則規定>
・事業主等に関する罰則(事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者、労働保険事務組合又は特別加入に係る団体)
→ 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・事業主等以外の者に関する罰則(労働者や保険給付を受ける者などが対象)
→ 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金
令和2年度の問題は、事業主に対する罰則です。
事業主に対する罰則を確認しましょう。次の2つです。
① 第46条の規定による行政庁の報告命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は行政庁の文書提出命令に対し、文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合
② 第48条第1項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
①、②に該当した場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
(労災保険法第51条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H30年出題その1>
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣先の事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
②<H30年出題その2>
行政庁は、労災保険法の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができ、立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

【解答】
①<H30年出題その1> 〇
第46条の「使用者に対する報告、出頭命令」の規定です。
対象になるのは、労働者を使用する者、労働保険事務組合、特別加入に係る団体、派遣先の事業主、船員派遣の役務の提供を受ける者です。
(労災保険法第46条)
②<H30年出題その2> 〇
第48条の「立ち入り検査」の規定です。
対象は、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは特別加入に係る団体の事務所、派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場です。
(労災保険法第48条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
労災「第三者行為災害の調整」
R3-095
R2.11.26 第三者行為災害・保険給付と特別支給金の違い
令和2年の問題をどうぞ!
<問7-C>
第三者の不法行為によって業務上負傷し、その第三者から同一の事由について損害賠償を受けていても、特別支給金は支給申請に基づき支給され、調整されることはない。

【解答】 〇
第三者の損害賠償と労災保険の保険給付が二重にならないよう、損害賠償と保険給付の間で調整が行われます。
しかし、特別支給金の場合は、損害賠償との調整は行われず、損害賠償を受けていても特別支給金は支給されます。
特別支給金は社会復帰促進等事業として行われているからです。
特別支給金と保険給付とで違う点は意識していてくださいね。
では、もう一問どうぞ!
<R2年出題>
労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。

【解答】〇
同一の事由で、労災保険法の保険給付と、社会保険(国民年金・厚生年金保険)の年金給付が支給される場合、労災保険の支給額が減額されることになっています。両方100%支給されると保障が過分になるからです。
ただし、減額されるのは保険給付で、特別支給金は減額されずに100%支給されます。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(労災)
R3-085
R2.11.16 <R2出題>覚える「労災・給付制限」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
 <問1-B>
<問1-B>
業務遂行中の負傷であれば、負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合であっても、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。
 <問1-C>
<問1-C>
業務遂行中の負傷であれば、労働者が過失により自らの負傷を生じさせた場合、それが重大な過失でない限り、政府は保険給付の全部又は一部を行わないとすることはできない。

【解答】
 <問1-B> ×
<問1-B> ×
負傷の原因となった事故が、負傷した労働者の故意の犯罪行為によって生じた場合、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
「行わないとすることはできない」が誤りです。
 <問1-C> 〇
<問1-C> 〇
保険給付の全部又は一部を行わないことができるのは、単なる過失ではなく「重大な過失」による場合です。
では、選択練習問題をどうぞ!
① 労働者が、< A >に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは< C >により、又は正当な理由がなくて< D >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
A 故意
B 直接の原因
C 重大な過失
D 療養に関する指示
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(労災)
R3-074
R2.11.5 <R2出題>問題の意図「解雇制限と労災保険の関係」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問6-B>
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第19条第1項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。

【解答】 ×
「3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り」の「限り」の部分が×です。
「労働基準法第81条の規定による打切補償を支払った」ものとみなされる日が2つあることを知ってくださいというのがこの問題の意図です。
★「打切補償を支払った」ものとみなされ、解雇制限が解除される日は次の2つのどちらかです。
①開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合はその日
又は
②療養開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合は傷病補償年金を受けることとなった日
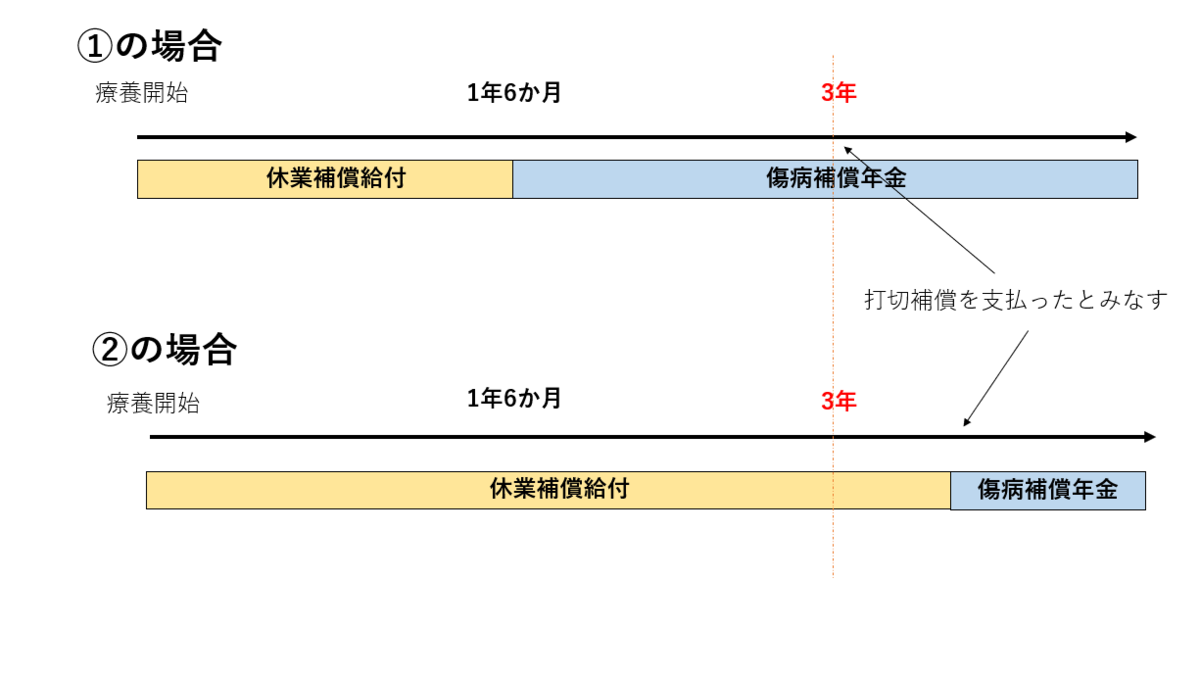
まず、労働基準法では「業務上の負傷又は疾病で療養のため休業する期間」は解雇できないことになっているので、治ゆする前に解雇はできません。
ただし、「療養の開始後3年を経過していること」、「打切補償を支払うこと」によって、解雇制限が解除される例外があります。
労災保険法では、①療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている、又は②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合は打切補償を支払ったとみなし、解雇できることになっています。
単に傷病補償年金を受けているだけではなく、療養開始後3年経過していることがポイントです。
ちなみに、休業補償給付から傷病補償年金の切り替えは、一番早くて療養の開始後1年6か月を経過した日ですが、1年6か月経過した日後に切り替わることもあり得るので注意してください。
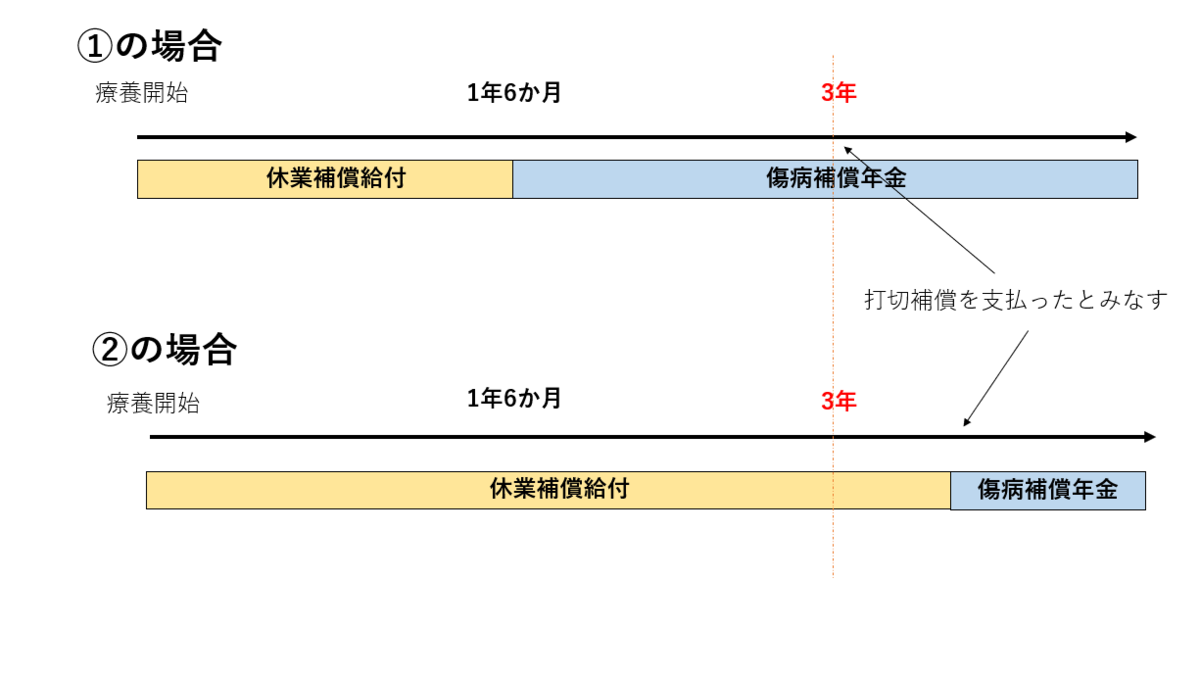
まず、労働基準法では「業務上の負傷又は疾病で療養のため休業する期間」は解雇できないことになっているので、治ゆする前に解雇はできません。
ただし、「療養の開始後3年を経過していること」、「打切補償を支払うこと」によって、解雇制限が解除される例外があります。
労災保険法では、①療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている、又は②療養開始後3年を経過した日後に傷病補償年金を受けることとなった場合は打切補償を支払ったとみなし、解雇できることになっています。
単に傷病補償年金を受けているだけではなく、療養開始後3年経過していることがポイントです。
ちなみに、休業補償給付から傷病補償年金の切り替えは、一番早くて療養の開始後1年6か月を経過した日ですが、1年6か月経過した日後に切り替わることもあり得るので注意してください。
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(労災)
R3-065
R2.10.27 R2出題・【選択練習】特別支給金~算定基礎年額
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄<A>、<B>、<C>を埋めてください。
労災保険特別支給金支給規則第6条第1項に定める特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前< A >間(雇入後< A >に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の< B >期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額とするのが原則であるが、いわゆるスライド率(労災保険法第8条の3第1項第2号の厚生労働大臣が定める率)が適用される場合でも、算定基礎年額が< C >円を超えることはない。
(参考:問7A)

【解答】
A 1年
B 3か月を超える
C 150万
 特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類がありますが、「算定基礎年額」は、ボーナス特別支給金の計算の基になるものです。
特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類がありますが、「算定基礎年額」は、ボーナス特別支給金の計算の基になるものです。
算定基礎年額とは、簡単に言うと、年間のボーナスの総額ですが、あまり高くならないように上限が設定されています。
<手順>
まず、(ア)と(イ)を比較して算定基礎年額を出します。
(ア)負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者、雇入後の期間)の特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。)の総額
(イ)給付基礎日額×365×20%
(ア)と(イ)のどちらか低い方となります。
ただし、(ア)と(イ)が150万円を超える場合は、算定基礎年額は150万円となります。
関連問題をどうぞ!
<H28出題>
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】 〇
なぜ、休業特別支給金の支給申請の際に、「特別給与の総額」を記載するのか?
解説はこちらの記事をどうぞ
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(労災)
R3-055
R2.10.17 R2出題・不正受給者からの費用徴収
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
 R2年問2Cより
R2年問2Cより
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
 R2年問2Dより
R2年問2Dより
偽りその他不正の手段により労災保険に係る保険給付を受けた者があり、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯してその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部である徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

【解答】
 R2年問2Cより 〇
R2年問2Cより 〇
なお、「保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部」とは、受けた保険給付のうち不正受給した部分をさしています。不正受給した部分は全部回収されます。
例えば、保険給付をまるごと全部不正受給した場合は全部回収されます。また、保険給付の一部を不正受給した場合は、不正受給した部分は全部回収されます。回収されるのは、「不正受給した金額の全部又は一部」ではありません。
 R2年問2Dより 〇
R2年問2Dより 〇
不正受給に事業主が加担している場合は、事業主にも責任を負わせる趣旨です。
では、選択練習問題もどうぞ!
① < A >により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
② ①の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と < B >して①の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

【解答】
A 偽りその他不正の手段
B 連帯
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(労災)
R3-045
R2.10.7 R2出題・難問解決策「傷病特別支給金・傷病特別年金の申請」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2・問7より>
特別支給金の支給の申請は、原則として、関連する保険給付の支給の請求と同時に行うこととなるが、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、当分の間、休業特別支給金の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱う。

【解答】 〇

保険給付の傷病(補償)年金は、職権で支給決定されるので、請求は不要です。

特別支給金(傷病特別支給金、傷病特別年金)は、「申請」が必要です。
この「申請」が今回の問題のテーマです。
まず、この問題の解説に入る前に、「休業特別支給金」のことについて少しだけ
「休業(補償)給付」には特別支給金として「休業特別支給金」が上乗せされます。
また、休業(補償)給付には、ボーナス特別支給金はありません。
しかし、休業特別支給金の申請の際は、届書に「特別給与(ボーナス)の総額」を記載することになっています。
なぜなら、最初の休業特別支給金の申請時に特別給与の総額を届出しておけば、後で、障害特別年金、障害特別一時金、傷病特別年金、遺族特別年金、遺族特別一時金の申請を行う場合に、特別給与の総額を記載する必要がなくなるからです。
そこでこの問題に戻ると
・原則 特別支給金の支給の申請は、関連する保険給付の支給の請求と同時に行う
・傷病特別支給金、傷病特別年金の申請については、
→ 傷病補償年金又は傷病年金の支給の決定を受けた者は、所定の申請を行ったものとして取り扱う。(休業特別支給金の申請の際に特別給与の総額についての届出を行っていない者を除く)
同じ論点の問題をどうぞ!
①H24年出題
休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付又は休業給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付又は休業給付の請求と同時に行わなければならない。
②H28年出題
休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
③H28年出題
傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

【解答】
①H24年出題 〇
休業特別支給金の支給の申請は、休業(補償)給付の請求と同時に行う。
※ 休業特別支給金の申請書と休業(補償)給付の支給請求書は、一本の様式になっている。
②H28年出題 〇
③H28年出題 〇
社労士受験のあれこれ
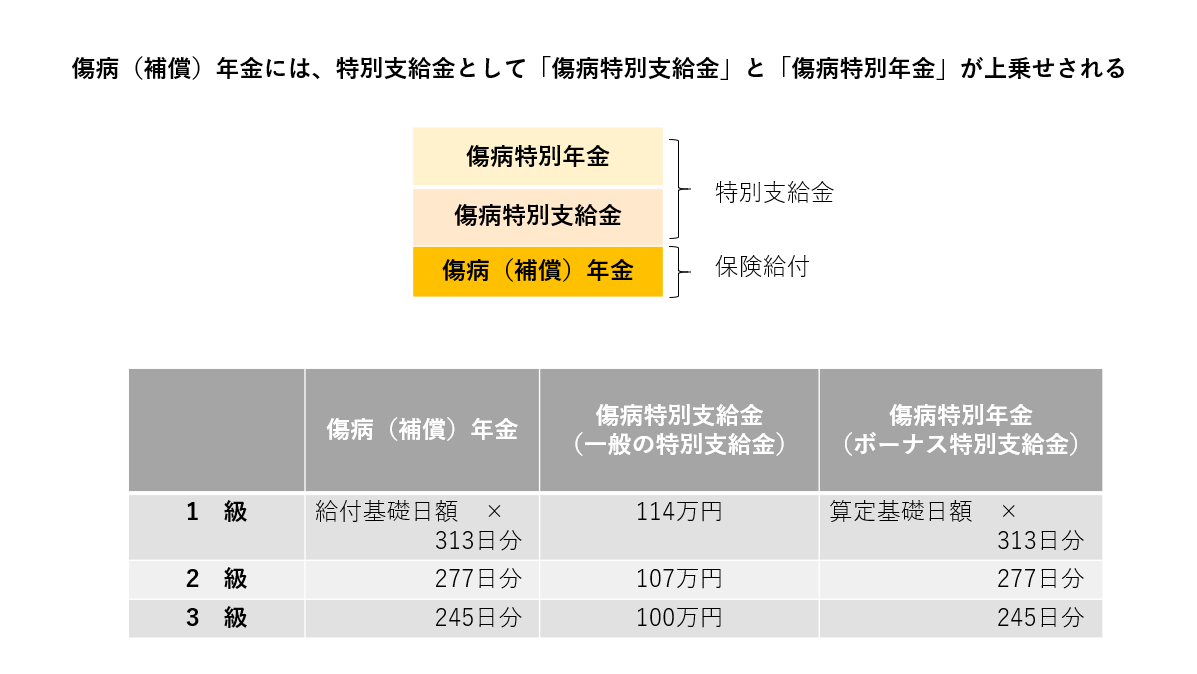
R2年問題から~労災保険法
R3-035
R2.9.27 R2出題・介護補償給付の最低保障額
労災保険の「介護(補償)給付」は、
親族又はこれに準ずる者の介護を
・受けていない
・受けている
の2つに分けることができます。
 今日のポイントは、
今日のポイントは、
「親族又はこれに準ずる者の介護を受けている」場合は、
「最低保障額」が適用されることです。
介護補償給付の問題
<R2年問6E>
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

【解答】 ×
「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。」が誤りです。
親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は、介護費用の支出がなくても、最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給されます。
(注)翌月からです。(後述)
【最低保障額が適用されるパターン】
★ 親族又はこれに準ずる者(友人・知人)の介護を受けている(これが大前提)
かつ
①介護の費用を支出していない
→ 最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給される
②介護の費用を支出していて、その額が最低保障額を下回っている
→ 最低保障額(常時介護72,990円、随時介護36,500円)が支給される
③介護の費用を支出していて、その額が最低保障額を上回る
→ 実費が支給される(ただし、上限(常時166,950円、随時83,480円)あり
 最低保障額は「親族又はこれに準ずる者介護を受けている」ことが大前提です。親族等の介護の負担を補うためだと考えてください。
最低保障額は「親族又はこれに準ずる者介護を受けている」ことが大前提です。親族等の介護の負担を補うためだと考えてください。
ですので、問題文の「介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合」(=すべて親族等で介護したので費用がかかっていない場合)でも、親族等の負担を鑑み、最低保障額が支給されます。
では、こちらの問題もどうぞ!
<H25出題>
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支給された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】 〇
介護補償給付は、「月単位」で支給されます。
問題文の「支給すべき事由が生じた月」がポイントです。支給すべき事由が生じた月は、最低保障額は適用されません。
★支給すべき事由が生じた月は、親族等による介護を受けていても
①介護の費用を支出していない場合 → 介護補償給付は支給されない
②介護の費用を支出していてその額が最低保障額を下回っている場合 → 実費のみ
この問題文は②に該当するので、「当該介護に要する費用として支出された額(実費)」のみが支給されます。
シリーズ・歴史は繰り返す(労災法)
R3-025
R2.9.17 過去の論点は繰り返す(R2・労災「加重障害」)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
障害/加重
問題<H30年出題>
既に業務災害による障害補償年金を受ける者が、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度を加重した場合には、現在の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額から、既存の障害の該当する障害等級に応ずる障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給され、その差額の年金とともに、既存の障害に係る従前の障害補償年金も継続して支給される。

【解答】 〇
例えば、既に7級の身体障害があり、新たな業務災害により同一の部位について身体障害の程度が4級に加重した場合は、
↓
新しい障害等級(4級)の障害補償生年金の額から、もともとの障害等級(7級)の障害補償年金の額を差し引いた額の障害補償年金が支給されることになります。
簡単に言うと、4級と7級の差額の障害補償年金が支給される、ということです。
↓
なお、既存の障害は、業務上、業務外を問いません。
問題文のように、既存の障害が業務上だった場合は、既存の障害補償年金(7級)は継続して支給されます。
差額の年金と既存の年金の2本立で支給されます。
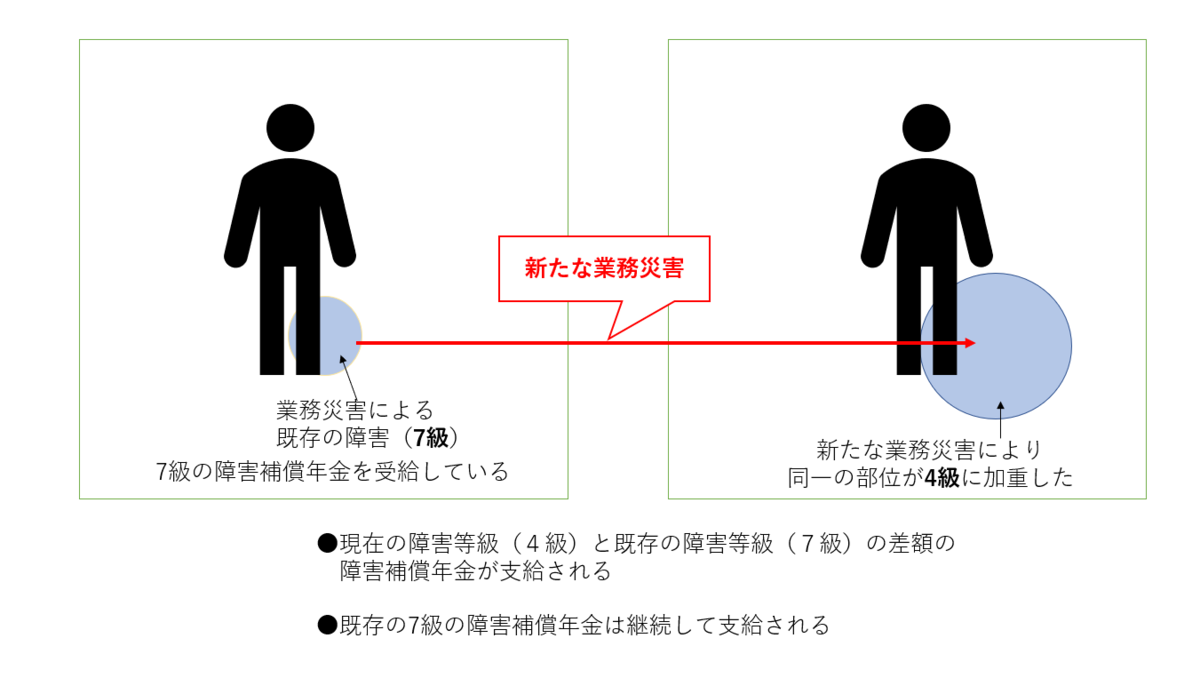
では、令和2年度の問題をどうぞ!
<R2年問5より>
障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第12級の9、障害補償給付の額は給付基礎日額の156日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第11条の6(障害補償給付の額は給付基礎日額の223日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 給付基礎日額の67日分
B 給付基礎日額の156日分
C 給付基礎日額の189日分
D 給付基礎日額の223日分
E 給付基礎日額の379日分

【解答】 A 給付基礎日額の67日分
先ほどの過去問と同じ考え方です。
新しい等級(11級)と既存の等級(12級)の差額が支給されます。
223日分 - 156日分 = 67日分です。
12級も11級も「一時金」ですので、67日分の一時金が支給されます。
 では、既存の等級が「一時金」、現在の等級が「年金」の場合は?
では、既存の等級が「一時金」、現在の等級が「年金」の場合は?
<H21年出題>
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償一時金を支給されていた者が新たな業務災害により同一の部位について障害の程度が加重され、それに応ずる障害補償年金を支給される場合には、その額は、原則として、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額による。

【解答】 〇
加重前の等級は「一時金」、加重後の等級が「年金」に該当するパターンです。
この場合も、「差額」となりますが、「差額」の出し方がポイントです。
例えば、加重前の等級が10級、加重後の等級が5級の場合、差額は、5級の年金額から10級の一時金の額の25分の1を差し引いて算出します。
 ポイントは、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1であること。
ポイントは、既存の障害に係る障害補償一時金の額の25分の1であること。
一時金は、25年分の年金をまとめて1回で支払った額とされていますので、一時金を25で割ることによって1年分の額が計算できるのです。
問題文の場合、新たな等級の障害補償年金から既存の等級の障害補償一時金の額の25分の1を差し引いた額が支給されます。
「加重障害」の問題はパターンが3つ
| 加重前 | 加重後 | 過去問 |
| 年金(7級以上) | 年金(7級以上) | H30年 |
| 一時金(8級以下) | 年金(7級以上) | H21年 |
| 一時金(8級以下) | 一時金(8級以下) | R2年 |
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(労災保険法)
R3-015
R2.9.7 第52回試験・択一労災の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 労災 択一式
問3の特別加入することができる「厚生労働省令で定める種類の作業」は、少々難しい。問4の罰則規定も完璧には覚えられない部分です。
それ以外は、だいたい大丈夫だと思います。と言いましても、丸暗記で解ける問題ではなく、覚えていたことを頭の中で論理的に組み立てながら問題を解く感じになったと思います。
問1は支給制限の問題ですが、「故意の犯罪行為」の場合、「全部又は一部を行わないことができる。」です。が、問題文は「全部又は一部を行わないとすることはできない」となっているので、文章をひっくり返して読まないといけない。「えーと」と考えるのに少し時間がかかってしまいました。
問4は、「D」が正解ですが、同一の災害で身体障害が2以上ある場合に、重いほうの障害等級となる。それは「一方の障害が第14級」に該当するときという部分がポイントです。
13級以上の障害が2以上ある場合は、重いほうを1級~3級繰り上げることになるので。
問7は、「休業特別支給金」の申請は「5年」じゃなくて2年というポイントをおさえていれば、自動的に「D」が選べたと思います。
全体的に きちんと勉強した方にとっては、解きやすい良い問題だったと思います
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(労災保険)
R3-006
R2.8.29 第52回試験・選択(労災保険)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 労災 選択式
「通勤」の定義からの出題です。
通勤の定義については定番問題ですが、単身赴任者の「住居間の移動」の要件の細かい部分からの出題は珍しいです。
住居間の移動の要件は、労働者災害補償保険法施行規則第7条に規定されています。
「なんとなく見たことがある」と思った方も多いのでは?
前後の文章の流れで空欄を埋めていくタイプの問題でした。
社労士受験のあれこれ
目的条文check 1 労働編
1 労働編
R2-260
R2.8.17 労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック
目的条文は要チェック!
本日は、「労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「労働基準法」
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、< D >において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< E >各々その義務を履行しなければならない。

【解答】
A 人たるに値する生活
B 基準
C 向上
D 対等の立場
E 誠実に
問2 「労働安全衛生法」
(目的)
第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< A >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。

【解答】
A 自主的活動
B 安全と健康
C 快適な職場環境
問3 「労災保険法」
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< A >に寄与することを目的とする。
第2条 労働者災害補償保険は、< B >が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、 < C >を行うことができる。
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び< D >(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

【解答】
A 福祉の増進
B 政府
C 社会復帰促進等事業
D 官公署の事業
問4 「雇用保険法」
 R2年4月1日改正 要チェックです!
R2年4月1日改正 要チェックです!
(目的)
第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。
(管掌)
第2条 雇用保険は、< C >が管掌する。
2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、< D >が行うこととすることができる。
(雇用保険事業)
第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< E >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

【解答】
A 子を養育するための休業
B 福祉の増進
C 政府
D 都道府県知事
E 育児休業給付
社労士受験のあれこれ
横断編(不服申立て)
R2-259
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「審査請求を棄却したものとみなすことができる」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
A 3か月
問2 「雇用保険法」
① 資格取得・喪失の確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して < B >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
B 3か月
問3 「健康保険法」
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
審査請求をした日から< C >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
C 2月
D 社会保険審査会
問4 「国民年金法」
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は< E >その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
審査請求をした日から< F >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
E 保険料
F 2月
問5 「厚生年金保険法」
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
② ①の審査請求をした日から< G >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< H >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
G 2月
H 社会保険審査会
| 棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
では、こちらをどうぞ!
①<国民年金 H30年出題>
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
②<厚生年金保険法 H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】
①<国民年金 H30年出題> 〇
「2か月」がポイントです!
②<厚生年金保険法 H29年出題> ×
・第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行います。
・脱退一時金については、「社会保険審査会」で〇です。
(国民年金も「脱退一時金」は、「社会保険審査会」に対して審査請求ができます。
社労士受験のあれこれ
横断編(公課の禁止)
R2-258
R2.8.15 横断編/課税されるもの、されないもの
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「課税されるもの、されないもの」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
<H24年出題>
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

【解答】 〇
労災保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」と規定されています。
※ 労災保険の保険給付には、「現金給付」と「現金給付」があるので「金品」
問2 「雇用保険法」
<H28年出題>
租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

【解答】 ×
雇用保険法では「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とされています。
常用就職支度手当は失業等給付の中に入っていますので、課税できません。
※雇用保険法には現物給付がないので「金銭」となっています。
なお、雇用保険二事業の助成金等は失業等給付ではありませんので、公課を課することができます。
問3 「健康保険法」
<H18年出題>
出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

【解答】 〇
健康保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされています。
保険給付(もちろん出産手当金出産育児一時金も含まれます。)は、課税されません。
問4 「国民年金法」
<H25年出題>
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

【解答】 〇
国民年金法のルールは、以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、公課を課することができる。
問5 「厚生年金保険法」
障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。

【解答】 〇
厚生年金保険法のルールは以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、公課を課することができる。
※ 「老齢厚生年金」は課税されますが、障害厚生年金は課税されません。
社労士受験のあれこれ
横断編(療養に関する指示に従わないとき)
R2-257
R2.8.14 横断編/療養に関する指示に従わないときの制限
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「療養に関する指示に従わないときの制限」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が故意の犯罪行為若しくは< A >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの< B >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の< C >。

【解答】
A 重大な過失
B 原因
C 全部又は一部を行わないことができる
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< D >。

【解答】
D 一部を行わないことができる
 「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその< F >となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< G >。
自己の故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその< F >となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

【解答】
E 重大な過失
F 原因
G 全部又は一部を行わないことができる
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは< H >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの< I >となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の< J >。
障害厚生年金の受給権者が、< K >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
H 重大な過失
I 原因
J 全部又は一部を行わないことができる
K 故意
こちらもどうぞ!
 問1労災保険法
問1労災保険法
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
 問2 健康保険法
問2 健康保険法
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
 問3 国民年金法(R元年出題)
問3 国民年金法(R元年出題)
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題)
問4 厚生年金保険法(R元年出題)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
 問1労災保険法 ×
問1労災保険法 ×
キーワードは、「故意に」「直接の原因」。
全部又は一部を行わないことができるではなく、「保険給付を行わない」です。
 問2 健康保険法 ×
問2 健康保険法 ×
キーワードは、「闘争、泥酔又は著しい不行跡」。
行わないではなく、「全部又は一部を行わないことができる」です。
 問3 国民年金法(R元年出題) 〇
問3 国民年金法(R元年出題) 〇
キーワードは、「故意に」。
故意に死亡させた者には支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
故意に障害 → 障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
重大な過失 → 保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士受験のあれこれ
横断編(支給制限~全部制限)
R2-256
R2.8.13 横断編/支給制限「行わない」のはどんなとき?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「支給制限「行わない」のはどんなとき?」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】
A 故意に
B 直接の原因
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< C >により、又は< D >給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

【解答】
C 自己の故意の犯罪行為
D 故意に
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
< E >障害又はその< F >となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < E >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によっ遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を< E >死亡させた者についても、同様とする。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< E >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
E 故意に
F 直接の原因
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< G >、障害又はその< H >となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< G >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< G >死亡させた者についても、同様とする。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< G >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
G 故意に
H 直接の原因
社労士受験のあれこれ
横断編(受給権の保護)
R2-255
R2.8.12 横断編/受給権の保護
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「受給権の保護」です。
では、どうぞ!
「労災保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外あり)
年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・国年、厚年も同様)
「雇用保険法」
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外なし)
「健康保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外なし)
「国民年金法」
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、厚年も同様)
・ 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢基礎年金、付加年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
「厚生年金保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、国年も同様)
・ 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢厚生年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
 では、問題をどうぞ!
では、問題をどうぞ!
 労災保険法<H24年出題>
労災保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
 雇用保険法<H23年出題>
雇用保険法<H23年出題>
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
 健康保険法<H24年出題>
健康保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。
 国民年金法<H28年出題>
国民年金法<H28年出題>
給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H26年出題>
厚生年金保険法<H26年出題>
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、< A >に行わせるものとされている。

【解答】
 労災保険法<H24年出題> 〇
労災保険法<H24年出題> 〇
 雇用保険法<H23年出題> 〇
雇用保険法<H23年出題> 〇
 健康保険法<H24年出題> ×
健康保険法<H24年出題> ×
保険給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押さえ、すべてできません。
 国民年金法<H28年出題> 〇
国民年金法<H28年出題> 〇
脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
※厚生年金保険でも、脱退一時金は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
 厚生年金保険法<H26年出題> ×
厚生年金保険法<H26年出題> ×
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押えの対象にはなりません。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
A 独立行政法人福祉医療機構
社労士受験のあれこれ
横断編(未支給の保険給付・給付)
R2-249
R2.8.6 横断編/未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?」です。
では、どうぞ!
問 題
 雇用保険<H29年出題>
雇用保険<H29年出題>
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。

【解答】
 〇
〇
ポイント!
★未支給の失業等給付を受けることができる範囲と順序を覚えましょう。
・死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」(順序もこのとおり)
★「失業」の認定を受けなければならない
受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当の支給を請求する者 → 当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
★請求期間がある
未支給給付請求者は、死亡した受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、請求しなければならない。
次は労災、どうぞ!
 労災保険<H22年出題>
労災保険<H22年出題>
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

【解答】
 C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
ポイント!
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順序を覚えましょう。
労災保険からもう一問!
 労災保険法<H30年出題>
労災保険法<H30年出題>
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
未支給の遺族(補償)年金の支給を請求できるのは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」です。
では、国民年金法です!
 国民年金法<R元年出題>
国民年金法<R元年出題>
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。

【解答】 〇
ポイント!
国民年金の未支給年金を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
最後は厚生年金保険です!
 厚生年金保険<H30年出題>
厚生年金保険<H30年出題>
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
厚生年金保険の未支給の保険給付を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
→ 国民年金と同じです。
なお、国民年金の未支給の対象は「年金給付」、厚生年金保険は「保険給付」です。
社労士受験のあれこれ
横断編(障害等級・労災、国年、厚年)
R2-248
R2.8.5 横断編/それぞれの障害等級~労災、国年、厚年
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「障害等級・労災、国年、厚年」です。
では、どうぞ!
問 題
 傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
 ×
×
「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。
ポイント!
ちなみに、傷病補償年金の支給要件として、「当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」があります。
厚生労働省令で定める傷病等級は「第1級~第3級」です。
第1級 → 常時介護を要する状態
第2級 → 随時介護を要する状態
第3級 → 常態として労働不能
★ 傷病等級は、「治っていない傷病」です。
次どうぞ!
 障害(補償)給付
障害(補償)給付
空欄に埋めてください。
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は < A >とする。

【解答】
 A 障害補償一時金
A 障害補償一時金
ポイント!
障害等級第1級~第7級 → 障害補償年金
障害等級第8級~第14級 → 障害補償一時金
★ 障害等級は、「負傷し又は疾病にかかり治った」ときです。
 傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
第1級 → 給付基礎日額の313日分
第2級 → 給付基礎日額の277日分
第3級 → 給付基礎日額の245日分
 障害基礎年金(国民年金法)
障害基礎年金(国民年金法)
空欄を埋めてください。
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の①、②のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して< B >を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、< C >であること。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから< D >とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
B 1年6月
C 60歳以上65歳未満
D 1級及び2級
ポイント!
障害基礎年金の障害等級は、重いほうから1級、2級
1級の年金額は、2級の年金額×100分の125
 障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金・障害手当金
(障害手当金の受給権者)
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して< E >を経過する日までの間におけるその< F >日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

【解答】
E 5年
F 傷病の治った(障害手当金は「治っている」ことが要件です。)
ポイント!
厚生年金には、「障害厚生年金」と「障害手当金」があります。
障害厚生年金 → 障害等級1級~3級
障害手当金 → 3級よりも軽い状態
社労士受験のあれこれ
横断編(遺族の範囲その1「労災」)
R2-245
R2.8.2 横断編/「労災」遺族の範囲・要件と順位を覚える
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「遺族の範囲その1「労災」」」です。
◇労災保険
・遺族(補償)年金
・遺族(補償)一時金
・障害(補償)年金差額一時金
◇国民年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
◇厚生年金保険法
・遺族厚生年金
「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。
整理しておきましょう。
今日は、労災編です。
では、どうぞ!
問 題
 遺族(補償)年金<H19年出題>
遺族(補償)年金<H19年出題>
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。

【解答】
 ×
×
①夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(本則では60歳以上)
②子又は孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
③兄弟姉妹 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間又は55歳以上(本則では60歳以上)
遺族(補償)年金を受けることができる遺族のポイント!
・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたこと
・遺族の順位を覚える
| 1 | 配偶者 | 妻 年齢、障害状態問わない 夫 60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 2 | 子 | 18歳年度末までの間 又は 一定の障害状態 |
| 3 | 父母 | 60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 4 | 孫 | 18歳年度末までの間 又は 一定の障害状態 |
| 5 | 祖父母 | 60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 6 | 兄弟姉妹 | 18歳年度末までの間若しくは60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 7 | 夫 | 55歳以上60歳未満 55歳以上60歳未満(障害状態にない)の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位は後回しになる |
| 8 | 父母 | |
| 9 | 祖父母 | |
| 10 | 兄弟姉妹 |
・年金を受けることができる(受給権者になる)のは受給資格者のうちの最先順位者
・例えば、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族として、
父(63歳)
子(3歳)
弟(20歳)
がいる場合(3人とも障害状態にない)
「受給資格者」は、父(63歳)と子(3歳)の2人。受給資格者の中の順位は1位が子、2位が父です。
1位の子(3歳)が「受給権者」となります。
・転給あり。受給権者が失権したら、次の順位の者に受給権が移ります。
次は遺族(補償)一時金です!
 遺族(補償)一時金<H19年出題>
遺族(補償)一時金<H19年出題>
遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族の順位も、この順序による。

【解答】
 ×
×
遺族(補償)一時金の場合、死亡の当時の生計維持要件は問われません。(ただし、生計維持関係の有無は、順位には影響します。)
遺族(補償)一時金を受けることができる遺族のポイント!
・配偶者は生計維持関係があってもなくても第1順位
・兄弟姉妹は、生計維持関係あがってもなくても最下位
・それ以外の遺族は、生計維持「有」が優先
| 1 | ①配偶者 | |
| 2 | 労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた | ②子、③父母、④孫、⑤祖父母 |
| 3 | 生計を維持していなかった | ⑥子、⑦父母、⑧孫、⑨祖父母 |
| 4 | ⑩兄弟姉妹 |
・遺族(補償)年金の受給権失権後に、遺族(補償)一時金の受給権者になることがある
最後は障害(補償)年金差額一時金!
 障害補償年金差額一時金<H26年選択>
障害補償年金差額一時金<H26年選択>
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、< A >の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、< A >である。

【解答】
 A 祖父母及び兄弟姉妹
A 祖父母及び兄弟姉妹
障害(補償)年金差額一時金を受けることができる遺族のポイント!
・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断
| 1 | 労働者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていた | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
| 2 | 生計を同じくしていなかった | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
・生計を同じくしていた方が優先する
社労士受験のあれこれ
横断編(労基・労災・雇用の「船員」)
R2-243
R2.7.31 横断編/労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?」です。
では、どうぞ!
問 題
 <労働基準法>
<労働基準法>
船員法第1条第1項に規定する船員については、労働基準法は、全面的に適用されない。
 <労災保険法>
<労災保険法>
船員法上の船員については、労災保険法が適用される。
 <雇用保険法>
<雇用保険法>
船員法第1条に規定する船員を雇用する(政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては、雇用保険の強制適用事業となる。

【解答】
 <労働基準法> ×
<労働基準法> ×
船員法第1条第1項に規定する船員には、労働基準法が一部適用されます。
労働者全般に当てはまる基本原則の部分(第1条から第11条まで)、それに関する罰則規定は船員にも適用されますが、これ以外は労働基準法は適用されません。
船員の労働形態は特殊ですので、一般労働者向けの労働基準法は一部だけ適用され、他は船員法によって保護されます。
 <労災保険法> 〇
<労災保険法> 〇
船員法上の船員は、労災保険法適用です。
 <雇用保険法> 〇
<雇用保険法> 〇
船員法第1条に規定する船員を雇用する事業は、雇用保険の強制適用事業です。
ただし、
・政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員 → 適用除外
※漁船に乗り組むため雇用される者でも、1年を通じて船員として雇用される場合は適用されます。
こちらもどうぞ!
①<雇用保険法・H22年出題>
船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。
②<雇用保険法・H25年出題>
船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

【解答】
①<雇用保険法・H22年出題> ×
労働者を1人でも雇用すれば、雇用保険は適用です。
ですので、船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、人数関係なく強制適用となります。
②<雇用保険法・H25年出題> 〇
漁船に乗り組むため雇用される者であっても、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-234
R2.7.22 選択式の練習/業務災害に関する保険給付
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「業務災害に関する保険給付」です。
労災保険の保険給付は次の3つです。
①業務災害に関する保険給付
②通勤詐害に関する保険給付
③二次健康診断等給付
今日は、そのうちの「業務災害に関する保険給付」です。
では、どうぞ!
問 題
業務災害に関する保険給付(< A >を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は< B >第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は < C >に対し、その請求に基づいて行う。
【選択肢】
① 療養補償給付 ② 傷病補償年金及び介護補償給付
③ 遺族補償年金 ④ 船員法 ⑤ 地方公務員法 ⑥ 国家公務員法
⑦ 事業主 ⑧ 介護を行う者 ⑨ 葬祭を行う者

【解答】
A ② 傷病補償年金及び介護補償給付
B ④ 船員法
C ⑨ 葬祭を行う者
 業務災害に関する給付は、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金」「介護補償給付」の7種類です。
業務災害に関する給付は、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金」「介護補償給付」の7種類です。
「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」の5つは、労働基準法の災害補償に基づく給付ですが、「傷病補償年金」「介護補償給付」は、労働基準法の災害補償としては規定されていない、労災保険独自の給付です。
 「船員法」上の船員についても労災保険法が適用されます。
「船員法」上の船員についても労災保険法が適用されます。
 「葬祭料」は、「葬祭を行う者」に支給されます。(「遺族」とは限らないので注意しましょう。)
「葬祭料」は、「葬祭を行う者」に支給されます。(「遺族」とは限らないので注意しましょう。)
こちらもどうぞ!
①<H26年出題>
船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
②<H22年出題>
労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。

【解答】
①<H26年出題> ×
船員法上の船員についても労災保険法は適用されます。
②<H22年出題> ×
傷病補償年金と介護補償給付は、労働基準法の災害補償の規定にはありませんが、労災保険の保険給付として行われます。
また、労働基準法のみならず、船員法の災害補償にも対応しています。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-224
R2.7.12 選択式の練習/事業主からの費用徴収
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「事業主からの費用徴収」です。
労災保険は、その事業が開始された日(労働者を使用した日)に、自動的に、保険関係が成立します。
ただし、徴収法では、事業主は「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に届け出ることが規定されています。
※保険関係成立届を提出しないと、政府が保険料を徴収できないからです。
もし、事業主が保険関係成立届を出していないうちに、労災事故が起こった場合でも労働者に対しては保険給付が行われます。しかし、事業主にはペナルティが課されることがある、それが今日のテーマです。
では、どうぞ!
問 題
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額< A >。
一 事業主が< B >労災保険にかかる保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について認定決定をしたときは、その決定のあった日の前日までの期間)中に生じた事故
二 事業主が概算保険料のうち一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限までの期間は除く。)中に生じた事故
三 事業主が< B >生じさせた業務災害の原因である事故
【選択肢】
① を事業主から徴収しなければならない
② の全部又は一部を事業主から徴収することができる
③ で保険給付をしないことができる
④ 故意又は重大な過失により ⑤ 過失により
⑥ 故意又は過失により

【解答】
A ② の全部又は一部を事業主から徴収することができる
B ④ 故意又は重大な過失により
こちらもどうぞ!
<H19年出題>
事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。

【解答】 ×
「事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害」については、費用徴収の対象ですが、「労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害」については費用徴収の対象にはなっていません。
もう一問どうぞ!
<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

【解答】 〇
「事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合」
・ 労働者に対する保険給付は通常どおりに行われる。(労働者に非はないので)
・ 政府は、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。(保険関係成立届を提出していない事業主には、保険給付にかかった費用の全部又は一部を払ってもらうことでペナルティをかけます。)
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-214
R2.7.2 選択式の練習/通勤・日常生活上必要な行為
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「通勤・日常生活上必要な行為」です。
通勤経路を逸脱・中断した場合の扱いを確認しておきましょう。
労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合
<原則> 逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。
<例外> 逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合
逸脱又は中断の間は通勤としない。しかし、合理的な経路に復した後は通勤となる。
今日のテーマは「日常生活上必要な行為」です。
日常生活上必要な行為は、厚生労働省令で定められています。
ではどうぞ!
問 題
(日常生活上必要な行為)
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
 < A >その他これに準ずる行為
< A >その他これに準ずる行為
 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
 選挙権の行使その他これに準ずる行為
選挙権の行使その他これに準ずる行為
 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
 要介護状態にある配偶者、子、父母、< B >並びに配偶者の父母の介護(< C >行われるものに限る。)
要介護状態にある配偶者、子、父母、< B >並びに配偶者の父母の介護(< C >行われるものに限る。)
【選択肢】
① 食料品の調達 ② 日用品の購入 ③ 子の送迎
④ 孫及び兄弟姉妹 ⑤ 孫及び祖父母 ⑥ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
⑦ 継続的に又は反復して ⑧ 継続的に又は定期的に
⑨ 一定の頻度で定期的に

【解答】
A ② 日用品の購入
B ⑥ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
C ⑦ 継続的に又は反復して
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

【解答】 ×
美容院に立ち寄る行為は、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当します。
美容院で髪のセットをしている間(逸脱又は中断中)は通勤となりませんが、髪のセットが終わって元の経路に復した後は、「通勤」となります。
もう一問どうぞ!
<H23年出題>
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

【解答】 ×
逸日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであったとしても、逸脱又は中断の間は通勤とはなりません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-204
R2.6.22 選択式の練習/休業補償給付の額の出し方
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「休業補償給付の額の出し方」です。
ではどうぞ!
問題
(原則)
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の< A >から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の< B >に相当する額とする。
【選択肢】
① 第3日目 ② 第4日目 ③ 第1日目
④ 100分の60 ⑤ 100分の80 ⑥ 100分の40

【解答】
A ② 第4日目
B ④ 100分の60
では、所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の計算は?
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から< C >を控除して得た額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
【選択肢】
① 当該労働に対して支払われる賃金の額
② 平均賃金の100分の60 ③ 1日あたりの賃金の額

【解答】
C ① 当該労働に対して支払われる賃金の額
 数字で確認してみると
数字で確認してみると
例えば、給付基礎日額が1万円の場合
★丸一日全く労働しなかった(賃金の全部を受けない)日の休業補償給付
10,000円×100分の60 = 6,000円
★所定労働時間の一部のみ労働し、労働した部分の賃金が3,000円の日の休業補償給付
(10,000円-3,000円)×100分の60 = 4,200円
→ 労働できなかった7,000円分の60%を補償するという考え方です。
こちらもどうぞ!
<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】 〇
★全部労働不能で休業中に事業主から支給があった場合の扱い
全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合は、「休業する日に該当しない」ので、労災の休業補償給付は支給されません。
問題文は、「事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている」となっていますので、休業補償給付は支給されないで「〇」です。
ちなみに、全部労働不能で、事業主から、平均賃金の100分の60未満の金額しか支払われていない場合は、「休業する日として」扱われ、労災の休業補償給付が支給されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-194
R2.6.12 選択式の練習/二次健康診断等給付の手続き
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「二次健康診断等給付の手続き」です。
二次健康診断等給付とは、
・ 一次健康診断で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常が あると診断された労働者が対象
・ 労働者の請求に基づいて、二次健康診断等給付(二次健康診断及び特定保健指導)が行われる
・ 労災病院又は都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所で、直接二次健康診断及び特定保健指導を給付。(現物給付です)
ではどうぞ!
問題
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して< A >に提出しなければならない。
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から< B >以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から< B >以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業主は、当該二次健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
医師からの意見聴取は、当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業主に提出された日から< C >以内に行うこととされている。
【選択肢】
① 所轄労働基準監督署長 ② 都道府県知事
③ 所轄都道府県労働局長 ④ 1か月 ⑤ 3か月
⑥ 2か月 ⑦ 1年 ⑧ 2年 ⑨ 3年

【解答】
A ③ 所轄都道府県労働局長
「二次健康診断等給付」の事務は労働基準監督署長ではなく、都道府県労働局長が行います。
B ⑤ 3か月
C ⑥ 2か月
★ 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内
↓
二次健康診断の実施から3か月以内に結果を事業主に提出
↓
結果を証明する書面の提出から2か月以内に事業主は医師からの意見を聴取
ここからは安全衛生法です。安衛法と比較してみましょう!
労働安全衛生法では、健康診断の結果(異常の所見がある労働者に限る。)について、医師等から意見徴収を行うことが義務付けられています。
<健康診断の結果についての医師等からの意見聴取>
・ 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。
・ 深夜業従事者の自発的健康診については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
※ 自発的健康診断の結果を証明する書面は、当該健康診断を受けた日から3か月以内に提出できます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-184
R2.6.2 選択式の練習/業務上の疾病と通勤による疾病を比較
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「業務上の疾病と通勤による疾病を比較」がテーマです。
「業務上の疾病」と「通勤による疾病」、違いは?
ではどうぞ!
問題
業務上の疾病の範囲は、< A >別表第一の二に掲げる疾病とする。
通勤による疾病の範囲は、< B >第18条の5に、「通勤による負傷に起因する疾病その他< C >」と定めらている。
【選択肢】
① 労働基準法施行規則 ② 労働基準法 ③ 労働安全衛生規則
④ 労働者災害補償保険法 ⑤ 労働者災害補償保険法施行令
⑥ 労働者災害補償保険法施行規則
⑦ 業務に起因することの明らかな疾病
⑧ 通勤に起因することの明らかな疾病
⑨ 通勤と因果関係のある疾病

【解答】
A ① 労働基準法施行規則
B ⑥ 労働者災害補償保険法施行規則
C ⑧ 通勤に起因することの明らかな疾病
労災保険法は、もともとは労働基準法の使用者の災害補償義務を代行するためにできた保険なので、「業務上の疾病の範囲」は労働基準法施行規則に規定されています。
一方、「通勤」については、労働基準法上の補償義務はありませんので、疾病の範囲は労働者災害補償保険法施行規則に規定されています。
もう少し比較してみましょう
①<H21年出題>
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。
②<H20年出題>
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。

【解答】
①<H21年出題> 〇
業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二各号(第1号から第11号のどれか)に該当しないと業務上の疾病になりません。別表第1の2は職業病リストのようなものだと思ってください。
②<H20年出題> ×
上記で勉強しましたように、通勤による疾病は、厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)で、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されているだけです。業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定を準用するというルールはありません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-174
R2.5.23 選択式の練習/介護(補償)給付の支給額
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「介護(補償)給付の支給額」です。
ではどうぞ!
問 題
介護補償給付は、< A >を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する< A >の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< B >介護を要する状態にあり、かつ、< B >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< C >に対し、その請求に基づいて行う。
【選択肢】
① 障害補償給付又は傷病補償年金 ② 休業補償給付又は傷病補償年金
③ 障害補償年金又は傷病補償年金 ④ 常時 ⑤ 常態として
⑥ 常時又は随時 ⑦ 介護を行う者 ⑧ 当該労働者
⑨ 事業主

【解答】
A ③ 障害補償年金又は傷病補償年金
B ⑥ 常時又は随時
C ⑧ 当該労働者
こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】 〇
介護補償給付は「介護の費用として支出した額(実費)」が支給されますが、最高限度額と最低保障額が設定されています。
「最低保障額」の注意点をどうぞ
<H25年出題>
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】 〇
この問題のポイントは、「支給すべき事由が生じた月」の部分です。
介護費用を支払って介護を受け始めた月(支給すべき事由が生じた月)は、最低保障額は適用されず、実際に支払った実費が支給されます。
 最低保障額が適用されるポイントは、親族等(親族又は知人、友人)の介護を受けていることです。
最低保障額が適用されるポイントは、親族等(親族又は知人、友人)の介護を受けていることです。
例えば、常時介護の場合
親族等の介護を 受けている | 支出した介護費用がゼロ | 72,990円(最低保障)注意1 |
| 支出した費用が72,990円未満 | 72,990円(最低保障)注意2 | |
| 支出した費用が72,990円超えている | 実際に支出した費用 (ただし、 上限は166,950円) | |
親族等の介護を 受けていない | 実際に支出した費用 (ただし、 上限は166,950円) ※最低保障額の適用なし |
注意1について
→ 介護を受け始めた月は、最低保障が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(最低保障額は翌月から適用されます。)
注意2について
→ 介護を受け始めた月は、最低保障が適用されないので、実際に支出した額となります。(最低保障額は翌月から適用されます。)
 ちなみに、上記の平成25年の問題は、
ちなみに、上記の平成25年の問題は、
・ 親族等による介護を受けている + 実際に支出した額が72,990円未満だった
↓
・ 原則は最低保障額の72,990円が支給されるが、問題の前提が「支給すべき事由が生じた月」となっている
↓
・ 「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額は適用されない
↓
・ 「支給すべき事由が生じた月」なので、最低保障額ではなく「介護に要する費用として支出された額」(実際に払った額)が支給される=支給されるのは72,990円未満の実際に支払った額
という流れです。
「随時」介護の場合は、上限83,480円、最低保障額36,500円です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-164
R2.5.13 選択式の練習/特別加入者の保険給付
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、特別加入者の保険給付です。
労災保険法の対象は、労働基準法上の労働者です。そして属地主義をとっていますので、国内で使用される人が対象です。
しかし、労働者でなくても、中小事業主や一人親方等は特別加入することができますし、海外に派遣されている人も同様です。
特別加入すれば、原則として労働者と同じ補償が受けられます。
しかし、労働者と特別加入者でルールが違うところもいくつかあります。
その「違う」ルールをおさえるのが勉強のポイントです。
ではどうぞ!
問 題
第1種特別加入者(中小事業主等)の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、< A >。
【選択肢】
① その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる
② 当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる
③ その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる

【解答】 A ② 当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる
ポイント
 保険料を滞納しているのも、事故にあったのも中小事業主本人で、「保険給付を行う」→「その後その費用を徴収する」という手続きをとるのは合理的ではありません。
保険料を滞納しているのも、事故にあったのも中小事業主本人で、「保険給付を行う」→「その後その費用を徴収する」という手続きをとるのは合理的ではありません。
ですので、特別加入者の場合は、保険給付の支給制限(全部又は一部を行わないことができる)という方法をとっています。
(一人親方等、海外派遣者も同じ方法です。)
比較しましょう
<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

【解答】 ○
保険関係の成立の届出をしていない、保険料を納付していないのは、事業主の責任で、労働者に非はありません。
ですので、この場合は、労働者に対する保険給付の支給制限を行う方法はとらず、事業主から費用を徴収する方法をとります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-154
R2.5.3 選択式の練習/事業主に対する費用徴収
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、労災法「事業主に対する費用徴収」です。
<参 考> 法第31条
政府は、次の①~③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
① 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出をしていない期間中に生じた事故
② 事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故
③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
今日は、「故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出をしていない」の「故意」又は「重大な過失」の認定についての問題です。
★平成27年の択一式をアレンジしています。
ではどうぞ。
問 題
 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を< A >%とする。
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を< A >%とする。
 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を< B >%とする。
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を< B >%とする。
【選択肢】
①30 ②40 ③50 ④60 ⑤70 ⑥80 ⑦90 ⑧100

【解答】
A⑧100 B ②40
こちらの問題もどうぞ!
<H27年出題>
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】 ○
ポイント!
「保険関係成立届の提出をしていない期間中に生じた事故」について
★ 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けた
→ にもかかわらず10日以内に提出していなかった
→ 「故意」と認定
→ 費用徴収率100%
★ 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない
→ 保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった
→ 「重大な過失」と認定
→ 費用徴収率40%
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-144
R2.4.23 選択式の練習/心理的負荷による精神障害の認定基準について
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、どうぞ。
今日は「心理的負荷による精神障害の認定基準について」からです。
問題
 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を< B >どう受け止めるかという観点から評価されるものであるとされている。
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を< B >どう受け止めるかという観点から評価されるものであるとされている。
 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね< A >の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として< C >に区分することとされている。
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね< A >の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として< C >に区分することとされている。
【選択肢】
①1か月 ②3か月 ③6か月 ④1年
⑤労働者本人が主観的に ⑥同種の労働者が一般的に ⑦医師が医学的に ⑧所轄労働基準監督署長が客観的に
⑨「強」、「弱」の2段階 ⑩「A」、「B」、「C」、「D」の4段階 ⑪「強」、「中」、「弱」の3段階

【解答】
A ③6か月 B ⑥同種の労働者が一般的に
C ⑪「強」、「中」、「弱」の3段階
★Bについて
「強い心理的負荷」とは
精神障害を発病した労働者がその出来事及 び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるもの。
なお、「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似す る者のこと。
 択一式もどうぞ!
択一式もどうぞ!
①<H30年出題>
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
②<H27年出題>
認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシャルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。

【解答】
① × 120時間ではなく「160時間」です。
② × 主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-134
R2.4.13 遺族補償年金の失権後に遺族補償一時金は受けられる?
今日のポイント!
遺族(補償)年金も遺族(補償)一時金も、死亡した労働者と遺族との関係は、「死亡当時」で判断されます。
 (H28年出題)
(H28年出題)
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
【解答】 ×
遺族補償年金の受給権を失権した後、遺族補償一時金の受給権者になることもあり得ます。
例えば、
・夫(労働者)の死亡当時、生計維持関係のあった妻は、遺族補償年金の受給権者となる(他に受給資格者はいない)
↓
・その後、妻は再婚し、遺族補償年金の受給権は消滅した
↓
・支給された遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の額が1000日未満の場合、差額を遺族補償一時金として受けることができる
※ 再婚して年金は失権しているのに、なぜ一時金は受けることができるの?
遺族補償一時金も「死亡当時」で要件をみます。
再婚した妻でも、労働者の死亡当時は、「労働者の「妻」だったからです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-124
R2.3.30 傷病(補償)年金、傷病等級に該当しなくなったとき
傷病(補償)年金は、傷病等級1~3級に該当する場合に支給されますが、傷病等級に該当しなくなった場合は?
 (H29年出題)
(H29年出題)
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】 ○
傷病補償年金受給の要件である「傷病等級1~3級」に該当しなくなった場合、受給権は消滅します。
そして、休業補償給付の要件(療養している・労働することができない・賃金を受けられない)を満たす場合は、休業補償給付を請求できます。
傷病補償年金は、労働基準監督署長の職権で支給決定されますが、休業補償給付は労働者からの請求が要ることも注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-114
R2.3.15 遺族(補償)年金・生計維持の要件
 遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を息していた」一定の遺族に支払われます。ここでいう「生計維持」とは、どの程度までをさすのでしょう?
遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を息していた」一定の遺族に支払われます。ここでいう「生計維持」とは、どの程度までをさすのでしょう?
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

【解答】 ×
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたものにあたり、遺族補償年金を受けることができます。
遺族(補償)年金の「生計維持」の判断ポイント
・労働者の収入によって生計の一部を維持されていればいい。→もっぱら又は主として生計を維持されていることは要しない。
共稼ぎでも「生計を維持されている」に含まれる。
★「生計維持」という用語は、あらゆるところで出てきますが、判断ポイントがそれぞれ違いますので、注意してくださいね。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H17年出題>
遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。

【解答】 ○
基準を定める「厚生労働省労働基準局長」の役職名を覚えておいてください。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-104
R2.2.28 業務上の疾病の範囲
 「業務上の疾病」はどのように決められているのでしょうか?
「業務上の疾病」はどのように決められているのでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

【解答】 ○
業務上の疾病として労災保険で補償される疾病の範囲は、労働基準法(労災保険法ではないので注意しましょう)施行規則別表第一の二の各号で定められています。
労働基準法施行規則別表第一の二(業務上の疾病リスト)は、第1号から第11号まで区分されています。
1号から10号までは疾病が例示列挙されていて、それに該当すれば業務上の疾病となります。もし、1号から10号に該当しない場合は、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」(11号には具体的な疾病が例示されていません。)に該当すれば、業務上の疾病となります。
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H21年出題>
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。

【解答】 ○
労働基準法施行規則別表第1の2の第1号から第11号までのどれにも当てはまらない場合は、業務上の疾病とは認められません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-94
R2.2.9 通勤経路の逸脱・中断
★ まず、通勤の定義から確認しましょう。
 通勤とは、
通勤とは、
・ 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うこと
① 住居と就業の場所との間の往復
② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
ただし、業務の性質を有するものを除く。
 通勤経路を逸脱し、中断した場合
通勤経路を逸脱し、中断した場合
・ 逸脱又は中断の間及びその後の移動 → 通勤としない。
・ 逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合
→ 逸脱又は中断の間を除き通勤となる。
 H27年出題
H27年出題
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

【解答】 ×
通勤経路を逸脱又は中断した場合でも、それが「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」は、逸脱・中断の間は通勤にはなりませんが、元の経路に復した後は通勤となります。
出退勤の途中で理髪店や美容院に立ち寄る行為は、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」に該当しますので、問題文の場合は、髪のセットを終えて合理的な経路に復した後は通勤となります。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H23年出題>
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

【解答】 ×
逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであったとしても、逸脱・中断の間は通勤とはなりません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-84
R2.1.22 支給制限/労働者の「故意」
業務遂行中の災害でも、それが労働者の「故意」による場合は、保険給付に制限がかかります。
 H26年出題
H26年出題
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】 ○
労働者が故意に(事故を発生させようとして)負傷した場合は、たとえ業務遂行中でも保険給付はまったく行われません。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H26年出題>
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者の故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 ○
「故意」と「故意の犯罪行為」では、支給制限の内容が異なるので注意してください。
「故意の犯罪行為」の場合、保険給付はまったく行わない、ではなく、「全部又は一部を行わないことができる」。裁量によることになります。
 練習問題もどうぞ!
練習問題もどうぞ!
<労災保険法 第12条の2の2>
① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< A >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて< C >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 A 直接の原因 B 重大な過失 C 療養に関する指示
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-74
R2.1.6 遺族補償一時金の受給者(労災)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H28 労災保険法(問6)より
H28 労災保険法(問6)より
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】 ○
遺族補償給付には、「年金」と「一時金」がありますが、「一時金」については、労働者の死亡の当時、「生計維持していなかった」場合でも、受給権者になり得るのがポイントです。
※ただし、子、父母、孫、祖父母は、生計維持していた、生計維持していなかったで順位が変わります。(生計維持していた方が優先)
配偶者は生計維持の有無にかかわらず最優先、兄弟姉妹は生計維持の有無にかかわらず最下位です。
労働者の死亡当時、配偶者も子も父母も孫も祖父母もいない場合は、生計維持していなかった兄弟姉妹が遺族補償一時金を受けることもあり得ます。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H17年出題】
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

【解答】 ○
遺族(補償)給付のうち、「年金」を受けることができるのは、労働者の死亡の当時、「生計維持していた」ことが条件です。(生計維持していなかったものはダメ)
 こちらもどうぞ
こちらもどうぞ
【H13年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

【解答】 ×
問題文の頭に注目してください。頭が「遺族補償年金」となっていれば「○」ですが「遺族補償給付」となっているので「×」です。
「遺族補償給付」には年金だけでなく「一時金」もあります。「一時金」なら、生計維持していなくても受けられる可能性がありますので。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-64
R1.12.19 R1労災/社会復帰促進等事業
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「社会復帰促進等事業」についてです。
 R1労災保険法(問7)より
R1労災保険法(問7)より
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。
A 被災労働者に係る葬祭料の給付
B 被災労働者の受ける介護の援護
C 被災労働者の遺族の就学の援護
D 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護
E 業務災害の防止に関する活動に対する援助

【解答】 A
「葬祭料」の給付は、社会復帰促進等事業としてではなく、「保険給付」として行われます。
この問題のポイント!
労災保険法の第一(主たる)の目的は「保険給付」を行うことです。保険給付は、①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付の3種類があります。
また、第二(従たる)の目的が、「社会復帰促進等事業」です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-54
R1.11.25 R1労災/傷病特別支給金の支給額
和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「傷病特別支給金の支給額」についてです。
 R1労災保険法(問6)より
R1労災保険法(問6)より
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

【解答】 ○
「傷病特別支給金」は傷病(補償)年金(保険給付)に上乗せされる特別支給金のうちの一般の特別支給金です。
問題文のとおり、傷病等級に応じて定額の「一時金」で支給されるのがポイントです。
ちなみに、特別支給金のうち「ボーナス特別支給金」は、「算定基礎日額(ボーナスをもとに算定される)」を使って計算される年金です。
| 特別支給金 | ボーナス特別支給金 | 傷病特別年金 | 1級→算定基礎日額の313日分 2級→ 277日分 3級→ 245日分 |
| 一般の特別支給金 | 傷病特別支給金 (一時金) | 1級→114万円 2級→107万円 3級→100万円 | |
| 保険給付 | 傷病(補償)年金 | 1級→給付基礎日額の313日分 2級→ 277日分 3級→ 245日分 | |
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-43
R1.11.6 R1労災/特別支給金と保険給付の違い
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「特別支給金と保険給付の違い」についてです。
 R1労災保険法(問6)より
R1労災保険法(問6)より
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

【解答】 ×
保険給付と違って、特別支給金は、譲渡、差押えの対象となります。
 「特別支給金と保険給付の違い」はよく問われる論点です。コチラの問題もチェックしましょう。
「特別支給金と保険給付の違い」はよく問われる論点です。コチラの問題もチェックしましょう。
<H22年出題>
特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的給付の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。

【解答】 ○
同一の事由で労災保険の給付と社会保険の年金が支給される場合、労災保険の保険給付は減額されますが、特別支給金の支給額は減額されません。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-33
R1.10.20 R1労災/特別加入者の特別支給金
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災「特別加入者の特別支給金」についてです。
 R1労災保険法(問6)より
R1労災保険法(問6)より
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

【解答】 ×
特別加入者にも傷病特別支給金は支給されますが、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金は支給されません。なぜなら、特別加入者にはボーナス(=特別給与)の概念が無いからです。
| 労働者 | 特別加入者 | ||
| 特別支給金 | ボーナス特別支給金 | 傷病特別年金 | なし |
| 一般の特別支給金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別支給金 | |
| 保険給付 | 傷病(補償)年金 | 傷病(補償)年金 | |
 平成28年にも同様の問題が出ています。
平成28年にも同様の問題が出ています。
【H28年問題より】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

【解答】○
特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金は支給されません。
しかし、特別支給金のうち、「一般の特別支給金」は特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-23
R1.10.2 R1労災保険法/指定病院等を変更するとき
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「指定病院等の変更」についてです。
 R1労災保険法(問5)より
R1労災保険法(問5)より
療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

【解答】 ○
この問題のポイントは、「新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出」の部分です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-13
R1.9.17 R1労災保険法より・「療養の給付」は指定病院等で行う
令和元年の問題を振り返っています。
今日は労災保険法の基本的な問題を解いてみます。
 R1労災法(問5)より
R1労災法(問5)より
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

【解答】 ○
療養補償給付は、原則として現物給付で行われます。現物給付である「療養の給付」は、指定病院等で行われます。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、労災の指定病院等でなければ、労災の療養の給付は行われません。
平成21年にも同様の問題が出題されています。
こちらの記事をどうぞ → R1.5.15 【労災】療養の費用の支給
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(労災保険法)
R1.9.3 R1選択式(労災保険法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第3回目は、「労災保険法 選択式」です。
【労災保険法】
 A~Cはしっかり解けたと思います。
A~Cはしっかり解けたと思います。
A 労災保険法の「労働者」は、労働基準法上の労働者
B 労災保険法の保険給付は3つ
①業務災害に関する保険給付
②通勤災害に関する保険給付
③二次健康診断等給付
C 通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるもの
・障害年金
・遺族年金
・傷病年金
 D、Eは、「保険関係成立届」の提出が行われていない間に労災事故が起きた場合の事業主からの費用徴収に関する問題です。
D、Eは、「保険関係成立届」の提出が行われていない間に労災事故が起きた場合の事業主からの費用徴収に関する問題です。
★ 「事業主からの費用徴収」については、今年の7月4日に記事にしています。
コチラ R1.7.4 事業主が保険関係成立届を提出していない場合
R1.7.4 事業主が保険関係成立届を提出していない場合
★ 今回の選択式では、「故意」「重大な過失」の認定の基準が問われました。
この論点は、平成27年に択一式で出題されています。
<参考 H27年出題その1>
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
<参考 H27年出題その2>
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
(解答)
その1 ○
「故意」の認定 → 保険手続に関する指導や加入勧奨を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合
「故意」が認定された場合の費用徴収率は100%
その2 ○
「重大な過失」の認定 → 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、保険関係成立日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していない
「重大な過失」が認定された場合の費用徴収率は40%
なお、「重大な過失」が認定された場合の費用徴収率については、H26年選択式でも出題されています。
★今後の勉強のポイント★
労働基準法同様、択一式で出題された箇所は、「選択式」に姿を変えて出題されることが多いです。
択一式の過去問を解くときは、常に「選択式で出題されるかも」と意識して、キーワードをおさえてくださいね。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】労災保険法/支給制限
R1.8.22 【選択式対策】労災支給制限の条文を確認
本日のcheckは労災保険法です。
(H12年選択式で出題された問題です)
労働者が< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、< C >を行わない。
労働者が< D >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの < E >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は< C >の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
A 故意に B 直接の原因 C 保険給付 D 故意の犯罪行為
E 原因
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労働分野】目的条文
R1.8.16 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)
 夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。
【労働基準法】
(労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として< B >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
この法律は、労働基準法と相まつて、< C >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< D >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< E >を確保するとともに、< F >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して< G >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< H >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >等を図り、もつて労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< K >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< L >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。

【解答】
A 人たるに値する生活 B 労働条件を低下させてはならない
C 労働災害の防止 D 自主的活動の促進 E 安全と健康
F 快適な職場環境の形成 G 迅速かつ公正な H 社会復帰の促進
I 安全及び衛生の確保 J 福祉の増進 K 生活及び雇用の安定
L 職業の安定 M 福祉の増進
★ 注意 ★
Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」
Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保
社労士受験のあれこれ
特別加入者のポイント(労災保険法)
R1.7.16 特別加入者と労働者の違い
まずは過去問をどうぞ
<H28年出題>
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

【解答】 ○
労災保険に特別加入することによって
・労働者と同じ保険給付
・労働者と同じ社会復帰促進等事業
を受けることができます。(原則)
しかし、特別加入者にはボーナスの概念がないので、特別給与(ボーナス)を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)は支給されません。
※特別支給金のうち、一般の特別支給金は、特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。
もう一問どうぞ
<H20年出題>
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者とみなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。

【解答】 ×
保険給付(①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付)のうち、二次健康診断等給付は、特別加入者には行われません。
二次健康診断等給付の前提である一次健康診断(労働安全衛生法の健康診断)の対象にならないからです。
また、一人親方等の一部には通勤災害に関する保険給付が行われません。
社労士受験のあれこれ
事業主からの費用徴収(労災保険)
R1.7.4 事業主が保険関係成立届を提出していない場合
過去問をどうぞ
<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

【解答】 ○
保険関係成立届を提出すること、保険料を納付することは「事業主」の義務です。
事業主がそれを怠ったとしても、労働者に責任はないので、労働者の保険給付は制限されません。
ただし、事業主からはペナルティとして費用徴収が行われます。
もう一問どうぞ
<H26年出題>
事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故について、政府が保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。

【解答】×
費用徴収の対象になるのは、事業主が「故意又は重大な過失」により、労災保険成立届を提出していない期間中に生じた事故です。
過失でも、それが重大でない場合は、費用徴収は行われません。
社労士受験のあれこれ
遺族補償年金の失権(労災)
R1.6.10 遺族補償年金が失権するとき
過去問をどうぞ
【H23年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態になくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。

【解答】 × 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は消滅しません。
「孫」が遺族補償年金の受給権者になる条件は、労働者の死亡当時、年齢要件(18歳の年度末までの間)か障害要件のどちらかにあてはまることです。
障害要件にあてはまらなくなっても、年齢要件(18歳の年度末まで)に当てはまっている間は失権しません。
もう一問どうぞ!
【H28年出題】
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が、自分の伯父の養子となったときは、消滅する。

【解答】 ○
遺族補償年金の受給権は、直系血族又は直系姻族以外の者の養子になったときは失権します。
伯父は傍系となりますので、叔父の養子になったときは失権します。
社労士受験のあれこれ
特別加入者の通勤災害(労災保険法)
R1.6.6 特別加入者の「通勤災害」で気を付けるところ
まずは過去問をどうぞ
<① H26年出題>
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
<② H26年出題>
特別加入制度において、家内労働者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。

【解答】① ○ ② ○
・個人タクシー業者、個人貨物運送業者、・漁船による自営漁業者、・特定農作業従事者、・指定農業機械作業従事者、・家内労働者等は、どこからどこまでが通勤なのか明確にならないため、通勤災害に関する保険給付は支給されません。
※通勤災害の保険給付を受けられないのは、「一人親方等」の一部です。「一人親方等」のすべてではありません。
こちらもどうぞ
<H8年出題>
自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を営む中小事業主等の特別加入者については、業務災害に関して保険給付の支給を受けることができるが、通勤災害に関して保険給付の支給を受けることはできない。

【解答】 ×
「中小事業主等」の特別加入者は、通勤災害は保険給付の対象となります。通勤災害に対する保険給付が支給されないのは、一人親方等の一部です。
社労士受験のあれこれ
年金の内払い(労災保険法)
R1.5.24 内払いとみなすのはどんなとき?(労災)
まず、過去問をどうぞ
<H25年出題>
同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払いとみなす。

【解答】○
乙年金と甲年金の内払いのポイント!
①乙年金と甲年金が「同一の傷病」によること
②乙年金・甲年金ともに「遺族補償年金、遺族年金」は除かれる。同一人物に対して同一の傷病による遺族補償年金、遺族年金が支給されることはあり得ないから
例えば・・・
傷病補償年金(「乙年金」)を受けていたが治ゆし、障害補償年金(「甲年金」)という。)を受ける権利を有することになった。傷病が治ゆして受給権が消滅したにも関わらず、消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、支払われた傷病補償年金は、障害補償年金の内払いとみなす。→ いちいち返してもらって支払い直すのは、かなりの労力だからです。
こちらもどうぞ
<H19年出題>
同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払とみなされる。

【解答】 ○
同一の傷病による異なる保険給付の間の内払は、年金だけでなく休業補償給付(休業給付)も対象となります。(ちなみに、障害補償一時金(障害一時金)も対象です。)
社労士受験のあれこれ
療養の給付と療養の費用の支給【労災保険】
R1.5.15 【労災】療養の費用の支給
労災保険の「療養補償給付・療養給付」には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。
原則は、現物給付の「療養の給付」、例外が現金給付の「療養の費用の支給」となります。
まず過去問からどうぞ
<H28年選択>
労災保険法第13条第3項によれば、政府は、療養の補償給付として療養の給付をすることが困難な場合、療養の給付に代えて< A >を支給することができる。

【解答】 A 療養の費用
もう一問どうぞ
<H21年出題>
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

【解答】 ×
現物給付の「療養の給付」は、指定病院等(労災病院や指定医療機関等)で行われます。厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等でも、労災保険の指定病院等になっていない場合は、療養の給付は行われません。
※指定病院等 → 社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者のこと
さらにもう一問どうぞ
<H21年出題>
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

【解答】 ×
療養の支給が行われるのは、①療養の給付をすることが困難な場合(例えば、当該地区に指定病院等がない等)と②療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合(例えば、当該傷病が指定病院等以外の病院、診療所等で緊急な療養を必要とする等)の2つの場合です。
労働者が指定病院等でない病院等でない病院等での療養を望んでも①か②に当てはまらない場合は療養の費用の支給は行われません。
社労士受験のあれこれ
特別加入者のポイント(労災保険)
R1.5.2 特別加入者にも支給されるもの・されないもの
労災保険は、「労働者」の業務災害や通勤災害等を補償する保険ですが、「中小事業主等」、「一人親方等」、「海外派遣者」は特別加入することによって、労働者と同じように労災保険の保護を受けることができます。
ただし、保護の内容には労働者と違う点があり、本試験ではそこがポイントです!
では過去問をどうぞ
<H28年出題>
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

【解答】 ○
「特別給与を算定基礎とする特別支給金」とは、特別給与(ボーナス)をもとに算定されるボーナス特別支給金と言われるものです。特別加入者には、「ボーナス」の概念がないので、ボーナス特別支給金は支給されません。
※特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」の2種類があります。一般の特別支給金は特別加入者にも支給されます。
社労士受験のあれこれ
療養の給付の請求手続き(労災保険)
H31.4.30 現物給付である「療養の給付」の請求
療養補償給付及び療養給付は、原則として現物給付で行われます。(「療養の給付」と言います。)
例外的に、現金給付である「療養の費用の支給」が行われることもあります。例外は2つ。1つは「療養の給付をすることが困難な場合」、2つ目は「療養の給付を受けないことについて、労働者に相当の理由がある場合」です。
現物給付である「療養の給付」と現金給付である「療養の費用の支給」は、請求方法が違いますので確認しましょう。
過去問をどうぞ
<H27年出題>
療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、厚生労働省令に規定された事項を記載した請求書を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】 ×
療養の給付(現物給付)の請求書は、直接ではなく、「指定病院等を経由」して所轄労働基準監督署長に提出します。
※療養の費用の支給(現金給付)の請求書は、「直接」、所轄労働基準監督署長に提出します。
社労士受験のあれこれ
傷病補償年金のポイント(労災保険)
H31.4.26 傷病補償年金の出題ポイント
さっそく、過去問をどうぞ
<①H19年選択式出題>
業務災害に関する保険給付(<A >及び介護補償給付を除く。)は、労働基準法に定める災害補償の事由、又は船員法に定める災害補償の事由のうち一定のものが生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は<B >に対し、その請求に基づいて行われる。
<②H20年出題>
労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。
<③H18年出題>
傷病補償年金を受ける権利は、当該傷病の療養の開始後1年6か月を経過した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】
<①H19年選択式出題>
A 傷病補償年金
→ 労災保険の業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償(療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料)の事由が発生したときに行われます。ただし、「傷病補償年金」と「介護補償給付」は、労働基準法の災害補償の中には無いものなので、カッコで除かれています。
B 葬祭を行う者
→ 葬祭料を請求できるのは、遺族だけに限らないことに注意してください。
<②H20年出題> ×
傷病補償年金と傷病年金は、他の保険給付とは違い、労働者からの請求ではなく所轄労働基準監督署長の職権で支給が決定されます。
<③H18年出題> ×
傷病補償年金は、職権で支給が行われるので、時効は関係ありません。
社労士受験のあれこれ
遺族補償年金を受けることができる遺族の要件(労災保険)
H31.4.15 労災遺族の要件である「一定の障害」とは?
さっそく、過去問をどうぞ
<H19年出題>
遺族補償年金又は遺族年金の受給資格要件の一つである厚生労働省令で定める障害の状態は、身体に障害等級第5級以上に該当する障害がある状態又は傷病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態である。

【解答】 ○
「障害等級第5級以上」、「労働が高度の制限」がキーワードです。覚えましょう。
 遺族補償年金(遺族年金)の受給資格要件は、まず労働者の死亡当時「生計維持」していたこと。また、「妻」は年齢要件、障害要件は問われませんが、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
遺族補償年金(遺族年金)の受給資格要件は、まず労働者の死亡当時「生計維持」していたこと。また、「妻」は年齢要件、障害要件は問われませんが、夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、年齢要件か障害要件を満たす必要があります。
社労士受験のあれこれ
労災保険法/遺族補償給付
H31.3.5 遺族補償年金と遺族補償一時金の違い
 まずは過去問をどうぞ。
まずは過去問をどうぞ。
<H25年出題>
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】 ○
遺族補償「一時金」は、労働者の死亡当時に生計維持関係がなくても受給できる可能性があります。
一時金の受給資格者
① 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
② 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
③ その他の子、父母、孫、祖父母
④ 兄弟姉妹
※ 遺族の順位は、①、②、③、④の順。②~③は、子、父母、孫、祖父母の順
 では、もう一問どうぞ。
では、もう一問どうぞ。
<H17年出題>
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当するものに限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。

【解答】 ○
遺族補償「年金」、遺族「年金」は労働者の死亡当時「生計維持していた」ことが要件です。「一時金」との違いに注意しましょう。
 最後にもう一問どうぞ。
最後にもう一問どうぞ。
<H18年出題>
遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

【解答】 ×
問題文の最初に注目してください。遺族補償「給付」となっています。
遺族補償「給付」には「年金」と「一時金」がありますが、「一時金」の方は、死亡当時生計維持関係がなくても受けられる可能性があります。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法)
H31.2.5 H30年出題/二次健康診断等給付の請求書
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「二次健康診断等給付の請求書」です。
H30年 労災保険法(問7E)
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】 〇
二次健康診断等給付の請求書は、健診給付病院等を経由・提出先が「所轄都道府県労働局長」なのがポイントです。所轄労働基準監督署長ではないので注意してください。
なお、二次健康診断等給付以外の保険給付に関する事務は、所轄労働基準監督署長が行います。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法)
H31.2.4 H30年出題/介護補償給付が支給されないとき
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「介護補償給付が支給されないとき」です。
H30年 労災保険法(問2B)
介護補償給付は、障害補償年金、又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、病院又は診療所に入院している間も行われる。

【解答】 ×
介護補償給付は、病院又は診療所に入院している間は行われません。病院等で介護サービスが受けられるので、介護補償給付の必要が無いからです。
穴埋め式もどうぞ
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< A >介護を要する状態にあり、かつ、< A >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、< B >に対し、その請求に基づいて行う。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
2 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
3 病院又は診療所に入院している間

【解答】 A 常時又は随時 B 当該労働者
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法)
H31.1.22 H30年出題/障害補償年金の受給権の消滅
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「障害補償年金の受給権の消滅」です。
H30年 労災保険法(問6D)
同一の負傷又は疾病が再発した場合には、その療養の期間中は、障害補償年金の受給権は消滅する。

【解答】 〇
障害補償年金は傷病が「治った」場合に支給されるものです。
「再発」とは、再び療養を必要とするに至ったということですので、障害補償年金の受給権を失権することになります。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法)
H31.1.21 H30年出題/傷病補償年金の支給要件
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「傷病補償年金の支給要件」です。
H30年 労災保険法(問2A)
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】 ×
療養開始後1年を経過した日ではなく、「療養開始後1年6か月を経過した日」です。
過去問もどうぞ
<H18年出題>
傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日において、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
① 当該傷病が治っていないこと
② 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること

【解答】 ×
傷病等級第7級以上ではなく、「第3級」以上です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法)
H31.1.4 H30年出題/二次健康診断等給付
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」です。
※ 今日は、「二次健康診断等給付」です。
H30年 労災保険法(問7B)
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。

【解答】 ×
特定保健指導は、医師又は歯科医師ではなく、「医師又は保健師」による保健指導です。
選択式でも解いてみましょう。
二次健康診断等給付は、< A >法第66条第1項の規定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(「一次健康診断」という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による< B >の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断の結果その他の事情により既に< B >の症状を有すると認められるものを除く。)に対し、その請求に基づいて行う。
二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりとする。
① < C >の状態を把握するために必要な検査(上記の検査を除く。)であって厚生労働省令で定めるものを行う< D >による健康診断(1年度につき1回に限る。「二次健康診断」という。)
② 二次健康診断の結果に基づき、< B >の発生の予防を図るため、面接により行われる< E >による保健指導(二次健康診断ごとに1回に限る。「特定保健指導」という。)

【解答】
A 労働安全衛生 B 脳血管疾患及び心臓疾患 C 脳血管及び心臓
D 医師 E 医師又は保健師
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法)
H30.12.18 H30年出題/障害補償給付・障害等級
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「障害等級表について」です。
H30年 労災保険法(問6A)
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害等級を定めることとされている。

【解答】 ○
負傷・疾病が治った後、身体に障害が残り、その障害が障害等級表に定めらている障害等級に該当した場合は、それに応じた障害補償給付が支給されます。
障害等級は、則別表第1の障害等級表に、第1級から第14級まで定められています。
ただし、障害等級表に定められているのは、類型的な140種の障害だけです。そのため、障害等級表に載っていない障害もあり得ます。その場合は、問題文にあるように、「同表に掲げる身体障害に準じて」障害等級を定めることになっています。
【同じ切り口の過去問です】
(H21年出題)
障害補償給付を支給すべき障害は、厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが、同表に掲げるもの以外の障害は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる障害に準じて障害等級が認定される。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法)
H30.11.26 H30年出題/療養の費用の支給について
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」を確認しましょう。
※ 今日は、「療養の費用の支給について」です。
H30年 労災保険法(問2E)
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、そのうち③及び⑥について事業主の証明を受けなければならない。

【解答】 ×
事業主の証明が必要なのは、③負傷又は発病の年月日と④災害の原因及び発生状況です。
【過去にも出題されています。過去問をどうぞ】
H22年出題
療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、①労働者の氏名、生年月日及び住所、②事業の名称及び事業場の所在地、③負傷又は発病の年月日、④災害の原因及び発生状況、⑤傷病名及び療養の内容、⑥療養に要した費用の額、⑦療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。
A ①~⑦
B ②~⑦
C ③~⑦
D ③、④
E ③、④、⑦

【解答】 D
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法 基礎編)
H30.11.6 H30年出題/休業補償給付と傷病補償年金
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「労災保険法」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、労災保険法「休業補償給付と傷病補償年金の関係」です。
H30年 労災保険法(問5C)
休業補償給付と傷病補償年金は、併給されることはない。

【解答】 ○
「休業補償給付」と「傷病補償年金」は、「療養中(傷病が治っていない)の所得補償」という共通点があるので、同時に支給されることはありません。
【「療養補償給付」との併給の問題もよく出ます。チェックしましょう!】
<① H24年出題>
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
<② H24年出題>
療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

【解答】 ① ○ ② ○
「療養補償給付=治療」を受けながら所得補償として休業補償給付を受ける、又は「療養補償給付=治療」を受けながら傷病補償年金を受ける、どちらもあり得ます。
★「療養補償給付」、「休業補償給付」、「傷病補償年金」。どれも「治ゆ前」の給付であることを意識してください。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法 基礎編)
H30.10.18 H30年出題/休業補償給付の支給
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労災保険法の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「休業補償給付」の支給です。
会社の所定休日。「休業補償給付」は支給される?されない?
H30年 労災保険法(問5D)
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。

【解答】 ×
休業補償給付は、会社の所定休日にも支給されます。
★チェックポイント★
休業補償給付は、①業務上の負傷又は疾病による療養のため+②労働することができない+③そのため賃金が受けられない日に支給されます。
休業補償給付は、休業1日(↑上の3つの要件が揃った日)ごとに支給事由が生じますので、会社の所定休日は関係ありません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険法 基礎編)
H30.10.1 H30年出題/労災保険法基礎問題
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
労災保険法の「基礎」を確認しましょう。
H30年労災保険法問6B
障害補償一時金を受けた者については、障害の程度が自然的経過により増進しても、障害補償給付の変更が問題となることはない。
【解答】 ○
障害補償年金ではなく障害補償一時金の問題であることがポイントです。
「年金」の場合、障害の程度が自然的に変更した場合は、額の改定などが行われます。
例えば、5級の障害補償年金を受ける者の障害の程度が自然的経過により増進し2級に該当した場合は、2級の障害補償年金が支給されます。逆に自然的経過により軽減し10級に該当した場合は、年金の支給が打ち切られ、10級の障害補償一時金が支給されます。
しかし、障害補償一時金を受けた者の障害の程度が自然的経過により、増進又は軽減しても、このような変更は行われません。一時金は一度支給されて完了するから、と考えてください。
<過去にも出題されています。確認しましょう>
平成21年出題
障害補償年金を受ける者の障害の程度について自然的経過により変更があった場合には、新たに該当することとなった障害等級に応ずる障害補償給付が支給され、その後は、従前の障害補償年金は支給されない。
【解答】 ○
「障害補償年金」を受ける者についての問題なので「○」です。
「障害補償一時金」を受けた者については、あてはまりません。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(労災保険 選択編)
H30.9.5 <H30年選択>労災保険法振り返ります

 最近、「社会保険労務士合格研究室」HPをご覧の方から、嬉しいメッセージを頂きます。
最近、「社会保険労務士合格研究室」HPをご覧の方から、嬉しいメッセージを頂きます。
励みになります。ありがとうございます!
さて、H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、労災保険法の選択式です。
AとB 中小事業主等の特別加入の要件より
これは解けたと思います。
「中小事業」の規模はきちんと覚えてくださいね。
★過去問もチェック
<H22年にこんな問題が出ています。>
労災保険法第4章の2は、中小事業主及び一人親方等労働者に当たらない者であっても一定の者については、申請に対し政府の承認があったときは、労災保険に特別に加入できるとしている。次の者のうち、特別加入を認められる者として正しいものはどれか。
A 常時100人の労働者を使用する小売業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
B 常時100人の労働者を使用するサービス業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
C 常時100人の労働者を使用する不動産業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
D 常時300人の労働者を使用する金融業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
E 常時300人の労働者を使用する保険業の事業主で、労働保険徴収法に定める労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者
<解答> B
「中小事業」の規模を覚えていないと、どうにもならない問題です。
C 特別加入者の給付基礎日額の上限
覚えていれば、難なく解ける「数字」の問題。
受験勉強は「理解する」ことはもちろん大切ですが、何も考えずにただただ「覚える」ことも同じくらい大切だと思っています。
D 一人親方等
「一人親方等」として特別加入できる事業は、7つ(例えば個人タクシー業者、大工など)です。7つの事業がイメージできれば、解答できたと思います。
なお、問題文にある労災保険法第33条第3号及び第4号は「一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人(一人親方等)」、同条第5号は「特定作業従事者」のことです。
E 通勤災害に関する保険給付が行われない者
よく出題されているところなので、大丈夫だったと思います。
★過去問もチェック
<H26年にこんな問題が出ています。>
特別加入制度において、個人貨物運送業者については通勤災害に関する保険給付は支給されない。
<解答> ○
どこまでが通勤なのか明確にできないためです。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】基本の条文(労働編)
H30.8.20 【選択式対策】基本条文チェック!(労基、安衛、労災、雇用)
 涼しくなりましたね。風に秋を感じます。
涼しくなりましたね。風に秋を感じます。
あと1週間です!
迷いは捨てて、ご自分の直感で勉強を進めてくださいね。
■■
前回までは「目的条文」を確認してきました。
今回からは、おさえておきたい基本条文を取り上げます。
【労働基準法】
(労働条件の決定)
① 労働条件は、労働者と使用者が、< A >において決定すべきものである。② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< B >各々その義務を履行しなければならない。
【労働安全衛生法】
(定義)
・ 労働災害
→ 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は< C >その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
・ 労働者
→ 労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
・ < D >
→ 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
・ 化学物質
→ 元素及び化合物をいう。
・ < E >
→ 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。
【労災保険法】
(通勤の定義)
通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、< F >により行うことをいい、< G >を除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する< H >の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
【雇用保険法】
(失業等給付)
失業等給付は、< I >、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

【解答】
A 対等の立場 B 誠実に C 作業行動 D 事業者
E 作業環境測定 F 合理的な経路及び方法 G 業務の性質を有するもの
H 住居間 I 求職者給付
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労働分野】目的条文
H30.8.15 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)
 夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
夏休みの方も多いでしょうか?数字の暗記にも時間をとってくださいね。暗記ものは「覚えれば得点」できます。どんどん覚えてしまいましょう!
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第3回目「労働分野・目的条文」です。
【労働基準法】
(労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として< B >ことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(目的)
この法律は、労働基準法と相まつて、< C >のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< D >の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< E >を確保するとともに、< F >を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して< G >保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< H >、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< I >等を図り、もつて労働者の< J >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< K >を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< L >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< M >を図ることを目的とする。

【解答】
A 人たるに値する生活 B 労働条件を低下させてはならない
C 労働災害の防止 D 自主的活動の促進 E 安全と健康
F 快適な職場環境の形成 G 迅速かつ公正な H 社会復帰の促進
I 安全及び衛生の確保 J 福祉の増進 K 生活及び雇用の安定
L 職業の安定 M 福祉の増進
★ 注意 ★
Eについて・・・安全と衛生ではなく安全と「健康」
Iについて・・・こちらは、安全と「衛生」の確保
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労災保険法】業務災害に関する保険給付
H30.7.23 【選択式対策】業務災害に関する保険給付の種類
 今日、熊谷市で、国内最高気温の41.1℃を観測し、気象庁もこの暑さは「災害」と言ってます。まさかこんなに暑い夏になるとは思っていなかったです。
今日、熊谷市で、国内最高気温の41.1℃を観測し、気象庁もこの暑さは「災害」と言ってます。まさかこんなに暑い夏になるとは思っていなかったです。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
<業務災害に関する保険給付の種類>
1.業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
① 療養補償給付
② 休業補償給付
③ 障害補償給付
④ 遺族補償給付
⑤ < A >
⑥ < B >年金
⑦ < C >給付
2. 1.の保険給付(< B >年金及び< C >給付を除く。)は、< D >法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は< E >法第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、< D >法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は< F >に対し、その請求に基づいて行う。

【解答】
A 葬祭料 B 傷病補償 C 介護補償 D 労働基準 E 船員
F 葬祭を行う者
ポイント
■ 労災保険法の業務災害に関する保険給付は、労働基準法の災害補償の事由とリンクしていますが、傷病補償年金と介護補償給付については、労災保険独自の給付です。
■ 補償を請求できるのは、労働者と遺族だけでなく、「葬祭を行う者」も忘れないようにしてください。
「葬祭料」は、「葬祭を行う者」の請求に基づき行われます。(例えば、社葬を行った会社に支給されることもあり得ます。)
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労災保険法】心理的負荷による精神障害の認定基準
H30.6.29 【選択式対策】心理的負荷による精神障害の認定基準
 今日は突然の大雨に遭遇してしまいました。この時期、天候が不安定ですね。
今日は突然の大雨に遭遇してしまいました。この時期、天候が不安定ですね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
【心理的負荷による精神障害の認定基準 】
認定要件
次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。
1 対象疾病を発病していること。
2 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、< B >による強い心理的負荷が認められること。
3 < B >以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
・ 労働基準法施行規則別表第1の2第9号 → < C >にかかわる事故への遭遇その他心理的に< D >を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病

A 6か月 B 業務 C 人の生命 D 過度の負担
過去問もどうぞ
<H24年出題>
認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。

【解答】 ○
ポイントはアンダーラインの部分です。 ↓
認定基準においては、「業務による強い心理的負荷」について、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めかではなく、職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似する同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるとしている。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労災保険法】休業給付基礎日額
H30.5.29 【選択式対策】休業給付基礎日額のスライド
 どんどん問題を解いていきましょう!テキストを読むだけではなかなか頭に入りません。
どんどん問題を解いていきましょう!テキストを読むだけではなかなか頭に入りません。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
今日のテーマは、「休業給付基礎日額のスライド」です。
 問題文の字が多くて読みにくい方は、赤の文字の部分を重点的に読んで下さい。
問題文の字が多くて読みにくい方は、赤の文字の部分を重点的に読んで下さい。
問題文は全部読まなくても大丈夫なのです。重要ポイントを拾う練習にもなります。
休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
① スライドが適用されない場合(=第8条の給付基礎日額)
第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。
② スライドが適用された場合(=第8条の給付基礎日額×スライド率)
1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する< A >における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の< B >に至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の< C >に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率(スライド率)を第8条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

【解答】
A 毎月勤労統計 B 100分の110を超え、又は100分の90を下る
C 翌々四半期
★ 休業給付基礎日額は、第8条の規定で算定した給付基礎日額(平均賃金に相当する額)が原則です。
ただし、休業給付基礎日額は世間の給与の動向に合わせて見直しが行われます。それがスライド制です。
スライド制は、四半期ごとの「平均給与額」(簡単に言うと労働者1人当たりの給与の1か月の平均)が、算定事由発生日の四半期の平均給与額と比べて±10%を超えて変動した場合、変動した四半期の翌々四半期から、変動した比率を基準にしたスライド率が給付基礎日額にかかる(改定日額といいます)という仕組みです。
★ 過去問の傾向は、「四半期ごとの平均給与額」を比べる、「100分の110を超え、又は100分の90を下る」のがスライドの条件、変動した四半期の「翌々四半期」の最初の日からスライドが適用される、というキーワードをおさえておけばOkという感じです。
(深く読み込みすぎると難しいので、ほどほどに)
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労災保険法】社会復帰促進等事業
H30.5.8 【選択式対策】社会復帰促進等事業
 ゴールデンウィーク明け、調子は戻りましたか?
ゴールデンウィーク明け、調子は戻りましたか?
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「労災保険法」です。
条文の空欄を埋めてください。
(社会復帰促進等事業)
① < A >は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の< B >の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに < C >の確保を図るために必要な事業
② < A >は、社会復帰促進等事業のうち、< D >法第12条第1項に掲げるものを< D >に行わせるものとする。

【解答】
A 政府 B 安全及び衛生 C 賃金の支払
D 独立行政法人労働者健康安全機構
※ 社会復帰促進等事業は、①社会復帰促進事業、②被災労働者等援護事業、③安全衛生確保等事業の3つからなっています。
ポイント!
・ 社会復帰促進等事業を行うのは原則「政府」
・ ただし
社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項に掲げるもの(療養施設の設置及び運営、健康診断施設の設置及び運営、未払賃金の立替払事業など)を「独立行政法人労働者健康安全機構」に行わせる。
労災年金受給権者に対する年金の受給権を担保とする小口資金の貸付けは、「独立行政法人福祉医療機構」に行わせる
・ ちなみに
特別支給金の支給は政府が行う
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・労災】支給制限
H30.4.12 【選択式対策】労災・支給制限
本試験まで、あと4か月と少し。
そろそろ、選択式の勉強にも力を入れていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ では、今日は労災保険法です。
条文の空欄を埋めてください。
(支給制限)
第12条の2の2
① 労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又は< B >を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が< C >若しくは< D >により、又は正当な理由がなくて< E >ことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 A 故意に B その直接の原因となつた事故
C 故意の犯罪行為 D 重大な過失 E 療養に関する指示に従わない
ちょっとポイント★
① 保険給付を行わない
結果の発生を意図した故意による事故については、労災保険の保険給付は行われません。(絶対的)
② 保険給付の全部又は一部を行わないことができる
給付制限は①のような絶対的なものではなく「裁量的」な制限となります。支給制限の対象となる保険給付や支給制限の期間・率は、通達で規定されています。(詳しくはまた日を改めて記事にします)
社労士受験のあれこれ
労災保険・適用除外(公務員)
H30.3.19 H29年問題より「労災保険・公務員の適用について」
H29年本試験【労災保険法問4】を解いてみてください。
次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。
B 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。
C 労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。
D 労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。
E 労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

【解答】 D
★ 労災保険法第3条第2項では、
① 国の直営事業
② 官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)
については、「労災保険法は適用しない」、と規定されています。
ですので、問題Dの「労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。」が正しい答となります。※なお、現在「国の直営事業」に該当する事業はありません。
★ 一般職の国家公務員について
一般職の国家公務員の公務上や通勤による災害は、「国家公務員災害補償法」で保護されていますので、補償内容が重なる労災保険法の適用は除外されます。これは、非常勤職員、行政執行法人の職員も同様です。
問題Bの「行政執行法人の職員」、問題Cの「非現業の一般職の国家公務員」には労災保険法は適用されません。
★ 地方公務員の場合は、「常勤」か「非常勤」かで適用が異なります。
「常勤職員」について
→ 地方公務員災害補償法が適用されますので、労災保険の適用は除外されます。
「非常勤職員」について
→ 「現業の非常勤職員」には、労災保険法が適用されます。
→ 上記以外は、地方公務員災害補償法等が適用され、労災保険の適用は除外されます。
問題Eの「常勤の地方公務員」には労災保険法は適用されません。
問題Aの「市の経営する水道事業」は「現業部門」で労災保険の適用事業所です。そこで勤務する非常勤職員には、労災保険法が適用されます。
社労士受験のあれこれ
通勤災害について
H30.2.15 H29年問題より「通勤災害について」
H29年本試験【労災保険法問5C(通勤災害)】を解いてみてください。
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

【解答】 ×
★ 業務の性質を有するものは、「通勤災害」から除外されます。
通勤途上の事故でも、業務の性質を有するものは「業務災害」となります。例えば、事業主の提供する専用の通勤バスの利用が原因の事故は、「業務上」となります。
社労士受験のあれこれ
傷病補償年金の支給要件
H30.1.24 H29年問題より「傷病補償年金の支給要件」
H29年本試験【労災保険法問2B】を解いてみてください。
傷病補償年金の支給要件について、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとされている。

【解答】 ○
★ 労災保険法施行規則第18条で、障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態により認定するものとする、と規定されています。
「6か月以上」の部分が暗記ポイントです。
社労士受験のあれこれ
「傷病の状態等に関する届」
H30.1.8 H29年問題より「傷病の状態等に関する届」の提出/労災保険法
H29年本試験【労災保険法問2A】を解いてみてください。
所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な書類を添えて提出させるものとしている。

【解答】 ○
★ この問題のチェックポイント → 「療養開始後1年6か月経過した日において治っていない」の部分です。
★ 療養開始後1年6か月を経過した日に傷病が治っていない・障害の程度が傷病等級1級~3級に該当している場合、所轄労働基準監督署長が職権で傷病補償年金の支給を決定します。
傷病の状態を把握するため、「療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」」を提出させることになっています。
ちなみに
★ 療養開始後1年6か月を過ぎても、傷病が治らないで、「傷病等級に該当しない」場合は引き続き休業補償給付が支給されます。
その場合は、毎年1月1日から1月31日までの休業補償給付の請求書を提出するときに、それに添えて「傷病の状態等に関する報告書」も提出します。
社労士受験のあれこれ
基本の問題その2(労災保険法)
H29.12.16 H29年問題より「基本」を知ろう・労災保険法
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
休業補償給付と傷病補償年金
傷病補償年金の受給権が消滅した後、休業補償給付は受けられるか?
★ 傷病補償年金を受けている人の障害の程度が軽くなって、1~3級に該当しなくなったら、傷病補償年金の受給権は消滅します。
その際、休業補償給付の要件(療養のため労働することができず賃金を受けない)に当てはまっている場合は、休業補償給付の請求をすることができます。
★ ちなみに、休業補償給付と傷病補償年金の共通点は、「治ゆ前」に支給される給付であることです。
では、平成29年【問2】Cを解いてみましょう。
★問題です。
(平成29年【問2】C)
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
定番問題その13(労災保険法)
H29.11.23 H29年問題より「定番」を知る・労災保険法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (退職後の労災保険)
退職後も労災保険の給付は受けられる。
★ 自己都合退職でも、契約期間満了でも、定年退職でも、解雇でも、退職事由は問いません。
これを覚えると、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。
(平成29年【問7】D)
保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
定番問題その3(労災保険法)
H29.10.30 H29年問題より「定番」を知る・労災保険法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
今日から、定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (療養補償給付と療養給付の違い)
療養給付(通勤災害)は一部負担金が徴収される場合あり
★ 労災保険では、業務上や通勤によるケガや病気について、治るまで療養(原則、現物給付)が受けられます。この給付のことを療養補償給付(通勤災害の場合は療養給付)といいます。
★ 業務災害(療養補償給付)の場合は、一部負担金は徴収されません(労働者は無料で療養が受けられる)が、通勤災害(療養給付)の場合は一部負担金が徴収されます。
業務災害は、本来は事業主に補償責任があるのに対し、通勤災害は事業主に補償責任はありません。そのため、通勤災害の場合は、労働者に一部を負担してもらおうという考え方です。
これを覚えると、平成29年【問5】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問5】B)
療養給付を受ける労働者は、一部負担金を徴収されることがある。

<解答> 〇
療養給付=通勤災害ですので、一部負担金が徴収されます。(場合によっては徴収されないこともある。)
★一部負担金の額
200円(健康保険法の日雇特例被保険者は、100円)
※ ただし、「現に療養に要した費用の総額 < 200円(100円)」の場合は、現に療養に要した費用の総額に相当する額が一部負担金の額になります。
★ 一部負担金は、「休業給付」から控除されます。
★ 以下の場合は、一部負担金は徴収されません。
① 第三者の行為による事故で療養給付を受ける
② 療養の開始後3日以内に死亡したその他休業給付を受けない(休業給付から控除できないから)
③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した(一部負担金は、最初の分だけが初回の休業給付から控除される。)
社労士受験のあれこれ
覚えれば解ける問題その3(労災保険法)
H29.10.12 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・労災保険法
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (通勤災害)
「業務の性質を有するもの」は、通勤災害にならない
★ 労災保険法第7条に「通勤」の定義が以下のように規定されています。
「通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」
「業務の性質を有するもの」は通勤から除外されています。
★ 例えば、会社の用意した送迎バスでの往復などが「業務の性質を有するもの」に当たります。会社の送迎バスは「事業主の支配下」にありますので、送迎バスの事故で負傷等をした場合は、通勤災害ではなく「業務災害」として保護されます。
これを覚えると、平成29年【問5】Cが解けます。
★問題です。(平成29年【問5】C)
移動の途中の災害であれば、業務の性質を有する場合であっても、通勤災害と認められる。

<解答> ×
◆ 業務の性質を有する場合は、「業務災害」です。
社労士受験のあれこれ
まずは原則!その3(労災保険法)
H29.9.27 H29年問題より原則を学ぶ・労災保険
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
■今日、取り上げる「給付制限」は、各科目で同じようで違う規定があります。本当は横断学習が効果的ですが、まずは、一科目ずつみていきましょう。
今日の原則
【「故意」による場合は、保険給付は行わない】(労災保険法第12条の2の2)
労働者が結果が分かったうえで意図的に起こした事故については、労災保険による保護はありません。
「故意」に負傷、疾病、障害、死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を「行わない」(絶対に行わない「絶対的給付制限」)となることがポイントです。

★ 故意の犯罪行為や重大な過失等の場合も支給制限が行われますが、こちらは絶対的給付制限ではなく「全部又は一部を行わないことができる。」(全部ではなく「全部又は一部」となり、給付制限をする、しないは「任意」)となります。こちらは、また別の機会に。
この原則で、平成29年【問7】Eが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】E)
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
平成29年度選択式を解きました。(労災保険編)
H29.9.5 平成29年度選択式(労災保険編)~次につなげるために~
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、労災保険法です。
【A、B、C】
「不服申立て」からの出題です。
問題文の中に「3か月」がありますが、Cの解答も3か月。問題文中に同じ文言があるから選択肢から外すという判断は危険です。
とは言っても、この問題は解けた方が多かったかと思います。
なお、不服申し立ては、横断学習が効果的です。
当サイトでも取り上げていますので、よろしければご覧ください。
コチラです → H28.7.22 金曜日は横断 (不服申し立て その1)
【D、E】
時効の基本的な問題です。
こちらも解けた方が多かった問題だと思います。
なお、時効も横断学習が効果的です。
コチラをどうぞ → H28.7.1 金曜日は横断 時効(労働編)
今後の勉強のポイント!
★ 「不服申立て」、「時効」のような「暗記すれば解ける!」問題は落とさない。
「不服申立て」や「時効」はどの科目から出題されてもおかしくありません。暗記するだけで得点できるので、横断的に覚えてしまいましょう。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】選択式の練習(労災保険法)
H29.8.8 選択式の練習(労災保険法)
選択式の練習問題です。
本日は、労災保険法の改正個所からです。
空欄を埋めてください。
労災保険法施行規則第8条 (日常生活上必要な行為)
法第7条第3項の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
一 日用品の購入その他これに準ずる行為
二 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
三 選挙権の行使その他これに準ずる行為
四 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
五 要介護状態にある配偶者、子、父母、< A >の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
<参考 労災保険法第7条第2項、3項>
② 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
③ 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

<解答> A 孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母
※ 改正前は、孫、祖父母、兄弟姉妹は、「同居しかつ扶養している」ことが要件でしたが、その要件がなくなりました。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)
H29.7.31 目的条文のチェック(労働編)
いよいよ7月最終日です!
明日から8月。8月の頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(労働編)です。
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< A >を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の< B >の確保等を図り、もつて労働者の < C >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が< A >場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< B >及び雇用の安定を図るとともに、< C >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< D >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< E >を図ることを目的とする。

<解答>
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が<A 人たるに値する生活>を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、<B この基準>を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<C 向上>を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、<A 労働基準法>と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B 安全と健康>を確保するとともに、<C 快適な職場環境>の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な<A 保険給付>を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の<B 安全及び衛生>の確保等を図り、もつて労働者の<C 福祉の増進>に寄与することを目的とする。
ここもポイント!
「労働安全衛生法」と「労災保険法」の目的条文の比較
安全と○○
→ こちらの記事をどうぞ! H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が<A 自ら職業に関する教育訓練を受けた>場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<B 生活>及び雇用の安定を図るとともに、<C 求職活動>を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<D 職業の安定>に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<E 福祉の増進>を図ることを目的とする。
社労士受験のあれこれ
通勤災害
H29.3.8 逸脱・中断後の移動
今日は、久しぶりに労災保険法です!テーマは「通勤災害」です。
通勤経路を逸脱(回り道)、中断(寄り道)した場合の扱いを、確認しましょう。
【法第7条】
★ 労働者が、通勤の経路を逸脱し、又は中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。
→ 例えば、会社帰りに、回り道をして映画館に向かったり(逸脱)、飲み会のため経路上の居酒屋に入った(中断)場合、そこから後は「通勤」ではなくなります。
★ ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
→ 例えば、逸脱や中断が、「日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のもの」である場合は、元の経路に戻ったところから「通勤」が復活します。
 では、「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令で定めるものを確認しましょう。空欄を埋めてください。
では、「日常生活上必要な行為」として厚生労働省令で定めるものを確認しましょう。空欄を埋めてください。
【則第8条】
1. < A >の購入その他これに準ずる行為
2. 職業訓練、学校教育法第一条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
3. < B >の行使その他これに準ずる行為
4. 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
5. 要介護状態にある配偶者、子、父母、< C >並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

<解答>
A 日用品 B 選挙権 C 孫、祖父母及び兄弟姉妹
※ Cについて
平成29年1月より、育児・介護休業法の「介護休業」の対象家族の改正に合わせて、労災保険法の「日常生活上必要な行為」である介護の対象家族の範囲も改正になりました。
改正前は、孫、祖父母、兄弟姉妹は「同居かつ扶養していること」が条件でしたが、改正後は、その条件が撤廃されています。
 過去問もどうぞ。
過去問もどうぞ。
【H23年出題】
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

【解答】×
逸脱、中断が、日常生活上必要な行為であったとしても、逸脱・中断中は通勤にはなりません。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.11.23 ひっかけ問題(労災)
平成28年度の本試験から、「ひっかけ問題」をピックアップします。
ひっかけ問題にひっかかると本当に悔しいです。
本日は平成28年度労災保険法問7のBです。(恥ずかしながら私もひっかかりました)
<問題文>
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

【答え】 ×
★ 「算定基礎日額」ではなく「休業給付基礎日額」です。
| 給付基礎日額 | 原則として「平均賃金」に相当する額 |
| 算定基礎日額 | 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(年3回以下のボーナス)をもとに算定され、「ボーナス特別支給金」の算定につかわれる。 |
社労士受験のあれこれ
労災保険法の誕生
H28.10.14 昭和22年労災保険法施行
労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」と略します。)は、労働基準法と同時に、昭和22年4月に公布され、9月から施行されています。
労災保険法は、労働基準法の「使用者の災害補償義務」を代行する目的で制定されました。
昨日は、大正11年に制定された「健康保険法」のお話をしましたが、当時の健康保険法は、「業務上の事由」による傷病等についても保険給付を行っていました。
しかし、昭和22年に労災保険法が制定され、業務上の事由による傷病等については労災保険法で保護されることになったので、健康保険法から切り離されることになりました。
なお、通勤災害が労災保険法で保護されるようになったのは、昭和48年です。
昭和20年代と比べ交通事情が変わり、通勤途上に労働者が災害を被ることが増えてきたからです。
では過去問です。
<社保一般常識H18年選択>
ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、< A >の給付から業務上災害がのぞかれ、< B >も事業主責任の分離を行ったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった。

<解答>
A 健康保険 B 厚生年金保険
社労士受験のあれこれ
ひっかけ問題(引っかかってはいけない)
H28.10.3 シリーズひっかけ(労災・遺族(補償)給付)
さて、次の問題を解いてみてください。
<平成13年出題>
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

<解答> ×
「生計維持関係」が必要なのは遺族補償年金(遺族年金)で、遺族補償一時金(遺族一時金)は「生計維持関係」がなくても支給されることがあります。
問題文の「遺族補償給付」という表現に注目してください。「給付」には、「年金」と「一時金」の両方が含まれます。
問題文が「遺族補償年金」なら「○」です。
ポイント!
| 遺族(補償)給付 | 遺族(補償)年金 (生計を維持していた者に限る) |
| 遺族(補償)一時金(生計を維持していた者に限られない) |
社労士受験のあれこれ
平成28年度選択式を解きました。その2(労災、雇用編)
H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~
平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。
本日は、労災保険法と雇用保険法です。
なお、労基・安衛編はコチラからどうぞ
→ H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
<労災保険法>
【A】と【B】
療養(補償)給付は、原則は療養の給付(現物給付)ですが、例外的に療養の費用の支給(現金支給)が行われる、ということで【A】は答えやすいと思います。
【B】は支給制限からの問題です。
過去の選択式では平成12年と平成15年に出題されています。また、択一式でも支給制限は頻出項目です。
特に選択式は、1回出ると、同じ個所は出ないだろうと思ってしまいがちですが、意外と同じ個所からの出題が繰り返されていますね。
当サイトでも解説しています。→H28.6.24 金曜日は横断 給付制限(労災保険編)
【C】、【D】、【E】
脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準からの出題です。
「異常な出来事」、「短期間の過重業務」、「長期間の過重業務」をテーマとして、平成22年に択一式で出題されています。
過去問対策をきっちりされた方には解きやすかったと思います。
<雇用保険法>
【A】、【B】、【C】
目的条文からの出題です。
目的条文は、平成22年の選択式でも出題されています。(やはり繰り返されていますね。)
当サイトでも直前対策として目的条文を取り上げました。
コチラ → H28.8.1 目的条文のチェック(労働編)
【D】
移転費の額についての出題です。
平成23年に次のような問題が出題されています。
「移転費の額は、受給資格者等が住所又は居所を変更するに当たり、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かによって、異なることはない。」
答えは「×」で、その者により生計を維持されている同居の親族を随伴するか否かで移転費の額が変わることがポイントになる問題でした。
選択肢の⑨と⑩で迷ったかもしれませんね。ちょっと細かい個所からの出題でした。
【E 】
国庫負担については平成15年と平成24年の選択式で出題されていて、択一式でもよく出るところなので、しっかり勉強された方が多いと思います。
ただし、過去問をみても、広域延長給付を取り上げた出題は無かったように思います。
でも、「あ!テキストに書いてあった」とピンときた方も多かったのではないでしょうか?
次回は、一般常識です。
社労士受験のあれこれ
【直前】「労災保険法」の選択対策
H28.8.16 直前!「労災保険法」の選択対策
本試験は、8月28日。まだ、時間はあります!
あれこれ手を広げるよりも、基本をしっかり復習して迷いをなくしましょう。
今日は労災保険法の選択問題です。
①<年金給付基礎日額>
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。
1 算定事由発生日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の< A >以前の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。
2 算定事由発生日の属する年度の< B >以後の分として支給する年金たる保険給付については、第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の< C >(当該月が4月から7月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の< D >(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。)を算定事由発生日の属する年度の< D >で除して得た率を基準として< E >が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。
②<特別加入者>
中小事業主等の特別加入者の給付基礎日額は、最低< F >円から最高< G >円の範囲(16階級)のうちから定める。

<解答>
①<年金給付基礎日額>
A 翌々年度の7月 B 翌々年度の8月 C 前年度 D 平均給与額 E 厚生労働大臣
※算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前 → スライド適用なし
第8条の規定による給付基礎日額 = 年金給付基礎日額
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後 → スライド率がかかる
第8条の規定による給付基礎日額×スライド率 = 年金給付基礎日
②<特別加入者>
F 3,500 G 25,000
※ ちなみに家内労働者等の下限は2,000円です。この問題では、「中小事業主等」の給付基礎日額の範囲が問われています。迷わないでくださいね。
特別加入者の給付基礎日額は、特別加入者本人の選択に基づきます。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(労基・安衛・労災・雇用)
H28.8.1 目的条文のチェック(労働編)
いよいよ8月です!
8月の頑張りが、結果につながります。
最後まで一緒に頑張りましょう!!!
今日は目的条文のチェック(労働編)です。
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、< A >と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< B >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な< A >を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の< B >の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の< C >に寄与することを目的とする。
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が< A >場合に必要な給付を行うことにより、労働者の< B >及び雇用の安定を図るとともに、< C >を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の< D >に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< E >を図ることを目的とする。

<解答>
【労働基準法】
(第1条 労働条件の原則)
① 労働条件は、労働者が<A 人たるに値する生活>を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、<B この基準>を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その<C 向上>を図るように努めなければならない。
【労働安全衛生法】
(第1条 目的)
この法律は、<A 労働基準法>と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び<B 自主的活動>の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、<C 快適な職場環境>の形成を促進することを目的とする。
【労働者災害補償保険法】
(第1条 目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な<A 保険給付>を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の<B 社会復帰>の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の<C 福祉の増進>に寄与することを目的とする。
ここもポイント!
「労働安全衛生法」と「労災保険法」の目的条文の比較
安全と○○
→ こちらの記事をどうぞ! H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)
【雇用保険法】
(第1条 目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が<A 自ら職業に関する教育訓練を受けた>場合に必要な給付を行うことにより、労働者の<B 生活>及び雇用の安定を図るとともに、<C 求職活動>を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の<D 職業の安定>に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の<E 福祉の増進>を図ることを目的とする。
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その2
H28.7.29 金曜日は横断 (不服申し立て その2)
金曜日は「横断」です。
今週は、「不服申し立ての横断整理その2」で、テーマは「処分の取消しの訴え」です。
その1はこちら → 「審査請求」と「再審査請求」の期限
厚年一元化に伴う改正点はこちら → H28.7.25 月曜日は厚生年金保険改正個所の練習問題
※雇用保険の解答を修正しました。(H28.8.1)
では問題です。空欄を埋めてください。
【労災保険法】
保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての< >に対する< >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
【健康保険法】
ⅰ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
ⅱ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
Ⅲ < A >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<A>に入るのは次のどちらでしょう?
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分
【国民年金法】
ⅰ 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ ⅰに規定する処分(< B >(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<B>に入るのは次のどちらでしょう。
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)
② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分
【厚生年金保険法】
ⅰ 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
ⅱ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
ⅲ < C >の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
◆◆<C>に入るのはどちらでしょう?
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分
② 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分

【解答】
【労災保険法】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<労働者災害補償保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、労働者災害補償保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
【雇用保険法】
確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴えは、当該処分についての<審査請求>に対する<雇用保険審査官>の決定を経た後でなければ、提起することができない。
★「①確認、②失業等給付に関する処分、③不正受給に係る失業等給付の返還命令若しくは納付命令の処分の取消しの訴え」をするには、雇用保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、労働保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
※審査請求と雇用保険審査官が入れ替わっていましたので訂正しました。(H28.8.1)
【健康保険法】
<A>には、「① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることが可能です。
【国民年金法】
<B>には、「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分」が入ります。
★「① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)」について処分取消しの訴えをするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「② 保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分」については、社会保険審査官に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
【厚生年金保険法】
<C>には、「① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分」が入ります。
★ 「厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴え」をするには、社会保険審査官への審査請求を経ることが必要です。
なお、社会保険審査会へ再審査請求をする、しないは任意です。
★ 「厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分」については、社会保険審査会に審査請求をしないで、処分取消しの訴えをすることも可能です。
社労士受験のあれこれ
【横断】不服申し立て その1
H28.7.22 金曜日は横断 (不服申し立て その1)
金曜日は「横断」です。
今週から、「不服申し立て」の横断整理に入ります。(何回かに分けてUPします。)
今週は、「審査請求」と「再審査請求」の期限を整理しましょう。
以下の問題の空欄を埋めてください。
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して < >を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して< >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から< >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して< >を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
<参考>
次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
| 1 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合審査会 |
| 2 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合審査会 |
| 3 第4号厚生年金被保険者 | 日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 |

<解答>
【労災保険法】
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 保険給付に関する決定について審査請求をしている者は、審査請求をした日から <3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【雇用保険法】
① 確認、失業等給付に関する処分又は不正受給に係る返還命令等の規定による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して <3カ月>を経過したときはすることができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)
③ 審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して<3カ月>を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 労働保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(労働保険審査官及び労働保険審査会法第38条)
【健康保険法】
① 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の規定による審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
【国民年金法】
① 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行つた障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
【厚生年金保険法】
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定(訂正請求に対する措置)による決定については、この限りでない。
② 審査請求は、原処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
③ 審査請求をした日から<2カ月>以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
④ 社会保険審査会に対する再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して<2カ月>を経過したときは、することができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第32条)
⑤ 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促及び滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑥ ⑤の社会保険審査会に対する審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときは、することができない。
⑦ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
⑧ 脱退一時金に関する処分に対する審査請求は、脱退一時金に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して<3カ月>を経過したときはすることができない。(社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条)
ポイント!
★労災保険・雇用保険・健康保険・国民年金・厚生年金保険 <共通>
審査請求 → 3カ月
再審査請求 → 2カ月
★労災保険・雇用保険
棄却したものとみなす → 3カ月
★健康保険・国民年金・厚生年金保険
棄却したものとみなす → 2カ月
社労士受験のあれこれ
労災保険法<支給制限と費用徴収>
H28.7.21 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(労災保険)
◆ 例えば、「労働者」が「故意に」事故を生じさせた場合は、「保険給付は行わない」。(労働者に非があるので労働者の保険給付が制限される→労働者にペナルティ)
※ 保険給付の支給制限についてはコチラの記事もどうぞ
◆一方、例えば「事業主」が「故意又は重大な過失により」生じさせた業務災害の原因である事故は、「保険給付に要した費用の全部又は一部を事業主から徴収することができる」。
(非は事業主にあるので労働者の保険給付は通常通り行われ、事業主にペナルティが課せられる。)
※ 事業主からの費用徴収についてはこちらの記事もどうぞ
◆「特別加入者」も注意。
例えば、「保険料の滞納中の事故」は労働者の場合は「事業主から費用徴収」となるが、特別加入者の場合は「支給制限」が行われる。
では、次の過去問を解いてみましょう。
問題①H14年出題
事業主が故意又は重大な過失により保険関係の成立に係る届出を怠っている間に生じた事故については、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
問題②H14年出題(問題文変えています)
事業主が故意又は重大な過失より一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故については、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
問題③H14年出題
特別加入保険料が滞納されている期間中に当該特別加入者について生じた事故に係る保険給付については、政府は、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
問題①H14年出題 ×
事業主にペナルティが課されるパターンです。
保険給付の支給制限ではなく、事業主から費用徴収が行われます。
問題②H14年出題 ×
①と同様、保険給付の支給制限ではなく、事業主から費用徴収が行われます。
問題③H14年出題 ○
<特別加入者の場合>
以下の場合は、「保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。」(事業主からの費用徴収ではないことに注意)
①特別加入保険料が滞納されている期間中に生じた事故
②業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じた場合
→ ②は中小事業主等の特別加入者のみ
社労士受験のあれこれ
【横断】時効(労働編)
H28.7.1 金曜日は横断 時効(労働編)
金曜日は「横断」です。
今週は、労働基準法、労災保険法、雇用保険法の「時効」を横断的に整理しましょう。
労災保険法は、時効の起算日や時効が関係ないものをおさえることもポイントです。
【労働基準法】
① この法律の規定による賃金(< A >を除く。)、災害補償その他の請求権は < B >年間、この法律の規定による< A >の請求権は< C >年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
【労災保険法】
② H13年出題
障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
② H16年出題
療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける権利については療養の必要が生じたときから、療養の費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出した日の翌日から、時効が進行する。
③ H18年出題
休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
④ H18年出題
障害補償給付を受ける権利は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
【雇用保険法】
⑤
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、3年を経過したときは、時効によって消滅する。

<解答>
【労働基準法】
① A 退職手当 B 2 C 5
【労災保険法】
② H13年出題 ×
障害補償一時金、遺族補償一時金の時効は5年です。
★覚え方のポイント
「障害」「遺族」と名の付く給付(年金、一時金、差額一時金)の時効は5年。
ただし、障害も遺族も「前払一時金」の時効は2年。
② H16年出題 ×
療養の給付は現物給付なので、時効は関係ないので×です。
療養の費用の支給を受ける権利の時効は、「療養の費用を支出した日の翌日」から起算して2年です。
③ H18年出題 ×
休業補償給付を受ける権利の時効は、「当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から」2年です。
④ H18年出題 ○
障害補償給付は、「治ゆ」したときに支給される給付なので、時効の起算日も、「当該傷病が治って障害が残った日の翌日」から起算します。
ここもチェック!
★傷病(補償)年金は、政府の「職権」で支給決定されるので、時効はありません。
傷病(補償)年金の時効についてはコチラの記事(4月3日UP)をどうぞ。
【雇用保険法】
⑤ ×
失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利の時効は2年です。
社労士受験のあれこれ
全部?全部又は一部?一部?(労災・給付制限)
H28.6.24 金曜日は横断 給付制限(労災保険編)
先日は、健康保険法の給付制限の記事をUPしました。
5月5日の記事です。コチラ → 全部?全部又は一部?一部?(健保・給付制限)
今日は労災保険法です。健康保険法と比較してくださいね。
では過去問でチェックしましょう。
【問題① H15年選択式】
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うこと等を目的としており、労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< A >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
行政解釈によれば、この場合における故意とは<B >をいう。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は<C >行為を思いとどまる精神的な抑制力が阻害されている状態で<C >が行われたと認められる場合には、<B >には該当しない。
労働者が故意の<D >若しくは重大な<E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
① 逸脱 ② 意図的な恣意 ③ 違法行為 ④ 主な原因 ⑤ 過失 ⑥ 間接の原因 ⑦ 危険行為 ⑧ 結果の発生を意図した故意 ⑨ 結果の発生を意図しない故意 ⑩ 錯乱 ⑪ 自殺 ⑫ 自暴自棄 ⑬ 重大な故意 ⑭ 直接の原因 ⑮ 犯罪行為 ⑯ 非行 ⑰ 不正 ⑱ 法令違反 ⑲ 未必の故意 ⑳ 有力な原因
【問題② H17年出題】
労働者又は労働者の遺族(遺族となるべき者を含む。)を故意または重大な過失により死亡させた遺族は、遺族補償給付若しくは遺族給付又は葬祭料若しくは葬祭給付を受けることができない。
【問題③ H20年出題】
労働者がその過失により負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合においても、その過失が重大なものでない限り、その保険給付の支給制限は行われない。
【問題④ H17年出題】
常時又は随時介護を要する状態にある労働者の障害が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたものであるときは、政府は、介護補償給付又は介護給付の全部又は一部を支給しないこととしている。
【問題⑤ H24年出題】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

<解答>
【問題① H15年選択式】
A ⑭ 直接の原因 B ⑧ 結果の発生を意図した故意 C ⑪ 自殺 D ⑮ 犯罪行為 E ⑤ 過失
| 保険給付を行わない(絶対的支給制限) | 故意 |
| 保険給付の全部又は一部を行わないことができる(相対的支給制限) | ・故意の犯罪行為 ・重大な過失 ・正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない |
健康保険法と比較してみましょう
健康保険法では
◆「自己の故意の犯罪行為又は故意」 → 保険給付を行わない(絶対的給付制限)
◆「正当な理由なしに療養に関する指示に従わない」 → 保険給付の一部を行わないことができる(★全部又は一部ではない)
【問題② H17年出題】 ×
遺族補償給付(遺族給付)の対象となる遺族としない、と規定されているのは「故意に死亡させた者」です。「重大な過失により死亡させた者」には適用されません。
また、葬祭料若しくは葬祭給付は、欠格規定の対象ではありません。
【問題③ H20年出題】 ○
「単なる過失」と「重大な過失」は扱いが違うので注意しましょう。
よくひっかけてくるポイントです。
【問題④ H17年出題】 ×
<相対的支給制限の対象>になる保険給付
| 故意の犯罪行為・重大な過失 | 休業補償給付(休業給付)、傷病補償年金(傷病年金)、障害補償給付(障害給付) |
| 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わない | 休業補償給付(休業給付)、傷病補償年金(傷病年金) ※「療養」なので障害(補償)給付は入りません。 |
・支給制限の対象は、傷病や障害に対する「所得補償」に当たる保険給付です。介護補償給付(介護給付)は、支給制限の対象となりません。
ここもポイント!
<絶対的支給制限の対象>
「故意」の場合は「保険給付は行わない」(絶対的支給制限)と規定されています。故意の場合は、業務や通勤との因果関係が成立しないので、全ての保険給付が支給制限の対象です。ですので、「故意に傷病等の原因となった事故を生じさせた場合」は介護補償給付(介護給付)の支給は行われません。
【問題⑤ H24年出題】 ×
保険給付を受ける者が行政庁の命令に従わないときは保険給付の支払を「一時差し止めることができる」です。
<一時差し止め>
・ 正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出(年金受給権者の定期報告等)をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき
・ 報告・出頭命令、受診命令に従わないとき
<ちなみに、健康保険法では>
「保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。」とされています。
社労士受験のあれこれ
国・地方公共団体の扱い
H28.6.17 金曜日は横断 (国・地方公共団体の扱い)
金曜日は横断です。
国・地方公共団体の扱いについて過去の出題ポイントを集めました。
【労災保険法】
① H11年記述
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業や< A >の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)については、適用されない。
② H20年出題
労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)には適用されないが、独立行政法人(行政執行法人を除く。)の職員には適用される。
【雇用保険法】
③ H22年出題
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、いかなる場合も適用事業とならない。
④ H27年出題
国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する者として国の事業に雇用される者のうち、離職した場合に法令等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められる者は、雇用保険の被保険者とはならない。
【健康保険法】
⑤ H14年出題
健康保険法の適用される法人の事業所には、市町村等の地方公共団体を含まない。
⑥ H20年出題
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。
【厚生年金保険法】
⑦
適用事業所に使用される70歳未満の者であっても、その者が私立学校教職員共済制度の加入者であるときは、厚生年金保険の被保険者とはならない。

<解答>
【労災保険法】
① H11年記述 A 官公署
労働者を1人でも使用する事業は業種関係なく原則として労災保険法の適用事業となります。
ただし、国の直営事業(現在当てはまる事業はありません)、官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く。)= 非現業の官公署のことは、労災保険法から除外されています。国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法で保護されるからです。
さらにポイント!
都道府県、市町村の現業部門は、労災保険法上では適用除外になっていませんが、「常勤職員」は地方公務員災害補償法の規定で労災保険法の適用が除外されています。
また、都道府県、市町村の現業部門の「非常勤職員」は、地方公務員災害補償法の適用が受けられないので、労災保険法の適用を受けることになります。
さらにさらにポイント!!
労災保険法は「国」の事業は全面的に適用除外ですが、「都道府県、市町村」の事業の場合は、「現業部門の非常勤職員」に労災保険法が適用されます。
労働保険徴収法で「二元適用事業」になるのは、「都道府県及び市町村の行う事業」で、国の行う事業は二元適用事業にはなりませんよね。「国」の行う事業は、そもそも労災保険が成立することがないからです。
② H20年出題 ○
行政執行法人の職員 → 国家公務員災害補償法が適用され、労災保険法は適用除外
行政執行法人以外の独立行政法人の職員 → 労災保険法適用
【雇用保険法】
③ H22年出題 ×
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業は、原則として雇用保険法の適用事業です。
④ H27年出題 ○
国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業には雇用保険が適用されます。しかし、公務員が離職した場合は、法令、条例、規則等で確実な保障が設けられているため、その諸給与の内容が、求職者給付、就職促進給付の内容を超えると認められ、一定の要件を満たした者は、雇用保険の適用は除外されます。
<適用除外されるもの>
■国又は行政執行法人の事業に雇用される者(非常勤職員で国家公務員退職手当法の規定により職員とみなされないものを除く。)
■都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
■市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
ポイント!
「都道府県等」と「市町村等」は、雇用保険の適用除外の「承認を受けること」が要件です。
【健康保険法】
⑤ H14年出題 ×
国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所に含まれます。
⑥ H20年出題 ×
先ほどの問題でも勉強したように、国、地方公共団体の事業所も強制適用事業所です。そして、国や地方公共団体に使用される者は、健康保険法上適用除外になっていないので、法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となります。
ただし、健康保険法第200条(共済組合に関する特例)で、「共済組合の組合員に対しては、この法律による保険給付は行わない」と規定されているため、実際は健康保険給付の保険給付(保険料の徴収も)は行われません。
<まとめ>
共済組合の組合員(国家公務員、地方公務員)は適用除外されていないため、健康保険法の被保険者となります。ただし、保険給付は行われないし、保険料も徴収されません。
私立学校教職員共済制度の加入者も同じ扱いです。
【厚生年金保険法】
⑦ ×
私立学校教職員共済制度の加入者は厚生年金保険の第4号厚生年金被保険者となります。
◆厚生年金保険の被保険者は4種類
1.2.から4.までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者 → 第1号厚生年金被保険者
2.国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第2号厚生年金被保険者
3.地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 → 第3号厚生年金被保険者
4.私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者 → 第4号厚生年金被保険者
社労士受験のあれこれ
書類の保存期間 2年3年4年5年
H28.6.10 金曜日は横断 書類の保存期間
書類の保存期間は2年、3年、4年、5年、それ以外と各法律さまざまです。
でも、覚えておけば得点できます。どんどん覚えましょう。
では、過去問をどうぞ。
① 労働基準法(H22年出題)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
② 労働安全衛生法(H22年出題)
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する特別の安全衛生教育を行わなければならないが、その業務に関する特別の安全衛生教育を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、3年間保存しておかなければならない。
③ 労働安全衛生法(H19年出題)
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。
④ 労働安全衛生法(H21年出題)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
⑤ 労災保険法
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)を、その完結の日から2年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題)
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては4年間)保管しなければならない。
⑦ 徴収法(H19年出題)
事業主もしくは事業主であった者又は労働保険事務組合もしくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しなければならない。
⑧ 徴収法(H22年出題)
労働保険事務組合が備え付けておく雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の保存期間は4年である。
⑨ 健康保険法(H22年出題)
事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より5年間保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題)
事業主は、厚生年金保険法に関する書類のうち、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、その完結の日から5年間、保険料に関するものは、その完結の日から2年間、保存しなければならない。

【解答】
① 労働基準法(H22年出題) ○
ポイント
・ その他労働関係に関する重要な書類 → タイムカード等の記録、残業命令書等が該当する
・ 企画業務型裁量労働制の実施状況にかかる労働者ごとの記録 → 決議の有効期間中+その満了後3年間)
② 労働安全衛生法(H22年出題) ○
・ 雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育、職長教育のうち、保存義務があるのは特別教育のみ。
・ 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の議事で重要なものに係る記録も保存期間は3年
③ 労働安全衛生法(H19年出題) ○
④ 労働安全衛生法(H21年出題) ○
・ 保存期間が5年のもの → 健康診断個人票、面接指導の結果の記録(長時間労働、ストレスチェック)
⑤ 労災保険法 ×
2年間ではなく、3年間保存しなければならない。
⑥ 雇用保険法(H25年出題) ○
・ 雇用保険に関する書類(雇用保険二事業及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。) → 2年間
・ 被保険者に関する書類 → 4年間
⑦ 徴収法(H19年出題) ×
⑧ 徴収法(H22年出題) ○
・ 労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類 →その完結の日から3年間
・ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 → 4年間
ポイント
・ 労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿もおさえておきましょう。
① 労働保険事務等処理委託事業主名簿
② 労働保険料等徴収及び納付簿
③ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
①と②は3年間、③は4年間保存
⑨ 健康保険法(H22年出題) ×
5年間ではなく「2年間」保存しなければならない。
⑩ 厚生年金保険法(H20年出題) ×
厚生年金保険法に関する書類 → その完結の日から2年間保存
健康保険法と同じなのでおぼえやすいです。
二次健康診断等給付のまぎらわしいところ
H28.6.2 木曜日はまぎらわしいところをチェック!(二次健康診断等給付)
二次健康等給付には、①二次健康診断と②特定保健指導の二つがあります。
二次健康診断等給付の規定自体はそれほど難しくありませんが、なかなか覚えにくい箇所があります。
今日は、そんなところをチェックしていきます!
では、平成21年の問題から。
(H21年出題)
二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、その請求は、一次健康診断の結果を知った日から3か月以内に行わなければならない。
【解答】
答は「×」です。一次健康診断の結果を知った日から3か月以内ではなく、一次健康診断を受けた日から3か月以内です。
<まぎらわしいところ一覧表・請求関係>
| 請求期限 | 一次健康診断を受けた日から | 3か月以内 |
| 事業者へ結果を証明する書類の提出 | 二次健康診断の実施の日から | 3か月以内 |
| 医師からの意見聴取 | 書面が事業者に提出された日から | 2か月以内 |
※ ちなみに、事業者へ結果を証明する書類の提出の期限(3か月)と、医師からの意見聴取の期限(2か月)は、労働安全衛生法の「自発的健康診断」の規定と同じです。
<まぎらわしいところ一覧表・時効関係>
二次健康診断等給付の時効は2年 ちなみに、 時効が問題になるのは「特定保健指導」 なぜなら、二次健康診断等給付は、一次健康診断を受けた日から3か月以内に請求しないといけないので。 | 一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 |
※ 「請求期限の起算日」と「時効の起算日」を間違えないようにしてくださいね。
それでは次の問題も解いてみましょう。
(H16年出題)
二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労災保険法第26条の定める検査において異常な所見があると診断された日の属する月の翌月の初日から進行する。
【解答】
答は「×」です。一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行します。
社労士受験のあれこれ
遺族(補償)給付と生計維持(労災保険)
H28.5.27 遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の大きな違い
労災保険の遺族(補償)給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」があります。
早速ですが、次の問題を解いてみてください。
① H17年出題
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
② H25年出題
労働者が業務災害により死亡した場合、その祖父母は、当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】
① H17年出題 ○
遺族(補償)年金の受給者となるには、死亡労働者との間に「生計維持関係」があったことが大前提です。
② H25年出題 ○
遺族(補償)一時金は、死亡労働者との間に生計維持関係がなかった者でも受給できる可能性があります。
★遺族(補償)一時金を受けるべき遺族の順序は、配偶者は生計維持関係の有無を問わず1位で、兄弟姉妹は生計維持関係の有無を問わず最後ですが、子、父母、孫、祖父母は、生計維持関係があった方が優先です。

では、次の問題も解いてみてください。
③ H13年出題
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

【解答】
③ H13年出題 ×
冒頭の「遺族補償給付」に注意してください。
遺族補償給付には年金と一時金があります。
「遺族補償年金」としてなら正しい文章ですが、「遺族補償一時金」の場合は、生計維持関係がなくても支給される可能性があります。
典型的なひっかけ問題ですので、「給付」なのか「年金」なのか「一時金」なのかはしっかりチェックしてください。
社労士受験のあれこれ
厚生年金と労災保険 併給調整その3
H28.5.26 厚年「障害手当金」と労災保険の保険給付
社会保険と労災保険の調整のルールを2回お話ししました。
第1回目はコチラ → 同一事由で国年・厚年と労災保険から給付を受けられるとき
第2回目はコチラ → 第30条の4の障害基礎年金と労災保険の調整
★第3回目は、厚生年金保険法の「障害手当金」と労災保険の障害(補償)給付等の併給調整についてです。
まず、厚生年金保険法をチェックしてみましょう。
障害の程度を定めるべき日において次の①~③のいずれかに該当する者には、障害手当金の支給要件を満たしていても、障害手当金は支給されません。
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③ 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者

③に注目してください。
同じ傷病が原因で、労働基準法の障害補償、労働者災害補償保険法の障害(補償)給付を受ける権利がある場合は、障害手当金は支給されない、と規定されています。

では、次の過去問を解いてみましょう。
H25年出題(厚年)
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。

【解答】×
労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者にも、支給されません。

ついでにここもチェック
先ほどの①と②についてもついでに見ておきましょう
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
→ 厚生年金保険の年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)の受給権者には障害手当金は支給しない、ということ。
<例外> 障害厚生年金の受給権者でも、最後に障害状態に該当しなくなってから3年経過している者には、要件に合えば障害手当金が支給される
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
→ 厚生年金保険の年金と同じ考え方。国民年金の年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者には障害手当金は支給しない、ということ。
例外の考え方も同じです。
社労士受験のあれこれはコチラ
国年と労災保険 併給調整その2
H28.5.21 第30条の4の障害基礎年金と労災保険の調整
併給調整その1はこちら → ★
今日は併給調整その2。労災保険法の年金と国民年金の30条の4の障害基礎年金との調整です。
30条の4の障害基礎年金(20歳前に初診日がある障害基礎年金)は、国民年金に加入前の傷病によって支給されるもので、国庫負担の率が高いので、通常の障害基礎年金とは異なる支給停止事由がありましたよね。
確認してみましょう。
国民年金法第36条の2
第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
1 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であつて政令で定めるものを受けることができるとき。
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
3 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。
4 日本国内に住所を有しないとき。
★<原則>上記1号に注目して下さい。
労災保険法の規定による年金を受けることができるときは、労災保険法の年金は全額支給され、「第30条の4の障害基礎年金」は支給停止されます。(同一事由であるかどうかは問われません。)
★<例外>ただし、以下のような例外規定があります。
2 前項第1号に規定する給付(労災保険法の年金)が、その全額につき支給を停止されているときは、同項の規定を適用しない。 → 労災保険法の年金が全額支給停止されているときは、第30条の4の障害基礎年金は支給停止にならず、支給されます。

では過去問を解いてみましょう。
H25年出題(国年)
労働者災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているときは、20歳前傷病による障害基礎年金は支給停止されない。
【解答】 ○
労災保険法の年金が全額支給停止のときは、第30条の4の障害基礎年金は支給されます。

【参考】労災保険法附則第59条、第60条のお話
労災保険法の、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」には「前払一時金」の制度があります。
前払一時金を受けると、一定額までは障害(補償)年金、遺族(補償)年金の支給が停止されます。でも、その場合でも月々の年金をまとめて前払いしているだけで、実際は年金が支給されているのと同じです。
ですので、前払一時金を受けて労災保険の年金が支給停止されている場合は、第30条の4の障害基礎年金は原則どおり支給停止となります。
| 労災保険の年金 | 第30条の4 障害基礎年金 |
| 支給 | 支給停止 |
全額支給停止
| 支給 |
| ※前払一時金を受けたことにより年金が停止される場合 | 支給停止 |
併給調整その3に続きます。
社労士受験のあれこれはこちら
国年・厚年と労災保険 併給調整その1
H28 .5.18 同一事由で国年・厚年と労災保険から給付を受けられるとき
まず、労災保険、国民年金、厚生年金保険の目的を確認してみるとこんな感じになります。
| 労災保険 | 国民年金 | 厚生年金保険 |
業務上・通勤による 負傷、疾病、障害、死亡等 | 老齢、障害、死亡 (業務上外は問わない) | 老齢、障害、死亡 (業務上外は問わない)
|
例えば、民間企業のサラリーマンが業務上や通勤により死亡した場合は、労災保険と国民年金と厚生年金保険から、遺族に対して遺族年金が支給されることになります。が、すべて100%ずつ支給されるわけではありません。
ポイント!
「同一の事由」で労災保険の年金給付と社会保険(国民年金・厚生年金保険)が支給される場合は、労災保険の年金給付が減額されます。
※社会保険は本人が保険料を負担しているので減額するのは問題ありです。一方、労災保険の保険料は全額事業主負担(本人負担なし)なので労災保険の方を減額しましょうという考え方です。
ということでポイントは
| 「同一事由」による労災保険の年金給付と社会保険(国年・厚年)の調整 |
| 労災保険の年金給付 → 減額支給 |
| 社会保険(国年・厚年) → 全額支給 |

では、問題を解いてみましょう!
① H14年出題(労災)
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金又は遺族年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。
② H12年出題(労災)
休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることになる。
③ H12年出題(労災)
労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。
④ H26出題(国年)
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
⑤ H12年出題(国年)
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

【解答】
① H14年出題(労災) ○
「同一の事由」で社会保険(国年・厚年)の年金と労災保険の年金給付が支給される場合は、労災の年金給付が減額調整されるので○です。
なお、国民年金法の寡婦年金も「死亡」によって支給される年金ですので忘れないでくださいね。
② H12年出題(労災) ○
休業補償給付(休業給付)と厚生年金保険法の障害厚生年金又は国民年金法の障害基礎年金が同一事由で支給されることもあり得ます。その場合は、休業補償給付(休業給付)が減額調整されます。
労災保険は年金給付だけでなく、休業補償給付(休業給付)も減額調整の対象ですので押さえてくださいね。
③ H12年出題(労災) ○
労災保険の年金給付が減額調整されるのは「同一事由」の社会保険(国年・厚年)の年金です。老齢厚生年金・老齢基礎年金と同一事由の労災保険の年金給付はありませんので、同時に受ける労災の年金給付も減額調整されません。
④ H26出題(国年) ○
同一事由で、遺族基礎年金と労災保険法の遺族補償年金を受けることができる場合は、労災保険法の遺族補償年金が減額調整され、遺族基礎年金は全額支給されます。
⑤ H12年出題(国年) ○
労災保険の年金給付との調整と間違えないようにしてくださいね。
併給調整その2に続きます!
社労士受験のあれこれはこちら
【横断】「死亡(葬儀等)」の給付
H28.5.15 労災(葬祭料)・健保(埋葬料)比較
死亡したときの給付として、労災保険には葬祭料(葬祭給付)、健康保険には埋葬料(埋葬費)があります。
健康保険の埋葬料は「埋葬」の費用ですが、労災保険の葬祭料(葬祭給付)は、埋葬だけでなく葬式全般の費用を補償するものなので、労災保険の方が手厚い額になります。
では、比べてみましょう。
【労災保険・葬祭料(葬祭給付)】
| 額 | 受給者 | 時効 |
315,000円+給付基礎日額30日分 (最低保障 給付基礎日額60日分) | 葬祭を行う者 | 2年 |
【健康保険・埋葬料、埋葬に要した費用に相当する金額(埋葬費)、家族埋葬料】
| 額 | 受給者 | 時効 | |
| 埋葬料 | 5万円 | 生計を維持していた者であって埋葬を行う者 | 2年 |
| 埋葬費 | 埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用 | 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合 埋葬を行った者 | 2年 |
| 家族埋葬料 | 5万円 (被扶養者が死亡したとき) | 被保険者 | 2年 |

では、過去問を解いてみましょう。
①労災(H12年出題)
葬祭料は、遺族補償給付を受けることができる遺族のうち最先順位の者に支給される。
②労災(H14年出題)
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日の翌日から進行する。
③健保(H25年出題)
死亡した被保険者により生計を維持されていなかった兄弟姉妹は、実際に埋葬を行った場合であっても、埋葬費の支給を受ける埋葬を行った者に含まれない。
④健保(H26年出題)
埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

【解答】
①労災(H12年出題) ×
葬祭料は、「葬祭を行う者」に支給されます。遺族補償給付を受けることができる遺族とイコールになるとは限りません。
②労災(H14年出題) ×
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効→死亡した日の翌日から進行
葬祭料(葬祭給付)は「葬祭を行った」ことに支給されるのではなく、「死亡」したことに対して支給されるからです。
③健保(H25年出題) ×
親族でも、生計を維持されていなかった場合は「埋葬料」の対象にはなりません。が、実際に埋葬を行った場合は、埋葬費の対象になります。
④健保(H26年出題) ○
埋葬料→「死亡」について給付。(実際に埋葬しなくても給付される)
埋葬費→「埋葬を行った」ことについて給付。
時効の起算日も、埋葬料は死亡した日の翌日、埋葬費は埋葬した日の翌日となります。
社労士受験のあれこれはコチラ
業務災害と解雇制限
H28.5.11 業務上の傷病と解雇制限 ~労災保険編~
業務上の負傷、疾病で療養のために休業している間は「解雇できない」こととその例外が労働基準法で規定されていることをお話ししました。
労働基準法では使用者に「災害補償」(業務上の負傷や疾病等について使用者に補償する責任がある)が課せらています。といっても、現実的に使用者が全責任を負うことは経済面からも不可能ですよね。
「労働者災害補償保険」はその点をカバーするために存在する保険です。事業主が労災保険に加入することにより、労働基準法の「災害補償」責任を「労災保険」に代行してもらえるという仕組みです。
災害補償責任は実際は労災保険が代行してくれるため、原則として使用者が労働基準法の災害補償を行うことはありません。
ということは労働基準法の「打切補償」を支払って補償義務を免れるということも実際はないわけです。
そこで、労災保険法では、「打切補償を支払ったとものとみなす」(イコール解雇制限が解除される)という規定が設けられています。条文を確認してみましょう。
第19条
業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
「打切補償を支払つたもの」とみなし、解雇が可能になるという規定です。
打切補償を支払ったとみなされるのは次の2つです。
① 療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合
② 療養の開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合
「3年」がポイント。労働基準法の「打切補償」が認められる時期とリンクしているので押さえておいてくださいね。
あとは、「傷病補償年金」を受けているということは「まだ治っていない」ため、本来は解雇ができない時期だなーというのも意識してください。

では、問題を解いてみましょう。
① H16年出題
休業補償給付又は休業給付の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される。
② オリジナル
傷病年金の支給を受けている労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される。
③ H17年出題
業務上の傷病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法により打切補償を支払ったものとみなされる。

【解答】
① H16年出題 ×
休業補償給付受けていて療養開始後3年を経過しても解雇制限は解除されません。また「休業給付」は通勤災害の場合です。通勤災害の場合はそもそも解雇制限されません。
② オリジナル ×
「傷病年金」は通勤災害の場合です。通勤災害については使用者の補償責任はありませんので、解雇制限も適用されません。
③ H17年出題 ○
キーワードは、「療養の開始後3年」、「傷病補償年金」です。「打切補償を支払ったものとみなされる」と解雇制限が解除されます。
社労士受験のあれこれはこちら
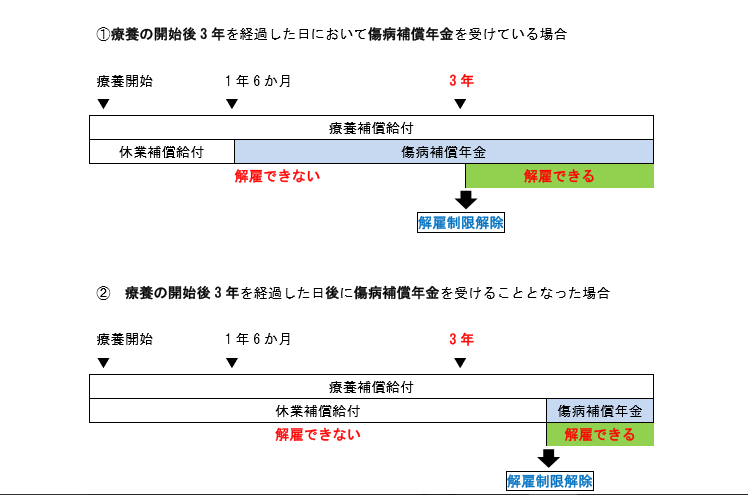
遺族の失権 ~労災保険法~
H28.5.3 子孫兄弟姉妹の失権の時期■労災■
今日は、労災保険の遺族(補償)年金の「子、孫、兄弟姉妹」の失権の時期について、勉強しましょう。
◆◆まず、子、孫、兄弟姉妹について、遺族(補償)年金の受給者になる要件は、労働者の死亡当時「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること」又は「厚生労働省令で定める障害の状態にあること」でしたよね。(労働者の死亡当時、「年齢」か「障害状態」のどちらかに当てはまれば、受給者になるのがポイント)
逆に、この要件に該当しなくなると受給権が消滅することになります。
「子、孫、兄弟姉妹」は次の①②のときに受給権が消滅します。
① 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。
→ 高校卒業の年度末に遺族(補償)年金の受給権は消滅します。ただし、労働者の死亡当時に障害状態にあった場合は、障害状態にある限りは失権しません。
② 厚生労働省令で定める障害の状態にある子、孫、兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)。
→ 障害の状態でなくなっときは、遺族(補償)年金の受給権は消滅します。ただし、障害の状態でなくなっても年齢要件に当てはまる間(高校卒業の年度末まで)は失権しません。

では、次の過去問を解いてみてください。
H23年出題
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する、労災保険法第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあった孫が、その障害の状態がなくなったときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときであっても、消滅する。
【解答】 ×
子、孫、兄弟姉妹は障害状態でなくなったときでも、18歳に達する日以後の3月31日までは失権しません。
比較してみましょう!
国民年金(子)、厚生年金保険(子、孫)の失権はこちらから → ★
社労士受験のあれこれはこちら
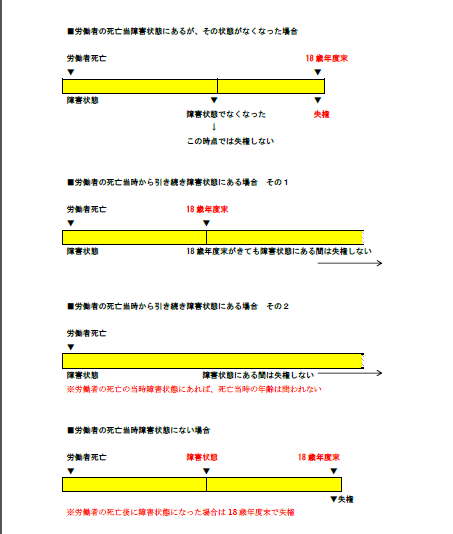
選択式の練習 ~労災保険法~
H28.4.22 事業主からの費用徴収
労災保険法第31条(事業主からの費用徴収)の空欄を埋めてください。
労災保険法第31条(事業主からの費用徴収)
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は A の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
① 事業主が B により徴収法の規定による C を提出していない期間(政府が当該事業について徴収法の規定による認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
② 事業主が徴収法の一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故
③ 事業主が B により生じさせた業務災害の原因である事故
施行規則第44条
法第31条第1項の規定(事業主からの費用徴収)による徴収金の額は、 D が保険給付に要した費用、保険給付の種類、一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。

【解答】
A 船員法 B 故意又は重大な過失 C 保険関係成立届
D 厚生労働省労働基準局長
■■労働者を雇えば、当然に労災保険は成立します。その場合、事業主は成立した日から10日以内に保険関係成立届を提出しなければならないことになっています。
では、もし、事業主が提出期限を過ぎても保険関係成立届をしてなかった場合はどうなるでしょう?(保険関係成立届を提出していないということは保険料も納付していないということです)
事業主が保険関係成立届を提出していなくても労災保険は当然に成立しています。ですので事故があった場合、労働者は労災保険から保険給付を受けることができます。
ただし、故意又は重大な過失で保険関係成立届を提出していなかった事業主には、ペナルティーとして保険給付にかかった費用の全部又は一部を払ってもらいます!ということです。
社労士受験のあれこれはこちら
横断 労災保険法と厚生年金保険法の遺族
H28.4.20 転給 → 労災(有)、厚年(無)
労災保険 遺族(補償)年金 | 厚生年金保険 遺族厚生年金 |
労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 (妻以外の者は、一定の年齢要件又は障害要件に該当すること)
| 被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は入らない) (妻以外の者は、一定の年齢要件に該当すること) (注)H8.4.1前に死亡した者の夫、父母、祖父母の場合は死亡当時一定の障害状態に該当していれば遺族となっていた |
| ○共通点○ 「妻」には、年齢要件も障害要件もつかない | |
「受給資格者」のうち最先順位者が「受給権者」となる。 受給権者が失権した場合、転給の制度がある。(転給=受給資格者の中で受給権が移っていく制度) | 最先順位者のみ受給権を取得。 後順位者は遺族の範囲に入らない。(遺族厚生年金は受けられない。) 転給制度なし。 |
問題を解いてみましょう。
<労災保険法>
①H17年出題
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の年齢要件又は障害要件に該当するものに限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者に限られる。
②H18年出題
遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順である。
<厚生年金保険法>
③H16年出題
夫婦とも被保険者であり、妻が死亡した場合に死亡当時夫婦の収入によって生計を維持されていた障害等級に該当しない18歳未満の子及び60歳以上の母がいる場合、当該子が受給権者となったときは、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日を終了して失権しても、60歳以上の母は受給権者となることはできない。
④H23年出題
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

【解答】
<労災保険法>
①H17年出題 ○
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族(受給資格者)の要件
・ 労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(妻以外は、一定の年齢要件又は障害要件あり)
・ 労働者の死亡の当時生計を維持されていたこと
②H18年出題 ○
受給資格者の内の順位です。
受給資格者の中で最先順位者が受給権者(年金を受ける権利がある者)となります。
例えば、死亡当時生計を維持されていた妻と母(60歳)がいる場合、受給資格者は妻と母の2人です。受給資格者の内の順位は①妻、②母となり、「受給権者」は最先順位の妻となります。
その後、妻の受給権が失権した場合は、次の順位の母に受給権が移ります。このことを転給といいます。
ポイント!
受給資格者のうち、最先順位者が受給権者となります。
<厚生年金保険法>
③H17年出題 ○
死亡当時子と母がいた場合、先順位の子だけが遺族厚生年金の受給権者になり、後順位の母は遺族厚生年金の対象にはなりません。転給の制度もないので、子が失権した後に母が受給権者になることもありません。
④H23年出題 ×
上の③H16年の問題と同じです。死亡当時妻と母がいた場合、妻が遺族厚生年金の受給権者になり、母は遺族厚生年金の対象にはなりません。転給の制度もありませんので、母に受給権が移ることもありません。
ポイント!
厚生年金保険法第59条2項
「父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。」
遺族厚生年金の順位は、①配偶者又は子、②父母、③孫、④祖父母です。
例えば「①配偶者又は子」が受給権を取得したら、②父母③孫④祖父母は遺族厚生年金の対象から外れるということです。
社労士受験のあれこれはこちら
横断 所定労働時間の一部休業
H28.4.18 労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」の違い
所定労働時間の一部を休業した日について、労基「休業手当」と労災「休業(補償)給付」を比べてみましょう。
<労基 休業手当の場合>
・平均賃金 10,000円
・1日の所定労働時間 8時間
【問】使用者の責めに帰すべき事由で労働時間が4時間に短縮された。その日の賃金として実際に労働した4時間分に対する5,000円を支払えば問題ないか?
【答】×間違い
1日の所定労働時間の一部を使用者の責めに帰すべき事由で休業させた場合でも、その日の保障として、平均賃金の100分の60以上を支払う必要があります。問の場合は、平均賃金の100分の60(6000円)と労働分の賃金5000円との差額の1000円をプラスしなければなりません。
<労災 休業(補償)給付の場合>
・ 給付基礎日額 10,000円
・ 1日の所定労働時間 8時間
【問】所定労働時間のうち4時間労働して、4時間が労働不能だった。その日の4時間分の労働に対して5,000円支払われた場合、休業(補償)給付の額は?
【答】休業(補償)給付の額は3,000円
給付基礎日額(10,000円)と労働に対する賃金(5,000円)との差額の60%が支給されます。(10,000円-5,000円)×100分の60=3,000円。
★労働不能だった時間の60%が労災保険から支給されるという考え方です。
| 労基法 休業手当 | 労災保険法 休業(補償)給付 |
使用者は、労働した時間分の賃金+休業分の保障として、平均賃金の100分の60以上は支払わなけばならない。 | 休業(補償)給付として、労働不能分の給付基礎日額の100分の60が支給される |
社労士受験のあれこれはこちら
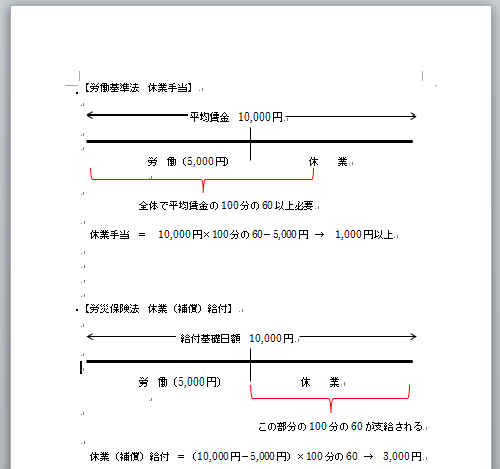
通勤による疾病の範囲
H28.4.7 業務上の疾病の範囲と通勤による疾病の範囲の違い
通勤災害のうち、通勤による疾病の範囲は、「労働者災害補償保険法施行規則」で定められています。
労働者災害補償保険法施行規則第18条の4では、通勤による疾病を次のように定めています。空欄を埋めてください。
通勤による A 疾病その他通勤に起因することの B 疾病とする。

【解答】
A 負傷に起因する B 明らかな
過去問のポイントもチェクしてみましょう。
◇◇平成13年出題
「通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる。」

答えは「×」
通勤による負傷に起因する疾病だけでなく、通勤に起因することの明らかな疾病も通勤による疾病に含まれます。
◇◇平成13年出題
「通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。」

答えは「○」
通勤による疾病は、「厚生労働省令」(さきほど空欄を埋めた労働者災害補償保険法施行規則第18条の4)で定めるものに限られています。
◇◇平成14年出題
「通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が列挙されている。」

答えは「×」
業務上の疾病とは違い、通勤による疾病については、具体的な疾病の種類は列挙されていません。

★ここもポイント★
業務上の疾病の範囲 → 労働基準法施行規則で定められている
・労働基準法施行規則別表第1の2に業務上の疾病が例示列挙されている
通勤による疾病の範囲 → 労働者災害補償保険法施行規則で定められている
選択式の練習 ~労災保険法~
H28.4.6 適用事業・適用除外
労働者災害補償保険法の「適用事業・適用除外」について、次の空欄を埋めてください。
<適用事業及び適用除外>
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、 A 及び B (労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

【解答】
A 国の直営事業
B 官公署の事業
傷病(補償)年金
H28.4.3 保険給付請求権の時効と会計法の時効
労災保険法第42条では、時効について次のように規定しています。
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

労災保険法の保険給付は、原則として、労働者(又は遺族、葬祭を行う者)が、請求することによって行われます。
第42条の時効で消滅するのは、「保険給付を支給決定を受ける権利」(基本権)です。(実体としては請求書の提出期限)
「傷病(補償)年金」は請求ではなく、「職権」で支給決定されるので、42条の時効の問題は生じない、ということでしたよね。

では、政府に保険給付を請求し、政府が支給決定した後はどうなるのでしょう?
支給が決定された保険給付の支払請求権(年金の場合は、支払期月ごとに生ずる支分権)については、労災保険法ではなく「会計法」の規定により5年で時効消滅します。
それでは、次の問題を解いてみましょう。
【H11年出題】
請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(年金の場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)については、労働者災害補償保険法の規定によらず、公法上の金銭債権として会計法第30条の規定が適用されるので、その消滅時効は5年となる。
【H15年出題】
傷病補償年金又は傷病年金は、政府の職権によって支給が決定されるものであるから、これを受ける権利に関して労災保険法では時効について定めていないが、支給が決定された年金の支払期ごとに生ずる請求権については、会計法上の時効の規定が適用される。

<解答>
【H11年出題】 → ○
【H15年出題】 → ○
* 傷病(補償)年金について
基本権 → 時効の定め無し
支分権 → 会計法の規定が適用され5年で時効消滅
「確認」
H28.3.22 健・厚・雇にはあるが、国、労災にはない
厚生年金保険法では、「被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によって、その効力を生ずる」と規定されています。(ただし例外有)
健康保険法、雇用保険法にも「確認」について規定があります。
厚生年金保険法・健康保険法・雇用保険法の共通点は、資格の取得や喪失について、事業主に「届出」が義務づけられている点です。
何月何日に誰が入社して、何月何日に誰が退職したのかをチェックするのが確認です。
一方、「国民年金法」、「労災保険法」には確認の規定はありません。
国民年金法、労災保険法には、資格の得喪について事業主からの届出義務はありませんよね。労災保険は、労働者なら誰でも保護が受けられるので、個人ごとに得喪を届け出る必要はありません。
傷病(補償)年金の手続
H28.3.8 「傷病の状態等に関する届」と「傷病の状態等に関する報告書」
労災保険の保険給付は「請求」にも基づいて行われるのが原則です。ただし、「傷病(補償)年金」は例外で、請求ではなく労働基準監督署長の「職権」で支給決定されます。
労働者側の手続としては、「傷病の状態等に関する届」と「傷病の状態等に関する報告書」があります。どちらも「請求書」という名称ではありませんので注意してくださいね。
■提出のタイミング■
・療養開始後1年6か月を経過した日に治っていないとき
→ 同日以後1か月以内に「傷病の状態等に関する届」を提出する

<傷病(補償)年金の支給要件に該当していない場合> 引き続き休業(補償)給付が支給される

<療養開始後1年6か月を経過した後>
・毎年1月1日から1月31日までの間、休業(補償)給付の請求書に添えて、「傷病の状態等に関する報告書」を提出する
ポイント!
休業(補償)給付、傷病(補償)年金は「治ゆ」するまでの保険給付
傷病(補償)年金の支給決定のタイミングは
①療養開始後1年6か月を経過した日に支給要件に該当するとき
②療養開始後1年6か月を経過した日「後」に支給要件に該当することとなったとき
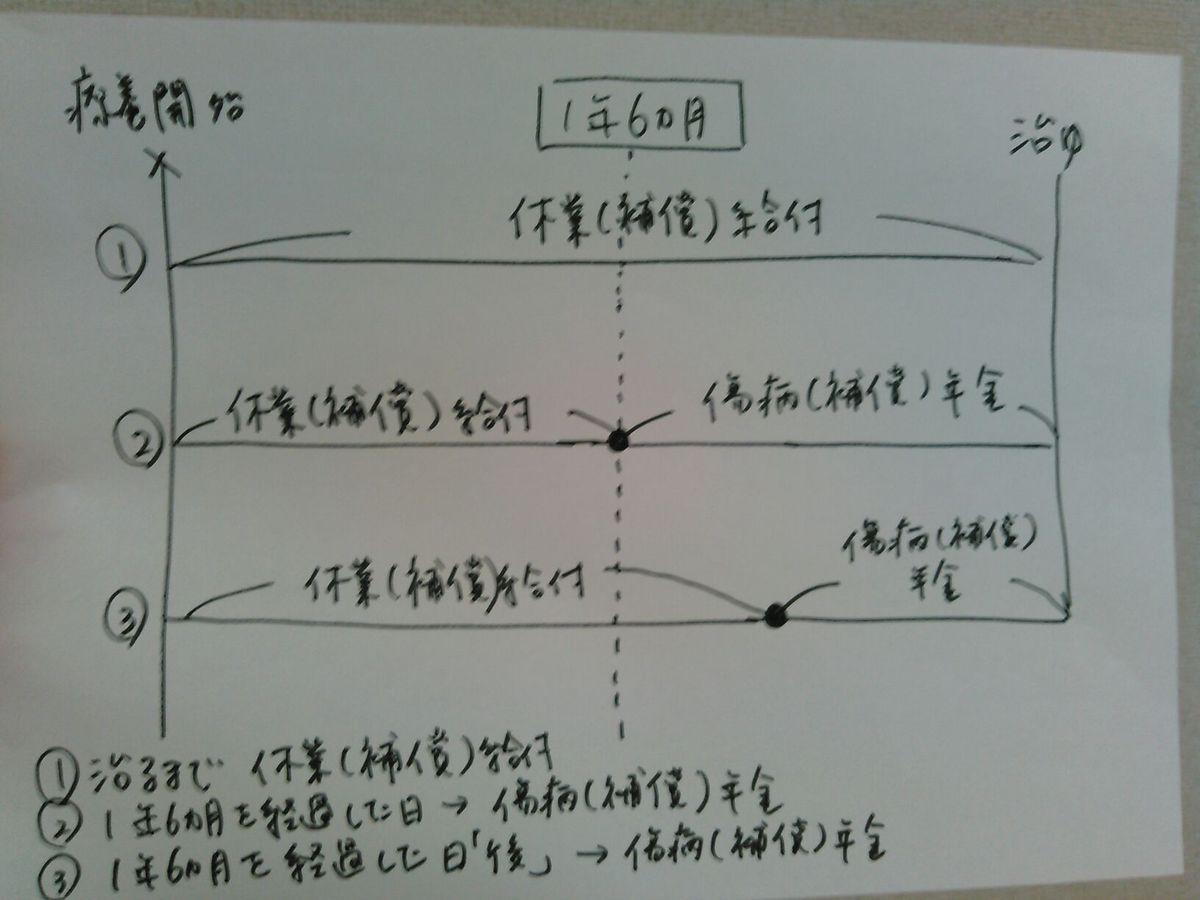
過去問よく出る論点~労災保険法~
H28.3.3 介護(補償)給付のよく出る所
次の問題の正誤を考えてみてください。
<平成21年出題>
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者がその受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

【解答】×
現に介護を受けているだけでは支給されない。厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあって、かつ現に常時又は随時介護を受けていることが条件。
→ 現に介護を受けているだけではダメということ。常時又は随時介護を要する状態にあることも必要。
■条文もチェック ポイントは「かつ」!
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であつて厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
二 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所している間
三 病院又は診療所に入院している間

■厚生労働省令で定める程度のものとは?■
障害等級・傷病等級1級 すべて
障害等級・傷病等級2級 精神神経・胸腹部臓器の障害
さらにポイント
一、二、三に該当する場合は介護(補償)給付は支給されない。
例えば、病院に入院している場合は、十分な介護が提供される。そのため、介護(補償)給付の対象にはならないということ。
療養の費用の支給 ~労災保険法~
H28.2.28 「療養(補償)給付」には療養の給付と療養の費用の支給があるが・・・
労災保険法の「療養補償給付」(通勤災害の場合は「療養給付」)は、原則は「療養の給付」(現物給付)で行われます。
現物給付とは、労災病院や都道府県労働局長が指定する医療機関等で、自己負担なしで治療を受ける方法です。

一方、「療養の費用の支給」は現金給付です。病院等でかかった治療費をいったん立替て支払い、後日かかった費用が払い戻される方法です。
「療養の費用の支給」が行われるのは、次の2点です。
1 療養の給付をすることが困難な場合
2 療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合
「1 療養の給付をすることが困難な場合」とは、「政府側の事情」
*当該地区に指定病院がないなど
「2 療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合」とは、「労働者側の事情」
*最寄りの病院等が指定病院等でないなど
過去問チェック
H28.2.22 労災保険法 第三者行為による事故のポイント
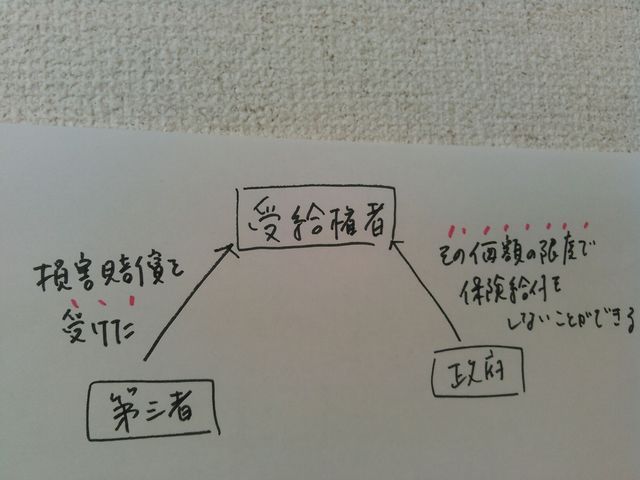
次の二つは、どちらも、第三者行為の事故についての損害賠償と保険給付の調整の問題です。
正誤を考えてみてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【平成18年問7B】
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
【平成15年問5D】
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるときは、政府は、その価額の限度において保険給付をしないことができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】
【平成18年問7B】 ○
【平成15年問5D】 ×
■チェックポイント■
【平成18年問7B】は、 「当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき」(現実に損害賠償を受けた)、【平成15年問5D 】は、「当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けることができるとき」(損害賠償を受けることはできるが、まだ現実に損害賠償を受けていない)
◆◆政府が保険給付をしないことができるのは、「当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき」=現実に損害賠償を受けたときです。
労災保険法 保険給付と特別支給金
H28.2.17 業務上の傷病による休業中に支給されるもの
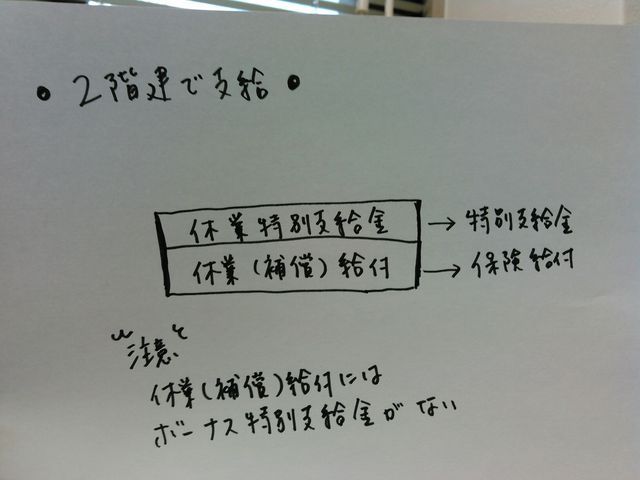
労働者が
・業務上の(又は通勤による)負傷又は疾病による療養のため
・労働することができない
・賃金を受けない日の第4日目から
支給されるものは次の2つです。
1 保険給付として → 休業補償給付(休業給付)
(給付基礎日額の100分の60)
2 特別支給金として → 休業特別支給金
(給付基礎日額の100分の20)
1と2の合計で給付基礎日額の100分の80の給付が行われます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに、「特別加入者」の場合も、休業補償給付(休業給付)と休業特別支給金が支給されます。
※ 特別加入者の場合は、入院などで全部労働不能の状態であることが要件。所得喪失の有無は問われません。
H28.1.24 療養の給付の範囲
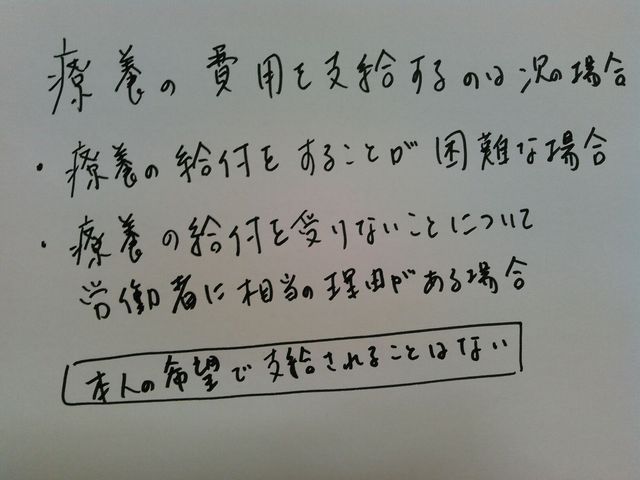
次の文章の空欄をうめてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・療養補償給付は、療養の給付とする。
・療養の給付の範囲は、次の各号( A が必要と認めるものに限る。)による。
1 診察
2 薬剤又は治療材料の支給
3 処置、手術その他の治療
4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6 移送
・政府は、療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解答】 政府
※ 医師、使用者などと間違えないように注意してください。
(さらにポイント)
療養補償給付は、原則は「療養の給付」(現物給付)です。
「療養の費用の支給」(現金給付)は例外です。
H28.1.5 目的条文(労働安全衛生法と労災保険法)
労働安全衛生法と労災保険法の目的条文です。
AとBをそれぞれ埋めてください。
<労働安全衛生法>
この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の A を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
<労災保険法>
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の B の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<解答>
A 安全と健康
B 安全及び衛生
法律の名前は労働安全衛生法ですが、目的として、労働者の安全と「健康」(衛生ではない)を確保することが掲げられています。
逆に、労災保険法の目的条文では、健康ではなく、安全及び「衛生」となっているので、注意しましょうね。