合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
社会保険に関する一般常識「社会保険審査官及び社会保険審査会法」
R8-134 01.05
社会保険審査官及び社会保険審査会法について
今回は、「社会保険審査官及び社会保険審査会法」をみていきます。
・社会保険審査官について
→ 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます
厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が任命します
・社会保険審査会について
→ 厚生労働大臣の所轄の下に置かれます
委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します
審査会は、委員長及び委員5人をもって組織されます
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2年」を経過したときは、することができない。」となります。
(法第4条第2項)
②【R2年出題】
審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。

【解答】
②【R2年出題】 〇
審査請求は、「文書のみならず口頭でも」することができます。
(法第5条第1項)
➂【R7年出題】
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。

【解答】
➂【R7年出題】 〇
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができますが、審査請求の取下げは、「文書で」しなければならないとされています。
(法第12条の2)
④【R2年出題】
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができますが、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限られます。
(法第5条の2)
⑤【R7年出題】
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。

【解答】
⑤【R7年出題】 〇
「審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。」とされています。
(法第12条)
⑥【H29年出題】
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

【解答】
⑥【H29年出題】 ×
「社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。」とされています。
(法第2条)
⑦【R5年出題】
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命じ、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれる。

【解答】
⑦【R5年出題】 〇
社会保険審査官は、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれます。
(法第1条、第2条)
⑧【R7年出題】
社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。

【解答】
⑧【R7年出題】 〇
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織され、合議制です。
(法第20条、第21条)
⑨【R7年出題】
社会保険審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

【解答】
⑨【R7年出題】 〇
社会保険審査会は、「公開審理」が原則です。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができます。
(法第37条)
⑩【R5年出題】
社会保険審査会は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。

【解答】
⑩【R5年出題】 〇
社会保険審査会は、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱います。
また、「審査会の合議は、公開しない。」とされています。
(法第27条、第42条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「介護保険法」
R8-132 01.03
地域包括ケアシステム|地域で包括的な支援・サービスを提供する体制
今回のテーマは「地域包括ケアシステム」です。
さっそく令和7年の問題を解いてみましょう
①【R7年出題】
いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目指している。

【解答】
①【R7年出題】 〇
「「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。」とされています。
(参照:令和6年版厚生労働白書)
②【R7年出題】
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
要介護認定を受けようとする被保険者は、「地域包括支援センター」に、当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされています。
(令和6年版厚生労働白書、介護保険法第27条第1項)
なお、地域包括支援センターは、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」と定義されています。(介護保険法第115条の46第1項)
過去問も解いてみましょう
【令和元年選択式】
介護保険法第115条の46第1項によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、< A >を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
<選択肢>
⑰ その地域における医療及び介護
⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進
⑲ 地域住民との身近な関係性の構築
⑳ 要介護状態の軽減又は悪化の防止

【解答】
<A> ⑱ その保健医療の向上及び福祉の増進
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「国民年金の歴史」
R8-131 01.02
国民年金の歴史|無拠出制・拠出制の実施、基礎年金の導入
年金の学習に欠かせない「国民年金の歴史」をみていきましょう
令和7年の問題を解いてみましょう
【社一R7年出題】
核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに、平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。

【解答】
【社一R7年出題】 ×
基礎年金が導入されたのは、平成元年ではなく、「昭和60(1985)年改正」です。
「当時、我が国の公的年金制度は大きく3種8制度に分立し、給付と負担の両面で制度間の格差や重複給付などが生ずるとともに、産業構造の変化等によって財政基盤が不安定になるという問題が生じていた。このため、全国民共通の基礎年金を創設するとともに、厚生年金等の被用者年金を基礎年金に上乗せする2階部分の報酬比例年金として再編成した。
基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。」とされています。
昭和34(1959)年 | 国民年金法制定 |
昭和34(1959)年11月 | 無拠出制の福祉年金制度の実施 |
昭和36(1961)年4月 | 拠出制の国民年金制度の実施(国民皆年金の実現) |
昭和61(1986)年4月 | 基礎年金の導入(昭和61年4月~新法) |
(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)
過去問をどうぞ!
【国年H19年出題】
国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。

【解答】
【国年H19年出題】 ×
「国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年「10月」でなく「11月」から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。」となります。
なお、「福祉年金」については、「高齢のため受給に必要な加入期間を満たせない人や、すでに障害のある人等に対して、無拠出の老齢福祉年金、障害福祉年金及び母子福祉年金等を支給することとし、その費用は全額国庫で負担することとした。」とされています。
(参照:[年金制度の仕組みと考え方]第4 公的年金制度の歴史 厚生労働省)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」
R8-130 01.01
高齢者医療確保法|子育てを社会全体で支援する~出産育児支援金
まず、令和7年の問題からみていきましょう
【R7年出題】
出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6年(2024)年度から導入することとした。

【解答】
【R7年出題】 〇
・子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みが導入されています。
(令和6年版厚生労働白書より)
◇◇◇もう少し詳しくみていきましょう◇◇◇
① 後期高齢者医療の被保険者は、保険料を負担しています。
「保険料率」の定め方について、条文を読んでみましょう
法第104条第3項(令和8年4月改正) 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、 第117条第2項の規定による拠出金(特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金)及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |
※少子化を克服し、子育てを全世代で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入されています。
②「支援」の流れについて条文を読んでみましょう
★ 後期高齢者医療制度で、保険者(国保・健保組合・協会けんぽ・共済組合)の出産育児一時金の費用の一部を支援するイメージで読んでください。
法第124条の2 (出産育児支援金の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」)は、第139条第1項第3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。 → 第139条第1項第3号の業務 「後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務」 → 「保険者」 全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団 ② 後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。
法第124条の4 (出産育児交付金) ① 支払基金は、出産育児一時金等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 ② ①の出産育児交付金は、支払基金が徴収する出産育児支援金をもって充てる。
法第124条の5 (出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務) ① 支払基金は、第139条第1項第3号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。 ② 保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「船員保険法」
R8-090 11.22
船員保険の行方不明手当金
船員保険法の「行方不明手当金」をみていきましょう
行方不明手当金について条文を読んでみましょう
法第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。
法第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
法第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3月を限度とする。
法第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

【解答】
①【H28年出題】 〇
行方不明手当金は
・被保険者が職務上の事由により行方不明となったとき
・被扶養者に対し支給されます。
・行方不明の期間が1か月未満であるときは、支給されません
・行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません
②【R7年出題】
船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。

【解答】
②【R7年出題】 ×
行方不明手当金の額は1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額です。
➂【H23年出題】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。

【解答】
➂【H23年出題】 ×
行方不明となった日「の翌日」から起算して「3か月」が限度とされます。
④【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】
④【R3年選択式】
<A> 被扶養者
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」
R8-055 10.18
社会保険労務士の業務など
今回は、社会保険労務士法をみていきます。
問題を解きながらポイントをつかみましょう。
では、過去問を解いていきましょう
①【R7年出題】
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2にいう「提出に関する手続を代わつてする」は、法律行為の代理のことをいい、本来事業主が意思決定すべき事項にも及ぶため、代理業務、即ち申告、申請、不服申立等について事業主その他の本人から委任を受けて代理人として事務を処理することが含まれる。

【解答】
①【R7年出題】 ×
「提出に関する手続を代わつてする」=提出手続を代行することは、申請書等の提出手続の際、行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまります。
(昭61.10.1庁保発第40号)
②【R7年出題】
特定社会保険労務士は、男女雇用機会均等法に定める調停手続において紛争当事者の代理人としての業務を行うことができ、調停委員や相手方の当事者への説明、主張、陳述、答弁等のほか、調停案の受諾、拒否もその業務に含まれる。

【解答】
②【R7年出題】 〇
社労士法第2条第1項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務を「紛争解決手続代理業務」といいます。紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限って行うことができます。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」の紛争調整委員会におけるあっせんの手続、「障害者雇用促進法」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「男女雇用機会均等法」、「労働者派遣法」、「育児・介護休業法」、「短時間労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理することは、紛争解決手続代理業務の一つです。(法第2条第1項第1号の4)
また、紛争解決手続代理業務には次の事務が含まれます。(法第2条第3項)
① 第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
➂ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
➂【R7年出題】
社会保険労務士について、社会保険労務士法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や同法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に限り、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
「社会保険労務士会の会員、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会」に限りません。
条文を読んでみましょう
第25条の3の2 (懲戒事由の通知等) ① 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 ② 何人も、社会保険労務士について、法第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒)や法第25条の3(一般の懲戒)に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |
問題文の場合、「適当な措置をとるべきことを求めることができる」のは、「何人も」となります。
④【R7年出題】
社会保険労務士法人の社員には、社会保険労務士でない者もなることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
「社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。」と規定されています。社会保険労務士でない者は、社会保険労務士法人の社員になることはできません。
(法第25条の8第1項)
⑤【R7年出題】
社会保険労務士法人の社員は、第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならないが、自己のためにこれを行うことはできる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
「社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。」とされています。
自己若しくは第三者のためにその属する社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできません。
(法第25条の18第1項)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「確定拠出年金法」
R8-054 10.17
確定拠出年金「個人型年金」のポイント!
確定拠出年金法のポイントをみていきます。
確定拠出年金には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。
今回は、「個人型」を重点的にみていきます。
まず、用語の定義を確認しましょう。
企業型 | 個人型 |
厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する | 国民年金基金連合会が実施する |
「企業型年金加入者」→事業主により掛金が拠出され、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者 | 「個人型年金加入者」→掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者 |
「確定拠出年金運営管理業」→運営管理業務の全部又は一部を行う事業 ①記録関連業務 ②運用関連業務(運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供) | |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

【解答】
①【H21年出題】 ×
個人型年金とは、企業年金連合会ではなく「国民年金基金連合会」が実施する年金制度をいいます。
(法第2条第3項)
②【H30年出題】
第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書を参照している)

【解答】
②【H30年出題】 〇
個人型確定拠出年金の加入者の範囲は、基本的に20歳以上60歳未満の全ての方となっています。(平成29年版厚生労働白書)
「個人型年金加入者」について条文を読んでみましょう。
第62条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。 (1) 国民年金法の第1号被保険者 ※国民年金の保険料を免除されている者は除かれます ただし、障害基礎年金の受給権者であることにより、法定免除の適用を受けている者は加入できます (2) 国民年金法の第2号被保険者(企業型掛金拠出者等は除かれます) (3) 国民年金法の第3号被保険者 (4) 国民年金法の任意加入被保険者(60歳以上65歳未満の者又は20歳以上65歳未満の海外居住者が対象) |
➂【R3年出題】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
➂【R3年出題】 〇
国民年金第3号被保険者も個人型年金加入者となることができます。「国民年金基金連合会」に申し出の部分もポイントです。
(法第62条第1項)
④【R7年出題】
確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
④【R7年出題】 ×
個人型年金加入者となることはできません。
条文を読んでみましょう
法第62条第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、個人型年金加入者としない。 (1) 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者又はその受給権を有する者であった者 (2) 国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有する者 |
⑤【R6年出題】
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
・ 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。
・ 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更します。
(法第68条)
⑥【R7年出題】-
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
個人型年金の給付は、「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」です。
当分の間、「脱退一時金」を請求することができます。
⑦【R7年出題】
確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
国民年金基金連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に「委託することができる」ではなく「委託しなければならない」です。
また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができます。
(法第60条)
⑧【R7年出題】
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
⑧【R7年出題】 〇
個人型年金加入者期間を計算する場合には、「月」によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までが算入されます。
(法第63条)
⑨【R7年出題】
国民年金基金連合会は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。

【解答】
⑨【R7年出題】 ×
個人型年金規約の見直しは、「少なくとも10年ごと」ではなく「少なくとも5年ごと」に必要です。
(法第59条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」
R8-037 9.30
高齢者医療確保法の基本問題を解いてみる
「後期高齢者医療」では、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行います。
事務を処理するため、後期高齢者医療広域連合が設けられています。
条文を読んでみましょう。
法第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 |
※保険料徴収などの窓口業務は、地域住民の身近な存在である市町村が担います。
では、問題を解いてみましょう
①【R7年出題】
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】
①【R7年出題】 ×
都道府県は入りません。
条文を読んでみましょう。
法第48条 後期高齢者医療広域連合及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 |
後期高齢者医療の制度の運営は広域化を図るため、後期高齢者医療広域連合が事務を処理しますが、保険料徴収などの窓口業務は身近な市町村が行っています。
後期高齢者医療広域連合及び市町村は、特別会計を設けなければなりません。
②【R7年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。

【解答】
②【R7年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の者のみではありません。
条文を読んでみましょう。
法第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |
➂【R7年出題】
高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。

【解答】
➂【R7年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合ではなく、「市町村」の条例で定めます。
保険料の徴収の事務は「市町村」が担うことに注意しながら条文を読んでみましょう。
第104条第1項 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるための拠出金及び出産育児支援金並びに感染症の予防及び流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 第105条 市町村は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療に要する費用に充てるため、後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療広域連合の規約で定めるところにより、第99条第1項及び第2項の規定による繰入金並びに保険料その他この章の規定による徴収金(市町村が徴収するものに限る。)を納付するものとする。 第106条 保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。 |
※保険料の徴収の方法には、「特別徴収」=年金から天引きする方法と「普通徴収」=個別に納付する方法があります。
第108条 ① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ➂ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 第109条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。 |
④【R7年出題】
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

【解答】
④【R7年出題】 〇
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。
⑤【R7年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
その日の翌日からではなく、「その日」からその資格を喪失します。
後期高齢者医療の被保険者の資格喪失の時期について条文を読んでみましょう。
法第53条 ① 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日若しくは第50条第2号の状態(65歳以上75歳未満で障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた)に該当しなくなった日又は第51条第2号に掲げる者(後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者)に該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。 ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、第51条第1号(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者)に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「国民健康保険法」
R8-020 9.13
国民健康保険の保険給付「法定」と「任意」
国民健康保険の保険給付には、「法定給付」と「任意給付」があります。
法定給付 | 絶対的必要給付 | 療養の給付など(必須) |
相対的必要給付 | 出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付 ・国民健康保険上、「行うものとする」 ・ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 | |
任意給付 | 傷病手当金の支給その他の保険給付 ・行うことができる (給付を行うかどうか、給付内容は任意) | |
過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「移送費」は法定給付の絶対的必要給付ですので、支給は必須です。
「市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。」と規定されています。
(法第54条の4)
②【R7年出題】
国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。

【解答】
②【R7年出題】 ×
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、「移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する」となります。
③【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は必須ではなく、法定給付の相対的必要給付です。
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、「葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」となります。
(法第58条第1項)
④【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる

【解答】
④【H26年出題】 〇
傷病手当金は「任意給付」です。
傷病手当金の支給を「行うことができる」となります。
(法第58条第2項)
⑤【R1年出題】
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
⑤【R1年出題】 〇
出産育児一時金の支給、葬祭料の支給、葬祭の給付は、法定給付の相対的必要給付です。
(法第58条第1項)
⑥【R7年出題】
国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
→ 出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。
→ 傷病手当金の支給を行うことができる。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和7年選択式(社会保険に関する一般常識)から学ぶ
R8-009 9.02
国年保険料納付状況・高齢者医療確保法・介護保険法・確定給付企業年金法・白書
社会保険に関する一般常識の選択式については、令和7年は、5つのテーマから出題されています。
順番にみていきましょう
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、< A >%となっている。
<選択肢>
① 53.1 ② 68.1 ③ 83.1 ④ 98.1

【解答】
<A> ③ 83.1
今回の問題は、「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」ですが、令和7年6月に「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」が公表されていますので、最新のデータを読んでみます。
「令和6年度の国民年金の加入・保険料納付状況」のポイント!
・第1号被保険者の令和6年度の最終納付率(令和4年度分保険料)は、84.5%となっています。前年度から1.5ポイント増加し、平成24年度の最終納付率(平成22年度分保険料)64.5%から20.0 ポイント増加し、12年連続で上昇しています。
・平成22年1月に発足した日本年金機構では、発足当初60%台であった最終納付率について、80%台の安定的確保とその持続的向上を目指して取組を実施した結果、最高値を更新しています。(3年連続で80%台)
解き方のヒントについて
国民年金の保険料を納付しやすい取り組みが様々行われていること(口座振替やコンビニ納付など)で、納付率を考えてみるとよいと思います。
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
高齢者医療確保法第4条第1項では、「< B >は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
<選択肢>
⑥ 国 ⑦ 後期高齢者医療広域連合 ⑮ 地方公共団体 ⑳ 保険者

【解答】
<B> ⑮ 地方公共団体
高齢者医療確保法では、「国の責務」、「地方公共団体の責務」、「保険者の責務」、「医療の担い手等の責務」が定められています。
「国」の責務のキーワードは、「国民の高齢期における医療」、「関連施策を積極的に推進しなければならない。」です。(第3条)
「地方公共団体の責務」のキーワードは、「住民の高齢期における医療」、「所要の施策を実施しなければならない。」です。(第4条)
「保険者」の責務のキーワードは、「加入者の高齢期における健康の保持」、「高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。」です。(法第5条)
なお、「後期高齢者医療広域連合」は、後期高齢者医療の事務を処理するために、設けられたものです。
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、< C >に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
<選択肢>
⑤ 医療との連携 ⑫ 事業者又は施設との連携 ⑱ 被保険者の心身の状況
⑲ 被保険者の自立した日常生活

【解答】
<C> ⑤ 医療との連携
★介護保険法第2条第2項は、平成20年に択一式でも出題されています。
介護保険法の総則の部分は毎年のように出題されていますので、択一式でも選択式でも対応できるようにしましょう。
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
確定給付企業年金法第60条第2項では、「< D >は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
<選択肢>
⑧ 最低積立基準額 ⑭ 責任準備金の額 ⑯ 積立金の額 ⑰ 積立上限額

【解答】
<D> ⑭ 責任準備金の額
用語の定義を確認しましょう。
法第59条 (積立金の積立て) 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。 法第60条 (積立金の額) ① 積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第3項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。 ② 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 ③ 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 |
■責任準備金は、「今後とも年金制度を継続するとした場合に現在保有しておくべき積立金」です。(継続基準といいます)
■最低積立基準額は、「現時点で年金制度を終了させるとした場合に加入者等の給付を賄うことのできる積立金」です。(非継続基準といいます)
(参考 厚生労働省「確定給付企業年金の積立基準について」)
 【R7年選択式】
【R7年選択式】
令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「< E >」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
<選択肢>
⑨ 資産所得倍増プラン ⑩ 生涯現役計画 ⑪ 所得倍増プラン
⑬ 人生100年計画

【解答】
<E> ⑨ 資産所得倍増プラン
(令和6年厚生労働白書)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
当日の最終チェック
R7-361 8.24
いよいよ当日です!社一の第1条をチェックします
当日です! 100%の力が発揮できるよう、祈っています。 一つずつ、落ち着いて取り組んでくださいね。 応援しています! |
社一の法律の第1条を総ざらいしましょう。
★国民健康保険法 第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
★高齢者の医療の確保に関する法律 第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
★船員保険法 第1条 (目的) この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★介護保険法 第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
★確定給付企業年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★確定拠出年金法 第1条 (目的) この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
★児童手当法 第1条 (目的) この法律は、子ども・子育て支援法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
★社会保険労務士法 第1条 (目的) この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険労務士法に出てくる数字
R7-358 08.21
意外と問われる社会保険労務士法の数字
社会保険労務士法で問われる数字をチェックしましょう。
過去問からどうぞ!
①【R4年出題】
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。

【解答】
①【R4年出題】 〇
「3年」をおぼえましょう。
条文を読んでみましょう。
法第5条 (欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士となる資格を有しない。 (1) 未成年者 (2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (4) この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの (5) 前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの (6) 第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの (7) 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者 (8) 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの (9) 税理士法の規定により同法第44条第3号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの |
②【R2年出題】
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。

【解答】
②【R2年出題】 ×
「60万円」ではなく「120万円」です。
条文を読んでみましょう。
「紛争解決手続代理業務」について(法第2条第1項1号の4~1号の6) ① 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」及び「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 ② 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 ③ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 |
※③について
単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は120万円となります。
③【R5年出題】
他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から1年間保存しなければならない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
「1年間」ではなく「2年間」保存しなければなりません。
条文を読んでみましょう。
法第19条 (帳簿の備付け及び保存) ① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 ② 開業社会保険労務士は、帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。 |
④【H24年選択式】
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

④【H24年選択式】
<A> 2年間
<B> 100万円以下の罰金
⑤【H15年出題】
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。

【解答】
⑤【H15年出題】 ×
・労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為(第15条不正行為の指示等の禁止)
→ 罰則が科せられます
・信用又は品位を害するような行為(第16条信用失墜行為の禁止)
→ 罰則は科せられません。
ポイント!
第15条違反については、社会保険労務士法で最も重い罰則が科せられます。
第32条 第15条(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定(不正行為の指示等の禁止)に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。 |
⑥【H15年出題】
開業社会保険労務士が、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。

⑥【H15年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第21条 (秘密を守る義務) 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても、また同様とする。 |
第21条に違反した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
(法第32条の2)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「横断編」
R7-346 08.09
社一横断「都道府県」それとも「市町村」?
例えば、介護保険法では、介護認定審査会は「市町村」に置かれます。また、介護保険審査会は、「都道府県」に置かれます。
よく似た名称が出てきますし、「市町村」か「都道府県」かを問う問題も繰り返し出題されます。
今回は、よく出題される個所を横断的にみていきます。
条文を読んでみましょう。
★国民健康保険法
法第11条 (国民健康保険事業の運営に関する協議会) ① 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 ② 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
第91条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第92条 (審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 第93条 (組織) ① 審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |
★高齢者医療確保法
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 第49条 (特別会計) 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第104条 (保険料) 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
第128条 (審査請求) ① 後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第129条 (審査会の設置) 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 |
★介護保険法
第14条 (介護認定審査会) 第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。 第15条 (委員) ① 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。 第16条 (共同設置の支援) ① 都道府県は、認定審査会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 ② 都道府県は、認定審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。
第183条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第184条 (介護保険審査会の設置) 介護保険審査会は、各都道府県に置く。 第185条 (組織) ① 保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 (1) 被保険者を代表する委員 3人 (2) 市町村を代表する委員 3人 (3) 公益を代表する委員 3人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数 ② 委員は、都道府県知事が任命する。 ③ 委員は、非常勤とする。 |
過去問をどうぞ!
★国民健康保険法
①【H18年出題】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
①【H18年出題】 ×
審査請求は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」に対して行います。
②【R6年出題】
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

【解答】
②【R6年出題】 ×
「保険医又は保険薬剤師を代表する委員」が誤りです。
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織されます。
★高齢者医療確保法
①【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
最初の「都道府県は」が誤りです。
後期高齢者医療広域連合を設けるのは都道府県ではなく、「市町村」です。
②【H23年出題】※改正による修正あり
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
「都道府県及び市町村(特別区を含む。)は」が誤りです。
後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならないのは、「市町村(特別区を含む。)」です。
(第104条)
③【H22年出題】
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】
③【H22年出題】 ×
「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない、となります。
(第49条)
④【H25年出題】※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
④【H25年出題】 ×
「社会保険審査会」ではなく「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができる、となります。
⑤【R4年出題】※改正による修正あり
後期高齢者医療給付に関する処分(第54条第3項及び第5項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
⑤【R4年出題】 〇
「後期高齢者医療審査会」に審査請求をすることができます。
★介護保険法
①【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

【解答】
①【H29年出題】 〇
介護認定審査会は、市町村から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされています。
(第27条第5項)
②【R3年出題】
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。

【解答】
②【R3年出題】 ×
介護認定審査会は、市町村に置かれ、介護認定審査会の委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。」とされています。
③【H27年出題】
市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
市町村は、介護認定審査会を共同で設置することができます。
④【R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

【解答】
④【R3年出題】 〇
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければなりません。
⑤【R5年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」という規定はありません。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識(給付を比較してみましょう)
R7-345 08.08
給付について(確定給付企業年金法・確定拠出年金法)
確定給付企業年金法と確定拠出年金法の「給付」をみていきます。
最初に、それぞれの給付の種類を確認しましょう。
過去問をどうぞ!
(確定給付企業年金法)
【H26年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】
【H26年出題】 〇
・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う
・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)
(第29条)
(確定拠出年金法)
【H20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
【H20年出題】 〇
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。
また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。
では、給付の内容をみていきます。
過去問をどうぞ!
(確定給付企業年金法)
①【H26年出題】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

【解答】
①【H26年出題】 〇
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、「事業主等」が裁定します。
ちなみに「事業主等」とは、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金「基金型企業年金」を実施する場合にあっては、企業年金基金)のことです。
(法第30条)
②【H26年出題】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】
②【H26年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、<A>にわたり、<B>以上定期的に支給するものでなければならない。
<A> 終身又は5年以上
<B> 毎年1回
(第33条)
次は、「老齢給付金」の問題です。
まず、条文を読んでみましょう。
第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② 規約で定める要件は、次に掲げる要件(「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。 (1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 (2) 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ 前項(2)の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
第38条 (支給の方法) ① 老齢給付金は、年金として支給する。 ② 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
第40条 (失権) 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。 (1) 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。 (2) 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 (3) 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。 |
過去問をどうぞ!
①【H26年出題】
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

【解答】
①【H26年出題】 〇
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならないとされています。
②【H26年出題】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

【解答】
②【H26年出題】 ×
老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができます。
③【H30年選択式】
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】
③【H30年選択式】
<A> 60歳以上70歳以下
<B> 50歳未満
④【R2年出題】
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】
④【R2年出題】 ×
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が「死亡したとき」、老齢給付金の「支給期間が終了したとき」と、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」に消滅します。
次は脱退一時金の問題です。
【R3年選択式】
確定給付企業年金法第41条第3項の規定によると、脱退一時金を受けるための要件として、規約において、< A >を超える加入者期間を定めてはならないとされている。

【解答】
【R3年選択式】
<A> 3年
(確定拠出年金法)
①【R5年出題】
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が確定拠出年金法第33条の規定により老齢給付金の支給を請求することなく< A >に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型記録関連運営管理機関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する。
<A> 75歳
(第34条)
②【R1年選択式】
確定拠出年金法第37条第1項によると、企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が、傷病について < A >までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に企業型記録関連運営管理機関等に障害給付金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
②【R1年選択式】
<A> 障害認定日から75歳に達する日の前日
③【H29年出題】
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】
③【H29年出題】 ×
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができます。
この要件においては、通算拠出期間が政令で定める期間内であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であることとされています。
政令で定める期間内は1月以上5年以下、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下とされています。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
↓
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については<A>であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が<B>であることとされている。
<A> 1月以上5年以下
<B> 25万円以下
(附則第3条、令第60条)
ちなみに、個人型年金に加入していた者の脱退一時金を請求するための要件として、他に、「60歳未満であること」などもあります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識(比較してみましょう)
R7-344 08.07
保険料の比較(高齢者医療確保法と介護保険法)
最初に、「高齢者医療確保法」と「介護保険法」の財源を確認しましょう。
★高齢者医療確保法の「後期高齢者医療」の財源について
公 費(約5割) | |
保険料(約1割) | 後期高齢者支援金(約4割) |
※後期高齢者(原則75歳以上)の保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)
→令和6・7年度は12.67%
★介護保険法の財源について
公費(50%) |
保険料(50%) |
第1号被保険者→23%
第2号被保険者→27%
今回は、「保険料」をみていきます。
★後期高齢者医療の保険料について条文を読んでみましょう。
高齢者医療確保法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

【解答】
①【R5年出題】 ×
「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収」の定義が逆です。
・市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付します。
「市町村による保険料の徴収」について条文を読んでみましょう。
第107条第1項 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 |
②【R4年出題】
後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】
②【R4年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
③【H30年出題】
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

【解答】
③【H30年出題】 ×
後期高齢者医療制度の保険料が年金から特別徴収されるのは、年間の年金額が18万円以上の場合です。
ただし、同一の月に徴収されると見込まれる後期高齢者医療の保険料と介護保険の保険料の合計が、老齢年金等給付の額の2分の1を超える場合等は、「特別徴収」の対象にはなりません。「普通徴収」の対象となります。
「口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない」ことはありません。
(令第22条、第23条)
④【H23年出題】※改正による修正あり
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】
④【H23年出題】 ×
「おおむね5年」ではなく、「おおむね2年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。
★介護保険の保険料について条文を読んでみましょう。
介護保険法第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
第131条 (保険料の徴収の方法) 保険料の徴収については、第135条の規定により特別徴収(老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第1号被保険者又は当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第1号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。
第132条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) ① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む)」です。
保険料が課されるのは、「第1号被保険者」です。
②【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】
②【R3年出題】 ×
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。
第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料と一緒に徴収し、医療保険者から納付金として社会保険診療報酬支払基金に納付しています。
③【R3年出題】
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。

【解答】
③【R3年出題】 ×
配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
④【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
④【H30年選択式】
<A> 3年
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識(国民健康保険法)
R7-343 08.06
国民健康保険法の制度について
国民健康保険法の目的などをみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第1条 (この法律の目的) この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民健康保険) 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条 (保険者) ① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 ② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。 |
過去問をどうぞ!
<目的>
【R6年選択式】
国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >に寄与することを目的とする。」と規定している。

【解答】
【R6年選択式】
<A> 社会保障及び国民保健の向上
<保険者>
【R2年選択式】
国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、< A >の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

【解答】
【R2年選択式】
<A> 1又は2以上の市町村
【R4年出題】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】
【R4年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第17条 ① 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 ② 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 |
問題文の「10人以上」と「100人以上」が誤りです。
また、「都道府県知事の認可」もポイントです。厚生労働大臣ではありませんので注意しましょう。
【H28年出題】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

【解答】
【H28年出題】 〇
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
<国、都道府県及び市町村の責務>
【R1年選択式】
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、< A >、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。

【解答】
【R1年選択式】
<A> 安定的な財政運営
【R6年出題】
市町村(特別区を含む。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

【解答】
【R6年出題】 ×
市町村(特別区を含む。)ではなく「都道府県」の責務です。
<被保険者>
被保険者について条文を読んでみましょう。
第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 (1) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 (2) 船員保険法の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 (6) 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 (7) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。(ただし以下省略) (8) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 (9) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (10) 国民健康保険組合の被保険者 (11) その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第7条 (資格取得の時期) 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得する。
第8条 (資格喪失の時期) ① 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日又は第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至った日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 ② 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第9号又は第10号に該当するに至った日から、その資格を喪失する。 |
【R3年出題】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】
【R3年出題】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にはなりません。(その保護を停止されている世帯を除きます。)
【H20年出題】※改正による修正あり
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
【H20年出題】 〇
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
【H20年出題】※改正による修正あり
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
【H20年出題】 〇
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
【R3年出題】
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

【解答】
【R3年出題】 ×
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得します。「翌日」が誤りです。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識は「比較」が有効
R7-342 08.05
確定給付企業年金法・確定拠出年金法を比較してみましょう
確定拠出年金法は「平成13年10月」、確定給付企業年金法は「平成14年4月」から施行された法律です。
過去問で比較しながら覚えていきましょう。
★目的条文の比較
(確定給付企業年金法)
【H19年出題】
確定給付企業年金法とは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいて給付を受ける仕組みのものである。

【解答】
【H19年出題】 ×
問題文は、「確定拠出年金法」の目的です。
確定給付企業年金法は、「事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受ける」仕組みです。
(確定給付企業年金法第1条)
(確定拠出年金法)
【H18年出題】
この法律において、「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。

【解答】
【H18年出題】 ×
問題文は「確定給付企業年金法」の目的です。
「確定拠出年金」とは、「個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受ける」ことができるようにする仕組みです。
(確定拠出年金法第1条)
★用語の定義を比較
(確定給付企業年金法)
【H28年出題】
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

【解答】
【H28年出題】 ×
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、第4号厚生年金被保険者が含まれます。
条文を読んでみましょう
第2条 ① 「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。 ③ 「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。 |
(確定拠出年金法)
【R3年出題】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
【R3年出題】 〇
・「確定拠出年金」には、「企業型年金」と「個人型年金」があります。
「企業型年金」→厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施
「個人型年金」→「国民年金基金連合会」が実施
・「企業型年金加入者」
→ 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者
第1号等厚生年金被保険者=第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者
・「個人型年金加入者」
→ 国民年金法第1号被保険者
法定免除(生活保護法の生活扶助を受ける者に限る。)、申請全額免除、一部免除を受ける者を除く。
→ 国民年金法第2号被保険者
企業型掛金拠出者等を除く。
→ 国民年金法第3号被保険者
→ 国民年金法任意加入被保険者
20歳以上60歳未満の老齢給付等を受けることができるものを除く。
★給付の種類を比較
(確定給付企業年金法)
【H26年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

【解答】
【H26年出題】 〇
・老齢給付金と脱退一時金の給付を行う
・規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる(任意)
(第29条)
【H30年選択式】
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < A >

【解答】
【H30年選択式】
<A> 脱退一時金
【R4年出題】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

【解答】
【R4年出題】 ×
「障害給付金」については、「規約で定めるところにより、給付を行うことができる」となります。
(確定拠出年金法)
【H20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
【H20年出題】 〇
確定拠出年金の給付には、「老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金」があります。
また、当分の間、「脱退一時金」の支給を請求することができるとされています。
★掛金の拠出を比較
(確定給付企業年金法)
【H28年出題】
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】
【H28年出題】 ×
「事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。」とされています。
また、事業主は、掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとされています。
(第55条第1項、第56条第1項)
【R2年出題】
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。

【解答】
【R2年出題】 ×
「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」とされています。加入者が、掛金の全部を負担することはできません。
(第55条第2項)
(確定拠出年金法)
【R3年出題】
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】
【R3年出題】 〇
企業型年金については、事業主は、年1回以上、定期的に掛金を拠出します。
(第19条第1項)
【R6年出題】
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

【解答】
【R6年出題】 〇
企業型年金加入者は、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができるとされています。
(第19条第3項)
【R3年出題】
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
【R3年出題】 〇
・「事業主掛金」の額は、企業型年金規約で定めるものとされています。(ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とされています。
・「企業型年金加入者掛金」の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更するとされています。
(第19条第2項、第4項)
【R5年出題】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。

【解答】
【R5年出題】 ×
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するとされています。
(第68条第1項)
【R6年出題】
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
【R6年出題】 〇
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。
(第68条第2項)
【R2年選択式】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】
【R2年選択式】
<A> 48,000
国民年金第1号被保険者の拠出限度額は月額68,000円です。ただし、国民年金基金の掛金を納付している場合は、その額を控除した額となります。
そのため、68,000円−20,000円=48,000円となります。
(令第36条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「介護保険法」
R7-339 08.02
介護保険法の制度について
介護保険は、平成12年4月に施行された社会保険です。
被保険者になるのは、40歳以上の者です。
では、目的条文などを読んでみましょう。
第1条 (目的) この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 ① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。 ② 保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 ③ 保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 ④ 保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、< A >並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< B >に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【解答】
①【H27年選択式】
<A> 機能訓練
<B> 国民の共同連帯の理念
②【R5年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、介護保険を行うのは、「市町村(特別区を含む。)」です。
(法第3条)
③【H27年出題】
市町村又は特別区(以下「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

【解答】
③【H27年出題】 ×
「市町村又は特別区」ではなく「国」の責務です。
条文を読んでみましょう。
第5条 (国及び地方公共団体の責務) ① 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。 ② 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 ③ 都道府県は、助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならない。 ④ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。 ⑤ 国及び地方公共団体は、④に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。 |
④【R1年出題】
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

【解答】
④【R1年出題】 〇
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする「市町村介護保険事業計画」を定めます。
条文を読んでみましょう。
第116条第1項 (基本指針) 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第117条第1項 (市町村介護保険事業計画) 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 |
⑤【H29年選択式】
介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して< A >とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。

【解答】
⑤【H29年選択式】
<A> 常に健康の保持増進に努める
第4条第1項「国民の努力及び義務」からの出題です。
ちなみに、第4条第2項には、「国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。」と定められています。
⑥【H24年出題】
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。

【解答】
⑥【H24年出題】 〇
第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
(第9条)
⑦【R4年選択式】
介護保険法における「要介護状態」とは、< A >があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、< B >の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である< A >が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が < B >に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

【解答】
⑦【R4年選択式】
<A> 身体上又は精神上の障害
<B> 6か月
★「要介護状態」とは
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)
★「要介護者」とは
(1) 要介護状態にある65歳以上の者
(2) 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
(第7条、則第2条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「高齢者医療確保法」
R7-338 08.01
高齢者医療確保法の制度について
高齢者医療確保法では、75歳以上の後期高齢者について、健康保険法などの医療保険各法から独立した医療制度を設けています。
また、65歳以上75歳未満の前期高齢者については、保険者間の負担の不均衡を調整する仕組みが設けられています。
目的条文などを読んでみましょう。
第1条 (目的) この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (基本的理念) ① 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 ② 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
第3条(国の責務) 国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
第4条 (地方公共団体の責務) 地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。 ② 前項に規定する住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組においては、都道府県は、当該都道府県における医療提供体制の確保並びに当該都道府県及び当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の国民健康保険事業の健全な運営を担う責務を有することに鑑み、保険者、後期高齢者医療広域連合、医療関係者その他の関係者の協力を得つつ、中心的な役割を果たすものとする。
第5条 (保険者の責務) 保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
第7条 (定義) ① この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。 (1) 健康保険法 (2) 船員保険法 (3) 国民健康保険法 (4) 国家公務員共済組合法 (5) 地方公務員等共済組合法 (6) 私立学校教職員共済法 ② この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 |
過去問をどうぞ!
① 【R6年選択式】
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< A >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< B >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。

【解答】
① 【R6年選択式】
<A> 共同連帯
<B> 費用負担
②【H22年出題】
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講じなければならない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
都道府県ではなく「国」の責務です。
ヒントは、「必要な各般の措置を講じなければならない」です。
③【H24年出題】
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

【解答】
③【H24年出題】 ×
国ではなく「地方公共団体」の責務です。
ヒントは、「住民」、「所要の施策を実施しなければならない」です。
④【H24年出題】
保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

【解答】
④【H24年出題】 〇
「保険者」の責務です。
ヒントは、「推進するよう努める」と、「協力しなければならない」です。
⑤【H29年出題】※改正による修正あり
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

【解答】
⑤【H29年出題】 〇
高齢者医療確保法における「保険者」の定義です。
全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団です。
⑥【R5年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。

【解答】
⑥【R5年出題】 〇
都道府県が定める「都道府県医療費適正化計画」の問題です。
条文を読んでみましょう。
第8条 (医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画) 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第9条 (都道府県医療費適正化計画) 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
第10条 (厚生労働大臣の助言) 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。 |
⑦【H30年出題】
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。

【解答】
⑦【H30年出題】 〇
条文を読んでみましょう。
第9条第8項 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。 |
⑧【H29年出題】※改正による修正あり
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。

【解答】
⑧【H29年出題】 ×
5年ごとに、5年を1期ではなく、「6年ごとに、6年を1期として」です。
条文を読んでみましょう。
第18条 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
第19条 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
第20条 (特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。 |
⑨【R5年選択式】
高齢者医療確保法第20条の規定によると、保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< A >以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は同法第26条第2項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。

【解答】
⑨【R5年選択式】
<A> 40歳
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「社会保険労務士法」
R7-337 07.31
社会保険労務士法の懲戒について
社会保険労務士法の懲戒処分についてみていきましょう。
条文を読んでみましょう。
第25条 (懲戒の種類) 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。 (1) 戒告 (2) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 (3) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒) ① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、①に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 (参考) 法第15条 (不正行為の指示等の禁止) 社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第25条の3 (一般の懲戒) 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。
第25条の3の2 (懲戒事由の通知等) ① 社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。 ② 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 |
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】
①【R1年出題】 ×
問題文の場合は、社会保険労務士会は、「注意勧告」をすることができます。
条文を読んでみましょう。
第25条の33(注意勧告) 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 |
②【H25年出題】
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。

【解答】
②【H25年出題】 〇
故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、厚生労労働大臣は、1年以内の業務の停止又は失格処分の処分をすることができます。
問題文のように、失格処分を受けることがあります。
③【H28年出題】
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。

【解答】
③【H28年出題】 ×
開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、厚生労働大臣は、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる。」とされています。
「失格処分」の対象にはなりません。
④【H20年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

【解答】
④【H20年出題】 ×
懲戒処分をすることができる厚生労働大臣の権限は、全国社会保険労務士会連合会には委任されていません。
⑤【H26年出題】
社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえる。

【解答】
⑤【H26年出題】 〇
社会保険労務士法第25条の30では、「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。」と定められています。
また、第25条の3 (一般の懲戒)で、「この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき」は、厚生労働大臣は懲戒処分することができることが定められています。
所属する社会保険労務士会の会則の不遵守=社会保険労務士法に違反した場合は、厚生労働大臣による懲戒処分の対象となりえます。
⑥【H25年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士に対し戒告の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが、官報をもって公告する必要はない。

【解答】
⑥【H25年出題】 ×
官報をもって公告する必要があります。
条文を読んでみましょう。
第25条の5 (懲戒処分の通知及び公告) 厚生労働大臣は、第25条の2又は第25条の3の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険に関する一般常識「船員保険法」
R7-336 07.30
船員保険の保険給付~健保との違いを意識しながら
健康保険との違いを意識しながら、船員保険の保険給付をみていきましょう。
★療養の給付
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、療養の給付を行うが、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給も当該療養の給付に含まれる。

【解答】
①【H28年出題】 〇
船員保険も健康保険と同様に療養の給付が行われますが、船員保険の療養の給付には、「自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給」が含まれます。
(法第53条)
★傷病手当金
条文を読んでみましょう。
第69条 ① 被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 ② 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。(以下省略します) ④ 疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。 ⑤ 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。 ⑥ 被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関しその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前1年間において3月以上又はその日前3年間において1年以上であることを要する。 ⑦ 傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。 |
過去問をどうぞ!
②【R2年出題】
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

【解答】
②【R2年出題】 ×
船員保険の傷病手当金には、待期がありません。
「その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から」が誤りです。
③【H28年出題】※改正による修正あり
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6か月間とする。

【解答】
③【H28年出題】 ×
傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から通算して「1年6か月間」ではなく「3年間」です。
④【R4年出題】
船員保険の被保険者であった者が、令和3年10月5日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4年4月11日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。

【解答】
④【R4年出題】 ×
疾病任意継続被保険者にも傷病手当金が支給されますが、疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して1年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、傷病手当金は支給されません。
問題文は、令和3年10月5日に疾病任意継続被保険者の資格を取得し、令和4年4月11日に傷病を発しています。資格取得から1年以上経過していませんので、傷病手当金の支給を受けることができます。
★出産手当金
⑤【H28年出題】
出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
船員法第87条で「船舶所有者は、妊娠中の女子を船内で使用してはならない。」と定められています。
そのため、出産手当金の支給期間は、出産の日以前は、「妊娠中のため職務に服さなかった期間」となります。出産の日後は56日以内において職務に服さなかった期間です。
(法第74条)
★行方不明手当金
条文を読んでみましょう。
法第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
法第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
法第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。
法第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
過去問をどうぞ!
⑥【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。

【解答】
⑥【H28年出題】 〇
・被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。
・行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。
・被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合は、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されません。
⑦【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】
⑦【R3年選択式】
<A> 被扶養者
⑧【R2年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。

【解答】
⑧【R2年出題】 〇
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金が支給されます。ただし、行方不明の期間が1か月未満のときは、支給されません。
⑨【R5年出題】
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

【解答】
⑨【R5年出題】 ×
「2か月」ではなく「3か月」が限度です。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険一般常識「介護保険法」
R7-281 06.05
介護保険法の保険料について
介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。
法第9条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
では、「保険料」について条文を読んでみましょう。
法第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】
①【H21年出題】 〇
市町村又は特別区から保険料を徴収されるのは、第1号被保険者です。
②【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
②【H30年選択式】
<A> 3年
③【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者からは保険料を徴収しません。
・第2号被保険者については、医療保険者が医療保険料といっしょに介護保険料を徴収します。
医療保険者は、社会保険診療報酬支払基金に納付金を納付します。
条文を読んでみましょう。
法第150条 (納付金の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金は年度ごとに、医療保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。 ③ 医療保険者は、納付金を納付する義務を負う。
法第125条(介護給付費交付金) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護給付及び予防給付に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金をもって充てる。 第126条 (地域支援事業支援交付金) 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に第2号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。 |
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
社会保険一般常識「高齢者医療確保法」
R7-280 06.04
高齢者医療確保法の保険料について
高齢者医療確保法の保険料についてみていきましょう。
高齢者医療確保法の「後期高齢者医療制度」の被保険者は以下の通りです。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |
では、保険料について条文を読んでみましょう。
法第104条 (保険料) ① 市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、特別高額医療費共同事業による費用の拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、高齢者保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
法第107条 (保険料の徴収の方法) 市町村による保険料の徴収については、特別徴収(市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者から年金保険者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによつて保険料を徴収することをいう。)の方法によらなければならない。 |
過去問をどうぞ!
①【H23年出題】※改正による修正あり
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
①【H23年出題】 ×
保険料を徴収するのは、「都道府県及び市町村(特別区を含む。)」ではなく、「市町村(特別区を含む。)」です。
②【H23年出題】※改正による修正あり
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第125条第1項に規定する高齢者保健事業及び同条第5項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】
②【H23年出題】 ×
おおむね「5年」ではなく、「2年」です。
③【R5年出題】
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる普通徴収の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する特別徴収の方法によらなければならない。

【解答】
③【R5年出題】 ×
特別徴収と普通徴収の説明が逆です。原則は「特別徴収」です。
「市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収し、後期高齢者医療広域連合に納付する。市町村による保険料の徴収については、市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させる「特別徴収」の方法による場合を除くほか、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する「普通徴収」の方法によらなければならない。」となります。
④【H30年出題】
高齢者医療確保法では、老齢基礎年金の年間の給付額が18万円以上である場合、後期高齢者医療制度の被保険者が支払う後期高齢者医療の保険料は、年金からの特別徴収でなければならず、口座振替の方法により保険料を納付することは一切できない。

【解答】
④【H30年出題】 ×
年金の年間の給付額が18万円以上の場合は特別徴収の対象です。
ただし、一定の要件に該当する場合は、特別徴収ではなく普通徴収となります。口座振替の方法により保険料を納付することは一切できないわけではありません。
(法第110条、令第21条、22条)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
高齢者医療確保法「後期高齢者医療制度」
R7-185 03.01
後期高齢者医療制度の内容と対象者
後期高齢者医療は、原則として75歳以上の人が対象です。
75歳になるまでは、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法)の加入者となります。
では、後期高齢者医療制度について条文を読んでみましょう。
第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 (1) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 (2) 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 (1) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 (2) 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
過去問をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合を設けるのは、都道府県ではなく「市町村」です。
②【H22年出題】
都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

【解答】
②【H22年出題】 ×
『「後期高齢者医療広域連合及び市町村」は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、「政令」で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。』となります。
③【H29年出題】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとされています。死亡に関する給付も行っています。
なお、出産に関する給付はありません。
④【H22年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

【解答】
④【H22年出題】 ×
年齢が誤りです。
70歳以上ではなく「75歳以上の者」、「65歳以上70歳未満」ではなく「65歳以上75歳未満の者であって・・・」となります。
⑤【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療の適用が除外されます。
⑥【R5年出題】
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
⑥【R5年出題】 ×
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
問題文の誤りの部分は、「都道府県」ではなく「後期高齢者医療広域連合」、「高齢者医療確保法の定めるところにより」ではなく、「条例の定めるところにより」となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(国民健康保険法)
R7-066 10.30
<令和6年の問題を振り返って>(社一)国民健康保険法の問題【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、国民健康保険法の択一式です。
国民健康保険法の問題を解いてみましょう。
押さえておきたいのは、①と④の問題です。
①【R6問8-A】重要!
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

【解答】
①【R6問8-A】重要! ×
国民健康保険組合に指導及び助言を行うのは、「市町村(特別区を含む)」ではなく「都道府県」です。
国、都道府県、市町村の責務を条文で確認しましょう。
第4条 ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 |
②【R6問8-B】
国保組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

【解答】
②【R6問8-B】 〇
国民健康保険組合は、「組合員及び組合員の世帯に属する者」を被保険者としますので、世帯単位で適用されるのが原則です。
また、「国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」と定められています。
(法第19条)
③【R6問8-C】
国保組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、監事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において監事以外の者を選任したときは、この限りでない。

【解答】
③【R6問8-C】 ×
監事ではなく理事です。
条文で確認しましょう。
第32条の4 (清算人) 国民健康保険組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 |
④【R6問8-D】重要!
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び保険医又は保険薬剤師を代表する委員各3人をもって組織される。

【解答】
④【R6問8-D】 ×
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれ、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び「公益」を代表する委員各3人をもって組織されます。
国民健康保険審査会について条文を読んでみましょう。
第91条第1条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
第92条(審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。
第93条 (組織) ① 国民健康保険審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。 ② 委員は、非常勤とする。 |
⑤【R6問8-E】
市町村若しくは国保組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

【解答】
⑤【R6問8-E】 ×
厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
条文を読んでみましょう。
第107条(事業状況の報告) 次の各号に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を、それぞれ当該各号に定める者に報告しなければならない。 (1) 都道府県 → 厚生労働大臣 (2) 市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 → 当該市町村若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会をその区域内に含む都道府県を統括する都道府県知事 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返りましょう(確定拠出年金法)
R7-040 10.4
<令和6年度社一>確定拠出年金法です【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、確定拠出年金法の択一式です。
令和6年の問題をどうぞ!
①【R6年問7-A】
企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。

【解答】
①【R6年問7-A】 〇
企業型確定拠出年金の掛金は事業主が拠出しますが、事業主掛金に加えて、加入者も掛金を拠出することができます。マッチング拠出といいます。
条文で確認しましょう。
第19条 ① 事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。 ③ 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 ④ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 |
ちなみに、企業型年金加入者掛金は、事業主掛金を超えず、かつ、事業主掛金との合計が拠出限度額の範囲内であることが必要です。
②【R6年問7-B】
企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。

【解答】
②【R6年問7-B】 〇
企業型年金加入者掛金は、「事業主を介して」資産管理機関に納付します。
条文で確認しましょう。
第21条第1項 (事業主掛金の納付) 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする。
第21条の2第1項 (企業型年金加入者掛金の納付) 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
第21条の3(企業型年金加入者掛金の源泉控除) ① 企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 ② 事業主は、企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金加入者に通知しなければならない。 |
③【R6年問7-C】
企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。

【解答】
③【R6年問7-C】 〇
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わります。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによります。
(法第31条)
④【R6年問7-D】
個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。

【解答】
④【R6年問7-D】 ×
「個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を国民年金基金連合会に届け出なければならない」とされています。
(法第66条)
⑤【R6年問7-E】
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。

【解答】
⑤【R6年問7-E】 〇
個人型年金加入者掛金の額は、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。
条文で確認しましょう。
第68条 (個人型年金加入者掛金) ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
厚生労働白書が活用できる読み方
R7-022 9.16
厚生労働白書を読んで年金の勉強に役立てましょう
厚生労働白書をチェックして、年金の勉強に役立てましょう。
ポイントを意識しながら読むと、年金制度がイメージできます。
<テーマ>
・日本の公的年金制度は世代間扶養
・年金給付は国民の老後生活の基本
・短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大のメリット
・マクロ経済スライド
・令和6年度の年金額改定の仕組み
YouTubeでお話しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度択一式を振り返ります(社会保険に関する一般常識)
R7-018 9.12
<令和6年度社一>確定給付企業年金法の問題を解いてみましょう【社労士受験対策】
令和6年度の試験を振り返って、今後の勉強に役立てましょう。
今日は、確定給付企業年金法の択一式です。
令和6年社会保険に関する一般常識問6の問題をどうぞ!
①【R6年出題】
企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、基金の分割は、実施事業所の一部について行うことができる。

【解答】
①【R6年出題】 ×
基金は、分割しようとするときは、「厚生労働大臣の認可」を受けなければなりませんが、基金の分割は、「実施事業所の一部について行うことはできない」とされています。
(法第77条第1項、第2項)
解き方のヒント!
健康保険法にも同じような規定があります。
健康保険法第24条第1項、2項 ① 健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ② 健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。 |
②【R6年出題】
確定給付企業年金法第78条第1項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない、とされています。
(法第78条第1項)
解き方のヒント!
健康保険法にも同じような規定があります。
健康保険法第25条第1項 健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。 |
★「事業主の全部」が同じです。
③【R6年出題】
基金は、代議員会において代議員の定数の3分の2以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。

【解答】
③【R6年出題】 ×
基金は、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる、です。
(法第85条第1項)
解き方のヒント!
こちらも健康保険法に同じような規定があります。
健康保険法第26条第1項 健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。 (1) 組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決 (2) 健康保険組合の事業の継続の不能 (3) 厚生労働大臣による解散の命令 |
★「4分の3以上」が同じです。
④【R6年出題】
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができる。

【解答】
④【R6年出題】 ×
「事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。」とされています。
(法第89条第3項)
⑤【R6年出題】
確定給付企業年金法第89条第6項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。

【解答】
⑤【R6年出題】 〇
なお、確定給付企業年金法第89条第7項では、「残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。」と規定されています。
(法第89条第6項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和6年度の選択式を振り返ります(社保一般常識)
R7-008 9.2
<令和6年度社保選択式>国民生活基礎調査・介護保険事業状況報告・目的条文【社労士受験対策】
令和6年度の試験問題を振り返り、これからの勉強に役立てましょう。
今日は、社会保険に関する一般常識の選択式です。
令和6年 選択問題1
厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が< A >の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
<選択肢>
「40~60%未満」、「60~80%未満」、「80~100%未満」、「100%」

【解答】
<A> 100%
「国民生活基礎調査の概況」の中の「各種世帯の所得等の状況」の「所得の種類別の状況」からの出題です。
ポイント!
各種世帯の所得の種類別1世帯当たり平均所得金額の構成割合は、
・全世帯では「稼働所得」が 73.2%、「公的年金・恩給」が 20.1%。
・高齢者世帯では「公的年金・恩給」が62.8%、「稼働所得」が 25.2%。
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は 44.0%。
(2022(令和4)年 国民生活基礎調査の概況より)
令和6年 選択問題2
厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で< B >%となっている。
<選択肢>
「3.9」、「18.9」、「33.9」、「48.9」

【解答】
<B> 18.9
第1号被保険者に占める認定者の割合は、全国平均で18.9%です。
ちなみに、第1号被保険者数は、令和3年度末で3,589万人です。
(令和3年度介護保険事業状況報告より)
令和6年 選択問題3
国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< C >に寄与することを目的とする。」と規定している。
<選択肢>
「社会保険及び国民福祉の向上」、「社会保険及び国民保健の向上」
「社会保障及び国民福祉の向上」、「社会保障及び国民保健の向上」

【解答】
<C> 社会保障及び国民保健の向上
(法第1条)
令和6年 選択問題4
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< D >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< E >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
<選択肢>
「給付費用」、「給付割合」、「費用負担」、「負担割合」
「共助連帯」、「共同連帯」、「自助と共助」、「自助と連帯」

【解答】
<D> 共同連帯
<E> 費用負担
(法第1条)
★「後期高齢者医療」制度の対象は、原則として75歳以上の後期高齢者です。
後期高齢者医療については、公費+現役世代からの支援金で約9割が賄われています。
★「前期高齢者」は、健康保険などの医療保険に加入しています。しかし、制度によって、前期高齢者の占める割合が異なります。そのため、前期高齢者の医療費については、制度間の財政調整が行われています。
問題文の<D>「共同連帯」は、高齢者医療を社会全体で支えるということです。
<E>の、前期高齢者に係る保険者間の<費用負担>の調整は、保険者間で行う財政調整の仕組みのことです。
「目的条文」を読むと、その法律の全体像をつかむことができます。
勉強に行き詰まったら、読んでみてください。
こちらにあります。
↓
■<横断編>目的条文などを読みます!練習問題もあります。労基・安衛・労災・雇用・徴収・健保・国年・厚年
■<横断編>一般常識科目の目的条文などを読みます!労働一般常識・社保一般常識
令和6年の選択式 データから2問、目的条文から3問でした。 一般常識についても、目的条文をはじめ、条文を読むことも大切です。 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
いよいよ当日です。合格を祈ります!
R6-364 8.25
最後に社会保険労務士法をチェックしましょう【社労士受験対策】
いよいよ本番です。
社会保険労務士法の条文のポイントを確認しましょう。
第1条 (目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
第1条の2 (社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第2条第2項、第3項
② 「紛争解決手続代理業務」は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
③ 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
(1)第1項第1号の4のあっせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあっせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。) について相談に応ずること。
(2)紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
(3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
第15条 (不正行為の指示等の禁止)
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第16条 (信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第19条 (帳簿の備付け及び保存)
① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
② 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から 2年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。
第25条 (懲戒の種類)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
(1) 戒告
(2) 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
(3) 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒)
① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
今日は長い1日ですが、頑張りましょう!
応援しています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-234 4.17
社労士受験のための 国民健康保険法 法定給付と任意給付
過去問から学びましょう。
今日は国民健康保険法です。
国民健康保険法の保険給付は、「法定給付」と「任意給付」に分かれています。
また、「法定給付」には、必ず行わなければならない「絶対的必要給付」と、特別な理由がある場合は全部又は一部を行なわないことができる「相対的必要給付」があります。
法定給付 | 絶対的必要給付 |
相対的必要給付 | |
任意給付 |
|
「相対的必要給付」と「任意給付」について条文を読んでみましょう。
第58条第1項、2項 ① 市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 ② 市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。 |
①出産育児一時金、葬祭費、葬祭の給付は、「行うものとする」とされていますが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる「相対的必要給付」です。
②傷病手当金その他の保険給付(出産手当金)は「行うことができる」となっています。行うかどうかや給付の内容は、市町村及び組合が決定できる「任意給付」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「移送費」は法定給付の絶対的必要給付です。
被保険者が療養の給付を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給します。
移送費は、必ず行わなければならない「絶対的必要給付」で、給付内容も法令で定められています。
(第54条の4)
②【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる

【解答】
②【H26年出題】 〇
傷病手当金は、条例又は規約の定めるところにより行うことができる「任意給付」です。
(第58条第2項)
③【H26年出題】※改正による修正あり
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
「死亡」に関しては、『「葬祭費の支給又は葬祭の給付」を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。』とされています。
「絶対的必要給付」ではなく、「相対的必要給付」です。
④【R1年出題】
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
④【R1年出題】 〇
出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は、相対的必要給付です。
(第58条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-218
R6.4.1 国民健康保険法の保険者
過去問から学びましょう。
今日は国民健康保険法です。
条文を読んでみましょう。
第3条 (保険者) ① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 ② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条 (国、都道府県及び市町村の責務) ① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 ② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。 ③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。 ④ 都道府県及び市町村は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。 ⑤ 都道府県は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。 |
過去問をどうぞ!
①【R4年出題】
国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】
①【R4年出題】 ×
・国民健康保険組合の設立には、「都道府県知事の認可」を受けなければなりません。この部分は正しいです。
・認可の申請は、10人ではなく「15人」以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人ではなく「300人」以上の同意を得て行うものとされています。
(第17条第1項、2項)
②【R1年選択式】
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、< A >、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとされている。
(選択肢)
①安定的な財政運営 ②国民健康保険の運営方針の策定
③事務の標準化及び広域化の促進 ④地域住民との身近な関係性の構築

【解答】
②【R1年選択式】
A ①安定的な財政運営
③【R3年出題】
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った「日」又は第6条各号(適用除外規定)のいずれにも該当しなくなった「日」から、その資格を取得します。「翌日」ではありません。
(第7条)
④【R3年出題】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】
④【R3年出題】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、適用除外です。被保険者になりません。
(第6条第9号)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-202
R6.3.16 児童手当法のあれこれ
過去問から学びましょう。
今日は児童手当法です。
まず、児童手当法の「児童」の定義を条文で読んでみましょう。
第3条第1項 この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 |
では、過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
②【R2年出題】
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
③【R2年出題】
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
④【R2年出題】
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
⑤【R2年出題】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による

【解答】
①【R2年出題】 〇
「児童」の定義についての問題です。
(第3項第1項)
ちなみに、「支給要件児童」という用語もあります。
「支給要件児童」は、
・15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。「中学校修了前の児童」という。)
・中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)
をいいます。
(第4条第1項第1号)
②【R2年出題】 ×
児童手当は、原則として、毎年「2月、6月及び10月」の3期に、それぞれの前月までの分を支払います。
(第8条第4項)
③【R2年出題】 〇
例えば2人目以降の子が生まれた場合、児童手当の増額改定は、その改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。
(第9条第1項)
ちなみに、「児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額することとなるに至っ場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から」行われます。
(第9条第3項)
④【R2年出題】 〇
「未支払の児童手当」についての問題です。
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合は、未支払の児童手当は中学校修了前の児童であった者に支払われます。
(第12条第1項)
⑤【R2年出題】 〇
児童手当法の罰則規定です。
(第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-188
R6.3.2 国民健康保険法 保険料を滞納した場合
過去問から学びましょう。
今日は国民健康保険法です。
条文を読んでみましょう
第9条第3項、6項、則第5条の6 市町村は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 |
※ 世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付します。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者は除かれます。(第9条第6項)
※国民健康保険組合にも準用されます。(第22条)
第63条の2第1項、3項、則第32条の2 ① 市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 ③ 市町村及び組合は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。 |
過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。
②【R1年出題】
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。
③【R1年出題】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
④【R2年出題】
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

【解答】
①【H28年選択式】
A 1年間
B 被保険者資格証明書
★流れをおさえましょう。
保険料を1年間滞納した
↓
市町村は、世帯主に対し被保険者証の返還を求める
↓
被保険者証を返還する
↓
市町村は被保険者資格証明書を交付する
(第9条第3項、6項、則第5条の6)
②【R1年出題】 ×
1年間保険料を滞納し、被保険者証を返還すると、被保険者資格証明書が交付されます。
しかし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(問題文の場合は15歳の子)には、「有効期間を6か月とする被保険者証」が交付されます。
(第9条第6項)
③【R1年出題】 ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養費ではなく「特別療養費」が支給されます。
被保険者資格証明書で療養を受けた場合は、病院等の窓口で医療費を全額支払い、後から一部負担金を引いた分が支給されます。これを特別療養費といいます。
(第54条の3)
④【R2年出題】 〇
★流れを確認しましょう。
・納期限から1年6か月以上保険料を滞納している
↓
・市町村は保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める
↓
・なお滞納している保険料を納付しない
↓
・市町村は一時差し止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができる
(第63条の2第1項、3項、則第32条の2)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険労務士法
R6-174
R6.2.17 紛争解決手続代理業務について
過去問から学びましょう。
今日は社会保険労務士法です。
条文を読んでみましょう。
第2条第2項、3項 ② 紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。 ③ 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 (1) 紛争解決手続について相談に応ずること。 (2) 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 (3) 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H19年選択式】
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< A >を行うことが含まれている。
ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < B >に合格し、かつ社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< C >社会保険労務士に限られる。
<選択肢>
①あっせん ②裁判所への提訴 ③和解の交渉 ④調停
⑤紛争解決手続代理業務試験 ⑥特定社会保険労務士試験 ⑦特認紛争解決業務試験 ⑧紛争解決手続業務試験 ⑨上級 ⑩特定 ⑪特認 ⑫上席
②【H23年出題】
具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は、紛争解決手続代理業務に含まれないため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士も行うことができる。
③【R1年出題】
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

【解説】
①【H19年選択式】
A ③和解の交渉
B ⑤紛争解決手続代理業務試験
C ⑩特定
(法第2条)
②【H23年出題】 ×
法第2条第3項第1号に規定する「相談」は、具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務受任前の「相談」です。
このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことはできません。
(平成19.3.26/厚生労働省基発第0326009号/庁文発第0326011号/)
③【R1年出題】 ×
紛争調整委員会におけるあっせんの手続について相談に応じること、あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができるのは、「特定社会保険労務士」に限られます。
(法第2条第2項、3項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-165
R6.2.8 介護保険法の被保険者
過去問から学びましょう。
今日は介護保険法です。
介護保険の被保険者には、「第1号被保険者」と「第2号被保険者」があります。
条文を読んでみましょう。
第9条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 (1) 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) (2) 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
※なお、介護保険の保険者は、「市町村及び特別区」です。
過去問をどうぞ!
①【H24年出題】
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
②【H23年出題】
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
③【R4年出題】
介護保険の第2号被保険者(市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の、介護保険法第7条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
④【H29年出題】
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
⑤【R1年出題】
A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。
⑥【R1年出題】
A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。

【解答】
①【H24年出題】 〇
介護保険の第1号被保険者は、「市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者」です。
(第9条第1項)
②【H23年出題】 ×
介護保険の第2号被保険者は、「市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。
(第9条第2項)
③【R4年出題】 ×
介護保険の第2号被保険者は「医療保険加入者」であることが条件ですので、医療保険加入者でなくなった場合は資格を喪失します。
「医療保険加入者でなくなった日の翌日」からではなく、「医療保険加入者でなくなった日」から、その資格を喪失します。
(法第11条第2項)
④【H29年出題】 ×
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から資格を喪失します。第2号被保険者の資格を継続する制度はありません。
⑤【R1年出題】 〇
第2号被保険者は「医療保険加入者」であることが条件ですので、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない60歳の者は、介護保険の被保険者となりません。
A県A市に住所を有する65歳の者は、医療保険加入者でなくても介護保険の第1号被保険者となります。
(第9条)
⑥【R1年出題】 ×
住民票のある市町村の被保険者になることが原則です。
しかし、住所地特例という例外があります。
B県B市の介護保険施設に入所することによりB県B市に住民票を異動させた場合でも、もともとA県A市に住所を有していた場合は、「A県A市」が行う介護保険の被保険者となります。
介護保険施設などが多い市町村に、被保険者が偏ってしまうことを防ぐためです。
(第13条第1項)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
過去問から学ぶ 社会保険に関する一般常識
R6-155
R6.1.29 介護保険法 介護保険料の徴収
過去問から学びましょう。
今日は介護保険法です。
条文を読んでみましょう。
第129条 (保険料) ① 市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② 保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
市町村(特別区を含む。)は、第1号被保険者から保険料を徴収します。
保険料の徴収方法には、「特別徴収」(年金から天引きする方法)と「普通徴収」があり、特別徴収が原則です。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
②【R3年出題】
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村(特別区を含む。)が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
③【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
①【R3年出題】 ×
市町村は、第2号被保険者からは、保険料を徴収しません。
(法第129条第4項)
★第2号被保険者の介護保険料の流れ
市町村 |
③ ↑ |
社会保険診療報酬支払基金 |
② ↑ |
① 医療保険者 |
①医療保険者が医療保険の保険料と介護保険料を一括して徴収します。
②医療保険者は、徴収した介護保険料を、社会保険診療報酬支払基金に納付します。
③徴収した納付金は、社会保険診療報酬支払基金から、市町村に交付します。
(法第125条、126条、150条)
②【R3年出題】 ×
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
条文を読んでみましょう。
① 第1号被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 ② 世帯主は、市町村が当該世帯に属する第1号被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 ③ 配偶者の一方は、市町村が第1号被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
③【H30年選択式】
(A)3年
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度の問題より 社会保険に関する一般常識
R6-049
R5.10.15 確定拠出年金法 個人型年金加入者の掛金
今日は、確定拠出年金法です。
確定拠出年金には、企業型と個人型があります。
今日は、個人型年金加入者の掛金をみていきます。
条文を読んでみましょう。
第68条 (個人型年金加入者掛金) ① 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 ② 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
第70条 (個人型年金加入者掛金の納付) ① 個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会に納付するものとする。 ② 第2号加入者(=厚生年金保険の被保険者)は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 ③ ②の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない。 ④ 国民年金基金連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない。 |
過去問をどうぞ!
【H22年選択式】 ※修正あり
確定拠出年金の個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を国民年金基金連合会(以下本問において「連合会」という。)に納付することになっている。ただし、第2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。
また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を< A >に通知しなければならない。

【解答】
【H22年選択式】 ※修正あり
A 個人型記録関連運営管理機関
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。
②【R5年出題】
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。

【解答】
①【R5年出題】 ×
年2回以上ではなく、「年1回以上」です。
②【R5年出題】 ×
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を「国民年金基金連合会」に納付します。
こちらの過去問もどうぞ!
【R2年選択式】
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】
(A)48,000
国民年金第1号被保険者の掛金の上限は68,000円です。
ただし、付加保険料又は国民年金基金の掛金の納付に係る月は、68,000円から付加保険料又は国民年金基金の掛金の額を控除した額が上限となります。
問題文の場合、確定拠出年金の掛金は、68,000円-基金の掛金20,000円= 48,000円まで拠出できます。
(令第36条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識
R6-040
R5.10.6 船員保険の行方不明手当金
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、船員保険法です。
条文を読んでみましょう。
第93条 (行方不明手当金の支給要件) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
第94条 (行方不明手当金の額) 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
第95条 (行方不明手当金の支給期間) 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。
第96条 (報酬との調整) 被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。 |
まず過去問をどうぞ!
①【R2年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
②【H28年出題】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
③【H23年出題】
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給するが、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする。
④【R3年選択式】
船員保険法第93条では、「被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、< A >に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が一月未満であるときは、この限りでない。」と規定している。

【解答】
①【R2年出題】 ○
行方不明手当金は、船員保険独自の給付です。
1か月以上の行方不明が行方不明手当金の対象です。
また、「職務上の事由」、「被扶養者」がキーワードです。
②【H28年出題】 ○
被保険者の行方不明の間に報酬が支払われている場合は、行方不明手当金はその差額となります。
③【H23年出題】 ×
行方不明手当金の支給期間は被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して 「3か月」を限度とします。なお、行方不明が3か月以上となったときは、「死亡の推定」により「行方不明となった日」に死亡したものと推定されます。
④【R3年選択式】
A被扶養者
では、令和5年の問題をどうぞ!
【R5年出題】
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して2か月を限度とする。

【解答】
【R5年出題】 ×
行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して「3か月」が限度です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識
R6-031
R5.9.27 介護保険法の基本問題
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、介護保険法です。
まず過去問からどうぞ!
①【H18年出題】
介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
②【R1年出題】
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
③【H24年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が、現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村(特別区を含む。)をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。

【解答】
①【H18年出題】 ○
介護保険の保険者は、「市町村及び特別区」です。
(法第3条)
②【R1年出題】 ○
要介護状態や要支援状態になった場合は、介護保険からサービスを受けることができます。
介護給付を受ける場合は、「要介護者に該当すること」・「その該当する要介護状態区分」について、市町村の認定(=「要介護認定」といいます。)を受けなければなりません。
市町村は、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知することになります。
要介護認定の効力は、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
(法第27条第8項)
③【H24年出題】 ○
要介護状態区分には、要介護1から要介護5まで5つの区分があります。
状態が変化し、要介護状態区分が変化したと認めるときは、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
(法第29条第1項)
④【R3年出題】 ○
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができます。
また、介護保険審査会は、「各都道府県」に置かれます。
(法第183条、第184条)
では、令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
②【R5年出題】
要介護認定は、市町村(特別区を含む。)が当該認定をした日からその効力を生ずる。
③【R5年出題】
要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。
④【R5年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
介護保険の保険者は、市町村(特別区を含む。)です。
国や都道府県は、市町村を重層的に支える立場です。
②【R5年出題】 ×
要介護認定の効力は、市町村が当該認定をした日からではなく、「その申請のあった日にさかのぼって」発生します。
③【R5年出題】 ○
状態が変化した場合は、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができます。
④【R5年出題】 ×
「介護保険審査会の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。」の部分が誤りです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度過去問で解ける問題 社会保険に関する一般常識
R6-021
R5.9.17 高齢者医療確保法のよく出るところ
「過去問」で解ける問題を解説していきます。
今日は、高齢者医療確保法です。
まず、過去問からどうぞ!
①【H28年出題】
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
②【H30年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
③【H29年出題】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入して設けられる。
④【R1年出題】
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【H28年出題】 ×
都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。
条文を読んでみましょう。
第118条第1項 社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。 |
②【H30年出題】 ×
「5年ごとに、5年を1期」ではなく「6年ごとに、6年を1期」です。
条文を読んでみましょう。
第9条第1項 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。 |
③【H29年出題】 ○
条文を読んでみましょう。
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。 |
④【R1年出題】 ×
「あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴いて」が誤りです。
「条例の定めるところにより」行われます。
条文を読んでみましょう。
第86条第1項 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 |
では令和5年の問題をどうぞ!
①【R5年出題】
都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収する。
②【R5年出題】
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画を定めるものとする。
③【R5年出題】
都道府県は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下本問において「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
④【R5年出題】
都道府県は、被保険者の死亡に関しては、高齢者医療確保法の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
①【R5年出題】 ×
都道府県ではなく「社会保険診療報酬支払基金」です。
②【R5年出題】 ○
「6年ごとに、6年を1期」がポイントです。
③【R5年出題】 ×
都道府県ではなく「市町村」です。
④【R5年出題】
都道府県ではなく「後期高齢者医療広域連合」、高齢者医療確保法の定めるところによりではなく、「条例の定めるところにより」です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和5年度選択式振り返り 社会保険に関する一般常識
R6-012
R5.9.8 社一選択式 船員保険法・高齢者医療確保法・確定給付企業年金法・児童手当法・白書からでした
令和5年度の選択式を振り返ります。
今日は社会保険に関する一般常識です。
 Aは、船員保険法の傷病手当金の問題です。
Aは、船員保険法の傷病手当金の問題です。
条文を読んでみましょう。
第69条第5項 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする。 |
Aには3年が入ります。
船員保険法は健康保険法と比較して、異なる点をチェックしてください。
 Bは、高齢者医療確保法の特定健康診査の問題です。
Bは、高齢者医療確保法の特定健康診査の問題です。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
第19条第1項 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。
第20条 (特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。(以下省略) |
Bには40歳が入ります。
 Cは確定給付企業年金法の掛金の額の基準の問題です。
Cは確定給付企業年金法の掛金の額の基準の問題です。
条文を読んでみましょう。
第57条 (掛金の額の基準) 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 |
Cには、財政の均衡を保つことが入ります。
 Dは、児童手当法の児童手当の額の問題です。
Dは、児童手当法の児童手当の額の問題です。
小学校修了後中学校修了前の児童(中学生)については、一律1か月1万円です。
Dには10,000円が入ります。
 Eは、令和4年版厚生労働白書から高齢化の問題です。
Eは、令和4年版厚生労働白書から高齢化の問題です。
問題文を読んでみましょう。
高齢化が更に進行し、「団塊の世代」の全員が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< E >人に1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
Eには、5.5が入ります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険に関する一般常識 介護保険法
社会保険に関する一般常識 介護保険法
R5-355
R5.8.17 介護保険最終チェック!
今日は介護保険法をチェックしましょう!
過去問をどうぞ!
①【H27年出題】
市町村又は特別区(以下「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
②【H27年出題】
市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
③【H27年出題】
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
④【H27年出題】
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。
⑤【H27年出題】
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。

【解答】
①【H27年出題】 ×
法第5条第1項で、「国」は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない、と規定されています。
市町村ではなく「国」の責務です。
あわせて、法第5条第2項も読んでみましょう。
| 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。 |
→必要な助言及び適切な援助は、都道府県の責務です。
②【H27年出題】 ×
第14条で、「介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く」と規定されています。
また、介護認定審査会は、共同で設置することができます。
(地方自治法第252条の7第1項)
③【H27年出題】 ×
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の「100分の12.5」に相当する額を負担します。
(第124条第1項)
④【H27年出題】 〇
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担します。
(法第124条第3項)
⑤【H27年出題】 ×
法第27条第1項で、「要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。」とされています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社保一般常識 介護保険法
社保一般常識 介護保険法
R5-327
R5.7.20 介護保険法 過去問でみる要介護認定など
今日は、介護保険法の過去問をみていきましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
②【H29年出題】
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
③【H29年出題】
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。
④【H29年出題】
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
⑤【H29年出題】
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
「介護認定審査会」とは
・審査判定業務を行わせるため、市町村に置かれています。
・介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命します。
(第14条、第15条、第27条第5項)
②【H29年出題】 〇
要介護認定は、申請のあった日から30日以内に行われるのが原則です。
(第27条第11項)
③【H29年出題】 〇
要介護認定は、有効期間内に限って、その効力を有します。
有効期間が満了した後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができます。
(第28条)
④【H29年出題】 〇
介護保険法による保険給付は次の3つです。
①「介護給付」・・・要介護状態に関する保険給付
②「予防給付」・・・要支援状態に関する保険給付
③「市町村特別給付」・・・要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの
(第18条)
⑤【H29年出題】 ×
第2号被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」と定義されています。
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失します。
(第9条、第11条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 介護保険法 選択式
介護保険法 選択式
R5-307
R5.6.30 毎年のように選択式で出題されている介護保険法
過去10年間で、介護保険法は選択式で6回出題されています。
まとめてチェックしましょう。
さっそく過去問をどうぞ!
①【H27年選択式】
介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、< A >並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< B >に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
②【R4年選択式】
介護保険法における「要介護状態」とは、< A >があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、< B >の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である< A >が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が< B >に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
③【H29年選択式】
介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して< A >とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。
④【R1年選択式】
介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、< A >を包括的に支援することを目的とする施設とされている。
⑤【R2年選択式】
介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から< A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。
⑥【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
①【H27年選択式】
A 機能訓練
B 国民の共同連帯の理念
②【R4年選択式】
A 身体上又は精神上の障害
B 6か月
(則第2条)
③【H29年選択式】
A 常に健康の保持増進に努める
④【R1年選択式】
A その保健医療の向上及び福祉の増進
⑤【R2年選択式】
A 1年6か月
⑥【H30年選択式】
A3年
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法 保険給付
国民健康保険法 保険給付
R5-289
R5.6.12 国民健康保険の法定給付と任意給付
まず、国民健康保険法の第1条と第2条を読んでみましょう。
第1条 (目的) 国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 (国民健康保険) 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 |
■国民健康保険の保険給付は、3つに分けられます。
法定給付 |
任意給付 | |
絶対的必要給付 | 相対的必要給付 | |
療養の給付 入院時食事療養費 入院時生活療養費 保険外併用療養費 療養費 訪問看護療養費 特別療養費 移送費 高額療養費 高額介護合算療養費 | 出産育児一時金 葬祭費、葬祭の給付 | 傷病手当金 出産手当金 |
相対的必要給付と任意給付の条文を読んでみましょう。
第58条 ① 市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
② 市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、①の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。 |
①は相対的必要給付です。
「給付を行うものとする」となっていますが、「特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」のがポイントです。
②は任意給付です。
傷病手当金その他の保険給付(出産手当金)は、「行うことができる」となっています。給付を行うか行わないか、また、内容についても保険者が決定します。
では、過去問をどうぞ!
①【H26年出題】※改正による修正あり
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
②【R1年出題】
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
③【H26年出題】※改正による修正あり
市町村(特別区を含む)及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる

【解答】
①【H26年出題】 ×
「移送費」は絶対的必要給付です。
条文では、「市町村及び組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を支給する。」となっています。
問題文の「条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。」では相対的必要給付になりますので間違いです。
②【R1年出題】 〇
出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付は、相対的必要給付です。
③【H26年出題】 〇
「傷病手当金の支給」は任意給付です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者医療確保法 費用
高齢者医療確保法 費用
R5-275
R5.5.29 後期高齢者支援金
75歳以上の後期高齢者は、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
後期高齢者医療の財源は、「公費・後期高齢者支援金・後期高齢者の保険料」です。
今日は、後期高齢者支援金を中心にみていきます。
後期高齢者支援金は、現役世代からの支援金のことです。
では、条文を読んでみましょう。
第100条第1項、4項 (後期高齢者交付金) ① 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において負担する費用のうち、負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の50を控除して得た率を乗じて得た額並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額の合計額(以下「保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金をもって充てる。 ④ 後期高齢者交付金は、第118条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が徴収する後期高齢者支援金をもって充てる。 |
★後期高齢者負担率とは
・後期高齢者の保険料で負担する割合で、2年ごとに政令で定められます。令和4年度・5年度は、11.72%です。
★100分の50とは
・公費で負担する割合です
第118条 (後期高齢者支援金等の徴収及び納付義務) ① 社会保険診療報酬支払基金は、第139条第1項第2号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)を徴収する。 ② 保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負う。 |
★保険者とは
・医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団です。
後期高齢者医療広域連合 |
↑ 後期高齢者交付金 |
社会保険診療報酬支払基金 |
↑ 後期高齢者支援金等 |
保険者 |
↑ 保険料 |
医療保険の被保険者(現役世代) |
★高齢者医療の財政のうち、後期高齢者支援金(現役世代からの支援)の占める割合は約4割です。
過去問をどうぞ!
①【H28年出題】(※改正による修正あり)
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
②【H22年出題】
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。

【解答】
①【H28年出題】(※改正による修正あり) ×
保険者(国民健康保険にあっては、都道府県。)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収するのは、都道府県ではなく、「社会保険診療報酬支払基金」です。
②【H22年出題】 ×
国が交付する調整交付金は、3分の1ではなく「12分の1」です。
(法第95条)
★公費について
(国の負担)
・負担対象額の12分の3+調整交付金(負担対象額の12分の1)
(都道府県の負担)
・負担対象額の12分の1
(市町村の一般会計における負担)
・負担対象額の12分の1
(法第93条、95条、96条、98条)
12分の3+12分の1+12分の1+12分の1=「12分の6」です。公費が占める割合は約50%となります。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者医療確保法 特定健康診査
高齢者医療確保法 特定健康診査
R5-264
R5.5.18 高齢者医療確保法 40歳以上の加入者に対する特定健康診査
特定健康診査は、40歳から74歳の人を対象に、生活習慣病を予防するために行われます。
条文を読んでみましょう。
第18条第1項 (特定健康診査等基本指針) 厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
第19条第1項 (特定健康診査等実施計画) 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
第20条(特定健康診査) 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、 40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 |
高齢者医療確保法で「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。(法第7条第2項)
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
・ 厚生労働大臣は、< A >(糖尿病その他の政令で定める< B >に関する健康診査をいう。)及び< C >の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「< A >等基本指針」という。)を定めるものとする。
・ 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、< A >等基本指針に即して、< D >年ごとに、< D >年を1期として、< A >等実施計画を定めるものとする。
・ 保険者は、< A >等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< E >歳以上の加入者に対し、< A >を行うものとする。

【解答】
A 特定健康診査
B 生活習慣病
C 特定保健指導
D 6
E 40
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】(改正による修正あり)
保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村。)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。
②【H29年出題】(改正による修正あり)
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定めます。
↓
保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めます。
↓
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行います。
②【H29年出題】 〇
高齢者医療確保法における保険者は、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 確定拠出年金法 脱退一時金
確定拠出年金法 脱退一時金
R5-247
R5.5.1 確定拠出年金法 脱退一時金の支給要件
確定拠出年金法の給付は、「老齢給付金、障害給付金、死亡一時金」ですが、「当分の間、脱退一時金の支給を請求することができる」とされています。
今日は、脱退一時金の要件をみていきましょう。
では、条文を読んでみましょう。
「企業型年金」と「個人型年金」がありますが、今回は「個人型」です。
附則第3条第1項、施行令第60条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。 1. 60歳未満であること。 2. 企業型年金加入者でないこと。 3. 個人型年金に加入できない者であること。 4. 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。 5. 障害給付金の受給権者でないこと。 6. その者の通算拠出期間が1月以上5年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が25万円以下であること。 7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。 |
ポイント!
3.について
個人型年金に加入できない者とは
・国民年金第1号被保険者で、保険料の申請免除の対象者、生活保護法による生活扶助を受ける法定免除の対象者
・日本国籍を有しない海外居住者
4.について
国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者とは
・国民年金の任意加入被保険者のうち「日本国籍を有する海外居住者」です。
★ 令和4年5月から、外国籍の人が海外に居住し、国民年金の被保険者になることができなくなった場合に、要件を満たせば、脱退一時金を請求することができるようになりました。
ポイントを穴埋めで確認しましょう。
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては < A >に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
1. < B >歳未満であること。
2. 企業型年金加入者でないこと。
3. 個人型年金に加入できない者であること。
4. 国民年金法附則第5条第1項第3号に掲げる者に該当しないこと。
5. 障害給付金の受給権者でないこと。
6. その者の通算拠出期間が< C >以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が< D >円以下であること。
7. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < E >年を経過していないこと。

【解答】
A 個人型記録関連運営管理機関
B60
C1月以上5年
D25万
E 2
では、過去問をどうぞ!
【H29年出題】
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】
【H29年出題】 ×
通算拠出期間については「1月以上5年以下」であること、又は個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については「25万円以下」であることです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律
R5-235
R5.4.19 後期高齢者医療制度の基本
後期高齢者医療は、原則として75歳以上の人を被保険者としています。
後期高齢者医療は、「後期高齢者支援金(現役世代からの支援金)」と「公費」と「被保険者の保険料」で賄われています。高齢者も被保険者として保険料を負担していることがポイントです。
条文を読んでみましょう。
第47条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第49条 後期高齢者医療広域連合及び市町村は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2. 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1. 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 2.1.に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
②【H29年出題】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入して設けられる。
③【H22年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
④【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】
①【H29年出題】 ×
後期高齢者医療は、高齢者の「疾病、負傷又は死亡」に関して必要な給付を行います。死亡に関しても給付を行います。
②【H29年出題】 〇
後期高齢者医療制度を運営するのは、後期高齢者医療広域連合です。後期高齢者医療広域連合は都道府県単位の広域連合で、当該区域内のすべての市町村(特別区を含む。)が加入しています。
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務を処理しますが、「保険料の徴収の事務」は除かれていることに注意してください。
保険料の徴収は、市町村が行います。
③【H22年出題】 ×
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する「75」歳以上の者、または65歳以上「75」歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者です。
④【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療の被保険者になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険労務士法
社会保険労務士法
R5-220
R5.4.4 社会保険労務士に対する懲戒処分
社会保険労務士に対する懲戒処分をみていきましょう。
社会保険労務士に対する懲戒処分は次の3種類です。(法第25条)
① 戒告
② 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
③ 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)
懲戒処分の条文を読んでみましょう。
第25条の2(不正行為の指示等を行った場合の懲戒) 1 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等の禁止の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、1に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
第25条の3(一般の懲戒) 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分をすることができる。
|
社会保険労務士に対して懲戒処分をする権限があるのは、「厚生労働大臣」です。
では、過去問をどうぞ!
①【H20年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。
②【H26年出題】
社会保険労務士は、所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえる。
③【R1年出題】
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】
①【H20年出題】 ×
懲戒処分をする権限は、全国社会保険労務士会連合会には委任されていません。
②【H26年出題】 〇
社会保険労務士法第25条の30で、「社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。」と規定されています。
そのため、会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となりえます。
③【R1年出題】 ×
社会保険労務士会は、「所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき」は、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、『注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。』と規定されています。(第25条の33)
社会保険労務士会による注意勧告の対象になります。
社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分の対象ではありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険一般常識
社会保険一般常識
R5-207
R5.3.22 社会保険制度改正の施行日
社会保険制度の改正の施行日を確認しましょう。
さっそく、令和元年の過去問をどうぞ!
【R1年問10】
社会保険制度の改正に関する次の①から⑥の記述について、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、後記AからEまでのうちどれか。
① 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。
② 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。
③ 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。
④ 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号(マイナンバー)でも行えるようになった。
⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。
⑥ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。
A①→②→③→⑤→④→⑥
B③→①→②→⑤→⑥→④
C②→①→④→⑤→③→⑥
D③→②→①→⑤→⑥→④
E②→③→①→⑤→⑥→④

【解答】
A①→②→③→⑤→④→⑥
① 被用者年金一元化の施行は、平成27年10月1日です。
70歳未満の共済組合の組合員や私立学校教職員共済制度の加入者が、厚生年金保険法の被保険者になったのは、平成27年10月1日からです。
その際、厚生年金保険の被保険者が4つの種別に区分されるようになりました。
1 第1号厚生年金被保険者 → 2から4までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(民間企業の会社員)
2 第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
3 第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者
4 第4号厚生年金被保険者 → 私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者
② 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額は、平成28年4月1日に改正されました。
端数処理もチェックしておきましょう。
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額(→ 5円未満切捨て、5円以上10円未満10円に切り上げ)に3分の2を乗じた額(→ 50銭未満切捨て、50銭以上1円未満1円に切り上げ)です。
③ 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになったのは、平成29年1月1日です。
④ 老齢基礎年金の年金請求について、マイナンバーでも行えるようになったのは、平成30年3月5日です。
⑤ 老齢基礎年金の受給資格期間が「10年以上」に短縮されたのは、平成29年8月1日です。
⑥ 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになったのは平成31年4月1日です。
ちなみに、国民年金法の「保険料納付済期間」は国民年金法第5条第1項で、「第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定により徴収された保険料を含み、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。」と定義されています。
「産前産後の国民年金保険料免除期間」は保険料免除期間ではなく、保険料納付済期間に入りますので注意しましょう。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法 被保険者
国民健康保険法 被保険者
R5-184
R5.2.27 国民健康保険の適用除外
国民健康保険の対象になるのは、被用者保険(健康保険など)に加入していない人です。
また、国民健康保険の保険者には「都道府県等」と「国民健康保険組合」があります。
今日は、国民健康保険の適用除外を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第5条 (被保険者) 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。 1 健康保険法の規定による被保険者。ただし、日雇特例被保険者を除く。 2 船員保険法の規定による被保険者 3 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 4 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 5 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 6 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 7 健康保険法の日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。 8 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 9 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 10国民健康保険組合の被保険者 11 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
国民健康保険から除外されるのは、以下の通りです。
・健康保険などの被用者保険の被保険者とその被扶養者
・後期高齢者医療の被保険者
・生活保護を受けている人
などです。
では、過去問をどうぞ!
①【R3年出題】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。
②【H20年出題】
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
③【H20年出題】
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
①【R3年出題】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となりません。
②【H20年出題】 〇
後期高齢者医療の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
※なお、後期高齢者医療の被保険者になるのは、次の人です。
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
③【H20年出題】 〇
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者になりません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険一般常識 確定拠出年金法
社会保険一般常識 確定拠出年金法
R5-173
R5.2.16 確定拠出年金のポイント!
過去問を解きながら、確定拠出年金のポイントをみていきましょう。
では、過去問をどうぞ!
①【R3問6-A】
企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月のみ、企業型年金加入者となる。
②【R3問6-B】
企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。
③【R3問6-C】
企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。
④【R3問6-D】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
⑤【R3問6-E】
個人型年金加入者期間を計算する場合には、個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。

【解答】
①【R3問6-A】 ×
法第12条で、企業型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、「その資格を取得した日にさかのぼって、企業型年金加入者でなかったものとみなす。」と規定されています。
(法第12条)
②【R3問6-B】 〇
法第19条第1項で、企業型年金において、事業主は、政令で定めるところにより、「年1回以上」、定期的に掛金を拠出すると規定されています。「年1回以上」がポイントです。
なお、第19条第3項で、「企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。」と規定されていて、企業型年金加入者も自ら掛金を拠出することができます。
語尾にも注目してください。事業主は「掛金を拠出する」ですが、企業型年金加入者の方は「掛金を拠出することができる」で任意になっていることにも注意してください。
③【R3問6-C】 〇
企業型年金加入者掛金は、自ら掛金を拠出することができますが、企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、「企業型年金加入者が決定し、又は変更する。」とされています。(法第19条第3項)
なお、事業主掛金の額は、「企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。」とされています。(法第19条第2項)
④【R3問6-D】 〇
国民年金第3号被保険者も、個人型年金加入者となることができます。
(法第62条)
⑤【R3問6-E】 〇
個人型年金加入者期間については、条文を読んでみましょう。
第63条第1項、第2項
① 個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
② 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 児童手当法 児童手当いろいろ
児童手当法 児童手当いろいろ
R5-146
R5.1.20 児童手当の支給ルール
児童手当法はよく出題されます。ポイントをしっかりおさえましょう。
では、さっそく令和2年の過去問をどうぞ!
①【R2問8-A】
「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。
②【R2問8-B】
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
③【R2問8-C】
児童手当の支給を受けている者につき、児童手当の額が増額することとなるに至った場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
④【R2問8-D】
児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
⑤【R2問8-E】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

【解答】
①【R2問8-A】 〇
「児童」の定義です。「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」ですので、高校卒業までが児童となります。
児童は、「日本国内に住所を有すること」が条件ですが、留学などの理由で海外に住んでいる場合も対象となります。
なお、「支給要件児童」は、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(施設入所等児童を除く。「中学校修了前の児童」という。)と「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(施設入所等児童を除く。)」ですので、年齢の違いに注意してください。
(法第3条第1項、第4条第1項第1号)
②【R2問8-B】 ×
児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払います。例えば、10月に支給されるのは、6月~9月分です。
前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払われます。
(法第8条第4項)
③【R2問8-C】 〇
児童手当の増額は、額の改定の認定の請求をした日の属する月の翌月から行われます。手続きが遅れた場合は、原則として遅れた分が受けられなくなります。
(法第9条)
④【R2問8-D】 〇
児童手当を受けるのは、支給要件児童を監護し、かつこれと生計を同じくする父又は母等です。児童本人が受けるのではありませんので注意してください。
一般受給資格者が死亡した場合で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、支給の対象になっていた児童に、その未支払の児童手当が支払われます。
(法第12条)
⑤【R2問8-E】 〇
児童手当を不正受給した場合は、罰則があります。
(法第31条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 確定給付企業年金法
確定給付企業年金法
R5-137
R5.1.11 確定給付企業年金の掛金・支給のルール
今日のテーマは確定給付企業年金です。
確定給付企業年金の給付には、「老齢給付金」と「脱退一時金」があります。
また、規約で定めるところにより、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付も行うことができます。
さっそく過去問をどうぞ!
①【R2問6-A】
加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
②【R2問6-B】
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
③【R2問6-C】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
④【R2問6-D】
老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
⑤【R2問6-E】
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】
①【R2問6-A】 ×
★加入者期間の計算について
加入者期間の計算は月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の「前月」までが算入されます。
(法第28条)
②【R2問6-B】 ×
★掛金について
・事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
・加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。
(法第55条)
加入者が負担できるのは、掛金の一部です。加入者が掛金の全部を負担することはできません。
③【R2問6-C】 ×
★年金給付の支給期間について
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
(法第33条)
年金給付の支給期間は、終身又は10年以上ではなく、「終身又は5年以上」です。
④【R2問6-D】 〇
老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができます。
(法第39条)
⑤【R2問6-E】 ×
★老齢給付金の失権について
老齢給付金の受給権は、1~3のいずれかに該当することとなったときは、消滅します。
1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
(法第40条)
老齢給付金の受給権は、「老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき」にも、消滅します。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
R5-106
R4.12.11 R4択一式より 住所地特例の適用(介護保険)
介護保険法の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類があります。
条文を読んでみましょう。
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(以下「第1号被保険者」という。) 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(以下「第2号被保険者」という。) |
 介護保険の保険者は「市町村及び特別区」です。第1号被保険者も第2号被保険者も、住所地の市町村の介護保険の被保険者となるのが原則です。
介護保険の保険者は「市町村及び特別区」です。第1号被保険者も第2号被保険者も、住所地の市町村の介護保険の被保険者となるのが原則です。
しかし、介護保険法には「住所地特例」があります。住所地特例とは、一定の施設に入所し住民票を移しても、引き続き、移す前の市町村の被保険者となる仕組みです。
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問10-E】
介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となる。

【解答】
【問10-E】 〇
問題文の場合は、住所地特例によって、特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村が引き続き保険者となります。
住所地特例対象施設は、「介護保険施設」、「特定施設」、「老人福祉法に規定する養護老人ホーム」です。
(法第13条)
用語の定義も確認しましょう。
・「介護保険施設」は、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院をいいます。
(法第8条第25項)
・「特定施設」は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいいます。
(法第8条第11項)
では、過去問をどうぞ!
【R1年出題】
A県A市に住所を有していた介護保険の第2号被保険者(健康保険の被扶養者)が、B県B市の介護保険法に規定する介護保険施設に入所することとなり住民票を異動させた。この場合、住所地特例の適用を受けることはなく、住民票の異動により介護保険の保険者はB県B市となる。

【解答】
【R1年出題】 ×
介護保険法に規定する介護保険施設は、住所地特例対象施設です。
問題文の場合は、住所地特例の適用を受けますので、介護保険の保険者はA県A市のままです。
(法第13条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(介護保険法)
R5-074
R4.11.9 R4択一式より 介護保険法の保険給付
今日は介護保険の保険給付を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第18条 (保険給付の種類) 介護保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 ① 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。) ② 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。) ③ ①、②に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(「市町村特別給付」という。) |
第62条 市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対し、前2節の保険給付のほか、条例で定めるところにより、市町村特別給付を行うことができる。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-C】
介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。

【解答】
【問9-C】 ×
市町村特別給付は、「行わなければならない」ではなく、「行うことができる」です。
では、過去問もどうぞ!
①【H29年出題】
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。
②【H24年出題】
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
介護保険法の保険給付は、「介護給付」、「予防給付」、「市町村特別給付」の3つです。
②【H24年出題】 ×
厚生労働大臣ではなく「市町村又は特別区」の認定を受けなければなりません。
条文をチェックしましょう。
第19条 (市町村の認定)
1 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(以下「要介護認定」という。)を受けなければならない。
2 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(高齢者医療確保法)
令和4年の問題を復習しましょう(高齢者医療確保法)
R5-073
R4.11.8 R4択一式より 後期高齢者医療・保険料の徴収
後期高齢者医療の費用は、「公費」、「後期高齢者交付金(医療保険各法の保険者からの支援金)」、「後期高齢者が負担する保険料」で構成されています。
今日のテーマは後期高齢者の保険料の徴収です。
まず、後期高齢者の保険料のポイントを確認しましょう。
市町村は、後期高齢者医療に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。(第104条)
ポイント!保険料を徴収するのは「市町村」です。
では、保険料の徴収の方法を条文で読んでみましょう。
第107条第1項 (保険料の徴収の方法) 市町村による保険料の徴収については、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によらなければならない。 |
 保険料の徴収には「特別徴収」と「普通徴収」がありますが、「特別徴収」が原則です。
保険料の徴収には「特別徴収」と「普通徴収」がありますが、「特別徴収」が原則です。
特別徴収とは、「市町村が老齢等年金給付を受ける被保険者(政令で定める者を除く。)から老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させること」をいいます。→ 年金保険者が年金から保険料を天引きし、それを年金保険者が納入する方法です。
特別徴収以外は、普通徴収となります。
普通徴収とは、「市町村が、保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収すること」をいいます。 → 個別に保険料を納付する方法です。
「普通徴収」の条文を読んでみましょう。
第108条 (普通徴収に係る保険料の納付義務) 1 被保険者は、市町村がその者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合においては、当該保険料を納付しなければならない。 2 世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 3 配偶者の一方は、市町村が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問9-D】
後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村(特別区を含む。)が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

【解答】
【問9-D】 〇
世帯主は、保険料を連帯して納付する義務を負っています。
では、過去問もどうぞ!
①【H23年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
②【H23年出題】
保険料徴収には、①特別徴収、②普通徴収、③その他の3つの方法があるが、そのうち、①は老齢等年金給付を受ける被保険者から老齢等年金給付の支払をする者に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいい、②は保険料を課せられた被保険者又は当該被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該被保険者の配偶者に対し、地方自治法第231条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。
③【H27年出題】
高齢者医療確保法では、配偶者の一方は、市町村(特別区を含む。)が被保険者たる他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うことを規定している。
④【H23年出題】
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令で定める。

【解答】
①【H23年出題】 ×
保険料を徴収するのは、市町村(特別区を含む。)です。都道府県は徴収しません。なお、保険料は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために徴収します。
②【H23年出題】 ×
保険料徴収の方法は、①特別徴収、②普通徴収の2つです。③その他はありませんので誤りです。
①特別徴収と②普通徴収の定義は問題文の通りです。
③【H27年出題】 〇
配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負います。
④【H23年出題】 ×
普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、政令ではなく「市町村の条例」で定めます。(第109条)
ちなみに、「政令」は内閣が制定するものです。条例は自治体の法令です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(国民健康保険法)
令和4年の問題を復習しましょう(国民健康保険法)
R5-072
R4.11.7 R4択一式より 国民健康保険組合の設立
まず、国民健康保険の「保険者」を確認しましょう。
条文を読んでみましょう。
第3条 (保険者) 1 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 |
・都道府県と市町村がともに、保険者として国民健康保険を運営します。
・国民健康保険組合は、業種ごとに組織されています。
今日のテーマの「国民健康保険組合の設立」について条文を読んでみましょう。
第13条(組織) 1 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 2 組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
第17条 (設立) 1 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。 5 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。 |
では、令和4年の問題をどうぞ!
【問8-A】
国民健康保険組合(以下「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100人以上の同意を得て行うものとされている。

【解答】
【問8-A】 ×
認可の申請は、「15人以上」の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者 「300人以上」の同意を得て行うものとされています。
では、過去問もどうぞ!
①【H28年出題】
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。
②【R2年選択】
国民健康保険法第13条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、< A >の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。

【解答】
①【H28年出題】 〇
「都道府県知事」の認可がポイントです。厚生労働大臣の認可ではありませんので注意してください。
②【R2年選択】
A 1又は2以上の市町村
1又は2以上の「都道府県」ではありませんので、注意してください。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年の問題を復習しましょう(社会保険労務士法)
令和4年の問題を復習しましょう(社会保険労務士法)
R5-035
R4.10.2 R4択一式より『補佐人制度』
社会保険労務士は、労働や社会保険に関する事項について、裁判所で、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができます。
令和4年の問題から、補佐人制度を確認しましょう。
では、条文を読んでみましょう。
第2条の2 ① 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 ② 陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第25条の9の2 社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。 |
では、過去問からどうぞ!
①【R1年出題】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
②【H28年出題】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
③【H30年出題】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちからその補佐人を選任しなければならない。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく、「弁護士である訴訟代理人とともに」出頭し、陳述をすることができます。
②【H28年出題】 ×
補佐人として、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができるのは、特定社会保険労務士に限られません。
③【H30年出題】 ×
社会保険労務士法人は、裁判所において補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述する事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができます。
この場合、当該社会保険労務士法人は、「委託者に」、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければなりません。
『「当該社会保険労務士法人」がその社員のうちからその補佐人を選任しなければならない。』が誤りです。
令和4年の問題をどうぞ!
【問5-A】
社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、行った陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが、当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

【解答】
【問5-A】 〇
社会保険労務士が補佐人として行った陳述は、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取リ消し、又は更生しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年基本問題(社会保険一般常識)
令和4年基本問題(社会保険一般常識)
R5-026
R4.9.23 R4択一式より『高齢者医療確保法 審査請求』
国民健康保険法、介護保険法、高齢者医療確保法の「審査請求」は、横断学習が効果的です。
令和4年は、高齢者医療確保法から審査請求の問題が出題されました。
では、3つまとめて条文を読んでみましょう。
(国民健康保険法) 第91条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 第92条 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。
(介護保険法) 第183条 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 第184条 介護保険審査会は、各都道府県に置く。
(高齢者の医療の確保に関する法律) 第128条 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。 第129条 後期高齢者医療審査会は、各都道府県に置く。 |
★ 審査請求先は「社会保険審査会」ではありませんので注意しましょう。
「国民健康保険審査会」「介護保険審査会」「後期高齢者医療審査会」は各都道府県に置かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【国民健康保険法・H18年出題】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
②【国民健康保険法・R1年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
③【介護保険法・R3年出題】
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
④【高齢者医療確保法・H25年出題】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
令和4年の問題です!
⑤【高齢者医療確保法・R4問7-E】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

【解答】
①【国民健康保険法・H18年出題】 ×
社会保険審査会ではなく、「国民健康保険審査会」です。
②【国民健康保険法・R1年出題】 〇
ポイントは、「国民健康保険審査会」です。
なお、「徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)」のカッコの部分は、国民健康保険法第78条に規定されています。
③【介護保険法・R3年出題】 〇
介護保険審査会は、各都道府県に置かれます。
④【高齢者医療確保法・H25年出題】 ×
社会保険審査会ではなく、「後期高齢者医療審査会」です。
⑤【高齢者医療確保法・R4問7-E】 〇
後期高齢者医療審査会がポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 令和4年択一式を解いてみる(社保一般常識)
令和4年択一式を解いてみる(社保一般常識)
R5-016
R4.9.13 R4「社一択一」は全て法令からの出題。今日は『確定給付企業年金法』について
令和4年の社会保険一般常識の択一式は、全問、法令からの出題でした。
細かい箇所からの出題も多かったので、難しく感じた方も多かったのではないでしょうか。
今日は、「確定給付企業年金法」の問題をみていきましょう。
では、令和4年問6「確定給付企業年金法」の問題をどうぞ!
A
確定給付企業年金法第16条の規定によると、企業年金基金(以下「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。
B
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。
C
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
D
企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10以上の事業主等が発起人とならなければならない。
E
連合会は、毎事業年度終了後6か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

【解答】
A × 基金は、規約の変更については、厚生労働大臣の同意ではなく、厚生労働大臣の「認可」を受けなければならないとされています。
(法第16条)
B × 障害給付金は、「給付を行わなければならない」ではなく「給付を行うことができる」です。
(法第29条第2項)
C ×
少なくとも6年ごとではなく、少なくとも「5年」ごとに掛金の額を再計算しなければならないとされています。
(法第57条、第58条)
D ×
10以上ではなく、その会員となろうとする「20以上」の事業主等が発起人とならなければならない、です。
(法第91条の5)
E 〇
「6か月以内」がポイントです。
(法第100条の2)
選択式の練習もどうぞ!
| 第16条 基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の< A >を受けなければならない。 |
(給付の種類) ① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 < B > ② 事業主等は、規約で定めるところにより、①各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 1 障害給付金 2 < C > |
第57条 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。 第58条 事業主等は、少なくとも< D >ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。 |
事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。 連合会は、全国を通じて1個とする。 連合会を設立するには、その会員となろうとする< E >以上の事業主等が発起人とならなければならない。 |
連合会は、毎事業年度終了後< F >以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 |

選択練習の解答
A 認可
B 脱退一時金
C 遺族給付金
D 5年
E 20
F6か月
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 復習しましょう/令和4年選択式⑥
復習しましょう/令和4年選択式⑥
R5-006
R4.9.3 令和4年「社一選択」は統計から1問、法令から4問
令和4年の社会保険の一般常識の選択は、統計から1問、法令から4問出題されました。
 「令和元年度国民医療費の概況」から
「令和元年度国民医療費の概況」から
~令和元年度の国民医療費の状況~
・令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円です。
前年度の43兆3,949億円に比べ9,946億円、2.3%の増加となっています。
~年齢階級別国民医療費~
・年齢階級別にみると、0~14歳は 2兆 4,987億円(構成割合5.6%)、15~44 歳は 5兆2,232億円(同11.8%)、45~64 歳は9兆6,047億円(同 21.6%)、65歳以上は 27兆629億円(同61.0%)となっています。
★65歳以上の構成割合が問われました。
参照:厚生労働省 令和元(2019)年度 国民医療費の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/19/index.html
 確定拠出年金の「死亡一時金」を受ける遺族の順位
確定拠出年金の「死亡一時金」を受ける遺族の順位
確定拠出年金法第41条からの出題です。
第41条 死亡一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者が、死亡する前に、配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示したときは、その表示したところによるものとする。 ① 配偶者 ② 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたもの ③ 前号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していた親族 ④ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって②に該当しないもの |
遺族の順位は、条文に並んでいる順位です。
配偶者は「生計維持」の条件が無いことに注目してください。
「生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹」がいた場合、第一順位は「配偶者」です。
★「死亡一時金」の遺族の順位まで覚えていた人は少ないと思います。優先されるのが「配偶者」なのか、それとも「生計維持」なのかで、迷った方が多かったのではないでしょうか?
 児童手当法の費用の負担について
児童手当法の費用の負担について
児童手当法で「児童」とは、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。」と定義されています。
また、「支給要件児童」は、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)、中学校修了前の児童を含む2人以上の児童(どちらも施設入所等児童を除く。)」をいいます。
★被用者に対する児童手当の支給に要する費用の問題ですが、費用が発生するのは、中学校修了前の児童と考えると、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」が選べると思います。
 介護保険法の「要介護状態」の定義について
介護保険法の「要介護状態」の定義について
介護保険法第7条で、「「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6か月の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。」と定義されています。
★重要用語の定義は、きちんと覚えておくことがポイントです。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 厚生年金保険・国民年金事業の概況
厚生年金保険・国民年金事業の概況
R4-367
R4.8.24 令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況
「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をチェックしましょう。
★適用状況 ・ 公的年金被保険者数は、令和2年度末現在で6,756万人となっており、前年度末に比べて6万人(0.1%)減少している。 ・ 国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、令和2年度末現在で1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)減少している。 ・ 厚生年金被保険者数(第1~4号)は、令和2年度末現在で4,513万人(うち第1号4,047万人、第2~4号466万人)となっており、前年度末に比べて25万人 (0.6%)増加している。 ・ 国民年金の第3号被保険者数は、令和2年度末現在で793万人となっており、前年度末に比べて27万人(3.3%)減少している。
★厚生年金保険 適用状況 ※ この統計では基本的に、被用者年金一元化により新たに厚生年金保険の適用対象となった、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団の情報を含まない。 ・ 令和2年度末現在の適用事業所数は、250万9千か所であり、前年度末に比べて7.4万か所(3.0%)増加している。 ・ 被保険者数は、令和2年度末現在で4,047万人となっており、前年度末に比べて 10万人(0.2%)増加している。男女別にみると、男子は2,479万人(対前年度末比9万人、0.4%減)、女子は1,569万人(対前年度末比19万人、1.2%増)となっている。 ・ 短時間労働者数は、令和2年度末現在で53万人となっており、前年度末に比べて6万人(12.3%)増加している。男女別にみると、男子は14万人(対前年度末比1万人、6.6%増)、女子は39万人(対前年度末比5万人、14.4%増)となっている。 ・ 育児休業等期間中(産前産後休業期間を含む)の保険料免除者数は、令和2年度末現在で45万人であり、前年度末に比べて2万人(5.0%)増加している。男女別にみると、男子は1万人(対前年度末比3千人、35.2%増)、女子は44万人(対前年度末比2万人、4.5%増)となっている。
★国民年金 適用状況(第1号被保険者及び第3号被保険者) ・ 令和2年度末現在の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)減少している。男女別にみると、男子は758万人(対前年度末比1万人、0.2%増)、女子は691万人(対前年度末比5万人、0.7%減)となっている。 ・ 令和2年度末現在の第3号被保険者数は、793万人となっており、前年度末に比べて27万人(3.3%)減少している。男女別にみると、男子は12万人(対前年度末比3千人、2.9%増)、女子は781万人(対前年度末比28万人、3.4%減)となっている。 ・ 令和2年度末現在の全額免除・猶予者数は609万人、全額免除・猶予割合は 42.6%となっている。 ・ 令和2年度末現在の一部免除者数は36万人、一部免除割合は2.5%となっている。 ・ また、令和元年度から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が施行されている。令和2年度末現在の産前産後免除者数は、1万人となっている。 |
問題を解いてみましょう。
【問題1】
国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)は、令和2年度末現在で1,449万人となっており、前年度末に比べて4万人(0.3%)< A >している。
(選択肢)
① 増加
② 減少
【問題2】
短時間労働者数は、令和2年度末現在で53万人となっており、前年度末に比べて 6万人(12.3%)増加している。男女別にみると、男子は< B >万人(対前年度末比1万人、6.6%増)、女子は< C >万人(対前年度末比5万人、14.4%増)となっている。
(選択肢)
① 14
② 30
③ 39
④ 23
【問題3】
令和元年度から国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が施行されている。令和2年度末現在の産前産後免除者数は、< D >万人となっている。
(選択肢)
① 1
② 10
③ 100

【解答】
【問題1】
A ② 減少
【問題2】
B ① 14
C ③ 39
【問題3】
D ① 1
参照:厚生労働省『令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106808_1.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保障統計
社会保障統計
R4-357
R4.8.14 介護保険・後期高齢者医療の統計
出題実績のある統計をチェックしましょう。
<令和3年度 後期高齢者医療制度被保険者実態調査> ■被保険者の年齢構成 令和3年9月30日現在の被保険者数は18,145千人となっており、うち75歳以上の被保険者数は17,852千人で、被保険者の98.4%を占めている。一定の障害の状態にあるとして認定を受けた65歳から74歳の被保険者数は293千人となっている。また、被保険者の平均年齢は82.9歳となっている。 |
<令和元年度 介護保険事業状況報告> ■要介護(要支援)認定者数 要介護(要支援)認定者(以下「認定者」という。)数は、令和元年度末現在で 669万人となっている。うち、第1号被保険者は656万人(男性204万人、女性452万人)、第2号被保険者は13万人(男性7万人、女性6万人)となっている。
認定を受けた第1号被保険者のうち、前期高齢者(65歳~75歳未満)は73万人、後期高齢者(75歳以上)は583万人で、第1号被保険者の認定者に占める割合は、それぞれ11.1%、88.9%となっている。
認定者を要介護(要支援)状態区分別にみると、要支援1:93万人、要支援2: 94万人、要介護1:135万人、要介護2:116万人、要介護3:88万人、要介護4:82万人、要介護5:60万人となっており、軽度(要支援1~要介護2)の認定者が 約65.6%を占めている。 |
では、問題をどうぞ!
【問1】 (平成27年に出題された問題を修正しています。)
「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省)」によると、令和3年9月30日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数は、5,547千人となっており、うち75歳以上の被保険者数は被保険者の79.6%を占めている。
【問2】 (平成27年に出題された問題を修正しています。)
「令和元年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」によると、要介護(要支援)認定者数は、令和元年度末現在で1,561万人となっており、そのうち軽度(要支援1から要介護2)の認定者が、全体の約83.5%を占めている。

【解答】
【問1】 ×
「令和3年度後期高齢者医療制度被保険者実態調査(厚生労働省)」によると、令和3年9月30日現在の後期高齢者医療制度の被保険者数は、「18,145千人」で、うち75歳以上の被保険者数は被保険者の「98.4%」を占めています。
【問2】 ×
「令和元年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」によると、要介護(要支援)認定者数は、令和元年度末現在で「669万人」で、そのうち軽度(要支援1から要介護2)の認定者が、全体の約「65.6%」を占めています。
※厚生労働省「後期高齢者医療制度被保険者実態調査」を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/seido/kouki_jittai.html
※厚生労働省「令和元年度 介護保険事業状況報告」を参照しています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/19/index.html
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保障費用統計
社会保障費用統計
R4-347
R4.8.4 令和元(2019)年度社会保障費用統計
令和元(2019)年度社会保障費用統計のポイントを確認しましょう。
・ 2019 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は 123 兆 9,241 億円であり、対前年度増加額は 2 兆 5,254 億円、伸び率は 2.1%、対 GDP 比は 22.14%であり対前年度比で 0.34%ポイント増加した。
<社会保障給付費(ILO 基準)> (1)社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して部門別にみると、「医療」が 40 兆 7,226 億円で総額に占める割合は 32.9%、 「年金」が 55 兆 4,520 億円で44.7%、「福祉その他」が 27 兆 7,494 億円で 22.4%である。 (2)部門別給付費の対前年度伸び率は、「医療」が 2.5%、「年金」が 0.4%、「福祉その他」が 5.1%である。 (3)子どものための教育・保育給付費交付金が増加したことなどにより、「福祉その他」の伸び率が高かった。 |
では、問題をどうぞ!
<問題>
「令和元年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、令和元年度の社会保障給付費の総額は123 兆 9,241 億円であり、部門別にみると、「医療」が55 兆 4,520 億円で全体の44.7%を占めている。次いで「年金」が40 兆 7,226 億円で全体の32.9%、「福祉その他」は 27 兆 7,494 億円で 22.4%となっている。

【解答】 ×
「年金」が 55 兆 4,520 億円で全体の44.7%を占めていて、「医療」は 40 兆 7,226 億円で全体の32.9%です。
国立社会保障・人口問題研究所ホームページ(https://www.ipss.go.jp/)を参照しています
令和元年度社会保障費用統計(概要)
https://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-R01/R01-houdougaiyou.pdf
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律
R4-345
R4.8.2 後期高齢者医療
条文を読んでみましょう。
第47条 (後期高齢者医療) 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
第48条 (広域連合の設立) 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
第50条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
第51条 (適用除外) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 2 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
②【H22年出題】
市町村(特別区を含む。以下同じ)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
③【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
④【H23年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
後期高齢者医療は、高齢者の「疾病、負傷又は死亡」に関して必要な給付を行います。死亡についても給付の対象です。
②【H22年出題】 〇
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の運営主体です。
都道府県ごとにすべての市町村が加入して設けられています。
③【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、適用除外となっています。
④【H23年出題】 ×
保険料を徴収するのは、市町村(特別区を含む。)です。都道府県は徴収しません。
保険料を徴収するのは、後期高齢者医療広域連合ではないことにも注意してください。
後期高齢者医療広域連合の行う事務から、保険料の徴収の事務は除かれています。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険に関する一般常識
社会保険に関する一般常識
R4-304
R4.6.22 介護保険法「介護支援専門員」
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、訪問介護、デイサービスなどのサービスを受けられるようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行います。 (参考:厚生労働省ホームページ)
条文を読んでみましょう。
第69条の2 (介護支援専門員の登録) 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、介護支援専門員実務研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、一定の事由に該当する者については、この限りでない。 |
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りでない。
②【H26年出題】
介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。

【解答】
①【H22年出題】 〇
(参考)介護保険法第69条の2第1項各号に掲げられているのは、「心身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者」等です。
②【H26年出題】 〇
登録を受けている者は、都道府県知事に対し、「介護支援専門員証」の交付を申請することができます。介護支援専門員証の有効期間は、5年です。ただし、法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い交付されたものは除かれます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「要介護状態」の比較
「要介護状態」の比較
R4-279
R4.5.28 「要介護状態」比較/介護保険法と育児・介護休業法と労災保険法
■介護保険の保険給付には、「介護給付」「予防給付」「市町村特別給付」があります。
「介護給付」は要介護状態にある者に対しての保険給付です。
■育児・介護休業法の「介護休業」は、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための休業です。
それぞれの「要介護状態」の定義を比較しましょう。
まず、介護保険法の条文を読んでみましょう。
第7条 (定義) 介護保険法において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。 施行規則第2条 厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。 |
次に、育児・介護休業法の条文を読んでみましょう。
第2条 (定義) 要介護状態とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
施行規則第2条 厚生労働省令で定める期間は、2週間以上の期間とする。 |
介護保険法の要介護状態は、「6月間」にわたり継続して、常時介護を要する状態、育児介護休業法の要介護状態は、「2週間以上の期間」にわたり常時介護を必要とする状態です。
法律によって違いますので、注意しましょう。
では、過去問をどうぞ!
「労災保険法」の問題です。
労災【H25年出題】
女性労働者が1週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所から帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。

【解答】
労災【H25年出題】 〇
合理的な通勤経路を逸脱・中断した場合は、逸脱・中断の間とその後の移動は通勤になりません。
しかし、逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、合理的な経路に戻ってからの移動は通勤となります。(この場合でも、逸脱・中断の間は通勤になりません。)
問題文は、日常生活上必要な行為に該当しますので、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当します。
■ ここでも「要介護状態」という用語が出てきます。定義は「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」をいいます。
(則第7条、第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法
国民健康保険法
R4-259
R4.5.8 国民健康保険の審査請求
今回は、国民健康保険の審査請求です。
条文を読んでみましょう。
第91条 (審査請求) ① 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(附則第10条第1項に規定する拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 ② 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 第92条 (審査会の設置) 国民健康保険審査会は、各都道府県に置く。 |
ポイント!
国民健康保険審査会は、各都道府県に置かれます。
では、過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
②【H18年出題】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
③【H29年出題】
国民健康保険の保険料に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【解答】
①【R1年出題】 〇
審査請求先は、「国民健康保険審査会」です。
②【H18年出題】 ×
審査請求先は、社会保険審査会ではなく「国民健康保険審査会」です。
③【H29年出題】 〇
第103条で、『第91条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。』と規定されています。
訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 介護保険法
介護保険法
R4-241
R4.4.20 要介護認定
要介護状態や要支援状態になった場合、介護保険から介護サービスが受けられます。
介護サービスを受けるには、市町村の認定が必要です。
では、条文を読んでみましょう。
第19条 (市町村の認定) ① 介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(「要介護認定」という。)を受けなければならない。 ② 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(「要支援認定」という。)を受けなければならない。 |
<要介護認定の流れ>
一次判定
市町村の認定調査員による心身の状況調査+主治医の意見書に基づくコンピュータ判定
↓
二次判定
介護認定審査会で審査判定
では、過去問をどうぞ!
①【H29年出題】
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
②【R1年出題】
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

【解答】
①【H29年出題】 〇
処分とは要介護認定申請の結果のことです。要介護認定は、原則として、申請のあった日から30日以内に行われます。
(法第27条第11項)
②【R1年出題】 〇
要介護認定は、その『申請のあった日にさかのぼって』効力が生じます。
(法第27条第8項)
次に、「介護認定審査会」の条文を読んでみましょう。
第14条 (介護認定審査会) 審査判定業務を行わせるため、市町村に介護認定審査会を置く。
第15条 (委員) ① 介護認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。 ② 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。)が任命する。
|
「介護認定審査会」は、「審査判定業務」を行うため、「市町村」に置かれるのがポイントです。
※なお、要介護認定に関する処分に不服がある場合は、「介護保険審査会」に審査請求ができます。名前が似ているので注意しましょう。「介護保険審査会」は、都道府県に置かれます。
では、過去問をどうぞ!
③【R3年出題】
介護認定審査会は、市町村(特別区を含む。)におかれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
④【H29年出題】
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。

【解答】
③【R3年出題】 ×
委員は、「要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者」のうちから、市町村長が任命します。
④【H29年出題】 〇
介護認定審査会は、厚生労働大臣が定める基準に従い「審査及び判定」を行います。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
R4-227
R4.4.6 後期高齢者医療・費用の負担
後期高齢者医療の財源は、「後期高齢者の保険料」「後期高齢者交付金」「公費」で構成されています。
構成比のイメージです。
後期高齢者の保険料
約10% | 後期高齢者交付金 (現役世代からの支援)
約40% | 公費
50% |
※現役並み所得者(3割負担の人)の費用には公費負担はありません。
では、過去問をどうぞ!
①【H22年出題】
国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象額の見込額の総額の3分の1に相当する額を調整交付金として交付する。
②【H29年出題】
市町村(特別区を含む。)は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、その一般会計において、負担対象額の一部を負担している。

【解答】
①【H22年出題】 ×
調整交付金は、負担対象額の見込額の総額の「12分の1」です。
「公費」は「国」「都道府県」「市町村」が負担しています。
負担割合は以下の通りです。
・国の負担
→ 負担対象額の12分の3+調整交付金12分の1
・都道府県の負担
→ 負担対象額の12分の1
・市町村の一般会計における負担
→ 負担対象額の12分の1
★国+都道府県+市町村=12分の6です。公費が50%を占めます。
(第93条、95条、96条、98条)
②【H29年出題】 〇
市町村(特別区を含む。)は、その一般会計において、負担対象額の12分の1を負担しています。
次に、「保険料」の過去問をどうぞ!
③【H23年出題】
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
③【H23年出題】 ×
後期高齢者医療の被保険者は保険料を負担します。
保険料を徴収するのは、「市町村(特別区を含む。)」で、「都道府県」は保険料の徴収は行いません。
(法第104条)
最後に「後期高齢者交付金」の過去問をどうぞ!
④【H28年出題】
高齢者医療確保法では、都道府県は、年度ごとに、保険者から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。

【解答】
④【H28年出題】 ×
「都道府県」ではなく、「社会保険診療報酬支払基金」が徴収します。
(法第118条)
「後期高齢者支援金」は現役世代から後期高齢者世代への支援です。
保険者
↓
↓
社会保険診療報酬支払基金
保険者から「後期高齢者支援金等」を徴収
後期高齢者医療広域連合に「後期高齢者交付金」を交付
↓
↓
後期高齢者医療広域連合
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 社会保険労務士法
社会保険労務士法
R4-226
R4.4.5 不正行為の指示等に関する懲戒
社会保険労務士に対する懲戒処分は3種類あります。
条文を読んでみましょう。
第25条 (懲戒の種類) 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。) |
次に、不正行為の指示等を行ったときの懲戒規定を読んでみましょう。
第25条の2 (不正行為の指示等を行った場合の懲戒) ① 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は不正行為の指示等を行ったときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 ② 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、①項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。 |
①は「故意に」、②は「相当の注意を怠り」の部分に注目してください。
「故意」の方が処分が重いのがポイントです。
また、主語が「厚生労働大臣」であるのもポイントです。
過去問をどうぞ!
①【H25年出題】
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。
②【H28年出題】
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができる。
③【H20年出題】
厚生労働大臣は、社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合、懲戒処分をすることができるが、この権限は政令に定めるところにより、全国社会保険労務士会連合会に委任されている。

【解答】
①【H25年出題】 〇
「故意に」真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、「1年以内の業務停止又は失格処分の処分をすることができる」とされているので、失格処分を受けることもあります。
②【H28年出題】 ×
「相当の注意を怠り」、不正行為の指示等を行ったときは、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分をすることができる」です。失格処分までは規定されていません。
③【H20年出題】 ×
懲戒処分は厚生労働大臣が行い、全国社会保険労務士会連合会への委任はありません。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法
国民健康保険法
R4-190
R4.2.28 被保険者資格証明書と特別療養費
前回からの続きです。
国民健康保険料を1年間滞納すると、被保険者証の返還が求められ代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
その場合、医療機関の窓口では医療費を全額支払い、後から自己負担以外の分が現金で返ってきます。これを「特別療養費」といいます。
では、条文を読んでみましょう。
第9条 ⑥ 世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。 |
滞納により被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書」が交付されます。
ただし、18歳の年度末までの者(高校生以下)には、有効期間6か月の短期被保険者証が交付されます。
過去問をどうぞ!
①【R1年出題】
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、その世帯の属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

【解答】
①【R1年出題】 ×
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」にある者には、有効期間を6か月とする被保険者証が交付されます。
被保険者資格証明書が交付されているときは、療養の給付等の現物給付は受けられません。しかし、高校生以下には6か月間有効の被保険者証が交付され、現物給付が受けられます。
次は「特別療養費」の条文を読んでみましょう。
第54条の3 (特別療養費) ① 市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。 |
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、「特別療養費」が支給されます。
では、過去問をどうぞ!
②【R1年出題】
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。

【解答】
②【R1年出題】 ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、「特別療養費」が支給されます。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 国民健康保険法
国民健康保険法
R4-189
R4.2.27 国民健康保険料を滞納した場合
国民健康保険の保険料の滞納については、滞納の期間で扱いが変わります。
条文を読んでみましょう。
第9条 ③ 市町村は、保険料を滞納している世帯主が、当該保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 ※ 国民健康保険組合にも準用されます。
第63条2 ① 市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6か月間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 ③ 市町村及び組合は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。 |
★ 滞納が「1年間」になると被保険者証の返還が求められ、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。(被保険者資格証明書については次回お話します。)
また、滞納が1年6カ月になると、保険給付の全部又は一部が差し止められます。
保険給付を差し止められていても、さらに滞納している場合は、差し止め中の保険給付から滞納保険料に充当されます。
では、過去問をどうぞ!
①【H28年選択式】
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。
②【R2年出題】
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

【解答】
①【H28年選択式】
A 1年間
B 被保険者資格証明書
「被保険者資格証明書」が交付されると、現物給付が受けられなくなるので、医療機関では医療費を一旦全額支払うことになります。
(法第9条第3項、6項)
②【R2年出題】 〇
滞納が1年6カ月になると保険給付の全部又は一部が差し止められ、さらに滞納すると、差し止められている保険給付から、滞納保険料に充当されます。
(法第63条の2)
★次回に続きます
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!確定給付企業年金法
ここを乗り越えよう!確定給付企業年金法
R4-165
R4.2.3 確定給付企業年金法の老齢給付金
確定給付企業年金法の給付の種類を条文で確認しましょう。
第29条 (給付の種類) ① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。 1 老齢給付金 2 脱退一時金 ② 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。 1 障害給付金 2 遺族給付金 |
確定給付企業年金の給付には、「老齢給付金」と「脱退一時金」があります。「障害給付金」と「遺族給付金」は任意です。
過去問をどうぞ!
①【H30年選択式】
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < A >

【解答】
①【H30年選択式】
A 脱退一時金
 今日は老齢給付金のお話です。
今日は老齢給付金のお話です。
老齢給付金の支給要件を条文で読んでみましょう。
第36条 (支給要件) ① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。 ② ①に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で定める年齢以上1の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。 ③ ②の政令で定める年齢は、50歳未満であってはならない。 ④ 規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
施行令第28条 (老齢給付金の支給を開始できる年齢) 法第36条第2項第2号の政令で定める年齢は、50歳とする。 |
 ポイント!
ポイント!
老齢給付金の支給開始時期は、60歳から70歳の間で、規約で設定することができます。
また、規約で定めることにより、50歳以上の規約で定める年齢で労働者が退職した場合に支給することもできます。
老齢給付金を支給するための加入者期間は20年以下であることが条件です。
では、過去問をどうぞ!
②【H30年選択式】 ※改正による修正あり
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1) < A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2) 政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達 した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】
②【H30年選択式】 ※改正による修正あり
A 60歳以上70歳以下
B 50歳未満
こちらもどうぞ!
③【H26年出題】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
④【H26年出題】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】
③【H26年出題】 ×
老齢給付金は、年金として支給することとされていますが、規約でその全部又は一部を一時金として支給することを定めた場合は、一時金で支給することができます。
(法第38条)
④【H26年出題】 〇
年金給付は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給することが条件です。
(法第33条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 ここを乗り越えよう!介護保険法
ここを乗り越えよう!介護保険法
R4-155
R4.1.24 介護保険法・保険料のしくみ
介護保険法の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類です。
それぞれ介護保険料を負担していますが、徴収の方法が違います。
では、条文を読んでみましょう。
第129条 (保険料) ① 市町村(市町村又は特別区)は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 ② ①の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 ③ 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。 ④ 市町村は、①の規定にかかわらず、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。 |
ポイント!
・ 市町村が徴収するのは「第1号被保険者」に対する保険料
・ 「保険料率」は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
・ 市町村は第2号被保険者からは保険料を徴収しない
★第1号被保険者からの徴収方法は、「特別徴収」と「普通徴収」があります。
①特別徴収
老齢等年金給付(老齢・退職、障害、遺族)が年額18万円以上の者が対象
(年金から徴収される)
②普通徴収
納付書などで徴収する
では、過去問をどうぞ!
①【H21年出題】
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるために保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
②【H30年選択式】
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】
①【H21年出題】 〇
市町村又は特別区が徴収する保険料は、第1号被保険者に対するものです。
②【H30年選択式】
A 3年
では、もう一問どうぞ!
③【R3年出題】
市町村(特別区を含む。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。

【解答】
③【R3年出題】 ×
市町村は、第2号被保険者から保険料は徴収しません。
(第2号被保険者の流れ)
第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が医療保険料といっしょに徴収します。
そして、各医療保険者から、社会保険診療報酬支払基金を通して、市町村に交付されます。
各医療保険者
↓ 『介護給付費・地域支援事業支援納付金』として納付
↓
社会保険診療報酬支払基金
↓ 『介護給付費交付金』、『地域支援事業支援交付金』として交付
↓
市町村
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩㉑」法律によって定義が異なる用語
「最初の一歩㉑」法律によって定義が異なる用語
R4-121
R3.12.21 「児童」の定義(労基法・児童手当法)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
労働基準法第56条 (最低年齢) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 |
労働基準法では、中学校を卒業するまでの年齢の児童を労働させることを、原則として禁止しています。
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日」が終了するまでが、保護の対象です。
児童手当法第3条 児童手当法において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。 |
児童手当法の「児童」は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間」にあって、「日本国内に住んでいる」又は「留学などのために海外に住んでいて一定の要件をみたす」者と定義されています。
そして、もう一つ、「支給要件児童」という用語もあります。
支給要件児童は、第4条で「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童」)又は「中学校修了前の児童を含む2人以上の児童」と定義されています。
では、過去問を解いてみましょう
【労働基準法】
①【H29年出題】
労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達するまで、これを使用してはならない。」と定めている。
②【H23年出題】
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者について、労働基準法第56条による所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用する場合の労働時間は、修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内でなければならない。

【解答】
①【H29年出題】 ×
「満15歳に達するまで」ではなく、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで」です。原則として労働させることができないのは、義務教育終了までです。
②【H23年出題】 〇
「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者」でも、所轄労働基準監督署長の許可を受けて使用することができる例外規定があります。
満13歳以上の場合は、「非工業的事業の職業」、満13歳未満の場合は、「映画の製作又は演劇の事業」(子役の俳優)で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものが許可の条件です。
といっても義務教育中のため学校優先です。「修学時間外に使用することができる」と規定されています。そのため、労働時間は「修学時間を通算して、1週間について40時間以内、かつ、1日について7時間以内」とされています。
(法第56条第2項、第60条第2項)
では、「児童手当法」の過去問を解いてみましょう。
【児童手当法】
③【H30年選択式】
11歳、8歳、5歳の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき< A >である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

【解答】
③【H30年選択式】
A35,000円
ポイント!
・支給の対象
児童手当は、父母、父母指定者、里親、施設の設置者などに支給されます。児童に支給するのではないので注意してください。
・児童手当の額(1人当たり月額)※施設入所等児童を除く
3歳未満 → 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 → 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 → 一律10,000円
問題文の場合は、10,000円+10,000円+15,000円です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑳」過去問の活用(社保一般常識)
「最初の一歩⑳」過去問の活用(社保一般常識)
R4-120
R3.12.20 医療保険や年金等の歴史(社一編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
医療保険、年金等の法律の施行日をおさえましょう。
では、過去問を解いてみましょう。
①【H28年選択式】
世界初の社会保険は、< A >で誕生した。当時の< A >では、資本主義経済の発達に伴って深刻化した労働問題や労働運動に対処するため、明治16年に医療保険に相当する疾病保険法、翌年には労災保険に相当する災害保険法を公布した。
一方日本では、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点から、 < A >に倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、< B >に「健康保険法」を制定した。
②【H21年出題(健保)】
健康保険法は、大正11年に制定され、同時に施行された日本で最初の社会保険に関する法である。
③【H19年出題】
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。
④【H19年出題】
高齢化や核家族化等の進行に従い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された。

【解答】
①【H28年選択式】
A ドイツ
B 大正11年
ポイント!
世界初の社会保険はドイツで誕生しました
②【H21年出題(健保)】 ×
「同時に施行」が間違いです。
健康保険法の制定は「大正11年」ですが、施行は大正15年、ただし保険給付及び費用の負担に関する規定は昭和2年施行です。
関東大震災の影響で、全面施行は昭和2年まで延期されました。
健康保険は、日本で最初の医療保険です。
(法附則第1条)
③【H19年出題】 〇
ポイント!
国民皆保険体制の実現は昭和36年4月です。
④【H19年出題】 〇
ポイント!
介護保険法は平成12年4月から施行されました。
では、引き続き過去問を解いてみましょう
⑤【H22年出題】
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。
⑥【H19年出題】
医療面で国民皆保険が進められるのに対応して国民皆年金の実現が強く要請されるようになり、自営業者等を対象とする国民年金法が昭和34年に制定され、昭和36年4月から全面施行された。
⑦【H24年出題】
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
⑧【H19年出題】
確定給付企業年金法は、平成13年に制定・施行された

【解答】
⑤【H22年出題】 ×
船員保険法の制定は、「昭和」14年です。
船員保険制度は船員のみを対象とした年金等給付を含む総合保険で、健康保険に相当する疾病給付も対象でした。
ポイント!
船員保険制度の養老年金等は、「社会保険方式」による「日本最初の公的年金」制度です。(参照:平成23年版厚生労働白書)
⑥【H19年出題】 〇
国民年金法が昭和36年4月に全面施行されたことによって、国民皆年金が実現しました。
ポイント!
国民皆保険も国民皆年金も「昭和36年4月」です。
⑦【H24年出題】 〇
ポイント!
確定拠出年金法は、平成13年6月制定・同年10月施行です。
⑧【H19年出題】 ×
確定給付企業年金法は、平成13年制定ですが、施行は平成14年4月です。
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
 「最初の一歩⑲」条文の読み方(高齢者医療確保法)
「最初の一歩⑲」条文の読み方(高齢者医療確保法)
R4-119
R3.12.19 専門用語に慣れましょう「後期高齢者医療の被保険者」(社一編)
 社労士受験勉強のファーストステップ
社労士受験勉強のファーストステップ
ファーストステップについては
では、条文を読んでみましょう。
第50条 (被保険者) 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの |
第51条 (適用除外) 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としない。 1 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 2 前号に掲げるもののほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの |
★国民の全てが何らかの医療保険に加入していることを、「国民皆保険」といいます。
医療保険は、職業によって以下の種類があります。
・健康保険 → 民間企業の会社員とその被扶養者
・船員保険 → 船員とその被扶養者
・共済組合 → 国家公務員又は地方公務員とその被扶養者
・私立学校教職員共済 → 私立学校教職員とその被扶養者
・国民健康保険 → 上記以外の人とその家族
そして、75歳(障害の認定を受けた場合は65歳以上75歳未満)になると、各医療保険の被保険者や被扶養者の資格を喪失し、「後期高齢者医療」の被保険者となります。
「後期高齢者医療」は、各医療保険から独立していることがポイントです。
では、過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
②【H28年出題】
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】
①【H22年出題】 ×
年齢が間違っています。
70歳以上ではなく「75歳以上」、65歳以上70歳未満ではなく、「65歳以上75歳未満です。
②【H28年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)は、後期高齢者医療の被保険者になりません。
★後期高齢者医療に必要な費用について
費用のうち、5割を公費(税金)で負担しています。
残りの約4割が、現役(各医療保険の保険者)からの支援金です。
そして、約1割が、後期高齢者が負担している保険料となります。
公費(税金) 5割 | |
各医療保険からの支援金 約4割 | 保険料 約1割 |
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)過去問から学ぶ社保一般常識
R4-059
R3.10.20 確定拠出年金法(企業型と個人型)
令和3年の問題から社保一般常識を学びましょう。
今日は「確定拠出年金」です。
では、どうぞ!
①【R3年問6D】
国民年金法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、国民年金基金連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。

【解答】
①【R3年問6D】 〇
国民年金第3号被保険者は、「個人型年金加入者」となることができます。
確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」の2種類ありますが、それぞれの対象者をおさえましょう。
| 企業型年金 | 個人型年金 | |
| 実施 | 厚生年金適用事業所の事業主 | 国民年金基金連合会 |
| 加入者 | ・第1号等厚生年金被保険者 (第1号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者) (原則は60歳未満→規約に定めがある場合、65歳までの規約で定める年齢まで加入できる。ただし、60歳前と同一の実施事業所で引き続き使用されること等が必要。) | ・国民年金第1号被保険者 ・60歳未満の厚生年金保険の被保険者 ・国民年金第3号被保険者 |
(法第2条、第9条、第62条)
こちらもどうぞ!
②【H24年出題】
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。
②【H30年出題】
第190回国会において成立した「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」では、私的年金の普及・拡大を図るため、個人型確定拠出年金の加入者範囲を基本的に20歳以上60歳未満の全ての方に拡大した。(平成29年版厚生労働白書参照)
③【H29年出題】
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

【解答】
②【H24年出題】 〇
確定拠出年金法は、「平成13年6月制定、10月施行」は、おさえておきましょう。
②【H30年出題】 〇
平成29年版厚生労働白書「第5章 若者も高齢者も安心できる年金制度の確立」に記載されています。「私的年金の普及・拡大」を図る、「高齢期に向けた個人の継続的な自助努力の支援」に取り組むことなどが載っています。
③【H29年出題】 〇
60歳未満の第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員)は、個人型年金加入者になることができます。
なお、第2号厚生年金被保険者(国家公務員)、第3号厚生年金被保険者(地方公務員)も個人型年金の加入者になることができます。
※第2号(国家公務員)、第3号(地方公務員)は、企業型年金には加入できません。
(法第9条、第62条)
では、「定義」を穴埋めでチェックしましょう
第2条 (定義)
確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
確定拠出年金法において「企業型年金」とは、< A >が、単独で又は共同して実施する年金制度をいう。
確定拠出年金法において「個人型年金」とは、< B >が、実施する年金制度をいう。

【解答】
A 厚生年金適用事業所の事業主
B 国民年金基金連合会
(法第2条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)社保一般常識 応用問題
R4-051
R3.10.12 国民健康保険法「国民健康保険の適用除外」
令和3年の問題から、応用問題を振り返りましょう。
今日は国民健康保険法です。
では、どうぞ!
①【R3年問7B】
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者となる。

【解答】
①【R3年問7B】 ×
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第9号)
こちらもどうぞ!
②【H20年出題】(改正による修正あり)
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
③【H20年出題】(改正による修正あり)
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。
④【H20年出題】(改正による修正あり)
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】
②【H20年出題】 〇
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く))に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第9号)
③【H20年出題】 〇
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第8号)
④【H20年出題】 〇
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外です。
(法第6条第10号)
では、こちらもどうぞ!
⑤【R3年出題】
都道府県が当該都道府県の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日の翌日又は国民健康保険法第6条各号のいずれにも該当しなくなった日の翌日から、その資格を取得する。
⑥【H25年出題】(改正による修正あり)
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有する至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
「翌日」が誤りです。資格取得は「その日」です。
・都道府県の区域内に住所を有するに至った日
・国民健康保険法第6条各号(適用除外)のいずれにも該当しなくなった日
から、その資格を取得します。
(法第7条)
⑥【H25年出題】 ×
資格喪失は原則として「翌日」です。
・都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の翌日
・国民健康保険法第6条の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日の翌日
から、その資格を喪失します。
ただし、例外もあります。
・都道府県の区域内に住所を有しなくなった日に他の都道府県の区域内に住所を有する至ったときは、その日から資格を喪失します。
・適用除外事由の中の第9号(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者)及び第10号(国民健康保険組合の被保険者)については、該当するに至った日から、その資格を喪失します。
(法第8条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)社保一般常識よく出るところ
R4-041
R3.10.2 社一「令和2年版厚生労働白書」
令和3年の問題から、よくでるところを振り返りましょう。
今日は社会保険一般常識です。
では、どうぞ!
①【R3年問10D】
社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が49.5%、介護、福祉その他が39.4%を占めていたが、医療は1990年代半ばから、介護、福祉その他は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成29)年度には、年金が21.6%と、1989年度の約2倍となっている。

【解答】
①【R3年問10D】 ×
ヒント!
法律の制定の順番を思い出しましょう。
・健康保険法制定(大正11年) 日本最初の医療保険
・船員保険法制定(昭和14年) 社会保険方式による日本最初の公的年金制度
・介護保険法施行(平成12年)
この順番を意識して問題文を読んでみると、1989(平成元)年度に、介護、福祉その他が39.4%を占めてる、という部分に違和感を覚えると思います。
令和2年版厚生労働白書によると、
(社会保障給付費の部門別構成割合の推移)
・1989(平成元)年度においては年金が49.5%、医療が39.4%を占めていた
・医療は1990年代半ばから、年金は2004 (平成16)年度からその割合が減少に転じ、介護、福祉その他の割合が増加してきている。
・2017年度には、介護と福祉その他を合わせて21.6%と、1989年度の約2倍となっている
(参照:令和2年版厚生労働白書 P120)
では、もう一問どうぞ!
②【R3問10A】
公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第1号被保険者は、対前年比 70万人増で近年増加傾向にある一方、第2号被保険者(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第 3号被保険者は、それぞれ対前年比 34万人減、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。

【解答】
②【R3問10A】 ×
(公的年金制度の被保険者数の増減について)
・ 第 2号被保険者は対前年比 70万人増 で、近年増加傾向にある
・ 第 1号被保険者や第 3号被保険者はそれぞれ対前年比 34 万人、23万人減で、近年減少傾向にある
・ (要因)被用者保険の適用拡大や厚生年金の加入促進策の実施、高齢者等の就労促進などが考えられる。
(参照:令和2年版厚生労働白書)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
(令和3年出題より)社会保険労務士法の定番問題
R4-031
R3.9.22 社会保険労務士法/補佐人
令和3年の問題から、定番問題を振り返ります。
今日は社会保険労務士法です。
では、どうぞ!
①【R3年問5B】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。

【解答】
①【R3年問5B】 ×
社会保険労務士は補佐人として、弁護士とともに裁判所に出頭し、「陳述」をすることができます。「尋問」は入りません。
複雑化する労働保険や社会保険に関する行政訴訟や、個別労働紛争に関する民事訴訟に、対応するためです。
(法第2条の2)
では、こちらもどうぞ!
②【R1年出題】
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。
③【H28年出題】
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
④【H30年出題】
社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる場合、当該社会保険労務士法人がその社員のうちからその補佐人を選任しなければならない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく、「弁護士である訴訟代理人とともに」です。
(法第2条の2)
③【H28年出題】 ×
弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができるのは、特定社会保険労務士に限りません。
(法第2条の2)
④【H30年出題】 ×
補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述する事務について、社会保険労務士法人がその社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができます。その場合、「委託者」に選任させなければならない、とされています。
「当該社会保険労務士法人」が選任しなければならない、は誤りです。
(法第25条の9の2)
最後に条文を確認しましょう。
(第2条の2)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、< A >として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、< B >をすることができる。
(第25条の9の2)
社会保険労務士法人は、第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。
この場合において、当該社会保険労務士法人は、< C >に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。

【解答】
A 補佐人
B 陳述
C 委託者
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回試験・社会保険一般常識【択一】
R4-018
R3.9.9 第53回社一(択一)より~介護保険法
第53回試験を振り返ってみましょう。
★☆☆ 法令4問、白書1問で構成されていました。白書は「令和2年版」からの出題です。前年度の白書はチェックしておきましょう。法令はそれほど難しくなく、一般常識の法令は広く浅く勉強することが肝要です。
【R3年問8】
(問8-A)
市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、第2号被保険者から保険料を普通徴収の方法によって徴収する。
(問8-B)
介護認定審査会は、市町村におかれ、介護認定審査会の委員は、介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員から任命される。
(問8-C)
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の一方は、市町村が第1号被保険者である他方の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負うものではない。
(問8-D)
介護保険審査会は、各都道府県に置かれ、保険給付に関する処分に対する審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の介護保険審査会に対してしなければならない。
(問8-E)
介護保険法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から14日以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。

【解答】
(問8-A) ×
介護保険の保険料は市町村が徴収しますが、対象は第1号被保険者で、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
第2号被保険者の介護保険料は市町村が徴収するのではなく、以下の流れになります。
・各医療保険者が医療保険の保険料といっしょに介護保険料を徴収する
↓
・社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から納付金を徴収する
↓
・社会保険診療報酬支払基金から各市町村に交付する
(法第125条、第131条、第150条)
(問8-B) ×
<介護認定審査会のポイント>
・市町村におかれる
・審査判定業務を行う
・介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長が任命する
問題文の「介護支援専門員から任命される」の部分が誤りです。
(法第14条)
(問8-C) ×
世帯主、配偶者の一方は、保険料を連帯して納付する義務を負っています。
(法第132条)
(問8-D) 〇
<介護保険審査会のポイント>
・各都道府県に置かれる(Bの介護認定審査会と比較してください)
・保険給付に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる
(法第183条)
(問8-E) ×
「14日以内」が誤りです。
<ポイント>
・要介護認定は、有効期間内に限り、その効力を有する。
・有効期間の満了後も要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護更新認定の申請をすることができる。(※要介護更新認定の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行う)
・災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
(法第28条、則第39条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
第53回選択式(社会保険一般常識)
R4-007
R3.8.29 第53回選択社一~やや難しい★★☆
第53回試験を振り返ってみましょう。
★★★ 難しい
★★☆ やや難しい
★☆☆ 暗記が肝心、消去法で解く
☆☆☆ どうにか解ける
今日は、「社会保険に関する一般常識」の選択式です。
問題1 国民健康保険法(第76条)
市町村は被保険者の属する世帯の世帯主から国民健康保険の「保険料」を徴収します。その「保険料」についての問題です。
「Aを解く手順」→選択肢の中の「納付」か「交付」のどちらになるかをまず検討する → 後に続くかっこ書きの前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、介護納付金の納付に要する費用を含む、という点に注目する → 「納める」(納付)を選ぶ → かっこ書きのような納付金なども含んだ名称として「国民健康保険事業費納付金の納付」を選ぶ。
Bは、直前の「その他の」がヒントです。Bには、「その他の」の前に出てくる国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用も含まれます。そのような費用も含めた全体の費用と考えると、「国民健康保険事業に要する費用」が出てくると思います。
問題1 ★★☆ やや難しい
問題2 船員保険法(第93条)
船員保険独自の給付「行方不明手当金」からの問題です。
問題2 ★☆☆ 暗記が肝心
問題3 児童手当法(第8条)
児童手当の支給はよく出題されるところですが、ちょっと難しいです。
問題3 ★★★ 難しい
問題4 確定給付企業年金法(第41条)
脱退一時金を受けるための要件についての問題です。5年と迷うかもしれませんが、10年、15年は長すぎると感じるのではないでしょうか?
問題4 ★☆☆ 暗記が肝心
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
令和2年版厚生労働白書より
R3-360
R3.8.18 「地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度」より
今日は「令和2年版厚生労働白書」からの問題です。
第7章「国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現」の第4節「地域包括ケアシステムの構築と安心で質の高い介護保険制度」から抜粋しています。
ではどうぞ!
空欄を埋めてください。
( 介護保険制度の現状と目指す姿)
介護サービスの利用者は在宅サービスを中心に着実に増加し、2000年4月には149万人であったサービス利用者数は、2019(平成31)年4月には< A > になっており、介護保険制度は着実に社会に定着してきている。
高齢化がさらに進展し、「団塊の世代」が75歳以上となる2025(令和7)年の日本では、およそ< B >人に 1人が75歳以上高齢者となり、認知症の高齢者の割合や、世帯主が高齢者の単独世帯・夫婦のみの世帯の割合が増加していくと推計されている。
このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために「< C >」の実現を目指している。「< C >」とは、地域の事情に応じて高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいう。
介護費用の増大に伴い、介護保険制度創設時に全国平均3,000円程度であった介護保険料は、現在約5,900円になっており、2025年には約< D >円になると見込まれている。
(医療・介護の連携の推進)
地域包括ケア強化法において、「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設を
「< E >」として 2018(平成 30)年4月に創設した。2020(令和2)年3月末現在、 < E >は 343施設(21,738療養床)となっている。

【解答】
A 487万人と、約3.3倍
B 5.5
C 地域包括ケアシステム
D 7,200
E 介護医療院
こちらもどうぞ!
第2条
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 1の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、< A >との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 1の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の< B >に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 1の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その< C >において、その有する能力に応じ< D >を営むことができるように配慮されなければならない。

【解答】
A 医療
B 選択
C 居宅
D 自立した日常生活
(介護保険法第2条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
【改正】確定給付企業年金法
R3-316
R3.7.5 【改正】確定給付企業年金~支給開始年齢
昨日、高年齢者雇用安定法の改正「70歳までの就業確保措置」の努力義務についてお話しました。
確定給付企業年金法も改正で70歳までの拡大が行われています。
まずは、こちらをどうぞ
<H30年選択(修正)>
確定給付企業年金法第36条の規定によると、老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとするが、この規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならないとされている。
(1)< A >の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
(2)政令で定める年齢以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
また、(2)の政令で定める年齢は、< B >であってはならないとされている。

【解答】
A 60歳以上70歳以下(←今回の改正点です)
B 50歳未満
(法第36条、施行令28条)
 確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢
確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始年齢
(1) 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したとき
(2)50歳以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったとき(※規約で当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る)
では、こちらもどうぞ!
①<H30選択>
確定給付企業年金法第29条第1項では、事業主(企業年金基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、企業年金基金。)は、次に掲げる給付を行うものとすると規定している。
(1) 老齢給付金
(2) < C >
②<H26年出題>
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
③<H26年出題>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

【解答】
①<H30選択>
C 脱退一時金
★確定給付企業年金では、「老齢給付金」と「脱退一時金」の給付を行います。
また、規約で定めるところにより、それらの給付に加え、「障害給付金」、「遺族給付金」の給付を行うことができます。
(法第29条)
②<H26年出題> 〇
老齢給付金の支給要件は、20年を超えてはならない、とされています。
(法第36条)
③<H26年出題> 〇
老齢給付金を年金で支給する場合は、「終身又は5年以上」にわたり、「毎年1回以上定期的」に支給するものでなければなりません。
(法第33条)
※老齢給付金は、原則として年金として支給。ただし、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合は、一時金として支給することができます。(法第38条)
 解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
解説動画はこちらからどうぞ!毎日コツコツYouTubeチャンネル
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします
国民健康保険法
R3-286
R3.6.5 国民健康保険 保険料を滞納したとき
今日は、国民健康保険法「保険料を滞納したとき」です。
滞納期間によって対応が変化します。
では、どうぞ!
①<H28年選択>
市町村は、国民健康保険料を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から < A >が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
世帯主が国民健康保険料の滞納に関し、被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る< B >を交付する。
なお、本問の世帯には、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者はいないものとする。

【解答】
A 1年間
B 被保険者資格証明書
(法第9条)
ポイント!
1年間滞納 → 被保険者証の返還 → 被保険者資格証明書が交付される
次はこちらをどうぞ
②<R2年出題>
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から被保険者資格証明書の交付を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。

【解答】
②<R2年出題> 〇
ポイント!
・ 1年6か月滞納 → 保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止め
・ なお滞納している保険料を納付しない → 一時差し止めに係る保険給付の額から滞納保険料額を控除できる
(法第63条の2)
では、最後にこちらをどうぞ!
③<R1年出題>
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、療養費を支給する。
④<R1年出題>
国民健康保険に加入する50歳の世帯主、45歳の世帯主の妻、15歳の世帯主の子のいる世帯では、1年間保険料を滞納したため、世帯主は、居住する市から全員の被保険者証の返還を求められ、被保険者証を返還した。この場合は、世帯に属する被保険者全員に係る被保険者資格証明書が交付される。

【解答】
③<R1年出題> ×
被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、療養費ではなく、「特別療養費」が支給されます。
療養の給付等の現物給付ではなく、いったん、全額自己負担し、後から保険給付分が償還払いされます。
(法第54条の3)
④<R1年出題> ×
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(問題文では15歳の子)には、被保険者資格証明書ではなく、有効期間が6か月の被保険者証が交付されます。
(法第9条)
社労士受験のあれこれ
社一 確定拠出年金法
R3-285
R3.6.4 確定拠出年金法の脱退一時金
今日は、確定拠出年金法の脱退一時金がテーマです。
では、どうぞ!
①<H20年出題>
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。

【解答】
①<H20年出題> 〇
~~給付の種類~~
・老齢給付金
・障害給付金
・死亡一時金
・脱退一時金(当分の間)
(法第28条、附則第2条の2、3条)
では、脱退一時金をどうぞ!
★企業型
当分の間、次の各号のいずれにも該当する企業型年金加入者であった者は、企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に、脱退一時金の支給を請求することができる。
1. 企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
2. 個人別管理資産の額が< A >以下であること。
3. 最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して< B >か月を経過していないこと。
★個人型
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
1. 国民年金の保険料免除者であること。
2. < C >の受給権者でないこと。
3. 通算拠出期間が1月以上< D >年以下であること又は個人別管理資産の額が < E >円以下であること。
4. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < F >年を経過していないこと。
5. 企業型の脱退一時金の支給を受けていないこと。

【解答】
A 15,000円
B 6
C 障害給付金
D 5
E 25万
F 2
※Dについて
改正により、1月以上3年以下から1月以上5年以下になりました。
(附則第2条の2、第3条、施行令第60条)
では、「確定給付企業年金法」と比較してみましょう!
確定給付企業年金法 (給付の種類)
① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
1 老齢給付金
2 < G >
② 事業主等は、規約で定めるところにより、①に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
1 障害給付金
2 < H >

【解答】
G 脱退一時金
H 遺族給付金
★確定給付企業年金の給付
・基本 → 老齢給付金、脱退一時金
・任意 → 障害給付金、遺族給付金
(法第29条)
社労士受験のあれこれ
社一 医療費適正化計画と介護保険事業計画
R3-284
R3.6.3 比較してみましょう・医療費適正化計画と介護保険事業計画
「医療費適正化計画」は高齢者医療確保法、「介護保険事業計画」は介護保険法で出てきます。
それぞれの計画のサイクルを覚えましょう。
では、どうぞ!
【高齢者医療確保法】
(医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画)
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定めるとともに、 < A >年ごとに< B >年を1期として、全国医療費適正化計画を定めるものとする。
(都道府県医療費適正化計画)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、< A >年ごとに、< B >年を1期として、都道府県医療費適正化計画を定めるものとする。
(特定健康診査等基本指針)
厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
(特定健康診査等実施計画)
< C >(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、< A >年ごとに、< B >年を1期として、特定健康診査等実施計画を定めるものとする。
(特定健康診査)
< C >は、特定健康診査等実施計画に基づき、< D >歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。
【介護保険法】
(基本指針)
厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(「基本指針」という。)を定めるものとする。
(市町村介護保険事業計画)
市町村は、基本指針に即して、< E >年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画という。)を定めるものとする。
(都道府県介護保険事業支援計画)
都道府県は、基本指針に即して、< E >年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。

【解答】
A 6
B 6
C 保険者
保険者 → 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う「全国健康保険協会」、「健康保険組合」、「都道府県及び市町村(特別区を含む。」、「国民健康保険組合」、「共済組合」、「日本私立学校振興・共済事業団」
D 40
E 3
では、こちらもどうぞ!
①<H30年出題>
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。
②<H24年出題>
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県医療費適正化計画の作成の手法その他都道府県医療費適正化計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
③<R1年出題>
市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。

①<H30年出題> 〇
「公表するよう努める」努力規定に注意しましょう。
(高齢者医療確保法第9条)
②<H24年出題> 〇
(高齢者医療確保法第10条)
③<R1年出題> 〇
「市町村介護保険事業計画」の問題です。
(介護保険法第117条)
社労士受験のあれこれ
年齢問題~介護保険法、高齢者医療確保法
R3-241
R3.4.21 何歳から?(介護保険、後期高齢者医療)
今日のテーマは、介護保険、後期高齢者医療制度の対象になる年齢です。
まずは、「高齢者医療確保法」からどうぞ!
①<H22年出題>
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。

【解答】
①<H22年出題> ×
「年齢」が誤り。70歳ではなく75歳です。
<後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者>
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
・65歳以上75歳未満の者で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者
(法第50条)
※「後期高齢者医療広域連合」とは?次の問題を解いてください。
②<H22年出題>
市町村(特別区を含む。以下同じ)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。

【解答】
②<H22年出題> 〇
「後期高齢者医療広域連合」は、都道府県ごとに設けられています。
(法第48条)
なお、後期高齢者医療の事務から、「保険料の徴収の事務」が除かれていることに注意しましょう。保険料を徴収するのは、後期高齢者医療広域連合ではなく「市町村」です。
次は「介護保険法」をどうぞ!
③<H24年出題>
市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
④<H23年出題>
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
⑤<H29年出題>
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

【解答】
③<H24年出題> 〇
④<H23年出題> ×
「20歳以上65歳未満」ではなく「40歳以上65歳未満」です。
⑤<H29年出題> ×
第2号被保険者は、「医療保険加入者」であることが要件なので、医療保険加入者でなくなった場合は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失します。
※介護保険の被保険者は「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類です。
1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 → 「第1号被保険者」
2 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
→ 「第2号被保険者」
(法第9条、第11条)
社労士受験のあれこれ
介護保険法
R3-240
R3.4.20 介護給付を受けようとするときの手続き
今日のテーマは、介護給付を受けるときの手続きです。
①介護給付を受けるには認定を受けなければならない
①<H24年出題>
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

【解答】
①<H24年出題> ×
厚生労働大臣の認定ではなく、「市町村又は特別区」の認定を受けなければなりません。
(法第19条)
<認定の流れ>
・要介護認定の申請
↓
・認定調査
↓
・主治医の意見
↓
・介護認定審査会による審査判定
↓
・認定
②認定の効力はいつから発生する?
②<R1年出題>
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

【解答】
②<R1年出題> 〇
「申請のあった日」までさかのぼるのがポイントです。
(法第27条第8項)
③認定結果が出るのはいつ?
③<H29年出題>
要介護認定の申請に対する処分は、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合を除き、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。

【解答】
③<H29年出題> 〇
認定の結果が通知されるのは、原則として申請から30日以内とされています。
(法第27条第11項)
④要介護認定の有効期間
④<H24年出題>
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
⑤<H29年出題>
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下本問において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村又は特別区に対し、当該要介護認定の更新の申請をすることができる。

【解答】
④<H24年出題> 〇
要介護認定には、有効期間があります。
⑤<H29年出題> 〇
有効期間満了後も要介護状態の場合は更新申請ができます。
社労士受験のあれこれ
社会保険労務士法
R3-239
R3.4.19 社労士法~紛争解決手続代理業務
今日はのテーマは、紛争解決手続代理業務です。
では、まずは選択問題からどうぞ!
<H19年選択>
1 社会保険労務士法第1条には、同法の目的として「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。」と規定されている。
2 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< C >を行うことが含まれている。
3 ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < D >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< E >社会保険労務士に限られる。

【解答】
A 発達 (※発展ではなく「発達」です。注意しましょう。)
B 福祉の向上
C 和解の交渉
D 紛争解決手続代理業務試験
E 特定
(法第1条、第2条)
こちらもどうぞ!
①<R1年出題>
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

【解答】 ×
紛争解決手続代理業務ができるのは「特定社会保険労務士」だけです。「すべての社会保険労務士」が誤りです。
・「紛争解決手続代理業務」に含まれる事務
① 紛争解決手続について相談に応ずること。
② 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
③ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
社労士受験のあれこれ
年金の歴史(創成期)
R3-190
R3.3.1 社会保険方式の年金制度はいつ始まった?
今日から年金の歴史を勉強しましょう。
20歳で国民年金に加入 → 40年保険料を納付 → 65歳から老齢年金を受給 → 人生100年と考えると年金を受ける期間は約40年近くなる。
考えてみたら、年金との付き合いは「被保険者」+「受給権者」で約80年という期間なのですね。
その間、社会や経済はどんどん変化していくので、それに合わせて年金も法改正が行われます。
年金の勉強に必要なのは、そんな変化の歴史です。
本日は、年金の創成期のお話です。
まずはこちらをどうぞ!
<社一 H22年出題>
船員保険法は、大正14年に制定され、翌年から施行された。同法に基づく船員保険制度は船員のみを対象とし、年金等給付を含む総合保険であるが、健康保険に相当する疾病給付は対象としていなかった。

【解答】 ×
船員保険法の制定は大正14年ではなく、昭和14年です。(昭和15年から施行)
また、年金等給付を含む総合保険で、「健康保険に相当する疾病給付」も対象となっていました。
★船員保険は、日本で最初の社会保険方式による「公的年金」★
創成期の船員保険は、船員を対象とする「年金」、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」、「健康保険に相当する疾病給付」を総合的に行う保険でした。
戦時体制下で、物資の海上輸送を担う船員の確保が急務だった頃です。
その後の船員保険は?
船員保険の「年金」は、昭和61年4月1日に、厚生年金保険法に統合されました。被保険者の減少や著しい高齢化で年金財政が悪化し、船員保険のみでは存続が厳しくなったからです。
また、「労災に相当する給付」、「雇用保険に相当する給付」は、平成22年からそれぞれ労災保険法、雇用保険法に統合されました。
現在の船員保険は、「職務外の疾病等に関する給付(健康保険に相当する部分)」と労災についての船員独自の上乗せの給付を行っています。
(参考:厚生労働白書平成23年版)
社労士受験のあれこれ
(社一)確定拠出年金の掛金
R3-174
R3.2.13 確定拠出年金~掛金拠出限度額
今日は確定拠出年金法です!
令和2年度の問題をどうぞ!
<問2-選択>
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で< A >円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。

【解答】
A 48,000
確定拠出年金には、「企業型」と「個人型」があります。
国民年金の第1号被保険者が加入できるのは「個人型」ですが、その場合の掛金の拠出限度額は、68,000円(月額)です。
ただし、付加保険料又は国民年金基金の掛金を納付している場合は、それらを合算して68,000円以内となります。
問題文では、国民年金基金の掛金を20,000円納付しているので、確定拠出年金の掛金は48,000円までとなります。
(確定拠出年金法施行令36条)
こちらの問題もどうぞ!
①<H21年出題>
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
②<H29年出題>
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。
③<H20年出題>
個人型年金加入者は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。

【解答】
①<H21年出題> ×
「企業年金連合会」が誤り。
「確定拠出年金」には、企業型年金及び個人型年金があり、「個人型年金」とは、「国民年金基金連合会」が、第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいいます。
なお、「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、実施する年金制度をいいます。
(法第2条)
②<H29年出題> 〇
個人型年金加入者になることができるのは以下の通り。
・ 国民年金の第1号被保険者
・ 60歳未満の厚生年金保険の被保険者 (企業型年金加入者の場合は、企業型年金規約で個人型への加入が認められている場合に限る。)
・ 国民年金の第3号被保険者
(法第62条)
③<H20年出題> ×
個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、「個人型年金加入者」が決定し、又は変更します。
(法第68条)
社労士受験のあれこれ
解説動画です!
(社一)船員保険法の一般保険料率
R3-102
R2.12.3 船員保険の一般保険料率は、疾病保険料率+災害保健福祉保険料率
令和2年の問題をどうぞ!
<問10‐C>
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用されている後期高齢者医療制度の被保険者である船員保険の被保険者に対する船員保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合計した率を乗じて算定される。

【解答】 ×
「後期高齢者医療制度」の被保険者であることがポイントです。後期高齢者医療制度の被保険者の場合は、災害保健福祉保険料率のみで、疾病保険料率は合算されません。
<船員保険法の「一般保険料率」について>
■ 船員保険一般保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率を乗じて計算します。
■ 一般保険料率とは、「疾病保険料率」と「災害保健福祉保険料率」の合計です。
・一般保険料率 → 職務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産に関する保険給付等に充てる(健康保険の保険給付に相当する部分)
・災害保健福祉保険料率 → 職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷に関する給付に充てる(労災保険の上乗せの部分)
■ 後期高齢者医療制度の被保険者の場合、業務外の疾病等の「医療」については後期高齢者医療制度の対象になるため、船員保険では行いません。そのため保険料についても、疾病保険料率はかけずに、災害保健福祉保険料率のみで算定します。
では、こちらもどうぞ!
 <H30年出題その1>
<H30年出題その1>
一般保険料率は、疾病保険料率、災害保健福祉保険料率及び介護保険料率を合算して得た率とされている。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者にあっては、一般保険料率は、災害保健福祉保険料率のみとされている。
 <H30年出題その2>
<H30年出題その2>
疾病保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内において、協会が決定するものとされている。
 <H30年出題その3>
<H30年出題その3>
災害保健福祉保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、協会が決定するものとされている。

【解答】
 <H30年出題その1> ×
<H30年出題その1> ×
一般保険料率の内訳は、疾病保険料率+災害保健福祉保険料率です。一般保険料率に介護保険料率は含まれていません。
(介護保険第2号被保険者の場合は、一般保険料額と介護保険料額を合算した額が保険料になります。)
なお、後半の「後期高齢者医療の被保険者等である被保険者及び独立行政法人等職員被保険者は、災害保健福祉保険料率のみ」の部分は令和2年の問題と同じ主旨ですので後半は「〇」です。
 <H30年出題その2> ×
<H30年出題その2> ×
疾病保険料率は、1000分の40から1000分の130までの範囲内です。
 <H30年出題その3> ×
<H30年出題その3> ×
災害保健福祉保険料率は、1000分の10から1000分の35までの範囲内です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~覚えるところ(社一)
R3-092
R2.11.23 <R2出題>覚える「社労士違反するおそれがあると認めるとき」
令和2年の出題から、「覚えるところ」をつかみましょう。
ではどうぞ!
<問5-エ>
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めにかかわらず、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

【解答】 ×
第25条の33(注意勧告)からの出題です。
「会則の定めにかかわらず」ではなく、「会則の定めるところにより」です。
穴埋めで確認しましょう!
第25条の33(注意勧告)
< A >は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に< B >があると認めるときは、< C >の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

【解答】
A 社会保険労務士会
B 違反するおそれ
C 会則
では、関連問題をどうぞ!
<R1年出題>
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】 ×
「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる」ではなく、「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」です。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~問題の意図を考える(社一)
R3-082
R2.11.13 <R2出題>問題の意図「後期高齢者医療の自己負担」
令和2年の出題から、問題の意図を考えましょう。
出題される問題には必ず意味がある!
ではどうぞ!
<問10-D>
単身世帯である後期高齢者医療制度の80歳の被保険者(昭和15年4月2日生まれ)は、対象となる市町村課税標準額が145万円以上であり、本来であれば、保険医療機関等で療養の給付を受けるごとに自己負担として3割相当を支払う一定額以上の所得者に該当するところであるが、対象となる年間収入が380万円であったことから、この場合、被保険者による申請を要することなく、後期高齢者医療広域連合の職権により一定以上の所得者には該当せず、自己負担は1割相当となる。

【解答】 ×
★後期高齢者医療の自己負担割合は原則として1割ですが、現役並所得者は3割です。
この問題の意図は、「被保険者による申請」が要るか要らないか?です。
対象となる市町村課税標準額が145万円以上の場合は、現役並所得者として、自己負担割合が3割となります。
ただし、市町村課税標準額が145万円以上でも、収入が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、1割負担となります。この場合は申請が必要です。→ここがこの問題のポイントです。
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~選択式の勉強に活かそう(社一)
R3-071
R2.11.2 R2出題【選択練習】社会保険労務士法・紛争解決手続代理業務
令和2年の択一式の問題から、選択式の勉強に活かせる問題をピックアップしました。
キーワードを< >で空欄にしています。
空欄を埋めてください。
R2年のアレンジ問題です
空欄を埋めてください。
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は< A >万円とされている。
(参照:問5ア)

【解答】
A 120
★紛争の目的の価額が120万円を超える場合は、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限られます。
★個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものとして、社会保険労務士会が設置している社労士会労働紛争解決センターなどがあります。
さらにこちらもどうぞ
<H19年選択式>
・ 社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< B >を行うことが含まれる。
・ ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < C >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< D >社会保険労務士に限られる。

【解答】
B 和解の交渉
C 紛争解決手続代理業務試験
D 特定
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~定番問題(社一)
R3-062
R2.10.24 R2出題・【よく出る】児童手当の支給
R2年の問題から定番問題をどうぞ!
R2年の問題です
R2問8より
児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

【解答】 ×
支払期月は、毎年2月、6月、10月の3期です。
・それぞれの前月までの分を支払います。
もう一問どうぞ!
<H29選択>
児童手当の一般受給資格者(公務員である者を除く。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、< A >の認定を受けなければならない。
なお、本問において一般受給資格者は、法人でないものとする。

【解答】 住所地の市町村長(特別区の区長を含む。)
最後にもう一問どうぞ
児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の < B >における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

【解答】 B 6月1日
毎年6月1日~6月30日までの間に提出しなければなりません。
★実は、毎年のように出題されている児童手当法。出題箇所はほぼ決まっているので、しっかり過去問を勉強していれば大丈夫です!
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~難問の解決方法(社一)
R3-052
R2.10.14 R2出題・難問解決策「児童手当法の所得制限」
択一式の問題は、7科目×10問で合計70問です。
1問の中には5つの選択肢。全体では、350の選択肢(問題文)が出題されています。
この350の問題文の中には、「試験対策としては難しすぎる」=「解けなくていい」問題文が含まれています。
受験勉強するにあたって、「ここまでやらないとダメなのかな・・・」と不安になってしまって、重箱の隅まで勉強してしまうのは、効率が悪く、そして続かないので。。。
意識してほしいのは、「満点とらなくても合格できる」ということ。
今日から、R2年の問題から「難問」とその解決策をお話していきます!
R2年の問題です
<R2問10より>
10歳と11歳の子を監護し、かつ、この2人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額1万円(10歳の子の分として月額5千円、11歳の子の分として月額5千円)が支給されることになる。

【解答】 ×
児童手当には所得制限があり、所得が所得制限以上の場合は、当分の間、月額5千円の「特例給付」が支給されています。
なお、所得制限額は、 主たる生計者のみの所得で判断し、世帯合算はしません。
父と母の所得を合算すると所得制限額以上だとしても、主たる生計者の所得が所得制限額を超えていなければ、特例給付ではなく、通常の児童手当が支給されます。
ここで、児童手当の額を確認しましょう。
| 支給対象児童 | 1人当たりの月額 |
|---|---|
| 0歳~3歳未満 | 15,000円(一律) |
| 3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降15,000円) |
| 中学生 | 10,000円(一律) |
「特例給付」は、児童1人当たり5,000円です。
同じ論点の問題をどうぞ!
<H30年選択>
11歳、8歳、5歳の児童を監護し、かつ、この3人の児童と生計を同じくしている日本国内に住所を有する父に支給する児童手当の額は、1か月につき< A >である。なお、この3人の児童は、施設入所等児童ではなく、かつ、父の所得額は所得制限額未満であるものとする。

【解答】 A 35,000円
3歳~小学校修了前の児童は1人10,000円ですが、第3子以降は15,000円となるので、合計35,000円となります。
では、選択の練習をどうぞ!
児童手当法において「児童」とは、< A >に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の < B >で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

【解答】
A 18歳
B 内閣府令
社労士受験のあれこれ
R2年問題から~社保一般常識
R3-042
R2.10.4 R2・社会保険審査官及び社会保険審査会法
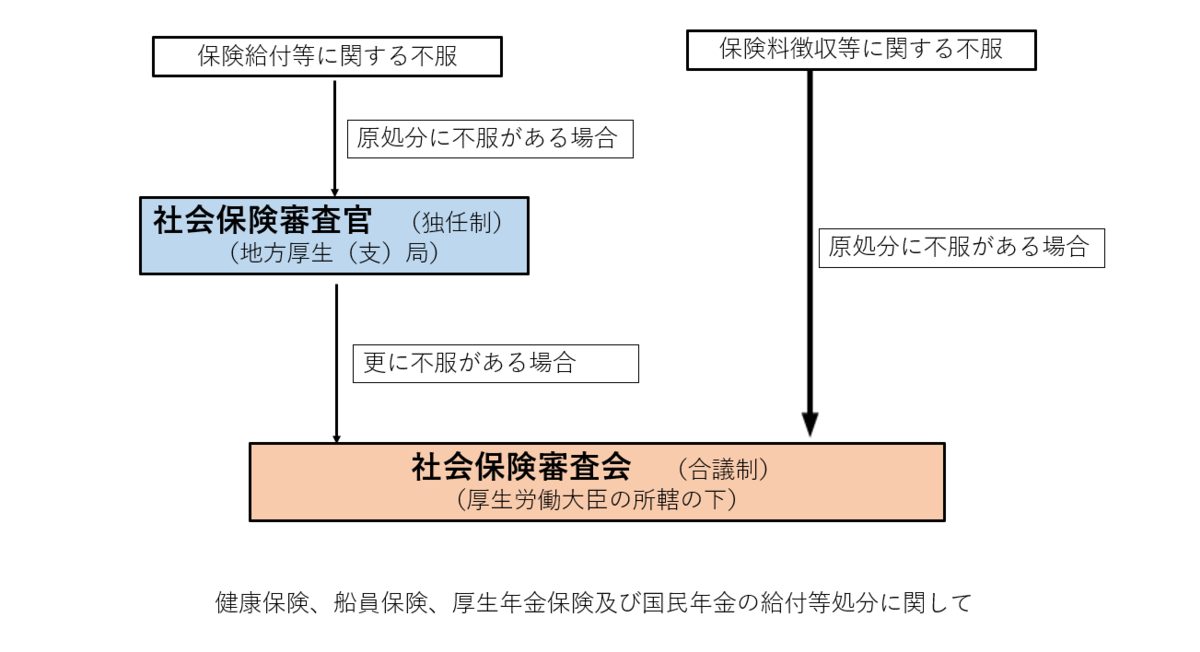
今日のテーマは、「社会保険審査官と社会保険審査会」です。
 <R2年問9A>
<R2年問9A>
審査請求は、政令の定めるところにより、文書のみならず口頭でもすることができる。
 <R2年問9D>
<R2年問9D>
審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。

【解答】
 <R2年問9A> 〇
<R2年問9A> 〇
審査請求は、文書でも口頭でもできます。
 <R2年問9D>
<R2年問9D>
審査請求の取下げは、文書でしなければなりません。口頭ではできません。
では、こちらもどうぞ!
 <H21年出題・改>
<H21年出題・改>
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条(同条第2項及び第6項を除く。)及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項、国民年金法第101条(同法第138条において準用する場合を含む。)並びに年金給付遅延加算金支給法第8条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。
 <H21年出題>
<H21年出題>
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

【解答】
 <H21年出題・改> 〇
<H21年出題・改> 〇
社会保険審査官は、地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に置かれるのがポイントです。
 <H21年出題> 〇
<H21年出題> 〇
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれるのがポイントです。委員長および委員5人をもって組織され、合議制となっています。
社労士受験のあれこれ
シリーズ・歴史は繰り返す(社保一般常識)
R3-032
R2.9.24 過去の論点は繰り返す(R2・確定給付企業年金法)
受験勉強で大切なのは、過去の論点を知ること。
なぜなら、何回も繰り返し出題されるからです。
出題傾向をつかめば、勉強が格段に楽になります。
「歴史は繰り返す」
確定給付企業年金法
 <H26年出題>
<H26年出題>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
 <H26年出題>
<H26年出題>
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。
 <H28年出題>
<H28年出題>
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】
 <H26年出題> 〇
<H26年出題> 〇
年金給付の支給期間及び支払期月は、規約で定めるところによる。
・終身また5年以上、毎年1回以上定期的に支給すること
 <H26年出題> ×
<H26年出題> ×
老齢給付金は、年金として支給するのが原則。
規約で定めた場合は、その全部又は一部を一時金として支給できる。
 <H28年出題> ×
<H28年出題> ×
「毎月、翌月末までに」が誤り。
掛金の拠出は「年1回以上、定期的に」です。
では、令和2年度の問題をどうぞ!
 <R2問6B>
<R2問6B>
加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、事業主が拠出すべき掛金の全部を負担することができる。
 <R2問6C>
<R2問6C>
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は10年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
 <R2問6E>
<R2問6E>
老齢給付金の受給権は、老齢給付金の受給権者が死亡したとき又は老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ、消滅する。

【解答】
 <R2問6B> ×
<R2問6B> ×
「加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる。」です。
加入者が掛金の全部を負担することはできません。
 <R2問6C> ×
<R2問6C> ×
「終身又は10年以上」ではなく「終身又は5年以上」です。
 <R2問6E> ×
<R2問6E> ×
老齢給付金の受給権は、消滅は次の3つです。
1 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
2 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
老齢給付金は「一時金」として支給されることもあるので、「3 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。」も消滅事由としておさえてください。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 択一式の感想(社保一般常識)
R3-019
R2.9.11 第52回試験・択一社一の感想
第52回社労士試験の択一式の感想を書いていきます。
令和2年度 社保一般常識 択一式
問6 確定給付企業年金法
問7 船員保険法
問8 児童手当法
問9 社会保険審査官及び社会保険審査会法
問10 社会保険制度の費用の負担及び保険料等
白書等からの出題は無く、すべて法令からの出題でした。
問6 確定給付企業年金法
テキストの基本事項をおさえていればOK。
特に、確定拠出年金法との横断的な整理は必須です。
問7 船員保険法
一般の会社員が加入する「健康保険法」と比べると、船員が加入する「船員保険法」は、給付内容が手厚く設計されています。
健康保険法の給付内容と比較しながら、「違う点」を意識して勉強するのがポイントです。
問8 児童手当法
対策は、テキストの基本事項と過去問で大丈夫です。
問9 社会保険審査官及び社会保険審査会法
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法の不服申し立ての勉強でカバーできたと思います。
問10 社会保険制度の費用の負担及び保険料等
テキストと過去問の勉強でOKです。
全体的に 「横断」学習が効果的。「同じところ」「違うところ」を意識しながら。
社労士受験のあれこれ
令和2年度 選択振り返り(社保一般常識)
R3-009
R2.9.1 第52回試験・選択(社一)
第52回社労士試験、選択式問題を解いていきます。
次の合格のためにも、振り返りは大切なのです。
令和2年度 社保一般常識 選択式
1 平成29年社会保障費用統計からの出題です。
「120兆円」という数字は、新聞やネットで見かけた方も多いと思いますが、100兆、140兆、160兆と並んでいると、迷ってしまうかもしれません。
社会保障給付費の中で「年金」の占める割合が最も高いという部分は、解きやすかったのではないでしょうか?
例えば、会社員でも「健康保険」より「厚生年金」の保険料の方が高いので。(年金の方がお金がかかる)
2 介護保険料の滞納についての出題
介護保険料の滞納対応としての「保険給付の支払いの一時差し止め」のルールについてですが、択一式でも同じテーマの問題が出ていました。
「1年」「1年6カ月」を区別して覚えていればOKな問題です。
3 国民健康保険組合についての出題
そういえばあまり意識していなかった部分ですが、なんとなく選択できる問題です。
4 個人型確定拠出年金の掛金についての出題
国民年金第1号被保険者の掛金の上限(68,000円)は、国民年金基金との合算枠なのを覚えていればOKな問題でした。
ポイント! 択一式で出るような論点は選択式でも出る
社労士受験のあれこれ
横断編(確認しましょう60・65・70・75歳)その2
R2-254
R2.8.11 横断編/60・65・70・75歳その2(社一編)
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「60・65・70・75歳その2(社一編)」です。
では、どうぞ!
 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
空欄を埋めてください。
<被保険者>
次の1、2のいずれかに該当する者は、< A >が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1 < A >の区域内に住所を有する< B >の者
2 < A >の区域内に住所を有する< C >の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該 < A >の認定を受けたもの
<特定健康診査>
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< D >の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

【解答】

A 後期高齢者医療広域連合
B 75歳以上
C 65歳以上75歳未満
D 40歳以上
 介護保険法
介護保険法
空欄を埋めてください。
<被保険者>
次の1,2のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
1 市町村の区域内に住所を有する< E >の者(「第1号被保険者」という。)
2 市町村の区域内に住所を有する< F >の医療保険加入者(「第2号被保険者」という。)

【解答】
E 65歳以上
F 40歳以上65歳未満
ついでにこちらもどうぞ!
①<高齢者医療確保法 H23年出題>
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
①<高齢者医療確保法 H23年出題> ×
保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む。)」です。都道府県は保険料の徴収は行いません。
ちなみに、保険料の決定は、後期高齢者医療広域連合が行います。
穴埋めで確認しましょう!
① < A >は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
② ①の保険料は、< B >が被保険者に対し、< B >の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い< B >の < C >で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。

【解答】
A 市町村(特別区を含む。)
B 後期高齢者医療広域連合
C 条例
もう一問どうぞ!
②<介護保険法 H21年出題>
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】
②<介護保険法 H21年出題> 〇
介護保険法の保険者は市町村及び特別区(以下「市町村」)保険料の徴収も保険者である市町村が行います。
保険料の徴収の対象は第1号被保険者のみ。
第2号被保険者からは保険料を徴収しません。第2号被保険者分は、医療保険各法で医療保険料と合わせて介護保険料を徴収するからです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-241
R2.7.29 選択式の練習/平成29年度 国民医療費の概況より
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「平成29年度 国民医療費の概況」からです。
では、どうぞ!
問 題
<財源別国民医療費>
平成29年度の国民医療費は43兆710億円となっている。
国民医療費を財源別にみると、公費は< A >、保険料は< B >となっている。
【選択肢】
① 16兆5,181億円(構成割合38.4%)
② 21兆2,650億円(構成割合49.4%)
③ 4兆9,948億円(構成割合11.6%)

【解答】
A ① 16兆5,181億円(構成割合38.4%)
B ② 21兆2,650億円(構成割合49.4%)
「公費」16兆5,181億円(構成割合38.4%)
(公費負担医療制度、医療保険制度、後期高齢者医療制度等への国庫負担金及び地方公共団体の負担金)
「保険料」21兆2,650億円(同49.4%)
(医療保険制度、後期高齢者医療制度、労働者災害補償保険制度等の給付費のうち、事業主と被保険者が負担すべき額)
「その他」5兆2,881億円(同12.3%)
(患者負担及び原因者負担)
※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf
もう一問どうぞ!
<国民医療費の状況>
平成29年度の国民医療費は43兆710億円、前年度の42兆1,381億円に比べ9,329億円、2.2%の増加となっている。
人口一人当たりの国民医療費は< C >円となっている。
国民医療費の国内総生産(GDP)に対す る比率は7.87%(前年度7.85%)、国民所得(NI)に対する比率は10.66%(同10.77%)となっている。
【選択肢】
① 10万9,500 ② 33万9,900 ③ 59万8,300

【解答】
C ② 33万9,900
※ 人口一人当たりの国民医療費は33万9,900円、前年度の33万2,000円に比べ 7,900円、2.4%の増加となっている。
※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf
最後にもう一問!
<年齢階級別国民医療費>
平成29年度の国民医療費は43兆710億円となっている。
年齢階級別にみると、65 歳以上の国民医療費は < D >となっている。
【選択肢】
① 5兆2,690 億円(構成割合12.2%) ② 25兆9,515 億円(構成割合60.3%)
③ 9 兆3,112 億円(構成割合21.6%)

【解答】
D ② 25兆9,515 億円(構成割合60.3%)
0~14歳 → 2兆5,392 億円(構成割合 5.9%)
15~44歳 → 5兆2,690億円(構成割合12.2%)
45~64歳 → 9兆3,112億円(構成割合21.6%)
65歳以上 → 25兆9,515億円(構成割合60.3%)
※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-231
R2.7.19 選択式の練習/介護保険法・国等の責務
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険法・国等の責務」です。
では、どうぞ!
問 題
< A >は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
< B >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
< C >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
< D >は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
【選択肢】
① 国 ② 事業主 ③ 国民
④ 厚生労働省 ⑤ 都道府県 ⑥ 市町村
⑦ 医療保険者 ⑧ 健康保険組合 ⑨ 国及び地方公共団体
⑩ 医療機関 ⑪ 医療従事者

【解答】
A ⑨ 国及び地方公共団体
キーワード医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
B ⑤ 都道府県
キーワード助言及び適切な援助をしなければならない
C ① 国
キーワード 必要な各般の措置を講じなければならない
D ⑦ 医療保険者
キーワード協力しなければならない。
※ちなみに、「医療保険者」とは・・・
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う
・全国健康保険協会
・健康保険組合
・都道府県及び市町村(特別区を含む。)
・国民健康保険組合
・共済組合
・日本私立学校振興・共済事業団
こちらもどうぞ!
①<H12年出題>
介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。
②<H20年出題>
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。

【解答】
①<H12年出題> 〇
保険者である市町村を、国や都道府県が支えている図をイメージしてくてください。
②<H20年出題> ×
国と都道府県の責務が逆です。
国 → 各般の措置を講じなければならない
都道府県 → 必要な助言及び適切な援助をしなければならない
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-221
R2.7.9 選択式の練習/社労士法・社労士の義務
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「社労士法・社労士の義務」です。
ではどうぞ!
問 題
社会保険労務士は、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は< B >を害するような行為をしてはならない。
社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その < C >を図るように努めなければならない。
【選択肢】
① 不当に ② 不正に ③ 虚偽に
④ 品位 ⑤ 品格 ⑥ 信義
⑦ 能力の向上 ⑧ 知識の研鑽 ⑨ 資質の向上

【解答】
A ② 不正に
B ④ 品位
C ⑨ 資質の向上
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
 H15年出題
H15年出題
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。
 H13年出題
H13年出題
社会保険労務士は、行政機関の実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。

【解答】
 H15年出題 ×
H15年出題 ×
「不正行為の指示等」と「信用失墜行為」の罰則が逆です。
不正行為の指示等 → 罰則あり(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
信用失墜行為 → 罰則なし
 H13年出題 ×
H13年出題 ×
行政機関の実施する研修ではなく、社会保険労務士会及び連合会が行う研修です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-211
R2.6.29 選択式の練習/高齢者医療確保法・生活習慣病予防のために
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「高齢者医療確保法・生活習慣病予防のために」です。
ではどうぞ!
問 題
厚生労働大臣は、< A >(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「< A >等基本指針」という。)を定めるものとする。
保険者(都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、< A >等基本指針に即して、< B >として、 < A >等実施計画を定めるものとする。
保険者は、< A >等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< C >の加入者に対し、< A >を行うものとする。
【選択肢】
① 特定健康診査 ② 特定健康診断 ③ 特定健康検診
④ 3年ごとに、3年を一期 ⑤ 5年ごとに、5年を一期
⑥ 6年ごとに、6年を一期
⑦ 40歳以上 ⑧ 60歳以上 ⑨ 65歳以上

【解答】
A ① 特定健康診査
B ⑥ 6年ごとに、6年を一期
C ⑦ 40歳以上
特定健康診査の目的は、生活習慣病の予防。健康が気になる40歳以上が対象です。その結果、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して行われるのが特定保健指導。生活習慣の改善のサポートが行われます。
ちなみに、「特定健康診査等基本指針」を定めるのが厚生労働大臣。
「特定健康診査等実施計画」を定め、その実施計画に基づき特定健康診査を行うのは「保険者」です。
※高齢者医療確保法の「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。
「保険者」について、こちらもどうぞ!
<H29年出題>
高齢者医療確保法における「保険者」には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

【解答】 〇
「医療保険各法」と保険者
| 健康保険法 | 全国健康保険協会、健康保険組合 |
| 船員保険法 | 全国健康保険協会 |
| 国民健康保険法 | 都道府県及び市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合 |
| 国家公務員共済組合法 | 共済組合 |
| 地方公務員等共済組合法 | 共済組合 |
| 私立学校教職員共済法 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-201
R2.6.19 選択式の練習/確定拠出年金・脱退一時金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「確定拠出年金・脱退一時金」です。
確定拠出年金法の給付は、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」で、当分の間「脱退一時金」があります。
本日のテーマは「脱退一時金」です。
ではどうぞ!
問題1
個人型年金の脱退一時金
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料免除者であること。
②< A >の受給権者でないこと。
③その者の通算拠出期間が1月以上< B >以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が< C >円以下であること。
④最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < D >を経過していないこと。
⑤確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと
【選択肢】
① 障害年金 ② 老齢年金 ③ 障害給付金
④ 5年 ⑤ 3年 ⑥ 25年 ⑦ 6月 ⑧ 2年 ⑨ 3月
⑩ 25万円 ⑪ 1万5千円 ⑫ 50万円

【解答】
A ③ 障害給付金
B ⑤ 3年
C ⑩ 25万円
D ⑧ 2年
こちらもどうぞ!
個人型年金の脱退一時金の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては厚生労働大臣に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ行うものとする。

【解答】 ×
「厚生労働大臣」ではなく「個人型記録関連運営管理機関」に請求します。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-191
R2.6.9 選択式の練習/介護保険・都道府県知事or市町村長?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険・都道府県知事or市町村長?」です。
 平成30年4月に、介護保険施設に「介護医療院」が加わりました。
平成30年4月に、介護保険施設に「介護医療院」が加わりました。
まずは、介護医療院を確認しましょう!
ではどうぞ!
問題
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
< A >を受けなければならない。
【選択肢】
① 市町村長の指定 ② 都道府県知事の指定 ③ 都道府県知事の許可

【解答】
A ③ 都道府県知事の許可
介護サービスを行う事業者や施設については、「市町村長の指定」を受けるパターン、「都道府県知事の指定」を受けるパターン、「都道府県知事の許可」を受けるパターンがあります。
介護医療院と同じく「都道府県知事の許可」を受けるパターンに該当するのは、「介護老人保健施設」です。
こちらもどうぞ!
介護医療院の許可は、< B >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
【選択肢】
① 5年 ② 6年 ③ 3年

【解答】
B ② 6年
ついでにもう一問どうぞ!
指定居宅介護支援事業者の指定は、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所ごとに、< C >が行う。
【選択肢】
① 市町村長 ② 都道府県知事 ③ 厚生労働大臣

【解答】
C ① 市町村長
ちなみに、こちらの指定の効力の有効期間も6年です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-181
R2.5.30 選択式の練習/社会保障協定
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「社会保障協定」からです。
日本と外国との間で、外国に派遣される日本人がいる一方、外国から日本に派遣される外国人もいて、それに伴い問題も生じています。
一つ目は、「二重加入」の問題。例えば、日本から相手国に派遣されて就労している場合、日本でも相手国でも二重に公的年金に加入し、保険料も二重に支払うケースがあること。
二つ目は、「年金受給資格」の問題。外国の公的年金に加入したとしても、その国の老齢年金の受給資格要件を満たせず、支払った保険料が掛け捨てになるケースがあること。
このような問題を解決する仕組みが社会保障協定です。
ではどうぞ!
問題
 社会保障協定発行済みの国は?
社会保障協定発行済みの国は?
| 発効日 | |
| 2000年2月1日(平成12年) | < A > |
| 2001年2月1日(平成13年) | 英国 |
| 2005年4月1日(平成17年) | 韓国 |
| 2005年10月1日(平成17年) | アメリカ |
| 2007年1月1日(平成19年) | ベルギー |
| 2007年6月1日(平成19年) | フランス |
| 2008年3月1日(平成20年) | カナダ |
| 2009年1月1日(平成21年) | オーストラリア |
| 2009年3月1日(平成21年) | オランダ |
| 2009年6月1日(平成21年) | チェコ |
| 2010年12月1日(平成22年) | スペイン |
| 2010年12月1日(平成22年) | アイルランド |
| 2012年3月1日(平成24年) | ブラジル |
| 2012年3月1日(平成24年) | スイス |
| 2014年1月1日(平成26年) | ハンガリー |
| 2016年10月1日(平成28年) | インド |
| 2017年8月1日(平成29年) | ルクセンブルク |
| 2018年8月1日(平成30年) | フィリピン |
| 2019年7月1日(令和元年) | < B > |
| 2019年9月1日(令和元年) | < C > |
【選択肢】
① インドネシア ② オーストリア ③ ドイツ
④ スロバキア ⑤ ノルウェー ⑥ ベトナム
⑦ メキシコ ⑧ 中国 ⑨ マレーシア

【解答】
A ③ ドイツ
B ④ スロバキア
C ⑧ 中国
我が国初の年金通算協定はドイツとの間で締結されました。
2019年度(令和元年度)は、スロバキアとの間、中国との間に社会保障協定が発効しました。
現在、20か国との間で社会保障協定が発効されています。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-171
R2.5.20 選択式の練習/確定拠出年金・中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、確定拠出年金法です。
テーマは、平成30年5月にスタートした「中小事業主掛金納付制度」です。
「iDeCo+」(イデコプラス)と呼ばれるこの制度は、
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している従業員の掛金に、事業主が掛金を追加して拠出できる制度です。
ではどうぞ!
問 題
 iDeCo+を導入できる事業主の要件
iDeCo+を導入できる事業主の要件
中小事業主※は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が個人型年金加入者掛金を拠出する場合(< A >納付を行う場合に限る。)は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、< B >、定期的に、掛金を拠出することができる。
※中小事業主の定義
企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が< C >人以下のものをいう。
【選択肢】
① 滞納することなく ② 自ら直接 ③ 当該中小事業主を介して
④ 毎月1回以上 ⑤ 年1回以上 ⑥ 終身にわたり
⑦ 100 ⑧ 300 ⑨ 1000

【解答】
A ③ 当該中小事業主を介して
B⑤ 年1回以上
C ⑦ 100
iDeCo+のポイント!
・ 企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない中小企業が対象(従業員100人以下に限る)
・ 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員の掛金に追加して、掛金を拠出できる(中小事業主が掛金が拠出されることに同意した者が対象)
・ 事業主の掛金と従業員の掛金との合計は、月額23,000円
社労士受験のあれこれ
選択式対策(介護保険法)
R2-161
R2.5.10 選択式の練習/介護保険・公費による負担
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険法の公費の負担」です。
介護給付・予防給付に要する費用の半分は、被保険者の保険料で賄われていますが、残りの半分は公費で負担しています。
その「公費」については、国・都道府県・市町村それぞれの負担割合が決まっています。
ではどうぞ!
平成27年択一式を参照しました。
問 題
市町村又は特別区は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の< A >に相当する額を負担する。
【選択肢】
①100分の12.5 ②100分の25 ③2分の1 ④3分の1

【解答】 A ①100分の12.5
もう一問どうぞ!
(H19年択一式を参照しています)
介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその< B >に相当する額を負担する。
【選択肢】
①100分の12.5 ②100分の20 ③100分の25 ④3分の1

【解答】 B ②100分の20
ポイント!
国 → 介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の20を負担+調整交付金(100分の5)を交付
ちなみに、都道府県は、介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の12.5を負担しています。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-151
R2.4.30 選択式の練習/厚生労働白書・介護保険制度
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「平成28年版 厚生労働白書」からの問題です。
問 題
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度を創設することとし、< A >年に介護保険法が施行された。
制度の基本的な考え方は、自立支援、利用者本位、< B >の3つである。具体的には、自立支援とは、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよう支援することを理念とするものである。また、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを総合的に受けられる制度とした。さらに給付と負担の関係が明確な< B >を採用した
【選択肢】
①2000(平成12) ②2003(平成15) ③1986(昭和61)
④税方式 ⑤診療報酬方式 ⑥皆保険方式 ⑦社会保険方式

【解答】
A①2000(平成12) B ⑦社会保険方式
(H28年厚生労働白書 第3章「高齢期を支える医療・介護制度」より)
★ 問題文にあるように、社会保険方式の特徴は、「給付と負担の関係が明確」であることです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社保一般常識)
R2-141
R2.4.20 平成29年国民年金被保険者実態調査結果の概要より
平成28年に、「平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要」から出題がありました。
今日は、平成29年版の国民年金被保険者実態調査結果の概要をもとに、解説します。
 (H28年出題)出題当時はH26年版でしたが、H29年版に改定しています。
(H28年出題)出題当時はH26年版でしたが、H29年版に改定しています。
厚生労働省から平成31年3月に公表された「平成29年国民年金被保険者実態調査結果の概要」によると、平成27年度及び平成28年度の納付対象月の国民年金保険料を全く納付していない者(平成28年度末に申請全額免除、学生納付特例又は若年者納付猶予を受けていた者を除く。)が納付しない理由は、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が約7割と最も高くなっている。

【解答】 ○
<参考>
・すべての年齢階級で「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が最も高い。
・ 次いで高いのは、
20歳代→「うっかりして忘れた、後でまとめて払おうと思った」の割合
30歳代→「年金制度の将来が不安・信用できない」の割合
40歳代及び 50歳代前半→「納める保険料に比べて、十分な年金額が受け取れないと思う」の割合
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社保一般常識)
R2-131
R2.4.8 確定給付企業年金/企業年金基金の設立
確定給付企業年金には、「規約型」と「基金型」があります。
制度を開始するときの手続きは?が今日のテーマです。
 (H28年出題)
(H28年出題)
企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

【解答】 ×
受けるのは、許可ではなく「認可」です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(高齢者医療確保法)
R2-121
R2.3.24 後期高齢者医療制度の適用除外
後期高齢者医療の被保険者は、①75歳以上の者、②65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある旨、後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものです。
しかし適用除外規定もありますので確認しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】 ○
①生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者と、②後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは適用除外とされています。
類似問題・国民健康保険法!
<H20年出題/国民健康保険法>
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】 ○
(注) 国民健康保険法からの問題です。
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者から除外されています。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(確定給付企業年金法)
R2-111
R2.3.10 掛金の拠出(確定給付企業年金法)
 <確定給付企業年金法>事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を拠出しなければなりません。また、加入者も規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができます。
<確定給付企業年金法>事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を拠出しなければなりません。また、加入者も規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができます。
 (H28年出題)
(H28年出題)
(確定給付企業年金法に関して)事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】 ×
掛金は、「毎月、翌月末までに」というルールはありません。
掛金については、
・年1回以上定期的に拠出しなければならない
・規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付する
と定められています。
 こちらもどうぞ
こちらもどうぞ
<H19年出題>
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社保一般常識)
R2-101
R2.2.20 確定給付企業年金法
 「確定給付企業年金法」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度のことです。
「確定給付企業年金法」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度のことです。
では「確定給付企業年金法」でいう「厚生年金保険の被保険者」の定義は?というのが今日の主題です。
 (H28年出題)
(H28年出題)
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

【解答】 ×
確定給付企業年金法の「厚生年金保険の被保険者」は、厚生年金保険法の第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者とされています。
ちなみに、第4号厚生年金被保険者とは、私立学校教職員共済の加入者のことです。
 「第4号厚生年金被保険者」について、もう一問どうぞ!
「第4号厚生年金被保険者」について、もう一問どうぞ!
<H29年出題>
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

【解答】 ○
確定拠出年金の個人型年金加入者の範囲は基本的に20歳以上60歳未満のすべての方です。
1 国民年金第1号被保険者
※一部除外規定あり
2 60歳未満の厚生年金保険の被保険者
※公務員や私学共済の加入者も対象。
企業型年金加入者については、企業型年金規約において個人型年金への加入が認められている者に限る。
3 国民年金第3号被保険者
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社会保険労務士法)
R2-90
R2.2.3 懲戒(社会保険労務士法)
★ 今日は社会保険労務士法「不正行為の指示等を行った場合の懲戒」です。
 H28年出題
H28年出題
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。

【解答】 ×
「相当の注意を怠り・・・」の場合は、失格処分ではなく、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分を行うことができる」です。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H25年出題>
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。

【解答】 ○
「故意に・・・」の場合は、1年以内の業務停止処分又は失格処分をすることができる、とされています。
 こちらもどうぞ。
こちらもどうぞ。
<空欄を埋めてください。>
(懲戒の種類)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1 戒告
2 < A >以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
3 < B >(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)

【解答】 A 1年 B 失格処分
社会保険労務士に対する懲戒処分は次の3つです。
①戒告 ②1年以内の業務の停止 ③失格処分
では、こちらもどうぞ
(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
1 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、< C >に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、< D >、1に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

【解答】 C 故意 D 相当の注意を怠り
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(介護保険法と高齢者医療確保法)
R2-81
R2.1.17 財政の均衡を保つことができる期間(社一)
今日は、介護保険法と高齢者医療確保法の比較です。
では、さっそく、次の問題を解いてみてください。
 H23年出題
H23年出題
(高齢者医療確保法に関する問題)
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】 ×
おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができる、ではなく、おおむね「2年」を通じ財政の均衡を保つことができる、です。
 では、次の問題はどうでしょう?
では、次の問題はどうでしょう?
【H30年選択式】
(介護保険法に関する問題)
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】 3年
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-71
R1.12.30 R1社一/社会保険労務士法
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社保一般常識「社会保険労務士法」についてです。
 R1社保一般常識(問5)より
R1社保一般常識(問5)より
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】 ×
最後の「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。」が誤りです。「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」が正解です。
違反するおそれがあると認めるときは、社会保険労務士会は注意勧告ができます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-61
R1.12.11 R1社一/国民健康保険法の出産と死亡
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社保一般常識「国民健康保険法の出産と死亡」についてです。
 R1社一(問6)より
R1社一(問6)より
(国民健康保険法に関する問題)
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 ○
出産育児一時金の支給、葬祭費の支給(葬祭の給付)については、給付の要件や内容等は、保険者ごとに条例又は規約で定められる点がポイントです。
また、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H26年出題 ①】(国民健康保険法に関する問題)
保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
【H26年出題 ②】(国民健康保険法に関する問題)
保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。
【H26年出題 ③】(国民健康保険法に関する問題)
保険者は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

【解答】
【H26年出題 ①】(国民健康保険法に関する問題)
<解答> ×
移送費は法定の給付ですので、条例や規約でその全部又は一部を行わないことはできません。
【H26年出題 ②】(国民健康保険法に関する問題)
<解答> ○
傷病手当金の支給は任意ですので、条例又は規約の定めるところによって行うことができる給付です。
【H26年出題 ③】(国民健康保険法に関する問題)
<解答> ×
葬祭費の支給(葬祭の給付)については、給付の要件や内容等は、保険者ごとに条例又は規約で定められ、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-51
R1.11.17 R1社一/国民健康保険・審査請求
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社保一般常識「国民健康保険・審査請求」についてです。
 R1社一(問6)より
R1社一(問6)より
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】 ○
 国民健康保険の審査請求は、「国民健康保険審査会」であるのがポイント。
国民健康保険の審査請求は、「国民健康保険審査会」であるのがポイント。
社会保険審査官(社会保険審査会)ではありません。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H21年出題>
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【解答】 ○
国民健康保険審査会は、各都道府県に設けられているのがポイントです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-40
R1.10.29 R1社一/社会保険労務士法(紛争解決手続代理業務)
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社一「社会保険労務士法(紛争解決手続代理業務)」についてです。
 R1社一(問5)より
R1社一(問5)より
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

【解答】 ×
「すべての社会保険労務士」が誤りです。紛争解決手続代理業務を行うことができるのは、特定社会保険労務士のみです。
 平成19年に選択式で出題されています。確認しましょう。
平成19年に選択式で出題されています。確認しましょう。
(H19年選択式)
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< A >を行うことが含まれる。
ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < B >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< C >社会保険労務士に限られる。

【解答】
A 和解の交渉 B 紛争解決手続代理業務試験 C 特定
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(介護保険法)
R2-30
R1.10.15 R1社一/介護保険・要介護認定の効力
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、介護保険法「要介護認定の効力」についてです。
 R1一般常識(問7)より
R1一般常識(問7)より
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

【解答】 ○
 平成23年に選択式で出題されています。
平成23年に選択式で出題されています。
<問題>
要介護認定は、< A >その効力を生じ、要介護認定有効期間は、(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
(1) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 6月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、< B >で月を単位として市町村が定める期間)
要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期間を要介護認定有効期間とする。

【解答】
A その申請のあった日にさかのぼって
B 3月間から12月間までの範囲内
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社会保険労務士法)
R2-20
R1.9.27 R1一般常識/社労士法・補佐人の業務
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社会保険労務士法「補佐人の業務」についてです。
 R1一般常識(問5)より
R1一般常識(問5)より
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

【解答】 ×
「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく、弁護士である訴訟代人とともに出頭し、陳述をすることができる、です。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(社保一般常識)
R2-7
R1.9.6 R1選択式(社保一般常識)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第6回目は、「社保一般常識 選択式」です。
 AとBは「船員保険」からの出題です。
AとBは「船員保険」からの出題です。
船員保険法。たまーに出題されるので油断できません。しかも選択式で登場は珍しいです。
船員保険法の保険給付は、傷病手当金と行方不明手当金だけしっかり覚えてくださいね、と言うところなので、葬祭料とは意外でした。。。
 Cは、「介護保険法」からの出題です。
Cは、「介護保険法」からの出題です。
地域包括支援センターの目的についての問題ですが、難しいです。。。しっかりおさえてましたと言える方は少ないのでは?
 Dは「国民健康保険法」からの出題です。
Dは「国民健康保険法」からの出題です。
都道府県の責務についての問題。平成30年に都道府県も保険者となったことから、都道府県の役割については、チェックできていたと思います。
 Eは「確定拠出年金法」からの出題です。
Eは「確定拠出年金法」からの出題です。
「70歳」を覚えているかどうかがポイントでしょうか。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】介護保険法
R1.8.19 【選択式対策】昨年の改正・介護保険法
介護保険法の昨年の改正個所をcheckしておきましょう。
この法律において「< A >」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第107条第1項の< B >の許可を受けたものをいい、 「< A >サービス」とは、< A >に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

【解答】A 介護医療院 B 都道府県知事
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社保一般常識】目的条文
R1.8.15 【選択式対策】社保一般常識・目的条文チェック!
台風10号気を付けてくださいね。
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第2回目「一般常識(社会保険)」です。
【国民健康保険法】
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び < B >に寄与することを目的とする。
【児童手当法】
この法律は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、< C >その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
【高齢者の医療の確保に関する法律】
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、< D >の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< E >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< F >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて< G >及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【介護保険法】
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< H >を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< I >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の< J >及び福祉の増進を図ることを目的とする。
【社会保険労務士法】
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、< K >と労働者等の < L >に資することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
この法律は、< M >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< N >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< O >を支援し、もって < P >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定拠出年金法】
この法律は、< Q >の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を< R >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< S >を支援し、もって< T >と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【解答】
A 社会保障 B 国民保健の向上 C 父母 D 医療費
E 国民の共同連帯 F 費用負担 G 国民保健の向上 H 尊厳
I 国民の共同連帯 J 保健医療の向上 K 事業の健全な発達
L 福祉の向上 M 少子高齢化 N 給付の内容 O 自主的な努力
P 公的年金 Q 少子高齢化 R 個人が自己の責任
S 自主的な努力 T 公的年金の給付
社労士受験のあれこれ
社会保険審査官・社会保険審査会
R1.8.12 穴埋めで確認・社会保険審査官、社会保険審査会
空欄を埋めてください
<社会保険審査官>
健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官を置く。
社会保険審査官は、< A >のうちから、< B >が命ずる。
<社会保険審査会>
健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法、国民年金法及び年金給付遅延加算金支給法の規定による再審査請求並びに健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法及び年金給付遅延加算金支給法の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、< C >の所轄の下に、社会保険審査会を置く。
社会保険審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。
委員長及び委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、< D >の同意を得て、 < E >が任命する。

【解答】
A 厚生労働省の職員 B 厚生労働大臣
C 厚生労働大臣 D 両議院 E 厚生労働大臣
社労士受験のあれこれ
社会保険労務士法・帳簿の保存
R1.5.3 社会保険労務士・帳簿の保存
まず過去問をどうぞ
<H24年選択式出題>
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し、関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から< A >保存しなければならない。
なお、この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は、< B >に処せられる。

【解答】 A 2年間 B 100万円以下の罰金
社労士受験のあれこれ
介護保険の財源構成
H31.4.3 介護保険・公費負担の割合は?
まず過去問をどうぞ
<H27年出題>
市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。

【解答】 ×
100分の25ではなく、100分の12.5です。
 介護給付・予防給付に要する費用負担について
介護給付・予防給付に要する費用負担について
介護給付・予防給付に要する費用は、50%が被保険者からの保険料から、50%が公費から構成されています。
公費の割合は、「国」→200分の20+調整交付金100分の5、「都道府県」→100分の12.5、「市町村」→100分の12.5となっています。(※一定の施設等給付については、割合が変わります。)
もう一問どうぞ
<H20年出題>
都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。

【解答】×
市町村に調整交付金を交付しているのは都道府県ではなく国です。
社労士受験のあれこれ
社会保険労務士法
H31.2.27 社会保険労務士の職責
社会保険労務士法第1条の2に規定されている「社会保険労務士の職責」。
穴埋め式で確認しましょう。
【社会保険労務士の職責】
社会保険労務士は、常に< A >を保持し、業務に関する法令及び< B >に精通して、< C >な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

【解答】
A 品位 B 実務 C 公正
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(厚生労働白書 基礎編)
H30.10.30 H30年出題/国民負担率(平成29年版厚生労働白書)
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
「厚生労働白書」の「基礎」を確認しましょう。
※ 今日は、「厚生労働白書」です。
H30年 一般常識(問10A)
我が国の国民負担率(社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比)は、昭和45年度の24.3%から平成27年度の42.8%へと45年間で約1.8倍となっている。

【解答】 ○
★平成29年版厚生労働白書からの出題です。
正確な数字は覚えていなくても、45年前と比較して「社会保障負担と租税負担の合計額の国民所得比が増えている」のは直感で「正しいかも?」と解答できるかと思います。
なお、厚生労働白書では、「租税負担」と「社会保障負担」に分けて解説しています。それによると、「租税負担率」はバブル崩壊やリーマンショック後の不況の影響で、約1.3倍の伸びにとどまっている、一方、「社会保障負担率」は、1970年度の5.4%から2015年度は17.3%となり、45年で3倍超となっているそうです。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(高齢者医療確保法 基礎編)
H30.10.14 H30年出題/都道府県医療費適正化計画
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
高齢者医療確保法の「基礎」を確認しましょう。
H30年社保一般常識(高齢者医療確保法)(問7A)
都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を1期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下本問において「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

【解答】 ×
5年ごとに、5年を1期ではなく「6年ごとに、6年を1期」として、です。
★ポイント
何度も繰り返し出題される箇所です。
「6・6」覚えてしまいましょう。
 こちらもついでに覚えましょう。空欄を埋めてください。
こちらもついでに覚えましょう。空欄を埋めてください。
① ★「医療費適正化基本方針」を定めるのは厚生労働大臣
厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、< A >年ごとに、< B >年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
② 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、6年ごとに、6年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
③ ★「特定健康診査等基本指針」を定めるのは厚生労働大臣
厚生労働大臣は、特定健康診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下同じ。)及び特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(以下「特定健康診査等基本指針」という。)を定めるものとする。
④ 保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「国民健康保険」という。)にあっては、市町村。以下同じ。)は、特定健康診査等基本指針に即して、< C >年ごとに、< D >年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。

【解答】 A 6 B 6 C 6 D 6
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(社会保険労務士法 基礎編)
H30.10.12 H30年出題/社会保険労務士名簿
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
社会保険労務士法の「基礎」を確認しましょう。
H30年社会保険労務士法(問5A)
社会保険労務士法第14条の3に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。

【解答】 ×
社会保険労務士名簿を備えるのは、「全国社会保険労務士会連合会」。
社会保険労務士名簿の登録も、「全国社会保険労務士会連合会」が行う。
★ポイント
「社会保険労務士会」と「全国社会保険労務士会連合会」
「社会保険労務士会」 → 都道府県の区域ごとに設立されたもの
「全国社会保険労務士会連合会」 → 全国の社会保険労務士会の連合組織として設立されたもの
 過去問もどうぞ
過去問もどうぞ
①H22年出題
社会保険労務士名簿の登録は、全国社会保険労務士会連合会が行う。
②H20年出題
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、全国社会保険労務士会連合会から免許を受けることが必要である。

【解答】
①H22年出題 ○
②H20年出題 ×
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるためには、「社会保険労務士名簿」に「登録」を受けることが必要です。「登録」を行うのは、全国社会保険労務士会連合会です。
社労士受験のあれこれ
H30年本試験振り返り(社会保険一般常識 選択編)
H30.9.15 <H30年選択>社会保険一般常識振り返ります
H30年度本試験の問題を振り返るシリーズ。
今日は、社会保険の一般常識の選択式です。
A 介護保険料率より
「介護保険料率」については、こちらの記事で取り上げていました。
↓
B 児童手当の額より
意外とよく出る児童手当法です。
問題文の子どもたちは、全員3歳以上小学生までですね。
第一子 → 10000円
第二子 → 10000円
第三子 → 15000円
合計 35000円です。
<過去問チェック・平成26年選択式でも出題されていました>
児童手当制度については、「児童手当法の一部を改正する法律」が、平成24年3月に成立し、同年4月1日から新しい児童手当制度が施行された。
これにより児童手当は、所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対して、< A >については児童1人当たり月額1万5千円を支給することになった(所得制限は同年6月分から適用。)。
【解答】 A 3歳未満と、3歳から小学生の第3子以降
C・D・E 確定給付企業年金法より
■ Cについて
選択肢として、「障害給付金」、「遺族給付金」、「脱退一時金」がありますが、老齢給付金と脱退一時金が法定給付、障害給付金と遺族給付金は、任意給付であることを覚えていれば、答えられる問題です。
<過去問チェック・平成26年に出題されています>
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
【解答】 ○
■ Dについて
確定給付企業年金法は、従業員の老後の生活を安定させるためのものです。老齢給付金の支給開始年齢は、企業の定年年齢とだいたい一致している感じです。
■ Eについて
50歳以降の退職時に、支給開始することも可能ですよ、という規定です。
社労士受験のあれこれ
【選択式対策】介護保険法の改正
H30.8.24 【選択式対策】介護保険の改正チェック!
 台風が過ぎ去ったあとのこちら(兵庫県)は蒸し暑い1日でした。
台風が過ぎ去ったあとのこちら(兵庫県)は蒸し暑い1日でした。
さあ、いよいよ明後日が本番です。
まだ、やれることあります。頑張りましょう!
■■
今日は、介護保険法の改正からです。
・この法律において「< A >」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第107条第1項の< B >の< C >を受けたものをいい、 「< A >サービス」とは、< A >に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

【解答】
A 介護医療院 B 都道府県知事 C 許可
★ 介護医療院とは → 医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社保一般常識】目的条文
H30.8.11 【選択式対策】社保一般常識・目的条文チェック!
 残暑が厳しいです。試験まであと2週間。基本事項の確認を忘れずに。
残暑が厳しいです。試験まであと2週間。基本事項の確認を忘れずに。
■■
毎年恒例。本試験直前の目的条文チェックを始めます。
大切だけど、後回しになってしまう目的条文。
まとめてチェックしてしまいましょう!
★ 今日は第2回目「一般常識(社会保険)」です。
【国民健康保険法】
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び < B >に寄与することを目的とする。
【児童手当法】
この法律は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、< C >その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
【高齢者の医療の確保に関する法律】
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、< D >の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、< E >の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の< F >の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて< G >及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
【介護保険法】
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が< H >を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、< I >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の< J >及び福祉の増進を図ることを目的とする。
【社会保険労務士法】
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、< K >と労働者等の < L >に資することを目的とする。
【確定給付企業年金法】
この法律は、< M >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と< N >を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< O >を支援し、もって < P >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【確定拠出年金法】
この法律は、< Q >の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を< R >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る< S >を支援し、もって< T >と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

【解答】
A 社会保障 B 国民保健の向上 C 父母 D 医療費
E 国民の共同連帯 F 費用負担 G 国民保健の向上 H 尊厳
I 国民の共同連帯 J 保健医療の向上 K 事業の健全な発達
L 福祉の向上 M 少子高齢化 N 給付の内容 O 自主的な努力
P 公的年金 Q 少子高齢化 R 個人が自己の責任
S 自主的な努力 T 公的年金の給付
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社保一般常識】介護保険法
H30.7.17 【選択式対策】 国及び地方公共団体の責務
 連休明け、調子はいかがですか?疲れたなーと思ったら、少し休憩しましょう!
連休明け、調子はいかがですか?疲れたなーと思ったら、少し休憩しましょう!
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「介護保険法」です。
① < A >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
② < B >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
③ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ< C >を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における< C >の支援のための施策を、医療及び< D >に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
④ 国及び地方公共団体は、③の規定により③に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、< E >その他の者の福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めなければならない。

【解答】
A 国 B 都道府県 C 自立した日常生活
D 居住 E 障害者
※ ①と②については、介護保険法が施行された平成12年に出題された問題でイメージしてみてください。
↓ H12年出題(答えは「○」です。)
「介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。」
※ ③は、国と地方公共団体の責務として、地域包括ケアを推進するという規定です。
地域包括ケアシステムとは?
→ 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括変えシステムの構築を実現していきます。(厚労省ホームページより抜粋)
※ ④ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置付けられました。(厚生労働省ホームページより)
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社保一般常識】国民健康保険
H30.6.21 【選択式対策】国?都道府県?
 雨や曇りの日が続きますね。カラっと晴れるのはいつでしょう。
雨や曇りの日が続きますね。カラっと晴れるのはいつでしょう。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「国民健康保険法」です。
(責務)
1 < A >は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。
2 < B >は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。
3 < C >は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
4 < D >は、前2項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。
5 < B >は、第2項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な < E >を行うものとする。

A 国 B 都道府県 C 市町村 D 都道府県及び市町村
E 指導及び助言
社労士受験のあれこれ
【選択式対策・社保一般常識】介護保険・保険料
H30.4.27 【選択式対策】介護保険の保険料
 ゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィークですね。
お仕事が休みの方も多いと思います。
自分のペースを守って、計画通りに勉強を進めてくださいね。
■■
そろそろ、選択式の勉強もスタートしていきましょう。
貴重な時間を無駄にできないので、一から十まで丸暗記ではなく、「要点」だけ覚えることを意識しましょう。
選択式対策として、各科目順番に「要点」に絞った問題をアップしています。
★ 今日は「介護保険法」です。
条文の空欄を埋めてください。
第129条 (保険料)
1 < A >は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 保険料は、< B >に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
3 保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービスの見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の予想額、第147条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉事業に要する費用の予定額、< B >の所得の分布状況及びその見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね< C >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。
4 < A >は、< D >からは保険料を徴収しない。

【解答】
A 市町村 B 第1号被保険者 C 3年 D 第2号被保険者
おさえるポイント★
A → 介護保険の保険者は市町村ですので、保険料の徴収も保険者である市町村が行います。
B → 市町村は、第1号被保険者から保険料を徴収します。徴収方法は、特別徴収(老齢等年金給付から天引き)と普通徴収(納付書などで納付)の2種類があります。
C → 保険料は、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定されています。
D → 市町村は、第2号被保険者から保険料は徴収しません。
第2号被保険者については、医療保険者が医療保険料と一緒に介護保険料を徴収する → 社会保険診療報酬支払基金に納付する → 社会保険診療報酬支払基金から市町村に交付する、という流れです。
★ついでにもう一問解いてみましょう。
(市町村介護保険事業計画)
市町村は、基本指針に即して、< E >を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
(都道府県介護保険事業支援計画)
都道府県は、基本指針に即して、< E >を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。

【解答】 E 3年
★ 介護保険事業計画(都道府県の場合は介護保険事業支援計画)は3年を一期として策定されます。保険料率の財政の均衡を保つ「3年」とセットで覚えてください。
社労士受験のあれこれ
介護保険の第2号被保険者の定義
H30.4.5 H29年問題より「介護保険第2号被保険者」
H29年本試験【一般常識(社保)問7E】を解いてみてください。
(介護保険法の)第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。

【解答】 ×
★ 介護保険の被保険者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」の2種類があり、それぞれ次のように定義されています。
| 第1号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 |
| 第2号被保険者 | 市町村の区域内に住所を有する 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 |
★ ポイントは、第2号被保険者の条件は、「医療保険加入者」であることです。
ですので、第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合は、医療保険加入者でなくなった日から介護保険の被保険者資格は喪失します。問題文のような例外規定はありません。
社労士受験のあれこれ
確定拠出年金(個人型)・脱退一時金
H30.3.7 H29年問題より「確定拠出(個人型)の脱退一時金」
H29年本試験【一般常識問9D】を解いてみてください。
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50万円未満であることとされている。

【解答】 ×
★ 数字が誤っています。
「通算拠出期間」については1月以上3年以下であること、「個人別管理資産の額」として政令で定めるところにより計算した額については25万円以下であること、です。
★ 個人型年金の脱退一時金の支給要件は以下の通りです。空欄を埋めてください。
当分の間、次の全てに該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
【1】 < A >であること。
【2】 障害給付金の受給権者でないこと。
【3】 その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額(< B >円)以下であること。
【4】 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
【5】 企業型年金の資格喪失した後の脱退一時金の支給を受けていないこと。

【解答】
A (国民年金の)保険料免除者 B 25万
社労士受験のあれこれ
介護保険の審査請求
H30.2.8 H29年問題より「介護保険の審査請求」
H29年本試験【一般常識問6C】を解いてみてください。
介護保険の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。

【解答】 ×
★ 都道府県知事ではなく「介護保険審査会」に審査請求をすることができる、です。
★ 介護保険審査会は、各都道府県に置かれることがポイントです。
社労士受験のあれこれ
後期高齢者医療広域連合
H30.1.19 H29年問題より「後期高齢者医療広域連合の役割」
H29年本試験【一般常識問8D】を解いてみてください。
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。

【解答】 ○
★ 「後期高齢者医療広域連合」は都道府県単位で設けられています。
★ こちらもチェック
「保険料」について
→ 徴収は「市町村」が行う
第104条第1項
市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
→ 保険料率は「後期高齢者医療広域連合」の条例で定める
第104条第2項
保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。(以下略)
社労士受験のあれこれ
基本の問題その9(社会保険の一般常識)
H29.12.30 H29年問題より「基本」を知ろう・社会保険審査官・社会保険審査会
深く考えず、さらりと「そんなもんだ」と覚えてしまえばOKな問題を取り上げます。
社会保険審査官と社会保険審査会
社会保険審査官と社会保険審査会の違いを押さえましょう
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法等の行政不服審査を行う機関として、「社会保険審査官」と「社会保険審査会」があります。それぞれの特徴を押さえましょう。
| 社会保険審査官 | 社会保険審査会 |
| 地方厚生局に置かれる | 厚生労働大臣の所轄の下に置かれる (厚生労働省に設置) |
| 厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命する | 委員長・委員は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する |
| 独任制 | 合議制 委員長と委員5人で組織される |
これを覚えると、平成29年【問6】Aが解けます。
★問題です。
(平成29年【問6】A)
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

<解答> ×
★社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命します。
社労士受験のあれこれ
定番問題その20(社会保険の一般常識)
H29.12.13 H29年問題より「定番」を知る・確定拠出年金
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (確定拠出年金(個人型)に加入できる人)
「個人型年金加入者」の要件(平成29年1月より加入枠が拡大)
★ 「個人型年金加入者」になることができる人
① 国民年金第1号被保険者 ※ 保険料免除者は加入できない(ただし、障害基礎年金の受給権者で法定免除を受けている者等は加入できる) |
② 60歳未満の厚生年金保険の被保険者 ※ 「企業型年金加入者」は、規約で個人型年金加入者となることができることを定めている場合は、個人型に加入できる ※ 公務員、私学共済の加入者も加入できる |
| ③ 国民年金第3号被保険者 |
これを覚えると、平成29年【問9】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問9】B)
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができるとされた。

<解答> 〇
★平成29年1月の改正で、公務員、私学共済加入者、専業主婦も加入できるようになりました。
社労士受験のあれこれ
定番問題その10(社会保険の一般常識)
H29.11.19 H29年問題より「定番」を知る・高齢者医療確保法【修正あり】
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
★ 改正により修正しています。(H30.5.17)★
定番問題 (特定健康診査等実施計画)
「特定健康診査等実施計画」は、「6年」ごとに「6年」を一期として定める。
★ 3つの「計画」を整理しておきましょう。
| 誰が | サイクル | |
| 全国医療費適正化計画 | 厚生労働大臣が定める | 6年ごとに、6年を一期 |
| 都道府県医療費適正化計画 | 都道府県が定める | 6年ごとに、6年を一期 |
| 特定健康診査等実施計画 | 保険者が定める | 「5年ごとに、5年を一期」から「6年ごとに、6年を一期」に改正(H30.4.1施行) |
これを覚えると、平成29年【問8】Bが解けます。
★問題です。
(平成29年【問8】B)
保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとされている。

<解答> ×
★ 出題当時は○でしたが、改正により6年ごとに、6年を1期になりましたので、「×」となります。
社労士受験のあれこれ
定番問題その9(社会保険労務士法)
H29.11.8 H29年問題より「定番」を知る・社会保険労務士法
何度も何度も繰り返し出題され、テキストには、ゴシック体・太字・色付き・アンダーラインで示される箇所。
そんな「定番問題」は、慣れてしまえば大丈夫。
定番問題を取り上げていきます。
定番問題 (信用失墜行為の禁止)
禁止されている「信用失墜行為」を行った場合、罰則は適用されるか?
★ 社会保険労務士法第16条では、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」と規定されています。(信用失墜行為の禁止)
★ 第16条(信用失墜行為の禁止)に違反があっても罰則はありません。
★ちなみに、同法第15条には、(不正行為の指示等の禁止)が規定されていますが、第15条違反については、罰則が規定されています。(社労士法上一番重い罰則・3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
これを覚えると、平成29年【問3】Cが解けます。
★問題です。
(平成29年【問3】C)
社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。

<解答> ×
★ 罰則規定はありません。
社労士受験のあれこれ
覚えれば解ける問題その10(社会保険一般常識)
H29.10.24 H29年問題より「暗記」ポイントを学ぶ・高齢者医療確保法
あれこれ考えないと解けない「ひねった難しい問題」ばかりではありません。
覚えているだけで簡単に解ける問題も出題されています。
「暗記」するだけで得点できる箇所は、どんどん覚えていきましょう!
覚えれば解ける (後期高齢者医療)
「後期高齢者医療」は、高齢者の「疾病、負傷又は死亡」に関する給付を行う。
★ 後期高齢者医療の対象者は?
① 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
② 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
★ 後期高齢者医療の運営主体は?
後期高齢者医療広域連合が運営している
★ 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
※ 「出産」に関する給付はありません。
これを覚えると、平成29年【問8】Aが解けます。
★問題です。(平成29年【問8】A
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。

<解答> ×
「死亡」に関する給付は行われます。
社労士受験のあれこれ
まずは原則!その7(一般常識(社会保険))
H29.10.3 H29年問題より原則を学ぶ・一般常識(介護保険)
「なかなか、勉強がはかどらない~、面白くない!」と感じる方のために。
枝葉に気を取られてしまっていませんか?
そんなときは、思い切って「原則」に集中しましょう!
「原則」の問題が解けるようになれば、「例外」や「応用」は自然についてきます。
今日の原則(介護保険の保険給付は3種類)
介護保険の保険給付は、「介護給付」、「予防給付」、「市町村特別給付」の3種類。
| 介護給付 | 被保険者の要介護状態に関する保険給付 |
|---|---|
| 予防給付 | 被保険者の要支援状態に関する保険給付 |
| 市町村特別給付 | 要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの |
◆ポイント 条例で定める「市町村特別給付」があることを忘れずに。
この原則で、平成29年【問7】Dが解けます。
★問題です。(平成29年【問7】D)
介護保険法による保険給付には、被保険者の要介護状態に関する保険給付である「介護給付」及び被保険者の要支援状態に関する保険給付である「予防給付」のほかに、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定める「市町村特別給付」がある。

<解答> 〇
社労士受験のあれこれ
平成29年度選択式を解きました。(社会保険一般常識編)
H29.9.11 平成29年度選択式(社会保険一般常識編)~次につなげるために~
平成29年度の選択式を順番に見ていきます。
今後の選択対策に生かせるよう、傾向を分析していきます。
本日は、「社会保険に関する一般常識」です。
【A、B】
「国民健康保険法第1条(目的)、第2条」からの出題です。
毎年、どこかで出題されているのが「目的条文」です。
試験直前にはチェックが必須です。
コチラの記事で取り上げています。
→ H29.8.4 目的条文のチェック(一般常識・社保編その1)
Bは「誰のため・何のための保険なのか?」ということで、健康保険法との違いを押さえておけばOKな問題です。
【C】
介護保険法第4条(国民の努力及び義務)からの問題です。
国民の「努力と義務」についての規定です。前半の「自ら要介護状態となることを予防するため」の部分と後半の「要介護状態となった場合においても・・・能力の維持向上に努める」の部分がヒントになろうかと思います。
【D、E】
「児童手当法」からの出題です。
Dは、児童手当の支給を受ける際の認定、Eは、児童手当の支払い月についての問題です。
児童手当は平成21年、26年、27年、28年と立て続けに出題されています。
過去問対策をしていた方には、解答しやすい問題だと思います。
今後の勉強のポイント!
★ 白書だけでなく法令も忘れずに
「社会保険の一般常識」と聞くと、ついつい白書対策の方に気持ちが行きがちですが、基本的な法令の内容も忘れずに。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】選択式の練習(確定拠出年金法)
H29.8.15 選択式の練習(確定拠出年金法・脱退一時金)
選択式の練習問題です。
本日は、確定拠出年金法の個人型年金の「脱退一時金」の支給要件の改正個所からです。
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
附則第3条
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
一 < A >であること。
二 障害給付金の受給権者でないこと。
三 その者の通算拠出期間が1月以上3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額 (< B >円)以下であること。
四 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
五 前条第1項による脱退一時金(企業型年金加入者の資格喪失時の脱退一時金)の支給を受けていないこと。

<解答>
A 保険料免除者 B 25万
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(一般常識・社保その2)
H29.8.7 目的条文のチェック(一般常識・社保編その2)
今日も目的条文のチェックです。「一般常識・社保編その2」です。
それでは、空欄を埋めてください。
<確定給付企業年金法>
(第1条 目的)
この法律は、< A >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< B >が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって < C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
<確定拠出年金法>
(第1条 目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< A >又は事業主が拠出した資金を< A >が< B >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって< C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
<社会保険労務士法>
(第1条 目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。
(第1条の2 社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に< C >を保持し、業務に関する法令及び< D >に精通して、< E >な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

<解答>
<確定給付企業年金法>
(第1条 目的)
この法律は、<A 少子高齢化>の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<B 事業主>が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
<確定拠出年金法>
(第1条 目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<A 個人>又は事業主が拠出した資金を<A 個人>が<B 自己の責任>において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
<社会保険労務士法>
(第1条 目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の<A 健全な発達>と労働者等の<B 福祉の向上>に資することを目的とする。
(第1条の2 社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に<C 品位>を保持し、業務に関する法令及び<D 実務>に精通して、<E 公正>な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(一般常識・社保その1)
H29.8.4 目的条文のチェック(一般常識・社保編その1)
今日は目的条文のチェック「一般常識・社保編その1」です。
空欄を埋めてください。
<国民健康保険法>
第1条 (目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び < B >の向上に寄与することを目的とする。
<高齢者の医療の確保に関する法律>
第1条 (目的)
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び< A >による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の< B >の理念等に基づき、前期高齢者に係る< A >間の< C >の調整、後期高齢者に対する適切な< D >の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (基本的理念)
国民は、< E >と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な< F >を受ける機会を与えられるものとする。
<介護保険法>
第1条 (目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の < A >を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した< B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

<解答>
<国民健康保険法>
(第1条 目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて<A 社会保障>及び<B 国民保健>の向上に寄与することを目的とする。
★Bは「国民保健」。健康の「健」です。
<高齢者の医療の確保に関する法律>
第1条 (目的)
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び<A 保険者>による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の<B 共同連帯>の理念等に基づき、前期高齢者に係る<A 保険者>間の<C 費用負担>の調整、後期高齢者に対する適切な<D 医療>の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 (基本的理念)
国民は、<E 自助>と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。
2 国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な<F 保健サービス>を受ける機会を与えられるものとする。
<介護保険法>
(第1条 目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の <A 医療>を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した<B 日常生活>を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の<C 共同連帯>の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
社労士受験のあれこれ
社会保険労務士試験(社会保険労務士法)
H29.3.31 社会保険労務士試験の実施
平成29年度(第49回)の社会保険労務士試験の詳細は、4月中旬に公示されます。
社会保険労務士試験の実施については、社会保険労務士法に規定されています。
今日は、その規定を確認しましょう。空欄<A>と<B>を埋めてください。
<社会保険労務士法>
第10条
社会保険労務士試験は、毎年1回以上、< A >が行なう。
第10の2 < A >は、< B >に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができる。

<解答>
A 厚生労働大臣 B 全国社会保険労務士会連合会
→ 試験事務は厚生労働大臣から全国社会保険労務士会連合会に委託されています。

★ ちなみに
「全国社会保険労務士会連合会」と「社会保険労務士会」の違いにも注意してください。
「社会保険労務士会」は都道府県ごとに一つずつ設立されていますが、「全国社会保険労務士会連合会」は全国に一つです。
★ もうひとつ
社会保険労務士となるには登録を受けますが、登録を受けたときに社会保険労務士会の会員となることになっています。(社会保険労務士法第25条の29)
例えば、私の場合、事務所が兵庫県にありますので、兵庫県の「社会保険労務士会」の会員となっています。
社労士受験のあれこれ
<シリーズ>平成28年度本試験の検証
H28.12.21 必ず出る改正点(一般常識・社労士法編)
法改正部分は「絶対出る!」という前提で、取り組みましょう。
平成28年度本試験で、改正点がどのように出題されたのか振り返っています。
こちらのページにまとめています → 平成28年度本試験の検証
本日は平成28年度一般常識問3のDです。社労士法からの問題です。
<問題文>
社会保険労務士法人の設立には2人以上の社員が必要である。

【答え】 ×
★ 以前は、社会保険労務士法人を設立するためには、2人以上の社員が必要でした。が、改正で平成28年1月1日からは社員が1人でも社会保険労務士法人を設立できるようになりました。
ポイント!
「社員」とは従業員のことではありません。社会保険労務士法人の社員は「社会保険労務士」であることが条件です。
社労士受験のあれこれ
介護保険法の誕生
H28.10.18 介護保険法のスタート
もともと「介護」については、「老人福祉制度(措置制度)」と「老人保健制度(医療保険)」の2つに制度が分かれていました。
しかし、高齢化の進展や核家族化の進行等で、家族だけで介護をすることが難しくなってたこともあり、従来の介護のシステムが見直され、誕生したのが「介護保険法」です。
介護保険は、健康保険や年金などと同じように「負担」と「給付」が明確な「社会保険方式」で運営されていることがポイントです。
介護保険法がスタートしたのは「平成12年4月」です。
それでは過去問を解いてみましょう。
<平成19年出題>
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された。

【解答】
<平成19年出題> ○
社労士受験のあれこれ
H28年度選択式を解きました。その3(一般常識編)
H28.9.2 平成28年度選択式(一般常識編)~次につなげるために~
平成28年度の選択式問題から、今後の対策を探ります。
★労基・安衛編はコチラから。
→ H28.8.31 平成28年度選択式(労基、安衛編)~次につなげるために~
★労災・雇用編はコチラから。
→ H28.9.1 平成28年度選択式(労災、雇用編)~次につなげるために~
本日は、一般常識です。
<労務管理その他の労働に関する一般常識>
【A】、【B】、【C】
現金給与額が労働費用総額に占める割合、現金給与以外の労働費用に占める法定福利費の割合の問題です。(平成23年就労条件総合調査からの出題)
「法定福利費の構成(厚生年金保険料、健康保険料・介護保険料の占める割合)」、「労働費用総額の構成(現金給与部分と現金給与以外の割合)」については、平成22年に択一式で出題実績があります。
労働費用については択一式で出題実績があったので気になっていましたが、直近の調査結果が平成23年のものだったので、当サイトでは取り上げていませんでした。
反省です。
過去1~2年のデータを中心に取り上げていましたが、今後は重要なデータは少々前のものでもチェックが必要だと感じました。
特に【A】と【B】に入る割合は、悩んだ方が多かったのではないでしょうか?
【D】、【E】
推定組織率の定義、組合活動の重点課題からの出題です。
感想は、「うーん、難しい。」
【D】は、各統計の調査事項を思い出した上で、「雇用労働者数」をヒントに考えた方が多いと思いますが、かなり迷ったのではないでしょうか?
やはり、労働経済に出てくる「用語の定義」は、今後も丁寧なチェックが必要だと思いました。
【E】については、他にたくさん覚えなければならないことがあるなかで、ここまで覚えておいてくださいね、とは言えません・・・。難しいです。
<社会保険に関する一般常識>
【A】、【B】
平成23年版厚生労働白書からの出題です。
【A】は少々難しかったかもしれませんが、【B】については、平成21年択一式にも出題されているので、解けた方も多かったのではないでしょうか?
★実は、平成23年版厚生労働白書は面白いです。平成23年版の「社会保障の検証と展望~国民皆保険・皆年金から半世紀」という特集では、社会保障制度の変遷が主な社会情勢とともに紹介されています。医療保険や年金を勉強する上で為になる特集なので、ぜひ読んでいただきたいところです。(厚生労働省のホームページからも読むことができます。)
【C】
児童手当からの問題です。
支給要件児童の定義を思い出せれば大丈夫だったと思います。
【D】、【E】
国民健康保険料を滞納したときの被保険者証の返還からの出題です。
きちんと勉強されていた方が多かった個所だと思います。
次回は、年金です。
社労士受験のあれこれ
【直前】「社会保険の一般常識」の選択対策
H28.8.24 直前!「社会保険の一般常識」の選択対策
ラストスパートです。
あともう一息です。暑いですが頑張りましょう。
<国民健康保険法・審査請求>
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、< A >に審査請求をすることができる。
< A >は、各< B >に置く。
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して< C >以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
<介護保険法・審査請求>
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、< D >に審査請求をすることができる。
< D >は、各< E >に置く。
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して< F >以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
<高齢者の医療の確保に関する法律・審査請求>
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、< G >に審査請求をすることができる。
< G >は、各< H >に置く。
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して< I >以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

A 国民健康保険審査会 B 都道府県 C 3月
D 介護保険審査会 E 都道府県 F 3月
G 後期高齢者医療審査会 H 都道府県 I 3月
社労士受験のあれこれ
【直前対策】目的条文(一般常識・社保)
H28.8.4 目的条文のチェック(一般常識・社保編)
今日は目的条文のチェックの最終回で「一般常識・社保編」です。
★目的条文のチェック(労働編)はコチラ
★目的条文のチェック(社会保険編)はコチラ
★目的条文のチェック(一般常識労働編)はコチラ
それでは目的条文チェック「一般常識・社保編」にいきます。
<国民健康保険法>
(第1条 目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて< A >及び < B >の向上に寄与することを目的とする。
<高齢者の医療の確保に関する法律>
コチラの記事をどうぞ → H28.4.11 高齢者医療確保法・目的等
<介護保険法>
(第1条 目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の < A >を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した< B >を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の< C >の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
コチラの記事もどうぞ → H28.4.9 介護保険の総則をチェック
<確定給付企業年金法>
(第1条 目的)
この法律は、< A >の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< B >が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって < C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
こちらの記事もどうぞ → H28.3.1 確定給付企業年金法(確定拠出年金との比較)
<確定拠出年金法>
(第1条 目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、< A >又は事業主が拠出した資金を< A >が< B >において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって< C >の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
<社会保険労務士法>
(第1条 目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の< A >と労働者等の< B >に資することを目的とする。
(第1条の2 社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に< C >を保持し、業務に関する法令及び< D >に精通して、< E >な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

<解答>
<国民健康保険法>
(第1条 目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて<A 社会保障>及び<B 国民保健>の向上に寄与することを目的とする。
★Bは「国民保健」。健康の「健」です。
<高齢者の医療の確保に関する法律>
コチラの記事をどうぞ → H28.4.11 高齢者医療確保法・目的等
<介護保険法>
(第1条 目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の <A 医療>を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した<B 日常生活>を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の<C 共同連帯>の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
コチラの記事もどうぞ → H28.4.9 介護保険の総則をチェック
<確定給付企業年金法>
(第1条 目的)
この法律は、<A 少子高齢化>の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<B 事業主>が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
こちらの記事もどうぞ → H28.3.1 確定給付企業年金法(確定拠出年金との比較)
<確定拠出年金法>
(第1条 目的)
この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、<A 個人>又は事業主が拠出した資金を<A 個人>が<B 自己の責任>において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって<C 公的年金>の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
<社会保険労務士法>
(第1条 目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の<A 健全な発達>と労働者等の<B 福祉の向上>に資することを目的とする。
(第1条の2 社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に<C 品位>を保持し、業務に関する法令及び<D 実務>に精通して、<E 公正>な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
社労士受験のあれこれ
選択対策/社会保険労務士法
H28.5.23 社会保険労務士の業務【改正】
社会保険労務士の業務として、1号業務、2号業務、3号業務の3つが規定されています。基本的な用語は押さえておきましょう。
少しだけ改正点があります。
次の空欄を埋めてください。
社会保険労務士法第2条(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
①の1 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
①の2 申請書等について、その A に関する手続を代わつてすること。
①の3 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(以下「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、 B すること。(以下「事務代理」という。)
①の4 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定する紛争調整委員会における C の手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に規定する D の手続について、紛争の当事者を B すること。
①の5 地方自治法の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(一定の紛争を除く。)に関する C の手続について、紛争の当事者を B すること。
①の6 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が E 円を超える場合には、 F が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を B すること。
② 労働社会保険諸法令に基づく G (その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
③ 事業における H その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

【解答】
A 提出 B 代理 C あっせん D 調停 E 120万 F 弁護士
G 帳簿書類 H 労務管理
①の1から①の6までが1号業務、②が2号業務、③が3号業務です。
3号業務(相談、指導)は、社会保険労務士以外でも、業として行うことができます。

ちなみに改正点は、
申請等から異議申立てがなくなったこと(行政不服審査法の改正により)と、調停の対象に「障害者の雇用の促進等に関する法律」が加わったことです。
ここもチェック
①の4から①の6までの業務を、「紛争解決手続代理業務」といいます。紛争解決手続代理業務を行うことができるのは、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限られています。
<紛争解決手続代理業務に含まれる事務>
Ⅰ ①の4のあっせんの手続及び調停の手続、①の5のあっせんの手続並びに①の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。
Ⅱ 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
Ⅲ 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
社労士受験のあれこれ
選択式の練習 ~目的条文~
H28.4.11 高齢者医療確保法・目的等
「高齢者の医療の確保に関する法律」の第1条(目的)と第2条(基本的理念)の空欄を埋めてください。
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び A による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の B の理念等に基づき、 C に係る A 間の費用負担の調整、 D に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
国民は、 E の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を F に負担するものとする。
国民は、年齢、心身の状況等に応じ、 G 若しくは地域又は H において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

【解答】
A 保険者 B 共同連帯 C 前期高齢者 D 後期高齢者
E 自助と連帯 F 公平 G 職域 H 家庭
選択式の練習 ~介護保険~
H28.4.9 介護保険の総則をチェック
空欄を埋めてください。
<介護保険>
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 1の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 A との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 1の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の B に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 1の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その C において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
<保険者>
D は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
<努力及び義務>
1 E は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 E は、 F の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
<責務>
1 G は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 H は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
3 G 及び I は、被保険者が、可能な限り、 J でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
<協力>
K は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。

【解答】
A 医療 B 選択 C 居宅 D 市町村及び特別区 E 国民
F 共同連帯 G 国 H 都道府県 I 地方公共団体
J 住み慣れた地域 K 医療保険者
【H28.4.1改正】高齢者の医療の確保に関する法律
H28.3.28 全国医療費適正化計画・都道府県医療費適正化計画
平成28年4月1日より、医療費適正化計画の規定が改正されます。
空欄部分がポイントですので、チェックしてください。
(医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画)
第8条 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(以下「医療費適正化」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(以下「医療費適正化基本方針」という。)を定めるとともに、 A 年ごとに、 A 年を一期として、医療費適正化を推進するための計画(以下「全国医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。
(都道府県医療費適正化計画)
第9条 都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、 A 年ごとに、 A 年を一期として、当該都道府県における医療費適正化を推進するための計画(以下「都道府県医療費適正化計画」という。)を定めるものとする。

A 6
「5年ごとに、5年を一期として」が「6年ごとに、6年を一期として」に改正されています。

ちなみに、「特定健康診査等実施計画」は「5年ごとに、5年を一期として」のままです。
(特定健康診査等実施計画)
第19条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を一期として、特定健康診査等の実施に関する計画(以下「特定健康診査等実施計画」という。)を定めるものとする。
■■ところで、主語の「保険者」の定義は押さえていらっしゃいますか?
「高齢者の医療の確保に関する法律」でいう「保険者」とは、
「保険者」→ 医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
★★保険者とは「後期高齢者医療広域連合」のことではないので注意してくださいね★★
選択式の練習 ~高齢者の医療の確保に関する法律~
H28.3.25 後期高齢者医療・保険料
「高齢者の医療の確保に関する法律」第104条では、保険料について規定しています。空欄を埋めてください。
1 A は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
2 1の保険料は、 B が被保険者に対し、 B の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い B の C で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課する。ただし、当該 B の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であつて厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別に B の C で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保険料額によつて課することができる。
3 2の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、第116条第1項第2号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、保健事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第100条第1項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね D 年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】
A 市町村 保険料を「徴収」するのは市町村
B 後期高齢者医療広域連合 保険料を「課す」のは後期高齢者医療広域連合
C 条例
D 2
選択式の練習
H28.3.1 確定給付企業年金法
次の「確定給付企業年金法」の目的条文の空欄に入る文章を、選択肢の中から選んでください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、 A にするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
【選択肢】
① 事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるよう
② 個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるよう

【解答】①
確定給付企業年金は、将来の給付額が約束されている「確定給付型」の年金です。
キーワードは、事業主が従業員と「給付の内容を約している」こと、高齢期に従業員が「その内容に基づいた給付」を受けることができること。従業員は、事業主と約束した給付内容を将来うけとることができるのがポイントです。
選択肢②は「確定拠出年金法」の目的です。確定拠出年金は、将来の給付内容は約束されておらず、自分の運用しだいで将来の給付内容が決まるタイプの年金です。
キーワードは、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行うこと、高齢期にその結果に基づいた給付を受けること。将来の給付額はあくまでも自己責任、事業主は給付内容については保障しないというのがポイントです。
年金制度の歴史
H28.2.29 厚生年金、共済年金、いつからスタートしたの?
平成27年10月より、被用者年金が一元化されています。
一元化された厚生年金、共済年金など、これまでの年金の歴史をおさえておきましょう。
被用者(会社員、船員など)
| 昭和14年 | 船員保険法制定 ・昭和15年6月施行 ・昭和61年4月 厚生年金保険法に統合 |
| 昭和16年 | 労働者年金保険法制定 ・昭和17年6月施行 ・昭和19年 厚生年金保険法に改称 |
被用者(公務員など)
| 昭和23年 | 国家公務員共済組合法制定 ・昭和23年7月施行 |
| 昭和28年 | 私立学校教職員共済法制定(当時の名称は私立学校教職員共済組合法) ・昭和29年1月施行 |
| 昭和37年 | 地方公務員等共済組合法制定 ・昭和37年12月施行 |
自営業者など
| 昭和34年 | 国民年金法制定 ・昭和34年11月 無拠出制スタート ・昭和36年 4月 拠出制スタート |
今日のポイント!
被用者年金(厚生年金、共済年金)のほうが、国民年金よりも歴史が古い。
横断 確定拠出年金法と確定給付企業年金法
H28.2.25 給付の種類
◇給付の種類◇
次の問題を解いてみてください。
確定給付企業年金
【問題1 平成15年出題】
確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定めにより、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。
確定拠出年金
【問題2 平成20年出題】
企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。
【解答】
【問題1 平成15年出題】 ×
※老齢給付金及び死亡一時金を基本ではなく、老齢給付金及び「脱退一時金」を基本とする。
【問題2 平成20年出題】 ○
※企業型年金も個人型年金も給付の種類は同じ。(脱退一時金の要件に違いがある)
<給付の種類>
| 確定給付企業年金 | 確定拠出年金 |
老齢給付金、脱退一時金 (障害給付金、遺族給付金も行うことができる) | 老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金 |
ちなみに、確定給付企業年金は「遺族給付金」、確定拠出年金は「死亡一時金」です。
似た用語
H28.2.23 介護保険法 ○○審査会
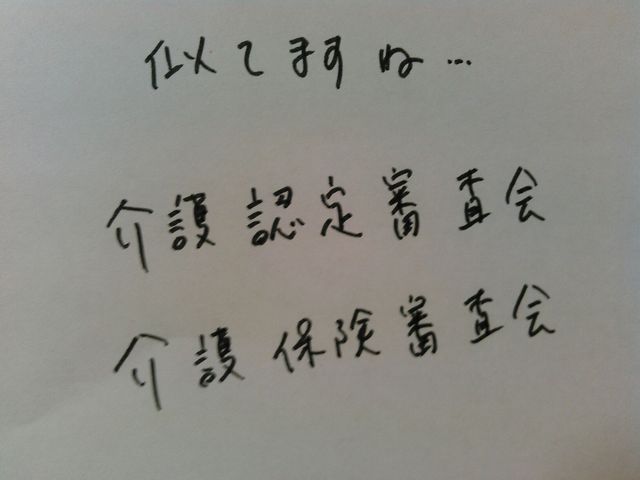
次の空欄を以下の選択肢から埋めてください。
◆選択肢◆
1 介護認定審査会
2 介護保険審査会
【問題1】
第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に A を置く。
【問題2】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の支給に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、 B に審査請求をすることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解答】
問題1A 審査判定業務は → 1 介護認定審査会
問題2B 審査請求は → 2 介護保険審査会
名称が似ているので引っかからないように注意してください。
ちなみに、「介護認定審査会」は市町村、「介護保険審査会」は都道府県に置かれます。
H28.2.11 社会保険労務士法 罰則
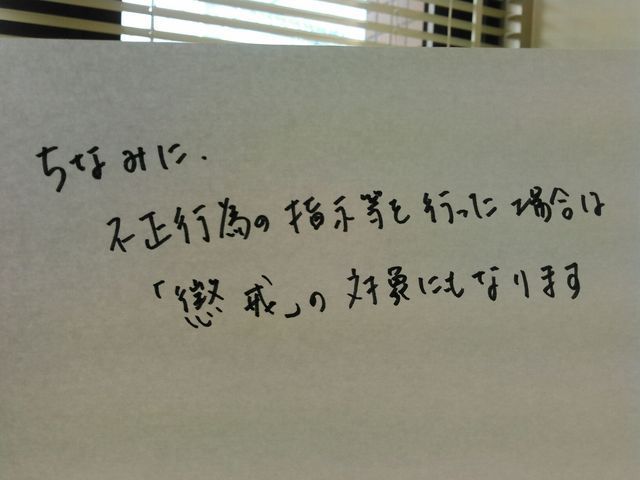
社会保険労務士法の次の2つの条文を見てください。
(第15条 不正行為の指示等の禁止)
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
(第16条 信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
不正行為の指示をすること等や信用失墜する行為をすることは社会保険労務士として禁止されています。
では、これらの禁止事項に違反した場合の罰則はどのようになっているでしょうか?次の1~4のうちから選んでください。
1 (第15条 不正行為の指示等の禁止)、(第16条 信用失墜行為の禁止)両方とも罰則あり
2 (第15条 不正行為の指示等の禁止)、(第16条 信用失墜行為の禁止)両方とも罰則なし
3 (第15条 不正行為の指示等の禁止)のみ罰則あり
4 (第16条 信用失墜行為の禁止)のみ罰則あり
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】3 (第15条 不正行為の指示等の禁止)のみ罰則あり
第15条の不正行為の指示等の禁止規定に違反した場合は、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が規定されています。社会保険労務士法上で一番重い罰則です。
一方、第16条の信用失墜行為の禁止規定には罰則規定はありません。
出題実績がある個所なので、注意してくださいね。
H28.2.6 介護保険法 実施主体など
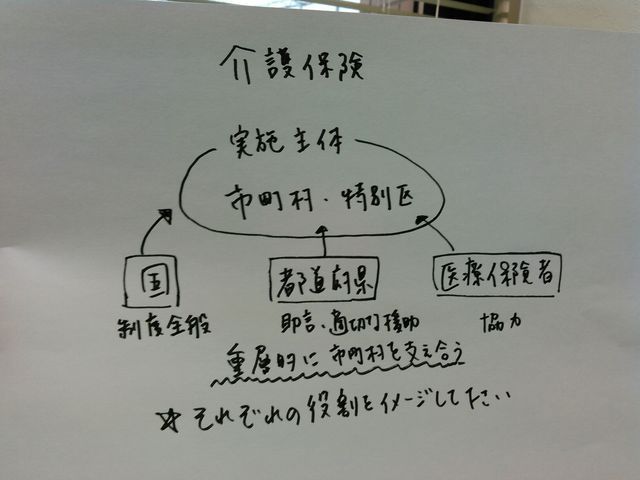
介護保険法について、次の空欄を埋めてください。
■介護保険の実施主体(保険者)は?
A は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】 A 市町村及び特別区
住民に身近な市町村が保険者となり、介護保険の保険給付や保険料の徴収を行います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■では、市町村を支える役割をもつものは?■
・ B は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講じなければならない。
・ C は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
・ D は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【答】B 国 C都道府県 D医療保険者
○ポイント
問題文の太字のアンダーラインに注目してください。「国」は制度全般について必要な措置を講ずる役割、「都道府県」は助言と援助をする役割です。「国」と「都道府県」を逆にする問題がよく出ますので注意です。
医療保険者は「協力」です。
○ちなみに「医療保険者」とは?
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
H28.1.13 年齢
60歳、65歳、70歳、75歳。法律によって年齢の基準が違うので頭の中がごちゃごちゃしませんか?
次の空欄を埋めて整理してみてください。
■雇用保険法
<高年齢継続被保険者>
同一の事業主の適用事業に ① 歳に達した日の前日から引き続いて ② 歳に達した日以後の日において雇用されているもの
■徴収法
<雇用保険料の免除の対象になる高年齢労働者>
保険年度の初日に ③ 歳以上の労働者
■健康保険法
<一部負担金>
1 ④ 歳に達する日の属する月以前 → 100分の30
2 ⑤ 歳に達する日の属する月の翌月以後 (3の場合を除く。)
→100分の20
3 ⑥ 歳に達する日の属する月の翌月以後の一定以上所得者
→ 100分の30
■厚生年金保険法
<被保険者>
適用事業所に使用される ⑦ 歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
■高齢者の医療の確保に関する法律
<後期高齢者医療の被保険者>
1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑧ 歳以上の者
2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する ⑨ 歳以上 ⑩ 歳未満の者で、一定の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
■介護保険法
<介護保険の被保険者>
・第1号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑪ 歳以上の者
・第2号被保険者
市町村の区域内に住所を有する ⑫ 歳以上 ⑬ 歳未満の医療保険加入者
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【解答】
①65 ②65 ③64 ④70 ⑤70 ⑥70 ⑦70 ⑧75 ⑨65 ⑩75 ⑪65 ⑫40 ⑬65
H28.1.12 平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況
平成27年12月22日に、厚生労働省より「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」が発表されました。
それによると、平成26年度末現在の公的年金加入者数は6713万人。前年度末に比べると4万人減少しているそうです。
では、「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から作った次の問題を考えてみてください。
【問題】
「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、平成26年度末現在の第1号被保険者数と第3号被保険者数は前年度末に比べると増加しているが、被用者年金被保険者数は、前年度末に比べると減少している。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「平成26年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、
・第1号被保険者数 1742万人(前年度末に比べて63万人減少)
・第3号被保険者数 932万人(前年度末に比べて13万人減少)
・被用者年金被保険者数 4039万人(前年度末に比べて73万人増加)
【解答】 ×
