合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
令和2年度版
社労士受験のあれこれ(過去記事)
このページは令和2年度版です。
頑張ろう!
R2-266
R2.8.23 合格を祈ります
いよいよ本番です。
積み重ねてきたこと、自分を信じて。
120%の力が発揮できますように。
合格を祈ります
最後に雇用保険法をどうぞ!
【改正 雇用保険法】
(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(雇用保険事業)
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
社労士受験のあれこれ
令和2年度の国民年金の数字
R2-265
R2.8.22 令和2年度の国民年金の数字check
 本試験の前日・当日にチェックしてほしいこと
本試験の前日・当日にチェックしてほしいこと
「数字」
覚えていたら解けるけど、覚えてなければ手も足も出ません。
当日、ぎりぎりまで数字を頭に叩き込んでください。
では、どうぞ!
令和2年度 老齢基礎年金の満額
780,900円 × 改定率< A > ≒ < B >円
<老齢基礎年金の額 40年間すべて保険料納付済期間の場合>
老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に< C >未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、< C >以上< D >未満の端数が生じたときは、これを< D >に切り上げるものとする。)とする。
令和2年度 国民年金保険料
17,000円 × 保険料改定率< E > ≒ < F >円

【解答】
A 1.001
B 781,700
C 50円
D 100円
780,900円×1.001=781,680.9円 → 781,700円(100円未満で四捨五入)
E 0.973
F 16,540円
17,000円(法定額)×0.973(保険料改定率)=16,541円 → 16,540円
(10円未満で四捨五入)
社労士受験のあれこれ
雇用保険法 教育訓練給付(特定一般教育訓練)
R2-264
R2.8.21 特定一般教育訓練(R1.10.1施行)
 最後の最後にチェックしてほしいのは
最後の最後にチェックしてほしいのは
・改正項目
→ 出題可能性が高いから。
・どうしても分からなかった箇所
→ どうしても分からなかった箇所でも、一回だけ読んでみてください。
案外、すんなり頭に入ることがありますので。
本日は、「特定一般教育訓練(R1.10.1施行)」です。
では、どうぞ!
「特定一般教育訓練」
→ 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練
【問題】
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練の受講のために支払った費用の額に< A >を乗じて得た額(その額が< B >円を超えるときは、< B >円)とする。
特定一般教育訓練受講予定者は、当該特定一般教育訓練を開始する日の < C >前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
① 担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであって厚生労働大臣が定めるものをいう。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
②以下 略
教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に、教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して< D >以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
① 特定一般教育訓練修了証明書
②以下 略

【解答】
A 100分の40
B 20万
C 1カ月
D 1カ月
社労士受験のあれこれ
パートタイム・有期雇用労働法
R2-263
R2.8.20 パ・有法 R2年4月1日改正
本日は、「パ・有法 R2年4月1日改正 」です。
」です。
パートタイム・有期雇用労働法のポイント!
「正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差の禁止」
R2年4月1日施行(中小企業はR3年4月1日~)
では、どうぞ!
(基本的理念)
短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び< A >に応じて就業することができる機会が確保され、< B >の充実が図られるように配慮されるものとする。

【解答】
A 能力
B 職業生活
こちらもどうぞ!
(不合理な待遇の禁止)
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う< C >に照らして< D >と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

【解答】
C 目的
D 適切
★ 同じ企業の正社員と短時間労働者・ 有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることを禁止しています。
「均衡待遇」といいます。(均衡=バランスのこと)
社労士受験のあれこれ
障害者雇用促進法
R2-262
R2.8.19 R2年4月1日改正あり 障害者雇用促進法
本日は、「R2年4月1日改正あり 障害者雇用促進法」です。
では、どうぞ!
(基準に適合する事業主の認定)
厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時< A >人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

【解答】
A 300
★ 障害者の雇用の促進等に関する取組みについて、実施状況が優良であること等の基準に適合する中小事業主を認定する制度ができました。
こちらもどうぞ!
厚生労働大臣は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、納付金関係業務を行う。
一 略
一の二 特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にある対象障害者を特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満のものをいう。)として雇い入れる事業主又は対象障害者である特定短時間労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金を支給すること。
二以下 略
特例給付金の支給額
| 事業主区分 | 支給額 |
| 常時雇用労働者数 100人超 | < B >円/人 月 |
| 常時雇用労働者数 100人以下 | < C >円/人 月 |
※ 支給上限は、週20時間以上の雇用障害者数

【解答】
B 7,000
C 5,000
※BCともに、特定短時間労働者1人当たりの額です。
※特定短時間労働者 → 1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満のもの
※短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため
社労士受験のあれこれ
目的条文check 2 社保編
2 社保編
R2-261
R2.8.18 健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック
目的条文は要チェック!
本日は、「健保・国年・厚年/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「健康保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者又はその被扶養者の< A >(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する< A >をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(基本的理念)
第2条 健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、< C >の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び< D >並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して< E >検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

【解答】
A 業務災害
B 福祉の向上
C 高齢化
D 後期高齢者医療制度
E 常に
問2 「国民年金法」
(国民年金制度の目的)
第1条 国民年金制度は、< A >に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって< B >の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(国民年金の給付)
第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(管掌)
第3条 国民年金事業は、政府が、管掌する。
2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合(単に「共済組合」という。)、国家公務員共済組合連合会、 < C >、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた< D >(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。
3 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、< E >が行うこととすることができる。

【解答】
A 日本国憲法第25条第2項
B 健全な国民生活
C 全国市町村職員共済組合連合会
D 日本私立学校振興・共済事業団
E 市町村長(特別区の区長を含む。)
問3 「厚生年金保険法」
(目的)
第1条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の< A >の安定と< B >に寄与することを目的とする。
(管掌)
第2条 厚生年金保険は、< C >が、管掌する。

【解答】
A 生活
B 福祉の向上
C 政府
社労士受験のあれこれ
目的条文check 1 労働編
1 労働編
R2-260
R2.8.17 労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック
目的条文は要チェック!
本日は、「労基・安衛・労災・雇用/目的条文などまとめてチェック」です。
では、どうぞ!
問1 「労働基準法」
(労働条件の原則)
第1条 労働条件は、労働者が< A >を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の< B >は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この< B >を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その< C >を図るように努めなければならない。
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、< D >において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、< E >各々その義務を履行しなければならない。

【解答】
A 人たるに値する生活
B 基準
C 向上
D 対等の立場
E 誠実に
問2 「労働安全衛生法」
(目的)
第1条 この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び< A >の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の< B >を確保するとともに、< C >の形成を促進することを目的とする。

【解答】
A 自主的活動
B 安全と健康
C 快適な職場環境
問3 「労災保険法」
第1条 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の< A >に寄与することを目的とする。
第2条 労働者災害補償保険は、< B >が、これを管掌する。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、 < C >を行うことができる。
第3条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
② 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び< D >(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

【解答】
A 福祉の増進
B 政府
C 社会復帰促進等事業
D 官公署の事業
問4 「雇用保険法」
 R2年4月1日改正 要チェックです!
R2年4月1日改正 要チェックです!
(目的)
第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< A >をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の< B >を図ることを目的とする。
(管掌)
第2条 雇用保険は、< C >が管掌する。
2 雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、< D >が行うこととすることができる。
(雇用保険事業)
第3条 雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び< E >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

【解答】
A 子を養育するための休業
B 福祉の増進
C 政府
D 都道府県知事
E 育児休業給付
社労士受験のあれこれ
横断編(不服申立て)
R2-259
R2.8.16 横断編/審査請求を棄却したものとみなすことができる
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「審査請求を棄却したものとみなすことができる」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
① 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日から< A >を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
A 3か月
問2 「雇用保険法」
① 資格取得・喪失の確認、失業等給付及び育児休業給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は不正受給に係る返還命令等に関する処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
② ①の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して < B >を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
B 3か月
問3 「健康保険法」
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
審査請求をした日から< C >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
C 2月
D 社会保険審査会
問4 「国民年金法」
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は< E >その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第14条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
審査請求をした日から< F >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

【解答】
E 保険料
F 2月
問5 「厚生年金保険法」
① 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第28条の4第1項又は第2項の規定による決定については、この限りでない。
② ①の審査請求をした日から< G >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、< H >に対して審査請求をすることができる。

【解答】
G 2月
H 社会保険審査会
| 棄却したものとみなすことができる | |
労災保険 雇用保険 | 審査請求をした日から3カ月を経過しても審査請求についての決定がないとき |
健康保険 国民年金 厚生年金保険 | 審査請求をした日から2月以内に決定がないとき |
では、こちらをどうぞ!
①<国民年金 H30年出題>
給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
②<厚生年金保険法 H29年出題>
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は社会保険審査官に対して、また、第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険審査会に対して、それぞれ審査請求をすることができる。

【解答】
①<国民年金 H30年出題> 〇
「2か月」がポイントです!
②<厚生年金保険法 H29年出題> ×
・第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者の審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査会」に対して行います。
・脱退一時金については、「社会保険審査会」で〇です。
(国民年金も「脱退一時金」は、「社会保険審査会」に対して審査請求ができます。
社労士受験のあれこれ
横断編(公課の禁止)
R2-258
R2.8.15 横断編/課税されるもの、されないもの
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「課税されるもの、されないもの」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
<H24年出題>
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

【解答】 〇
労災保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。」と規定されています。
※ 労災保険の保険給付には、「現金給付」と「現金給付」があるので「金品」
問2 「雇用保険法」
<H28年出題>
租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

【解答】 ×
雇用保険法では「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」とされています。
常用就職支度手当は失業等給付の中に入っていますので、課税できません。
※雇用保険法には現物給付がないので「金銭」となっています。
なお、雇用保険二事業の助成金等は失業等給付ではありませんので、公課を課することができます。
問3 「健康保険法」
<H18年出題>
出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。

【解答】 〇
健康保険法では、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」とされています。
保険給付(もちろん出産手当金出産育児一時金も含まれます。)は、課税されません。
問4 「国民年金法」
<H25年出題>
原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

【解答】 〇
国民年金法のルールは、以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、公課を課することができる。
問5 「厚生年金保険法」
障害厚生年金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課すことはできない。

【解答】 〇
厚生年金保険法のルールは以下の通り。
原則 → 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、公課を課することができる。
※ 「老齢厚生年金」は課税されますが、障害厚生年金は課税されません。
社労士受験のあれこれ
横断編(療養に関する指示に従わないとき)
R2-257
R2.8.14 横断編/療養に関する指示に従わないときの制限
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「療養に関する指示に従わないときの制限」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が故意の犯罪行為若しくは< A >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの< B >となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の< C >。

【解答】
A 重大な過失
B 原因
C 全部又は一部を行わないことができる
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の< D >。

【解答】
D 一部を行わないことができる
 「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
「全部又は一部」ではなく、「一部」なので注意してください。
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその< F >となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その< G >。
自己の故意の犯罪行為若しくは< E >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその< F >となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。

【解答】
E 重大な過失
F 原因
G 全部又は一部を行わないことができる
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは< H >により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの< I >となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の< J >。
障害厚生年金の受給権者が、< K >若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。

【解答】
H 重大な過失
I 原因
J 全部又は一部を行わないことができる
K 故意
こちらもどうぞ!
 問1労災保険法
問1労災保険法
労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
 問2 健康保険法
問2 健康保険法
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
 問3 国民年金法(R元年出題)
問3 国民年金法(R元年出題)
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題)
問4 厚生年金保険法(R元年出題)
被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】
 問1労災保険法 ×
問1労災保険法 ×
キーワードは、「故意に」「直接の原因」。
全部又は一部を行わないことができるではなく、「保険給付を行わない」です。
 問2 健康保険法 ×
問2 健康保険法 ×
キーワードは、「闘争、泥酔又は著しい不行跡」。
行わないではなく、「全部又は一部を行わないことができる」です。
 問3 国民年金法(R元年出題) 〇
問3 国民年金法(R元年出題) 〇
キーワードは、「故意に」。
故意に死亡させた者には支給しない。
 問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
問4 厚生年金保険法(R元年出題) 〇
故意に障害 → 障害厚生年金又は障害手当金は支給しない。
重大な過失 → 保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
社労士受験のあれこれ
横断編(支給制限~全部制限)
R2-256
R2.8.13 横断編/支給制限「行わない」のはどんなとき?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「支給制限「行わない」のはどんなとき?」です。
では、どうぞ!
問1 「労災保険法」
空欄を埋めてください。
労働者が、< A >負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< B >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

【解答】
A 故意に
B 直接の原因
問2 「健康保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< C >により、又は< D >給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

【解答】
C 自己の故意の犯罪行為
D 故意に
問3 「国民年金法」
空欄を埋めてください。
< E >障害又はその< F >となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を < E >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によっ遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を< E >死亡させた者についても、同様とする。
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< E >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
E 故意に
F 直接の原因
問4 「厚生年金保険法」
空欄を埋めてください。
被保険者又は被保険者であった者が、< G >、障害又はその< H >となった事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者を< G >死亡させた者には、支給しない。
被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を< G >死亡させた者についても、同様とする。
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を< G >死亡させたときは、消滅する。

【解答】
G 故意に
H 直接の原因
社労士受験のあれこれ
横断編(受給権の保護)
R2-255
R2.8.12 横断編/受給権の保護(譲り渡し、担保、差押え)
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「受給権の保護」です。
では、どうぞ!
「労災保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外あり)
年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合は、担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・国年、厚年も同様)
「雇用保険法」
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外なし)
「健康保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(例外なし)
「国民年金法」
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、厚年も同様)
・ 老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢基礎年金、付加年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
「厚生年金保険法」
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(例外あり)
・ 年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供することができる。
※年金を受ける権利を、独立行政法人福祉医療機構が行っている年金担保貸付事業の担保に供することができる。(年金のみ・労災、国年も同様)
・ 老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることができる。
※老齢厚生年金は、国税滞納処分による差し押さえの対象になる
 では、問題をどうぞ!
では、問題をどうぞ!
 労災保険法<H24年出題>
労災保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、譲り渡すことができない。
 雇用保険法<H23年出題>
雇用保険法<H23年出題>
教育訓練給付の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供することができない。
 健康保険法<H24年出題>
健康保険法<H24年出題>
保険給付を受ける権利は、健康保険法上、必要と認める場合には、譲渡や担保に供したり又は差し押さえることができる。
 国民年金法<H28年出題>
国民年金法<H28年出題>
給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H26年出題>
厚生年金保険法<H26年出題>
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分により差し押さえることができる。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
政府は、政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の貸付けを、< A >に行わせるものとされている。

【解答】
 労災保険法<H24年出題> 〇
労災保険法<H24年出題> 〇
 雇用保険法<H23年出題> 〇
雇用保険法<H23年出題> 〇
 健康保険法<H24年出題> ×
健康保険法<H24年出題> ×
保険給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押さえ、すべてできません。
 国民年金法<H28年出題> 〇
国民年金法<H28年出題> 〇
脱退一時金を受ける権利は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
※厚生年金保険でも、脱退一時金は国税滞納処分の例により差し押さえの対象になります。
 厚生年金保険法<H26年出題> ×
厚生年金保険法<H26年出題> ×
遺族厚生年金を受ける権利は、国税滞納処分による差し押えの対象にはなりません。
 厚生年金保険法<H28年選択>
厚生年金保険法<H28年選択>
A 独立行政法人福祉医療機構
社労士受験のあれこれ
横断編(確認しましょう60・65・70・75歳)その2
R2-254
R2.8.11 横断編/60・65・70・75歳その2(社一編)
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「60・65・70・75歳その2(社一編)」です。
では、どうぞ!
 高齢者医療確保法
高齢者医療確保法
空欄を埋めてください。
<被保険者>
次の1、2のいずれかに該当する者は、< A >が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
1 < A >の区域内に住所を有する< B >の者
2 < A >の区域内に住所を有する< C >の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該 < A >の認定を受けたもの
<特定健康診査>
保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< D >の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。

【解答】

A 後期高齢者医療広域連合
B 75歳以上
C 65歳以上75歳未満
D 40歳以上
 介護保険法
介護保険法
空欄を埋めてください。
<被保険者>
次の1,2のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
1 市町村の区域内に住所を有する< E >の者(「第1号被保険者」という。)
2 市町村の区域内に住所を有する< F >の医療保険加入者(「第2号被保険者」という。)

【解答】
E 65歳以上
F 40歳以上65歳未満
ついでにこちらもどうぞ!
①<高齢者医療確保法 H23年出題>
都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

【解答】
①<高齢者医療確保法 H23年出題> ×
保険料を徴収するのは「市町村(特別区を含む。)」です。都道府県は保険料の徴収は行いません。
ちなみに、保険料の決定は、後期高齢者医療広域連合が行います。
穴埋めで確認しましょう!
① < A >は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
② ①の保険料は、< B >が被保険者に対し、< B >の全区域にわたつて均一の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い< B >の < C >で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課する。

【解答】
A 市町村(特別区を含む。)
B 後期高齢者医療広域連合
C 条例
もう一問どうぞ!
②<介護保険法 H21年出題>
市町村又は特別区は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。当該保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。

【解答】
②<介護保険法 H21年出題> 〇
介護保険法の保険者は市町村及び特別区(以下「市町村」)保険料の徴収も保険者である市町村が行います。
保険料の徴収の対象は第1号被保険者のみ。
第2号被保険者からは保険料を徴収しません。第2号被保険者分は、医療保険各法で医療保険料と合わせて介護保険料を徴収するからです。
社労士受験のあれこれ
横断編(60・65・70・75歳)その1
R2-253
R2.8.10 横断編/年齢再確認!60・65・70・75歳その1
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「年齢再確認!60・65・70・75歳 その1」です。
では、どうぞ!
 国民年金法
国民年金法
空欄を埋めてください。
<任意加入被保険者>
次の1から3のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
2 日本国内に住所を有する< A >の者
3 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< B >のもの
<特例による任意加入被保険者>
昭和< C >年4月1日以前に生まれた者であって、次の1,2のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く。)は、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。
ただし、その者が国民年金法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
1 日本国内に住所を有する< D >の者
2 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない< D >のもの

【解答】

A 60歳以上65歳未満
B 20歳以上65歳
C 40
D 65歳以上70歳未満
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 昭和40年4月1日以前に生まれた者
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権がないこと
 厚生年金保険法
厚生年金保険法
空欄を埋めてください。
<任意単独被保険者>
適用事業所以外の事業所に使用される< E >の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< F >を得なければならない。
<高齢任意加入被保険者>
適用事業所に使用される< G >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、実施機関に< H >て、被保険者となることができる。
適用事業所以外の事業所に使用される< I >の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものは、< J >を受けて、被保険者となることができる。
認可を受けるには、その事業所の< K >を得なければならない。

【解答】
E 70歳未満
F 事業主の同意
G 70歳以上
H 申し出
I 70歳以上
J 厚生労働大臣の認可
K 事業主の同意
特例による任意加入被保険者のポイント!
・ 国民年金の「特例による任意加入被保険者」と違い、生年月日の要件がない
・ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないこと
・ 「適用事業所」と「適用事業所以外」で要件が違うので、注意。
こちらもどうぞ!
<国民年金 H27年出題>
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】 〇
原則 → 厚生年金保険の被保険者=国民年金の第2号被保険者
ただし、厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する場合は、第2号被保険者にはならない。
問題文の場合、「在職老齢年金を受給する」「65歳以上70歳未満の被保険者」ということで、「老齢年金の受給権がある+65歳以上」ですので、厚生年金保険の被保険者なのですが、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
一方、第3号被保険者は、「第2号被保険者」の配偶者であることが条件です。
問題文の場合は、第2号被保険者の配偶者に当たりませんので、第3号被保険者にはなりません。
なお、厚生年金保険の「高齢任意加入被保険者」は、「国民年金の第2号被保険者」です。なぜなら、「老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない」からです。
社労士受験のあれこれ
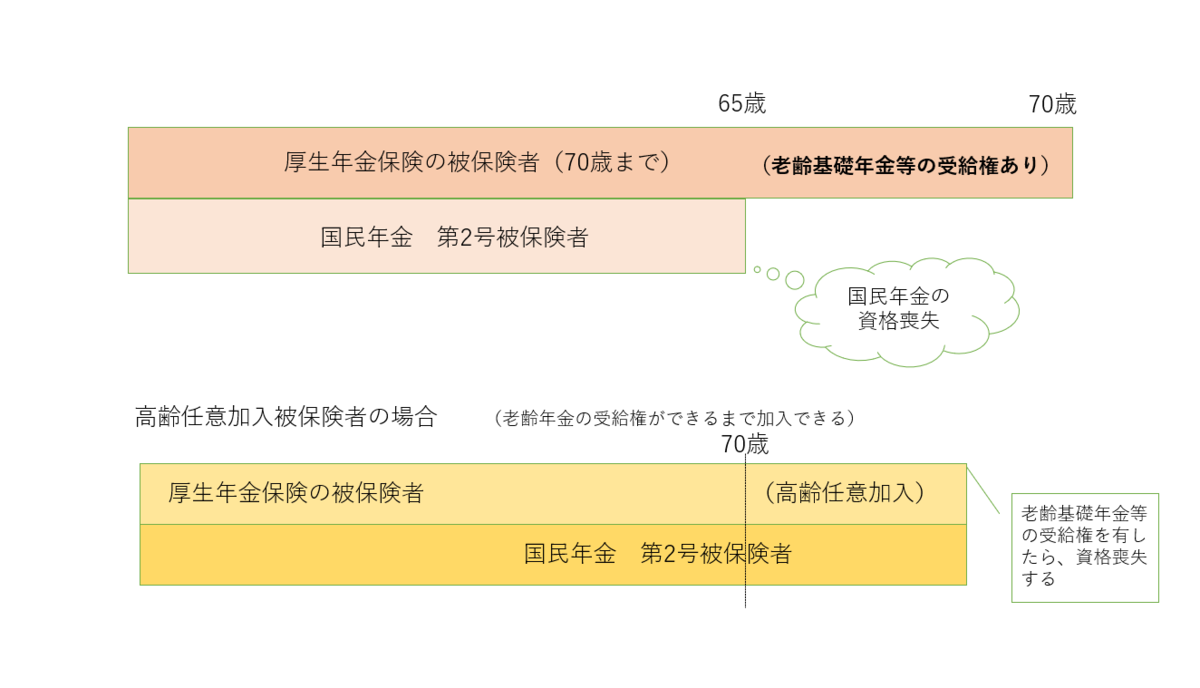
横断編(標準賞与額・健保と厚年)
R2-252
R2.8.9 横断編/健保と厚年~標準賞与額どう違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「健保と厚年~標準賞与額どう違う?」です。
では、どうぞ!
まずは「健康保険法」から
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< A >円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額が< B >円を超えることとなる場合には、当該累計額が< B >万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

【解答】

A 1,000
B 573万
 健康保険<H27年出題>
健康保険<H27年出題>
全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所であるA社で、3月に200万円、6月に280万円の賞与が支給され、それぞれ標準賞与額が200万円及び280万円に決定された被保険者が、A社を同年8月31日付で退職し、その翌日に資格喪失した。その後、同年9月11日に健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であるB社で被保険者資格を取得し、同年12月に100万円の賞与の支給を受けた。この場合、「健康保険標準賞与額累計申出書」を当該健康保険組合に提出することにより、当該被保険者の標準賞与額は60万円と決定される。

【解答】 ×
・ 標準賞与額の累計額は、「年度」で573万円が限度。
(3月までと4月以降では年度が違う。3月分の賞与は4月以降分と累計しない。)
・ 標準賞与額の累計は「保険者」単位で行う。
(A社(協会けんぽ)、B社(健保組合)の賞与は累計しない。)
この問題の場合は、12月の標準賞与額は「100万円」となります。
次は、厚生年金保険です!
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに< C >円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
この場合において、当該標準賞与額が< D >円を超えるときは、これを < D >円とする。

【解答】

C 1,000
D 150万
厚生年金保険の標準所与額は、月150万円が上限です。
社労士受験のあれこれ
横断編(標準報酬月額・健保厚年を比較)
R2-251
R2.8.8 横断編/標準報酬月額・健保と厚年の違いは??
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「標準報酬月額・健保と厚年の違いは??」です。
では、どうぞ!
まずは「健康保険法」から
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
健康保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、
最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 58,000
B 50
C 1,390,000
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
毎年< D >における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が< E >を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< F >から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の< D >において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が< G >を下回ってはならない。

【解答】
D 3月31日
E 100分の1.5
F 9月1日
G 100分の0.5
次は、厚生年金保険です!
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
厚生年金保険の標準報酬月額の最低は、第1級の< A >円で、
最高は第< B >級の< C >円となっている。

【解答】

A 88,000
B 31
C 620,000
 空欄を埋めてください。
空欄を埋めてください。
毎年< D >における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の < E >に相当する額が標準報酬月額等級の< F >の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の< G >から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該< F >の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

【解答】

D 3月31日
E 100分の200
F 最高等級
G 9月1日
社労士受験のあれこれ
横断編(日雇労働者の定義)
R2-250
R2.8.7 横断編/「日雇労働者」の定義は雇用保険と健康保険で違う
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「「日雇労働者」の定義は雇用保険と健康保険で違う」です。
では、どうぞ!
「雇用保険法」の日雇労働者の定義
 雇用保険
雇用保険
空欄を埋めてください。
日雇労働者とは、次の各号のいずれかに該当する労働者をいう。
一 < A >雇用される者
二 < B >以内の期間を定めて雇用される者
ただし、前2月の各月において< C >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び同一の事業主の適用事業に継続して< D >以上雇用された者(雇用保険法第43条第2項の認可を受けた者を除く。)は、日雇労働者とならない。

【解答】

A 日々
B 30日
C 18日
D 31日
では、「日雇労働被保険者」とは?
被保険者である日雇労働者であって、①から④のいずれかに該当するものを「日雇労働被保険者」といいます。
日雇労働被保険者が失業した場合には、日雇労働求職者給付金が支給されます。
① 適用区域に居住し、適用事業に雇用される者
② 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
③ 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
④ ①~③のほか、公共職業安定所長の認可を受けた者
次は健康保険法の「日雇労働者」です
 健康保険
健康保険
健康保険法において「日雇労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
二 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
三 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
 さらに!
さらに!
「日雇特例被保険者」 → 適用事業所に使用される日雇労働者
※ ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者、又は次のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、除外されます。
・ 引き続く2月間に通算して26日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
・任意継続被保険者であるとき。
・その他特別の理由があるとき。
ちなみに、健保「日雇特例被保険者」でおさえておきたいのはこの問題!
問題<H15年出題>
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者で組織される。

【解答】 ×
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者、任意継続被保険者で組織され、日雇特例被保険者は入りません。
日雇特例被保険者の「保険者」は全国健康保険協会のみだからです。
社労士受験のあれこれ
横断編(未支給の保険給付・給付)
R2-249
R2.8.6 横断編/未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「未支給の保険給付・給付各法でどこが違う?」です。
では、どうぞ!
問 題
 雇用保険<H29年出題>
雇用保険<H29年出題>
失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。

【解答】
 〇
〇
ポイント!
★未支給の失業等給付を受けることができる範囲と順序を覚えましょう。
・死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」(順序もこのとおり)
★「失業」の認定を受けなければならない
受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当の支給を請求する者 → 当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
★請求期間がある
未支給給付請求者は、死亡した受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6か月以内に、請求しなければならない。
次は労災、どうぞ!
 労災保険<H22年出題>
労災保険<H22年出題>
労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)等であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができるが、この未支給の保険給付を受けるべき者の順位として、正しいものは次のうちどれか。
A 配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹
B 子、配偶者、父母、兄弟姉妹、孫、祖父母
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
D 子、配偶者、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
E 配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

【解答】
 C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
C 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
ポイント!
「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」の順序を覚えましょう。
労災保険からもう一問!
 労災保険法<H30年出題>
労災保険法<H30年出題>
労災保険法に基づく遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族は、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
未支給の遺族(補償)年金の支給を請求できるのは、「当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族」です。
では、国民年金法です!
 国民年金法<R元年出題>
国民年金法<R元年出題>
未支給の年金を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている。

【解答】 〇
ポイント!
国民年金の未支給年金を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
最後は厚生年金保険です!
 厚生年金保険<H30年出題>
厚生年金保険<H30年出題>
保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であれば、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

【解答】 〇
ポイント!
厚生年金保険の未支給の保険給付を請求できるのは
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族で、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(順位もこの順序)
→ 国民年金と同じです。
なお、国民年金の未支給の対象は「年金給付」、厚生年金保険は「保険給付」です。
社労士受験のあれこれ
横断編(障害等級・労災、国年、厚年)
R2-248
R2.8.5 横断編/それぞれの障害等級~労災、国年、厚年
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「障害等級・労災、国年、厚年」です。
では、どうぞ!
問 題
 傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病(補償)年金<H30年出題>
傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年を経過した日において次の①、②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①、②のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
② 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

【解答】
 ×
×
「療養の開始後1年を経過した日」ではなく、「療養の開始後1年6か月を経過した日」です。
ポイント!
ちなみに、傷病補償年金の支給要件として、「当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。」があります。
厚生労働省令で定める傷病等級は「第1級~第3級」です。
第1級 → 常時介護を要する状態
第2級 → 随時介護を要する状態
第3級 → 常態として労働不能
★ 傷病等級は、「治っていない傷病」です。
次どうぞ!
 障害(補償)給付
障害(補償)給付
空欄に埋めてください。
障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は < A >とする。

【解答】
 A 障害補償一時金
A 障害補償一時金
ポイント!
障害等級第1級~第7級 → 障害補償年金
障害等級第8級~第14級 → 障害補償一時金
★ 障害等級は、「負傷し又は疾病にかかり治った」ときです。
 傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
傷病(補償)年金、障害(補償)年金ともに、年金額は
第1級 → 給付基礎日額の313日分
第2級 → 給付基礎日額の277日分
第3級 → 給付基礎日額の245日分
 障害基礎年金(国民年金法)
障害基礎年金(国民年金法)
空欄を埋めてください。
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の①、②のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して< B >を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
① 被保険者であること。
② 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、< C >であること。
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから< D >とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

【解答】
B 1年6月
C 60歳以上65歳未満
D 1級及び2級
ポイント!
障害基礎年金の障害等級は、重いほうから1級、2級
1級の年金額は、2級の年金額×100分の125
 障害厚生年金・障害手当金
障害厚生年金・障害手当金
(障害手当金の受給権者)
障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して< E >を経過する日までの間におけるその< F >日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。

【解答】
E 5年
F 傷病の治った(障害手当金は「治っている」ことが要件です。)
ポイント!
厚生年金には、「障害厚生年金」と「障害手当金」があります。
障害厚生年金 → 障害等級1級~3級
障害手当金 → 3級よりも軽い状態
社労士受験のあれこれ
横断編(遺族の範囲その3「厚年」)
R2-247
R2.8.4 横断編/「厚生年金」遺族の範囲は国年とどう違う?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「遺族の範囲その3「厚年」」です。
国民年金法の遺族基礎年金は、子のための年金で、受給できるのは、父子、母子、子に限定されています。
一方、厚生年金保険の遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母と受給できる範囲が広くなります。
「妻」に対する加算(中高齢寡婦加算など)が行われるのも特徴です。
では、どうぞ!
問 題
 遺族厚生年金<R元年出題>
遺族厚生年金<R元年出題>
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

【解答】
 ×
×
夫も子も遺族の範囲に入りません。
遺族厚生年金を受けることができる遺族のポイント!
・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母(兄弟姉妹は入りません)
・妻 → 年齢・障害要件なし
・夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(60歳までは原則支給停止(若年停止)
・子、孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない
次どうぞ!
 遺族厚生年金<H23年出題>
遺族厚生年金<H23年出題>
被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚したことによってその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた母がいる場合は、当該母がその遺族厚生年金を受給することができる。

【解答】
 ×
×
遺族の中で、支給順位が決まっています。妻が受給権を取得した場合は、母は受給権は取得できず、転給の制度もありません。
支給順位のポイント!
① 配偶者、子
② 父母
③ 孫
④ 祖父母
例えば、①の配偶者、子がいれば、②以下は遺族厚生年金を受けることができる遺族にはなりません。
社労士受験のあれこれ
横断編(遺族の範囲その2「国年」)
R2-246
R2.8.3 横断編/「国年」遺族の範囲を整理する
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「遺族の範囲その2「国年」」です。
「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。
整理しておきましょう。
今日は、国年編です。
では、どうぞ!
問 題
 遺族基礎年金<R元年出題>
遺族基礎年金<R元年出題>
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくしていれば遺族基礎年金を受けることができる遺族となる。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】
 〇
〇
遺族には国内居住要件はありません。
遺族基礎年金を受けることができる遺族のポイント!
・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者又は子
・配偶者の要件 → 子があること(子と生計を同じくすること)
・子の要件 → ①18歳の年度末までの間にある
②20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある
婚姻していない
次は寡婦年金です!
 寡婦年金<H20年出題>
寡婦年金<H20年出題>
寡婦年金は、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した60歳以上65歳未満の妻に限り受給権が発生する。

【解答】
 ×
×
「65歳未満」の妻であることが条件です。
夫の死亡当時、妻が60歳未満でも受給権は発生しますが、支給は60歳以降(60歳にに達した日の属する月の翌月から)になります。
寡婦年金を受けることができる妻のポイント!
・寡婦年金を受けることができるのは妻のみ。(夫はダメ)
・夫の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた妻
・夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻
 穴埋め式で寡婦年金をチェックしましょう。
穴埋め式で寡婦年金をチェックしましょう。
寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の< A >までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が< B >年以上である夫(保険料納付済期間又は学生納付特例期間及び納付猶予期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、
夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が< C >年以上継続した< D >歳未満の妻があるときに、その者に支給する。
ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は < E >の支給を受けていたときは、この限りでない。

【解答】
A 前月
B 10
C 10
D 65
E 老齢基礎年金
最後は死亡一時金!
 死亡一時金<H28年選択>
死亡一時金<H28年選択>
死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

【解答】 ×
死亡一時金の対象になる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。これらの者以外の三親等内の親族は遺族に入りません。
死亡一時金を受けることができる遺族のポイント!
・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断
社労士受験のあれこれ
横断編(遺族の範囲その1「労災」)
R2-245
R2.8.2 横断編/「労災」遺族の範囲・要件と順位を覚える
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「遺族の範囲その1「労災」」」です。
◇労災保険
・遺族(補償)年金
・遺族(補償)一時金
・障害(補償)年金差額一時金
◇国民年金
・遺族基礎年金
・寡婦年金
・死亡一時金
◇厚生年金保険法
・遺族厚生年金
「遺族」といっても、法律ごとにその範囲は異なります。
整理しておきましょう。
今日は、労災編です。
では、どうぞ!
問 題
 遺族(補償)年金<H19年出題>
遺族(補償)年金<H19年出題>
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるが、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時①夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については60歳以上、②子又は孫については18歳未満、③兄弟姉妹については18歳未満又は60歳以上、④上記の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については厚生労働省令で定める障害の状態にある場合に限られる。

【解答】
 ×
×
①夫、父母又は祖父母 → 55歳以上(本則では60歳以上)
②子又は孫 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間
③兄弟姉妹 → 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間又は55歳以上(本則では60歳以上)
遺族(補償)年金を受けることができる遺族のポイント!
・労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していたこと
・遺族の順位を覚える
| 1 | 配偶者 | 妻 年齢、障害状態問わない 夫 60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 2 | 子 | 18歳年度末までの間 又は 一定の障害状態 |
| 3 | 父母 | 60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 4 | 孫 | 18歳年度末までの間 又は 一定の障害状態 |
| 5 | 祖父母 | 60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 6 | 兄弟姉妹 | 18歳年度末までの間若しくは60歳以上 又は 一定の障害状態 |
| 7 | 夫 | 55歳以上60歳未満 55歳以上60歳未満(障害状態にない)の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位は後回しになる |
| 8 | 父母 | |
| 9 | 祖父母 | |
| 10 | 兄弟姉妹 |
・年金を受けることができる(受給権者になる)のは受給資格者のうちの最先順位者
・例えば、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた遺族として、
父(63歳)
子(3歳)
弟(20歳)
がいる場合(3人とも障害状態にない)
「受給資格者」は、父(63歳)と子(3歳)の2人。受給資格者の中の順位は1位が子、2位が父です。
1位の子(3歳)が「受給権者」となります。
・転給あり。受給権者が失権したら、次の順位の者に受給権が移ります。
次は遺族(補償)一時金です!
 遺族(補償)一時金<H19年出題>
遺族(補償)一時金<H19年出題>
遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であり、遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けることができる遺族の順位も、この順序による。

【解答】
 ×
×
遺族(補償)一時金の場合、死亡の当時の生計維持要件は問われません。(ただし、生計維持関係の有無は、順位には影響します。)
遺族(補償)一時金を受けることができる遺族のポイント!
・配偶者は生計維持関係があってもなくても第1順位
・兄弟姉妹は、生計維持関係あがってもなくても最下位
・それ以外の遺族は、生計維持「有」が優先
| 1 | ①配偶者 | |
| 2 | 労働者の死亡の当時その収入によって 生計を維持していた | ②子、③父母、④孫、⑤祖父母 |
| 3 | 生計を維持していなかった | ⑥子、⑦父母、⑧孫、⑨祖父母 |
| 4 | ⑩兄弟姉妹 |
・遺族(補償)年金の受給権失権後に、遺族(補償)一時金の受給権者になることがある
最後は障害(補償)年金差額一時金!
 障害補償年金差額一時金<H26年選択>
障害補償年金差額一時金<H26年選択>
障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、< A >の順序であり、それらの者がいない場合には、生計を同じくしていなかった配偶者、子、父母、孫、< A >である。

【解答】
 A 祖父母及び兄弟姉妹
A 祖父母及び兄弟姉妹
障害(補償)年金差額一時金を受けることができる遺族のポイント!
・「生計維持」ではなく「生計を同じくしていた」か否かで判断
| 1 | 労働者の死亡の当時その者と 生計を同じくしていた | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
| 2 | 生計を同じくしていなかった | 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 |
・生計を同じくしていた方が優先する
社労士受験のあれこれ
横断編(健保・厚年の「船員」)
R2-244
R2.8.1 横断編/健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「健保と厚生年金「船員」の適用で違うところ」です。
では、どうぞ!
問 題
 <健康保険法>
<健康保険法>
船員保険の被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)は、日雇特例被保険者となる場合を除き、健康保険の被保険者となることができない。
 <厚生年金保険法>
<厚生年金保険法>
船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

【解答】
 <健康保険法> 〇
<健康保険法> 〇
船員保険の被保険者は、健康保険の被保険者にはなりません。なぜなら、職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産については「船員保険」から保険給付が受けられるからです。
なお、船員保険の疾病任意継続被保険者は、健康保険の被保険者となることができるので注意してください。
 <厚生年金保険法> 〇
<厚生年金保険法> 〇
船員は厚生年金保険の被保険者となります。
<参考>船員保険について
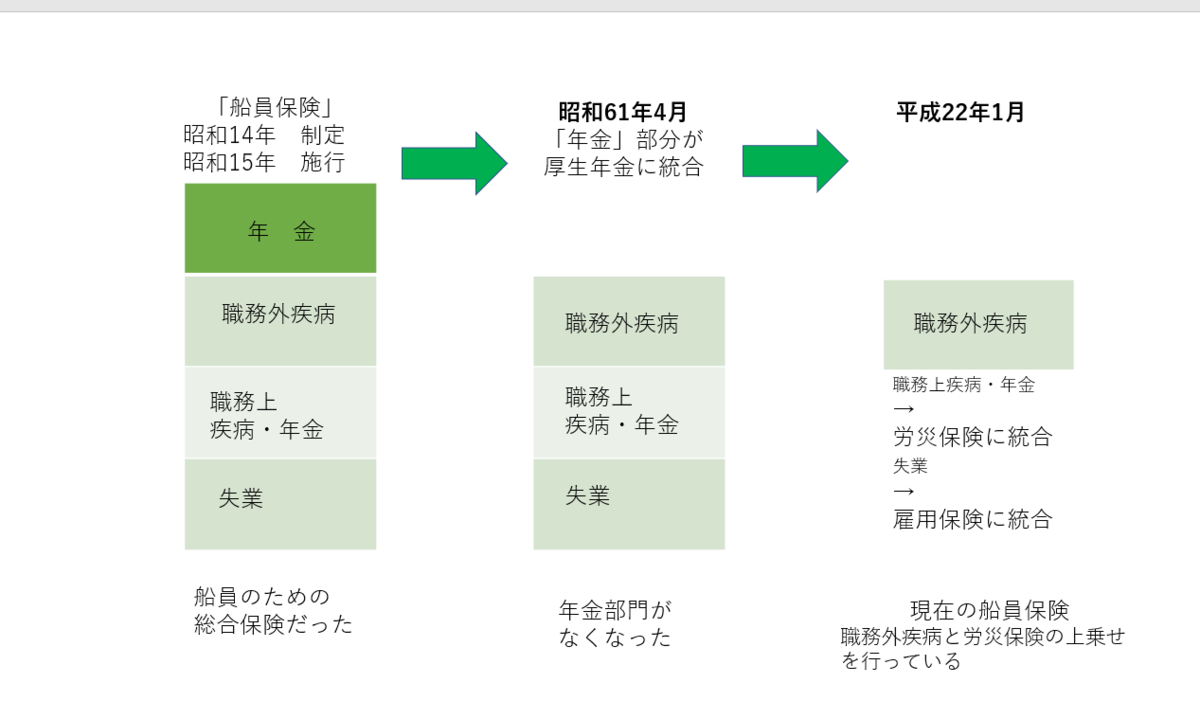
こちらもどうぞ!
①<厚生年金保険法・H30年出題>
船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。
②<厚生年金保険法・H25年出題>
船舶使用者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

【解答】
①<厚生年金保険法・H30年出題> ×
「当該期間を超えて使用されないとき」でも、厚生年金保険の被保険者となる。
・通常
2月以内の期間を定めて使用される者 → 厚生年金保険の被保険者にならない
※ただし、所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合は被保険者となる
・船員
「2月以内の期間」の定めであっても、当初から被保険者となる。(所定の期間を超えなくてもOK)
②<厚生年金保険法・H25年出題> ×
船員の場合は、継続して4か月を超えない季節的業務に使用されても、厚生年金保険の被保険者となります。
社労士受験のあれこれ
横断編(労基・労災・雇用の「船員」)
R2-243
R2.7.31 横断編/労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「労基・労災・雇用「船員」の適用の違いは?」です。
では、どうぞ!
問 題
 <労働基準法>
<労働基準法>
船員法第1条第1項に規定する船員については、労働基準法は、全面的に適用されない。
 <労災保険法>
<労災保険法>
船員法上の船員については、労災保険法が適用される。
 <雇用保険法>
<雇用保険法>
船員法第1条に規定する船員を雇用する(政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員(1年を通じて船員として雇用される場合を除く。)のみを雇用している場合を除く。)事業にあっては、雇用保険の強制適用事業となる。

【解答】
 <労働基準法> ×
<労働基準法> ×
船員法第1条第1項に規定する船員には、労働基準法が一部適用されます。
労働者全般に当てはまる基本原則の部分(第1条から第11条まで)、それに関する罰則規定は船員にも適用されますが、これ以外は労働基準法は適用されません。
船員の労働形態は特殊ですので、一般労働者向けの労働基準法は一部だけ適用され、他は船員法によって保護されます。
 <労災保険法> 〇
<労災保険法> 〇
船員法上の船員は、労災保険法適用です。
 <雇用保険法> 〇
<雇用保険法> 〇
船員法第1条に規定する船員を雇用する事業は、雇用保険の強制適用事業です。
ただし、
・政令で定める漁船に乗り組むために雇用される船員 → 適用除外
※漁船に乗り組むため雇用される者でも、1年を通じて船員として雇用される場合は適用されます。
こちらもどうぞ!
①<雇用保険法・H22年出題>
船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、常時雇用される労働者の数が15名未満であれば、暫定任意適用事業となる。
②<雇用保険法・H25年出題>
船員法第1条に規定する船員であって、漁船に乗り組むため雇用される者であっても、雇用保険法が適用される場合がある。

【解答】
①<雇用保険法・H22年出題> ×
労働者を1人でも雇用すれば、雇用保険は適用です。
ですので、船員法第1条に規定する船員を雇用する水産の事業は、人数関係なく強制適用となります。
②<雇用保険法・H25年出題> 〇
漁船に乗り組むため雇用される者であっても、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は、雇用保険法が適用されます。
社労士受験のあれこれ
横断編(労基と安衛)
R2-242
R2.7.30 横断編/労基法は「使用者」、安衛は?
毎年、好評の横断編にいきます!
本日は、「労基法は「使用者」、安衛は?」です。
では、どうぞ!
問 題
<労働基準法>
労働基準法で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の < A >に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
<労働安全衛生法>
労働安全衛生法において、< B >とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
【選択肢】
① 労務 ② 人事 ③ 労働者
④ 事業主 ⑤ 事業者 ⑥ 事業所

【解答】
A ③ 労働者
B ⑤ 事業者
★労働基準法の責任主体は使用者。使用者は次の3つに分けられます。
・事業主(その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの)
・事業の経営担当者
・労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者
★労働安全衛生法では、使用者という用語は使っていません。労働安全衛生法の義務主体は、規定の多くが「事業者」。
・事業者とは、その事業の経営の主体。個人企業の場合はその事業主個人、法人組織の場合は法人そのもの
→ 労働基準法では、例えば、係長に労務管理についての権限があれば、その権限の範囲で係長は労働基準法の使用者(責任主体)となります。(使用者の概念が幅広い)
一方、労働安全衛生法は、「事業者(その事業の経営の主体)」と明確です。
こちらもどうぞ!
<労基法・H16年出題>
ある法人企業の代表者が労働基準法第24条の規定に違反して賃金を支払わなかった場合には、法人の代表者の行為は法人の行為として評価されるから、当該賃金不払いについては、当該法人企業に対してのみ罰則が科される。

【解答】 ×
労働基準法の違反行為をした者(この問題では法人の代表者、違反行為をした本人)には、もちろん、罰則が科されます。
また、両罰規定により、事業主(法人そのもの)に対しても罰金刑が科されます。(法人は人間ではないので懲役刑はありません。)
安衛法から一問どうぞ!
【労働安全衛生法・事業者の責務】
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と< C >を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
【選択肢】
① 労働者の地位の向上 ② 作業環境の改善 ③ 労働条件の改善

【解答】
C ③ 労働条件の改善
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-241
R2.7.29 選択式の練習/平成29年度 国民医療費の概況より
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「平成29年度 国民医療費の概況」からです。
では、どうぞ!
問 題
<財源別国民医療費>
平成29年度の国民医療費は43兆710億円となっている。
国民医療費を財源別にみると、公費は< A >、保険料は< B >となっている。
【選択肢】
① 16兆5,181億円(構成割合38.4%)
② 21兆2,650億円(構成割合49.4%)
③ 4兆9,948億円(構成割合11.6%)

【解答】
A ① 16兆5,181億円(構成割合38.4%)
B ② 21兆2,650億円(構成割合49.4%)
「公費」16兆5,181億円(構成割合38.4%)
(公費負担医療制度、医療保険制度、後期高齢者医療制度等への国庫負担金及び地方公共団体の負担金)
「保険料」21兆2,650億円(同49.4%)
(医療保険制度、後期高齢者医療制度、労働者災害補償保険制度等の給付費のうち、事業主と被保険者が負担すべき額)
「その他」5兆2,881億円(同12.3%)
(患者負担及び原因者負担)
※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf
もう一問どうぞ!
<国民医療費の状況>
平成29年度の国民医療費は43兆710億円、前年度の42兆1,381億円に比べ9,329億円、2.2%の増加となっている。
人口一人当たりの国民医療費は< C >円となっている。
国民医療費の国内総生産(GDP)に対す る比率は7.87%(前年度7.85%)、国民所得(NI)に対する比率は10.66%(同10.77%)となっている。
【選択肢】
① 10万9,500 ② 33万9,900 ③ 59万8,300

【解答】
C ② 33万9,900
※ 人口一人当たりの国民医療費は33万9,900円、前年度の33万2,000円に比べ 7,900円、2.4%の増加となっている。
※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf
最後にもう一問!
<年齢階級別国民医療費>
平成29年度の国民医療費は43兆710億円となっている。
年齢階級別にみると、65 歳以上の国民医療費は < D >となっている。
【選択肢】
① 5兆2,690 億円(構成割合12.2%) ② 25兆9,515 億円(構成割合60.3%)
③ 9 兆3,112 億円(構成割合21.6%)

【解答】
D ② 25兆9,515 億円(構成割合60.3%)
0~14歳 → 2兆5,392 億円(構成割合 5.9%)
15~44歳 → 5兆2,690億円(構成割合12.2%)
45~64歳 → 9兆3,112億円(構成割合21.6%)
65歳以上 → 25兆9,515億円(構成割合60.3%)
※平成29年度国民医療費の概況(厚生労働省)を参照しました
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/17/dl/data.pdf
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-240
R2.7.28 選択式の練習/平成31年就労条件総合調査より
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「平成31年就労条件総合調査より」です。
★「就労条件総合調査」とは?
目 的
→ 主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすること
根拠法令
→ 統計法に基づく一般統計調査
では、どうぞ!
問 題
特別休暇制度のある企業割合は、< A >%となっており、これを特別休暇制度の種類別にみると、「< B >」42.9%、「病気休暇」25.7%、「リフレッシュ休暇」13.1%、「ボランティア休暇」4.5%、「教育訓練休暇」5.8%、「左記以外の1週間以上の長期の休暇」14.4%、となっている。
【選択肢】
① 80.3 ② 72.0 ③ 59.0
④ 夏季休暇 ⑤ アニバーサリー休暇 ⑥ 慶弔休暇

【解答】
A ③ 59.0
B ④ 夏季休暇
 特別休暇制度のない企業割合は41.0%です。
特別休暇制度のない企業割合は41.0%です。
 特別休暇制度のある企業で、休暇中の賃金を全額支給する企業割合
特別休暇制度のある企業で、休暇中の賃金を全額支給する企業割合
「夏季休暇」81.3%
「病気休暇」45.5%
「リフレッシュ休暇」95.9%
「ボランティア休暇」79.4%
「教育訓練休暇」90.8%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」82.6%
※厚生労働省「平成31年就労条件総合調査」結果の概況をもとに作成しました。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaikyou.pdf
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-239
R2.7.27 選択式の練習/実施機関のことなど
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「実施機関のことなど」です。
では、どうぞ!
問 題
 厚生年金保険は、< A >が、管掌する。
厚生年金保険は、< A >が、管掌する。
 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。
保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(「受給権者」という。)の請求に基づいて、< B >が裁定する。
【選択肢】
① 厚生労働大臣 ② 実施機関 ③ 政府 ④ 実施機関等

【解答】
 A ③ 政府
A ③ 政府
 B ② 実施機関
B ② 実施機関
ちなみに、
実施機関は、
被保険者の資格、標準報酬、事業所及び被保険者期間、保険給付、当該保険給付の受給権者、基礎年金拠出金の負担(納付)、拠出金の納付(第2号、第3号、第4号厚生年金金被保険者)、保険料その他この法律の規定による徴収金並びに保険料に係る運用に関する事務を行います。
実施機関は、被保険者の種別に応じて定められています。
↓
<実施機関>
第1号厚生年金被保険者 → 厚生労働大臣
第2号厚生年金被保険者 → 国家公務員共済第組合及び国家公務員共済組合連合会
第3号厚生年金被保険者 → 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会
第4号厚生年金被保険者 → 日本私立学校振興・共済事業団
こちらもどうぞ!
問題
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る< C >における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
【選択肢】
① 障害認定日 ② 初診日 ③ 初診日の前日

【解答】
C ② 初診日
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】 ×
※ 障害認定日に2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の障害厚生年金の額
(公務員と民間企業勤務経験があるような場合)
↓
2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」が計算の基礎となるのではありません。
また、障害厚生年金の裁定・支給事務は、初診日に加入していた実施機関が、他の実施機関の加入期間分も含めて行います。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-238
R2.7.26 選択式の練習/おぼえておきたい合算対象期間
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「合算対象期間」です。
「合算対象期間」(カラ期間)
保険料納付済期間と保険料免除期間では10年に足りない場合に、合算対象期間を入れて10年以上になれば、老齢基礎年金の受給資格ができます。ただし、年金額には反映されません。
では、どうぞ!
問 題
① 第2号被保険者としての被保険者期間のうち< A >の期間は、合算対象期間である。
② 国会議員であった期間(60歳前の期間に限る。)のうち、昭和36年4月1日から < B >までの期間は合算対象期間となる。
③ 厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間のうち、< C >(昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る。)は、合算対象期間となる。
【選択肢】
① 20歳以上60歳未満 ② 20歳未満及び60歳以上
③ 20歳未満及び65歳以上 ④ 昭和55年3月31日
⑤ 昭和61年3月31日 ⑥ 昭和56年12月31日
⑦ 昭和36年4月1日前 ⑧ 昭和36年4月1日以後
⑨ 昭和61年4月1日以後

【解答】
A ② 20歳未満及び60歳以上
 第2号被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」(老齢基礎年金の額に反映する期間)は20歳以上60歳未満の期間です。(第1号被保険者の年齢に合わせている)
第2号被保険者期間のうち、「保険料納付済期間」(老齢基礎年金の額に反映する期間)は20歳以上60歳未満の期間です。(第1号被保険者の年齢に合わせている)
ですので、20歳未満と60歳以上の期間は、年金額に反映しない合算対象期間となります。
B ④ 昭和55年3月31日
 国会議員は、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用を除外されており、国民年金に加入することができなかったので合算対象期間とされています。(ただし、60歳未満に限りますので注意してください。)
国会議員は、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までは、国民年金の適用を除外されており、国民年金に加入することができなかったので合算対象期間とされています。(ただし、60歳未満に限りますので注意してください。)
昭和55年4月1日からは、国会議員は「任意加入」できることになりました。任意加入しなかった場合は合算対象期間です。
なお、新法になってから(昭和61年4月1日から)は、強制加入です。
C ⑧ 昭和36年4月1日以後
こちらもどうぞ!
①<H25年出題>
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とされる。
②<H25年出題>
60歳以上65歳未満の期間を含む国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は合算対象期間に算入される。
③<H25年出題>
20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。
(女性は昭和29年4月2日生まれ、「現在」は平成25年4月12日とする)

【解答】
①<H25年出題> ×
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間のうち、保険料納付済期間になるのは20歳以上60歳未満の期間です。20歳前、60歳以後の期間は合算対象期間となります。
②<H25年出題> ×
昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの間で国会議員だった期間のうち、合算対象期間になるのは60歳未満に限ります。60歳以上65歳未満の期間は合算対象期間には入りません。
③<H25年出題> ×
厚生年金保険の脱退手当金の計算期間となった期間が合算対象期間となるには、昭和61年4月1日以後65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限られます。
問題文は、保険料納付済期間又は保険料免除期間がないので、合算対象期間には入りません。
社労士受験のあれこれ
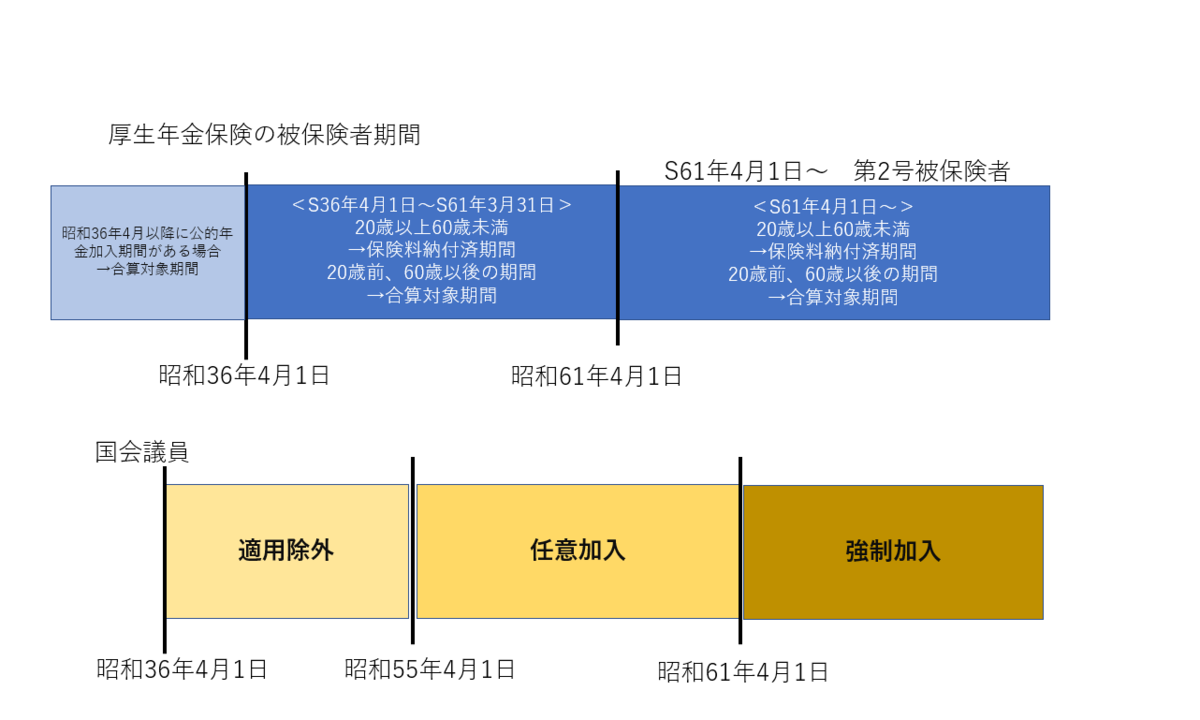
選択式対策(健康保険法)
R2-237
R2.7.25 選択式の練習/協会けんぽの一般保険料率
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「協会けんぽの一般保険料率」です。
では、どうぞ!
問 題1
協会 → 全国健康保険協会のことです。
協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、< A >までの範囲内において、< B >(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として協会が決定するものとする。
【選択肢】
① 1000分の10から1000分の120 ② 1000分の20から1000分の130
③ 1000分の30から1000分の130 ④ 支部被保険者
⑤ 協会被保険者 ⑥ 都道府県被保険者

【解答】
A ③ 1000分の30から1000分の130
※健康保険組合管掌の一般保険料率も1000分の30から1000分の130までの範囲内で、健康保険組合ごとに決定します。
B ④ 支部被保険者
※支部被保険者単位で決定する一般保険料率を「都道府県単位保険料率」といいます。
問 題2
協会は、< C >ごとに、翌事業年度以降の< D >間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
【選択肢】
① 1年 ② 2年 ③ 3年 ④ 4年 ⑤ 5年 ⑥ 6年

【解答】
C ② 2年
D ⑤ 5年
※協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間について
・被保険者数
・総報酬額の見通し
・保険給付に要する費用の額
・保険料の額
・その他
の収支の見通しを公表するものとされています。
問 題3
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、< E >の議を経なければならない。
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について< F >。
【選択肢】
① 評議会 ② 運営委員会 ③ 社会保障審議会
④ 地方社会保険医療協議会の議を経なければならない
⑤ 厚生労働大臣の承認を得なければならない
⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない

【解答】
E ② 運営委員会
※ 「運営委員会」は協会に置かれる
「評議会」は支部ごとに設けられる
※ 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするとき→事前に理事長は各支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければなりません。
F ⑥ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、運営委員会が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、理事長に対しその変更について意見の申出を行う。

【解答】 ×
あらかじめ、「理事長」が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、「運営委員会の議を経なければならない」です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-236
R2.7.24 迷わないために覚えておく数字@徴収法
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「迷わないために覚えておく数字@徴収法」です。
では、どうぞ!
問題 1
労働保険徴収法第7条(有期事業の一括)の規定の要件に該当する立木の伐採の事業の規模は、素材の見込み生産量が1000立方メートル未満、又は概算保険料の額に相当する額が160万円未満のものである。

【解答】 ×
又はではなく「かつ」です。
有期事業の一括の対象になる事業の規模は、
・ 立木の伐採の事業 → 素材の見込み生産量が1000立方メートル未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満
・ 建設の事業 → 請負金額が1億8千万円未満かつ概算保険料の額に相当する額が160万円未満
問題 2
<H27年出題>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が建設の事業である場合は、その事業の規模が、概算保険料を算定することとした場合における概算保険料の額に相当する額が160万円未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

【解答】 ×
下請負事業の分離の認可の規模の要件は、
概算保険料の額に相当する額が160万円以上、又は、請負金額が1億8000万円以上
問題 3
<H27年出題>
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けるためには、当該下請負人の請負に係る事業が立木の伐採の事業である場合は、その事業の規模が、素材の見込生産量が千立方メートル未満、かつ、請負金額が1億8000万円未満でなければならない。

【解答】 ×
「請負事業の一括」の対象は建設の事業だけです。
立木の伐採の事業は請負事業の一括の対象ではないので、下請負事業の分離の対象にもなりません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-235
R2.7.23 選択式の練習/基本手当の日額=賃金日額×一定の率
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「基本手当の日額=賃金日額×一定の率」です。
では、どうぞ!
問 題
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算する。
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、賃金日額に100分の80から100分の< A >までの範囲の率を乗じて得た額である。
賃金日額は、< B >において< C >として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。
ただし、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、上記の最後の6か月間に支払われた賃金の総額を< D >で除して得た額の< E >に相当する額の方が高い場合は、後者の額を賃金日額とする。
【選択肢】
① 50 ② 45 ③ 55
④ 算定対象期間 ⑤ 算定基礎期間 ⑥ 支給対象期間
⑦ 支給単位期間 ⑧ 被保険者期間 ⑨ 受給期間
⑩ 当該最後の6か月間に労働した日数
⑪ 当該最後の6か月間の所定労働日数
⑫ 当該最後の6か月間の総日数
⑬ 100分の50 ⑭ 100分の60 ⑮ 100分の70

【解答】
A ② 45
※「一定の率」の原則は、100分の80から100分の50ですが、60歳以上65歳未満は、100分の80から100分の45となります。60歳以上65歳未満の例外の方がよく出ますので気を付けてくださいね。
B ④ 算定対象期間
C ⑧ 被保険者期間
D ⑩ 当該最後の6か月間に労働した日数
E ⑮ 100分の70
こちらもどうぞ!
①<H22年出題>
賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本手当の日額が異なることはない。
②<H26年出題>
賃金日額の最高限度額は45歳以上60歳未満が最も高いが、最低限度額は年齢に関わりなく一律である。
③<H22年出題>
基準日に52歳であった受給資格者Aと、基準日に62歳であった受給資格者Bが、それぞれの年齢区分に応じて定められている賃金日額の上限額の適用を受ける場合、Aの基本手当の日額はBのそれよりも多い。

【解答】
①<H22年出題> ×
家族手当、通勤手当、住宅手当すべて賃金日額の計算に入ります。ですので、例えば、家族手当の有無や額によって基本手当の日額は変わります。
②<H26年出題> 〇
賃金日額の最高限度額は、年齢によって4段階に区分されています。
受給資格に係る離職の日において
①60歳以上65歳未満 15,890円
②45歳以上60歳未満 16,660円
③30歳以上45歳未満 15,140円
④30歳未満 13,630円
最も高いのは、45歳以上60歳未満です。また、下限は、年齢に関係なく2,500円です。
③<H22年出題> 〇
52歳の受給資格者Aの基本手当の日額 → 16,660円×100分の50=8,330円
62歳の受給資格者Bの基本手当の日額 → 15,890円×100分の45=7,150円
※賃金日額が上限の場合は、一番小さい率を乗じます。原則は100分の50、60歳以上65歳未満は100分の45です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-234
R2.7.22 選択式の練習/業務災害に関する保険給付
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「業務災害に関する保険給付」です。
労災保険の保険給付は次の3つです。
①業務災害に関する保険給付
②通勤詐害に関する保険給付
③二次健康診断等給付
今日は、そのうちの「業務災害に関する保険給付」です。
では、どうぞ!
問 題
業務災害に関する保険給付(< A >を除く。)は、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由又は< B >第89条第1項、第91条第1項、第92条本文、第93条及び第94条に規定する災害補償の事由(同法第91条第1項にあっては、労働基準法第76条第1項に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る。)が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は < C >に対し、その請求に基づいて行う。
【選択肢】
① 療養補償給付 ② 傷病補償年金及び介護補償給付
③ 遺族補償年金 ④ 船員法 ⑤ 地方公務員法 ⑥ 国家公務員法
⑦ 事業主 ⑧ 介護を行う者 ⑨ 葬祭を行う者

【解答】
A ② 傷病補償年金及び介護補償給付
B ④ 船員法
C ⑨ 葬祭を行う者
 業務災害に関する給付は、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金」「介護補償給付」の7種類です。
業務災害に関する給付は、「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」「傷病補償年金」「介護補償給付」の7種類です。
「療養補償給付」「休業補償給付」「障害補償給付」「遺族補償給付」「葬祭料」の5つは、労働基準法の災害補償に基づく給付ですが、「傷病補償年金」「介護補償給付」は、労働基準法の災害補償としては規定されていない、労災保険独自の給付です。
 「船員法」上の船員についても労災保険法が適用されます。
「船員法」上の船員についても労災保険法が適用されます。
 「葬祭料」は、「葬祭を行う者」に支給されます。(「遺族」とは限らないので注意しましょう。)
「葬祭料」は、「葬祭を行う者」に支給されます。(「遺族」とは限らないので注意しましょう。)
こちらもどうぞ!
①<H26年出題>
船員法上の船員については労災保険法は適用されない。
②<H22年出題>
労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。

【解答】
①<H26年出題> ×
船員法上の船員についても労災保険法は適用されます。
②<H22年出題> ×
傷病補償年金と介護補償給付は、労働基準法の災害補償の規定にはありませんが、労災保険の保険給付として行われます。
また、労働基準法のみならず、船員法の災害補償にも対応しています。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-233
R2.7.21 選択式の練習/特定機械等の検査など
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「特定機械等」です。
突然ですが、「特定機械等」の種類は覚えていますか?
空欄を埋めてみてください。
↓
① ボイラー(小型ボイラー等を除く。)
② 第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く。)
③ つり上げ荷重が< A >以上(スタツカー式クレーンにあっては、1トン以上)のクレーン
④ つり上げ荷重が< A >以上の移動式クレーン
⑤ つり上げ荷重が< B >以上のデリツク
⑥ 積載荷重が< C >以上のエレベーター
⑦ ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト(積載荷重が0.25トン未満のものを除く。)
⑧ ゴンドラ

【解答】
A 3トン
B 2トン
C 1トン
では、どうぞ!
問 題
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、< D >を受けなければならない。
特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは< E >の検査を受けなければならない。
【選択肢】
① 厚生労働大臣の許可 ② 労働基準監督署長の認可
③ 都道府県労働局長の許可
④ 登録製造時等検査機関 ⑤ 労働基準監督署長
⑥ 厚生労働大臣

【解答】
D ③ 都道府県労働局長の許可
クレーンなど特に危険な作業を必要とするもの(特定機械等)は、製造段階から基準が設けられているため、製造許可制度をとっています。
E ④ 登録製造時等検査機関
特定機械等の「製造時等の検査」です。
「製造時等の検査」には、1 製造時の検査、2 輸入時の検査、3 厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとするときの検査、4 使用を廃止したものを再設置し、又は再使用しようとするときの検査、の4つがあります。
特別特定機械等以外 → 都道府県労働局長が実施
特別特定機械等 → 登録製造時等検査機関が実施
なお、特定機械等を設置するとき、それ以後の検査として
1 特定機械等(移動式のものを除く。)の設置時の検査、2 厚生労働省令で定める部分に変更を加えたときの検査、3 使用を休止したものを再び使用しようとするときの検査
がありますが、これらの検査を実施するのは、< F >です。
【Fの選択肢】
① 厚生労働大臣 ② 都道府県労働局長 ③ 労働基準監督署長

【解答】
F ③ 労働基準監督署長
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-232
R2.7.20 選択式の練習/労基法の時効
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労基法の時効」です。
令和2年4月の改正点の確認です。
では、どうぞ!
問 題
法第115条
この法律の規定による< A >の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
↓ アンダーライン部分は附則で以下のように読み替えます。
法附則第143条
この法律の規定による退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による< A >(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権 (< A >の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
【選択肢】
① 年次有給休暇 ② 労働条件通知書 ③ 賃金

【解答】
A ③ 賃金
労基法の時効
・賃金(退職手当除く。) → 5年間(当分の間3年間) 改正点です。
改正点です。
 令和2年4月の民法改正に合わせ、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間は5年間に延長されました。ただし、経過措置で当分の間は3年とされています。
令和2年4月の民法改正に合わせ、労働基準法の賃金請求権の消滅時効期間は5年間に延長されました。ただし、経過措置で当分の間は3年とされています。
 「賃金(退職手当除く。)」の内容は?
「賃金(退職手当除く。)」の内容は?
金品の返還(23条。賃金の請求に限る。)、賃金の支払 (24条)、非常時払(25条)、休業手当(26条)、出来高払制の保障給(27条)、時間外・休日労働に対する 割増賃金(37条1項)、有給休暇期間中の賃金(39条 9項)、未成年者の賃金請求権(59条)
・退職手当 → 5年間(変更なし)
・災害補償 → 2年間(変更なし)
・その他 → 2年間(変更なし)
 「その他」の内容は?
「その他」の内容は?
帰郷旅費(15条3項、64条)、退職時の証明(22条)、 金品の返還(23条。賃金を除く。)、年次有給休暇請求権 (39条)
こちらもどうぞ!
賃金等請求権の消滅時効の起算点は、現行の労働基準法の解釈・運用を踏襲するため、客観的起算点である< B >を維持し、これを労働基準法上明記すること。
【選択肢】
① 雇い入れの日 ② 賃金支払日 ③ 退職の日

【解答】
B ② 賃金支払日
賃金消滅時効の起算点は、「賃金支払日」です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-231
R2.7.19 選択式の練習/介護保険法・国等の責務
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険法・国等の責務」です。
では、どうぞ!
問 題
< A >は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
< B >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
< C >は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
< D >は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
【選択肢】
① 国 ② 事業主 ③ 国民
④ 厚生労働省 ⑤ 都道府県 ⑥ 市町村
⑦ 医療保険者 ⑧ 健康保険組合 ⑨ 国及び地方公共団体
⑩ 医療機関 ⑪ 医療従事者

【解答】
A ⑨ 国及び地方公共団体
キーワード医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
B ⑤ 都道府県
キーワード助言及び適切な援助をしなければならない
C ① 国
キーワード 必要な各般の措置を講じなければならない
D ⑦ 医療保険者
キーワード協力しなければならない。
※ちなみに、「医療保険者」とは・・・
医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う
・全国健康保険協会
・健康保険組合
・都道府県及び市町村(特別区を含む。)
・国民健康保険組合
・共済組合
・日本私立学校振興・共済事業団
こちらもどうぞ!
①<H12年出題>
介護保険制度の保険者は市町村で、国や都道府県が重層的に支える。
②<H20年出題>
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。

【解答】
①<H12年出題> 〇
保険者である市町村を、国や都道府県が支えている図をイメージしてくてください。
②<H20年出題> ×
国と都道府県の責務が逆です。
国 → 各般の措置を講じなければならない
都道府県 → 必要な助言及び適切な援助をしなければならない
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-230
R2.7.18 選択式の練習/労働力調査(令和元年平均)より
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労働力調査(令和元年平均」です。
労働力調査(総務省)とは?
・統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査
・就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることが目的
・労働力人口、就業者数・雇用者数、就業時間、完全失業者数、完全失業率、非労働力人口など
では、どうぞ!
問 題
完全失業率(< A >に占める完全失業者の割合)は、2019年平均で < B >%と、前年と同率となった。
※「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」(総務省統計局)を加工して作成しています。
【選択肢】
① 15歳以上人口 ② 生産年齢人口 ③ 労働力人口
④ 2.4 ⑤ 3.8 ⑥ 5.2

【解答】
A ③ 労働力人口
B ④ 2.4
「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」(総務省統計局)より
URL https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index.pdf
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
若年層(ここでは 15~34 歳とした。)の完全失業者数は,2019年平均で 60 万人と、前年と同数となった。若年層の完全失業率は< C >%と、前年と同率となった。
【選択肢】
① 1.8 ② 3.4 ③ 8.3

【解答】
C ② 3.4
「労働力調査(基本集計)令和元年平均結果」(総務省統計局)より
URL https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/pdf/index.pdf
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-229
R2.7.17 選択式の練習/遺族厚生年金の支給停止
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「遺族厚生年金の支給停止」です。
では、どうぞ!
問 題
(遺族厚生年金の支給停止)
遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について < A >の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から< B >年間、その支給を停止する。
< C >に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、< D >に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、< D >が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
【選択肢】
① 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金
② 労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付
③ 労働基準法の規定による遺族補償
④ 5 ⑤ 6 ⑥ 10
⑦ 配偶者、父母又は祖父母 ⑧ 夫、父母又は祖父母
⑨ 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹
⑩ 妻 ⑪ 配偶者 ⑫ 夫

【解答】
A ③ 労働基準法の規定による遺族補償
B ⑤ 6
 労働者が業務上死亡した場合は、使用者は労働基準法の規定により遺族補償を行います。労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡の日から6年間、遺族厚生年金は支給停止となります。
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は労働基準法の規定により遺族補償を行います。労働基準法の規定による遺族補償が行われる場合は、死亡の日から6年間、遺族厚生年金は支給停止となります。
 しかし、実際、業務上死亡した場合は、労災保険法から遺族補償年金が支給されます。(通勤災害の場合は遺族年金が支給されます)
しかし、実際、業務上死亡した場合は、労災保険法から遺族補償年金が支給されます。(通勤災害の場合は遺族年金が支給されます)
同一人の死亡に対し、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)と遺族厚生年金が支給される場合は、労災保険の遺族補償年金(遺族年金)が減額され、遺族厚生年金は調整されず全額支給されます。
労災保険の保険料は全額事業主負担ですが、厚生年金保険の保険料は労使折半です。本人も保険料を負担している厚生年金は減額せず、本人負担のない労災保険の方を減額して調整しています。
C ⑧ 夫、父母又は祖父母
D ⑫ 夫
 被保険者の死亡の当時55歳以上の夫、父母又は祖父母については遺族厚生年金の遺族の範囲に入ります。しかし、受給権があったとしても60歳までは遺族厚生年金は支給停止されます。
被保険者の死亡の当時55歳以上の夫、父母又は祖父母については遺族厚生年金の遺族の範囲に入ります。しかし、受給権があったとしても60歳までは遺族厚生年金は支給停止されます。
ただし、夫については、夫が遺族基礎年金の受給中の場合は、60歳未満でも合わせて遺族厚生年金が支給されます。
こちらもどうぞ!
<H29年出題>
15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。
なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。

【解答】〇
妻の死亡当時、夫55歳以上で子がいる場合、夫に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生します。
その場合、夫が60歳未満でも、遺族厚生年金は支給停止にならず、遺族基礎年金受給中は、遺族厚生年金も支給されます。
問題文の場合、夫が60歳になる前に、子が18歳の年度末を迎えるので、その時点で遺族基礎年金は失権します。
遺族基礎年金が失権してから60歳になるまでは、夫の遺族厚生年金は支給停止されます。
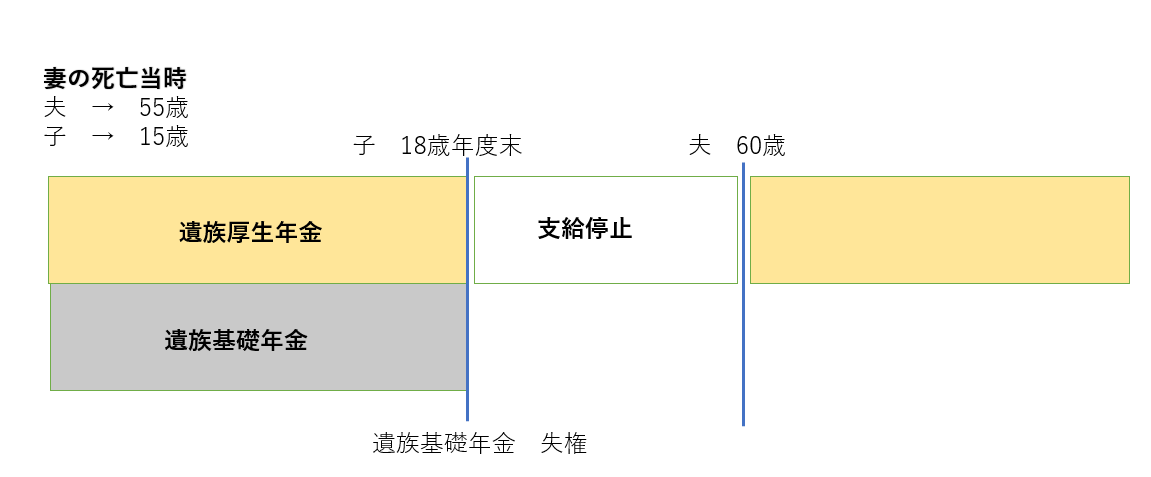
選択式対策(国民年金法)
R2-228
R2.7.16 選択式の練習/繰下げ支給の老齢基礎年金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「繰下げ支給の老齢基礎年金」です。
では、どうぞ!
問 題
老齢基礎年金の受給権を有する者であって< A >に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が< B >歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(< C >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付 (< D >を支給事由とするものを除く。)をいう。)の受給権者であったとき、又は< B >歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。
【選択肢】
① 65歳に達する前 ② 66歳に達する前 ③ 60歳に達する前
④ 65 ⑤ 60 ⑥ 70
⑤ 付加年金 ⑥ 遺族基礎年金 ⑥ 障害基礎年金
⑦ 障害 ⑧ 遺族 ⑨ 老齢

【解答】
A ② 66歳に達する前
B ④ 65
C ⑤ 付加年金
D ⑨ 老齢
 繰下げの要件
繰下げの要件
・ 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していない
・ 65歳に達したとき、又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に
他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないこと
※付加年金の受給権者は繰下げの申し出OK
厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権者でないこと
※特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は繰下げOK
ポイント!
繰下げ支給は、老齢基礎年金の受給権発生から1年以上待つことが条件です。
こちらもどうぞ!
 R1年出題
R1年出題
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。
 H24年出題
H24年出題
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。

【解答】
 R1年出題 〇
R1年出題 〇
65歳に達したとき、又は「65歳に達した日から66歳に達した日まで」の間に、他の年金給付(障害基礎年金、遺族基礎年金)の受給権者でないことが、繰下げの要件です。
問題文は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に障害基礎年金の受給権者になっていますので、繰下げの申し出はできません。
 H24年出題 ×
H24年出題 ×
寡婦年金は65歳に達したときに失権するので、寡婦年金の受給権者であった者でも、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けられます。
ちなみに・・・66歳に達した日後に障害基礎年金の受給権を取得したら繰下げは?
例えば、67歳で障害基礎年金の受給権取得後に、繰下げの申し出をした場合、繰下げの増額率はどうなる?
↓
実際に繰下げの申し出をした時点ではなく、障害基礎年金の受給権が発生したときに繰下げの申し出をしたものとみなされます。
・ 増額率は、「障害基礎年金の受給権が発生」した時点で計算されます
・ 繰下げの老齢基礎年金は、「繰下げの申出をした日の属する月の翌月から」ではなく、障害基礎年金を受ける権利が発生した月の翌月から支給されます。
繰下げでよく出る問題
<H21年出題>
振替加算の受給対象者が老齢基礎年金の繰下げの申出をしたときは、振替加算も繰下げ支給され、当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が加算される。

【解答】 ×
老齢基礎年金の繰下げを申し出た場合、振替加算も繰下げされますが、振替加算は増額されません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-227
R2.7.15 選択式の練習/定時決定について
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「定時決定について」です。
では、どうぞ!
問 題
<定時決定>
保険者等は、被保険者が毎年< A >現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額を< B >で除して得た額を 報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の< C >までの各月の標準報酬月額とする。
定時決定は、< D >までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定の規定により < E >までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
【選択肢】
① 6月1日 ② 4月1日 ③ 7月1日
④ 6 ⑤ その期間の月数 ⑥ 12
⑦ 9月から翌年の8月 ⑧ 10月から翌年の9月 ⑨ 8月から翌年の7月
⑩ 5月1日から6月1日 ⑪ 6月1日から7月1日 ⑫ 7月1日から8月1日
⑬ 5月から8月 ⑭ 6月から9月 ⑮ 7月から9月

【解答】
A ③ 7月1日
B ⑤ その期間の月数
C ⑦ 9月から翌年の8月
D ⑪ 6月1日から7月1日
E ⑮ 7月から9月
こちらもどうぞ!
<H29年出題>
特定事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払いの基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払いの基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。
※ 短時間労働者とは
1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である者又は1か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数の4分の3未満である者のこと

【解答】 〇
定時決定、随時改定、育児休業を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定については、報酬支払の基礎となった日数が17日以上か17日未満かがポイントになりますが、短時間労働者の場合は17日ではなく11日となります。
こちらもどうぞ!
<H24年出題>
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

【解答】 ×
7月1日に被保険者資格を取得した者 → 定時決定は行わない。
資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の8月31日まで用いる。
「翌年の6月30日までの1年間用いる」が誤りです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-226
R2.7.14 徴収法でよく出る端数処理
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「徴収法でよく出る端数処理」です。
切り上げ?切り捨て?
1円単位?10円単位?1000円単位?
この機会に覚えてしまいましょう!
では、どうぞ!
問題 1
<H17年出題>
賃金総額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額が一般保険料の算定の基礎となる。

【解答】 〇
概算保険料は、「賃金総額の見込額 × 一般保険料率」で計算します。
端数処理は
・賃金総額 → 1,000円未満切り捨て
・概算保険料の額又は確定保険料の額 → 1円未満切り捨て
となります。
問題 2
<H24年出題>
個人事業主が労災保険法第34条第1項の規定に基づき、中小事業主等の特別加入の承認を受けた場合、当該事業主に係る当該承認を受けた保険年度の第1種特別加入保険料の額の算定の仕方について、正しいものは次のうちどれか。
なお、事業の種類等は次のとおりである。
・事業の種類 飲食店
・当該事業に係る労災保険率 1000分の3
・中小事業主等の特別加入申請に係る承認日 令和元年12月15日
・給付基礎日額 8千円
・特別加入保険料算定基礎額 292万円
| A | 8千円×107日×1000分の3 |
| B | 8千円×108日×1000分の3 |
| C | 292万円×12分の1×3か月×1000分の3 |
| D | 292万円×12分の1×3.5か月×1000分の3 |
| E | 292万円×12分の1×4か月×1000分の3 |

【解答】 E
ポイント! 保険年度の途中で特別加入した又は中途脱退した場合は「月割計算」
特別加入期間の月数に1か月未満の端数があるときは、1か月としてカウントします。
・保険年度の中途に特別加入者になった
承認日の属する月 → 1か月でカウントする
・保険年度の中途に特別加入者に該当しなくなった
地位の消滅の前日の属する月 → 1か月でカウントする
問題文の場合、特別加入の承認を受けたのは令和元年12月15日。12月は1か月でカウントします。令和元年度の特別加入期間の月数は、令和元年12月から令和2年3月までの4か月となります。
(注意)有期事業の場合は端数処理の方法が異なります。有期事業についての特別加入期間を全期間で端数処理しますので、注意してください。
問題 3
<H29年出題>
概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

【解答】 ×
ポイント! 1円未満の端数は、1期分でまとめます。
170,000円÷3=56666.6666
第1期 → 56,668円
第2期、第3期 → 56,666円
問題 4
延滞金は、労働保険料の額が100円未満であるとき又は延滞金の額が10円未満であるときは、徴収されない。

【解答】 ×
延滞金は、労働保険料の額が1,000円未満であるとき又は延滞金の額が100円未満であるときは、徴収されない。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-225
R2.7.13 選択式の練習/再就職手当と就業促進定着手当のこと
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「再就職手当と就業促進定着手当」のことです。
「再就職手当」「就業促進定着手当」はどんなときに支給される?
・ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
↓
・ 安定した職業に就いた
↓
・ 再就職手当の支給を受ける
↓
・ 再就職先に6か月以上雇用される
↓
・ 再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合
↓
・ 就業促進定着手当が支給される
では、どうぞ!
問 題
就業促進手当の額は、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上であるものについては、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< A >(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(以下「早期再就職者」という。)にあっては、< B >)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用される者であって厚生労働省令で定めるものにあっては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に< C >(早期再就職者にあっては、< D >)を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)とされている。
【選択肢】
① 10分の1 ② 10分の2 ③ 10分の3 ④ 10分の4
⑤ 10分の5 ⑥ 10分の6 ⑦ 10分の7 ⑧ 10分の8
⑨ 10分の9 ⑩ 10分の10

【解答】
A ⑥ 10分の6
B ⑦ 10分の7
C ④ 10分の4
D ③ 10分の3
 再就職手当の額
再就職手当の額
基本手当の支給残日数によって率が変わります。
3分の1以上 → 基本手当日額×(支給残日数×10分の6)
3分の2以上(早期再就職者) → 基本手当日額×(支給残日数×10分の7)
 就業促進定着手当の額
就業促進定着手当の額
(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×みなし賃金日額の算定に係る期間の賃金支払基礎日数
※上限あり
基本手当日額×(再就職手当×支給残日数×10分の4)
(再就職手当の給付率が 10 分の7の場合は、10分の3)
こちらもどうぞ!
<就業促進定着手当の支給申請手続>
受給資格者は、同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて6か月間以上雇用される者であって、就業促進定着手当の支給を受けようとするときは、同日から起算して6か目に当たる日の翌日から起算して< E >以内に、就業促進定着手当支給申請書に、所定の書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
<就業促進定着手当の支給>
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業促進定着手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して< F >以内に就業促進定着手当を支給するものとする。
【選択肢】
① 10日 ② 1か月 ③ 2か月
④ 7日 ⑤ 14日 ⑥ 21日

【解答】
A ③ 2か月
支給申請の手続きは、「再就職手当に係る安定した職業に就いた日から起算して 6 か月目に当たる日の翌日」から 「2か月以内」に行います。
B ④ 7日
こちらもどうぞ!
<H30年出題>
再就職手当を受給した者が、当該再就職手当の支給に係る同一の事業主にその職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用された場合で、当該再就職手当に係る雇用保険法施行規則第83条の2にいうみなし賃金日額が同条にいう算定基礎賃金日額を下回るときは、就業促進定着手当を支給することができる。

【解答】 〇
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-224
R2.7.12 選択式の練習/事業主からの費用徴収
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「事業主からの費用徴収」です。
労災保険は、その事業が開始された日(労働者を使用した日)に、自動的に、保険関係が成立します。
ただし、徴収法では、事業主は「保険関係成立届」を保険関係が成立した日から10日以内に届け出ることが規定されています。
※保険関係成立届を提出しないと、政府が保険料を徴収できないからです。
もし、事業主が保険関係成立届を出していないうちに、労災事故が起こった場合でも労働者に対しては保険給付が行われます。しかし、事業主にはペナルティが課されることがある、それが今日のテーマです。
では、どうぞ!
問 題
政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額< A >。
一 事業主が< B >労災保険にかかる保険関係成立届を提出していない期間(政府が当該事業について認定決定をしたときは、その決定のあった日の前日までの期間)中に生じた事故
二 事業主が概算保険料のうち一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限までの期間は除く。)中に生じた事故
三 事業主が< B >生じさせた業務災害の原因である事故
【選択肢】
① を事業主から徴収しなければならない
② の全部又は一部を事業主から徴収することができる
③ で保険給付をしないことができる
④ 故意又は重大な過失により ⑤ 過失により
⑥ 故意又は過失により

【解答】
A ② の全部又は一部を事業主から徴収することができる
B ④ 故意又は重大な過失により
こちらもどうぞ!
<H19年出題>
事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害又は労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害について保険給付を行ったときは、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができる。

【解答】 ×
「事業主の故意若しくは重大な過失により生じた業務災害」については、費用徴収の対象ですが、「労働安全衛生法その他労働者の安全及び衛生の確保を図るための法令に事業主が違反したことにより生じた業務災害」については費用徴収の対象にはなっていません。
もう一問どうぞ!
<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

【解答】 〇
「事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届け出をせず、保険料を納付していない場合」
・ 労働者に対する保険給付は通常どおりに行われる。(労働者に非はないので)
・ 政府は、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる。(保険関係成立届を提出していない事業主には、保険給付にかかった費用の全部又は一部を払ってもらうことでペナルティをかけます。)
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-223
R2.7.11 選択式の練習/特定元方事業者の講ずべき措置
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「特定元方事業者の講ずべき措置」です。
特定元方事業者とは?
特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者です!
建設業や造船業の現場では、同じ場所に複数の請負人が入り組んで作業を行うことが一般的です。
複数の企業が混在することによって起こりうる災害を防ぐため、特定元方事業者が講ずべき措置が定められています。
では、どうぞ!
問 題
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 < A >の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための< B >に対する指導及び援助を行うこと。
(以下略)
【選択肢】
① 安全委員会 ② 現場組織 ③ 協議組織
④ 健康管理 ⑤ 安全管理 ⑥ 教育

【解答】
A ③ 協議組織
B ⑥ 教育
こちらもどうぞ!
<H20年出題>
特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全衛生のための教育を行う必要はない。

【解答】 ×
関係請負人の労働者に対する安全衛生教育は、特定元方事業者が行うのではなく、関係請負人である事業者が行わなければなりません。
特定元方事業者は、関係請負人の労働者に対する安全衛生教育を直接行うのではなく、「教育に対する指導及び援助」を講じることになります。例えば、教育を行う場所や資料の提供などの措置です。
もう一問どうぞ!
<H27年出題>
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために、作業期間中少なくとも1週間に1回、作業場所を巡視しなければならない。

【解答】 ×
作業期間中少なくとも1週間に1回、ではなく、「毎作業日に少なくとも1回」です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-222
R2.7.10 選択式の練習/高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「高度プロフェッショナル制度の対象労働者の範囲」です。
高度プロフェッショナル制度の導入の流れ
 労使委員会を設置
労使委員会を設置
 労使委員会で決議
労使委員会で決議
 労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出
労使委員会の決議を労働基準監督署長に届け出
 対象労働者の同意を得る(書面で)
対象労働者の同意を得る(書面で)
 対象労働者を対象業務に就かせる
対象労働者を対象業務に就かせる
POINT! 定期報告
 決議の有効期間満了
決議の有効期間満了
 の労使委員会で決議すべき事項は、「対象業務」、「対象労働者の範囲」などですが、今日は、「対象労働者」がテーマです。
の労使委員会で決議すべき事項は、「対象業務」、「対象労働者の範囲」などですが、今日は、「対象労働者」がテーマです。
ではどうぞ!
問 題
高度プロフェッショナル制度の対象労働者
次のいずれにも該当する労働者
イ 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による< A >に基づき< B >が明確に定められていること。
ロ 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の< C >の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
【選択肢】
① 同意 ② 契約 ③ 合意
④ 職務 ⑤ 裁量 ⑥ 役割
⑦ 2倍 ⑧ 3倍 ⑨ 5倍

【解答】
A ③ 合意
B ④ 職務
C ⑧ 3倍
ロの要件をもう少し詳しく見てみましょう
基準年間平均給与額の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額は、< D >円以上であること。
【選択肢】
① 850万 ② 1075万 ③ 1275万

【解答】
D ② 1075万
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-221
R2.7.9 選択式の練習/社労士法・社労士の義務
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「社労士法・社労士の義務」です。
ではどうぞ!
問 題
社会保険労務士は、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、< A >労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は< B >を害するような行為をしてはならない。
社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その < C >を図るように努めなければならない。
【選択肢】
① 不当に ② 不正に ③ 虚偽に
④ 品位 ⑤ 品格 ⑥ 信義
⑦ 能力の向上 ⑧ 知識の研鑽 ⑨ 資質の向上

【解答】
A ② 不正に
B ④ 品位
C ⑨ 資質の向上
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
 H15年出題
H15年出題
社会保険労務士が、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これに類する行為をしたときは、罰則は科せられないが、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が科せられる。
 H13年出題
H13年出題
社会保険労務士は、行政機関の実施する研修を受け、その資質の向上を図るよう努めなければならない。

【解答】
 H15年出題 ×
H15年出題 ×
「不正行為の指示等」と「信用失墜行為」の罰則が逆です。
不正行為の指示等 → 罰則あり(3年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
信用失墜行為 → 罰則なし
 H13年出題 ×
H13年出題 ×
行政機関の実施する研修ではなく、社会保険労務士会及び連合会が行う研修です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-220
R2.7.8 選択式の練習/厚生労働省の統計調査
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「厚生労働省の統計調査」です。
ではどうぞ!
問 題
<H26年選択>
労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている< A >である。この調査は、統計法に基づいて行われる< B >であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。
< A >は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、< C >についても調べている。
【選択肢】
① 労働力調査 ② 毎月勤労統計調査 ③ 就労条件総合調査
④ 基幹統計調査 ⑤ 一般統計調査 ⑥ 悉皆統計調査
⑦ 出勤日数 ⑧ 有給休暇日数 ⑨ 裁量労働対象者数

【解答】
A ② 毎月勤労統計調査
B ④ 基幹統計調査
C ⑦ 出勤日数
 基幹統計調査とは?
基幹統計調査とは?
・ 基幹統計調査は、国の行政機関が作成する統計のうち総務大臣が指定する特に重要な統計。毎月勤労統計調査は「基幹統計調査」。
・ 国の行政機関が行う統計調査は、「基幹統計調査」と「一般統計調査」に分けられている。
・ 報告義務(報告の拒否や虚偽報告についての罰則規定)は、一般統計調査にはない基幹統計調査の特別な規定。
 ついでにこちらもチェック
ついでにこちらもチェック
 「就労条件総合調査」とは?
「就労条件総合調査」とは?
調査事項:企業の属性、労働時間制度、賃金制度、資産形成に関する事項
一般統計調査
厚生労働省が実施
 「労働力調査」とは?
「労働力調査」とは?
目 的:我が国の就業・不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ること
調査範囲:我が国に居住している全人口
基幹統計調査
総務省が実施

たぶん、今年の本試験にはあまり関係ないです。ちょっとしたこと
令和2年7月7日に、「毎月勤労統計調査 令和2年5月分結果速報」が厚生労働省から公表されました。
現金給与総額(就業形態計)は、269,341 円で、きまって支給する給与は 258,366 円。きまって支給する給与のうち、所定内給与は 243,765 円(前年同月比0.2%増)、所定外給与は 14,601 円(前年同月比25.8%減)。
総実労働時間は、122.3 時間。そのうち、所定内労働時間は 115.0 時間(前年同月比7.4%減)、所定外労働時間は 7.3 時間(前年同月比29.7%減)。
→ 前年同月と比べて、所定外給与と所定外労働時間の減少が大きいですね。コロナの影響で残業が減ったことが想像できる数字です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-219
R2.7.7 選択式の練習/65歳未満の在職老齢年金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「65歳未満の在職老齢年金」です。
「在職老齢年金」の問題は、65歳以上か65歳未満か、まずは年齢を確認してくださいね。
ではどうぞ!
問 題
60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が200,000円であり、その者の総報酬月額相当額が300,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は< A >円となる。
なお、加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、基本月額は加給年金額を< B >ものである。
【選択肢】
① 110,000 ② 90,000 ③ 15,000
④ 含めた ⑤ 除いた

【解答】
A ① 110,000
<1月当たりの支給停止額の計算>
(30万円+20万円-28万円)×2分の1
B ⑤ 除いた
基本月額=老齢厚生年金の額÷12
(老齢厚生年金の額から加給年金額は除く。)
こちらもどうぞ!
<H27年アレンジ>
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は< C >円(加給年金額を除く。)となる。
【選択肢】
① 105,000 ② 95,000 ③ 10,000 ④ 190,000

【解答】
C ② 95,000
計算の手順
1.まず、総報酬月額相当額を計算する
240,000円 + (600,000円÷12) = 290,000円
2.基本月額+総報酬月額相当額を計算する
200,000円 + 290,000円 = 490,000円
280,000円を超えているので、在老の仕組みで支給停止される。
3.1月当たりの支給停止額を計算する
基本月額が28万円以下、総報酬月額相当額が47万円以下の計算式を使う
(200,000円+290,000円-280,000円)÷2=105,000円
4.支給停止後の年金月額を計算する
200,000円-105,000円=95,000円
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-218
R2.7.6 選択式の練習/年金・旧法と新法
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「旧法と新法」です。
年金制度は「昭和61年4月1日」がポイントです。
昭和61年4月1日前の制度を旧法、昭和61年4月1日以後の制度を新法といいます。
昭和61年4月1日に、「基礎年金」が導入され、すべての職業の人が国民年金に加入することになり、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の区分ができました。
また、それまで任意加入だった会社員に扶養される妻(夫)が第3号被保険者として強制加入となりました。
1階に「基礎年金」、2階にサラリーマンや公務員が加入する厚生年金が乗っかる2階建ての年金制度になったのもこのときでした。
今日のテーマは旧法から新法への切り替えがテーマです。
ではどうぞ!
問 題
<H15年選択式>
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については< A >以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く。)、障害基礎年金については< B >が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。
【選択肢】
① 大正15年4月1日 ② 大正15年4月2日 ③ 昭和40年4月2日
④ 初診日 ⑤ 20歳に達した日 ⑥ 障害認定日

【解答】
A ② 大正15年4月2日
新法の「老齢基礎年金」の対象は、原則として大正15年4月2日以降生まれの者
B ⑥ 障害認定日
障害認定日(受給権が発生する日)が昭和61年4月1日以降なら新法の障害基礎年金の対象になります。
引き続きこちらも!
①<H16年出題>
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には昭和61年4月1日以後は、遺族基礎年金を支給する。
②<H16年出題>
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当するものとみなして、遺族基礎年金を支給する。

【解答】
①<H16年出題> ×
旧法の国民年金の母子年金及び準母子年金は、今の遺族基礎年金にあたる年金です。新法施行日の前日(昭和61年3月31日)に、旧国民年金法の母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には、昭和61年4月1日以後も、そのまま母子年金、準母子年金として支給されます。遺族基礎年金への裁定替えはしません。
②<H16年出題> 〇
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、母子年金、準母子年金の保険料納付要件などを満たさなかった場合の年金です。(「福祉」年金という名称に着目してください。)
旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金は、遺族基礎年金に裁定替えされ、遺族基礎年金として支給されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-217
R2.7.5 選択式の練習/全国健康保険協会のこと
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「全国健康保険協会のこと」です。
健康保険の保険者は、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。
今日は、「全国健康保険協会」について。
ではどうぞ!
問 題
全国健康保険協会について(以下「協会」という。)
協会に、役員として、理事長1人、理事6人以内及び監事2人を置く。
理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。
理事長及び監事は、< A >が任命する。
理事は、理事長が任命する。
事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に< B >を置く。
< B >の委員は、9人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、< A >が各同数を任命する。
【選択肢】
① 内閣総理大臣 ② 厚生労働大臣 ③ 社会保障審議会
④運営委員会 ⑤ 評議会 ⑥ 理事会

【解答】
A ② 厚生労働大臣
B ④運営委員会
協会に置かれるのが「運営委員会」、支部ごとに設けられるのが「評議会」です。
引き続きこちらも!
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、 < C >。これを変更しようとするときも、同様とする。
協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の< D >までに完結しなければならない。
協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び会計監査人の意見を付けて、決算完結後< E >以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
【選択肢】
① 厚生労働大臣に届け出なければならない
② 厚生労働大臣の許可を受けなければならない
③ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない
④ 4月30日 ⑤ 5月31日 ⑥ 6月30日
⑦ 1か月 ⑧ 2か月 ⑨ 3か月

【解答】
C ③ 厚生労働大臣の認可を受けなければならない
B ⑤ 5月31日
C ⑧ 2か月
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
全国健康保険協会の理事長は全国健康保険協会の業績について事業年度ごとに評価を行い、当該評価の結果を遅滞なく、厚生労働大臣に対して通知するとともに、これを公表しなければならない。

【解答】 ×
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
★評価をするのは厚生労働大臣。評価を行ったら、協会にフィードバックし、公表する。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-216
R2.7.4 第1種特別加入保険料率の決め方
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「第1種特別加入保険料率の決め方」です。
中小事業主が労災保険に特別加入した場合の労災保険率は?
では、どうぞ!
問題
<H26年出題>
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主等が行う事業に適用される保険料率から、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間に発生した通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率とされている。

【解答】 ×
「通勤災害に係る災害率」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。
特別加入者には、「二次健康診断等給付」は行われませんよね?
ですので、「二次健康診断等給付に要した費用の額」を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率となります。
※なお、「二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率」は現在ゼロなので、第1種特別加入保険料率は、通常の労災保険料率と同じ率です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-215
R2.7.3 選択式の練習/基本手当の日額の算定ルール
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「基本手当の日額の算定ルール」です。
基本手当の日額の算定手順
① 賃金日額を算定する
↓
② 賃金日額に一定の率を乗じた額が「基本手当の日額」となる
ではどうぞ!
問 題
<賃金日額の算出>
(原則) 賃金日額は、< A >において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を< B >で除して得た額とする。
(最低保障)
① 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、最後の6か月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の< C >に相当する額
② ①のほか賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によって定められている場合には、1か月を30日として計算する。)で除して得た額と①の額との合算額
【選択肢】
① 算定基礎期間 ② 被保険者であった期間 ③ 算定対象期間
④ 総日数 ⑤ 労働した日数 ⑥ 180
⑦ 100分の60 ⑧ 100分の70 ⑨ 100分の80

【解答】
A ③ 算定対象期間
B ⑥ 180
C ⑧ 100分の70
次は「基本手当の日額」です!
<基本手当の日額の算定>
基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算する。
賃金日額に乗じる一定の率は、原則として100分の80から100分の< D >までの範囲で定められている。
また、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の< E >までの範囲で定められている。
【選択肢】
① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50 ⑥55

【解答】
D ⑤ 50
E ④ 45
こちらもどうぞ!
①<H22年出題>
基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることはない。
②<H26年出題>
受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者に係る基本手当の日額は賃金日額に100分の45を乗じて得た額を下回ることはない。

【解答】
①<H22年出題> 〇
賃金日額に乗じる一定の率は、離職日の年齢に関係なく「100分の80」が最高です。
②<H26年出題> 〇
離職日に60歳以上65歳未満の場合、賃金日額に乗じる一定の率は100分の45~80の範囲内です。なので、基本手当の日額は「賃金日額×100分の45」を下回ることはありません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-214
R2.7.2 選択式の練習/通勤・日常生活上必要な行為
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「通勤・日常生活上必要な行為」です。
通勤経路を逸脱・中断した場合の扱いを確認しておきましょう。
労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合
<原則> 逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。
<例外> 逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合
逸脱又は中断の間は通勤としない。しかし、合理的な経路に復した後は通勤となる。
今日のテーマは「日常生活上必要な行為」です。
日常生活上必要な行為は、厚生労働省令で定められています。
ではどうぞ!
問 題
(日常生活上必要な行為)
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
 < A >その他これに準ずる行為
< A >その他これに準ずる行為
 職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
 選挙権の行使その他これに準ずる行為
選挙権の行使その他これに準ずる行為
 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
 要介護状態にある配偶者、子、父母、< B >並びに配偶者の父母の介護(< C >行われるものに限る。)
要介護状態にある配偶者、子、父母、< B >並びに配偶者の父母の介護(< C >行われるものに限る。)
【選択肢】
① 食料品の調達 ② 日用品の購入 ③ 子の送迎
④ 孫及び兄弟姉妹 ⑤ 孫及び祖父母 ⑥ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
⑦ 継続的に又は反復して ⑧ 継続的に又は定期的に
⑨ 一定の頻度で定期的に

【解答】
A ② 日用品の購入
B ⑥ 孫、祖父母及び兄弟姉妹
C ⑦ 継続的に又は反復して
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

【解答】 ×
美容院に立ち寄る行為は、「日用品の購入その他これに準ずる行為」に該当します。
美容院で髪のセットをしている間(逸脱又は中断中)は通勤となりませんが、髪のセットが終わって元の経路に復した後は、「通勤」となります。
もう一問どうぞ!
<H23年出題>
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

【解答】 ×
逸日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであったとしても、逸脱又は中断の間は通勤とはなりません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-213
R2.7.1 選択式の練習/産業医の選任、産業医の職務
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「産業医の選任、産業医の職務」です。
一定規模の事業者は、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
なお、「産業医」は、「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者」であることが要件です。
ではどうぞ!
問 題
事業者は、< A >労働者を使用する事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理等を行わせなければならない。
産業医を選任すべき事由が発生した日から< B >選任すること。
常時< C >人以上の労働者を使用する事業場又は一定の有害業務に常時 < D >人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任すること。
常時< E >労働者を使用する事業場にあっては、2人以上の産業医を選任すること。
【選択肢】
① 常時50人をこえる ② 常時10人以上の ③ 常時50人以上の
④ 30日以内に ⑤ 遅滞なく ⑥ 14日以内に
⑦ 1,000 ⑧ 300 ⑨ 2,000 ⑩ 3,000 ⑪ 100
⑫ 500 ⑬ 1,000人をこえる ⑭ 1,000人以上の
⑮ 3,000人をこえる ⑯ 3,000人以上の

【解答】
A ③ 常時50人以上の
※ 50人以上規模の事業場は「全業種」が対象です。
B ⑥ 14日以内に
※ 「14日以内」に選任し、選任後、「遅滞なく」、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
C ⑦ 1,000
D ⑫ 500
E ⑮ 3,000人をこえる
こちらもどうぞ!
<H17年出題>
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

【解答】 〇
一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、専属の産業医が必要ですが、この「有害業務」に「深夜業含む業務」が入るのがポイントです。
なお、6か月以内ごとに1回の健康診断が必要な特定業務従事者の業務の範囲もこの「有害業務」の範囲と同じです。同様に「深夜業を含む業務」が入るのがポイントです。
※ 常時500人を超える事業場で、坑内労働又は一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければなりませんが、ここの有害業務には、深夜業は入りません。
有害業務といってもそれぞれ範囲が違います。特に「深夜業」は入るか否かはよく問われますので、意識して勉強してみてください。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-212
R2.6.30 選択式の練習/解雇予告制度が除外される労働者は?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「解雇予告制度が除外される労働者は?」です。
労働者を解雇しようとする場合は、原則として、解雇予告が必要です。
・ 少くとも30日前にその予告をする
・ 30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う
※ 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することも可能
しかし、予告制度が除外される場合もありますので、確認しましょう。
ではどうぞ!
問 題
解雇の予告の規定は、次の労働者については適用しない。
 日日雇い入れられる者
日日雇い入れられる者
 2か月以内の期間を定めて使用される者
2か月以内の期間を定めて使用される者
 < A >以内の期間を定めて使用される者
< A >以内の期間を定めて使用される者
 試の使用期間中の者
試の使用期間中の者
ただし、 に該当する者が< B >を超えて引き続き使用されるに至った場合、
に該当する者が< B >を超えて引き続き使用されるに至った場合、 若しくは
若しくは に該当する者が< C >を超えて引き続き使用されるに至った場合又は
に該当する者が< C >を超えて引き続き使用されるに至った場合又は に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇の予告の規定が適用される。
に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、解雇の予告の規定が適用される。
【選択肢】
① 30日 ② 季節的業務に4か月 ③ 季節的業務に6か月
④ 1か月 ⑤ 31日 ⑥ 2週間 ⑦ 所定の期間
⑧ 4か月 ⑨ 6か月

【解答】
A ② 季節的業務に4か月
B ④ 1か月
C ⑦ 所定の期間
こちらもどうぞ!
①<H15年出題>
使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
②<H23年出題>
労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、6か月の期間を定めて使用される者が、期間の途中で解雇される場合には適用されることはない。

【解答】
①<H15年出題> ×
2か月の期間を定めて雇い入れた労働者には、解雇予告の規定は適用されませんので、期間の途中で解雇する場合でも解雇の予告はいりません。
なお、2か月の期間で雇い入れられた労働者を、所定の期間(この問題の場合なら2か月)を超えて引き続き使用した場合には、解雇予告の規定が適用されます。
②<H23年出題> ×
「6か月の期間を定めて使用される者」には解雇予告の規定が適用されますので、期間の途中で解雇する場合には、予告が必要です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-211
R2.6.29 選択式の練習/高齢者医療確保法・生活習慣病予防のために
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「高齢者医療確保法・生活習慣病予防のために」です。
ではどうぞ!
問 題
厚生労働大臣は、< A >(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。)及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(「< A >等基本指針」という。)を定めるものとする。
保険者(都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、< A >等基本指針に即して、< B >として、 < A >等実施計画を定めるものとする。
保険者は、< A >等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、< C >の加入者に対し、< A >を行うものとする。
【選択肢】
① 特定健康診査 ② 特定健康診断 ③ 特定健康検診
④ 3年ごとに、3年を一期 ⑤ 5年ごとに、5年を一期
⑥ 6年ごとに、6年を一期
⑦ 40歳以上 ⑧ 60歳以上 ⑨ 65歳以上

【解答】
A ① 特定健康診査
B ⑥ 6年ごとに、6年を一期
C ⑦ 40歳以上
特定健康診査の目的は、生活習慣病の予防。健康が気になる40歳以上が対象です。その結果、生活習慣病の発症リスクが高い人に対して行われるのが特定保健指導。生活習慣の改善のサポートが行われます。
ちなみに、「特定健康診査等基本指針」を定めるのが厚生労働大臣。
「特定健康診査等実施計画」を定め、その実施計画に基づき特定健康診査を行うのは「保険者」です。
※高齢者医療確保法の「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいいます。
「保険者」について、こちらもどうぞ!
<H29年出題>
高齢者医療確保法における「保険者」には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。

【解答】 〇
「医療保険各法」と保険者
| 健康保険法 | 全国健康保険協会、健康保険組合 |
| 船員保険法 | 全国健康保険協会 |
| 国民健康保険法 | 都道府県及び市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合 |
| 国家公務員共済組合法 | 共済組合 |
| 地方公務員等共済組合法 | 共済組合 |
| 私立学校教職員共済法 | 日本私立学校振興・共済事業団 |
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-210
R2.6.28 選択式の練習/障害者雇用促進法 差別の禁止など
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害者雇用促進法 差別の禁止など」です。
ではどうぞ!
問 題!
(障害者に対する差別の禁止)
事業主は、労働者の< A >について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と< B >をしてはならない。
【選択肢】
① 一切の待遇 ② 募集及び採用 ③ 配置及び昇進
④ 不当な差別的取扱い ⑤ 不利益な取扱い
⑥ 異なる取扱い

【解答】
A ② 募集及び採用
B ④ 不当な差別的取扱い
もう一問どうぞ!
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の< C >必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の< C >職務の円滑な遂行に必要な施設の整備、援助を行う者の配置その他の必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。
【選択肢】
① 希望に応じた ② 職務遂行能力に応じた ③ 障害の特性に配慮した

【解答】
C ③ 障害の特性に配慮した
では、こちらもどうぞ!
<R1年出題>
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。

【解答】 〇
「障害者に対する差別の禁止」規定は、常時使用する労働者数に関係なく適用されるのがポイントです。
こちらもどうぞ!
事業主は、その雇用する労働者の数が常時< D >人以上であるときは、障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない。
【選択肢】
① 101 ② 50 ③ 45.5

【解答】
D ③ 45.5
選任は「努力義務」であることにも注意しましょう。
 常時45.5人以上の労働者を雇用する一般事業主は
常時45.5人以上の労働者を雇用する一般事業主は
・ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況を管轄公共職業安定所長に報告しなければならない。
・ 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-209
R2.6.27 選択式の練習/厚生年金の費用はどのように負担する?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「厚生年金の費用はどのように負担する?」です。
★ 厚生年金保険は、「国庫負担」(税金)と保険料で賄われています。
国庫は、どの部分にどの程度、負担しているのか?等が今日のテーマです。
ではどうぞ!
まずは国庫負担からどうぞ!
(国庫負担等)
国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する< A >に相当する額を負担する。
【選択肢】
① 基礎年金拠出金の額の2分の1 ② 保険給付に要する額の2分の1 ③ 年金たる保険給付に要する額の2分の1

【解答】
A ① 基礎年金拠出金の額の2分の1
国民年金の基礎年金は、第1号被保険者のみならず、厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)とその被扶養配偶者(第3号被保険者)も対象です。
第2号被保険者と第3号被保険者の基礎年金に充てる費用のため、厚生年金保険から国民年金に対して「基礎年金拠出金」を拠出していますが、その基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額は国庫が負担します。
では、こちらもどうぞ!
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の< B >(基礎年金拠出金の負担に関する< B >を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
実施機関(厚生労働大臣を除く。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の< B >の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
① 業務 ② 事務 ③ 事業

【解答】
B ② 事務
次は保険料です!
(保険料)
政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(< C >を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
【選択肢】
① 事務費 ② 第3号被保険者に係る費用 ③ 基礎年金拠出金

【解答】
C ③ 基礎年金拠出金
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H15年出題>
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。

【解答】 〇
保険料は「月単位」で徴収されます。
例えば、
・6月30日に資格取得した → たとえ1日でも6月分の保険料は徴収される
・6月29日退職、6月30日資格喪失した → 資格喪失月の6月分の保険料は徴収されない
・6月30日退職、7月1日資格喪失した → 月末まで被保険者だった6月分の保険料は徴収される
 最後についでにもう一問!
最後についでにもう一問!
<H28年出題>
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者の資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】 〇
★「同月得喪」をおさえましょう。
「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する」のが原則です。
例えば、令和2年6月1日に資格取得し、同月20日退職、21日資格喪失の場合は、6月は1か月の被保険者期間としてカウントされます。
 ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない、という例外規定があります。
ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない、という例外規定があります。
先ほどの続きで、6月21日に国民年金の第1号被保険者又は第3号被保険者となったときは、6月は国民年金の1号又は3号であった月となり、厚生年金保険の被保険者期間にはカウントされません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-208
R2.6.26 選択式の練習/繰上げ支給の老齢基礎年金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「繰上げ支給の老齢基礎年金」です。
★ 法律は、「本則」と「附則」で構成されています。老齢基礎年金の繰上げは「附則」に規定されていて、「当分の間」の措置とされているのがポイントです。
一方、「老齢基礎年金の繰下げ」は、「本則」で規定されています。
ではどうぞ!
問題
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であって、60歳以上< A >歳未満であるもの(< B >でないものに限る。)は、当分の間、< A >歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
ただし、その請求があった日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期を合算して10年以上あることが要件となる。
請求があったときは、その< C >から、その者に老齢基礎年金を支給する。
< D >の受給権は、受給権者が繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
【選択肢】
① 70 ② 65 ③ 75
④ 任意加入被保険者 ⑤ 第1号被保険者
⑥ 確定拠出年金の加入者
④ 請求があった日の翌日 ⑤ 請求があった日
⑥ 厚生労働大臣の確認があった日
⑦ 寡婦年金 ⑧ 障害基礎年金 ⑨ 遺族厚生年金

【解答】
A ② 65
繰上げ請求ができるのは、60歳以上65歳未満
B ④ 任意加入被保険者
任意加入被保険者は繰上げの請求はできない。
C ⑤ 請求があった日
老齢基礎年金は、通常は「65歳に達した日」に受給権が発生しますが、繰上げ請求を行った場合は、「請求があった日」に受給権が発生します。
なお、年金の支給は、「支給すべき事由が発生した日の属する月の翌月から」となりますので、繰上げ支給の老齢基礎年金は、請求のあった日の翌月から支給されます。
D ⑦ 寡婦年金
繰上げ支給の老齢基礎年金を請求した場合、「寡婦年金は支給停止」、「寡婦年金とどちらか選択」はどちらも間違いです。寡婦年金の受給権は消滅しますので注意しましょう。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。

【解答】 ×
65歳まで
繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は、どちらかを選択となります。
65歳以降
繰上げて減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金の併給が可能です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-207
R2.6.25 選択式の練習/埋葬料と埋葬費どこが違う?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「埋葬料と埋葬費どこが違う?」です。
★埋葬料と埋葬費の違いをしっかり確認しましょう。
ではどうぞ!
問題
① 被保険者が死亡したときは、< A >であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、< B >円を支給する。
② ①により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、< C >に対し、< B >円の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
【選択肢】
① その者と生計を同じくしていた者 ② 被扶養者
③ その者により生計を維持していた者
④ 30万 ⑤ 10万 ⑥ 5万
⑦ 埋葬を行うべき者 ⑧ 埋葬を行った者 ⑨ 埋葬を行おうとする者

【解答】
A ③ その者により生計を維持していた者
B ⑥ 5万
C ⑧埋葬を行った者
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H23年出題>
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって埋葬を行うものに対して、埋葬料として、政令で定める金額を支給するが、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対して、前述の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

【解答】 〇
埋葬料 → 政令で定める金額(定額5万円)
埋葬費 → 5万円以内で実際に埋葬にかかった費用
 では、もう一問
では、もう一問
<H28年出題>
被保険者が死亡し、その被保険者には埋葬料の支給を受けるべき者がいないが、別に生計をたてている別居の実の弟が埋葬を行った場合、その弟には、埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額が支給される。

【解答】 〇
死亡した被保険者により生計を維持していた者がいない場合、「埋葬料の支給を受けるべき者」がいませんので、実際に埋葬を行った者に5万円以内で実費が支給されます。問題文の場合は、別に生計をたてている実弟が実際に埋葬を行っていますので、その弟に埋葬費が支給されます。
ちなみに、埋葬料も埋葬費も時効は2年ですが、起算日が異なります。
埋葬料 → 被保険者の「死亡」に対して支給される。時効の起算日は、「死亡日の翌日」
埋葬費 → 実際に埋葬を行ったことに対して支給される。時効の起算日は、「埋葬を行った日の翌日」
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-206
R2.6.24 追徴金でよく出るところ
選択式の練習中ですが、徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「追徴金でよく出るところ」です。
確定保険料の額を認定決定した場合、印紙保険料の額を認定決定した場合、それぞれ追徴金が徴収されます。
今日は「追徴金」がテーマです!
では、どうぞ!
問題
①<H25年出題>
事業主が認定決定された確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合(天災その他やむを得ない理由により、認定決定を受けた場合等一定の場合を除く。)に、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金が課せられるが、この追徴金に係る割合は、印紙保険料の納付を怠った場合の追徴金に係る割合に比して低い割合とされている。
②<H28年出題>
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の100の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】
①<H25年出題> 〇
②<H28年出題> × 100分の10ではなく100分の25
★追徴金の率がポイント!
確定保険料の認定決定 → 100分の10
印紙保険料の認定決定 → 100分の25
どちらも、納付すべき額の1,000円未満の端数は切り捨てです。
印紙保険料の認定決定についてもう一問どうぞ!
<H25年出題>
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】 〇
「納入告知書」がポイントです。(納付書ではありません。)
さらに、ポイントです!
認定決定された印紙保険料の追徴金は、印紙ではなく現金で納付しなければならないことにも注意しましょう。
こちらもどうぞ!
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、追徴金を納期限までに納付しない事業主に対し、期限を指定して当該追徴金の納付を督促するが、当該事業主は、その指定した期限までに納付しない場合には、未納の追徴金の額につき、所定の割合に応じて計算した延滞金を納付しなければならない。

【解答】 ×
延滞金がかかるのは「労働保険料」のみです。追徴金は労働保険料ではないので、延滞金はかかりません。
ポイント!
「追徴金」は「労働保険料」ではありません。
 督促及び滞納処分
督促及び滞納処分
・労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。
・ 督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。
↓
★ 追徴金は、「その他この法律の規定による徴収金」に該当しますので、「督促」「国税滞納処分の例による処分」は、追徴金も対象となります。
 延滞金
延滞金
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
↓
「労働保険料その他この法律の規定による徴収金」ではなく、「労働保険料」になっていることに注目してください。延滞金の対象は「労働保険料」のみで、その他この法律の規定による徴収金は対象外です。ですので、追徴金も延滞金の対象にはなりません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-205
R2.6.23 選択式の練習/雇用保険の被保険者とならないもの
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「雇用保険の被保険者とならないもの」です。
例えば、働く期間や時間が短い人、公務員など他の制度で失業等について保護が受けられる人は、雇用保険の被保険者の適用は除外されます。
ではどうぞ!
問題
(適用除外)
次に掲げる者については、雇用保険法は、適用しない。
1. 1週間の所定労働時間が< A >未満である者(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
2. 同一の事業主の適用事業に継続して< B >雇用されることが見込まれない者(前2月の各月において< C >以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
3. 季節的に雇用される者であって、①< D >の期間を定めて雇用される者、②1週間の所定労働時間が< A >以上であって30時間未満である者、のいずれかに該当するもの
4. 学校教育法の学校の学生又は生徒であって、前3号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
5. 船員法第1条に規定する船員であって、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
6. 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、< E >の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
【選択肢】
① 10時間 ② 15時間 ③ 20時間
④ 31日以上 ⑤ 30日以上 ⑥ 1か月以上
⑦ 11日 ⑧ 14日 ⑨ 18日
⑩ 4か月未満 ⑪ 4か月以内 ⑫ 6か月以内
⑬ 失業等給付 ⑭ 基本手当 ⑮ 求職者給付及び就職促進給付

【解答】
A ③ 20時間
B ④ 31日以上
C ⑨ 18日
D ⑪ 4か月以内
E ⑮ 求職者給付及び就職促進給付
 1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、原則として雇用保険の被保険者にはなりませんが、例外があります。
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は、原則として雇用保険の被保険者にはなりませんが、例外があります。
例外をどうぞ!
↓
<H22年出題>
1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、雇用保険法を適用することとした場合において日雇労働被保険者に該当することとなる者については、同法の適用対象となる。

【解答】 〇
先ほどの選択練習の1.を見てみましょう。
「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」は被保険者から除外されますが、かっこ書きのこの部分→(日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)に注目してください。
20時間未満でも「日雇労働被保険者に該当することとなる者」は適用除外から除外=雇用保険の適用を受ける、ということです。
 では、こちらもどうぞ
では、こちらもどうぞ
<H23年出題>
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者であっても、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者は、被保険者となり得る。

【解答】 〇
こちらは、先ほどの選択練習の2.を見てみましょう。
同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者は、原則として雇用保険の適用を除外されます。
ただし、かっこ書きの部分を見てください。
・前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者
・日雇労働被保険者に該当することとなる者
は、被保険者となり得ます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-204
R2.6.22 選択式の練習/休業補償給付の額の出し方
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「休業補償給付の額の出し方」です。
ではどうぞ!
問題
(原則)
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の< A >から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の< B >に相当する額とする。
【選択肢】
① 第3日目 ② 第4日目 ③ 第1日目
④ 100分の60 ⑤ 100分の80 ⑥ 100分の40

【解答】
A ② 第4日目
B ④ 100分の60
では、所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の計算は?
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、給付基礎日額から< C >を控除して得た額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
【選択肢】
① 当該労働に対して支払われる賃金の額
② 平均賃金の100分の60 ③ 1日あたりの賃金の額

【解答】
C ① 当該労働に対して支払われる賃金の額
 数字で確認してみると
数字で確認してみると
例えば、給付基礎日額が1万円の場合
★丸一日全く労働しなかった(賃金の全部を受けない)日の休業補償給付
10,000円×100分の60 = 6,000円
★所定労働時間の一部のみ労働し、労働した部分の賃金が3,000円の日の休業補償給付
(10,000円-3,000円)×100分の60 = 4,200円
→ 労働できなかった7,000円分の60%を補償するという考え方です。
こちらもどうぞ!
<H30年出題>
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。

【解答】 〇
★全部労働不能で休業中に事業主から支給があった場合の扱い
全部労働不能で平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合は、「休業する日に該当しない」ので、労災の休業補償給付は支給されません。
問題文は、「事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている」となっていますので、休業補償給付は支給されないで「〇」です。
ちなみに、全部労働不能で、事業主から、平均賃金の100分の60未満の金額しか支払われていない場合は、「休業する日として」扱われ、労災の休業補償給付が支給されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-203
R2.6.21 選択式の練習/元方事業者が講じなければならないこと
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「元方事業者が講じなければならないこと」です。
ではどうぞ!
問題
(元方事業者の講ずべき措置等)
1. 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。
2. 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な< A >を行なわなければならない。
3. < A >を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。
【選択肢】
① 勧告 ② 指示 ③ 助言

【解答】
A ② 指示
作業をともに行っている下請企業の災害防止のため、元方事業者には、関係請負人とその労働者に対して法令順守のための指導や指示を行うことが義務付けられています。
こちらもどうぞ!
①H18年出題
業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない。

【解答】 〇
「元方事業者」とは → 「一の場所において行う仕事の一部を請負人に請け負わせているもので、仕事の一部を自ら行うもののうち最も先次のもの」です。
単に「元方事業者」というときは業種は問いませんので、この規定は、業種を問わずすべての元方事業者に適用されます。
なお、「特定元方事業者」というときは、特定事業(建設業又は造船業)の元方事業者のことです。
もう一問どうぞ!
②H22年出題
製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

【解答】 ×
元方事業者が行う指導・指示は、関係請負人だけでなく関係請負人の労働者もその対象となります。
ちなみに、製造業の元方事業者だけでなくすべての業種の元方事業者に適用されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-202
R2.6.20 選択式の練習/労働基準法の適用を除外されるのは?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労基法・適用除外」です。
労働基準法は、労働者を一人でも使用する事業に適用されます。
今日のテーマは労働基準法第116条の「適用除外」です。
ではどうぞ!
問題
第116条(適用除外)
① 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、< A >については、適用しない。
② この法律は、< B >及び家事使用人については、適用しない。
【選択肢】
① 船員法第1条第1項に規定する船員 ② 一般職の国家公務員
③ 一般職の地方公務員 ④ 行政執行法人の職員
⑤ 同居の親族を使用する事業 ⑥ 同居の親族のみを使用する事業

【解答】
A ① 船員法第1条第1項に規定する船員
船員法の船員には、労働基準法の総則(第1条~第11条)、適用除外、罰則は適用されますが、それ以外は適用除外です。
B ⑥ 同居の親族のみを使用する事業
同居の親族のみを使用する事業は労基法は適用除外ですが、同居の親族+他人を使用している事業は、労基法は適用です。
こちらもどうぞ!
①H20年出題
労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
②H16年出題
船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は適用されず、したがって、同法第1条「労働基準法の原則」、第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用されない。

【解答】
①H20年出題 〇
②H16年出題 ×
船員法の船員には、労働基準法の総則(第1条~第11条)は適用されます。
船員については、労基法は全面除外ではなく、適用される部分も一部あります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-201
R2.6.19 選択式の練習/確定拠出年金・脱退一時金
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「確定拠出年金・脱退一時金」です。
確定拠出年金法の給付は、「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」で、当分の間「脱退一時金」があります。
本日のテーマは「脱退一時金」です。
ではどうぞ!
問題1
個人型年金の脱退一時金
当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
①保険料免除者であること。
②< A >の受給権者でないこと。
③その者の通算拠出期間が1月以上< B >以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が< C >円以下であること。
④最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して < D >を経過していないこと。
⑤確定拠出年金法附則第2条の2第1項の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと
【選択肢】
① 障害年金 ② 老齢年金 ③ 障害給付金
④ 5年 ⑤ 3年 ⑥ 25年 ⑦ 6月 ⑧ 2年 ⑨ 3月
⑩ 25万円 ⑪ 1万5千円 ⑫ 50万円

【解答】
A ③ 障害給付金
B ⑤ 3年
C ⑩ 25万円
D ⑧ 2年
こちらもどうぞ!
個人型年金の脱退一時金の支給の請求は、個人型年金運用指図者にあっては厚生労働大臣に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、それぞれ行うものとする。

【解答】 ×
「厚生労働大臣」ではなく「個人型記録関連運営管理機関」に請求します。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-200
R2.6.18 選択式の練習/労働力調査の用語
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労働力調査の用語」です。
労働力調査とは、「労働力調査は、統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査であり、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としている。」 (総務省「労働力調査」出典)
労働力調査は総務省が実施しています。
ではどうぞ!
問題1
「労働力人口」とは就業者と< A >を合わせたものをいう。
【選択肢】
① 非労働力人口 ② 求職者 ③ 完全失業者

【解答】
A ③ 完全失業者
★ 労働力人口 は、既に仕事を持っている者(就業者)とこれから仕事を持とうと求職活動している者(完全失業者) の合計です。
問題2
 「労働力人口比率」とは、< B >に占める労働力人口の割合のこと
「労働力人口比率」とは、< B >に占める労働力人口の割合のこと
 「完全失業率」とは、< C >に占める完全失業者の割合のこと
「完全失業率」とは、< C >に占める完全失業者の割合のこと
【選択肢】
① 15 歳以上人口 ② 18歳以上人口 ③ 15歳以上65歳未満人口
④ 就業者 ⑤ 就労可能人口 ⑥ 労働力人口

【解答】
 B ① 15 歳以上人口
B ① 15 歳以上人口
 C ⑥ 労働力人口
C ⑥ 労働力人口
 就業者+失業者 → 労働力人口
就業者+失業者 → 労働力人口
15 歳以上人口のうち労働力人口以外の者 → 「非労働力人口」
 労働力人口比率(%) → 15 歳以上人口に占める就業者の割合
労働力人口比率(%) → 15 歳以上人口に占める就業者の割合
 完全失業率(%) → 労働力人口に占める完全失業者の割合
完全失業率(%) → 労働力人口に占める完全失業者の割合
★ 完全失業者は、労働力人口のうち実際には活用されていない部分です。完全失業率は、労働市場に供給されている人的資源活用の度合いを示す指標となります。
(注) 「労働力調査結果」(総務省統計局)の「労働力調査に用いている基本的諸概念と用語」を加工して作成しています。
https://www.stat.go.jp/data/roudou/10.html
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-199
R2.6.17 選択式の練習/遺族厚生年金の受給権の消滅(30歳未満の妻)
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「遺族厚生年金の受給権の消滅(30歳未満の妻)」です。
ではどうぞ!
問題
 遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時< A >未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、< B >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時< A >未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、< B >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
 遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が< A >に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、< C >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が< A >に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、< C >から起算して5年を経過したときに、消滅する。
【選択肢】
① 40歳 ② 60歳 ③ 30歳
④ 30歳に達した日 ⑤ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
⑥ 夫の死亡した日の翌日
⑦ 子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
⑧ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
⑨ 当該遺族基礎年金の受給権を取得した日

【解答】
A ③ 30歳
B ⑤ 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
C ⑧ 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
 について
について
夫の死亡当時30歳未満の妻
子なし(遺族基礎年金の受給権なし)
↓
遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年で遺族厚生年金の受給権は消滅
(夫の死亡時30歳未満の妻で子がいない場合、遺族厚生年金は5年で失権)
 について
について
夫の死亡当時、30歳未満の妻
子あり(遺族基礎年金の受給権あり)
↓
妻が30歳になる前に子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した
↓
遺族基礎年金の受給権が消滅した日か5年で遺族厚生年金の受給権は消滅
(妻が30歳未満で遺族基礎年金が失権した場合は、遺族基礎年金の失権から5年で遺族厚生年金は失権)
こちらもどうぞ!
H29年出題
遺族厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得した妻について、当該受給権の取得から1年後に子の死亡により当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合であって、当該消滅した日において妻が30歳に到達する日前であった場合は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに当該遺族厚生年金の受給権は消滅する。

【解答】 ×
遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年ではなく、「遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年」です。
 に当てはまるパターンです。
に当てはまるパターンです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-198
R2.6.16 選択式の練習/申請全額免除の要件
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「申請全額免除の要件」です。
ではどうぞ!
問題
<保険料の全額申請免除の要件>
被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の3免除、半額免除、4分の1免除の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。
<要件>
1. 保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から< A >月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額(扶養親族等の数に1を加えた数を< B >円に乗じて得た額に< C >円を加算した額)以下であるとき。
2. 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。
3. 地方税法に定める障害者又は寡婦であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額(< D >円)以下であるとき。
4. 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが、要件に該当しないときは、免除されない。
【選択肢】
① 22万 ② 25万 ③ 32万 ④ 35万 ⑤ 42万 ⑥ 50万 ⑦ 3 ⑧ 6 ⑨ 12
⑩ 65万 ⑪ 103万 ⑫ 125万

【解答】
A ⑧ 6
B ④ 35万
C ① 22万
全額免除の所得要件 → (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
所得要件は前年の所得で。(1月から6月までの間は、前々年の所得)
D ⑫ 125万
こちらもどうぞ!
①H24年出題
法第9条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
②H26年出題
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。

【解答】
①H24年出題 ×
本人、世帯主、配偶者が免除の要件に該当することが必要です。
②H26年出題 〇
全額免除の所得要件をあてはめてみると、
(4人+1)×35万円+22万円=197万円
夫の所得は197万円、妻の所得は0円なので全額免除の対象になります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-197
R2.6.15 選択式の練習/短時間労働者の健康保険の適用
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「短時間労働者の健康保険の適用」です。
・ 平成28年10月1日→ 特定適用事業の短時間労働者に対する適用のルール
・ 平成29年4月1日 → 任意特定適用事業所のルール
がそれぞれ始まりました。
ではどうぞ!
問題
<健康保険の被保険者資格の取得基準>
短時間労働者については、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の< A >以上である者は、健康保険の被保険者として取り扱う。
【選択肢】
① 2分の1 ② 3分の2 ③ 4分の3

【解答】
A ③ 4分の3
「4分の3基準」といいます。
こちらもどうぞ!
<4分の3基準を満たさない者について>
4分の3基準を満たさない者でも、次の①から⑤までの5つの要件を満たすものは、健康保険の被保険者として取り扱う。
① 1週間の所定労働時間が< B >時間以上であること
② 同一の事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること
③ 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が
< C >円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所に使用されていること
【選択肢】
① 10 ② 20 ③ 25
④ 58,000 ⑤ 88,000 ⑥ 98,000

【解答】
B ② 20
C ⑤ 88,000
では、こちらもどうぞ!
「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時< D >人を超えるものの各適用事業所をいう。
【選択肢】
① 300 ② 500 ③ 1,000

【解答】
D ② 500
ちなみに
「任意特定適用事業所」とは?
★ 被保険者数が常時 500 人以下でも、労使の合意に基づき申出をすることによって適用を受けることができます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-196
R2.6.14 労災保険率の決定
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「労災保険率の決定」です。
労災保険率は、事業の種類ごとに、1000分の2.5~1000分の88の間で定められています。今日のテーマは、労災保険率の決定ルールです。
では、どうぞ!
問題
労災保険率は、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに特別加入者に係る保険給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。

【解答】 ×
「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」ではなく、「二次健康診断等給付に要した費用の額」です。
こちらもどうぞ!
非業務災害率とは、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率をいう。

【解答】 〇
非業務災害率には、「通勤災害」の災害率と二次健康診断等給付の費用が反映されています。
労災保険率のうち、1000分の0.6が非業務災害率となります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-195
R2.6.13 選択式の練習/介護休業給付金の支給について
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護休業給付金の支給について」です。
介護休業給付金 → 被保険者が、対象家族を介護するための休業(「介護休業」という。)をした場合に支給されます。
ではどうぞ!
問題
介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の < A >に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の< A >に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。
この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の< A >に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
1. 同一の対象家族について当該被保険者が< B >回以上の介護休業をした場合における< B >回目以後の介護休業
2.同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が< C >に達した日後の介護休業
【選択肢】
① 100分の80 ② 100分の40 ③ 100分の67
④ 2 ⑤ 4 ⑥ 3
⑥ 30日 ⑦ 3か月 ⑧ 93日

【解答】
A ① 100分の80
★事業主から介護休業の期間を対象とした賃金を支払われた場合の扱い
・ (賃金の額+給付金の額)が賃金月額の80%に相当する額を超えるとき
→ 当該超えた額を減額して支給する(合計が80%になるように調整する)
・ 賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上となるとき
→ 給付金は不支給
※ちなみに、賃金月額とは、休業開始時賃金日額×支給日数のことです
B ⑤ 4
C ⑧ 93日
★ 同一の対象家族について、通算して 93 日を限度として 3 回までの介護休業給付金の支給が行われます。
介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、 同一対象家族について 4 回目以降の介護休業については、介護休業給付金の対象になりません。
こちらもどうぞ!
<H30年出題>
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給金を受給することができる。

【解答】 〇
例えば、母の介護で介護休業給付金の支給を受けた後、父の介護で介護休業を取得
する場合、父の介護休業開始日に受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-194
R2.6.12 選択式の練習/二次健康診断等給付の手続き
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「二次健康診断等給付の手続き」です。
二次健康診断等給付とは、
・ 一次健康診断で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常が あると診断された労働者が対象
・ 労働者の請求に基づいて、二次健康診断等給付(二次健康診断及び特定保健指導)が行われる
・ 労災病院又は都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所で、直接二次健康診断及び特定保健指導を給付。(現物給付です)
ではどうぞ!
問題
二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して< A >に提出しなければならない。
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から< B >以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から< B >以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業主は、当該二次健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
医師からの意見聴取は、当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業主に提出された日から< C >以内に行うこととされている。
【選択肢】
① 所轄労働基準監督署長 ② 都道府県知事
③ 所轄都道府県労働局長 ④ 1か月 ⑤ 3か月
⑥ 2か月 ⑦ 1年 ⑧ 2年 ⑨ 3年

【解答】
A ③ 所轄都道府県労働局長
「二次健康診断等給付」の事務は労働基準監督署長ではなく、都道府県労働局長が行います。
B ⑤ 3か月
C ⑥ 2か月
★ 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内
↓
二次健康診断の実施から3か月以内に結果を事業主に提出
↓
結果を証明する書面の提出から2か月以内に事業主は医師からの意見を聴取
ここからは安全衛生法です。安衛法と比較してみましょう!
労働安全衛生法では、健康診断の結果(異常の所見がある労働者に限る。)について、医師等から意見徴収を行うことが義務付けられています。
<健康診断の結果についての医師等からの意見聴取>
・ 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。
・ 深夜業従事者の自発的健康診については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。
※ 自発的健康診断の結果を証明する書面は、当該健康診断を受けた日から3か月以内に提出できます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-193
R2.6.11 選択式の練習/衛生委員会の構成
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「衛生委員会の構成」です。
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種問わず、衛生委員会を設置する必要があります。
今日のテーマは衛生委員会の構成メンバーです。
ではどうぞ!
問題
事業者は、全業種び常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。
衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、①の委員は、1人とする。
① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を< A >するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
② 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
③ < B >のうちから事業者が指名した者
④ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
⑤ 当該事業場の労働者で< C >であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
安全委員会の議長は、①の委員がなるものとする。
事業者は、①の委員以外の委員の< D >については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
【選択肢】
① 総括管理 ② 統括管理 ③ 代表
④ 安全管理者 ⑤作業環境測定士 ⑥ 安全衛生推進者
⑦ 衛生推進者 ⑧ 医師又は歯科医師 ⑨ 産業医
⑩ 医師又は保健師 ⑪ 4分の3 ⑫ 半数 ⑬ すべて

【解答】
A ② 統括管理
B ⑨ 産業医
C ⑤作業環境測定士
D ⑫ 半数
★Aについて
「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者」は、総括安全衛生管理者の選任がいらない事業場についての規定です。「これに準ずる者」とは、統括管理する者以外の者、例えば副所長などが該当します。
総括安全衛生管理者を選任する事業場 → 議長は総括安全衛生管理者
総括安全衛生管理者の選任がいらない事業場
→ 議長は、統括管理する者(所長など)か準ずる者(副所長など)
こちらもどうぞ!
<H16年出題>
労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。

【解答】 ×
委員の半数が間違いです。
議長(総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者)以外の委員の半数です。
議長以外の委員の半数です。議長は入らないので注意してください。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-192
R2.6.10 選択式の練習/就業規則と「就業規則に準ずるもの」
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「就業規則と「就業規則に準ずるもの」」です。
 フレックスタイム制について、労基法第32条の3では、「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については・・・(以下略)」
フレックスタイム制について、労基法第32条の3では、「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については・・・(以下略)」
と定められています。
フレックスタイム制は労働者の自主的な時間管理が前提ですので、「始業と終業の時刻は労働者が決定する」ことを就業規則その他これに準ずるもので約束しておくことが必要です。
今日のテーマは、「就業規則その他これに準ずるもの」の意味です。
ではどうぞ!
問題
常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、< A >により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。
(平成30年択一式の問題を参考に作成)
【選択肢】
① 就業規則その他これに準ずるもの ② 就業規則
③ 就業規則に準ずるもの

【解答】
A ② 就業規則
フレックスタイム制については、「就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねること」とするのが要件です。
10人以上の場合は就業規則の作成義務がありますので、「就業規則に準ずるもの」は使えません。問題文は10人以上の事業場ですので、「就業規則」によることが必要です。
こちらもどうぞ!
労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定すべきものである。

【解答】 〇
コアタイムやフレキシブルタイムは、設ける・設けないは任意ですが、そのような時間帯を設けるときには就業規則に規定する必要があります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-191
R2.6.9 選択式の練習/介護保険・都道府県知事or市町村長?
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険・都道府県知事or市町村長?」です。
 平成30年4月に、介護保険施設に「介護医療院」が加わりました。
平成30年4月に、介護保険施設に「介護医療院」が加わりました。
まずは、介護医療院を確認しましょう!
ではどうぞ!
問題
介護医療院を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
< A >を受けなければならない。
【選択肢】
① 市町村長の指定 ② 都道府県知事の指定 ③ 都道府県知事の許可

【解答】
A ③ 都道府県知事の許可
介護サービスを行う事業者や施設については、「市町村長の指定」を受けるパターン、「都道府県知事の指定」を受けるパターン、「都道府県知事の許可」を受けるパターンがあります。
介護医療院と同じく「都道府県知事の許可」を受けるパターンに該当するのは、「介護老人保健施設」です。
こちらもどうぞ!
介護医療院の許可は、< B >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
【選択肢】
① 5年 ② 6年 ③ 3年

【解答】
B ② 6年
ついでにもう一問どうぞ!
指定居宅介護支援事業者の指定は、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所ごとに、< C >が行う。
【選択肢】
① 市町村長 ② 都道府県知事 ③ 厚生労働大臣

【解答】
C ① 市町村長
ちなみに、こちらの指定の効力の有効期間も6年です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-190
R2.6.8 選択式の練習/労働政策総合推進法の目的条文
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労働政策総合推進法の目的条文」です。
 法律の題名は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」。略して労働政策総合推進法です。
法律の題名は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」。略して労働政策総合推進法です。
平成30年7月6日、「雇用対策法」から題名が改正されました。
目的条文を見てみましょう。
ではどうぞ!
問題
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、< A >に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の< B >に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに< C >の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
【選択肢】
① 雇用 ② 労働 ③ 職業
④ 適性 ⑤ 年齢 ⑥ 多様な事情
⑦ 労働生産性 ⑧ 職業能力 ⑨ 職場環境

【解答】
A ② 労働
雇用対策法の時代は「雇用」だった箇所です。労働政策総合推進法になって「労働」に変わりました。
B ⑥ 多様な事情
C ⑦ 労働生産性
こちらもどうぞ!
(事業主の責務)
事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が< D >を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。
【選択肢】
① 生活との調和 ② 職業生活と家庭生活の両立
③ 多様な就業形態

【解答】
D ① 生活との調和
「事業主の責務」に関する条文。職業生活の充実に対応するため、事業主の果たす役割は重要です。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現は、働き方改革のポイント。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-189
R2.6.7 選択式の練習/厚年・財政の現況及び見通しの作成
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「財政の現況及び見通しの作成」です。
 平成16年の年金改正で、「保険料水準固定方式」が導入されました。
平成16年の年金改正で、「保険料水準固定方式」が導入されました。
この方式のポイントは、
・ 最終的な保険料(保険料率)の水準を法律で定める
・ 給付はその負担の範囲内で行う
ことです。
そのため、給付水準は、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて、毎年度自動的に調整されています。
また、定期的にその時点の長期的な財政調整の見通しを作成し、給付水準の調整の必要の有無などを検証すること(財政検証)も平成16年の改正で導入された制度です。
ではどうぞ!
問題
(財政の現況及び見通しの作成)
政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び< A >の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね< B >とする。
政府は、財政の現況及び見通しを作成したときは、< C >、これを公表しなければならない。
(調整期間)
政府は、財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、< D >の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
(調整期間の開始年度)
調整期間の開始年度は、< D >とする。
【選択肢】
① 国庫補助 ② 積立金 ③ 国庫負担
④ 10年間 ⑤ 100年間 ⑥ 25年間
⑦ 遅滞なく ⑧ 10日以内に ⑨ 年度末までに
⑩ 保険料 ⑪ 保険給付 ⑫ 基礎年金拠出金
⑬ 平成16年度 ⑭ 平成17年度 ⑮ 平成18年度

【解答】
A ③ 国庫負担
B ⑤ 100年間
C ⑦ 遅滞なく
D ⑪ 保険給付
E ⑭ 平成17年度
こちらの問題もどうぞ!
この法律による< F >の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
【選択肢】
① 保険料 ② 年金たる保険給付 ③ 国庫負担

【解答】
F ② 年金たる保険給付
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-188
R2.6.6 選択式の練習/障害基礎年金の額の改定請求
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害基礎年金の額の改定請求」です。
ではどうぞ!
問題
(障害の程度が変わった場合の年金額の改定)
1 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が< A >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 2の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が< A >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して < B >を経過した日後でなければ行うことができない。
(改定の請求)
障害基礎年金の額の改定の請求は、一定事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
改定の請求の請求書には、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにする書類、当該請求書を提出する日前< C >以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書等を添えなければならない。
加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前< D >以内に作成された「加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本」、「加算額対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類」を添えなければならない。
【選択肢】
① 変化 ② 増進 ③ 軽減
④ 1年 ⑤ 1年6か月 ⑥ 3年 ⑦ 1月 ⑧ 2月
⑨ 3月 ⑩ 6月

【解答】
A ② 増進
B ④ 1年
C ⑨ 3月
D ⑦ 1月
★ 障害給付額改定請求書には、提出する日前1月以内の障害の状態を記入した診断書を添えることになっていましたが、令和元年8月より、提出する日前「3月」以内の障害の状態を記入した診断書を添えることに改正されました。
加算額対象者があるときの身分関係を明らかにすることができる証明書等は、提出する日前1月以内に作成されたものとなります。(変更なし)
こちらの問題もどうぞ!
<H26年出題>
障害基礎年金の額の改定請求は、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。

【解答】 〇
障害基礎年金の額の改定請求ができるのは、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後です。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年たつ前でも改定請求ができます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-187
R2.6.5 選択式の練習/任意継続被保険者の保険料の前納
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「任意継続被保険者の保険料の前納」です。
任意継続被保険者は保険料を前納することができます。
前納のルールは?
ではどうぞ!
問題
1. 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2・ 前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を< A >による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。
3・ 前納された保険料については、前納に係る期間の< B >ときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
【選択肢】
① 年5分の利率 ② 年4分の利率 ③ 年3分の利率
④ 各月の初日が到来した ⑤ 各月が経過した
⑥ 各月10日が到来した

【解答】
A ② 年4分の利率
B ④ 各月の初日が到来した
こちらの問題もどうぞ!
任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の< C >までに払い込まなければならない。
【選択肢】
① 初月の前月末日 ② 初月の末日 ③ 初月の10日

【解答】
C ① 初月の前月末日
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-186
R2.6.4 徴収法上の賃金
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「徴収法上の賃金」です。
労働者の労災保険、雇用保険の保険料は、労働者に支払う「賃金」をもとに計算します。
保険料の計算ベースになる「賃金」の定義を確認しましょう。
では、どうぞ!
問題
労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいうが、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金には含まれない。

【解答】 ×
労働基準法で定める休業手当は賃金ですので、労働保険料を計算する際の賃金総額に算入します。
問題2
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲)
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、< A >の定めるところによる。
【選択肢】
① 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
② 厚生労働大臣

【解答】 A ① 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
賃金には、「通貨以外のもの(現物給与のこと)であって、厚生労働省令で定めるもの」も含まれます。
算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)の範囲は、徴収法施行規則で、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」と規定されています。
現物給与で賃金に算入されるのは、①食事の利益、②被服の利益、③住居の利益、④所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるもの、です。
問題3
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

【解答】 〇
現物給与の評価額は、「厚生労働大臣」が定めることになっています。
ちなみに、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化推進のため、
健康保険法でも「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。」となっています。(健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。)
厚生年金保険法も同様に現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることになっています。
(参考)雇用保険法はちょっと違います。
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
雇用保険法では、評価額は公共職業安定所長が定めるとされています。さらっと読むだけでOKです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-185
R2.6.3 選択式の練習/雇用保険・国庫負担
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「雇用保険・国庫負担」です。
雇用保険事業は、事業主と被保険者から徴収した保険料と国庫負担(税金)で賄われています。
今日のテーマは「国庫負担」です。
ではどうぞ!
問題
国庫は、求職者給付(< A >を除く。)及び雇用継続給付(< B >に限る。)、< C >並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
【選択肢】
① 高年齢雇用継続給付 ② 就職促進給付 ③ 高年齢求職者給付金
④ 高年齢雇用継続基本給付金 ⑤ 高年齢再就職給付金
⑥ 介護休業給付金 ⑦ 育児休業給付 ⑧ 教育訓練給付
⑨ 日雇労働求職者給付金

【解答】
A ③ 高年齢求職者給付金
B ⑥ 介護休業給付金
C ⑦ 育児休業給付
 「雇用継続給付」のうち国庫負担が行われるのは、「介護休業給付金」のみです。
「雇用継続給付」のうち国庫負担が行われるのは、「介護休業給付金」のみです。
 改正で失業等給付から切り離された「育児休業給付」の国庫負担は原則として8分の1です。
改正で失業等給付から切り離された「育児休業給付」の国庫負担は原則として8分の1です。
こちらもどうぞ!
<H22年出題>
教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が負担するものとされている。

【解答】 ×
教育訓練給付に要する費用には国庫負担はありません。
 ポイント!
ポイント!
「国庫負担がないもの」は?
・求職者給付のうち「高年齢求職者給付金」
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付のうち「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」
・雇用安定事業
・能力開発事業
→ ※就職支援法事業については国庫負担あり
こちらもどうぞ!
①<R1年出題>
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
②<H24年出題>
雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。

【解答】
①<R1年出題> 〇
②<H24年出題> 〇
就職支援法事業の国庫負担について
・ 就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金の費用を除く。)
→ 予算の範囲内で国庫が負担
・ 就職支援法事業の職業訓練受講給付金に要する費用
→ 国庫が2分の1(平成29年度から令和3年度までの各年度は2分の1の100分の10)を負担
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-184
R2.6.2 選択式の練習/業務上の疾病と通勤による疾病を比較
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「業務上の疾病と通勤による疾病を比較」がテーマです。
「業務上の疾病」と「通勤による疾病」、違いは?
ではどうぞ!
問題
業務上の疾病の範囲は、< A >別表第一の二に掲げる疾病とする。
通勤による疾病の範囲は、< B >第18条の5に、「通勤による負傷に起因する疾病その他< C >」と定めらている。
【選択肢】
① 労働基準法施行規則 ② 労働基準法 ③ 労働安全衛生規則
④ 労働者災害補償保険法 ⑤ 労働者災害補償保険法施行令
⑥ 労働者災害補償保険法施行規則
⑦ 業務に起因することの明らかな疾病
⑧ 通勤に起因することの明らかな疾病
⑨ 通勤と因果関係のある疾病

【解答】
A ① 労働基準法施行規則
B ⑥ 労働者災害補償保険法施行規則
C ⑧ 通勤に起因することの明らかな疾病
労災保険法は、もともとは労働基準法の使用者の災害補償義務を代行するためにできた保険なので、「業務上の疾病の範囲」は労働基準法施行規則に規定されています。
一方、「通勤」については、労働基準法上の補償義務はありませんので、疾病の範囲は労働者災害補償保険法施行規則に規定されています。
もう少し比較してみましょう
①<H21年出題>
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。
②<H20年出題>
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。

【解答】
①<H21年出題> 〇
業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二各号(第1号から第11号のどれか)に該当しないと業務上の疾病になりません。別表第1の2は職業病リストのようなものだと思ってください。
②<H20年出題> ×
上記で勉強しましたように、通勤による疾病は、厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)で、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されているだけです。業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定を準用するというルールはありません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-183
R2.6.1 選択式の練習/機械等の設置等の計画の届出
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「機械等の設置等の計画の届出」です。
※ 危険又は有害な作業を必要とする機械等(例えばボイラーなど)を事業場に設置するときは、労働者の安全衛生を守るため、労働基準監督署長に事前に設置等の計画を届け出ることになっています。
ではどうぞ!
問題
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の< A >に、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
ただし、第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が、< B >した事業者については、この限りでない。
【選択肢】
① 開始の日の14日前まで ② 開始の日以後30日以内
③ 開始の日の30日前まで ④ 許可 ⑤ 認定 ⑥ 承認

【解答】
A ③ 開始の日の30日前まで
B ⑤ 認定
 危険若しくは有害な作業を必要とする機械等の設置、移転、変更しようとするときは、事前にその計画を所轄労働基準監督署長に届け出しなければなりません。
危険若しくは有害な作業を必要とする機械等の設置、移転、変更しようとするときは、事前にその計画を所轄労働基準監督署長に届け出しなければなりません。
 ただし、労働安全衛生マネジメントシステムを適正に実施していると労働基準監督署長が認定した事業場は、計画の届出義務が免除されます。
ただし、労働安全衛生マネジメントシステムを適正に実施していると労働基準監督署長が認定した事業場は、計画の届出義務が免除されます。
こちらもどうぞ!
↑上記の問題で勉強しましたように、
「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動」を適切に実施しているなどの要件に適合し所轄労働基準監督署長から認定を受けた事業者は、機械等の設置等の計画の届出義務が免除されます。
では、次は、その「認定の有効期間」と「実施状況の報告義務」を見ていきましょう。
(認定の有効期間)
労働基準監督署長の認定は、< C >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(実施状況等の報告)
労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、 < D >以内ごとに1回、実施状況等報告書に第87条の措置(労働安全衛生マネジメントシステム)の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【選択肢】
① 6か月 ② 1年 ③ 2年 ④ 3年
⑤ 5年 ⑥ 10年

【解答】
C ④ 3年
→ 認定には有効期間がありますので、3年ごとの更新が必要です。
D ② 1年
→ 認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに報告が必要です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-182
R2.5.31 選択式の練習/災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働」です。
時間外労働・休日労働をさせることができるのは、
・ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合
・ 公務のために臨時の必要がある場合
・ 36協定を締結し行政官庁に届け出た場合
です。
ではどうぞ!
問題
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その< A >において第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、< B >のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
【選択肢】
① 許可の範囲 ② 労使協定の範囲 ③ 必要の限度
④ 事態急迫 ⑤ 非常事態 ⑥ 緊急事態

【解答】
A ③ 必要の限度
B ④ 事態急迫
 事後に遅滞なく届出があった場合 → 行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
事後に遅滞なく届出があった場合 → 行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
こちらもどうぞ!
<H22年出題>
労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度におい行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。

【解答】 〇
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-181
R2.5.30 選択式の練習/社会保障協定
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「社会保障協定」からです。
日本と外国との間で、外国に派遣される日本人がいる一方、外国から日本に派遣される外国人もいて、それに伴い問題も生じています。
一つ目は、「二重加入」の問題。例えば、日本から相手国に派遣されて就労している場合、日本でも相手国でも二重に公的年金に加入し、保険料も二重に支払うケースがあること。
二つ目は、「年金受給資格」の問題。外国の公的年金に加入したとしても、その国の老齢年金の受給資格要件を満たせず、支払った保険料が掛け捨てになるケースがあること。
このような問題を解決する仕組みが社会保障協定です。
ではどうぞ!
問題
 社会保障協定発行済みの国は?
社会保障協定発行済みの国は?
| 発効日 | |
| 2000年2月1日(平成12年) | < A > |
| 2001年2月1日(平成13年) | 英国 |
| 2005年4月1日(平成17年) | 韓国 |
| 2005年10月1日(平成17年) | アメリカ |
| 2007年1月1日(平成19年) | ベルギー |
| 2007年6月1日(平成19年) | フランス |
| 2008年3月1日(平成20年) | カナダ |
| 2009年1月1日(平成21年) | オーストラリア |
| 2009年3月1日(平成21年) | オランダ |
| 2009年6月1日(平成21年) | チェコ |
| 2010年12月1日(平成22年) | スペイン |
| 2010年12月1日(平成22年) | アイルランド |
| 2012年3月1日(平成24年) | ブラジル |
| 2012年3月1日(平成24年) | スイス |
| 2014年1月1日(平成26年) | ハンガリー |
| 2016年10月1日(平成28年) | インド |
| 2017年8月1日(平成29年) | ルクセンブルク |
| 2018年8月1日(平成30年) | フィリピン |
| 2019年7月1日(令和元年) | < B > |
| 2019年9月1日(令和元年) | < C > |
【選択肢】
① インドネシア ② オーストリア ③ ドイツ
④ スロバキア ⑤ ノルウェー ⑥ ベトナム
⑦ メキシコ ⑧ 中国 ⑨ マレーシア

【解答】
A ③ ドイツ
B ④ スロバキア
C ⑧ 中国
我が国初の年金通算協定はドイツとの間で締結されました。
2019年度(令和元年度)は、スロバキアとの間、中国との間に社会保障協定が発効しました。
現在、20か国との間で社会保障協定が発効されています。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-180
R2.5.29 選択式の練習/労働時間等設定改善指針より
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「労働時間等設定改善指針」からです。
平成31年4月(去年ですが)に労働時間等設定改善法が改正されました。
労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)も平成31年4月に改正されています。
少しだけ目を通しておきましょう。
ではどうぞ!
問題
 労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)より(抜粋)
労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)より(抜粋)
労使の真摯な取組により労働時間の短縮は着実に進み、近年は、過去に労働時間短縮の目標として掲げられてきた年間総実労働時間1,800時間< A >で推移している。
年次有給休暇の取得率は< B >状態である。さらに、長い労働時間等の業務に起因した脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高水準で推移している。そして、急速な少子高齢化、労働者の意識や抱える事情の多様化等が進んでいる。
< C > (前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することをいう。 )は、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、労働者の健康の保持や仕事と生活の調和を図るために有効であることから、その導入に努めること。なお、当該一定時間を設定するに際しては、労働者の通勤時間、交替制勤務等の勤務形態や勤務実態等を十分に考慮し、仕事と生活の両立が可能な実効性ある休息が確保されるよう配慮すること。
【選択肢】
① にほぼ近い水準である、おおむね1,800時間台前半
② を下回る、おおむね1,700時間台前半
③ を大きく下回る、おおむね1,600時間台前半
④ 5割を下回った
⑤ 6割を上回る
⑥ 上昇傾向の
⑦ 勤務間インターバル ⑧ テレワーク ⑨ ノー残業デー

【解答】
A ② を下回る、おおむね1,700時間台前半
B ④ 5割を下回った
C ⑦ 勤務間インターバル
★労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)より抜粋しました。
補足です
BとCの文章の間に、「しかしながら、その内実を見ると、全労働者平均の労働時間が短縮した原因は、主に、労働時間が短い者の割合が増加した結果であり、いわゆる正社員等については 2,000時間前後で推移しており、依然として労働時間は短縮していない。一方、労働時間が長い者と短い者の割合が共に増加し、いわゆる「労働時間分布の長短二極化」が進展している。」という文章が入ります。
厚生労働省のホームページには、労働時間等見直しガイドラインについて、
「事業主のみなさまに労働時間等の見直しに向けて取り組んでいただくにあたり、参考としていただきたい事項を記載したもの」との記載があり、続けて、「指針に書いていない労働者の抱える事情への配慮や取組の具体的内容についても、労使でよく話し合ってご検討ください。」とあります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-179
R2.5.28 選択式の練習/配偶者加給年金額の特別加算
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「配偶者加給年金額の特別加算」です。
一定の要件を満たした場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
加給年金額の対象になるのは、生計維持関係のある65歳未満の配偶者又は子ですが、配偶者加給年金額には、特別加算がプラスされることもあります。
「特別加算」がプラスされる要件は?
ではどうぞ!
問題1
< A >年4月2日以後に生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が加算される。
【選択肢】
① 大正15 ② 昭和9 ③ 昭和4

【解答】② 昭和9
配偶者加給年金額に特別加算が行われるのは、生年月日が昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者です。
問題2
< B >に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、165,800円に改定率を乗じて得た額である。
【選択肢】
① 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間
② 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間
③ 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間
④ 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間
⑤ 昭和18年4月2日以後

【解答】
B ⑤ 昭和18年4月2日以後
ポイント!
昭和18年4月2日以後生まれの老齢厚生年金の受給権者の配偶者加給年金額の特別加算は、生年月日に関係なく一律165,800円×改定率です。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれの受給権者の特別加算の額は、33,200円×改定率で、段階的に多くなります。昭和18年4月2日以後生まれからの額が一番多いのがポイントです。
こちらもどうぞ
<H28年出題>
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

【解答】 ×
特別加算は、配偶者の生年月日ではなく、受給権者の生年月日に応じて加算されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-178
R2.5.27 選択式の練習/令和2年度の年金額
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「令和2年度の年金額」です。
ではどうぞ!
問題
老齢基礎年金の額は、780,900円に< A >を乗じて得た額(その額に < B >ものとする。)とする。
ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする。)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
1. 保険料納付済期間の月数
2. 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の7に相当する月数
3.保険料4分の1免除期間の月数から2.に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
4.保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の3に相当する月数
5.保険料半額免除期間の月数から4.に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
6.保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数
7.保険料4分の3免除期間の月数から6.に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
8.保険料全額免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の < C >に相当する月数
【選択肢】
① 物価変動率 ② 名目手取り賃金変動率 ③ 改定率
④ 5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる
⑤ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
⑥ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる
⑦ 2分の1 ⑧ 3分の1 ⑨ 4分の1

【解答】
A ③ 改定率
B ⑤ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
C ⑦ 2分の1
ポイント!
老齢基礎年金を計算する際、「全額免除期間」の月数は2分の1で計算します。
ただし、全額免除期間のうち、「学生納付特例の期間」と「50歳未満の納付猶予期間」は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入しますが、老齢基礎年金の額の計算には算入しませんので、注意してください。
ちなみに、令和2年度の年金額は??
基礎年金は、「780,900円×改定率」で計算します。
令和2年度の年金額は、780,900円×< D > = < E >円です。
【選択肢】
① 1.001 ② 0.999 ③ 1.003
④ 781,700 ⑤ 780,100 ⑥ 783,200

【解答】
C ① 1.001 令和2年度の改定率は「1.001」です。
D ④ 781,700
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-177
R2.5.26 選択式の練習/健保・国庫負担
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「健保・国庫負担」です。
ではどうぞ!
問 題
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の< A >(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する< A >を含む。)の執行に要する費用を負担する。
< B >に対して交付する国庫負担金は、各< B >における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
< B >に対して交付する国庫負担金については、概算払をすることができる。
【選択肢】
① 業務 ② 事務 ③ 職務
④ 健康保険組合 ⑤ 全国健康保険協会 ⑥ 市町村

【解答】
A ② 事務
B ④ 健康保険組合
健康保険の事業運営のための「事務費」については、予算の範囲内で、国庫が負担しています。(全国健康保険協会、健康保険組合を問わず、事務費は国庫が負担します。)
健康保険組合に対する国庫負担金は、被保険者数を基準に算定します。
こちらの問題もどうぞ!
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数と総報酬額の総額を基準として、厚生労働大臣が算定する。

【解答】 ×
算定の基準は、「被保険者数と総報酬額の総額」ではなく、「被保険者数」です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-176
R2.5.25 令和2年度の雇用保険率
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「令和2年度の雇用保険率」です。
では、どうぞ!
問題
①<H26年出題(アレンジ)>
雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、令和2年度の雇用保険率は、一般の事業では、1000分の8とされている。
②<H30年出題(アレンジ)>
建設の事業における令和2年度の雇用保険率は、令和元年度と同じく、1000分の11である。

【解答】
①<H26年出題(アレンジ)> ×
一般の事業の令和2年度の雇用保険率は、1000分の9です。(令和元年度と同率)
②<H30年出題(アレンジ)> ×
建設の事業の令和2年度の雇用保険率は、1000分の12です。(令和元年度と同率)
こちらもどうぞ!
<R1年出題>
一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。

【解答】 ×
雇用保険料率は、①一般の事業、②農林水産、清酒製造業、③建設の事業の3つのグループに分けて設定されています。
問題文の「園芸サービスの事業」は一般の事業のグループに入りますので、この問題は×となります。
ポイント!
園芸サービス、⽜⾺の育成、酪農、養鶏、養豚、内⽔⾯養殖、特定の船員を雇用する 事業 → 一般の事業の雇用保険率(1000分の9)が適⽤されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-175
R2.5.24 選択式の練習/常用就職支度手当の支給対象者
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「常用就職支度手当の支給対象者」です。
ではどうぞ!
問 題
常用就職支度手当は、安定した職業に就いた受給資格者等であって、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが対象です。
常用就職支度手当の対象になる受給資格者等とは?
↓
・ 受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の< A >である者に限る。)
・ 高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して< B >を経過していないものを含む。)
・ 特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して< C >を経過していないものを含む。)
・ < D >(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。)
【選択肢】
① 3分の1以上 ② 3分の1未満 ③ 3分の1以下
④ 3か月 ⑤ 6か月 ⑥ 50日 ⑦ 90日 ⑧ 1年
⑨ 4年 ⑩ 日雇労働被保険者 ⑪ 日雇受給資格者
⑫ 日雇労働者

【解答】
A ② 3分の1未満
B ⑧ 1年
C ⑤ 6か月
D ⑪ 日雇受給資格者
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-174
R2.5.23 選択式の練習/介護(補償)給付の支給額
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「介護(補償)給付の支給額」です。
ではどうぞ!
問 題
介護補償給付は、< A >を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する< A >の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< B >介護を要する状態にあり、かつ、< B >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< C >に対し、その請求に基づいて行う。
【選択肢】
① 障害補償給付又は傷病補償年金 ② 休業補償給付又は傷病補償年金
③ 障害補償年金又は傷病補償年金 ④ 常時 ⑤ 常態として
⑥ 常時又は随時 ⑦ 介護を行う者 ⑧ 当該労働者
⑨ 事業主

【解答】
A ③ 障害補償年金又は傷病補償年金
B ⑥ 常時又は随時
C ⑧ 当該労働者
こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。

【解答】 〇
介護補償給付は「介護の費用として支出した額(実費)」が支給されますが、最高限度額と最低保障額が設定されています。
「最低保障額」の注意点をどうぞ
<H25年出題>
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。

【解答】 〇
この問題のポイントは、「支給すべき事由が生じた月」の部分です。
介護費用を支払って介護を受け始めた月(支給すべき事由が生じた月)は、最低保障額は適用されず、実際に支払った実費が支給されます。
 最低保障額が適用されるポイントは、親族等(親族又は知人、友人)の介護を受けていることです。
最低保障額が適用されるポイントは、親族等(親族又は知人、友人)の介護を受けていることです。
例えば、常時介護の場合
親族等の介護を 受けている | 支出した介護費用がゼロ | 72,990円(最低保障)注意1 |
| 支出した費用が72,990円未満 | 72,990円(最低保障)注意2 | |
| 支出した費用が72,990円超えている | 実際に支出した費用 (ただし、 上限は166,950円) | |
親族等の介護を 受けていない | 実際に支出した費用 (ただし、 上限は166,950円) ※最低保障額の適用なし |
注意1について
→ 介護を受け始めた月は、最低保障が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(最低保障額は翌月から適用されます。)
注意2について
→ 介護を受け始めた月は、最低保障が適用されないので、実際に支出した額となります。(最低保障額は翌月から適用されます。)
 ちなみに、上記の平成25年の問題は、
ちなみに、上記の平成25年の問題は、
・ 親族等による介護を受けている + 実際に支出した額が72,990円未満だった
↓
・ 原則は最低保障額の72,990円が支給されるが、問題の前提が「支給すべき事由が生じた月」となっている
↓
・ 「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額は適用されない
↓
・ 「支給すべき事由が生じた月」なので、最低保障額ではなく「介護に要する費用として支出された額」(実際に払った額)が支給される=支給されるのは72,990円未満の実際に支払った額
という流れです。
「随時」介護の場合は、上限83,480円、最低保障額36,500円です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-173
R2.5.22 選択式の練習/新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の面接指導
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の面接指導」です。
 労働基準法には、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)の規定が設けられていますが、「新技術・新商品等の研究開発業務」については、上限規制の適用が除外されています。
労働基準法には、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)の規定が設けられていますが、「新技術・新商品等の研究開発業務」については、上限規制の適用が除外されています。
そのため健康の保持が必要。
労働安全衛生法では、時間外・休日労働時間が一定時間を超えた新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者対しては、面接指導を行うことが義務付けられています。
ではどうぞ!
問 題
事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間※を超える労働者(新技術・新商品等の研究開発業務に従事する者に限る。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
 厚生労働省令で定める時間※とは?
厚生労働省令で定める時間※とは?
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間とする。
【選択肢】
① 45 ② 80 ③ 100

【解答】
A ③ 100
ポイント!
時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える新技術・新商品等の研究開発業務従事に対する医師による面接指導のポイント
・労働者からの申し出がなくても、事業者には行う義務あり
・行わなかった場合、罰則の適用あり
続きをどうぞ
<新技術・新商品等の研究開発業務に従事する者の面接指導実施後の措置>
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、< A >、< B >の付与、労働時間の短縮、< C >等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【選択肢】
① 作業の転換 ② 業務の転換 ③ 職務内容の変更
④ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)
⑤ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を含む。)
⑥ 特別休暇
⑦ 勤務間インターバルの導入
⑧ 育児・介護を行う労働者への配慮
⑨ 深夜業の回数の減少

【解答】
A ③ 職務内容の変更
B ④ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)
C ⑨ 深夜業の回数の減少
 「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」と比較してみてください。
「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」と比較してみてください。
こちらの記事をどうぞ → R2.5.12 選択式の練習/高プロ対象労働者の面接指導
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-172
R2.5.21 選択式の練習/時間外、休日、深夜の割増賃金の率
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「時間外、休日、深夜の割増賃金の率」です。
ではどうぞ!
問 題
使用者が、法33条又は36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、
< A >又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ< B >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について< C >時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、< A >の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、 < A >の賃金の計算額の< D >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【選択肢】
① 通常の労働時間 ② 法定労働時間 ③ 平均的な労働時間
④ 厚生労働省令で定める率 ⑤ 就業規則その他これに準ずるもので定める率
⑥ 政令で定める率 ⑦ 45 ⑧ 60 ⑨ 80
⑩ 3割5分 ⑪ 2割5分 ⑫ 5割

【解答】
A ① 通常の労働時間
B⑥ 政令で定める率
C ⑧ 60
D ⑪ 2割5分
ポイント!
Bの「政令で定める率」について
→ 時間外及び休日の割増率は「政令」で具体的に定められています。
「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で
・時間外労働については2割5分
・休日労働については3割5分
と定められています。
 ちなみに
ちなみに
政令は「内閣」が、省令は「大臣」が制定します。
こちらの問題もどうぞ
<H29年出題>
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

【解答】 ×
休日は原則として暦日で考えます。休日には法定労働時間の概念がないので、8時間を超えたとしても休日割増の3割5分以上のみで計算します。
しかし、休日労働が深夜の時間帯になったときは、3割5分(休日割増)+2割5分(深夜割増)=6割以上で計算します。
体に負担のかかる深夜の時間帯の労働については、別枠で割増をプラスするという考え方です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-171
R2.5.20 選択式の練習/確定拠出年金・中小事業主掛金納付制度(iDeCo+)
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、確定拠出年金法です。
テーマは、平成30年5月にスタートした「中小事業主掛金納付制度」です。
「iDeCo+」(イデコプラス)と呼ばれるこの制度は、
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している従業員の掛金に、事業主が掛金を追加して拠出できる制度です。
ではどうぞ!
問 題
 iDeCo+を導入できる事業主の要件
iDeCo+を導入できる事業主の要件
中小事業主※は、その使用する第1号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が個人型年金加入者掛金を拠出する場合(< A >納付を行う場合に限る。)は、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第1号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、< B >、定期的に、掛金を拠出することができる。
※中小事業主の定義
企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない厚生年金適用事業所の事業主であって、その使用する第1号厚生年金被保険者の数が< C >人以下のものをいう。
【選択肢】
① 滞納することなく ② 自ら直接 ③ 当該中小事業主を介して
④ 毎月1回以上 ⑤ 年1回以上 ⑥ 終身にわたり
⑦ 100 ⑧ 300 ⑨ 1000

【解答】
A ③ 当該中小事業主を介して
B⑤ 年1回以上
C ⑦ 100
iDeCo+のポイント!
・ 企業型年金及び確定給付企業年金を実施していない中小企業が対象(従業員100人以下に限る)
・ 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している従業員の掛金に追加して、掛金を拠出できる(中小事業主が掛金が拠出されることに同意した者が対象)
・ 事業主の掛金と従業員の掛金との合計は、月額23,000円
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-170
R2.5.19 選択式の練習/労働組合法
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労働組合法」です。
ではどうぞ!
問 題
<労働組合>
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他< A >の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、次に該当するものは、この限りでない。
一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ< B >、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する < B >その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
【選択肢】
① 社会的地位 ② 経済的地位 ③ 労働者の福祉
④ 監督的地位にある労働者 ⑤ 役職者
⑥ 機密の事務を取り扱う者

【解答】
A ② 経済的地位
B④ 監督的地位にある労働者
こちらの問題もどうぞ!
労働組合法における「労働者」とは、職業の種類を問わず、< C >をいう。
【選択肢】
① 賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者
② 事業に使用される者で、賃金を支払われる者
③ 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者

【解答】
① 賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-169
R2.5.18 選択式の練習/障害厚生年金の最低保障額
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害厚生年金の最低保障額」です。
障害厚生年金の額は、
平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 被保険者期間の月数
で計算します。
 被保険者期間の月数が300に満たないとき → 300で計算する
被保険者期間の月数が300に満たないとき → 300で計算する
 障害等級1級の障害厚生年金の額 → 100分の125に相当する額となる
障害等級1級の障害厚生年金の額 → 100分の125に相当する額となる
 障害等級1級又は2級 → 受給権者により生計を維持している65未満の配偶者がある → 加給年金額が加算される
障害等級1級又は2級 → 受給権者により生計を維持している65未満の配偶者がある → 加給年金額が加算される
 今日のテーマ
今日のテーマ
障害厚生年金に最低保障額が適用されるのはどんなときでしょう?
ではどうぞ!
問 題
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に< A >を乗じて得た額(その額に< B >ものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【選択肢】
① 2分の1 ② 3分の2 ③ 4分の3
④ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
⑤ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる
⑥ 5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる

【解答】
障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額についての問題です。
A ③ 4分の3
B④ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
ポイント
障害基礎年金を受けることができない場合は、障害厚生年金の額に最低保障額が適用されます。
→ → 障害基礎年金を受けることができない場合は次の2つです。
・ 障害等級3級の場合
・ 初診日に「厚生年金保険の被保険者だけど、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がある」場合、障害厚生年金は受給できます。しかし、初診日に国民年金の第2号被保険者ではないので、障害等級1級・2級でも障害基礎年金は受給できません。
こちらの問題もどうぞ!
 令和2年度障害厚生年金の最低保障額は?
令和2年度障害厚生年金の最低保障額は?
計算式
↓
< C >円 × 4分の3 = < D >円
【選択肢】
① 780,900 ② 977,125 ③ 781,700
④ 585,700 ⑤ 732,800 ⑥ 586,300

【解答】
C ③ 781,700
D ⑥ 586,300
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-168
R2.5.17 選択式の練習/(改正)国年・強制加入被保険者
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「強制加入被保険者」です。
国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの区分があります。
令和2年4月1日より、第1号被保険者と第3号被保険者の要件が改正されました。
ではどうぞ!
問 題
■第1号被保険者■
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満
 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない
第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない
 第1号被保険者から除外される者
第1号被保険者から除外される者
・ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者
・ この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
■第2号被保険者■
 厚生年金保険の被保険者
厚生年金保険の被保険者
■第3号被保険者■
 第2号被保険者の配偶者
第2号被保険者の配偶者
 主として第2号被保険者の収入により生計を維持する(被扶養配偶者)
主として第2号被保険者の収入により生計を維持する(被扶養配偶者)
 20歳以上60歳未満
20歳以上60歳未満
 < A >を有する者
< A >を有する者
又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る
 第3号被保険者から除外される者
第3号被保険者から除外される者
・ 第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
【選択肢】
① 日本国内に所得 ② 日本国内に住所 ③ 日本国内で職業

【解答】
A ② 日本国内に住所
ポイント
令和2年4月1日より、第3号被保険者については「国内居住要件」が付くことになりました。
<例外> 海外に居住していても渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、特例で第3号被保険者となります。
 「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、第1号被保険者、第3号被保険者から適用除外されます。
「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、第1号被保険者、第3号被保険者から適用除外されます。
適用除外として厚生労働省令で定める者は
↓
① 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの → 在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)
② 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの → 在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」
こちらの問題もどうぞ!
<R元年出題>
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

【解答】 ×
| 国籍要件 | 国内居住要件 | 年齢要件 (20歳以上60歳未満) | |
| 第1号被保険者 | なし | あり | あり |
| 第2号被保険者 | なし | なし(原則65歳未満) | |
| 第3号被保険者 | あり(例外あり) | あり |
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-167
R2.5.16 選択式の練習/(改正)被扶養者の認定要件
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「被扶養者の認定要件」です。
令和2年4月1日改正です。
ではどうぞ!
問 題
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者(省略)で、< A >を有するもの又は外国において留学をする学生その他の< A >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
【選択肢】
① 日本国内に所得 ② 日本国内に住所 ③ 日本国内で職業

【解答】
A ② 日本国内に住所
ポイント
令和2年4月1日より、被扶養者の認定要件に「国内居住要件」が追加になりました。
 例 外
例 外
海外に居住していても、留学中の学生など日本国内に生活の基礎があると認められる者は、被扶養者として認められる例外があります。
↓
(海外居住でも例外的に被扶養者と認められる者)
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められるもの
⑤ ①から④までの他、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
こちらの問題もどうぞ!
<H28年出題アレンジ>
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、日本国内に住所を有し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。

【解答】 ○
後期高齢者医療の被保険者は、被扶養者にはなりません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-166
R2.5.15 労働保険事務組合の責任
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「労働保険事務組合の責任」です。
労働保険事務組合の責任についてテーマごとに確認しましょう。
問題1
<テーマ>
労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主が、
↓
労働保険料等の納付のため、
↓
金銭を事務組合に交付した
↓
そのときの事務組合の責任は??
<H17年出題>
事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。

【解答】 ○
事業主は労働保険料納付のための金銭を事務組合に委託した。事務組合は委託された金額の限度で、政府にその労働保険料を納付する責任がある、ということです。
「その交付を受けた金額の限度で」の部分がポイントです。
問題2
<テーマ>
例えば、確定保険料を申告するにあたり、事業主は事務組合に賃金総額などを報告していた
↓
にもかかわらず、事務組合は確定保険料申告書を提出していなかった
↓
その結果、政府が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することになった
↓
そのときの事務組合の責任は??
<H15年出題>
事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。

【解答】 ×
この問題の場合、追徴金が徴収されるのは、事業主が賃金等の報告をしなかったことが原因。事務組合にはその責めに帰すべき理由がない、と問題文に書かれていますので、事務組合は追徴金納付の責は負いません。
(事務組合の責に帰すべき理由がある場合は、納付の責を負います。)
問題3
<テーマ>
では、労働保険料その他の徴収金納付の金銭を事務組合に交付した事業主は
↓
その後は全ての責任を免れるのでしょうか?
<H29年出題>
委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

【解答】 ×
上の2問で勉強したように、「事業主が労働保険料納付のための金銭を事務組合に交付した」、「事務組合の責に帰すべき理由によって追徴金や延滞金が課された」。このような場合、事務組合が納付の責を負います。
しかし、事務組合に滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限って、事業主も納付の責任を負うことがあります。
なお、問題文の「当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる」という規定はありません。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-165
R2.5.14 選択式の練習/(改正)雇用保険の目的
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「雇用保険の目的」です。
第201回国会で成立しました。
令和2年4月1日改正の目的条文などを確認しましょう。
ではどうぞ!
問 題
第1条(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< A >に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条(雇用保険事業)
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、< B >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
【選択肢】
① 対象家族を介護するための休業をした場合
② 子を養育するための休業をした場合
③ 高齢期に就業した場合
④ 失業等給付
⑤ 失業等給付及び雇用継続給付
⑥ 失業等給付及び育児休業給付

【解答】
A ② 子を養育するための休業をした場合
B ⑥ 失業等給付及び育児休業給付
ポイント
<改正前>
育児休業給付は「失業等給付」の中に位置づけ。
雇用保険事業は「失業等給付」と「雇用保険二事業」。
↓
 <改正後>
<改正後>
・育児休業給付は失業等給付から独立しました。
・雇用保険事業は、「失業等給付」、「育児休業給付」、「雇用保険二事業」という体系になりました。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-164
R2.5.13 選択式の練習/特別加入者の保険給付
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、特別加入者の保険給付です。
労災保険法の対象は、労働基準法上の労働者です。そして属地主義をとっていますので、国内で使用される人が対象です。
しかし、労働者でなくても、中小事業主や一人親方等は特別加入することができますし、海外に派遣されている人も同様です。
特別加入すれば、原則として労働者と同じ補償が受けられます。
しかし、労働者と特別加入者でルールが違うところもいくつかあります。
その「違う」ルールをおさえるのが勉強のポイントです。
ではどうぞ!
問 題
第1種特別加入者(中小事業主等)の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、< A >。
【選択肢】
① その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる
② 当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる
③ その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる

【解答】 A ② 当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる
ポイント
 保険料を滞納しているのも、事故にあったのも中小事業主本人で、「保険給付を行う」→「その後その費用を徴収する」という手続きをとるのは合理的ではありません。
保険料を滞納しているのも、事故にあったのも中小事業主本人で、「保険給付を行う」→「その後その費用を徴収する」という手続きをとるのは合理的ではありません。
ですので、特別加入者の場合は、保険給付の支給制限(全部又は一部を行わないことができる)という方法をとっています。
(一人親方等、海外派遣者も同じ方法です。)
比較しましょう
<H20年出題>
事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

【解答】 ○
保険関係の成立の届出をしていない、保険料を納付していないのは、事業主の責任で、労働者に非はありません。
ですので、この場合は、労働者に対する保険給付の支給制限を行う方法はとらず、事業主から費用を徴収する方法をとります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-163
R2.5.12 選択式の練習/高プロ対象労働者の面接指導
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、高度プロフェッショナル制度の対象労働者の面接指導です。
昨日は、労働基準法の高プロ対象者の「健康福祉確保措置等」がテーマでした。
昨日の記事 → R2.5.11 選択式の練習/高プロ・健康福祉確保措置等
労働安全衛生法では、高プロ対象労働者の健康保持のため、面接指導の実施が規定されています。
ではどうぞ!
問 題
 高プロ対象労働者への面接指導
高プロ対象労働者への面接指導
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(高度プロフェッショナル制度の対象労働者)であって、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり< A >時間を超えるものに対し、医師による面接指導を行わなければならない。
【選択肢】
① 45 ② 80 ③ 100 ④ 120

【解答】 A ③ 100
ポイント
 健康管理時間とは(労基法第41条の2)
健康管理時間とは(労基法第41条の2)
対象労働者が事業場内にいた時間 + 事業場外において労働した時間 の合計
※ 事業場内にいた時間から、休憩時間など労働していない時間を除くことを労使委員会で決議することできます。
 健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導は、事業者の義務です。対象労働者本人からの申出は不要です。
健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導は、事業者の義務です。対象労働者本人からの申出は不要です。
 健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導を実施しなかった場合は、罰則が適用されます。
健康管理時間の超過時間が1か月100時間を超えた高プロ対象労働者に対する面接指導を実施しなかった場合は、罰則が適用されます。
 高プロ対象労働者の面接指導実施後の措置
高プロ対象労働者の面接指導実施後の措置
事業者は、 による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
その事後措置について
↓
事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、< B >、有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、< C >等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
【選択肢】
① 就業場所の変更 ② 作業の転換 ③ 職務内容の変更 ④ 健康管理時間が短縮されるための配慮 ⑤ 労働時間の短縮 ⑥ 深夜業の回数の減少

【解答】
B ③ 職務内容の変更
C ④ 健康管理時間が短縮されるための配慮
ポイント
「長時間労働者に対する面接指導」の事後措置、「新技術・新商品等の研究開発業務に就く労働者に対する面接指導」の事後措置と、項目が違いますので注意してください。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-162
R2.5.11 選択式の練習/高プロ・健康福祉確保措置等
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、高度プロフェッショナル制度の健康福祉確保措置等です。
→ 高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定が適用されません。
頑張りすぎて健康を害することのないようするため、高プロを運用する過程で、健康・福祉確保措置等を講ずる必要があります。
ではどうぞ!
問 題
 健康管理時間の把握
健康管理時間の把握
対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(労使委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間(=休憩時間その他対象労働者が労働していない時間)を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法※に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
※厚生労働省令で定める方法
タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法とする。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、< A >によることができる。
【選択肢】
① 勤務間インターバル ② 自己申告 ③ 上司の確認

【解答】 A ② 自己申告
ポイント
対象労働者の健康管理時間を把握することと把握方法
 休日の確保
休日の確保
対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ< B >日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
【選択肢】
① 103 ② 104 ③ 105

【解答】 B ② 104
ポイント
対象労働者には、年間104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与える
 選択的措置
選択的措置
対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
イ 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに< C >時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜の時刻の間において労働させる回数を1箇月について < D >以内とすること。
ロ 健康管理時間を1箇月又は3箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
※ 厚生労働省令で定める時間
1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、
・ 1箇月 100時間
・ 3箇月 240時間
ハ 1年に1回以上の継続した2週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(使用者が当該期間において、第39条の規定による有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く。)について、休日を与えること。
ニ 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断(厚生労働省令で定める項目を含むものに限る。)を実施すること。
【選択肢】
① 10 ② 11 ③ 12 ④13
⑤ 3回 ⑥ 4回 ⑦ 5回 ⑧ 6回

【解答】 C ② 11 D ⑥ 4回
ポイント
イ~ニのいずれかを決議で定めて実施する
イ → 勤務間インターバルの確保(11時間以上)、深夜業の回数の制限
ロ → 健康管理時間の上限
ハ → 1年間に継続2週間以上の休日を与える(本人が請求した場合は連続1週間を2回以上)
二 → 臨時の健康診断
 健康管理時間の状況に応じた健康・確保措置
健康管理時間の状況に応じた健康・確保措置
対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇(第39条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
※ 厚生労働省令で定める措置
①  に掲げるいずれかの措置(
に掲げるいずれかの措置( で使用者が講ずることとした措置以外のもの)
で使用者が講ずることとした措置以外のもの)
② 健康管理時間が一定時間を超える対象労働者に対し、医師による面接指導を行う
③ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与する
④ 対象労働者の心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する
⑤ 対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をする
⑥ 産業医等による助言若しくは指導を受け、又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせる
※①~⑥の措置の中から決議で定め、実施する必要があります。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(介護保険法)
R2-161
R2.5.10 選択式の練習/介護保険・公費による負担
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険法の公費の負担」です。
介護給付・予防給付に要する費用の半分は、被保険者の保険料で賄われていますが、残りの半分は公費で負担しています。
その「公費」については、国・都道府県・市町村それぞれの負担割合が決まっています。
ではどうぞ!
平成27年択一式を参照しました。
問 題
市町村又は特別区は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の< A >に相当する額を負担する。
【選択肢】
①100分の12.5 ②100分の25 ③2分の1 ④3分の1

【解答】 A ①100分の12.5
もう一問どうぞ!
(H19年択一式を参照しています)
介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその< B >に相当する額を負担する。
【選択肢】
①100分の12.5 ②100分の20 ③100分の25 ④3分の1

【解答】 B ②100分の20
ポイント!
国 → 介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の20を負担+調整交付金(100分の5)を交付
ちなみに、都道府県は、介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の12.5を負担しています。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(パートタイム・有期雇用労働法)
R2-160
R2.5.9 選択式の練習/(改正)パート有期雇用労働法
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「パート有期雇用労働法」の改正点です。
パートタイム労働法(正式名称「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が、令和2年4月1日より、パートタイム・有期雇用労働法(正式名称「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)に改正されました。
(中小企業は令和3年4月1日施行です。)
ではどうぞ!
問 題
第8条
事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う< A >に照らして適切と認められるものを考慮して、< B >。
【選択肢】
①理由 ②目的 ③必要 ④態様
⑤不利益な取扱いをしてはならない ⑥差別的取扱いをしてはならない
⑦合理的に取り扱わなければならない
⑧不合理と認められる相違を設けてはならない

【解答】
A ②目的 B ⑧不合理と認められる相違を設けてはならない
ポイント
同じ企業の通常の労働者(一般的に言う正社員)と、非正規雇用労働者(短時間労働者・有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差の解消のための取組です。
 第8条は、「均衡待遇規定」(待遇について不合理な差を設けることを禁止)です。
第8条は、「均衡待遇規定」(待遇について不合理な差を設けることを禁止)です。
均衡とはバランスのこと。待遇を同一にしなければならないということではありません。
①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の違いに応じた範囲で、待遇を決めてください、ということです。
→ 同じ企業の正社員と「短時間労働者・有期雇用労働者」とで待遇の違いがある場合、働き方や役割などが違うからそれに合わせた待遇の違いだと説明できればいいですが、それができない場合、待遇の差が不合理だと判断される可能性があります。
ちなみに、第9条は、「均等待遇規定」(差別的取扱いの禁止)です。
第9条
事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。
→ ①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲が、正社員と同じ短時間労働者・有期雇用労働者については、待遇について差別的に取り扱うことが禁止されています。
(①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲が正社員と同じなら、待遇についても同じにしてくださいということです。(均等待遇))
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-159
R2.5.8 選択式の練習/老厚・報酬比例部分の計算ルール
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「老齢厚生年金の報酬比例部分」のルールです。
ではどうぞ!
問 題
老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式
被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の< A >に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
【選択肢】
①5.125 ②5.481 ③7.125 ④7.5

【解答】
A ②5.481
※給付乗率の1000分の5.481は、昭和21年4月1日以前生まれの者は、生年月日に応じた読み替えがあります。(生年月日が古い方が乗率が高く設定されています。)
こちらの問題もどうぞ
報酬比例部分の「平均標準報酬額」とは?
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、< B >を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
【選択肢】
①改定率 ②再評価率 ③調整率 ④マクロ経済スライド率

【解答】 ②再評価率
平均標準報酬額とは、簡単に言うと、新入社員時代から退職までの在職中の標準報酬月額と標準賞与額を全部合算して、厚年に加入した月数で割った額のことです。
しかし、例えば同じ10,000円でも、40年前の新入社員時代と現在では価値がちがいます。過去の賃金を現在の水準に読み替えるために使う率のことを「再評価率」といいます。
再評価率は、性年度別に設定されていて、毎年度自動的に改定されます。
もう一問どうぞ!
再評価率の改定の仕組み(H18年出題)
※調整期間以外の期間
■新規裁定者(< C >歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、原則として< D >を基準とした再評価率を用い、既裁定者(< C >歳到達年度以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として前年の< E >を基準とした再評価率を用いる。
【選択肢】
①消費者物価指数 ②名目手取り賃金変動率 ③実質賃金変動率
④名目賃金変動率 ⑤物価変動率 ⑥65 ⑦68 ⑧70

【解答】
C ⑦68 D ②名目手取り賃金変動率 E ⑤物価変動率
参 考
国民年金の基礎年金は、毎年度「改定率」を改定することによって、年金額を見直しますが、国民年金の「改定率」と厚生年金保険の「再評価率」の改定の仕組みは同じです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-158
R2.5.7 選択式の練習/令和2年度の国民年金保険料
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「令和2年度の国民年金の保険料」です。
ではどうぞ!
問 題
令和2年度の保険料の額
→ 17,000円 × < A >
【選択肢】
①名目賃金変動率 ②名目手取り賃金変動率 ③物価変動率 ④改定率 ⑤保険料改定率

【解答】
A ⑤保険料改定率
こちらの問題もどうぞ
保険料改定率の計算式は、
前年度の保険料改定率 × < B >です。
【選択肢】
①名目賃金変動率 ②名目手取り賃金変動率 ③物価変動率 ④改定率

【解答】 ①名目賃金変動率
名目賃金変動率 → 前々年の物価変動率 ×4年前の年度の実質賃金変動率
もう一問どうぞ!
令和2年度の保険料の計算式
17,000円 × < C > ≒ < D >円
【選択肢】
①0.967 ②0.965 ③0.973 ④16,340 ⑤16,410 ⑥16,540

【解答】
C ③0.973 D ⑥16,540
※ 5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-157
R2.5.6 選択式の練習/入院時食事療養費について
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、健康保険法「入院時食事療養費」です。
★平成27年の択一式をアレンジしています。
ではどうぞ。
問 題
入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき < A >円※とされているが、被保険者及び被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき< B >円とされている。
※難病、小児慢性特定疾病の患者は除く
【選択肢】
①100 ②160 ③210 ④260 ⑤360 ⑥460

【解答】
A ⑥460 B ①100
食事療養標準負担額 → 入院した際の食費のうち、被保険者本人が負担するもの。
こちらの問題もどうぞ
<H23年出題>
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。

【解答】 ×
中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額ではなく、「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額です。
※厚生労働大臣は、基準を定めようとするときは、「中央社会保険医療協議会に諮問」するとされています。
ポイント!
入院時食事療養費は、食費について定めた「基準額」から、被保険者が負担する「食事療養標準負担額」を控除した額です。
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

【解答】 ○
ポイント!
入院時食事療養費は、現物給付です。
※ 本来は、被保険者が病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用を、保険者が被保険者に代わって病院又は診療所に直接支払う方式です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-156
R2.5.5 請負事業の一括
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
問題
<H26年出題>
立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、労働保険徴収法の規定の適用については、それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。

【解答】 ×
「請負事業の一括」の対象は、建設の事業のみ。立木の伐採の事業は対象外です。
ポイント
元請負人→下請け→孫請け・・・と数次の請負で行われる建設の事業の保険関係は、元請負人のみを適用事業主として成立します。
下請負人の保険関係は、元請負人に当然に一括されます。(認可などの手続きは要りません。)
★下請負事業の分離については「認可」が必要。こちらの記事をどうぞ
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H26年出題>
労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみが当該事業の事業主とされることなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。

【解答】 ○
請負事業の一括は、労災保険の保険関係だけが対象です。
雇用保険の保険関係については一括されず、原則通り、各事業ごと(元請けは元請けで、下請けは下請けで、孫請けは孫請けで)に適用されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-155
R2.5.4 選択式の練習/高年齢雇用継続基本給付金の額
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、雇用保険法「高年齢雇用継続基本給付金の額」です。
★平成27年の択一式をアレンジしています。
ではどうぞ。
問 題
高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、当該支給対象月に支払われた賃金の額に< A >を乗じて得た額となる。
【選択肢】
①100分の6 ②100分の7 ③100分の9 ④100分の15 ⑤100分の25

【解答】
A ④100分の15
こちらの問題もどうぞ
<H22年出題>
高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

【解答】 ○
ポイント!
支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳時点の賃金(みなし賃金日額×30)の61%未満の場合は、
→ 給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額×15%で計算します。
ただし、
計算した給付金の額+賃金の額が支給限度額(363,359円)を超える場合は、
→ 給付金の額は、支給限度額(363,359円)-賃金の額となります。
※賃金の額+給付金が363,359円になるように、給付金の額を調整します。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-154
R2.5.3 選択式の練習/事業主に対する費用徴収
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、労災法「事業主に対する費用徴収」です。
<参 考> 法第31条
政府は、次の①~③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
① 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出をしていない期間中に生じた事故
② 事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故
③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
今日は、「故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出をしていない」の「故意」又は「重大な過失」の認定についての問題です。
★平成27年の択一式をアレンジしています。
ではどうぞ。
問 題
 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を< A >%とする。
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を< A >%とする。
 事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を< B >%とする。
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を< B >%とする。
【選択肢】
①30 ②40 ③50 ④60 ⑤70 ⑥80 ⑦90 ⑧100

【解答】
A⑧100 B ②40
こちらの問題もどうぞ!
<H27年出題>
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。

【解答】 ○
ポイント!
「保険関係成立届の提出をしていない期間中に生じた事故」について
★ 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けた
→ にもかかわらず10日以内に提出していなかった
→ 「故意」と認定
→ 費用徴収率100%
★ 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない
→ 保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった
→ 「重大な過失」と認定
→ 費用徴収率40%
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-153
R2.5.2 選択式の練習/安衛・事業者の講ずべき措置
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、安衛法「事業者の講ずべき措置」です。
問 題
労働安全衛生法第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の< A >の保持のため必要な措置を講じなければならない。
【選択肢】
①安全、風紀及び健康 ②健康、安全及び風紀 ③健康、風紀及び生命
④安全、生命及び地位

【解答】
A③健康、風紀及び生命
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働基準法)
R2-152
R2.5.1 選択式の練習/高度プロフェッショナル制度の対象労働者
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「高度プロフェッショナル制度」です。
問 題
〔高度プロフェッショナル制度の対象労働者〕
 と
と のいずれにも該当すること
のいずれにも該当すること
 使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき < A >が明確に定められていること。
使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき < A >が明確に定められていること。
 厚生労働省令で定める方法 → 次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
厚生労働省令で定める方法 → 次に掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付を受ける方法(当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録の提供を受ける方法)とする。
①業務の内容
②責任の程度
③< A >において求められる< B >その他の< A >を遂行するに当たって求められる水準
 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が< C >の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が< C >の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること。
 厚生労働省令で定める額 → < D >万円
厚生労働省令で定める額 → < D >万円
【選択肢】
①職務 ②職務遂行能力 ③結果 ④成果 ⑤能力 ⑥職制 ⑦評価 ⑧基準 ⑨平均給与額 ⑩基準年間平均賃金 ⑪基準給与 ⑫基準年間平均給与額 ⑬1,080 ⑭1,075 ⑮1,095 ⑯885

【解答】
A①職務 B ④成果 C ⑫基準年間平均給与額
D ⑭1,075
基準年間平均給与額=厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額のこと
社労士受験のあれこれ
選択式対策(社保一般常識)
R2-151
R2.4.30 選択式の練習/厚生労働白書・介護保険制度
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「平成28年版 厚生労働白書」からの問題です。
問 題
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとしての介護保険制度を創設することとし、< A >年に介護保険法が施行された。
制度の基本的な考え方は、自立支援、利用者本位、< B >の3つである。具体的には、自立支援とは、単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者ができるだけ自立した生活を送れるよう支援することを理念とするものである。また、利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービスや福祉サービスを総合的に受けられる制度とした。さらに給付と負担の関係が明確な< B >を採用した
【選択肢】
①2000(平成12) ②2003(平成15) ③1986(昭和61)
④税方式 ⑤診療報酬方式 ⑥皆保険方式 ⑦社会保険方式

【解答】
A①2000(平成12) B ⑦社会保険方式
(H28年厚生労働白書 第3章「高齢期を支える医療・介護制度」より)
★ 問題文にあるように、社会保険方式の特徴は、「給付と負担の関係が明確」であることです。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働一般常識)
R2-150
R2.4.29 選択式の練習/最近の労務管理用語
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「平成30年版 労働経済白書」からの問題です。
問 題
労働者のモチベーションや労働生産性に関連し、「< A >」といった考え方に注目が集まっている。 「< A >」とは、オランダのユトレヒト大学のSchaufeli教授らが提唱した概念であり、島津(2014)によると、「仕事に誇りや、やりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)、「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力) の3つが揃った状態として定義されている。
【選択肢】
①ワーカホリズム ②ワーク・エンゲイジメント ③バーンアウト
④職務満足感

【解答】 ②ワーク・エンゲイジメント
平成30年版労働経済白書 ―働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について―を基に作成した問題です。
ワーク・エンゲイジメントの概念については、「ワーク・エンゲイジメントが労働者の健康・仕事のパフォーマンス等へ与える影響」というタイトルのコラムで紹介されています。
※ ちなみに、問題文に出てくる「島津」さんについては、「島津明人(2014)「ワーク・エンゲイジメント―ポジティブ・メンタルヘルスで活力ある毎日を―」(労働調査会)」との注釈がついています。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(厚生年金保険法)
R2-149
R2.4.28 選択式の練習/在職老齢年金の計算
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、問題です。
※平成27年択一式を選択式にアレンジしています。
問 題
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、支給停止後の年金月額は< A >円(加給年金額を除く。)となる。
<選択肢>
①105,000 ②10,000 ③190,000 ④95,000

【解答】 ④95,000
「特別支給の老齢厚生年金」ですので、60歳代前半の在老の計算式を使います。
問題文の条件だと、
・基本月額+総報酬月額相当額>28万円で、
基本月額≦28万円、総報酬月額相当額≦47万円です。
支給停止基準額の計算式は
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×2分の1となります。
実際に数字を当てはめましょう。
総報酬月額相当額は24万円+(60万円÷12)=29万円です。
支給停止月額は、
(29万円+20万円-28万円)×2分の1=105,000円となります。
支給停止後の年金月額は、200,000円-105,000円=95,000円となります。
※支給停止される額と、支給される額を間違えないようにしましょう。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H24年出題>
60歳代前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。

【解答】 ×
基本月額は老齢厚生年金の額÷12で計算しますが、その際加給年金額は除いて計算します。
在老の仕組みで老齢厚生年金が一部カットされても、加給年金額はそのまま加算されます。(老齢厚生年金が全額支給停止の場合は、加給年金額も全額支給停止になります。)
社労士受験のあれこれ
選択式対策(国民年金法)
R2-148
R2.4.27 選択式の練習/老齢基礎年金の計算
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、問題です。
※平成28年択一式を選択式にアレンジしています。
問 題
昭和30年4月8日生まれの男性の年金加入歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給できる年金額及び計算式の空欄を埋めてください。
※振替加算は考慮しなくていい
※年金額は令和2年度価額で計算
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月
■計算式
781,700円 × < A >/480月 + < B >
■年金額
< C >円
<選択肢>
①456月 ②180月 ③420月
④8500円 ⑤200円×36月 ⑥400円×36月
⑦691,188 ⑧691,200 ⑨691,088

【解答】
A ③420月 B ⑤200円×36月 C ⑦691,188
年金給付の額は、50銭未満切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H27年出題>
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

【解答】 ○
200円×300月で計算します。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(健康保険法)
R2-147
R2.4.26 選択式の練習/健保・保険給付の制限
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、問題です。
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る< A >。
保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書の提出等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、< B >。
【選択肢】
①保険給付は行わない ②保険給付を行わないことができる
③保険給付の一部を行わないことができる
④保険給付の全部又は一部を行わないことができる

【解答】
A ①保険給付は行わない
B ④保険給付の全部又は一部を行わないことができる
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H22年出題>
保険者は、被保険者または被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 ×
全部又は一部を行わないことができる、ではなく、「一部」を行わないことができる、です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-146
R2.4.25 労働保険料の還付請求と充当
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
問題
<H29年出題>
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

【解答】 ×
事業主による充当についての承認は不要ですが、当該事業主への充当後の通知は必要です。
ポイント
概算保険料 > 確定保険料の場合
・事業主が還付請求をした場合 → 還付
・事業主が還付請求をしない場合 → 充当
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
①<H24年出題>
継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。
②<R1年出題>
事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
①<H24年出題> ○
還付請求が行われないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が充当します。
②<R1年出題> ×
労働保険料還付請求書の提出先は、「官署支出官」又は「所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(所轄都道府県労働局資金前渡官吏)です。
ちなみに、充当するは、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(雇用保険法)
R2-145
R2.4.24 選択式の練習/教育訓練給付
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
★教育訓練には、①一般教育訓練、②特定一般教育訓練、③専門実践教育訓練の3つがあります。
では、どうぞ。
問題
教育訓練給付金の額は、
教育訓練給付対象者が教育訓練の受講のために支払った費用の額×厚生労働省令で定める率
で算定します。
「厚生労働省令で定める率」をそれぞれ埋めてください。
1 一般教育訓練を受け、修了した者 < A >
2 特定一般教育訓練を受け、修了した者 < B >
3-1 専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(3-2に掲げる者を除く。) < C >
3-2 専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者として雇用された者 < D >

【解答】
A 100分の20 B 100分の40 C 100分の50 D 100分の70
 択一式もどうぞ!
択一式もどうぞ!
<H28年出題>
教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【解答】 ○
チェックポイントは、「1か月」前までにです。
雇用保険法は、「提出期限」は暗記必須です。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労災保険法)
R2-144
R2.4.23 選択式の練習/心理的負荷による精神障害の認定基準について
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、どうぞ。
今日は「心理的負荷による精神障害の認定基準について」からです。
問題
 認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
 認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を< B >どう受け止めるかという観点から評価されるものであるとされている。
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を< B >どう受け止めるかという観点から評価されるものであるとされている。
 認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね< A >の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として< C >に区分することとされている。
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね< A >の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として< C >に区分することとされている。
【選択肢】
①1か月 ②3か月 ③6か月 ④1年
⑤労働者本人が主観的に ⑥同種の労働者が一般的に ⑦医師が医学的に ⑧所轄労働基準監督署長が客観的に
⑨「強」、「弱」の2段階 ⑩「A」、「B」、「C」、「D」の4段階 ⑪「強」、「中」、「弱」の3段階

【解答】
A ③6か月 B ⑥同種の労働者が一般的に
C ⑪「強」、「中」、「弱」の3段階
★Bについて
「強い心理的負荷」とは
精神障害を発病した労働者がその出来事及 び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるもの。
なお、「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似す る者のこと。
 択一式もどうぞ!
択一式もどうぞ!
①<H30年出題>
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
②<H27年出題>
認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシャルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。

【解答】
① × 120時間ではなく「160時間」です。
② × 主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されます。
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労働安全衛生法)
R2-143
R2.4.22 安衛法/選択式の練習
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、どうぞ。
問題1
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は< A >その他< B >、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
【選択肢】
①作業方法 ②作業環境 ③作業行動 ④作業手順
⑤業務に起因して ⑥業務遂行中に ⑦就業時間中に ⑧事業場内で

【解答】
A ③作業行動 B⑤業務に起因して
 択一式もどうぞ!
択一式もどうぞ!
<H28年出題>
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
選択式対策(労基法)
R2-142
R2.4.21 労働基準法/選択式の練習
今日から、選択式の練習問題に入ります。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、どうぞ。
問題1
労働基準法第4条は、< A >について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、< A >以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
【選択肢】
①雇入れ ②定年 ③賃金 ④ 退職理由
問題2
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、< B >及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは含まれない。
【選択肢】
①通勤手当 ②家族手当 ③臨時に支払われた賃金 ④割増賃金
問題3
労基法24条1項本文は、いわゆる賃金全額払いの原則を定めており、賃金の控除を禁止しているが、右原則の趣旨とするところは、使用者により賃金が一方的に控除されることを禁止し、もって労働者に賃金の全額を受領させ、労働者の < C >をはかろうとするものであるから、その趣旨に鑑みると、使用者が労働者の同意を得て相殺により賃金を控除することは、それが< D >に基づくものである限り、右賃金全額払いの原則によって禁止されるものではないと解するのが相当である。
【選択肢】
①生活保障 ②経済生活の安定 ③雇用の安定 ④経済の発展
⑤労働者の完全な自由意思 ⑥労働協約 ⑦就業規則 ⑧労使協定

【解答】
A ③賃金
B ③臨時に支払われた賃金
C ②経済生活の安定
D ⑤労働者の完全な自由意思
問題3は「日新製鋼事件」より。
 択一式もどうぞ!
択一式もどうぞ!
①<H25年出題>
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
②<H27年出題>
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
③<H30年出題>
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。

【解答】
① ○
② ×
通勤手当及び家族手当は、平均賃金の計算の際の賃金総額に含まれます。
③ ○
日新製鋼事件です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社保一般常識)
R2-141
R2.4.20 平成29年国民年金被保険者実態調査結果の概要より
平成28年に、「平成26年国民年金被保険者実態調査結果の概要」から出題がありました。
今日は、平成29年版の国民年金被保険者実態調査結果の概要をもとに、解説します。
 (H28年出題)出題当時はH26年版でしたが、H29年版に改定しています。
(H28年出題)出題当時はH26年版でしたが、H29年版に改定しています。
厚生労働省から平成31年3月に公表された「平成29年国民年金被保険者実態調査結果の概要」によると、平成27年度及び平成28年度の納付対象月の国民年金保険料を全く納付していない者(平成28年度末に申請全額免除、学生納付特例又は若年者納付猶予を受けていた者を除く。)が納付しない理由は、「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が約7割と最も高くなっている。

【解答】 ○
<参考>
・すべての年齢階級で「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が最も高い。
・ 次いで高いのは、
20歳代→「うっかりして忘れた、後でまとめて払おうと思った」の割合
30歳代→「年金制度の将来が不安・信用できない」の割合
40歳代及び 50歳代前半→「納める保険料に比べて、十分な年金額が受け取れないと思う」の割合
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働一般常識)
R2-140
R2.4.19 平成30年若年者雇用実態調査より
平成28年に、「平成25年若年者雇用実態調査(厚生労働省)」の調査結果から出題がありました。
今日は、平成30年版の若年者雇用実態調査をもとに、解説します。
解いてみてくださいね。
 (H28年出題)
(H28年出題)
若年正社員労働者の定着のために実施している対策をみると、「職場での意思疎通の向上」が最も高くなっている。

【解答】 ○
平成30年若年者雇用実態調査によると、若年正社員労働者の定着のために実施している対策(複数回答)では、「職場での意思疎通の向上」が最も高いです。正社員以外の若年労働者も同様です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-139
R2.4.18 遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の「死亡した者」の要件は次の4つです。
 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む。)が、死亡したとき。
 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。
老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

 、
、 の場合は、保険料納付要件を満たす必要があります。
の場合は、保険料納付要件を満たす必要があります。
 (H28年出題)当時の問題文を改正に合わせて改定しています。
(H28年出題)当時の問題文を改正に合わせて改定しています。
次の記述のうち、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるものはいくつあるか。
ア 20歳未満の厚生年金保険の被保険者が死亡した場合。
イ 保険料納付要件を満たしている被保険者が行方不明となり、その後失踪の宣告を受けた場合。
ウ 国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算してが25年以上あるものとする)。
エ 保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合。
オ 63歳の厚生年金保険の被保険者が令和2年4月に死亡した場合であって、死亡日の前日において、その者について国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満であり、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満であるが、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者であった場合。

【解答】 5つとも○
 アについて
アについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
厚生年金保険の被保険者だったら、年齢は関係ありません。
 イについて
イについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
「被保険者の死亡」には「失踪の宣告を受けた者であって、行方不明となった当時被保険者であったもの」も含みます。
なお、失踪宣告を受けた場合、保険料納付要件、生計維持関係、被保険者資格は、行方不明になった日を死亡日として取り扱うことになっています。
問題文の場合、行方不明になった時点で「保険料納付要件を満たしている被保険者」ですので、要件を満たしています。
 ウについて
ウについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
厚生年金保険の被保険者になったことがなくても、離婚時みなし被保険者期間のみで老齢厚生年金の受給権を得ることがあります。
そのような人が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金が支給されることがあります。
 エについて
エについて
 に当てはまります。
に当てはまります。
初診日から起算して5年を経過する日前に死亡がポイントです。
「資格喪失日から5年」に間違えないようにしてくださいね。
 オについて
オについて
問題文の注目ポイントは
・ 63歳の厚生年金保険の被保険者が死亡した →  に該当する
に該当する
・保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満である → 25年未満なので には当てはまらない
には当てはまらない
 の場合、保険料納付要件を満たす必要があります。
の場合、保険料納付要件を満たす必要があります。
問題文の場合、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2未満、となっていますので、原則の保険料納付要件は満たしていません。
しかし、現在63歳で、60歳から継続して厚生年金保険の被保険者である、とのことなので、死亡日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないことになるので、特例が適用できます。(令和8年4月1日前、かつ65歳未満)
こちらの問題もどうぞ!
<R1年出題>
障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、遺族厚生年金の支給要件について、死亡した当該受給権者の保険料納付要件が問われることはない。

【解答】 ○
 に当てはまります。
に当てはまります。
保険料納付要件は問われません。(既に障害厚生年金の受給資格を満たしているので、遺族厚生年金の保険料納付要件は問わない。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-138
R2.4.17 障害基礎年金の保険料納付要件
障害基礎年金の受給要件は次の3つです。
 初診日
初診日
①初診日に被保険者である。
②被保険者であった者で、日本国内に住所有、60歳以上65歳未満
 保険料納付要件
保険料納付要件
初診日の前日に初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上ある
 障害認定日
障害認定日
初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日)に障害等級に該当する程度の障害の状態にある
障害等級 → 1級又は2級
 (H28年出題)
(H28年出題)
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

【解答】 ×
障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」でみます。問題文の場合、22歳の誕生月に全額免除の申請をし、さかのぼって保険料全額免除期間となりましたが、初診日の前日の時点では、被保険者期間のすべてが滞納期間です。
ですので、保険料納付要件を満たしていないので、障害基礎年金の受給権は発生しません。
こちらの問題もどうぞ!
<H22年出題>
初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。

【解答】 ×
平成22年7月分までの1年間ではなく、平成22年6月分までの1年間です。
★初診日が令和8年4月1日前にある場合の特例(初診日に65歳未満であること)
→ 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、保険料納付要件を満たす。
初診日の属する月の前々月までの1年間ですので、平成22年6月までの1年間となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-137
R2.4.16 産前産後休業を終了した際の改定
産前産後休業を終了したときに、例えば、子育てのため残業が無くなったなどの理由で以前より報酬が下がることがあります。
このような場合、標準報酬月額の改定の対象になるでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。

【解答】 ○
産前産後休業を終了した際の改定(育児休業等を終了した際の改定も)については、固定的賃金の変動は必須要件ではありません。
<比較>随時改定は、固定的賃金が変動することが条件です。残業手当の減少だけでは対象になりません。
| 随時改定 | 育児休業等終了時の改定 産前産後休業終了時の改定 |
| 固定的賃金が変動した | 固定的賃金の変動がなくてもOK |
| 原則として2等級以上の差が生じた | 1等級でもOK |
| 報酬支払基礎日数17日以上の月が3月継続している | 17日未満の月は除く |
こちらの問題もどうぞ!
<H25年出題>
育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

【解答】 ×
17日未満の月がある場合は、その月を除いて平均を出し、改定を行います。
随時改定と比較しておさえてくださいね。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-136
R2.4.15 労働保険/有期事業とは?
徴収法には、「継続事業」と「有期事業」という概念が登場します。
改めて、「有期事業」の定義を確認しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。

【解答】 ×
徴収法上の有期事業は、建設の事業と立木の伐採の事業です。ビルが建ったらそこで事業が終了する建設現場などを想像していただければOKです。
なお、有期事業は労災保険の保険関係だけのもので、雇用保険の保険関係には有期事業の考え方はありません。
こちらの問題もどうぞ!
<H28年出題>
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。

【解答】 ×
有期事業の一括の要件に、労働者数は入っていませんので、「かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満」の部分が誤りです。
なお、概算保険料が160万円未満は共通要件ですが、さらに、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満であることも要件です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(雇用保険法)
R2-135
R2.4.14 基本手当/受給期間の延長
基本手当の受給期間(基本手当を受けられる期間)は、原則として、基準日の翌日から起算して1年間(所定給付日数が360日→1年+60日、所定給付日数が330日→1年+30日)です。
今日は、受給期間が4年まで延長できる特例の問題です。
 (H28年出題)
(H28年出題)
配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。

【解答】 ×
出産を理由に、受給期間を延長できるのは、本人のみです。配偶者の出産を理由とする延長の申出はできません。
こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

【解答】 ○
受給期間の延長の申出をしなければ、基本手当を受給できる期間は1年間しかありませんが、申出をすることによって1年+180日まで期間が延長されます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-134
R2.4.13 遺族補償年金の失権後に遺族補償一時金は受けられる?
今日のポイント!
遺族(補償)年金も遺族(補償)一時金も、死亡した労働者と遺族との関係は、「死亡当時」で判断されます。
 (H28年出題)
(H28年出題)
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
【解答】 ×
遺族補償年金の受給権を失権した後、遺族補償一時金の受給権者になることもあり得ます。
例えば、
・夫(労働者)の死亡当時、生計維持関係のあった妻は、遺族補償年金の受給権者となる(他に受給資格者はいない)
↓
・その後、妻は再婚し、遺族補償年金の受給権は消滅した
↓
・支給された遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の額が1000日未満の場合、差額を遺族補償一時金として受けることができる
※ 再婚して年金は失権しているのに、なぜ一時金は受けることができるの?
遺族補償一時金も「死亡当時」で要件をみます。
再婚した妻でも、労働者の死亡当時は、「労働者の「妻」だったからです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働安全衛生法)
R2-133
R2.4.11 健康診断について
今日は、労働安全衛生法の健康診断のルールを穴埋め式でお届けします。
 (H23年選択)
(H23年選択)
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。
 (H26年選択)
(H26年選択)
労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の< B >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。
 (H25年選択)
(H25年選択)
労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、< C >を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
<選択肢>
① 労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断
② 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
③ 労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断
④ 労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便
【解答】
A 常時使用する
B 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
C ② 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H17年出題>
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。

【解答】 ×
・ 雇入れ時の健康診断の対象 → 常時使用する労働者
・ 雇入れ時の安全衛生教育の対象 → すべての労働者
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-132
R2.4.10 割増賃金/1時間当たりの賃金額の出し方
「第52回(令和2年度)の社会保険労務士試験の詳細が公示されました。 試験日は、令和2年8月23日(日)です。
|
今日は、割増賃金/1時間当たりの賃金額の出し方です。
時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の2割5分以上で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
通常の労働時間1時間当たりの賃金はどのように計算するのでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働基準法第37条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金を計算するについて、労働基準法施行規則第19条に定める割増賃金の基礎となる賃金の定めに従えば、通常の労働時間1時間当たりの賃金額を求める計算式のうち、正しいものはどれか。
なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。
賃金:基本給のみ 月額300,000円
年間所定労働時間数:240日
計算の対象となる月の所定労働日数:21日
計算の対象となる月の暦日数:30日
所定労働時間:午前9時から午後5時まで
休憩時間:正午から1時間
A 300,000円÷(21×7)
B 300,000円÷(21×8)
C 300,000円÷(30÷7×40)
D 300,000円÷(240×7÷12)
E 300,000円÷(365÷7×40÷12)

【解答】 D
労基法施行規則第19条の通常の労働時間1時間当たりの賃金額の計算式
 月によって定められた賃金の場合
月によって定められた賃金の場合
月給 ÷ 月の所定労働時間数
※月によって所定労働時間数が異なる場合は
月給 ÷ 1年間の一月平均所定労働時間数
問題文の場合、対象月の所定労働日数が21日、年間所定労働日数が240日なので、月によって所定労働時間数は異なります。ですので、月給÷1年間の一月平均所定労働時間数で計算します。
240日×7時間(拘束時間8時間-休憩1時間=1日の所定労働時間7時間)が年間の所定労働時間の合計です。それを12か月で割ると、1年間の一月平均所定労働時間数となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社保一般常識)
R2-131
R2.4.8 確定給付企業年金/企業年金基金の設立
確定給付企業年金には、「規約型」と「基金型」があります。
制度を開始するときの手続きは?が今日のテーマです。
 (H28年出題)
(H28年出題)
企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

【解答】 ×
受けるのは、許可ではなく「認可」です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働の一般常識)
R2-130
R2.4.7 平成30年若年者雇用実態調査より
平成28年に、「平成25年若年者雇用実態調査(厚生労働省)」の調査結果から出題がありました。
今日は、平成30年版の若年者雇用実態調査をもとに、解説します。
解いてみてくださいね。
 (H28年出題)
(H28年出題)
若年正社員の採用選考をした事業所のうち、採用選考にあたり重視した点について採用区分別にみると、新規学卒者、中途採用者ともに「職業意欲・勤労意欲・チャレンジ精神」、「コミュニケーション能力」、「体力・ストレス耐性」が上位3つを占めている。

【解答】 ×
平成30年若年者雇用実態調査によると、
「新規学卒者」、「中途採用者」とも上位3つは、
1 「職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神」
2 「コミュニケーション能力」
3 「マナー・社会常識」
となっています。
積極性や他者との関わり合いの中で円滑に業務を遂行することができる能力、スキル が重視されているようです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-129
R2.4.6 加給年金額と老齢基礎年金の繰上げとの関係
例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合、その加給年金額は、妻が65歳に達するまで加算されます。
しかし、その妻が65歳前に繰上げ支給の老齢基礎年金の支給をうけたとしたら、夫の老齢厚生年金に加算されている加給年金額はどうなりますか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

【解答】 ×
加給年金額の対象の配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとしても、加給年金額に相当する部分は、その配偶者が65歳に達するまで支給されます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-128
R2.4.4 寡婦年金の額の算出
国民年金法の「寡婦年金」は、ポイントがたくさんで、高頻度で出題されています。
ポイントを一つ一つおさえましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額とされている。

【解答】 ×
老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額の4分の3です。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H24年出題>
寡婦年金の額の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

【解答】○
寡婦年金の額には、死亡した夫の第1号被保険者としての被保険者期間だけが反映されます。
先ほどの問題でチェック してほしい箇所
してほしい箇所
↓
寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額の4分の3に相当する額とされている。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-127
R2.4.2 労災保険の給付を受けられない業務上の傷病等について
健康保険法の保険給付は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して行います。
労災保険の業務災害以外の傷病等とはどんなものなのか、イメージしてみてください。
 (H28年出題)
(H28年出題)
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

【解答】 ○
考え方の流れは以下の通りです。
とある会社員(健康保険の被保険者)が、副業として請負業務を行っている。
↓
その人が、もし請負業務中に負傷した場合、業務中であっても労働者ではないので、労災保険の給付は受けられない。
↓
原則として、健康保険の保険給付が受けられる。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-126
R2.4.1 暫定任意適用事業・保険関係消滅について
暫定任意適用事業の場合は、事業主の申請によって、保険関係を消滅させることができます。
その申請要件について、労災保険と雇用保険で違いはあるでしょうか?
 (H29年出題)
(H29年出題)
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

【解答】 ×
労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業では手続きが異なります。
<労災保険暫定任意適用事業>
・労働者の過半数の同意
・保険関係成立後1年経過している
・特別保険料を徴収する期間が経過している
<雇用保険暫定任意適用事業>
・労働者の4分の3以上の同意
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H21年出題>
厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。

【解答】 ○
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H27年出題>
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

【解答】 ×
事業を廃止した場合は、法律上当然に、廃止の日の翌日に保険関係が消滅します。
ですので、消滅の申請、所轄都道府県労働局長の認可、ともに不要です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(雇用保険法)
R2-125
R2.3.31 被保険者期間(賃金支払基礎日数)
基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが要件です。(原則)
「被保険者期間」とは?(原則)
離職日からさかのぼって1か月ごとに区切る → 区切った1か月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合 → その1か月を被保険者期間1か月として算定する。(11日未満の場合は被保険者期間に算入しない)
今日のテーマは、「賃金支払基礎日数」です。
 (H29年出題)
(H29年出題)
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。

【解答】 ×
被保険者期間1か月として算入されます。
年次有給休暇を取得した日は「賃金」が支払われますので、賃金支払基礎日数の計算に入れます。問題文の場合は、出勤8日+年休14日=22日ですので、被保険者期間1か月でカウントできます。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H26年出題>
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。

【解答】 ×
離職日から1か月ごとに区切っていくと、9月25日~8月26日、8月25日~7月26日・・・となりますが、資格取得日が4月1日ですので最後の区切りは4月25日~4月1日となります。
この最後の区切りのように、1か月に足りない期間の扱いは、第14条(被保険者期間)のただし書きに規定されています。
当てはめてみますと、「当該被保険者となった日(4月1日)からその日後における最初の喪失応当日の前日(4月25日)までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。」となります。
ですので、4月1日から4月25日までの期間は2分の1か月となり、問題文の被保険者期間は、5か月と2分の1か月となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-124
R2.3.30 傷病(補償)年金、傷病等級に該当しなくなったとき
傷病(補償)年金は、傷病等級1~3級に該当する場合に支給されますが、傷病等級に該当しなくなった場合は?
 (H29年出題)
(H29年出題)
傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

【解答】 ○
傷病補償年金受給の要件である「傷病等級1~3級」に該当しなくなった場合、受給権は消滅します。
そして、休業補償給付の要件(療養している・労働することができない・賃金を受けられない)を満たす場合は、休業補償給付を請求できます。
傷病補償年金は、労働基準監督署長の職権で支給決定されますが、休業補償給付は労働者からの請求が要ることも注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働安全衛生法)
R2-123
R2.3.28 ストレスチェックの実施者
ストレスチェック制度とは?
年に1回、労働者のストレスの状況について検査 → 本人にその結果を通知 → ストレスの状況について気付きを促す。(個々のストレス低減)
ストレスの高い者を早期に発見 → 医師による面接指導
目的は、「 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止すること」
 (H28年選択)改
(H28年選択)改
労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、< A >又は公認心理士とされている。

【解答】 A 精神保健福祉士
ストレスチェックの実施者として規定されています。
こちらの問題もどうぞ!
<H30年出題>
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

【解答】 ○
「50人以上」がポイントです。50人未満の場合は努力義務です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-122
R2.3.25 労働基準法第1条の趣旨は?
労働基準法第1条では、
① 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
② この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
と規定されています。
労働基準法の最初に出てくる条文ですが、この条の趣旨は?
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。

【解答】 ○
第1条第1項は、労働憲章的規定です。労働条件は、人間らしく生活するための必要を満たすべきものであること。
こちらもどうぞ。
<H18年出題>
労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。

【解答】 ○
第1条第2項に規定されています。
 こちらもどうぞ!
こちらもどうぞ!
<H19年出題>
労働基準法第1条第1項においては、「労働条件は、労働者< A >ための必要を充たすべきものでなければならない。」と規定されている。

【解答】 が人たるに値する生活を営む
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(高齢者医療確保法)
R2-121
R2.3.24 後期高齢者医療制度の適用除外
後期高齢者医療の被保険者は、①75歳以上の者、②65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にある旨、後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものです。
しかし適用除外規定もありますので確認しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。

【解答】 ○
①生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者と、②後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは適用除外とされています。
類似問題・国民健康保険法!
<H20年出題/国民健康保険法>
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者にならない。

【解答】 ○
(注) 国民健康保険法からの問題です。
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者から除外されています。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(就労条件総合調査より)
R2-120
R2.3.23 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合
 みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合はどの程度でしょう??
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合はどの程度でしょう??
みなし労働時間制の種類
・事業場外みなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制
 (H28年出題)
(H28年出題)
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

【解答】 ○
平成31年就労条件総合調査によると9.1%です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-119
R2.3.22 加給年金額の支給が停止されるとき
 例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合を考えてみましょう。
例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合を考えてみましょう。
もし妻が老齢厚生年金の支給を受けることができるとき、夫の老齢厚生年金に加算された加給年金額はどうなりますか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

【解答】 ×
300か月以上ではなく、240か月以上です。
加算対象になっている配偶者が単に老齢厚生年金を受けることができるだけでは、加給年金額は支給停止になりません。
その配偶者の受けることができる老齢厚生年金が、何カ月の被保険者期間で計算されているのかがポイントです。
加給年金額が停止されるのは、その配偶者が受けることができる老齢厚生年金が被保険者期間が原則として240月以上で計算されている場合に限られます。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H22年出題>
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金(その全額が支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-118
R2.3.21 子に支給する遺族基礎年金の額
 遺族基礎年金を受給できるのは、
遺族基礎年金を受給できるのは、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時生計を維持していた配偶者又は子です。
支給のパターンとしては、①子のある配偶者に支給する、②子に支給する、の2つがあります。
ポイントは、「子」の加算額の出し方です。①と②で異なりますので注意しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。

【解答】 ×
受給権者が子3人のときの遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率」です。
それぞれの子がそれぞれ受給権者です。それぞれの子に支給されるのは、合計額を子の人数である3で割った額となります。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H22年出題>
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。

【解答】 ×
受給権者が子2人の場合の遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率+224,700円×改定率」です。それぞれの子に支給されるのは、その額を2で割った額です。
 受給権者が「子のある配偶者」か「子」であるかで、年金の額の計算方法が変わります。
受給権者が「子のある配偶者」か「子」であるかで、年金の額の計算方法が変わります。
| 子のある配偶者 | 子 | |
| 子1人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率 | 780,900円×改定率 (加算無し) |
| 子2人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 224,700円×改定率 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率 |
| 子3人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 224,700円×改定率+ 74,900円×改定率 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 74,900円×改定率 |
ポイント
配偶者が遺族基礎年金を受けるには、子と生計を同じくすること(子のあること)が条件です。
・子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されない
・配偶者の遺族基礎年金には、子の数に応じた加算額が必ず加算される
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-117
R2.3.19 任意適用事業所の取消し
 任意適用事業所の被保険者から、任意適用からの脱退を求められた場合、事業主は任意適用事業所の取消しの申請をする義務はあるのでしょうか?
任意適用事業所の被保険者から、任意適用からの脱退を求められた場合、事業主は任意適用事業所の取消しの申請をする義務はあるのでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなければならない。

【解答】 ×
任意適用事業所に使用される被保険者から、任意適用取消の申請の希望があったとしても、事業主は取消しの申請をする義務はありません。
 こちらの問題もどうぞ!
こちらの問題もどうぞ!
<H24年出題>
従業員が15人の個人経営の理髪店で、被保険者となるべき者の2分の1以上が希望した場合には、事業主に速やかに適用事業所とするべき義務が生じる。

【解答】 ×
従業員から「任意適用事業所にしてほしい」と希望があったとしても、事業主には任意適用事業所とするべき義務はありません。
 任意適用事所となって健康保険に加入する、任意適用事業所を脱退する、どちらも、従業員からの希望があったとしても、事業主にはその申請をする義務は生じません。
任意適用事所となって健康保険に加入する、任意適用事業所を脱退する、どちらも、従業員からの希望があったとしても、事業主にはその申請をする義務は生じません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-116
R2.3.17 メリット制の適用
 継続事業と有期事業、メリット制の違いは?
継続事業と有期事業、メリット制の違いは?
 (H28年出題)
(H28年出題)
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。

【解答】 ×
「有期事業を含め」の部分が間違いです。
継続事業(一括有期事業含む)の場合、収支率が85%超になれば、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から労災保険率が引き上げられ、収支率が75%以下になれば引き下げられます。
事業が継続的に続くので、労災保険率を上下させることによって、メリット制を適用させます。
一方、有期事業の場合は、事業が終了してしまうので、労災保険率を上下させるのではなく、確定保険料を増減させることによってメリット制を適用します。
 では、こちらの問題もどうぞ
では、こちらの問題もどうぞ
<H25年出題>
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

【解答】 ×
メリット制が適用されるのは、収支率がメリット収支率が85%を超え、又は75%以下である場合です。問題文の100%は間違いです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(雇用保険法)
R2-115
R2.3.16 雇用保険の租税その他の公課
 雇用保険から支給される金銭は課税対象になりますか?
雇用保険から支給される金銭は課税対象になりますか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。

【解答】 ×
「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と規定されています。常用就職支度手当も失業等給付の一部ですので、課税されません。
★「失業等給付」の体系図はしっかり頭に入れてくださいね。
 では、こちらの問題もどうぞ
では、こちらの問題もどうぞ
<H22年出題>
高年齢雇用継続給付は、賃金の減少分を補うものであり、賃金に準ずる性格を有するので、所得税及び住民税の課税対象とされている。

【解答】 ×
上記と同じく高年齢雇用継続給付も失業等給付の一部ですので、課税対象にはなりません。
 「雇用保険二事業」は課税される?
「雇用保険二事業」は課税される?
雇用保険二事業は、主に事業主に対する雇用関係の助成金の給付を行っていますが、雇用保険二事業からの金銭は課税対象となります。雇用保険二事業は、失業等給付とは別の事業だからです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-114
R2.3.15 遺族(補償)年金・生計維持の要件
 遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を息していた」一定の遺族に支払われます。ここでいう「生計維持」とは、どの程度までをさすのでしょう?
遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を息していた」一定の遺族に支払われます。ここでいう「生計維持」とは、どの程度までをさすのでしょう?
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。

【解答】 ×
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたものにあたり、遺族補償年金を受けることができます。
遺族(補償)年金の「生計維持」の判断ポイント
・労働者の収入によって生計の一部を維持されていればいい。→もっぱら又は主として生計を維持されていることは要しない。
共稼ぎでも「生計を維持されている」に含まれる。
★「生計維持」という用語は、あらゆるところで出てきますが、判断ポイントがそれぞれ違いますので、注意してくださいね。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H17年出題>
遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。

【解答】 ○
基準を定める「厚生労働省労働基準局長」の役職名を覚えておいてください。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働安全衛生法)
R2-113
R2.3.14 「労働災害」の定義
 改めて、「労働災害」の定義を確認しましょう。
改めて、「労働災害」の定義を確認しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

【解答】 ○
労働災害は、その原因として、「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等」又は「作業行動その他業務」の二つを掲げています。
ですので、問題文にあるように、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」になることはありません。事業場内で発生したとしても、原因によっては労働災害に当てはまらないこともあるからです。
なお、「労働災害」は、人的損害が生ずることがポイントですので、物的損害だけの場合は労働災害にはなりません。
 穴埋め式で確認しましょう。
穴埋め式で確認しましょう。
労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は< A >その他< B >して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

【解答】 A 作業行動 B 業務に起因
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-112
R2.3.11 年次有給休暇の残余の数え方
 年次有給休暇を時間単位で取得すると、有休の残余が「○日と○時間」となります。
年次有給休暇を時間単位で取得すると、有休の残余が「○日と○時間」となります。
年の途中で、所定労働時間が変わった場合、有休の残余の数え方はどうなるのでしょう?
 (H28年出題)
(H28年出題)
所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。

【解答】 ○
日単位に満たない時間単位の部分は、所定労働時間の変更に比例して時間数が変わります。
変更前の1日の所定労働時間は8時間ですので、残余の10日と5時間の「5時間」の部分は所定労働時間の「8分の5」残っていると考えてください。
変更後の1日は所定労働時間は4時間です。時間単位の部分は「所定労働時間の4時間×8分の5=2.5」。1時間未満を切上げて「3時間」となります。ですので、残余は10日と3時間となります。
なお、1日当たりの時間数は、変更前は8時間ですが、変更後は4時間となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(確定給付企業年金法)
R2-111
R2.3.10 掛金の拠出(確定給付企業年金法)
 <確定給付企業年金法>事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を拠出しなければなりません。また、加入者も規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができます。
<確定給付企業年金法>事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を拠出しなければなりません。また、加入者も規約で定めるところにより掛金の一部を負担することができます。
 (H28年出題)
(H28年出題)
(確定給付企業年金法に関して)事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

【解答】 ×
掛金は、「毎月、翌月末までに」というルールはありません。
掛金については、
・年1回以上定期的に拠出しなければならない
・規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付する
と定められています。
 こちらもどうぞ
こちらもどうぞ
<H19年出題>
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(就労条件総合調査より)
R2-110
R2.3.9 フレックスタイム制を採用している企業割合
 フレックスタイム制を採用している企業の割合はどの程度でしょう??
フレックスタイム制を採用している企業の割合はどの程度でしょう??
 (H28年出題)
(H28年出題)
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【解答】 ×
フレックスタイム制を採用している企業割合は3割もありません。平成31年就労条件総合調査によると5.0%です。
★ちなみに、企業規模別でみると、
1000人以上 26.6%
300~999人 12.5%
100~299人 6.6%
30~99人 3.1%
(同じく、平成31年就労条件総合調査より)
企業規模が大きいほど採用割合が高いですね。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-109
R2.3.8 審査請求と再審査請求(厚年)
 第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある場合、社会保険審査官に審査請求ができますが、、、
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある場合、社会保険審査官に審査請求ができますが、、、
 (H28年出題)
(H28年出題)
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

【解答】 ○
穴埋め式でポインを確認しましょう。
 【厚生年金保険法第90条、第91条】
【厚生年金保険法第90条、第91条】
 厚生労働大臣による被保険者の資格、< A >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
厚生労働大臣による被保険者の資格、< A >又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
 審査請求をした日から< B >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
審査請求をした日から< B >以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
 資格、< A >又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< C >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
資格、< A >又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての< C >の決定を経た後でなければ、提起することができない。
 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は督促・滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。
厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は督促・滞納処分に不服がある者は、< D >に対して審査請求をすることができる。
 【社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項、32条第1項】
【社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第1項、32条第1項】
(審査請求期間)
 審査請求は、被保険者若の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して< E >を経過したときは、することができない。
審査請求は、被保険者若の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して< E >を経過したときは、することができない。
(再審査請求期間)
 厚生年金保険法第90条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< F >を経過したときは、することができない。
厚生年金保険法第90条第1項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して< F >を経過したときは、することができない。

【解答】
A 標準報酬 B 2月 C 審査請求に対する社会保険審査官
D 社会保険審査会 E 3月 F 2月
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-108
R2.3.6 追納するときの加算
 追納とは
追納とは
免除された保険料を、後から納付できる制度のことです。
追納すると、保険料免除期間から保険料納付済期間に変わります。
 (H18年出題)
(H18年出題)
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。

【解答】 ○
追納する場合は、一定額の加算がついた保険料を納付することになります。
ただし、免除を受けた年度の翌々年度までに追納する場合は、加算額はつきません。(保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額で納付することができることが考慮されています)
例えば、免除を受けたのが平成29年度の場合は、令和元年度中に追納する場合は、加算がつかない本来の額で納付できます。
★ポイント★ と言っても免除月が3月の場合は注意!
平成30年3月の保険料の納付期日は平成30年4月。保険料の徴収権の時効が消滅するのは、そこから2年後の令和2年4月。
平成30年3月に免除を受けた場合、令和2年4月中に追納するときは加算はつきません。→ 問題文のカッコ書きの部分(免除の月が3月のときは、翌々年の4月までなら加算されない)です。
※平成30年3月は「平成29年度」、令和2年4月は「令和2年度」です。平成30年3月から見て令和2年4月は、翌々年度ではなく、翌々年4月ですので注意してくださいね。
 もう一問どうぞ
もう一問どうぞ
<H19年出題>
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

【解答】○
・免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後の年度から加算が行われる。
例えば、免除月が平成28年10月なら、翌々年度(平成29年度、30年度)中なら加算は行われませんが、令和元年度(平成28年4月1日から起算して3年を経過した日以後の年度)から加算が行われます。
※免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合は除かれていることにも注意。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-107
R2.3.4 特定健康診査&特定保健指導
 特定健康診査とは
特定健康診査とは
・生活習慣病の予防が目的
・40歳から74歳までの人が対象のメタボリックシンドロームに着目した健診のこと
 (H28年出題)
(H28年出題)
健康保険法第150条第1項では、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導を行うように努めなければならないと規定されている。

【解答】 ×
「行うように努めなければならない」努力義務ではなく、「行うものとする」義務規定です。
高齢者医療確保法の規定
・厚生労働大臣が「特定健康診査等基本指針」を定める
↓
・保険者は、特定健康診査等基本指針に即して6年ごとに6年を1期として、特定健康診査等実施計画を定める
↓
・保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行う
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-106
R2.3.2 徴収法/書類の保存期間
 徴収法の規定による書類の保存期間は?
徴収法の規定による書類の保存期間は?
 (H28年出題)
(H28年出題)
事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則の規定による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、4年間)保存しなければならない。

【解答】 ○
徴収法の書類の保存期間は基本的に3年ですが、雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿だけは、4年ですので注意しましょう。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(雇用保険法)
R2-105
R2.3.1 「代理人」による失業の認定が認められるのは?
 代理人による失業の認定が認められるのはどのような場面でしょう?
代理人による失業の認定が認められるのはどのような場面でしょう?
 (H28年出題)
(H28年出題)
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められる。

【解答】 ○
・未支給失業等給付について
→未支給の失業等給付を自己の名で請求できるのは、死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹。
→受給資格者が死亡前に失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当を請求する場合は、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
→未支給給付請求者は、代理人に請求を行わせることができます。
・公共職業能力開発施設に入校中は、受給資格者が失業の認定のために出頭することが難しいため、 訓練施設に入校中の受給資格者については、代理人による失業の認定が認められています。
 ちなみに
ちなみに
未支給失業等給付に係る失業の認定については、代理人による失業の認定が認められていますが、通常の失業の認定は、代理人による失業の認定はできません。なぜなら、受給資格者本人の求職の申込みが必要だからです。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-104
R2.2.28 業務上の疾病の範囲
 「業務上の疾病」はどのように決められているのでしょうか?
「業務上の疾病」はどのように決められているのでしょうか?
 (H28年出題)
(H28年出題)
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

【解答】 ○
業務上の疾病として労災保険で補償される疾病の範囲は、労働基準法(労災保険法ではないので注意しましょう)施行規則別表第一の二の各号で定められています。
労働基準法施行規則別表第一の二(業務上の疾病リスト)は、第1号から第11号まで区分されています。
1号から10号までは疾病が例示列挙されていて、それに該当すれば業務上の疾病となります。もし、1号から10号に該当しない場合は、11号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」(11号には具体的な疾病が例示されていません。)に該当すれば、業務上の疾病となります。
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H21年出題>
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。

【解答】 ○
労働基準法施行規則別表第1の2の第1号から第11号までのどれにも当てはまらない場合は、業務上の疾病とは認められません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働安全衛生法)
R2-103
R2.2.27 総括安全衛生管理者の資格
 今日は、総括安全衛生管理者の資格についてです。総括安全衛生管理者として選任できる要件は?
今日は、総括安全衛生管理者の資格についてです。総括安全衛生管理者として選任できる要件は?
 (H28年選択)
(H28年選択)
労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、< A >をもって充てなければならない。」とされている。

【解答】 当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者
ポイント!
総括安全衛生管理者の資格は、事業の実施を「統括管理」する者であること。総括管理ではないので注意してくださいね。
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H24年出題>
常時120人の労働者を使用する清掃業の事業場の事業者は、総括安全衛生管理者を選任する義務があるが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を総括安全衛生管理者に選任し、当該事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。

【解答】 ○
ポイントを2つおさえましょう。
① 事業の実施を統括管理する者であれば、他に資格等を有していなくても総括安全衛生管理者に選任できる
② 総括安全衛生管理者には、事業場の労働災害を防止するため必要な業務を統括管理させることができる。(「統括管理」することが仕事。総括管理ではありません。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-102
R2.2.24 出来高払制の保障給
 今日は、出来高払制の保障給のルールを確認しましょう。
今日は、出来高払制の保障給のルールを確認しましょう。
 (H28年出題)
(H28年出題)
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

【解答】 ○
労基法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定されていて、「労働時間」に応じた一定額のものであることが必要です。
出来高払制その他の請負制の場合、出来高がゼロだったら賃金もゼロというのは許されず、労働者が働いた以上は、労働時間に応じた一定額の保障をしなければなりません。
 もう一問どうぞ!
もう一問どうぞ!
<H13年出題>
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

【解答】 ×
出来高払制その他の請負制で労働した場合は、「労働時間」に応じた一定額の保障が必要ですが、問題文のように「休業する」(=労働していない)場合は、第27条の保障給は不要です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社保一般常識)
R2-101
R2.2.20 確定給付企業年金法
 「確定給付企業年金法」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度のことです。
「確定給付企業年金法」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して実施する年金制度のことです。
では「確定給付企業年金法」でいう「厚生年金保険の被保険者」の定義は?というのが今日の主題です。
 (H28年出題)
(H28年出題)
確定給付企業年金法における「厚生年金保険の被保険者」には、厚生年金保険法に規定する第4号厚生年金被保険者は含まれない。

【解答】 ×
確定給付企業年金法の「厚生年金保険の被保険者」は、厚生年金保険法の第1号厚生年金被保険者と第4号厚生年金被保険者とされています。
ちなみに、第4号厚生年金被保険者とは、私立学校教職員共済の加入者のことです。
 「第4号厚生年金被保険者」について、もう一問どうぞ!
「第4号厚生年金被保険者」について、もう一問どうぞ!
<H29年出題>
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く。)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。

【解答】 ○
確定拠出年金の個人型年金加入者の範囲は基本的に20歳以上60歳未満のすべての方です。
1 国民年金第1号被保険者
※一部除外規定あり
2 60歳未満の厚生年金保険の被保険者
※公務員や私学共済の加入者も対象。
企業型年金加入者については、企業型年金規約において個人型年金への加入が認められている者に限る。
3 国民年金第3号被保険者
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働一般常識)
R2-100
R2.2.18 年次有給休暇取得率
 今日は、「平成31年就労条件総合調査(厚生労働省)」からの問題です。
今日は、「平成31年就労条件総合調査(厚生労働省)」からの問題です。
 (H28年出題参考)
(H28年出題参考)
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50%を下回っている。
(平成31年就労条件総合調査(厚生労働省)より)

【解答】 ×
平成31年就労条件総合調査によると、男性は49.1%ですが、女性は58.0%でした。
※ ちなみに、H28年出題時は、平成27年の調査の結果からの出題でした。その当時も男性は50%を下回っていましたが、女性は50%を超えていました。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-99
R2.2.17 2以上の種別の被保険者であった期間を有する障害厚生年金
 厚生年金保険の被保険者には、第1号、第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の4つの種別があります。
厚生年金保険の被保険者には、第1号、第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の4つの種別があります。
例えば、民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)と国家公務員(第2号厚生年金被保険者)の2つの種別の被保険者であった期間を有する者が、障害厚生年金の支給を受ける場合、支給に関する事務はどの実施機関が行うのでしょうか?
 H28年出題
H28年出題
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

【解答】 ×
障害認定日における被保険者の種別ではなく、「初診日」における被保険者の種別で決まります。初診日にあてはまっていた被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。

【解答】 ×
「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」で計算するのではなく、2以上の被保険者の種別の被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。
初診日に加入していた種別の実施機関が、他の種別の実施機関で加入していた期間分も合算して年金額の計算をし、支給事務を行うことになります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-98
R2.2.16 保険料全額免除期間に含まれるもの
 国民年金法第5条では、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」などの用語の定義が規定されています。
国民年金法第5条では、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」などの用語の定義が規定されています。
また、「保険料免除期間」とは、「保険料全額免除期間」「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」を合算した期間とされています。
今日の問題は、第5条からです。
 H28年出題
H28年出題
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。

【解答】 ×
「学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間」も保険料全額免除期間に含まれます。
国民年金法第5条第3項では、「保険料全額免除期間」は次のように定義されています。
「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、全額申請免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※ ちなみに50歳未満の納付猶予期間も保険料全額免除期間に含まれます。(法附則)
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H21年出題>
国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。

【解答】 ×
学生納付特例も含まれます。また、附則により、50歳未満の納付猶予も保険料全額免除期間に含まれます。
 では、こちらの問題もどうぞ
では、こちらの問題もどうぞ
<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】 ○
保険料全額免除を受けた期間でも、保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。(保険料全額免除期間からは追納した期間は除かれます。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-97
R2.2.15 保険医療機関又は保険薬局のみなし指定
 厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所、薬局のことを「保険医療機関又は保険薬局」といい、療養の給付を担当します。
厚生労働大臣の指定を受けた病院、診療所、薬局のことを「保険医療機関又は保険薬局」といい、療養の給付を担当します。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、病院又若しくは診療所又は薬局の開設者の申請によって行いますが、例外もあります。
 H29年出題
H29年出題
保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。

【解答】 ○
保険医療機関又は保険薬局のみなし指定からの出題です。みなし指定の対象は個人開業医と個人薬局のみなのがポイントです。
個人開業医と個人薬局の場合、保険医又は保険薬剤師の登録をすれば、保健医療機関又は保険薬局の指定の手続をしなくても指定があったとみなされます。
ここもポイント
保険医又は保険薬剤師 → 登録
保険医療機関又は保険薬局 → 指定
「登録」と「指定」の使い分けにも注意です。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H29年出題>
保険医療機関又は保険薬局は、14日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができ、保険医又は保険薬剤師は、14日以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

【解答】 ×
保険医療機関又は保険薬局の指定の辞退 → 1か月以上の予告期間
保険医又は保険薬剤師の登録の抹消 → 1か月以上の予告期間
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-96
R2.2.13 概算保険料延納の際の納期限
 概算保険料は、一定の要件を満たせば延納(分割納付)が可能です。労働保険事務組合に事務処理を委託している場合の納期限は?
概算保険料は、一定の要件を満たせば延納(分割納付)が可能です。労働保険事務組合に事務処理を委託している場合の納期限は?
 H27年出題
H27年出題
概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。

【解答】 ○
継続事業(一括有期事業含む)の延納の場合は、労働保険事務組合に委託している場合、第2期分と第3期分の納期限が14日延長して設定されていますが、単独の有期事業の場合は、そのような取り扱いはありません。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H27年出題>
概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。

【解答】 ○
継続事業(一括有期事業を含む。)で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合でも、4月1日から7月31日までの期分(第1期分)の納期限は延長されず、原則通りの7月10日となります。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(雇用保険法)
R2-95
R2.2.11 「傷病手当」の支給要件について
 求職の申込後に疾病又は負傷のために、公共職業安定所に出頭することができない場合、支給されるのは傷病手当?それとも基本手当?
求職の申込後に疾病又は負傷のために、公共職業安定所に出頭することができない場合、支給されるのは傷病手当?それとも基本手当?
 H28年出題
H28年出題
求職の申込後に疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができない場合において、その期間が継続して15日未満のときは、証明書により失業の認定を受け、基本手当の支給を受けることができるので、傷病手当は支給されない。

【解答】 ○
「15日未満」がポイントです。
疾病又は負傷のため安定所へ出頭することができない場合で、その期間が15日未満のときは、証明書で失業の認定を受けることができます。
証明書は、理由がやんだ後の最初の失業の認定日に出頭して提出し、失業の認定を受けることによって、基本手当の支給を受けることができます。
なお、15日以上の傷病の場合、要件を満たせば、基本手当の代わりに傷病手当が支給されます。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H22年出題>
受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭して求職の申込みを行う前に、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になった場合でも、そのような状態が30日以上継続したことについて公共職業安定所長の認定を受ければ、傷病手当を受給することができる。

【解答】 ×
傷病手当は、「 離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後」で、疾病又は負傷によって職業に就くことができない状態になったことが条件です。
求職の申込を行う以前からそのような状態の場合には傷病手当は支給されません。
ちなみに、
公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行う以前に疾病又は負傷により職業に就く
ことができない状態にある場合は、基本手当の受給期間の延長を申し出ることが可能です。 (引き続き30日以上職業に就くことができない場合)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-94
R2.2.9 通勤経路の逸脱・中断
★ まず、通勤の定義から確認しましょう。
 通勤とは、
通勤とは、
・ 労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うこと
① 住居と就業の場所との間の往復
② 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
③ 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)
ただし、業務の性質を有するものを除く。
 通勤経路を逸脱し、中断した場合
通勤経路を逸脱し、中断した場合
・ 逸脱又は中断の間及びその後の移動 → 通勤としない。
・ 逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合
→ 逸脱又は中断の間を除き通勤となる。
 H27年出題
H27年出題
会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。

【解答】 ×
通勤経路を逸脱又は中断した場合でも、それが「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合」は、逸脱・中断の間は通勤にはなりませんが、元の経路に復した後は通勤となります。
出退勤の途中で理髪店や美容院に立ち寄る行為は、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」に該当しますので、問題文の場合は、髪のセットを終えて合理的な経路に復した後は通勤となります。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H23年出題>
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め同条の通勤とする。

【解答】 ×
逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものであったとしても、逸脱・中断の間は通勤とはなりません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働安全衛生法)
R2-93
R2.2.8 就業制限業務(安衛法)
★ 例えば、ボイラー等は爆発するおそれがあり、万が一、ボイラーの作業に伴い災害が起こった場合、労働者だけでなく周りにまで被害が及ぶ可能性があります。
そのため、ボイラー(小型ボイラー以外)の取扱い業務につくためには、免許が必要です。
一定の危険な作業を伴う業務については、免許を受けた者や技能講習を修了した者等しか従事させることができないことが、労働安全衛生法に定められています。
 H28年出題
H28年出題
作業床の高さが5メートルの高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者でなければその業務に就くことはできない。

【解答】 ×
高所作業車の運転の業務については、作業床の高さが10メートル以上なら、「就業制限業務」で、高所作業車運転技能講習を修了した者しか業務に就くことができません。
問題文の高所作業車は、作業床の高さが5メートルですので、就業制限業務ではなく、「特別教育」の対象です。
簡単に言うと、大きいものは就業制限業務、小さいものは特別教育です。
(例)ボイラー(小型ボイラー以外)の取扱い → 就業制限業務(免許)
小型ボイラーの取扱い → 特別教育
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-92
R2.2.5 1週間単位の非定型的変形労働時間制
★ 今日は「1週間単位の非定型的変形労働時間制」です。この制度は、対象の事業・規模が限定されているのがポイントです。
 H28年出題
H28年出題
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。

【解答】 ×
一週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、
「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつこれを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる事業(=小売業、旅館、料理店、飲食店)」で常時使用する労働者数が「30人未満」であること。
事業の種類と規模、どちらにも該当していることが条件です。
 こちらもどうぞ。
こちらもどうぞ。
<H22年出題>
労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。

【解答】 ×
1日の労働時間の上限は10時間と定められています。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(育児介護休業法)
R2-91
R2.2.4 パパママ育休プラス(育児介護休業法)
★ 今日は育児介護休業法「父親と母親がともに育児休業をする場合」です。
 H28年出題
H28年出題
育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。

【解答】 ×
父親と母親がともに育児休業を取得する場合(パパママ育休プラス)、1歳6か月ではなく1歳2か月までです。
 こちらもどうぞ。
こちらもどうぞ。
<空欄を埋めてください。>
(育児介護休業法の目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び < A >の促進を図り、もってこれらの者の< B >と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の< C >を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

【解答】 A 再就職 B 職業生活 C 福祉の増進
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(社会保険労務士法)
R2-90
R2.2.3 懲戒(社会保険労務士法)
★ 今日は社会保険労務士法「不正行為の指示等を行った場合の懲戒」です。
 H28年出題
H28年出題
社会保険労務士法第25条の2第2項では、厚生労働大臣は、開業社会保険労務士が、相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、当該社会保険労務士の失格処分をすることができるとされている。

【解答】 ×
「相当の注意を怠り・・・」の場合は、失格処分ではなく、「戒告又は1年以内の業務の停止の処分を行うことができる」です。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H25年出題>
開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら、故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合は、失格処分を受けることがある。

【解答】 ○
「故意に・・・」の場合は、1年以内の業務停止処分又は失格処分をすることができる、とされています。
 こちらもどうぞ。
こちらもどうぞ。
<空欄を埋めてください。>
(懲戒の種類)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。
1 戒告
2 < A >以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
3 < B >(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。)

【解答】 A 1年 B 失格処分
社会保険労務士に対する懲戒処分は次の3つです。
①戒告 ②1年以内の業務の停止 ③失格処分
では、こちらもどうぞ
(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
1 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、< C >に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条(不正行為の指示等の禁止)の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、< D >、1に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

【解答】 C 故意 D 相当の注意を怠り
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚生年金保険法)
R2-89
R2.1.31 老齢厚生年金の繰上げと繰下げ
★ 老齢厚生年金の繰上げ、繰下げのルールを確認しましょう。
 H27年出題
H27年出題
老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。

【解答】 ○
老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給繰上げの請求は、同時にしなければなりません。
 では、老齢厚生年金の繰下げはどうでしょう?
では、老齢厚生年金の繰下げはどうでしょう?
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H28年出題>
平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者の支給繰下げの申出は、必ずしも老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行うことを要しない。

【解答】 ○
老齢厚生年金の繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時でなくても構いません。
 <番外編>もどうぞ。
<番外編>もどうぞ。
<H30年出題>
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について、支給繰下げの申出を行う場合、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出と、第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の申出を同時に行わなければならない。

【解答】 ○
<2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老齢厚生年金の繰下げ>
→ 一の期間に基づく老齢厚生年金の繰下げの申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金の繰下げの申出と同時に行うこと。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国民年金法)
R2-88
R2.1.28 第2号被保険者の20歳前、60歳以後の期間
★ 国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者は「20歳以上60歳未満」という年齢制限がありますが、第2号被保険者にはそのような年齢制限がありません。
国民年金の年金額の計算上、第2号被保険者の20歳未満、60歳以後の期間の扱いはどうだったでしょう?というのが今日のテーマです。
 H28年出題
H28年出題
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。

【解答】 ○
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間が全て保険料納付済期間であれば満額支給される仕組みです。
ですので、第2号被保険者としての被保険者期間も、保険料納付済期間として老齢基礎年金の年金額に反映されるのは「20歳から60歳まで」となり、20歳前、60歳以後の期間は合算対象期間となります。
<老齢基礎年金の計算額のルール>
「第2号被保険者としての被保険者期間」は、
・ 保険料納付済期間 → 20歳から60歳まで
・ 合算対象期間 → 20歳前、60歳以後
 「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のルールも確認しましょう。
「障害基礎年金」「遺族基礎年金」のルールも確認しましょう。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H24年出題>
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

【解答】 ×
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間の保険料の納付状況で年金額を計算しますが、障害基礎年金はそうではありません。
ですので、障害基礎年金については、第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間も「保険料納付済期間」となります。
(遺族基礎年金も障害基礎年金と同様の考え方です。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健康保険法)
R2-87
R2.1.27 傷病手当金の待期の起算日
★ 傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給されます。
では、もし、就業中に労務不能になった場合の起算日は?
 H28年出題
H28年出題
被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該翌日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

【解答】 ×
待期は、労務に服することができない状態に置かれた日から起算します。
問題の場合は入院した日(=労務に服することができない状態に置かれた日)から起算しますので、翌日を起算とするのが誤りです。
※ なお、労務に服することができない状態に置かれたときが業務終了後の場合は、翌日から起算します。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H25年出題>
傷病手当金の支給に関して、労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算するが、その状態になったときが業務終了後である場合は、その翌日から起算する。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-86
R2.1.26 日雇労働被保険者の一般保険料(徴収法)
★ 事業主は、使用する日雇労働被保険者については印紙保険料を納付しなければなりません。が、印紙保険料だけ?というのが今日のテーマです。
 H28年出題
H28年出題
事業主は、その使用する日雇労働被保険者については、印紙保険料を納付しなければならないが、一般保険料を負担する義務はない。

【解答】 ×
事業主は、印紙保険料だけでなく、一般保険料も負担しなければなりません。
日雇労働被保険者については、一般保険料にプラスして印紙保険料がかかります。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H22年出題>
雇用保険の日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担しなければならないが、当該日雇労働被保険者に係る一般保険料を負担する必要はない。

【解答】 ×
先ほどの問題は、「事業主」の負担でしたが、こちらは「日雇労働被保険者」の負担についての問題です。
日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1にプラスして、一般保険料の被保険者負担分も負担する必要があります。
★ちなみに
一般保険料は、労災保険料+雇用保険料です。
一般保険料のうち、労災保険料は全額事業主負担なので、労働者の負担はありません。
雇用保険料は、賃金総額×(雇用保険率-二事業に係る率)の2分の1が被保険者負担分です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(雇用保険法)
R2-85
R2.1.23 基本手当(待期)
★ 基本手当は、離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は、支給されません。→ 待期と言います。
今日は、待期の問題です。
 H23年出題
H23年出題
受給資格者が基準日後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して5日の時点で安定した職業に就いて被保険者となった場合、その5日について基本手当が支給されることはない。

【解答】 ○
待期日数は、現実に失業し、失業の認定を受けた日数が通算7日に達することが条件です。5日の時点で就職した場合は、待期日数を満たさないので、基本手当は支給されません。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H26年出題>
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなかったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。

【解答】 ×
待期日数は、受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日から起算された通算7日間ですが、この日数には、傷病のため職業に就くことができない日数も含まれます。
問題文の場合、3日間疾病により職業に就くことができない日も含んで7日間で待期日数は満たしますので、8日目から基本手当が支給されます。
 もう一問どうぞ
もう一問どうぞ
<H29年出題>
失業の認定は、雇用保険法第21条に定める待期の期間には行われない。

【解答】 ×
失業の日(又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日)として認められるには、「失業の認定」が必要です。
ですので、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定は待期の7日についても行われます。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-84
R2.1.22 支給制限/労働者の「故意」
業務遂行中の災害でも、それが労働者の「故意」による場合は、保険給付に制限がかかります。
 H26年出題
H26年出題
業務遂行中の災害であっても、労働者が故意に自らの負傷を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。

【解答】 ○
労働者が故意に(事故を発生させようとして)負傷した場合は、たとえ業務遂行中でも保険給付はまったく行われません。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H26年出題>
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者の故意の犯罪行為により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 ○
「故意」と「故意の犯罪行為」では、支給制限の内容が異なるので注意してください。
「故意の犯罪行為」の場合、保険給付はまったく行わない、ではなく、「全部又は一部を行わないことができる」。裁量によることになります。
 練習問題もどうぞ!
練習問題もどうぞ!
<労災保険法 第12条の2の2>
① 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその< A >となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
② 労働者が故意の犯罪行為若しくは< B >により、又は正当な理由がなくて< C >に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 A 直接の原因 B 重大な過失 C 療養に関する指示
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働安全衛生法)
R2-83
R2.1.21 派遣労働者の健康診断(派遣元or派遣先??)
労働安全衛生法はもちろん派遣労働者にも適用されます。
派遣労働者の場合、「派遣元」の事業者or「派遣先」の事業者、どちらが安衛法上の責任を負うのかが受験勉強のポイントです。
 H27年出題
H27年出題
派遣就業のため派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。

【解答】 ×
一般的な項目の「一般健康診断」は雇用主である派遣元の事業者に実施義務があります。
一方、有害業務に従事する労働者に対して行う「特別の項目」の健康診断(第66条第2項に規定されている=特殊健康診断)は、派遣労働者が有害業務に実際に就いている「派遣先」の事業者が実施義務を負います。
 こちらの問題もどうぞ
こちらの問題もどうぞ
<H27年出題>
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。

【解答】 ×
長時間労働者への医師による面接指導について、派遣労働者への面接指導は、派遣先ではなく、派遣元事業者に実施義務が課せられています。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-82
R2.1.20 「通勤手当」と「家族手当」→含むor含まない?
「通勤手当」と「家族手当」
控除するのか、含めるのか、迷いませんか??
では、さっそく、次の問題を解いてみてください。
 H27年出題
H27年出題
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

【解答】 ×
「平均賃金」の問題です。
通勤手当及び家族手当は、控除の対象になっていません。平均賃金の計算に算入します。
 では、次の問題はどうでしょう?
では、次の問題はどうでしょう?
H26年出題
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】 ○
こちらは、「割増賃金」の問題です。
「労働とは直接関係のない個人的事情」の部分がポイントです。「通勤手当」は、個々人の通勤距離や通勤に要した費用によって決まるもので、労働の内容と全く関係ないからです。
ここもチェック!
なお、「通勤手当でも距離に関係なく支払われる部分がある場合は、その部分を算定基礎に算入する」という通達にも注意してください。
通勤に要した費用や距離に関係なく支給するものは、割増賃金の計算に算入しなければなりません。
 では、もう一問どうぞ
では、もう一問どうぞ
H23年出題
労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)はいわゆる通常の賃金であり、家族手当は算定基礎賃金に含めないことが原則であるから、家族数に関係なく一律に支給されている手当は、算定基礎賃金に含める必要はない。

【解答】 ×
こちらも「割増賃金」の問題です。
扶養家族がいる労働者に対して、家族の人数に応じて支給されるものは、割増賃金の計算から除外します。扶養家族の人数などは個人的事情だからです。
しかし、家族数に関係なく一律に支給されているとなると、算定基礎賃金に含めなければなりません。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(介護保険法と高齢者医療確保法)
R2-81
R2.1.17 財政の均衡を保つことができる期間(社一)
今日は、介護保険法と高齢者医療確保法の比較です。
では、さっそく、次の問題を解いてみてください。
 H23年出題
H23年出題
(高齢者医療確保法に関する問題)
保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金及び第117条第2項の規定による拠出金の納付に要する費用の予想額、国庫負担等に照らし、おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

【解答】 ×
おおむね5年を通じ財政の均衡を保つことができる、ではなく、おおむね「2年」を通じ財政の均衡を保つことができる、です。
 では、次の問題はどうでしょう?
では、次の問題はどうでしょう?
【H30年選択式】
(介護保険法に関する問題)
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね< A >を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。

【解答】 3年
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働契約法)
R2-80
R2.1.16 労働契約法の適用除外(労一)
今日は、労働契約法です。
では、さっそく、次の問題を解いてみてください。
 H28年出題
H28年出題
労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約及び家事使用人の労働契約については、適用を除外している。

【解答】 ×
労働契約法では、「使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない」と規定されています。
「家事使用人の労働契約」は適用除外になっていませんので、×となります。
 では、次の問題はどうでしょう?
では、次の問題はどうでしょう?
【H24年出題】
労働契約法における「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうとされており、これに該当すれば家事使用人についても同法は適用される。

【解答】 ○
家事使用人は適用除外されていないので、労働者の要件にあてはまっていれば労働契約法が適用されます。
 ちなみに、労働基準法は、
ちなみに、労働基準法は、
「同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と定められています。
労働基準法は、家事使用人には適用されませんので注意してください。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(厚年法)
R2-79
R2.1.14 65歳以上の在老のルール(厚年)
今日は、いただいたご質問にお答えします。
テーマ「65歳以上の在職老齢年金のルール」
~~「経過的加算額と繰下げ加算額」の扱いについて~~
ポイント
支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上のときは、老齢厚生年金の全額が支給停止される。
ただし、経過的加算額と繰下げ加算額は支給停止にはならずに、全額支給される。
このポイントを押さえたうえで、次の問題を解いてみてください。
 H22年出題
H22年出題
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から47万円を控除した額の2分の1に相当する額に相当する部分が、老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(繰下げ加算額を除く。)が支給停止される。

【解答】 ○
<ご質問内容>
問題文で、「(繰下げ加算額を除く。)」となっていますが、経過的加算額も支給停止の対象から除かれるはず。
この問題は、「経過的加算額」が入っていないのに、なぜ「○」なのでしょうか?
<解説>
 まず、「経過的加算額」は、法附則で規定されている制度で、あくまでも「当分の間」の措置です。(ということは、いずれ無くなるかもしれない)
まず、「経過的加算額」は、法附則で規定されている制度で、あくまでも「当分の間」の措置です。(ということは、いずれ無くなるかもしれない)
 60歳台後半の在職老齢年金の条文(法第46条)では、「繰下げ加算額を除く」と規定されていて、「経過的加算額」には触れられていません。
60歳台後半の在職老齢年金の条文(法第46条)では、「繰下げ加算額を除く」と規定されていて、「経過的加算額」には触れられていません。
だたし、法附則によって、当分の間、法第46条の在職老齢年金は、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と読み替えることが規定されています。
 本来は「繰下げ加算額を除く」でOKですが、当分の間、経過的加算額が加算されている人については、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と附則で読み替えているということです。
本来は「繰下げ加算額を除く」でOKですが、当分の間、経過的加算額が加算されている人については、「繰下げ加算額と経過的加算額を除く」と附則で読み替えているということです。
 ですので、平成22年の問題は、附則ではなく、本来のルールが問われていると考えて、「○」になるということです。
ですので、平成22年の問題は、附則ではなく、本来のルールが問われていると考えて、「○」になるということです。
ちなみに。。。
この問題は、平成22年(問2)で、「誤っているもの」を選ぶ問題でした。
問2のAからEのうち、「A」の肢が明らかに誤っている問題でした。
もし、判断に迷ったら、よりはっきり誤っている方を選ぶ、というテクニックも必要かもしれません。
 では、次の問題はどうでしょう?
では、次の問題はどうでしょう?
【H24年出題】
60歳台後半の在職老齢年金においては、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金と経過的加算額であり、老齢基礎年金は支給停止の対象にはならない。

【解答】 ×
60歳台後半の在職老齢年金では、経過的加算額は支給停止の対象にならないので「×」です。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(国年法)
R2-78
R2.1.13 年金の支給期間(国年)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H27 国年法(問5)より
H27 国年法(問5)より
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。

【解答】 ×
年金は、権利が消滅した日の属する月まで支給されます。
問題文の場合、遺族基礎年金は、婚姻した日の属する月の前月分までではなく、婚姻した日の属する月まで支給されます。
【穴埋め式で確認しましょう】
<年金の支給期間>
1 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する< A >から始め、権利が消滅した日の属する< B >で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する< C >からその事由が消滅した日の属する< D >までの分の支給を停止する。
ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止< E >。

【解答】
A 月の翌月 B 月 C 月の翌月 D 月 E しない
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(健保法)
R2-77
R2.1.10 健康保険と後期高齢者医療の関係(健保)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H28 健保法(問10)より
H28 健保法(問10)より
被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となることができるが、後期高齢者医療の被保険者である場合は被扶養者とならない。

【解答】 ○
後期高齢者医療の被保険者は、健康保険の対象から除かれます。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H20年出題】
健康保険の被保険者が75歳に達したときは、健康保険の被保険者資格を有したまま後期高齢者医療の被保険者となる。

【解答】 ×
後期高齢者医療の被保険者は、健康保険の対象から除かれますので、健康保険の被保険者資格は喪失します。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(徴収法)
R2-76
R2.1.8 下請負事業の分離の条件(徴収法)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H27 徴収法(労災問10)より
H27 徴収法(労災問10)より
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の元請負人及び下請負人が、下請負事業の分離の認可を受けようとするときは、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内であれば、そのいずれかが単独で、当該下請負人を事業主とする認可申請書を所轄都道府県労働局長に提出して、認可を受けることができる。

【解答】 ×
厚生労働省令で定める事業(=労災保険の保険関係が成立している建設の事業)が数次の請負で行われる場合、労災保険の保険関係は、元請負事業に一括されます。(下請負事業の分も含めてすべて元請負事業にまとめられるということ。=請負事業の一括)
請負事業の一括は法律上当然に行われますが、そこから下請負事業を分離させることもできます。ただし、その場合は法律上当然ではなく、「認可」が必要です。
上記は、下請負事業を分離させるときの認可の条件についての問題です。
下請負事業の分離の認可を受けるには、「元請負及び下請負人」が申請することが条件です(共同で申請しなければならない)。上記の問題は、「そのいずれかが単独で」の部分が間違っています。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H27年出題】
厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合の下請負人を事業主とする認可申請書は、天災、不可抗力等の客観的理由により、また、事業開始前に請負方式の特殊性から下請負契約が成立しない等の理由により期限内に提出できない場合を除き、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

【解答】 ○
下請負人を事業主とする認可申請書は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に提出するのが原則です。(やむを得ない理由の場合は、期限後でも提出できる例外があります。)
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(雇用保険法)
R2-75
R2.1.7 失業の認定(雇用)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H27 雇用保険法(問7)より
H27 雇用保険法(問7)より
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

【解答】 ○
失業の認定の原則は、「4週間に1回ずつ」ですが、
★この問題でチェックしてほしいポイントは
・どこから起算するの?
→ 離職後最初に出頭した日から
・今回の認定日の対象はどの日?
→ 「直前の28日の各日」。「直前」に注目です。前回の認定日から今回の認定日の前日までの28日分です。認定日当日は今回の認定日では対象外です。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

【解答】 ×
失業の認定日には、「失業認定申告書」に「受給資格者証」を添えて提出します。
ちなみに、「離職票」は、離職後、管轄公共職業安定所に出頭し求職の申込をするときに提出します。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労災保険法)
R2-74
R2.1.6 遺族補償一時金の受給者(労災)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H28 労災保険法(問6)より
H28 労災保険法(問6)より
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。

【解答】 ○
遺族補償給付には、「年金」と「一時金」がありますが、「一時金」については、労働者の死亡の当時、「生計維持していなかった」場合でも、受給権者になり得るのがポイントです。
※ただし、子、父母、孫、祖父母は、生計維持していた、生計維持していなかったで順位が変わります。(生計維持していた方が優先)
配偶者は生計維持の有無にかかわらず最優先、兄弟姉妹は生計維持の有無にかかわらず最下位です。
労働者の死亡当時、配偶者も子も父母も孫も祖父母もいない場合は、生計維持していなかった兄弟姉妹が遺族補償一時金を受けることもあり得ます。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H17年出題】
遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

【解答】 ○
遺族(補償)給付のうち、「年金」を受けることができるのは、労働者の死亡の当時、「生計維持していた」ことが条件です。(生計維持していなかったものはダメ)
 こちらもどうぞ
こちらもどうぞ
【H13年出題】
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

【解答】 ×
問題文の頭に注目してください。頭が「遺族補償年金」となっていれば「○」ですが「遺族補償給付」となっているので「×」です。
「遺族補償給付」には年金だけでなく「一時金」もあります。「一時金」なら、生計維持していなくても受けられる可能性がありますので。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働安全衛生法)
R2-73
R2.1.3 深夜業に従事する労働者の健康診断(安衛法)
日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H27 安衛法(問10)より
H27 安衛法(問10)より
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置換えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

【解答】 ○
特定業務従事者の健康診断の問題です。
この問題のポイントは、「深夜業」と「6月以内ごとに」の部分です。
通常、定期健康診断は、1年以内ごとに1回行わなければなりませんが、特定業務従事者については、配置換えの際と6月以内ごとに1回行うことが定められています。有害な業務に就いているので、定期健康診断の頻度が多く設定されています。
「深夜業」も特定業務の中に入りますので、問題文のとおりとなります。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H17年出題】
深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

【解答】 ○
①「常時1000人以上の事業場」と②「常時500人以上で有害業務を行う事業場」では、専属の産業医を選任しなければなりません。②の有害業務に、深夜業が入るのがポイントです。
ちなみに、専属の産業医を選任しなければならない有害業務の範囲と、特定業務従事者の有害業務の範囲は同じです。
特定業務従事者の健康診断と専属の産業医の問題で「深夜業」ときたら、深夜業が対象か否かが問われます。深夜業対象と覚えてくださいね。
社労士受験のあれこれ
問題の解き方(労働基準法)
R2-72
R2.1.2 時間外労働の端数処理(労働基準法)
あけましておめでとうございます!
今年も、「社会保険労務士合格研究室」どうぞよろしくお願いいたします。
さて、日々忙しい中、勉強時間を捻出しなければならない、また、試験当日は限られた時間の中で、焦らず、問題を解かなければならない。
受験勉強は、常に、時間との戦いです。
「どの辺まで勉強しなければならないのか?」
「本番の試験で、時間の無い中、問題文は隅々まで読まなければならないのか?」
など、考えたことはありませんか?
今日から、過去問を使って、時間をかけない問題の解き方、勉強方法を書いていきます。
 H28 労基法(問3)より
H28 労基法(問3)より
1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

【解答】 ○
この問題のポイントは、冒頭の「1か月の」の部分です。
1か月の時間外労働等の時間数の「合計」についてなら、このような端数処理方法が許されますが、例えば、「1日」単位でこの端数処理をすると、第24条(全額払の原則)違反となってしまいます。
 この問題も解いてください。
この問題も解いてください。
【H19年出題】
割増賃金の計算の便宜上、1日における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数に1時間未満の端数がある場合は、1日ごとに、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げて計算する措置は、法違反として取り扱わないこととされている。

【解答】 ×
「1日における」、「1日ごとに」の部分で迷わず「×」にしてください。問題文は最後まで読まなくていいです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-71
R1.12.30 R1社一/社会保険労務士法
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社保一般常識「社会保険労務士法」についてです。
 R1社保一般常識(問5)より
R1社保一般常識(問5)より
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

【解答】 ×
最後の「社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分をすることができる。」が誤りです。「注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」が正解です。
違反するおそれがあると認めるときは、社会保険労務士会は注意勧告ができます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働の一般常識)
R2-70
R1.12.28 R1労働一般常識/障害者雇用促進法
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働一般常識「障害者雇用促進法」についてです。
 R1労働一般常識(問4)より
R1労働一般常識(問4)より
事業主は、障害者と障害者でない者のとの均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときを除いて、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。

【解答】 ○
合理的配慮の事例が指針に記載されています。
一例として、募集及び採用時、障害区分が視覚障害の場合、「募集内容について、音声で提供すること」などが掲げられています。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-69
R1.12.27 R1厚年/加給年金額の対象者である配偶者が65歳になったとき
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年法「加給年金額の対象者である配偶者が65歳になったとき」についてです。
 R1厚年法(問6)より
R1厚年法(問6)より
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

【解答】 ×
この場合の届書の提出は不要です。
ポイント★
加給年金額対象者の不該当の届出は、10日以内に日本年金機構に提出しなければなりません。
ただし、配偶者が65歳に達したときの不該当届の提出は不要です。(対象者の「年齢」は、把握できているから)
ちなみに、不該当の事由が、加給年金額対象者が死亡した、生計維持の状態がやんだ、離婚又は婚姻の取消をしたというときは、不該当届を提出しなければなりません。
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H21年出題>
老齢厚生年金の受給権者は、加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき、子(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が20歳に達したときは、10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】 ×
不該当の事由が「年齢」の場合は、不該当届の提出は不要です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-68
R1.12.26 R1国年/遺族基礎年金の受給権消滅
和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「遺族基礎年金の受給権消滅」についてです。
 R1国年法(問2)より
R1国年法(問2)より
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となったとしても、当該子の受給権は消滅しない。

【解答】 ×
死亡した被保険者の兄の養子(ということは、叔父の養子)となったときは、子の受給権は消滅します。
ポイント★
養子になったときは遺族基礎年金の受給権は消滅。
※ただし、養子でも、直系血族又は直系姻族の養子になった場合は受給権は消滅しません。「叔父」は直系ではなく傍系なので、叔父の養子になった場合は受給権は消滅します。
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H16年出題>
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【解答】 ○
夫の父(ということは直系姻族)の養子になった場合、遺族基礎年金の受給権は消滅しません。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-67
R1.12.24 R1健保/全国健康保険協会の決算
和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「全国健康保険協会の決算」についてです。
 R1健保法(問1)より
R1健保法(問1)より
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これを当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

【解答】 ○
全国健康保険協会(協会)の決算のルールです。
財務諸表等をいつまでに(決算完結後2か月以内)、どこに(厚生労働大臣に)提出し、何が必要か(承認を受ける)をチェックしてください。
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H22年出題>
全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表、事業報告書及び決算報告書を作成し、それらについて、監事の監査のほか、厚生労働大臣の選任する会計監査人の監査を受け、それらの意見を付けて、決算完結後1か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を得なければならない。

【解答】 ×
決算完結後1か月以内ではなく、「2か月以内」です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-66
R1.12.23 R1徴収/保険関係成立届の提出先
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「保険関係成立届の提出先」についてです。
 R1徴収法(労災問10)より
R1徴収法(労災問10)より
一元適用事業であって労働保険事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、保険関係成立届を所轄公共職業安定所長に提出することとなっている。

【解答】 ○
一元適用事業で労働保険事務組合に事務処理を委託しない事業の保険関係成立届は
→ 所轄労働基準監督署長に提出
→ ただし、雇用保険に係る保険関係のみが成立する事業は、所轄公共職業安定所長に提出
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H28年出題>
① 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
② 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

【解答】
① ○
一元適用事業・労働保険事務組合に委託なし(雇用保険のみが成立している事業を除く。)
→ 所轄労働基準監督署長
② ○
一元適用事業・労働保険事務組合に委託あり
→ 所轄公共職業安定所長
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(雇用保険法)
R2-65
R1.12.21 R1雇用/高年齢雇用継続給付
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「高年齢雇用継続給付」についてです。
 R1雇用保険法(問6)より
R1雇用保険法(問6)より
60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

【解答】 ○
60歳に達した日に算定基礎期間が5年未満の場合でも、その後継続雇用され5年に達した場合は、その時点から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
支給されるのは、5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月までです。(翌月から、とか、前月まで、などと迷わないように)
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H22年出題>
60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。

【解答】×
「60歳に達した日の属する月に遡って支給」の部分が間違いです。遡りません。
「5年に達する日の属する月」から支給されます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-64
R1.12.19 R1労災/社会復帰促進等事業
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「社会復帰促進等事業」についてです。
 R1労災保険法(問7)より
R1労災保険法(問7)より
政府が労災保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について行う社会復帰促進等事業として誤っているものは、次のうちどれか。
A 被災労働者に係る葬祭料の給付
B 被災労働者の受ける介護の援護
C 被災労働者の遺族の就学の援護
D 被災労働者の遺族が必要とする資金の貸付けによる援護
E 業務災害の防止に関する活動に対する援助

【解答】 A
「葬祭料」の給付は、社会復帰促進等事業としてではなく、「保険給付」として行われます。
この問題のポイント!
労災保険法の第一(主たる)の目的は「保険給付」を行うことです。保険給付は、①業務災害に関する保険給付、②通勤災害に関する保険給付、③二次健康診断等給付の3種類があります。
また、第二(従たる)の目的が、「社会復帰促進等事業」です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)
R2-63
R1.12.17 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その4
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。
 R1労働安全衛生法(問8)より
R1労働安全衛生法(問8)より
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題】
乙社は、自社の労働者、丙社及び丁社の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織を設置しなければならないが、この協議組織には、乙社が直接契約を交わした丙社のみならず、丙社が契約を交わしている丁社も参加させなければならず、丙社及び丁社はこれに参加しなければならない。

【解答】 ○
この問題のポイント!
協議組織の設置及び運営は、特定元方事業者の義務です。
※特定元方事業者とは、建設業又は造船業の元方事業者
特定元方事業者である乙社は協議組織を設置しなければなりません。
また、協議組織は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加することになっています。関係請負人である丙社及び丁社は参加しなければなりません。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H18年出題>
製造業に属する事業(労働安全衛生法第15条第1項に規定する特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び運営を行うことに関する措置、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

【解答】 ×
協議組織の設置及び運営の措置を講ずる義務があるのは、特定元方事業者(建設業又は造船業の元方事業者)です。
製造業(造船業以外)の元方事業者には、協議組織の設置及び運営の義務はありません。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-62
R1.12.12 R1労基/休業手当の性質
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「休業手当の性質」についてです。
 R1労基(問5)より
R1労基(問5)より
労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。

【解答】 ×
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき休業の場合は、休業手当の支払を使用者に義務付けています。
休業手当は「賃金」と解され、その支払いについては第24条が適用されます。
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H19年出題】
労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

【解答】 ○
ポイント!
休業手当は労働基準法第11条の「賃金」
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-61
R1.12.11 R1社一/国民健康保険法の出産と死亡
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社保一般常識「国民健康保険法の出産と死亡」についてです。
 R1社一(問6)より
R1社一(問6)より
(国民健康保険法に関する問題)
市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

【解答】 ○
出産育児一時金の支給、葬祭費の支給(葬祭の給付)については、給付の要件や内容等は、保険者ごとに条例又は規約で定められる点がポイントです。
また、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H26年出題 ①】(国民健康保険法に関する問題)
保険者は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
【H26年出題 ②】(国民健康保険法に関する問題)
保険者は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。
【H26年出題 ③】(国民健康保険法に関する問題)
保険者は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

【解答】
【H26年出題 ①】(国民健康保険法に関する問題)
<解答> ×
移送費は法定の給付ですので、条例や規約でその全部又は一部を行わないことはできません。
【H26年出題 ②】(国民健康保険法に関する問題)
<解答> ○
傷病手当金の支給は任意ですので、条例又は規約の定めるところによって行うことができる給付です。
【H26年出題 ③】(国民健康保険法に関する問題)
<解答> ×
葬祭費の支給(葬祭の給付)については、給付の要件や内容等は、保険者ごとに条例又は規約で定められ、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働一般常識)
R2-60
R1.12.10 R1労一/労働契約法「労働契約の内容の理解の促進」
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働一般常識「労働契約法「労働契約の内容の理解の促進」」についてです。
 R1労一(問3)より
R1労一(問3)より
労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。

【解答】 ×
労働契約の締結前に説明等をする場面も含まれます。
締結前から、締結の場面、変更する場面、各場面が広く含まれています。
※労働基準法第15条第1項の「労働条件の明示義務」は、労働契約の締結時のルールです。
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H23年出題】
労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含め、労働契約の内容については、できるだけ書面により確認するものとされている。

【解答】 ○
労働契約法第4条第2項では、労働者と使用者は、労働契約の内容をできる限り書面で確認することが規定されています。
「期間の定めのある労働契約に関する事項」が含まれていることに、注目してください。更新の有無や更新の判断基準があいまいだと、トラブルになる可能性が高いためです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-59
R1.12.8 R1厚年/特別支給の老齢厚生年金の要件
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年法「特別支給の老齢厚生年金の要件」についてです。
 R1厚年法(問1)より
R1厚年法(問1)より
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。

【解答】 ○
特別支給の老齢厚生年金(=60歳代前半の老齢厚生年金)は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていて、かつ厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です。
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H24年出題】
老齢厚生年金の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上必要であり、同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、当該被保険者期間が1年以上必要である。

【解答】 ○
65歳から支給される老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月あれば支給されます。特別支給の老齢厚生年金とは違う点です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-58
R1.12.5 R1国年/老齢基礎年金の繰上げと繰下げの違い
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「老齢基礎年金の繰上げと繰下げの違い」についてです。
 R1国年法(問5)より
R1国年法(問5)より
老齢基礎年金の支給の繰上げについては国民年金法第28条において規定されているが、老齢基礎年金の支給の繰下げについては、国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている。

【解答】 ×
繰上げと繰下げが逆です。
・繰上げ → 国民年金法附則9条の2で当分の間の措置として規定されている
・繰下げ → 国民年金法第28条で規定されている
 コチラの問題もチェック
コチラの問題もチェック
【H23年出題】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。

【解答】 ×
国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されているのは、繰上げ支給です。繰下げ支給の規定は附則ではなく本則です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-57
R1.12.4 R1健保/強制適用事業所について
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「強制適用事業所」についてです。
 R1健保法(問4)より
R1健保法(問4)より
代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とならない。

【解答】 ×
法人の事業所は、業種を問わず、従業員1人だけでも強制適用です。
健康保険(厚生年金保険も)の場合、社長も「法人に雇われる者」として、強制加入となりますので、社長1人だけで他に従業員がいない法人でも強制適用事業所となります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-56
R1.11.29 R1徴収/認定決定の納期限
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「認定決定の納期限」についてです。
 R1徴収法(労災問9)より
R1徴収法(労災問9)より
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

【解答】 ×
確定保険料の認定決定の通知を受けた場合の納期限は、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内です。(概算保険料の認定決定も同じです。)
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H26年出題>
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、 事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知するが、この通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額がその決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは所轄都道府県歳入徴収官の決定した労働保険料を、その通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。

【解答】 ○
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(雇用保険法)
R2-55
R1.11.26 R1雇用/失業の認定日の変更
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「失業の認定日の変更」についてです。
 R1雇用保険法(問3)より
R1雇用保険法(問3)より
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。

【解答】 ○
就職する場合などやむを得ない理由の場合は、管轄公共職業安定所長に申し出ることによって、失業の認定日の変更ができます。
 コチラの問題もチェック!
コチラの問題もチェック!
<H27年出題>
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。

【解答】 ×
配偶者の死亡はやむを得ない理由に当たるため、認定日の変更の申出ができます。
また、認定日の変更の申出を事前に行った場合は、その申し出をした日に、その前日までの各日について失業の認定を受けることができます。
問題文のように、失業の認定日後に申し出た場合は、当該失業の認定日における失業の認定の対象になる日に加えて、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-54
R1.11.25 R1労災/傷病特別支給金の支給額
和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「傷病特別支給金の支給額」についてです。
 R1労災保険法(問6)より
R1労災保険法(問6)より
傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

【解答】 ○
「傷病特別支給金」は傷病(補償)年金(保険給付)に上乗せされる特別支給金のうちの一般の特別支給金です。
問題文のとおり、傷病等級に応じて定額の「一時金」で支給されるのがポイントです。
ちなみに、特別支給金のうち「ボーナス特別支給金」は、「算定基礎日額(ボーナスをもとに算定される)」を使って計算される年金です。
| 特別支給金 | ボーナス特別支給金 | 傷病特別年金 | 1級→算定基礎日額の313日分 2級→ 277日分 3級→ 245日分 |
| 一般の特別支給金 | 傷病特別支給金 (一時金) | 1級→114万円 2級→107万円 3級→100万円 | |
| 保険給付 | 傷病(補償)年金 | 1級→給付基礎日額の313日分 2級→ 277日分 3級→ 245日分 | |
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)
R2-53
R1.11.22 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その3
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。
 R1労働安全衛生法(問8)より
R1労働安全衛生法(問8)より
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題】
丁社の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法に違反していると認めるときに、その是正のために元方事業者として必要な指示を行う義務は、丙社に課せられている。

【解答】 ×
元方事業者として必要な指示を行う義務は、「元方事業者」の乙社に課せられます。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H13年選択式>
労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な< A >を行なわなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、< B >適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、< A >の義務を負わせることとしたものである。

【解答】 A 指示 B 業種の如何にかかわらず
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-52
R1.11.20 R1労基/労働契約締結時の労働条件の明示
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労基法「労働契約締結時の労働条件の明示」についてです。
 R1労基(問4)より
R1労基(問4)より
労働契約の期間に関する事項は、書面等により明示しなければならないが、期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい。

【解答】 ×
 「労働契約の期間」に関する事項は、労働契約を締結する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」で、書面の交付等による明示が必要です。
「労働契約の期間」に関する事項は、労働契約を締結する際に必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」で、書面の交付等による明示が必要です。
期間の定めのある労働契約の場合は「その期間」を明示し、期間の定めをしない場合は「その旨」の明示が必要です。
 問題文の「期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい」の部分が誤りです。期間の定めがない場合は、「定めがない」と明示しなければならない。
問題文の「期間の定めをしない場合においては期間の明示のしようがないので、この場合においては何ら明示しなくてもよい」の部分が誤りです。期間の定めがない場合は、「定めがない」と明示しなければならない。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H25年出題>
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。

【解答】 ○
更新する場合がある有期雇用については、労働契約締結時に「更新の基準」を明示しなければならないのがポイントです。
更新の判断基準を明示することによって、労働者が自身の雇用の継続の可能性をある程度予見できるようになるからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-51
R1.11.17 R1社一/国民健康保険・審査請求
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社保一般常識「国民健康保険・審査請求」についてです。
 R1社一(問6)より
R1社一(問6)より
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(同法附則第10条第1項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

【解答】 ○
 国民健康保険の審査請求は、「国民健康保険審査会」であるのがポイント。
国民健康保険の審査請求は、「国民健康保険審査会」であるのがポイント。
社会保険審査官(社会保険審査会)ではありません。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H21年出題>
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会は、各都道府県に設置する。

【解答】 ○
国民健康保険審査会は、各都道府県に設けられているのがポイントです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働一般常識)
R2-50
R1.11.15 R1労一/平成29年労使間の交渉等に関する実態調査より
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働一般常識「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査より」についてです。
 R1労一(問2)より
R1労一(問2)より
労働組合と使用者(又は使用者団体)の間で締結される労働協約の締結状況をみると、労働協約を「締結している」労働組合は9割を超えている。

【解答】 ○
 「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」からの出題です。
「平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)」からの出題です。
平成29年労使間の交渉等に関する実態調査(厚生労働省)によると、「労働協約を締結している」が94.7%、「締結していない」が4.7%となっています。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H23年出題>
労働協約は、書面に作成されていない場合であっても、その内容について締結当事者間に争いがない場合には、労働組合法第16条に定めるいわゆる規範的効力が生ずる。

【解答】 ×
労働組合法第14条では、労働協約の効力の発生について、「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」と規定されています。
書面に作成されていなければ効力は生じません。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-49
R1.11.14 R1厚年/擬制的任意適用事業所
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「擬制的任意適用事業所」についてです。
 R1厚年法(問4)より
R1厚年法(問4)より
個人経営の青果商である事業主の事業所は、常時5人以上の従業員を使用していたため、適用事業所となっていたが、その従業員数が4人になった。この場合、適用事業所として継続するためには、任意適用事業所の認可申請を行う必要がある。

【解答】 ×
 「任意適用事業所の認可申請」は不要です。
「任意適用事業所の認可申請」は不要です。
個人経営・青果商・常時5人以上の従業員の場合は、強制適用事業所ですが、従業員数が4人になると、強制適用事業所ではなくなります。
しかし、従業員にとっては厚生年金保険の資格が存続する方が有利です。ですので、任意適用事業所の認可申請をしなくても、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、そのまま適用事業所として継続されます。このことを擬制的任意適用事業所といいます。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H19年出題>
強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。

【解答】 ○
擬制的任意適用事業所についての問題です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-48
R1.11.12 R1国年/老齢基礎年金の繰上げ減額率
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「老齢基礎年金の繰上げ減額率」についてです。
 R1国年法(問4)より
R1国年法(問4)より
昭和31年4月20日生まれの者が、平成31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合において、当該支給繰上げによる老齢基礎年金の額の計算に係る減額率は、12%である。

【解答】 ○
 昭和31年4月20日生まれの人は、令和3(2021)年4月に65歳になります。
昭和31年4月20日生まれの人は、令和3(2021)年4月に65歳になります。
老齢基礎年金の繰上げ減額率は、「1,000分の5×繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数」です。
問題の場合ですと、繰上げ請求月の平成31(2019)年4月から、65歳に達する月の前月である令和3(2021)年3月まで、24か月です。
繰上げ減額率は1,000分の5×24=12%となります。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H29年出題>
64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。

【解答】 ×
繰上げ減額率=1,000分の5×12か月で6%となります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-47
R1.11.10 R1健保/共済組合の組合員と健康保険
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健康保険法「共済組合の組合員と健康保険」についてです。
 R1健保法(問3)より
R1健保法(問3)より
国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わない。

【解答】 ○
 共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。共済組合からの保険給付と健康保険の保険給付が二重になるのを避けるため、共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法の保険給付を行わないことになっています。
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。共済組合からの保険給付と健康保険の保険給付が二重になるのを避けるため、共済組合の組合員であるものに対しては、健康保険法の保険給付を行わないことになっています。
なお、健康保険法の保険料も徴収されません。
 コチラの問題もチェックしましょう。
コチラの問題もチェックしましょう。
<H20年出題>
法律によって組織された共済組合の組合員は、共済組合の組合員資格を有したまま健康保険の被保険者となることはない。

【解答】 ×
共済組合の組合員は、同時に健康保険の被保険者でもあります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-46
R1.11.9 R1徴収/労働保険事務組合
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「労働保険事務組合」についてです。
 R1徴収法(雇用問9)より
R1徴収法(雇用問9)より
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。

【解答】 ○
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託できる中小事業主の範囲は覚えておきましょう。
「金融業」の場合、委託できるのは常時使用する労働者が50人以下の事業主です。
社労士受験のあれこれ
令和元年の合格発表。
R2-45
R1.11.8 合格発表に思うこと
本日は、令和元年度第51回社労士試験の合格発表でした。
合格通知を手にされた方おめでとうございます!
これまでの努力が実り、喜びもひとしおだと思います。
残念ながら悔しい思いをされている方。
強く信じて、強く願ったことは実現すると思っています。
「絶対合格するんだ!」と強く思い、努力すれば、きっと合格します。
これからは口にする言葉も「ダメだー、分からない」ではなく、「覚えられる、分かる、絶対受かる」ですよね。口に出した言葉は叶ってしまうので大切。
この先にある「合格」を信じて。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(雇用保険法)
R2-44
R1.11.7 R1雇用/不服申立て(審査請求)
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「不服申立て(審査請求)」についてです。
 R1雇用保険法(問3)より
R1雇用保険法(問3)より
公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。

【解答】 ○
 チェックポイント!
チェックポイント!
 審査請求期間
審査請求期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまで
 雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる
雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-43
R1.11.6 R1労災/特別支給金と保険給付の違い
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「特別支給金と保険給付の違い」についてです。
 R1労災保険法(問6)より
R1労災保険法(問6)より
特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

【解答】 ×
保険給付と違って、特別支給金は、譲渡、差押えの対象となります。
 「特別支給金と保険給付の違い」はよく問われる論点です。コチラの問題もチェックしましょう。
「特別支給金と保険給付の違い」はよく問われる論点です。コチラの問題もチェックしましょう。
<H22年出題>
特別支給金は、関連する保険給付と併せて支給されるものであるが、他の公的給付の給付が併給されて労災保険の保険給付の額が減額される場合でも、特別支給金の支給額が減額されることはない。

【解答】 ○
同一の事由で労災保険の給付と社会保険の年金が支給される場合、労災保険の保険給付は減額されますが、特別支給金の支給額は減額されません。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)
R2-42
R1.11.2 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その2
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。
 R1労働安全衛生法(問8)より
R1労働安全衛生法(問8)より
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題】
乙社は、特定元方事業者として統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせなければならない。

【解答】 ○
 乙社は「特定元方事業者」に当たる。
乙社は「特定元方事業者」に当たる。
特定元方事業者とは → 「特定事業(建設業又は造船業)」の元方事業者のこと。
 乙社には統括安全衛生責任者の選任義務がある
乙社には統括安全衛生責任者の選任義務がある
元方事業者の労働者と関係請負人の労働者の合計が50人以上(原則)の事業場が対象
 統括安全衛生責任者の職務
統括安全衛生責任者の職務
元方安全衛生管理者を指揮させること
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-41
R1.10.30 R1労基/解雇予告期間
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労基「解雇予告期間」についてです。
 R1労基(問4)より
R1労基(問4)より
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。

【解答】 ×
予告期間は労働日ではなく「暦日」で計算されます。
 平成26年に具体的な日数計算の問題が出題されています。確認しましょう。
平成26年に具体的な日数計算の問題が出題されています。確認しましょう。
(H26年出題)
平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働基準法第20条第1項に抵触しない。

【解答】 ×
9月30日解雇しようとする場合は、8月31日までに予告しなければなりません。
予告した当日(8月31日)は予告期間の「30日」の計算には入りませんので注意しましょう。8月31日は、予告した時点で既に何時間か過ぎていて丸1日ないからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社保一般常識)
R2-40
R1.10.29 R1社一/社会保険労務士法(紛争解決手続代理業務)
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社一「社会保険労務士法(紛争解決手続代理業務)」についてです。
 R1社一(問5)より
R1社一(問5)より
すべての社会保険労務士は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあっせんの手続について相談に応じること、当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと、当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる。

【解答】 ×
「すべての社会保険労務士」が誤りです。紛争解決手続代理業務を行うことができるのは、特定社会保険労務士のみです。
 平成19年に選択式で出題されています。確認しましょう。
平成19年に選択式で出題されています。確認しましょう。
(H19年選択式)
社会保険労務士法第2条第2項に規定されている紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に< A >を行うことが含まれる。
ただし、上記の紛争解決手続代理業務を行うことができる社会保険労務士は、 < B >に合格し、かつ、社会保険労務士法第14条の11の3第1項の規定による紛争解決手続代理業務の付記を受けた社会保険労務士である< C >社会保険労務士に限られる。

【解答】
A 和解の交渉 B 紛争解決手続代理業務試験 C 特定
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働一般常識)
R2-39
R1.10.28 R1労一/労働費用(就労条件総合調査)
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労一「労働費用(就労条件総合調査)」についてです。
 R1労一(問1)より
R1労一(問1)より
本問は、「平成28年就労条件総合調査(厚生労働省)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。
(問題)
「法定福利費」に占める割合を企業規模計でみると、「厚生年金保険料」が最も多く、「健康保険料・介護保険料」、「労働保険料」がそれに続いている。

【解答】 ○
 厚生年金保険料の保険料率が一番高いことを思うと、納得いくと思います。
厚生年金保険料の保険料率が一番高いことを思うと、納得いくと思います。
ちなみに、厚生年金保険料が「法定福利費」に占める割合は、企業規模計で54.3%です。
 用語の定義(厚生労働省ホームページより)
用語の定義(厚生労働省ホームページより)
「労働費用」とは → 「使用者が労働者を雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)」のこと。
★現金給与額、法定福利費、法定外福利費、現物給与の費用、退職給付等の費用 等
法定福利費 | 法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分) ★健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働保険料 等 |
法定外福利費 | 法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用 ★住居に関する費用、医療保健に関する費用、食事に関する費用、慶弔見舞い等の費用 等 |
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-38
R1.10.27 R1厚年/障害手当金と障害厚生年金
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚年「障害手当金と障害厚生年金」についてです。
 R1厚年法(問10)より
R1厚年法(問10)より
障害厚生年金の支給を受けている者が、当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により、障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合は、当該障害厚生年金と当該障害手当金を併給することができる。なお、当該別の傷病に係る初診日が被保険者期間中にあり、当該初診日の前日において、所定の保険料納付要件を満たしているものとする。

【解答】 ×
 障害厚生年金と障害手当金は原則として併給できません。
障害厚生年金と障害手当金は原則として併給できません。
★ 障害の程度を定めるべき日において次のいずれかに該当する場合は、障害手当金は支給されません。
① 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
② 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
③ 当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律若しくは労働基準法、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
 この問題の場合、①に該当するので障害手当金は支給されません。ちなみに①の年金たる保険給付とは「老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金」のことです。
この問題の場合、①に該当するので障害手当金は支給されません。ちなみに①の年金たる保険給付とは「老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金」のことです。

厚生年金保険の年金(老齢、障害、遺族)・国民年金の年金(老齢、障害、遺族)・労災保険の障害補償給付、障害給付の受給権者には、「障害手当金」は支給されません。

ただし、障害厚生年金(障害基礎年金)の受給権者の場合は、例外があります。

 こんな問題も出題されています。
こんな問題も出題されています。
【H18年出題】
障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。

【解答】 ○
障害厚生年金の受給権者でも、最後に障害等級に該当しなくなった日から障害状態に該当することなく3年を経過した者(現に障害状態に該当しない者に限る。)には、障害手当金が支給されることがあります。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-37
R1.10.26 R1国年/老齢基礎年金繰下げのルール
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国年法「老齢基礎年金繰下げのルール」についてです。
 R1国年法(問4)より
R1国年法(問4)より
65歳に達し老齢基礎年金の受給権を取得した者であって、66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。

【解答】 ○
 老齢基礎年金の繰下げの申出の条件を整理しておきましょう。
老齢基礎年金の繰下げの申出の条件を整理しておきましょう。
 又は
又は の場合は、繰下げの申出はできない。
の場合は、繰下げの申出はできない。
 65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき
65歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき
 65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき
65歳に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったとき
問題文では、「65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となった」とあるので、 に当てはまり、老齢基礎年金の繰下げの申出はできません。
に当てはまり、老齢基礎年金の繰下げの申出はできません。
 平成21年には選択式で出題されています。
平成21年には選択式で出題されています。
【H21年選択式】
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が< A >に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付 (< B >を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(< C >を支給事由とするものを除く。)をいう。以下同じ。)の受給権者であったとき、又は< A >に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。

【解答】
A 65歳 B 付加年金 C 老齢
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-36
R1.10.24 R1健保/出産手当金の時効
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健保法「出産手当金の時効」についてです。
 R1健保法(問4)より
R1健保法(問4)より
出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

【解答】 ×
 出産手当金の時効は2年ですが、時効の起算日は「出産した日の翌日から」は誤り。正しくは「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。
出産手当金の時効は2年ですが、時効の起算日は「出産した日の翌日から」は誤り。正しくは「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。
出産手当金は、「労務に服さなかった日」に対して支給されるからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-35
R1.10.23 R1徴収/労働保険料の種類
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「労働保険料の種類」についてです。
 R1徴収法(労災問8)より
R1徴収法(労災問8)より
労働保険徴収法第10条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料及び印紙保険料の計5種類である。

【解答】 ×
一般保険料、第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料、第3種特別加入保険料、印紙保険料、特例納付保険料の6種類です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(雇用保険法)
R2-34
R1.10.21 R1雇用/公共職業訓練を受けるときの失業の認定
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険「公共職業訓練を受けるときの失業の認定」についてです。
 R1雇用保険法(問3)より
R1雇用保険法(問3)より
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

【解答】 ×
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとする、です。
よく出る問題です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-33
R1.10.20 R1労災/特別加入者の特別支給金
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災「特別加入者の特別支給金」についてです。
 R1労災保険法(問6)より
R1労災保険法(問6)より
特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

【解答】 ×
特別加入者にも傷病特別支給金は支給されますが、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金は支給されません。なぜなら、特別加入者にはボーナス(=特別給与)の概念が無いからです。
| 労働者 | 特別加入者 | ||
| 特別支給金 | ボーナス特別支給金 | 傷病特別年金 | なし |
| 一般の特別支給金 | 傷病特別支給金 | 傷病特別支給金 | |
| 保険給付 | 傷病(補償)年金 | 傷病(補償)年金 | |
 平成28年にも同様の問題が出ています。
平成28年にも同様の問題が出ています。
【H28年問題より】
特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

【解答】○
特別加入者には、特別給与を算定基礎とする特別支給金は支給されません。
しかし、特別支給金のうち、「一般の特別支給金」は特別加入者にも支給されますので、注意してくださいね。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)
R2-32
R1.10.18 R1安衛/建設工事現場における安全衛生管理その1
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「建設工事現場における安全衛生管理」についてです。
 R1労働安全衛生法(問8)より
R1労働安全衛生法(問8)より
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業 者。常時10人の労働者が現場作業に従事している。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20人の労働者が現場作業に従事している。
【問題】
丙社及び丁社は、それぞれ安全衛生責任者を選任しなければならない。

【解答】 ○
「安全衛生責任者」とは?
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うもの」とは下請事業者のこと。下請事業者は「安全衛生責任者」を選任しなければなりません。
問題文でいうと、一次下請事業者の丙社と二次下請事業者の丁社に安全衛生責任者を選任する義務があります。
安全衛生責任者は、統括安全衛生責任者との連絡等の職務を行います。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-31
R1.10.17 R1労基/1か月単位の変形労働時間制
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「1か月単位の変形労働時間制」についてです。
 R1労働基準法(問2)より
R1労働基準法(問2)より
1か月単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は16時間、1週間の労働時間の限度は60時間の範囲内で各労働日の労働時間を定めなければならない。

【解答】 ×
1か月単位の変形労働時間については、1日についても、1週間についても、労働時間の上限は設けられていません。
 1年単位の変形労働時間制については、1日、1週間の労働時間の上限が定められています。比較しましょう。平成30年に出題されています。
1年単位の変形労働時間制については、1日、1週間の労働時間の上限が定められています。比較しましょう。平成30年に出題されています。
<H30年出題>
いわゆる1年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

【解答】 ×
1週間の労働時間の限度は54時間ではなく、52時間です。
1年単位の変形労働時間制の場合は、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間と、それぞれ上限が設定されているのがポイントです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(介護保険法)
R2-30
R1.10.15 R1社一/介護保険・要介護認定の効力
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、介護保険法「要介護認定の効力」についてです。
 R1一般常識(問7)より
R1一般常識(問7)より
要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。

【解答】 ○
 平成23年に選択式で出題されています。
平成23年に選択式で出題されています。
<問題>
要介護認定は、< A >その効力を生じ、要介護認定有効期間は、(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。
(1) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
(2) 6月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、< B >で月を単位として市町村が定める期間)
要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期間を要介護認定有効期間とする。

【解答】
A その申請のあった日にさかのぼって
B 3月間から12月間までの範囲内
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働者派遣法)
R2-29
R1.10.14 R1労働一般常識/派遣労働者の最低賃金
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働一般常識「派遣労働者の最低賃金」についてです。
 R1一般常識(問4)より
R1一般常識(問4)より
労働者派遣法第44条第1項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金が適用される。

【解答】 ○
派遣労働者には「派遣先」の最低賃金が適用されます。
例えば、派遣元が兵庫県で、派遣先の事業の事業場が大阪府の場合は、大阪府の最低賃金が適用されます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-28
R1.10.12 R1厚年法/強制適用事業所と任意適用事業所
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「強制適用事業所と任意適用事業所」についてです。
 R1厚年法(問4)より
R1厚年法(問4)より
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。

【解答】 ×
「法人」の事業所の場合は、常時1人でも従業員を使用すれば業種関係なく今日背適用事業所となりますが、「個人経営」の事業所の場合は、「業種」と「5人以上」か「5人未満」かで変わりますので注意しましょう。
問題文ですと、業種が「農林水産業」の個人経営ですので、常時5人以上でも強制適用事業所にはなりません。
適用事業所となるには、厚生労働大臣の認可が必要です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-27
R1.10.9 R1国年法/障害基礎年金・初診日の要件
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「障害基礎年金・初診日の要件」についてです。
 R1国年法(問2)より
R1国年法(問2)より
傷病について初めて医師の診療を受けた日において、保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は、障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしている場合でも、障害基礎年金が支給されることはない。

【解答】 ×
障害基礎年金は、以下の3つの要件を満たせば、障害認定日に受給権が発生します。
①初診日要件を満たしていること
初診日に
1.被保険者であること。
2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
②障害認定日要件を満たしていること
障害認定日に障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
③保険料納付要件を満たしていること
 問題文は、初診日に保険料の納付猶予の適用を受けているという前提ですが、納付猶予の適用を受けていても被保険者ですので初診日要件は満たしています。
問題文は、初診日に保険料の納付猶予の適用を受けているという前提ですが、納付猶予の適用を受けていても被保険者ですので初診日要件は満たしています。
さらに、障害認定日に1級又は2級に該当し、保険料納付要件を満たしているということなので、障害基礎年金の支給要件は満たしています。
「障害基礎年金が支給されることはない。」は誤りです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(健康保険法)
R2-26
R1.10.8 R1健保法/被扶養者に関する保険給付
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、健康保険法「被扶養者に関する保険給付」についてです。
 R1健保法(問2)より
R1健保法(問2)より
67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給される。

【解答】 ×
典型的なひっかけ問題です。慌てて解答しないようにしてくださいね。
67歳の「被扶養者」が生活療養を受けた場合は、被保険者に対し、入院時生活療養費ではなく、「家族療養費」が支給されます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-25
R1.10.5 R1徴収法/労災保険暫定任意適用事業の保険関係消滅
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、徴収法「労災保険暫定任意適用事業の保険関係消滅」についてです。
 R1徴収法(労災問10)より
R1徴収法(労災問10)より
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。

【解答】 ×
「労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。」の部分が誤りです。
労災保険暫定任意適用事業の場合、そもそも労災保険の加入が任意ですので、申請によって保険関係を消滅させることができます。
しかし、労働者の立場から見ると、労災保険の保護が無くなることになるので、事業主は保険関係消滅申請書に労働者の同意書を添付しなければなりません。
※なお、労災保険に任意加入するときは、同意書は要りません。労働者が労災保険料を負担する必要が無いからです。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(雇用保険法)
R2-24
R1.10.4 R1雇用保険法/早期再就職者に係る再就職手当
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、雇用保険法「早期再就職者に係る再就職手当」についてです。
 R1雇用保険法(問5)より
R1雇用保険法(問5)より
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。

【解答】 ×
10分の6ではなく、10分の7です。
<再就職手当の額>
支給残日数が3分の2以上(早期再就職者)→ 支給残日数×10分の7×基本手当日額
支給残日数が3分の1以上 → 支給残日数×10分の6×基本手当日額
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-23
R1.10.2 R1労災保険法/指定病院等を変更するとき
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労災保険法「指定病院等の変更」についてです。
 R1労災保険法(問5)より
R1労災保険法(問5)より
療養の給付を受ける労働者は、当該療養の給付を受けている指定病院等を変更しようとするときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出するものとされている。

【解答】 ○
この問題のポイントは、「新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出」の部分です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働安全衛生法)
R2-22
R1.10.1 R1安衛法/健康診断の結果の通知
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、安衛法「健康診断の結果の通知」についてです。
 R1安衛法(問10)より
R1安衛法(問10)より
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。

【解答】 ×
「健康診断を受けた労働者」に対して、異常の所見の有無に関係なく通知しなければなりません。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働基準法)
R2-21
R1.9.30 R1労基法/解雇制限のルール
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働基準法「解雇制限」についてです。
 R1労基法(問4)より
R1労基法(問4)より
使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

【解答】 ○
第19条の解雇制限は、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間に適用されます。「休業」する期間は解雇制限がかかりますが、産前休業を請求しないで「就労」している場合は、解雇制限はかかりません。
※産前休業は労働者からの請求が要件です。忘れないようにしてくださいね。
☆同様の問題が平成29年に出題されています。
コチラの記事もご覧ください。

社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(社会保険労務士法)
R2-20
R1.9.27 R1一般常識/社労士法・補佐人の業務
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、社会保険労務士法「補佐人の業務」についてです。
 R1一般常識(問5)より
R1一般常識(問5)より
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人に代わって出頭し、陳述をすることができる。

【解答】 ×
「弁護士である訴訟代理人に代わって」ではなく、弁護士である訴訟代人とともに出頭し、陳述をすることができる、です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労働契約法)
R2-19
R1.9.26 R1一般常識/労契法・「懲戒」の意味
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、労働契約法第15条の「懲戒」についてです。
 R1一般常識(問3)より
R1一般常識(問3)より
労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義である、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。

【解答】 ○
■労働基準法 → 「制裁」(=懲戒)の定めをする場合は、就業規則に記載しなければならない。(相対的必要記載事項)
(懲戒するには、あらかじめ就業規則に懲戒の種別及び事由を定めておく必要がある)
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(厚生年金保険法)
R2-18
R1.9.24 R1厚年/遺族厚生年金・夫の要件
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、厚生年金保険法「遺族厚生年金・夫の要件」についてです。
 R1厚年(問2)より
R1厚年(問2)より
被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54歳の夫と21歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。

【解答】 ×
54歳の夫は遺族厚生年金を受けることはできません。
夫は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、55歳以上であることが要件です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(国民年金法)
R2-17
R1.9.23 R1国年/被保険者期間のカウント
令和元年の問題を振り返っています。
今日は、国民年金法「被保険者期間」についてです。
 R1国年(問3)より
R1国年(問3)より
平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

【解答】 ×
平成11年4月1日生まれの者は、誕生日の前日の平成31年3月31日に20歳に達し、その日に第1号被保険者の資格を取得します。
被保険者期間は、「月単位」で、資格を取得した日の属する月から算入されますので、問題文の場合は、平成31年3月から被保険者期間に算入されます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/ご質問いただきました(健保)
R2-16
R1.9.22 R1健康保険法/被扶養者の認定
和元年の問題を振り返っています。
健康保険法の「被扶養者の認定」についてご質問がありました。ありがとうございます。
今日はその問題を解いてみます。
 R1健康保険法(問5)より
R1健康保険法(問5)より
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という。)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当する。

【解答】 ○
認定対象者が、被保険者と同一世帯に属している場合は、認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者である場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の2分の1未満であれば原則として被扶養者に該当することになっています。
 この問題は、年収が被保険者の2分の1未満という要件が抜けているので誤りではないか?というご質問を頂きました。
この問題は、年収が被保険者の2分の1未満という要件が抜けているので誤りではないか?というご質問を頂きました。
認定対象者の年収が被保険者の2分の1以上の場合は、原則として被扶養者には該当しません。
しかし、被保険者の収入の2分の1以上でも一定の場合は、被扶養者に該当するものとして差し支えないという例外も設けられています。(一定の場合というのが問題文にある〝当該世帯の生計の状況を総合的に勘案し・・・〟の部分です。)
受験対策としては、「例外」がある、ということをおさえておけばいいかと思います。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(徴収法)
R2-15
R1.9.21 R1徴収法/概算保険料の延納
令和元年の問題を振り返っています。
今日は徴収法の基本的な問題を解いてみます。
 R1徴収法(労災問8)より
R1徴収法(労災問8)より
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれている。

【解答】 ×
継続事業、一括有期事業の場合、延納の対象から除外されるのは、当該保険年度の「10月1日」以降に保険関係が成立した場合です。
ちなみに、保険関係成立日が4月1日から5月31日までの場合は3回、6月1日から9月30日までの場合は2回に分けて延納できます。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(雇用保険法)
R2-14
R1.9.18 R1雇用保険法/就業手当と再就職手当の違い
令和元年の問題を振り返っています。
今日は雇用保険法の基本的な問題を解いてみます。
 R1雇用保険法(問5)より
R1雇用保険法(問5)より
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。

【解答】 ×
「厚生労働省令で定める安定した職業」がキーワードです。安定した職業に就いた者が受給できるのは、就業手当ではなく再就職手当です。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労災保険法)
R2-13
R1.9.17 R1労災保険法より・「療養の給付」は指定病院等で行う
令和元年の問題を振り返っています。
今日は労災保険法の基本的な問題を解いてみます。
 R1労災法(問5)より
R1労災法(問5)より
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(「指定病院等」という。)において行われ、指定病院等に該当しないときは、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、療養の給付は行われない。

【解答】 ○
療養補償給付は、原則として現物給付で行われます。現物給付である「療養の給付」は、指定病院等で行われます。
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院であっても、労災の指定病院等でなければ、労災の療養の給付は行われません。
平成21年にも同様の問題が出題されています。
こちらの記事をどうぞ → R1.5.15 【労災】療養の費用の支給
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(安衛法)
R2-12
R1.9.16 R1安衛法より・雇入れ時の健康診断
令和元年の問題を振り返っています。
今日は安衛法の基本的な問題を解いてみます。
 R1安衛法(問10)より
R1安衛法(問10)より
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないが、医師による健康診断を受けた後、6か月を経過しないものを雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目については、この限りでない。

【解答】 ×
6か月ではなく「3か月」です。
安全衛生法は暗記科目です。少しずつ進めて行きましょう。
社労士受験のあれこれ
R1年出題より/基本問題(労基法)
R2-11
R1.9.15 R1労基法より・1か月単位の変形労働時間制採用ルール
令和元年の問題を振り返っています。
今日は労基法の基本的な問題を解いてみます。
 R1労基法(問2)より
R1労基法(問2)より
1か月単位の変形労働時間制は、就業規則その他これに準ずるものによる定めだけでは足りず、例えば当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と書面により協定し、かつ、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、採用することができる。

【解答】 ×
1か月単位の変形労働時間制は、「労使協定」によるか又は「就業規則その他これに準ずるもの」に定めることによって、採用することができます。
☆「又は」がポイントです。「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」のどちらかでOK。
この問題の場合は、「就業規則その他これに準ずるもの」による定めだけでも足りるということです。
ちなみに、「就業規則に準ずるもの」で採用できるのは、就業規則の作成義務がない常時10人未満の事業場だけです。
・常時10人以上 → 「労使協定」か「就業規則」
・常時10人未満 → 「労使協定」か「就業規則その他これに準ずるもの」
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(国民年金法)
R2-10
R1.9.11 R1選択式(国民年金法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第9回目は、「国民年金法 選択式」です。
 AとBは「積立金の運用の目的」からの出題です。
AとBは「積立金の運用の目的」からの出題です。
★「積立金の運用の目的」は、H20年にも選択式で出題されています。
<参考 H20年選択>
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の < A >のために、< B >から、< C >に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(解答)
A 被保険者の利益 B 長期的な観点 C 安全かつ効率的
 Cは、「指定代理納付者による納付」についての出題です。
Cは、「指定代理納付者による納付」についての出題です。
★クレジットカードの納付に関する規定です。
「保険料の徴収上有利と認められるときに限り」という文言は、「口座振替による納付」でも出てきますので、覚えやすいと思います。
 DとEは「延滞金」からの出題です。
DとEは「延滞金」からの出題です。
どの科目でもよく出題される部分なので、解きやすい問題だったと思います。
といっても、科目ごとに少しずつルールが異なるので、横断的な勉強が効果的です。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(厚生年金保険法)
R2-9
R1.9.10 R1選択式(厚生年金保険法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第8回目は、「厚生年金保険法 選択式」です。
 AとBは「督促、滞納処分」についての出題です。
AとBは「督促、滞納処分」についての出題です。
★Aは、督促状に指定する期限についてですが、よく出題されるところです。
<参考 H25年出題>
保険料等の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合は、この限りでない。
(解答) ○
★Bも平成26年に出題実績があります。
厚生労働大臣から財務大臣に、滞納処分等に係る権限を委任することができます。
委任の要件の中に、「納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること」、「滞納保険料等の額が5000万円以上あること」等があります。
 Cは、「財政の現況及び見通しの作成」についての出題です。
Cは、「財政の現況及び見通しの作成」についての出題です。
「保険料水準固定方式」をとっているので、調整するのは「保険給付の額」の方と考えればスムーズだと思います。
 DとEは「年金の端数処理」からの出題です。
DとEは「年金の端数処理」からの出題です。
こちらの記事をどうぞ。(国民年金法ですが、内容は同じです。)

社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(健康保険法)
R2-8
R1.9.9 R1選択式(健康保険法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第7回目は、「健康保険法 選択式」です。
 Aは「任意継続被保険者の標準報酬月額」についての出題です。
Aは「任意継続被保険者の標準報酬月額」についての出題です。
「任意継続被保険者」に関するルールは、どこをとっても問題が作りやすいので、「確実に出る」ことを前提に勉強するのがポイントです。
今回の箇所は、択一式でもよく出題されています。H24年には、今回の選択式と全く同じ論点で出題されています。
<参考 H24年出題>
任意継続被保険者の標準報酬月額は、当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。
(解答) ×
3月31日ではなく「9月30日」です。
 BとCは、「傷病手当金の支給を始める日」についての出題です。
BとCは、「傷病手当金の支給を始める日」についての出題です。
ポイント!
・ Bについて
休休休出休 → 連続3日休んでいるので待期は完成している。5日目から傷病手当金が支給されます。
・ Cについて
こちらの記事をどうぞ。

 DとEは「準備金」からの出題です。
DとEは「準備金」からの出題です。
保険者は、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならないことになっています。(予測がつかない支出に備えるため)
協会の保険給付費については、準備金の積立金の基準は「12分の1」(1か月相当分)となります。
平成28年択一式でも出題されています。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(社保一般常識)
R2-7
R1.9.6 R1選択式(社保一般常識)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第6回目は、「社保一般常識 選択式」です。
 AとBは「船員保険」からの出題です。
AとBは「船員保険」からの出題です。
船員保険法。たまーに出題されるので油断できません。しかも選択式で登場は珍しいです。
船員保険法の保険給付は、傷病手当金と行方不明手当金だけしっかり覚えてくださいね、と言うところなので、葬祭料とは意外でした。。。
 Cは、「介護保険法」からの出題です。
Cは、「介護保険法」からの出題です。
地域包括支援センターの目的についての問題ですが、難しいです。。。しっかりおさえてましたと言える方は少ないのでは?
 Dは「国民健康保険法」からの出題です。
Dは「国民健康保険法」からの出題です。
都道府県の責務についての問題。平成30年に都道府県も保険者となったことから、都道府県の役割については、チェックできていたと思います。
 Eは「確定拠出年金法」からの出題です。
Eは「確定拠出年金法」からの出題です。
「70歳」を覚えているかどうかがポイントでしょうか。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(労働一般常識)
R2-6
R1.9.5 R1選択式(労働一般常識)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第5回目は、「労働一般常識 選択式」です。
 AとBは「技能検定」からの出題です。
AとBは「技能検定」からの出題です。
「技能検定制度」は平成21年に択一式で出題されていますが、社労士の受験対策としては、それほど深く入り込む分野ではありません。
ですので、今回の問題については空欄を埋めるのに迷った方が多かったのでは?
Bのヒントは「若者」ですが、年齢を選ぶのに苦労されたと思います。。。
 Cは、「女性活躍推進法」からの出題です。
Cは、「女性活躍推進法」からの出題です。
認定マークの名称、くるみんは子育てサポート企業の証ですので、それ以外の選択肢の中で選べたでしょうか?
 DとEは「就業構造基本調査」からの出題です。、
DとEは「就業構造基本調査」からの出題です。、
これも「バッチリおさえてました!」と言える方はかなり少ないのでは?
しかし、バッチリとまではいかなくても、昨今の社会情勢から考えて、なんとなくこれくらいかな?と解ける感じでしょうか・・・。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(雇用保険法)
R2-5
R1.9.4 R1選択式(雇用保険法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第4回目は、「雇用保険法 選択式」です。
【雇用保険法】
 AとBは「待期」からの出題です。
AとBは「待期」からの出題です。
A、Bどちらも、択一式でも問われる論点です。
★ 待期は求職の申込をした日以後、失業している日が「7日」で満了です。
(待期のポイント!)
・待期には、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む
・通算7日でOK(連続7日でなくてもよい)
<参考 H26年択一>
受給資格者が求職の申込みをした日の翌日から3日間、疾病により職業に就くことができなくなったときは、他の要件を満たす限り、当該求職の申込をした日の11日目から基本手当が支給される。
(解答) ×
待期は求職の申込をした日以後(求職の申込をした日から数える)、負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含んで7日で満了します。この問題の場合は、8日目から基本手当が支給されます。
 C、D、Eは、「育児休業給付の支給要件」に関する問題です。
C、D、Eは、「育児休業給付の支給要件」に関する問題です。
★ 給付の「支給要件」は用語の定義や数字など、正確におさえておきましょう。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(労災保険法)
R2-4
R1.9.3 R1選択式(労災保険法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第3回目は、「労災保険法 選択式」です。
【労災保険法】
 A~Cはしっかり解けたと思います。
A~Cはしっかり解けたと思います。
A 労災保険法の「労働者」は、労働基準法上の労働者
B 労災保険法の保険給付は3つ
①業務災害に関する保険給付
②通勤災害に関する保険給付
③二次健康診断等給付
C 通勤災害に関する保険給付のうち年金として支払われるもの
・障害年金
・遺族年金
・傷病年金
 D、Eは、「保険関係成立届」の提出が行われていない間に労災事故が起きた場合の事業主からの費用徴収に関する問題です。
D、Eは、「保険関係成立届」の提出が行われていない間に労災事故が起きた場合の事業主からの費用徴収に関する問題です。
★ 「事業主からの費用徴収」については、今年の7月4日に記事にしています。
コチラ R1.7.4 事業主が保険関係成立届を提出していない場合
R1.7.4 事業主が保険関係成立届を提出していない場合
★ 今回の選択式では、「故意」「重大な過失」の認定の基準が問われました。
この論点は、平成27年に択一式で出題されています。
<参考 H27年出題その1>
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
<参考 H27年出題その2>
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を40%とする。
(解答)
その1 ○
「故意」の認定 → 保険手続に関する指導や加入勧奨を受けたにもかかわらず、10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合
「故意」が認定された場合の費用徴収率は100%
その2 ○
「重大な過失」の認定 → 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない場合で、保険関係成立日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していない
「重大な過失」が認定された場合の費用徴収率は40%
なお、「重大な過失」が認定された場合の費用徴収率については、H26年選択式でも出題されています。
★今後の勉強のポイント★
労働基準法同様、択一式で出題された箇所は、「選択式」に姿を変えて出題されることが多いです。
択一式の過去問を解くときは、常に「選択式で出題されるかも」と意識して、キーワードをおさえてくださいね。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(安衛法)
R2-3
R1.9.2 R1選択式(安衛法)振り返ります!
令和元年の問題を振り返っています。
第2回目は、「安衛法 選択式」です。
【労働安全衛生法】
D→目的条文、E→衛生管理者の資格、からの出題でした。
 目的条文は必ずチェックしてくださいね。
目的条文は必ずチェックしてくださいね。
今年は、8月16日に記事にしていました。コチラです。
「R1.8.16 【選択式対策】労働分野・目的条文チェック!(労基、安衛、労災保険、雇用保険)」
※「快適な職場環境の形成」が出題されていました。
 衛生管理者は、「免許又は一定の資格を有する者」のうちから選任しなければならないのがポイントです。一方、「安全管理者」には免許などはありませんので、比較しておさえてくださいね。
衛生管理者は、「免許又は一定の資格を有する者」のうちから選任しなければならないのがポイントです。一方、「安全管理者」には免許などはありませんので、比較しておさえてくださいね。
<参考 H22年択一>
常時50人以上の労働者を使用する製造業の事業者は、安全管理者を選任しなければならないが、安全管理者は労働安全コンサルタントのほか、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許を有する者の中から選任しなければならない。
(解答) × 安全管理者には、第1種安全管理者免許又は安全工学安全管理者免許というような免許制度はありません。
社労士受験のあれこれ
R1年 選択式(労基法)
R2-2
R1.9.1 R1選択式(労基法)振り返ります!
第51回試験から1週間たちました。
今日から、令和元年の問題を振り返ります。
第1回目は、「労基法選択式」です。
【労働基準法】
A、Bは最高裁判例「あけぼのタクシー事件」、Cは出来高払いの保障給の条文の出題です。
 「あけぼのタクシー事件」はH23年選択式でも出題されています。
「あけぼのタクシー事件」はH23年選択式でも出題されています。
<参考 H23年選択>
「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇制限期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、右労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり右利益〔…(略)…〕の額を賃金額から控除することができるが、右賃金額のうち労働基準法第12条1項所定の< A >に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されていると解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。
(解答)平均賃金の6割
★択一式でも出題されています。
<参考 H21年択一>
労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨を包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である。
(解答) ×
「使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されない」の部分が×です。
最高裁判所の判例では、「解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許される」となっています。
 出来高払制の保障給はH28年に出題されています。
出来高払制の保障給はH28年に出題されています。
<参考 H28年択一>
労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。
(解答)○
「出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず」の部分がポイントです。
今後の勉強のポイント
択一式で出題された箇所は、「選択式」に姿を変えて出題されることが多いです。
択一式の過去問を解くときは、常に「選択式で出題されるかも」と意識して、キーワードをおさえてくださいね。
社労士受験のあれこれ
試験お疲れさまでした!
R2-1
R1.8.29 まずはゆっくり休んでくださいね。
8月25日終わりました。
皆さま、試験お疲れさまでした。
ずっと頑張っていた体と頭を、まずは休ませてあげてください。
そして心も解放してあげてくださいね。
今回の試験の感想なども書いていきますので、良ければお読みください。
社労士受験のあれこれ
